加藤太一 (京都大学理学研究科)
(本ページの内容への問い合わせ先: tkato@kusastro.kyoto-u.ac.jp
著者の所属する ML Kbird への投稿の形でも歓迎。他の方の意見も仰げるかも知れない)
(2025-07-30改訂)
◆ご紹介
本ページはくまたか/日本野鳥の会筑豊支部にかつて掲載された「野鳥の学名入門」を元に内容の改訂・備考の追記を行って作成しているものである。
日本鳥類目録 改訂第7版と第8版をベースとしているが世界の分類動向など最新情報も紹介している。
掲載順は日本鳥類目録改訂第7版であるが、#第8版配列のリンクに第8版掲載順の一覧を示してあり、どちらからでも参照できる。
学名と解説は第7版、第8版ともに掲載している。#第8版新規掲載種 (最後に付記) も付記しており、(外来種は除く) 第8版の亜種を含む学名辞典としても活用いただけると思う。
第8版で#検討種一覧と若干の考察も追記した。
作成に当たっては日本野鳥の会筑豊支部および (旧)「野鳥の学名入門」作者の了承を得ている。現在は各種情報追記などの作業中であるが、すでに記述した部分だけでも有益な情報が含まれていると考えられるため、公開とともに逐次改訂を進めている。
補足の大部分の記述は著者自身が調査したものであるが、一部の (主に伝聞) 情報には出典がわからなくなっているものも含まれており、適切な引用先をご存じの方はご一報いただければ幸いである。
当初は改訂第7版をベースとしていたが、本稿準備中に日本鳥学会による日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開 (2023年9月30日) が行われ、「やむを得ない場合の修正を除いて、第8版の掲載順や分類、和名については本リストに従います」とされている (このリストの掲載順は IOC 13.2 に準拠とのこと)。さらに第二回パブリックコメントに向けた暫定リスト (2023年10月31日。国内分布情報、学名の著者情報を追加) が発表されている。
その後「一部学名の変更の見込みについて」(2023年11月28日) が発表された。
第2回パブリックコメントが発表された (2024年4月1日)。学名の一部修正と国内分布情報の追加が行われた。目録第8版の出版は2024年9月に行われた。
ちなみに IOC は国際鳥類学委員会 (International Ornithological Committee) の略。現在は IOU 国際鳥類学者連合 (International Ornithologists' Union) の名前になっているが、チェックリストの名前を呼ぶ時は IOC が使われている。IOC World Bird List から最新の分類を知ることができる。
本稿では改訂第7版時代の資料性も保持するため配列順 (および掲載種。一部例外を含む) は改訂第7版を維持し、学名等に関する記述も改訂第7版・第8版の両者を含む形とした。
更新途中時点での情報は「日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)」「日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)」して表記した。これは日本鳥類目録第8版の最終版を意味するわけでないことにご留意いただきたい (参考文献参照)。その後目録第8版が出版され、第7版から変更があるものは最終版への変更を反映している (まだ作業もれが残っているかも知れない)。
本文中などで (IOC も同じ) などとある場合は第8版発表当時の IOC 14.2 を指している。それ以降変更があったものは追記してある。
学名は世界共通の名称の考え方は正しい。しかし様々な事情により異なる学名も使われてきた。
鳥の世界 (現生の鳥と近年の絶滅種) では 2025年6月にようやく学名が世界で事実上共通化された。
この話題を手っ取り早く知りたい方は途中を飛ばして AviList がついに公開された (ファイルの日付は 2025.6.11) の部分を見ていただいてから前半の説明を読んでいただくとよいだろう。英名は共通化の対象外だが実際には多くの英名も共通化された。
学名・和名・英名索引を更新!。学名は第7版以降のもののみ含めた。さらに古くは別の概念を指していたこともあるので注意。
検討種は8版のみで学名は IOC 14.2 に合わせてある。
「野鳥の学名入門」との連続性を保つため現在使われる名称でなくても古い時代の英名も含めている。特別な注釈のないものは同じ英名が使われている。分離などによって過去の英名が現在では別の種を指すこともあるので注意。
英名索引ではかなり古い名称を見出しに含めたものもある。これは英語の表現の面白さや現在の名称を理解する上の手がかりとなるものが含まれるため。例えば学名の種小名でも過去に使われたがシノニムなどの理由で使われなくなった種小名を修飾した学名がしばしば現れる。
英名でも同様で過去の経緯が引き継がれている場合もある。古くから使われていた別種の名称に対比にする形で付けられた名前が残り、古い方の名称が別名に整理されたなどの場合に該当する。
また英国では該当種が1種で1語で十分だったが、北米で該当種が複数種あるため修飾が必要になったため名前が変わったものもある。
一方広範に分布する種類では英国式と米国式でそもそも違う単語を持ちいることもしばしばある (アビ類など)。これらもなるべく含めてある。IOC 名と eBird などの名称にしばしば違いがあるのはこれらの理由によるものが大きい。
英名は IOC リストなどで使われる英国式の綴りを主に用いている (色彩を表す grey と gray は grey に統一している)。米国式綴りでも英国文献に現れる場合は通常英国式に統一されるため。多少の例外もある。現れる種は日本産かそれに近い種なので、英名別名から何者かを想像してみるのは面白いクイズになるだろう。
このページ内へのリンク (備考参照など) には # を付けて外部ページへのリンクと区別している。これらのリンク先は [別ウインドウで開く] などで見ていただければ使いやすいと思う。
[#タカ類を新しい分類で見る]
(2024.3 掲載; 2024.8 亜科定義変更に基づく小さな修正あり; 2024.11 アメリカオオタカの位置を修正、伝統的チュウヒ亜科の説明追加) ← タカ類の最新の全分類はこちら [世界の共通リストを目指す AviList / WGAC でも採用され 2025 年前半にリリース予定。2024 年後半に IOC 14.2, Clements/eBird 2024 でも採用。GenBank Taxonomy でも採用 2025.3 確認。2025.4 海ワシ類の配列を Canatach et al. (2024) に揃えた]
[#鳥類系統樹2024] (2024.4)
◆索引
検索法 このページで検索するには
- ボタンですべてを表示(このボタンはイメージです)
- Ctrl(Macは⌘)キーを押したままFキーを押すと検索窓がポップアップ
- 検索語の入力で、ページ中の一致部分が黄色くハイライト表示
- 目的の情報が見つかるまでEnterやreturnキーを押してください。
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
新! 学名索引
学名索引 学名による種名検索です。
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z
新! 和名索引
和名索引 主に標準和名を検索します。
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
ス
セ
ソ
タ
チ
ツ
ト
ナ
ニ
ノ
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
マ
ミ
ム
メ
モ
ヤ
ユ
ヨ
ラ
リ
ル
レ
ロ
ワ
新! 英名索引
英名索引 英語の鳥名を検索します。
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z
新! 英名索引2
英名索引2 英語の鳥名を検索します。
A
B
- Baldpate (別名)
- Bargander (旧別名)
- Bee-eater, Blue-tailed (8版追加)
- Bee-eater, Rainbow
- Bergander (旧別名)
- Besra (ミナミツミ・かつてツミはこの亜種)
- Bird, Butcher (旧別名)
- Bird, Snake (旧別名)
- Bittern (旧)
- Bittern, Black
- Bittern, Chinese Little (旧)
- Bittern, Cinnamon
- Bittern, Eurasian (7・8版)
- Bittern, Schrenck's Little (旧)
- Bittern, Tiger (旧別名)
- Bittern, Von Schrenck's (7・8版)
- Bittern, Yellow (7・8版)
- Black-back, Lesser (旧別名)
- Blackbird (分離前・旧/米では別グループを指す)
- Blackbird, Chinese (分離前・8版)
- Blackbird, Common (分離前・7版・現ニシクロウタドリ?)
- Bluechat, Siberian (旧)
- Bluetail, Red-flanked
- Bluethroat
- Bonxie (広い概念の旧英別名・現キタオオトウゾクカモメ)
- Boobook, Northern (分離・8版)
- Booby, Brown (8版・IOC 分離)
- Booby, Cocos (IOC で分離)
- Booby, Masked
- Booby, Nazca (検討新規)
- Booby, Red-footed
- Boomer (旧)
- Brambling
- Brant (旧別名・北英・北米)
- Brent (別名)
- Bufflehead
- Bulbul, Black (検討継続)
- Bulbul, Brown-eared
- Bulbul, Chinese (旧)
- Bulbul, Light-vented (7・8版)
- Bullfinch (旧)
- Bullfinch, Eurasian (7・8版)
- Bunting, Black-faced (分離・8版シベリアアオジ)
- Bunting, Black-faced (分離前・7版種アオジ・分離・8版シベリアアオジ)
- Bunting, Black-headed
- Bunting, Chestnut
- Bunting, Chestnut-eared (7・8版)
- Bunting, Common Reed (7・8版)
- Bunting, Crested (検討移行)
- Bunting, Grey
- Bunting, Grey-headed (旧)
- Bunting, Grey-hooded (旧広義別名)
- Bunting, Grey-hooded (旧広義別名)
- Bunting, Grey-necked
- Bunting, Japanese Reed (7版旧)
- Bunting, Japanese Yellow (7版旧)
- Bunting, Lapland (別名)
- Bunting, Little
- Bunting, Masked (分離・8版アオジ)
- Bunting, Meadow (7・8版)
- Bunting, Ochre-rumped (8版)
- Bunting, Ortolan
- Bunting, Pallas's Reed
- Bunting, Pine
- Bunting, Red Headed
- Bunting, Reed (旧)
- Bunting, Rustic
- Bunting, Siberian Meadow (別名)
- Bunting, Snow
- Bunting, Tristram's
- Bunting, Yellow (8版)
- Bunting, Yellow (キアオジ旧別名)
- Bunting, Yellow-breasted
- Bunting, Yellow-browed
- Bunting, Yellow-throated
- Burgomaster (旧別名)
- Burrough-Duck (旧別名)
- Bush-Robin, Northern Red-flanked (分離時旧別名)
- Bush-Warbler, David's (検討継続・別名)
- Bushchat, Grey (別名)
- Bushchat, White-throated (検討継続)
- Bustard, Great
- Bustard, Little
- Bustard-quail, Common (別名)
- Buttonquail, Barred (7・8版)
- Buttonquail, Yellow-legged (検討新規)
- Buzzard (旧・分離前)
- Buzzard, Asiatic Honey (旧別名)
- Buzzard, Common (7版旧・分離前)
- Buzzard, Crested Honey (8版)
- Buzzard, Eastern (分離・8版)
- Buzzard, Eastern Honey (別名)
- Buzzard, Grey-faced (7・8版)
- Buzzard, Himalayan (ヒマラヤノスリ・亜種/別種?/分類次第)
- Buzzard, Honey (旧・分離前・7版)
- Buzzard, Japanese (分離前亜種または分離別名)
- Buzzard, Javan (旧別名 Seebohm 時代)
- Buzzard, Mongolian (別名)
- Buzzard, Oriental Honey (別名・eBird)
- Buzzard, Rough-legged
- Buzzard, Siberian (旧別名 Seebohm 時代)
- Buzzard, Siberian Honey (亜種または分離の概念あり)
- Buzzard, Upland
- Buzzard-eagle, Grey-faced (旧)
C
- Calloo (英地方名)
- Canvasback
- Chaffinch, Common (7版)
- Chaffinch, Eurasian (8版)
- Chat, Grey Bush (7・8版)
- Chat, Pied Bush
- Chatterer, Bohemian (旧別名)
- Chiffchaff (旧)
- Chiffchaff, Common (7・8版・分離しない場合)
- Chiffchaff, Siberian (亜種または分離する場合)
- Cisticola, Zitting (分離・7・8版)
- Clinker (旧別名)
- Cock, Ouzel (分離前・旧別名)
- Cock, Water (旧)
- Coot (旧)
- Coot, Eurasian (7・8版)
- Corbie (旧英・複数種を含む)
- Corbie (旧英・複数種を含む)
- Cormorant (旧)
- Cormorant, Black (旧別名・オーストラリア名)
- Cormorant, Common (旧)
- Cormorant, European (旧・米)
- Cormorant, Great (7・8版)
- Cormorant, Great Black (旧別名)
- Cormorant, Japanese
- Cormorant, Large (インド名)
- Cormorant, Pelagic
- Cormorant, Red-faced
- Cormorant, Temminck's (旧別名)
- Corncrake (別綴・8版追加)
- Coucal, Lesser
- Coween (旧別名)
- Cracke, Band-bellied
- Crake, Ashy (旧別名)
- Crake, Baillon's (7・8版)
- Crake, Banded (広義旧別名)
- Crake, Corn (8版追加)
- Crake, European Corn (別名・8版追加)
- Crake, Lesser Spotted (旧別名)
- Crake, Marsh (旧・別名)
- Crake, Ruddy (旧別名/現ズグロコビトクイナ)
- Crake, Ruddy-breasted (7・8版)
- Crake, Slaty-legged
- Crake, Slaty-legged Banded (旧別名)
- Crake, Spotted (検討移行)
- Crake, Tiny (旧)
- Crake, White-browed (7・8版)
- Crane (旧英)
- Crane, Canadian (旧別名)
- Crane, Common
- Crane, Demoiselle
- Crane, Eastern Eurasian (亜種)
- Crane, Eurasian (別名)
- Crane, Great White (旧別名)
- Crane, Hooded
- Crane, Japanese (旧)
- Crane, Manchurian (旧別名)
- Crane, Red-crowned (7・8版)
- Crane, Sandhill
- Crane, Siberian
- Crane, Siberian White (旧別名)
- Crane, White-naped (7・8版)
- Crane, White-necked (別名)
- Creeper, Brown (同種時代米/現アメリカキバシリ)
- Creeper, Nettle (旧別名・検討新規)
- Creeper, Tree (旧)
- Crossbill (旧英)
- Crossbill, Common (旧)
- Crossbill, Red (7・8版・米名由来)
- Crossbill, Two-barred
- Crossbill, White-winged (別名)
- Crow, Carrion
- Crow, Common (ヨーロッパのものを指して使われることがあった)
- Crow, Grey (亜種ズキンガラス旧英名/リストにより分離)
- Crow, Hooded (亜種ズキンガラス/リストにより分離)
- Crow, Jungle (旧・分離前)
- Crow, Large-billed (分離・7・8版)
- Crow, Oriental (亜種?別種?・分離候補)
- Crow, Royston (亜種ズキンガラス旧英名/リストにより分離)
- Crowned-Warbler, Temminck's (旧別名)
- Cuckoo (旧)
- Cuckoo, Chestnut-winged
- Cuckoo, Common (7・8版)
- Cuckoo, Drongo
- Cuckoo, Himalayan (分離後/現ヒマラヤツツドリ)
- Cuckoo, Hodgson's Hawk (旧・分離前/現インドシナジュウイチ)
- Cuckoo, Horsfield's (別名)
- Cuckoo, Jacobin (検討継続)
- Cuckoo, Large Hawk
- Cuckoo, Lesser (7・8版)
- Cuckoo, Little (旧)
- Cuckoo, Long-tailed (7版)
- Cuckoo, Oriental
- Cuckoo, Pacific Long-tailed (8版)
- Cuckoo, Pied (検討継続・別名)
- Cuckoo, Plaintive (8版追加)
- Cuckoo, Red-winged Crested (旧別名)
- Cuckoo, Short-winged
- Cuckoo-Dove, Philippine (検討継続)
- Cuckooshrike, Black-winged
- Cuckooshrike, Lesser (分離前旧/現コアサクラサンショウクイ)
- Curlew (旧)
- Curlew, Australian (旧別名)
- Curlew, Black (8版追加・旧別名)
- Curlew, Bristle-thighed
- Curlew, Eastern (旧概念)
- Curlew, Eurasian (7・8版)
- Curlew, Far Eastern (7・8版)
- Curlew, Little (7・8版)
- Curlew, Pygmy (旧別名)
- Curlew, Slender-billed
D
- Dabchick (旧英)
- Daw (旧英・分離前)
- Dipper, Asiatic (旧別名・米由来?)
- Dipper, Brown
- Dipper, Pallas's (旧別名)
- Dishwasher (旧別名)
- Diver, Black-throated (米)
- Diver, Great Northern (米)
- Diver, Pacific (米)
- Diver, Red-throated (米)
- Diver, White-billed (米)
- Dollarbird (別名・Avibase)
- Dollarbird, Oriental (7・8版)
- Dotterel (別名)
- Dotterel, Eurasian
- Dotterel, Ring (英旧別名)
- Dove, Asian Emerald (別名)
- Dove, Black-chinned Fruit
- Dove, Collared (旧)
- Dove, Collared Turtle (旧別名)
- Dove, Common Emerald (8版)
- Dove, Eastern Collared (旧別名)
- Dove, Emerald (7版旧)
- Dove, Eurasian Collared
- Dove, Green (別名)
- Dove, Green-backed (別名)
- Dove, Green-winged (別名)
- Dove, Grey-capped Emerald (別名)
- Dove, Leclancher's (別名)
- Dove, Oriental Turtle
- Dove, Red Collard (8版)
- Dove, Red Turtle (7版)
- Dove, Red-collard (別綴)
- Dove, Rock
- Dove, Rufous Turtle (旧別名)
- Dove, Spotted (検討継続)
- Dove, Stock
- Dowitcher, Asian (7・8版)
- Dowitcher, Asiatic (旧)
- Dowitcher, Long-billed
- Dowitcher, Short-billed
- Draw-water (旧別名・検討継続)
- Drongo, Ashy (7・8版)
- Drongo, Black
- Drongo, Hair Crested
- Drongo, Pale Ashy (旧)
- Duck, American Black (検討新規)
- Duck, Brahminy (インド名)
- Duck, Burrow (旧別名)
- Duck, Eastern Spot-billed (7・8版)
- Duck, Falcated
- Duck, Ferruginous (7・8版)
- Duck, Harlequin
- Duck, Lesser Tree (別名)
- Duck, Lesser Whistling
- Duck, Long-tailed
- Duck, Mandarin
- Duck, Philippine
- Duck, Ring-necked
- Duck, Spot-billed (旧・分離前)
- Duck, Spotbill (旧・分離前)
- Duck, Tufted
- Dun-Fly-catcher (旧別名)
- Dunlin
- Dunnock, Alpine (別名)
- Dunnock, Siberian (別名)
E
- Eagle, American (別名)
- Eagle, Bald
- Eagle, Black (若鳥英旧別名/同名は現カザノワシ名称/コシジロイヌワシの別名)
- Eagle, Crested Serpent
- Eagle, Eastern Imperial (分離・7・8版)
- Eagle, Fish (旧別名)
- Eagle, Golden
- Eagle, Greater Spotted
- Eagle, Grey Sea (旧米)
- Eagle, Hodgson's Hawk (別名)
- Eagle, Imperial (旧・分離前)
- Eagle, Japanese Golden (亜種イヌワシ)
- Eagle, Mountain Hawk
- Eagle, Pacific Sea (別名)
- Eagle, Sea (旧)
- Eagle, Spotted (旧・分離前)
- Eagle, Steller's Fish (別名)
- Eagle, Steller's Sea
- Eagle, Steppe (検討継続)
- Eagle, Tawny (検討継続・旧概念ソウゲンワシ/分離・現アフリカソウゲンワシ/サメイロイヌワシ)
- Eagle, White (イヌワシの白変型?)
- Eagle, White-headed (別名)
- Eagle, White-headed Fish (別名)
- Eagle, White-headed Sea (別名)
- Eagle, White-shouldered Imperial (ニシカタシロワシの旧別名)
- Eagle, White-shouldered Sea (別名)
- Eagle, White-tailed
- Eagle, White-tailed Fish (別名)
- Eagle, White-tailed Sea (別名)
- Egret, Cattle (分離前・7・8版)
- Egret, Chinese
- Egret, Common (別名)
- Egret, Eastern Cattle (IOC 分離)
- Egret, Eastern Great (亜種または別種チュウイサギ)
- Egret, Great
- Egret, Great White (別名)
- Egret, Indian Cattle (旧別名)
- Egret, Intermediate (7・8版)
- Egret, Large (別名)
- Egret, Little
- Egret, Medium (IOC)
- Egret, Plumed (同種時代オセアニア/分離後オーストラリアチュウサギ)
- Egret, Swinhoe's (旧別名)
- Egret, Yellow-billed (同種時代アフリカ/分離後アフリカチュウサギ?)
- Eider, Common (検討継続)
- Eider, King
- Eider, Steller's
- Erne (別名)
F
- Fairytern, Indo-Pacific (分離案あり)
- Falcon, Amur
- Falcon, Eastern Red-footed (別名)
- Falcon, Gyr (別綴)
- Falcon, Jer (別綴)
- Falcon, Manchurian (旧別名)
- Falcon, Manchurian Red-footed (旧別名)
- Falcon, Peregrine
- Falcon, Red-footed (旧・分離前/現ニシアカアシチョウゲンボウ)
- Falcon, Saker (検討移行)
- Falcon, Stone (若鳥旧別名)
- Felfer (旧別名)
- Felt (旧別名)
- Fieldfare
- Finch, Asian Rosy (7・8版)
- Finch, Long-tailed Rose
- Finch, Rosy (旧)
- Finch, Scarlet (旧別名)
- Firetail (旧別名)
- Flamingo, European (別名・検討新規)
- Flamingo, Greater (検討新規)
- Flycatcher, Amur Paradise (分離・検討新規・記録種?)
- Flycatcher, Asian Brown (7・8版)
- Flycatcher, Asian Paradise (分離前・検討新規・分離後未定)
- Flycatcher, Asiatic Paradise (分離前・別名・検討新規・分離後未定)
- Flycatcher, Black Paradise (8版)
- Flycatcher, Blue-and-white
- Flycatcher, Broad-billed (旧別名)
- Flycatcher, Brown (旧)
- Flycatcher, Brown-breasted (8版追加)
- Flycatcher, Brown-chested Jungle (検討新規)
- Flycatcher, Chinese (分離・検討継続・別名)
- Flycatcher, Dark-sided (7・8版)
- Flycatcher, European Pied
- Flycatcher, Ferruginous
- Flycatcher, Green-backed (分離・検討継続)
- Flycatcher, Grey-spotted (旧)
- Flycatcher, Grey-streaked (7・8版)
- Flycatcher, Indian Paradise (分離・検討新規・記録種ではない?)
- Flycatcher, Japanese Paradise (7版旧)
- Flycatcher, Mugimaki
- Flycatcher, Narcissus
- Flycatcher, Red-breasted (旧・分離前/分離・7・8版ニシオジロビタキ)
- Flycatcher, Ryukyu (分離・8版)
- Flycatcher, Siberian (旧別名)
- Flycatcher, Sooty (旧名/現ススチャヒタキ)
- Flycatcher, Spot-breasted (旧別名)
- Flycatcher, Spotted
- Flycatcher, Taiga (分離・7・8版オジロビタキ)
- Flycatcher, Tricolor (旧・属統合・先取権問題由来)
- Flycatcher, Verditer
- Flycatcher, Yellow-rumped
- Frigatebird, Christmas (検討継続)
- Frigatebird, Christmas Island (検討継続・別名)
- Frigatebird, Great
- Frigatebird, Lesser
- Fulmar (旧)
- Fulmar, Northern (7・8版)
G
- Gadwall
- Gallinule, Common (同種時代米名・現アメリカバン)
- Garganey
- Gawk (旧英地方名)
- Godwit, Bar-tailed
- Godwit, Black-tailed
- Godwit, Hudsonian
- Godwit, Red (旧別名・夏羽)
- Godwit, Red (旧別名・夏羽)
- Goldcrest
- Goldeneye (旧)
- Goldeneye, Barrow's (検討継続)
- Goldeneye, Common (7・8版)
- Goldfinch (別名・検討継続)
- Goldfinch, European (検討継続)
- Goosander (別名・ヨーロッパ名)
- Goose, Bar (旧別名)
- Goose, Bar-headed
- Goose, Bean
- Goose, Blue (色彩型)
- Goose, Blue Snow (色彩型・別名)
- Goose, Brant
- Goose, Brent (米・eBird)
- Goose, Cackling (分離・シジュウカラガン)
- Goose, Canada (分離前・分離後カナガン)
- Goose, Chinese (家禽品種・旧種名)
- Goose, Cotton Pygmy (8版)
- Goose, Emperor
- Goose, Greater Snow (大型亜種とされた時代)
- Goose, Greater White-fronted
- Goose, Greylag
- Goose, Lesser Snow (小型亜種とされた時代)
- Goose, Lesser White-fronted
- Goose, Rain (英旧別名)
- Goose, Red-breasted (8版追加)
- Goose, Snow
- Goose, Swan
- Goose, Taiga Bean (オオヒシクイ・亜種/リストにより分離)
- Goose, Tundra Bean (ヒシクイ・亜種/リストにより分離)
- Goshawk (旧)
- Goshawk, Chinese (旧)
- Goshawk, Eastern (分離・別名)
- Goshawk, Eurasian (分離・8版)
- Goshawk, Grey (旧別名)
- Goshawk, Northern (分離前・7版)
- Grassbird, Marsh (7・8版)
- Grebe, Black-necked
- Grebe, Crested (過去米=誤解)
- Grebe, Eared (別名・米)
- Grebe, Great Crested
- Grebe, Holboelli's (米亜種または種別名)
- Grebe, Horned (7・8版)
- Grebe, Little
- Grebe, Red-necked
- Grebe, Red-throated Little (旧別名)
- Grebe, Slavonian (旧・主にヨーロッパ名)
- Greenfinch, Bonin (分離・8版)
- Greenfinch, Grey-capped (IOC 旧)
- Greenfinch, Ogasawara (分離・別名)
- Greenfinch, Oriental
- Greenshank (旧)
- Greenshank, Armstrong's (旧別名)
- Greenshank, Common (7・8版)
- Greenshank, Nordmann's
- Greenshank, Spotted (別名)
- Grosbeak, Bonin
- Grosbeak, Chinese (7・8版)
- Grosbeak, Japanese
- Grosbeak, Pine
- Grosbeak, Yellow-billed (旧)
- Grouse, Hazel
- Guillemot (旧別名)
- Guillemot, Black (検討新規)
- Guillemot, Brunnich's (旧別名)
- Guillemot, Pigeon
- Guillemot, Sooty (旧別名)
- Guillemot, Spectacled
- Gull, American Herring (分離・検討移行)
- Gull, Black-headed
- Gull, Black-tailed
- Gull, Bonaparte's
- Gull, Brown-headed
- Gull, California (検討継続)
- Gull, Caspian (検討継続)
- Gull, Chinese Black-headed (旧別名)
- Gull, Common
- Gull, East Siberian (分離・別名)
- Gull, Franklin's
- Gull, Glaucous
- Gull, Glaucous-winged
- Gull, Great Black-headed (旧別名)
- Gull, Herring (分離前・7版)
- Gull, Iceland
- Gull, Ivory
- Gull, Japanese (旧別名)
- Gull, Laughing
- Gull, Lesser Black-backed
- Gull, Little
- Gull, Mew (別名・特に米)
- Gull, Pallas's
- Gull, Relict
- Gull, Ring-billed (検討継続)
- Gull, Ross's
- Gull, Sabine's
- Gull, Saunders's
- Gull, Slaty-backed
- Gull, Slender-billed
- Gull, Temminck's (旧別名)
- Gull, Thayer's
- Gull, Vega (分離・8版)
- Gull, Yellow-legged
- gyr (略)
- Gyrfalcon
H
- Hammer, Yellow (別綴)
- Harrier (米・旧)
- Harrier, Eastern Marsh (分離・7・8版)
- Harrier, Eurasian Marsh (分離前・旧)
- Harrier, Hen
- Harrier, Marsh (分離前・旧)
- Harrier, Montagu's (検討継続)
- Harrier, Northern (分離・8版追加)
- Harrier, Northern Marsh (分離前・旧)
- Harrier, Pale (別名・検討移行)
- Harrier, Pallid (検討移行)
- Harrier, Pied
- Harrier, Western Marsh (分離・検討移行)
- Harry, King (旧別名・検討継続)
- Hawfinch
- Hawfinch, Black-tailed (旧別名)
- Hawk, Chinese Sparrow (別綴)
- Hawk, Duck (米旧別名)
- Hawk, Fish (旧別名)
- Hawk, Grey Frog (旧別名)
- Hawk, Marsh (別名)
- Hawk, Pigeon (旧米別名)
- Hawk, Rough-legged (米)
- hawk sp., Accipitrine (日本のハイタカ属相当の eBird 概念)
- Hawk, Sparrow (別綴)
- Hawk-Cuckoo, Northern (分離・8版)
- Hawk-Cuckoo, Rufous (分離・7版)
- Heron, Amur Green (旧別名)
- Heron, Black-crowned Night (7・8版・もと米名)
- Heron, Chinese Pond
- Heron, Eastern Reef (旧)
- Heron, Green-backed (分離前)
- Heron, Grey
- Heron, Indian Pond (検討新規)
- Heron, Japanese Night
- Heron, Javan Pond (検討継続)
- Heron, Little (IOC 15.1 分離)
- Heron, Malay Night (旧別名)
- Heron, Malayan Night (7・8版)
- Heron, Malaysian Night (旧)
- Heron, Nankeen Night (7・8版)
- Heron, Night (旧)
- Heron, Pacific Reef (7・8版)
- Heron, Purple
- Heron, Rufous Night (旧)
- Heron, Striated (7・8版・IOC 15.1 分離前)
- Heron, White (亜種または別種チュウイサギのニュージーランド名)
- Hobby (旧)
- Hobby, Eurasian (7・8版)
- Hobby, Northern (別名)
- Honeyeater, Bonin (旧)
- Hoodie (亜種ズキンガラス旧英名/リストにより分離)
- Hoopoe (旧)
- Hoopoe, Eurasian (7・8版)
- Hwamei (旧)
- Hwamei, Chinese (7・8版)
I
J
K
- kawau (ニュージーランド名マオリ名・亜種)
- Kestrel (旧)
- Kestrel, Common (7・8版)
- Kestrel, Lesser
- Kingfisher (旧)
- Kingfisher, Black-capped
- Kingfisher, Collared
- Kingfisher, Common
- Kingfisher, Crested (7・8版)
- Kingfisher, Crested Pied (旧)
- Kingfisher, Miyako (IOC に含まれず・別名)
- Kingfisher, Miyako Island (IOC に含まれず・7版・H&M4 英名)
- Kingfisher, Oriental Dwarf
- Kingfisher, Ruddy
- Kingfisher, Ryukyu (8版・IOC に含まれず)
- Kingfisher, White-breasted (検討移行・別名)
- Kingfisher, White-throated (検討移行)
- Kinglet (旧別名)
- Kinglet, Ruby-crowned (検討継続)
- Kite (英国ではアカトビを指す)
- Kite, Black
- Kite, Black-eared (別名または亜種・分離の考えもある)
- Kite, Black-shouldered (分離前・検討移行)
- Kite, Black-winged (分離後・検討移行)
- Kite, Blue (旧別名・検討移行)
- Kite, Brahminy (検討継続)
- Kite, Common Black-shouldered (分離後別名・検討移行)
- Kite, Eared (別名または亜種・分離の考えもある)
- Kite, Large Indian (別名または亜種・分離の考えもある)
- Kittiwake (旧)
- Kittiwake, Black-legged (7・8版)
- Kittiwake, Common (旧)
- Kittiwake, Red-legged
- Knot, Great
- Knot, Red
- Koel (旧別名)
- Koel, Asian
- Koel, Long-tailed (旧)
L
- Lark, Mongolian
- Lark, Red-capped (旧・分離前別名/現アフリカヒメコウテンシ)
- Lark, Shore (別名・ヨーロッパ名)
- Lark, Short-toed (旧・分離前)
- Laughingthrush, Melodius (旧別名)
- Leaf-Warbler, Grey-legged (Avibase)
- Leaf-Warbler, Inornate (別名)
- Leaf-Warbler, Izu (別名)
- Leaf-Warbler, Pallas's (Avibase)
- Leaf-Warbler, Radde's (別名)
M
- Magpie (旧)
- Magpie, Azure-winged
- Magpie, Black-billed (分離前・米/現アメリカカササギ)
- Magpie, Eurasian (分離前・8版)
- Magpie, Oriental (分離・8版)
- Mallard
- Martin, Asian House
- Martin, Asian Plain (分離・別名・暫定同定)
- Martin, Bank (旧別名・eBird)
- Martin, Brown-throated (分離前・8版)
- Martin, Collared Sand (インド名)
- Martin, Common House (旧・7版・分離・検討種・分離後日本記録亜種を含まず)
- Martin, European Sand (別名)
- Martin, Grey-throated (分離・IOC 同定暫定)
- Martin, House (旧・分離前・検討移行)
- Martin, Pale (検討新規)
- Martin, Plain (分離前・8版)
- Martin, Sand
- Martin, Siberian House (分離・検討移行・分離後日本記録亜種を含む)
- Martin, Western House (分離・検討移行・分離後日本記録亜種を含まず)
- Mate, Cuckoo's (旧英)
- Mavis (旧別名・8版追加)
- Merganser, Chinese (旧)
- Merganser, Common
- Merganser, Hooded (8版追加)
- Merganser, Red-breasted
- Merganser, Scaly-sided (7・8版)
- Merlin
- Merlin, Jack (オス旧別名)
- Minivet, Ashy (分離前・7版種または亜種サンショウクイ・8版サンショウクイ)
- Minivet, Ryukyu (分離・8版)
- minivets, grey (種グループ/サンショウクイ上種)
- Mollymawk (Thalassarche 属名)
- Mollymawk (旧別名)
- Monarch, Black-naped
- Moorhen (旧)
- Moorhen, Common (7・8版)
- Morillon (メス・若鳥を指し別種とみなされた時代もあり)
- Mouse-hawk (旧英別名)
- Murre, Common
- Murre, Thick-billed (7・8版)
- Murrelet, Ancient
- Murrelet, Crested (旧)
- Murrelet, Japanese (7・8版)
- Murrelet, Kittlitz's (検討継続)
- Murrelet, Long-billed (7・8版)
- Murrelet, Marbled (旧・別名)
- Muttonbird (地方名・別名)
- Myna, Daurian (旧別名)
- Myna, Red-cheeked (旧別名)
- Myna, White-cheeked (別名)
N
O
- Owl, Eastern Grass (7版・8版検討移行)
- Owl, Eurasian Eagle (7・8版)
- Owl, Grass (8版検討移行・旧分離前)
- Owl, Himalayan (分離・検討新規)
- Owl, Japanese Scops (分離・8版)
- Owl, Long-eared
- Owl, Oriental Scops (分離・7・8版)
- Owl, Ryukyu Scops
- Owl, Scops (旧・分離前)
- Owl, Short-eared
- Owl, Snowy
- Owl, Tawny (分離前モリフクロウ・検討新規)
P
- Parrotbill, Bearded (旧別名)
- Parrotbill, Vinous-throated (検討継続)
- Partridge, Bamboo (旧)
- Partridge, Chinese Bamboo (7・8版)
- Pastor, Rosy (旧別名)
- Pelican, Dalmatian
- Pelican, Great White (7・8版)
- Pelican, Rosy (旧)
- Pelican, Spot-billed
- Pelican, White (旧)
- Peregrine (英別名)
- Petrel, Band-rumped Storm (7・8版)
- Petrel, Black-winged
- Petrel, Bonin
- Petrel, Bulwer's
- Petrel, Cape (検討継続)
- Petrel, Cook's (検討継続)
- Petrel, Dark-rumped (7版)
- Petrel, Fork-tailed (旧別名)
- Petrel, Fork-tailed Storm
- Petrel, Fulmar (旧別名)
- Petrel, Fulmarine (別名・総称でも使われる)
- Petrel, Harcourt's Storm (旧別名・分離前)
- Petrel, Hawaiian (8版)
- Petrel, Herald (分離・検討継続・推定名)
- Petrel, Juan Fernandez
- Petrel, Kermadec
- Petrel, Leach's (別名)
- Petrel, Leach's Storm (別綴)
- Petrel, Least Storm (検討継続)
- Petrel, Matsudaira's Storm
- Petrel, Mottled
- Petrel, Providence
- Petrel, Slender-billed (別名)
- Petrel, Stejneger's
- Petrel, Swinhoe's Storm
- Petrel, White-naped (分離・8版追加・別名)
- Petrel, White-necked (分離前オオシロハラミズナギドリ・分離・8版追加)
- Petrel, Wilson's Storm
- Phalarope, Grey (別名・主にヨーロッパ名)
- Phalarope, Hyperborean (米別名)
- Phalarope, Northern (米別名)
- Phalarope, Red (米別名)
- Phalarope, Red-necked
- Phalarope, Wilson's
- Pheasant, Common (7版旧・分離前/現タイリクキジ)
- Pheasant, Copper
- Pheasant, Green (分離・IOC・8版)
- Pheasant, Japanese (7版旧・分離前)
- Pheasant, Reed (旧別名)
- Pheasant, Ring-necked (同種時代米名/現タイリクキジ)
- Pigeon, Black Wood (8版)
- Pigeon, Bonin Wood (7・8版)
- Pigeon, Green-winged (別名)
- Pigeon, Hill (検討新規)
- Pigeon, Japanese Green (旧)
- Pigeon, Japanese Wood (7版旧)
- Pigeon, Jouy's Wood (旧別名)
- Pigeon, Little Green (別名)
- Pigeon, Ogasawara Islands Wood (旧)
- Pigeon, Red-capped Green (旧・分離前別名・台湾亜種または種)
- Pigeon, Rock (オーストラリアの別属の名称にもある)
- Pigeon, Ryukyu Green (IOC で分離)
- Pigeon, Ryukyu Wood (7・8版)
- Pigeon, Silver-banded Black (旧)
- Pigeon, Taiwan Green (分離後・8版・IOC でさらに分離)
- Pigeon, Whistling Green (分離前・7版旧)
- Pigeon, White-bellied Green (7・8版)
- Pintail (旧)
- Pintail, Northern (7・8版)
- Pipit, Blyth's
- Pipit, Buff-bellied (分離前・7・8版)
- Pipit, Godlewski's (別名)
- Pipit, Indian Tree (旧概念・分離前)
- Pipit, Japanese (別名・分割後に対応)
- Pipit, Meadow
- Pipit, Olive-backed (7・8版)
- Pipit, Pechora
- Pipit, Red-throated
- Pipit, Richard's
- Pipit, Rosy
- Pipit, Siberian (分離・IOC)
- Pipit, Tawny (検討継続)
- Pipit, Tree
- Pipit, Water (旧分離前/検討継続・現サメイロタヒバリ/ヒガシヨーロッパタヒバリ)
- Pipit, Water (旧分離前・6版タヒバリ)
- Pitta, Blue-winged (旧分離前/現ミナミヤイロチョウ)
- Pitta, Fairy (7・8版)
- Pitta, Hooded
- Plover, American Golden (検討移行)
- Plover, Black (旧別名)
- Plover, Black-bellied (旧別名・米)
- Plover, Caspian (分離前別名・現ニシオオチドリ)
- Plover, Common Ringed
- Plover, Eastern Grey (亜種)
- Plover, European Golden (7・8版)
- Plover, Golden (旧)
- Plover, Greater Sand
- Plover, Green (旧別名)
- Plover, Grey
- Plover, Kentish
- Plover, Lesser Golden (旧)
- Plover, Lesser Sand (7版旧)
- Plover, Little Ringed
- Plover, Long-billed (7・8版)
- Plover, Long-billed Ringed (旧)
- Plover, Mongolian (旧)
- Plover, Oriental
- Plover, Pacific Golden (7・8版)
- Plover, Ringed (英別名)
- Plover, Semipalmated
- Plover, Siberian Sand (8版)
- Plover, Snowy (同種時代米名/現ユキチドリ)
- Plover, Wrangel Island Grey (亜種)
- Ploverspage (英旧別名)
- Pochard (旧)
- Pochard, Baer's
- Pochard, Common (7・8版)
- Pochard, European (旧別名)
- Pochard, Red-crested
- Pochard, Siberian (別名)
- Pochard, White-eye (旧)
- Pratincole, Indian (分離前旧別名)
- Pratincole, Oriental
- Prewit (旧別名)
- Prinia, Plain (分離・検討継続・推定名)
- Ptarmigan (旧英名)
- Ptarmigan, Rock (米名由来)
- Puffin, Horn-billed (旧別名)
- Puffin, Horned
- Puffin, Tufted
- Pyewipe (旧別名)
- Pygmy-goose, Cotton (7版)
Q
R
- Rail, Ashy (旧別名)
- Rail, Brown-cheeked (分離・8版)
- Rail, Land (旧別名・8版追加)
- Rail, Okinawa
- Rail, Slaty-breasted
- Rail, Swinhoe's (7・8版)
- Rail, Swinhoe's Yellow (旧別名)
- Rail, Water (分離前・7版/現ヨーロッパクイナ)
- Rail, White-browed (別名)
- Rail, Yellow (旧別名)
- Raven (旧)
- Raven, Common (旧)
- Raven, Northern (7・8版)
- Raven, Oriental (旧別名)
- Razorbill (検討移行)
- Red-leg (旧別名)
- Redbreast (旧別名)
- Redhead
- Redpoll (統合・8版・IOC)
- Redpoll, Arctic (統合前・7版コベニヒワ・8版亜種概念変更)
- Redpoll, Common (統合前・7版ベニヒワ・8版統合後英名)
- Redpoll, Hoary (米・統合前・7版コベニヒワ・8版亜種概念変更)
- Redshank (旧)
- Redshank, Common (7・8版)
- Redshank, Dusky (旧別名)
- Redshank, Spotted
- Redstart (旧)
- Redstart, Black
- Redstart, Blue-fronted (検討継続)
- Redstart, Common (7・8版)
- Redstart, Daurian
- Redstart, Eversmann's (7・8版)
- Redstart, Plumbeous (8版追加・別名)
- Redstart, Plumbeous Water (8版追加)
- Redstart, Rufous-backed (別名)
- Redwing
- Reedling (旧別名)
- Reedling, Bearded
- Reeve (メス)
- Ring-tail (メスや若鳥別名・ヒメハイイロチュウヒも含む)
- Ring-tail (検討継続・メスや若鳥別名・ハイイロチュウヒも含む)
- Robin (旧)
- Robin, Amami (旧)
- Robin, American (検討新規)
- Robin, European (7・8版)
- Robin, Izu (タネコマドリ・亜種または分離)
- Robin, Japanese
- Robin, Okinawa (分離・8版ホントウアカヒゲ)
- Robin, Orange-flanked Bush (同種時代別名/現ヒマラヤルリビタキ)
- Robin, Pekin (旧別名)
- Robin, Rufous-tailed
- Robin, Ryukyu (分離前・7版・分離・8版アカヒゲ)
- Robin, Siberian Blue
- Robin, Swinhoe's Red-tailed (旧別名)
- Robin, White-tailed (検討継続)
- Rock-thrush, White-throated
- Rockthrush, Blue (別綴)
- Rockthrush, White-breasted (旧別名)
- Roller, Broad-billed (旧)
- Roller, Eastern Broad-billed (別名)
- Rook
- Rosefinch (旧)
- Rosefinch, Common
- Rosefinch, Pallas's (7・8版)
- Rubythroat, Chinese (検討新規・分離・推定名)
- Rubythroat, Siberian
- Ruff
S
- Saker (別名・検討移行)
- Saker, Common (別名・検討移行)
- Saker, Siberian (別名・検討移行)
- Sanderling
- Sandgrouse (旧)
- Sandgrouse, Pallas's (7・8版)
- Sandpiper, Armstrong's (旧別名)
- Sandpiper, Baird's
- Sandpiper, Broad-billed
- Sandpiper, Buff-breasted
- Sandpiper, Common
- Sandpiper, Curlew
- Sandpiper, Green
- Sandpiper, Grey-rumped (旧別名)
- Sandpiper, Grey-tailed (旧別名)
- Sandpiper, Marsh
- Sandpiper, Okhotsk Tringine (旧別名)
- Sandpiper, Pectoral
- Sandpiper, Purple (旧分離前/現ムラサキハマシギ)
- Sandpiper, Red-headed (米旧別名)
- Sandpiper, Rock
- Sandpiper, Semipalmated (検討継続)
- Sandpiper, Sharp-tailed
- Sandpiper, Spoon-billed
- Sandpiper, Spotted
- Sandpiper, Stilt
- Sandpiper, Terek
- Sandpiper, Western
- Sandpiper, White-rumped
- Sandpiper, Wood
- saw-bills (カワアイサ・ウミアイサ総称)
- Scaup (旧)
- Scaup, Greater (7・8版)
- Scaup, Lesser
- Scoter, American (別名)
- Scoter, Black
- Scoter, Common (旧)
- Scoter, Stejneger's (分離・8版)
- Scoter, Surf
- Scoter, Velvet (7版旧ビロードキンクロ/分離・検討新規ヨーロッパビロードキンクロ)
- Scoter, Velvet (旧分離前/分離・検討新規ヨーロッパビロードキンクロ)
- Scoter, White-winged (分離前米名・分離・8版)
- Sea-Lark (英旧別名)
- Shag, Black (旧別名)
- Shaheen (インド亜種別名)
- Shangar (別名・検討移行)
- Shearwater, Audubon's (旧・分類変更)
- Shearwater, Bannerman's (分離)
- Shearwater, Bryan's
- Shearwater, Buller's
- Shearwater, Christmas
- Shearwater, Flesh-footed
- Shearwater, Manx (検討移行)
- Shearwater, Newell's
- Shearwater, Pale-footed (別名)
- Shearwater, Pink-footed
- Shearwater, Sable (改名提案)
- Shearwater, Short-tailed
- Shearwater, Slender-billed (別名)
- Shearwater, Sooty
- Shearwater, Streaked
- Shearwater, Townsend's (検討新規)
- Shearwater, Wedge-tailed
- Shearwater, White-faced (別名)
- Sheldrake (旧別名・オス)
- Sheldrake, Ruddy (旧別名・オス)
- Shelduck (別名)
- Shelduck, Common
- Shelduck, Crested
- Shelduck, Northern (別名)
- Shelduck, Ruddy
- Shoveler (英・旧)
- Shoveler, Common (別名)
- Shoveler, Northern (7・8版)
- Shrike, Brown
- Shrike, Bull-headed
- Shrike, Chinese Great Grey (旧別名)
- Shrike, Chinese Grey
- Shrike, Great (旧・分離前)
- Shrike, Great Grey (分離前・7版)
- Shrike, Isabelline (検討移行)
- Shrike, Long-tailed
- Shrike, Northern (分離・8版・分類変更)
- Shrike, Red-back (別名)
- Shrike, Red-backed
- Shrike, Rufous-backed (旧別名)
- Shrike, Tiger
- Sibia, White-eared (検討継続)
- Sie-pie (英旧別名)
- Siskin (旧)
- Siskin, Eurasian (7・8版)
- Skua, Arctic (旧・ヨーロッパ名)
- Skua, Buffon's (旧別名)
- Skua, Great (広い概念の旧別名/現キタオオトウゾクカモメ)
- Skua, Great (広い概念の旧別名/現キタオオトウゾクカモメ)
- Skua, Long-tailed (ヨーロッパ名)
- Skua, McCormick's (別名)
- Skua, Pomarine (7版・ヨーロッパ名)
- Skua, Pomatorhine (旧別名)
- Skua, Richardson's (旧別名)
- Skua, South Polar (7・8版)
- Skylark (旧)
- Skylark, Eurasian (7・8版)
- Skylark, Oriental (検討継続)
- Smew
- Snipe, Australian (旧別名)
- Snipe, Chinese (別名)
- Snipe, Common
- Snipe, Forest (別名)
- Snipe, Greater Painted (7・8版)
- Snipe, Jack
- Snipe, Japanese (旧)
- Snipe, Latham's (7・8版)
- Snipe, Martin (英旧別名)
- Snipe, Painted (旧)
- Snipe, Pin-tailed (8版)
- Snipe, Pintail (7版)
- Snipe, Sea (英旧別名)
- Snipe, Solitary
- Snipe, Summer (英旧別名)
- Snipe, Swinhoe's
- Snowflake (英旧別名)
- Sparrow, English (旧米)
- Sparrow, Eurasian Tree (7・8版)
- Sparrow, Fox (分離前・7・8版)
- Sparrow, Golden-crowned
- Sparrow, House
- Sparrow, Pit (旧別名)
- Sparrow, Red Fox (分離・IOC 該当でない?)
- Sparrow, Reed (旧別名)
- Sparrow, Russet
- Sparrow, Savannah
- Sparrow, Song
- Sparrow, Sooty Fox (分離・IOC 推定)
- Sparrow, Tree (旧)
- Sparrow, White-crowned
- Sparrow-Hawk, Chinese (ツミ旧別名 Seebohm ミナミツミから分離時代)
- Sparrowhawk (旧)
- Sparrowhawk, Asian (地方名)
- Sparrowhawk, Asiatic (ミナミツミと同種時代の旧別名)
- Sparrowhawk, Besra (ミナミツミ別名・かつてツミはこの亜種)
- Sparrowhawk, Chinese (7・8版)
- Sparrowhawk, Eastern (ミナミツミと同種時代の旧別名)
- Sparrowhawk, Eurasian (7・8版)
- Sparrowhawk, Horsfield's (旧別名)
- Sparrowhawk, Indian (地方名)
- Sparrowhawk, Japanese (7・8版)
- Sparrowhawk, Japanese Lesser (旧)
- Sparrowhawk, Lesser (ミナミツミと同種時代の旧名)
- Sparrowhawk, Little (旧別名)
- Sparrowhawk, Northern (別名)
- Spoonbill (旧)
- Spoonbill (旧別名)
- Spoonbill, Black-faced
- Spoonbill, Eurasian (7・8版)
- Stare (旧別名)
- Starling (旧)
- Starling, Asian Glossy (検討継続)
- Starling, Chestnut-cheeked (7・8版)
- Starling, Common
- Starling, Daurian
- Starling, European (米・eBird)
- Starling, Grey (旧)
- Starling, Grey-headed (旧別名)
- Starling, Purple-backed (別名)
- Starling, Red-billed
- Starling, Red-cheeked (旧 Seebohm 時代)
- Starling, Rose-coloured (旧別名)
- Starling, Rosy (7・8版)
- Starling, Silky (旧別名)
- Starling, White-cheeked (7・8版)
- Starling, White-shouldered
- Stilt (旧)
- Stilt, Black-winged
- Stilt, Pied (分離・8版追加)
- Stint, Little
- Stint, Long-toed
- Stint, Red-necked
- Stint, Rufous-necked (旧別名)
- Stint, Temminck's
- Stonechat (英北部旧別名)
- Stonechat (旧・分離前)
- Stonechat, Amur (分離・改名・IOC 15.1)
- Stonechat, Common (7版旧・分離前)
- Stonechat, Eastern (再統合された場合の Siberian Stonechat の別名・H&M4 名称)
- Stonechat, Siberian (この概念に再統合可能性あり・IOC 15.1 では未採用)
- Stonechat, Stejneger's (分離・8版)
- Stonehatch (英旧別名)
- Stork, Black
- Stork, Oriental
- Stork, White (旧・分離前/現シュバシコウ)
- Storm-Petrel, Grey-backed (検討継続)
- Storm-petrel, Leach's (7・8版)
- Storm-petrel, Madeiran (旧・分離前)
- Storm-petrel, Tristram's
- Stormcock (旧別名)
- Stubtail, Asian (7・8版)
- Swallow, Bank (米)
- Swallow, Barn (7・8版)
- Swallow, Eastern Red-rumped (分離・IOC)
- Swallow, House (旧)
- Swallow, Pacific
- Swallow, Red-rumped (分離前・7版)
- Swallow, Sea (英旧別名)
- Swallow, Sea (英旧別名)
- Swallow, Striated (検討新規)
- Swallow, Tree (検討移行)
- Swallow, White-breasted Wood (別表記)
- Swallow-Plover, Eastern (旧別名)
- Swamphen, Purple (分離・検討継続・推定名・別名)
- Swamphen, Western (分離・検討継続・推定名)
- Swan, Bewick's (別名・同種扱いでユーラシア亜種)
- Swan, Mute
- Swan, Trumpeter
- Swan, Tundra (7・8版・同種扱いで eBird も採用)
- Swan, Whistling (旧・米亜種由来)
- Swan, Whooper
- Swift, Common (検討継続)
- Swift, House
- Swift, Northern White-rumped (別名・アフリカコシジロアマツバメから派生する名称)
- Swift, Pacific (7・8版)
- Swift, Spine-tailed (旧別名)
- Swift, White-rumped (旧・分離前/現アフリカコシジロアマツバメ)
- Swift, White-throated Needle-tailed (旧別名)
- Swift, White-throated Spine-tailed (旧別名)
- Swiftlet, Edible-nest (分離前・検討継続)
- Swiftlet, German's (分離・検討継続)
- Swiftlet, Himalayan (検討移行)
- Swiftlet, Uniform (検討継続)
T
- Tattler, American Wandering (英旧)
- Tattler, Grey-tailed
- Tattler, Polynesian (旧別名)
- Tattler, Siberian (旧別名)
- Tattler, Wandering (米由来)
- Teal (7版旧)
- Teal, Baikal
- Teal, Blue-winged
- Teal, Common (8版種コガモ・IOC 15.1 分離)
- Teal, Eurasian (8版種コガモ・IOC 15.1 分離・eBird 亜種名)
- Teal, Green-winged (分離時アメリカコガモ/IOC 15.1 では分離/eBird で亜種名/同種時でも使われた)
- Tern, Aleutian
- Tern, Arctic
- Tern, Black (7・8版)
- Tern, Black-naped
- Tern, Bridled
- Tern, Brown-winged (旧別名)
- Tern, Caspian
- Tern, Chinese Crested (検討新規)
- Tern, Common
- Tern, Common White (別名)
- Tern, Crested (旧別名)
- Tern, Fairy (別名・同種時代は広く使われた/通常は別種ヒメアジサシによく使われる)
- Tern, Great Crested (旧別名)
- Tern, Greater Crested
- Tern, Grey-backed (別名)
- Tern, Gull-billed
- Tern, Least (8版追加・同種時米名)
- Tern, Lesser Crested
- Tern, Little
- Tern, Roseate
- Tern, Sooty
- Tern, Spectacled
- Tern, Swift (旧別名)
- Tern, Whiskered
- Tern, White (分離後の種グループ名の考えもある)
- Tern, White-winged (8版)
- Tern, White-winged Black (7版・別名)
- Throstle (旧別名・8版追加)
- Thrush, Amami (オオトラツグミ・海外で別種)
- Thrush, Black-throated (分離・8版)
- Thrush, Blue Rock
- Thrush, Bonin
- Thrush, Bonin Islands (旧別名)
- Thrush, Bramble (旧別名)
- Thrush, Brown (旧)
- Thrush, Brown-headed (7・8版)
- Thrush, Common Rock (8版追加)
- Thrush, Dark-throated (旧・分離前)
- Thrush, Dusky (分離前・7・8版)
- Thrush, Eye-browed (誤綴と言えるが使われていた)
- Thrush, Eyebrowed (7・8版)
- Thrush, Golden Mountain (分離前・旧別名)
- Thrush, Grey (旧)
- Thrush, Grey-backed
- Thrush, Grey-cheeked
- Thrush, Grey-headed (旧)
- Thrush, Izu
- Thrush, Izu Island (旧別名別綴)
- Thrush, Izu Islands (旧別名)
- Thrush, Japanese (7・8版)
- Thrush, Japanese Grey (旧別名)
- Thrush, Laughing (旧別名)
- Thrush, Melodius Laughing (旧別名)
- Thrush, Mistle
- Thrush, Naumann's (分離・8版ハチジョウツグミ)
- Thrush, Orange-headed (8版追加)
- Thrush, Pale
- Thrush, Red-throated (分離・8版ノドアカツグミ・検討追加)
- Thrush, Red-throated (分離前・7版ノドグロツグミ)
- Thrush, Scaly (8版・海外概念と相違)
- Thrush, Siberian
- Thrush, Song (8版追加)
- Thrush, White's
- Thrush, White's Ground (旧)
- Tit, Asian (統合・8版・別名 eBird など)
- Tit, Azure
- Tit, Bearded (別名)
- Tit, Bottle (別名)
- Tit, Chinese Penduline (分離・8版)
- Tit, Cinereous (統合・8版/7版では分離)
- Tit, Coal
- Tit, Cole (別綴)
- Tit, Eurasian Penduline (分離前・7版/現ニシツリスガラ)
- Tit, European Penduline (旧・分離前別名/現ニシツリスガラ)
- Tit, Great (旧・分離前/現ヨーロッパシジュウカラ)
- Tit, Iriomote (分離・8版)
- Tit, Japanese (旧別名)
- Tit, Japanese (統合前・7版旧)
- Tit, Long-tailed
- Tit, Marsh
- Tit, Ox-eye (旧別名・分離前/現ヨーロッパシジュウカラ)
- Tit, Penduline (旧・分離前)
- Tit, Varied
- Tit, Willow
- Tit, Yellow-bellied
- Titlark (旧別名)
- Titterel (旧別名)
- Treecreeper (旧)
- Treecreeper, Common (別名)
- Treecreeper, Eurasian (7・8版)
- Tropicbird, Red-tailed
- Tropicbird, White-tailed
- Tufted-Owl, Streaked (旧英別名)
- Turnstone (旧・英)
- Turnstone, Common (主に英別名)
- Turnstone, Ruddy (7・8版)
V
W
- Wagtail, Black-backed (亜種ハクセキレイ・別種とされたこともある)
- Wagtail, Black-headed (亜種別名・分類次第)
- Wagtail, Blue-headed (旧分離前 Seebohm 時代)
- Wagtail, Citrine
- Wagtail, Eastern Yellow (分離・8版)
- Wagtail, Forest
- Wagtail, Grey
- Wagtail, Japanese
- Wagtail, Japanese Pied (旧別名)
- Wagtail, Kamchatka Pied (亜種ハクセキレイ別名・別種とされたこともある)
- Wagtail, Pied (旧別名)
- Wagtail, Western Yellow (分離・8版)
- Wagtail, White
- Wagtail, Yellow (分離前・7版)
- Wagtail, Yellow-fronted (亜種別名・分類次第)
- Wagtail, Yellow-headed (旧別名)
- Wagtail, Yellow-hooded (旧別名)
- Warbler, Arctic (分離前のメボソムシクイ・オオムシクイも)
- Warbler, Arctic Leaf (分離前のメボソムシクイ・オオムシクイも・別名)
- Warbler, Arctic Willow (分離前のメボソムシクイ・オオムシクイも・別名)
- Warbler, Baikal Bush (検討継続)
- Warbler, Black-browed Reed
- Warbler, Blyth's Reed
- Warbler, Booted
- Warbler, Buff-browed (検討継続・別名)
- Warbler, Bush (旧・分離前)
- Warbler, Chinese Leaf (8版・分類概念変更)
- Warbler, Chinese Leaf (検討移行キバラムシクイ旧広義名)
- Warbler, Crowned Willow (旧別名)
- Warbler, Dusky
- Warbler, Dusky Willow (別名)
- Warbler, Eastern Crowned
- Warbler, Eastern Crowned Leaf (別名)
- Warbler, Eastern Crowned Willow (旧)
- Warbler, European Willow (別名)
- Warbler, Fan-tailed (旧・分離前)
- Warbler, Gray's Grasshopper (分離前・7版/現シベリアエゾセンニュウ)
- Warbler, Great Reed (旧・分離前/現ニシオオヨシキリ)
- Warbler, Greenish (検討継続)
- Warbler, Greenish (分離前ヤナギムシクイ)
- Warbler, Hume's Leaf (検討継続)
- Warbler, Ijima's (別名)
- Warbler, Ijima's Leaf
- Warbler, Ijima's Willow (旧別名)
- Warbler, Inornate (別名)
- Warbler, Japanese Bush (7・8版・分離前も)
- Warbler, Japanese Leaf
- Warbler, Japanese Marsh (旧別名)
- Warbler, Japanese Pale-legged Willow (分離・別名)
- Warbler, Japanese Swamp (旧)
- Warbler, Kamchatka Leaf
- Warbler, Korean Bush (分離・別名)
- Warbler, Lanceolated
- Warbler, Leaf (旧別名)
- Warbler, Lemon-rumped (分離前旧)
- Warbler, Manchurian Bush (分離・8版)
- Warbler, Middendorff's (旧)
- Warbler, Middendorff's Grasshopper (7・8版)
- Warbler, Myrtle
- Warbler, Northern Willow (別名)
- Warbler, Oriental Reed (分離・7・8版)
- Warbler, Pacific Leaf (Avibase)
- Warbler, Paddyfield (検討移行)
- Warbler, Pale-legged (旧・分離前)
- Warbler, Pale-legged Leaf (分離・7・8版/旧エゾムシクイ)
- Warbler, Pale-legged Willow (旧・分離前別名)
- Warbler, Pallas's
- Warbler, Pallas's Grasshopper
- Warbler, Pallas's Leaf (旧別名)
- Warbler, Pallas's Willow (旧別名)
- Warbler, Plain Leaf (別名)
- Warbler, Radde's
- Warbler, Radde's Bush (別名)
- Warbler, Radde's Willow (別名)
- Warbler, Sakhalin Grasshopper (分離・8版)
- Warbler, Sakhalin Leaf (分離・7・8版)
- Warbler, Schrenck's Reed (旧別名)
- Warbler, Sedge (8版追加)
- Warbler, Short-tailed Bush (旧)
- Warbler, Siberian Inornate (別名)
- Warbler, Siberian Lemon-rumped (別名)
- Warbler, Speckled Reed (検討移行)
- Warbler, Styan's Grasshopper
- Warbler, Temminck's Crowned Willow (旧別名)
- Warbler, Thick-billed
- Warbler, Thick-billed (別名カラフトムジセッカ)
- Warbler, Thick-billed Leaf (別名)
- Warbler, Thick-billed Willow (別名)
- Warbler, Tickell's Leaf (検討移行)
- Warbler, Tickell's Willow (検討移行・別名)
- Warbler, Two-barred
- Warbler, Two-barred Greenish (別名)
- Warbler, Two-barred Leaf (別名)
- Warbler, Willow
- Warbler, Wilson's (検討移行)
- Warbler, Wood
- Warbler, Yellow-browed
- Warbler, Yellow-browed Leaf (別名)
- Warbler, Yellow-browed Willow (別名)
- Warbler, Yellow-rumped (分離前)
- Warbler, Yellow-rumped Willow (別名)
- Warbler, Yellow-streaked (検討継続)
- Watercock (7・8版)
- Waterhen, White-breasted
- Waxwing (旧英名)
- Waxwing, Bohemian (米名由来)
- Waxwing, Japanese
- Wheatear (旧)
- Wheatear, Desert
- Wheatear, Greenland (米亜種)
- Wheatear, Isabelline
- Wheatear, Northern
- Wheatear, Pied
- Whew (旧米)
- Whew (旧米)
- Whilk (旧英)
- Whimbrel (7・8版)
- Whimbrel, Eurasian (分離・IOC)
- Whimbrel, Little (旧)
- Whinchat
- Whistler (旧米ヒドリガモ)
- Whistler (旧米ホオジロガモ)
- Whistler, Seven (旧別名)
- White-eye, Bonin (7・8版)
- White-eye, Chestnut-flanked
- White-eye, Ferruginous (旧別名)
- White-eye, Japanese (分離前・7版旧)
- White-eye, Siberian (別名)
- White-eye, Warbling (分離・8版)
- Whitefront, Lesser (別名)
- Whitethroat, Common (検討新規)
- Whitethroat, Lesser
- Wicket, Willy (英旧別名)
- Wideawake (別名)
- Wigeon, American
- Wigeon, Eurasian (7・8版)
- Willow-Warbler (別綴)
- Windhover (旧英)
- Woodcock (旧)
- Woodcock, Amami
- Woodcock, Eurasian (7・8版)
- Woodlark (英北部旧別名)
- Woodpecker, Amami (亜種オーストンオオアカゲラ・分離する考えあり)
- Woodpecker, Barred (旧別名)
- Woodpecker, Black
- Woodpecker, Eurasian Three-toed
- Woodpecker, Great Spotted
- Woodpecker, Greater Spotted (別名)
- Woodpecker, Grey-headed
- Woodpecker, Japanese (旧)
- Woodpecker, Japanese Green
- Woodpecker, Japanese Pygmy
- Woodpecker, Lesser Spotted
- Woodpecker, Northern Three-toed (別名)
- Woodpecker, Okinawa (7・8版)
- Woodpecker, Pied (旧別名)
- Woodpecker, Pryer's (旧)
- Woodpecker, Pygmy (現 Avibase/同種時代旧名)
- Woodpecker, Rufous-bellied
- Woodpecker, Three-toed (旧分離前)
- Woodpecker, White-backed
- Woodpecker, White-bellied
- Woodpecker, White-bellied Black (旧別名)
- Woodswallow, White-breasted
- Wren (旧)
- Wren, Common (旧)
- Wren, Eurasian (8版)
- Wren, Gold-crested (旧別名)
- Wren, Golden Crested (旧別名)
- Wren, Golden-crest (旧別名)
- Wren, Northern (旧)
- Wren, Willow (旧別名)
- Wren, Winter (分離前米・7版/現フユミソサザイ)
- Wren, Wood (旧別名)
- Wryneck (旧)
- Wryneck, Eurasian (7・8版)
X
Y
科名索引
◆鳥類学名の読みと意味・名前のことなどさまざま
- 種の学名は属名 (genus; generic name) と種小名 (specific name; species epithet; 学名を扱っていることが明らかな文脈では単純に epithet と略すこともある) から成っている。学名はカナで読みを示し、またそれぞれに意味などを説明している。[wikipedia 日本語版学名にもかなりの情報がある]。
それに引き続き命名者と年を記述するのが完全な形式になるが本文中では大部分省略している。
日本産種については改訂第8版準拠の#リンク集に命名者と記載年を含めた学名が収められているので参考にしていただきたい。若干長くなって面倒だがこの形式が図鑑などでも標準的に用いられるようになればもう少し普及するだろう。
(Linnaeus, 1758) のように "命名者, 記載年" 部分が丸かっこで囲まれるものは記載時学名から属が変化したもの。命名者部分に丸かっこの付く学名が多いがこれは補足的な意味で使われた丸かっこではなく別の意味がある。
本稿では記載者が2名の場合には普及している "&" の記号を用いている。ラテン語で書く場合は "et" となる。どちらも使われている。論文の著者2名の場合には引用に際して普及している英語式の "and" を用いているので学名表記と少し異なっている。
New unified list of birds - Avilist (BirdForum 2025.7) で紹介されている通り、記載者名が姓だけでは特定できない場合は特に名のイニシャルを与えることが推奨されている (ICZN Recommendation 51A)。IOC 15.1 では同姓の著者が存在する場合のみ名のイニシャルを与えていたが、AviList では全例で記載者名のイニシャルを与える形式に変更された。
本稿では改訂第8版準拠のリストに従ったためイニシャルを与えていない。現在は学術論文一般でも、同一文献内で紛らわしくなくてもフルネームを用いた著者名が用いられる傾向が現れてきており、鳥の学名の記載者表記も AviList 準拠、あるいはいずれはさらにフルネームを用いる表記が好まれるようになるかも知れない。
- 学名の読みをカナ書きで表記してあるが、日本語の発音に近似させたもので、ラテン語の発音を正しく表しているわけではない。ラテン語の発音について詳しいわけではないが、アクセント位置は後ろから2つめまたは3つめの音節に来るとのこと。
カナ書きで読むと任意の場所にアクセントを置きがちであるが、語末や子音に対応するカナにはアクセントを置かないように。2音節以上の単語では最後の音節には長音であってもアクセントは現れない。
語末が2重母音であっても1つめが長音でなければアクセントはない。例えば ardea のアクセントは "アルデア"。
ラテン語は現役言語ではないので何と読んでもよさそうではあるが、せっかく学名を覚えるならば古典式ラテン語の発音規則に合わせるのも外国語を扱う上での一つの見識と考えてよいだろう。
自己流でアクセントを置いたり長母音にするよりは多少の根拠があると見ていただくとよいだろう。
読み方がわからないために学名を敬遠されてきた方もこの機会に少し見ていただけば面白い部分もあるだろう。
よく現れる具体的な例を挙げておくと、minor, major はアクセントは冒頭 (2音節しかないので自動的に決まる)。"ミノール" と不適切なカナ書きにすると "ノー" にアクセントを置きがちだが、この表記はむしろ誤りと考えた方がよい。
語末は長音にならず、英語の minor, major のアクセントと同じで読み方だけが異なる (ミノル、マヨル) と考えるとわかりやすい。
もし英語読みする場合でもこのアクセント位置が適切。
ラテン語読みでは o は伸ばさない (マイヨル のように jo を 分けて発音することはある。minor ももし伸ばす場合でもアクセント音節を伸ばす)。
wikipedia 日本語版の解説によれば
1. 後ろから2番目の音節が閉音節である場合、および、長母音もしくは二重母音を含む音節である場合、強勢は後ろから2番目の音節に置かれる。
2. 上記以外の場合、後ろから3番目の音節に置かれる。但し、2音節しか持たない単語の場合は後ろから2番目の音節に置かれる。
とのこと。閉音節とは子音で終わる音節とのこと。また多くの学名に現れる -cola の "コーラ" とアクセントを置いて読みたくなるが、-co- は短母音で2.に当てはまりここにはアクセントがなく "コラ" と短く読んでその前の音節にアクセントを置くとよい。
多くの場合指小辞に由来する -ula の語尾も同様で伸ばさず、-cola と同じようなアクセント位置になる。
一方で motacilla は -cil- が子音で終わるので1.に当てはまり -cilla (キルラ) の方にアクセントがある (英語読みではモタシーラ)。
accipiter は -pi- が閉音節でないため -ci- にアクセントがある。英語でもアクセント位置は同じで2つめの c の発音だけが異なると考えれば近い音であることがわかる (アクキピテル。英語読みでも実用上多分構わない)。
よく使われるところでは emberiza を何と読むか問題になりそうだが、規則によれば -be- がアクセントで、発音の聞けるページを参照するとそのようになっている。
"エムベーリザ" (本来は長音ではないが "ベ" にアクセントを置くためこの表記とした。アクセントに慣れれば短音に戻していただいてもよい) のような読み方がよいのだろう [イタリア語の同じ綴りの単語は -iddza のリズムと解釈され "リ" の方にアクセントがあるとのこと]。
"Emberiza 某" 等名乗る方はこのような細部もこだわっていただきたい。
ラテン語で h を発音するかどうかは時代にもよるようで読まない場合もあるらしい (ラテン語起源のフランス語などでは発音しない)。ここでは "h + 母音" は h を発音する表記を採用した。学名記載などに使われる (著者) 自身を指す mihi の h は時代によらず必ず発音されるとのこと (h の音を外せば英語の me に対応することがわかりやすい)。
si の発音はラテン語ではおそらく "shi" の音は出てこないので紛らわしいことはないが、アクセント母音やその前、二重母音になる場合などは "スィ" と表記して注意を促すこととした。表記が煩雑になるのでアクセントに関係ない場合などは "シ" の表記が一部残っているが音は "si" である点は少し注意。
2重子音は分けて読むのが本来の読み方。前述 (-cil-la, ac-ci-) のようにここで音節が分離されることが多いので基本的に分けて表記している。ただしカナで表記困難な場合は促音 (詰まる音) を用いている。
ここに示した長音の読みは古典式で、後の時代では短くなる傾向があるので短く読んでいただいても問題ない。しかし長音かつアクセント母音となる造語語尾 (-atus, -ata など) は覚えやすいので積極的に長音を活用していただくとよいだろう。またギリシャ語の "尾" 由来の -urus, -ura、"足" 由来の -pus のように統一して発音すると意味も理解しやすくなる。
-phone のように長音と短音で意味が違うこともある。
解説では英語などに合わせて "長母音" の用語を用いているがラテン語やギリシャ語では正しい用語ではないかも知れない。これは例えばギリシャ文字の ε を "イプシロン/エプシロン" と短く読み、η を "エータ" と長く読むのに対応していると考えていただいてよい。ギリシャ語由来の学名で η は長母音と表記している。
古典式ラテン語時代ののんびりした読みを楽しまれたい方は長音で読むのもよいだろう。
原則的な考えを示しておくと、ここで (1) ここで示した長音は短音で読んでも差し支えない。(2) しかし短音であるべきものを長音で読むことは不自然。(3) 辞書にも載っている語など、アクセント位置が確定できている場合は他の場所にアクセントを置くのは不自然。
と解釈していただいてよいだろうか。
発音部分の記述がかなり詳しくなっているが、もともとはアクセント位置を確認する作業から始めたもので、アクセントになる可能性のある音が長音か短音かを判定する必要が生じ、結果的に個々に発音を確認することとなった。wiktionary で古典式発音記号を確認できる語はそのまま採用し、ギリシャ語由来のものも可能な範囲で原音を検討している。
基本的に古典式ラテン語に従った表記としているが、人名や地名など不自然になる場合に多少の例外を設けている。例えば sch の読みは両方があるが明らかににドイツ語読みを意識したものはドイツ語読みとしている。タカ類の属語尾に現れる -spiza など命名者意図が感じられる場合にも話者の言語も考慮して多少の例外を許している (いずれも注記してある)。
よく知られていて今更の感じもあるが、ラテン語は英語とは違って文法上の性 (男性・女性・中性) の区別がある。動物では中性はあまり現れないが皆無ではない。属の文法上の性に従って種小名や亜種小名の性が決まる。
一番よく出会うのは形容詞語尾の -us (男性) -a (女性) だろう。分類変更によって属の性が変わる場合はこのように種小名や亜種小名が変わるものがある。以前に使われた学名を覚えている場合は多少切り替えが必要。ただしラテン語形容詞でない -us や -a の語尾もあり、これらは変わらない。
形容詞でよく現れるものに "黒い" を表す ater があるが女性形は atra と形が少し変わる (いずれも冒頭が長母音)。セットで覚えておくとよい。
身近なところでは japonicus, japonica の語尾も同様 (ただし japon- の部分に長音を含むかどうかは微妙でどちらの読み方もある。japonicum は中性の形で鳥では多分現れない)。
japonensis とは何が違うのか気になるだろうが、japonicus / japonica は "日本の" で、-ensis (これも冒頭が長音でアクセントがある) は出所を表す接尾語 (wiktionary では英語で of or from [a place] と説明がある。古フランス語を経由して英語の -ese の語源とのこと)。
意味の上では微妙な違いがあるが特に訳し分けていない。この形容詞語尾は男性・女性は同じ形で、中性のみ -ense となる (日本の場合は鳥ではおそらく出てこないが植物の学名に登場する)。
ないと思われるが japonensis を持つ種がもし将来中性の属名に移されることがあればこの形に変化することになる。
#イワツバメや、検討種の中の #ニシイワツバメ、#マダラフルマカモメが中性の学名になっている (クイズに使えそう?)。#ミヤマモリフクロウの種小名も中性形に由来している。この項目に中性の属名の由来について少し詳しい解説がある。
このように見ていただけば種小名のラテン語は一見多様に見えてもそれほど難しいものでないことがわかっていただけるのではないかと思う。
(個々の種で処理中だが基本的に処理済み。読みに不明な点など注記のあるもの以外はある程度信頼していただいてよいと思う)
- 学名の意味を調べるに当たって、英名と学名、さらに和名の意味がよく一致する事例が多数あった。見れば自明な場合は特別な注記を行っていないことが多いが、現在の英名と学名の意味が一致しない場合に英名の起源が過去に使われていた学名に遡れる事例が多数あることがわかった。
wikipedia 英語版などの解説を見ても現在の学名の解説のみで必ずしも触れられていないものも多く、ほとんどは独自調査の結果である。これらの英名は和名の由来となっていると推定できるものも多く、和名の由来を考える上でも興味深いと考える。
この部分の記述は過去の学名が使われなくなった経緯なども含まれるため非常に複雑になっているものが多いが、ある程度の予備知識があれば興味深く読んでいただけるものもあると考える。例えば特に背が黒くないのにセグロカモメと呼ばれるのはなぜか、タヒバリはなぜヒバリが付くのかなど。
いずれの問題も分類学の扱いの変遷や亜種となる場合の種学名の扱い、学名の先取権の扱いや有効性など学名を扱う上で本質的な事項が多数含まれている。歴史が英名や和名に残っていると考えれば非常に興味深い。過去に疑問に感じられていた和名や英名などの理由が氷解するものもあるのではないだろうか。
またアビ類のように日本と共通種の多いロシア名や文献からヒントが得られる場合もある (記載文献はドイツ語だったりフランス語だったりするので各国語を行き来しないといけない。理学では英語以外の基本外国語は従来独仏露とされていたがその意味を実感することができる)。
このような経緯がオンラインで簡単にアクセスできる文献にしっかり記載されているものは少なく、また過去に使われた学名を完全に知ることはおそらく誰にとっても困難なので推測に伴うものも多く、不正確な部分がある可能性がある点には注意していただきたい。
単に学名の意味を知っておしまいでなく、このような考察まで含めると学名の世界は非常に奥が深い上に、系統分類とも密接に関連していることがわかる。調べてみると予想外のことが多く、まさに謎解きであまりに面白いのである。ここまで知ればトリビアを超えて世界でも自慢できるのではないだろうか。
新しい方の分類変遷については文献を読めば理解しやすく説明もしやすいと想像できるが、鳥のことを深く知るためには古い方も含めて学名を詳しく知ることは第一歩であると認識できる。
- これも今更、の感じがあるが、学名の成り立ちを少し紹介しておこう。もっと早く系統的に述べておけばよいのだろうが詳しい規則や歴史までは知らないため、本稿を読むにあたって関連する件のみ紹介とする。
まずよくある誤解として学名はカール・フォン・リンネが「自然の体系」の第 10 版 (1758) で決めた (末尾の参考文献に URL あり)、とされる場合があるが、いくつかの点で正しくない。
元来の名前は Carl Nilsson Linnaeus で、功績によって Carl von Linne の貴族の称号を得たのは 1757 年で、これ以前は Linnaeus である。ちなみに von は称号を表すもので、姓は Linne か von Linne であるべきかは解釈による
(例えば小笠原の鳥に名前を多く残している Kittlitz は von Kittlitz を姓とすべきかなどの議論がある。学名に記載者を載せる場合に問題になる。論文を書く人であれば引用文献での同様の著者の姓の扱いに困惑される方も多いだろう)。
Linnaeus が「自然の体系」初版を出版したのは 1735 年で、1758 年以降も Linnaeus の名称を使い続けていたので、我々が普通にみかける鳥の学名の記載者には Linne は出てこず、すべて Linnaeus ではないかと思う。
すなわちいかにも高校生物などで習いそうな「カニス・ファミリアニス・リンネ」(イヌのこと。なおイヌはオオカミから家畜化されたものとする捉え方ではオオカミの種小名を用いるべきとなり、この扱いはまだ確定していない模様) の読み方は正しくないことになる。
wikipedia 日本語版の解説によれば植物学では L. と略されるが、動物では省略しないとのことで L. と書くのは正しくないらしい (古い文献の用例にはみかける)。
次の誤解として「リンネが学名を発明した」があるが、これもあまり正しくない。ラテン語で名称を記述することはそれ以前から行われていた。ただしこの方法が人によって違っていた。簡単な種類の場合はラテン語1単語で示されることもしばしばあり、それに記述的な修飾を付ける形で次第に複雑な学名が使われるようになった。
ラテン語では形容詞による修飾は名詞の後に付く (ラテン語と系統の近いフランス語などでもよく使われる) ので、名詞 + 修飾語 の形になる。
以下ちょっと長いが余談: この順序となることは多少のメリットもあり、学名索引は同属のものが並ぶが、英名をそのままアルファベット順の索引とすると大変わかりにくくなる。
そのため英名索引では多くの場合最後の単語を先頭に回すなど学名に近い語順がよく用いられる。しかしながら英語特有の問題があって2単語からなる単語を別の単語とするか、ハイフンを入れるか、さらには合体させて1単語とするさまざまな段階の扱いがある (ドイツ語やオランダ語では単語を直接結合することが多いのでしばしば長い単語ができる)。
リストによって英名のハイフンの有無などが違うのはこの扱いの違いに由来する。Hawk-eagle とした場合は、索引では Eagle の下に置くべきか、Hawk-eagle の見出しにするか悩ましいわけである (さらに途中段階として Hawk-Eagle のようにハイフンの後の先頭を大文字表記にする場合がある。これは単語の独立性が高いが文法上は1単語扱いにしてハイフンを入れたい場合に相当する)。
ヘビクイワシを Secretary Bird と表記してもよいが、これをそのまま採用すると索引では Bird の下に置かざるを得ずちょっと困ったことになる。
学名の話に戻ると Linnaeus はこれを体系化し、2語による学名に統一した。名詞に相当する部分が属名、修飾語の部分が種小名ということになる。
学名がなぜラテン語文法規則に則っているかはこの成り立ちを考えるとよくわかる。修飾語は形容詞が使われることが多いので名詞の文法性に合わせて変化することになる。また修飾語が地名や人名などの場合は形容詞語尾を補って形容詞の変化をさせるのが一般的。
なお Linnaeus は種小名が形容詞でない場合は冒頭を大文字で記述して名詞であることを表しており、この用法も一定期間使われていた。
これが二名法で、Linnaeus はさらに綱、目、科という上位の分類階級を設け、それらを階層的に位置づけた (最後の部分は wikipedia 日本語版の解説から、と書こうと思ったが科とすべきところが属になっていた... 2024年11月段階)。なお属より上の分類階級を高次分類群と呼ぶそうで、上位分類は相対的な表現に使われることが多いがこの解説ではあまり使い分けていない (日本語名称はそれぞれ order と rank の英語に対応するが使い分けは英語に対応したものでもない)。
Linnaeus 当時は亜種の概念は直接的には現れず、これは 19 世紀後半に種と生物進化の関係が判明してきて初めて一般的になった概念である。この問題は #カンムリツクシガモ の第一標本を記述した者がなぜ亜種概念を用いず雑種と記載したかなどの推論にも関係する。
生物進化の考え方に否定的な立場だった命名者であれば記載に亜種を用いないことも理解できる。もちろん 20 世紀に入っても生物進化の問題は長く議論されていた。
Linnaeus の命名体系が広く用いられる以前に3語を用いた一見亜種学名に見える名称も使われていたが、これは現代の亜種概念とは異なったものである。
また亜種概念が広く使われるようになる前は違うものは別種として記載せざるを得なかったので、その当時の学名を指して「かつては別種扱い」の表現を読む時には注意が必要である。亜種概念がなかった、あるいは命名者の立場上使いたくなかったために別種となっていただけの場合も多い。
このように Linnaeus 以前より学名は存在したので、規約を作るにあたってはどこかで区切りを付ける必要がある。そこで「自然の体系」の第 10 版 (1758) の出版年を基準として、それ以前に発表されたものはたとえ Linnaeus が用いたものでも、また Linnaeus (1758) の用いたものと同じ学名であっても有効なものとして扱われなくなった。
ある意味この区切りは多少人工的なもので、その結果多くの種の記載者が Linnaeus となることになった。「この学名は Linnaeus が 1758 年に命名した」などの文章を読む時には若干注意が必要である。
ちなみに 1758 年の同年の文献が (少なくとも鳥に関係したものでは) もう1つあるとのこと。
Linnaeus (1758) 以降でも二名法に従っていないものもあり、著者が二名法に則っていないと判断されれば一見同じ2語の学名を用いていても有効なものとみなされないらしい。
また二名法ならば必ず2単語かと言えばそうでもなかったようで、AviList v2025 - errors, typos (2025.7) で示されているような人名が2語で、二名法なのに3単語となっていた例もあった。
シロスジヒメドリ 現在の学名で Ammospiza leconteii LeConte's Sparrow の種小名は記載時 Le Conteii の2単語だった。
後は皆さんもご存じの先取権の原則がある。同じものを指す場合には最初に記載された学名が採用される。
過去に誰かが用いた学名は無効である。
これらは自明な規則のように思えるがこれがしばしば混乱の原因となってきて、現在でもなっている。
Linnaeus (1758) の自然の体系」の第 10 版の記述が曖昧で何を指しているか判断できないために当初は使われなかったが、後にこの学名は何を指しているなどの同定がなされて学名が変わったことはしばしばある。「最初に記載された学名」という規則は合理的に見えるが、古い記載ほど記述が曖昧なのはある意味当然で同定に困難が伴うのである。このために学名が変わった事例は非常に多くある。
また古い文献を見つけるのも大変な作業である。一度は学名が確定してから、その種類が古い百科事典やどこかで出版された探検日誌のどこかに載っていたなど、およそ学名の記載とは思えないような文献が原記載とされることがあるのはそのような事情による。
古い文献では出版年が不明瞭なものもある。例えば出版年が記されているが実際の出版は後だった、複数の巻があって全体しての出版年の範囲はわかるが特定の記述が出版された年がわからないなど。
これらが特定されたり出版日時が改めて定義されることによって優先順位が変わって学名が変わることもある。
現在では厳格な要件になっており、少なくともある年以降に記載された学名はこの要件を満たす形になっている。例えば属の新記載では「その属の共通の特徴」「この特徴があれば他と区別できる」(diagnosis) などを記述する必要があり、「この特徴があれば他と区別できる」条件が不十分なもの (別の属なのにこの属と判定できてしまう) と判定されれば無効とされることもあるらしい。
現代ではそのような場合は一旦無効として、要件を満たす形で同じ名称で再命名となることもある。
「過去に誰かが用いた学名は無効である」も極めて妥当な規則に見えるが、同様に古い文献を探してゆくと同じ学名がみつかって無効となった (命名者が気づいていない) 例は非常に多数ある (例えば日本で記載されても不思議でなかった #サンコウチョウ)。すでに利用された名称は preoccupied と表記される。
種小名や亜種小名がすでに利用された名称かどうかは同属の範囲で判断される。
気づきにくいがこれは動物全体に対するもので (もちろん化石種も含む)、同じ属名が例えば虫にあってはいけないのである。鳥だけのリストならば過去に使われた全学名データベースのようなものもある程度あるが、動物全体となるとなかなか大変である。現在は動物と植物に同じ属名があっても構わないが古い時代ではそのように扱われず、遅く用いられた同一の属名は避けられることもあった (#アマツバメでは属名が長く確定しなかった)。
また一字一句違わないもののみを同一とみなすと支障が生じる場合もある。ギリシャ語由来のラテン語など綴り方が一通りでないものもあり、ラテン語アルファベットで同一のものを表す別の文字も存在する。
かつては同じ単語の男性形と女性形が別の属名に用いられ、これは同一なのか別のものなのか議論となったこともあった。実際に見てゆくとわずかに違う学名がいくつもあって同一性の定義が難しいことがわかる。
古い学名では違った音を表す記号や合字も使われており、これらを現代の表記に変換する際に若干の不定性が生じている。例えばミサゴの種小名とオジロワシの属名は過去には同じ綴りだったが変換する際に別のものになってしまった。
アカヒゲとコマドリの種小名と和名との対応が逆になっており、一度付けた学名は変更できないと説明されることも多いが、記載時の学名に文法的誤りがあれば正されることもある。
例えば #キバラムシクイ や #ヘラシギ では異なる綴りに変更されている。#ハヤブサ の亜種のシマハヤブサは献名が明示されていたため同一文献内の情報を用いた訂正が行われた。#クロウミツバメ も人名由来で訂正されたものが一般的に使われている。
クマタカの Nisaetus の属名も綴りを間違っていて訂正された。
ややこしいことに Linnaeus はしばしば省略形を見出しに用いており、すべての見出しが "." で終わっているために省略形かどうかが区別できず、省略された学名を採用すべきか、初出文献には出ていなくても省略されない学名を採用すべきかなどの議論もある。日本の鳥では#モリツバメや#サカツラガンなどが問題となる。
前者は ICZN が省略形と裁定し、省略する場合・省略しない場合の唯一の学名表記が決められた経緯がある。
学名を付けた時は別の学名だったのだが、分類変更で属が変わりたまたま同じ学名になってしまうこともある。これは分類学の問題なのでいつの時代でも起き得る。この時もそのような学名の使用を避けることになり、優先度の低い学名が使われたりや新称が与えられることもある。
また古くは属名が変わると新しい種小名が提案されることもしばしばあった (#ノスリの備考参照)。新属を提案すると自身が命名者になることができるため新属や改名された学名が氾濫し、現在のような規則に改められたものと思われる。
オオトラツグミ (#トラツグミ備考) の学名がトラツグミが Turdus 属に含められていた一時期に変わっていたのはこの影響があると思われる。#ノスリの現在の種小名や#チョウゲンボウの亜種小名も複雑な経緯をたどっていた。
ノスリの現在の種小名に japonicus が現れるのもケアシノスリを含む属統合の玉突きの結果だった。複雑であるが学名がどのように決まるかよい歴史的題材となっている。学名に関心のある方は時間をかけてじっくり吟味していただきたい。
これらの結果、素直な (わかりやすい) 種小名や亜種小名は早めに使われてしまい、後に名付けられた学名ほど性質をうまく記述していない (命名に苦労している) 偏りが発生していると想像できる。地名や人名、現地名を冠した (見方によってはややつまらない) 学名が多いのもそのような理由が背景にあると思われる。
学名字義を見る場合にはより早く付けられた学名 (ヨーロッパの種類であることが多い) も一緒に見渡すのが望ましい。種レベルであれば第8版準拠の#リンク集に記載者・記載年が示されているのでご活用いただきたい。
日本の鳥の学名も、そのような視点で見るとなぜそのような種小名 (特に亜種小名) が使われたのか想像できる傾向があるように思える。和名が学名に採用されていることもこのような事情が背景にありそうに思える (わかる範囲で個々の項目で説明してある)。
日本で記載されれば japonensis と名付けてもよさそうだが、一度使われるていると同じ属ではもう使うことができない。日本で記載された亜種小名に何でも japonensis (や japonicus など) が付いていない理由にもなる。
また日本の鳥の学名を多数付けた Temminck は同じグループが複数種する存在する場合は地域名を用いた japonensis を意識して避けていたと考えられる (#タンチョウの備考参照。Temminck 自身は Grus japonensis を適切な学名と考えておらず改名提案を出していた)。
人名を付ければ一般的には重なる心配が少ないと思われるが、それでも同じ属ですでに使われた人名の亜種小名が使われて変更されたことがあった (例えば#コゲラ)。
属を細かく分けることは細分主義と批判されることもあるが、種小名や亜種小名の自由度の観点からは属は分かれている方が都合がよいことになる。
#クロジのようにおそらく解釈の誤りから付けられたと思われる学名もあり、付けた学名を変更することはできないので解釈を含む命名は命名者にとってもリスクが大きいとも言える。色彩のような客観的性質をもとにした名称が多いのもそのためかも知れない。
古い文献に現在の分類に対応する過去気づかれていなかった学名が後日見つかることもある。多数が同意すればその学名に変更されることもあるが、ほぼ使われた形跡のない学名であれば「忘れられた学名」(nomen oblitum) と処理されることもある。
このあたりは判断の分かれる部分もあり、裁定が必要となれば ICZN が行う。
#オオムシクイなどの定義が決まったかのように見えるがこの問題が残っている。メボソムシクイ (世界的にはコムシクイ) のグループにさらに古く記載された学名があり、もしオオムシクイと同種であればこちらに先取権が発生する可能性がある。
しかし繁殖地でなく渡り途中に記載されたものでどこで繁殖する個体群かわからない。記載時の標本があるはずだが分子系統研究でオオムシクイが別種とされた論文ではこの標本を見つけ出すことができず、複数の種に分かれることを主眼とした論文なので先取権の扱いが曖昧なままとなっている。将来標本が発見され DNA 解析が行われ、変更すべきとの主張があればオオムシクイの学名が変わる可能性がある。
属と種、種と亜種の関係は似ているところもあるが若干違う。種と亜種の関係ではその種内で最初に記載された亜種が基亜種となり、種小名はその亜種と同じになる。分類変更などで種の分割・統合などが行われれば基亜種はそのグループ内で最初に記載された亜種になるので分割の場合はどちらかの種の種小名が変わり、統合の場合は地理的に遠く離れた亜種が基亜種となることもある。
属の場合はこの規則ではなく、属ごとにタイプ種を決める (新しく記述する場合は命名者が定義することになる)。Linnaeus (1758) のような古い時代になるとこのタイプ種定義がないため、例えば同じ属内の出現順など別途定義することになる。#サンコウチョウの属名は古い属名の時代にタイプ種の提案が複数あり、複雑な経緯を経て決まったもので自明な属名ではなかった。
属のタイプ種は定義によるものなので表面上 属名 = 種小名 であってもタイプ種とは限らない (#ミソサザイや#オガワコマドリ の解説参照)。
分子系統解析などによって属が分割される場合はどの種がどの属名になるかはその種の属する (現代の分子系統解析によるものならば) クレードのタイプ種で決まる。そのため現在 属名 = 種小名 のミソサザイであっても別の属学名に変わることが考えられる。
属が分割される場合、分割されて新しく生じる系統の中に過去の属のタイプ種となるものがあれば話は簡単で新しい属名はその属になる。複数ある場合は記載の早いものが採用される。優先順位が決まらない場合は裁定が行われる (Accipiter 属が分離されて生じた Tachyspiza 属はこのようにして決まった)。
ない場合には新しく決める必要がある。種を分割する時に亜種の記載順でほぼ自動的に決まるのとは多少異なる。
属分類については類縁性や独自性を指標とする従来の分類学では分類学者によって扱いに多くの違いがあった。分類学者によっては少しでも違った特性のあるものを独立属とすることもしばしばあった。
#ヘラシギがなぜ現在の学名になったのか、歴史を知らないとまったくわからないだろう。
おかげで上記のように属を分割する場合は過去の名前があることが多く比較的問題が少ないが、Charadrius 属の分割で選択肢が1つしかなくあまり適した名称でないためにちょっと困った状態になっている。複数ある、あるいはまったくない場合はより適切な属名が選べるが、1つだけあるのが問題となっている。
#イスカでも同様の問題があって、このあたりの属名が比較的細かく分かれている理由の一つとなっている。属を統合すると Linnaeus (1758) が記載した "イスカ属" になってしまうのである。
また属学名は分類学者が与えるものなので、同じ学名を別の分類学者が異なる分類群 (しかも鳥とは限らない) に対して与えてしまうことがしばしばあった。
ある属名がなぜ使われなくなったのか、鳥の学名辞典 (大変すぐれたものがあるが鳥以外は載っていない) だけではわからない場合もある。
分類学者が同じグループだと考えて与えた属が実は複数のグループを含むことが判明し、タイプ種の指定によって先取権のある属名のシノニムとなり、いかにも由緒ある名前でも使われなくなったものもある (トキ類の Ibis 属など)。
亜種についてはかつては色彩や計測値のわずかな違いで別亜種と記載された例が多数あり、「区別できない」として一部は整理されたがまだ多数の亜種が未解決のまま残っている。これも現代は分子系統解析待ちの部分が多く、かつて亜種や別種とされたものが分子系統解析では入り混じっていることが判明して統合される場合もある (種レベルではベニヒワとコベニヒワなど)。
外見での区別可能性より分子系統解析で個別のグループとして区別可能かが次第に重視されるようになってきている。
亜種概念は比較的新しいため、それ以前に使われていた「変種」(var.) を現代の亜種と同等のものとみなすかどうかの議論もある。例えばコサメビタキの学名が IOC リストで何度も変わったのはこのため。亜種時代であれば目立たなかった問題だが、種に分割された後の種小名は最初に記載された名前で決まるため。「変種」(var.) は亜種とは違う、いやそうでない用例がある、などの見解が対立していた。
これも「最初に記載された名前」である要件が理由で、どうしても古い時代の文献になる。亜種が一般的に使われる前の記載はどのように扱うかが問題となった。過去に別種扱いで同種扱いになった場合は (さらに合体などがなければ) 過去の種小名が亜種名となる。
もう一つ、このような分類変更に伴って重要となるのが基産地 (type locality。ラテン語 terra typica 模式地 の方が厳密な訳語かも) である。繁殖分布などではあるい程度わかりやすく、繁殖地で採集された標本であれば、種や亜種に分割される場合はその場所を含むグループの名前になる。
例えば#フクロウでは日本で最初に記載されたのが九州であったためこの場所を含むグループの名前が決まる。
九州の採集地フクロウの亜種学名は変わる心配はないが、日本の他地域は分類や亜種分布の考え方次第で何とも言えなくなる。Temminck and Schlegel (1850) の記載でも実はあまりすっきりせず、後に Hartert (1913) が九州と判定したというもの。
古い記載は先取権の原則から生き残る可能性が高いが、場所の特定はこのように確実性を欠く場合もある。偉い人が定義し、異論がなかったのでそれに落ち着いている感じ。世界から見れば日本列島は小さなものなので九州まで特定すれば十分だろうとしたと見えなくもない。
北海道以外のフクロウは同一亜種とする立場であれば北海道以外は亜種 fuscescens となることになる。
現状では自分が住んでいる場所のフクロウがどの亜種なのか自信を持って言えないのである。
IOC では世界で 10 亜種なので、そのうち3亜種が (離島の固有亜種ならば理解しやすいが) 狭い本州以南の日本列島に集まっているのはちょっとおかしい、もうちょっと整理して欲しいと感じる人も (おそらく世界的視点からも) あるだろう。
自分は IOC を使っていて亜種 momiyamae は有効だが、自分の地域 (京都) のフクロウは亜種 hondoensis としている。
世界を最小の8亜種とする分類ではそうなっていることも理由の一つだが、momiyamae は整理されるならば一番最初にシノニムになる可能性が高いので今のうちから準備しておこうと...。
このように種や亜種を見る時は図鑑の分布だけでなく基産地にも注意していただくときっと面白い。
Temminck and Schlegel (1850) が記載したはずの #アオゲラの基亜種では (北部) 九州が基産地になっていないなど不自然なところも見受けられる。
普通種の中に「こんなところが基産地?」と驚かれるものがおそらくいくつもある。
例えば亜種ハヤブサはいかにも日本の繁殖地で記載されたかのような印象を受けるが実はそうではない。
亜種の分布の記述には基産地周辺のみを示したと想像できるものがいくつもあり、そもそも亜種に値するかわからないが研究がなされていないために便宜上そのまま残されているもの多いと思われる。
種の識別の次は亜種識別と掘り下げたいことはよく理解できるが、このような事情で残っている亜種もあるのであまり深入りする必要もないのではと感じる。
状況は種によって大きく違い、種分割に値する亜種から単なる地域で色の傾向の違いを表したものなどさまざまなものがある。標本による分類の時代が長かったので音声などはあまり考慮されてこなかったことが多い。歴史も見ながら個々に検討されるのがよいだろう。
Should we consider lumping more subspecies? (BirdForum 2025.1) にも議論があるので紹介しておく。全亜種数はあまり変化がないが種数は増えている (新しい亜種の記載はほとんどない)。古く記載された亜種は現代の解析を行えば生き残らないものも多いだろう。英国のリストでは自国に別亜種を与えたかったらしいなど。
亜種を過剰に記載するのもどうかと感じる場面が多いが、記載されていないことで困る場合もある。分子系統解析では#ミサゴの極東個体群は亜種相当と考えられるが過去に記載された適切な亜種がない。分子系統解析で亜種名が記載される可能性のある個体群である。
学名の歴史を見ていると、18 世紀後半から 19 世紀に主にヨーロッパで急速に物事が進展したことがわかる。世界史的には当たり前なのだろうが歴史の教科書のできごとで少し実感が薄い。
自身は本文中でもしばしば述べているがクラシック音楽、特に近代産業の申し子のようなピアノをやっていたこともあってこの時代は非常に馴染みがある。19 世紀半ばにはロマン派音楽もほとんど完成形で、我々が普段よく聞くクラシック音楽作品はこの時代の名作が多い。
この時代に音楽家たちがどれほど腕を競い、限界を極めて名作を残したかを知っていると、博物学 (学名) の世界もよく似て見える。つまり 19 世紀半ばにはすでに完成度の高いものになっていて、ヨーロッパからみて海外の標本を記述する時代に移っていたことがわかる。日本の鳥に学名が付けられたのはこの時期と考えると時代背景が非常によくわかる気がする。
クラシック音楽 (以外でももちろん構わないが) に興味のある方は記載年代の類似性にも注意を払っていただくと面白いだろう。プロコフィエフの日本滞在は 1918 年で西洋の大作曲家の最初の日本訪問であった。日本の「越後獅子」がピアノ協奏曲第3番に影響を与えたとも言われるが、この時代になるとかなり近代のクラシック音楽でついて行きにくい方もあろう作風の時代であった。
作風とは言えないかも知れないが、この当時の学名を見ると 19 世紀半ばまでの絶頂期からはかなり離れている印象を受ける。新しい学名がすでにあまり付けられない時期に入っていた。他の分野の歴史とも比較して楽しんでいただきたい。
個人的に日本産種で傑作の学名と感じるのが#ゴビズキンカモメ。記載当時の学名だけで本質を見事に表していた。
- 本ページでは、「日本鳥類目録 改訂第7版
 」掲載の 633 種を同書の配列順により掲載している。
改訂第8版で新規掲載された種も掲載しており、第8版準拠の#リンク集も用意している。
亜種についても備考で触れている。「日本鳥類目録 改訂第7版」非記載の鳥 (外来種) を掲載している。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、パブリックコメントへの回答、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト (目録第8版出版前段階のもの) も踏まえている。種名見出しでは目録第8版で種の分割、合体により学名が変化するものに注意を促す意味で注釈を加えた。属名のみの変更は記していない。
」掲載の 633 種を同書の配列順により掲載している。
改訂第8版で新規掲載された種も掲載しており、第8版準拠の#リンク集も用意している。
亜種についても備考で触れている。「日本鳥類目録 改訂第7版」非記載の鳥 (外来種) を掲載している。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、パブリックコメントへの回答、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト (目録第8版出版前段階のもの) も踏まえている。種名見出しでは目録第8版で種の分割、合体により学名が変化するものに注意を促す意味で注釈を加えた。属名のみの変更は記していない。
- 改訂第7版から第8版への移行に伴い、第8版学名と第7版学名を併記した。種分割などにより学名が変化するものは由来をわかりやすくするために第7版時代の学名に亜種も追記してある。
複数の亜種がある場合、多くの場合は最も古く命名された亜種と最も一般的な亜種が同一であるが、例外もあって例えば第8版の亜種キジの亜種小名は第8版で使われる種小名と同じではない。
さまざまなケースがあるため統一的な取り扱いはできない点をご了承いただきたい。
#ツメナガセキレイのように複雑なケースもある。この場合では第7版で用いられた亜種が別亜種のシノニムとみなされ、第7版亜種名に現れない種小名に変わっている。
#オオモズでは種分割が行われた結果、日本産亜種が主に北米種の亜種となったため第7版亜種名に現れない種小名に変わっている。
#オジロビタキと#ニシオジロビタキは一見第8版で分割されたかのように見えるが、第7版ですでに分割されていた。
- なぜ第8版配列版を用意しないか疑問に思われている (あるいは待たれている) 方もあろう。
日本鳥類目録改訂第8版の配列は IOC 13.2 に基づくものですでに最新のものではなくなっている。このころから現在 (2024) に至る IOC 配列は世界のリスト統合作業を優先しているため上位 (高次) 分類にはあまり変更を加えていない。
この作業は1年程度で完了すると想像される。IOC 14.2 までの IOC 配列は実質 Prum et al. (2015) のままであるが、2024 年に現生鳥類全体を含む新しい系統研究が発表されており、これらの結果も吟味した上で次第に反映されてゆくことだろう。つまり数年のうちの上位 (高次) 分類の配列は変わると予想される。
例えば Boyd のページでは上位 (高次) 分類の配列変更をすでに取り入れている。
IOC 15.1 では分子系統研究の進んだタカ目内部配列は新しいものを採用することが表明されており、これは他の分類群においても今後同様に進んでゆくだろう。IOC 15.1 で Turdus (ツグミ) 属内配列を並べ替えることが表明された (2025.1.20) が、
Latest IOC Diary Updates 問題点の指摘を受けて元に戻した。オープンな議論を受けて柔軟に対応しているのは素晴らしい。
IOC World Bird List Updates (2024.11.16 参照) によれば IOC 14.2 で分類が変わったものは 105 種、15 属が追加、2 属が削除、1 科が追加、とこれまでの更新の中でも規模が大きかったことがわかる。
2021 (IOC 11.1) 年以降のデータが載せられているが近年の分子系統研究や世界のリスト統合への機運を受けた加速傾向が読み取れる。分子系統研究による分類が広く受け入れられるようになって客観的な判断材料や基準が整ってきたため世界のリスト統合もようやく可能な段階になったとも言える。
この状況をふまえるとどちらも最新でない点では第7版配列でも第8版配列でも実質大差なく、第7版から第8版移行で検討種になったものもあるので第8版配列順に変更するのは少し扱いにくいのである (第8版に間に合わなかったが、カタグロトビの記載論文はすでに出版されている。これまで通りの扱いであれば今後 10 年ぐらい検討種のままとなるのだろうか。本稿には含まれていた方がよいと考える)。
IOC 13.2 で中途半端に固定にするのか、配列を今後の世界の変更に合わせるのかの問題もあり、物理的な順序入れ替えは行わずに新リストはリンク集として配列を示すこととした。
今後新しい IOC 配列に従ったリンク集を用意することも想定できる。
- 和名による分類階級は、目・科・種を記載し、日本鳥類目録第8版で新たに付いたもの以外の属和名の表記は原則省略している。
- このページへの個々のご意見・ご質問等は上記執筆者メールアドレスか ML Kbird を通じてご連絡ください。サイトへの全般的ご意見・ご質問等は、[ご連絡] のページより、メッセージ先頭に「野鳥の学名入門」と記し送信してください。
- 追記した備考では細分した中間的な分類概念をしばしば用いている。上位概念から順に 目 (order) - 亜目 (suborder) - 科 (family) - 亜科 (subfamily) - 族 (tribe) - 属 (genus) - 亜属 (subgenus) - 種 (species) - 亜種 (subspecies) のようになる (Taxonomic rank)。
太字が必須項目 (亜種まで記載する場合は亜種も必須になる)。亜種のない種を単形種 (または単型種、漢字の選択は日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に合わせた) と呼ぶ。英語では monotypic species。
近年は分子遺伝学の進歩により従来単一であった属が単系統でないことが判明し、複数の属に分割されることも多くある。日本国内の種に限れば一属が一種となるものも多く、属名から類縁関係を推測しにくくなっているケースもしばしばある。これらの場合に族などの中間的な分類概念を適切に使うことで分類的位置がわかりやすくなることもあり、実際に利用されている。
また非常に大きな分類群においては下位の中間的な分類概念を使うことは実用上も意義があり、従来も「ヒタキ科ツグミ亜科」のような使い方がなされてきた。近年の分類で亜科の分け方が大きく変わっているものもあるので (#ヨーロッパコマドリの備考参照) 注意が必要である。
種より上位の分類概念には定まった規則がないため、現在でも、そして今後も属の境界をどこに置くか、中間的な分類概念をどの段階に適用するかなど分類学者の間でも意見が分かれる場合もある (もちろん独立種と認めるか亜種とみなすかなどの議論もさまざまな形で存在する)。
現生鳥類を何科に分けるかのようなレベルでも議論があり完全な合意が得られているわけではない。
分類学進展の一断面と取り扱っていただくのがよいだろう。
この (生物学的) 階級 (rank) の他に、上種 (superspecies)、例えばメボソムシクイ上種のように、近縁種をグループ化した名称 (species complex、例えば herring gull complex、sibling species 兄弟/姉妹種) もしばしば使われる (Species complex)。対応するラテン語用法に sensu lato (s.l.) 「広い意味で」があり、種名の後に s.l. を付けて類縁種を含むことを意味する。
〜の一種を意味する sp. は属名に付けて、その属の一種を意味するものだが、メボソムシクイ属のように大きな属の場合は、メボソムシクイ属 sp. のような使い方は望ましくないかもしれない。メボソムシクイ s.l. とすればメボソムシクイ上種を表すことができるであろう (が、分類専門家の意見を聞いたわけではないので正確ではないかも知れない)。
近年提唱されているこれまでの Accipiter 属の分割が行われれば、これまでのハイタカ属 sp. のような表現は厳密には意味をなさなくなる (eBird では 2024.10.22 よりこの表現が廃止された)。
sensu lato の反対の意味のラテン語は sensu stricto 「厳密な意味で」で、s.s. または s.str. と略される (が分類学の論文以外で略号で使われるのをあまり見たことがない)。これらの用語を知っておくと海外の分類などを見る時に役立つだろう。どちらにしても厳密な定義のある概念ではない。
- 亜種そのもの記述は属名・種小名・亜種小名からなる三名法を用いるのが正統的であるが、備考では亜種の解説などの際に煩雑になることを避けるため、亜種(小)名を主に用いている。
- 外国語を記述する際に、非ラテン文字 (ギリシャ語、ロシア語など) は標準的なラテン文字転記で表示している。英語以外ラテン文字やラテン文字転記されたギリシャ語で広く使われるアクセント記号類は省略しているので、出版物などに用いられる場合はもとの綴りを確認されたい。
ロシア語のラテン文字転記は基本的にもとの表記に戻すことができるが、ギリシャ語ではアクセント記号類を省略しているためこのラテン文字転記からもとのギリシャ文字表記に戻すことはできない。なおドイツ語のウムラウトのみは標準表記に従い、e を追記して示している (同じ文字を使っていてもスウェーデン語では e を追記しないなどの不統一が発生するがご理解願いたい)。
- 標準和名は日本鳥学会が定めた名称で、これ以外の名前を使ってはいけないわけではない (例えば分野によっては実用上の観点から古くから知られた別名が使われることもある)。論文などを記述する場合にはどのリストに従うかが示されていると思われるので、日本の鳥については標準和名を用い、それ以外については他のリストを用いることなどになるだろう。
この稿では備考などに登場する日本鳥学会のリストにない鳥については原則 Avibase (一部 eBird) の和名を用いている。英名はもっと事情が複雑で頻繁に変化すると考えてよい。学名も結構よく変化するので、日本の鳥に限って観察・記録する場合は標準和名を使っておくと後々名前の修正を行う手間が少なくて済むだろう。
- 写真などを整理する時に、生物の階層分類に従ってファイルを整理するのは極めて自然なアイデアであるが、分岐分類学の進歩に伴って大胆な分類変更が行われることがある (例えばウ類はかつてペリカン目だったものが現在はカツオドリ目に移されている、サギ類はコウノトリ目だったものがペリカン目になっている、ツグミ類とヒタキ類の再編が行われたなど)。
上位分類はもうあまり変わらないかも知れないが、属分類の変更は今後もあると思われるので、分類を基準に体系的な配置を行ってこられた方 (あるいは種の説明に上位分類まで記載されてきた方など) は最新分類を常時意識されるとよい。
思わぬところで思わぬ変更があったりする。あまり「がちがち」にデータベースを作ると変更に大変な思いをすることもあるので、柔軟に変更できる構造にしておくとよい。
- 海外探鳥などをされる方は日本産鳥類ではカバーできないので IOC 分類などを用いられる方もあるだろうが、これもよく変更がある (1年に2回更新) ので最新版をフォローするのはなかなか大変である (それはそれで面白いわけだが)。もうちょっと高度 (超マニアック?) な楽しみとして、最新文献をチェックして次の分類変更を予測するなどもある。
海外にはそのように楽しんでいるバーダーや野鳥関係のフォーラムもあり、日本のバーダーも学会の判断を待つだけでなく、もっと関心を持つとよいのではないかと思う。
例えば日本鳥類目録第8版が出ても次の改訂には時間がかかるであろうから、海外の分類動向も変わってゆくであろう。(用いるリストが指定されている論文や出版物に使用する場合を除いて) その間に第8版の学名を使い続けるのか、海外のものに合わせてゆくかは個人の裁量の範囲であろう。
日本鳥類目録第8版の編集について [西海功 (目録編集委員長) 日本鳥学会 鳥学通信 2022] で西海氏も「IOC Listを基本にして著者の判断も加えながら独自の分類でフィールドガイドを作ることもできる。このような図鑑を良く思わない人もいるが、私はむしろ歓迎したい」と書かれている。
日本のサービスでも IOC 分類をベースに定期的に分類を更新しているものもある (例 https://zoopicker.com/)。
後の各種ごとの補足説明にもしばしば現れるが、日本周辺だけデータが不足していて分類が確定できないケースがある。バーダーがもっと関心を持って取り上げれば遺伝子解析などを行える専門家にとってもよい刺激になるのではないかと期待している (最初から余談ばかりであるが...以後脇道が多いので不要の方は読み飛ばしていただきたい)。
- 海外の国のチェックリストはどう管理されているのかを知ることもよい刺激になるだろう。例えばフィリピンでは The Wild Bird Club of the Philippines (日本野鳥の会のような組織) が管理をしており、毎年更新されている: Checklists of the Birds of the Philippines。コメントを送ったこともあるが文献も付けてしっかり返事をもらえた。信頼できる野鳥のチェックリストがない国もあり、世界のデータベースなどを検索して気づかれるかも知れない。
- 国レベルのチェックリストではないが、日本で言えば都道府県レベルのチェックリストを維持しているところも多くある。スウェーデンのサイト Vastmanlands faglar などは地域レベルの記録を管理されている方には興味深いだろう。個々の文献も収集してスキャンなどを公開している (Referenser から見られる)。
- ドイツの鳥学会が世界の鳥のドイツ語リストを 2022 年に発行。Die Voegel der Erde で 540 ページの本を無料公開!
- こちらはフランス語版世界の鳥リスト。IOC よりさらに先行してここで紹介しているような新学名にも対応! 改訂も頻繁に行われている模様。Noms francais normalises des oiseaux du monde - 2024 - version 6.3。
ダウンロードも可能。学名は Gaudin のものを使っているかも知れない。
- 本稿ではさまざまな論文にリンクを張っているが、なるべくフリーアクセスできるものを優先した。ページから [Download PDF] などのメニューに従えば読めるものが多いと思う。
文脈や学術雑誌名からオープンアクセスに見えにくい場合のみ「オープンアクセス」と明示したものがあるが、その表示がなくても実際にはここで示した論文の多くは誰でもフリーで読むことができる。
アクセス制限が表示される場合は論文表題を用いて検索してみていただきたい。例えば著者レポジトリなどで全文が読めるかもしれない。また雑誌によっては一定期間後にオープンアクセスになるものがある。
報道記事などへのリンクはたどれなくなっているかもしれない。その場合はインターネットアーカイブなどで読めるかもしれないので試していただきたい。
(論文以外の) ロシア語の書物は原則リンクを張っていないが、ここで挙げてある文献はほぼオンラインで見ることができる。探し方は最後の参考文献の部分を参照。
- そもそも学名を知って何の役に立つのだろうと思われる方も多いだろう。かつては「世界共通の名称なので海外の人に伝える時や海外図鑑を見る時などに役立つ」とも言われていたが、日本鳥類目録第7版以前で日本で使われていた学名は古いものもあり、世界のリストと異なる分類も採用されていたために実はあまり世界共通の名称として使えなかった。
目録第7版ではかなり世界の分類に近づいたが、それ以降に分類が改訂されたものなどは反映できていないため、ごく身近な鳥、例えばウグイスでさえも日本の学名が海外のものと合わなくなってしまった。1種が複数に分割された種などでは日本の学名で海外に出すと全然違う種類を指してしまうことも生じた。
海外図鑑を購入された時に和名を書き込む作業をされる方もあると思うが、学名がいかに異なるかを実感されたであろうと思う。目録第8版では世界のリストとほぼ同じになる見込みだが個々のケースでは注意が必要なものもある (それぞれの備考に記載)。
実際上は英語のわかる海外バーダーであれば英名は把握していることが多いので、海外バーダーもそもそも知らない学名よりも英名の方が通じることが多く、この意味での学名の必要性はあまりなくなってしまったかも知れない (それでも亜種等の細かい話ではやはり学名を使わざるを得ない)。英語圏以外の場合は長い学名を使うよりもそれぞれの現地語を覚える方が手っ取り早いこともある。
それでも英語以外で書かれた海外の書物やウエブページを参照する場合は学名は一定の役に立つ。また画像や映像を検索する場合でも学名で検索すれば日本語や英語以外のページも多数ヒットするのでこの効用は大きい。もっとも検索程度であればその場でコピー・アンド・ペーストをすればよいので学名を記憶するほどの必要性は少ない。
近年分子遺伝学の目覚ましい進歩で系統樹を見る機会が圧倒的に多くなった感じがする。例えばヒトの進化や新型コロナウイルスの新しい株の名前など、一般的なメディアでもよく見かけ、系統樹に馴染みのある人も増えているだろう。
ちなみにこのような目覚ましい進歩は次世代シーケンサー (Next Generation Sequencer, NGS) のような分析装置や、その結果から塩基配列を構成するコンピュータプログラムの進展によるものである。遺伝子やゲノムの解読は日常的に行われる時代であり、「ヒトゲノム計画」の時代には月着陸に匹敵する大偉業と呼ばれていたのとは隔世の感がある。
新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) が「新型肺炎」の形で最初に見つかった時に NGS が使われたことを後に知り、初期になぜあのような形 (まず SARS の再来が疑われた) で物事が進んだのかを納得できた。このあたりは報道に出てくることもまずなく、現代生物学のリテラシー不足によって疑似科学的な説を容易に受け入れてしまう原因にもなっているように感じる。
事情は鳥類でももちろん同じで、全鳥類種のゲノム解読を行う野心的プロジェクト The Bird 10,000 Genomes (B10K) Project が走っている。
別種か、あるいは別亜種か、などの説明を見る時には分子系統樹を目にする機会が増えている。系統樹では一般向けに分かりやすく描き直したもの以外では通常学名しか出てこない。すなわち学名をある程度読めないと系統樹をまったく読めないのである (これは種や亜種分布の地図などでも同様)。
これは現代生物学の面白みを半分捨てているようなものである。ちようど辞書を引けば英語が読めるがそのままでは読めない状況に似ていて、手間をかけて知っている和名などに翻訳して書き込むか、そのままで読めるかの違いになる。後者の方がずっと気軽に扱えることは間違いないだろう。このような経験を通じれば学名も (見ればわかる程度には) 案外覚えてしまえるものである。
また、海外の保護種 (レッドデータブック) リストなどで現地名と学名表記のことがある。知らない言語の場合は学名が手がかりになることは従来と同じである。
それ以外にも、和名や英名と同様、学名にも命名者の思いが (時には勘違いも) 込められていることもある。それらも読み取って歴史を振り返る楽しみがあるだろう。
- 作業を通じて改めてわかってきたのだが、現在は分子遺伝学による系統分類の大変革の時代のようである。日本鳥類目録 改訂第7版 で分類や学名が大きく変わったものがあり、第8版でも多くの属分類が変わる予定で、この傾向はまだしばらく続くであろう。
その昔は新しい地域を探検すれば新種や新亜種が次々と記載されて行ったが、その分子生物学版がまさに進行中で、昔で言えば探検に相当するであろう遺伝子やゲノムを調べれば系統にかかわる新しい知識が次々と生み出されていく段階に当たっている。
ただしこれも全種を十分調べればいずれは種レベルでは全系統がほぼ (種境界や解釈の難しい系統の問題などは残るだろうが) 明らかになって、ある程度の期間で落ち着くと思われる。第8版ではまだその段階に達しておらず、未処理部分が多く残っていて将来の改訂を待つことになるだろう。
次々と新種が発見されるように、これまでわかっていなかった系統関係が次々とわかってゆく現代に生きる者として、その面白さをリアルタイムに味わわないのはもったいないぐらいである。
ほとんどの情報は英語論文などの形になって残念ながら日本語のみではほとんどうかがい知れないだろう。
そのような英語論文や記事などの系統樹を読むにあたって、本記事が手引きの一つとなれば幸いである。
また遺伝情報はデータベース (GenBankなど: 学名検索もできるのでうまく使えばいろいろな情報にアクセスできる) で公開されており、それなりの計算機資源は必要だが分子系統樹を作ってみたい人は自分でも作ることができる。
GenBank のサービスを用いた簡易系統樹の作り方の解説: Owls (BirdForum 2025.1)。
#ハチクマ備考 [フィリピンのハチクマの不思議] 末尾に実行例を示した。関心のある種グループの系統解析の論文が見当たらない、あるいはオープンアクセスでなく読めないなどの場合は遠慮なく BLAST を試してみよう。論文に示される系統樹1つだけからはわからない事情が見えてくることもある。
ごく最近になって知ったのだが日本と共通種のゲノムが海外で結構読まれている。興味ある方は探してみていただきたい。同種で日本と大陸とゲノムがどの程度違うのかなど解析さえできれば調べることができるものもある。Catanach et al. (2024) のタカ類系統樹作成にも使われていた。
識別を極めたい方はゲノム解析にも挑戦されてはいかがだろうか。
科学のいろいろな分野でも同様であるが、最先端の情報は専門家だけのものの時代ではなくなっている。
- 自分も詳しく知っているわけではないが、学名の命名には詳細な規約がある。現在使われる学名はその規約に基づいて了承されているものだが、そこに至る経緯は必ずしも平坦なものばかりではなかった。
学名には先取権 (priority) の原理があり、同じものに名前を付けた場合は早く付けられた名称が有効になる。後に付けられた名称はシノニム junior synonym となる (junior synonym の和訳は複数ありジュニア・シノニム、後行シノニム、新参シノニム。シノニムの部分も異名と訳されることもある。本稿では紛らわしいことはほとんどないので単純にシノニムと表記した)。
気づかずにすでに他で発表された学名と同じものを発表してしまうと無効な学名になる。
このあたりは常識的にも理解しやすいが、実際に学名が決まる過程はしばしば非常にややこしく、使われるようになってからかなり後にその名称がすでに使われていたことがわかって改名されたことや、
古い文献では綴りが違っていたり語尾が省略されていたりしたものが訂正されて使われていることもあって、どれが正しいのか議論が発生するなど様々なケースがある (サカツラガンの学名変更は未確定のケースにあたる)。
個々のケースでわかる範囲で説明を加えてあるので学名の世界を楽しんでいただきたい。
最近多い学名変更は分類の見直しによるもので、分子系統解析の結果1つの属が単系統でないことが判明して複数に分割されるケースなどが多い。我々が通常みかける学名変更はこのケースが多い。
ラテン語には文法上の性があるので、属変更の結果で属の性が変わると種小名の性もそれに合わせて変化する (形が変わらないこともある)。
また種の中の亜種が独立種とされる場合も種に相当する学名が付くことも容易に理解できるであろう。
その亜種がもとの種の基亜種 (その種で最初に記載された亜種) であった場合は2種に分離された場合に分離された種の方が学名を引き継ぐことになる。日本で通常記録される亜種が基亜種でない場合は日本で通常記録される種の学名の方が変わることになる (ツグミとハチジョウツグミ、アオジとシベリアアオジなど)。
ある亜種が別の種の亜種とするべきことが判明した場合は亜種の移動になるが、これも基亜種の移動の場合や移動先で基亜種になる場合は種の学名に影響が及ぶ。
これらは分類概念による部分があるので、異なる分類学者が異なる学名を用いる要因の一つとなる。
また現代では珍しいが、異なる属が統合された結果同じ属に同名の種小名が生じ、後に付けられた方の学名を変える必要が生じることもある。
これらも個々の事例でわかる範囲で説明を加えてある。
(この部分は先に記述したもので書き加えたものと内容が重複する部分があるが残してある)。
- アメリカやカナダでは、個人名の付いた英語の鳥名の名称変更の動きがある。American Ornithological Society Will Change the English Names of Bird Species Named After People (2023年11月)
はアメリカ鳥学会の動きであるが、特定の人名よりは鳥の特徴を表す名称に変えてゆくとのことである
(現代では受け入れがたい価値観の個人にちなんで付けられたなどが問題となったことが発端にある。Bird Names for Birds 運動についての wikipedia 解説。スウェーデン鳥学会や NASA も名称や取り扱いを変更したとのこと)。
この動きは世界の英名、あるいは場合によっては他国語名にも影響を与えると考えられ、今後注視してゆくべきであろう。
日本ではむしろ和名の由来となった人物を紹介するなど行われているが、あるいは我々は個人名を鳥名に付ける議論への感度が低いのかも知れない。
この動きを受けてアメリカでは早速「元オバマ大統領にちなんで付けられた鳥の名前はどうなる?」の議論が出ている。これはニシオオガシラ Nystalus obamai IOC 英名 Western Puffbird であるが、英名 (アメリカ名では Western Striolated Puffbird) に人名が入っていないことから変わらないそうである。学名はそのまま維持される。
英語以外の言語ではオバマを冠している名称もあるようである。
wikipedia 英語版によれば Mr. Donald Trump にちなんだ学名を持つ生物は複数あるそうだが、鳥は含まれていない。
ウイルソンアメリカムシクイ Cardellina pusilla (Wilson's Warbler) も改名の対象となっており、英名が変更された場合に和名はどうするだろうか。
改名に関する話題については#クロハゲワシの備考 [ハゲワシ類の名称や迫害、改名]、#アホウドリの備考 [語源や関連する用例] もご覧いただきたい。
学名に関する規則は違うが、植物では 2026 年から一部の学名を変えることが決まった。Hundreds of racist plant names will change after historic vote by botanists (Nature news)。差別的な名称に基づく理由で生物の学名が変わるのは史上初めてとのこと。
ここでは当たり前のように Nature news を紹介させていただいているが、Mr. Donald Trump の科学政策を批判しているためか、何と米国で Springer Nature 系列の雑誌購読を打ち切りとのこと: Trump team axes contracts with publishing giant Springer Nature。文中に現れる [sic] は ("そのまま" の意味で、ここでは雑誌は複数あるのに単数形で記述されているのは、そもそもわかって行っていないことを暗示している)。NASA も購読中止作業中を確認したとのこと。
おそらく報道などには現れそうもないが、今後は科学雑誌の論文を見る時でさえ政治の影響を考えなくてはいけなくなるのだろう。
- その後アメリカ鳥学会の動きが予期せぬ波紋をもたらしている。北米と南米の種の検討委員会 (南米は South American Classification Committee, SACC) は近年は 20 年以上協力して名称を決めていたが、アメリカ鳥学会の英名決定に SACC が関与できなくなったため協力関係を打ち切り、SACC は IOC と連携して世界の鳥のチェックリスト作成に関与することとなったとのこと
(#ハヤブサの備考の [ハヤブサ目の系統分類] と紹介リンク先参照)。
北米と南米は共通の渡り鳥などがあるが、米国と南米で異なる英名が使われる事態も発生しそうである
(深読みしたいこともあるのだが皆様のご想像にお任せしたい)。
- 2024.5.13 上記 SACC のことも触れられ、パイロットプロジェクトで国外への影響の少ない種に絞ったパブリックコメントが開始された: AOS Pilot Project to Change Harmful English Common Bird Names。
AOC/AOU の動きに連動して分離などで種に新しい英名を用いる際は人名を排除する傾向が強まっており、後述の WGAC でも合わせる動きがある。#カツオドリや#オガサワラミズナギドリ (旧名セグロミズナギドリ) の備考など参照。
Winker (2024) Bird names as critical communication infrastructure in the contexts of history, language, and culture
(特に人名由来の) 英語鳥名の変更の動きについての議論。歴史的な様々な経緯がある。英名の方が学名より安定している。
確かにハクトウワシが "Bald Eagle" と呼ばれるのは適切な名前ではないが、変更するとより多くの人とのコミュニケーション上支障をきたす可能性があるので、著者としては不本意ではあるが受け入れるなど (決断して変えればいずれは定着するのだろうが...)。
種英名を大文字で始める習慣は (本来はどちらでも構わないが)、種名を固有名詞のように扱って一般的記述と区別しやすくできる利点がある (日本の例だと white wagtail は白いセキレイだが、White Wagtail と書けば種ハクセキレイを表していることが区別できるなど)。
- 世界に鳥が何種いるのか、面白い考察がある。Barrowclough et al. (2016) How Many Kinds of Birds Are There and Why Does It Matter?
種に形態的違いによって分けられた生物学的種から新世界の 200 種をサンプルして形態、遺伝情報、分布をもとに進化的種概念で種数を推定すると 18043 種 (95% 信頼区間 15845-20470 種) と推定され、現在用いられている分類学は種多様性を大幅に過小評価している可能性があるとのこと。
種数が2倍になっても過剰評価とは考えず、むしろ多様性の正しい理解の結果であり、保全にもより有効であると考えている。亜種は古く形態学的に記載されたものが多く、地理的なクラインなども多いためそのまま種に昇格が適当とも言えない。
- Clements 2024 checklist update によれば、Clements 2024 の改訂草稿が公開されているとのこと (2024.6.25)。2024年10月に発表の予定。
The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2024 にて公開された (2024.10.22)。
Clements Checklist v2024: Excel spreadsheet; CSV file。
同じページから eBird で報告可能な分類概念一覧もダウンロードできる。Accipiter sp. の概念はなくなり、4属を含んで我々からみるとより広義の Accipitrine hawk sp. の名称となった。
Island Thrush はなんと 17 種に分離! #アカハラの備考参照。
シジュウカラは Parus cinereus に含まれた: #シジュウカラの備考参照。IOC 14.2 もこれに従っている。
タカ類の新分類を採用: #アカハラダカの備考参照。Say hello to Astur for Cooper's Hawk and American Goshawk for you Americans! (アメリカ人にとって Astur = オオタカ属さんこんにちは) とある。
アメリカのデラウエア自然史博物館も展示の学名変更に向けた記事を出している: Evolutionary Breakthrough of Hawks and Eagles (Accipitridae)。この博物館の学芸員が論文共著に入っているので率先して行われるのだろう。
birdforum.net の記事によればこれまでの Accipiter から分割された -spiza で終わる属名は女性名詞とのこと (ICZN Article 30.1.2, 30.1.3 による)。
個々の種の分離の話題などは birdforum.net のスレッドを参照。
IOC でも 14.2 に向けて Proposed Splits/Lumps, Taxonomic Updates
などの改訂が順次発表されており、Clements 2024 を少し後追いする形となっているが、用いている文献が同一なのでほぼ同じものを採用している (例えば Island Thrush は 17 種)。
その後 14.2 が発表されたが、一部改訂は 15.1 に回ることとなるとのこと。
Working Group Avian Checklists (WGAC, 世界の統一チェックリスト。次項目参照), version 0.04 もタカ類の新分類を採用。世界の主要リストの学名が一気に変わるだろう。
2024.8.2 IOC 14.2 もこれまでの Accipiter を5属に分割 (一安心)。
2024.8.14 IOC 14.2 に移行開始とのこと。v14.2 red, Excel File を公開。
2024.8.19 IOC 14.2 に移行 v14.2 Excel File。
wikipedia 英語版も新しい学名を用いている (2024.8.29)。2024年9月上旬段階でドイツ語版、オランダ語版、スウェーデン語版、韓国語版などでもオオタカの学名が新しいものになっていた。
従来の国内独自分類を採用するかと思えたロシア語版も9月下旬に IOC 14.2 を採用。分離された属の解説ページもすでに作られていた。
さらに 2025.2.16 IOC 15.1 v15.1 red, Excel File を公開。
2025.2.28 v15.1 Master List が公開された。
Balatskij Birds of Northern Eurasia の分類では 2023 年にすでにこれら分類が採用されていた。なんとロシアでも新しいタカ類分類が早々と標準学名となっていた (よく見ると Tachyspiza 属への分割が完全でなくツミが Accipiter 属に残ってしまっている。これはもしかすると過去に発表されたツミのミトコンドリアゲノムに誤りがあったためかも知れない)。
ホオジロ類の部分はロシアの独自分類なので IOC などをそのまま採用した分類体系でないことが判断できる。
属名のロシア語表記は種名と異なる部分もあるが、Tachyspiza 属のいくつかのもの (タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] 関連種) はもともと tyuvik と呼ばれており、ロシア語慣用名段階ですでに別名があったためまったく違和感がなかったのだろう。Tachyspiza 属への分割に従って過去のロシア名も tyuvik を付けた名称に変更された。
Tachyspiza 属の新しいロシア語名は "趾の短いタカ" (アカハラダカのロシア名でアカハラダカ属に相当する) に相当する。
Clanga 属も慣用名段階で別扱いとなっていた。
日本周辺では中国のみがまだ動向がわからないが、Lophospiza (カンムリオオタカ属) は wikipedia 中国語版ですでに使われており、Catanach et al. (2024) の研究にも言及があるので時間の問題で取り入れられてゆくのではないだろうか。
これまでの Accipiter 属からの変更点が多いので一気に処理できていないものと想像できる。
さて日本語版は - 2024.10 末「タカ科」の項目で Catanach et al. (2024) が参照され、wikipedia 英語版に対応する一覧が盛り込まれた。ただ他の項目には古いものも含まれているため参照される際は注意が必要と思われる。全面改訂にはかなりの手間が必要でなかなか大変だろう。
wikipedia ポーランド語版では早くから反映されていたが、ポーランド語の世界の鳥名リストを見てびっくり。Coracornithia (Telluraves の名称より早く使われた系統名があるとのこと)
Catanach et al. (2024) や Stiller et al. (2024) はもちろん取り入れられているが何と亜種にまでポーランド語が与えられている (英名はもちろん表記)。
Complete Checklist of the Birds of the World (メインページ)。系統分類は Marka Kuziemko が行っているとのこと。全体的に亜種をあまり分けないリストになっているが、種候補になるぐらいに分けるべきところは分けているようで自身の感覚に近い部分がある。分類は H&M 由来で IOC とはやや異なる部分がある。
2024.10.7 IOC 15.1 ではタカ類内配列を Catanach et al. (2024) に合わせることにした。オナガヘビワシの学名が IOC 14.2 では古いままだったがこちらも合わせることになった。
この記事に紹介済みのタカ類の新分類通りの順になると思われる。
日本産種ではそれほど大きな変更があるわけではないが、クロハゲワシとカンムリワシ、アカハラダカとツミが逆順になるなどが想定される。
カタグロトビも記録種と認定されればハチクマの前になる。
チュウヒ類内部は多少入れ替えがあってチュウヒは最後になると考えられる。オジロワシ類の間も多少の入れ替えが考えられる。ノスリ類はあまり変わらず日本のノスリが最後になると想定される。
いずれも最新知見による系統関係を反映するもので、単なる分類学的順序変更以上に系統関係や生物地理学 (より新しく現れた系統はどちらかなど) を意識するのに役立つだろう。他の系統ではルリカケスのような遺存固有がいくつか見られるが、タカ類では (日本でこれまで調べられた範囲では) 遺存的な種類は見られないよう。
全般的には日本のタカ類は比較的遅くユーラシア東端の新天地に到着した描像が想像できる。
ツミの方が原型に近く、アカハラダカが渡り能力を活かして後にアジアからオセアニアの島に分散した描像となり、順序もそれを反映するものになる。
Tachyspiza 属はそれなりに分岐が深いので属内の構造を考えることも多少意義があるだろう。その場合はツミとミナミツミが姉妹種の関係になる。アカハラダカから始まるクレードはちょうどハヤブサ類の上種 Hierofalco の概念に対応する位置づけとなる。
単に順序が入れ替わっただけではなく、分類や新学名にはこれほどの情報が込められており活用して楽しまない理由はない。
タカ類や分類や学名については世界的にもあまり異論なく決断できるレベルまで確定してきたと考えられる。タカ類については IOC 15.1 がしばらく標準で使われ今後は細かい調整レベルと推定される。
アメリカ American Birding Association (ABA) のチェックリストも 2024.11 に更新 American Birding Association Checklist Committee Report, November 2024 (Pyle 2024)。
反映が遅れていた Avibase も 2024.12.29 までにこれらを新学名に変更。これほどに時間のかかる規模の大きな変更で年内に何とか間に合わせた印象。
iNaturalist に Accipiter Shake-Up の投稿 (2024.10.24) も出ていた。
少し前に分離されたアメリカオオタカでは属名も種小名も変わることになり、北米ではよく知られた種の学名が短期間で完全に別のものに変わってしまった。投稿者によっては記録を投稿してからアメリカオオタカの学名がわずかの間に2回変わったとのこと。
accipiter はこのグループのタカを指す英語一般名にもなっている (一般名と属名が一致していた) のでこの変更はかなり余波が大きい。一般的には accipiter と呼べるのになぜ学名は異なるのかなど入門者への説明も必要でしばらく話題が続くことだろう。
Accipiter split has resulted in lots of conflicting ID's 過去に単に Accipiter としか書いていない記録が多数ありすぎて困っている。
Accipiter をそのままにしておくと属レベルで間違った記録が多発することになる。亜科などのレベルを使うとチュウヒ類を含んでしまう概念になって受け入れられないだろう、など。
こちらは苦労話: Taxonomic Swap 147312 クーパーハイタカだけで 10 万件以上のデータを移動する必要がある。システムの仕様を超えかねない。管理者が不在中に走らせたいが大丈夫か。チェックするだけで多分1週間以上かかるだろう。
移動中は両方の名称が有効で、移動途中でもすでに古い学名での投稿があった。種が分離されることは慣れていても大規模な属変更はあまり経験がなくどの順序で動かすかなどなかなか大変らしい。
Taxonomic Split 147038 (Committed on 11-02-2024) 作業が終わる前に次の変更を走らせないように。属の違っているものは手動で修正する必要がある。この作業だけで数日かかる。
wikipedia 英語版などでも変更の反映に時間がかかったのは、個々の記事内の修正点が多すぎる上にどのレベルの作業から開始するか一筋縄では行かなかったのだろう。よほど好きな人でもない限りタカ類全種の表を作るだけで力尽きるだろう。
英語は世界のバーダーの事実上の共通語でもあり、もちろん北米に限った話ではない。
タカ類の分類変更は 2024 年の鳥の系統分類変更の最大の話題とも言えるものだった。
日本語風に言えば「Accipiter (ハイタカ属) ショック」と言えるだろうか。言語圏も違うが、さて日本には「Accipiter ショック」は訪れるだろうか。
この部分に加筆しているのがちょうど 2024 年末で、2024 年の鳥の世界の 10 大ニュースなどもちらほらと考えてもよさそうな感じ。
タカ類の系統樹が全面的に明らかになり「Accipiter ショック」、2015 年以来の鳥類の系統樹全貌が発表される、シロハラチュウシャクシギの絶滅宣言などは上位に入りそうな気がするが皆さんの感覚はいかがだろうか。世界のリストの統一も 2024 年の重要な進展だったが本格的には 2025 年のニュースに譲ることになるだろうか。
2023 年の研究を受けてサギ類の分類や学名も世界的にはかなり変わるのでご注意を。例えば#アマサギは新しい海外学名を見ても何かわからないかも知れない。英名は統一の対象外だが#チュウサギの WGAC 英名は分類変更を受けてこれまで親しんだものとは変わる。
#ササゴイの学名も変わるが、提案されている新英名は何と Little Heron (2025.1.12 段階)。
#タヒバリも新大陸と分離され学名・英名ともに変わる。
2024 年の研究により、淡水カモ類の分類にももう一度大きな変更が生じると想像される。
- Toward a Unified List of the World’s Bird Species
世界の鳥の統一リスト作りが始められている (2024.7.1 のニュース)。2025 年初めにも統一リストを公開する見込みとのこと。Clements 2024 と IOC 14.2 が同じ改訂を採用しているのはこの動きが背景にあるとのこと。その後も毎年1回ぐらいの改訂を出すだろうとのこと。
過去提唱されながら実現されなかった試みで、現在は一番ホットな時期に立ち会っていることになる。
Working Group Avian Checklists (IOU の部会) 英名も含めた慣用名は統一視野外。eBird/Clements, IOC は WGAC のこれらの改訂を採用する。Clements の移行が少し先行しているよう。
WGAC が公開されるとすぐに移行する準備を進めている。今後は分類と学名は WGAC 準拠に移行となりそう。WGAC の検討の終わった科の一覧も出ている。6月の時点でタカ目は終わったがハヤブサ目はまだなどの状況。
BirdLife も多くを採用する予定とのことだが、IUCN リストとの統一もあり作業は多少時間がかかるとのこと。
BirdLife が 2024.10 新しいリストを発表したが現段階は分類よりも評価の変更が中心。2025 年の早いうちに AviList (WGAC) に合わせてゆくことが発表された。
BirdLife は保全上の評価も行う必要があるため、種分割・統合などに伴った評価見直しの必要があり、世界のリストの動きに比べて少し余分に時間がかかる (over the next few years とあるので多少かかるかも知れないが AviList を分類体系の基礎とする)。
参考資料: HBW / BirdLife Taxonomic Checklist。
世界の主要リストが 2025 年の早い時期に統一されることが鮮明となった (2024.11.14 に得た情報より)。世界中の人が待望していたがおそらく史上初で学名も基本的に世界共通になると考えられる。
HBW / BirdLife Taxonomic Checklist v9 にコメント (2014.11.20) があり、属や一般名 (英名) の変更は保全上の評価を待たずして行うことができる (スレッドの流れから Accipiter 属を分割する予定であることを示唆している。今年の分類変更の中でも特に関心が高い)。
しかし種レベルで分類変更があるので保全上の評価を行う必要がありその作業の後になるとのこと。現在 2016-2025 年の保全上の評価作業の途中。評価が済めば分類変更は迅速に行えるだろうとのこと。
Clements 2024 checklist update に 2024 年9月末の続報があり、eBird の分類は 2024.10.22 に全面変更とのこと。後述の WGAC が 2025 年初めに発行するリストは AviList とのことで、eBird/Clements の分類・学名はそれに従うとのこと。
WGAC の名称よりは呼びやすいと歓迎のコメントあり。北米 AOS-NACC と南米の SACC の微妙な関係についても述べられており、SACC は AOS のパートナーではなくなっていることも表記から明瞭になっている。
2024 Taxonomy Update-COMING SOON (eBird の解説 2024.9.24)。'Accipiter sp.' No More もはやこれまでのように Accipiter sp. と報告できなくなるので注意。
前々から予期されていたことではあったが今年ついに分離された。
属が分離されたことによって識別が容易になるわけではないが、属固有の行動 (特にディスプレイ) に注目するよい機会である。
eBird では候補種が2種の場合は / で区切って "どちらか" の形で報告を受け付ける。本当にわからない場合は Accipitrine hawk sp. と報告する逃げ道は残してある。
日本の場合では "オオタカまたはハイタカ" のような表記とすることになるだろうか。
鳥類の分類 更新のおしらせ (2024年) (eBird Japan 日本語版のアナウンス 2024.12.24)。Accipitrine hawk sp. に対応する日本語版は "ハイタカ属" となったとのこと ("ハイタカ属 sp." ではなくなった)。
ここで "属" の用語を使うよりも "ハイタカ類" の方が英語ともよく対応する感じがする。なるほどと感じたのは日本では新しい属を用いていないので属の和名が確定しておらず、"属" を使う場合でも "ハイタカ属" と書かざるを得ないのだろう。
このページの事例にある "ツミのメスかハイタカのオスか" は "ツミまたはハイタカ" の項目があってもよさそうに思えるが、eBird では Eurasian Sparrowhawk/Eurasian Goshawk - Accipiter nisus/Astur gentilis の組み合わせ (他にも Levant/Eurasian Sparrowhawk - Tachyspiza brevipes/Accipiter nisus, Besra/Japanese Sparrowhawk - Tachyspiza virgata/gularis などがある) があるのに "ツミまたはハイタカ" に対応する項目はないらしい。
必要ならば要望を出せばよい気がする (2025.3 追加コメント)。
日本鳥類目録改訂第8版の出版予定に相前後して世界の分類がおおよそ統合される形となる。海外の種と比較したり未記録の鳥の名前や学名が必要となることもあるだろうから、日本産種のみは日本の学名で、海外種は海外の学名と使い分けるのも不自然に思える。
和名は日本鳥類目録を用い、分類と学名は世界の動向に合わせて WGAC に従うなどのハイブリッド利用が現実的なものになって行くかも知れない。その場合は例えばオオトラツグミは種扱いとなる。
執筆中の現段階では WGAC のリストも作成途上で作業途上の誤りも含まれている模様。予想される WGAC の学名はかなり確定したと思われるものを中心に紹介している。
Conix et al. (2024) Measuring and explaining disagreement in bird taxonomy。分類における各種リストの相違を調べて特に種境界などを議論した意見論文。IOC, Clements などの動き以前の議論と見てよいだろう。
- 英国も WGAC の動きに合わせてリストを見直す見通しが紹介されている British list set for major taxonomic shake-up (birdguide.com 2024.10.18)。
英国の BOU は IOC 分類を採用するようになって以降 IOC が変更すれば数か月以内にすぐに反映しているとのこと。
これまで別種扱いだったハシボソガラスとズキンガラス、コガモとアメリカコガモは同種扱いとなる見通し。
ノビタキ (現在の学名で Saxicola stejnegeri) とシベリアノビタキ (現在の学名で Saxicola maurus) が再度統合される可能性がある。この場合シベリアノビタキの記載の方が早いので、日本のノビタキの学名は Saxicola maurus (亜種まで記して Saxicola maurus stejnegeri) に変わることになる。
同日時点での IOC 15.1 の変更点にはまだ現れていないが Working Group Avian Checklists, version 0.02 以降で統合されている。解説は#ノビタキ参照。
雑誌 Birdwatch でこれらの分類変更の詳細を紹介することになるだろうとのこと。日本の雑誌で紹介されるのはいつになるだろう?
その後 2025 年2月号が記事で New Order: World taxonomy set for major shake-up が表紙タイトル。Alex Berryman の解説とのこと。記事タイトルは New world order で "新しい世界秩序" と分類学の order ("目" や分類順などの意味) を掛けている。なお同号に RSPB の財政問題が取り上げられている。不採算施設の閉鎖など。自然保護先進国の英国でまさに起こっていること。
Clements 2024 checklist update の情報によれば Avibase の中心メンバーである Denis Lepage が WGAC 編纂に関わっているとのこと。現代のチェックリスト編纂は手作業では限度があり極めて高い計算機技術を必要とされることも想像できる。
- 公式情報ではないが Which world bird list/taxonomy to use for your life-list: a comparison between the major ones (Ecotours 2025.2.24) に最新状況あり、2025 年 4-5 月に AviList が公開されるだろうとのこと。
ひとたび公開されれば eBird/Clements 独自のリストはなくなると宣言されているとのこと。
2024 年の Clements list が最終のものになる見込みで、以降は AviList を用い、eBird もこのリストに従うことになると考えられる。
これまで分離されていたものが統合されて不満を持っているバーダーも結構あるだろうとのこと。ニュアンスを伝えるスレッド: Increasing dissent amongst birders regards taxonomic changes and seeking an alternative listing authority? (BirdForum 2025.3)。
一般的には分離される方がライフリスト数が増えて好まれるだろうが、種境界をさらに低いレベルまで下げて多くの島に固有種を認め、世界の鳥が 30000 種になったらそれはそれで呆然とする人も出てくるだろう、など。例えば日本の離島ヒヨドリの亜種をすべて種と認めると大変なことになるだろうことは十分予想できる...。
また重要な指摘もあって、地域によっては識別可能で別種扱いが適切に見えるものがあっても別地域ではそうではない場合がある (北米のベニヒワが挙げられている)。一地域の印象で判断すると世界的視点として適切でないこともある。
- こちらもまだ公式情報と言えないかも知れないが、IOC は v. 15.2 が最終となる見込み。Clements 2025 も出す予定で、この段階で世界のリストは基本的に統一される模様。ヤツガシラも種統合の結果英名は Eurasian Hoopoe から Common Hoopoe となる見込みとのこと: New unified list of birds - Avilist (2025.5 の項目)。
この話題はとても関心が高く、New unified list of birds - Avilist (2025.5 の項目) のような世界のリスト動向の予想も出されている。IOC リストは AviList と重複するためいずれ吸収されるだろう。eBird は ("何とかまたは何とか" のような区分の表記が必要なので) 独自に維持するだろうが AviList を基本にすることになるだろう。
この段階では Sibley and Monroe や Howard and Moore などのリストはもやは過去のもの扱い。記憶の中にぼんやり登場する (our recollections - つまり回想!) 程度のものになるだろうとの予測。
日本のリストの第8版学名で AviList と異なるものも、時間の問題で日本でしか通じない学名となり、いずれ "日本でしばらくの間使われていた学名" として回想の中に現れることになるのだろう。
- AviList がついに公開された (ファイルの日付は 2025.6.11) AviList (aricles) 無料公開で毎年更新予定とのこと。
Media and Support に各種サービスでのアナウンス、メディアでの紹介など。
BirdLife International, Cornell Lab of Ornithology, eBird/Clements もいずれも解説記事を出している。BirdLife も世界のリストの統一は保全にも役立つと述べている。
BirdLife のスウェーデンのパートナーは AviList の全種の公式のスウェーデン語名リストを提供。スウェーデンでは 20 分のラジオ番組で紹介。
Unified global taxonomy published for first time (BirdGuides 2025.6.13)。
アジア地域を中心とした Oriental Bird Club でももちろん採用と会誌 "The Banded Pitta" の newsletter で連絡あり。フィールドガイドで採用されている splits (種の分割) や将来可能性のある splits のリスト作成の作業中とのこと (2025.7.6)。
Cornell Lab が AviList を紹介する Webinar を開催 (2025.7.31): BOW Discovery Webinar: Introducing AviList: a unified global avian checklist Paul Donald (BirdLife International), Pamela Rasmussen (The Cornell Lab, Birds of the World), Marshall Iliff (The Cornell Lab, eBird) がパネリストとのこと (BOW Team 2025.6.27 の記事・追記)。
AviList Core Team. 2025. AviList: The Global Avian Checklist, v2025. https://doi.org/10.2173/avilist.v2025
リストをダウンロード可能となっている。複雑なログインや登録なども必要なくそのままダウンロードできる。AviList-v2025-11Jun-extended.xlsx と AviList-v2025-11Jun-short.xlsx の2つ。
今後世界でしばらくこのリストの分析・検討が続くだろう。
個々の種の分離・統合や学名の変化などは誰もがすぐに調べると考えられるので、日本鳥類目録 改訂第7版と第8版との間でかなり変化のあった目配列を見ておく。AviList には目より上位の概念は示されていないがわかりやすくグループ化するために [ ] に含めておいた:
[古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae]
ダチョウ目 Struthioniformes
ヒクイドリ目 Casuariiformes
キーウィ目 Apterygiformes
レア目 Rheiformes
シギダチョウ目 Tinamiformes
[以下 新口蓋類 (新顎類) Neognathae]
[Galloanseres (キジカモ類)]
カモ目 Anseriformes
キジ目 Galliformes
[Mirandornithes]
フラミンゴ目 Phoenicopteriformes
カイツブリ目 Podicipediformes
[Columbaves]
エボシドリ目 Musophagiformes
ノガン目 Otidiformes
カッコウ目 Cuculiformes
クイナモドキ目 Mesitornithiformes
サケイ目 Pterocliformes
ハト目 Columbiformes
[Elementaves]
ツメバケイ目 Opisthocomiformes
ツル目 Gruiformes
チドリ目 Charadriiformes
ジャノメドリ目 Eurypygiformes
ネッタイチョウ目 Phaethontiformes
アビ目 Gaviiformes
ペンギン目 Sphenisciformes
ミズナギドリ目 Procellariiformes
コウノトリ目 Ciconiiformes
カツオドリ目 Suliformes
ペリカン目 Pelecaniformes
ヨタカ目 Caprimulgiformes
アブラヨタカ目 Steatornithiformes
タチヨタカ目 Nyctibiiformes
ガマグチヨタカ目 Podargiformes
ズクヨタカ目 Aegotheliformes
アマツバメ目 Apodiformes
[Telluraves]
フクロウ目 Strigiformes
コンドル目 Cathartiformes
タカ目 Accipitriformes
ネズミドリ目 Coliiformes
オオブッポウソウ目 Leptosomiformes
キヌバネドリ目 Trogoniformes
サイチョウ目 Bucerotiformes
ブッポウソウ目 Coraciiformes
キリハシ目 Galbuliformes
キツツキ目 Piciformes
ノガンモドキ目 Cariamiformes
ハヤブサ目 Falconiformes
オウム目 Psittaciformes
スズメ目 Passeriformes
これがこれから少なくとも1年間世界の標準配列となる。[#鳥類系統樹2024] の Stiller et al. (2024) と基本的に同じである (線形配列の順序に任意性のある部分を除く)。
かつても同様の扱いがあったが、コンドル目をタカ目から分離、キリハシ目をキツツキ目から分離などが興味深いところ。アマツバメ目とフクロウ目が並ぶのはかつての夜鳥類の復活ではなく、別系統だが線形配列とする必要性から生じたもの。
フクロウ目の方がタカ目より早い順序が採用された。Telluraves の配列は日本鳥類目録 改訂第8版で採用されているものとも違っていて、大きな系統で言えば フクロウ系統、タカ系統、ブッポウソウやキツツキなどの系統、ハヤブサやオウムやスズメ目などの4系統の順序が少し入れ替わり、タカ系統 → フクロウ系統 → ブッポウソウやキツツキなどの系統順序を想定した Prum et al. (2015) 時代の考えが断ち切られたことになる。
この配列の場合は表面上はフクロウ目と (コンドル目 + ) タカ目をまとめた Hieraves の概念 (Wu et al. 2024) が可能に見えるが、Springer and Gatesy (2024) は系統の存在を積極的に支持していない。タカ系統とフクロウ系統がまとまったわけではなく、現在の知見ではむしろ分断が深まったと見るのがよいだろう。
目順序は IOC 15.1 までかなり保守的だったが、これは当時から世界のリストの統一化の準備が進められており、高次分類の整理は後回し (統一化を見越してむしろ積極的に避けられていたのかも) となったためと考えられる。
IOC 13.2 を採用した日本鳥類目録 改訂第8版は結果的にその狭間に落ち込んでしまうことになった。
高次分類は独自に検討を行った改訂第7版の方が進んでいた部分がいくつもあった。
配列順を入れ替えた方がよいだろうか、と問われれば、個人的には「入れ替えた方がよい」と答えるだろう。
本文では AviList (2025.6) の表現で取り上げており、この文字列で検索してみていただきたい。フクロウ目とタカ目の関係など一部少し深い解説を用意したが。個々の種についてはまだごく一部を反映したにとどまっている。公開されているリストを見ていただけばよいので徐々に作業してゆく予定。
AviList paper accepted for publication AviList の論文が受理されたとのこと。共著者顔ぶれと Abstract を見ていただければ内容をほぼ把握いただけるだろう。
オーストラリアの著者がかなり目立つがオセアニアの特異な鳥類相と多様性の高さを考えると納得できる。南米と中国からそれぞれ1名の参加、Per Alstrom は中国の研究所にも所属。
論文は出版されたがオープンアクセスではないとのことで、2025年 7-8 月限定で リンク先 から読めるとのこと。
DNA 研究が重要な推進力であったが、音声研究がそれに次ぐ重要要素を占めるようになった。アマチュアの貢献も大変大きい (注: DNA 研究の十分行われていない種も多いが音声で別種や別亜種と判断できる場合もあり、多くの場合後の DNA 研究で妥当性が確認されている。DNA 研究が十分に行われていない場合はフクロウ類のように音声も判定基準とすることが行われるようになってきた。現代の鳥類分類学の2本の柱と見てよい)。
Howard & Moore は 2014 年の改訂が最後で、相違点は近年の文献情報を反映できていないためと考えられ AviList では検討されなかった。
種概念は Mayr (1942) に始まる multi-dimensional Biological Species Concept を基準とする。特に 1990 年代に別の種概念もしばしば使われるようになったがその後 10-20 年の議論を経て鳥類では Mayr (1942) を引き継ぐ integrated Biological Species Concept が広く採用されるに至った。
セグロカモメ類を含む事例をどのように扱ったかなどいくつか紹介されている。
AviList は何と言っても誕生したばかりの初版であり、今後も改良や検討が続けられるとともに、一般からの意見も受け付ける体制を整え透明性の高いものを目指すとのこと。
しかし絶対的なリストを与えるものではなく、(根拠がある場合は特に) 他の扱いを提案しても構わない。リストに対する新しい仮説を提供する場合に雑誌編集者が特定のリストを強要することはそもそも生産的でないなど。フィールドガイドの著者も新しい仮説に注意を喚起するために異なる扱いをすることもあるだろう (注: 例えば種の分割や未記載亜種の提案など。この「新・野鳥の学名入門」でも積極的に紹介している)。これら仮説の提案は分類学の進歩のためにも歓迎される性質のものである。
また AviList が他の生物分類群の分類学統一の刺激となることも期待すると結んでいる (鳥の世界が世界の生物分類学統一を先行している。かっこいい!。もっとも植物学では史上初めて差別的な学名の変更も行われつつある。動物と植物では規約が異なるが今後相互に影響を与えてゆくだろうことが予想される)。
AviList 発表前はいろいろな心配事が議論されたが、おそらくそれらの要望も取り込む形で発表されることになり、旧 IOC リスト同様に透明性が確保され、一般利用者も改良に意見を出せる見通しで、旧 IOC リストより情報量も増えておおむね好評らしくリストそのものへの意見はほとんど出なくなった。
一方で限られたメンバーで限られた時間で作られたリストには検討不十分な部分も残っており、属学名や出所、属のタイプ種が正しいかなどの文献的検証は BirdForum で進められている。この過程を経て世界の鳥の学名の基本情報源である "The Key to Scientific Names" も多くの属名についてほぼ確実な文献由来や規約との整合性が整理される見通し。科名は次の段階に残されているが多少時間がかかるだろうとのこと (2025.7 段階)。学名字義も世界的な統一見解に収束されつつある段階と見てよいだろう。
音声による新タクソン候補がどのように提案されているか、例えば ID Unknown from Somalia (XC898341) ("Daallo Cisticola") (2024.4) を参照。未記載亜種または種と考えられたが既知の種の音声に合致するか検討中。
現在は "Daallo Cisticola" Cisticola tax.nov. の扱い。アマチュアの観察記録が大きく役立っている。
- この解説を編集するにあたり、半ば積読状態にあった過去の本などを改めて読む機会があった。どこかの種の備考に入れてもよい話ではあるが、日本野鳥の会関連でもあるのでここで触れておきたい。
「柳生博 鳥と語る」(ぺんぎん書房 2005)。柳生博氏 (1937-2022) は 2004-2019 年日本野鳥の会の会長を務められて、皆さんもごくご存じであろう。
NHK の「生き物地球紀行」の取材とナレーションを担当し、「左手にサイエンス! 右手にロマン!」がポリシーだったとのこと (p. 43)。
柳生氏の考えられていたサイエンスとロマンとは少し違うかも知れないが、この解説の [備考] も柳生氏のポリシーと同様、サイエンス中心で時にロマンと、小むづかしいことも怪しいことも、時には気に障るかも知れないことも書いてあるかも知れないが、寛容の精神で見ていただければよいと思う。
サイエンス (なぜそうなっているのか) を突き詰めて理解にたどり着いた驚きは「ロマン」としか言い表せない場合もあると感じる。#アマツバメの備考で紹介する渡り鳥の磁気定位はまさしくそうだった。
偶然の発見に基づく理詰めからはこの分子しか考えにくい、と最有力とされていて、渡り鳥の目に磁場情報が見えているニュースも追跡していたが、何事も疑い深い自分にはまだまだ実証には程遠いと感じていた。
しかし 2024 年夏に発表されたゲノム系統解析の結果は驚くべきもので、確かにこの分子を渡り鳥が役立てていることは疑いないように思える。そしてその進化を考えてみると...。渡り鳥のロマンと最新科学がこのように結びつくとは! 続きはアマツバメの備考をお読みいただきたい。
柳生氏も動物と話されていたのだと読み直して認識した (pp. 44-46)。本が出た当時は自分も同じようなことをやって鳥と遊んでいたので (#オオルリの備考参照)、それほど特殊とは思わず読み流してしまっていたらしいが、それ以降にハチクマの経験も経て柳生氏の言われていることを認識できるようになった模様。
会長職を引き受けるようになられた経緯も大変よくわかる気がする (p. 29)。しかしいながらにしてイヌワシがしばらく見られたとは何とぜいたくな。
日本鳥類目録改訂第8版の書物の出版物そのものではなく、掲載鳥類リスト (Excelファイル | 2024年10月8日 ver.1) のファイルより暫定的に作成したもの。英名は日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)」のファイルより。IOC 14.2 と英名が異なるもののみ IOC 英名を追記してある。
外来種は含まれていない。
記載者の後に * マークのあるものはアクセント記号などが省かれた、ウムラウトを2文字表記としたなどもとの綴りそのままではないもの。
"第7版学名より変更"、"IOC 14.2 分類または学名と相違あり" などが記されているものの学名解説は備考の項目も参照いただきたい。
第7版で種扱いではなかったものは "第7版学名より変更" は付いていない。
なお日本鳥類目録改訂第8版の配列順は IOC 13.2 準拠のため、高次分類概念や配列順は必ずしも最新のものに一致していない可能性がある。
IOC 14.2 との対比などは機械的に作成したもののため、対応関係などに不十分な点があればご容赦いただきたい。
例えば IOC 14.2 ではオオトラツグミはミナミトラツグミに含まれないが対応する学名が存在するので特に注記は付いていない。
本文解説は第7版をベースに作成したものなので、
第8版で検討種や外来種に移行したものはこのリンク集には含まれないが、第7版のみ掲載種に十分な解説の含まれる項目もあるのでぜひお見逃しなく。
記載者名の TeX (LaTeX) 表記:
Breme*: Br\`eme
Bruennich*: Br\"unnich
Guldenstadt*: G\"uldenst\"adt
Lonnberg*: L\"onnberg
Menetries*: M\'en\'etries
Mueller*: M\"uller
Palmen*: Palm\'en
- カモ目 Anseriformes カモ科 Anatidae -
-
#リュウキュウガモ
- 第8版学名: Dendrocygna javanica (Horsfield, 1821)
- 英名: Lesser Whistling Duck
-
#コクガン
- 第8版学名: Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
- 英名: Brant Goose
-
#アオガン
- 第8版学名: Branta ruficollis (Pallas, 1769)
- 英名: Red-breasted Goose
-
#カナダガン
- 第8版学名: Branta canadensis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Canada Goose
-
#シジュウカラガン
- 第8版学名: Branta hutchinsii (Richardson, 1832)
- 英名: Cackling Goose
-
#インドガン
- 第8版学名: Anser indicus (Latham, 1790)
- 英名: Bar-headed Goose
-
#ミカドガン
- 第8版学名: Anser canagicus (Sevastianov, 1802)
- 英名: Emperor Goose
-
#ハクガン
- 第8版学名: Anser caerulescens (Linnaeus, 1758)
- 英名: Snow Goose
-
#ハイイロガン
- 第8版学名: Anser anser (Linnaeus, 1758)
- 英名: Greylag Goose
-
#サカツラガン
- 第8版学名: Anser cygnoid (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更、IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Swan Goose
-
#ヒシクイ
- 第8版学名: Anser fabalis (Latham, 1787)
- 英名: Bean Goose (IOC 14.2: Taiga Bean Goose)
-
#マガン
- 第8版学名: Anser albifrons (Scopoli, 1769)
- 英名: Greater White-fronted Goose
-
#カリガネ
- 第8版学名: Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Lesser White-fronted Goose
-
#コブハクチョウ
- 第8版学名: Cygnus olor (Gmelin, 1789)
- 英名: Mute Swan
-
#ナキハクチョウ
- 第8版学名: Cygnus buccinator Richardson, 1831
- 英名: Trumpeter Swan
-
#コハクチョウ
- 第8版学名: Cygnus columbianus (Ord, 1815)
- 英名: Tundra Swan
-
#オオハクチョウ
- 第8版学名: Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Whooper Swan
-
#ツクシガモ
- 第8版学名: Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Shelduck
-
#アカツクシガモ
- 第8版学名: Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
- 英名: Ruddy Shelduck
-
#カンムリツクシガモ
- 第8版学名: Tadorna cristata (Kuroda, 1917)
- 英名: Crested Shelduck
-
#オシドリ
- 第8版学名: Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
- 英名: Mandarin Duck
-
#ナンキンオシ
- 第8版学名: Nettapus coromandelianus (Gmelin, 1789)
- 英名: Cotton Pygmy Goose
-
#トモエガモ
- 第8版学名: Sibirionetta formosa (Georgi, 1775) (第7版学名より変更)
- 英名: Baikal Teal
-
#シマアジ
- 第8版学名: Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Garganey
-
#ミカヅキシマアジ
- 第8版学名: Spatula discors (Linnaeus, 1766) (第7版学名より変更)
- 英名: Blue-winged Teal
-
#ハシビロガモ
- 第8版学名: Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Northern Shoveler
-
#オカヨシガモ
- 第8版学名: Mareca strepera (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Gadwall
-
#ヨシガモ
- 第8版学名: Mareca falcata (Georgi, 1775) (第7版学名より変更)
- 英名: Falcated Duck
-
#ヒドリガモ
- 第8版学名: Mareca penelope (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Eurasian Wigeon
-
#アメリカヒドリ
- 第8版学名: Mareca americana (Gmelin, 1789) (第7版学名より変更)
- 英名: American Wigeon
-
#アカノドカルガモ
- 第8版学名: Anas luzonica Fraser, 1839
- 英名: Philippine Duck
-
#カルガモ
- 第8版学名: Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866
- 英名: Eastern Spot-billed Duck
-
#マガモ
- 第8版学名: Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
- 英名: Mallard
-
#オナガガモ
- 第8版学名: Anas acuta Linnaeus, 1758
- 英名: Northern Pintail
-
#コガモ
- 第8版学名: Anas crecca Linnaeus, 1758
- 英名: Green-winged Teal (IOC 14.2: Eurasian Teal)
-
#アカハシハジロ
- 第8版学名: Netta rufina (Pallas, 1773)
- 英名: Red-crested Pochard
-
#オオホシハジロ
- 第8版学名: Aythya valisineria (Wilson, 1814)
- 英名: Canvasback
-
#アメリカホシハジロ
- 第8版学名: Aythya americana (Eyton, 1838)
- 英名: Redhead
-
#ホシハジロ
- 第8版学名: Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Pochard
-
#アカハジロ
- 第8版学名: Aythya baeri (Radde, 1863)
- 英名: Baer's Pochard
-
#メジロガモ
- 第8版学名: Aythya nyroca (Guldenstadt*, 1770)
- 英名: Ferruginous Duck
-
#クビワキンクロ
- 第8版学名: Aythya collaris (Donovan, 1809)
- 英名: Ring-necked Duck
-
#キンクロハジロ
- 第8版学名: Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
- 英名: Tufted Duck
-
#スズガモ
- 第8版学名: Aythya marila (Linnaeus, 1761)
- 英名: Greater Scaup
-
#コスズガモ
- 第8版学名: Aythya affinis (Eyton, 1838)
- 英名: Lesser Scaup
-
#コケワタガモ
- 第8版学名: Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
- 英名: Steller's Eider
-
#ケワタガモ
- 第8版学名: Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
- 英名: King Eider
-
#シノリガモ
- 第8版学名: Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Harlequin Duck
-
#アラナミキンクロ
- 第8版学名: Melanitta perspicillata (Linnaeus, 1758)
- 英名: Surf Scoter
-
#アメリカビロードキンクロ
- 第8版学名: Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850)
- 英名: White-winged Scoter
-
#ビロードキンクロ
- 第8版学名: Melanitta stejnegeri (Ridgway, 1887)
- 英名: Stejneger's Scoter
-
#クロガモ
- 第8版学名: Melanitta americana (Swainson, 1832)
- 英名: Black Scoter
-
#コオリガモ
- 第8版学名: Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Long-tailed Duck
-
#ヒメハジロ
- 第8版学名: Bucephala albeola (Linnaeus, 1758)
- 英名: Bufflehead
-
#ホオジロガモ
- 第8版学名: Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Goldeneye
-
#ミコアイサ
- 第8版学名: Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Smew
-
#オウギアイサ
- 第8版学名: Lophodytes cucullatus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Hooded Merganser
-
#カワアイサ
- 第8版学名: Mergus merganser Linnaeus, 1758
- 英名: Common Merganser
-
#ウミアイサ
- 第8版学名: Mergus serrator Linnaeus, 1758
- 英名: Red-breasted Merganser
-
#コウライアイサ
- 第8版学名: Mergus squamatus Gould, 1864
- 英名: Scaly-sided Merganser
- キジ目 Galliformes キジ科 Phasianidae -
-
#エゾライチョウ
- 第8版学名: Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
- 英名: Hazel Grouse
-
#ライチョウ
- 第8版学名: Lagopus muta (Montin, 1781)
- 英名: Rock Ptarmigan
-
#ヤマドリ
- 第8版学名: Syrmaticus soemmerringii (Temminck, 1830)
- 英名: Copper Pheasant
-
#キジ
- 第8版学名: Phasianus versicolor Vieillot, 1825 (第7版学名より変更)
- 英名: Green Pheasant
-
#ウズラ
- 第8版学名: Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849
- 英名: Japanese Quail
- ヨタカ目 Caprimulgiformes ヨタカ科 Caprimulgidae -
-
#ヨタカ
- 第8版学名: Caprimulgus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 (第7版学名より変更)
- 英名: Grey Nightjar
- アマツバメ目 Apodiformes アマツバメ科 Apodidae -
-
#ハリオアマツバメ
- 第8版学名: Hirundapus caudacutus (Latham, 1801)
- 英名: White-throated Needletail
-
#クロビタイハリオアマツバメ
- 第8版学名: Hirundapus cochinchinensis (Oustalet, 1878)
- 英名: Silver-backed Needletail
-
#アマツバメ
- 第8版学名: Apus pacificus (Latham, 1801)
- 英名: Pacific Swift
-
#ヒメアマツバメ
- 第8版学名: Apus nipalensis (Hodgson, 1837)
- 英名: House Swift
- ノガン目 Otidiformes ノガン科 Otididae -
-
#ノガン
- 第8版学名: Otis tarda Linnaeus, 1758
- 英名: Great Bustard
-
#ヒメノガン
- 第8版学名: Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
- 英名: Little Bustard
- カッコウ目 Cuculiformes カッコウ科 Cuculidae -
-
#バンケン
- 第8版学名: Centropus bengalensis (Gmelin, 1788)
- 英名: Lesser Coucal
-
#カンムリカッコウ
- 第8版学名: Clamator coromandus (Linnaeus, 1766)
- 英名: Chestnut-winged Cuckoo
-
#オニカッコウ
- 第8版学名: Eudynamys scolopaceus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Asian Koel
-
#キジカッコウ
- 第8版学名: Urodynamis taitensis (Sparrman, 1787)
- 英名: Pacific Long-tailed Cuckoo
-
#ヒメカッコウ
- 第8版学名: Cacomantis merulinus (Scopoli, 1786)
- 英名: Plaintive Cuckoo
-
#オオジュウイチ
- 第8版学名: Hierococcyx sparverioides (Vigors, 1832)
- 英名: Large Hawk-Cuckoo
-
#ジュウイチ
- 第8版学名: Hierococcyx hyperythrus (Gould, 1856)
- 英名: Northern Hawk-Cuckoo
-
#ホトトギス
- 第8版学名: Cuculus poliocephalus Latham, 1790
- 英名: Lesser Cuckoo
-
#セグロカッコウ
- 第8版学名: Cuculus micropterus Gould, 1838
- 英名: Indian Cuckoo
-
#ツツドリ
- 第8版学名: Cuculus optatus Gould, 1845
- 英名: Oriental Cuckoo
-
#カッコウ
- 第8版学名: Cuculus canorus Linnaeus, 1758
- 英名: Common Cuckoo
- サケイ目 Pterocliformes サケイ科 Pteroclidae -
-
#サケイ
- 第8版学名: Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)
- 英名: Pallas's Sandgrouse
- ハト目 Columbiformes ハト科 Columbidae -
-
#ヒメモリバト
- 第8版学名: Columba oenas Linnaeus, 1758
- 英名: Stock Dove
-
#カラスバト
- 第8版学名: Columba janthina Temminck, 1830
- 英名: Black Wood Pigeon
-
#オガサワラカラスバト
- 第8版学名: Columba versicolor Kittlitz, 1832
- 英名: Bonin Wood Pigeon
-
#リュウキュウカラスバト
- 第8版学名: Columba jouyi (Stejneger, 1887)
- 英名: Ryukyu Wood Pigeon
-
#キジバト
- 第8版学名: Streptopelia orientalis (Latham, 1790)
- 英名: Oriental Turtle Dove
-
#シラコバト
- 第8版学名: Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
- 英名: Eurasian Collared Dove
-
#ベニバト
- 第8版学名: Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804)
- 英名: Red Collared Dove
-
#キンバト
- 第8版学名: Chalcophaps indica (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Emerald Dove
-
#アオバト
- 第8版学名: Treron sieboldii (Temminck, 1835)
- 英名: White-bellied Green Pigeon
-
#ズアカアオバト
- 第8版学名: Treron formosae Swinhoe, 1863
- 英名: Whistling Green Pigeon (IOC 14.2: Taiwan Green Pigeon)
-
#クロアゴヒメアオバト
- 第8版学名: Ptilinopus leclancheri (Bonaparte, 1855)
- 英名: Black-chinned Fruit Dove
- ツル目 Gruiformes クイナ科 Rallidae -
-
#クイナ
- 第8版学名: Rallus indicus Blyth, 1849 (第7版学名より変更)
- 英名: Brown-cheeked Rail
-
#ウズラクイナ
- 第8版学名: Crex crex (Linnaeus, 1758)
- 英名: Corn Crake
-
#ミナミクイナ
- 第8版学名: Lewinia striata (Linnaeus, 1766) (第7版学名より変更)
- 英名: Slaty-breasted Rail
-
#ヤンバルクイナ
- 第8版学名: Hypotaenidia okinawae (Yamashina & Mano, 1981) (第7版学名より変更)
- 英名: Okinawa Rail
-
#バン
- 第8版学名: Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Moorhen
-
#オオバン
- 第8版学名: Fulica atra Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Coot
-
#シマクイナ
- 第8版学名: Coturnicops exquisitus (Swinhoe, 1873)
- 英名: Swinhoe's Rail
-
#ヒクイナ
- 第8版学名: Zapornia fusca (Linnaeus, 1766) (第7版学名より変更)
- 英名: Ruddy-breasted Crake
-
#コウライクイナ
- 第8版学名: Zapornia paykullii (Ljungh, 1813) (第7版学名より変更)
- 英名: Band-bellied Crake
-
#ヒメクイナ
- 第8版学名: Zapornia pusilla (Pallas, 1776) (第7版学名より変更)
- 英名: Baillon's Crake
-
#オオクイナ
- 第8版学名: Rallina eurizonoides (Lafresnaye, 1845)
- 英名: Slaty-legged Crake
-
#マミジロクイナ
- 第8版学名: Poliolimnas cinereus (Vieillot, 1819) (第7版学名より変更)
- 英名: White-browed Crake
-
#ツルクイナ
- 第8版学名: Gallicrex cinerea (Gmelin, 1789)
- 英名: Watercock
-
#シロハラクイナ
- 第8版学名: Amaurornis phoenicurus (Pennant, 1769)
- 英名: White-breasted Waterhen
- ツル目 Gruiformes ツル科 Gruidae -
-
#ソデグロヅル
- 第8版学名: Leucogeranus leucogeranus (Pallas, 1773) (第7版学名より変更)
- 英名: Siberian Crane
-
#カナダヅル
- 第8版学名: Antigone canadensis (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Sandhill Crane
-
#マナヅル
- 第8版学名: Antigone vipio (Pallas, 1811) (第7版学名より変更)
- 英名: White-naped Crane
-
#アネハヅル
- 第8版学名: Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Demoiselle Crane
-
#タンチョウ
- 第8版学名: Grus japonensis (Mueller*, 1776)
- 英名: Red-crowned Crane
-
#クロヅル
- 第8版学名: Grus grus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Crane
-
#ナベヅル
- 第8版学名: Grus monacha Temminck, 1835
- 英名: Hooded Crane
- カイツブリ目 Podicipediformes カイツブリ科 Podicipedidae -
-
#カイツブリ
- 第8版学名: Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
- 英名: Little Grebe
-
#アカエリカイツブリ
- 第8版学名: Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
- 英名: Red-necked Grebe
-
#カンムリカイツブリ
- 第8版学名: Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Great Crested Grebe
-
#ミミカイツブリ
- 第8版学名: Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Horned Grebe
-
#ハジロカイツブリ
- 第8版学名: Podiceps nigricollis Brehm, 1831
- 英名: Black-necked Grebe
- チドリ目 Charadriiformes ミフウズラ科 Turnicidae -
-
#ミフウズラ
- 第8版学名: Turnix suscitator (Gmelin, 1789)
- 英名: Barred Buttonquail
- チドリ目 Charadriiformes ミヤコドリ科 Haematopodidae -
-
#ミヤコドリ
- 第8版学名: Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Oystercatcher
- チドリ目 Charadriiformes セイタカシギ科 Recurvirostridae -
-
#セイタカシギ
- 第8版学名: Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black-winged Stilt
-
#オーストラリアセイタカシギ
- 第8版学名: Himantopus leucocephalus Gould, 1837
- 英名: Pied Stilt
-
#ソリハシセイタカシギ
- 第8版学名: Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
- 英名: Pied Avocet
- チドリ目 Charadriiformes チドリ科 Charadriidae -
-
#タゲリ
- 第8版学名: Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Northern Lapwing
-
#ケリ
- 第8版学名: Vanellus cinereus (Blyth, 1842)
- 英名: Grey-headed Lapwing
-
#ヨーロッパムナグロ
- 第8版学名: Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
- 英名: European Golden Plover
-
#ムナグロ
- 第8版学名: Pluvialis fulva (Gmelin, 1789)
- 英名: Pacific Golden Plover
-
#ダイゼン
- 第8版学名: Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
- 英名: Grey Plover
-
#ハジロコチドリ
- 第8版学名: Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
- 英名: Common Ringed Plover
-
#ミズカキチドリ
- 第8版学名: Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825
- 英名: Semipalmated Plover
-
#イカルチドリ
- 第8版学名: Charadrius placidus Gray & Gray, 1863
- 英名: Long-billed Plover
-
#コチドリ
- 第8版学名: Charadrius dubius Scopoli, 1786
- 英名: Little Ringed Plover
-
#シロチドリ
- 第8版学名: Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Kentish Plover
-
#オオメダイチドリ
- 第8版学名: Charadrius leschenaultii Lesson, 1826 (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Greater Sand Plover
-
#メダイチドリ
- 第8版学名: Charadrius mongolus Pallas, 1776 (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Siberian Sand Plover
-
#オオチドリ
- 第8版学名: Charadrius veredus Gould, 1848 (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Oriental Plover
-
#コバシチドリ
- 第8版学名: Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Eurasian Dotterel
- チドリ目 Charadriiformes タマシギ科 Rostratulidae -
-
#タマシギ
- 第8版学名: Rostratula benghalensis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Greater Painted-snipe
- チドリ目 Charadriiformes レンカク科 Jacanidae -
-
#レンカク
- 第8版学名: Hydrophasianus chirurgus (Scopoli, 1786)
- 英名: Pheasant-tailed Jacana
- チドリ目 Charadriiformes シギ科 Scolopacidae -
-
#ハリモモチュウシャク
- 第8版学名: Numenius tahitiensis (Gmelin, 1789)
- 英名: Bristle-thighed Curlew
-
#チュウシャクシギ
- 第8版学名: Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Whimbrel (IOC 14.2: Eurasian Whimbrel)
-
#コシャクシギ
- 第8版学名: Numenius minutus Gould, 1841
- 英名: Little Curlew
-
#ホウロクシギ
- 第8版学名: Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766)
- 英名: Far Eastern Curlew
-
#シロハラチュウシャクシギ
- 第8版学名: Numenius tenuirostris Vieillot, 1817
- 英名: Slender-billed Curlew
-
#ダイシャクシギ
- 第8版学名: Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Curlew
-
#オオソリハシシギ
- 第8版学名: Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
- 英名: Bar-tailed Godwit
-
#オグロシギ
- 第8版学名: Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black-tailed Godwit
-
#アメリカオグロシギ
- 第8版学名: Limosa haemastica (Linnaeus, 1758)
- 英名: Hudsonian Godwit
-
#キョウジョシギ
- 第8版学名: Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
- 英名: Ruddy Turnstone
-
#オバシギ
- 第8版学名: Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821)
- 英名: Great Knot
-
#コオバシギ
- 第8版学名: Calidris canutus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Red Knot
-
#エリマキシギ
- 第8版学名: Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Ruff
-
#キリアイ
- 第8版学名: Calidris falcinellus (Pontoppidan, 1763) (第7版学名より変更)
- 英名: Broad-billed Sandpiper
-
#ウズラシギ
- 第8版学名: Calidris acuminata (Horsfield, 1821)
- 英名: Sharp-tailed Sandpiper
-
#アシナガシギ
- 第8版学名: Calidris himantopus (Bonaparte, 1826)
- 英名: Stilt Sandpiper
-
#サルハマシギ
- 第8版学名: Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
- 英名: Curlew Sandpiper
-
#オジロトウネン
- 第8版学名: Calidris temminckii (Leisler, 1812)
- 英名: Temminck's Stint
-
#ヒバリシギ
- 第8版学名: Calidris subminuta (Middendorff, 1853)
- 英名: Long-toed Stint
-
#ヘラシギ
- 第8版学名: Calidris pygmaea (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Spoon-billed Sandpiper
-
#トウネン
- 第8版学名: Calidris ruficollis (Pallas, 1776)
- 英名: Red-necked Stint
-
#ミユビシギ
- 第8版学名: Calidris alba (Pallas, 1764)
- 英名: Sanderling
-
#ハマシギ
- 第8版学名: Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
- 英名: Dunlin
-
#チシマシギ
- 第8版学名: Calidris ptilocnemis (Coues, 1873)
- 英名: Rock Sandpiper
-
#ヒメウズラシギ
- 第8版学名: Calidris bairdii (Coues, 1861)
- 英名: Baird's Sandpiper
-
#ヨーロッパトウネン
- 第8版学名: Calidris minuta (Leisler, 1812)
- 英名: Little Stint
-
#コシジロウズラシギ
- 第8版学名: Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)
- 英名: White-rumped Sandpiper
-
#コモンシギ
- 第8版学名: Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) (第7版学名より変更)
- 英名: Buff-breasted Sandpiper
-
#アメリカウズラシギ
- 第8版学名: Calidris melanotos (Vieillot, 1819)
- 英名: Pectoral Sandpiper
-
#ヒメハマシギ
- 第8版学名: Calidris mauri (Cabanis, 1857)
- 英名: Western Sandpiper
-
#シベリアオオハシシギ
- 第8版学名: Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)
- 英名: Asian Dowitcher
-
#オオハシシギ
- 第8版学名: Limnodromus scolopaceus (Say, 1822)
- 英名: Long-billed Dowitcher
-
#アメリカオオハシシギ
- 第8版学名: Limnodromus griseus (Gmelin, 1789)
- 英名: Short-billed Dowitcher
-
#ヤマシギ
- 第8版学名: Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Woodcock
-
#アマミヤマシギ
- 第8版学名: Scolopax mira Hartert, 1916
- 英名: Amami Woodcock
-
#コシギ
- 第8版学名: Lymnocryptes minimus (Bruennich*, 1764)
- 英名: Jack Snipe
-
#アオシギ
- 第8版学名: Gallinago solitaria Hodgson, 1831
- 英名: Solitary Snipe
-
#オオジシギ
- 第8版学名: Gallinago hardwickii (Gray, 1831)
- 英名: Latham's Snipe
-
#ハリオシギ
- 第8版学名: Gallinago stenura (Bonaparte, 1831)
- 英名: Pin-tailed Snipe
-
#チュウジシギ
- 第8版学名: Gallinago megala Swinhoe, 1861
- 英名: Swinhoe's Snipe
-
#タシギ
- 第8版学名: Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Snipe
-
#ソリハシシギ
- 第8版学名: Xenus cinereus (Guldenstadt*, 1775)
- 英名: Terek Sandpiper
-
#アメリカヒレアシシギ
- 第8版学名: Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819)
- 英名: Wilson's Phalarope
-
#アカエリヒレアシシギ
- 第8版学名: Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Red-necked Phalarope
-
#ハイイロヒレアシシギ
- 第8版学名: Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)
- 英名: Red Phalarope
-
#イソシギ
- 第8版学名: Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Sandpiper
-
#アメリカイソシギ
- 第8版学名: Actitis macularius (Linnaeus, 1766)
- 英名: Spotted Sandpiper
-
#クサシギ
- 第8版学名: Tringa ochropus Linnaeus, 1758
- 英名: Green Sandpiper
-
#メリケンキアシシギ
- 第8版学名: Tringa incana (Gmelin, 1789) (第7版学名より変更)
- 英名: Wandering Tattler
-
#キアシシギ
- 第8版学名: Tringa brevipes (Vieillot, 1816) (第7版学名より変更)
- 英名: Grey-tailed Tattler
-
#コキアシシギ
- 第8版学名: Tringa flavipes (Gmelin, 1789)
- 英名: Lesser Yellowlegs
-
#アカアシシギ
- 第8版学名: Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Redshank
-
#コアオアシシギ
- 第8版学名: Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
- 英名: Marsh Sandpiper
-
#タカブシギ
- 第8版学名: Tringa glareola Linnaeus, 1758
- 英名: Wood Sandpiper
-
#ツルシギ
- 第8版学名: Tringa erythropus (Pallas, 1764)
- 英名: Spotted Redshank
-
#アオアシシギ
- 第8版学名: Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
- 英名: Common Greenshank
-
#カラフトアオアシシギ
- 第8版学名: Tringa guttifer (Nordmann, 1835)
- 英名: Nordmann's Greenshank
-
#オオキアシシギ
- 第8版学名: Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)
- 英名: Greater Yellowlegs
- チドリ目 Charadriiformes ツバメチドリ科 Glareolidae -
-
#ツバメチドリ
- 第8版学名: Glareola maldivarum Forster, 1795
- 英名: Oriental Pratincole
- チドリ目 Charadriiformes カモメ科 Laridae -
-
#クロアジサシ
- 第8版学名: Anous stolidus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Brown Noddy
-
#ヒメクロアジサシ
- 第8版学名: Anous minutus Boie, 1844
- 英名: Black Noddy
-
#ハイイロアジサシ
- 第8版学名: Anous ceruleus (Bennett, 1840) (第7版学名より変更)
- 英名: Blue Noddy
-
#シロアジサシ
- 第8版学名: Gygis alba (Sparrman, 1786)
- 英名: White Tern
-
#ミツユビカモメ
- 第8版学名: Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black-legged Kittiwake
-
#アカアシミツユビカモメ
- 第8版学名: Rissa brevirostris (Bruch, 1855)
- 英名: Red-legged Kittiwake
-
#ゾウゲカモメ
- 第8版学名: Pagophila eburnea (Phipps, 1774)
- 英名: Ivory Gull
-
#クビワカモメ
- 第8版学名: Xema sabini (Sabine, 1819)
- 英名: Sabine's Gull
-
#ハシボソカモメ
- 第8版学名: Chroicocephalus genei (Breme*, 1839) (第7版学名より変更)
- 英名: Slender-billed Gull
-
#ボナパルトカモメ
- 第8版学名: Chroicocephalus philadelphia (Ord, 1815) (第7版学名より変更)
- 英名: Bonaparte's Gull
-
#チャガシラカモメ
- 第8版学名: Chroicocephalus brunnicephalus (Jerdon, 1840) (第7版学名より変更)
- 英名: Brown-headed Gull
-
#ユリカモメ
- 第8版学名: Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) (第7版学名より変更)
- 英名: Black-headed Gull
-
#ズグロカモメ
- 第8版学名: Saundersilarus saundersi (Swinhoe, 1871) (第7版学名より変更)
- 英名: Saunders's Gull
-
#ヒメカモメ
- 第8版学名: Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) (第7版学名より変更)
- 英名: Little Gull
-
#ヒメクビワカモメ
- 第8版学名: Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1824)
- 英名: Ross's Gull
-
#ワライカモメ
- 第8版学名: Leucophaeus atricilla (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Laughing Gull
-
#アメリカズグロカモメ
- 第8版学名: Leucophaeus pipixcan (Wagler, 1831) (第7版学名より変更)
- 英名: Franklin's Gull
-
#ゴビズキンカモメ
- 第8版学名: Ichthyaetus relictus (Lonnberg*, 1931) (第7版学名より変更)
- 英名: Relict Gull
-
#オオズグロカモメ
- 第8版学名: Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas, 1773) (第7版学名より変更)
- 英名: Pallas's Gull
-
#ウミネコ
- 第8版学名: Larus crassirostris Vieillot, 1818
- 英名: Black-tailed Gull
-
#カモメ
- 第8版学名: Larus canus Linnaeus, 1758
- 英名: Common Gull
-
#ワシカモメ
- 第8版学名: Larus glaucescens Naumann, 1840
- 英名: Glaucous-winged Gull
-
#シロカモメ
- 第8版学名: Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
- 英名: Glaucous Gull
-
#アイスランドカモメ
- 第8版学名: Larus glaucoides Meyer, 1822
- 英名: Iceland Gull
-
#セグロカモメ
- 第8版学名: Larus vegae Palmen*, 1887 (第7版学名より変更)
- 英名: Vega Gull
-
#オオセグロカモメ
- 第8版学名: Larus schistisagus Stejneger, 1884
- 英名: Slaty-backed Gull
-
#ニシセグロカモメ
- 第8版学名: Larus fuscus Linnaeus, 1758
- 英名: Lesser Black-backed Gull
-
#ハシブトアジサシ
- 第8版学名: Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
- 英名: Gull-billed Tern
-
#オニアジサシ
- 第8版学名: Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) (第7版学名より変更)
- 英名: Caspian Tern
-
#オオアジサシ
- 第8版学名: Thalasseus bergii (Lichtenstein, 1823) (第7版学名より変更)
- 英名: Greater Crested Tern
-
#ベンガルアジサシ
- 第8版学名: Thalasseus bengalensis (Lesson, 1831) (第7版学名より変更)
- 英名: Lesser Crested Tern
-
#コアジサシ
- 第8版学名: Sternula albifrons (Pallas, 1764) (第7版学名より変更)
- 英名: Little Tern
-
#アメリカコアジサシ
- 第8版学名: Sternula antillarum Lesson, 1847
- 英名: Least Tern
-
#コシジロアジサシ
- 第8版学名: Onychoprion aleuticus (Baird, 1869) (第7版学名より変更)
- 英名: Aleutian Tern
-
#ナンヨウマミジロアジサシ
- 第8版学名: Onychoprion lunatus (Peale, 1849) (第7版学名より変更)
- 英名: Spectacled Tern
-
#マミジロアジサシ
- 第8版学名: Onychoprion anaethetus (Scopoli, 1786) (第7版学名より変更)
- 英名: Bridled Tern
-
#セグロアジサシ
- 第8版学名: Onychoprion fuscatus (Linnaeus, 1766) (第7版学名より変更)
- 英名: Sooty Tern
-
#ベニアジサシ
- 第8版学名: Sterna dougallii Montagu, 1813
- 英名: Roseate Tern
-
#エリグロアジサシ
- 第8版学名: Sterna sumatrana Raffles, 1822
- 英名: Black-naped Tern
-
#アジサシ
- 第8版学名: Sterna hirundo Linnaeus, 1758
- 英名: Common Tern
-
#キョクアジサシ
- 第8版学名: Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763
- 英名: Arctic Tern
-
#クロハラアジサシ
- 第8版学名: Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)
- 英名: Whiskered Tern
-
#ハジロクロハラアジサシ
- 第8版学名: Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)
- 英名: White-winged Tern
-
#ハシグロクロハラアジサシ
- 第8版学名: Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black Tern
- チドリ目 Charadriiformes トウゾクカモメ科 Stercorariidae -
-
#オオトウゾクカモメ
- 第8版学名: Stercorarius maccormicki Saunders, 1893
- 英名: South Polar Skua
-
#トウゾクカモメ
- 第8版学名: Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
- 英名: Pomarine Jaeger
-
#クロトウゾクカモメ
- 第8版学名: Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Parasitic Jaeger
-
#シロハラトウゾクカモメ
- 第8版学名: Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
- 英名: Long-tailed Jaeger
- チドリ目 Charadriiformes ウミスズメ科 Alcidae -
-
#ヒメウミスズメ
- 第8版学名: Alle alle (Linnaeus, 1758)
- 英名: Little Auk
-
#ハシブトウミガラス
- 第8版学名: Uria lomvia (Linnaeus, 1758)
- 英名: Thick-billed Murre
-
#ウミガラス
- 第8版学名: Uria aalge (Pontoppidan, 1763)
- 英名: Common Murre
-
#ウミバト
- 第8版学名: Cepphus columba Pallas, 1811
- 英名: Pigeon Guillemot
-
#ケイマフリ
- 第8版学名: Cepphus carbo Pallas, 1811
- 英名: Spectacled Guillemot
-
#マダラウミスズメ
- 第8版学名: Brachyramphus perdix (Pallas, 1811)
- 英名: Long-billed Murrelet
-
#ウミスズメ
- 第8版学名: Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789)
- 英名: Ancient Murrelet
-
#カンムリウミスズメ
- 第8版学名: Synthliboramphus wumizusume (Temminck, 1836)
- 英名: Japanese Murrelet
-
#アメリカウミスズメ
- 第8版学名: Ptychoramphus aleuticus (Pallas, 1811)
- 英名: Cassin's Auklet
-
#ウミオウム
- 第8版学名: Aethia psittacula (Pallas, 1769)
- 英名: Parakeet Auklet
-
#コウミスズメ
- 第8版学名: Aethia pusilla (Pallas, 1811)
- 英名: Least Auklet
-
#シラヒゲウミスズメ
- 第8版学名: Aethia pygmaea (Gmelin, 1789)
- 英名: Whiskered Auklet
-
#エトロフウミスズメ
- 第8版学名: Aethia cristatella (Pallas, 1769)
- 英名: Crested Auklet
-
#ウトウ
- 第8版学名: Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811)
- 英名: Rhinoceros Auklet
-
#ツノメドリ
- 第8版学名: Fratercula corniculata (Naumann, 1821)
- 英名: Horned Puffin
-
#エトピリカ
- 第8版学名: Fratercula cirrhata (Pallas, 1769)
- 英名: Tufted Puffin
- ネッタイチョウ目 Phaethontiformes ネッタイチョウ科 Phaethontidae -
-
#アカオネッタイチョウ
- 第8版学名: Phaethon rubricauda Boddaert, 1783
- 英名: Red-tailed Tropicbird
-
#シラオネッタイチョウ
- 第8版学名: Phaethon lepturus Daudin, 1802
- 英名: White-tailed Tropicbird
- アビ目 Gaviiformes アビ科 Gaviidae -
-
#アビ
- 第8版学名: Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
- 英名: Red-throated Loon
-
#オオハム
- 第8版学名: Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black-throated Loon
-
#シロエリオオハム
- 第8版学名: Gavia pacifica (Lawrence, 1858)
- 英名: Pacific Loon
-
#ハシグロアビ
- 第8版学名: Gavia immer (Bruennich*, 1764)
- 英名: Common Loon
-
#ハシジロアビ
- 第8版学名: Gavia adamsii (Gray, 1859)
- 英名: Yellow-billed Loon
- ミズナギドリ目 Procellariiformes アシナガウミツバメ科 Oceanitidae -
-
#アシナガウミツバメ
- 第8版学名: Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820)
- 英名: Wilson's Storm Petrel
- ミズナギドリ目 Procellariiformes アホウドリ科 Diomedeidae -
-
#コアホウドリ
- 第8版学名: Phoebastria immutabilis (Rothschild, 1893)
- 英名: Laysan Albatross
-
#クロアシアホウドリ
- 第8版学名: Phoebastria nigripes (Audubon, 1839)
- 英名: Black-footed Albatross
-
#アホウドリ
- 第8版学名: Phoebastria albatrus (Pallas, 1769)
- 英名: Short-tailed Albatross
- ミズナギドリ目 Procellariiformes ウミツバメ科 Hydrobatidae -
-
#ハイイロウミツバメ
- 第8版学名: Hydrobates furcatus (Gmelin, 1789) (第7版学名より変更)
- 英名: Fork-tailed Storm Petrel
-
#ヒメクロウミツバメ
- 第8版学名: Hydrobates monorhis (Swinhoe, 1867) (第7版学名より変更)
- 英名: Swinhoe's Storm Petrel
-
#クロウミツバメ
- 第8版学名: Hydrobates matsudairae (Kuroda, 1922) (第7版学名より変更)
- 英名: Matsudaira's Storm Petrel
-
#コシジロウミツバメ
- 第8版学名: Hydrobates leucorhous (Vieillot, 1818) (第7版学名より変更)
- 英名: Leach's Storm Petrel
-
#クロコシジロウミツバメ
- 第8版学名: Hydrobates castro (Harcourt, 1851) (第7版学名より変更)
- 英名: Band-rumped Storm Petrel
-
#オーストンウミツバメ
- 第8版学名: Hydrobates tristrami (Salvin, 1896) (第7版学名より変更)
- 英名: Tristram's Storm Petrel
- ミズナギドリ目 Procellariiformes ミズナギドリ科 Procellariidae -
-
#フルマカモメ
- 第8版学名: Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
- 英名: Northern Fulmar
-
#ハジロミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma solandri (Gould, 1844)
- 英名: Providence Petrel
-
#オオシロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma externa (Salvin, 1875)
- 英名: Juan Fernandez Petrel
-
#カワリシロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma neglecta (Schlegel, 1863)
- 英名: Kermadec Petrel
-
#ハワイシロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma sandwichensis (Ridgway, 1884) (第7版学名より変更)
- 英名: Hawaiian Petrel
-
#マダラシロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma inexpectata (Forster, 1844)
- 英名: Mottled Petrel
-
#クビワオオシロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma cervicalis (Salvin, 1891)
- 英名: White-necked Petrel
-
#ハグロシロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma nigripennis (Rothschild, 1893)
- 英名: Black-winged Petrel
-
#シロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma hypoleuca (Salvin, 1888)
- 英名: Bonin Petrel
-
#ヒメシロハラミズナギドリ
- 第8版学名: Pterodroma longirostris (Stejneger, 1893)
- 英名: Stejneger's Petrel
-
#オオミズナギドリ
- 第8版学名: Calonectris leucomelas (Temminck, 1836)
- 英名: Streaked Shearwater
-
#オナガミズナギドリ
- 第8版学名: Ardenna pacifica (Gmelin, 1789) (第7版学名より変更)
- 英名: Wedge-tailed Shearwater
-
#ミナミオナガミズナギドリ
- 第8版学名: Ardenna bulleri (Salvin, 1888) (第7版学名より変更)
- 英名: Buller's Shearwater
-
#ハイイロミズナギドリ
- 第8版学名: Ardenna grisea (Gmelin, 1789) (第7版学名より変更)
- 英名: Sooty Shearwater
-
#ハシボソミズナギドリ
- 第8版学名: Ardenna tenuirostris (Temminck, 1836) (第7版学名より変更)
- 英名: Short-tailed Shearwater
-
#シロハラアカアシミズナギドリ
- 第8版学名: Ardenna creatopus (Coues, 1864) (第7版学名より変更)
- 英名: Pink-footed Shearwater
-
#アカアシミズナギドリ
- 第8版学名: Ardenna carneipes (Gould, 1844) (第7版学名より変更)
- 英名: Flesh-footed Shearwater
-
#コミズナギドリ
- 第8版学名: Puffinus nativitatis Streets, 1877
- 英名: Christmas Shearwater
-
#オガサワラヒメミズナギドリ
- 第8版学名: Puffinus bryani Pyle, Welch & Fleischer, 2011
- 英名: Bryan's Shearwater
-
#ハワイセグロミズナギドリ
- 第8版学名: Puffinus newelli Henshaw, 1900
- 英名: Newell's Shearwater
-
#オガサワラミズナギドリ
- 第8版学名: Puffinus bannermani Mathews & Iredale, 1915 (第7版学名より変更)
- 英名: Bannerman's Shearwater
-
#アナドリ
- 第8版学名: Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828)
- 英名: Bulwer's Petrel
- コウノトリ目 Ciconiiformes コウノトリ科 Ciconiidae -
-
#ナベコウ
- 第8版学名: Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black Stork
-
#コウノトリ
- 第8版学名: Ciconia boyciana Swinhoe, 1873
- 英名: Oriental Stork
- カツオドリ目 Suliformes グンカンドリ科 Fregatidae -
-
#オオグンカンドリ
- 第8版学名: Fregata minor (Gmelin, 1789)
- 英名: Great Frigatebird
-
#コグンカンドリ
- 第8版学名: Fregata ariel (Gray, 1845)
- 英名: Lesser Frigatebird
- カツオドリ目 Suliformes カツオドリ科 Sulidae -
-
#アオツラカツオドリ
- 第8版学名: Sula dactylatra Lesson, 1831
- 英名: Masked Booby
-
#アカアシカツオドリ
- 第8版学名: Sula sula (Linnaeus, 1766)
- 英名: Red-footed Booby
-
#カツオドリ
- 第8版学名: Sula leucogaster (Boddaert, 1783) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Brown Booby
- 備考: IOC 14.2 ではさらに2種に分離
- カツオドリ目 Suliformes ウ科 Phalacrocoracidae -
-
#チシマウガラス
- 第8版学名: Urile urile (Gmelin, 1789) (第7版学名より変更)
- 英名: Red-faced Cormorant
-
#ヒメウ
- 第8版学名: Urile pelagicus (Pallas, 1811) (第7版学名より変更)
- 英名: Pelagic Cormorant
-
#ウミウ
- 第8版学名: Phalacrocorax capillatus (Temminck & Schlegel, 1849)
- 英名: Japanese Cormorant
-
#カワウ
- 第8版学名: Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
- 英名: Great Cormorant
- ペリカン目 Pelecaniformes トキ科 Threskiornithidae -
-
#クロトキ
- 第8版学名: Threskiornis melanocephalus (Latham, 1790)
- 英名: Black-headed Ibis
-
#トキ
- 第8版学名: Nipponia nippon (Temminck, 1835)
- 英名: Crested Ibis
-
#ブロンズトキ
- 第8版学名: Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
- 英名: Glossy Ibis
-
#ヘラサギ
- 第8版学名: Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Spoonbill
-
#クロツラヘラサギ
- 第8版学名: Platalea minor Temminck & Schlegel, 1849
- 英名: Black-faced Spoonbill
- ペリカン目 Pelecaniformes サギ科 Ardeidae -
-
#サンカノゴイ
- 第8版学名: Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Bittern
-
#ヨシゴイ
- 第8版学名: Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Yellow Bittern
-
#オオヨシゴイ
- 第8版学名: Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Von Schrenck's Bittern
-
#リュウキュウヨシゴイ
- 第8版学名: Ixobrychus cinnamomeus (Gmelin, 1789) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Cinnamon Bittern
-
#タカサゴクロサギ
- 第8版学名: Ixobrychus flavicollis (Latham, 1790) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Black Bittern
-
#ミゾゴイ
- 第8版学名: Gorsachius goisagi (Temminck, 1836)
- 英名: Japanese Night Heron
-
#ズグロミゾゴイ
- 第8版学名: Gorsachius melanolophus (Raffles, 1822)
- 英名: Malayan Night Heron
-
#ゴイサギ
- 第8版学名: Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black-crowned Night Heron
-
#ハシブトゴイ
- 第8版学名: Nycticorax caledonicus (Gmelin, 1789)
- 英名: Nankeen Night Heron
-
#ササゴイ
- 第8版学名: Butorides striata (Linnaeus, 1758)
- 英名: Striated Heron
-
#アカガシラサギ
- 第8版学名: Ardeola bacchus (Bonaparte, 1855)
- 英名: Chinese Pond Heron
-
#アマサギ
- 第8版学名: Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Cattle Egret (IOC 14.2: Eastern Cattle Egret )
-
#アオサギ
- 第8版学名: Ardea cinerea Linnaeus, 1758
- 英名: Grey Heron
-
#ムラサキサギ
- 第8版学名: Ardea purpurea Linnaeus, 1766
- 英名: Purple Heron
-
#ダイサギ
- 第8版学名: Ardea alba Linnaeus, 1758
- 英名: Great Egret
-
#チュウサギ
- 第8版学名: Ardea intermedia Wagler, 1829 (第7版学名より変更)
- 英名: Intermediate Egret (IOC 14.2: Medium Egret )
-
#コサギ
- 第8版学名: Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
- 英名: Little Egret
-
#クロサギ
- 第8版学名: Egretta sacra (Gmelin, 1789)
- 英名: Pacific Reef Heron
-
#カラシラサギ
- 第8版学名: Egretta eulophotes (Swinhoe, 1860)
- 英名: Chinese Egret
- ペリカン目 Pelecaniformes ペリカン科 Pelecanidae -
-
#モモイロペリカン
- 第8版学名: Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758
- 英名: Great White Pelican
-
#ホシバシペリカン
- 第8版学名: Pelecanus philippensis Gmelin, 1789
- 英名: Spot-billed Pelican
-
#ハイイロペリカン
- 第8版学名: Pelecanus crispus Bruch, 1832
- 英名: Dalmatian Pelican
- タカ目 Accipitriformes ミサゴ科 Pandionidae -
-
#ミサゴ
- 第8版学名: Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Osprey
- タカ目 Accipitriformes タカ科 Accipitridae -
-
#ハチクマ
- 第8版学名: Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)
- 英名: Crested Honey Buzzard
-
#クロハゲワシ
- 第8版学名: Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
- 英名: Cinereous Vulture
-
#カンムリワシ
- 第8版学名: Spilornis cheela (Latham, 1790)
- 英名: Crested Serpent Eagle
-
#クマタカ
- 第8版学名: Nisaetus nipalensis Hodgson, 1836
- 英名: Mountain Hawk-Eagle
-
#カラフトワシ
- 第8版学名: Clanga clanga (Pallas, 1811) (第7版学名より変更)
- 英名: Greater Spotted Eagle
-
#カタシロワシ
- 第8版学名: Aquila heliaca Savigny, 1809
- 英名: Eastern Imperial Eagle
-
#イヌワシ
- 第8版学名: Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
- 英名: Golden Eagle
-
#アカハラダカ
- 第8版学名: Accipiter soloensis (Horsfield, 1821) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Chinese Sparrowhawk
-
#ツミ
- 第8版学名: Accipiter gularis (Temminck & Schlegel, 1845) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Japanese Sparrowhawk
-
#ハイタカ
- 第8版学名: Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Sparrowhawk
-
#オオタカ
- 第8版学名: Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Eurasian Goshawk
-
#チュウヒ
- 第8版学名: Circus spilonotus Kaup, 1847
- 英名: Eastern Marsh Harrier
-
#ハイイロチュウヒ
- 第8版学名: Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
- 英名: Hen Harrier
-
#アメリカハイイロチュウヒ
- 第8版学名: Circus hudsonius (Linnaeus, 1766)
- 英名: Northern Harrier
-
#マダラチュウヒ
- 第8版学名: Circus melanoleucos (Pennant, 1769)
- 英名: Pied Harrier
-
#トビ
- 第8版学名: Milvus migrans (Boddaert, 1783)
- 英名: Black Kite
-
#オオワシ
- 第8版学名: Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811)
- 英名: Steller's Sea Eagle
-
#オジロワシ
- 第8版学名: Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
- 英名: White-tailed Eagle
-
#ハクトウワシ
- 第8版学名: Haliaeetus leucocephalus (Linnaeus, 1766)
- 英名: Bald Eagle
-
#サシバ
- 第8版学名: Butastur indicus (Gmelin, 1788)
- 英名: Grey-faced Buzzard
-
#ケアシノスリ
- 第8版学名: Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
- 英名: Rough-legged Buzzard
-
#オオノスリ
- 第8版学名: Buteo hemilasius Temminck & Schlegel, 1844
- 英名: Upland Buzzard
-
#ノスリ
- 第8版学名: Buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 (第7版学名より変更)
- 英名: Eastern Buzzard
- フクロウ目 Strigiformes フクロウ科 Strigidae -
-
#アオバズク
- 第8版学名: Ninox japonica (Temminck & Schlegel, 1845) (第7版学名より変更)
- 英名: Northern Boobook
-
#キンメフクロウ
- 第8版学名: Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Boreal Owl
-
#コノハズク
- 第8版学名: Otus sunia (Hodgson, 1836)
- 英名: Oriental Scops Owl
-
#リュウキュウコノハズク
- 第8版学名: Otus elegans (Cassin, 1852)
- 英名: Ryukyu Scops Owl
-
#オオコノハズク
- 第8版学名: Otus semitorques Temminck & Schlegel, 1844 (第7版学名より変更)
- 英名: Japanese Scops Owl
-
#トラフズク
- 第8版学名: Asio otus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Long-eared Owl
-
#コミミズク
- 第8版学名: Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
- 英名: Short-eared Owl
-
#シロフクロウ
- 第8版学名: Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Snowy Owl
-
#ワシミミズク
- 第8版学名: Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Eagle-Owl
-
#シマフクロウ
- 第8版学名: Ketupa blakistoni (Seebohm, 1884)
- 英名: Blakiston's Fish Owl
-
#フクロウ
- 第8版学名: Strix uralensis Pallas, 1771
- 英名: Ural Owl
- サイチョウ目 Bucerotiformes ヤツガシラ科 Upupidae -
-
#ヤツガシラ
- 第8版学名: Upupa epops Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Hoopoe
- ブッポウソウ目 Coraciiformes ブッポウソウ科 Coraciidae -
-
#ブッポウソウ
- 第8版学名: Eurystomus orientalis (Linnaeus, 1766)
- 英名: Oriental Dollarbird
- ブッポウソウ目 Coraciiformes カワセミ科 Alcedinidae -
-
#アカショウビン
- 第8版学名: Halcyon coromanda (Latham, 1790)
- 英名: Ruddy Kingfisher
-
#ヤマショウビン
- 第8版学名: Halcyon pileata (Boddaert, 1783)
- 英名: Black-capped Kingfisher
-
#ナンヨウショウビン
- 第8版学名: Todiramphus chloris (Boddaert, 1783)
- 英名: Collared Kingfisher
-
#ミヤコショウビン
- 第8版学名: Todiramphus miyakoensis (Kuroda, 1919) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Miyako Island Kingfisher (IOC 14.2: 種や亜種として認めず名称なし)
-
#カワセミ
- 第8版学名: Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Kingfisher
-
#ミツユビカワセミ
- 第8版学名: Ceyx erithaca (Linnaeus, 1758)
- 英名: Oriental Dwarf Kingfisher (IOC 14.2: Black-backed Dwarf Kingfisher)
-
#ヤマセミ
- 第8版学名: Megaceryle lugubris (Temminck, 1834)
- 英名: Crested Kingfisher
- ブッポウソウ目 Coraciiformes ハチクイ科 Meropidae -
-
#ルリオハチクイ
- 第8版学名: Merops philippinus Linnaeus, 1767
- 英名: Blue-tailed Bee-eater
-
#ハチクイ
- 第8版学名: Merops ornatus Latham, 1801
- 英名: Rainbow Bee-eater
- キツツキ目 Piciformes キツツキ科 Picidae -
-
#アリスイ
- 第8版学名: Jynx torquilla Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Wryneck
-
#コゲラ
- 第8版学名: Yungipicus kizuki (Temminck, 1835) (第7版学名より変更)
- 英名: Japanese Pygmy Woodpecker
-
#ミユビゲラ
- 第8版学名: Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Three-toed Woodpecker
-
#コアカゲラ
- 第8版学名: Dryobates minor (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Lesser Spotted Woodpecker
-
#チャバラアカゲラ
- 第8版学名: Dendrocopos hyperythrus (Vigors, 1831)
- 英名: Rufous-bellied Woodpecker
-
#アカゲラ
- 第8版学名: Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
- 英名: Great Spotted Woodpecker
-
#ノグチゲラ
- 第8版学名: Dendrocopos noguchii (Seebohm, 1887) (第7版学名より変更)
- 英名: Okinawa Woodpecker
-
#オオアカゲラ
- 第8版学名: Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
- 英名: White-backed Woodpecker
-
#キタタキ
- 第8版学名: Dryocopus javensis (Horsfield, 1821)
- 英名: White-bellied Woodpecker
-
#クマゲラ
- 第8版学名: Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
- 英名: Black Woodpecker
-
#アオゲラ
- 第8版学名: Picus awokera Temminck, 1836
- 英名: Japanese Green Woodpecker
-
#ヤマゲラ
- 第8版学名: Picus canus Gmelin, 1788
- 英名: Grey-headed Woodpecker
- ハヤブサ目 Falconiformes ハヤブサ科 Falconidae -
-
#ヒメチョウゲンボウ
- 第8版学名: Falco naumanni Fleischer, 1818
- 英名: Lesser Kestrel
-
#チョウゲンボウ
- 第8版学名: Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
- 英名: Common Kestrel
-
#アカアシチョウゲンボウ
- 第8版学名: Falco amurensis Radde, 1863
- 英名: Amur Falcon
-
#コチョウゲンボウ
- 第8版学名: Falco columbarius Linnaeus, 1758
- 英名: Merlin
-
#チゴハヤブサ
- 第8版学名: Falco subbuteo Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Hobby
-
#シロハヤブサ
- 第8版学名: Falco rusticolus Linnaeus, 1758
- 英名: Gyrfalcon
-
#ハヤブサ
- 第8版学名: Falco peregrinus Tunstall, 1771
- 英名: Peregrine Falcon
- スズメ目 Passeriformes ヤイロチョウ科 Pittidae -
-
#ズグロヤイロチョウ
- 第8版学名: Pitta sordida (Mueller*, 1776)
- 英名: Hooded Pitta (IOC 14.2: Western Hooded Pitta)
-
#ヤイロチョウ
- 第8版学名: Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1850
- 英名: Fairy Pitta
- スズメ目 Passeriformes モリツバメ科 Artamidae -
-
#モリツバメ
- 第8版学名: Artamus leucorynchus (Linnaeus, 1771)
- 英名: White-breasted Woodswallow
- スズメ目 Passeriformes サンショウクイ科 Campephagidae -
-
#サンショウクイ
- 第8版学名: Pericrocotus divaricatus (Raffles, 1822)
- 英名: Ashy Minivet
-
#リュウキュウサンショウクイ
- 第8版学名: Pericrocotus tegimae Stejneger, 1887
- 英名: Ryukyu Minivet
-
#アサクラサンショウクイ
- 第8版学名: Lalage melaschistos (Hodgson, 1836) (第7版学名より変更)
- 英名: Black-winged Cuckooshrike
- スズメ目 Passeriformes コウライウグイス科 Oriolidae -
-
#コウライウグイス
- 第8版学名: Oriolus chinensis Linnaeus, 1766
- 英名: Black-naped Oriole
- スズメ目 Passeriformes オウチュウ科 Dicruridae -
-
#カンムリオウチュウ
- 第8版学名: Dicrurus hottentottus (Linnaeus, 1766)
- 英名: Hair-crested Drongo
-
#ハイイロオウチュウ
- 第8版学名: Dicrurus leucophaeus Vieillot, 1817
- 英名: Ashy Drongo
-
#オウチュウ
- 第8版学名: Dicrurus macrocercus Vieillot, 1817
- 英名: Black Drongo
- スズメ目 Passeriformes カササギヒタキ科 Monarchidae -
-
#クロエリヒタキ
- 第8版学名: Hypothymis azurea (Boddaert, 1783)
- 英名: Black-naped Monarch
-
#サンコウチョウ
- 第8版学名: Terpsiphone atrocaudata (Eyton, 1839)
- 英名: Black Paradise Flycatcher
- スズメ目 Passeriformes モズ科 Laniidae -
-
#オオカラモズ
- 第8版学名: Lanius sphenocercus Cabanis, 1873
- 英名: Chinese Grey Shrike
-
#オオモズ
- 第8版学名: Lanius borealis Vieillot, 1808 (第7版学名より変更)
- 英名: Northern Shrike
-
#チゴモズ
- 第8版学名: Lanius tigrinus Drapiez, 1828
- 英名: Tiger Shrike
-
#セアカモズ
- 第8版学名: Lanius collurio Linnaeus, 1758
- 英名: Red-backed Shrike
-
#アカモズ
- 第8版学名: Lanius cristatus Linnaeus, 1758
- 英名: Brown Shrike
-
#モズ
- 第8版学名: Lanius bucephalus Temminck & Schlegel, 1845
- 英名: Bull-headed Shrike
-
#タカサゴモズ
- 第8版学名: Lanius schach Linnaeus, 1758
- 英名: Long-tailed Shrike
- スズメ目 Passeriformes カラス科 Corvidae -
-
#カケス
- 第8版学名: Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Jay
-
#ルリカケス
- 第8版学名: Garrulus lidthi Bonaparte, 1850
- 英名: Lidth's Jay
-
#オナガ
- 第8版学名: Cyanopica cyanus (Pallas, 1776)
- 英名: Azure-winged Magpie
-
#カササギ
- 第8版学名: Pica serica Gould, 1845 (第7版学名より変更)
- 英名: Oriental Magpie
-
#ホシガラス
- 第8版学名: Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
- 英名: Spotted Nutcracker (IOC 14.2: Northern Nutcracker)
-
#ニシコクマルガラス
- 第8版学名: Corvus monedula Linnaeus, 1758 (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Western Jackdaw
-
#コクマルガラス
- 第8版学名: Corvus dauuricus Pallas, 1776 (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Daurian Jackdaw
-
#ミヤマガラス
- 第8版学名: Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
- 英名: Rook
-
#ハシボソガラス
- 第8版学名: Corvus corone Linnaeus, 1758
- 英名: Carrion Crow
-
#ハシブトガラス
- 第8版学名: Corvus macrorhynchos Wagler, 1827
- 英名: Large-billed Crow
-
#ワタリガラス
- 第8版学名: Corvus corax Linnaeus, 1758
- 英名: Northern Raven
- スズメ目 Passeriformes レンジャク科 Bombycillidae -
-
#キレンジャク
- 第8版学名: Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Bohemian Waxwing
-
#ヒレンジャク
- 第8版学名: Bombycilla japonica (Siebold, 1824)
- 英名: Japanese Waxwing
- スズメ目 Passeriformes シジュウカラ科 Paridae -
-
#ヒガラ
- 第8版学名: Periparus ater (Linnaeus, 1758)
- 英名: Coal Tit
-
#キバラガラ
- 第8版学名: Pardaliparus venustulus (Swinhoe, 1870) (第7版学名より変更)
- 英名: Yellow-bellied Tit
-
#ヤマガラ
- 第8版学名: Sittiparus varius (Temminck & Schlegel, 1845) (第7版学名より変更)
- 英名: Varied Tit
-
#オリイヤマガラ
- 第8版学名: Sittiparus olivaceus Kuroda, 1923
- 英名: Iriomote Tit
-
#ハシブトガラ
- 第8版学名: Poecile palustris (Linnaeus, 1758)
- 英名: Marsh Tit
-
#コガラ
- 第8版学名: Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)
- 英名: Willow Tit
-
#ルリガラ
- 第8版学名: Cyanistes cyanus (Pallas, 1770)
- 英名: Azure Tit
-
#シジュウカラ
- 第8版学名: Parus cinereus Vieillot, 1818 (第7版学名より変更)
- 英名: Cinereous Tit
- スズメ目 Passeriformes ツリスガラ科 Remizidae -
-
#ツリスガラ
- 第8版学名: Remiz consobrinus (Swinhoe, 1870) (第7版学名より変更)
- 英名: Chinese Penduline Tit
- スズメ目 Passeriformes ヒゲガラ科 Panuridae -
-
#ヒゲガラ
- 第8版学名: Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Bearded Reedling
- スズメ目 Passeriformes ヒバリ科 Alaudidae -
-
#ヒバリ
- 第8版学名: Alauda arvensis Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Skylark
-
#ハマヒバリ
- 第8版学名: Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
- 英名: Horned Lark
-
#ヒメコウテンシ
- 第8版学名: Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
- 英名: Greater Short-toed Lark
-
#クビワコウテンシ
- 第8版学名: Melanocorypha bimaculata (Menetries*, 1832)
- 英名: Bimaculated Lark
-
#コウテンシ
- 第8版学名: Melanocorypha mongolica (Pallas, 1776)
- 英名: Mongolian Lark
-
#コヒバリ
- 第8版学名: Alaudala cheleensis Swinhoe, 1871 (第7版学名より変更)
- 英名: Asian Short-toed Lark
- スズメ目 Passeriformes ヒヨドリ科 Pycnonotidae -
-
#ヒヨドリ
- 第8版学名: Hypsipetes amaurotis (Temminck, 1830)
- 英名: Brown-eared Bulbul
-
#シロガシラ
- 第8版学名: Pycnonotus sinensis (Gmelin, 1789)
- 英名: Light-vented Bulbul
- スズメ目 Passeriformes ツバメ科 Hirundinidae -
-
#ショウドウツバメ
- 第8版学名: Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
- 英名: Sand Martin
-
#タイワンショウドウツバメ
- 第8版学名: Riparia paludicola (Vieillot, 1817)
- 英名: Brown-throated Martin
-
#リュウキュウツバメ
- 第8版学名: Hirundo tahitica Gmelin, 1789
- 英名: Pacific Swallow (IOC 14.2: Tahiti Swallow)
-
#ツバメ
- 第8版学名: Hirundo rustica Linnaeus, 1758
- 英名: Barn Swallow
-
#イワツバメ
- 第8版学名: Delichon dasypus (Bonaparte, 1850)
- 英名: Asian House Martin
-
#コシアカツバメ
- 第8版学名: Cecropis daurica (Laxmann, 1769) (第7版学名より変更)
- 英名: Red-rumped Swallow (IOC 14.2: Eastern Red-rumped Swallow)
- スズメ目 Passeriformes ウグイス科 Cettiidae -
-
#ウグイス
- 第8版学名: Horornis diphone (Kittlitz, 1830) (第7版学名より変更)
- 英名: Japanese Bush Warbler
-
#チョウセンウグイス
- 第8版学名: Horornis canturians (Swinhoe, 1860)
- 英名: Manchurian Bush Warbler
-
#ヤブサメ
- 第8版学名: Urosphena squameiceps (Swinhoe, 1863)
- 英名: Asian Stubtail
- スズメ目 Passeriformes エナガ科 Aegithalidae -
-
#エナガ
- 第8版学名: Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Long-tailed Tit
- スズメ目 Passeriformes ムシクイ科 Phylloscopidae -
-
#モリムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1792)
- 英名: Wood Warbler
-
#キマユムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)
- 英名: Yellow-browed Warbler
-
#シセンムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus yunnanensis La Touche, 1922
- 英名: Chinese Leaf Warbler
-
#カラフトムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)
- 英名: Pallas's Leaf Warbler
-
#カラフトムジセッカ
- 第8版学名: Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863)
- 英名: Radde's Warbler
-
#ムジセッカ
- 第8版学名: Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842)
- 英名: Dusky Warbler
-
#キタヤナギムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Willow Warbler
-
#チフチャフ
- 第8版学名: Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
- 英名: Common Chiffchaff
-
#センダイムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus coronatus (Temminck & Schlegel, 1847)
- 英名: Eastern Crowned Leaf Warbler (IOC 14.2: Eastern Crowned Warbler)
-
#イイジマムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus ijimae (Stejneger, 1892)
- 英名: Ijima's Leaf Warbler
-
#ヤナギムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus plumbeitarsus Swinhoe, 1861
- 英名: Two-barred Warbler
-
#エゾムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus borealoides Portenko, 1950
- 英名: Sakhalin Leaf Warbler
-
#アムールムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus tenellipes Swinhoe, 1860
- 英名: Pale-legged Leaf Warbler
-
#メボソムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus xanthodryas (Swinhoe, 1863)
- 英名: Japanese Leaf Warbler
-
#オオムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus examinandus Stresemann, 1913
- 英名: Kamchatka Leaf Warbler
-
#コムシクイ
- 第8版学名: Phylloscopus borealis (Blasius, 1858)
- 英名: Arctic Warbler
- スズメ目 Passeriformes ヨシキリ科 Acrocephalidae -
-
#オオヨシキリ
- 第8版学名: Acrocephalus orientalis (Temminck & Schlegel, 1847)
- 英名: Oriental Reed Warbler
-
#コヨシキリ
- 第8版学名: Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe, 1860
- 英名: Black-browed Reed Warbler
-
#スゲヨシキリ
- 第8版学名: Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Sedge Warbler
-
#マンシュウイナダヨシキリ
- 第8版学名: Acrocephalus tangorum La Touche, 1912
- 英名: Manchurian Reed Warbler
-
#ヤブヨシキリ
- 第8版学名: Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
- 英名: Blyth's Reed Warbler
-
#ハシブトオオヨシキリ
- 第8版学名: Arundinax aedon (Pallas, 1776) (第7版学名より変更)
- 英名: Thick-billed Warbler
-
#ヒメウタイムシクイ
- 第8版学名: Iduna caligata (Lichtenstein, 1823)
- 英名: Booted Warbler
- スズメ目 Passeriformes センニュウ科 Locustellidae -
-
#エゾセンニュウ
- 第8版学名: Locustella amnicola Stepanyan, 1972 (第7版学名より変更、IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Sakhalin Grasshopper Warbler
-
#オオセッカ
- 第8版学名: Locustella pryeri (Seebohm, 1884) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Marsh Grassbird
-
#シベリアセンニュウ
- 第8版学名: Locustella certhiola (Pallas, 1811) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Pallas's Grasshopper Warbler
-
#シマセンニュウ
- 第8版学名: Locustella ochotensis (Middendorff, 1853) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Middendorff's Grasshopper Warbler
-
#ウチヤマセンニュウ
- 第8版学名: Locustella pleskei Taczanowski, 1890 (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Styan's Grasshopper Warbler
-
#マキノセンニュウ
- 第8版学名: Locustella lanceolata (Temminck, 1840)
- 英名: Lanceolated Warbler
- スズメ目 Passeriformes セッカ科 Cisticolidae -
-
#セッカ
- 第8版学名: Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
- 英名: Zitting Cisticola
- スズメ目 Passeriformes ズグロムシクイ科 Sylviidae -
-
#コノドジロムシクイ
- 第8版学名: Curruca curruca (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Lesser Whitethroat
- スズメ目 Passeriformes メジロ科 Zosteropidae -
-
#メグロ
- 第8版学名: Apalopteron familiare (Kittlitz, 1830)
- 英名: Bonin White-eye
-
#チョウセンメジロ
- 第8版学名: Zosterops erythropleurus Swinhoe, 1863
- 英名: Chestnut-flanked White-eye
-
#メジロ
- 第8版学名: Zosterops japonicus Temminck & Schlegel, 1845
- 英名: Warbling White-eye
- スズメ目 Passeriformes キクイタダキ科 Regulidae -
-
#キクイタダキ
- 第8版学名: Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Goldcrest
- スズメ目 Passeriformes ミソサザイ科 Troglodytidae -
-
#ミソサザイ
- 第8版学名: Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Wren
- スズメ目 Passeriformes ゴジュウカラ科 Sittidae -
-
#ゴジュウカラ
- 第8版学名: Sitta europaea Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Nuthatch
- スズメ目 Passeriformes キバシリ科 Certhiidae -
-
#キバシリ
- 第8版学名: Certhia familiaris Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Treecreeper
- スズメ目 Passeriformes ムクドリ科 Sturnidae -
-
#ギンムクドリ
- 第8版学名: Spodiopsar sericeus (Gmelin, 1789)
- 英名: Red-billed Starling
-
#ムクドリ
- 第8版学名: Spodiopsar cineraceus (Temminck, 1835)
- 英名: White-cheeked Starling
-
#シベリアムクドリ
- 第8版学名: Agropsar sturninus (Pallas, 1776)
- 英名: Daurian Starling
-
#コムクドリ
- 第8版学名: Agropsar philippensis (Pennant, 1781)
- 英名: Chestnut-cheeked Starling
-
#カラムクドリ
- 第8版学名: Sturnia sinensis (Gmelin, 1788)
- 英名: White-shouldered Starling
-
#バライロムクドリ
- 第8版学名: Pastor roseus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Rosy Starling
-
#ホシムクドリ
- 第8版学名: Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
- 英名: Common Starling
- スズメ目 Passeriformes ツグミ科 Turdidae -
-
#ハイイロチャツグミ
- 第8版学名: Catharus minimus (Lafresnaye, 1848)
- 英名: Grey-cheeked Thrush
-
#トラツグミ
- 第8版学名: Zoothera aurea (Holandre, 1825) (第7版学名より変更)
- 英名: White's Thrush
-
#ミナミトラツグミ
- 第8版学名: Zoothera dauma (Latham, 1790)
- 英名: Scaly Thrush
-
#オガサワラガビチョウ
- 第8版学名: Cichlopasser terrestris (Kittlitz, 1830) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Bonin Thrush
-
#マミジロ
- 第8版学名: Geokichla sibirica (Pallas, 1776) (第7版学名より変更)
- 英名: Siberian Thrush
-
#オレンジジツグミ
- 第8版学名: Geokichla citrina (Latham, 1790)
- 英名: Orange-headed Thrush
-
#ウタツグミ
- 第8版学名: Turdus philomelos Brehm, 1831
- 英名: Song Thrush
-
#ヤドリギツグミ
- 第8版学名: Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
- 英名: Mistle Thrush
-
#クロウタドリ
- 第8版学名: Turdus mandarinus Bonaparte, 1850
- 英名: Chinese Blackbird
-
#ワキアカツグミ
- 第8版学名: Turdus iliacus Linnaeus, 1758
- 英名: Redwing
-
#クロツグミ
- 第8版学名: Turdus cardis Temminck, 1831
- 英名: Japanese Thrush
-
#カラアカハラ
- 第8版学名: Turdus hortulorum Sclater, 1863
- 英名: Grey-backed Thrush
-
#マミチャジナイ
- 第8版学名: Turdus obscurus Gmelin, 1789
- 英名: Eyebrowed Thrush
-
#シロハラ
- 第8版学名: Turdus pallidus Gmelin, 1789
- 英名: Pale Thrush
-
#アカハラ
- 第8版学名: Turdus chrysolaus Temminck, 1832
- 英名: Brown-headed Thrush
-
#アカコッコ
- 第8版学名: Turdus celaenops Stejneger, 1887
- 英名: Izu Thrush
-
#ノハラツグミ
- 第8版学名: Turdus pilaris Linnaeus, 1758
- 英名: Fieldfare
-
#ノドグロツグミ
- 第8版学名: Turdus atrogularis Jarocki, 1819
- 英名: Black-throated Thrush
-
#ツグミ
- 第8版学名: Turdus eunomus Temminck, 1831
- 英名: Dusky Thrush
-
#ハチジョウツグミ
- 第8版学名: Turdus naumanni Temminck, 1820
- 英名: Naumann's Thrush
- スズメ目 Passeriformes ヒタキ科 Muscicapidae -
-
#エゾビタキ
- 第8版学名: Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861)
- 英名: Grey-streaked Flycatcher
-
#サメビタキ
- 第8版学名: Muscicapa sibirica Gmelin, 1789
- 英名: Dark-sided Flycatcher
-
#ミヤマヒタキ
- 第8版学名: Muscicapa ferruginea (Hodgson, 1845)
- 英名: Ferruginous Flycatcher
-
#チャムネサメビタキ
- 第8版学名: Muscicapa muttui (Layard, 1854)
- 英名: Brown-breasted Flycatcher
-
#コサメビタキ
- 第8版学名: Muscicapa dauurica Pallas, 1811
- 英名: Asian Brown Flycatcher
-
#ムナフヒタキ
- 第8版学名: Muscicapa striata (Pallas, 1764)
- 英名: Spotted Flycatcher
-
#オオルリ
- 第8版学名: Cyanoptila cyanomelana (Temminck, 1829)
- 英名: Blue-and-white Flycatcher
-
#ロクショウヒタキ
- 第8版学名: Eumyias thalassinus (Swainson, 1838)
- 英名: Verditer Flycatcher
-
#ヨーロッパコマドリ
- 第8版学名: Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
- 英名: European Robin
-
#オガワコマドリ
- 第8版学名: Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
- 英名: Bluethroat
-
#ノゴマ
- 第8版学名: Calliope calliope (Pallas, 1776) (第7版学名より変更)
- 英名: Siberian Rubythroat
-
#コルリ
- 第8版学名: Larvivora cyane (Pallas, 1776) (第7版学名より変更)
- 英名: Siberian Blue Robin
-
#コマドリ
- 第8版学名: Larvivora akahige (Temminck, 1835) (第7版学名より変更)
- 英名: Japanese Robin
-
#アカヒゲ
- 第8版学名: Larvivora komadori (Temminck, 1835) (第7版学名より変更)
- 英名: Amami Robin (IOC 14.2: Ryukyu Robin)
-
#ホントウアカヒゲ
- 第8版学名: Larvivora namiyei (Stejneger, 1887)
- 英名: Okinawa Robin
-
#シマゴマ
- 第8版学名: Larvivora sibilans Swinhoe, 1863 (第7版学名より変更)
- 英名: Rufous-tailed Robin
-
#マミジロキビタキ
- 第8版学名: Ficedula zanthopygia (Hay, 1845)
- 英名: Yellow-rumped Flycatcher
-
#キビタキ
- 第8版学名: Ficedula narcissina (Temminck, 1836)
- 英名: Narcissus Flycatcher
-
#リュウキュウキビタキ
- 第8版学名: Ficedula owstoni (Bangs, 1901)
- 英名: Ryukyu Flycatcher
-
#ムギマキ
- 第8版学名: Ficedula mugimaki (Temminck, 1836)
- 英名: Mugimaki Flycatcher
-
#ニシオジロビタキ
- 第8版学名: Ficedula parva (Bechstein, 1792)
- 英名: Red-breasted Flycatcher
-
#オジロビタキ
- 第8版学名: Ficedula albicilla (Pallas, 1811)
- 英名: Taiga Flycatcher
-
#マダラヒタキ
- 第8版学名: Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
- 英名: European Pied Flycatcher
-
#ルリビタキ
- 第8版学名: Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)
- 英名: Red-flanked Bluetail
-
#セアカジョウビタキ
- 第8版学名: Phoenicurus erythronotus (Eversmann, 1841)
- 英名: Eversmann's Redstart
-
#カワビタキ
- 第8版学名: Phoenicurus fuliginosus Vigors, 1831
- 英名: Plumbeous Water Redstart
-
#クロジョウビタキ
- 第8版学名: Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774)
- 英名: Black Redstart
-
#シロビタイジョウビタキ
- 第8版学名: Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Redstart
-
#ジョウビタキ
- 第8版学名: Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776)
- 英名: Daurian Redstart
-
#ヒメイソヒヨ
- 第8版学名: Monticola gularis (Swinhoe, 1863)
- 英名: White-throated Rock Thrush
-
#コシジロイソヒヨドリ
- 第8版学名: Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
- 英名: Common Rock Thrush
-
#イソヒヨドリ
- 第8版学名: Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
- 英名: Blue Rock Thrush
-
#ヤマザキヒタキ
- 第8版学名: Saxicola ferreus Gray & Gray, 1847
- 英名: Grey Bush Chat
-
#マミジロノビタキ
- 第8版学名: Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
- 英名: Whinchat
-
#クロノビタキ
- 第8版学名: Saxicola caprata (Linnaeus, 1766)
- 英名: Pied Bush Chat
-
#ノビタキ
- 第8版学名: Saxicola stejnegeri (Parrot, 1908) (第7版学名より変更)
- 英名: Amur Stonechat
-
#ハシグロヒタキ
- 第8版学名: Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
- 英名: Northern Wheatear
-
#イナバヒタキ
- 第8版学名: Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)
- 英名: Isabelline Wheatear
-
#サバクヒタキ
- 第8版学名: Oenanthe deserti (Temminck, 1825)
- 英名: Desert Wheatear
-
#セグロサバクヒタキ
- 第8版学名: Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770)
- 英名: Pied Wheatear
- スズメ目 Passeriformes カワガラス科 Cinclidae -
-
#カワガラス
- 第8版学名: Cinclus pallasii Temminck, 1820
- 英名: Brown Dipper
- スズメ目 Passeriformes スズメ科 Passeridae -
-
#ニュウナイスズメ
- 第8版学名: Passer cinnamomeus (Gould, 1836) (第7版学名より変更)
- 英名: Russet Sparrow
-
#スズメ
- 第8版学名: Passer montanus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Tree Sparrow
-
#イエスズメ
- 第8版学名: Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
- 英名: House Sparrow
- スズメ目 Passeriformes イワヒバリ科 Prunellidae -
-
#イワヒバリ
- 第8版学名: Prunella collaris (Scopoli, 1769)
- 英名: Alpine Accentor
-
#ヤマヒバリ
- 第8版学名: Prunella montanella (Pallas, 1776)
- 英名: Siberian Accentor
-
#カヤクグリ
- 第8版学名: Prunella rubida (Temminck & Schlegel, 1845)
- 英名: Japanese Accentor
- スズメ目 Passeriformes セキレイ科 Motacillidae -
-
#イワミセキレイ
- 第8版学名: Dendronanthus indicus (Gmelin, 1789)
- 英名: Forest Wagtail
-
#ニシツメナガセキレイ
- 第8版学名: Motacilla flava Linnaeus, 1758
- 英名: Western Yellow Wagtail
-
#ツメナガセキレイ
- 第8版学名: Motacilla tschutschensis Gmelin, 1789 (第7版学名より変更)
- 英名: Eastern Yellow Wagtail
-
#キガシラセキレイ
- 第8版学名: Motacilla citreola Pallas, 1776
- 英名: Citrine Wagtail
-
#キセキレイ
- 第8版学名: Motacilla cinerea Tunstall, 1771
- 英名: Grey Wagtail
-
#ハクセキレイ
- 第8版学名: Motacilla alba Linnaeus, 1758
- 英名: White Wagtail
-
#セグロセキレイ
- 第8版学名: Motacilla grandis Sharpe, 1885
- 英名: Japanese Wagtail
-
#マミジロタヒバリ
- 第8版学名: Anthus richardi Vieillot, 1818
- 英名: Richard's Pipit
-
#コマミジロタヒバリ
- 第8版学名: Anthus godlewskii (Taczanowski, 1876)
- 英名: Blyth's Pipit
-
#マキバタヒバリ
- 第8版学名: Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Meadow Pipit
-
#ヨーロッパビンズイ
- 第8版学名: Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Tree Pipit
-
#ビンズイ
- 第8版学名: Anthus hodgsoni Richmond, 1907
- 英名: Olive-backed Pipit
-
#セジロタヒバリ
- 第8版学名: Anthus gustavi Swinhoe, 1863
- 英名: Pechora Pipit
-
#ウスベニタヒバリ
- 第8版学名: Anthus roseatus Blyth, 1847
- 英名: Rosy Pipit
-
#ムネアカタヒバリ
- 第8版学名: Anthus cervinus (Pallas, 1811)
- 英名: Red-throated Pipit
-
#タヒバリ
- 第8版学名: Anthus rubescens (Tunstall, 1771) (IOC 14.2 分類または学名と相違あり)
- 英名: Buff-bellied Pipit (IOC 14.2: Siberian Pipit)
- スズメ目 Passeriformes アトリ科 Fringillidae -
-
#ズアオアトリ
- 第8版学名: Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
- 英名: Eurasian Chaffinch
-
#アトリ
- 第8版学名: Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
- 英名: Brambling
-
#シメ
- 第8版学名: Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
- 英名: Hawfinch
-
#コイカル
- 第8版学名: Eophona migratoria Hartert, 1903
- 英名: Chinese Grosbeak
-
#イカル
- 第8版学名: Eophona personata (Temminck & Schlegel, 1845)
- 英名: Japanese Grosbeak
-
#ギンザンマシコ
- 第8版学名: Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
- 英名: Pine Grosbeak
-
#ウソ
- 第8版学名: Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
- 英名: Eurasian Bullfinch
-
#ハギマシコ
- 第8版学名: Leucosticte arctoa (Pallas, 1811)
- 英名: Asian Rosy Finch
-
#アカマシコ
- 第8版学名: Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
- 英名: Common Rosefinch
-
#オガサワラマシコ
- 第8版学名: Carpodacus ferreorostris (Vigors, 1829) (第7版学名より変更)
- 英名: Bonin Grosbeak
-
#ベニマシコ
- 第8版学名: Carpodacus sibiricus (Pallas, 1773) (第7版学名より変更)
- 英名: Siberian Long-tailed Rosefinch
-
#オオマシコ
- 第8版学名: Carpodacus roseus (Pallas, 1776)
- 英名: Pallas's Rosefinch
-
#カワラヒワ
- 第8版学名: Chloris sinica (Linnaeus, 1766)
- 英名: Oriental Greenfinch
-
#オガサワラカワラヒワ
- 第8版学名: Chloris kittlitzi (Seebohm, 1890)
- 英名: Bonin Greenfinch
-
#ベニヒワ
- 第8版学名: Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Common Redpoll (IOC 14.2: Redpoll)
-
#イスカ
- 第8版学名: Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
- 英名: Red Crossbill
-
#ナキイスカ
- 第8版学名: Loxia leucoptera Gmelin, 1789
- 英名: Two-barred Crossbill
-
#マヒワ
- 第8版学名: Spinus spinus (Linnaeus, 1758) (第7版学名より変更)
- 英名: Eurasian Siskin
- スズメ目 Passeriformes ツメナガホオジロ科 Calcariidae -
-
#ツメナガホオジロ
- 第8版学名: Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Lapland Longspur
-
#ユキホオジロ
- 第8版学名: Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
- 英名: Snow Bunting
- スズメ目 Passeriformes ホオジロ科 Emberizidae -
-
#キアオジ
- 第8版学名: Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
- 英名: Yellowhammer
-
#シラガホオジロ
- 第8版学名: Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771
- 英名: Pine Bunting
-
#ホオジロ
- 第8版学名: Emberiza cioides Brandt, 1843
- 英名: Meadow Bunting
-
#イワバホオジロ
- 第8版学名: Emberiza buchanani Blyth, 1845
- 英名: Grey-necked Bunting
-
#ズアオホオジロ
- 第8版学名: Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
- 英名: Ortolan Bunting
-
#シロハラホオジロ
- 第8版学名: Emberiza tristrami Swinhoe, 1870
- 英名: Tristram's Bunting
-
#ホオアカ
- 第8版学名: Emberiza fucata Pallas, 1776
- 英名: Chestnut-eared Bunting
-
#コホオアカ
- 第8版学名: Emberiza pusilla Pallas, 1776
- 英名: Little Bunting
-
#キマユホオジロ
- 第8版学名: Emberiza chrysophrys Pallas, 1776
- 英名: Yellow-browed Bunting
-
#カシラダカ
- 第8版学名: Emberiza rustica Pallas, 1776
- 英名: Rustic Bunting
-
#ミヤマホオジロ
- 第8版学名: Emberiza elegans Temminck, 1836
- 英名: Yellow-throated Bunting
-
#シマアオジ
- 第8版学名: Emberiza aureola Pallas, 1773
- 英名: Yellow-breasted Bunting
-
#シマノジコ
- 第8版学名: Emberiza rutila Pallas, 1776
- 英名: Chestnut Bunting
-
#ズグロチャキンチョウ
- 第8版学名: Emberiza melanocephala Scopoli, 1769
- 英名: Black-headed Bunting
-
#チャキンチョウ
- 第8版学名: Emberiza bruniceps Brandt, 1841
- 英名: Red-headed Bunting
-
#ノジコ
- 第8版学名: Emberiza sulphurata Temminck & Schlegel, 1848
- 英名: Yellow Bunting
-
#シベリアアオジ
- 第8版学名: Emberiza spodocephala Pallas, 1776
- 英名: Black-faced Bunting
-
#アオジ
- 第8版学名: Emberiza personata Temminck, 1836
- 英名: Masked Bunting
-
#クロジ
- 第8版学名: Emberiza variabilis Temminck, 1836
- 英名: Grey Bunting
-
#シベリアジュリン
- 第8版学名: Emberiza pallasi (Cabanis, 1851)
- 英名: Pallas's Reed Bunting
-
#コジュリン
- 第8版学名: Emberiza yessoensis (Swinhoe, 1874)
- 英名: Ochre-rumped Bunting
-
#オオジュリン
- 第8版学名: Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
- 英名: Common Reed Bunting
- スズメ目 Passeriformes ゴマフスズメ科 Passerellidae -
-
#ゴマフスズメ
- 第8版学名: Passerella iliaca (Merrem, 1786)
- 英名: Fox Sparrow (IOC 14.2: Red Fox Sparrow)
-
#ミヤマシトド
- 第8版学名: Zonotrichia leucophrys (Forster, 1772)
- 英名: White-crowned Sparrow
-
#キガシラシトド
- 第8版学名: Zonotrichia atricapilla (Gmelin, 1789)
- 英名: Golden-crowned Sparrow
-
#サバンナシトド
- 第8版学名: Passerculus sandwichensis (Gmelin, 1789)
- 英名: Savannah Sparrow
-
#ウタスズメ
- 第8版学名: Melospiza melodia (Wilson, 1810)
- 英名: Song Sparrow
- スズメ目 Passeriformes アメリカムシクイ科 Parulidae -
-
#カオグロアメリカムシクイ
- 第8版学名: Geothlypis trichas (Linnaeus, 1766)
- 英名: Common Yellowthroat
-
#キヅタアメリカムシクイ
- 第8版学名: Setophaga coronata (Linnaeus, 1766)
- 英名: Yellow-rumped Warbler (IOC 14.2: Myrtle Warbler)
| 略号 | 説明 |
| m | 男性名詞 形容詞の男性形 |
| f | 女性名詞 形容詞の女性形 |
| n | 中性名詞 形容詞の中性形 |
| adj | 形容詞 例 albus-a-nm(adj)白い(男性形・女性形 中性形、形容詞) |
| adv | 副詞 |
| 属 | 名詞の属格 例 anas-atis(f) カモ (単数主格単数属格(anatis)女性名詞) |
| tr | 他動詞 |
| intr | 自動詞 |
| int | 間投詞 |
| 合 | 合成語、造語や手を加えた外国語 |
| 外 | ラテン語以外の外国語 |
| 神 | ギリシャ神話などにでてくる人物など |
| Gk | ギリシャ語 |
| L | ラテン語 (一部のみ使用) |
| 独 | ドイツ語 |
| 伊 | イタリア語 |
| 仏 | フランス語 |
| 露 | ロシア語 |
| 英 | 英語 |
| 接頭辞 | 言語の前につけて意味を付加する接辞 |
| 語尾 | 語幹につけて意味をもった語に完成させるもの |
| 接尾辞 | 語尾の一種で語幹につけて派生語をつくるもの |
| 指小辞 | 名詞や形容詞につけて「小さいものや可愛い」をあらわす接尾辞 |
| 父称 | ギリシャ語の固有名詞につけて〜の息子、娘をあらわすもの |
| トートニム | 属名と種小名が同一の学名 |
-
標準和名
- 学名:学名 (読み) 説明 (第8版、第7版、IOC で相違がある場合は併記している)
- 属名:属名の説明 (同上)
- 種小名:種小名の説明 (同上)
- 英名:英名 (やや古い英名も含まれている。IOC 準拠英名が異なるものは追記している)
- 備考:備考。学名や亜種の追加説明。分類学情報や面白い関連情報(一般的な図鑑などで読める色彩や形態、分布、生態などは原則省略している)
― キジ目 GALLIFORMES キジ科 PHASIANIDAE ▽
-
エゾライチョウ
- 学名:Tetrastes bonasia (テトゥラステース ボナーシア) エゾライチョウまたはヤギュウの声のような音を出すライチョウの歌い手
- 属名:Tetrastes < Tetrao ライチョウ < tetras Symmachus が記述した鳥の名前。食べられる狩猟鳥でおそらく Aristophanes 他が用いた tetrax と同一だが正体ははっきりしない (野ガモとする著者もある) (Gk) -astes (行うもの) (Gk); ライチョウの歌い手 (コンサイス鳥名事典, Gk)
- 種小名:bonasia イタリア語でエゾライチョウ < 原意は bonasus < bonasos バイソン (Gk); ヤギュウの(声のような音を出す) (コンサイス鳥名事典)
- 英名:Hazel Grouse
- 備考:
tetrastes は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は tetras は短母音。-astes は e が長母音でそれを反映した。-ras- がアクセント音節と考えられる (テトゥラステース)。
bonasia は bonasus に従えば a が長母音でアクセントもある (ボナーシア)。ギリシャ語 bonassos も -na- が長母音でアクセントがある。
bonasia の由来はあまりはっきりわかっておらず (The Key to Scientific Names) いろいろな考えがあり得る。bonasus の変化形に現れる形ではない。
-ia の由来を -ius の語尾由来と考えれば短母音となるのが自然に思えるが性変化させたものではなさそう。
エゾライチョウの亜種の亜種小名を見ると一見性が統一されていないように見えるが Tetrastes は男性名詞の扱いと考えられる。griseonota の一見女性形に見える亜種小名が存在するがこれは不変との注釈が H&M 4:45 にあると IOC リストにある。つまり bonasia は -ius から女性形を採用したものとは解釈できない。
記載時学名 Tetrao Bonasia Linnaeus, 1758 (原記載) も大文字表記で名詞の扱い。属の性による変化は受けないことになるのだろう。Tetrastes 属は von Keyserling and Blasius (1840) が提唱したもので、当時はエゾライチョウのみを含んでいた。
Tetrastes bonasa Olphe-Galliard, 1886 (参考) の用例があり、綴りを誤ったものか改名 (修正) を意図したものか、とある。
ユーラシアやや北部に広く分布し、11 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は vicinitas (近い、似ている)。基亜種に似ているが違う点もあると命名された (参考 基産地Hakodate, Yezo, Japan 北海道)。英名の hazel はハシバミ(属)。
キジ科は2亜科の分割されるが、日本のものは Phasianinae 亜科。
これは直立するかしないかで2クレードに分割される (erectile clade, nonerectile clade)。
日本に関係する種ではウズラが後者。ニワトリの野生種であるセキショクヤケイも後者。
erectile clade の中では Tetrastes 属および Lagopus 属 (日本に関係ある属のみを示す) は Tetraonini 族 に分類される
(この程度の分類を見ていただくと 族 tribe の意義や範囲がわかりやすいだろう)。
参考 Gutierrez et al. (2000) A classification of the grouse (Aves: Tetraoninae) based on mitochondrial DNA sequences。
Luo et al. (2024) Description of the mitochondrial genomes of Sichuan Tetrastes sewerzowi (Galliformes: Tetraonidae) and phylogenetic relationship
にミトコンドリアゲノムを用いた新しい分子系統樹が出ている。
情報がやや不足気味ではあるが、Tetrastes 属と Bonasa 属は分けた方がよいと結論している。エゾライチョウはTetrastes 属のタイプ種なので属は変わらないが、エリマキライチョウ Bonasa umbellus Ruffed Grouse は Tetrastes 属に合体するより現行の扱い通り別属でよいとのこと。
ミヤマエゾライチョウ Tetrastes sewerzowi 英名 Chinese Grouse との遺伝的関係を調べた論文: Song et al. (2021) Demographic history and divergence of sibling grouse species inferred from whole genome sequencing reveal past effects of climate change。この2種は 46-337 万年前に分かれたとのこと。両種とも近年は実効個体数が減っている。
英語圏では、冬に白い羽となるライチョウ属の種を ptarmigan、羽の色を変化させない種は grouse と呼び区別される (wikipedia 日本語版より)。ptarmigan はゲール語 tarmachan に由来し、意味は croaker (があがあ鳴くもの) だがそれ以上の語源は不明とのこと。pt- の綴りはギリシャ語由来と誤解され ptero- (翼 Gk) に合わせたものらしい (wiktionary)。英語でもライチョウ類総称では grouse。
grouse は 1530 年代には複数形で grows と呼ばれていたが起源にはいくつかの説がある。例えば中世フランス語でツルを表す grue、同じく中世ラテン語の gurta などが挙がっている (wiktionary)。
ロシア語ではライチョウ属は英語のような区別はなく様々な名前がある。エゾライチョウは ryabchik で ryaboj (斑点のある) に由来。
ライチョウ属の一部はロシア語で teterev と呼ばれ、遡れば Aristophanes 他が用いた tetrax になるらしい (Kolyada et al. 2016)。teterev から派生するロシア名に#オオタカ teterevyatnik がある。
[クジャクの目玉模様は目立つか?]
Kane et al. (2019) How conspicuous are peacock eyespots and other colorful feathers in the eyes of mammalian predators?
の研究によれば、2色色覚型の哺乳類捕食者にとってはクジャクの目玉模様は目立たず、普通の距離ではパターンが検出限界以下になるとのこと。むしろ隠蔽色になっている可能性がある。哺乳類捕食者は色彩パターンよりも他の手がかりを用いている。
クジャクは捕食者回避能力も高く、野外研究でも哺乳類による捕食の頻度は低いとのこと。目玉模様が多いほど捕食されやすい傾向も見つかっておらず、長い上尾筒が逃走行動を邪魔している証拠もないとのこと。
[インドクジャクの白変の遺伝的原因]
Wang et al. (2025) Genomic evidence for hybridization and introgression between blue peafowl and endangered green peafowl and molecular foundation of leucistic plumage of blue peafowl
高精度全ゲノム解析で EDNRB2 遺伝子に停止コドンへの変異がありメラノサイトから羽毛へのメラニン移行が起きなくなっていた。白色のガチョウではこの位置に 14 塩基の挿入があり同様に作用している (#マガモ備考の [白い大きなアヒルの起源] も参照)。
異なる系統の鳥で対象遺伝子が共通する白変化のメカニズムがあった。この遺伝子はメラニン合成には関与しない。白変個体の写真も掲載されている。
Maclary and Shapiro (2025) Widespread variation in EDNRB2 is associated with diverse melanin loss phenotypes across avian species (preprint)。
カナリア原種にあった濁った色が品種改良で失われた系統はこの遺伝子に変異があった。
完全に白くなったオウム類の系統もこの遺伝子の関与が示唆されるとのこと。オウム類は独自の色素 (ppsittacofulvins) を持っており、カナリア類もカロテノイドを色彩に持ちている点で共通点があり、生態的に色彩が必要な条件下で EDNRB2 の進化と相互 (例えば相補的) 作用、あるいは着色にかかわる代謝経路を通じて関連があった可能性が示唆されるがまだよくわかっていない。
メラニンを含まない白いパッチは多くの種で信号に用いられているが、全身羽毛にメラニンを持たない極端なもの以外でも EDNRB2 の制御によって模様を作り出している可能性も考えられるとのこと。
-
ライチョウ
- 学名:Lagopus muta (ラゴープース ムーター) 静かなライチョウ
- 属名:lagopus (f) ライチョウ (lagos ノウサギ pous 足 Gk)
- 種小名:muta (adj) 静かな (mutus)
- 英名:Rock Ptarmigan
- 備考:
lagopus は#ケアシノスリ参照 (ラゴープース)。
muta はいずれも長母音 (ムーター)。派生する他言語では伸ばさないものが多いが英語 mute は長音。
北半球高緯度に分布。23 亜種が認められている (IOC)。日本に分布する亜種は japonica (日本の) とされる。
かつての学名は Lagopus mutus だったが、種小名語尾は従来は属名が男性名詞と思われていたため。古ギリシャ語由来でこれはギリシャ語、ラテン語とも女性名詞であるため、種小名が修正されたとのこと (wikipedia 英語版より)。
Clements 3rd edition - 5th edition (incl. 2003 revisions), HBW, Peters' Check-list of the Birds (2nd edition までも含む), Sibley and Monroe (1993, including corrections up to 1998), American Ornithologists' Union 4th - 7th edition (incl. 44th suppl.) が mutus を用いていた。
Dement'ev and Gladkov (1952) では Lagopus mutus となっていた。
変更されたのが比較的最近で、日本の記事でも出典次第でしばしば見かけるので注意が必要。
ギリシャ語由来で足の意味の -pus で終わる名詞の性は女性というわけではなく apus (アマツバメ) は男性名詞であり Apus 属の種小名も男性形になっている。
日本産の種で 足の意味の -pus で終わる属名を持つもので女性形の種小名は見当たらず男性に統一されているように見える。
apus のもととなるギリシャ語の apous は形容詞でこの形は男性または女性とのこと。ギリシャ語にはアマツバメを指す用例はない (wiktionary)。
ライチョウを意味する単語がギリシャ語に存在して女性名詞だった点が異なっている模様。
参考までにタコを意味する octopus はギリシャ語に名詞が存在してこの場合は男性名詞。ラテン語も同様。なおムシクイ属の Phylloscopus は -pus の語尾でも足とは無関係。
Lagopus 属のタイプ種は ヌマライチョウ (旧名カラフトライチョウ) Lagopus lagopus Willow Ptarmigan。北半球北極圏に広く分布する。サハリンは分布の南限で亜種は okadai (Momiyama 1928 が命名)。
AviList v2025 - errors, typos で AviList の属名記載の正当性が順次検証されている。
AviList では Tetrao lagopus [Linnaeus, 1758]; type by tautonymy = Tetrao lagopus Linnaeus, 1758 とあるが正しくなく、これはおそらく古い時代の記述をそのまま使っているためで現代の命名規約にはこの概念はなく、Type by subsequent designation (Gray 1840, List of the genera of birds : 62) とタイプ種は後に定められたとするのが正しいとこと。
特別天然記念物。絶滅危惧 IB 類 (EN)。世界的に種全体では IUCN 3.1 LC 種 (LC は Least Concern で「低懸念」と訳されるが、「少し懸念がある」と読まれがちである。
本来の英語の意味は「ほとんどない」、例えば least likely は「ほとんどあり得ない」の意味で、「懸念なし」と解釈する方が意味は近いだろう。日本のレッドデータブックの分類ではランク外に相当する。ドイツ語訳では nicht gefaehrdet 懸念なし とされている)。
英国には Ptarmigan と呼ばれる種が1種のみなのでイギリス英語では単に Ptarmigan と呼ばれていた。アメリカには複数種存在するため Rock Ptarmigan などと呼び分ける必要があった。
ドイツ語名 Alpenschneehuhn (アルプスの雪のニワトリ)。ロシア語名 tundryanaya kuropatka (ツンドラの、後半は kur ニワトリから派生。ツンドラのニワトリと訳せそうである)。
スウェーデン語 fjallripa (fjal 山の ripa ライチョウ) など。
千島列島北部のライチョウ: Lobkov et al. (2025) Distribution and abundance of the Kurile rock ptarmigan Lagopus muta kurilensis in the northern part of Kuril Island chain in accordance with natural appearance of the islands (pp. 453-465)。
[ライチョウ類の植物毒解毒]
日本の種とは近縁ではないが (エゾライチョウの方がやや近い?) 保全上でも話題となるためこちらに含めておく。
Kohl et al. (2016) Microbial detoxification in the gut of a specialist avian herbivore, the Greater Sage-Grouse
キジオライチョウ Centrocercus urophasianus の植物毒の解毒の研究がある。ヨモギ属 Artemisia を食べるスペシャリストであるが有毒物質を含んでいる。
腸内細菌が分解しており、フェノールをピルビン酸に分解する生化学経路を明らかにした。この機能はニワトリや牛など草食哺乳類 14 種には認められなかった。
ヨモギ属の主な毒性成分であるモノテルペン (monoterpene) を分解する証拠はそこまで確実でないがこの代謝経路に関係する酵素をいくつか同定した。植物毒の解毒における腸内細菌の役割は草食哺乳類や昆虫に似ているとのこと。キジオライチョウ類では糞に排泄される植物由来物質濃度が低いことから腸内細菌の役割が示唆されていた。
また必須アミノ酸 (植物にはあまり含まれない) を腸内細菌が合成している可能性もあるが、これは今後の研究が必要である。論文のまとめ方は保全よりもライチョウ類の腸内細菌に応用上有用な特異な酵素が見つかることが期待できると実用的側面を示している。
Sun et al. (2022) The avian gut microbiota: Diversity, influencing factors, and future directions に植物食の鳥の腸内細菌の役割についてレビュー論文がある。
ツメバケイではそのうでの発酵で解毒している証拠があり、ライチョウ類についても示唆されている:
Dearing et al. (2005)
The Influence of Plant Secondary Metabolites on the Nutritional Ecology of Herbivorous Terrestrial Vertebrates のレビュー参照。
ニホンライチョウでは ニホンライチョウの味覚・解毒機能の高山環境適応機構の解明と保全に向けた飼料開発 (橋戸南美) の研究がおこなれているので今後成果が出てくるだろう。
[足に羽毛の生える鳥]
ライチョウそのもの研究は見つけられなかったが、足に羽毛の生える (ptilopody) 鳥についての遺伝子変異や制御の研究がある。
Bortoluzzi et al. (2020) Parallel Genetic Origin of Foot Feathering in Birds
ニワトリとハトの飼育品種で足に羽毛を持つものは PITX1, TBX5 遺伝子の発現に共通の特徴が見られる。Fig. 1 を見ていただくとニワトリの品種でどのような形態変化があるか見ていただけるだろう。足に翼のような羽毛を持つ品種すらある。
ニワトリにおいては第 13 染色体 PITX1 の上流 200 kb に発現に関係すると思われる 17 kb の脱落があり、ハトでは同様に 44 kb の脱落があるとのこと。structural variant (構造変異) は両種で独立に何度も起きたとのこと。
タンパク質をコードする遺伝子だけを比べてもわからないだろう。
PITX1 は通常は後肢にのみ発現し、前肢には発現しない。前肢と後肢の発生の違いを生み出している。
PITX1 は小型の羽毛の発育に主に関係し、TBX5 は大型の羽毛に主に関係するとの先行研究がある。
Boer et al. (2019) Pigeon foot feathering reveals conserved limb identity networks はハト品種での足の羽毛と遺伝子発現の関係を調べている。PITX1 と TBX5 が羊膜類で前肢・後肢を決める共通の遺伝子とのこと。
Li et al. (2020) Mutations Upstream of the TBX5 and PITX1 Transcription Factor Genes Are Associated with Feathered Legs in the Domestic Chicken
もほぼ同様の研究で、ニワトリでは第 15 染色体の TBX5 遺伝子の上流に変異がある。後肢で PITX1 の発現が抑制され、TBX5 が異所的に発現することで羽毛の生えた足になる。
いずれも過去の研究で提唱されていたものを詳しい解析で確認したもの。過去の研究は引用文献を参照いただきたい [Takeuchi et al. (1999) Tbx5 and Tbx4 genes determine the wing/leg identity of limb buds の日本の研究もある]。
これらの表現型の特徴をニワトリでは ptarmigan、ハトでは grouse と呼ぶらしいことも面白い。
ライチョウはニワトリに近縁なので制御メカニズムもおそらくよく似ているのだろう。
#カワラバト備考の [家禽ハト品種の形態に関連する遺伝子] にも関連話題がある。
[鳥類と爬虫類のうろこは別物]
鳥類の足の "うろこ" と爬虫類のうろこが同じ起源かどうか長く議論されてきた。
Wu et al. (2018a)
Comprehensive molecular and cellular studies suggest avian scutate scales are secondarily derived from feathers, and more distant from reptilian scales
は発生過程の鳥類の足の "うろこ" は羽毛の発生の早い段階に類似していることを見出した。分子レベルでも羽毛、うろこにそれぞれ特徴的な遺伝子の発現を調べることでワニのうろことニワトリの羽毛や "うろこ" とは異なることが示された。形態的にはワニとニワトリの "うろこ" は似ているが、幹細胞の分布、そしておそらく働きも異なり両者の "うろこ" は収斂進化の結果と考えられる。
つまり論文表題が示すように鳥類の足の "うろこ" は羽毛から二次的に生じたものと考えられ、爬虫類への先祖返りを見ているというわけでも、「鳥が爬虫類であることの証拠」というわけでもない。
鳥類の足の "うろこ" が羽毛から二次的に生じたものとの考えは Dhouailly (2009) A new scenario for the evolutionary origin of hair, feather, and avian scales で提唱されていた。
この論文では羊膜類の中でも鳥類の皮膚は羽毛、哺乳類の皮膚は毛と最も複雑な付属物を作る機能に共通の遺伝子が働いているとのこと。実験でもニワトリで単純なうろこ、マウスで単純な (付属) 腺 (gland) のみを生じさせることはできなかった。まず羽毛や毛が発生するプログラムが働き、これを抑制する機構でより単純な構造 (皮膚の角質は両者に共通) が生じるとの考え方。
足の "うろこ" が比較的簡単な遺伝子制御機構の変化で羽毛に変わり得る現代の知見とも整合性がよい。
Wu et al. (2018b) Multiple Regulatory Modules Are Required for Scale-to-Feather Conversion
によればうろこから羽毛への進化は何段階もの制御モジュール再構築が必要である。この論文が羽毛に特徴的な遺伝子を同定したもの。
ふしょの "うろこ" (scutate scales) と足の裏の reticulate scales とは異なっているとのこと。reticulate scales は α ケラチンからなる。
確かに足に羽毛が生えるニワトリやハトの飼育品種でも足の裏は羽毛にならないことが知られている。
Liu et al. (2023) Molecular and Cellular Characterization of Avian Reticulate Scales Implies the EvoDevo Novelty of Skin Appendages in Foot Sole
鳥の足の裏の皮膚の構造は哺乳類の tactile skin (外界を接触感知する皮膚。例えばヒトの手のひらや足の裏) と類似点があるとのこと。
著者は圧力に対する構造的適応で、常時摩耗するため細胞更新の頻度を高めることに適した幹細胞の分布となっていて (羽毛や毛は換羽のような更新サイクルがある) 傷を治すのに十分な速度となっているが、reticulate scales のような大きな構造物を再生するのには十分でないと考えている。
Cooper and Milinkovitch (2025) In vivo sonic hedgehog pathway antagonism temporarily results in ancestral proto-feather-like structures in the chicken
にも最新の研究が出ていた。足の「うろこ」部分の皮膚の発生途中を阻害すると羽毛になってしまう。羽毛の発生をのものを完全に止めることは困難。羽毛の発生は遺伝メカニズムにも非常に頑強で、例えば羽毛発育への選択圧がかからなくなっても原始的な形態の羽毛が発生することを意味する。
Cooper et al. (2019) Conserved gene signalling and a derived patterning mechanism underlie the development of avian footpad scales
はこの研究に先行するものだが、鳥の足の裏の皮膚の特殊性を取り上げている。恐竜の "うろこ" についてはまだ学説が固まっていないが、現在の系統研究に基づけば reticulate scales は鳥類の起源以前に遡る可能性があるとのこと。
Dhouailly (2023) Evo Devo of the Vertebrates Integument 脊椎動物の皮膚付属物の進化のレビュー論文。
鳥類の足の "うろこ" が羽毛から生じ、逆ではない証拠は集積しつつある。
すべての鳥は足の裏に reticula を持っているがフクロウ類など少数は pedal scales を持たないことも述べられている [cf. 川口 (2024) Birder 38(8): 52-53]。
鳥類・哺乳類に共通する Shh/BMP のバランスのメカニズムによって羽毛・毛皮になるか裸の皮膚になるかが決まる。足の裏が発達することで地上生活に適応した。哺乳類の毛は化石に残りにくいので進化過程は羽毛以上にあまりよくわかっていないが古くからあった模様。
爬虫類のうろこ、鳥類の reticula、哺乳類の指紋は dermal condensate (原基内での細胞集積) ではなく intra-epidermal signaling (上皮内のシグナル伝達) で形成されるものとのこと。これらはパターン形成的には同じように作られるものと考えてよさそう。上皮内のシグナル伝達で形成される
(指紋は原文で fingerprints。日本語の方が語彙が豊富なようで、解剖学的には皮膚紋理の用語がある。皮膚の構造の名称も皮溝 sulcus cutis 皮丘 crista cutis 皮野 area cutanea も日本語は詳しい)。
そういえば鳥肌が立つというのはそういうことか、と妙に納得できてしまう。
Nogare and Chitnis (2017) Self-organizing spots get under your skin
に入門者向けの皮膚のパターン形成のレビューがある。"your skin" とあるが羽毛のこともずいぶん述べている。
鳥類の羽毛発生と哺乳類の毛の発生が非常によく似ていることは出てくるが爬虫類については出てこない。羽毛の発生はそれだけよく調べられているのだろう。鳥肌はほぼ鳥の肌と考えて大きな間違いはなさそう。
このようなパターン形成のアイデアは Alan Turing アラン・チューリング「コンピュータ科学の父」が 1952 年に数学的理論として提唱したもので、近距離で促進、遠距離で抑制的に働く作用を考えるだけでパターンを再現できる。"The Chemical Basis of Morphogenesis" (形態形成の化学的基礎) の論文。
斑点や縞模様などの規則性も同じように考えられるのだろう。
Youn et al. (2024) Tissue-scale in vitro epithelial wrinkling and wrinkle-to-fold transition
ヒトの細胞を用いたものだが "しわ" の形成に働く力。
Santos-Duran et al. (2024) Self-organized patterning of crocodile head scales by compressive folding こちらはワニの表皮の "うろこ" がどのように作られるかを調べた研究。
羊膜類の表皮に見られるパターンは上記の (遺伝子発現で制御された) チューリング型の化学的シグナルによる自己組織化または力学的な力によるフィードバックが加わって形成されると考えられていたが、ワニの頭の不規則なうろこは力学的な機構のみで形成されて例外的と考えられてきた。遺伝子発現によるチューリング型の制御は関わっていないことが過去に示されていた。
EGF (表皮増殖因子) を投与する実験から、表皮と真皮の硬さの違いに起因して成長に伴う物理的な圧縮力が構造形成にかかわっていることを示したもの。
EGF の働き具合の違いだけでうろこの目の粗さが変わるとのこと。
The mechanics of crocodile head scales patterning (解説ビデオ)。
スズメ目では足のうろこが目立たなくなる傾向があるとされるが、小型であることと防水機能をあまり必要としないためでは (上記物理的メカニズムを考えると単に相似形に小型のうろこになるとは考えにくい)。
Cooper et al. (2025) Exacerbated sonic hedgehog signalling promotes a transition from chemical pre-patterning of chicken reticulate scales to mechanical skin folding
ニワトリの胚の特定の時期に操作を加えることで足のうろこ部位の変化を調べたもの。皮膚に多くのケラチンが含まれる実験的条件 (hyper-keratinization) では皮膚の剛性を増してうろこ状の構造形成が抑制されるとのこと。基本的には物理的な力で構造形成が決まっていると考えてよさそう。
bumblefoot (バンブルフット ulcerative pododermatitis) 趾瘤症は猛禽類に起きやすい疾患と思っていたが、哺乳類にも共通しているようで Bajwa (2016) Canine pododermatitis のような獣医学のレビューもある。足の裏の収斂進化の産物と思ってよいのだろうか。
もしかすると何かの参考になるかも知れないのでメモしておくと Schwehn et al. (2024) Blood Vessel Topography of the Feet in Selected Species of Birds of Prey and Owls
に猛禽類の足の血管系を比較研究した論文がある。足の裏の血液供給がタカ類とハヤブサ類に多少違いがあるそうで、ハヤブサ類の方が足の裏の血管が少なめでバンブルフットが起きやすい原因にもなっているかも知れないとのこと。タカ類では調べられた範囲で共通性が高く、ヨーロッパノスリ、ハイタカ、ヨーロッパハチクマ、オオタカともに同じ動脈のパターンでグループ2に属するとのこと。
グループ1がハヤブサ類、グループ3がフクロウ類 (足から趾への動脈がどこで分岐するかで区別している)。ハヤブサ目でもカラカラでは趾への動脈供給がニワトリと似ているとのこと。
Schwehn et al. (2025) The Comparative Anatomy of the Metatarsal Foot Pad in Eight Species of Birds of Prey and Owls with Regard to the Development of Pododermatitis にも後続論文があり皮下の血管の構造や脂肪組織の違いなどが調べられている。
皮膚はどこかの段階で爬虫類型から鳥類型に進化したはずだが、化石研究から経緯を探ったもの:
Yang et al. (2024)
Cellular structure of dinosaur scales reveals retention of reptile-type skin during the evolutionary transition to feathers
皮膚部分の保存状態のよい Psittacosaurus の化石で皮膚構造を調べた。羽毛のない皮膚を現代の鳥の "うろこ" のない裸出した皮膚と比べると現在の鳥のケラチン層の方がずっと厚く、むしろ現生の爬虫類に近いものだった。
現代の鳥では羽毛のない部分にメラニン着色はほとんどないが Psittacosaurus では着色に用いていてメラニン分布はワニと共通性があるとのこと。
皮膚の構造は外気温に対する適応などいろいろな解釈が考えらえるが、四足歩行の爬虫類に比べて二足歩行によって地上から体が離れ、物理的な保護の必要性が下がったのではとの解釈も挙げている。
羽毛進化の最初の段階では羽毛のない部分には爬虫類に似た皮膚を残しておく必要性があったのでは、などの議論が出ている。今の鳥類の皮膚は哺乳類型とも共通性のある鳥類型になっていて爬虫類型の特徴は残っていないと考えてよいのだろう。
Holthaus et al. (2018) Comparative Analysis of Epidermal Differentiation Genes of Crocodilians Suggests New Models for the Evolutionary Origin of Avian Feather Proteins
上皮形成に関係する Epidermal Differentiation Complex (EDC) の遺伝子群は羊膜類内の系統ごとにすべて違いがある。カメ、ワニが共通で持っている EDPQ は鳥類では失われている。
EDCRP は鳥類・ワニ類の共通祖先で生じたものだが、鳥類で特に発達 (リピート数の増加) して羽毛をもたらすことになった。ワニ類の EDCRP ではシステイン残基が最大で 22 なのに対してニワトリでは 160 ある (羽毛にシステインが多いのはジスルフィド結合で強度を高めるためと考えられている)。
羽毛を燃やす時の特有の悪臭はシステインに起因する硫黄が多いため。また羽毛の発育には多量のシステインを必要とするため、換羽時には他の生理学的要求と競合が生じ、生理学的要求が大きい時に換羽の中断などの現象にもつながるなど換羽の理解にも役立つ。
哺乳類の毛にもシステインが多いが、タンパク質が異なっており収斂進化の結果とのこと:
Strasser et al. (2015) Convergent evolution of cysteine-rich proteins in feathers and hair;
Ehrlich et al. (2020) Convergent Evolution of Cysteine-Rich Keratins in Hard Skin Appendages of Terrestrial Vertebrates。
Strasser et al. (2015) の結果ではワキスジハヤブサやシロエリヒタキのリピート数が多く、これは羽毛強度がそれだけ重要なことを意味するのだろうか。
羽毛より起源の古い subperiderm に羽毛に関連する祖先的な遺伝子の発現があり、羽毛はここから進化したのではとの考え。
2.4 億年前の共通祖先の段階では羽毛を持っておらず、どのような役割で進化したものか興味あるとのこと [Lachner et al. (2019) Immunolocalization and phylogenetic profiling of the feather protein with the highest cysteine content]。
Davis and Greenwold (2021) Evolution of an Epidermal Differentiation Complex (EDC) Gene Family in Birds
に鳥類内での EDC の進化の研究がある。ニワトリやカッコウでは遺伝子数も多くて複雑だったものが、アデリーペンギン、ハクトウワシ (この2種はよく似ている) では遺伝子数が少ない。キンカチョウではさらに1つ失っている。進化段階をたどると水鳥の多かった系統では羽毛形成の遺伝子が重要だったが、陸に移るにつれて次第に必要性が下がったのだろうか。
ペンギンは水中生活に適応して水鳥に近いかと思ったが意外にも遺伝子は陸鳥型だった。陸から海に戻ったが遺伝子は祖先型に戻すことはできなかったらしい。
論文では生態との相関は見つけることができず、完全な遺伝子の検出が不十分なのでよりデータが必要とのこと。
Li et al. (2025) Skin regional specification and higher-order HoxC regulation
Polish chicken では HoxC10 のイントロンに 195 bp の重複があってとさかの部分が冠羽になっている。この部分を除くなど操作を行うと形質が変わる。この 195 bp の領域は鳥類とワニ類に見られるが哺乳類にはなく、鳥類の皮膚付属物の進化に役立っていると考えられるとのこと。
Kane et al. (2019)
Successful, Full-Thickness Skin Graft in a Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus)
おそらく感電で頭部の皮膚を失ったハクトウワシに腿部から自家皮膚全層移植に成功したとの報告があった。羽毛が正しい向きに生えるように方向も注意したなど。6週間で放鳥に至った。このような事例は鳥類で初とのこと。
これをもとに調べてみると Stroud et al. (2003) The Use of Skin Flaps and Grafts for Wound Management in Raptors
のような文献もあって、鳥類の皮膚は哺乳類のものと似ている。羽毛がある点は違う (これは当たり前か)。
視点や実用目的が少し異なる (生体工学の視点が中心) が羽毛の微小構造のレビュー: Hendrickx-Rodriguez and Lentink (2025) The feather’s multi-functional structure across nano to macro scales inspires hierarchical design (オープンアクセス)。
汗腺がない点は異なるが、皮膚に holocrine glands (全分泌腺。ホロクリン腺) を持っていて sebokeratinocytes が皮膚に脂肪を分泌する。尾脂腺、総排泄孔、外耳道にもあるとのことで、形態は違うものの哺乳類の脂腺と同じような部位に分布して似た機能を果たしていると考えてよさそう (他の文献を見ても哺乳類と同じような役割を果たすと書かれている)。
哺乳類の乳腺が汗腺由来であると同様、ピジョンミルクを生成する上皮も皮膚分泌腺の延長と考えてよさそう。これは #フルマカモメの備考の [におう鳥のリスト] の記述と大きく違うわけではないが、哺乳類と似た進化を遂げたらしいことがよりわかりやすい。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 100 V では「その特有のにおいは人にはむしろ耐えがたい」(黒田長久) と書かれていた。ピジョンミルクはかなり臭いものらしく、皮膚分泌腺らしさが現れている (?)。通常の皮膚に脂肪を分泌する方向には進化しなかったがやはり似たようなものか。
海に住む哺乳類では鳥類にあるような sebokeratinocytes と類似の lipokeratinocytes を持っているとのこと [Eias et al. (1987) Avian sebokeratocytes and marine mammal lipokeratinocytes: Structural, lipid biochemical, and functional considerations]。
哺乳類は夜行性を体験して嗅覚コミュニケーションの役割が増えて汗腺が重要になったが、昼行性で水分喪失を避けつつ空冷が重要な鳥類では少し違う形になったと解釈すればよいだろうか。
Stettenheim (2000) The Integumentary Morphology of Modern Birds-An Overview に鳥の皮膚付属物のレビューがあり、個々にはそれほど深くはないが守備範囲が広く、オープンアクセスなので見ておいてよさそう (記事を書いた時はオープンアクセスだったが 2025.5 現在ではオープンアクセスでなくなっていた。当然のことながら近年の遺伝子発現の研究などは入っていない)。
鳥の皮膚全体が皮脂分泌器官として働いているが尾脂腺、外耳道腺は特化している。尾脂腺の分泌物は化学的にも皮膚の分泌物と異なってエステルが中心。鳥にも耳垢に相当する分泌がある。
総排泄孔腺はムコタンパク質のみを分泌し受精に役立っていると考えられる。
シチメンチョウでは首の基部から垂れ下がる "beard" ("ひげ") があり羽毛とは違って伸び続ける (最長 677 mm)。羽毛のように follicle (羽嚢) から発生するのではなく、皮膚の肥厚部から直接生じるとのこと (この点はうろこに似ている)。ということで鳥の皮膚から生えるものはすべて羽毛が変形したものというわけでもなさそう。
ツメバケイが重いそのうを枝に乗せる部位は sternal callus と呼ばれる肥厚構造になっているそう。
嘴を覆う rhamphotheca も皮膚が特殊化して厚くなったもので、真皮 (dermis) も存在して触覚の知覚センサーがある。触覚センサーの数や分布は最食様式や種類によって大きく異なっている (よく知られているようにカモ類やシギ類、オウム類で触覚が発達している)。ツカツクリ類では温度センサーとしても知られている。
鼻孔部の nare やその一部であるろう膜 cere も rhamphotheca の一種。オウム類の舌先端のケラチン化した lingual nail も組織的には rhamphotheca に似ているが構造は β ケラチンがフィラメント状に並んで scutellate scales (趾表面の "うろこ") に似ている。
蹴爪 (spur) についても簡単な言及がある。またレンカクなどの wing spur は蹴爪同様に骨から出た突起 (ツメバケイなどの wing claw とは別物)。
Widelitz et al. (2007) Mammary glands and feathers: Comparing two skin appendages which help define novel classes during vertebrate evolution
一見意味がないように見えるが羽毛と乳腺の類似性の比較。最近の遺伝子発現などの証拠は含まれていないので想像による図になっているが皮膚付属物を進化させることで鳥類・哺乳類の2大系統に繁栄をもたらした。根底にあるメカニズムは似ている。
尾脂腺のまだ発達していないひよこを使って羽毛 (ダウン) の脂肪成分を調べてみると尾脂腺とは成分が異なっていた: Zeisler-Diehl et al. (2020) Detection of endogenous lipids in chicken feathers distinct from preen gland constituents。
尾脂腺の成分とは決定的に異なっている。未発表だが他の種でも見られるとのことで鳥類全般で成り立つのではとのこと。各種羽毛にも存在する証拠があり、濃度は低いが役割を果たしていると考えられる。
組成からは疎水機能があることはほぼ自明で、ウなどではどうなっているか調べるのは興味があるとのこと。
羽毛は死んだ組織なので血流で除かれることなく長期間安定に存在できる。
(これまでは尾脂腺の分泌物の組成などを中心に研究されてきたが) 羽毛の脂分は尾脂腺のみに由来すると考えてはいけないよう。
この論文では疎水機能を中心に議論しているがおそらく他にも機能があるのだろう。
また粉綿羽も調べているわけではないのでこちらも調べると興味深い結果になるかも。
こちらは少し違う系統だが鳥 (調べられたのはスズメ目。ヨーロッパの研究なので日本と共通または近縁種も多い) の羽毛の細菌叢が羽毛を劣化させる細菌に対する抗菌物質を作っている:
Javurkova et al. (2019) Unveiled feather microcosm: feather microbiota of passerine birds is closely associated with host species identity and bacteriocin-producing bacteria
宿主の系統とともに共進化がみられる。Streptococcus と Lactobacillus の割合が高かった。Streptococcus (レンサ球菌) はヒトも含めて多くの脊椎動物の皮膚に普遍的に存在するが、Lactobacillus (ラクトバチルス属。乳酸菌群の一つ) が皮膚の細菌叢を形成しているのはこれまでヒトと霊長類のみでしか知られていなかったとのこと。
鳥の皮膚/羽毛の細菌叢の研究は始まったばかりとのこと。
家禽のマレック病 (alphaherpesvirus 類) が皮膚の keratinocytes で増殖する証拠: Souci et al. (2025) Marek's disease virus replication in chicken skin reconstructed in vitro: evidence for viral particles in corneocytes 角化組織がそのまま排泄され環境に分散するのでウイルスにとって大変都合のよい感染経路となる。面白いことに表皮のうちでも表面のみで増殖するとのこと。
alphaherpesvirus 類ではヒトでは Simplexvirus 属 (いわゆる単純ヘルペス。帯状疱疹ウイルスとは別属だが同じ亜科) があって粘膜から唾液に分泌されて感染が広がるが (この部分 wikipedia 英語版から)、鳥では keratinocytes が分泌機能を持つ由来の増殖様式と言えるのだろう。なお鳥でも哺乳類でも alphaherpesvirus 類には糞口感染など別の感染経路もある。
ウイルスの増殖様式・感染経路から機能の共通性を考えるのも面白いアプローチではないだろうか。
こちらは鳥類ではないが皮膚常在菌が皮膚独自の免疫応答に関与している証拠を示す研究: Bousvaine et al. (2024) Discovery and engineering of the antibody response to a prominent skin commensal
ここで話題になっている Staphylococcus epidermidis は鳥類皮膚にも常在菌として知られているのであるいは同じような機構が働いているかも。
Gribonika et al. (2024) Skin autonomous antibody production regulates host-microbiota interactions こちらも同じく皮膚常在菌と皮膚独自の免疫応答の研究。The skin's 'surprise' power: it has its very own immune system より (Nature news 2024.12.13)。
Zhang et al. (2025) Medulla-free barb rami highlight the morphological diversity of early feathers;
Developmentally Incomplete Barb Rami Increased the Morphological Diversity of Early Feathers (preprint 段階のもの)
微細構造が未発達だった初期の羽毛について。3つの階層構造 (羽軸、羽枝、小羽枝) からなる羽毛はジュラ紀までに現れていたが、現代の鳥のような強度を持った構造はその後の白亜紀後期でもまだ完全に発達していなかったと考えられるとのこと。
ビルマの琥珀に保存された羽のサンプルを解析。現代の鳥に比べて構造がかなり未発達で微細形態的にはモデル計算から高速気流に対して安定な形状ではなく、現代の鳥ではこの形態は採用されていない。
さらに現代の鳥での知見をもとに羽毛発達に関連する遺伝子が進化段階を追ってどのように働いていたかを推定。
1.5 億年前から羽はほとんど変化していないとの従来の考え方に修正を迫るものとなった。
四肢動物の皮膚付属物についての最新のレビュー論文: Holthaus et al. (2025) Skin Appendage Proteins of Tetrapods: Building Blocks of Claws, Feathers, Hair and Other Cornified Epithelial Structures。
この論文でも爬虫類と鳥類のうろこは縁が遠い立場に立っている。四肢動物のそれぞれの構造を作っている分子の種類や発生段階での発現など。
メキシコサンショウウオ (アホロートル) Ambystoma mexicanum を用いて上皮のコラーゲンは keratinocytes が作っていることが示された: Ohashi et al. (2025) Keratinocyte-driven dermal collagen formation in the axolotl skin。
従来考えられていたように間葉 (中胚葉) 由来の fibroblasts (線維芽細胞) ではなかった (この名称の由来も線維を作ると考えられていたため)。成熟した哺乳類の生きた皮膚は不透明なため研究が難しかったが透明度の高いアホロートルを用いることで可能となった。遺伝子発現はニワトリやマウスでも確認され四肢動物に共通の機構と考えられる。
研究は皮膚のコラーゲン生成など医学や美容への応用を考えているが、keratinocytes が鳥類でさまざまなものを作っており、我々にとっても面白い結果と思う。
Kim et al. (2025) The Melanophilin knockout chicken, as a new alopecia animal model
イヌで知られている color-diluted alopecia と呼ばれるタイプの脱毛症に関わる遺伝子 Melanophilin をニワトリでノックアウトするとイヌに似た color-diluted alopecia の表現型が生じたとのこと。この遺伝子の機能が失われても発達初期の羽毛にはあまり影響がないが、加齢とともに羽毛の質が低下して脱毛症の表現型が生じるとのこと。羽毛進化の過程を考える上でも面白いと思う。
[現生爬虫類の頭のうろこは鳥類と異なる] Shh に関係して羊膜類の頭蓋骨や顔の形成の進化について。Marchini et al. (2025) Sonic hedgehog and fibroblast growth factor 8 regulate the evolution of amniote facial proportions
爬虫類と鳥類の頭骨の類似性など気にされている方はこのような論文を見ておくのがよいのだろう。哺乳類と鳥類の顔の形成に関わる遺伝子制御は似ているが、トカゲには鳥類の frontonasal ectodermal zone (FEZ。顔を形成する) に相当するものが認められず、羊膜類の祖先形質に近いと考えられる。
昔から言われてきた通り現代の哺乳類と現代の鳥類は祖先形質から派生した (derived) 顔の骨格を形成するプログラムがあり、これは全羊膜類に共通した性質ではない。皮膚の類似性のみならず哺乳類と鳥類で共通に進化した性質がきっとあるのでしょうね。
頭骨や顔の進化を考える上では特殊化したヘビ類やカメ類などの研究が望まれるとのこと。顔は羊膜類で複数回独立に進化した?
Cooper et al. (2025) Chemical and mechanical patterning of tortoise skin scales occur in different regions of the head
カメの頭のうろこのパターンの微細構造と形成を調べた結果。機械的力による頭のうろこ形成 (mechanical head-scale patterning) は Testudinata と Archosauria の分岐以前に生じたが、鳥類で後に失われたと考えられるとのこと。
カメとワニに同じようなパターンが見られるので鳥でも同じというわけではなさそう。
興味深いと考えているのは川口 (2020) Birder 34(2): 52-53 のように「鳥の嘴鞘はうろこがいくつかくっついてできたものだが」とほぼ断定的に書かれているものをしばしば見かけるため。
この記事で引用されている文献は Heilmann (1927) と何と 100 年近く前のもの。その後肯定されたのか否定されたのかを調べてもよくわからない。早い話がほとんど注目されていないわけである。
現代の考えの mechanical head-scale patterning を考えれば、番号を付けることもそもそもそれほど意味があるように思えず、例えば皮膚の "しわ" などに順番に番号を振っても同じような概念を作ることができる - と思ったらこれは手相用語みたいなものか。個体差はあっても手相全般に同じ名前を使うことができてしまう。ヒト全体に共通の性質だと言えることになる。
サル類の手相の系統進化すらも考えることができる。系統解析により複雑な手相を持つのはヒトが進化している証拠、などの結論も出すことができるわけだ。
ヒトの手に決まった手相があるのはヒトが爬虫類だった時代の名残り、と言っても信じる人はまずないだろう。
参考までにいくつか文献を挙げておくと、Yenmis and Ayaz (2023) The Story of the Finest Armor: Developmental Aspects of Reptile Skin に新しいレビュー論文があるが上記のような考え方は出てこない。
わずかに存在する研究では Hieronymus and Witmer (2010) Homology and Evolution of Avian Compound Rhamphothecae 程度。
ここで当時新しくわかった系統樹をもとに系統解析をしてみても、あまりはっきりした結論が得られず、compound rhamphotheca (複数のブロックから形成された嘴鞘) の一部は Neornithes の祖先形質的だが、さらなる構造は複数の系統で独立に派生したと考え、この文献では嘴鞘の新しい区分名を提案している。爬虫類だった時代の形質をそのまま受け継いでいるとは考えにくそう。
ただしアイデアの発端は判明し、Lonnberg (1904) "On the homologies of the different pieces of the compound rhamphotheca of birds" だった。始祖鳥化石発見で鳥類と爬虫類の関係がホットな話題だった時期に別の類縁性を指摘したのだろう (Lonnberg に先見性があったのか、暇があって標本を見ていて単に思いついたものかよくわからないが)。
Heilmann (1927) はちょうどその後ぐらいで、当時は「さすが Lonnberg、目の付け所が違う」と注目を集めた考え方だったらしいことは想像できる。
発生学や遺伝的制御機構が判明してくると次第に意義が薄れてきたのだろう。
Birder (など?) 雑誌にこのような話がしばしば取り上げられるのは選択効果だろうと想像する。つまり印刷物なのでビジュアルでなければいけない。どうしても見た目 (写生など) の特徴がテーマとして好まれやすく、目に見えない機構の議論などは難しい話として敬遠される。(川口氏の表現を少し真似させていただくと) だからいつまで経っても見た目の印象しか話題にならないわけだ。従となる文章など読まなくてもよいので絵を比べて欲しいとなると、印象に頼った話がいつまでも幅をきかすことになる。
[ライチョウの換羽]
年1回換羽を行う鳥が多いが、極北の鳥類・哺乳類では年2回 molt を行う (以下アメリカ綴りで表記する。英語では哺乳類でも同じ用語を使うらしい。日本語では換毛の用語があるが、鳥類・哺乳類に共通した用語はない?)。
総説論文: Beltran et al. (2018) Convergence of biannual moulting strategies across birds and mammals
fig. 1 に環境要求に応じた molt の進化がまとめられている。鳥類を例にとると、
(1) 季節による環境条件が変化しない場合: 連続した molt が可能 (ネズミドリ類で知られている)
(2) 羽毛損傷に季節性がない場合: 年1回の換羽
(3) 羽毛損傷に季節性があり、断熱性の必要性に季節変動がない場合:
(3a) 色彩による配偶者選択の要求がない場合: 年1回の換羽
(3b) 色彩による配偶者選択の要求がある場合: 不完全な年2回の換羽
(4) 羽毛損傷に季節性があり、断熱性の必要性に季節変動がある場合:
(4a) カモフラージュ必要性に季節変動がない場合: 不完全な年2回の換羽
(4b) カモフラージュ必要性に季節変動がある場合: 完全な年2回の換羽
のようになる。ライチョウは (4b) にあたる。table 1 に molt 様式がまとめられていて、continuous shedding (上記 1)、annual molt (年1回の換羽): 変形として catastrophic molt (ペンギン類)、simultaneous molt (ガン・カモの一部など)、
complete biannual molting (完全な年2回の換羽)、
incomplete biannual molting (不完全な年2回の換羽)、
split molt (中断のある場合。哺乳類では知られていないとのこと)。
対応種や引用文献などは見ていただきたい。極地の特に哺乳類を中心とする論文なので我々が普通に出会う中緯度帯の鳥の換羽についてはそれほど詳しくない。
極地では molt に適した期間が短く、捕食危険性や断熱効果を損なうことに伴うエネルギーコストの増加のため熱帯の動物に比べて短時間に molt を行う。molt のコストが高いのでこのような制約が少ない熱帯のような場合はゆっくり molt を行う。このような環境要因から鳥類・哺乳類で molt の戦略に収斂進化が起きていると考えているとのこと。
他に考えるべき要因として、メラニンを含有した羽はケラチン層も厚く摩耗に強い。日光の吸収も強く病原体の増殖に適した温度以上を保ちやすい。結果的に低緯度の色の濃い Gloger (グロージャー) の法則となる。
極地の夏は紫外線が強く、冬は低温でいずれも損傷が進みやすい。そのため環境要因のみで年2回の molt が起き得る理由になる。
白色の羽毛は開けた環境で繁殖する種では日光を吸収しにくいため有利に働く。一方で高速飛行時の対流冷却を起こしにくく、熱負荷の大きい条件では体温を逃がすのに不利に働く可能性がある。
日本のライチョウは体羽は年3回の換羽を行うとのこと (初列風切は1回)。ライチョウ (Bird Research News 2012)。この記事での出典は 西野優子・中村浩志 2011。年3回換羽するライチョウの換羽時期と様式。鳥学会 2011 年度大会要旨集。
Pyle (2007) Revision of Molt and Plumage Terminology in Ptarmigan (Phasianidae: Lagopus spp.) Based on Evolutionary Consideration
によれば Lagopus 属は年3回の換羽を行うと考えられてきた:
"spring molt" (2-6 月の display plumage への換羽)、"summer molt" (7-9 月の隠蔽色への換羽)、"fall molt" (9-11 月の白い羽衣への換羽)。
3回目の換羽について十分記載されてこなかったこと、Humphrey-Parkes の用語 (#カタグロトビの備考 [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] で紹介) と整合性がよくないのでここで記述とともに用語を整理したとのこと。
この論文では Humphrey-Parkes システムを修正して Lagopus 属に対応する prealternate molt, presupplemental molt, prebasic molt の名称を提案。prebasic molt の名称は他の分類群と共通。
性により前2者の順序が異なり、種によって一部のみのものもある。
オスのライチョウが年4回換羽するとの過去の報告 (Johnsen 1929) は確かめられなかった。
複数回の換羽でもたらされる色彩変化による適応的意義については以前から指摘されている通りであろう。
マガモではオス・メスが別の時期に prealternate molt を行うとのことで多少対応性がある。
コオリガモも年3回換羽するとのこと (wikipedia ロシア語版 "羽衣" より)。
Payne et al. (2015) Patterns of Molt in Long-Tailed Ducks (Clangula hyemalis) during Autumn and Winter in the Great Lakes Region, Canada
では秋の換羽を中断するとの解釈のよう。
[換羽・換毛の共通機構]
Wu et al. (2025) Cyclic Renewal in Three Ectodermal Appendage Follicles:Hairs Feathers and Teeth (レビュー) 毛嚢 (hair follicle)、羽嚢 (feather follicle)、歯小嚢 (dental follicle) は収斂進化した周期的な更新 (cyclic renewal) を持った皮膚付属物。表皮と間葉の相互作用で作られる。
刺激に対する換羽・換毛も鳥類・哺乳類で類似していることが知られている。
サメの歯や魚のうろこの再生機構は異なるとのこと。脊椎動物でうろこは何度も独立に進化したが follicle を持たず皮膚の恒常性維持と同じ機構で維持される。羽嚢や毛嚢は外界に適応するため反復更新可能で一段進化した構造と言えるとのこと。周期的な更新のためのモジュールを確立させたとも言えるだろう。ここでも鳥類・哺乳類の共通性と一段と進んだ機能を見ることができる。
うろこは連続して成長することができるが周期的な更新機能は持たないとのこと。換羽と脱皮は現象的に似ていても機構は異なっているよう。換羽の理解を深めようと思えば molt で現象論的情報を検索するよりも follicle の生理機構を学ぶべきなのだろう。遺伝子発現の機構などはおそらく再生医学的に興味が持たれているのではないかと想像する。
関連論文をいくつか紹介: Lin et al. (2013) Feather regeneration as a model for organogenesis 幹細胞からの羽毛再生が臓器形成のモデルになる。羽毛の形態形成など。
Wu et al. (2021) Cyclic growth of dermal papilla and regeneration of follicular mesenchymal components during feather cycling。周期的な更新のメカニズムは鳥類・哺乳類で少し違いがあり、独立に進化したものであることがわかる。幹細胞が活性化されることによって更新サイクルがどのように始まるかなど換羽の理解に役立ちそう。
Widelitz et al. (2019) Morpho-regulation in diverse chicken feather formation: Integrating branching modules and sex hormone-dependent morpho-regulatory modules
羽毛の更新は外界の環境変化への適応と考えられるが3段階が想定できる。ここではホルモンによる羽毛形成の制御、雌雄差を生み出す機構など。
Chuong et al. (2013) Module Based Complexity Formation: Periodic Patterning in Feathers and Hairs のように外界の環境変化に対し、例えば隠蔽や性・社会選択の必要性に応じて衣装を変える機構として、生涯の決まった時期や一定の季節にまとまって起きる換羽が進化した可能性も面白い。
Oh et al. (2015) Regenerative metamorphosis in hairs and feathers: follicle as a programmable biological printer
換羽・換毛によって "変態" を実現することができる。マウスではあまり変化がないために毛の形成プログラムはハードウェア的に決まっているかのように捉えられがちだったが、哺乳類でも明らかな "変態" が見られるものもある。同じ follicle が異なる構造や色彩を生み出すので、ソフトウエア的な部分があると考えられる (プログラムを "reload" する表現になっている)。つまり微細構造や着色は 3D プリンターに似た原理を考えることができるとのこと。
哺乳類の毛の出現は約2億年前と見積もられている。鳥類の方はホットな議論の最中で哺乳類の毛と同じような時期に進化したと一般に考えられている。
ただし羽毛形成は単系統的に起きたことを仮定していると注釈付き。羽毛のような複雑な構造が複数回進化することはあり得ないと常識的に考えそうだが、哺乳類で早い時期に独立に進化したぐらいなので自己組織化のプログラムが多系統で進化した可能性はまだ排除できないのだろう。鳥類以外に現生系統がないため遺伝子レベルで起源が同じか調べるのが難しい。
この点については Xu and Barrett (2025) The origin and early evolution of feathers: implications, uncertainties and future prospects の議論も参照。all modern feathers grow from a follicle, which is considered a key criterion for identifying modern feather とのことで、現代の羽毛は follicle から形成されることが重要な判断基準となっている。
化石に見られるフィラメント状の付属物が follicle から形成されるか明らかでない。
爬虫類のうろこに分岐構造を示すものが知られていない点を考慮すれば ornithischians, pterosaurs の構造は羽毛と呼べるかも知れないが、あくまで相似性を見ていることに注意すべき。一般に使われる系統樹を想定した上で構造物の進化が考察されているが系統樹の妥当性もさらに確認が必要である。
例えばシチメンチョウの "ひげ" は上皮が成長してでき、羽毛を作るものと同じ corneous beta protein (β ケラチン) から作られて羽毛に似た分岐構造を持つが、follicle から形成されないので真の羽毛とはみなされていない。古生物 (ornithischians, pterosaurs) でも同様に follicle から形成されるのであれば明らかに羽毛と呼べるが、そうでない場合は follicle は派生した (進化した) 形質と認識しつつ "現代の羽毛" の定義を見直す必要もあるかも知れない。
羽毛と呼べるものがいつ生まれたかの見解も分かれている。Avemetarsalia の中核となるグループの化石の保存状態がよくなく軟部組織の情報があまり残っていない。原始的なものも含めて羽毛らしきものを持つ系統を包含する系統を考えると起源が非常に古いものになってしまう (pterosaurs が特に問題で、これを包含すると Avemetatarsalia またはそれ以前とならざるを得ない) が本当か?
Avemetatarsalia の出現は 2.45 億年前との見積もりがあるが、羽毛の出現はもっと遅く複数の系統で独立に獲得されたと考える研究者もある。
Avialae 系統に含まれる Anchiornis の羽毛が主に α ケラチンではないかとの未検証結果があり (それならば鳥には含まれないのか?)、もっともそれほど古いサンプルの元来の分子組成が保存されているか疑問である、など書かれている。
Spiekman et al. (2025) Triassic diapsid shows early diversification of skin appendages in reptiles
鳥類とはまったく別系統で外見は一見羽毛に似ているが異なる構造が進化していた証拠。
合わせて過去に羽毛かどうか議論のあった Longisquama はこちらの系統に含まれ、鳥の羽毛の起源とは関係がないことがわかった。
Oh et al. (2015) のレビューの方に戻ると哺乳類の毛と鳥類の羽毛の分子機構の共通性は高く "Agouti domain" (Agouti アグーチ 齧歯目アグーチ科に由来。元来毛皮の色違いをもたらす遺伝部位として命名された) が色彩のパターン形成 (クジャクの目玉模様など) に関わっている。
色彩多形の研究でよく調べられる MC1R も同様に色彩発現に関わっている。いずれも哺乳類の体色調節に現れる遺伝子だが、脳の構造が異なるのと同様に哺乳類と鳥類で体色調節に同じ遺伝子が働いていることは必ずしも自明なことではない。
クジャクの目玉模様が作られるのは奇跡のように思えるが 3D プリンターを知ってしまうと原理が理解できる次第。
構造形成・着色には方向性があるので、例えば縞模様のような羽毛パターンは作りやすいなど特性が現れるのだろう。タカの尾羽の縞模様など間近に見ると確かに 3D プリンターで着色したのではないかと思えてしまう規則性がある感じがする。
仕組みは違うが、カオス写像でマンデルブロ集合を描かれた、あるいは関数の可視化ソフトでわずかなパラメータの違いで新規な模様が現れることに驚かれた方もあるのではないだろうか。follicle の発生過程でもわずかなパラメータの違いでたまたま目玉模様に似たものが生じるとそれを強化する方向に選択が働いて精緻な構造が作られるようになったのではないだろうか。
feather follicle の形態形成の数学的モデル研究: Estavoyer et al. (2025) Mathematical modeling of the feather follicle morphogenetic wave in birds。均衡状態を突破してどのように follicle 形成の波が始まるか。
-
ウズラ
- 学名:Coturnix japonica (コートゥルニークス ヤポニカ) 日本のウズラ
- 属名:coturnix (f) ウズラ
- 種小名:japonica (adj) 日本の (japonicus -icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Japanese Quail
- 備考:
coturnix は o, i が長母音で -tur- がアクセント音節 (コートゥルニークス)。
japonica は短母音のみ (ヤポニカ)。ほとんど学名のみに使われる。伸ばす発音もあり、アクセント部分を伸ばしてもよい。
単形種。
かつては (現在の和名で) ヨーロッパウズラ Coturnix coturnix 英名 Common Quail の亜種 (Coturnix coturnix japonica) とされた。
quail の語源は後世ラテン語の quaccola (ウズラ) に由来。OED によれば 1381 年にすでに現在の形の用例があり大変歴史が古い。こちらでは直接の語源を Anglo-Norman の quaile, quaille や中世フランス語の caille としている。
ロシア語は perepel で古ロシア語 pippalnis で鳥を意味する。ラテン語 papilio チョウ に由来とのこと (Kolyada et al. 2016)。日本のウズラは別名 nemoj perepel で、無言のウズラの意味だが現実とは合わないと解説がある。perepel から派生するロシア名に#ハイタカ perepelyatnik がある。
Coturnix 属は Tetrao Coturnix Linnaeus, 1758 (原記載) の種小名を属名に昇格したもので Bonnaterre (1791) が設けた。
Coturnix communis Bonnaterre, 1791 (参考) の名称があった。
さらに Coturnix vulgaris の学名があり、Blyth 1835 や Bouteille 1843 が用いていた。
これは種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる (#ノスリの備考参照)。
種小名から属名に昇格する場合に種小名を変える必要がないとなって現在の学名になったものだろう。
AviList v2025 - errors, typos で AviList の属名記載の正当性が順次検証されている。
Coturnix は若干不明の点が残っていて AviList でも特に記述されていないが、現代の規約に合わせれば Coturnix Bonnaterre "1790", type Tetrao coturnix Linnaeus 1758 by "absolute tautonymy" と定義するのが正しいだろうとのこと。
Coturnix vulgaris japonica Temminck & Schlegel, 1849 (原記載) は後者の学名を用いていた。ヨーロッパウズラの日本版の位置づけ。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には Coturnix communis の学名が使われており、日本の亜種 (現在は種) は Coturnix communis japonica の表記で和名アカノドウズラの名前がある。
Coturnix communis orientalis Bogdanov, 1884 (参考) とシベリアでの命名もあった。日本のものと同種かは知らないが、Temminck & Schlegel (1849) の命名の方が早かったので japonica が学名に残ることになった模様。
ウズラとヨーロッパウズラの現代的な種分化の研究は Dey et al. (2024) Mitogenomic Insights into the Evolution, Divergence Time, and Ancestral Ranges of Coturnix Quails。
分岐年代は 225 (118-357) 万年前と推定。チベット高原が障壁となって分散過程で分化したものと考えられるが系統的には近く野外で交雑帯の研究も望まれるとのこと。
大西洋の島のヨーロッパウズラにおける大型染色体の大きな領域の逆位と(亜)種分化機構の関係: Sanchez-Donoso et al. (2022) Massive genome inversion drives coexistence of divergent morphs in common quails こちらは1番染色体で、逆位を起こした個体群はより暗色でヨーロッパウズラで普通にみられる長距離の渡りを行わない。(亜)種分化以前に起きたと考えられる。
Ravagni et al. (2025) Large Inversions Shape Diversification and Genome Evolution in Common Quails こちらは2番染色体。1番染色体の逆位は表現型変化をもたらしたが2番染色体ではもたらさなかった。両者を合わせてヨーロッパウズラではゲノム全体の 15.6% が逆位を起こしたとのこと。
特に1番染色体の逆位は地域の条件への適応など、(亜)種分化機構に関わっていると考えられるとのこと。
スペインで在来種のヨーロッパウズラを脅かすウズラ: Japanese Quail threatening Common Quail in Spain (BirdGuides 2025.6.5)。1999 年から 2019 年の間にヨーロッパウズラが 74% 減少したとのこと。私有地でのウズラの狩猟用放鳥が続いている。
ウズラの鳴き声 (さえずり) はアジャパーと聞きなしされることがあるが、(ヨーロッパウズラであるが) クラシック音楽にも出てくる。楽譜の読める方であればメシアンの メシアン 最大にして最高峰のピアノ独奏曲〜「ニワムシクイ」 のウズラのところを見ていただくと面白いと思う。手元に演奏可能な楽器をお持ちであれば特有のリズムをすぐ覚えられるだろう。
3月ごろに動物園の飼育個体がよく鳴いているのを聞いたことがあるが、少し離れたところで飼育員の方に「あれがウズラの声」と話してもさっぱりわからないとのこと。仕事で毎日のように聞かれているはずだが意識しないと印象に残りにくい声なのかも知れない。
独断と偏見の識別講座 第62回 Japanese Quail <ウズラ> (2018) に波多野邦彦氏の音声に関する記述がある。
参考までに Dement'ev and Gladkov (1952) が何と記述しているか調べてみると、ヨーロッパウズラであるが pod'polot', fit'pil'-vit' となっている。やはりどんな音かわかりそうもないが、メスが tyuryuryu または bribit と応じると記載されている。オスがこの声を出す行為を指す動詞が bit' だそうで訳語には「(時計などが) 打つ」のようなものがある。
「水鶏 (くいな = ヒクイナ) のたたき」という日本語があるが、「打つ」意味の動詞が独立に使われているのだろう。
[キジ目と鳥インフルエンザ]
ニワトリは鳥インフルエンザウイルスへの感受性が特に高いことが知られており、巷では単一品種を人為的に選抜したもののためなどの説も出ているが、キジ目共通に生じた免疫応答機能の欠如が原因である可能性が指摘されている。#インドガン備考の [野鳥と鳥インフルエンザ (9) インドガン] 以下の "最新状況" コーナーに紹介した。
この起源は非常に古くキジ目内で 4500-6500 万年前に起きたと推定されている。キジ目の進化と病原体対応にかかわる選択圧にも関係するものと考えられ、生態的にも興味深いのでキジ目内での遺伝子進化や鳥類他系統との類似性などここで紹介された文献で見ていただきたい。
[ウズラ精液の泡抹様物質]
学術用語では proctodeal foam, 分泌腺が proctodeal gland と呼ばれ、ウズラに特有で受精能力を高めると考えられている。
Mason et al. (2025) Proteomic characterisation of Japanese quail's unique seminal foam (preprint) タンパク質成分を調べた研究。対応するニワトリの遺伝子と比較して精子の運動、成熟、DNA 保護に関わる役割を持つタンパク質が見つかった。ニワトリに対応する遺伝子のないウズラ特有のものもいくつか見つかった。免疫反応や炎症の調節に関わるタンパク質も見つかり、精子を抗原から保護したりメスの免疫応答を抑制する効果があると考えられるとのこと。
[鳥類に性的興奮はあるか]
外見で性的興奮状態が判別しやすい哺乳類とは異なり、鳥類が性的興奮を感じているかどうかの客観的判断は難しい。Ball and Balthazart (2011) Sexual arousal, is it for mammals only?
がウズラを用いた研究のレビュー論文を書いている。交尾が期待できる状況 (性的興奮とは言い切れないが) でウズラは食欲を示す行動をとる。この時の脳の活動部位 (当時は放射性標識)、遺伝子発現、ドーパミン放出の関連性から哺乳類同様に性的興奮を感じているのではないかと推定。
オスにメスを見せると medial preoptic areas (視床下部に位置するが発生起源は大脳。哺乳類でも対応部位が食欲、攻撃、不安、生殖に関係する) でドーパミンが増えたとの実験がある。同じ条件で交尾を行わなかった個体もあり、ドーパミンが増えなかったとの結果がある。
fMRI などで脳の活動部位を調べる研究が望まれるとのこと (MRI 装置の中で交尾を期待するか??)。
Sachs (2007) A contextual definition of male sexual arousal 哺乳類でも勃起を伴わなくても性的興奮を感じている可能性もある。また REM 睡眠のように性的興奮がなくても勃起が起きるので実は定義が難しい。
Wysocki and Dudzinska-Nowak (2025) False Mating of Blackbirds (Turdus merula) and Fieldfares (Turdus pilaris)
ニシクロウタドリとノハラツグミの擬交尾 (false copulation) の研究。相手は巣立ち雛だったとかコケを相手にするとのこと。
鳥の交尾が技術が必要なのでトレーニングに役立って適応的などの解釈もあるらしい。
この著者は Brindle et al. (2023) The evolution of masturbation is associated with postcopulatory selection and pathogen avoidance in primates
の自慰の研究も引用している。この研究は霊長類が対象だが系統進化があるらしい。自慰は一見適応的に見えないが行動の進化を促す2つの主要仮説があるそうで、Postcopulatory Selection Hypothesis (Sexual Arousal Hypothesis + Sperm Quality Hypothesis)。自慰行動が劣位の個体が素早く交尾するのに役立つ例がイグアナで知られているとのこと + 精子の質を高める)
と Pathogen Avoidance Hypothesis (病原体を排出する) で、この研究ではいずれも可能性があり、適応的に系統進化する性質と考えている。霊長類やイグアナで知られているならば鳥で見られても不思議でない? (論文の趣旨とはちょっと違うかも知れないが関連して紹介。詳しくはそれぞれの論文を直接参照いただきたい)。
[鳥類胚の形成に働く力]
Caldarelli et al. (2024) Self-organized tissue mechanics underlie embryonic regulation
によるウズラ胚の発生初期の研究で、近距離力である物理的な力 (actomyosin による収縮) が自己組織化的に働いて遠距離の構造形成に関わっている。体の軸の前後はこのように作られる。
[鳥の低温適応とミトコンドリア機能]
Correia et al. (2025) Postnatal development in the cold render bird mitochondria more susceptible to heat stress
ウズラを用いた実験で、生後低温にさらされた中で育った個体はミトコンドリアの高温耐性が低いとのこと。細胞の代謝のレベルで低温適応と高温耐性の間にトレードオフが存在することを示唆するとのこと。
[コリンウズラの名称由来]
外来種でここでは項目として取り上げていないが、コリンウズラ Colinus virginianus Northern Bobwhite (北米が原産) の属学名の由来はウズラ類を指すアステカの言葉 Zolin に由来。
Hernandez (1651) が Colinicuiltic を用いたが de Buffon 1770-1783 がフランス名 "Colin" と短縮したとのこと。Colinus の属名は Goldfuss (1820) が用いたとのこと (The Key to Scientific Names)。
和名も英名とはまったく関係なくこの名称に由来するが、漢字では「古林」と書かれる。漢字での名称を見ると由緒あるように思えてしまうが当て字のよう。
[ウズラの漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 95 VII (藤堂) によれば中国では今では晏 (あん) の文字を添えて2文字で表し、anchun と発音するが晏は低く下がる意味を添えたもの (低い、落ち着く)。
鶉の文字の "じゅん" の部分はこぶくれでずっしりしている意味とのこと。
かつてはキジ目のことを鶉鶏目と呼んでいた。
-
ヤマドリ
- 学名:Syrmaticus soemmerringii (シュルマティクス ソエムメルリンギイ) ゼメリンクの喪裾のついた衣服を着た鳥
- 属名:syrmaticus (adj) 裳裾のついた衣服を着た (syrma -atis (n) 裳裾のついた衣服 < 引きずる -icus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:soemmerringii (属) ゼメリンクの (ラテン語化 -ius を属格化) ドイツの解剖学者、科学者 Samuel Thomas von Soemmerring
- 英名:Copper Pheasant
- 備考:
syrmaticus は短母音のみで -ma- がアクセント音節 (シュルマティクス)。
soemmerringii はラテン語読みならば -rin- がアクセント音節と考えられる (ソエムメルリンギイ) 語末は i が2つ並ぶ発音になる。
原音はアクセントが冒頭だが、ラテン語読みならばここにはアクセントはあり得ないと割り切った方が単純。
旧属名に使われる phasianus は#キジ参照。
かつてはキジと同属で Phasianus soemmerringii Temminck, 1830 が記載時学名。
Syrmaticus 属の記載は Wagler (1832) による。これによると対応するドイツ語は Schleppe (引き裾)。
Schleppe によれば syrma との直接の語源的関係はなさそう。
Erlkoenig によればドイツ語で古く syrma の用例はあり、長い尾との関連があり、schleppe とも説明されている。ラテン語同義に peniculamentum がある。
この syrma はラテン語から取り込んだもののよう。OED によれば英語でも 1753 年に syrma の用例がありラテン語由来とのこと。Wagler (1832) の時代には言語を問わずそれなりに知られた用語だったのかも知れない。ここでは由来となっているラテン語を採用しておく。
syrma は裾をひきずる長い衣装でギリシャやローマ時代に悲劇の役者が着たものを指す (wiktionary)。古ギリシャ語 surma (引きずっているもの) に由来。
Soemmerring は多才な科学者だったようで wikipedia 英語版によれば外科医、解剖学者、人類学者、古生物学者 (化石の記載も行っている) となっている。ヒトの目の黄斑の発見者。23 歳で脳神経の記述を行い学位の一部となった。この研究は現在でも正しいと認められている。
Soemmerring の綴りはドイツ語でも -oe- と o のウムラウト表記の両方がある。
日本名ではゼンメリング、ゾンメリング、ゼマリングなどとも表記されるが、Sommer は英語 summer に相当するもので -mm- は2音に分けて発音しない方が適切だろう。プロイセン出身で出生地は Thorn (Torun) トルン (トルニ) とありポーランド中北部。
ニシコクマルガラスの亜種名にも soemmerringii がある。The Key to Scientific Names によれば鳥の学名に現れるのはヤマドリとこの亜種のみとのこと。
wikipedia ドイツ語版には Soemmerring の学名を持つガゼルなどいくつかの生物学名が紹介されているが、日本固有種のヤマドリに気づく人は少ないようで英語版ともに記述がない。
ヤマドリの別名にアカシトドがあったとのこと (コンサイス鳥名事典)。"シトド" はホオジロ類だけを指すものではなかったよう。他にヤマキジ、オナガの名称もあったとのこと。
[Syrmaticus 属の系統分類]
Syrmaticus 属は尾の長いキジ類5種からなる。例えば台湾のミカドキジ Syrmaticus mikado 英名 Mikado Pheasant が有名。
Zhan et al. (2005)
Molecular Phylogeny of Avian Genus Syrmaticus Based on the Mitochondrial Cytochrome b Gene and Control Region。wikipedia 英語版の情報は少し古く、以下の研究がその後出ている。
Lee et al. (2018) Whole-genome de novo sequencing reveals unique genes that contributed to the adaptive evolution of the Mikado pheasant
ミカドキジの全ゲノム解析が行われ、台湾には約 347 (278-471) 万年前に北から定着したと考えられる。
この論文の fig. 4 に全5種の分子系統樹がある。ヤマドリとの分岐はかなり古く 1059 (900-1448) 万年前と推定される。
この系統解析からは Syrmaticus 属は
オナガキジ、ヤマドリ、ミカドキジ、{カラヤマドリ + ビルマカラヤマドリ} の順になる。最後の2種はほとんど差がない。
オナガキジは中国内陸部に生息するので、この系統を起源としてまだ陸続きであった時代の日本、台湾、中国南部から東南アジア北部に分布し、陸続きでなくなった順に種分化が進んだと考えることができる。
台湾のミカドキジは暗色型で創始個体群が小さかったと考えられる (wikipedia 英語版)。
ミカドキジの現在の標準的な中国名は黒長尾雉 (帝雉も使われる)。
学名命名由来は 原記載。Ogilvie-Grant (1906) により狩猟者から受け取った尾の羽2枚のみを、既知のどの種とも異なることからタイプ標本として記載された。
東京の帝 (明治天皇) がつがいを飼育していると伝えられたが Rothschild は実際に見ることはできなかった。これらの鳥は青くて足が赤いと伝えられ、同じく台湾に生息するサンケイ Lophura swinhoii (現学名) Swinhoe's Pheasant ではないかと推測している。
ややこしいことに英名でほぼ同じような意味となる Imperial Pheasant Lophura imperialis が記載されて使われていた (和名テイオウキジ)。
こちらはベトナムの王朝阮朝 (Nguyen) の第 12 代の皇帝 Khai Dinh に基づくとのこと (The Key to Scientific Names)。
2003 年の研究で雑種と判明し、現在の分類には現れない。中国名では Imperial に "皇" の文字を用いており (wikipedia 英語版、中国語版)、"帝雉" は紛らわしいこともあってミカドキジの方の名称が変更されたのかも知れない。
ミカドキジの wikipedia ロシア語版にある記述は中国語でこれら2者がほぼ同じ意味となることを意味していると考えられる。出典は Beebe (1990) A monograph of the pheasants. Volume 3 とのこと。
mikado の学名は他にヒメミフウズラ Turnix sylvatica Small Buttonquail の亜種名に現れ、こちらは昭和天皇を指すとのこと (The Key to Scientific Names)。現在は通常亜種 davidi のシノニムとされる。
Reichenbach (1853) によりヤマドリに属名 Graphephasianus (graphe 絵画 Gk phasianos キジ Gk) も提唱されたことがあり (この場合単形属になる)、将来の研究で正しいとされる可能性はあるものの、一般的には支持されていない。
上記分子系統樹からは独立属とすることは可能で分岐年代的には他の事例と比較して微妙なところ。もし別属にする場合はオナガキジも一属一種になる。Syrmaticus 属の系統分類は以下のようになる。分岐が少し古いところに空行を入れてある。
ヤマドリ属 Syrmaticus
オナガキジ Syrmaticus reevesii Reeves's Pheasant
ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii Copper Pheasant
ミカドキジ Syrmaticus mikado Mikado Pheasant
カラヤマドリ Syrmaticus ellioti Elliot's Pheasant
ビルマカラヤマドリ Syrmaticus humiae Mrs. Hume's Pheasant
Li et al. (2023) The draft genome of the Temminck's tragopan (Tragopan temminckii) with evolutionary implications
にもゲノム解析によるキジ類の属レベルの分子系統樹がある。この図を見ても分岐年代 1000 万年前を別属にするかちょうど微妙なところにあたることがわかる。
Phasianinae 亜科 Erectile clade の中では Syrmaticus 属と Phasianus 属は Phasianini 族に属する。この族には他に日本に分布しない属も含まれる。
[亜種]
ヤマドリには5亜種が認められている (IOC)。scintillans (輝く、明るい) 亜種ヤマドリ、subrufus (少し赤っぽい) ウスアカヤマドリ、intermedius (中間の) シコクヤマドリ、
soemmerringii (ドイツの解剖学者 Samuel Thomas von Soemmerring に由来) アカヤマドリ、ijimae (Isao Ijima 由来) コシジロヤマドリ、及び亜種不明が日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)にリストされている。
上記の種レベルの分子系統関係を見ても分散能力が非常に低そうなので島レベルで隔離されて比較的簡単に亜種が分化するのだろう。現行の亜種は分布範囲が明確でなく再検討が必要とされる。
亜種ヤマドリは最初に記載された亜種とは異なるので注意が必要。
亜種ヤマドリはキタヤマドリと呼ばれていた時期もあり、この時は亜種ヤマドリの名称はなかった。
記載順の記載時学名: 以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種記載もわかる範囲で含めた。
・Phasianus soemmerringii Temminck, 1830 o 基産地日本。アカヤマドリ
・Phasianus (Graphophasianus) scintillans Gould, 1866 o (原記載)。基産地日本 = 横浜。亜種ヤマドリ
・Phasianus ijimae Dresser, 1902 o (原記載) 基産地 Province of Hiuga, island of Kiusiu コシジロヤマドリ
・Phasianus soemmerringi subrufus Kuroda, 1919 o (原記載) 基産地 Oisan, Province of Suruga, Hondo, Japan ウスアカヤマドリ
・Phasianus soemmerringi intermedius Kuroda, 1919 o (原記載) 基産地 Yunoyamamura, Province of lyo, Shikoku, Japan シコクヤマドリ
・Graphophasianus sommerringi septentrionalis Momiyama, 1923 * (参考) 基産地 本土の北東、北西、中央部 = Kuroda (1932) により scintillans のシノニム
・Graphophasianus scintillans inabaensis Momiyama, 1928 * (参考 1, 2) 基産地 near Tottori, Prov. Inaba, Japan (鳥取近く) = Kuroda (1932) により intermedius のシノニム
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
川路 (2013) Birder 27(1): 34-35 にヤマドリと亜種の記述がある。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代にはヤマドリは3種となっていた (上記リストでコシジロヤマドリまで)。
[鳥の漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 66 VIII 鳥の文字の起源 (藤堂) によれば「鳥」を音読みでチョウと読むのは、長く垂れ下がるものを指して鳥、蔦、吊はいずれも同系由来とのこと。植物で長く垂れ下がるので蔦の文字となった。
島 (tan) と鳥 (ten) も同系語で鳥が羽を休める海中の山にみたてて 山 + 鳥 から島となったとのこと。
「鳥の漢字の意味」はヤマドリの項目に入れるのがふさわしそうなのでここに入れたが、「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の」は漢語原意の長く垂れ下がるものを典拠とし、現実の山鳥にかけたのかも知れないと考えてみた。そのような深い文化的意味があったため高く評価されたのかも知れない。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) ではこの歌は作者不詳、8世紀後半と示されており、文献に現れる「山鳥」の用例の中でも非常に早い。
もともとはもっと抽象的な長く垂れ下がる尾を持つ山の鳥 (歌の文字数の決まりがあるのでこの結合になったのかも) を指して使われたものであったが、現実のヤマドリを指すものと判断されて現在に至っているものかも知れない。
ヤマドリの名称については大橋 (2022) Birder 36(5): 52-53 にも考察がある。上記の歌の作者は柿本人麻呂とされていてネットを検索してもその解説が多いが、あしびきの... の解説 (bou-tou.net 2021) によれば、はっきりと柿本人麻呂の作という証拠はなく、詩人の大岡信も、「人麿の歌が一般にもっている調子とは大変ちがっている」と書いています、とのこと。
どうやら『万葉集』の段階では、「ある本の歌に曰く」と、作者不明だった歌が、平安時代以降、柿本人麻呂が作ったものだと言われるようになったようです、と解説されている。
万葉集に取り入れられたことで、ヤマドリがオス・メス別に寝る考え方が生まれ、知識人の常識とされるようになっていったのかも。
-
キジ (分割された)
- 第8版学名:Phasianus versicolor (パスィアーヌス ウェルスィーコロル) さまざまな色をしたキジ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Phasianus colchicus (パスィアーヌス コルキクス) コルキス地方のキジ
- 第7版亜種学名:Phasianus colchicus versicolor (パスィアーヌス コルキクス ウェルスィーコロル) さまざまな色をしたコルキス地方のキジ (日本産最初の亜種。他亜種あり第8版亜種キジは別亜種)
- 属名:phasianus (m) キジ
- 第8版種小名:versicolor (さまざまな色をした)
- 第7版種小名:colchicus (adj) colchis 地方 (黒海東岸、ジョージア西部) の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 第7版亜種小名:versicolor (さまざまな色をした)
- 英名:Green Pheasant (or) Japanese Pheasant, IOC: Green Pheasant
- 備考:
phasianus は2つの a が長母音で2つめの a にアクセントがある (パースィアーヌス)。
起源となるギリシャ語では phasianos で冒頭が長音。Phasis 川の (鳥) の意味 Phasis の冒頭が長音 (wiktionary より)。ラテン語では帰属の接尾辞 -anus の冒頭が長音のためこの発音になっていると推定できる。
versicolor は短母音のみで -si- がアクセント音節 (ウェルスィーコロル)。伸ばす発音でもアクセント音節を伸ばす。ラテン語の color は英語とは違って短母音のみ。
colchicus は短母音のみで冒頭にアクセント (コルキクス)。
分割のため第7版学名は日本産最初の亜種まで記した。第7版時代は日本の亜種は versicolor にまとめられることもあり、亜種コウライキジ (旧名) colchicus とともに種キジを構成する形になっていた。
新しい種小名は versicolor (さまざまな色をした) となる。海外の主なチェックリストでは IOC version 1.5 以降、HBW/Birdlife 2014 年以降、Howard and Moore 2nd edition 以降、eBird 2022 年以降はこの名称が使われている。
Phasianus versicolor は日本固有種となり、大陸のコウライキジ (旧名) Phasianus colchicus は対馬で自然分布の可能性があるが (ただし対馬でもコウライキジの人為移入が行われた)、日本の他の地域では移入分布となる [Brazil (2009) "Birds of East Asia"]。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Phasianus colchicus は外来種扱いでタイリクキジと新称を与え、対馬は自然分布として認めていない。日本固有種のキジは Phasianus versicolor に改名している。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。
"タイリクキジ" の和名は以前よりあったものを利用して世界分布に整合させたものと想像できるが、同様にカラフトワシ、カラフトフクロウも分布を反映する名称の方がふさわしい感じがする。
タイリクキジはアメリカに移入されサウスダコタ州の州鳥となっている (コンサイス鳥名事典)。
South Dakota State Bird - Who Is The Ring-necked Pheasant (Patrick O'Donnell 2023, 2024) によれば 1943 年に投票で選ばれたとのこと。1908 年に移入されたものだが、しっかり親しまれており在来種でない州鳥を選ぶことに違和感はなかったとのこと。
日本で言えばカササギやシラコバトのようなものだろうか。
亜種も従来通り与えられているが、人工放鳥によって亜種の境界が非常にわかりにくくなっていると言われる。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版のパブリックコメント"分類学上疑問がある国内固有(亜)種について"の項目にも言及があり、鳥類目録の分類は、新たな研究が行われるまで現状維持されるという原則に基づくとのこと。
4亜種あり (IOC)。robustipes (robustus 強い pedis 足) 亜種キジ、tohkaidi (東海道が由来) トウカイキジ、tanensis (種子島が由来) シマキジ、versicolor キュウシュウキジ、及び亜種不明が日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)にリストされている。
かつては robustipes はキタキジと呼ばれた時期もあった。この時代には亜種キジの名称はなかった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代にはキジとコウライキジ (旧名。新称 タイリクキジ) は別種扱いとなっていた。後者の分布は対馬とされていた。
キジ科 Phasianidae などの名称は黒海に注ぐ川の名前から (コンサイス鳥名事典)。The Key to Scientific Names によればキジ類が最初に見つかったのは黒海東岸、ジョージア西部コルキス地方の River Phasis / Rioni River (現 ジョージア) とのこと。ジョージア西部の主要河川。Phasis はこの川の古代ギリシャ語名。
Phasianus colchicus を見つけたのは Argonauts アルゴナウタイ。ギリシア神話においてコルキスの金羊毛を求めてアルゴー船で航海をした英雄たちの総称とのこと。金羊毛というのはギリシア神話に出てくる秘宝のひとつで、翼を持つ金色の羊の毛皮のこと。コルキスの王が所有し、眠らないドラゴンによって守られていたとのこと (wikipedia 日本語版より)。
コルキスはカフカース地方にあった古代グルジアの王国。コルキス人は、青銅器時代中期には既にカフカースに定住していたものと思われる。コルキス王国は、紀元前6世紀から紀元前1世紀にかけて存在した、最初のグルジア国家。川の名前は日本語ではファシス川となっている (wikipedia 日本語版より。地名はいずれもロシア読みのよう)。
語源が同地域に関連する種類に他に #ソリハシシギ (ただし黒海でなくカスピ海沿岸) がある。
例えば AB164626.1 から BLAST を行ってみるとキジとタイリクキジが遺伝的にどの程度異なるかわかる。別種レベルの分岐で妥当そうに見える。同じ BLAST 結果にヤマドリも含まれて大陸種とどの程度異なるかもわかる (こちらの方が違いが大きく、キジとタイリクキジはかなり近い)。
[日本の国鳥]
日本の国鳥がどのように決まったのか、中西悟堂「野鳥記コレクション」I 野鳥と共に pp. 131-135 に資料があったので紹介しておく。これは公式見解というより中西氏から見たメモとして見ていただくととといと思う。
1947.4.22 オースチン博士邸で行われた日本鳥学会例会で決定されたとのこと。
p. 134 で鶴 (タンチョウのこと) も挙がったが日本以外に産する鳥でない。ウグイスも呼び声が高かったとのこと。キジを提案したのは黒田長禮氏であったとのこと。
当時は朝鮮には「朝鮮キジ」が居り、満州には「満州キジ」が居るが、どれも日本のキジとは違う。ただ「キジ」と言われるものは、日本の本州と四国のみにしか繁殖しないと中西氏は記述されていた。ヤマドリもまた日本だけだが山地の深い森林で生活していてあまり人目に触れないが、キジは誰でもよく知っている (原文から一部要約)。
ということで決定に際しては固有性が重視されたことがわかる。ヤマドリを推したのはオースチン博士であったことは別に読んだ。
山科鳥類研究所の標本データベース YIO-17648 などから判断すると、「朝鮮キジ」に対応するのは Phasianus colchicus karpowi 記載時学名 Phasianus karpowi Buturlin, 1904 (原記載) 基産地 Te-lin, southern Manchuria.
記載時は種扱いだったので種相当の名前でよかったのかも知れない。しかし基産地はこちらの方が満州なので不思議さが残る。いずれにしても中西氏が記述した「朝鮮キジ」の概念は前まで使われていたコウライキジとは異なる。
山崎・亀谷 (2023) カモ目・キジ目の新しい種和名 によれば "コウライキジ" はもともと朝鮮半島産亜種 Phasianus colchicus karpowi を指す名称との記述がある (ただし "カラフトライチョウ" とは異なり文献を直接引用していない)。
「満州キジ」は当時の学名で Phasianus colchicus pallasi だったものと思われる。記載時学名 Phasianus torquatus pallasi Rothschild, 1903 (原記載) 基産地 Restricted type locality, lower Sidemi River (Avibase による)。
記載時は Phasianus torquatus が別種とされていたのでその亜種となっていたが統合されて Phasianus colchicus の亜種となった。現在は種コウライキジから改名されてタイリクキジの亜種の扱い。
ラベルを付ける際に亜種扱いが導入されたもので、過去の分類で「朝鮮キジ」は Phasianus colchicus、「満州キジ」は Phasianus torquatus を指して名付けられたものだったかも知れない。
torquatus の意味は他の種でも多用されるように "首飾りのある" で、英名の Ring-necked Pheasant に対応している。
第8版で分離されるまでは日本のキジは Phasianus colchicus の亜種扱いとなり、種キジの学名は Phasianus colchicus となっていた。つまり種レベルでは日本の国鳥がユーラシアに広く分布していたことになる。
wikipedia 英語版では現在の Phasianus colchicus の亜種数が非常に多いため、いくつかにグループ化をしていて pallasi も karpowi も torquatus グループに含まれている。かつて種に分けられたほど大きな違いと考えられておらず、色彩が違う程度とみなされている。
△ カモ目 ANSERIFORMES カモ科 ANATIDAE ▽
-
リュウキュウガモ
- 学名:Dendrocygna javanica (デンドゥロキュグナ ヤウァニカ) ジャワの樹洞に巣をつくる白鳥
- 属名:dendrocygna (合) 樹洞に巣をつくる白鳥 (dendro 木 Gk、cygnus 白鳥)
- 種小名:javanica (adj) ジャワの (javanicus -icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Lesser Whistling Duck
- 備考:
dendrocygna は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみで長母音は現れないと考えられる。-cyg- がアクセント音節と考えられる (デンドゥロキュグナ)。
javanica は短母音のみで "ヤウァニカ"。-va- を伸ばす発音もあるようなので伸ばしても間違いでない。
Dendrocygna 属のタイプ種はオオリュウキュウガモ Dendrocygna arcuata Wandering Whistling Duck。
単形種。日本鳥類目録改訂第8版の配列では先頭で、「カモ」の名前は付いているが系統は離れていることがわかる。
大塚・立松 (2024) Birder 38(12): 38-39 に 2024 年 4-5 月の石垣島での目撃事例が報告されている。近年もそれらしい記録があったことが紹介されているが、確実な記録は約 60 年ぶりとのこと。
図鑑の識別点でもよく首と足が長いと書かれている。属名の由来に含まれる「白鳥」も首の長さを示したものであろう。文献 (#コブハクチョウの備考参照) によると Dendrocygna 属で頸椎の数は 17-18 個とあり、カモ (従来の広い意味の Anas 属で典型的には 16 個) とガン (Anser 属で 18-20 個) の中間にあたる。リュウキュウガモのデータもあり 17 個とのこと。
別名フエフキガモとも呼ばれる (英名に対応)。
Dendrocygna 属を含むカモ類の分子系統解析は Sun et al. (2017) Rapid and recent diversification patterns in Anseriformes birds: Inferred from molecular phylogeny and diversification analyses
も参照。系統的にはカモ類の中で最初に分岐した古いもので、学名から想像されるように典型的なカモ類とハクチョウ類の中間に位置するわけではない。ハクチョウ類は大きく分けるとガン類に含まれ、ハクチョウ類の長い首は採食のために頸椎数を増やして (二次的に) 進化したことがわかる。
きっと誰か調べてそうだが、#コブハクチョウ備考の [鳥類の頸椎] の Woolfenden (1961) Postcranial morphology of the waterfowl の数字を見ながらこの論文の系統樹 (fig. 2) を眺めると大変わかりやすい (コブハクチョウ備考の後に調べたため順序が逆転している。鳥類の頸椎全般についてはコブハクチョウを先にお読みいただくとよい)。
カモ類系統の頸椎数の祖先型はおそらく 16 個で、カモ類の多くも 16 個 (水面採食ガモ) や 17 個 (潜水ガモ。潜水して食物を探すのに多少便利なのだろう) である。オナガガモは例外的でハクチョウ類との一種の収斂進化と言えるかも。一見中間的に見えるツクシガモでも 16 個。
ハクチョウ類の含まれるクレードの古い系統でも Biziura, Nomonyx, Oxyura, Malacorhynchus はいずれも 16 個である
(1961 年当時は系統関係がよくわかっていなかこともわかる)。
これを見るとガン・ハクチョウ類も最初は首が長くなかったことがわかる。頸椎数は実は進化に伴って結構よく保存されている。
変化が見えるのは {ロウバシガン Cereopsis novaehollandiae Cape Barren Goose (オーストラリア) の 19-20 個 + カモハクチョウ Coscoroba coscoroba Coscoroba Swan (南米) の 21 個} (この2種がクレードを作る。これらの学名などで画像検索していただくとあまり馴染みない印象の鳥を見ることができる)
からで、この種を含むクレードから首の長いガン・ハクチョウ類が始まったと考えるとわかりやすい。この後ハクチョウ類とガン類の2つのクレードに分かれるが、ガン類で 18-20 個、ハクチョウ類で 22-25 個とハクチョウ類が特に水面下採食に特化したことがわかる。
ガン類はこの系統 (ロウバシガン以降) の祖先型に近く「もともと首が長かった」形質をそのまま引き継いでいるよう。もちろん他にも役に立つ面があるので (少なくともこの系統では) 首が短くなる方への進化は起きにくかったのだろう。
池内 (1997) Birder 11(1): 27-31 によればヒシクイ、特にオオヒシクイは水底の根を掘って採食する bottom feeder で、確かに適応が現れている感じする。
Anser 属を細かく見ておくと、ハイイロガン 18、マガンやカリガネ 19、ヒシクイ 20 個なので傾向が現れている (ハイイロガンがヨーロッパで馴染みなのでガン類代表とみなしがちだがそのように考えない方がよさそう)。琵琶湖ではコハクチョウと一緒にいて大概寝ているのでそこまで首が長い印象を受けなかったが。
池内氏の記事によればマガンの亜種オオマガン (gambelli) でも同様とのこと。
このグループでは非常に古く (5600 万年前程度) 分岐して外群に近い位置にあたるカササギガン Anseranas semipalmata Magpie Goose (オーストラリアからニューギニア) は 19-20 個で独自に進化したものらしい。
この系統には (分岐年代 4400 万年前程度と相当離れている) カモらしくないツノサケビドリ Anhima cornuta Horned Screamer と カンムリサケビドリ Chauna torquata Southern Screamer が含まれるがカモらしくないためか Woolfenden (1961) では調べられていない。別の出典ではサケビドリは 20 個とあった。
ここに出てくる種類やコクチョウなど、オーストラリアや南米で首の長い水鳥を進化させやすい理由があったのだろうか (たとえば放熱役割は期待できるかも知れない)。
そう思ってみるとツルでもオーストラリアの種類の方が首が長いように見える。参考写真 オーストラリアヅル: Brolga (James Berry 2024)。
新しい系統樹を用いて見ると面白い発見が隠れてそう。
Wang et al. (2025) Analysis of morphological parameters of vertebrae in domestic geese and ducks
に新しい研究があった。家禽のサカツラガンとアヒルの比較。首の長さと頸椎数は両種でかなり違うが形態や機能的にはカモ類の範囲ではあまり違わなかったらしい。少数パラメータの部位による変化の図しか出ていないので今ひとつ詳細不明。頸椎数の実測値もあまりはっきり書かれていない。
[アカリュウキュウガモ]
週間アニマルライフ (1973) pp. 3944-3946 のリュウキュウガモの項目 (安部) に紹介があった。
この項目はおそらく原著で Whistling Duck ではないかと想像できるが、名前の由来と一般的習性以外あまり情報がなく紹介に苦労されたものと思われる。
アカリュウキュウガモ Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling Duck の分布域が非常に広く、メキシコ、西インド諸島、南米、アフリカ、マダガスカル、インド亜大陸の一部 (バングラデシュなど) に隔離分布している。古い系統で古くは赤道帯に広く分布する連続分布だったものが途中が消滅して現在の分布になったものだろうと説明されていた。
気になって調べてみるとなんと2亜種しか認められていない。それほど古い系統ならば遺伝的にはかなり違うものになっているのではと想像するが、おそらく地理的な違いまでまだ調べられておらず分子遺伝学的に亜種に分けるべきなどの話も出てこないのだろう。
EU585646.1 (cyt b) から BLAST を行ってみると Dendrocygna 属内の種は一致率 90% 程度と別属に分けてもよいぐらい違いが大きい。リュウキュウガモ類の分類はおそらく今後検討されることになるだろう。日本では分布の限られた1種のみでしかも迷鳥なので実用上の問題はあまりないかも知れない。
アカリュウキュウガモの分布は現在では複数種に分割されることが多い広義アマサギに似ている感じがする。広義アマサギ同様の分布拡大を果たしたのかも知れない。
-
サカツラガン (海外リストで学名が異なる)
- 第8版学名:Anser cygnoid (アンセル キュグノイド) 白鳥に似たガン
- AviList 学名:Anser cygnoides(アンセル キュグノイーデース) 白鳥に似たガン
- 第7版学名:Anser cygnoides (アンセル キュグノイーデース) 白鳥に似たガン
- 属名:anser (m) ガン
- 第8版種小名:cygnoid (adj) 白鳥に似た (cygnus 白鳥 -oides (接尾辞) 〜に似た を短縮)
- AviList 種小名:cygnoides (adj) 白鳥に似た (cygnus 白鳥 -oides (接尾辞) 〜に似た)
- 英名:Swan Goose
- 備考:
anser は#ハイイロガン参照。
cygnoides の場合は発音は自明で -oides の i, e が長母音となるため "キュグノイーデース" と典型的なラテン語アクセントと発音になる。
cygnoid の場合はそのような規則がなく (-oid は英語では普通だがラテン語的語尾でない)、綴りから o を長母音となる積極的要素もないため、発音規則により冒頭にアクセントになる (キュグノイド または キュグノイード)。
英語風に "シグノイド" と読むと (アクセントは冒頭かも知れないが) i より o にアクセントを置く発音になるため原学名の読み方からはやや離れてしまう。
発音上も cygnoides の方が自然なものになる。やはり伝統的なこちらの方がよいのでは?
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire の英名は Chinese Goose (当時は国名がよく用いられていた)。Seebohm は日本で留鳥だろうと考えていた。
"Fauna Japonica" の 図版 Anser cygnoides ferus の学名が用いられていた。当時は亜種記述方法はまだ確立されておらず、この ferus は "野生の" の意味。本文 では学名に ferus が付いていない。
家禽品種に見られるこぶがないので野生のものと Pallas の記述した race に整合するとのこと。
OED によれば英名は Ray (1678) 年による Willughby, Ornithology のラテン語からの訳に登場するとのことで、Anser cygnoides Hispanicus seu Guineensis 由来で英名は当時のラテン名由来。
和名について中西悟堂「定本・野鳥記」8 p. 257 で誰がつけたのか無風流とあまり評判がよくなかった。"サカツラ" が付く和名ではサカツラトキ Phimosus infuscatus があり、AviList などの英名は Bare-faced Ibis となっているが、風流でないと感じられたのか Avibase の見出しは別名の Whispering Ibis となっている。
属名の Phimosus は "黙らさせられている" でこちらも由来は手綱やくつわ起源であまりよいものでないが、英名の由来は古い学名 Ibis nudifrons (現在は亜種) 由来のよう。"赤い顔の" の語義を用いているのはスウェーデン語など北欧に多い。この名称がかつてあったものと想像できる。
日本語にする際にこれではホオアカトキと同じような名前となっていまうので、"顔" を意味して "サカツラ" を与えたのだろう。ホオアカトキの他言語名では別系統の単語が用いられているものも多く、日本語では "トキ" に相当する語彙が豊富でなかったため訳出が困難だった事情があったのだろう。サカツラトキとサカツラガンの和名がどちらが先に付けられたのかわからないが命名者は同じかも知れない。確かにあまり風流でない感じがする。
[学名の問題]
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Anser cygnoid となっているがこの学名を用いているのは Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) で HBW/BirdLife 2014 以降などはおそらくこれに由来
(#モリツバメの備考参照。モリツバメの場合には ICZN が Linnaeus の記載は短縮形と裁定したものだが、サカツラガンでは Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では短縮形である文献の内部的な証拠は認められないと書いているのでモリツバメの裁定を意識して主張しているものかも知れない)。
IOC version 13.2, Clements などでは Anser cygnoides のまま。IOC 14.2 でも同じ学名が使われている。
"The Key to Scientific Names" によればオリジナルの学名は Anser cygnoides Linnaeus, 1758 であり、印刷時に -es が次の行に分割されないように "cygnoid." と印刷されたのが2種類の名称が生じている原因との説明がある。
Linnaeus 原典 (1758) Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, p. 122。
Linnaeus (1758) を命名の原典と考えると (学名の適格性の要件に 1758 年以降に公表されていることとある) には表記は ANAS の下、Cygnoid. 2. australis. と Cygnoid. β. orientalis. の2タイプが見出しの表記である。
見出しが Cygnoid. のように大文字で始まっているものと小文字のものがあるが、大文字のものは属名の意味というわけではなさそうである (追記: 名詞の種小名は大文字としていた時代があったことを後に知った)。
この見出しは1行のみで、次の行には小見出しが入るため "-es が次の行に分割されないように" (分割して2行に分けることができない) の説明は通用する気がする。他で短い語尾でも分割を行っている見出しは2行使える状況になっている。この種では説明が短く、小見出しがすぐ始まるため短縮せざるを得なかったと解釈できる感じがする。小見出しが入る種は少ない。
この種の歴史的経緯は A Brief History of the Swan Goose (Anser cygnoides) under Domestication in the West (Jonathan M. Thompson 2011) に詳しい。
かなり混乱があったようで 17 世紀に Anser cygnoides Hispanicus seu Guineensis とされていた図版は実はカナダガンであった。Comte Marsili (1726) が Anser Hispanicus seu Cygnoides としたものはリュウキュウガモの1種だったらしい。
Eleazar Albin (1731, 1734) が頭にこぶのあるガンに2種類あるとしており、Willughby (1676) と Albin の言う Anser cygnoides は同じ種類を指していることは確かとのこと。これらの記述の時期は 60 年離れているが記述はほぼ同じ。
Albin には図版があり、現代のサカツラガンそっくりのものを指して The Spanish Goose, or Swan Goose. Anser cygnoides のタイトルで表示している。
Albin は Moscovian Gander and Goose も紹介しており、これはアフリカのガンとの雑種とみられるが学名は与えていない。
Linnaeus (1758) の中に現れる Anser cygnoides. Alb. av. I. p. 89. t. 91 は Albin の Anser cygnoides を指すものであろう。
もう一つ Anser cygneus guineensis. Raj. av. 138. Will. orn. 275. が挙げられている。
いずれも Cygnoid. 2. australis. のタイトルの下に置いているが、
Linnaeus (1758) の言う2つめのタイプ orientalis に Anser chinensis, Anser moschoviticus が入っている。australis と orientalis の地理的な意味と現行の分類の対応などもあまり釈然としない感じも残る。
Linnaeus (1758) の記載した他のガン類の学名では先人の種小名をそのまま用いているものもあるので Cygnoid. への変更の理由はよくわからない。
Dement'ev and Gladkov (1952) では Cygnopsis cygnoid の学名を用い (属名は下記参照)、protonym を Anas cygnoid Linnaeus, 1758 としている。
シノニムとして Anas orientalis Gmelin, 1788 を挙げているが Linnaeus 以前の Anser cygnoides Albin などは触れられていない。
birdforum.net AOS to discard patronyms in English names
にも議論があり、2023.11.6 の投稿によれば、ICZN では言及されておらず Linnaeus の意図も実際は誰にもわからないが、モリツバメなどの ICZN 裁定を見れば ICZN の意図は明らかに見える
(どちらが広く使われているかも議論の対象になるだろう)。しかし Anser cygnoides が公式に改名の対象と認められているというわけではない。
モリツバメなどの例も見た上で、自身の印象では cygnoid とするのは "pedantic" な改名に思える。
Anatidae (birdforum.net) がさらにこの問題を検討しており (2024.7.19 から)、Linnaeus は Fauna Svecica (1761)、
Systema naturae の 1766 年版 Caroli a Linne... systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis
では Cygnoides と表記しているとのこと。
Linnaeus は省略形として使っていたらしいが、同一文献内でない根拠をどのように判断するかなどまだ難しい問題が残ってそうである。
他の例で Psittacus haematod. Linnaeus 1771 を haematodus と裁定された例が紹介されている。
この問題は HBW/BirdLife が変更した時点から取り上げられていたようで、HBW-BirdLife Version 3.0 (November 2018) (2018.11.24) にもある。
GenBank Taxonomy では Anser cygnoides となっており、Anser cygnoid は寄生生物の宿主名として少数が残るのみとなっている (2025.4 現在)。少なくとも市民権は得ていないよう。
AviList (2025.6) では 336 N-45 Anser cygnoid has also been used. The spelling cygnoides is in prevailing usage and thus protected by Article 33.3.1. Even if the argument of prevailing usage were to be discounted, a majority of the community considered it preferable to spell out this intended abbreviation to comply with widespread practice among zoologists in many other animal groups to spell out obvious cases of abbreviations.
とのことで、普及している Anser cygnoides が保護される正当な理由がある。たとえ反論 (Howard and Moore 4th edition などが念頭にあると思われる) があったとしても様々な動物学の分野で、省略形でなく完全な綴りを用いることが広く行われる慣習となっているので、コミュニティの大半がこの慣習に従うことを好んでいるとのこと。
BirdForum で取り上げられてきた論調と同じである。
HBW/BirdLife も AviList 公開に対する声明を同時に出しているので、世界の学名は Anser cygnoides に統一されると考えられる。
[Howard and Moore Checklistについて]
今後の他の分類群にも関係があるので Howard and Moore Checklist of the Birds of the World (H&M) の意図と将来について調べた結果を少し紹介しておく。
このリストは Clements 5th edition が出るまで全亜種を扱った唯一のリストだった。
現在の最新版は 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2)。
Current concerns (H&M 公式サイト。2024年1月時点のものに基づいているが、少なくとも 2022 年段階でほぼ同じ内容だったらしい) によれば、2014年に IOC 総会が東京で開催された時に世界のチェックリストの共通化も議題となった。
同じ議題が 2018 年のバンクーバーの IOC 総会で取り扱われたが H&M リストの母体である The Trust for Avian Systematics (TAS)
の代表は招待されなかった。H&M の副編集長の Les Christidis が代弁してくれると考えていたが利益相反の問題からそうならなかった。そのため TAS は 2014 年以降はこの問題に関わっていない。
世界のチェックリストの共通化をすべきか、可能かは現在も議論の対象である。
H&M は 2003 年から (それ以前は必ずしもそうでなかったが)「生物学的種概念」にできる限り忠実に従う方針で、多少緩めることはあっても 2013/14 段階でも同じ立場をとっていた。
H&M の編集者の哲学では異なる基準に基づくリストがあった方が (議論の余地があり) 科学の発展に役立つとの考えであった。しかし多くのバーダーはチェックリストの共通化を歓迎するだろうことは認める。
もちろん TAS はリストを知的財産として保護する義務もあるが現在ではオープンアクセスが当たり前になってきてウエブサイトで公開して維持するコストも問題となっている。
これらの理由から TAS は世界のチェックリストの共通化にはあまり関わらないと読める方針が述べられている。
15-20 年後に H&M が存続するかどうかはユーザーがどう評価するか、どれだけ需要があるか次第である。
Schweizer et al. (2023) The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the
World: framework for species delimitation
に種の境界をどのように扱っているかと今後の見込みに関する解説がある。
The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World (5th Edition)
への言及もある。H&M 5th edition では十分な生殖隔離をもって種とする方向性が示されている
(ここまでが H&M/TAS の立場の説明)。
2022年9月段階のスレッドであるが
Howard and Moore downloadable spreadsheet (birdforum.net)
によると H&M 4.0, 4.1 はチェックリストをスプレッドシートのファイルで公開していたが約1年前 (2021) に取りやめたとのこと (上記知的財産の問題らしい)。
(2022 年段階の話で) 2016 年以降改訂されておらず新しい種が入らないのでもはや興味がないとのユーザーの意見がある (気になって見てみると確かにオガサワラカワラヒワが別種になっておらずコメントもない)。
定期的更新がなく電子版が無料でなければユーザーは減るだけだろう。最後の更新には非常に手間がかかっているはずで TAS も大規模更新を「二度とやりたくない」と感じていても不思議でない。
世界のチェックリストの共通化こそ保護関係者、鳥類学者、バーダーの視点から進むべき道であると考えるが、知的財産の保護を必要とするグループはなじまないのだろうとの見解が出されている (かなり意訳しているが)。
一方で Howard and Moore が完全になくなってしまうのは惜しいとの意見もある。属より上のレベル (族や亜科) を取り入れているリストは他にない。
別のコメントですべての分類概念は Avibase がすでに網羅して番号を与えており、チェックリスト間の違いはそれを見ればよいだけ (Avibase の taxon grid)。ただ更新には多少のタイムラグがある。
IOC の Master Lists - IOC World Bird List が亜種までカバーした比較リストを出している
との意見や情報が出ていた。
個人的にはこの稿をまとめるにあたり H&M 4th (online) に文献情報も出ているのはありがたいが、新しいものが入っていないので有用性は少し古い情報に限られてしまう。
まとめると IOC と Clements が中心となって世界のチェックリストの共通化を検討しているところ。
H&M はそれには関与せず独自路線をとるが、しかしながらチェックリスト共通化の後追いもせざるを得ない部分もある。財政的には存続も危ぶまれている、というところだろうか。
H&M の初版 (書籍) は 1980 年出版で、昼行性猛禽類の大家である Leslie Brown が前文を書いている。また山階 (1986)「世界鳥類和名辞典」は H&M の分類に従っているなど我々が現在使っている名称にも関係が深い。初版から半世紀近くを経て役割も変わってきたと言えるだろうか。
このような大規模なチェックリストの維持・管理などは手作業レベルでも行えた昔とは異なり、計算機技術に長けた人材も不可欠だろう。Avibase の技術管理者レベルで作業を行える人材がいないと今では時代に追いつけないかも知れない [参考 Lepage et al. (2014) Avibase - a database system for managing and organizing taxonomic concepts]。
McClure et al. (2020) Towards reconciliation of the four world bird lists: hotspots of disagreement in taxonomy of raptors
にも世界のリストの共通化の必要が述べられている。この研究は猛禽類のみを調べているが、H&M と IOC で猛禽類の種類数 (学名の違いの数ではなく) が 52 も違うとのこと。特にフクロウ類で顕著だそうである。H&M の更新頻度が低いため新しい情報が取り込まれていないことも要因と考えている。
ただしこの論文の著者はほとんどがアメリカ、そしてカナダ、オーストラリアが1人ずつとアメリカのリスト (特に eBird や AOU) を念頭に置いている傾向も見られるので少し割り引いて考える必要もあるだろう。ヨーロッパの人は別の見解があるかも知れない。
New unified list of birds - Avilist (BirdForum) の情報 (2025.1.23) によれば H&M は改訂版を出さないと聞いた人があるとのこと。知的財産の考えから有料とするならば商売としても厳しいものになるだろうとのこと。
[過去の実効個体数の変化]
Qi et al. (2025) Whole-genome resequencing reveals the population structure and domestication processes of endemic endangered goose breeds (Anser cygnoides)
20 万年前ぐらいに実効個体数 (Ne) のピークがあり現在よりずっと数が多かった。最終氷期の後に Ne を減らして低いレベルで安定化した。この減少の結果各地の個体群が絶滅した可能性が考えられる。
その他家禽化によって選抜された遺伝子の候補などが挙げられている。
[家禽化]
サカツラガンの家禽化で何が変わったか全ゲノム解析で調べた研究: Chen et al. (2023) Population Structure and Selection Signatures of Domestication in Geese
ヨーロッパの家禽化されたガチョウの方が由来はより複雑で2系統にはシナガチョウも混ざっているとのこと。中国の Yili geese はハイイロガンの方に近い。ヨーロッパの Rhine goose は家禽化されてから両者がかけ合わされたものらしい。
Wen et al. (2023) Origins, timing and introgression of domestic geese revealed by whole genome data
ではシナガチョウの家禽化は 3499 年前、ヨーロッパは 7552 年前と推定される。
家禽化への選択に伴い、神経に関係する遺伝子が強く選択されて向社会的行動 (prosocial behavior) を生み出しているのでは。
飛翔の必要がなくなり、酸素運搬に関わる遺伝子も変化している。家禽は視力も低いが、関連している可能性のある遺伝子も挙げられている。頭の見栄えのこぶも選択の結果だが、野生のツクシガモもこのこぶが社会的地位を表しているとのこと。関連する遺伝子 (EXT1) 変異の候補が見つかっている。
Xu et al. (2024) Transcriptome Profiling Unveils Key Genes Regulating the Growth and Development of Yangzhou Goose Knob でも関連する複数の遺伝子が発現していることが示されている。
身近な家禽としてここに含めておくが、ニワトリの白色レグホンが毎日のように産卵できる仕組みについて: Johnson et al. (2015) The domestic chicken: Causes and consequences of an egg a day
もちろんこの性質は人為的に選抜されたものであるが、白色レグホンでは他の動物ではあまり見られない卵巣ガンが見られ、2.5 年で 30-35% の高率で発生するが、商用のニワトリではそこまで生かされないので通常は見られない。ホルモンや遺伝子の働きの概略を述べている。卵管上皮が反復する卵胞放出で破壊され修復されるため変異が起きやすくなるとの仮説もあるとのこと。
産卵しても抱卵しないことで次の卵胞が発育できるのだが、抱卵する性質 (就巣性 broodiness) を支配する遺伝子は何か。Xu et al. (2010) The dopamine D2 receptor gene polymorphisms associated with chicken broodiness
抱卵する性質はポリジーンだが、遺伝的性質を調べた実験の結果は研究者により異なる。この研究ではドーパミン D2 受容体 (松果体経由でプロラクチンの分泌に関わる) を一つの候補と考えている。
ハトでも同様の研究がある: Yin et al. (2018) Association of Dopamine D2 Receptor Gene Polymorphisms with Reproduction Traits in Domestic Pigeons (Columba livia)。
最新の RNA 転写研究では複雑な機構も報告されている: Tan et al. (2024) Long noncoding RNAs and mRNAs profiling in ovary during laying and broodiness in Taihe Black-Bone Silky Fowls (Gallus gallus Domesticus Brisson)。
産業への応用のために盛んに調べられている分野ではあるが、分子機構まではまだ解明されていない模様。
Liu et al. (2018)
Whole-transcriptome analysis of atrophic ovaries in broody chickens reveals regulatory pathways associated with proliferation and apoptosis
抱卵を行うニワトリで抱卵に伴う卵巣の萎縮機構。
抱卵鳥が抱卵に関係する遺伝子を何か失っているならば、非托卵性に戻ることはできないのでは、と考え抱卵に関係する遺伝子は托卵鳥でも変異があるのではと想像するが、探した範囲では研究は見つからなかった。
卵の構造に「カラザ」があるが、「カラザ」とは?意味や役割などをご紹介 によれば英語由来ではなく、ラテン語 chalaza (霰) < ギリシア語 khalaza (塊) とのこと。英語の chalaza は語源は新ラテン語 chalaza (1695-1705) < ギリシア語 khalaza とのこと (wordreference.com)。
ポルトガル語でも同じなので日本に入ったのはこのルートかも? 多くの言語でそのまま使っているのである意味世界共通の用語と言える。
多くの鳥類で片側の卵巣のみが発達する分子伝達機構が明らかにされた: (ニワトリ) Peng et al. (2023) A PITX2-HTR1B pathway regulates the asymmetric development of female gonads in chickens。
PITX2 (Paired-Like Homeodomain 2) は脊椎動物の左右非対称な発達に関与する因子。
(アヒル、ガチョウ) Ran et al. (2023) Exploring right ovary degeneration in duck and goose embryos by histology and transcriptome dynamics analysis。
卵の殻が水分を逃さない物理的理由: Sun et al. (2025) Unidirectional spontaneous motion of water droplets on eggshell pores 卵の殻の小孔の構造と毛細管現象が水滴を外から内側に運ぶ。
[脊椎動物の腫瘍発生率]
白色レグホンの卵巣腫瘍に関連してこの項目に含めておくが、両生類以降の系統の脊椎動物の腫瘍発生率の系統的研究が発表された: Compton et al. (2024) Cancer Prevalence across Vertebrates (PDF 版のみ。オープンアクセス)。
気になる鳥類を見ると哺乳類に比べて全体的にだいぶ低い。動物園で飼育の鳥で腫瘍が死因のケースをあまり聞かないのはこのような系統的特性が現れているかも。
両生類などでも腫瘍発生は見られ比率も極めて低いわけではない。腫瘍発生率は鳥類の方が爬虫類より低い。特に悪性腫瘍では差が顕著で鳥類では少ない (これらはいずれも 哺乳類 > 爬虫類 > 鳥類 >= 両生類 の順)。
さまざまな変数との相関も調べられているが上位にくるのはやはり哺乳類が中心。
系統樹を用いた表示もありこれもわかりやすい (種については学名でなく英語の通称名で記されている)。鳥類の低さが全体的に目立つが一部高めの系統があり、キジ類・カモ類が中心。新しい系統ではオウム類が少し高い (これは臨床的に報告される知見にも現れている)。
白色レグホンの卵巣腫瘍についても、キジ類はそもそも腫瘍発生率が高めの背景があるためかも知れない。
哺乳類では肉食のものと齧歯類が高い傾向があり霊長類は中間的。鳥類では肉食のものの腫瘍発生率は高くない。
爬虫類で肉食哺乳類に相当する程度高い系統があるが鳥類では (調べられている範囲で) そのような傾向が見られない。哺乳類ではコウモリで発生率が低く、鳥類ではペンギンの低さが目立っていると Abstract にあるが、コウモリ類はその通りのようだがよく知られた種類を取り上げたものの可能性があって系統樹表示ではペンギン類がそれほど目立っているようではない。
Butler et al. (2025) No evidence for Peto's paradox in terrestrial vertebrates
腫瘍発生率が体重によらないとの過去の知見は Peto's paradox と呼ばれるとのこと。この研究ではこの証拠はないとのこと。セキセイインコは体重 30 g なのに体重から予想される腫瘍発生率の 40 倍とのこと。鳥類・哺乳類で体重に対する傾きの傾向は似ていて、体サイズの大型化を可能にする抗腫瘍発生メカニズムが存在する可能性があるとのこと (傾きは同じだが鳥類の方が2桁ぐらい低い)。
このメカニズムは脊椎動物で大イベントである恒温性の獲得に関連があると考えられる。
両生類や爬虫類では再生能力が高いものがあるがこの機構が腫瘍発生にも関連している可能性も考えられる。セキセイインコとニワトリ (こちらは家禽化された品種のため?) は鳥類の中でも特例らしい
(いずれも飼育個体のデータと思われるので、与えている餌と野生生活の食物が異なっている影響もあるかも知れない。セキセイインコとニワトリに通常与えられる餌を考えるといかにもリスクを上げるかも知れない。検討すれば逆に人の食べ物のうち何がよくないかなど判明するかも?)。
個々の種のデータは Compton et al. (2024) と同じようなものが使われており、系統による違いはこちらを見ていただいてよいだろう。
爬虫類には再生能力の高いものがあり (トカゲの尾など)、哺乳類と遺伝子の多くは共通しているので何が異なるのかも興味が持たられている。付属物の完全な再生能力を持つ哺乳類に最も近い系統とのこと: 'Super-healing' animals inspire human treatments (Smriti Mallapaty Nature news 2025.6.20)。もちろん再生医療や幹細胞関連で興味が持たれている。
[サカツラガンの歩き方]
Wang et al. (2025) Study on the characteristics of head and neck movements of geese walking in a straight line at different speeds
家禽のサカツラガンが歩く時にどのように首を振るか調べた研究。提示されている画像を見るとハトほど首振りが目立っていない感じ。ハトとの共通性もあるがハトでは上部頸椎を主に動かすなど異なる点もある。
「世界の鳥 1」(小学館 1985) pp. 150-151 にダチョウの解説があり (柳澤紀夫)、動物園では放飼場の中に小さな溝などがあると、よくそこに落ちて事故になる。全力で走る時も頭はほとんど動かさないでいつも前方をしっかりみすえているが、その時には全く足元を見ていないのである、と記述されていた。
現代では事故が起きにくいように工夫されているかも知れない。動物園などでダチョウを見る際に注意しておいてよいだろう (しかし我々もあまり下を見ずに歩いているようなのでそれほど違わないかも)。
ダチョウの網膜は地平線方向の解像度のみよいことが知られている (#イヌワシ備考の [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] にも登場する Boire et al. (2001) Quantitative Analysis of the Retinal Ganglion Cell Layer in the Ostrich, Struthio camelus こととも整合する。
タカ類が歩く時に下をあまり見ていないらしいのとは少し違う模様。ガン類もおそらく地平線方向の地上性外敵に注意を払う必要があるとともに、地上の食物を探すために首の振り方も中間的なのかも知れない。
[その他]
サカツラガンは現在は Anser 属に分類されているが、Cygnopsis 属 (Johann Friedrich von Brandt 1836 < Cygnus ハクチョウ属の名前 opsis 外見 Gk) が使われていたこともある。これは最初 Cygnus 属の亜属として提唱された名前で、つまりハクチョウ類とされていたことがある。
頸椎数 19 個とある。どちらにしても旧北区のガンの中ではハクチョウの体型に一番近いのでこのような分類になったのだろう。
シナガチョウ Anser cygnoides var. domesticus の原種。
属名の Anser は菊池氏のオリジナルでは (m,f) であったが、anser (wiktionary) では m (男性名詞) とあり、学名でも男性名詞で扱われているようなのでそのようにした。ラテン語全体では女性名詞の用例もあるのかも知れない。
また多くの言語でガンとガチョウは単語レベルでは区別されていないのでガチョウと訳される場合も多いが、ここでは野生種を主に扱うのでガンとした。
サカツラガンのロシア名 sukhonos は sukhoj 乾いた nos 嘴。Kolyada et al. (2016) によれば警戒時体をほとんど水に沈め、首から上だけを出すような行動を示すことから付いた名前ではないかとのこと。
-
ヒシクイ (AviList ではオオヒシクイは独立種)
- 学名:Anser fabalis (アンセル ファバーリス) 豆の (収穫期にやってくる) ガン
- AviList 学名:Anser fabalis (アンセル ファバーリス) 豆の (収穫期にやってくる) ガン (オオヒシクイ) と Anser serrirostris (アンセル セルリローストリス) ぎざぎざの嘴のガン (現在の亜種ヒシクイを含む)
- 属名:anser (m) ガン
- 種小名:fabalis (adj) 豆の (faba (f) 豆 -alis (接尾辞) 〜に関連する)
- AviList 種小名:fabalis (adj) 豆の (faba (f) 豆 -alis (接尾辞) 〜に関連する) と serrirostris (serra ぎざぎざの/鋸歯状の -rostris 嘴の) に分離
- 英名:Bean Goose, IOC, AviList: Tundra Bean Goose (亜種ヒシクイを含むもの) と Taiga Bean Goose (オオヒシクイ) に分離
- 備考:
anser は#ハイイロガン参照。
fabalis は2つめの a が長母音でアクセントもここにある (ファバーリス)。
亜種名の発音は serrirostris は "セルリローストリス" と考えらえる。
middendorffii はラテン語風だと "ミドゥデンドルフフィイ" と考えらえるが、よく知られた人名でドイツ語またはロシア語的発音 (日本語の読み方と同じ) で構わないだろう。
種小名の由来は Pennant (1768)、Latham (1785) の時代から Bean Goose の名前があった。豆の収穫期になるとやってくると Strickland (1858) が記述している (The Key to Scientific Names)。
OED によれば Bean Goose は 1776 年 Pennant, British Zoology が初出で from the likeness of the nail of the bill to a horse bean と豆を好むことが由来。
フランス名では Oie des moissons と明確に小麦なども含む "収穫期" (moisson) を用いている。
ドイツ名は Saatgans と種 (英語 seed に対応) を用いている。
ロシア名 gumennik で gumno (穀物小屋) に由来 (Kolyada et al. 2016)。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Anser segetum、記載時 Anas segetum Gmelin, 1788 (参考) を用いて英名 Bean-Goose としていた。segetum は seges 農地 の。
Anas Fabalis Latham, 1787 (原記載) 基産地 Great Britain の方が早いことがまだ知られていなかった時代の学名と考えられる。
IOC では (IOC で種。14.2 でも同様) ヒシクイ Anser serrirostris (serra ぎざぎざの/鋸歯状の -rostris 嘴の) 英名 Tundra Bean Goose として2亜種を認めている。いずれも日本で記録され、この扱いでは基亜種 serrirostris と rossicus (ロシアの) ヒメヒシクイである。
(IOC で種。14.2 でも同様) オオヒシクイ Anser fabalis 英名 Taiga Bean Goose として3亜種を認めている。日本で記録される亜種はこのうち middendorffii (ロシアの動物学者でシベリアや中央アジアを探検した Aleksandr Fedorovich von Middendorf に由来) オオヒシクイである。
serrirostris の記載は Anser segetum var. serrirostris Gould, 1871 (原記載) 基産地 near Amoy, China。H&M4 でも有効な亜種扱いで記載年は 1852 年に遡るとのこと。
middendorffii は Anser Middendorffii Severtsov, 1873 基産地 eastern Siberia。記載 p. 70 の表、p. 149 に本文記載がある。北東シベリアで Middendorff が採集 (原文 "掘り出し") したもの。
Middendorff 自身は Pallas の用いた学名 Anser grandis で記載したが Pallas の用いたものは Brandt によるとサカツラガンを指していて誤用だったとのこと。
初出学名は Anas grandis Gmelin, 1789 (参考 Great goose シベリア東部にすごい数とある。基産地はカムチャツカ) だったよう。
そのため新しい学名を与えたもの。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではこれらを同種として扱い、Anser fabalis 種ヒシクイの亜種として3亜種を認める立場になっており、IOC 英名とは整合性が悪くなっている。
世界の主要リストでは Clements, AOU, IOC, eBird は種 Anser serrirostris を認める立場で、HBW/BirdLife と Howard and Moore 4th が Anser fabalis serrirostris と亜種扱いにしている。
Working Group Avian Checklists では最初から Anser serrirostris としており、世界的には分離が主流になりそう。
ロシアの現在のチェックリストは別種としていない。
分子系統学研究では Ruokonen et al. (2008) Taxonomy of the bean goose-pink-footed goose は コザクラバシガン Anser brachyrhynchus (brakhus 短い rhunkhos 嘴 Gk) 英名 Pink-footed Goose を含め、これら3種を3つのクレードに分かれ、系統が十分分離していて別種扱いでよいと述べている。3種の外見的類似性は似た環境での収斂進化によるものとみなしている。
もう少し広い範囲のガン類の分子系統は Ottenburghs et al. (2016) A tree of geese: A phylogenomic perspective on the evolutionary history of True Geese が調べている。
この研究ではヒシクイとオオヒシクイの関係は新たに調べられておらず、研究当時の Clements 分類 (2015) に従ってオオヒシクイをヒシクイの亜種として分離した扱いはしていない。Ruokonen et al. (2008) は引用しており、コザクラバシガンを広義のヒシクイの姉妹種、これら全体を species complex としている。これらの間の進化的位置づけを再構成するにはもっと広範なデータが必要としている。
ヒシクイとオオヒシクイをそれぞれ独立種とすべきかについては特に情報のある論文ではない。個人的には独立種としてよい論文 Ruokonen et al. (2008) や海外リストを根拠としてヒシクイとオオヒシクイを別種として取り扱った方が実用的には利便性が高まると感じる
(それぞれ識別困難な種類ではないこと、日本は分布の東端に位置するため両グループの中間型に悩まされることが少ないだろうことも理由に挙げられよう。「十分な量のデータ」が揃うのを待っていてはいつまでも決まらないような気がする...)。
さらに Ottenburghs et al. (2023) Highly differentiated loci resolve phylogenetic relationships in the Bean Goose complex が Anser brachyrhynchus コザクラバシガン、Anser fabalis ヒシクイ、Anser serrirostris の分類上の問題を扱っている。
A. fabalis と A. serrirostris を同種にすると、A. brachyrhynchus を内包してしまって単系統にならないので、
A. fabalis と A. serrirostris は別種にするか、これら全部を1種にして違いは全部亜種扱いにするかのどちらかになる、ということのようである。
また使用する遺伝領域によって結果が異なり、強く分化した部位を使うとこの系統関係になるが他の部位を使うと遺伝子浸透の影響も生じて相互に単系統にならないなどの相違が生じる。
ただしこの解析には (亜種) オオヒシクイは含まれていない。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版のパブリックコメント "亜種和名の原則に関わる問題" で、(現状の) 種ヒシクイと亜種ヒシクイが同じ名称なので実際上も混乱の原因となっているため、亜種ヒシクイにハシブトヒシクイを与える提案がなされたが、長年使われてきた名称なので継続して使用するのが妥当、またハシブトヒシクイは Anser mentalis に対してすでに使われた和名のため不適当との回答であった。
Anser mentalis (顎に特徴がある) の再検討については Ruokonen and Aarvak (2011) Typology Revisited: Historical Taxa of the Bean Goose - Pink-Footed Goose Complex
でなされ、遺伝子型は特定の亜種に同定するまでは至らなかったが独立種とする根拠はないとのことであった。
AviList で別種扱い。この場合の学名は Anser fabalis middendorffii (オオヒシクイの亜種まで含めた表記) と Anser serrirostris (ヒシクイ。第8版和名概念とは包含関係が異なる) で、亜種まで含めると Anser serrirostris serrirostris (亜種ヒシクイ) と Anser serrirostris rossicus (亜種ヒメヒシクイ) となる。
日本ではオオヒシクイがヒシクイの亜種でオオヒシクイが分離されるように見えるが、fabalis の記載の方が古いため世界的には逆で日本で呼ばれる "オオヒシクイ" から "ヒシクイ" が分離される形になる。大変紛らわしいので注意。英名で オオヒシクイ Taiga Bean Goose と ヒシクイ Tundra Bean Goose とする方が現在ではむしろわかりやすい。
判定理由も現状は複雑で、
344 8 Taxon serrirostris (polytypic, including rossicus) is treated as a species separate from Anser fabalis (polytypic, including johanseni and middendorffii) based on available evidence. The species are morphologically diagnosable (de Jong 2019) and ecologically separated to a large extent (Sangster & Oreel 1996).
Genetic data are complicated by a history of introgressive hybridization (Ottenburghs et al. 2020, 2023), rapid speciation (Ottenburghs et al. 2016), and incongruent phylogenetic reconstructions (Ruokenen et al. 2008; Ottenburghs et al. 2016, 2020, 2023).
However, genomic data consistently show A. brachyrhynchus to be nested within the fabalis-serrirostris complex (Ottenburghs et al. 2016, 2023) with highly differentiated genomic regions providing strong support for a 3-species treatment (Ottenburghs et al. 2023): A. fabalis, A. brachyrhynchus, and A. serrirostris.
For taxonomic stability, middendorffii is treated as a subspecies of A. fabalis, but a more comprehensive genomic review is needed to determine if species status is warranted (Ruokenen et al. 2008).
middendorffii は学名の安定性の観点から現状 fabalis の亜種として扱うが将来別種に分離される可能性を残している。
その場合は Anser middendorffii がオオヒシクイの学名となって、日本産ヒシクイから Anser fabalis の学名が消えることになる。独立種となれば英名も Tundra Bean Goose とは別のものになるだろう。
世界の絶滅危惧ランクなどを決めている IUCN は BirdLife の分類を採用しており、BirdLife は AviList に合わせることを示しているので今後ヒシクイとオオヒシクイは別々に評価されることになるだろう。
現状では種ヒシクイとまとめてしまわず、亜種ヒシクイと亜種オオヒシクイと分離して記録しておくのがよいだろう。サンショウクイとリュウキュウサンショウクイの関係と同じ。
日本ではヒシクイは天然記念物。これも分類や名称をあまり細かく変更したくない理由の一つかも知れない。
亜種オオヒシクイは準絶滅危惧 (NT)、亜種ヒシクイは絶滅危惧 II 類 (VU)。世界的には IUCN 3.1 LC 種。
Ottenburghs et al. (2016) Abstract でガン類の近年 (400-200 万年前) の種分化要因が取り上げられている。寒冷化に伴う極地方のツンドラ形成と中緯度帯の草原の広がりを要因と考えている (この現象は多くのグループで見られる)。
オープンアクセスで見られる分子系統樹は Sun et al. (2017) Rapid and recent diversification patterns in Anseriformes birds: Inferred from molecular phylogeny and diversification analyses も参照。
ヒシクイとマガンの中国ポーヤン湖での GPS-GSM 追跡: Zhang et al. (2025) The Fragile First Year: GPS Tracking Identifies Post-Release Survival Risks in Migratory Geese
装着1年以内の生存率がさまざまな因子の影響を受けやすかった。天候では特に風。装着方法ではバックパック方式より首環の方が好適との結果が得られた。
バックパック方式は重心位置や航空力学的特性に影響を与え、空気抵抗を増して余分なエネルギー消費が必要との近年の研究が紹介されている。バックパック方式は渡り前に大量に食べる時期に胸部の膨らみを制限するとの指摘もあるとのこと。
これ以外にも他にもいろいろな情報が得られているはずで別途論文が出てくるのだろう。
-
ハイイロガン
- 学名:Anser anser (アンセル アンセル) ガン
- 属名:anser (m) ガン (かつては灰色のガンの学名だった)
- 種小名:anser (トートニム)
- 英名:Greylag Goose
- 備考:
anser は短母音のみで規則通り "アンセル"。冒頭を伸ばす発音もある。ここでは短母音のみを採用した。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは rubrirostris (ruber 赤い -rostris 嘴の) とされる。
最初に記載された際は Anas anser Linnaeus, 1758 のカモ類とされていた。Anser 属は 1760 年 Brisson により設けられた。
ラテン語 anser はイタリア祖語に想定される *hans 由来と考えられ、ラテン語化の際に *hansez から (h)anser と変化したと議論されている。*hans はインド・ヨーロッパ祖語でガンを指す *gh2ens に由来とのこと。
同じ語源の単語に古代ギリシャ語 khen、英語の gos など がある (wiktionary)。
AviList v2025 - errors, typos で AviList の属名記載の正当性が順次検証されている。Anser の属名はトートノミーとは呼べない。Anser Brisson 1760 のタイプ種は確定されていないのではとの意見。
コンラート・ローレンツ (Konrad Lorenz) が「刷り込み」を発見した種類としても有名
(wikipedia 英語版)。ローレンツの行動学には当時の学問背景が色濃く現れているので多少注意が必要である (#ミサゴの備考 [feather taxis・頭かき] 参照)。
英名の greylag の由来は grey (色から) + lag [ガン (ガチョウ) の古名。これらの鳥を移動させる時に使われた音声に由来] (wiktionary)。つまり Greylag Goose の名称にはガンの意味が二重に入る。ガチョウの原種。
OED によれば 1685 年 Anser Palustris noster, Grey Lagg, dictus とラテン語で記述があった。lag の語源は wiktionary に書かれているほど確かでないとのこと。英国では渡って来るのが遅いため lag の動詞または形容詞 (遅れるなど) の由来も考えられる。19 世紀初めに lag-goose の散発的な用例があるが、おそらく擬人化した "遅いガン" の意味が想定されるとのこと。
廃れてしまった用例に Gill laggoose があってナマケモノを擬人化したものとのこと。"lag" がガチョウを指して広く使われていた証拠はあまりないらしい。leg (脚) の語源説はおそらく俗用法とのこと。
Kessler (1853) p. 89 (#オオハム参照) によれば Anser cinereus Meyer, 1810 (参考。
ここでは Anas Anser Linnaeus, 1758 に登場する ferus 野生のものを指したもの に新称を与えている) の学名 ("灰色のガン") があり、現在の和名 (英名あるいはドイツ語名などとも相互に関係したかも知れない) はこれに由来すると考えるとわかりやすい。Meyer が名付けた学名のため後述の資料のようにドイツ語名由来の可能性が高そう。
当時のロシア名もこの学名に基づき "灰色のガン" でこの名称は現在まで使われている。
Anas Anser Linnaeus, 1758 から昇格して Anser 属を設けた際のトートニムを避けた新名と考えられる (#ノスリの備考参照)。
Anser ferus Schaeffer, 1789 (参考) も同様の措置を行っている。こちらは "野ガン" の意味になる。
Anser vulgaris Pallas, 1811 (参考) の用例があって "普通のガン" の意味だが本種かどうか不明。
Hartert (1910-1922) p. 1278 では当時のドイツ語名 Graugans でハイイロガンの名称と同じ。ドイツからの学問の輸入の際にこの名称がそのまま和名となったのかも知れない。マガンの Blaessgans, Blaessegans (蒼白色のガン) に対比する名称だった。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire で Pallas は千島列島や日本の現地名も挙げているが種類はよくわからない (ヒシクイの項目で登場し、Pallas の述べたものがヒシクイでなければ Blakiston が採集したヒシクイが日本初記録との文脈で現れる)。
Li et al. (2020) Annual migratory patterns of Far East Greylag Geese (Anser anser rubrirostris) revealed by GPS tracking
日本と同亜種ハイイロガンの中国の衛星追跡。
[鳥の編隊飛行の仕組み]
Newbolt et al. (2024) Flow interactions lead to self-organized flight formations disrupted by self-amplifying waves
が鳥の群れ形成の仕組みを扱っている。どこに入れてもよいのだがここで扱われている種類がガン類などの大型種なのでここに含めておく。
模型を使った流体力学実験で、前方の個体の後報に位置する力 (位置がずれた場合に元の位置に戻す復元力) が働き結晶格子のような規則的配列を作る傾向があることが説明できる。しかし全体としては振動のモードがパターンとして生まれて flonons と呼んでいる (結晶中における音波に相当する格子振動を量子化したフォノンに類似の概念)。
この振動が成長すると衝突が起きたり群れを崩壊させることになる (この現象は実際の現象とも対応がある)。個体差を与えるとの個々の個体の位置にはばらつきが生まれるが、この振動の成長が抑制されることがわかった。これは現実でもそうなっているだろう (なお物理学では振動が成長するか否かが非常によく扱われるので物理の話を読む時の着眼点としてよい)。
個々の個体に働く力のミクロのメカニズムが大域的な構造形成を行う自己組織化として扱っている (自己組織化については [#鳥類系統樹2024] の記述も参照)。
流体中の群れについて一般的に成り立つ法則と考えられ、魚の群れの形成などもおそらく同様の構造形成が働くのだろう。もちろん個々の個体が意識を持って行動していないとは言っていない。エネルギー的に最も低い (つまり楽ができる) 位置を選択すれば自然にそのような構造が生まれると解釈するとよい。
これはやはり物理学 (分野的には物性か) の論文と言ってよいだろう。鳥の編隊飛行は結晶格子と同じように捉えることができる。
英文解説記事。
Hardt et al. (2025) Propelling ferrimagnetic domain walls by dynamical frustration
の論文があってこちらは磁性体を構成する磁石の向きが揃う機構を応用している (active matter と呼ばれる。wikipedia 日本語版にも項目があり 自発的に運動する多数の要素からなる集団のこと、あるいはそれを対象とする研究分野の名称である と説明されている)。
短時間で一斉に向きを変えること (例えばハマシギの飛翔など) がなぜ可能なのか、Vicsek et al. (1995) Novel Type of Phase Transition in a System of Self-Driven Particles が回転軸に対する自発的対称性の破れ (回転の右巻き、左巻きが回転軸に対して非対称となる) の考えを提唱し、理論研究によって新しいタイプの相転移が生じることがわかったとのこと。
Hardt et al. の研究では鳥の方向が磁石のスピンのように扱えることからそのような系の特性を調べたもの。例えば右巻きに回ろうとする鳥と逆向きに回ろうとする鳥の間で "dynamical frustration" が生じてもっと大きな規模の構造が形成される。構造はノイズに強いとのこと。
ガンではないがハトの群れのエネルギーコストの研究: Bishop et al. (2025) Pigeons in a flock go cheap: a re-evaluation of the energetics of flying in cluster flocks
ハトが理論的にエネルギー的に効率がよさそうに見える V 字編隊飛行をとらないのでエネルギーを犠牲にしている議論がよく行われるが、著者の加速度計や心拍計による推定結果は必ずしもそうではなかったとの意見論文。羽ばたき回数をエネルギー消費の指標とするのは正しくない可能性がある。少なくとも緩い群れで飛ぶ場合は単独で飛ぶ場合に比べてエネルギー的に不利にはなっていないのではないかとのこと。
[コンラート・ローレンツ Konrad Lorenz とハイイロガン]
Lorenz がハイイロガンなどを用いて刷り込みを研究したことは非常に有名で、著作も多数ある。
その一つ Das Jahr der Graugans (1979) 英訳されて The Year of the Greylag Goose (1979) は邦訳されていないようなので紹介しておく。
いわば写真物語のような形、同一の写真は後の著作にもおそらく現れていて目にしたことがあるものもある。
少しハードルが高いかも知れないが、ロシア語訳 (1984) があって lorenz1984_god_serogo_gusya のようなファイル名で見つけられるのでないかと思う。Panov が前文を書いている。写真が多いので写真を見る分には何語でもそう違わないだろうし、機械翻訳でも十分読めそう。
「ハイイロガンの動物行動学」(大川けい子訳 平凡社 1996) は原書 Hier bin ich - wo bist du? : Ethologie der Graugans (1988)。
#イヌワシ備考の [コンラート・ローレンツのワシ類の記述] でも「ソロモンの指環」を中心に取り上げた。
[首の短い鳥は危険?]
同じ模型でも動かす方向によってタカに見えたりガンに見えたりして、タカに見えるシルエットには逃避反応を示すローレンツとティンバーゲンによる有名な実験をご存じの方も多いだろう。自分が習った時代の本にはよく書いてあった。
その顛末が紹介されていた:
Schleidt and Shalter (2011) The Hawk/Goose Story: The Classical Ethological Experiments of Lorenz and Tinbergen, Revisited
ティンバーゲンの 1951 年の本に出てくるイラストとのこと。シチメンチョウに見せた場合の反応を調べた (Lorenz 1939)。
Oscar Heinroth がニワトリが首が短く尾の長いシルエットをより警戒するとの観察結果を受けて Lorenz が 1937 年に実験したの最初とのこと。つまり Heinroth が仮説の最初の提唱者とのこと。
Lorenz (1939) はシチメンチョウの反応しか述べていないが、Tinbergen はニワトリ類からカモやガンまで一般化してしまったとのこと。Lorenz は速度 (角速度) の遅さも要因と考えたが、
Tinbergen は首が短いことが一番重要な刺激だと結論し、Tinbergen "The Study of Instinct" (1951) の本には Heinroth の観察によると (首の短い) ヨーロッパアマツバメが渡ってきてすぐの時期はベルリン動物園の多くの鳥が逃避行動をとるとの記述まであるとのこと (!)。
Tinbergen の書物はこの世界ではバイブルであったため信じられていたが、1967 年の実験で覆ってしまったとのこと。
Tinbergen の仮説を覆した実験やその後の追試結果や解釈なども述べられている。
Schleidt (1961) の観察では猛禽類よりもむしろ気象バルーンを警戒した。シュバシコウにも反応したのは "短い首仮説" にとって逆説的である。
Tinbergen は仮説を取り下げて selective habituation hypothesis を受け入れ、1965 年にはひなは落ち葉も含め頭上を通り過ぎるものすべてに "生得的" に臆病だが、経験を積むにつれて当たり前の刺激に慣れて恐怖を感じなくなる。しかし猛禽類を見かけることはまれなので慣れが生じないと記していた。
しかし 1951 年の著作があまりにも有名で、訂正が行われず再販されたり他の形で出版・引用されるなど1979 年の教科書にも長く登場していたとのこと。
Lorenz が実験した当時の比較心理学は学習によるものに重点が置かれていて、"短い首" という単純な刺激で猛禽類を見分ける生得的能力があることが衝撃的に受け止められたことが背景にあるとのこと。
"短い首" 仮説を否定する過程そのものが "生得的" 認知 (本能的プログラム) を否定するプロセスそのものとなったとのこと。
著者の実験でも放し飼いのシチメンチョウは毎日出会う犬には慣れるが見慣れない犬には激しく反応するという。ヘビのような形の水撒き用のホースは他の家禽は関心を示さなかったが、シチメンチョウは激しく反
応したという。しかし数時間もすれば慣れてためらいなく上を横切るようになったとのこと。
wikipedia 英語版にも対応する解説があった Hawk/goose effect。
参考になるかも知れない日本語のページ: 高校生物 テインバーゲン「本能の研究」を読む (池田博明 2012)。
Nikolaas Tinbergen の百科事典には Hawk/goose effect で知られているとの記述がある。
なおハイイロガンが卵を転がす行動 (巣の外に出た卵を戻す行動で、途中で転がってしまっても観察者が卵を取り去ってもあたかも卵があるかのように行動を続ける) は Fixed Action Pattern (信号刺激) の典型例のように呼ばれるが、別の解釈も提案されている:
Marken (2002) Looking at behavior through control theory glasses
この著者によれば親鳥から卵が直接見えないので触覚に頼るしかない。突然刺激が消えた場合何が起きるか、人を被検者にしたネットのデモンストレーションサイトがあり、マウスで画面のものを動かす作業の最中に画面から突然マウスカーソルが消えた場合人がどのような行動をするか結果を比べてみよとのこと。
Schleidt and Shalter (2011) の論文では (動かない) 猛禽の絵を貼って衝突防止に用いたり (この効果は Lorenz-Tinbergen でも調べられていないとのこと) 剥製を置くことがあまりにも頻繁に行われているが、1962 年の Loehrl のレビューで意味がないことがすでに述べられているとのこと。
生物学的な方法は "選択的な慣れ" を簡単に起こすとのこと。猛禽があまりにも繁用されているので窓に加工するならばもう少し別のやり方があると述べられている。
参考までに 鳥がガラス窓に飛び込むのを防止するには (バードライフ・インターナショナル東京 2019) では「猛禽類の形のステッカーが、小鳥を怖がらせて追い払う」は俗説とある。猛禽類のデザインは「アート」と捉えた方が楽しめそう。
日本語では「本能の研究」(N.ティンベルヘン著 永野為武訳 三共出版 1957) が最初の紹介のようだがその後の版も訳されているよう。直接この著書からでなくともいろいろな形で紹介されていたはずだが、自分が知ったのはいったいどのルートからだろうか。Tinbergen が仮説を取り下げた後であることは間違いない。今でもこの説が流通しているかも知れないので要注意だろう。
コンラート・ローレンツ Konrad Lorenz、カール・フォン・フリッシュ Karl von Frisch、ニコ・ティンバーゲン Nikolaas Tinbergen 個体的および社会的行動様式の組織化と誘発に関する発見 に与えられた 1973 年のノーベル生理学・医学賞は今から振り返ってみるどうなのだろうか、という論説もある:
Dewsbury (2003) The 1973 Nobel Prize for Physiology or Medicine: Recognition for behavioral science?
行動学に対して初めて与えられたノーベル賞で、人の健康にかかわる行動学 (それゆえ生理学・医学賞) が今後受賞することが期待されたが一つもなかった。3人の受賞にまつわるできごとや論争、現代の視点から見た賞の意義を議論している。
Font (2023) 50 years of the Nobel Prize to Lorenz, Tinbergen, and von Frisch: integrating behavioral function into an ethology for the 21st century
が受賞 50 周年となるはずなのだが動物行動学をやる者はほとんど気づいていない。学問の世界では現実の世界以上に無視されるようになった。Tinbergen の提唱した4つの「なぜ」のうち一つである行動生物学 (社会生物学) のみに置き換わってしまった。
"ethology" は死んだ、あるいは絶滅の縁にあるとすら言われるようになったが正しくない。学生や研究者も "ethologist" よりは自身を evolutionary biologists と呼んでいるなど、ethology の名称を避けている。1930-1940 年代の ethology と連続性はあるが現在は異なるものなっており、他分野との関係など学問領域として定義も難しくなっている。
Tinbergen の提唱した4つの「なぜ」を追求する分野として ethology を用いてよいのではとのこと。
最後の部分の表題に使われている what’s in a name? は#アホウドリの備考参照。何と呼ぼうが動物の行動を解釈する学問であり、名前にそこまでこだわらなくてもよいのでは、の意味を込めているのだろう。
Font (2023) に引用されている Alcock による2000年代初頭の本は、「社会生物学の勝利: 批判者たちはどこで誤ったか」(ジョン・オルコック著 長谷川眞理子訳 新曜社 2004; 原著 The triumph of sociobiology 2001) で読むことができる。
E. O. Wilson (1975) は "Sociobiology, The New Synthesis" (邦訳「社会生物学」) でいみじくも行動生物学の将来進展を予測し (訳本 図1-2; 「社会生物学の勝利」にも引用されている) 1950 年には ethology が全盛であったものが1975年には社会生物学・行動生態学と統合的神経生理学に分離し、2000 年には ethology が衰退しているだろう図を示している。
Alcock は社会生物学・行動生態学からさらに進化心理学の分野が広がったことも記している。
訳者の長谷川氏によると欧米では盛んに議論が起きていたが、日本では目立った議論にならなかったとのこと。文化背景の違いなども挙げられているが、日本にはそのような学問の素地がまだ希薄だったのかも知れない。
社会生物学が成功を収めた一つの背景として、研究者が互いに仮説を競わせることのできる学問構造が内在していた理由もあるだろう。#カッコウ類の托卵あるいは宿主の排除戦術の議論などを見ても大変面白く、新しい研究者にとっても魅力的だったのだろう。
-
マガン
- 学名:Anser albifrons (アンセル アルビフロンス) 白い額のガン
- 属名:anser (m) ガン
- 種小名:albifrons (adj) 白い額の (albus (adj) 白い frons (f) 額)
- 英名:Greater White-fronted Goose
- 備考:
anser は#ハイイロガン参照。
albifrons は albus は短母音で frons は短母音、長母音両方の読みがある。いずれも短母音を採用すれば "アルビフロンス" と考えられる。
発音の聞けるページでは日本語同様アクセントの目立たない発音もあったが、アクセントを置く分 "ビ" を若干長めに発音している例があった。どちらでもよいだろう。
英名に含まれる White-fronted Goose は学名と同じ意味。Greater (マガン) と Lesser (カリガネ) としたもの。
記載時学名 Branta albifrons Scopoli, 1769 (原記載) 基産地 Northern Italy? (Avibase による)。と自身が提唱した Branta 属にまとめていた。
日本ではガン類の基本であってもヨーロッパの多くの地域やスウェーデンでは馴染みの種類ではなく Linnaeus が記載しなかった模様。一方カリガネの方は Linnaeus (1758) の命名。
"Fauna Japonica" には短く 記述 がある。ヨーロッパのものと特に違いはない。フランス語名 l'oie rieuse (笑うガン)。この名称は現在も使われており、wikipedia フランス語版では鳴き声が音楽的であるとのこと。
5亜種あり (IOC)。
日本で記録されるものは基亜種 albifrons 亜種マガン、及び亜種不明とされる。
亜種 gambelli (アメリカの探検家・博物学者の William Gambel, Jr. に由来) オオマガン が検討亜種に含まれている。
-
カリガネ
- 学名:Anser erythropus (アンセル エリュトゥロプース) 赤い足のガン
- 属名:anser (m) ガン
- 種小名:erythropus (合) 赤い足の (erythro- (接頭辞) 赤い pous 足 Gk)
- 英名:Lesser White-fronted Goose
- 備考:
anser は#ハイイロガン参照。
erythropus は -ry- の音節にアクセントがある (エリュトゥロプース)。-pus は#ナンキンオシ参照。伸ばす方を採用した。
記載時学名 Anas erythropus Linnaeus (1758) (原記載) 基産地 Restricted type locality. North Sweden. Lonnberg, Ibis, 1913, p. 401-402 (スウェーデンに限定。Avibase による)。Linnaeus はヨーロッパ北部としていた。
単形種。
絶滅危惧 IB 類 (EN)。IUCN 3.1 で VU 種。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では学名を Anser minutus Naumann, 1842 としていた。
この学名はそれなりに使われていたようで、対応する英名 Dwarf Goose の用例 (1915) もあった。
Hartert (1910-1922) p. 1282 は多数の学名が挙げられており、かつては Linnaeus (1758) の記載がカリガネを指すかマガンを指すか議論があったらしく、Lonnberg (1913) がカリガネと判定したとのこと。
Linnaeus の用いた Anas 属からの移動に伴う新名ではなかったよう。
Linnaeus (1758) の記載の不定性があって確実に同定できる記載が何種類も提案されていたものらしい。この書籍ではドイツ語名 Zwerggans (英語 Dwarf Goose と同じ) または Kleine Blaessgans (小型のマガン) となっていた。Linnaeus (1758) を有効とみなして現在の学名に落ち着いたよう。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によればマガンの別名がカリガネで、現在のカリガネはコカリガネの名前が付けられていた。
多数のマガンの中でカリガネを探すのが困難なほど似ていることを考えると、カリガネとコカリガネの旧名称は納得できる。
カリガネの声は聞いたことがないが (マガンの群れの中で鳴いても多分気づいていない)、もともとはマガンを指していたと考えると音声由来も納得できる。
-
インドガン
- 学名:Anser indicus (アンセル インディクス) インドのガン
- 属名:anser (m) ガン
- 種小名:indicus (adj) インドの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Bar-headed Goose
- 備考:
anser は#ハイイロガン参照。
indicus は短母音のみで冒頭にアクセントがある (インディクス)。
記載時学名 Anas indica Latham, 1790 (原記載) 基産地 India in winter, and Tibet。原記載に英名の Bar-headed Goose が示されており、学名以前からあった英名がそのまま使われている。当時のインドは東インド会社時代で英名の方が先にあったのは不思議ではない。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
[インドガンの高所適応]
標高 8000 m 以上の低酸素環境のヒマラヤ山脈を超える、世界最高の高さを飛ぶ鳥として有名 (wikipedia 日本語版)。最近の文献では例えば Hawkes et al. (2011) The trans-Himalayan ights of bar-headed geese (Anser indicus)
で衛星追跡の結果が見られる。風の助けを借りず、むしろ風の弱い条件で自身の飛行能力でヒマラヤ山脈を超えるとのことである。8000 m の数字はおそらくやや誇張で、これらの研究によれば 6000 m 以下の谷を主に通っているとのこと。7290 m の記録はあるそうである (wikipedia 英語版)。
このためどのような生理機構で高所順応をしているのか注目され、古くから研究されている。
呼吸器の機能も低酸素状態でも働くように最適化され、心筋への毛細血管も低地に住む鳥に比べて多いとのこと。
血液中で酸素を運ぶヘモグロビンも他のガン類と異なる変異があり、酸素との結合性を増しているとのこと。[Natarajan et al. (2018) Molecular basis of hemoglobin adaptation in the high-flying bar-headed goose]。
Butler (2016) The physiological basis of bird flight
にも高所適応に限らず飛翔に必要な生理機能の総説がある。インドガンが定常的に高所を選んで飛んでいる証拠はないとのこと。それでも 5500 m で自力の羽ばたき飛行を行えるのは大したものであると記されている。トラッキングデータから例外的に高く上昇する際に心拍数は上がらず、好適な風の助けで上昇したものであることを裏付けるとのこと (ローラーコースターのようなものとの比喩も使われる)。
ヒトなどでは過換気により血中の CO2 が下がると (hypocapnia) 脳への血流が下がるが、カモやインドガンでは起きないとのこと。カモやインドガンでは低酸素状態ではヒトなどより脳への血流が増し、これらの効果で哺乳類よりずっと高所での低酸素に強いとのこと。
低酸素・血中の CO2 低下でインドガンではよりアルカローシスが強く起きてヘモグロビンの酸素結合性との効果と合わさって組織への酸素供給を維持、あるいは高めることさえできるとのこと。
鳥には気のうシステムがあるため、との説明するのはおそらく不十分で、このような生理的適応の効果が大きい。原理的には他のガンにできない 9000 m を飛行する能力はあるが実際にはわざわざ高いところを飛ぶわけではない。
Hawkes et al. (2017) Do Bar-Headed Geese Train for High Altitude Flights? 渡りの前に人間のような高所トレーニングが必要か。そもそも余力がある感じに見えるがホルモンによる季節変動など関心が持たれている。
Parr et al. (2019) Tackling the Tibetan Plateau in a down suit: insights into thermoregulation by bar-headed geese during migration
高所の寒冷な場所を飛ぶ時も体温の日内変動パターンはあまり変わらず安定している。極度な環境変化にも適応できる体温調節を行っていると考えられる。
Wang et al. (2020) First de novo whole genome sequencing and assembly of the bar-headed goose 初のゲノム解析。正の選択を受けている遺伝子の候補など。
Zhang et al. (2022) Chromosome-level genome assembly of the bar-headed goose (Anser indicus) もより高精度な解析。臓器固有の発現も調べられているが機能の解析はこれからの段階か。
[野鳥と鳥インフルエンザ (1)]
このように生態・生理的には大変興味深い種であるが、"bar-headed goose" (インドガン) の名前はまったく違う分野の研究者にも大変よく知られていたことがある (現在でもそうかもしれない)。
近年世界のさまざまな地域で鳥類 (および一部の哺乳類) を危機に晒している鳥インフルエンザに関係する話である。
wikipedia 英語版の記事 2020-2023 H5N8 outbreak
にあるように、2020 年から 2021 年にかけて世界で大規模な感染爆発が起きたことは記憶に新しい。この時の株は H5N8 であったが、2021-2022 年の冬から夏近くにかけて H5N1 株がヨーロッパで水鳥コロニーに壊滅的な被害を与えた。そしてヨーロッパから北米にも広がって多くの種類の鳥を犠牲にした。
Caliendo et al. (2022) Transatlantic spread of highly pathogenic avian influenza H5N1 by wild birds from Europe to North America in 2021 北大西洋の渡りでどのように運ばれたかが Fig. 4 に出ている。
(#ハクトウワシの備考も参照)。
ギリシャのペリカンコロニーで鳥インフルエンザ集団死 ハイイロペリカン 600 羽近くが死んだ。
Bird flu has killed nearly 1,500 threatened Caspian terns on Lake Michigan islands
ミシガン州の湖で 1500 羽近いオニアジサシ (英名はカスピ海由来だが北米にも生息する) が犠牲となった。神経症状で震える姿や、それでも抱卵しようとする中で亡くなった姿が記録されている。
多数の経験豊富な成鳥を失い、個体群に与える影響がどれほどのものか想像がつかないとのこと。
関連した論文報告 (地域は異なる): Haman et al. (2024) A comprehensive epidemiological approach documenting an outbreak of H5N1 highly pathogenic avian influenza virus clade 2.3.4.4b among gulls, terns, and harbor seals in the Northeastern Pacific (2024.11.6)
ワシントン州の Rat Island での 2023 年の大発生によってオニアジサシのコロニー個体群の成鳥の少なくとも 56% が死亡。それ以降繁殖に成功していない。
2023 年の発生で太平洋フライウエイのオニアジサシの 10-14% の個体が死亡したと推測している。
もう1種ワシカモメ (雑種とある) も影響を受けたが影響は相対的に小さかった。
オレゴン州のカモメ類での発生が発端と推定され、その後ワシントン州に及んだことが分子系統解析からもフィールドデータからも裏付けられた。この研究では鳥から海の哺乳類への複数回の導入があったと推定される。
オランダでサンドイッチアジサシ Thalasseus sandvicensis 英名 Sandwich Tern のコロニーが犠牲となり、長年保護に取り組んできたチームを嘆かせた。Rijks et al. (2022) Mass Mortality Caused by Highly Pathogenic Influenza A(H5N1) Virus in Sandwich Terns, the Netherlands, 2022、記事 Kolonie grote sterns op Texel weggevaagd door vogelgriep:
テクセルの自然保護区 De Petten のサンドイッチアジサシの繁殖コロニーは、鳥インフルエンザによって一掃された。7000 羽の鳥のうち、3000 羽が死んでいるのが発見された。残りは海で死んで浮いているか、離れて移動していると考えられる。
Avian Flu Threatens Seabird Nesting Colonies on Both Sides of the Atlantic (Audubon の記事): アジサシ類が特に壊滅的被害を受けている。
個体が長命で子の数の少ない生存戦略は、一時的な天候悪化や食物不足には有利だが鳥インフルエンザ流行のような場合にリスク要因になる。
病気そのもののコントロールは難しいが、人為要因による環境悪化などの他の要因が個体数回復を遅らせるのでそれを防ぐのはよい手段である。
同じように集団繁殖するニシツノメドリも心配である (メーン州で失われた個体群が 1970 年代に復元されたもの) とのこと。
これはさらに南米に広がってペルーなどで大規模な集団死が発生した。
Bird flu kills almost 14,000 pelicans, seabirds in Peru (2022年11月の記事)、
Peru reports hundreds of sea lion deaths due to bird flu (アシカの集団死、2023年2月の記事)。
日本でも大きな影響を与えていることは報道でご存じであろう (幸いにこれまでのところヨーロッパやアメリカのような壊滅的な野鳥への影響は日本ではあまりないが、2022-2023 年の鹿児島県出水では1月の段階でツル 1421 羽が回収され、越冬地を変えたツルもあるらしいと報道があった。また北海道でオジロワシなど貴重種も失われている)。
ヨーロッパ (ノルウエー) のオジロワシについては Boe et al. (2024) Emergence of highly pathogenic avian influenza viruses H5N1 and H5N5 in white-tailed eagles, 2021-2023
を参照。英国の海鳥コロニーでの集団死に関連し、それらの鳥を食した感染経路が考えられる。
神経症状を示すオジロワシのビデオへのリンクもある。肉眼解剖的な所見がないが PCR で調べると全身の多臓器でウイルスが増殖。
2024 年初頭に南米からさらに南極大陸本土に達してしまった。 'We’re going to see some haunting images': Bird flu has reached Antarctica (Candice Marshall, Australian Geographic 2024)。
Avian influenza virus is adapting to spread to marine mammals (2024 年論文へのリンクもあり)。
気候変動の脅威に晒されている最中に病原体とも戦わねばならない。
[野鳥と鳥インフルエンザ (2) 高病原性と低病原性]
最近ではあまりに毎年のように起きているため、「野鳥は本来鳥インフルエンザウイルスを持っているもので、感染するのは運が悪いだけ」のような印象を持たれる方もあるだろう。
ヒトの場合にはインフルエンザウイルス (*1) が人から人への感染で維持されており、時折新型インフルエンザが現れてパンデミックとなる点は上記印象でほぼ合っていると考えてよい。有史以来、そしておそらく有史以前からこの関係は続いてきたのであろう。
それでは現在問題となっている鳥インフルエンザも同じように考えてよいのだろうか。忘れ去られた情報も多いと思われるのでここで少し整理しておきたい。
まず報道などで使われる用語がかつて非常に紛らわしいものであったため改めて注意を促しておく (この時代に知識を得られた方は要再確認)。
高病原性鳥インフルエンザという用語があるが、これは行政用語であって科学的な概念や世界で使われる名称とは必ずしも対応していない (いなかった)。
この定義は家畜伝染病予防法でなされているもので、2011年4月に改正される以前は H5、H7 亜型のウイルスをすべて高病原性鳥インフルエンザと呼んでいた。
当時はすでに鳥インフルエンザの世界進展の時期であり、日本の用語と海外の名称が異なるためややこしい状況が生じていた。現在の定義は 我が国における鳥インフルエンザの分類 を参照。
海外では強毒の高いものを HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) そのまま訳すと高病原性鳥インフルエンザになるが、2011 年以前の日本の用語では毒性にかかわらず H5、H7 亜型のウイルスをすべてこう呼んでいた。
そのため「高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)」のように略すのは少なくとも従来は間違っていたわけである。
これは H5、H7 型のウイルスは最初はそもそも無害であっても養鶏場で感染を繰り返すうちに強毒化することがあることが知られていたためであり、無害であっても H5、H7 亜型のウイルスを検出した場合は届け出て法律に定められた措置をとる必要があることによる。
国際的な分類では弱毒の鳥インフルエンザウイルスは LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza) と呼ばれており毒性と名称が整合している。H5、H7 型のように届け出を要するウイルスを意味する場合には N (notifiable) を補って LPNAI と呼ぶ。以前の日本の分類で高病原性鳥インフルエンザ
(弱毒タイプ) が LPNAI に相当していた。
現在の日本の名称では LPNAI に相当するものは法定伝染病の低病原性鳥インフルエンザ (LPAI) となっていて、H5、H7 亜型以外は届出伝染病の鳥インフルエンザとなっている。国際的な定義に合致するようになったのは HPAI の方のようである。この文書も含めて「鳥インフルエンザ」と言う場合は届出伝染病の鳥インフルエンザを指すわけではなく、もっと広い意味で使っていることはご注意いただきたい。
かつての報道では「強毒の」や「毒性の強い」をよく補っていたが、これは当時の高病原性鳥インフルエンザには弱毒のものも含まれていたためで、同じことを冗長に言っていたわけではない。
現在では少なくとも高病原性に関しては日本の用語と海外の用語が同じ意味になったため、高病原性鳥インフルエンザ (ウイルス) を指して HPAI を使うことにする。また強毒性の同意語として高病原性も使うことにする。
[野鳥と鳥インフルエンザ (3) 高病原性はなぜ生じる]
さて「養鶏場で感染を繰り返すうちに強毒化する」ことの分子機構も判明している。また生態学的には強毒のウイルスは通常生態学的に安定状態とならない (宿主を即座に殺してしまうと病原体自身も死滅してしまうため) が、養鶏場のような本来あり得ないほどの高密度であれば宿主が死ぬ前に別の個体に感染させることができて病原体自身も生き延びることができる。
これは野外のような通常の条件では低病原性しか生態学的には安定解を持たない、と表現しなおすこともできる。養鶏場のような特殊な条件でのみ高病原性の安定解が存在するのである。
[これはプラム「美の進化」(#エトロフウミスズメの備考参照) に対する批判「ランナウェイ過程は、メスに選別コストがわずかでもあると、大きな装飾の安定的な平衡点をもてない」と同じようなことを表していると考えていただいてよい。
自然界で高病原性のウイルスがたまたま生じても、それは平衡点にはなり得ないのでいずれ安定な低病原性に変異してゆくことを示している (それにどれだけの時間を要するかは平衡点理論は教えてくれない)]。
(ここからしばらくは少し高度なので最初は飛ばしていただいてよい)
強毒化の分子機構についても多少補足しておこう。インフルエンザウイルスではヘマグルチニン (HA、後にもう少し詳しい説明あり) の遺伝子から翻訳されたタンパク質 (HA0) を持つウイルスそのものには感染性がなく、宿主の持つ酵素によって2つに分割され、HA1, HA2 となることで感染性を持つウイルス粒子となる。
この分離される部位のことを開裂部位 (cleavage site) と呼ぶ。HA0 を開裂するためには一部の臓器に存在する分解酵素トリプシンが必要である。一般的なインフルエンザウイルスが特定の臓器 (例えばヒトでは呼吸器、鳥では腸管) で主に増殖するのはこの性質による。
高病原性鳥インフルエンザでは開裂部位に塩基性アミノ酸 (リジン K、アルギニン R: それぞれ1文字略号も示す) が並び、塩基性アミノ酸 (basic amino acids) のアミノ基は水素イオンと結合して正の電荷を持って互いに反発しあうため、開裂がより容易に起きる。そのため特定の臓器だけでなくあらゆる臓器に存在する一般的なタンパク質分解酵素で簡単に開裂が起きてしまう。
これは高病原性鳥インフルエンザが全身のあらゆる細胞で増殖可能である原理である (海外のバーダーなども参加するメーリングリストでもこのような用語は普通に飛び交っていた。何のことかわからない人もあったかも知れない)。
全身のあらゆる細胞には中枢神経細胞も含まれ、高病原性鳥インフルエンザに感染した鳥に特有の神経症状が現れるのはこの性質による。
また心筋細胞や重要臓器でも増殖するため、命にかかわることも理解いただけるであろう。
HPAI H5N1 で死亡したヨーロッパノスリの研究がある: Caliendo et al. (2022) Pathology and virology of natural highly pathogenic avian influenza H5N8 infection in wild Common buzzards (Buteo buteo)。11羽中9羽に脳の壊死、7羽に心筋壊死が見られた。
少なくとも H5 亜型においては低病原性ウイルスの HA 開裂部位の塩基配列に比較的少数の変異が加わるだけで塩基性アミノ酸が並ぶようになる。実験的にもニワトリに継代接種を行うことで LPAI が HPAI に変化することが示された
[Ito et al. (2001) Generation of a Highly Pathogenic Avian Influenza A Virus from an Avirulent Field Isolate by Passaging in Chickens。これが実証されたのは世界初だったとのこと。10回弱程度の変異が起きると K と R ばかりが並ぶウイルスができ得る様子がわかる]。
これが H5、H7 亜型が強毒化しやすい原因と考えられる。
ただし毒性には他の遺伝子も関連があり (例えばウイルスを増殖させるポリメラーゼ遺伝子) HA の開裂部位のみが毒性や宿主特異性をすべて決定するわけではないが、上記メカニズムは現在問題の高病原性 H5 に関係するものなので話だけでも知っておいてよいだろう (*2)。
[野鳥と鳥インフルエンザ (4) 自然界の高病原性鳥インフルエンザの由来]
ここまでの説明をある程度理解していただければ、自然界に高病原性鳥インフルエンザはもともと存在しないこと、そして人工的条件で生まれ、野生動物に持ち込まれた病気であることを納得していただけるであろう。
高病原性鳥インフルエンザとは人が家畜を扱うようになって生まれたもので、鳥インフルエンザウイルスは長年月に渡って水鳥にとってほとんど無害なもの (つまり低病原性の平衡状態) だったのである。
歴史的には高病原性鳥インフルエンザがかつて養鶏場から野外流出してアジサシ類の集団死が起きた程度のことはあったが、病原性があまりにも高かったためそれ以上に広がらず、現在のような異常な状態には至らなかった。現在の状況がいかに異常であるかは過去の事例が示してくれている。
現在の異常事態は自然に起きた「天災」ではなく、人為がもたらしたものであることを改めて理解しておきたいし、自信を持ってそのように説明していただいてよい。
[野鳥と鳥インフルエンザ (5) (鳥)インフルエンザの亜型の意味]
さて、H5N1 とか H5N8 とかは何なのか、いったい何が違うのか、それとも実質同じものなのか疑問をお持ちの方も多いであろう。復習になる方も多いと思うがインフルエンザウイルスについて簡単に整理しておく。よくご存じの方は読み飛ばしていただいて構わない。
インフルエンザウイルスには A-D の型があるが、ここで問題となるのは A 型なので A 型のみを扱う (この「型」が「属」に対応していて、インフルエンザウイルス全体では4属4種だそうである)。鳥インフルエンザは A 型。B 型はほとんどヒトのみに感染し病原性も弱め、など。
新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) もインフルエンザウイルスも一本鎖 RNA ウイルスである点は共通しているが、SARS-CoV-2 では1セグメントのみからなる遺伝子構造であるのに対して、インフルエンザウイルスは8個のセグメント (分節。別々の RNA 分子) からなるずっと複雑な構造を持っている。
SARS-CoV-2 の場合には RNA の複製の際に生じるエラーで変異が積み重なって新しい株が生まれる仕組みだが、インフルエンザウイルスの場合は複数のセグメントに分かれているために RNA の複製の際に生じるエラー以外にも新しいタイプのウイルスを作る機構が存在する。変異速度を上げて宿主の免疫から逃れて生き残るのがインフルエンザウイルスの生き残り戦略と言ってもよいだろう。
同じ細胞が2つの異なったインフルエンザウイルスに同時感染した場合、複数のセグメントの間で入れ替わりが生じることがある (遺伝子再集合 reassortment という; お菓子などの「アソート」と同じ。ばらばらになった混ぜこぜのセグメントが再構成される時に新しい組み合わせが生じる *3)。遺伝子組み換えとは意味が違うので注意。
インフルエンザウイルスの H というのは ヘマグルチニン (HA: haemagglutinin) のことで、要するにウイルスが細胞に付着する機能を果たす部分である。
N は ノイラミニダーゼ (NA: neuraminidase) のことで、細胞内で増殖したウイルスが細胞表面に現れたものを切り出してウイルス粒子にする酵素のこと。つまりこの酵素を阻害すればウイルスの増殖を抑えることができ、ノイラミニダーゼ阻害剤という一連の薬剤 (商品名ではタミフルやリレンザなど) はこの酵素を標的としたものである (*4)。
HA と NA には抗原性の異なる (現代では生物の分類と同様に分子系統樹を描いて分類する) いくつかの種類があり、番号を付けて呼ばれる。HA で 18 種、NA で 11 種が現在知られており (亜型という。最近さらに増えて修正した。2025.2 現在)、H5N1 などの名前はその組み合わせを表す。例えば同じ HA であっても少しずつ性質が異なるものがあることは生物の亜種と同様。原理的にはすべての HA, NA の組み合わせが可能であると考えられている。
ちなみにヒトで過去にパンデミックを起こしたことが知られているインフルエンザウイルスは H1, H2, H3 である。H5 にもその能力があるかははっきりわからないが、いくつかの変異を導入すると哺乳類から哺乳類 (実験室でよく使われるのはヒトに似た性質を示すフェレット) に感染するウイルスを作ることができることは実験的に確かめられており、哺乳類への感染が警戒されている所以である
[参考: 哺乳類間で伝播しうる鳥インフルエンザウイルス、
リスクの高い研究に関する論文の掲載 (Nature 2012) のようにこの研究結果を公開すべきか議論を呼んだ] (*5)。
HA と NA は異なるセグメントに乗っているため、遺伝子再集合で別々の HA と NA を持つウイルスが比較的簡単に作られる。つまり同じ H5 亜型であっても NA が入れ替わったウイルスも生じる。これが H5N1 が流行したり別の年には H5N2 や H5N8 に変わったりする仕組みである。
現在問題となっている H5 ははるか昔 (1996年ごろ) に生じた高病原性の系統が継続しているもので、NA は入れ替わることがあるが高病原性の性質は維持されている。
[野鳥と鳥インフルエンザ (6) 高病原性 H5N1 の出現]
この高病原性 H5 (H5N1) が最初に (少なくとも世間的に) 明るみに出たのは (鳥インフルエンザなのに) なんと鳥ではなく、1997 年香港で人が感染した事例に始まる。ちょうど同じ時期に香港のニワトリでも鳥インフルエンザの発生があり、香港中の 150 万羽のニワトリを 1997 年末までに処分することで流行は終息したが、18 人が感染し6名が死亡した。この時はあるいは人から人感染かと懸念されたが人の間では大きな流行に至らなかった。
ちなみにタミフルは当時はまだ使えず、伝統的な抗インフルエンザ薬であったアマンタジンが使われた。
当時までは鳥インフルエンザは人に感染しない (いわゆる「種の壁」) と考えられていたため、防御も行わずに病気のニワトリをさばいたりしていたのであろう。
この株が最初に見つかったのは 1996 年に中国のガチョウから見出されたものであったため、現在問題となっている H5N1 の発見は 1996 年とされる。
その後しばらく小康状態が続いていたが (中国や東南アジアで局地的に発生していたものと思われる。2000年にはベトナムで多数のニワトリが死んでいた
とのことで地方病のような状況だったらしい)、2003 年に再度大規模な拡大があり、韓国の家禽で発生したしばらく後、2004年1月日本でも山口県の養鶏場で発生 (日本での HPAI 発生は 79 年ぶりのことであった)、2月大分県で小規模な発生があり、2-3月京都府の養鶏場で大規模な発生があった。
当時はこの時期に韓国から日本への渡り鳥のルートは知られておらず、何がウイルスを持ち込んだのか議論がなされていた (人の往来も十分多く、人が運んだ可能性もある *6)。
ほぼ同じころベトナムやカンボジアで人への感染も相次ぎ、1人感染がある度に報道されるぐらいであった。高病原性の定義は家禽に対するものであるが、人に対しても毒性が高く未治療では 50% が死亡すると見積もられていた。毒性が高いままで人から人へ簡単に感染するようになるとどのようなことになるか、特に専門家の間では大変恐れられていた。
[野鳥と鳥インフルエンザ (6) 2005 年青海湖の大事件]
日本での発生が一段落したため日本では鳥インフルエンザへの関心は次第に薄れて行ったが、2005年4月末から6月にかけて世界を震撼させる事件が中国青海省の青海湖で起きた [Chen et al. (2006) Properties and Dissemination of H5N1 Viruses Isolated during an Influenza Outbreak in Migratory Waterfowl in Western China を参照]。
この時に最初の感染例として見つかったのがインドガンであり、この論文によれば5月4日に2羽が死んでいるのが見つかり、翌日には 105 羽が死んだ。この感染爆発で最終的にインドガン 3282 羽、全体で 6184 羽の死体が回収されたとのこと。
ウイルスの系統解析の結果からインドガンが最初に保有していたウイルスが他の種類に感染したことが示されている。これ以来、鳥インフルエンザに関心を寄せる人たちの間でインドガンの名前は忘れられないものとなり、そしてそもそもなぜインドガンなのか不思議に思われていた。
これは高病原性鳥インフルエンザが渡り鳥に大規模感染を起こした前代未聞の事例となった。人に感染することもあって致死率が高いことはすでにわかっていたため、もし渡り鳥を通じて世界に拡散し、その経緯で人から人感染を起こすウイルスが生まれると大惨事になりかねないと考えられた。
養鶏場や地域感染にとどまっている間はまだともかく (当時までは東南アジアでの人感染が中心であったため、もしパンデミックが起きるならばそこから発生することを前提としたシミュレーションも行われていた。例えば東南アジアのある都市で人から人感染を起こす株が出現した場合、発生後何時間以内に半径何km以内の住民全員にタミフルを投与すれば拡大を防げるかなど調べられていたが、現実的にはほぼ達成不可能な数字が出るのみであった)、H5N1 はもはや制御不能と多くの専門家は考えた。
当時 Nature がこの事象を受け、5月に早々と On a wing and a prayer との記事を出した。
渡り鳥に大規模感染が起きた以上パンデミックは時間の問題との認識が強かった。もはやアジアだけの問題はなく世界中どこで発生するかわからない。どこにいてもパンデミックからは逃れることはできない。
1918 年に多くの人を犠牲とし、結果的に第一次世界大戦を終結させることになった通称「スペイン風邪」と呼ばれる新型インフルエンザを引き合いに出している。これは H1N1 亜型のパンデミックであったが、それでもまだ低病原性であり (1918 年のパンデミックの前に野鳥や養鶏場で集団死があった報告などはなかった)、
1918 年に比べて飛躍的に進んだ移動手段のある中で高病原性のパンデミックが起きればどうなるか、想像を絶するとの文脈である。
これほどの大事件であったにもかかわらず、日本での扱いは極めて小さかった (科学報道が重視されないことが痛感される)。
青海湖での発生が終結すると (つまり感染した鳥がすべて死ぬか移動していなくなった)、世界は一時的に平穏を取り戻していた。しかしこの間にロシアやモンゴルで感染が拡大していたのであった。
英文報道のような通常ルートで入ってきていた情報は8月にモンゴルのオオハクチョウでの感染が見つかったというもので、事例としても少なく、渡り鳥が運んだのか、あるいは人為的に運ばれた可能性があるのかなどの小規模な議論や現地調査にとどまっていた。
日本野鳥の会の金井裕 (2007) 「野鳥の渡りや生態と感染拡大の関係」「鳥インフルエンザ」 に収録 (北里大学農医連携学術叢書 3号) によれば野鳥一般に繁殖期であまり移動しない時期で、オオハクチョウは換羽でそもそも飛べない時期であり渡りで運ばれたと考えるのには無理があるとの考察がある。
[野鳥と鳥インフルエンザ (7) 2005 年ロシアでの大進展]
事態をある意味で一変させたのが、Recombinomics 社 (バイオのベンチャー企業?) の Henry L Niman によるもので、彼は協力者とともに海外ニュースを集めてロシアで鳥インフルエンザ感染が起きていることを見つけていた。
当時は現在のようなオンラインの機械翻訳サービスも限られていたが、彼らはその初期のサービスを用いてロシア語の現地ニュースを翻訳して読んでいたのだった。
Niman の論点は終始渡り鳥が H5N1 を運んでいるというもので、彼らはその文脈に合うニュースのみを選んで紹介していたのだった。
当時はまだウイルスを運ぶ主役は渡り鳥なのか人の移動によるものなのかよくわかっていない時代で、一方的視点だけでニュースを提供されると自然保護側としては看過できない状況であった。ロシアの農家による渡り鳥撃ち落とし計画なるものも報道され、それは日露渡り鳥条約にも関わる問題であるとの指摘も獣医師の方よりいただいた (話題作りの記事だったようで、実際には大規模には行われなかったようである)。
彼らと同じようにロシア語の現地ニュースを機械翻訳して読むと大規模養鶏場で発生したものが広がって、など彼らが紹介しない記事も多数あるため機械翻訳での紹介を始めたのが自分が鳥インフルエンザ問題に (世界的な文脈で) 関わったきっかけであった (ロシア語をしっかり勉強すべしと感じたのはこの後の話)。
ちなみに当時のロシアはまだソ連崩壊後の経済危機状態を脱しておらず、研究者も研究費を得るのが大変だった時期にあたる。当時のロシア発行の猛禽類保護の専門雑誌 Raptors Conservation に記事 Lapshin (2005)
People, Birds and Viruses. What is the Arboviruses and Avian Influenza and How do they Threaten Raptors?
があったが、鳥インフルエンザ騒動は少なくとも一部の研究者にとっては「救世主」のようなもので、渡り鳥に責任を押し付けることはウイルス研究者にとっても研究費獲得に有利で、野鳥保護関係者には迷惑な話であったとのこと (論文はロシア語・英語併記であるが上記肝心のところは英訳されていない。英語でニュアンスを伝えるのは難しかったのであろう)。
ロシアの経済状況は厳しいものであったが、情報公開には意外に熱心で最初の発生地であるノボシビルスク近郊の発生地点の詳細な地図までオンラインで入手することができた。
ロシアの野鳥に関係の深い英文のメーリングリストにも翻訳情報を投稿したりしていたが、
この活動が BirdLife の鳥インフルエンザ担当者の目にとまり、BirdLife が主宰するメーリングリストに加えてもらい、ボランティアによる国際的な感染症ホットラインである ProMED にも情報を提供するようになった。
ProMED は SARS の発生を最初に感知したり、新型コロナでも的確な情報を最初から提供するなど信頼性の高い感染症の情報源である。鳥インフルエンザはもちろん最も重要なテーマの一つであったが、あまりにも急速に進展してボランティアベースでは世界情報を追えなくなったり、それまではロシア在住の情報提供者があったがその時期はいなくなっていたと聞き、提供した情報は役立っていたようである。
そのメーリングリストは Nature の記者もオブザーバー参加していて、我々の活動に注目していたようである。
[野鳥と鳥インフルエンザ (8) そして 2005-2006 年ヨーロッパへの進展と新型インフルエンザ騒動]
ロシア進展の間はほぼシベリア横断鉄道に沿うように西進していった。これも解釈に悩む要因となっていた。物流の大動脈であり周辺には養鶏場も当然ある。渡り鳥の移動に伴って拡大したものか、養鶏場で発生したものが人や物の移動に伴って運ばれていたのかを区別することは難しい。
この経路は Gauthier-clerc et al. (2007) Recent expansion of highly pathogenic avian influenza H5N1: a critical review にも示されており、ここでは人や物の移動に伴って運ばれたことを圧倒的に支持すると述べられている。
上記 Lapshin (2005) によれば検査のための物資が圧倒的に不足していて、現実の進展を反映していたものかもよくわからないようである。
日本を含め、世界のメディアが注目したのは同年の 10 月にルーマニアなどヨーロッパで発生してからであった。この年には日本ではとある国政選挙があり、報道関係者はそちらの取材に忙殺されていたため世界がこんなことになっているとは知らなかった、と後に聞いた。
世界の一流誌はいずれもこのころ大特集を組んでいた。例えば TIME は青海湖でレンジャーの目の前でインドガンがよろめきながら死んで行く様子を生々しく伝えていた。
同年 TIME 9/26 号 "Avian Flu Death Threat" より冒頭の引用と抄訳:
But for migratory birds, the island-actually a small peninsula protruding
into Qinghai Lake, China's largest saltwater lake-is the avian equivalent
of a busy international airport.
人々にとっては秘境かも知れないが、青海湖の小さな半島は渡り鳥にとって込み
合った国際空港のようなものだった。
his daily rounds near an area popular with bar-headed geese when he spotted
something he'd never seen in his two decades at the reserve.
青海湖のレンジャーは 20 年来観察を続けてきたが、それは初めて目にする光景
だった。
"It was walking so strangely, wobbling from side to side as if it were
drunk."
群れから離れた1羽のインドガンが、まるで酔っ払っているかのように揺れな
がら歩いていた。
"This goose seemed to be shivering."
あのガンは震えているのではないか・・
その瞬間から起きた世界の戦慄の反応は、"If that sounds like an alarmist's
hype, it's not." 警告家の誇張のように聞こえるかも知れない・・しかしそれは
本当なのだ。
ルーマニアで発生となるとロシアとの間はどうであったのか気になるところであったが、報道をチェックするとウクライナでもそれを疑わせる事例がすでにあったらしいことがわかった。住民の証言レベルの話だったが当時のウクライナの体制がいかなるものであったを多少なりともうかがうことができた (現在なぜあのような事態になっているのかの遠因もわかるような気がした)。
ウクライナでの発生が正式に報告されたのはこの年も終わりに近づいてからのことであった。
2005 年中のヨーロッパでの発生はまだ散発的であったが、2006 年に入ってから大発生が相次いだ。
ギリシャではアオガンの死亡もあり、当時 BirdLife 担当者の Richard Thomas が「養鶏場のウイルスがこんな貴重な鳥を殺している!」と怒り心頭のメッセージを記していた。
ドイツ北部のリューゲン島でハクチョウ類の集団死があり、真冬の最中に防護服を着て非常に重いハクチョウ類の死体を回収する担当者がどれだけ重労働であるかも述べられ、都市部で発生が起きた時には市内に幾重にも防疫線が引かれるなど日常生活への影響もかなりのものであったそうである。
人々をさらに驚かせたのが2006年1月にアフリカのナイジェリアの農場で発生したことである。そして隣接するニジェール、カメルーン、ブルキナファソ、スーダン、コートジボワールへと2-4月にかけて次々と波及した。
設備の揃ったヨーロッパならばまだ封じ込めも可能であろうが、アフリカの最も貧しい国々に定着すると絶望的であると考えられた。食料も十分でないアフリカで先進国同様の家禽の処分を行わざるを得ず、関係者の苦悩も大変なことであっただろう。
先述の Gauthier-clerc et al. (2007) によれば感染地域からナイジェリアへひなの空輸があったことが BirdLife により報告されている (先述の BirdLife が主宰するメーリングリストでも空輸される現場を実際に見たとの目撃レポートが報告されていた)。
あくまで当時の事情下ではあったが、H5N1 がもしヒトの間でパンデミックとなった場合の対応についてもさまざまな問題が投げかけられた。行動制限や感染者が増えて社会が回らなくなった場合の対応などシミュレーションも行われていたが、新型コロナウイルスに対して活かされただろうか。なお人と話をする時は最低 2 m の距離をとる、お互いの方を向いて話さない、などの対策も当時から提案されていたものである。
予防方法はワクチン (*8) となるが、当時はまだインフルエンザワクチンは従来の方法で作られていた (これを執筆中の現在も同様)。つまり発育鶏卵にウイルスを接種して培養し、そこから取り出したものを断片化してワクチンの原料とするものであった。
このような製造ラインはパンデミックが起きても簡単に増やせるものではなく、また鳥インフルエンザが流行している最中に必要な鶏卵をそもそも集めることができるのか、ウイルスの毒性が高すぎて発育鶏卵で十分に増殖しない、そもそもウイルスの出現からワクチンを作るまでには非常に時間がかかるなどの議論がなされていた。
当時の日本はある意味で先進的な対策を準備していて、「日本人しか使わないだろう」と言われたタミフルも迅速診断キットも日常的に用いられており、もし当時 H5N1 のヒトの間でのパンデミックが発生すれば世界でも最も準備が進んでいた国とされていた。タミフルも迅速診断キットも次のパンデミックが必ずいつか起きることを前提に戦略的に整備されていたものだったからである。
(それに比べると新型コロナウイルスに対してワクチンも海外から輸入せざるを得なかった日本の存在感のなさは一体何がそれほど変わってしまったのだろうと愚痴も言いたくなる)
2006 年の春の時期にもまた 2005 年と春と同じような発生があった。
中国青海省ではやはりインドガンを中心とする集団死があった。
2006年6月にはロシア・モンゴルの国境にあるウヴス・ヌール (オブス) 湖で青海湖と同規模の水鳥の集団死が発生したが、情報はほとんど出て来なかった。後にこの発生に関する論文 L'vov (2006) が発表されたことを知って (もちろん一段落してから) 取り寄せてみたがまったく読めなかったため、この論文が文法的に完全に読めるようになろうと一発奮起したのがロシア語独習を本格的に始めたきっかけである (結果的に語学知識が鳥の情報を知るのに想像以上に役に立つことがわかったのは思わぬ副産物となった)。
この当時にはまた注目の発見もあった。2005年10月に 1918 年の「スペイン風邪」が猛威をふるった時期のイヌイットの凍結状態の遺体からウイルス遺伝子の解読の成功が伝えられ、参考記事、H5N1 との類似性や、起源としての鳥インフルエンザが改めて注目されることとなった。
Kobasa et al. (2007) Aberrant innate immune response in lethal infection of macaques with the 1918 influenza virus はこの遺伝情報をもとにウイルスを再構築することに成功し (*5)、1918 年の「スペイン風邪」が宿主の免疫反応を狂わせて死に至らせるいかに凶悪なウイルスであったかを明らかにした。
同様のことが H5N1 でも起きるのではとの示唆を与える研究であった。
インフルエンザウイルス研究の世界の第一人者である河岡義裕「インフルエンザ危機」(集英社新書 2005) が出版されたのもこの時期で、さらに知りたい方はこの本をお読みいだだくとよい。
H5N1 の発生はいったん下火となり、2009 年にブタ起源 (遺伝子の一部は鳥インフルエンザ由来だった) の新型 H1N1 インフルエンザ [A(H1N1)pdm09] がパンデミックとなったことで H5N1 の話題はしばらく忘れ去られていた。
「スペイン風邪」の末裔 (正確には 1977 年に再登場したもので、保存されていたウイルスが流出したことが原因と言われる) にあたる H1N1 は当時まで流行が続いており、この株はタミフル耐性となっていたため厄介であった (医療現場で使われる迅速判定キットでは亜型まで判別されないため、タミフルを投与しても効かない確率も高かった)。
2009 年の新型 H1N1 インフルエンザは病原性も低く、また多くの人が H1 への基本的な免疫を持っていたため大きな被害は生まなかった。タミフル耐性となっていた従来の H1N1 を駆逐したため、ある意味ではよい面もあった。ただし「新型」ゆえに生活に制約が生まれたり社会的混乱があったことは記憶されておられる方も多いだろう。現在も流行が続いている H1N1 亜型はこの株である。
[野鳥と鳥インフルエンザ (9) インドガン]
自分もなぜインドガンが重要な役割を果たしたのだろうと関心を持っていた一人であったが、インドガンの生態を調べているうちに衝撃の情報を発見してしまった。
インドガンはチベットなどの高地に生息するため、英語で探しても繁殖地での情報がそれほどない。仕方なく中国語で検索をしていた (漢字文化圏の者にとっては種名ぐらいならば判別でき、むしろ比較的簡単であった)。
その最中にインドガンが養殖されている記事を見つけてしまったのである (記事さえ見つかれば機械翻訳で読めばよい。英語圏の者には簡単にできない芸当である)。当時国内・世界ともガン類の研究者はいたが、このことは誰一人知らなかったとのことである。
ガン類の研究者も後から考えると飼育は簡単なので確かに商業利用に使われることは考えても不思議でないと述べていた。
商業的な飼育は 2003 年にラサから 100 km ぐらい南の湖で始まり、さらに規模を拡大していたとのこと。野生個体数が減少していたので 2005 年には飼育個体の野外放鳥も行った (青海湖の発生の後ではあるが)。
珍味であり、消費地である都市部との流通ルートも確保されていたとのこと。
詳しくは以下の論文となっているので参照されたい (第2著者で共著論文となっている。筆頭著者が獣医、第3著者は BirdLife の鳥インフルエンザ担当者):
Feare et al. (2010) Captive Rearing and Release of Bar-headed Geese (Anser indicus) in China: A Possible HPAI H5N1 Virus Infection Route to Wild Birds。
この発見はメーリングリストに参加していた Nature の担当者の目にもとまり、"Blogger reveals China's migratory goose farms near site of flu outbreak" Nature 2006 May 18; 441(7091): 263
という記事としても掲載された。現在はオープンアクセスとなっているようなのでぜひお読みいただきたい。香港在住で中国の渡り鳥での感染論文を Nature に出した Yi Guan も噂は聞いたことがあったが知らなかったとのこと。
2005-2006 年の世界進展の時も話題となっていたのだが、この「青海湖株」には特異な変異がある。それはインフルエンザの遺伝子の一つ PB2 (ポリメラーゼのユニットの一つ) の 627 番目のアミノ酸がグルタミン酸 (E) からリジン (K) に変異しているもので、専門的な表現では PB2 E627K と表記される。この表記で検索するとすぐわかるが、これは鳥インフルエンザの哺乳類への感染力を高める変異としてよく知られたものである。アミノ酸変異のこの表記方法は本稿の他所でも特に説明なく登場するのでこの意味と理解いただきたい (*7)。
先述の 1997 年に香港で人に感染を起こした H5N1 ウイルスにもまさしく同じ変異があった。
この変異は鳥の間のみで感染を繰り返して生じるとは考えにくく、最も素直な解釈は途中に哺乳類への感染が起きたもので、家畜/家禽から獲得した可能性が高い。家禽の集団は上空からも見つけやすく、野生個体が容易に混じることができて、飼育/野生インドガン個体中に定着してインドガンへの感染に適応した株を生み出したと考えると納得が行く。
ラサ周辺ではその後も発生が続き、中国の研究者は渡り鳥が帰ってきたためと解釈しているが、家禽状態のインドガン個体群中に定着していた可能性も考えられる。
BirdLife の組織は基本的に英語圏で漢字文化圏への障壁は高かったようで、日本人ならではの貢献となったかも知れない。BirdLife にも中国の協力者はいたが鳥インフルエンザへの関心は高くなかったようでこのような情報追求はできなかったようである。
この話は実は深いところでここ数年の問題となっている新型コロナウイルスの起源にも関わっているのではないかと考えている (同じようなことに気づいている人はきっと他にもありそうだが)。
先に紹介の ProMED に 2021年3月15日に紹介されたものだが、
WHO Points To Wildlife Farms In Southern China As Likely Source Of Pandemic
というアメリカの公共放送 (NPR) のインタビュー記事がある。残念ながら日本ではこのような情報はほとんど報道されないが、WHO の Peter Daszak が現地視察で何を知ったのか紹介されている。
Peter Daszak の言葉で印象的な発言を紹介しておこう (以下の article とは 2020 年 Scientific American の記事を指す):
He praised her and defended her staunchly in the article, which notes
that Shi and he are "long-term collaborators". Daszak said:
"Shi leads a world-class lab of the highest standards...
It's crystal clear that bats, once again, are the natural reservoir.
"crystal clear" の表現があまりに印象的。(新型コロナウイルスがコウモリからやってきていることは) 水晶のように澄み切った、一点の曇りもない。
中国では野生動物を捕獲して養殖する政策がこの 20 年行われてきて、都市部と農村の貧富の差の解消にに奏功していたとのこと。この成果については NPR が 2020 年にすでに報道していた。
NPR はアメリカ合衆国の非営利・公共のラジオネットワークと wikipedia にあり、これまでにも H5N1 は渡り鳥が運んでいるのか (2005-2006 年当時の状況)、などの数々の重要な専門家インタビューを紹介してきていた信頼度も高いとされるメディアである。
Peter Daszak 氏は 2020 年 Scientific American の記事 How China's 'Bat Woman' Hunted Down Viruses from SARS to the New Coronavirus (2020年6月1日)
で中国のコウモリのウイルス研究者の Shi Zhengli = 石正麗 (セキセイレイ) をインタビューし、高く評価していた。この記事は日経サイエンス7月号 (2020) に掲載されたとのこと (これは読んでいない)。
Shi Zhengli が新型コロナウイルスの発生報告を聞いた時どこにいて何をしていたのか、この記事に記載されているので (インドガンの話題から少し離れるが) 2020年3月11日にオンライン公開され、4月27日に改訂された当時の記事の部分抄訳を紹介しておく ([kbird:03001] コロナウイルスの起源 2020.5.6より):
SARS の発生以来 16 年コウモリのウイルスを求めて遠征を行ってきたとのこと。初めて新型肺炎のニュースを聞いた時、もっと危険な中国南部ではなく中央部の武漢で発生するとは考えておらず、中央政府が何か間違えたのかと思ったとのこと。本当にコロナウイルスならばうちの研究所が起源の可能性があるかと考えた。
(コウモリのウイルスを求めての遠征で) horseshoe bat species の3種に SARS に対する抗体を見つけたとのこと。Shitou Cave 洞窟へと絞り込み、5年の研究で多数のコウモリ由来のコロナウイルスを見つけた。多くのものは無害だったが
SARS に近いものが 10 ぐらいあった。人間の肺細胞に感染し、ネズミで SARS に似た病気を起こした。
(これらの研究の結果、現在 SARS の起源とされる野性動物にたどり着いた)。
この洞窟近くの村の住民を調べて 3% に SARS 類似コロナウイルスへの抗体を持っていることを明らかにしたが症状はなかった。
その3年前に鉱山で6人が肺炎になって2人が死んだ事件で調査を依頼され、鉱山で多数のコロナウイルスを見つけた。
コウモリの糞で地獄のようだった。その時の原因は真菌だったが閉鎖していなければコロナウイルスに感染するのは時間の問題だった。
1年以上前に彼女らのチームは2本の総説論文を出版し、コウモリ由来のコロナウイルスの危険性を訴えていた。
昨年12月30日武漢へ戻る列車の中で、患者のサンプルを検査する方法を同僚と相談していた。16 年間自分が準備してきた最悪の悪夢と戦っているように感じた。PCR でコロナウイルスに共通の配列を確認。他の研究所に送って完全配列を解読。
その間に実験室の過去数年の記録と照合し、実験ミスで漏洩があったのかを調べた。
洞窟のサンプルに該当するものがなかったことがわかって胸をなでおろした。「心の重しがようやく取れました」「数日間一睡もできませんでした」
2021 年の調査 Daszak 氏の率いる WHO チームは中国の研究者とも長年の信頼関係があり、論文発表前の資料なども得られたのであろう (*9)。
鳥インフルエンザに戻って、希少種インドガンを養殖して商用利用とともに野生個体を増やす事業が行われていたわけであるが、まさにこのプロジェクトの一つだったのではないかと考えると時期的にも非常によく符合するように思える。
あくまで想像に過ぎないが、もしインドガンに適応した H5N1 の株が生じていなかったら事態はどうなっていただろう。渡りのカモがやってくる状態でも HPAI H5N1 が出現した 1996 年から長い間渡り鳥の間に大きな問題は生じていなかったので、もしかするとインドガンに人為が関わっていなければ今でも中国と東南アジアの風土病程度にとどまっていたのかも知れない。
なお、現時点の HPAI H5 は渡り鳥が運搬していることは明瞭である。日常的に発生するようになった時期からはそうでないかと思われる。特に最初に述べた 2020 年以降の拡大速度はそれまでにも増して大きく、既知の渡り経路にも沿うものになっている。
青海湖株の発生当初に比べて野鳥への毒性が弱まり、一部の鳥に適応して渡りながら感染を拡大させることができるようになったと考えられている。[野鳥と鳥インフルエンザ (3) 高病原性はなぜ生じる] で述べたような自然界では不安定な高病原性状態が次第に低病原性に移行してゆく過程を見ていると考えられる。
ただし現在問題となっている株は変異によって毒性を高めている。一部の宿主には毒性が低く容易に運搬できるものの他の種類には毒性が強いことはあり得る。
現時点の HPAI H5 は渡り鳥が運搬できるようになったとはいえ、これを過去まで遡って適用するのは拡大解釈であろう。2005-2006 年の拡大パターンは渡り経路にも時期にも合わない点が多く、現時点の拡大パターンとはかなり異なっている。
現在では今も昔も同じように考えられがちであるが、当時の詳しい情報に基づく分析については前述の金井裕 (2007) 「野鳥の渡りや生態と感染拡大の関係」や Gauthier-clerc et al. (2007) をお読みいただければと思う。当時も指摘されていた点であるが、当時の鳥インフルエンザは同一国内ではすぐに広まるのに国境を越えるのには時間がかかったのは人や物の移動が関係していたことの表れとも言えるだろう。
Yang et al. (2024) Synchrony of Bird Migration with Global Dispersal of Avian Influenza Reveals Exposed Bird Orders
のウイルスゲノムの研究で 2.3.2.1 (過去の系統) では渡りとの相関があまり見られなかったが、2.3.4.4 (2010-2017) で相関が見られるようになり、2.3.4.4 (2018-2023) では相関が一層強まり、渡り鳥が主な運び屋になったのは 2.3.4.4 以降のよう。2.3.2.1 では移動に季節性が見られなかった。
ただし渡り鳥の経路についてはよくわかっていない部分も多く限界もある。著者はカモ目に加えてタカ目も渡りで運ぶ可能性も考えているようだが (ミサゴの写真が使われている)、2次感染や重点サンプリング種などの考察は不十分でやや誤解を招く可能性がある印象を受ける。
Zhang et al. (2022) Airborne Avian Influenza Virus in Ambient Air in the Winter Habitats of Migratory Birds
越冬期の水鳥周辺の空気に含まれるウイルスを検出したもの。オナガガモ、コガモなどとの相関が高かった。もちろんウイルスが含まれているからと言って空気感染する可能性があるとは言えないことに注意。
一時期「鶏インフルエンザ」の名前が使われたことがあったがこれはもちろん正式用語ではない。
Birder (2004) 18(7): 68-69 で編集部による記事で「野鳥と鳥インフルエンザ公開シンポ」の対談を取材した記事がある。主な感染相手はニワトリで「鳥インフルエンザ」と書くより「鶏インフルエンザ」と書くほうが正確だろう (動物衛生研究所 山口成夫氏の講演に基づく)。
野鳥関係者に対する講演なのでそのような表現を使われたかも知れないが、Birder のこの記事は「鶏インフルエンザ」とすべきところをマスコミが「鳥インフルエンザ」と報道したと誤解を招いた可能性があるように思う。
なお、海外でも「鶏インフルエンザ」に対応する poultry flu を世界進展の際に使われた方があったが、これは屈辱的な意味で用いられたもの。「養鶏場のウイルスがこんな貴重な鳥を殺している!」に相当する怒りの表現であった。日本で少し使われた用例とは意味が違い、当時の日本の鳥学者からもこのような見解はあまり聞かなかった。
2004 年のことでまだ理解が進んでおらず、やむを得ない部分もあったかも知れない。
Uyeki et al. (2024) Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus Infection in a Dairy Farm Worker
で2024年3月家畜からヒトへの感染が確認された。PB2 E627K を持っており、哺乳類への感染力を高める変異があるが、HA の方は鳥タイプのもので哺乳類の間で効率的な感染する能力はなさそうだが注意は必要らしい。
Restori et al. (2024) Risk assessment of a highly pathogenic H5N1 influenza virus from mink
ミンクから分離された株はさらなる PB2 T271A の変異を持ち増殖能力を増しているが致死率は下げ、"空気" 感染をより容易にしている。
A/American wigeon/South Carolina/22-000345-001/2021 (アメリカヒドリ) は北米に導入された早期の株でフェレットに対して弱い病原性を示したが、A/Bald eagle/Florida/W22-134-OP/2022 (ハクトウワシ) は北米の LPAI と遺伝子再集合を起こしたものでフェレットに対して強い毒性を示したとのこと。
まだ効率的な空気感染の能力はないものの、2.3.4.4b H5N1 の系統に少し変異が加わるとパンデミック株になる能力を持つ可能性がある。インフルエンザに免疫を持たないフェレットを用いた実験だが、多くの人が H1N1 や H3N2 を経験していて H5N1 にどの程度の交差防御機能があるかも考察されている。
Meade et al. (2024)
Detection of clade 2.3.4.4b highly pathogenic H5N1 influenza virus in New York City
ニューヨークの鳥でも 1927 検体中6例に検出された (カナダガン、猛禽類、ニワトリ)。
Guan et al. (2024) Cow’s Milk Containing Avian Influenza A(H5N1) Virus - Heat Inactivation and Infectivity in Mice
感染した牛の生乳からマウスに感染する可能性が見つかったとのこと。牛のウイルスは1クレードで牛への導入は1回の現象だったとのこと。
Carrasco et al. (2024) The mammary glands of cows abundantly display receptors for circulating avian H5 viruses (preprint)、
Nelli et al. (2024) Sialic Acid Receptor Specificity in Mammary Gland of Dairy Cattle Infected with Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus
牛やヤギの乳腺に H5 受容体機能 (鳥型のリセプター) がある。
Eisfield et al. (2024) Pathogenicity and transmissibility of bovine H5N1 influenza virus
現在牛で広まっている HPAI H5N1 は乳腺を含めた全身の細胞で増える (ただし乳腺を好む傾向は HPAI H5N1 の古い株でも同様とのこと)。このウイルスはヒトの上気道の受容体に結合し、効率は悪いがフェレットの間で感染する。哺乳類に感染しやすい特徴を持っている可能性がある。
Caserta et al. (2024) Spillover of highly pathogenic avian influenza H5N1 virus to dairy cattle。疫学的に牛から牛への効率的な感染が起きている証拠があり、一見健康に見える牛を別の州に運ぶことで感染が広がったと考えられる。
実験により牛の呼吸器ではあまり増殖しないが乳腺からミルクが主なルートとなっている: Halwe et al. (2024) H5N1 clade 2.3.4.4b dynamics in experimentally infected calves and cows。
アメリカミズーリ州で家畜との接触歴のない人の感染があった: Is bird flu spreading among people? Data gaps leave researchers in the dark (Nature news 2024.9.19)。
牛への感染実験 Baker et al. (2024) Dairy cows inoculated with highly pathogenic avian influenza virus H5N1 (2024.10.15) 飛沫により呼吸器から、また乳腺からの感染ルートがある。現在牛の間で広まっている株は鳥からの直接感染が疑われ牛の間で広まった。
最新状況 2024 年秋から冬 Gu et al. (2024)
A human isolate of bovine H5N1 is transmissible and lethal in animal models
2024 年前半に牛の株に感染し弱い呼吸器症状と結膜炎を起こしたが回復したアメリカの作業者から分離された株 A/Texas/37/2024 はフェレットなどの実験動物には効率的に感染し高率で死亡したとのこと。ヒトの培養細胞では結膜上皮よりも肺胞細胞でよく増殖する (注: ヒトでは上気道よりも肺胞細胞に鳥型の受容体が多い)。
少なくとも実験動物系においては現在の牛の HPAI H5N1 は特別な適応なしに致死的な病気を引き起こすことができる。
この株は野鳥のものと大きな違いはなく牛に導入されたもの。2つの変異で哺乳類で効率的に感染を起こすようになったと考えられる。病原性を高めるようになった変異を持つウイルスがその後再度検出されていない点は朗報である
(河岡氏などを含む日本人研究者も多数入ったチームによる 2024.10.28)。
Pulit-Penaloza et al. (2024) Transmission of a human isolate of clade 2.3.4.4b A(H5N1) virus in ferrets (2024.10.28) こちらも関連論文で人から分離された上記論文と同じ株 A/Texas/37/2024 は鳥型の受容体に結合する能力を有したままでフェレットの間で効率的に感染して多量のウイルスが空中に排泄される。
2024 年の牛での集団発生以前の clade 2.3.4.4b クレードのウイルスに比べて病原性、感染性を高めている。
Lin et al. (2024) A single mutation in bovine influenza H5N1 hemagglutinin switches specificity to human receptors (2024.12.5) HA 遺伝子の Q226L の1アミノ酸変異で人型受容体への結合能力を高める。タンパク質の3次元構造予測から分子機構も明らかにされている。
牛の間で感染している間は牛の上気道や乳腺は主に鳥型の受容体からなるため (牛なのに鳥型とややこしい) 鳥型を維持する選択圧が働くと考えられるが、牛から作業員に感染を繰り返すと人型受容体への変異を起こす選択圧となる可能性がある。北半球はインフルエンザの流行期に入っているので重複感染による遺伝子再集合で人に適応した株が生まれる可能性がある (下記の 2024.9.24 Nature review の原稿事前公開も参照)。
南米のミナミゾウアザラシ Mirounga leonina で野生哺乳類間で感染が起きている証拠: Uhart et al. (2024) Epidemiological data of an influenza A/H5N1 outbreak in elephant seals in Argentina indicates mammal-to-mammal transmission (2024.11.11)
哺乳類から鳥 (分子系統解析からミユビシギやナンベイアジサシ Sterna hirundinacea South American Tern) への感染もある。鳥からアザラシへの直接感染経路は少ないのでアザラシの間で感染が継続していると考えられる。
H5N1 は新しい経路で哺乳類により容易に適応するようになってきていると考えられる。
2022-2023 の期間に南米でどのように拡大したか地図も出ている。アザラシの回遊に伴う拡大も示唆されている。アザラシ類の保全上でも問題となっている。
鳥の間で感染を繰り返している場合より哺乳類の間で感染を繰り返す方が哺乳類に適合した変異が選択されやすいと考えられ、我々にとっても警告のサインとも言える。
こちらも南米のアザラシの間で感染が維持されている証拠: Pardo-Roa et al. (2025) Cross-species and mammal-to-mammal transmission of clade 2.3.4.4b highly pathogenic avian influenza A/H5N1 with PB2 adaptations。
台湾では定着してしまった: Li et al. (2024) From emergence to endemicity of highly pathogenic H5 avian influenza viruses in Taiwan。ウイルスの分子系統解析より。clade 2.3.4.4c で上記のものとは少し違う系統。2015-2019 年の間にどのような形で感染が維持されたか推定している。
2015 年に大きな流行があった。台湾ではニワトリの間で感染が維持され、カモはあまり関わっていない結果となっている。
家禽の移動や渡り鳥の移動は主要な要因ではない。2023-2024 年の台湾での発生は大部分が Yunlin (雲林県) で起きている。家禽の間なので封じ込めができる性質のもの。
台湾に渡るマガモは日本などに比べて少数なので渡り鳥の影響はより限定的なものになっているのかも。
Sultankulova et al. (2024) Reassortants of the Highly Pathogenic Influenza Virus A/H5N1 Causing Mass Swan Mortality in Kazakhstan from 2023 to 2024 (写真あり)
2023-2024 年の冬のシーズンにカスピ海東部の沿岸の Lake Karakol でコブハクチョウとオオハクチョウの集団死があり、複数の遺伝子が別の種類の鳥に由来する遺伝子再集合の結果生じた株と判明した。
過去にカザフスタンで起きた集団感染とは遺伝的に異なる。
PB 遺伝子には哺乳類への適応を示す変異も存在した。
カザフスタンのこの地域はさまざまな地域からの渡り鳥の越冬地にあたる。また周囲にニワトリも少なく家禽から感染した可能性は低い。長距離の渡りルートに沿って複雑な遺伝子再集合が起きたと考えられる。
最も最近の集団感染の事例は 2022 年にあってカスピ海西部沿岸のロシア側でニシズグロカモメ Ichthyaetus melanocephalus、(カスピアカモメ) Larus cachinnans Caspian Gull、オニアジサシやハイイロペリカンが犠牲となったとのこと
[Sobolev et al. (2023) Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus-Induced Mass Death of Wild Birds, Caspian Sea, Russia, 2022 2022年5月]。
この地域で鳥が死ぬことは普通にあるがよく調べられていない。
続報 Kydyrmanov et al. (2024) Mass Mortality in Terns and Gulls Associated with Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses in Caspian Sea, Kazakhstan (写真あり)。
Bruessow (2024) The Arrival of Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses in North America, Ensuing Epizootics in Poultry and Dairy Farms and Difficulties in Scientific Naming
アメリカを中心とした拡大経緯について。2014 年以前に HPAI H5N1 が検出された証拠はない。2014 年以降突然状況が変わってしまった。
Wille et al. (2024) A call to innovate Antarctic avian influenza surveillance
南極大陸に到達してしまっているが現地には検査施設がない。
Bennett-Laso et al. (2024) Confirmation of highly pathogenic avian influenza H5N1 in skuas, Antarctica 2024
2024.2.28 に複数のトウゾクカモメ類の死体が James Ross Island 付近で見つかり、チャイロオオトウゾクカモメ (ミナミオオトウゾクカモメ) Catharacta skua Brown Skua (種概念が複雑なので代表的表記とした) のサンプルから確認された。
Fildes Peninsula でのトウゾクカモメ類が減少した理由を説明できる可能性がある。
北半球の海鳥コロニーでの発生に比べて南極大陸での発生規模が小さいとはいえ、ペンギン類も感受性があることがわかっていて懸念される。
2023 年初めの South Shetland Islands にはまだ到達していなかったと考えられる: Munoz et al. (2024) Lack of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 in the South Shetland Islands in Antarctica, Early 2023。
Lisovski et al. (2024) Unexpected Delayed Incursion of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 (Clade 2.3.4.4b) Into the Antarctic Region。
南極大陸をとりまくように 2023-2024 年にすでに複数の疑い例があり、このフライウエイからオセアニアに入る可能性がある: Plaza et al. (2024) Potential Arrival Pathway for Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 to Oceania。
Moutinho (2025) Deadly avian flu strain is spreading rapidly in Antarctica (Science, 2025.3.13) 南極大陸で急進展中。調査から持ち帰ったサンプルから判明。
南極大陸では小さな島に大きなコロニーを作って繁殖するため大変危険である。1つの島が個体群の 90% をなす種類もある。クルーズではほんの一部を短時間で通り過ぎるに過ぎず全貌がわからない。昨年ペンギンの集団死のあった場所は大丈夫に見えて免疫を獲得した可能性がありこの点は朗報である。
インド洋からオーストラリアは現在このウイルスの到達していない地球上唯一の場所で、ひとたび侵入するとどれほどの被害が生じるか非常に懸念される。
Iervolino et al. (2025) The expanding avian influenza panzootic: skua die-off in Antarctica (preprint) 南極でトウゾクカモメ類の集団死広がる。Abstract で impact of this poultry-origin disease on Antarctica's unique wildlife とあり、家禽由来のウイルスが南極の独自の生態系に与える影響と、たぶん「けしからん」と言いたいのだろう。
Wannigama et al. (2025) Surveillance of avian influenza through bird guano in remote regions of the global south to uncover transmission dynamics
これまで研究の及んでいなかったグローバル・サウスの 10 か国で 2021-2023 年にグアノのサンプルを採取。無人地域でも多くの種類の鳥インフルエンザが検出され、H5N1 は急激に増えたとのこと。モルジブ、スリランカ、インドネシアなどで検出された。パプアニューギニアの Stuers Islands では H1N1 が多かったなど。
H5N1 陽性のサンプルはソマリアの Bajuni Islands やイエメンの Socotra Archipelago などでも検出されている。個体数の少ない固有種の多い島の名前も散見され心配なところもある。
Caliendo et al. (2025) Highly Pathogenic Avian Influenza in Northern Fulmars (Fulmarus glacialis) in the Netherlands
2024 年 1-2 月にオランダで死亡したフルマカモメから H5N5 株を検出。哺乳類への適応の変異マーカーを持っていた。
ブラジルの家禽での初めての発生 (2025) について: Martins-Filho and Quintans-Junior (2025) Brazil's First H5N1 Outbreak in Commercial Poultry: A Sentinel Event for Cross-Border Preparedness。
Schlachter et al. (2025) High pathogenicity avian influenza H5N1 clade 2.3.4.4b natural infection in captive Humboldt penguins (Spheniscus humboldti)
2022 年の冬に英国で室外飼育されていたフンボルトペンギンで集団死が発生、H5N1 が原因と同定され、ペンギン類も感受性が高いことが明らかになった。
Kuiken et al. (2025) Emergence, spread, and impact of high-pathogenicity avian influenza H5 in wild birds and mammals of South America and Antarctica 南米から南極にかけて広がった HPAI H5 の主に野生動物保全の観点からのレビュー。
まだアイデアのみだが、1918 年のパンデミックに馬が関与した可能性は? Furmanski and Murcia (2025) Did horses act as intermediate hosts that facilitated the emergence of 1918 pandemic influenza?
第一次世界大戦の時期で北米で大量の馬の移動があったことを背景に考えられたもの。
2021-2023 年の北米の発生の解析
Damodaran et al. (2024) Intensive transmission in wild, migratory birds drove rapid geographic dissemination and repeated spillovers of H5N1 into agriculture in North America (preprint)
ウイルスのゲノム解析の結果から 2021-2023 年に北米には大西洋 - 太平洋フライウエイを通じて約8回の独立の導入があった。ヨーロッパから大西洋ルートが中心だが、アジアから太平洋ルートで北米への導入も 2022-2023 年に検出された。ヨーロッパや北米の主な株とは異なる系統。
2022-2023 年のシーズンは日本でも野鳥の間で大きな発生があったが、水鳥の繁殖地域のロシアの情報はほとんどわからない。北米にも及んでいたことがゲノム解析の結果判明し、この時期に北米と渡り鳥の交流のあるユーラシア北東部で感染が広まっていたことがわかる。当時の日本での発生と北米への導入タイミングの関係を考慮して図を見ていただくと明らかになる点があるかも。
感染は主にカモ目、シギ・チドリ類とキジ目 (主に家禽) の間で維持されその他の系統は主に終端宿主だった。野鳥から家禽への感染は独立に 46-113 回起きたと推定。
キジ目では感染が長く維持されない傾向があるがカモ目での持続期間は 0.71 年と長い。シギ・チドリ類も 0.65 年と推定されこれらの鳥がウイルスを維持していると考えられる。
これまで想像されていなかった結果としてフクロウ類を除く猛禽類からカモ目、シギ・チドリ類への感染がしばしば起きている可能性がある。北米で LPAI との遺伝子再集合の結果哺乳類を含む広範な宿主への適応を高めるなどこれまでのウイルスと性質が変わってきている可能性があるとのこと。
ウイルスの野生動物間の動態に猛禽類が関わっている可能性や、これまでと感染パターンが異なってきているのかさらに調査が必要である (論文でも多少示唆されているが猛禽類での発生は気づかれやすくよく検査されるため生じる統計的バイアスによるものかも知れない)。
なおこの論文ではタカ・ハヤブサ類を Raptors とほぼ目に近い扱いにしている (昔のワシタカ目相当)。系統よりも生態を考えるとこのような場合や北米の保全関係者には妥当なグループ名になるのだろう。
こちらもより新しい北米の発生の解析とウイルス系統との関係: Signore et al. (2025) Spatiotemporal reconstruction of the North American A(H5N1) outbreak reveals successive lineage replacements by descendant reassortants
興味深いと感じたのは北米に入ったうち、純粋なユーラシアの系統 B4.1 は地理的広がりをあまり見せず北米北西部にとどまっていた点。北米から南米に広がった株は北米で遺伝子再集合を起こしたものだった。
アメリカで大事件を起こしているような性質の株は東アジアではまだ発生していないだけなのかも。
またカモ目が大きな役割を果たしているが、遺伝子型によって他の目や哺乳類感染の程度がかなり違っている。例えば B3.6 は高度にカモ目に適応しているようで他にほとんど見られない。A1 は海鳥、シギ・チドリ類にも大きく広がるとともにスズメ目にも感染している。B3.2 はカモ目以外ではむしろスズメ目から感染が広がる傾向が認められた。スズメ目は二次的に感染して終端宿主となる従来の考え方を遺伝子型によっては改めないといけないかも知れない。先行する以下の Ringenberg et al. (2024) の研究も参照。
Barman et al. (2025) Reassortment of newly emergent clade 2.3.4.4b A(H5N1) highly pathogenic avian influenza A viruses in Bangladesh
バングラデシュの生鳥市場で 2.3.4.4b clade (2022 年日本の株に近い) と LPAI との新しい遺伝子再集合のタイプが見つかった。バングラデシュでは 2.3.2.1a clade (比較的おとなしかった) が流行していて、これまで 2.3.4.4 clade 系統に置き換わることはなかったが今後の動向が注目される。
2.3.2.1a と 2.3.4.4b の間の遺伝子再集合の証拠がある。
人の近くで生息する鳥での調査、カラス類・猛禽類での頻度など
Ringenberg et al. (2024) Prevalence of Avian Influenza Virus in Atypical Wild Birds Host Groups during an Outbreak of Highly Pathogenic Strain EA/AM H5N1
アメリカの人の近くで生息する種類について調べたもの。人の近くで生息する生きた鳥を捕まえる方法ではハト目、スズメ目では陽性サンプルがなかった。 2022-2023 年に弱ったり死んだ鳥を検査した結果では捕食者やスカベンジャーの陽性率が高かった。コンドル科 Cathartidae が特に高く最大 53% に達した。特にカラス類に似た習性のクロコンドルが高く 67.9%。
後者の方法では少数のハト目の例はあったが陽性率も低くリスクは小さいと考えられる。カラス類ではかなり高く、ワタリガラス、ウオガラス、カササギ類、アメリカガラスの順だった。
ツバメ類では少ないかと考えられるがアメリカの Tachycineta 属 (ミドリツバメ、スミレミドリツバメの2種5個体で検出) では意外に高くツバメ科 Hirundinidae 全体で 14%。アトリ科 Fringillidae でも数 % 程度ある。スズメ科 Passeridae や ツグミ科 Turdidae は 1% 未満と低いとのこと。
種ツバメでの検出例はまだないようだが、ツバメ類で鳥インフルエンザが検出された事例はないと言えなった。鳥インフルエンザは基本的に水鳥のウイルスで、非特異免疫の弱いニワトリには感受性が高いとの過去の常識が通用しなくなりつつあるような気がする。
ツバメ類のコロニーで集団発生などの報告はないのだろうか。陸鳥は免疫機能を次第に省略する傾向があり、もし高病原性鳥インフルエンザがこれまで主な標的でなかった陸鳥に本格的に適応すればどうなるのかあまり予見できない感じがする。
タカ類ではミサゴでも 4.9% と意外にある。最も高いのはケアシノスリで 50%、アカオノスリ (26%)、ハクトウワシ (26%) などと続く。ハヤブサ類ではハヤブサが 31% と最も高かった。フクロウ科 Strigidae 全体で 23% とタカ科 20%、ハヤブサ科 15% より高かった。フクロウ科ではアメリカワシミミズクが 38%、コミミズクで 32% などが高かった。食性をほぼ反映していると考えられそう。
他ではタイリクキジで 13% など。詳しくは論文参照。
ユーラシアのケアシノスリには影響は出ていないのだろうか。2006 年のドイツの発生ではヨーロッパノスリ (3.1%)、ハヤブサ (33% ただし少数例) だった: van den Brand et al. (2015) Host-specific exposure and fatal neurologic disease in wild raptors from highly pathogenic avian influenza virus H5N1 during the 2006 outbreak in Germany
この時代とは株の性質や宿主分布がかなり違っているようなので過去の知見をもとにするのは要注意かも。
2022-2023 年に北米のケアシノスリが大きな影響を受けている点について #ケアシノスリ 備考の [鳥インフルエンザの影響を強く受ける北米のケアシノスリ] を参照。
Cunningham et al. (2025) Outbreaks of Highly Pathogenic H5N1 Influenza A Virus infection in Black Vultures (Coragyps atratus), USA, 2022
北米のクロコンドルではスカベンジャー行動で感染するだけでなく、同種内で死体を食べるスカベンジャー行動 (死体の共食い) で持続感染が起きていた可能性があるとのこと。2022 年末までに最も事例の多かった (それぞれ少なくとも) フロリダで 2674 例、米国全体で 5707 例を記録。他の種で流行が収束しても流行を持続させる能力がある可能性がある。
世界動向や宿主の変化
Li et al. (2024) Spatiotemporal and Species-Crossing Transmission Dynamics of Subclade 2.3.4.4b H5Nx HPAIVs 主にユーラシアで拡大ルートを推定。
2024 年段階の主に野生動物感染のレビュー: Sacristan et al. (2024) Novel Epidemiologic Features of High Pathogenicity Avian Influenza Virus A H5N1 2.3.3.4b Panzootic: A Review。世界の報告例の地図などがある。
2005-2020 年 (ウミスズメ科 Alcidae が多かった) と 2020-2023 年では影響を受けた科の構成がかなり異なっている。
適応した宿主の範囲を広げ、これまで無関係だった種類や地域に及んで絶滅危惧種を脅かしている。ペルーで数千のペリカンやカツオドリ類が犠牲となった。アメリカではこれまで無関係だったカリフォルニアコンドルに感染。
南アフリカでは IUCN EN 種のケープウ Phalacrocorax capensis Cape Cormorant 24000 羽が犠牲に。他にも多数の事例が紹介されており詳しくは論文参照。
(2024.9.24 Nature review の原稿事前公開): Peacock et al. (2024) The global H5N1 influenza panzootic in mammals 現状いくつかの哺乳類の間で感染が起きており panzootic 状態となっている。次がヒトの可能性はあるのか。
従来はブタが鳥インフルエンザをヒトのインフルエンザに変える宿主と考えられてきたが、現在問題となっている牛やミンクなどが知られていなかった経路になる可能性はあるのか。
ポリメラーゼ遺伝子は簡単に変異してすぐ哺乳類宿主に適応できるが、今のところ HA 遺伝子は変異に対して比較的選択圧がかかっているようで現在問題となっている哺乳類の間で感染する株はそれらの宿主で長期維持されていない (もちろんどこかで突破される可能性は残る)。
野生の哺乳類間は長期間維持されないが畜産動物はより大きな役割を果たしていると思われる。
これから秋を迎えるにあたり、ヒトの間で流行するインフルエンザとの間で遺伝子再集合を起こすリスクはある。アメリカでは H5N1 がブタで見つかっていない点は朗報である。
事態が変わってきている現状で家禽にワクチンを投与すべきかの問題もある。野生動物に経口的に与えられる H5N1 ワクチンは存在しない。家禽のワクチンは感染を防止することはできないが症状を和らげる (ウイルス量を減らす) 効果はあり、中国の国家的な家禽のワクチン接種は H5, H7 に対して一定の効果を収めている。一方メキシコの H5N2 ワクチンなどはあまり成功しなかった。
家禽にワクチンを接種することで感染が潜在化したり抗原性の変異を速めるおそれも指摘されている。
ワクチンを接種すると家禽の輸出が制限されるので輸出国はワクチンを使いたがらないが、野鳥の間で enzootic (地域流行) になっている現状では輸出制限規定を見直すべきでは。
World Organization of Animal Health (WOAH 世界動物保健機関。フランス名だった OIE 国際獣疫事務局が 2022 年に改称された) は 2023 年に家禽へのインフルエンザワクチン接種が安全な貿易の制約となるべきではないとの声明も出している。
ワクチン接種を行う場合はヒトで行われているようなモニタリングやワクチン株の更新は欠かせない。
いずれは多様なインフルエンザ株に対する万能ワクチンが開発されることが期待されるがまだ研究の初期段階である。
現在の 2.3.4.4b 系統の H5 ワクチンは確保されており mRNA 技術を用いて大量生産は可能である (COVID-19 の例を見ると実際に使われるまでには結構かかりそうな感じはするが...)。
ヒトのパンデミックとなった場合の重症度はよくわからない。(これまでも言われてきたが) 高齢者は過去の H1N1, H2N2 感染で "刷り込み (imprinting)"
(免疫の刷り込みについては 感染したインフルエンザの亡霊 nature ダイジェスト 2018 を参照 - 原著者の Declan Butler はインドガン事件の時のレポーターでもあった) があって部分的免疫を持っている可能性がある。
1968 年の H3N2 パンデミック以降の者は (抗原性が違うので) より感受性が高い可能性も指摘されている。
2009 年の H1N1 パンデミック (いわゆる当時の新型インフルエンザ) によって部分的免疫があるかも知れない。
図にどの動物からどの動物へ感染が伝わったか、それに伴う遺伝的変化も示されていてわかりやすい。
現在問題となっている北米の株はヨーロッパのものそのままではなく、北米の野鳥の LPAI と遺伝子再集合を起こしたもの。南米にはその株が到達したが、北米では野鳥の LPAI とさらに遺伝子再集合を起こして現在牛などの間で流行する株になっている。
ヨーロッパではユーラシアの LPAI と遺伝子再集合を起こして 2.3.4.4b (そしてこれが北米に広まった)、そしてさらにユーラシアの LPAI と遺伝子再集合で 2.3.4.4b (AB) となり、さらにカモメ類に適応した H13/H16 と別の遺伝子再集合が起きて、2.3.4.4b (BB) となった。
これが現在ヨーロッパで問題となっている株 (想像: ヨーロッパで遺伝子再集合が起きやすかったのはシベリアに比べてカモメ類との接点が比較的多かったのかも)。
H13/H16 の主な保有者であるカモメ類についての研究: Peng et al. (2025) Novel H16N3 avian influenza viruses isolated from migratory gulls in China in 2023。
Lizak (2025) Tracking gulls to prevent a bird flu pandemic (Nature news 2025.3.3) アイスランドはこの地で繁殖するカモメ類とより北方で繁殖するものの接点にあたり、H5N1 のヨーロッパから北米への進展に重要な役割を果たしている可能性がある。
2022-2023 年の鹿児島県出水での発生を調べた論文: Esaki et al. (2025) Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Outbreak in Endangered Cranes, Izumi Plain, Japan, 2022-23。
1425 羽のナベヅル、79 羽のマナヅルが弱っているか死体で回収された。そのうち 295 羽のインフルエンザウイルスの検査をした。12 月には陽性率が下がり始めたが 2023.3.20 の段階でも陽性サンプルがあった。2020-2021 年に比べて環境への排泄は高くなく、ツルでも総排泄孔サンプルより気管サンプルの方が陽性率が高く、排泄物から水を介した感染より呼吸器を通じた感染を起こしやすくなっていると考えられる。
他の鳥では HPAI H5N1 はオナガガモとトビの2例で検出されたとのこと。
近傍の養鶏場でニワトリから検出されたものとはウイルスの系統が異なり少なくともこの事象では因果関係がないと考えられる。
ツル類の間での感染途中で遺伝子再集合を起こした証拠もあった。抗体陽性率はこれほどの大発生にもかかわらず比較的低く集団免疫にあまり寄与していないのではないかとのこと。
株の遺伝子は 2021 年イスラエルでクロヅルで集団死を起こしたものに近いとのこと。この系統はツル類で特に致死率が高いのではないかとのこと。個体群全体の集団免疫があまり形成されておらず、今後も発生する可能性があるとのこと。
2022-2024 年の北海道での発生の解析: Hew et al. (2024) Continuous Introduction of H5 High Pathogenicity Avian Influenza Viruses in Hokkaido, Japan: Characterization of Viruses Isolated in Winter 2022-2023 and Early Winter 2023-2024。
ヨーロッパと異なり 2022 年の夏には日本では報告がなかった。
Isoda et al. (2025) Dynamics of high pathogenicity avian influenza virus infection with multiple introductions in a crow flock in an urban park in Hokkaido, Japan
北海道の都市公園カラスの集団死 (2022-2024) の研究。
増殖率 (case reproduction number) が 2022 年の発生で 0.52 - 1.57、2023 年に 0.55-1.78 と推定され、複数回の導入があったと考えられるが、カラスの間で持続感染を続けることも可能な数字となっている。特に冬にカラスが集団生活を行っている時期は要注意の感染源となり得る。
この数字を "low" と表現されているが、コロナウイルス時代に話題となった数字と比較すると結構高い感じもする。2年連続の流行で同じような値が出たことから、カラスに集団免疫が成立しておらず複数回の導入があったと推論されているのではないかと思う。類縁した株なので交差免疫が生じそうに思えるがどうなっているのだろうか (Abstract/Short summary に解釈を少し補った)。
カラスの死体の全数のウイルス検査が行われ始めたのは 2022 年 8 月とのこと。
最近の情報では中国の家禽では最近大きな発生はないが野鳥や生鳥市場では検出されているとのこと: Zhang et al. (2025) Unique Phenomenon of H5 Highly Pathogenic Avian Influenza Virus in China: Co-circulation of Clade 2.3.4.4b H5N1 and H5N6 results in diversity of H5 Virus。
2021 年以降に中国で検出されたウイルスは2タイプに分けられ、G-I H5N6 は中国で地域流行が中心、G-II H5N1 は中国南部が流行の中心で中国や周辺地域に感染が広がっているが G-I より野鳥や水鳥に依存しているとの結果が出ている。
Bo et al. (2025) Characterization of the avian influenza viruses distribution in the environment of live poultry market in China, 2019-2023
中国の生鳥市場のデータ (LPAI を含む)。2022 年以降 H5 亜型の検出が減ってきており H7 はほとんど検出されなかったとのこと。中国北部では H9 亜型が 10-2 月にピーク、南部で H9, H5 は 1-2 月がピークとのこと。H5 + H7 の2価ワクチンが使われていて家禽へのワクチン接種の効果が現れているらしく、H5 の減少要因やこれまで人感染も問題となった H7N9 がほぼ駆逐できるようになってきたらしいとのこと。
一方で H9N2 へのワクチンの効果で変異ウイルスがワクチンの効果を逃れるようになって H9 の検出率にあまり変化がない。
2003-2024 年の韓国の発生の研究: Lee et al. (2025) Epidemiology and pathobiology of H5Nx highly pathogenic avian influenza in South Korea (2003-2024): a comprehensive review
2003-2004: Clade 2.5; 2006-2007: Clade 2.2; 2008: Clade 2.3.2; 2010-2011: Clade 2.3.2.1; 2014-2015: Clade 2.3.4.4 (H5N8); 2016-2017: Clade 2.3.4.4 (H5N6/H5N8); 2017-2018: Clade 2.3.4.4b (H5N6); 2020-2021: Clade 2.3.4.4b (H5N8); 2021-2024: Clade 2.3.4.4b (H5N1, H5N6)
とこちらでも 2011 / 2014 年の間に少しギャップがあるのがわかる。2014 年以降は野鳥の検出事例が増えている。2014/2015, 2016/2017 年の冬の発生も多かったが家禽が中心。その後は 2020/2021, 2022/2023 年の冬の発生規模が大きく野鳥の検出例が多くなった。
ロシアの近年の情報も出てきた: Genetic diversity of A(H5N1) avian influenza viruses isolated from birds and seals in Russia in 2023
極東ロシアのデータは1セットとのこと。カムチャツカのニワトリの株があって韓国のサギから分離された株に近い系統だった (Ru-23-G3)。この地域のデータはまだ少ない。
同じ系統の株の韓国での解析結果は Kang et al. (2023) Introduction of Multiple Novel High Pathogenicity Avian Influenza (H5N1) Virus of Clade 2.3.4.4b into South Korea in 2022 参照。
この論文では大半の株はアジア由来で1事例のみ北米の株と類似性が高く、北米からやってきた可能性も指摘しているが、2021-2023 年の北米の発生の解析の Damodaran et al. (2024) では逆の過程を考えている模様。
英国の Dorset で繁殖中だったハヤブサのつがいが死亡。卵は無精卵だった: Bird flu detected in dead nesting Peregrine Falcon (BirdGuides 2025.6.4) メスが 5/6 死亡、オスは2日後に死亡。
オーストラリアではなぜまだ発生していないのか: Nature news Why hasn't deadly bird flu reached Australia yet? (2024.10.4)。いくつかの説が考えられているがよくわかっていない。
オーストラリアは生きた家禽を輸入しておらず、オーストラリアの多くの鳥は固有種で感染地域に渡らない。
しかし渡ってくる鳥は感染している可能性があり、ミズナギドリ類を捕獲して調べている。
カモ類がウイルスを広げている可能性が考えられているが、カモ類の上皮には RIG-I と呼ばれる "センサー" があって免疫反応 (インターフェロン) を活性化して通常はインフルエンザウイルスを排除する。
カモ類はアジアで複数回の LPAI 感染を起こすことでこのような防御機構を発達させた可能性があるとのこと。カモ類は H5N1 で発病しないかも知れないがウイルスを運ぶことはできる。
生物地理学的理由も考えられウォレス線 (Wallace Line) でスンダ地域と生態系が隔離されており、ウォレス線の西側の種は鳥インフルエンザによく適応している一方、東側では遺伝的な違いによって鳥インフルエンザがあまり適応していないのかも知れないが実証されていない。
この地域の多くのカモ類は長い渡りをしないが、マミジロカルガモ Anas superciliosa Pacific Black Duck や シラボシリュウキュウガモ Dendrocygna guttata Spotted Whistling Duck のような種類もあってカモ類が導入する可能性は否定できない。
オーストラリアの種の H5N1 への感受性はほとんどわからないがおそらく感受性があると推定され、ウイルスの導入があると大きな影響が及ぶ可能性がある。
カモ類の RIG-I が自然免疫として働いている件については Barber et al. (2010) Association of RIG-I with innate immunity of ducks to influenza。
ニワトリは RIG-I が失われているとのこと。参考: Krchlkova et al. (2021) Repeated MDA5 Gene Loss in Birds: An Evolutionary Perspective。ニワトリの各種ウイルスへの抵抗力の弱さの原因の一つと考えられる。
Magor et al. (2013) Defense genes missing from the flight division も鳥類免疫の特性についての情報。いくつかの系統 (主に家禽) で失われたり部分的になった機能がある。鳥類は接する病原体の種類が比較的少ないのかも知れない。
Krchlkova et al. (2023) Dynamic Evolution of Avian RNA Virus Sensors: Repeated Loss of RIG-I and RIPLET が鳥類での系統進化を調べている。散発的に何度も失われているが意外にも古い系統の方が多く失われている。
スズメ目はほぼ完全に持っている。オウム目もほぼ完全に持っているがハヤブサ目では失われている。タカ目やフクロウ目ではほぼ完全に持っているなどここでも猛禽類の中でハヤブサ目の免疫の特異性が目立つ (ただし調べられている種類の範囲で)。オウム目とハヤブサ目は同じ系統をなすが相互にそれほど近いわけでないこともわかる。
ハヤブサ目の方が獲物由来の病原体暴露が多そうだがなぜ不要になったのか不思議な点もある。
ペンギン目やミズナギドリ目でもほぼ失われている。それぞれ系統特異的に失われたものらしい。
ツル目は別系統 (MDA5) を失っている。出水のツルで集団発生にも免疫的特性が関係しているのかも知れない (ツル目にはクイナ類も含まれることも注意。カモと一緒に暮らすことの多いオオバンにも影響があるかも)。
非特異的免疫には他のルートのものもあって冗長性に富んでいるので1系統をたまたま失ってもそれほど支障がなかったのかも。
参考情報: #ミサゴ備考の [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] の "非特異的免疫遺伝子から見る系統関係・哺乳類との比較"。
カモ類やチドリ類はインフルエンザウイルスへの暴露が多いので保存される方向の選択圧が働いているかも (論文ではこれらの点はあまり議論されていない)。興味の中心は家禽で、キジ目で失われたのはかなり古く 4500-6500 万年前と推定されている。ニワトリでは RIG-I の遺伝子の痕跡も残っていないとのこと。代わりに MDA5 の経路が進化している可能性が述べられている。
Salve et al. (2023) Concurrent loss of ciliary genes WDR93 and CFAP46 in phylogenetically distant birds
によれば繊毛の非特異的免疫にかかわる遺伝子が離れた系統で何度も失われていることを示している。キジ目はこちらも失っているが、カモ類とガン類では異なっていてガン類の方がウイルス感受性の高い理由になり得るとのこと。
キジ目の RIG-I に比べると失われた時期が遅く、カモ類とガン類の分岐以降に起きた現象となる。
Neoaves でも散発的に失われているものがある。鳥インフルエンザと関係のありそうな種類ではエリマキシギが失っており、鳥インフルエンザの通常の研究対象外で役割はよくわかっていないがチドリ目にもウイルス保有に関係のある種類があるかも知れないとのこと。
ニュージーランドの渡りをしないミドリイワサザイ Acanthisitta chloris Rifleman でも失われており、渡り鳥が病原体を持ち込んだ場合に保全上の問題となり得る。
チャイロネズミドリ Colius striatus Speckled Mousebird は MDA5 遺伝子も失っておりどのような機構で病原体に対応しているか興味深いとのこと。
鳥インフルエンザに対する反応がカモとニワトリでなぜ違うのかなどに関連して盛んに調べられている分野のようで、Campbell et al. (2023) Evolution and expression of the duck TRIM gene repertoire のような研究もある。
ゲノムデータを利用してどの系統や種でどの遺伝子が生じたり失われているかわかりつつある段階のよう。免疫にかかわる TRIM 遺伝子ファミリーで爬虫類特異的なものは少なめだが (爬虫類 + 鳥類共通のものはかなりあり、哺乳類を含めたすべてに共通するものも多くある)、鳥類や哺乳類に特異的なものは多く見つかっており鳥類や哺乳類の大規模な適応放散に応じて独立に生じたものと考えられる。
ここでも TRIM 類似の RNF135 はニワトリやウズラ、ペンギン、ハヤブサで共通して失われているとのこと。
マガモが鳥インフルエンザの自然宿主として耐性を持つ理由の一つとして提案されているもの: Huang et al. (2013) The duck genome and transcriptome provide insight into an avian influenza virus reservoir species。
自然宿主としてウイルスと平衡関係を保ってきたメカニズムの一端と考えられるが HPAI の出現でマガモの免疫機能が突破された (現在のように渡りで長距離運ばれるようになる以前の研究である点は注意)。
関連してヤンバルクイナでは MDA5 遺伝子に変異があって培養細胞で自然免疫の発動が遅いとの日本の研究がある: Katayama et al. (2023) Cultured fibroblasts of the Okinawa rail present delayed innate immune response compared to that of chicken。
ツル目共通のものかはもう少し調査が必要かも知れない。こちらもキジ目の RIG-I に比べると失われた時期が遅いと考えられる。
離島の鳥はまだあまり調べられていないだろうが、ミドリイワサザイの例もあり、系統的に調べれば離島の鳥の免疫特性などに共通性が見つかるかも知れない。
Becker et al. (2024) Mammalian ZAP and KHNYN independently restrict CpG-enriched avian viruses (preprint)
にも面白い結果が出ている。哺乳類にある ZAP, KHNYN が鳥型のウイルス (鳥インフルエンザや鳥型のレトロウイルス) への抵抗性の一つの要因と考えられるとのこと。
KHNYN 遺伝子は起源的には古く、類似の遺伝子は魚やトカゲ、ワニにも存在するが鳥 (ニワトリ) にはないことがわかったとのこと。哺乳類では鳥類の祖先と分岐後に遺伝子重複を起こしたらしいとのこと。哺乳類の中でも特異なカモノハシにも存在する。
ワニにも類似遺伝子が存在することから鳥類系統が特異的に失ったらしい。個人的には陸上生活が進んで一部の免疫機能を失っても構わない (保持する方向に選択圧が働かない) 状況を想像するが違っているかも知れない。
論文中に過去のヒトのインフルエンザのパンデミックと鳥インフルエンザがどのように関わってきたかの図もある。1957-1967 年 (いわゆる香港風邪) の H2N2 には鳥インフルエンザから3つのセグメント、2009 年 (いわゆる 2009 年の新型インフルエンザ) には2つのセグメントが遺伝子再集合で含まれている。
ヒトインフルエンザの遺伝子を見ることで鳥類から哺乳類へ何度も感染に伴う導入があったことがわかるがいずれもニワトリやアヒルが家禽化された以降の話で、それ以前はどうだったのだろうか (鳥類と哺乳類の相互のウイルス感染はどの程度あったのだろうか) と感じてしまう。
(論文の趣旨に従えば) KHNYN の遺伝子を保持しているのは哺乳類が分岐後も鳥類からの導入がしばしばあってそれを防ぐためだったのだろうか。
2022 年のヨーロッパでの発生時のシロエリハゲワシの GPS 追跡の結果、成鳥の多くは感染しても生き延びたがひなの大部分は死んだ。罹患中は巣で平均 5.6 日間動かなかったとのこと: Duriez et al. (2023) Highly pathogenic avian influenza affects vultures’ movements and breeding output。
成鳥のうち2羽は過去の感染を示す抗体があったとのこと。(#クロハゲワシ備考に続く)
猛禽類が従来考えられていた以上に感染を生き延びている可能性
Rayment et al. (2025) Exposure and survival of wild raptors during the 2022-2023 highly pathogenic influenza a virus outbreak
ハクトウワシで特に高率 (69-76%) に抗体が見られた。鳥インフルエンザ全体への中和抗体はあるが、H5, N1 への特異抗体は若鳥には見られなかった (成鳥は弱毒の他の鳥インフルエンザなどに暴露・感染を経験していて交差免疫で H5N1 感染を生き延びたのかも知れない。免疫を持たない若鳥はやはり H5N1 感染の死亡率が高いのかも)。
他種でも抗体を持つ猛禽類の例が挙げられているがハクトウワシに比べると比率はかなり低い。個体数も少ないものが多いので結論は出しにくいとのこと。
ケアシノスリでは 25% に抗体が見られたが H5, N1 への特異抗体を持つものは少なかった。病気の水鳥を食べる頻度など生活様式の違いもあってどの種に抵抗性があるかなどはすぐにはわからないが、これまで考えられていたよりは朗報と言える。
コウモリ類とウイルスの関係
Morales et al. (2025) Bat genomes illuminate adaptations to viral tolerance and disease resistance コウモリ類がなぜウイルス抵抗性が高いのかゲノム系統解析から明らかにした研究。
コウモリ類が哺乳類の中でも免疫遺伝子に強い選択が起きている。コウモリ類の共通祖先段階から生まれた性質のようで飛翔性の獲得と関係があるならば、鳥類ではいくつもの系統で免疫関連遺伝子が失われる傾向と逆にも見える。コウモリ類では特に ISG15 遺伝子が SARS-CoV-2 耐性に関連しているとのこと。
Liu et al. (2024) Characterization of the induction kinetics and antiviral functions of IRF1, ISG15 and ISG20 in cells infected with gammacoronavirus avian infectious bronchitis virus
によれば ISG15 遺伝子は鳥類では失われている (哺乳類、爬虫類にはある) とのことでニワトリが IBV (avian infectious broncchitis 鶏伝染性気管支炎のウイルスでコロナウイルス科) に感受性があることに関係している可能性もあるがさらに研究が必要であるとのこと。ここでも羊膜類の中で鳥類の特異性が見られる。
Shepard et al. (2022) The Structure and Immune Regulatory Implications of the Ubiquitin-Like Tandem Domain Within an Avian 2'-5' Oligoadenylate Synthetase-Like Protein
によればニワトリでは OASL 遺伝子の配列に ISG15 との共通性があり代替機能を果たしているのではとの研究もある。鳥類は哺乳類に比べ OASL のコピー数も少ないとのこと。
この論文で鳥類・哺乳類のこの遺伝子の配列比較もある。鳥類は主に家禽と水鳥で Telluraves で含まれているものはイヌワシのみ (当時は高精度のゲノムの得られている種類は限られていた)。どのぐらい共通性が高いかは見比べていただきたい。
(コウモリ類の免疫) もしかしたら猛禽類の影響?
飛翔性動物であるコウモリ類と鳥類の免疫の違いについて私的考察を行ってみると、これはコウモリ類が圧倒的に捕食される側であるためではないだろうか。コウモリ類が夜行性となった有力仮説の一つが鳥類による捕食圧だが、常に捕食され、積極的な防御を行えない側の適応として群れを作って集団生活をして希釈効果などで捕食を免れる戦略が進化したと考えることができるだろう
(#トラフズク備考の [コウモリを主に食べる北京郊外のトラフズク]、#ハヤブサ備考の [視覚特性・薄明かりや夜間の狩り] 参照。#カンムリワシ備考に [コウモリダカ] の項目あり)。
そして夜行性で集団生活のために洞窟に住むようになると個体密度が高まり通気性も悪くて感染症が流行しやすくなくなる (この点は水鳥と鳥インフルエンザの関係にも似ている)。その対策として免疫機能を高める選択圧が常に働いてきたのではないだろうか。マガモが特に鳥インフルエンザ耐性を強めて自然宿主となったようにコウモリ類が各種ウイルスの自然宿主となっても不思議でない。
この論文では the evolution of flight is directly or indirectly linked to immune system changes と書いているように飛翔の進化と免疫の関係を想定しているが、捕食される側であるため生じた生活様式により深い関係があるのではないだろうか。もっとも、飛翔するようになったが構造や感覚上の制約から鳥類を上回ることができなかったと考えれば飛翔の進化と間接的に関係しているとも言える。
論文の図 (fig. 2) を見るとコウモリ類のすべての系統で免疫遺伝子への正の選択があるわけではなく、コウモリ類の祖先系統からの特徴というよりは複数回独立に生じたようにも見える。
正の選択が強く働いている系統に限って分岐年代を timetree.org で見積もってみると (論文に年代の calibration まで示されていないので)、4000 万年ぐらい前となってタカ類の適応放散の時期にかなり近い。例えばカタグロトビ類と他が分かれたのが 4500 万年前ぐらい。その後のタカ類の主要系統の適応放散は 3500-2500 万年前ぐらいに起きて現在の主な系統を生み出した。
コウモリ類が飛翔性を獲得したころ (6000 万年前より古いぐらい。最も古いコウモリ類の部分的な化石証拠は 5500-5600 万年前、5200 万年前に完全な化石がある。wikipedia 英語版から) はのびのびと暮らしていたのだろうがハヤブサ類も含めて次第に厄介な相手が現れてきたことになる。
逆に捕食性鳥類の方から見れば格好の獲物があったとも言える。
この推論には妙に納得してしまうのだが、このように考えると我々が現在コロナウイルスに悩まされているのは、猛禽類などの捕食性鳥類がコウモリ類の生態を形作っただろうことに遠因を求めることができるのかも知れない。やはり世界を形作った猛禽類の影響恐るべし。もっとも、近因はヒトがコウモリ類を捕食したり生息地破壊など生活圏に接近しすぎたためで、コウモリ類とコロナウイルスが共生している分には問題なかったのだろうが。
ブタのコロナウイルスである Porcine deltacoronavirus は哺乳類にも鳥にも感染して似た症状を示すとのこと: Liu et al. (2025) Differential Susceptibility to Porcine Deltacoronavirus: Ducks Show Greater Vulnerability Than Geese。
最新状況 2025.1 Kozlov (2025) Will bird flu spark a human pandemic? Scientists say the risk is rising (Nature news 2025.1.27)
この数か月重症のヒト感染者が報告されていて懸念材料となっている。この真っ最中に家畜感染の中心となっているアメリカが WHO 離脱を宣言してしまった。主に牛に感染している株が (clade 2.3.4.4b のうち) B3.13、主に鳥に感染している株が D1.1。D1.1 の感染を起こした人2名が重症で1人は何か月も入院した、1人は死亡。パンデミック株になる可能性があるとすれば牛からか、それとも鳥からか? まだ数が少なすぎて難しい。
B3.13 株のカニクイザル (Macaca fascicularis) への感染実験が報告されている: Rosenke et al. (2025) Pathogenesis of bovine H5N1 clade 2.3.4.4b infection in Macaques 鼻への投与では弱い症状だったが気管では重症だった。消化管経由の感染では症状は出ず抗体陽性転化も限られていた。
Wang et al. (2025) Avian influenza mRNA vaccine encoding hemagglutinin provides complete protection against divergent H5N1 viruses in specific-pathogen-free chickens
ニワトリで立体構造の異なる複数の H5 mRNA ワクチンを用いて完全に感染防御できたとの研究。
mRNA ワクチンとニワトリの抗体はそれほど強力なのか...。
Fabrizio et al. (2025) Genotype B3.13 influenza A(H5N1) viruses isolated from dairy cattle demonstrate high virulence in laboratory models, but retain avian virus-like properties
乳牛で流行している B3.13 が鳥型の特徴を持ちながら実験動物に高い毒性を示した。ヒトの気管支ではやはり鳥型の受容体によく結合する点は変わりない。フェレットで空気感染は起きなかった。
FDA の認可している抗ウイルス薬は効果があり、WHO 推奨の候補ワクチンも防御効果があったとのこと。
備考:
*1: そもそもヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザの何が違うのかは、ヒトに感染しやすいインフルエンザウイルスをヒトのインフルエンザウイルスと呼び、主に鳥に感染するものを鳥インフルエンザウイルスと呼ぶ程度の違いである。
インフルエンザウイルスが宿主の細胞に付着して (後述の HA が関わる) 入り込む際に細胞表面の受容体 (receptor) が重要な役割を果たす。ヒト型のウイルスは α 2-6 シアル酸の受容体に、鳥型は α 2-3 シアル酸と少し構造が異なっている (よく鍵と鍵穴の関係と言われる)。
ブタは両方の受容体を持っているためどちらのウイルスにも感染することができることはよく知られていて、家禽とブタが一緒に飼育されているような環境でヒトにも感染するウイルスが生じやすいとみられている。
鳥型と言われる受容体はヒトが持っていないわけではなく肺の奥深くにあるとのことである。ヒトの上気道 (鼻や喉) では鳥インフルエンザウイルス感染が成立しにくいが、肺の奥深くまでウイルスが侵入できればその限りではない。2004 年ごろベトナムなどで小児の感染が中心であったのは小児は気道が短いため肺の奥深くまでウイルスが届きやすいとの解釈が出ていたが、その後どう解釈されたかまでは調べていない。
鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染しにくい理由のもうもう一つに体温の違いがある。ウイルス増殖も化学反応なので至適温度がある。ヒトのウイルスでは上気道のような低い温度 (33 ℃) で増えることができるが鳥のウイルスは鳥の高い体温に最適化されているためヒトの上気道のような低い温度では増えない
[河岡義裕「インフルエンザ危機」(集英社新書 2005) では第1章 pp. 32-33, p. 44 参照。
(*8) で出てくる生ワクチンはこの増殖温度を 25 ℃ まで下げた株で、毒性がたまたま弱まったものとのこと]。
実際のところインフルエンザウイルスにとっては鳥もヒトも似たようなものなのである
(恒温動物以外にはインフルエンザウイルス、あるいは類縁ウイルスはそもそもほとんど存在しない)。
水鳥のように冬季に群れをなす習性とヒトが集団生活 (特に冬場は多数の人を集めるイベントなども多数行われるなど) をする習性は非常に似ていて、ウイルスが他個体に伝播して数を増やすのに絶好の場を提供している。
水鳥はおしゃべりなどをするわけではないので感染経路は糞口感染でウイルスは腸管で増える。ヒトでは飛沫感染で呼吸器で増殖するのは鳥との行動の違いを考えればわかっていただけるであろう。ウイルスがそのような経路を望んで進化してきたのではなく、鳥でもヒトでもそれぞれの個体の行動がそのような感染経路に適応したウイルスを選抜してきた結果である。
逆に言えばそのような経路を意識して離断すれば感染拡大が防げることは新型コロナでも体験済みの通り。
宿主の行動がウイルスの感染経路を決めているように思える事例として HIV や狂犬病などを思いつくことができる。
さらに考えると恒温動物の体内は温度もほぼ一定に保たれ栄養も十分にある培養器のようなものであり、放っておくと細菌やウイルスだらけになるだろう。それを防いでいるのが免疫で、鳥類と哺乳類が極めて優れた免疫系を独立に確立した背景にはそれがないと恒温動物として成り立たなかったからであろう。
例えば爬虫類は免疫グロブリンの IgM, IgY (IgG 相当) を持っているが抗体価はあまり高くならなず、抗原特異的抗体ではなく自然免疫の方が役割を果たしているのではとの研究がある。
鳥類は哺乳類同様の高度な獲得免疫システムを持っている。膨大な数の抗原に対応する抗体を作るいわゆる B 細胞というのは鳥類の総排泄孔近くの腸管が膨らんだファブリキウス嚢 bursa Fabricii の bursa の B が由来。鳥類においては B 細胞の成熟に必須の器官。哺乳類では独立した器官ではなく骨髄がファブリキウス嚢と同じ役割を果たしているとされている
(哺乳類の話では bone marrow の B が B 細胞の由来と説明しているものもあるが、ちょっとこじつけっぽく感じる)。
膨大な数の抗原に対応する抗体は免疫グロブリンの遺伝子再構成 [V(D)J recombination, (somatic) gene conversion] という現象で作られ、鳥類ではファブリキウス嚢で起きる (これは家禽中心の話で、種類によって違うかも知れない。ハトではファブリキウス嚢除去でニワトリのように免疫不全にはならないとのこと)。
生物学の常識を覆すこの体細胞の遺伝子再構成現象は 1976 年利根川進らが発見し 1987 年のノーベル生理学・医学賞を受賞。
鳥類の免疫について説明している wikipedia 英語版 (Avian immune system) によれば羊水から母体免疫を得るが生まれた時点では自身では抗体を生成することができない。そのため生後数週間は病原体に弱い。生後6週間 (ニワトリの数字だろう) はファブリキウス嚢で盛んに遺伝子再構成が行われる。
遺伝子再構成に使われる遺伝子部位は哺乳類では複数の V, D, J の領域がある。鳥類ではこのうち一部の組み合わせがあるのみで理論的には鳥類の方が作ることのできる抗体の種類が少ないが、鳥類では上流の偽遺伝子群が遺伝子再構成に関わって抗体の多様性を高めている。
T 細胞の T は胸腺 thymus 由来で、これは鳥類・哺乳類に共通 (鳥類・哺乳類に共通のものは共通祖先の段階ですでに存在したことを意味する。共通でないものはそれぞれ独立に進化させたと考えればよい)。
卵にも母体由来の大量の抗体が含まれ、「ダチョウ抗体」で知られるように鳥類の免疫能力は高いと言われる。
後日追記部分: Eriksson and Larsson (2025) Avian Antibodies as Potential Therapeutic Tools
鳥類の抗体価は高く、卵から抽出できる利点がある。リウマトイド因子 (Rheumatoid factor) は 変性した IgG に対する抗体で抗体の作用を妨害するが IgY には反応しない利点がある。
この論文では遺伝子再構成のメカニズムの違いは鳥類のやり方 (偽遺伝子群を用いる gene conversion) の方が可変部位のアミノ酸の変異率を高める (somatic hypermutation) ことに主に頼っている哺乳類の方法より利点がある書き方になっている。
鳥類抗体をヘビ咬傷に用いる可能性も考えられるとのこと (ウマ抗体では副反応もあってあまり実用になっていない)。製薬業界では特許を得ることが重要で IgY の臨床応用にはなかなか結びついていないとのこと。
さらに Esmaeili et al. (2025) A systematic review of the avian antibody (IgY) therapeutic effects on human bacterial infections over the decade
のレビューがあり、抗生剤耐性菌が増える中で新しい抗生剤はなかなか見つからず、IgY が代替や抗生剤の効力を補強する候補に挙がっているとのこと。哺乳類の IgG とは異なるので単に中和機能 (病原体表面や毒素と結合する) だけを利用しているのかと思っていたら、補体 (complement) は活性化しないもののサイトカインなど別経路で哺乳類でも炎症を起こして病原体と戦う可能性があるとのこと。
鳥類は分泌型 IgA 抗体を持っていて粘膜に分泌し感染を防ぐ点は我々と同じ。
生後の発育においてニワトリでは粘膜の IgA は2週間後から急速に上がって3週間で定常値に達する。カモではもっと時間がかかるらしい。
爬虫類までの系統は IgA を持たないものもあり、IgA の役割は鳥類・哺乳類ほど明らかでない。鳥類・哺乳類のように子育てをする (まだ免疫の不十分な幼若な個体に乳汁として、あるいは餌と一緒に IgA を与えるなど) 必要性から一層の進化を遂げたものかも知れない (調べればどこかに書いてありそうな話だが)。
よく調べられている鳥類はニワトリのように早成性のものが多いので、晩成性の種類では免疫の発達に異なる点があるのかも知れない
[Jacquin et al. (2012) Prenatal and postnatal parental effects on immunity and growth in 'lactating' pigeons
ではハトのピジョンミルクが免疫形成に役立っている可能性を示している。小鳥の人工孵化でそのう抽出液を与える必要があった小西正一氏のエピソード (#ヒガシメンフクロウの備考参照) も関係があるかも知れない。
吐き戻して餌を与える種類 (ハゲワシ類、アマツバメ類を例に挙げている) で抗体を与えている可能性が考えられている文献があるとのこと (Apanius 1998)]。
鳥類を含む主に瞬膜を持つ動物は (鳥では眼球の後ろ) 眼窩にリンパ組織であるハーダー腺 (Harderian gland) を持ち、頭部で IgA などを産生する主要組織となっている (ハーダー腺は霊長類にはほとんどないそうだが他にもヒトのマイボーム腺同様に目の潤滑物質などを分泌し、哺乳類では毛づくろいのための脂腺やフェロモン分泌器官などとしても働いている)。
この分泌物は目から鼻腔へと流れて上気道の免疫機能の一部を担っている。
鳥類は哺乳類にある IgD (役割は不明)、IgE を持たない。IgD は系統進化的には古くからあるが、哺乳類では量も少なく遺残物のようなものかも知れない。IgE は哺乳類ではアレルギー反応に関係する。
鳥類にもアレルギー反応は存在し、IgY が IgE 同様の機能を果たしているとのこと。
*2: 河岡「インフルエンザ危機」では第2章 さまざまなインフルエンザウイルス の後半参照。
*3: 河岡「インフルエンザ危機」では第1章 p. 35 に模式図がある。
*4: 抗インフルエンザ薬には主に3系統がある。アマンタジン (amantadine) が最初に用いられたもので、A 型インフルエンザウイルスの M2 タンパク質のプロトンチャンネルを阻害し、ウイルスが細胞外に出るのを妨げる (現在では耐性のためほぼ使われていない)。
鳥インフルエンザは A 型なので本来効果があり、1997 年にヒト感染した時にまだタミフルが臨床現場で用いられなかったので使われた (耐性は持っていなかった)。同じ系統の薬にリマンタジンがある。
ちなみにこれらの薬はアダマンタンという対称性の高い炭化水素骨格を持ち、炭素骨格がダイアモンドと同じであることからこの名前が付けられた。有機合成化学でも歴史的意義を持つ物質。
中国の鳥インフルエンザが問題となっていた時期、中国ではアマンタジンをニワトリに与えているとの噂が出ていたが真偽のほどは不明 (そんな高価な薬をニワトリに与えないだろうと言われていた)。
また中国では市販の風邪薬成分にアマンタジンを含むものがあって薬のパッケージ写真まで紹介されていたがこちらも真偽のほどは不明。
本文中にあるノイラミニダーゼ阻害薬がタミフルなど4種類。その後開発されたゾフルーザはウイルスの RNA ポリメラーゼの一部をなすキャップ依存性エンドヌクレアーゼに作用してウイルス複製を阻止する。
アビガンも RNA ポリメラーゼ阻害効果のある薬で新型コロナでも話題となったが期待されたほどの効果がなかったことはご存じの通り。現在市場流通していない。
*5: 河岡「インフルエンザ危機」では第4章 インフルエンザウイルス研究最前線 に基本的な技術の解説がある。インフルエンザウイルスの人工合成 (リバース・ジェネティックス reverse genetics) は著者のグループが 1999 年に最初に成功 (pp. 129-133)。「スペイン風邪」ウイルスのリバース・ジェネティックスによる復元はこの著書の書かれた後に行われた。
*6: 河岡「インフルエンザ危機」では第1章 新型インフルエンザの足音 pp. 22-25 に考察がある。マスコミが「渡り鳥犯人説」を盛んに取り上げていたが、著者の考察はもう少し慎重である。
韓国で 2003 年に流行していたが当時は詳細が公表されず、事件や被害が報告されたのは2004年2月になってからであったことも記されている。
また食材として大量のニワトリを日本にも輸出していたタイも感染が広まっているにもかかわらず輸出先に知らせず、鳥インフルエンザに感染した子供がいることのリークがメディアにあってようやく2004年1月に公式に認めたことも書かれている。
この著書は2005年8月に書かれたもので、H5N1 HPAI のロシア進展の最中だった。「あとがき」でそのことも、日本ではほとんど話題になっていなかったことも触れられている。当時マスコミに出るウイルス学者は「渡り鳥犯人説」が主流であったが河岡氏は終始慎重な記述を行っていた。
*7: 河岡「インフルエンザ危機」では第4章 インフルエンザウイルス研究最前線「たった1個のアミノ酸がウイルスの毒性を左右した」(pp. 122-126)。
この変異が哺乳類への適応を高める分子機構が明らかになった: Arragain et al. (2024) Structures of influenza A and B replication complexes give insight into avian to human host adaptation and reveal a role of ANP32 as an electrostatic chaperone for the apo-polymerase。
*8: 河岡「インフルエンザ危機」では第4章 新型インフルエンザから身を守るには に興味深い記述がある。(引用開始) 1962 年から 94 年まで、日本中の小学校でインフルエンザワクチン接種が義務付けられていた。(中略) 学童のインフルエンザワクチン集団接種は、子供たちで増えるインフルエンザウイルスの量を減らすことにより、社会全体におけるインフルエンザウイルスの量を減らしていたわけだ。
こうしたシステムを採用していたのは日本だけで、国際的にも注目されていた。
しかし 1994 年に予防接種法が改正され、学童への集団接種は中止されてしまった。改正のきっかけになったのは、一部の人たちが「インフルエンザワクチンの集団接種は効いていない」という説を唱えたことだった。この説への対応が正しくなされなかったために、集団接種が任意接種に変更されてしまったのである 。
(中略) そしてその結果はというと、インフルエンザにかかる人が増加し、死亡者も増えてしまったのである。
一方的な解釈で「ワクチンは効かない」とした人の意見を通したために、多くの犠牲者がでてしまった。
ワクチン集団接種中止に関わったすべての関係者の責任は、ひじょうに重い。(中略)
今、インフルエンザ被害を最小に食い止めるためにワクチンが必要不可欠であることに異議を唱える専門家はほとんどいない。
しかし、世界に誇れるシステムであった学童への集団接種は、社会全体のインフルエンザ量を減らすために "子供を利用して" いるという理由から、再開されることはないだろう。(引用終わり)
アメリカのワクチン事情、生ワクチンのことも記されている。アメリカでは 2003 年から (日本でも使われている) 不活化ワクチンに加えて年齢制限はあるが生ワクチンも接種可能となったこと、スーパーで簡単に接種を受けられ、相対的に安価で高齢者は無料であったとのこと。著者は一日も早く日本の子供たちが生ワクチンを接種できることを願っていると記している。
[追記: 2023年3月 経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの 2 歳から 19 歳未満に対する使用について、薬事承認された。厚生労働省ページより]
前述のように呼吸器感染症のように外部から病原体が侵入する場合、粘膜の IgA が感染成立を防ぐ役割は大きい。抗原を注射するタイプのワクチンでは IgA 誘導能力は十分高くないのでしばしば感染を防ぐ効果よりも重症化を防ぐ効果が説かれる。新型コロナウイルスの mRNA ワクチンによる実験では IgG, IgA のいずれも誘導されたが IgA の方が早く低下したとのこと。
鼻腔や点眼で投与できるワクチン (上記のようなインフルエンザ生ワクチンや無害なウイルスに遺伝子を組み込んだ遺伝子組み換えワクチンなど) の方が効果が高いと言われるゆえんである。鳥における鳥インフルエンザワクチンでも点眼、鼻腔で接種できるワクチンの研究が行われているとのこと。
これらの情報は報道記事などを読む時にも役立つかも知れない。
*9: 2024.12.2
FINAL REPORT: COVID Select Concludes 2-Year Investigation, Issues 500+ Page Final Report on Lessons Learned and the Path Forward
が武漢の研究所から漏れた (most likely emerged from a laboratory in Wuhan) とのレポートをホワイトハウスが発表し、Nature に早速反論記事が出ている:
Sick animals suggest COVID pandemic started in Wuhan market (Mallapaty 2024.12.4)。まだ査読されていないがゲノムデータが国際会議で紹介され、武漢の市場の動物間で感染が起きていた証拠が得られているとのこと。
このウイルスに感受性のある動物が武漢の市場にいたことまでは判明していたが、感染していたことはこれまで判明していなかったとのこと。この研究により動物間の感染のミッシングリンクがつながることになった。大部分の科学者は動物起源と考えているとのこと。
Nature にさらに続報があった。Wuhan lab samples hold no close relatives to virus behind COVID (Mallapaty 2024.12.6)
本文の方で紹介の 2020 年 Scientific American の記事と同様だが、Shi Zhengli = 石正麗 は武漢の研究所には最も近縁のウイルスはなかった。まだ査読されていないがゲノムデータを公開した。2004-2021 年にサンプルされたもの。その中にはこれまで知られているウイルスより近縁のものはなかった。
既知のウイルスで最も近縁のものはラオスと中国雲南省のコウモリで見つかったもので、COVID-19 を起こしたウイルス (SARS-CoV-2) との共通祖先は何年か前 (数十年ではないだろうとのこと) に分岐したと考えられる。
Shi Zhengli は長年アメリカの Peter Daszak (EcoHealth Alliance、ニューヨーク市をベースとする非営利団体) と共同研究をしていたが、2024 年 5 月にアメリカ政府はこの団体への資金補助を中断した話も書かれている。
What sparked the COVID pandemic? Mounting evidence points to raccoon dogs (Mallapaty Nature news 2025.2.21) 奥地に住むコウモリから都市部でヒトへ直接感染する可能性は低いが、中間の動物を介して感染した可能性が考えられている。感染を中継した動物としてタヌキ Nyctereutes procyonoides が注目されている。
このウイルスに感染して病気にならないが他に感染を広める能力があることが実験的に示されており、毛皮や食用として武漢の市場で多く売られていたことがわかっている。2020 年に市場閉鎖後のサンプルに COVID-19 陽性サンプルの他にタヌキのミトコンドリア DNA が多く検出された。
この動物がウイルスに感染しいていた直接の証拠はないが、他種も含めて病気らしい個体もあったとの未発表データがあるとのこと。市場の他の動物種のウイルスへの反応はタヌキほどはわかっていないので現状第一候補となっている模様。
Exclusive: Inside the thriving wild-animal markets that could start the next pandemic (Jane Qiu Nature news 2025.6.3) 生きた野生動物の市場と流通、パンデミックを起こすウイルスのリスク。センザンコウが薬になると信じられていて中国に密輸されている。一部は押収されてウイルスの検査対象となって類縁コロナウイルスが見つかっている。ベトナムやインドネシアの市場の実態など。祭りの時期に特に多数売買される。
鳥インフルエンザ同様、鳥類・哺乳類に共通するウイルスとしてウエストナイル熱ウイルス (西ナイル熱ウイルス, West Nile Virus, WNV) がよく知られていて、1999 年北米に毒性の高い株がおそらく人為 (イスラエルで分離された株に最も似ていた) によって持ち込まれ惨劇をもたらした (現在も継続している) ことはよく知られている通り。
レビュー論文: Saiz et al. (2021) Pathogenicity and virulence of West Nile virus revisited eight decades after its first isolation。
WNV は温暖化の影響も受けてヨーロッパ (イタリア北部低地やバルカン半島など) で拡大している: Erazo et al. (2024) Contribution of climate change to the spatial expansion of West Nile virus in Europe。
蚊が媒介するため niche modelling は他の生物分布の推定と基本的に同じ。
WNV はワニにも感染するらしいが皮膚症状で免疫反応はやや異なる模様: Piras et al. (2025) The pathogenesis of West Nile virus-associated lymphohistiocytic proliferative cutaneous lesions of American alligators (Alligator mississippiensis)。
Kocabiyik et al. (2025) West Nile virus - a re-emerging global threat: recent advances in vaccines and drug discovery WNV に対するワクチンと治療薬の進展について。人用はまだ実用化されていないが馬についてはいくつかのワクチンが承認された。
西ナイル熱ウイルスに近縁のウイルスはよく知られたところでは日本脳炎ウイルスがあるが、他にも西部ウマ脳炎 (Western Equine Encephalitis Virus, WEEV) などもあり、これも感染環は鳥と蚊の間で維持されており、哺乳類にも感染する。日本の感染症法では日本脳炎、ウエストナイル熱同様に4類感染症に分類されている。
WEEV は 1930 年に発見されたウイルスで 1960 年代にはアメリカで多くの患者が出たが近年は見られなくなった。その原因を明らかにした論文が発表された。Li et al. (2024) Shifts in receptors during submergence of an encephalitic arbovirus。
哺乳類受容体への結合能力を失ったが鳥の受容体への結合能力は引き続き持っている。爬虫類にも存在するとのこと。この変化が農業様式の変化で農地のウマが減ったためなどの要因で哺乳類感染の適応度が減少したことによるものか、ウイルス自身の遺伝的浮動によるものかはよくわからないが、再度感染力を持つ株が現れる可能性もあるとのこと。
Xiaoyi Fan et al. (2025) Molecular basis for shifted receptor recognition by an encephalitic arbovirus
(一般向け解説)。受容体のわずかな変化で鳥と蚊の間の感染環から哺乳類感染を起こすものに変化できる。北米の 1958 年以降の株は鳥類・哺乳類いずれの受容体にもよく結合していたが、2005 年の株は哺乳類への結合力が低下した。南米の株にはこの変異がないとのこと。
鳥とは関係がないが、新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) の分子系統解析によって、ヒトからの感染で野生動物に広まっていることが判明。特に 2023 年には顕著。
野生動物側からは自分たちにとって外来病原体を増殖してばらまく困った宿主に見えるだろう: Goldberg et al. (2024) Widespread exposure to SARS-CoV-2 in wildlife communities。
動物のウイルスの広がる速度と系統解析から人為的な動物の移動がどの程度関係しているか調べた研究: Dellicour et al. (2024) How fast are viruses spreading in the wild?
単独粒子のブラウン運動 (この場合は距離的広がりは時間の平方根に比例) を指標するパラメータやどの程度外れているかを定量的に評価。diffusion coefficient (拡散係数) の物理用語が用いられている。
メコン川地域の H5N1 (現在渡り鳥にも定着しているもの以前の株) は中程度に人為的な移動が関わっている。北米の WNV では急速拡大期に "転移" のような遠方への広がりを見せた。
そう言えば H5N1 の初期のロシア進展時の地理的広がりがブラウン運動的でないことから人為がかかわっているのではと議論していたことがあった。
自然免疫に関連してもしかすると関係するかも知れない研究が報告されたので紹介しておく。COVID-19 に免疫を持たないがウイルスに暴露されても発症しない人がある原因を調べた: Lindeboom et al. (2024) Human SARS-CoV-2 challenge uncovers local and systemic response dynamics。
粘膜上皮の繊毛の HLA-DQA2 が感染を防ぐ効果があった。
野生動物感染症関連の話題: Cheng et al. (2025) An Unusual 'Gift' from Humans: Third-Generation-Cephalosporin-Resistant Enterobacterales in migratory birds along the East Asian-Australasian Flyway
第3世代セフェム系抗生剤耐性を持つ細菌が東アジア - オーストラリアフライウエイの渡り鳥から検出された。言うまでもなく人が抗生剤を用いた結果生じたものだが、この薬剤耐性プラスミドは細菌の適応度を落とすことなく別の細菌に導入されることがわかったとのこと。
ヒトの動物由来感染症の由来は家畜化以降: Animal diseases leapt to humans when we started keeping livestock (Nature news 2025.7.9) 人骨に残る病原体の解析から 6500 年前以降のみ認められ、5000 年前にピークを迎えた。アイデア自身は新しいものではないが DNA をもとにしたデータで示したものは初めて。
論文は Sikora et al. (2025) The spatiotemporal distribution of human pathogens in ancient Eurasia (オープンアクセス)。ユーラシアの大陸部の広い範囲が調べられている。家畜化のタイミングや場所など細かく読むと面白い情報がいろいろありそう。なお DNA しか調べていないので RNA ウイルスの情報はない。インフルエンザの起源はどこまで遡ることができるのだろうか。
-
ハクガン
- 学名:Anser caerulescens (アンセル カエルレースケーンス) 青みがかったガン (アオハクガンを指していた)
- 属名:anser (m) ガン
- 種小名:caerulescens (adj) 青みがかった (caeruleus (adj) 青い) #カタグロトビの備考参照
- 英名:Snow Goose
- 備考:
anser は#ハイイロガン参照。
caerulescens は後半の2つの e が長母音で前者にアクセントがあると考えられる (カエルレースケーンス)。学名に使われるのみのようで古典式発音は確かでないが文字表記より推定。語形解説は#ワシカモメの備考参照。この形の語尾の読みは長音に統一することにした。
ハクガンには2つの morph があり、blue morph が存在する (wikipedia 英語版より)。英語で blue goose とも呼ばれる (日本語ではアオハクガン)。Linnaeus (1758) による種小名はハドソン湾を基産地とするこの morph を指したもの
(Avibase の情報による。原記載。記載時学名 Anas caerulescens)。
Anser hyperboreus Pallas, 1769 の学名もあり現在はシノニム。
Boie (1822) がこの種のみからなる Chen 属を導入 (ギリシャ語でガンを表す khen, khenos ギリシャ語から "ケーン" の発音と考えられる)。したが後に Anser 属にまとめられた。hyperboreus は "北の"。
この属が使われていた時代には Chen nivalis Foster (または亜種として Chen hyperboreus nivalis) の学名があった。nivalis は "雪の" の意味で、この学名と英名がよく対応している。北米中心に目立つ鳥であったため、学名も北米中心に記載が進んだ模様。
Hartert (1910-1922) p. 1290 を見ると hyperboreus この種で2番めに早い記載のよう。
Hartert の当時は多くの鳥類学者 (Salvadori, Ridgway など) が青っぽいガンを白っぽいハクガンの若鳥に似ているとして "Anser hyperboreus" と一緒にまとめ特別の種として扱い、Anser caerulescens にまとめていたとのこと。
当時は Anser (Chen) hyperboreus の方に大 (nivalis) 小 (hyperboreus) 2亜種を認める見解になっていた。
Hesse は caerulescens は変異型 (Aberration) に過ぎないとして Farbenschlaege (色変わりまたは色の型) と名付けていた。Hartert は "Phase" (相) と呼ぶよりはよい表現と考えていた (Phase は時間とともに変化する意味がある)。両者の中間型もごくまれにあり、オランダの Blaauw の飼育実験の結果 (1915) もこれを裏付けるものだった。
が、caerulescens と hyperboreus が色違いの関係にあるならば、より少ない方のものであっても先に命名された Anser caerulescens に当然先取権があり、その場合は白いハクガンの方が色違いとすら形式上解釈とすることもできるとのこと。
この Hartert の時代に用法が統一された模様。
Linnaeus (1758) が指したものがアオハクガンであったために別のものと考えられ Snow Goose = Chen hyperboreus nivalis として扱われていた模様。種小名の意味と色彩がよく対応しない印象を受けるのはそのため。
白色型のハクガンとは違ってアオハクガンはシベリア東部のみに分布とコンサイス鳥名事典にある。
2亜種あり (IOC)。
日本で記録されるものは基亜種 caerulescens 亜種ハクガン とされる。亜種 atlanticus (大西洋の) オオハクガンは日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で検討亜種。絶滅危惧 IA 類 (CR)。IUCN 3.1 LC 種。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では当時の慣例によって Anser hyperboreus の学名の方が用いられていた。英名は Snow-Goose となっていた。そのうち小型の亜種 (hyperboreus) と考えられていた。
ちなみに "Fauna Japonica" では短い 記述 で学名は Anser hyperboreus、フランス語名 l'oie de neige ordinale (普通の雪のガン)。Pallas の記載ではシベリアのレナ川やヤナ川に多数生息したがカムチャツカでは非常にまれ、と記述。
志村 (2000) Birder 14(2): 48-51 に 1975-1976 年にかけて伊豆沼に "blue goose" が来ていることが NHK のニュースで放映され訪れられた時期の記事がある。当時の日本の図鑑には記載されておらず、その後一時は図鑑にも載ったがマガンとハクガンの雑種と判定されて (当時の) 図鑑からも消えたとのこと。
最寄りの新田駅の当時の状況も記述されていて、当時の面影の残っていた時代を知っている者にとっては懐かしい。情報を知って訪れてその1羽をよく見つけられたものだと感心する。
1980 年代から「東アジアにおけるハクガン Anser caerulescens の復元計画」が行われた。以下の資料を参照。
ハクガン復元計画資料館・暫定版 (日本雁を保護する会 JAWGP)、
シジュウカラガン・ハクガンの回復・復元計画の経過と課題 (呉地正行)。
池内 (1997) Birder 11(1): 44-49 によれば 19 世紀から 20 世紀初頭にかけてシベリアのツンドラから姿を消したとのこと。理由は過剰な狩猟や卵の採取、トナカイの過剰放牧と考えられるとのこと。そして人の訪れない島でのみ繁殖することとなった。
Dement'ev and Gladkov (1952) にも記述があり、17, 18 世紀には北氷洋沿岸の東シベリアの Pyasina 川 (タイミル半島) からチュコト半島の東端までおそらく分布しており、東シベリアの大河下流や北氷洋の島で繁殖していた。19 世紀半ばには交易品となっていたが、Pallas (1811) によれば 19 世紀初頭にはすでに非常にまれになっていて、1820-1824 年にはコリマ川デルタ (とウランゲル島) に追い込まれ、そして 20 世紀初めには大陸で完全に絶滅したとのこと。
この種の絶滅の主要要因は繁殖地、換羽地、渡り途中、越冬地での絶え間ない迫害の結果 (ロシア、アメリカとも) と考えらえる。最も破壊的だったのは繁殖地と換羽地での迫害であり、20 世紀初頭まで無人であったウランゲル島に数百の巨大なコロニーが残るだけとなったと述べられている。
ロシアのハクガンの繁殖地はウランゲル島が唯一知られているがそれらは米国に渡る。東アジアの渡り経路はほぼ消滅しているのにカムチャツカで群れが見られた カムチャツカのハクガンの報道 (2020)。家族で移動する習性があるのに親鳥がいないのは不思議だとのこと。
上記日本雁を保護する会の情報によれば 2019 年、2020 年とも日本の越冬個体群が多く、繁殖が順調な年は幼鳥率も高いとのこと。繁殖成功率が高い年は、幼鳥だけの群れでさまよって、これまであまり見られなかった地域に出ることがよくあるとのこと [故シロエチコフスキー氏による。澤祐介氏 kbird:05134 (2022.7.15) からの情報による]。
サハリンと千島の記事 (2020)
サハリンや千島での目撃例が増えているとある。Andrej Zdorikov が話を説明しており、保護区ができてから個体数が増えて、カムチャツカでは RDB にも記載された。
今年はサハリンや千島でハクガンだけの群れが見られるようになって、大陸の個体群の復活を意味するとある。
国後島で初のハクガンの群れの渡来 (2019)。
ロシア極北のガンはどこへ飛ぶ の記事 (2018) もあり、過去からの変遷や標識方法、繁殖地 (ヨーロッパ方面も含む) の写真などが出ている。いずれも機械翻訳で問題なく読めるだろう。
ハクガンのロシアでの分布はごく限られているので、我々が想像するほどロシアの人に身近な種類ではないようである。Dement'ev and Gladkov (1952) にも含まれていなかった。
[北米のハクガンの鳥インフルエンザ研究]
論文所在の紹介まで: Sullivan et al. (2025) Potential impacts of 2.3.4.4b highly pathogenic H5N1 avian influenza virus infection on Snow Goose (Anser caerulescens) movement ecology。
越冬個体の H5 抗体陽性率は高いが、夏季滞在して渡りを行わない個体ではさらに高かった。2022 年に H5N1 陽性の確認された1羽は 14 日間動きが緩慢であったが同種と春の渡りを終えたとのことで、完治する例も標識後に感染して死亡した例もさまざまあるらしい。捕獲時に検査されて陽性ならばそのまま放鳥できないだろうから感染後の渡りルートが判明するのは偶然の産物ということだろうか。
-
ミカドガン
- 学名:Anser canagicus (アンセル カナギクス) カナガ島のガン
- 属名:anser (m) ガン
- 種小名:canagicus アラスカのアリューシャン列島 Canaga 島/Kyktak 島/Kanaga (アリュート語)島 から。アラスカのエスキモーは自身を Kanagiamoot (Kanag の住民) と呼ぶとのこと (The Key to Scientific Names)
- 英名:Emperor Goose
- 備考:
anser は#ハイイロガン参照。
canagicus はすべて短母音としてラテン語読みならば "カナギクス" と推定される。
原記載 (Sevastianov 1802) で、Billings がカナガ島で発見し、自身のカタログで Anas Canagica の名称を与えていたとのこと。現在の英名を示唆する記述は特に出てこない。
Brandt (1836) Note sur l'Anser canadensis... (シジュウカラガンの記載文献) にも言及がある。
過去に記述された Painted Goose (Latham) とそれに由来する Anser pictus Pallas, 1811 (参考。Anas Canagica のシノニムとの記述あり) もあって Anser canagicus の名称をここでは新規に与える形になっている。
和名は英名由来? ロシア語やウクライナ語名は白い首のガンの意味。分布地でない地域の言語では多くが "皇帝のガン" に相当する名前となっているので英名由来が多いと思われる。
単形種。カナガ島はタイプ標本の産地。
-
シジュウカラガン
- 学名:Branta hutchinsii (ブランタ フトゥキンスィイ) ハッチンスの黒いガン
- 属名:branta 古ノルド語 Brandgas (焼かれたガン/黒いガン) をラテン語化したもの (#コクガンの備考も参照)
- 種小名:hutchinsii (属) ハッチンス (Thomas Hutchins 英国の外科医) の (ラテン語化 -iusを属格化)
- 英名:[Canada Goose 分離前の名称], IOC: Cackling Goose
- 備考:
branta は#コクガン参照。
hutchinsii はラテン語的読み方では "フトゥキンスィイ" と推定される。"ハッチンス" の音とはだいぶ違うが、英語の母音の発音の方が特異なためでここではラテン語的読みを採用しておく。
分離前の種小名だった canadensis は "カナデンシス" または "カナデーンシス"。
亜種名の leucopareia はギリシャ語からの合成語で発音は明確でないが、pareion の e が長母音のためここを長母音とするとアクセント的にも都合がよい (レウコパレーイア)。
4亜種が認められている (IOC)。
日本で認められる亜種は leucopareia (leukos 白い pareion ほお Gk) 亜種シジュウカラガン と minima (最小の) ヒメシュジュウカラガン、及び亜種不明とされる。
亜種 taverneri (カナダの鳥類学者 Percy Algernon Taverner に由来) アラスカシジュウカラガン (チュウシジュウカラガン) が検討亜種に含まれている。
かつてはカナダガン Branta canadensis 英名 Canada Goose と同種とされ、(外来種を含む) 現在のカナダガンを指してシジュウカラガンと呼ばれていた (またはその逆) ために混乱があった。現在の分類でのカナダガンには7亜種が認められている (IOC)。
ガン類の分子系統分類については#ヒシクイの備考参照。Branta canadensis と Branta hutchinsii は結構離れている。
かつてはカナダガンとシジュウカラガンが同種とされていて、記録のあるシジュウカラガンの名称が現在のカナダガンも指す種名和名として使われており、外来種で飼育されるカナダガンもシジュウカラガンと呼ばれたなどいろいろな誤解も発生していた。種和名に日本で記録のある亜種和名を優先するかどうかの問題だった [参考: 渡辺 (2006) Birder 20(11): 59]。
カナダガンの和名は地域を指したものとも言えるが英名や旧学名の Anser canadensis 由来でそのまま訳したと考えられる。というのも現在の Antigone canadensis 旧学名で Grus canadensis もそのまま訳せばカナダヅルになるため。アメリカ合衆国にも分布するため英語では Sandhill Crane。
先崎 (2019) Birder 33(11): 46-49 にあるシジュウカラガンとカナダガンの分類を紹介しておく。
出典は Reeber (2015) "Waterfowl of North America, Europe and Asia" とのこと。
種シジュウカラガン Branta hutchinsii
亜種シジュウカラガン B. h. leucopareia
ヒメシュジュウカラガン B. h. minima
アラスカシジュウカラガン B. h. taverneri (検討亜種)
(基亜種) B. h. hutchinsii (国内未記録)
種カナダガン Branta canadensis
チュウカナダガン B. c. parvipes (検討亜種)
オオカナダガン B. c. moffitti (外来種)
亜種カナダガン B. c. canadensis (国内未記録)
ナイチカナダガン B. c. interior (国内未記録)
オニカナダガン B. c. maxima (国内未記録)
クロカナダガン B. c. occidentalis (国内未記録)
オオクロカナダガン B. c. fulva (国内未記録)
亜種シジュウカラガンは種 Anser leucopareius Brandt, 1836 (原記載) 基産地 Unalaska, Aleutian Islands として記載されたもの。
基亜種は Anser Hutchinsii Richardson, 1832 (原記載) 基産地 Melville Peninsula。
シジュウカラガンはかつて千島列島からアリューシャン列島で繁殖していたが 20 世紀初頭、毛皮目的でアカギツネやホッキョクギツネが繁殖地の島々に持ち込まれ激減した。更に渡りの途中や越冬地での狩猟圧も加わって、個体数は急激に減った。1938-1962 年まで観察記録が途絶え、絶滅したと考えられた。
1963 年にアリューシャン列島のバルディール島で偶然再発見され、保護活動が開始された (雁の里親友の会)。日本雁を保護する会と八木山動物公園・米国魚類野生生物局による保護計画が開始され、米国魚類野生生物局から譲渡された個体を八木山動物公園で飼育下繁殖させる試みが進められた (wikipedia 日本語版、呉地正行) が渡りの復元には至らなかった。
その後、日米露3国のプロジェクトとしてロシアのカムチャツカのゲラシモフ夫妻が飼育下繁殖させ、1995 年千島列島エカルマ島での放鳥を開始して現在の東アジアの渡りの復活につながっている。それ以前は亜種 minima ヒメシュジュウカラガンとともに迷鳥であった。
呉地正行・須川恒編「シジュウカラガン物語」(京都通信社 2021) で詳細を読むことができる。ゲラシモフ夫妻による (夫人は亡くなられた)
「ガンとともに 20 年」(ロシア語) に当時ロシアの厳しい状況や飼育の詳細、主にロシア側から見たシジュウカラガン復活プロジェクトなどが記されて公開されている。映像も多数含まれている。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では学名 Anser hutchinsii 英名 Hutchins' Bernacle Goose となっている。Blakiston and Pryer の時点では千島列島で繁殖していて東京湾の標本もあった。
英名の括弧内はカナダガンと分離される前の名前。ロシア語ではコクガン属のガンを kazarka、他を gus' と区別して呼んでいる。
-
コクガン
- 学名:Branta bernicla (ブランタ ベルニクラ) エボシ貝から生まれた黒いガン
- 属名:branta 古ノルド語 Brandgas (焼かれたガン/黒いガン) をラテン語化したもの
- 種小名:bernicla (合) 伝説、エボシ貝から生まれた (barnacle エボシガイ 英)
- 英名:Brant Goose
- 備考:
bernicla は外来語由来で発音が明確でないが、規則からは冒頭がアクセント考えられる (ベルニクラ)。英語の barnacle も冒頭アクセントなので対応はよい。
Branta 属は Scopoli (1769) によるものでタイプ種は Bannister (1870) がコクガンと定めた。同じ属名を Boie (1822) がアカハシハジロを指して使った (The Key to Scientific Names)。
3亜種あり (IOC)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版以降では亜種名は orientalis (東洋の) から nigricans (黒っぽい) に変更されている。
カオジロガン Branta leucopsis (英名 Barnacle goose) とコクガンは長く区別されていなかった。エボシ貝から生まれた伝説は 12 世紀まで遡り、John Gerard は貝から生まれるのを目撃したと伝えている。伝説は 18 世紀まで続いた (The Key to Scientific Names)。
コクガンの和名は外観から直接付いたとも考えられ、現在の学名の意味するものと大筋で合っているが、Anser nigricans Lawrence, 1846 の学名も使われていた [Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではこの学名] ので当時の学名とも整合性を取っていたかも知れない。
この学名はよく知られていたそうだが何を指していたか議論があったらしい。Delacour and Zimmer (1952) The Identity of Anser nigricans Lawrence 1846 の検討により亜種と認められた。
亜種 orientalis (Tougarinov 1941) もこの文献では亜種として使われていたが現在の IOC では使われていない。nigricans と同じものを指しているとすればこちらの方が先行になり、現在はシノニム扱いのよう。
Dement'ev and Gladkov (1952) ではそれぞれ別亜種としており、太平洋の東西で別亜種と考えていた。
ガン類の分子系統は Ottenburghs et al. (2016) (#ヒシクイの備考参照) を参照。
現在どちらも Branta 属 (コクガン属) であるが、黒っぽいコクガンの亜種グループとカナダガンのグループはそれなりによく分離した系統で分岐年代もコクガンとそれ以外が 670 万年前、アオガン Branta ruficollis 英名 Red-breasted Goose (日本鳥類目録改訂第8版で掲載) とカナダガンのグループとの分岐年代が 580 万年前と見積もられている。
同じコクガン属であってもコクガンとカナダガンとはかなり系統が違っていることは意識しておいてよいだろう。ハワイガン Branta sandvicensis 英名および現地名 Nene (英名別名 Hawaiian goose) はこのうちカナダガンの方のグループで、初期に分化した種類と考えられる。野生での観察がなかなか難しいと言われるが至近で見た経験があるのがちょっとした自慢である (ハワイ島)。
-
コブハクチョウ
- 学名:Cygnus olor (キュグヌス オロル) 白鳥
- 属名:cygnus (合) 白鳥 (cycnus (m) 白鳥)
- 種小名:olor (m) 白鳥
- 英名:Mute Swan
- 備考:
cygnus は#オオハクチョウ参照。
olor は短母音のみで語末は伸ばさない (オロル)。
kuknos 白鳥 (Gk)。ギリシャ神話で Cycnus の名を持つ少なくとも3人が白鳥に変えられた。単形種。英名は他のハクチョウ類に比べて静かなの意味で、鳴かないわけではない。ヨーロッパや中央アジアに主に分布するがユーラシア東部にも離散した分布域がある。世界の他地域で移入種となっている。
系統的に最も近いのはオーストラリアのコクチョウ Cygnus atratus 英名 Black Swan と南米のクロエリハクチョウ Cygnus melancoryphus 英名 Black-necked Swan。少なくとも前者は世界の他地域にも移入されている。
種小名の olor はインド・ヨーロッパ祖語の *hiel- (水鳥の一種) に由来とのこと。古ノルド語 alka (後の auk) とも同根とのこと (wkitionary)。ラテン語では主にハクチョウの詩的な表現で使われるとのこと。olor には英語 odor に対応する語義がある (スペイン語の olor はこちらの意味) が語源が別とのこと。
コブハクチョウは飛翔時に強い音を出す。これは夜間飛行の際の衝突を防ぐ効果があるとも言われる。
リヒャルト・ワーグナー作曲の「ニーベルングの指環」の第1幕の有名な「ワルキューレ」(Die Walkuere, Valkyries。皆もが聞いたことのある音楽だろう) はコブハクチョウの飛翔時の音に着想を得たとのこと [Peter Young "Swan" Reaktion (2008)]。
英語の swan の語源は遡るとサンスクリット語 svanos で音を意味するとのこと (同上)。
近年になって絶滅した "swan" と呼ばれる鳥にモーリシャスの Mascarene Swan と呼ばれるものがある。現在はツクシガモに近い仲間と考えられ Alopochen mauritiana Mauritius Sheldgoose と呼ばれる。最後の目撃は 1668 年モーリシャス島、1670 年レユニオン島とされる。外来種や生息環境の破壊が原因とされる。
ニュージーランドにも New Zealand Swan Cygnus sumnerensis が生息しており、こちらは Cygnus属で一時期はコクチョウのニュージーランド亜種と考えられていたが遺物の遺伝情報解析で別種となった
[Rawlence et al. (2017) Ancient DNA and morphometric analysis reveal extinction and replacement of New Zealand's unique black swans]。
Alice Klein Mysterious mega-swan once waddled through New Zealand (New Scientist 2017)。
最後の個体群がチャタム島に生息していたが人が住むようになって 1650 年絶滅とのこと。
コクチョウよりもさらに大型でマオリ名では pouwa と呼ばれていた (wikipedia 英語版)。
black swan theory ブラック・スワン理論というのは、「ありえなくて起こりえない」と思われていたことが急に生じた場合、「予測できない」、「非常に強い衝撃を与える」という理論とのことである。
ヨーロッパでは白鳥は白い鳥だけと思われていたが、1697 年にオーストラリアで黒い白鳥が発見されたとのこと (wikipedia 日本語版)。チャイコフスキーの「白鳥の湖」では黒鳥のオディールが出てきて、このバレエの見せ場の一つとなっているが、年代を考えるとチャイコフスキーは黒鳥のことは知っていたのだろうか。
コクチョウを黒くする遺伝子がごく最近同定された。Karawita et al. (2023) The swan genome and transcriptome, it is not all black and white。
これによれば SLC45A2 という遺伝子の違いがコクチョウを黒くすることを決めているとのこと。
[東アジアのコブハクチョウの渡り]
大陸ではコブハクチョウは自然分布とされている。
Meng et al. (2020) The migratory Mute Swan Cygnus olor population in East Asia
中国とモンゴルからの GPS 追跡の結果。追跡された個体は朝鮮半島まで記録されたが、日本を訪れたものはなかった。
東アジアのコブハクチョウの渡りは主に東西2経路に分けられるが、追跡された個体は中国・モンゴル国境付近の中央の個体群のもの。アムール地方で繁殖する個体群は調べられていない。
日本では "留鳥" (移入分布) とされる個体が夏場に少ないので渡り個体も含まれているのでは、ただし直接の証拠はないので今後の検証が望まれるとのこと。
Tracking swans in the East Asian flyway (Cao et al. Swan Specialist Group)。
Mute Swan, a Level I Endangered Species, migrated from Mongolia and was spotted in Korea (韓国の National Migratory Birds Center のプレスリリース 2022)
モンゴルと韓国の共同研究が行われており、2021 年モンゴルで発信機を付けた個体が 10 月に韓国に到着し、越冬地を離れるまで追跡されたとのこと。
富沢他 (2023) モンゴル国で標識された野生のコブハクチョウ Cygnus olor の石川県における観察記録 石川県河北潟 で 2021-2022 の冬に越冬とのこと。
iNaturalist の報告分布図を見ると東アジア沿岸ほぼ全域、さらには台湾から東南アジアやインド南部も記録があり、東南アジアについては飼育個体由来の個体群らしい。
台湾では飼育個体由来もあってよくわからないとのこと: Mute Swan (小雨燕 燕雀之誌 2022)。
Cygnus olor (Taiwan Biodiversity Network) では 原生 native としている。
[北米の外来種としてのコブハクチョウ]
北米では在来種に被害を与える外来種として駆除されている: Marks (2018) Mute Swans (Wildlife Damage Management Technical Series)。19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて観賞用の池や湖、動物園や飼育用に持ち込まれた。最初は北東部の州に限られていたが分布を拡大して被害も出るようになったとのこと。
[鳥類の頸椎]
鳥類の頸椎が多いことはよく知られていて、11 (下の値は出典によって異なる) から 25 個と呪文のように覚えている人もあるだろう。最大値の 25 個はなぜか出典による違いはなく、しかも丁寧に「ハクチョウ(類)」と添えてあることがある (この原稿の執筆中に専門家の文章でタンチョウの頸椎が 25 個と書いてあるのを見つけてしまった。ハクチョウをタンチョウと書き間違えてしまったのかも知れないが、「首の長い鳥は 25 個」は案外広まっている誤解なのかも知れない)。
鳥類豆知識の好きな方にとってはこれは格好の題材で、ハクチョウ類を見てこのように説明されている方もあるだろう。実際はどうなのだろうかと調べてみたことがあるが、鳥類の頸椎数をまとめて表にしたような文献はなかなか見当たらず (科や目ぐらいの分類群ぐらいでは載っている本がある)、水鳥については Woolfenden (1961) Postcranial morphology of the waterfowl にまとまっている。
自分が調べた範囲では、ハクチョウ類で頸椎数 25 個はコクチョウとコブハクチョウの一部 (24-25 個とある) だけで、間違いなく 25 個と言ってよさそうなのはコクチョウのみのようである。つまりに日本で普通に越冬する種類としてみかけるものは 25 個と言ってはいけない。
コハクチョウは 22-23 個、オオハクチョウは 24 個とのことである。それぞれ識別点にもなるぐらいでハクチョウ類(およびカモ類)では首の長さと頸椎数がよく相関していることがわかる。コブハクチョウやコクチョウはたまには野外で、また飼育されているものも多いので見る機会も多いだろう。コクチョウは日本のハクチョウ類に比べて一段と首が長いことがわかる。
これだけでも普段の観察時に「マニアック知識」として役立ちそうだが、では他の首が長い鳥はどうなっているのか気になる方もあるだろう。別の出典ではフラミンゴは 19 個、ヘビウ 20 個などとある。首が長いサギ類 (Ardeae) は 19-20 個となっている (出典により多少異なり、後に出てくる Boehmer et al. の部分も参照)。
ハクチョウ類は数で勝負、フラミンゴは骨を長くする戦略になっていることが読み取れる (なぜそうなっているのかは知らないが)。
ただし鳥類の頸椎数は「ヒトの頸椎は7個」のように単純に割り切れない部分もある。鳥類の頸椎下部には頸肋(骨) (cervical rib) が存在し、どこまでが頸椎でどこからが胸椎とするかは資料によって異なる。ここで用いた数字は肋骨が前方で完全に癒合するところからを胸椎とする数え方によっているが、頸肋骨のある脊椎を胸椎に数える著者もある。
この場合数が約2個異なる。13(2) 個のような書き方は括弧内が頸肋骨のある脊椎の数を意味する。前者の数え方ではこの場合は 15 個になる。「フクロウの首の骨はいくつ?」と聞かれても明瞭に答えにくいのはこういう事情もある (なおフクロウの首の骨が鳥類の中で多いわけではない。後の Boehmer et al. や #フクロウの備考参照)。
タンチョウとナベヅルの研究例があるので参考までに Hiraga et al. (2014) Vertebral Formula in Red-Crowned Crane (Grus japonensis) and Hooded Crane (Grus monacha)。
タンチョウ、ナベヅルともに 17 個が基本のようだが 18 個の個体もあるとのこと (この文献に他の種類の文献が出ているので必要な方は調べられるかも)。この数字は記述からはおそらく頸肋骨のある骨の数も含めていると想われるが、引用されている文献は必ずしもそうでなさそうである。
鳥類の頸椎は頸椎数はまだともかく、長さの測定値があまりないようである。首の長さは生態や重心などを決める因子として大きく関係があるはずで、データベースがあればよいのだがどうもなさそうである (研究者も分析因子として使えないので困っている模様。
後の Boehmer et al. を参照して脚の長さで代用されることもあるがこれはちょっと...と感じる)。これは四肢の骨のような測定が難しいことと、真面目に調べようとすると多数の頸椎を測定して足し合わせる (化石生物だとこのようにするしかないが、軟骨や、哺乳類だと椎間板の厚みをどう評価するかなど一筋縄では行かないようである) ことが必要になって研究者があまり取り組みたくないテーマだろうことが背景にあることは想像できる。
3次元 CT を使えば多少は問題が緩和されることになるかも知れないが、調べられているのは少数に限られるようである。
近年個々の頸椎を真面目に測定して足し合わせた論文 (上記のように軟骨が含まれないので生体ではもう少し長くなるはず) がある。Boehmer et al. (2019) Correlated evolution of neck length and leg length in birds で、詳しくはご覧いただきたい。
この文献は頸肋骨のある骨は数えていないので個数は上記のような数字より約2個少なくなっている (そのため最大 23 個になっている)。103 種を調べた結果では鳥類の頸椎数は 10-23 個 (頸肋骨のある骨も数えると多分2増える) で、両端はごく少数で 11-19 個が一般的な範囲のようである (この文献はオウム類を多数調べているので数の少ない種類が多く、頻度分布はあまり参考にならない)。
鳥類の頸椎は進化にも関連して近年興味を持たれているテーマのようで、Marek and Felice (2023) The neck as a keystone structure in avian macroevolution and mosaicism の3次元 CT を使った論文が出ている (調べられた種類はまだ少ないようだが)。#クロハゲワシの備考も参照。
鳥類の環境への適応として頭部や翼の形状が重要なのは簡単にわかるが、それだけでは不十分で、頭部、首、翼を一体として捉える必要があるとのことである。頸椎の形態の進化速度も議論されていて、大きなグループの分岐点では進化も早いことが示されている。
水鳥はかなりよく調べられていて、#リュウキュウガモの備考で現代的な分子系統樹に基づく考察を行ってみた。
鳥類の頸椎数はこのように種類によって異なり、哺乳類では一部の例外を除いて7個であることもよく知られている。問題はむしろ哺乳類の頸椎がなぜそれほど厳格に7個に定まっているのかと言うこともできるだろう。これは哺乳類には横隔膜があるため、という説がある Buchholtz et al. (2012) Fixed cervical count and the origin of the mammalian diaphragm。
もしこの説が正しいならば、鳥類は優れた気のう (air sacs) システムがあるため横隔膜が必要ないところにまで由来を遡ることができることになる。
哺乳類は鳥類に比べて「呼吸器システムの初期設計を誤った」とも言われることがある通りで、インドガンのような高所活動はとてもできない (#インドガンの備考にあるようにそれ以外にも低酸素環境に対応できる哺乳類と異なる生理機構がある)。
鳥類の呼吸器システムの基本設計はさらに頸椎数の自由度を通じて多様な環境に適応できる一要因ともなっているのかも知れない。
広い分類群において長い首は何のために進化したかを統一的に説明しようとしたレビュー: Wilkinson and Ruxton (2012) Understanding selection for long necks in different taxa
鳥類現生種ではおおむね採食行動に関係しているとされるが、水鳥やダチョウでは高さを増すためにまず足の長さを増したがそれに伴って首も長くなったとの解釈。魚食の鳥では逃げるのが速い獲物を捉えるための加速度を得る機構として進化したと考えられる (#カワウの備考 [ウの視力] とも整合する)。ハクチョウ類やハゲワシ類では食物に届くのに役立っている。
ガン類はこれでは説明できず遠くを監視する役割の方が大きそうだが、低い位置を採食する行動においてエネルギー的に有利かも知れない (草食恐竜などになされる説明と同様)。
首の長いハトの品種とキリンに関係して #ハチクマの備考 [フィリピンのハチクマの不思議] でも少し取り上げている (一度まとめたため記述が少し分散している。ハクチョウ類やガン類の話が含まれるためこちらに一部分離した)。
キリンの首では現在も性選択の論争が続いている。かつては恐竜でも性選択説も提唱されていたらしいがさすがに反論が多い模様。
[鳥類の形態データベース]
なお、近年の鳥類の形態データベースとして AVONET があり 11009 種、90020 個体の測定値が含まれているとのこと [Toblas et al. (2022) AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds]。これには頸椎の情報は含まれていない。
このデータベースは R のパッケージとして公開されており、生物学者の基本言語が圧倒的に R であることも感じさせる。このデータをダウンロードし、少し R で作図をすれば自分の興味ある分類群の生態と形態 (例えば脚の長さ)との関係などを手軽にプロットして楽しむことができる (#ハイタカの備考参照)。興味ある方は試していただきたい。
-
ナキハクチョウ
- 学名:Cygnus buccinator (キュグヌス ブクキナートル) ラッパ手の白鳥
- 属名:cygnus (合) 白鳥 (cycnus (m) 白鳥)
- 種小名:buccinator (m) 頬筋、bucinator (m) ラッパ手
- 英名:Trumpeter Swan
- 備考:
cygnus は#オオハクチョウ参照。
buccinator は a が長母音でアクセントもここにある (ブクキナートル)。
英語にも同じ綴りの単語があり、アクセントは冒頭で a は2重母音で発音するなど全体の音はだいぶ違う。
単形種。オオハクチョウの亜種とされたこともあった。
-
コハクチョウ
- 学名:Cygnus columbianus (キュグヌス コルムビアーヌス) コロンビア川の白鳥
- 属名:cygnus (合) 白鳥 (cycnus (m) 白鳥)
- 種小名:columbianus (adj) コロンビア川の (-anus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:(Whistling Swan これは通常アメリカコハクチョウを指す英名)。コハクチョウは Tundra Swan または Bewick's Swan が適切と思われる。IOC: Tundra Swan
- 備考:
cygnus は#オオハクチョウ参照。
columbianus は a が長母音でアクセントもここにある (コルムビアーヌス)。接尾辞 -anus の一般的読み方。
2亜種とされる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では2亜種が記載されていた。
jankowskyi (jankowskii の綴りも使われる) ポーランドからシベリアに流刑され刑期を終えて居住した博物学者 Michal Jankowski に由来。Michal の最後の l は斜め棒が入るが、ポーランド語では英語の "w" に相当する発音になる。ポーランド語の w は [v] の発音になる。
ロシア綴りでは Mikhail Ivanovich Yankovskij となるが姓の部分の発音は同じ。
Jankowski の名前は極東地域の鳥類や他の分類群にもしばしば現れるので知っておくとよい。「ヤンコフスキー家の人々」(遠藤公男 講談社 2007) がある。コハクチョウと
columbianus アメリカコハクチョウであるが、パブリックコメントにて前者は bewickii (英国木版画師 Thomas Bewick に由来) であるべきと指摘された。
多くのリストでは jankowskyi を bewickii のシノニムとしており、これが採用される見通し。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でそうなっている。C. c. jankowskii を用いて、他亜種との遺伝的違いを調べている論文はある
[Wang et al. (2014) Complete mitochondrial genome of Tundra swan Cygnus columbianus jankowskii (Anseriformes: Anatidae)] が、亜種の妥当性を議論したものではなく、種小名の選択も適切でないように思える。
C. columbianus と C. bewickii を別種とするリストもあった。
現在の世界のリストでは同種として扱われるようになった。
2種を認め、亜種 jankowskyi を認める場合は、Dement'ev and Gladkov (1952) に示されているように C. bewickii の亜種とする扱いが適切と思われる。論文にはいずれの表記も現れる。
2種を他の北極のハクチョウ類とともに亜属 Olor として扱う考えもある。
Kbird にて須川恒氏より尾崎清明さんからの情報としてロシアのガンカモ類渡りのアトラス (英文) が紹介された:
Kharitonov et al. (2024) Migration Atlas of European species of palearctic Anatidae with the
population outline (from the data of the Bird Ringing Centre of Russia)
Peter Young "Swan" Reaktion (2008) ではハクチョウ飛来地で3月に旅立ち前の催しが開催されるとして下田公園・間木堤 (八戸北丘陵下田公園) が紹介されているが東京の南西と書いてあって何か誤解されているようである。実際は青森県。
-
オオハクチョウ
-
ツクシガモ
- 学名:Tadorna tadorna (タドルナ タドルナ) ツクシガモ
- 属名:tadorna (合) ツクシガモ (tadorne ツクシガモ 仏)
- 種小名:tadorna (トートニム)
- 英名:Common Shelduck
- 備考:
tadorna は外来語由来で発音はよくわからないがアクセント位置は -dor- と考えられる。すべて短母音とすれば日本語の自然な読みと同様 "タドルナ"。この単語の存在するポルトガル語でも同じ発音になっている。
記載時学名 Anas Tadorna Linnaeus, 1758 (原記載)。
Boie (1822) が種小名を属に昇格し、ツクシガモは Tadorna familiaris とした (馴染みのツクシガモの意味) これは種小名から属名に昇格する場合の当時の用法 (#ノスリの備考参照)。
Hartert (1910-1922) p. 1302 によれば他にも多数あり、上記 Tadorna familiaris は無効名とのこと。Tadorna Bellonii Stephens, 1824 (参考)、Tadorna Vulpanser Fleming, 1828 (vulpes キツネ anser ガン) などの新名があった。
他にも Tadorna vulpina Wood, 1837 (参考) 当時の英名 Greenheaded Sheldrake を指していたが大陸とは別種としたかったものかも知れない。ここでも vulpina とキツネが使われているのも面白い。褐色部分が目立つためか。
イタリア語の volpoca (volpe キツネ + oca ガン) に痕跡が残っている。
AviList v2025 - errors, typos で AviList の属名記載の正当性が順次検証されている。
AviList の採用している Tadorna (not Anas) familiaris Boie 1822 が由来であれば1種のみに与えた属名なので monotypy であってトートノミーによる定義ではない。しかしこの文献を採用するか議論の余地がある。"Tadorna familiaris" が無効名の可能性があるとのこと。
tadorne ツクシガモ (仏) の語源はケルト語で白黒の水鳥、英語の shelduck < sheld (染め分けた) duck とほぼ同意義。単形種。
-
アカツクシガモ
- 学名:Tadorna ferruginea (タドルナ フェルルーギネア) 鉄錆色のツクシガモ
- 属名:tadorna (合) ツクシガモ (tadorne ツクシガモ 仏)
- 種小名:ferruginea (adj) 鉄錆色の (ferrugineus)
- 英名:Ruddy Shelduck
- 備考:
tadorna は#ツクシガモ参照。
ferruginea は u が長母音でアクセントもここにある (フェルルーギネア)。-rr- を単音とする発音もあるが u が長母音でアクセントがある点は変わらない (フェルーギネア)。
主に中央アジアを中心に繁殖する種。アジアのものは冬はアジア南部に渡る。アフリカの一部に留鳥の孤立個体群が存在。単形種。
Anas rutila Pallas, 1770 (参考) の名称も色彩をよく表していて Temminck and Schegel の Fauna Japonica でもこの学名で登場する。
Pallas (1764) の記載の方が早く ferruginea の方が使われるようになった。
#カンムリツクシガモの標本の記述で気づいたが、Tadorna casarca または Casarca casarca の学名が使われていた時代があった。
これは Anas Casarca Linnaeus, 1768 で用いられた学名で、
Anas ferruginea Pallas, 1764 Vroeg's Cat. Adumbr. で無記名で記載した学名 (参考) の方が早かったためこちらが採用されるようになった。
casarca はロシア語由来で小型のガン (シジュウカラガン) やツクシガモ類を指す kazarka から。タタール語の karakchas (黒いカモ) に由来するとのこと。この種小名を昇格した属名 Casarca も使われていたことがあった (The Key to Scientific Names)。
Hartert (1910-1922) では p. 1303 で、Tadorna 属とは嘴の形がまったく違うとのこと。p. 1304 にアカツクシガモの記述がある。
#カンムリツクシガモに登場する Nowak (1983) もドイツ名 Kazarka と呼んでおり、現在でもいくつかの言語に残っている (イタリア語やオランダ語 Casarca など)。ロシア名は ogar' (obgorat' 焼ける) と色に由来、ドイツ名は Rostgans, Rostkasarka で赤いガンのような名前になっている。
Kolyada et al. (2016) は kazarka の語源ははっきりしないとある。こちらではロシア語でコントラストのはっきりした小型のガン類一般を指すと記述。ポーランド語では kazarka はアカツクシガモを指すとのこと。Dement'ev and Gladkov (1952) のアカツクシガモの別名にも kazarka は現れないので本家とされるロシア語ではアカツクシガモに対して使われていなかったのかも。
-
カンムリツクシガモ
- 学名:Tadorna cristata (タドルナ クリスタータ) 冠のあるツクシガモ
- 属名:tadorna (合) ツクシガモ (tadorne ツクシガモ 仏)
- 種小名:cristata (adj) 冠がある (crista (f) 冠 -atus (接尾辞) 〜備わっている)
- 英名:Crested Shelduck
- 備考:
tadorna は#ツクシガモ参照。
cristata は最初の a が長母音でアクセントもある (クリスタータ)。
過去にも目撃回数が少ないが、かつては韓国から日本に輸出され、複数の写生画に登場する。
柿澤・菅原 (1989) 江戸時代の写生図にみられる絶滅鳥カンムリツクシガモ Tadorna cristata (Kuroda) などもっと広範に生息していたと考えられる。
1916 年に韓国で撃たれた以来世界的に記録がなく一度は絶滅が宣言された。1943 年に韓国中部で目撃事例があり、1964 年にウラジオストク近郊のリムスキー-コルサコフ列島でシノリガモの小さな群れの中にメス2羽、オス1羽が目撃された。
1971 年に北朝鮮の北岸、1985 年にロシア東部で2羽の目撃例があるが、1971 年の記録は信頼性が低いとされる。その後も散発的な可能性のある記録があるが、いずれも未確認。もし種が生存していても個体数は 50 羽以下であろうとの見積もりがある (以上 wikipedia 英語版より抜粋。情報の多くは BirdLife International 由来)。
IUCN 3.1 で CR 種、絶滅した可能性があるとされる。環境省レッドリストでは絶滅種。単形種。
世界に3点しかない絶滅鳥 - カンムリツクシガモ (ガンカモ目ガンカモ科) - (山階鳥類研究所の解説)。
[記載と歴史について]
Crested Shelduck (1890) で 1877 年ウラジオストク近郊で採集され、Philip Lutley Sclater (1829-1913) がアカツクシガモとヨシガモの雑種と考えてラベルを付けた標本を含めた世界で3体の標本を見ることができる。
Sclater (1890) の標本写真は 図版 およびその次ページから解説を見ることができる。
Nowak (1983) Die Schopfkasarka, Tadorna cristata (Kuroda 1917) - eine vom Aussterben bedrohte Tierart (Wissensstand und Vorschlaege zum Schutz) に年を追った詳しい歴史が紹介されている。
世界的な歴史についてはこの文献が最も詳しいものではないだろうか。
Nowak (1983) によれば Sclater はそれまでにも多数の新種を命名してきたが、"種は不変" の概念の擁護者として晩年には新しい種を認めることに慎重であったとのこと。
ちょうど進化思想 (「種の起源」の発表が 1859 年) が興隆してきたころで亜種の概念を用いた三名法の流れもあったが、Sclater は保守的な分類学者でこれらの動きには反対していたとのこと。
彼の立場では新種と記載するには良質の十分な研究に基づいた確実な証拠が必要で、それには不十分でああった。"型" や "亜種" のような憶測を排する彼の考えでは雑種と記載するほかなかったと Nowak (1983) が推論している。
Sclater が新しい考えを取り入れてもし亜種名を与えていれば第一標本の記載が先取権を持っていたことになる。
日本から新種を記載できたことは、当時の進化思想の興隆に逆らう慎重で保守的なヨーロッパの分類学者の考えにも助けられていたらしい。黒田長礼氏が Sclater の判断をどのようにとらえていたかは以下の Kuroda (1924) に見ることができる。
黒田氏の記載論文では Pseudotadorna cristata Kuroda, 1917 の学名で On one new Genus and three new Species of Birds from Corea and Tsushima が原記載。
1916年12月に採集されたメス1羽による記載。
Hartert (1910-1922) では別属扱いで p. 1305 に現れる。Hartert には日本からかなり情報が入っていたようで、野生のカモ類の雑種はまれで、野生個体であることから雑種の解釈に否定的でこれまで見逃されていた独立種・属とするのが妥当と考えていた。
朝鮮半島から日本に輸入されていた時代には多く生息していたと考え、今後の研究で雑種でないことがわかるだろうと記していた。
項目にも使われている Pseudotadorna cornuta Kuroda は間違いとのこと (The Key to Scientific Names)。
Nowak (1983) では 1916年3月に朝鮮半島北西沿岸で Akagawa (赤川) という猟師が6羽の群れを見て3羽を捕獲した。過去にこのような鳥を見たことがないと黒田に伝え、記述から黒田はカンムリツクシガモだったと結論したが、獲物は科学者の手に渡ることはなかったと記述されている。
この件はさまざまに記述されているが、黒田から Dement'ev への私信によれば残念なことにその標本は残っていない (Dement'ev and Gladkov 1952) とある。Nowak (1983) はロシアの研究者にも情報が正しく届いていなかったと推定している。
この件について黒田氏の直接の言及 (日本語) は以下の Kuroda (1924) pp. 179-180 にある。異形の海鴨とあり色彩をどのように判定したかなどは原文を参照。当時は珍しいものがあればまず採集の時代であったらしく、海岸にいた6羽の群れから2羽を撃ちとり、海に逃げて戻ってきたもう1羽を撃ったとのこと。
Kuroda (1917) のこの論文で新属も提唱された。当時は Sclater はすでに世を去っており、以下の議論には関与していない。新種ではなく雑種とした理由は Sclater 本人から確かめることはできず推論に頼るしかない。
ヨーロッパでは過去にカモ類雑種に新たな学名を付けた例がいくつもあり慎重だったようで、1920 年代に独立種か雑種かの議論がなされていた。
Nowak (1983) を見てヨーロッパでは分類学の歴史が長く、怪しいものは証拠が出るまではまず疑う姿勢があったのではないかと感じた。すでに標本が存在していたことを知らなかった黒田氏にとっても世界のこの反応は予想外だったのではないだろうか。当時 Hartart が Sclater の報告を見て黒田氏に送られた手紙の内容は柿澤・菅原 (1989) で紹介されている。
1924 年に黒田がもう1個体の標本を記述 On a third Specimen of rare Pscuidotadorna cristata Kuroda。ここまでの3体が現在残る全て。
1940 年にかけて日本から過去の写生画なども発表され、世界でも独立種と認められるようになり、世界の水鳥の権威 Franzose Jean Delacour と Peter Scott が 1954 年の書物 "The waterfowl of the world. Vol. 1" に種として掲載したとのこと。
しかしその間、その後も種に値するか、あるいは分類学的な位置の議論は数多く行われていた。現在考えられているほど自明ではない時代が長く続いていた模様。
Dement'ev and Gladkov (1952) では種の扱いとしていた。
Nowak (1983) が述べている最後の確実な目撃記録とされるものは Labzyuk (1972, 2017 再掲) The crested shelduck Tadorna cristata in the southern Primorye (pp. 133-135) で読むことができる。1964.5.16 のこと。
飛び立つ時の様子や色彩などかなり詳しい記述が残っている。1964, 1967 年に再度調査したが見つからなかったとのこと。
沿海地方でカモに詳しい猟師などにもアンケートを行ったが確認につながる結果は得られなかった。著者は図版を見てこの種に違いないと確証するに至ったとのこと。記述内容を訳したものが Nowak (1983) に含まれている。
このように見るとほとんどの記録が朝鮮半島など国外で、日本での写生も基本的に朝鮮半島から持ち込まれたもの。日本産鳥類と言えるのかと感じるが、1822年10月に函館市亀田で捕獲された雌雄の写生画に基づくとのこと。この写生画が現存する日本唯一の記録とのこと。
「鳥学の100年」(井田徹治著、日本鳥学会、山階鳥類研究所協力 2012) p. 109 によれば色彩図「鳥之種類」の小冊子に収められていたことが 1939 年に判明したとのこと。Nowak (1983) の図 11 の8の点にあたる。
論文は Kuroda (1940) An Old Record for a Pair of Pseudotadorna cristata obtained near Hakodate (カンムリツクシガモ函館にて捕獲の古記録)。
Nowak (1983) は信頼に値する記録と判定しており、場所も特定されて実際に観察された (リアルタイムではないが) 世界初の記録と位置づけている。その次が 1877 年採集された標本。
この小冊子が見つかっていなければ日本人が命名した鳥であったが日本産とは認められなかったであろうことになる。
Nowak (1983) は遺存種と考え、人為開発の著しい地域で残っていたことは奇跡的であった捉え方になっている。wikipedia 英語版では (おそらく) 絶滅したとされる要因に Beacham and World Wildlife Fund (1997) を引いて生息地の減少、狩猟の他に overcollection も挙げている。
他種でもしばしばあったように絶滅に近づいた鳥を学術的に確実な標本に残すために鳥類学者が奮闘した結果が絶滅の一つの要因になり得ただろう状況をここにも見ることができる。
黒田 (1889-1978) 氏は Nowak (1983) の推論を目にすることなく世を去っているが、Nowak が出版に配慮したかも知れない。Nowak が確実と考えた目撃記録は 1943 年以降 1967 年まで飛んでいるので、もし残っていたとしても戦火で失われた可能性もあるだろう。
Eugeniusz Nowak (1933-2024) と Nowak もごく近年に没されていた。wikipedia ドイツ語版によればポーランド生まれでワルシャワとベルリンで学び、1974 年にボンに移住。ドイツで重要な活躍をしているが、東西を結ぶ役割もあって極東のカンムリツクシガモにも強い関心を持っていたのだろう。
カンムリツクシガモの論文ももう2つあり、Nowak (1984) On the presumable breeding and wintering range of the Crested Shelduck, Tadorna cristata (原文ドイツ語)。
Nowak (1982) "Die unbekannte Schopfkasarka" (知られざるカンムリツクシガモ) 雑誌 Wir u. d. Voegel (我々と鳥たち) のドイツの一般向け記事。アルジェリアで 1983 年にハンターに撃たれて標本となったシロハラチュウシャクシギの記事 (1995) も著していた。
Crested Shelduck (Extinction Archives) では絶滅した可能性が極めて高いと判断している。Nowak は 1983 年に捜索隊を組織したが見つけられなかった。
中国北部では Zhao Zhengjie が 1985-1991 年に調査を行いこの時期や遡った目撃情報もあるとのことで 1992 年に中国で論文となっているが国際的に確実な情報とは考えられていないらしい。
IUCN が現在も CR 種としているのはこの不定性 (および北朝鮮の情報がわからないこと) が残っていて、中国北部に残存している希望をまだ完全に捨てていないためだろう。現在では中国北部は情報も増えている地域にもかかわらず目撃事例がないのはやはり絶滅したのだろうか。
極東特産種であったと思われ、#オシドリの備考で隔離メカニズムを考察してみた。
石井 (2018) Birder 32(8): 34-35 によれば江戸時代中期にはオシドリとカンムリツクシガモの認識は錯綜していて、オシドリとカンムリツクシガモの特徴を併せ持つ絵などがあるとのこと。
Rutt et al. (2024) Global gaps in citizen-science data reveal the world's "lost" birds 過去 10 年以上記録のない種類のリスト。144 種が該当していたが調査開始で 126 種まで減少。論文はオープンアクセスではないが、
Search for Lost Birds から一覧を見ることができる。日本に関係の深い種類ではカンムリツクシガモ (及び日本の記録に疑問が残るがシロハラチュウシャクシギ - IUCN は 2024 年絶滅を宣言) が含まれている。
-
オシドリ
- 学名:Aix galericulata (アイクス ガレーリクラータ) 小さな帽子をかぶった水鳥
- 属名:aix aigos (Gk) アリストテレスの記載した足に大きな水かきのある鳥の一種 (小型ガンか大型カモと考えられている)
- 種小名:galericulata (adj) 小さな帽子をかぶった (galericulum (n) 小さな帽子 -atus (接尾辞) 〜備わっている)
- 英名:Mandarin Duck
- 備考:
aix は他に読み方を考えにくいが "アイクス"。
galericulata は e と語末の -ata の冒頭が長母音で -cu- にアクセントがあると考えられる (ガレーリクラータ)。e の長母音は galerum (帽子) の e が長母音のため。
単形種。ヨーロッパ、アメリカ等に持ち込まれ、移入種となっている。ヨーロッパでは多数の個体が広く分布。
例えばベルギーでの評価 Aix galericulata - Mandarin duck。拡大中だが生態系へのインパクトがある程度高いグループには含まれていない。
同属にアメリカオシ Aix sponsa Wood Duck がある。こちらの読みは "スポーンサ" でラテン語の花婿の意味。Aix 属のタイプ種はこちら。Eyton (1838) が定めたもの。
佐藤 (2020) Birder 34(12): 35 がドイツでつがい相手が生きている限りつがいが解消された証拠が今のところない研究を紹介している。
Maedlow (2018) Phenology of the Mandarin Duck Aix galericulata in the Potsdam area: population trends, non-breeding occurrence, moult, and mating がその論文 (英文要約あり)。
最大9つがいを標識して5年間観察した。7-8月はつがい関係が完全に途絶える。これまでカモ類は全般につがい関係が永続しない、Cramp and Simmmons (1977) はオシドリではそうではないなどさまざまに議論されてきたが一応の結論が出た模様。現在では「オシドリのつがい関係を調べた人はいないので」とは言えなくなった。
[オシドリと他のカモの雑種は存在するか]
「動物の世界」2版 6 (日本メール・オーダー 1986) pp. 764-767 (浦本・安部) にオシドリとアメリカオシ両種の間の交雑はない。山階が両種の染色体が異なっていることを示したとの記述があったので調べてみた。
Can Mandarin Ducks hybridize with other duck species? (Avian Hybrids 2019) に考察があった。
オシドリとアメリカオシの交雑個体の可能性のある記述が "Reference to possible Mandarin x Wood (Carolina) Duck and Wood Duck x Mandarin Hybrids Bred at Tracy Aviaries, Salt Lake City" Avicultural Magazine (1965) にあるとのことだが信頼性はわからないとのこと。
オシドリが他のカモと交配不可能との考えは Delacour and Mayr (1945) と Seth-Smith (1922) が最も近縁のアメリカオシとさえ交配不可能と考えたことに遡るとのことで、Yamashima (1952) による染色体が特異であるとの報告を受けて、Prestwich (1960) と Gray (1958) が交配不可能と結論したとのこと。
オシドリのすべての染色体は acrocentric (アクロセントリック 端部動原体染色体) とのこと。
このページで引用されている核型データは Shields (1982) Comparative avian cytogenetics: a review で見られる。
Yamashina, Y. 1952. Classification of the Anatidae based on the cyto-genetics. Papers Coordinat. Comm. Res. Genet. 3:1-34 が上記 Yamashima (1952) らしいが、山階芳麿 私の履歴書 第 17 回 染色体形の研究 (山階鳥類研究所) によれば "昭和22年5月31日の日本鳥学会の総会の席上、「雁鴨類の新分類法」として発表した" とあるものが最初の出典になるだろうか。
昭和 24 年に出版した「細胞学に基づく動物の分類」がそれに続くが、戦争末期から終戦直後に当たっていたため英文を使えなかったとのこと。
現代的なオシドリのゲノム解析は Ng et al. (2022) Genome Assembly and Evolutionary Analysis of the Mandarin Duck Aix galericulata Reveal Strong Genome Conservation among Ducks。
この結果と染色体構造の特異性を合わせて見ると反復配列やトランスポゾンが特異な染色体構造を生み出し、種分化に貢献したことになるのだろうが、他種との遺伝的交流の可能性がほぼ完全に閉ざされてしまったため他種に遺伝的に吸収されてしまうこともなく、オシドリの分布が世界でも狭い地域となっているのかも知れない。
他の分類群でも提案されているものと同様、種分化機構と反復配列やトランスポゾンの関係を考える上でも興味深い。
ふと気になったのは、オシドリと同じように分布域が狭く形態的な類縁種があまりない #カンムリツクシガモ でも同様の隔離メカニズムが働いていたのではないだろうか。
今となっては調べることは極めて困難だろうが、もしゲノムを調べることができればオシドリとアメリカオシの関係同様に、カンムリツクシガモとツクシガモとは実は想像以上に近縁だが染色体構造由来で遺伝的交流が起きなかった、あるいはカンムリツクシガモの近縁種がまったくなく独立属を形成するいずれの結果が得られても不思議でない感じがする。ただしここでの推論根拠は地理的分布とオシドリの事例が存在することのみ。
[オシドリや他の鳥類の出生時性比]
動物園個体を用いて出生時性比が 1:1 からどの程度外れているかの研究: Miranda et al. (2025) Biased birth sex ratios of mammals and birds in zoos
この中ではオシドリはわずかであるが統計的に有意にオスに偏っていた。"統計的に有意" と表記される種がいくつかある程度で、出生時性比が 1:1 から大きく外れる種類はあまりないらしい。ハワイガンが最も偏っていてオスの割合が 0.399 だった (数字を見るといかにも大きく違うように見えるが、統計的には 5% 水準で有意の程度。それほど有意でないのかと R で binom.test(1823,4558) で試してみるとこの p 値は間違っているのでは?)。
複数種を用いた傾向の解析ではクラッチサイズ (子供の数) や配偶様式とは相関なし。性的二形は鳥類では統計的に有意な相関があると言えるが指標の取り方にとって有意とならないなど微妙。哺乳類では相関がなかった。
全体的にいずれの因子も系統的傾向もあまり影響がなく見える。つまり出生時性比が 1:1 から外れているので一夫多妻 (または逆) になったり、性的二形を発達させる説明はふさわしくなかった。
このようなあまり目立った相関の得られなかった結果が論文になっているのは、出生時性比が 1:1 から外れているならば絶滅危惧種の飼育下保全で悪影響が心配される可能性があるが、そのような状況がないことがわかったため。基本的には保全の論文となるが生物学的には副産物の方が面白い。
社会システムの説明に出生時性比云々の議論はほとんど意味がなかった。
[鴛鴦の偶]
河田聡美 漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 大修館書店 (1989) p. 122 に李白・去婦詞が紹介されている。
去婦詞参照。この語を調べてみると韓国語でもそのまま使われているが、ロシア語でも紹介されていた 鴛鴦。仲の良い夫婦との説明。
[鴛鴦の漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 94 VII (藤堂) によればペアが仲良いことから中国で古くから匹鳥と呼ばれていた。
ダブルベッドのクッションを鴛鴦被と呼び、楊貴妃は宮殿を鴛鴦瓦でふいたとのこと。
白楽天による「鴛鴦の瓦冷たくして霜華多し」は楊貴妃亡き後の玄宗の独り身の寂しさを歌ったものとのこと。
エンの字は鳥の上に付く部分が2人の人が体をまげてかがめた姿、しなやかで丸みを帯びていることを示す。オウは 央 + 鳥 で央の文字は人の中心を首かせなどで押さえた姿。いずれもオシドリの背の低さを表しているとのこと。
wiktionary を見るとエンの字の上部は寝る、または横になる姿。日本語では "えん" または "おん" と読む。音由来 (*qu:n, *qon) と解釈しており、Starostin は古代中国語の *war をチベットの skyar po (ヤマシギ) と関連づけており、いずれも Proto-Sino-Tibetan language に共通語源を見いだせるとのこと。
また鴦の字は音由来 (*qa:n, *qan) とあって藤堂氏とは多少解釈が異なる。ヨーロッパ言語から見ると音声を重視、漢字文化圏では象形文字解釈を行っているように見える。
-
ナンキンオシ
- 学名:Nettapus coromandelianus (ネーッタプース コロマンデリアーヌス) インドのコロマンデル地方のカモの足の鳥
- 属名:nettapus (合) カモの足 (netta カモ pous 足 Gk)
- 種小名:coromandelianus (adj) インドのコロマンデル地方の (-ianus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Cotton Pygmy Goose
- 備考:
nettapus は外来語由来の合成語のため発音は明確でないが、起源となるギリシャ語 netta では e が長母音。pous に由来する -pus も長母音でも構わない (例 apus)。"ネーッタプース" を採用してみた。
学名のために作られた言葉で古典ラテン語ではないのでこの読みに必ずしも従わなくてもよい。"足" の意味の -pus を伸ばすかどうかは両方の用例があるので好み次第でよいだろう。"足" の場合は "プース" と統一して読むのも一つの考え方。
coromandelianus は前半が地名で特に長音では読まれていないよう。-ianus の接尾辞は a が長母音でアクセントがある (コロマンデリアーヌス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。Nettapus 属はナンキンオシ属。
英名で Pygmy Goose と付くように小型のガンの扱いであった。アフリカマメガン Nettapus auritus 英名 African Pygmy Goose が足と体はカモ、嘴と首はガンに見えるとのことでこの属名が付けられた (The Key to Scientific Names)。
和名もかつてはマメガン属の名称があった (コンサイス鳥名事典)。
2亜種が認められている (IOC)。日本で記録された亜種は基亜種 coromandelianus とされる。
[分子系統研究による位置づけ]
最新の分子系統研究で典型的なカモ類との類縁関係はなく、むしろハクチョウやガンの系統とそれに先立つ分岐のリュウキュウガモ類の間に位置することがわかった。ナンキンオシ属とオタテガモ属 Oxyura の系統関係は近い (#オカヨシガモの備考参照)。
日本鳥類目録改訂第8版 = IOC 13.2 の配列ではオシドリの次の中途半端な場所に含められているが近い将来変更されるだろう。
-
オカヨシガモ
- 第8版学名:Mareca strepera (マレカ ストゥレペラ) 騒々しいカモ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas strepera (アナス ストゥレペラ) 騒々しいカモ
- 第8版属名:mareca Marreco ブラジルのポルトガル語で小型カモ類。他説あり。
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:strepera (adj) 騒々しい (strepo -ere (intr) 大きな音をたてる -a 女性形の形容詞にする)
- 英名:Gadwall
- 備考:
mareca は外来語で発音がよくわからないが短母音のみであれば "マレカ"。
strepera は発音はよくわからないが strepere は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。アクセント位置は -re- (ストゥレペラ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Mareca 属 [Marreco ブラジルのポルトガル語で小型カモ類を意味する (ローマ伝説で Marica は川または水の精)]、に変更。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。Mareca 属はヨシガモ属。
Gonzalez et al. (2009) Phylogenetic relationships based on two mitochondrial genes and hybridization patterns in Anatidae の分子系統研究で旧 Anas 属が単系統でないことが示され、いくつかの属に分離された。
北半球中緯度に広く分布。2亜種あり、他の亜種はキリバスの Teraina 環礁に生息していた couesi (アメリカの軍医 Elliott Ladd Coues 由来) があったが絶滅した。雌雄の 1874 年の標本が残っているのみとのこと。ファニングオカヨシガモの和名がある (コンサイス鳥名事典)。
英名 Gadwall の由来は不明だが、1666 年にはすでに使われていた (wikipedia 英語版)。
[Anas 属の分割は必要か]
全ゲノムを用いた解析によってこの取り扱いが適切でない可能性も示唆されている: Zhang et al. (2024) Whole-genome sequences restore the original classification of dabbling ducks (genus Anas)。
伝統的な Anas 属は単系統であり、必ずしも分割する必要はないとの見方。ハシビロガモやトモエガモも含めて 47 種が Anas 属でよいのではとの見解。
カモ類は雑種が多いため遺伝子浸透 (introgression) も多く、用いる遺伝部位によって異なる系統樹形態が可能であるとのこと。これを考慮すると複数の属に分ける必要はないとの考えのよう。
もともとは "北京ダック" などの家禽の起源を探る研究だった (#カルガモの備考参照) が範囲を広げるとカモ類分類まで再考した方がよい結論となった。Gonzalez et al. (2009) の根拠は否定される形となり、他の分類群でも議論されている、単系統ならば多種を含む属でもよいか、あるいは何らかの特徴で分岐年代も参考に分割した方がよいかの程度問題となりそう。
Zhang et al. (2024) のトポロジーを見る限り、もし 47 種すべてを Anas 属としない場合は、ハシビロガモやトモエガモは順序は変わる可能性はあるものの現行の属を変える必要はあまりないように見える。
Mareca と現行の狭義 Anas の関係が相互に単系統にならない可能性があるが、現行全ゲノムまで調べられた種類が少ないのでまだ様子見段階であろう。
属に分割した上でオナガガモが狭義 Anas に収まらなければ古い属名の Dafila (#オナガガモの備考参照) が復活する可能性もあるだろう。
近年は単系統性が非常に重視されており、新しい分子系統研究も比較的早く取り入れられる傾向があるので、あるいはこの提案はすでに議論の俎上に載せられているかも知れない。個人的には種サンプルを増やした後に判定した方がよいと感じるが、全体を Anas にまとめ直すこと自体は問題ないので案外簡単に受け入れられるかも知れない。
日本鳥類目録改訂第8版で変えたばかりの段階で世界が元に戻すこともあり得ないことではない。
なお Mareca と Anas 属を分離したチェックリストは Howard and Moore 4th edition とのことで、アメリカの the 58th AOS Supplement でも採用されたとのこと (Boyd)。
他の主なリストでは Birdlife, BOU が 2014 年、Clements, eBird が 2017 年、IOC が 7.3 (2017) で、日本鳥類目録改訂第7版が出版されて数年で世界の一般的扱いが変わっていたことになる。
第8版でようやく追いついた形になるが、世界の扱いがタイミング悪くすぐに変わってしまうかも。
系統と形態進化を調べた研究: Chatterji et al. (2024) Dietary specialization drives adaptation, convergence, and integration across the cranial and appendicular skeleton in Waterfowl (Anseriformes) (preprint)
Anatidae カモ科は 10 系統あり、それぞれ族にふさわしい。
この系統樹では Mareca と Anas が互いに単系統の関係になっている。
Mareca と Anas を分ける場合は単系統性の要請よりは分岐年代などに由来すると解釈されることになるなろうか。ほとんど違わない分岐年代 (1000 万年前ぐらい) で Anas 属が 3-4 系統に分かれているので微妙なところ。少し古い Gonzalez et al. (2009) を根拠とする分類は多少見直しが迫られるかも。
Netta 属が単系統になっておらず、アカハシハジロの学名は影響を受けないが、もし分離する場合はベニバシガモ Netta peposaca Rosy-billed Pochard と ネッタイハジロ Netta erythrophthalma Southern Pochard をアカハシハジロとは別属になる可能性がある。
Boyd はこれら2種をそれぞれを別属にしているがそこまでの必要性はなさそう。
サザナミガモ Salvadorina waigiuensis Salvadori's Teal は Boyd は不明に分類していたが Anas 属に落ち着きそう。
潜水性など習性は複数の系統で独立に進化し、形態もそれらに応じた収斂進化を遂げている。
カルガモはマガモと同種レベルとして扱われたのかも知れないが登場しない。
さらに Chen et al. (2024) The Complete Mitochondrial Genome of the Siberian Scoter Melanitta stejnegeri and Its Phylogenetic Relationship in Anseriformes
がミトコンドリアゲノムと一部核ゲノムを用いた系統解析を発表している。この系統樹では Mareca, Spatula, Anas が単系統の関係をなさない。
どの解析が系統をよく反映しているかまだ吟味の必要がありそうだが、Gonzalez et al. (2009) を基にした分類は問題がある証拠が増えてきているように見える。系統樹サポート率は高いので解析などに誤りがなければかなり信頼できそう。
シマアジがこれまでとまったく違う場所になっている。海ガモ類は比較的問題が少なそう。
世界の共通リストを検討しているチームはこれらの論文をどう評価するだろうか。
数種の属を変えることで Anas 属と Mareca 属を生かすのは一つの解決方法となるだろうが、シマアジの存在を考えるとそれほど簡単ではなく、続きは同じく影響を受ける Spatula 属のタイプ種である#ハシビロガモの方にまとめた。
幸い Spatula 属の記載が古いのでハシビロガモが別属に移動とはならずに済みそう。
BirdForum でも議論があり、New unified list of birds - Avilist (2025.7) 問題があることは認識されている。どれかの解析に誤りがある可能性もあるのではとの見方も示されている。
Lubbe et al. (2025) Plio-Pleistocene Environmental Changes Drove the Settlement of Aotearoa New Zealand by Australian Open-Habitat Bird Lineages の論文も取り上げられているが、これはニュージーランドの鳥の定着時期を主に推定したもので、カモ類は GenBank のデータを用いており特にカモ類の系統関係を明らかにした論文ではなかった。
当面現状維持されるだろうがいずれ評価の必要性が迫られる問題であろう。
-
ヨシガモ
- 第8版学名:Mareca falcata (マレカ ファルカータ) 鎌形の羽のあるカモ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas falcata (アナス ファルカータ) 鎌形の羽のあるカモ
- 第8版属名:mareca Marreco ブラジルのポルトガル語で小型カモ類。他説あり。
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:falcata (adj) 鎌形の (falcatus) 三列風切の鎌形の羽から
- 英名:Falcated Duck
- 備考:
mareca は#オカヨシガモ参照。
falcata は最初の a が長母音でアクセントもここにある (ファルカータ)。falx を -ata 持っている と分解できる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Mareca 属に変更。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。単形種。
-
ヒドリガモ
- 第8版学名:Mareca penelope (マレカ ペーネロペー) ペーネロペーを救ったカモ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas penelope (アナス ペーネロペー) ペーネロペーを救ったカモ
- 第8版属名:mareca Marreco ブラジルのポルトガル語で小型カモ類。他説あり。
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:penelope (f) penelopis カモの一種 (Gk)
- 英名:Eurasian Wigeon
- 備考:
mareca は#オカヨシガモ参照。
Penelope (固有名詞) は2つの e が長母音。-ne- にアクセントがある (ペーネロペー)。英語では長母音ではないがアクセント位置はラテン語と同じ。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Mareca 属に変更。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。
Mareca 属は Stephens (1824) が導入した属でヒドリガモがタイプ種。Stephens は属提案とともにヒドリガモに Mareca fistularis の新名を与えていた (参考。#ノスリの備考参照)。fistularis は羊飼いのパイプ (fistula) 由来。
種小名の由来である penelops, penelopos (Gk) はギリシャ神話で両親がペーネロペーを海に投げ込んだ時に救って食べ物を与えた紫の縞のあるカモとされる Penelope < pene 編み紐、織物 opos 外見 でユリシーズの妻 (Gk) (The Key to Scientific Names, wikipedia 英語版)。Linnaeus 以前から複数の著者が使っていたラテン名。
Penelope 属が別にあり、キジ目ホウカンチョウ科のシチメンチョウに似た南米の属で、英語では一般名 guan と呼ばれる。
和名はシャクケイ (舎久鶏) で鷹司信輔が付けた名称とのこと (コンサイス鳥名事典)。
こちらの Penelope の由来もよくわかっていないとのことだが、Teixeira (1995) 他は模様を指したものではないか (pene 糸、網 + -ope 外見 Gk)、あるいは冠状に見えるため (pene ほとんど L + lophos 冠 Gk) との解釈があるとのこと (The Key to Scientific Names)。
OED によれば 1605 年にある種のカモらしい鳥を指して Penelope, the name of the..wife of Ulysses, which was given to her, for that she carefully loved and fed those birdes with purpre neckes called Penelopes (Camden, "Remaines") の用例があったがこの用法は廃れたとのこと。
1811 年の用例から英語では上記キジ目の Penelope 属を指して penelope と呼ばれていた。この用法は 20 世紀でも使われていた。
カモの方の Penelope はラテン語 Penelope 由来で、おそらくギリシャ語の penelops 由来で野ガモの1種で首の色彩が際立っているとのこと。この語義は 1605 年用例に見られ、後のラテン名の起源となった可能性があるとのこと。ヒドリガモを指すラテン名 penelope の用例は 1678 年またはそれ以前に遡るとのこと。
英名の Eurasian はアメリカヒドリの英名に対応させるため。Wigeon だけでもヒドリガモを指して使われる。単形種。
英名 wigeon は 16 世紀初めにはすでに使われていたが、中世フランス語 vigeon 由来とされる。これは古フランス語 vignier (鼻を鳴らす、叫ぶ) -on (名詞化) とされる (Wiktionaryより)。1508 年の chekyns pygyons teeles wegyons mallardes の用例がある。この時代にはカモ類を区別した名前が用いられていたことがわかる (OED)。OED ではフランス語由来説ではなく、むしろ音声の whew, whewer 由来説を紹介し、フランス語は逆に英語から入った可能性もあるとのこと。
フランス語の vigeon はラテン語でツルの1種を指す *vipio (#マナヅル参照) 由来の可能性も提唱されているとのこと。
現代の言語では Penelope はほぼ残っていない。音声に着目している言語が多い (ドイツ語 Pfeifente 笛のカモ、フランス語 Canard siffleur、ロシア語 sviyaz'、ウクライナ語 svishch など)。色彩に着目しているのはノルウェー語の Brunnakke (茶色の首) など。中国語も同じ系統で赤頸鴨。英名の wigeon がむしろ特殊と言えるだろう。
-
アメリカヒドリ
- 第8版学名:Mareca americana (マレカ アメリカーナ) アメリカのカモ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas americana (アナス アメリカーナ) アメリカのカモ
- 第8版属名:mareca Marreco ブラジルのポルトガル語で小型カモ類。他説あり。
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:americana (adj) アメリカの (-anus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:American Wigeon
- 備考:
mareca は#オカヨシガモ参照。
americana は1つめの a が長母音でアクセントもここにある (アメリカーナ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Mareca 属に変更。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。単形種。
ユーラシア北東端でも繁殖しているとのことである。参考記録 Beshkarev (1999 初出、2018 再掲) The American wigeon Anas americana in the upper reaches of the Pechora (p. 4263)。
クレチマル・千村 (訳) (1991) Birder 5(7): 27 に北米からシベリアにアメリカヒドリが進出しているとの記載がある。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) には繁殖種としての記載は特になく、迷鳥の扱いになっている。
森岡 (2005) Birder 19(11): 53 にコメントがあり「日本の野鳥 山渓カラー名鑑」に記載されていたアメリカヒドリとヒドリガモが一緒に繁殖している記述は NHK 取材の時にコンドラチェフ博士から聞いた情報であったとのこと。
Rohwer et al. (2022) Interspecific forced copulations generate most hybrids in broadly sympatric ducks
によればアメリカ西岸で多くの場合オスのヒドリガモがアメリカヒドリと雑種形成 (F1 個体からの判定) を行い、多数のアメリカヒドリの中でメスのヒドリガモが相棒を見つけるのが難しいため雑種形成が起きる仮説は否定的とのこと。北米のカモの雑種は強制交尾が主因との説を支持する。
-
マガモ
- 学名:Anas platyrhynchos (アナス プラテュリュンコス) 幅広い嘴のカモ
- 属名:anas (f) カモ
- 種小名:platyrhynchos (合) 幅広い嘴の (platos 幅 rynchos 鼻口部 Gk)
- 英名:Mallard
- 備考:
anas は他に発音は考えにくいが "アナス"。現代のイタリア式発音では伸ばすこともあるそうで、冒頭を長音で読んでも間違いとは言えない。逆に "ナ" を伸ばす方はおそらく受け入れられない。
platyrhynchos は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-rhyn- がアクセント音節と考えられる (プラテュリュンコス)。
北半球に広く分布。2亜種が知られ (IOC)、日本の亜種は基亜種 platyrhynchos とされる。もう1亜種はグリーンランドの大型だが嘴は小さく色の淡い conboschas とされるがこの亜種を認めないこともある。
英語の由来は古フランス語でオスの野ガモを表す malard, malart, mallart から (Wiktionaryより)。カルガモとの遺伝的関係については#カルガモの備考を参照。
Anas 属のタイプ種。
現在マガモとされるものが Linnaeus (1758) に2回登場すると言われる。#オオタカの備考も参照。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" も Anas boschas の学名を用いていた。この時点では Linnaeus (1758) の Anas platyrhynchos のシノニムとは気づかれていなかった模様 (他学名としてリストされていない)。
Anas platyrhynchos と
Anas boschas
後者に domestica が含まれているので、アヒルを表す学名として使われていたこともあったがシノニムとみなされ、先取権のある Anas platyrhynchos の方が使われるようになった。AOU も 2nd ed. (incl. 13th suppl.) まで Anas boschas を用いていた。
さらに Anas adunca の家禽品種も含まれていて Linnaeus (1758) に3回登場とのこと。
Donegan (2023)
Towards a more rational and stable nomenclature for Mallard Anas platyrhynchos, Greylag Goose Anser anser and their domesticates, including various priority issues, designation of lectotypes, and a First Reviser act
がこの問題を整理している。Linnaeus は野鳥を意図して Anas platyrhynchos を使っていた。Anas boschas には家禽と野鳥の両方が含まれていた。
Linnaeus はさらに混乱していたようで Anas platyrhynchos とハシビロガモ (当時の学名で Anas clypeata) をシノニムの関係にあると考えていた。
Linnaeus の発表後 150 年以上も経過して、Lonnberg (1906) が Anas platyrhynchos はメスで、Anas boschas は主にオスを指すことに気づき、前者の方が先に現れるので先取権があるとした。
しかし長期間使われていた学名が保護される規則もある。これは Lonnberg (1906) の提案を無効にするわけではなく、結果的に 20-21 世紀の大部分の分類学者がこの提案を受け入れることで現在の学名に落ち着いている。
ハイイロガンの学名も同様に扱われている。ガン・カモは家禽で多様な学名が使われており歴史的に複雑だったよう。
川口 (2016) Birder 29(12): 48-49 でマガモの巻き羽が上尾筒か尾羽かを議論している。結論は後者とのこと。「生物進化とハンディキャップ原理: 性選択と利他行動の謎を解く」(Amotz Zahavi and Avishag Zahavi "The handicap principle: a missing piece of Darwin's puzzle" 1997 原著、アモツ・ザハヴィ、アヴィシャグ・ザハヴィ著; 大貫昌子訳 白揚社 2001)
でザハヴィがクジャクの飾り羽を尾羽としている点をとりあげ、名のある鳥類学者でも、こんなものだ! と指摘している。
これは訳の問題ではないかと想像して調べてみると peacock's tail の表現は英語ではあまりに普通に使われ、peacock's tail-feathers の表現は英語的には特に間違いがあるわけではない。
クジャクの飾り羽を指す用語として "tail" または "train" が用いられるとのこと (wikipedia 英語版より)。鳥類学的に言えば tail covert とか補足してあると曖昧さがなかったのだろうが、あまりにも専門用語なので避けたのでは?
訳者もファインマンなどの物理の訳書を多く手がけており (E. O. ウィルソンの「生命の多様性」もこの方の訳)、鳥類学まではさすがに専門でなく訳者が注釈で補う必要も感じなかったのではと想像する。
rectrices とか専門用語で限定して書いてあるわけではないようなので、偉い学者が間違えているかどうかまでは判断できない気がする。
雑誌 "Birder's World" 1989.12 pp. 30-34 に Paul A. Johnsgard の "On Display" の記事があり、本文では upper tail coverts や tail part (coverts を含む) と書き分けているが図版キャプションは fanned tail of a displaying Common Peafowl とあり英語表現としてこれでよいことがわかる (Johnsgard を偉大な鳥類学者と呼ばない人は多分ないだろう)。
この記事は非常に詳しく、キジ類の (広い意味で) 尾の模様の進化を取り上げている。尾羽も上尾筒のいずれもが用いられ中間的な進化形態もある。尾羽か上尾筒かは枝葉末節の問いで、この系統のディスプレイでは "尾" と総称した方が機能をずっとよく表現している。
[カモ類の気管球 (tracheal bulla)]
川口 (2018) Birder 32(1): 52-53 で、カモ類の性的二形に関係してオス・メスで声が違うことが紹介されている。多くのカモのオスには気管に特別な構造 (tracheal bulla 気管球, syringeal bulla などの名称がある) がある。
解剖学的には違いは明らかでもそれがどのように音声に影響を与えるかは、筋肉をどう制御するかの他の問題もあり簡単には結論できるものでもなさそうである。共鳴についても同様で音響学的シミュレーションをやってもわからないパラメータが多くてそう簡単には物が言えない。スズメ目でも同様。
オープンアクセスの研究を少し紹介しておく:
Warner (1971) The structural basis of the organ of voice in the genera Anas and Aythya (Aves)
Anas 属ではおそらく共鳴に関与し、構造的にはオスの方が高いと想像される。Aythya 属では (基音とは) 別の音を作る役割を持っているのではとのこと。
Miller et al. (2007) Allometry, bilateral asymmetry and sexual differences in the vocal tract of common eiders Somateria mollissima and king eiders S. spectabilis
ケワタガモ類で同種内の tracheal bulla の大きさには差が少なく、体サイズが大きいものでもそれほど大きくなかった。tracheal bulla のサイズを一定に保つ選択が働いていると考えられる。
川口氏の疑問は雌雄同色のカルガモでオス・メスで声がどのように違うかだが、マガモの声に似たもので雌雄で声が違うとの情報はあるがこの時点では詳しくはよくわからない模様。xeno-canto ではマガモのメスの声は明瞭に識別できることが周知事実となっていて (聞くだけでわかる) 多くの記録がある。
カルガモでは性別を入れている報告はほとんどなく (そもそも記録数も少ないが) 野外での音声による識別方法は確立されていないのだろう。マガモの雌雄と同様と考えて分類するだけでも意義がありそうに思えるがどうだろうか。
Mishkind et al. (2025) Courtship vocalizations in male ducks: spectral composition and resonance of the syringeal bulla (preprint)
micro-CT を用いて共鳴構造となっているかを検証。ヘルムホルツ共鳴管と仮定して気管球のみの共鳴周波数の推定を行っているがそれほど大したことはやっていない。気管が周波数を変えるはずだがこちらは実測せず文献の値を用いている。各種の気管球の CT 画像が出ているので参考になるかも。
[カモ類の嘴の触覚]
(一部#ハチクマの備考の脳の構造より)
Gutierrez-Ibanez et al. (2009) The independent evolution of the enlargement of the principal sensory nucleus of the trigeminal nerve in three different groups of birds。
によれば、三叉神経の感覚に関係する脳の principal sensory nucleus of the trigeminal nerve (PrV) この核のサイズを見れば採食に触覚をどの程度用いているか推定できる模様で、直感的にもわかりやすい結果になっている。嘴で探索を行うシギ類、水鳥 (特にろ過して食物を得るカモ類など)、オウム、キーウイなどでよく発達しており、嘴の感覚が鋭敏であることとよく対応している。
味蕾 (みらい taste bud) も嘴の先端にあって味を感じている (#メジロの備考 [鳥類の味覚] 参照)。
Ziolkowski et al. (2022) Tactile sensation in birds: Physiological insights from avian mechanoreceptors
によれば鳥類と哺乳類の間で触覚はよく保存されている。Grandry (Meissner) と Herbst (Pacinian) 小体 (かっこ内が哺乳類での名称) が触覚センサーで嘴で探索を行う種類で嘴の皮膚に触覚センサーが高密度に分布している。これらの種類の嘴の皮膚の繊細なセンサーは舌や咽頭にも及ぶこともあるとのこと。
Schneider et al. (2017) Molecular basis of tactile specialization in the duck bill にカモの嘴先端の触覚の分子メカニズムが同定されている。Piezo2 チャンネルが関与しており、マウスの触覚以上の役割を果たすとのこと。嘴先端には Grandry, Herbst 小体が多数ある。脊椎動物の中でも特に触覚に特化していると言える。
Syeda (2017) Dabbling with Piezo2 for mechanosensation の解説記事。カモ類は嗅覚や視覚よりも触覚に頼って食物を探す。霊長類が指先の触覚を用いて探すのと同様。
運動センサーに関連する TrkB 遺伝子発現も視覚で食物を探すニワトリとは対照的な結果となった。
なお TrkA は温度や痛み感覚に関連し、カモでは TrkB 遺伝子発現の方が圧倒的に多かった。触覚を用いて食物を探すセンサーに最適化されていると考えられる。
[マガモの雌雄の頭の色を決める遺伝子]
Ma et al. (2021) Transcriptome Analysis Reveals Genes Associated With Sexual Dichromatism of Head Feather Color in Mallard
によればトランスクリプトーム解析によって TYR, TYRP1 遺伝子が頭部羽毛のメラニン形成に関与しており、オスではメスより TYRP1 の発現が 256 倍強かったという。メラニンによる構造色であることも改めてわかる。Z 染色体関連遺伝子がオス (ZZ) でより多く発現して TYRP1 のプロモーター領域に働いている可能性があるとのこと。
[カモ類の翼鏡]
翼鏡 (speculum) は構造色だが、その微細構造を調べた研究: Eliason and Shawkey (2012) A photonic heterostructure produces diverse iridescent colours in duck wing patches
発色の機構は論文に譲るとして、気になるのは役割だろう。この論文で引用されている研究では実はあまりよくわかっていない。
マガモから取り除いても繁殖には影響がなかった: Omland (1996) Female mallard mating preferences for multiple male ornaments - II. Experimental variation。
マガモとコガモでは体の状態 (栄養状態など) と相関がある: Legagneux et al. (2010) Condition dependence of iridescent wing flash-marks in two species of dabbling ducks。
種認識に役立っているのでは: Ritchie (2007) Sexual Selection and Speciation (これはレビュー論文で役割の提案)。
カモ類の多くの種類は交配して雑種を残せるが同所的に複数種が存在することは交配前の生殖隔離が存在することを示唆する。もし雑種が子孫を残す能力が低ければ翼鏡の色へ種分化のための適応となり得る。そうでなければ色そのものの浮動によって種分化につながる可能性がある。この例は Carduelis 属のフィンチ類で知られているとのこと。
学術用語では英語でもラテン語の speculum もそのまま使われるが、語源は specio (見る) + -ulum (道具) から鏡や (比較的歴史的な) 医療用具で開口部を広げて中を見るものを指す (現在は何とかスコープなどと呼ぶことが多い)。複数形 specula または speculums。
英語でそのままの意味で mirror の名称も使われる。こちらはカモメ類の初列風切の白斑も指して使われることはご存じの通り。OED によれば 1903 年の用例があるそうで、Blackwood's Edinburgh Magazine に The black tips of the long wings waving in the wind, showing the large white 'mirrors' on the first three feathers distinctly のように現れるとのこと。
同じ意味で wing-bar は 1844 年から、speculum は 1847 年、wing-band は 1872 年から用例がありこちらの方が起源が古い。現在はほぼ使われない beauty spot (1804 年から) の用語があった。
カモ関連で参考までに eclipse の用例を調べると OED によれば Waterton, Essays on Natural History の 1838 年のものがあり、drake goes, as it were, into an eclipse オスのカモがあたかも食に入るように... と比喩的に使われたのが最初とのこと。1906 年ではまだ 'eclipse' と比喩的に使われていた。1913 年には eclipse-feathers のように特に比喩を示すことなく使われていた。
ドイツ語では冬羽を指して Schlichtkleid (地味な衣装)、Ruhekleid や Winterkleid と呼ぶとのこと (wikipedia ドイツ語版) 写真説明にも特にエクリプスを示す用語は出てこない。英独辞書によれば Schlichtkleid は英語の eclipse plumage, basic plumage, winter plumage に対応するとあり、エクリプスに対応する特別な用語はないらしい。
wikipedia ロシア語版でも特に現れないよう。英語の "食に入る" の比喩から始まった用語らしく他の言語でも普遍的に使われているわけでもなさそう。
[白い大きなアヒルの起源]
Wang et al. (2023) Duck pan-genome reveals two transposon insertions caused bodyweight enlarging and white plumage phenotype formation during evolution
によれば、アヒルの全ゲノム解析により、トランスポゾン Gypsy の2か所の挿入によって体重が劇的に増加して (27.61% でこれほどの増加率は家禽でも最大とのこと) 白色の羽毛を獲得したとのこと。
マガモの家禽化は紀元前 500 年ごろの中国で行われたとのこと。IGF2BP1 の調節領域に挿入された Gypsy がエンハンサーの役割を果たしているとのこと。
MITF のイントロンに挿入された Gypsy が白色化に関連しているとのこと。トランスポゾンが多様な表現型に関わっていることが一層明らかになった (#ツリスガラ備考 [スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン] も参照。
マガモで特によく調べられているが、カモ類は鳥インフルエンザウイルスの自然宿主となっている。なぜ自然宿主となり得るのか、ニワトリは何が違うのか、免疫にかかわる仮説は#インドガン備考の [野鳥と鳥インフルエンザ (9) インドガン] 以下の "最新状況" コーナーに紹介した。
[カモのひなはなぜ親鳥を追う?]
カモのひなはなぜ親鳥を追うか? - と問われれば即座に「刷り込み」(imprinting) の回答が返ってくるだろう。
物事はそう単純でないことが示されているので紹介しておく。出典は #ミサゴの備考 [feather taxis・頭かき] で紹介の「本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」(マーク・S・ブランバーグ著; 塩原通緒訳 早川書房 2006) pp. 139-148。
Gottlieb は孵化したばかりのひながそれぞれ自分の種の母親の呼び声を、母親と接触する前から聞き分ける能力を持つことを示し、Lorenz の言う刷り込みは呼び声に引きつけられる状況で副次的に生じるものとの解釈を 1971 年の研究会で示したとのこと。
その場に同席していた Lorenz は生得的 (本能的) なものと環境から入る情報 (刷り込み) の2つがあって、Gottlieb の発表は生得的なものの重要性を示したと聴衆に語ったという。大御所の解説で生得的なもの刷り込みの二分法、そして生得的な本能がいかに重要であるかが聴衆や科学界に刷り込まれたというわけである。
Gottlieb はそもそも Lorenz の考えに懐疑的であって実験を始めたものだったが、さらにマガモとアメリカオシドリを用いて実験を進め、
・親の声を聞かせないで育てても同種の声への好みは変わらず
声の好みは本能だと信じ込んでいると、この実験結果でもう満足して終了にしてしまうだろう。Gottlieb の偉いところはここでまだ疑って実験を続けたことである。親の声を聞かなくても一緒に育てた卵の孵化の少し前から他の卵から聞こえる鳴き声を聞いている可能性に気づいた。
・卵の中で他の卵からの声を聞くことで選り好みが強まる
・他の卵からも含めて音声を完全に隔離する (自分の声も出せないように操作してある) と母鳥とニワトリの声を区別できない
・しかし自身の声を流して聞かせると好みが誘発された
との驚くべき実験結果を出した。さらには
・音声隔離実験で他種の卵から聞こえる声を聞かせると他種を好む実験にも成功
また音声を離断されて育つと知覚の発達がほとんど阻害されているように見えたとのこと。卵の中の声と親鳥の声は一見まったく似ていないので、よほど注意深い人でなければ関連性に気づかなかったことだろうとのこと。卵の中の声と親鳥の声の共通成分を抜き出して人工音声による実験を行い、意義がようやく判明したとのこと。
自然条件ではこれらの状況は起きないので親鳥の声に反応する結果、視覚刺激による刷り込みが起きる、という次第。Lorenz の古典的実験は相当割り引いて考えた方がよいらしい。
托卵鳥の音声認識 (#カッコウの備考 [托卵鳥の同種認識]) も併せて読まれたい。
Gottlieb (1991) Experiential Canalization of Behavioral Development: Results
に実験結果や主に自身の先行研究も紹介されている。
ここで使われている canalization は心理学用語で Conrad Hal Waddington (1942) が最初に用いたものとのこと。canal は水路のような意味で、水路づけ (運河化) とも訳される。
かつてベストセラーだった「頭の体操」(多湖輝 光文社 1966-?) でも用いられていたのでご存じの方もあるだろう。
この論文では卵から発せられる声を vocalizations in embryo と記述してあり、特別の用語はない模様。
他に Gottlieb (1992) Individual development and evolution: The genesis of novel behavior、
Gottlieb (1997) Synthesizing naturenurture: Prenatal roots of instinctive behavior
の書籍が「本能はどこまで本能か」で紹介されている。
日本でも使われる「胎教」の科学的根拠はもしかしてこれらの研究か、とも思ったのだが簡単に調べても見つけられなかった。古代中国ですでにあったとのこと。
「本能はどこまで本能か」には他にも面白い話があるので紹介しておく (pp. 235-236)。
Wynn (1992) Addition and subtraction by human infants (Nature 論文)、
Wynn (1998) Psychological foundations of number: numerical competence in human infants
で、鳥類や哺乳類のさまざまな種に数に対する識別能力を持っている。鳥類と哺乳類が分岐する前のどこかで生じたものかも知れないし、いくつかの分岐した種の中で別々に同じように進化したのかも知れないと述べているとのこと。
動物に数の概念があるとすればそういう議論にもなるだろうが、そもそも人間の幼児は数を認識しているのかどうかの問題はあまり明瞭でない。
Clearfield and Mix (1999) Number Versus Contour Length in Infants' Discrimination of Small Visual Sets がこの問題に挑戦し、数のような抽象的なものよりも (輪郭の長さのような) 基本的な知覚に訴える刺激をもとにしている結果を得たとのこと。数以外にも認知の手がかりがあるが十分実験されていない。
この考えに対する新しい反論論文 [例えば Xu et al. (2004) Number sense in human infants] もあるようでこの問題はまだ決着していないようだが、Nature 論文で世間に広まった情報を修正するのは容易なことではなく、学説としてはあまり知名度がないとのこと。Gottlieb がカモの実験で示したように、精緻な実験を行えば実は幼児も動物も数の概念を認識していない結果が出る可能性もあるのかも知れない。
ヒトでは大きな問題なので多くの研究が行われているが、鳥が数を数えられるかどうかはそこまで踏み込んだ議論にはなっていない模様。しかしこのような落とし穴があり得ることも考えておいてよいかも知れない。他の動物でも数を認識したとの研究が報道されることがあるがヒトの幼児ほどの厳密な実験が行えるとは思えず、少し割り引いて見た方がよいのだろう。
"Number sense in animals" wikipedia 英語版では霊長類での議論は多少出ている。approximate number system というものがあるそうで、1 と 2、2 と 4、4 と 8 のような Weber 則 (#オオルリの備考 [オオルリはなぜ青い] で登場) に従う区別がなされるとのこと。
つまり比は判断できる (対数の引き算になる) が、数そのものの引き算はできていない、ということになる。
数を理解できると言われるカラスやオウムの話はもうちょっと割り引いて捉えた方がよさそう。
ハトでも同様との結果が報告された: Wu et al. (2025) Visual numerical cognition in pigeons: conformity to the Weber-Fechner law。鳥の中では古い系統に属しながらハトの数の認知能力は高く、サル類を上回る結果すら報告されているとのこと。
進化とも関連しそうな面白い話が出ている。
Trut (1999) Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment
旧ソ連時代のノボシビルスクで Dmitry Belyaev が動物の家畜化メカニズムを研究するためにアカギツネ Vulpes vulpes の色彩型であるギンギツネ (silver fox) をある特徴に従って継代選抜した (1959 年開始) 結果短期間で家畜らしい他の特徴が同時に選抜されたという [Belyaev, D. K. (1969). Domestication of animals. Science 5: 47-52]。
Belyaev が実験を始めた時代背景も上記 Trut (1999) 論文を読むと理解しやすい (ソビエト時代、スターリンの支持の下のルイセンコ遺伝学から解き放たれた時代だったとのこと)。
Trut (1999) によれば Belyaev の死後もこの時点で 40 年も研究が引き継がれ、野生型にない特性なども現れたとのこと。当時のロシアの経済危機で実験の継続も危機的状況となり、実際に昨年は職員に給与すら支払えなかったとのこと。ペットとして売って費用をまかなっていたがそれも途絶えつつある。
ロシアの研究費制度も変わってこのような継続的研究が資金を獲得することが一層難しくなった。
「本能はどこまで本能か」(pp. 296-300) ではこれは家畜化プロセスそのものを反映していないかも知れないが、結果的に発達速度の遅いものを選抜したことになっていると解釈している。
いわゆるネオテニー (幼形成熟) の形質を選抜したことになるのか。ヒトは自己家畜化した動物など使われることがあるがここではそちらには深入りしないでおく。
こんなに短期間に幼形成熟が起きるならば、島で飛ぶ必要のなくなった鳥が簡単に飛翔力を失っても不思議でないと思う次第だが実際にはそれほど簡単ではないのだろう。
なお鳥が幼形成熟で飛翔力を失うアイデアは古くからある。Condon (1957) Neoteny and the Evolution of the Ratites 参照。
新しい研究ではいろいろなプロセスが考えられていて、幼形成熟もその一つ Faux and Field (2017) Distinct developmental pathways underlie independent losses of flight in ratites。
この研究ではヒクイドリに対して可能性があるとしている。ガラパゴスコバネウと唯一の飛べないスズメ目の絶滅種スチーフンイワサザイ Traversia lyalli Stephens Island Wren については引用文献参照。
ガラパゴスコバネウはゲノムレベルの追加情報があり、#カワウ備考の [ガラパゴスコバネウの進化] に追記した。
ゲノムレベルの研究では Sackton et al. (2019) Convergent regulatory evolution and loss of flight in paleognathous birds
古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae (ダチョウ目など) で複数回の飛べない鳥への進化があった。これらは収斂進化と言え、ポリジーンかつタンパク質をコードする部位よりも調節部位 (ネットワーク) がかかわっていると考えられるとのこと。幼形成熟というよりはむしろ必要なくなったものに投資しなくなったと見るべきであろうか。
Kukekova et al. (2018) Red fox genome assembly identifies genomic regions associated with tame and aggressive behaviours がゲノム解析をした結果、SorCS1 遺伝子がこの Belyaev のキツネに関与していることが明らかにされた。
従順か攻撃的かの遺伝子特定か、ペットのキツネで (ナショナル ジオグラフィック) で日本語解説が読める。
もっとも Belyaev が用いたものは野生捕獲のギンギツネではなく、カナダで少なくとも1880年代から飼育されていたものであったが [Lord et al. (2019) The History of Farm Foxes Undermines the Animal Domestication Syndrome]、
Belyaev と共同研究者も最初はそれほど古くから家畜化されていたものとは気づいていなかった可能性がある。論文でも曖昧な表記だったため野生個体との誤解が広まっていたとのこと。広く使われる "家畜化" とはあまりにも単純化した見方ではないか。"家畜化症候群" はそもそも存在するのか、意味も問い直す必要があるとのこと。
「野鳥」2020年4月号 (No. 843) pp. 6-13 に岡ノ谷氏と上田氏の対談があり、その中でも岡ノ谷氏の仮説に関連して扱われている。かなり単純化して扱われているのでこの記事だけを読まれた方は多少注意が必要かも知れない。
関連する遺伝子候補は見つかったものの、おそらく飛べない鳥への進化同様にポリジーンかつ調節部位がかかわってそうなので、タンパク質をコードする遺伝子だけを見ているとまだ尻尾を少し掴んだぐらいの段階だろうか。
A new vision for how evolution works is long overdue (Nature Book Review 2025.1.13) に家畜化症候群にも関連した話題がある。特定の形質がセットで選抜されるのはいずれも特定の細胞 (neural crest 神経堤) に由来するもので同じような遺伝子に左右されるため。
偶然にしては考えにくいほど特定の形質のセットが生まれるのは、それぞれが独立に選抜されるためではない。
またエピジェネティックな修飾が遺伝子の働きを変え、遺伝子の進化にも影響を与える (遺伝子自身の進化に先行することができる)。"Evolution Evolving: The Developmental Origins of Adaptation and Biodiversity" Kevin Lala et al. Viking Books (2024) の書評から。
スズメ目のペットの "家畜化症候群" についてゲノム変化を調べた研究: Farias-Virgens et al. (2025) The genomics of the domestication syndrome in a songbird model species
対象種はジュウシマツで岡ノ谷氏も共著者に含まれている。野生種に比べて攻撃性、ストレス反応に関係するものよりもモチベーションを変化させたり報酬に関連する脳の回路が選択されている可能性があり、哺乳類の場合と似ているとのこと。
多くの大型猛禽類が人を極度に恐れるのは、過去に迫害を受け、人を恐れない遺伝的性質を持つ個体が狩猟などで選択的に失われたのだろうかと思ってしまう。現在の性質を見てそれがその種本来の性質と判断するのは危ないかも知れない。
Zhao et al. (2025) Cytoskeletal signaling as a shared pathway for convergent genetic mechanisms underlying loss of flight in birds
従来は飛翔能力の喪失は形態学的収斂と捉えられる傾向があったが、遺伝的背景が次第に明らかとなってきており、キジ目とカモ目での比較ゲノム解析の結果代謝や細胞内骨格に関係する少数の遺伝子への選択圧が家禽の飛翔能力の喪失と野鳥 (飛翔能力を失った走鳥類、キジ目とカモ目) で共通に認められるとのこと。
おまけで Galloanserae の分岐は 9102 万年前ぐらいと推定 (同文献の他の年代推定に比べてこの数字は比較的精度が高い) されたとのこと。
[レイサンマガモ]
レイサンマガモ Anas laysanensis Laysan Duck はマガモに近縁のハワイのほとんど飛べないカモ。移入捕食者や植生破壊のために一時は絶滅寸前状態 (1912 年に成鳥9羽の若鳥5羽) となったが移入捕食者の駆除で個体数を回復 (1950 年代に 500 羽程度) したが、1993 年のエルニーニョ現象による干ばつで 100 羽程度まで再度減少。現在は 500 羽を超えるまで回復した。
2004, 2005 年に絶滅を避けるためにミッドウエイの環礁にも個体群移住が行われた。IUCN CR 種。
レイサン島のみに残っていたが、かつてはハワイの広域に分布していた化石証拠がある。渡りのマガモが迷鳥として定着したとの解釈があったが、南半球のマガモの祖先由来とのこと (wikipedia 英語版)。
[カモノハシ]
マガモの学名から気づかれた方もあるかも知れない。カモノハシの英名 platypus は platus 平らな + pous 足 (Gk) で過去の学名由来。
Platypus anatinus Shaw, 1799 と記載されたもので、種小名もカモの Anas に由来している ("カモに似た" の意味)。
Ornithorhynchus paradoxus Blumenbach, 1800 が独立に記載しており、Platypus の属名がすでに甲虫に使われていることがすぐに判明したため Ornithorhynchus anatinus の学名となった。
Ornithorhynchus は ornith 鳥 rhunkhos 口吻、嘴 (Gk) に由来する。学名を見てもまるで鳥のような哺乳類。
通常の哺乳類の XY 染色体が5対の性染色体をなし、X 染色体は爬虫類や鳥の持つ Z 染色体 と相同性が高く、鳥で Z 染色体にある DMRT1 遺伝子を X 染色体に持つとのこと。毒は爬虫類に似ている。
嘴は電気信号を出し、嘴にある4万個の受容体で電気的な餌探索を行うとのこと (wikipedia 英語版より)。
報道にあまりに誤解が多いとのことで出された解説: Interpreting Shared Characteristics: The Platypus Genome
爬虫類の毒とは独立に進化したものほか。授乳は鳥にはない点で、ハトのミルクなどは別の適応であるとしている。
Zhou et al. (2021) Platypus and echidna genomes reveal mammalian biology and evolution
も興味深い内容で、Fig. 8 に鳥類も含めた歯に関連する遺伝子がどのように失われたかわかる。ニワトリではここで示された8個の遺伝子が 1.2 億 - 6500 万年前の間にすべて失われ、カモノハシ等単孔類祖先ではもう少し遅い時期に4遺伝子、ハリモグラ科でさらに2遺伝子を失ったとのこと。
ハプトグロビン (haptoglobin 赤血球から放出された遊離ヘモグロビンに高い親和性で結合して有害な酸化活性を阻害する; HP 遺伝子) が走鳥類にはあるがその後のニワトリに至るどこかの系統で失われているらしいが、別の PIT54 が機能を果たしているとのこと。
HP 遺伝子は単孔類でも失われていて CD163 遺伝子ファミリーによる別の仕組みを使っていると考えられる。旧世界サルではヒトも含めて重複 (HPR 遺伝子) が起きている。
カモノハシは潜水中目と鼻を閉じるそうで、視力・嗅覚は採食に役立たないため、電気的な餌探索に頼る必要があったのだろうとのこと。嗅覚遺伝子数も相対的に少ないとのこと。
卵生だが、子宮内でも栄養を吸収するため、また (初期段階で栄養を卵黄から得る早成性の鳥類とは違って) 授乳できるので鳥類や爬虫類ほど卵のタンパク質に頼っていない。孵化までの日数も短いとのこと。
哺乳類の乳にはカゼインが含まれるが、これを作る遺伝子は歯の形成にかかわる遺伝子と共通性があり、Ca 結合性のタンパク質として進化した可能性があるとのこと。鳥では歯を失った結果、哺乳類同等の乳は作ることができなかった?
カモノハシは卵の期間は窒素を尿酸で排泄するという (wikipedia 日本語版より)。他の哺乳類でも砂漠に住む種では尿酸排泄のものがあるとのと: Dipodomys属 Kangaroo rats (wikipedia 英語版より)。さらに詳しい情報は #カワウの備考 [鳥類の窒素排泄・栄養状態ストレスとの関係] 参照。
日本の研究者も含まれる共同研究なので日本語情報を探してみると、この話とは直接関係がないが意外なものが見つかったので紹介しておく:
佐藤・江積 (2023) 脊椎動物の変遷についての大学生の認識と 中学校および高等学校の教科書の記述
なんと哺乳類の祖先は鳥類と考える大学生は爬虫類と考える人と同じぐらい多いとのこと。鳥類から脊椎動物が進化したと捉える割合も (この選択肢では正解である魚類以外で) 他の分類群より多い。教科書にどう書かれているかは学習者の認識に影響を与えていないことを示唆するとある。
始祖鳥は習うので爬虫類と鳥類の関係はかなりよく把握されているとのこと。
しかし 哺乳類の胎盤獲得に至る分子進化プロセスの一端を解明 (2022) には「鳥類から哺乳類への進化」と書いてある。
逆の意味で面白いタイトルの論文があったので紹介しておく: Scanes (2020) Avian Physiology: Are Birds Simply Feathered Mammals?
日本と欧米で違っているかも知れないが、"鳥類は羽の生えた哺乳類である" とのゼロ次近似は広く信じられているとのこと。飛翔への適応や卵生に由来する点は異なるが、他の点はだいたい同じように考えてよいとの考え (迷信?) がある (日本で鳥学をやっている人はむしろええっ? と思われるかも知れない)。
特に生理学者は暗黙の前提のように考えているが (*1) いくつか重要な違いがあることに注意が必要である。特に免疫システム (これはそれぞれかなり独自に進化したもの)、卵の形成など。消化器の違いも挙げているがそのうの有無など多少些細な違いかも知れない。
注意すべきは鳥類の (生理学) 情報の多くは家禽として選択を受けたものが由来なので、野鳥との違いを意識する必要がある。家禽研究者と野鳥研究者の交流が少なすぎるなど。
「鳥類から哺乳類への進化」の文言が際立って不自然に感じられないのも "鳥類は羽の生えた哺乳類である" 視点由来かも知れない。
胎生の鳥がいない理由はしばしば議論されるが、哺乳類など各種生物の隠れたコストを見積もった研究がある。How much energy does it take to make a baby? Researchers are rethinking what they know (Wong, Nature news 2024.10.22)。
Ginther et al. (2024) Metabolic loads and the costs of metazoan reproduction が論文。
授乳を除外しても哺乳類が胎児を育てて運ぶなどの間接的な代謝コスト (必要なエネルギー) はこどもを作るコストの 90% と極めて高いとのこと。鳥類は比較対象になっていないが卵生に比べてこのコストが極めて高いので胎生の鳥がいないのも納得できるところかも。
哺乳類でも飛行するのがあるのでは、と考えられるが調べられたコウモリ (Little brown bat) では間接的な代謝コストは哺乳類中最小で、体重あたりの代謝コストも小さい方に属する。
卵生動物で間接的な代謝コストの高いものより低い比率だったとのこと。何らかの部分を生理的に切り詰めることで胎生でありながら飛行を可能としているものだろうか。
Nature news の記事によれば過去にこのような見積もりが行われたことはなく、(適応度の評価や例えば最適な体サイズの見積もりなどにもつながる) 数学的取り扱いでも無視されてきたとのこと。男性中心の研究分野では無視されてきても驚かないだろうと述べたとのこと。
羊膜類の性染色体の分化については例えば Kostmann et al. (2021) Poorly differentiated XX/XY sex chromosomes are widely shared across skink radiation
(preprint 版)
がトカゲ類の性染色体を調べている。哺乳類は一般的には XX/XY、鳥類や分化の進んだヘビ類では ZZ/ZW だがトカゲ類は性染色体の分化度が低いが XX/XY 型。恒温動物では染色体による性決定が安定している。
トカゲ類は少なくとも 8500 万年間この状態と推定され、鳥類や分化の進んだヘビ類の ZZ/ZW の年代 (1.0-1.2 億年以上。なお胎生哺乳類では 1.65 億年以上) に匹敵しており、分化度が低い状態でも進化的に安定であったと考えられる。
Shylo et al. (2024) Chamaeleo calyptratus (veiled chameleon) chromosome-scale genome assembly and annotation provides insights into the evolution of reptiles and developmental mechanisms (preprint)
カメレオンの1種 (エボシカメレオン) では常染色体に XX/XY に対応する部位が同定された。
環境によらない性決定が説明できる結果となった。カメレオン類の中でも性染色体はさまざまなタイプがある。
このような視点で見ると鳥類はまとまりがよく、爬虫類が単系統にならないのが問題ならば系統の異なる爬虫類を分割するのが妥当に見えてくる。
Gardner et al. (2020) The relationship between genome size and metabolic rate in extant vertebrates (preprint 版)
の図も参考になりそうなので紹介しておくと、基礎代謝率とゲノムサイズには相関が認められなかった (例えば鳥類のようにゲノムが小さいほど細胞が小さくなって代謝率が上がるなどの効果が考えられる)。
恒温動物の基礎代謝率が高いのは当然としても、図を見るとやはり体温も高い鳥類の圧勝。同程度のゲノムサイズの動物でも恒温動物でなければ基礎代謝率が高いわけではなかった。恒温動物化に伴って基礎代謝率の上昇、脳の機能の高度化、性決定機構の安定化などが必要となったとおおまかには言えそう。
系統樹を見慣れた人ならば系統樹形だけ見ても爬虫類を少なくとも2つに分割したくなるのではないだろうか。この論文では爬虫類は3系統 (Apoda, Lepidosauria, Urodela) に分割したプロットになっている。
爬虫類と鳥類の関係を見る上でもう一つ興味深い論文を紹介しておく: Minias and Babik (2024) Palaeognaths Reveal Evolutionary Ancestry of the Avian Major Histocompatibility Complex Class II
キーウイには鳥類型以外に爬虫類型の MHC class II 遺伝子 (DAA3) が残っていた。2.5 億年にわたって保存されていたことを示すとともに、キーウイの系統の特異性が現れる結果となった。
ダチョウ目と合わせて古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae とまとめられ、DAA2 の分子系統樹ではキーウイは Palaeognathae に内包されるので現生鳥類の系統関係とは矛盾しない。DAA3 の消失は現生鳥類の適応放散の早い時期に起きたと考えられるがキーウイの系統のみが何らの理由で持ち続けていたもののよう。
DAA1 遺伝子は現生鳥類の複数系統で独立に失われている (#ハヤブサの [ハヤブサ類の免疫の特殊性] など) ので他の機能で代替できるならば失われることがあっても不思議ではない。
Salve et al. (2024) Evolutionary diversity of CXCL16-CXCR6: Convergent substitutions and recurrent gene loss in sauropsids (preprint 版)
が免疫に関係する CXCR6 遺伝子を調べ、主なモチーフ (ここでは1文字記号で表記したアミノ酸配列) のが系統ごとに異なることを示した。哺乳類、カメ類、カエル類は DRF モチーフで、DRY はヘビ類とトカゲ類、鳥類の大部分は DRL で鳥類は爬虫類と特に共通性がなかった。
鳥類の中でもスズメ目に共通する CXCR6 に2塩基の欠損が見つかった。オウム類ではまとまった欠損があった (欠損パターンが違うので独立に生じたもの)。Eucavitaves (キヌバネドリ類、サイチョウ類、カワセミ類やキツツキ類を含む) の系統の後半オオブッポウソウ以降で独立にまとまった欠損が生じている。この遺伝子を見るとタカ、フクロウ、ハヤブサ類までが共通に見えるのが面白いところ。
2塩基の欠損以外の部分を見るとハヤブサ類とスズメ目は少し違って見え、またタカ、フクロウ類 (これらは比較的似ている) とも多少違っている。
次もまた面白く不思議な結果となっている。secretoglobin セクレトグロビン (代表的なものは肺のサーファクタントなどに関係する分泌性タンパク質。慢性閉塞性肺疾患 COPD への治療応用が期待されているなど) は wikipedia 英語版 2025.2 の時点では哺乳類にしか存在しないと書かれているが、ゲノム解析の結果この遺伝子ファミリーが羊膜類に広く存在することがわかった。
Karn and Laukaitis (2025) A broad genome survey reveals widespread presence of secretoglobin genes in squamate and archosaur reptiles that flowered into diversity in mammals
両生類には見つけられず羊膜類の共通祖先の段階で生じたと考えられる。哺乳類、特に有胎盤類に特徴的と考えられていた5種類以外に鳥類・ワニ類にも見られるもの (鳥類は現時点で1種類しか見つかっていないが、ワニ類では哺乳類と共通のものをさらに1種類持っている)、カメ類とトカゲ類のみに見られるものそれぞれ1種類の3種類が新発見。
一覧表を見ていただくと状況がわかるが、なんと {古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae + Galloanseres (キジカモ類)} と Neoaves でパターンが異なるのである。Neoaves では1種類のみだがこの遺伝子は哺乳類やワニ類とも共通しているが他の爬虫類では欠損している。
{古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae + Galloanseres (キジカモ類)} も1種類しか持たないがこの遺伝子は Neoaves は持っていない。一方有胎盤類の哺乳類や一部の爬虫類と共通している。ワニ類はこの2種類を両方持っている。
{古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae + Galloanseres (キジカモ類)} から直接 Neoaves が進化したと考えるのは無理がありそうで、Neoaves がどのように誕生したか興味を持たれる理由ともなるだろう。もっとも高精度ゲノムは一部の種類しか得られておらず、この研究も鳥類の系統を調べる目的ではないので全貌はまだわからないとしておこう。
この研究の範囲では {古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae + Galloanseres (キジカモ類)} と Neoaves の系統の違いの大きさがわかる。どちらも現生の鳥ではあるが、見方によってはカメとトカゲほど違っているとも言える。哺乳類で多数の遺伝子を新たに生み出したが、有胎盤類でも Afrotheria アフリカ獣類では少ない。Cape golden mole Chrysochloris asiatica では Neoaves と共通の1種類しか持たないので胎盤や哺乳に必須というわけではなさそう。
哺乳類で獲得されたものの一部は齧歯類でステロイドフェロモンと結合するとのことで、鳥類では必要性が低いかも知れない。
単孔目では2種類のみで1つは Neoaves と共通。
上記の鳥類2系統は哺乳類で言えば単孔目と有胎盤類ぐらい異なると考えてよいのかも知れない。
霊長類を含む Euarchontoglires 真主齧類で多数の遺伝子が存在して、ヒトの視点でみればこの系統が高等で多数の遺伝子の存在が繁栄の基盤となっているように見え、論文タイトルもその趣旨に沿っているように見えるが...。
羊膜類の祖先で生み出された時には3種類あったがそれぞれの系統で失ったため現在のような状況になっていると考えられる。論文系統樹 (fig. 3) にも示されている。
調べられたゲノムにはどれかが存在しているので、1種類だけでも他の機能を代替可能だが完全に失うことはできないよう。
Neoaves で1種類しかない遺伝子が一番汎用性が高そうだが {古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae + Galloanseres (キジカモ類)} とワニ類以外の爬虫類では失われている。この遺伝子はもしかすると恒温動物にとって特に役割が大きいのかも知れない。何と言ってもこの研究で初めて発見されたばかりの遺伝子で役割はまったくわかっていない。
他の遺伝子を積極的に失う理屈はまた考えなければいけないのだろう。鳥類の肺は構造的にあまりに優秀なので基礎代謝率を上げるために哺乳類ほどの防御物質を必要としなかった? (あくまで想像)。
哺乳類の場合で遺伝子ファミリーが獲得されたのはもしかすると夜行性ボトルネック時代の生活での必要性に関係しているのかも。
遺伝子をたくさん持っていることが優秀と必ずしも言えない結論になるのではないかと想像しておく。
一般向け解説 2025.5.1。この遺伝子は羊膜類の発明とも言えるとのこと。マウスでは顔と首の腺に発現されており、互いににおいをかぎ合って血縁度を知るのに役立っているのではとの考え。鳥類でもにおいによる血縁認識の実験的証拠があるので、今後の役割研究も少し気にしておこう。
備考:
*1: つまり生理学に馴染みのある者にとっては鳥類・哺乳類はそれぞれ互いにかなり外挿できる。遺伝子の働きなども同様。哺乳類、つまり代表的にはヒトの生理学や医学の知見がだいたい参考になる。哺乳類で何かの機能が見つかると鳥にも同じようなものがあるかを探すのはいかにもこの発想による。
自分も生理学に馴染みがあるので違いより共通性の高さの方が目につく感じがする
(しかも違いに着目すると「気のう」や色覚のようにしばしば鳥類の方が機能が上だったりする)。
「鳥類は哺乳類のようなもの」と考えるのは生理学志向の強い人かも知れない (形態や系統を主に見ている人にとっては見え方が違うかも知れない。生理学は化石に残りにくくテーマになりにくいかも)。
わかりやすい例を挙げると、両生類や爬虫類は毒を持っているものも多い。哺乳類でも毒を持つものは原始的な系統のものに限られるので、「高等動物ほど毒を持たない」が半ば常識となっていた。
それゆえに "毒鳥" の発見は衝撃を持って迎えられた次第。それでも毒を合成できる鳥は見つかっていないはず。また毒鳥は捕食者対策よりむしろ食物中の毒排泄の産物との考え方も有力になりつつある。
系統的に鳥類は爬虫類に含まれることを強調したい人は、鳥類がほとんど毒を持たないのはなぜかを考えてみるのもよいのではと思う。
さらに例えば「ハチクマはハチに刺されてもなぜ大丈夫なのか?」のような疑問も、鳥類は哺乳類と同じような反応を示すだろうと暗黙に仮定していることに由来するだろう。系統的には爬虫類の方に近いのだから爬虫類の反応を調べる必要があるはずなどの問いかけは聞いたことがない。
Farris and Doss (2025) Use of Haloperidol in Companion Psittacine Birds: 19 Cases (2012-2022) を見てオウム類の毛引き症にハロペリドール (Haloperidol) が用いられていることを知った。抗精神病薬でやはり脳内作用は我々に似ているのだと改めて納得した。
鳥類・哺乳類の類似性に関する若干の違和感について別の視点から考えてみる。timetree.org を用いてヒトのスズメの分岐年代を見積もってみると 3.19 (3.160-3.224) 億年と出る (こんなに精度よく求められているのか! - 統計的内部誤差評価のみかも知れないが、ここではこの値をそのまま使っておく)。つまりこれが古すぎるのである。
別の系統を何でもよいので試してみると、ヒトとナイルワニでも、ヒトとキングコブラでも当然ながら同じ値が帰ってくる。つまりワニやヘビの外見が我々とかけ離れているのは分岐年代が古いためとまずは納得することができる。
ちなみにスズメとキングコブラだと 2.80 (2.749-2.868) 億年、スズメとナイルワニだと 2.45 (2.412-2.470) 億年で、現生爬虫類で鳥類に一番近いはずのワニでも、我々と鳥類の分岐年代と極端に違うわけではない。同じ系統に含まれるが意外に縁が遠いのである。
この数字を見て違和感の原因がある程度納得できる。3.19 億年も別の道を歩んできたはずなのに鳥は我々と似た点が多すぎるのである。それほど離れているのになぜ場合によってはお互いの意思疎通までできるのだろうか、あまりにも驚異的である。
もし世の中に鳥がいなければ (K-Pg 境界で完全に滅びてしまっていれば)、むしろそのような不思議さを感じなかったかも知れない。もっとも世の中に鳥がいなければ我々自身が生まれていなくて、そのような世界を観察できなかった可能性もある。これは人間が観察していることによるバイアスでもあり、いわゆる人間原理の考え方につながる。
周辺にいる古く分かれた系統の動物がワニやヘビのようなもののみであれば、我々は 3.19 億年の莫大な年月の間にこれほど違った生物に進化したとおそらく理解して納得するであろう。そこまで離れていると互いの意識が通じる方が不自然と感じるかも知れない。
しかし、同じ年月なのになぜ鳥には同じ理屈が当てはまらないのか。
少し飛躍して考えれば、このぐらい離れていても意思疎通ができるならば、独立に進化した宇宙人と遭遇しても意思疎通ができそうな感じもする。鳥と意思疎通できるならば根拠に挙げることもできるだろう。相手は鳥のようなものでもよいかも知れない、そうだ宇宙に生命を探そう! 動機にもなるかも知れない。
しかしながら我々と鳥は地球上の環境を共有し、共通の選択圧の下に互いに影響を及ぼし合いながら進化してきた道筋もおそらく要因に含まれるのだろう。宇宙の他の惑星ではどうなのだろう。
なぜ鳥がそれほど特別なのか、もし鳥が完全に滅びてしまっていればもう一度進化を繰り返しただろうか。それとも哺乳類の系統が空を制覇したのだろうか。少なくとも現生哺乳類は初期デザインの制約から鳥ほどの成功者になれそうな気がしない。いろいろと空想できる題材になりそうである。
3.19 億年の根拠に関係した新しい化石の発見と研究が発表された: Long et al. (2025) Earliest amniote tracks recalibrate the timeline of tetrapod evolution (一般向け解説)
羊膜類の初期進化はこれまで考えられていたより古く、3.5-4.0 億年の早い時代にオーストラリア (この点は過去の見解を裏付ける) で適応放散した可能性がある。この研究では Synapsids (単弓類) と Sauropsids (竜弓類) の分岐はこれまで考えられていたよりずっと古く、3.589 億年前に遡る可能性がある。これまでの想像以上に両生類の分岐時期と近接する可能性が出てきた。
まだ解釈は確定おらず複数の可能性があり、形態学的な収斂進化の可能性を除外できるか否かも試論の対象となるらしい。
またこの時代は化石証拠の少ない時期に当たっている。特に Synapsids の古い化石証拠は少ないので分岐年代がここまで古いものになれば従来以上に哺乳類の初期進化の位置づけが怪しくなってくるかも知れない。
[鴨の漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 97 VII (藤堂) によれば鴨の漢字に含まれる 甲 は音符で kap と読まれる。カモは kap, kap と鳴くため古代中国では ap と読まれ、ap → a → ia と変化して現在では ya と呼ばれる。押の文字は ap と発音される。
-
アカノドカルガモ
-
カルガモ
- 学名:Anas zonorhyncha (アナス ゾーノリュンカ) 帯のある嘴のカモ
- 属名:anas (f) カモ
- 種小名:zonorhyncha (合) 帯のある嘴 (zona (f) 帯、rynchos 鼻口部 Gk)
- 英名:[Spotbill Duck, Spot-billed Duck 分離前の名称], IOC: Eastern Spot-billed Duck
- 備考:
anas は#マガモ参照。
platyrhynchos は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は zone が長母音のみ。ラテン語 zona は冒頭のみ長母音。-rhyn- がアクセント音節と考えられる (ゾーノリュンカ)。長母音を伸ばさなくても構わないだろうが#マガモ同様でアクセント位置は合わせた方がよいだろう。
単形種。
以前は Anas poecilorhyncha 現英名 Indian Spot-billed Duck (その当時のこの種の英名は Spot-billed Duck、この英名を持つ種の現在の和名はアカボシカルガモ) の亜種とされていた。poecilo poikilos まだらの (pied, spotted) rhyncha 嘴 (Gk) で、Spot-billed Duck の名称は分離前の学名に由来。
"Fauna Japonica" 図版 にこの学名でカルガモの図版があるが雑種と考えていた模様。
記述 ではフランス語名 le canard a bec peint (嘴が塗られたカモ)。英名よりも上手に表現している。家禽種の変種 (variete domestique croisee) と考えていた。そのため学名を新たに付けていない。
日本ではカモが多くの数家禽になっていて2種の雑種の可能性がある (nous parait etre le produit d'un melange de ces deux especes)。
インドでは野生で見られるが日本では夏の標本がなかったとのことで、図版は残したものの家禽種の雑種とも考えてあまり重視していなかった模様。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire の時代にはよく知られていて学名は現在と同じ、英名は Dusky Mallard とこれも今ひとつの名前。
留鳥であることはよく知られていて、Temminck and Schlegel は Anas poecilorhyncha と Anas boschas (現在のマガモ。学名は#マガモの備考参照) の雑種と間違えていたと記述している。
Seebohm は十分独立種で中国、モンゴル、シベリア東部にも分布するとしていた。
大橋 (2024) Birder 38(12): 52-53 でカルガモの英名が実態と合っていないことを気にされているがこの事情による。アカボシカルガモは和名の通りオスの嘴基部に赤い斑点がある (spot の由来)。
アカボシカルガモの原記載 (p. 23 に登場) は Forster (1781) (基産地セイロン = 現在のスリランカ) と早いのは当然でオランダ領セイロン (1658-1796) の時代。さらに東インド会社がコロンボを占拠し植民地化を始める (イギリス領セイロン、1796-1948) (wikipedia 日本語版より)。
インドの方がヨーロッパにとってはよく知られた地域で博物学の知識も豊富だったはず。
カルガモの現在の英名に "Eastern" が付いていることがヒントで、過去に本家となるものがあったはずと考えれば見つけることができる。
日本のカルガモを指して付けた英名ではなく本家から分家ぐらいの意味になる。
ちなみに Forster (1781) の記載はドイツ語とラテン語によるもので英名は登場していない。ドイツ語の記述や学名を参考にして Spot-billed Duck と付けられたものと想像できる。
同種時代の学名は Anas poecilorhyncha zonorhyncha。
当時は6亜種で Grey Duck の英名もあった (コンサイス鳥名事典。現在では Grey Duck の名称は事実上使われておらず、指す場合もオーストラリア・ニュージーランドの Grey Teal Anas gracilis を指すようである。
1991 年に Bradley Livezey が形態の研究から独立種として分離を提案、香港や中国南部でこれらの雑種ペアがまれであることから別種扱いとなった。アメリカ鳥学会が独立種としたのは 2008 年。
日本でもかなり最近まで Anas poecilorhyncha の学名、Spot-billed Duck の英名が使われていた。Chinese Spot-billed Duck の英語別名もある (以上 wikipedia 英語版より。この英名を見るとカルガモそのものも中国が本家と言えるかも知れない)。
[マガモとカルガモの遺伝子は同じ?]
マガモ (日本野鳥の会京都支部) の解説によれば、西海功氏 (当時国立科学博物館研究主幹) によると、マガモとカルガモの (ミトコンドリア) DNA は全く同じとのこと。
この記事では「種が分化してまだ時間が経っていない。あるいは、両種が交雑して遺伝子が溶けてしまったと考えられる」と話しているとある。
出典は「分子が明かす鳥の世界 (6) 遺伝的違いが小さいのに別種 マガモとカルガモなどに事例」西海 (2013) 森と人の文化誌 (414): 2013.6 p. 22-23 とのこと。
Saitoh et al. (2015) DNA barcoding reveals 24 distinct lineages as cryptic bird species candidates in and around the Japanese Archipelago
に結果があり、ミトコンドリアのチトクローム c オキシダーゼ I (COI) の部分配列 (648 塩基) の解析による。
この論文で差の小さかった組み合わせは マガモとカルガモ (0%)、アカコッコとアカハラ (0.15%)、
カッコウとツツドリ (0.3% 互いに単系統でない結果が得られている)、シマセンニュウとウチヤマセンニュウ (0.63%)、ケイマフリとウミバト (0.85%)。
大雑把な目安は 2% が種の境界程度とされる。
核遺伝子も含めたもう少し詳しい解析は例えば Wang et al. (2018) Incomplete lineage sorting and introgression in the diversification of Chinese spot-billed ducks and mallards
にあり、差異はあるが分離が不完全で、(この研究で調べた範囲の) 遺伝情報から2種のどちらに属するのかを判定することができないとの結論になった。
カルガモの方からマガモへの遺伝子浸透 [(genetic) introgression; 遺伝子移入などとも呼ばれる。解説は例えば長谷川 (2012) 鳥類における種間交雑と遺伝子浸透 参照]
が非対称に起きているらしい。
全ゲノムを扱った研究もなされている: Feng et al. (2021) Whole-genome resequencing provides insights into the population structure and domestication signatures of ducks in eastern China
この2種はやはり遺伝的に非常に近いが分離されないほどではない程度の微妙な違いがある。遺伝的には非常に近いが外見は大きく異なるとのこと。この2つの研究ではアカボシカルガモは分析に含まれていないのでさらに調べる必要があるとのこと。
これらの研究は中国のアヒルの起源を調べるためのもので、マガモとカルガモの外見がなぜそれほど異なるのかは深入りしておらず、関心のある研究者が調べるべしというところであろう。
ハクセキレイの亜種で遺伝型と外見による亜種分類が整合しないことが知られているが (#ハクセキレイの備考参照)、ヨーロッパのハクセキレイでは顔の模様を決める遺伝領域が一部明らかになりつつある。
これに類似する状況かも知れない。
「マガモとカルガモの遺伝子が同じ」話は日本の研究者によるもので比較的よく知られているため探鳥会などで話題になることもあるだろうが、外見を決める遺伝子が調べられているわけではないので「遺伝的に非常に近い」程度の表現にとどめておくのがよさそうである。以下の研究でもう少し判明した。
アカボシカルガモも含めた関係をミトコンドリアゲノムを用いて調べた研究: Nagarajan et al. (2024) Mitochondrial genome of the Indian spot-billed duck and its phylogenetic and conservation implications
カルガモとアカボシカルガモはかつて亜種関係とされていたほど近縁ではなかった。カルガモとマガモの方がグループを形成し、カルガモとマガモは系統樹サポート率 100% で分離された。我々としては別種として扱う分子遺伝学的証拠が増えたことになる。ただし mtDNA のみを用いる限界もある (#コガモの備考参照)。
系統的には確かに近いが、DNA バーコーディングに用いられるミトコンドリアのチトクローム c オキシダーゼ I (COI) の部分配列は短いものだったのでたまたま完全に一致してしまった、というところだろうか。
簡易解析だが我々でも簡単に系統樹を見ることができる。MZ593724.1 から出発して BLAST を実行すればミトコンドリアゲノムの系統樹を見ることができる。確かにカルガモとマガモは非常に近いことがわかる。
同じ系統樹に現れるヒドリガモとアメリカヒドリはほぼきれいに分かれるが分岐年代はむしろ浅い。
サンプル数は少ないがコガモとアメリカコガモも同程度に分かれる (将来また別種扱いに戻ってもおかしくないように見えるが、ゲノムレベルではこれほど分岐していないとのこと。カモ類はオスによる異種との強制交尾が起きやすいので mtDNA とゲノムの間で分岐度が異なることがある)。
これらと比べるとカルガモとマガモはより古い時代に系統が生じているものの接触範囲が広いためか互いにずっとよく混ざっていることがわかる。
この解析の時点 (2025.2) では同じ枝にツクシガモが現れラベルのミス? すぐ実行できるので皆さんもお試しを。
[和名について]
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 49 によればマガモより軽く感じるので狩人たちは「軽る鴨」、あるいは単に「軽鴨」と読んでいたとのこと。万葉集に歌われた「軽ケ池」由来説も中西悟堂など複数の著者により有力視されているが、ちょっと理屈っぽい感じもする。
民間語源として "軽い鴨" は間違いではないのでは (OED の英語語源表示などでは併記されているレベル)。
河合氏は、夏に留まって繁殖する習性から「夏留鴨」説を推していた。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 9 (1940 年初出) によれば万葉集の軽ケ池のカモを軽鴨とすればカルガモは1首のみ登場とのこと。この解説を見ると定説レベルから程遠いかも知れない。万葉集の小鴨は小さいカモの意味 (当時はコガモの名称はまだなかった。pp. 9, 11)。確かに真鴨、軽鴨、小鴨と並ぶとカルガモだけ地名由来と考えるよりは、大きさや重さを主に表したものの方が納得しやすい感じがする。
あじ (トモエガモ) は万葉集にすでに登場するが、味鳧の表示だった (p. 9)。wiktionary を調べておくと、鳧 は中世中国語で bju (現代は fu)。日本の漢字の読みには出てこないので、鳧に "じ" を当てるのは中世漢語由来なのだろう。日本語では鳧はケリを表す漢字だが、中国語では野生のカモのこと。文字は象形文字由来。鳥の足は2本なのに点が4つあるのはおかしいから足を別に補った...かどうかは知らない。
大橋 (2021) 35(1): 66-67 には食材としての味を定説として紹介されているものの、群れる、集まる意味の説も紹介されていた。万葉集であぢ群、「あぢさはふ」は枕詞があり、国語辞典「大言海」では集の転じたもの、大群説が示されているとのことで、大橋氏も傾聴に値する語源説とされていた。
銃器のなかった時代に食材として味わうほど捕獲されていたのだろうかと片野鴨池の坂網猟 (さかあみりょう) を調べてみると江戸時代 (元禄年間 1700 年前後) に始められたものとのこと (wikipedia 日本語版より)。それほど簡単に捕獲できるものではなさそう。
万葉集の時代にすでに "あじ" の名前があったので、トモエガモについては食材としての味よりは別語源の方が考えやすい気がする。"味鳧" の表記が使われたために食材としての味と理解されて伝わってきたのでは? "あじ" の別表記である 有+鳥 の文字は中国語ではキジ類の一種。この文字は広東語で juk と読む (wiktionary)。康煕字典 に現れるがこちらを用いるのも当て字かも。"あじ" のうち "あ" の音に意味があるように思える。
万葉集収録の「あぢかまの塩津を指して...」に現れる琵琶湖北部の塩津の「あぢかま」とは塩津の地域をさす枕言葉で、びわ湖の水辺で冬を越す鴨に由来していますとのこと (長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト)。探鳥地としてもよい地域で地名にも馴染みがある。地元の人から聞いた話では水辺にカモが戻ってくると賑わいが戻ってきたような感覚を受けるとのこと。
アトリの "ア" の解釈の一つと同様に、やはり集まるカモではないだろうか。片野鴨池のトモエガモの集団を見ると納得できる気がする。"じ" は上記のように漢語由来の可能性がある。
-
ミカヅキシマアジ
- 第8版学名:Spatula discors (スパトゥラ ディスコルス) 不調和な (染め分けられた?) スプーン(の嘴) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas discors (アナス ディスコルス) 不調和な (染め分けられた?) カモ
- 第8版属名:spatula (f) スプーン
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:discors (adj) 不一致の、異なった
- 英名:Blue-winged Teal
- 備考:
spatula は#ハシビロガモ参照。
discors は短母音のみで "ディスコルス"。語源は dis- 離れる cor 心臓 とのこと。同じ意味で英語の discord とアクセント位置が一致する。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Spatula 属 (spatula スプーン) に分離。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。Spatula 属はハシビロガモ属。南北アメリカに分布する種。単形種。
種小名の由来はオスのまだら顔の模様に由来。BOU (1915) は飛翔時の特異な翼の模様を挙げている。
Gruson (1972) は不調和な鳴き声を挙げているが、記載時学名 Anas discors Linnaeus, 1766 (原記載) には習性や声の記載はないとのこと (The Key to Scientific Names)。
類似語の dispar の使われた用例が他にもあり、Falco dispar Temminck, 1825 でオジロトビ (現在の学名で Elanus leucurus) を指していた。この例では通常にトビ類と異なって最外側尾羽が短い点を "不規則な" と表現したものだった (#カタグロトビ備考参照)。
ミカヅキシマアジの原記載は確かに様々な色が挙げられていて色彩由来の印象を受ける。"通常のシマアジ/コガモ類とは違う" 点を同様に指摘した学名ではないだろうか。
Linnaeus 以前の学名 (有効な学名ではない) の一部に variegata を与えているものがあり、染め分けられた、変化に富むの意味 (Querquedula americana variegata 名称全体で "染め分けられた、変化に富むアメリカのシマアジ" の意味だった)。ヤマガラの記述に使われたものと同様だろうか。
伊藤・福田 (1996) Birder 10(3) 78-79 にミカヅキシマアジの日本初記録 (1996年1月) の紹介記事がある。伊藤 (2005) 日本におけるミカヅキシマアジの初記録。
-
ハシビロガモ
- 第8版学名:Spatula clypeata (スパトゥラ クリュペアータ) 盾で武装したスプーン(の嘴) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas clypeata (アナス クリュペアータ) 盾で武装したカモ
- 第8版属名:spatula (f) スプーン
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:clypeata (adj) 盾で武装した (clypeatus) 嘴の形状に由来
- 英名:(Common) Shoveler, IOC: Northern Shoveler
- 備考:
spatula は短母音のみで冒頭にアクセント (スパトゥラ)。
clypeata は1つめの a が長母音でアクセントがある (クリュペアータ)。この場合の -ata は所有の語尾ではなく clypeo (盾で武装する) の変化形とのこと。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Spatula 属に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。北半球に広く分布し、単形種。Spatula 属は Boie (1822) が導入した属でハシビロガモがタイプ種 (The Key to Scientific Names)。
英名の shoveler の由来は簡単ではないかと思ったが、OED を見るとそうではなかった。かつては shovelard の意味で使われており、これはヘラサギのこと。1460 年頃の用例がすでに知られていた。1552 年には誤ってペリカンを指して使われていた。ハシビロガモの意味で使われるようになったのは新しく 17 世紀後半とのこと。1674 年の用例が知られている。shuffler の綴りもあり、Shoveller Duck のように Duck を付けることも、また Spoon-bill Duck の別名もあった。
shoveler をヘラサギに用いる用例は 18 世紀末まであり、混同を避けるために Duck を付けたり別名が使われていたよう。
ショベルで掘る者の現在の第一語義は 1440 年代の用例がある。ヘラサギやハシビロガモが shoveler と呼ばれたのは shovel (かつては schovel) の影響を受けていることは間違いないが、必ずしも "掘る者" を直接意味するわけではなく、かつては -ard の語尾だったのは malard (マガモ) や中世オランダ語の lepelaar (ヘラサギ) の影響を受けた語尾が -er に変化したとも考えられるとのこと (wiktionary)。shoveler の第一語義から直接派生したものではないらしい。
[ハシビロガモ関連種の分子系統]
英名に Northern が付くのはオーストラリア・ニュージーランドに ミカヅキハシビロガモ Spatula rhynchotis Australian Shoveler、南アフリカに ケープハシビロガモ Spatula smithii Cape Shoveler、南米に アカハシビロガモ Spatula platalea Red Shoveler が存在するため。
これら3種が単系統をなしているわけではなく、日本鳥類目録第8版で用いられた分子系統分類によればミカヅキシマアジなど "Teal" の付く一部の種類と類縁関係がある。
後述のようにカモ類の嘴の形態進化の速度が速いので系統的に近縁であっても嘴の形が必ずしも似ていないこともあるのだろう。(シマアジや) ミカヅキシマアジとハシビロガモがそれほど似て見えないのに同属になったのは分子系統解析の結果を反映したもの。
シマアジを含むクレードとアカハシビロガモから始まるクレードを分けることは可能で、この場合は "ハシビロガモ" の名前のつく種は後者のみに含まれる。別属にするほどの分岐ではなかったため分けられなかったのだろう...、と思ったが#オカヨシガモ備考の
Chen et al. (2024) The Complete Mitochondrial Genome of the Siberian Scoter Melanitta stejnegeri and Its Phylogenetic Relationship in Anseriformes
の分子系統樹によれば別系統になっている。
この系統樹を受け入れればシマアジは Anas を含むクレードに戻される可能性がある。似て見えない印象の方が正しかったのかも。
つまり第8版でシマアジとハシビロガモが同属とされたが実はおそらく正しくなかった。
しかしシマアジを Anas 属に戻してしまうと Anas 属と Mareca 属が互いに単系統の関係にならないので、
Mareca 属を Anas 属に含めてしまうか (その場合 Mareca 属の種の学名が元に戻ることになる)、
シマアジとシロスジコガモ (現在の学名で Anas bernieri) Bernier's Teal (シマアジにあまり似ていない) を別属に分離することになるだろう。あまり似ておらず分岐もそこそこ深いのでこれらはそれぞれ単形属とする解もあり得る。
シマアジとシロスジコガモを別属にするならばマガモ類と {オナガガモ + コガモ} は同じ程度の分岐の深さなので別属の考えが出てくる可能性がある、というよりオナガガモとコガモがそれぞれの属を作るなど。以前のように全体を Anas 属とする方が簡単そうではある。
もし細かく分ける方を採用すれば Anas 属はマガモ、カルガモ、アカボシカルガモを含むごく少数のグループで、"本家" の属にほとんど残らなかった Accipiter 属のような状況となる可能性がある。アカノドカルガモは調べられていないようなのでこれらの結果待ちか。
判断は Mareca 属を残したいかどうかで決まりそう。
せっかく覚えたのに...となる可能性は十分ありそう。
またこの系統樹ではハシビロガモを含む Spatula 属2種が他の属の作るクレードに内包される形となっている。これらの属の記載年を調べると Spatula 属より新しいため、このクレード全体が Spatula 属となる可能性がある。
具体的には Tachyeres (フナガモ) 属やアフリカの Anas 属とされていたアカハシコガモ (現在の学名で Anas capensis) Cape Teal と南米のキバシオナガガモ (現在の学名で Anas georgica) Yellow-billed Pintail、
カンムリガモ Lophonetta specularioides Crested Duck、
ノドジロガモ Speculanas specularis Spectacled Duck が問題になる。
これらは見かけもかなり異なるのでまとめて Spatula 属とするのは抵抗がある可能性があり、その場合はこのクレードを4属に分けざるを得ない。その場合は Tachyeres はタイプ種フナガモ Tachyeres brachypterus 1種のみからなる属で、アカハシコガモとキバシオナガガモには別途属名が必要。
アルゼンチンフナガモ (現在の学名で Tachyeres leucocephalus) Chubut Steamerduck にも属名が必要となるが、このクレードにはタイプ種となっているカンムリガモがあるのでこの属にまとめられるのだろうか。
ざっと見たところでアカアシコガモ Amazonetta brasiliensis Brazilian Teal が含まれていないのでこの種の遺伝情報の解析待ちになるだろうか。この種は1種だけで属を作っているので属の再編を考える上ではあまり問題がない。
さてどうなるだろうか。
[鳥類の嘴の形態進化速度]
ハシビロガモの嘴の形が特異なのでここに含めておくが、鳥類全体で嘴の形態進化速度を比較した研究: Conney et al. (2017) Mega-evolutionary dynamics of the adaptive radiation of birds
系統樹を見てどのグループが形態進化速度が速いか見るだけでも十分面白い。カモ類は全般に進化速度が早く嘴が非常に重要な役割を果たしていることがわかる。
チドリ類は一部の系統。サイチョウ類やオウム類も速い。スズメ目ではカラス小目の最後、すなわちモズやカラス類、種子食の鳥で速いことがわかり常識ともよく一致する。昆虫食のスズメ目ではそれほどでない。
孤立系統でではフラミンゴ類など予想される通り。他は目レベルで全体的傾向のあるグループが多いが細かく見ると面白いところもありそう。
分子系統解析の結果、チドリ類の広義 Charadrius 属が単系統でないことが判明して IOC 14.1 以降一部の種が Anarhynchus 属となっている (#タゲリの備考参照)。
これは先取権の原則に基づくものではあるが、本来はハシマガリチドリ1種を指す属名なので非常に違和感がある。しかしこのように嘴の形態の進化は速い場合もあるのでそれほど目くじらを立てるほどではないのかも知れない。
嘴の形態は黙認して系統関係を重視することになるのか。
power cascade モデルを用いた嘴の形態の定量化と新しい研究については#オオソリハシシギ備考の [嘴の形を決める法則] を参照。この研究でも進化速度の速い系統が見出されている。
嘴の形態や集団採食方法の意義については #オオフラミンゴの備考 [フラミンゴ類の採食と嘴の形・動かし方] と参考文献を参照。ハシビロガモについても同様のメカニズムが過去にも提唱されていたが、フラミンゴ類の測定の結果、流体力学的効果が示唆されることとなった。
[湿地の鳥の行動ビデオデータベース]
どこに入れてもよいが紹介されているサンプルの最初に登場するのがハシビロガモだったためここに含めておく。スペインでの研究。Rodriguez-Juan et al. (2025) Visual WetlandBirds Dataset: Bird Species Identification and Behavior Recognition in Videos。
ここでも音声データベースの xeno-canto が音声種別をカテゴリーで分けているなど成功を収めていることが一つの契機となっている。その行動ビデオ版が欲しい。映像から鳥の個体の切り出しアルゴリズムは進化してきているのでビデオからの抜き出しは省力化できるようになっている。人が種類と行動を判別し、さらに計算機に処理させるハイブリッド形式となっている。
計算機に種類を自動判別させた場合の判別の正確さなども示されていてこちらも面白い。
ブロンズトキの正答率が特に悪く正しく判定されれたものはなかった。ブロンズトキと判定されたものはすべてバンだった。ハクセキレイの認識率も低く写っていても背景と判断されたものの方が多かったなど。
カモメ類 (ただしここでは対象は2種) の正答率が意外に高かった。
-
オナガガモ
- 学名:Anas acuta (アナス アクータ) 尾の先が尖ったカモ
- 属名:anas (f) カモ
- 種小名:acuta (adj) 先の尖った (acutus)
- 英名:Pintail, IOC: Northern Pintail
- 備考:
acuta は u が長母音でアクセントもある (アクータ)。英語の acute も同じように長母音でアクセントがある。英語の acute をラテン語風に発音すればよい。
北半球に広く分布し、単形種だが亜種 (tzitzihoa メキシコ、modesta 太平洋離島の旧名 Sydney Island 現在キリバスの Manra 島) が記載されたこともあった (記載)。
この亜種は Tristram's pintail とも呼ばれ絶滅亜種とも考えられるが基亜種と区別できないとされた (wikipedia 英語版より)。
標本は3体残っているそうで原理的には DNA 判定をすることが可能なはずとのこと。
近縁種にインド洋南部の離島に生息する イートンオナガガモ Anas eatoni Eaton's Pintail があり、渡りによる長距離分散で定着して種分化した経緯が想像できる。
かつては Anas eatoni はオナガガモの亜種とされ亜種和名がつけられていた。ケルゲレン島の eatoni にコオナガガモ、クローゼット島の drygalskii にホソフコオナガガモ (コンサイス鳥名事典)。
現代のチェックリストでは別種 Anas eatoni とされている。Kerguelen Pintail, Southern Pintail の英語別名もある (このためオナガガモに "Northern" がつくことになる)。
ドイツ名 Spiessente (槍のカモ)、フランス名では Canard pilet で canard はカモで問題ないが、pilet はあまり使われる単語ではなく辞書に現れない。ラテン語 pilus (髪) あるいは pila (柱) 由来か。イタリア名は codone でこれもおそらく coda (尾。音楽用語にもある) 由来。
ロシア名は shilokhvost' で shilo (錐) khvost (尾)。中国語でも尖尾鴨または針尾鴨ですぐにわかる範囲の言語ではほぼ世界共通の名称のよう。
和名のオナガガモと同じ意味の英名 Long-tailed Duck はコオリガモの英名に使われている。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Dafila acuta の学名が用いられていた。これはブラジルのカモに学名 Dafila caudacuta を与えて Stephens (1824) が用いた属名。後にオナガガモのシノニムと判定された。
新 Anas 属をさらにクレードに分ける可能性も考えられ、その場合は Dafila 属が生きるとのこと (Boyd の系統樹参照)。古い概念で根拠のない属名というわけではない。
Pintail Duck (Gould 1837) にあるように両学名は長期間併用されていた模様。Gould (1837) では Dafila 属は Leach によるものとしているが、これは手稿段階で正式に用いたものは Stephens とのことらしい (The Key to Scientific Names)。
尾が特徴的なので別属にしても不自然でない状態が続いていた模様。
他の (旧、広義) Anas 属のカモより首が長く骨も多いと図鑑にある。文献によるとオナガガモ 17-19 個、他の Anas 属は 16 個とある (#コブハクチョウの備考参照)。採食習性と関連させて観察すると面白いであろう。
Kaup (1829) が 記載 でオナガガモ1種に Trachelonetta 属を提唱している。trackhelos 首 netta カモ (Gk) の意味で、現在はもちろん使われていないがやはり細長い首 (Enten mit sehr langem, duennem Hals...) に注目した学名が存在した。
記載ではもちろん中央尾羽が長く伸びていることも特徴としている。
-
シマアジ
- 第8版学名:Spatula querquedula (スパトゥーラ クゥェルクゥェドゥラ) クアークと鳴くスプーン(の嘴) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas querquedula (アナス クゥェルクゥェドゥラ) クアークと鳴くカモ
- 第8版属名:spatula (f) スプーン
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:querquedula (f) Varro や Columella の述べたカモの一種。Skeat によれば声 (querq, kark) からの擬声語
- 英名:Garganey
- 備考:
spatula は#ハシビロガモ参照。
querquedula は短母音のみで2つめの音節にアクセントがある (クゥェルクゥェドゥラ)。-du- は長音でもなくアクセントもない。
que の音は kwe のように w を添える発音 (国名のクゥエートの発音同様)。"クゥェ" の表記で短く発音すればカモの声にも近そう。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Spatula 属に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。
一見矛盾するような属変更については#ハシビロガモの備考参照。
また戻される可能性も出てきた。
和名のシマは縞、アジは味がよいことからとされる。トモエガモの別名がアジガモだったことからも納得できる。
大橋 (2021) Birder 35(1): 66-67 にトモエガモの語源とともに考察があり、シマは島 (遠くから来る) と考える説もあるとのこと。
ただし「あじ」については #カルガモ備考の [和名について] にまとめた。いわゆる味ではないかも知れない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" での学名は Querquedula circia だった。Querquedula については#トモエガモの備考参照。
Anas Querquedula の 原記載。
Anas Circia はこの次のページで 記載。circia kirke (Gk) は不明の鳥でおそらく空想上のものか (The Key to Scientific Names)。
Fauna svicica の 111. が Anas Circia に該当する種で基産地はこの文献からスウェーデンと判定された、Linnaeus (1758) は Anas Querquedula を追加で挙げた経緯のよう。
おそらく Anas Circia が先に認識 (記述) されたとの考えからだろうか、Anas circia の学名はかなり使われていたようで、アメリカコガモがこの学名の種の亜種とされることもあった。Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でも用いられていた。後に同じものと判明したらしい。
ユーラシアに広く分布する単形種。ヨーロッパの個体群はサハラ以南のアフリカにも渡り、かつて強毒性鳥インフルエンザ (H5N1) のナイジェリアなどのアフリカへの拡大の際にこの種の渡り経路を例に解説されたことがあった (#インドガンの備考参照)。
英名の由来はロンバルド語 gargenei (garganell の複数形)。水面をすくように採食することかオスの特徴ある (ねじを巻くような音と形容される; 渡り途中に滞在中の個体でも聞くことができる) 声からか。イタリア語 garganella (瓶から連続的に飲む意味) にも似ている。
遡ると garg- 喉 (L)、あるいは gargling (うがいすること。日本語でもうがい薬をガーグルと言う) gargareon 口蓋垂、気管 (Gk) (American Heritage Dictionary)。
OED によれば 1668 年に Gargane の用例、1678 年に Ray が Willughby のラテン語から訳した Garganey の名称が現れる。OED は Gesner Hist. Anim. (1555) をもとにイタリア語 (現在スイスの Bellinzona ベッリンツォーナ 地域の名称) からの借用としている。
英語別名に Cricket Teal があり繁殖期のオスの鳴き声が特徴的 [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)]。
こちらも OED によれば 1813 年 Montagu の用例があり、1885 年 Swainson が鳴き声 Cric cric (Jura); Criquet (savoy); Kriechentlein (Germany) の鳴き声由来の他言語表記を紹介していた。
-
トモエガモ
- 第8版学名:Sibirionetta formosa (シビリオネーッタ フォールモーサ) 美しいシベリアのカモ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Anas formosa (アナス フォールモーサ) 美しいカモ
- 第8版属名:sibirionetta シベリアのカモ Sibiria シベリア (L) netta カモ (Gk)
- 第7版属名:anas (f) カモ
- 種小名:formosa (adj) 美しい (formosus)
- 英名:Baikal Teal
- 備考:
sibirionetta は外来語を含む合成語で発音はよくわからないが、ギリシャ語 netta の冒頭は長母音なので伸ばすかも知れない。この音はアクセント音節 -net- とも一致するのでわかりやすさを重視して伸ばす方を採用した (シビリオネーッタ)。
formosa は「美しい」の形容詞では前2つが長母音。2番めにアクセントがある (フォールモーサ)。固有名詞で台湾の意味の Formosa も発音は同じとのこと。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Sibirionetta 属 (Sibiria シベリア L netta カモ Gk) に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)も同じ。種小名は変化なし。
Sibirionetta 属はトモエガモ属で単形属。単形種。東シベリアに高緯度まで繁殖分布を持つ東洋特産のカモ。
属の記載は Boetticher (1929) による。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では現在の学名が用いられているが、Nettion formosum を別名としていた。
nettion は小さなカモ (Gk)。Nettion 属はコガモをタイプ種として Kaup (1829) が設けたもの。Entchen (小さなカモ) と意味が記述されている (The Key to Scientific Names)。
Nettion はギリシャ語指小辞 -ion に基づいて中性の属で formosum も中性の形となっている。
ドイツ語の -chen (小さな) も中性名詞を作る語尾で性が一致している (Maedchen メートヒェン 少女 も中性名詞で生物学的な性と文法上の性が必ずしも一致しないこともわかる)。
同じく別学名とされていた Anas glocitans Pallas, 1779 (glocitans コッコッなどの声を出す) も広く用例があり、Bemaculated Duck の英名で呼ばれていた。
最初に紹介したのが Pennant だったため、こちらの学名が優先されることになった模様。Bemerk. Reise Russ. Reich に出版で記載年は後に 1775 と判定された。
Baikal Teal (Historical Rare Birds)。
Querquedula formosa の学名も使われていたことがわかる。この属はシマアジをタイプ種として Stephens (1824) が用いたもの。しかし同じ属名はコガモをタイプ種として Eyton (1838) が用いるなど混乱していた模様 (The Key to Scientific Names)。
これらの属名は古く使われていたものの、シマアジやコガモなど異なった系統を指していたためかなり後になるが Sibirionetta が採用された模様。
種小名に使われる formosa はここでは美しいの意味。ポルトガル語由来で台湾を指す Formosa があり、この意味で使われる場合は formosae (名詞の属格), formosana / formosanus の形になる。種小名になぜ formosa と formosae (アオバトなど) の両方があるのか気になる方もあるだろうが、このような事情による。
formos- の入っている日本の鳥の学名では、調べた範囲でトモエガモのみが「美しい」の形容詞が使われていた。
Ogawa (1908) に別学名としてリストされている Nettion formosum はかなり用例があり広く使われていたよう。この学名で Nettion を中性名詞、formosum を形容詞と考えて活用させていたことがわかる。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では英名に Spectacled Teal を用いていた。種小名にふさわしい英名だった。
ロシア名は klotkun (または chirok-klotkun) でこれも klokhtat' というかつてニワトリが卵に呼びかける声 (vo-kvo, klyu...klyu...) 由来とのこと (Kolyada et al. 2016)。
Dement'ev and Gladkov (1952) にも音声の記述があり、klo, klo, ... と鳴くとのことで遠くからも聞こえるとのこと。春にはオスは飛んでいる時もとまっている時もずっと鳴いている。メスの声はマガモに似ているとのこと。
もう一つ学名シノニムが掲載されており、Anas cucullata Fischer, 1831。カムチャツカで記載。cucullatus フードをかぶった。
XC380276 (Andrew Spencer 2017) に繁殖地 (ヒメクビワカモメの繁殖地) での音声がある。越冬地での録音は難しいようでバードリサーチ鳴き声図鑑にも2024年9月現在収録されていない。
トモエガモの鳴き声 (hideo suzuki 2023) に動画あり。
石川県片野鴨池に例年多く越冬し何度も訪問したが距離も遠くて音声が記録できる印象を受けなかった。むしろ少数個体が近くで見られる条件で渡り前の春に声を聞くことができることがあるかも。Anas glocitans やロシア名の由来となっている繁殖地で鳴き続けるような声は越冬地で聞くことは無理かも知れない。
中国名は中国の戯曲 (英語で chinese opera) で使われる色彩を施した顔 (painted face) に相当する単語を用いる名称が一般的のよう。画像検索で見ていただく方がわかりやすい。
和名別名の「あじ」については #カルガモ備考の [和名について] にまとめた。
Ukolov et al. (2018 初出、2024 再掲) The Baikal teal Sibirionetta formosa in the lower Indigirka River basin (pp. 4560-4563)
ヤクーチアのインディギル川河口での繁殖について。越冬地での数の変動の情報はあるが繁殖地の情報はほとんどない。20 世紀中頃まではトモエガモはインディギル川で最も数の多いカモで海に近いツンドラ以外の全域に生息していた。1960 年の調査でも同地域で最も数の多い水鳥だった。
1993-1995 年の調査でインディギル川河口デルタで繁殖の証拠は得られなかった。1999 年も同様だった。
2018.6.28 の調査で抱卵中の巣がみつかり、オスはすでに去った後だったとのこと。この調査から繁殖密度を推定している。
-
コガモ (アメリカコガモ が分離されることもあるが AviList では分離されず)
- 学名:Anas crecca (アナス クレッカ) コガモ
- 属名:anas (f) カモ
- 種小名:crecca (合) コガモ Kricka、Kracha コガモ スウェーデン語 (声から擬声語)
- 英名:Teal, IOC: Eurasian Teal, アメリカコガモ Green-winged Teal さらに合体後 AviList: Green-winged Teal
- 備考:
anas は#マガモ参照。
原記載 (Linnaeus 1758)。Fauna svicica の 109. とのことで Linnaeus (1746) は当初は Anas fusca の学名を用いていた。
スウェーデン語では Swarta とある。どちらにも種小名由来は明確に示されていないので学名由来は後世の研究によるものらしい。スウェーデン語の現在の名称は kricka だが Linnaeus は使っていなかったように見え、語源関係は逆順なのかも知れない。しかし当時から俗名として存在したかも知れない。
歴史的なスウェーデン語名称では arta (最初の a の上に丸が付く。wikipedia スウェーデン語版より) で Linnaeus の時代にはこちらの方が学術的に使われていたかも知れない。
"クレッカ" 以外の読みは考えにくい気がする。
carolinensis は i が長母音、-nen- がアクセント音節で短母音 (カロリーネンスィス)、長母音 (カロリーネーンスィス) のいずれもある。場所の -ensis は伸ばすとすれば後者だろうか。
学名由来の情報: Linnaeus (1761) Fauna svecica Ed. 2 に項目、次ページにスウェーデンの Bothniensis による名称 Kraecka となっている。Linnaeus (1761) はここで種小名を訂正した (Anas Crecia) ようだが認められなかった。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でもコガモに2亜種ある立場だが、世界の主要リストでは立場が分かれており、IOC、HBW/BirdLife などは carolinensis (カロライナの) を独立種アメリカコガモ Anas carolinensis (英名 Green-winged Teal) として認めている。この場合2種とも単形種となる。
アメリカ鳥学会、Clements、eBird などでは亜種扱い。アメリカ鳥学会もかつては別種扱いとしていた。
オナガガモに Dafila 属を認める立場であればコガモやアメリカコガモは Dafilonettion 属となる (Boyd の系統樹参照)。
もう1種近縁の種があり、キバシコガモ Anas flavirostris (英名 Yellow-billed Teal) があり、コガモ、アメリカコガモ、キバシコガモの関係は現在ある限られた遺伝情報だけでは解決できず、核 DNA の解析が必要とある (wikipedia 英語版)。ここでは IOC 分類に従った英名を挙げておく。
SACC Split Anas crecca (Green-winged Teal/Common or Eurasian Teal) into two species: A. crecca (Common Teal or Eurasian Teal) and A. carolinensis (Green-winged Teal)
ではこれまで通り亜種として扱う判断。文献も示されている。
Working Group Avian Checklists では version 0.04 より亜種扱いで、おそらく IOC もこれに従うと考えられるので世界的には同種の扱いにまとまりそう。その場合は英名は Green-winged Teal。
IOC 14.2 はまだ従来通り2種に分けている。IOC 15.1 (red) では別種のままの扱い。
British list set for major taxonomic shake-up によれば BOU も WGAC に従ってアメリカコガモを分離しない見通しとのこと。
該当論文 Spaulding et al. (2023) Population genomics indicate three different modes of divergence and speciation with gene flow in the green-winged teal duck complex。アリューシャン列島などの個体を調査。
核 DNA の UCEs も用いた。ミトコンドリアと核 DNA で系統関係に違いがある。ミトコンドリアではこれまで提案されていた種が分離されるが核 DNA では系統が混ざってしまって互いに単系統関係をなさない。これらも証拠として同種の扱いとなったものと思われる。
ただし用いられたのは交雑帯に近い限られた地域のものなので、ユーラシア大陸や北米全体でみると少し描像が違ってくるかも知れない。Latest IOC Diary Updates にも議論があり、それを根拠とするならばミトコンドリア DNA を根拠としたツメナガセキレイの分離も同様の問題があるとの指摘がある。
さらにこの論文ではサンプルした個体が交雑個体でない根拠を示していない (それを議論すると論文自身の論旨が怪しくなる) との指摘がある。
現段階はまだ世界のリストの共通化の途上で、生物学的な種の分離の議論よりはリストの共通化作業が重視されているとのこと。
コガモとアメリカコガモを同種とする扱いも限られた情報に基づくまだ暫定的なものと考えたほうがよさそう。
AviList では、
566 7 Taxon carolinensis is treated as a subspecies of Anas crecca based on high levels of introgression, coupled with a lack of known differences in courtship vocalization. Although mitochondrial DNA data show a relatively deep divergence between these taxa (Peters et al. 2012), a lack of genomic divergence (McLaughlin et al. 2020; Spaulding et al. 2023) indicates that male-mediated gene flow is extensive.
近年の遺伝学研究では、mtDNA では比較的分離が深いものの、ゲノムレベルでは分離が弱く、オスを通じた introfression が広範に起きていることを示唆する。courtship vocalization (求愛の声) に違いが知られていないことも同種とする根拠。
この部分もライフリストが1種減る問題があって特にバーダーの間で議論が盛り上がっている部分で (例えば BirdForum)、種とは何か、生物学的種概念とは何かが議論されているものの、盛り上がっているのは主にバーダーの間のみなのも興味深い (この点は種数の減るベニヒワやズキンガラスも同様。外見は明らかに違うのに同種になるのはけしからん、というところか)。
コガモとアメリカコガモを別種として英名で記録していた場合は、統合後はアメリカコガモの英名 Green-winged Teal の方にまとまって、この英名がコガモに対応することになる。和名では想像しにくいがミカヅキシマアジの英名 Blue-winged Teal に対応する形の名称になる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Nettion 属だった (#トモエガモの備考参照)。
[飛べないカモの進化]
南半球 Anas 属でコガモに近い飛べないカモの分子系統研究: Rosinger et al. (2024) The radiation of Austral teals (Aves: Anseriformes) and the evolution of flightlessness。
ハイイロガモ Anas gracilis Grey Teal (ニューギニア、ニューカレドニア、オーストラリア、ニュージーランド) と アオクビコガモ Anas castanea Chestnut Teal は分子系統的には互いに単系統の関係になく同種とみなすのが適切になりそう。
統一された場合は Anas castanea となるが、世界のリストではまだ別種扱い。分子系統的な関係と表現型の違いをどのように解釈するかここでも問題となりそう (互いに単系統の関係にないので単純に亜種ともできない)。
#ミコアイサの備考のように、長距離を渡るカモ類から南半球へ複数回の進出があった。
カモ類は一般に non-sequential molt で一時的に飛べなくなるが、飛べないカモも結構ある (渡りをしないので馴染みがないだけのよう)。
Terrill (2020) Simultaneous Wing Molt as a Catalyst for the Evolution of Flightlessness in Birds のように翼の同時換羽は例えば島や開けたニッチで迅速に飛翔性を失う前適応か、との議論がある (#ハチクマ備考の [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] から)。
-
アカハシハジロ
- 学名:Netta rufina (ネーッタ ルーフィナ) 赤みがかったカモ
- 属名:netta (合) カモ (netta, nessa カモ Gk。The Key to Scientific Names)
- 種小名:rufina (adj) 赤みがかった (rufinus)
- 英名:Red-crested Pochard
- 備考:
netta は起源のギリシャ語に従えば長母音で "ネーッタ"。
rufina は u が長母音でアクセントもここにある (ルーフィナ)。
カザフスタン、モンゴルなど中央アジアを中心に分布する種。日本でも定常的に迷行例があるが、ヨーロッパにも多数の迷行例がある。単形種。
Netta 属、Aythya 属のカモ類のロシア名は nyrok (潜るもの)。
10 秒以内の短く浅い潜水で Aythya 属よりも水中生活に適していない。嘴の形もむしろ淡水ガモに近い。Aythya 属と淡水ガモの中間的な性質を持つ (コンサイス鳥名事典)。
最新の分子系統研究では Netta 属は単系統でない可能性があり、アカハシハジロ (タイプ種) のみが Netta 属に残る可能性がある (#オカヨシガモの備考参照)。
アカハシハジロの祖先系統にあたるバライロガモ Rhodonessa caryophyllacea Pink-headed Duck は IUCN CR 種。かつてはインド、バングラデシュ、ミャンマーに生息していたが 1950 年代より目撃がなく絶滅した可能性がある。
可能性のある地域で調査されているが確認されていない。証拠不十分な目撃事例がないわけではない。
最後の写真は 1925 年ごろに撮られたもの (wikipedia 英語版より)。
人為由来で絶滅した可能性が考えられるが、Ericson et al. (2017) A genomic perspective of the pink-headed duck Rhodonessa caryophyllacea suggests a long history of low effective population size
によれば 280 万年前に分岐し、少なくとも過去 10 万年は実効個体数は低いままであったことが判明した。生態的理由などで個体数を増やすことができなかった可能性があるが詳細は不明。
もともとまれな種であったが人為的影響で簡単に滅んでしまったのだろうか。
ちなみにアカハシハジロはかつては数が減少しつつあると考えられていたが、近年はヨーロッパの目撃例が増えており (参考: Red-crested Pochard BTO。英国では著明に増加。飼育個体由来も考えられる)、数はむしろ増えていると推定されている。
ヨーロッパ繁殖地でも見つかりにくい種だそうで、日本の最近の目撃例の増加は個体数が増えたのか観察者が増えた効果なのか判断が難しいかも。
-
オオホシハジロ
- 学名:Aythya valisineria (アユテュア ウァルリスィネリア) セキショウモを好む海鳥
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:valisineria (合) セキショウモの (海草 vallisneria セキショウモの属名)
- 英名:Canvasback
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
valisineria の発音はよくわからないがすべて短母音とすると -ne- がアクセント音節で、"ウァルリスィネリア" となる。
北米の種で単形種。
-
アメリカホシハジロ
- 学名:Aythya americana (アユテュア アメリカーナ) アメリカの海鳥
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:americana (adj) アメリカの (-anus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Redhead
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
americana は -ca- の a が長母音でアクセントもある (アメリカーナ)。
北米の種で単形種。
部分的な托卵 (任意托卵) が知られている。アニマ 1992年6月号 pp. 78-81 にこの種の研究の第一人者の Sorenson の解説の翻訳記事がある (#カッコウの備考 [托卵鳥の同種認識] も参照)。
托卵を行う/自身で育てる両方の戦略を持つ。1988 年の日照りの年は水位が低く、巣が見えやすくなってしまうためにほとんどのメスは托卵を行ったとのこと。抱卵中はメスにとっても危険なため、変わりやすい大草原の環境に適応した行動かとのこと。
-
ホシハジロ
-
アカハジロ
- 学名:Aythya baeri (アユテュア バエーリ) ベールの海鳥
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:baeri (属) baer の (プロイセンの発生生物学者でシベリアを探検した Karl Ernst von Baer Edler von Huthorn に由来。反ダーウィン派だったとのこと。ドイツ語でもウムラウトなしでそのまま Baer と綴るようだが、ロシア名も別にあってベールと読まれていたことがわかる。日本語読みはそれに従った)
- 英名:Baer's Pochard
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
baeri は e を長母音として発音するか次第だが、"バエリ" または "バエーリ"。後者の方が原音に近い可能性があるためこちらを採用した。
東アジア地域のみで繁殖する希少なカモ。単形種。メジロガモと同種と考えられたこともあった。アカハジロ、メジロガモを含む目の白い潜水ガモに亜属 Nyroca (メジロガモの学名語源参照)が提唱されたこともあった。Aythya 属、Betta 属などを Aythyini 族とまとめることは受け入れられているが、アカハジロ、メジロガモの分子遺伝学的研究はまだ不十分である (wikipedia 記述の段階)。
現在ではゲノムアセンブリが報告されている [Zhang et al. (2023) Chromosome-level genome assembly of the critically endangered Baer’s pochard (Aythya baeri)。この論文の段階で個体数は 150 と 700 の間と見積もられている]。
メジロガモについても 2021 年段階でミトコンドリアゲノムが解読されており、分子系統解析が得られるのは時間の問題と思われる。
かつてはロシア南東部と中国東北部でも繁殖していて日本を含む南へ渡っていたとされる。現在は中国の北部から中部で留鳥。現在では世界の成鳥の個体数は 1000 羽を割っている可能があり、さらに減少中と考えられている。2010 年以降北京より北側では見られなくなったと報告されている。
繁殖個体数が越冬個体数よりも少ないため、未知の繁殖地があるとされており、中国で従来記載の繁殖地から遠く離れた新しい繁殖地の発見も報告されている。2010-2011 年以降中国本土以外での定常的な越冬個体群はなく、迷鳥となっている。中国本土の越冬地でも数が大きく減少している。
IUCN 3.1で CR 種。East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) による アカハジロタスクフォース が作られた。2021 年中国の国家一級保護種に指定された (New protection for Baer’s Pochard in China)。
2022 年に北京動物園で飼育個体群が確立され、将来の野生再導入計画がある [Yong et al. (2022) The first captive population of Baer's pochard in China was established] (wikipedia 英語版)。
なお中国の国家保護種は 国家重点保護野生動物目録 (wikipedia 中国語版) で見ることができる (これらを見る時には学名のありがたみがわかる)。
この時に新たに指定された鳥類については China updates list of species with special protection に解説がある。
1989 年に「国家級保護動物」のリストが出されてから2種追加されただけだったそうである。2021 年の改訂が 32 年ぶり初めての大幅な見直しとなった。従来は大型種のように目立つものが対象だったが、研究が進んで (中国内の動物学者も圧倒的に増えた)、科学ベースのリストになり、経済的価値から生態系や生息地の保護へのシフトを明確にしたとのこと。
今後は5年程度で見直すことにした (A new hope for China’s endangered animals)。
シマアオジもこの時に登場。
又野 (2019) アカハジロがヒシの実を食べる行動 (大阪の飛来数記録の表もあり)。
この種の音声記録は公表されているものでは世界にまだ1例もない (#コウライアイサの備考参照) が、おそらく飼育下で記録されているものと思われる。
-
メジロガモ
- 学名:Aythya nyroca (アユテュア ニュローカ) 潜るカモ
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:nyroca (外) nyrok 潜る者 (< nyryat' 潜る) 露
- 英名:Ferruginous Duck
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
nyroca は任意の読み方が可能だが、原音を活かすならば "ニュローカ" と伸ばしてここにアクセントを置くとよい。
ラテン語化 (おそらく女性形を意識) して語尾が変えられているが、ロシア語で nyroka の綴りの場合はアクセントが移動して o は短く、語末の -a がアクセントになる。
原記載 は原形 (主格) を採用している。女性名詞の当時の属 Anas に置くために -a を追加したものと思われる。
Aythya 属も女性名詞のため一見わからないが、もし男性名詞の属に変わっていたら語尾の不整合を感じたかも知れない。
和名は外見からかも知れないが、英語別名に White-eyed Pochard があり英名を訳したものかも知れない。
東欧からロシア西部、中央アジア、中国西部、アフリカ北部などに主に分布する。単形種。日本で記録される数はアカハジロと同程度であるが、世界的個体数はメジロガモの方がずっと多く、IUCN 3.1 で NT 種。#アカハジロの備考も参照。
-
クビワキンクロ
- 学名:Aythya collaris (アユテュア コルラーリス) 首輪のある海鳥
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:collaris (属) 首輪のある (collare -is (n) 首輪)
- 英名:Ring-necked Duck
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
collaris は中央が長母音でアクセントがある (コルラーリス)。
記載時学名 Anas collaris Donovan, 1809 (記載) で英名 Collard Duck、記述も neck encircled with a sub-ferruginous ring および a pretty and very distinct collar of deep ferruginous とあってこの collaris は "首輪のある" で問題ない (#イワヒバリの備考参照)。
和名通りの特徴を探してよい。
北米の種で単形種。かつて東京都不忍池で 1984 年から 1994 年に 11 年連続の飛来記録があり、(少なくとも関東在住の古参バーダーには) あまり珍しくなくなった印象を受けるが飛来はやはりまれ (当時の不忍池はカモ類の餌付けが行われており、一面カモだらけ、クビワキンクロも足元にいた光景もあり双眼鏡すら不要で全く珍しさを感じさせなかった。さらにコスズガモまで飛来していた。Birder 誌にも当時のいろいろな逸話が掲載されていた)。
日本鳥学会誌にも他所の記録論文が複数出ている。
-
キンクロハジロ
- 学名:Aythya fuligula (アユテュア フーリーグラ) スス色の喉の海鳥
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:fuligula (f) スス色の喉の (fuligo (f) スス gula 喉)
- 英名:Tufted Duck
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
fuligula は fuligo (フーリーゴ) すす と長母音が並ぶ (#カワビタキも参照)。gula は短母音。i にアクセントがあり "フーリーグラ"。
母音を伸ばさない場合もアクセントはこの位置。
属名の由来の aithuia はアリストテレス他の記載した未同定の海鳥。ミズナギドリ、ウ、カモ、ウミスズメなどの解釈がある。ギリシャ神話で水鳥に変えられた Cygnus の母親に Thyr (Thryie) があり関連する可能性がある (The Key to Scientific Names)。ユーラシアに広く分布する単形種。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 60 では "キン" は "襟" の解釈もあることが示されていた。オスの首の艷やかな黒さを示したもの。着目点ではこちらの解釈の方が種小名のラテン語とよく合うかも。「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) では重訂本草綱目啓蒙 (1847) できんくろがも一名きんくろ羽白の用例が示されていて、この時点では漢字が使われていなかった。
-
スズガモ
- 学名:Aythya marila (アユテュア マリラ) 少し黒い海鳥
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:marila (合) 少し黒い (mauro 黒い Gk、-illa (指小辞) 小さい)、charcoal embers
- 英名:Scaup, IOC: Greater Scaup
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
marila はすべて短母音のみと考えられ "マリラ"。
2亜種あり、日本で記録されるものは従来基亜種 marila とされていたが、「一部学名の変更の見込みについて」(2023年11月28日) にて nearctica (新北区の; 北米を指す) に変更された。
Howard and Moore では現在この分類になっている。
Marchowski and Leitner (2019) Conservation implications of extraordinary Greater Scaup (Aythya marila) concentrations in the Odra Estuary, Poland
の解説によれば世界でフライウエイに応じたいくつかのグループがあり、(1) A. m. nearctica 北米のグループで4つのフライウエイ、(2) A. m. nearctica 東アジアのグループ、(3) A. m. marila アジア北西部とヨーローパ北東部で繁殖しカスピ海や黒海周辺で越冬、(4) A. m. marila ヨーローパ北東部で繁殖し北海やバルト海周辺で越冬、
の4つに分けられるとのこと。日本の個体群は (2) にあたるようである。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" でもこの亜種となっている。
東アジアの個体群はかつて中間にあたると考えられて mariloides (marila スズガモ -oides に似た Gk) が使われたことがあったがこれは本来コスズガモに与えられた学名で無効とのこと (wikipedia 英語版)。
文献: Banks (1986) Subspecies of the Greater Scaup and their names (それ以前の分類概念経緯も記載されている)。
この文献では東アジアの個体をヨーロッパのものと区別できないためユーラシアをまとめた marila としていた。
mariloides (学名の正統性はともかく) を認める立場であれば東アジアの個体群はこれに属するが、Avibase でも nearctica のシノニムとして扱っている。Howard and Moore は 2nd edition まで mariloides を認めていた。
コンサイス鳥名辞典では北ヨーローパから西シベリア北部をオオスズガモ A. m. marila、東シベリア、アラスカ、カナダ北部を A. m. mariloides としていた。
今後の基亜種の名前はオオスズガモかも知れない。
他に Lesser Scaup (コスズガモ) が存在するため英名は Greater Scaup が望ましい。
scaup の語源はスコットランド語で貝類の繁殖場所 (shellfish bed) のことか、あるいは鳴き声からとのこと (wikipedia 英語版より)。
OED によれば scaup-duck が 1676 年にすでに使われており、scaup 単独の用例は 1798 年に見られるとのこと。こちらもスコットランド語 scalp (意味は貝類の繁殖場所) 由来と想定している。
ロシア語ではスズガモ類は chernet' で「黒いやつ」ぐらいの意味だろう。ドイツ語では Bergente < Berg (山) Ente (カモ) で生態をあまり反映していない?
北米での別名は Bluebill (北米に生息するコスズガモの Little Bluebill に対応)。
Marchowski and Leitner (2019) によれば基亜種は近年減少傾向が目立つとのこと。
wikipedia 英語版によれば 1980 年代から減少が始まったとのこと。
記載時学名 Anas Marila Linnaeus, 1761 (原記載) 基産地 Lapland (ラプランド)。
Fuligula 属が使われていたことがあり、これは Swainson (1837) が用いた属で Gray (1855) がホシハジロがタイプ種としたもの、
Stephens (1824) がキンクロハジロの種小名を属名に昇格したものがあった。後者の方が早いが前者がスズガモ類を指して使われていたよう (#コスズガモ参照)。
Aythya Boie, 1822 が早いためにこちらが使われるようになった (The Key to Scientific Names の情報より)。
実は Fuligula 属の方が多く使われており、Aythya 属の記載が判明したのはかなり遅い時期になったものと想像できる。
種小名から属名への昇格に伴って名付けられた Fuligula cristata Stephens, 1824 (参考) の学名もあった (冠のあるスズガモの意味)。(#ノスリの備考参照)。
Fuligula vulgaris Hodgson, 1844 (参考) の用例 (ネパール) があったが単に普通のスズガモの意味で属を代表する学名を意図したものではなさそう。
-
コスズガモ
- 学名:Aythya affinis (アユテュア アフフィーニス) スズガモに似た海鳥
- 属名:aythya (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:affinis (adj) 隣の、姻戚関係の。この場合はスズガモに似たの意味。
- 英名:Lesser Scaup
- 備考:
aythya は#ホシハジロ参照。
affinis は -fi- の i が長母音でアクセントもここにある (アフフィーニス)。ad + finis が語源。-ff- を単音で、i を短母音にする英語読みでも実用上問題ないだろう。
北米の種で単形種。
英名の別名 Little Bluebill, Broadbill。
記載時学名 Fuligula affinis Eyton, 1838 (原記載) 基産地 North America (北米)。スズガモに似ているゆえの命名由来はここに記されている。
-
コケワタガモ
- 学名:Polysticta stelleri (ポリュスティクタ ステルレリ) シュテラーの多くの斑のある鳥
- 属名:polysticta (合) 多くの斑のある (poly- (接頭辞) 多くの stikos 斑 Gk、-tus (接尾辞) 〜を備えている)
- 種小名:stelleri (属) ステッラーの (ドイツの博物学者 Georg Wilhelm Steller に由来)
- 英名:Steller's Eider
- 備考:
polysticta は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-stic- と区切るならば "ポリュスティクタ" (#ハギマシコの考察参照)。
stelleri は人名由来だがラテン語風に読んで stel-le-ri と区切れば "ステルレリ" となる。"レ" を伸ばすなど原語の音を優先するかは好み次第でよいだろう。
極北の種で単形属で単形種。英語 eider の語源はアイスランド語 aedr に由来すると考えられるがその語源は不明。
-
ケワタガモ
- 学名:Somateria spectabilis (ソーマテリア スペクタービリス) 美しい羊毛の体の鳥
- 属名:somateria (合) 羊毛の体 (somatos 体 erion 羊毛 Gk)
- 種小名:spectabilis (adj) 美しい、見える
- 英名:King Eider
- 備考:
somateria は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は somatos の冒頭が長母音。アクセントは -te- の音節と考えられる (ソーマテリア)。このギリシャ語由来の多くの単語は so- を長音としているので (英語の -some で終わる生物用語) 同様に伸ばすのが適切と思える。
spectabilis は a が長母音でアクセントもここにある (スペクタービリス)。
AviList v2025 - errors, typos で AviList の属名記載の正当性が順次検証されている。
Somateria のタイプ種記載は "Somateria Mollissima (Cuthbert's Eider)" や "Somateria spectabilis. King Eider" (Leach 1819) 由来となっているが、属名は 1818 年にすでに使われ、1819 年の文献に現れる。ここではタイプ種記載は Anas molissima Linnaeus 1758 by monotypy であるべきと指摘されている。この場合タイプ種はケワタガモからホンケワタガモに変わる。
極北の種で単形種。この属ではヨーロッパ等に比較的普通のホンケワタガモ Somateria mollissima (英名 Common Eider) が世界的には有名。ケワタガモの名前はケワタガモの産座の綿羽が良質の保温材の採取対象とされてきたことによる。
コンサイス鳥名事典によれば執筆当時も商業利用されていたそうである。同書によれば別名アカハナケワタガモがあるとのこと。
英語 eider は OED によれば 1744 年に用例があり、究極的にはアイスランド語 aedar 由来で、スウェーデン語の古い形 eider、デンマーク語 eder なども同様。現在の英語の綴りはおそらく Von Troil が用いたものに由来するとのこと。
-
シノリガモ
- 学名:Histrionicus histrionicus (ヒストゥリオーニクス ヒストゥリオーニクス) 役者のような鳥
- 属名:histrionicus (adj) 役者のような (histrio -onis (m) 役者 -icus (接尾辞) 〜に関連する)
- 種小名:histrionicus (トートニム)
- 英名:Harlequin Duck (道化師の意味でフランス語由来)
- 備考:
histrionicus は o が長母音でアクセントもここにある (ヒストゥリオーニクス)。histrio の最後が長音。
記載時学名 Anas histrionica Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 America, restricted type locality, Newfoundland, ex Edwards (Edwards がニューファンドランドに限定)。
Histrionicus 属は Lesson (1828) が導入したもの。記載。亜属の扱い。Cuvier を引いているが Cuvier は Garrot とフランス語名で表記しただけのため学名と認められなかったよう。1種のみを属にしたため当時は種小名を特に与えていなかった。
現代のフランス語では Garrot はキンクロハジロ類を指すとのこと (wiktionary)。
Histrionicus 属の提唱以前は Clangula 属とされたことがあった。Clangula torquata Brehm , 1855 (参考)。"首飾りのある Clangula" の意味で属変更に伴う一種の改名。
Hartert (1910-1922) p. 1361 に情報あり、当時のドイツ語名 Kragenenete も Clangula の意味を反映している。
別の属名があり、Cosmonessa Kaup, 1829。ドイツ語属名 Schmuckente で Schmuck 飾り Ente カモ。-nessa は -netta を意図したものと考えられる (The Key to Scientific Names, Hertert)。この Cosmo- はよく想像する宇宙の cosmos ではなく、別語義の花のコスモスにつながる方 (語源は同じ)。英語 cosmetic も同語源だが直接 cosmos から派生したものではない (wiktionary)。
ほぼ同時代に複数の属名が提唱されていたが Lesson (1828) のものが有効で一番早いと認定された模様。
OED によれば英名の用例は 1772 年 Foster によるもので、時期的には学名から採用されたと想像できる。
AviList v2025 - errors, typos で AviList の属名記載の正当性が順次検証されている。
これによれば AviList のタイプ種記述 type by original designation and tautonymy は正しくなく、同時にこの条件を満たすことはないので type by original designation が正しいとのこと。
単形属で単形種。日本でも北海道と東北地方山地渓流で繁殖する。
wikipedia 日本語版には「太平洋岸繁殖個体群を H. h. pacific として分割する説もあったが、有力ではない」とあるが pacificus (太平洋の) が正しい。
記載時学名 Histrionicus histrionicus pacificus Brooks, 1915 基産地 Cape Shipunski, Kamchatka (Avibase による)。Clements 2017 まで、Howard and Moore 2nd edition などで亜種扱い。現在の世界の主要リストではシノニムとされる。
Scribner et al. (2024) A phylogeographical study of the discontinuously distributed Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus)
に氷河期の大西洋のレフージアから各地の個体群に広がって太平洋由来の個体群と二次的に接触した描像が得られた。
ロシアのハバロフスク地方のブレインスキー保護区で放棄された卵から育てて最終的に野外に放った事例が紹介されている (#ハチクマの備考も参照)。シノリガモの黒子ちゃん - またの名を 異類の中の同類、同類の中の異類 に翻訳を掲載。
和名の由来はあまりよくわからないが、"晨鳧" は中国語では野鴨 (種類不明) を指して、"後漢書" (卷六○上 馬融傳) に現れるとのこと。遊雉群驚、晨鳧輩作 (参考: 晨鳧)。
関連する用例をみておくと晨烏は古代神話で太陽に住むと考えられたカラスのこと。鳥関係ではこれのみが他に見つかった。太陽ならば黒点、シノリガモならば斑点を表したものだろうか。
英名に使われる Harlequin はセキセイインコの品種名ハルクインにも使われ、週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 98 V (宇田川) によれば雑色の、色紋の意味。また原種の黒い班が翼に残っている (コンサイス鳥名事典) 説明があった。こちらも斑点を特徴としている。
Recessive Pied budgerigar の wikipedia 英語版によれば the Danish Pied variety, aka Harlequin で劣性突然変異によるものとのこと。
シノリガモは流れの速い河川のそばに営巣し、まったく系統の異なるカワガラス類と習性や隠蔽色が似ているとのこと: 参考 Gray Camouflage: Dippers and Female Harlequin Ducks (Bob Sundstrom, BirdNote 2019)。
ここで扱われている種類はメキシコカワガラス Cinclus mexicanus American Dipper でヨーロッパのムナジロカワガラス Cinclus cinclus White-throated Dipper に対応するとされているが、日本のカワガラスも同様に考えてよいだろう。
シノリガモやカワガラス類の生息しない南米ではヤマガモ Merganetta armata Torrent Duck が同じニッチを占めるとのこと。日本の種ではツクシガモの系統が比較的近い。シノリガモはアイサ類に近い系統で異なっている。
ニュージーランドのアオヤマガモ Hymenolaimus malacorhynchos Blue Duck も同様。古く分岐したものだがアカハシハジロや Aythya 属などの潜水ガモの祖先に相当する系統と考えられている。
高地で潜水するヤマガモの生理学的適応については例えば Dawson et al. (2016)
Mitochondrial physiology in the skeletal and cardiac muscles is altered in torrent ducks, Merganetta armata, from high altitudes in the Andes。
雑誌 "Birder's World" 1989.10 pp. 60-61 に Robert W. Storer (#カワウ備考の [ガラパゴスコバネウの進化] 参照) による "Torrent Duck" の記事がある。
クラッチサイズは4と非常に小さく産卵間隔は1週間とのこと。コガモに比べてずっと発育した状態で誕生するが、これは早成性のためひなの羽毛が未発達であれば急流に対応できないと説明されている。
-
アラナミキンクロ
- 学名:Melanitta perspicillata (メラニッタ ペルスピキルラータ) 眼鏡をかけた黒いカモ
- 属名:melanitta (合) 黒いカモ (melan- (接頭辞) 黒い netta カモ Gk)
- 種小名:perspicillata (adj) 眼鏡をかけた (perspicillum 眼鏡 -ata (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Surf Scoter
- 備考:
melanitta は#ビロードキンクロ参照。
perspicillata は perspicillum は短母音のみ (ガリレオが 1610 年に作った単語とのこと)。
-ata は所有で冒頭が長母音でアクセントもある (ペルスピキルラータ)。
主に北米の単形種。
-
ビロードキンクロ (アメリカビロードキンクロ が分離された。ビロードキンクロの学名も変わった)
- 第8版学名:Melanitta stejnegeri (メラニッタ ステイネゲリ) シュタイネゲルのカモ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Melanitta fusca (メラニッタ フスカ) 黒ずんだカモ
- 第7版亜種学名:Melanitta fusca stejnegeri (メラニッタ フスカ ステイネゲリ) シュタイネゲルの黒ずんだカモ (代表的亜種。他亜種あり)
- 属名:melanitta (合) 黒いカモ (melan- (接頭辞) 黒い netta カモ Gk)
- 第8版種小名:stejnegeri ノルウエーの動物学者 Leonhard Hess Stejneger の
- 第7版種小名:fusca (adj) 黒ずんだ (fuscus)
- 第7版亜種小名:stejnegeri ノルウエーの動物学者 Leonhard Hess Stejneger の
- 英名:(White-winged Scoter アメリカビロードキンクロ), IOC: Stejneger's Scoter
- 備考:
melanitta は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は netta ならば冒頭が長母音で同様に伸ばすかも知れない。-nit- にアクセントがあることは疑いないので "メラニッタ" としておく。"メラニータ" でもおそらく構わない。
stejnegeri は規則通りであれば "ステイネゲリ" のアクセントになる。-ge- を伸ばせばこちらがアクセントとなる (ステイネゲーリ)。
名前のアクセントは冒頭らしくどちらにしてもアクセント位置は変わる。ラテン語読みと理解することにする。原語に合わせた読み方でもおそらく実用上問題ない。
英名の scoter は語源不明とのこと (wiktionary)。OED によれば 1673 年に用例があり、当時のラテン名 Anas niger (黒いカモ) を指していた。語源は不明としているが、scout (1600 年ごろの先住地方名でさまざまな海鳥を総称的に指していた) 由来が考えやすいとのこと。
黒いカモとして soot + -er やドイツ語の古い名称 Russente (スズガモを指す) 由来説が取り上げられることがあるが、英語の名称と関連している直接の証拠はないとのこと。
分割のため第7版学名は代表的亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Melanitta stejnegeri となる。ノルウェー生まれの鳥類学者 Leonhard Hess Stejneger にちなむ。
Steineger 家だったが、1870 年ごろより Stejneger の綴りを用い生涯使ったとのこと (wikipedia 英語版)。英語読みでは "スタジンガー" や "スタジネガー" のような発音が多い。
シュと読むのはドイツ系の名字であるためか (Stein 石)。現代のノルウエー語でも同様らしい。
ちなみにロシア語でもシュと表記しており、実際にどのように読まれていたかは問わず慣用としてシュタイネゲルの名前を残しておく。
かつては Melanitta deglandi (フランスの鳥類学者 Come-Damien Degland にちなむ; こちらの英名は White-winged Scoter アメリカビロードキンクロ) と同種と考えられていた。
アメリカビロードキンクロは日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で含まれた。いずれも単形種となる。IOC 9.2, Clements 2019 以降別種。
AviList v2025 - errors, typos で AviList の属名記載の正当性が順次検証されている。
AviList では Melanitta は Anas fusca [Linnaeus, 1758]; type by subsequent designation (Eyton, 1838, Monograph on the Anatidae, p. 52) とのこと。
この文献を用いる範囲では正しい記述だが、1822 年の記述がある。しかしこの文献が出版された証拠はないとのこと。どちらを採用してもタイプ種は同じとのこと。
ビロードキンクロの新学名に対応する英名は Stejneger's Scoter または Siberian Scoter となる (後者は AOU の名称)。
現在の分類では Melanitta fusca はユーラシア西部の種類となり、英名は Velvet Scoter (ヨーロッパビロードキンクロ)。和名はこの種の英名に対応していて現在の分類で正確に使おうとすると大変ややこしい。ただ外国人バーダーも古い時代の velvet の名を知っていた人もあったためか、この英名でも通じた。
越冬時は海岸で観察されるため繁殖地も海に近いと考えそうだが、大陸奥深く内陸で繁殖する。ビロードキンクロはエニセイ川以東に広く分布。モンゴルでも繁殖個体群が観察される。アメリカビロードキンクロも同様でアラスカからカナダ西部の内陸で繁殖する。
Cadiz et al. (2024) Demographic History and Inbreeding in Two Declining Sea Duck Species Inferred From Whole-Genome Sequence Data
の全ゲノム研究によれば、コオリガモは過去の実効個体群サイズが比較的安定していたが Velvet Scoter (ヨーロッパビロードキンクロ) は減少傾向が見られる。分布範囲が狭いため氷河期に生息域がより縮小した可能性がある。両種とも過去数千年に実効個体群サイズの減少が認められ人為的圧力となっている可能性がある。
2種の間無視できないレベルの交雑があり、個体数減少に伴って近年生じたよりは過去から存在していたと考えられる。さらなる個体数減少があれば交雑による遺伝的劣化の恐れも考えられる。
-
クロガモ
- 学名:Melanitta americana (メラニッタ アメリカーナ) アメリカの黒いカモ
- 属名:melanitta (合) 黒いカモ (melan- (接頭辞) 黒い netta カモ Gk)
- 種小名:americana (adj) アメリカの (-anus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Black Scoter
- 備考:
melanitta は#ビロードキンクロ参照。
americana は1つめの a が長母音でアクセントもここにある (アメリカーナ)。
北米からユーラシア北東部に分布。ビロードキンクロよりは沿岸に近い場所で繁殖する。単形種。
近縁種にヨーロッパクロガモ Melanitta nigra 英名 Common Scoter があり、かつては同種とされていた。
ロシア北極圏では両種が繁殖するがシベリア北部ではクロガモの方が多いらしい。クロガモの方が東寄りでヨーロッパクロガモは主にヨーロッパで越冬する。
サハリンでもクロガモの繁殖が知られている: Vshivtsev (1979初出、2012再掲) Nesting of the black scoter Melanitta nigra on the Sakhalin Island (pp. 2661-2665)。
-
コオリガモ
- 学名:Clangula hyemalis (クラングラ ヒュエマーリス) 冬の声の響く鳥
- 属名:clangula (f) 声が響く (clangere 反響する -ula (指小辞) 小さい)
- 種小名:hyemalis (合) 冬の (hiemalis (adj) 冬の hiems (f) 冬)
- 英名:Long-tailed Duck
- 備考:
clangula は -ula の指小辞発音に従えば長母音が現れない (#キクイタダキ学名などと同様)。規則によれば "クラングラ" のアクセントになる。
hyemalis は a が長母音でここにアクセントがある (ヒュエマーリス)。
極北に広く分布する単形種。越冬中の群れは特徴的な歌うような声を出し、遠くからも聞こえるという The Key to Scientific Names の注釈に沿った訳とした。
属名とホオジロガモの種小名の関係については#ホオジロガモの備考参照。どちらも音が由来と考えられるがそれぞれ独立に付けられたもので意味は同じとは限らない。
Karwinkel et al. (2025) Individual Variation in Migration and Wintering Patterns of Long-Tailed Ducks Clangula hyemalis From a Population in Decline
バルト海はかつて主要な越冬地だったが 1990 年代から激減している。データロガーを付けて追跡した結果個体レベルでは越冬域の再現性がよく、越冬地が北に移動したと考えるよりも個体数が減少したことを表しているのではとの推測。
-
ヒメハジロ
- 学名:Bucephala albeola (ブーケパラ アルベオラ) 少し白い大きな頭の鳥
- 属名:bucephala (合) 牛の頭 (bous 牡牛 kephali 頭 Gk)
- 種小名:albeola (adj) 少し白い (albus (adj) 白い -ola (指小辞) 小さい)
- 英名:Bufflehead
- 備考:
bucephala は#ホオジロガモ参照。
albeola は -ola の指小辞発音を考慮すると長母音は生じないと思われる (アルベオラ)。
北米に分布する単形種。英名の由来については#ホオジロガモの備考参照。
-
ホオジロガモ
- 学名:Bucephala clangula (ブーケパラ クラングラ) 羽音の響く大きな頭の鳥
- 属名:bucephala (合) 牛の頭 (bous 牡牛 kephali 頭 Gk)
- 種小名:clangula (f) 声が響く (clangere 反響する -ula (指小辞) 小さい)
- 英名:Common Goldeneye
- 備考:
bucephala は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語の bous の長音を採用すれば "ブーケパラ" (#モズ参照)。
clangula は#コオリガモ参照。
種小名の和訳は wikipedia 日本語版では「やかましく騒ぐ」となっている。
ホオジロガモの羽音はよく響いて独特なのでそれを意味する可能性 (例えば日本語のスズガモの語源にように) を考えた。やはり羽音から "whistler" と呼ばれることを知った (羽音を whistling sound と呼ぶ)。
狩猟用語でカモの識別に役立つとのこと。Common Goldeneye。ディスプレイの声よりは羽音が目立つ気がするので、種小名の語源はおそらくこちらではないだろうか。「羽音の響く」と訳してみた。
clangere に関連する学名は #コオリガモ、#カラフトワシ (可能性あり) も参照。
#オオジシギ備考の [タシギ類のドラミング] で紹介の Clark and Prum (2015) にも含まれている。
なお英名で whistling duck が付くものも別に存在する (リュウキュウガモなど)。こちらは鳴き声由来と説明がある (wikipedia 英語版から)。
"wing whistle" の用語も用いられることがあるが、上記 Clark and Prum (2015) によればあまり適切でない用語とのこと。
wikipedia 日本語版の「属名 Bucephala はアレクサンドロス3世 (大王) の馬の名前からつけられたもの」については当初出典を見つけられなかったのだが、
Bucephalus Bucephalus or Bucephalas に馬の記述があり、牛の頭 (bous 牡牛 kephali 頭 Gk) の由来はおそらく同じよう。
属名の原記載には意味は特に現れないが、
この Baird (1858) は (同属でタイプ種の) ヒメハジロの英名について "The name buffle head is a corruption of buffalo head, under which name it is mentioned by Bartram, in 1791" と説明しているので「牛の頭」でよさそう。そのままギリシャ語由来の属名としたものだろう。不釣り合いに頭が大きいの意味と OED には説明がある。
Why are they called Bufflehead? (Birdful) にも英名由来の考察がある。Baird の属名の意味は上記でよいと思われるが、Bartram (1791) ですでに使われている英名なので、英名は起源がさらに古く議論の余地が残るのだろう。
Baird (1858) では "whistle wing" がホオジロガモの別名になっているので、種小名に使われる clangula はやはり翼の音と解釈するのが適切そう。
種小名に clangula が使われているのに、なぜ Clangula (コオリガモ) 属に含まれないのか疑問を持たれるだろうが、Clangula 属は Anas glacialis で最初に使われたためこのグループの名称には使えないとの説明が Baird (1858) にある。
Baird (1858) の時点では Clangula glacialis Boie, 1822 に対応していて、これはコオリガモを指していたが Clangula glacialis Leach, 1819 の属の用例が見つかり (コオリガモがタイプ種になる) こちらが採用された。
種の記載そのものは Linnaeus が最初に行ったため学名は Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) となる。
ここで Boie の用いた種小名の glacialis は現在 Anas 属でハイイロガモ Grey Teal に使われている。属が違うので衝突しないのだろうが非常にややこしい。Anas glacialis は現在はハイイロガモを指すが、コオリガモのシノニムにも挙がっている。古い文献を読む時にはよほど注意しないと間違えそう。
ホオジロガモは Anas Clangula Linnaeus, 1758 と記載されたもの (原記載)。この中には Clangula. Gesn. av. 119 とあるので、Clangula はすでに1語の学名として使われていたもので Linnaeus はこれを利用したよう。
Linnaeus のこの種小名を属名に昇格して新たに種小名を与えた (#ノスリの備考参照) 例もあった Clangula chrysopthalmos Stephens, 1824 (参考) がより遅い時代で用いられなかった。
属名の Clangula と種小名の clangula は別々に付けられたものでそもそも直接の関係はなかった (Leach も単純に挙げているだけで他種はリストされていない)。カモ類を分類する過程で整理された結果、一見矛盾する現在の学名となった。
まとめると以下のようになる。太字が採用されたもの。
| ホオジロガモ | コオリガモ | ヒメハジロ |
| Linnaeus (1758) | Anas Clangula
= Anas bucephala
= Anas Glaucion | Anas hyemalis | Anas Albeola |
| Leach (1819) | | Clangula glacialis | |
| Baird (1858) | Bucephala americana
(亜種アメリカホオジロガモ) | | Bucephala albeola
(タイプ種) |
英名の Goldeneye の由来は自明だが、OED によると用例は 1622 年初出とのこと。キンクロハジロなど他の種を指して地域的に使われたこともあるが現在では廃れている。
2亜種あり日本のものは基亜種 clangula とされる。もう1亜種 americana アメリカホオジロガモは北米に分布。
-
ミコアイサ
- 学名:Mergellus albellus (メルゲルルス アルベルルス) 白くてかわいい小さなアイサ
- 属名:mergellus (m) 小さいアイサ (mergus (m) 少し沈んで泳ぐ海鳥 -ellus (指小辞) 小さい)
- 種小名:albellus (adj) 白くてかわいい (albus (adj) 白い bellus (adj) かわいい)
- 英名:Smew
- 備考:
mergellus は長母音を持たないと考えられ、-gel- がアクセント音節となる (メルゲルルス)。
albellus は長母音を持たないと考えられ、-bel- がアクセント音節となる (アルベルルス)。
Mergellus 属は Selby (1840) がミコアイサのみを指して設けたもの。Mergus の小型版の意味だったが系統的にも異なっており現在も使われる属名となっている。
英名の smew は OED によれば 1674 年の用例が最初とのこと。語源は不明とのこと。ミコアイサを指した smee (1668 年初出) との関係も考えられ、こちらは smeath (1622 年初出。これもアイサ類を指す) の変形とも考えられるとのこと。現代のオランダ語など類似語の smeente などが残っているが関連は不明とのこと。
nun の名称の方が先に知られていて 1666 年 Merret によるラテン語記述に現れる。Ray (1673) がこの記述をもとに nun と呼ぶこととし、ドイツ語では (英訳して) White Nun と呼ばれているとの記載がある。ドイツ語原語では weisse Nonne。white nun の由来はドイツ語だった。
ユーラシアに広く分布する単形種。属名の由来は#カワアイサの備考も参照。
中国名白秋沙鴨で秋沙 (アイサ) の部分は和名に由来とのこと [福井・チャン (2003) Birder 17(8): 68-69]。
和名のミコアイサの語源はオスの羽衣が巫女の白装束のように見えることに由来すると wikipedia 日本語版から (出典: 安部直哉 「山溪名前図鑑 野鳥の名前」、山と溪谷社、2008年)。
気になったのは英語別名に White Nun があること。nun = 修道女 と発想が非常に近い。これは日本語・英語で独立に作られた名称であろうか、あるいは和名成立に外国語の影響はあっただろうか。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば "みこあいさ" の名称は重訂本草綱目啓蒙 (1847) に現れるとのこと。他にうみあいさ、黒あいさ一名すずがもなどいくつかあるが、うばあいさ、うあいさ、どうながあいさなど現在の和名と対応しないものも多い。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではアイサ類3種は現在の名前で登場している。
重訂本草綱目啓蒙 (1847) の時期とそれほど大きく離れていないのでこの間にアイサ類の名称が整理され、カワアイサはうみあいさに対応して付けられた想像ができる。
"アイサ" と付く日本産種類の中でミコアイサのみが別属であるが、これはアイサ類の中で最も早く分岐した系統で、アイサ類の現代的な分子系統 (ただし mtDNA のみ) は以下のようになる。
この部分は最後3種の順序に不定性があるが他の部分は系統分岐順になっている。
他のグループで一番近縁なのはホオジロガモ類の Bucephala 属の3種。
カモ亜科 Anatinae: Ducks
ミコアイサ? 族 Mergini: Sea Ducks (ミコアイサ系統のみ掲載)
ミコアイサ属 Mergellus
ミコアイサ Mergellus albellus Smew
オウギアイサ属 Lophodytes
オウギアイサ Lophodytes cucullatus Hooded Merganser (北米)
ウミアイサ属 Mergus ("True" mergansers)
ウミアイサ Mergus serrator Red-breasted Merganser
コウライアイサ Mergus squamatus Scaly-sided Merganser
クロアイサ Mergus octosetaceus Brazilian Merganser (ブラジル)
オークランドアイサ Mergus australis New Zealand Merganser (ニュージーランド。絶滅種)
カワアイサ Mergus merganser Common Merganser
このグループの大半の種が北半球に広く分布しておりご存じお馴染みのものが多い。コウライアイサのみが非常に局地的に分布する。南半球では事情が異なっており2種が分かれて分布していたが1種が絶滅種であるため系統関係はわからなかった。
Rawlence et al. (2024) Ancient mitogenomes reveal evidence for the Late Miocene dispersal of mergansers to the Southern Hemisphere
は保存状態のよい標本から南半球には少なとも 700 万年前から2回の独立の進出があったことを示した。
Mergus 属は属内の種の分岐年代が古く、ホオジロガモ類やケワタガモ類とは対照的である。この論文にそれぞれの種類の分布図も出ている。
南半球の分布は北半球からの渡り個体に由来すると考えられる。
参考までに NC_016723 (コウライアイサのミトコンドリアゲノム) から BLAST を行ってみると、ウミアイサ属の系統関係は ウミアイサ、コウライアイサ、オークランドアイサ、クロアイサ、カワアイサ の順になった。基本的に上記配列順でよい結果となった。
ウミアイサが各地に分布を広げてコウライアイサなどの種を形成したが、その後生じたカワアイサが強力であったため古く分岐した系統は分布の遠いものやコウライアイサぐらいしか残っていないのかも知れない。
コウライアイサとカワアイサは地域的には共存しているので競争排除とまでは至らなかったが、コウライアイサにとって得意な地域以外ではカワアイサの方が優勢で分布を広げられなかったのかも知れない。
ウミアイサが分布を広げた時期にはコウライアイサは (東洋の) 隔離固有的な種だったが、カワアイサが勢力を拡大すると次第に遺存固有的になって行ったと解釈できるかも知れない。
ただしコウライアイサとウミアイサの一致率は 93% 程度、コウライアイサとカワアイサでも同程度と相当離れている。ウミアイサから分岐してから相当の期間が経過しているはず。
#キアシシギ備考 や #タヒバリ備考で紹介の [極東ロシア山地の種類数の少なさ] の Biserov (2008) の考えのように極東ロシアのアムール地域の気候の特徴が分布障壁となっているのかも知れない。
もっとも古い分岐で分かれた種類なのでもっと複雑な分布拡大・種分化や系統の消滅の歴史があるかも知れない。
[ミコアイサとウミアイサの雑種]
カムチャツカで記録されたミコアイサとウミアイサの雑種と考えられる個体: Artukhin (2023) Record a hybrid between smew and red-breasted merganser Mergellus albellus × Mergus serrator in the Avachinskaya Bay, South-East Kamchatka (pp. 1400-1403)。
ディスプレイ時と思われる行動 (sprint, salute, curtsy, head-fling display) も撮影されている。Jen Coates が非常によく似た個体の写真を Pinterest に投稿しているが残念ながら情報が不足とのこと。
ornithomedia.com に紹介された記事。
BirdGuides の記事。
日本でも可能性のある個体が撮影されているとこのページに紹介されている: Smew × Red-breasted Merganser (「空 」2015)。
[オウギアイサの視力]
Urban et al. (2020) Amphibious vision - Optical design model of the hooded merganser eye
オウギアイサの目のモデルを使った解像度の研究。空中での分解能は 2.12' と視力 0.5 ぐらいに相当。網膜の視細胞の密度とも合っている。そのまま水中に潜ると角膜の屈折力 56 D を失って大きくぼけてしまうが (視力の定義も困難)、水晶体のコア部分を移動させ、厚みも増すことで 6.27' と 1/3 程度の低下にとどめることができるとのこと。水中よりも空中視力の方がよい示唆が得られ、ウ類など潜水して食物をとる他の鳥の考察にも適用できるだろうとのこと。
若干不自然な感じがする図になっているが、水中では焦点を結ぶように瞳孔も縮小させて最大視力を評価しているものと思われる。水中で瞳孔を開くと焦点を結ばない部分も生じて結像性能は犠牲になるはず。
水晶体の厚みを変えて水中で調節ができるがそれでも光学的には理想的な条件とはならないよう。
視細胞の密度は地上生活のために最適化されたもので、水中では近い獲物を見るためにそれほどの分解能は必要としないのだろう。
-
カワアイサ
- 学名:Mergus merganser (メルグス メルガンセル) 少し沈んで泳ぐガン
- 属名:mergus (m) 少し沈んで泳ぐ海鳥
- 種小名:merganser (m) 沈んで泳ぐガン (mergo (tr) 沈める anser (m) ガン)
- 英名:Common Merganser
- 備考:
mergus は#ウミアイサ参照。
merganser は短母音のみと考えられ -gan- がアクセント音節 (メルガンセル)。
北半球に広く分布し3亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 merganser 亜種カワアイサと orientalis (東洋の) コカワアイサとされるが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では両亜種和名は検討中だった。最終的にこの名称となった。
亜種 orientalis は「東洋の」の意味が適切でなく、アフガニスタンからチベット、中国南部で繁殖し、インドや中国南西部に渡る (Clements) とある。英語では Central Asian と形容され、こちらの方が分布をよく反映している。ちなみに orientalis の方がやや大きいとされる (wikipedia 英語版)。
orientalis の記載時学名は Mergus Orientalis Gould, 1845 (原記載) 基産地 Amoy, China。
記載者にとってカワアイサはヨーロッパのものが比較対象で、中国で記載されたため Orientalis と付けたらしい。O は大文字で名詞扱いか。Gould の用いた英語では大文字表記の the Orient の名詞があり地域を指すので、特に東アジアを指して固有名詞的に使われた種小名 (現在亜種) かも知れない (wiktionary を参考とした)。
現在では(亜)種小名で大文字・小文字を使い分けないが、記載時に戻ると意図が見えることもある。
ユーラシアでは Goosander の英名も使われる。これは goose (ガン) と gander (オスのガン) からの合成語で 1622 年にすでに使われていた (wiktionary)。Merganser はアメリカでの名称。
-
ウミアイサ
- 学名:Mergus serrator (メルグス セルラートル) 嘴ののこぎりで魚を捕るアイサ
- 属名:mergus (m) 少し沈んで泳ぐ海鳥
- 種小名:serrator (嘴の) のこぎり状の突起に由来 (serro のこぎりで引く -ator 行為者)
- 英名:Red-breasted Merganser
- 備考:
mergus は短母音のみ (メルグス)。
属名に使われる mergus は Pliny などが用いた種類不明の水鳥 < mergere 潜る。
Linnaeus (1758) の用いた由緒ある属名で、Eyton (1838) がタイプ種を Mergus Castor Linnaeus, 1766 (参考。Linnaeus は Gesner や Brisson の情報をもとにヨーロッパ南部のウミアイサを別物と考えて分離した) に指定。
Mergus Castor は Mergus Linnaeus, 1758 には含まれていなかったがシノニムと判定された結果、Linnaeus (1758) にも含まれていたウミアイサがタイプ種となった (The Key to Scientific Names より推定)。
シノニムと判定されなければ Linnaeus (1758) の属記載に含まれない種類なのでおそらくややこしいことになっていただろうと想像できる。
serrator は a が長母音でアクセントがある (セルラートル)。語末は長音にならないので注意。
愛媛の野鳥「はばたき」では種小名 serrator を「のこぎりで材木をひく人」と訳している。
serra (のこぎり) に由来し嘴ののこぎり状の突起に由来する (wikipedia 英語版)。
記載時学名 Mergus Serrator Linnaeus, 1758 原記載。
これを見ると Serrator は名詞扱い。wiktionary によれば -ator は行為者を作る語尾とのことで、抽象名詞を作る -or の語尾ではなく、動詞の serro (セルロー) のこぎりで引くから派生する行為者と考えるのが自然と思われる。
Linnaeus (1758) にも Hujus methodus piscandi habetur in Actis Stockh. 1749 とあり、魚を捕るこの方法 (能力) は Actis Stockh. で考察されている、と機能を重点に置いた種小名と考えらえる。「のこぎりで材木をひく人」で大丈夫だが少し意味を補足した訳を採用した。
「長い嘴の」意味の学名も過去に使われ、いくつかの言語では標準名がこの意味になっている。
Hartert (1910-1922) p. 1379 によればこの意味の Mergus serrator longirostris Brehm, 1866 は無効名とのこと。
ただし当時のドイツ語名では Langschnaebliger Saeger と Brehm が付けたと思われるドイツ語名が別名となっていた。「長い嘴の」の他言語名はこの当時のドイツ語名または学名を訳したものと想像できる。標準的なドイツ語名は当時 Mittelerer Saeger 現在は Mittelsaeger で "中ぐらいの" の意味であまり面白みがない。カワアイサとミコアイサの中間の意味らしい。
カタラン語のように Bec de serra mitja のように嘴ののこぎり状の突起を表している名称もある。
北半球高緯度に広く分布。単形種。
-
コウライアイサ
△ カイツブリ目 PODICIPEDIFORMES カイツブリ科 PODICIPEDIDAE ▽
-
カイツブリ
- 学名:Tachybaptus ruficollis (タキュバプトゥス ルーフィコルリス) 赤い首の速く潜る鳥
- 属名:tachybaptus (合) 速く潜るもの (tachy- (接頭辞) 速く (Gk) bapto 潜る (Gk)、-tus (接尾辞) 〜に関連する)
- 種小名:ruficollis (adj) 赤い首の (rufus (adj) 赤い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Little Grebe
- 備考:
tachybaptus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-bap- がアクセント音節と考えられる (タキュバプトゥス)。tachy- に慣れていればそこまで難しくないが和名や英名に比べて長くて難解であることは否めない。
ruficollis は冒頭が長母音 (rufus ルーフス)。-col- がアクセント音節で "ルーフィコルリス"。和名からはアカエリカイツブリの方により適した種小名と思えるが、アカエリカイツブリの方にもかつてほぼ同じ意味の種小名が使われていた。
ユーラシアからアフリカに広く分布する。7亜種が認められている (IOC)。
日本で記録される種類は poggei (中国滞在のドイツ人軍人。東プロイセンの森林官 Karl Pogge に由来) 亜種カイツブリと kunikyonis (大東島在住の日本人採集家 Kunihira Kunikyo 由来) ダイトウカイツブリが日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)にリストされている。
後者は世界のリストではほとんど認められておらず、poggei のシノニムとされるのが一般的。前者もおそらく亜種 japonicus が poggei のシノニムとなった結果。
Tachybaptus Reichenbach, 1853 (図版) が属の原記載とされる。
[他言語語源]
カイツブリ類英名の grebe は 16 世紀フランス語の grebe 由来とのことだがその語源はあまりよくわかっていない。一部の種には冠羽があるので krib (くし) に関係がある可能性があるとのこと (Etymology Online)。フランス語の grebe は サヴォワ (Savoie 現在のフランスとイタリアの境界付近) の名称とのこと (wiktionary)。
OED によれば英語の用例は意外に新しく Pennant (1758) British Zoology (new edition) が用いたもの。
同じく Pennant (1766) で The little Grebe が使われていた。
dabchick (または類似綴り) の名称の方が古く、1520 年ごろの用例がある。grebe は分類の知識が入ってきてから用いられたよう。
ドイツ名は Taucher で潜るもの (tauchen 潜る) とそのままの名前になっている (#メジロガモの学名由来や#アカハシハジロのロシア名なども関連する)。
ロシア名は poganka で poganyj (食べられないなど悪い意味を指す) に由来。肉が脂ぎっていて魚臭いとのこと。もう一つ解釈があって poganka には (同じ意味から) 毒キノコを指す意味もあり、カンムリカイツブリが浮かんでいる姿がキノコに似ているためとの説もある (Kolyada et al. 2016)。
非常によく似た名前に peganka があり、こちらはツクシガモ類を指す。語源は pegij (まだらの。意味は英語の pied に似ている感じがする) で、マダラチュウヒのロシア名にも登場する。
[音声]
カイツブリにはさまざまな音声があり、短い地鳴きや警戒音 (知らないと何の声かと思ってしまう)、そしてよく聞く「さえずり」(キュルルルルーという声) がある (バードリサーチ鳴き声図鑑では地鳴きとしているが、世界的にはさえずりに分類するのが一般的)。この「さえずり」に非常に似た声をヒクイナも出す (#ヒクイナの備考参照)。探鳥会担当者などは即断で聞き慣れたカイツブリと判定してしまわないように注意が必要であろう。
[警戒の音声]
「夏の鳥」(小学館 1984) pp. 140-141 (渡辺央) がカイツブリの暮らしを紹介している。卵が途中で外敵に襲われる最大要因はヘビ。その時に巣の周りで「クィー、クィー」と鳴きわめき、水しぶきを上げ、他のつがいも集まってきて鳴きわめくが多くの場合ほとんど効果がないとのこと。
このあたりは大変よく思い当たる部分があり、「クィー、クィー」と記述されるものに相当する声は最初何かと思った。カイツブリには近くでピッと鳴く短い声などいろいろな音声があり、「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) には松田氏の記録が文字表記のみで紹介されているが、あれほど目立つ声なのに「クィー、クィー」に相当する音源は含まれていない。
バードリサーチ鳴き声図鑑にも 2025.6 時点で該当の声は登録されていない。
xeno-canto には多数あって XC363320 (Stanislas Wroza 2017), XC73273 (Stuart Fisher 2011) など。しっかりした海外バーダーは普通に知っている。
図鑑にもほとんど見当たらず、日本の観察者層の薄さを感じざるを得ない (カイツブリの鳴き声の図鑑の記述はほとんど他の記述を写しただけのようなものが多い)。
興味深いのは捕食者であるヘビの聴覚はおそらくこの警戒の音声の周波数にはほとんど感度がない。
ヘビの聴覚については諸説乱れているので文献を引いておこう: Zdenek et al. (2023) Sound garden: How snakes respond to airborne and groundborne sounds。
つまり鳴きわめいてもヘビを追い払う機能はないことになる。おそらくばたばたする低い音の方を感じているだろう。鳴きわめくのはカイツブリの他の個体に危険を知らせる役割が大きいと想像できる。
ヘビも水面を器用に渡り、どの部分を水面に触れさせて高速移動するかわかる。これがミズヘビか (違う!) と思うこともあった。
カイツブリの子育て物語はしばしば写真で紹介されてわかったような気になってしまいがちだが、このような場面や音声がすっぽり抜け落ちてしまう。夏場が近づくと観察するものがなくなったなあ、と思われている方こそあまり天気を気にする必要のないカイツブリの暮らしをじっくり観察してみて欲しい。
これらの観察は圧倒的に "待ち" の観察になる。巣が直接見えないところで待つなど注意が必要だろう。幸い音声は隠れていても十分聞こえる。いつ起きるかわからない発声に備えて録音機は常時記録した状態にしておいて、行動メモなども一緒に録音しておくとよい。他にもいろいろな声が記録できるかも知れない。
知らない人が見たら何が面白いのだろうと思われるかも知れないが、カイツブリは普通種なので「他に何もいませんね」と先を急ぐのはややもったいない。探鳥会ではそうも言っておれないので個人探鳥をおすすめする。カイツブリが繁殖する環境ならば場所によっては夏のタカなども期待できるかも。
[パンくずを疑似餌に使うカイツブリ]
諸角 (1995) Birder 9(10): 56-58 に東京の不忍池で人が投げたパンを細かくして撒き餌のように用いるカイツブリ (1991) の紹介がある。(#ゴイサギの備考参照)
[絶滅した飛べないカイツブリ類]
カイツブリが空を飛ぶ印象は受けにくいが、渡りをする個体がある通り空を飛べる。夜間の渡り途中の地鳴き nocturnal flight call (NFC) (#マミチャジナイの備考参照) では頻繁に記録される種類である。
飛んでいるビデオを撮影したいと何度も試しているがなかなか成功していない。
しかしカイツブリ類が飛びにくいことは確かなようで、世界には飛べないカイツブリ類もある。その一つにマダガスカルのワキアカカイツブリ Tachybaptus rufolavatus 英名 Alaotra Grebe があり、1985 年の目撃が最後で外来魚によって絶滅 (2010 年に絶滅宣言された) したと考えられている。現存する写真は1枚のみとのこと (wikipedia 英語版による)。
属は異なるが、グアテマラのオオオビハシカイツブリ Podilymbus gigas 英名 Atitlan Grebe (現地名 poc ポック) も有名である。これも飛べないカイツブリで、外来魚、想定外の地震などの天災や他種との交雑もあり、Anne LaBastille による 25 年の保護努力により一時は個体数 210 (1973) まで回復したが 1989 年の目撃が最後となり、1990 年に絶滅宣言された (wikipedia 英語版による)。
Anne LaBastille による著書 "Mama Poc: An Ecologist's Account of the Extinction of a Species" (1990) があり、「絶滅した水鳥の湖」(幾島幸子訳 晶文社 1994) と邦訳されている。
交雑により poc が飛べるようになった (絶滅を意味する) ことなど、#カワウ備考の [ガラパゴスコバネウの進化] で飛翔能力を失った進化経緯なども合わせて考えると面白い。飛翔能力を失った初期段階では交雑による遺伝子ネットワークの変化を飛翔力を取り戻すこともあり得るのだろう。
[Mirandornithes の系統分類]
Boyd による Mirandornithes (フラミンゴ目 + カイツブリ目) の分類一覧を示す。
フラミンゴ目 Phoenicopteriformes
フラミンゴ科 Phoenicopteridae: Flamingos
オオフラミンゴ属 Phoenicopterus
チリフラミンゴ Phoenicopterus chilensis Chilean Flamingo
オオフラミンゴ (旧名ヨーロッパフラミンゴ) Phoenicopterus roseus Greater Flamingo
ベニイロフラミンゴ Phoenicopterus ruber American Flamingo
コフラミンゴ属 Phoeniconaias
コフラミンゴ (コガタフラミンゴ) Phoeniconaias minor Lesser Flamingo
アンデスフラミンゴ属 Phoenicoparrus
アンデスフラミンゴ Phoenicoparrus andinus Andean Flamingo
コバシフラミンゴ Phoenicoparrus jamesi James's Flamingo
いずれもどこが違うのかと思えるほどよく似た属学名になっている。
Phoenicopterus (phoinix, phoinikos 紅色の -pteros 翼の)、
Phoeniconaias は naias, naiados 水の妖精 naiad、
Phoenicoparrus は parrus, parra は不明の不吉な鳥 (ヨタカ、フクロウ、キツツキ、タゲリ、サバクヒタキ を指すとのさまざまな解釈がある) (The Key to Scientific Names)。
属和名はタイプ種を採用したが、オオフラミンゴの分布は近年東に広がっており [Zhu et al. (2017)
Distribution of Greater Flamingo in China]、
自然分布で冬鳥としてしばしば記録されるようになるのも時間の問題かも知れない。すでに検討種扱いとなっている。この属のタイプ種はベニイロフラミンゴだが、この事情を考慮してオオフラミンゴを採用した。
これらの属はもとは形態学から分類されたものだったが、分子系統解析でも支持されたとのこと: Campo (2024)
Using physiological and molecular approaches to study micro- and macro-evolutionary patterns of selected waterbirds of the High Andes (学位論文)。
pp. 109-111 に系統樹。遺伝子流入もあった。これまで考えられたいたより分岐年代は新しく 370-410 万年前と見積もられた。
カイツブリ目 Podicipediformes
カイツブリ科 Podicipedidae: Grebes
オビハシカイツブリ属 Podilymbus
オビハシカイツブリ Podilymbus podiceps Pied-billed Grebe
オオオビハシカイツブリ Podilymbus gigas Atitlan Grebe (絶滅種)
カイツブリ属 Tachybaptus
ワキアカカイツブリ Tachybaptus rufolavatus Alaotra Grebe (絶滅種)
カイツブリ Tachybaptus ruficollis Little Grebe
* Tachybaptus tricolor Tricolored Grebe
ノドグロカイツブリ Tachybaptus novaehollandiae Australasian Grebe
マダガスカルカイツブリ Tachybaptus pelzelnii Madagascar Grebe
ヒメカイツブリ Tachybaptus dominicus Least Greb
シラガカイツブリ属 Poliocephalus
シラガカイツブリ Poliocephalus poliocephalus Hoary-headed Grebe
ニュージーランドカイツブリ Poliocephalus rufopectus New Zealand Grebe
オオカイツブリ属 Podicephorus
オオカイツブリ Podicephorus major Great Grebe (Podiceps 属より分離)
クビナガカイツブリ属 Aechmophorus
クビナガカイツブリ (アメリカカイツブリ) Aechmophorus occidentalis Western Grebe
クラークカイツブリ Aechmophorus clarkii Clark's Grebe
カンムリカイツブリ属 Podiceps
アカエリカイツブリ Podiceps grisegena Red-necked Grebe
カンムリカイツブリ Podiceps cristatus Great Crested Grebe
ミミカイツブリ Podiceps auritus Horned Grebe
ミミジロカイツブリ Podiceps rolland White-tufted Grebe (Rollandia 属を統合)
コバネカイツブリ Podiceps micropterus Titicaca Grebe (Rollandia 属を統合)
パタゴニアカイツブリ Podiceps gallardoi Hooded Grebe
ギンカイツブリ Podiceps occipitalis Silvery Grebe
ペルーカイツブリ Podiceps taczanowskii Junin Grebe
ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis Black-necked Grebe
* Podiceps californicus Eared Grebe (ハジロカイツブリより分離)
コロンビアカイツブリ Podiceps andinus Colombian Grebe (絶滅種)
Boyd の行った属分割、統合は IOC などでは未採用。ただし日本産種への影響はほぼない。
Tachybaptus tricolor Tricolored Grebe はカイツブリから最近分離されたもので和名が見当たらない。そのまま訳せばサンショクカイツブリのような名前になるのだろうか (サンショクの用例はサンショクウミワシなどいろいろある)。
Podiceps californicus Eared Grebe については #ハジロカイツブリ参照。ハジロカイツブリの北米グループだが実際に種として扱われるようになるかは微妙な感じ。
Aechmophorus 属は IOC 他でも古くから採用されている。ギリシャ語の aikhmophoros < aikhme 槍 phero 運ぶ とのこと (The Key to Scientific Names)。
嘴やふしょ骨が長いなど説はいくつかある模様。
The Bell Pettigrew Museum in St Andrews (Jake McGowan-Lowe 2013) でクビナガカイツブリ (アメリカカイツブリ) の骨格写真が見られる。このまま脚が伸びて首はすでに十分長いが骨がさらに長くなればフラミンゴのような形になることも納得できる (?)。
アメリカで grebe と言えば普通はこの種を指す (種カイツブリはいない)。カイツブリ科ではカンムリカイツブリがこの種に次いで2番めに大きいとのこと。
カンムリカイツブリの骨格は川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019) でも見ることができ、水面で休んでいる時はよくカモと間違われる外観とはだいぶ印象が違う。
Hayes et al. (2024)
Mate choice and hybridization in the Western Grebe and Clark's Grebe: tests of the scarcity of mates and sexual selection hypotheses
近縁のクビナガカイツブリ (アメリカカイツブリ) と数のより少ないクラークカイツブリの間に雑種が見られるが、コロニーサイズや繁殖時期との相関を調べた結果、つがい相手の不足が雑種形成の要因との従来仮説は裏付けられず、托卵やつがい外交尾に伴った誤ったインプリンティングの可能性がより考えられるとのこと。
[フラミンゴ目とカイツブリ目の関係]
フラミンゴ目とカイツブリ目の関係が近いことに最初に気づいた研究は van Tuinen et al. (2001) Convergence and divergence in the evolution of aquatic birds
で、Sibley and Ahlquist (1990) のデータも類縁性を示していたが、Sibley and Ahlquist は気づいていなかったとのこと。外見の類似性がほとんどなかったが後の研究でもこの関係は支持されることとなった。
Sangster (2005) A name for the flamingogrebe clade は両者を称して Mirandornithes と名付けた (#ミサゴの備考参照)。
あまりに思いがけない類縁性の発見の意味も込めて表しているのだろうか。
系統関係が明らかになってから共通の形態特性なども発表されているが、後付けの感は否めない。
参考 Mayr (2004) Morphological evidence for sister group relationship between flamingos (Aves: Phoenicopteridae) and grebes (Podicipedidae) (出版社サイト。この時点でもノガンモドキ類の位置がよくわかっていなかったこともわかる)。
Mayr (2006) The contribution of fossils to the reconstruction of the higher-level phylogeny of birds。
この分類概念は Phoenicopterimorphae (フラミンゴ上目?) と呼ばれることも多いが問題がある。後の解説参照。この点を考えると Mirandornithes と和名を用いた場合のフラミンゴ上目? は同じものを指しているわけだろうが、Mirandornithes に "上目" の意味は含まれないのでフラミンゴ上目? の和名はここでは使わないことにしておく。
Exploring the relationship between flamingos and grebes: The wonderful birds (David J. Ringer 2013) でも興味深い歴史が読める。
Livezey は 2011 年事故死するまでこの考えを否定し、フラミンゴ類はコウノトリ類に近縁と考えていた。次の批判論文を読むことができる。過去の研究もまとめられているので役立つだろう。
Livezey (2010) Grebes and flamingos: standards of evidence, adjudication of disputes, and societal politics in avian systematics
自分が独自データも用いて解析するとフラミンゴ類はアビ類に一番近縁になった。論調は分子遺伝学に頼りすぎでコミュニティも結果をセンセーショナルに報道しすぎる、といったところだろうか。
系統分類に果たす分子遺伝学の役割があまりに急速な進歩を遂げたため生じた伝統的研究者の拒否感が現れているとも読める。
ハヤブサ類とオウム類、スズメ目の近縁性が明らかになった時期とほぼ同じころの時代背景と考えて読むと興味深い。
2012 年になって化石証拠が見つかり、骨学から原始的なフラミンゴ類と考えられるがカイツブリ類に似た巣と卵が見つかった:
Grellet-Tinner et al. (2012) The First Occurrence in the Fossil Record of an Aquatic Avian Twig-Nest with Phoenicopteriformes Eggs: Evolutionary Implications
驚異的な鳥たちだが、歴史も同じぐらい驚くべきであると結ばれている。
化石鳥類の Palaelodus 属が形態的にはカイツブリ類とフラミンゴ類の中間的な特徴を示すとのこと (wikipedia 英語版より。この記事の主な部分ははカイツブリ類とフラミンゴ類の類縁関係が明らかになってから書かれたように見える)。
引用されている文献を1つ挙げておくと Mayr (2015) Cranial and vertebral morphology of the straight-billed Miocene phoenicopteriform bird Palaelodus and its evolutionary significance。
頭骨の形態はフラミンゴ類と大きく違うが、脊柱以下はフラミンゴ類とよく似ていておそらくろ過型の採食様式をすでに進化させていたのではないかとのこと。
さらに見ているとこんなページがあった: The Pterosaur Heresies。少し先の方の Bird neck length correlated to leg length (May 21, 2019) の項目を例えば参照。DNA を使ってカイツブリ類とフラミンゴ類を近縁とするのは間違いであると述べている (!)。
古生物 (特に Reptilia) の系統の視点からはそう見えるのかも知れないが、この項目にある系統樹では "足が長い" は祖先系統の性質と考えている。カイツブリ類とフラミンゴ類がまとまるはずがない、となる。
この視点で形態形質をもとに系統解析すると高い系統樹サポートでノガンモドキ類とフラミンゴ類が最も近縁な系統となるとのこと (!)。#ハヤブサの項目 [ハヤブサ目の系統分類] で紹介の Cariama (Reptile Evolution) はこの解釈に従っており、あるいはこの分野ではこの考えが浸透しているのかも知れない。
2019 年ならばすでに系統関係の証拠が固まっていた時期で (例えば 2011 年のレトロトランスポゾンの研究。#ミサゴ備考の [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] 参照)。DNA 研究などは無視せよとでも言わない限り考えられない話で、日常的にこの分野に馴染んでいて分子系統研究にはあまり馴染みがない方 (日本でもそういう方がもしあれば) の見解はだいぶ割り引いて考えた方がよい感じがする。
すごい系統樹がらあるからと頭から信じ込まない方がよい。
[フラミンゴ類]
Frias-Soler et al. (2022) Phylogeny of the order Phoenicopteriformes and population genetics of the Caribbean flamingo (Phoenicopterus ruber: Aves)
にカリブ海フラミンゴ類を中心とした分子系統解析がある。フラミンゴ類は通常3属と扱われるが、この研究は2属になるとのこと (コフラミンゴ属をアンデスフラミンゴ属まとめるか。この分岐年代はオオフラミンゴ属内の種の分岐年代より新しい結果となった)。
Sangster et al. (2022)
Phylogenetic denitions for 25 higher-level clade names of birds
がこのグループを何と呼ぶかについても例示して議論している。Mirandornithes と自分が正式に名付けたにもかかわらず別グループが別の名前で呼んだり、過去に使われた名前を別の概念に用いているので混乱を引き起こしているとのこと。
flamingo の英名は OED によれば 1589 年の古くから用例がある。語源は複数あるらしくポルトガル語 flamengo、スペイン語 flamenco、これらはロマンス語 flama (炎) + -enc (-ing に相当する語尾) などが挙げられている。
フラミンゴ類は代表的な極限環境に生息する生物 (extremophiles。その中でも最大のものとのこと) でさまざまな適応を行っている: 参考ページ Tough Birds Fragile Homes、
Are Flamingos Extremophiles? (査読論文はあまり出ていないらしい)。
Flamingos Are Totally Hardcore (Amy King 2024) によれば
フラミンゴの群れを指す flamboyance (きらびやかさ、燃えるような華麗さ、建築様式のフランボワイヤン) との用語があるとのこと。高地の夜は寒くて凍ることもあるが、片足で立って放熱を抑えている。強いアルカリ性に対しては皮膚が厚いことで対応。塩分濃度の高さは塩腺による排出で対応とのこと。
Byrne et al. (2024) Productivity declines threaten East African soda lakes and the iconic Lesser Flamingo
によれば東アフリカのコフラミンゴが採食を行う塩湖の水位が上がり濃度が下がってプランクトンが不足しているとのこと。気候変動から予測される変動とも合っていて、これまでの環境破壊とも合わさって塩湖の特異な生態系は今後の維持が危ぶまれるとのこと。
-
アカエリカイツブリ
- 学名:Podiceps grisegena (ポーディケプス グリーセゲナ) 灰色の頬の尻足の鳥
- 属名:podiceps (合) お尻のほうにある足、尻足の (podex -dicis (m) 肛門と podium (n) 足、-ceps (kaps) くっついている 古伊)
- 種小名:grisegena (adj) 灰色の頬の (griseus (adj) 灰色の gena (f) 頬)
- 英名:Red-necked Grebe
- 備考:
podiceps は#カンムリカイツブリ参照。
grisegena は griseus の i が長母音、gena は短母音。-se- がアクセント音節と考えられる (グリーセゲナ)。
2亜種ある (IOC)。日本で記録されるものは holbollii (デンマークの動物学者 Carl Peter Holboll 由来) とされる。
Kessler (1853) p. 65 (#オオハム参照) によれば複数の著者が用いていた Podiceps rubricollis Latham の学名 (赤い首のカイツブリ) があり、英名、和名、ロシア名 (現在も "赤い首の" 部分は同じ) はこの学名に由来または逆の関係と考えられる。
rubricollis は ruficollis などと意味はほとんど同じだが、
この学名の記載時は Colymbus rubricollis Gmelin, 1789 (参考) で
Colymbus ruficollis Pallas, 1764 (参考) の用例がすでにあったため語形を少し変えたものと想像できる。この用例が現在のカイツブリの記載となっている。
当時の属内での衝突を避ける措置だろうか。
Colymbus grisegena Boddaert, 1783 の記載が早かったために現在のアカエリカイツブリの種小名はこれが採用されている。OED によれば Pennant (1785) の Red-necked Grebe の用例があり英名の方が Gmelin の学名より早かったらしい。
山階鳥類研究所の標本データベースの YIO-61336 (1893) では和名の代わりに Eastern Rednecked Grebe のラベルがあり、和名は英名由来と考えるのがもっともらしい感じがする。
[目に紫外線フィルターのあるカイツブリ類]
Osik et al. (2022) Nicotinamide adenine dinucleotide reduced (NADH) is a natural UV filter of certain bird lens
(#トビの備考の [視覚特性] も参照) によれば、カイツブリ類は眼球のレンズに NADH 含有量が高く、紫外線フィルターとして作用しているらしいとのこと。
この文献で調べられているカイツブリ類はアカエリカイツブリ、カンムリカイツブリ、ミミカイツブリ、カイツブリ (日本とは異なる学名を用いている) で、いずれも高い値を示している。
[飛べないひなを運んだ? アカエリカイツブリ]
Kloskowski and Fraczek (2017) A novel strategy to escape a poor habitat: red-necked grebes transfer flightless young to other ponds
食物の少ない場所でひなとともに移住したと思われるアカエリカイツブリの報告。池の傾斜は強くてひなが自力で登るのは難しかった。親が背中に乗せて移動した可能性もあるが地上の移動はカイツブリ類は得意でなく非常に危険。ひなを乗せて飛んで移動した可能性も考えられ、カンムリカイツブリでそのような逸話が残されているとのこと。
-
カンムリカイツブリ
- 学名:Podiceps cristatus (ポーディケプス クリスタートゥス) 冠羽のあるカイツブリ
- 属名:podiceps (合) お尻のほうにある足、尻足の (podex -dicis (m) 肛門と podium (n) 足、-ceps (kaps) くっついている 古伊)
- 種小名:cristatus (adj) 冠羽のある
- 英名:Great Crested Grebe
- 備考:
podiceps は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、ラテン語 podex の冒頭が長音のため冒頭は長母音が適切と考えられる。アクセント音節もこの位置と考えられ伸ばすとアクセント位置に合う (ポーディケプス)。
cristatus は a が長母音でアクセントもある (クリスタートゥス) 所有の -atus。名詞の crista は例えば "とさか" などの意味 (英語 crest 参照)。
podiceps の由来は podex の属格 podicis + pes, pedis (いずれもラテン語) の合成語との解釈もある (The Key to Scientific Names)。英国の John Latham (1787) による造語。
ラテン語語尾の -ceps は頭を指すのでこちらが由来とは考えられない。
ラテン語 podium はやはりギリシャ語の足 pous の指小形に由来するが通常の意味はバルコニー。英語では演台などの意味。これは短母音で発音される。
podex (肛門) とは形は似ているが語源は異なる。こちらは長母音なので語源を残す意味から podiceps の冒頭は長音で発音するのが適切と考えられる。
3亜種ある (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 cristatus とされる。
ロシア名は bolishaya poganka (大きなカイツブリ) の他によく使われる chomga の名称がある。語源はよくわかっていないとのこと。古い文献ではこの名称は広くカイツブリ類 (= 単数形では poganka) を指していた (Kolyada et al. 2016)。ユーラシアではごく馴染みの種類でよく現れるので知っておいてよい名称。
カイツブリ類他種は poganka に形容詞を付けて表しているので現代の用法ではカンムリカイツブリが別格扱いとなる。
[アメリカにもカンムリカイツブリが生息していた?]
OED によれば英名 Great Crested Grebe の用例は案外古く、1766 年に Pennant が British Zoology に用いていた (しかし後述のように別物の可能性もあった)。
Crested Grebe の別名もあって Audubon など北米の著者の間はむしろこちらが用いられていた: Audubon (1844) The Crested Grebe (The birds of America: ...)。
このあたりまで調べればイギリス英語とアメリカ英語の違いと思って一見落着としてしまいそうなところだったが...
アメリカの鳥として記述されているが現代の分布には現れない (!) ... と思ったらやはり問題となっていた。The Great Crested Grebe in America (Rick Wright 2013 in Birding New Jersey)。図版は Audubon の英国滞在中 (1835) に描かれたらしく、アメリカの標本をもとに描いたかどうかも確かでないとのこと。
Audubon はいかにも見てきたかのように渡りの様子まで描写しているが、これはアカエリカイツブリとの習性の違いを示す意図があったと考えられるとのこと。
当時までの博物学者の間ではミミカイツブリとハジロカイツブリに混乱もあり、英語ではそれぞれ "The greater crested or copped Doucker" や "The greater crested and horned Doucker" と呼ばれるなど、"greater crested" はむしろミミカイツブリを指していた。英語の用例はあっても現代のものと同じとは限らない次第。
図版が悪い問題もあって博物学者の間に混乱があり、Buffon Le Grebe huppe (冠のあるカイツブリの意味) は北米にも生息すると記述していた。この記事には Linnaeus のスウェーデン派とフランスの博物学者の間で確執があったことも示唆されている (Linnaeus の誤りを指摘した Brisson などの背景事情がわかる: #ワライカモメ備考参照)。
その後も Audubon に限らず多くの著者が北米に生息すると記述しており、Richardson et al. (1829) Fauna boreali-americana, or, The zoology of the northern parts of British America は至るところの湖にいるなどと記述していた。
これは本来はカイツブリ類全体を記述した文章だったが、版組上の都合からカンムリカイツブリの名前を挙げた後に続く形となってしまったため、普通の読者ならばカンムリカイツブリの記述と読むだろうとのこと。
そしてこの誤解は引用されてさらに続き、カンムリカイツブリは新旧両大陸の北側全域に分布するとの記述まであった: Nuttall's Manual of the ornithology of the United States and of Canada (1832-1834) Crested Grebe, or Gaunt (図版付き)。
The Crested Grebe, inhabiting the northern parts of both the old and new continents (p. 251)。
Audubon はおそらくこれを読んで信じてしまったのだろうとのこと。
Spencer Baird は Audubon 自身が採集したとされる標本まで持っていて 1859 年のリストに含めており、ニューヨークでの観察記録やメーン州での繁殖まで記述があったとのこと。
Robert Ridgway が 1881 年にアメリカの鳥から暫定的除外を提案するまでアメリカの鳥のリストに含まれていたとのこと。
Baird and Ridgway が調査を行い 1884 年に北米の確実な記録はない、と結論したとのこと。
American Ornithologists' Union (AOU) も誕生したばかりだったがチェックリストには一度も入れなかった。これまでアメリカに一番近い記録は 1984 年のカナリア諸島のものとのこと。
最も偉大なアメリカの鳥類学者でさえも間違いだらけの出版物や誤った解釈の中では間違いを犯してしまったのだろうと結ばれている。
少なくとも Great を付けるのは比較的英国流儀だったらしく、アメリカで主に使われた "Crested Grebe" はこのような間違いが判明し、一度も AOU のチェックリストに掲載されることがなかったためアメリカ英語の名称を主張することは行わず、現在使われる英名から除外されたのだろう。
英名が学名や当時のフランス語名から素直に推測される "Crested Grebe" にならなかった歴史的理由はこんなところにあった。現代でも IOC などのチェックリストではイギリス式英語が主に使われているが、この種についてはアメリカ式の名前をまったく見かけない (どちらを使うか議論の対象にもならない) 十分な理由になるだろう。
カイツブリ類の和名が整理される際に Audubon の図版や学名の影響を受けたかも知れない。
またこのような事例を見るとカイツブリ類の飛翔能力の低さも実感できる。翼があるのだから迷鳥記録があってもよさそうなものだが、これだけ注目されながら北米の確実な記録はいまだない。
カイツブリ類が飛翔能力を失って高地の湖で地域固有個体群となって絶滅しやすい理由もわかる気がする。
英名で Great Grebe と呼ばれる南米の種類があり、オオカイツブリ Podiceps major がある。wikipedia 英語版によればカイツブリ類の中で世界最大となっている。コンサイス鳥名辞典ではクビナガカイツブリが最大でカンムリカイツブリはそれに次ぐと書かれていた。
[弁足の流体力学的働き]
カイツブリ類、特にカンムリカイツブリの弁足の流体力学的働きを調べた論文: Johansson and Norberg (2001) Lift-Based Paddling in Diving Grebe
水の抵抗を利用しているとこれまで考えられてきたが、揚力を用いているらしい。抵抗を用いて推進する場合に予想される方向と異なる方向に動かしている。
水かきで水面を推進するカモ類とは別の形態や足の動かし方になっている。
カイツブリ類は非常に古い系統で過去から形態もあまり変化しておらず、この方法は十分に最適化された推進方法の一種と考えられる。
同じ著者によるもので Johansson and Norberg (2003) Delta-wing function of webbed feet gives hydrodynamic lift for swimming propulsion in birds
は航空力学の延長上で解釈できるとした。カイツブリ類は「漕いでいる」のではなく「水中を飛んでいる」とも言える。
水中の速度 1 m/s ではレイノルズ数は 10^5 のオーダーで空中を飛ぶ鳥の場合とあまり違わない (#アホウドリの備考 [海鳥の翼先端にはなぜスロットがない?] も参照)。
-
ミミカイツブリ
- 学名:Podiceps auritus (ポーディケプス アウリートゥス) 耳の長いカイツブリ
- 属名:podiceps (合) お尻のほうにある足、尻足の (podex -dicis (m) 肛門と podium (n) 足、-ceps (kaps) くっついている 古伊)
- 種小名:auritus (adj) 耳の長い
- 英名:Slavonian Grebe, IOC: Horned Grebe
- 備考:
podiceps は#カンムリカイツブリ参照。
auritus は i が長母音でアクセントもある (アウリートゥス)。所有の -itus 由来。
記載時学名 Colymbus auritus Linnaeus, 1758 (原記載)。
auritus は過去に用いられていたものではなく Linnaeus が付けた模様。
2亜種ある (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 auritus とされる。
旧英名の Slavonian はスラヴォニア (クロアチア語: Slavonija) 由来。クロアチアの東部の地域。
Hartert (1910-1922) p. 1450 によればドイツ語名 Ohrensteissfuss で種小名に対応する名称となっている。
OED によればミミカイツブリを指す Eared Grebe の用例は 1772 年にあり、Linnaeus (1758) の学名を訳したものと考えれば年代的に整合する。Eared Grebe は後にハジロカイツブリまたは北米亜種 californicus を指して用いられたため、ミミカイツブリを指して Eared Grebe と呼ぶことは避けられるようになった模様。
Hartert (1910-1922) の時代にはすでに英名 Slavonian Grebe が示されており、少なくともヨーロッパでは早い時期に整理されたものと考えられる。
当時の混乱 (?) が残っているようで、ミミカイツブリのロシア語名は "アカエリカイツブリ" を意味するものとなっていて大変紛らわしい。アカエリカイツブリのロシア語名は "頬の灰色のカイツブリ" で学名に対応している。
-
ハジロカイツブリ
- 学名:Podiceps nigricollis (ポーディケプス ニグリコルリス) 黒い首のカイツブリ
- 属名:podiceps (合) お尻のほうにある足、尻足の (podex -dicis (m) 肛門と podium (n) 足、-ceps (kaps) くっついている 古伊)
- 種小名:nigricollis (adj) 黒い首の (niger (adj) 黒い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Black-necked Grebe
- 備考:
podiceps は#カンムリカイツブリ参照。
nigricollis は短母音のみで -col- にアクセントがある (ニグリコルリス)。
記載時学名 Podiceps nigricollis Brehm, 1831 (原記載) 基産地ドイツ。
当時のドイツ語名は Der schwarzhaelsige Ohrensteisssfuss で Black-necked eared grebe に相当する。ミミカイツブリの記載 Colymbus auritus Linnaeus, 1758 が先に行われていたが、ミミカイツブリ類はこの1ページ前に紹介され Ohrensteisssfusse (複数形) となっていた。
この中で2種ハジロカイツブリとアカエリカイツブリを分離した形になっている。当時は "クロエリミミカイツブリ" と "アカエリミミカイツブリ" に相当するドイツ語名が使われていた。
Hartert (1910-1922) p. 1451 ではドイツ語名 Schwarzhalssteissfuss で英名や学名と同じ。
"アカエリミミカイツブリ" は短縮されて現在の和名に至っているが、ハジロカイツブリの和名は独自に付けられたものらしい。
Federn des Nackens weiss ... (後頸の羽毛は白い) Handschwingen braun. Schaefte schwarz, die innersten 1-3 Paare meist ganz, oft aber nur groesstenteils weiss (初列風切の最も内側 1-3 対が大部分白い) Armschwingen mit Ausnahme der letzten (innersten) weiss (次列風切は最も内側を除いて白い)
の記述があり和名の由来と言われるものも含まれているがハジロカイツブリで目立った特徴というほどではなく、あまり決定的でない感じがする。Brehm (1831) にも "ハジロ" の候補となる部位があり、例えば der Spiegel weiss なども含まれていて翼鏡の扱いとなっていた。
山階鳥類研究所の YIO-01547 の標本ラベルを見るとかつて別名があったのではと思える (ラベルが読み取れないが Umikaits... のように読める)。
OED によれば Black-necked Grebe の用例は比較的新しく Jameson (1831) Wilson & Bonaparte's American Ornithology (revised edition) が初出とのこと。当時は Black-necked eared grebe と呼ばれていた。Gould (1863) の Black-necked Grebe の用例がある。
Jameson (1831) は Brehm (1831) の記載をそのまま取り入れてドイツ語から英訳した名称と考えられる。名前が長いのでそのうち "eared" が外されるようになったのだろう。
日本ではハジロカイツブリが圧倒的に多いので (他類似種があまり区別されていなかったかも知れない) "ハジロ" を冠した名前が先に用いられていて、後に追加されたミミカイツブリやアカエリカイツブリは学名あるいは外国語名が用いられたのかも知れない。これらの複雑な経緯があったためこれら3種の和名が識別点をあまり的確に表していない (と感じる) のかも知れない。
ヨーロッパでは事情が逆でミミカイツブリの方が先に記載されていたため、この名称を修飾する形の名称となっていたのだろう。
2亜種ある (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 nigricollis とされる。
カイツブリ属 (Podiceps) の分子系統研究は Ogawa et al. (2015) Opposing demographic histories reveal rapid evolution in grebes (Aves: Podicipedidae)
にある。
Boyd はこれをもとに Podiceps californicus Eared Grebe (ハジロカイツブリの北米グループ) と Podiceps nigricollis ハジロカイツブリを分離しているがどうだろうか。
Ogawa et al. (2015) は前者を North American Black-necked Grebe と呼んでいる。
コロンビアカイツブリ Podiceps andinus Colombian Grebe (絶滅種) とハジロカイツブリ全体の間で単系統をなさず、このサンプルではコロンビアカイツブリがハジロカイツブリの北米グループと並ぶ形となっている。コロンビアカイツブリを種として維持するにはハジロカイツブリの北米グループを種と認めると都合がよいとの Boyd の判断だろう。
研究はまだ限定的なようでどのように判断されるだろうか。
Eared Grebe の名称はハジロカイツブリの別名として使われてきた (北米の) 英名を復活したものと思われるが、採用されるとミミカイツブリの和名との対応が紛らわしくなる可能性がある。Eared Grebe が避けられてきた経緯は #ミミカイツブリ備考も参照。
南アメリカの種で我々には関係が薄いが、ギンカイツブリ Podiceps occipitalis Silvery Grebe とペルーカイツブリ Podiceps taczanowskii Junin Grebe も単系統の関係をなしていない。これは個体群の保護的な意味も重視した分類が採用されたためだろう。
普通種であるが、ハジロカイツブリの声を聞かれたことはあるだろうか。越冬中の声の記録は国内・国外の音声データベースでも意外に記録が少ない。鳴いているところに気づかれた場合は録音をお勧めしたい。
△ ネッタイチョウ目 PHAETHONTIHORMES ネッタイチョウ科 PHAETHONTIDAE ▽
-
アカオネッタイチョウ
- 学名:Phaethon rubricauda (パエトーン ルブリカウダ) 赤い尾のパエトン
- 属名:phaethon (m) 太陽神の息子パエトン (輝く者の意)
- 種小名:rubricauda (adj) 赤い尾の (ruber (adj) 赤い cauda (f) 尾)
- 英名:Red-tailed Tropicbird
- 備考:
Phaethon は o が長母音で冒頭にアクセントがある (パエトーン)。
rubricauda は短母音のみと考えられる。-ca- がアクセント位置と考えられる (ルブリカウダ)。
学名、英名、和名ともによく一致している。しかし Phaeton phoenicruos Gmelin, 1789 の学名 (意味はほぼ同じ) があってこの学名を用いた図版などもあった。図版 例を見ると Red-tailed Tropicbird の由来は現在の学名ではなくこの学名由来と思える。
フランス語名も添えられていて Paille-en-queue a brins rouges (Buffon)。brins は繊維などの意味で、直訳すれば "尾に赤い繊維のあるネッタイチョウ" とより記述的になっている。
この図版の記述では Phaeton rubricauda の学名の記載はまだ知られていなかったように見える。
Boddaert (1783) の記載の方が少し早かった (原記載) で一覧に現れる。基産地モーリシャスでいずれにしてもフランスの博物学者による記載だった。英名はフランス語名または学名から二次的に付けられたものと想像できる。
4亜種ある (IOC)。日本で記録されるものは melanorhynchos (melanos 黒い rhunkhos 嘴) 英語でこの亜種を Black-billed Tropic Bird とも呼ぶ。
ネッタイチョウ類は [#鳥類系統樹2024] で名付けられたクレード名 Elementaves の重要な構成要員。「4元素」のうち「火」の役割を担っている。
-
シラオネッタイチョウ
- 学名:Phaethon lepturus (パエトーン レプトゥールス) 細い尾のパエトン
- 属名:phaethon (m) 太陽神の息子パエトン (輝く者の意)
- 種小名:lepturus (合) 細い尾の (leptos 細い oura 尾 Gk)
- 英名:White-tailed Tropicbird
- 備考:
Phaethon は o が長母音で冒頭にアクセントがある (パエトーン)。
lepturus は u が長母音 (尾のギリシャ語 oura 由来) でアクセントがある (レプトゥールス)。学名のみに使われる。
学名と英名の整合性が少し悪いが、これは Red-tailed Tropicbird に対応するものとして名付けられたか、あるいは Phaeton leucurus Dubois, 1872 (白い尾のネッタイチョウ) に対応するものか。
6亜種ある (IOC)。日本で記録されるものは dorotheae (オーストラリアの発生学者 Henry Luke White の妹の Dorothy Ebsworth White 由来) とされる。
△ サケイ目 PTEROCLIFORMES サケイ科 PTEROCLIDAE ▽
-
サケイ
- 学名:Syrrhaptes paradoxus (シュルラプテス パラドクスス) 変な縫い合わされた指の鳥
- 属名:syrrhaptes (合) 縫い合わされたもの (syrrapto 縫い合せる Gk の変化形 surrhaptos 由来) 羽の生えた足の指がつながっているため (The Key to Scientific Names)
- 種小名:paradoxus (合) 予想外の、驚くべき、変わった (paradoxos 定説に逆らうものの意 Gk)
- 英名:Sandgrouse, IOC: Pallas's Sandgrouse (プロイセンの生物学者 Peter Simon Pallas に由来)
- 備考:
syrrhaptes は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語には長音は含まれない。The Key to Scientific Names の説明通りにギリシャ語の変化形をそのまま用いたものであれば短母音のみと考えられる。
-tes がギリシャ語起源のラテン語接尾辞と考えると e が長母音となる可能性がある。いずれの場合でも -rhap- がアクセント音節であることは変わりない (シュルラプテス または シュルラプテース)。
paradoxus は短母音のみで -dok- がアクセント音節 (パラドクスス)。
属名は Illiger (1811) が設けたもの (属記載) で、属名の説明はラテン語で consuere < consuo (縫う) の分詞形。
当時はドイツ語名を Fausthuhn (拳のニワトリ) としていた。属を設けるに当たり Tetrao paradoxus から Syrrhaptes Pallasii Illiger, 1811 と新名を付けた (#ノスリの備考参照)。(The Key to Scientific Names)。
wikipedia 英語版によればこの属の足は形態的には鳥の足というよりむしろ哺乳類の paw に似ているとのこと (van Grouw "Unfeathered Bird")。
単形種。
Pallas (1773) の記述ではライチョウ属とノガン属の両方の特徴を示し、様々な点でそれぞれの属にない特別な特徴が見られるとのこと (The Key to Scientific Names)。
種小名の原意はこのように解釈するとよさそうである。
英名の意味は自明だが、OED によると 1783 年に Latham, General Synopsis of Birds が学名 Tetrao arenaria とともに示したもので、arena (砂) の変化形で当時の学名をそのまま英訳したものらしい。Sand Partridge の英名も現れる: 参考 Shaw (1803-1809) Sand Partridge (英語は図版の後に)。
この学名は Tetrao arenarius Pallas, 1775 参考だったが Hertert が Tetrao orientalis Linnaeus, 1758 のシノニムとした。
この種は現在では別属でクロハラサケイ Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse となっている。ハチクイ同様日本産種に最も単純なサケイの名称を与えたために英名との関係がわかりにくくなっている。
和名の由来はおそらく英名かドイツ語名由来だろうが、遡れば Pallas が別種に対して付けた学名由来となる可能性がある。
[サケイ目の系統]
サケイ目に最も近縁なグループはマダガスカルのクイナモドキ目 (Mesitornithidae)。これら2目とハト目 で Columbimorphae の系統をなす。
Hackett et al. (2008) A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History (#ミサゴの備考にも登場)
ではサケイ目、クイナモドキ目、ハト目の順に分岐する結果が得られている。Prum et al. (2015) (#アマツバメの備考参照) では前2者が逆順になっている。
いずれもハト目とはまとまるが系統的にはかなり離れていると考えてよい。
[#鳥類系統樹2024] の Stiller et al. (2024) によれば {クイナモドキ目 + サケイ目} がまとまったクレードをなし、ハト目と並ぶ形になる。これらの2クレードの分岐年代は 6300 万年前程度と相当古い。
ハト目は2系統に分かれ (2300 万年前ぐらい)、{Raphinae ドードー/アオバト?亜科 + Claravinae アルキバト亜科? (南米の地上性のハト類)} の系統と Columbinae (多くのハト類を含む) の系統となる。
2300 万年前ぐらいには果実食のハト類と地上性ハト類がすでに分かれていたことになる。Claravinae に属する代表的な種である南米のイチモンジバト Columbina picui Picui Ground-Dove は乾燥環境を中心に住むのでハト目では早く (例えば 2300 万年前ぐらい以降) から乾燥地適応は進んでいたのだろう。
サケイ目、クイナモドキ目も同様なので、Columbimorphae 全体にその傾向があり、果実食のハト類が生態的にはむしろ例外的と言えるかも知れない。ハト目内の系統について #ズアカアオバトに備考に続く。
[飲水と羽毛で水を運ぶ行動]
サケイはハトのように水を吸うことができると考えられていたが、そうではないとのこと: Cade et al. (1966) Drinking behavior of sandgrouse in the Namib aud Kalahari deserts, Africa。
一方サケイ類が羽毛に水を含ませて遠方まで運ぶ能力があることはよく知られているが、そのための羽毛の微細構造の特殊化: Mueller and Gibson (2023) Structure and mechanics of water-holding feathers of Namaqua sandgrouse (Pterocles namaqua)
クリムネサケイを用いた micro-CT による研究で、羽毛の異なる部位の硬さにそれぞれ特殊化があり、表面張力で微細構造に水を保ちつつそれを支える強度があるとのこと。
[Pallas の読み方]
様々なところに名前の出てくる Pallas (カワガラスの種小名などにも現れる) の日本語での読み方はいろいろな表記があり、パラス、パーラス、パラースを見たことがある。
原語のドイツ語発音であればアクセントは最初なのでパーラスとしてもよいかも知れない。Pallas の広く活躍したロシアでの発音はアクセントが後になるようで、こちらを重視すればパラースとしてもよい。どの言語を用いるか次第の問題でどれも正しいと言って構わないようである。
なおギリシャ神話にも Pallas が登場し、男性は前アクセント、女性は後ろアクセントだそうである。
元素のパラジウム (Pd) の名称も直接の由来は小惑星パラスだが、遡れば神話で同じ語源になる。
△ ハト目 COLUMBIFORMES ハト科 COLUMBIDAE ▽
-
ヒメモリバト
- 学名:Columba oenas (コルムバ オエナス) ハト
- 属名:columba (f) ハト
- 種小名:oenas < oinas, oinados ハト 古 Gk, Aldrovandus (1599) が Oenas (Gk) と用いた
- 英名:Stock Dove
- 備考:
columba は短母音のみで -lum- がアクセント音節 (コルムバ)。
起源は#ウミバト参照。
oenas は由来となるギリシャ語には長母音は現れない。冒頭がアクセント位置と考えられる (オエナス)。ギリシャ語の oinas では na にアクセントがある。一方ワインの意味の oinos は冒頭がアクセント。oinos + -as でアクセントが移動したもの。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。
種小名に使われる oenas は他の種ムラサキサンジャクでワイン色の意味で使われるが、ギリシャ語の由来 (oinos) が異なる (The Key to Scientific Names)。2亜種あり (IOC)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種不明とされる。
英名の由来は雑木の切り株 (stock の古めの英語での意味) に群生する枝の間に巣をつくることから (コンサイス鳥名事典)。Columba 属のタイプ種。
-
カラスバト
- 学名:Columba janthina (コルムバ イアンティナ) 紫色のハト
- 属名:Columba (f) ハト
- 種小名:janthina (合) 紫色の ianthinos Gk (wiktionary) 由来
- 英名:Japanese Wood Pigeon (7版), 8版, IOC (13.2 から), AviList: Black Wood Pigeon
- 備考:
columba は#ヒメモリバト参照。
janthina は短母音のみで -an- がアクセント音節 (イアンティナ)。ianthinus の別綴りとのことで ja を分割した表示にした。アクセント音節なので "ヤンティナ" の方が音が近いかは微妙なところ。ヤンティナ" の場合も前に短い i を補うつもりで発音するとよいのだろう。
3亜種あり (IOC)。
基亜種 janthina 亜種カラスバト、nitens (輝く) アカガシラカラスバト、stejnegeri (ノルウェー生まれのアメリカの鳥類学者 Leonhard Stejneger に由来) ヨナグニカラスバト。
種として天然記念物。
アカガシラカラスバトは絶滅危惧 IA 類 (CR)、ヨナグニカラスバトは絶滅危惧 IB 類 (EN)。
亜種カラスバトは準絶滅危惧 (NT)。
IOC 14.2 でより記述的な種英名が採用された。参考までに他言語を少しみておくと "日本のハト" に相当する名称が結構あり (例えばウクライナ語やセルビア語など)、一般的に "日本のハト" を指す名称と混乱が起きないのかと思ってしまう。"黒いハト" を採用している言語もいくつかある (チェコ語、ポーランド語など)。ドイツ語では "すみれ色のハト"。
AviList, Clements v2024 では Black Wood Pigeon、BirdLife v9 で Japanese Woodpigeon。
亜種英名を使い分けるためにもこの英名変更が適切だったかも知れない。亜種 nitens Red-headed Wood Pigeon の名称がある。亜種で呼び分ける場合は基亜種 janthina を Japanese Wood Pigeon と呼ぶことになる。
記載時は Columba janthina Temminck, 1830 だったが、その後カラスバトをタイプ種とする Janthaenas 属 (ianthos 紫色の oinas, oinados ハト Gk) (Reichenbach 1853) とされていた (The Key to Scientific Names)。
カラスバト、リュウキュウカラスバト (絶滅) を含む分子系統解析は Soares et al. (2016)
Complete mitochondrial genomes of living and extinct pigeons revise the timing of the columbiform radiation
を参照。カラスバトとリュウキュウカラスバトは非常に近い関係だった。現在の属名にも現れているように系統的には (アオバトやキジバトとは異なり) カワラバト系統に属するが分岐年代 1000 万年程度なので別属にしても構わない程度。別属とした方がわかりやすくなる点は #キジバト の備考 [キジバトの名称考察] でも触れた。
Oliver et al. (2023) (#ズアカアオバト備考参照) の系統樹を見ると、カラスバト、リュウキュウカラスバトをカワラバト系統から分離するならば タイワンジュズカケバト Columba pulchricollis Ashy Wood Pigeon、カノコモリバト Columba elphinstonii Nilgiri Wood Pigeon (インド) が同じクレードに属する。写真を見ると確かに多少似たところもあるように見える。
さらに古い分岐にあたるクレード (レモンバト Eastern Lemon Dove など) は Aplopelia 属に分けられることが多く [Oliver et al. (2023) では Columba に含まれている]、カラスバト類を別属にするかどうかは境界領域のよう。
Aplopelia 属への分離は近年のことで (IOC 14.2 では未採用。WGAC version 0.02 から採用など IOC は次回改訂で盛り込まれるかも)、
あるいは将来遺伝情報がより確かなものになった場合、分類改訂で Janthaenas 属が復活するかも知れない。"Janthaenas" グループの方が bootstrap 確率 100% とこちらの方が系統樹形態はよりしっかりしている。
[絶滅の淵を生き延びた (亜種) アカガシラカラスバト]
Tsujimoto et al. (2025) Genetic purging in an island-endemic pigeon recovering from the brink of extinction
小笠原の亜種。基亜種からの分岐年代は 67 万年前と見積もられている。1830 年代に人が入植して生息地の破壊や持ち込まれたネコによって 2008 年には 80 羽未満の個体数となり、2010 年に父島でノネコの捕獲が始まってノネコの個体数は急速に減少し、それとともにアカガシラカラスバトの個体数も急速に増えた。また上野動物園で域外保全のための飼育下増殖が行われていたが近親交配が著明となって 2012 年に野生個体から 13 羽が飼育個体群に導入された。2022 年終わりには飼育下個体は 198 羽となった。
野生個体と飼育個体のゲノムを読み、近親交配に伴うホモ接合度や過去の実効個体数 (Ne) の変動を求めた研究。基亜種に比べて小さな島の個体群である小笠原の亜種は近親交配の影響が現れていて、また飼育下個体群ほど影響が大きかった。基亜種に比べて有害遺伝子が除かれている証拠が見られ、他種にも同様の事例がある。
個体数減少のボトルネックには遺伝的多様性を減らす効果と良質の遺伝子を選択する効果の両方があり、#タンチョウ 備考の [アメリカシロヅルの遺伝的劣化] でも議論されている通り。アメリカシロヅルと比較するとアカガシラカラスバトの方がボトルネックの期間は短い。
有害遺伝子が減っているのは個体数減少のボトルネックを体験したためと考えられるがまだ平衡状態には達していないと考えられるので今後も注意が必要であるとのこと。
Ne の歴史的変化の推定では、Ne の急減が人為活動以降と合うパラメータならば過去の Ne は 2000 程度と人為によって 1/30 程度に減った見積もりになる。
図に一緒に示されている島の人口変化が一見して何かとわからないほど激しい (要因は触れるまでもないが)。
飼育下個体では近親交配の程度が高くなるほどむしろ寿命が伸びる相関が認められたが、飼育技術の進歩も反映しているものと考えられる。海外事例では近親交配の程度と寿命にはそれほど相関が認められていないものがあるが、逆にモーリシャスバト Nesoenas mayeri Pink Pigeon のように保護策が奏効して数を増やしたものの頭打ちになっている事例があり、この場合は近親交配の影響も考えられているとのこと。
この論文で参照されている遺伝学と形態学研究 (分岐年代の根拠) は Seki et al. (2007) Distribution and genetic structure of the Japanese wood pigeon (Columba janthina) endemic to the islands of East Asia と
Tsujimoto et al. (2023) Has long-distance flight ability been maintained by pigeons in highly insular habitats?。
-
オガサワラカラスバト
-
リュウキュウカラスバト
- 学名:Columba jouyi (コルムバ イオウィイ) ジョウイのハト
- 属名:columba (f) ハト
- 種小名:jouyi (属) jouy の (アメリカの博物学者 Pierre Louis Jouy 由来)
- 英名:Ryukyu Wood Pigeon
- 備考:
columba は#ヒメモリバト参照。
jouyi はラテン式で#カラスバト同様に "イオウィイ" のアクセントを想定して jo の部分を分けた表記としてみた。"ヨウイ" や "ヨウィ
イ" でもよいと思われる。アクセント位置は確実でないが "オ" か "ウ" と考えられる。
ラテン式にこだわらず原音に近い音でも構わないと思われる。
絶滅種。
原記載。当時はカラスバトとともに Fruit-Pigeon, Janthaenas 属に分類されていた。
Soares et al. (2016) (#カラスバト備考) の推定分岐年代をみると独立種に値するか微妙なところ。
wikipedia 英語版によれば沖縄で最後に記録されたのが 1904 年で、おそらく狩猟で絶滅したと推定される。大東諸島では 1936 年以降に姿を消し、これらの小さな島は第二次世界大戦前に樹木が完全に伐採され建物が建てられたために絶滅したと考えられる。狩猟圧が高かったようだが離島の生息地が失われたのは第二次世界大戦のための間接的影響とも言えるのだろう。
沖縄の他の島に残っている可能性が考えられたが再発見されなかった。
沖縄の山には十分な生息地が残っているはずだが目撃されなかった。トカラ島には森林がほぼそのまま残っているのにまったく記録がないのは不思議である。座間味島は沖縄から遠く離れ過去に記録があるのに残存していないのは不思議であると記述されている。
-
キジバト
- 学名:Streptopelia orientalis (ストゥレプトペリア オリエンターリス) 東洋の首飾りのあるハト
- 属名:streptopelia (合) 首飾りのあるハト (streptos 首輪、首飾り peleia ハト Gk)
- 種小名:orientalis (adj) 東洋の (-alis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Oriental Turtle Dove
- 備考:
streptopelia は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は含まれないと考えられる。-pe- がアクセント音節と考えられる (ストゥレプトペリア)。
orientalis は a が長母音でアクセントもある (オリエンターリス)。
"Fauna Japonica" での学名は Columba gelastis Temminck, 1835 で gelastis は 笑う (Gk) の意味。図版。
Columba orientalis Latham, 1790 の記載が早く現在は亜種にも名前は残っていない。基産地は中国。
海外研究者が日本の鳥に接する機会も少なかったためか gelastis を含む学名の用例ほとんど見当たらない。Dement'ev and Gladkov (1952) にもシノニムとして扱われておらず、完全に忘れ去られてしまったか要件を満たさなかった学名なのかも。
英語別名に Rufous Turtle Dove がある。
ヨーロッパでは単に Turtle Dove と言えばコキジバト (以下参照) なのでこちらが本家。その東洋版の意味になる。
5亜種 (IOC)。日本で記録される亜種は基亜種 orientalis 亜種キジバトと stimpsoni (アメリカの技師で北太平洋を探検した William Stimpson に由来) リュウキュウキジバト。
望月 (2021) mtDNA ハプロタイプが大きく2系統に分かれるキジバトの集団遺伝構造の解明
ミトコンドリア DNA と核 DNA のハプロタイプの遺伝構造の違いについての暫定的報告が紹介されている。
Birder 34(6): 70 に関連記事 (2020) がある。
ヨーロッパに広く分布するコキジバト Streptopelia turtur European Turtle Dove に近縁。こちらの turtur は Linnaeus (1758) の記載 (Columba turtur) には生息地はインドとなっていたが誤りで実際は英国とされるとのこと。
Turtur 属は上記 turtur ではなく、アオフバト Turtur afer Blue-spotted Wood Dove がタイプ種と実は結構ややこしい。Garsault (1764) がアオフバトに対して Turtur 属を正しい二名法で先に用いていたと認定されたため。
Turtur 属はアフリカ南部に生息。
Streptopelia 属はシラコバトをタイプ種として Bonaparte (1855) が用いたもの。シラコバトの decaocto は記載時は変種名だったにもかかわらず亜種名と認められてタイプ種となり、先取権の規則により最も普及していたはずの名称の turtur はタイプ種として残らなかった。
同様の事例が分類見直しで#ミソサザイで発生する可能性がある。
英名の turtle はラテン語 turtur の変形で 1300 年ごろから使われているとのこと。一方カメを意味する方の turtle は由来不明のフランス語 tortue, tortre (13 世紀) 由来で 1600 年ぐらいから使われているとのこと。tortoise の方が英語での用例は古く、これはラテン語 tartaruchus に遡ることができるとのこと (Ethymology Online)。
turtur がラテン語のためヨーロッパ言語でも広く使われている。ロシア語やウクライナ語では gorlitsa, gorlitsya と系統が異なるが、これは gorlo (のど) が由来で、着眼点それほど違わない。クロアチア語やチェコ語なども子音交代が起きているが同様の単語を用いている。
発声全般については #タンチョウの備考 [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] 参照。
#ウグイスの備考 [ウグイスは息を吸う時に声を出すか] でハト類を取り上げている。ハト類のこもったようなクーの声は息を吐きながら短い間隔で息継ぎをしつつ作っていると思われる。
[キジバトの名称考察]
キジバトの名称由来について大橋 (2023) Birder 37(1): 50-51 で紹介されていた。"雉鳩" の比較的名称は新しく江戸時代に現れたとのこと。
参考までに "雉鳩" の wiktionary を見ておくと、中国語ではゴクラクバト Otidiphaps nobilis Pheasant Pigeon を指すとのことで、中国からは海外種なので英名から翻訳したものらしい。多くの言語でも採用されていて "雉鳩" に対応するのは世界的にはこの種が主流のよう。"雉鳩" は日本国内で生まれた名称と考えられる。
キジバトの方は中国語で多数の別名があって "斑鳩" 系統がよく使われている。山斑鳩など。
ドイツ語名別名に Bergturteltaube があって Berg (山の) が入っている点は西洋のコキジバトに対応させたものだろう。
Meena-Turteltaube の Meena はおそらくインドの地域を指す名称由来ではないだろうか。
キジバトの名称そのもの由来には特に異論はないが、"山鳩" などの名称の成り立ちを考えてみた。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) pp. 16-17 に「梅園禽譜」(毛利梅園 1839 序文) の図版が紹介されており、絵では特徴が今ひとつ捉えられていない感じがするが、単に「鳩」とありハト、真バト、キジバトの名称が添えられていた。
ハト類は日本には4種あって (他にも琉球の種の記述も別にある)、ドウハト (合+鳥の漢字。集まる鳥の意味かと思ったが、wiktionary を見ると形声文字で古代中国語では *ku:b とのこと。ハトの声と納得せざるを得ない。現代中国語でもハトを表している。#カワラバトの備考 [鳩の漢字の意味] も参照)、
ドハト (斑鳩)、青鳩 (アヲハト)、真鳩とのこと。
ドウハトとドハトがどのように違うのかわかりにくいが、ドウハトは社堂などに群れを成し俗に色バトという。ドハト (斑鳩) は灰土色の毛で土鳩と言い色バトと交じるとのことで、ドウハトとドハトは現代のドバトのことで、色彩の目立つ方をドウハト、灰土色のものをドハトと呼んでいたらしい。
青鳩は現代と同じで問題なし、ということでキジバトは一般には単に「鳩」と呼ばれていたらしい。真バトの名前も今で言えば「ただバト」ということになる。
#ツミの備考 [和名について] でも取り上げたが、このキジバトの図版でも「種」の表記で、この当時は交配能力などはそれほど念頭になく、生物学的な種の概念は西洋の学問が入って広まって行ったのではないだろうか。
この時代に "山鳩" の別名が示されていないのは、猟銃による捕獲が一般的になる前で、農地にも普通に住んでいた最も一般的なハトだったのだろう。"つちくればと" の名称も一番身近なハトで、ごく近くで土の上を歩いて食べ物を探している姿などが普通に見られたのを反映しているのだろう。
狩猟鳥として捕獲したり追い払うことが一般的になってから山に追いやられて "山鳩" になってしまったのではないだろうか。今は警戒心も次第に薄れて (あるいは人をあまり恐れない遺伝的性質がまた広まって) 次第に戻りつつある過程を見ているところだろうか。
鳥学者が名前を整理する時代にはキジバトがすでに "山鳩" として追いやられていて、"ヤマバト" ではアオバトの生息環境と区別しにくいために別名として存在したキジバトが採用されたのではないだろうか。
このような過去の記述を見ると、外来種とされるドバトを除けば日本の平地はキジバトがほとんど独占していたらしいことがわかる。なぜそれほど種多様性が低かったのだろうか。
ハト類は系統が古いため、何が渡来していてどのように適応放散したのか網羅的には調べていないが、現在日本に存在する系統では Columba 系統は、伝書鳩のように帰巣能力は高いものの渡りを利用した分散能力はそれほどでないようで、アフリカや中東の乾燥地域を由来とするカワラバトはアジアの森林地帯を超えて分散することができなかったよう。
そのためどちらかと言えば Columba 属に適したユーラシア東端部の生息環境もキジバトが占めていたが、余裕があったため後にドバトが導入されると多数増えることができたなど考えられる。
アオバトは別系統で別途定着。
定位研究にカワラバトがよく使われてきたが、このような渡り特性を考えると代表とするのはあまりふさわしくなく、新しい系統の鳥の渡りの定位とは異なる点もあるかも知れない。
カラスバト、リュウキュウカラスバト (絶滅) も Columba 属に含められているが、#カラスバトの備考のように分岐年代 1000 万年程度なのでカワラバトと別属にしても構わない程度に違っている。生態的違いを考慮すると別属でよいのかも。またあるいはこの系統中でカワラバトと類縁種のみが特別な適応を遂げたものかも知れない。
Streptopelia 属はアフリカ、ヨーロッパ、アジアまで広く分布しているが、本来東アジアに生息しても構わなかったカワラバトが分散能力の限界から分布することができず、その生息空間も占めるような形で森林環境にも適したキジバトが分布したため環境適応範囲も高く、人為活動に頼って生息してきた同属の外来種シラコバトも競争排除できてしまうのだろう。
また地域の狭さから Streptopelia 属から複数種が分化するほどのこともなく、キジバト1種のみになっているのだろう。
望月 (2021) のような遺伝的状況もカワラバト不在のため多少異なる複数の環境に適応したものが気候変動などで隔離され、再度接触した結果と考えると納得できる気がする。
このように考えるとキジバトは広い意味で単に "野バト" と考えればよいのかも知れない。
キジバトの模様は捕食者対策の隠蔽色になっていると思えるが、カラスバトの備考の Soares et al. (2016) の分子系統樹を見ると Streptopelia 属は 1700-1300 万年前ぐらいの分岐年代となる。Streptopelia 属でもシラコバトやヒメモリバトの模様はもっと単調なので、Streptopelia 属内でキジバトやヨーロッパのコキジバトが分岐してから生じた模様と想像できる。
timetree.org によれば文献は1つあってキジバトとシラコバトの推定分岐年代は 940 万年前ぐらいとのこと。
模様を見分ける色覚に優れた捕食者はやはりタカ類が考えやすいが、現在日本でキジバトを主に捕食しているオオタカの系統は 1200 万年前ぐらいに生まれたもので年代的には一応整合性がある。コキジバトの色彩は北方型である主にオオタカ対策で多分構わないだろう。
ただしオオタカの繁殖分布は北に寄っていて東洋のキジバトの色彩を決めたのは別の南方系のタカ類かも知れない。
-
シラコバト
- 学名:Streptopelia decaocto (ストゥレプトペリア デカオクトー) 18(デカオクト)と鳴くハト
- 属名:streptopelia (合) 首飾りのあるハト (streptos 首輪、首飾り peleia ハト Gk)
- 種小名:decaocto (合) 18 (Gk)
- 英名:Eurasian Collared Dove
- 備考:
streptopelia は#キジバト参照。
decaocto は語末の o が長母音 (octo も同様) でアクセントは1つめの o にある (デカオクトー)。いずれにしてもギリシャ語由来。
タコを意味する英語の octopus は短母音のみだが、ラテン語では語源通り "オクトープース" になる。
鳴き声からギリシャ人は Decoctouri、フランス人は Dixhuit と名付けたと Sibthorp (1795) が記載している。こきつかわれた女中が年に 18 回コインしかもらえないことを嘆いていたが、ゼウス神によってハトに変えられて"Deca-octo"と嘆きの声で鳴き続けたとのギリシャの神話がある。
古代ローマの百人隊長が十字架上のイエスを憐れみ、価格が 18 コインであることを繰り返すことを主張した老婆から牛乳を買って捧げようとしたが 17 コインしか持っていなかった。強情な老婆は呪われて 18、18 としか鳴けないハトに変えられた。17 と鳴くと人間の姿に変えられるのだが、19 と鳴けば世界が終わりに近づく、とのギリシャの伝説がある (The Key to Scientific Names, wikipedia 英語版)。
英名は単に Collared Dove, Collared Turtle Dove, Eastern Collared Dove [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)] もあった。Collared Turtle Dove はコキジバト (単に Turtle Dove と言えばこの種) に対するもの。
Eastern Collared Dove はユーラシア中部からインドなどが基本分布であった時期に英国から見れば "東側" となる。その後バルカン半島から北部を除くヨーロッパ全体に分布をどんどん広げてもはや "Eastern" がふさわしくなくなった。
単形種。天然記念物。
亜種が用いられていたこともあり、森岡 (2003) Birder 17(11): 56 に石垣島で2003年1月に観察されたシラコバトの考察がある。亜種 stoliczkae に似ているが基亜種のシノニムとするのが妥当との見解がある。
参考までに stoliczkae の記載時学名 Turtur stoliczkae Hume, 1874 (原記載) 基産地 Kashgar。Kashgar Ring Dove。stoliczkae はチェコの動物学者でヒマラヤで採集活動を行った Ferdinand Stoliczka 由来。
ビルマの個体群が亜種 xanthocycla とされることもあったが、やはり種に値するとのこと: van Grouw et al. (2024)
On the taxonomic status of Burmese Collared Dove Streptopelia (decaocto) xanthocycla。
ミトコンドリア DNA ではあまり分かれなかったが、核 DNA の解析ではっきり分離された。
xanthocycla は生きた鳥をもとに記載されたもので標本の形で保存されておらず、将来の交雑の危険もあるためネオタイプ標本を定義した。
記載時はシラコバトの亜種だった。リスト次第でシラコバトの亜種。IOC では 11.2 で分離されて Streptopelia xanthocycla。比較的最近まで亜種扱いで、stoliczkae が基亜種のシノニムとされた時期にはビルマの個体群のみがシラコバトの亜種となっていた。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 100 p. 2 によればヨーロッパでシラコバトが分布を広げたのは家禽の餌を横取りできたためとのこと。ヨーロッパでもシラコバトが外来種か否かの議論があった。日本 (埼玉県) での減少要因もいかにも対応している。
-
ベニバト
- 学名:Streptopelia tranquebarica (ストゥレプトペリア トゥランクゥエバリカ) インドのトランケバールのハト
- 属名:streptpelia (合) 首飾りのあるハト (streptos 首輪、首飾り peleia ハト Gk)
- 種小名:tranquebarica (adj) インドのトランケバール Tranquebar の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Red Collared Dove
- 備考:
streptopelia は#キジバト参照。
tranquebarica は外来語由来で発音はよくわからないが特に長母音が生じる理由はなさそうに思える。
Tranquebar の地名はデンマーク人渡来の時期のものでデンマーク語では特に長音はないとのこと。また b は p の音になる (wikipedia 英語版より)。トランケバールは英語経由の日本語読みと考えてよさそう。
原記載 (Hermann 1804) では地名はラテン語で Tranquebaria と記載されている。wikipedia 英語版によれば英国に売却されたのが 1845 年とのこと。まだデンマーク時代だった時期に記載されたものと考えられる。
ここでは短母音のみを採用し、"トゥランクゥエバリカ" とした。
2亜種ある (IOC)。日本で記録される亜種は humilis (小さい、つつましい、地面のなどの意味) とされる。
-
キンバト
- 学名:Chalcophaps indica (カルコパプス インディカ) (東インド会社時代の) インドのブロンズ色ハト
- 属名:chalcophaps (合) ブロンズ色ハト (khalkos ブロンズ phaps, phabos ハト Gk)
- 種小名:indica (adj) インドの (-icus (接尾辞) 〜に属する) 東インド会社時代の地名。備考参照。
- 英名:Emerald Dove, IOC: Common Emerald Dove
- 備考:
chalcophaps は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は含まれないと考えられる。-co- がアクセント音節と考えられる (カルコパプス)。
indica は冒頭にアクセント (インディカ)。
キンバトがあるならギンバトがあるはず、と考えるがこれはジュズカケバトの白色型とのこと (コンサイス鳥名事典)。
6亜種あり (IOC)。日本の亜種は yamashinai (日本の鳥類学者 Yoshimaro Marquis Yamashina 由来) とされるが、世界の主要リストではほとんど認められておらず、基亜種 indica のシノニムとするのが一般的。
種小名は indica で、インドにも分布するため意味の解釈は何の問題もないように見えるが、これは現在のインドではなく東インド会社時代の東インド由来とのこと (#サシバと同様) (wikipedia 英語版より)。
記載時学名 Columba indica Linnaeus, 1758 (原記載) 生息地は India orientalis (東洋のインド) となっている。ここが基産地となるが、マレーシア、インドネシア、フィリピンからインドにかけて基亜種が分布するため、亜種名を与える際にあまり問題が発生しなかったよう。
もしインド亜大陸と東南アジアが別亜種とされることがあれば、インド亜大陸の方の亜種名が変わる可能性がある。
Linnaeus (1758) の記載の1つ上を見ると Columba sinica (無効名とされる) となっていて (東インド会社時代の) インドと中国のそれぞれの地域名を付けただけのよう。
基産地については Chalcophaps indica (Linnaeus, 1758)
に解説があった。East Indies (as India orientali), Salvadori (1893) "Catalogue of the Birds in the British Museum" とのこと。
Stresemann が示している基産地 Amboina (アンボン島 インドネシア東部モルッカ諸島) はシノニムとなった学名の基産地で Linnaeus (1758) の原記載とは異なるとのこと。
Hachisuka (1938) A new Race of Bronze-winged Dove (yamashinai の記載文献)
では台湾のもの (Swinhoe による formosanus。これも現在は通常基亜種のシノニムとされる) と異なると述べている。India, Indo-China, S. E. China, Java と測定値を比較しているが、これらは基亜種とみなす記述になっている。台湾のものはこれらとは異なる可能性があると述べている。
英名は Linnaeus (1758) の記載より早く、George Edwards が "A Natural History of Uncommon Birds" (1743) に "Green Wing'd Dove" と含めたものがあり、Green-winged Dove の英名が別名となっている (wikipedia 英語版より)。
ドイツ語名では Glanztaube など、Glanz (光沢) を主眼とした命名になっている。
天然記念物 (指定名称は「リュウキュウキンバト」)。絶滅危惧 IB 類 (EN)。世界的には懸念なし (IUCN 3.1)。
-
アオバト
- 学名:Treron sieboldii (トゥレーローン スィエボルディイ) シーボルトのハト
- 属名:treron (合) ハト (treron, treronos ハト < treo 怖がって逃げる Gk)
- 種小名:sieboldii (属) シーボルト Philipp Franz Balthasar Freiherr von Siebold (ドイツの医師、博物学者で、日本で 1823-1829年に採集活動を行った) の (ラテン語化した sieboldius を属格化)
- 英名:Japanese Green Pigeon, IOC: White-bellied Green Pigeon
- 備考:
treron は由来のギリシャ語では2つとも長母音。"トゥレーローン" が適切と考えられる。短く読む場合でもアクセントは冒頭になる。
ギリシャ語では treo (トゥレーオー。驚いて逃げる) が語源。
ラテン語 terreo ともつながっており、英語の terror (恐怖) も元をたどればこのラテン語に由来する (wiktionary)。アオバトの学名と恐怖がこんなところでつながっていたとは。恐怖でハトが一斉に逃げる様子を表したものだろう。
sieboldii は規則からは "スィエボルディイ" のアクセント位置と考えられる。人名なのであまりこの読みにとらわれることなく日本語風に sie- を "シー" (より正確には "スィー") と読んでも構わないだろうが最後に i が2つ並ぶことは意識して発音するとよい。
なお鳥の学名に sieboldii の例はほとんどなく、他はヤマガラのシノニムが知られる程度とのこと (The Key to Scientific Names)。
記載時学名 Columba sieboldii Temminck, 1835 (原記載) 基産地 Japan。この記載では和名が紹介されていて Jamo-hato (pigeon de montagne とあるの山鳩の意味。フランス語では "ヤ" の音は Ja と書かざるを得なかったのかも) と Awo-hato (pigeon vert 緑色のハト)。
Siebold の日本探検の結果多くの新種が見つかったなどの記載が詳しく、Siebold への献名も一見納得できる感じがするが、これは日本から別の新種をハトを記載するためにそれぞれ発見者の名前をフランス語名や学名に用いたものと考えられる。
同時に記載された当時 Columba の同属のもう1種は Columba kitlizii (参考) でオガサワラカラスバトのこと。Kittlitz (1832) が同じ標本を用いてすでに記載していたため使われない学名となった。
参考 Mlikovsky (2016) Type specimens and type localities of birds (Aves) collected during Friedrich Heinrich von Kittlitz’s circumnavigation in 1826-1829. Part 2. Specimens in other collections。
Temminck の手元には Kittlitz (1832) の文献はまだ届いておらず、それならば...と考えたのかも知れない。この記載では発見者 Kitlitz への献名とわざわざ書いている (nous le dedions a M. Kitliz, qui fit la decouverte de cette Colombe)。
Kittlitz も Columba 属を用いていたので、記載は知っていたが属名変更のために種小名に新しいものを付けた解釈はここでは考えられない。Kittlitz / Kitlitz の表記の違いは本稿の誤植ではなく、現在ではドイツ語でもフランス語でも Kittlitz と表記される。Temminck が Kitlitz と考えていたものと思われる。知られている用例では kitlizii が用いられているのはこの事例のみとのこと (The Key to Scientific Names)。
おそらく Temminck が日本から2種記載したかったために与えた種小名で、Siebold の業績を妙に褒めているのは後付の理由とも思える。アオゲラと異なり和名を用いなかったのは Awo-hato はフランス語で発音困難で、また Columba kitlizii と対比させるためとも想像できる。Kittlitz の業績を横取りするようなものなのでこちらは献名を使わざるを得ず、Siebold の方も、などの事情も見え隠れする気がする。
Siebold がそれだけ貢献しているなら他にもありそうなものなのに鳥の学名に sieboldii の例はほとんどなく... の説明とも整合し、Temminck 側の事情 (人柄と言うべきか) と考えてよさそう。アオバトならば外見的特徴を表す学名は他にも考えられそうなところだが。
Siebold と Temminck の間で先取り争いがあった例は #ヒレンジャク 参照。
日本から中国南東部、台湾に分布。4亜種あり (IOC)。日本の亜種は基亜種 sieboldii とされる。
[アオバト近縁種の属名の変遷と亜種]
日本産の種のうちではアオバトとズアカアオバトはかつて Sphenurus 属に含まれていたことがあった。
この属は キバラハリオアオバト 現在の学名で Treron oxyurus Sumatran Green Pigeon に対する属名として Swainson (1837) が与えたもの (この種がタイプ種)。
ギリシャ語 sphen, sphenos 楔 oura 尾由来 (スペーヌールス) で中央尾羽が長く巣からはみ出るとの記載 (The Key to Scientific Names)。
比較的最近 1990 年代 - 2000 年代初頭まで使われていた学名で論文などにも見ることができる。
オナガアオバト Treron sphenurus Wedge-tailed Green Pigeon の種小名にも現れるがこの種がタイプ種ではない (記載時学名は Vinago sphenura Vigors, 1832 だった)。
いかにもどこにでもありそうな意味の属名で Sphenura Lichtenstein, 1823 が同じキバラハリオアオバトに対して用いた属名ですでに使用されており無効として Gray が Sphenocercus Gray, 1840 と改名した。意味はほとんど同じで kerkos 尾 (Gk) (スペーノケルクス) (The Key to Scientific Names の Sphenocercus の項目から)。
#ズアカアオバトにあるように Ogawa (1908) はズアカアオバト類にこの属名を用いていたが、アオバトには Treron を用いていた。
ズアカアオバト類については 1840 年以降に Sphenura と Sphenurus は同一ではないと判定されて後者が一時期復活した属名だろう。
男性・女性形の綴りの違いだけで別属として使われている属名に例えば Polysticta (#コケワタガモの属名) と Polystictus (カンムリタイランチョウ Polystictus pectoralis の属名) がある。
sphenocercus もいかにも頻繁に使われそうな種小名で、例えば#オオカラモズに現れる。
Treron の属名は Vieillot (1816) が J. F. Gmelin (1789) を引き継いで ハシブトアオバト 現在の学名で Treron curvirostra Thick-billed Green Pigeon 1種のみに対して与えたもの (記載)。
属をまとめる場合は先取権の原則からこの名称になるのが自明に見えるが、Reichenbach (1853) がブルアオバト 現在の学名で Treron aromaticus Buru Green Pigeon をタイプ種とする属の定義があった (The Key to Scientific Names)。
aromaticus は芳香のあるの意味だが、ハトに芳香のあるわけではなく基産地の Amboina が香辛料の島 (Spice Islands) として知られていたため。しかし英名でも "Aromatic Pigeon" (Latham 1783) として紹介された (The Key to Scientific Names)。
Reichenbach (1853) は何らかの理由によって Vieillot (1816) の用いた Treron を再定義したのかも知れない。現在では Vieillot (1816) のものが受け入れられているが現代の分類では結局この2種は同属となった (タイプ種の定義のみが異なる)。
Peters' Check-list of the Birds もアオバトやズアカアオバトは初版 (1937) から 2nd edition は Sphenurus を使っていたが、ハシブトアオバト、ブルアオバト は Treron 属と別属扱いとされていた。
H&M4 によれば Husain (1958) Subdivisions and Zoogeography of The Genus Treron (Green Fruit-Pigeons) が生物地理学と進化を考慮して Treron 属にまとめ、属以下のレベルで細分することが適当と判断した模様。
分子系統研究を待たずして別属扱いが適当でないと認識されるようになり、Clements の 1st edition (1981) ではアオバトも Treron 属となっており、世界的には Treron 属に統合されたが日本のリストでの扱い変更が少し遅れ、日本の文献では非常に遅くまで Sphenurus が現れた。世界の多くのリストでは早い時期に統合されていた。
この当時の属名を反映した White-bellied Wedge-tailed Green Pigeon の長い英名も使われていた。
アオバトの記載時学名は Columba sieboldii Temminck, 1835。
分子系統解析については#ズアカアオバトの備考に。
Qu et al. (2024) の分子系統樹によればオナガアオバトとかなり近縁。
「アオバトのふしぎ」こまたん著 (エッチエスケー 2004) にアオバトの由来から特異な習性、繁殖などの興味深い情報が満載された本がある。巣を見つけることは非常に難しいようである。
「アオバトのふしぎ」では中国の図鑑に基づきアオバトを4亜種に分けている。現在の IOC も亜種は同じなのでリストしておく:
・sieboldii (日本と中国東部)
・sororius (台湾)
・fopingensis (中国四川省東部から上海南部)
・murielae (中国南部中央からベトナム北部、中部、タイ北部)
「アオバトのふしぎ」によれば sieboldii の中国記録は 1933 年の1例で日本人が持ち込んだ飼い鳥らしいとの見解が中国の研究者により示されているそうである。
また九州以北の日本と台湾は不連続分布を示し、南西諸島にはズアカアオバトが分布する地図が
示されている。この地図では台湾近くの中国の分布を sororius
としている。
sororius を sieboldii を同一と捉える立場もある。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) によれば別亜種とする根拠は Cheng Tso-hsin (1987) だが根拠は弱い (Collar 2004) との記載がある。
神奈川県立生命の星・地球博物館のアオバトのページ。
[アオバトが海水を飲む行動の意義]
神奈川県大磯町照ヶ崎海岸でアオバトが海水を飲む行動はよく知られている。上記「アオバトのふしぎ」にも詳しいが、少なくとも英語圏にはほとんど情報が出ていないようで引用できる英語文献もほとんどないようである (「アオバトのふしぎ」を引用すればよいのだろうがあまりにも "in Japanese" 過ぎるのかも知れない)。
Sundukov and Sundukova (2016)
The white-bellied green pigeon Treron sieboldii in the Southern Kuriles (pp. 4203-4208。極東の鳥類43: 千島列島特集 で和訳が読める。この号にはアオバト情報がかなり含まれている)
に千島でのアオバトの記録があるが海水を飲む行動は観察されていない。
サハリンでは記録があるとのこと: Zdorikov (2016) New data on some rare birds of Sakhalin Oblast (pp. 4038-4042, Smirnov による飲水写真があり、ビデオも撮影されたとのこと p. 4040)。
(千島のアオバト調査の記事) にも解説記事 (2017)がある。営巣は (確認が難しいことはわかっているが) 確認できなかった。
ロシアでも紹介ビデオがあり アオバト (ロシア語) 映像は日本のものだろうか。最もよく調べられている日本でさえも少数の巣が知られているのみとある。小犬のような、あるいはカエルのような声を出すと比喩されており、「笛吹きバト」の異名もあるとのこと。
アオバトは世界でも最も驚くべき鳥の一つで、研究者が将来秘密を明らかにしてくれるかも知れないと結んでいる。
ハト類は一般に塩を好むことは知られていて、レース鳩に塩土を与える必要性が知られている (飼育小鳥用の塩土もあるがこちらはカルシウム補給の意義の方が大きそうである)。我々も塩を好むと言えばそう言えるように思え、
本当に必要な塩分量はずっと低い (無塩文化では一日 1 g で生活している。ナトリウム摂取が少ない場合には腎臓で再吸収される。基本的なメカニズムは脊椎動物で共通のようである) ことも知られているのでここでは考察範囲を野生のハト類とする。
アメリカのナゲキバト Zenaida macroura 英名 Mourning Dove を捕らえる時のおびき餌として塩を使う情報があった。
鉱物を食べる (geophagy) 行動は果実食のコウモリで知られていてミネラルを補給するため、あるいは植物由来の毒を中和するためなどの役割が考えられていたが、Voigt et al. (2011) Nutrition or Detoxification: Why Bats Visit Mineral Licks of the Amazonian Rainforest
によればミネラル補給よりも子育て時に大量の食物を摂食するため植物由来の有毒物質の中和に役立っているのではとのこと。
鳥類における鉱物食についてこの文献に触れられている研究は2つで Brightsmith and Munoz-Najar (2006) Avian Geophagy and Soil Characteristics in Southeastern Peru と
Gilardi et al. (1999) Biochemical Functions of Geophagy in Parrots: Detoxification of Dietary Toxins and Cytoprotective Effects
で前者はどちらかと言えば胃石関連、後者ではオウムに粘土を与えることで植物の有毒物質の吸収が大きく抑制された結果が出ている。
この文脈での研究は多少あるようだが、アオバトの事例とは異なるかも知れない。
Downs et al. (2019) More than eating dirt: a review of avian geophagy
のレビューで6種類の役割が考えられている。系統的には散在して発生しており 2% の種にしか認められずまれな習性のよう。
比較的よく調べられてきたのは陽イオン交換でナトリウムやカルシウムイオンと陽イオンの植物由来の毒物 (例えばアルカロイド) を交換することで毒物を排泄する機能 (他の機能もあるが海水とは関係なさそうなので省略)。
鉱物食は果実食の鳥と関連があってナトリウム補給の意味がある研究が増えてきているとの記述がある。
ハト類での研究例として Sanders and Koch (2018) Band-Tailed Pigeon Use of Supplemental Mineral
が挙がっている。この研究ではオビオバト Patagioenas fasciata 英名 Band-tailed Pigeon を実験に用いているがカルシウムよりもナトリウムを求めているとのこと。例えば卵にはそれなりの量のナトリウムが含まれるので果実食の鳥では食物以外に補助的なナトリウム源が必要である。
水分とカリウムの多い果実では水を大量に排泄するためその時にもナトリウムが失われる。ピジョンミルクを与える際にもナトリウムが失われる。
オビオバトの場合はナトリウムを求めてやってくるとのことで冬にも少ないが観察事例がある。この論文では特に卵やピジョンミルクにナトリウムが必要と考えている。
この研究の中でバードリサーチのアオバトのページ Japanese Green Pigeon [Bird Research News Vol. 8 No. 9 Osaka et al. (2011) 英文]
への言及があり、オビオバトの状況と同様と考えられるが大磯のアオバトでは冬には海水を飲む行動は観察されないとのこと。
週間アニマルライフ (1971) 2 pp. 44-45 にアオバトの項目 (浦本) があるが、これはかなり苦しい内容。原著ではおそらく Fruit Dove が扱われていたものと思われるが、日本で対応種を探すと事実上アオバトになる。アオバトの生態は当時ほとんど知られていなかったはずで、原著で Fruit Dove として一般的に扱われているものをアオバトのように記述した部分があり、どの部分がアオバトなのか海外のハトのことか区別が難しい。
熱帯のヒメアオバトの色は保護色となっている。それを示唆するような巣にいるハトの写真が紹介されていてアオバトのキャプションとなっているがもちろんアオバトではない。
アオバトの巣は 6-7 月ごろ、高い枝のしげみに細い枝を皿状に組まれたそまつなものがつくられる。「鳩の乳」も与えられることになっている。
「アオバトのふしぎ」 pp. 156-160 によれば 1971 年以前のアオバトの巣の確かな目撃事例は永田洋平による 1950-1951 年の3例のみで、巣の高さは 1-5 m で、キジバト同様あまり高い樹上に作られないと記されており、時期も高さも上記記述と矛盾する。「鳩の乳」の観察もこの記録に出てこない。熱帯地方の Fruit Dove の1種の記述をあたかもアオバトのように記したものではなかったのだろうか。
また島育ちのアオバトもいるとして日本の飲水行動の写真が紹介されている。木々の果実をもとめて海を渡り、岩礁に下りて水を飲むと解釈されていた。
同項目の他情報ではリョコウバトやドードーのことも触れられており、原著でも扱う生態情報が少なくて困っていたのだろうと想像できる。翻訳版を作りながらアオバトはほとんど調べられてなくて補足することも少なく困ったなあとなっていたのではないだろうか。
「日本動物大百科」(1997) 4 pp. 22, 23, 25 (浜口) では食物、採食行動、飲水行動などが挙げられているが、繁殖生態などは巣の発見例がまれなことなどから、ほとんどわかっていない、と述べられていた。
[ハト類の飲水行動の由来]
ハト類が水を飲む時に頭を上げずに吸うことができうことはよく知られていて、ピジョンミルクを飲むために発達した行動としばしば説明される。
Hallager (1994) Drinking methods in two species of bustards
によればハト類以外にも水を吸うことができる種類が散発的にあり、カエデチョウ科 Estrildidae、(Spermestidae 現在ではカエデチョウ科に統合されている)、ネズミドリ科 Coliidae、ミフウズラ科 Turnicidae、ノガン科 Otididae で報告例があるとのこと。吸い上げてから頭を上げて流し込む第3の方法もあるとのこと。
カエデチョウ科ではブンチョウがよく知られている [cf. 海老沢 (2024) Birder 38(8): 22-23]。
一般的には少ない水を効率的に利用する乾燥環境への適応と考えられているとのこと。
Cade (1965) Relations between raptors and columbiform birds at a desert water hole
のアフリカでの観察によれば、飲水行動中に猛禽類による捕食が危険で、ハト類はなるべく短時間に必要な水を飲む方法を発達させたと考えられるとのこと。水場に直接降りるハト類はおらず、近くに降りて安全を確認してから近寄るという。
Cade et al. (1966) Drinking behavior of sandgrouse in the Namib aud Kalahari deserts, Africa
がナミブ、カラハリ砂漠でのサケイの飲水を報告している。この行動が系統的に決まっているとの考えは Lorenz (1939) まで遡るとのこと [コンラート・ローレンツ Konrad Lorenz が何を考えていたかも含め、#ハイイロガンの備考も参照]。
Wickler (1961) がカエデチョウ科 (オーストラリアのものだそうでいかにも乾燥地域) や ズグロムシクイ科 Sylviidae の鳥でも見られるとの過去の報告を取り上げ、系統で決まっているわけではないと主張。さらにネズミドリ科でも見つかった。
ハト類の中でも原始的とされたオオハシバト Didunculus strigirostris Tooth-billed Pigeon ではガンのように水を飲むとの反例を示した。
こんなところにもコンラート・ローレンツの動物行動学解釈の流れをめぐる議論があった。
この論文ではサケイ類のことが述べられているが、クロハラサケイ Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse では 150 ml まで飲むことができるという伝説的な報告もある。この論文の観察では1回に飲む量は 1.5 ml ぐらいで7回繰り返し、しばらく間を置いて 3 ml を飲んだという。これが典型的な最大値だろうとのこと。
Cade and Greenwald (1966) Drinking behavior of mousebirds in the Namib Desert, southern Africa
にネズミドリ類についての報告。高温に晒すと同じタイプの飲水行動を示した。ハト類との驚くべき収斂進化としている。
Speckled Mousebirds drinking water by sucking and keeping the head down (チャイロネズミドリの飲水ビデオ)。
特化した舌を利用して吸う行動は蜜を吸う鳥 (ハチドリ類、ミツスイ類) やオウム類で知られている。
こちらは比較的時流に乗っているようで研究をいくつか紹介しておく。
Rico-Guevara et al. (2015) Hummingbird tongues are elastic micropumps 毛細管現象との従来の解釈は誤り。
Rico-Guevara and Rubega (2017) Functional morphology of hummingbird bill tips: their function as tongue wringers 嘴の構造と舌の作用で送り込む。
Hewes et al. (2023) How do honeyeaters drink nectar? ミツスイ類の研究。ハチドリ類と類似点もある。
通常の鳥類が哺乳類のように水を飲まない理由は食道の蠕動運動がないためとしばしば説明されるが、これも正しくないよう。ニワトリの食道蠕動の研究例: Bartlet (1973) Myogenic peristalsis in isolated preparations of chicken oesophagus など。
ハトの研究もあり Fileccia et al. (1984) Primary peristalsis in pigeon cervical oesophagus: two EMG patterns。
ペリットを吐く行動も peristaltic egestion と呼ばれる (Bildstein 2017)。Houston and Duke Gastrointestinal Physiology (レビュー)。
ペリットを吐く行動は胃の動きと食道の逆方向蠕動によるもので、哺乳類の嘔吐や反芻とはかなり違うとのこと [Duke et al. (1976) Mechanism of pellet egestion in great-horned owls (Bubo virginianus)]。
鳥類の食道は調べられている範囲で平滑筋で、哺乳類では横紋筋と平滑筋が混ざっているがその機能的違いはそれほどはっきりしていない。
Edeani et al. (2023) Effect of Inter-swallow Interval on Striated Esophagus Peristalsis; A Comparative Study with Smooth Muscle Esophagus
のように横紋筋の方が急速な反復運動に適しているらしいとの実験結果が報告されている。これは主にヒトの誤嚥に関係して行われた研究。
[アオバトは歩く時首を振らない?]
つい先日コサメビタキの生態を観察していると目の前に鳥が舞い降りた。何とアオバトだった。おかげで至近で歩いたり採食の様子を見ることができたが、ドバトとは違って歩く時ほとんど首を振らなかった。
大きな実を拾って食べていた (飲み込めるかぎりぎりぐらい) ので地上の食物を探して歩いた点はドバトの場合と同じだろう。地上の食物を探して歩く場合は下を見ているので首を振る解釈とは合わないように思える。
映像や動物園で見慣れているハチクマの歩いている状況と比べてみると、アオバトの方がずっと後ろまで見えている感じ。ハチクマは多分ほとんど見えていない。アオバトは首を伸ばして地上の実を拾う (樹上の実を食べる時と同様)。ハチクマはそのような印象を受けず体を動かして獲物に近づくように見える。
この比較が気になったのは #ハチクマ備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] にある Murphy et al. (1995) Raptors lack lower-field myopia に関係があるため。アオバトは地上に焦点を合わせることができていると思われるので、猛禽類はその能力が欠けているので首を振って歩かないとの論理も必ずしも成り立たない感じがする。
系統も関係あるが、ドバトとアオバトの関係の方がハトとタカより圧倒的に類縁関係が近いので樹上性・地上性の生活様式の違いが現れているのだろうか。アオバトも樹上で食物を採ることが基本なので歩く時も樹上採食に似た様式に合わせているのかも。
ハトの首振りについては詳しく調べられていて、アオバトの研究グループもあるのでアオバトの観察例もどこかに載っているかも知れない。独立した観察記録として紹介しておく。
ついでながら座って観察していたら飛び降りてきたので、やはり野鳥観察で姿勢を低くするのは有効と思われる。行動からは地上性捕食者と認識していないものと思われた。
アオバトが飲み込む時はカケスのように食道が膨れ、目一杯食べて飛んで行った (脅かしてしまう恐れがあったのでカメラは取り出さず映像記録はない)。丸のみに一生懸命で味わっているらしい印象は受けなかった。
コサメビタキの音声を記録していたおかげで至近で羽音も記録でき、アオバトの飛び立つ音もやはり他のハト同様大きいことを再度確認できた。
アオバトはしばしば警戒心が強く姿はなかなか見られないと書かれるが、これは声は聞こえるのに見つけるのが難しい意味だろうか。当地 (京都) では 2025 年 4-5 月はアオバトに出会う頻度はかなり高かった。もしかすると冬場に京都御苑などで人慣れしている個体も混ざっているのかも知れないが、繁殖地であっても言われているより簡単に出会える気がする。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 88 p. 20 ヤツガシラは地上で首を振ってハトのように歩くとある。地上を長時間歩く鳥ではむしろ当たり前で、アオバトが首を振らないのが目立ったのかも知れない。
鳥の首振りの進化を研究しているグループは海外にもあり、Santos-Lopes et al. (2025) Automated analysis of bird head motion in unconstrained settings: a foundational study on semicircular canal evolution in archosaurs 高速度撮影されたビデオから自動検出を試みる。
このグループの興味は首を振って歩く仕組みがどのように進化したか。恐竜の動きなど。三半規管の進化を想定しているが研究の方向性が合っているかどうかはよくわからない (化石だと脳の神経核の発達を議論するのはおそらく難しく、三半規管の構造は調べやすいため最初に選ばれているのかも)。
系統研究の副産物として今後多様な種類の首振り運動の情報がわかるかも知れない。研究に役立つビデオを意図して撮影する場合はフレームレートを上げよ、ということになる。
[その他]
Siebold の読み方は多少注意が必要かも知れない。学名の発音は上記でよいと考えられるが、人名を表記する場合標準ドイツ語だとジーボルトとなる。wikipedia 日本語版によればオランダ国籍で入国しており、出身地方言での発音も濁音にならないことが多いそうで、日本語表記は通常使われるシーボルトとした。
ドイツ語ではジーボルトと読まれているだろう。文字から発音がわかるロシア語でも濁音で記載されている。
-
ズアカアオバト (分類次第で学名が変わる)
- 第8版学名:Treron formosae (トゥレーローン フォールモーサエ) 台湾のハト
- IOC 学名:Treron permagnus (トゥレーローン ペルマグヌス) 非常に大きいハト
- 属名:treron (合) ハト (treron, treronos ハト < treo 怖がって逃げる Gk)
- 第8版種小名:formosae (属) 台湾の (formosa 台湾 < ポルトガル語で Ilha Formosa 美しい島 と名付けられた)
- IOC 種小名:permagnus 非常に大きい per- 非常に magnus 大きい
- 英名:Whistling Green Pigeon, IOC: Ryukyu Green Pigeon (備考参照)
- 備考:
treron は#アオバト参照。
formosae は2つの o が長母音で後者にアクセントがある (フォールモーサエ)。
permagnus は短母音のみで -mag- がアクセント音節 (ペルマグヌス)。
IOC では独立種 Treron permagnus (per- 非常に magnus 大きい) 英名 Ryukyu Green Pigeon とされ、Treron formosae 英名新称 Taiwan Green Pigeon に分離された (将来別種とされるならば和名はタイワンズアカアオバトが過去に使われている)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代にはアオバト類は3種に分けられていて、当時の学名で Sphenocercus permagnus (原記載) Amami-Oshima, Okinawashima, Yakushima にリュウキュウアオバト、
Sphenocercus medioximus (原記載) Ishigakishima, Iriomoteshima にチュウダイアオバトの和名が記されていた。
世界の主要リストでは IOC は 11.2 以降、HBW/BirdLife はこの分類を採用。Clements、Howard and Moore は Treron formosae の亜種としている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では後者の扱い。
IOC 14.2 の扱いでは Treron formosae が4亜種、Treron permagnus が2亜種としている。
日本で記録される亜種は permagnus [IOC の扱いでは Ryukyu Green Pigeon の基亜種。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)の和名では亜種ズアカアオバト。過去には亜種リュウキュウズアカアオバトとも呼ばれていた] と medioximus (中央にある) チュウダイズアカアオバト とされる。後者は IOC 扱いでは Ryukyu Green Pigeon の亜種。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではタイワンズアカアオバトを検討亜種として扱っている。
和名ズアカアオバトの由来は後述。日本で記録される(亜)種は頭が赤くないので、IOC の分類に従えば現在の和名が特徴に一致しなくなる可能性が残る。
[ハト類の系統分類]
Nowak et al. (2019) A molecular phylogenetic analysis of the genera of fruit doves and their allies using dense taxonomic sampling が分子遺伝学的研究を行っている。これによれば日本のアオバトもサンプルに入っているが、ズアカアオバトは入っていない。
Treron 属の独立性はこの論文の系統樹からは問題なさそうであるが、日本周辺の関連種がサンプルされていないのでそれらとの関係はわからない。
アフリカの種類である Turtur 属と Oena 属も統合される可能性がありそうである。Treron 属とこれらのグループを含めて "fruit pigeons and doves" または "fruit doves" と呼ばれ、かつては亜科 Treroninae (おそらくアオバト亜科) をなすとされていたが、
分子系統研究で範囲が広がり先取権の原則から亜科 Raphinae (絶滅種ドードー Raphus cucullatus を含む) と呼ぶのが適当とされている (ドードー亜科、かつては独立科とされてドードー科だった。wikipedia 日本語版の出典はやや古いので、この 2019 年論文を参考にするのがよさそうである)。
もしこの分類階層を加えて記述すれば「ドードー亜科アオバト属」のようになる。後述のように 亜科 Raphinae の範囲をもっと狭める (細分化する) 分類もあり、その場合は 亜科 Treroninae の名称が復活する (例えば Boyd の分類)。
「ドードー亜科アオバト属」であればこれはこれで面白いであろう。どのぐらい過去の絶滅種まで現代の分類に取り入れるかは議論があるのかも知れないが、世界の主要リストはドードーを含めている。eBird でももし万一観察できれば報告できる扱いになっているのではないかと思われる。
なおドードーをベースとした系統名は広く使われているが、タイプ標本が指定されていないなど命名規約上の不安定さが残るとのこと: Young et al. (2024) The systematics and nomenclature of the Dodo and the Solitaire (Aves: Columbidae), and an overview of columbid family-group nomina。
系統樹はまたハト類の他の属の位置づけに問題がある可能性を示している。他の文献などををよく調べたわけではないが、Streptopelia 属 (キジバト属) とColumba 属 (カワラバト属) は系統樹上で区別できない可能性がある。
もう少し研究が進めばキジバト属はカワラバト属に統一されるかも知れない (2019 年時点)。これらはこの文献では亜科 Columbinae (カワラバト亜科?) に属する。
Oliver et al. (2023) Oligo-Miocene radiation within South-west Pacific arc terranes underpinned repeated upstream continental dispersals in pigeons (Columbiformes)
fig. 2 に世界分布と分子系統樹があり、Supplementary data (figs. S4, S5) により詳しい分子系統樹がある (系統に関心のある方はぜひダウンロードしてこちらを見て欲しい。ただし伝統的な遺伝子を用いた解析)。
この研究で状況が改善され、Streptopelia 属、Columba 属はそれぞれ単系統をなしており問題ない。
Streptopelia 属、Columba 属ともに系統的には古めで、種分化年代も集中しておらず、特に草原の広がり (例えば C4 植物) に合わせて急激な種分化を果たしたグループではなさそう。
Ptilinopus 属 (クロアゴヒメアオバト) も単系統でなくなっているが、これは包含されている小さな属が統合されるのではと想像される。
Chalcophaps 属 (キンバト) は少数種からなる属で他の属 (Oena, Turtur) に比較的近い。
この部分が気になったのは「野鳥」1994年7月号 (No. 571) にハト類の特集があり、上田氏が果実食のハト類から草原で植物食のハト類が進化した可能性を推定されていたため (pp. 4-7)。以下の考察もこの記事を参考にした。
#サケイの備考のようにハト類を含む古い系統 (Columbimorphae) から乾燥地適応はすでにあったのだろう。
位置づけがまだはっきりしていないが、ハト類の最も古い系統と考えられるクロヒゲバト Starnoenas cyanocephala Blue-headed Quail-Dove / Blue-headed Partridge-Dove (キューバの低地にのみ生息し、絶滅が危ぶまれている) も森林の地上で採食しハト類の生活様式の原型に近いかも。
(後に追記) その後 Oswald et al. (2025) Genomic data reveal that the Cuban blue-headed quail-dove (Starnoenas cyanocephala) is a biogeographic relict
がゲノム解析によりキューバの クロヒゲバト Starnoenas cyanocephala Blue-headed Quail Dove がハト類の早期の分岐の孤立系統で1亜科に相当することを明らかにした。この研究では遺存系統と結論している
(https://www.floridamuseum.ufl.edu/science/unique-dove-species-is-the-dodo-of-the-caribbean-and-in-similar-danger-of-dying-out/ 一般向け記事)。
この研究でハト類 51 属のうち 35 属の分子系統樹が示されており、Treron 属からは2種。日本と共通種ではない。これまでの分子系統樹と特に違うわけではないが新しい解析で参考になる部分があるだろう。
メラネシアからフィリピンの果実食のハト類 (fruit doves) Ptilinopus (ヒメアオバト) 属 がむしろ比較的最近種分化を遂げている。アオバトの系統 Treron とは少し離れている。Ptilinopus 属 は単系統でハト類中でも大きなグループをなすことがわかる。これも "ドードー亜科" に含まれる。
Treron 属はむしろ Turtur 属に近い関係となった。Treron 属そのものは単系統で問題なし。
これらをまとめたクレードの名称は Treroninae: Emerald and Wood Doves, Green-Pigeons (Boyd による。細分する立場の場合はこのクレードを "アオバト亜科" と呼ぶのが適切そう)。
Treron 属の適応放散は 1500 万年前以降と推定される。これらのハトが緑の色彩なのは空からの捕食者対策とする考えがある。広義 Accipiter 属を考えると (#カッコウの備考 [カッコウのタカへの擬態] 参照)、南方系の Tachyspiza 属が東南アジアに分布を広げたのが 700 万年前ぐらい (ただしアカハラダカは小型すぎる)。
狭義 Accipiter 属は日本ではハイタカの分布が重なるがあまり低緯度には分布しない。Astur 属のオオタカも同様。シロハラオオタカ Astur meyerianus Meyer's Goshawk はニューギニア付近では候補となる。
狭義 Accipiter 属、Astur 属 ともに適応放散は遅いので Treron 属以前から存在した捕食者ではなさそう。ハヤブサ類も遅く状況は同様。
クマタカ類などを含むイヌワシ亜科は 1500 万年前以降以降の系統で、特に問題となりそうなクマタカ類は 1000-500 万年前ごろに種分化を遂げている。やはり Treron 属より少し遅そう。より古い系統のチュウヒワシ亜科 Circaetinae、ハチクマ亜科 Perninae、さらに カタグロトビ亜科 Elaninae は時期的には可能性があるが現在ハト類を食べている種類はあまりなさそう。
緑色のハト類の保護色は空からの捕食者が現れてから後に身につけたものか、あるいはチュウヒワシ亜科や
ハチクマ亜科にもハト類を食べる種類が存在したのか。チュウヒワシ亜科やハチクマ亜科 - カタグロトビ亜科につながる系統も強力な絶滅種を生んでいるので可能性は十分ありそう。
小鳥を捕まえるほど敏捷さが要求されないハト類は絶好の獲物で、初期のタカ類でもよい捕食者になっていたのかも。
哺乳類捕食者にとってはもっと見分けにくい色のはずだがアオバト類を捕食する哺乳類をあまり思いつかないのでここでは特に検討していない。
Xu et al. (2021) は分子遺伝学的には Treron 属はあまり研究されていないと述べ、ハシブトアオバト Treron curvirostra 英名 Thick-billed Green Pigeon のミトコンドリアゲノムを解読したものが最初としている
The mitochondrial genome and phylogenetic characteristics of the Thick-billed Green-Pigeon, Treron curvirostra: the first sequence for the genus で、Treron 属と Hemiphaga 属 (ニュージーランドバトともう1種) と類縁関係にあることが示された。
Chen et al. (2022) が オナガアオバト Treron sphenurus 英名 Wedge-tailed Green Pigeon を同様に調べて同様の結論を得ている:
Complete mitogenome of Treron sphenurus (Aves, Columbiformes): the first representative from the genus Treron, genomic comparisons and phylogenetic analysis of Columbidae。
この2論文は (日本には分布しないが) アジアの種を扱っている点は貴重である。しかし Nowak et al. (2019) をよく研究したものかどうかは疑問である。
音声的にも Ryukyu Green Pigeon と Taiwan Green Pigeon の間にそれほど違いがあるわけではないようである。同種にするか別種にするかは現代的なレベルの根拠のない段階で、どちらを採用するのがより適当かまでは議論できないようである。
Oliver et al. (2023) でも同様の位置づけでアオバトとは明瞭に分離できるが、Ryukyu Green Pigeon と Taiwan Green Pigeon は系統樹サポートは不完全。調べられた遺伝情報がまだ少なすぎる模様。
Qu et al. (2024) Mitochondrial Genomes of Streptopelia decaocto: Insights into Columbidae Phylogeny
がミトコンドリアゲノムを用いたハト類系統樹を示しており、現在の Treron 属は単系統でよくまとまっている。1種コアオバト Treron vernans Pink-necked Green-Pigeon は離れた系統で別属になる可能性がある (外見はアオバト類によく似ている)。
Treron 属内ではタイプ種のハシブトアオバトとは少し異なりクレードに属するので (多分必要とされないだろうが) Treron 属を分割するならばアオバトの属の方が変わることになる。
日本産の種に関係する系統ではこの研究では Columba 属が単系統でなくなっているが、日本産でない一部の種を Streptopelia 属に移動することで解決されるだろう。カラスバト、リュウキュウカラスバトはいずれも読まれていて分類変更の要素はなさそう。
Qu et al. (2024) を信用すればコアオバトは分岐年代が古いので Treron 属との類似性は収斂進化になるのだろうか。
[和名の由来]
コンサイス鳥名事典では (当時の分類で) フィリピン産の亜種 T. f. australis は頭頂部が明るい赤銅色で、和名はそれに由来すると述べられている。
しかしこの亜種名は現代の分類ではマダガスカルのマダガスカルアオバト Treron australis の名称であり、Treron formosae の亜種には出てこない (filipinus はある)。
その後の調査で Sphenocercus australis McGregor, 1907 (参考 基産地 Camiguin Id., Cagayan Prov. = Camiguin de Babuyanes, ルソン島の北にある島) と判明。
Sphenocercus 属だった時代は問題なかったが、Treron 属にまとめられるとマダガスカルアオバト (記載時学名 Columba australis Linnaeus, 1771) があるため使えなくなった模様。
そのため Treron formosae mcgregorii Hachisuka, 1952 (原記載) と改名された。
Treron formosae mcgregorii Husain, 1958 の改名もあったが目ざとく気づいた (?) Hachisuka (1952) の方が早くシノニムとなった次第。
Treron 属の表記になってからも australis はしばらく使われていたようなので蜂須賀氏の知見が受け継がれていなかったのかも。
[オオハシバト]
系統解析関係でこちらに含めておく。絶滅したドードー類2種に近い系統となるもので、この系統は地上性が大変強い。
オオハシバト Didunculus strigirostris Tooth-billed Pigeon はサモアの2島のみに生息する IUCN CR 種。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 100 pp. 13-14 によれば主に地上生活で、もと地上に巣を造っていたが、樹上にも造巣することにも慣れたらしく絶滅の危機に瀕したが生き残ったと解説されていた。
この知見は現在でも正しいのかどうかわからないが、地上営巣性から樹上営巣性に変わることがあるのだろうか。あるいは樹上営巣性だったが地上捕食者のいない島で地上営巣性に進化する途上で、まだ後戻りができたのだろうかと考えてしまった。
wikipedia 英語版では 19 世紀に書かれた原稿ではひなは林床にしかいないことが示唆されるが、巣の場所はまだ確認されていないとなっている。Dysoxylum 属の果実に依存していると信じられているがよくわかっていない。
コンサイス鳥名事典によれば肉が美味のため地元の人が捕えていたが、20 世紀後半に銃が使われるようになって乱獲され激減したとある。外来捕食者の影響で樹上営巣するようになった、は外来種を悪者にする一種の都合のよい解釈で、実際は人が食べ尽くしたことがより重要な要因だったのかも知れない。
なぜこのような見解の相違が生じていたのか、そういえば週刊「世界動物百科」の出典はフランス語だった。サモア (かつて西サモア) は 1900-1914 年はドイツが統治、1914-1961 年はニュージーランド統治下で、人為が原因ならばヨーロッパ人の責任が大きいことになり、外来種を主要因としておくのが収まりがよかったのだろう。あるいは生態までねじ曲げられていたかも知れない (あくまで推測)。
wikipedia 英語版の時点では飼育下の個体もなく、2013 年に1羽の若鳥が記録されるまでは若鳥の目撃もなかった。現在のわずかな個体群は高齢個体ばかりではないかと危惧されているとのこと。
1970 年ごろの方がまだ希望が持てたのだろうが、今や絶滅寸前となっている。
もう一つ興味あるのは英名にもある通り下嘴に歯のような突起があって種子を砕くのに役立っていると考えられている点。wikimedia commons に標本写真や骨格の図がいくつかある。
記載時は Gnathodon (gnathos 顎 odon 歯 Gk) と嘴の歯に注目した属名が付けられたがすでに使用されていた属名で無効となった。
ハト類でも嘴のオウム類に似た形状は存在するのだった (#ハチクマ備考[タカ類の嘴縁突起]、#カワセミ備考 [カワセミの嘴先端の形・鳥の寄生虫対策] のフウキンチョウ科ののこぎりの歯のような刻み 参照)。
嘴縁突起・刻歯そのものは系統をたどる材料にはなりそうもない。
Falco (reptileevolution.com) によれば形態学特徴からはこの種はハトの仲間でなく、ハヤブサの仲間に分類されてしまうとのこと。
またこの嘴の形は進化の点からも興味深く、オウム類のような嘴は普通の形の嘴から進化できるのだろうか。#ミサゴの備考で紹介の Jollie (1976, 1977) p. 240 では肉食となってもコウノトリ類の嘴に肉食適応が見られないことからワシタカ目とコウノトリ類の類縁関係は遠いと考えていた。
オウム類とハヤブサ類の嘴の形が似ているのは系統が近いためなのか、それともそれぞれ独立に進化させたものなのだろうか、オオハシバトの事例を見ると改めて考えてしまう。
独立に進化させた解釈であれば、オウム類とハヤブサ類の嘴の形が似ているのは系統関係を表していない可能性がある。
ハワイミツスイの一種であるオウムハシハワイマシコ Pseudonestor xanthophrys Maui Parrotbill でもオウム類のような嘴先端の形となっているが、ヒワ亜科なのでハト類ほどは不自然でないかも。
それともオオハシバトには祖先的な形質が残っているもので、最初の陸鳥類であるハト類の祖先グループ (Columbaves) には肉食にものも含まれていたが、現在のハト類には肉食のものが残っていないため、などの理由も考えてしまう (#カッコウ備考 [Otidimorphae とはいったい何者?] 参照)。
果実食ハト類とは食性があまりに違うので眉唾ものではあるが、猛禽類でもおそらく二次的に果実中心の食性となったヤシハゲワシもあり、ハヤブサ類とオウム類の関係を考えると食性がまったく違うのでまったく荒唐無稽とまでは言えないかも知れない。
オオハシバト、さらに祖先系統と考えられるハシブトアオバト Treron curvirostra Thick-billed Green Pigeon の嘴の形態は、もしかするとハト類祖先に肉食のものがあったが絶滅した痕跡を示している? 何と言っても非常に古い系統なので現在のハト類に至るまでいろいろなことがあったのかも知れない。
猛禽類とハト類は進化過程がだいぶ違う。ハト類は祖先的なゲノムを持っている一方、猛禽類は大規模な染色体再構成が目立つ (特にハヤブサ類、タカ類) など後の時代に体制をかなり変えた可能性がある。猛禽類の曲がった嘴はその結果二次的に生じた可能性もある程度考えられる気がする。高精度ゲノムが解読されれば進化経緯や曲がった嘴を作るメカニズムなども次第に解明されてゆくだろうと期待できる。
しかし 2024 年で Treron 属ミトコンドリアゲノムが初解読の段階ではまだまだ先が長いかも知れない。
-
クロアゴヒメアオバト
- 学名:Ptilinopus leclancheri (プティリノプース レクランケリ) ルクランシェールの足に羽毛のある鳥
- 属名:ptilinopus (合) 羽毛のある足 (ptilon 羽毛 pous 足 Gk)
- 種小名:leclancheri (属) Charles Rene Augustin Leclancher (フランスの外科医、博物学者、探検家) の
- 英名:Black-chinned Fruit Dove (= IOC, or) Leclancher's Dove
- 備考:
ptilinopus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語および他事例から足を表す -pus は長母音と考えられる。-li- がアクセント音節と考えられる (プティリノプース)。
leclancheri は規則通りならば "レクランケリ" のアクセント位置と考えられる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。4亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは taiwanus (台湾の) とされる。
旧別名ノドグロヒメアオバト 英語別名 Black-throated Fruit Dove。
Qu et al. (2024) の分子系統樹 (#ズアカアオバトの備考参照) で Ptilinopus 属に内包される2属の記載年代を調べておいた。
Ptilinopus Swainson, 1825、
Alectroenas Gray, 1840、
Drepanoptila Bonaparte, 1855
となっており、Ptilinopus の記載が古いため内包される属を Ptilinopus に改名するだけで済みそう。
内包される2属を残したままで Ptilinopus 属を分割するとかなりの分割が必要でおそらく現実的でなさそう。
クロアゴヒメアオバトの学名はこのため変わる心配はないと想像される。ただしクロアゴヒメアオバトそのものはこの系統樹に含まれていない。
△ アビ目 GAVIFORMES アビ科 GAVIDAE ▽
-
アビ
- 学名:Gavia stellata (ガーウィア ステールラータ) 星斑のある海鳥
- 属名:gavia (f) 未同定の海鳥で岩場に営巣するカモメの一種か
- 種小名:stellata (adj) 星をちりばめた (stellatus)
- 英名:Red-throated Diver, IOC: Red-throated Loon
- 備考:
gavia は冒頭が長母音でアクセントもここにある (ガーウィア)。
stellata は最初の2母音が長母音で最初の a にアクセントがある (ステールラータ)。stella 星 の冒頭が長母音で、所有の -ata の冒頭も長母音のため。
単形種。英名 loon の由来は古英語 lumme、スウェーデン語 lom、スカンジナビア語 lum などが候補になっている。不具の、ぎこちないなどの意味で、陸上での動作を表したものであろう (wikipedia 英語版)。loon がアメリカ英語、diver がイギリス英語の呼称。
属名の gavia はラテン語でミコアイサを指すとのことで、白と黒で潜って魚を採る海鳥を古代ローマの人たちは区別していなかった可能性がある。
アビ類は 18 世紀までカモ類に分類されていて初期の博物学者は mergus (#カワアイサ参照) または colymbus (未同定の水鳥でカイツブリか? The Key to Scientific Names) と呼んでいた (wikipedia 英語版 Gavia 項目参照)。#ハシグロアビの備考も参照。
ここでは属名の解釈は The Key to Scientific Names に従って「未同定の海鳥」とした。
アビ類はロシア語名では gagara と声にちなんでわかりやすい。ドイツ語 Eistaucher (氷の潜水士)、ノルウェー語、スウェーデン語では islom で氷と上記 lom の合成。スペイン語では colimbo と colymbus が残っている。
ご存じの方も多いだろうが昔の図鑑では先頭に並んでいた。分類の最初に現れるほど "原始的" と考えられる傾向が強く、「アビは原始的なのでしょうか」のような質問に対する回答も用意されていた。分子系統解析で位置づけが最も大きく変わったグループの一つと言える。
[学名の変遷]
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Colymbus septentrionalis Linn. となっており Linnaeus (1766) に記載に基づく学名が長く使われていたことがわかる。
別学名に Colymbus lumme または Urinator lumme が挙げられているがこれは Gavia lumme Forster, 1788 が最初の用例のよう。Foster の名前が出てこないので、Ogawa (1908) の時代にはこの用例はまだ知られておらず後世に使われた学名を挙げていた模様。
Urinator lumme Stejneger, 1882 の用例もある。
おそらく後に Colymbus Stellatus Pontoppidan, 1763 の記載が見つかり、これが最初の記載と認定され現在の学名となった模様。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではすでに現代の学名が用いられている。Gavia 属のタイプ種はハシグロアビ。属名裁定は 1956 年 ICZN によるもの。
septentrionalis は妙に長いが "北の" の意味で "セプテントリオーナーリス" と読む。-alis は形容詞を作る語尾で冒頭が長母音。septentrio (セプテントリオー) が "北" の名詞。septem は数字の7 (英語でも7月の名称に用いられる通り)。trio は耕作用のすき、だが英語 the Plough のようにおおぐま座、こぐま座も指す。
数字の7と合わせてすなわち北斗七星のこと。こぐま座にはおおぐま座をそのまま小さくしたような北斗七星の配列があり (北斗七星を柄杓にたとえて小柄杓とも呼ばれる)、その端が北極星。現代の都会では配列を見ることも難しいが人工の光もない古代にはよく目立っていたのだろう。
学名として残っていれば面白かったかも知れない。
そのように考えると Pontoppidan による "Danske Atlas" の Stellatus "星をちりばめた" の意味の形容詞ではなく特定の星々 (例えば北斗七星や北極星の配列) を意図していた可能性もあるのでは? もしそうであれば "北の星の海鳥" の意味になるのかも知れない。一つの可能性として挙げておく。
lumme は容易に類推できるように古ノルド語でアビを指す Lomr に由来。
英名 Red-throated Loon (ロシア名も同じ意味) と現在の学名の対応がよくなく、何かあるのだろうと想像するとやはり対応する学名があった。
Kessler (1853) p. 68 (#オオハム参照) によれば Colymbus rufogularis Meyer, 1839 とのこと。
この時点では見つかっていた Colymbus stellatus の用例は Gmelin, 1850 の方が遅かった。
A propos des materiels originaux de Cotylurus platycephalus et de Cotylurus variegatus (Dubois 1978) にも情報がある。
Red-throated Diver, colymbus rufogularis の絵画にも現れる。
wikipedia オランダ語版のアビ Roodkeelduiker のページにもシノニムとして登場する。他にはほとんど現れないので有効な学名ではなく一般的にはシノニムとして扱われないものかも知れない。
Colymbus septentrionalis が一般的に使われるようになる前の 19 世紀のある時期にはこの学名が使われていて現在は痕跡を残さないほどに忘れられているが、英名やロシア名に残っているのだろう。
[アビの和名由来考察]
叶内 (2001) Birder 15(6): 91-98 によれば "アビ" の名称は江戸時代中期に存在したとのことだが、"アビ漁" に使われたのが主にシロエリオオハムであったらしいように特定の種類を指したものではなかったらしい。古名かずくとり (潜鳥) などもあったとのこと。
"アビ" は現在も語源が明確でない名称の一つで、ある程度古くからあった鳥の名前であるらしいことは間違いないだろうが、集団を作る性質から "あ" は "集まる" 由来でもよいかも知れない (#カルガモ備考の [和名について] の "あじ" から推定)。
それとは別に学術的に名称を整理する際にいくつかの候補の中から "アビ" がグループの基本名として採用されたのは別の理由があったのだろう。その中で種アビが代表となった理由、また同じグループにアビとオオハムの両方が用いられて一つに統一されなかった理由も特に説明を見つけられなかった。
属名に用いられる Gavia に関係があるかもと思ったがこれはずっと後の話で、当時使われていた学名には含まれていなかった。当時はむしろカモメ類水鳥を指して Gaviae が使われていた。もっともミサゴと水鳥が混同されていたぐらいなので、カモメ類もアビ類も同じように水辺に集まる鳥と思われていたかも知れない。
当時よく使われていた属名は Colymbus で、これは本来はギリシャ語の kolumbis (不明の水鳥) 由来 (The Key to Scientific Names) だったが、ラテン語の辞書を引くと colymbus = 水泳場 (英訳例では swimming bath, place for swimming) の意味 (当時の辞書に何と訳されていたか不明ではあるが) となるので水浴び場と訳したのではないだろうか。"浴び" に相当して過去に存在した "アビ" の名称が選択された可能性がある気がする。
1956 年の ICZN の裁定以降は使われなくなったが、Colymbus の属名は従来非常によく用いられていたので、これはいったい何なのだ、と鳥学者が気になっていたことは間違いないだろう。そして辞書を調べて "水浴びをする鳥のことか" と納得したのかも知れない。
現代の属名解釈では不明の水鳥が現れて単なる水鳥の一種と解釈できてしまうが、これらの語源が詳しく調べられる前はラテン語語義を参考にしたのではないだろうか。
#オオハムの備考の [和名の考察] も参照。
現代の語義解釈では kolumbos は Pre-Greek substrate 由来で、ラテン語の columba (ハト) との語源的関係も指摘されており、また kolumbao (潜る) との関係を指摘する者もある (wiktionary)。
要するに水辺に住むハトぐらいの印象を受ける鳥 (カモやハクチョウなどと区別できるぐらいの意味)、特に潜る鳥をみな kolumbos と読んでいたのではないだろうか。ウミバトの名称にもハトとの類縁性を見ることができる。
[アビ類が地上を歩くのに向かない理由]
Clifton et al. (2017) Comparative hindlimb myology of foot-propelled swimming birds
に下肢の比較解剖がある。足のひれで水中を推進する鳥では下肢の下部しか体外に出ておらず (水中抵抗を少なくして流線型のラグビーボールのような体型になる)、下肢の上部をあまり動かせない。立っている時の体の重心は体外に出た下肢よりはるか上で、動かせる部分が少ないために姿勢をうまく制御できない。
カイツブリ類も同様。
カモ類のように足のひれで水面を推進する鳥ではここまでの特殊化はない。ウ類は中間にあたるとのこと。
潜水能力の非常に高い鳥は足を動かす筋肉の付着部位である膝蓋骨 (patella。膝の皿。現生爬虫類の多くは持たない) や tibiotarsus (脛足根骨。日本語名称はそれほど使われないかも知れない。ヒトでは 脛骨 tibia 腓骨 fibula の用語が使われるが、鳥類では腓骨はかなり退化している。両生類と爬虫類の多くは腓骨と脛骨が同じ太さなので、後ろ足で力強いジャンプができないと wikipedia 日本語版にある)
の近位にある突起 tibiotarsal cnemial crest が発達しているとのこと。
付着する主な筋肉である femorotibialis medius (中大腿脛骨筋) が泳ぐ時に膝の屈曲運動を抑制し、水中を推進する際に足が受ける抗力による膝関節を曲げるモーメントに対抗する働きがあると考えられる。
足の最も大きな筋肉である gastrocnemius (腓腹筋)、digital flexor muscles (趾の屈筋群) も付着し、足のひれで推進する力を生み出している。
骨格だけを解説した書物よりもこのような筋肉も含めたレビューを読むと水中推進への適応がよりわかりやすいだろう。
足で泳ぐ鳥以外にも足の力の必要な猛禽類でもこれら突起は比較的発達しているので骨格写真を見て確認いただきたい。
Manafzadeh et al. (2025) Fibular reduction and the evolution of theropod locomotion
に面白い研究が出ている。鳥類では腓骨はかなり退化していて生体力学にはあまり意味がないと考えられていたが、腓骨と踵が分離することによって鳥類の地上運動に必須の膝関節の長軸まわりの回転に役立っているとのこと。二足歩行への進化の過程で生じたものらしい。確かに系統の近いワニ類と形状が大きく異なる。
Shin et al. (2024) Fast ground-to-air transition with avian-inspired multifunctional legs
鳥を模倣したロボットが主眼となる研究だが、離陸の際に足でジャンプするとエネルギー的に有効であるとのこと。また陸鳥は足をさまざまな目的に使うので足の筋肉に投資している。
さまざまな話に応用が可能そうで、本格的な猛禽類が陸鳥の系統になって生まれた理由 (#ミサゴの備考参照)、器用な足 (#ハチクマの備考参照) からもしかして知能の進化などの鳥類進化全般、
オオタカの飛び出しの初速が遅いことを補う鷹狩りの手法、対してハヤブサがなぜ高低差を利用する狩りに特化したかなど考察にも役立ちそう。
-
オオハム
- 学名:Gavia arctica (ガーウィア アルクティカ) 北極の海鳥
- 属名:gavia (f) 未同定の海鳥で岩場に営巣するカモメの一種か
- 種小名:arctica (adj) 北極の arktikos (Gk)
- 英名:Black-throated Diver, IOC: Black-throated Loon
- 備考:
gavia は#アビ参照。
arctica は短母音のみでアクセントは冒頭 (アルクティカ)。
2亜種あり (IOC)、日本で記録されるものは viridigularis (viridis 緑の gularis のどの) とされる。
Dwight (1918) A New Species of Loon (Gavia viridigularis) from Northeastern Siberia。
[さまざまな学名と英名について]
現在の学名と英名が結びつかないが、これは Colymbus atrogularis Meyer, 1839 の学名を反映したものと想像できる (後述の Karl Kessler による 1853 年のロシア語書物 p. 67 から知った)。これは Colymbus glacialis Linnaeus, 1766 のシノニムとされる
(参考: Gavia glacialis (L.) 1766.)
が、現在は Colymbus glacialis Linnaeus, 1766 はハシグロアビのシノニムとなっている。
ハシグロアビは Colymbus immer Bruennich, 1764 の記載の方が早かったためにこちらの学名が使われるが、当時から 19 世紀に入ってもアビ類の同定に混乱があり多数の学名が使われていたことがわかる。
Hartert (1910-1922) では p. 1459 では Colymbus atrogularis Meyer, 1839 はオオハムのシノニムとした。当時のドイツ語名では Polartaucher と当時の学名で Colymbus arcticus 語義を採用していたが、英語では Black-throated Diver、フランス語で Plongeon a gorge noire と atrogularis に対応する名前となっていた。
ドイツ語名では "極の" の意味になるが、これはアビの Colymbus septentrionalis Linnaues, 1766 (現在はシノニム) と同じような意味になってしまう。アビのドイツ語名は Nord-Seetauber など (p. 1462) があって "北の" を意味する名称が使われていたことも確か。
ドイツ語名でよく似た意味の2種の名前が存在したため、アビについては色彩を用いた Rotkehliger Seetaucher (英名の Red-throated Diver または Red-throated Loon に対応。同上 p. 1462 に現れる) の方が英名などで優先して採用されるようになったのではないだろうか。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば英名と同じ意味のロシア名は Kessler (1847) の用例が最初とあり、おそらくドイツ鳥類学者 Karl Kessler による Rukovodstvo dlya opredeleniya ptits, kotorye vodyatsya ili vstrechayutsya v Evropejskoj Rossii ("ヨーロッパロシアの鳥の識別ガイド" のような意味。見られるのは本の外観まで)。
この書物が見られないかと探したところ同著者による 1853 年のほぼ同じような表題の著書が見つかり、前述の古い学名を知った次第。
Linnaeus などの学名の同定が十分検討されていたのかどうかはわからないが、Meyer (1839) が付けたばかりの学名を用いたと思われる。
現在の学名は Colymbus arcticus Linnaeus, 1758 由来 (原記載)。
[和名の考察]
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Colymbus arcticus Linn. と原記載の学名がそのまま使われており、シロエリオオハムとは別属扱いだが Urinator arcticus の別学名も載せられている。この時点で和名オオハムはすでに用いられていた。
#アビの備考 [アビの和名由来考察] で紹介の叶内 (2001) Birder 15(6): 91-98 によればオオハムに対してシロエリオオハムをコハムと呼んでいたらしいとのこと (p. 93)。大きさは確かに少し違う数字になっているがそんなものを区別していただろうか、というのが正直なところ。
"オオハム" は比較的大型のもの、"コハム" は似た水鳥で比較的小型のものを指していたのではないだろうか。
西洋でも Colymbus をカイツブリ類にも用いていたので、例えば群れをなして潜る習性のはるハジロカイツブリを指していても不思議でない気がする。
どちらにしても "オオハム" が選択されて現在の標準和名と採用されたわけである。"アビ" 類の中でなぜオオハムは別語源の名称で呼ばれたかを考えてみると、オオハムにはいくつもの亜種があってシロエリオオハムが一時期オオハムの亜種とみなされた [例えば Hartert (1910-1922) はこの扱い] ように亜種和名を与える必要があったからではないだろうか。
"なんとかアビ" に統一してしまうと、オオハムに対応する種の亜種名にさらに地名など何かの識別子を追加する必要が生まれて煩雑になる。そのためこの種のみ "オオハム" と呼び分けるようになったのではないだろうか。亜種であれば "コハム" とは呼べない。シロエリオオハムは亜種に対応する名前と考えれば納得できる感じがする。
日本ではシロエリオオハムの方がより一般的な種類なので、"オオハム" を基本種としてシロエリオオハムを派生する名称にしたのは亜種扱いが関係していたのではないかと想像する。
"オオハム" の名称は過去に使われた原義とは異なるかも知れない。参考事項を上げておくとオオハムの学名シノニムに Colymbus macrorhynchos Brehm, 1831 (参考) や Colymbus megarhynchos Brehm, 1855 (参考) があり、いずれも "嘴が大きい" の意味で参考にされたかも知れない。
"オオハシアビ" のような訳名は可能だったかも知れないが諸事情により "アビ" 系統と別になったのだろう。
同系列の Colymbus microrhynhos Brehm, 1855 (参考) "嘴が小さい" 方はアビのシノニムとされた。これも "コバシアビ" のように訳すことが可能であるが、もしこの学名を考慮したとしても基準種なので "アビ" で十分だったと想像できる。
このように考えると選択された "オオハム" の名称の "ハ" には嘴の意味も含まれていたかも知れない。
当時は同じようなサイズの水鳥に Colymbus 属がもてはやされていた時代で、この属の記載が非常に多く、西洋の学問を導入した日本の鳥学者にとっても何のことか想像できなかったものも多かったかも知れない。Ogawa (1908) で近縁種が別属扱いになっていることからも統一描像がなかったらしいことが想像できる。
ある程度分類が落ちついたのはその後で、属名統一はさらに後の時代であった。
-
シロエリオオハム
- 学名:Gavia pacifica (ガーウィア パーキフィカ) 太平洋の海鳥
- 属名:gavia (f) 未同定の海鳥で岩場に営巣するカモメの一種か
- 種小名:pacifica (adj) 太平洋の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Pacific Diver, IOC: Pacific Loon
- 備考:
gavia は#アビ参照。
pacifica は "パーキフィカ" (#アマツバメ参照)。
単形種。かつてはオオハムの亜種扱い (当時の学名 Gavia arctica pacifica) だった。American Ornithologists' Union 5th edition (incl. 33rd suppl.) までこの学名が使われていた。1985 年 AOU が別種に分離。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではこの学名を用いており、ロシア名で "白い首のオオハム" または "太平洋のオオハム" の名前となっている。後者は学名または英名由来と考えられる。前者は和名と一致するがどちらが早いかは不明。ウクライナ語も同様で、スロバキア語では和名とほぼ同じ意味になっている (対応英語 white-naped)。
#オオハムの英名や (現在使われていない) 学名に対応して付けられた名称かどうかはわからないがオオハムの場合のロシア名は学名に対応した "のど (そのう)" が用いられ、シロエリオオハムでは "首" が用いられていることから起源は違うと思われる。
Dwight (1918) A New Species of Loon (Gavia viridigularis) from Northeastern Siberia にもヒントがあり、
Turkestan のオオハムの新亜種 suschkini はオオハムの基亜種より後頭部から首が淡色だが Urinator pacificus Lawrence (シロエリオオハムの当時の学名) ほど顕著ではないとある。当時から後頭部から首の色彩がオオハムとの違いと認識されており、それが命名の由来と考えられる。
この文献の記述からもオオハム類の識別などの記述はロシアの文献で主に行われていたことがわかる。後頭部から首の色彩であるために "のど" ではなく "白い首" (ロシア名)、"シロエリ" (和名、スロバキア語) などの名前になったものと想像できる。
この文献では Striped Diver (縞のあるオオハム) の英名がオオハム類の総称として使われていた。肩や背中の縞模様を指しているよう。記述から後頭部から首の色彩の違いは冬羽 (ないし秋の渡り時期) に対して与えられたもののよう。ピーターソン方式的な識別点ではなくなかなか難しい違いを指している。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも Urinator pacificus (Lawr.) の学名で載っている (Hakodate) が和名は空欄になっている。
Urinator 属はハシグロアビをタイプ種として Lacepede (1799) が用いたもの。後に Gavia 属に統合された。
ラテン語 urino (ウーリーノー。潜る) 由来で "潜るもの" (ウーリーナートル)。名詞 urina は英語 urine と同じで尿の意味。語源はイタリア祖語の *urinos (水の) で "潜る" も尿も水に関係することは確かに共通している。
記載時学名 Colymbus pacificus Lawrence, 1858 (原記載)。一時期 Urinator 属に編入されたことがわかる。
-
ハシグロアビ
- 学名:Gavia immer (ガーウィア イムメル) ハシグロアビ
- 属名:gavia (f) 未同定の海鳥で岩場に営巣するカモメの一種か
- 種小名:immer (外) ハシグロアビ ノルウエー語
- 英名:Great Northern Diver (or) IOC: Common Loon
- 備考:
gavia は#アビ参照。
immer は外来語で発音がわからないが "イムメル" と推定される。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
記載時は属名 Colymbus が使われており、この属はアビ類の他にカイツブリ類も含んでおり、動物命名法国際審議会が Gavia 属をアビ類に与えた 1956 年まで使われていた (wikipedia 英語版)。
記載時学名 Colymbus immer Bruennich, 1764 (原記載)。
The Key to Scientific Names にはもう少し詳しい説明があり、Linnaeus の用いた Colymbus 属はオオハム、カンムリカイツブリなど3種類の (現在 Podiceps 属の) カイツブリ類を含んでいた。Linnaeus はタイプ種を指定したわけでも意図を示す記述も残さなかったとのこと。
Brisson (1760) が Colymbus をカイツブリ類、Mergus をアビ類に用いる提案を行って、この属の First Reviser の役割を果たしたかのように見えたが、Brisson は二名法による分類を採用しておらず、Linnaeus の仕事を引用しているわけでもないので First Reviser には値しないと書いてある。
改めて見てみると Genus Colymbi,
Genus Mergi と属定義はある (一覧)。
Colymbus は Linnaeus がすでに用いた属名であったため、Brisson (1760) が新たに提唱した属名 (Accipiter など) とは異なる扱いになったものと考えられる。Brisson (1760) 由来で認められた属名は多数ある。
属新規記載と既存の属の First Reviser の場合は扱いが異なるらしい。
Latham (1787) は Colymbus をアビ類に、Podiceps をカイツブリ類に用いた。この属名が長年標準的に使われていたが、1915 年には BOU が問題を提起した。ICZN が 1956 年に Colymbus を用いない判断を下した。
なお Urinator Lacepede, 1799 の属名 (ハシグロアビがタイプ種) も用いられていて Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも登場する。
これは urinator (潜るもの) < urinare (潜る) の意味。
種小名の immer (ノルウエー語より) に近い他言語名はアイスランド語の himbrimi があり、語源をたどるとスウェーデン語 immer/emmer (灰) に、あるいはラテン語 immergo (浸す) または immersus (沈んだ) に由来する可能性があるとのこと (wikipedia 英語版より)。
ドイツ語の immer (常に) と同じ綴りであるが語源の関連性はないようである。
普通に使われる単語ではないようだが英語 immer もアビ類を指す。
和名はかつて使われていた英名 Black-billed Loon (Yellow-billed Loon に対する名称か) に由来すると想像される。
Young Guns (2017) Birder 31(2): 44-47 にハシジロアビとハシグロアビの識別が出ている。
Common Loon の英名が示すように世界的にはハシグロアビが普通種で、ハシジロアビよりもデータはずっと豊富にあるが、日本ではハシグロアビの方がずっとまれ。
Gayk et al. (2020) Genomic insights into natural selection in the common loon (Gavia immer): evidence for aquatic adaptation
にゲノム研究と正の選択を受けている可能性のある遺伝子候補が述べられている。当時はゲノムが読まれている種類はまだ少なく、同様に潜水して採食するペンギンとの比較や海水でのイオン環境に適応する遺伝子などが中心になっている。
-
ハシジロアビ
- 学名:Gavia adamsii (ガーウィア アダムスィイ) アダムスの海鳥
- 属名:gavia (f) 未同定の海鳥で岩場に営巣するカモメの一種か
- 種小名:adamsii (属) アダムスの (ラテン語化して -ius を属格化) 発見者、英国の船医 Edward Adams
- 英名:White-billed Diver, IOC: Yellow-billed Loon
- 備考:
gavia は#アビ参照。
adamsii は "アダムスィイ"。
和名はイギリスの英名の White-billed Diver 由来と推定される。アメリカの英名が Yellow-billed Loon。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Hasujiro-abi の表記になっていた。
単形種。
△ ミズナギドリ目 PROCELLARIIFOMES アホウドリ科 DIOMEDEIDAE ▽
-
コアホウドリ
-
クロアシアホウドリ
- 学名:Phoebastria nigripes (ポエバストゥリア ニグリペース) 足の黒いアホウドリ
- 属名:phoebastria (f) 女性の予言者のような鳥 (phoebastris (adj) 予言者のような -ia (接尾辞) 質を表す phoebas (f) 女性の予言者)
- 種小名:nigripes (adj) 足の黒い (niger (adj) 黒い pes (m) 足)
- 英名:Black-footed Albatross
- 備考:
phoebastria は#コアホウドリ参照。
nigripes は e が長母音で冒頭にアクセントがある (ニグリペース)。
学名、英名、和名ともによく一致する。和名は英名の訳か。
単形種。
気候変動の影響を大きく受けている種。These animals are racing towards extinction. A new home might be their last chance (Nature のニュース 2023)。
ハワイのクロアシアホウドリの移住が行われている。海水面に近いコロニーではすでに海面上昇と嵐によって多数のコロニーが失われている [出口 (2019) Birder 33(7): 32-33 にチャタムアホウドリと合わせて言及がある]。
同じニュースで扱われているオーストラリアの希少カメの場合について、科学者や保護団体には悩みもある。移住はほとんど最後の手段であり、費用もかかりリスクもある。移住が行われるカメの場合は (現時点で) 冷涼な気候で繁殖できるか未知の点がある。生育に非常に時間がかかるので成否が出るまでに (生息地の消失は危急の課題にもかかわらず) 長い年月を要する。
-
アホウドリ
- 学名:Phoebastria albatrus (ポエバストゥリア アルバトゥルス) アホウドリ
- 属名:phoebastria (f) 女性の予言者のような鳥 (phoebastris (adj) 予言者のような -ia (接尾辞) 質を表す phoebas (f) 女性の予言者)
- 種小名:albatrus (合) アホウドリ (Albatros アホウドリ 独)
- 英名:Short-tailed Albatross
- 備考:
phoebastria は#コアホウドリ参照。
albatrus は外来語のため発音はよくわからないが、規則通りに読めば -bat- がアクセント音節 (アルバトゥルス)。ドイツ語の Albatros や英語の albatross は冒頭がアクセント。フランス語では特にアクセントはないが、語末は長音 (アルバトゥロース)。英語でも語末を長音で読む発音もある。
英名の Short-tailed Albatross は Diomedea brachyura Temminck, 1836 (記載, 図版)
の学名やフランス語名 Albatros a courte queue (尾の短いアホウドリ) または Albatros trapu、
さらに "Fauna Japonica" で用いた Diomedea brachyura に由来すると考えられる (図版) に由来すると考えられる。
Temminck (1836) の記載では和名 Ga-ran-tsjoo が紹介されている。ガランチョウの古名は現在ではハイイロペリカンを指すとされている (#ハイイロペリカン参照)。
生息地は meres a l'orientt du Japon, et dans le voisinage des iles Liou-kiou, vers le sud (日本の東側の海や琉球から南の方)。
当時はフランス語名で l'albatros trapu と呼ばれていたようで、trapu は大きくてずんぐりして力強い人や動物を指す形容詞とのこと。名称からは尾が短いことを意味したいことはわかるがこの部分の本文中には記述が見当たらない。
アホウドリ類の解説 の部分には Buffon が l'albatros de la Chine (中国のアホウドリ) と呼んだものと同じとのこと。
Diomedea chinensis Temminck, 1820 (参考) の用例があり、Temminck (1836) より早かった。2番めに早い学名で Pallas (1769。出版年は現代の解釈による) の記載が有効と認められなければ "中国のアホウドリ" の学名となっていた可能性もある。
Buffon が Diomedea brachyura のラテン名を与えたとのこと。Temminck が初めて "尾の短い" と呼んだものではなく Buffon の名称を引き継いだ模様。
Buffon がどのように記したかまではわからないが、参考までに同じ書物で 海鳥の分類 の部分でネッタイチョウ類に Paille-en-queue の (尾がストローのような) と分類しているので、"尾の短い" は海鳥の中でネッタイチョウ類と対比したものかも知れない。
Diomedea albatrus Pallas, 1769 (原記載) 基産地 off Kamchatka (カムチャツカ沖) の方が早いために Temminck の学名は残らなかったが、英名に (あまりふわさしくない?) 痕跡を残すこととなった。
なお Temminck 自身の用例では Diomedea brachiura Temminck, 1827 (参考), Diomedea brachiura Temminck, 1835 (参考) ともに綴りが違っているとのこと。
brachyura はその訂正とのこと (参考)。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で2種に分離され、Phoebastria albatrus は センカクアホウドリ、もう一種は学名未定の和名アホウドリとなる見込み。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に対してこの提案が出されていたが、その段階ではどちらが Phoebastria albatrus を引き継ぐか不明であったため保留とされた。
第8版では結果的に分離は行われず、Phoebastria albatrus はアホウドリのままで単形種の扱い。
江田・樋口 (2012) 危急種アホウドリ Phoebastria albatrus は2種からなる!?、Eda et al. (2020) Cryptic species in a Vulnerable seabird: short-tailed albatross consists of two species、
Yamasaki et al. (2022) Neotype designation of the Short-tailed Albatross Phoebastria albatrus (Pallas, 1769) (Aves: Procellariiformes: Diomedeidae)
タイプ標本が失われているためかつて記載された Phoebastria albatrus がどちらを指すかわからなくなっていた。ここでネオタイプ標本を提示し、尖閣諸島で繁殖するより小型種を Phoebastria albatrus と再定義した。
鳥島などのより大型のもう1種については albatrus のシノニムから選ばれると思われるが、まだ確定できるまで (文献) 調査が進んでいないということであろう。尖閣グループの鳥は鳥島も少数訪れるが行動も異なり、自身と同じグループの個体とつがいになるのを好むとのことである
[Eda et al. (2016) Assortative mating in two populations of Short-tailed Albatross Phoebastria albatrus on Torishima。
江田 (2021) Birder 35(6): 34-35 に「アホウドリは2種いると解明!」の記事がある。
Avibase (2024.10 時点) ではネオタイプはまだ取り入れられておらず、Pallas (1769) のまま基産地は off Kamchatka となっている。
Royle et al. (2022) Documenting the short‐tailed albatross (Phoebastria albatrus) clades historically present in British Columbia, Canada, through ancient DNA analysis of archaeological specimens
はカナダのブリティッシュコロンビアの古生物標本を調べ、鳥島グループ (Clade 1) が乱獲以前の過去にはずっと訪れていたが、少数は尖閣グループ (Clade 2) に属することを示した。両グループ (新分類では種) の分布は乱獲前においても違っていたことを意味する。
記載論文が発表されれば英名もいずれ修正されると思われる。
Huynh et al. (2023) Whole-genome Analyses Reveal Past Population Fluctuations and Low Genetic Diversities of the North Pacific Albatrosses
が北太平洋のアホウドリ類5種のゲノムを解読している。主な目的はコアホウドリとクロアシアホウドリの関係と歴史的な個体数変動を調べるもの。ベーリング海のアホウドリは外群の扱いで読まれている。
アホウドリのゲノムは 2020 年にもう1例 (CEBS in NIES Japan 国立環境研究所) が読まれている。
実効個体数変動は最終氷期の水深の低い状況で生息に適する海岸線が増えて最大となったがシロハラアカアシミズナギドリはそのピーク時期に減少し、気候変動により適した繁殖場所が減少したことや食物の減少に対応していると解釈されている。これらアホウドリ類全体で免疫に関係する MHC 多様性が非常に低く、ほとんど単形に近いとのこと。
海水浸透圧に対する適応は MYL12B, CDC42EP3 などの遺伝子に対する選択圧として現れているとのこと (浸透圧が高い外部環境では細胞骨格の維持機能が重要である。なるほど。さらにこれら遺伝子機能は tidal marsh sparrows で調べられているとのことで、スズメ目でも塩分環境への適応が遺伝子レベルで知られている模様。トゲオヒメドリ Ammospiza caudacuta Saltmarsh Sparrow のような種がある。詳細は引用文献参照)。
「アホウドリは2種いる」話はいったいどうなったのかと思って調べてみたが、上記 Royle et al. (2022) は配列が 141 bp と大変短く、BLAST で解析しても系統分離が難しいレベル (そもそも無理と言われればごもっとも)。一致率も 99% を超えている。
もう少し長い cyt b OK077985.1 を使ってみると2系統に分かれるように見えるがアホウドリ内の一致率は 98% を超えている (この解析サンプルに問題の2種が含まれるかどうかは不明)。
Eda et al. (2020)
Cryptic species in a Vulnerable seabird: short-tailed albatross consists of two species が2種を示した論文で、mtDNA CR2 domain I (341 bp) とこちらもかなり短いものだった。BLAST を試してもあまりよくわからなかった。
この論文の系統樹には現れないアンティポデスアホウドリ Diomedea antipodensis Antipodean Albatross も比較的近い位置に現れる。この配列で Phoebastria 属と Diomedea 属がうまく分かれないようなので種分割の指標として適切かよくわからない感じがする。
種内の遺伝的多様性が高いことは確かだが2種に相当するかは現状遺伝情報ではまだ何とも言えない気がする。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に対して和名「オキノタユウ」への改名を求める意見も出されたが、変更した場合への影響が大きいと考えられるため変更しないとの見解になった (詳しくは原文参照)。不適切名称の改名の事例については#クロハゲワシの備考 [ハゲワシ類の名称や迫害、改名] も参照。
長谷川 (2005) Birder 19(4): 26-27 はオキノタユウ (沖の太夫) の名称を解説し、記事全体もこの名称で記述している。
「オキノタユウの島で: 無人島滞在 "アホウドリ" 調査日誌」(長谷川博 偕成社 2015) は定年退職 (2014) に際してまとめられた本で、プロローグが「アホウドリからオキノタユウへ」となっている。自身が図鑑の名前を見て子ども心にもひどい名前をつけられた、かわいそうな鳥と思ったこと、
1990 年代保護計画を小学校で紹介する際にデコイを見せると子どもたちがアホウと鳴くと考えたエピソードなどが語られている。この鳥の地球上での再生に見とおしが立った時点が、もっとふさわしい名前に変えるのによいのではないかと考えたことが述べられている。
本稿では長谷川氏の見解をふまえ、和名索引に別名として挙げさせていただくこととした。
天然記念物。絶滅危惧 II 類 (VU)。IUCN 3.1 VU 種。
[語源や関連する用例]
種小名の由来は Albatros アホウドリ 独 とされ、The Key to Scientific Names にもそのようにあるがなぜドイツ語なのか今一つすっきりしない。Pallas (1769) の記載より 属名 Albatrus が先に使用されていて (Brisson 1760。現在は使われない属名) こちらはフランス語 albatros 由来とある。
言語出典までは必ずしも明確でなくて、ドイツ語でもフランス語でも albatros が同じように使われていて、記載者がドイツあるいはフランスだったのでそれぞれの言語由来と判定したものと想像できる。
何語由来かが問題になるのは名詞の性を決める必要があるためと知った。#ツリスガラ備考参照。ドイツ語 Albatros フランス語 albatros はいずれも男性名詞だったためこの場合は問題なし。
ドイツ語の Albatros の由来は航海士の英語から入ったとのこと (wikipedia ドイツ語版より)。
スペイン語やポルトガル語の alcatraz で、現在は一般にはカツオドリ類を意味するが、もとは大型の水鳥、特にペリカンを指していたものが変形したと考えられるとのこと。
スペイン語やポルトガル語の alcatraz はアラビア語の al-qadus 水車の水をくむバケツ部分に由来し、ペリカンののど袋を連想されたらしいとのこと。あるいは al-ghattas "海のワシ" に由来すると考えられる (Etymology Online)。
alba- (albus) がラテン語で白の意味のため、おそらくこの影響を受けて語形が大きく変化したのではないかとのこと。
英語ではミズナギドリ目の鳥を指して使われており、以前にはグンカンドリ類も指していたとのこと。
フランス語の albatros も同じ語源の説明が書いてあってどこから入ったかは明確でなかった。
wikipedia 英語版では In Hawaiian mythology, Laysan albatrosses are considered aumakua, being a sacred manifestation of the ancestors, and quite possibly also the sacred bird of Kane.
Japanese mythology, by contrast, refers to the short-tailed albatross as ahodori, "fool bird", due to its habit of disregarding terrestrial predators, making it easy prey for feather collectors
とハワイではコアホウドリが先祖を表す神聖な鳥との神話があるが、日本では "ばかな鳥" と扱っていて対照的であると記載されている。
同じページの西洋文化のところでは the most legendary of all birds (最も伝説的な鳥) で、神の創造の汚れない美しさを表したとされた。船乗りが実際には食べていたが、撃ったり殺したりすることは凶事につながると信じられていた。
死んだ船乗りの魂が宿っているとして捕まえたが放した事例などが紹介されている。
伝説から転じて、albatross の語は逃れられない心理的な重荷 (呪い) の意味にも使われるようになった。出典は "The Rime of the Ancient Mariner" (1798) の詩からとのことだが一般的に使われるようになったのは 1960 年代からとのこと。現代でもさまざまな映画などで扱われる題材で、2011年には逃れられない重荷を表した "Albatross" という題の映画も英国で作られた (wikipedia 英語版)。
和名に関しては The rare 'idiot bird' (Tobias Hayashi 2019) が語源を紹介している。英名の Short-tailed Albatross も (尾が短いことは他の Phoebastria, Diomedea 属でも同じなので) 同様に silly (ばかげている) としている (注: 英名の方はおそらく現在使われていない Temminck の学名由来)。
使われている What's in a name? は直訳すると「名前に込められたものは?」となるが、シェークスピアのロメオとジュリエットが由来らしい (名前というものにはどんな意義があるのか? とジュリエットが自問自答した部分。a rose by any other name どんな名前で呼んでもバラ、と続く)。
名前の意味を説明するとともに、掛詞のように用いておよそ実体を表していない和名であることを伝えたいのだろう (also silly のところで伝えたいことがわかる)。
What's in a name? のフレーズは学名解説でもしばしば現れる。ふさわしくない学名が付いてしまったが規約上変えられなく実体を反映しないものになっている場合を指す。
Barwell (2012)
What's In A Name? What Names For Albatross Genera Reveal About Attitudes To The Birds (この文献は属名由来などの解説にもなっている) では、
英語の mollymawk (Thalassarche 属などの一般名: オランダ語で mal ばか + mok カモメ 由来説がある)、gony/gooney (北太平洋の albatrosses を指した英語で OED では 1957, 1966 年にも用例がある) などとともに
also being the meaning of the Japanese words, aho-dori and baka-dori,
"fool-bird", for the Short-tailed Albatross (Austin 284).
The attitudes lying behind these sorts of names are those which legitimated the unrestrained exploitation of the environment, for profit,
sport, or other motives, in the nineteenth and twentieth centuries.
19-20 世紀の節操ない自然搾取時代の態度が残されたものとしている。
この種の復活物語を英語に翻訳された The Recovery of the Short-Tailed Albatross: A Preservation Success Story (Ishi Hiroyuki 2017) 記事では "屈辱的な" を derogatory と訳してある。
"アホウドリ" の名前は輸出され、何と海外 (ベトナム) でも使われていた: Galapagos Aho Dori - Wikipedia。
ロシア語名では belospinnyj al'batros (背の白いアホウドリ) で、対応する学名が見当たらないので独自路線に見える。カムチャツカや千島列島では記録されるのでロシアでの扱いを見ておくことは意味がある。
wikipedia ロシア語版によれば迫害の歴史のかなり直接的な表現があり、1886 年に日本に会社が設立されて 1902 年までのわずか 15 年の間に 500 万羽が根絶 (絶滅) させられたと記されている。
"乱獲" よりもさらに強い意味の語が用いられている。当時の状況は日本語書物でも触れられているのでさらに詳しいことを知りたい方は簡単に調べることができる。例えば「日本の希少鳥類を守る」(京都大学学術出版会 2009) の第2章で出口智広氏が文献も紹介して取り上げられている。
シジュウカラガンや危なかったルリカケスもみなこの時代の犠牲者だった。
羽毛産業に待ったをかけた英国の RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) が設立されたのは 1889 年。Emily Williamson が 1889 年に設立した The Plumage League を母体の一つとして 1891 年結成。設立当初のメンバーは全員が女性だったとのこと (wikipedia 英語版から)。
RSPB の物語を描いた "For the Love of Birds: Story of the Royal Society for the Protection of Birds" (Samstag, RSPB 1988) の第2章タイトルは Those formidable women だった。
wikipedia ロシア語版によれば 2010 年のレッドデータブックシリーズの2ルーブル硬貨でアホウドリが取り上げられたとのこと (硬貨写真あり)。
[鳥の繁殖開始年齢と繁殖様式の関係]
Taylor and Prum (2023) Social Context and the Evolution of Delayed Reproducytion in Birds に preprint 段階であるが繁殖開始年齢と繁殖様式の関係の研究結果がある。
古典的な生活史戦略はできるだけ早く繁殖を開始する選択が働くはずだが、発育が可能であれば繁殖開始を遅らせる戦略も有利になり得る。鳥類・哺乳類で体のサイズと繁殖開始年齢の相関はこれまで知られていたが、鳥類はほとんどの場合すぐに成鳥と同じ大きさになるのでこの説明は直接適用できない。
いくつかの種においては体の発育ではなく行動 (社会行動、採食行動など) の発育に時間がかかり繁殖開始が遅れる例が報告されている。オナガセアオマイコドリ Chiroxiphia linearis Long-tailed Manakin は体重 20 g しかないが、メスは1-2年めに繁殖するののに比べ、オスは身体の発育が終わっても社会的順位を確立し、オスの集団ディスプレイを発達させるのに 10 年を要するとのこと。
共同繁殖を行ったりやレックを作る鳥でレックでの雌雄の役割に対応して雌雄で繁殖開始が異なることが最近明らかになった。
Ancona et al. (2020) Sex differences in age‐to‐maturation relate to sexual selection and adult sex ratios in birds によれば一夫多妻、オスの方が重い、集団の性比がメスに偏っているほどオスの繁殖開始が遅れる傾向が見られた。
Taylor and Prum (2023) は調査範囲を広げて系統・生活史と繁殖開始年齢の関係を調べたもの。
コロニー性の鳥で繁殖開始年齢の遅れが大きく、共同繁殖でも弱い傾向があり一夫多妻・一妻多夫の性差の傾向も確かめられたが。生態の多様性が大きく、簡単なカテゴリー変数を用いたモデルでは系統モデルを取り入れても現実を説明するのは十分ではない可能性がある。
コロニーで繁殖するハイガシラアホウドリ Thalassarche chrysostoma Grey-headed Albatross の 13 年、共同繁殖をするヒゲワシで 10 年などのモデル推定値が得られた。ワタリアホウドリの野外研究では 11 年とのこと。
繁殖開始年齢と繁殖様式を含めた系統樹が示されているのでご覧いただきたい。
データは Data and code repository for the manuscript: Social context and the evolution of delayed reproduction in birds
にあるので詳しく見ていただければ興味深い情報がみつかるかも知れない。文献から繁殖開始年齢を調査した一覧が data_raw_2023-07-23.xlsx にある。
Schoenjahn et al. (2022) Delayed juvenile behavioral development and prolonged dependence are adaptations to desert life in the grey falcon
によればオーストラリアのハイイロハヤブサでは体サイズから推定すると 12 か月で繁殖可能になると考えられるがその時期でもまだ親と一緒にいるとのこと。他の Falco 属に比べてこの種では行動発育が特に遅い。オーストラリアの暑く乾燥した夏を乗り越えて生まれたその年に繁殖を始めても生存する可能性は極めて低いための特徴と考えている。
[海鳥の翼の上面はなぜ黒い]
Rogalla et al. (2021) The evolution of darker wings in seabirds in relation to temperature-dependent flight efficiency
海鳥の翼の上面は黒っぽいものが多いが、これは空気が熱せられることによって揚力/抵抗の比率が上がり、長距離の滑空に有利であるとの解釈がある (もちろん紫外線防御、摩耗耐性、外部寄生虫耐性など他にも要因があるだろう)。この研究では滑空時の沈下速度との相関、風洞実験でその効果を実際に確かめた。
カツオドリ類で若鳥で黒く、成鳥で一部白くなるものがあるが風洞実験での飛行効率への影響は翼の下げ角が大きい時に認められた。
黒い翼の航空力学的利点は長距離を渡る鳥や長距離を羽ばたかず飛ぶコンドルなどにも同様にあると考えられるとのこと。ウ類からカモメ類までを含む水鳥で調べられているので図を見ると他にも思いつくことがありそう。
Hassanalian et al. (2017) Role of wing color and seasonal changes in ambient temperature and solar irradiation on predicted flight efficiency of the Albatross
によれば季節で色の変わるアホウドリ類でも黒い色の方が飛行効率がよいいとのこと。
Goumas (2022) Dark wing pigmentation as a mechanism for improved flight efficiency in the Larinae によれば羽ばたき飛行のカモメ類でも成り立つとのこと。風切先端の黒色も翼面荷重 (wing loading) と相関がある。
大型種ほど翼面荷重が大きくなるので翼を幅広くする (アスペクト比を下げる) 必要があり、操縦性能と長距離飛行効率との兼ね合いで進化した可能性がある。黒い翼はは体温調節に有利との考え方もあって独立に働くだろうとのこと。この論文では飛べるようになったカモメ類では保護色として働く必要はないと考えている。
なおカウンターシェーディング (countershading) の考え方は古くから (*1) 提唱されていて有効であることは特に疑われていないが、(獲物からは見えない) 上面の黒さの説明はあまり満足なものがなかった。例えばカモメ類では翼だけ黒くて他は白っぽい種類も多い理由が説明できなかったが、航空力学的効果を考えると説明が与えられるかも知れないという趣旨。
備考:
*1: 川口 (2017) Birder 31(1): 50-51 では Thayer (1896) The Law Which Underlies Protective Coloration
が紹介されているが、wikipedia 英語版によればさらに早くから知られていたようで Poulton (1890) "The Colours of Animals" で昆虫の色彩を記述しているとのこと。
The Colours of Animals (wikipedia 英語版) によれば当時すでに警告色や擬態、進化メカニズムも議論されていて現代的なテーマがすでに出揃っていた模様。当時はまだ遺伝学の理論も未発展だった。Wallace は性選択を支持していることを批判したとのこと。
The Colours of Animals: Their Meaning and Use Especially Considered in the Case of Insects (archive.org) で読める。
Abbott Handerson Thayer の wikipedia 英語版 の記事にも "father of camouflage" (カモフラージュの父) と呼ばれることもあるが彼が発明したわけではないとある。当時まさに議論の対象のころで、そのうちの一人で早い時期に系統的に研究を行ってまとめた著書を執筆していることは確か。
同ページには Thayer はすべての動物がカウンターシェーディングになっているとの誤った考えに取り憑かれていたとある。
もっとも海鳥でもクロアジサシ類のように下面が白くなく魚を捕えている種もあるので、この説明がどこまで普遍的なのか疑問も感じる。比較的批判的な立場から議論した論文では Rowland (2008) From Abbott Thayer to the present day: what have we learned about the function of countershading?
があった。ほとんどの研究はこの色彩の他に考え得る機能を考察していないとのこと。
こちらも Thayer の人となりを述懐する論文で面白い: Behrens (2008) Revisiting Abbott Thayer: non-scientific reflections about camouflage in art, war and zoology
そもそも画家であって効果は知っていたが "発見" したのはずっと後になってからであった。動物学者の Poulton (1886) がすでに発表していたが自身では countershading とは呼ばなかった。Thayer が Poulton の発見であることをしぶしぶ認めたが、Poulton (1902) は自分が行ったのは発見の一部に過ぎない (partial discovery) とおおらかに認め、Poulton は Thayer の "発見" を宣伝する側に回ったとのこと。
先立って Thayer はアメリカ鳥学会で招待講演も引き受けていた (1896)。用語の発明とともに宣伝活動の活発な方だったらしい。米西戦争 (Spanish-American War) が 1898 年に始まると知人の画家とともに早速軍艦のデザインに関わったとのこと。戦争はすぐに終わってしまい、直接得られたものは "Process of Treating the Outsides of Ships, etc. for Making Them Less Visible" の 1902 年の特許だけだったとのこと。
第一次世界大戦で用いられ、Thayer は戦時の迷彩のための "background picturing" の概念を発明したとのこと。(Thayer 亡き後の) 第二次世界大戦で英国生まれオーストラリアの動物学者の William Dakin が同様の手法を採用したのは興味深いと書かれている。fig. 5 には Thayer (1918) が提案したどんな背景にも万能 (!) の隠蔽デザインが紹介されている。
Thayer は 1921 年に自殺で生涯を終えたが、この著者は Thayer にとって不足していたのは動物学者や博物学者が彼の説を目に見える形で認めなかったためだろうと分析している。彼の生きた時代にはアメリカの画家の間では紹介不要なぐらい知られていたが、現代の芸術家からはほぼ無視されている。現在 Thayer の業績を知って研究に発展させているのはむしろ動物学者の方であること、しばしばカモフラージュのさまざまな側面の発見者として引用されるのは皮肉なことだと締めくくっている。
戦争に役立った (かもしれない) ことは Thayer にとってはあまり慰めにならなかったような書き方となっている。今では動物学である程度は評価されているので、Thayer の性格の方の要因も、異業界からの貢献をすぐに認めたがらなかった学会の性質にも要因があった感じがする。
戦艦にシマウマ模様が用いられた事例は川口 (2019) Birder 33(7): 52-53 で紹介されている。役立っていたかどうかはよく知らないが、特許も取ったので当然使うべきだったのだろう。
[海鳥の翼先端にはなぜスロットがない?]
タカ類などでは初列風切先端の羽毛の (anterior vane) emargination (外弁欠刻) と (posterior vane) notch (内弁欠刻) (emargination は総称的にも使われる) で スロット状の構造 (論文から採用した記述的表現では emarginated, vertically separated primary feathers や slotted distal primary feathers のように使われている。
emargination は個々の羽毛にかかわる用語なので wing を修飾するのは適当でなく、この用語を使う場合は wings with emarginated primaries のような長い表現になってしまう)
があって滑空中に抗力を小さくするのに有利などの解釈がなされるが、長時間の滑空を行う海鳥にはなぜないのかなど説明しにくい部分もある。
van Oorschot et al. (2016) Aerodynamic consequences of wing morphing during emulated take-off and gliding in birds
は実験により、高速の滑空中よりもむしろ飛び立ちなど速度が遅い時に役立っているのではとの仮説を提唱。海鳥は飛び立ちの頻度が少ないが猛禽類は地上から頻繁に飛び立つ必要があるので異なる適応を遂げているのではとのこと。
過去に猛禽類を用いた実験では Tucker (1993) Gliding Birds: Reduction of Induced Drag by Wing Tip Slots Between the Primary Feathers (induced drag = 誘導抗力、後の解説参照)
や Tucker (1995) Drag Reduction by Wing Tip Slots in a Gliding Harris' Hawk, Parabuteo Unicinctus
のように滑空中に注目した研究が中心だったが他の点に着目したものはあまりなかったよう。
van Oorschot による学位論文 (2017) Aerodynamics and Ecomorphology of Flexible Feathers and Morphing Bird Wings も読める。
KleinHeerenbrink et al. (2017) Multi-cored vortices support function of slotted wing tips of birds in gliding and flapping flight
のニシコクマルガラスを用いた研究もあり、従来から想定されていた滑空中の航空力学的効率を上げる効果、羽ばたき時の効果の両者を確認できた。いずれの場合にも vortex spreading (翼端に生ずる渦を分散させる効果) が生じて抗力を弱める効果があった。
ソアリングも滑空も行わない系統にも見られることなどから滑空のために進化した構造というより、もっと一般的な意味があって、初期は羽ばたき効率を上げるために進化したのではないかとのこと。
Liu et al. (2021) A Brief Review on Aerodynamic Performance of Wingtip Slots and Research Prospect にウィングレットの役割にかかわる過去の研究も紹介されている。
この文献では prominent and separated feathers at wingtip called wingtip slots と表現している。"突出"、"分離" のどちらもふさわしい使われ方になっており、翼先分離でも翼先突出のどちらの用語でも表現上は構わない感じがする。"fingers" は英語でも普通に使われるので "翼指" でも差し支えないように思える。
wingtip slots は一般的に使われるが、この数で識別などを表記したものは見つけられなかった。
KleinHeerenbrink et al. (2017) では number of slotted feathers of the wing tip の表現になっていて翼先分離/翼先突出/翼指数に対応する (おそらく適切な学術用語がない)。
この表現を見ると「隙間があって流れを分割する」ことが本質的なようなので、"翼先分離" の方がメカニズムにより対応した名称になっているだろうか。
航空力学について、誘導抗力やアスペクト比などの説明は 人力飛行機を実現する原理[プラントルの揚力線理論](アスペクト比と揚力/誘導抗力比) が参考になりそう。
ウィングレットの項目に大型陸鳥の初列風切羽についての言及がある。
仕組みの日本語解説があるが非常に難しい。自分も流体力学を勉強したことはなく、このような数式をすらすら読める必要はないのでご安心を (*1)。鳥関係で物理学が難しいので...と言われるのはおそらくいきなり飛翔のメカニズムに入ろうとするためではないだろうか。
この解説を見ると流体力学は直感に反する部分が多々あり、完全に演繹的な物理学でもないので初めて取り組むには難しすぎて挫折する恐れ濃厚。
日本語の 空気力学、航空力学 のどちらも英語では aerodynamics なのでそれほど違うわけではない。空気を媒質とする流体力学。ここでは英語で aerodynamics とある場合、飛翔に関係する場面では主に航空力学と訳してある。空気力学的効果のような使い方は聞いたことがないので流体力学的効果としている。
関連して 渦抵抗 (カルマン渦列と抗力) の解説もある。
3. 渦動後流と物体が受ける抗力 (円柱の場合) の解説部分も渦の効果が直感的にわかりやすい部分があり参考になる感じがした。
また「流れの中に置かれた弦などは一定の振動数で振動し音を発するが、このような音響的現象は古くから知られていた」の部分は、羽毛と空気の相互作用で音を発生する種類でも起きているかも知れない (羽毛と羽毛をこすり合わせて音を出る音とは別物 *2)。
現実の鳥の飛行でのレイノルズ数は 25000-375000 の範囲程度とのこと: Alerstam et al. (2007) Flight Speeds among Bird Species: Allometric and Phylogenetic Effects。
「渦抵抗 (カルマン渦列と抗力)」のページに「レイノルズ数が小さい領域 (30 以下) で抵抗係数 C_D が増大するのは、圧力の項より粘性による物体表面の摩擦の効果が勝ってくるから」に該当するのは鳥では着陸・着地の時あたりの超低速飛行の時。
Gowree et al. (2018) Vortices enable the complex aerobatics of peregrine falcons
によればレイノルズ数は 5.8 x 10^5 (22.5 m/s) とあり、このあたりが上限と思ってよさそう。先のページではこの領域では「レイノルズ数が 10^5 を超えると抵抗係数 C_D は急激に減少し ... この抵抗係数の変化は乱流が発生して流れの様子が全く異なった様相を呈するためで、この稿でした渦列の議論は全く成り立たなくなる。抵抗係数急減の説明には乱流境界層の考え方が必要で」
に対応する。Gowree et al. (2018) でもこの領域を扱っており、Prandtl (1931) も引用している。flow separation, re-attachment and vortex generation と乱流境界層がハヤブサの高速飛行を助けているとのこと。
小翼羽 (alula) と渦発生にかかわる過去研究も含めたものは Linehan and Mohseni (2020) Scaling trends of bird's alular feathers in connection to leading-edge vortex flow over hand-wing
で読める。低速飛行中で翼を大きい角度に保った場合に 揚力/抗力の比 を最大にする (13% ぐらい上昇するとのこと) 場所に alula があるとのこと。もっと体に近い位置にあると揚力を完全に失ってしまう結果が得られた。
翼全体の形で最適場所が少し異なり、楕円形のスズメ目の Zimmerman wing では少し内よりに、矩形の猛禽類の翼では中央より少し外側にあるのが最適とのことでほぼ現実を再現している。
Matloff et al. (2020) How flight feathers stick together to form a continuous morphing wing
羽毛の微細構造の方向性のある鈎が "directional Velcro" (方向性のあるファスナー) のように確率的に絡み合うことで隙間を埋めて自動的に理想的な流体力学的構造を作る。ただし無音飛行を行う種類にはこの構造がない (ファスナーを閉じる時のような音がしない)。
高輝度 X 線によるスキャンで明らかになった。10 分以内のスキャンで数千本の羽毛の構造が得られるとのこと。時間もかからないので多数の種を調べることができたとのこと。
アルゴンヌ国立研究所 (Argonne National Laboratory) の運用する高輝度 X 線の研究機関で行われたもの。
Hooks on the feathers stick together: Visualizing how birds form continuous wings in flight (一般向け解説)。
この研究室は他にも構造色の機構の研究などを行っている。
備考:
*1: ただし古い時代の教科書は持っているので、一般的な流体力学の教科書にどのように書かれているかを確認してみた。
粘性のない流体の場合は流れに対して等速度運動している物体には抵抗力が働かないため (D'Alembert's paradox ダランベールのパラドックス として有名)、
翼に働く抵抗を考察するには流体の粘性を扱う必要がある。粘性のない流体にはよく完備した理論があるので、大学で流体力学を勉強する場合には体系立てて理論を学べるこれを主に扱い (出てくる数学は大学で理系の1-2回生段階が中心だがおそらく選択科目なので分野によっては学ばない人も多いかも)、
最後の方で粘性のある流体を扱うのが一般的のよう (ただし単純な場合のレイノルズ数などの概念はもっと早い段階から扱う)。
粘性のある流体中で働く力などは数学的な厳密解が得られないためコンピュータを用いた数値計算や風洞実験などが必要で、学習段階としても後回しになるよう。この場合も円柱や球など理想的な形状を扱っていて翼など複雑な形状は "お話" 程度に出てくるぐらい。また乱流は主に大学院生程度で学ぶのが一般的とのこと。
大学 (理学部を想定) でたとえ物理を勉強したとしても、鳥の翼の流体力学を系統的に学ぶには専門課程ぐらいの知識が必要になる模様。このぐらい専門的な内容になると日本語の専門書や記事を探すよりは英語の教科書を見た方がてっとりばやい、となるのだろう。
論文などのイントロダクションから定性的な話をまず読み取り、必要に応じて上記で紹介したようなページなどを参照して、応用 (現実) と理屈の間を行きつ戻りつ理解を深めてゆくのが現実的そう。
揚力の発生を生徒にどう説明するか (山本明利 2019) も興味深いので紹介しておく。変化球などのマグヌス効果も同様の現象。「誤った、あるいは誤解を招きやすい説明」の項目は注意しておいてよさそう。「ベルヌーイの定理説」の問題点は因果関係が逆転しているということのよう。
説明されているものは Kutta-Joukowski theorem (クッタ・ジューコフスキーの定理)。
この説明は粘性のない流体に対するものだが (ただし以下参照)、現実の流体でも定常流で剥離が発生しない場合はよく成り立つとのこと (wikipedia 英語版より)。まずは粘性のない流体に対する説明を理解するのが多分よいのだろう。
いつまで見られるかわからないが有意義な解説があった。
飛行機の飛ぶ訳 (流体力学の話) (京都大学 OCW 早川尚男)。「しかしこの問を理論物理を研究している大学院生に聞いてみても殆んどはかばかしい答えが帰って来ない」とのこと。物理を専門とする学生でも普通は知らないと思って差し支えなさそう (少し安心)。
ベルヌーイの定理に基づく説明が全く間違っている事にはならないが...あたりも参考になる (ベルヌーイの定理を用いて解説しているものを読む時には、多分ちょっと間違いやごまかしがあってもっと適切な説明があることを知っておくとよい)。
完全流体 (粘性はない) ではそもそも Kutta-Joukowski theorem で言うところの "循環" (circulation, 渦度) が生じない問題も答えが書かれていて、正しい解答は... 以下を参照。
大域的な揚力の発生は粘性がない流体の説明を使ってよいが、そのための渦を発生させるミクロなメカニズムは、物体と流体の接点で現実には物体と流体の速度差が0になるまで流体が減速されるため (この説明は自分にはわかりやすい。boundary layer)。
"循環" は力学の角運動量に対応する概念と対比させると確かに多少わかりやすい感じがする。
これらを知った上で、より大局的な渦の発生や (翼端の渦や翼面の渦の剥離など) それに伴う抗力の発生を把握し、鳥の翼や飛翔羽の形状の適応を考えるのがよさそう。
我らがギルの「鳥類学」の訳本を見ると全体にそれらしい書き方になっているが (ベルヌーイの定理は一部を説明しているに過ぎないなど)、通読しても意味がわからないかも知れない (そもそも循環の意味がわからない)。これらの訳文では原語も添えてあった方が手がかりも得やすい気がする。
*2: #タシギ備考の [タシギ類のドラミング] にまとめた。
[ソアリングの分類]
海鳥類が dynamic soaring (ダイナミックソアリング) を行っている説明はよく読むが、上昇気流によるソアリングとは何が違うのか図があってもわかりにくい。ギルの「鳥類学」(訳本) でもあまり詳しくない。
Mohamed et al. (2022) Opportunistic soaring by birds suggests new opportunities for atmospheric energy harvesting by flying robots
のレビューがあり、流体力学効果による揚力の説明より簡単に理解できるようにに思えたので紹介しておく。力はもちろん流体力学効果が関係するが、ここでは力学で説明できる範囲を扱っているため (まだ) 理解しやすい表現になっている。
一見面倒に感じるが式 2.1 を見るのがわかりやすい。この式は単位時間、単位質量あたりのエネルギー獲得率を表している。最初の項はソアリングとは関係なく推進力と抗力によるものでここでは考えなくてよい。以降は空中の物体 (質点) に働く力を考えた場合のエネルギー獲得を説明していると思って読んでおおよそ正しいはず。
風の流れに対する相対速度を作るのは鳥の役割で姿勢のコントロールなど流体力学効果を用いているわけだが、それはあるものとして定式化している。
2つめが static soaring を表すもので、上昇気流の上向き成分があればその速度で上昇できる (航空力学的な力のみを考えているので重力で落下する項は含まれない)。力学の最初の方で習うように位置エネルギーは mgh なので単位質量あたりとすると m が消えて gh、単位時間あたりにすれば高度 h を時間で微分するので上昇速度になりこの式が得られる。
static soaring の項は上昇気流が時間や場所によって変化しなくても生じる。
第3項が dynamic soaring で、気流が時間 (t) や場所 (ここでは飛行経路 s に沿ったもの) で変化することで生じる成分。風の強さが変化する時、概念的にはエネルギー獲得率は風の速度の変化率 (= 加速度。F = ma から力と思えばよい) と鳥の対空速度 (力の方向に移動すればエネルギーを得る) の積となる
[なお鳥の対地速度 ground velocity は対空速度 air velocity (V) + 風の対地速度 wind velocity (W) いずれもベクトル量 に対応するが単純な足し算にはならないよう]。
この効果を風の速度の時間変化 (後述 gust soaring) と移動経路の沿った風の速度の変化の成分 (後述 gradient soaring) に分けたもの。dynamic soaring を2種類の成分に分けるための表式と考えてよい。
なお進行方向と風の向きによって違うのでは、というのはもっともな疑問で、力と垂直に移動してもエネルギーは得られない。"進行方向の風の加速度成分" のような複雑な表現をとる代わりに内積で表現している。
static soaring のメカニズムを thermal soaring (熱気泡によるソアリング)、orographic soaring (地形によって風が曲がる効果) に分けている。
dynamic soaring は1つめが gradient soaring (風速勾配による効果): ここでは3つ例を挙げていて (a) 海面近くはこちらも boundary layer の効果で風が遅いが海面から離れると速くなる、(b) 海面に波が立つ場合の風が曲がる効果、(c) 地形で生じる風の乱れ。
いずれも場所によって風の速度が異なるため速度勾配が生じる。海鳥の dynamic soaring はこの gradient soaring の効果が中心。
実際にはそれほど穏やかな空気の流れがあるわけではなく、波が立てば乱流も発生するだろうと考えるのは自然で、ここは物事を理解するための単純化と考えていただければよいだろう。
また「勾配」(gradient) と聞くだけで難しそうに感じる。日常的に普通に使われる "勾配" は地表面の高さの傾きのことだが (地表面の高さを水平距離で微分したもの)、風速を地表面の高さと同様に考えて距離で微分したもの。速度勾配の概念は流体ぐらいしか出てこないのでどうしても難しくなる。
速度と速度勾配、あるいは圧力と圧力勾配はよく混同して使われるので、ここは意識して "勾配" のことと捉えるとよい。
2つめが gust soaring (乱流による一時的な風の変化を利用したソアリング)。上昇気流の起きにくい地表付近や森林上空でも活用できるもので多くの鳥が使える時 (opportunistic) に用いている。
地表近くを揺れながら飛ぶチュウヒ類 (#チュウヒの備考 [チュウヒ類の飛翔形] 参照) や不安定な飛行で有名なダルマワシ (#カンムリワシの備考参照) も用いていると考えられている。チュウヒの備考では安定化機構として浅い V 字型をとる仮説を紹介したが、static soaring が期待できない条件でのソアリングのため (羽ばたき飛行に比べてエネルギー消費が少なく獲物にも気づかれにくい) の適応の一つとも言えるのかも。
Mallon et al. (2016) In-flight turbulence benefits soaring birds は地表付近を飛ぶハゲワシで乱流が役に立っているだろうと提案している (チュウヒ類は出てこない)。
このような概念的なエネルギー獲得率が実際に成り立っているかどうかは議論もあるらしい。Richardson et al. (2018) Flight speed and performance of the wandering albatross with respect to wind
はワタリアホウドリのトラッキングでどのようにソアリングを行っているか調べている。風が比較的弱い時は理論の予測する効果が現れているようだが、風が強い時は対空速度を抑えていて制御のための筋力や翼の制約で翼の形を変えて対応しているのではとのこと。
風速に応じて上昇時・下降時の速度を制御することで対地速度を稼ぎ、単位時間あたりに採食のために探索できる範囲を広げている可能性がある。
Richardson and Wakefield (2022) Observations and models of across-wind flight speed of the wandering albatross
も同じグループによる研究で、dynamic soaring が可能な理論値より低い風速でも飛行を行っている。波による風速の変化 [Mohamed et al. (2022) にある上記分類の (b)] からエネルギーを得ているのではと推論。風の強い場合の制約は Richardson et al. (2018) と同様の結果となっている。
Darby et al. (2024) Strong winds reduce foraging success in albatrosses いかに風の利用に長けたアホウドリとは言え強風ではさすがに採食効率が落ちるとのこと。
翼竜 (pterosaurs, 鳥類とは別系統) が種によりソアリング、羽ばたきを用いていた可能性を示唆する化石証拠: Rosenbach et al. (2024) New pterosaur remains from the Late Cretaceous of Afro-Arabia provide insight into flight capacity of large pterosaurs。
海上で thermal soaring を行っていたのではと推定。
飛翔と構造に関連する話題なのでここに含めておくが、鳥類では翼と後肢が独立に進化できるのに対してコウモリでは前肢と後肢に強い相関があることがわかったとのこと: Orkney et al. (2024) Evolutionary integration of forelimb and hindlimb proportions within the bat wing membrane inhibits ecological adaptation
コウモリでは飛翔に皮膜を用いるため前肢と後肢が関連しつつ進化する制約があったのに対して鳥類はその制約がなかったとの解釈。コウモリは独自の飛行方法を開拓したがその仕組みが進化の制約要因ともなって鳥類ほど多様な生活様式を取ることができなかったとの見方。
多少鳥ひいきの感じはあるが面白い結果と言えるだろう。
Keskin et al. (2025) Adaptive cross-country optimization strategies in thermal soaring birds
はソアリングを行う系統の陸上の鳥について GPS データを用い、水平速度と垂直速度の関係が生活様式によって異なることを示している。渡りのコウノトリ類やトキ類は長距離の移動に適した性能があり、長距離を移動して食物を探すハゲワシ類も似た点がある。一方積極的な狩りを行うハヤブサ類では長距離のソアリングのための能力は低めで敏捷な動きを可能にしている。ワシ類は中間ぐらいなどの結果。
△ ミズナギドリ目 PROCELLARIIFORMES ミズナギドリ科 PROCELLARIIDAE ▽
-
フルマカモメ
- 学名:Fulmarus glacialis (フルマルス グラキアーリス) 氷の臭いカモメ
- 属名:fulmarus (合) 臭いカモメ (Fulmar 古ノルド語で臭いカモメ; 英語の foul mew に対応)
- 種小名:glacialis (adj) 氷の (glacies (f) 氷 -alis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Fulmar (or) IOC: Northern Fulmar
- 備考:
fulmarus は外来語由来で発音がよくわからないが、短母音のみで -rus- で音節が区切られるならばここにアクセントがある (フルマルス)。アクセントを長音で発音しても差し支えないと思える (フルマールス)。英語の fulmar は冒頭にアクセント。
glacialis は -alis の a が長母音でアクセントがある (グラキアーリス)。-alis の接尾辞の発音による。
種小名「氷の」はこの種の場合スピッツベルゲン島を指す。3亜種 (IOC) あり、日本で記録されるものはベーリング海近くに分布する rodgersii (アメリカ軍人で探検家の John Rodgers 由来)。属名の由来はミズナギドリ科の構成種は、本種に限らず危険を感じると口から液体を吐き出す防御行動を取ることに由来する (wikipedia 日本語版)。
Fulmarus 属 (フルマカモメ属) は Northern Fulmar と Southern Fulmar Fulmarus glacialoides (ギンフルマカモメ、南半球南部の大陸沿岸から南極大陸沿岸にかけて分布) の2種のみ。姿はカモメ類に似ているが、系統的にはかなり異なり、ミズナギドリ目に属する。
トロール船の活動に伴って 20 世紀に分布を広げたとされ、世界の大部分の地域で個体数は増加している (wikipedia 英語版)。
「動物の世界」2版 24 (日本メール・オーダー 1986) pp. 3289-3290 のフルマカモメの項目 (内田) によれば英国では (この原著は英国で出版されたため英国の動物が多く扱われている) 1878 年まではコロニーは1つだけだったが、この記事の時点で英国で最も普通の海鳥となっていたとのこと。
[におう鳥のリスト]
珍しい研究として Weldon and Rappole (1997) がアンケート調査によって (さまざまな意味で) においが感じられる、あるいは毒気を感じる (ヒトにとって不快な味がする *1) 鳥のリストを挙げている:
A Survey of Birds Odorous or Unpalatable to Humans: Possible Indications of Chemical Defense。これは鳥類におけるにおい物質による化学防御やコミュニケーションの役割を考えるのに役立つ。
アンケートに応じた鳥類学者も好意的な反応で、常日頃知りたい、あるいは情報を残しておきたいと思いつつももまとまった研究がなかったので興味津々だったのかも知れない。
新世界カッコウの仲間の Ani (Crotophaga) は集団でいると数 m 離れていてもわかるぐらいだそうである。フルマカモメはもちろん、ツメバケイ、ヤツガシラのような有名な種も含まれている。
スズメ目ではムクドリモドキ (grackles, Quiscalus) はだいたいにおう。アンチルクロムクドリモドキ Quiscalus niger Greater Antillean Grackle は足がにおうとの報告があり、におい物質は尾脂腺由来と一般に考えられているのと異なる。オウム類は一般にもよく知られている通りで、この調査でもたくさん見つかっている。
新世界ハゲワシは嗅覚が優れているが、多くの人がにおいを報告している。死体のようなにおいがするので新世界ハゲワシの肉は他のスカベンジャーも食べようとしないとされる (トキイロコンドル、ヒメコンドルについては別文献から後述)。しかし旧世界ハゲワシはそうではない。
ミサゴ (これは救助個体などでよく知られている。#ミサゴの備考参照) とカラカラもにおう方に入っている。
同著者による Weldon (2023) Chemical aposematism: the potential for non-host odours in avian defence
化学防御のレビュー論文があり、さまざまな種類の鳥での分泌物質研究やカや外部寄生虫の防御などの情報がまとめられている。エトロフウミスズメやヤツガシラなどの分泌物質などもレビューされている
(#エトロフウミスズメ、#ヤツガシラの備考参照)。
キツツキの仲間で Hemicircus 属は腺でなく、背中のヒゲのような特殊な羽 (fat quill) からにおいを出す脂肪分を分泌している。
Bock and Short Jr. (1971) "Resin Secretion" in Hemicircus (Picidae) が調べたところでは分泌している皮脂腺は見当たらなかった。
尾脂腺以外の鳥の皮膚からの分泌については、Menon and Menon (2000) Avian Epidermal Lipids: Functional Considerations and Relationship to Feathering
によれば、鳥には尾脂腺以外の皮脂腺は知られていないが、皮膚に脂肪が含まれていて分泌される例もある (ニワトリのとさか、指の間の水かきなど)。
粉綿羽 (powder downs) も羽毛による皮脂分泌に含まれている。
毒鳥 (Pitohui) の分泌も皮膚機能の一つ。
皮膚からの色素分泌については#トキの備考も参照。
脂肪を出して皮膚を防水するよりは水分蒸発で体を冷やす機能の方を優先している (皮膚が水分をよく通すことで高い体温を逃したり飛翔時に体を冷やすのに役立つ)。
皮膚の脂肪の分子配列構造の温度変化で水分の通りやすさが調節されている: Champagne et al. (2018) Presence and persistence of a highly ordered lipid phase state in the avian stratum corneum。
哺乳類よりも脂肪を構成する脂肪酸分子が長く、より高い体温に対応している可能性があるとのこと。
コウモリでも皮膜に鳥類同様の皮膚角化組織にセレブロシド (cerebroside, スフィンゴ糖脂質) が蓄積して水分含有量を調整している。通常の (病的でない状態の) 哺乳類の角化組織には含まれず、収斂進化と考えられるとのこと: Ben-Hamo et al. (2016)
The cutaneous lipid composition of bat wing and tail membranes: a case of convergent evolution with birds。
この研究は鳥類にあるならば飛ぶ哺乳類にもあるだろうと予測してその通りだった事例。
Haeglin and Jones (2007) Bird Odors and Other Chemical Substances: A Defense Mechanism or Overlooked Mode of Intraspecific Communication?
によればにおう鳥のすべてが尾脂腺を持っているわけではない。エトロフウミスズメも、フルーツのような甘い香りのするニュージーランドの飛べないオウムのフクロウオウム (カカポ) Strigops habroptilus も尾脂腺から出たばかりの分泌物は人にはにおいを感じられなかったとのこと。
オウム類のいわゆる「インコ臭」では粉綿羽が役割を果たしている可能性がある。
なおオウム類と系統の近いハヤブサ類もオウム類ににおいが似ているとの記述がある ["Where Song Began" #ミサゴの備考も参照]。
海鳥類の (無臭の) 分泌物が細菌で分解されて酸やアルコールのにおい成分となっている可能性がある。
この研究の時点ではヤツガシラ類の悪臭が自然の天敵を遠ざける効果がある実験的検証はまだなされていなかったが、ネコなどに効果のある試験的データはあるとのこと。
哺乳類捕食者のいない島では強いにおいを持つ傾向があり (前述のカカポも同様。カカポは嗅覚遺伝子数も多く 667 とのこと)、ハワイミツスイ類 (Drepanidinae) ではほとんどの種の羽毛ににおいがある (wikipedia 英語版ではキャンバステント (canvas tent) のようなにおいがあるとのこと (哺乳類捕食者が少なくにおいを消す必要がなかった?) で分類の系統にも関連があるらしい。
Pratt (1992) Is the Poo-uli a Hawaiian Honeycreeper (Drepanidinae)?
では実際にさまざまな標本を使ってにおいを調べて、属の根拠としている。袋に入れて見えないようにしても区別できるという。著者によれば同様のにおいを持つ新世界スズメ目、特にヒワ亜科の標本はなかったとのこと。解剖学的分類中心の時代では一番有力な分類手段でもあったとのこと。
コンサイス鳥名事典によれば南米のトキイロコンドル Sarcoramphus papa King Vulture は食後は悪臭がするが、ほかの時はジャコウの香りがするとのこと。週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 114 p. 6 にほぼそのままの記述で、人間に耐えられないほどの悪臭とあって出典と考えられる。
wikipedia 英語版によれば捕食者を遠ざけるために巣に悪臭があるとのこと。
Maraci et al. (2018) Olfactory Communication via Microbiota: What Is Known in Birds?
の総説によればヒメコンドル Cathartes aura Turkey Vulture の皮膚は特別の細菌叢 (おそらく獲物由来) を持っていてにおいに関係していると考えられるが、嗅覚コミュニケーションに関係があるかは不明とのこと。
Haeglin and Jones (2007) に戻ると鳥類学者は3種の化学受容 (嗅覚、味覚、三叉神経システム) をあまり区別してこなかった。嗅覚の研究は比較的あるが他は少ない。
鳥類はヒト同様鋤鼻器 (vomeronasal organ 別名ヤコブソン器官 Jacobson's organ) を持たないのでフェロモンの役割は限られていると考えられてきたが神経端末は存在するのでフェロモンを感じる役割が否定されるわけではない
(この点は最近進展があり #エトロフウミスズメ備考の [鳥類の嗅覚] 参照)。
尾脂腺の分泌は CD1 遺伝子が制御している可能性が指摘されており、これは MHC (major histocompatibility complex 主要組織適合遺伝子複合体) の祖先遺伝子にあたるので鳥類でもヒトでも嗅覚コミュニケーションはこれまで見過ごされた役割を持つかも知れない。
鳥のにおい/嗅覚の話は最近少し注目を浴びているようで、こんな本も出ている。Whittaker (2022) "The Secret Perfume of Birds" (あるいは訳本が出ないかと期待しているが...)。
関連講演の YouTube 動画もある。
Feb 13, 2023 Secret Perfume of Birds Danielle Whittaker。
嗅覚に関連する話の続きは #エトロフウミスズメ備考の [鳥類の嗅覚] にまとめた。
フルマカモメの防御行動で吐き出される液体にはビタミン D, A が多く、食物の甲殻類に多量に含まれる ビタミン A の排泄機能にも役立っている説があるとのこと。#サンショウクイ備考の [サンショウクイの色彩と系統] にて紹介。
備考:
*1: unpalatable は palate (口蓋、味覚 < ラテン語 palatum) 由来で、不快な味がする、おいしくないなどの意味。鳥類の生態学で "まずい" と出てくるのはこの単語の意味と考えてよさそう。
よく似た単語に impalpable があって (特に触覚で) 知覚できないの意味。語源は異なり、ラテン語 palpo そっと触れる由来 < インド・ヨーロッパ祖語語幹の *pal- 感じるが語源とも考えられている。医師の触診は palpation。
[2018 年カリフォルニアのフルマカモメ集団死]
Greenwald et al. (2024)
Investigation of a Mass Stranding Event Reveals a Novel Pattern of Cascading Comorbidities in Northern Fulmars (Fulmarus glacialis)
が報告をまとめている。フルマカモメやウミガラス、アメリカウミスズメ Ptychoramphus aleuticus Cassin's Auklet の集団漂着が見られ神経症状が見られた。
藻が生成する有毒なドウモイ酸 (domoic acid。グルタミン酸受容体に結合) やサキシトキシン (saxitoxin。有毒渦鞭毛藻が生成し Na+ チャネルを阻害。テトロドトキシンと同じ機序でフグ毒の成分の一つともなる) が認められ、環境中の異常な高濃度の記録とも一致した。尿路系にも強い影響を与えて感染症による腎炎などを併発していたとのこと。
wikipedia 日本語版によればドウモイ酸は徳之島で駆虫薬として用いられていた紅藻ハナヤナギから分離・命名されたとのこと。
1961年8月18日カリフォルニア沿岸のキャピトラ、サンタクルーズに錯綜した海鳥の群れが出現し、ヒッチコックの「鳥」はこの事例から着想を得たと言われる。この事象もドウモイ酸中毒と推定されている (wikipedia 英語版より)。
参照: Bargu et al. (2011) Mystery behind Hitchcock's birds。
中枢神経が侵されるため他の動物でも人を襲った事例などもあるらしい。
極端気候によりアメリカ西岸でドウモイ酸発生が起きやすくなっている: Trainer et al. (2020)
Climate Extreme Seeds a New Domoic Acid Hotspot on the US West Coast
海水温が 4 ℃ 上がるとドウモイ酸発生量が 11 倍に増えたとの実験結果がある: Xu et al. (2023) Plastic responses lead to increased neurotoxin production in the diatom Pseudo-nitzschia under ocean warming and acidification。
この場合は酸性化より温暖化の効果の方が大きかった。
-
ハジロミズナギドリ
- 学名:Pterodroma solandri (プテロドゥロマ ソランドゥルィ) ソランデルの翼で走る鳥
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:solandri (属) solander の (スウェーデンの植物学者 Daniel Carl Solander、Linnaeus の弟子)
- 英名:Providence Petrel
- 備考:
pterodroma は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-ro- がアクセント音節と考えられる (プテロドゥロマ)。
solandri は -lan- がアクセント音節と考えられる (ソランドゥルィ)。
単形種。
英語の petrel の語源はおそらく Peter の指小形で、Saint Peter (ペトロ) が海の上を歩いたとの伝説に由来する (Matthew 14:29, wiktionaryより)。
フランツ・リストの音楽に「波の上を渡るパオラの聖フランチェスコ」(St. Francois de Paule marchant sur les flots) という曲があり、「あなたは聖人だからキリストのように歩いて海の上を渡れるはずだろう」と船頭に言われ、船を出すのを断られた聖フランシスは、自分のマントと杖を筏 (いかだ) のように使い、メッシナ海峡を歩いて渡ったという」(「クラシックばっか 時空間」より)。
この曲は「2つの伝説」という2曲のうちの一つで、もう一つが「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」(St. Francois d'Assise: la predication aux oiseaux) と鳥が出てくるので紹介しておく。鳥の声を表現しているが特に何かを模した感じではない。
ピアノ曲としては前者が秀逸でよく演奏されるので、鳥には関係ないかも知れないが例えば petrels が波間に飛ぶの姿でも思い出していただきながら演奏ビデオを見ていただけるとよいだろう。クラシック音楽に関心のない方でも十分堪能していただける曲だと思う。
脱線ついでに紹介しておくと、邦楽で「新曲浦島」(坪内逍遥作、5世杵屋勘五郎・13 世杵屋六左衛門作曲の長唄 1904。1906 初演) がある。当時は洋楽も日本に入っており、西洋音楽を取り入れた要素も多くある。嵐の海を表現している点で上記リストの音楽とも共通するところがある。日本舞踊付きの舞台のビデオも YouTube に掲載されており、海外の方に紹介すると大変喜ばれる。
petrels のロシア名は tajfunik (台風の者)。この種も tajfunik Solandera (Solandra) と呼ばれる。
-
オオシロハラミズナギドリ
- 学名:Pterodroma externa (プテロドゥロマ エクセテルナ) 遥か彼方のミズナギドリ
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:externa (adj) 外の (externus)
- 英名:Juan Fernandez Petrel (チリ沖合いのファン・フェルナンデス諸島由来)
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
externa は短母音のみで x を分割した -se- の音節にアクセントがある (エクセテルナ)。
Mas a Fuera 島で発見され、これはスペイン語で「遥か彼方」の意味 (The Key to Scientific Names)。現在は単形種。
かつてはクビワオオシロハラミズナギドリ (日本鳥類目録改訂第8版で掲載。改訂第7版では検討種だがすでに別種扱いとなっていた) が亜種とされていた。
そのため和名オオシロハラミズナギドリに相当するかつての英名は White-necked Petrel だった。
現在はこの英名はクビワオオシロハラミズナギドリを指すものとなっている。
-
カワリシロハラミズナギドリ
- 学名:Pterodroma neglecta (プテロドゥロマ ネグレークタ) 無視されたミズナギドリ
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:neglecta (adj) 無視された (neglectus)
- 英名:Kermadec Petrel (ケルマディック諸島の)
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
neglecta は2つめの e が長母音でアクセントもある (ネグレークタ)。
IOC では2亜種。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種不明。
-
ハワイシロハラミズナギドリ (分割された)
- 第8版学名:Pterodroma sandwichensis (プテロドゥロマ サンドウィケーンシス) サンドウィッチ伯爵のミズナギドリ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Pterodroma phaeopygia (プテロドゥロマ パエオピュギア) 灰色の腰のミズナギドリ
- 第7版亜種学名:Pterodroma phaeopygia sandwichensis (プテロドゥロマ パエオピュギア サンドウィケーンシス) サンドウィッチ伯爵の灰色の腰のミズナギドリ
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 第8版種小名:sandwichensis John Montagu 4th Earl of Sandwich (第4代サンドウィッチ伯爵) の
- 第7版種小名:phaeopygia (合) 灰色の腰の鳥 (phaios 灰色の -pugios 腰の Gk)
- 第7版亜種小名:sandwichensis John Montagu 4th Earl of Sandwich (第4代サンドウィッチ伯爵) の
- 英名:Hawaiian Petrel
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
sandwichensis は接尾辞 -ensis の e が長母音でアクセントもある (サンドウィケーンシス)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Pterodroma sandwichensis となる。John Montagu 4th Earl of Sandwich (第4代サンドウィッチ伯爵、英国の貴族・政治家。料理の「サンドウィッチ」も同語源) に由来。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
Pterodroma phaeopygia (現在ガラパゴスシロハラミズナギドリ、Galapagos Petrel) の亜種から独立種となる。新分類で単形種。ガラパゴスシロハラミズナギドリとハワイシロハラミズナギドリとは海上で識別不能と言われる。
Sessi et al. (2025) First Whole-Genome Assembly of the Galapagos Petrel (Pterodroma phaeopygia) Using Oxford Nanopore Sequencing to Advance Conservation Genomics in a Critically Endangered Seabird (preprint)
ガラパゴスシロハラミズナギドリのゲノムアセンブリの初解析。
-
マダラシロハラミズナギドリ
- 学名:Pterodroma inexpectata (プテロドゥロマ イネックスペクタータ) 思いがけないミズナギドリ
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:inexpectata (adj) 思いがけない [inexpectatus; Foster (1844) が記述の際に (猟師が) 思いがけない新種の喜びをもたらしたとした (The Key to Scientific Names)]
- 英名:Mottled Petrel
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
inexpectata は1つめの a が長母音でアクセントがある (イネックスペクタータ)。所有の -ata ではなく変化形由来。
単形種。
-
ハグロシロハラミズナギドリ
- 学名:Pterodroma nigripennis (プテロドゥロマ ニグリペンニス) 黒い翼のミズナギドリ
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:nigripennis (adj) 黒い翼の (niger (adj) 黒い pennis (f) 羽 翼)
- 英名:Black-winged Petrel
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
nigripennis は短母音のみで -pen- がアクセント音節 (ニグリペンニス)。
学名・英名・和名ともに対応がよい。
単形種。
-
シロハラミズナギドリ
- 学名:Pterodroma hypoleuca (プテロドゥロマ ヒュポレウカ) 腹が白いミズナギドリ
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:hypoleuca (合) 下部が白い (hypo- (接頭辞) 下の leukos 白い Gk)
- 英名:Bonin Petrel (bonin 無人、小笠原諸島)
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
hypoleuca は短母音のみで -le- がアクセント音節 (ヒュポレウカ)。hypoleuca はマダラヒタキの種小名にも使われ、ヨーロッパではお馴染みの名前。
単形種。
-
ヒメシロハラミズナギドリ
- 学名:Pterodroma longirostris (プテロドゥロマ ロンギローストゥリス) 長い嘴のミズナギドリ
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:longirostris (adj) 長い嘴の (longus (adj) 長い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Stejneger's Petrel (ノルウェー生まれのアメリカの鳥類学者 Leonhard Stejneger にちなむ)
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
longirostris は -ros- の o が長母音でアクセントもここにある (ロンギローストゥリス)。rostrum の発音に由来。
単形種。
-
オオミズナギドリ
-
オナガミズナギドリ
- 第8版学名:Ardenna pacifica (アルデンナ パーキフィカ) 太平洋のアルデナ島の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Puffinus pacificus (プフフィーヌス パーキフィクス) 太平洋のツノメドリのような鳥/ミズナギドリ
- 第8版属名:ardenna ダイオミード諸島の島の名前。別説あり。
- 第7版属名:puffinus (合) ツノメドリのような鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:pacifica / pacificus (adj) 太平洋の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Wedge-tailed Shearwater
- 備考:
ardenna の発音はよくわからないが -den- がアクセント音節で、短母音のみとすれば "アルデンナ"。
pacifica は "パーキフィカ" (#アマツバメ参照)。
puffinus は -inus の接尾辞発音から i が長母音でアクセントもここにある (プフフィーヌス)。
英名は Puffinus sphenurus Gould, 1844 (参考) に由来 (楔形の尾のツノメドリのような鳥)。Procellaria pacifica Gmelin, 1789 の記載が早かったため学名変更となった。
この基産地は太平洋 (= 種小名) と広すぎるが、Mathews, Bds. Austr., 2, 1912, p. 80 によって Kermadec Islands (ケルマデック諸島。南太平洋のニュージーランド領) と判定された (Avibase の情報による)。
"Wedge-tailed" を冠する現行の英名は他に数種あるが、この種とオナガイヌワシ (クサビオワシの名称もあった) が圧倒的に有名。慣れ親しまれた英名のため学名が変わってもそのまま使われているのだろう。
もう1種挙げるとすればオナガアオバト (#アオバト参照)。
和名もオナガイヌワシやオナガアオバト同様に英名または学名由来と考えるとわかりやすい。ドイツ語でも "クサビオ" に相当する名称になっていて (Keilschwanz Sturmtaucher, Keilschwanzsturmtaucher) オナガイヌワシのドイツ語名と同様。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Ardenna 属 (ダイオミード諸島の島の名前、ベーリング海峡の中間にあたる; ardenna, artenna ミズナギドリのイタリア語方言の説もある) に分離。Ardenna pacifica となる。
以下の備考の Ardenna 属について、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。Ardenna 属はハシボソミズナギドリ属となる。
Reichenbach (1853) が用いた名称で、Ardenna gravis ズグロミズナギドリ (英名 Great Shearwater) がタイプ種。
Great Shearwater の英名は旧学名 Puffinus major Faber, 1822 由来と考えられる。
オナガミズナギドリは IOC では単形種だが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種 cuneata (楔形の) としている。この亜種を認めているのは世界ではアメリカ鳥学会など少数。
海鳥類の分子系統樹は Obiol et al. (2022) Palaeoceanographic changes in the late Pliocene promoted rapid diversification in pelagic seabirds を参照。この研究ではオナガミズナギドリに最も近縁な種類はミナミオナガミズナギドリと判明し、superspecies を形成するとされる。
-
ミナミオナガミズナギドリ
- 第8版学名:Ardenna bulleri (アルデンナ ブルレリ) ブラーのアルデナ島の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Puffinus bulleri (プフフィーヌス ブルレリ) ブラーのミズナギドリ
- 第8版属名:ardenna ダイオミード諸島の島の名前。別説あり。
- 第7版属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:bulleri (属) buller の (ニュージーランドの法律家で鳥類学者の Walter Lawry Buller に由来)
- 英名:Buller's Shearwater
- 備考:
ardenna は#オナガミズナギドリ参照。
bulleri はラテン語式では冒頭がアクセントと考えられる (ブルレリ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Ardenna 属。種小名は変化なし。単形種。
-
ハイイロミズナギドリ
- 第8版学名:Ardenna grisea (アルデンナ グリーセア) 灰色のアルデナ島の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Puffinus griseus (プフフィーヌス グリーセウス) 灰色のミズナギドリ
- 第8版属名:ardenna ダイオミード諸島の島の名前。別説あり。
- 第7版属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:grisea / griseus (adj) 灰色の
- 英名:Sooty Shearwater
- 備考:
ardenna は#オナガミズナギドリ参照。
grisea は i が長母音でアクセントもここにある (グリーセア)。
学名・英名・和名ともに対応がよい。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Ardenna 属。Ardenna grisea となる。単形種。
-
ハシボソミズナギドリ
- 第8版学名:Ardenna tenuirostris (アルデンナ テヌイローストゥリス) 細い嘴のアルデナ島の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Puffinus tenuirostris (プフフィーヌス テヌイローストゥリス) 細い嘴のミズナギドリ
- 第8版属名:ardenna ダイオミード諸島の島の名前。別説あり。
- 第7版属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:tenuirostris (adj) 細い嘴の (tenuis (adj) 細い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Short-tailed Shearwater
- 備考:
ardenna は#オナガミズナギドリ参照。
tenuirostris は -ros- の o が長母音でアクセントもここにある (テヌイローストゥリス)。rostrum の発音由来。
和名と学名の対応がよいが英名との対応が悪い。英名は Puffinus brevicaudus Gould, 1841 (参考。短い尾のツノメドリに似た鳥) を訳したものと考えられる。このカードによればこれは後にアカアシミズナギドリと同定されたようで、英名にのみ古い学名が残ったものと想像される。
tenuirostris の種小名に対応する英名 Slender-billed Petrel, Slender-billed Shearwater も存在する。
さらに Procellaria tenuirostris Temminck, 1836 の 記載 基産地 seas north of Japan and shores of Korea が早いと認定されてこの学名となった。
フランス語名 Puffin a bec grele (学名と同じ意味。英語では slender-billed に近い)。
ミズナギドリ類は区別が難しいために同一であることが確認されるまで時間がかかったのかも知れない。
Fauna Japonica の 図版。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Ardenna 属。種小名は変化なし。単形種。
-
シロハラアカアシミズナギドリ
- 第8版学名:Ardenna creatopus (アルデンナ クレアトプース) 肉色の足のアルデナ島の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Puffinus creatopus (プフフィーヌス クレアトプース) 肉色の足のミズナギドリ
- 第8版属名:ardenna ダイオミード諸島の島の名前。別説あり。
- 第7版属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:creatopus (合) 肉色の足の (kreas, kreos 肉、pous 足 Gk)
- 英名:Pink-fooded Shearwater
- 備考:
ardenna は#オナガミズナギドリ参照。
creatopus は -pus がギリシャ語由来で長音となると考えられる。アクセント位置は -a- と考えられる (クレアトプース)。
アカアシミズナギドリとよく似た種小名・英名だがアカアシミズナギドリの方が命名が早かったためギリシャ語を用いて少し違った種小名を与えた模様。
ギリシャ語 kreas が肉の意味で、pancreas (膵臓) や creatine (クレアチン)、creatinine (クレアチニン) などの語源となっている。
記載時学名は Puffinus creatopus Coues, 1864 (参考) で一時は Puffinus major Faber, 1822 (参考) = Procellaria Gravis O'Reilly, 1818 = 現在のズグロミズナギドリ Ardenna gravis Great Shearwater のシノニムとされた。
Obiol et al. (2021) Palaeoceanographic changes in the late Pliocene promoted rapid diversification in pelagic seabirds
によればアカアシミズナギドリに非常に近く、同種にしてもよい程度とのこと。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Ardenna 属。種小名は変化なし。単形種。
矢吹・森岡 (2009) Birder 24(3): 51-52 に銚子沖での日本初のシロハラアカアシミズナギドリの記録が掲載され、この属 (新分類では Ardenna 属) の識別についての記述・考察がある。
-
アカアシミズナギドリ
- 第8版学名:Ardenna carneipes (アルデンナ カルネイペース) 肉色の足のミズナギドリ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Puffinus carneipes (プフフィーヌス カルネイペース) 肉色の足のミズナギドリ
- 第8版属名:ardenna ダイオミード諸島の島の名前。別説あり。
- 第7版属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:carneipes (adj) 肉色の足の (carneus (adj) 肉の pes (m) 足)
- 英名:Flesh-footed Shearwater
- 備考:
ardenna は#オナガミズナギドリ参照。
carneipes は carneus は短母音。-pes は足の意味のギリシャ語由来で長音。アクセント音節は -nei- となる (カルネイペース)。
carneus は caro (肉) 由来で、英語でも肉食を意味する carnivorous は同語源 (この場合はラテン語をそのまま使用)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Ardenna 属。種小名は変化なし。
学名とこれまでの英名はよく対応している。和名も対応関係がよいが、英名は改名が提案されている: Shearwater name change proposed (BirdGudes 2024.9.20) 新しい名前として Sable Shearwater が提案されているとのこと。
Bond and Lavers (2024) A feathered past: Colonial influences on bird naming practices, and a new common name for Ardenna carneipes (Gould 1844)
に命名の歴史などが述べられている。これまでの英名はやはり記載時記述 (学名) 由来で 1872 年から使われたが、pale-footed の別名が用いられたのは 1912 年とのこと。
この鳥の名称には植民地時代の歴史が含まれており、クレヨンの名前にも用いられていた "肌色" と同様 (英語で flesh color に対応。この論文によれば Crayola Corporation のクレヨンもこの色彩名称でが 1962 年まで販売されていたとのこと) で、そもそも flesh color の意味に相当するものなのか、肉の色を指すのか、臓器の色なのかなど明確でない (記載時の記述はラテン語)。
古く使われた基産地由来の名称も検討されたが分布域の広い鳥には適切でない。またそもそも植民地由来の地名を使うことも趣旨に反するとのことで新称が提案されることになった。
単形種。
歴史的には亜種がいくつも提案されていた。
・Puffinus carneipes carbonarius Mathews, 1912 (参考) 基産地 New Zealand (ニュージーランド) preoccupied で無効 = zealandicus と改名。これも preoccupied で = neozealandicus と改名
・Puffinus carneipes hakodate Mathews, 1912 (参考) 基産地 日本 (函館?)
・Puffinus carneipes hullianus Mathews, 1912 (参考) 基産地 Norfork Id. (ノーフォーク島。太平洋のオーストラリア領の島)
・Puffinus carneipes zealandicus Mathews, 1926 (参考) carbonarius を改名したがすでに使われていた
・Puffinus carneipes neozealandicus Mathews, 1926 (参考) zealandicus を改名したもの
記述を見ると Hertert がすべてシノニムとして扱った模様。
-
コミズナギドリ
- 学名:Puffinus nativitatis (プフフィーヌス ナーティーウィターティス) クリスマス島生まれのミズナギドリ
- 属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:nativitatis (属) 起源の (nativitas -atis (f) 起源)
- 英名:Christmas Shearwater (クリスマス島の)
- 備考:
puffinus は -inus の接尾辞発音から i が長母音でアクセントもここにある (プフフィーヌス)。
nativitatis は3つの長母音を持ち、最後の a にアクセントがある (ナーティーウィターティス)。natus (生まれ) -ivus (行っている) がいずれも長音で始まるため。-tas は状態を表す接尾辞 で a が長母音。原形の nativitas は冒頭にアクセント。変化形で母音が追加されてアクセント位置が変わる。
Ardenna 属の分離に伴い、Puffinus 属はマンクスミズナギドリ属となった。Puffinus 属のタイプ種もマンクスミズナギドリ (第8版では日本産種に含まれない)。単形種。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではこの学名の種を Minami-Torishima ミズナギドリの名称で載せている。現代の分類と同じものか判断できないが、オオミズナギドリの和名はこの名称に対応するものであったよう。
種小名は「生まれの」(英語 native に相当)。Capt. James Cook が 1777 年のクリスマスイブに訪れたためクリスマス島と名前が付いた太平洋の島が由来 (The Key to Scientific Names)。
この由来は英名によく表れている。
-
マンクスミズナギドリ (第8版で検討種)
- 学名:Puffinus puffinus (プフフィーヌス プフフィーヌス) ツノメドリのような鳥
- 属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:puffinus (トートニム)
- 英名:Manx Shearwater (マン島の)
- 備考:
puffinus は#コミズナギドリ参照。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。世界的には2亜種ある (IOC) が、日本鳥類目録では亜種の記載はない。
-
ハワイセグロミズナギドリ
- 学名:Puffinus newelli (プフフィーヌス ネウェルリ) ニュウェルのミズナギドリ
- 属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:
puffinus は#コミズナギドリ参照。
newelli はラテン語式読みで -wel- がアクセント音節と考えられる (ネウェルリ)。
newelli (属) newellの (命名者 ハワイの宣教師 Matthias Newell)
- 英名:Newell's Shearwater
- 備考:日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
-
(旧名セグロミズナギドリ亜種オガサワラミズナギドリ) オガサワラミズナギドリ
- 第8版学名:Puffinus bannermani (プフフィーヌス バンネルマニ) バナーマンのミズナギドリ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Puffinus lherminieri (プフフィーヌス ルヘルミニエリ) レルミニアーのミズナギドリ (種和名セグロミズナギドリ)
- 第7版亜種学名:Puffinus lherminieri bannermani (プフフィーヌス ルヘルミニエリ バンネルマニ) バナーマンのレルミニアーのミズナギドリ (亜種和名亜種オガサワラミズナギドリ)
- 属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 第8版種小名:bannermani 英国鳥類学者 David Armitage Bannerman の
- 第7版種小名:lherminieri (属) L'herminier の (フランスの薬剤師 Felix Louis l’Herminier)
- 第7版亜種小名:bannermani 英国鳥類学者 David Armitage Bannerman の
- 英名:(Audubon's Shearwater), IOC: Bannerman's Shearwater
- 備考:
puffinus は#コミズナギドリ参照。
bannermani はすべて短母音でラテン語風に読めば "バンネルマニ"。
lherminieri はすべて短母音でラテン語風に読めば "ルヘルミニエリ" と考えられる。原語との違いが大きいがやむを得ないだろう。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Puffinus bannermani オガサワラミズナギドリ (英名 Bannerman's Shearwater)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
種小名はスコットランドの鳥類学者 David Armitage Bannerman に由来。
川上他(2019) 日本鳥類目録におけるセグロミズナギドリ和名変更の提案; 参考記事。
英名の Audubon's Shearwater は日本鳥類目録改訂第7版まで Puffinus lherminieri に含まれていた時期のもの。
日本鳥類目録改訂第7版では Puffinus lherminieri の亜種扱いだったが、どの種の亜種にするかはリストによって異なり Clements 6th edition (incl. 2009 revisions) - version 2018, Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2), 4th edition (incl. corrigenda vol.1-2) では Puffinus bailloni の亜種扱い。
Kawakami et al. (2018) Phylogenetic position of endangered Puffinus lherminieri bannermani 分子系統解析から独立種が妥当する研究。
IOC は当初から、Clements は version 2019 から独立種の扱い。
第8版分類ではセグロミズナギドリ Puffinus lherminieri (英名: Audubon's Shearwater: AOC は Sargasso Shearwater を採用) とオガサワラミズナギドリ Puffinus bannermani (英名: Bannerman's Shearwater) に区別されることになり、前者は日本産鳥類から外れる。単形種。
-
オガサワラヒメミズナギドリ
-
アナドリ
- 学名:Bulweria bulwerii (ブルウェリア ブルウェリイ) ブルウァーの鳥
- 属名:bulweria (合) bulwer の鳥 (-ia (接尾辞) 人名の属名化に使用する)
- 種小名:bulwerii (属) bulwer の (ラテン語化して -ius を属格化) 発見者 マデイラ島 (クロコシジロウミツバメも参照) 在住のスコットランドの牧師、博物学者 Revd. James Bulwer に由来。
- 英名:Bulwer's Petrel
- 備考:
Bulweria bulwerii はすべて短母音でラテン語風に読めば "ブルウェリア ブルウェリイ" と考えられる。前者は属名語尾にするために -a に変化させたもの (参考 Ketupa 属)。
単形種。
北米で通称から人名を排除する動きに関連して代わりの名前が話題になっている: Yet another thread on eponyms... But this one might actually be fun!
Bulwer はタイプ標本を得る以外鳥類学にあまり貢献していないなどなかなか手厳しい。
属名・種小名ともに名前が残るので通称は変えてもよいのでは (とまで書いてないが)。
△ ミズナギドリ目 PROCELLARIIFORMES ウミツバメ科 HYDROBATIDAE ▽
-
アシナガウミツバメ (近々分離され学名が変わる可能性が高い)
- 学名:Oceanites oceanicus (オーケアニテース オーケアニクス) 大洋の鳥
- 属名:oceanites (合) 大洋の鳥 (oceanus -i (m) 大洋、-tes (接尾辞) 〜するもの Gk)
- 種小名:oceanicus (adj) 大洋の (oceanus -i (m) 大洋 -icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Wilson's Storm Petrel
- 備考:
oceanites は oceanus は冒頭が長母音、-tes はギリシャ語由来の接尾辞でやはり長母音を含む。
-a- がアクセント音節と考えられる (オーケアニテース)。
oceanicus は冒頭は同様、-icus は短母音。"オーケアニクス" と考えられる。
exasperatus が生きるならば a が長母音でここにアクセントがある (エクスペラートゥス)。所有の -atus ではなく変化形の語尾。
記載時学名 Procellaria oceanica Kuhl, 1820 (原記載) 基産地 No type locality. South Georgia designated by Murphy, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 38, 1918, p. 128 (Avibase の情報による)。
Oceanites 属は Keyserling and Blasius (1840) が設けたもの。おそらくトートニムに近いため Oceanites wilsoni Bonaparte, 1857 の新名もあった (#ノスリの備考参照)。
Oceanites が男性名詞か女性名詞か判断が揺らいだ時期があり、時期によって種小名の性が変わっていた。
3亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは exasperatus (苛立たしい) とされる。亜種の語源は、記載者が過去の標本の計測値が過去に記載された名前の特徴と合致しないため、本来は別名を付けるつもりではなかったのではないかと考えたため (The Key to Scientific Names)。
新種を記載し Cytb 遺伝子の解析から Oceanites 属を7種とする論文 (2024.7.29):
Norambuena et al. (2024) Resolving the conflictive phylogenetic relationships of Oceanites (Oceanitidae: Procellariiformes) with the description of a new species。
この論文では Oceanites exasperatus Antarctic Storm-Petrel は種の扱いになる。
亜種から種への昇格だけでなく、亜種の帰属もこれまでに提案された分類と変わっているそうで、関心のある方は見ていただきたい。
SACC は早々に検討を開始 Revise the taxonomy of Oceanites species。
提唱されている種の繁殖分布図も出ている。日本で記録された個体がどれに該当するか再検討されることになるかも知れない (Oceanites exasperatus の繁殖地は日本から最も遠い)。
議論はかなり沸騰しているようで (Yet another thread on eponyms... But this one might actually be fun!)
意見の多くは海鳥を専門としない人が述べているとのこと。
種概念というよりは分布による色彩の違いなのでは。外見では区別できなくても1個体の DNA で新種認定をしてもよいのか、など。
ミズナギドリ目 Procellariiformes はかつて管鼻目と呼ばれていた。これは Tubinares ラテン語 tubus (管) + nares (naris 鼻 の複数形) 由来 (wiktionary)。英語でもそのまま訳されて Tubenoses とされており現在も使われる。英語から訳されたものかも知れない。系統名を表す形容詞で tubinare が普通に用いられる。専門語過ぎて OED にも出てこない。
Tubinares の語尾は Strisores (#ヨタカ備考参照) 同様に古い時代の目名で用いられたもの。
wikipedia 英語版によれば Procellariiformes の名称は Fuerbringer (1888) が名付けたものとのこと。参考 この時点では -formes が用いられていた。この時点で Tubinares の概念はすでに存在していた。
Hartert (1910-1922) p. 1409 では Tubinares を採用したが別名 Procellariiformes も載せていた。この時代の文献をもとにすれば管鼻目と訳されるのが自然だった。
両者がともに用いられてきた背景は Strisores (Caprimulgiformes) と似たところがあって、アホウドリ科 Diomedeidae を含めるかどうかだろうか。現代の分子系統解析 (第7版時代とは異なる) ではアホウドリ科が最も分岐にあたり、形態的分類を重視してアホウドリ科 と アシナガウミツバメ科 Oceanitidae 以降の系統で分けてそれぞれを目にしても構わない状況。
しかし第7版時代は逆順であったようにアホウドリ科とアシナガウミツバメ科の分岐年代が近接しており、全部まとめてミズナギドリ目とするのが妥当となったのだろう。どちらの場合も Tubinares または Procellariiformes の概念拡張が必要で後者を用いる方が広く受け入れられたものと想像できる。
アホウドリ目を分離する考え方にまったく意味がないわけではないが、アシナガウミツバメ科の分岐年代関係がまだ確実でない状況もあって細かく分けすぎとなったものだろう。
系統関係の状況は Cuevas-Caballe et al. (2022) The First Genome of the Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) Provides a Valuable Resource for Conservation Genomics and Sheds Light on Adaptation to a Pelagic lifestyle
の系統樹でも見ることができる。別目とされたペンギン目との違いに比べると遺伝子の違いはやはり小さい。
-
クロコシジロウミツバメ
- 第8版学名:Hydrobates castro (ヒュドゥロバテース カストゥロ) 水を歩く鳥カストロ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Oceanodroma castro (オーケアノドゥロマ カストゥロ) 大洋を走る鳥カストロ
- 第8版属名:hydrobates hudro- 水を bates 歩く (Gk)
- 第7版属名:oceanodroma (合) 大洋を走るもの (okeanos 大洋 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:castro (外) カストロ [マデイラ諸島での呼び名、鳥の声を変化させた呼び名との考えがある (The Key to Scientific Names)]
- 英名:Madeiran Storm-petrel, IOC: Band-rumped Storm Petrel
- 備考:
hydrobates, oceanodroma は#オーストンウミツバメ参照。
castro は cas- がアクセント音節となる。
英語別名に Harcourt's Storm-Petrel もあった。記載時学名 Thalassidroma castro Harcourt, 1851 (原記載) 基産地 Desertas Islets, Madeira。
現地名 Roque de Castro で Koque de Crasto と発音されるとある。綴りは castro だが (誤植でなければ) 読み方は "クラスト" らしい。ここでは綴りのラテン語読みを採用した。
種小名は現地名由来、英名はマデイラ諸島または記載者由来。Madeiran Petrel と呼ばれる種類が別にあり Pterodroma madeira (マデイラミズナギドリ)。
あまりに紛らわしいのでこの種は英語で Zino's Petrel とも呼ばれ (ケープベルデミズナギドリ Pterodroma feae Fea's Petrel から別種に分離した研究者の名前から)、クロコシジロウミツバメには記述的な Band-rumped Storm Petrel の英名が採用されたと考えられる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Hydrobates 属 (hudro- 水を bates 歩く Gk)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でオーストンウミツバメ属の名前が与えられている。種小名は変化なし。単形種。
-
ヒメクロウミツバメ
- 第8版学名:Hydrobates monorhis (ヒュドゥロバテース モノリス) 鼻孔が一つの水を歩く者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Oceanodroma monorhis (オーケアノドゥロマ モノリス) 鼻孔が一つのウミツバメ
- 第8版属名:hydrobates hudro- 水を bates 歩く (Gk)
- 第7版属名:oceanodroma (合) 大洋を走るもの (okeanos 大洋 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:monorhis (合) 鼻孔が一つ (mono- (接頭辞) 一つの ris 鼻 Gk)
- 英名:Swinhoe's Storm Petrel (英国博物学者 Robert Swinhoe に由来)
- 備考:
hydrobates, oceanodroma は#オーストンウミツバメ参照。
monorhis は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-no- がアクセント音節と考えられる (モノリス)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Hydrobates 属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。種小名は変化なし。単形種。
Birder 編集部 (2000) Birder 14(8): 16 に 1992 年に京都で保護され大阪南港野鳥園で放鳥されたヒメクロウミツバメについて触れられている。臭いが非常にきつかったとのこと。
-
コシジロウミツバメ
- 第8版学名:Hydrobates leucorhous (ヒュドゥロバテース レウコロウス) 腰の白い水を歩く者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Oceanodroma leucorhoa (オーケアノドゥロマ レウコロア) 腰の白いウミツバメ
- 第8版属名:hydrobates hudro- 水を bates 歩く (Gk)
- 第7版属名:oceanodroma (合) 大洋を走るもの (okeanos 大洋 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:leucorhous / leucorhoa (合) 白い腰の leukos 白 orrhos 腰 Gk。The Key to Scientific Names)
- 英名:Leach's Storm Petrel (英国動物学者 William Elford Leach による)
- 備考:
hydrobates, oceanodroma は#オーストンウミツバメ参照。
leucorhous は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-cor- がアクセント音節と考えられる (レウコロウス / レウコロア)。
種小名と和名は対応がよい。英語で white-rumped storm-petrels と呼ぶと複数種を指す (腰の白いチュウヒ類のような概念) ので種小名そのままの英名は使われないよう。
対照させるための Band-rumped Storm Petrel (クロコシジロウミツバメ) や Wedge-rumped Storm Petrel (ガラパゴスウミツバメ) の名称は存在する。Storm Petrel にハイフンを入れるのは主にアメリカの書き方で IOC の英名ではハイフンなし。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Hydrobates 属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。学名は Hydrobates leucorhous となる。2亜種あり (IOC)、日本で記録されるものは基亜種 leucorhous とされる。
[嗅覚]
Sin et al. (2022) Olfactory receptor subgenome and expression in a highly olfactory procellariiform seabird によればこの研究の段階で嗅覚遺伝子数が水鳥の中で最大、偽遺伝子化率は最小であったとのこと。
この文献ではコサギが次いで高い値になっているがコサギはそれほど嗅覚に頼っているのだろうか。
コシジロウミツバメとフルマカモメの共通祖先段階で嗅覚レパートリーの拡大があったがフルマカモメ系統は失ったとの解釈になっている。
遺伝子長に比べて読み取り配列が短いこと、嗅覚遺伝子族は数も多く互いに類似性が高いので正確に数えるのは難しいとのこと。一部の他種では長い読み取りを行って精度を上げる取り組みもあるとのこと。
フルマカモメで数が少ないのは地上営巣性のためで嗅覚の役割が低い解釈があるとのこと (採食における嗅覚との関係が紹介されているが自分の巣穴を見つけるための嗅覚の役割が高いのだろう。引用文献に書いてあるかも)。
コシジロウミツバメの視力が低いとの報告もあるとのこと。ただしゲノム精度依存なのでフルマカモメの方が嗅覚が劣っていると結論するにはまだ早いとこと。OR family 14 は揮発性疎水性物質とよく結合するのでこの遺伝子を豊富に持っていることがジメチルスルフィドに誘引されるコシジロウミツバメの生態と整合しているとのこと。
[LED に誘引されたウミツバメ類の集団死?]
New lights cause hundreds of seabird deaths in Cape Verde (BirdGuides 2025.4.1)
アフリカ大陸の西側の島カーボベルデで古いタイプの街や港の街灯を輝度の高い白色 LED に取り替えたところウミツバメ類の集団死が続発。4種でそのうち3種がこの島で繁殖。コシジロウミツバメは渡り鳥。
LED に切り替えて省エネとメンテナンス手間が減っても結局は光が多用されて光の量を増やすだけになっているケースが多い感じがする。
-
オーストンウミツバメ
- 第8版学名:Hydrobates tristrami (ヒュドゥロバテース トゥリストゥラーミ) トリストラムの水を歩く者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Oceanodroma tristrami (オーケアノドゥロマ トゥリストゥラーミ) トリストラムのウミツバメ
- 第8版属名:hydrobates hudro- 水を bates 歩く (Gk)
- 第7版属名:oceanodroma (合) 大洋を走るもの (okeanos 大洋 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:tristrami (属) tristram の
- 英名:Tristram's Storm Petrel (英国の聖職者 Henry Baker Tristram による)
- 備考:
hydrobates は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は bates の語末が長母音のためここが長音となると考えられる。-dro- がアクセント音節と考えられる (ヒュドゥロバテース)。
tristrami は外来語で発音はよくわからないが、ごく普通のラテン語 ramus (枝) の変化形と同様と考えれば少なくとも a は長母音となるのが自然に思える。アクセントも置きやすいのでこの発音を採用した (トゥリストゥラーミ)。
oceanodroma は外来語で発音はよくわからないが、okeanos は冒頭が長母音。-no- がアクセント音節と考えられる (オーケアノドゥロマ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Hydrobates 属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。種小名は変化なし。
和名はアラン・オーストン (Alan Owston) 由来でもとは Cymochorea owstoni。現在はシノニムとなったが和名は維持された [川田 (2016) アラン・オーストン基礎資料]。単形種。
-
クロウミツバメ
- 第8版学名:Hydrobates matsudairae (ヒュドゥロバテース マツダイラエ) 松平の水を歩く者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Oceanodroma matsudairae (オーケアノドゥロマ マツダイラエ) 松平のウミツバメ
- 第8版属名:hydrobates hudro- 水を bates 歩く (Gk)
- 第7版属名:oceanodroma (合) 大洋を走るもの (okeanos 大洋 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:matsudairae (属) 松平頼孝の (matsudaira -ae) 発見者
- 英名:Matsudaira's Storm Petrel
- 備考:
hydrobates, oceanodroma は#オーストンウミツバメ参照。
matsudairae は ts をこのように発音するとして、アクセントは "マツダイラエ" と考えられる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Hydrobates 属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。種小名は変化なし。単形種。
記載時学名 Oceanodroma melania matsudariae Kuroda, 1922 (原記載)。相模湾の沿岸から離れたところで 1921 年に5羽採集されたもので記載当時は亜種扱い。
アメリカの種で Seebohm が日本で採集した標本を Oceanodroma melania と同定したが、Oceanodroma tristami と同定されるべきではないかとの Salvin の見解が紹介されており、Kuroda も同意するとのこと。もし Seebohm の同定が誤っていれば日本で最初の Oceanodroma melania の記録となり、計測値の違いから亜種を提案したもの。
記載時の亜種小名は綴りを間違っていたが Matsudaira の人名は原記載に記されているので訂正した(亜)種小名が広く受け入れられているとのこと。PROCELLARIIFORMES Albatrosses, petrels, and shearwaters (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealand より)。
海外の名称では松平を採用しているものも多いが、"日本の"、あるいは "硫黄島の" を付けた名称もある。スウェーデン語では以前は人名を用いていたが 2023 年に硫黄島に変更した (wikipedia スウェーデン語版より。アメリカ・カナダの改名の動きに合わせたものだろう)。
-
ハイイロウミツバメ
- 第8版学名:Hydrobates furcatus (ヒュドゥロバテース フルカートゥス) 叉木状の尾の水を歩く者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Oceanodroma furcata (オーケアノドゥロマ フルカータ) 叉木状の尾のウミツバメ
- 第8版属名:hydrobates hudro- 水を bates 歩く (Gk)
- 第7版属名:oceanodroma (合) 大洋を走るもの (okeanos 大洋 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:furcatus / furcata (adj) 叉木状の (furca (f) 叉木 -atus (接尾辞) 〜を所有する)
- 英名:Fork-tailed Storm Petrel
- 備考:
hydrobates, oceanodroma は#オーストンウミツバメ参照。
furcatus は a が長母音でアクセントもここにある (フルカートゥス)。-atus の所有の接尾辞由来。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Hydrobates 属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。学名は Hydrobates furcatus となる。2亜種あり (IOC)、日本で記録されるものは基亜種 furcatus とされる。
△ コウノトリ目 CICONIIFORMES コウノトリ科 CICONIIDAE ▽
-
ナベコウ
- 学名:Ciconia nigra (キコーニア ニグラ) 黒いコウノトリ
- 属名:ciconia (f) コウノトリ
- 種小名:nigra (adj) 黒い (niger)
- 英名:Black Stork
- 備考:
ciconia は#コウノトリ参照。
nigra は短母音のみ (ニグラ)。
英名は学名に対応している。シュバシコウを用いた Ciconia 属が作られた際に Ciconia alba が使われたが (#コウノトリの備考参照)、それと対比する形の種小名にもなっている。
単形種。
-
コウノトリ
- 学名:Ciconia boyciana (キコーニア ボイキアーナ) ボイスのコウノトリ
- 属名:ciconia (f) コウノトリ
- 種小名:boyciana (adj) Robert Henry Boyce (英国の調査官、上海でも仕事を行った) の (boyce (m) を形容詞化して boycianus 更に女性形にして boyciana)
- 英名:Oriental Stork
- 備考:
ciconia は o が長母音でアクセントもここにある (キコーニア)。
語源は難しいようでインド・ヨーロッパ祖語の *kekoh2n- (コウノトリ) や *keh2n- (この単語から派生した歌う・鳴く) 由来と考えられている (成鳥コウノトリは鳴かないが)。ラテン語の歌う cano (カノー。#カッコウの種小名参照) とも関係がある。
ドイツ祖語の *hano (雄鶏) や *hanjo (めんどり)、スラブ祖語の *kana (タカ類) とも関係があるとのこと。ブルガリア語方言ではコウノトリを kanyusha と呼び、ロシア語ではほぼ同じ綴りで kanyuk はノスリ類を指す (wiktionary)。コウノトリとタカが微妙につながっている。分子系統関係がわかるまではタカ類がコウノトリ目に含まれていたのもある程度納得できる (?)。
boyciana はラテン語化の際に用いられた -anus (ここでは人名の形容詞化) の a が長母音でここにアクセントがある (ボイキアーナ)。
かつては シュバシコウ Ciconia ciconia 英名 White Stork の亜種とされた (当時の学名 Ciconia ciconia boyciana)。
コウノトリの一般的英名も White Stork だった。
同種時代はシュバシコウの種和名もコウノトリだった。現在でもシュバシコウを指してコウノトリと呼ぶこともしばしばある。
シュバシコウの記載時学名は Ardea Ciconia Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe, Asia, Africa; restricted type locality, Sweden (スウェーデンに限定)。
Ciconia の属名はこの種小名から昇格されたもので Brisson (1760) が名付けたもの。英語の White Stork やフランス語名の cicogne blanche は古くから知られていて、Linnaeus (1746) (有効な学名とみなされる前) も Ardea alba を使っていた。
Ciconia 属を設けるにあたって Ciconia alba の種小名が与えられた (#ノスリの備考参照)。
後に Linnaeus (1758) の種小名に戻された。
コウノトリの記載時学名は Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 (原記載) 基産地 Yokohama (横浜)。当時は White Storks が2種知られていてそれらとは異なるとのこと。Boyce's Stork の英名を与えている。個体は生きたままロンドンに輸送中とのこと。
Fauna Japonica には書かれていないが日本では大きな群れを作ってしばしば見られると教えられた。大陸に生息するかどうかの情報は少なく少なくとも標本になったものはない (ヨーロッパのシュバシコウが連続分布していることをある程度否定している)。
分離され現在は単形種。
英名 (現在はシュバシコウを指す) の White Stork は Black Stork (ナベコウ。こちらの英名は学名と同じ意味) に対比させたものと想像できる。おそらく Stork だけで十分だった (なおどちらも現在の英国には通常分布ではない)。
ドイツ語 Storch とともにさまざまな伝説にもなっているように普通に使われていた単語だが、コウノトリ類を指して集合的にも用いられるため、学術的に種を明確に表すために White が補われたもの (ドイツ語でも同じ意味で Weissstorch) であろう。
よく知られた種類であるスキハシコウ類の属名も興味深いので紹介しておくと Anastomus (アナストムス)。ギリシャ語 ana- は上向き、開ける、後ろ向きなどの意味 (最後の意味はハシマガリチドリの属名に使われる。#シロチドリ参照)。
stoma は口。解剖学用語の anastomosis 動静脈吻合 (ふんごう) も同じ語源。
コウノトリの高精度ゲノム研究が出ている: Yang et al. (2024) Genomic exploration of the endangered oriental stork, Ciconia boyciana, sheds light on migration adaptation and future conservation
絶滅の懸念されている他種に比べて遺伝的多様性は高い。生の選択を受けている遺伝子に渡りに関わる可能性のある候補遺伝子が含まれている。
[コウノトリ科の系統分類]
de Sousa et al. (2023) Cytotaxonomy and Molecular Analyses of Mycteria americana (Ciconiidae: Ciconiiformes): Insights on Stork Phylogeny
で用いられている系統樹による。系統樹に現れないものは Boyd から補ってある。
コウノトリ科 Ciconiidae: Storks
スキハシコウ属 Anastomus
スキハシコウ (スキバシコウ) Anastomus oscitans Asian Openbill
クロスキハシコウ Anastomus lamelligerus African Openbill
ハゲコウ属 Leptoptilos
アフリカハゲコウ Leptoptilos crumenifer Marabou / Marabou Stork
コハゲコウ Leptoptilos javanicus Lesser Adjutant
オオハゲコウ Leptoptilos dubius Greater Adjutant
トキコウ属 Mycteria
アメリカトキコウ (トキコウ) Mycteria americana Wood Stork
アフリカトキコウ Mycteria ibis Yellow-billed Stork
シロトキコウ Mycteria cinerea Milky Stork
インドトキコウ Mycteria leucocephala Painted Stork
ズグロハゲコウ属 Jabiru
ズグロハゲコウ Jabiru mycteria Jabiru
セイタカコウ属 Ephippiorhynchus
セイタカコウ Ephippiorhynchus asiaticus Black-necked Stork
クラハシコウ Ephippiorhynchus senegalensis Saddle-billed Stork
コウノトリ属 Ciconia
アオハシコウ Ciconia abdimii Abdim's Stork
エンビコウ Ciconia episcopus Woolly-necked Stork
スンダエンビコウ Ciconia stormi Storm's Stork
ナベコウ Ciconia nigra Black Stork
シロエンビコウ Ciconia maguari Maguari Stork
シュバシコウCiconia ciconia White Stork
コウノトリ Ciconia boyciana Oriental Stork
この系統樹を調べてみたのは成鳥が発声を行わなくなったのはどの系統からか知りたかったためだったが、ナベコウの音声記録があり、成鳥が発声を行わないのはコウノトリとシュバシコウで最も "派生した" 形質らしいことがわかった。ただしそもそも珍しい種類で音声記録のないものもあり、コウノトリ以外の系統で散発的に失っているものもあるかも知れない。
セイタカコウ属のデータはないが、ズグロハゲコウではサギのような声が記録されている。
アメリカトキコウはあまり発声しないようで少数の記録にとどまっているがサギの声に似ている。インドトキコウも成鳥の声の記録はあまりない。スキハシコウの成鳥が鳴くかどうかよくわからないが、コロニーの音声はサギのコロニーに似ている。
一部の種で嘴の音が記録されているが コウノトリ / シュバシコウ ほどはっきりしたものではなさそう (以上 xeno-canto を用いた調査)。
スキハシコウの wikipedia 英語版では他のコウノトリ類同様に clattering でコミュニケーションをすると書かれているが、この記述は コウノトリ / シュバシコウ と近縁と考えられていた時期のものかも知れない。現代的な分子系統樹ではかなり縁が遠く、コウノトリ科の中でも最も古く分岐した系統にあたる。サギのコロニーに似た声でも不思議でない感じがする。
アフリカハゲコウの wikipedia 英語版ではあまり声を出さないが bill-rattling courtship displays があると書かれている。セイタカコウでは同様に They then clatter their bills and walk away. とディスプレイの記述がある。ナベコウでは bill-clattering をまれに行うとあるがディスプレイは音声が中心のよう。
コウノトリ科は全体的に成鳥が発声をあまり行わず bill-clattering は複数系統で見られるが コウノトリ / シュバシコウ と最も近縁なナベコウでは音声が中心で、音声・clattering に系統的にはそれほどはっきりした段階的変化は見られないよう。
DNA-DNA hybridization の時代のコウノトリ科の系統解析の論文があった。Slikas (1997) Phylogeny of the avian family Ciconiidae (storks) based on cytochrome b sequences and DNA-DNA hybridization distances
DNA-DNA hybridization 単独でも現在の系統樹とかなりよく一致する結果を導いいていた。一方従来系統が近いと考えられていた新世界ハゲワシ類と系統が遠いことも示されていた。内部鳴管筋 (internal syringeal muscles) を欠いていることもコウノトリ科と新世界ハゲワシ類の類似点とされていたとのこと。
[シュバシコウの嗅覚]
シュバシコウで刈られたばかりの芝生から出る揮発性化合物 (Z)-3-hexenal, (Z)-3-hexenol, hexenyl acetate がシュバシコウを引きつけるとの研究があった: Wikelski et al. (2021) Smell of green leaf volatiles attracts white storks to freshly cut meadows
我々でも青草の匂いを感じるので不思議ではないが、鳥類は一般に嗅覚に乏しいと考えられていた従来の考えからは思いつかない結果だったかも知れない。風向きを考慮すると視覚よりもむしろ匂いを感じて集まってくる証拠が得られ、人工的な散布実験でも同じ結果が得られた。嗅覚により遠方の食物を探る能力は鳥類で普通にあるのかも知れないとのこと。
[渡りを止めたシュバシコウ]
Andrade et al. (2025) Mechanisms underlying the loss of migratory behaviour in a long-lived bird (2024 preprint)
イベリア半島のシュバシコウは 1995-2020 年の間に渡りをしない個体が 18% から 68-83% に急増した。生態的な究極要因は明らかにされていて、遺伝的背景があることを示唆するものだが、遺伝的メカニズムなどは不明だった。
全ゲノム解析を行ったところ、渡りを行う個体も行わないものも区別ができなかった。若鳥の大部分はジブラルタル海峡を越えて渡るが、成長とともに渡らない比率が増え、GPS 追跡された成鳥では 19% しか渡らなかったとのこと。近年渡らない個体が増えているのは渡らない個体が自然選択されたなどの要因は考えにくく、成長過程のある時期の可塑性 (developmental plasticity) が由来ではないかとのこと。
Delmore et al. (2020) The evolutionary history and genomics of European blackcap migration
遺伝的な変化でズグロムシクイが渡りを止めるようになった遺伝的基盤を提唱している。
渡りをするグループは種分化途中の段階ではないか (3万年前ぐらいから分化開始、5000 年前ぐらいに留鳥グループと再度交流あり)。候補となった遺伝部位は他の渡りの鳥で指摘されているものとは異なっていたとのこと。
de Zoeten and Pulido (2020) How migratory populations become resident
が理論的な個体群シミュレーションを行っている。
この話にはさらに続きがあり、こちらは遺伝子そのものよりも構造多型による調節機構が関わっている: #ハシボソガラスの備考の Delmore et al. (2023) を参照。
△ カツオドリ目 SULIFORMES グンカンドリ科 FREGATIDAE ▽
-
オオグンカンドリ
- 学名:Fregata minor (フレガータ ミノル) 小さなフリゲート艦
- 属名:fregata (外) fregate 敏捷で獰猛なグンカンドリ類のフランス航海者による名前 < fregate, frigate フリゲート艦 < fregata 伊 だが語源は不明
- 種小名:minor (adj) 小さい
- 英名:Great Frigatebird
- 備考:
fregata の読み方はよくわからないが、"フレガータ" が自然な発音と思われるので採用しておく。ちなみに現代のイタリア語では特に伸ばさないがアクセント位置はこの場所で、かつては伸ばして読んでいたのだろうと想像できる。
フリゲート艦の意味の語源は明確でないようだが、ギリシャ語由来のラテン語 aphractus (船) が縮まったものとの説がある (wiktionary)。
minor は "ミノル" のアクセントに注意。
5亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 minor とされる。
和名や英名と学名が整合しないが、John Latham が "A General Synopsis of Birds" (1785) に Gmelin が "lesser frigate pelican" Pelecanus minor と記述し (1789)、Linnaeus が採用した (原記載) ためこの学名になったとのこと (wikipedia 英語版)。
他言語では "大きい" を付けているものが多いがポーランド語のように "中間の" を付けているものもある。シロハラグンカンドリ Fregata andrewsi Christmas (Island) Frigatebird の方がより大きいとのこと。ポーランド語の "中間の" はこの意味かとも思ったが、シロハラグンカンドリに "大きい" を付けているわけではなく色で表している。
オオグンカンドリはドイツ語では Bindenfregattvogel だが、これは "ネクタイをした" の意味だろうか。
赤い喉袋の色素は 85% がアスタキサンチンで、これほど濃度の高い鳥は他にないとのこと [wikipedia ドイツ語版から知った。出典は Joula et al. (2008) Carotenoids and throat pouch coloration in the great frigatebird (Fregata minor)]。
Fregata 属にはメスグログンカンドリ Fregata aquila Ascension Frigatebird という "ワシ" を種小名に持つ種類がある。英名はアセンション島に由来。
多くの言語で "ワシ" またはアセンション島由来の名前が使われており、和名はメスの喉袋に相当する部位が黒いことに由来するが他言語に比べて少し特殊。
Linnaeus (1758) の時代からある (原記載) 由緒ある学名。イヌワシ属の Aquila の方が後の用例 [Brisson (1760)。Linnaeus (1758) はイヌワシ類を Falco 属に含めていたため]。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にはこの学名の種類を和名空欄、Minami-Torishima としてリストしている。同リストに載せられているグンカンドリ類はオオグンカンドリ (当時の名称グンカンドリ) のみで現在の分類とは別概念か。
[オオグンカンドリの飛行中の睡眠・鳥類の睡眠の話題]
ヒトを含む哺乳類では急速眼球運動を伴うレム REM (rapid eye movement) 睡眠がよく知られているが、レム睡眠とノンレム (NREM) 睡眠は鳥類でも脳波ではっきり確認できる。この2種類の睡眠がはっきり分化しているのは鳥類と哺乳類のみである。
Rattenborg et al. (2016) Evidence that birds sleep in mid-flight
はオオグンカンドリの脳波や加速度を測定し、飛行中に NREM 睡眠と REM 睡眠が見られることを明らかにした。
目からの信号がほぼ完全に反対側の脳に送られるため、片側の脳で NREM 睡眠を行いつつももう片側で注意を怠らないことを可能にしている。旋回方向に対して外側に目を開ける形の半球睡眠となっているとのこと。
飛んでいる時は 2.9% の時間しか寝ないのに対し、地上では 53% の時間を睡眠に使っている。
飛んでいる時は夜も注意を払う必要があり長時間、あるいは深い睡眠には限界がある。
飛んでいる時に短時間しか睡眠を取ることのできない悪影響が考えられるが、どのように克服しているのか。
飛んでいる時の脳波で睡眠が確認されたのはこれが初めてとのこと (#アマツバメの備考 [アマツバメは飛びながら寝る?] も参照。こちらは直接検証はできていない)。
オオグンカンドリは夜間にほとんど採食しないのに睡眠を節約してまで飛んでいる必要があるのは着水して休憩できない生理的要因があるのだろう。系統的な原因の可能性があると考え、#ヒメウの備考 [ウ類の嗅覚] で考察してみた。
Rattenborg (2017) Sleeping on the wing
が他のグループの鳥も含めた長時間連続飛行中の睡眠についてトラッキングデータをもとに考察している。
アマツバメ類は有名だがこの著者の解釈はかなり慎重で、横向きになって翼を動かしていないことが必ずしも飛びながら寝ている証拠にはなっていないとしている。
ヨーロッパアマツバメは繁殖期にとまって寝るが、立って寝ることも横になって寝ることもある。
4分に1点のサンプリングでその間にとまって寝ている可能性は否定できない。
渡りの時期でも体を立てて動きを止める部分もあり、崖にとまって寝ているかも知れない。
長期間飛べることを示したもので、飛びながら眠っている証拠を示したものではない。
飛びながら寝ることはオオグンカンドリで初めて明確に示されたことを強調する意味もあるだろうが、指摘は説得力があるように見える。アマツバメ類の空中睡眠について言及する際は、古くからの推測や一般向け記事などは一旦忘れて「可能性がある」としておくのがよさそう。
長距離の海上を渡るシギ類でも考えられるが、長距離無着陸の飛行を特に選んでいるわけではない。
グンカンドリ類は連続で飛ぶが、アホウドリ類は着水できるので飛びながら寝る必要は少ないかも知れない。
タカ・ハヤブサ類は主に昼間に渡るので普通は寝る機会は十分あるはず。アカアシチョウゲンボウは 5.4 日かけてインド洋 5600 km を横切る。この論文では同じ空を渡るトンボを食べている可能性も考えているが確かめられていない。アカアシチョウゲンボウが飛びながら寝ることができるかはわからない。
スズメ目ではあまりよくわからないが眠りに関係して警戒度が落ちて建物にぶつかったりしているかも知れない。声を出しているから寝ていないとは言い切れない。声を出している合間に半球睡眠をとっている可能性はある。実験室内の渡りの小鳥では渡りの不穏時期に夜は寝ていないが、昼は居眠りをして過ごし、昼に休憩できるならば夜は寝なくても大丈夫なのかも知れない。
無着陸の渡りの要因として、そもそも着陸できる場所がない場合と、途中で休憩を入れずに目的地に早く到着する方が効率的な戦略として選ばれている側面もある。
鳥は寝ながら立てることは知られているので (有蹄類では REM 睡眠中は横になるとのこと) ソアリングや滑空状態を維持して眠ることもできるかも知れないし、羽ばたきさえできるかも知れない。しかし REM 睡眠中の羽ばたきはより難しいだろうとのこと。数秒の REM 睡眠で滑空しているかも知れない。
ハトでの実験では3時間の睡眠が奪われるだけでも起こしておくのに連続した刺激が必要だったとのことで、グンカンドリは睡眠不足に対する特殊な適応を行っていることが示唆される。
一方で一夫多妻のアメリカウズラシギは極北で3週間のつがい形成時期にほとんど寝なくても能力が維持されていることが示されている: Lesku et al. (2012) Adaptive Sleep Loss in Polygynous Pectoral Sandpipers。
この場合は睡眠時間の短い個体ほど子孫を残せる結果となっている。
しかしアメリカウズラシギでもグンカンドリでも最小限の睡眠はとっており限界があることを示唆する。
全般的には数日間の連続飛行において渡り鳥が寝ないでやり過ごせるかどうかはまだ結論が出ていない。
飛びながら寝るのは鳥にとっても簡単な、あるいは生理的の好ましいことではないようで、多くの鳥は飛行中は大部分起きていて、一部の種が生態的要求に迫られて行っている論調に感じられる。いかに鳥とはいえできればとまって寝たいのだろう。
アメリカウズラシギのように競争により睡眠時間がとれないのはその昔受験勉強で言われた「四当五落」(1950-1980 年代によく使われた用語) を思い出してしまう。生態学的要求はなかなか厳しい。
半球睡眠は特殊な能力と考えられがちだが、ヒトでも "first night effect" (最初の夜の影響) が知られていて、睡眠中の音に対する反応が最初の晩は左が悪く、よく寝られた翌晩からから非対称性が消えるという [Tamaki et al. (2016) Night Watch in One Brain Hemisphere during Sleep Associated with the First-Night Effect in Humans]。
新しい環境に即してヒトでも部分的な半球睡眠を行っている可能性がある (蛇足的に付け加えておくと片目を開けた場合は鳥類とは違って大脳両半球に信号が行くため、両目を閉じないと半球睡眠にはならないだろうと想像する)。
"REM" の名前はヒトを含む哺乳類の眼球運動に対して名付けられたものであったが、鳥類でも眼球運動を伴っているかどうかを調べるのは案外難しい。ごく最近になって半透明なまぶたを持つハトの目を赤外線カメラで記録し (しかし頭を羽にうずめてしまうと記録できない)、脳波とともに fMRI (磁気共鳴機能画像法) で脳のどの部分が働いているかを調べることができるようになった。
Ungurean and Rattenborg (2023) A mammal and bird's-eye-view of the pupil during sleep and wakefulness
を見ると、哺乳類とはパターンは異なるが REM 睡眠の時にやはり目が動いていることがわかる
(比較に用いている哺乳類は夜行性だがその影響はどうであろうか?)。
また NREM 睡眠中に瞳孔が最大に広がっているがこの点は哺乳類と逆になっているとのこと
(寝る時に頭を羽にうずめてしまう種類が多いので、外敵の存在に気づける程度の光が網膜に達するようにするためではないかとこの論文では推測している)。
鳥では起きている時ではリラックスすると瞳孔が大きくなる。
Ungurean et al. (2023) Wide-spread brain activation and reduced CSF flow during avian REM sleep
では NREM 睡眠中に脳脊髄液がよく流れて老廃物を排泄しているらしい点は哺乳類と同じであること、REM 睡眠中にに脳が起きている時のように活発に活動していることを示している。
活発に活動する部位は視覚情報処理に関係する部分で、飛んでいる時に働く部分も働いていて飛んでいる夢を見ているのではないかとの推測も報道された。
研究の舞台裏もあってハトを MRI に入れるとすぐ寝てしまうので、鳥を起こしておくのに工夫した
とか (クラシック音楽を大音量で聞かせたとか、研究者の好みが出てそうである)。
寝ている時の眼球の動きが見えるようにまぶたが透けて見えるハトの品種を用いたとのこと。
いずれにしても鳥類でも眼球は動き、睡眠中の急速眼球運動もある、そして REM 睡眠中に夢も見ているのではとの最新研究結果も出ている。
Rial et al. (2022) The Birth of the Mammalian Sleep のような面白い提案もあるので紹介しておく。
鳥類・哺乳類が共通の睡眠を示すことは共通祖先の段階からあったものか、それとも独立に進化したものか。この著者によれば爬虫類が眠るという過去の報告は実験条件に問題があり、真の睡眠と呼べるものはないのではないかと結論している (なお俗に言われるように瞼がないので寝ないとは言いきれない。鳥類・哺乳類でも目を開けて NREM 睡眠をとることもある。やはり脳波を見ないとわからないよう)。
そうであれば鳥類・哺乳類の睡眠は独自に進化した (収斂進化) ものとなる。
この著者は哺乳類の睡眠の起源を恐竜支配下の夜行性時代に求めている。夜行性に適応した目には昼の光は明るすぎて目を閉じる必要があり、それが睡眠の進化につながったのではないかとのこと。鳥類はそのような解釈ができないので別の機構が必要になるだろう。皆さんはどう考えられるだろうか。
Rattenborg and Ungurean (2022) The evolution and diversification of sleep
ではもっと原始的な系統でも REM / NREM 睡眠に似た現象の報告があるが違いも大きい。1種類の睡眠は相当古くまで遡ることができるが、2種類の睡眠の起源はまだまだ研究途上のよう。
日本のグループの研究もあり Yamazaki et al. (2020) Evolutionary Origin of Distinct NREM and REM Sleep こちらは共通祖先段階から生じたものではないかとの考えを示している。
半球睡眠を行う動物 (オオグンカンドリ、オットセイ) では REM 睡眠が非常に少ないという。水中や空中で REM 睡眠を行うのはあまりに危険との考え方もできる。
NREM 睡眠で脳活動の低下 (脳温度低下など) が起きるが REM 睡眠によって周期的に脳温度を上げる作用があるのでは (恒温動物で見られる理由になる) とも考えられるが変温動物に REM 睡眠的なものが見られてこの仮説に疑問も投げかけられている。哺乳類の REM 睡眠中で働くものと同等のニューロンが爬虫類にも存在し起源はもっと古い可能性がある。ただし2種類の睡眠の機能は恒温動物と異なるかも知れない。
Siegel (2023) REM sleep function: mythology vs. reality
のレビューも脳温度を上げる作用を考えており、哺乳類を中心に調べて体温の低い動物ほど REM 睡眠の量が多く (カモノハシは REM 睡眠が8時間もあり、1日 14 時間寝ている)、鳥類で短いのはその延長上で解釈できか、と述べている。大型の動物ほど睡眠サイクルが長いのも冷却に要する時間で説明できるという。
クジラ・イルカ類は REM 睡眠がないとのことで、絶対的に必須のものでもなさそう。REM 睡眠の割合と知的能力の高さとは関係ないと考えている。
van Hasselt et al. (2024) Sleep and Thermoregulation in Birds: Cold Exposure Reduces Brain Temperature but Has Little Influence on Sleep Time and Sleep Architecture in Jackdaws (Coloeus monedula)
哺乳類では低温環境で REM 睡眠が減少するが、ニシコクマルガラスではそうならなかった。哺乳類では REM 睡眠中に体温調節機能 (ふるえ、あえぎなど) がほぼ失われるが、鳥類では異なっている可能性がある。外気温が下がると脳の温度も下がり、REM 睡眠中は脳の温度が上がることは確かめられたが、これは体温調節機能の有無を示す証拠ではない。
鳥類では REM 睡眠中に筋肉活動がほぼ完全に失われることはなく、筋肉での熱産生による体温調節が可能なのでは。頸筋の脱力 (うなだれる) は測定していたが胸筋は測っていなかったのでこの実験からは判断できないとのこと。
Lyamin et al. (2021) Sleep in ostrich chicks (Struthio camelus)
ダチョウ成鳥では鳥類の中で最も REM 睡眠の比率が高い (24%) とのこと。ひなではもっと多いかと調べたら逆だった。これは他の鳥類・哺乳類の傾向とは逆とのこと。
ダチョウの群れ生活では成鳥は同時に食べたり休んだりせず、集団による外敵への警戒に役立っている。
NREM 睡眠の時にも両目を開けているが REM 睡眠では閉じるとの報告がある。目を開けるのは危険に素早く反応するためで多くの鳥類・哺乳類でも観察されている現象。上述のハトの目で NREM 睡眠中に瞳孔が最大に広がる研究でも同じ解釈が紹介されている。
カモなどで見られる半球睡眠の代わりとなる戦略だろうとのこと (この記載によればすべての鳥が半球睡眠をするわけではなさそう)。
ダチョウのひなは成鳥に比べて NREM 睡眠の時に目を閉じていることが多い。生後3か月ぐらい経過しないと警戒能力が発達しないとのことで関連している可能性がある。成鳥が外敵に対して危険な長時間の REM 睡眠を行う適応的意味は不明とのこと。
鳥の話は特に出てこないがトカゲで REM / NREM 睡眠があり、そのリズム (ultradian rhythm) を作る中枢神経メカニズムを提唱するもの: Fenk et al. (2024) Central pattern generator control of a vertebrate ultradian sleep rhythm 脳幹内の振動子を考えている。
この研究者の主眼は哺乳類の睡眠解明にあるようで、哺乳類と同様のパターンが鳥や爬虫類にも見られることを文献を引用する形で紹介している。
哺乳類の睡眠を理解するためのモデル動物と捉えているようだが系統はだいぶ違うかも知れない。パターン発生の神経回路機構の提案として見るのがよさそう。
半球睡眠に関する関連研究: van Hasselt et al. (2025) Sleep pressure causes birds to trade asymmetric sleep for symmetric sleep
ニシコクマルガラスを用いて睡眠を奪う程度が高いほど半球睡眠の比率が少なかったとのこと。
Lesku (2025) Neuroscience: Kryptonite for half-awake sleepers によれば鳥の半球睡眠の能力は従来言われていたほど高いわけではない。鳥もやはり両半球で熟睡したい。
表題の Kryptonite (クリプトナイト) はアメリカン・コミックスのスーパーヒーロー「スーパーマン」の弱点。弱点を指して使われる "アキレス腱" 同等の知名度があるとのこと (wikipedia 日本語版より。もう覚えがないぐらいの古い話)。
特に渡りをする鳥の睡眠事情など、鳥における概日リズムの乱れに伴う脳や生理学の知見をヒトの医学に応用するアイデアがあるとのこと。BaHammam (2025) のレビュー論文: From Wings to Wellness: A Research Agenda Inspired by Migratory Bird Adaptations for Sleep and Circadian Medicine。
鳥とのヒトの知見の比較研究は相互の理解に役立つとのこと。共通性の高い部分が多く、ヒトのリズム形成で知られている BMAL2 が鳥でも同じ働きをしているか、鳥の半球睡眠に対応するものは何か、またそれぞれどのような生態的適応から進化したものかなどの検証材料がある。
-
コグンカンドリ
- 学名:Fregata ariel (フレガータ アリエル) 空気の精のグンカンドリ
- 属名:fregata (外) fregate 敏捷で獰猛なグンカンドリ類のフランス航海者による名前 < fregate, frigate フリゲート艦 < fregata 伊 だが語源は不明
- 種小名:ariel (外) 中世伝承で空気の精 (遡ると神のライオン ヘブライ語 に由来?)
- 英名:Lesser Frigatebird
- 備考:
fregata は#オオグンカンドリ参照。
ariel の発音は明確でないが、短母音として "アリエル" (日本語の標準的な読みとも一致する) を採用した。英語でも冒頭がアクセント。ドイツ語では冒頭アクセントで e を伸ばす。参考までにラテン語の aries (羊、おひつじ座にも使われる) は起源は違うが e は長母音でアクセントは冒頭。
おそらく伸ばしてもよいが冒頭アクセントは変わらない。
商品名に合わせて "アリエール" と書くとアクセントが後半と誤解されやすいので避けた方がよいだろう。
天王星の衛星名はウィリアム・シェイクスピアの作品、もしくはアレクサンダー・ポープ (Alexander Pope) の作品にちなんで名付けられたもので、日本語の通常表記のアリエルは ポープの戯曲「髪盗人」に登場する精霊の名前とのこと (wikipedia 日本語版)。
和名は英名に対応している。#オオグンカンドリの学名由来も参照。
3亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 ariel とされる。
△ カツオドリ目 SULIFORMES カツオドリ科 SULIDAE ▽
-
アオツラカツオドリ
- 学名:Sula dactylatra (スラ ダクテュラートゥラ) 指(羽の先)の黒いカツオドリ
- 属名:sula (外) カツオドリ ノルウエー語
- 種小名:dactylatra (合) 指の黒い (dachtylo 指 Gk、ater (adj) 黒い) 初列風切が黒いことを意味する
- 英名:Masked Booby
- 備考:
sula は#アカアシカツオドリ参照。
dactylatra は外来語を含む合成語なので発音はよくわからないが、ラテン語部分である -atra は冒頭が長母音でアクセントもここにある (ダクテュラートゥラ)。
4亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは personata (仮面をかぶった) とされる。この場合は亜種名と一般的な英名が対応している。記載時は Sula personata Gould, 1846 (原記載) で、Gould の影響力もあってこの学名と英名が主に用いられていたのかも。
英語別名に Blue-faced Booby があり、対応する学名が Sula cyanops Cheeseman, 1889 (青い顔のカツオドリの意味。同様の種小名に cyanopus があるがこれは足が青いの意味で1文字の違いで意味が大きく変わる。-pus の語末の長音を使って読み分けるとよい)
[SULIFORMES Frigatebirds, gannets, darters, and cormorants (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealand より]。
和名はこの英名または学名に対応すると想像できる。Red-fooded Booby とちょうとよい対応になっていたがさらに古い学名が見つかるなど、どちらも学名が変わってしまった。
Sula dactylatra Lesson, 1831 (原記載) 基産地 Ascension Island (大西洋アセンション島)。フランス語名 Fou manche de velours (辞書訳だとビロードの袖を持つばか) と学名語義と少し異なっている。
ポルトガル語の le manga de Velado に由来とのこと (Velado は固有名詞扱いなので普通の velado = 英語の veiled ベールをかけた とは意味が違うかも。manga の方が気になる方もあるだろうが当時日本語由来のこの単語があるはずはなく、袖の意味とのこと)。
フランス語 fou (= 英語 fool) は "ばか" の意味で採集家にはあまりに簡単に採集できてしまう意味なのだろう。
遠く離れたアセンション島付近が生息地と考えられ、同一種の判断が遅くなって Sula personata や Sula cyanops の学名が普通に使われていたのかも知れない。
[兄弟殺し]
Bizberg-Barraza et al. (2024) Parental overproduction allows siblicidal bird to adjust brood size to climate-driven prey variation
によるアオアシカツオドリ Sula nebouxii Blue-footed Booby の兄弟殺し (#イヌワシ備考 [兄弟殺し] 参照) の研究がある。
生後 5-9 日から最初のひなによる兄弟への攻撃が始まり、3-4 週でピークを迎えるとのこと。親は争いに介入せず、食物の少ない時に闘争が激しくなるという。
人工的に孵化タイミングを調整した実験では間隔を短くしても長くしても兄弟殺しの割合は変わらず、餌運びが増える結果となった研究が紹介されている (Guerra and Drummond 1995)。Guerra and Drummond (1995) の研究では、自然状態の孵化間隔で親による餌運びのコストが最適化されていると考えている。アオアシカツオドリは逆サイズ性的二形を示し猛禽類と共通点があるが、ひなを捕食する捕食者には対抗手段を持たない。
ひなの生存状況を追跡することで余分に子供を作る要因として resource-tracking hypothesis (資源量に応じた対応仮説)、insurance hypothesis (保険仮説)、facilitation hypothesis (最後のひながいることで兄弟の適応度を高める) を調べた。
resource-tracking hypothesis がよく支持される結果となったが、保険仮説はひなが3羽の時には生き残った最後のひなの生存率が高まることで支持されたが、2羽の時は支持されなかった。facilitation hypothesis を支持する証拠はなかったとのこと。
アオアシカツオドリの戦略は、条件が思わしくない時に早期にひなを減らして親の負担を減らし、ある程度予測可能性のある翌シーズンに備える長いタイムスケールの気象変動には適しているが、極端気象のように頻繁にひなを減らす必要がある状況には向いていない可能性があるとのこと。
-
アカアシカツオドリ
- 学名:Sula sula (スラ スラ) カツオドリ
- 属名:sula (外) カツオドリ ノルウエー語
- 種小名:sula (トートニム)
- 英名:Red-fooded Booby
- 備考:
属名の sula はノルウエー語で古ノルド語の sula から来ている。sulao 盗む Gk あるいは souler ゲール語 に由来するとする説は誤り。
古ノルウエー語の sula または sulu は山岳部で現在も使われており、ツバメを意味するとのこと (The Key to Scientific Names) この単語はゲルマン祖語の swalwo に由来し、カツオドリとツバメはいずれも楔形の尾に由来する Kroonen の説があるが他説もあり (wiktionary)。
sula のラテン語読みは明確でないがアクセントが冒頭であることは問題ない (スラ または スーラ)。古ノルド語の起源となるドイツ祖語では *suliz で冒頭を伸ばしているので伸ばして発音されていた可能性がある (wiktionary)。
冒頭を伸ばしてもアクセント移動はないのでどちらで読んでもよい。
3亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは rubripes (ruber 赤い pes 足) とされる。
素直に考えれば Sula sula が Sula 属のタイプ種となりそうだがそうではない。Sula leucogaster の方がタイプ種 [(広義)カツオドリ。種分割される前のものを指している]。
Brisson (1760) が与えた属だが、Brisson の記述した Sula sula はアカアシカツオドリではなく(広義)カツオドリだったとのこと。こちらの最も早い学名が Pelecanus Leucogaster Boddaert, 1783 だったためこの名称が採用された。Pelecanus sula Linnaues, 1766 は(広義)カツオドリとは判定できないとされた (B. O. U. 1915)。
Gray (1840) は Brisson の Sula 属のタイプ種を Pelecanus Bassanus Linnaeus, 1758 の記載 (上記前ページ) シロカツオドリと同定していたとのこと (The Key to Scientific Names の Sula の項目)。
そのためアカアシカツオドリの学名は種小名から属名に昇格されたものではない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では当時の学名 Sula piscatrix = Sula piscator にアカアシカツオドリ、Sula sula にリュウキュウカツオドリの名称を与えていた。現在はこれらはシノニムとされる。
Pelecanus Piscator Linnaeus, 1758 (記載)。
参考によればかつては標本がウプサラにあったが失われたとのこと (Lonnberg)。
Sula piscator Red-legged Gannet の名前は広く使われていたようで Sula piscator Gould (1848) の図版もある。
古い学名だが Linnaeus (1758) の記述は標本も失われて同定できないとして使われなくなったよう (The Key to Scientific Names の piscator の項目)。
現在の学名は Pelecanus Sula Linnaeus, 1766 (原記載) と新たに付けられたもの。この版でも引き継いで piscator を載せていた。
Sula 属は性染色体を複数持つ特殊な性決定様式 Z1Z1Z2Z2/Z1Z2W となっているとのこと。関連研究 Pozzobon et al. (2025) Satellite DNA Mapping in Suliformes (Aves): Insights into the Evolution of the Multiple Sex Chromosome System in Sula spp.。オスは 2n = 76, メスは 2n = 75 と染色体数が異なるとのこと。詳しくは引用文献参照。
-
カツオドリ (リスト次第で2種に分離)
- 学名:Sula leucogaster (スラ レウコガステル) 白い腹のカツオドリ
- IOC 学名:Sula leucogaster (スラ レウコガステル) 白い腹のカツオドリ と Sula brewsteri (スラ ブレウステーリ) ブリュースターのカツオドリ
- 属名:sula (外) カツオドリ ノルウエー語
- 種小名:leucogaster (合) 白い腹の (leuko- (接頭辞) 白い Gk、gaster (f) 腹)
- 英名:Brown Booby, IOC 14.2 では2種に分離され Brown Booby と Cocos Booby
- 備考:
sula は#アカアシカツオドリ参照。
leucogaster は外来語を含む合成語なので発音はよくわからないが、ラテン語部分の gaster は -gas- にアクセントで長母音を含まない (レウコガステル)。
なお gaster の由来となるギリシャ語は e が長母音であったが古くラテン語化される際に短母音化されたのだろう。
ロイコガスターの表記も見かけるがドイツ語読み。
brewsteri は -ste- を長母音とすれば "ブレウステーリ" の読みとなる。音節の区切り方に不定性があるがこの発音であればアクセントを固定できて原音にも近いので採用した。
4亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは plotus (平らな足の) 亜種カツオドリ と brewsteri (アメリカ鳥類学者 William Brewster に由来) シロガシラカツオドリ とされる。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 でも採用され Sula brewsteri Cocos Booby となった。Clements 2024, IOC 14.2 でも採用。
Treat Sula brewsteri as a separate species from Brown Booby S. leucogaster (Part A), and if Part A passes, establish English name for Sula brewsteri (Part B)
も参照。Cocos Plate (コスタリカの離島 Cocos Island ココ島を含む。ココヤシに由来する名前) が分布域として適切な名称と判断。
地名に由来する英名では政治情勢などで名称が変わったりする可能性もあるが、地球物理レベルのプレート名であれば学術的名称の安定性の範囲で名前が保証されることを利用したものと考えられる。近年の名称はかなり気を使って決められていることが読み取れる。
Sula leucogaster の英名は Brown Booby のまま。
IOC 15.1 に向けた改訂も始まっていて亜種 etesiaca は Sula brewsteri に移動とのこと。
[カツオドリ類の飛び込み時にかかる力]
シロカツオドリ Morus bassanus Northern Gannet が水面に頭から飛び込む時の速度は 24 m/s (86 km/h) に達し、水面下 10-20 m の魚を捕る [この深度まで到達するために大きな運動量 (物理用語の momentum = 質量 × 速度 の方) が必要] とのこと。
このダイビング時にかかる力を推定した研究: Chang et al. (2016) How seabirds plunge-dive without injuries によれば、
頭部が水面に接触した瞬間は頭部が急速な減速を受けるが、胴はまだ水面に接しておらず等速で落下しており、首が損傷を受ける可能性が一番高い。カツオドリ類では頭部の長さと首の長さがほぼ等しい。頭部が水中に入った時に水中にできる空泡が胴体が入った時に閉じられるとのこと。
発生する波の安定性解析 (波が成長するかどうか) を行っていて実験とよく合うとのこと。速度が速いと buckling (座屈 という用語があるらしい) が起きる。
曲げに対する首の筋肉の力があると buckling がさらに抑制される。後頭部と頸椎の連結部の筋肉がよく発達していてこの筋肉を収縮させると頭と首を安定できる。
モデルを用いて計算すると筋肉の力で 3400 N まで耐えられると推定された。
実際の飛び込み時に受ける静水圧と抵抗による力 30 N よりもずっと大きいので十分余裕を持って耐えられ、損傷を受けずに済むとのこと。80 m/s だと損傷が起きる予想結果となった。
Pandey et al. (2022) Slamming dynamics of diving and its implications for diving-related injuries はヒトにおける飛び込み時衝撃が中心だがカツオドリ類も比較考察されている。
嘴が鋭角に尖っているため衝撃力 (大まかに開き角の半分の tan の3乗に比例: 2乗が断面積、残り1乗が水に接する面の傾きに相当) が小さく、首をまっすぐ伸ばした状態で飛び込むので受ける衝撃が小さいとのこと。
こちらの研究は主に簡単に見積ることのできる衝撃力を扱っていて、Chang et al. (2016) の方が少し踏み込んだ流体・生体力学的考察になっている。
Bhar et al. (2019) How localized force spreads on elastic contour feathers
は胸や肩、腹にかかる圧力を推定しており、長く伸びた体羽の層があることで圧力が 1/3 になっていると見積もっている。
Chang et al. (2016) に紹介されている情報ではこのような飛び込みで怪我をした例は鳥同士の衝突以外では知られていないとのこと。よく噂される飛び込みに失敗して首の骨を折るというのはどうも俗説のよう。
カツオドリ類の鳥同士の衝突については Gannet study reveals perils of high-speed diving
の解説ページがある。魚の群れを狙って複数の個体がどのように飛び込んでくるか、同じ目標を狙うために衝突したり、獲物を奪い合うなどの水中映像のビデオが紹介されている。
論文: Capuska et al. (2011) Evidence for fatal collisions and kleptoparasitism while plunge-diving in Gannets。
頭蓋骨に他の鳥の嘴が突き刺さった事例がある。首に刺さった事例もあるがこれは獲物を奪おうとした結果か。ビデオ撮影では空中でぶつかった証拠はない。
水中でぶつかる時も大部分は減速して翼で推進している時期で、水面突入時期にぶつかったのは2例とのこと。事故リスクより利益が上回っていると解釈している。
水中で視力を使って魚を捕まえているかについては、Machovsky-Capuska et al. (2012) Visual accommodation and active pursuit of prey underwater in a plunge-diving bird: the Australasian gannet
の研究があり、頭が水中に入るとすぐに目の調節能力 (水晶体の形を変える) で水中で失われる 45 D 以上相当の角膜の屈折能力を補っているらしいとのこと (この点は #カワウの備考 [ウの視力] と異なるよう)。
水中での捕食の大部分は翼で推進している時期に起きており、視力で獲物を捕まえていることを示唆するとのこと。
これらの論文から推定してまとめると、水中で獲物を捕まえるために首はある程度長いことが有利だろうが、飛び込み時に buckling を防ぐためには長さに上限値があり、その兼ね合いで形態が決まっていると解釈するとよさそうに見える。ウ類は飛び込まないので首が長くても構わずよりサギ型に近い捕食方法が可能と考えられる。
このような習性・形態の類似性をみると、現代の系統分類で ウ科 Phalacrocoracidae と カツオドリ科 Sulidae がカツオドリ目 Suliformes に含まれるのはそれほど不思議でないかも知れない (#クロトキ備考 [ペリカン目やトキ科などの系統について])。
「野鳥」2022年7・8月号 (No. 859) pp. 4-5 の上田氏の記事に「謎が多いウの分類」があり、どのような点でウ科とカツオドリ科に共通点があるかを考察されている。皆さんも考えてみていただくと面白いかも。
gannet skeleton など (水中を泳ぐと時の姿勢などを再現した骨格もある) で画像検索していただくと確かにウに似ている感じがする。
#クロトキ備考の [ペリカン目やトキ科などの系統について] も参照。[#鳥類系統樹2024]の結果によれば グンカンドリ科 Fregatidae がこの系統の最も古い分岐にあたり、ウ科とあまり似ていないのは理解できる。
これらは4科はまとまった系統をなすが、他の系統の系統間の関係見直し次第ではカツオドリ目は目にふさわしくない可能性も残る。単系統性やレトロトランスポゾン解析の結果、分岐年代をどの程度重視するか次第。
モモグロカツオドリ Papasula abbotti Abbott's Booby というカツオドリ類の中で最も早く分岐し、クリスマス島 (ジャワ島南にあたるオーストラリアの外洋の島) のみで繁殖する珍しいカツオドリがあり、顔つきはカツオドリ類に見えるが非常に大型で飛翔時の写真などグンカンドリ科/カツオドリ科/ウ科の関連性が少し見えるような気がする。
海鳥の中ではほとんど知られていない種の一つ。気候変動も脅威の一つで絶滅のおそれもある (Conservation Advice for Abbott's Booby - Papasula abbotti)。好みの獲物は飛ぶ魚とのこと。採食方法も他のカツオドリ類と違うのかも知れない。
Hume (2023) A new fossil subspecies of booby (Aves, Sulidae: Papasula) from Mauritius and Rodrigues, Mascarene Islands, with notes on P. abbotti from Assumption Island
これまでに東太平洋で大型の絶滅亜種が記載されていたが、インド洋南西部の島で 18 世紀に絶滅した同程度の大きさの亜種が見つかったとのこと。
Tyler and Younger (2022) Diving into a dead-end: asymmetric evolution of diving drives diversity and disparity shifts in waterbirds
が潜水する鳥の系統解析を行っている。(1) 翼を推力とするペンギン類など、(2) 足を推力とするウ類など、(3) 飛び込み型のカツオドリ類などの3種類は別々に進化したもので、一度潜水方法が決まると別のタイプへの進化はなく、潜水型への移行したものが祖先型に戻ることもなかった。水鳥の中で少なくとも 14 回独立に進化している。
カツオドリ類同様に頭から飛び込み採食を行う種類はカワセミやアジサシ類など他にもあるが、派手なのはカッショクペリカン Pelecanus occidentalis Brown Pelican とペルーペリカン Pelecanus thagus Peruvian Pelican が挙げられる。ペリカン類の中でも褐色系統のものが行うとのこと。
こちらはカツオドリ類ほどは生体力学が調べられていないようだが、飛び込み時のビデオを見ると飛び込む直前に首を伸ばして突入時はカツオドリ類と同じような形になっている。
ペリカン類と言えば最も重い飛ぶ鳥に一つなので、飛び込んだ時の衝撃は半端でない印象を受けるが、カツオドリ類での解析にあるように接触角と突入速度が重要で、体重が大きくても突入速度が特に速くなるわけでもないので (ニュートンの引力法則そのまま) あまり問題がないのだろう。ただしカッショクペリカンはペリカン類の中では一番小型とのこと。
なおカワガラス類はスズメ目で唯一潜水するグループで翼を推力をしている (#カワガラス参照。他のグループも含めた潜水する鳥の系統樹もある)。
[水鳥の目の大きさ]
水鳥全般で目の大きさを調べた研究: Ausprey (2024) Eye morphology contributes to the ecology and evolution of the aquatic avifauna。
系統樹を見て個々に考察したり納得いただくのが面白いだろう。陸鳥よりは相対的に小さい。草食のものは比較的小型。カツオドリ類やネッタイチョウ類のように飛び込み型の採食をするグループや、サギ類、上空から獲物を見つけるグループで相対的に大きい。系統的にかなり決まっているが、生態にもかなり関係がある。視覚が生態や進化に果たす役割は他の系統でも述べられてきたが、水鳥でもやはり重要。
△ カツオドリ目 SULIFORMES ウ科 PHALACROCORACIDAE ▽
-
ヒメウ
- 第8版学名:Urile pelagicus (ウリーレ ペラギクス) 海の千島列島の鳥 (ウ) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Phalacrocorax pelagicus (パラクロコラックス ペラギクス) 海の頭の白いワタリガラス
- 第8版属名:urile (合) 千島列島の
- 第7版属名:phalacrocorax (合) 頭の白いワタリガラス (phalakros はげ頭の、頭の白い < phalos 白い korax ワタリガラス Gk)
- 種小名:pelagicus (adj) 海の (pelagus -i (n) 大海 -icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Pelagic Cormorant
- 備考:
urile は#チシマウガラス参照。
pelagicus は短母音のみで -la- がアクセント音節 (ペラギクス)。英語の pelagic も同じ位置にアクセントがある。
phalacrocorax は#カワウ参照。
Kennedy and Spencer (2014) の分子遺伝学研究 Classification of the cormorants of the worldによると Urile pelagicus となる。
#チシマウガラスの備考参照。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で採用され、ヒメウ属の和名が与えられている。
Urile 属の位置づけについては#ウミウの備考 [カワウとウミウの関係] 参照。
2亜種あり(IOC)。日本で記録される亜種は基亜種 pelagicus とされる。
[ウ類の嗅覚]
ウ類は外鼻孔が閉じているので嗅覚は発達していないのではとの推測があるが、Policarpo et al. (2024) Diversity and evolution of the vertebrate chemoreceptor gene repertoire (#エトロフウミスズメの備考参照)
の付属データから OR 遺伝子数を調べてみるとヒメウで 36 個と確かに少ない。旧分類で他の Phalacrocorax 属で4種調べられているが (日本と共通種はヒメウのみのためこの項目に記した)、他種でも 30-35 個と少ない。ゲノム精度の問題がある可能性はあるがウ類はあまり嗅覚に頼っていない可能性が高い。
比較のために近縁系統を見るとヘビウ類 (Anhinga) 1種が 30 個、グンカンドリ類やカツオドリ類のデータはなし。まだまだデータが不足している。
シロエンビコウ Ciconia maguari Maguari Stork で 90 個。
これらが コウノトリ目 Ciconiiformes + カツオドリ目 Suliformes で調べられている全種。
これらはペリカン目 Pelecaniformes を広義とする場合にはペリカン目に含まれる。上記はそのうちウ科を含むクレード。ペリカン目を広く含んでも嗅覚はあまりよくないよう。
これらの系統はあまり嗅覚に頼っていないことが想像できる。ミズナギドリ目海鳥とは大きく違う。魚食性と嗅覚とは特に関係がなさそう。嗅覚が鋭敏でないと言われる猛禽類以上に嗅覚に頼っていない可能性があるかも。
ウ類は空中視力、空中聴力ともにあまりよくないようで、水中感覚に特化しているのか。
改めて#鳥類系統樹2024の系統樹による Elementaves の中の最後の系統を並べると、
(1) (Austrodyptornithes の系統名がある)
ペンギン目 Sphenisciformes が最も古い分岐
ミズナギドリ目 Procellariiformes
アホウドリ科 Diomedeidae
アシナガウミツバメ科 Oceanitidae
ウミツバメ科 Hydrobatidae
ミズナギドリ科 Procellariidae
(2) Stiller et al. (2024) は以下全体を ペリカン目 Pelecaniformes としている (Pelecanimorphae の系統名も使われる)
コウノトリ科 Ciconiidae が最も古い分岐
トキ科 Threskiornithidae (ヘラサギ類は調べられていないがここに入る)
サギ科 Ardeidae
以下の3つはまとまった系統をなす (Pelecani の名称が使われることもある)。
ハシビロコウ科 Balaenicipitidae
ペリカン科 Pelecanidae
シュモクドリ科 Scopidae
以下もまとまった系統をなす (カツオドリ目 Suliformes とされることもある)。
グンカンドリ科 Fregatidae (最も古い分岐。以下の3系統は比較的近い)
カツオドリ科 Sulidae
ヘビウ科 Anhingidae
ウ科 Phalacrocoracidae
この中で系統 (1) が海鳥で鋭い嗅覚、(2) は嗅覚を比較的使わない。
#クマタカ備考の [タカ類の鼻汁] にある塩腺機能 (Chiu et al. 2024) をみるとサギ類では持たない傾向が強い。シュバシコウも持たないなど、この系統 (2) は基本的に淡水型から始まり陸上生活のため嗅覚遺伝子をかなり失ったように見える。海上生活の系統はもちろん塩腺を持っている。
なおカツオドリ類も外鼻孔が閉じているとのこと。しばしば同列に議論されるネッタイチョウ目 Phaethontiformes (外鼻孔は開口的) はこれらの系統から外れてジャノメドリ目 Eurypygiformes とグループを系統をなすことになった。ここでの外鼻孔や嗅覚の類似性の議論の対象から外れることになる。
グンカンドリ科以降の系統は海に進出したが祖先が嗅覚をかなり失った系統のため、ミズナギドリ目の海鳥とは異なった戦略で魚を検知するようになっているのかも知れない。
グンカンドリ類が空中生活が中心で海には下りないのも祖先が陸上生活だったための制約 (?)、視力で獲物を見つけたり他の海鳥の群れを探ったりするために労働寄生 (kleptoparasitism) がよく起きるのかと想像してみたりする。
ソアリングもアホウドリ類などのダイナミックソアリングとは異なり上昇気流を利用するソアリング (thermal soarer) とのことで、例えてみれば旧世界ハゲワシ (主に Gyps 属) の海上版に相当する戦略と言ってよいのだろうか。
Weimerskirch et al. (2003) Frigatebirds ride high on thermals によれば上昇気流で 2500 m まで上がるとのこと。
カツオドリ類もどのように獲物を探すか意外にわかっていないらしいが視覚中心なのだろうか。
Weimerskirch et al. (2005) The three-dimensional flight of red-footed boobies: adaptations to foraging in a tropical environment?
にまとめられている情報によればミズナギドリ目は夜間も採食するが、カツオドリ類は夜間に採食しないとこと (この論文の引用文献参照)。
ワタリアホウドリでは嗅覚を用いていることが調べられている: Nevitt et al. (2008) Evidence for olfactory search in wandering albatross, Diomedea exulans。
半数ぐらいを占めるジグザグな探索経路も嗅覚による探索でうまく説明できる。昼間は飛びながら、夜間はとまって獲物を待つ (sit and wait) のが中心で採食は昼間の方が多い。視覚と嗅覚の両方を用いていると考えられる。
あまり文献調査はできていないが、夜間も飛んでいるオオグンカンドリでも採食は昼間のみ (早朝と午後遅くが多いとのこと) との記述があった: Weimerskirch et al. (2004) Foraging strategy of a top predator in tropical waters: great frigatebirds in the Mozambique Channel。
Gilmour et al. (2012) Satellite telemetry of great frigatebirds fregata minor rearing chicks on tern island, north central pacific ocean
によれば夜間の採食の可能性のある記録もあって、月夜ならば見えている可能性があると説明している。
視覚と嗅覚の利用度への頼り方の違いが現れているように見える。
ウ類も鼻を閉じたため嗅覚が弱まったというより、そもそも嗅覚をそれほど使わない系統だったので鼻を閉じてもあまり支障なかったのだろうか。
[潜る鳥の羽毛の適応]
グンカンドリ類の羽毛に耐水性がなく海上で休むことができないために夜間も (ほとんど眠らず) 飛び続ける必要があるが、羽毛の適応はなぜ起きなかったのか疑問にもなる。直接の情報は得られなかったが、ウ類の羽毛は濡れるのか調べた研究があった:
Srinivasan et al. (2014) Quantification of feather structure, wettability and resistance to liquid penetration
羽毛に付着した微小な空気の泡 ("plastron" と名付けられた) が壊れる (= 濡れる) 圧力を推定し、ウ類 (ヘビウも含む) はカモ類と同程度だった。実測値は "完全に濡れていない" 状態が熱力学的に安定したものになるとのこと。
水圧が上がると相転移のようにいつかは完全に濡れると予想されるが、鳥が水から上がると完全に濡れた状態は安定でなく水は抜けてゆくと考えられる。これは従来言われる意味の乾燥とは異なる概念。
水圧の変化による平衡状態の変化によるもので、"spontaneous dewetting" (自発的に水がはじける) と呼んでいる。
ただし多少の水が局所的な構造に取り残されて抜けにくい状態も考えられ、翼を広げる行動は水滴との接触面積を小さくして水が抜けるのを促進することに役立っていると考えられる (もちろん乾かすのにも役立っているのだろう)。
ハトの羽毛は中程度に疎水性があるが、ウ類も含めた水鳥の羽毛はハトに比べて尾脂腺の脂でコートされている点と微細構造の間隔が小さい (ウ類は特に小さい) ことでより濡れにくくなっている。
How cormorants emerge dry after deep dives (MIT News 2014) に一般向け解説がある。
なおこの実験では天然のコートではなくまず尾脂腺のコートを中和してから全種共通の人工的なコート材でコートしたものを用いている。この結果羽毛自身の持つ性質の違いを調べることができるとのこと。
潜水する鳥の羽毛の適応は羽毛微細構造だけで十分とのことで、過度の機能は持たず濡れた状態のままになならない条件のぎりぎりのところに最適化された設計になっているとのこと。そのような羽毛微細構造の維持にはコストがかかる、あるいは構造の制約が潜水深度を決めていると解釈すればよいのだろう。
ウ類がよく濡れているように感じるのは長時間深く (防水の耐水圧を超えて?) 潜る結果だろうか。
Stangier et al. (2023) The uropygial gland of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo): I. Morphology
が潜る鳥のうちでウ類のみ羽毛構造が異なっており、きっと羽毛が濡れる理由があるだろうと尾脂腺の構造を調べたが他の水鳥と大差なかった。ノバリケン Cairina moschata Muscovy Duck の方がウ類より濡れにくい羽毛を持っていた。結論では羽毛構造の方が疎水性に役立っているとの上記 Srinivasan et al. (2014) の結果を支持する形となっている。
グンカンドリ類の羽毛が濡れる理由はおそらく微細構造の間隔を調べれば想像が付きそう。これらの構造はある程度系統的に決まっているのかも知れない。
Muzio and Rubega (2025) Differences in Microstructure Morphology Results in Variable Wettability Across Feather Types in a Terrestrial Bird Species (オープンアクセスではない) こちらは陸鳥のクーパーハイタカで羽毛の種類と撥水性の関係を調べたもの。小羽枝の構造と相関が高く、小羽枝が撥水性に重要な役割を果たしていると考えらえるとのこと。陸鳥でも多くの地域でもちろん雨が降るので撥水性が必要。
-
チシマウガラス
- 第8版学名:Urile urile (ウリーレ ウリーレ) 千島列島の鳥 (ウ) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Phalacrocorax urile (パラクロコラックス ウリレ) 千島列島の頭の白いワタリガラス
- 第8版属名:urile (合) 千島列島の
- 第7版属名:phalacrocorax (合) 頭の白いワタリガラス (phalakros はげ頭の、頭の白い < phalos 白い korax ワタリガラス Gk)
- 種小名:urile (合) 千島列島の
- 英名:Red-faced Cormorant
- 備考:
urile は外来語由来で読みはわからないがロシア語の千島列島 Kuril'skie ostrova は i にアクセントがあるので同様に i にアクセントを置くのが自然に思える。長音で読んで "ウリーレ" とすれば発音も自然でアクセント位置規則とも整合するのでこの読みを採用した。
phalacrocorax は#カワウ参照。
記載時学名 Pelecanus Urile Gmelin, 1789 (原記載) 基産地 Kamchatka。
Kennedy and Spencer (2014) の分子系統解析 Classification of the cormorants of the world
でウ類の系統が見直され、Urile 属に分離された。
Pelecanus Urile Gmelin, 1789 (チシマウガラス) から Charles Lucien Bonaparte (1856) が Urile 属に昇格したもの。
Bonaparte (1856) は7種を含んでいたがトートニムであったチシマウガラス (この分類で Urile urile) がタイプ種となる。現在は他の属となる種も含まれていたが、分子系統解析で属相当のクレードにチシマウガラスがタイプ種となる属が存在したため採用された。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版ではまだ採用されていなかったが、世界の多くのチェックリスト [IOC 11.2 以降、HBW 2018 以降、AOU 7th ed. (incl. 62nd suppl.)、eBird 2021 以降] ですでに採用されており、wikipedia 英語版にも反映されている。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で採用され、ヒメウ属の和名が与えられている。名称の由来は Steller (1774) によるカムチャツカでのチシマウガラスの名称からとある。ロシアの地方名由来で、おそらく千島列島を指したもの (The Key to Scientific Names)。
wikipedia ロシア語版によると地方名として Uril が挙げられている。単形種。
Phalacrocorax bicristatus Pallas, 1811 (参考) のシノニムもあり、Temminck and Schegel (1850) Fauna Japonica ではこの学名から属を変えた Carbo bicristatus で紹介されている (参考)。
bicristatus は2つの冠のある、の意味。他文献でもしばしば現れ、英名別名の Double-crested Cormorant の由来にもなる。Fauna Japonica にはアメリカでは Pennant の "Violet Cormorant" や Brant の Carbo bilophus も紹介されている。
#カワウの備考で英名について取り上げたが、この種はまさにその問題がある。形態を重視する英名では Red-faced Shag と呼ばれ、どちらも使われている。
チシマウミガラスと誤って書かれていることもあるので注意。こちらの方が日本語的には自然な感じがするので自分も間違っていたことがある。別名としてあるわけではなさそうである。
Urile 属の位置づけについては#ウミウの備考 [カワウとウミウの関係] 参照。
「北海道の鳥」(小学館 1984) pp. 139-140 によれば、昔は現在の鵜のことを体が黒色をしていることから鵜烏と呼んでいた。海鵜烏、川鵜烏となどと言われていたものが簡略化されてウミウ、カワウなどとなったが、チシマウガラスには昔のままの名前が使われているとのこと。
-
カワウ
- 学名:Phalacrocorax carbo (パラクロコラックス カルボー) 炭のように黒い頭の白いワタリガラス
- 属名:phalacrocorax (合) 頭の白いワタリガラス (phalakros はげ頭の、頭の白い < phalos 白い korax ワタリガラス Gk)
- 種小名:carbo (m) 炭
- 英名:Common Cormorant, IOC: Great Cormorant
- 備考:
phalacrocorax 外来語由来で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-cro- がアクセント音節と考えられる (パラクロコラックス)。
carbo は語末が長母音でアクセントは冒頭 (カルボー)。
記載時学名は Pelecanus Carbo Linnaeus, 1758 (原記載) とペリカン類の扱いだったが、Brisson (1760) が整理して Phalacrocorax 属を与えた。同名の属名が クロハサミアジサシ Rynchops niger Black Skimmer に対して Linnaeus 以前 (Moehring 1752) が用いていたが、1758 年以降が有効な規則によって Linnaeus (1758) の用いた学名となった。
記載時は基産地 Europe となっていたが、Hartert (1910-1922) p. 1387 の時代には (augenblicklich 目下 の表現が使われている) スウェーデンでは繁殖していないため、他の種のように基産地をスウェーデンと指定することができなかった。
Linnaeus の時代でも繁殖していなかったらしい [参考 Engstrom (2001) The occurrence of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Sweden, with special emphasis on the recent population growth]。
そのため restricted to the 'rock-nesting form of the north Atlantic Ocean' by Hartert, 1920, Vogel Pal. Fauna, p. 1387 (Avibase による) と大西洋沿岸の岩場に営巣するものを指定することとなった。原文では Ich beschraenke daher Linnes Namen carbo auf die an Felsen nistende Form des nordatlantischen Ozeans。
wikipedia 英語版によれば、Linnaeus の時代にはスウェーデンに生息していたがその後すぐに絶滅と情報が多少異なる。最近になって再定着したものは sinensis であるとややこしいことになっている。
この情報の出典は Ericson et al. (1997) Subspecific identity of prehistoric Baltic cormorants Phalacrocorax carbo とのこと。
現在使われる「伝統的」亜種は Hartert の指定に従っているが、後述のように分布拡大で亜種概念が不明瞭となっている。
カワウの種小名を昇格して Carbo を属名に用いたのは de Lacepede (1799) だった (上記 The Key to Scientific Names より)。
Carbo vulgaris Lacepede, 1790 (参考) が用いられ、これは種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる (#ノスリの備考参照)。この学名は Common Cormorant の英名と同じ意味で学名と整合性がよい。
同様にカワウを指して Carbo cormoranus Meyer, 1810 (参考) の学名も付けられ、これも種小名から属名に昇格する際の当時の慣習によるものと考えられる。
Carbo の属名はかなりよく用いられておりたくさんの用法がある。
Carbo ater Lesson, 1831 は "黒いウ" で違和感はまったくない学名に思えるが、実はクロクビムナジロヒメウ 現在の学名で Phalacrocorax magellanicus Magellanic Cormorant の若鳥だったとのこと (参考)。
#ウミウなどの記載にはこの属名が用いられたが、Phalacrocorax の使用が早いためにこちらに統一された模様。
ユーラシア、オーストラリア、北大西洋沿岸に分布し、5亜種あるとされる (IOC)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)によれば日本で記録される亜種は hanedae (千葉県の地名「羽田」が由来。カワウの亜種では最も小型) 亜種カワウ と sinensis (中国の) シナカワウの和名が用いられていたが最終的にタイリクカワウとなった、及び亜種不明とされる。
中西悟堂「定本・野鳥記」1 p. 26 によれば羽田は黒田家のかつての鴨場のあった場所で、中西氏の書かれた時点ではすでに住宅街になっていたとのこと。
hanedae の記載は黒田 (1925) 日本産ウミウに就て
[当時は ウミウ (カハツ = カワウの旧名) と表記されていた]。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によれば現在のウミウがカワウと呼ばれ、別名がシマツだった。
Moores (2015) Identification Challenge: Korea's Cormorant Conundrum にカワウの亜種の妥当性の検討がある。
韓国では亜種 sinensis が繁殖するとされるが、hanedae も日本に近い地域では記録されていると思われる。識別は可能なのか、それとも hanedae と sinensis は同一タクソンとみなした方がよいのか。
日本の個体群にも sinensis は含まれていないのかなどの疑問を呈している。もし亜種 hanedae が確固たるものであれば、種レベルよりも亜種レベルの保全面の考慮が必要になる。
茂田 (2002) Birder 16(6): 12-15 によれば1955年5月11日に八丈島でシロハラコビトウ Microcarbo melanoleucos (現在の学名による) Little Pied Cormorant の亜種シロハラヒメウ melvillensis (現在通常は基亜種のシノニムとされる) の撮影記録があるが日本産とは認められていないとのこと。
英語 cormorant の語源はラテン語 corvus marinus (海のカラス) あるいはコーンウォール語 (Cornish language) で海の巨人を意味する Cormoran に由来すると考えられている英語で shag (冠羽のことを意味する)と呼ばれるものもウ類であるが、この2つの単語には厳密な区別はなく (例えば eagle と hawk 同様)、同じ種類を cormorant とも shag とも呼ぶことがあるそうである (wikipedia 英語版)。
2024.12.12 IOC 15.1 は Phalacrocorax lucidus White-breasted Cormorant (アフリカ) を他のリストに合わせてカワウと同種に。白い部分が多いなど見かけはかなり違う。ズキンガラスのように黒系統の鳥の色違いで別種扱いとされたものはかなり見直されつつある模様。
KM066487.1 から試しに BLAST を行ってみるとウミウもカワウの hanedae も世界のカワウからほとんど分離できないことがわかる。カワウの他亜種と同所的に生息しないので Phalacrocorax lucidus はカワウの亜種に含められたが、さてウミウはどうなるのか?
Marion and Le Gentil (2006) (ウミウの備考参照) にカワウとウミウの関連の考察がある。亜種 sinensis は 1500-1800 年ごろにバルト海に進出し、本来のヨーロッパ亜種 carbo に次第に取って代わるようになった可能性がある。
ヨーロッパでは sinensis 1930-1960 年ごろに個体数の大幅な減少を体験したとのこと。日本でも似た時期に個体数の減少があり 1971 年には全国3か所のコロニーに 3000 羽以下が残るのみとなったとのこと [福田他 (2002) 日本におけるカワウの生息状況の変遷]。
カワウの一時的な衰退は世界的現象だったのだろうか (この文献にもヨーロッパでの個体数変動への言及がある)。カワウを見るために遠くまで出かけた話は古い時代のバーダーからも聞くことがある。
ヨーロッパでの亜種 carbo と sinensis の判別について: Grondahl and Johnsen (2024) Combining biometrics and genetics to distinguish two subspecies of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo carbo and P. c. sinensis at an inland lake in southeast Norway。
sinensis と両者の混ざった carbo/sinensis グループは一つの枝にまとまるが、純粋な carbo は複数祖先を示唆するとのこと。相互に遺伝子浸透が頻繁に起きていると想像される。
英国に分布を広げたカワウはどちらの亜種なのか? Winney et al. (2001) The subspecific origin of the inland breeding colonies of the cormorant Phalacrocorax carbo in Britain
伝統的な亜種 carbo は沿岸部で地上や崖に営巣すると考えられていた。かつては両亜種は同所的に生息せず分布から区別できるとされてきたが、現代の個体の分子遺伝学は伝統的な亜種と部分的にしか一致しないとのこと。ヨーロッパでは区別が曖昧になりつつある。
現在最も carbo らしいものはグリーンランド西部からカナダ、アメリカ合衆国北西部らしい。
北米ではミミヒメウ Nannopterum auritum Double-crested Cormorant の方が数が多い。Cormorants of North America (North American Nature) によれば北米ではカワウは沿岸沿いに生息する種類。殺虫剤を使わなくなって近年数が増えている。
Nannopterum 属以外のカワウもこちらは大西洋ルートで今後分布を広げてゆくのかも。
このような状況を見ていると、日本のカワウなので自動的に hanedae と記述するのは正しくないかも知れない。もしかしたら sinensis であったり混ざったものも含まれているかも?
[ウの視力]
「鵜の目鷹の目」と言われるが、ウの視力が本当に良いのか調べた研究があった。White et al. (2007)
Vision and Foraging in Cormorants: More like Herons than Hawks?。タイトルを見る限りでは西洋でもタカの目のようによいと考えられているのかもしれない。カワウの視力を調べると水中でゴーグルなしの人間の視力と大差なく、タカの目にははるかに劣るとのこと。
獲物は 1 m ぐらいの距離でしか認識できないようで、視力で獲物を捕まえるよりも、サギ型に近い捕食方法で、獲物を見つけて首を瞬時に伸ばす。
ウ類の頸椎数の多さ [20 個、サギ類は 18-20 個; いずれもある文献によるが、Boehmer et al. (2019, #コブハクチョウの備考を参照) では ケルゲレンヒメウ Phalacrocorax verrucosus で 17 個、アオサギ 16 個とあるので数え方の違いの2個を加えればだいたい合っているようである - もこの捕食方法に適応したものか] を進化させることで効率よく獲物を獲っているとのこと。
解説付きのスライドもある。
水中の採食を行う種類でウ類とペンギン類で首の長さが大きく違うが、加速度計で調べた結果ウ類は水中の速度が遅いために首を瞬時に伸ばす方法がエネルギー効率が良いとのこと: Wilson et al. (2017) Long necks enhance and constrain foraging capacity in aquatic vertebrates。
ただし冷水の中では長い首 (体表面積の 10% 程度とのこと) から逃げるエネルギーも大きいことも考察しており、ウ類はペンギン類ほど長時間水中に潜らないので影響が少ない可能性も挙げている。
この議論を少し延長すると熱帯から亜熱帯地域のヘビウ類の首がさらに長いことも整合性があるのかも。
Wilkinson and Ruxton (2012) Understanding selection for long necks in different taxa はペンギン類のように海の透明度の高い水中で魚を追うには視覚を用いるのが適切で、ウ類のように濁った水中では視覚にあまり頼ることができないと考えたとのこと。
この考えに従えばウ類は視力をあまり発達させる必要がなかった代わりに長い首を用いて獲物を獲るように進化したと言えるのだろう。ウ類の生態と適応を考える上で面白そうな話題。
Strod et al. (2004) Cormorants keep their power: visual resolution in a pursuit-diving bird under amphibious and turbid conditions
では空中視力も調べられており他の鳥より低いとのこと。空中でも「鷹の目」ではなかった。ウが黒いのはあまりよくない視力でも同種を見つけやすくするためなのかも知れない。
Borges et al. (2015) Gene loss, adaptive evolution and the co-evolution of plumage coloration genes with opsins in birds
によれば色覚に関係する遺伝子ではカワウはフクロウと同じパターンになっていて、あるいは水中深いところでの暗所視に適応しているのかも知れない
(ただし技術的な問題で検出できないものもあるとの記載もあり、遺伝子だけで語るのは危ないかも知れない。網膜の細胞の顕微鏡的研究や、行動実験で視力や色覚を調べる必要があるだろう)。
Hansen et al. (2017) Great cormorants (Phalacrocorax carbo) can detect auditory cues while diving によれば、カワウの水中聴力は意外に良く、アザラシやクジラなみであるとのこと。水中で獲物を獲るために聴覚が発達している可能性もある。空中での聴力もこれまで考えられていたよりよいそうである (これは違う可能性がある)。
川口 (2012) Birder 33(6): 53 によればカワウの外耳口は小さく 1 mm ほどしかないとのこと。これは潜水への適応らしいが、空中聴力はあまりよくないのかも。水中では骨伝導で音を聞いているのだろうか。
Gremillet et al. (2005) Cormorants dive through the Polar night
によればグリーンランドで越冬するカワウは極夜でも潜って魚を獲るとのこと。しかも季節によって行動パターンはあまり変化しない (他の潜水性魚食の水鳥とは異なる)。(少なくとも極夜では) 触覚か聴覚に頼っている可能性があり調べる必要がある。
Zeyl et al. (2022) Aquatic birds have middle ears adapted to amphibious lifestyles
によれば、潜水する鳥は特有の中耳の形態的適応があるとのこと。水中で音を聞くのに適した特性 (以下の音響インピーダンス参照) になっている可能性と、潜水に伴う圧力変化に耐えるため複数系統で進化したと考えられる。
空中の耳の感度はカワウとメンフクロウで 44 dB も違うとのことで、前述の「空中での聴力もこれまで考えられていたよりよいそうである」と同じ文献 [Maxwell et al. (2017) In-air hearing of the great cormorant (Phalacrocorax carbo)] を引いているのにニュアンスがまったく違う。
Maxwell et al. (2017) の論文をチェックしてみると同様のサイズの鳥との比較をしており、シチメンチョウやカモ類を用いている。陸鳥を比較対象に用いていないのでこのような結論になった模様。
Zeyl et al. (2022) によれば潜水性のペンギンも外耳道が狭い。水鳥では cochlear aqueduct が広がっており、骨伝導や水中での音の定位に役立っている可能性が指摘されているとのこと。
比較対象のメンフクロウは特に聴力がよいが、カワウは構造的にも一般的な陸鳥と比べると空中ではあまり聞こえていないと言ってよさそう。
Johansen et al. (2016) In-Air and Underwater Hearing in the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) も空中聴力は相対的に良くないとの結果を得ている。ただし他の水鳥を用いて脳幹反応を用いた測定は行動実験で測定した聴力より悪く出るとの研究もある。
これら一連の研究はまだ途上段階で少し割り引いて読んだ方がよいかも。
水中聴覚による音源定位は原理的問題がある。水中の音速は速い (1500 m/s 程度) ので左右の時間差がほとんどない。さらに空気と生体とは違い、水と生体は性質 (音響インピーダンス) が似ているので検出に不利。空中と同じ方法では音源定位がほとんど無理と考えられてきた。
この常識を破って魚が音の方向を聞き分けることが明らかとなった: Veith et al. (2024) The mechanism for directional hearing in fish
ヒトが音を聞く時は振動を感知しているが、この魚では圧力と分子運動を検知しているとのこと。考え方によってはヒトより豊かな音環境を感受している可能性もある。魚の一部は Weberian apparatus という器官を持っていて浮き袋 (swim bladder) から内耳に音を伝える中耳に似た役割を果たしているとのこと。
Dooling and Therrien (2012) Hearing in birds: what changes from air to water は潜水性の鳥で中耳の空気が浮き袋と同様の役割を果たしている可能性に触れている。
Gomez-Laich et al. (2015) Selfies of Imperial Cormorants (Phalacrocorax atriceps): What Is Happening Underwater?はズグロムナジロヒメウ (現在の学名は Leucocarbo atriceps) にカメラを付けて行動記録をしたもの。
やはり 1 m 以内しか見ていないようで、追い出したものの動きを捉えて捕食しているらしい。移動時にハトの歩行時首振りと同様の動作が見られ、視覚に頼っていることは間違いない (#ハチクマ備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] 紹介の Gutierrez-Ibanez et al. (2012) による脳の ION 核の発達度と合わないかも知れない)。
しかし最も深く潜る時には光が届かないため視覚に頼れないと思われ、視覚以外の感覚を利用している可能性がある。
熊田 (2012) Birder 26(7): 28-29 にもカワウが水中でどの距離まで見えているか、水中採食方法についての考察がある。
書物によっては潜水する鳥は瞬膜で調節して水中で物を鮮明に見ていると解説してあるものもあるが、これは誤りだそうである [Sivak et al. (1978) The refractive significance of the nictitating membrane of the bird eye]。
[ウの虹彩はなぜ緑色?]
#ヤマセミ備考の [派手な色彩の鳥はまずい?] から派生した項目の 虹彩色に関係する遺伝子 より再掲:
Si et al. (2021) The genetics and evolution of eye color in domestic pigeons (Columba livia) によればウの目が青系統なのは SLC2A11B の機能をフレームシフト変異で失って虹彩に pteridine 色素を持たないためではないかとのこと。ウの系統の早い時期に起きたようでヘビウ類ですでに失われていたがアメリカヘビウ Anhinga anhinga Anhinga では虹彩に黄色の色素があってこの変異だけでは説明できないとのこと。
まだ一部の種の遺伝子を見ている段階なので確かではないが、ウの系統全体で起きているならばウの目の色の説明になるかも知れない。カワウやウミウでも同様かは実際には色素や遺伝子を調べてみる必要があるだろうが面白い仮説に思える。
続きをまとめた方があって Corbett et al. (2023) Bird Eye Color: A Rainbow of Variation, a Spectrum of Explanations (preprint) がある。遺伝子を新たに調べたのではなく過去の研究のレビューと系統ごとの目の色の関係。目の色彩写真が多数紹介されている。
目の色については過去にも多数の研究があり、気になる事例があればこの論文に載っているか調べるのがよさそう。
虹彩の色が視力に関係する仮説が挙げられたことがあるがあまり支持されていないよう。目立つ色または隠蔽色となる可能性も提唱されているがあまり支持する研究がない。Davidson et al. (2017) は洞営巣性でない鳥では明るい虹彩色が避けられる傾向があることを示し、洞営巣性では捕食者にあまり目立たないため虹彩色への選択圧が弱いと考えている。夜行性の鳥で昼間に攻撃を受ける可能性のあるものは特に隠蔽色となっており、ヨタカ類の目は必ず黒いと述べられている (個々の参考文献はこの論文参照)。
Worthy (1978-1997) は捕食様式との相関があるとした。待ち伏せ型の捕食者は虹彩色が明るい傾向があり、追跡型は黒い色が多いとのこと。ここではサギ類やアマツバメ類を念頭に置いていて猛禽類にはそのまま当てはまらないかも知れない。Worthy は色彩が視力に関係していると考えたこともあってあまり受け入れられなかったとのこと。やや古い時代の話で当時は系統関係もよくわかっていなかったので新しい知見をもとに系統制約要因も含めて検討すべきとの意見のよう。
Craig and Hulley (2004) はカラス科や南米のムクドリモドキ科では森林性の種類ほど虹彩色が明るい傾向を見出したが環境によるものか系統を表すものかはよくわからなかったとのこと。
目の色が信号となっている考えは古くからあり、アオアズマヤドリの目の青さは羽衣やあずまやの飾りに用いる色とよく合っている。ウ類の目の色はここで取り上げられており、婚姻色で目の周囲の皮膚に鮮やかな色を出すものが多くその延長だろうとの考えがある。目の色が質を表すシグナルになっていることも提唱されているが検証は不十分とのこと。Gay et al. (2007) はヨーロッパのカモメ類で雑種形成を妨げる効果があるのではと提案している。
ヨーロッパのハイタカではオスの目の色と繁殖成功率に相関がある報告があるが性選択の要素になっているかどうかは不明とのこと。カロテノイド着色の場合は健康状態を表している可能性があるが、猛禽類を含め虹彩色の明るい鳥の大部分では当てはまらないのではとのこと。pteridine 着色の場合は一層調べられていない。
鳥では自分の意思で虹彩を拡大 (eye-blazing)・縮小 (eye-pinning) できるので興奮状態を伝えるなどディスプレイに役立っていると考えられ、オウム類でよく知られている。類似の行動は虹彩色の明るい鳥で広く見られるとのこと (個々の参考文献はこの論文参照)。
哺乳類にこの機能がないのは夜行性生活が長く、虹彩色があまり重要なコミュニケーション手段にならなかったためでは? (この部分は私見)
gaze sensitivity (視線を知らせる、注視していることを知らせるなど) と関係がある可能性もあって、ヒトでは "白目" の部分 (強膜) はこの目的で進化した仮説があるが疑問視する考えもあるとのこと。
通説に反するところもあるので論文を見ておくと Caspar et al. (2021) Ocular pigmentation in humans, great apes, and gibbons is not suggestive of communicative functions。チンパンジーでは他の類人猿より隠蔽色の目になっているなど系統があまり表れていない。ヒト以外の大型類人猿で視線をコミュニケーション手段として用いる実験的証拠があまりないとのこと (ヒトでさえ異論があるので鳥の視線機能は余計に語りにくいのかも)。
ヒトの強膜が色素を失ったのは必ずしも適応的なものとは限らず、コミュニケーション手段よりも性選択なども考えられるし遺伝的浮動の結果も否定できないのではとのこと。詳しくは論文の主張をお読みいただきたい。
鳥では gaze sensitivity はまだ検討の初期段階。鳥の場合はこちらを見ていないと虹彩外側の "黒目" が見えたりするが機能はあるのだろうか。
そういえばヒゲワシは虹彩の外側は赤かった。bearded vulture で検索すればいくらでも写真が見つかるので探してみていただきたい。この種を見ると瞬膜はピンク色で鉄さび色の鉱物による羽毛着色が社会的地位に関係しているらしいとの報告がある。Margalida et al. (2023) New Insights into the Cosmetic Behaviour of Bearded Vultures: Ferruginous Springs Are Shared Sequentially (#クロハゲワシ備考 [ヒゲワシの化粧色])。
虹彩の外側の色彩はやはり状況によっては適応的なもので、アオアズマヤドリの虹彩の色と同様ではないだろうか。ちなみにヒゲワシの目の写真を見ると鳥の眼球は一般に考えられているより動くこともわかる。タカの目の虹彩の外側はすべて黒いわけではなかった。目を見ればどの方向を見ているかわかり、正面を向いて食べている時はこちらを見ていないことがわかる。この情報を他の個体は利用しているのだろうか。
アメリカチョウゲンボウなどで後頭部に偽の目 (false eyes) の模様があると言われて関連話題として取り上げていたが、あまりにタカの話になってしまったので、この部分を#ハチクマの備考 [目を隠す模様は何のため?] の方に移動した。
目の周囲の特に裸出部を同じ色彩とするのは目を大きく見せる効果 (例えば同種内や対捕食者) が考えられるとのこと (ちょっと古いアイデアもある。個々の参考文献はこの論文参照)。いわゆるアイリングの役割もあまりよい仮説がないらしい。メジロ類では白い羽毛が反射効率を上げて取り込む光の量を増やす説もちらっと見たことがあるが出典を忘れた。あまり顧みられていないらしい。
Bird Eyes Come In an Amazing Array of Colors - but Why Is a Mystery (Audubon の紹介記事)。
[カワウを使った日本と中国の鵜飼]
日本でもカワウを使った鵜飼が水深の浅い九頭竜川、相模川で以前に行われていたとのこと (コンサイス鳥名事典)。
中国でカワウのことを魚鷹 (= ミサゴ) とも呼び、英訳されると osprey fishing という妙な表現になるが、これはミサゴに魚を捕らせるのではなく鵜飼のこと。
中国の鵜飼の記事 にも使われている。綱をつけずに放すそうで、これは世界でもまれだとのこと。
調べると何と本当にミサゴを使って挑戦している人があった。以下 #ミサゴの備考 [ミサゴに魚を捕らせることは可能か?] へ。
鵜飼のカワウを用いて7まで数を数えることができるとの報告がある: Egremont and Rothschild (1979) The calculating cormorants [茂田 (2002) の記事で紹介された]。原始的で今では認めてもらえそうもない実験だろうが。
「野鳥」2022年7・8月号 (No. 859) pp. 6-10 に卯田宗平氏と上田氏の対談「鵜飼から見る日本と中国の自然観・動物観の違い」がある。卯田氏は「鵜と人間 日本と中国、北マケドニアの鵜飼をめぐる鳥類民俗学」(東京大学出版会 2022) を出されている。
自分はこの本は読んでいないが、この記事に北マケドニア (注: 国名。マケドニア北部の意味ではない。湖は北マケドニア共和国の南端にあり、ギリシャ国境に近い。地中海性気候とのこと) の湖で旧ユーゴスラビア時代に大規模な鵜飼が行われていたことが紹介されている。
冬季に飛来するカワウを捕獲し、定置網に魚を追い込むために利用していたとのこと。カワウの捕獲道具にはカンムリカイツブリやカワアイサなどもかかるが、それらも一緒に利用していたとのこと。春先にはすべて放鳥していたと記述されている。
この件に興味があって少し調べてみると Beike (2012) The history of Cormorant fishing in Europe
にヨーロッパの鵜飼の歴史が述べられている。16 世紀から記録があるが主に貴族の楽しみ (sports) と行われてた。
北マケドニアのドイラン (Dojran) 湖のものはヨーロッパ他地域とは独自に発展したもので手法も異なり、いつ始まったかはわかわらないとのこと。mandra (複数 mandri) と呼ばれるアシでできた柵 (定置網) で行う。
Apostolski and Matvejev (1955) が紹介していたが、彼らが示唆したように紀元前からの記録があるわけではない模様。魚の非常に豊富な湖で、この記述を見ると古くから追い込み猟で魚を捕らえていたようだが (動物をこのように追い込むのは石器時代から行われて知られていたとのこと)。
魚が追い込まれて集まると野鳥が狙ってやってくるのでそれを追い払うためにひもの先に石をつけたものを投げていた。現代のドイラン湖では鳥は狙わず、鳥と mandri の間に (構造は後述) 投げるという。野生の鳥も追い込みに役立つため。
この時点では観光客対象に「伝統的鵜飼」と称して中国をモデルに行われているようだが Apostolski and Matvejev (1955) によれば漁に使われた 30% の鳥が死ぬとか、20% は逃げる、また風切羽を切られているので春の渡りができない、との記述があるとのこと。実際に犠牲になった鳥はもっと多いのではないかと懸念している。
卯田氏の記事の春先にはすべて放鳥とあるが、Beike (2012) では少し違って否定的なニュアンスの報告になっている (1950 年代のやり方と異なっているのかも知れない)。
(Dojran Lake) にも旅行者のレポート (言語判定をするとブルガリア語と出た) によるドイラン湖の鵜飼の記述があり、カワウの訓練は2週間しかかからないとのこと。魚をとって戻ってくるとのことで中国で行われるものと同様とある。「伝統的鵜飼」と称しているがこれは中国のやり方を真似て観光目的で行われているものかも。
(Dojransko Lake) こちらはマケドニア語。
伝統的方法では 10 月から3月まで行われる漁法。
11 月にウがやってくる。魚を狙って mandri に近づくが、漁師が魚が十分あると判断すれば mandri の湖側を閉じる。polokatnik と呼ばれる区画で鳥を捕まえ風切羽を切る。
羽を切った鳥は argati (同名のブルガリア語では男性の農夫、男性の召使いの意味でトルコ語、さらには古代ギリシャ語に遡る、から借用とのこと) と呼ばれる。鳥の役割は柵の外に魚を逃さないこと。
そして柵の間隔を次第に狭めていって kotets と呼ばれる小さな区画から魚を捕獲する。
この記述を見ると羽が切られているのでやはり渡りはできないのでは?
Talevski et al. (2024) Fish and Fisheries of the Republic of North Macedonia, Current Situation, and its Perspective の論文にも登場するようだが中身までは見ていない。
このように見ると、石器時代のヒトに起源を遡るまでもなくペリカンの行う追い込み猟、あるいはハシビロガモの共同採食のような習性と、定置網を用いた人の追い込み猟がたまたま (あるいは収斂進化? または水鳥のやり方から学んだ?)
よく似ていて、人の追い込み猟にカワウなどの水鳥がやってくるのを最初は追い払っていたが、次第にもっと効率的に追い込みに協力させる方法に気づき進化した猟法なのかも知れないと思った。
水鳥に一般的な習性と人の思惑がうまく一致したものか?
ウに獲物を捕らえて戻ってこさせるにはもう一段階の飛躍が必要そうだが、魚を食道に蓄えて吐き戻して与える種類では行動的には自然な習性を利用しているようにも見える。食道の構造や機能も関係しているだろう。
「野鳥」の対談で猛禽類とは違って (おそらく鷹狩りなどを想定したものだろう) カワウが短時間で慣れることについて上田氏は「一般的に晩成性の鳥は知能が高いといわれているようですが」と受けられているが、少し違うような気がする。インプリントされた鳥が食物を食べて帰ってくる (人が少し操作して全部飲み込めないようにしている) だけでそれほど特別なことをやっているわけでないのでは。
ミサゴは獲物は足で捕らえることと、そのまま飲み込むわけではない点が大きく違うので同じようなことをするのははるかに難しいだろう。猛禽類とは単独生活を主にするなど生活様式も違うし、知能はあまり関係ないような気がするがどうだろうか。
wikipedia 英語版によればボリビア・ペルーの Uru people (Uros ウル族) がナンベイヒメウ Nannopterum brasilianum Neotropic Cormorant を鵜飼に用いるとのこと (調べてもあまり資料がない)。
[Cormorant culling]
wikipedia 英語版にこの項目があったのでそのままの題名で紹介しておく Cormorant culling。
日本の事例も紹介されている。
[ウの増加と生態系への影響]
北米の研究: Wyman et al. (2017) Great lakes double-crested cormorant management affects co-nester colony growth
ミミヒメウ Nannopterum auritum Double-crested Cormorant の駆除によって同一コロニー内の下部に営巣するゴイサギが増加したとのこと。
系統的にはヒメウの方に近いが、生態的・人との軋轢などの面で日本ではカワウに近いのでこちらに含めておく。北米のカワウは伝統的なヨーロッパ沿岸部の亜種で、日本ではウミウに対応するような沿岸種。
漁業への影響がよく問題になるがウ類が増えすぎると他の鳥にも影響が及ぶ。
ミミヒメウがこれほど増加したのは五大湖に外来魚 alewife (Alosa pseudoharengus) が底なしで増殖している影響も大きいとのこと。Madura and Jones (2016) Invasive species sustain double-crested cormorants in southern Lake Michigan。
エリー湖の近況 People can once again kill cormorants (Steven Maier 2018)。2006 年からミミヒメウの駆除が始まったとのこと。上記 Madura and Jones (2016) では漁業対象種はそれほど食べていないので漁業への影響のためにウの個体数をコントロール根拠は現状あまりないとしているが、ゴイサギの減少と相関するなど生態系に影響が及んでいる証拠が出ているならば無視できない状況なのかも。
この記事を見てもウの個体数をコントロールする生易しい方法はなさそう。
The rise of the Double-crested Cormorant on the Great Lakes: WINNING THE WAR AGAINST CONTAMINANTS (Minister of Public Works and Government Services Canada, 1995)
によれば少なくとも北米では有機塩素系殺虫剤の影響が非常に大きく、使用が規制されるとともに爆発的に増えたとのこと。この時点ではある程度の個体数で安定化すると考えられていた。当時はハクトウワシが戻ってきた、ミサゴの個体数が増えたなど大成功だったが、ウについてはやや成功しすぎたとの表現となっている。
雑誌 "Birder's World" 1989.12 pp. 14-17 に Marie Read の "Return of the Seacrow" の記事があった。ミミヒメウがようやく戻ってきて美しい鳥だと珍しがられていた時代。
北米の東海岸の歴史をそのまま反映しており、人口が増えたことで初期の入植者が卵を採集し、競争相手になることを恐れた漁業者がコロニーを破壊して回ったとのこと。この結果 19 世紀末には激減し、1896 年にはもはや繁殖しなくなったとのこと。
当時は羽毛目当てでサギ類などが乱獲され、オージュボン協会 (Audubon Societies) の設立でこの乱獲には歯止めがかかった。しかしミミヒメウは捕食性の性質から保護されなかった (excluded from this umbrella of safety - アンブレラ種のアンブレラはこのような使い方がなされていた。確認しておくと umbrella species の用語は Bruce Wilcox が 1984 年に最初に用いたとのこと - wikipedia 英語版から)。
しかし保護されている種と共通のコロニーで繁殖する種類のため次第に数を増やしてニュー・イングランドで 1925 年に再度繁殖、1940 年代には再度普通の鳥となった。
しかしこの状態も長く続かず第二次世界大戦後は漁業者のロビー活動によって再びコロニー破壊を政府が認めるようになった。その後有機塩素系殺虫剤の大量使用の時代となって数が激減、1970 年代に規制が始まってようやく数が回復してきた時代の記事。日本のカワウ以上に過激な人為の影響を受ける歴史をたどっていた。上記 1995 年記事はこの後の時代となる。
バイカル湖のカワウの事例: Pyzhyanov and Mokridina (2023, 2025 再掲) Reintroduction of the great cormorant Phalacrocorax carbo to Baikal: causes and consequences (pp. 2554-2558)
英文表題を見ると再導入のように読めてしまうが、再定着のこと。バイカル湖では 20 世紀初頭にすでに多くの地域で消滅していて 1950-1960 年代 (場所による) の記録が最後となってしばらく絶滅したいた。イルクーツク州 (バイカル湖北西岸地域。2010) とブリヤート共和国 (2005) の RDB 初版で絶滅危惧種とされた。
なぜバイカル湖で絶滅したのか記録されていないが原因は単一でないだろう。魚の減少、狩猟や繁殖妨害などが挙げられていた。その後はたまに迷行するだけであったが 2006 年に2巣、その後急速に生息数を拡大したもののまた減少した地域もある。環境収容力の限界に達したのではないかと考えられるとのこと。
これらはおそらく中国北東部やモンゴル東部から分布を拡大したのではないかとのこと。
2020-2021 年に数が増えた地域もあったが繁殖成功率は特に低かったとのこと。(養魚に関連した?) 人間活動の "助け" を得られなかったわけではないだろう (現地の事情を知っている人には自明な内容なのかも知れないが外からはよくわからない)。
アメリカの事例を参考にすると、漁師には迫害されていたのかも知れないが記録には残らなかった、RDB に登録されたことで表立っては撃てなくなった、などだろうか。
おそらくどこかで議論されているだろうと思うが、ウ類がなぜこれほど爆発的に個体数を増やすことができるのか自分なりに考察してみた [この部分は須川 (2002) Birder 16(6): 23 オオミズナギドリとカワウの比較 から着想を得た]。
おそらく生活史戦略の問題だろうと見当をつけてみた。類似の魚食性のグループにミズナギドリ目があるが、こちらは長命で有名。ウ類は爆発的に個体数を増やしたことから見て真逆の生活史戦略をとっていて、r-K 選択説 (MacArthur and Wilson 1967) に従えばウ類は r 戦略的、ミズナギドリ目は K 戦略的と言えるのだろう。
(ここから挿入) なお他の項目からの参照の便宜も考え、クラッチサイズを決める Lack's principle (1954) "The regulation of animal numbers" が提唱され、population biology または個体群生態学 (population ecology) の発展の基礎となったことも挙げておこう。r 戦略的 / K 戦略的 のように相対的な表現で使うのが適切であろう。
Lack's principle は wikipedia 英語版のページがあり、自身の言葉で "the clutch size of each species of bird has been adapted by natural selection to correspond with the largest number of young for which the parents can, on average, provide enough food" と表現されている。Lack の一連の論文は 1946, 1947, 1948 に出版。古い論文はそもそもオンラインで見るのが難しいことが多く、後にまとめられたものを読むのがおそらく得策。
Avian clutch size の wikipedia 英語版ページがある。
clutch を OED で見ておくと英語で a brood of chickens, a 'laying' or 'sitting' of eggs の意味で使われたのは 1721 年 lost Clutch of Eggs の用例があり、1874 年に現代の clutch size と同じ意味の range from three to six in a clutch で使われていた。
語源は方言の cletch で A brood, a hatching (of chickens) 1691 年初出とのこと。
古くから clutch と brood の概念は曖昧に使い分けられていたこともわかる。brood は動物一般に使われて起源はより古い。現在のドイツ語でも Brut で孵化、動物の子供の両方の意味があり、語源は bro- で温める。
clutch の方はもう少し複雑なようで別語源 (語源不明) で掴むなどの意味の方が早く、もともとは獣や猛禽類の爪を意味して使われた (1230 年ごろより)。こちらは現在機械用語でクラッチと呼ばれるもの。概念的に似たところもある感じがするが別語源で同じ綴りになった模様。
ドイツ語では Gelege で語源は簡単明瞭 (legen 産むなどの意味) で、辞書を見ると "一腹の卵" や "卵の産んである巣" と訳してある。ということで "一腹卵数" などの用語はこれらの訳語ではなく独自のものと思われる。中国語には同様の意味がないので日本独自で、魚の腹子を数える単位由来だろうか (挿入ここまで)。
同じ魚食性のグループでありながら何が違うのか考えてみると、ウ類は陸上性、ミズナギドリ目は海洋性。
いずれも Elementaves の系統で起源的には比較的古く、まだ猛禽類が活躍していなかったと考えられるので進化の早い段階では哺乳類捕食者が最大の外敵だったと考えられる。
上空の天敵を察知する能力があまり必要ないので、ウ類の視力や陸上聴力がそれほどよくなくても構わないのだろう。
この状況は今でも変わっておらず、ウ類やミズナギドリ目は猛禽類の主な捕食対象になっていない。猛禽類が増えてくれればウ類の個体数も制御されると期待するのはおそらく甘い。
ウ類は哺乳類捕食者から逃れるために陸上ならば到達できない島や岸壁など、そしてミズナギドリ目は徹底的に海上を舞台とした。陸上の生息環境は降水量次第で河川の中洲が陸続きになったり流されたりしておそらく変化が大きく、好適な生息環境を失った場合でも環境が復活すればすぐに数を増やせる r 戦略が有利となった。
ミズナギドリ目は海上にはそもそも哺乳類捕食者も地上性猛禽類もおらず、環境変化の影響を受けにくいため長命で基本増殖率の低い K 戦略が有利となった。
ウ類はこの性質のため例えば有機塩素系殺虫剤などの影響で増殖率が低下すれば個体数が急減する。ただし個体寿命はおそらくそれほど長くないため影響が一段落すれば残留殺虫剤の影響が長期に及びにくく、基本増殖率の高さを利用して比較的早く回復できると考えられる。猛禽類はウ類と比較すると基本的に K 戦略的なので、同様に数が減ってしまったハクトウワシやミサゴが回復するのには時間がかかった。
ミズナギドリ目は乱獲などで個体数が激減すると基本増殖率が低いため目に見えて数を増やすには時間がかかるため一見絶滅が近いように見えるが、個体寿命が長いために影響が除かれれば長期的には個体数を回復できる余地がある。アホウドリも絶滅の縁に追い込まれたように見えるが、たとえ人が関与しなくても (時間は余分にかかったかも知れないが) 復活できたのではないだろうか。
ウ類の話に戻るとユーラシアで特に問題となっているカワウでは狩猟圧の変化、有機塩素系殺虫剤、河川改修、外来魚など地域によって寄与の異なるさまざまな要因が複合的に働いたのだろうが、狩猟圧や殺虫剤の影響が除かれればいずれ本来の生息密度に戻るのだろう。外来魚の増殖は本来の生態系とは異なるので、状況によっては北米エリー湖のようなウ類の数が過剰になる要因となり得るのだろう。
現代の日本でのカワウの増加の原因を河川改修に求める人も多いが、かつて個体数が減少して保護する必要が生じた時も原因が河川改修に求められたこともあった。その時々で都合のよい解釈をしているような印象も受ける [この部分は福田 (2002) Birder 16(6): 16-17 も参考にした]。
河川改修は一方的な影響を及ぼすというより、大雨でも渇水でもどちら方向にも極端に作用して結果的に r 戦略の有効性を高める結果となっているのではないだろうか。
カワウの害が問題となるのは漁業や釣りなどと本質的に競合する部分があるためで、この競合がなければ生息数が増えても生態的には実はあまり問題はないのでは? コロニーの営巣木の枯死や土壌の悪化はあっても、もともとカワウの方はそのような状況で繁殖地を移し替えて転々と移動し、新しいコロニーを形成するのが本来の生態なのだろう。
営巣木の枯死があっても時間がいずれ解決するだろうし、転々と移動することで陸上各地に栄養素を提供することにもなる。
栄養循環や林の枯死によってもたらされる生物などのカワウの役割は石田 (2002) Birder 16(6): 28-29 にも触れられていた。Birder のこの号は総合的な視点で含蓄も深いと思った。
愛知県知多郡美浜町 (現在) にあるカワウの繁殖地である天然記念物 "鵜の山ウ繁殖地" (1934.1 指定) ではフンでマツが枯死し、近隣に移動 (週間アニマルライフ 1973 の天然記念物一覧から) とあった。
日本野鳥の会のページもあって JP112 鵜の山 (うのやま) 。"保全への脅威" の項目では「カワウの繁殖地では、カワウの糞により樹木が枯れるため、保護区内や外の山へ移動することを繰り返している。保護区での松等の植林が必要である」の項目があり、もう一つが魚釣りの釣り糸の影響が挙げられていた。
コメントがないわけではないが事実関係の紹介のみとしておく。
ウ類がものすごい量の魚を食べることはよく話題になるが、その理由を #ミサゴの備考 [ミサゴは不器用?] で考察してみた。
(影響の評価が難しいかも知れない外来魚のことを除けば) カワウ本来の分散した分布や生息密度に戻ればおそらく生態系への影響も大した問題にならないだろう。カワウが住みたい場所を人が占拠している、あるいは利用し過ぎているのが根本的問題で、カワウを限られた地域に閉じ込めて個体数制御を問題にするのは徹底して人間側の都合とも言えるのだろう。
同じところに住んでくれないと困ると考えるのはあくまで現代人がそのように暮していることに由来する社会的決まりや観点に由来するのだろう。
カワウが住みたい場所に自由に住ませることを人間側が許容できないならば人為的駆除が現状唯一の解となるのもやむを得ないのだろう。
さらに少しばかり考察しておくと、資源 (食物、繁殖場所など) を "情報資源" と読み替えれば情報空間 (この場合の「空間」は物理や数学に特徴的な抽象的な概念で、構造が似ているものを同じように表現しているだけ。用語を恐れずに見ていただきたい) における現代の人の行動はカワウに似ているのではと思えてきた。
情報資源に集まって各々が消費し、資源が尽きれば (例えば情報の新規性がなくなれば) 次の場所へ (例えば新規性のある情報へ) と転々とする。結局またもとの場所に戻ってくることもあるわけだ (例えばブーム再来。雑誌の特集タイトルにも同じような回帰傾向があり、数理的には同じ現象かも知れない)。
カワウのコロニーの移動と大差ない。情報空間で非常に r 戦略的な生き方をしていることになる。
そしてカワウの r 戦略的な部分の説明と同じく、現代のインターネットは特にブログやソーシャルメディア (= 日本語では SNS。英語では圧倒的に Social Media の表現が使われる) の発展以降 r 戦略を極度に促進する方向に働いているのだろう。
Birder もこの傾向を打ち破って「鳥の首に萌える」とか「鳥のうろこに萌える」とか1冊まるまるそれのみ扱った特集を組めばこれまでとまったく異なる世界が広がるかも知れない。翼とか羽毛は何度も特集があるので別の部位を取り上げても不思議でない。気持ち悪いとか植え込んでいるのはメディアのそのものなのだから。
そんなものは売れないからボツ、となりそうだが、むしろまったく違う読者層が関心を持つのでは? そんな特集号があれば世界の鳥の歴史にも残る画期的事件かも知れない。きっと珍しいもの好きの世界の読者が争って買ってくれるよ。
問題はそんな部位を狙って写真を撮っている人が多分いないので画像が集まらない、記事を書く人が見当たらない、などになるだろうか (笑)。
ウ類の黒い色、サギ類の白い色の役割に同種を見つけて集団を作るのに有利などの説明があるが、同じように情報空間での集団を作っているのだろう。鳥が群れる理由にはもちろんそれぞれの個体が有利になる生態的理由があり (共同防衛や食物を探すのに有利などいくつも提唱されている)、情報空間上で集団を作る理由もおそらく同様にそれぞれの個体にとって有利な点があるのだろう。
インターネットで注目を浴びる、あるいは金銭的報酬を得ることなどは、それぞれの個体にとっては「小遣い稼ぎ」程度であっても十分適応的なのだろう。進化を促す選択圧とはそもそもそんなものである。古い時代に自然選択による生物進化を否定した学派もこのことをあまりに軽視していた。
いずれもうまく本能的部分をくすぐられていることになる (ついつい手塚治虫氏の「火の鳥」のムーピーゲームを連想してしまう)。
そんな本能をくすぐる仕組みに日常的に頼っていてばかりでよいのだろうかと少し気味悪く思ってしまう (「火の鳥」では人類絶滅の引き金となっていた。1967-1968 年の漫画でとんでもない先読みになっている)。
そのような仕組みは各個体の選択によって自発的にも生まれて進化するだろうし、誰かが気づいたのかも知れない。いずれにしてもこれだけ普及しているのはこの仕組みが「適応的」だったからに違いない。
他の仕組みを考案したサービスもあったかも知れないが、選択されず消滅したわけだ。
集団ねぐらの意義の一つに情報センター仮説があるが、多くの人が起きてまず行っている (だろう) 作業はまさしくこの情報センター仮説に当てはまるのではないだろうか。こちらの目当ては本物の「情報」そのものである。
昔ならば (今でも?) 行列に並んだり、集団を見つけるととりあえず何なのか見に行ってみる、も同様。話題になっている鳥の場所に行って撮影しよう、などもまあ同じようなものだろうか。
鳥の行動を解釈するための仮説が、なんと人間行動の方をずっとよく説明してしまっているかも知れない。
カワウのコロニーを見て我が身の行動を解釈してみよう、ということになる。
Birder (2002) 16(6) の特集タイトルは「カワウ的生活」だったが、カワウから見ればむしろ「ヒト的生活」と呼べるかも知れない。
r 戦略を極度に促進する方向が多分よろしくないのは、カワウ (シカなり他の野生動物でも結構) の増加に困っている現状にも現れているだろう。情報空間ならば情報の拡散などに相当するだろうか。そして生物学と同じく基本増殖率の高い方の情報が、正しいかどうかにかかわらず優占するわけだ (競争排除。生態学と同じように密度効果なども考えられるので完全に占拠することは難しい)。
保全生物学でも r 戦略傾向の強い種のみを増やすなどの努力は現在では多分行われず、r 戦略的でない種も生存できるように多様性を保つのが基本だろう。我々の世界でも r 戦略性の高い行動に有利な仕組みがすでに行き渡っている以上、この仕組みの生態学的危険性を意識して扱わねばならないのだろう。
近年 (2025) 日本に限らず野鳥写真と AI のことがしばしば話題になっている。AI による加工写真の方が現物を上回る (?) ようになって、こちらの方がアクセス稼ぎにより効果的ならば基本増殖率が高いかも知れない。AI が進歩したためとも言えるが、費用や機材 (そして体力) の限界など野鳥写真の方がそろそろ頭打ちになりかけている兆候ではないだろうかとも感じる。
機材に投資してより見栄えのする写真を撮るよりも、加工技術に頼った方がよい結果が得られるならば投資意欲が減退しそうに思える。幸いにして AI 生成画像には著作権が生じない解釈になっているので、他人が撮ったような写真と同じようなものでさらに良質のものが生成できても現状は盗作にならない。
いずれにしてもどこかで逆転現象が発生すると考えられるが、それ以降も野鳥写真ブームは続くのだろうか。費用も手間もかかる野鳥写真のブームもいずれ下火になりそうに思えるが、その後のことを少し想像してみると、写真家による妨害は減って保全面ではむしろよい効果を生むかも知れない。
しかしながら機材が売れなくなれば機材の進展もなく、野鳥向けに特化した高度な写真システムは採算が取れず企業もいずれ撤退してゆくだろう。現在ある機材でさえも使えなくなるかも知れない。このような現象はあまり予期なく一気に進み得る (物理学用語では例えば不安定と呼ぶ)。古いアナログ機材と異なり、デジタル機材は修理できないあるいは後継品が出なくなればその時点で終わりとなり得る。
ブームが去った後は偽画像や偽映像が氾濫した世界で、現在は普通に利用できる野鳥向け写真機材も特注となって庶民に手が出なくなるかも知れない。「売れませんので」と言われれば返す言葉がない。
このようなことを考えているのはアマチュア観測天文学が (要因は AI や写真機材の限界というわけでもないが、機材の選択肢が狭まっているのは確か。かつてアマチュア向けに3雑誌が競い合っていたが今やその面影はない) すでに同様の状況で、自宅に観測設備があるなど恵まれた環境に人のみの趣味になりつつあるためである。
それならば以前のように自分の目で見て記録する方に戻るかと言えばあまりそうではなく、海外のインターネット望遠鏡に移行するなど、費用をかけられる人しか取り組めない状況になりつつあるためである。
もし同様であれば、野鳥業界の未来は野鳥写真以外の野鳥観察や鳥学の魅力をどこまで伝えられているか問われることになる。
識別が特に話題となってきたのも機材の進歩による部分も大きく、こちらもある程度で落ち着き、難しい部分はいつまでも難しいだろうが (しかしこちらも系統分類の理解が進み、ベニヒワのように、あるいは亜種のシノニム化によって識別の意味が減少する部分もありそう) 新規の識別情報はあまり話題にならなくなるかも知れない。しかし野鳥写真と識別を除けばいったい何が残るのだろうか。
他の事例や、過去のブッポウソウ・コノハズク問題 (#コノハズク備考 [姿のブッポウソウ] 参照) などを見ていても感じたのだが、基本的には「競争を好む」ことが driving force (推進力、原動力。英語の方が先に出てくるのは英語の語感の方がよく合うため。日本語は英語を訳したのものではないだろうか) となっているのだろう。
他国でも状況は同様の部分があるが日本では特に目立つ感じがする。もちろんこの driving force は人類進化の原動力ともなってきただろうし、本質的には他の動物の「社会的地位の向上」のための行動と違わない。
鳥の世界では古くは新種発見や命名争い (そのためあまり大した意義のなさそうなタクソン/タクサが量産されたわけだ。また多くの種類の絶滅にも手を貸したり早めたりしたことだろう)、ブッポウソウ・コノハズク問題の時期ならば冷静そうに書いている中西悟堂氏も巻き込んで、誰が最初に明らかにするかが競われた (中西氏も鳥獣商から入手しようとしていて「野の鳥は野に」の精神になっていない)。
歴史物語としては面白いが、わかってしまって冷静に見るとあの騒動は何だったのだろうということになる。中西氏も体力自慢を強調して山登りをずいぶん披露されていたが、鳥学者側からも無理はほどほどにを示唆する諌めもあった。
バードウォッチングと呼べるような時代になれば、例えばライフリスト自慢だったり、写真自慢で無理を承知や餌付け撮影も行うなど過剰競争も発生した。識別力が能力の代表とされて競い合った時代があった (今でもそうかも)。写真が雑誌に掲載されることはステータス・シンボルであり (例えばかつての「アニマ」)、メディアはかなりの部分が競争を助長するためのものであった。
質を高めたことはある程度確かだろうが、そこまで目立った競争を行っていない海外状況と比べると、日本で自慢される野鳥写真がむしろ海外写真に簡単に負けてしまって自慢にならないことも多々ある。海外ではむしろそれほどの競争なしに良質の画像も撮影されているのでおそらく過剰競争の必要はないのではと思う。
国内では「自慢」行動に (無駄な) エネルギーが割かれ過ぎで、日々自慢できる成果を求めて結果的に効率を落とすとともに考え方の多様性や発展性を制約しているのではないかと感じる部分もある。もう少し視点を広く持ってみよう。
日本のバーダーの音声録音が存在感のある状況にならないのは、しばしば野鳥録音をしても発表の場がないためと言われる。発表の場というのはおそらく正しくなくて、平たく言えば「競争の場」ということだろう。野鳥録音をしても褒めてくれる人も競争相手もいないので流行らないわけだ。そんなことはないと言われる方はぜひ世界のライブラリに登録して貢献して欲しい。
筑豊支部ではもっと着実な活動をされていることは理解しているのでその路線をさらに生かして欲しい。
中西悟堂「定本・野鳥記」1 p. 110 で中西氏が面白いことを書かれている。ふんだんにいる留鳥を、人人はなぜ飼鳥にしないのだろうか。故に少ない珍しいもの、ふだん見かけぬもの、さえずりのよいものを好んで飼おうとするのは人情の常ではあろうが (以下略)。これは人情の常 =「自慢のため」だと思えばすべて納得できる。
少ない珍しいものは自慢の対象となり、さえずりのよいものは鳴き合わせ会など競い合ったわけだ。これは日本に限った話ではなく#ベニマシコ備考の [赤い鳥はなぜ赤い] にもあるように西洋でも同じだった。東欧やイスラム圏など飼い鳥文化が健在な地域も多く残っており、現代的なコンテストが行われ、インターネットが自慢の場になっている。
主に飼育下繁殖の確立した種が扱われているが、野生種も密猟されることがあったり域外放鳥などもあるので飼い鳥文化を卒業した地域からはしばしば批判の目で見られることになっている (飼育が一律に批判される傾向があるが一部の種以外でどの程度野生個体群の脅威になっているのかよくわからない)。
日本でも鳴き合わせ会などの競技的要素のある部分が最後まで残ったが、自慢相手のなくなった飼い鳥文化は衰退したことになる。少ない珍しいものは現代で言えば珍鳥撮影と同じ。写真の出来栄え自慢、あるいは珍しい鳥の情報をいかに早く手に入れられるかを自慢し合っているのと構造的には同じである。
野生動物輸入大国と批判されたのも本質的には同じだろう。
ライフリストは海外バーダーとは勝負にならないので国内限定で数を競う (これは英国事情もよく似ている)。まあ比べ合いの趣味なのでさまざまなルールがあってもよいわけではあるが。
海外の鳥のコミュニティにもあまり参加しないのは言語障壁もあるだろうが、自慢できる要素が少ないこともあるのだろう。
中西氏の日本野鳥の会の設立も本質的には同じようなものだったのだろう。中西氏の書き残した経緯を見ても、鳥業界で自身がいかに優れていて、これまでの日本になかった視点を示すことができるかを示したかったのだろう (もっとも現代でも科学上の発見を広報するなども似たようなものだが)。巷の飼い鳥趣味 (といってもこの視点で見れば飼い主の腕自慢) とは一線を画す一般的な鳥の飼育自慢話や、その後は野鳥の普及を自慢したいのがおそらく本音だったのだろう。
自身が絶対的に優れていることを示すのは数学的に考えても難しいのでどうしても比較対象が必要である。科学ならば対立仮説との比較となり、この場合はかなり客観的に評価できる点が「科学」たる原理となるわけである。しかし世の中一般の比較は客観的判断が難しいため、比較相手を批判することで優位性を示すことにつながりやすい。こうなると科学的視点から離れがちで不毛な議論が起きる原因ともなる。
野鳥そのものがある程度大衆化してしまうと保護に目が向かう。
海外からの働きかけもあって複数のグループが保護を訴えるようになった。
愛鳥週間 (バードウイーク) は日本では 1947 年に「バードデー」が定められ、1950 年に愛鳥週間となったもので、現在の日本鳥類保護連盟の母体が主体となって広報活動が行われた (情報は wikipedia 日本語版より)。
中西氏が批判されていたが過去には国主導で巣箱かけ競争があったらしい。今でもその時代の残骸らしいものをみかけることがある。
しばしば「日本野鳥の会ではなぜバードウイークに特別な活動をしないのですか」と聞かれることがあり、「代わりに秋にバードウォッチングウィークがある」と答えるのが常だった (過去の探鳥会での話で、現在では事情も違い、地域によっては排他的でないところもあっただろう) が、要するに出所が違うのである。このように答えると実につまらない理由と言われるが、そういうものである。
事務所をどこに置くかやメンバーなどは互いに入れ替わっていたものの、このように複数の自然保護団体が競い合っている状況では自然保護も活気があって会員集めにも力が入っていたが、自然保護そのものが当たり前になってくると次第に競争要素も失われてどこも活動が停滞して行ったということになる。
愛鳥週間がメディアなどに露出する頻度も次第に下がってしまった。定められた経緯を知らずなぜ鳥ばかり保護するのかと反発する意見も出てくることになる。
行政が費用をかけずに競争させて保護させようとの考え方は #タンチョウ 備考の [学名や英名の由来] にあるように浦本氏が手厳しく批判されていたが、中西氏が巣箱かけ競争を批判されていたのは愛鳥週間運動の一環であって出所が違うこともあったのだろう。
中西氏は欧米先進国で実績のあるサンクチュアリの方が効果的であると主張されていて、これは現代の活動にもつながっている。確かに実績は残したと思うが、場所を所有するには費用も必要でなるべく安価に広い面積を求めると都心近くには持ちにくい。この要求は広い面積を安価に購入したいメガソーラー計画などとも競合することになり、どちらを採用すべきかとなると社会的判断が難しいところもある。
固定した場所を保有するのが本当に得策なのか検討も必要だろう。
一度獲得した方法論、すなわち自分の出所やなわばりを守ろうとするのは、これまた生態学的には適応的なところがあり進化しやすい性質だろう。
学問でも異なる出所の分野は専門領域が狭いほど先鋭化しやすいがお互いに混じり合うところが少ない。
学会で話をしていかにも交わっているように感じるが、多くの場合は大したことはない (あくまで過去の体験から)。個々の専門領域のカバーする範囲が狭いため、間に大きな空間があることになかなか気づかないのである。「葦の髄から天井を覗く」というのもあったなあ。昔から問題点はよく理解されていたわけだ。
1 + 1 が 2 以上にならないのが日本 (だけではないだろうが) の悪いところで、数理的に何か言えそうな気がするがあまり健全な競争になっていなかったのだろう。
自然保護でも本来ならば複数の団体があれば相乗作用でさらなる力を発揮しそうなところが少なくとも近年では大したことはなかった。好意的な表現ならばお互いの活動を尊重して介入しない、別の書き方をすればなわばり争いやお山の大将のようなものとも言える。故事で言えば「鶏口となるも牛後となるなかれ」。
日本野鳥の会でも、支部間の競争要素もあったため一時期は会員もかなり増えることになったが現在はご存じの通りである。
要するに小さいレベルから大きいレベルまで競争要素がないといずれ衰退してゆくのが世の常であった。
後の項目 [ガラパゴスコバネウの進化] で登場するように選択圧が働かなくなればコストのかかるものは維持されなくなる (relaxed selection) のと同じ原理である。残念ながらヒトが進化の過程で獲得してきた「競争を好む」心と、普遍的法則から避けられない運命なのである。
これは個体に働く選択圧であって群淘汰のように集団に働く選択圧を考えるのは間違いとの指摘があると思うが、個人がどのような行動や趣味を選択するかは個体の意思で決められるものの、個体の行動や選択が社会的に縛られている効果によって構造が生まれるのであろう。
[ガラパゴスコバネウの進化] で取り上げたプログラムの例では、個人がどんなパッケージを使うのも自由であるが、他者と違うものを使って維持するのはコストがかかるので結果的に一般的には主流派が残ることになる。
メカニズムを考えた上でこれまでの経験的法則性を認めた方が賢明であろうし、生態学が専門の現会長も現在起きていることは当然理解しておられるだろう。
ここでは何かを批判する意図はないが、現象の仕組みを理解しようとする科学の営みであるとご理解いただきたい。何か矛盾を感じることがらがあれば多くの場合何かの理由がある。
「野の鳥は野に」(小林照幸 新潮選書 2007) pp. 180-181 に興味深い記述がある。日本野鳥の会の古くからの会員の思い出話として中西氏はバードウォッチングという言葉が好きではありませんでしたね 「バードウォッチングという言葉は、鳥をモノとして見ている気がしてならない (後略)」と話されていたとのこと。小林氏は「ビギナーは、何種類の鳥を見たとか、体のどの部分が何色だとかに興味が向かう (後略)」と補足されていた。
(後略) の部分には鳥のいる環境も大事であることが含まれているが、これらは当時の自然保護運動の考え方に対応する形で表現されたものかも知れない。
この部分はまったく同感で、「制覇」とか「攻略」「リベンジ」などの表現をもし中西氏が存命中に読まれたら卒倒されるのではないだろうか。仮にも日本野鳥の会会員を名乗る方が野鳥に対して使うべき用語ではないだろうと思う。
そう言えば天然記念物という用語もまさしく "モノ" だなあ...。
また、今でもそのまま通じそうだが、ビギナーに「何種類の鳥を見たとか、体のどの部分が何色だとか」に興味を向けさせているのは誰なのだろうか。これも「競争」や「自慢」で説明できてしまうのだろうか。
現代でも形態や化石との関係ばかりが重視されると、どうしても "鳥をモノとして見る" 視点が中心となってそれだけの紹介は正直あまり好きになれない。形態や化石との関係も知りつつ「モノではない鳥」が語られるとよいのだが。
ここでは過去の現象や記述の理解を深めるために中西氏の活動の背景にあるものを分析させていただいた部分があるが、"鳥をモノとして見ない" ことはかなり一貫されていたように感じる。コノハズクのように買い取って明らかにしようとされたらしい面もあったが、出発点は本性を知るための飼育であったと感じる。
「野の鳥は野に」を非常に狭義に受け取った時代の洗礼を受けた世代が、野鳥を迫害の対象としたり食料とは考えないものの、"鳥をモノとして見ない" ことを忘れてしまったのではないだろうかと感じる。
自然保護活動も鳥は保護や管理対象の "モノ" の性格が強まり、中西氏の思いから離れていったのかも知れない。
ベニマシコ備考でも触れたが、野鳥を徹底的に遠ざけた結果忘れ去られてしまった、鳥と人が空間や時には意識すらも共有できる仲間であることを、科学の目から解いて行ってみることも本稿の役割と考えている。
もちろん自分にも鳥とふれ合う原体験 [このガチガチの科学信奉者 (笑) さえ虜にしてしまうぐらい、とても賢い *1] があるゆえに感じることができるのだが、鳥と人の関係がなぜそうなっているのか (まったく自明でない) を科学的に知りたいわけである。
ダーウィンが「天使のようなハト」の虜になることができたことも、彼が進化論の考えをまとめる重要な動機となっていた [#カワラバト備考の Darwin (1868) "The Variation of Animals and Plants Under Domestication" 参照]。鳥は人類にとって最も大切なことを教えてくれたのだった。
DNA は一見 "モノ" のようにも見えるが、そこには生物の生きている姿や生きていた痕跡を読み取ることができる。形態や化石も同様ではあろうが、現代では DNA の方が雄弁に語ってくれることも多い。生身の鳥の魅力 (例えば#ハチクマで逐次紹介中の海外の子育てビデオなどご覧いただければ。いくら見てもまったく飽きない) と相補的に扱って行ければと思う。分子生物学も生態学もあくまで道具であって、鳥をよりよく理解するためのものと捉えればよい。
取り上げる視点こそ異なっているが、この部分は中西氏の望まれていたことと同じであろうと思う。
備考:
*1: 実は小学生のころは犬を飼っていて遊びまくっていた。今のように "学校から帰ると塾" のような時代ではなく、犬を連れては遊びに出かけていて、勉強らしいことをした覚えがほとんどない。"散歩" から犬があまりにくたくたになって帰ってくるのでいったい何をしているのかと心配されたぐらい。当時は哺乳類の方が好きで教室図書に置いてあった「狼王ロボ」を読んでオオカミに憧れていた次第。
当時の百科事典にも鳥類は「体制は爬虫類に近く、卵生で云々」など書いてあったと思う。哺乳類よりも劣ったグループの先入観を植え込まれても不思議でない (鳥学者が認識をどのように伝えるか責任重大)。「鳥は恐竜の生き残り」も同じような先入観を与えるのではと心配する理由でもある。
論理立てて伝えようとするあまり系統関係が冒頭に出てくるのは (後半の説明など覚えていないものなので) 誤解を招きそうな気がする。鳥類の魅力をまず挙げて系統のことは後でもよいのでは。「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) はその点工夫があって「鳥類は美しい動物」で始まって系統の話は最後だった。
鳥学者が魅力を伝えようとされたことが読み取れるが、やはり形態的魅力に始まっていた。知らない者が読むと「花は美しい」と大した違いがないし、熱帯の鳥に比べるとあまり美しくない日本の鳥は優れていないのかと思ったりしがちであろう。
セキセイインコを飼うようになったのはその後の小学生高学年のころの話で、それまでは鳥なんか飼ってもつまらないと思っていたが何と驚かせてくれた。オオカミに憧れていたはずなのが今度は見向きもしていなかったはずの鳥 (各種図鑑の中でも一番開いたことがなかった) に興味を持ち、今度は「爪王」を読んでワシ・タカに憧れるようになったいかにも子供らしい単純な動機である。ネットを調べると中学生の教科書に登場したらしいが教科書で読んだものではなかった。
この程度遡って深堀りしてみないとなぜ鳥が好きになったのか伝えにくい。順序関係もあって意外に難しい。
表現の仕方は動物それぞれの違いがあるものの、帰って来た時の喜び方、遊んで欲しい時の態度、遊んだり何かを達成した後の満足な表情など犬もセキセイインコもほとんど共通だった。羽の生えた友達としか呼びようがなかった。
いずれも報酬を与えるわけでもなく、用もないのに出てきたり、合図だけで往復したり純粋に遊びたいから遊んでいたものだった。天才ヨウムと呼ばれたアレックスに報酬の餌を与える映像や、鷹匠がその都度肉片を与えたりするのを見るとちょっと興ざめしてしまうところがある。
これらを体験していると野生動物に餌を与えて近寄らせようなどの考えは毛頭出るはずがない。餌付けをしてしまう人はこのような体験がないのか、あるいは動物は餌で釣るものとの先入観からそのような接し方が中心になってしまったのだろう (そして既述のように、よりよい写真を撮るための競争要素が多分に入るのだろう)。
犬は家畜に選抜された品種で、セキセイインコは鳥の中でも飼育下繁殖方法も確立され人に親しみやすいなどバイアスが入っていると考えられるが、野生や飼育の別系統の種類をもう2つぐらい体験すると鳥の賢さ (少なくともオウム類、タカ類などの近代的な陸鳥。スズメ目もおそらく当てはまるが大きめの種類がやはり賢い) をある程度一般化してもよい感じがする。
なおタカ類 (と言ってもおそらくオオタカなどの鷹狩りに用いる種類か) については 「野の鳥の生態」(下村兼史 1931 初出。「日本野鳥記」1 講談社 1985 収録より) p. 65 で語られていて「優良な犬のように (中略) 非常に人懐こい鳥 (中略) 幼鳥に限らず成鳥も飼い馴らせば全く可憐な鳥であることは飼養に経験のある人が皆云う所である」。もちろん餌によって馴らせている部分はあるだろうが、タカが賢いことはすでによく認識されていた。「優良な犬」の比喩は他所でも読んだことがある。
動物園個体なのでそのまま当てはまらないかも知れないが、こちらはごく近年の事例で、帰ろうとするとハチクマが引き留めようとしたことがあった。これもセキセイインコの行動を知っているのですぐに意図することがわかった。ハチクマの野生個体の気性もすでにある程度知っていて、驚きではあったが特に違和感なく (そのぐらいのことはあってもよいと) 感じられた。
意図の通じる相手らしいことはおそらく理解できていて、その通りに応じると手応えを感じたのではないだろうか。
猛禽類は食べ物への執着が非常に強く餌を報酬として慣らすものと考えられているのも伝授されてきた鷹匠技術からの思い込みかも知れない。飼育下環境で餌を他者に横取りされる心配のない場合は、おそらくそこまで餌に執着せず、少し食べて一旦満足すれば最後まで食べ尽さず残しておいて後でまた食べることにして遊ぶ方を優先しようぐらいの知恵は働くだろう。この点はセキセイインコでも同じ。
餌を与える人より相手をしてくれる人に馴染むのはセキセイインコでも犬でも体験している通りで、遊ぶ方専門の役割だったため「なぜ餌を与える者に懐かないのか」と餌を与える側からしばしば文句も出ていた。食料さえ満足にあればタカも楽しいことの方が好きなのではないだろうか。動物園でも構ってくれる飼育員が好きなようだった (そういえばベテラン飼育員の方が何をしているのかと見にこられていたことがあった。自分が餌を与えているのに...とおそらく不思議に思われたのだろう)。
タカ全体に一般化してよいかわからないが少なくともハチクマでは成り立つと言ってよいのではないだろうか。
モモアカノスリなど鷹狩り (デモンストレーション) に使うタカは餌を使った訓練が行われていて餌で行動を誘発する方に慣れているが、野生由来個体ではそのような訓練が行われていないためむしろ本来の性質がよく表れているのかも。タカは餌で手懐けるものとの先入観を捨てれば案外よい友達付き合いができるのか知れない。
欧米の動物行動学者の記述にはむしろこのような比喩が現れない気がするが、おそらく言語的にあまり影響を受けていないロシアでカラス類と猛禽類が賢い鳥の代表に挙げられているのは面白いと思った。
タカ類が野生味が強くて人を受け入れない印象は、動物文学で誇張されて伝えられ熟成されてきた先入観によるものではないだろうか。「爪王」の調教の場面も現実にはあまり起きそうもない感じがする。White (初版 1951) "The Goshawk" (Penguin Modern Classics) でも同様だが、基本的に文学表現の世界であって現実の鳥も同じと考えてしまうのはおそらく間違いのもとになるだろう。
欧米でも過去に誰かが述べたことが先入観となっていたのではないだろうか。
もっとも「爪王」を読んだならこそワシ・タカに憧れるようになったものなので動機を与えてくれたことは確かである。一般的には孤高で冷酷とされるクマタカとここまで心を通わせることができることを表現したい作品であり、表現はあまり正確でなかったかも知れないが伝えたいことは同じだったかも知れない。
もっと科学的視点を持って現実を追求した文学であればむしろ興味を持たなかったかも知れない。
タカ類の孤高さを表現できなければ良質の映像でない、と作品を評価するのは「写真とはこうあるべし」先入観由来かも知れない。評者は名の知れた写真家であることも多いし。
そしてそのような写真や映像のみが選択的に世に出て印象を形作っているのではないだろうか。タカ類はそうだ、と初めから思い込むのでオウム類やカラス類が賢いと言われるだけかも知れない。
同じような "孤高の" 生活様式のモズならば人に慣れて賢いと言われるが実はよく似ているのでは。
タカ類は相手からも人を認識して行動するぐらいに本来もっと親しみやすい生き物なのではと思う。狩猟などであまりにも迫害しすぎたため、人を恐れる遺伝形質が選択されてきただけかも知れない。
孤高でありながら子育ては細やかで愛情豊かと表現されるのも「生態系の頂点の動物は子育ても厳しい」先入観の裏返しかも知れない (これもおそらく植え込まれた考え方)。無駄には動かないがよく観察していて、子育てに限らず感情豊かだと思う。
タカが動物を食べるのは生きるために必須なためであって、余裕があれば他にも楽しいことを望んでいると考えればタカに対する一方的な捕食者の印象も和らぐのではないだろうか。
冷酷な捕食者であってもあまりに美しいのでやはりタカはよい、あるいはタカが美しくてかっこよすぎると "ねたむ" (?) 人もあるかも知れないが、これもタカと我々の審美意識が似ているため生じた自然選択の結果かも知れない。羽毛を持たない我々はそこまで美しくなれなかった (笑)。
タカの社会でも美しくてかっこよい性質が優れた配偶相手の資質を示すと認識されているのだろう、おそらく。
そして獲物を捕える能力とこの性質がちょうどうまく整合するので、我々にとって "無駄" にも思える一部の鳥にあるような装飾に凝る必要がない。同じく狩猟採集を行って進化した我々と認知的共通性が高いのではないだろうかと想像が膨らむ。
もとの話題に戻ると、犬もセキセイインコも両方知っているので、鳥類・哺乳類の収斂進化と言っても空想の議論ではなく現実の体験に基づいている。知的能力が大変高く、"好奇心を満たすためや楽しむために行動している" ことは見ていてある程度わかってしまう。
学者が頭の中で考えただけの理屈よりは多少は信頼していただいてもよいだろう。また現物を知るのに野外の原体験が必須というわけではなさそう。
この部分を書いてから改めて考えてみると、飼い犬と戯れる長い準備期間があったため相手に合わせることを自然に体得していて、飼い鳥に接してもすぐに慣れることでき、相手の表情もすぐに読み取れるようになったのだろうと思う。
鷹匠ならばタカに仕えると表現されるのとおそらく同様だが、おそらく動物に接した経験のない者にも理解できる伝授方法だったのだろう。別にタカだから特別に仕える必要があるのではなく、鳥に接する時は一般的にそのようにすればよいだけである。相手が知的な鳥であれば同じように合わせてくれ、お互いに happy ということになる。早成性の鳥ではそこまでではないかも知れない。
飼い鳥の経験があったので野鳥でも表情がある程度読み取れて相手が嫌がらない作法に自然に気づき、またビデオを見ても鳥の表情が読み取れるのかも知れない。
#シジュウカラ備考の [オクターブ認識能力] で触れたように、おそらく音感を養っていないと鳥の声に気づきにくいのと同様、学習してこそ身につく能力かも知れない。
おそらく物事 (経験) には依存関係があって、段階を踏んで親しんで行くのがよいのだろう。
もし最初から知り合いに「バードウォッチング道」に引き込まれていたらまったく違う経緯になっていて、鳥をモノとして見るように育ったかも知れない (経済学者の言う経路依存性とは違うかも知れないが若干似ている)。写真から野鳥に入られた方が鳥を飼われても接し方があまりこなれていないように見受けるのも同様の理由かも知れない。
鳥の声の聞き取り能力の個人差から想像すると、同じ映像や行動を見ても感じ取ることは過去の経験次第で人によって大きく違うのかも知れない。逆に言えば「バードウォッチング道」を追求された方の見かたを理解できていないかも知れない。
アニマルセラピーと言われるものも相手に合わせることを体得する行為なのかも知れない。おそらく単に動物を連れてくればよいわけではなく、海外でエビデンスがあるからと言って日本の環境でも同様に成り立つかどうかわからない気がする。
もっともこのような原体験ができたのは当時の社会情勢由来でもあって、今ならば犬を散歩に連れて行って遊べるような場所もほとんどないし、学校の校庭でそんなことをしていたら怒られるだろう。
近所への鳴き声騒音もあるし、在宅でない時に誰が面倒を見るのかなどなかなか条件が整いそうもない。少なくとも現在の日本の都市部では昭和世代の思い出話だと思って聞いていただいてよい。
多少自慢話をしておくと、そこそこの期間セキセイインコを飼っていて繁殖 (巣引き) もしておすそ分けもしていたが、一度も逸出させたことがなかった。かごから出す時は部屋を閉めるなどもちろん基本的なことは行っていたが、人の出入りもあるので逃げようと思えば逃げる機会はあったのではないかと思う。
一度だけ家族の者が散らかった餌を食べさせようと物干し (と昔は呼んだ) で日光浴も兼ねて出していた時に逃げてしまって (これは明らかな不注意)、幸い近くの店舗のひさしにとまっているのが見つかって無事連れ帰ることができた。この時も特に餌で呼ぶわけではなくきちんと見分けて呼べば戻ってきた。
「鳥は逃げる習性がある」わけでもなさそう。住み慣れた場所を離れる方が危ないはずなので進化しにくい行動と考えられる (専門用語らしく書けば site fidelity に対応する)。逃げるのはやはり理由があるのではないだろうか。
おすそ分けした方は案外成績が悪く、逃してしまったり不慮の事故で死なせてしまったり、結局消滅してしまった。遺伝的には性質はほとんど同じと思われるので飼い主側の違いが現れたのだろう。
「鳥をモノとして見ない」に関連して、鳥の声を録音していると話をするとなぜその録音を使わないのかと聞かれてしばらく意味がわからないことがあった。つまりなぜ再生しておびき寄せをしないのかと不思議がられたのだった。プレイバックは研究や調査のために必須の道具ではあるが、自分はそこまでのことは行っていないので野外でプレイバックをした経験がないし行わたいと思わない。
記録したばかりの音声を再生して録音状況を確認したり探鳥会で確認に使ってもらう程度のことはできるが、途中から再生したり戻したりする操作方法を知らないので冒頭に音声が入っている時のみ可能である。
リュウキュウサンショウクイの時 (当時は季節外れのサンショウクイと思った) は探鳥会でこれができたがムジセッカは途中だったのでできなかった (いずれも当時の探鳥会の初記録種)。
そう言えば音楽を聞くために高品質機器を購入していると思われることもあるようで妙な疑いを持たれたことがあったがもっぱら録音にしか使っていない。一般利用者から見れは不思議な使い方かも知れない。
このように再生操作に慣れていないので、動物園でハチクマに音声再生を試させてもらう時も、見事に途中で止め方がわからなくなって慌てていた。こちらが慌てふためいていただけで、とまっているハチクマはいつも通り平然と見ていて、この様子ならば音声再生をしても大丈夫ですねと担当者の方に確認していただいた次第。
この時はハチクマで初記載の音声の論文だったためヨーロッパハチクマの音声との反応の違いを見ておきたかった。どうも文脈がない条件での音声にはあまり反応がないらしい (この点はスズメ目のさえずりへの反応と異なる)。一つだけほぼ確実に明らかになったのは自発発声に対して自身の声を聞かせると発声を中断したこと。自身の声が聞こえるのは不自然に思えるらしい。詳細は #ハチクマ備考の [音声] の方に論文へのリンクがある。
音声再生を試したのはこの実験の時だけでその後の訪問ではそれまで通り。気持ちよく鳴いているのを邪魔したくないので。話しかけ程度は行っていた。
野外で pish / pishing や鳥寄せの笛も使ったことがないし、柳生さんや中西氏が行われていた程度にお話をした程度。最近はそれも行っておらず (録音をしたい場合は余分な音はむしろ避けたい)、それでもこちらの動きに応じて相手をしてくれるので大したものだと思う。
プレイバックをすればあるいは珍鳥に出会える可能性は高まるのかも知れないが、それは目的ではないので、珍鳥さん来られるならどうぞ、鳴いてくれれば記録して聞き分けましょう。「鳴くまで待とうほととぎす」としている。探鳥地で再生らしい音を聞くとがっかりする方。
さらなるおまけで感情移入のことに触れておきたいと思う。感情移入と擬人化は別概念だと思う。後者は人間の行動との類似性に気づくもので、仮説を立てる上でも有益と思う。
飼っている動物や野鳥に感情移入が起きるかと問われると、少なくとも自分の場合は起きない。対等の立場なので感情移入の必要を特に感じない。感情移入は外から見ている (場合によっては見下していると言える場合があるかも知れない) 状況で意味があるもので、「鳥をモノとして見る」よりはよいかも知れないがその延長上にある感じがする。
このようなことを考えたのは「タカが小鳥を襲う場合にどちらに感情移入するか」の問いかけがあったためである。どちらかに二分法で答えなさい、どちらでもない・わからないの選択肢を用意してアンケートを取るなど形式的には可能であろうが自分には愚問に思える。
感情移入がなぜ生まれるかと言えば教育の効果が大きいのではないかと思う。「登場人物の気持ちになって考える」は国語や道徳で教えられる (られた、かも知れない) 基本項目であろうが、例えば「ごんぎつね」を読んでキツネの気持ちにもなって考えることができるかを繰り返し教育されるのだろう。登場人物や動物の気持ちになって考えた読書感想文が高評価されるわけである。
あまりにも繰り返し同じような課題が出されるので、いい加減いやになって反対の意味の読書感想文を提出したことがある。読書感想文に丸を付けて返すのがよい教育方法とあまり感じないが、その時はアンダーラインだけが引いてあった。保護者には「世界を滅ぼすような科学者にはならないように」と伝えられたらしい。おそらく抽象的な形で内申書にも書かれたことであろう。このようにして社会的適応度が下がるわけだ。「忖度」が発生するメカニズムとなる。
当時はもちろん犬もセキセイインコも経験を持っていたので生き物の素晴らしさや対等に接することの意義はよく把握していた。読書感想文で感情移入能力を測ろうとするのは間違いだろうと思う。ということを小学生が考えていたとすれば実は恐ろしい (!?)。さすがに高校生ぐらいになるとそのような課題は出されなくなり、厳しいことで知られる国語教師も勝手な解釈も容認するようになった。多様な読み方が認められたというわけだ。
今から考えると小学校の先生は国語を教えるのが得意でなく、定型的にできる仕事は漢字の書き取りをさせるなどで、教科書を読ませて感想を述べさせることで授業を終えていたのではないかと思う。昔は自分は英語を話すこともなく生徒に当てて読ませるだけの英語教師とか、模範演奏を決して示さないピアノ教師とかあったなあと思い出してしまった。今ではもう少し良質になっていると思いたい。
「爪王」ならば鷹匠とクマタカの両方に感情移入するのが文学・道徳的には正しい読み方なのだろうが、作品を味わうには必ずしもその必要はないらしい。クマタカに狩られる動物には感情移入しないのか、などもし問えば「小難しいことを言う」と発想を評価されるよりむしろおそらく減点の対象になる。作者もそこまでは描ききれないわけで、あくまで理想化された表現の世界に過ぎない。
なぜ国語や道徳でそのような技量を養成する必要があるのか何か理由があるような気がするが「忖度」のメカニズムあたりから想像にお任せする。小学校の担任の先生は社会派として知られていて、社会科には非常に詳しかったがここまでは考えておられなかったのではないかと想像する (文系の先生も生物や行動の進化のメカニズムに馴染んでおいた方がよい)。
「タカが小鳥を襲う場合にどちらに感情移入するか」の問いには国語教師も満足な答えを出せない。先生もよい説明の方法がわからないのでそれではみんなで考えてみましょう、先生も一緒に学びます、というのが現代の行き方かも知れない。一見自主性を尊重しているように見えるが、先導役を放棄して限られた枠内で思考を巡らせているに過ぎないことも多い。教育というものはまあこんなものである。
ということで自分はタカにも小鳥にも感情移入はしない。自然をありのままに捉えるならばその方がよい。
捕食・被食の関係を捉える際はこのように考え、生物進化や生物多様性の発展の仕組みに目を向ける方が精神衛生上もよいのではないだろうか。
時に通説に反して弱いとされている種が想像以上に強力であることを見てさすがに興奮することはあるが、これは弱い方に「頑張れ」というよりも、生態に驚かされ、知らなかったことを知った喜びの効果の方が大きい。そしてそのうち通説は単なる先入観の産物に過ぎないことがわかることも多い。見たことを自慢する必要もないし、通説が間違っていることを述べ、なぜそのような通説が生まれたかを考察すれば十分であろう。
観察会などでもまれに捕食場面に遭遇することがあって感情移入された感想が出ることもあるだろう。
そのまま自由に感想を出し合うだけならば「それではみんなで考えてみましょう」と同じようなものである。
昔言われたような「弱肉強食の掟」と説明するか、あるいは生態系のバランスの維持の役割 (などそもそもあるのか知らないが) などと説明するのか、生物進化や生物多様性の発展の仕組みに関心を持ってもらうきっかけとするのか解説者の力量次第ということになる。
「野の鳥は野に」の精神はこの場合どのように適用すればよいのかと聞かれても回答に困る。
発展の仕組みを知らずして「生物多様性は重要」と経文のように唱えるのが適切とも思えない (外来種を持ち込めば生物多様性が増えるのでは、との至極当たり前の疑問に答えるのも難しい)。生物学者がやるべき仕事だろうと思うが、残念ながら本格的な解説は海外書物の訳書に頼る部分が大きくなっていまう。
学者も咀嚼して自分の言葉で伝えればよいのだろうが、その役割を放棄して「これこれを読むとよい」となりがちである。そして読まれずに終わり、いつの時代になっても直感的議論に戻ってしまいがちである。
さて "感情移入" は英語では何と言うのだろうと考えてもあまり適訳がない。近い意味の単語の empathy (共感) があり、これは心理学で研究されている。
Miralles et al. (2019) Empathy and compassion toward other species decrease with evolutionary divergence time の研究があって、他の生物に対する "empathy" は分岐年代が長いほど下がるとのこと。
鳥に対する "empathy" がそれほど低いとも信じがたいのでデータを見てみるとなんと(ヨーロッパ)クロウタドリへの "empathy" しか調べていない。哺乳類は多種調べているのに。研究者がおそらく哺乳類好きで集中的に調べた可能性もあるが、オウムなどのペット鳥を多数サンプルに加えると論文の結論が曖昧になってしまうのではないだろうか。分岐年代が同じでも恒温動物とそれ以外ではおそらく差があるのでは。
生物多様性への知識が豊富な者は "empathy" の程度が統計的に有意な程度は違っているらしい。ただし日本語で言うところの "感情移入" の概念とは必ずしも合致しないので注意して見るべきかも知れない。
Fancovicova et al. (2021) Factors Influencing the Sponsoring of Animals in Slovak Zoos によれば、Borgi and Cirulli (2015) Attitudes toward Animals among Kindergarten Children: Species Preferences のような研究もあって子供はチンパンジーより系統的に遠いオウムやイルカを好んだとのこと。
チンパンジーよりも遊び好きで他者にも好意的な (原文では altruistic 利他的。生態学の論文ではないので生態学で用いられる語義と異なる意味で使われている可能性がある) やオウムやイルカの方が好まれたのではないかとのことで、何だオウムとイルカは同程度に altruistic であることを認めているわけだった。
いずれも心理学的考察なので自然科学のアプローチとはやや違う面がある。ま、いいか。心理学の分野で自然科学で用いられるような統計解析が使われると検証されたように見えがちだが学問分野によってだいぶ違うと見た方がよさそう。
「タカが小鳥を襲う場合」には適用できても「魚が魚を襲う場合」「虫が虫を襲う場合」となるとだんだん怪しくなってくる。生態系を語る場合には感情を媒介にしない方がよろしいということだろう。
"empathy" の wikipedia 英語版によれば結構いろいろな概念があるようで、"compassion fatigue" (感情移入疲れ?) のような状態もあるらしい。「タカが小鳥を襲う場合」などを思い浮かべて悩むのもこの一つに当たるかも知れない。
また "empathy" は文学表現の可能性を拡大したとあり、スーパーヒーローのような話が取り上げられ比較的最近の話のよう。"empathy" そのものは生得的な性質か、学習可能らしいものかなどのレベルでも議論されている。
Paul Bloom は "Against Empathy" (邦訳本なし) の著者で、"empathy" の弊害も指摘しているとのこと。偽りを見抜く能力が低下する、誤った使い方によって悪用されることも可能である (ここでは例えば反ワクチン運動が取り上げられている)。この部分は日本語版でもほぼ翻訳されているが英語版も見た方がニュアンスをより正確に知ることができるだろう。偽情報の拡散の一要因となっているだろうことも想像できる。
「動物の気持ちになって考えよう」は自然保護を語る時に有効な場面もあるだろうが、使い方を誤ると弊害もあり得る。「ツグミたちの荒野」に登場するような表現は一過的にはともかく、自然保護のための普遍的な考え方とはなり得ず、同じように考えると小鳥を襲うタカは悪者か、クジラを食べるのはよくないのかなどあまり生産的でない議論にも用いることができてしまう。それぞれ別の理屈を考え出す必要が生じる。
このアプローチは努めて避けて自然科学的に伝えるのがよいだろう。
コトバンクによると "感情移入" はドイツ語 Einfuehlung の訳とのこと (独和辞書を見ると感入[能力]となって語義説明もあった。一般的に通じる日本語ではなく、訳語が作られた当時でも新しい概念だったらしいことがわかる)。
wiktionary を確認しておくと Johann Gottfried von Herder (18 世紀) や Robert Vischer (19 世紀) が主に起源とされるとのことで想像通り新しい概念で、ドイツ語から輸入とすればそのまま対応する概念が英語にないことが理解しやすい。Konrad Lorenz 由来の "解発因" Ausloeser と似たようなものだった。
wikipedia ドイツ語版には Einfuehlungstheorie のページがある。独和辞書ではリップスの説とある。対応する項目を見ておくと Theodor Lipps (1903) Aesthetik: Schrift Psychologie des Schoenen und der Kunst とのこと。もともとは美学の概念だったが拡大適用されていったらしい。
Nowak (2011) The Complicated History of Einfuehlung には The development of national socialism, numerous Nazi propaganda rallies and the ease with which German civilians involved themselves in the totalitarian machinery showed Einfuehlung theory in the worst possible light.
とあって "感情移入" に拡大された理論は全体主義のプロパガンダに最悪の結果をもたらした、と歴史がすでに示してしまっていたのだった。そのような経緯もあってか、Einfuehlung は wiktionary の本家ドイツ語版に出てこない。もはや問題点の方が多いとの認識となっているのだろう。肯定的に解釈できる部分が empathy と訳されるがそれでも上述のように問題が指摘されている。
まあ考えてみれば算数を学ばせる必要があるのは、別に数学者を育てようというわけではなく、税の徴収をスムーズに行うためとか、もともとはそれぞれに理由があったであろう感じがする。農耕文明が生まれて貯蔵・運搬可能な収穫を得られるようになってこそ可能な話である (なぜハチクマ以前の系統でハチの子があまり注目されなかったのかの話となぜか結びついてしまう)。数字に強い文化圏はそのような社会システムの下で進化しやすい予想になる。
定住生活をすると領域を意識することになり (概念的には鳥のなわばりと同じようなもの)、内か外かの二分法的考え方にもうまくなじむ (そしてそのような文化圏が世界を制したことが現在の国境にも現れていることになる)。ヒトは二分法的思考を好むとしばしば言われるが、これは必ずしも生得的な性質ではなく教育の結果もあるのではないだろうか (例えば #イヌワシの備考 [イヌワシに憧れるインディアンの話] 参照)。
なわばりを持っても全般的に鳥の方が致死的な争いもほとんどなくうまくやっているように見えるのも、我々にとっては生得的な (進化の過程で洗練された) 性質でないことを裏付けているのかも知れない。
鳥の方がうまくやっている、見習うべきだと感じられた場合にはこのような進化的背景も考えると理解が深まるかも知れない。
動物の認知機能の実験でヒトと同じようにカテゴリー化の概念を持っているかしばしば議論されるのも、カテゴリー化の概念に慣れた研究者のバイアスが入っているかも知れない。
あまり意義の見出しにくい英語を学ばせることなどは、高等教育で学べば十分とごく最近まで重要視されなかった理由にもなるのだろう。
さらに深読みのし過ぎかも知れないが、生態系の栄養階層レベルの概念や、高次捕食者にシステムを安定化させる機能があるなどの考え方は支配者にとってはまことに都合のよい概念だったのではないだろうか。
つまり階層構造があってより低い地位のものが高い地位のものを支える。そして高い地位のものが存在するからこそシステムが安定化する (小鳥を襲うタカが悪者でないのは生態系のバランスを保つため、など都合よく解釈できる)。いろいろな場面に都合よく一般化できてしまうわけだ。
オオカミの群れのアルファオスの概念も Schenkel (1947) Expression Studies on Wolves - Rudolph Schenkel, 1947 (英訳版。オリジナルはドイツ語 Ausdrucks-Studien an Woelfen; Gefangenschafts-Beobachtungen) が提唱し、後の研究者が支持する論文を出したのも時流に乗った自然な発想で科学でも使いやすかったのだろう。
後には Mech (2011) Alpha status, dominance, and division of labor in wolf packs 研究者自身が否定的見解を示し、霊長類でもかなり否定的な結果も出されている: Huchard et al. (2025) The evolution of male-female dominance relations in primate societies。
まだ研究進行中の分野で結論は急がない方がよいだろうが、少なくとも従来考えられたほど簡単ではないらしい。もし誤った方向に研究が進んだものであったならば、なぜそのようなことが起きたか検証がなされるだろう。
分野を問わずピラミッド型の絵を見た時は無意識のバイアスを生み出していないか注意した方がよいのだろう。
このような無意識のバイアスは鳥類学の世界でも過去にもいくらも現れていたのではないかと思う。系統の中で高等・下等の序列づけも似たようなものだし (#ミサゴ備考 [猛禽類の分類など] 参照)、ヨーロッパでは歌の上手な鳥が高等と考えられていたため、スズメ目の中では例えば(ヨーロッパ)クロウタドリは上位に置かざるを得ない。
ツグミ科を分けてしまうと形質的にはヒタキ科より原始的なところがあるので、不都合なほど大きな科になっても合わせてヒタキ科とした方が落ち着きがよいと考えられたかも知れないなど。
生態系ピラミッドの上層・下層も研究者が分業する傾向があり、スズメ目専門の人はタカ類をあまり知らない、またはその逆。スズメ目の研究者にとって捕食者は外の世界 (物理ではよく "場" や "外場" の表現を使う) で、スズメ目とタカ類が互いに影響を与えながら進化する発想が浮かびにくいなどいろいろ制約を与えてきた可能性がある。
栄養段階 (trophic levels) が存在することは間違いがないし、生物進化の自然な産物だろう。生物濃縮などを説明するには確かに有用な概念である。しかしそれがピラミッド型の階層性として理想化されて表現され、さらには上位の捕食者の生息基盤がより弱く保護を必要とする論拠とされると違和感を感じる次第である。
生物ピラミッドを図示して保護の必要性を説くのも、「動物の気持ちになって考えよう」同様に気をつけて使うべきで、そもそもそのような意味で保護が必要である概念が成り立っているのか、立ち戻って考えるべきではないかと思う。
[コルヌリン遺伝子を失ったウ類]
ウ類、タカ類、鳴禽類の共通点は何かあるだろうか? Feng et al. (2020) Dense sampling of bird diversity increases power of comparative genomics
によればこの3系統が食道から口腔上皮に関係するコルヌリン遺伝子 (cornulin, CRNN) を失っているとのこと。
この論文では鳴禽類では食道上皮が柔軟になることで複雑な音声発声に役立っている可能性を指摘している。ウ類はいかにも食道が膨れても大丈夫そうだが、タカ類はウ類ほどは丸のみしないので関係あるだろうか (そのうに多量の食物を蓄えられる性質に関係があるかも?)。あるいはこの遺伝子を失ったことが鵜飼を可能にしているのかも?
この論文で用いられている分類では Accipitriformes は新世界ハゲワシ類を含まないヘビクイワシから始まる系統。新世界ハゲワシ類はこの遺伝子を持っている。
ペリットを吐くことにも関係があるかも知れないが、フクロウ類、ハヤブサ目の多くではこの遺伝子が働いているので別の理由かも。ヘビクイワシまで含まれるならば相当古い時期に機能を失ったと考えられるが、半分ぐらいの種で偽遺伝子 (働かない遺伝子) として検出されているのも不思議
(cf. 鳴禽類ではほとんど見つからない。タカ類は鳴禽類より世代が長い、不要となった遺伝子を鳴禽類の方が積極的に除去している可能性などが考えられそう)。
ハヤブサ目ではワキスジハヤブサで偽遺伝子となっているが、近縁のハヤブサも含めて調べられた範囲で他は働いている。
ウ系統では Sula (カツオドリ類) 以降の系統で偽遺伝子 (働かない) となっている。グンカンドリ類以前の系統では存在する。{カツオドリ類 + ヘビウ類 + ウ類} の共通祖先段階で偽遺伝子となったものと思われる (これまで推定された系統関係の正しさもわかる)。
散発的に偽遺伝子となっているものにヤツガシラ、シロチドリ、カンムリカイツブリがある。これらはいずれも近縁種が働く遺伝子を持っているので散発的に生じたものと考えられる
(ゲノムアセンブリ精度次第で単純に検出できていないだけの場合もあると考えられるので、散発例は偽遺伝子が見つかったもののみを扱った)。
鳴禽類では早い段階で失われたようで偽遺伝子すら見つかっていない。最も古い系統の一つであるコトドリ Menura novaehollandiae Superb Lyrebird のみ偽遺伝子が見つかっている。これらは遺伝子が検出されていないものでも系統的に広く検出されないので技術的問題で検出できないのではなく失われたと考えられる。
亜鳴禽類では働く遺伝子が検出されているものが多く、大規模には失われていないよう。
ヒトでも機能があまりよくわかっていない遺伝子だが、鳥類での系統的パターンから機能が判明してくる可能性があるのかも。
コルヌリン遺伝子はピジョンミルクを分泌中のハトで強力に働いているとのこと。Gillespie et al. (2013) Transcriptome analysis of pigeon milk production role of cornification and triglyceride synthesis genes
ピジョンミルクは上皮の keratinocyte (角化細胞) が細胞内に脂肪を蓄えて cornification (角化) することで分泌されるもので、細胞内に色素を蓄えて剥がれる #トキの化粧色のメカニズムにも似ている。
ピジョンミルク生成には β ケラチンが重要な役割を果たしている。哺乳類の keratinocyte は細胞内に脂肪を蓄えることができない点が異なる。β ケラチンを持たない点も異なる。哺乳類の乳腺で脂肪形成に働く遺伝子も大部分働いているがハトで独自のものもある。
ハトでは大部分の脂肪はそのうでその場で合成され、哺乳類との脂肪合成遺伝子の働きの違いはハトの食物に含まれる脂肪の量の違いを反映しているかも知れないとのこと。
鳥類皮膚などの脂肪分泌については #ライチョウの備考 [鳥類と爬虫類のうろこは別物] にも紹介。
[リンの起源]
海鳥のどこかに入れてもよい項目だが、身近なところでリンを陸地に運ぶ重要な役割を果たしている魚食性の身近な鳥のところで紹介しておく。参考: 鵜と上野間小学校。
リンが生命に必須で、しかも陸上では比較的希少な資源であることから枯渇が問題となっていることはご存じであろう。かつては海鳥の糞 (グアノ) から大量にリン資源を得て輸出したものの資源が枯渇した悲劇の物語もよく知られている。
リン酸塩は水溶性が低く、海に蓄積した陸に循環してくるには地球化学的時間がかかり非常に効率が悪い。
海で生物を捕食した鳥が陸に運んでリン循環に大いに貢献している次第である。
海鳥やカワウとは関係がないが、オウギワシで面白い研究があった: de Miranda et al. (2023) Long-term concentration of tropical forest nutrient hotspots is generated by a central-place apex predator
オウギワシはアマゾン森林に生息するが土壌は一般的に低栄養な地域。営巣木周辺の栄養を調べたところ巣の下の土壌は低栄養で、周辺の樹冠部が高栄養だったとのこと。糞が地上に届く前に葉で栄養が吸収されていると考えられる。これはオウギワシが営巣に必要とする巨木に栄養を与える一種の共生となっていると言える。
しかしなぜリンなのだろう。生物を構成している元素は H, C, N, O と水素以外は星が作る元素で、CNO サイクルと呼ばれる元素合成反応があるようにそもそも存在量が多い。それ以上は原子番号が2増える (α 元素と言われる) 反応が中心で原子番号が奇数の元素はもともと存在量が少ない (#オオワシの備考 [鳥類、特に猛禽類の鉛中毒] 参照)。
タンパク質を構成する硫黄 S はこの α 元素で存在量が多い。生命の進化初期に H, C, N, O, S と存在量の多い元素が用いられたのは極めて自然であったが、リン P はリン酸がつながることができる (ポリリン酸など) 特異な性質があるため、ATP, ADP, RNA, DNA といった生命に必須の物質に採用されたものと考えられる (*1, *2)。
なぜリンが採用されたかは化学的特性から理解できるが、リンはどこからやってきたのだろうか。上記のように星の内部ではそれほど多量に作られず超新星爆発でも現在の存在量を説明できるほど放出されない。最近の研究で面白い可能性が浮上してきた。
Bekki and Tsujimoto (2024) Phosphorus Enrichment by ONe Novae in the Galaxy;
リンは新星爆発が生み出した - 必須元素の起源に迫る - (日本語プレスリリース。ただしこの想像図は恐ろしく間違っているのでそのままの印象を残されないように)。
連星の中の白色矮星に相手の星 (この想像図よりもずっと小さい) から降り注いだガスが暴走的に核融合反応を起こす新星 (nova) 現象があるが、白色矮星が酸素・ネオンからなるタイプのもの (白色矮星のなかでも少数) の場合に多量のリンが合成されるとのこと。これらの新星爆発の発生は 80 億年前にピークを迎え、地球で生命誕生が可能となった 46 億年前に間に合ったとの仮説
[新星の解説は 新星とはいったいどのような天体でしょうか (2013 年記事。同サイトの他の記事も参照。命名規則など学名の話とも関係する話題もあり) もどうぞ]。
同時に塩素 Cl も作られることが期待されるが、こちらはまだ観測的には検証されていないとのこと。まだ仮説段階ではあるが、生命を作る元素の起源に宇宙がどのようにつながっているかまた一つ面白い材料が増えた。いろいろな話を知っておくと科学は一層面白くなる。
Taguchi et al. (2023) Spectra of V1405 Cas at the Very Beginning Indicate a Low-mass ONeMg White Dwarf Progenitor
の研究もよいところを行っていたが、連星進化理論との整合性がむしろ問題となっていて宇宙生物学との関連までは意識されていなかった。第3周期元素と聞いたところで思い浮かべればよかったのかも知れない (論文で扱われているアルミニウムとリンは原子番号2違うだけ)。
生物学的視点からは Bekki and Tsujimoto (2024) が扱っている新星よりも Taguchi et al. (2023) の扱ったものの方がさらによい供給源かも。天文学者も生命で何が問題となっているかよく知っておいた方がよさそう。
補足:
*1: 「進化の特異事象: あなたが生まれるまでに通った関所」ド・デューブ [#鳥類系統樹2024] で紹介 でも特異事象として挙げられている。同書 pp. 35-37。リン酸が2個つながったピロリン酸は生物によっては ATP の機能を一部代替しているものがあるとのことで、ピロリン酸は ATP の起源と考えられるとのこと。
火山性環境でみられるポリリン酸をエネルギー源として初期生命が誕生した可能性があるとのこと。
ここで名前の出るもう一つの必須元素である硫黄 S はチオエステル結合を作ることで電子伝達系 (酸化還元、ATP を用いて化学反応を進める) の起源となったと考えられる。硫黄も火山性環境に多い元素で、生命誕生の場としてふさわしい (pp. 62-63)。
鉄 Fe はこの硫黄に結合する形で二次的に取り込まれるようになり、機能の中心が次第に (現在のように) 鉄に移ったものと考えられるとのこと。
鉄は多量に存在するため選択されたこと、d 軌道電子を持つ遷移元素であるため複数の酸化数をとりやすく (Fe 2+/Fe 3+) 電子移動を伴う酸化還元には都合がよかったのであろう。ここでもルイス酸・塩基の特性が現れていると思う (#オオワシの備考 [鳥類、特に猛禽類の鉛中毒] 参照)。硫黄の負イオンは代表的な軟らかい塩基で、鉄イオンは典型元素金属イオンより軟らかい酸のため相性がよい。
銅 Cu にも似た性質があり、いくつかの酵素で用いられている。エビ・カニ・昆虫の一部 等の節足動物、貝の一部やイカ・タコ等の軟体動物に銅を中心とするヘモシアニン (hemocyanin) が呼吸色素として存在する。エボシドリ類の銅を含む色素の由来にも関係するかも知れない。Cu と Fe の原子番号は2違うだけである。
亜鉛 Zn は Cu の次の原子番号だが、これは生体で広く使われているのはご存じの通り。
Fe の次の元素コバルト Co はビタミン B12 の成分で、役割は Fe とは少し違ってメチル基転移を行う。
バナジウム V もホヤが用いていることなど有名。これらの元素はいずれも Fe に近い原子番号のもので、星の進化で比較的作りやすいために採用されたものだろう。
モリブデン Mo は原子番号 42 と Fe よりもだいぶ原子番号が大きく存在量も少ないが、マメ科植物の根に共生する根粒菌の窒素固定を行うニトロゲナーゼ (nitrogenase) が用いているのが有名であり、他にもいくつも酵素が知られている (Mo の起源はオオワシの備考で紹介の s 過程と連星中性子星合体が半々ぐらいと見積もられている)。
もともとは Fe を使っていたのだが、Mo の方がより機能が高いためそちらが選択されてきたのか。
Mo を持つキサンチンオキシダーゼ (xanthine oxidase) は我々も用いていて核酸代謝産物の尿酸合成にかかわっている。他にも生物が用いる金属元素があり、例えば wikipedia 英語版の Metalloprotein などをご覧いただきたい。
生命発生の初期過程で硫黄がこれまで想像されていたよりも積極的に用いられていたらしい証拠: Wehbi et al. (2024) Order of amino acid recruitment into the genetic code resolved by last universal common ancestor’s protein domains
アミノ酸使用率を調べてアミノ酸がどのように使われるようになったかを遡って再構成して現在のコドンの起源を探る。
初期生命は硫黄の豊富な環境で誕生したと考えられ、硫黄含有アミノ酸はこれまで考えられてきたより早い段階から用いられてきたと推定される。宇宙・惑星化学的な知見とも合致する。
この再構成ではトリプトファンやチロシンなどが古くから使われてきた結果となり、一般的なアイデアとは多少異なっている (#アマツバメ備考の [アマツバメやハチドリは夜行性を体験したか?] 備考 *3 参照)。現在使われているコドンと翻訳システム以前の太古の別システムが存在した可能性を示唆するとのこと。しかしこのような形の祖先形質の復元にはさまざまな議論がありそう。
*2: 一昔前、リンを必要とせず代わりにヒ素を使って生きる極限状態の生物が 2010 年に Science に発表されて話題となったことを覚えておられる方もあるだろう。各方面からあり得ないと批判を浴びてきたが、15 年後の 2025 年 Science が撤回に至った。しかし著者は納得していないとのこと: Controversial 'arsenic life' paper retracted after 15 years - but authors fight back (Lauren Wolf Nature news 2025.7.24)。
化学的に見ても安定に存在するはずがない、痕跡量のリンに頼って生存することは可能であるなど。
Science が当初撤回を行わなかったのは明らかな不正行為などの根拠がなかったため。しかしその後基準を変更して主要結論を支持する実験が行われていない場合は撤回に値するとしたもの。
微生物学者の Rosie Redfield は、結論が間違っていることはもはや誰もが知っているが、新しい読者が間違ってしまうことを防ぐために撤回は有益であるとコメントしたとのこと。
論文共著者の1人は実験の解釈はいくつも考えられ、解釈が間違っていることを理由に撤回するのは正しくないと主張。もしその論理が通るならば世の中の論文の半分は撤回されることになるだろうとのこと。
Nature と Science はライバル雑誌でもあり Science 編集部がすぐおかしいと気づいてもよい問題点を認識せず掲載してしまったことや世間の話題に合わせて基準を変えた可能性を暗に批判しているように読める (もしあっても明かされないだろうが、Nature に投稿して reject された可能性もあるかも)。2011 年に Science は反論コメントを8本掲載するとともに著者からの反論も掲載したとのこと。追試に成功しなかった論文を 2012 年に掲載したが本家の論文は撤回しなかった。
2025.2 に The New York Times に掲載された記事によれば、2010 年の研究を率いた研究者はこの研究に対する悪評価のために研究者としての道が制限される結果となったが、再度研究費を獲得したことによって議論が再燃した経緯となっているとのこと。背景事情など詳しいことはこの記事まで読んでいないので不明だが、センセーショナルな発表がただちに否定された場合の影響の大きさも感じることができる。
1996 年 NASA の研究者が火星からの隕石に生命の痕跡発見か、NASA が 2003 年に生命の兆候を示す可能性のある火星大気中のメタンの存在を発表するなど地球外生命がすぐにでも見つかるかのような発表がなされていた時期で、同じく論文著者の所属していた NASA の競争社会の中でよりセンセーショナルな研究が急がれた、あるいは上層部からさらなる発見はないのかと求められた時代背景を思いつくことができる。Nature news は本質的なところを突いていることも多くやはり面白い。
学問にも流行があるので注意して見るべきところはいくらでもあるだろう。
なお話題になった STAP 細胞の論文は Nature に掲載されたものだったが後に撤回された。wikipedia 日本語版の情報によれば 2012 年の投稿論文を Nature 他のトップジャーナルが reject した経験があった。2013 年にメンターが変わって再投稿された論文が受理された経緯だった (このメンターが代わって引き継いだ部分が非常によくわかってしまうが本筋とは関係ないので省略しておく)。不審な部分があれば Nature が前年の投稿の時点で気づいていても不思議ではなかった。
[鳥類の窒素排泄・栄養状態ストレスとの関係]
尿酸合成から糞の話に戻ると、爬虫類や鳥類では窒素を尿酸で、両生類 (成体) や哺乳類は尿素、さらに魚類ではアンモニアで排泄する違いがある (いずれも大雑把な話) ことはよく知られている。生化学機構は Raidal et al. (2007) The Advantages and Disadvantages of Excreting Uric Acid
の解説がわかりやすい。尿素合成の回路は哺乳類でも同じだが、多くの哺乳類はさらにより無害なアラントインまで酸化するとのこと。
哺乳類でも霊長類やイヌのダルメシアン (Dalmatian) 品種は最後の段階の酵素を失っていて尿酸を排泄するとのこと。鳥類も同じ酵素を欠いている。
一部の霊長類は尿酸の抗酸化能力によりビタミン C の合成能力を必要としなくなった (直鼻猿亜目) 話もある (#クロハゲワシ備考の [猛禽類の植物食] でも少し触れる)。
鳥類で尿酸が酸化ストレスで酸化され、アラントインとして排泄されることも知られている [cf. Tsahar et al. (2006) The relationship between uric acid and its oxidative product allantoin: a potential indicator for the evaluation of oxidative stress in birds]。
これは抗酸化物質として消費された証拠となる。
アンモニアの解毒回路は鳥類と哺乳類で多少違っていて、鳥類では主に哺乳類ミトコンドリアで働いている Carbamoyl phosphate synthetase I (CPSI *1)
の代わりにグルタミンシンテターゼ (グルタミン合成酵素) glutamine synthetase が同様の役割を果たしているとある
[参照: Stern and Mozdziak (2019) Differential ammonia metabolism and toxicity between avian
and mammalian species, and effect of ammonia on skeletal
muscle: A comparative review および参考文献]。
アンモニアを代謝する最初の主なステップが異なり、後はどちらにも存在する代謝経路で尿素になったり尿酸になったりする模様。
しかし鳥類にも尿素回路の酵素は存在していて、ある種の鳥では低温環境でよりエネルギーの必要な尿素合成を節約して尿素排泄が増えるとのこと。さらに水分が十分あればハチドリ類は半分近くをアンモニアのまま排泄できるという (ハチドリ類は食物に水分が非常に多いため、尿もあまり濃縮する必要がない)。鳥類・哺乳類の絶対的な違いというよりある程度相対的なものらしい。
ヒヨドリ類では水分を多量に摂取している場合はアンモニア排泄が中心になるとのこと: Tsahar et al. (2005)
Can birds be ammonotelic? Nitrogen balance and excretion in two frugivores (アラビアヒヨドリ Pycnonotus xanthopygos White-spectacled Bulbul で調べられたもの)。ハチドリ類だけの特技ではなかった。
尿酸は排泄物であると同時に抗酸化物質でもあるので、余分な窒素を他に捨てる経路があるならば尿酸を再吸収して利用している可能性があるとのこと。
そういえば捕食者のない地上性の離島の鳥でアンモニア臭があるものがあるらしいが、もしかしてアンモニアも排泄していないだろうか。
2023 年の伊吹山のイヌワシ子育て生中継で餌がほとんど運ばれず、猛禽類は何日絶食できるか ML Kbird で話題となった (スタッフによる介入直前ぐらいの段階)。その時に調べた文献から紹介:
Ferrer and Dobado-Berrios (1998)
Factors affecting plasma chemistry values of the Spanish Imperial Eagle, Aquila adalberti
のスペインカタシロワシの研究によれば、栄養状態が悪いと尿素 (尿酸も) の血中濃度が際立って高まるとのこと。絶食によって自身のタンパク質を異化した代謝産物であると考える文献を引用している。再度タンパク質の豊富な餌を与えられるとこれらの高い値は正常値以下に下がる。
ちょっとかわいそうな話だが、ヨーロッパノスリの人工的飢餓実験があるとのこと。
Garcia-Rodriguez et al. (1987)
Metabolic responses of Buteo buteo to long-term fasting and refeeding
この実験では 13 日間の絶食で7羽での実験。この実験でも尿素 (尿酸も) が急上昇してゆくとのことで、種による違いがあってペンギンではそうならなかった (ペンギンでは絶食がそもそもライフサイクルの中に入っていて、より効率のよい脂肪燃焼で絶食期を過ごす。食物不足時の猛禽類とペンギンでは戦略がそもそも違う)。
猛禽類ではタンパク質を異化することでエネルギーをまかなうらしい。血中タンパク質量は大きく減らなかったがグロブリンが減ってアルブミンが維持された (アルブミンが栄養を体に送るのに働いている。グロブリンが減ると免疫能力は低下するかも知れない)。
13 日めには血中グルコースが上昇。長期絶食で血糖コントロールシステムが緩んだ (変調をきたした) 可能性がある。この実験では (正常状態の個体で飼育環境で管理されている) 13 日の絶食に耐えることが示された。その後正常に食物を食べることができたとのこと。
これらの研究でなぜ尿素が急上昇したのか昨年のイヌワシ子育てライブの時点では気づかなかったが、上に示したような窒素排泄経路を考えると納得が行く。エネルギーの必要な尿素合成を節約して尿素に回すことになったのだろう。尿素排泄には尿酸より多くの水分を必要とするため、伊吹山のイヌワシひなのように水分もとれない状況では排泄できず尿素濃度が高くなって中毒になるだろう。
Spee et al. (2010)
Should I stay or should I go? Hormonal control of nest abandonment
in a long-lived bird, the Adelie penguin
アデリーペンギンではタンパク質を燃焼させる段階に入ると抱卵放棄すると考えられていた。
この文献ではそれだけが要因ではなくて、プロラクチン (哺乳類では乳汁分泌作用のあるホルモンでこの名前が付いた) 濃度が低いことと組み合わさると放棄することになるとのこと。
伊吹山のイヌワシも両親が食物不足でタンパク質を燃焼させる段階になると育児放棄が発生しやすくなるのかも、などの議論をしていた。
Angelier and Chastel (2009)
Stress, prolactin and parental investment in birds: a review
栄養状態のストレスでプロラクチンレベルが下がる (これは個体の生存を考えれば適応的な反応) ので、栄養状態でプロラクチンレベルも介して抱卵 (育児も?) 放棄につながる関連が読み取れる。
Riou et al. (2010)
Stress and parental care: Prolactin responses to acute stress throughout the breeding cycle in a long-lived bird
海鳥でよく調べられていて、子育ての間はプロラクチンレベルは高いまま、とのこと。
ストレスに対してプロラクチンレベルが下がる反応は抱卵時には弱い (俗な言葉で言えばたとえば母性本能が強いように見える)。ひなを育てる時期の後の方にこのストレス反応が高まる (育児放棄が起きやすい)。これは渡り鳥の研究なので、親自身の生存可能性を高めるための反応と考えれば理解できるかも、とのこと。
備考:
*1: 尿素回路またはオルニチン回路 (ちなみにオルニチン ornithine の名前は 1877 年 Jaffe にニワトリの糞から発見されたことに由来する) よりに入る手前の反応に関わる酵素。
ニワトリのゲノム解析の結果では CPSI 遺伝子は失っていないが、ミトコンドリアに輸送するための補因子 (cofactor。両生類や哺乳類でアロステリックに酵素活性を補強するように働く) となると考えられる N-acetyl glutamate synthase (NAGS) の遺伝子は失っており、哺乳類のような機能は果たせないとみなされている。
このため生成されたアンモニアはグルタミンシンテターゼによる尿酸生成に向かう。ニワトリでは尿素回路の遺伝子は発現しているが弱いとのこと。
Wertman (2012) Poultry Evolution: A Concentration on NAG, CPSI and the Urea Cycle および wikipedia 英語版を参照した。
Haskins et al. (2008) Inversion of allosteric effect of arginine on N-acetylglutamate synthase, a molecular marker for evolution of tetrapods
にも考察があり、ニワトリに CPSI や ornithine transcarbamylase (OTC 尿素回路でオルニチン + cambamyl phosphate からシトルリンを合成する酵素) があるのは、祖先が尿素排出をしていた名残りであろうとしている。爬虫類でもワニ、トカゲ、ヘビで CPSI が失われているがカメには存在するとのこと。
NAGS が CPSI に対してアロステリックに働くかは条件次第で、働かないものもあるらしい (哺乳類での働きから想像されているものなので必ずしも必須ではないかも知れない)。鳥類では CPSI, OTC 遺伝子は存在するので効率は悪いが尿素合成の回路は持っているということか。前述の例を見ると条件次第で使っているかも知れない。
NAGS 遺伝子はアルギニン代謝に関係しており、NAGS を持たないことはニワトリの餌のアルギニン必要量と合うとのこと。
CPSIII は魚に存在し、陸上生活に伴って CPSI に役割が入れ替わった。これは脳に対するアンモニア毒性を素早く取り除くのに役立ったのだろうとのこと。
なお、ヒトの尿酸は窒素代謝物というより核酸代謝物である点は異なる。腎臓以外に腸管でも行われる。
大内他 (2015) 尿酸代謝異常 にも参考情報あり。
尿素回路またはオルニチン回路はハンス・クレブス (Hans Krebs 原語読みではクレプスとなる。クレブスは英語読み)
が発見した回路の一つで、1932 年に、1937 年のクエン酸回路 (TCA 回路) に先駆けて発見されたもの。後者が一般にクレブス回路と呼ばれる (1953 年 ノーベル生理学・医学賞)。
Krebs はさらに2種類の回路を発見しており glyoxylate cycle (グリオキシル酸回路 Krebs and Kornberg 1957) そして尿酸サイクル
(Mapes and Krebs 1978 Rate-limiting factors in urate synthesis and gluconeogenesis in avian liver; グリオキシル酸回路を共同発見した Kornberg は Kreb の発見した回路は3つと数えていて、忘れられたクレブス回路とも言われる)。
代謝経路にはこのように冗長性があるため、尿素排泄から尿酸排泄への進化は比較的簡単に行えたのだろう [#鳥類系統樹2024] 紹介の Ng et al. (2023) も参照。
[ウの舌は痕跡器官か]
Jackowiak et al. (2006) Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the cormorant Phalacrocorax carbo (Phalacrocoracidae, Aves)
舌腺は見つからず通常の鳥のように舌体部が発達していない。舌全体が繊維質の結合組織となっていたとのこと。
位置や構造的にも痕跡器官と言えるとのこと。同一著者による研究ではオジロワシの舌は舌腺も発達しているとのこと: Jackowiak and Godynicki (2005) Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the white tailed eagle (Haliaeetus albicilla, Accipitridae, Aves)。
ウは実際に丸のみと言ってよさそう。
[ガラパゴスコバネウの進化]
Burga et al. (2017) A genetic signature of the evolution of loss of flight in the Galapagos cormorant
が飛べないガラパゴスコバネウ (現在通常使われる学名は Nannopterum harrisi。この属名は新大陸のグループで、Phalacrocorax 属にまとめて構わないとの見解もあり扱いが多少分かれている) Flightless Cormorant (Galapagos Flightless Cormorant)
の形態にかかわるメカニズムを解析している。和名は単にコバネウが使われたこともあった。
200 万年前ぐらいに大陸から定着したことは分子系統解析からも裏付けられた。
渡る必要がなくなったため潜水機能を強化する方向に選択圧が働いたと考えられる。
偽遺伝子化の証拠は見つからず、形態変化をもたらした遺伝子変異候補が挙げられている。細胞の繊毛 (cilia、シリア) に関係する変異が関与している可能性があるとのこと。
島の鳥が飛翔力を失いやすいことについて「鳥もできれば飛びたくない」と比喩的に説明されることもあるが、適応のための他の選択圧が働く中で重要でない飛翔能力を失ったり、遺伝子ネットワークの変化で他部位の適応のために二次的に飛翔にかかわる機能が変化した可能性もあるだろう。
「できれば飛びたくない」はあまり適切な比喩ではない感じがする。遺伝子ネットワークがどのように形質を決めるかは未知の部分が多く、この論文でも示唆するにとどめている。何かの遺伝子が失われて飛べなくなったような簡単な描像ではない。
飛翔能力の喪失とそれに付随する形態変化について新しい研究があった: Saitta et al. (2025) Feather Evolution Following Flight Loss In Crown Group Birds: Relaxed Selection And Developmental Constraints
(prepeint; 一般向け解説)。
Saitta の本来の専門は古生物学で恐竜などをよく調べていたが、鳥の標本の大規模コレクションを目にして感銘を受けこの研究を行ったとのこと。
飛翔能力を喪失した鳥の形態と喪失年代の関係を広い範囲で調べた。無飛翔化に伴って骨格のような大きな構造の方が先に変化し、風切羽の非対称性が失われるなどの羽毛の変化はより遅く生じる。
つまり古い時期から飛翔能力を喪失していた鳥 (ダチョウ、ペンギンなど) は羽毛の微細構造にも大きな変化があるが、比較的近年飛翔能力を喪失した鳥ではまだ変化が小さい。飛ばないことによる構造への選択圧が弱まる (relaxing selection) ことが原因。
相対的には羽毛に比べて骨格の方が高コストなので骨格の方への選択圧 (例えば同種内競争で大型化するなど) の方が先に強まり、選択圧が弱まることによる飛翔のための羽毛の変化は後回しになるとのこと。
羽毛の構造の特性がどのような順序で失われるかは、系統的に新しく獲得された形質が発生学的制約 (例えば複数の遺伝子が関与し、段階的に複雑なプロセスで作られるもの) から早く失われる効果が現れている可能性が考えられる。
複雑ネットワーク的な解釈では、限られた数の遺伝子の制御機構を調整することでたまたま特別な形質を作るルートに到達 (発見) したがそれには時間がかかった。しかしひとたび必要がなくなると制御機構の維持に選択圧が働かなくなってその機構が失われてしまいやすいのだろう。
計算機に例えればさまざまなアプリケーション (ライブラリ) を組み合わせて作ったシステムのようなものだろうか。そのアプリケーション (ライブラリ) がバージョンアップされると機能を喪失したりする例は我々もよく体験する。そしてそのようなシステムの維持にはコストがかかるので、リストラなどでメンテナンス費用や人手の優先順位が下がると簡単に失われ、同様の機能を復元するのは多くの場合困難。結局忘れられてゆく。
R なり python なりバージョンが上がるたびに動かなくなるライブラリを体験されている方にはわかりやすいだろう...と話がすぐ明後日の方向に行きがちなので生物の話に戻ろう。
もっと簡単に実現され得る形質はそれらの変化に強く、より遅くまで残るのだろう。
後の系統で獲得された微細構造 (例えば青色の構造色) が競争が弱まるなど不必要になった場合、失われるプロセスなどの解釈にも応用できそう (#オオルリ備考の [オオルリはなぜ青い] 参照。オオルリを含む系統では性的二形を示さないものも多い。また青色は比較的新しい時代に獲得された形質)。
例によって途中から自分の解釈も混ざっているので (失礼)、詳しくは原文を読んでいただきたい。
それでは我らがカンムリワシはなぜ小さいのか多少気になってくる。飛翔能力を喪失した鳥ではないが、あまり移動能力を必要としなくなれば骨格の方への選択圧が高まって大型化はしないのだろうか。タカ類では飛翔能力は重要で飛翔力の維持に選択圧がかかっていることが想像でき、大型化する方が飛翔面の能力維持が難しくなるかも知れない。
日本のカンムリワシでは競争相手の種がほとんどいないので小型化の方に向かったのか? 小さい方が小回りがきいて獲物が捕れる?
このように考えるとタカ類では同種内より他種との競合の方が体サイズの選択圧となっている印象を受ける。大陸や台湾のカンムリワシが大きいのはクマタカ類など競争種がそこそこいるため?
日本のイヌワシが小さいのは有力な競争相手がいないため? 他所でも考察したがクマタカが大きいのはイヌワシのいる地域に進出したため?
タカ類では同種内競争は大きくなる方に働かないのか - 逆性的サイズ二型の説明にも関係するかも知れないので検討してみていただきたい。
なおガラパゴスコバネウの遺伝的多様性は低く、創始個体群も小さく、現在の個体群も小さいことも反映していると考えられるとのこと。wikipedia 英語版によれば 1983 年のエルニーニョ現象で個体数が半減して 400 個体まで減少したとのこと。IUCN EN 種だったがかつての見積もりほど個体数が少なくないと判明し、2011 年に VU 種に変更。
雑誌 "Birder's World" 1989.12 pp. 64-65 に Robert W. Storer による "The Flightless Cormorant" の記事があり、ガラパゴス島にはタカとフクロウがいるがガラパゴスコバネウを食べるほど大型でない。しかし小型の飛べない鳥の進化には影響を与えたかも知れないと興味深い考察があった。
当時はまだタカの方が先住者と思われていたようだが現代の理解では逆で、ガラパゴスノスリはアレチノスリから 30 万年前に分岐したばかりでアレチノスリの亜種とみなせるぐらい (#ノスリ備考 [Buteo (ノスリ) 属の系統分類] 参照)。
飛べないウの方が先に進化していた。ウ類は大型化する方がおそらく有利で (#ミサゴ備考 [ミサゴは不器用?] 参照)、飛翔能力を失う方への進化は起きやすいかも知れない。猛禽類の有無にかかわらず生理学的には小型のウの方がむしろ考えにくいかも。そもそも大型の鳥由来であったため創始個体群も小さかったのだろう。
ウ類も身近なカワウが系統の典型的な種と考えるよりも、体を水に沈めるヘビウ科の方が本来形質がよく現れているかも知れない。ペリカン目も大きな鳥がとても多い。
飛翔能力を失ったペンギン目がそれほど遠い系統でないのも、飛べないウと同じような生態的制約や進化機構が働いているのでは。
[ミサゴは不器用?] で "ウ類が羽を乾かしているように見える行動も、次の狩りまでの間隔が短いため羽の状態を急いで整えていると考えればミサゴの「足洗い」と同様の意義があるのかも知れない" と触れてみたが、これは早い話無駄な待ち時間とも言える。飛ぶ必要がないなら翼のメンテナンス時間を最小にすべき方向に進化するのが自然では。もしこの解釈が成り立つならば、副次的に飛ばなくなると考えるよりも、ウ類では捕食者のない環境では翼をなるべく持たない方が適応的な形質と言えるのだろう。
ウ類の尾が短いのも制御に必要な最小限度を残して尾のメンテナンスの手間を節約しているのかも。
ミサゴも海鳥もそうかも知れないとかふと感じた。航空力学的要請とどちらが上回っているだろう。
ウ類についてのこの部分の自分の発想は Saitta et al. (2025) とは少し異なって、飛ばないことによる構造への選択圧が弱まるのではなく、ウ類では翼や羽毛の構造を維持する遺伝部位に負の選択が生じているのではとの考え。
Saitta et al. (2025) は走鳥類も含めた全体をまとめて扱っているが、ウ類 (およびおそらくペンギン類) における翼の飛翔機能の喪失と走鳥類における意義が違っているならば同列に扱えない可能性もあるかも知れない。
ここではガラパゴスコバネウは進化の中間段階を表す位置づけとなっているが、積極的な負の選択圧がかかっているならばそうでない系統より進化が早いかも知れない。
微細構造についても濡れた時のメンテナンスに要する時間を短くする構造が進化しているかも知れない。風切羽の構造に興味が向かいがちだろうが、ウ類の尾の粗雑さを考えるとこちらの構造も調べると面白いかも。興味ある方はご検討を。
Robert W. Storer (1914-2008) は鳥類学者で当時ミシガン大学の名誉教授。"Birder's World" の "Avian Exotica" コーナーの常連執筆者だった。雑誌も創刊 (1987) されて間もなく、執筆陣も大御所が揃っていて鳥類学を一般にわかりやすく伝えるなど非常に読み応えがあった。当時はまだそこまで理解できていなかったが今読み返すと改めて意気込みに感心する。
川口 (2019) Birder 33(2): 52-53 では (飛べない鳥である) ダチョウ、カグー、ガラパゴスコバネウはどの風切羽もほぼ対称だ、とあるのでカグーの写真を調べてみた。
Kagu (Bruce Robinson 2005.10.2) あまり対称とは言えない気がするが...。
そう思ってみると Saitta et al. (2025) もカグーは調べていなかった。標本が手に入らなかったのか、近縁種が少ない (ジャノメドリのみ) ためか。カグーの wikipedia 英語版によればニューカレドニアに定着したのは 6000-2500 万年前と見積もられていて、捕食者がないため飛翔能力を失ったと書いてある。
timetree.org によるカグーとジャノメドリの分岐年代推定は 3400 (2900-4100) 万年前とのこと。
このぐらいの数字を想定すると、Saitta et al. (2025) で用いられたダチョウの祖先が飛翔能力を失ったのは 7958 万年前 (Yonezawa et al. 2017) と桁がそれほど違わない。Saitta et al. (2025) では比較対象に南半球の飛べないカモ Tachyeres pteneres を挙げていてこちらは 1.5 万年前と非常に最近 (Fulton et al. 2012)。
ガラパゴスコバネウが上述のように 200 万年前ぐらいなので、論文の論理に従えばカグーの風切羽はもっと対称であってもよいのだ。それを考慮すると結論が怪しくなるので (飛翔能力を失ったのがいつかわからないとも言えないこともないので) カグーは比較対象から除いた可能性もあるのかも知れない。
カグーの風切羽はジャノメドリ同様にディスプレイのために非対称な形質が有利なため、と説明できるならば、非対称な風切羽は飛翔能力を示すとも言い切れないわけだ。
[鵜翼を濡さず]
河田聡美 漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 大修館書店 1989 p. 127 から。小人が政府の要職に就いていることの異常さをたとえた言葉とのこと。「ていよくをぬらさず」と読む。まあ古くからよくあったらしい。
「詩経」曹風「候人」の一節。日本語解説では 候人 (引用1: 小者が握る実権) (崔浩先生の「元ネタとしての『詩経』」講座)。
注釈付き原典は例えば 候人。中国の "鵜" は我々が使う "ウ" よりも広い意味に使われていたらしい。
現代の分類だと ペリカン目 Pelecaniformes なのか カツオドリ目 Suliformes なのか、それとも全部まとめて Pelecanimorphae と呼ぶべきかややこしいことにもなる。
-
ウミウ
- 学名:Phalacrocorax capillatus (パラクロコラックス カピルラートゥス) ふさふさした髪の生えた (例えば彗星の尾を思わせるような) 頭の白いワタリガラス
- 属名:phalacrocorax (合) 頭の白いワタリガラス (phalakros はげ頭の、頭の白い < phalos 白い korax ワタリガラス Gk)
- 種小名:capillatus (adj) 髪の豊かな (capillus (m) 髪の毛 -atus (接尾辞) 〜が備わっている); 棘毛の多い (愛媛の野鳥「はばたき」); 比喩的に彗星の尾を想像するとよい (備考参照)
- 英名:Japanese Cormorant
- 備考:
phalacrocorax は#カワウ参照。
capillatus は2つめの a が長母音でアクセントもある (カピルラートゥス)。所有の -atus 発音に由来。
単形種。
原記載 Carbo capillatus Temminck and Schlegel, 1850。Holthuis and Sakai (1970) によれば 1849 が正しいとのこと。
別の図版。
当時の属名は Carbo でカワウをタイプ種とする属を指していた。Temminck and Schlegel は Carbo filamentosus (フィラメント状の意味) の別学名でも紹介しており、
Le Cormoran Chevelu. Carbo Filamentosus. Pl. 83, en plumage d'amour ... Habit de noces: ... Dessus de la tete et partie superieure du cou garnis, outre le petit plumage noir, de plumes plus longues, soyeuses ou filamenteuses et d'un blanc tirant au jaunatre.
と記載している (The Key to Scientific Names)。
これから派生した学名 Phalacrocorax filamentosus も使われていたが、現在は通常こちらがシノニムとされる。
Temminck and Schlegel の Fauna Japonica (1850) の同じ文献で filamentosus の方が本文中、capillatus は図版に用いられており、図と本文で学名が違うことになる。どちらを用いるかおそらく見解が分かれていたらしく、Dement'ev and Gladkov (1951) は前者を採用している。
現在の世界のチェックリストは capillatus を用いているが、2000年以降の論文でも Phalacrocorax filamentosus の学名が使用されているものがある。
例えば越智・綿貫 (2008) ウミウの採餌トリップ長の個体変異が繁殖成績に及ぼす影響 のように日本鳥学会誌でも用いられていたので、少なくとも当時はこの学名も普通に用いられていたものと考えられる。
H&M4 vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2 の解説によれば、Morioka et al. (2005) が capillatus を選択したが、Mlikovsky (2012) The dating of Temminck & Schlegel's Fauna Japonica: Aves, with implications for the nomenclature of birds
によれば図版の方が本文より先に出版され、capillatus にそもそも先取権があるため、特にどちらを選択するかを考える必要はないとのこと。#ノジコではこの関係が逆転しており、それほど自明な状況ではなかった。
現在の属名に含まれる phalakros "はげ頭の、頭の白い" と種小名の "髪の豊かな" が矛盾するように見えるが、これは原記載時に使われた Carbo 属より先取権のある Phalacrocorax Brisson, 1760 に変更されたことも要因の一つであろう。
Temminck and Schlegel の記載では頭の羽毛が伸びて「フィラメント状」(英語ならば例えば thread に対応) になっていることを意図していたと考えられ、capillatus を「髪の豊かな」とする訳は少しニュアンスが異なるかも知れない。
英語で毛細血管や毛細管を示す capillary も同じ語源で「毛のような」の意味から発したもの。もとは capillus (指小形) < caput (頭) なので、「頭の羽毛に特徴がある」ぐらいの意味に訳してよいかも知れない。
記載時のフランス語名に使われた chevelu は辞書訳では "ふさふさした髪の生えた" の意味。cheveu が髪の毛。名詞の chevelure が彗星の尾に使われることや、中世の絵画での髪の生えたような彗星の描写などを想像すると "フィラメント状の" 以上に何を意味していたかわかりやすい。繁殖期の羽 (plumage d'amour) の頭の羽毛が彗星の尾のように見えた。なるほどと思ってしまう。
ちなみに彗星の広がった頭部を学術用語で "コマ" (coma) と呼ぶ。光学の "コマ収差" (coma / comatic aberration) も語源は同じでギリシャ語 kome から (彗星を指す英語の comet も同一語源。英語の coma には別語源の "昏睡" の意味もある)。
これはギリシャ語でもともと髪の意味で#おまけ: 星座名と共通の学名に登場する Coma Berenices (かみのけ座。意味は "北の髪" だが対応する "南" があるわけではない) に登場する。
この星座はかみのけ座星団 (かみのけ座銀河団ではない。Coma Cluster の名称は普通こちらを指す) と呼ばれる散開星団 Melotte 111 があり、ちょうど肉眼の限界に近い程度の暗い星が集まっているものを髪の毛に喩えたもの。古い星座絵にも髪の毛が描かれている。
ウミウの頭にみられるちょうどこのように細かい星のような白い羽毛を同様に髪の毛に喩えたと考えると理解しやすいように思える。
かに座にあるもう少し暗い星からなる散開星団 M44 (プレセペ星団) は英語では Beehive Cluster (蜂の巣星団) と呼ばれ似た発想も面白い。
カワウの亜種とされたこともある。
英名は Temminck's cormorant とも呼ばれる。
Moores (2015) Identification Challenge: Korea's Cormorant Conundrum によれば分布を考え、またほぼ日本固有とされるカワウ亜種 Phalacrocorax carbo hanedae があるので英名の Japanese Cormorant はあまりふさわしい名前でなく、Temminck's cormorant の方がよいのでは、とのこと。
海外の名称を見て見ると多くが "日本の" を付けている (英名からの翻訳か)。ロシア語では "日本の" とともに "ウスリーの" の名称もある。中国語では 暗背 のウ (中国語のウの漢字は難しい) または 丹氏 (Temminck) を冠している。"日本の" の付いた中国名もある模様。
フランス語では Cormoran de Temminck になっている。
[カワウとウミウの関係]
Young Guns (2016) Birder 30(5): 44-47 にカワウとウミウの識別がある。
この記事によればヨーロッパ北部のカワウにウミウに近い遺伝子型があり、亜種が提案されているとのこと。これは Marion and Le Gentil (2006)
Ecological segregation and population structuring of the Cormorant Phalacrocorax carbo in Europe, in relation to the recent introgression of continental and marine subspecies
(出版社サイト)
で、カワウの亜種 sinensis とヨーロッパの亜種はよく分離されるが、ヨーロッパの亜種は北部・西部の2系統があって、西部のものは本来のカワウの基亜種 carbo であるものの、北部はウミウに近く、氷河期に大陸東西に分離されたものの遺存の可能性を示唆している。この個体群はほとんど渡りを行わないとのこと。
この文献では同個体群にカワウの亜種 norvegicus を提案しているが、世界の主要リストでは carbo のシノニムとされている。
IOC 15.1 のコメントによれば The population of P. c. carbo from the northern part of its range in Norway, and along the coasts from Sweden to Brittany has been named P. c. norvegicus by Marion & Le Gentil (2006), but lacks a formal description and must be regarded as a nomen nudum
とのことで、独立したタクソンになることは考えられるが、正式な記述が行われていないので現状無効名の扱いとのこと。
Sangster and Luksenburg (2023) The importance of voucher specimens: misidentification or previously unknown mtDNA diversity in Phalacrocorax capillatus (Aves: Phalacrocoracidae)?
は Honda et al. (2022) Complete mitochondrial genome of the Japanese Cormorant Phalacrocorax capillatus (Temminck & Schlegel, 1850) (Suliformes: Phalacrocoracidae)
が解読したウミウとされる (2010 年青森市で救助されたが死亡した) 個体のミトコンドリアゲノムがカワウグループに属することを示した。これがこれまで知られていない日本における遺伝子浸透の結果なのか種名の誤りなのかは検証のための標本 (voucher) が残されていないため判定できないとのこと。Honda et al. (2022) の系統樹でもカワウとほとんど差がないことが示されていた。
Ochiai et al. (2020) Genetic variation of mitochondrial DNA in Phalacrocorax carbo in Japan に日本のカワウ個体群の遺伝構造の解析があり、カワウの他亜種と共通のハプロタイプがあって遺伝的には carbo と日本のカワウを分離できないとのこと。ノルウエーの個体群の場合とは異なる。
地理的障壁の証拠もほとんど認められないとのこと。解析の外群にウミウのサンプルが1つ含まれているがカワウと分離できないかも知れないレベルの違いとなっている。
wikipedia 英語版ではウミウはカワウと Ecologically separated from P. c. hanedae, more strictly marine, rarely inland の関係としてカワウの亜種一覧に完全を期すため含まれている (2025.4 時点)。
IOC 15.1 のコメントでは The phylogenies of Kennedy & Spencer (2014) and Kennedy et al. (2020) suggest that P. carbo may be paraphyletic with respect to P. lucidus and P. capillatus, with P. c. sinensis and presumably P. c. hanedae in a clade with P. lucidus, while P. capillatus is sister to other taxa of P. carbo.
However, P. capillatus is sister to both P. c. carbo and P. c. sinensis in the phylogeographic study of Marion & Le Gentil (2006).
とあり分子遺伝学的にはまだ結果が固まっておらず、ウミウはカワウが単系統の関係にならない研究結果も示唆されている。
核ゲノムなどが詳しく調べられるとハシボソガラスとズキンガラスのような関係になるのかも知れない。
日本近海にのみ生息するウミウは世界的に見れば準固有種に近いので成り立ちを検討しておく。似た地域に生息する Urile 属も合わせて検討することが望ましいので、
MN356399.1 (ヒメウのミトコンドリアゲノム) から出発して BLAST をやってみると、Urile 属が Phalacrocorax 属に対して古い分岐であることがわかる (現在使われるリストの配列順にも相応している)。
ウの仲間の祖先系統が東アジアの比較的北部に分布を広げたことが想像できる。系統的には Urile 属とは異なるがウミウも同じ議論の延長で捉えることができそうである (ウミウのミトコンドリアゲノムは上述のような問題がありこの解析からは省いてよい)。
その後誕生した Phalacrocorax 属の新しい系統は主に淡水・地上環境に適応して分布を広げたがカワウの競争力が特に強かったため、古い系統である Urile 属が地上に分布を広げることを困難としたが、これらの系統がオホーツク海沿岸の厳しい気象条件にも耐え得る仕組みを獲得していたためこの地域の海岸沿いでのみカワウより優位に立てたと考えると納得できる気がする。
状況はオオワシとオジロワシの関係に似ている気がする (#オジロワシ備考の [オジロワシ属の系統分類] 参照)。
カワウの中でさらに優勢なのが亜種 sinensis で、ヨーロッパ東部まで勢力圏となっている。このような描像のもとでは東方にも勢力を拡大していても不思議でなく、#カワウの備考で検討されているように、カワウの hanedae と sinensis は同一タクソンとみなした方がよい意見にも多少賛同したい気がする。
hanedae の方が少し小型であるが、サイズと遺伝的差異の間の関係は必ずしも自明でない (イヌワシの日本と大陸亜種の関係など)。
Kennedy et al. (2019) The phylogenetic placement of the enigmatic Indian Cormorant, Phalacrocorax fuscicollis (Phalacrocoracidae) の系統樹を見るとウミウはカワウの亜種でも構わないように見える。識別が難しいと言われるが亜種レベルの識別を行っていると思えば納得しやすい。
我々も習った時点の分類がカワウとウミウを別種とするものでそのように考えているが、ウミウはヨーロッパの carbo と同じようにカワウの海岸沿い亜種だと習っていればそのように扱っていただけかも知れない。
Urile 属とカワウの中間に位置する系統にヨーロッパヒメウ Gulosus aristotelis European Shag (ヨーロッパ沿岸部) やミミヒメウ Nannopterum auritum Double-crested Cormorant (アリューシャン列島を通じて北米に分布) があり、かつては Urile 属同様に Phalacrocorax 属にまとめられていた。
カワウの系統が温暖な地域出身で、Urile 属の系統が比較的低温環境に適応したためベーリンギアを通じて北米まで分布を広げることができたとも言えるのだろう。
絶滅種にメガネウ (ベーリングシマウ) Urile perspicillatus Spectacled Cormorant / Pallas's Cormorant がありカムチャツカ半島東 200 km のコマンドル諸島に分布。Steller によればカムチャツカ原住民の方法で調理すると美味だったとのこと。発見当時は多数生息していたとのことで、コマンドル諸島唯一の哺乳類捕食者のホッキョクギツネが到達できない海岸の崖に営巣していたとのこと。
直接的には羽毛採取、捕鯨基地としての活用、ホッキョクギツネの養殖のために絶滅したとのことで、標本は7体が残るのみ。最後の目撃は 1850 年とされる。Steller の記述からも標本からもガラパゴスコバネウ同様に飛翔性をかなり失っていたと考えられるとのこと。
しかしかつては広く分布しており、12 万年前には日本にも化石があるとのことで、カムチャツカ半島東 200 km のコマンドル諸島は遺存分布だったとのこと (以上 wikipedia 英語版、ロシア語版より。表現の重点など多少違いがある)。
文献は Watanabe et al. (2018) Pleistocene fossils from Japan show that the recently extinct Spectacled Cormorant (Phalacrocorax perspicillatus) was a relict。
人と接触する以前から分布域が大幅に縮小していたと考えられる。最終氷期の食物の減少を衰退の原因と考えている。
この論文でもカワウの亜種 hanedae の正当性は多くの著者が疑問視していると記述されている。カワウに比べてメガネウ (ベーリングシマウ) は巨大だったとのこと。
分子系統解析も考慮して、全体的には Urile 属は Phalacrocorax 属の分布拡大に対する遺存系統とみなしてよいのではないだろうか。
日本のカワウとウミウの関係と同様、ヨーロッパではカワウとヨーロッパヒメウが陸域と海域を分けあっている状況で、Urile 属のグループはヨーロッパに到達しなかったがヨーロッパヒメウが該当する位置も占めていると考えればよいだろうか。
ヨーロッパではウミウのような非常に近い系統がないため、カワウの一部が沿岸から海に潜る個体群を生み出したと考えると理解しやすい気がする。ウミウの分布のする地域ではそこまで海に進出できなかったのだろうか。もっとも前述のようにウミウはそもそもカワウの亜種と考えるのが適切で、ヨーロッパのカワウの亜種 carbo と同じような位置と考えることもできるだろう。
古い図鑑を見てもカワウの分布は局所的と書かれており、気候条件の比較的厳しい日本列島はカワウにとってそもそも住みにくく (近年の図鑑でも北海道では夏鳥)、ウミウと地理的に隔離されていたが、カワウに適した環境が広がっての分布を拡大することでカワウとウミウが接触するようになり、ヨーロッパのカワウの carbo と sinensis の関係と同じような状況になりつつあるのかも知れない。
接触によって交雑が起きるのかはよく知らないが、純粋なウミウのゲノムを解読するならば今のうちに行っておいた方がよい気もする。
オーストラリアでは沿岸部にマミジロウ Phalacrocorax varius Australian Pied Cormorant が生息、主に淡水域にカワウが生息する点はウミウとカワウの関係に似ているが、マミジロウはカワウからだいぶ離れた系統で、分子系統的には Phalacrocorax 属がオセアニアや一部南アジアから中東に進出してそれぞれ種分化を遂げた (オセアニアに5種) 後にカワウが世界的に勢力を広げている状況が読み取れる。
なおウ類に似たヘビウ類 (Anhingidae, Anhingas) はウ類よりも古い分岐にあたる。カワウもアジア熱帯地域で留鳥で、ウ類は熱帯地方で進化したと考えてよいのではないだろうか。
ヘビウ類は樹上営巣性、北米に進出したミミヒメウも樹上営巣性。ミミヒメウと同属の南米のナンベイヒメウ Nannopterum brasilianum Neotropic Cormorant は樹上にも営巣するがもっと低い位置にも巣を造るらしい。
ベーリンギアを経て到達した後でもウの系統は樹上営巣の能力を本質的には失っていないのだろう。現在のウミウや Urile 属が岸壁に営巣するのは環境要因のためと感じられる。
ヘビウ類はかつてはヨーロッパにも生息していたが寒冷化・乾燥化に伴って絶滅したと考えられるとのこと: Mayr et al. (2020) The large-sized darter Anhinga pannonica (Aves, Anhingidae) from the late Miocene hominid Hammerschmiede locality in Southern Germany。
ヘビウ類はアメリカ大陸起源で温暖な時期にユーラシア、アフリカ、オーストラリアに分布を広げたと考えられているらしい。潜水機能を高めるために羽毛が水に濡れやすく寒冷地で乾かすことができず適応できなかったとこの著者は考えている。
寒冷化に伴い寒冷気候への適応能力の高かったウ類に入れ替わって行ったらしい。
ヘビウ類の婚姻色は目の色が面白いので紹介 Anhinga (Sue Riffe 2025)。拡大 Anhinga (Cuneyt Yilmaz 2025)。
オーストラリアヘビウ Anhinga novaehollandiae Australasian Darter の頭かきならぬ首かき Australasian Darter (Annabelle Bueman 2025)。
ひなの写真を見るとペリカンの仲間のように見える Australasian Darter (Brendan Schembri 2025)。
鳴いているところはサギを思わせる Australasian Darter (Ken Tay 2025)。
Anhinga の名称由来はブラジルの Tupi language とのこと。記載時学名 Plotus anhing Linnaeus, 1766 ですでに用いられていた。英語別名 snakebird, darter, American darter など。ドイツ語名が記述的で Schlangenhalsvogel (蛇首鳥)。
wikipedia 英語版によればかつて巨大化と無飛翔化の傾向があり、小型種のみが生き残ったとのこと。
Nannopterum 属から南米・南極海を経てニュージーランドに到着した系統 (Leucocarbo 属) の解析は Rawlence et al. (2022) Rapid radiation of Southern Ocean shags in response to receding sea ice を参照。
遠距離の分散力がそれほど高くないウ類で、Urile 属に近い系統が北米・南米を通じてこのように分布を広げてオセアニアに到達していたとは驚き。
現在懸念されている H5N1 のオセアニアへの到着経路にも相当する。
[長い首の水中での役割]
この件はウ類全般に当てはまると考えられるが、ウ類の祖先的形質をよりよく表しているように思えるヘビウ類関連事項として紹介しておく。
古生物は鳥類に関係のある恐竜以外は興味がないと言われる方もおられるだろうが、形態と生態の関係を考える上では他の分類群も見ておくと面白いこともある。
O'Keefe et al. (2025) A name for the Provincial Fossil of British Columbia: a strange new elasmosaur taxon from the Santonian of Vancouver Island
2002 年に北米で見つかったエラスモサウルス類の化石で、この論文で Traskasaura sandrae と命名された。化石に保存されている頸椎だけで 36 個もあって実数は不明、脊椎骨は 100 以上あって祖先的な形質だが付属器の骨格は派生的である (古い特徴と新しい特徴が混在している)。
Mystery of "very odd" elasmosaur finally solved: one of North America’s most famous fossils identified as new species (一般向け解説と想像復元図)。
骨格からの機能推定では下向きに泳ぐことができ、上方向から捕食が可能だったのではとの推測が出されている。ウ類の採食様式や形態との関連などを思わせる感じがする。ウ類は地上から進化したため、あるいはさらに進化したグループで機能的に十分であったためそこまで極端な形態にはならなかったが、要求される形態への選択圧は似たものだったのでは?
派生してヘビ類の頸椎は何個かの問題もある。伸びているのはどの部分? それともみかけ上区分がないが途中までが首なのか、尾が長くなっているだけなのか?
Woltering (2012) From Lizard to Snake; Behind the Evolution of an Extreme Body Plan
に議論があるので紹介しておく。一部のヘビ類 (特にタマゴヘビ類のように鳥の卵を飲み込んで割って食べる種類。アオダイショウでも同様) に ventral (vertebral) hypapophyses (食道に突出して食道歯とも呼ばれる) があり、これは一般的に頸椎にみられる特徴なので、ヘビ類では首が極端に長く伸びているとの解釈もあった。
ventral hypapophyses はヘビ類の中でも変化が大きくあまり目安にならないとも考えられた。
週間アニマルライフ (1971) 2 pp. 44-45 のアオダイショウの項目 (松井) ではアオダイショウの ventral hypapophyses は 30 番目前後の椎骨にあるとのこと。さすがにそこまで全部頸椎とはみなしにくい、というところだろう。
著者 Woltering は Hox 遺伝子発現のパターンからはヘビの頸椎は3個ぐらいかなあ、と見積っている。
水中生活を送る Dolichosaurus や Adriosaurus 属 (いずれも古生物) のトカゲでは頸椎数は 10-19 個と首が長くなっていて、水中生活への適応とも考えられる (ということで上記話題につながる)。この著者は否定まではできないがヘビ類が水中から進化したと考えるよりも、地上生活から進化したシナリオを支持するものでは、と考えている。
気に入らないのは、爬虫類の進化を議論しているのになぜ哺乳類と比較するのみで鳥のことはまったく取りげていないのか (!)。もう少し鳥の首の進化についての情報を期待したわけである。
論調を見るとヘビから見ればマウスもニワトリも似たようなものだからマウスで代表させている感じも見えないこともない。系統的には逆なのではと感じるわけだが、ヘビでは上肢がないのでどうもマウスとニワトリの方が似ているらしい。
比較できるモデル生物としてマウスしかなかったのかも知れないが、現生系統ではヘビと鳥は系統があまりに違っているので直接比較が難しくそれほど有益な情報にならないのだろうか。他の研究を見てもヘビと鳥の比較はほとんどみかけない。
日本の著者の関連論文も、ということで Tsuihiji et al. (2012) Finding the neck-trunk boundary in snakes: anteroposterior dissociation of myological characteristics in snakes and its implications for their neck and trunk body regionalization
こちらは筋肉を調べて議論したもの。
ventral (vertebral) hypapophyses のような構造が食道に突出しても大丈夫なのかと思ってしまうが、爬虫類の食道では大丈夫なのだろうか。あるいは食道壁が頑丈になっているのかも知れない。まあ消化管は一続きのものだし、食道の一部が拡大して一部の鳥ではそのうになったり一部のヘビで食物を砕く器官となってもそれほど驚くべきことではないかも知れない。おそらくヒトの解剖学をベースに考えるので奇妙に見えるだけなのだろう。
対応する構造は鳥では首を前に曲げる筋肉の付着部位 (= ventral processes) となっている。なるほど hypapophyses のある部位は頸椎と判定する解釈になるわけだ (特に鳥では胸椎以下はほとんど曲がらないのでそのような構造が必要ない)。
これらのヘビでは脊椎を前に曲げることで食物を砕く行動に合わせてに骨の形も進化したと考えれば理解できる気がする。鳥は飲み込む場合は消化器、解体する場合は嘴に頼り、脊椎の力で直接砕く選択肢は選ばなかったのだろう。嘴の扱いがそれだけ器用だったためとも言える感じがする。飲み込んだ卵を首を曲げて砕く鳥が進化しても不思議ではなかったが、飛翔のバランスのためには上半身に筋肉を集中させるのは得策でなく採用されなかったのだろう。
そんな特殊な行動や形態を進化させるより、頭脳を発達させて工夫して卵を割った方が多分賢い (ので生き残った)。
今後飛翔性を失った鳥が進化して上肢を失うことになっても、嘴と頭脳で切り抜けていくのだろうなとか考えてしまう。
鳥類と哺乳類の頸椎を比較して、鳥類の方が脊椎の分化度が低い (頸椎と胸椎の境界が明瞭でない) と言われることがしばしばあり、いかにも哺乳類の方が進化していると言いたげに感じることがあるが、現生の恒温動物である鳥類と哺乳類の比較であれば、哺乳類の方は気のうシステムを持たなかったため、肺を膨張・収縮させる必要が生じ、恒温動物の代謝率を支えるためには肺を大きく動かす仕組みが必要となり、その機能のために胸郭がより分化しているだけではないだろうか。
上記のような事例を見ていると椎骨の形は必要な機能に応じて比較的容易に変化することができて、単に必要な機能を反映しているに過ぎないのでは (哺乳類だけが特殊化していると考えればより "進化している" と言えないこともないが、呼吸器については鳥類の生理機能の方が優れていることは疑いないので鳥類と哺乳類を比較して一般的表現に用いるのは誤解のもとになりそう。「哺乳類では劣った呼吸機能を補うために頸椎と胸椎の分化が進んだ」とは表現したくないわけだ。しかしここは鳥のページなのでこのように書いてしまおう)。
さらに霊長類のポートー (Perodicticus potto West African potto が属の代表種) では頸椎の 4-6 番目の後突起が皮膚をほとんど突き破るほどに発達しており、武器として利用するとのこと (wikipedia 英語版より)。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3412-3414 のポートーの項目 (榎本) からこの情報を知った。アフリカジャコウネコ Civettictis civetta に致命傷を与えることもできるとのこと。
Lemur (reptileevolution.com) で骨格標本を見ることができる。何だ、ポートーの方が鳥より恐竜的なのではないか (笑。俗説かも知れないが)。
[音声]
野鳥録音をする際にウミウは難関の一つと思う。カワウは地上の樹上に営巣するため営巣地で簡単に声を記録できるがウミウの声はなかなか記録できない。京都からだと地理的にも遠い場所が中心になってしまう。
姿は見られてもそもそも遠いことが多く、波の背景音が大きい、風が強いなど録音に不向きな条件が揃っている。またあまり鳴かない気がする。
バードリサーチに1件の音源があるが (2025.4 時点)、ノイズリダクションがどの程度行われているのかわからずカワウとの比較などに事実上利用困難に思える。もちろん鵜飼いで使われる個体を記録することができるが、できれば野生環境でも記録しておきたいところ (声は同じだろうと想像するが)。世界的にも音声のほとんど知られていない (2025.4 現在 xeno-canto, ML とも登録なし) 数少ない種なので皆さんも機会があれば試みていただきたい。
むしろチシマウガラスやヒメウの方がカムチャツカやアリューシャンでも記録されるため音声が記録されている。
考えたこともなかった方はこの機会に少し意識していただくとよいのではと思う。遺伝子の面でも音声の面でもウミウは世界的には東洋の謎の種類となっている可能性がある。
△ ペリカン目 PELECANIFORMES ペリカン科 PELECANIDAE ▽
-
モモイロペリカン
- 学名:Pelecanus onocrotalus (ペレカーヌス オノクロタルス) ペリカン
- 属名:pelecanus (m) ペリカン
- 種小名:onocrotalus (m) ペリカン < onokrotalos ペリカン (Gk)
- 英名:White Pelican, IOC: Great White Pelican
- 備考:
pelecanus は a が長母音でアクセントもある (ペレカーヌス)。
語源はギリシャ語 pelekan, pelekanos 由来。これは plekus (斧) に由来し、一般的に鳥を指す語尾変化したもの (wiktionary)。ギリシャ語では a は長音ではないがアクセントがあり、ラテン語もこれを踏襲したものだろう。-canus が "白" の意味ではない。
onocrotalus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-cro- がアクセント母音と考えられる (オノクロタルス)。
Kessler (1853) p. 69 (#オオハム参照) によれば Pelecanus roseus Eversmann, 1835 の学名があり和名もはこれに由来するかも知れない。英語別名にも Rosy Pelican がある。
当時のロシア名もこの学名に合わせており、"ペリカン" を指すロシア名は変化しているが "モモイロ" の部分は現在も使われている。
単形種。
ペリカン類の分子系統研究は Kennedy et al. (2013) The phylogenetic relationships of the extant pelicans inferred from DNA sequence data
を参照。
従来考えられてきたような白色の種類と茶色の種類で系統が違うのではなく、旧世界とオーストラリアを含む系統と新世界の系統に分かれる。ハイイロペリカン、ホシバシペリカンは前者のグループ、モモイロペリカンは少し離れるが前者に属する。
["ペリカンと少年"]
「ペリカンと少年」という旧ソ連の映画があった。何かの機会に TV で2回見ることがあって (もちろん日本語吹き替えで、原作ごろよりずっと後の時代に) 印象に残っているのだが、原作は 1963 年で原題は Slepaya Ptitsa (盲目の鳥) とのこと。ペリカンと少年にストーリーのほぼ全解説がある。
Slepaya Ptitsa で原作を見ることができる (データベースでは 65 分とあり、英語版でのみ見られるシーンがあるため原作よりわずかに短縮されているかも知れない)。
The Blind Bird - Slepaya Ptitsa - Russian Children's Movie from 1963 で英語版が見られるが若干編集・短縮されており、原作にない部分に音楽が入っていたりする。英語版ではあるが 1960 年代アメリカ流脚色付きと言ってよいかも知れない。日本版はどうなっていたのか再度見たいところであるが...。
上記記載で内容はほぼわかるが、原作や解説情報を見た上でもう少し詳しめに紹介しておく。この程度のストーリーがあれば原作のままでもかなり理解いただけるのではないだろうか。
映画はペリカンの繁殖コロニー調査で生態映像で始まる。足環標識をするために追い込んでいるところ。
そこでワーシャが逃げないペリカンに気づいた。「こいつ怖がらないよ?」、鳥類学者のおじいさんは手をかざして「目が見えないんだ」。ここから Slepaya Ptitsa (盲目の鳥) が始まる。
(解説記事には「ペリカン島」とあるがどこかはわからない)
連れて帰りペリカと名前を付けてワーシャはいつも一緒に行動。学校にも連れていって騒動もあり。
ペリカと一緒に外で食べていた時包装紙の新聞記事に目がとまる。モスクワのアルバートフ教授が手術で盲目の人の視力を取り戻したという。
そして仲間のペリカンは渡って行き、雪の積もる中ワーシャとペリカは部屋の中で一緒に冬を越す。
本を読みながら冬は暖かい地域に渡ることを知り、遠くへの思いを馳せる。
また季節がめぐってきたころワーシャはレニングラードのおばあさんのところに行くことになり、剥製のペリカンを代わりに置いてペリカをこっそり箱に入れて連れて列車に乗った。
乗客が腐った魚の臭いに気づき、
乗務員が「規則により客車に生きた鳥は持ち込んではいけません」。不潔でもし伝染病を持っていたらどうするんだとうるさい乗客と騒動となる。「人に慣れているのだし」とか擁護する乗客もいる。規則を持ち出した乗務員もなぜか顔は笑っている (うるさいのはむしろ一部乗客だけだったりする描写が面白い)。
「オウムかい?」「ペリカンです」。
そして親切な車掌さんの部屋へ。「なぜ乗せてるんだ」「目が見えないんだ」「そうなんだ」(中略) 何度も名前を聞いているはずの車掌さん「えっと何というんだっけ?」「ペリカン」「そうそうペリカン」あたりのやりとりが面白い。「何か食べさせてやりたいんだ」「安心して、食べ物は何とかするから」。
そして列車にはキッチンがあり、「魚おくれ」「了解」メニューを並べるシェフの言葉に「いやそんなのでなく...新鮮な凍ったのを...」「え、生で?」と驚くシェフ。「これは内緒」でお互い納得。次に現れた客もためらいつつ「すみませんが生で、できたら2つ」と魚を注文。
親切な乗客にも助けられてモスクワで下車。翌朝また来ればレニングラードに連れてあげるからと伝えられる。
いろいろなところで道を訪ねたりするが、そのうち都会の少年たちに目をつけられ「箱の中身を見せろ」と追いかけられることに。
一度は逃げることに成功したが結局みつかってしまい、箱を開けた。ペリカンに一同驚き、少年たちも協力してくれることになった。
公園のベンチで夜を過ごす間にペリカンはいなくなっていたがまた再会を果たす。
しかし餌がなく通りすがりの少年の持っていた金魚にお金を払うなどしていた。その少年も返しに戻ってくるあたりの描写も細かい。道を歩いていると婦人の持っていた荷物の魚が気になって仕方がない。あの一匹でもあれば...頼んでみようか...くれそうもないや...今日中に教授が見つからなかったらレニングラードに行こうか...。
そこで魚がすべり落ち、拾ったところで泥棒扱いされ警察 (補導官?) へ。
警察で事情を説明しペリカンを出してみせると (この部分が上記紹介の原作に抜けているようで一部カットされている可能性がある。英語版から補充)
その婦人も協力してくれ魚やワーシャにも食べ物も与えてくれた。
その間に警察がアルバートフ教授に電話し、「いやこの子の目が見えないのではなくて...」そして
無事に医師のもとへ。しかし一旦は断られ、「新聞記事は嘘か?」「いや本当だ」。鳥の手術などやったことがない。落ち込み帰りかけたワーシャに、レントゲンを撮ってみようかと教授は声をかける。
レントゲン写真を前に猟銃の弾が神経を圧迫していると説明。治る可能性はあるが神経がやられているとだめだ。「説明は全部わかるか」「わかります。手術をお願いします」「保証はできないが」、
そして手術がうまく行かず「もし死んだら?」...ワーシャはしばらくの沈黙の後「一生見えないよりも」。「任せてくれるか」「はい」。「それでは決断しよう」「決断します」。
手術中の待合室、そしてアルバートフ教授が現れ「これが弾だ。君のペリカンは素晴らしい。手術にこの上なくよく耐えた。10日もすれば結果がわかるだろう」。
そしてしばらく後に包帯が取れて診察室へ。「やはり見えてないですか?」「うむ」。
しばらく沈黙の後、教授は「できる限りのことはしたはずだなのだが...」。
そしてお礼の後、これほど面倒なことをお願いしてごめんなさいと涙を流すワーシャを抱擁する教授。
家に戻ったワーシャとペリカ。あるところからペリカの目が見えていることに気づく。
アルバートフ教授にペリカの目が見えるようになったと手紙を書くワーシャ「暖かい地域に行けるように明日おじいさんと放しに行きます」。
そしておじいさんとボートで野生ペリカンのところへ。ワーシャとペリカはすでに親友でもう別れ難い。しかし放さないといけない。
おじいさんの「友達にお別れをするんだ」。「放して!」の一声で放されたペリカはためらいつつも飛び立ち、そして見事な飛翔で群れに加わってゆく。羽根1枚だけを残して。
-
ホシバシペリカン
- 学名:Pelecanus philippensis (ペレカーヌス ピリッペーンシス) フィリピンのペリカン
- 属名:pelecanus (m) ペリカン
- 種小名:philippensis (adj) フィリピンの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Spot-billed Pelican
- 備考:
pelecanus は#モモイロペリカン参照。
philippensis は場所を表す形容詞であれば -ensis の e が長母音でアクセントもここにある (ピリッペーンシス)。短音でも構わない。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。フィリピンペリカンとも呼ばれた。
森岡 (1999) Birder 13(5): 66-69 に考察があり、Pelecanus crispus はかつて Pelecanus philippensis の亜種とされた。
フィリピンは基産地ではあるが [Gmelin (1789) の 原記載]、現在の繁殖分布でも通常の越冬分布でもないのでフィリピンペリカンの名称は適切でないと述べられていた。
現在の世界の他言語でもフィリピンの名前はほとんど用いられていない。"東洋の" を付ける言語もあり、ヨーロッパからはわかりやすい名前だろう。
-
ハイイロペリカン
- 学名:Pelecanus crispus (ペレカーヌス クリースプス) 髪がちじれたペリカン
- 属名:pelecanus (m) ペリカン
- 種小名:crispus (adj) ちじれた (後頭部の羽毛がよじれている)
- 英名:Dalmatian Pelican (ダルマチア: 現在はクロアチアのアドリア海沿岸地域一帯)
- 備考:
pelecanus は#モモイロペリカン参照。
crispus は i が長母音でアクセントもここにある (クリースプス)。
ニシハイイロペリカンとも呼ばれる。単形種だが化石亜種 palaeocrispus が知られている。
ペリカン類で最大種。飛べる鳥の中でも最大に近い。
かつてはホシバシペリカンと同種とする考えもあった。Bruch (1932) の 原記載 の方が遅いので同種にする場合は Pelecanus philippensis の亜種になる。
Pelecanus roseus Gmelin, 1789 (原記載) との関係も問題になる (Pelecanus philippensis と同年なので) が、森岡 (1999) Birder 13(5): 66-69 はシノニムとして扱う考えを紹介している。
Clements 1st, Howard and Moore 2nd edition, Peters' Check-list of the Birds は別種扱い (Southern White Pelican) としていたが、現在の世界のチェックリストは無効な種学名として扱っている模様。別種モモイロペリカン Pelecanus onocrotalus の亜種 roseus として使われることがあったが、これも現在は使われていない。
「和漢三才図会」(わかんさんさいずえ) や「本草綱目」にもペリカンが登場し、ハイイロペリカンと考えられるとのこと (コンサイス鳥名事典)。「伽藍鳥」(ガランテウ/ガランチョウ) が当時の古名で、
江戸時代の博物誌 珍禽奇獣異魚によれば、「永享2年 (1430) に京都伏見の舟津で捕えられたのが日本における最古の記録ですが、江戸時代にはかなりの数の記録があり、しばしば見世物にも出されていました。
この図は右下に「文久二年 (1862) 壬戌秋八月 於尾張熱田沖 桜新田海岸 捕之」とあります。このペリカンはおそらく台風に運ばれてきた迷鳥でしょう。著者の清水淇川は尾張の画家です」
と記されている。
志村 (1994) Birder 8(11): 74-76 によれば中国語では鵜の漢字をペリカンに用いる。
また古くはペリカンとハゲワシの混同があり、再生にまつわる言い伝えはエジプト神話に共通性があるとのこと。
この記事でも紹介されているがギリシャ語 pelekanos は pelekus (斧) と語源的関係があるとのこと (wiktionary)。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 106 に内田氏による迷鳥としてのハイイロペリカンの解説があり、Dalmatian Pelican のことで学名は Pelecanus crispus と Pelecanus pelecanus を同種とする考えがあり、その場合は先取権の原則から後者となることが紹介されていた。
この記事では曖昧さを防ぐために英名 Dalmatian Pelican が使われていた。和名は学会の意見に従ってハイイロペリカンを用いたが、私見としては適当とは思えないことが記されていた。
ハイイロペリカンに対応する英名があったのだろうと調べてみると、ホシバシペリカンの旧名だった。おそらく同種とまとめられた時の英名で、同じ意味の名称はドイツ語などにも幅広く残っていて、古くは広く使われていたのだろう。ヨーロッパにはモモイロペリカン、英名では (Great) White Pelican が生息するので、それに比べれば灰色の概念はおそらくわかりやすかったのだろう。
内田氏が適当と思われなかった理由までは示されていなかったが、種が分離されているのに統合時代の名称を使うのは適切でないと考えられたのかも知れない。#カタグロトビの和名が、アメリカの鳥に対して付けられた英名から同種時代を経由して地理的には反対方向に回ってきたのと似ている。
△ ペリカン目 PELECANIFORMES サギ科 ALDEIDAE ▽
-
サンカノゴイ
- 学名:Botaurus stellaris (ボータウルス ステールラーリス) 星斑のある雄牛のようなヨシゴイ
- 属名:botaurus (合) 雄牛のようなヨシゴイ (butio ヨシゴイ類 taurus (m) 雄牛)
- 種小名:stellaris (adj) 星の (stella (f) 星 -aris (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Bittern, IOC: Eurasian Bittern
- 備考:
botaurus は起源となるラテン語 bos (雄牛) またはギリシャ語 bous が長母音、butio は u, o が長母音であることから、bo- は長母音で読むのが適切と考えらえる (#モズ参照)。直後に2重母音が続くので音韻的には短く読むかも知れない。ここでは意味を保存するために伸ばしておいた。
taurus は短母音のみ。-ta- がアクセント音節 (ボータウルス)。
由来はおそらく異なるが butio は音韻的にはノスリ類の buteo と同じとのこと (wiktionary)。
stellaris は e, a が長母音で、-la- がアクセント音節 (ステールラーリス)。stella (星) の冒頭が長母音。形容詞を作る語尾の -aris も冒頭が長母音。
英名の由来はラテン語 butio (ヨシゴイ類) taurus (雄牛) から合成。学名の由来と同じ。
botor/butio はもともとは bos (m) 雄牛に由来する。
AviList, Clements 2024, BirdLife v9 はいずれも Eurasian Bittern で統一されているが、Avibase は Great Bittern を見出しに用いている。
ユーラシアに広く分布し、アフリカにも局所的に分布する。2亜種あり、日本で記録されるものは基亜種 stellaris とされる。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 27 によれば和名は羽色が茅葺の山家のイメージにぴったりだったためだろうとの解釈。生息地が "山家" は疑問に思っていたが、茅葺の色と言われればそうかも知れない。
山階鳥類研究所の標本データベースを確認しておくと、1880 年代の古い標本があって最も古そうなラベルには和名のないものもある。かなり古く見えるものでサンカノゴイの名称があるものがあるが、ラベルの変色が著しいだけで後に付けられたものかも知れない。当時から統一した名前で呼ばれていたかどうかは確認できなかった。
[サギ類の系統分類]
Hruska et al. (2023) Ultraconserved elements resolve the phylogeny and corroborate patterns of molecular rate variation in herons
(Aves: Ardeidae)
に UCE (ultraconserved elements) を含めた詳細な分子系統解析が発表された。
種のサンプルはまだ十分ではないが、少なくとも系統関係に関してはタカ類に匹敵する精度で系統樹を議論できるようになった (#アカハラダカの備考参照)。
従来通りミトコンドリア遺伝子のみを使うと結果が少し異なるとのこと (同文献 fig. 3) だが、核遺伝情報ではここに示された系統が支持されるとのこと。
特に 2021 年ぐらいよりこのような系統解析が普通に発表されるようになってきており、これが世界標準になりそうである。
これまでの系統樹と多少異なる点があるので、他の文献も用いて全種の系統を網羅した Boyd の分類に従った最新分類を紹介する。Boyd によれば古い研究はもう忘れてもよいぐらいで、新しい分子系統分類は形態特徴に基づく系統分類ともよく一致するとのこと。
これまで部分的な遺伝情報に頼って属間の移動が行われたりしたが、多少の修正が必要になりそうである。
Hruska et al. (2023) によって アカハラサギ亜科 Agamiinae (アカハラサギのみ) が新設された。
分類、学名、順序は Boyd による。英名はわずかな綴り調整以外 Boyd の表記をそのまま採用した。
IOC 英名とは少し違うところもあるので統一的な英名を必要とされる方はご確認いただきたい。
Boyd によれば Mendales (2023) の修士論文 Ultraconserved elements resolve the phylogeny of a globally distributed genus, Butorides (Aves: Ardeidae)
で分子系統解析でササゴイが複数種に分離される証拠があり、ここでは色彩に基づいて暫定的に5種 (南米のものは分子系統で確実に分かれるとのこと) に分けたとのこと。これらは Boyd の解説しているところの「時には未発表データも取り入れて」系統樹を検討した例である。
これまでのササゴイの基亜種 striata が南米のものなので、もし分離されれば日本のササゴイも学名が変わる。
この分類によればアジア地域で最も早い記載により Butorides javanica となる。南米のものを別種とするならば学名変更は避けられない。
American Striated Heron の名称が与えられているが、そのまま和訳のアメリカササゴイはすでに別種に使われているので暫定的にナンベイササゴイとしてみた。他の新和名も暫定である。
ダイサギも Raty (2014) の DNA バーコーディングにより複数種に分けられる証拠があり、4亜種の繁殖期の羽衣の色彩がすべて異なるため4種としたとのこと。アフリカダイサギ? Casmerodius melanorhynchos のみは DNA を用いている。
この分類に従えばダイサギとチュウダイサギが別種となり、チュウサギと一緒に1系統を形成することになる。これまでの分類に比べ、我々の直感とも合っている感じがするが学名は大きく変わる。
広義 Ardea 属のままでも単系統をなすが、特徴のあるアマサギ属 Bubulcus の名称を残したいならばこの分離は必須になる。
ダイサギ系とアオサギ系はだいぶ違いが感じられるのでこの分け方で妥当かも知れない。
属名の性が変わることで種小名が変わるものも多数ある。
ロシア沿海地方でダイサギの繁殖を紹介している Gluschenko et al. (2024) The great egret Casmerodius albus in the south of Russian Far East (pp. 939-961)
でもこの学名を採用している。ロシアでは以前から使われていた属名らしい。
英語圏のリストでは Ardea が使われているがとの言及付き。
"シラサギ属" の和名はかつて使われていたものだが、現在では分類概念が異なっているのでここでは使わないことにしておく。
Ardea occidentalis Great White Heron はオオアオサギからの分離候補で AOU, HBW/BirdLife では古くから分離している。英名はこの名称が定着しているようだが、ダイサギの英名として使われることもある Great White Egret と大変紛らわしい。
和名を付けるにも悩ましそうでオオアオサギより大きいのならばオニアオサギかと思えばすでに他種で使われている上に姿の印象とかなり違う。
真っ白なんだからオオダイサギでよいかと言えばこれは亜種ダイサギの旧名。シロオオアオサギ? のような矛盾した (?) 名前を付けるか、分布が南フロリダからカリブ海なので地名を付ける?
かつてから種扱いもあったので何か和名があったかも知れないが調べられていないと思って探してみるとオオシロサギの名前がコンサイス鳥名辞典にあった。"シラサギ" でなく "シロサギ" が紛らわしくならないポイントだろうか。
オオアオサギのうち、この亜種または種のみが "白色型" で中間型も知られているとのこと。
アオサギの白色型とは? どんな感じに見えるかは画像検索などしてみていただきたい。
#クロサギでは白色型は morph で分類上異なるわけではないが、オオアオサギでは異なることが提唱されている。この2種で白色型の意味がどう違うのかなど調べると面白いだろう。
なおサギ類は世界的に非常に分布の広い種が多数ある。日本で観察できる印象と前後の種で名称から分布がずいぶん違っているように見えることもあるが、分布図を見ていただければ近い関係にあってもおかしくないことを理解いただけるだろう。
サギ科の系統分類について、用いられた資料は少し古いが日本語の解説がある。サギ科の系統分類 (アオサギを議論するページ 2015)。Prum et al. (2015) が使われており、サギ科の位置づけの理解は現在もこの通りだろう。
サギ科内は新しい研究でやはり様相が変わっており、Ardeinae 亜科の下位の階層分類と考えられていた Nycticoracini, Ardeni, Egrettini 族のうち Nycticoracini, Egrettini は現代的な分子遺伝分類では単系統にならない。
単系統性に基づく概念を設けることはできるが Hruska et al. (2023) は亜科以外の分類を特に示していないのでここでは取り扱わないことにする。
過去に提唱されていた Ardeni 族は単系統であるが、日本語でシラサギと言われるグループに特に対応するわけでなく、ササゴイも含まれる。
ミゾゴイ、ヨシゴイ、ササゴイがサギ科の中でもすべて違うグループに属することも注目しておいてよいだろう。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 (2024) で Ixobrychus 属は Botaurus 属に統合され、今後は世界のリストでこちらの扱いになるだろう。
実はアメリカでは相当ややこしいことになっている模様。Proposals 2024-A Comments
コヨシゴイ Botaurus exilis Least Bittern とオーストラリアのセグロヨシゴイ Ixobrychus dubius Black-backed Bittern はしばしば同種とされることもあるぐらい (さらにヨシゴイも) 似ているが、コヨシゴイは Hruska et al. (2023) では UCE サンプルが行われておらず、(同種とされた名残り?) でセグロヨシゴイをコヨシゴイとして解析している。
属を判断する上でさらに複雑な問題があって、Ixobrychus 属のタイプ種がヒメヨシゴイ Ixobrychus minutus Little Bittern だが Hruska et al. (2023) ではサンプルされていない。タイプ種がサンプルされていない段階で属の範囲について結論を出すことができない。
ただしこれまで使われたきた分類と新しい分子系統樹が整合していないことも確かなので、単系統になるように Botaurus 属を拡大して Ixobrychus 属を含めてはどうかとのアイデアが出された (暫定的な扱いとしてこれが採用された? IOC 14.2 ではこの学名になっている)。
しかし新大陸系統と東洋小型サギ類は別なのでは? 音声も違うとの指摘がある (ヨシゴイの声にも言及がある)。ヨシゴイの録音をお持ちの方は Xeno-Canto に登録されるとこのような議論には大変役立ちそう。Xeno-Canto の録音を聞いてみて判断してほしいとの呼びかけがある。
AOU-NACC Proposals 2024 も参照。属レベルで違っているはずと考えている人も多い。
もっと新しく分岐したはずのサギ類の属を分割しているのにここは統合するのは整合性がない、など。
小型の Ixobrychus 属は外見は違って見えるが形態や色彩の進化は速いこともある (外見の違いはそこまで確実な証拠でない)。
SACC では Merge Bubulcus into Ardea (2025.5) の議論がなされているところ。Bubulcus 属を Ardea 属に統合するか、Ardea 属を分割するかいずれかになる。
どちらの判断であってもこれまで馴染みのサギ類一部の属名が変わる。
さらに SACC のサギ類全体の分類の検討提案: Modify classification of the Ardeidae: (A) change the linear sequence and (B) add subfamilies
Merge Ixobrychus into Botaurus こちらも世界の動向の合わせた検討だが、コヨシゴイを移動して Ixobrychus 属を維持する方法も考えられる。外見から考えられた種グループと DNA の整合性があまりよくないので Remsen はかなり悩んでいる。
(Boyd の分類による)
トラフサギ亜科 Tigriornithinae: Tiger Herons
アフリカトラフサギ属 Tigriornis
アフリカトラフサギ Tigriornis leucolopha White-crested Tiger Heron
トラフサギ属 Tigrisoma
トラフサギ Tigrisoma lineatum Rufescent Tiger Heron
ハゲノドトラフサギ Tigrisoma mexicanum Bare-throated Tiger Heron
ズグロトラフサギ Tigrisoma fasciatum Fasciated Tiger Heron
ヒロハシサギ亜科 Cochleariinae: Boat-billed Heron
ヒロハシサギ属 Cochlearius
ヒロハシサギ Cochlearius cochlearius Boat-billed Heron
アカハラサギ亜科 Agamiinae: Agami Heron
アカハラサギ属 Agamia
アカハラサギ Agamia agami Agami Heron
サンカノゴイ/ヨシゴイ亜科 Botaurinae: Bitterns
コビトトラフサギ属 Zebrilus
コビトトラフサギ Zebrilus undulatus Zigzag Heron
サンカノゴイ属 Botaurus
ナンベイヨシゴイ Botaurus involucris Stripe-backed Bittern (Ixobrychus より移動)
コヨシゴイ Botaurus exilis Least Bittern (Ixobrychus より移動)
サンカノゴイ Botaurus stellaris Eurasian Bittern
オーストラリアサンカノゴイ Botaurus poiciloptilus Australasian Bittern
アメリカサンカノゴイ Botaurus lentiginosus American Bittern
ナンベイサンカノゴイ Botaurus pinnatus Pinnated Bittern
ヨシゴイ属 Ixobrychus (世界的には Botaurus に統合の見込み。属学名の後に * を付けておいた)
タカサゴクロサギ Ixobrychus* flavicollis Black Bittern
リュウキュウヨシゴイ Ixobrychus* cinnamomeus Cinnamon Bittern
オオヨシゴイ Ixobrychus* eurhythmus Von Schrenck's Bittern
クロヨシゴイ Ixobrychus* sturmii Dwarf Bittern
ヒメヨシゴイ Ixobrychus* minutus Little Bittern
ヨシゴイ Ixobrychus* sinensis Yellow Bittern
セグロヨシゴイ Ixobrychus* dubius Black-backed Bittern
オーストラリアヨシゴイ Ixobrychus* novaezelandiae New Zealand Bittern (絶滅種)
ゴイサギ亜科 Nycticoracinae: Night Herons
ミゾゴイ属 Gorsachius
ズグロミゾゴイ Gorsachius melanolophus Malayan Night Heron
ミゾゴイ Gorsachius goisagi Japanese Night Heron
シラガゴイ属 Nyctanassa
シラガゴイ Nyctanassa violacea Yellow-crowned Night Heron
バーミューダゴイサギ Nyctanassa carcinocatactes Bermuda Night Heron (絶滅種)
ゴイサギ属 Nycticorax
ハシブトゴイ Nycticorax caledonicus Nankeen Night Heron
ゴイサギ Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron
アセンションゴイサギ? Nycticorax olsoni Ascension Night-Heron (絶滅種)
レユニオンゴイサギ? Nycticorax duboisi Reunion Night Heron (絶滅種)
モーリシャスゴイサギ? Nycticorax mauritianus Mauritius Night Heron (絶滅種)
ロドリゲスゴイサギ? Nycticorax megacephalus Rodrigues Night Heron (絶滅種)
アオサギ亜科 Ardeinae: Egrets and Herons
セジロミゾゴイ属 Calherodius
セジロミゾゴイ Calherodius leuconotus White-backed Night Heron (Gorsachius属より移動)
ハイナンミゾゴイ属 Oroanassa
ハイナンミゾゴイ Oroanassa magnifica White-eared Night Heron (Gorsachius 属より移動)
シロゴイサギ属 Pilherodius
シロゴイサギ Pilherodius pileatus Capped Heron
キムネゴイ属 Syrigma
キムネゴイ Syrigma sibilatrix Whistling Heron
コサギ属 Egretta
ムナジロクロサギ Egretta picata Pied Heron
カオジロサギ Egretta novaehollandiae White-faced Heron
ヒメアカクロサギ Egretta caerulea Little Blue Heron
サンショクサギ Egretta tricolor Tricolored Heron
アカクロサギ Egretta rufescens Reddish Egret
ユキコサギ Egretta thula Snowy Egret
コサギ Egretta garzetta Little Egret
アフリカクロサギ Egretta gularis Western Reef Heron
マダガスカルクロサギ Egretta dimorpha Dimorphic Egret
クロコサギ Egretta ardesiaca Black Heron
ノドアカクロサギ Egretta vinaceigula Slaty Egret
カラシラサギ Egretta eulophotes Chinese Egret
クロサギ Egretta sacra Pacific Reef Heron
ササゴイ属 Butorides
ナンベイササゴイ? Butorides striata American Striated Heron
アメリカササゴイ Butorides virescens Green Heron
ガラパゴスササゴイ Butorides sundevalli Lava Heron
アフリカササゴイ? Butorides atricapilla African Striated Heron (Butorides striata より分離。IOC 15.1 でも採用。英名は Little Heron)
アラビアササゴイ? Butorides brevipes Arabian Striated Heron (Butorides striata より分離)
ササゴイ Butorides javanica Asian Striated Heron (Butorides striata より分離)
オーストラリアササゴイ? Butorides macrorhyncha Australasian Striated Heron (Butorides striata より分離)
パプアトラフサギ属 Zonerodius
パプアトラフサギ Zonerodius heliosylus Forest Bittern
アカガシラサギ属 Ardeola
クロアマサギ Ardeola rufiventris Rufous-bellied Heron
カンムリサギ Ardeola ralloides Squacco Heron
マダガスカルカンムリサギArdeola idae Malagasy Pond Heron
アカガシラサギ Ardeola bacchus Chinese Pond-Heron
インドアカガシラサギ Ardeola grayii Indian Pond Heron
ジャワアカガシラサギ Ardeola speciosa Javan Pond Heron
ダイサギ/チュウサギ属 Casmerodius
シロガシラサギ Casmerodius pacificus White-necked Heron (Ardea 属より移動)
アフリカチュウサギ? Casmerodius brachyrhynchus Yellow-billed Egret (Ardea intermedia より分離)
チュウサギ Casmerodius intermedius (Intermediate Egret), Medium Egret Ardea 属より移動)
オーストラリアチュウサギ Casmerodius plumiferus Plumed Egret (Ardea intermedia より分離)
チュウダイサギ Casmerodius modestus Eastern Great Egret (Ardea alba より分離)
ダイサギ Casmerodius albus Great White Egret (Ardea 属より移動)
アフリカダイサギ? Casmerodius melanorhynchos African Great Egret (Ardea alba より分離)
アメリカダイサギ? Casmerodius egretta American Egret (Ardea alba より分離)
アマサギ属 Bubulcus
ニシアマサギ Bubulcus ibis Western Cattle Egret
アマサギ Bubulcus coromandus Eastern Cattle Egret
アオサギ属 Ardea
マダガスカルサギ Ardea humbloti Humblot's Heron
シロハラサギ Ardea insignis White-bellied Heron
スマトラサギ Ardea sumatrana Great-billed Heron
ムラサキサギ Ardea purpurea Purple Heron
オニアオサギ Ardea goliath Goliath Heron
ズグロアオサギ Ardea melanocephala Black-headed Heron
アオサギ Ardea cinerea Grey Heron
ナンベイアオサギ Ardea cocoi Cocoi Heron
オオアオサギ Ardea herodias Great Blue Heron
オオシロサギ Ardea occidentalis Great White Heron (Ardea herodias より分離)
Hruska et al. (2023) に従った配列とすると以下のようになる。
トラフサギ亜科 Tigriornithinae: Tiger Herons
トラフサギ属 Tigrisoma
トラフサギ Tigrisoma lineatum Rufescent Tiger Heron
ハゲノドトラフサギ Tigrisoma mexicanum Bare-throated Tiger Heron
ズグロトラフサギ Tigrisoma fasciatum Fasciated Tiger Heron
アフリカトラフサギ属 Tigriornis
アフリカトラフサギ Tigriornis leucolopha White-crested Tiger Heron
ヒロハシサギ亜科 Cochleariinae: Boat-billed Heron
ヒロハシサギ属 Cochlearius
ヒロハシサギ Cochlearius cochlearius Boat-billed Heron
アカハラサギ亜科 Agamiinae: Agami Heron
アカハラサギ属 Agamia
アカハラサギ Agamia agami Agami Heron
サンカノゴイ/ヨシゴイ亜科 Botaurinae: Bitterns
コビトトラフサギ属 Zebrilus
コビトトラフサギ Zebrilus undulatus Zigzag Heron
サンカノゴイ属 Botaurus
アメリカサンカノゴイ Botaurus lentiginosus American Bittern
オーストラリアサンカノゴイ Botaurus poiciloptilus Australasian Bittern
サンカノゴイ Botaurus stellaris Eurasian Bittern
ナンベイサンカノゴイ Botaurus pinnatus Pinnated Bittern
コヨシゴイ Botaurus exilis Least Bittern (Ixobrychus より移動)
ナンベイヨシゴイ Botaurus involucris Stripe-backed Bittern (Ixobrychus より移動)
ヨシゴイ属 Ixobrychus (世界的には Botaurus に統合の見込み。属学名の後に * を付けておいた)
クロヨシゴイ Ixobrychus* sturmii Dwarf Bittern
ヨシゴイ Ixobrychus* sinensis Yellow Bittern
ヒメヨシゴイ Ixobrychus* minutus Little Bittern
タカサゴクロサギ Ixobrychus* flavicollis Black Bittern
リュウキュウヨシゴイ Ixobrychus* cinnamomeus Cinnamon Bittern
オオヨシゴイ Ixobrychus* eurhythmus Von Schrenck's Bittern
セグロヨシゴイ Ixobrychus* dubius Black-backed Bittern
オーストラリアヨシゴイ Ixobrychus* novaezelandiae New Zealand Bittern (絶滅種)
アオサギ亜科 Ardeinae
ミゾゴイ属 Gorsachius
ミゾゴイ Gorsachius goisagi Japanese Night Heron
ズグロミゾゴイ Gorsachius melanolophus Malayan Night Heron
セジロミゾゴイ属 Calherodius
セジロミゾゴイ Calherodius leuconotus White-backed Night Heron (Gorsachius 属より移動)
ハイナンミゾゴイ属 Oroanassa
ハイナンミゾゴイ Oroanassa magnifica White-eared Night Heron [Gorsachius 属より移動。Hruska et al. (2023) では Calherodius magnificus]
キムネゴイ属 Syrigma
キムネゴイ Syrigma sibilatrix Whistling Heron
シロゴイサギ属 Pilherodius
シロゴイサギ Pilherodius pileatus Capped Heron
コサギ属 Egretta
ムナジロクロサギ Egretta picata Pied Heron
カオジロサギ Egretta novaehollandiae White-faced Heron
アカクロサギ Egretta rufescens Reddish Egret
サンショクサギ Egretta tricolor Tricolored Heron
ヒメアカクロサギ Egretta caerulea Little Blue Heron
クロコサギ Egretta ardesiaca Black Heron
クロサギ Egretta sacra Pacific Reef-Heron
ユキコサギ Egretta thula Snowy Egret
コサギ Egretta garzetta Little Egret
アフリカクロサギ Egretta gularis Western Reef Heron
ノドアカクロサギ Egretta vinaceigula Slaty Egret
マダガスカルクロサギ Egretta dimorpha Dimorphic Egret
カラシラサギ Egretta eulophotes Chinese Egret
ゴイサギ属 Nycticorax
ゴイサギ Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron
ハシブトゴイ Nycticorax caledonicus Nankeen Night Heron
アセンションゴイサギ? Nycticorax olsoni Ascension Night Heron (絶滅種)
レユニオンゴイサギ? Nycticorax duboisi Reunion Night Heron (絶滅種)
モーリシャスゴイサギ? Nycticorax mauritianus Mauritius Night Heron (絶滅種)
ロドリゲスゴイサギ? Nycticorax megacephalus Rodrigues Night Heron (絶滅種)
シラガゴイ属 Nyctanassa
シラガゴイ Nyctanassa violacea Yellow-crowned Night Heron
バーミューダゴイサギ Nyctanassa carcinocatactes Bermuda Night Heron (絶滅種)
パプアトラフサギ属 Zonerodius
パプアトラフサギ Zonerodius heliosylus Forest Bittern
アカガシラサギ属 Ardeola
カンムリサギ Ardeola ralloides Squacco Heron
インドアカガシラサギ Ardeola grayii Indian Pond Heron
ジャワアカガシラサギ Ardeola speciosa Javan Pond Heron
アカガシラサギ Ardeola bacchus Chinese Pond Heron
マダガスカルカンムリサギArdeola idae Malagasy Pond Heron
クロアマサギ Ardeola rufiventris Rufous-bellied Heron
ササゴイ属 Butorides
アメリカササゴイ Butorides virescens Green Heron
アフリカササゴイ? Butorides atricapilla African Striated Heron (Butorides striata より分離。IOC 15.1 でも採用。英名は Little Heron)
アラビアササゴイ? Butorides brevipes Arabian Striated Heron (Butorides striata より分離)
ササゴイ Butorides javanica Asian Striated Heron (Butorides striata より分離)
オーストラリアササゴイ? Butorides macrorhyncha Australasian Striated Heron (Butorides striata より分離)
ガラパゴスササゴイ Butorides sundevalli Lava Heron
ナンベイササゴイ? Butorides striata American Striated Heron
アオサギ属 Ardea
アオサギ Ardea cinerea Grey Heron
オオアオサギ Ardea herodias Great Blue Heron
オオシロサギ Ardea occidentalis Great White Heron (Ardea herodias より分離)
ナンベイアオサギ Ardea cocoi Cocoi Heron
シロガシラサギ Casmerodius* pacificus White-necked Heron
ズグロアオサギ Ardea melanocephala Black-headed Heron
ムラサキサギ Ardea purpurea Purple Heron
オニアオサギ Ardea goliath Goliath Heron
ダイサギ Casmerodius albus Great White Egret
アフリカダイサギ? Casmerodius* melanorhynchos African Great Egret (Ardea alba より分離)
アメリカダイサギ? Casmerodius* egretta American Egret (Ardea alba より分離)
チュウダイサギ Casmerodius* modestus Eastern Great Egret (Ardea alba より分離)
ニシアマサギ Bubulcus* ibis Western Cattle Egret
アマサギ Bubulcus* coromandus Eastern Cattle Egret
アフリカチュウサギ? Casmerodius* brachyrhynchus Yellow-billed Egret (Ardea intermedia より分離)
チュウサギ Casmerodius* intermedius (Intermediate Egret), Medium Egret
オーストラリアチュウサギ Casmerodius* plumiferus Plumed Egret (Ardea intermedia より分離)
シロハラサギ Ardea insignis White-bellied Heron
スマトラサギ Ardea sumatrana Great-billed Heron
マダガスカルサギ Ardea humbloti Humblot's Heron
Hruska et al. (2023) では Boyd の分離している Ardea, Casmerodius, Bubulcus の3属を統合して Ardea 属としているが (該当のものの属名に * を付けた) 、ここでは Boyd との対応関係を示すため3属に分けた学名で紹介している。Ardea 属とする場合は性により種小名が変わる場合があるので注意。
Hruska et al. (2023) の系統樹を見ると確かに分けるほどでもない分岐の深さで、多少の移動を行ってアマサギに対して伝統的な Bubulcus 属を残したいかどうかの程度問題。
[シロハラサギ]
「野鳥」2024 年 9・10 月号 (No. 872) pp. 24-29 にブータンのシロハラサギ保護プロジェクトの紹介がある (島野智之)。IUCN CR 種。ブータンでは現存数 27 羽とのこと。
Japanese support for White-bellied Heron breeding scheme (BirdGuides の紹介記事)。
2022 年にブータンで White-bellied Heron Conservation Centre (WBHCC) が設立され、2023 年に野生から3卵を採取して人工孵化をしたが3羽とも異常があり (個体数が少なく近親交配の影響による遺伝的問題とみられていた) 安楽死させられたとのこと。ただし日本の専門家によればコウノトリやトキでもしばしばあった現象で遺伝的問題よりも飼育技術の問題の可能性も考えられるとのこと。
2028 年までに飼育下で8つがいを確立して 2050 年までに少なくとも 50 羽を野生放鳥したいと考えている。日本でもコウノトリやトキの人工飼育の確立に 20 年かかった。
-
ヨシゴイ (将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Ixobrychus sinensis (イクソブリュクス シネンシス) 中国の葦原の大声で鳴く鳥
- AviList 学名:Botaurus sinensis (ボータウルス シネンシス) 中国の葦原の雄牛のようなヨシゴイ
- 第8版属名:ixobrychus (合) 葦原で大声で鳴く鳥 (ixias アシのような植物 brukhomai 大声で鳴く、吠える Gk)
- AviList 属名:botaurus (合) 雄牛のようなヨシゴイ (butio ヨシゴイ類 taurus (m) 雄牛)
- 種小名:sinensis (adj) 中国の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Chinese Little Bittern, IOC: Yellow Bittern
- 備考:
ixobrychus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-bry- がアクセント音節と考えられる (イクソブリュクス)。
botaurus は#サンカノゴイ参照。
sinensis は規則通り "シネンシス" のアクセント。長音でもよい。
属名は「蘆笛を吹き鳴らす」との優雅な意訳もある (愛媛の野鳥「はばたき」)。Botaurus 属に比べて小型のヨシゴイ類を指す。単形種。
WGAC 0.04 で Botaurus sinensis に変更。
記載時学名 Ardea Sinensis Gmelin, 1789 (原記載) 基産地 Sina, parva = China。当時すでに Chinese Heron (Latham) の英名があった。
ヨシゴイの英語別名 Chinese Little Bittern も学名と整合性がよい。
茂田 (1993) Birder 7(8): 36-40 によると
Ixobrychus exilis 英名 Least Bittern、
Ixobrychus minutus 英名 Little Bittern
と上種 (superspecies) を形成するとのこと。上記2種の和名はコヨシゴイ、ヒメヨシゴイが現在与えられているようであるが、これは山階 (1986) による名前。黒田 (1966) は逆の名称を与えており、茂田氏はこちらの方がふさわしいとの見解である (英名とも対応がよい)。
茂田 (1993) によれば日本鳥学会 (1974) はヨシゴイに亜種を認め、亜種 bryani マリアナヨシゴイをリストに含めていた。この記録 (1937) の論文は三島 (1961) ミクロネシア、朝鮮、日本からの新記録の鳥。
[飼育下のヨシゴイ]
中西悟堂「定本・野鳥記」1 (1935 年初出) に詳しい記述があった。趾のしもやけについては #カッコウの備考の [カッコウは変温動物?] の項目で取り上げた。鳥もしもやけになる。
p. 22 に飼い猫に対しては平気だが、むしろリスには威嚇したとのこと。巣の主な捕食者を反映しているだろうとともに、飼い猫が外来種となった場合地上性の鳥がしばしば無防備となってしまう理由もわかる気がする。
[粉綿羽と櫛状の爪]
茂田 (1993) Birder 7(7): 36-41 はヨシゴイを題材にサギ類の分類とその変遷を取り扱っている。粉綿羽区 (powder down patches; powder down の別称 pulviplumes) の分布も分類上重要な要素であり、この羽毛は絶えず伸び続けて先端が粉綿羽 (bloom 鳥類学用語というより一般の意味で「白い粉」) を形成する。
サギ類は中趾にある櫛状の爪 [pectinate(d) claw, または櫛歯] で粉を他の羽毛に付けて羽毛の状態を整えると言われている。
茂田 (1993) によれば同様の櫛状の爪を持つ系統として他にカツオドリ科、グンカンドリ科、シュモクドリ科、イシチドリ科、メンフクロウ亜科、ヨタカ科を挙げている。
川口 (2014) Birder 28(5): 51 はヨタカの足を取り上げ、同様の特徴を持つ種類としてサギ類があるが生態がかなり異なるので収斂進化と考えるのは無理があり、ヨタカとサギ類がある程度近縁で共通祖先が
櫛歯を持っていたのではとの解釈を述べている。
現代的な系統樹 (#鳥類系統樹2024) によればいずれも Elementaves ではあるがこの系統関係であれば通常は独立に獲得したもの (収斂進化) と解釈されるだろう。
Elementaves には水鳥が多く、その中にかつてはフクロウ類に近いとされていたヨタカ目が入っているのがむしろ意外で系統的に大きく飛んでいるように見えているだけかも知れない。
Cattle Egret Pectinate Claw (YC Wee 2021) に鮮明な写真と、Clayton et al (2010) が 118 科を調べて 17 科のみに見られた研究を紹介している。
機能は外部寄生虫除去に役立つと考えられるが、古くなった粉綿羽の除去や顔の口ひげ状の羽毛を整えるのにも役立つと記しているとのことである (確かにヨタカの場合は最後に挙げられた機能が役立つかも知れない: #ヨタカの備考参照)。この著者は実際にそのように使っているのを見たことがないとのこと。
言及されている論文は以下: Clayton et al. (2010) How Birds Combat Ectoparasites。
この文献ではカワガラス類のメキシコカワガラス Cinclus mexicanus、アメリカグンカンドリ Fregata magnificens 英名 Magnificent Frigatebird の写真が示されている。
Table I に櫛状の爪の有無を調べた結果が出ているが、結構いろいろなグループで見られている。カイツブリ類、ウ類、サギ類、カツオドリ類、ヨタカ類は保有率が高いようであるが、他の分類群でも散発的に見られるものがある。陸鳥では少なくスズメ目では例がなさそうである。ヨタカ類は例外的のようである。
猛禽類ではメンフクロウ亜科のみに見られるのも何か意味があるのだろう。
表を見て何か共通点を考えて見られるのも面白いかも知れない。
Table II に粉の出る鳥のリスト (完全なものではない) や、砂浴び、日光浴なども紹介されており、行動面でも読んで面白そうな論文である。
Waller et al. (2024) Influence of Grooming on Permanent Arthropod Associates of Birds: Cattle Egrets, Lice, and Mites によれば実験的に櫛状の爪がハジラミを除去する証拠は得られなかったとのこと (この論文でも gromming の用語が使われている)。飼育下のアマサギの櫛状の爪を人工的に除去する実験が行われている。
文献では粉綿羽はサギ類や一部のタカ類で発達していると書かれているものがあるが、タカ類の粉綿羽についてはあまり情報がこの項目を記述した当初見当たらなかった。
Bildstein (2017) "Raptors" p. 23 によれば (昼行性猛禽類の) 多くの種が持っていて体に散在しているとのこと。猛禽類では獲物などとの接触する羽の汚れを粉が吸収するのに役立つとある。
How many feathers do hawks, eagles and falcons have?
にもほぼ同じ記述があって出典は同じなのだろうと想像できるが一次文献がわからなかった。
おそらく Wetmore (1920) The function of powder downs in herons が出典か。粉綿羽が見られるグループが散在している例の一つに入っていて the diurnal birds of prey (where they may be found in many other species than currently recognized) とある。
Hindwood (1933) The Green-backed Mangrove-heron. Part 2. Powder down feathers. Emu にもあり、インコ類に並んで some Hawks と出ている。もしかするとインコ類と系統の近いハヤブサ類の可能性もあるかと多少感じてしまった。
Powder down and the Black-crowned Night-Heron (Sibley Guide 2011) のコメントにフクロウ類が粉綿羽を持っているとの記載の紹介がある。
Miller in 1924 (p. 329 of Further notes on ptilosis)
にメンフクロウで "a well-marked patch [of powder down] on each side of the rump, as well as scattered downs on the interscapular and scapular regions and on the breast" の記述があり、あまり記述されないだけで多くの種に痕跡器官のように存在するのではと述べている。
Chandler in 1916 (p. 258 of A study of the structure of feathers, with reference to their taxonomic significance) にアナホリフクロウでも見つけたとの記述があるとのこと。
この文献によれば Chandler (1914) "Modifications and Adaptations to Function in the Feathers of Circus hudsonius" がアメリカハイイロチュウヒで "powder-down" と記述したとあるので、"powder-down" の英語の用例の出典は何とタカだった。
Chandler (1916) では a few Falconiformes とある (この名称は当時はハヤブサ類も含めたワシタカ目)。
Gadow (1891) "Voegel. I. Anatomischer Teil" も引いていて多くの種類に見られることがすでに述べられており、古くから知られていたが英語ではラテン語由来の学術用語が使われていた模様。
Ernst Schuez (1927) "Beitrag zur Kenntnis der Puderbildung bei den Voegeln" で粉綿羽の古典的レビューがあるが、フクロウ類が粉綿羽の最適の例とは言えないと述べているとのこと。
レバントハイタカ Tachyspiza brevipes Levant Sparrowhawk で脇腹にフェルト状のパッチを見たが、北米の (広義) Accipiter では他に見たことがないとのコメントがあるが後続の情報はない。
野生動物救護センターの方もサギ類では気づいていたがハト類にあるとは知らなかったとのコメントが出ている。
Holland (1861) Umriss einer allgemeinen Ptrographie にも出ていた。p. 31 にドイツ語名で Puderdunfluren (Puder = 英語 powder。Dunenfedern 綿羽。Flur 平野、境界など から派生して日本語の羽区に相当) とされ、Circus 属では骨盤部両側に左右1対の粉綿羽区があるとのこと。
Elanus 属でも見られるものがあると書いてあると「一部のタカ類で発達している」と解釈されて伝えられて行っても不思議でなさそう。
Jollie (1976, 1977) p. 35 fig. 25 のシンジュトビ [高野 (1973) ではシロクロトビ] Gampsonyx swainsonii Pearl Kite (Elanus 属ではないが近縁の カタグロトビ亜科 Elaninae) の粉綿羽区の図があることに気づいた。一緒に示されているカンムリカッコウハヤブサ Aviceda subcristata Pacific Baza (ハチクマ亜科 Perninae) にはない (図の番号が上下逆順になっているので注意)。これを見ると何の役割なのか気になってしまう。
シンジュトビは非常に小型のタカで主な食物はトカゲで小鳥やカエル、昆虫も食べるとのこと。Vigors (1825) が記述した時にはヒメハヤブサ類 (falconets) と色彩面でもそっくりであると述べたとのこと (この例でもタカとハヤブサは連続的で中間型があると考えられても不思議ではなかった)。20 世紀中頃まではハヤブサ類に含められていたとのこと。例えば Peters (1931)。タカ類と判断されたのは嘴縁突起がない点と換羽様式からとのこと (wikipedia 英語版より)。
粉綿羽が何の役に立っているのかこの例ではわからなかった。トカゲやカエルのぬめり対策 (??) (もっともチュウヒ類でもよくわからないが)。
粉綿羽の名称に戻るとおそらく Chandler (1914) は英語以外の文献、特に Gadow (1891) などドイツ語文献からヒントを得て "powder-down" の英語用語を作ったのではないだろうか。北米の Circus 属でも探すと文献にある通り同じように見つかったのかも知れない。
かつてのコウノトリ目に含まれていたサギ類 (またはサギ目コウノトリ科の名称もあった) のような粉綿羽区を持つタカ類があったため、かつて広義のワシタカ目がコウノトリ目に近縁と考えられた理由の一つになっていたのかも知れない。
Bailey (1952) The Incubation Patch of Passerine Birds によれば抱卵斑も最初に記述されたのはドイツ語で Faber (1826) が Brutflecke と読んだとのこと。そのまま日本語に訳せば抱卵斑となる。英語用語の incubation patch はドイツ語を訳したものらしい。
粉綿羽の日本の用語もドイツ語由来かも知れない。この文献に当たったのは後羽の由来を調べたのが経緯だったが、ドイツ語では後羽は Afterschaft (Afterfeder, Nebenschaft の用語もあるとのこと) で英語の aftershaft はドイツ語をそのまま取り入れたものではないだろうか。Afterfeder はそのまま訳せば後羽となる。
なおドイツ語の after- は英語の after とは意味が少し違い、後、副、偽などの意味がある。名詞 After では後部、臀部などの意味があり、After- を付けた名詞が生物学用語などに使われる。
羽枝の Ast (複数 Aeste, p. 21) も小枝 (Zweig) よりも太い枝で小枝と幹の中間のような意味だがラテン語 (ramus / rami) をドイツ語に訳しただけかも知れない。
羽の Ast であることを明確にするために Federast (フェーダーアストと読む) とも記され、これをそのまま訳せば羽枝となる (wikipedia ドイツ語版の Feder 参照)。
英語の barb から日本語の用語を想像するのは難しいがドイツ語ならば対応している。
通常のドイツ語用語では小羽枝に対応するものは Strahl (光線などを指す意味) でこの用語は日本語と対応していないように思える。
用語は羽小枝か小羽枝かの問題 [「羽小枝」か「小羽枝」か? (マーリン通信) を参考に検討]
は「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) では「小羽枝」が用いられており、第一人者の黒田長久氏が記述されているので当時から市民権のある用語だったのではないかと想像する。ちなみにもう少し後の時代の旺文社の学習図鑑でも「小羽枝」が用いられていた。
日本語の段階で生じた違いかも知れないが、ドイツ語に少し厄介な問題があって -chen (ヒェンと読む) の指小辞・愛称がある。Astchen (アストヒェン) の使い方もあって指小辞だと思えば "小さい" を付けた用語に、あるいは愛称と解釈すれば特に "小さい" を付けない訳が考えられる (Vogelchen は Vogel "鳥" の愛称で、小鳥と訳すのは必ずしも適切でない)。このあたりの曖昧さ、あるいはラテン語から訳す場合の考え方の違いから羽小枝と小羽枝の両方の用語が生じたのではないだろうか。
Vogelfeder - Lexikon der Biologie によれば Nebenast の名称もあった。この場合は副枝ぐらいの意味。
本稿では上記一般向けで知名度の高い図鑑で広く使われていた理由から小羽枝の用語を用いておく。どの分野でも同様だが学術用語集と現場で使われる日本語の用語が必ずしも対応していないこともあり、研究者もそれぞれの立場で用いつつもお互いに同意語と認識して他者の用例を気にしないこともしばしばある (もっとも、学術界では英語の用語を用いれば何の問題もないことが多い)。
この場合はそのケースではないかも知れないが、用語集を作るに当たって日本語の用語が必要になり、あまり使われていなくても載せざるを得なかったものも多いのではないだろうか。
なお「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4) では "ふしょ" に相当する名称に "ふしょう" を用いていた。中足骨の旧称である蹠骨 (中国語ではそのまま使われている) の読み方が "しょこつ" らしいので "ふしょ" または "ふしょう" の読み方で正しいのでは? 蹠の漢字の読みに ショ / セキ の両方があるので、よく言われるように "ふせき" を誰かが書き誤って "ふしょ" となったのは俗説のような気がする。
鳥の体の部位の名称とドイツ語用語の関連は#カタグロトビ備考 [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] にも考察がある。
天文学でもそうだったが当時の世界の学問の中心地はドイツで、雑誌もドイツのものが主流だった。アメリカの雑誌はドイツの雑誌名をそのまま英語に訳したようなものが発刊され、後追いする形で進歩していた (そして第二次世界大戦を迎えることになる...)。当時の科学英語でもドイツ語などの外国語から概念を輸入したものが多くあるはず。
日本も開国時代にこれらの 19 世紀後半の文献が主に入ってきていたのではないだろうか。
ご存じのように日本ではかつてはドイツ医学を輸入していたため用語にドイツ語が多数残っている (かつてはカルテもドイツ語で書かれることも多かった)。今ではあまり使われないかも知れないが赤血球沈降速度 (血沈) Blutkoerperchensenkungsgeschwindigkeit (4単語の合成) はドイツ語の名詞がいかに長くなることができるか代名詞のような存在であった。
鳥類学でも関連が深い可能性があり、用語の由来を調べる時は英語に閉じるよりも先例となった可能性のあるドイツ語文献も見た方がおそらくよい。
尾脂腺の機能
Elder (1954) The Oil Gland of Birds に面白い情報があった。
尾脂腺は走鳥類 (平胸類) の成鳥に存在しないことから尾脂腺を欠く形質は祖先的なものと考えられたが一部の種の胚には存在するので二次的に失ったものとされるとのこと。
この文献に尾脂腺の機能について過去のさまざまなアイデアが出ていてこれも面白い。我々は尾脂腺の機能を早々に教えられるが、歴史的にはさまざまな議論があったとのこと。19 世紀に観察記録があったものの、哺乳類との類似性から臭腺だろうとのアイデアも結構受け入れられていたらしい。羽毛の脂分への尾脂腺の寄与は大したことがないと考えられていた。
尾脂腺の脂分が撥水性を与える解釈も案外新しく 20 世紀前半でも解釈は混沌としていた。実は powder down の方の機能が先に知られていたようで、尾脂腺が同じ役割を果たすことは Schuez (1927) や Esther (1938) が提唱したとのこと。Percy (1951) がサンカノゴイやアオサギがウナギのぬめりで羽毛が汚染された場合に powder down と脂分を同時に用いる写真記録を残したとのこと。
それまでのアイデアが研究を整理し、自ら実験も行ったこの Elder (1954) の研究によって尾脂腺の役割が確立したと言えるよう。歴史は意外に新しかった。
尾脂腺の機能を再検討したレビュー: Moreno-Rueda (2017) Preen oil and bird fitness: a critical review of the evidence。研究者の間で意見が一致している機能についても調べると意外にわかっていない。羽毛のメンテナンスに重要であることは確かだが機構はよくわかっていない。
抗病原体機能は実験室では確かめられているが生体で起きているかは不明。ハジラミに対する効果は証拠がない。撥水性を与えることは間違いないが細かい機構はよくわかっていない。一方揮発性化学物質がコミュニケーションに役立っている証拠は増えてきている。
こちらは尾脂腺があまり発達していないハトでも抗病原体に役立っていて加齢とともに能力が下がるとの研究: Moustafa et al. (2025) Morphological and Molecular Identifications of the Microbial Population Inhabiting the Feathers of the Domestic Pigeon at Different Ages, With Special Reference to the Antimicrobial Impact of Preen Secretions Against the Identified Microbes。
-
オオヨシゴイ (将来の属学名変更に注意)
- 学名:Ixobrychus eurhythmus (イクソブリュクス エウリュトゥムス) バランスのよい (羽衣の) ヨシゴイ
- AviList 学名:Botaurus eurhythmus (ボータウルス エウリュトゥムス) バランスのよい (羽衣の) 雄牛のようなヨシゴイ
- 第8版属名:ixobrychus (合) 葦原で大声で鳴く鳥 (ixias アシのような植物 brukhomai 大声で鳴く、吠える Gk)
- AviList 属名:botaurus (合) 雄牛のようなヨシゴイ (butio ヨシゴイ類 taurus (m) 雄牛)
- 種小名:eurhythmus (合) eurhuthmos 優雅な、バランスのよい < rhuthmos 調和、形 (Gk)
- 英名:Schrenck's Little Bittern (ロシアの博物学者 Leopold von Schrenck から), IOC, AviList: Von Schrenck's Bittern
- 備考:
ixobrychus は#ヨシゴイ参照。
botaurus は#サンカノゴイ参照。
eurhythmus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。ラテン語の rhythmus (リズムの意味) は rhyth-mus と区切りアクセントは冒頭 (エウリュトゥムス)。
単形種。
絶滅危惧 IA 類 (CR)。世界的には特に懸念なしとされる (IUCN)。
WGAC 0.04 で Botaurus eurhythmus に変更。
英名は AviList が Von Schrenck's Bittern、Clements 2024, BirdLife v9 が Schrenck's Bittern と扱いが分かれているが、この中では AviList が最も新しいので Clements 2025 でこちらに統一されるかも。
英名に現れる人名表記の扱いについては Minor on Chloris kittlitzi (Seebohm, 1890) and others を参照。"von" はプロイセン時代に称号として与えられたもので人名の一部とみなすかが議論になっている。
学位論文では Leopold Schrenk となっているとのこと。人名由来の英名を排除する動きもあるが学名からよい英名を思いつかないとのこと。学名の eurhythmus は Swinhoe (1873) が成鳥は美しい鳥で、若鳥の羽衣に独特の特徴があることしたから、とのこと (The Key to Scientific Names)。
原記載、
図版 では今一つよくわからない。
ドイツ名は満州のゴイサギに相当するがこれも分布をよく反映していないとのこと。
v. Schrenck の Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856
での記述 (Ardetta cinnamomea = 現在はリュウキュウヨシゴイ の学名になっている)。
Swinhoe (1873) は v. Schrenck は幼鳥を観察したと考え、Ardetta cinnamomea (リュウキュウヨシゴイ) からは区別できるので新種として記載したとの流れのよう。
虹彩にある特徴的な模様 (heterochromia) については関連情報が #シロアジサシ備考 [縦長の瞳孔を持つ鳥] と
#カッコウの備考 [非対称な色彩の虹彩を持つコミチバシリ] にある。
後者は heterochromia の生態的適応についても考察しているがオオヨシゴイにも当てはまる説明かどうかは不明。
オオヨシゴイやリュウキュウヨシゴイの正面顔の写真を見て別の解釈を思いついた。正面から見ると瞳孔の後側に影があるように見えて瞳孔の輪郭がわかりにくいのである。
参考 Schrenck's Bittern (Yifei Zheng 2024.12.20)。Cinnamon Bittern (Mei-Luan Wang 2025.1.13)。
つまり目を隠しているのだろうか。擬態 (自身が捕食する際も対捕食者に対しても) の一部と言えるかも知れない。ヨシゴイも過眼線があって瞳孔がわかりにくくなっている。誰かがすでに記述しているかも知れない。
-
リュウキュウヨシゴイ (将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Ixobrychus cinnamomeus (イクソブリュクス キンナモーメウス) シナモン色のヨシゴイ
- AviList 学名:Botaurus cinnamomeus (ボータウルス キンナモーメウス) シナモン色の雄牛のようなヨシゴイ
- 第8版属名:ixobrychus (合) 葦原で大声で鳴く鳥 (ixias アシのような植物 brukhomai 大声で鳴く、吠える Gk)
- AviList 属名:botaurus (合) 雄牛のようなヨシゴイ (butio ヨシゴイ類 taurus (m) 雄牛)
- 種小名:cinnamomeus (adj) シナモンのような (cinnamomum (n) シナモン -eus (接尾辞) 〜色の)
- 英名:Cinnamon Bittern
- 備考:
ixobrychus は#ヨシゴイ参照。
botaurus は#サンカノゴイ参照。
cinnamomeus は o が長母音でアクセントもここにある (キンナモーメウス)。ほとんど学名のみに使われる。ラテン語の cinnamomum の -mo- の o が長母音であるため。起源となるギリシャ語も同位置が長母音。
単形種。
WGAC 0.04 で Botaurus cinnamomeus に変更。
虹彩にある特徴的な模様 (heterochromia) については関連情報が #シロアジサシ備考 [縦長の瞳孔を持つ鳥] と
#カッコウの備考 [非対称な色彩の虹彩を持つコミチバシリ] にある。
後者は heterochromia の生態的適応についても考察しているがリュウキュウヨシゴイにも当てはまる説明かどうかは不明。#オオヨシゴイの備考も参照。
Lansdown (1988) Some Calls, Displays and Associated Morphology of the Cinnamon Bittern (Ixobrychus cinnamomeus) and Their Possible Functions
によれば首の基部にある粉綿羽区からの粉が頭頂の着色に寄与している可能性が高いとのこと。
-
タカサゴクロサギ (将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Ixobrychus flavicollis (イクソブリュクス フラーウィコルリス) 黄色い首のヨシゴイ
- AviList 学名:Botaurus flavicollis (ボータウルス フラーウィコルリス) 黄色い首の雄牛のようなヨシゴイ
- 第8版属名:ixobrychus (合) 葦原で大声で鳴く鳥 (ixias アシのような植物 brukhomai 大声で鳴く、吠える Gk)
- AviList 属名:botaurus (合) 雄牛のようなヨシゴイ (butio ヨシゴイ類 taurus (m) 雄牛)
- 種小名:flavicollis (adj) 黄色い首の (flavus (adj) 黄色の collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Black Bittern
- 備考:
ixobrychus は#ヨシゴイ参照。
botaurus は#サンカノゴイ参照。
flavicollis は a が長母音で -col- がアクセント音節 (フラーウィコルリス)。
タカサゴクロサギの "タカサゴ" は海外の意味で理解できるが、クロサギは英名 Black Bittern 由来だろうか。この英名の由来がはっきりしない。
オーストラリア地域に同属の種が複数分布し、ヒメヨシゴイ Botaurus minutus Little Bittern や セグロヨシゴイ Botaurus dubius Black-backed Bittern は同種とされたこともあり、後者には過去の学名 Botaurus melanotos Brehm, 1842 があって英名は明らかにこの学名を引き継いでいる。
これら同地域に分布する種類をまとめて Black Bittern と呼んでいた時期があって、最もふさわしいタカサゴクロサギに名前を残したのだろうか。総称して Black Bittern と呼ばれていた時期があったらしい痕跡としてタカサゴクロサギの英語別名に Mangrove Black Bittern がある。
Mangrove Heron は分割される前のササゴイの名称でもあった。
タカサゴクロサギをタイプ種として Dupetor 属が設けられたことがあった (Heine 1890)。doupetor < doupeo 重く響く音を出す (Gk)。これは当時使われていた Ardeiralla Bonaparte, 1855 は造語に問題があり、Butoroides Gould, 1865 はすでに使用されていると考えて新しい属名を設けたもの (The Key to Scientific Names)。
Butoroides は現在ササゴイ属として残っている。Ardeiralla 属 (Ardea 属と Rallus 属の合成) はクロヨシゴイをタイプ種として設けられたもので、現在は Ixobrychus 属に吸収された後、現状さらに Botaurus 属に吸収される形になっている。
Dupetor 属もタカサゴクロサギのみを含む属として近年でも時々用例がある。見ての通りサギ類の分子系統解析はまだ混乱の最中で Botaurus 属を分割する必要性が生じればこれらの古い属名の中には復活するものがあるかも知れない。
Ixobrychus 属のタイプ種がヒメヨシゴイなので、この種がどの系統に含まれるか次第でタカサゴクロサギなどの属名も変わる可能性が残っている。
3亜種あり (IOC)、日本で記録されるものは基亜種 flavicollis とされる。
WGAC 0.04 で Botaurus flavicollis に変更。
-
ミゾゴイ
- 学名:Gorsachius goisagi (ゴルサキウス ゴイサギ) ゴイサギ
- 属名:gorsachius (合) ゴイサギから? (グワッと鳴くワタリガラスから?)
- 種小名:goisagi (外) ゴイサギ
- 英名:Japanese Night Heron
- 備考:
gorsachius は独自音型なので発音はよくわからないが、すべて短母音とすれば -sa- がアクセント音節と考えられる (ゴルサキウス)。
goisagi もラテン語風ですべて短母音とすれば "ゴイサギ"、-sa- を長音で読めば "ゴイサーギ" となるがどちらかが優先される理由は多分特にない。好み次第でどうぞ。
単形種。Gorsachius 属のタイプ種。
日本の繁殖固有種と思っていたが、AviList (2025.6) では繁殖分布に済州島と台湾が含まれていた。
wikipedia 英語版によれば台湾の繁殖事例は1例とあった。日本でも繁殖確認が難しいことを考えると、台湾で留鳥のズグロミゾゴイと音声が非常に似ているので実際にはもう少し数が多く音声記録で誤認されている場合があるかも知れない。
済州島の音声記録がある: XC482779 (Jungmoon Ha 2019.6.17)。記述を見ると複数つがいが繁殖しているらしい。ほぼ同時期の 2025.6.22 の早朝に地元京都で声を聞いた。音声記録は GW ごろの渡り時期が多いが、噂をすればなんとか、というものかも。また済州島での記録はこの種が想像されているよりは数を増やしている兆候となっているのかも知れない。
台湾で記録された地鳴き XC661525 (Sunny Tseng 2021.4.19)。
[属名由来の検討]
Nycticorax goisagi Temminck, 1836。原記載。
中で出てくる Bihoreau (gris) はゴイサギ Nycticorax nycticorax のことで、これは日本にも生息しているが、Goisagi はヨーロッパにもいる Bihoreau より少し小さいとか色が違うなど記述している。
フランス名は現在でも bihoreau goisagi となっているが、他言語では "日本の" が多く、色を用いたもの (ドイツ名 Rotscheitelreiher 頭の赤いサギ、中国名で栗または麻のサギ) もある。
Temminck (1836) では日本語の名称は Awogoisagi または略して Goisagi と記述しており、アオゴイサギが本来の名前だったのを略してしまったのかも知れない。この日本語の名称は見つけられなかったが、
青鷺火 (あおさぎび、あおさぎのひ) は、サギの体が夜間などに青白く発光するという日本の怪現象 (wikipedia 日本語版。中国語版にも紹介されている)。これはアオサギではなくゴイサギを指すとされるとのこと。関係があるかも知れない。古くはゴイサギなどを含むサギ類を広く五位鷺と呼んでいたらしい。
属名は Botaurus (現在はこの名称はサンカノゴイ属)
または Gorsachius (フランス動物学者 Jacques Pucheran による分類で種小名から作られたもの) とも名付けられていたものを Bonaparte (1855) が整理して記述したもの。Goisakius, Goisachius の綴りもあって (この綴りであれば由来がよくわかる) シノニムとされる (The Key to Scientific Names)。
属の記載。
"r" が入った理由はよくわからないが、命名者 (Pucheran) がフランス人で goi- が不自然な発音になる (フランス語では oi は wa の音になる。偶然ではあるが goi- を "グワ" と発音すればゴイサギの鳴き声にそっくりになる) ため発音しやすくするために "r" に変更したのかも知れない。
他の音 (特に s, n や l) を r に変える rhotacism (ロータシズム) という音韻現象があるので関係しているかも知れない。
属記載では必ずしも判然としないが、属名の Nycticorax の r を借用した (cor と gor の類似性から corax ワタリガラス を部分的に活かした) のかも知れない。こちらがよりがあり得そうな気がする。
我々は Gorsachius を見て日本語の "ゴイサギ" 由来と考えるが、実は corax の冒頭を goisagi の g を借用して g に変えて (フランス語読みするとヨーロッパにも生息するゴイサギの声そっくりになるのに掛けているかも) 属名にふさわしいラテン語風の語尾を付けたものかも。#ゴイサギの和名にも音声由来説がありこちらも参照。
Pucheran が初めてこの属名を用いた時の学名は Gorsachius typus (資料) で、これは有効な学名とはみなされないが typus はタイプ種の意味。これを見ると goisagi を属に昇格を意図したものと思える。
同様の例では種小名の ducorps から昇格され Ducorpsius typus Bonaparte, 1850 (現在では Cacatua ducorps のシノニム) となった例があった。より属名らしくなるように末尾を変えていた (The Key to Scientific Names の typus, Ducorpsius の項目から)。
これがそのまま当てはまるとすれば goisagi は属名語尾におそらくふさわしくないので語尾を変えて Goisachius としようとしたが、記載時属名の Nycticorax を部分的に活かしたというところだろうか。
同様の意味の typus がそのまま種小名に採用されている例としてチュウヒダカ Polyboroides typus がある。こちらは属名が種小名から昇格ではなくそのまま残っている。
もう一つ考えられる理由は当時は属名と種小名が同じとなるトートニムが避けられていた (#ノスリの備考参照)。そのため種小名と相違点を与えてトートニムらしくならない形にした可能性がある。#トキで Nipponia 属を提唱した Reichenbach (1853) も擬似トートニムを避けて (別理由もありそうだが) 新種小名を与えた。
Gorsachius ならば goisagi と十分違って見えるので擬似トートニムとされる恐れが少ない、の判断もあったかも知れない。
あくまで個人的な解釈も含めてまとめると、現在のミゾゴイの属名、種小名ともに日本語ゴイサギに由来するが属名の形が大きく違う理由は:
(1) 既存のゴイサギ類属名の Nycticorax のうち corax ワタリガラス を部分的に活かして gor- の語幹を作った (この場合はハイブリッド属名とも言える) (2) Goisachius は特に命名者のフランス語の視点から発音上やや難がある (3) 擬似トートニムを避けて意識的に文字を変えた、が考えられそうに思える。
Temminck (1836) が名付けたように最初は Nycticorax 属とされており、そのまま英名を付ければ Night Heron が付くのは当然で、属名が習性などを反映しているとは限らない点は#イソヒヨドリなども参照。標本を使って分類する学者が異国の鳥の習性まで考慮しないだろう。
かつては夜行性と考えられていたことがあったが、英名やかつての学名に由来する部分もあるのではないだろうか。
[ミゾゴイ類似サギ類の分子系統解析]
Hruska et al. (2023) (#サンカノゴイの備考) によればミゾゴイ類は Ardeinae (アオサギ) 亜科に含まれており、Boyd の分類とは異なっている。
この解析によればミゾゴイやゴイサギ類はむしろコサギやアオサギの系統になり、直感的に似ているように思えるサンカノゴイ類やヨシゴイ類とは別系統になる。ミゾゴイ属は Ardeinae 亜科の中でも最も古く分岐した系統にあたる。ミゾゴイが夏鳥であることから想像できるようにおそらく熱帯や亜熱帯出身で渡り能力を利用して (別項目にあるように完全な渡りを行うものはサギ類では非常に珍しい) より北方に定着したものらしい。
ゴイサギ属は Ardeinae 亜科ではむしろ新しい系統で、現生種では単型属のアメリカ大陸のシラガゴイ Nyctanassa violacea Yellow-crowned Night Heron が祖先系統に対応する。ゴイサギは世界にも広く分布し、フィリピンからオーストラリアに主に分布するハシブトゴイと分布を分け合っている。
ミゾゴイやズグロミゾゴイの分布が比較的限られているのは、世界的な優占種となった後発のゴイサギの影響もあってあまり分布を広げられなかったのかも知れない。ではなぜゴイサギは夜行性でミゾゴイは昼行性なのかと問われるとよくわからないが。
もっとも wikipedia 英語版 Gorsachius を見るとミゾゴイ類はもっとも厳格な夜行性と書かれているので単にそのように信じられているだけなのか、日本のミゾゴイは例外的に昼行性なのか今ひとつすっきりしない。
ハシブトゴイの主な分布域にはアカガシラサギ類などの競合のありそうな種が分布するのであるいは関係があるのかも。例えば日本には昼行性の競合種が繁殖しないためミゾゴイは昼行性となることができたなど。共通祖先が夜行性のため暗い時期によく鳴く性質が残っている (ほんとうか?)。
(この部分後に気づいた) Hruska et al. (2023) で Gorsachius 属が分割される前の話で、ハイナンミゾゴイ 現在の学名で Oroanassa magnifica) White-eared Night Heron などが含まれていた時代の話と想像できる。ハイナンミゾゴイは夜行性とされる (しかしミゾゴイのように調べると昼行性だったと判明したケースもあるので思い込みもあるかも)。
この種はほとんど知られていないが IUCN EN 種。かつては CR 種だったが推定よりも個体数が多かったらしい。しかし減少中と考えられる (wikipedia 英語版より)。
Hruska et al. (2023) の Fig. 3 に示されている通り、伝統的なミトコンドリア遺伝子を用いて解析すると系統樹形が少し変わる。この点はミゾゴイの NC_028194 から出発して BLAST を行っても多少確認できる。
この BLAST 解析結果では Gorsachius の分岐時期がサギ類主要2系統の分岐時期に近い結果となり、どちらに属するか自明でなかった。しかしどの解析を用いても現在の Gorsachius 属 (2種) が古い系統である結論は変わらないよう。
ミゾゴイのこの配列は Zhou et al. (2016) Complete mitochondrial genomes render the Night Heron genus Gorsachius non-monophyletic で調べられたもので、当時の Gorsachius 属が単系統をなさないことを明らかにしたもの。
AviList (2025.6) では Gorsachius 属はミゾゴイとズグロミゾゴイの2種のみとの判断となった。
5293 899 Gorsachius is treated as 3 genera based on the genomic and mitochondrial DNA data of Hruska et al. (2023): monospecific Calherodius (C. leuconotus) and monospecific Oroanassa (O. magnifica), with taxa goisagi and melanolophus retained in Gorsachius. Although Hruska et al. (2023) proposed combining leuconotus and magnificus in Calherodius, these taxa are deeply diverged and occur on different continents, prompting treatment as separate genera.
[島に渡って繁殖するサギ類]
Ferrer et al. (2011) Why Birds with Deferred Sexual Maturity Are Sedentary on Islands: A Systematic Review
によれば大陸から比較的離れた島に完全な渡り (同種のすべての個体が渡りをする) をして繁殖するサギ類は2種のみで、ミゾゴイとマダガスカルカンムリサギ Ardeola idae Madagascar Pond Heron とのこと。後者はアフリカ大陸で越冬する。ミゾゴイの越冬地がフィリピン、台湾などであれば島から島に渡って繁殖する世界唯一のサギかも知れない。
-
ズグロミゾゴイ
- 学名:Gorsachius melanolophus (ゴルサキウス メラノロプス) 黒い冠羽のゴイサギ
- 属名:gorsachius (合) ゴイサギから
- 種小名:melanolophus (合) 黒い冠羽の (melano- (接頭辞) 黒い lophos 丘、冠羽 Gk)
- 英名:Malaysian Night Heron, IOC, AviList: Malayan Night Heron
- 備考:
gorsachius は#ミゾゴイ参照。
melanolophus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-no- がアクセント母音と考えられる (メラノロプス)。
英名は AviList と Clements 2024 が Malaysian Night Heron、BirdLife v9 は Malay Night Heron だが BirdLife の対応が遅れているため、最終的には AviList と同じものになるかも知れない。
単形種。
-
ゴイサギ
- 学名:Nycticorax nycticorax (ニュクティコラックス ニュクティコラックス) 夜のワタリガラス
- 属名:nycticorax (合) 夜のワタリガラス (nychta 夜 Gk、corax (m) ワタリガラス)
- 種小名:nycticorax (トートニム)
- 英名:Night Heron, IOC: Black-crowned Night Heron
- 備考:
nycticorax は外来語由来で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。corax はラテン語では co-rax と区切るのでここにはアクセントが現れず、-ti- がアクセント音節と考えられる (ニュクティコラックス)。
nycticorax のラテン語の用例ではヨタカ類やサンカノゴイ類などを指すとのこと (wiktionary)。
ユーラシア、アフリカ、南北アメリカの中・低緯度帯に広く分布。4亜種が認められている(IOC)。日本で記録される亜種は基亜種 nycticorax とされる。
nycticorax はラテン語で不明の鳥、おそらくフクロウ類 < nuktikorakos (Gk) アリストテレスなどが用いた不吉な鳥でおそらくフクロウ類の一種と思われるが、長らくゴイサギと考えられてきた (The Key to Scientific Names)。
英名の Night Heron は OED によれば 1785 年の Pennant, Arctic Zoology の用例があるとのこと。意外に新しいが学名由来ではなさそう。
ロシア名は kvakva と音声にちなみわかりやすい。
和名の由来は五位を授けられた言い伝えが一般によく採用されているが、鳴き声由来説もあるとのこと。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば 音幻論 (幸田露伴 1947) に登場するとのこと。
茂田 (1993) Birder 7(7): 36-40 では鳴き声由来説の方が有力ではないかと示唆しており、出典に川口 (1937) を紹介している。
鳴き声由来説を面白く感じるのは、ミゾゴイなどの現在の属名 Gorsachius も日本語の "ゴイサギ" 由来でなく音声由来と共通解釈できる可能性が考えられるため。命名者の言語のフランス語で goi- と書けば "グワ" の音になるので音声由来であればゴイサギの名前の由来は東西 (ロシアも) 共通の可能性がある。
#ミゾゴイの備考も参照。
英名の Black-crowned Night Heron は単に性状を示した名称かも知れないが、かつて同属であった シラガゴイ Nyctanassa violacea Yellow-crowned Night Heron に対応する形で付けられたものの可能性がある。
wikipedia 英語版によれば北米で見られる night herons はこの2種のみとのことで、特徴を表してアメリカで2種に付けられたものかも。"Yellow-crowned" を日本では "シラガ" と表現しているようにアメリカの2種では際立って違う特徴として挙げられるだろう
(当時の和名命名者は "シラガ" の名称を気に入っておられたのか他にも多くの用例がある。シラガホオジロもその一つ)。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) でも英国での名称は Night Heron となっている (現代の Collins Bird Guide でも Black-crowned はかっこ付きで、国内の英名と国際的な場合の英名の併記となっている)。
英国では Night Heron に相当するものが1種のみなのでわざわざ長い名前を使う必要がないが、アメリカではそうではなかったので修飾語を加える必要があった。
ご存じの通り頭の黒い night herons はアジアに他にも存在するため日本の鳥の英名としてはあまりふさわしいものでない。あくまで北米の事情に基づく英名と捉えるのが適切であろう。
記載時学名 Ardea Nycticorax Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 southern Europe (南部ヨーロッパ)。
Nycticorax 属は Foster (1817) が種小名から属に昇格したもの。これに伴ってゴイサギには (当時の手法で) Nycticorax infaustus Forster, 1817 の新名が与えられた (当時の人たちは Night-raven と呼んでいて infaustus は不運ななどの意味で死を連想させる鳴き声由来とのこと)。(種小名から属に昇格の場合の扱いについては #ノスリの備考参照)。
Nycticorax 属の用例はシラガゴイをタイプ種とした Boie (1826) にもあったとのこと。こちらは種小名から属への昇格ではない (The Key to Scientific Names の情報より)。
Nycticorax 属への昇格に伴う新名は他にもあって Nycticorax vulgaris Orbigny, 1839 (参考) これは "普通のゴイサギ" の意味。記述によればトートニムを避けるためとのことで、当時はトートニムが積極的に避けられていたらしい。
おそらくその結果新名が氾濫してトートニムでもよい規則となったのだろう。
[疑似餌を使うゴイサギ]
サギ類の中で採食行動に疑似餌を使うものがあることが知られている。アメリカササゴイ Butorides virescens 英名 Green Heron でまず発見され、近縁のササゴイでも見つかった。
Combs and Reglade (2022) Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax) bait-fishes with aninedible lure in Vietnam
によればベトナムのゴイサギで同様の事例が発見されたとのこと。
諸角 (1995) Birder 9(10): 56-58 に東京の不忍池で人が投げたパンを利用して魚を捉えるゴイサギ (1991) の記載がある。この場合は自身が疑似餌として投げたものではないが類似例として興味深い。同記事にはコサギも同様の行動をするとのこと。またカイツブリはパンを細かくして撒き餌のように用いるとのこと。
[ゴイサギの減少とウの増加の関係]
北米でミミヒメウの駆除によって同一コロニー内の下部に営巣するゴイサギが増加した報告がある。生態的地位の近い#カワウの備考に。
[その他]
新倉 (1992) Birder 6(7): 36-41 にコサギに育てられたゴイサギの記事がある (神奈川県 1991 年)。
-
ハシブトゴイ
- 学名:Nycticorax caledonicus (ニュクティコラックス カレードニクス) カレドニアの夜のワタリガラス
- 属名:nycticorax (合) 夜のワタリガラス (nychta 夜 Gk、corax (m) ワタリガラス)
- 種小名:caledonicus (adj) カレドニアの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Rufous Night Heron, IOC: Nankeen Night Heron
- 備考:
nycticorax は#ゴイサギ参照。
caledonicus は e が長母音でアクセントは -do- にある (カレードニクス)。長母音はラテン語の Caledonia の発音由来で本来はスコットランドの意味。ニューカレドニアは新しいスコットランドの意味。Nouvelle-Caledonie がフランスの海外領土の名称。
種和名は過去に記録された以下の日本の亜種 crassirostris に対応するもの考えるとわかりやすい。この亜種の記載時学名は Nycticorax crassirostris Vigors, 1839 (原記載) でこの学名をそのまま訳せばハシブトゴイになる。
原記載には英名は与えられていなかった。
フィリピンからオーストラリアに分布。6亜種が認められているが1亜種は絶滅 (IOC)。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)によれば日本で記録される亜種に crassirostris (crassus 厚い -rostris 嘴の) がリストされるがかつて小笠原諸島に生息していた 1827, 1828, 1889 年の標本があるのみの絶滅亜種 (コンサイス鳥名事典)。他に亜種不明がリストされている。
かつては 亜種 crassirostris をオガサワラハシブトゴイと呼んでいたが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)によればこの亜種をハシブトゴイと呼ぶ。
現在観察されているものは亜種不明のもの。川上他 (2015)
小笠原諸島母島におけるハシブトゴイ Nycticorax caledonicus の記録 によれば亜種 hilli (オーストラリアの昆虫学者 Gerald Freer Hill に由来。オーストラリアの亜種) または pelewensis (Pelew/Palau/Belau ミクロネシアのパラウ島由来、ナンヨウハシブトゴイの和名あり) の迷行が考えられるとのこと。
ちなみにフィリピンの亜種 manillensis (マニラの、マニラハシブトゴイの和名がある) は色彩などの特徴から否定されるとのこと。
絶滅亜種 crassirostris は 亜種 hilli に近いとある (コンサイス鳥名事典)。
IOC 英名の nankeen は中国由来の薄い黄色の絹の織物を指す。織物の由来した南京 (Nanjing) から (wikipedia 英語版)。
Hume (2024)
Osteological and historical data on extinct island night herons (Aves: Ardeidae), with special reference to Ascension Island, the Mascarenes and Bonin Islands
が亜種 crassirostris (Bonin Night Heron) の標本も含めた検討を行っている。crassirostris は基亜種に比べて嘴がよりまっすぐで厚く長い (写真比較あり)。翼が短くふしょが短い点は島で隔離進化した亜種に共通している。
crassirostris はこれらの点が他亜種に比べて最も特徴的とのこと。少数の島にのみ生息する pelewensis (ナンヨウハシブトゴイ) に最も似ているとのこと。
標本として残っている小笠原のハシブトゴイの2個体には違いがあり、媒島 (1889 年最後の標本) のものは嘴がより短いなど比較的 manillensis (マニラハシブトゴイ) に似ている。小笠原内部でも個体差があるか、あるいは単一亜種ではなかった可能性がある。他亜種との分子系統の関連を調べるのは興味深いとある。
-
ササゴイ (世界のリストで亜種が分離される。将来の学名変更に注意)
- 第7・8版学名:Butorides striata (ブートリデース ストッリアータ) 条斑のあるサンカノゴイに似ているサギ
- AviList 学名:Butorides atricapilla (ブートリデース アートゥリカピルラ) 黒い髪のサンカノゴイに似ているサギ
- 属名:butorides (合) サンカノゴイに似ている鳥 (かつてあったサンカノゴイ類を示す Butor 属、-ides (接尾辞) 〜に似ている)
- 第7・8版種小名:striata (adj) 条斑のある (striatus)
- AviList 種小名:atricapilla (adj) 黒い髪毛の (ater (adj) 黒い capillus (m) 髪毛)
- 英名:[Green-backed Heron 分離前の名称], IOC: Striated Heron (14.2 まで), Little Heron (15.1 = AviList)
- 備考:
butorides の読みはラテン語 butio (#サンカノゴイ参照) を参考にし、-ides (似ている。ギリシャ語由来) の語末が長母音であることを参考にした。アクセントは -to- にあると考えられる (ブートリデース)。
striata は最初の a が長母音でアクセントもある (ストッリアータ)。-ata は所有の語尾ではなく strio (縞。語末が長母音) の変化形由来。
atricapilla は冒頭が長母音で (ater 由来) -pil- がアクセント音節 (アートゥリカピルラ)。
Green-backed Heron の英名はかつて同種とされた Butorides virescens 英名 Green Heron アメリカササゴイ と Butorides sundevalli 英名 Lava Heron ガラパゴスササゴイ が分離される以前のもの。これらが別種とされる以前は北半球・南半球の中・低緯度に汎世界的に分布する種類であった。
ササゴイは 21 亜種 (IOC 14.2 段階) が認められている。日本で記録される亜種は amurensis (アムールの) とされる。
上記 IOC 15.1 の学名・英名は Proposed Splits/Lumps IOC Version 15.1 (DRAFT) (2025.1.12) より推定。
この記述では分離後の Butorides striata は何と単形種 (これまで 21 亜種もあったのに!)。英名の Striated Heron はこの種が引き継ぐ。
記述は簡明なもので、単形種の表現から個々の亜種がどちらに含まれるか疑問点はないが、系統樹も含めてよく見ないと何が起きているのかわかりにくい。
この記述および Mendales (2023) Ultraconserved elements resolve the phylogeny of a globally distributed genus, Butorides (Aves: Ardeidae) (修士学位論文) の分子系統樹から判断すると、残り全てが Butorides atricapilla で日本のササゴイの種英名も Little Heron となるものと考えられる。
striata が基亜種で、基亜種のみを別種に分離するために発生する現象。
AviList (2025.6) では日本のササゴイの種学名は Butorides atricapilla。
5358 1171 Four species are recognized in the Butorides striata complex based on the genomic DNA evidence of Mendales (2023): monotypic B. sundevalli from Galapagos; polytypic B. virescens from North America; monotypic B. striata from South America; and a polytypic Old World B. atricapilla group. While further splits in the B. atricapilla group may be warranted, genetic sampling was too geographically limited to properly assess these; further research needed.
Butorides atricapilla がさらに分割される含みを残しているが、現状遺伝的にも地理的にもサンプルが不完全すぎる。
英名を決めているリストは IOC 15.1 のみで、AviList はこの名称を引き継いで Little Heron を採用。ササゴイの英名は世界的レベルでは Little Heron となる。
前述の Boyd の分類はさらに分割して英名も学名も異なるものとなっているが、現状は AviList に従うのがよいだろう (後の解説に経緯がすでに含まれているので参照)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではアムールサギの名称が与えられていた。
「夏の鳥」(小学館 1984) p. 177 によれば光沢のある白い縁取りのある羽をササに見立てたのが和名の由来と説明されていた。
どこにでも生息していたと思われる割には現在の和名の由来は意外に新しいようで、山階鳥類研究所標本データベースを見ても確実な日付の入っている古い時代の日本列島中央部のものがあまりない。
YIO-08197 (神奈川県 1886) でミノゴイのラベルあり。ササゴヰのラベルも別に付いていた。
YIO-08207 (埼玉県 1888) ではミノゴイ、ササゴイの名称がラベルに示されていた。
YIO-08195 (東京都小石川区 1891) のラベルにササゴヰとなっていた。
この時代には表記がまだ統一されていなかったらしい。古い時代はミノゴイの方が主流だったのかも。
"ミノ" で始まる和名を持つ種はいくつかあるが、"ミノゴイ" と同じ意味で用いられているだろう例はミノバト Caloenas nicobarica Nicobar Pigeon (Vulturine Pigeon の別名もあった - 顔つきから)。ササゴイの方はそこまで形態的に特殊でないかも知れない。
ややこしいことにミノゴイと呼ばれる種が別にある。シラガゴイ Nyctanassa violacea Yellow-crowned Night Heron で、日本産種ではないのでどちらが標準和名というわけではないが、wikipedia 日本語版はミノゴイを用いている (2025.6 現在)。ササゴイの別名だったことを考慮するとシラガゴイの方がよいのかも知れない。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 24 によればササゴイの "ササ" にはいささか、ささやか、さざ波など小さい、こまやか、ほっそりの意味があるとのこと。この書物では雨覆羽が笹の葉のように見えるのでササゴイの説を採用している。
植物の方の "ササ" も複数の語源説があるが、そのうち一つのササダケ (細小竹) に対応した説明と思われる。wiktionary を確認すると中国語の笹の文字は日本語からの借用とある。つまり国字。
[分類と学名]
#サンカノゴイの備考にあるように、2023 年の分子系統解析結果からササゴイが分割される可能性が高い (上記アメリカササゴイの分割とは別物)。
現在の名称のササゴイの分布は非常に広く、世界各地のサンプルが調べられたわけではないのでどのように分割すべきかはまだ確定していないが、南米を別種とすべき点はほぼ確実とのこと。
基亜種 striata は南米のものなので、分割されれば日本のササゴイを含めて残りのグループの種小名が変わることになる (IOC 15.1 でこの通りとなった)。
以下記載年代順による名前。南米以外がもしすべて同種とされれば Butorides atricapilla となるだろうがこの亜種はアフリカのもの。もしアフリカのものも別種とされればアジアのものが Butorides javanica とまとめられることになり、Boyd はこの学名を採用している。
問題となるのは日本周辺の夏鳥の亜種 amurensis とアジア熱帯地域の留鳥亜種の javanica グループとどの程度違うかであろう。
もし亜種相当でよければ Butorides javanica amurensis となるが、種扱いであれば Butorides amurensis となることもあり得る。これは DNA を調べないとわからないだろう。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 で Striated Heron Butorides atricapilla を採用。eBird では以前から採用されている。南米とそれ以外を分ける形となった。IOC 14.2 でも採用され、現状の世界標準になると思われる (← この部分は 2024 年段階の記述で誤っていた。まだ採用されていなかった)。
IOC 14.2 で変更点があまりに多くて全てを処理しきれず、一部が 15.1 に先送りとなった分類変更に含まれていたのだろう。
その後 IOC 15.1 で別英名で採用。Little Heron Butorides atricapilla。
南米の種は Working Group Avian Checklists, version 0.04 で Grey-necked Heron Butorides striata が提案されていた。和名がすでにあるのか知らないがナンベイササゴイは妥当なところか。
IOC 15.1 では英名 Striated Heron はこちらが引き継ぐことになった。
新称 "Little Heron" は確定すれば海外のバーダーも用いるようになると思われるので我々も慣れておくのが望まれる。コサギと勘違いしないように。
すでに別種となっていた ガラパゴスササゴイ Butorides sundevalli Lava Heron とこれまでの広義のササゴイが Mendales (2023) の研究で互いに単系統とならないため、ガラパゴスササゴイをササゴイの亜種とするか (ガラパゴスの他の固有種を考慮すると独立種とするのが妥当なのだろう) ササゴイを分割するかいずれかを選択する必要があった。
分子系統研究が行われていて確実に分離できる南米のグループのみをササゴイ類縁グループ内で最低限分離したもの。
Latest IOC Diary Updates (BirdForum 2025.1) でもこの修士論文をどのように評価するか議論がなされている。論文出版済みの結果ではないのでもう1年待ってもよいとの意見もある。
Little Heron と Striated Heron の分割は誰もが興味を持っているが、ガラパゴスササゴイと互いに単系統の関係にならない点は誰もあまり言及していないのも不思議。#オオタカとアメリカオオタカだけを見比べても別種にすべきかどうか判定が難しいが、他の種と互いに単系統の関係にならないのと同様の問題。
さらに分離を行うか否かは、アジアの大部分とアフリカは別クレードとなっているのでこれを別種と判定するか次第となる。アジアのものでは javanica のみがアフリカのクレードに入っており、分離前に 21 亜種もあったのでまだ未解析のものが多いため分割が見送られたものと想像できる。
ガラパゴスササゴイとササゴイを別種とみなすならば、同程度より古い分岐年代のクレードを別種と考える Boyd のような扱いが意味を持つだろう。
今後アジアなどの分子系統研究が進めばさらに分離されて学名や英名が変わる可能性がある。日本のササゴイと javanica が同じクレードに入るかどうかはわからないので Boyd の分割が適切かは今後の研究次第。
[ササゴイの夜間飛翔中の声]
2025.5.20 早朝に聞いたので声の確認をしておくこととした。録音は行っていなかったので確実な証拠とはならないが参考記録として。
「キュ」と1声ずつかなり間を置いて区切って鳴き、音の移動から明らかに飛んでいることがわかる。他に該当する種類を思いつかない。時期的には少し遅いかも知れないが2日前にホトトギスなどを集中的に記録した時期でもあり、渡り途中かも知れない。
「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) p. 43 によれば "また夕方や夜間、明け方には、「キュ」「キュウ」などと1声ずつ鳴きながら飛んでいくのが見聞できる。このときの声は、前記の繁殖地のものと比べて、短く鋭い印象がある" との記述がある。よく該当している。
xeno-canto では中国などで nocturnal flight call (NFC) がかなりの数記録されている。
XC992682 (Ray Tsu 2024.4.20) など都市部でも記録されていて知らないと気づかない (あるいはキツツキ類などと誤認されている? が、夜間空から聞くのは不自然?) かも知れない。繁殖地で聞く声とは少し違う可能性があり、そもそも話題になりにくい種類なので参考までに紹介しておく。
バードリサーチの音源図鑑では平野敏明氏の地鳴きがある (2025.5 現在1つ) が声の性状は異なる。自分が過去に繁殖地で記録した「キュ」タイプの音声は平野氏のものと同じものだった。他のタイプの音声に他のサギ類に似たしわがれ声もある。
ゴイサギの夜間飛翔時の声はよく知られているが、系統の違いを反映するのかササゴイでは声がまったく異なっている。ミゾゴイではさえずりに相当する声を聞くが、ササゴイのような音声はあるのだろうか。
松田 (2022) Birder 36(10): 34-37 に夜間飛翔時の声が紹介されていた (ササゴイは p. 37)。この記事は最後の2種がかなり "通" 向けでもう1種がシマアジ。
繁殖地と夜間飛翔中の声が異なっていることで有名な種類にカイツブリがあり (#カイツブリ備考 [絶滅した飛べないカイツブリ類] に関連して NFC に触れた)、カイツブリもしっかり飛べること、NFC をどのようにして見えないカイツブリと判断できるのかなど話題も多い。
[その他]
アメリカササゴイの CT scan データが公開されている: Green heron (Florida Museum oVert)。
-
アカガシラサギ
- 学名:Ardeola bacchus (アルデオラ バククス) ブドウ酒色の小さなアオサギ
- 属名:ardeola (f) 小さなアオサギ (ardea (f) アオサギ -ola (指小辞) 小さい)
- 種小名:bacchus (m) 酒神バッカス、ブドウ酒
- 英名:Chinese Pond Heron
- 備考:
ardeola は短母音のみで -de- がアクセント音節 (アルデオラ)。指小辞の -ola は伸ばさない (-ulus 同様)。
Bacchus (ラテン語では固有名詞) は短母音のみで冒頭がアクセント (バククス)。-cc- は長い k の音にする読み方もあるらしいが一般的には分けて読む。
記載時学名 Buphus bacchus Bonaparte, 1855 (原記載)。基産地マレー半島。
属名に使われた Buphus bouphos (Gk) は不明の鳥で夜中に大きな声で鳴くとのこと。異なる種とタイプ種としたこの属名の用例が2つあったがいずれもサギ類だった (The Key to Scientific Names)。
Ardeola の属名は3つの用例があったが、最も早い Boie (1822) のものが採用された。この属はカンムリサギ Ardeola ralloides Squacco Heron の1種を指したもので自動的にタイプ種となる。この種の記載時学名は Ardea ralloides Scopoli, 1769 だった。
Boie は (サギ類にしては) 足が短いとの表記 (Kennzeichen der Gattung: die kurzen Fuesse)。(The Key to Scientific Names よりまとめ)。
分子系統解析によってアカガシラサギなどがこの種を含む系統に含まれることが明らかになった。
カンムリサギの和名もなんとなくすっきりしない。この程度の冠羽ならば他にもあるのでは、と思ってしまう。
単形種。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではカラサギの名称が与えられていた。
山階鳥類研究所標本データベースでは YIO-08095 (Momiyama collection Hoihow. Hainan 1903) でこの名称が用いられていた。
アカガシラサギの記されたラベルは新しく付けられたものらしく、古い時代は学名のみ、あるいは単にサギと記してあるものもあって、Ogawa (1908) の名称からも推定できるようにアカガシラサギの名称は新しく整理された結果と思われる。
山階鳥類研究所標本データベースでは Ardeola にアカガシラサギ属の名称があり、現在の分類体系の名称とは一致するが、この属にはササゴイも含まれていて、なぜササゴイ属にならなかったのか不思議でもある。分類体系・学名・和名は、原則として「世界鳥類和名辞典」(山階 1986) に準拠 とのこと (2025.7 時点)。
他の種の和名から想像すると Ardeola 属にアカガシラサギ属の名称を与え、他の種は地域名で修飾して統一したがすでに名前のあったササゴイなどはそのまま残したのだろうか。カンムリサギの名称はそれ以前からあったものなのだろうか。
-
アマサギ (AviList では亜種が分離されて独立種。将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Bubulcus ibis (ブブルクス イービス) トキのような牛追い
- AviList 学名:Ardea coromanda (アルデア コロマンダ) コロマンデル地方のサギ
- 第8版属名:bubulcus (m) 牛飼い、(牛を使って耕作する) 農夫
- AviList 属名:ardea (f) アオサギ
- 第8版種小名:ibis (属) トキの (ibis -is (f) トキ科の鳥。備考参照)
- AviList 種小名:coromanda インドのコロマンデル地方の
- 英名:Cattle Egret, IOC 14.2, AviList: Eastern Cattle Egret
- 備考:
bubulcus は短母音のみで -bul- がアクセント音節 (ブブルクス)。
この単語も長母音の box (雄牛) 由来だが造語の際のアクセント音節との関係で短くなったものだろうか。
-bulcus (追う、守るもの。英語の -herd に相当) の語尾の単語は同様になっている。sus (ブタ。長母音) subulcus では短母音になっている (wiktionary)。
ibis は冒頭が長母音 (イービス)。
ibis の変化形は一貫して使われていないとのことで、属格 (通常の変化では ibidis) ではなくむしろ主格 (単に "トキ") かも知れない。
coromanda は地名で -man- がアクセント音節になることは問題ない。すべて短母音とすれば "コロマンダ"。語源説の一つであるオランダ語では -ro- を長母音とするのであるいは伸ばすかも知れない。
ardea は#アオサギ参照。
IOC は古くから2種に分割しており、Clements、eBird が 2023 年にこの分類に変更。
Howard and Moore と HBW/BirdLife は分離していないが最新リストは 2022 年あるいはそれ以前のものである。
分離した場合は Bubulcus coromandus (インドのコロマンデル地方の) 英名 Eastern Cattle Egret (日本のものはこちら) と Bubulcus ibis 英名 Western Cattle Egret (ニシアマサギの和名があるらしい) となり、どちらも単形種となる。
分離しない場合 (従来通り) は日本のものは亜種名まで含めて Bubulcus ibis coromandus となる。
SACC (2024) Treat Cattle Egret Bubulcus ibis as two species の検討。
これまでの研究の概要も含まれている。世界の潮流に合わせてほぼ賛成意見だが、形態 (色彩) と声だけでなく遺伝情報がもっと欲しいとの意見もある。SACC が検討した理由は、coromandus は分布域外だが分割によって英名に影響が及ぶため。
SACC はこの分離を 2024.7.27 版で不採択とした。
ibis の意味は本来はエジプトのアフリカクロトキ Threskiornis aethiopicus (英名 African Sacred Ibis) であるが、エジプトでこのトキが絶滅しつつある状況で、鳥類学者はコウノトリ類やサギ類に似た鳥にもこの名称を使うようになったとのこと (The Key to Scientific Names)。誤命名とされることもある (Helm Dictionary)。
アフリカクロトキは豊穣をもたらすナイル川に伴って現れることから神聖な鳥とされたが、現在ではエジプトにいないとこのこと (コンサイス鳥名事典)。
日本鳥類目録 改訂第8版の第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開 (2023年10月) ではアマサギ属 Bubulcus としているが、サギ類の現代的な分子系統分類 (#サンカノゴイの備考参照) では Bubulcus 属を残すためには Ardea 属の分割が必要になる。
Hruska et al. (2023) は Ardea 属に含めている。世界の主要リストも Hruska et al. (2023) にまだ追いついていないが、近々反映されて学名に影響が及ぶと考えられるので現代的な分子系統分類を検討しておく必要があるだろう。
Bubulcus の属名は広義アマサギを指すものとして Blyth (1852) が設けたもので古くからあった名称。広義アマサギの現在はシノニムの当時の学名 Ardea bubulcus Audouin, 1823 を属名に昇格したもの。
Ardea Ibis Linnaeus, 1758 の原記載 (基産地エジプト) が有効と認められたために使われなくなった種小名となったが属名に残った (The Key to Scientific Names の情報からまとめた)。
エジプトの例えばアフリカクロトキとの区別が不明瞭であったため Linnaeus (1758) の学名が使われていなかったのかも知れない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" でも主な学名は Ardea coromanda (何と 100 年強を経て IOC 14.2 学名がこの学名に戻る!) で、学名リストにも Linnaeus (1758) の学名は載せられていない。当時は有効な学名と考えられていなかったのだろう。アマサギ、ショウジョウサギ両方の和名が載せられていた。
Blyth (1852) の属記載に "... associate with herds of cattle grazing" とあるようにこの当時の学名は英名の Cattle Egret と非常によく一致しており英名は学名由来かあるいはその逆であろう。
Western Cattle Egret (ニシアマサギ) は当初は南スペインとポルトガル、熱帯・亜熱帯アフリカと熱帯西アジアに地域的に分布していたが、19 世紀の終わりに南アフリカに急速に分布を広げ、南アメリカに 1877 年に目撃 (自然飛来と考えられる)、1930 年代に南アメリカに定着、北アメリカでは 1941 年に最初に記録され、その後も急速に分布を広げた。
この種はもともと野生の大型草食動物に頼った生活をしていたが、放牧が拡大するとともに家畜に頼って急速に分布を広げたと考えられる。
Eastern Cattle Egret も同様に 1940 年代にオーストラリアで急速に分布を広げた (wikipedia 英語版)。
日本でもかつては珍鳥だった。桑原 (1991) 日本の生物 5(5): 33 によれば「日本鳥類図説」(内田清之助 1913) では本州ではまれだが台湾にはとても多いと記載されているそうである。
大西 (2008) Birder 22(5): 60 にアマサギは第二次世界大戦後に急に数が増えたが、熱帯林の大規模伐採でアマサギの好む牧草地が増えたとの説明がある。Western Cattle Egret (ニシアマサギ) も含んだ記述かも知れない。
Rasmussen and Anderton (2005) "Birds of South Asia: the Ripley guide" が繁殖期の羽衣と音声の違いからこれらを2種に分類することを提案したものである。
これら2(亜)種および亜種の可能性のあるセーシェル (インド洋) の個体群の比較検討は Ahmed (2011) Subspecific identification and status of Cattle Egret にある。2(亜)種は繁殖期の羽衣や計測値で区別することができるとしているが、音声についてはまだ検討の余地があるとのこと。
2024.7.18 AOS も別種を採用: Chesser et al. (2024) Sixty-fifth Supplement to the American Ornithological Society's Check-list of North American Birds。
Working Group Avian Checklists, version 0.02 は Bubulcus coromandus だったが 0.04 で Ardea coromandus に変更。AOS は Ardea coromanda で WGAC は種小名の性の変更忘れのよう。
IOC 14.2 updates の注に性に注意とあり直されると思われる。IOC 14.2 ではこの学名を採用。
英名は IOC 同様 Eastern Cattle Egret。IOC / AOS では Eastern Cattle-Egret。
どちらも Hruska et al. (2023) を採用した模様。これまで用いられてきた学名と大きく異なるので注意が必要。
AviList では分離を採用。決定理由は
5407 902 1187 Taxon coromanda is treated as a species separate from Ardea ibis based on consistent differences in proportions and breeding plumage. A comprehensive genetic review is needed. Bubulcus is merged into Ardea based on the genomic DNA evidence of Hruska et al. (2023).
[和名の由来]
大橋 (2020) Birder 34(5): 66-67 が和名の由来の考察を行っている。和名のすでに存在した時期には海外由来の「亜麻」はまだ知られておらず、伝統的な色の名称である「飴色」が由来であろうとのこと。コンサイス鳥名事典では両方の説を紹介しているが、「亜麻色」の渡来時期についての考察はない。
鳥名の漢字表記はいずれでもなく「黄毛鷺」と書く。
大橋 (2020) によればドビュッシーの名曲「亜麻色の髪の乙女」がこの名称で翻訳されて紹介されたことなどで亜麻色の名称がよく知られるようになったとのこと。原曲は La fille aux cheveux de lin で 1910 年に前奏曲集のうちの1曲として出版された。cheveux de lin が亜麻色の髪で白に近い金髪を指すと辞書に記載されている。
ショウジョウサギ (ショウジョウ 猩猩、猩々: 中国に古くから伝わる酒が大好きな霊獣、能の演目で猩々が酩酊して舞う様子から赤みを帯びた生物の名称に使われるとのこと) の別名があるそうである。
「ショウジョウサギ」の名称が現れる論文は例えば高島 (1952) クロトキに関する知見。
一見同じような意味に見える麻鷺は中国語 (主に台湾) でミゾゴイの名前の一つ (主に冬鳥)。
[アマサギはなぜ家畜を追う?]
Kuang et al. (2025) Why do Cattle Egrets forage with cattle? An analysis from an anti-predation perspective
家畜と一緒に採食することで捕食を避ける効果があるのではとの仮説をもとに飛び立ち距離から評価してみたがその証拠は認められなったとのこと。採食効率を上げる考えの方が有効ではないかとしているが、実験方法も単純なのでもう少し検討してもよい考え方かも知れない。
-
アオサギ
- 学名:Ardea cinerea (アルデア キネレア) 灰色のアオサギ
- 属名:ardea (f) アオサギ
- 種小名:cinerea (adj) 灰白色の (cinereus)
- 英名:Grey Heron
- 備考:
ardea は短母音のみでアクセントは冒頭 (アルデア)。起源はギリシャ語の eroidos (サギ) やセルビア・クロアチア語の roda (コウノトリ) などが考えられるが語形が大きく変化して起源は明確でない (wiktionary)。
cinerea は短母音のみで -ne- がアクセント音節 (キネレア)。
Ardea 属は Linnaeus (1758) が用いたもので、Gray (1840) がタイプ種をアオサギと定めた。Linnaeus の用いた Ardea 属は現在よりずっと広義でツル類も含んでいた (The Key to Scientific Names)。
チュウサギの属名が変わったのは分子系統研究でアオサギ、コサギのどちらの系統に属するかの認識が改まったため。
4亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は jouyi (アメリカの博物学者 Pierre Louis Jouy 由来) とされる。
[アオサギの亜種の問題]
4亜種のうち1-2亜種は分離されることもある: Ardea monicae Mauritanian Heron、firasa (マダガスカル)。
これらを別と考えて、日本で観察されるアオサギが jouyi なのか cinerea なのかについてはあまりすっきりしない。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" ではユーラシア東北部に夏鳥として飛来する、また日本で留鳥のアオサギを jouyi とし、アジアでは中国の大部分で留鳥のアオサギを "おそらく" cinerea としている。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではシベリアの大部分が cinerea でバイカル湖以東がより明るい色の jouyi とある。
Dement'ev and Gladkov (1951) では cinerea を北方型で日本もこの分布に含めている。jouyi は中国と朝鮮半島、インドに分布する南方型の扱いになっており、区分概念が少し異なっている。
jouyi は Ardea cinerea jouyi Clark, new subspecies に原記載があり、韓国での3個体によるものとのこと。
基亜種に比べて白っぽい色で、クロヅルの東方亜種 Grus grus lilfordi に対応するとのこと。クロヅルのこの亜種を認めているリストは現在あまりなく IOC では単形種としている (#クロヅルの備考も参照)。
アオサギの亜種については調べられた文献もあまり見当たらず、あまり検討されないまま過去の分類を引き続き使っているだけでそれほど意味のある亜種分類ではないのかも知れない。
参考までに冬鳥で普通種であるフィリピンのリストでは Ardea cinerea jouyi 別名 Ardea (cinerea) cinerea としているが後者は記入ミスかも。東アジアから渡ってくるものは jouyi と判断している模様。
Trivedi and Parasharya (2019) Inland nesting of grey heron Ardea cinerea: An important record for Gujarat state, India
のインドの文献では cinerea を時々やってくる冬鳥、jouyi を繁殖する亜種で日本も分布域に含めている。
分布の基本情報は Heron Conservation によるものだが、Trivedi and Parasharya (2019) の Taxonomic Status のところにはインドの亜種がどちらかわからない。この2亜種はクラインの大陸の両端の表しているとの考えも紹介している (その場合は連続分布)。
インドでは亜種 restirostris として記載されていた。従来の分布の考えに従って jouyi のシノニムとされたが、
HBW では最近はインド、スリランカを cinerea に分類し、jouyi はロシア極東・日本南部から... (Russian Far East and Japan S to N Myanmar, Indochina,...) の表記に読め、北海道は別亜種と意識しているものかも知れない。省略形で書かれているので原意は確実ではないがどなたかご確認いただきたいところ。
これに従えばインドの亜種を jouyi と素直に書けないので困った事態になっている模様。一部の標本を見て亜種が区別できないなどの断片的研究はあるが、インドの個体についての系統的な亜種の検討はなされていない。さもなければこんなことははるか昔に決着しているはずだ、と書いている。この状況は東アジアでもあまり違わないのかも知れない。
Heron Conservation のページでは jouyi の分布に関係して Matsunaga et al. (2000) Changing Trends in Distribution and Status of Grey Heron
Colonies in Hokkaido, Japan, 1960-1999
が引用されているが北海道 (夏鳥) の繁殖コロニーの変遷の論文で亜種にかかわる記述はない。
Ye et al. (2018)
First Description of Grey Heron Ardea cinerea Migration Recorded by GPS/GSM Transmitter
に中国からロシア・中国東北部に渡るアオサギのルートが調べられている。この文献では jouyi は中国に広く分布としているが、1世代前の HBW の記述に基づくよう。この論文の時点ではアオサギの渡り経路の研究は初とのこと。
[アオサギ、サギ類の日本語情報源]
日本語の興味深い情報源として アオサギを議論するページ を紹介しておく。
このサイトの著者の英語論文もある: Matsunaga (2018) Changes of the nesting sites of Grey Herons (Ardea cinerea) in Hokkaido, northern Japan。
アオサギを議論するページの アオサギの名 にギリシャ語の由来が示されていたので調べてみた。
古代ギリシャ語で erodios で、語末 -ios は他の鳥の名前と共通性があるとのこと。
aigupios (ハゲワシ)、aigolios (小型のフクロウの1種)、kharadrios (イシチドリまたは神話の鳥で治癒力のある caladrius)。-ios は日本語の鳥名語尾の "メ" のような役割か。
古代ギリシャ語の別型があり aroidios, rhoidios。ラテン語の ardea (サギ)、セルビア-クロアチアの roda (コウノトリ) との類似性が無関係とは考えにくいとのこと。複数の形態があるのでギリシャ語以前に起源があるのではとのこと (wikitionary)。Beekes (2010) の語源研究の本が出ているとのこと。
この解説のページでは エロス (Eros) の関係は出てこなかった。Eros の -os から想定すると誤る可能性があるということだろうか。
ラテン語の ardea の方は The Key to Scientific Names は Friedman (2022) Archives Nat. Hist., 49 (1), p. 19 の説を採用していてローマ神話で Ardea の町が燃えたときに灰から立ち上がった鳥。ardere は燃えるの意味で、燃える糞をしてタカもそれに触れると体が腐ってしまうとの伝説があるとのこと。
wikitionary の解説はそこまで書いてなくて、古代ギリシャ語の erodios と セルビア-クロアチアの roda との関係、インド・ヨーロッパ祖語に遡る可能性があるがおそらく異なる言語の接触によって音が変わった可能性がより考えやすいとしている。こちらでは ardeo (ardere 燃える、が変化形) は別系統の単語 (古イタリア語 *azideo 由来) とみなしている。
アオサギの他言語の名称調査では「アオサギを議論するページ」とほぼ同じ結果になった。
スペイン語、ポルトガル語で使われる real は2語義があって、一つは英語と同じ「真の」だがもうひとつは「王の」(英語の royal に相当)。イヌワシ (aguila real) は後者の例とされるので、スペイン語 garza real もそちらの意味かも。ムラサキサギを garza imperial と呼んでいるので、スペイン人は堂々とした体格を「王」で表している可能性が高いとみた。
英語の heron は 1300 年ごろから使われ、古フランス語 harion, eron (12世紀) 由来とのこと。古英語の hraga は中世には生き残らなかった。egret も中世フランス語の aigrette 由来で14世紀半ばから使われている (Online Etymology Dictionary)。
OED によれば 1340 年 heyrone, 1405 or 1395 年に heron の用例があるとのこと。"heron" の音は 1300 年ごろから使われていたがおそらく文字にする時は揺れがあったのだろう。
[食用アオサギ?]
食としてのサギ にも面白い話があって「サハリンではアオサギが食用としてマーケットに並んでいる」とある (2001)。wikipedia ロシア語版を見てみると、中世に鷹狩りで狩られていたことは同様に記述されている。
Tugarinov and Portenko (1952) によれば、肉は美味しくなく魚の臭いがして他の狩猟目的の副産物として狩られる程度であったとある。一方で Evgen'evich (2011) Bolotnye ptitsym tsaplya は逆に肉の質はよいとしている。
2009 年の法改正で狩猟鳥から外されており、現在ではアオサギを目的とした狩猟は行われていないとのこと。現在ならばマーケットに並べば違法になるだろう。
Evgen'evich (2011) のページにはアオサギの狩猟方法が記されていて多少歴史的な側面も出ているので紹介しておくと、食用の他に (それよりむしろ?) 装飾用の羽根 (天国の羽根と呼ばれたそう) 目当てに狩猟されていたとのこと。鷹狩りで好まれたのはアオサギが反撃するため見せ物として好適だったためとのこと。
「鷹狩りの書」(フリードリッヒ二世著 吉越英之訳 文一総合出版 2016) pp. 138-142 にハヤブサ類による狩りとサギなどによる反撃、ツルとノガンの図版が紹介されている。
[鷺の漢字の意味]
週刊「世界動物百科」で藤堂氏が取り上げておられたかも知れないが、全号を持っているわけではないので鷺の漢字については手持ち資料では不明。
Birder 編集部 (2023) Birder 37(12): 27 で「透き通るように白い」意味が解説されていた。
漢字の起源となった中国に白いサギが生息するのか確認してみると、ダイサギは沿岸域で地域により夏鳥から冬鳥、コサギは多くの地域で夏鳥、南部で留鳥、チュウサギは主に夏鳥。カラシラサギは "カラ" の名前は入るがやはり珍しいよう。夏鳥の地域が多いが分布が広そうなのはアオサギなので、必ずしも白いサギを指していなかったかも知れない。
鷺の文字を wiktionary で確認しておくと形声文字に分類されており、古代中国語で路 は *gra:gs の発音とのこと。鷺は *ra:gs。Zhengzhang (2003) によれば同系の音を持つ文字に露 (*gra:gs)、各、洛、格などが挙げられていた。ここまで一連の文字が知られているならば音声由来がもっともらしい。
鷺は日本語では呉音で "る"、漢音で "ろ"。日本語での文字の用例は古事記 (712) で用いられたのが由来とのこと。
ベトナム語 (Han character) でも同じ文字を用いて発音は lo とのこと。現代の中国語でも発音表記は lu などで、日本語で L と R の音の区別が失われたため ro となったらしい。
同ページでは現代の日本語と韓国語の鳥 (sae) の類似性が指摘されている。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば「サギ」の名称由来には複数説があるが定説があるわけではなさそう。朝鮮半島の音声由来も考えられるのかも。
-
ムラサキサギ
-
ダイサギ
- 学名:Ardea alba (アルデア アルバ) 白いアオサギ
- 属名:ardea (f) アオサギ
- 種小名:alba (adj) 白い (albus)
- 英名:Great Egret
- 備考:
ardea は#アオサギ参照。
alba は短母音のみで "アルバ"。
modesta は短母音のみで "モデスタ"。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 alba 亜種ダイサギ (冬鳥として渡来とされる。過去の別名オオダイサギ、モモジロ) と modesta (中庸の) チュウダイサギ (国内繁殖するものはこちらとされる。過去の別名コモモジロ)、及び亜種不明とされる。
英名に Great White Heron があった [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)] "オオシラサギ" に相当。過去の別名オオダイサギに影響があったかも知れない。オーストラリアでは Great Egret だがニュージーランドでは White Heron と呼ばれているとのこと (Ardeidae BirdForum 2025.3)。
英名では Egret と Heron の名称が混ざっており、分類学的にも違いがあるわけではないので統一を焦る必要はないとの考えが出されている。ワシとタカの違いのようなものか。和名の "サギ" の方が状況は単純な模様だが、"シラサギ" と総称するとややこしくなるのと同様。
サギ類の現代的な分子系統分類 (#サンカノゴイの備考参照) ではダイサギを Ardea 属とすることとアマサギを Bubulcus 属に残すことは相容れないこととなる (#アマサギの備考参照)。
ダイサギの世界分布が広く、個々の亜種が異なった繁殖期の羽衣を持つこと、Raty (2014) の DNA バーコーディングによる部分的証拠から世界4地域に分かれた複数種の分割が提案されている。
ダイサギとチュウダイサギも繁殖域などが大きく異なり外見も違うので種分割は妥当に思える。
これらが採用された場合は別種となるので、記録を残す場合もできるかぎりこの2つを区別して残すことが望ましい。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" もこれらが別種相当と述べ、英名に Great White Egret (ダイサギ) と Eastern Great White Egret (チュウダイサギ) の名称を与えている。
属名も Boyd のリストと同じく Casmerodius 属を採用していたが、当時はチュウサギが同じグループに属することが判明しておらず、Mesophoyx 属とされていた (この属は最新分子系統が判明するまで Boyd も用いていた)。
Gluschenko et al. (2024) The great egret Casmerodius albus in the south of Russian Far East (pp. 939-961)
によればロシア沿海地方のハンカ湖ででは両方がコロニーで繁殖し、繁殖生態や営巣習性も異なり、別種が適切であろうとのこと。この論文では別種として扱い、日本の表記では亜種ダイサギの繁殖生態のみを報告している。数は近年増えている。
Dugintsov and Logunov (2024) The first discovery of a nest of the great egret Casmerodius albus in the Amur Oblast (pp. 2907-2912) アムール州ではかつては迷鳥だったが 21 世紀に入って数が増え、繁殖も初確認された。
ヨーロッパでも分布域が北に拡大している: Wlodarczyk et al. (2020) Migratory behaviour and survival of Great Egrets after range expansion in Central Europe。20 世紀末に北部・西部に分布を広げ、21 世紀に入ってヨーロッパの 13 国で新たに繁殖種となった。越冬個体群も増えている。
IOC 15.1 では C. modesta should not be split (Pratt 2011) とあり、チュウダイサギは別種としていないが別種扱いのリストもある。どのぐらい違うのか AF193822.1 から BLAST を行ってみると結構違いがある。
alba と modesta の一致率は 93.6% 程度でそれほど高くない。GenBank でも Ardea modesta の学名を採用しているため (検索時は要注意) いずれ再検討が行われそう。
ミトコンドリアゲノムでは modesta のみ調べられていて [参考 Zhou et al. (2014) The complete mitochondrial genomes of sixteen ardeid birds revealing the evolutionary process of the gene rearrangements]、alba の情報がないのでまだデータ待ちのよう。
IOC 15.1 でもアメリカ大陸のダイサギ (亜種 egretta) は American Egret is a proposed split (Pratt 2011); more data desired とあって分離候補に挙がっている。もし分離されれば Egretta 属と同名の種小名を持つ種が別属に誕生することになる。Pratt (2011) は今となってはだいぶ古いので新しいデータを用いて再検討されるだろうか。
[ダイサギの皮膚は黒い?]
Nicolai et al. (2020) Exposure to UV radiance predicts repeated evolution of concealed black skin in birds
が標本から鳥の皮膚の色を調べる膨大な研究を行っている。99% 以上の属をカバーしているとのこと。黒い皮膚を持つ鳥は少ないが一定の数はあった。全体の 5% 程度だが多くの系統にみられ、黒い皮膚は 100 回以上独立に進化したとのこと。基本的に紫外線対策で説明できる。そのため赤道付近に多く、Gloger の法則に従っているとのこと。
皮膚が不必要に黒いものはあまりなさそうで、黒い皮膚を維持する (メラニン着色を続ける) のはコストがかかるのだろうとのこと。
地理的に日本の鳥では少ないがダイサギ、アマサギは首の皮膚が黒いとのこと (確かめられた方はおられるだろうか?)。白いサギでは首の皮膚にも日光が入り込むため紫外線対策が必要ということだろうか。
フラミンゴ類も同様でおそらく細い首の場合は羽毛で紫外線を防ぎきれないのだろうか。
標本の地理的分布の制約もあって東洋のカラス類は調べられていないが、Corvus 属では ムナジロガラス Corvus albus Pied Crow のみが調べられていて皮膚は黄色とのこと。
頭や首のはげた鳥は黒いものが多いなど知られた結果も得られている。
ウ類も皮膚は黄色から赤 (カワウは赤とのこと)。
カモ類では多少例があってハクガン、ミコアイサは首が黒いとのこと。南アメリカの飛べないカモのオオフナガモ Tachyeres pteneres Flightless Steamerduck は腹が黒いとのこと。
猛禽類では頭や首に羽毛のない種類は該当するが、ハイガシラトビ Leptodon cayanensis Grey-headed Kite も首が黒いとのこと。頭が白っぽくて光が入り込みやすいのだろうか。
パプアオオタカは首に黒い部分があるらしい。ミサゴは首・体ともに赤と他のタカ類とは色の傾向が少し違う。
シベリアムクドリは全身がオスが黄色、メスが黒となっているがあるいは標本の質の問題もあるのかも。ケイマフリ、ニシセグロカモメ、ノガン、ノグチゲラは首が黒い。
気がついたものをピックアップしたが一部だけなので興味ある方は調べていただければ面白いと思う。
Nicolai et al. (2023) Back in black: melanin-rich skin colour associated with increased net diversification rates in birds は同じグループがさらにサンプルを増やして調べているが論文はオープンアクセスではない。
-
チュウサギ
- 第8版学名:Ardea intermedia (アルデア インテルメディア) 中間のアオサギ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Egretta intermedia (エグレッタ インテルメディア) 中間のサギ
- 第8版属名:ardea (f) アオサギ
- 第7版属名:egretta (合) シラサギ (aigrette シラサギ 仏)
- 種小名:intermedia (adj) 中間の (intermedius)
- 英名:(Ietermediate Egret), IOC, AviList: Medium Egret
- 備考:
ardea は#アオサギ参照。
intermedia は短母音のみで "インテルメディア"。
"Fauna Japonica" では Ardea egrettoides Temminck, 1840 の学名が使われた。Egretta + -oides (似た) (Gk)。Ardea intermedia Wagler, 1829 (原記載) 基産地ジャワ島 の用例が早かった。
もっとも Ardea egrettoides Gmelin, 1774 のさらに早い用例があり (ダイサギのシノニム) (The Key to Scientific Names)、Temminck の学名は有効なものではなかった。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Ardea 属に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。種小名は変化なし。この変更は一世代前の分子系統樹 (#トキの備考参照) では納得できるものであった。
サギ類の現代的な分子系統分類 (#サンカノゴイの備考参照) ではチュウサギを Ardea 属とすることとアマサギを Bubulcus 属に残すことは相容れないこととなる。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" では Mesophoyx 属とされていた (#ダイサギの備考参照)。現代的な分子系統分類ではダイサギと同属とするのが適切である。
世界の分類ではアマサギを Ardea 属に移動することで解消される見通し (#アマサギの備考参照)。
3亜種あり(IOC)、日本で記録されるものは基亜種 intermedia とされる。亜種 plumiferus を種 Plumed Egret オーストラリアチュウサギ と分離する考えがあり、IOC, eBird, BirdLife で採用されている。
亜種 brachyrhynchus を種 Yellow-billed Egret とする考えもあって IOC 等同様であるが和名が見当たらないため、オーストラリアチュウサギの例に従ってアフリカチュウサギの名称を仮に与えてある。この扱いは AviList でも採用された。
判定 5404 904 Three monotypic species are recognized in the Ardea intermedia sensu lato complex based on differences in breeding bare parts color, plumage, and morphology, and possibly in display and vocalizations: A. intermedia; A. brachyrhyncha; and A. plumifera. However, genetic data are lacking and further work is needed to corroborate this split.
近年の分子遺伝学によるサギ類の分類は従来と比べてかなり変化がある。
plumiferus も Plumed も「羽で着飾った」のよい名前をもらっているので、和名はもう少し凝ってもよい気がする。
種英名は IOC 14.1, Working Group Avian Checklists で Medium Egret。これまでの Ietermediate Egret は分離前の古い概念に対応する英名となる。これまでは種小名と対応していてわかりやすかったが少し注意が必要。
AviList, Clements 2024 では Medium Egret を採用、BirdLife v9 のみが Ietermediate Egret となっているが BirdLife の更新がこの中では最も古いため将来的に Medium Egret に統一されるかも知れない。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 187 (1946 年初出) によればチュウサギは一般にシラサギと言われているものの標準型で、白鷺属 (当時の名称) でもっとも数が多い。
p. 190 では コサギをチュウサギと並んで、シラサギと言われるものの代表者 (中略) どこでもコサギのほうが数がやや少なく、朝鮮からはまだ繁殖の記録がないとのことであった。
田園地帯では今でも確かにそのような印象を受けるが、自分の経験した範囲では音声記録の難しい種だと思う。ダイサギはもちろん、コサギも比較的よく鳴くが、チュウサギはコロニー以外で音声を聞くのが意外に難しい。
「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) にもコロニーの音声しか収録されていない。自分が記録したことのある単独個体の音声はコロニーに向かって飛んできたものだけだが、想像通りこの条件では識別が難しいわけである。飛翔中のチュウサギの識別方法も図鑑にあまり出ていないし。
図鑑にも音声のことはあまり書かれておらず、声にも注意してみていただきたい。コサギもダイサギも声を聞いた覚えがないと感じられる方はこの機会に注意してみていただきたい。
海外情報によれば慣れた人であればチュウサギは音声だけで判別できるとのこと。また逆に言えば声を出しているシラサギはチュウサギでない可能性の方が高い。
#アオサギの備考 [鷺の漢字の意味] はシラサギ類ではなくアオサギに含めたのはこの音声のため。古代中国語の音 *gra:gs の形声文字であればアオサギが真っ先に連想される次第。
-
コサギ
- 学名:Egretta garzetta (エグレッタ ガルゼッタ) シラサギ
- 属名:egretta (合) シラサギ (aigrette シラサギ 仏)
- 種小名:garzetta (外) garzetta/sgarzetta コサギ 伊
- 英名:Little Egret
- 備考:
egretta は外来語由来だが -ret- がアクセント音節であることは問題ない。すべて短母音とすれば "エグレッタ"。フランス語でも aigrette を同じように発音する ("エグレット"。アクセントは特にない)。英語 egret の方が発音は要注意で冒頭にアクセントがあって i の音である。
r と l を取り違えて発音すると eaglet (ワシの子) になってしまう。
garzetta も外来語由来で発音は明確でないが、-zet- がアクセント音節であることは問題ない。すべて短母音とすれば "ガルゼッタ"。
Egretta 属はコサギのみを指して使われた名称 (Forster 1817) で自動的にタイプ種となる。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 garzetta とされる。
旧世界に広範に分布するが大部分は亜種 garzetta とされ、スンダ列島からオーストラリア、ニュージランドの亜種が nigripes とされる。世界の多くのリストが同じ分類を採用している。
この意味では日本もアフリカも同じ亜種となる。
コンサイス鳥名事典の時点の亜種は少し違っていて garzetta がヨーロッパ南部、アフリカ、南アジア。
nigripes がジャワ、ニューギニア、フィリピン。
immaculata がオーストラリア。
dimorpha がマダガスカルとアルダブラ諸島とあり、マダガスカルクロサギ Egretta dimorpha に対応する。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) はこの亜種を種として分離していないため、コサギは3亜種になる。
immaculata は現在は通常 nigripes のシノニムとされる次第である。
IOC 15.1, WGAC で Butorides atricapilla が Butorides striata 南米のササゴイ から分離され Little Heron の英名が与えられることになった。日本のササゴイも後者に属すると考えられる。ササゴイ類の分子系統研究を踏まえたものでコサギと紛らわしい英名となった。
アフリカ東部やマダガスカルに灰色の暗色型が存在し、東京の多摩川 (1978)、名古屋の庄内川 (1978-1983) に暗色型が記録されたとのこと (コンサイス鳥名事典)。
2012-2013 年東京都町田市の記録が見られる コサギ 暗色型 (「ミツユビカモメと仲間たち」の探鳥記録)。
コサギ (2021年茨城県 kobori)。
コサギ暗色種 (森の自然誌) ではアフリカからインドに棲息する亜種と書かれている。
Little Egret (HeronConservation) では多数の亜種を記載しているので、それをふまえた解説かも知れない。これによればこれら提唱されている "亜種" 間の形態、遺伝的違いなどはあまり調べられていないとのことで分類に関する最近の情報はなさそうに読める。
Ashkenazi (1993) Dark-Morph Individuals of Egretta spp. in Israel
にイスラエルでの暗色型の報告がある。
Melanistic Little Egret sighted in Jaisalmer district (Times of India) インドで目撃された暗色型。
[鳥の体のサイズを決める遺伝子]
体軸の長さや体型を決める遺伝子が (初めてとある) ある程度明らかになったらしい。どの項目に入れてもよい内容だが研究対象となっている種の中で日本でも見られ遺伝子の特徴が多いコサギに入れた。
Luo et al. (2024) Insight Into Body Size Evolution in Aves: Based on Some Body Size-Related Genes
複数の因子があって個々には複雑なので論文の系統樹を直接見て考察していただきたい。
-
クロサギ
- 学名:Egretta sacra (エグレッタ サクラ) 神聖なシラサギ
- 属名:egretta (合) シラサギ (aigrette シラサギ 仏)
- 種小名:sacra (adj) 神聖な (sacer)
- 英名:Eastern Reef Heron, IOC: Pacific Reef Heron
- 備考:
egretta は#コサギ参照。
sacra は短母音のみ (サクラ)。日本語の "桜" のように "ク" に母音は入らない。
記載時学名 Ardea sacra Gmelin, 1789 (原記載) 基産地 Tahiti (タヒチ)。Latham の英名の Sacred Heron も挙げられていた。
PELECANIFORMES Pelicans, herons, and ibises (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealand 2019) によれば Latham 1785, Gen. Synop. Birds 3: 92 とのこと。
その次に登場する Ardea atra は Brisson の用いた学名 (有効な学名ではない) で Heron noir, Black Heron の名称が登場する。分布域が Sikesia (ヨーロッパ中部) とクロサギと異なるのでクロサギの黒色型を意味していたわけではなさそう。Gmelin は過去の記載を整理したものなので勘違いなどもあったかも知れない。
このスキャンに手書きされている Ardea nigra の同定が正しければ Linnaeus (1758) の命名したナベコウを指していることになる。
今ひとつ実体はよくわかっていなかったようだが、クロサギの種小名は Latham の英名由来。
英名で Black Heron はクロコサギ Egretta ardesiaca と別の種になる。中国語でも黒鷺はこちらの種を指す。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 sacra とされる。
国内の「白色型」の地域分布について調べた論文: Itoh (1991) Geographical Variation of the Plumage Polymorphism in the Eastern Reef Heron (Egretta sacra)
この研究では白色型は南西諸島で見られ、赤道から遠ざかるほど白色型の比率が減る。白黒2型の多形を説明する仮説も紹介されているが、どれも十分満足できる説明ではないとのこと。
-
カラシラサギ
- 学名:Egretta eulophotes (エグレッタ エウロポテース) 立派な冠羽のシラサギ
- 属名:egretta (合) シラサギ (aigrette シラサギ 仏)
- 種小名:eulophotes (合) 立派な冠羽を持ったもの (eu (int) よい、lophos 丘、冠 -otes (接尾辞) 〜の質の Gk)
- 英名:Chinese Egret
- 備考:
egretta は#コサギ参照。
eulophotes は起源となるギリシャ語の -otes の e が長母音であることを考慮すると伸ばす可能性がある。-lo- がアクセント音節と考えられる (エウロポテース)。
単形種。
△ ペリカン目 PELECANIFORMES トキ科 THRESKIORNITHIDAE ▽
-
クロトキ
- 学名:Threskiornis melanocephalus (トゥレースキオルニス メラノケパルス) 黒い頭の神聖な鳥
- 属名:threskiornis (合) 神聖な鳥 (threskeia 宗教 ornis 鳥 Gk) 古エジプトではトキ (アフリカクロトキ) は神聖な鳥とされた
- 種小名:melanocephalus (合) 黒い頭の (melano- (接頭辞) 黒い kephali 頭 Gk)
- 英名:[Oriental (White) Ibis, Indian White Ibis], IOC: Black-headed Ibis
- 備考:
threskiornis は外来語由来で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は threskeia の e が長母音のためここが長母音になると考えられる。-or- がアクセント音節と考えられる (トゥレースキオルニス)。
melanocephalus は外来語由来で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-ce- がアクセント音節と考えられる (メラノケパルス)。
単形種。
トキ科 Threskiornithidae の学名は実は自明なものではなかった。かつては Ibis 属に基づいて Ibididae と呼ばれていたが Ibis が最初に使われたのはトキ科でなくコウノトリ類の Mycteria だった。
そのため科の学名を変える必要が生じた。Eudociminae の方が古く使われた名前 (シロトキ、真紅のショウジョウトキの属名由来) であったが ICZN が最終的に Threskiornithidae と決定した (Boyd)。
Ibis 属の名称も現在の属名には使われていない。
クロトキ、アフリカクロトキ Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis、オーストラリアクロトキ Threskiornis molucca Australian Ibis は上種を形成すると考えられ、Holyoak (1970) はオーストラリアクロトキは成鳥がアフリカクロトキ、幼鳥がクロトキの羽衣に類似するとして1種 Threskiornis aethiopicus にまとめた。
この扱いは Lowe and Richards (1991) が再検討を行うまで広く認められいたがその後それぞれ種扱いとなった (オーストラリアクロトキの wikipedia 英語版から)。総称時代は "White Ibis" とも呼ばれていたため Oriental (White) Ibis の英名はその時代の名残り。
あまりに紛らわしいので IOC の英名はまったく異なったものが与えられている。
クロトキなのに英名には White Ibis が付いていた理由。現在の White Ibis の英名は Eudocimus albus に与えられいる (こちらは学名とも対応してわかりやすい)。
しかし現在のショウジョウトキ Eudocimus ruber Scarlet Ibis はこの種と同種で色彩の違いは morph との解釈もあった。交雑していないことが判明して別種とされた経緯もある (コンサイス鳥名事典)。トキ類の分類は意外に複雑だった模様。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でも英名 White Ibis を用いていた。
[ペリカン目やトキ科などの系統について]
Gibb et al. (2013) Beyond phylogeny: pelecaniform and ciconiiform birds, and long-term niche stability
によればトキ類とサギ類は従来考えられていたような単系統をなさない。
Boyd はそれぞれを目にすれば話が簡単であると以下のようにしている (ここでは紹介のみを意図とする。後に述べるように必ずしもすぐに推奨できるものではない)。
和名があるものは 山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類 に従っている。包含される中身は同一ではない場合があるので注意。
コウノトリ目 Ciconiiformes
コウノトリ科 Ciconiidae: Storks
カツオドリ目 Suliformes
グンカンドリ科 Fregatidae: Frigatebirds
カツオドリ科 Sulidae: Gannets, Boobies
ヘビウ科 Anhingidae: Anhingas
ウ科 Phalacrocoracidae: Cormorants
ヘラサギ/トキ目? Plataleiformes
トキ科 Threskiornithidae
ペリカン目 Pelecaniformes
シュモクドリ科 Scopidae: Hamerkop
ハシビロコウ科 Balaenicipitidae: Shoebill
ペリカン科 Pelecanidae: Pelicans
サギ目 Ardeiformes
サギ科 Ardeidae: Herons, Egrets, Bitterns
ヘラサギ/トキ目? (目の学名は先取権による。文字そのままだとヘラサギ目になるがトキ科のみが含まれることを考えるとトキ目とも呼べる) とサギ目を独立させることがポイントで、このようにすればトキ科やサギ科をどこにするか悩むことはない。一つの解決法だろう。
他の系統はこれまでの分類そのままである。
Kuramoto et al. (2015) Determining the Position of Storks on the Phylogenetic Tree of Waterbirds by Retroposon Insertion Analysis
レトロポゾンの挿入比較に基づく水鳥類の系統解析 (蔵本多恵 2016 博士論文)
では Gibb et al. (2013) の系統樹サポートは低いことも指摘されており、レトロトランスポゾンの解析 [この方法はオウム類とハヤブサ類の近縁性を明らかにする (2011) のにも用いられた。#ハヤブサの備考参照]
でペリカン類、トキ類、サギ類は系統が近く、サギ科とトキ科は分岐初期に交雑があり (初期に急速に種分化したと考えられる) レトロトランスポゾンの解析で系統分離が不完全になっていることも示唆されている。
従来の研究でも示唆はあったがコウノトリ目とカツオドリ目を独立させるのはこの論文の結果で十分で、この研究はペリカン類、トキ類、サギ類が近縁であることを支持する結果となっている。
Gibb et al. (2013) の研究ではサギ類とコウノトリ類が同一の枝にまとまる結果となったがこれは否定されることになった。
この結果を見るとペリカン類、トキ類、サギ類をペリカン目にまとめることが適切のようにも見えるが、レトロトランスポゾンを用いる方法は系統はわかるが分岐年代はわからないので別情報が必要になる。
Gibb et al. (2013) の fig. 3 を見ると分けてもよい印象も受ける。目をどの程度の単位と考えるか次第だろう。
Gibb et al. (2013) の結果ではタカ類が捕食性の水鳥グループの祖先にあたる系統樹となっていて現代の認識とは異なる。水鳥とタカ類 (他はわずかで陸鳥を含まず) のみを含めた解析なのでこのような結果になっているのだろう。タカ類とハヤブサ類の系統が離れていることが明らかになった後ぐらいの研究なので、タカ類をどこに置くかはまだ自由度があったのだろう。
かつては水鳥とワシタカ類 (ハヤブサ類も含む) の系統が近いと考えられていたので、捕食性の水鳥の祖先にタカ類が位置する結果は比較的大きな獲物をとる肉食グループとなって水鳥の系統を研究する者には理解しやすかったと思われる。
かつてはワシタカ類 (ハヤブサ類も含む) はカモ類とキジ類の間に置かれていたが、その場所よりも捕食性の水鳥と一緒にすると解釈に都合がよいとのアイデアになる。結果的にはこれは多分正しくないのだが、
#ミサゴの備考にあるように捕食性の陸鳥の祖先に猛禽類を置くアイデアに近く、タカ類など猛禽類はさまざまなものの祖先となり得るまことに都合のよいグループなのだろう。
この系統樹と年代推定ではタカ類は恐竜絶滅を生き延びていたことになってこれはこれで面白い。Accipitriformes の総称一般名に accipiters が使われていて、この方面はあまり詳しくないだろうことも想像できる。
Kimball et al. (2013)
Identifying localized biases in large datasets: A case study using
the avian tree of life
にも含まれている種のサンプルは少ないが広範な分類群を含む分子系統解析がある。これもコウノトリ類がこのグループの最初の分岐であることをうかがわせるが、Kuramoto et al. (2015) の方がより決定的な結果となっている。
Kuramoto et al. (2015) および博士論文によれば、用いた遺伝子数は増えたものの種のサンプルは少なく、解析に用いる種の選定などが系統推定を誤らせた可能性があるとのこと。
Boyd は上位分類を最初は Gibb et al. (2013) (面白い結果の提案であったが) にかなり頼ってしまっていたが、結果的に Gibb et al. (2013) の精度が低かったことに引きずられることになった模様である。Kuramoto et al. (2015) 以前にこの部分が書かれていて、十分に再検討が行われていなかったのかも知れない。
さて最新の#鳥類系統樹2024の系統樹によれば Elementaves の中の最後の系統になる。以下 Stiller et al. (2024) の系統樹配列順。
ネッタイチョウ目 Phaethontiformes
ネッタイチョウ科 Phaethontidae
ジャノメドリ目 Eurypygiformes
ジャノメドリ科 Eurypygidae
カグー科 Rhynochetidae
がまとまった系統をなす。これらからツル目は分離され、Elementaves の中の古い系統に移動。最新分類ではツル目とジャノメドリ科、カグー科は別の系統となった。
アビ目 Gaviiformes は独立した系統。
以下2系統に分かれ、
(1)
ペンギン目 Sphenisciformes が最も古い分岐
ミズナギドリ目 Procellariiformes
アホウドリ科 Diomedeidae
アシナガウミツバメ科 Oceanitidae
ウミツバメ科 Hydrobatidae
ミズナギドリ科 Procellariidae
(2) Stiller et al. (2024) は以下全体を ペリカン目 Pelecaniformes としている
コウノトリ科 Ciconiidae が最も古い分岐
トキ科 Threskiornithidae (ヘラサギ類は調べられていないがここに入る)
サギ科 Ardeidae
以下の3つはまとまった系統をなす。
ハシビロコウ科 Balaenicipitidae
ペリカン科 Pelecanidae
シュモクドリ科 Scopidae
以下もまとまった系統をなす。
グンカンドリ科 Fregatidae (最も古い分岐。以下の3系統は比較的近い)
カツオドリ科 Sulidae
ヘビウ科 Anhingidae
ウ科 Phalacrocoracidae
目の範囲の扱い次第だが、現在のペリカン目とカツオドリ目を認めるならば、コウノトリ、トキ、サギもそれぞれ目扱いが適切であることがわかる (Boyd の分類の通り)。そうでなければ従来通り全部をペリカン目とするかどうかの問題。Stiller et al. (2024) は上記の (2) の系統がまとまっていること、レトロトランスポゾンの結果も考慮して全体をペリカン目として扱ったのかも知れない。
分岐年代的には (2) の中の分岐は少し新しい (5500 万年前ぐらい) のでそれ以前の系統ほどは分ける必然性は高くないかも知れない。全体をペリカン目とする扱いとするか、レトロトランスポゾンの共通性は多少容認して実用的にトキ、サギを目扱いとするか。
コウノトリ目のみ分けて残りをペリカン目とする扱いも考えられる。細分しない限りカツオドリ目が消滅してしまう可能性があるがどうだろうか。
カツオドリ目とされていた中でグンカンドリ科だけはあまり似ていない印象を受けるが、分子系統解析からも縁がやや遠いことがわかり納得できる結果となった。
この系統関係については #カワウの備考 [コルヌリン遺伝子を失ったウ類] の情報も参照。
-
トキ
- 学名:Nipponia nippon (ニッポニア ニッポン) 日本の鳥 (原学名で日本のトキ)
- 属名:nipponia (種小名から作られた属名)
- 種小名:nippon (外) 日本 (当時の名称では北海道を除く本土を指していたよう)
- 英名:Japanese Crested Ibis, IOC: Crested Ibis
- 備考:
nipponia は規則によれば -po- がアクセント音節 (ニッポニア)。
nippon は規則によれば nip- がアクセント音節 (ニッポン)。
ほぼ常識通りの発音になるが、属名を作る際に記載者も不自然な音にならないよう音韻は考慮したのだろう。
記載時の学名は Ibis nippon Temminck, 1835。
IBIS NIPPON (Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux, pour servir de suite et de complement aux planches enluminees de Buffon, edition in-folio et in-4° de l'Imprimerie Royale, 1770: 600 gravures coloriees)。
別リンク。
シーボルトが持ち帰ったもので、和名のトキも紹介されている。
tres-rare et seulement de passage accidentel dans le iles du domaine de l'empire du Japon と 非常にまれで日本帝国の領土の島々を通過中に偶然見られるのみ、となるだろうか。伝聞と思われるので現代の感覚とはやや異なるが、他の種より日本の固有性を意識した表現となっているように見える。
フランス語でもトキ類は ibis なので特別なフランス語名はなく学名をそのまま使っている。
Coup-d'oeil sur la faune des iles de la Sonde et de l'empire du Japon: discours preliminaire, destine a servir d'introduction a la Faune du Japon
を見ると Jesso (蝦夷) と Nippon (主要な島がこの名前で呼ばれるとのこと) の概念となっていたよう。国名概念 (Japon) ではなさそう。
japonensis を使わなかった理由がもしあるとすればこのニュアンスの違いを反映しているのかも知れない。
なおフランス語で Nippon (nippon) の意味を調べてみるとなんと国名の意味は普通はないようで、日本人あるいはその形容詞とのこと = japonais。名詞の女性形もあって Nippone / Nipponne とのこと (wiktionary)。
海外の命名者による鳥での nippon の用例は調べた範囲では同じく Temminck がシメの仲間に用い、Coccothraustes nippon Cabanis, 1849 (参考) Cabanis が Temminck を引用する形で紹介したもの。
現在何に相当するかは見つけられなかったが、シメの亜種であれば japonicus Temminck & Schlegel, 1848 がある。
ニホンジカの Cervus nippon も Temminck (1838) による命名。エゾジカと別種扱いの時期もあったようでこの種小名も産地を反映しているのかも知れない。
冒頭の Ce bel oiseau (この美しい鳥) はトキ類の他種にも使われているのでトキのみを称賛したわけではない。
sa forme svelte et le coloris elegant de son plumage (形はほっそりして羽毛の色はエレガントである) の解説がある。
同文献で Temminck が用いた他のトキ類の学名では Ibis leucon = Threskiornis melanocephalus (Latham, 1790) クロトキ は他に早い学名があった。
Ibis papillosa = Pseudibis papillosa アカアシトキ は属は変わったが現在も使われている。
Ibis plumbeus = Theristicus caerulescens (Vieillot, 1817) ハイイロトキ も他の記載の方が早かった。
もう1種 Tentalus chalcopterus = Rhinoptilus chalcopterus スミレスナバシリ はトキ類ではないが一緒に含まれていた。これも属は変わったが現在も使われている。
いずれも色などの特徴が中心の学名でトキのみ例外だった模様。
Ibis 属の名称に問題があったことは、Bock (1994) History and nomenclature of avian family-group names (pp. 39-40, 96) に記述されている。
Ibis Cuvier, 1816 が用いられていたが、Ibis Lacepede, 1799 の用例の方が早かったことがわかった。Lacepede (1799) の用いたものは Mycteria Linnaeus, 1758 (アメリカトキコウなど。コウノトリ目コウノトリ科) のシノニムとなって Ibis 属は表面上現れなくなった。
ここで問題となっているのは Ibis 属がコウノトリ目に移動したとともに引き継がれてコウノトリ科の名称が Ibididae とされた点。
Ibididae Degland, 1849 (Ibis Cuvier, 1816) は Ibis の属名が後行シノニムにあたるため有効でなく、Ibididae auct., post-1850 (Ibis Lacepede, 1799) の Lacepede (1799) の属名に基づく科の名称は別物とのこと。これは現在のコウノトリ科 Ciconiidae のシノニムとなっているとのこと。
Ibis 属がトキ類を指すものとしてまだ有効だった時代に Reichenbach が 1852 年提案した分類 Nipponia temmincki [Handb. Spec. Orn. Die Voegel (1852) p. 14]。
属名の記載年は Reichenbach, 1853 (Avium Systema Naturale) の Genera et species typicae の p. XIV: トキ類を細かく属に分けている) とされる。
この時点では Nipponia temminckii Reichenbach。
属名の Nipponia は特に意味を持たせたというより、種小名から語尾を属名に昇格しただけと考えるとよさそうである (当時は種小名から属に昇格の場合にトートニムになるのを避けて別の種小名を与えることは普通に行われていたよう。おそらくその後その必要はない規則となったものと想像できる)。
これに基づき、Gray が 1871 年に用いた Nipponia nippon が使われるようになったとある (wikipedia 日本語版など)。
Reichenbach (1853) は当時の扱いで属を細かくわけていたが、トキは旧広義 Ibis 属の中でも分離した系統だったためにここで付けられた属名が現在に至るまで使わてきた次第だろう。
また一部の分類群では属を細かく分けたものを再度統合していた時期があったが、トキ類を指した Ibis 属が無効となったため統合して大きな属に戻す機運が起きにくかった理由も考えられるかも知れない。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でも Ibis 属を用いており、特異なために他のトキ類のいずれに近縁か不明とある。この時点では Ibis 属はまだ有効で Reichenbach の属分類も採用していなかった。
Temminck が種小名に japonensis などではなく固有名詞の nippon を用いたことで種小名から属名への昇格が可能となったとも言える。もし japonensis や、"冠のある" などの意味の種小名を用いていればおそらくまったく違う学名になっていたことだろう。
当時の記述を読んでいて気づいたのだが、フランス語名でトキ類一般は ibis であるため、過去の学名と重複を避ける他に、フランス語名にした場合に他のトキ類のフランス語一般名と紛らわしくならない表現が必要とされたと考えられる。
"顔が禿げた" の意味ではサカツラトキ 現在の学名で Phimosus infuscatus Whispering Ibis (Bare-faced Ibis) がすでに記載されており、フランス語名で Ibis a face nue で、"顔が禿げた" 特徴は学名に残しにくかったと想像できる。
"白いトキ" ではシロトキ 現在の学名で Eudocimus albus が Linnaeus (1758) が早々に命名 (Scolopax alba! これ以前は Numenius が使われていた。原記載) していてフランス語名でも同様なのでこれも学名にはふさわしくない。
フランス語名 "顔の黒いトキ" ではカオジロブロンズトキ 現在の学名で Plegadis chihi White-faced Ibis と英語名と意味が逆になっている。この chihi は Vieillot (1817) が与えたもので Azara が用いた用語をフランス語の音にしたものとのこと (The Key to Scientific Names)。
この種は記載時 Numenius 属で、なんとダイシャクシギの仲間だった。嘴を見るとトキ類とダイシャクシギ類が近い関係にあったと想像されても確かに不思議でない。
Numenius ibis Cuvier なる学名も存在したぐらいなので [cf. Curtis et al. (2018) The Sacred Ibis debate: The first test of evolution] 当時はこの2つのグループが混同されていたふしがある。
そう思ってみると過去の Numenius 属の学名に現在はトキ類のものが見つかる。こちらも気にすると選択肢がより狭まったかも知れない。
顔の色をもとに学名を作ることは可能だったと思われるが、トキ類の顔つきはまずまず似ているので他種にもあてはまってしまう色名は使いにくい。カオジロブロンズトキに chihi が使われた時点で記述的な学名がすでに難しくなりかけていた兆候かも知れない。
肝心の "冠のあるトキ" はマダガスカルトキ 現在の学名で Lophotibis cristata Madagascar Ibis (IOC 14.2) / Madagascar Crested Ibis / Crested Wood Ibis / White-winged Ibis で Boddaert (1783) が早々に命名しており、Boddaert の記載時の属は違っていたとはいえトキ類では cristata/cristatus はそもそも事実上使えなかったものだろう。
学名も Ibis cristatus となっていた時期があった模様で、Zoologia. Aves. Pagina 629 Tomo 3. Los Tres Reinos de la Naturaleza に登場する。
さらにマダガスカルトキのフランス語名が Ibis huppe と "冠のあるトキ" そのままの意味。
"冠のある" 意味だけが目的であれば代わりの種小名を使うことも可能である (例えばカンムリクマタカの coronatus)。
日本のトキに "冠のある" を使えなかったのはフランス語で既存の種と同じ名前になってしまうのがより重要な理由だったかも知れない。
英名を見ていても気づきにくいが、学名に近い表記を使うフランス語では使いたいだろう名称はすでに使われていたものが多かった。結果的に "日本のトキ" とせざるを得なかった部分もあるのでは。
トキの現在の標準的な英名は Crested Ibis だが、特徴が該当する種が他にもあり、他言語の用例と比べてもなかなか悩ましかったかも知れない。マダガスカルトキの英名も苦労している感じがある。Madagascar Ibis の英名は マダガスカルクロトキ Threskiornis bernieri にも使われたことがあってそれぞれの間で英名を譲り合った経緯が想像できる。
記載者がマダガスカルトキに "冠のある" のような簡単な学名を与えるのでなくもっと気を遣ってくれていれば、の恨み節が聞こえそうである。
なおこんな話題があった。こちらは別の動物群で Nipponia がトキにすでに使われていることが問題となった。マクラギヤスデ概説 (Kuwahara 2022)。
単形属。単形種。
[Nipponia 属の位置づけ]
Boyd のページによるとトキ類の約半数をサンプルした Krattinger (2010) の研究 (修士論文) では Bostrychia, Lophotibis, Nipponia の分離は十分でないが、
Chesser et al. (2010) Molecular phylogeny of the spoonbills (Aves: Threskiornithidae) based on mitochondrial DNA
と整合性はあるとのこと。
Ramirez et al. (2013) Molecular phylogeny of Threskiornithidae (Aves: Pelecaniformes) based on nuclear and mitochondrial DNA
にも研究があるが、主に新世界のトキ類が中心で東洋のトキ類の系統について新しいことがわかったわけではなさそうである。
De Pietri (2013)
Interrelationships of the Threskiornithidae and the
phylogenetic position of the Miocene ibis 'Plegadis' paganus from the Saint-Gerand-le-Puy area in central
France
に化石を含めた形態学による系統研究があり、現在通常受け入れられているトキ亜科 Threskiornithinae とヘラサギ亜科 Plataleinae の関係は単純でなく、ヘラサギ亜科がトキ亜科の Threskiornis 属に内包される形になっている。
ヘラサギ亜科とトキ亜科に分離することが分子系統学的に支持されない可能性は Chesser et al. (2010) にも記されている。
トキ属については言及がないがこのグループとは別系統になる可能性もある。
Gibb et al. (2013) (#クロトキの備考参照)、
Treutlein et al. (2014) Phylogeny of water birds inferred from mitochondrial DNA sequences of nine protein coding genes
で {Threskiornis属 + Platalea (ヘラサギ) 属} の外に Nipponia 属がある驚きの関係になっている。
あまりにもサンプルが少ないが、旧世界 (アフリカなど) のトキ類とヘラサギ類を合わせたものとトキの縁が遠い可能性がある。他のトキ類が調べられていないのでトキ属が独立系統になるかどうかまではわからない。
Kim et al. (2019) The complete mitochondrial genome of an Asian crested ibis Nipponia nippon (Pelecaniformes, Threskiornithidae) from South Korea も参照。
Threskiornis 属と異なることは他の研究同様に明瞭である。
サギ類についても分子系統樹がある程度わかる。
現在までの研究をまとめると、トキ科の中の系統は Threskiornis (クロトキ) 属とヘラサギ類がまとまる可能性が高く、従来の分類を見直す必要がありそうとのこと。
トキはこの系統からは遠いが他の関連属との関係はまだ明らかでない。
これを調べたのは、Nipponia nippon はあまりにもよく知られた学名であるが、他の種類で学名が変化しているケースがあるので将来の分類変更で学名が変わる可能性があるのか気になったため。
種小名の nippon の方は亜種などもなく変わる恐れはないだろう。
現在のところ系統関係が十分分離できていないとされる Bostrychia, Lophotibis はいずれも Nipponia と同じ文献で Reichenbach (1853) が細かく分けた結果生まれた属名であるため将来統合される可能性がまったくないとは言い切れない。
同じ文献なので先取権は何とも言えず、もしどれかのグループが統合された場合の判断は誰かが行うことになるだろう。
Bostrychia 属は5種が含まれアフリカの種類。見かけはトキに特に似ているわけではない。
Lophotibis 属は1種でマダガスカルトキ Lophotibis cristata White-winged Ibis (Madagascar ibis, Madagascar Crested Ibis) で色彩などはトキに特に似ていないが、属名は lophotos 冠のある ibis トキ (Gk) なので日本のトキの属名はこれでもふさわしいものになっている。
Nipponia 属は見かけなどは大きく違うのでおそらく別属だろうと想像するが、こればかりは分子系統解析を待つしかないだろう。マダガスカルトキも Kuramoto et al. (2015) (#クロトキの備考) でトキグループの1種として調べられているだけなので他のトキ類との類似性はわからない。
[トキの遺伝的多様性]
日本では野生絶滅し、中国から再導入されたがどの程度「同じトキ」と言えるのか関心をお持ちの方も多いだろう。
「日中トキ、やはり同一種 DNA分析で確認」(2003)、「能登、佐渡のトキは同一種 県など、DNA鑑定で確認「能里」の子孫、里帰りへ」(2009) の報道が wikipedia 日本語版に出ている。
以下はさらに詳しい研究で、Feng et al. (2019) The Genomic Footprints of the Fall and Recovery of the Crested Ibis がこの疑問にある程度答えてくれる。
1841-1922 年の過去の分布域の 57 標本の分子遺伝学解析を行ったところ、かつて持っていた遺伝的多様性のほぼ半分が失われ、過去に分布していた複数の系統が失われたことが明らかになった (つまりかつての日本からロシア極東の個体群と、現存する個体群のもとになった中国中央部の個体群、及び中国東部、中国北西部の個体群は互いに独立した個体群と分離できる程度には違っていたことがわかる)。
過去の実効個体数推定の結果では人為的影響は 600 年前には始まっていたと推定される。この種にとって過酷な状況は 100 年程度続いたようである。現存の個体群は2繁殖つがいからもたらされたもので、個体数のボトルネック効果は非常に大きく、近親交配と遺伝的浮動によってかつての多形性が大きく失われることになった。
2009 年の日本の報道(上記)では金沢市城北児童会館の剥製ではこれまでに発見されている4種類の遺伝子系統とは別の新しい系統であることがわかったともある。国内産トキの間でも多形性があったことがわかる。
トキの野生復帰の現状〜佐渡の現場から では「中国のトキと日本にいたトキのミトコンドリア DNA は 0.06% しか違わない。これは、個体間の変異程度である」と書かれているが、Feng et al. (2019) の解析によれば同一クレード内の個体による違い (これを個体間の変異に相当するものとしてよいだろう) に比べ、クレード間の距離はずっと大きい。「個体間の変異程度である」との表現は現在では正しくないと思われる。
これらを見るとトキの遺伝的多様性にとって日本の系統が失われてしまったことは非常に残念なことだったと思える。最近では中国由来の個体の増殖が進み、過去のことは忘れ去られがちであるが、やや古い書物ではトキの人工授精の試みの失敗の生々しい記述も見られる。これらを読むと日本の系統を保存できるチャンスは実は何度もあったのではないかと感じる。
日本産トキを救えなかったことについて、日本に内在する構造的問題 (これは現代にも通じるものがありそうである) があったことを小林照幸「朱鷺の遺言」(中央公論社 1998) が指摘している (内容には正確でない部分もあるようである。wikipedia 日本語版注釈も参照)。
wikipedia 日本語版によれば、「ミドリ」や「キン」の組織は冷凍保存されており、この2羽の皮膚細胞から人工多能性幹細胞 (iPS 細胞) を作り、日本産の遺伝子を受け継ぐ個体を復活させる取り組みを、国立環境研究所が 2012 年から開始しているとのことである。
絶滅危惧鳥類における iPS 細胞の作成はヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウですでに報告されている [Katayama et al. (2022) Induced pluripotent stem cells of endangered avian species]。
トキでもおそらく成功するであろうが、鳥類は哺乳類と同様の技術ではクローニングができない。卵黄が大きすぎて顕微鏡下の操作ができないためである (Audubon の解説)。そのため iPS 細胞が確立されても個体 (群) の復活に結びつけるにはまだ道が遠そうである。
[中国のトキの再発見]
日本で全羽捕獲され野生絶滅となった時 (1981年1月)、ちょうど中国でトキの再発見 (1981年4月) の知らせがあった。その再発見物語を中国の研究者の劉蔭増が「美人鳥朱鷺」(湖南少年児童出版社 1988) として著し、桂千恵子によって翻訳された「トキが生きていた - 国際保護鳥トキ再発見の物語」[ポプラ・ノンフィクション(58) 1992] がある。
当時中国ではトキは絶滅したと考えられており、絶滅を確認するための調査であった。広大な中国のどこを捜索すればよいか、またわずかな手がかりから生息の可能性に迫る過程など、科学者の着想がいかんなく発揮されたことが記述され、児童書とはいえ厚みのある内容となっている。また絶滅に瀕した他のトキ類への温かい眼差しも感じられ、機会があればぜひお読みいただきたい本である。
また、例えば劉蔭増第一発見者で発見 40 周年 (2021) の報道が読める。
[繁殖時の色変わり]
繁殖期は頸部の皮膚が内分泌により黒くなり、ここから剥がれ落ちた皮膚を上半身に塗り付けるため黒灰色になる (wikipedia 日本語版より)。Delhey et al. (2017) Cosmetic Coloration in Birds: Occurrence, Function, and Evolution によれば鳥類で皮膚からの色素分泌が知られているのはトキのみで、特異であるとは記述されているがそれ以上調べられていないと記されている。
論文になっているものでは、Wingfield et al. (2000) Biology of a critically endangered species, the Toki (Japanese Crested Ibis) Nipponia nippon
があり、皮膚の分泌部位の写真が示されているが、この論文の時点では成分 (メラニン?) や実際にどのように分泌されるかはわかっていなかったようである。
同じ論文の紹介であるが、Avian Integument では表皮細胞の脂質が分泌されると解説している。他の鳥の表皮構造・機能などとも比較してこの機構が妥当であろうと説明されているものと思う。
この研究者による総説もあって Ritchison (2023) Integument (in "In a Class of Their Own", Fascinating Life Sciences book series, Springer) 基本的に同じことが書かれている。
なお初期の論文は Uchida (1970) On the color change in Japanese Crested Ibis にある (羽毛の鞘を取り囲む細胞から分泌されているとの考えで、上記解説とは多少違いがある)。
森本 (2015) Birder 29(10): 70 にトキの「化粧色」と題して記事がある。換羽や摩耗による以外の色変わりは発見当時はなかなか受け入れられなかったことも記されている。この記事によれば研究が行われているようなので結果に期待したい。
Sun et al. (2020) Transcriptome Comparison Reveals Key Components of Nuptial Plumage Coloration in Crested Ibis が遺伝子発現 (トランスクリプトーム) の解析からユーメラニン合成にかかわる遺伝子が活発に働いていることを見出した。
メラニン系統の物質であろうと推定。鳥類の繁殖羽衣の色彩には比較的使われていない。
この着色の前に着色部位の綿羽を入れ替えるとのこと。この新しい綿羽は形態も特殊で物質を結合しやすくしているとのこと (Wingfield et al. 2000)。ほとんどの溶媒に溶けないので化学分析が難しいとのこと。推定分泌機構が fig. 4 に示されている。
皮膚の keratinocyte (角化細胞) に含まれた色素が落屑によって分泌されると推定している。早い話が普通の皮膚細胞の入れ替わりが促進されている状態。
ということで遺伝子発現からほぼ正解と言える答えが出た模様。主に家禽の品種の色に関係して羽毛や皮膚のトランスクリプトーム解析はかなり行われていてそれが応用された感じ。
最近になって Liu et al. (2023) A Breeding Plumage in the Making: The Unique Process of Plumage Coloration in the Crested Ibis in Terms of Chemical Composition and Sex Hormones に組成分析の論文が出版された。
fig. 2 に首の黒い皮膚と細胞内の黒い顆粒の写真がある。首やのどのパッチから粘性のある物質が分泌されるそうで、黒色物質の分析の結果水に溶けない 117 種の化学物質が検出され、23 種類のエステル (20%)、50 種類の炭化水素 (42%) その他が認められた。ケトン、アルデヒド、アルコールも少量含まれていて同定された化学物質の一覧が出ている。
エステルは脂溶性の層を作って耐水機能を持つとのこと。炭化水素は色彩に関係している可能性がある。
全体的な組成はユーメラニン (eumelatin) に非常に似ているとのこと。よく知られているユーメラニンに含まれる (重合要素となる) 化学物質 (インドール骨格を含む。窒素を含む) は含まれていなかったが、
類縁物質 [窒素を含んでいるが挙げられている大部分はインドール骨格は持たない。8,19-Secoyohimban-19-oic acid, 16,17,20,21-tetradehydro-16-(hydroxymethyl)-, methyl ester, (15.beta.,16E)- は似ている。化学物質の系統名は非常に長い。Secoyohimban というのはアルカロイドの名称のよう] があるとのこと。ユーメラニン同様にこれらの化学物質が重合して黒い色彩を作っていると考えられる。
分泌は性ホルモンで制御されている。化学物質の合成経路などの研究は今後の課題。
完全に同じとは言い切れないかも知れないが、トキの化粧色はユーメラニン類似物質と考えてよさそう。
化粧色のレビューは Delhey (2007) Cosmetic coloration in birds: occurrence, function, and evolution にあるとのこと。これまで考えられていた以上に広く少なくとも 13 科に存在するとのこと。尾脂腺、皮膚からの分泌、粉綿羽、そして外部の物質を使うタイプがある。
[過去の生息地の再導入]
韓国の報道 (英文) Crested ibises return to wild in S. Korea 40 years after going extinct (2019)。
ロシア: ハバロフスクでの報道 (2020 ロシア語) 絶滅したトキがハバロフスクの自然保護区のシンボルに。
[その他]
Xu et al. (2024) Evolution and expression patterns of the neo-sex chromosomes of the crested ibis
にトキの高精度の染色体レベルのゲノム解読の報告がある。かつての性染色体と微小染色体の融合があって neo-sex chromosome になっているとのこと。クロツラヘラサギでも同様と思われる結果が出ており、トキ科の共通祖先の段階で起きたと考えられる。
さらに関連した考察があり Charlesworth (2025) When did recombination suppression events occur in bird ZW sex chromosomes? 鳥類の染色体進化と鳥類の系統進化に関わる興味深い問題とのこと。
Neoaves の系統の中でトキ類の系統で特異的に (つまり独立に) 起きたものか、Neoaves の祖先段階であったものか。詳しく調べられている種類はまだ限られているので今後の進展に期待。
-
ヘラサギ
- 学名:Platalea leucorodia (プラタレア レウコローディア) 白いサギのヘラサギ
- 属名:platalea (f) ヘラサギ (platos 幅 Gk)
- 種小名:leucorodia (合) 白いサギの (leuko- (接頭辞) 白い erodios サギ Gk)
- 英名:Spoonbill, IOC: Eurasian Spoonbill
- 備考:
platalea は短母音のみで -ta- がアクセント音節 (プラタレア)。
leucorodia は起源となるギリシャ語では -ro- の o が長母音とのこと (由来となるサギの erodios の母音を引き継ぐ)。アクセントもこの位置で都合がよい (レウコローディア)。
現在はハシビロガモを指す英語の shoveler は本来はヘラサギを指していた (当時の綴り shovelard または別綴り) #ハシビロガモの備考参照。
shoveler をヘラサギに用いる用例は 18 世紀末まであったとのこと。
英語の spoonbill の由来は想像通りであるが、ヘラサギを指す事例は 1678 年から知られているとのこと。他の種にも用いられており Dwarf Spoon-bill, Platalea pygmea Latham (1785), General Synopsis of Birds は Linnaeus (1758) のヘラシギの学名と同じ。起源的にどちらが古かったまでは不明だった (OED)。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 leucorodia とされる。
日本での原記載 Platalea major Temminck & Schlegel, 1849。図版。
major は leucorodia のシノニムとされ、現在は一般には使われていない。
この major, minor は#タシギのように属を分離するために改めて付けられたものではない。
Howard and Moore 2nd edition, Peters' Check-list of the Birds では major を亜種として取り扱っていた。
種ヘラサギの原記載。Linnaeus 以前にも Leucorodias の学名が使われており、踏襲して整理した種小名の模様。
当時はもちろん系統関係などはわからず、フラミンゴ、ヘラサギ、サギ、シギ、クイナ類などは同じグループ Grallae (水鳥) にまとめられていた。
大橋 (2024) Birder 28(1): 50-51 でサギでないのにヘラサギの種小名にサギが現れることを気にされているようだったが、Linnaeus 時代にはあまり区別されていなかった。そもそも和名にサギが現れている。
[嘴先端の触覚で採食する鳥]
ヘラサギ類は嘴先端の触覚で採食することがよく知られていて観察していてもわかりやすいが、同じような仕組みを持つのはトキ科、シギ小目 Scolopaci、そしてキーウイで、嘴の感覚器の数と系統関係を調べた研究がある:
du Toit et al. (2020) Cretaceous origins of the vibrotactile bill-tip organ in birds。
上記の3系統は遠くのものに触れて採食する (remote-touch probing) のグループに含まれているが、嘴を感覚器官として用いるグループは別タイプの構造のカモ類、他の系統でもクイナ類、セイタカシギ類の一部など多系統にわたっており、他のグループにも嘴先端に痕跡的な付属物が見られることからこの感覚は祖先形質であろうと考えられる。
Telluraves の新しいグループの鳥では事実上見られないがヤツガシラ類が嘴の触覚を利用しているとのこと。
この論文の Supplementary Information に嘴の感覚器官に通じる穴の存在形態と過去の文献、自身が標本で調べたが一覧が出ている。スズメ目は関係がないがシギ類など他の種がどうなっているか気になる方は見ていただくとよい。
これまで主に嗅覚に頼って採食すると考えられていたキーウイが嘴先端の触覚 (Herbst 小体による振動刺激検出) も利用していることを示した研究: Cunningham et al. (2007)
A new prey-detection mechanism for kiwi (Apteryx spp.) suggests convergent evolution between paleognathous and neognathous birds。この時点では収斂進化と考えられていたが範囲を広げて調べると祖先形質らしい結果となった。
キーウイが触覚を用いていることは脳科学の結果とも整合性がよい: Cunningham et al. (2013) The Anatomy of the bill Tip of Kiwi and Associated Somatosensory Regions of the Brain: Comparisons with Shorebirds。
この論文には嘴の解剖学の図版も紹介されているので脳科学に興味がなくても一見の価値あり。
du Toit et al. (2024) Tactile bill-tip organs in seabirds suggest conservation of a deep avian symplesiomorphy
はアホウドリ類、ペンギン類でも見つかったとのことで海鳥での発見はこれが初めてとのこと。嘴の触覚を採食などに用いていると考えられる。用いられている系統樹はやや古いので注意。
Cunningham et al. (2007) と基本的に同じような結論を導いているが調査範囲を広げたもの。
[ヘラサギ類の嘴はなぜ先が広がっているか]
#オオフラミンゴの備考 [フラミンゴ類の採食と嘴の形・動かし方] と参考文献を参照。ヘラサギ類についても同様のメカニズムが 1990 年代に提唱されていたが、フラミンゴ類の測定の結果より詳しく判明した。
-
クロツラヘラサギ
- 学名:Platalea minor (プラタレア ミノル) 小さなヘラサギ
- 属名:platalea (f) ヘラサギ (platos 幅 Gk)
- 種小名:minor (adj) より小さい
- 英名:Black-faced Spoonbill
- 備考:
platalea は#ヘラサギ参照。
minor は "ミノル"。
単形種。
記載は Temminck and Schlegel (1849) によるもので原記載。
La petite spatele du Japon (日本の小さなヘラサギ) とあり日本で記載、ヘラサギに比べて petite taille で体格が小さいことから。
同書 (前ページ) でヘラサギには Platalea major の学名と La grande spatele du Japon (日本の大きなヘラサギ) の名称を与えており、ヨーロッパのヘラサギとは別種と考えていた。
この major は現在使われる学名には残っていないが、Temminck and Schlegel (1849) は日本のヘラサギ類を大小セットで命名していた。クロツラヘラサギの種小名 minor のみが現在残ることになった。
図版。この絵では "クロツラ" の顔になっておらず若鳥を指したもののよう。Temminck and Schlegel は "クロツラ" は意識していなかったと想像できる。
Platalea melanorhynchos Reichenbach, 1845 の学名が存在 (黒い嘴のヘラサギ) があり、こちらはオーストラリアヘラサギ 現在の学名 Platalea regia Royal Spoonbill のシノニムとされる。Reichenbach (1845) の学名由来で Black-billed Spoonbill の英名もある。
ヘラサギ類の中でクロツラヘラサギに最も近縁の種類。
クロツラヘラサギの英名 (和名と同じ意味) の Black-faced Spoonbill はこの Black-billed Spoonbill との違いを明らかにする目的で付けられたものではないだろうか。
しかし学名が Platalea regia Gould, 1838 (こちらの方が早かった) と変わったことで Royal Spoonbill の英名が標準となって現在では英名の類似性がわからななくなった、などの経緯が考えられる。Royal Spoonbill の画像を見ていただければ、こちらもほとんど "クロツラ" と呼んで差し支えないことがわかっていただけるだろう。
クロツラヘラサギの和名は独立に付けられたものかも知れないが、英名と一致しているので英名から導入されたものかも知れない。もしこの2種の英名が対比させる形で付けられたものであれば Reichenbach (1845) の学名に由来することになる。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では英名が Swinhoe's Black-faced Spoonbill となっていて Temminck and Schlegel の図版の顔の色は間違っていると注釈があり、Swinhoe のタイプ標本では黒色なのに "Fauna Japonica" では記述にも絵にも示されていないとのこと。
やはりオーストラリアヘラサギを Platalea melanorhyncha の学名で挙げており、との顔の色の関係について記されており、"クロツラ" はここで確立した概念だったと考えられる。
Gluschenko and Korobov (2023) Interesting ornithological observations and finds in the southwest of Primorsky Krai in 2023 (pp. 5038-5057)
によれば 2023 年夏から秋にロシア沿海地方でヘラサギとの混群が見られた。雑種とみられる個体も記録された (fig. 13 右)。親に食物をねだる若鳥も記録された (fig. 16)。
Hong Kong Biodiversity Genomics Consortium (2024) Chromosomal-level genome assembly and single-nucleotide polymorphism sites of black-faced spoonbill Platalea minor
香港のチームによるクロツラヘラサギのゲノム解析。
△ ツル目 GRUIFORMES ツル科 GRUIDAE ▽
-
ソデグロヅル
- 第8版学名:Leucogeranus leucogeranus (レウコゲラヌス レウコゲラヌス) 白いツル (IOC も同じ)
- 第7版学名:Grus leucogeranus (グルース レウコゲラヌス) 白いツル
- 第8版属名:leucogeranus (合) 白いツルの (leuko- (接頭辞) 白い geranos ツル Gk)
- 第7版属名:grus (f) ツル
- 種小名:leucogeranus (合) 白いツルの (leuko- (接頭辞) 白い geranos ツル Gk)
- 英名:Siberian Crane
- 備考:
leucogeranus は起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-ge- がアクセント音節と考えられる (レウコゲラヌス)。
-geranus 部分は別説があり、ラテン語 gerere (原形 gero) 帯びている、着ている 由来とも言われる (The Key to Scientific Names)。
grus は#クロヅル参照。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Leucogeranus 属。Bonaparte (1855) が種小名より昇格させた属名。
Sharpe (1893) もソデグロヅルに別属 Sarcogeranus を与えた (sarco 肉色の geranos ツル Gk)。これはおそらくトートニムになるのを嫌ったためではないだろうか。この属名は化石の用例がある (Serebrovski 1940)。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じで、属名はソデグロヅル属となる。単形種。
世界的希少種。
分布図を見ていただければ東西の2個体群があることがわかる。中央にもかつては個体群があったが絶滅した。
大型の渡り鳥の衛星追跡が日本で行われるようになった初期の1995-1996年、日本野鳥の会が関わったソデグロヅルの渡りルート解明が行われた。Kanai et al. (2002)
Migration routes and important resting areas of Siberian cranes (Grus leucogeranus) between northeastern Siberia and China as revealed by satellite tracking,
が論文。これは東の個体群に対応する。
Kanai et al. (2002)
Discovery of breeding grounds of a Siberian Crane Grus leucogeranus flock that winters in Iran, via satellite telemetry
が西の個体群の繁殖地を衛星追跡で明らかにした論文。
日本語の解説記事などがもう少し Web で読めるかと期待したが、時代が少し古いこともあって見つけられなかった。
代わりに 2017 年に千葉県に飛来したソデグロヅルの記事があった。
珍鳥 vs カメラマン(奴賀) (バードリサーチブログから)。
西の個体群は絶滅に瀕している。比較的最近世界的にも話題となった
ロシアのプーチン自身が音頭をとって超軽量飛行機に乗ってソデグロヅルの若鳥に渡りルートを教えるプロジェクト "flight of hope" (ロシア語 polet nadezhdy) が2012年9月に始まったが頓挫したとのことである
プーチン大統領のツル誘導飛行、大失敗に終わる 日本語訳された報道記事 (2012)。
Russian Effort To Save Cranes Fails To Get Off The Ground (2017 年の記事)。
当時のプーチンは絶滅に瀕する種類の保護に前向きな姿勢を示していたが、その後はどうなったのあろうか...
以下に 2011 年のインドの記事と映像資料がある Technology to bring back Siberian crane to India。
ツルは生まれた時から渡りルートを知っているわけではなく、何らかの方法で教わる必要がある。
The "Lily of Birds" A Journey To Help the Most Unique and Endangered of Cranes (CMS booklet)
によれば卵から孵化させたツルをロシアの繁殖地などで放鳥する、あるいは仮親を使う試みが1990年代中盤より行われ約 15 年で 100 羽が放された。生存率は20%を超えなかった。仮親について渡りをしたがその後行方不明となり越冬地では1羽も観察されなかった。
イランやインドで放鳥された鳥は渡りをせず姿も見られなくなったそうである。
イタリアの飛行家、冒険家。ハンググライダー、無機関・無動力の超軽量飛行機などを使用した冒険飛行で世界記録を保持していた Angelo d'Arrigo アンジェロ・ダリーゴ は 2001 年鳥とともに飛行する冒険を開始し、2002 年ソデグロヅルの群れとともにシベリアからカスピ海を経て、イランに抜ける飛行を行った
(この飛行も polet nadezhdy "flight of hope" と呼ばれている。wikipedia 日本語版/ロシア語版より追記。wikipedia ロシア語版にも 2012 年以降のことは記載がない)。
当時の英語記事例 Hanging With the Cranes (Los Angeles Times)。
アンジェロ・ダリーゴは 2006 年航空ショーの最中に墜落死したそうである。
なお上記の "プーチンの失敗" 記事は多少尾ひれが付いているようで、cyclowikiの記事 によれば
最初の飛行では全部が飛び立たなかった。2回目では全部が飛び立った。全部がすぐに飛び立たなかったのはリーダーの責任で、速度と高度を早く上げすぎた。群れをなして飛ばなかった。とプーチンが述べている。2012年11月に1羽がカザフスタンで見つかってロシアに戻されたとのこと。
プーチンのソデグロヅルはどこへ行った? の 2018 年の記事では、プロジェクトが途中で終わったのは資金不足のためで、1機のモーターグライダーでは不十分で地上部隊も必要だがロシアの鳥類学者にはそのお金がなかった。
しかしあきらめたわけではなく、育った鳥は野生個体群に加えており、費用さえあればプロジェクトは再開されると期待している。ツルの増殖施設で働いている人は大変よくやっている、とのこと。
ソデグロヅルを救う の Interfax 2019 年の記事では、
1990 年代の終わりには放鳥を開始した。それまで個体数は急減していたが横ばいになった。西シベリアの個体群は 20 羽に過ぎず、手を貸さなければ残っていなかっただろう。
ソデグロヅルは通常2卵を産むが1羽しか育たない。ソデグロヅルにも「兄弟殺し」があるらしい。2羽めを育てる余裕はない。
アフガニスタンやパキスタンの方に飛んでゆくとハンターに撃たれてしまうのでそれとは違うルートを覚えさせる必要がある (安全な越冬地をウズベキスタンのアムダリア川流域に確保したいとの目的が上記文献にも含まれていた)。
ヤマル半島での放鳥は 10 年前に途絶えた。資金不足となった。
クロヅルに道案内をさせようとしているが、実際どこに飛んで行っているのかよくわからない。
資金さえ予定通りに入ってくれば計画は再開できると考えている。最初の渡り個体群が確立できれば後は個体を追加するだけでずっと費用がかからず回復できるだろうとのこと。
飛行機で誘導してツルに渡りルートを教える方法はアメリカシロヅル Grus americana 英名 Whooping Crane で使われた。この種はアメリカの自然保護のシンボルとも言える鳥。この分野の古典と言える「復活 - アメリカシロヅル絶滅への挑戦」(原書 The Whooping Crane F・マックナルティ; 藤原英司訳 どうぶつ社 1978) では「絶滅の危機に直面した鳥、アメリカシロヅルがいま 124 羽まで復活した。生命の賛歌を歌い上げたアメリカ自然保護の生きた見本」とある。
渡辺 (1996) Birder 10(1): 36-39 の記事にアメリカシロヅル保護活動の初期からの状況が載っている。この記事によれば軽飛行機で誘導する試みは1995年に始まったものとのこと。
ソデグロヅルのロシア名は sterkh (カタカナではスチェルフとしか書けないが音はだいぶ違うかも)。何か由緒ありそうな名前だがドイツ語の Storch コウノトリが語源とのこと。白くて似ているために動物学者の Pallas が与えた名前であろうと考えられている。
「世界の鳥 1」(小学館 1985) pp. 148-149 の記事 (竹下信夫) によれば植物の地下茎や根の養分を食べることができる。頭部に羽が生えていないので嘴を深く泥の中に差し込むことができ、ガンにはできない芸当であるとのこと。改めて写真を見ると目が浸かるぐらいまで入れても大丈夫そう。
-
カナダヅル
- 第8版学名:Antigone canadensis (アンティゴネー カナデーンシス) カナダのアンティゴネー (IOC も同じ)
- 第7版学名:Grus canadensis (グルース カナデーンシス) カナダのツル
- 第8版属名:Antigone トロイの Laomedon 王の娘でコウノトリに変えられた
- 第7版属名:grus (f) ツル
- 種小名:canadennsis (adj) カナダの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Sandhill Crane
- 備考:
Antigone (固有名詞) はラテン語では末尾が長母音。ギリシャ語でも同様でアクセントは短母音の o にある。ラテン語規則では -ti- がアクセント音節と考えられる (アンティゴネー)。
Antigonos も日本語でもアンティゴノスと呼んでいる。Antigone は wikipedia 日本語版でも "アンティゴネー" (または アンティゴネ) の見出しになっているので "アンティゴーネ" の表記は俗発音由来と思われる。ここでは "アンティゴネー" に統一しておく。
grus は#クロヅル参照。
canadensis は地名由来の語尾 -ensis を強調したい場合は e が長母音でアクセント (カナデーンシス)、短くしてもアクセントの移動はない (カナデンシス) のでどちらでもよい。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Antigone 属。Antigone はトロイの Laomedon 王の娘でコウノトリに変えられた。
Linnaeus はこの神話とツルに変えられた Gerana の神話を混同した。両者とも lese-majeste (英語で a crime against The Crown の意味に相当する中世フランス語)の罪を犯したとされる。
Antigone 属は Reichenbach (1853) によるものでタイプ種は Grus torquata Vieillot, 1817 と指定され、Ardea antigone Linnaeus, 1758 (オオヅル) と同定されたとのこと (The Key to Scientific Names)。
オオヅルの現在の学名は Antigone antigone (英名 Sarus Crane) だが種小名から属名への直接の昇格ではなかった。
Gruiformes (BirdForum 2023.7) によれば Antigone 属の名称は過去に別の動物 Antigona Schumacher, 1817 の別綴りとして用いられたように見えたことがあったとのこと。
ここで用いられた Antigone はフランス語の慣用名で、Gray がそのまま属名として用いた事例があるが Antigona を改名する意図は示されておらず単純な誤りと判定された。この事例が属名の改名と認められなかったため使用済みとは認められず、Antigone Reichenbach, 1853 は有効で現在の学名に至っている。
Antigone は首をつって自殺したので首が赤く裸出するオオヅルにこの名を与えたのだろうとの解釈もある (コンサイス鳥名事典)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では同じ分類の扱いで、Antigone 属はマナヅル属となる。種小名は変化なし。
5亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は基亜種 canadennsis とされる。
久井 (2013-2014) 江戸時代の文献史料に記載されるツル類の同定 - タンチョウに係る名称の再考察 - には "Fauna Japonica" にはカナダヅルが記されていて、江戸時代の日本にカナダヅルが飛来していた事実が確認できるとあるのでこれも見ておかないといけない:
図版 当時の学名 Grus cinerea longirostris。本文。
学名をみるとクロヅルの別型 (亜種に相当) 扱い (しかし嘴の長いツルとはいかにも当たり前すぎる学名)。Hartert (1910-1922) p. 1817 では基産地日本、カナダヅルと判定で標本はライデン博物館にあるとのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) には亜種シノニムとしても現れないので、Hartert では preoccupied とはなっていないものの何か問題のある学名だったのだろうか。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 100 (内田) によれば、その後の国内のカナダヅルの記録はなかったそうで、1963.12.6 の鹿児島県荒崎で高野伸二氏の記録がそれ以降の初となったとのこと。当時は 100 年ぶりなど報道でも大きく扱われたらしい。
クレチマル・千村 (訳) (1991) Birder 5(7): 27 に北米からシベリアにカナダヅルが進出しているとの記載がある。
Barykina and Solobyova (2023 初出、2024 再掲) Breeding density of the lesser sandhill crane Antigone canadensis canadensis in Western Chukotka (pp. 4618-4621)
北米で過去 30 年で7倍に数を増やし、現在ではヤクーチア北部ツンドラでソデグロヅルとともに繁殖している。チャウン湾での 2011-2022 年の観察記録があるがこの期間に特に数は増えていない。
[2025 年アメリカで鳥インフルエンザによる集団死]
アメリカインディアナ州で 2025 年 1-2 月に 1500 羽のカナダヅルが H5N1 で死亡 Bird flu kills thousands of Sandhill Cranes in Indiana (BirdGuides 2025.3.13)。
越冬に来るとともに集団全体に広がったとのこと。現在ちょうど北帰行の最中で移動途中の地域でも死亡例が報告されている。1500 羽でもおそらく過小評価とのこと。距離を開けろと鳥に頼むことはできないので人ができることは限られている。死体回収をボランティアが行っている。
-
マナヅル
- 第8版学名:Antigone vipio (アンティゴネー ウィピオー) (アンティゴネーの) 小型のツルの一種 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Grus vipio (グルース ウィピオー) 小型のツルの一種
- 第8版属名:Antigone トロイの Laomedon 王の娘でコウノトリに変えられた
- 第7版属名:grus (f) ツル
- 種小名:vipio バレアレス言語で食用のツルの一種に由来
- 英名:White-naped Crane
- 備考:
Antigone は#カナダヅル参照。
grus は#クロヅル参照。
vipio は末尾が長母音で冒頭にアクセント (ウィピオー)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Antigone 属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。種小名は変化なし。単形種。
Pallas (1831) による 原記載。極東での記載なのになぜバレアレス言語が出てくるのかすっきりしないが、小型のツルを表すラテン語として存在したものを Pallas がたまたま (適当に?) 採用したのだろうか。ヨーロッパ産の種類ならばもう少し名称を考えていたかも知れない。
Temminck (1827) は Siebold の日本の標本から Grus leucauchen Temminck, 1827 (参考) と名付けていた。leucauchen は leukos 白 aukhen 首 (Gk) で英名はこの学名が由来と考えられる。ドイツ語名も Weissnackenkranich とこの学名と同じ意味。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でもこの学名が用いられており、意味はわかりやすいので長く使われていたものと想像できる。
Seebohm (1890) は複数の種類のツルが white-naped にあてはまるのでこの英名はちょっと不運であると述べている。
vipio の種小名も我々には馴染みがないので学名に恵まれなかった種類か?
1940 年でもこの学名の用例があった: Erfolgreiche Zucht von Weissnackenkranichen (Grus leucauchen) (Hagenbeck)。
Hartert (1910-1922) p. 1818 によれば Pallas の学名が正当か議論があったようで、Blaauw は monachus との混同を問題にしていた模様。Hartert は Pallas の記述が本種を指すことは疑いない。大きさの記述が合わないらしいがこれは Pallas が実際には見ておらず Gmelin の記述をもとに記載したので理解できるとのこと。
このように Pallas の学名が正当か問題提起があったため次に古い Temminck の学名がよく使われていた模様。
国松 (2010) Birder 24(3): 69 で古代エジプトでクロヅルとアネハヅルが生息しており食用にされていた記述がある。
widgeon (Etymology Online) によればラテン語 vipio からフランス語 vigeon そして widgeon (ヒドリガモ類の英名) が派生したとの考えがあるとのこと。
OED の wigeon の項目によれば vipio に相当するイタリア語 bibbio (ツルの1種、1562 年の用例があり Pliny を参照しているとのこと。語源は不明とのこと) が紹介されている。
バレアレスから派生するツル類の属名に Balearica がある。
ハチ類に Vipio 属 (寄生蜂 コマユバチ科 Braconidae) が存在する。
[大陸のマナヅルの渡り研究]
渡りの最新研究: Yanco et al. (2024) Migratory birds modulate niche tradeoffs in rhythm with seasons and life history。
アネハヅル、クロヅル、オグロヅル、マナヅルが研究対象。この研究で対象となったモンゴルのマナヅルは多くが中国ポーヤン湖で越冬。White-naped crane Mongolia WSCC のプロジェクトによるもので 2013-2021 年に追跡。
White-naped crane Mongolia WSCC (Movebank) でデータが公開されている (他の種も同様)。
出水で越冬する個体は朝鮮半島非武装地帯でしばらくとどまるなどもあるなど現代的なデータの詳細を見ることができる。
さらに詳しい解析を行いたい者も使うことができる。
朝鮮半島で越冬するマナヅルの渡り研究: Nam et al. (2025) Migration and population characteristics of white-naped cranes wintering on the Korean Peninsula 朝鮮半島の個体数は 2000-2024 年の間に急激に増加中。ほとんど 10000 羽に達している。また西ルート (中国で越冬) の個体も一部朝鮮半島に移動することが確認された。
朝鮮半島の越冬環境の改善が要因の一つに考えられるかも知れないとのこと。海を越えて遠くまで越冬に行かなくても十分であれば...とツルがみなすことは、渡りルートを見るといかにも考えられそう。
また突然の変化が見られていないことから、鳥インフルエンザの影響を受けてルートを変えたわけではなさそうなことも想像できる。
日本の越冬個体数をすでに上回っており、朝鮮半島内でもある程度分散している。これまでも越冬地分散の必要性が訴えられてきたが、別の形で実現しつつあるのかも知れない。
-
タンチョウ
- 学名:Grus japonensis (グルース ヤポネーンシス) 日本のツル
- 属名:grus (f) ツル
- 種小名:japonensis (adj) 日本の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Japanese Crane, IOC: Red-crowned Crane
- 備考:
grus は#クロヅル参照。
japonensis は地名由来の語尾 -ensis を強調したい場合は e が長母音でアクセント (ヤポネーンシス)。短くしてもアクセント移動はなくどちらでもよい。
一度は古典式で読んでみて感覚を確かめるのがよいだろう。
単形種。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では日本産の Grus 属は3種のみとなる (分類について#アネハヅルの備考参照)。
属名の和名はツル属となっているが和名検討中だった。最終的にクロヅル属 (Grus 属のタイプ種) となった。
注意すべきはマナヅルとナベヅルは別属となることで、厳密に書けばこの2種のいずれかを指して「Grus 属の一種 (または sp.)」と書けなくなる。
[学名や英名の由来]
原記載 では Ardea (grus) Japonensis Mueller, 1776 と Ardea (grus) の位置づけだった (表記上は亜属の扱い)。#クロヅル備考のように当時は Grus 属は中途半端な状況でしっかりした属定義はまだなかった。
Mueller 自身はツル類 Kraniche. Grues. とドイツ語と (たぶん) フランス語で表しているが Grus を属名として示したものではない。
Der Japanische Kraninich (日本のツル) として紹介されたもの。
一つ上に Ardea (Grus) mexicana Mueller, 1776 があり、こちらは Der mexicanishce Kraninich (メキシコのツル) で、Mueller はツル類を4種紹介している。Grus mexicana はカナダヅルのことで Ardea canadensis Linnaeus, 1758 の記載の方が早いので現在はこちらが使われる。
4種のうち記述の詳しいのは Ardea (grus) Leucogerana Mueller, 1776 のみでソデグロヅル。Grus Leucogeranus Pallas, 1773 としてすでに記述されており、Mueller の記述もそれに基づくもの。
残り3種は他者からの伝聞のみでもう1種はアメリカの Ardea (Grus) Buccinator Mueller, 1776 アメリカシロヅル (Whooping Crane をそのままドイツ語と種小名にしたと想像できる)。こちらも Ardea americana Linnaeus, 1758 の記述が早い。
Mueller (1776) は grus (亜)属を用いことで Linnaeus (1758) と異なる種小名を与えたものと想像できる (#ノスリの備考参照)。
この4種を見るとタンチョウの原記載とは思えないほど短いもので、たまたまこの文献に最初に登場したため原記載となった印象を受ける。
Er ist weiss, oben am Kopfe roth, am Halse und den Schwungfedern schwanz, aber an den Ruderfedern weiss (白色で頭頂が赤く、首と風切羽は黒いが翼は白色)。特徴の記述はたったこれのみ。特徴は捉えられているのでタンチョウと疑いなく判定されたのだろう。伝聞ではこのあたりが精一杯だったのかも。後述の Brisson (1760) よりもさらに短縮されている。
メキシコのツルと日本のツルはいずれも Boddaert (Pieter Boddaert 1730-1795) の情報によるもので、どちらも伝えられた生息地から命名したらしくあまり深い意味はなさそう。「日本にこんなツルがいるらしい」ぐらいの情報だったと想像できる。この情報に基づき基産地日本となっているが、18 世紀に誰がどのように知った情報だったのだろう。本当に日本で目撃されたものだったのだろうか。
Boddaert は 1783 年にトビなど多数の学名を発表しているが、Mueller はその一足前に発表した形になっている。当時はすでに博物学者に知られていた学名で誰が発表するかは問題でなかったのかも知れないが。なお Boddaert の 1783 年の書物にはタンチョウは現れない。
季刊アニマ「鶴」(1975) の林田恒夫氏の解説 (p. 54) によれば記録としてのタンチョウの出現は徳川光圀 (水戸黄門) の命令で蝦夷地の探検を行った際にタンチョウを持ち帰ったことが渉海記事に現れるとのこと。wikipedia 日本語版によれば 1688 年とのこと。
1715 年貝原益軒の「大和本草」で「丹頂松前にあり、日本西州之無」の記述があり、すでに 17 世紀後半にはタンチョウが北海道に生息していたことがわかるとのこと。
1781 年の「松前誌」にタンチョウの生態が記されているとのことで、北海道の東部や勇払原野に多い。後趾が短いことから樹上には棲みがたい。古今の画師が鶴の飛翔するところを画いた時に、尾に色をつけているは誤っている、などの指摘があり生態も詳しく記録されているとのこと。家臣が銃で鶴を 300 羽も獲っているとあり当時はタンチョウがかなりいたと推定されるとのこと。
季刊アニマ「鶴」の村重寧氏の解説 (p. 113) によれば正倉院の金銀平脱八角鏡に花をくわえる飛鶴の文様があり、中国からの将来品と思われるとのこと。平安時代には松喰鶴などの図柄が好んで使われたとのこと。中国伝来のタンチョウの図柄に日本独自の味付けをしたらしく、「松前誌」はこれらの図柄が誤っていることを指摘したものだろう。
Brisson (1760) やそれ以前の Latham, Buffon との関係を考えると国内で北海道に生息することが報告されていた程度の時期にあたり、西洋にどの程度伝わっていたものだろうか。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire に面白い情報がある。以下この解説に従って少し歴史を振り返ってみる。
Brisson (1760) が Ciconia grus japonensis (参考)、
Gmelin が Ardea grus β、Latham は the Japanese Crane、Buffon は la Grue du Japon (日本のツル) と呼んだ。日本語では O-tsuri または Tsurisama とのこと。
Brisson の名称 (学名というよりラテン語で "日本産の灰色のコウノトリ" の意味) は現代のものに近いが Brisson のこの書物は二名法に則ったものでないため有効な学名ではない。
なお Grus 属は Brisson (1760) が設けたものでこれは有効として使われている。
Brisson (1760) には Habitat in Japonensi Regno の記述があり、文面上は日本統治の地域を指していた。時代を考えると現在の日本国外とは考えにくいが、北海道のタンチョウが知られるようになった程度の時期なので具体的に何を指していたのか判然としない。
日本の絵画にはさらに以前より現れたので日本に生息するものとして海外に伝わっていたのかも知れない。
この記述にも (有効な学名ではないが) Grus Japonensis の過去の用例2例を引用しており、Brisson 以前からあった名称であることがわかる。
アホウドリを同じ Buffon が l'albatros de la Chine (中国のアホウドリ) と呼んだ理由なども歴史的考証の手がかりとなるかも知れない。
「タンチョウの四季」(林田恒夫 1984) p. 43 に当時の日本の動物園のタンチョウはみんな朝鮮半島で捕らえられたものとあった。北海道で厳重に保護されている貴重なタンチョウは動物園で飼育するわけに行かず、朝鮮半島から輸入する (贈答品かも知れないが) のは大丈夫だったのか (?)。
18 世紀に西洋で呼ばれていた「日本のツル」はそもそもどこが由来のものだったのか気になった次第でもあり、朝鮮半島から輸入していなければカンムリツクシガモも絶滅していなかったかも知れないとふと思ってしまう。
久井 (2013-2014) 江戸時代の文献史料に記載されるツル類の同定 - タンチョウに係る名称の再考察 - によれば「丹頂」と「丹鳥」の別の意味の名称があり混用されてきた、丹鳥が現在のタンチョウと一対一に対応する文献的証拠はなかった。「朝鮮鶴」はタンチョウを指す事例があるものの朝鮮半島由来のツル類を広義に指していたとみられるとのこと。
この論文に中国の史料も紹介されている。江戸時代の本草学は、注に注が重ねられて肥大していく東洋的学問であり...とのこと。見たことがないので詳細はわからないが様々な考察を重ねていく形になっているらしい (やって来ていない時期のホトトギスの声を忍び音と呼んだ時代にも通ずるよう。現代でも誰かが言ったり書いたことが原典の適切な引用もなく受け継がれて拡大解釈されて行く状況とあまり違いがないかも)。
これは西洋の Latham, Buffon 時代でも同様だったのではないだろうか。見たこともないが博物学者が何かの伝聞をもとに「日本のツル」と伝えていったものと想像できる。確固たる根拠があるわけでもなく、結局は 1758 年以降に最初に登場した有効な学名を用いる規約によって現在のタンチョウの学名となったと言えるかも知れない。
Brisson (1760) には他にも多くのツル類が載せられているが、メキシコのツルと日本のツルは記述がほとんどなく、色の特徴以外に情報がほとんどなかったものと想像できる。
Grus viridirostris Veillot, 1823 (参考。"緑の嘴の" の意味) と実は記述的な学名も存在した。
Temminck (1829) Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux... は Grus collaris フランス語名で Grue a collier noir (首に黒いところのあるツル。種小名の collaris はこの場合は "首に特徴がある" 意味) と呼んたとのことで、
これは Brisson の Grus Japonensis (前述のように有効な学名ではないと判定されているが当時はまだこの規則がなかったかも知れない) を指しているが、ここでは意図的に改名した。
denomination locale qu'on ne peut conserver, parce que quatre especes distinctes de Grues se trouvent dans cette ile. Patrie, la Chine et probablement le Japon
地域名を残すことは適切でない。この付近には4種の異なる種類のツルが存在するので "日本のツル" の学名は適当でないとの判断のよう。日本に4種のツルがいることまでは確認していないので "おそらく" が付いている。日本にもきっと4種いるだろうから日本を代表させるのはふさわしくないとの考え。
実際に後の時代にマナヅルを指して "日本のツル" に相当する一般名が使われたこともあってこの指摘は正しかった。
Temminck の改名 (Mueller や Brisson の名称が無効であればこちらが最初になり得た) は理屈が通っているように見えるが、Grus Collaris Boddaert, 1783 (参考) がすでに使っていて (記載) そもそも無効名だった。
Temminck の平凡な (?) 学名はこのような preoccupied のケースが多く、この時点では "japonensis" を用いることに否定的考えを示していたが次第に地名や地方名を用いるようになったのかも知れない。もっとも Temminck (& Schlegel) は現在使われている学名の範囲では "japonensis" は使っていない。
他種で紹介するようにいずれも japonica / japonicus で "日本版の" ぐらいの意味で用いていて、Temminck (1829) のこの記述を見ると japonensis と japonica / japonicus の微妙なニュアンスの違いを意識して使い分け、国名として使うのは避けていたように見える。
ちなみに IOC 14.2 に登場する japonensis は4つのみで、タンチョウ、ハヤブサの亜種 (Gmelin)、ハシブトガラスの亜種 (Bonaparte)、キクイタダキの亜種 (Blakiston)。
なお Boddaert の Grus Collaris の用例は "首に特徴のある" (collum 首 -aris 関連した) の意味でオオヅルとされる (意味は#カナダヅル備考の Antigone 参照)。
Antgone montignesia Bonaparte, 1854 (参考 1, 2) でこちらは満州を基産地として記載したもので人名 Louis Charles de Montigny にちなむ (The Key to Scientific Names)。
Dement'ev and Gladkov (1951) によればこのツルのロシアでの同定経緯も単純なものではなかったようで、アムールとウスリーで "白いツル" の繁殖が見つかって Schrenck (1861) と Maak (1861) が記述したがソデグロヅルと考えられていたとのこと。後の研究で沿海地方のソデグロヅルの繁殖は確認できなかった。
Przhevalsky (または Przheval'skij トランスバイカル探検を行った) が 1870 年沿海地方で "中国のツル" (Grus montignesia) を見つけた (報告)。
この報告では Grus leucauchen Temminck, 1827 = 現在のマナヅル を日本のツルと呼び、Grus montignesia を中国のツルと呼んでいた。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば Schrenck や Maak が記録したものはおそらくこれだろうとのこと。さらに 1858 年に Maak が "ソデグロヅル" のひなを確認していたとのこと。当時は海外で日本からのタンチョウはほとんど知られていなかったためによく知られていた別種のツルと混同されていたらしい。
Grus montignesia の名称はシノニムですぐに使われなくなったわけではなく、Gray (1872) (Bartlert 1861) Notes on the breeding and rearing of the Chinese Crane (Grus montignesia) in the Society's Gardens
のように一般名 Chinese Crane として使われて、なんと飼育下 (現在のロンドン動物園の前身となった研究施設) で繁殖まで行われていた。
Nikol'skij (1905) Zemlya i mir zhivotnykh: geografiya zhivotnykh も Grus montignesia の学名を使用 (ついでに Ibis nippon も出てくる)。
このように見ると両方の学名が使われていたようで、英語やロシア語でも "中国のツル" と呼ばれていた時代もあった。しかも 19 世紀に英国で飼育下繁殖まで行われていたとは驚き。
後述のように日本のタンチョウの情報が海外に伝わったのは 19 世紀末らしく、西洋では中国由来のタンチョウの方がむしろ知られていたことになる。
これらの Richmond Index の学名カードを見ると Hartert が Ardea Japonensis が一番古くて有効な記載であると判断した様子がわかる。どの記述が有効か判断の分かれそうな部分で、当時の権威が決めて反論がなかったのでこの学名に落ち着いたものと推定できる。
Seebohm (1890) に戻ると、Seebohm は Sacred Crane と呼んでいた。日本では "神聖なツル" なのでそのように呼ぶとのこと。最高の貴族 (原文 nobles of the highest rank でこのように訳しておく) が大きな儀式の際のみタカで狩ることが許されていた。
この部分は Blakiston and Pryer (1878) A Catalogue of the Birds of Japan をほぼそのまま使っている
(学名は Grus leucauchen, Temminck, 1827 とマナヅルのもの。一方の "Mana-tsuru" は Grus sp. inc. となっているが編集者が Grus monachus ではないかとコメントを残している)。
Seebohm (1890) によればおそらく神聖なツルで標本にすることができなかったため、Siebold のコレクションに含まれていなかったのだろうとのこと。
当時はシベリア東部や満州で繁殖することも知られていたが、中国には冬鳥として渡るのみと考えられていたとのこと (当時西洋に知られていた文献によるもので現代の地理概念とは異なっている)。
Blakiston and Pryer (1882) が "Yezzo" で記録したが、マナヅルと混同されていたとのこと。
Seebohm の記述では all the Japanese Islands で見られるとあり、これは "Yezzo" を含まない意味かも知れない。
しかし外国人には指一本触れさせない (...はちょっと大げさかも知れないが) "神聖なツル" だったはずなのに、わずかの期間に害鳥として絶滅寸前まで追い込まれたことになる。文化の継承などはなかったのだろうか。
週間アニマルライフ (1972) pp. 2325-2330 のタンチョウの項目 (浦本) はさらに手厳しい。1923 年に釧路湿原に生き残っていることが知られ (地元の猟師は知っていた)、道庁がおどろいて中央に報告、翌年の調査で「20 羽以上ハ認メ難シ」と報告された。
1935 年に天然記念物、1952 年に特別天然記念物に指定し湿原も保護されたが指定のしっぱなしで、当時 (記事から想像すると 1972 年のことらしい) に至るまで (中央から地方まで) 官庁は何一つとして調査も保護もしていないのである。本来重要であるはずの繁殖地の調査は行わず、予算措置を必要としない越冬期の調査のみを学校に頼ったらしい。そこまでは書かれていないが、大事なものだと頼まれれば先生も断れないわけだっただろう。
長年続けられている他種の数の記録も発端はこのようなものだったのかも知れない。今では多少の手当は付くのだろうが、各種調査が手弁当のボランティア頼りの部分が多いのもこの時代を引き継いでいるのかも知れない。
しかも指定地域外に繁殖するものが大部分であることがアメリカの学者の調査で 1972 年明らかになった (この文献は不明)、それにもかかわらず企業の開発は続くとほとんど怒りの口調で述べられていた。当時のタンチョウの 100 年の歴史は日本の 100 年の歴史そのものであると述べられており、おそらくその通りだったのだろう。要約で全文の口調までは再現困難なので機会があれば一度お読みいただきたい。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" には Grus japonensis の他に Grus viridirostris, Grus montignesia のいずれも載せられていた。
Hartert (1910-1922) p. 1816 では満州、ウスリー、朝鮮半島で繁殖し、言われるような日本での繁殖は誤りで、日本には渡りで訪れるがどこでもまれと記されていた。
現在のドイツ名は Mandschurenkranich (満州のツル) となっている。他のヨーロッパ言語では日本の、中国の、満州のが混在しているが色 (黒と白など) を用いているものもある。英語の Red-crowned Crane に相当するものは意外に少ない。
2008-2012 年本州北部から北海道西部で記録された3羽のタンチョウが大陸由来であることを示す論文: Miura et al. (2013) Origin of Three Red-Crowned Cranes Grus japonensis Found in Northeast Honshu and West Hokkaido, Japan, from 2008 to 2012。
大陸との遺伝的交流を示唆する研究: Kawasaki et al. (2022) Origin of a pair of red-crowned cranes (Grus japonensis) found in Sarobetsu Wetland, northwestern Hokkaido, Japan: a possible crossbreeding between the island and the mainland population。
[ツル類の系統とディスプレイ行動の関係]
ツル類の系統と行動の関係を調べた研究がある: Novakova and Robovsky (2021) Behaviour of cranes (family Gruidae) mirrors their phylogenetic relationships
どの系統でどの行動が生まれ、あるいは消滅したかが示されている。例えば Grus 属では交尾時の声が現れた。Grus 属内でタンチョウが分岐した後の系統 (クロヅル、ナベヅルなど) で「蝶のポーズ」が出現したとのこと。
ディスプレイ行動の系統進化は他の系統でも知られており、神経機構の進化との関連が示唆されるようになってきている [#オウチュウ備考の [さえずりの進化] の Schwark et al. (2022)。この論文ではマイコドリのディスプレイが扱われている]。
[ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム]
ツル類やハクチョウ類の中には胸骨の中でとぐろを巻く長い気管を持っている種類がある。
「行動・生態の進化」(岩波書店 2006) p. 163 では鳥についての解説ではないが、声道の長さは音声のフォルマント周波数に影響を与え、哺乳類では体サイズや齢のよい指標となることが示されている。
アカゲザル (アカシカとなっている) では発声時に喉頭を下げ、できるだけ声道を長くして共鳴した声を作っているとのこと。フォルマント周波数が低いオスは体も大きく繁殖成功率も高いとのこと。
紹介されていた論文は Fitch (1997) Vocal tract length and formant frequency dispersion correlate with body size in rhesus macaques。
同じ研究者による Fitch (2006) Acoustic exaggeration of size in birds via tracheal elongation: comparative and theoretical analyses
に鳥類の長い気管が体サイズを誇張する効果があるのではないかとの理論的考察がある。
アメリカアリゲーター (ミシシッピワニ) での研究があり、こちらは読みやすそう: Reber et al. (2017) Formants provide honest acoustic cues to body size in American alligators。
ツル類の体内部の長い気管は、渡りに際しては体は小さい方が有利だが、音声は大きくして社会的あるいは性選択に有利とする要請の両方を満たすために進化した仮説がある: Jones and Witt (2014)
Migrate small, sound big: functional constraints on body size promote tracheal elongation in cranes。
長い気管は死腔 (dead space) となって呼吸効率が悪くなる可能性がある。
Ludders (2001) Inhaled Anesthesia for Birds
によれば同じサイズの哺乳類に比べて長さで 2.9 倍、太さで 1.29 倍とのことで、空気抵抗は哺乳類と違いがないが死腔は 4.5 倍とのこと。鳥は呼吸が深く呼吸数も少ない (哺乳類の 1/3 とのこと) ことでこの問題を解決しているとある。単位時間あたりの気管の流量は哺乳類の 1.5-1.9 倍程度に過ぎないとのこと。
もちろん鳥類の肺の優れたシステム、血液と空気の間の障壁が非常に薄くガス交換の効率の良いことで呼吸効率を上げている。以下 [鳥類の肺の優れた機能] の項目に続く。
Jones and Witt (2014) にはいくつかの種類の気管の図も紹介されているので参考になるだろう。
「鳥類のデザイン 骨格・筋肉が語る生態と進化」(カトリーナ・ファン・グラウ、監訳 川上和人 みすず書房 2021) にも長大な気管の例が出ている。原著 "The Unfeathered Bird" (Katrina van Grouw, Princeton University Press, 2013) で世界的にも有名となったもの。
同じ著者による書物に "Unnatural Selection" (Princeton University Press, 2018)
(日本語訳本は出ていない?) があり、鳥類のみではないが人為選択により作られた奇抜な形態などが紹介されている (ダーウィンも夢中になったハトの品種など)。
表紙は人類進化を模式的に (しかし不正確に) 表す "Ascent of Man" で有名になった図版 (Ascent of Man image should be 'the other way around', leading expert in human evolution says
参照) の鳥類版になっている
[ちなみにオリジナルは Darwin's Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871)]。
化石種でもみつかった。キジ類で初めてかつ気管の特殊化が記録された最も古い (725-1110 万年前) 記録とのこと: Li et al. (2018) Vocal specialization through tracheal elongation in an extinct Miocene pheasant from China。
Prange et al. (1985) Respiratory responses to acute heat stress in cranes (Gruidae): the effects of tracheal coiling
によれば、気管が長いことで高温時のあえぎによる熱放出に役立ったり呼吸性アルカローシスを防ぐ役割も考えられるがその効果は弱く、音声増強が主たる役割だろうとのこと。
それでは首の長い鳥の音声は全部そうだろうかと微妙に気になってくる。代表的な種類ならばアオサギの声には皆さん驚かれたことがあろう通りで、大型サギ類は総じて美声とは言い難いだろう。サギ類でもミゾゴイなどの音声が低いのは関係があるのか?
動物園で聞くフラミンゴの声もあれだけ優美な姿からは想像しにくい。そういえばカンムリカイツブリも繁殖時派手な声を出すが、フラミンゴと系統関係がある (Mirandornithes: #カイツブリ備考参照) ことに由来しているのか?
コウノトリは成鳥は鳴かないのでわからないが、ハゲコウ類は声を出す。ダチョウも音程が低すぎてわかりにくいようなものを含めていろいろ声を出す。いずれも美声とは言い難い感じがする。ウの仲間もご存じの通り。ヘビウの音声はそれほど低くないが雑音みたいに聞こえる。ノガンもカモのような声。ホロホロチョウはそれほど悪声ではないがとにかくうるさい (笑)。
トキはカラスの声かと思った。コンドル類は鳴管がないがコンドルは大きな声が記録されている。
しかしヒメコンドル Cathartes aura Turkey Vulture では数少ない音声記録でも喉頭の呼吸音のような感じがする。系統によるのかも知れない。
旧世界ハゲワシ類も悪い声と言ってよいだろう。優美な外見の印象から意外だったのがヘビクイワシで、ほとんど大型サギ類のような声を出す (どんな声を想像していたのかと聞かれても何とも言えないが、猛禽類の他種からはこの声は想定外。もっとも 6000 万年ぐらい前とも推定される非常に古い分岐なので全然違っていても不思議ではないが)。
網羅的に調べたわけではないがこの規則はもしかすると例外がないのだろうか。
ノガンモドキ類を見ておくとこちらは低い声ではなく番犬代わりになる大声とのこと。
そう言えばオオワシなどの海ワシ類など大声で鳴く種類は後ろに反り返るが、これは声道を長くするためだろうか、と思ってみるとカモでは関連する話があった:
潜水ガモで一部の種で気管軟骨が骨化しているが、これは水圧に耐えるためと考えられる。しかし一部の種ではそうではなく、反り返りディスプレイの際に気管が柔軟な方が有利で、オウギアイサ Lophodytes cucullatus Hooded Merganser では 110 mm の気管を 155 mm まで伸ばせたとの実験結果がある。
これは音声の質を変えるのに役立っていると考えられる。潜水ガモ一般にこの能力があるのではとのこと
[Miller et al. (2007) Allometry, bilateral asymmetry and sexual differences in the vocal tract of common eiders Somateria mollissima and king eiders S. spectabilis
およびその参考文献から。オウギアイサの実験は Beard (1951) The Trachea of the Hooded Merganser. Including a Comparison with the Tracheae of Certain Other Mergansers で読める。上記論文では cm になっていたが mm の間違いだった]。
鳥の発声器官の鳴管が気管支付近と気道下部にあるのは、喉頭で発声して重心から離れたところを重くするのはバランス的に不利でその方向に進化が進まなかったかも知れないが (調べていない)、結果的に喉頭で発声するより共鳴可能な気道の容積を増やす効率的な方法になっている。
Yoshida et al. (2023) An ankylosaur larynx provides insights for bird-like vocalization in non-avian dinosaurs (日本語資料: 世界初! 恐竜の喉化石を発見)。
の引用文献でも同じように触れられている模様。この文献によれば恐竜化石ではまだ鳴管は見つかっていないとのこと。
Yang et al. (2025) A new neornithischian dinosaur from the Upper Jurassic Tiaojishan Formation of northern China 2 例目の発見。
喉頭にある輪状軟骨 (cricoid cartilage。我々でも甲状軟骨の下に表面から触れることができる。上記プレスリリースでは輪状骨となっている。ヒトでは最初は骨化していないので軟骨の名称が使われる。鳥類でも輪状軟骨などの名称が用いられるが年齢とともに骨化するとのこと。ヒトでは甲状軟骨は 30-65 歳ぐらいで骨化するが輪状軟骨は一部起きるのみとのこと)
や披裂軟骨 (arytenoid cartilage) まわりの構造が発達していて、もしかすると音声調節に役立っていたのではないかと推論。この論文の図を見ると鳥の喉頭は確かに音声を調節しているらしいことがわかる。
恐竜が声を出していても大型種ではダチョウのような声だったのだろうか。ヒメコンドルのような例をみると系統次第だろうがほとんど声を出していなかった可能性もあるかも。
「鳥類学者無謀にも恐竜を語る」(川上和人 2013, 2018) pp. 159-165 に上記化石の発見前だが考察がある。比較対象にワニを取り上げ、恐竜の Parasaurolophus の「とさか」に音響効果があった可能性を取り上げている。
Parasaurolophus の wikipedia 英語版によれば内耳の構造はもっと高音の声に反応するとの指摘があるが、Weishampel はそれは親と幼体のコミュニケーションに役立っているので矛盾しないと言っているとのこと。
Weishampel (1981) Acoustic Analysis of Vocalization of Lambeosaurine Dinosaurs (Reptilia: Ornithischia)
がその論文とのこと。1998 年の研究 Scientists Use Digital Paleontology to Produce Voice of Parasaurolophus Dinosaur。
その他にもいろいろな機能が提唱されてきて、嗅覚のため、温度調節の機能、種内の視覚的認識のためなどが挙がっている。
McInerney et al. (2025) The hearing capabilities of the Dromornithidae (Aves), with inferences on acoustic communication and ecology 内耳の解剖学的性質から絶滅した Dromornithidae (ドロモルニス科 オーストラリア) の聴覚特性を推定したもの。
低音に感度があり周波数帯域も狭かったと推定される。茂った環境下で低音で音響コミュニケーションを行っていたのではとの推測。といっても一部の種以外では中心感度 1-2 kHz を見積もっているのでそれほど低音というわけではない。現代の一般的な鳥よりは低音と想定される。
ワニは喉頭で発声とのことで Riede et al. (2015)
Functional morphology of the Alligator mississippiensis larynx with implications for vocal production
に解剖学がある。神経支配は迷走神経と舌下神経のようなので哺乳類に似ている [cf. Lessner and Holliday (2020)
A 3D ontogenetic atlas of Alligator mississippiensis cranial nerves and their significance for comparative neurology of reptiles;
Schmidt and Wild (2014) The respiratory-vocal system of songbirds: Anatomy, physiology, and neural control]。
鳥類の鳴管は完全に舌下神経支配 (外部筋肉は2種類で musculus tracheolateralis と musculus sternotrachealis。鳴管周辺のみに存在する筋肉 intrinsic syringeal muscles を発達させているグループもある) で、現生種では鳥類のみが異なるよう。
#オウチュウの備考 [さえずりの進化] の Schwark et al. (2022) で、鳥類と哺乳類の中枢神経から末梢コントロールで異なる点として鳥類では舌下神経以外に胸部や腹部の呼吸筋も支配していることを挙げている。
ワニと哺乳類の類似性を考えるとこれが祖先形で、鳥類では鳴管での発声コントロールと同時に複雑な呼吸動作の高度な統合 [後述 Schmidt and Wild (2014) 参照] を行う必要が生まれ、鳥類で新たに追加された神経回路かも知れない。
Jorgemich-Cohen et al. (2022) Common evolutionary origin of acoustic communication in choanate vertebrates に choanates (カメやハイギョなどを含む) の発声の系統研究がある。4億年前に起源を遡ることができるという。
大部分の系統で喉頭が主な発声部位だが鳥の鳴管は発生学的に別のものを利用している。鳥でも喉頭で音 (hissing sound) を出すことができるとのこと: Policht et al. (2020) Hissing of geese: caller identity encoded in a non-vocal acoustic signal。
コウノトリ成鳥でもクラタリングの際に声らしいものが聞こえるが、こちらが発声機構なのかも。
Kingsley et al. (2018) Identity and novelty in the avian syrinx に脊椎動物の発声の進化が取り上げられている。不完全な気管支の軟骨と連続呼吸は鳥の (祖先のどこか) 系統で獲得したもので、他にはない独自のものとのこと。喉頭の構造は基本的にどれも共通とのこと。
interclavicular air sac (鎖骨間にある対をなさない気のう) が鳴管での発声に役割を果たしていることが指摘されているが、気のうと鳴管のどちらが先に進化したかはわからない。
鳥とワニの共通祖先では喉頭を用いていたのだろうが、鳥に至る進化段階のどこかの段階で両方を用いるようになったのか、それとも一度声を失った時期もあったのか。
Goller (2022) The syrinx のレビューもフリーで読める。
鳴管は最初は息を止める (*1) 機能として進化した可能性があるが起源はよくわかっていない。いずれにしても気のうに囲まれた場所で音を出す効率が高く、上部気道を共鳴に使えるため喉頭よりこちらを使う方が有利だったのだろうと推測している。
喉頭と鳴管は発生学的には異なるが、気道を形作る遺伝子制御機構は共通のものがあり収斂進化の産物と言ってもよいとのこと。
鳴管の音源は通常2つ (左右1対) だが、1つのものもある (ハト類やオウム類など独立に進化したと考えられる)。3つのものもある (tracheophone suboscines カマドドリ科など)。いずれも何らかの選択圧が働いていると考えられる。
音声学習はあるかないかというよりもっと連続的なものと考えられる。
通常音声学習を行わないとされるグループに属するスズドリ類 [スズドリ Procnias albus White Bellbird は鳥の中で最も大きな声 125 dB が記録されたという cf. Podos and Cohn-Haft (2019) Extremely loud mating songs at close range in white bellbirds]
などで音声学習のある程度の証拠が知られているなど書かれている。
鳥類で喉頭でなく鳴管が使われるようになった解釈について Riede et al. (2019) The evolution of the syrinx: An acoustic theory も面白い (レビューの著者の Goller も含まれている)。
実験と物理モデルで喉頭と鳴管で発声した声がどのように気道の長さで影響を受けるか調べた。最適値があって体重 20-30 kg だと 40-70 cm ぐらいが適切か。
鳥類では気のうシステムがあって呼吸機能に余裕があり、長い気道を持つことは哺乳類に比べて負担にならず、祖先型もより多くの頸椎を持っている
[Mueller et al. (2009) Homeotic effects, somitogenesis and the evolution of vertebral numbers in recent and fossil amniotes で祖先型の推定をしており、鳥類祖先にあたる Saurischia 竜盤類では頸椎 10 個とのこと。羊膜類の祖先型は6個とのこと]。
気道が 50-100 cm の場合では鳴管で発声する仕組みの方が有利であるとの考え。哺乳類では気道が短く、ヒトの場合も共鳴周波数とよく合っておらず、発音体を鳴管に相当する場所に置いてもあまり効果がない。
小型の鳥には当てはまらないのではの疑問については制約から逃れるいくつかメカニズムが提唱されているとのこと。
そういえばと思いついたのだが、鳥類は羽繕いを行う必要から首の柔軟性が必要となり、後の項目 [鳥の気管と食道の配置] にあるように (Klingler 2016 の考察を見て気づいた) 喉頭に余分なものを持っていると動きが束縛されたり、哺乳類のように筋肉による場所保持機構も付随的に発達させる必要があるので喉頭付属物を極力単純化したのかも知れない (もちろん前述のように重量や飛行時バランスなども関与しそう)。
そもそも最初から2か所の発声部位があったとすれば有利な方が残りそうな気がする。
[場所保持機構では例えば我々でもよくわかる胸鎖乳突筋 m. sternocleidomastoideus。人体解剖では名称の長さに最初に挫折しそうになる名称の一つ。Jollie (1976, 1977) p. 238 によれば鳥で対応する筋肉は m. sternocleidoccipitalis とのことで皮筋となっている。筋肉の名称は何と何を結ぶか由来となるものが多いので名称は多少異なるが、想像以上に人体に対応する筋肉がある]。
鳥類の古い系統は水鳥のように頸椎も多くてあまり邪魔にならないのではとも言われそうだが、Saurischia では頸椎 10 個と推定されるとのことなのでおそらく初期系統ではそれほど場所に余裕があるわけではない。
古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae (ダチョウ目など) では頸椎が多いように見えるが無飛翔性となったために二次的に増えた系統かも知れないので飛翔する古い系統を見ておく。Galloanseres (キジカモ類) ではキジ類が 16 (14+2) 個と非常に多いわけではない。カモ類では#リュウキュウガモ備考に頸椎数の進化を取り上げているがカモ類系統の頸椎数の祖先型はおそらく 16 個。
鳥類の後のクレードではだいたい 14 個ぐらいが標準で古い系統の方が際立って多いわけではない。
首の柔軟性の必要に伴う喉頭簡略化説を一つ候補に挙げておきたい。
例えばどのあたりの系統から現代の鳥のような羽繕いが必須となったのか、喉頭を保持するための筋肉付着部の痕跡が骨格に残っていないかなどが検討ポイントになるだろうか。
Aureliano et al. (2022) The absence of an invasive air sac system in the earliest dinosaurs suggests multiple origins of vertebral pneumaticity
では common avemetatarsalian ancestor (2.33 億年前) には気のうシステムがなかったようで、気のうシステムは複数回進化したことになる。系統の離れた翼竜 Pterosauria も気のうを持っていた。
鳴管の構造研究が最近進んだ: Birdsong and Human Voice Built from Same Genetic Blueprint
鳴管と哺乳類の喉頭の構造形成に同じ遺伝子メカニズムがかかわっている。
Chiappone et al. (2023) Ostrich (Struthio camelus) syrinx morphology and vocal repertoire across postnatal ontogeny and sex: Implications for understanding vocal evolution in birds
ダチョウの鳴管構造、雌雄差の研究。ヒス音と通常の音声を同時に出すことができる。嘴を閉じたまま boom 音を出すのはオスのみ。
Legendre et al. (2024)
Evolution of the syrinx of Apodiformes, including the vocal-learning Trochilidae (Aves: Strisores)
音声学習を行うハチドリと同じ鳴管構造がヨタカ類、アマツバメ類にも見つかった (現代の分子系統学ではこれらはいずれも近縁 Strisores とされる)。ハチドリ類が音声学習を行う上で前適応があったとも言える。
ごく最近までヨタカ類を含む夜行性の鳥は最も古い系統の一つとされており、日本鳥類目録第8版 (= IOC 13.2) がまさしくその順序になっている
[IOC 15.1 のファイルでも Apodiformes is revised to include only the dirurnal treeswifts, swifts and hummingbirds. Along with the nocturnal nightjars, oilbird, potoos, frogmouths, and owlet-nightjars it forms Strisores which is a basal clade of Neoaves とあって、Neoaves の中でも最も分岐の早い (一般的には "原始的な" とほぼ読み替えることができる) グループと考えられた時代のコメントが残っている]。
第8版配列ではカモ目、キジ目、ヨタカ目... となるのでこの順序で原始的なのだと理解してしまいがちだが、音声学習を行うグループが含まれていることにもう少し注意を払うべきだろう。古い系統でも音声学習が行えるほど Neoaves は高度な中枢神経を持っているのか、それともヨタカ類は実はもっと後の系統なのか。
[#鳥類系統樹2024]を参照。"実はもっと後の系統" の方がもっともらしい。少なくともこの部分は第8版配列を覚えてしまわない方がよさそう。
ハチドリ類は通常の鳥には聞こえない高い声を聞く能力もある: Duque et al. (2020) High-frequency hearing in a hummingbird
エクアドルヤマハチドリ Oreotrochilus chimborazo Ecuadorian Hillstar は中心周波数 13.4 kHz でさえずり、これまで記録されている最も高い声のさえずりとのこと。
クロハチドリ Florisuga fusca Black Jacobin は Olson et al. (2018) Black Jacobin hummingbirds vocalize above the known hearing range of birds で声も聞くことができるが、
こちらは xeno-canto に上記論文著者のデータがあり、さえずりを聞くことができる (XC898140 など オンラインで聞く声は .mp3 に変換されているので音声ファイルをダウンロードして原音のまま聞いていただきたい)。192 kHz サンプリングで録音している。80 kHz まで達する高次の倍音まで発声されており、この点ではヤブサメのさえずりと性質が異なる。
以下にスパースモデリングによる高解像度ソノグラムを作ってみた [Kato (2021) A code for two-dimensional frequency analysis using the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (Lasso) for multidisciplinary use のコード、
XC898140 を読み取り、
pgm <- getpergrmlasso2(d,28.4,36,1,60,200,0.15,0.03)
drawpgmlasso(pgm,0,0,5,3,xlab="Time (msec)",ylab="Frequency (kHz)")
のパラメータを使用した (使い方は論文参照)]。
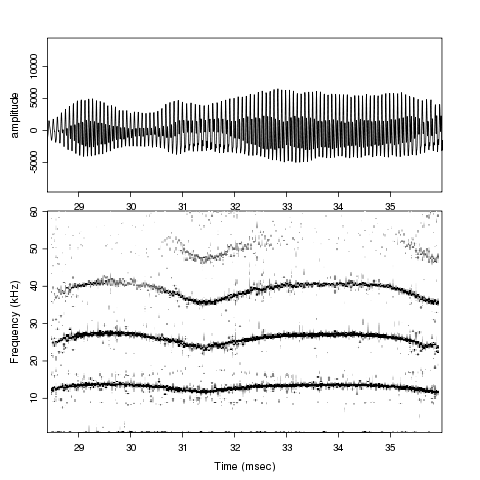 上が波形。正弦波でないため高次の倍音が現れるが波の波形そのものは複雑ではない。自分が IC レコーダーで記録したヤブサメはこのようなきれいな結果にはならかなったので、やはり超音波を記録できる性能のマイクロフォンだけのことはあるように見える。
上が波形。正弦波でないため高次の倍音が現れるが波の波形そのものは複雑ではない。自分が IC レコーダーで記録したヤブサメはこのようなきれいな結果にはならかなったので、やはり超音波を記録できる性能のマイクロフォンだけのことはあるように見える。
Longtine et al. (2024) Homology and the evolution of vocal folds in the novel avian voice box
組織発生学的には喉頭と鳴管は異なっているが、発生に共通の遺伝子メカニズムが働いている。
鳥類祖先で鳴管に音源が2つあったことが想像されるが、非鳥類型恐竜ではまだ鳴管は見つかっていない。
μCT が使われるようになって鳴管研究が活発になっている模様。また鳥類の系統関係が明らかになったことで鳴管の系統研究なども興味深いテーマとなってきたよう。
Gladman and Elemans (2024) Male and female syringeal muscles exhibit superfast shortening velocities in zebra finches
によればキンカチョウの鳴管の筋肉は1秒に 100-250 回収縮できて、他の筋肉や鳥類以外の骨格筋の収縮速度を上回るとのこと。メスの方が筋力は弱いが最大速度はオスと同様とのこと。
参考までに哺乳類ではどのような研究が行われているか: Janik and Knornschild (2021) Vocal production learning in mammals revisited
鳥ではよく調べられているが哺乳類の研究は不十分であるとのこと (鳥の方が先行している研究分野があるのは面白い)。音声学習がある・なしではなく段階的なものを考えている。
コウモリで特によく知られているが call convergence の概念があり、他の個体の周波数に合わせることができる。コウモリの オオシマサシオコウモリ Saccopteryx bilineata Greater Sac-winged Bat (霊長類以外で鳥での "ぐぜり" に相当する発声が見つかった最初の例とのこと) が歌を学習する過程は鳴禽類と類似している。
マウスでも歌 (song) の表現が使われているが、大脳皮質のないマウスでも歌を発することができ、より下位の神経機構で作られている。
鳥が息を吸う時も発声できるとしばしば言われるが [例えば Birder 編集部 (1999) Birder 13(5): 32 には "息を吸っている時も鳴くことができる" と書かれている]、根拠はあまりはっきりしない。前述の Schmidt and Wild (2014) のレビュー論文では、キンカチョウでは1音ごとに息を吐く筋肉が活動している (expiratory pulse または pulsatile expiration)。シラブルやフレーズの間に約 30 ms の短い息継ぎをしており、発声中に失われた空気を補充するのに十分であるとのこと。
早い連続音 (trill) の際はこの息継ぎが失われ、気のうの圧力も何十倍にも上がる。この時には腹筋が働いているとのこと。
チャイロツグミモドキ Toxostoma rufum Brown Thrasher は左右の鳴管を独立に制御して2音を重ねて出すことができる。左右の気管支の空気の流量も異なっている。途中に短い息継ぎがあってその時は気嚢の圧力も下がって発声していない。
この論文ではほとんど音声は息を吐く時に出るとある。
鳴禽類では左右の鳴管は種類によるが同側の脳の RA 核 (robust nucleus of the Arcopallium) が支配しており、左右の大脳半球を直接結ぶ構造 (脳梁) がないので左右をどのように統合しているか不明であるが呼吸と関連した部分が統合を行っている可能性があるとのこと。
ハトが鳴く時に前後の気のうの圧力が少し違うことが報告されており、気のうを個別にコントロールできる可能性はあるとのこと (以下 #ウグイスの備考 [ウグイスは息を吸う時に声を出すか] へ)。
備考:
*1: 息をこらえる。例えば産卵や排泄、複雑な飛行などの行動の際に役立つ可能性があるが実証されていないとある。
複雑な飛行というのは急に向きを変えるなど瞬間的に強い力を出す必要がある場合などを想定したものか。我々も力を出す時や細かい作業をする時に息をこらえることがあるが、飛行中の鳥でも瞬間的に力を出す必要がある場合に息をこらえたりするのだろうか。
排泄については多少思い当たるところがあって、タカ類が糞を飛ばす時にどこに力を入れるのかと考えると体腔内圧ぐらいしか思い浮かばない。詳細な映像であれば呼吸の様子も見えることもあるので、糞を飛ばす時に息をこらえているか調べてみるのも面白いだろう。タカ類以外でも糞を飛ばす鳥はあるのだろうか、行動の系統進化は?
潜水する鳥や哺乳類はもちろん息を止めるが、それ以外の地上性動物が自発的に息を止められるか調べられた研究が見当たらない。すべての鳥や哺乳類は息を止める能力があるはずだが、どのようにすれば止めてもらえるのかわからない、と書かれているページもあり、質問コーナーでも回答が出ていなかったりするのでそもそも研究がないのかも。
哺乳類では横隔神経 (phrenic nerve) が横隔膜の運動を支配している。ヒトでは C4 の脊髄神経が中心で、イヌ類では C5-C7 とのこと。いずれにしても胸部・腹部を分ける位置なのに胸部の脊髄神経ではなく頸部が支配している。肺がエラから進化した名残り。
鳥類には横隔膜がないので胸郭を動かすことで呼吸を制御している (我々も用いている) が、その筋肉の付着部位として肋骨の鉤状突起 uncinate process も役立っている。骨格を見た時にこれは何だろうと思う突起 (思わないか?)。
骨性の鉤状突起は鳥類特有とのことで、始祖鳥にはないとの話もあるが、あるとの話もある [Codd et al. (2008) Avian-like breathing mechanics in maniraptoran dinosaurs]。持たない鳥 (サケビドリ類) もないわけではない。
気のうの進化も含めた進化過程の構築の試みは Wang et al. (2023) Deep reptilian evolutionary roots of a major avian respiratory adaptation にある。鳥の祖先系統のさらに以前に遡ることができる?
鳥類の呼吸と発声の関係は Schimidt and Wild (2014) The respiratory-vocal system of songbirds: Anatomy, physiology, and neural control
で見られるが、呼吸の制御は胸部の脊髄神経を用いているよう。鳥類に横隔膜がないことは横隔神経核がないことに関連している可能性があるがよくわからないとのこと。哺乳類では横隔膜の神経支配から呼吸器は頸部由来の内蔵から発達したものとも言えたが鳥類を見るとそこまですっきりしない感じ。
呼吸筋の神経支配は哺乳類とは違いがある模様。どちらも延髄にある上位の呼吸中枢が脊髄神経を制御している。
ちなみに大胸筋はヒトでは C5-C7 が支配、鳥類でも頸部下部の脊髄が支配で同様 (どちらも brachial plexus) で、発生的には頸部由来となる。頸部の上部から動く舌 (第 XII 脳神経の舌下神経が支配、これは C0 に対応するとも言われる) が生まれ、下部から上肢の一部が生まれたことになる [「くびは何のためにあるか」(山田宗睦編 風人社 1995) を参照]。
鳥類では迷走神経は鳴管の制御にはかかわらないが、気のうなどに関わる神経として発声に関与している可能性はあるとのこと [Wild et al. (2009)
Avian Nucleus Retroambigualis: Cell Types and Projections to Other Respiratory-Vocal Nuclei in the Brain of the Zebra Finch (Taeniopygia guttata)
この文献では鳥類・哺乳類の呼吸に関わる神経の対応関係などが示されている]。
[鳥の気管と食道の配置]
鳥の気管や食道はヒトとは違って正中線からなぜ外れているのかを議論した研究があった:
Klingler (2016)
On the Morphological Description of Tracheal and Esophageal Displacement and Its Phylogenetic Distribution in Avialae
昔から言われてきた知見であったが真面目に比較検討した研究はなかったとのこと。この著者はこの現象を tracheal and esophageal displacement と名付けた。
気管は一定ではなくハト類は気管が左側を通り、タカ類は種差があってクーパーハイタカは気管、食道ともに左側を通り、アカオノスリはどちらも右側、ハネビロノスリは食道が右側、気管は正中線と系統を限定しても一概に言えない結果となった。Larus 属のカモメ類でも配置が異なるものがあるとのこと。
鳥類で正中線から外れる要因として、哺乳類では筋肉が気管や食道の位置を固定していること、鳥類では頸椎が S 字カーブを作るため、気管や食道が余分な経路をとらず最短距離で結ぶならばどちらかに寄った方が効率がよい (ただこれだけだと左右を同等に通ってもよいがそうなっていない) などの理由を提唱している。
大きなそのうの有無も多少関係しているかも知れないが多分大きな要因ではないと議論されている。
[鳥類の肺の優れた機能]
Maina (2000) What it takes to fly: the structural and functional respiratory refinements in birds and bats コウモリは哺乳類型の肺でも飛べるので気のうシステムが不可欠であるとは言えない、とはいえ、
West and Fu (2007) The human lung: did evolution get it wrong?
もやはり呼吸機能は鳥類に軍配を上げざるを得ないと結論。容積を変えて呼吸する部分が哺乳類では肺胞、鳥類では気のうで、哺乳類では呼吸のたびに肺胞が動くために壁を薄くできない。ガス交換の表面積を上げるために哺乳類の肺胞は脆弱な構造になっている。
哺乳類では肺の片側の動脈が閉塞すると血管抵抗が急激に下がるが、鳥類ではこれが起きずガス交換にかかわる組織の頑強性を示す。
哺乳類は激しい運動で肺出血を起こすこともあり高所適応の限界にもなっている。
ではなぜ哺乳類は別の道を歩んだのか。おそらく何かへの適応というよりは進化は目標があって進むものではないので鳥類がよりよい解に到達したとの考え。哺乳類の呼吸器の研究者の視点から調べると鳥類の肺の方が面白いとわかって研究対象を転向したような印象を受ける。先述の Maina も近年は鳥類の肺で論文を書いている。
鳥類の呼吸器で入る空気と出る空気がこれまで考えられていたように混じり合わないわけではないが、肺の中の空気は一方通行とのこと。
West and Fu (2006) The honeycomb-like structure of the bird lung allows a uniquely thin blood-gas barrier にも鳥類の肺のハニカム構造は哺乳類の肺胞構造より頑強で構造的にも強い。
Watson et al. (2008) Minimal distensibility of pulmonary capillaries in avian lungs compared with mammalian lungs 哺乳類の肺の毛細血管が押しつぶされる圧力でも鳥類ではほとんど影響がなかった。外部構造に強度があって毛細血管を支えている。
哺乳類と鳥類は体循環と肺循環が分かれていて構造的には似ているように語られることも多いが、実は圧力差などかなり違う部分もある。鳥類の方がより進化した呼吸システムを発達させたと考えて概ね間違いでない。
Cieri et al. (2014) New insight into the evolution of the vertebrate respiratory system and the discovery of unidirectional airflow in iguana lungs
は鳥類に比べてはるかに単純な構造のイグアナの肺でも一方向の流れがあることを発見。一方向の流れは恒温性や代謝率を高めるた進化したとの従来の見解を覆し、独立に進化したものか、あるいは鳥類と共通祖先の形質だったのか再考を迫る。
なおワニではすでに知られていた [Farmer and Sanders (2010) Unidirectional airflow in the lungs of alligators。気のうは持たない] が系統的にはそれほど不思議ではない。
鳥類や関連系統の呼吸器の分野は最近比較的注目を浴びているようで新しい論文もいくつも出ている (哺乳類至上主義を見直すことで見えてきたことが多いのだろうと想像する。鳥類学者の関心からはむしろ遠かったかも知れないが)。
大部分の哺乳類の赤血球は核を持たず (ラクダ科は有核と言われてきたが誤りとのこと)、他の脊椎動物と異なっている。これはしばしば "より進化した形質" と解釈される。
Snyder et al. (1999) Red Blood Cells: Centerpiece in the Evolution of the Vertebrate Circulatory System では赤血球が大型なのは祖先型と考えられていたが合わない例もある。赤血球を小型化しても粘性が変わるわけではない。
鳥類や哺乳類への進化で赤血球のヘモグロビン量が増えているが、これも赤血球のサイズと相関しているわけではない。この著者の仮説はガス交換の効率を高めるためで、特に呼吸器の細い毛細血管を通ることが制約となっているのではと提唱している。
鳥類では気のうシステムのおかげで肺のガス交換の効率が高いためにこのような適応が必要なかったのかも知れないと思ったが、おそらく他にも要因があるのだろう。なお哺乳類では赤血球にミトコンドリアも存在せず、この点でも例外的らしい。
他の例を見ていても "より進化した形質" というよりは哺乳類独自の理由があるのだろうか。
Yap and Zhang (2021) Revisiting the question of nucleated versus enucleated erythrocytes in birds and mammals によればヘモグロビン濃度は鳥類・哺乳類で違いはなかった。
従来の方法で解析すると鳥類の方が赤血球が大きい結果となるが、系統を考慮に入れた解析では違いが出なかったとのこと。これまでの仮説は核を持つ・持たないの理由は説明できないとのこと。
有核であることで成熟した赤血球がヘモグロビンを合成できるとの仮説も赤血球内の RNA を調べた結果では実証されていない。
同様に鳥類の赤血球にミトコンドリアがある理由も飛翔への適応のようにも見えるがよくわからないとのこと。
「哺乳類の赤血球に核がないのはヘモグロビン濃度を高めるため」との (古い?) 教科書的記述は正しくない模様。
Bhardwaj et al. (2023) Altered dynamics of mitochondria and reactive oxygen species in the erythrocytes of migrating red-headed buntings
は少し答えてくれているように見える。チャキンチョウ Emberiza bruniceps Red-headed Bunting で渡りを模した実験で渡りの時期に赤血球のミトコンドリアの活性酸素除去や脂肪輸送に関わる遺伝子発現が高まる。赤血球のミトコンドリアが渡りのような高い酸化ストレスに有効に働いている模様。
現状の知見では哺乳類と鳥類の赤血球の違いの理由はこのあたりまでを回答にできそうな感じ。
Soulsbury et al. (2022) Energetic Lifestyle Drives Size and Shape of Avian Erythrocytes
によれば鳥類の赤血球サイズと生活様式に相関があるとのこと。
図を見ると小型種ほど赤血球が小さい傾向が見えるが、それ以上の点は統計的に有意なのか微妙なぐらいのレベル。機能を調べずに形態だけで議論するのはちょっと難しいか。
潜水する鳥ほど大きい傾向は確かにあるようで、より多くの酸素を蓄える必要性と一応整合するように見える。
The biology of the avian respiratory system (Philosophical Transactions of the Royal Society B Vol. 380, Issue 1920, 2025) が鳥の呼吸器の特集号。一部の論文がオープンアクセス。#ミサゴ備考の [ミサゴの大腿骨は含気骨でない] に関連研究を少し紹介した。
紹介しなかった部分では Kunchala et al. (2025) Adaptation and conservation of CL-10/11 in avian lungs: implications for their role in pulmonary innate immune protection
も免疫と関係あり、肺に発現する CL-10/11 遺伝子は脊椎動物 (この研究ではヒトと鳥を比較している) でよく保存されており自然免疫に重要な役割を果たしていると考えられる。
鳥類では surfactant protein-D (SP-D) を失っている (ワニ類やカメ類も持っている) とのこと。鳥類系統で選択的に失われているよう。CL-10/11 が機能を補っている可能性が考えられている。
O'Connor (2025) Insights into the early evolution of modern avian physiology from fossilized soft tissues from the Mesozoic
化石からわかる鳥類の軟部組織の進化について。構造的に硬い肺は現代的な鳥類の発展以前に始まっていた部分的証拠があるが、neornithines 以外で気のうの存在証拠は今のところない。
#マガモ備考の [カモノハシ] で鳥類と爬虫類の関係から派生して肺の機能にも関係する secretoglobin セクレトグロビン の進化を扱っている。鳥類の肺の優秀性や哺乳類の夜行性ボトルネック経験が背景にあるのではと想像している。
[脊椎動物の心臓の適応]
Phillips et al. (2025) Developmental and Evolutionary Heart Adaptations Through Structure-Function Relationships に面白いレビューがあったので紹介しておく。
鳥類・哺乳類は2心房2心室、爬虫類は不完全などをおそらく中学で習うと思うが、丸暗記でなく何に役に立っているの考えてみると面白い。鳥類・哺乳類は代謝率が格段に向上して肺循環と体循環を完全に分離して酸素利用効率を上げることが重要だが、空気呼吸をしない動物には必要ない。
爬虫類には長時間の潜水をする種類も多いが、肺循環と体循環が一定程度混ざる (シャント) あるいは弁がある (ワニ類) ことは長時間の潜水と地上生活を両立させるために有利であるとの説明があるとのこと。水中では肺で呼吸を行わないため。
鳥類・哺乳類でも長時間の潜水を行う種類があるが、ヘモグロビンの酸素結合や心拍数を下げるなど他の部分を調整することで対応している。これらの潜水を行う種類では潜水時に肺の末梢抵抗が高まり、事実上シャントと同じような血流配分が実現されている。これらは潜水に伴う機能的な収斂進化と考えてよい。
ヒトでも胎児の時期には動脈管 (ductus arteriosus) や右心房と左心房の間の卵円孔 (foramen ovale) が動静脈シャントとして働いているが肺呼吸が始まるとともに閉じる。閉じた動脈管は動脈管索 (ligamentum arteriosum) と呼ばれる靭帯のような組織として残る。鳥類でも発生過程は基本的に同様で哺乳類の心臓発生研究のモデル (例えば薬剤の発生への影響を調べる) に用いられるぐらい。わずかな違いが説明されている程度。
他の資料も見ると鳥類では ductus arteriosus は左右2本あるが哺乳類では1本。
鳥類・哺乳類の心臓の違いについては例えば Lansford and Rugonyi (2020) Follow Me! A Tale of Avian Heart Development with Comparisons to Mammal Heart Development にまとめられている。
それぞれが少し異なる構造を進化させたことがわかる。
Cordero et al. (2025) The Interplay of Ontogeny and Phylogeny at the Transcriptome Level of the Tetrapod Heart
に最新の遺伝子発現の研究があり、隔壁を作る遺伝子は完全な系統分離以前から生じていた。鳥類・哺乳類・ワニ類の心臓構造は単純な収斂進化の結果とはみなしにくい (ワニ類は特に異なる)。
論文でも少し示唆する表現があるが、恒温動物が胎児期でも完全な心臓構造を発育させるのは代謝率を高めるために適しており、少し類推してみると鳥の場合は危険な卵やひなの期間をなるべく短くするためと考えることができそう。
[水鳥などはなぜ一本足で立って眠るか]
最近になって物理的に一本足で立つ方が安定して筋力も少なくて済む説明もなされるようになってきたが、出典は Chang and Ting (2017) Mechanical evidence that flamingos can support their body on one leg with little active muscular force
この研究はフラミンゴを用いたものだがツルでよく議論されるテーマなのでここに含めておく。
これまでよく行われていた説明では熱の放出を抑制するものでこれが否定されているわけではない。
この研究ではフラミンゴが最小限の筋力による調整で一本足で立つことが可能か (whether it is possible と原文にある) を調べたもので、鳥において passive, gravity-driven body weight support mechanism (重力により受動的に体重を支えるメカニズム) の存在を知る範囲では初めて示したもの、との位置づけで、実験的証拠はまだないが一本足で立つ方が筋肉制御に必要なエネルギー量が少ないのではとの仮説を提唱する、とある。
ウマでは受動的に体重を支えるメカニズムでエネルギー消費を減らしているとある。
熱帯の水鳥では熱の放出の抑制はそれほど重要でないと考えられるので、あるいは受動的に体重を支えるメカニズムの方がより効いているのではないか、との可能性を提唱したもの。著者も査読者もフラミンゴの生息地の環境を多分あまり知らないらしい (#カイツブリの備考参照)。
この種の話は尾ひれが付きがちだが、上記のように論文著者も可能性を述べる仮説のレベルとしているもので、体温を逃さない従来の解釈は引き続き有効なので説明される時はご注意を。
この論文では非常に単純な物理モデルを使っているが、Abourachid et al. (2023) An upright life, the postural stability of birds: a tensegrity system
によれば関節と一本の筋肉を真似たシステムは物理的に安定でない (1要素では多分制御できない)。4本にすると安定となって生体工学的要請を満たすことができるとのこと。この特性は鳥の解剖学的特性と関係する部分もあり、鳥が発明したとも言えるとのこと。一本足ロボットへの応用ができるかを考えている。一本足で立った方が自動的に安定になるというわけではない模様。
Anderson and Williams (2013) Why do flamingos stand on one leg?
によれば温度が上がるとフラミンゴが一本足で立つ割合が減り、温度調節にとって重要であることを強く示唆するとのこと。
Rose et al. (2024) What influences feather care and unipedal resting in flamingos? Adding evidence to clarify behavioural anecdotes
も調べているが過去研究も含めてそれほどすっきりした結果が得られていないよう。この文献では羽繕い頻度などが何で決まるかも調べているが、これもフラミンゴが水鳥の中で特殊な結果は得られていない。
塩湖で生活し結晶が付着するためしばしば水浴びが必要である考えも紹介されれていた。
[中国の国鳥]
中国の国鳥はタンチョウと書いてあるものも、未定とあるものもあり調べてみた。
(2021年の記事)
によれば 2003 年に国鳥を定める動きが高まり、投票の結果タンチョウ (中国では "仙鶴" としてよく知られている) が最多得票を得て一度は決定しかけたがネットで異論が出て定まらなかったとのこと。
英名が Japanese Crane だったためともここでは述べられている。
大航海時代の清は西側に門戸を開いておらず、日本の方がむしろ西洋とつながりがあった。そのため日本に固有の鳥と考えられていた。
鳳凰のモデルとも言われるキンケイ Chrysolophus pictus Golden Pheasant もよい候補だが知らない人が多いのが難点。
(2008 年の記事) によれば 2008 年時点でタンチョウが最終的に選ばれないならば理由は日本の名前が入っていることと報道された模様。この時点ではタンチョウが唯一の国鳥の候補であると述べられたことはなく、国鳥選定のどの段階にあるかは申し上げられないが決まり次第公表したいと答えたとのこと。
(2022 年のキンケイの記事)。
(2020 年のタンチョウの記事) は学名が「日本のツル」である理由を説明している。日本と西洋とつながりについてはこの記事の方が正確か。この学名のために中国の国鳥になれないが、英名は Manchurian Crane の方が使われるようになってきているので心配することはないともある。
他の記事では英名が変わったので学名も変わらないかと期待しているニュアンスも多少あるが、それはさすがに変わらない (ここまで詳しく解説している記事は少ない)。インターネットの中国の記事ではタンチョウは日本では冬鳥としてのみ見られる、あるいは日本では絶滅したとの誤った情報が広く知られているよう。トキと混同されている部分があるかも知れない。
(2024 年の記事)
中国の国鳥は未確定が正解のよう。キンケイが一時期使われたことがあったが正式ではなかった。
1990 年代から国鳥を決めようとの動きがあったらしい。キジやカササギも候補に挙がっていたとのこと。
2001 年の北京オリンピックの際に各国の代表団がそれぞれの国鳥のロゴを示したが、中国はキンケイを代わりに使ったとのこと (その時の写真あり)。国鳥を早く決める必要性が認識されたとのこと。
タンチョウについては上記の通りの説明になっている。スズメも選ばれたそうだがさすがに、となった模様。
キンケイについては中国名に「ニワトリ」を意味する文字が含まれるので品位に問題があるとされた。
トキは個体数が少なく不安定要素もあるので国を代表する重役は適さないかも知れない問題がある。
これらの有名な鳥はいずれも高い支持率を得ているが、最近はインターネットで議論が盛り上がっていて、それ以外にも国鳥にふさわしい候補がいくつも出てきたとのこと。
最近になって急浮上してきたのが "ギンノドエナガ" (直接調べると Aegithalos glaucogularis Silver-throated Tit となるが写真を見る限りではおそらく現地名でエナガの大陸亜種のことでは?) でも皆が可愛いと盛り上がっているとのこと (中国語でも "萌" 属性 と呼ばれるらしい)。
しかしこのような流行で決めるわけにもいかないだろうし...
中国は国土も文化も膨大で、地域によって馴染みの種類も異なり、これまであまり注目されていなかった国鳥にふさわしい種類がまだまだあるのではと選びきれていない模様。
やはりタンチョウがふさわしいとの意見も出ていてまとまりきらない様子。
タンチョウの除外に関連して
(2009 年の記事)
"日本" の名前が含まれることで国鳥にふさわしくないとするのはもはや科学の問題ではなく、むしろわが国の文化の成熟度が問われている。日本でさえも「日本鶴」とは呼ばずにタンチョウと呼んでいるではないか。世界の湿地保護のシンボルともなっている。
単なる名前を問題にするのは "仙鶴" と呼んできた自国の歴史と文化を無視するようなもので世界から笑われるだろう、という冷静な見解も出ていた。
オグロヅルこそふさわしいとの 2024 年提案
初期は人気投票的要素が強かったが、新しい時代になって推薦根拠をより科学・文化的に挙げるようになってきている。
ここまで議論が長引くと、国鳥にふさわしい条件をすべて満たすか、また何か少しでも欠点がないか (他国文化で悪い印象を持たれていないかなど) など条件が厳しくなっている状況のよう。少々のことでは決められなくなっているかも。
[タンチョウが長寿な理由]
Lee et al. (2020) Whole Genome Analysis of the Red-Crowned Crane Provides Insight into Avian Longevity
全ゲノム解析でタンチョウが長寿な理由となる遺伝子候補を探ったものだがダチョウと比較している程度でそれほどの結果は得られていない。活性酸素除去の SOD3 は候補の一つのよう。
むしろ実効個体数 (Ne) 変化の変化の方が興味深いかも。8万年前の 70000 個体ぐらいがピークだったと考えられるとのこと。ツル科の化石記録が多かった時期とも合うとのこと。
[アメリカシロヅルの遺伝的劣化]
(タンチョウの世界規模の保全ランク変更に関連してこちらに入れた)
Fontsere et al. (2024) Persistent genomic erosion in whooping cranes despite demographic recovery (preprint)
1941 年に個体数 16 まで減少。その後の個体数回復努力によって数は増えた。過去と現代のサンプルにの高精度ゲノム解析で実効個体数が過去 1000 年にゆっくり減少していたものがヨーロッパ人入植に伴って過去 300 年で急激に減少。遺伝的多様性の 70% が失われたままであることがわかった。
それ以前の過去の減少傾向はヨーロッパでの2種のツルの絶滅と同期 (メガファウナ絶滅時期。これも人為起源の可能性が提唱されている) していた。アメリカシロヅルはその絶滅は逃れた。かつてから実効個体数が多い時期はなく過去 10 万年でゆっくり減少。
現代の個体群ではヘテロ接合度が過去の個体群より低く、more realized load than masked load (不利となる遺伝子などが隠れて影響が見えない状態より影響を与える形になっている) によって適応度を下げている可能性がある (学術論文とはいかに抽象的でわかりにくい表現を使うものか! - これはおそらく語数制限があるため)。
個体数増加をもとに IUCN や Endangered Species Act の評価を見直す方向に再考を促す結果となっている。
週間アニマルライフ (1972) p. 2445 (浦本・内田) にはヨーロッパ人がアメリカに着いたころでも 1500 羽ぐらいしかいなかっただろうといわれている、とのこと。当時の正直な見積もりなのだろうが、ヨーロッパ人の果たした役割は衰退要因の一部に過ぎないと主張したかった論者もあったのかも知れない。
Ne 変化を見るとおそらく一桁近い過小見積もりで、ヨーロッパ人入植以前の変化は全体的な衰退傾向の上にあってヨーロッパ人入植以前から大幅に数を減らしていたとは言い難い。
上記の Lee et al. (2020) のタンチョウの結果と比較すると興味深い。アメリカシロヅルの研究ほど時間軸解像度はないとはいえ、最近の Ne で評価するとアメリカシロヅルの方がほぼ1桁低く、遺伝的多様性に乏しいことがわかる。ヨーロッパ人入植がもたらした影響は非常に大きかった。
[松に鶴ほか]
「松に鶴」は、実はコウノトリを鶴と見誤ったものだった説がよく聞かれる。
清代の有名な「松鶴図」(1759) など中国由来。松鶴図 など。
鶴寿千歳 (鶴は千年) は准南子 (えなんじ / わいなんし 前漢の武帝の頃、淮南王劉安(紀元前 179 年 - 紀元前 122 年)が学者を集めて編纂させた思想書: wikipedia 日本語版より)「鶴寿千歳、以極其遊」由来 (河田聡美 漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 大修館書店 1989 p. 123)。この記事では准南子は漢代の百科全書に相当するとのこと。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 98 によれば北海道の支笏湖の名称があるが、シコツの音は死骨に通じるため鶴は千年にちなんで千歳の名称が作られたとのこと。参考 歴史散歩ちとせ (千歳市)。こちらでは音の響きが悪いためと説明されている。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 99 VII (藤堂) によればコウノトリを漢語では鶴と呼んだとのことで、この表現であればコウノトリでもそもそも間違っていないことになる。
[白い鳥への変身譚]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 66 I-III 鳥たちのシンボリズム (加藤秀俊) に世界のいろいろな地域で白い鳥への変身譚が共通してみられることが取り上げられていた。
西洋では白鳥に変身する (させられる) 作品がいくつもあるが、日本の場合は夕鶴 (鶴女房) が取り上げられていた。中国やアラビアにも同様の話があるとのことで、リグ・ヴェーダ (Rig Veda) の物語にも登場し、源流はインドにあったのではとの解釈を述べられていた (当時未検証)。
-
クロヅル
- 学名:Grus grus (グルース グルース) ツル
- 属名:grus (f) ツル
- 種小名:grus (トートニム)
- 英名:Common Crane
- 備考:
grus は1音節だが長母音 (グルース)。由来となるイタリア祖語 *grus でも長音。インド・ヨーロッパ祖語 *gerh2- (荒々しい声で鳴く) に由来とのこと。英語の grouse とは無関係 (wiktionary)。
古典式では長母音が原則だが、短く読んでも構わない。
wiktionary によれば通常女性名詞とされるとのこと。後述 ICZN の定義もあり現在の属名の用法もこの性に統一されている。
英名の Common Crane はユーラシアの視点から付けられたもので、別名 Eurasian Crane はアメリカの視点由来と想像できる。
[学名の由来]
記載時学名 Ardea Grus Linnaeus, 1758 (原記載)
属名の決定経緯は簡単ではなかった。
Pallas (1766) が Grus 属を導入。しかし Pallas の示した種は Psophia crepitans Linnaeus, 1758 ラッパチョウ, Grey-winged Trumpeter と同定できるとのことで、通常の理屈であれば Grus は Psophia のシノニムとなるところだった。
Gray (1841) はこのことに気づき、クロヅルに対して Megalornis 属を提唱したとのこと。
しかしクロヅルを指して Grus を用いる用法は Bechstein (1793) 以来ずっと続いていたので BOU (1915) は Grus の名称を nomen conservandum と判定し、先に用いられた Pallas の Grus 属を用いないこととした。
もっとも Linnaeus (1758) 以前にも Grus の名称は使われており、Gray (1841) は Grus Moehring, 1752 よりも Grus Linnaeus, 1735 の方が早いとの議論も行っていたとのこと。これらは 1758 年以前の名称で規約により有効ではない。
ICZN が opinion no. 103 にて Grus, Pallas の属名がラッパチョウ1種ではなくツル類 10 種を指すと規定して一度決着したが、さらに ICZN が 1956 年 Grus 属の記載者を Brisson, 1760 と改めたとのこと
(The Key to Scientific Names, Opinions and declarations rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature)。
Brisson, 1760 を採用すれば種小名から属名への直接の昇格でクロヅルが Grus 属のタイプ種となる。
この決定は後の時代になされたものだが、クロヅルに Grus 属を用いる場合には当時の用法に従って改名が提案された (#ノスリの備考参照)。
Grus communis Bechstein, 1792 (参考)、Grus communis Bechstein, 1793 (参考) はその用例で、ここでは "普通のツル" の意味で、英名 Common Crane と同じ意味で相互に関係があるかも知れない。
Grus vulgaris Fishcer, 1803 (参考) も同じ意味の別称。
Grus vulgaris Pallas, 1811 (参考) でも用いられていた。
さらに Grus canorus Forster, 1817 (参考) もあってこちらは鳴き声をもとに "声のよいツル"。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では当時の学名 Grus communis とともに Grus cinerea Bechstein (灰色のツル) も与えていた。この由来は Grus cinerea Meyer, 1809 (参考) と考えられ、これも上記の複数の名称同様に改名の産物。
当時は先を争って改名が提案されていたらしい (提案者の名前が残るメリットが大きかったのだろう)。
用例を見てもこの学名は長く使われていた。Hartert (1910-1922) p. 1813 では当時のドイツ語名 grauer Kranich も同様。現在でもフランス名 Grue cendree、ロシア語名、中国語名などにそのまま残っている。
当時の別名ネズミヅルは Grus cinerea の訳名かも知れないと思ったが本草綱目にも登場するので独自の比喩だろう。
クロヅルをタイプ種とした Megalornis Gray, 1841 (megale 大きな ornis 鳥 Gk) もあったがこれもトートニムを避ける目的があったのかも。この属名もしばらく使われていたようでカナダヅルの亜種記載 (1925) に用いられていた。
タンチョウにもこの属名が使われたことがあった。
今では見かけない属名となっているが早い時期にこの属名が使われたことが思わぬ波及的影響を及ぼした。
化石種ジャイアントモア 当時の学名で Dinornis Novae-Zealandiae Owen, 1843 (現在では複数種に分割) に Owen (1843) がこの属名を使いかけたがすでに使われていることがわかって修正し、出版に間に合わせたとのこと (The Key to Scientific Names Megalornis の項目)。
しかし DINORNITHIFORMES Moa (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealan) によれば Megalornis Owen, 1843: Proc. Zool. Soc. London 1843 (11): 19. Unnecessary nomen novum for Dinornis Owen, 1843 とあるので The Key to Scientific Names Megalornis の説明とは違って見える。
Dinornis Novae-Zealandiae を発表した後のページに Megalornis の属名が現れるらしい。直しきれなくて残ってしまったのかも。形式的には Dinornis を与えた後に Megalornis が現れるのここで新属名を与える形となり unnecessary nomen novum との取り扱いになる次第。
ジャイアントモア = Dinornis ! といかにも納得されている方もあるだろうが Owen が付けたかった学名は違っていた。
もし学名が Owen の当初意図通りに付けられていれば モア目 Dinornithiformes (かつては恐鳥目の名称もあった) のような高次の分類名まで現在と異なるものになっていただろう。Owen が考え直して付けた属名の方がよりふさわしかったかどうかは読者に判断を委ねたい。(モアが生きていた時代は ハーストイーグル (Haast's Eagle) の時代でもあった。#イヌワシの備考 [ハーストイーグル (Haast's Eagle)] 参照)
日本語解説などでしばしば現れる学名の Dinornis giganteus はシノニムとのこと。Dinornis maximus Haast, 1869 は Dinornis ingens var. robustus Owen, 1846 のシノニムとのこと。
[亜種]
クロヅルはユーラシアに広く分布する。単形種 (IOC)。2亜種とする考えもあり、日本鳥類目録 改訂第8版第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開ではこちらに従って亜種 lilfordi (英国鳥類学者 Thomas Lyttleton Powys 4th Baron Lilford にちなむ) を採用している。
この亜種の記載時学名は Grus lilfordi Sharpe, 1894 (原記載) 基産地 Swatow, China (Avibase による)。当時の種小名の由来は疑いないが原記載には何も書かれていない。
世界の主要リストでこの亜種を採用しているものは Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) なので (ただし may not be diagnosable と付記されている) 日本鳥学会の見解もおそらくこれに基づくものと思われる。IOC も 4.3 まではこの亜種を用いていた。
単形種とする扱いは Archibald and Meine (1996) によるとのこと。
改訂第8版ではこの亜種は残されている。
Species Review: Eurasian Crane (Grus grus) (IUCN SSC Crane Specialist Group)
では4亜種とみなし、基亜種と lilfordi の境界はウラル山脈で後者に英名 Eastern Eurasian Crane を与えている。
コーカサスの Transcaucasian Eurasian Crane (G. g. archibaldi)、チベットの Tibetan Eurasian Crane (G. g. korelovi)
が他の2亜種。これらが実際に単系統か evolutionarily significant unit (進化的に意義のある単位: ESU) に値するかはさらなる研究が必要としている。
[渡り]
クロヅルの東個体群の渡りの衛星追跡の最近の研究は Erdenechimeg et al. (2023) Migration Pattern, Habitat Use, and Conservation Status of the Eastern Common Crane (Grus grus lilfordi) from Eastern Mongolia
で見ることができる。モンゴル東部で繁殖し、渤海沿岸、黄河デルタなどで越冬する経路が記録されている。
Pekarsky et al. (2024) Cranes soar on thermal updrafts behind cold fronts as they migrate across the sea (preprint 版)
大型の陸鳥が海上を渡る際は羽ばたき飛行をせざるを得ないと考えられていたが、クロヅルの渡り追跡で特に秋に寒冷前線の通過を利用してソアリングを行っていることが判明。冷たい空気が流れ込んだ時の海と空気の温度差の大きさを利用している。陸鳥が海域を避けて渡るのは上昇気流がないわけではなく、むしろ上昇気流発生の不確実さや羽ばたき飛行のコストの問題と解釈できる。
[ツルや crane の名称の由来]
「ツル」の語源は新谷 (1983) による ユーラシア比較言語学の試み IV - ツルとカラスの語源学 -
がある。タヅとの関係は不詳とのこと。
その後も研究が進められて別説が出ているかも知れないが、「コンサイス鳥名事典」では朝鮮語のトゥルミー (上記 turumi と同じ) を提案している。この事典にデンマーク、スウェーデン、アイスランドで同じような音の名前があるとのことで調べてみることにした。
デンマーク語 trane スウェーデン語 trana アイスランド語 (gra)trana で、古ノルド語の trana が起源とのこと (wiktionary)。
北部ドイツ語の trana 由来で Kran(ich) が音韻変化したものと説明されているとのこと (参照)。gr → tr への音変化は意外であるとのこと。
インド・ヨーロッパ祖語では Reconstruction:Proto-Indo-European/gerh2- とのこと。東アジアの音声については検討外の模様であるが turumi/tsuru と古ノルド語との直接の関係はなさそうである。
wiktionary を見ておくと中世の朝鮮半島 (1449 年の用例がある) turumi の語源の可能性として古チュルク語に *turna (トルコ語の turna が派生) が挙げられており、モンゴル語の togoruu、ハンガリー語の daru がいずれもツルを指すとのこと (文献出典は記されていない)。
沖縄では chiru、国頭では chiru- と伸ばす。wiktionary では 日琉祖語 (Proto-Japonic) で *turum の音が推定されて -m の音が落ちたのではないかとの考えがあるとのこと。
この解説では "弦" または "蔓" (*turu) とは別語源 (こちらは *tura 派生して例、弦、面 でいずれも tura と読む。列、連も同根) を推定している。
現在のハングル表記の hak は漢語の鶴の読み由来 (日本語音読みと同じ)。ベトナム語でも hac と読む。
"タヅ" は日本独特らしい。田鶴とも表記される。
"鶴" から鳥を除いた文字は日本語版と英語版の語義が異なる。英語版では高く飛ぶ鳥、非常に高い、野望を表す文字とのこと。日本語でも表外漢字で同じ意味を表し、こく、ごく、かく の読みが示されている。
音は古代中国語で *[g]awk、中世で howk。その後 hu, he の音となった。que と読む別の語義があるとのこと。音からはツルでもガンでもハクチョウでもよさそうな印象を受ける。
英語 crane は OED によれば 1275 年ごろ (おそらく 1200 年ごろ) にすでに用例があるとのこと。ツル以外のサギやコウノトリも指す語義の方が新しく、1678 年に用例があるとのこと。
建設などに用いられるクレーンの語義は 1487 年 (おそらく 1380 年ごろには) 用例がある。
Online Etymology Dictionary によれば後者の建設機械の意味は 13 世紀遅くに登場するとのことで、ドイツ語、フランス語などと共通とのこと。現代のドイツ語では使い分けていて、鳥の方は Kranich、建設機械は Kran。
語源的には鳥の方が古いが、建設機械に用いられたのは中世オランダ語の krane が最初とのこと (Wiktionary)。
ドイツ祖語の krano はインド・ヨーロッパ祖語の *gerh2- の "荒っぽい声で鳴く" に由来するとのこと。
ロシア語のツルの zhurabl' が大きく違うので確認しておくと擬音語の ger、ギリシャ語 geranos などが語源とのこと (Kolyada et al. 2016)。学名に使われる Grus と縁が近かった。元をたどるといずれも声が由来か。
-
ナベヅル
- 学名:Grus monacha (グルース モナカ) 修道女のツル
- 属名:grus (f) ツル
- 種小名:monacha (f) 修道女 (monachus (m) 修道士)
- 英名:Hooded Crane
- 備考:
grus は#クロヅル参照。
monacha は短母音のみで冒頭にアクセント (モナカ)。
記載時学名 Grus monacha Temminck, 1835 (原記載。図版は1ページ前に。図版に学名がないため本文が原記載となった) 基産地 Hokkaido and Korea (Avibase による)。フランス語名 Grue moine (修道僧のツル)。日本では Kirodsur と呼ばれていると記述がある。現在のクロヅルの方の和名は後に整理されたものらしい。
単形種。ロシア語名ではこのツルが "黒いツル" に相当する。wikipedia ロシア語版 でこのツルが使われた 1982 年の切手、2000 年の硬貨を見ることができる。中国語名は白頭鶴または白い冠のツルに相当する。
wikipedia 英語版によれば 2020 年フィリピンで7羽が初記録され、その後頻繁に渡ってくるようになったとのこと。2011 年にアメリカのテネシー州で迷鳥記録があるとのことで、カナダヅルの渡りに従って渡来した可能性が考えられていた。
2022-2023 年の鹿児島県出水での H5N1 集団感染の論文は#インドガン備考の [野鳥と鳥インフルエンザ] の方に含めた。2022-2023 年の鹿児島県出水での発生を調べた論文 の項目。
-
アネハヅル
- 学名:Anthropoides virgo (アントゥローポイデース ウィルゴ) 乙女のようなツル
- IOC 学名:Grus virgo (グルース ウィルゴ) 乙女のようなツル
- 属名:anthropoides anthropos 女性 -oides 似た (Gk); 人の形をした (コンサイス鳥名事典)
- 種小名:virgo (adj) 未婚の (f) 乙女
- 英名:Demoiselle Crane
- 備考:
anthropoides は起源となるギリシャ語では1つめの o と最後の e が長母音。ラテン語では -po- がアクセント音節になると考えられる (アントゥローポイデース)。
virgo は短母音のみ (ウィルゴ)。
grus は#クロヅル参照。
記載時学名 Ardea Virgo Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 'In Oriente' (東方) = India (インドと認定)。
アネハヅルを指して使われた属名に Scops があり、Moehring, 1752 と有効な属名となる以前の年代であった。Scops Gray, 1841 がこれに基づいて用いたものがツル類を指して用いた最初の Scops 属とされる。ギリシャ語 skops (見張り人) 由来で o は短音。
しかし同じ綴りの Scops de Savigny, 1809 がフクロウ類に使われていたためツル類を指した Scops 属はおそらく無効となった。両者の語源は異なる (#コノハズクの備考参照)。
Hartert (1910-1922) では p. 1822 に登場する。1758 年以前の学名は有効でないと定めた規則による結果フクロウ類に用いられた同じ綴りの属名が有効となったが、フクロウ類では系統的に Otus 属にまとめられたため現在は見かけなくなっている。
Anthropoides Vieillot, 1816 もアネハヅルだけを指したもので自動的にタイプ種となる。
英語別名に Numidian Crane が示されており、Numidia ヌミディアはカルタゴや共和政ローマの時代にベルベル系の部族が住んでいたアフリカ北部の地域・王国。ヌミディアとは古代ローマによる呼称とのこと (wikipedia 日本語版)。
属名は日本鳥類目録改訂第7版時代からアネハヅル属。単形種。
[ツル類の分子系統研究]
ツル類の分子系統研究は Krajewski et al. (2010) Complete Mitochondrial Genome Sequences and the Phylogeny of Cranes (Gruiformes: Gruidae)。
Anthropoides 属を認めるかどうかは分類学者次第で、IOC は version 2.5 まで認めていたが以降は Grus 属に統合している。Howard and Moore は 3rd edition まで認めていたがその後は Grus 属。
IOC 14.1 では Grus 属だが、Perhaps best separated into Anthropoides と注釈があり、属の分離も正当化できる見解のようである。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 では Grus 属。
Clements は 2005 年まで Grus 属だったがそれ以降 Anthropoides 属。
もう1つ問題となる属があり Bugeranus 属でホオカザリヅル (英名 Wattled Crane) 1種のみを含み、Anthropoides 属の前の分岐に相当する。
Anthropoides 属を認める立場 (例えば日本鳥学会 日本鳥類目録 改訂第7版や第8版) ならばこの属も認める必要があり、この種の学名は Bugeranus carunculatus となる。
原理的にはこの種もまとめて Anthropoides 属とすることは可能だが、そのような用例は見当たらないので Anthropoides 属を認めるならば Bugeranus 属も認めることになるだろう。
これら全体と残りの Grus 属をまとめても単系統となるので、これらをすべて Grus 属としても差し支えなく、現在の IOC と Howard and Moore はその立場と考えてよいだろう。
その場合はアネハヅルの学名は Grus virgo となる。現在の海外のページなどでは IOC に準拠してこちらが主に使われているので検索などの際は注意。現在の IOC 分類では Grus 属は8種になる。
属をどの程度細かく分けるかの自由度の問題と言える。
IOC 15.1 のコメントでは Perhaps best separated into Anthropoides (Krajewski et al. 2010; BLI)? とあり、世界のリストの統合に合わせて IOC でも Anthropoides 属が復活する可能性がある。
Antigone 属を認める立場 (例えば日本鳥学会 日本鳥類目録 第8版) ではマナヅルは Antigone 属になって、Anthropoides 属を認めるか否かにかかわらずナベヅルと別属になる。
古い分類ではこれらもすべて含めて Grus 属としていたが、現代の知識ではそれに内包される Anthropoides 属 と Bugeranus 属を別属にしていたことになる。
Anthropoides 属を認める場合はこの属にもう1種あり、種小名 paradisea のハゴロモヅル 英名 Blue Crane がある (IOC 学名では Grus paradisea)。
このツルは Tetrapteryx の属名が用いられたことがあり、「4つの翼 (羽)」なのでもしかして後肢に羽が生えているのかと期待したがそうではなく、地面に届くほど伸びた3列風切を指したものとのこと。
英名の一つの demoiselle は Marie Antoinette 女王が姿から名付けたもの (wikipedia 英語版)。英語の demoiselle はフランス語に由来。
[アネハヅルの渡り]
アネハヅルはヒマラヤを超える渡りをするツルとして有名。1981年10月にヒマラヤの上空を飛んでいるのが日本の登山隊に目撃され、編隊飛行している写真が発表されたことがある。
当時はソデグロヅルと言われていたが、これは後にアネハヅルと判断された [科学ドキュメント ヒマラヤを越えるツル マナスル登山隊の記録 1982 (30分) NHK総合: 出典]。
Demoiselle Crane High Resolution Mongolia でモンゴルを出発したアネハヅルの渡りルートを見ることができる。秋の渡りではヒマラヤを越えるがパキスタンで越冬するが、春は北へ向かって大きな迂回路を通る。
Galtbalt et al. (2022) Differences in on-ground and aloft conditions explain seasonally different migration paths in Demoiselle crane
に論文があり、このルートが風の助けや地上の条件が有利である考察を行っている。
Mi et al. (2022) Time and energy minimization strategy codetermine the loop migration of demoiselle cranes around the Himalayas にも考察がある。
ロシアから出発するルートも調べられており 1000 Cranes. Russia. Caspia
こちらはそれほど複雑でなく中東を通ってエチオピアに到着している。
ロシア2地点からの経路追跡の論文があり、Ilyashenko and Ilyashenko (2023, 2024 再掲) Migration routes of the demoiselle crane Anthropoides virgo from the Orenburg Oblast (pp. 2579-2585)
によれば西経路と東経路があり、西はスーダンで越冬。東はインドで越冬して Galtbalt et al. (2022) にあるモンゴル個体の春のルートに似ている。モンゴルに分布を広げても行き帰りともこのルートを延長すればよさそうに見えるが、秋はヒマラヤ越えが風の助けも得られて渡りに要する時間も短く有利な形質として選択されたのかも。
クロヅルの西部個体と同様に最初はアフリカを主たる越冬地としていたものが東に分布を広げることでパキスタンやインドに越冬地を移す個体群が生じ、一部がさらに東からヒマラヤ越えを行うようになったのだろうか。
Pu and Guo (2023) Autumn migration of black-necked crane (Grus nigricollis) on the Qinghai-Tibetan and Yunnan-Guizhou plateaus
によればオグロヅルはチベット高原や雲南高原などの高所で越冬する結果になっている。クロヅルやナベヅルとの共通祖先段階ではもっと低地で越冬していたのだろうが、ヒマラヤ越えをするほどの越冬地執着がなく高所適応してあまり動かず越冬するようになったものだろうか (このあたり想像)。さらに東に種分化したものがナベヅルやタンチョウの祖先となったと考えるとなんとなく理解できるようにも見える。
ヒマラヤハゲワシ Gyps himalayensis Himalayan Vulture はソアリングでヒマラヤを越えるが、空気密度が半分でもソアリングの回転半径を大きくすることと対空速度を増すだけで対応できているとのこと: Sherub et al. (2016) Behavioural adaptations to flight into thin air。
同様の手法はヒメコンドルも用いているとのこと: Rader and Hedrick (2024) Turkey vultures tune their airspeed to changing air density
翼や構造や筋力を変えるような特別な適応は不要とのこと。
渡りの最新研究: Yanco et al. (2024) Migratory birds modulate niche tradeoffs in rhythm with seasons and life history。
アネハヅル、クロヅル、オグロヅル、マナヅルが研究対象。マナヅルについては #マナヅルの備考へ。
[ツル科・ツル目の系統分類]
上記の分類上の検討をふまえ、日本鳥学会 日本鳥類目録 第8版の予定と整合性のある分類 (eBird/Clements 2023 に一致する) でツル科 Gruidae の分類を示しておく。
もちろん日本で見られない種類も多いが、動物園などで比較的よく飼育されているため見る機会も多いだろう。参考にしていただきたい。
学名の後に (*) があるものは IOC 14.1 では Grus 属。
ツル科 Gruidae
カンムリヅル亜科 Balearicinae
カンムリヅル属 Balearica
ホオジロカンムリヅル Balearica regulorum Grey Crowned Crane
カンムリヅル Balearica pavonina Black Crowned Crane
ツル亜科 Gruinae
ソデグロヅル属 Leucogeranus
ソデグロヅル Leucogeranus leucogeranus Siberian Crane
マナヅル属 Antigone
カナダヅル Antigone canadensis Sandhill Crane
マナヅル Antigone vipio White-naped Crane
オオヅル Antigone antigone Sarus Crane
オーストラリアヅル Antigone rubicunda Brolga
ホオカザリヅル属 Bugeranus
ホオカザリヅル Bugeranus carunculatus (*) Wattled Crane (アフリカ)
アネハヅル属 Anthropoides
ハゴロモヅル Anthropoides paradiseus (*) Blue Crane (アフリカ)
アネハヅル Anthropoides virgo (*) Demoiselle Crane (ユーラシア)
クロヅル属 Grus
タンチョウ Grus japonensis Red-crowned Crane
アメリカシロヅル Grus americana Whooping Crane
クロヅル Grus grus Common Crane
ナベヅル Grus monacha Hooded Crane
オグロヅル Grus nigricollis Black-necked Crane
なおツル目 Gruiformes の中の位置づけは以下のようになる。絶滅科を含めた構成は wikipedia 英語版による。
科の和名は山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類 による。ツル科 Gruidae と クイナ亜目 Ralli で大きく形態が異なるが、ツルモドキやラッパチョウ類がどの程度ツルに似ているかは画像検索などで確かめていただきたい。
ツル目 Gruiformes
ツル亜目 Grui
ツル上科 Gruoidea
? Geranoididae (絶滅科)
? Parvigruidae (絶滅科)
ツルモドキ科 Aramidae (北米南部から南米)
ツルモドキ属 Aramus
ツルモドキ Aramus guarauna Limpkin
ラッパチョウ科 Psophiidae (アマゾン地域)
ラッパチョウ属 Psophia
ラッパチョウ Psophia crepitans Psophia crepitans
ハジロラッパチョウ Psophia leucoptera Psophia leucoptera
アオバネラッパチョウ Psophia viridis Psophia viridis
ツル科 Gruidae (前記)
クイナ亜目 Ralli (#クイナの備考参照)
ツル目に属すると考えられる絶滅種にニュージーランドの大型種 Aptornis 属 (Adzebills) があり大型バンとも呼ばれることがある。記載した Richard Owen はモアの小型種と考えたとのこと。
全長 80 cm、体重 18 kg と推定され飛べない鳥でマオリ族による狩猟、ポリネシア人の持ち込んだネズミやイヌによって絶滅したと考えられる。
Musser and Cracraft (2019) A new morphological dataset reveals a novel relationship for the adzebills of New Zealand (Aptornis) and provides a foundation for total evidence neoavian phylogenetics
が分子系統と形態解析でラッパチョウ属との関連性を明らかにしている。このぐらい大型だとツル類と飛べないクイナ類の類縁関係も垣間見えるような気がする。
Worthy et al. (2011)
Fossils reveal an early Miocene presence of the aberrant gruiform Aves: Aptornithidae in New Zealand にも形態と系統の詳しい解析がある。
モーリシャスに生息したとされる Leguatia gigantea Schlegel, 1858 も体高 1.5 m の巨大クイナ (super-rail) とされることもあるが、現在ではコウノトリ目に入れられていることもある (Reunion Stork の名前がある)。
Francois Leguat が記述した le geant は実際に何を見たか明瞭でなく、フラミンゴだったとの説もある Giant water hen。
Angst and Buffetaut Paul Carie, Mauritian naturalist and forgotten collector of dodo bones。
BirdLife は種として認めておらず絶滅種に含まれていない。Extinct Species (BirdLiefe Data Zone) によればコウノトリ属の骨の化石が1個みつかっているとの主張 Cowles (1987) があるが、この種? のものではない可能性が高いとのこと。ツルのようなクイナが生息していた可能性があるが目撃談にとどまっている模様。
川口 (2024) Birder 38(9): 40 に紹介されているものもこれと同じもの。
かつてのツル目には
クイナモドキ科 Mesitornithidae (現在はクイナモドキ目 Mesitornithiformes、ハト目、サケイ目を含むクレード Columbimorphae に属する)、
ミフウズラ科 Turnicidae と クビワミフウズラ科 Pedionomidae (現在はチドリ目 Charadriiformes)、
カグー科 Rhynochetidae、ジャノメドリ科 Eurypygidae [現在はジャノメドリ目 Eurypygiformes。系統的位置づけはよくわからず単独系統をなす。Jarvis (2014) によればネッタイチョウ目の遠い親戚か。最新の [#鳥類系統樹2024] Stiller et al. (2024) によればネッタイチョウ目とまとまった系統をなすことがわかった。
ジャノメドリの英名は Sunbittern とかつてはサギの仲間とされていたことがわかる。大変特徴的な種類なので画像検索などで見ていただきたい]、
ノガンモドキ科 Cariamidae (現在はノガンモドキ目 Cariamaformes で近代的な陸鳥の方に含まれハヤブサ目を含むクレードに属する。猛禽類としても扱われる)、
ノガン科 Otididae (現在はノガン目 Otidiformes。カッコウ目、エボシドリ目を含むクレード Otidimorphae に属する)
が含まれていて、Boyd に言わせると「ゴミ箱」状態だったとのこと。
ノガンモドキ目以外は近代的な陸鳥グループには含まれない。
Stiller et al. (2024) による Elementaves の系統分類:
(Elementaves その1)
ツメバケイ目 Opisthocomiformes
ツメバケイ科 Opisthocomidae
(Elementaves その2 Cusorimorphae)
ツル目 Gruiformes
(系統 1 = クイナ亜目に相当)
ヒレアシ科 Heliornithidae
クイナ科 Rallidae
(系統 2 = ツル亜目に相当)
ラッパチョウ科 Psophiidae
ツルモドキ科 Aramidae
ツル科 Gruidae
チドリ目 Charadriiformes
(Elementaves その3 Strisores: ヨタカ、アマツバメ、ハチドリ類)
(Elementaves その4 Phaethoquornithes: #クロトキ備考へ)
[日本産ツル類の系統的位置づけ]
タンチョウが極東地域に限定した分布をしているため、この種の進化史を考えてみようと分子系統解析を行ってみた。出発点は NC_020577.1 として BLAST を行ってみると上記の系統樹が再現できるので、ミトコンドリアのみだがこの結果をもとに考察してよさそう。
ソデグロヅル属 Leucogeranus が最も古い分岐でツル類の中でも生態的弱さと関係があるのかも (おそらくはかなりの部分が人間活動によるものだろうが)。
北半球のツル類ではマナヅル属 Antigone がその次の分岐でその中ではカナダヅルが最も古い分岐。一度は北半球に広く分布したが次第に衰退しつつユーラシアでいくつかの種に分化していったよう。
アネハヅル属 Anthropoides がその次の分岐でユーラシアではアネハヅルのみでそれほど強力な系統ではなかったかも知れないが独自の生態に適応した印象を受ける。
クロヅル属 Grus がツル類の最後の系統で北半球に分布を広げて種数も比較的多い。この中ではタンチョウが最初の分岐で Grus 属の他種からやや離れている。独立属を作ってもよいぐらい。ユーラシア東部に進出したこの系統が Grus 属が北米にも分布を広げる足がかりになったのであろうことは想像できる。
北米では種分化は進まずアメリカシロヅル1種となった。Grus 属の残り3種 (クロヅル、ナベヅル、オグロヅル) の分岐年代は大きく違わず、Grus 属がユーラシアに分布を広げた結果 (ツル類の躍進時期。おそらくツル類に適した生息環境が広がったため) を反映していると考えられる。
特にクロヅルは分布も広く、あるいは過去の Antigone 属や Anthropoides 属の他種を競争排除した場合もあったかも知れない。
Grus 属の後発系統の方が生態的に有利な面があったかも知れないが、アネハヅルの場合は渡りの特殊性、タンチョウ (そしてさらに古いソデグロヅル) は体が大きいことで比較的局地的な分布ながら生き残ったのかも知れない。
競争相手の少なかったアメリカシロヅルが人による乱獲以前は広く分布していたことから考えると、タンチョウも競争相手がなければ (生じなければ) 大陸にさらに広く分布することができたのでは? 北半球ツル類他の属の種分化はユーラシア中央部で起きたように見えるので、Grus 属の最も古い系統のタンチョウが極東に偏っているのは少し不自然な感じがする。
例えばかつては分布がもっと広かったものが新しい系統の誕生の影響も受けて消退した結果で、日本固有種ではないため成り立ちがあまり話題に登らないが、やはり少し遺存的な部分が感じられる気がする。
国内固有種に限定せず、極東など分布の狭い種類も一度まとめて取り上げてもよいのではと感じる。もっともそのような分布の種は一般に研究が不十分であまり情報がないかも知れない。
このような視点で見ると Grus 属内のタンチョウ、Muscicapa 属内のエゾビタキの位置が非常に似ているように見える。いずれも最も古い分岐で分布が極東の狭い地域に限られている。エゾビタキも遺存的な種だろうか。続きは#エゾビタキの方に。
[アネハヅル個体群の遺伝学的研究]
Mudrik et al. (2025) Mitochondrial DNA data allow distinguishing the subpopulations in the widespread Demoiselle crane (Anthropoides virgo) 渡り経路の応じた個体群があり、遺伝的にも区別できるとのこと。
△ ツル目 GURIFORMES クイナ科 RALLIDAE ▽
-
シマクイナ
- 学名:Coturnicops exquisitus (コートゥルニーコープス エクスクイスィートゥス) 非常に美しいウズラのような鳥
- 属名:coturnicops (m) ウズラの外観をした (coturnix (f) ウズラ, ops, opus 外観 Gk)
- 種小名:exquisitus (adj) 類いまれな; 非常に美しい (コンサイス鳥名事典)
- 英名:IOC: Swinhoe's Rail (英国博物学者 Robert Swinhoe が記載した)
- 備考:
coturnicops は coturnix は o, i が長母音でギリシャ語で外観を表す -ops は長母音。-tur- がアクセント音節と考えられる (コートゥルニーコープス)。
exquisitus は -si- が長母音でアクセントもある (エクスクイスィートゥス)。
旧学名に用いられた noveboracensis は novus (ノウウス。新しい) + Eboracum (イギリスの York のこと。a が長母音) つまり New York の意味。場所を表す -ensis の冒頭を長母音でアクセントを置けば "ノウエボラーケーンシス" となると推定できる。
記載時学名 Porzana exquisita Swinhoe, 1873 (原記載) 基産地 Cheefoo, China。
Porzana undulata Taczanowski, 1874 (参考 1, 2) の1年違いの記載があった。
旧英名の Yellow Rail は現在 IOC では Coturnicops noveboracensis アメリカシマクイナ に使われる。同種扱いだった時代の名残り。和名の "シマ" は縞に由来。
単形種。
三戸 (2007) Birder 21(1): 20-22 に青森県仏沼 (オオセッカ繁殖地で有名) における「シマクイナ発見記」が記載されている。「クル、クル、グー」というカエルのような聞いたことのない声を発見の始まり。音声再生 (プレイバック playback) によって正体を確認した。鳴き声以外での発見はほとんど不可能と記載されている。当時の記事では Coturnicops noveboracensis が用いられていた。
プレイバック法による関東地方での調査、音声の記述などについては高橋他 (2018) 関東地方におけるシマクイナ Coturnicops exquisitus の冬季の生息状況 が参考になる。
図2に示されているシマクイナとヒクイナの非繁殖期の声の声紋は#カイツブリや#ヒクイナの備考で紹介した両種間で類似する音声に対応する。この論文では特徴的な「キュルルルルー」と聞こえる尻下がりの鋭い声と記載されている。
他にも福田他 (2019) 茨城県におけるシマクイナの生息状況、
Senzaki et al. (2021)
Breeding evidence of the vulnerable Swinhoe's Rail (Coturnicops exquisitus) in Japan、
北沢、吉岡 (2021) 九州北部におけるシマクイナの越冬を示唆する記録 の研究があり、プレイバック法により各地での生息・越冬が明らかになっている 研究誌新着論文:九州北部におけるシマクイナの越冬を示唆する記録 (バードリサーチニュース 2021)。
これまでも (目視は難しいとしても) 音声を聞いて他種と判定されていた例があるかも知れない。
絶滅危惧 IB 類 (EN)。
Aoki et al. (2023) Phylogenomics reveals an island as a genetic reservoir of a continental population (preprint)
シマクイナのアムール地方 (6サンプル)、バイカル地方 (6サンプル) を含む 52 個体の遺伝情報を用いて過去に島から大陸に遺伝子流入があったことを示した。(かつての) 島の大きな個体群が大陸個体群の遺伝子プールの供給源となっている可能性がある。
大陸から島に移り住むことが古典的な描像だがそれとは異なる結果となった。
マダガスカル (ヨシキリ科など、#オオヨシキリ参照) やメジロ属 #メジロ の [Great Speciator] など種供給源としての島の役割は近年注目されているところ。
-
オオクイナ
- 学名:Rallina eurizonoides (ラルリーナ エウリゾーノイーデース) ナンヨウオオクイナに似たクイナ
- 属名:rallina (合) クイナに似た鳥 [Rallus属 (クイナ属) の指小形]
- 種小名:ナンヨウオオクイナに似た (備考参照)
- 英名:Slaty-legged Crake
- 備考:
rallina は rallus は短母音のみ、-ina は冒頭が長母音でアクセントもここにある (ラルリーナ)。
eurizonoides は起源となるギリシャ語では zone はともに長母音、ラテン語語尾の -oides は i, e ともに長母音。i がアクセント母音となる。これらを採用すると "エウリゾーノイーデース"。
種小名は ナンヨウオオクイナ Rallina fasciata 英名 Red-legged Crake の旧学名 Gallinula eurizona Temminck, 1826 (綴りが変更され euryzona になった。
この種小名の意味は eurus 広い zone 帯) に -oides (接尾辞) 〜に類似の の意味 (The Key to Scientific Names)。
7亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は sepiaria (生け垣の < sepis, saepes, saepis 生け垣) とされる。
-
ヤンバルクイナ
- 第8版学名:Hypotaenidia okinawae (ヒュポタエニディア オキナワエ) 沖縄の下に小さな帯のあるクイナ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Gallirallus okinawae (ガルリラルルス オキナワエ) 沖縄のヤケイのようなクイナ
- 第8版属名:hypotaenidia hupo 下 tainidion 小さな帯 (Gk) (The Key to Scientific Names)
- 第7版属名:gallirallus (合) ヤケイのようなクイナ Gallus 属 (ニワトリのもとになったセキショクヤケイなどを含む属) と Rallus 属 (クイナ属) から合成された、当初は亜属の名称だったものを属名とした (The Key to Scientific Names)。
記載時は Rallus 属だった。
- 種小名:okinawae (属) 沖縄の (okinawa -ae)
- 英名:Okinawa Rail
- 備考:
hypotaenidia は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-ni- がアクセント音節と考えられる (ヒュポタエニディア)。
okinawae はラテン語規則では -na- がアクセント音節 (オキナワエ)。
gallirallus は短母音のみで -ral- がアクセント音節 (ガルリラルルス)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Hypotaenidia 属 (hupo 下 tainidion 小さな帯 Gk) で小さな島固有種クイナを多く含む属。種小名は変化なし。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じで、Hypotaenidia 属はヤンバルクイナ属。旧 Gallirallus 属はニュージーランドクイナ属と呼ばれることもあった [尾崎 (2003) Birder 17(11): 41]。
単形種。
絶滅危惧 IA 類 (CR)。IUCN 3.1 EN 種。
ヤンバルクイナの免疫特性に関する研究は#インドガン備考の [野鳥と鳥インフルエンザ (9) インドガン] 以下の "最新状況" コーナーに紹介した。
[外来種マングースについて]
ヤンバルクイナといえば意図的に導入されたマングースの問題がよく知られているが、これは 1910 年にハブの駆除目的で導入されたもの。今から見るとどんな動物学者が考えたのかと思ってしまうが、ジャマイカで成功例とされたものがあったらしい。
Island Mongoose: Conservation Villain or Scapegoat? Or Both? (Matthew L. Miller 2015, 2018 The Nature Conservancy)
によれば、19 世紀半ばのジャマイカでサトウキビのプランテーションがネズミの被害に困っていたとのこと。
インドの入植者がフイリマングース Urva auropunctata (Small Indian mongoose かつてはジャワマングースと同種とされ、Herpestes javanicus の学名だった) が効率よくネズミを食べることを見つけてジャマイカに導入 (1872) したとのこと。
収穫は上がったらしいが因果関係は不明とのこと。
wikipedia 英語版のフイリマングースのページではサトウキビのプランテーションは世界各地で行われていて、トリニダード島の導入 (1870) はネズミのコントロールには有効でなかったと報告されている。1900年代にハワイに導入され、ネズミの数は減らせたが在来の鳥などに影響を及ぼした (ことが後にわかった)。
沖縄の事例 (1910) も紹介されていてハブ Protobothrops flavoviridis やネズミなど (こちらもサトウキビが重要な収入源) 有害動物を減らすためで、同じ目的で奄美大島にも1979年放獣された (ただし以下参照) とあるが、結果的にマングース自身が有害動物となったとある。
ダルマチアの島 (現クロアチア) にもハナダカクサリヘビ Vipera ammodytes (horned viper) を減らす目的で同じ1910年、当時のオーストリア=ハンガリー帝国政府が導入したとのこと。
当時は生物農薬 (生物的防除 biological pest control) が導入され始めた時代で1870年代から始まったと wikipedia 英語版にある。ネコやメンフクロウもネズミ類の駆除に用いられたことがあるとのこと。
このページにも The Nature Conservancy のページにもあるがネズミは夜行性なのにマングースは昼行性でむしろ鳥の方を捕食した (ただし下記 Hays and Conant も参照)。ネズミもマングースも鳥の卵を食べるので捕食圧が増してしまった。マングースの導入事例はこの関係が理解されていない時期 (生物学者は誰も予見しなかったのか?) に行われたものと説明されている。
1910 年当時は動物学の権威であった東京大学・渡瀬庄三郎 (1862-1929) の発案と2016年5月3日の The Page の記事にある (国立環境研究所の五箇公一解説)。報道でも「期待の星 (ホープ) 来る!」と宣伝されたとある。
この記事では導入にかかわる真実かどうか不明の逸話が紹介されているが、上記のような時代背景を振り返ると欧米の学問をそのまま輸入したのだろうか [後の金子 (2021) の歴史研究では当時明確に触れられていなかったらしい]。海外でも弊害が認識されずに行われていた時期で、この研究者の発想の貧困に即つながることではなさそうに見える。
金子 (2021) 渡瀬庄三郎による沖縄島へのフイリマングース導入に関連する
1910 年前後刊行の外来種文献の史料的検討 ("瀬" の文字は異字)
に詳しい歴史研究があり、中川(1900) がジャマイカの事例やその後の経緯も紹介していたとのこと。生物間相互作用は当時はまだ仮説なり哲学の問題だったのかも知れない印象を受けた。「どんな動物学者が考えたのか」は正直感じることなので、最新の知見に基づくこの論文を参照していただくのがよいだろう。
クロアチアの事例 (2000 年の導入 90 周年を記念した報告。クロアチア語) では 1927 年にはヘビとネズミがマングースの主要な獲物で、ドイツの探検者は島で毒蛇をまったく見かけなかったと 1961 年に報告している。この成果を受けて 1920 年代に他所にも放獣されたとのこと。
ヘビが減ったためマングースは別の獲物をターゲットとして特にヨーロッパウズラ、ゴイサギなどが捕食されたとのこと。上記 1961 年のドキュメンタリーでマングースがヘビを食べることが成功談として紹介されている。
20 年で個体数が増えてしまってヘビの駆除に成功したため、1949 年に狩猟の保護対象から外されたとのこと。
ここでは在来の鳥や渡り鳥の捕食はバランスを崩した程度の書き方で、むしろヘビの駆除には成功し、マングース自身も狩猟家のよい獲物となって狩猟圧も高くそこまで数を増やせなかった模様 (このあたりは狩猟の盛んな地中海ならではで日本とはだいぶ事情が違う。狩猟家も撃っているのでヨーロッパウズラなども特に問題にならなかったのかも)。
1959 年には干ばつで多くの個体が死亡したとのこと。低温の冬を乗り越えられないなども沖縄と異なる制約要因となっているのだろう。
Tvrtkovic and Krystufek (1990)
Small Indian mongoose Herpestes auropunctatus (Hodgson, 1836) on the Adriatic Islands of Yugoslavia
の方では野鳥も含めた食害は 1927, 1928, 1949 年の報告があるとのこと。ただしおそらく国外には知られていなかっただろう。ワシミミズクによるマングースの捕食が確認されている。ワシミミズクは普通にみられるとのことでさらに高次の捕食者が存在したことも日本の事例と違っているのだろう。
ちなみに 1990 年にはクロアチアはまだユーゴスラビアの一部だった。今となっては懐かしい名前。
Hays and Conant (2006)
Biology and Impacts of Pacific Islands Invasive Species. 1.
A Worldwide Review of Effects of the Small Indian Mongoose, Herpestes javanicus (Carnivora: Herpestidae)
に総説があり、ハワイのものはジャマイカから導入。
フィジーではフィジークイナ Hypotaenidia poeciloptera Bar-winged Rail は 1875 年には普通だったが、1883 年にマングースが導入されて数年以内に絶滅したという (Gorman 1975)。wikipedia 英語版では 1973 年が最後の未確認報告とのこと。
ジャマイカではジャマイカミズナギドリ Pterodroma caribbaea Jamaica Petrel は 18 世紀には多数生息していたが 1872 年のマングース導入後、1893 年以降見られていないとのこと (Collar et al. 1992)。wikipedia 英語版では 1936 年ごろ絶滅とある。
この2例が因果関係が最もはっきりしてと考えられているもののようで、ジャマイカコヨタカ Siphonorhis americana Jamaican Poorwill は 1859 年以来確認されておらず Bangs and Kennard (1920) はマングースによるものと考えたが、マングース導入以前に絶滅していたと思われ、Collar et al. (1992) は (プランテーションに伴う) 森林伐採とネズミによるものと考えている。
ハワイで鳥の巣を襲って食べている示唆は早くからあったが実証はなかなかなされず、Baldwin et al. (1952) がミズナギドリを捕食している証拠を見つけた。
King and Gould (1967) も証拠は示さなかったがハワイの主な島でハワイセグロミズナギドリ Puffinus newelli Newell's Shearwater を絶滅させた要因とした。1968年にはハワイマガモ Anas wyvilliana Hawaiian Duck の地域絶滅の要因とも指摘された。
マングースのいない島のみ一部のクイナ類が残っているとの報告 (Gorman 1975) があり、ジャマイカでチャバラクイナ Amaurolimnas concolor Uniform Crake が1881年以降のある時点で絶滅したとのことで、Raffaele et al. (1998) はマングースの影響が大きい可能性があると指摘した。
セント・クロイ島 (カリブ海) ではオオテリハウズラバト Geotrygon mystacea Bridled Quail-Dove は元来地上性でマングース導入 47 年後の 1921 年に絶滅したと考えられマングースが原因とされたが、樹上に営巣するようになりまた増えたという (Nellis and Everard 1983)。
セントビンセント島 (カリブ海) では Geotrygon 属のハトがマングースにより絶滅したという (Allen 1911)。
プエルトリコで5種類の地上営巣性の鳥の減少をマングースのためとされた (Wetmore 1927) が、絶滅したと考えられた種類が生存していることが後にわかり、マングースのいる島いない島いずれにも生存していたがいる島の方が少なかったという。
減少したとされるコミミズクの亜種はハワイにもマングースと同所的に生息するが特に影響は報告されていないとのこと。マングースとの因果関係がかなりはっきりしている事例もあるが、必ずしも根拠ある推論がなされていたわけではなくはっきりしない事例も多い模様。
セントルシア島とマルティニーク島 (カリブ海) ではムナジロツグミモドキ Ramphocinclus brachyurus White-breasted Thrasher への捕食圧を増したのではないかと考えられるが、Collar et al. (1992) は生息地破壊の方が重要な要因で、アフリカ由来の外来種であるキメジリオリーブツグミ Turdus tephronotus Bare-eyed Thrush との競争の影響もあるのではと考えている。
トリニダード島 (南米ベネズエラの北に位置する) では 61 年後でも絶滅した鳥はないとのこと (Urich 1931)。
マングース導入以外の人為的要因 (ネズミ、野生化したネコやイヌ、生息地への人の進出など) が鳥の個体数の減少にどのような影響があったかを見積もることは難しく、現在マングースと一緒に暮らしているハワイの鳥は1世紀以上その状態を保っていることは注目に値する。
カリブ海では地上性の鳥とある種の平衡状態が保たれている可能性がある (Westermann 1953) が、地上性の鳥のかつての生息域への再導入の障壁となっていることは確かである。
絶滅との因果関係がはっきりしているとされるのは上記2種の鳥とヘビの Hispaniola racer Alsophis melanichnus のみであるが、これら事例のいずれも他の要因も十分ある。
マングースは多数の場所に導入され、生態的には比較的脆弱な種類であることを考えると、マングースの役割はそれほど大きくなく、もっと普通の人為的外来種となっているネコやイヌ、ネズミの方が影響が大きかったのではないか。マングースの導入時期はこれらより比較的遅く、すでに劣化していた生態系にさらなる負荷を与えたと考えるのが妥当ではないかとのこと。
カリブ海の爬虫類への影響などは誇張されすぎていると考えている (外来種に責任を押し付けてしまうのはいかにも考えやすい)。
Hays and Conant (2006) でも Tvrtkovic and Krystufek (1990) は引用されているが、クロアチアの "成功" とされる事例は詳しい情報がなく言葉の壁などが厚かったのかも知れない。
この論文を見ると 1979 年の奄美大島への導入は世界でも最後の事例となるわけだが、環境省 奄美野生生物保護センター の「平成 18 年度奄美群島の概況」
資料 によれば聞き取り調査の結果 1949 年 (米軍時代) にはすでに導入があったらしいが 1979 年に2例の目撃例があるまで情報はなく、このころに島内で放されたものが奄美大島で定着したと考えられるとのこと。
マングースの分布拡大には土地の造成などマングースの定着しやすい環境を創出していたとみることができるとある。しかし、定着後、マングースは奄美大島の様々な環境に適応し、1990 年代前半には奄美市金作原原生林へも分布を拡大していると記載されている。
1979 年に放獣されたこともネットや文献で取り上げられているが誰が行ったかも含めてどうもそれほど明瞭ではないらしい。この件を調べておくと、
阿部他 (1991) 第 34 回シンポジウム記録「1990 年代の人間活動と哺乳動物界」奄美大島におけるマングース (Herpestes sp.) の定着 に聞き取り調査と考察があり、1949 年に放獣が行われたらしいことはある程度の信頼性はあるが失敗に終わったと考えられる。
1979 年頃当時は赤崎鳥獣保護区は市街地隣接地域で、公園の整備や「県立奄美少年自然の家」の建設に伴う土地の造成などが頻繁に、しかも広い範囲にわたって行われていたとのこと。現在のような分布は林道建設や森林伐採の影響で自然環境が貧弱になったことで侵入が容易となった要因がある可能性があると分析している。
Yamada and Sugimura (2004)
Negative Impact of an Invasive Small Indian Mongoose
Herpestes javanicus on Native Wildlife Species and Evaluation of a Control Project in Amami-Ohshima and Okinawa Islands, Japan
でも 30 頭が放獣されたと言われるが公式の記録はないとのこと。
この文献で紹介されている Simberloff et al. (2000) にもクロアチアは図示されておらず、やはり当時はあまり知られていなかったことがうかがえる。
Yamada and Sugimura は2004 年段階の論文なので、Hays and Conant (2006) はもちろん参照していない。伝え方も少し違うところがあり、2000 年ごろに外来種問題がクローズアップされた時流も反映していた印象を受ける。
2000 年 IUCN 世界の侵略的外来種ワースト 100 (100 of the World's Worst Invasive Alien Species)。日本ではよく知られているが海外での関心はそれほどでもないようで wikipedia でも 14 言語にとどまっている。日本は島国なので関心が高い (さらに捕食者の外来種の意味は一般的にもわかりやすい) ことは理解できないこともない。
この Invasive Species Specialist Group (ISSG) のページでは 1979 年に奄美大島に放されて在来種を脅かしていることは述べられているが、1910 年の沖縄への導入については特に言及がない。
引用されている文献は Watarai et al. (2008)
Effects of exotic mongoose (Herpestes javanicus) on the native fauna of Amami-Oshima Island, southern Japan, estimated by distribution patterns along the historical gradient of mongoose invasion。
その後 2005 年 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行。このころブラックバスの扱いなどよく報道があり、他の環境問題を若干覆い隠してしまったかのような印象も受けた。
当時の状況は「外来種ハンドブック」(日本生態学会50周年記念出版 地人書館 2002) でも読むことができる。生物利用に伴う侵入の「無法地帯」といえる日本 (p. 33, 村上・鷲谷) との記述があり、海外に比べても大きく遅れていた模様。日本生態学会も 1997 年から部会を設けて外来種問題に取り組むことになったとのこと。
Yagihashi et al. (2021) Eradication of the mongoose is crucial for the conservation of three endemic bird species in Yambaru, Okinawa Island, Japan
にも山原地方の経緯が述べられているが、マングースがヤンバルクイナ減少に関与しているとの文字の記述は意外に新しいようで 尾崎他 (2002) ヤンバルクイナの生息域の減少 にある。
この引用文献でも Harato and Ozaki (1993) Roosting Behavior of the Okinawa Rail (この中では可能性のある捕食者の一つとして挙げられている)、
尾崎清明 (1996) クイナ類の保護 - ロードハウクイナ - ヤンバルクイナシンポジウム、
日本野鳥の会やんばる支部 (1997) 沖縄島北部における貴重動物と移入動物の生息状況及び移入動物による貴重動物への影響報告書 が出てくるもので、ヤンバルクイナ減少に対するマングースの寄与が大きいことがわかったのは比較的最近のことらしい。「外来種ハンドブック」の記載でも 1990 年代前半ぐらいに可能性が指摘されていたもので、理解が含まったのは 1990 年代後半のよう。
コンサイス鳥名事典 (1988) でも野生化したネコ、イヌの方が取り上げられ (これはもちろん現在に至っても大きな問題だが)、マングースはまだ挙げられていなかった。
Watari et al. (2010) New detection of a 30-year-old population of introduced mongoose Herpestes auropunctatus on Kyushu Island, Japan すでに30年前に九州にも導入があった。
阿部 (2021) Birder 35(8): 32-35 に奄美大島のマングース対策の記事がある。参考として読むべき日本語の文献も示されている。
まとめておくと、日本の経緯については
・1910年の導入については 金子 (2021)
・奄美大島については阿部他 (1991); Yamada and Sugimura (2004); Yagihashi et al. (2021)
世界では
・Hays and Conant (2006)
をまず見ておくとよさそう。足りない部分を他の資料から補えばよい感じがする。世界最悪の侵略的外来種との見方もやや一面的過ぎる印象を受ける。
1910 年の導入を決めた学者を評価するにあたっては金子 (2021) に目を通して当時どこまで知られていたのか、何を考えたのだろうか納得しておくのがよいだろう。
外来種関係でここで紹介: Hsu et al. (2024) Free ride without raising a thumb: A citizen science project reveals the pattern of active ant hitchhiking on vehicles and its ecological implications
台湾の外来アリ Dolichoderus thoracicus black cocoa ant
などは車に便乗して分布を広げているとのこと。
-
ミナミクイナ
- 第8版学名:Lewinia striata (レウィニア ストゥリアータ) 条斑のあるリューインのクイナ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Gallirallus striatus (ガルリラルルス ストゥリアートゥス) 条斑のあるヤケイのようなクイナ
- 第8版属名:lewinia 英国の彫刻師、博物学者でオーストラリアに入植した John William Lewin に由来
- 第7版属名:gallirallus (合) ヤケイのようなクイナ Gallus 属 (ニワトリのもとになったセキショクヤケイなどを含む属) と Rallus 属 (クイナ属) から合成された、当初は亜属の名称だったものを属名とした (The Key to Scientific Names)
- 種小名:striata / striatus (adj) 条斑がある
- 英名:Slaty-breasted Rail
- 備考:
lewinia は最初の i がアクセント母音と考えられる (レウィニア)。
gallirallus は#ヤンバルクイナ参照。
striata/striatus は -ata/-atus の冒頭が長母音でアクセントがある (ストゥリアータ/ストゥリアートゥス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Lewinia 属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。英国の彫刻師、博物学者でオーストラリアに入植した John William Lewin に由来。
学名は Lewinia striata となる (語尾が変わるので注意)。Lewinia 属はミナミクイナ属。ハシナガクイナの別名もあった。
英名で Lewin's Rail はまた別にある オーストラリアクイナ Lewinia pectoralis。この種の記載時学名が Rallus lewinii Swainson, 1837。種小名が変わったのは Rallus pectoralis Temminck, 1831 の記載の方が早かったため。
6亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。
[中国で外来水草に急速に適応したミナミクイナ]
Wang et al. (2025) The First Record of the Slaty-Breasted Rail Lewinia striata Inhabiting the Invasive Spartina alterniflora in Dafeng, Yancheng, China。
-
クイナ (分割された)
- 第8版学名:Rallus indicus (ラルルス インディクス) インドのクイナ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Rallus aquaticus (ラルルス アクアーティクス) 水辺にいるクイナ
- 第7版亜種学名:Rallus aquaticus indicus (ラルルス アクアーティクス インディクス) インドの水辺にいるクイナ
- 属名:rallus (合) クイナ [ralleクイナ 独 (これもフランス語 rale 由来とも言われる。声を示す)、rasle/rale クイナ 中世仏 (これも音声由来とされる) 由来の両説がある。The Key to Scientific Names, wiktionary。備考参照]
- 第8版種小名:indicus インドの
- 第7版種小名:aquaticus (adj) 水の (aqua (f) 水 -aticus 〜に関連する)
- 第7版亜種小名:indicus インドの
- 英名:(Water Rail), IOC: Brown-cheeked Rail
- 備考:
rallus は短母音のみで ral-lus と分割され冒頭にアクセント (ラルルス)。
indicus は短母音のみで冒頭にアクセントがある (インディクス)。
aquaticus は2つめの a が長母音でアクセントもここにある (アクアーティクス)。-aticus の発音由来。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Rallus aquaticus indicus から種に昇格され Rallus indicus となり亜種はなくなる (indicus インドの)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
旧英名の Water Rail は IOC では分離された Rallus aquaticus ヨーロッパクイナ の名前となる。
OED によれば water rail の用例は古くからあって 1655 年にすでに使用例があった。Rallus aquaticus もそのままの意味。
記載時学名 Rallus indicus Blyth, 1849 と記載時学名に戻る (原記載) 基産地はインド。
Rallus japonicus Jerdon, 1863 (参考) (Bonaparte 1856 に由来するがこれは無効とのこと) の記載があったが Hartert (1910-1922) p. 1826 によれば Rallus indicus の単なる改名に過ぎないとのこと。
この用例があるため日本産の Rallus 属には亜種名に japonicus を与えることができない。
[属名の由来]
The Key to Scientific Names によればおそらく中世フランス語 rasle, rale (Sundevall 1873: "Nomen Rallus, primum Rasle, Belon, dein Rale ..." の文献があり、BOU 1915 は "the latinized form of the French Rale, our Rail, Dutch Ral" としている)。
Gessner 1555 がこの鳥を指して Rallus とする用例があるようで、Macleod 1954 は "Latinized form of German ralle, rail (bird)" としている。Rallus がドイツ語由来説はこれが出所と思われる。Gessner がドイツ人であるためにドイツ語由来らしいとされた模様。
Rallus Linnaeus, 1758 だが Linnaeus 以前にすでに用いられていた属名で、"Rallus aquaticus" of Willughby 1676, and "Water Rail. Rallus Aquaticus" of Albin 1731 の用例があった。
[音声]
様々な鳴き声を示し、姿が見えにくいので水辺の探鳥会などで音声同定に悩まされる種類の一つ。クイナ (バードリサーチ鳴き声図鑑) などを参照して声に馴染んでおくとよい。声がわかれば (適切な時期と場所であれば) 結構な個体数がいることがわかる。
[クイナ類の系統分類]
分子系統学に基づくクイナ類の分類は Kirchman et al. (2021) Phylogeny based on ultra-conserved elements clarifies the evolution of rails and allies (Ralloidea) and is the basis for a revised classification を参照。
これは核遺伝情報 (UCE) も用いた新しいタイプの系統分類 (#アカハラダカの備考参照)。
Kirchman et al. (2022) Corrigendum to: Phylogeny based on ultra-conserved elements clarifies the evolution of rails and allies (Ralloidea) and is the basis for a revised classification
に訂正がある。Rufirallus 属の再編成にあたってどちらの属に先取権があるかを判断していなかった。訂正は以下のリストには影響がない。
同年に Garcia-R. and Matzke (2021) Trait-dependent dispersal in rails (Aves: Rallidae): Historical biogeography of a cosmopolitan bird clade (図は見られる)
も系統樹を出していて、Boyd はこちらを主に用いている。
この文献は現状ではオープンアクセスでないのと、UCE を用いた方が一般的に精度が高いと考えられるので Kirchman et al. (2021) をベースとした分類を紹介する。
日本産種類の日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版の属変更はこの論文に一致しているので「何がなんだかわからない」クイナ類の分類変更の意味はこの論文を見ていただければよいだろう。
この論文の順序はクイナ科以降は分岐順をあまり意識していない (分岐時期が近すぎて判定できないのだろう) ので科以下の配置順序は任意性があると思って見ていただくとよい。
IOC、あるいは日本鳥類目録改訂第8版分類順とは一致していない。
科名については山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類から用いてある。属名は日本産の種のある属は日本鳥類目録 改訂第8版の第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開 (2023年10月) による。それ以外については自動的に決まるものやほぼ推測できるものを仮に入れてある。
属移動に際して性変更に伴って起きたと思える種小名の語尾の違いがあり、他のリストの間でも統一されていない。ここでは IOC 14.1 の語形を示し、Kirchman et al. (2021) の表記をかっこに入れてある。和名は山崎・亀谷 (2022) アフリカクイナ科・クイナ科の新しい種和名から。
クイナ類は過去にすでに多数の属に細分化されており、従来の分類と分子系統研究の結果が入り組んでおり、過去の属名をなるべく活かすためには複雑な移動や分離が必要になった模様である。山崎・亀谷 (2022) で用いられた IOC の 2020 年段階ともかなり変化がある。
日本鳥類目録 改訂第8版の第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開に記載されている種 (第8版掲載見込み種) は緑字で示してある。この他にも検討種扱いが少数存在する。
Kirchman et al. (2021) 準拠の分類による:
ツル目 クイナ亜目 Ralli
ヒレアシ科 Heliornithidae
アフリカヒレアシ属 Podica
アフリカヒレアシ Podica senegalensis
アジアヒレアシ属 Heliopais
アジアヒレアシ Heliopais personatus Masked Finfoot
アメリカヒレアシ属 Heliornis
アメリカヒレアシ Heliornis fulica Sungrebe
? 科 Aptornithidae (絶滅科)
? 属 Aptornis (adzebills、ニュージーランド)
(アフリカクイナ)科 (*) Sarothruridae
マダガスカルクイナ属 Mentocrex
マダガスカルクイナ Mentocrex kioloides Madagascar Wood Rail
ハリヤマクイナ (ツィンギクイナも使われた) Mentocrex beankaensis Tsingy Wood Rail
ニューギニアクイナ?属 Rallicula
アカパプアクイナ Rallicula rubra Chestnut Forest Rail
セスジパプアクイナ Rallicula leucospila White-striped Forest Rail
セグロパプアクイナ Rallicula forbesi Forbes's Forest Rail
クリイロパプアクイナ Rallicula mayri Mayr's Forest Rail
? 属 Sarothrura (アフリカに分布)
シラボシクイナ Sarothrura pulchra White-spotted Flufftail
キボシクイナ Sarothrura elegans Buff-spotted Flufftail
ムネアカシマクイナ Sarothrura rufa Red-chested Flufftail
クリガシラシマクイナ Sarothrura lugens Chestnut-headed Flufftail
アカエリシマクイナ Sarothrura boehmi Streaky-breasted Flufftail
クリオシマクイナ Sarothrura affinis Striped Flufftail
マダガスカルシマクイナ Sarothrura insularis Madagascar Flufftail
アフリカシマクイナ Sarothrura ayresi White-winged Flufftail
マダガスカルムジクイナ Sarothrura watersi Slender-billed Flufftail
クイナ科 Rallidae
ウロコクイナ亜科 Himantornithinae
ウロコクイナ族 Himantornithini
ウロコクイナ属 Himantornis (アフリカ)
ウロコクイナ Himantornis haematopus Nkulengu Rail
? 族 Gymnocrecini
? 属 Gymnocrex (インドネシア、ニューギニア)
アオメクイナ Gymnocrex rosenbergii Blue-faced Rail
メジロクイナ (タラウドクイナも使われた) Gymnocrex talaudensis Talaud Rail
アカメクイナ Gymnocrex plumbeiventris Bare-eyed Rail
オオバン族 Fulicini
ワキジロバン属 Porphyriops (南米)
ワキジロバン Porphyriops melanops Spot-flanked Gallinule
サンクリストバルオグロバン/サモアオグロバン属 Pareudiastes (Gallinula 属から分離。ソロモン地域離島)
サンクリストバルオグロバン Pareudiastes silvestris Makira Woodhen
サモアオグロバン Pareudiastes pacifica Samoan Woodhen (絶滅種)
オグロバン属 Tribonyx (オーストラリア)
オグロバン Tribonyx ventralis Black-tailed Nativehen
タスマニアオグロバン Tribonyx mortierii Tasmanian Nativehen
コモンクイナ属 Porzana (北半球)
カオグロクイナ Porzana carolina Sora
コモンクイナ Porzana porzana Spotted Crake
ミナミヒメクイナ Porzana fluminea Australian Crake
ヒメバン属 Paragallinula (アフリカ)
ヒメバン Paragallinula angulata Lesser Moorhen
バン属 Gallinula (世界に分布)
ネッタイバン Gallinula tenebrosa Dusky Moorhen
アメリカバン Gallinula galeata Common Gallinule
ゴーフバン (ゴフバンも使われた) Gallinula comeri Gough Moorhen
トリスタンバン Gallinula nesiotis Tristan Moorhen (絶滅種)
バン Gallinula chloropus Common Moorhen
オオバン属 Fulica (世界に分布)
アカビタイオオバン Fulica rufifrons Red-fronted Coot
ツノオオバン Fulica cornuta Horned Coot
ナンベイオオバン Fulica armillata Red-gartered Coot
オニオオバン Fulica gigantea Giant Coot
アフリカオオバン Fulica cristata Red-knobbed Coot
オオバン Fulica atra Eurasian Coot
(チャタムオオバン)? Fulica chathamensis (絶滅種)
アメリカオオバン Fulica americana American Coot
ハワイオオバン Fulica alai Hawaiian Coot
ハジロオオバン Fulica leucoptera White-winged Coot
アンデスオオバン (ハイイロオオバンも使われた) Fulica ardesiaca Andean Coot
Kirchman et al. (2021) には記載がないがこの分類か:
マスカリンオオバン Fulica newtonii Mascarene Coot (絶滅種)
セイケイ族 Porphyrionini
セイケイ属 Porphyrio [世界の熱帯から南半球。Kirchman et al. (2021) で属名綴り間違い]
アメリカムラサキバン Porphyrio martinica (martinicus?) Purple Gallinule
ナンベイバン (ナンベイムラサキバン) Porphyrio flavirostris Azure Gallinule
アフリカムラサキバン Porphyrio alleni Allen's Gallinule
ヨーロッパセイケイ (セイケイも使われた) Porphyrio porphyrio Western Swamphen
ロードハウセイケイ Porphyrio albus White Swamphen (絶滅種)
オオタカヘ (モホとも呼ばれる) Porphyrio mantelli North Island Takahe (絶滅種)
タカヘ (ノトルニス) Porphyrio hochstetteri South Island Takahe
Kirchman et al. (2021) には記載がないが以下はヨーロッパセイケイの亜種から分離されたもの:
アフリカセイケイ Porphyrio madagascariensis African Swamphen
セイケイ Porphyrio poliocephalus Grey-headed Swamphen
スンダセイケイ Porphyrio indicus Black-backed Swamphen
フィリピンセイケイ Porphyrio pulverulentus Philippine Swamphen
ナンヨウセイケイ Porphyrio melanotus Australasian Swamphen
シマクイナ/コビトクイナ?族 Laterallini
ズアカコビトクイナ属? Rufirallus (属の再編成。南米)
アカシロクイナ Rufirallus leucopyrrhus Red-and-white Crake (Laterallus 属より移動)
クロジマコビトクイナ Rufirallus fasciatus Black-banded Crake (Laterallus 属より移動)
セボシクイナ Rufirallus schomburgkii Ocellated Crake (Micropygia 属より移動)
ズアカコビトクイナ Rufirallus viridis Russet-crowned Crake (もと Rufirallus 属はこの1種のみ)
シマクイナ属 Cotunicops (アメリカにも分布)
アメリカシマクイナ Cotunicops noveboracensis Yellow Rail [Kirchman et al. (2021) 学名綴り間違い]
シマクイナ Cotunicops exquisitus Swinhoe's Rail
ダーウィンシマクイナ Cotunicops notatus Speckled Rail
? 属 Hapalocrex (新属。南米)
キムネヒメクイナ Hapalocrex flaviventer Yellow-breasted Crake (Laterallus 属より移動)
ハイムネコビトクイナ Hapalocrex exilis Grey-breasted Crake (Laterallus 属より移動)
コビトクイナ属? Laterallus (南米・北米の8種)
クロコビトクイナ Laterallus jamaicensis Black Rail
アルゼンチンヒメクイナ Laterallus spiloptera (spilopterus?) Dot-winged Crake
マメクロクイナ Laterallus rogersi Inaccessible Island Rail
ガラパゴスコビトクイナ Laterallus spilonota Galapagos Crake
ノドジロコビトクイナ Laterallus melanophaius Rufous-sided Crake
ズグロコビトクイナ Laterallus ruber Ruddy Crake
キタノドジロコビトクイナ Laterallus albigularis White-throated Crake
? 属 (新属) (Laterallus 属から分離。属学名未定。南米)
ワキアカコビトクイナ "Laterallus" levraudi Rusty-flanked Crake
シロオビコビトクイナ "Laterallus" xenopterus Rufous-faced Crake
Kirchman et al. (2021) には記載がないがこの分類か:
[Boyd は Laterallus 属から分離された Creciscus 属に他種とまとめているが、Kirchman et al. (2021) はそれらの種に異なる属を与えている。以下の絶滅属についてはそのままにしておく]
アセンションクイナ属 Mundia
アセンションクイナ Mundia elpenor Ascension Crake (絶滅種)
セントヘレナクイナ属 Aphanocrex
セントヘレナクイナ Aphanocrex podarces St. Helena Rail (絶滅種)
シロハラクイナ族 Amaurornithini
マミジロクイナ属 Poliolimnas
マミジロクイナ Poliolimnas White-browed Crake
パプアクイナ属 Megacrex
パプアクイナ Megacrex inepta New Guinea Flightless Rail
チャバラヒメクイナ属 Aenigmatolimnas (アフリカ)
チャバラヒメクイナ Aenigmatolimnas marginalis Striped Crake
ツルクイナ属 Gallicrex
ツルクイナ Gallicrex cinerea Watercock
シロハラクイナ属 Amaurornis (東南アジア、東・南アジアの一部、オーストラリア北部)
チャバネクイナ Amaurornis akool Brown Crake (Zapornia属から移動)
フィリピンバンクイナ (バンクイナも使われた) Amaurornis olivacea Plain Bush-hen
シロハラクイナ Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen
チャバラバンクイナ Amaurornis isabellina Isabelline Bush-hen
バンクイナ (アカオクイナも使われた) Amaurornis moluccana Pale-vented Bush-hen
タラウドバンクイナ Amaurornis magnirostris Talaud Bush-hen
ヒメクイナ族 Zapornini
オオクイナ属 Rallina (東南アジア、東・南アジアの一部、オーストラリア北部)
ミナミオオクイナ Rallina tricolor Red-necked Crake
アンダマンオオクイナ Rallina canningi Andaman Crake
ナンヨウオオクイナ Rallina fasciata Red-legged Crake
オオクイナ Rallina eurizonoides Slaty-legged Crake
ヒメクイナ属 Zapornia
アフリカクロクイナ Zapornia flavirostra Black Crake
ヒクイナ Zapornia fusca Ruddy-breasted Crake
コウライクイナ (コウライヒクイナ) Zapornia paykullii Band-bellied Crake
コクイナ Zapornia parva Little Crake
ヒメクイナ Zapornia pusilla Baillon's Crake
レイサンクイナ Zapornia palmeri Laysan Rail (絶滅種)
マダガスカルクロクイナ Zapornia olivieri Sakalava Rail
オグロクイナ Zapornia bicolor Black-tailed Crake
ハワイクイナ Zapornia sandwichensis Hawaiian Rail (絶滅種)
ヘンダーソンクイナ Zapornia atra Henderson Crake
ミナミクロクイナ Zapornia tabuensis Spotless Crake
ナンヨウコクイナ Zapornia monasa Kosrae Crake
Kirchman et al. (2021) には記載がないがこの分類か:
セントヘレナヒメクイナ (セントヘレナクイナも使われた) Zapornia astrictocarpus St. Helena Crake (絶滅種)
タヒチヒメクイナ (タヒチクイナも使われた) Zapornia nigra Tahiti Crake (絶滅種)
クイナ亜科 Rallidae
クイナ族 Rallini
アフリカクイナ?属 Canirallus
アフリカクイナ Canirallus oculeus Grey-throated Rail
クイナ属 Rallus (オーストラリアを除く世界に分布)
ニシオニクイナ Rallus obsoletus Ridgway's Rail
ヒガシオニクイナ Rallus crepitans Clapper Rail
メキシコクイナ (アステッククイナも使われた) Rallus tenuirostris Aztec Rail
ミナミオニクイナ (種分割される前はオニクイナ) Rallus longirostris Mangrove Rail
オウサマクイナ Rallus elegans King Rail
ムジオニクイナ Rallus wetmorei Plain-flanked Rail
コオニクイナ Rallus limicola Virginia Rail
ナンベイクイナ Rallus semiplumbeus Bogota Rail
ミナミコオニクイナ (ミナミクイナも使われた) Rallus antarcticus Austral Rail
ニシクイナ (ヨーロッパクイナも使われた) Rallus aquaticus Water Rail
クイナ Rallus indicus Brown-cheeked Rail
アカハシクイナ Rallus caerulescens African Rail
チャムネクイナ Rallus madagascariensis Madagascar Rail
Kirchman et al. (2021) には記載がないがこの分類か:
オニクイナ Rallus crepitans Clapper Rail (ミナミオニクイナの亜種とされていた)
エクアドルコオニクイナ Rallus aequatorialis Ecuadorian Rail (コオニクイナの亜種とされることもある)
アビシニアクイナ属 Rougetius (エチオピア)
アビシニアクイナ Rougetius rougetii Rouget's Rail
アフリカウズラクイナ属 Crecopsis
アフリカウズラクイナ Crecopsis egregia African Crake
ノドジロクイナ属 Dryolimnas (マダガスカル地域)
ノドジロクイナ Dryolimnas cuvieri White-throated Rail
レユニオンクイナ Dryolimnas augusti Reunion Rail
ウズラクイナ属 Crex
ウズラクイナ Crex crex Corn Crake
セレベスクイナ属 Aramidopsis
セレベスクイナ Aramidopsis plateni Snoring Rail
ミナミクイナ属 Lewinia (東南アジア・南アジアからオーストラリア)
ミナミクイナ (ハシナガクイナ) Lewinia striata Slaty-breasted Rail
ルソンクイナ Lewinia mirifica Brown-banded Rail
オーストラリアクイナ Lewinia pectoralis Lewin's Rail
オークランドクイナ Lewinia muelleri Auckland Rail
カラヤンクイナ属 Aptenorallus (新属。フィリピン北のカラヤン島)
カラヤンクイナ Aptenorallus calayanensis Calayan Rail (Gallirallus 属より分離)
ハルマヘラクイナ属 Habroptila (インドネシアのハルマヘラ島)
ハルマヘラクイナ Habroptila wallacii Invisible Rail
Kirchman et al. (2021) には記載がないが次の2絶滅属はこの付近か:
ロドリゲスクイナ属 Erythromachus (Boyd は Habroptila 属と Aptenorallus 属の間に置いている)
ロドリゲスクイナ Erythromachus leguati Rodrigues Rail (絶滅種)
ワレカウリクイナ属 Diaphorapteryx (Boyd は Habroptila 属と Aptenorallus 属の間に置いている)
ワレカウリクイナ属 Diaphorapteryx hawkinsi Hawkins’s Rail (絶滅種)
ニュージーランドクイナ/ニューカレドニアクイナ属 Gallirallus
ニュージーランドクイナ Gallirallus australis Weka
ニューカレドニアクイナ Gallirallus lafresnayanus New Caledonian Rail (Cabalus 属より移動)
マングローブクイナ属 Eulabeornis (オーストラリア北部)
マングローブクイナ Eulabeornis castaneoventris Chestnut Rail
ヤンバルクイナ属 Hypotaenidia (ヤンバルクイナなど8種と絶滅種4種)
ヤンバルクイナ Hypotaenidia okinawae Okinawa Rail
ムナオビクイナ (クビワクイナも使われた) Hypotaenidia torquata Barred Rail
ニューブリテンクイナ Hypotaenidia insignis Pink-legged Rail
フィジークイナ Hypotaenidia poeciloptera Bar-winged Rail (絶滅種)
ウッドフォードクイナ Hypotaenidia woodfordi Woodford's Rail
グアムクイナ Hypotaenidia owstoni Guam Rail
ソロモンクイナ Hypotaenidia rovianae Roviana Rail
チャタムクイナ Hypotaenidia modesta Chatham Rail (Cabalus 属より移動。絶滅種)
ウェーククイナ Hypotaenidia wakensis Wake Island Rail (絶滅種)
チャタムオビクイナ Hypotaenidia dieffenbachii Dieffenbach's Rail (絶滅種)
ロードハウクイナ Hypotaenidia sylvestris Lord Howe Woodhen
ナンヨウクイナ Hypotaenidia philippensis Buff-banded Rail
Kirchman et al. (2021) には記載がないがこの分類か:
タヒチクイナ Hypotaenidia pacificus Tahiti Rail (絶滅種)
Kirchman et al. (2021) には記載がないが以下の属はこの分類か:
モーリシャスクイナ属 Aphanapteryx [Boyd はチャタムクイナと同属としてこれらを Aphanapteryx 属としている。このままとしておく]
モーリシャスクイナ Aphanapteryx bonasia Red Rail (絶滅種)
マダラクイナ族? Pardirallini
ムネアカクイナ属 Anurolimnas (南米)
ムネアカクイナ Anurolimnas castaneiceps Chestnut-headed Crake (Rufirallus 属より移動)
チャバラクイナ属 Amaurolimnas (中南米)
チャバラクイナ Amaurolimnas concolor Uniform Crake
モリクイナ属? Aramides (主に中南米。タイプ種はコンゴウクイナ)
オオモリクイナ Aramides ypecaha Giant Wood Rail
チャイロモリクイナ Aramides wolfi Brown Wood Rail
ヒメモリクイナ Aramides mangle Little Wood Rail
コンゴウクイナ (ハイクビモリクイナ) Aramides cajaneus Grey-cowled Wood Rail
ズアカモリクイナ (シロハラモリクイナも使われた) Aramides albiventris Russet-naped Wood Rail
チャクビモリクイナ Aramides axillaris Rufous-necked Wood Rail
アカバネモリクイナ Aramides calopterus Red-winged Wood Rail
ハイムネモリクイナ Aramides saracura Slaty-breasted Wood Rail
ナンベイヒメクイナ属? Mustelirallus (南米)
ナンベイヒメクイナ Mustelirallus albicollis Ash-throated Crake
コロンビアヒメクイナ Mustelirallus colombianus Colombian Crake (Neocrex 属より移動)
アカアシヒメクイナ Mustelirallus erythrops Paint-billed Crake (Neocrex 属より移動)
マダラクイナ属? Pardirallus (中南米)
ハイイロクイナ Pardirallus sanguinolentus Plumbeous Rail
キタハイイロクイナ Pardirallus nigricans Blackish Rail
マダラクイナ Pardirallus maculatus Spotted Rai
キューバクイナ族 (族学名未定)
キューバクイナ属 Cyanolimnas
キューバクイナ Cyanolimnas cerverai Zapata Rail (かつて Mustelirallus 属)
山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) の Sarothruridae, 新和名: アフリカクイナ科 はアフリカクイナの種名を持つもの (Canirallus oculeus) が新分類のクイナ科 Rallidae に移動したためため、名称を変える方が望ましいだろう。
この分類での Zapornia 属のタイプ種は Zapornia minuta Leach, 1816 = Rallus parvus Scopoli だが、第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開では Zapornia pusilla にヒメクイナを与えているのでタイプ種とは一致していない。
Zapornia parva にはコクイナの名前があるが日本では記録されていないため、どの種を属名に用いるかは任意性もある。知名度も遭遇頻度も高く、先に記載されたヒクイナ Zapornia fusca (Linnaeus, 1766) があえて選ばれていないのは何か理由があるのだろうか。
ただし和名ヒメクイナ属は当時の属 Porzana に対して改訂第7版よりすでに使われている。ちなみに Porzana 属だった時代はコモンクイナがタイプ種だった (現在の Porzana 属でもタイプ種)。
Porzana 属からまとまって移動された際に属和名もそのまま移行したものかも知れない。
Boyd の提案によれば Zapornia 属をさらに細分してヒクイナに Limnobaenus fuscus の学名を与えている (2種のみ)。
Kirchman et al. (2021) の系統樹ではヒクイナとコクイナの遺伝的距離は近いのでここではこの細分類は取り扱わないことにする。
Lewinia 属は Kirchman et al. (2021) では3種のみがリストされており、オークランドクイナ Lewinia muelleri Auckland Island Rail が含まれていない。本文中にも言及がないが、オーストラリアクイナの亜種とされることもあるためだろう。
Rallus aequatorialis Ecuadorian Rail も同様でコオニクイナ Rallus limicola の亜種とすることもある。エクアドルクイナのような名称が想定できるが探した範囲ではみつからなかった。
旧 Cabalus 属は分割され消滅。旧 Neocrex 属は統合で消滅 (Mustelirallus 属のシノニムとなる)。
シマクイナ/コビトクイナ?族 Laterallini の和名は日本産種を重視すれば前者、もとになった属を重視すれば後者となるだろうか。
Laterallus 属は主に南米で一部北米にも分布する属で日本産種とは現状関連が薄いが Laterallini 族が導入されれば多少の関係が生じる。
この属も複雑な経緯があるようで、Rallidae (BirdForum 2025.5) に説明されている。
Laterallus Bonaparte, 1854 は属の性質を記述しておらず無効、Latterallus Gray, 1855 は有効。Laterirallus Bonaparte, 1856 の記載があるそうで、Gray (1855) の属記載が先にあるので表面上問題はないが、この属名が 1854 年のものを訂正したものか解釈上で問題がある。
Latterallus Gray, 1855 の方はタイプ種 Rallus melanophaius Vieillot 1819 (= ノドジロコビトクイナ Laterallus melanophaius Rufous-sided Crake) が明示されており問題ないが、Laterirallus Bonaparte, 1856 では示されておらず後に決められた。
もしこの属が Latterallus Gray を継承したものと解釈すればノドジロコビトクイナを Bonaparte (1856) が明示的に含めていないのでタイプ種になり得ない。Bonaparte (1856) が単に Laterallus Bonaparte, 1854 の綴りを間違っただけであれば (訂正の意図は文献上明らかでない) 有効な属名にならない。
つまり Laterirallus Bonaparte, 1856 は有効な属名でないとする考え方と、有効であるがタイプ種未定とする考え方の両方があり得るとのこと。
Latterallus Gray, 1855 のタイプ種と、もし有効であれば Laterirallus Bonaparte, 1856 のタイプ種が異なる可能性があり、例えば系統解析で Latterallus 属を分割する必要が生じた場合などに問題となり得る。
この解説に現れる nominal species は日本語では名義種。動物と植物で属のタイプの定義方法が異なり、動物の場合は「xx 属のタイプ種は yy」と表現して問題ない。厳密に書きたい場合はここで現れる "種" の概念は名義種に対応する。分類学の概念を検索してしばしば植物の方の解説文に到達してしまい、動物でも同じとみなしてしまうと誤解のもとになり得る。訳語は古い時代に作られたものですべて日本語で通すよりも英語の用語をそのまま用いた方がわかりやすい気がする。
ニューギニアクイナ?属 Rallicula 属の名称はパプアクイナが別属に存在するため、分布からニューギニアを与えてみた。
パプアクイナとなっている種も英名はニューギニア飛べないクイナなので新分類を見た上で和名を調整した方がよいかも知れない。
この種の種小名 inepta は「適さない」を意味するラテン語から愚かななどの意味として使われているようである。飛べないことなどが由来になっているかも知れない。
フランス名では Rale geant で geant は英語 giant に相当し、属名の由来となった「巨大なクイナ」となっている。
キューバクイナは和名からはキューバに広く生息している印象を受けるが、Zapata ザパタ半島の沼地のごく限られた場所にのみ生息し、IUCN CR 種である。
Porphyrio mantelli North Island Takahe と
Porphyrio hochstetteri South Island Takahe
は同種とされることもあり和名は両者を指してタカヘとしていることが多いと思う。
カラヤンクイナ (フィリピン北のカラヤン島) が 2004 年に発見された時はヤンバルクイナに (最も) 近縁かと話題になったが、現代的な分子系統研究では別属が適切となった。これらの知見は IOC ではすでに取り入れられている。
Oliveros et al. (2011) カラヤンクイナの巣および卵の初記載。
Allen (2005) Birder 19(1): 36-39 (Birder 編集部訳、尾崎監訳) カラヤンクイナ発見記 がある。
Oswald et al. (2021) Ancient DNA from the extinct Haitian cave-rail (Nesotrochis steganinos) suggests a biogeographic connection between the Caribbean and Old World
によればカリブ海ハイチの絶滅クイナ Nesotrochis steganinos の近縁種はアフリカの種類だったとのこと。祖先が飛翔性があって渡りをしていたものと考えられる。
上記分類では (アフリカクイナ)科 Sarothruridae のグループになり、アフリカ、ニューギニアに分布。ニュージーランドの Aptornithidae (絶滅科) がその前の分枝となり、世界に広く分布していたことがわかる。
ガラパゴスコビトクイナ Laterallus spilonota の保全の遺伝的研究: Chavez et al. (2024)
Whole-genome analysis reveals the diversification of Galapagos rail (Aves: Rallidae) and confirms the success of goat eradication programs。
約 120 万年前にガラパゴスに定着、飛翔力をかなり失った。かつてはガラパゴス全域の7つの島に生息していた (かつてはつながっていた) が人がヤギを持ち込んで環境が大きく悪化。50 個体以下まで減少。39 個体の全ゲノム解析を行い島の個体間の系統関係を明らかにした。
少し離れた小島 Pinta 島で再発見されたものはガラパゴス諸島の古い系統にあたり、再定着したものではないことがわかった。
ヤギの導入に伴う可能性のある長いホモ接合 (homozygosity) が見つかり、ヤギを駆除することが近親交配に極めて重要であったと考えられる。
渡りの鳥がガラパゴスに定着して固有種となった事例は #カワウ備考の [ガラパゴスコバネウの進化] を参照。こちらの方が定着時期が少し古い (200 万年前ぐらい) ようだが潜水への適応への選択圧が強く、無飛翔化がさらに進みやすかったのかも。
最近のニュースがあり Press Release-Return of the Rails: Signs of Recovery on Floreana Island (Island Conservation 2025.2.27)。
Floreana Island の生態系復元計画が始まって早々に姿を見せたという。この記事では絶滅の恐れがあっても resilient and resourceful little bird と表現している (柔軟性がある、回復力がある; 機転の利く などの意味。迫害を受けた猛禽類の回復力の表現などにも使われている単語)。
ここでは外来種の排除が奏功しているらしい。
-
シロハラクイナ
- 学名:Amaurornis phoenicurus (アマウロルニス ポエニクールス) 尻の赤い(赤紫の)暗色の鳥
- 属名:amaurornis (合) 暗色の鳥 (amauros 暗色の ornis 鳥 Gk)
- 種小名:phoenicurus (合) ジョウビタキ (床屋の看板の赤色から赤い鳥の意); 赤紫の (コンサイス鳥名事典)
- 英名:White-breasted Waterhen
- 備考:
amaurornis は起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-or- がアクセント音節と考えられる (アマウロルニス)。
phoenicurus は#ジョウビタキ参照。
記載時学名 Gallinula phoenicurus Pennant, 1769 (原記載) 基産地 Ceylon (スリランカ)。
当時の英名 The red-tailed Water-Hen 当時セイロンの現地ではごく普通の鳥で現地名 Kaloe-kerewaka とのこと。フランス語名も同時に与えられ La poule d'eau a queue rouge (赤い尾の水の鶏)。
ほぼ同じ意味の学名 Gallinula erythrura Bechstein, 1812 (参考) もあった。
英名は日本で記載された当時はどちらも Gallinula 属だったヒクイナの学名由来の Ruddy-breasted Crake に対応する形で付けられたのではないかと想像する。
意味的には候補となりそうな学名 Gallinula leucosoma Swainson, 1838 (参考) 基産地インド があり、これはマミジロクイナを指す可能性がある。Avibase ではかつてはマミジロクイナのシノニム扱いだったが現在は含まれていない。あるいはシロハラクイナと関連があったかもしれない。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 phoenicurus とされる。
-
ヒメクイナ
- 第8版学名:Zapornia pusilla (ザポルニア プスィルラ) ごく小さいクイナ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Porzana pusilla (ポルザナ プスィルラ) ごく小さいクイナ
- 第8版属名:zapornia Porzana (ベネチア名でクイナ) のアナグラム
- 第7版属名:porzana (合) Porzana ベネチア名でクイナ
- 種小名:pusilla (adj) ごく小さい (pusillus)
- 英名:Tiny Crake, IOC: Baillon's Crake (フランスの博物学者 Louis Antoine Francois Baillon に由来)
- 備考:
zapornia は発音がよくわからないが、-or- がアクセント音節と考えられる。すべて短母音であれば "ザポルニア"。
porzana も同様で "ポルザナ"。
pusilla は短母音のみで -sil- がアクセント音節 (プスィルラ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Zapornia 属。これは Porzana のアナグラム (Stephens 1824)。
Stephens (1824) の提唱時は Zapornia minuta Forster, 1817 (参考 英名 Little Craker) の用例がすでにあって Stephens (1824) もこの名称を参照して与えているが Foster の記載はコモンクイナを指しており無効とされる。早い段階からアナグラムを用いた属名が使われていたことがわかる。
属変更に伴う種小名は変化なし。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
Zapornia 属はヒメクイナ属。
6亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は基亜種 pusilla とされる。
英名変更の理由は Little Crake Zapornia parva コクイナ と紛らわしいためかも知れないが、Baillon's Crake の名称は過去から使われていた。
これは Rallus Ballino Vieillot, 1819 (参考) の記載に由来するもので、Hartert (1910-1922) p. 1829 が亜種 intermedia に含めたため現在は表面に現れなくなっている。
Yet another thread on eponyms... But this one might actually be fun!
に人名の付く鳥の英名から人名を排除した場合にどのような代替名があるか考察がある。
例えば Least Crake と付けてしまうともっと小さいクイナは存在しないのか、など議論がある。
-
コモンクイナ (第8版で検討種)
- 学名:Porzana porzana (ポルザナ ポルザナ) クイナ
- 属名:porzana (合) Porzana ベネチア名でクイナ
- 種小名:porzana (トートニム)
- 英名:Spoted Crake
- 備考:
porzana は#ヒメクイナ参照。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。第7版で使われた Porzana 属は分子遺伝学解析で単系統でないことがわかり、多くの種が Zapornia 属他に移された。
日本産とされていた種で Porzana 属にとどまるのはタイプ種のコモンクイナのみ。コモンクイナは日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では検討種 (文献で類似種との識別点の記載がない) に移動で、Porzana 属は日本産リストから消える可能性がある。
Porzana 属は Rallus Porzana Linnaeus, 1766 をもとに Vieillot (1816) が提唱。
コモンクイナはヨーロッパからモンゴルにかけて主に分布する種類で、ロシア極東にも記録がある。Porzana 属の日本鳥類目録改訂第7版での名称はヒメクイナ属であったが、これは Zapornia 属の名称となる予定のため、異なる名前が必要が必要になる。#クイナの備考に記載のリストではコモンクイナ属 (日本でも知名度がありタイプ種でもある) としてある。
和名のコモンは「小紋」とのこと。チュウクイナの別名があった (コンサイス鳥名事典)。
Hartert (1910-1922) p. 1827 によればドイツ語名 Gesprenkeltes または Tuepfelsumpfhuhn で和名とよく一致する。英名も意味が近い。OED によれば英名は 1824 年の Stephens, Shaw's General Zoology に登場するとのこと。和名は英語またはドイツ語名由来かも知れない。
-
ヒクイナ
- 第8版学名:Zapornia fusca (ザポルニア フスカ) 黒ずんだクイナ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Porzana fusca (ポルザナ フスカ) 黒ずんだクイナ
- 第8版属名:zapornia Porzana (ベネチア名でクイナ) のアナグラム
- 第7版属名:porzana (合) Porzana ベネチア名でクイナ
- 種小名:fusca (adj) 黒ずんだ (fuscus)
- 英名:Ruddy Crake, IOC: Ruddy-breasted Crake
- 備考:
zapornia, porzana は#ヒメクイナ参照。
fusca は短母音のみで冒頭にアクセント (フスカ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Zapornia 属。これは Porzana のアナグラム (Stephens 1824)。種小名は変化なし。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
4亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は erythrothorax (eruthros 赤い thorax, thorakos 胸板 Gk) 亜種ヒクイナ と phaeopyga (phaios 褐色の -pugos 腰の) リュウキュウヒクイナ とされる。
亜種ヒクイナ記載時学名 Gallinula erythrothorax Temminck & Schlegel, 1849 (原記載) 基産地日本。図版。
フランス語名 La poule d'eau a poitrine rouge (胸の赤い水の鶏) で英名は学名やフランス語名由来と考えられる。
リュウキュウヒクイナの記載時学名 Porzana phaeopyga Stejneger, 1887 (原記載) 基産地 Yayeyama Island, Riu Kiu Islands, Japan (八重山諸島)。
基亜種は記載時学名 Rallus fuscus Linnaeus, 1766 (原記載) 基産地 Philippines (フィリピン)。記載があまりにも簡単で当初はこの学名が用いられていなかったのかも知れない。
日本産のものを指す英名が現在も使われて続けているが、現在のフランス語では基亜種に相当する名称になっているなど言語による。
Temminck and Schlegel (1849) の日本でのヒクイナの記載以前にセイロン (スリランカ) でシロハラクイナが先に記載されていた (Pennant 1769)。現在のヒクイナでもフィリピンの基亜種が同じころに記載されているなど、どの地域がヨーロッパに順次知られるようになったかわかる。
かつては "くいな" (くひな) の名称はヒクイナを指す方が普通であった。使い分ける場合はナツクイナやフユクイナ。「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) を参考とした。ヒクイナを指す用例は 10 世紀中旬のものがすでに知られていた。
中西悟堂「定本・野鳥記」2 p. 100 (1940 年の記事) では "ふつうのクイナは褐色で (中略) 顔から体下面へのかけての赤栗色が特に濃いことから鳥学では「緋クイナ」と言われるが" と、若干不満げな書き方。「水鶏 (くいな) のたたき」のようにこれほど歴史と伝統のある名前を変えなくてもよいのでは、ということだろう。
中西氏の他の著作でも現在の種クイナを指して「ただクイナ」「冬クイナ」の表記を多用しており、かなり違和感を持たれていたらしいことも想像できる。古来からの季語との整合性が失われることも気にされていたのだろう。
[音声]
さまざまな音声を出す。ヒクイナ (バードリサーチ鳴き声図鑑) などを参照して声に馴染んでおくとよい。よく「クイナの叩き」と言われる音声は一般的に「さえずり」に分類される。ここにも書かれているが、カイツブリに似たギュルルルルという声も出す。この図鑑では威嚇 (あるいは警戒音) 栃木県渡良瀬 2009-05-11 の音声が参考になる。
この音声はカイツブリの「さえずり」に大変よく似ていてつい (より普通に聞く) カイツブリと判定してしまうが、特に相手が見えていない場合ヒクイナの声の可能性はないかを念頭に置くべき識別対象である。紛らわしい場合はソノグラム (*1) も併用するとよい。#シマクイナの備考も参照。
(注釈)
*1: 音声を時間軸と周波数で2次元表示したもの。スペクトル表示 (sound spectrogram, spectrograph) などとも呼ぶ。日本では先人が「ソナグラム」をよく用いていたためこちらの名称の方がよく使われるようだが、英語では sonogram あるいは sonagram で、どちらも使われている。前者の方が使用頻度が高いため、この文書ではよく使われる方の英語の綴りを反映する意味で「ソノグラム」と記す。
専門的論文でも sonogram (sonagram) は問題なく使われているので学術用語として普通に用いてよいはずである。
sonograph, sonagraph の名称もあるが、これは少し古い時期に (高価な専用機材の名称とともに) よく使われていたもの。
なお一般の英語では sonogram (こちらも sonagram の使用頻度の方が低い) は医学などの超音波検査を指すものとして使われることが多い。厳密に表現したい場合は spectrogram や spectrum (複数 spectra) を含めた名称を使うのがよいだろう (これらの表現は音響学以外でも普通に使われる Spectrogram)。
時間とともに変化する信号の2次元スペクトル表示を指す名称として、他に dynamic spectrum という表現もあり、物理や工学の専門用語として使われる。生物の音を扱う学問は生物音響学 (bioacoustics) と呼ばれる。
鳥の音声をスペクトル表示できるソフトはさまざまなものがあるが、フリーソフトウェアかつさまざまな編集作業のできるソフトとして Audacity が特にヨーロッパのバーダーによく使われている。
Raven (Lite) のように鳥の音声に特化したものではないので、最もよく見えるようにウインドウ幅を簡単に調整する機能などはないが、適切なパラメータを与えておけばほとんどの場合用が足りる。
Raven (Lite) で試された方は経験されているだろうがウインドウ幅を小さくする (時間分解能を上げる) と周波数の分解能は低下する。逆もまた真であり、スペクトルのどの部分に注目するか目的によってウインドウ幅を決めるものである。
「適切なパラメータを与えておけばほとんどの場合用が足りる」と書いたのは主にさえずりに対するもので、短時間の地鳴きの場合はウインドウ幅を小さくするのが適切、また音程の非常に低いあるいは高いものにはウインドウ幅を周波数に合わせて変更する。
時間分解能と周波数分解能の間の関係は (広義の) ハイゼンベルクの不確定性原理で決まっている。時間分解能と周波数分解能を同時に高めることは原理的にできない。つまり非常に短い音の周波数を正確に決めるのには限度がある。
少し専門的になるが、スペクトル表示を行う多くのソフトは短時間フーリエ変換 (Short-time Fourier transform, STFT) という手法を使っている。ウインドウ幅が 256, 512 のように2のべき乗になっているのはこの場合に高速に計算できる手法が知られているためである。
wikipedia 日本語版の短時間フーリエ変換
に重要な情報はほぼ含まれているので音声解析をされる方は参照されるとよい。
すなわち音声のスペクトル表示をする論文であればウインドウ幅と窓関数に何を使ったかは記述しておいた方がよい (窓関数は通常 Hanning を使っておけば十分。結果にはあまり影響はない)。
古めの出版物などに掲載されているソノグラムで信号の周波数幅が妙に広いものを時々見受けるが、これは過剰に時間分解能を高めすぎて (= ウインドウ幅を小さくし過ぎて) 周波数方向に幅ができてしまっていると思われる。
このような場合は窓関数の影響も受け、適切な窓関数を使わないと疑似的な信号も現れる (サイドローブ sidelobe)。逆に言えばこのような極端な使い方をしない場合は窓関数は結果にはあまり影響を与えない。これらの過剰に時間分解能を高めた表示を見習うべきではないし、原理や限界も知って使うのがよい。
またフーリエ変換の知識が多少あると目的信号に影響を (ほぼ) 与えないやってよい操作 (例えばハイパスフィルター high-pass filter、ローパスフィルター low-pass filter) と目的信号を変えてしまうやるべきでない操作 (ノイズ除去、ノイズリダクション noise reduction) の違いが理解できると思う。
日本の鳥声録音では先駆者の影響もあってノイズリダクションを使いすぎの場面が目立つように感じる。
海外では (少なくとも研究に使われる可能性のある録音に対して) このような編集が好ましくないことは常識となっていて、Audio preparation and upload guidelines eBird/Macaulay Library (ML) の投稿ガイドにもきちんと記載されている
(8. Avoid filters and cosmetic editing: Noise reduction and other extreme editing techniques should never be used when editing your recordings for upload to the archive)。
「人に聞いてもらうために必要」な考えや、音源として販売するにはノイズリダクションが必要なこともあるかも知れないが、一般的に使わない方がよいと考えていただいてよい。また xeno-canto などにアップロードする場合にノイズリダクションを使いたい場合は処理後のものと元音源を両方アップロードしておくとよい。研究者は必要になれば後者を使うことができる (eBird/ML ではそもそも受け付けないかも知れない)。
この eBird のガイドには Audacity の使い方 (ただし英文かスペイン語) ガイドもあるので一読されるとよい。
費用のかかるソフトを使わなくても野鳥録音の編集は十分行える。
録音には (例えばメモ程度の場合でも) できる限りリニア PCM (LPCM) 録音をすべきで (一般的には .wav 形式となる)、.mp3 形式では情報が失われる。どの程度失われるかは設定 (ビットレート) や背景音によって異なるが、現在の世界の主要音声データベースは .wav 形式に対応しているので最初から LPCM で録音し、.wav 形式でアップロードすべきである。
.mp3 形式などに変換すると例えば中心周波数に系統誤差が発生することも知られており、特に研究に用いる場合は低品質 (圧縮度が高い、背景音が大きいなど) .mp3 の使用は注意が必要である。
.mp3 形式などの不可逆的圧縮では重要でない部分の情報を捨てている。例えばバックでセミが大きく鳴いているような場合には情報がそちらに奪われてしまい、もっと低い周波数の鳥の声にわずかな情報量しか残らないことがある。LPCM で記録しておけば低い周波数の鳥の声に影響を与える不必要な高い周波数のセミの声をローパスフィルターで除去できるが .mp3 では鳥の声の部分だけを取り出しても貧弱なものになってしまう。
この点はビデオに記録された音声についても同様で、ビデオに音声も記録されているので大丈夫と考えると必ずしもそうでないこともある。ビデオを記録していても可能ならば同時に LPCM 録音をしておくこととおすすめする。
なぜ LPCM 録音が必要かは eBird/ML の Why wave (.wav) files? にも説明がある。
解析の方では STFT には限界があることもよく知られていて、古くから知られている wavelet (ウェーブレット) 変換 (有限波連を用いる) などもしばしば用いられる。#タンチョウの備考の [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] で解析例を紹介したスパースモデリングは別の考え方によるもの。
野生動物の低い音の解析には STFT の限界が著明で、Jancovich and Rogers (2024) BASSA: New software tool reveals hidden details in visualisation of low-frequency animal sounds
は wavelet 変換の一形である superlet transform で低音のソノグラムの描写能力が改善したとのこと。ただし有料ソフトの MATLAB 上での開発で誰でも手軽に使えるわけではなさそう (python や R などで開発するとソフトの進化が早すぎて研究者側のメンテナンスが大変、などの理由もあるのだろう)。
(さらに専門的になるので興味ある方以外は読み飛ばしていただいて構わない)
ソフトにはソースコードが公開されているオープン・ソースのものがあり、Audacity もそうである。
この場合は中でどのような処理が行われているか外部からも検証可能である。そうでないソフトはある意味ブラックボックスとして使うことになる。そのため自分がソフトを推奨する時はオープン・ソースのものを優先している (サンプルを紹介している R もそうである)。
世界的な音声データベース (現在では鳥以外も扱われ、生物の発する音全般を目指しているとのこと) の一つである xeno-canto はデータベース本体のソースコードを公開している GitLab xenocanto。
xeno-canto で使われているソノグラムの作成ソフトのソースコードも公開されており (GitLab soundprint/sonogen)、GitHub GStreamer のスペクトル生成機能を用いている。
プログラミングのできる人であればこれらを改良することも可能であろうし、技術継承のためにも有益であろう。
2024 年のノーベル賞を受賞したタンパク質立体構造の予測ソフト AlphaFold の第3版がオープンソースで公開されるとのこと: AI protein-prediction tool AlphaFold3 is now open source
コードは誰でもダウンロードできるが、データを用いたトレーニングの依頼は当面学術関係者に限定とのこと。
研究者にとっても喜ばしいことだろうし、多くの人がコードを研究することでコードそのものの改良もより進むだろう。
#アマツバメ備考で紹介の磁気定位に関わると考えられるタンパク質の立体構造や機能解明にも役立つだろう。
一方 AlphaFold is running out of data - so drug firms are building their own version (Nature news 2025.3.27) によれば製薬会社が情報を公開データベースに置かず囲い込みが生じているとのこと。
知的財産の考え方にも違いがあるのだろうが、少なくとも鳥の分野ではソースコードなどの公開やデータの Creative Commons (CC, リンク先は wikipedia日本語版) 扱いについてヨーロッパが一歩進んでいるように思える (画像についても CC 扱いがよく行われている)。
Movebank というドイツの Max Planck Institute of Animal Behavior がホストとなっている移動性動物の経路追跡データベースがある。多くの種類が公開されており (Data -> Explore Map -> Search で学名などを入れると検索できる)、カムチャツカのカッコウ (#カッコウの備考参照) の渡り経路も公開されている。
オホーツク海を横切ってほぼ最短経路を飛び、インド洋も少し横切っていることがわかる。
この研究は CC ライセンスが与えられていないが、他の研究では CC ライセンスのものもいくつもあり、これらは出典を明示すれば複製などの利用ができる。例えばヨーロッパハチクマではフィンランドデータの追跡測位などが CC-BY ライセンスで公開されており、誰でも解析に用いることができる。
くまたか/日本野鳥の会筑豊支部でもさまざまな情報を積極的に公開されており、大変好ましいと感じている。一段進めて CC ライセンスの導入や海外データベースへの音声登録などさらに検討をいただければと感じる。
[夜鳴く鳥の系統]
La et al. (2012) Diurnal and Nocturnal Birds Vocalize at Night: A Review
が北米の種で夜鳴くことが記録されている種の解析を行っている。クイナ類は高率だが、他の系統はどうなっているか見てみると面白いだろう (日本の種類とはだいぶ違うが)。ただし夜間の渡り途中に鳴くものも含まれているので繁殖地での夜間発声とは異なるかも。なぜ夜間に鳴くかこれまで挙げられている仮説も紹介されている。ほとんどの研究は昼行性の鳥が夜鳴く現象を取り扱っているものとのこと。
出てくる鳥の種類もヨーロッパやアメリカのスズメ目が中心なので種類は省略する。
提唱されている仮説を簡単に列挙しておくと:
・薄明時に明るくなるのに反応している
・夜は声の競争相手が少ない
・夜間の渡りの途中の声 (群れ内のコミュニケーションなど)
・昼行性の捕食者を避けるため
・ねぐらでのコミュニケーション
・なわばり防衛 (夜間も行われる)
・異性を引きつける (夜間渡るメスへの信号も考えられる)
・つがいの絆を強める (採食など他の行動の必要が少ないので夜間は都合がよい)
・生殖活動への生理的刺激を高める
・mate guarding (配偶者防衛。つがい外交尾の防止。夜間にもあるのか?)
・子供が歌を学習するため (夜に必要な積極的理由はあまりないよう)
スズメ目で夜間のプレイバック実験の結果: Buda et al. (2024) Nocturnal playback experiments: The response of two European species of birds to singing of foreign male at night
キアオジとチフチャフでは夜間のプレイバック実験で音声による反応はなく昼間とは異なっている。また夜間のプレイバックでは捕食者を引きつけたとのこと。夜間のさえずりは昼間の延長上にあるとは考えにくい。
キアオジでは夜間のプレイバックでもスピーカーへの攻撃と考えられる行動が記録されたがチフチャフでは見られなかったとのこと。夜間の捕食圧が異なっている、夜間視力の違いなどの理由が考えられる。
全般的に夜のさえずりは捕食者によって制約を受けている可能性が示唆されるとのこと。
夜鳴く鳥は捕食されにくいものが多いのか考えてみると面白いかも。
-
コウライクイナ
- 第8版学名:Zapornia paykullii (ザポルニア パイクルリイ) パイクルのクイナ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Porzana paykullii (ポルザナ パイクルリイ) パイクルのクイナ
- 第8版属名:zapornia Porzana (ベネチア名でクイナ) のアナグラム
- 第7版属名:porzana (合) Porzana ベネチア名でクイナ
- 種小名:paykullii (属) paykull の (スウエーデンの詩人で鳥類学者 Gustaf Friherre von Paykull に由来)
- 英名:Band-bellied Crake
- 備考:
zapornia, porzana は#ヒメクイナ参照。
paykullii は規則によれば -kul- がアクセント音節 (パイクルリイ)。最後は ii と音が2つ並ぶ。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Zapornia 属。これは Porzana のアナグラム (Stephens 1824)。種小名は変化なし。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
記載時学名 Rallus Paykullii Ljungh, 1813 (原記載) 基産地 Bandjarmasin, Borneo, and Batavia, Java (Avibase による)。Paykull のコレクションから記載したとのこと。
Porzana rufigenis Wallace, 1865 (参考)、Porzana mandarina Swinhoe, 1870 (参考) の記載もあった。
単形種。「世界鳥類和名辞典」(山階 1986) ではコウライヒクイナとされていた。
渡辺 (2005) Birder 19(5): 59-65 にクイナ類の解説と識別が記載されている。
先崎 (2017) Birder 31(2): 31 に 2013年5月の北海道天売島での記録例がある。
The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声) part 2 3:10 コウライクイナ Tam, zhe tajga ustupaet mesto lugam, pochti vsyu noch' naprolet slyshitsya skripuchaya drob' bol'shogo pogonysha (ほらタイガが草地に席をゆずっています。ほとんど一晩中コウライクイナのきしんだ断続音が聞かれます) (聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
-
マミジロクイナ
- 第8版学名:Poliolimnas cinereus (ポリオリムナス キネレウス) 灰白色のクイナ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Porzana cinerea (ポルザナ キネレア) 灰白色のクイナ
- 第8版属名:poliolimnas polio 灰色の (Gk) limnas クイナ < limnas 沼地の (Gk)
- 第7版属名:porzana (合) Porzana ベネチア名でクイナ
- 種小名:cinereus / cinerea (adj) 灰白色の
- 英名:White-browed Crake
- 備考:
poliolimnas は起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-lim- がアクセント音節と考えられる (ポリオリムナス)。
porzana は#ヒメクイナ参照。
cinereus/cinerea は短母音のみ (キネレウス/キネレア)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Poliolimnas 属。polio 灰色の (Gk) limnas クイナ < limnas 沼地の (Gk)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。Poliolimnas 属はマミジロクイナ属。
学名は Poliolimnas cinereusとなる (語尾が変わるので注意)。分子系統学に基づくクイナ類の分類は Kirchman et al. (2021) Phylogeny based on ultra-conserved elements clarifies the evolution of rails and allies (Ralloidea) and is the basis for a revised classification を参照。
Amaurornithini 族 Poliolimnas 属の単形属となっている。
英名は現在はシノニムとなっている学名 Porzana leucophrys Gould, 1847 (記載) 由来と考えられる [leucophrys (合) 白い眉 (leuko- (接頭辞) 白い phrydi 眉 Gk。#ミヤマシトドの種小名と同じ]。
和名もおそらく英名か学名に由来と想像できる。
Porphyrio cinereus Vieillot, 1819 の記載の方が早かったため学名が変わった。
Avibase の記述を見ると Mathews, Bds. Austr., 1, 1911 が基産地を与えているので、この時に Vieillot (1819) の記載が見つかったのかも知れない。Gould (1847) 由来の学名はおそらく長く使われていて世界の多くの言語で同じ意味が採用されている。
ロシア語では Vieillot (1819) の学名を用いたものか "灰色のクイナ" となっているが Gould (1847) 由来の別名もある。中国語でも両者の名称があり、英語にも Ashy Crake の別名がある。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)での亜種は brevipes (短い脚) で、この亜種を認めていた世界の主要リストは Peters' Check-list of the Birds の 2nd edition までのみで、一般的には単形種とされる。
この亜種は Ingram, C (1911) の記載による硫黄島のもので、英名では Iwo Jima Rail, Iwo Jima White-Browed Crake と書かれる。日本鳥類目録では亜種マミジロクイナとなる。1911 年の採集以降の確実な記録がないとのこと。マミジロクイナの絶滅 (山階鳥類研究所の解説)。
wikipedia 英語版によれば、最終観察は 1924 年 T. T. Moniyama によるものとのこと。亜種としては doubtfully valid (正統性が疑わしい) と記述されているが、世界の絶滅(亜)種一覧の項目として記載がある。
山階鳥類研究所の上記解説では島のクイナ類が絶滅しやすいことを説明している。この中でウェーククイナ Hypotaenidia wakensis 英名 Wake Island Rail (ヤンバルクイナ属) は第二次世界大戦の間接的結果により失われたことは記憶にとどめておくべきであろう (ウェーククイナの wikipedia 日本語版、英語版を参照。この歴史は世界の鳥類学の中でもよく知られている)。
雑誌 "Birder's World" 1990.12 pp. 36-40 に Craig S. Harison による "Spirits of the Pacific" のアホウドリ類の記事があり、ウェーク島のアホウドリ類も同時期に一掃されこの記事の時点で回復していないと記されていた。
Jones (1995) Bird Observations on Wake Atoll の論文が読め、かつて営巣していたコアホウドリはこの時点で営巣を試みた証拠は見つけられなかったとのこと。
Wake Atoll National Wildlife Refuge によればコアホウドリとクロアシアホウドリが近年再定着したとのこと。
-
ツルクイナ
- 学名:Gallicrex cinerea (ガルリクレックス キネレア) 灰白色のヤケイのようなクイナ
- 属名:gallicrex (合) ヤケイのようなクイナ Gallus 属 (ニワトリのもとになったセキショクヤケイなどを含む属) と Crex 属 [ウズラクイナなどを含む属 < Crex (Gk) 鳴き声由来 (コンサイス鳥名事典)] から合成された属名 (The Key to Scientific Names)
- 種小名:cinerea (adj) 灰白色の
- 英名:Water Cock, IOC: Watercock
- 備考:
gallicrex は Gallus, Crex いずれの属名も短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。gal-li-crex と分解されれば冒頭がアクセントと考えられる (ガルリクレックス)。
cinerea は短母音のみ (キネレア)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではこの学名でセイケイの和名が記されており、分布は Musashi, Owari, Nagasaki, Iriomote-shima となっていた。
セイケイは現在は別の種の和名に使われている (かつて Porphyrio porphyrio Purple Swamphen, Western Swamphen 分割されてこの学名はヨーロッパセイケイ、セイケイの名称は Porphyrio poliocephalus Grey-headed Swamphen)。確かに似ていると言われれば似ている。
単形属で単形種。
-
バン
- 学名:Gallinula chloropus (ガルリーヌラ クーロロプース) 緑色の足のクイナまたはバン
- 属名:gallinula (f) クイナまたはバン (< gallina (f) めんどり -ula (指小辞) 小さいもの)
- 種小名:chloropus (合) 緑色の足の (chloros 緑色の pous 足 Gk)
- 英名:Moorhen, IOC: Common Moorhen
- 備考:
gallinula は由来となる gallina の i が長母音 (gallus + ina で女性形を作る語尾。i が長母音)、-ula が長母音を持たないので -li- がアクセント音節となる (ガルリーヌラ)。
chloropus は由来となるギリシャ語 khloros の最初の o が長母音、-pous も長母音。-lo- がアクセント音節と考えられる (クーロロプース)。
属名は中世ラテン語でクイナまたはバン。ニワトリのような尾と立ち止まる動作から名付けられた (The Key to Scientific Names)。
5亜種あり(IOC)。日本で記録されるものは基亜種 chloropus とされる。
かつては日本の亜種は indica/indicus とされたが基亜種のシノニム扱いとなった。
この亜種の記載時学名 Gallinula chloropus var. Indicus Blyth, 1842 (記載) 基産地 Calcutta (インド)。
英国で見慣れたバンよりも小さい、それ以外の違いはほとんどない。他にもいくつか亜種の記載があったが整理されて北方のものは基亜種にまとめられた。
他の気になる亜種では orientalis が認められており記載時学名 Gallinula orientalis Horsfield, 1821 (記載)。基産地 Java。
他に lozanoi (フィリピンのルソン島)、seychellarum (インド洋のセーシェル) も記載されたが orientalis にまとめられた。
他にアフリカ南部と離島亜種がある。
Dement'ev and Gladkov (1951) では多数の亜種を認めており、日本本土からサハリンは基亜種 chloropus、琉球諸島は indica の扱いだった。
この時代にはインドから中国、台湾も含めて琉球諸島までが indica、インドネシアの島が orientalis、フィリピンが lozanoi だった。
当時は南北アメリカ大陸のものも同種扱いで、現在は南北アメリカは別種アメリカバン Gallinula galeata Common Gallinule として扱われる。
バン (鷭) の由来は中世中国語とのこと 鷭 発音 bjon (現在は fan)。鷭鳥がオオバンを指す。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 104 によればバンの由来は身近な水辺で番 (つがい) が仲良く繁殖行動する習性によるとある。日本で作られた漢字というわけではなさそうなので、中国語でも同様の解釈だったのだろうか。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では列挙された別学名から判断すると亜種 orientalis と考えていた可能性がある。
[バンのヘルパー]
井田 (1993) Birder 7(11): 36-43 に「バンのヘルパー」の記事がある。シーズン2回繁殖の場合、先に巣立った中びながほとんど子育てを行っていた時期もあったとのこと。
バンのヘルパーは世界的にも有名で Gibbons (1987) Juvenile helping in the moorhen, Gallinula chloropus
の論文もあり、若鳥がヘルパーとなっている状況は日本の記録とほぼ同じ。繁殖環境が飽和しているので若鳥が分散できないためとの解釈を行っている。
Green et al. (2016) Variation in helper effort among cooperatively breeding bird species is consistent with Hamilton's Rule
では主にスズメ目のヘルパーの統計的研究を行っているがバンも含まれている。若鳥がヘルパーとなるケースはそれほど多いわけではない模様。全体的にはハミルトンの包括血縁度理論の予想とよく整合するとのこと。
-
オオバン
- 学名:Fulica atra (フリカ アートゥラ) 黒いオオバン
- 属名:fulica (f) オオバン 語源推定は備考参照
- 種小名:atra (adj) 黒い (ater)
- 英名:Coot, IOC: Eurasian Coot
- 備考:
fulica は短母音のみで冒頭にアクセントがある (フリカ)。
atra は冒頭が長母音でアクセントがある (アートゥラ)。
fulica の語源は Pokorny によればインド・ヨーロッパ祖語の *bhel- (輝く) とのことで古高地ドイツ語で belihha (オオバン) となり、現代のドイツ語では Belche となっている。
古ギリシャ語の phalos (白) にも関係がある。
オオバンの属名由来は "輝く色" と解釈できて現代のドイツ語とも整合する模様。
fuligo (f) すす と一見似ているが、こちらはインド・ヨーロッパ祖語の *dhuh2lis 由来で *dhewh2- (風が吹く、煙) が起源とのこと。ラテン語 fumus (フームス、煙) が派生、-igo は動詞を作る語尾 (wiktionary)。fuligo の方はこれらを引き継いで冒頭が長母音。fulica は語源が違うので短母音の理解でよいのだろう。
fuligo は#キンクロハジロ、#カワビタキの学名に登場する。
一方#ハイイロヒレアシシギはオオバン由来の学名で伸ばさない。
このような違いがあり、オオバンの "フリカ" は伸ばしてはいけない。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 atra とされる。
△ ノガン目 OTIDIFORMES ノガン科 OTIDIDAE ▽
-
ノガン
- 学名:Otis tarda (オーティス タルダ) 動きの鈍いノガン
- 属名:Otis (f) ノガン
- 種小名:tarda (adj) 動きの鈍い (tardus)
- 英名:Great Bustard
- 備考:
otis は冒頭が長母音 (オーティス)。由来となるギリシャ語も同様。
「コンサイス鳥名事典」や Helm Dictionary を含むいくつかの出典で、種小名はスペイン語でノガンの意味とあるが、現在はこの意味では使われておらず avutarda の単語が使われる。
これも avis tarda で動きの鈍い (ゆっくり歩く) 鳥を意味する。古スペイン語で tarda が使われたが、これもラテン語の「遅い」に由来する (ノガンの wikipedia スペイン語版より)。このため語義は原意のラテン語を採用した。ラテン語の語源は不詳でエトルリア語が起源の可能性があるとのこと (wiktionary)。
ノガンは原記載と Linnaeus (1758) が記載した。
wiktionary の記載の範囲ではラテン語に tarda の名詞は現れないが、種小名となる以前に単独の Tarda の学名 (Linnaeus が整理する以前) でノガンを指していたため、種小名のようにラテン語形容詞の変化形とは解釈できず別言語に語源を求める必要があったものと想像できる。
何語由来かを判定することは文法上の性を決めるために必要なのではと想像する (#ツリスガラの備考参照)。
英名の Great Bustard は Little Bustard (ヒメノガン) に対応させる形になっている。
中国語では日本でトキを表す鴇の漢字が使われるが、wiktionary を見ても語源があまりはっきりしない。この漢字の鳥の部分を馬に変えた文字があって毛の (根本は赤いが) 先端が黒と白の馬を指すとのこと (現代では廃れている)。関連があるかも知れない。日本でトキに用いられた由来は不明で、和名類聚抄 (931-938) に tsuki (toki の古い形) に現れるのが最初とのこと。現在用いられる鴇 (音読み "ほう"、訓読み "つき" または "とき") の用法は 15 世紀半ばのもので別語源と考えられている。
中国語でノガンを表す鴇の漢字は面白いことに日本語でノガンモドキ (鴇擬) にも用いられる。つまり中国語のノガンの意味が日本語でも使われている ("トキモドキ" ではない)。一方の中国語ではノガンに似ているとは表現せず叫鶴が用いられている。系統的にはどちらにも関係がなかった。
日比 (2001) Birder 15(2): 62-64 によれば Otis の意味する "耳の羽" が長く伸びたノガンはインドショウノガン (現行学名で Sypheotides indicus Lesser Florican) のみとのこと。
The Key to Scientific Names でも属名由来にかかわるこの問題が紹介されており、旧世界にそのようなノガン類はいない。しかし目立った "ひげ" のある種ノガンと同定されているとのこと。
jugulo utrinque cristato (jugulo = iugulo のどから utrinque = trimque 両側に cristato 冠や羽毛などがある) (Linnaeus 1758 の記載)。
Linnaeus の Otis 属は現在同定されているものでは4種だったがインドショウノガンは含まれていなかった。もう1種 audit Arabibus: Saf-saf, l. Rhaad があるが同定できないとのこと。
(The Key to Scientific Names の rhaad の項目。アラビア語でノガン類を指すとのこと。ヒメノガンの可能性があるが生息地の記述が合わないとのこと)。
ラテン語 otis ではノガン類の一種、由来となるギリシャ語 otis はノガンを指すと解釈されており、語源はやはり耳で、ミミズク類の otos と同根とのこと (wiktionary)。
単形属。2亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは dybowskii (ポーランドの動物学者でシベリアへ流刑された Benedykt Tadeusz Dybowski に由来) とされる。
英語の bustard は古フランス語 bistarda だが、遡ればいずれも avis tarda に由来する。
ノガン科はかつて3亜科に分けられ、ノガンは Otidinae 亜科に属するとされていたが現在ではこの概念はあまり使われないよう。
かつてはツル目に含められていたが、近年の分子系統解析ではカッコウ目が最も近縁となった。
ノガンは世界各国で減少しており、人工増殖などの取り組みが行われている。
いくつかの映像を紹介しておく ドイツの事例、ザクセンのノガン保護施設、
絶滅に瀕した美 カザフスタンの事例で 12:15 あたりから人工増殖の様子、23:30 あたりから渡りの話で、越冬先の国際的な保護体制も重要である。
カザフスタン南部でのノガン放鳥の様子、
アブダビのノガン増殖施設と戻ってきたノガン。
[Otidimorphae の系統分類]
Neoaves で出現した2番めのクレードである Columbaves に含まれる (#鳥類系統樹2024参照)。
ここでは Stiller et al. (2024) の系統順に従って Boyd の分類を紹介する。
エボシドリ目の最近の分子系統研究は Perktas et al. (2020)
Phylogeography, Species Limits, Phylogeny, and Classification of the Turacos (Aves: Musophagidae) Based on Mitochondrial and Nuclear DNA Sequences がある。
エボシドリ族? Musophaginae を中心に扱ったもの。Criniferinae とノガン (コウノトリも) が近い位置にあるが Musophaginae はやや離れていて、カンムリエボシドリは中間に近い。ただし用いた遺伝子は限られたものでツルも近い位置に来てしまうため、Criniferinae と Musophaginae が結構離れている程度に見ておくのがよさそう。
ノガン目の分子系統研究は Cohen (2011) The phylogenetics, taxonomy and biogeography of African arid zone terrestrial birds: the bustards (Otididae), sandgrouse (Pteroclidae), coursers (Glareolidae) and Stone Partridge (Ptilopachus) (学位論文)。
このグループの系統研究は他系統に比べてまだあまり行われていない。
1種または少数の種しか含まない属が多いが、Cohen (2011) によれば形態的には十分違いがあって自身もよく検討したのでそれぞれ属扱いが適当とのこと。属の取り扱いによって異なる分類の扱いも紹介している。
ヒメノガン属 Tetrax などの位置づけは暫定的のようで今後変わるかも知れない (属統合など。ただかなり離れているとの認識のようなのでこの属で固定になるかも)。
全体の傾向は現れているはずなので、ノガン目の中での進化の傾向などはこのリストでほぼ理解できそう。
(エボシドリ系統)
エボシドリ目 Musophagiformes
エボシドリ科 Musophagidae: Turacos
カンムリエボシドリ族 Corythaeolinae: Great Blue Turaco
カンムリエボシドリ属 Corythaeola (アフリカ赤道部)
カンムリエボシドリ Corythaeola cristata Great Blue Turaco
ハイイロエボシドリ族? Criniferinae: Go-away-birds and Plantain-eaters
シロハラハイイロエボシドリ属 Criniferoides
シロハラハイイロエボシドリ Criniferoides leucogaster White-bellied Go-away-bird (アフリカ東部赤道部)
(ムジハイイロエボシドリ)属 Corythaixoides
ムジハイイロエボシドリ Corythaixoides concolor Grey Go-away-bird (アフリカ中央・南部)
クロガオハイイロエボシドリ Corythaixoides personatus Bare-faced Go-away-bird (アフリカ東部赤道部)
ハイイロエボシドリ属 Crinifer (アフリカ赤道部)
ハイイロエボシドリ Crinifer piscator Western Plantain-eater
ヒガシハイイロエボシドリ Crinifer zonurus Eastern Plantain-eater
エボシドリ族? Musophaginae: Turacos
ズグロエボシドリ属 Gallirex (アフリカ南東部)
ズグロエボシドリ Gallirex porphyreolophus Purple-crested Turaco
アカエリエボシドリ Gallirex johnstoni Rwenzori Turaco
ホオジロエボシドリ属 Menelikornis
ホオジロエボシドリ Menelikornis leucotisWhite-cheeked Turaco (エチオピア)
ハシブトエボシドリ属 Pseudopoetus
ハシブトエボシドリ Pseudopoetus macrorhynchus Yellow-billed Turaco (アフリカ西部赤道部)
(ムラサキエボシドリ)属 Musophaga (アフリカ赤道部)
ニシムラサキエボシドリ Musophaga violacea Violet Turaco
ムラサキエボシドリ Musophaga rossae Ross's Turaco
(アカガシラエボシドリ)属 Proturacus (アフリカ赤道部)
ニシアカガシラエボシドリ Proturacus bannermani Bannerman's Turaco
シロガシラエボシドリ Proturacus leucolophus White-crested Turaco
アカガシラエボシドリ Proturacus erythrolophus Red-crested Turaco
エボシドリ属 Tauraco (アフリカ中南部)
ハシグロエボシドリ Tauraco schuettii Black-billed Turaco
シャローエボシドリ Tauraco schalowi Schalow's Turaco
オウカンエボシドリ Tauraco hartlaubi Hartlaub's Turaco
シラガエボシドリ Tauraco ruspolii Ruspoli's Turaco
ギニアエボシドリ Tauraco persa Guinea Turaco
エボシドリ Tauraco corythaix Knysna Turaco
リビングストンエボシドリ Tauraco livingstonii Livingstone's Turaco
フィッシャーエボシドリ Tauraco fischeri Fischer's Turaco
(ノガン + カッコウ系統)
ノガン目 Otidiformes
ノガン科 Otididae: Bustards
クロハラチュウノガン属 Lissotis (アフリカ)
クロハラチュウノガン Lissotis melanogaster Black-bellied Bustard
クロビタイチュウノガン Lissotis hartlaubii Hartlaub's Bustard
アラビアオオノガン属 Ardeotis
ヌビアチュウノガン Ardeotis nuba Nubian Bustard (Neotis 属を統合)
アフリカチュウノガン Ardeotis denhami Denham's Bustard (Neotis 属を統合)
ナンアチュウノガン Ardeotis ludwigii Ludwig's Bustard (Neotis 属を統合)
チュウノガン Ardeotis heuglinii Heuglin's Bustard (Neotis 属を統合)
アラビアオオノガン Ardeotis arabs Arabian Bustard
アフリカオオノガン Ardeotis kori Kori Bustard
インドオオノガン Ardeotis nigriceps Great Indian Bustard
オーストラリアオオノガン Ardeotis australis Australian Bustard
ヒメノガン属 Tetrax
ヒメノガン Tetrax tetrax Little Bustard (ユーラシア中西部)
ノガン属 Otis
ノガン Otis tarda Great Bustard (ユーラシア)
フサエリショウノガン属 Chlamydotis (アフリカ北部)
フサエリショウノガン Chlamydotis undulata Houbara Bustard
サバクフサエリショウノガン Chlamydotis macqueenii Macqueen's Bustard
ベンガルショウノガン属 Houbaropsis
ベンガルショウノガン属 Houbaropsis bengalensis Bengal Florican (ベンガル、インドシナに局所的)
インドショウノガン属 Sypheotides
インドショウノガン Sypheotides indicus Lesser Florican (インド)
カンムリショウノガン属 Lophotis
カンムリショウノガン Lophotis ruficrista Red-crested Korhaan (アフリカ南部)
ニシカンムリショウノガン Lophotis savilei Savile's Bustard (セネガル)
キタカンムリショウノガン Lophotis gindiana Buff-crested Bustard (エチオピアからタンザニア)
ノドグロショウノガン属 Heterotetrax
カッショクショウノガン Heterotetrax humilis Little Brown Bustard (エチオピアからソマリア)
コノドグロショウノガン Heterotetrax rueppelii Rueppell's Korhaan (ナミビアからアンゴラ)
ノドグロショウノガン Heterotetrax vigorsii Karoo Korhaan (南アフリカ)
クロエリショウノガン属 Afrotis (主に南アフリカ)
ハジロクロエリショウノガン Afrotis afraoides Northern Black-Korhaan
クロエリショウノガン Afrotis afra Southern Black-Korhaan
セネガルショウノガン属 (タイプ種より) Eupodotis
アオショウノガン Eupodotis caerulescens Blue Korhaan (南アフリカ)
セネガルショウノガン Eupodotis senegalensis White-bellied Bustard
カッコウ目 Cuculiformes (亜科までリスト)
カッコウ科 Cuculidae: Cuckoos
オオハシカッコウ亜科 Crotophaginae: Anis
アメリカジカッコウ亜科 Neomorphinae: Ground-Cuckoos, Roadrunners
マダガスカルジカッコウ亜科 Couinae: Couas
バンケン亜科 Centropodinae: Coucals
カッコウ亜科 Cuculinae: Cuckoos
Musophaga の名称は Musa (Linnaeus の導入したバナナ類の属名) < mauz (アラビア語のバナナ) -phagos を食べる (Gk)。
Go-away-bird は和名では全てエボシドリの名前が付いているが英名では比較的細かく分けている。"go away" は擬声語とのこと。単独個体の音声記録を聞いてもわかりにくいが、群れの録音を聞くとなるほどそのようにも聞こえる。
捕食者さえ追い払う (猛禽類でも嫌がる声はあるのだろうか?) 程度にうるさいのだろう。
Musophaga 属のタイプ種はニシムラサキエボシドリの方になるが、名前が長いので (ムラサキエボシドリ) としておいた。
Proturacus 属のタイプ種はニシアカガシラエボシドリの方になるが、名前が長いので (アカガシラエボシドリ) としておいた。
これら2属は Tauraco 属から分離されたもの。Musophaga 属は過去にも別属だったが一度 Tauraco 属に統合され、最近の研究で復活となった。
エボシドリ類とノガン類の多くはアフリカに分布するが、我々がよく目にする名前は南アフリカ共和国で見られる種類に圧倒的に偏っている。そのため和名のベースとなった種と属のタイプ種がしばしば異なる。
エボシドリ目は圧倒的にアフリカの種類だが、北米でも古い系統の化石が見つかっている: Field and Hsiang (2018) A North American stem turaco, and the complex biogeographic history of modern birds。
古第三紀 (Paleogene period) の南北アメリカ大陸間の橋を通じて新大陸にも分散したとの考えがある (North American Gateway hypothesis)。現代の鳥類がゴンドワナ大陸で進化したとの見方に少し修正を迫り、北米が鳥類進化に与えた影響も従来考えられていたより大きい。
この研究の時代には南米に生息するツメバケイとエボシドリ目の外見的類似性が注目されていて、生物地理学的な関係も考えられていたが、[#鳥類系統樹2024] の結果では別系統となり、そこまでの類縁性はなかった。
カッコウ目、カッコウ科はかつてはホトトギス目、ホトトギス科とも呼ばれた。これは漢字表記の時代の杜鵑目、杜鵑科由来だろう。Cuculiformes, Cuculidae の由来となったカッコウに合わせてカッコウ目、カッコウ科と呼ばれるようになったと想像できる。
[インドオオノガンの移動パターン]
Khan et al. (2025) Not All Those Who Wander Are Lost: Insights Into Movement Pattern of the Great Indian Bustard in the Deccan Landscape of India
インド南西部のデカン高原地帯での研究。絶滅の恐れのある種類であり慎重な事前調査による準備を行って捕獲し、Argos/GPS の発信機を装着した。不規則な降雨によって生じる環境の利用のために放浪的に移動すると考えられるが、飛行は時に大きな移動を伴う典型的な Levy 分布に従っていた。
-
ヒメノガン
- 学名:Tetrax tetrax (テトゥラックス テトゥラックス) 狩猟鳥の類
- 属名:tetrax tetrax, tetracis 不明の狩猟鳥 < tetrax, tetragos (Gk) 食べられる狩猟鳥で確実に同定されていない (ライチョウ類かホロホロチョウの類か)。中世ラテン語で tetrex は大きいガンの一種か (The Key to Scientific Names)
- 種小名:tetrax (トートニム)
- 英名:Little Bustard
- 備考:
tetrax は起源となるギリシャ語は短母音のみで "テトゥラックス" となると考えられる。
単形属で単形種。#ノガンの備考で紹介したように系統的には比較的微妙な位置で、将来の研究で他の属と統合される可能性もあるかもしれない。現在の系統樹では ノガン属 Otis (ノガンのみ) の少し古い分岐にあたっていて、単系統性を保つためこの2種がそれぞれ別属となっている。
Coutinho Soares et al. (2025) Individual variation in migration patterns of Iberian little bustards
ヒメノガンのイベリア半島個体群の渡りの研究。66 個体で1年に渡って記録された 105 の経路を分析し、留鳥から長距離の渡りをするものまでさまざまな渡り戦略があった。同一個体は高い割合 (76%) で同一戦略を取るが、異なる戦略を用いる個体もあり好適な環境が失われつつある現状でもある程度の適応能力があると考えられるとのこと。
△ カッコウ目 CUCULIFORMES カッコウ科 CUCULIDAE ▽
-
バンケン
- 学名:Centropus bengalensis (ケントゥロプース ベンガレーンシス) ベンガルの長い後爪のある足の鳥
- 属名:centropus (合) 長い後爪のある足 (kentron 後爪 pous 足 Gk)
- 種小名:bengalensis (adj) ベンガルの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Lesser Coucal
- 備考:
centropus はは由来となるギリシャ語 kentron は短母音のみ。-pous は長母音。cen- がアクセント音節と考えられる (ケントゥロプース)。
bengalensis は地名の -ensis から長母音を採用した (ベンガレーンシス) が短音でもアクセント位置は変わらずどちらでもよい。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。6亜種あり (IOC)。日本で記録された亜種は lignator (lignatoris 木を切るもの < lignum, ligni 木) とされる。
本若 (2001) Birder 15(8): 38-39 にバンケンの日本初記録の記事がある。2001.3.13 に与那国島で記録された。
バンケンの "ケン" はトケンの "ケン" であろうことは容易に想像が付いたが、"番鵑" の表記は中国語では別称 (通常は coucal を鴉鵑 と呼ぶ。カラスのケン。色彩か声由来か?) で日本での名称とあった。探してみると宋代の出典があって 番鵑。
トケンの声が月を斜めに裂く、のような意味から始まっているので、古典由来ならばバンケンの声を当てはめたのかも (ただし出典は全く別かも知れない)。
もう一つ思いつく可能性は番の漢字が畑を耕す際に行う「番」作業で、叩叩叩 (卜卜卜) の声を農作業の音と見立てたものかも知れない。動物/番鵑を参考とした。カッコウやホトトギスがそうであったように声が農作業の目安となっていたのかも。調べてみるとホトトギスは台湾に分布せず、カッコウも事実上いないのでこの考えはよさそうに思えるが、バンケンはツツドリと同じような時期に鳴くのでホトトギスに比べると有用性は低いかも知れない。
さらに "番いをなすカッコウ" の意味でもよいかも知れない (「番い」の由来も難しいらしい)。これが一番簡単かも知れない。一人で3つも解釈を作ってしまった...。
カッコウ目は "なんとかカッコウ" の系統の和名が中心なのでいずれにしてもそのトケン版として理解してよさそう。
Maurer et al. (2011) Breaking the rules: sex roles and genetic mating system of the pheasant coucal によればキジバンケン Centropus phasianinus Pheasant Coucal ではオスはメスよりずっと小さいが子育てはほとんどオスが行う珍しい形態をとっているとのこと。
配偶形態の理論的解釈は難しいが、一妻多夫への進化の途上かあるいはかつて一妻多夫だった名残りの可能性を考えている。
バンケン類では配偶形態は多様なようで Safari and Goymann (2018) Certainty of paternity in two coucal species with divergent sex roles: the devil takes the hindmost
によればムナグロバンケン Centropus grillii Black Coucal は晩成性の鳥で唯一オスのみが子育てをするとのこと。この例ではつがい外交尾で産まれるひなは最後のひなであることであることが多く (生存率が低い)、メスが抱卵を開始するとオスがメスをつがい外交尾を阻止する能力が下がる可能性がある。
メスにとってつがい外交尾はよい遺伝子を得ることより次のつがい相手へのアピールのためか。
バンケン類はオスが子育てをする傾向があり (性比とも関係?) このような配偶様式は比較的容易に進化するのではとのこと。
-
カンムリカッコウ
- 学名:Clamator coromandus (クラーマートル コロマンドゥス) コロマンデルの大声で叫ぶ鳥
- 属名:clamator (m) 大声で叫ぶ人 (clamo (tr) 叫ぶ -tor (接尾辞) 行為者を表す)
- 種小名:coromandus (adj) インドのコロマンデル地方の
- 英名:Chestnut-winged Cuckoo
- 備考:
clamator は2つの a が長母音。語末は伸ばさない。cla-ma-tor と分解され、アクセント音節は冒頭 (クラーマートル)。clamo は母音2つとも長母音。英語の clamor は長音でないが冒頭にアクセントがある。
coromandus はおそらく短母音のみで -man- がアクセント音節と考えられる (コロマンドゥス)。
記載時学名 Cuculus coromandus Linnaeus, 1766 (原記載) 基産地 Coromandel。
Clamator 属は Kaup (1829) が提唱 記載。..., welche ich Strausskuckuk Clamator nenne, und die durch die starken Fusswurzeln und die Bildung der Nasenloecher u. sich charakterisirt とのこと。
Strausskuckuk の Strauss にはいくつかの語義がある。闘争、(花などの) 束 (英語で bunch に相当)、やぶ、ダチョウ がそれぞれ異なった意味と語源を持つ。ラテン語の clamator との直接の関連はないよう。
辞書には (花などの) 束の派生語彙に冠毛が出てくるが wiktionary で見当たらず最近はあまり使われない語義なのかも知れない。
Straussenfeder (ダチョウの羽) の wikipedia ドイツ語版にヒントがあり、18-19 世紀にダチョウの羽を帽子などの装飾に用いたものを指すとのこと。
und die durch die starken Fusswurzeln ... sich charakterisirt の部分は強力な足根と鼻孔 (スリット状) で特徴付けられる、とあるので実はダチョウの意味で用いていたかも知れない。
属名の Clamator はおそらく鳴き声由来でこのように解釈せざるを得ないが、ドイツ語名は実は "ダチョウカッコウ" の意味で、Strauss に複数の語義があるために (あるいは誤って) 冠羽と訳されたものかも知れない。
ダチョウの羽の装身具を思わせる可能性はあるが特徴にはそれを思わせる記述がない。
現在のドイツ語ではこの属を Schopfkuckucke (カンムリカッコウ) と呼んでいる。Strausskuckuk は現在ほとんど見つけることができないので古い語義で使われなくなったのかも知れない。
属記載と以下の Brisson の名称は独立したものの可能性があるが、"冠羽" と共通解釈が可能だった可能性もある。
この属はマダラカンムリカッコウ Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo 1種に対して与えられたもので、この種は冠羽が目立たないので本来の Clamator 属を何語であれ "カンムリカッコウ" と読み替えるのは無理があると言える。Great Spotted Cuckoo (Tomas Grim 2024) のような画像を見ると足が立派と言えばそうかも知れない。
Great Spotted Cuckoo (Livio Rey 2017) や Great Spotted Cuckoo (Mike "Champ" Krzychylkiewicz 2021) の写真などを見ると地上性適応のような感じ。
Hartert (1910-1922) p. 955 ではマダラカンムリカッコウの種ドイツ語名を "Haeherkuchuck" としている。Haeher は (大陸の) カケスのこと。
ユーラシア北半球のカッコウ類を見慣れて樹上性の印象を持ってしまうがカッコウ類の系統 (Otidimorphae で古い系統) は Telluraves とは違ってそこまで樹上性にはなっておらず、地上に適応している種類も多く残っていると見るべきなのだろう (#カッコウ備考 [Otidimorphae とはいったい何者?] も参照)。
他の属でもしばしばあるが、カンムリカッコウがマダラカンムリカッコウと系統上同属に分類され、最も古く命名された Clamator が適用されるだけで種の特徴と属名称は必ずしも整合しない例と言えるかも知れない。類似のケースでは#サンショウクイが好例となっている。
英語別名 Red-winged Crested Cuckoo がある。他言語でも同様の事例が複数ある。
Brisson が Le coucou hupрe de Coromandel (コロマンデルの冠のあるカッコウ) と名付けていた。Brisson はクロシロカンムリカッコウ (Jacobin Cuckoo) との類似性に気づいていて Le Jacobin huppe de Coromande (コロマンデルの冠のあるクロシロカンムリカッコウ) とも呼んでいたとのこと (wikipedia 英語版より)。
Cuckow (wikipedia 英語版の出典)。現地名で Coukeel で明らかに音声由来とのこと。
現在の Clamator 属は4種が含まれるが標準的な英名で Crested Cuckoo が入っているものはない。この属のタイプ種はアフリカのマダラカンムリカッコウ Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo。
いかにもありそうな学名 Cuculus cristatus Linnaeus, 1766 (直訳でカンムリカッコウ) は現在は Coua cristata カンムリジカッコウ、Crested Coua と別属になっている。この名称と紛らわしいのでカンムリカッコウの英名から Crested が外されたのかも。
過去の属名経緯をみると、かつて属していた Coccystes Gloger, 1842 は冠のあるものとして Coccyzus から区別されたものらしく (The Key to Scientific Names の Coccystes の項目から)、英名や和名の起源に関連した可能性がある 。
Clamator Kaup, 1829 の方が古く、属記載の当初はマダラカンムリカッコウのみを含む属だった。Oxylophus 属 (これは lophus 冠 の意味がある) が同じくマダラカンムリカッコウのみに定義されたことがある (Blasius 1862)。
おそらく古い記載文献がいつ見つかった、分類変更などの理由によって属名変更が複数回あった。一時は "カンムリカッコウ" に相当する属名も使われていたので過去の英名にはその名残りの影響もあるかも (前述のようにフランス語の名称から英語になったものと考えるのがもっともらしい)。(The Key to Scientific Names の情報を利用)。
ただし現在使われる Clamator 属の記載に "カンムリ" の意味が含まれるかどうかはかなり怪しい。
グループの中で日本で最初に記録された種としてカンムリカッコウの名称が与えられたと考えるとわかりやすい気がする (ハチクイと同様)。
単形種。
Clamator 属はすべて絶対的な (obligate) 托卵性。
(Boyd の分類による。IOC と同じ)
カッコウ科 Cuculidae: Cuckoos
カッコウ亜科 Cuculinae: Cuckoos
(カンムリカッコウ) 族 Phaenicophaeini: Malkohas, Clamator, American Cuckoos
カンムリカッコウ属 Clamator
カンムリカッコウ Clamator coromandus Chestnut-winged Cuckoo
マダラカンムリカッコウ Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo
ムナフカンムリカッコウ Clamator levaillantii Levaillant's Cuckoo
#クロシロカンムリカッコウ Clamator jacobinus Jacobin Cuckoo
マダラカンムリカッコウ Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo の托卵習性については #カッコウの備考参照。マフィア的な行動とともに、ひな (宿主の卵やひなを排除しない) が悪臭物質を出し外敵を追い払うとのこと。
カンムリカッコウのミトコンドリアゲノム解析: Zhang et al. (2025) Phylogenetic Relationship and Characterization of the Complete Mitochondrial Genome of the Cuckoo Species Clamator coromandus (Aves: Cuculidae)
この属は系統的にはリスカッコウ Piaya cayana Squirrel Cuckoo に近い結果となった。
-
オニカッコウ
- 学名:Eudynamys scolopaceus (エウドュナミュス スコロパーケウス) ヤマシギに似た色彩の大変強力な鳥
- 属名:eudynamys (合) 大変能力のある (eu (int) よい、dunamis 能力、強さ Gk) ふしょと足が特に強力と記述された (The Key to Scientific Names)
- 種小名:scolopaceus (adj) ヤマシギのような (scolopax (f) ヤマシギ -aceus (接尾辞) 〜に似た) 体全体が濃灰色と濃褐色との記述 (The Key to Scientific Names)
- 英名:Asian Koel
- 備考:
eudynamys は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-dy- がアクセント音節と推定される (エウドュナミュス)。
scolopaceus は scolopax は短母音のみ、-aceus は冒頭が長母音でアクセントがある (スコロパーケウス)。-aceus の由来は -ax (長母音。〜に傾いている) + -eus (起源を示す)。
記載時学名 Cuculus scolopaceus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Bengal。
Eudynamys 属は Vigors & Horsfield, 1827 記載。eu よい (bene) dunamis 能力 (potentia) と紹介されている。p. 304 にカッコウ科の中でも強力で、嘴、ふしょ、足ともに強力と述べられている。またこの属は東アジアに幅広く分布していると考えられるとしており、身体的にも分布的にも強力さが目立っていたよう。
Gray (1840) がタイプ種をオーストラリアオニカッコウ Eudynamys orientalis Pacific Koel に指定。オニカッコウと同種とされていた時期もあった。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。5亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。
英名の Koel の由来はヒンディー語の koyal (声から) で、Eudynamys 属などの広い種類を指す。
かつては スラウェシオニカッコウ Eudynamys melanorhynchus Black-billed Koel
オーストラリアオニカッコウ Eudynamys orientalis Pacific Koel と同種とされた。遠方からの可能性は低いだろうが古い時代の記録はこれらが別種されていないものがあるはずなので多少の注意が必要だろう。
繁殖地ではごく普通の種類で、アジアの野外映像の背景に声を頻繁に聞くことができる。慣れておけば声で当地初記録も可能かと期待しているがまだ実現していない。コウライウグイスがいろいろな声を出してやや紛らわしい。
坂梨 (2012) 熊本県熊本市におけるオニカッコウ Eudynamys scolopaceus の落鳥記録
の事例では亜種 chinensis の可能性が高いとのこと。
浜地他 (2017) 宮古諸島におけるカッコウ科鳥類2種の観察記録
ではオニカッコウは複数羽での長期滞在で繁殖の可能性もあるとのこと。
「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) にによればオニカッコウのオスは宿主のイエガラス Corvus splendens に似ていて、イエガラスがテリトリーを守ろうとしてオスのオニカッコウを追いかけ、メスはその間に托卵するという。
Nahid et al. (2021) No evidence of host-specific egg mimicry in Asian koels によればオニカッコウが宿主の卵に似せている証拠は見つからなかったとのこと。
Nahid et al. (2024) Asian koel rapidly locates host breeding in novel nest sites
によれば宿主が巣を変えた場合オニカッコウは迅速に対応するとのこと。宿主の動きをよく観察しているらしいとのこと。
オニカッコウは雑食性だが、多くの脊椎動物にとって有毒な Cascabela thevetia の実を食べるという。実には Cardenolide (ステロイド毒。メカニズムは Na/K ATPase 阻害なので #カッコウ備考の [カッコウ類の植物毒耐性?] 同様) の Thevetin A, B が含まれている。
食べても無害な種類として タイヨウチョウ科 Nectariniidae、オニカッコウ、コウラウン Pycnonotus jocosus Red-whiskered Bulbul、
マミジロヒヨドリ Pycnonotus luteolus White-browed Bulbul、シリアカヒヨドリ Pycnonotus cafer Red-vented Bulbul、
ズグロムクドリ Sturnia pagodarum Brahminy Starling、
インドハッカ Acridotheres tristis Common Myna、
インドコサイチョウ Ocyceros birostris Indian Grey-Hornbill が知られている (wikipedia 英語版)。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 96 p. 6 によればオニカッコウとオオオニカッコウ Scythrops novaehollandiae Channel-billed Cuckoo はカッコウ類の中でも例外的に果実食とのこと。wikipedia 英語版によればオオオニカッコウは世界最大の托卵種とのこと。オセアニアに生息して飛翔時の外見は猛禽類に似ており食性から fig hawk とも呼ばれるとのこと。和名はオニカッコウと巨大なカッコウの名前を付けたらもっと大きいのが存在した経緯だろうか。
これら2種はカラス類などが宿主で、カラス小目 Corvida の祖先的な形質と考えられる毒耐性とちょうど符合することになる。仮親から有毒果実を与えられても大丈夫、ということになる。
ちなみにオニカッコウは同じく植物毒耐性の可能性が考えられているコウライウグイス類にも托卵する。
カラス類は賢いはずなのに托卵を受け入れてしまうのも面白い。
また果実食は突飛に見えるが、カッコウに近い仲間でもエボシドリ類は果実食で、肉 (昆虫) 食と果実食の関係は案外相性がよいらしく、ヨタカ類似系統とアブラヨタカの関係にも見られる (追加参考: #メジロ備考の [鳥類の味覚])。
-
キジカッコウ
- 学名:Urodynamis taitensis (ウーロドュナミス タイーテーンシス) タヒチの立派な尾羽の鳥
- 属名:urodynamis (合) 立派な尾羽の (oura 尾羽 Gk と Eudynamys 属の合成。The Key to Scientific Names)
- 種小名:taitensis (adj) タヒチの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Long-tailed Koel, IOC: Pacific Long-tailed Cuckoo (14.2 まで), Long-tailed Koel (15.1)
- 備考:
urodynamis は外来語由来の合成語で発音はわからないが、Eudynamys が短母音のみ、uro- をギリシャ語由来の長母音と考え、-dy- をアクセント音節と考えれば "ウーロドュナミス"。Eudynamys 属とは尾の長さで区別できると考えた命名 (Vigors and Horsfield 1826; Salvadori 1880)。
この記述は Salvadori (1880) によるもので Salvadori が属の命名者と考えられたことがあったが、Vigors and Horsfield (1826) の用例が先にあることがわかった (The Key to Scientific Names)。
1770-1783 年に Buffon が "Coucou brun varie de noir" と記述した。当時のフランス語由来で h の音が落ちたと想像できる (Taiti の名称、ただし i の上に点を2付けた長音で英語でもしばしば同様の表記がなされる naive と同様、の旧名も使われていた)。
tahitiensis のように h を落とさない用例も多い (ハリモモチュウシャクなど)。
ここでは Taiti の長音表記、h が i に変わったものとの考えや地名の発音から長音を残す表記を採用した。
taitensis は場所を表す -ensis に長音を採用した (タイーテーンシス)。短音でもアクセント移動はないのでどちらでもよい。
属名も含め、英語式発音はかなり異なっている。
記載時学名 Cuculus taitensis Sparrman, 1787 (原記載) 基産地 No locality given; Tahiti, fixed as type locality by Rothschild and Hartert, Nov. Zool., 12, 1905, p. 258 (Avibase による)。図版。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。ニュージーランドで繁殖し太平洋離島で越冬。
キジカッコウやオニカッコウは変な名前と思われるかも知れないが、戦前の日本の鳥時代に付けられた名称。中西悟堂「定本・野鳥記 3」p. 32 でキジカッコウ (マーシャル、カロリン、パラオ)、オニカッコウ (海南島、台湾) の分布となっていた。
かつては Koel (オニカッコウ類) に分類されていたが、分子系統解析の結果カッコウ類に近いことがわかって英名も変わった。
縦縞で、英語別名に sparrow hawk, home owl などがあって少なくとも人にはタカを連想させるところがあるらしい (wikipedia 英語版など)。ニュージーランドには馴染みのハイタカがいないため入植者が似た種類を sparrow hawk と呼んだのだろうと考えるとわかりやすい。
#カッコウ備考 [カッコウのタカへの擬態] でも検討。
ニューギニアやオーストラリア沿岸部のオオオニカッコウ Scythrops novaehollandiae Channel-billed Cuckoo はこの種に系統が近いと考えられる。
ニュージーランドで繁殖し越冬のために北に渡るカッコウ類は2種で、もう1種はヨコジマテリカッコウ Chrysococcyx lucidus Shining Bronze-Cuckoo でこちらがはるかに小型 (GPS 追跡も行われている Tracking shining cuckoos)。
ニュージーランドのカッコウ類の渡りや進化は興味深いので今後の進展に注目したい。
Mystery, migration and mucous membranes: 5 curious facts about the shining cuckoo のような記事もある。心毒性のある虫を食べてもなぜ大丈夫なのかなどいろいろ疑問がある。
ニュージーランドにはハイイロオオタカ Tachyspiza novaehollandiae Grey Goshawk (オオタカの名は付くが系統は違う) が生息するので縞模様はタカへの擬態の解釈は成り立つ (隠蔽色との解説もある)。キジカッコウの容貌や音声は擬態なのか収斂進化なのか?
Gill et al. (2018) Post-mortem examinations of New Zealand birds. 2.
Long-tailed cuckoos (Eudynamys taitensis, Aves: Cuculinae)
に死体を用いた食性などの研究がある。昆虫が多くを占め、若鳥が成鳥より数か月遅れてニュージーランドを離れるのはセミなどの大型昆虫の発生に合わせているためか。トカゲ類、鳥の卵やひなも多少食べる (過去記録事例の一覧も出ている)。タカ類ではカッコウハヤブサ類 Aviceda の食性に似ている感じがする。
鳥のひなをそのまま飲み込む能力に驚いたなどの古い記載も出ている。
食性はヒジリショウビン Todiramphus sanctus Sacred Kingfisher に似ているとのこと。
カワセミ類は Telluraves でそもそも捕食性のある系統だが、キジカッコウは最初の陸鳥系統 Columbaves の Otidimorphae 系統に属するのでこの食性はもっと注目してよいだろう。
羽賀・奴賀 (2009) 千葉県銚子市におけるキジカッコウ Eudynamys taitensis の日本初記録。
-
オウチュウカッコウ (第8版で削除)
- 学名:Surniculus lugubris (スルニクールス ルーグブリス) 喪服色の (縞模様の) 不吉な/腹黒いカッコウ
- 属名:surniculus (合) 不吉な/腹黒いカッコウ フクロウを意味する属名 Surnia (不吉な) の意味と Cuculus 属から合成、またはフランス語語義から (備考参照)
- 種小名:lugubris (adj) 悲しげな、喪服色の、不気味な
- 英名:(Drongo Cuckoo), IOC: Square-tailed Drongo-Cuckoo
- 備考:
surniculus は Surnia はギリシャ語 surnion 由来とされており短母音のみ。Cuculus は中央の u が長母音のためこの音は保存されると考えられる。アクセント位置も同じ (スルニクールス)。
ラテン語指小辞の -ulus は短母音で一般によく現れる語尾の -ulus は一般的には長く読まない (#キクイタダキなどが例)。
"尾" に関連して日本語読みで "クールス" と長音になる学名が他に多数あるが、Surniculus は文字も違いカッコウ由来。
Lesson (1830) の設けた属。記載。フランス語名では属総称が surnicous だった。フランス語で sournois が陰険な、腹黒いなど。この単語は古く遡ると古プロヴァンス語 (Old Occitan) の sorn (黒い) とのこと (wiktionary)。
surniculus の語源とされる Surnia とは語源が異なるので、Lesson (1830) はフランス語で音の一致する単語と一種の語呂合わせを行ったのかも。フランス語語義を優先すれば "腹黒いカッコウ" などの訳も考えられる。色彩はこちらが合っているかも知れない。
Gray (1855) がタイプ種をオオチュウカッコウ (当時はまだ分離されていなかった) と定めた (The Key to Scientific Names)。
lugubris は冒頭が長母音。lu-gu-bris と分割され冒頭にアクセントがある (ルーグブリス)。
和名は英名そのままのよう。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。かつてはエンビオウチュウカッコウ Surniculus dicruroides Fork-tailed Drongo-cuckoo の亜種とされていたが、形態や音声の違いから別種となった。
lugubris の意味はほぼ黒いヒメオウチュウ Dicrurus aeneus Bronzed Drongo に比べて白い縞などが目立つことを意味したのではと考察した (#ヤマセミの備考参照)。全面の黒さを意識させるだろう「喪服色の」に加えてこの解釈を学名訳のかっこ内に追記した。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。かっこ内の英名は分離前のもの。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)で種の分割に伴って削除とのこと。
国内記録は古いものが多く、2種に分割後のどちらの種に該当するのか明確な判断の示された記録がないためではないかと想像するが詳しいことは不明。海外データベースでも過去記録の扱いが問題となった種類。
改めて確実な日本初記録と認定できる報告論文を出して欲しい意味と考えた。
形態はオウチュウに似ているが、ちょうどジュウイチがタカに似ているように托卵に有利に働くとの説がある。
Thorogood and Davies (2013) (#カッコウの備考参照) によれば、オオチュウカッコウ類はオオチュウ類に托卵すると考えられていたことがあったが実際にはあまり托卵せず、攻撃的なオオチュウ類を模して宿主を脅しているらしい (Johnsgard 1997)。
「動物たちの地球 鳥類 I 10 カッコウ・ホトトギス・エボシドリほか」(週刊朝日百科 朝日新聞社 1991) p. (6) 310 では仮親に似た形態や色彩をし、なわばりをもった仮親がこの種のオスを侵入者として追い払っている間に、メスが托卵を成功させるとある (丸武志解説)。
鳥の長い尾は性選択が考えられがちだが他の可能性もある。航空力学的なもの、捕食者に対する信号など。不安定なアシの上で採食時のバランスに役立っていると考えられるケースもある。
Are long tails all about sex? (Zhou 2023)。論文は Zhou et al. (2023) Functions of avian elongated tails, with suggestions for future studies。
性選択を実証するために尾の長さを人工操作した古典的実験: Andersson (1982)
Female choice selects for extreme tail length in a widowbird (Nature論文へのリンク)。
扱われている種はコクホウジャク Euplectes progne Long-tailed Widowbird。
「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 118 ではオドリホウオウ Euplectes jacksoni Jackson's Widowbird となっている。別のページにディスプレイの写真があるがあまりにも雌雄差が著しく同じ種に見えない。wikipedia 英語版では前者の種に記述されている。
長い尾と赤いパッチ (epaulette 肩章) があり、Andersson (1994) "Sexual Selection" (Princeton University Press) はコクホウジャクでは尾の長さが、アカエリホウオウ Euplectes ardens では赤色が性選択要素と考えたが、
Pryke et al. (2001) Sexual Selection of Multiple Handicaps in The Red-Collared Widowbird: Female Choice of Tail Length but not Carotenoid Display
(Andersson も著者に含まれる) によればアカエリホウオウでも長い尾が重要で、カロテノイド色素が性選択に働いている証拠は得られなかったとのこと。このぐらい派手な違いがある種類でないと実験してもなかなか有意な結果にならないかも (出典情報など wikipedia 英語版より)。
いつのことかすでに調べられなくなっているのだが、20 年ぐらい前? に京都大学の生物の入試問題でこれが取り上げられたことがあった。振り返ってみるとこの時代ぐらいから分子生物学が急進展して高校教育にも大幅に取り入れられ、理科の科目の中でも生物の難易度が一番上がったような気がする。かなり昔には生物は履修していなくてもそこそこ解けてしまうようなのどかな科目だったような気がするのだが...。
-
オオジュウイチ
- 学名:Hierococcyx sparverioides (ヒエロコッキュクス スパルウェリオイーデース) ハイタカに似たタカのようなカッコウ
- 属名:hierococcyx (m) タカのようなカッコウ ヒエロ王 (hiero (m) ヒエロ王、転じて hierakos タカ coccyx (m) カッコウ)
- 種小名:sparverioides (adj) sparverius ハイタカ < スズメのようなタカ -oides (接尾辞) 〜に似た
- 英名:Large Hawk-Cuckoo
- 備考:
hierococcyx は#ジュウイチ参照。
sparverioides は sparverius は短母音のみ (単独で読む場合は e は伸ばしてもよい)。-oides がギリシャ語由来で i, e ともに長母音で i にアクセントがある (スパルウェリオイーデース)。
記載時学名 Cuculus sparverioides Vigors, 1832 (原記載) 基産地 Himalayas。
Catesby (1731) によるアメリカチョウゲンボウの種小名 sparverius「小さなタカ」にも現れるが、オオジュウイチの分布を考えると sparverius = ハイタカ として用いたものと考えられる。"タカのような" カッコウ類の形容は学名にもっと多く現れてもよさそうだが意外に少ない。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも和名なしで載せられていた。場所は日本とあるだけで詳細不明。別学名に挙げられている Cuculus strenuus Gould, 1856 は基産地マニラとのこと (資料)。
[Hierococcyx (ジュウイチ) 属の系統分類]
順序は Boyd による。
カッコウ科 Cuculidae: Cuckoos
カッコウ亜科 Cuculinae: Cuckoos
カッコウ族 Cuculini: Old World Parasitic Cuckoos
ジュウイチ属 Hierococcyx
(系統 1)
チャイロジュウイチ Hierococcyx vagans Moustached Hawk-Cuckoo (マレー半島、ジャワ島、ボルネオ島など。留鳥)
(系統 2)
クロジュウイチ Hierococcyx bocki Dark Hawk-Cuckoo (マレー半島、ジャワ島、ボルネオ島の主に標高の高いところ)
オオジュウイチ Hierococcyx sparverioides Large Hawk-Cuckoo (中国からネパール周辺まで夏鳥。東南・南アジアで越冬)
ハイタカジュウイチ Hierococcyx varius Common Hawk-Cuckoo (インド、バングラデシュ。留鳥)
(系統 3)
ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus Northern Hawk-Cuckoo / Rufous Hawk-Cuckoo (ロシア極東部・日本・中国の主に東北部で夏鳥)
フィリピンジュウイチ Hierococcyx pectoralis Philippine Hawk-Cuckoo (フィリピン)
マレーシアジュウイチ Hierococcyx fugax Malaysian Hawk-Cuckoo (マレー半島、ジャワ島、ボルネオ島。留鳥)
インドシナジュウイチ Hierococcyx nisicolor Hodgson's Hawk-Cuckoo (中国南部、インドシナ半島北部から西部の一部で夏鳥)
わずかな順序の違いがあるが IOC でも同じ。系統的にはチャイロジュウイチが古い分岐で、他は2系統に分かれる。クロジュウイチとジュウイチがそれぞれの系統の中で最も古い分岐になる。
カッコウ類はそれほど詳細な分子系統研究がなされていないようで、ジュウイチ属については現在でも Sorenson and Payne (2005) "Molecular systematics: cuckoo phylogeny inferred from mitochondrial DNA sequences" in Bird Families of the World: Cuckoos が使われている模様。
属レベルの系統樹は Krueger et al. (2009) Does coevolution promote species richness in parasitic cuckoos? で見られる。
#カッコウ備考で紹介の Thorogood and Davies (2013) Hawk mimicry and the evolution of polymorphic cuckoos
でカッコウ亜科の系統樹が見られる。
チャイロジュウイチはジュウイチの音声とは少し異なるが2音のパターンは似ている。また繰り返し音を高めてゆく音声がある (alarming song とも呼ばれ、ジュウイチの音声の原型かも?) 点は似ているが音程はジュウイチよりだいぶ低い。宿主はハシブトムジチメドリ Malacocincla abbotti Abbott's Babbler と チャバネアカメヒタキ Philentoma pyrhoptera Rufous-winged Philentoma が記述されている。
チャバネアカメヒタキはオスの上半身が青く翼から尾は褐色でオオハシモズ科 (生物地理学的に別とされることもある。#モリツバメの備考参照)。日本の鳥ではモリツバメに近い系統。
クロジュウイチはかつてオオジュウイチと同種とされた。
オオジュウイチの擬態相手は wikipedia 英語版には書いてないが、ハイタカジュウイチ同様にタカサゴダカを想定してもよさそうに見える。鳴き声はハイタカジュウイチ (あるいはジュウイチ) のようにピッチを上げて終わらないとある。音声は反復が長めだが単純で、それほどタカの声は似ていないように聞こえる。
宿主はチメドリ科やソウシチョウ科が多いとのことだが他にも数多く知られている (wikipedia 英語版に 2003 年文献に基づくリストあり)。
Yang et al. (2015) Coevolution between the large hawk-cuckoo (Cuculus sparverioides) and its two sympatric Leiothrichidae hosts: evidence for recent expansion and switch in host use?
にもヒゲチメドリ Pterorhinus lanceolatus Chinese Babax、カオジロガビチョウ Pterorhinus sannio White-browed Laughingthrush への托卵の研究があり (いずれの宿主も学名が変わっており、属統合が行われた模様)、
ヒゲチメドリの卵の色はあまり似ていないので最近宿主の範囲を広げたのではとの考察がある。
ハイタカジュウイチはタカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia Shikra への擬態が顕著とのこと。鳴き声から brainfever bird と呼ばれる ("brain-fever" と聞きなす。日本のジュウイチのようにピッチを上げて終わるとのこと)
主な宿主はツチイロヤブチメドリ Argya striata Jungle Babbler と キバシヤブチメドリ Argya affinis Yellow-billed Babbler とのこと (旧 Turdoides 属より分離)。宿主はほぼこの属に限られるとのこと。いずれも色彩は地味な種類 (wikipeida 英語版より)。
タカサゴダカの声が似ているか確認してみたところ、それなりに近いジュウイチ類に近いタイプの音声も記録されている。日本では最も近縁のツミとは少し違う感じがする。
ジュウイチ以降の4種はかつて同種とされていたものが分離されたもの。
マレーシアジュウイチの宿主としてアカハラシキチョウ Copsychus malabaricus White-rumped Shama (サメビタキ亜科? Muscicapinae シキチョウ族? Copsychini) と ハイガシラヒタキ Culicicapa ceylonensis Grey-headed Canary-Flycatcher (センニョヒタキ科 Stenostiridae、カラ類に近い) が挙げられている (wikipeida 英語版より)。
アカハラシキチョウのオスは上半身が黒っぽい青。ハイガシラヒタキのオスも頭に青みがある。
タカサゴダカはマレー半島の北部に分布するのみなので、ジャワ島、ボルネオ島、フィリピンなど島しょ部での擬態は別のタカを考える必要がある。ミナミツミ Tachyspiza virgata Besra は有力候補だろう。ジャワ島、ボルネオ島では主に標高の高いところに分布するのでマレーシアジュウイチでは少し合わないところがあるかも知れない。
Besra (Birds of Thailand: Siam Avifauna) と Malaysian Hawk Cuckoo (Cuculus fugax)
確かに似ている。
ジュウイチの擬態相手のタカは日本ではツミでよいのだろう。これらのジュウイチ類縁種が多分タカに擬態していることは、縞模様のある他の托卵性カッコウ類同様宿主を怖がらせる意味があるのだろう。
間接的だが日本のジュウイチの宿主もツミを恐れている証拠になるだろうか。
「決定版 日本の野鳥 650」(真木広造写真; 大西敏一, 五百澤日丸解説 平凡社 2014) では「他のカッコウ類よりもツミやハイタカの雄に似ている」とある。ジュウイチの系統が違っていること、ジュウイチ類 (系統 3) の主な相棒のタカも現在の分類では Tachyspiza 属となる違いが現れているのだろう。
ツミは西日本では関東ほど馴染みの繁殖種ではないし、ハイタカも北方が多い。ジュウイチの国内分布も東日本が多いようだがツミの分布と関係があるだろうか。
-
ジュウイチ
- 学名:Hierococcyx hyperythrus (ヒエロコッキュクス ヒュペリュトゥルス) 腹が赤いタカのようなカッコウ
- 属名:hierococcyx (m) タカのようなカッコウ ヒエロ王 (hiero (m) ヒエロ王、転じて hierakos タカ coccyx (m) カッコウ)
- 種小名:hyperythrus (合) 下が赤い (hyp- (接頭辞) 下の erythros 赤い Gk)
- 英名:(Hodgson's Hawk Cuckoo), IOC: Rufous Hawk-Cuckoo 13.2, 14.1 では Northern Hawk-Cuckoo
- 備考:
hierococcyx は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-coc- がアクセント音節と考えられる (ヒエロコッキュクス)。
属記載は Mueller (1842) Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen。オランダ語で havikkockoeken (タカのカッコウ = 英名の Hawk-Cuckoo そのまま) となっている。
当時はまだ分離されていなかったがそれまでの名称でジャワ島産 Cuculus fugax をタイプ種と Gray (1855) が判定 (The Key to Scientific Names)。リストの中で最初に現れた種。現在継承している種はマレーシアジュウイチ。
hyperythrus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-ryth- がアクセント音節と考えられる (ヒュペリュトゥルス)。
fugax 時代の読み方は "フガークス"。-ax (〜に傾いている) が長母音のため。原意は "逃げる性質のある"。
旧英名の由来は英国博物学者 Brian Houghton Hodgson。この英名は現在インドシナジュウイチ Hierococcyx nisicolor に対して使われ、ジュウイチの現在の通常の英名は Rufous Hawk-Cuckoo または Northern Hawk-Cuckoo。
英名がまだ統合されていないようでリストにより両方が使われている。
かつての学名は Cuculus fugax (fugax は「逃げ足の早い」; 音楽のフーガも同根で「逃げ去る旋律を追うように奏される」のような比喩も使われる) だった。fugio (逃げる) 由来。この学名は意味がわかりやすかった。英語の flee, fly の語源とは関係がないが、物理学用語に fugacity の概念がある。
分割されていずれも単形種となった。
hyperythrus の 原記載。
現在種小名 fugax を継承しているものはマレーシアジュウイチ Hierococcyx fugax (英名 Malaysian Hawk-Cuckoo)。
ジュウイチの和名が鳴き声由来であることは有名だが、ジュウイチの完全なさえずりはジュウイチ、ジュウイチ...とトーンを上げてゆき、ピピピピ...と鳴いて終わる。
もと Hodgson's Hawk Cuckoo に分類されていたジュウイチ類は同様のパターンで鳴くが (音程などは異なる)、フィリピンジュウイチ Hierococcyx pectoralis (英名 Philippine Hawk-Cuckoo) のみは「ジュウイチ」の部分は2音ではなく、ホトトギスのような複数音からなる。
英語の Hawk-Cuckoo は現在の属名 Hierococcyx の意味とよく対応しているように見えるが英名の付いた時期はまだ Cuculus 属だった。他言語では十分多彩でドイツ語 Fluchtkuckuck と逃走 (ラテン語 fugax に対応)、マレーシアの地名を付けたもの、スロバキア語やウクライナ語など「翼の広い」などいろいろある。
オランダ語は Maleise Sperwerkoekoek、スウェーデン語 hokgok (hok タカ gok カッコウ) などは英語に合わせている。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" に他種と同種と思われる時代のいくつかの学名が出ていて、Cuculus nisicolor Blyth, 1843 が少し面白い。nis- は Nisus で "ハイタカに似た色の" の意味。現在はインドシナジュウイチ Hierococcyx nisicolor と分離される。
Hartert (1910-1922) p. 953 は hyperythrus をシノニムと考え、日本のジュウイチをより記載の早いこの亜種 (当時の学名で Cuculus fugax nisicolor) に分類していた。
類縁種との音声比較も述べられているが録音して分析することまでできなかった当時では記述そのものも難しかったよう。
叶内 (2002) Birder 16(6): 99-106 でジュウイチの幼鳥と言われる腹部に横縞のある個体はメスの赤色タイプではないかと提案している (p. 103) 上面に赤色見があるとのこと (飛翔写真あり。下面は見えない)。
[ジュウイチのひなの分身の術]
Tanaka and Ueda (2005) ジュウイチのひなが口の黄色と翼角の黄色を用いた視覚刺激によって宿主から多くの餌を得ている有名な Science 論文へのリンク: Horsfield's Hawk-Cuckoo Nestlings Simulate Multiple Gapes for Begging。
そして Tanaka et al. (2005) Yellow wing-patch of a nestling Horsfield's hawk cuckoo Cuculus fugax induces miscognition by hosts: mimicking a gape?の研究がある。
田中啓太「ジュウイチのヒナの騙し戦略と感覚生態学」in 上田恵介(編)「野外鳥類学を楽しむ」(海游舎 2016) 4章に苦労話なども詳しく述べられている。
さらに同書 13 章に「テリカッコウとその宿主の托卵を巡る攻防」(佐藤望) がある。
Lotem (1993) Learning to recognize nestlings is maladaptive for cuckoo Cuculus canorus hosts (論文サイト)
にかかわる研究もある (p. 246)。「なぜホストはカッコウの卵は拒否するのに,自種のヒナと外観が全く異なるカッコウのヒナを排除しないのか」についてのオリジナルのアイデアは「ホスト親がヒナを識別するのは学習によるしかない。卵なら托卵されていても自分の卵を見る機会が必ずあるが、
カッコウのヒナはホストの卵を排除してしまうので托卵されていると自分のヒナを学習できずにカッコウのヒナを自種のヒナと誤学習してしまうリスクがある。そしてこの誤学習は生涯適応度をゼロにしてしまうほどコストが大きい。だからホストはそもそも学習してヒナ排除しようとしない方が合理的なのだ」
「行動・生態の進化」(岩波書店 2006) で該当する解説が pp. 201-203 にある。
オーストラリアでテリカッコウ類の托卵に対して卵排除せずにヒナ排除するホスト種
[Sato et al. (2010) Evicting cuckoo nestlings from the nest: a new anti-parasitism behaviour]
とこれに対抗するテリカッコウ類のヒナ擬態 [Sato et al. (2015) Nestling polymorphism in a cuckoo-host system] が見つかったことで再考が必要になったとのこと
(「Cuckoo」 "shorebird 進化心理学中心の書評など" の解説より)。詳しくはこのページか書物「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」pp. 191-198 をお読みいただきたい。
この本の pp. 197-198 には Lotem (1993) の理論的解釈に反してオーストラリアの宿主で托卵ひなの見分けが進化した理由として、渡り鳥の宿主では繁殖期間にゆとりがなくやり直しが行いにくいので、見分けて放棄することはリスクが大きいことや、
ルリオーストラリアムシクイ Malurus cyaneus Superb Fairywren は寿命が長いのでリスクの大きい行動も取れることを挙げている。
オーストラリアのスズメ目の寿命の長さについては #ミサゴ備考の Tim Low "Where Song Began" (2014) の解説も参照。その要因の一つとして挙げられる「北半球の生存条件の過酷さ」には北半球には小鳥食のタカの種類が多いことも挙げられるだろう (小鳥食のタカがアフリカやユーラシアから進化して適応放散したためオーストラリアには少ない)。
「鳥の行動生態学」第7章「騙しを見破るテクニック 卵の基準、雛の基準」江口和洋 (京都大学学術出版会 2016)
「視覚の認知生理学」第4章「色を操る悪魔の子 - 托卵鳥ジュウイチの雛: - 鳥類における色を用いたコミュニケーションと、寄生者による搾取」種生物学会編 (文一総合出版 2014)
でも日本語解説が読めるとのこと (いずれの本も持っていないのでタイトルのみ紹介しておく)。
Tanaka (2015) A colour to birds and to humans: why is it so different? 英文総説。
Grim et al. (2008) Wing-shaking and wing-patch as nestling begging strategies: their importance and evolutionary origins
はジュウイチのひなのシグナル進化を考えていて、餌をねだる行動は晩成性の鳥では普遍的にみられるもので、それに対する宿主の反応を引き出しジュウイチのパッチはそれを増強する効果があって進化したと考えている。
「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」p. 206 ではジュウイチでひなが何羽もいるようなトリックを音声よりも視覚刺激で行うのは、宿主の巣 (地上性) が音から位置を突き止める捕食者に特に弱いためとの解釈が紹介されている。
同書 pp. 208-209 ではカッコウでは巣内ひなでも猛禽類に似た防御を行うとのことで、口内のオレンジ色はこれに役立つ可能性が挙げられている (猛禽類の足はなぜ黄色いのか: [#鳥類系統樹2024]にある)。
黄色を認識できる捕食者 (主に鳥か霊長類?) に有効なのだろう。
Jenner (1788) XIV. Observation on the natural history of the cuckoo. By Mr. Edward Jenner. In a letter to John Hunter, Esq. F. R. S. が出典とのこと。
またカッコウのひなに触れると悪臭ある茶色い液体の糞を排泄するという。
[分身の術の2例目]
ジュウイチのひな類似の2例目があるとのこと: Luo et al. (2019)
Novel instance of brood parasitic cuckoo nestlings using bright yellow patches to mimic gapes of host nestlings
インドシナジュウイチ Hierococcyx nisicolor Hodgson's Hawk-Cuckoo による コチャバラオオルリ Niltava sundara Rufous-bellied Niltava への托卵。これぐらい系統が近いと同じような習性があっても不思議でなさそう。2種みつかると解釈もしてみたくなる。
コチャバラオオルリではひなの口内は明るい黄色とのこと。反射スペクトルまで出ていないのでルリビタキのひなとどの程度違うのかわからないが
(#カッコウの備考に Tanaka et al. (2011) Rethinking visual supernormal stimuli in cuckoos: visual modeling of host and parasite signals へのリンクあり)、ジュウイチ系統は熱帯の種類が中心で、チャバラオオルリ類などがこの系統の本来宿主で、たとえばジュウイチのひなの口内もそれに似せている可能性も気になった。
系統分類 (#オオジュウイチの備考) のところでも旧ジュウイチから4種に分離されたものでは青い部分のある鳥の宿主がよく現れる感じがする。
チャイロジュウイチでも青い部分のある鳥への托卵があるが、狭義ジュウイチ類 (系統 3) 以外の系統はチメドリ類など主に地味な鳥を托卵相手に選んでいる模様。狭義ジュウイチ類 (系統 3) で宿主を地上営巣性の青い鳥に広げて新たな分野に進出したのかも知れない。
これには短い波長を一層好むなど宿主側の色彩感覚も関係しているかも知れない (オプシン遺伝子の系統解析をすればわかるかも?)。
宿主の系統を考えるとオオルリ系統の方がルリビタキより一層ジュウイチ系統に向いた宿主の可能性があるかも知れない。ルリビタキやコルリは巻き添え (笑) ? もっとも卵の色の類似性から逆かも知れない。
ジュウイチがなぜ青い鳥に托卵するのか (最も適した宿主に似たものを選んでいる?)、この系統を考えると理解できる気もする。これら青い鳥が卵識別能力を進化させていない (かどうか知らないが) 理由も何かあるのだろう (留鳥の方が卵識別能力を進化させやすい理由は [ジュウイチのひなの分身の術] のように提案されているが、ここでも当てはまるのかも)。
熱帯の青い鳥グループからオオルリが進化して渡るようになったものに合わせて渡るようになったのがジュウイチ? (ほんとうか?)。#オオルリ備考の [オオルリはなぜ青い] も考えるとオオルリ系統は紫外線シグナルに特に感受性が高く進化していて、狭義ジュウイチ類はそれに特に適応したシグナルを発しているとか (このあたりになると妄想レベルだが...)。
[オオルリはなぜ青い] で検討したように、小鳥食のタカ類が適応放散した結果、それに対応して熱帯スズメ目の青い形質が選抜されたりカッコウ類のタカ類、特に Tachyspiza 属 (ユーラシアでは主に熱帯から温帯) や狭義 Accipiter 属 (ユーラシアでは北方から温帯) への擬態が進化した可能性が考えられるが、
カッコウ類の分岐年代はタカ類ほと明らかでなくまだ議論が難しいかも知れない。Tachyspiza 属と Accipiter 属の共通祖先で 2200 万年前ぐらい [Catanach et al. (2024) の年代による]。
Tachyspiza 属がアジアに分布を広げたのが 1500-1000 万年前ぐらいと考えられるので、カッコウ類のうち最も新しい2属 (カッコウ属 Cuculus + ジュウイチ属 Hierococcyx) が特にタカ類に似ていることと対応しているようで興味深い
[Thorogood and Davies (2013) Hawk mimicry and the evolution of polymorphic cuckoos (#カッコウの備考)]。
小鳥食のタカ類が生じたことでスズメ目がタカ類への警戒を強め、その結果カッコウ類の托卵戦略に有利に働いたならばタカがカッコウ類を托卵への進化を推し進めたのかも知れない。年代考証などは定かでないがタカがカッコウを生んだ?? (古い時代にはカッコウは冬にはタカに変わるとされていたが、実は結構関係があるのかも知れない)。
古い時代のカッコウ類 (エボシドリ目、ノガン目 とともに Otidimorphae に属する) はタカに似た生態を持つ捕食者だった可能性も考えられ (#カッコウ備考の [カッコウ類の足と近縁系統])、
趾の立派な爪を持たないカッコウ類は新しく現れたタカ類に地位を奪われたかも知れない。捕食者だった時代の隠蔽色の基本的な祖先形質が引き継がれてタカに似た模様が出しやすいとか (森林での捕食者だった時代は縞模様だったとか...ほんとうか??)。続きは#カッコウ備考 [カッコウのタカへの擬態] へ。
-
ホトトギス
- 学名:Cuculus poliocephalus (ククールス ポリオケパルス) 灰色の頭のカッコウ
- 属名:cuculus (m) カッコウ
- 種小名:poliocephalus (合) 灰色の頭の (polio- (接頭辞) 灰白色の kephalos 頭 Gk)
- 英名:IOC: Lesser Cuckoo
- 備考:
cuculus は#カッコウ参照。
poliocephalus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-ce- がアクセント音節と考えられる (ポリオケパルス)。
記載時学名 Cuculus poliocephalus Latham, 1790 (原記載) 基産地 India。Grey-headed Cuckow の英名があり、記載時点では学名と英名は同じ意味だった。
単形種。
世界の多くの言語で英語と同様に小さいカッコウの名前になっている。中国語も同様。ドイツ語では比較的珍しく小さいの意味は含まれておらず Gackelkuckuck (声由来) または Roetelkuckuck (色彩由来)。
英語旧名の Little Cuckoo は現在は南米からパナマのヒメリスカッコウ Coccycua minuta に使われる (我々の想像するカッコウとは似ていない)。
Horsefield and Moore (1856-1858) A catalogue of the birds in the Museum of the Honorable East India Company に当時の英名 Small Himalayan Cuckoo (Gray) が載っており、この英名が由来となっているかも。この small は当時の学名で Cuculus himalayanus Vigors (おそらく種の特定が困難なため現在使われていない) に対するもので、現在の名称で考えるとヒマラヤツツドリ Cuculus saturatus に対応する。
英名の lesser の由来は(ヒマラヤ)ツツドリに比べて小さいの意味だった可能性がある。ヒマラヤ地域にカッコウ類が2種 (+ 現地でよく知られていたセグロカッコウ) いてそのうち小さい方の名称だったと想像できる。
Latham (1790) 当時はカッコウ類が現在よりも広義に扱われており当時の学名で Cuculus pyrrhocephalus 当時の英名で Red-headed Cuckow (同文献 p. 222) があり、あまり一貫性はないがあるいは対比的に色彩の特徴をもとに名付けたものと想像できる。この種は現在はアカガオバンケンモドキ Phaenicophaeus pyrrhocephalus Red-faced Malkoha。
これに比べれば灰色とも言えるが、あまりよい学名ではなかったようで英名もあまり使われた形跡がない。
Hartert (1910-1922) p. 951 は Cuculus intermedius Vahl, 1789 (参考 1, 2 基産地インドの Tranquebar)
が疑いなくこの種に同定できるとしていた。このことは Bianford が 1893 年に発表したが2年後には ? を付けていたとのこと。
Hartert はこの記載に先取権を認めた学名としていた。しかしこの文献の発見年代が遅く、Cuculus poliocephalus Latham, 1790 がすでに使われていたことや Vahl の記載の有効性などもおそらく議論になって現在の学名に至ったものと想像できる。
もし Cuculus intermedius の学名が採用されていれば英名は Intermediate Cuckoo になっていたのかも (?)。
Hartert (1910-1922) には音声の記述もあり、他のカッコウ属とは違って6またはそれ以上の分離された音からなり "音楽的でない" と記述していた (ヨーロッパでカッコウのみ聞き慣れているとそのように聞こえるのだろう。日本人は好んでいたようだが音楽的と聞いていたのだろうか)。
夜でさえ鳴くとある (ヨーロッパからインドに渡った人たちからあまり好感を持たれていなかったらしい。おそらく耳障りな声で、故郷に戻って馴染みのカッコウの声を聞きたかったのではないだろうか)。中国語では tien-teng-tschao-tschae-ketsao と聞きなし、"ランプを点けて (体の) ノミを探せ" の意味とのこと。マレー語では音声から Kaonkaonkafotrae と呼ぶとのこと。
東洋のカッコウ類の記述には音声も結構現れるので過去の博物学者が音声に注目しなかったわけではなさそう。音声を学名にするのは難しいので形態的記述を優先したものと想像できる。フクロウ類とは違って現地名があまり付けられていないのは興味深い。現地の人はフクロウ類の方をよく見分けて名前も付けていたがカッコウ類は見かけで区別できなかった (例えば現地の人に標本を見せても名前がわからないなど) のかも知れない。
Golosa pits v prirode の 5-2 では Ee krik mestnye zhiteli peredayut slovami: vot-tut-to-ti-tyu-khe (地元の住民はホトトギスの声を次の言葉で表しています。意味は特にない) の聞きなしが紹介されている (聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
[Cuculus (カッコウ) 属の系統分類]
現在の標準的な系統分類を紹介しておく。
カッコウ科 Cuculidae: Cuckoos
カッコウ亜科 Cuculinae: Cuckoos
カッコウ族 Cuculini: Old World Parasitic Cuckoos (Boyd)
カッコウ属 Cuculus
クロカッコウ Cuculus clamosus Black Cuckoo (アフリカ中南部)
チャムネカッコウ Cuculus solitarius Red-chested Cuckoo (アフリカ赤道以南で繁殖)
ホトトギス Cuculus poliocephalus Lesser Cuckoo
セレベスジュウイチ Cuculus crassirostris Sulawesi Cuckoo
セグロカッコウ Cuculus micropterus Indian Cuckoo (インドから東アジア)
マダガスカルホトトギス (a) Cuculus rochii Madagascar Cuckoo
アフリカカッコウ (a) Cuculus gularis African Cuckoo (アフリカ中南部)
ヒマラヤツツドリ (b) Cuculus saturatus Himalayan Cuckoo (パキスタンからミャンマー、中国)
ツツドリ (b) Cuculus optatus Oriental Cuckoo
スンダツツドリ (b) Cuculus lepidus Sunda Cuckoo
カッコウ Cuculus canorus Common Cuckoo
セグロカッコウまではそれぞれ分岐順。(a) マダガスカルホトトギス、アフリカカッコウ、(b) ヒマラヤツツドリ、ツツドリ、スンダツツドリ (これらは最近分割されたもの) はそれぞれで系統を作る。カッコウの位置は最後でなく、(b) の系統の前でもよい。
このように見るとカッコウ属の中でもホトトギスが古い系統にあたること、起源がアフリカであることがわかる。
[分類と亜種]
亜種 assamicus (インド、アッサム地方由来) も記載されているが通常は poliocephalus のシノニムとされる。
インド亜大陸の個体群は高所 (標高 1500-3200 m) で繁殖し、冬はインド亜大陸の低所や南部に広く移動するとある。
海南島の個体群は留鳥とのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) では他に亜種 lepidus (スンダ列島)、insulindae (ボルネオ) が含められているが、この扱いは Check-list of the Birds of the World (Peters 1940) に従っている。
その後この2亜種はツツドリとともに Cuculus saturatus の亜種として扱われていたが、現在はこれらはスンダツツドリ Cuculus lepidus Sunda Cuckoo と分離されている。
比較的最近までホトトギスの分布域 (越冬地?) に東南アジアを含めている書物 (複数の亜種に分かれ、などの形で紹介されていた) もあったが、この時代の分類の名残りかも知れない。
近縁の種類の一つにマダガスカルホトトギス Cuculus rochii Madagascar Cuckoo があり、同種とされたこともあるが、近年の系統樹ではホトトギスの方が古い分枝にあたり、それほど近いわけではない。
Hartert (1910-1922) p. 952 が Cuculus intermedius rochii と地理的に離れているにもかかわらず同種にまとめた。
同じく Cuculus intermedius insulindae Hartert, 1912 と自身が東南アジア島嶼域の亜種 (現在のスンダツツドリの亜種) を提唱するに当たって一緒にまとめた感じ。Hartert は東南アジア島嶼域の亜種は Standvogel (留鳥) と記述していて北方のホトトギスが越冬しているものではないことを示唆していた。[このように見ると "留鳥" はドイツ語からの訳ではないかと思えてきた。英語の resident は "住む" 意味が中心]。
ホトトギスがアフリカで越冬することを知って系統的に近い可能性に気づいていたならばさすがと言えそうだが、そのような記述までは見当たらず表面的類似性にとどまっていたよう。
Hartert がホトトギスの亜種とした insulindae は現在はスンダツツドリに分離されるが、ホトトギスやツツドリ同様に赤色型があるとのこと。托卵相手はムシクイ類が多いよう (wikipedia 英語版から)。
この地域で代表的な広義 (旧) Accipiter 属は カンムリオオタカ Lophospiza trivirgatus Crested Goshawk (名称ほどはオオタカに近くなく広義 Accipiter 属で最初に分岐した系統) とミナミツミ Tachyspiza virgata Besra が挙げられるだろうか。
模倣相手のタカ類は存在するようで、赤色型が宿主にとってまれな相手で宿主の判別から逃れる仮説 (#カッコウの備考 [カッコウ類雌雄の擬態の進化] 参照) と整合するように見える。スンダツツドリと比較するとセグロカッコウに赤色型が存在しないのは低緯度地域で繁殖するからではなく、宿主の特性や宿主のタカ類擬態への反応の違いが要因のように感じられる。
Becking (1988) The taxonomic status of the Madagascar cuckoo Cuculus (poliocephalus) rochii and its occurrence on the African mainland, including southern Africa がこれらを別種とした論文。
マダガスカルホトトギスはマダガスカルで繁殖するが非繁殖期はアフリカ大陸赤道部、インド洋の島にも渡るとのこと。アルダブラタイヨウチョウ Cinnyris sovimanga Souimanga Sunbird への托卵例が知られている。
音声はホトトギスと少し異なってあまり抑揚のない3-4音からなる。似ているといえば多少似ているが、この論文では音声の違いも別種の根拠としている。
マダガスカルホトトギスのタカ類擬態の相手候補についてはマダガスカルハイタカ以外にマダガスカルカッコウハヤブサも考えられる (#カッコウ備考の [カッコウのタカへの擬態] 参考)。
[渡りと越冬地]
インド亜大陸の低所や南部以外の他の既知の越冬地はサハラ以南の東から南アフリカ。アフリカ越冬地では通常はあまり出会う鳥ではないが、ケニア、タンザニアの沿岸の林で南半球の夏遅くから秋の早い時期にまとまった数が観察されているとのこと。
先述の Becking (1988) ではホトトギスの渡りと越冬地も考察されており、日本を含む東の個体群はアンダマン諸島を通ってスリランカ、西の個体群は南インドに渡ると考えている。南インドではかなりの数が冬に見られる。
スリランカではアフリカや周辺の島に渡る前に特に多いとのこと。スリランカの標本は9月から2月初め、4月から5月に採集されているとのこと。
アフリカは海岸部のケニア、タンザニアまたはその北部にまず渡り、11 月から4月に記録されるとのこと。アフリカ中央部でも多くの記録があるとのこと。越冬地では鳴かなく潜行性なので気づきにくいが実際には多くの数がいると考えられる。
一部のホトトギスは経由地としてセーシェル (秋、春の渡りとも) を用いているとのこと。
南アフリカでの赤色型 (hepatic/rufous morph) の報告例もある
[Davies and Dvir (2020) Cuculus poliocephalus in South Africa, and the field identification of this morph in the Afrotropics]。
日本など東アジア個体群がどこで越冬しているかはよく調べられていないが Becking (1988) の考察のようにカッコウ同様にインド洋を越えているのかも知れない。多くの国のカッコウのアフリカへの渡りについては#カッコウの備考参照。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol. 1-2) によれば越冬域はアフリカ南東部が示され、(南アジア?) が付記されている。
ホトトギス、カッコウともにアフリカが起源らしいこと、両者とも広義ハイタカ Accipiter 属に擬態しているらしいことからホトトギスの進化を考えてみると、アフリカからマダガスカルに渡るようになったものがマダガスカルホトトギス (マダガスカルで進化したものでも構わない)、さらに遠くまで分布を広げたものがホトトギスと考えることができるだろう (なお現代の系統樹はホトトギスの方が先に進化したことを示唆する)。
アカトビとトビの関係 (#トビの備考 [トビとアカトビの交雑個体の渡り]) のようにより長距離を移動する遺伝子型が生まれた状況を考えてもよさそうに思える。
この状況はカッコウに非常によく似ている。カッコウの場合はハイタカが東に分布を広げるのを利用してユーラシア東端まで到着、しかしどちらかと言えば北方系 (#カッコウの備考 [カッコウのタカへの擬態] 参照。ツツドリは北方にも分布だがアフリカとは縁が切れている)。
ホトトギスは主に南方系のツミ属またはアカハラダカ属 Tachyspiza の分布拡大を利用したように見える。ホトトギスのインド亜大陸の個体群がもしインド南部で越冬するならばカッコウの亜種 subtelephonus (渡りについてよくわかっていない), bakeri に対応しており、長い渡りを省略するようになったものか。
マダガスカルには狭義ハイタカ属のマダガスカルハイタカ Accipiter madagascariensi が生息する。
Tachyspiza 属の北限がツミで、ホトトギスが世界的にもあまり北に分布を広げなかった要因にもなっているかも知れない。
広義ハイタカ Accipiter 属中、Tachyspiza 属の方が狭義ハイタカ Accipiter 属より少し早く分岐した系統で、ホトトギスの方がカッコウより古い系統であることにも対応しているかも知れない。
ホトトギスの社会構造の研究があり、同一地域に遺伝的に近縁でない複数のオス・メスが存在し、乱婚状態らしい。この形態は高等脊椎動物では珍しいとのこと:
Yun et al. (2019) Home range overlap and its genetic correlates in an avian brood parasite, the lesser cuckoo Cuculus poliocephalus。
電波トラッキングも行われているのでそのうち渡り経路も解明されるか?
韓国済州島で環境嗜好性を調べた論文: Yun et al. (2020) Habitat selection in the lesser cuckoo, an avian brood parasite breeding on Jeju Island, Korea。
中国東部でカッコウ類が鳴く時間帯を調べた論文: Mei et al. (2022) Diurnal and Seasonal Patterns of Calling Activity of Seven Cuculidae Species in a Forest of Eastern China。
ホトトギスは夜にも鳴く印象が強いが、計測してみると夜明け前数時間に集中的に鳴く。夜も鳴くが昼間はそれほど鳴かない。カッコウは圧倒的に昼に鳴きやはり夜明け前に急ピークを迎えるが夜間もわずかに鳴く。
ヒマラヤツツドリが最も昼間に限定されている。夕方に再度ピークがある (これらの点はツツドリも同様か?)。セグロカッコウはやや不規則とのこと。
夜に鳴く役割には渡り途中のメスを引きつける効果、夜間は音声面で他の鳥と競合しにくい、夜間の方が音声が遠くまで届く、捕食者が少ないなどの理由が提案されているとのこと。
季節変化も調べられており我々の印象にも近い。ホトトギスの飛来が一番遅い点は我々と同じよう。論文には特に述べられていないがカッコウ同様遠くから渡ってくるためだろうか。
中国のカッコウ類 (11 種! 日本では複数のカッコウ類が生息するので1種しかいないヨーロッパに比べて生態的関係を調べるのに好適、とも述べられたが中国の方がその点ではもっと好適だった) の宿主を調べた論文: Yang et al. (2012) Diversity of parasitic cuckoos and their hosts in China
ホトトギスはこちらでも Horornis fortipes Brownish-flanked Bush-Warbler とウグイス類が好みのよう。他種の好みも面白いのでご覧いただくとよい論文。
海外のホトトギスの記録を調べてみると不思議なことがいくつかあった。
Lesser Cuckoo (Scott Lin 2012.4.30) 日本の声とまったく似ていない。
ブータンで 4/23、インドで 4/27 の音声記録があるがツツドリのように早い季節からさえずっているわけではなさそう。5月には繁殖地で普通にさえずっている。
3月の (姿の) 記録は世界的にも非常に少ない。
越冬地の姿はスリランカ、インド以外にもモザンビークのものがあった。
[ホトトギスの「忍音」]
志村 (1995b) Birder 9(8): 70-72 にホトトギスの「忍音」考の記事がある ("しのびね" と読む)。
唱歌「夏は来ぬ」で有名だが、「枕草子」にもこの用例 (しのびたる郭公 = ホトトギス) があるとのこと。国語辞典類ではホトトギスの初音で、卯月 = 4月に鳴く声と見なしている。現代の知識から考えるとこれは合わないので、志村氏が過去の考察とともに解釈を紹介されている。
西村亭「王朝びとの四季」によれば、王朝びとは4月の間はホトトギスは鳴くにしても忍んで鳴くものだと決めていた、古代の日本人はホトトギスが渡り鳥であることを知らず4月はまだ山にいて5月になると里に下りてくる、古今和歌集の歌でも5月になると里に下りてくる考えが検証できるとのことだが、すべての歌で西村説が検証されるわけではないとのこと。
大伴家持はホトトギスは立夏の日に鳴き始めると考えており、旧暦の4月 = 卯月の初めごろと考えたとのこと。万葉集と古今和歌集で鳴き始めの時期が異なるのはホトトギスに寄せるイメージが異なっていたと志村氏は結論している。
さらに万葉集にも陰暦の5月に鳴くとする歌があり、いずれも大伴家持によるものとのこと。立夏の日に鳴き始めると考えていたものの現実のホトトギスはもっと後にならないと本格的に鳴かないと説明されている。
青木正児 (まさる) の「子規と郭公」(ホトトギスとカッコウと読むとのこと) ではホトトギスが立夏に鳴き始める根拠は中国にあるとのこと。王逸が註した説で「常に春分を以て鳴く」とのことで春分はもちろん現在と同じ時期。立夏よりも1か月半も早い。青木氏はこの根拠をもとに万葉集でホトトギスとされるものはカッコウであるとの仮説を提唱したが、志村氏はさすがに受け入れられないとしている。
大伴家持が立夏の日に鳴き始めると考えたのは中国の影響をもとに理念として考えたが実際に聞いたのは5月だったのだろうと推論している。も枕草子では最初は「遠くで空音かと思えるように鳴いた声」を表していたものが、「忍音」の用語ができて4月の山ホトトギスの考えとともにイメージが固定化されたものだろうと考察している。
王朝びとの間でポピュラーとなったのは中国文化の影響 (および時期的誤解) も大きかったのだろうと想像できるが、それでは「常に春分を以て鳴く」とされたものはいったい何だったのだろうか。現在ならば中国でホトトギスやカッコウがいつ鳴くかを調べることができるが、前述のようにホトトギスはまったく該当しそうにない。
Macaulay Library を用いてカッコウで調べると3月の音声記録はまったくないが、中国では4月は早い段階から記録がある。やはり西 (アフリカ?) からやってくるだけのことはあって中国には早く渡来するらしい。カッコウは候補となりそうだが春分はちょっと早すぎる気もする。ツツドリ (やヒマラヤツツドリ) は日本の渡来時期とあまり違わない。セグロカッコウも少し早い程度でさすがに3月には鳴かないよう。
中国ではカッコウは4月初めにはすでに鳴いていて書物にも現れるが、中国で指している種類との違いはあまり気にされておらず (文字の上で考察していたらしい点はブッポウソウやそしておそらくコウライウグイスの例を見ても想像できる) 日本ではカッコウでもホトトギスでも1月ぐらい遅れることが現れていたのかも知れない。
参考までに志村 (1995a) Birder 9(7): 62-64 の方を見ておくとホトトギスは古事記や日本書紀には登場しないとのこと。万葉集にホトトギスの出現頻度が非常に高いのは、この 17-20 巻が大伴家持の歌を年代順に収めたものであることも要因とのこと (大伴家持は一人で 65 首も詠じているとの情報がある)。大伴家持はホトトギスが立夏の日に必ず鳴くことと決まっていると注記を残しているとのこと。
また万葉集に名告げ (なのり) 鳴くなるほととぎすの歌があり、和名の由来を表しているとのこと [大橋 (2025) Birder 39(5): 70-71 の語源説に対応する]。
当時「時すぎにけり」の聞きなしがあったとのこと。トット (ツツドリ) に籾蒔き、カッコ (カッコウ) に栗蒔き、ホトトギスに田植えよ との秋田県の諺があり、万葉集にも「...ほととぎす鳴く声きけば時すぎにけり」があり、早く農作業をしないと時が過ぎてしまうとの警告とのこと。
自然現象を暦として農作業の目安として用いていたものだが、平安時代になるとホトトギスを農作業の監督者とみなし、農民を監督する連想を生み出したと説明されている。
中西 (1989)「古代人と鳥」漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 pp. 106-108 (大修館書店) には中国でもホトトギスを意味する霍公鳥 (コトバンクによれば霍公と郭公と中国で同音なのでやや小型で姿の似ているホトトギスに流用されたと説明がある) が死者の霊を運ぶと考えられた。日本にも輸出されて死出の山から来る田長 (たおさ) と称されたとのこと。死出田長 (しでのたおさ) の別名がある。
ホトトギスの声を死者の声とする考えは額田王 (ぬかたのおおきみ、ぬかたのきみ) 関係の歌や東歌にもみられるとのこと。志村 (1995a) によれば「しでのたおさ」の異名は平安時代に使われたとのこと。
志村氏は「しでの」を「四手」と読み替え「四手の田長」(農作業の監督者) を意味したと解釈していた。
大橋 (2025) にある対趾足を四手と呼ぶ説はこの時代の解説には見つけられなかった。
農作業を急がせる用例では「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば「いくばくの田をつくればかほととぎすしでのたおさをあさなあさなよぶ」(藤原敏行 905) の歌が紹介されている。
ホトトギスなどの声を農作業に関連させる考え方もあるいは中国伝来のものかも知れない。国松・長島 (2007) Birder 21(9): 72-74 によれば中国では蜀 (しょく) の4代目皇帝 (この記事による) にちなんで杜宇 (とう)、望帝 (ぼうてい。杜宇の号)、蜀魂 (しょうこん) と書くとのこと。
望帝は人々に作物の育て方などを教え、望帝はなくなった時さかんにホトトギスが鳴き、望帝の霊魂がホトトギスなってに飛んでいったのだと考えられた。ホトトギスが鳴くたびに望帝がやってきて種を蒔いたり田植えをはじめる時期を教えると考えられたなど説明されている。
wikipedia 日本語版によれば常きょによって編纂された華陽国志・揚雄に仮託した晋代の偽作とされる蜀王本紀に現れるとのことで、毎年2月、ホトトギスが鳴くとき、蜀の人は皆これは杜宇の魂が鳴いているのだというようになったと記述されている (これまた季節が合わない)。
wikipedia 中国語版では毎年農暦3月とありホトトギス/カッコウ (類を表す表記 杜鵑となっている) となって種を蒔いたりする季節を教えるとの記述になっている。この出典である太平寰宇記 (たいへいかんうき wikipedia 日本語版によれば北宋の楽史によって 10 世紀後半に編纂された地理書) はトケンのケンの文字 (鵑) となっており、ホトトギスと解釈されたのは後の時代で、ホトトギス/カッコウ をまとめて呼んでいたのかも知れない。
同記事ではまた中国ではホトトギスの鳴き声を聞くと別離の前兆とされるとのこと。鳴き声を真似すると血を吐くといわれ、これらの俗信が古代日本にも伝わり、平安時代には厠の中でホトトギスの声を聞くと災いや不幸から逃れるために厠の中で衣装を取り替えたとのこと。太平洋戦争前までこれら俗信は日本人に広く信じられていたとのこと。
「鳴いて血を吐くホトトギス」の由来も中国古典に遡るのかもと調べてみると中国語でも民間俗説として紹介されていた 杜鵑啼血。口の中が赤いからの解釈は同じ。中国語では du juan ti xue と読まれ "蜀志" に現れるとのこと。
英文解説があれば中国語の原典を見るより手っ取り早い可能性があり、The 'Chronicles of the Kings of Shu' (Brinckmann 2025 の翻訳プロジェクトがあるらしい)。
Dujuan, a type of cuckoo, but in the context of the history of Shu an embodiment of ... Duyu; it is 'a kind of bird that the people of Sichuan regard as a sacred symbol of the beginning of the agricultural cycle' (四川地方の人たちにとって農耕の始まりの聖なる象徴とされる鳥) などの解説を見ることができる。
関連する詩も英訳も出ているので両者を見るとより詳細に理解できるだろう。興味ある方はどうぞ。
四川地方はかなり南なので渡来時期が違うのではと Macaulay Library をチェックするとカッコウもホトトギスも圧倒的に5月の鳥で日本より格段に早いわけではなかったが、xeno-canto を見るとカッコウは 4/14 (雲南) のさえずり記録があり、少数は早い時期にやってくるのかも知れない。これならば農暦3月と整合する。ホトトギスではプレイバックへの反応が 5/5 に記録された例があったものが最も早かった。
大橋氏の記事 (2025) にある橘 (たちばな) とホトトギスの関係はよく調べていないが、中国語では 杜鵑花科 Ericaceae 越橘属 Vaccinium などの分類があるので関係があるかも (杜鵑花と呼ばれるのは杜鵑啼血と同様に色彩由来)。
杜鵑、花鳥同名 によれば李白 (701-762) が「宣城見杜鵑花」
(755 年。全文) に記しているとのこと。
この記事に現れる「鳩占鵲巣」は #アカアシチョウゲンボウの備考 [アカアシチョウゲンボウの営巣習性] を参照。
鵑の文字については、週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 114 VII (藤堂) によれば鵑の左部分 (ゲン) は細く体をくねらせるボウフラのことで、繊細で鋭い意味を表すとのこと。例えば絹の漢字に用いられる。杜鵑は故郷を離れた旅人に帰心を抱かせるので思帰と呼び、なまって子規となったとの説明がある。
さて「ホトトギス人気」については過去にも考察があり、細川 (2017) Birder 31(9): 68-69 によればホトトギスを詠んだ歌の一部はカッコウらしいとのこと。
中西悟堂「定本・野鳥記 5」の「万葉集中難解の鳥」の考察があり、p. 69 では万葉集時代ではツツドリとカッコウの区別がついておらず、ツツドリはカッコウのメスとの解釈が著名な国語辞典 (大言海 1932-1937) でも長年通用していた。万葉の呼子鳥はツツドリとカッコウのカクテルであって、古今伝授 (二条家の秘伝) の言うツツドリが一応正しく、そして鳩だ山彦だなどと持って回っているのは、口伝というものは手の込んだ独占主義の迷彩なのである (1940 年初出) と切り捨てている。
このように書かれると少しすっきりする気がするが、学名やその由来を一通り眺めていると「手の込んだ独占主義の迷彩」は学名や通称名の命名にも通ずるものがあるような気がする。そのようなつもりで学名や原記載の解説も見ていただけると一層面白い。中西悟堂の当時の人気はこのようにはっきり物を言うところにもあったのだろう。
桐原 (2005) 19(1): 14-15 も清少納言自身は「枕草子」に登場するこれらの鳥を実際にすべて見聞したのではなく、歌の題材としてよく用いられる鳥に甘い傾向がうかがえる。ウグイス批判の部分だけは自分の考えを書いているが、その他は世間の評判に従っているにすぎない結果のように思われる - と記していた (Birder も 20 年前には骨のある記事も多かった!) この記事は「読者が選ぶ好きな鳥 Best 10」特集で依頼されて書かれたもの。この時代から Birder は分類群も限定して人気投票をよく行っていた。
桐原氏の文章は多岐にわたる内容を含み、ここでは清少納言がホトトギスを取り上げた部分に関連して紹介するが、Birder の行う人気投票と同じようなものとの文脈で現れる。桐原氏が伝えられたい全体像は原文をお読みいただきたい。
おそらくその通りだろうと自分も感じている。一世を風靡した (?)「呼子鳥」などの名称が使われたのに何者かすらわからなくなったことや、見たこともないタンチョウの尾を黒く彩色した飛翔画が受け継がれてきた伝統を見てもわかる。みな本質を知らなくても世間の話題に合わせてコピーし続けてきた結果だろう。
どこかで流行が途絶えるともとは何者だったのかすらわからなくなる。
これは現在も同様の傾向があり、話題になる鳥だけが記録され、メディアや、今ならばソーシャルメディアを通じて増幅されているだけだろう。
ホトトギスが愛されていたように見えるのは現代のシマエナガブームと大差なく、大伴家持がホトトギスをあまりに使いすぎて「ほととぎす...」と詠み始めても新しい題材がなく、ブームとしては陳腐化したのでは。
さらに生態・進化学的考察を行っておくと、世間の話題に合わせてコピーする行為は生物の複製と基本的に同じである。突然変異が入って情報が少しずつ変質してゆく。たまに大きな間違いが生じて尾の黒いタンチョウのような "大進化" が生じることもあるが、小さな突然変異の蓄積は言葉では伝言ゲームのようなものである。
多少は選択圧もあってあまり気に入られない表現は流行しなかったり、冗長なものは遺伝子を失うように失わることもあるだろう (別項で示すように 1970 年代の解説を読む機会が生じ、現代忘れ去られた情報がいかに多いか痛感する)。流行を完全にコピーしようとすると上記のようになり、複数の複製を認めれば遺伝子重複のようなものとなるだろう。
ここから集団遺伝学の考えが活躍する。集団が小さいほど突然変異に対する浮動 (まったく選択を受けなければ中立説に対応する) の影響が大きく、もとあった情報が完全に変質することも起こりやすい。
また、もとになる情報が少ないほどいわゆる創始個体群が小さいことによる創始者効果が生まれやすい。
言語的にも地理的にも隔離度の大きい地域で、ある種の情報がブームを起こしたり、まったく忘れ去られたり、あるいは誤った情報が広まりやすい理由が理論的にも説明できるわけだ。同じ情報プラットフォームが用いられた均質な環境では balancing selection のように多形を維持する効果も弱まるわけだ (#ミサゴ備考の [オウム類・ハヤブサ類の年代推定]) 参照。あとは皆さんの想像力にお任せしよう。
個人の趣味なので何が好みでも構わないわけだが、話題にならない鳥の増減情報や初認記録の変化などは事実上わからない。季節に応じて訪れる探鳥地も決まっていて他の地域の情報はほとんど記録されない。
これらの点は自然史を大切にする欧米の市民科学事情とかなり違う。欧米と同じような統計的手法で信頼性を評価すると日本ではかなり違う結果になるのではないだろうか。
この話題は#コサメビタキ備考の [コサメビタキの初認時期] にも関係する。野鳥だより・筑豊 2025 年 3 月号 の初認日を予報する\夏鳥/有働孝士 に各種の初認時期の統計が示されているが、初認時期の標準偏差は各種の渡りの性質の違いよりも知名度・人気度指標なのではないだろうか。有働氏も注目度や声の識別の容易さにも注目されているが、例えば背景を知らない研究者が生態学的パラメータや系統との相関をとって何かを結論すると、たとえ相関が統計的に有意であってもおそらく間違った結果を導くのではないだろうか。
また初認時期の長期的変化は注意して調べないと知名度・人気度の変化を反映したものに過ぎなかったなどもあり得るかも。
話題に左右されず見ている人の視点は多分全然違うが、なかなか表に現れないので主流にはならないだろう。話題に合わせて皆が同じ場所を訪れるのもカメラマン問題の背景にあるのだろう。海外ではカメラマン問題がそこまで深刻にならないのはなぜだろうと軽く問題提起にとどめておく。
ちょうど日本の鳥の過去 40 年の数の変化を統計解析した論文が出された: Yamaura et al. (2025) Range size and abundance dynamics of Japanese breeding birds over 40 years suggest a potential crisis in warm areas
最も新しい breeding bird survey (全国鳥類繁殖分布調査) には自分も参加したので全然無関係というわけではないがこの論文には関係していない。海外の研究などを評価するのと同様に結果を批判的に見ると、少なくとも自分には論文表題や Abstract にあるように気候要因と関連付けるのは無理があるのではないかと思う。
Supplementary Material 1 に個々の種のデータありどのように変化したのか比べてみていただきたい (並び順は系統順ではないのか.. ??) が、個々の種の必要とする条件を個別に考慮しないで全体を一括して扱うのはさすがに無理な気がする。
全国鳥類繁殖分布調査の結果に分布拡大や生息数増加が正直に現れている種もいくつもある。納得できるものも多いが、簡単なところでタカ類ではオジロワシ、ノスリ、ミサゴ以外は軒並み数を減らしていることになっているが本当かと思ってしまう。
オジロワシ、ミサゴは世界的にも増加が顕著で日本で増えているのは当然のように見える。しかし海外の繁殖分布ではハチクマはどこでも数を増やしており分布域も広がっている。日本でハチクマの数が減っているならば特殊事例で、原因を探り保護の手を差し伸べるべきではないだろうか。
説明変数と相関を調べれば、例えば長距離の渡りを行う猛禽類に減少傾向があるなどの結果になるかも知れない (ほんとうか?)。
逆に日本だけで数が減っているように見えるのは実態を反映しておらず、検出効率が下がっているなど系統誤差要因に由来するのであれば、他の調査対象種にとっても信頼性の限界を示すことにならないだろうか。目立って数が増えたもののみが増えたと判定されているものの、検出率は全体的に落ちているのではないだろうか。
猛禽類は Abstract にも触れられているので特別なケースで本旨とは関連が薄いと考えられているわけではないだろう。なお Abstract のこの部分の Nevertheless, the abundance of open-land species did decline, despite range-size recovery; similar inconsistencies were detected for waterbirds and raptors. の inconsistencies が何を指すのか一見してわからなかったので猛禽類について何を述べたいか一層わかりにくかった。
分布域が回復すれば数が増えるべきである予測が書かれていないためだろう。論理を明示しない場合は discrepancy の方がよく合うように思う。
細かに見てみるとアオバトは増加でこれは昔も今も音声のわかりやすい種類で検出率が変化する理由はないだろう。自身の印象と同じく本当に増加しているのだろう。キバシリは高音音声なので検出率が落ちても不思議でない感じがするが顕著に増えている。これは自身の観察結果でもまったくその通りである。
同じような音声特性を持つヤブサメはほぼ変化なしなので、音声周波数の特性に起因する検出率の低下は目立った形では起きていないと言えるかも知れない。あるいは検出率は低下しているがそれを補う以上に増えていることを示唆しているのかも。
繁殖分布の平均気温が下がった特殊な事例3種が取り上げられており、コノハズク、サンコウチョウ、アカショウビンとなっている。論文ではこれらは温暖化に伴う森林の成熟に伴って分布を広げた (These forest species likely expanded into mature forests under warming temperatures) とあるが、
この中でコノハズクのみ数を減らしており全国鳥類繁殖分布調査の報告書の分布を見ると四国や紀伊半島の分布減少が目立つ。
分布を広げたというより一部地域にほとんど分布しなくなったための効果のように見える。夜の鳥なのでアンケート調査への依存度が高く確度は明らかでない点は報告書にも触れられている。
1970 年代、1990 年代にはこの地域の熱心な観察者の存在のため夜の記録もあったものか、本当に減少したものか判断が難しい印象を受ける。コノハズクの減少要因は他にも考えられるので (#コノハズク備考 [ヨーロッパコノハズクの減少] 参照)、もう少し精緻な議論が必要と思う。コノハズクを挙げるならば少なくともヨーロッパコノハズクは比較検討材料に取り上げるべきだろう。
アカショウビンの確認メッシュは増えているが、北海道ではむしろ減らしていて東北地方の増加が目立つ。九州南部や四国では引き続き多く記録され、むしろ増えているようなので気温変化との因果関係は必ずしも均一でないらしい。
サンコウチョウは全国的に増えているが分布域の北上はあまり明確でなく、増加傾向は中国地方や東海地方でも同様なので東北地方で特別に増えたというよりも、低地から少し標高の高い地域にも分布を広げた結果が見えているのかも知れない (この部分は論文の議論と矛盾するわけではない)。
サンコウチョウは一時的に数を減らしたと考えれば、本来の生息分布への回復過程を見ていると考えることができるようにも思える。
3種の分布変化の背景が異なるようなのでこの3種をとりまとめて扱うのは若干無理がある感じがする。またこの3種は気候変動に伴う環境変化に追随しているが、残りの種は追随していない1つの可能性を導くのはこれまた少し無理がある感じがする。論文では別の可能性として、これらの種は温度適応範囲が広いために気候変動に伴って移動しない可能性も同時に挙げられている。
Supplementary Material 1 には正直な傾向が出ている種が多いので、全国鳥類繁殖分布調査の報告書とともに、こちらをじっくり見る方が論文を形式的に追うよりも役立つのではないかと思う。まるで査読者のような紹介の仕方となっているが、査読者コメントは公開されていないようなので、このような読み方もあると見ていただければと思う。論文の論旨を正直に追うだけでなくこのような読み方をする方が科学にとっても有益だろうし、読み手にとっても面白いだろう。
さらに気づいたのだが、タカ類では開けたところで飛びながら食物を探す種類が増えた結果になっているのではないだろうか (トビは減少しているがもともと人為起源の食物が多すぎたと言えるだろう)。ノスリが増えているのは本当かどうかよくわからないが開けたところで食物を探して必要以上に目立つ種類である。
それ以外のタカ類が軒並み数を減らしているのは、調査コースの樹木が高くなって見通しが悪くなり、見通しが良かった以前ならば見つけられた森林性タカ類を見つけるのが難しくなったのではないだろうか。隠れ場所も増えて森林性タカ類は逆に増えているのではないだろうか。
つまり目立つ特性のある種類をこれまでより一層過剰評価する形になっているのではないだろうか。
-
セグロカッコウ
- 学名:Cuculus micropterus (ククールス ミクロプテルス) 小さい翼のカッコウ
- 属名:cuculus (m) カッコウ
- 種小名:micropterus (合) 小さい翼の (mikro- (接頭辞) 小さい pteros 羽 翼 Gk)
- 英名:Short-winged Cuckoo, IOC: Indian Cuckoo
- 備考:
cuculus は#カッコウ参照。
micropterus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。pterus はラテン語でも pte-rus と区切るようで -cro- がアクセント音節と考えられる (ミクロプテルス)。
原記載 (Gould 1838)。大したことは書かれていないので翼長の測定値がカッコウよりも小さい意味か。
Dement'ev and Gladkov (1951) では初列風切が翼の半分より少し短いとあり翼が少し小さいと言えるよう。基産地のヒマラヤでは留鳥なので相対的に翼が短いのだろう。
旧英名にある Short-winged はこの種小名由来と考えられるがおそらくそれほど的確な名前でなく (カッコウ類他種でも翼の短いものがある)、場所を示す名称に変更されたのだろう。以下の Hoffmann (1950) でも地名を用いたドイツ名が使われていた。
インドのカッコウを指して Cuculus canorus (indicus) Blyth, 1846 の用例があった (#カッコウの備考参照)。Gould (1838) の記載の方が早いが、あるいはこのような学名または類似名が文献には現れなくてもすでに使われていたため Gould が indicus を使用するのを避けたのかのかも知れない。
2亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は基亜種 micropterus とされる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" のリストに和名空欄で Japan とのみ記して載せられていた。どこで記録されたものかなどは不明。
Hartert (1910-1922) p. 952 では Unterscheidet sich von allen bisher beschriebenen Kuckucken durch die dunkel graubraune... とあって他の既述のカッコウ類に比べて暗褐色が目立つとのこと。和名の由来に関係しているかも知れない。
そこまで暗褐色と言えるのかはおそらく疑問を持たれる通りだろうが、Hartert はヨーロッパのカッコウを見慣れているのでそれに比べれば暗色に見えたのだろう。嘴はカッコウより大きいが翼は短い (これは学名の通り) とある。この種には色彩型はないと記述していた。
Die Angaben vom Vorkommen in Sibirien scheinen auf Irrtum zu beruhen, ebenso das angeblich in Jesso erbeutete Exemplar との記述があり、シベリアでの記録はおそらく間違いで、北海道で採集されたとされる標本もおそらく同様だろうと述べている (現在の知見ではロシア極東域にも分布する)。
日本で記録されたことがある・ないの問題はこの標本の判断によっていたのかも知れない。北海道で採集されたとされるセグロカッコウの標本の報告がおそらく存在したのだろう。
1977 年の録音により日本の鳥として認められたエピソードはよく紹介されている (「野鳥大鑑」鳴き声 420 p. 183 など) が、それ以前の日本の鳥のリストに載っていたことがあった模様。
カッコウが名前に付くので草原のような環境を想像しやすいが森林性の種類。国内記録例が増えている: セグロカッコウの情報をお寄せください (2018)、セグロカッコウの分布 北上中? (2021) (いずれもバードリサーチニュースより)。
先崎 (2013) 北海道におけるセグロカッコウ Cuculus micropterus の初記録。
中国名は四声杜鵑 (トケン)。
マレー語で Vishu-ppakshi で「祭りの鳥」の意味とのこと。新年の祭りの時期に声が聞かれるのでこの名で呼ばれるとのこと (出典 'Snake Bird' and 'Mountain Echo': What Traditional Names Teach Us About Birds Becca Cudmore 2016)。
Hoffmann (1950) Der Indische Kuckuck (Cuculus micropterus) Gould
の記述もあるので紹介しておく。中国各地の聞きなしなども紹介されている。
Hartert (1910-1922) にも音声が述べられていて、音楽的だが疲れるほど繰り返すとのこと。Bukotako や Kuphulpakka と表現していた。なかなか理解しやすい音訳になっている。
Horsefield and Moore (1856-1858) A catalogue of the birds in the Museum of the Honorable East India Company では Cuculus striatus Drapiez の学名を用いていたがこの学名は Hartert (1910-1922) には現れない。
英語別名が豊富に示されており、Great-billed Cuckoo (Blyth) や現地名など。
-
ツツドリ
- 学名:Cuculus optatus (ククールス オプタートゥス) 待望のカッコウ
- 属名:cuculus (m) カッコウ
- 種小名:optatus (adj) 望まれた、選ばれた
- 英名:Oriental Cuckoo
- 備考:
cuculus は#カッコウ参照。
optatus は a が長母音でアクセントもある (オプタートゥス)。所有の -atus とは関係なく opto (オプトー。選ぶ) の過去分詞。
原意は "選ばれた" でもよいが由来からは "待望の" が最適だろう。
旧種小名 saturatus は -atus の a が長母音でこれも saturo (サトゥロー。満足させるなど) の過去分詞で "サトゥラータ"。
長らくヒマラヤツツドリ (現名称) Cuculus saturatus (現在の英名 Himalayan Cuckoo) の亜種と考えられており、現在でもこの学名や対応する現地名を使っている出版物も多い (日本、海外とも)。
Cuculus saturatus の記載時学名は Cuculus saturatus Blyth, 1843 (原記載) 基産地 Nepal.
これらが別種とされていなかった時代には3種類 [ツツドリ、ヒマラヤツツドリ、スンダツツドリ Cuculus lepidus (英名 Sunda Cuckoo)] は Cuculus saturatus の亜種として扱われていた。
しかしこれらを指す英名が Oriental Cuckoo とされていたため、狭義の Cuculus saturatus が Oriental Cuckoo と呼ばれることも多く、しばしば誤解の原因となっている。分離されてこれらはすべて単形種となった。
Oriental Cuckoo のタイプ標本はヒマラヤ産なので、Cuculus saturatus を "Oriental Cuckoo" と呼ぶことは論理的にはふさわしい (wikipedia 英語版より)。日本語で扱っている範囲では誤解の心配はないが、英語で記述する際は新旧いずれの分類に基づいているかを明確にするために種小名 (optatus) を添えておくとよい。
なお Cuculus orientalis Linnaeus, 1766 の学名は早くから用いられ、インドのカッコウ Cuculus indicus niger Briss. と同定されているよう (資料)。基産地はインド東側とのこと。
これはオーストラリアオニカッコウ Eudynamys orientalis Pacific Koel の学名に引き継がれている。英名 Oriental Cuckoo の直接の由来とはなっていないと考えられる。
Hartert (1910-1922) p. 949 では Cuculus optatus の学名を採用していたが、Cuculus saturatus Blyth, 1843 の記述に問題があるため初記載としていなかったためだった。
Blyth 自身 (原記載参照) の記述では "micropterus" (現在のセグロカッコウに対応) の暗色型を Hodgson が "saturatus" と呼び、この2種が区別されていなかった可能性があるためとのこと。一方で Gould の Cuculus optatus の方は同定誤りの心配はないので安心して使える学名とのこと。
この件を見るとセグロカッコウの "セグロ" はもしかするとツツドリの旧学名の saturatus (暗色の) を指していたのかも。この件からもセグロカッコウが特別に暗色でないことも理解できる。カッコウに比べれば "セグロ" とも言えるがヒマラヤツツドリの方がより暗色なのだった。
ツツドリの記載の多くは当時ヨーロッパ人の到達しやすかった熱帯やオーストラリア地域のものだが、極東周辺地域の記載もその後あった。Cuculus bubu Dybowski & Parrex, 1868 (参考) 基産地 Dauria ただし無効学名。bubu は音声由来と考えられるとのこと。ブリヤート語では chuchu、スマトラ・ジャワの言語で bubut とのこと (The Key to Scientific Names)。
Cuculus peninsulae Stejneger, 1885 (参考) 基産地 コマンドルスキー諸島。peninsulae はカムチャツカ半島を指す。
Hartert (1910-1922) の脚注によれば Swinhoe (1863) はこれらのカッコウ類の分類は絶望的であるとさえ述べていた。あまりにも似ているため混乱もあり、他の類似種との識別点が明瞭に記述されていない記載があまりに多く誰を発見者とみなすか困難である、など。どの記載を有効なものとみなして先取権の対象とするか、セグロセキレイとハクセキレイの関係以上に複雑だったよう。
saturatus と optatus が生物学的にも根拠を持って別種に分離されて世界的にはむしろほっとした人も多かったかも。
面白いことに "Fauna Japonica" にはカッコウ類がまったくと言ってよいほど登場しない。唯一カッコウが種リスト一覧に登場するのみ。確かに標本を得るのが難しそうなことは理解できるが、おかげで日本に関連する学名がカッコウ類にまったく現れないことになった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではポンポンドリ、ツツドリの他にオオムシクイの和名が載せられていた。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) に古い和名の対応表 (pp. 164-167 表 7) があり、カッコウを "大むしくい" (「喚呼鳥」1710)、"おおむしくひ" (「百千鳥」1799) と呼んでいたとなっている。いずれも食性をよくとらえた名前になっているが、声による判別ではないと想像されるので、カッコウやツツドリの区別ができていたかなど多少疑問も残る。
大橋 (2020) Birder 34(6): 66-67 でも (センダイムシクイの和名話題で) むしくひの名称がカッコウ類に用いられていたことが紹介されている。
Xia et al. (2016) Song Characteristics of Oriental Cuckoo Cuculus optatus and Himalayan Cuckoo Cuculus saturatus and Implications for Distribution and Taxonomy
公開データを用いた中国と周辺のツツドリ、ヒマラヤツツドリの音声による分布の検討。中国本土では北部と南部で種が違うが、ヒマラヤツツドリの分布に隣接する台湾のものはツツドリ。
[種小名の由来]
種小名が saturatus だった時代には「濃い色の」の意味であまり問題にならなかったが、「望ましい」の語源はわかりにくい。Gould (1848) Cuculus optatus, Gould., Australian Cuckoo によれば、オーストラリアに英国より入植があったが、故郷の鳥がまったくいないので寂しく思っていた (もっと派手な鳥がいるのに)。
おかげで外来種もたくさん入植したわけであるが、さすがにカッコウは持ち込めなかった。そこで発見された「待望の」(故郷のものに似た) カッコウだったことが由来とのこと。
資料によれば一時期はカッコウと同種と考えられていたことがわかる。
Cuculus saturatus の亜種とされていた時は Cuculus saturatus horsfieldi (英名 Horsfield's Cuckoo) とされており、Cuculus horsfieldi の学名もしばしば使われたが、通常は Cuculus optatus のシノニムとされる
Cuculus horsfieldi Moore, 1857 (記載 なので Cuculus optatus Gould, 1845 より遅い。
この学名は Horsfield's Collection のジャワ島の標本由来で Java Cuckoo と呼ばれていた。Horsfield 自身はカッコウと同種と扱っていた。
この文献でもオーストラリアの Cuculus optatus Gould と同一であることが判明するかも知れないと記していた。
英名の Horsfield's Cuckoo は現在でも別名として使われることがある。ヒマラヤツツドリは台湾まで分布しており、日本でも記録される可能性がある。
Bachurin and Kapitonova (2010 初出, 2023 再掲) To the reproduction of the Oriental cuckoo Versiculus horsfieldi on Sakhalin (pp. 1751-1752)
にサハリンのツツドリ (用いられている学名があまりに違うので何かわからないぐらい) の生態がある。2008-2009 年の観察で見つかった托卵相手はカラフトムジセッカ、キマユムシクイだったとのこと。アオジの巣はたくさん見つかったが托卵されていなかった。
ツツドリは英名から東アジア地域の種の印象を受けるが、シベリアの分布は西にも広く、レニングラード州まで記録されている:
Kharabry (2023) New registration of the Oriental cuckoo Cuculus optatus in the Leningrad Oblast (pp. 2716-2717)。
分布の西端はよく調べられておらず、2023年6月のこの記録はおそらく漂行と考えているが Lapsin (2015) がすでに白海に隣接するカレリア共和国でツツドリを記録したように、分布拡大過程を見ている可能性もある。ルリビタキ、ヒメウタイムシクイ、マキノセンニュウ、コムシクイもここにいる、と記述されており、托卵候補種を指している模様だが、同様に過去に分布拡大を果たしたらしい種も入っている。
アフリカのザンビアで赤色型ツツドリの記録がある [Mann (2013) First record of Oriental Cuckoo Cuculus saturatus optatus in Africa]。
Mikula et al. (2024) Climate change is associated with asynchrony in arrival between two sympatric cuckoos and both host arrival and prey emergence
ロシアのモスクワとウラル山脈の間ぐらいに位置する Kazan' ではカッコウとツツドリが渡来する。ここではカッコウの方が先に到着する。1988-2023 年の間の渡来 (初認ではなくテリトリー行動に着目して調べている) はいずれも早くなっているが、宿主の渡来時期の変化の方が大きいとのこと。
もっとも図を見ると調べられた種類で早くなっていないものも多数あるので、気候変動が一律に渡り時期に影響しているわけではなさそう。カッコウ類の宿主となる種は早くなる傾向が強い。
具体的な数字は論文を見ていただきたい。ヨーロッパのカッコウについては同様の研究は過去からあるがツツドリが含まれる点が目新しい。
[ツツドリとカッコウの中間のような鳴き声]
ロシアでも極東からカムチャツカに広く分布し、ロシア語名は glukhaya kukushka (低い、あるいは深い声のカッコウ)。The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声)に収録されている (この音声ビデオは日本との共通種が多いので楽しく聞けるだろう) が、日本で聞くツツドリとは少し違う声に感じる。
この声とも類似する点が感じられるが、ツツドリとカッコウの中間のような鳴き声は極東でよく聞かれ (舳倉島でも海外バーダーによる記録がある)、ツツドリとカッコウの雑種ではないかとの推測もあったが、飼育下実験も含めて正体が判明した
[Meshcheryagina and Opaev (2021) Previously unknown behavior in parasitic cuckoo females: male-like vocalization during migratory activity]。
飼育下実験で紫外線量を変化させて季節を模倣したところ、ツツドリ (仮親の巣から採取) のメスが春の渡りに相当する時期にこの声を出すことが判明した。野外でこの声が記録された場所や時期とも整合する。なお1羽は飼育下産卵も行った。日本内地でも渡り時期にこの声が聞かれる可能性があり注意が必要であろう。もし離島や大陸でしか聞かれない音声ならばさらに別の要因の考察が必要になるだろう。
[ツツドリのさまざまな声]
松田 (2022) Birder 36(5): 32 に日本海側でのツツドリのイヌのような声を紹介している。
この音声と同一かどうかはわからないが、上記 Meshcheryagina and Opaev (2021) のメスのツツドリの声が紹介されている XC624322
と備考参照。「犬鳴き」と言えるような気がする。この研究者が複数のデータを提供しているので同リンク先を見ていただきたい。
これもメスの別タイプの声 XC624316。
以下は別の観察者による野外録音でさえずりの一種としている XC376538。
次は北海道で記録されたオス・メスのコンタクト中と思われる音声 XC286245。次もツツドリの変わった声とのこと XC114546
(プロジェクトM2024/鳥獣保護区をあるく 2024年度夜間録音調査報告 (真鍋直嗣 2024.7.7)「今年はツツドリにも数種の鳴き声があるのではという疑問が録音を聞いていて湧いた」に対応して音源へのリンクを追加)。
蒲谷 (1995)「野鳥」1995年11月号 (No. 585) p. 42 にツツドリのオスが最初「クワッ、クワッ」という低い声を出すことが多く、他のツツドリが近くにやってくると「クワッ、クワッ、カッカッ」と興奮したように鳴くと説明している。蒲谷氏によるホトトギス、カッコウ、ツツドリのメス (およびオス) のソノグラムが比較掲載されている。
デュエットの際のカッコウの3音節鳴き (#カッコウの備考 [カッコウの声の話題]) もソノグラムに記録されている。
[ツツドリとカッコウの渡りルート]
ロシアのツツドリとカッコウの追跡記事がある。
Solokov (2024) Udivitel'nye puteshestviya obyknovennoj kukushki (カッコウの驚くべき道筋, Nauka i zhizn' 科学と生活) 一般向け記事で、p. 53 にツツドリがバイカル湖付近からインドネシアやオーストラリアに渡る経路が示されている。
この記事はカッコウの驚きの経路を紹介する内容が中心で、ロシア東部のカッコウの越冬地がどこなのか、標識調査は長年行われてきたが不明のままだった。ヨーロッパでは 19000 個体以上を標識してアフリカで少数の個体が回収されたにとどまっていた。衛星追跡による解明が不可欠だった。
最初はヨーロッパの研究者によるものが中心だったが、2015-2019 年にカリーニングラード州 (ロシアの飛び地)、2017 年にカムチャツカ、2018-2019 年にシベリア南部 (ハカス共和国)、2021 年シベリア西部 (トムスク州) とバイカル湖と研究が進められた。表示されているツツドリの渡り経路はこの 2021 年の研究で得られたもののよう。
ウラル山脈以東のカッコウは東南アジアで越冬するのではとの見方もあったが、他のカッコウ同様にアフリカで越冬するのではと考えた。
シベリア西部から出発した個体はヨーロッパ東部からの経路に合流してアフリカに到着。
バイカル湖からの個体は一部が南へ向かって中国、南アジアルートをとってアフリカへ。
一部の個体は西に向かったがチベット高原を迂回したとのこと。
#カッコウの備考にあるようにカムチャツカのカッコウはアフリカまで 106-123 日かけて 17340 km を渡る。ボツワナやナミビアの越冬地では標高 900-1300 m の高地に生息。
カムチャツカのカッコウは 4/19 と 4/28 に越冬地を旅立ち、42 日かけて繁殖地に戻った。
東部のカッコウ個体群の渡り経路は複雑。幼鳥もおそらく似た経路をたどると考えられる。
アフリカから分布を拡大した経路が本能に刻まれているのだろう。ツツドリはインドネシアからオーストラリアで越冬する進化の途上なのだろうと想像している。
Movebank に登録されている研究によれれば、ツツドリの追跡はバイカル湖以外にもサハリン (カッコウ、ケアシノスリを含む)、トムスク州、ハカス共和国、アムールのいずれでも行われており、上記の記述からはいずれも東南アジアで越冬する結果が得られていると考えてよさそう。そのうち論文が出るだろう。
カムチャツカのカッコウを含む論文は Davidson et al. (2020) Ecological insights from three decades of animal movement tracking across a changing Arctic
に出ているそうで [#カッコウの備考の Sokolov et al. (2017) にも速報が一部出ている]、Study - Common cuckoo, Kamchatka で経路データを見ることができる。
-
カッコウ
- 学名:Cuculus canorus (ククールス カノールス) 声の美しいカッコウ
- 属名:cuculus (m) カッコウ
- 種小名:canorus (adj) 声の美しい
- 英名:Cuckoo, IOC: Common Cuckoo
- 備考:
cuculus は中央の u が長母音でアクセントもある (ククールス)。
語源は音声由来で明瞭だが長音の由来は特に明瞭ではない (ギリシャ語では短音)。
canorus の -no- は長母音でここにアクセントがある。cano (カノー。歌う) 由来。
4亜種が認められている (IOC)。
多くの言語でカッコウの声をそのまま取り入れた名称が使われていることはよく知られているが、ウクライナ語では違っていた。zozulya (発音規則からはおそらくズズーリャまたはゾズーリャと読む)。
カッコウまたはオカリナの意味があるようだが語源的関連は不明。子音交代 (k → z) の起きた類似単語もあるので、あるいはもとをたどれば音声由来かも知れないがそこまではわからなかった。
ドイツ語では Gauch (おそらくガウフと読む) の名称もあるとのこと。興奮した時の発声 (地鳴き?) を Guch-chae-chae と聞きなしたとのこと (wiktionary ドイツ語版)。
OED によれば古英語では geac で現在でも北部で gowk の単語が残っている。上記ドイツ語 Gauch とも関連がある。多くの言語で次第に声を真似たものに変わり、ドイツ語では 15 世紀に kuckuk で置き換わったとのこと。現在の英名はフランス語と共通語源でフランス語 coucou (12-15 世紀は cucu) でラテン語の直接の起源を見出すことができず、音声を直接真似たものと推定されるとのこと。
cuculus と直接関係するわけではないとの判定になっている。
イングランドではノルマン・コンクエスト (Norman Conquest, 1066-1071) 以前には用例が見られないことからフランス語の影響を受けたと推測されるが、毎年声を聞くために通常起きる音韻変化が起きなかった可能性があるとのこと (古フランス語では第2音節にアクセントがあり、現代の英語のアクセント位置とは異なる。スコットランドでは古フランス語同様のアクセント位置とのこと)。
[カッコウの衛星追跡]
カッコウはなぜ他の鳥に比べて比較的遅く渡ってくるのか、あるいはヨーロッパのカッコウ (日本と同種) はなぜ日本より早く渡ってくるのかに疑問を持たれた方もあるだろう。図鑑のカッコウの分布図では東南アジアやインドにも越冬域が示されていて、日本のカッコウはそこで越冬していると考えるのも自然であろう。
実際に Cramp (1985) The Birds of the Western Palearctic Vol. 4 によれば、ヨーロッパで繁殖する個体群はアフリカに渡り、中国、モンゴル、極東シベリアで繁殖するものはインド南部や中国、ベトナム、マレーシア、インドネシアで越冬するに違いないと考えられていた。
最近の衛星追跡による研究で東/北東アジアのカッコウもヨーロッパと同じくアフリカのサハラ以南で越冬していることが次々と明らかになりつつある:
The Beijing Cuckoo Project (2016) (北京)、The Mongolian Cuckoo Project (2019) (モンゴル)、
カムチャツカのカッコウは 17000 km にも及ぶ渡りを行っている:
Sokolov et al. (2017 初出の速報論文, 2020 再掲) Migration routes and wintering places of European and Asian populations of the common cuckoo Cuculus canorus (pp. 2150-2153)。
これによればカムチャツカで春に捕獲 (成鳥、若鳥とも)。秋の渡りではヨーロッパ個体群と異なりバルカン半島を通過。サハラ砂漠を通過した後はいずれの個体群も同様でサヘル地域にしばらく滞在したとのこと。
カムチャツカの個体群はヨーロッパ個体群より南のアンゴラで越冬したとのこと。
#ツツドリの備考にも解説がある。
北京近郊で標識されたカッコウの記録も触れられていて、5羽のうち少なくとも2羽は基亜種に属するとのこと。さらに春の飛行を続けてバイカル湖とモンゴルの間で夏を過ごし、8-9月に秋の渡りを始めて南へ渡り、ミャンマーに到着後西に移動、インドで1か月を超える休息をとり、アラビア海を超えて 11 月初めにはアフリカのソマリに到着。その後南に向きを変えてアフリカ東岸に沿うように南下してモザンビークで越冬。
春の渡りは秋のコースをほぼ逆行するものであった。これらの結果は東シベリアで繁殖するカッコウもこれまで考えられていた東南アジアやインドでなく、アフリカ東部で越冬することが明らかになった。
Lee et al. (2023) Long-distance migration of Korean common cuckoos with different host specificities (韓国)。
韓国のケースでは渡りルートは行き帰りともほぼ同じ。越冬地は3月に出発するが途中でしばらくとどまる。海を越えるための風の条件などが必要。
これらの事例を見ると日本のカッコウもおそらく同様と考えられ、ヨーロッパに比べて日本へのカッコウの渡来が遅いのはアフリカからの距離が遠いことを反映している可能性がありそうである。
なおヨーロッパのカッコウの渡りについてはよく知られていて、例えば Cuckoo Tracking Project のように公開されている。
東欧やロシア西部の例:
Sokolov et al. (2023)
Migration Routes and Wintering Grounds of Common Cuckoos (Cuculus canorus, Cuculiformes, Cuculidae) from the Southeastern Part of the Baltic Region (Based on Satellite Telemetry)。
The cuckoo sheds new light on the scientific mystery of bird migration
の記事によれば捕獲されたデンマークからスペインに移動して放した個体が正しいルートで渡ったとの実験がある。捕獲された場所に一度戻った個体もある。成鳥なのですでに渡りを経験済みと考えられ、完全に本能のみで渡る幼鳥でも調べる必要がある。
同様の実験はカムチャツカ個体についても行われており、同様の結果となっている (上記 Sokolov et al. 2017)。
Thorup et al. (2020) Flying on their own wings: young and adult cuckoos respond similarly to long-distance displacement during migration こちらは Rybachy (バルト海沿岸) から Kazan (ロシア中部) に移動して放した実験。この研究では Kazan で生まれて出発するものとほぼ同じ経路となり、正しい越冬地に到達する能力を遺伝的に持っているとの考察。
初めての渡りでは同種の渡りから学習する可能性もあるが、カッコウは個々の個体が個別に渡りをするのでこの可能性は低いと考察している。
関連するレビューがあり Chernetso and Utvenko (2025) Do first-time avian migrants know where they are going: the clock-and-compass concept today。
あまり何かが明確になった気がしないが、上述のカッコウの移動放鳥実験の結果が紹介されている (これが最も明確な事例らしい)。標識調査時代の歴史的実験もいくつも紹介されているので参考までに。
こちらは移動して放したものではないが、カッコウ若鳥の渡り追跡: Vega et al. (2016) First-Time Migration in Juvenile Common Cuckoos Documented by Satellite Tracking
若鳥でも問題なく越冬地に到着し、成鳥とはタイミングが異なっていた。若鳥が自身の本能のみで越冬地に到着できることを示したもの。
捕獲、標識、追跡タグ付けのビデオが紹介されている。カッコウの捕獲の難しさは悪評があるぐらいだそうである。解説: カッコウをどのように捕獲するか。網から簡単に逃げてしまい、羽毛の性状からかすみ網にかかりにくい。
ビデオ: How to Tag a Cuckoo。
Hewson et al. (2016) Population decline is linked to migration route in the Common Cuckoo
英国のカッコウの渡り経路に2種類あることがリアルタイム追跡で判明。予想通りサハラ砂漠横断のリスクが高かったが、短距離ルートの個体の方が死亡率が高く、近年の個体数減少 (2011-2014) により関連している。
[日本のカッコウ亜種の問題]
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では日本の亜種は telephonus とされていたが、Avibase (情報出典 Clements checklist) では基亜種 canorus がヨーロッパからシベリア、日本にかけて分布し、アフリカで越冬するとされていてこの時点の日本鳥学会の見解と異なっていた。
当時 Avibase の表示から telephonus は通常 subtelephonus のシノニムとされると記述していたがこの表示は誤りだった。
Brazil (2009) の "Birds of East Asia" でも亜種 canorus は中国北東、日本、(シベリアから)チュコト半島、カムチャツカ、コマンドル島まで普通の夏鳥で、台湾では迷鳥とされており、この書物の扱う範囲では亜種 subtelephonus の記載はない。
Dement'ev and Gladkov (1951) の分布図でもシベリア東部、朝鮮半島、日本は亜種 canorus の扱いである (越冬分布にインドネシアやマレーシアも含まれているので越冬地では別種との混同があった可能性がある)。亜種 telephonus についても記述があり、腹部の縞が比較的狭く、やや小型であるとされているが、年齢や個体差もあって Dement'ev and Gladkov は亜種として区別できないとしている。
Dement'ev and Gladkov (1951) では中国東部は亜種 fallax の扱いとなっているが、この亜種は現在は 亜種 bakeri のシノニムとして扱われている。この分布図と上記 Clements checklist での bakeri の現代的な分布の記載との整合性はあまりよくない。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol. 1-2) による亜種区分では日本北部は canorus の分布域となっており、アフリカに渡るとされる。
同リストでは subtelephonus の分布域は南ウラル、中央アジア、カザフスタン、アフガニスタン、パキスタン、中国北西部でこれらもアフリカに渡るとされている。
他亜種も含めて同リストではアフリカ以外の越冬域は示されていない。
亜種 subtelephonus はトルキスタンからモンゴル南部で越冬地は南アジアとアフリカ、亜種 bakeri は中国西部、北インド、ネパール、ミャンマー、タイ北西部の分布としている (長い渡りをしない)。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)で日本産亜種は canorus となった。
[亜種 telephonus と subtelephonus]
[日本のカッコウ亜種の問題] の記述後に歴史的背景がもう少し判明したので追記しておく。
telephonus の亜種名は Cuculus telephonus Heine, 1863 (原記載) に由来する。
日本で採集された (Temminck and Schlegel の Fauna Japonica にあるもの) Cuculus canorus とされていた標本をヨーロッパのものと比べ、東インドの Cuculus indicus Cabanis & Heine に相当する違いがあるため、Cuculus canorus の第3の "気候的な地域種" (climatische Local-Art) として与えたもの。
すなわち記載の段階で地理的クラインであることをすでに示唆しているものだった。
しかし Cuculus canorus (indicus) Blyth, 1846 の学名はすでに用いられていた (資料 1, 2)。
この学名も (indicus) の部分はかっこ付きでかごの中の単に "インドのカッコウ" のペアを意味したものかどうか明確でないとのこと。2つめの資料では Blyth は description を述べておらず、英国のカッコウに比べて声が小さく音楽的でないと述べていたにとどまるとのこと。
おそらく要件を満たす学名として扱われなかったが、Cuculus indicus Cabanis & Heine はすでに使用された学名としておそらく認められなかったものと思われる。
その結果 telephonus の方だけが残った形になったものと想像できる。
基産地は日本なのでこの亜種をそのまま認めれば日本の亜種はこの名前になっていた。
資料によれば、Heine の記述から Cuculus canorus と同種とみなされるとされている。"気候的な地域種" を現代的な亜種と同等のものと扱うか否かの問題だったと思われる。
Hartert (1910-1922) p. 948 は telephonus を亜種として認めていた。日本の目録に遅い時期まで登場していたはこのためかも知れない。
Hartert はこの亜種と先行する無効学名の Cuculus canoroides Mueller (ジャワ島、スマトラ島、ボルネオ島、チモール島) を同じ亜種としていたため、日本のカッコウの越冬地はこの地域と暗黙に考えられていたかも知れない。Hartert はカムチャツカや朝鮮半島のカッコウも日本と同じ亜種と考えていた。
近年の亜種の統一背景には近年になってカムチャツカや朝鮮半島のカッコウがいずれもアフリカに渡ることが明らかになって日本だけが特別とは考えにくくなってきた経緯が想像できる。
亜種 subtelephonus は Zarudny (1914) の 記載 基産地 Turkestan と遅いので Avibase の表示のように telephonus が subtelephonus のシノニムとなるのはおかしい。
亜種名も telephonus がすでに存在するのでそれに対して "より小さい" の意味で付けられたものと思われる。
この文献では Turkestan (トルキスタン。テュルク系民族が居住する中央アジアの地域を指す歴史的な名称) でみられるカッコウの大部分は Cuculus canorus telephonus と Cuculus canorus subtelephonus で表ではまずこの "2型" を区別せず計測値を示しているとのこと。
計測値は Cuculus intermedius Vahl, 1797 とはうまく合わない。しかしこれらの標本は telephonus Heine = Cuculus canorus johanseni Tschusi, 1903 とよく似ている。
Cuculus borealis Pallas, 1811? = telephonus とも似ているとある。ここでは Cuculus borealis Pallas, 1811? と telephonus はシノニムと考えていて Pallas の名称を採用していた。ただし Turkestan の個体は基亜種 canorus とは下面の色や模様が異なるとのこと。
Turkestan でみられるカッコウの翼長は2種類に分けられ、小さい方 (色彩にも違いがある) を新亜種 subtelephonus と提案に至ったとのこと。
当時はカッコウの分類が混乱しており、maximus, intermedius, minor のように大きさで表した種名があり、新しく名前の付けられた (亜) 種も含めてどれが同一かの議論は難しかった。
Cuculus minor Gmelin, 1788 は現在はマングローブカッコウ (現在の学名で Coccyzus minor Mangrove Cuckoo) の学名となっているが比較対象になるような種ではないので、ここで用いられている minor は別のもので、
おそらく Cuculus canorus minor Brehm, 1857 のことで (資料) 基産地はスペイン中部となっているもの。Gmelin の用例が先にあるのでおそらく無効学名となったと想像できる。
Ornithological Articles in Other Journals (1919) に資料がありやはりその通りだった (記載)。こちらは亜種 bangsi と改名された。
Cuculus intermedius は基産地スリランカに近いインドの Tranquebar (資料)。
ツツドリを含む旧 Cuculus saturatus に対応するとの記載もあり、Essays on Early Ornithology (McClymont 1920)
によれば Oriental Cuckoo の英名が与えられている (ツツドリの分離前の英名はこのころすでに付けられていたものか)。
一方で Avibase は ホトトギスのシノニムに含めておりおそらく複数種を含むなどの理由で Cuculus intermedius の学名は残らなかったのでは。
Ueber die Verbreitung von Cuculus optatus im europaeischen Russland Grete (1927) にヨーロッパロシアには2種類のカッコウがいて声がまったく違うなどの記述があり、Cuculus optatus は現在のツツドリ。
Cuculus intermedius によく似ているなどの記述がある。
ヤツガシラのような低い声で鳴き、この文献注釈で Cuculus intermedius もヤツガシラのような声で鳴くとある。音声記述からはホトトギスよりはやはりヒマラヤツツドリを含むツツドリかセグロカッコウを指していたのではないかと思える。
この中で kleine sibirische Kuckuck の名称 (小さなシベリアのカッコウ) が使われていることも興味深くドイツ語ではツツドリ類を "小さなカッコウ" と呼んでいたかも知れない。ホトトギスの英名やロシア名、ドイツ名の別名に関係しているか気になるところ。
Heine (1863) 備考によればこの著者は (日本の標本から記載された) telephonus が Hartert が想定したよりずっと西方にも広がっていてウラル山脈付近まで分布していると固く信じているとのこと。
[Hoffmann (1950) Der Indische Kuckuck (Cuculus micropterus) Gould も参照。この考えは長く受け入れれられていたようでこの時代は中国のものは telephonus と考えられていた]。
Heine (1863) はヨーロッパの典型的な canorus がヨーロッパロシアにどれだけ分布しているかさえ疑問と考えているとのこと (つまり基亜種 canorus はロシア外のヨーロッパ限定の亜種と考えていた)。
この記述を見ると、日本産のカッコウの亜種 (古い表記で telephonus) と subtelephonus は実質同じようなものとも著者次第で解釈できることになる。subtelephonus と telephonus の一方が残れば片方はシノニムとした Avibase の (多分計算機アルゴリズムによる判断) にも一定の理由がある。
telephonus 自身も Cuculus borealis Pallas, 1811? と同一との考えがあり、Cuculus borealis の処遇次第で亜種 canorus のシノニムともなる中途半端な状況だった。
borealis も Pallas 自身が Cuculus canorus のシノニムと記していた模様 (資料)。
telephonus が早い時期に日本の標本をもとに記載された (先取権を持つ可能性が高くなる) ためにむしろややこしい状況となっていた模様。
亜種 canorus のシノニムとならず、Pallas の borealis を認めない場合は telephonus に先取権が生じるのでこの解釈から歴代の日本鳥類目録に載せられ続けていたのだろう。
ただし Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" には telephonus は現れないのでこの時代にはまだ記述が認識されていなかったのかも知れない。
現代の世界のリストを見る限り canorus のシノニムとされたとしか考えられないので、世界のリストに合わせるならば自動的に亜種は canorus となる次第。
Dement'ev and Gladkov (1951) では日本の telephonus を canorus のシノニムとしている。他に maximus Neumann, 1934 (基産地サヤン山脈) もシノニムに含めている。
カッコウの中で比較的大型のものは canorus でよいとみなしているようで、やや小型の subtelephonus は別亜種扱いの価値があると判断しているようにみられる。
subtelephonus の方は世界のリストに残っているが、これは研究の少ない中央アジア地域で情報がほとんどないため残さざるを得なかったのだろう。
幸い比較的新しく記載された亜種なので、残しておいても他の亜種にまとめてしまってもカッコウの亜種全体の学名への影響は少ない。telephonus をもし認めると先取権のある名称なのでどこまでが telephonus なのか問題が発生するので他の証拠も合わせて canorus に吸収する方が簡単と考えられたとも想像できる。
telephonus が亜種として現れる世界のリストは American Ornithologists' Union 3rd edition (incl. 18th suppl.) まで、Howard and Moore 2nd edition、Peters' Check-list of the Birds 2nd edition。日本のリストが Howard and Moore を参考にしていたと考えると比較的最近まで残っていた理由もある程度納得できる。
日本にとっては (今のところ?) せっかく基産地になりながらちょっと不幸 (?) な事例だったかも知れない。日本からの渡り経路追跡が行われる前に基亜種のシノニムとなり、基亜種の越冬地はアフリカと一緒にまとめられてしまった形になる。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では世界で6亜種としている。
Dement'ev and Gladkov (1951) に従っていると考えれば、canorus, kleinschmidti, bangsi, subtelephonus, bakeri, fallax の6亜種で話が合う。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではもう1亜種あった gularis が現代の世界のリストではアフリカカッコウ African Cuckoo と別種扱い。
kleinschmidti と fallax をシノニム扱いしていない点が現代の世界の一般的リストとは異なっていた模様。
Dement'ev and Gladkov (1951) では kleinschmidti はコルシカ島 (?)、サルジニア島 との記述で基亜種のシノニムと思われるが判断材料の資料がないのでそのまま残してあるだけのよう。
Ryabitsev (2014) ではシベリアでは1亜種 canorus との記述になっている。subtelephonus が含まれてもおかしくない地域ではある。
記載時の Turkestan の範囲が漠然としすぎており、Dement'ev and Gladkov (1951) では分布を現在のカザフスタン以南 (西部を除いたイラン、中央アジア、アフガニスタン、ヒマラヤはチベットなど) としているのでロシアのみを扱った "シベリアの鳥" には含まれなかったものと想像できる。
少し小型のカッコウが中央アジア型として存在するとの認識のよう。
[青い卵を産むカッコウ]
青い卵を産むカッコウが知られている。Fossoy et al. (2016) Ancient origin and maternal inheritance of blue cuckoo eggsおよび日本語解説
によれば、この「青い卵」の遺伝子は母性遺伝することが明らかになった。ミトコンドリアの系統樹ではこの「青い卵」は他のカッコウ類 (例えばツツドリ) が種分化する以前に現れていた (ミトコンドリアで系統樹を描くと核 DNA による系統樹と別になってしまう)。他の点は全てカッコウだが、青い卵だけは別種相当ぐらい違っている、との驚くべき結果となった。
[カッコウの渡来時期は何で決まる?]
ヨーロッパのカッコウであるが、Davies et al. (2023)
Spring arrival of the common cuckoo at breeding grounds is strongly determined by environmental conditions in tropical Africa
多数の個体を衛星追跡した結果、ヨーロッパへの到来時期を決めているのは従来想像されていたような渡り途中の条件ではなく、アフリカの越冬地をいつ出発するかが重要であることがわかった。
多数の個体が同じ時期に移動することがわかり、越冬地からサハラ砂漠を越える渡りに適した条件に許される幅が狭く、あまり融通が効かないのだろうとのこと。また前年の秋の渡りからの持ち越し効果も考えられるとのこと。
森下 (2005) Birder 19(5): 38-39 によれば 1998 年のカッコウやホトトギスの渡来が1か月ほど遅れたが翌年は平常だった報告がある。古い話なので検索しても当時の状況が出てこないが、カッコウの出発が越冬地で決まり、日本のカッコウも (ホトトギスも?) アフリカで越冬するならば当時のアフリカの気象などを調べればヒントが得られるのかも知れない。
この年は最も強力なエル・ニーニョ現象が起きており 199798 El Nino event
越冬地の出発時期に影響を与える事象があったのかも知れない。
同年にヨーロッパのカッコウの渡来が遅い記事は探した範囲で見つからなかったが、極東のカッコウは東アフリカが経路になりそうなので気候の影響はヨーロッパの個体群とは違うかも知れない。
[カッコウの声の話題]
Moskat and Hauber (2021) Male common cuckoos use a three-note variant of their "cu-coo" call for duetting with conspecific females
オスのカッコウはメスがいる時には3音節のフレーズでデュエットをする。メスは "bubbling calls" を用いる。
Moskat and Hauber (2022) Syntax errors do not disrupt acoustic communication in the common cuckoo
オスのカッコウの2音 ("cu-coo") の順序を入れ替えたりして反応を調べた。オスは最初の "cu" 音の1音だけでも反応し、入れ替えても "cu" 音があれば反応したとのこと。メスがいる時に出す3音節のフレーズには反応しなかったとのこと。この声は少し音程が高く間隔が短く、通常の "cu-coo" とは異なる役割を持っていると考えられる。
[飼育下のカッコウ]
中西悟堂「定本・野鳥記」1 pp. 148-149 (おそらく「野鳥と共に」からの再掲) にカッコウの飼育の記事がある。初夏の日にある家に飛び込んできたカッコウの成鳥が餌を食べないので中西氏のところに譲られたとのこと。中西氏も「なかなかえづかない」と苦労されていたが、60 日目にカイコを与えると喜んで食べたとのことで、イナゴも与え、65 日後にはすりえも食べるようになって呼べば来るようになったとのこと。
絶対的托卵性のカッコウが人に懐くとは驚くべきであったが、カッコウ目に近縁目に属するハイイロエボシドリは非常に人懐っこいので ([カッコウ類の足と近縁系統] の項目参照)、北半球に広域分布した托卵系統に属する少数の特殊な種のみからカッコウ目の性質を判断すると先入観が入りすぎかも知れない。
絶対的托卵性のキツツキ目ノドグロミツオシエも人をハチの巣に誘導する (と言われる) ように、絶対的托卵性と人馴れしにくさは必ずしも関連しているわけではないかも知れない。ただしカッコウ目の方がキツツキ目よりはずっと古い系統である。
中西氏はこのカッコウを秋には放した。「定本・野鳥記」1 は中西氏の過去の著作や書き下ろしが含まれているが、中西氏は野鳥飼育を扱うこれらの部分は「定本・野鳥記」を構成する上で欠かせないことを後記の部分に述べられていた。それまで知られていなかった飼育下の習性を記述し、鳥の本性の理解のために必要なもので、飼育して調べれば野に返されていた。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) pp. 86, 109-110 でもホトトギスやカッコウを飼いたい者は多かったようだが飼いにくい上に冬越しをさせることは困難であったことが述べられている。
中西氏がカッコウを飼育しなければこのような特性はなかなか明らかにならないままだったかも知れない。
[カッコウのタカへの擬態]
カッコウ類の模様がタカへの擬態となり托卵に有利に働いたりタカに捕食を防ぐとの考えは昔からあったが宿主がどのように反応するかを調べた研究がある。
Davies and Welbergen (2008) Cuckoo-hawk mimicry? An experimental test。
下面の模様をハトのようにすると小鳥 (ヨーロッパシジュウカラやアオガラ) の警戒が激減し、カッコウの模様をハイタカのように認識している証拠が初めて得られた。これらカラ類はカッコウによる托卵を経験することはなく、カッコウをタカと誤認していることがわかる。
ちなみにタカの横縞は枝の中では目立たない (Newton 1986)。タカとカッコウの収斂進化による模様との考えもある。タカへの擬態でタカに捕食を防ぐ考えは Wallace (1889) に始まる。
タカと誤認させることによる行動で宿主が巣の位置を明らかにしてしまう (Craib 1994。後述のようにアイデアはさらに古く遡る) など。
Ma et al. (2018) Hawk mimicry does not reduce attacks of cuckoos by highly aggressive hosts
によれば攻撃的な宿主 (ここではオオヨシキリ) に対して、宿主はカッコウと無害な鳥を区別するがカッコウへの攻撃は減らずタカへの擬態はあまり有効でない結果が得られた。宿主によって反応が異なる模様。
Zhao et al. (2022) Fatal mobbing and attack of the common cuckoo by its warbler hosts
によればオオヨシキリの攻撃で死んだカッコウがあるとのこと。
Wang et al. (2023) Importance of cooperation: How host nest defenses effectively prevent brood parasitism from the cuckoos
によればオオヨシキリが3羽以上で協力すればカッコウの托卵を効率的に防ぐことができるとのこと。宿主と同種個体の協力行動まで関係してきた。
Attwood et al. (2023) Aggressive hosts are undeterred by a cuckoo's hawk mimicry, but probably make good foster parents
のように、攻撃的な宿主に托卵する方がその後の巣の防衛など托卵側にとっても有利な点がある議論もある (この論文ではアフリカカッコウ Cuculus gularis African Cuckoo とクロオウチュウ Dicrurus adsimilis Fork-tailed Drongo の関係を扱っている)。
我々もしばしば猛禽類のように思ってしまう (?) カッコウ類の地鳴きもメスが托卵する際にタカを音声で擬態して宿主を脅している可能性も指摘されているそうである:
York and Davies (2017) Female cuckoo calls misdirect host defences towards the wrong enemy。
ヨーロッパヨシキリ Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed-Warbler はオスのカッコウの声には特に反応を示さないが、メスの声に対してタカの声同様に注意するとのこと。
なお Tryjanowski et al. (2018) Functional significance of cuckoo Cuculus canorus calls: responses of conspecifics, hosts and non-hosts
によればオスのカッコウの声への反応は種によって違いがあり、ヨーロッパヨシキリの上記結果は一般則というわけではなさそう。
この論文では人の居住地近くに営巣する種類はカッコウの托卵や猛禽類が近づくのを防ぐ意味があると説明している (#ジョウビタキの備考も参照)。
[カッコウの声の話題] の項目も参照すると3音節のフレーズの意義がまだわかっていなかった時代の研究のため、実験デザインや解釈は少し注意が必要かも知れない。
Wang et al. (2022) Female Cuckoo Calls Deceive Their Hosts by Evoking Nest-Leaving Behavior: Variation under Different Levels of Parasitism
によればメスのカッコウの声で宿主が巣を離れる行動が観察され、托卵を有利に進めているとのことだが、必ずしもタカの声を真似ているわけではなく、音声の質が注意を逸らせる結果になっている可能性もある。
Moskat and Hauber (2023) On the sparrowhawk-like calls of female common cuckoos: testing for heterospecific vocal mimicry in a conspecific functional context。
カッコウのオスがカッコウのメスの声、ハイタカの声などに反応するかを調べた研究。
基本周波数は似ているが倍音が異なるためにカッコウのオスは音の質で同種メスを聞き分けている模様。
ハイタカの声も倍音をそれらしく操作するとカッコウのオスの反応が増したとのこと。
タカに音声で擬態するとともに同種内の信号として役立てているらしい。
後続の類似研究: Hauber and Moskat (2025) Acoustic overtones improve the discrimination of conspecific female calls by male common cuckoos from similar heterospecific calls。結論は上記とあまり違わない。逆に言えばカッコウは音の高さだけでなく音色も聞き分けている。
猛禽類の音声に対する忌避反応については #カンムリワシ備考の [霊長類はなぜヘビを恐れるか] も参照。霊長類の例だが 50-100 年間被食経験がないと音声を警戒しなくなったとのこと。カッコウ類の宿主でも過去に猛禽類に襲われる、あるいは他個体の逃避反応を通じて音声との関連を学習した個体がタカらしい声に反応しているかも知れない。
Medina and Langmore (2015) Coevolution is linked with phenotypic diversification but not speciation in avian brood parasites
にも紹介がある。
托卵性のカッコウ類では非托卵性のものに比べて色の進化は3倍早く、下面の縞模様、黄色の目と足などのタカに似た形質は速く進化するがそれ以外の色彩進化は速くなかった。色彩でタカに似ているのは偶然ではなく有利との仮説を裏付ける。
アカメテリカッコウ Chrysococcyx minutillus Little Bronze-Cuckoo では縞模様があるが、近縁のミミグロカッコウ Chrysococcyx osculans Black-eared Cuckoo では失われているなど (擬態に必要な) 進化が短時間で起きることを裏付ける (なおミミグロカッコウはオーストラリア内陸部に分布で小鳥食のタカ類が少ない)。
オオチュウカッコウ類 Surniculus がオウチュウに擬態していると考えられることもカッコウ類では多様な種に対する擬態が色彩進化 (ただし種分化にそのままつながるわけではない) を促した可能性が考えられる。
しかしながら、同じく托卵性のミツオシエ類 (キツツキ目) では逆の傾向になっていて、色彩も目立たない。隠蔽色が托卵に有利かどうか検証が必要である。
広範な種類を托卵相手にするグループほど表現形が多様と予測できるが、托卵相手が一番多様なミツオシエ類では逆になっている。
宿主の種類 (ここでは属) が広範かつ地理的に分布が重なっている托卵種 (例えばオーストラリアの托卵種) の間で競争があり、その結果より精密な擬態が進んで表現形の進化が速い可能性がある。
カッコウ Cuculus 属では托卵性カッコウ類の中でも表現形の進化が比較的遅いが、これは托卵種の間で宿主の重なりが小さく、地理的に広範に分布している (旧世界に広く分布) ためとも解釈できる。
この論文で調査対象となったのは世界の3大托卵系統である托卵性カッコウ類、ミツオシエ類、テンニンチョウ科 Viduidae とのこと。他の系統にも托卵種は存在するがここでは解析対象とはなっていない。
Gluckman and Mundy (2013) Cuckoos in raptors' clothing: barred plumage illuminates a fundamental principle of Batesian mimicry
カッコウ類の縞模様は同所的に生息するタカに似ている。他の地域のものとは関連がないとのこと。
さらにカッコウ類の系統進化と模様の進化、色彩の多形の関係を調べた論文: Thorogood and Davies (2013) Hawk mimicry and the evolution of polymorphic cuckoos
タカに似ているかどうかの系統樹を見るだけで十分面白いと思う (この文献の系統樹でカッコウ類全体の系統関係もわかる)。我々が日本で普通に出会うカッコウ類は カッコウ属 Cuculus とジュウイチ属 Hierococcyx で、カッコウ類の一番新しい系統になる。
これらの系統は #ジュウイチの備考で考察のように Tachyspiza 属や狭義 Accipiter 属の分布とよく合っているため、我々が普通に出会うカッコウ類は皆タカに似て見えるのだろう。
この文献ではジュウイチはタカに似ているマークが付いていないが、種が分離された後の情報をチェックしていないのか? フィリピンジュウイチもマークが付いていないがミナミツミでよいだろう (#ジュウイチの備考)。
これらも含めるとカッコウ属、ジュウイチ属 (すべて托卵性) でタカに似ていないのは系統的には最も古いクロカッコウ Cuculus clamosus Black Cuckoo (アフリカ南部) 1種のみとなる。サバンナ型と森林性の2亜種があり、サバンナのものは黒いとのこと (サバンナには小鳥食のタカがいないと思えば納得できる)。
森林性のものは喉が赤く腹は縞模様ものがあるようで Cuco negro (Cuculus clamosus) のようで、"Hawk-like, polymorphic" に分類してよさそう。
Coucou criard - Cuculus clamosus でも写真が見られる。
対応するタカ類は複数考えられるが ムネアカオオタカ Aerospiza toussenelii、同種ともされる アフリカオオタカ Aerospiza tachiro、ニシアフリカツミ Tachyspiza erythropus Red-thighed Sparrowhawk
などが有力か。広義 Accipiter 属は熱帯ほど赤みの多い種類が増えるので色の対応はよい。
新しい研究でオオヨシキリはカッコウの目の特徴を認識しているとのこと: Yan et al. (2025) Cuckoo eyes are an important identification cue for the Oriental reed warbler host。
関連の先行研究: Trnka et al. (2012) Uncovering Dangerous Cheats: How Do Avian Hosts Recognize Adult Brood Parasites?。
以降の話は Catanach et al. (2024) の系統樹と比較しながら見ていただくとわかりやすいだろう。
広義 Accipiter 属の最初に分化したアフリカオオタカ属 Aerospiza はアフリカで適応放散を遂げたため、同地で適応放散したカッコウ属には非常に都合がよかった可能性がある。ツミ属またはアカハラダカ属 Tachyspiza もアフリカ由来系統。
カッコウ属 + ジュウイチ属の共通祖先 (おそらくアフリカ発祥) でタカ類の適応放散に合わせた擬態を確立させたのだろう。
TimeTree のツールを使ってみるとカッコウとジュウイチの分岐年代は 1270 万年前ぐらいとなる [文献は Price et al. (2014) Niche filling slows the diversification of Himalayan songbirds とのこと]。タカ類のアフリカでの適応放散時期とよく合っている。
他の托卵系統のカッコウ類では Surniculus 属 (オオチュウカッコウ類) はタカではなくオオチュウ類に。ただし擬態が有効かどうかはよくわからない。Surniculus 属の分布域にも現在はタカは存在するので、タカがいないのでオオチュウ類に、というわけではなさそう。
オオチュウ類 (Dicruridae) の適応放散の時期は見積もられていて [Pasquet et al. (2007) Evolutionary history and biogeography of the drongos (Dicruridae), a tropical Old World clade of corvoid passerines]
アジアで 1190 万年前、アフリカで 1330 万年前とのこと。広義 Accipiter 属もあまり違わないのでオオチュウ類の方が先に現れてそちらが先に選ばれたのかも知れない。
オオチュウ類はスズメ目のカラスにつながる系統で、常識的に考えればタカの方がずっと古くからいるように思えるが、実はどちらが早いか微妙なぐらいにタカは結構新しい。Surniculus 属はアジアに分布なので、おそらくアジアのオオチュウ類の適応放散に合ったものだろう。
Surniculus 属に近縁の Cercococcyx 属 (オナガカッコウ類) はアフリカに分布でタカのような縞模様。
Cercococcyx 属 + Surniculus 属 の系統はいずれもタカかオオチュウ類を真似ているようだが、後者がアジア (タカ類到着が少し遅れたかも) だったためオオチュウ類を選択したかも。
さらに系統を遡ると Cacomantis 属 (ヒメカッコウなど) でアジアからオーストラリアに分布。多くはタカのような模様があるが、古い系統の種にはないものもあり、Cacomantis 属の中でも新しいものがタカのような模様を生じた模様。
タカのような模様がないとされる古い方の系統は
ハイイロカッコウ Cacomantis pallidus (オーストラリア)、
ユキボウシカッコウ Cacomantis leucolophus (ニューギニア)、
クリハラヒメカッコウ Cacomantis castaneiventris (ニューギニア)、
ウチワヒメカッコウ Cacomantis flabelliformis (オーストラリア、ニューギニアの一部から太平洋島しょ部)
と確かにタカ類の種類が少ないか到達が遅れた地域になる。この地域の主要種は Tachyspiza 属でアカハラダカに近い系統が何度か定着したよう。最も古い系統のアカハラダカで 700 万年前で、オーストラリア地域への分散はさらに新しくて 300 万年前前後程度 (そんなに新しいの? と思えるぐらい)。
Tachyspiza 属はアフリカで誕生したため到着に時間がかかったこと、他の小鳥食系統タカ類は比較的寒冷な気候への適応や大陸がつながっていないことなどが理由で赤道を簡単に越えられなかったのだろう。
こちらで種分化したハイイロカッコウなどの初期系統の段階ではタカがまだいなかったかも。
もっとも北半球のカッコウも実は大差なく、こちらは主にハイタカ (+ 他の広義 Accipiter 属) のユーラシア進出に助けられて分布を広げた (?)。ハイタカが現在カムチャツカまで分布していることと整合性がよい。より北方はオオタカ、南方はツミやアカハラダカ系統が補っていると考えることが可能そう。
ハイタカがいつごろ分布を広げたかについて、北米のアシボソハイタカとの分岐が 400 万年前ぐらいで、このころにはユーラシアの東端まで到達していて、アフリカの一番近い祖先と分岐したのが 800 万年前ぐらい。
この間にユーラシアに分布を広げたのだろう (こちらもそんなに新しいの? と思えるぐらい)。
カッコウとハイタカの類似性は Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) でも注目されていて、(英国の話) カッコウはオスのハイタカと見間違えられるほど似ていて撃たれてしまうこともある (タカは狩猟鳥を捕食するので迫害対象だった)。
カッコウの若鳥は後頭部 (原文 nape) に白斑があり、一部のハイタカにも同じ模様があるとのこと。
日本で赤色型カッコウが見られないのは、ハイタカの色彩を決める遺伝子頻度に関係があるかも知れないとちょっと思ってしまった (#ハイタカの備考参照)。
Chrysococcyx 属 (テリカッコウ類など) も事情は似ていて太平洋地域のものはタカがまだいなかったかも。
タカ模様がある ブロンズミドリカッコウ Chrysococcyx caprius と キノドミドリカッコウ Chrysococcyx flavigularis はいずれもアフリカの種でタカと一緒にいたと考えると話が合う。
カッコウとの分岐年代は 2390 万年前と推定されるので、この系統の一部しか小鳥食のタカ類と重複がなく、系統全部がタカ類に似ているわけでないことも整合性がありそう。小鳥食のタカ類が出てきてからタカ類への擬態が複数系統で独立に進化したと読める。
とはいえ Hawk-like に分類されていない ミドリテリカッコウ Chrysococcyx maculatus、ヨコジマテリカッコウ Chrysococcyx lucidus にもしっかり縞模様があるのでジュウイチ同様用いられた情報が不十分なだけかも知れない。
古い系統の中でニュージランドの托卵性のキジカッコウ Urodynamis taitensis Pacific Long-tailed Cuckoo は Hawk-like に分類されていないが、縦縞で、英語別名に sparrow hawk, home owl などがあって少なくとも人にはタカを連想させるところがあるらしい。音声はジュウイチと似たところがある。
この種と非常に系統が近いと思われるニューギニアやオーストラリア沿岸部のオオオニカッコウ Scythrops novaehollandiae Channel-billed Cuckoo もいかにもタカ類やフクロウの地鳴きを思わせる声もある。
タカに似た力強い飛び方で、ほかの鳥を襲うこともある (コンサイス鳥名事典)、また世界一大きな托卵鳥で、非托卵性も含めたカッコウ類で最大であるとのこと。ほとんどタカのような飛び方で、メスは縞模様がより強い。果実食中心とのことで、鳥のひなや卵を食べることは書かれているが鳥を食べるまでは書かれていない (wikipedia 英語版)。
Thorogood and Davies (2013) では Hawk-like らしさが感じられないが、おそらく色彩の判定基準に絞り込み過ぎで、これはほとんどタカのようなものなのではないだろうか (後述 [Otidimorphae とはいったい何者?] のようにカッコウ類はタカになりかけたがなり切れなかった?)。
それならばこの種のタカらしさは収斂進化で獲得したものか? カッコウ類のタカ類への擬態の側面だけでなく、タカ類の音声進化の解釈にも関係してくるかも知れない。
ジュウイチ類の例も含め Thorogood and Davies (2013) は文献資料が中心で実際に画像を探してみていないかも? この論文の分類に頼り切らず検証した方がよさそう。
完全に托卵性のものだけがまとまっているカッコウ類最後のクレード以外では、カンムリカッコウ属 Clamator (4種) がすべて托卵性でいずれもタカ類に似ていないとなっている。
アフリカ、ヨーロッパ南部からアジアまで分布しており、タカ類の分布とも重なっているがこちらの方は特に擬態しなかった模様。マダラカンムリカッコウ Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo は托卵相手のカササギに似ているとのこと。
#オニカッコウ備考に、オニカッコウが宿主イエガラス真似てテリトリー防衛を利用して托卵する話があり、マダラカンムリカッコウとカササギでも同じようなことが起きているのかも知れない感じがした。
まとめるとカッコウ類の完全托卵系統は初期のもの (あるいは小鳥食のタカ類がいなかった地域) はタカ類と無関係だったようだが、小鳥食のタカ類が出現してからは積極的に擬態を利用しているものが卓越している模様。少なくとも対応する小鳥食のタカ類のいる地域では擬態率がかなり高そう。
托卵性そのものの起源ではないだろうが、小鳥食のタカ類の出現が托卵性カッコウ類の適応度を上げた、言い換えれば托卵性カッコウ類はタカ類の威を借りて現在の姿になった (他の鳥の威を借り過ぎ) ?
もし小鳥食のタカ類が生まれていなければ? - カッコウ類の托卵は今ほどありふれた現象ではなかったかも。それどころかカッコウ類がタカ類に準じる生態的地位を占めていたかも (どちらにしても小動物には厄介者だったかも?)。
精度の良いタカ類系統樹が得られたことがどれほど役に立つかわかっていただけると思う。
まさしく「鷹の目で見る鳥類進化」とも呼んでもよさそうだが、本質的でもありえらくカッコいい。そのまま科研費の研究課題名に使えそうである (笑)。
川口 (2016) Birder 30(6): 50-51 はカッコウはタカへの擬態でない? 議論を行っており、根拠の一つとして田中 (2015) Birder 29(6): 28-29 で野外観察でタカに擬態して有利との証拠はないと紹介されていることを挙げている。野外観察にどこまで含めるかによるだろうが
Davies (2011) Cuckoo adaptations: trickery and tuning のレビュー論文や
Welbergen and Davies (2011) A parasite in wolf's clothing: hawk mimicry reduces mobbing of cuckoos by hosts の研究はすでになされていたので「証拠はない」はおそらく過剰であろう (*1)。
タカへの擬態の話は托卵鳥ではカッコウ類系統のみのようで、同じようにアフリカで托卵を行うミツオシエ類には当てはまらない。
こちらの方 (キツツキ目。ネズミドリ類から始まる Telluraves の系統の最後に当たる) がタカ類より一見新しい系統に思えるが、ミツオシエ科とキツツキ科の分岐年代は 3600 万年程度とかなり古く (この数字もかなり不定性がある)、小鳥食のタカ類の方が後に出現してもおかしくない。
ミツオシエ科の中ではいつ適応放散が起きたのかあまり資料が見当たらないが、Fleischer (2011) Ladies and gentes: Maternally inherited DNA and ancient honeyguide host races
ではノドグロミツオシエ Indicator indicator Greater Honeyguide では樹上性と地上性の托卵系統で少なくとも 300 万年の違いがあるとのこと。1種内でこの数字なのでミツオシエ科は小鳥食のタカ類より早い時期に種分化していたかも。
また、カッコウ類がタカに似ることができたのはやはりミツオシエ類とは異なる祖先系統の性質を引き継いでいるのでは? ミツオシエ類も原理的にはタカに似ることができたかも知れないが、系統的制約で似た模様を作るのが難しくて隠蔽色の方に進化した。それほど大きな鳥ではないので怖がってくれないなど。
ここでは小鳥食のタカ類である広義 Accipiter 属を主に扱ったが、少し気にしておいてよい系統が他にある。カッコウハヤブサ属 Aviceda でこちらは系統が古いのでカッコウ類より先に現れていた可能性がある。
カッコウ類に似た縞模様などがあり、クロカッコウハヤブサがより弱い鳥であるカッコウに擬態することで捕食を容易にする説の可能性も紹介されているぐらい (#ハチクマの備考 [ハチクマ亜科の他種] 参照)。カッコウがタカと間違われて避けられるぐらいならばこの説の信憑性も怪しい気がする。時期的にも縞模様のカッコウ類がやってきた方が後になると思える。
カッコウハヤブサ属はアフリカとアジアからオーストラリアに分布し、いずれもカッコウに似ている。カッコウハヤブサ属内の分岐年代 (アフリカとアジア・オーストラリア) は 1800 万年前ぐらい [Catanach et al. (2024) の数字による] で、この時代にはカッコウに似た模様はすでに共通に持っていたと考えられる。
アフリカカッコウハヤブサ Aviceda cuculoides African Cuckoo-Hawk の画像を見ればわかっていただけると思うが、異様にカッコウ類に似て見える。インドなどのハイタカジュウイチとよく似ているのだが地理的には合わない。
系統的にはハチクマ類の遠い親戚だが、目が比較的側面についている (これはそれぞれ別の適応の結果と考えられる) 以外は外見はあまり似ておらず、かなり遠い系統 (分岐年代 3000 万年前弱ぐらい) であろうことは想像できる。
タカに似たカッコウ類が広がったのはもっと後の時代が考えやすいので、カッコウハヤブサ属が共通祖先段階からカッコウ類に擬態している可能性は低そうに思う。逆の方ならば小鳥食のタカ類の出る前でもカッコウ類にとってモデルとなる種類が存在していたことになるが、カッコウハヤブサ属は少なくとも現在はそれほど強力な捕食者ではないので小鳥があまり恐れなかったかも。
その時代にはカッコウ類の方が強かったということはさすがにないだろうが...、もしかするとカッコウに似ることは多少のメリットがあるかも ([カッコウ類の植物毒耐性?] 参照)。
コンサイス鳥名事典にはアフリカカッコウハヤブサの若鳥がアフリカオオタカ現在の学名で Aerospiza tachiro に似ているとの記述があり擬態を示唆するものとなっているが、アフリカオオタカは Tachyspiza 属以前に分岐した系統で和名や英名から想像されるほど強力ではない。
カッコウハヤブサ属が現在はアフリカとアジアからオーストラリア隔離分布になっているが、かつては連続分布していて途中の系統が気候変動や新しいタイプの猛禽類との競争で消滅したのかも知れない (#アカハラダカ備考の [オーストラリアのタカ類] 参照)。
あるいはヨーロッパハチクマとハチクマのように共通祖先から分岐し、それぞれが北方まで渡りをしていたものが熱帯にのみ定着すれば現在のような分布になるかも知れないが想像に過ぎない。
カッコウハヤブサ属はこのような分岐年代になるがハチクマ類も古いのかといえばよくわからない。現生種はヨーロッパハチクマとハチクマ系統の2系統に分かれ、この分岐年代は 800 万年前ぐらいと意外に新しい。
もっと古い系統が消滅した可能性が高いが、ハチの子食生活が繁栄 (現在の系統の進展と分離) をもたらしたならば起源は案外新しい可能性も考えられる。我々の身近にやってきた時期はハイタカとあまり違わない可能性もある。
カッコウハヤブサ属とカッコウ類の関係同様、タカ類 (に限らないが) がいつから存在したのかは系統樹をよく検討して判断すべきだろう。学名で系統樹を読むことができる有難さが感じられる場面である...と最初の話題に戻しておこう。
改めて考えると、マダガスカルにはここで繁殖してアフリカ大陸で越冬する マダガスカルホトトギス Cuculus rochii Madagascar Cuckoo とほんんど同じような英名の マダガスカルカッコウハヤブサ Aviceda madagascariensis Madagascar Cuckoo-Hawk の両者が生息する。
マダガスカルホトトギスはかつてホトトギスと同種とされたぐらいなのでホトトギスのような模様と考えてよい。eBird を見ても識別がほとんど不可能な個体が多いとある。ホトトギスとは異なり赤色型は知られていないとのこと (系統的にもホトトギスより早い分岐なのでまだ赤色型が生まれていなかったのかも)。
マダガスカルカッコウハヤブサ (さらにマダガスカルハイタカ) が生息するのでわざわざマダガスカルに渡って繁殖するメリットがある可能性もありそうに思えてきた。北ユーラシアに注目するとカッコウ類の擬態相手のタカは広義 (旧) Accipiter 属がまず候補に上がるが、マダガスカルでは別の有力相手も考えられる。カッコウハヤブサ類の方がカッコウ類に擬態しているよりは逆の方がもっともらしそう。
参考画像 Madagascar Cuckoo-Hawk (Don Roberson 1992) マダガスカルオウチュウ Dicrurus forficatus Crested Drongo のモビングを受けるマダガスカルカッコウハヤブサ。
オウチュウ類は何でも攻撃することで有名だが、あるいは托卵相手と誤認して追い払っているのかも (??)。
アフリカ南部ではマダガスカルホトトギスよりも分岐の古い クロカッコウ Cuculus clamosus Black Cuckoo、チャムネカッコウ Cuculus solitarius Red-chested Cuckoo が繁殖するが、前者はアフリカカッコウハヤブサ Aviceda cuculoides African Cuckoo-Hawk にはそれほど似ておらずむしろオウチュウ類のような色彩。
チャムネカッコウはまずまず似ている。チャムネカッコウは南アフリカでは渡り鳥でマダガスカルカッコウとマダガスカルカッコウハヤブサの関係に似ていると言えば似ているかも知れない。タカに似せる色彩が進化したのはこのあたりからかも知れない。
カッコウ類がアフリカで進化していたころはタカの種類も多くて特定種への擬態に絞りきれなかったが北半球に進出すると広義 (旧) Accipiter 属が目立つので擬態相手が絞られて識別困難なほど似た模様に収斂したとか (ほんとうか?)。
補足:
*1: 別系統でもカッコウに似た種類があることに関連して、川口 (2016) はカッコウハヤブサを取り上げている。これはすでに紹介した。
オナガバト類 Macropygia属他数属 Cuckoo-Doves は尾が長いだけで特にカッコウに似た模様というわけではない。pheasant pigeon の別名もあり、この英語をそのまま訳せば "キジバト" になる。着眼点はやはり尾の長さだろう。
ヨコジマオナガバト Macropygia unchall Barred Cuckoo-Dove などは細かい縞模様があるがそれほどカッコウに似ていない。
マダガスカルのオオブッポウソウは #ブッポウソウの備考参照。
Cuckooshrikes (Campephaginae: Cuckooshrikes。南・東南アジアからオーストラリアに分布) も挙げられているが、#アサクラサンショウクイの備考にあるようにカッコウ類に似た主に青灰色の背中を持つことやカッコウ類に似た飛び方をすることが由来とのこと。
ヨコジマカッコウサンショウクイ Coracina lineata Barred Cuckooshrike / Yellow-eyed Cuckooshrike が例に挙げられていて下面に密な縞模様がある。
Ripley (1941) Notes on the Genus Coracina に比較表があるが、この系統の一部で腹部に縞模様があるとのこと。
一部の種類のみで縞模様がある理由は見つけられなかった。縞模様がある種類は虹彩が黄色のものが多く、アフリカカッコウハヤブサと雰囲気が似ている (特に正面姿) と言えば似ている気もするが、これをタカへの擬態と考えるのは多分考えすぎだろう。現在この地域に生息するクロカッコウハヤブサとはあまり似ていない。過去の種類まではわからない。
他にもタカに似た種類があるかどうかはカッコウがタカに擬態しているかどうかを左右する主要な問題ではないので現状よくわからないとしておこう。
なお cuckooshrikes にすべてサンショウクイの付く和名が与えられているだけなので、サンショウクイの習性を外挿してそのまま想像しない方がよいだろう。サンコウチョウを見てオウチュウの習性を予測できないのと同様。昔に付けられた名前でやむを得なかったかも知れないが、全部サンショウクイの付く和名でなく系統ごとに特徴を加味して違う系統の名前を変えた方がわかりやすかったのだろう。
英語でもサンショウクイは cuckooshrike とは呼んでおらず、cuckooshrikes 全体を日本語で表す時にやや困る気がする。
系統的には捕食者も多いカラス小目 Corvida に属し、小動物を捕食する報告もある。それほどおとなしい鳥ではなさそうなのでタカみたいにも見える外見は例えば巣の防衛など何か別の役に立つのかも。
カッコウのタカへの擬態の黒田氏の論文 (さらなる追記となったので後に挿入した) 週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 96 V-VI にカッコウのタカへの擬態 (黒田) の記事があった。黒田氏は保護されたツツドリを飼育していて威嚇に翼を広げた姿勢に驚かされたとのこと。スケッチが示されていた。
宿主の注意を引く仮説では Paulussen (1957)、威嚇効果では Makatsch (1955) が低く飛んで仮親の飛び出しを誘い、巣の位置を明らかにするなど提案されていたらしく、アイデアは古くからあったらしい。よく托卵される宿主では擬態と本物のタカの識別能力が高まり、地上性のものは識別能力が高くないとの研究もすでにあったらしい。
宿主の識別能力の進化によって擬態効果が次第に弱まったとしても、黒田氏自身が驚かされたように托卵の際の威嚇効果は継続するのではと考察されていた。またタカ斑は獲物への威嚇効果を想定しており、自分より大きな獲物を捕る種類で発達しているが例外もあると書かれていた。
古くから議論・研究されているテーマなので新しい論文ではあまり言及されていない研究もあるようだが、黒田氏自身の論文があった Kuroda (1966) 猛禽斑とカッコウ類のタカ斑の起原について。
(和文抄訳) ハチクマはヂバチを食べる弱い種でありながら、タカ斑を示す (とくに尾) 例外といえるが、これは他の猛禽とくに大型のクマタカの攻撃に対する予防的擬態であると考えうる (中略) セレベスのクマタカ Spizaetus lanceolatus とハチクマ Pernis celebensis は、幼鳥は幼鳥、成鳥は成鳥に極めて類似している。この鳥では、後者はその擬態によって種を維持できたとさえ考えられる とまで書いてある。
「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) p. 107 に示唆されているものと同じ考えだが、クマタカは強く、ハチクマはよほど弱くて擬態に頼らなければ生きて行けない鳥と思われていたことがわかる。
もっともこの部分は Warncke (1961), Maerz (1954), Meyer and Wiglesworth (1898) を組み合わせたらしい。このようにして伝えられて "ハチクマ観" が熟成されて行ったのだろう。
Makatsch (1955) は "Der Brutparasitismus in der Vogelwelt" に登場する Scheuch-Flug とのことでドイツ語論文なので近年の同種研究の引用に登場しにくいと想像できる。
Paulussen (1957) はどの文献かわからなかったが、姓よりおそらくドイツと思われる。黒田氏はドイツ語文献に親しんでいたらしいことが想像できる (おそらく鳥類学用語にも多大な影響を与えているだろうことも理解できる)。
Kuroda (1966) によればタカ斑を持たない点でイヌワシは例外だが、このグループは比較的弱いものを捕えるアシナガワシなどの小型種から進化したものと考えられる、これもしばしば聞くので "イヌワシ観" の熟成に役立ったかも知れない。現代的視点から見ると Aquila 属と Clanga 属は近いが別系統。これをまとめるならばクマタカ類も同一系統となって、タカ斑の目立つものも黒っぽいものも系統的には混ざっていてこのような単純な描像にはならない。
黒田氏自身もイヌワシを頂点に置く風潮に疑問を持たれていたのだろうが、現代的な分子系統樹と比較するとあまり的を得ていたわけではなかった模様。
もっとも本稿の別項目でも述べている通り、イヌワシ類はタカ類の中では比較的古い系統にあたる (#クマタカの備考 [クマタカ類の隔年繁殖の理由?] 参照)。
カッコウの項目なのにタカの話が中心になってしまった。カッコウ類のタカへの擬態の参照文献の原点の一部がわかったのでよしとしよう。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 96 p. 7 本文の方ではカッコウ類のタカへの擬態は Frank Finn (イギリス 1868-1932) が 20 世紀初頭に述べたとのこと。実際には Wallace (1889) が先に提唱していたので、Finn は後追いしたか独立に考えたのだろう。
The Birds of Calcutta (1901) などインドの鳥の書物が有名で、ハイタカジュウイチ (和名もあまりにそのまま) Hierococcyx varius Common Hawk-Cuckoo とその現地名 Brain-fever bird を紹介した。
The Rousing Call of the Common Hawk-Cuckoo (Prerna Gupta 2023)。タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia Shikra とあまりにそっくり。
[カッコウ類の植物毒耐性?]
#ヤマガラ備考 [ヤマガラの植物毒耐性] で考察するように意外な可能性が浮かび上がってきた。
Na/K ポンプの α-サブユニットの遺伝子解析により、非托卵性のものも含めてカッコウ科はある程度の植物毒 (毒虫) 耐性を持っている可能性が考えられる。カッコウ科は植物毒を持つ虫やそれに擬態する虫への特別な適応を遂げて他の鳥があまり食べない食物を食べる生態的地位を開拓したのかも知れない。
#オニカッコウ は有毒な植物の実を食べられるとのことでこの解釈に当てはまる。
毒虫を食べた場合はカッコウ類自身も多少の毒性を持つ可能性があり、タカ類にはこの耐性はなさそうなので、カッコウ類を食べて気分が悪くなったタカ類がカッコウ類のパターンを忌避しているかも知れない。タカ類にあまり妨害されずタカ類への擬態を成功させる要因の一つになっている可能性があるかも。
もしカッコウ類が多少なりとも有毒なのならば、カッコウ類に擬態することは捕食を避ける理由になり得るかも知れない (前述のカッコウハヤブサ類など)。いずれも実験的検証はないだろうが遺伝子からは想像可能に思える。
カッコウ科以外の托卵系統でタカ類への擬態が見られない (そもそも擬態する適切なタカ類がいない場合もあるだろうが) 一つの要因になるかも知れない。
田仲 (2023)「野鳥」2023年5・6月号 (No. 804) pp. 28-29 にインドネシアでオオバンケン Centropus sinensis Greater Coucal に薬効があるとされており、巣のひなの足を意図的に折り、親がひなに薬草を運ぶのを巣ごと捕えてオイルが販売されているとのこと。
薬効は迷信かも知れないが、耐毒性があるかも知れないことを考えると薬草を運ぶ行為は実際にあるのかも知れない気がした。鳥自身の色彩も黒と茶色で、毒性があって警告色になっている可能性もあるのかも?
wikipedia 英語版によれば、民間薬として結核や肺病に効くとして肉が食べられたことがあったとの記述がある。
Species Spotlight: The Greater Coucal (Hailey Brophy 2023)
によれば有毒なヘビ Banded Krait, Saw-scaled Viper を食べているのが観察されている。
また有毒な Oleander fruits を食べることが知られているという。
ここでも田仲氏の紹介された現地の薬効について記述されている。
しかし英国からの入植者時代はオオバンケンの形態がキジ類に似ているため美味しいだろうと考えたが、ひどい味だったと驚いたという (毒性があるかも?)。
「動物たちの地球 鳥類 I 10 カッコウ・ホトトギス・エボシドリほか」(週刊朝日百科 朝日新聞社 1991) p. (6) 310 の丸武志氏の解説記事で、カッコウ科は前胃は壁が厚く、毒を無毒化する液を分泌するようだとある。この効果もあるかも知れないが、遺伝子レベルで植物毒耐性を持っていればより本質的で有利だろう。
[カッコウ類雌雄の擬態の進化]
Merondun et al. (2024) Evolution and genetic architecture of sex-limited polymorphism in cuckoos
に興味深い研究が報告された。Color variants in cuckoos: The advantages of rareness (英文解説記事)。
色彩多形 (polymorphism) を示すカッコウとツツドリで研究者たちが灰色形と呼んでいるタカに似た模様のものと、赤色形 (rufous plumage, hepatic 肝臓色とも呼ばれる) があることはよく知られている。オスは赤色形を示さないが、赤色形はメスのみで見られる (ヨーロッパのカッコウでは一般的なようだが日本のカッコウでは聞いたことがない気がする)。
宿主が産卵に訪れるメスと擬態相手のタカ類を見分ける能力を持ったことによる選択圧の結果と考えられ、宿主の目を欺きやすいめったにみられない赤色形を遺伝子プールに持つことが有利であると考えられていた。
「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」(ニック・デイヴィス、中村浩志、永山淳子訳 地人書館 2016、原著 "Cuckoo: Cheating by Nature" Nick Davies, Bloomsbury Publishing 2015)
にも記述がある (訳書 pp. 171-172)。幼鳥と紛らわしい色彩であると指摘する研究もある。
上記 Thorogood and Davies (2013) も参照。
ゲノム解析の結果色彩多形は W 性染色体で決まっており、メスのみが赤色型を示す理由が明らかになった。系統解析の結果、この特徴はカッコウとツツドリが種分化する前に獲得されたものと考えられる。
ホトトギスは系統樹に出てくるが赤色形は図には現れていない。赤色形の存在するホトトギスも同様に解析すればあるいは系統をさらに遡ることになるかも知れないが、(色彩多形を聞いたことがない) セグロカッコウが途中の系統になる。どうだろうか。
ツツドリと同種とされていたヒマラヤツツドリ Cuculus saturatus もツツドリ同様の赤色形がある。この研究で用いられたツツドリのサンプルはロシアのもの。
この結果の面白い点は、[青い卵を産むカッコウ] で紹介したように「青い卵」の遺伝子はミトコンドリアにある点とも整合性がよく (この類似点は論文でも言及されている)、いずれも托卵を行うメスへの選択圧を強く示唆すること、種分化以前に獲得された形質であることが共通点として挙げられる。
さらに Medina and Langmore (2015) の色彩の進化速度の研究もあわせて、宿主はやはりタカらしい鳥を避けているらしい傍証になるのだろう。
種分化以前に獲得された形質であったならばセグロカッコウに赤色形が見られない (形質を失った) 理由も何かあるのだろう。宿主の違いによって擬態相手のタカ類を見分ける選択圧が異なりまれな形質は失われてしまったのだろうか。#ミサゴ備考の [オウム類・ハヤブサ類の年代推定] でフクロウオウム (カカポ) の色彩二形が維持されるメカニズム (頻度依存選択) を取り上げた論文を紹介している。こちらは捕食者の色覚を想定している。
この研究では捕食者絶滅によってフクロウオウム (カカポ) の色彩二形が時間とともに失われるシミュレーションが行われている。セグロカッコウのように失われた系統があるのであれば、カッコウ類の赤色型は積極的な維持メカニズムがあってこそ存続することを一層示唆するのかも知れない。
多少は考えておくと、ここで調査された系統のうちではセグロカッコウの分布が最も低緯度で宿主の好みも異なることが影響しているかも知れない。記述されているようにオウチュウ類に托卵するならば北方のカッコウ類の好む托卵相手より一層攻撃的で見境なく攻撃するかも知れない。文献までは調査していないがオスに対する攻撃を逆に利用する戦略も示唆されている。オスに対する攻撃が托卵戦略に含まれるならばメスの赤色形はあまり効果がなく失われてしまったのかも。一つのアイデアとして提供しておく。
なお卵擬態の系統の遺伝子がミトコンドリアにあることはより早くから知られていた: Gibbs et al. (2000) Genetic evidence for female host-specific races of the common cuckoo;
Marchetti et al. (1998) Host-Race Formation in the Common Cuckoo も参照。
メスの色彩多形の解釈には赤色形はチョウゲンボウへの擬態である解釈もかなり受け入れられていた模様: Trnka and Grim (2013) Color plumage polymorphism and predator mimicry in brood parasites。
宿主による識別実験に加え、スロバキアではハイタカよりもチョウゲンボウの分布の方が連続的でこの仮説を支持するとのこと。赤色形の比率が低いことを説明できているわけではないようだが、色彩多形の問題はまだ決着していないかも知れない。
また Lee et al. (2019) Common cuckoo females may escape male sexual harassment by color polymorphism
で紹介されているように、"harassment avoidance hypothesis" 仮説 (オスからの過剰なアプローチを避ける) もある。
Lee et al. (2021) Host-dependent dispersal demonstrates both-sex host specificity in cuckoos
の韓国の研究によればカッコウの宿主嗜好性はメスだけではなくオスにもある。オスの方が早く渡ってきてメス不在の状況で宿主密度の高いところを見つける必要があるので、オスにも宿主嗜好性がある要因となる。W 性染色体を通じて宿主嗜好性が伝わるメカニズムのみではこの結果を説明できない。
これまでの考えではオスには W 染色体がないので宿主嗜好性による種分化が起きない理由と考えられてきたが、オス・メスの交配がランダムに起こることで種分化を防いでいる可能性がある。
成長の過程で宿主または場所への刷り込みが起きるメカニズムも提案されている。
この論文ではこの時点で未発表データでこれらの個体群がアフリカに渡ることが判明しているとのこと [前出 Lee et al. (2023) で発表]。ホトトギスについては明瞭な根拠は示されていないがやはりアフリカに渡ることを想定している模様。
Langmore et al. (2024) Coevolution with hosts underpins speciation in brood-parasitic cuckoos
カッコウ類全般において托卵性が高く卵排除を行うもの (highly virulent cuckoo "強毒性カッコウ" と呼んでいる) ほど種分化頻度が高い (Cuculus 属など)。
宿主がとる対抗手段が種分化を促していると考えられる。
またオセアニアのテリカッコウ類を用いて、同じ托卵相手を用いる種でも assortative mating が起きている遺伝的証拠を見つけたとのこと。この解釈の一つにオス・メスともに宿主や環境への刷り込みが考えられる。
テリカッコウ類では (オス・メスいずれでも) ひなの色調が宿主に関連しており、母系だけでない複数の遺伝子が関与しているはず。
いずれも共進化が種分化を促す生物学でおそらく普遍的な現象を明らかにする結果となっている。
Study shows cuckoos evolve to look like their hosts―and form new species in the process (一般向け英語解説)。
[カッコウ類の足と近縁系統]
カッコウ類は対趾足 (zygodactyl) で前後に2本ずつの趾がある。
現生鳥類では少なくとも3回独立に進化したとのこと。キツツキ類、オウム類とカッコウ類で Telluraves 以外ではカッコウ類とエボシドリ類 (後者は semizygodactyl) が唯一とのこと
[Botelho et al. (2014) The developmental origin of zygodactyl feet and its possible loss in the evolution of Passeriformes]。
この論文はセキセイインコの足の発生を調べたものでカッコウ類は特に詳しく扱われてはいない。
エボシドリ類は果実食への適応で、外趾の関節が柔軟で前後に動き、細い枝先にも止まることができるとある (コンサイス鳥名事典)。
#鳥類系統樹2024 によればカッコウ目 Cuculiformes と エボシドリ目 Musophagiformes は単系統ではなく、カッコウ目に最も近縁なのはノガン目 Otidiformes となる。ノガン目では後趾がないが地上を走行する鳥では失われる傾向がある。
ノガン目では地上生活への適応で再度失われたなどの経緯があるのだろう。
Luo et al. (2023) A high-quality genome assembly highlights the evolutionary history of the great bustard (Otis tarda, Otidiformes) とは異なる系統樹となっている。
なお dos Santos et al. (2020) Chromosomal evolution and phylogenetic considerations in cuckoos (Aves, Cuculiformes, Cuculidae)
によればこれら3目の間で染色体構成が大きく異なっている報告がある。同様の事象はコンドル類・ミサゴ・タカ類の間でも生じているので、染色体構成から系統関係を述べるのは難しいのだろう。それぞれの系統が離れていて、しかも染色体再構成が短期間に大きく起きたグループなのだろう。
Kretschmer et al. (2024) Understanding the chromosomal evolution in cuckoos (Aves, Cuculiformes): a journey through unusual rearrangements
によればカッコウ目の中でも見られるとのこと。これは dos Santos et al. (2020) にもあってカッコウ目は最低3グループに分けられるとのこと。
O’Connor et al. (2024) A Bird’s-Eye View of Chromosomic Evolution in the Class Aves
にも (当時の) 分子系統樹と染色体再構成の関係が出ている。あるグループで染色体再構成の頻度が高い理由は新しい生態的地位を占める過程に関係するかも知れないがよくわからない。
2020年の研究と同じグループなので、分子系統研究によってこれら3目の間の関係がより支持されるようになってきて解釈を変えざるを得ないのだろう。
ハイイロエボシドリ Crinifer piscator Western Plantain-eater は掛川花鳥園の人気者になっているが [北條 (2021) Birder 35(6): 46-47 参照]、容貌も猛禽類に似たところもあって人懐こく Telluraves 以前の系統なのにずいぶん賢く見えて気になっている。
記載時は何と Falco piscator Boddaert, 1783 と広い意味でタカの仲間にされていたのもうなずける。初期に記載された図版はこの鳥よりもサンショクウミワシではないかとの疑いも持たれたこともある (wikipedia 英語版より)。
物まねがうまいとコンサイス鳥名事典にある。Telluraves 以前の系統で音声模倣をするならば画期的 (#ハクトウワシの備考も参照) なのだが文献が見当たらない。賢そうな表情を見るとそのような能力があってもよさそうにも見えるが。
ten Cate (2021) Re-evaluating vocal production learning in non-oscine birds
の非スズメ目の音声学習の論文にも出てこない。カッコウ目で餌乞いの声を真似るとの報告はあるが関係はあるだろうか (もちろん托卵で生まれたひなには有利に働くだろうが)。
カッコウ目とは印象がだいぶ違う感じがするので独立した系統となったことは理解しやすい感じがするが、カッコウ目とノガン目があまり似ているようにも見えないのが不思議。
ノガン目 + エボシドリ目 + カッコウ目 には特有の祖先形質があって音声学習なども可能にできたのかも知れないが、変わったグループだけが現存しているため一見関係がわからないだけかも知れない。
ten Cate (2021) の系統樹では音声学習がよく知られているハチドリ類に並ぶが、現代の知見では Elementaves と Columbaves レベルの違いがあって直接の系統的類縁性はなさそう。
エボシドリ目 (turacos) では緑と赤の色彩に銅を中心としたポルフィリンである turacoverdin と turacin をそれぞれ用いており、鳥類で唯一知られる緑の色素とのこと。生息地は銅の産地としても有名、天敵からの保護色の役割が考えられている。
銅は生体に有害であるが鉄ポルフィリンを多く含む食物を食べることで無害化して色素として用いているなどの記述がある (wikipedia 英語版)。いずれも比較的古くから記述されているが現代的な研究はあまりなされていない模様。
ポルフィリンを蛍光色に用いる鳥については #オオルリ備考の [蛍光を用いる鳥] も参照。
Porphyrins: The Colors of Life。
エボシドリ目では幼鳥の翼に爪があって登るのに用いるという。この点からツメバケイとの類似性が示唆されたが最新研究で関係がないことがわかった。群れで生活し、大声で警告音を出して天敵を追い払うという (wikipedia 英語版から)。
カッコウ科に属するミチバシリ類オオミチバシリ Geococcyx californianus Greater Roadrunner と コミチバシリ Geococcyx velox Lesser Roadrunner はほぼ地上性であるが対趾足で X 字の足跡が残るという。
樹上性ではないが木にはとまる。Roadrunner: Meet the Real Bird Behind the Cartoon (Justine E. Hausheer 2021, 2023)。巣も樹上に造る。後趾は走行の邪魔になるとよく言われるが、ミチバシリ類のこの形態は高速走行に適した足なのだろうか。
#ハチクマ備考の [ロシアのハチクマとヨーロッパハチクマの研究のための情報] でハチクマの足跡・歩き方に関係する情報に考察を加えた。
同様の形態を持つ化石鳥類があった: Earliest zygodactyl bird feet: evidence from Early Cretaceous roadrunner-like tracks
最初の対趾足の鳥類 (5000 万年前) の記録で、ミチバシリと同様の生態的地位を占めていたのでは。
この論文によれば樹上性の鳥での収斂進化の産物と考えられており (カッコウ類も同様)、ミチバシリは祖先系統を受け継いだものと考えている。この化石鳥類はキツツキ類の足の適応とは多分異なる。足跡だけでどの系統に属するかを考察するのは難しいとしている。
[非対称な色彩の虹彩を持つコミチバシリ]
van Dort and Juraez (2024)
Eye colour is geographically variable in Lesser Roadrunner Geococcyx velox Wagner, 1836
コミチバシリ はこれまで複数の亜種が提案されたが個体差とされ現状のリストでは単形種とされる。Macaulay Library の画像データを調べ、虹彩の色が地域個体群として判別できる特徴である可能性を示した。遺伝的な背景が示唆される地理的分布となっており遺伝情報の研究が望まれる。
オオミチバシリでは瞳孔の周囲にほぼ完全な淡い帯があるが、コミチバシリではほとんどの場合不完全で黒い部分が虹彩の前下方にある (heterochromia)。ミチバシリ類での環境適応意義は調べられていないが、開けた場所で採食するミフウズラ類やタゲリ類では獲物を探す際に日光の反射を抑制する (ハヤブサ髭と同様) 意義があると考えられているとのこと。
タゲリ類 (ズグロトサカゲリ Vanellus miles Masked Lapwing の亜種 novaehollandiae の論文: Cardilini et al. (2022) Dark heterochromia in adult masked lapwings is universal, asymmetrical and possibly slightly sexually dimorphic。5.4% の鳥類種に認められる特徴とのこと。
ミフウズラ類の論文: Gutierrez-Exposito (2019) Asymmetric iris heterochromia in birds: the dark crescent of buttonquails
ミフウズラ属 (Turnix) の全ての個体のあらゆる成長段階で見られるとのこと。選択圧の産物と考えられる。
[カッコウは変温動物?]
ミチバシリ (350 g) は夜には体温を大きく下げることが知られている (砂漠に近い条件で夜は冷える)。
Vehrencamp (1982) Body Temperatures of Incubating Versus Non-incubating Roadrunneers
によれば抱卵中でも体温が下がる。夜の抱卵はほとんどオスが行う。外気温 10 ℃ になる朝方は体温は 34 ℃ まで下がる。抱卵するメスも同様だが、抱卵していないメスの方がさらに下がるとのこと。このタイプの夜間に体温を下げる鳥では抱卵に余分なエネルギーを要することを示している。
なお捕獲にはネズミを餌にした猛禽類用のトラップなどを用いたとそうで、習性は確かに猛禽類に近いよう。
McKenchnie et al. (2002) Avian Facultative Hypothermic Responses: A Review
に体温を下げる報告のある鳥の一覧がある。ハチドリ類は有名だが他にもいくつか例があるとのこと。
リストはかなりまぜこぜのようで、1℃ ぐらい下がるだけのものも含まれているようで測定法も多分まちまち。カッコウ類に多いのかと気にしてみたが、他に出ているのはオオハシカッコウ Crotophaga ani Smooth-billed Ani のみで数字的にはミチバシリと同じぐらい。もっと派手に体温を下げるものもあるのでそれほど目立っていない。
同著者による学位論文 (2001): Patterns, Mechanisms and Evolution of Avian Facultative Hypothermic responses: a southern African perspective。
McKenchnie et al. (2023) Avian Heterothermy: A Review of Patterns and Processes
に新しい総説があるが、異温性 (heterothermy) の強い種は古い系統に多いとのこと。スズメ目強い異温性が見られない理由はよくわかっていない。
カッコウ類の托卵習性は体温を保つ能力が低いことに由来するとの仮説をどこかで読んだことがあって調べたものだが最初は文献を見つけられなかった。後に調べて Ando (1995) Fluctuation of body temperature and cuckoo brood parasitism と判明。
その後日本語で読める資料に気づいた: 「動物たちの地球 鳥類 I 10 カッコウ・ホトトギス・エボシドリほか」(週刊朝日百科 朝日新聞社 1991) p. (6) 309 に安藤滋氏の解説がある。温度センサーと送信機を付けて野外生活中に測定したもの。1日に 10 ℃ 近近い温度差があっては恒温性がよいとはいえない。爬虫類に近い特性である、と記されている。
この測定は体表面で行われているので外気温の影響をかなり受けそうである (我々でも体が冷え切った場合に通常の方法で体温を測ると 35 ℃ ぐらいしか出なくて測定値にならないことも体験する)。
卵が体の割に小さいことも夜の低体温から説明できるのではとしている。
この変温性のアイデアは爬虫類の残存特徴として考えられたもので、「変温性」の残存特徴を持つ鳥がいても驚くに当たらないと考えて研究を始めたとのこと。哺乳類の方が冬眠する種類は結構あるがそれが爬虫類的との解釈は聞いたことがない、爬虫類とのアナロジーを強調しすぎの感じがする。
#ヨタカの備考 ["冬眠" する鳥] でも取り上げた。
「知っているようで知らない鳥の話」(細川博昭 SBクリエイティブ 2017) p. 61 でも紹介されている。
派生する研究が見当たらないので、世界的には広く受け入れられている仮説ではないのだろうか。
「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」 p. 182 にはカッコウは産卵前に 24 時間の体内抱卵を行って産卵から孵化までの時間を短縮しているとある。その時のメスの中心体温は 40 ℃ で 24 時間の体内抱卵で相当の時間が稼げる、宿主に抱卵される時は 36-37 ℃ とあり。
体内抱卵のアイデアを最初に取り上げたのは Montagu (1802) Ornithological Dictionary が最初とのこと。Birkhead et al. (2011) Internal incubation and early hatching in brood parasitic birds が複数の系統の托卵種を用いた実験的検証を行っている。
中心体温は 40 ℃ というのはカッコウの実測値ではなく一般的な文献値のよう。40 ℃ の孵卵器で実験したキンカチョウの胚の発達がカッコウの胚で予測される発達段階とよく似ているので、おおよそこのように考えて構わないだろうとのこと。
托卵しないカッコウ類でも産卵間隔は2日で、托卵のために進化したというより受け継いだ形質が有利に働いていると解釈されている
(predisposed の表現はおおよそ前適応 preadaptation のようなものと解釈してよいだろう。Preadaptation may render some species predisposed for evolutionary response to new pressures のような文脈で使われる。Birkhead et al. では early hatching may have predisposed certain species to become brood parasitic)。
体温を保つ能力が低い説はどうも否定的なよう。Ando (1995) はこの文献でも引用されておらず、おそらくほとんど知られていないのだろう。もしかすると日本でのみ知られている仮説か?
ミチバシリの体温変化は昼と夜の温度差が極端な乾燥気候への一般的適応のように見える。
参考までに Bildstein (2017) "Raptors" から猛禽類で夜間体温を下げる (torpor) の事例をチェックしておくと、上記文献をそのまま使っているようで新旧大陸ハゲワシ類が挙げられている。これは昼夜の気温差の大きい乾燥気候で裸出部の多いハゲワシ類がエネルギー消費を抑える生理的対応でよいだろう。
そのため朝は日光を浴びて体温を上げる行動もあるとのこと。アカオノスリで2 ℃ 下がる報告もあるが、猛禽類ではそもそもあまり調べられていない。
最近になってアフリカカッコウ Cuculus gularis African Cuckoo (托卵種) の測定値が出ている: Voges et al. (2024) Functional role of metabolic suppression in avian thermoregulation in the heat。
もちろん他の種類も測定されている。基礎代謝率の体温依存性は他の種より大きい傾向があるが、体温がそれほど低いわけではなく同等の種も他にある。外れ値的ではあるが際立って変温動物というほどではなさそう。論文中でも托卵習性との関係は特に述べられていない。
高温環境で積極的に基礎代謝率を下げて体温調節を行う傾向が広い系統に認められる結論となっている。
化学反応の温度依存性を示すアレニウスの式 (Arrhenius equation, Arrhenius effect) の係数を求めてほとんどの鳥は化学反応の温度依存性より低い依存性を示した。
川口 (2010) Birder 24(10): 60 で「鳥の足は変温的で冷たい水につかっていると0 ℃ 近くになることもあるとか。それでも凍傷にならないのだ。形態だけでなく生理的にも爬虫類的ってこと」とある。
鳥類学、あるいはもっと一般的な生物学の教科書にも書いてあるだろうと思うが、多くの鳥にとって熱が最も逃げやすい足を冷やしてエネルギー消費を抑えている。むしろ恒温動物的ということ。
奇網 (rete mirabile) と呼ばれる動静脈からなる構造が対向流交換器 (countercurrent exchanger) この場合熱交換器 (heat exchanger) として働いて冷たい血流が中心体温を下げるのを防いでいる。他にも動静脈シャント (短絡) もある。
対向流交換器は熱交換以外にも塩腺のナトリウム排泄に使われる。鳥以外の生物でも用いられているが、水鳥の末梢温の制御は特に有名。「生態学入門」(日本生態学会 2004) ではイルカのヒレが取り上げられている。イルカが生理的に爬虫類的と言う人はさすがにいないだろう。
鳥ももちろん凍傷になる。Wellehan (2003)
Frostbite in Birds: Pathophysiology and Treatment
上記のような適応限界を超える寒冷に晒されると血管が収縮して、時々血管が拡張することで組織損傷を防ぐ (hunting reflex)。さらに寒冷状態が続くと血管拡張が起きなくなって主に虚血性の組織障害が起きる (いずれもヒトの場合と同じ)。
足に起きることが多いが、手でも起きる (wing tip oedema, distal wing necrosis #ハチクマの備考 *2: Wing tip oedema in raptors を参照)。
足は交互に暖めることができても手はそうもいかない。これはさすがにかわいそうに思える。
(主に足の凍傷の) 治療も述べられていて哺乳類と同様に迅速に暖める方が効率的とのこと。マッサージは外傷の原因になるので避けるべき。病態も同じで微小血栓が組織壊死の原因となる。そのため抗血液凝固作用のある (プロスタグランジン合成を阻害する) 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) が用いられる。鎮痛剤 (ここではカモの例が出てくるので水鳥も凍傷になる) や感染症防止の抗菌剤も有効である。基本的にヒトの医学と同じ。
野鳥におけるリスク原因としては異常な天候、治療のための麻酔などの措置、金属の足環、渡りコースから外れた場合などが挙げられている。
中西悟堂「定本・野鳥記」1 p.16 (1935 年初出) に飼育下のヨシゴイの記述があり、冬場は趾がしもやけになって困ったとのこと。冬は暖めて過ごしたりしたが癒らず、趾が落ちることもあったとのこと。
日本語でも古くから事例がしっかり紹介されていた。日本では夏鳥で寒冷気候適応のための奇網が発達していないのだろう。北から渡ってくる水鳥のことだけを考えると先入観のもとになる。
鳥はほとんど凍傷にならないなど書いてあるサイトもみつかるが、エビデンスのある情報を探しましょう。
Byron-Chance et al. (2024) Spontaneous Wing Tip Edema in Captive Birds of Prey: Review of 41 Cases in the United Kingdom (2004-2022) に新しい情報があったので紹介しておく。
[Otidimorphae とはいったい何者?]
系統に関係して、そういえば海外の鳥の写真を見る時に時々タカっぽく見えて種類をチェックしてしまうことがあるのだが (別項で述べるようにまるでサギのように見えたタカがあったため多少気をつけている)、しばしばひっかかる種類がバンケンの仲間 (coucals) とタカへの擬態とも言われるカッコウ類である。
この系統はそもそも現在のタカに類似した生態的地位に適応放散したのではないかと考えると都合がよいように思える。当時は後続の猛禽類はまだ現れていないし、樹上に最初に適応したハト類の祖先グループ (Columbaves) から現在における各種の生態的地位を持つ鳥が現れていたのかも知れない。
大部分の系統は Telluraves の適応放散で置き換わってしまったが一部残ったのではないだろうか。
そう思ってみてみるとカッコウ目系統は結構猛禽類的なところがある。バンケン類はトカゲ類やカエル類も食べる。アマゾンカッコウ Guira guira Guira Cuckoo (姿はカッコウと特に似ていないし托卵性でもない) もトカゲ、ネズミ、他種の鳥の卵を食べるという (コンサイス鳥名事典、wikipedida英語版)。
キバシカッコウ Coccyzus americanus Yellow-billed Cuckoo (アメリカ合衆国南部。姿はカッコウと特に似ていないし托卵性でもない) は樹上性カエル、トカゲ、他種の鳥の卵も食べるとのこと (コンサイス鳥名事典、wikipedida英語版)。
ミチバシリ類は地上を走ってトカゲ・ヘビなどを食べる。系統はまったく異なるがいかにも現代のノガンモドキ目やヘビクイワシに似ている。生態的地位は似ていると言ってよいのではないだろうか。
かつて広く分布していたとも想像されるヘビクイワシ (そしてノガン類系統) のいなかった新大陸でミチバシリ類が進化したと考えると話が整合する感じもする。
ノガンとノガンモドキの類似性は表面的なもの (収斂進化) だったが、ノガン類も食性は雑食で小型脊椎動物など小動物も食べる。
ノガン類と (我々のよく知っている旧世界の托卵性の) カッコウ類とはあまりにも似ていない気がするが、どちらも地上性の捕食者の最初の系統 (それぞれ開けた環境と森林) と思えば類似性が理解できるような気がする。地上性に適応して大型化すればノガン類のような形になるだろう。
ヘビクイワシやノガンモドキと小型のタカ・ハヤブサをいきなり比べても類似性がわかりにくいのと同様?
エボシドリ目は果実食に特化したが足の構造などは Telluraves 同様に器用さを備えているのだろう。
Remsen et al. (1990)
A classication scheme for foraging behavior of birds in terrestrial habitats
では Telluraves 以外の系統では珍しくミチバシリ類は嘴と足を使って獲物を殺すという (ノガンモドキに似ている)。Gutierrez-Ibanez et al. (2023) "Online repositories of photographs and videos provide insights into the evolution of skilled hindlimb movements in birds" (#ハチクマの備考参照)
ではオオバンケン Centropus sinensis Greater Coucal がグループの中でも足の器用な利用を発達させたとのこと。この研究では1種のみを取り上げているが観察記録が限られているだけで同系統の他の種類でも例があるのかも知れない。
このように考えると Otidimorphae は陸鳥最初の猛禽に似た系統で恐竜絶滅後いろいろな環境に進出したのだろうが、生きた動物の捕食者であることの難しさもあって、Telluraves 由来の高性能の猛禽類に追い抜かれ、一部の特殊な系統のみが現存して相互にあまり似ていないと解釈できるかも知れない (これも誰かが考えてそうな話だが...)。
姿には往時の習性の名残りがあってタカに似た形質 (旧世界の托卵性のカッコウ類) も出しやすいとか (ほんとうか?)。
Telluraves のタカ類と似た選択圧が働いて染色体再構成に共通性がある?
上記考察とは直接関係ないかも知れないが、 動物たちの地球 鳥類 I 10 カッコウ・ホトトギス・エボシドリほか」(週刊朝日百科 朝日新聞社 1991) p. (6) 308 に上田恵介氏が
「カッコウ科の鳥というと托卵習性だけが取り上げられるが、主に地上に近いところでトカゲなどの小動物を食べて生活するというニッチ (生活空間) を開拓した中型から大型の非托卵性のカッコウ類のほうが、このグループの性格をよく表していると思うのだが、どうだろうか」と述べている。同感である。
新しい情報も含めて付け加えると、上田氏の述べる空間的・捕食性のニッチに加えて、より特異的には [カッコウ類の植物毒耐性?] で述べたように植物毒を持つ虫への特別な適応を遂げ、他の鳥があまり食べない食物を食べる生態的地位を開拓し、それが現在まで受け継がれている可能性があるだろう。
なおノガン類は粉綿羽が豊富で尾脂腺もないとのこと。参考: Collar and Morales (2022) The Little Bustard and Its Family: An Overview of Relationships。
このような特徴はハト類に似たところがあり、Columbaves に属することは納得できる面もある (あるいは乾燥環境への適応と関係があるのかも?)。
[托卵と宿主の行動の進化]
日本語でも資料が十分あるので省略していたが、「これからの鳥類学」(裳華房 2002) 8章に数理生態学と鳥類学 - 托卵を題材にして - (高須夫悟) があり、当時の雑誌などでもしばしば取り扱われて、記事や論文を見る時に役立ちそうなので一度まとめておきたい。
宿主が卵やひなを排除しない理由はいくつかの説があり (簡単な方から順番に)、
(1) Evolutionary Lag 説 (Rothstein 1990 A Model System for Coevolution: Avian Brood Parasitism) 宿主の卵識別能力がまだ進化していない。
(2) Evolutionary Snapshot 説 (Davies and Brooke 1989 An Experimental Study of Co-Evolution Between the Cuckoo, Cuculus canorus, and its Hosts. I. Host Egg Discrimination) 宿主の卵識別能力が集団に広まるのに数千年程度を要し、現在はその進化途上を見ている。
(3) Evolutionary Equilibrium 説 (Lotem et al. 1992 下記, 1995) 現在すでに平衡状態となっている。托卵拒否のコストと托卵による損害が釣り合っている。
カッコウ類の托卵を議論している話はおおむねこれらの仮説のどれが当てはまるかを調べようとするものとおおむね考えてよいだろう。高須氏によれば数理生態学のモデルでは集団に広まるのは 100 年程度ともっと短いと考えられる。
特にヨーロッパでよく調べられているでも宿主ごとの gens ("家系" とも訳される。#オオタカの学名由来で考察しているものと同系語。
異なった色の卵を産むメスの系統) があって、それぞれの gens では宿主の受け入れ率 100% 近い平衡状態にあるのでは?
「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」pp. 226-228 にもカッコウの托卵系統が存在することが実証されているとある。オナガへの托卵を始めた日本のカッコウの中村浩志氏の研究も紹介されている (pp. 235-237 など)。
ヨーロッパでは人による環境の分断化が進みカッコウの gens の区別が少しずつなくなりつつあるかも (p. 234)。
なおオナガへのカッコウの托卵が始まって 30 年ほどでオナガの卵識別能力を発達させてオナガへのカッコウの托卵は見られなくなり、カッコウ卵が線模様を失いオナガ卵に似る (新しい gen ができる) 進化までは確認できなかったとのことである。
参考関連論文:
山岸・藤岡 (1986) カッコウ Cuculus canorus によるオナガ Cyanopica cyana への高頻度の托卵
中村 (1990) 日本におけるカッコウの托卵状況と新しい宿主オナガへの托卵開始
Nakamura (1990) Brood Parasitism by the Cuckoo Cuculus canorus in Japan and the Start of New Parasitism on the Azure-winged Magpie Cyanopica cyana
Nakamura et al. (1998) Co-evolution between the cuckoo Cuculus canorus and the azure-winged magpie Cyanopica cyana: rapid development of egg discrimination by a new host. In S. I. Rothstein and S. K. Robinson eds. "Parasitic Birds and Their Hosts; Studies in Coevolution" pp. 94-112
Marchetti et al. (1998) (中村氏も共著) Host-Race Formation in the Common Cuckoo
Andou et al. (2005)
Characteristics of brood parasitism by Common Cuckoos on Azure-winged Magpies, as illustrated by video recordings
Aviles (2004) Egg rejection by Iberian azure-winged magpies Cyanopica cyanus in the absence of brood parasitism
イベリア半島のオナガはカッコウによる托卵がなくても卵識別能力があった。同種内托卵に対抗するため進化したものか?
Liu et al. (2023) Egg rejection and egg recognition mechanism in a Chinese Azure-winged Magpie (Cyanopica cyanus) population
中国のオナガの卵排除 (セグロカッコウ、オニカッコウに托卵される) の研究。ウズラ卵は排除したが自身の卵も排除したものもあった。托卵種が多い地域とそうでない地域で違いがある?
Lotem et al. (1992) (中村氏も共著) Rejection of cuckoo eggs in relation to host age: a possible evolutionary equilibrium ではニシオオヨシキリでは年をとると自分の産んだ卵を覚えて卵識別能力が高まるらしい。卵識別能力は従来考えられていたように遺伝的なものではないと考えられ、卵識別能力は遺伝によって伝わるものではなさそう。
中村 (1992) アニマ 1992年6月号 pp. 60-67 に記事があり (この号の特集は「托卵の謎」)、コウウチョウのように最近分布を広げた種類では (1) が当てはまるものがあるかも知れないが、カッコウ類ではおそらく違っている? と述べられている。
Evolutionary Lag 説の根拠として、Rothstein はカッコウに托卵されなくなったモズの一種が高い卵識別能力を持っていることを挙げているとのこと。
1990 年代前半は盛んに取り上げられていたが、オナガへの托卵を行わなくなって話題も下火になったかも知れない。ネットに思ったほど最近の日本語記事がないのもそのためか。もっとも西日本ではオナガは身近な鳥ではなく、またカッコウが見聞できるところも限られているので自分にはやや縁が遠い話題だった。
卵識別の視覚情報処理については日本語の解説
卵の模様でカッコウの托卵に対抗、
論文は Stoddard et al. (2014) Pattern recognition algorithm reveals how birds evolve individual egg pattern signatures
パターン認識ソフトを用いて卵認識を模倣した点が新しいが、実際にそのように認識しているかは不明。
[托卵は相利共生となるか?]
「行動・生態の進化」(岩波書店 2006) p. 200 によればマダラカンムリカッコウ (ひなが宿主の卵やひなを排除しない) がカササギに托卵する際、托卵された卵を実験的に取り除いた方が捕食圧が高まるとのこと。捕食者は何と托卵を行ったマダラカンムリカッコウだったとのこと。カササギが托卵排除を諦める方が進化的に安定とのこと。
出典論文: Solar et al. (1995) Magpie Host Manipulation by Great Spotted Cuckoos: Evidence for an Avian Mafia?。
マダラカンムリカッコウの略奪行動はカッコウ類は捕食者系統から進化? ([Otidimorphae とはいったい何者?] 参照) とも話が合う気がする。
なお、状況はもう少し複雑そうで、必ずしも観察されない地域もある模様。Chakra (2016) Coevolutionary interactions between farmers and mafia induce host acceptance of avian brood parasites
の理論的考察があり、仕返し (mafia; 先述の Evolutionary Equilibrium 説を生む根拠ともなった。マフィア仮説は必ずしも完全に認められているわけではないらしい) または略奪 (farming) 行動の托卵者が多い場合は受け入れる方が有利になるが、逆の場合は排除する行動が有利になって安定状態がなく、両者の間を振動するとのこと。条件付きで托卵を受け入れる戦略が有利になることもあるらしい。
また Canestrari et al. (2014) From Parasitism to Mutualism: Unexpected Interactions Between a Cuckoo and Its Host
によればズキンガラスへの托卵でマダラカンムリカッコウのひなが悪臭物質を出して捕食者を追い払い、宿主側も利益を得ているとの研究がある。総排泄孔から焼け付くような感触のある腐った悪臭にある液体を出し、哺乳類も猛禽類も嫌うらしい (猛禽類側の感覚は #ハチクマ備考 [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] も参照)。
Trnka et al. (2015) Chemical defence in avian brood parasites: production and function of repulsive secretions in common cuckoo chicks
にさらなる研究がある。
同様の物質を出す行動はカッコウ科で広く報告があるらしく、カッコウ自身でも例があるとのこと。カッコウのひなは目立つので捕食も受けやすいと考えられるが、物質を出すコストも高いので捕食圧の高い時に適応的だろうとのこと。この実験ではカッコウのひなの分泌物を用いている。カッコウのひなが9日齢から分泌が増えてゆくとのこと。
鳥類捕食者 (実験で使われたものはオオタカ、ワキスジハヤブサ、トラフズク、ワシミミズク、カササギ、ニシコクマルガラス、ズキンガラス、ミヤマガラス)
より哺乳類 (イヌ、ネコ) に対する効果の方が強いとのこと。猛禽類でも4割ぐらいを食べている。カラス類はあまり反応しないとの意外な結果も得られた。カラス類はスカベンジャーで臭いを避けていないのではとのこと。
Canestrari et al. (2014) はカラス類が避ける逆の結果を得ているが、人工的に臭いを付けた実験では結果も違うとのこと。まだあまりすっきりしていない。ヘビでも実験したが食べてくれなくて失敗とのこと。
オオハシカッコウ類 Crotophaga、バンケン類 Centropus でも分泌があるので托卵のために進化した形質ではないと考えられるとのこと。
Soler et al. (2017) Great spotted cuckoo nestlings have no antipredatory effect on magpie or carrion crow host nests in southern Spain
では南スペインで、マダラカンムリカッコウのひなに捕食者を追い払う効果は予測通りではなかったとのこと。
Canestrari et al. (2017) Formal comment to Soler et al.: Great spotted cuckoo nestlings have no antipredatory effect on magpie or carrion crow host nests in southern Spain
のコメントがあり、地域により捕食者が違う (カラス類が臭いに鈍感な証拠はある)。実験デザインの問題もある? 最初に想像されたよりは複雑であることは明らかになったが、宿主側も利益を得ている仮説を否定するわけではない。
悪臭物質は Schmiedova et al. (2020) Gut microbiota in a host-brood parasite system: insights from common cuckoos raised by two warbler species
によればカッコウのひなの腸内細菌が作っているらしい。糞と悪臭物質は異なるもので、それぞれ別の細菌叢を持っている。宿主のスズメ目に比べてカッコウ類は長い盲腸を持っていて、悪臭物質は盲腸から排泄されたものと想像されるが確認が必要である。細菌には哺乳類で悪臭物質を放つものとも共通のものがある。
カッコウでは宿主によって細菌叢が異なる部分があるがあまりすっきりした結果にはなっていない。
鳥類の盲腸についての比較研究は Hunt et al. (2019) Phylogeny and herbivory are related to avian cecal size で見られる。論文そのもの結論は従来も言われていたことだが植物食とはよい相関があるが、飛翔能力とは特に関係が見られず、飛翔によって制約されるものではないだろう。
Supplementary information に種別の情報があるので見ていただくとよいだろう (植物食のものがあまりにも長いために論文の図ではあまりよくわからない)。カッコウ科が長い盲腸を持っていることわかる。
盲腸の長さが食性だけで決まっているわけではないことは、似た食性のタカ類ではほとんど発達していないのに比べてフクロウ類でよく発達していることからも明らか (フクロウ類の盲腸糞は有名)。この猛禽2系統は系統的にも関連があると考えられるのでなぜ片方のみ発達しているのか興味あるところである。この論文では他に栄養のことを考えているが、カッコウ類が捕食者を追い払う役割などは考えていない模様。
樹洞営巣性であるいは捕食者を追い払う時に使う可能性があるのか (実際に使っているかは調べていない) と見てみるとその傾向はあるようにも思えるが、カワセミ類やキツツキ類は盲腸がほとんど発達していないのでこの解釈が当てはまるものがあるとしても一部に限られそう。
[カッコウのひなの口は超常刺激か]
カッコウのひなの赤い口は超常刺激 (supernormal stimulus) となって親鳥に多くの餌を運ばせるアイデアは古くからあるが [例えば Dawkins (1976) は as if it were a helpless drug addict と記述した。Dawkins and Krebs (1979) Arms races between and within species]、
典型的宿主の3種について人工操作の実験結果から超常刺激とは言えないとの研究もある: Noble et al. (1999) The red gape of the nestling cuckoo (Cuculus canorus) is not a supernormal stimulus for three common hosts。
Kilner et al. (1999) Signals of need in parent-offspring communication and their exploitation by the common cuckoo では視覚・聴覚刺激両方を用いることで単独では得られない効果を得ている研究もある。
日本の研究で Tanaka et al. (2011) Rethinking visual supernormal stimuli in cuckoos: visual modeling of host and parasite signals
ジュウイチとルリビタキの関係で調べたものがある。Noble et al. (1999) は否定的な考えを示したが、紫外線が見えることを考慮していない。ジュウイチのひなの口と翼のパッチは宿主よりも紫外線反射率が高く、色彩のためのコストを考えると役に立っているだろうと考えるのが自然であろう。ジュウイチの反応まではわからないが超常刺激として働いている可能性もあるだろうとのこと。
この論文で "receptor noise" の表現を見た時には検出器ノイズ (フォトンノイズ、検出器の電気雑音など) を想像したのだが、概念が違うらしいことを知った。ヴェーバー-フェヒナーの法則 Weber-Fechner law (#オオルリの備考 [オオルリはなぜ青い] で登場) も含まれた定式化とのことで、
luminance discrimination threshold は色識別のしきい値を表すとのこと。[オオルリはなぜ青い] で触れたが天文学では伝統的に色指数の概念があって対数で定義されている (等級の概念がヴェーバー-フェヒナーの法則に由来する対数なので)。すなわち天文学者が天体の色を議論する時にはヴェーバー-フェヒナーの法則が暗黙に含まれている。
天文学でも複数の波長 (フィルター、バンド) で測定した等級を求めて対象の弁別を行ったりするが (遠方銀河を探すなどよくよく使われる)、伝統的なバンドならば UBV (それぞれの色の頭文字)、CCD ならば BVRI などが使われる (遠方銀河などの場合はさらに長い波長を使う)。
3バンドの場合の表示は2色図という2次元空間の図になり、4バンドだと2色図を通常2セットになる。
感覚生態学でも対数スケールでこれらの表示を試してみると面白いのではと感じた。Tanaka et al. (2011) で採用されている Weber fraction は 0.05 で、天文学では 0.05 等級に対応する。人が認知できる等級差は 0.1 等級ぐらい (実際にはよい条件ではもう少しよい) と言われるのでよく合っている。1 等級も違うと誰の目にも明らかなので1等星、2等星のようなランクに分けられた次第。
色指数の方もだいたい 0.1 違えば色の違いとして認知されると思う。
Vorobyev and Osorio (1998) Receptor noise as a determinant of colour thresholds
が引用されている文献。田中啓太「ジュウイチのヒナの騙し戦略と感覚生態学」in 上田恵介(編)「野外鳥類学を楽しむ」(海游舎 2016) 4章で扱われている。
たまたまこの人たちがこのように定式化したもので、他の人が違う式を使って定式化したものが使われてもおかしくなかった。式が少々違っていてもおそらく同じような結果になっていただろう
(Vorobyev は原語読みではヴァラビヨーフが近いだろうか。最後を伸ばしたのはアクセントがここにあるため。ヴォロビエフは英語綴りの読み方。原語ではスズメの複数生格 = 複数対格で、"スズメたちの"、または "スズメたちを" の意味になる。ロシアの人名ではこのようなケースが結構あり、Baklanov は同様にウの複数生格 = 複数対格 など)。
同じような定式化が色指数を用いて弁別を行っていた天文学の方ですでに行われていたのではないかと想像する次第。
[托卵鳥の同種認識]
カッコウ類などが育ての親を同種と認識してしまわないのはカッコウ類のさえずりなどの行動が本能的なものであるためなどの解釈がよく聞かれる。
「本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」ブランバーグ著 (#ミサゴの備考 [feather taxis・頭かき] 参照) によれば、大御所の Ernst Mayr (1974)
Behavior Programs and Evolutionary Strategies
は将来の交配相手を適切に見分けるプログラムがもともとの受精卵に完全に組み込まれていると考え。これを閉じた遺伝子プログラム (genetically "closed" behavior program) と呼び、動物における種の認識はほぼ例外なく閉じた遺伝子プログラムによると考えたとのこと (訳書 pp. 186-191)。
コンピュータが身近に登場した時代で、ソフトウエアとハードウエアの比喩が抵抗なく受け入れられやすかったことを反映しているとのこと。ただしこのような考えは Mayr 独自のものというより1961年ごろにすでに広まっていた考えで、Jacob and Monod (1961)、Ernst Mayr (1961) が同じような意味で使っている
[Peluffo (2015) The "Genetic Program": Behind the Genesis of an Influential Metaphor]。
カッコウ類ではこれで説明できるかも知れないが、音声学習を行い、しかも絶対的托卵性のスズメ目の鳥にも同じ説明が当てはまるかは明らかでない。北米のコウウチョウ類 (cowbirds, ムクドリモドキ科 コウウチョウ属 Molothrus) が有名で (旧世界のカッコウ類のようにタカへの擬態はなく、隠蔽色で托卵を成功させているらしい)、
コウウチョウ Molothrus ater Brown-headed cowbird がよく調べられている。200 種以上への托卵が知られている。
West and King (1977) Species Identification in the North American Cowbird: Appropriate Responses to Abnormal Song がコウウチョウを用いて実験を行い、驚くべき結果を発表した。
完全に人の手で育てたコウウチョウは本来の歌を歌えないが、メスはむしろそれをより好むように見えた。West and King (1977) は超常刺激 (supernormal stimulus) となっていると解釈し、繁殖期に確実に種を識別できるようにデザインされた独自のシステムを発見したとした。そしてそれは托卵種のメカニズムとして非常に都合よく見えた。
これは当時の考え方にあまりに合っていたため広く受け入れられることとなったが、その後問題点が見つかった。このようなオスはメスとうまく交尾できないことがわかり、また当時の実験手法に由来する問題点が明らかになって超常刺激ではないことがわかった。
極めつけは生後 50-100 日のコウウチョウを2グループに分け、一方はコウウチョウと、もう一方はカナリアと飼育した結果、繁殖時期である 10 か月後にはカナリアと飼育したものはカナリアに求愛し、一緒にいるコウウチョウを無視したのである。
West and King も生得的プログラム説を自ら却下せざるを得なかった。実は社会的交流を通じて同種を認識したのである。
さらに興味深いことにコウウチョウのオスに歌を教えるのはメスの役割で、若いオスから追いかけられた時に示す行動 (一度だけ羽ばたく) によって交配成功の方法を教えてゆくとのこと。
[West and King (1988) Female visual displays affect the development of male song in the cowbird および参考文献;
West and King (2001) Science Lies Its Way to the Truth ... Really]。
(ここまで「本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」から抜粋と文献紹介。現代でもコンピュータとの比喩は有効で生得的プログラム説は語られやすいが、それほど簡単なものではないことを知っておいてよいだろう)
Lynch et al. (2017) A neural basis for password-based species recognition in an avian brood parasite
の導入部分でこの問題が紹介されている。
パスワード仮説 (password hypothesis) があり、何らかのパスワードに晒された以降、同種の声や姿、社会性などを認識するとの仮説である。そのパスワードは学習で得るものではないはずである。
この論文は音声学習にかかわる脳内神経機構を同定したというもの。同種の "chatter" (餌要求などの地鳴き) には反応する回路は早くから存在するが、さえずりに反応する回路は同種の声を聞く経験で誘導されるらしい。
同種の声を聞くことなく宿主の声に長時間晒された場合は同種への神経反応を示さず刷り込みが起きる証拠も見られた。同種の "chatter" を頼りに同種の集団を聞き分け、その声に長時間晒されることで同種のさえずりを学習するらしいことがわかった。
"chatter" がパスワードの有力候補とする考えは過去にもあったが神経回路の発達の研究で裏付けられたことになる。音声学習の回路の働きを変えることで誤った刷り込みを避ける機能を進化させたらしい。
Louder et al. (2019) An Acoustic Password Enhances Auditory Learning in Juvenile Brood Parasitic Cowbirds
にも関連研究がある。パスワードとセットであれば異種のさえずりでも学習の対象になるとのこと。
托卵鳥しかこのメカニズムを使わないとも考えにくく、音声学習を行う鳥で同様のパスワードを見つけらるか興味ある課題である。
ここで調べているものは候補となっていた音声のみなので、他のパスワードが存在することを否定するものではない。
時に異種への托卵を行うカモで誤った刷り込みが起きた事例を説明できるかも知れないとのこと: Sorenson et al. (2010) Sexual imprinting misguides species recognition in a facultative interspecific brood parasite (アメリカホシハジロからオオホシハジロへの托卵例)。
なお南米のズグロガモ Heteronetta atricapilla Black-headed Duck はカモ類で唯一の絶対的托卵性で、孵化後すぐに宿主の巣を離れて独立するという [「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 182]。
「世界の鳥 行動の秘密」p. 183 によれば、中南米のツリスドリ類 (Psarocolius属) Oropendolas は鳥に寄生するハエ Philornis属 (学名由来は "鳥好き") 俗名 "bot flies" によるひなの死亡率が高い。
Philornis downsi 俗名 "avian vampire fly" でガラパゴスの侵略的外来種となっている。
O'Connor et al. (2009) Philornis downsi parasitism is the primary cause of nestling mortality in the critically endangered Darwin’s medium tree finch (Camarhynchus pauper)
によるとダーウインフィンチの一種 (種和名もダーウィンフィンチのよう) のひなの死亡の最大要因となっている大変困ったハエらしい。
Bulgarella et al. (2022) Persistence of the invasive bird-parasitic fly Philornis downsi over the host interbreeding period in the Galapagos Islands
1960年代にはすでに入っていたと考えられる。鳥の種を選ばず宿主とする。どのように冬を生き延びているかいくつかの仮説が提唱されている段階。
ツリスドリ類はミツバチやスズメバチ類の巣の近くで営巣 (和名の通り吊り巣で集団営巣) することで寄生ハエによる被害を軽減しているとのこと。ツリスドリ類そのものはミツバチやスズメバチ類に刺されても免疫があると書かれている (具体的情報は見当たらず)。
オオコウウチョウ Molothrus oryzivorus Giant Cowbird に托卵されるとハエの幼虫を食べてひなの死亡率が 90% 減少するとこの本にはある。
Smith (1968) The Advantage of being Parasitized が最初の報告のようで、オオコウウチョウとキゴシツリスドリ Cacicus cela Yellow-rumped Cacique の間で記述されたとのこと。
托卵が相利共生となっているように見えるが、Webster (1994) Interspecific Brood Parasitism of Montezuma Oropendolas by Giant Cowbirds: Parasitism or Mutualism? によればオオツリスドリ Psarocolius montezuma Montezuma Oropendola (どちらが学名でどちらが英名か区別が付かない?) でははまれな現象とのこと。
オオツリスドリでは積極的にオオコウウチョウを排除し、ミツバチやスズメバチ類の近くにも営巣しないので繁殖成功率が低いという。クリガシラオオツリスドリ Psarocolius wagleri Chestnut-headed Oropendola では起きているようで、種にもよるらしい (wikipedia 英語版)。
アフリカ中央部のスズメ目テンニンチョウ科 シコンチョウ Vidua chalybeata Village Indigobird はオスが育ての親の歌を学習することで、それを好むメスとつがいになり托卵相手の種に対応する系統が維持されるとのこと (「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」pp. 223-225)。
Payne et al. (2000) Imprinting and the origin of parasite-host species associations in brood-parasitic indigobirds, Vidua chalybeata。メカニズムは異なるがこちらも生得的プログラムではないことがわかった。
テンニンチョウ類の野外識別は難しく、オスの識別でも困難でメスや若鳥ではほとんど不可能である。シコンチョウの場合は宿主 コウギョクチョウ Lagonosticta senegala Red-billed Firefinch と一緒にいること、人家の近くに生息することが識別の手がかりとなる (wikipedia 英語版)。
Klein and Payne (1998) Evolutionary associations of brood parasitic finches (Vidua) and their host species: Analyses of mitochondrial DNA restriction sites
に Vidua 属の分子系統研究があり、歌の学習により宿主に対応した種分化が起きている (種ごとに托卵相手が決まっていることは以前から知られていた)。
Sorensen et al. (2003) Speciation by host switch in brood parasitic indigobirds、
Sorensen et al. (2004a) Clade-Limited Colonization in Brood Parasitic Finches (Vidua spp.)、
Sorensen et al. (2004b) Song mimicry of Black-bellied Firefinch Lagonosticta rara and other finches by the brood-parasitic Cameroon Indigobird Vidua camerunensis in West Africa。
メスのみが宿主に対応した系統を持つカッコウとは異なる。托卵する側も宿主もスズメ上科 Passeroidea - 系統 1 Estrildid カエデチョウ clade に位置する互いに近縁のグループで、日本の種類ではスズメ科に近い (#ツリスガラの備考 [スズメ小目 Passerida の系統分類] を参照)。
托卵する側と宿主の類縁関係が近いので、もとは同一グループで同種内托卵があったものが種分化の要因となり片方が托卵系統、片方が宿主系統に分かれたのかと少し考えたが、科レベルで違っていて単一系統に乗るほど近いものではなかった。この2系統の分岐年代は 1690 万年前ぐらいとなる (そのころから托卵習性があっても悪くないのかも知れないが)。
宿主の種分化と対応して種分化したことも想像されるが、分子系統解析の結果は否定的だった。ただし系統樹のトポロジーに似たところもある (Sorensen et al. 2004a)。Vidua属は 19 種。シコンチョウはさらに分割される可能性もあるとのこと。
Sorensen et al. (2004b) によれば複数の宿主を持つカメルーンシコンチョウ Vidua camerunensis Cameroon Indigobird グループの間で異なる歌を模倣するグループの間で形態的違いは認められなかったとのこと。
Phoebe Barnard (アニマ 1992年6月号 pp. 68-72 に翻訳記事) によるとテンニンチョウ類はひなの口蓋のマークを宿主のひな似せているが、これは托卵する側と宿主の系統が近いため擬態の鋳型があらかじめ存在して (前適応)、擬態は必ずしも複雑で特別な適応を示していると言えないとある。この系統の近さは現代の分子系統研究で裏付けられている。
田中 (2003) Birder 17(5): 82-83 にテンニンチョウ類の歌学習の解説がある。
托卵をする鳥にもカッコウ類とは異なるいろいろなものがあることがわかる。なお「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」ではカッコウ類でも宿主の刷り込みが起きているのではないかと推測しているが、飼育実験などが非常に難しいために解明は難しいとのこと。
托卵性への進化はいろいろなメカニズムがかかわっていたのだろう。
種固有の歌を持つわけではなく模倣で得た歌もやはり song なのだろうが、mimicry song と呼ばれているらしい。他種でも音声模倣はあるので托卵種だけで起きる現象なのだろうか、それとも音声模倣がつがい相手の選択に役立っているケースがあるのだろうかと想像が膨らむ結果である。
模倣された音声が識別の手がかりとなると生身の人間の識別能力を超えるかも知れない。ムシクイ類のように「鳴けばわかる」レベルなのだろうか。生殖隔離は起きているので生物学的種概念は満たしているだろうが不思議な気もする。
Colombelli-Negrel et al. (2012) Embryonic Learning of Vocal Passwords in Superb Fairy-Wrens Reveals Intruder Cuckoo Nestlings
ルリオーストラリアムシクイ Malurus cyaneus Superb Fairywren では抱卵中に親が地鳴きを出したものを学習し (こちらもパスワードと呼んでいる)、孵化後にその構成要素を発することで托卵宿主のマミジロテリカッコウ Chrysococcyx basalis Horsfield's Bronze-Cuckoo のひなと区別している研究結果がある。
実験的にはおそらく有意な結果なのだろうが、コウウチョウのパスワードほどは神経的なメカニズムはわかっていないはずで、コウウチョウ同様に神経発達のメカニズムも調べられてより明確になってゆくのだろう。
コウウチョウでは特に場所記憶などに重要な脳の海馬のサイズに雌雄差があるとの報告がある:
Sherry et al. (1993) Females have a larger hippocampus than males in the brood-parasitic brown-headed cowbird
托卵先の巣を探すのはメスだけが行うもので、場所を記憶して後に托卵に訪れるために海馬が発達しているとのこと。非托卵性のコウウチョウ類よりも大きいらしい。
飼育下では不必要なため小さくなるとのこと: Day et al. (2008) Sex Differences in the Effects of Captivity on Hippocampus Size in Brown-Headed Cowbirds (Molothrus ater obscurus)。
[托卵鳥に共通の遺伝的変化]
Osipova et al. (2025) Comparative population genomics reveals convergent adaptation across independent origins of avian obligate brood parasitism (preprint)
絶対的托卵のうち3系統 (コウウチョウ、ミツオシエ類、テンニンチョウ科 Viduidae) のゲノムを調べて近縁系統の非托卵種との違いを調べたもの。おそらく子育てをがないためオスの精子競争が激しく、精子に関わる部位の変化が多い。中枢神経に関わる部位も同様で托卵のために空間認識能力が必要になる可能性を挙げている。また全体的に非托卵種に比べて何度も選択的スイープ (selective sweeps; 選択的一掃) が起きていて宿主との競争の結果を反映しているのではないかとのこと。
ただしコウウチョウではそれほど高くない。托卵種となった歴史が浅い (300 万年程度) ことと托卵ジェネラリストであることが要因ではないかと推測している。カッコウ類が研究対象に含まれていないのはゲノム情報が限られているためだろう。他にも卵の彩色のための遺伝子など変化が大きい。
[カッコウのひなに対する親ツバメの反応]
Tian et al. (2025) Supernormal Stimulus Begging Calls of Brood-Parasitic Nestlings Depress the Parental Care in an Uncommon Host
ツバメは通常カッコウの宿主とならないと考えられてきたが 2013 年以降の研究で宿主となってカッコウのひなを育てることができることが判明してきた (文献は論文参照)。ツバメも托卵防御行動を行い、人家の近くに住むこともその方策の一つ。
実験の結果カッコウのひなの声がむしろ給餌頻度を下げ、カッコウのひなの音声が必ずしも超常刺激とはならないことがあることがわかった。中国遼寧省での研究。
△ ヨタカ目 CAPRIMULUGIFORMES ヨタカ科 CAPRIMULGIDAE ▽
-
ヨタカ (分割された)
- 第8版学名:Caprimulgus jotaka (カプリムルグス ヨタカ) ヨタカ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Caprimulgus indicus (カプリムルグス インディクス) インドのヨタカ
- 第7版亜種学名:Caprimulgus indicus jotaka (カプリムルグス インディクス ヨタカ) ヨタカのインドのヨタカ
- 属名:caprimulgus (m) ヨタカ (capra (f) 牝ヤギ mulgeo (tr) 乳をしぼる)
- 第8版種小名:jotaka ヨタカ
- 第7版種小名:indicus (adj) インドの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 第7版亜種小名:jotaka ヨタカ
- 英名:[Jungle Nigthjar 分離前の名称], IOC: Grey Nightjar
- 備考:
caprimulgus は短母音のみで -mul- がアクセント音節 (カプリムルグス)。
jotaka は日本語同様に短母音で読めば冒頭がアクセント (ヨタカ)。"ヨターカ" でも構わない。好みに合わせてどうぞ。
indicus は冒頭にアクセントで "インディクス"。
goat-suckerとも呼ばれ、ヤギの乳を吸うと考えられた。鳥 (オス、春に) を標本にする時に強いヤギの臭いを出すことに気づいて、ヤギの乳を吸うとの迷信も理解できると Coues (1874) は述べた。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
現在は以前の2亜種 jotaka、hazarae (パキスタン北東、バングラデシュ、中国南部、ミャンマー、マレー半島の亜種) が分離され、Caprimulgus jotaka (英名 Grey Nightjar) に含まれる。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱い。
日本で記録されるヨタカは亜種まで含めた学名で Caprimulgus jotaka jotaka となる。旧英名の Jungle Nigthjar は IOC では分離された Caprimulgus indicus ジャングルヨタカ が引き継ぐ。これは Indian Jungle Nightjar とも呼ばれる。
記載時学名 Caprimulgus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 (原記載)。フランス語名 l'engoulevent Jotaka。
sous le nom qu'elle porte au Japon と名前は日本の名前から。
しかし現代のフランス語では j はジュと読むのが普通なので、Jotaka がヨタカと読まれていたかどうかは疑問。学名の発音は問題なし。
ヨーロッパヨタカはお馴染みで、Engoulevent と言えばこの種を指すためフランス語名も悩ましくなく、Vigors and Horsefield がオーストラリアの種類についてすでにこの属に種小名 (guttatus や albogularis) を与えて新種記載をしているので同列の使い方のよう。命名状況はアオゲラやコゲラに似ている。
Vigors and Horsefield が "オーストラリア" を種小名に用いなかったのは Caprimulgus novaehollandiae Latham, 1790 (novaehollandiae = オーストラリアの意味) がすでに存在していたため。そのぐらい多数の名前がすでに付いていた。
Caprimulgus indicus Latham, 1790 も地名を用いてすでに命名されていた。
Grey Nightjar と呼ばれた別種があり、Caprimulgus griseus Gmelin, 1789 (参考)、現在のものは分割によるやむを得ない英名変更ではあるが過去の用例と重なってしまっている。
ヨタカ類は採集家に人気だったようこの時代には Caprimulgus 属に色彩や形態、地名を用いた非常に多くの学名がすでに存在して、簡単に思いつく種小名ではすでに使われているおそれがあったため Temminck and Schlegel が現地名を用いた可能性がある。
日本のヨタカはヨタカ類の中でも後発になっている。
Temminck 自身も 1820 年代に他のヨタカ類にいくつも命名しており、日本からちょっと違うヨタカの標本があってもおそらく珍しくもなかっただろう。ヨーロッパ中部・北部ではヨタカ類は1種だが熱帯・亜熱帯には多数の種が存在することがすでに明らかになっていた。色彩や形態に基づく命名は一段落した後の機械的命名段階だった可能性がある。他種で "ヨーロッパ産の種の日本版" と記載したものとは事情が異なっていた。
Chen and Field (2020) Phylogenetic definitions for Caprimulgimorphae (Aves) and major constituent clades under the International Code of Phylogenetic Nomenclature
ヨタカ、アマツバメ、ハチドリなどの系統と分類群の名称の提案の論文がある。
過去の分類ではこれらはフクロウ類の後に並べられており、夜行性グループがなんとなくまとまっている感じがあったが、現代の分子系統樹は全く異なっている。ヨタカ、アマツバメ、ハチドリが共通の系統に属することの意義について#アマツバメの備考も参照。
[ヨタカ目の範囲]
ヨタカ目 Caprimulgiformes は現在も広く使われる概念だが、どの範囲を含むか議論もある。
Caprimulgiformes Limits (BirdForum) に歴史的記録が紹介されている。2016 年の eBird/BOW ではアマツバメ目 Apodiformes が Caprimulgiformes に包含され、Caprimulgiformes と Apodiformes の双方を認めると単系統の関係にならない。
それぞれをの科を目とする解決方法もあるが (その場合は Caprimulgiformes は狭い範囲となる)、eBird/BOW は Apodiformes を目から科 Apodidae に変更して Caprimulgiformes に含めることにした、とある。
これは Prum et al. (2015) の結果などを受けたもの。[#鳥類系統樹2024] の Stiller et al. (2024) の結果も同様であるが、両方の扱いが可能であるため Strisores (Caprimulgiformes) としている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では両者を目として扱っている。
Boyd も
・Caprimulgiformes ヨタカ目 Nightjars
・Steatornithiformes アブラヨタカ目 Oilbird
・Nyctibiiformes タチヨタカ目 Potoos
・Podargiformes ガマグチヨタカ目 Frogmouths
・Aegotheliformes ズクヨタカ目 Owlet-nightjars
・Apodiformes アマツバメ目 Treeswifts, Swifts, and Hummingbirds
と分けていて、アマツバメ目を残すならばそれぞれを目にするのが分子系統に忠実な分類となるが、アマツバメ目以外は外見はヨタカ類と似ているので直感とは合わないところがある。さらにずいぶん異なるのにハチドリ類はアマツバメ目に含まれてこちらも見かけは目にふさわしいとの考えもありそう。
アブラヨタカは1種で1目というのもおそらく違和感の原因になるだろう。この目は Mayr が 2010 年に提案したもの。現生種は1種だが絶滅属がある。Nyctibiiformes も Yuri et al., 2013 と新しいとあったがその後訂正されたようで Boyd の記述ではタチヨタカ目を初めて目と認識したのは Boyd の Taxonomy in Flux とのことでまだ Informal な名称となっている (2025.5 時点)。
Aegotheliformes も Worthy et al., 2007 と同様。
ツメバケイは1種で1目だがアブラヨタカにはそこまで強いインパクトはないかも知れない。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 92 p. 6 によればガマグチヨタカの和名は英語の frogmouth が由来とのこと。OED によれば 1862 年、Jerdon, Birds of India で The Wynaad frog-mouth と紹介されたものが最初とのこと。属名は Batrachostomus で batrakhos カエル stoma 口 (Gk)、提唱者も Gould で、英名 = 属学名 だった。
科学名は Podargus 属由来で、こちらは Cuvier (1816) の用いたフランス語名 Podarge 由来で podagros < podagra ヤギ (Gk) から。Vieillot (1818) が属名を定義した (The Key to Scientific Names)。実態はわかっていなくてもヨタカに似た鳥はヤギを連想させたよう。
ズクヨタカはミミズクに似ていることから。
Strisores とは何か
wikipedia 英語版の解説によれば Strisores は Cabanis (1847) Ornithologische Notizen の用いた概念で2 "族" からなっていて Macrochires ハチドリ類、アマツバメ類、ヨタカ類、アブラヨタカ、タチヨタカ類を含んでいたがガマグチヨタカは含まれていなかった、そして Amphibolae ツメバケイ、ネズミドリ類、エボシドリ類 を含んでいた。
Cabanis (1847) の時代にはすでに Cypseselidae (下記参照), Caprimulgidae, Trochilidae などの名称はすでに存在していた。
この当時は Oscines (現在の鳴禽類にそのまま使われている), Clamatores, Strisores, Scansores の4グループの1つだった。
p. 345 によれば Strisores のドイツ語名は Schrillvoegel (金切り声を上げる鳥) でラテン語 strido 由来 (フクロウ類の strix とも関連があり、フクロウ類の英名にある screech owl も関連があり、フクロウ類の英名や属名も音声に由来していた) と書いてある。
さらには 雑誌 "Birder's World" 1989.10 pp. 10-13 に Don Alan Hall が "Quavering and Tootling Owls" によれば恐怖を連想させる声で夜に鳴く不明のものを指していたとのこと (#フクロウ備考参照)。
"夜" を意味する語義はそもそも含まれていなかった。
対比されている Clamatores もドイツ語名で Schreivoegel (叫ぶ鳥) で (#カンムリカッコウ備考参照)。oscine はラテン語 oscen (名詞) 由来で ops- 歌う -cen 者から。Cabanis は鳴き声を気にしていたよう。Oscines から始まる分類「歌う鳥、叫ぶ鳥、金切り声を上げる鳥」から想像すると、Cabanis にとっては音楽的にさえずる鳥こそ本命で、それ以外の鳴き声の鳥はうるさいだけと思っていたのでは (笑)。
今でも「さえずり」の定義に似た側面があり、音楽的に聞こえない鳥は「さえずり」と呼びにくいとの考え方もある。上田 (2007) Birder 21(5): 38-39 では比較的狭義に捉えられているようでキジの声はさえずりとは言えない、キジバトやフクロウはさえずりと言えるのか抵抗がある、モズの高鳴きやカッコウあたりからさえずりに入れる人があるでしょうなどと述べられている。
自分が使う場合は音声に明らかに違いがある場合は、機能を重視した song, call の分類を使っている。ほぼ xeno-canto の用例に近いがサンショウクイなどはどちらか悩ましいところ。キジバト、フクロウ、カッコウはいずれも song としている。モズの高鳴きは call にしている (春の subsong が別にある)。
xeno-canto の用例を見ておくとキジは song 1 例、call 3 例。タイリクキジはサンプルが多数あり song の例も多い。song と alarm call を分ける用例がある。キジバトでは圧倒的に song。モズの高鳴きは圧倒的に call。日本語用語と英語の感覚の違いはあるかも知れないが参考までに。
Cabanis 時代の考え方は現代のバードウォッチングでも、明朗にさえずる鳥以外の声はあまり相手にされない傾向のある音声の取り上げ方とあまり違わないかも知れない。山の夏鳥でオオルリ、キビタキ、クロツグミを聞き分けられる程度で鳥の声の聞き分けに強いと称賛されるぐらいでは困る (と勝手につぶやいておこう)。
Strisores についてはさすがの wikipedia もここまで語源を追求しておらず、専門用語すぎて OED にも出てこない。
最後に残る Scansores は何かと見てみると Klettervogel (よじ登る鳥) とのこと。Strisores と現代の分類は「たまたま一致した」程度と考えてよさそう。
Burmeister は後に Strisores から Amphibolae を除外したがカワセミ類やハチクイモドキ類を追加したとのこと。Strisores の名称そのものが現代の分子系統研究による系統に合致する概念で使われたことはなかった。当時はグループ名は上記4例からもわかるように複数形の -s で終わっていた。
Cypselomorphae は Huxley (1867) が設けたもので、ハチドリ類、アマツバメ類、ヨタカ類などを含んでいたがガマグチヨタカ類やアブラヨタカ類は含まれないと考えていた。この時代も -formes の語尾ではなかったようで、-morphae は現在使われる系統名と少しニュアンスが異なる。
Cypselomorphae は 当時のアマツバメ類の属名 Cypselus 由来ととてもややこしい。アマツバメ類の属名が Apus となった経緯は #アマツバメの備考参照。
この属名変更に伴い、また目名語尾が -formes に使われるようになり、アマツバメ類に対して Apodiformes が主に用いられるようになった次第。一方でハチドリ類をベースとした Trochiliformes の名称も使われた (Sibley-Ahlquist 分類)。目レベルの分類には属や種のような先取権の原則が明確に設けられていないためさまざまな名称が提案されることになる。
Caprimulgiformes (ヨタカ類の属名由来) はヨタカ類、アブラヨタカ類、タチヨタカ類、ガマグチヨタカ類、ズクヨタカ類の5つの外見が類縁した系統をまとめたもので 20 世紀に広く使われていた。
分子系統解析によってアマツバメ類やハチドリ類が Caprimulgiformes に内包されることが確実となり、リンネ式の階層分類にとって挑戦的課題となったとのこと。Caprimulgiformes は上記定義が広く使われてきたのでこの定義をアマツバメ類やハチドリ類まで広げることには抵抗もあり、古く Cabanis (1847) の用いた Strisores の名称を現代的な意味で用いる用法が提唱された。
Caprimulgiformes などを目として扱い、Caprimulgimorphae Cracraft, 2013 のように上目を設ける考え方もあったとのこと。
Strisores (Caprimulgiformes) と書かれる場合は、Strisores は古い名称を再定義して新しい概念を表現するために用いたもの、Caprimulgiformes はこれまで使われてきた名称の範囲を広げたものとなる。提唱された時代の概念と同じではないのでどちらが正しいとも言い切れない。
目記載時のドイツ語名 Schrillvoegel もおそらく語源を的確に反映していなかったが、語義に詳しい人にとっては Strisores は Strix 同様縁起の悪い音声を連想するため、Strisores の名称は存在しても避けられていた (いる) のかも知れない。
ついつい Strix の語感に考えが及んでしまう (ごめんね > 日本野鳥の会殿)。
また Strisores を現代流に -formes の語尾に変換すると語源は異なるものの フクロウ目 Strigiformes と似て紛らわしくなる点も要因だったのだろう。"Strisores" は分子系統に従って複数の目に分けた方が名称の面でも都合がよいことになる。"Strisores" は広義概念 (Caprimulgimorphae に相当) を表す系統名として残しておくとよいのだろう。
Strisores (Caprimulgiformes) の系統上の位置づけや進化の解釈を調べてみるとやはり相当の議論があることがわかった。Chen et al. (2019) Total-Evidence Framework Reveals Complex Morphological Evolution in Nightbirds (Strisores)
を見てみると Strisores の夜行性は祖先形質なのか、あるいは個々の系統が個別に獲得したものか意見が分かれている。夜行性が祖先形質とすると一度暗所視に適応して網膜の分子機構などを進化させたものが昼行性に戻る (アマツバメ、ハチドリ類) のは極めて考えにくいとの解釈がある。
ヨタカ類を除いて個々の現生系統に対応する古い化石証拠もあり年代推定も問題なさそう、分子系統解析も現在用いられている系統を強く支持するが夜行性の起源は未だに決着が付かないテーマとなっている。
この論文の系統樹 (化石種も含まれていてわかりやすいのでおすすめ) を見ていただくといずれも根に近いところで分岐しているのでヨタカに似たグループの目の関係が簡単に決着しないのも納得できる。分岐年代からはそれぞれを目とするのが妥当と考えられても、限られた証拠に基づくものでまだ暫定的扱いとみなされているのかも知れない。
いずれの系統も起源は古く 5600 万年前以前に分岐したと考えられる。この著者たちはヨタカ類の一部に見られる夜行性適応の反射板 (tapetum lucidum) の遺伝的基盤を気にしている。一部の系統にしか存在しないため tapetum lucidum が祖先形質とは考えにくく、個々の系統が個別に夜行性を獲得した考えの方が有利のように見えるが、tapetum lucidum 形成の遺伝的メカニズム次第では二次的に失った証拠が見つかるかも知れない (これは今後比較的検証しやすい可能性のある部分と言えるだろう)。
アブラヨタカ類似の化石種が現生のアブラヨタカ同様に果実食だったとの推論も形態学によるもので、適応によって祖先的な形態形質がこの時点ですでに失われていた可能性もある。
個人的にはなぜ夜行性になったのか解釈があるのか興味があるところで、この時代にはさすがにまだ昼行性猛禽類との競争によるとは考えにくい。祖先系統は非常に古いので陸上で有望な昼間の空の競争相手をあまり思いつかない。#カッコウ備考で紹介した [Otidimorphae とはいったい何者?] が本当に陸上の捕食者であったならば 5600 万年前のような比較的早い段階での競争もあり得たかも知れない。
もっと後の時代に個別に夜行性を獲得したならば昼行性猛禽類との競争もあり得るかも知れない。しかしアブラヨタカが洞窟に住むのはやはり昼行性捕食者対策では、と思ってしまう。昼行性猛禽類のまだいない時代に現在と同じような生態を想像するのはナンセンスかも知れない (いずれにしても現代の外見から祖先系統の外見を予測しない方がよいかも知れない)。
果実食の Strisores がアブラヨタカ以外現存しないのも競争によるものと考えてみると面白いかも知れない。こちらは競争相手がいくつも考えられそう。夜行性となるとコウモリ類 (こちらは鳥類による捕食圧が夜行性になった有力な理由とされている) も競争相手になるかも。
Chen et al. (2019) の系統樹を再度見ていただくと、狭義のヨタカ目のみが別系統で残りと分離できるように見える。現状の見かけが似ているので分離しにくいだけで見かけは収斂進化の要素の方が強いかも知れない。
狭義のヨタカ目のみは古い化石がなく、分岐は古いもののずっと弱小系統で地質学的に近年になって急激な適応放散を遂げたのでは。食性などを考えるとやはり乾燥化と草原の広がりで開けた環境に分布を広げ種分化を遂げたグループのように見える (草原などの開けた環境との関係は保全を考える上でも有意義かも知れない)。
弱小系統だったために化石も残りにくく、またその時代には現代の形態とはかなり違っていたのかも知れない。
そのように考えると Strisores の祖先系統は夜行性でなくても構わないような気がする。ハチドリ類が昼行性で色彩豊かなのも祖先形質と矛盾しないかも知れない。
また飛翔性昆虫食も後から発達した習性で、もとはいろいろな食性のものが存在したが、夜行性の飛翔性昆虫食のニッチを占めることのできた狭義のヨタカ目のみが競争に耐えて繁栄し (そして植物の繁栄などの時流にちょうど乗れたハチドリ類やアマツバメ類)、アブラヨタカのような果実食の系統は古くはいくつもあったがほぼ失われてしまっただけかも知れない。
おそらく比較的古い系統にありがちなパターンで、Otidimorphae の場合には生き残った系統 (ハト、ノガン、カッコウなど) があまりに違い過ぎて分子系統解析をするまで系統関係すらわからなかった、同様にヨタカ類似系統とハチドリ類やアマツバメ類の近さは一見してもわからない。ヨタカ類似系統で生き残ったものは夜行性の飛翔性昆虫食の生態的共通性 (それ以外の生態を持つ系統はの後の系統に及ばなかったなど) から系統が遠い割にはたまたま非常に似てしまった、などを考えるとよいだろうか。
Strisores に比較的近い段階にあるツメバケイは独自系統をなすと考えられるが (位置もまだ多少不確か) 特殊な食性や捕食者適応でたまたま生き残ったものだろう。同じような時期に放散した Strisores の進化も同様の経緯があったと考えることができるようにも思える。
McCullough et al. (2025) What is an eared nightjar? Ultraconserved elements clarify the evolutionary relationships of Eurostopodus and Lyncornis nightjars (Aves: Caprimulgidae)
が UCEs を使った解析で面白い結果を出している。これまで Eurostopodinae 亜科と認められていた Eurostopodus 属と Lyncornis 属とはかなり異なる系統だった。Caprimulgus 属は Lyncornis 属の含まれる枝に属する。Eurostopodus 属の総称として Indo-Pacific nightjars を提案。
[ヨタカ類の視覚特性]
ヨタカ類の視覚特性は他の鳥と大きく違っていることが知られている。
Salazar et al. (2020)
Anatomical Specializations Related to Foraging in the Visual System of a Nocturnal Insectivorous Bird, the Band-Winged Nightjar (Aves: Caprimulgiformes)
後方にも両眼視のできる視野を持っているが神経数から視力は悪いと考えられる。視力だけで獲物を捉えることは難しく、口を大きく開けると捕食対象が正面で見えないので、口ひげ状の羽毛が横方向にあってセンサーになっているのではと考えている (他に聴覚を使っている可能性も議論されている)。
ごく大雑把に比喩的に言えばヨタカ類の目は昆虫の複眼に近い機能で、虫がいることを検知すると後は触覚で対応しているのかも知れない。
#ヨシゴイの備考で櫛状の爪 [pectinate(d) claw, または櫛歯] がヨタカ類で発達していることを示す文献を紹介しているが、口ひげ状の羽毛が捕食に特に重要な役割を果たしているためそれを整える意義があるのかも知れない。
ヨタカ類の一部には網膜に「反射板」(tapetum lucidum) があり、光の利用効率を高めている [Nicol and Arnott (1974) Tapeta lucida in the eyes of goatsuckers (Caprimulgidae)]。
tapetum は解剖学で網膜色素上皮のこと。ヒトなど多くの動物で色素着色があるので pigmentum nigrum と呼ばれたが、一部の動物ではこの部分が透明なので tapetum lucidum と呼ばれた名称に由来。
tapetum lucidum の名称には直接には反射板の意味はなく、透明な tapetum の意味。日本語では輝板 / 輝膜と呼ぶらしい (wikipedia 日本語版より)。タペタムと呼ばれるらしいがこれはラテン語由来の用語が長いので英語圏でも省略されて呼ばれるためだろう。
「反射板」のメカニズム一般の新しい研究があり、Zueva et al. (2022) Multilayer subwavelength gratings or sandwiches with periodic structure shape light reflection in the tapetum lucidum of taxonomically diverse vertebrate animals。
光の波長以下の構造なのでもちろん電子顕微鏡が必要。
哺乳類では網膜の外の脈絡膜 (choroid) にあってコラーゲン繊維のナノ構造の回折格子的な配置による。構造色と言える (配列次第で光をほぼ完全に吸収することも反射率を高めることもできる。#オオルリ備考の [構造色について] 参照。反射率を高めている例では #ヤマシギ備考の [ヤマシギの尾の裏先端部の白色] を参照)。
ネコなど肉食哺乳類 (carnivores)、アザラシ類、古い系統の霊長類 (lower primates) で tapetum cellulosum、有蹄類で tapetum fibrosum と異なるタイプのものがある。
鳥類、爬虫類、両生類、魚類では網膜の色素上皮中にあって retinal-type tapetum (写真に choroidal tapetum とあるのは違っている気がする)。魚類や両生類では強膜 (sclera) に持つものもあるとのこと。この論文では夜行性鳥類のことは特に触れられておらず、鳥類の目の反射はそれほど強くない。
choroidal tapetum の方が起源が古く、retinal-type tapetum が後に独立に進化したと推定されている。
夜行性の哺乳類に目立つので哺乳類ベースの研究が中心のようだが、鳥類では昼行性種が多いのでそこまで高い反射率は必要でないのかも。夜行性鳥類のことは特に触れられていないので同様に調べると反射効率を上げる構造があるのかも知れない。
#チョウゲンボウ備考の [チョウゲンボウとコキンメフクロウの目の比較] にあるように解像度が必要な昼行性猛禽類ではむしろ反射を抑制している。
[ヨタカ類の "wing-clapping"]
ヨタカやヨーロッパヨタカなどでディスプレイの際に機械音を出すことが知られている。「動物の世界」2版 13 (日本メール・オーダー 1986) pp. 3877-3878 にヨーロッパヨタカで繁殖期の求愛でときおりつばさを打ちあわせてピストルのような音を出す。この音は日本のヨタカでは "ぬれ手ぬぐいを急激に振ったときのような音" と形容されているとのこと。なお記事全体は古い意味で名前に "ヨタカ" の付く別系統も含んだもの
[浦本・樋口 (1986)。前身となる週間アニマルライフ (1973) にも同じ記述があった]。
ヨーロッパヨタカの音源を探してみると XC734167 (Alan Dalton スウェーデン 2022.6.27) や XC809226 (Ulf Elman スウェーデン 2023.6.16) などが参考になりそう。
この音は wing claps (ハチクマの羽打ち合わせのディスプレイにも使われる表現) と表記されている。オオジシギの声や羽音同様、我々が普段耳にする「キョキョキョ...」のヨタカの声とは別のものがあり、ここではこの声を song と呼んでいる。その後 wing claps が続く。
初期には Coward (1928) The "Wing-Clapping" of the Nightjar の考察やコメントが British Birds にあり、"wing-clapping" と呼ばれるが翼は打ち合わせておらず、急速に翼を振り下ろすは時に出る音ではないかなど検討されていた。
より新しいところでは、Tipling (2021) A review of 'wing-clapping' in European Nightjars がよい条件のビデオ記録から翼が接触することはなく、また急速な打ち下ろしや打ち上げは伴っていないとのこと。
Nightjars (Caprimulgus europeus) clapping wings (Birdsong in Spring 2020) の映像があり、翼の後側から音が出ている (0:50 飛行姿勢を示す)。2:26 付近の音声は rattling song と表現している。「キョキョキョ...」の音声を急速に反復するとこのような声になるのかも。
こちらはアメリカ合衆国南部から中米のクビワヨタカ Antrostomus ridgwayi Buff-collared Nightjar の事例: Rattles, Claps, & Burp-clicks (Nathan Pieplow 2010)。
最初はマイクの落ちる音かと思ったが wing-claps, clucking or clicking calls と呼ばれるものと判明したとのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) にもヨーロッパヨタカの声の記述があり、オスの歌は 5 分まで続き、鋭いクリック音を 4-5 回までくり返して終わる。このクリック音は両翼を打ち合わせることに伴うと記述されていた。
それでは日本のヨタカはどのように記述されているのか、「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) を見てみるとメスの声や変わった声の記述はあるものの、
榎本 (1935) が「クパッ、クパッ、クラッ、コポッなどと聞こえる声は主として繁殖期に聞かれ、虫を捕らえる音、羽を打ち鳴らす音などの説があった。鳴き声であることは確認したが、意味は不明である」と記しているのが唯一該当する部分で、この記述は地鳴きや "低音のさえずり" が混ざっているようで、"羽を打ち鳴らす音" は直接含まれていない (おそらく伝聞情報のみ) のではないかと想像できる。
上記記事や海外情報を知らないと何のことか想像困難である。音のカタカナ表記がいかに無力であるかわかる。
バードリサーチ鳴き声図鑑にはさえずり、"低音のさえずり"、地鳴き? が含まれているが wing-claps に相当する音は入っていない感じがする。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 92 p. 20 では日本にいるヨタカもつばさを打ち合わせて "クパッ" とか "コポッ" とか聞こえる音をたてることがあり、ヨーロッパヨタカが求愛のときに出すものと同じであろう、と記されているが、榎本 (1935) およびその中で参照されたであろう表現をそのまま使っているように見える。
ヨーロッパヨタカの "wing-clapping" で記録されている音や、"ぬれ手ぬぐいを急激に振ったときのような音" とは多少違うものがカタカナ表記で伝わっていたものかも知れない。
ヨーロッパヨタカの wikipedia 英語版には外敵を追う時にもこの音を使うと書かれている。
浦本・樋口 (1986。1973 に遡る) の記事に出てくるように昔は知られていたが、比喩表現も一緒に忘れ去られたらしい。比喩表現が残っている以上、このおそらく機械的な音は日本のヨタカにも存在するのではないだろうか。
「キョキョキョ...」の声を song と呼ぶか (flight) call と呼ぶか海外で見解が多少分かれているのもこれらの繁殖期の多彩な声の存在のためだろう。
繁殖生態について、福丸 (2021) Birder 35(6): 38-41「貴重な求愛シーンを記録![ヨタカ観察レポート]」に求愛や交尾などの行動や音声について報告されている。上記の音が記録されているのか文章からは判断できなかった。
#タシギの備考 [羽音と流体力学] の Clark (2021) Ways that Animal Wings Produce Sound のレビューでは一応候補に取り上げられていて、percussion (マイコドリ類 Manakins) の音のメカニズム (硬い構造をぶつけて振動させる) 類似の可能性が考えられるが具体的な研究は知られていないらしい。
かつて日本と同種とされた Jungle Nightjar Caprimulgus indicus の wikipedia 英語版の記述では、This sometimes ends in quick whistling foo-foo with the quality of sounds obtained when air is blown over an open bottle. A call described as uk-krukroo attributed to this species by Ali and Ripley in their Handbook is in error and is the call of the Oriental scops owl (Otus sunia).
との表現があり、栓を開けた瓶を吹く時に似た音との表現がある。Ali and Ripley の示すところの uk-krukroo の表現はコノハズクの間違いであるとのこと。お互いに文字表現を見て同じだ、いや違うと議論しているようで、何語で書かれても文字で表す限界が感じられる。
Jungle Nightjar にあるならば日本のヨタカにも存在することはおそらく疑いなく、日本のヨタカでヨーロッパと同質の録音を聞いてみたいところである。もっともヨタカは日本固有種ではないので大陸などで先に記録されるかも。
関連があるかも知れない台湾の記録例: Gray Nightjar (Ting-Wei HUNG 2018.10.22)。Flight call に分類しているが、ソノグラムの周波数特性を見ると翼の音かも知れない。30 秒間ホバリングをして翼を震わせたとのことで、平均5分ごとに繰り返したとのこと。投稿者は空中で採食していると解釈して Flight call に分類した模様。しかし繁殖期の終わっているだろう秋の記録で、ヨーロッパヨタカの wing-claps とは違う機能かも知れない。
消音機能を持つ羽毛を持ちながらディスプレイの際に翼で音を出していると考えられる例については、#コミミズク の備考 [コミミズクの羽音] も参照。
繁殖生態については週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 92 p. 19 でヨーロッパヨタカは5月下旬と7月に年2回産卵とのこと。1回のクラッチサイズは2個とのこと。
wikipedia 英語版には産卵時期と月の位相の関係を調べた研究の中で、7月の2回めの産卵の方が月の光の条件に恵まれるとの記述がある [Holyoak and Woodcock (2001) "Nightjars and Their Allies: The Caprimulgiformes"]。
種も異なり、日本では梅雨の時期も重なるので、月の位相との関係は地中海性気候のヨーロッパとは状況がかなり異なるだろう。
[ヨタカの威嚇行動]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 92 pp. 18-20 のヨタカ属の項目で、獲物に襲いかかるコブラのように前後に体をゆすって息をふきかける動作もする。マムシのような外敵を遠ざけるのに役立つと解説があり、写真ではヨーロッパヨタカとヨタカ類の1種 (種名を特定しないのはいかにも当時らしい) の写真が紹介されていた。
類似の動き (息をふきかけるまではなかったが) は渡り中継地で見たことがあり、これは集まっている写真撮影者への威嚇だったのかも。隠蔽色の色彩で武器を持たない鳥がそれでも見つかってしまった場合の手段で、アリスイのヘビを真似る行動と同様かも知れない。
観察地では面白い行動と言われていたが負担をかけていることは間違いないので今後は気をつけよう。
[反響定位を行うアブラヨタカ]
日本の鳥ではないがアブラヨタカ Steatornis caripensis 英名 Oilbird という種類がある。
Brinkov et al. (2017) Oilbirds produce echolocation signals beyond their best hearing range and adjust signal design to natural light conditions
によれば夜行性で、洞窟に住んでコウモリのように反響定位 (echolocation エコーローケーション。エコロケーションの表記も使われるが原語や綴りを反映するためにエコーを使う方がよいと思う) を行う (食物は脂肪に富んだ果実)。
反響定位の音はコウモリに比べて低いが音の性質はよく似ている。人の可聴域にも入る。
アブラヨタカが高い音を聞き取る能力は他の鳥よりよいわけではなく、反響定位の音のピークとは一致しない。実際に聞いているのは 8 kHz 以下の部分であろうとのこと。
また目の感度は脊椎動物で最も優れており、瞳孔も 9 mm まで広がるそうである。
Martin et al. (2004) The eyes of oilbirds (Steatornis caripensis): pushing at the limits of sensitivity に視覚の研究があり感度は高いが分解能は低いはずで、そのため嗅覚や反響定位も用いるのだろうとのこと。
さらに Rojas et al. (2004) Retinal morphology and electrophysiology of two caprimulgiformes birds: the cave-living and nocturnal oilbird (Steatornis caripensis), and the crepuscularly and nocturnally foraging common pauraque (Nyctidromus albicollis)
参考までにアブラヨタカの生態研究も紹介しておく: Holland et al. (2009) The Secret Life of Oilbirds: New Insights into the Movement Ecology of a Unique Avian Frugivore GPS 追跡でこれまでの想像とは異なって平均3日に1回しか洞窟に戻らず、大半の時間を木にじっととまって過ごし、種子を反芻していたとのこと。
Stevenson et al. (2021) Oilbirds disperse large seeds at longer distance than extinct megafauna
南米コロンビアの研究で絶滅したメガファウナの哺乳類以上に長距離の種子散布者となっている。現存動物がメガファウナ時代のように長距離の種子散布者となっていないとの仮定は誤り。
アブラヨタカは現生の Strisores (Caprimulgiformes) で唯一の果実食で、飛翔性昆虫食の多いこのグループの中でどのように進化したのか興味が持たれている。Olson (1987) An early Eocene oilbird from the Green River Formation of Wyoming (Caprimulgiformes: Steatornithidae
によればアメリカのワイオミング州で始新世前期のアブラヨタカに類似した鳥の化石 Prefica nivea が見つかっており始新世前期以前に果実食が始まっており種子植物と共進化した可能性が考えらえる。現在アブラヨタカが南米にのみ生息するのは遺存分布と捉えている。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 92 p. 6 では育雛期間は約 120 日と非常に長く、ひなの生育が非常に遅いとのこと。果実食では栄養価 (記述ではたんぱく質となっていた) が低いためと解説されていた。この説明が正しいならば果実食は鳥の食物の本命になりにくかも知れない。
可能ならばもっと栄養価の高いものの方がよい (#クロハゲワシ備考の [猛禽類の植物食] にも多少関連する)。アミノ酸組成を考えるとやはり肉 (次善として虫) を食べる方がよく、猛禽類では果実食はおまけ程度。必要栄養素を補っている程度なのだろうか。
アオバトなどの果実食中心の鳥はむしろ特殊と言えるのかも知れない。線維性植物食も効率が悪く、ガン類などは食べてばかりいないといけないのだろう。
Birkhead による "Bird Sense: What It's Like to Be a Bird" (2012)、邦訳されてティム・バークヘッド著; 沼尻由起子訳「鳥たちの驚異的な感覚世界」(2013 河出書房新社) によればアナツバメ類にも反響定位を行うものがあるそうである。
この書の英語原題は Nagel (1974) による What is it like to be a bat?"の問いかけに対応。
Tim Birkhead, Bird Sense: What It's Like To Be a Bird の書評 (Oxford Literary Review) によれば Nagel (1974) の書物は悪名高いエッセイとのこと。前書きにも出ているそうなので今度また見てみよう。"bird question" そのまま訳せば鳥の疑問だが、英語では "ばかげた疑問" の意味にもなるのだろう。でも現代の科学では褒め言葉ともなっている。
Irwin (2024) What is it like to be a lizard? Directed attention and the flow of sensory experience in lizards and birds を参考にした。比較の鳥にオオワシが出てくる。
音は光と同様に波であり (光は電磁波で可視光の波長は1ミクロンより小さい。音は空気中の粗密波である点は違いがある)、光の回折限界が視力の上限を決めるように (#イヌワシの備考参照) どのぐらい小さな目標を反響定位できるかは音の波長で決まる (波長よりずっと小さなものは音を反射することができない)。
常温での音速は 340 m/s 程度で、2 kHz の音だと波長は 340/2000 = 0.17 m = 17 cm となる。「鳥たちの驚異的な感覚世界」によればアブラヨタカは電線のコードを避けることはできず、20 cm より小さいものは反響定位で認識できていないようでこの見積もりとよく合う (反響定位の音のピーク周波数もその程度で、もっと高い音は聞こえていないか反響定位に有効に用いられていないのだろう)。
コウモリが反響定位にずっと周波数の高い超音波を用いているのはこのため。例えば 50 kHz の超音波だと 7 mm ぐらいのものを検出することができる。鳥類の聴覚には哺乳類に比べて内耳の蝸牛が短いことによる物理的限界があり、コウモリレベルの反響定位は行うことができない。
鳥類 (+ 爬虫類) と 哺乳類の耳は独自の進化を遂げたもので構造も少し異なる。
Tucker (2017) Major evolutionary transitions and innovations: the tympanic middle ear
によれば鼓室を持つ中耳は鳥類・哺乳類の共通祖先段階では存在せず、それぞれが独自に進化させたとの考えが広く受け入れられているとのこと。爬虫類でもヘビやカメレオンのあるものでは鼓室を失っている。ヘビは音よりも振動を感じ取っているとのこと。
哺乳類では噛む行動に関連して関節を安定させるために軟骨を発達させているが、鳥類では二次的な軟骨を独自に発達させた。これに関連して中耳の構造も違うと考えている。中耳の骨の骨化は鳥類・爬虫類で1片、哺乳類で3片で独自に進化したと考えられる。
Peacock et al. (2025) Middle Ear Mechanics in the Barn Owl メンフクロウの耳小骨の増幅機能をレーザードップラー法で測定。35 dB の増幅に相当して哺乳類に匹敵するとのこと。新鮮な凍結死体を測定直前に解凍したものとこと。
ヒトやチンチラよりも上。1 kHz 以上の周波数でネコより上。
中耳が特に発達していると言われるアレチネズミ (gerbil) とそれほど違わない。哺乳類に比べて原始的な機能というわけではなかった。他の鳥よりも全般的によいが測定されたすべての他種のデータを上回っているわけでもない。どのように違うかは物理の話になるので詳しくは見ていただきたい。
中耳での伝達での時間遅れは哺乳類より大きいが可聴域とよい関係があり、哺乳類のように高音を聞く種類では短くなるとのこと。
Fettiplace (2020) Diverse mechanisms of sound frequency discrimination in the vertebrate cochlea に内耳の hair cell 有毛細胞 の音程判別機構の総説があり、鳥類と哺乳類 (およびカメ) の可聴域が異なる理由などが述べられている。
鳥類と哺乳類では2種類の hair cell を持ち、収斂進化と考えられるとのこと。
鳥類・爬虫類では electrical tuning (イオンチャネルを用いて音による運動と共鳴する) が中心で (イオンの運動速度が関係する) 温度に高く依存し、10°C 上がると基本周波数がほぼ2倍になるとのこと。
爬虫類に比べて鳥類は体温が高いのでこのメカニズムで高音を聞くのに適している。
哺乳類ではタンパク質の prestin (SLC26A5) が信号増幅や音程判別に働いていることが知られていて、細胞膜の prestin が周期的に形を変えることで hair cell の形が周期的に変わって音の信号を受け取る。イオンチャネルを用いない共鳴では温度依存性はあまりないとのこと。
鳥類では直接の証拠はまだ得られていないが遺伝子発現などから何らかの働きがあると考えられる。哺乳類では prestin を阻害すると感度が 40 dB も下がる実験結果がある。
prestin は 2000 年に発見され音の周波数に対応する急速な振動の動きから音楽の presto に基づいて命名されたとのこと [この部分 wikipedia 英語版より。詳しい分子メカニズムは Bavi et al. (2021) The conformational cycle of prestin underlies outer-hair cell electromotility]。
村越 (2017) 三列に並ぶ外有毛細胞の役割とその分子構造 に哺乳類におけるメカニズムの日本語解説論文がある。
鳥類は哺乳類同様に prestin を持っており、より高音を聞くような適応も原理的に可能だったと思われるが、おそらく自分の発声に敏感な周波数に合わせ、フクロウ類を除いて高音への感度を上げる選択は働かなかったのではないかとの考えもある (prestin そのものの起源は古いと考えられている)。
フクロウ類やハチドリ類などが高い周波数をどのように聞いているかの分子機構はまだわかっていない。実はまた驚きの結果が出てくるのかも?
Fuentes-Ugarte et al. (2025) Tracing the evolution of prestin's area-motor activity through ancestral sequence reconstruction and structural modeling (preprint) によれば哺乳類の prestin は構造が特化しているらしく、他の動物では陰イオン透過に用いられていた分子を別目的に用いられるようになったもの。哺乳類では系統の早い時期から変化が始まっている。
鳥類の prestin の祖先型にはその兆候はないようなので、やはり音を聞く目的には進化しなかったのだろうか (この論文は preprint 段階だが過去研究は引用されている論文から見ることができる)。
蝸牛の長さの違いが鳥類と哺乳類の可聴域の違いの由来としばしば説明されるが、センサー部分の分子機構にも違いがあるよう。哺乳類は高音を聞くために prestin を積極的に活用するようになった模様。
抵抗とコンデンサからなる RC 回路に例えることがでて、RC 時定数 (時定数 = 抵抗 R × コンデンサ容量 C; カットオフ周波数は時定数に反比例する) 問題として知られている。
鳥類 (R を減らす) と哺乳類 (C を減らす) は別の解決方法を選んだとの解釈がある: Iwata (2022) Of mice and chickens: Revisiting the RC time constant problem。
複雑な音声を用いる鳴禽類の出現は後の時代になるので、この解決方法の選択は進化の早い段階で起きたのだろう。系統的に古い鳥があまり高音を必要としなかった (自身の声も低かった) ためにそれ以上の進化の自由度が低く、哺乳類に比べて鳥類の聴覚の生理的限界が目立っていると解釈できるかも知れない。
もっとも我々自身が音楽で用いているように、鳥類が最も鋭敏な 2 kHz 周辺の音は空中コミュニケーションに適した音で、昼行性の鳥類は体温も高くイオンチャネルを最適化することで十分対応できただけかも知れない。
音の強さは距離の2乗に反比例と思われるだろうがこれは音源や波の形態にもよってあまり単純でない。音響の基礎: 音の発生と伝搬 (総務省ページ)。
実際の空気では温度差 (特に温度逆転層が発生した場合) による屈折も生じ、もちろん風があれば流されるので遠方なのによく聞こえることもある。
1羽の鳥の声を近くで聞くならばおそらく距離の2乗でよいと想像する。距離の2乗に反比例する場合は距離が2倍になると約 6 dB の減衰になる。これは距離に比例する減衰量にならないことに注意 [低周波騒音などを議論する場合にしばしば "距離の2乗で急激に減少するので"、のような表現が使われることがあるが "離れてもあまり減少しないので" と読む方がむしろ正しい]。
媒質である空気中を伝わる波であることによる減衰がさらに加わり、こちらは距離に比例するので遠くでは距離の2乗の効果よりもこちらの方が強くなる。例えば 250 m から 500 m になっても理想的に距離の2乗の効果は 6 dB だが高音では波の減衰効果の方がもっと大きい。
流体中の粘性による音の減衰に関する Stokes's law (ストークスの法則 1845) があって周波数の2乗に比例して減衰が早くなるとのこと。
さらに他のメカニズムもありこの値よりも減弱率は大きくなる。山田 (1990) 空気による音の吸収
に日本語解説がある。グラフを見ると 100 m の距離での減弱は 1 kHz の音で 1 dB (あまり吸収されない)、10 kHz だと 10 dB となり、さらに高い音では減弱がより大きい。高音の音の到達範囲を考える場合は主にこちらを考えればよい。
500 m 離れると 10 kHz の音は 1 kHz の音に比べて 50 dB も減衰し、事実上ほぼ聞こえなくなる。
高い音は物理的に遠くまで届かないので、空を飛ぶ鳥のように遠方の個体とコミュニケーションには適さない。
また低い音は不確定性原理による時間分解能の限界があり、多くの情報を送ることができない。遠距離の相手に最も多くの情報を送ることのできる条件を考慮すればこの周波数が選ばれた理由を論理的に説明できるかも (いかにもどこかに書いてありそう)。
夜行性だった哺乳類は捕食者や遠くの相手に聞こえにくい音で近傍個体とのコミュニケーションをするために既存の prestin の機能を上げて対応したのかも知れない。細胞を変形させるなど少々無理をしているので hair cell の劣化があり、高音が聞こえにくくなりやすい原因になっているかも知れない (これは個人的想像)。
鳥類は電気回路を工夫し、哺乳類は機械的増幅機構を取り入れることで感度を上げることや高音に対応したと見ることもできそう。
鳥類の聴覚には優れた点もあり、時間分解能が高い、聴覚細胞に再生能力があることが知られている。成熟した哺乳類では再生が起きないため、鳥類の知見が難聴の治療に応用できるかと盛んに研究されているが、今のところそれほどの成功を収めていない。もっともこの再生能力は鳥類に限られたものではない。
少し古い情報だが Stone and Cotanche (2007) Hair cell regeneration in the avian auditory epithelium には鳥類での聴覚再生機能が発見されて 20 年も経つが、哺乳類が再生能力を欠く理由、(薬剤を与えるなど) 別の条件を与えてすら再生しないかどうかは未だわかっていないとある
(哺乳類は寿命が短かったので使い捨ての初期設計で十分だったのだろうかと個人的推測。現代のヒトの寿命が設計寿命を超えていると考えれば微妙に納得できる気がする)。
Castano-Gonzalez et al. (2024) The crucial role of diverse animal models to investigate cochlear aging and hearing loss も哺乳類モデル動物が中心だが鳥類の情報もあり、最大寿命の 80% まで聴力感度曲線が変わらない "老いない耳" として取り上げられている。耳以外にも最大寿命近くまで生殖能力も保持することが多いなど我々の寿命の感覚と異なる点も取り上げられている。
Sadanandan et al. (2023) Convergence in hearing-related genes between echolocating birds and mammals
にも面白い結果が発表されており、反響定位を行う鳥と哺乳類の間で一部の遺伝子に収斂進化が見られるとのこと。哺乳類の間ではコウモリとクジラで収斂進化が知られていたが、鳥類でも類似性があった。
前述の prestin には収斂進化が見られず、反響定位を行う鳥と通常の鳥で違いはなかった。鳥類であまり活躍していないらしいことも間接的に読み取れる。
これもゲノムが多数解読されるようになって可能となった比較生理学研究。
参照されている鳥の耳の感度曲線 (スズメ目とフクロウ類が中心) Dooling (2002) Avian Hearing and the Avoidance of Wind Turbines
も大変面白いので一読の価値あり。アブラヨタカの感度は思ったほど高くなく、高音の感度も通常の鳥と大差ない。オーストラリアのクビワミフウズラ Pedionomus torquatus Plains Wanderer は感度が悪く高い方はほとんど聞こえていないが低音にかなり感度がある。ハトの特性に似ている。
ハイタカとチョウゲンボウはよく似ていて自分たちの声に最適周波数を合わせて聞いている感じ。
スズメ目では結構種差があってウソは高音もよく聞こえている。ホオジロ類に近い新世界のチャガシラヒメドリ Spizella passerina Chipping Sparrow は高音がよく聞こえている。
アメリカガラスは結構感度が高いが高い方は聞こえていない。これも自分たちの声に合わせたものか。
ミナミシマフクロウ Ketupa zeylonensis Brown Fish Owl はフクロウ類の中では感度が低く、高い音も聞こえていない (羽音を出して飛ぶらしい点とも整合する。#ウスハイイロチュウヒの備考 [音を出さない羽毛構造] 参照。
系統の近いシマフクロウもそうではないだろうかと思ったが調べるとやはり羽音を出して飛ぶとあった。とまって獲物を狙うので消音の必要がないとのこと)。
アメリカワシミミズク Bubo virginianus Great Horned Owl もフクロウ類の中では感度があまり高くないが高い方は聞こえている。フクロウ類はミナミシマフクロウを除いて感度がよいか高い方まで聞こえているよう。
音が波であって回折を伴うことは鳥類学の他の分野にも関係するので合わせて紹介しておく。例えば樹木があると幹の両側を通った音が回折を受けて干渉する。これは幹の太さと音の波長の関係で決まるので、幹の太さよりずっと長い波長の音 (低い音) はこの効果をほとんど受けずそのまま通過することができて遠くまで届く。
幹の太さ程度の波長の音は干渉の影響が大きく何度も干渉を受けることで急速に減衰して遠くまで届かない。高い音が短距離で減衰する効果と合わさって、森林性の鳥で遠くまで伝わる声とそうでない声があるのはこの原理による。
Viscosity によれば静止した空気の dynamic viscosity (ストークスの法則に関連するもの) は絶対温度の 0.7355 乗に比例するとあり、気温が高くなるほど音は遠く届きにくくなる。夜間や早朝に鳴く理由の一つにも挙げられる。
カラ類などの警戒音であるシー音は音源定位の難しい音なので捕食者にわかりにくいとされるが、飼育下のスズメフクロウとオオタカを用いた実験では定位ができてスピーカーの方向を向いたという [「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 125]。
この本ではこの音は木々の間で急激に衰えるので頭上の猛禽類には届かないとの説明がある。
それぞれの文献は、Marler (1955)、Konishi (1973) Locatable and Nonlocatable Acoustic Signals for Barn Owls が音源定位の難しい声についての議論。バンド幅の小さい音は定位しにくのでは。しかし、
Shalter and Schleidt (1977) The Ability of Barn Owls Tyto Alba to Discriminate and Localize Avian Calls はメンフクロウでの実験で定位できることを示した。
Shalter (1978) Localization of Passerine Seeet and Mobbing Calls by Goshawks and Pygmy Owls がスズメフクロウとオオタカが定位可能なことを示した。
その後の実験ではある程度の定位はできるが、やはり高い音による定位の方が精度が低い、つまり方向がわかりにくいことは実証されている。
上記の減弱率の数字を見ると空気を通過するだけで 100 m で 10 dB 減弱するので検出困難になるだろう。近傍個体に伝えるための警戒音と考えて問題なさそう。
高音難聴のあるカナリア
Madison et al. (2025) Whole genome sequencing identifies genetic candidates for high-frequency hearing loss in canaries (Serinus canaria)
カナリアの品種の中で Belgian Waterslager canary は大きな低い音のさえずり環境で育てられ、有毛細胞の損傷や欠失があって高音難聴を示すとのこと。Waterslager の名称は水の流れるような低く大きなさえずりから名付けられたものらしい [参考ページ Belgian Waterslager canaries (Laboratory of Comparative Psycoacoustics) にオーディオグラムがある。自身の声が大きく聞こえないために大きな声でさえずるらしい]。
全ゲノム解析で関連する候補遺伝子を調べたもの。哺乳類でこれまで報告されていた難聴に関連する変異と共通するものもあったとのこと。
上記ページの説明も合わせると、鳥類では通常有毛細胞の再生機能があって難聴にならないとされているが、この品種ではその機能を制約する要因を持っていると考えられる。
[ヨタカ系統の音声や羽毛装飾]
[ヨタカ類の "wing-clapping"] に関連してヨタカ類の他の種類の音声を調べると意外や意外。
ラケットヨタカ Caprimulgus longipennis Standard-winged Nightjar XC718946 (Peter Boesman 2022.3.19) の声を聞くとヨタカ類とハチドリ類が近縁でも全然おかしくない気がする。
XC899190 (Phil Gregory 2024.3.29) も同様。12 kHz を超えていてアブラヨタカが反響定位に用いても不思議でないような音声。ヤブサメのさえずりの比ではなく、これは気合を入れてしっかり聞かないとわからない。これもさえずりとのこと! 姿が見えているこそ鳴いていることがわかるのだろう。
ラケットヨタカの翼のどこが "standard" なのかと思ってしまうが、ここで言う standard は旗、軍旗、植物学では旗弁 (vexillum) も指す (#カタグロトビの備考 [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] ドイツ語 Fahne も参照)。ラケットヨタカの種小名は "長い翼" で面白くも何ともないが、この vexillum はフキナガシヨタカ Caprimulgus vexillarius Pennant-winged Nightjar の種小名の方に使われている。
なぜこれらの種類が気になったのかと言えば、これらのディスプレイに用いる吹き流し構造と "wing-clapping" の音の存在はもしかすると排他的ではないかと考えたため。フキナガシヨタカは初列風切の P2 の特殊化、ラケットヨタカは次列風切とのこと。ヨタカ類は種類によって視覚刺激のための羽毛の特殊化、視覚的でない方法をとった種類が聴覚刺激のための羽毛の特殊化で "wing-clapping" の音を出しているのではと考えた次第。今のところ事例数が少なすぎてどちらとも結論できていない。
音を出す部分の羽毛構造を同定すればよいはずなのでヨタカでも調べられるのでは (?)。
フキナガシヨタカの方も高音音声を用いている XC958776 (Dries Van de Loock 2024.10.11) など。ヨタカやヨーロッパヨタカの典型的な音声だけを念頭に置くとヨタカ系統の音声全般の理解を誤るかも知れない。
ヨタカ類が音声学習をするはずがないと考えるのも先入観が入っているかも知れない。音声学習を行うハチドリ類に似た声を出す種類は調べてみる価値があるのでは。アマツバメ類についても同様。
[あえて開けた環境でねぐらをとるエジプトヨタカ]
Wasserlauf et al. (2023) A telemetry study shows that an endangered nocturnal avian species roosts in extremely dry habitats to avoid predation
イスラエル、パレスチナ、ヨルダンの死海周辺の追跡による結果。通常は生物が住まないと考えられる極度に乾燥して開けた場所に昼のねぐらをとるとのこと。おそらく哺乳類の捕食者対策と考えられるが、通常は保全対象とは考えられないような環境。
昆虫の多い農地で盛んに採食を行っていた。またプランテーション地域は完全に避けていた。
地域では 1940 年代に絶滅したと考えられていたが 2016 年に再発見された個体群とのこと。
ヨタカ類の少なくともあるものは高温耐性が非常に高いとのこと: O'Connor et al. (2017) Avian thermoregulation in the heat: efficient evaporative cooling in two southern African nightjars
外気温が 40 ℃ 以上になると水分蒸発が急激に増えてホオアカヨタカ Caprimulgus rufigena Rufous-cheeked Nightjar は 56 ℃ まで、
ゴマフヨタカ Caprimulgus tristigma Freckled Nightjar は 52 ℃ まで対応したとのこと。ヨタカ類はのどをふるわせる (gular flutter) ことで効率的に蒸発による冷却できる仕組みを進化させて他の鳥では耐えられないような環境に適応しているとのこと。
死海周辺の開けた場所でねぐらをとるエジプトヨタカにもおそらく同様の生理機構が働いているのだろう。
日本のヨタカはどこでねぐらをとるなど議論を聞いたことがないが、真夏の昼間はどこに隠れているのだろう? 森林に生息するので高温耐性はあまり必要ないか、あるいは予想外の場所の可能性もあるかも。
Smit et al. (2018) Avian thermoregulation in the heat: phylogenetic variation among avian orders in evaporative cooling capacity and heat tolerance
の実験によれば (種類は違うが) ヨタカ類は同じ外気温に対して体温が低め。ハト類は主に皮膚からの蒸発で高温に適応している。gular flutter は古い系統の鳥によくみられ祖先形質か。新しい系統ではあえぎ呼吸が中心になる。舌骨の構造や機能の違いを反映したものか。
[ゲノムからみるヨーロッパヨタカの過去の渡りの歴史]
Day et al. (2024) Revealing the Demographic History of the European Nightjar (Caprimulgus europaeus)
ヨーロッパヨタカは6亜種あるとされるが mtDNA と亜種の整合性はよくないことが知られておりこの文献でも地理的な東西のクラインのように扱っている。
一方で南北の個体群の違いは興味あるところで、南北の個体群のゲノムから過去の実効個体数変化を遡ることで長距離の渡りがいつ始まったか情報が得られる。これまでは渡り行動は最終氷期 (2.2 万年前) の終わりに始まったと考えられていたが、過去の実効個体数変化は最終氷期よりずっと早くから渡りを行っており、これは種分化年代を考えても妥当とのこと。
ヨーロッパヨタカの渡り研究: Norevik et al. (2025) The spatial consistency and repeatability of migratory flight routes and stationary sites of individual European nightjars based on multiannual GPS tracks
繁殖地・越冬地は安定している。渡り途中経路は春の方が大きく異なる。
ヨーロッパヨタカも減少しており、英国で行われた複数個体の全ゲノム解析: The Genomic Signature of Demographic Decline in a Long-Distance Migrant in a Range-Extreme Population
過去 180 年で遺伝的多様性が 34.8% 失われ、近交度も増加した。英国は分布の西北端にあたる。同様の研究はヨーロッパの渡り鳥について知られている。分布の東北端にあたる日本のシマアオジなどもおそらく同様の結果になるのでは。ヨタカでも同様かも知れない。
[ヨタカ類とアリの意外な関係]
スペインのアカエリヨタカ Caprimulgus ruficollis Red-necked Nightjar の研究: Camacho et al. (2024) The nightjar and the ant: Intercontinental migration reveals a cryptic interaction
ヨタカ類は地上にいる時間が長く、しばしばグンタイアリ類 (army ants) の被害を受ける。1% 以上の個体が趾を失っているとのこと。アリによって足の機能が一部失われた鳥が長時間不自然な姿勢をとることによる他の部位の二次的な変形と思われる損傷が記録されたとのこと。ヒメヤマセミ Ceryle rudis Pied Kingfisher でもアリによる足の損傷が知られているとのこと。
趾1本の損傷だけでも感染を起こす可能性もあり影響が過小評価されているかも知れないとのこと。
["エチオピアヨタカ" は雑種だった]
エチオピアヨタカ Caprimulgus solala Nechisar Nightjar はエチオピアで 1990 年に記載された種だったが (参考)、多くの観察者が探したにも関わらず見つけられなかったらしい。
しかし IUCN では根拠もよくわからないまま VU 種となっていた。
Shannon et al. (2025) Genetic and morphological analysis shows the Nechisar Nightjar is hybrid (preprint) によれば DNA 解析の結果雑種と判明。
Caprimulgiformes (BirdForum 2025.4 の情報による)。
この研究によってヨーロッパヨタカの分類に再度変更が生じるかも知れないとのこと。
Caprimulgus 属の系統樹も出ているが、種類数が多いのでヨーロッパとアフリカに限定したもので cyt b を用いたもの。アジアの系統は含まれていない。ヨーロッパヨタカと判定されたサンプルも分子系統解析の結果別物と考えられるものも含まれるとのこと。
この地域ではゴマフヨタカ Caprimulgus tristigma Freckled Nightjar の新鮮なサンプルがなく熱望しているとのこと。
ヨタカ類は隠蔽的なグループなのでグループ全体で分子系統解析を行えば分類概念の認識も変わるかも知れないことも暗示している。
アジアの系統はどうなっているのかと調べてみるとほとんど読まれていない。KJ455345.1 (Caprimulgus jotaka の ND2) から BLAST を試してみると NC_086816.1 (Caprimulgus indicus のミトコンドリアゲノム。中国で読まれたもの) と全く同じ配列になる。
前者はヒマラヤの鳥の研究なのであるいは同じタクソンなのかも。アジアのヨタカ類の分子系統解析はまだ行えない段階となっている。
学名まで付けられながら DNA 解析で雑種と判明した事例として Cox's Sandpiper が有名 (#アメリカウズラシギの備考参照)。
["冬眠" する鳥]
"冬眠" する鳥として有名になったものにプアーウィルヨタカ Phalaenoptilus nuttallii Common Poorwill がある。
現在では "冬眠" (hibernation) の用語より torpor が主に使われる。wikipedia 英語版によれば数週間から数か月にわたる長い torpor を行うことが知られている鳥はこの1種のみとのこと。
ハチドリ類も夜間の torpor 状態が知られているが、同じく wikipedia 英語版の Strisores の項目では他の系統に比べて Strisores で torpor が格段に多く見られるとのこと。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 92 V-VII の記事 (浦本) では当時ちょうど話題となっていたようで、ヨーロッパアマツバメでも秋の渡りで異常な寒波に襲われた時に密集してかたまりとなっているのが発見されたことがあり、昏睡状態ではないかと想像されたとのこと。またヨーロッパアマツバメで天候が悪化して食物がとれない場合に巣内のひなが体温を下げて昏睡状態となるらしい。
当時からすでに系統的類似性による特徴か、あるいは食物の特徴から生じるものか解釈があったらしい。現代的な系統解析では Strisores に多いと言えることになるが、生理学が系統を反映しているのか、系統が近いため生態に共通性があって同様の特徴を進化させたのか議論のあるところだろう。
92 V ではプアーウィルヨタカが高温環境に特別な耐性があることも記されていた ([あえて開けた環境でねぐらをとるエジプトヨタカ] も参照)。
ここで取り上げられていたのは torpor 状態と関連が考えられて興味を持たれていたためだろう。
torpor (ラテン語の torpor 由来) は休眠と訳されているが何となく落ち着きが悪い。torpor のまま使う方がすっきりする感じがする。それはともかく torpor の wikipedia 英語版によれば精密に制御された体温調節機構 (thermoregulation) によるもので、従来考えられていたように体温調節を止めているわけではない。
哺乳類の方でむしろ多く見られる現象なので、鳥類・爬虫類でまとめる人はさすがにいないだろうが。また哺乳類でも有袋類と有胎盤類の torpor はメカニズムが異なるとのこと。
torpor は恒温性の獲得とともに進化したと考えられ、2.5 億年前程度の Lystrosaurus (Synapsida で哺乳類の方の系統) に冬眠類似現象の見つかったのが脊椎動物での最初の証拠とされている: Whitney and Sidor (2020) Evidence of torpor in the tusks of Lystrosaurus from the Early Triassic of Antarctica。
本当かどうかわからないが、torpor は対捕食者行動に必要なエネルギーを節約している可能性の指摘: Barratt et al. (2025) Torpor use in response to predation risk in a small, free-living bird。
研究対象種はルリオーストラリアムシクイ Malurus cyaneus Superb Fairywren でいろいろな面で変わった点の多い種類。
[ヨタカ類3種を用いた Bergmann の法則の検証]
Skinner et al. (2025) Environmental and geographic conditions on the breeding grounds drive Bergmannian clines in nightjars
ホイップアーウィルヨタカ Antrostomus vociferus Eastern Whip-poor-will、アメリカヨタカ Chordeiles minor Common Nighthawk (いずれもアメリカ、アメリカヨタカの名前は付くが日本のヨタカとは属が違う)、ヨーロッパヨタカ Caprimulgus europaeus European Nightjar の3種で、GPS を用いた追跡。
体サイズは、渡り距離の長さなど他に考えられる要因に比べ、繁殖地の温度環境と最もよい相関を示していたとのこと。
ヨタカ類は温度耐性が高いにもかかわらず Bergmann の法則に乗ることは興味深い。
Bergmann (1847) が提唱してからほとんど2世紀を経て強い証拠を提供するものとなったとのこと。
[その他]
ズクヨタカ科 (Aegothelidae, Owlet-nightjars) と呼ばれるヨタカに似た形態と習性を持つグループがありヨタカ目に含まれるか長く議論の対象だった、現在ではアマツバメ目を残す場合はこの科単独でズクヨタカ目 Aegotheliformes を形成する。ヨタカ目よりアマツバメ目に近縁。
和名の由来はズクがミミズクから (コンサイス鳥名事典)。
#アマツバメ備考の [アマツバメやハチドリは夜行性を体験したか?] で Feng et al. (2020) のオプシン遺伝子データをもとにこれらの系統関係を多少振り返っている。
南米のスナイロアメリカヨタカ Chordeiles rupestris Sand-colored Nighthawk は捕食者対策として アマゾンアジサシ Sternula superciliaris Yellow-billed Tern、オオハシアジサシ Phaetusa simplex Large-billed Tern、
クロハサミアジサシ Rynchops niger Black Skimmer の近くに営巣して巣の防衛に役立てるとのこと (wikipedia 英語版)。
雑誌 "Birder's World" 1990.10 pp. 76-77 に Robert W. Storer (#カワウ備考の [ガラパゴスコバネウの進化] 参照) による "The Potoos" (タチヨタカ類) の記事があった。この時点ではほとんど情報がなかった。夜行性の鳥の研究は大変遅れている。
夜行性のヨタカ類縁系統が隠蔽色で、昼間は擬態を行っている種類が多いことはよく知られていてタチヨタカ類の木の枝化けの写真が紹介されていた。しかし擬態している写真ばかり (つまり横向き) で、背面がどのように見えるのか一般記事にも学術論文にもこの時点で記述がなかったとのこと。
後ろからの捕食者に丸わかりであれば擬態の意味がないわけで、擬態研究の盲点とも言える (笑)。
そのつもりで考えると、擬態しているサギ類は後ろからはどのように見えるかなど確かに写真を見た覚えがない。
△ アマツバメ目 APODIFORMES アマツバメ科 APODIDAE ▽
-
ヒマラヤアナツバメ (第8版で検討種)
- 学名:Aerodramus brevirostris (アーエロドゥラムス ブレウィローストゥリス) 短い嘴の大空を走る鳥
- 属名:aerodramus (合) 大空を走るもの (aer (m) 大空、-dromos 走るもの Gk)
- 種小名:brevirostris (adj) 短い嘴の (brevis (adj) 短い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) の)
- 英名:Himalayan Swiftlet
- 備考:
aerodramus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、ラテン語の aeros は a を長母音としている。ギリシャ語の -dromos は短母音のみ。どこで音節を区切るかわかりにくいがギリシャ語では dro-mos と区切っている。ただし語源が -drom + -os で、ギリシャ語単独で発音する場合は dro- にアクセントがあり温存することも可能に思える。
ここではギリシャ語の音節区切り、pterodroma (この場合さすがに drom-a とは区切れない) など他の用例に合わせて -ro- をアクセント音節に採用した (アーエロドゥラムス)。
brevirostris は rostrum の o が長母音でここにアクセントがある (ブレウィローストゥリス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動 (同定に確実性なし)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。3亜種あり (IOC)。
五百沢・岡部 (2004) Birder 18(10): 67-69 にヒマラヤアナツバメ? の 1999 年の記録が紹介され、過去の 13 件のヒマラヤアナツバメ? の記録のリストがある。
アナツバメ類における反響定位 (#ヨタカの備考参照): Kevin and Clayton (2004) The evolution of echolocation in swiftlets。
従来は Aerodramus 属と Collocalia 属は反響定位の能力の有無で分けられていたが、Collocalia 属にも反響定位を行う種類が見つかったとのこと。
-
ハリオアマツバメ
- 学名:Hirundapus caudacutus (ヒルンダプース カウダクートゥス) 先の尖った尾のツバメのようなアマツバメ
- 属名:hirundapus (合) ツバメのようなアマツバメ (Hirundo (ツバメ) 属と Apus (アマツバメ) 属の合成)
- 種小名:caudacutus (adj) 先の尖った尾の (cauda (f) 尾 acutus (adj) 先の尖った)
- 英名:White-throated Needle-tailed Swift, IOC: White-throated Needletail
- 備考:
hirundapus は Hirundo の語末、Apus の語末がともに長母音だが、語構成の際に前者が落ちたものと考えれば -pus (足) が長音となると考えられる。-da- が短母音であればアクセント母音は -run- にあると考えられる (ヒルンダプース)。
caudacutus は cauda は短母音のみ。acutus は u が長母音でここにアクセントがある (カウダクートゥス)。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 caudacutus とされる。
記載時学名 Hirundo caudacuta Latham, 1801 (原記載) 基産地 New Holland = New South Wales, apud Mathews (Avibase による)。
Hirundapus 属は Hodgson 1836 (1837) が当時の学名で Cypselus (Chaetura) nudipes に対して与えたもの (現在はハリオアマツバメの亜種。こちらは基産地ネパール)。足と尾の両方を用いて木を登り非常に特徴的なので新属を与えた (The Key to Scientific Names)。
Hartert (1910-1922) では p. 843 と Chaetura Stephens, 1826 の属名を用いていた。khaite 長く流れる髪 oura 尾 (Gk)。この属名は現在はアメリカ大陸のエントツアマツバメ 現在の学名で Chaetura pelagica をタイプ種とする属として使われる。
この属名を用いたハリオアマツバメの改名もあって Chaetura australis Stephens, 1826 (参考)。
Hartert は統合派だったので Hirundapus を先に命名された Chaetura 属に含めたものと思われる。
Ruaux et al. (2023)
Drink safely: common swifts (Apus apus) dissipate mechanical energy to decrease flight speed before touch-and-go drinking
生物ではエネルギー効率を最適にする行動戦略がよくとられる。ヨーロッパアマツバメが水飲みをする際にエネルギー効率を最適にして (位置エネルギーを運動エネルギーに転換する) 高速で水面に接触するか不明であったが、高速撮影によって実際は減速してエネルギーを失っていることが明らかになった。
急速な方向転換による抗力で一部説明できるが不十分であり、何らかの追加の減速を行っているはず。接触面は数 mm のはずで非常に細かな運動のコントロールが必要。高速で接触すると姿勢を乱したり損傷の危険もある。別の種で水に落ちる事故もあったとのこと。いろいろなトレードオフの中で最適速度が決まっているのだろう。
Cui et al. (2024) Swifts Form V-Shaped Wings While Dipping in Water to Fine-Tune Balance
高速度撮影で判明した水を飲む際に翼を V 字型にするヨーロッパアマツバメの亜種 Apus apus pekinensis。流体力学的な評価も行っている。
笠野 (1996) Birder 10(4): 87 木にとまるハリオアマツバメ (山形県飛島) の写真がある。
-
アマツバメ
- 学名:Apus pacificus (アプース パーキフィクス) 太平洋の足のない鳥
- 属名:apus (合) 足無し (a 無い pous 足 Gk)
- 種小名:pacificus (adj) 太平洋の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:[White-rumped Swift 分離前の名称], IOC: Pacific Swift
- 備考:
apus は "アープス" と読んでしまいそうだが -pus が長母音 (#ナンキンオシ参照)。アクセントは冒頭で "アプース"。
単音で発音する場合でもアクセントは変わらない。
pacificus は冒頭が長母音 (pax パークス 平和 に由来) で -ci- がアクセント音節 (パーキフィクス)。英語風読みでも実用上は差し支えないだろう。
Apus 属はヨーロッパアマツバメの記載時学名 Hirundo Apus Linnaeus, 1758 (原記載) の種小名を属名に昇格したものだが、経緯は単純でなかった。
The Key to Scientific Names によると当時 Apvs Scopoli, 1777, Micropus Meyer & Wolf, 1810 (小さい足の意味), Cypselus Illiger, 1811 (cypselus ツバメやアマツバメ < kupselos Gk ツバメ) の3種類の属名が用いられていた。
Cypselus を用いた Linnaeus (1758) の学名の改名 (#ノスリの備考参照) もあった: Cypselus vulgaris Stephens, 1817 (参考 英名の Common Swift から作られた学名)。
Micropus murarius Wolf, 1810 (参考) も同様の改名かも知れないとのこと。
BOU (1915) は Apus = Apvs は Apos Scopoli, 1777 (甲殻類) と同じ名称と考えられ preoccupied と判断した。
Micropus (小さな足) は Linnaeus が植物に用いた属名で一時は無効とされたが、動物と植物の重複が許される規則になってからは有効な名称。
前2者が適切でないと考えた者は第3の属名を用いていた次第。
Hartert (1910-1922) p. 834 は preoccupied ではなく Apus を有効と扱っていた。
Peters (1940) は Apus が Apos とは異なるとみなして有効とした。
この場合は該当しないが、Illiger が他にもいくつもの新属名を与えた理由の解説があった。Tinamidae (BirdForum)。Illiger はラテン語またはギリシャ語に由来しない属名を排除したとのこと。我々が現在見聞する多数の属名が含まれていた。Illiger の判定によればキリン属 Giraffa も容認できないものだった。
この話題はシギダチョウ科 Tinamidae の分類改定提案論文に伴う話題として始まったもの: Bertelli et al. (2025) A new phylogeny and classification of the tinamous, volant palaeognathous birds from the Neotropics. Cladistics。日本と縁の薄いグループなのでパスしていたが Illiger の導入した属名の問題が派生して接点が出てきた。
Hartert に示されているヨーロッパアマツバメのドイツ語名は Mauersegler, Turmsegler で Segler は航海者、帆船、滑空するものやアマツバメなどの意味。Mauer は城壁など。Turm は塔。
p. 841 にアマツバメがある。この時代には属変更に伴って種小名の性を合わせるかまだ議論されていたことがわかる。Hartert は合わせる方を採用して pacificus を用いた。
Hartert は p. 833 と Cypseli 目に含めており、Cypselus の属名を用いた科や目の名称となっていた。その次にヨタカ目が出てくるのでここまでは現代の分類と似ていたがその次がハチクイ目、ヤツガシラ目になっていた。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には第3の属名が有効とみなされ、Cypselus pacificus の学名になっていた。アマツバメ科も Cypselidae となっている。
現在は当たり前に感じている Apus の属名が使われるようになったもの比較的最近ことだった。ただし Apus 自身が有効かどうかは問われていたものの、合成語の属名 Hirundapus (ハリオアマツバメ属) などは有効だった。
2亜種あり (IOC)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では kurodae 亜種アマツバメ と pacificus キタアマツバメ となっている。IOC では kurodae を kanoi (日本の人類学者 Tadao Kano に由来) にシノニムに含めている。これは Yamashina (1942) で記載されたもの。
記載時学名は Micropus pacificus kanoi Yamashina, 1942 (参考) 基産地 Botel Tobago (= Kotosho), South-east of Formasa と
Micropus pacificus kurodae Domaniewski, 1933 (参考) 基産地 Japan。
記載時亜種名に japonicus が使われなかったのは種小名に地域名がすでに入っており、地名が重なるのは美しくないと感じられたためだろうか。
[分類と亜種]
Dement'ev and Gladkov (1951) の扱いでは当時3亜種で、Apus pacificus pacificus Latham, 1811 (北に分布)、A. p. leuconyx Blyth, 1845 (ヒマラヤとデカン高原)、A. p. cooki Harrington, 1913 (インドスタン) であった。
同書で A. p. pacificus のシノニムとされていたものは、Hirundo apus var. leucopyga (バイカル)、Micropus pacificus kurodae Domaniewski, 1933 (日本)、Micropus pacificus kamtschaticus Domaniewski, 1933 (カムチャツカのペトロパブロフスク) となっていた。
Leader (2010) Taxonomy of the Pacific Swift Apus pacificus Latham, 1802, complex は亜種
pacificus, kanoi, cooki, leuconyx, kurodae, salimali (いずれも当時の亜種名) の標本を用いて計測値や羽衣で識別可能かを調べた。
cooki, salimali, leuconyx はそれぞれ他と容易に識別できる(生態にも異なる点がある)。kanoi と kurodae は pacificus と区別できるが、kanoi と kurodae は区別できなかった。
なお kurodae のホロタイプ標本は戦災で失われたため、ホロタイプ間での比較は不可能である。kurodae の採集地は日本としか記されていない。kanoi と kurodae はシノニムの関係にあり、先取権の原則からは亜種名は kurodae であるべきとしている。
Leader (2010) は当時のアマツバメを4種に分ける提案を行い、これは現在 IOC でも採用されている。Pacific Swift Apus pacificus, Salim Ali's Swift Apus salimalii サリムアリアマツバメ, Blyth's Swift Apus leuconyx ブライスアマツバメ, Cook's Swift Apus cooki クックアマツバメ。
Apus cooki はかつてアマツバメの亜種とされていた Dark-rumped Swift Apus acuticauda セグロアマツバメ と上記4種の間をつなぐ位置にあるとのこと。4種に分離されたうちのアマツバメの英名として、(かつて使われた) Fork-tailed Swift はふさわしくない (同属のほとんどの種類がこの特徴を持つため) としている。
wikipedia 英語版にも記載があり、南部の亜種は kurodae に先取権利があるため Clements は現在 (2011) こちらを用いているとの注釈がある。2023 年現在もこの扱いであり、もし北部と南部で亜種が分かれるのであれば IOC より日本鳥類目録の扱いが正しいように思われる。
なお Leader (2010) は Dement'ev and Gladkov (1951) で当時の亜種 pacificus のシノニムとされた他のものは調査していない。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では4亜種で leuconyx と salimalii を独立種としていない点が IOC と異なる。
この分類では kurodae について、pacificus に含まれる可能性を挙げ亜種リストには入れていない。
旧英名 White-rumped Swift はもともとセグロアマツバメ (Dark-rumped Swift) を アマツバメから分離する際に導入された名称だが、同じ英名は IOC では アフリカコシジロアマツバメ Apus caffer に使われている。
亜種の分布域については必ずしも明瞭でない。Clements では kurodae は日本南部、中国東部、台湾、フィリピン北部としている。Brazil (2009) "Birds of East Asia" では対応する kanoi は中国南東部、台湾、蘭嶼 (Lanyu 島) で繁殖する留鳥となっているが、この文献は Leader (2010) 以前に書かれたものであることにも注意が必要であろう。海外の観察者の報告を見ると、この地域の留鳥を kanoi と判断している (基産地からもっともらしい) 印象を受ける。
日本の kurodae を認めるか、亜種分類や分布についてはまだ明確と言い切れないようである。
アマツバメ類の分子遺伝学研究は Paeckert et al. (2012)
Molecular phylogeny of Old World swifts (Aves: Apodiformes, Apodidae, Apus and Tachymarptis) based on mitochondrial and nuclear markers にあるが、種レベルの系統である
(当時はアマツバメはまだ4種に分割されておらず、亜種の扱いで pacificus, cooki のみが調べられている。
現在の分類で Apus cooki は Apus acuticauda に近縁である結果となっており、Leader (2010) の見解とは整合性があるが、過去に Apus pacificus の亜種とされていたこととは整合性の悪い結果となっている。Leader (2010) の分離した他の種、アマツバメとして残された亜種との関係を今後調べる必要があるのだろう。
Leader (2010) にもたびたび登場するが、アマツバメ類の研究家としてデイヴィッド・ラック (David Lack) とその著書、丸武志訳「天上の鳥アマツバメ」(平河出版社 1997) を挙げておく必要があるだろう。
原著 "Swifts in the Tower" (1956)、2018 年に改訂版が再版された。これほど身近だった鳥だが英国では営巣場所の減少で個体数が減少しているとのこと。
ラックは他にも多数の本を著しており、古典的名著も多く邦訳もいくつもある。
これはヨーロッパアマツバメ Apus apus 英名 Common Swift を扱ったものでヨーロッパでは非常にありふれた鳥である。分布を見ると東アジア近くまで広がっていることにやや驚かされるが、日本でも記録があるとされているが類似種との識別の記載がないため検討種になっている。提案されている亜種は pekinensis (北京の) である。
ヨーロッパアマツバメの亜種 pekinensis のジオロケータを用いた渡りルートの研究: Zhao et al. (2022) A 30,000-km journey by Apus apus pekinensis tracks arid lands between northern China and south-western Africa
定常分布の東端に近い北京から乾燥地帯を主に通ってアフリカ南部を中心に動きながら越冬している。
このような経路であれば少しオーバーシュートすれば確かに日本にやって来てもおかしくなさそう。
サハリンからオーストラリアに渡るアマツバメのルート。まず大陸 (ロシア沿海地方) に移動する:
Ktitorov et al. (2021) Cross the sea where it is narrowest: migrations of Pacific Swifts (Apus pacificus) between Sakhalin (Russia) and Australia。
[アマツバメは飛びながら寝る?]
シロハラアマツバメ Tachymarptis melba Alpine Swift について Liechti et al. (2013)
First evidence of a 200-day non-stop flight in a bird の研究が有名になったが、調べたものは次のヨーロッパアマツバメと同じ。アクトグラムに羽ばたきのない期間があることと、長時間無着陸で睡眠のない状態を維持することは不可能と考えられることから、飛びながら眠っていると考えられるが、直接確かめられたわけではない。
Hedenstrom et al. (2016) Annual 10-Month Aerial Life Phase in the Common Swift Apus apus
がヨーロッパアマツバメの繁殖期の行動をアクトグラムとジオロケータで調べており、99% 以上の時間を空で過ごしている。一部の個体はずっと飛んでいたが、時々飛行活動が弱まることがあった。ほとんどの個体が夜間短時間着陸したとのこと。時々ねぐらをとることがあるとしても大部分の生活は空中とのこと。
飛びながら寝ているかどうかまではまだ調べられない。
鳥類における飛行中の確実な睡眠については#オオグンカンドリの備考を参照。これら2つのアマツバメ類の研究については同項目の Rattenborg (2017) の批判的解釈も参考に。鳥はあまり寝なくても大丈夫も含めて、巷で言われる話は誇張され過ぎている可能性がある。
[星空の Apus]
天文ファンであれば Apus の名前を見るとむしろ「ふうちょう座」を想像するかも知れない (星座の学名もラテン語である)。この「ふうちょう」はもちろんフウチョウ (風鳥。極楽鳥の別名もあり、英語名はこちらに対応) のことであり、フウチョウ科 Paradisaeidae の学名とは全く異なる。
16世紀、ヨーロッパに初めてオオフウチョウがもたらされた時、各個体は剥製にする際に交易用に翼と足を切り落とされた状態で運ばれていた。そのため、この鳥は一生枝にとまらず、風にのって飛んでいる bird of paradise (天国の鳥) と考えられた (wikipedia 日本語版から) ので、足のない (a-pus) のラテン語の起源は同じである。
「ふうちょう座」の wikipedia 日本語版にはいろいろ面白いことも書かれているのでご覧いただくとよい。ハチを意味する Apis (ヨーロッパハチクマの学名に登場する) と間違われたこともあるとのこと。なお日本からは (事実上) 見えない南半球の星座である。
鳥の名前の星座はいくつかあるが (はくちょう座、わし座などが有名で神話に基づく)、多くは南半球にあって日本からは見えないか見えにくいものが多い。これらは南方から珍しいものがヨーロッパにもたらされるようになった時期に作られたものが多い (鳥の世界とは違って今後新しい公式の星座が作られることはない)。南半球の天文ファンは夜空を見て鳥ばかり見ていることになり、北半球の鳥ファンにとってはうらやましい。
公式の星座名には現れないが「こぎつね座」はもと「ガチョウをくわえた小キツネ」であって星座絵にはガチョウが描かれている。こと座の一等星ベガ (Vega、織女星) は「落ちるワシ」(アラビア語の降下するワシ、ラテン語に訳され Vultur Cadens となった) の意味で、こと座の星座絵には琴を抱えたワシがよく描かれている。
つまり「夏の大三角」と呼ばれる一等星はすべて鳥と縁がある。この付近の星座絵を見ると鳥ばかりで図案的にも面白いので星座絵の代表的部分としてよく利用される。
[アマツバメやハチドリは夜行性を体験したか?]
そろそろ飽きて来られた方もありそうなので鳥の話に戻ろう。日本にはハチドリがいないので身近な鳥ではないが、アメリカではごく身近な鳥で庭に (日本の家の庭の規模を想像してはいけないが) 当たり前にフィーダーが置いてあったりする。蜜を吸っているところを見てあまりに鳥らしくないのでもっと近づいて見ようとすると逃げられて、やはり鳥なのだと認識させてくれる。
日本産の鳥のうち、ハチドリに最も近い系統がアマツバメ目である。これらは分子遺伝学による現生鳥類の系統分類ではヨタカ類が最初に分岐した枝に含まれる。新しい分類に基づく図鑑ではこれらの種類が一緒に並べられているのはそのためである。この分類群を Strisores (和名があるのかは知らないが、中国語名では夜鳥類と呼んでいる。英名の別名も nightbirds) と呼ぶ。
Prum et al. (2015)
A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing に系統樹が出ているのでご覧いただきたい。なおこの Prum プラム は#エトロフウミスズメの備考「美の進化」に出てくるのと同一研究者である。
系統解析からの最も "単純な解釈" では、ハチドリは夜行性のヨタカ類の枝に含まれていて、800 万年の夜行性生活の後に再度昼行性 (アマツバメ、ハチドリ) を獲得したことになる。
夜行性だったことの影響はどのように現れているかは (この論文の時点で) 未知であると書かれている。
哺乳類では長く夜行性生活を体験したために本来視覚にあったはずの4原色のうち2原色を失い、大半の種で2原色であることはよく知られている。鳥でも夜行性のものは4原色の一つである紫外線の受容体を失う傾向がある (例えばフクロウ類。#フクロウと#カタグロトビの備考も参照)。
しかしハチドリ類が優れた色覚を持っていると考えられる証拠がある。例えば
Venable et al. (2022) Hummingbird plumage color diversity exceeds the known gamut of all other birds。夜行性を経験した後でも優れた色覚を保持していたのか、あるいは失った後に獲得したのか、それとも夜行性を経験しない進化経路を経ていたのか、大変興味深いことである。
アマツバメ類についても同様の視点からぜひ調べるべきであろう ← ヨーロッパヨタカとハチドリ類は後にデータがあることを知った (#オオルリの備考 [オオルリはなぜ青い] 参照)。この系統の少なくともいくつかの種は夜行性を経験した後でも紫外線知覚を失っていなかった。
Feng et al. (2020) Dense sampling of bird diversity increases power of comparative genomics
にさらにデータがあり、ヨタカ類でも紫外線知覚を失っているものもあった
[なお以下の議論はオプシン遺伝子の有無のみで判定している。長波長オプシンには紫外線感度もあるので、フクロウ類のようにこちらを用いて紫外線を活用している可能性がある]。
コアメリカヨタカ Chordeiles acutipennis Lesser Nighthawk (渡りをする)、チャックウィルヨタカ Antrostomus carolinensis Chuck-will's-widow (渡りをする) では失われていた。この2種は近縁系統でこの系統で失われたものと思われる。
サビイロタチヨタカ Phyllaemulor bracteatus Rufous Potoo でも失われているが比較的単独に失われたもの。
ハチドリ類の属する系統の早い分岐に当たるシロエリズクヨタカ Aegotheles bennettii Barred Owlet-Nightjar では失われている。
同じ系統の次の枝にあたるエントツアマツバメ Chaetura pelagica Chimney Swift、コシラヒゲカンムリアマツバメ Hemiprocne comata Whiskered Treeswift では OPN1sw1 (紫外線) は失われているが OPN1sw2 (青) が残っている。
この系統につながるハチドリ類も同じパターンで、祖先が夜行性系統だった一定の影響を受けている模様。
シロエリズクヨタカでは完全に夜行性になってしまって完全に失われてしまったのだろう。
逆のパターンもあって OPN1sw1 が残っているものもある。アブラヨタカなど。
Strisores では夜行性傾向があって紫外線知覚を失う傾向があり、ハチドリ類のように昼行性に適応したものは紫外線知覚を失っていないものや、青の知覚機能を活用しているように見える。
Otidimorphae も散発的に紫外線知覚を失う傾向があり、一部の系統は夜行性を体験しているかも知れない。アフリカオオノガン Ardeotis kori Kori Bustard やキバシバンケンモドキ Ceuthmochares aereus Yellowbill では失われている。
他に Mirandornithes も失う傾向が目立っており OPN1sw2 が失われている (フラミンゴ)。カンムリカイツブリやオビハシカイツブリではさらに OPN1sw1 も失われて青から紫外線知覚を持たないよう。この系統はあるいは夜行性傾向があるのだろうか。
ガン・カモはごく散発的に片方を失っているものがあるが (サカツラガン。家禽化の影響もあるかも知れない)、全体的には紫外線受容体だけ見ると昼行性のものと同じパターンのように見える。本来は昼行性だが狩猟圧が高くて夜行性行動をとっている仮説の方を支持するように見える。
暗所視に重要なロドプシンの遺伝子は調べられたすべての鳥にみつかった (程度問題はあるだろうが調べられた範囲で暗所視能力のない鳥はいないと言える)。ただし RH1, RH2 (Rhodopsin-like 2。哺乳類にはない) の片側のみ欠損のものが数種あったとのこと。
メンフクロウは紫外線受容体の双方とともに長波長オプシン (OPN1lw)、さらに RH2 も失っており、色覚はほとんどないものと思われる [#ハヤブサ備考の [視覚特性・薄明かりや夜間の狩り] に出てくる Wu et al. (2016) と異なる点もあるので正しくないかも知れない]。1種類の視覚受容体のみでほとんど音の世界とモノクロ視力で生きているよう。
よく調べられているメンフクロウの研究をもとに他のフクロウ類も同様と考えるとかなり飛躍が生じる可能性がある。
同様の意味で視覚にあまり頼っていない (2種類の視覚受容体のみ) ように見える種類にアビがある。
タカ類でも2種類 (OPN1lw, OPN1sw2) を欠いているクロクマタカ Spizaetus tyrannus Black Hawk-Eagle があり、タカ類の色覚が優れていると一概に言えない可能性がある。色彩にあまり敏感でないかも知れない (成熟すると黒でタカ類でよくみられる褐色味があまりないのも関係があるかも)。
なお光受容オプシンの表記は動物種によって異なるので多少ややこしい。LWS, SWS1, SWS2, RH2, RH1 とも表記される (RH1 が Scotopsin の名称を持つロドプシンで桿体細胞 rod cell にあって暗所視に働く。RH2 は 錐体細胞 cone cell にある)。
ヒトなど霊長類では LWS が遺伝子重複の後2色に分かれ、OPN1LW (赤), OPN1MW (緑) の名称となっている。
ただしこの論文を用いた議論はゲノムアセンブリの精度依存で、個々に見ると存在する遺伝子が検出されないだけの場合もあり得る。この論文にも述べられているが、過去に失われたと考えられた遺伝子が見つかった事例も多くあるとのこと。
系統として傾向のあるもの (Strisores など) はおおむね上記にように考えてよさそうだが個々の種の議論は今後の解析で変わるかも知れない。
[渡り鳥における磁気定位]
ごく最近になって思わぬ方向からこれにも関係した知見が得られている。
ご存じの通り、渡り鳥、特に夜に渡る渡り鳥がどのように方向を定めているのか (定位)、長らく研究が続けられてきた。プラネタリウムも用いた実験により調べられた夜空の星の回転方向から方角を定める方法、日の出・日の入りの太陽の方向、薄明時の空の偏光が知られており、いずれも実験的証拠がある。
渡り鳥が地球磁場を感じていることも実験で示され、かつてはハトの嘴の付け根にある磁鉄鉱が磁気を感じているなどの仮説があったが、現在最も有力と考えられ、盛んに研究されているものは網膜に存在するクリプトクロム (*1) である。
主にヨーロッパコマドリを使った実験が行われているが、光を与えないと磁気定位ができないそうである (まったく暗黒では寝てしまうそうで実験ができないわけであるが)。その時に赤い光では磁気定位ができず、青い光が必要との実験的証拠が得られている。
このような光依存、波長依存性のある磁気感応物質として現在生体で知られている唯一のものがクリプトクロムであり、それが鳥の網膜に存在していることで、磁場を視覚で感知している可能性が高いことが明らかになった。
この先しばらくは分子の話など非常に難しくなり読み飛ばしていただいても構わないが、現在の「鳥の渡りの科学」の到達点の一つにもなりそうなので、少し頑張って読んでいただくとよいと思う (英語の大丈夫な方ならば、文章だけよりも後半に紹介されている YouTube 動画の説明を聞くとよい)。
クリプトクロムの中にあるフラビン色素 (flavin) とクリプトクロムタンパク質中のトリプトファン残基の間で、光を受けることでラジカル対が生成される (トリプトファン残基からフラビンに電子が1個移動してそれぞれの分子に不対電子ができる。光子のエネルギーが波長で決まる (*2) ことから青い光でないとこの反応が起きない)。
ラジカル対の寿命がそのままでは非常に短いため磁気検出に用いることができない。ところがクリプトクロムの中では3次元的に畳み込まれたタンパク質分子の中で4つのトリプトファン (*3) 残基が並び、電子伝達を行って片方の電子を遠く運ぶことで (*4) ラジカル対の寿命を大幅に延ばすことができて生体が磁場を感知することを可能にしていると考えられている。
フラビン色素にある方の不対電子は電子の持つスピン (後のもう少し詳しい説明を参照) と、フラビン色素を構成する一部の原子核の持つスピンとの間で相互作用を起こす (古くから知られている電子スピン共鳴に用いられるもの)。
この影響が引き離されたもう1個の不対電子と相関を通じて別の分子に伝わって 、何らの過程を経て神経の信号となり、磁場情報として取り出されると考えられている。
この部分を最初に書いたころは、この部分の具体的機構はまだ未解明と記していたが、最近の分子動力学計算により、電子を失ったトリプトファン残基の角度が変わることで分子全体の形が変化し、ClCry4 複合体部位の構造が変わって下流に情報が伝えられる可能性が提案されている: Schuhmann et al. (2024)
Structural Rearrangements of Pigeon Cryptochrome 4 Undergoing a Complete Redox Cycle。
Ramsay et al. (2024) Cryptochrome magnetoreception: Time course of photoactivation from non-equilibrium coarse-grained molecular dynamics。
磁場感知に関係するクリプトクロムは鳥が一般に持つ網膜の4種の色覚受容体細胞のうち、紫外線を感受する細胞にあると考えられている。クリプトクロムは網膜全体に分布していることが知られており
(視覚にそれほど役に立たないような眼球周辺部にもセンサーがあることはこの目的には役に立つ。また網膜にセンサーがあるとはいえ、映像として磁場方向を見ているとは言い切れない。眼球の形状は主に視覚への適応だろうが磁気知覚への適応の影響も考える必要があるだろう)、
眼球内で全方向を向いて整列分布することによって磁場の方向を検知することができると考えられている。この部分の具体的な処理機構はまだ未解明。
磁力線の方向はわかるが、N極・S極を区別することはできない。これは鳥の行動実験結果とも合っている。磁場の方向はわかっても南北はわからないことは、もしかすると逆方向への渡り (迷鳥) のメカニズムにも関係しているかも知れない。
実験室での渡り鳥の光依存、波長依存性行動はラジカル対仮説を裏付けるものであるが、さらにもう一つ実験的証拠がある。ラジカル対仮説では電波がラジカル対に影響を与えることが期待されるが (*5)、この影響も実験とほぼ合致した。
ちなみに渡り鳥の磁気定位を乱す電波の周波数上限は 120-220 MHz と理論的に見積もられていた。新しい実験で 116 MHz が上限と求められた。渡り鳥の定位に対して提唱されている他のメカニズムでこのような現象を説明することはできない。
Leberecht et al. (2023) Upper bound for broadband radiofrequency field disruption of magnetic compass orientation in night-migratory songbirds。
ちなみに現在使われている携帯電話などの電波は影響を与えない領域にあり、携帯電話の電波が渡り鳥の行動を乱すとの説は現在では根拠がない。
以下はしばらく歴史の話になる。
Wiltschko and Wiltschko (2022) The discovery of the use of magnetic navigational information の歴史のレビューも読める。Wiltschko のかかわる 1960 年代の仮説発表当時は世の中の反応は非常に懐疑的なものだった、かごの中で磁場を操作して仮想的な渡りを行わせる実験などなど。
渡り鳥が磁場を感じるメカニズムとしてのスピン状態 (*6) の可能性が提案されたのは意外に古く、Leask (1977) が色素 (当時は網膜で光を感じる色素のロドプシンが想定されていた) のスピン状態の変化が関わっている可能性を指摘していた。渡り鳥が磁場を感知する機構としてスピンを提唱した最初の研究を挙げる場合はこの Leask (1977) がふさわしい。
そして Schulten et al. (1978) が「ラジカル対」を提唱したが、あまりにも時代の先を行き過ぎていて理解されなかった。1970年代では化学者にとってさえもラジカル対の研究は始まったばかりであった。「鳥の渡りの謎」(1994 ベーカー、原書 1985) では「スピン状態」としてすでに言及されていた。
色素のスピン状態が関連しているアイデアは Hong (1977) がすでに出していたが、実験室で磁場がラジカル対化学反応に与える影響や光合成する細菌への影響なども確かめられた結果、Schulten et al. (1978)のアイデアにたどりついた模様である。
渡りの定位が周囲の光の波長に依存することは 1990 年代には知られていた。Gwinner (1974) "Endogenous temporal control of migratory restlessness in warblers" によると光がない状態では渡りの不穏 (*7) も止まるとのこと。
事態を一変させたのは Ritz, Adem, Schulten (2000) が生物学者にも読める形でクリプトクロムの関与する磁気受容を提唱したことに始まる (A Model for Photoreceptor-Based Magnetoreception in Birds)。
タンパク質のアミノ酸配列は遺伝子を解析すれば決まるが、タンパク質の3次元構造はすぐわかるわけではない。コンピュータプログラムの進歩でかなり正確な予測ができるようになっているが、やはり正確な構造決定にはタンパク質を結晶化させて (これには大変高度な技術が必要である)、その X 線などによる解析で3次元構造を知るのが王道であった。この手順を必要とせず計算機の中でかなりの精度で推定することを可能にした AlphaFold が 2024 年のノーベル化学賞を受賞した次第である。
脊椎動物 (ハト) のクリプトクロム (Cry4) の結晶化に初めて成功したのが Zoltowski et al. (2019) Chemical and structural analysis of a photoactive vertebrate cryptochrome from pigeon で、上記の解釈で想定されていた化学的性質を示すことが確認された。
このあたりはさまざまな分野の研究者 (化学者や物理学者および生物学者) の協力が必要で、現在最先端で盛んに研究が行われる集学的テーマとなっている。地球磁場程度の弱い磁場をいかに感知することが可能かどうかも最先端の量子化学計算で調べられている (鳥の渡りの研究はもはや生物学者だけのものではなくなってしまった)。
クリプトクロムは現在「本命」であるが、生物学者サイドから疑問 (批判的視点) も含めて渡り鳥の磁気定位についてレビューされた論文もある。Nimpf and Keays (2022) Myths in magnetosensation。
この中の疑問は現在では解決されている、あるいは有力な解決法が提案されているものもあり、生物学者が理解困難な領域であまりにも急速に進展したこの分野に対する「焦り」のようなものも感じられる。
クリプトクロムにも何種類かあり、一部は体内時計 (概日リズム、サーカディアンリズム) の維持に役立っているとされているが、夜に渡る渡り鳥 (*8) の磁場感知に最も関係が深いと考えられているものに Cry4 がある。
Frederiksen et al. (2023) Mutational Study of the Tryptophan Tetrad Important for Electron Transfer in European Robin Cryptochrome 4a が 362 種の鳥類ゲノムを調べ、322 種で Cry4 の遺伝子を検出し、そのすべてで4つのトリプトファンが完全に保存されていた (いかに重要な機能を果たしているかがわかる)。
Cry1, Cry2 は鳥類の間でほとんど同一で、強く保存されていることがわかる。これらは概日リズムに関係する遺伝子で、生命維持に不可欠なのだろう (#イヌワシの備考参照)。
哺乳類でも Cry1, Cry2 遺伝子は概日リズムに必要であることがわかっている: van der Horst et al. (1999) Mammalian Cry1 and Cry2 are essential for maintenance of circadian rhythms。
磁気受容の中心と考えられている Cry4 はもっと変化が大きい。例えばハチドリ、オウム、Tyranni (タイランチョウ類、日本ではヤイロチョウが含まれる) で失われている。
スズメ目に至るまでは変異速度が速かった、スズメ目では遅くなっている。これは (例えば渡りのコンパスの) 機能が成熟して、あまり進化する必要がないためと考えられる。
Cry4 は何度も失われており、渡りを行わなくなった (あるいは飛べない) 種類では (必要でなくなるため) 比較的簡単に機能を喪失する可能性がある。また前記記述のように磁場感知に関係するクリプトクロムは色覚受容体細胞のうち、紫外線を感受する細胞にあると考えられている。夜行性の鳥では紫外線受容体細胞が失われる傾向にあり、一緒に Cry4 を失うことも考えられるだろう。
クリプトクロムと渡りの定位の研究はスズメ目のヨーロッパコマドリで調べられてきたもので、それより前に分岐した (系統的に古い) グループでの役割が同じかどうかまではわからないが、得られた結果をみるとハチドリ、アマツバメ類のようにヨタカグループのものに遺伝子を失ったり一部失われているものが集まっているように見える。
フクロウ類でも不完全に失われている系統があるようである。これらから想像すると、ハチドリ、アマツバメ類はやはり夜行性を体験していたのであろうか (前述記述で追加のように夜行性は体験したがヨーロッパヨタカも含めて紫外線受容体は失われていなかった模様)。
フクロウ類に留鳥性の高いものが多いのもこれで説明できるのかもしれない。渡りをするアオバズクやヨタカ、ヤイロチョウではどうなっているのか、ゲノム解析が待たれるところである。亜鳴禽類は Tyranni (タイランチョウ類、日本ではヤイロチョウが含まれる) にあるように Cry4 を失う傾向が強く見られる。
このグループの鳥が日本にあまり縁がないのもこのためかも知れない。
Frederiksen et al. (2023) の論文中 Pitta 属で調べられているものが唯一あり、ズグロヤイロチョウ Pitta sordida 英名 Western Hooded Pitta で、この種は Cry4 が失われていた。
種の記述では渡りをするか不明瞭とされている。また東洋では Ninox 属、Asio 属に渡りをするフクロウ類がいるが、これらの種は調べられていない。Otus 属の世界分布や島での固有種化などの経緯も関連して考えれば面白そうだがこの研究で調べられたものには含まれていない。
一方で昼行性猛禽類 (タカ、ハヤブサ) の Cry4 は渡りの有無にかかわらず調べられた範囲で完璧に存在する。タカ、ハヤブサ類は必要があれば渡ることができる性質を持ち合わせていることを意味する (例えば恒温動物以外を主食とする種類も進化できる) のだろうか。
フクロウ類の多くの系統で夜行性適応のために紫外線受容体とともに Cry4 を失い、食性の範囲もタカ、ハヤブサほどには広げることができなかった、などの妄想も膨らむ (もっとも初期のフクロウ類はタカのような昼行性であった証拠もある。#ミサゴの備考参照)。
スズメ目の祖先形が Cry4 を失わなかった系統だったのでが大規模な渡りを行えるような形に進化できたのかも知れない。そうでなければ昆虫食のスズメ目が温帯にはあまりやって来ず、我々が満喫しているような夏鳥のコーラスは温帯では聞けなかったのかも知れない。
また鳥類祖先系統から (最適化はされていなかったかも知れないが) Cry4 システムを持っていたと考えることができるので、鳥類の祖先となる系統も磁場情報を用いていたことが想像できる。
これらの知見はゲノム生物学、分子系統学、量子化学や物理学の現代最先端の手法を組み合わせることで可能になった実に驚くべき結果で、渡りの進化や生態を考える上でも大変示唆に富むものと思う。
日本語で読める資料がほとんどないので少し詳しく解説させていただいた。
もちろん定位は磁場だけが関与するわけではないので、種類によっては磁場を頼りにせず渡っているのかも知れない。渡りをするアマツバメ類はどのようにしているのか。いずれもこれからの研究の題材となるだろう。
また地磁気逆転などの現象もあり、地球磁場の弱い時期を渡り鳥はどのように乗り切ってきたのかなども興味深い。これらは「地球磁場はあてにならない」反論の根拠の一つとなっている。
同様の状況は夜空をコンパスとして利用する場合も、天の北極が変化する (歳差運動) ことが問題になる。この問題は特定の星を目印にするのではなく、ひなの時期に回転中心 (天の北極) を学習することによって回避できることがすでに実験で確かめられている。地球磁場の方はそのような簡単な法則性がないのでまだ議論の最中である。
地球磁場の時間変動が営巣地への帰還に関係があるか (つまり磁場が変化すると巣に戻れないのではないか)、などの研究がある: Wynn et al. (2022)
How might magnetic secular variation impact avian philopatry?。モデル計算では地球磁場で2次元地図を持つとむしろ不利になるのでは。他の手がかりと1次元の磁場情報を組み合わせて用いる方が有利だろう。2次元地図を持っているかそうではないかはこれまでも繰り返し議論されてきた問題。
磁気嵐 (太陽活動による) をどう乗り切るか: Bianco et al. (2019) Magnetic storms disrupt nocturnal migratory activity in songbirds 磁気嵐を感じると活動が鈍る?
Schneider et al. (2023) Sense of doubt: inaccurate and alternate locations of virtual magnetic displacements may give a distorted view of animal magnetoreception ability (解説)
人工的に磁場を操作することで誤った位置を認識させる (渡りの向きが変化する) とのこれまでの実験は問題点が多い。
Schneider et al. (2024) Reply to: Animal magnetic sensitivity and magnetic displacement experiments
普通に考えると同じ位置に戻るには驚くべき地磁気測定精度が必要であまり現実的でないように見える。しかし 0.6° の精度しかなくても 100 日くり返して測定すれば 0.05° の精度で位置を定めることができるとのシミュレーション結果。
100 回測定すればノイズが正規分布ならば 100 の平方根で 10 倍精度が上がる仕組み (しかし移動しながら違う場所で測定した場合に理論通りの精度が出るかは自分も疑問を感じる)。
なお、この分野の専門家 (物理化学) である Peter Hore の招待講演が YouTube にある。Peter Hore on Radical pair mechanism of magnetoreception (2017)。講演者自身は冒頭で「鳥のことは何一つわからないが」とスライドを示して聴衆の笑いを買っている。
上記のようなラジカル対を通じた磁気受容のメカニズムはスピンを持たない原子核のみからなる分子では働かない。例えば生体を形成する炭素や酸素のほぼ全体を占める同位体の原子核はスピンを持たない。メカニズムに関係するのは水素および窒素の原子核で、量子化学計算によればフラビン分子内に存在する窒素の原子核が関わっていることが示されている (上記公演の 22:50 あたり)。
地球磁場程度の弱い磁場に反応するこの電子-原子核のスピン相互作用 (hyperfine interaction) には方向性があり、これによって分子に対する磁場の向きに応じた反応を示すとのことである。自分も前半しか見ていないので、上記の分子レベルのメカニズム説明もちょっと怪しいところがあるかも知れない。お気づきの点があればご指摘いただきたい。
なお地球磁場程度の弱い磁場に影響を受ける化学反応はかつては知られていなかったが、Maeda et al. (2008) Chemical compass model of avian magnetoreception
は人工的な化学物質ではあるが弱い磁場に影響を受け、渡り鳥の磁気コンパスのモデル分子となり得るものを発見した。この研究には前述の Peter Hore も関わっており、彼はクリプトクロムも同様であることをおそらく疑っていないだろう。
Denton et al. (2024) Magnetosensitivity of tightly bound radical pairs in cryptochrome is enabled by the quantum Zeno effect
の論文によれば (この論文そのものは理解の範囲を超えるので議論はパスする)、FAD- / W+ (トリプトファンからフラビンアデニンジヌクレオチド FAD に電子が1個移動) の標準的描像では地球程度の小さな磁場には反応しないのではとの疑念がずっと持たれていたが、FADH+ / O2- のラジカル対を作る反応経路があり、酸素原子核はスピンを持たないので (この部分のアイデアは面白いと思う) 磁場検出により有利であるとのアイデアもあるらしい。
FAD- / W+ に比べて1桁らい感度がよいとの分子動力学計算もあるとのこと。この論文でもやはり限界があるらしいが、特殊な量子力学効果が働けば可能性もあるらしい。論文表題から想像するほどは楽観的な結果ではなさそう。
専門家による査読レポートを見ると FADH+ / O2- は候補にはなっているが寿命が短いため理論的に限界がある。"non-trivial" (自明でない) な量子効果 (quantum Zeno effect) を考えることでこの問題点を克服できる可能性を示すもので面白いとのこと。
査読者によれば Katsoprinakis et al. (2010) Coherent triplet excitation suppresses the heading error of the avian compass が Zeno effect が生体のラジカル対の磁気受容に関与する可能性を指摘したものとのこと。
全体を通して見ると、これまで本命と考えられているラジカル対機構で地球程度の小さな磁場を検出可能かまだ理論的な根拠がはっきりしていない。別の反応で検出可能かを多少流行のアイデアをもとに追求した論文と言えそう。
ただ O2- がいかにして生体信号になり得るかはトリプトファンの場合より難しそうなので本命のメカニズムではなさそうに思える。
なお Can Xie のグループが 2016 年に鉄を含むタンパク質を報告し、(ヒトでも既知の IscA1 と相同のもの。ミトコンドリアの iron-sulfur cluster に関連) MagR と名付けて Cry4 と結合して磁気受容に働いている可能性を主張しているが、疑問視する研究者も多い。
例えば Pekarsky et al. (2021) Revisiting the Potential Functionality of the MagR Protein や
Hore (2024) Proteins as nanomagnets and magnetoreceptors。
Can Xie のグループは細菌からヒトに至るまで MagR の配列はよく保存されていると主張している: Zhang et al. (2024) On the evolutionary trail of MagRs。
磁気受容に役立っていることを示すには常温でも働き、磁気受容の波長依存性も説明する必要があるのでなかなかハードルが高い: Guo et al. (2021) Modulation of MagR magnetic properties via iron-sulfur cluster binding。
短波長に吸収があることは示しているがクリプトクロムのラジカル対のようなカットオフ波長を作ることは難しそう。
このグループ (のみ?) が MagR の論文を多数出しており否応なく目にすることになるが磁気受容の文脈で読む時は要注意だろう。
Gravell et al. (2025) Spectroscopic Characterization of Radical Pair Photochemistry in Nonmigratory Avian Cryptochromes: Magnetic Field Effects in Gg Cry4a
の興味深い実験論文が出ている (Hore が共著者に入っている)。渡りの定位実験など以外でもかなりのことが実験室内で調べられるようになっている。特に生体により近い条件で分光解析ができるようになった点が大きな進歩であるとのこと。
ヨーロッパコマドリの4つめのトリプトファンをフェニルアラニンに置換すると分子単体ではむしろ磁場への感度が上がった。
上記説明と一見矛盾するが、トリプトファン連鎖が3つになることでむしろラジカル対の寿命が伸びているのでは。また4つめのトリプトファンは3つめとは機能が異なって、単なる電子伝達を行ってラジカル対の寿命を伸ばすよりは、例えば他のタンパク質との相互作用に関係しているのではとのこと。
また Frederiksen et al. (2023) の論文の系統研究で示唆された、渡り鳥で強く選択されているアミノ酸に着目して渡りを行わないニワトリの Cry4a で置換実験を行ってみたが特に感度は上がらなかったとのこと。1点の変異だけでは渡らない鳥に磁気定位能力を持たせることはできなかった模様。
このような実験系を確立することもおそらく簡単ではないので、追試や反論などもなかなか難しいかも知れないが、実験を解釈するための量子力学計算などは別途進むだろう。
こちらはオーストラリアでガ Agrotis infusa Bogong moth がの星の光で渡りを行うことを示した研究: Dreyer et al. (2025) Bogong moths use a stellar compass for long-distance navigation at night。
月光のない星の光で、地磁気を打ち消した条件での実験。かすんだ天気で地磁気を打ち消すと定位ができず、かすんだ天気では地磁気を用いていると考えられる結果が得られている。
星の集合 (特に天の川) の方向を感知しているのだろうか、とのこと。星の光で方角を知ることができるのは著者の知る限りヒトと夜に渡るいくつかの鳴禽類のみとのこと。
図では半月の場合が示されているが、満月が天の川方向と重なるのは6月ごろなので渡りの時期と重ならず解釈にも都合がよいのだろう。
Bogong moth のどのニューロンが反応しているかも調査しており、活動を示すニューロンは他の昆虫で定位に関わる部位に位置しているが過去にはこのタイプのニューロンは特に記述されていなかったとのこと。
南半球では天の川は明るいので昆虫にも検知できる可能性がこれまで提唱されていた
(この点は北半球の渡り鳥の星空コンパスを用いた過去の実験でも考慮すべき点であろう。銀河中心が南半球方向なので北半球の天の川は全般的に暗い。過去にプラネタリウムで研究を行った Sauer 夫妻もドイツなので南天の天の川の明るさはあまりご存じでなかっただろう。自分は経験がないが、本当に暗いところでは天の川の光で星影ができるぐらいとのこと)。
南半球の天の川の最も明るい点は天の南極方向ではないので、単純に明るい方向を目指している解釈は考えにくい。ただし明るさのみに頼る解釈では月がある場合でも正しく定位できる理由をうまく説明できないかも知れない。
実験結果は星の光と地磁気を組み合わせて定位していることを示すが、どのような感覚情報を用いているのかは今後の研究を待つ必要があるとのこと。
この研究を見ると、鳥においても星の光も地磁気もそれほど高い視覚の空間分解能を必要としないのかも知れない。
(注釈)
*1: cryptochrome ギリシャ語で「隠れた色」。フォトリアーゼ系のタンパク質でフォトリアーゼは細菌からすでに存在していたもので、紫外線による DNA 損傷回復に関与する。植物と動物では独自に進化し植物の光への反応に関係している。同じものを違う機能に進化させることは生物でよくみられるが、そんなものが長距離を渡る鳥を生み出すことになろうとは、神様? でも考えなかったであろう。
*2: 光には波 (電磁波) としての性質も粒子としての性質もある。後者を指して光子 (フォトン) と呼ぶ。皆様がお世話になっているカメラも、レンズ部分では光の波としての性質を、センサー部分では光子としての性質を利用している。光だけではなく物質も同じように波としての性質を持ち、量子力学の根幹をなす概念。
アインシュタインがノーベル賞を受賞したのも、有名な相対性理論の方ではなくて、光が粒子としての性質も示すことを示した業績によるもの。格好良く書けば光子1個のエネルギー E=hν ここで h はプランク定数、ν は光の振動数。赤い光 (振動数が小さい) は青い光 (振動数が大きい) に比べて E が小さい。
青い光でないと起きない (光量子のかかわる、センサーでもよい) 現象に対して、赤い光をいくら強めても現象が起きないのはこの原理による。
鳥の世界でも色素による色彩は光子としての光の性質に、構造色は波としての性質による。
我々も鳥も色を知覚できるのは (というよりそもそも光が見えるのは) 光子としての光の性質による。
*3: トリプトファンは一般的なタンパク質では存在量が最も少ないアミノ酸で、これほどトリプトファンが連なるのは特殊な役割を果たしていると考えるのが自然である。トリプトファンをコードするコドンは 64 種のうち1つのみで、生命進化の初期段階ではおそらく必須のアミノ酸でなかった。
チロシンとトリプトファンについては、20-24 億年前の酸素増大イベント (大酸化イベント) に耐えるために獲得された可能性を、量子化学計算と生化学実験から提示した研究が発表されており、アミノ酸の機能的特性が遺伝暗号を決定づけていたことを示唆している (wikipedia 日本語版より)。
参考: Granold et al. (2017) Modern diversification of the amino acid repertoire driven by oxygen。
*4: このように引き離された (といってもタンパク質分子程度のスケールだが) の2つの電子の間には離れていても相互の状態に相関があり、「量子もつれ」(qunatum entanglement) の状態にあるとも表現される。ちなみに「量子もつれ」は 2022 年ノーベル物理学賞のテーマであった。
世の中で普通に出てくる「量子もつれ」は一般に光子と光子の間のもので、遠距離でも光子と光子の間に相関を持たせる実験に成功している。渡り鳥のラジカル対の場合は電子と電子の間のもので、世の中一般によく言われるものとは異なるので注意。これは光子の場合と異なり (一般的でない環境、しかも特別な条件下でやっと実現可能) ごく短距離の間でしか量子もつれの効果は現れない。
*5: 我々がスピン (*6 参考) のお世話になっているものに医学で使われる MRI がある。渡り鳥における磁気定位メカニズムに関連がある (と思われる) のは電子のスピン、およびそれに影響を与える原子核のスピンであるが、MRI の場合は水素原子核のスピンを測定している。
磁場中のスピンが (古典力学的に言えば) 周期的に向きを変える (みそすり運動と言う) ことでそれに対応する電波が発生し、電波の周波数と強度を測定して画像にしている。もっとも磁石の原理もスピンなので、すでに誰もがお世話になっているわけであるが、ここでは電波との関係を示すために MRI を例示した。
*6: 電子や一部の原子核には古典力学の回転 (電子は大きさを持たないので回転の比喩は正しくない)、正確には角運動量、に対応する「スピン」と呼ばれる量子力学の概念があり、よく上向きスピン、下向きスピンのような表現が使われる。おそらく大学1年程度の化学で習うが、元素や周期律に興味のある方にはもっと早い時期にお馴染みかも知れない。
大学入試の「化学」を暗記科目にしないために高校段階でもスピンを教えているところもあるはずである。
ただスピンがなぜあるのか、という質問には大学で物理を学んでもそうすぐには教えてもらえない。物理系の3-4回生で選択科目次第で習える程度だろうか (さわりだけでも見ておきたい方は wikipedia 日本語版で「ディラック方程式」の冒頭をどうぞ)。「いったい何なのか」には深入りせずにそういうものがあると思っておくのがおすすめ。
渡り鳥を扱った本でも三重項状態 (triplet) とか一重項状態 (singlet) のような専門用語が登場することがある。これはスペクトル線の特徴から名付けられた用語だが、上向きスピン、下向きスピンの表現を用いれば2つの電子が同じ向きなのが三重項状態、逆向きなのが一重項状態となる。
有名なところでは酸素分子 (O2) の結合電子は通常は三重項状態の方がエネルギーが低く (分子軌道の対称性に起因する)、酸素分子は通常は2つの不対電子を持つ (液体酸素は磁石にくっつく)。一重項酸素はよりエネルギーの高い励起状態で活性酸素の一種。ロドプシンが磁場を感知すると考えられた初期の解釈では、ロドプシン分子内での仮想的な一重項/三重項の遷移を考えていた。
*7: 渡り鳥が渡りの時期にかごの中で夜間に渡る方角を向いて動作する行動。古典的には鳥の足にインクを付けて足跡の方向を見ることで渡りの定位を研究していた。ドイツ語の Zugunruhe (原語読み ツークウンルーエ。合成語なのでツークで切って g は無声化。-gu- は続けて読まない) は英語でもよく使われる。
ツーグンルーエの読み [おそらく中村司氏による。cf. 樋口 (2019) 中村 司先生を偲ぶ] が知られているが、これは英語・ドイツ語の読みが混ざっているのでおそらく正しくない。
Zug 牽引、行進、渡り鳥の群れのことなど。cf. Zugvogel 渡り鳥。こちらはツークフォーゲルと読む。Unruhe 不穏。落ち着かないこと。渡りの衝動と書いてあるものもあるが、原意を考えると不穏の方が適切だろう。Unruhe はもちろん Un + Ruhe ルーエ 平穏、落ちつきなどの意味。
ツークウンルーエと読めないとドイツ語の先生から読めていないときっと訂正されるだろう。ドイツ語 (に限らないだろうが) の授業ではテキスト音読で実力はかなりわかってしまう。
#ハチクマの備考にある飼育下での渡り時期の記述もおそらく同様と思われるが、主に昼間に渡りをするハチクマがそういう衝動を起こすとすれば面白い。
ウズラを用いた遺伝子発現の研究から "Zugunruhe" の脳内機構が一部明らかになった: Marasco et al. (2024)
Brain gene expression reveals pathways underlying nocturnal migratory restlessness。渡りの時期に視床下部の脂肪の輸送やタンパク質・炭水化物代謝に関係する遺伝子が強く発現していた。候補となる apolipoprotein H 遺伝子が発現し、夜間の行動と相関があることがわかった。渡りを行わない時期にはこの相関は見られなかった。
*8: 磁気定位に光が必要なのになぜ夜間に渡りができるのか、という根源的疑問があるだろう。これは研究者も気にしているようで、闇夜でなければ磁気定位が可能などの理論計算を行っている。これはまだ十分に解決されていない。
ハチドリについてもう一つ話題を紹介しておく。Osipova et al. (2023) Loss of a gluconeogenic muscle enzyme contributed to adaptive metabolic traits in hummingbirds
の研究によればハチドリがホバリング飛行を進化させるにあたって FBP2 という筋肉で糖新生を行う酵素を失ったとのこと。この酵素を失うことで糖分解やミトコンドリア能力が高まることが実験的に示されており、高いエネルギー生産が必要なホバリング飛行が可能になる一つのステップであったと考えられる (もちろんそのために常時糖分を補給する必要性が生じたわけだが)。
Osipova et al. (2024) Convergent and lineage-specific genomic changes contribute to adaptations in sugar-consuming birds (preprint)
ハチドリ類やオウム類、スズメ目の鳥で糖分に主に依存する系統で特に MLXIPL (糖と脂質代謝に関連する) が収斂進化を遂げている。他にもいくつも糖に関連する遺伝子候補が挙げられている。
ハチドリがグルコースだけでなくショ糖の成分であるフルクトースも取り込むことのできる SLC2A5 を持っていることを示した研究: Gershman et al. (2023) Genomic insights into metabolic flux in hummingbirds。SLC2A ファミリー遺伝子は目の色素にも関係があり、#ヤマセミ備考の [派手な色彩の鳥はまずい?] 項目から派生情報を参照。
ハチドリの超高音の音声と聴覚については#タンチョウの備考 [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] も参照。
[受粉者が変わって香りを失った植物]
Darragh et al. (2025) The Convergent Evolution of Hummingbird Pollination Results in Repeated Floral Scent Loss Through Gene Downregulation
熱帯アメリカで Costus 属の植物の遺伝子を研究。かつてはハチ類が受粉していたと考えられるがハチドリ類に変わった種類がある。受粉者がハチドリ類に変わった複数の系統の種類で香りの化学物質の種類が収斂進化的に減少していることが判明。偽遺伝子化までは起きていないが遺伝子発現が抑制されているとのこと。
研究そのものは植物が急速に進化できることを示すものではあるが、ハチドリ類が相対的に嗅覚にあまり頼っていないこともわかる結果となり、鳥の方の観点からも面白い結果となった。例えば祖先が夜行性生活を体験することで嗅覚レパートリーが増えるわけでもなさそう。
-
ヒメアマツバメ
- 学名:Apus nipalensis (アプース ニパレーンシス) ネパールの足のない鳥
- 属名:apus (合) 足無し (a 無い pous 足 Gk)
- 種小名:nipalensis (adj) ネパールの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:House Swift
- 備考:
apus は#アマツバメ参照。
nipalensis は地名の -ensis の冒頭を長母音としてアクセントを置く読みで "ニパレーンシス"。短音にしてもアクセントは移動せずどちらでもよい。
種記載時学名 Cypselus Nipalensis Hodgson, 1837 (原記載) 基産地 Central region of Nepal。
当時 Hodgson がネパールの新種の鳥に片っ端から Nipalensis を付けていた時代の産物の一つ。同じページに Hirundo Nipalensis Hodgson, 1837 = コシアカツバメの亜種が現れる。
Cypselus は#アマツバメの備考参照。
同種扱いされることもある Apus affinis の方も見ておくと記載時学名 Cypselus affinis Gray, 1830 (原記載 図版に現れるが本文はないとのこと) 基産地 No locality - Ganges (Avibase による)。affinis は "似た" の意味だが何に似ているかは明確には示されていないらしい。
Hartert (1910-1922) では p. 843。場所は推定 Ganges-Tal (ガンジス川の谷)。西アフリカやスリランカの個体は暗色で研究が進めばさらに分離される可能性があることを述べていた。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは kuntzi (アメリカの軍医、採集家 Robert Elroy Kuntz に由来) とされる (しかし下記参照)。
この記載時学名は Apus affinis kuntzi Deignan, 1958 (原記載) 基産地 Shih Lin (a nothern suburb of Taipei), Taipei Hsien, Formasa。
この記載までは亜種 subfurcatus が台湾で少数繁殖すると考えられていたものが亜種に値するとして名称を与えたもの。subfurcatus はマレー半島の亜種とされていた。
[分類と亜種の問題]
かつては Apus affinis の亜種とされ、古い図鑑でもこの学名であった。このうちインドより東のものが Apus nipalensis ヒメアマツバメ House Swift と分離され、多くのリストがこれに従っている。
分離する場合 Apus affinis Little Swift にはニシヒメアマツバメの和名が与えられている (日本で記録がないため亜種を考えた場合は同じ名前がどの亜種を指すかは自明でない)。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では Rasmussen and Anderton (2005) "Birds of South Asia: The Ripley Guide" ではこれらのグループの中で複数種の証拠を見いだせなかったため同種に戻し、
nipalensis を独立種でなく、Apus affinis Little Swift/House Swift の亜種としている。この場合は全体で 10 亜種。
両者の分布するインドおよび南アジアのリスト (2022) は IOC を採用し2種としている Taxonomic updates to the checklists of birds of India, and the South Asian region - 2022。
Paeckert et al. (2012) (#アマツバメの備考参照) では分子系統解析でこの2種の系統の分離は不完全 (wikipedia 英語版 incomplete lineage sorting。日本語版もある) としている。
将来の研究により同一種に戻される可能性もあるかも知れないが、このグループの研究はまだかなり不完全である。
なお Saitoh et al. (2015) GenBank: AB843360.1 では東京のサンプルについて Apus affinis Little Swift の名称で登録している。関連する研究は Saitoh et al. (2015) (#カルガモの備考参照)。
より古い時期に日本から Apus nipalensis の名称での登録もあり、日本の研究者の間でも分類の扱いが必ずしも一貫していないようである。
試しに上記配列から BLAST をしてみると日本もインドもあまり違わない感じ。Apus affinis と別種にする必要があるかどうかもちょっと怪しい。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) の記載では kuntzi は台湾の亜種で、日本は nipalensis であるとしている。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" も同じ見解で kuntzi との外見の区別を記載している。
台湾の扱いでは Clements v2022 をベースとして kuntzi を固有亜種としている: The 2023 TWBF Checklist of the Birds of Taiwan。
フィリピンのリスト (2023) では nipalensis, subfurcatus を留鳥亜種としており、伝統的にはフィリピンの亜種は subfurcatus とされていたのでこれも nipalensis の島嶼への分布拡大を示唆しているのかも知れない。
さらに興味深いことに2012年カナダのブリティッシュコロンビアで瀕死の状態で到着したヒメアマツバメの記録がある: Szabo et al. (2017) First Record of House Swift (Apus nipalensis) in the Americas。
この論文ではミトコンドリア COI ハプロタイプは日本の1個体、(ニシヒメアマツバメとされる) インドの2個体とまったく同じであり affinis/nipalensis と DNA 判定している。
参考: KY242302.1。
論文中では日本はニシヒメアマツバメの分布の東端の可能性もある書き方になっている。
この文献では 2010 年代前半にヒメアマツバメが北海道東端にまで進出していることにも言及している。
Researchers untangle mystery of tiny bird’s trans-Pacific flight
の記事も参照。嵐で運ばれたか渡りのコンパスに異常があったのかなどの可能性が考えられているが、太平洋を越えるのは容易でないだけで、分布を広げる先駆的な個体であった可能性であるようにも思える。
またアマツバメ類はヨタカ類の夜行性系統に関係があるため、あるいはそもそも渡りの磁気定位能力があまり高くなく (#アマツバメの備考参照)、長距離の渡りに適していないかも知れない。つまり渡りのコンパスに異常というより種として渡りのコンパスの精度が低い可能性である。
またヒメアマツバメとニシヒメアマツバメの遺伝情報 (ここで比較された短い部分だけであるが) が同じであったことも注目に値しそうである。
カタグロトビの確認初期にそうであったようにヒメアマツバメの繁殖確認時期に地理的に最も近い亜種が想定されたものがそのまま残っているものかも知れないが、現在の世界のリストの扱いと異なったものとなっている。
留鳥性の比較的高い種であり、台湾は固有亜種 (他の種でもよく見られる現象) で、日本の個体群は大陸の個体群の分布拡大に従った結果と考えると海外リストの見解の方が正しいかも知れない。
Paeckert et al. (2012) ではアマツバメ類は既存の亜種区分にも問題があるとのことで、将来研究が進めば亜種分類の見直しもあるかも知れない。
日本鳥類目録改訂第8版ではヒメアマツバメとニシヒメアマツバメが別種扱いとなる可能性が高いが、もし世界の趨勢の変化などで将来これが同一種 Apus affinis に戻された場合はニシヒメアマツバメの名前は基亜種 Apus affinis affinis のみを指す可能性もあり現在の名称が指す範囲とかなり異なってくるかも知れない。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES チドリ科 CHARADRIIDAE ▽
-
タゲリ
- 学名:Vanellus vanellus (ワネルルス ワネルルス) 小さな唐箕
- 属名:vanellus (合) vanellus タゲリ [小さな唐箕 (とうみ) (vannus (f) 唐箕 -ellus (指小辞) 小さい]。フランス語で穀物をあおぎ分ける箕。飛翔時のゆっくりした羽ばたきから (コンサイス鳥名事典)
- 種小名:vanellus (トートニム)
- 英名:Lapwing, IOC: Northern Lapwing
- 備考:
vanellus は vannus は短母音のみ。-ellus も短母音のみで長母音は現れないと考えられる。-nel- がアクセント音節となる (ワネルルス)。
フランス語の van は vannus から派生したと考えられ、ラテン語 vannus はイタリア祖語の *watnos、遡ってインド・ヨーロッパ祖語の *h2weh1- (吹く) に由来すると説明されている。
vannus の指小語には vatillum (ショベルやフライパン) の別単語がある (wiktionary)。
記載時学名 Tringa Vanellus Linnaeus, 1758 (原記載)。
Brisson (1760) がこの種小名をもとに Vanellus 属を提唱した。
当時は属が変わる場合に新名が与えられることがしばしばあり (#ノスリの備考参照)、Vanellus vulgaris Bechstein, 1803 (参考) (普通のタゲリの意味)、
Vanellus capella Schaeffer, 1789 (参考) (Capella については #タシギの備考参照) があった (後者は新名を意図したものではないかも知れない)。
後に Linnaeus (1758) の種小名が最も早く有効と認定された。
Vanellus cristanus (Meyer) の学名が使われていたことがあった。フランス語名 vanneau huppe からの訳だったよう。Vanellus cristatus Wolf & Meyer, 1805 (GBIF) と書かれるが由来がやや不明で Richmond Index に見つからない。
しかし日本では古くこの学名が用いられていたようで、山階鳥類研究所標本データベースでは YIO-02184 (千葉 1898) の 小川三紀氏採集の標本が模範標本となっていた。
一方のケリは 1887 年の飯島氏の標本に後に整理された段階と思われるがかなり時期の "ケリ" がある。
いずれも多くのラベルは後の時期に付けられたようで、鳥学者の間で古くからタゲリの和名が用いられていたか明確でなかった。いずれも古い標本が思ったより少なかった。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 158 (1946 年初出) によれば当時は句例は古句しかないとのことで、画材には登場したが別名が付けられていたとのこと。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば 1175 年頃の冬の句で「たとり」、大和本草 (1709-1715) で「なべげり」の名前で関東では犬けりと呼ばれるとある。
鶴 (つる) と田鶴 (たず) が同じものを指していたり、「くいな」に夏くいなと冬くいなの両方があったように、「けり」も「たげり」の名称もさほど区別されていなかったのではないだろうか。というのはどちらも田で見られるので「けり」を「たげり」と読んでも不自然さを感じないため。
タゲリの和名は Vanellus 属 (属名が変わったこともある) に統一した名称を与えるに際して "ケリ" を修飾する形で選択されたものではないだろうか (連濁あり)。他の Vanellus 属も同様の名前になっている。
Vanellus coronatus Crowned Plover にオウカンゲリの名称が当たられている (Rosenberg 1910 の古い標本が山階鳥類研究所標本データベースにある) などいかにも直訳のものが見られる。英名では Plover なので、"ケリ" は属名由来と考えられる。
"たげり" は古典にもあまり現れないようなので、学名が入ってから和名統一の際に与えられた比較的由来の新しいものと感じる。
単形種。
[チドリ目の系統分類]
チドリ目は巨大な目で日本鳥類目録改訂第7版、第8版の配列 (順序は IOC 13.2。学名は必ずしも一致するわけではない) を見てもどのように分類されているのか想像しにくい。Boyd の用いている上位分類を紹介しておく。IOC 分類順とは多少異なっている。
wikipedia 英語版は Kuhl et al. (2021) (#ミサゴの備考 [近代的な陸鳥の進化] 参照) をもとにしており、Boyd の提案はこれとも異なっている。Kuhl et al. (2021) のサンプルも十分多いわけではないので個々の属の位置には不定性がある。
Boyd は Cerny and Natale (2022) Comprehensive taxon sampling and vetted fossils help clarify the time tree of shorebirds (Aves, Charadriiformes)
[2021 年版 preprint; 出版社サイト。preprint からの訂正あり。Dryad data file]
を参照しており、この系統樹 (問題点もあり、他の項目の解説も参照) を見ればこれまで大きくまとめられていたものが日本鳥類目録改訂第8版でかなり変わる予定であることも理解できる。
なお Cerny and Natale (2022) のこの論文は自身でデータを取ったのではなく、GenBank に公開されている塩基配列を解析したもの。
Cerny 自身のサイトからチドリ目の スライド, 解説音声ビデオ を見ることができる。
チドリ目の完全な系統樹を作るよりも、これまで曖昧だった分岐年代、種形成や消滅の年代依存性を調べることが主目的で、個々の系統関係を知るためや属分割の根拠としてこの系統樹を用いている我々の興味とは少し異なるかも知れない。チドリ目の複数の系統が K-Pg 境界を生き延びた。
系統推定ソフトウェア RevBayes の開発者の一人で過去には生態学のフィールドワークや古生物学なども経験しているとのこと。
恐竜の高次系統関係がそれほど安定して支持されるわけではない研究も面白い: Cerny and Simonoff (2023) Statistical evaluation of character support reveals the instability of higherlevel dinosaur phylogeny
その後さらに Dufour et al. (2024) Seasonal migration and the evolution of an inverse latitudinal diversity gradient in shorebirds
の Supporting Information (Figure S1) に新しく解析された分子系統樹が提示された。
簡単に見た範囲では形態面でも直感にも近く、最近の系統分類の方向性とも整合する部分が多いので今後はこの系統樹がベースとされるかも知れない。これまで使われてきた属で単系統群にならないものも出ているので今後改訂されてゆくものもあるだろう。
ここで紹介する分類の科の名称は山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類によるが、それ以外の和名は仮に与えてある。
[#鳥類系統樹2024] の Stiller et al. (2024) でも主要系統がサンプルされているが膨大なチドリ目の中では一部のみで、調べられたものがここで示したものと矛盾する結果にはなっていないので Cerny and Natale (2022) を用いた Boyd のものを紹介しておく。
追記: 2024 年 12 月までの版による。2024.12.11 の変更で高次分類に変更点があるが Recent Changes、用いられたデータは Cerny and Natale (2022) + Stiller et al. (2024) でそれほど変わっているわけではないので、Boyd 自身の再解釈程度に見ておいてよさそう。ここでは急いで反映していない。
Taxonomy in-flux updates によればこれまで論文化されているものでは新しいゲノムデータを用いておらず、取り入れるとこれまでの取り扱いの問題点も見つかるらしい。このスレッドでは分子系統樹も新たに解析され提示されている (データは公開されているので原理的には誰でも作ることができる)。非常に高度な内容になっている。
まず最上位の分類を示す。
チドリ目 Charadriiformes
チドリ亜目 Charadrii
シギ亜目 Limicoli
ミフウズラ亜目 Turnici
カモメ亜目 Lari
含まれる個々の分類群は分類によって違いがあってもこの亜目の分割は納得いただけるであろう。
wikipedia 英語版ではシギ亜目に相当するものが Scolopaci となっている。
Boyd によれば Scolopaci よりも Limicoli の方がずっと先取権があり、歴史的にも長く使われてきた (科名 Limicolae としての用例も含む) とのこと。
ミフウズラ科は従来 Lari に含まれていた (wikipedia 英語版でも) が、最新研究で非常に古い系統と判明して分離された (#ミフウズラの備考参照)。
チドリ亜目 Charadrii
サヤハシチドリ小目 Chionida
(サヤハシチドリ科) Chionidae: Sheathbills
マゼランチドリ亜科? Pluvianellinae: Magellanic Plover
サヤハシチドリ亜科 Chionidae: Sheathbills
イシチドリ科 Burhinidae: Thick-knees
ナイルチドリ小目 Pluvianida: Egyptian Plover
ナイルチドリ科 Pluvianidae: Egyptian Plover
チドリ小目 Charadriida
セイタカシギ上科 Recurvirostroidea
トキハシゲリ科 Ibidorhynchidae: Ibisbill
セイタカシギ科 Recurvirostridae: Stilts, Avocets (セイタカシギ属は#セイタカシギの備考参照。ソリハシセイタカシギ属は#ソリハシセイタカシギの備考参照)
ミヤコドリ科 Haematopodidae: Oystercatchers (ミヤコドリ属は#ミヤコドリの備考参照)
チドリ上科 Charadrioidea: Plovers
ムナグロ科 Pluvialidae: Golden-Plovers (独立科に)
チドリ科 Charadriidae: Plovers, Dotterels
ノドアカコバシチドリ亜科: Oreopholinae (Boyd 独自)
チドリ亜科 Charadriinae (日本産の大部分のチドリが入る。#ハジロコチドリの備考参照)
タゲリ亜科 Vanellinae: Lapwings
シロチドリ/メダイチドリ亜科? Anarhynchinae (日本産ではシロチドリ、メダイチドリ、オオメダイチドリ、オオチドリが入る。#シロチドリの備考参照)
シギ亜目 Limicoli
レンカク小目? Parrida
ヒバリチドリ上科? Thinocoroidea
クビワミフウズラ科 Pedionomidae: Plains-wanderer
ヒバリチドリ科 Thinocoridae: Seedsnipes
レンカク上科 Jacanoidea
タマシギ科 Rostratulidae: Painted-snipes
レンカク科 Jacanidae: Jacanas
シギ小目 Scolopaci
シギ上科 Scolopacoidea
シギ科 Scolopacidae: Sandpipers, Snipes
ダイシャクシギ亜科 Numeniinae: Curlews (#ダイシャクシギの備考参照)
オグロシギ亜科 Limosinae: Godwits (#オグロシギの備考参照)
ヤマシギ亜科 Scolopacinae: Dowitchers, Snipe, and Woodcock (#ヤマシギの備考参照)
クサシギ亜科 Tringinae: Phalaropes and Shanks (#クサシギの備考参照)
キョウジョシギ亜科 Arenariinae: Turnstones and Stints (#キョウジョシギの備考参照)
ミフウズラ亜目 Turnici
ミフウズラ科 Turnicidae: Buttonquail
カモメ亜目 Lari
ツバメチドリ小目 Glareolida
カニチドリ科 Dromadidae: Crab Plover
ツバメチドリ科 Glareolidae: Coursers, Pratincoles
カモメ小目 Larida
ウミスズメ上科? Alcoidea
トウゾクカモメ科 Stercorariidae: Skuas, Jaegers
ウミスズメ科 Alcidae: Auks
エトロフウミスズメ亜科? Aethiinae
ウミスズメ亜科 Alcinae
カモメ上科 Laroidea
アジサシ科 Sternidae: Terns and Skimmers (カモメ科より分離。#アジサシの備考参照)
ハサミアジサシ亜科 Rynchopinae: Skimmers
シロアジサシ亜科 Gyginae: White Terns
アジサシ亜科 Sterninae: Terns
カモメ科 Laridae: Gulls and Noddies (#カモメの備考参照)
クロアジサシ亜科 Anoinae: Noddies
カモメ亜科 Larinae: Gulls
Boyd は分子系統樹に基づいて属をかなり細分しており、従来分類の属概念と異なるものが多いのでここでは含まれる属は示さなかった。
日本産種で違う属名を用いているものについては個々の種の備考に示した。
個々の変更理由は前述 Cerny and Natale (2022) の系統樹をそのまま受け入れれば判断いただけるだろう。
カモメ亜目では最近の分子系統研究を受けてかなりの学名が変更されたが Boyd の分類とよく一致している。チドリ亜目ではまだこれから変更されるかも知れない。Boyd の学名はその時の学名変更判断の候補にもなるだろう。
広義 Charadrius 属が単系統でなく、Vanellus 属を内包していることは Barth et al. (2013)
Phylogenetic Position and Subspecies Divergence of the Endangered New Zealand Dotterel (Charadrius obscurus)
の系統樹を見てもよくわかる。Charadrius 属を分割する必要は早くからわかっていたのだろうが、種のカバー率が十分でなかったためにこれまでは見送られていたのだろう。
この論文の系統樹は種数も少ないので理由がわかりやすくおすすめ。
Qian et al. (2023) Taxonomic Status and Phylogenetic Relationship of the Charadriidae Family Based on Complete Mitogenomes にも参考データがある。
データも揃ってきたので今後早々に分類改訂が行われる可能性がある。
Vanellus 属を Charadrius 属に改名しない限り分割は避けられない。分岐年代を見てもこの統合は受け入れられない (比較的新しい分枝であるチュウヒ Circus 属と広義 Accipiter 属の関係よりさらに深刻: #アカハラダカの備考参照)。
Vanellus 属を一つとするか分割するかは意見が分かれそうなところで、Boyd はタゲリとその他がかなり離れているためタゲリを独立させるのがとよいと考えている。
この場合 Vanellus 属のタイプ種がタゲリであるため他の種の属名が全て変わることになる。多くの分類で分割が採用されていないのはこの変更が大きすぎるためかも知れない。もう少し詳細な分子遺伝学データが揃うのを待っていることもあるだろう。
Charadrius 属のタイプ種はハジロコチドリ Charadrius hiaticula で、この種と同じクレードのみ Charadrius 属に含まれることになる。つまり最低限図の下半分の Charadrius は別属になることになる (例えばシロチドリやメダイチドリなどの系統)。
IOC 14.1, eBird/Clements 2023 ではすでに別属の名前を与えているが、これは問題もある名前で暫定的と捉えた方がよいかも知れない (今後さらに変わる可能性がある。#シロチドリの備考参照)。
分岐年代を考え、同じ枝に複数の別の属の含まれているコチドリも Charadrius 属とは別にした方がよいことがわかる。
Anarhynchinae の名称はハシマガリチドリ Anarhynchus frontalis Wrybill (ニュージーランド。嘴が横に曲がっている唯一の鳥で、必ず右方向に曲がるとのこと) の属名に由来するが、他の事例からみて日本産種を優先した名称が望ましいだろう。
Parrida の名称は対応する下位分類がないが、これはナンベイレンカク Jacana jacana の原記載が Parra jacana Linnaeus, 1766 であったため。
分子系統解析でムナグロ属は他のチドリ類から大きく離れている結果となり科相当となった [上記 Barth et al. (2013) にも表れている]。
シギ類のそれぞれの種または属がどの亜科に入るかは英名を見れば判断できる。
ナイルチドリはワニチドリとも呼ばれナイルワニと共生関係にあるとされる。ヘロドロスがナイルワニがこの鳥を呼んで歯の間を掃除させると記述しているが、このような行動は疑問であり撮影された証拠はない。
Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) with Egyptian Plover or Crocodile Bird (Pluvianus aegyptius) - digital reconstruction of popular myth attributed to Herodotus, 5th Century BC. Africa は逸話に基づく合成写真 (wikipedia 英語版)。
かつてはツバメチドリ科スナバシリ亜科に分類されていたが、系統的には大きく違っていた。
クビワミフウズラ科 Pedionomidae: Plains-wanderer (オーストラリアの1種)、ヒバリチドリ科 Thinocoridae: Seedsnipe (南米の2属4種) は面白いグループで、クビワミフウズラは容貌の類似性から長くミフウズラに近縁 (またはゴミ箱状態だったツル目) と考えられてきたが、分子系統解析の結果これら2科が近縁でレンカク科やタマシギ科に近いことが明らかになった。この結果は Stiller et al. (2024) でも確認された。
推定分岐年代 3000-4500 万年前のオーダーで非常に古くから独立した系統ではなかった。
クビワミフウズラの wikipedia 英語版によればかつてキジ目に含められていたミフウズラ類とは驚くべき収斂進化の結果、または祖先的な形質ではないかと書かれている。しかしミフウズラ類もキジ目ではなくチドリ目と判明し、クビワミフウズラを含む1つの系統が多様な系統を生み出したことがわかったと記されている (would mean とあるが現代の分子系統解析はこちらの結果を得ているので断定調で記した)。
ミフウズラ類とは骨学的には似ていない (コンサイス鳥名事典。この事典ではツル目に入っていた)。
年代に興味が持たれている理由はオウム類の分布と同様、ゴンドワナ大陸でつながっていた時代に分布を広げた非常に古い系統の生き残りかと考えられたため (#ミサゴ備考の [オウム類・ハヤブサ類の年代推定])。レンカク科やタマシギ科に近縁と判明すると分布がそれほど不思議なものではなくなる。
移動能力もあってさまざまな環境で種分化したがごく少数の種のみが散発的に現存し、離れた地域の容貌の類似性は収斂進化また祖先形質と考えられる。タマシギとナンベイタマシギの見かけはよく似ているが分岐は深く別属と扱われて配偶様式も異なる。これも離れた地域にも関わらず容貌が類似している例 (#レンカク備考の [チドリ目の配偶様式] 参考)。
しかしクビワミフウズラの現在の生息域はオーストラリアのごく一部に限られており、人の入植によってかつての草地が失われ外来のキツネが導入されたため野生では危機的状況となっている。オーストラリアでは絶滅可能性の最も高い種の6位となっており、IUCN EN 種。2018 年から飼育下保全も行われている (wikipedia 英語版より)。
Bringing Plains-wanderers back from the brink (NSW Government 2022) によれば草地環境の好みの幅が狭く、近年の異常気象も生息地を減少させる原因となっている。ニューサウスウェールズ州で 300 羽程度、オーストラリア全体でも 1000 羽未満。
外来の肉食動物以外にも在来種の猛禽類も脅威となっていて、クコ類の侵略的外来種の African Boxthorn (Lycium ferocissimum) が止まり場を提供する状況になっているがこの駆除も難しいとのこと。
[jizz の語源]
三河 (2003) Birder 17(4): 99 で jizz を取り上げられていて、語源の説明と jazz とのひっかけもあったのではとの解釈を紹介されている。シギ・チドリに関係する項目であったためここに含めておく。
jizz (Wiktionary) によれば最も早い文字の用例は1921年12月に "Country Diary" で Thomas Coward が用いたもので、アイルランド発祥の用語とのこと。1922 年の本 "Bird haunts and nature memories" で
if we are walking on the road and see, far ahead, someone whom we recognise although we can neither distinguish features nor particular clothes, we may be certain that we are not mistaken; there is something in the carriage, the walk, the general appearance which is familiar; it is, in fact, the individual's jizz.
と解説されているとのこと。
語源は主に2説があって、(1) 軍用語の GIS ("general impression and shape” 全体的印象。三河氏が紹介されているものもこちら)、
(2) just is (見たまま、そのまま、ぐらいの意味) の短縮形、
があるとのこと。他にも考察があって、英語の guise, gist, gestalt の発音を誤ったものとの見解もあるらしい。Gestalt (ゲシュタルト) はドイツ語で「姿」などの意味で、感覚的には確かに語感が近い。
The etymology of "jizz", revisited (David McDonald 2016, Canberra Bird Notes 41, 113-117)
によれば (1) の GIS 説は第二次世界大戦時代の用語であり時代が合わない。Coward の時代には野外鳥学者などにすでに知られていた考え方で、文字としてまだ残されず音で伝えられていたものらしい。
Coward (1923) は上記の本の第2版で guise の単語の古い変化形として gis, jis が辞書に載っていると読者から指摘を受けてこれが由来に思えると記している (つまり Coward が発明した用語ではなかった)。
後の時代の軍用語の GIS (GISS) が jizz から影響を受けた可能性をむしろ探してみる価値があるとのこと。
ここまでが McDonald (1996) の結論だったが、この著者はさらに 1918 年の用例を見つけ、当時のアイルランド英語に jizz の単語が存在していて、活力などを意味する jism と同じ語源ではないか。
"jazz" にも同様の意味があってアメリカで 1912 年の用例がある、音楽で少なくとも 1915 年に使われており、音楽そのものも "活力" の意味とよく合う。
これらを検討すると軍用語の GIS 由来は考え難い。アイルランドの地方語で guise, gestalt を意味していた単語でもなく、19 世紀の "活力" を意味する共通語源から派生したものではとの新考察を行っている (jizz / jazz を混ぜた用例もあり、アメリカの jazz がアイルランドの地方語と独立に派生したと考えにくい)。その意味では jazz も同系語になる可能性がある。
いずれの解説でも jazz とのひっかけ説は出て来ないが語源的には同じものかも知れないということらしい。
東郷 (2019) Birder 33(7): 45 にもこの文献の紹介がある。
さて、我々が jizz を使っている時、脳の中ではどのような処理がなされているのだろうか。
Gauthier et al. (2000) Expertise for cars and birds recruits brain areas involved in face recognition (出版社サイト)
の面白い研究がある。車の車種や鳥の識別に長けた人は、人の顔を識別する脳の部分と同じ部位を働かせているとのこと (その割には人の顔が覚えられないが)。つまり既存の回路を別目的に用いている。
我々が jizz で判別する時もおそらく同様で、馴染みの人の顔の識別点を列挙せよと言われると困るのと同様、識別点による識別は挙げにくく直感的に馴染みにくいのだろう。「チャート式」などの記憶に慣れた人には扱いやすいのかも知れないが。
-
ケリ
- 学名:Vanellus cinereus (ワネルルス キネレウス) 灰白色の小さな唐箕
- 属名:vanellus (合) vanellus タゲリ [小さな唐箕 (とうみ) (vannus (f) 唐箕 -ellus (指小辞) 小さい]。
- 種小名:cinereus (adj) 灰白色の
- 英名:Grey-headed Lapwing
- 備考:
vanellus は#タゲリ参照。
cinereus は短母音のみで -ne- にアクセント (キネレウス)。
記載時学名 Pluvianus cinereus Blyth, 1842 (原記載) 基産地 Calcutta (インド。越冬地か)。
Blyth (1842) はインドでこの属の6種めと記している (当時は新しい地域から次々新種が発見される時代だった)。
Pluvianus の属名はムナグロ属 Pluvialis と語源は同様でやはり雨に関係する。
これぐらい似ていると別の属名として扱うか同じ属名とするかの議論があってもおかしくないぐらい。
Pluvianus は シロクロゲリ 現在の学名で Vanellus armatus Blacksmith Lapwing 1種に対して Selby (1840) が与えたもの。しかし同じ属名が 現在の学名でも ナイルチドリ Pluvianus aegyptius Egyptian Plover (Crocodile-bird) 1種に Vieillot (1816) が与えた用法が先にあったため無効となった。
ナイルチドリ は1種で1科を構成するに値するぐらい離れているのでこの属名は今後も有効だろう。むしろムナグロ属と似た綴りなので混同に注意、というところか。系統的にもチドリ目に入っている点は共通している。
"Fauna Japonica" では Lobivanellus inornatus Temminck & Schlegel, 1846 の学名で記載 (図版)。
Blyth (1842) の記載の方が早かったために Temminck and Schlegel (1846) の学名は事実上使われず、日本が基産地ともならなかった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも別学名として挙げられておらず ("Fauna Japonica" で命名されているのに)、他の用例が事実上なかったのだろう。
inornatus は "飾りのない" の意味。
Lobivanellus は lobus (さや、または葉) と Vanellus 属から。ヒレアシシギなどに使われる意味とは違い、目先に肉垂 (wattle) がある点を指していて、インドトサカゲリ 現在の学名で Vanellus indicus Red-wattled Lapwing を表したもの (The Key to Scientific Names)。
なおケリに使われた属名はこれに限らず多数あるよう。タゲリと同一属にまとめることには相当の抵抗があったものと想像できる。
"トサカゲリ" ならばふさわしい属名だったかも知れないが、現在は Vanellus 属に吸収されている。
Vanellus 属があるために分子系統解析でこれまでの Charadrius 属が単系統にならない (#タゲリの備考参照)。タゲリ類はそのぐらい見かけも異なるので Charadrius 属に改名することもできない、というところ。
この点が議論されるぐらいなので一般的には Vanellus 属をさらに分けることは多分まだ問題外なのだろう (Boyd は行っている。チドリ類全体で精度の高い分子系統樹が得られ分岐年代等がはっきりすると属境界が検討される可能性あり)。
Temminck and Schlegel (1846) の命名はおそらくインドのインドトサカゲリに比べて飾りがない、の意味だろう。
タゲリをタイプ種とする Vanellus 属は独特でケリは含めにくく、Lobivanellus 属はアジア中南部の Vanellus 属に対応する属として扱われていたのだろうか。
英名の Grey-headed Lapwing の由来が気になるところ (実はこれが気になっていて調べたのが上記) だが、学名の cinereus は灰色の意味でも記載文献には特に頭とは書いていない。
当時同じ Lobivanellus 属の中に当時の学名で Lobivanellus melanocephalus Ruppell, 1845 ("頭の黒いトサカゲリ") がある。
現在はムナフタゲリ Vanellus melanocephalus Spot-breasted Lapwing と学名に対応する名称ではないが、他言語には一部学名の意味を取り入れているものがあるのでおそらく学名由来の一般名もあったのではないだろうか。
Lobivanellus で同属だった時代にはこのように頭の色を対比した名称で構わなかったが Vanellus 属に統合されるとタゲリも頭が黒いので "頭の黒いタゲリ" とは呼びにくくなった。
タゲリにはたくさんの英語別名があり (peewit, green plover など)、この名前で単一種を指している分には困らなかったが、学問が進歩して多くの種をまとめて "なんとか" Lapwing に統一するようになるとムナフタゲリに "頭の黒いタゲリ" の英名はふさわしくないので別名を付けた、などの経緯が想像できる。
タゲリに比べて頭の黒いの意味ではなく、別の比較対象種があってケリの方のみが Grey-headed Lapwing で残った、の推論でいかがだろうか。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Grey-headed Wattled Lapwing となっていて Lobivanellus 属の名称が現れている。
単形種。
Boyd では Hoplopterus cinereus。
ケリ類の多くは翼角の突起(爪) (carpal spur/wing spur) を持つ [#レンカクの備考 Rand (1953) On the spurs on birds' wings]。
そのものずばりの名を持つツメバゲリ Vanellus spinosus Spur-winged Lapwing がある。メスで 7.5 mm 以下、オスで 11.5 mm 以上あるという (コンサイス鳥名事典。現在では種が分割されているのでいずれを指すか少し不明)。Boyd の分類ではケリと同属になる。
Nagai et al. (2024)
Analysis of Genetic Structure and Genetic Diversity in Japanese Grey-Headed Lapwing Population Using mtDNA
日本のケリの mtDNA ND2 ハプロタイプの研究から北部と南部に違いがあり、北方に多い型は中国と同じだった。日本南部に多いハプロタイプの起源は明らかでなく、日本の北方から分布を広げた可能性も大陸からの導入の可能性もある。
中国のケリの衛星追跡: Lei et al. (2021)
First description of migration and wintering home range of Gray-headed Lapwings (Vanellus cinereus) tracked with GPS-GSM satellite telemetry (ResearchGate)。
越冬地インドで分布域が広がっている: Bharos et al. (2019) Distribution range extension of grey-headed lapwing (Vanellus cinereus) in Chhattisgarh, Eastern Madhya Pradesh, and Jharkhand, India。
マダガスカルの Vanellus 属の絶滅種 (3000 年前以内に絶滅) にケリ類最大の翼角の突起(爪) が見つかった。
Goodman and Rasolonjatovo (2024)
Description of the wing spur in the subfossil Malagasy lapwing, Vanellus madagascariensis (Aves: Charadriiformes, Charadriidae): Insights into some of its possible life history traits and why it is extinct
によれば Vanellus 属でオス同士の争いに wing spur が用いられる事例は知られておらず、特に巣を狙う地上性捕食者に対する武器として用いていたのだろうと考えられるとのこと。3000 年前から始まった乾燥化で環境が変わって絶滅したのだろうと推論。
著者はマダガスカルヘビワシ (#ハチクマ備考)、キツネザル類 (#クマタカ備考) のところにも登場する着想豊かな研究者。
地上の開けたところで営巣し、喧嘩好きと言われるケリの祖先が武器に用いていた可能性も想像できる興味深い発見である。
ズグロトサカゲリ Vanellus miles Masked Lapwing の亜種 novaehollandiae の虹彩にある特徴的な模様 (heterochromia) 論文: Cardilini et al. (2022)
Dark heterochromia in adult masked lapwings is universal, asymmetrical and possibly slightly sexually dimorphic。5.4% の鳥類種に認められる特徴とのこと。
関連情報が #シロアジサシ備考 [縦長の瞳孔を持つ鳥] と
#カッコウの備考 [非対称な色彩の虹彩を持つコミチバシリ] にある。
-
ヨーロッパムナグロ
- 学名:Pluvialis apricaria (プルウィアーリス アプリカーリア) 日光浴をする雨に鳴く鳥
- 属名:pluvialis (adj) 雨に鳴く
- 種小名:apricaria (adj) 日光浴をする (apricor -ari (intr) 日光浴をする -ius (接尾辞) 〜に関連する)
- 英名:(Eurasian Golden Plover), IOC: European Golden Plover
- 備考:
pluvialis は#ムナグロ参照。
apricaria は apricor が i が長母音 (日光浴をする。apricus 日の照った 由来で i が長母音)。-ari は変化語尾で a, i が長母音で変化形では apricor の i が短母音になる模様。-ius を短母音と考えれば -ca- のみを長母音としてここにアクセントがあるのが自然と考えられる (アプリカーリア)。あまり使われない単語のようで詳細な変化形が出ていない。
Charadrius apricarius Linnaeus, 1758 と Charadrius pluvialis Linnaeus, 1758 の2種が記載されたが、シノニムとなって前者が採用された。属名は Mathurin Jacques Brisson により 1760 年に導入された (The Key to Scientific Names)。
英語の plover も属学名と同じ語源。
ムナグロ類をドイツ語で Regenpfeifer と呼ぶ。属名説明と同じ (コンサイス鳥名事典)。
括弧内の英名はユーラシアのムナグロ類が東西に分離される前の名前。
さらに以前は北米のものも合わせて Pluvialis dominica 英名 American Golden Plover と呼ばれ、比較的最近までこの学名だった。分離されて単形種だが日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種不明とあり、亜種を認める立場のよう。
Howard and Moore 2nd edition, Peters' Check-list of the Birds (2nd edition) では亜種 oreophilos (oreos 山 philos 好きな Gk) を認めている。
Pluvialis 属4種は英語では繁殖地がツンドラであることから tundra plovers とも呼ばれる。
この属が科相当であることが判明した現在では、この4種を取り上げて総称が付けられていたことが適切であったことが確認された。
Byrkjedal and Thompson (1998) "Tundra plovers : the Eurasian, Pacific and American golden plovers and grey plover" (T & AD Poyser, 1998) という本もある。
-
ムナグロ
- 学名:Pluvialis fulva (プルウィアーリス フルウァ) 黄黄金色の雨に鳴く鳥
- 属名:pluvialis (adj) 雨に鳴く
- 種小名:fulva (adj) 黄金色の (fulvus)
- 英名:Pacific Golden Plover
- 備考:
pluvialis は a が長母音でアクセントもある (プルウィアーリス)。pluvia (雨) と -alis 形容詞を作る語尾で a が長母音。
fulva は短母音のみ (フルウァ)。
pluvialis は Linnaeus が Rudbeck の鳥類学講義 (1728-1729) を聞き、ヨーロッパムナグロが雨が降る前に集まって鳴くと考えられていたことから regnpipare (使われなくなったスウェーデン語) と呼ばれていること知ったことによる (Linnaeus 自身による 1729 年の記述がある)。regnpipare は「雨に鳴く」(rain piper, rain-caller) の意味。
分割の経緯と過去の英名は#ヨーロッパムナグロの備考参照。分離されて単形種。
かつてはアメリカムナグロの亜種とされ、Pluvialis dominica fulva とされていた [茂田 (1997) Birder 11(2) 46-54]。
ムナグロ属 Pluvialis と他の日本産チドリ類は分子遺伝解析で科レベルで違うことがわかった (#タゲリの備考参照)。
-
アメリカムナグロ (第8版で検討種)
- 学名:Pluvialis dominica (プルウィアーリス ドミニカ) サン=ドマングの雨に鳴く鳥
- 属名:pluvialis (adj) 雨に鳴く
- 種小名:dominica (adj) (フランス植民地時代の) サン=ドマングの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:American Golden Plover
- 備考:
pluvialis は#ムナグロ参照。
dominica は短母音のみで -mi- がアクセント音節 (ドミニカ)。
分割の経緯と過去の英名は#ヨーロッパムナグロの備考参照。分離されて単形種。
現在のリストでは学名 Pluvialis dominica とされるが、最近まで Pluvialis dominicus の学名も使われていた。
茂田 (1997) Birder 11(2): 46-54 によれば原記載の名称 Dominicus は名詞で変化される必要がないにもかかわらず dominica と変化させていたものを訂正したものと書かれている。
その後元に戻されたようである。各種記述には両方の語尾が出てくる。
"Pluvier dore de Saint-Domingue" of Brisson 1760 であり、イスパニョーラ島のフランス植民地サン=ドマング (Saint-Domingue) が由来 (1659-1804 年。1804 年のハイチ革命で独立。現在のハイチ共和国にあたる。wikipedia 日本語版)。現在のドミニカや都市名のサントドミンゴが由来というわけでない (The Key to Scientific Names)。
さらに調べるとラテン語で普通に使われる dominicus (形容詞) は dominus (主人、皇帝など) + -icus で形容詞化したもので、スペイン語 Domingo, ポルトガル語 Domingos, フランス語 Dominique もこれから派生とのこと。
記載時学名 Charadrius Dominicius Mueller, 1776 と Avibase などで表示されるが 原記載 と合わないように見える。The Key to Scientific Names にもこの種小名は現れない。
Mueller (1776) の前後の種を見ると通常は形容詞として扱われる種小名も冒頭大文字にして名詞扱いにしているなど、大文字で始まっているので名詞とは必ずしも判定できないように見える。用例の揺れのようなものがあったのかも。
英語別名 Lesser Golden Plover (ヨーロッパの Golden Plover に対比したもの) があった [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)]。
-
ダイゼン
- 学名:Pluvialis squatarola (プルウィアーリス スクアタロラ) 雨に鳴くチドリの一種
- 属名:pluvialis (adj) 雨に鳴く
- 種小名:squatarola Sgatarola ベネチア名でチドリの一種 をラテン語化
- 英名:Grey Plover
- 備考:
pluvialis は#ムナグロ参照。
squatarola は起源もしっかりした記述がなく音声もよくわからないが、-ola の語尾を (意味は違うが) ラテン語の語尾と同じと考えれば長母音は現れない。その場合 -ta- がアクセント音節と考えられる (
スクアタロラ)。
よく似た綴りのラテン語 squama (鱗) は a が長母音なので同様に伸ばされる可能性もあるかも知れない (スクアータロラ)。
絶対的な規則がある単語ではないと思われるのでお好みの発音でよいだろう。
3亜種あり (IOC)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種の記載なし。
記載時学名 Tringa Squatarola Linnaeus, 1758 (原記載)。AOU, Clements などの英名は Black-bellied Plover となっており、アメリカではこの名称が使われていた。
Willughby (Willoughby) and Ray, Ornithologiae (1676) p. 309 に出典があり、called at Venice, Squatarola となっていた。ベネチア名の解釈はこの資料に起因すると思われる。
Linnaeus (1758) はこの記述に基づいて種小名を与えたと考えられる。この時点ですでに grey Plover の英名があった。現在は有効な学名とされない時期のラテン名 Pluvialis cinerea も使われていて英名の意味と対応している。
OED によれば Plovers grey の名称は 1549 年の用例があるとのこと。1750 年アメリカの用例もあるとのこと。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Squatarola helvetica の学名が使われていた。Squatarola については後述。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Charadrius helveticus 英名 Grey Plover となっていた。
これは Linnaeus (1766) 記載 で与えられた学名で Helvetica (ヘルヴェティアの名前で 1798 年から 1803 年の間にスイスに共和国が存在した。wikipedia 日本語版より) に生息するとしたもの。
The Key to Scientific Names によれば Brisson (1760) が Vanellus helveticus と呼んでいた。同じ書物に Tringa varia もあった。このページに squatarola も含まれているのでそれぞれ別の種類と考えていたよう。
Brisson (1760) は二名法に則っていないためこれらの学名は現在では有効とされない。
この資料 (Linnaeus による改訂版) を参照すると helvetica が最初に出てくるので先取権があると考えられていたのかも知れない。
Squatarola helvetica. Plumage of Winter and young of the year (Gould 1873)
や Squatarola helvetica. Grey Plover にこの学名を用いた図版がある。かなり長期間使われていた学名のよう。
このページには過去の学名も載せられており、Vanellus griseus Jenyns や、
Squatarola grisea Leach, 1816 (参考)。これは Linnaeus の種小名を属名に昇格させる際の当時の新名 (#ノスリの備考参照)。
Squatarola cinerea Flem. これらの名称がこの種の英名に対応している。
[亜種の問題]
亜種 squatarola (Eastern Grey Plover) は北ユーラシアからアラスカで繁殖、亜種 tomkovichi (Wrangel Island Grey Plover) の記載は新しく、
Engelmoer and Roselaar, 1998 Grey Plover - Pluvialis squatarola - 北極中心の地図では分布関係もよくわかる -
in "Geographical Variation in Waders" でウランゲリ島で繁殖とされる。
もう1亜種の cynosurae (American Grey Plover) はカナダの極北部で繁殖。
亜種間の区別はそれほど明確でなく、単形種とされることもある。
亜種 squatarola はアフリカからオーストラリアで広く越冬、tomkovichi は東アジア-オーストラリアフライウエイを渡るとされ、中国、朝鮮半島、日本、東南アジアを通るとされる。
この情報の出典である Minton and Serra (1999) Biometrics and moult of Grey Plovers, Pluvialis squatarola, in Australia
では越冬地のオーストラリアで計測値で2亜種を区別しており、tomkovichi はオーストラリア南東部に多いとある。オーストラリア南東部の標識個体が日本で目撃されている。
Conservation Advice for Pluvialis squatarola (grey plover)
(オーストラリア) も参考になる。
Tomkovich et al. (2014)
Observation on the East Asian-Australasian Flyway of a Grey Plover
Pluvialis squatarola originating from Wrangel Island
によればウランゲリ島で標識された個体が中国で目撃されている。ウランゲリ島への渡航は手続きなども含めた準備や多額の費用を要し、近い将来にジオロケータや衛星追跡で渡り経路を知るのは難しいだろうとのこと。
状況証拠的には tomkovichi は日本を通っていてもおかしくなさそうである。
フィリピンのチェックリスト (2023) では squatarola, tomkovichi の記載があり比較的普通だが局地的な冬鳥とある。亜種ごとの情報はない。
英名は新世界では主に Black-bellied Plover が使われるとのこと (wikipedia 英語版)。
Li et al. (2025) Migration of Wintering Grey Plover From Southeast Asia to North-Central Siberia Challenges Breeding Population Delineations in Russia
シンガポールで越冬するダイゼンの渡りルートが春と秋で大きく違うことがわかった。繁殖後の渡りの際に大きく西に迂回する。ツンドラでより多くの食物を得るためか、あるいは将来の繁殖地を求めたものかなどの議論がなされている。
ユーラシア極圏の東部と西部がそれぞれ東西で越冬する従来の描像ほど単純ではなかった。
[Squatarola 属]
茂田 (1997) Birder 11(2): 46-54 によればチドリ類は一般に後趾を持たないが、ダイゼンには爪のある小さな後趾があり、これを分類学的特徴と捉えて Squatarola 属とされたことがあったが、それほど重要な解剖学的特徴でないことがわかった。
Squatarola Cuvier, 1816。
ここには後趾のことは出てこないように見えるので後の文献によるものか。Vannneux-Pluviers のフランス名に属名が付記されているがほとんど区別できないため Tringa にまとめた記述になっている。
同年の Leach (1816) の一覧にも用いられ (Squatarola grisea) Grey Squatarolle の名前となっているが表に現れるのみ (文献出典は The Key to Scientific Names より)。
[高度 3000 m を飛行中のダイゼンが捕食された事例]
Boom et al. (2024) Migrating shorebird killed by raptor at 3000 m above ground as revealed by high-resolution tracking
シギ・チドリ類が高い高度をノンストップで渡るのは捕食を避けるためとの考えがあるが、GPS と加速度ロガーを付けたダイゼンが捕食されたと考えられる事例。日没後 25 分とのこと。
捕食されたと考えられる時点の 15 分前に加速が増し、ここで捕食者に気づいて逃げ始めたと考えられるとのこと。ハヤブサの巣から 200 m 以内にタグと標識が発見されハヤブサに捕食されたと考えられるとのこと。これだけの状況証拠があれば日没後にハヤブサが高高度の狩りを行う証拠にもなるのだろう。
(#ハヤブサの備考にも掲載。続きはハヤブサの方に)。
[DNA バーコーディングで探るダイゼンの食性]
ブルガリアの研究。論文 (オープンアクセス) の存在紹介のみ: Vassileva et al. (2025) Dataset of Grey plover (Pluvialis squatarola) diet composition on the SW Black Sea coast using DNA metabarcoding。
[和名について]
「冬の鳥」(小学館 1984) p. 137 によれば大膳大夫職 (だいぜんたいふくさ) の着物の模様に似ていることから名付けられたとある。大膳職 (だいぜんしき) 読み方は "シギ" にも似るが少し違う。
大膳大夫は大膳職の長官。日本官職の正五位の一つ。大宝律令以前は膳職という官司であったが、大宝律令制定時に、天皇の食事を掌る内膳司と饗膳の食事を掌る大膳職に分割された (wikipedia 日本語版より)。英訳では Banquet Agency となっていてわかりやすい (参考 Warren An English Translation of "The Royal Meal Protocols" in the Engi Shiki)。
ネットで由来を検索してもなかなか出典が書かれていないので最初の出典は不明だが、『ダイゼン (大膳)』は、宮中で食膳を司る役職・大膳職の略でありダイゼンがよく食材として用いられていた事から、名付けられたことが「野鳥の呼び名事典 - 由来がわかる」(大橋弘一 世界文化社 2016) に記述されているとのこと。
茂田 (1997) Birder 11(2): p. 46 に出所があり、榎本佳樹氏の『野鳥便覧』(1941) 下巻にあるとのこと。
大橋 (2020) Birder 34(12): 66-67 では他の説は見当たりませんとのことだが、着物の模様説は存在していた。「鳥賞案子」(比野勘六 1800-1802) の飼育書に大膳鴫の名前が登場するとのこと。
鳥賞案子 (東北大学総合知デジタルアーカイブ) でスキャンを見ることができてシギ類一覧の中で p. 77 に登場する。
着物の模様と食材ではかなり違うがどちらが正しいのだろう (食材がダイゼンであることはどのようにわかったのだろう)。
なお "シギ" の由来は諸説あるが、"職" 由来のものは「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) には含まれていなかった。
新しく付けられた名称で "シギ" に関係するものではシギダチョウ目が思い当たる。シギに似た斑模様でダチョウ類縁鳥として名付けられたとのこと (コンサイス鳥名辞典)。ダイゼンが模様由来の名称であれば、夏羽の白黒よりも斑模様に着目されたものかも。当時の着物の図柄を知らないが考察の参考になるかも知れない。
タカブシギの和名由来と着目された可能性のある模様とある程度の類似点が感じられる。鷹斑も大膳も位の高さに関連した模様の表し方ではなかっただろうか。
大膳職の着物の模様由来とした場合、役割を考えると主賓より目立つわけには行かず、しかも格式の高さを表現するには白黒を基調とした多少隠蔽色気味の色彩が適していたのではないだろうか。
そのように考えるとシギ・チドリ系統は適度に隠蔽色で、かつダイゼンの夏羽ならば色彩的にも適しているように思える。余計な色は邪魔なのでムナグロではなくダイゼンに似た配色となった。いかがだろうか。
このような着物に対する人の認識による選択圧が過去も現在もそれほど違いがないと仮定すれば、現代のシェフに確かにダイゼンの夏羽に似た配色が認められて整合性がある感じがする。
食材説の場合には、ムナグロはダイゼンほど美味しくなかったのかと問うとやや根拠に乏しい感じがする。
-
ハジロコチドリ
- 学名:Charadrius hiaticula (カラドゥリウス ヒアーティクラ) 割れ目に住むチドリ
- 属名:charadrius (m) チドリ
- 種小名:hiaticula (チドリ) < hiatus 割れ目 cola の住人
- 英名:Common Ringed Plover
- 備考:
charadrius は短母音のみで -ra- または -rad- にアクセントがある (カラドゥリウス)。音節の区切り方に絶対的な規則があるわけではなさそう。
hiaticula は hiatus が a が長母音。-cula は -cola 同様に短母音のみと考えられる。-ti- がアクセント音節と考えられる (ヒアーティクラ)。
記載時学名 Charadrius Hiaticula Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe and America, restricted type locality Sweden, ex ref. to Fn. Svec. (スウェーデンに限定)。
Brisson 時代のフランス語名 Pluiver a collier, Pluvialis torquata (Brisson の書物が二名法に則っていないため現在は有効な学名でないとみなされる) があり、対応する学名 Charadrius torquatus Pontoppidan, 1763 (参考) があった。
1758 年以降の学名では Linnaeus (1758) のものの方が早いが、これらの "首輪のある" または "首飾りのある" は英名の Ringed Plover に対応している。
この学名は Linnaeus のものより人気があったようでその後も何度も使われている。
Charadrius torquatus Forster, 1817 (参考) も改名を提案していた。
英名で単に Ringed Plover と言えば本種を指すが、何が ring なのかはこの学名の通り。正面で真上から見ればだるまさんのように本当にまん丸の輪に見える (ハジロコチドリに限った話ではないが)。コチドリのアイリングの意味ではない。
実はこの学名は Linnaeus (1766) 自身も後に使っており、Charadrius torquatus Linnaeus, 1766 (参考) 産地 Dominica となっている。Brisson の Pluvialis dominicensis torquata (これは無効学名) が由来とのこと。American Golden Plover が分離されていた時代の概念と思われるが、同じ学名を Pontoppidan (1763) がすでに別に用いていたため無効。
おそらく人気のあった学名だったが先取権の原則から現在の学名となった模様。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは tundrae (ツンドラの。ユーラシア東部に分布) とされている。Charadrius 属のタイプ種。
属名に使われる charadrius は未同定ののっぺりした鳥の kharadrios (Gk) に由来し、kharadra (川の谷間) を指すとのこと (The Key to Scientific Names)。
[チドリ亜科の系統分類]
広義 Charadrius 属は単系統でない (#タゲリの備考参照)。少なくとも3つの系統が存在する。その中にすでに他の属が含まれているものもあり、再編成が必要となる。
Cerny and Natale (2022) の分子系統樹を用いた Boyd の分類によれば以下の通り。英名は IOC より。
チドリ科 Charadriidae チドリ亜科 Charadriinae
ハシナガチドリ属 Phegornis
ハシナガチドリ Phegornis mitchellii Diademed Sandpiper-Plover (南米アンデス)
ムネアカチドリ属 Zonibyx
ムネアカチドリ Zonibyx modestus Rufous-chested Plover (Charadrius 属より分離。南米南部)
コバシチドリ属 Eudromias
コバシチドリ Eudromias morinellus Eurasian Dotterel (Charadrius 属より分離)
ハジロコチドリ属 Charadrius
フタオビチドリ Charadrius vociferus Killdeer
ハジロコチドリ Charadrius hiaticula Common Ringed Plover
ミズカキチドリ Charadrius semipalmatus Semipalmated Plover
フエコチドリ Charadrius melodus Piping Plover
ズグロチドリ属 "Thinornis" (新属学名が必要)
ズグロチドリ "Thinornis" cucullatus Hooded Dotterel (Thinornis 属より分離。タスマニアからオーストラリア南部)
ニシミスジチドリ属 "Afroxyechus" (新属学名が必要)
ニシミスジチドリ "Afroxyechus" forbesi Forbes's Plover (Charadrius 属または Afroxyechus 属より分離。アフリカ)
ミスジチドリ属 Afroxyechus
ミスジチドリ Afroxyechus tricollaris Three-banded Plover (アフリカ)
コチドリ/イカルチドリ属? Thinornis
コチドリ Thinornis dubius Little Ringed Plover
イカルチドリ Thinornis placidus Long-billed Plover
カタアカチドリ Thinornis melanops Black-fronted Dotterel (Elseyornis 属より移動。オーストラリア)
ノドグロチドリ Thinornis novaeseelandiae Shore Dotterel (ニュージーランド離島)
Thinornis 属の名称はノドグロチドリに由来するが、日本産種を優先すればコチドリ属かイカルチドリ属の名称になるだろう。世界的な知名度を考えれば前者、日本周辺分布を重視すれば後者になるだろうか。
ノドグロチドリは外来種による捕食などの結果でニュージーランドの離島であるチャタム諸島の Rangatira (ランガティラ) 島のみに生息していた、個体数 200 羽程度。この島は辛うじて絶滅から救われたチャタムヒタキ (#チョウゲンボウの備考 [離島のチョウゲンボウ類と超希少種の保全]) の生息地としても知られている。
かつては他の島への分散も試みられたが元の場所に戻ってしまったなどの問題もあった (コンサイス鳥名事典)。現在では飼育下の保全とともにチャタム諸島以外へも再導入が進められている (wikipedia 英語版)。IUCN EN 種。
コチドリ/イカルチドリと他のチドリ類の縁は遠かった。Thinornis の意味は this, thinos 浜 ornis 鳥 (Gk)。
コバシチドリの属名は #コバシチドリの備考参照。
AOS Classification Committee - North and Middle America Proposal Set 2025-A
(NACC p. 51) によれば WGAC は旧世界のものを Thinornis 属に分離する決断を行ったとのこと。北米で記録される種ではコチドリが対象になる。上記の Boyd のリストのズグロチドリ以降が Thinornis 属に分離される模様。日本産種ではコチドリとイカルチドリが対象。{コチドリ/イカルチドリ} と {ハジロコチドリ/ミズカキチドリ} が別属になる見通し (識別に悩むほど似ているのに!)。
この分離は Clements 2024/eBird がすでに採用している。
ミスジチドリのみからなっていた Afroxyechus 属は Thinornis 属に吸収される見通し。
-
ミズカキチドリ
-
イカルチドリ (将来の属名変更の可能性に注意)
- 第7・8版学名:Charadrius placidus (カラドゥリウス プラキドゥス) 静かなチドリ
- AviList 学名:Thinornis placidus (ティノルニス プラキドゥス) 静かな浜の鳥
- 第7・8版属名:charadrius (m) チドリ
- AviList 属名:thinornis (合) 浜の鳥 (thinos 浜 ornis 鳥 Gk)
- 種小名:placidus (adj) 静かな
- 英名:Long-billed Ringed Plover, IOC: Long-billed Plover
- 備考:
charadrius は#ハジロコチドリ参照。
thinornis は#コチドリ参照。
placidus は短母音のみで冒頭にアクセント (プラキドゥス)。
単形種。
Charadrius placidus Gray & Gray, 1863 が記載時学名。
原記載はリスト内に現れるのみで基産地は示されていなかった。"Catalogue of the specimens and drawings of Mammals, Birds, Reptiles of Nepal and Tibet, presented by B. H. Hodgson, Esq., to the British Museum" (2nd ed.) に Hodgson の図版があるとのこと。
本文。学名由来を示唆する言及はない。
Sharpe (1896) によって基産地はネパール (資料) と判定された。
いかにも日本的な種のように感じられるが基産地は日本ではなかった。どこにでも生息している感じがするが Temminck and Schlegel は図版も残していない。こんな普通種がなぜ Temminck and Schlegel の手に渡らなかったのかなど歴史的に検証することも面白いだろう。
Aegialites hartingi Swinhoe, 1870 も記載していた (資料) がこの記載の方が遅いため Gray and Gray (1863) の学名となった。Swinhoe の記載地は中国。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にはこの2つの学名が載せられている。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Hodgson's Ringed Plover の英名。
おそらく蝦夷で繁殖して南部の日本では冬鳥と考えられていたらしい。
日本のものを亜種 japonicus Mishima, 1956 (産地 Tamagawa, Tokyo) とする提案もあったが、現在世界の主要リストでは用いられていない。記載論文。翼長が短小とのこと。
種小名の意味は北米で繁殖・一部南米で越冬するフタオビチドリ Charadrius vociferus (騒々しい) 英名 Killdeer に対して静かであることから付けられたとのこと [日比 (2000) Birder 14(1): 68-70]。
フタオビチドリの英名はよく聞かれる2音節の声 ("kil-deee") を模したものだそうで非常によく鳴く (wikipedia 英語版)。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではハジロコチドリの亜種 Charadrius hiaticula placidus として掲載されている。ロシア名では現在もウスリーのチドリ。
ややこしいことにロシア名では malyj zuek (小さいチドリ) がハジロコチドリを意味する名前になるが別名 galstuchnik も使われる。zuek (ズヨークと読む) は zudet' (単調な金属的な音を出す) とおそらく音声由来 (Kolyada et al. 2016)。
Dement'ev and Gladkov (1951) 当時はハジロコチドリをどのように (種または亜種) 分類するかが主題となっていたようでイカルチドリはあまり扱われていない。嘴が長いなど少し特徴のある亜種と扱われていたよう。
旧英名の Long-billed Ringed Plover に亜種時代だった痕跡が残っているよう。独立種となって Ringed が省かれたものと想像できる。すなわち従来の広義ハジロコチドリの中では嘴が長いの意味。特徴的な長い嘴を指すというよりハジロコチドリと区別する点を取り上げた名称だった。
Ogawa (1908) にはイカルチドリの他に別名オージュン、クビダマチドリの名前が載せられている。チドリ類の和名はかなり遅く整理されたよう。「千鳥」の名称は古くから使われていたが種類はあまり区別していなかった模様。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) の "大くびしぎ" をイカルチドリと判定している。
"クビダマチドリ" は理解できる名前で、"大くびしぎ" は語源は同じようなものか。英語だと collared に対応するだろうか。
"オージュン" の "ジュン" はわからないが "オー" は大きいの意味か。
wikipedia 日本語版では和名のイカルは古語で「大きい、厳めしい」の意との解釈を紹介している。
Boyd では Thinornis placidus。Clements 2024/eBird が採用。AviList (2025.6) でもこの属名が採用された。
-
コチドリ (将来の属名変更の可能性に注意)
- 第7・8版学名:Charadrius dubius (カラドゥリウス ドゥビウス) 疑わしいチドリ
- AviList 学名:Thinornis dubius (ティノルニス ドゥビウス) 疑わしい浜の鳥
- 第7・8版属名:charadrius (m) チドリ
- AviList 属名:thinornis (合) 浜の鳥 (thinos 浜 ornis 鳥 Gk)
- 種小名:dubius (adj) はっきりしない
- 英名:Little Ringed Plover
- 備考:
charadrius は#ハジロコチドリ参照。
dubius は短母音のみで冒頭にアクセント (ドゥビウス)。
日本で記録される亜種 curonicus は -icus が短母音のみ。前半は地名でドイツ語では Kurland の冒頭が明確に長音で、フランス語では Courland と綴る
(この単語の母音の長短は不明だが名詞 cour は長音のためそのまま使っているかも知れない)
ため "クーロニクス" でよいと思われる。短く読んでもよいが "ク" に母音が含まれることを意識する点からも長音風に読む方が (cro- などで始まる単語との) 誤解が生じにくいのではと思う。
日本語ではこの地名はドイツ語読みでクールラント、クール人と表記されている (wikipedia 日本語版より)。
Curonian language は日本語では通常クロニア語と表記されている。ラトビア語の綴り規則をみると短音で発音されるよう。
AviList で採用された属名の thinornis は thinos 浜 ornis 鳥 (Gk)。いずれも長母音を含まないため "ティノルニス" の読みと思われる。
記載時学名で Thinornis rossii Gray, 1845、現在ではノドグロチドリ Thinornis novaeseelandiae Shore Plover のみを指して使われた属名。分子系統解析によりコチドリ、イカルチドリを含む系統にこの種がタイプ種となる属 (本来は1種のみからなる属だった) が含まれることからこの属名となった (The Key to Scientific Names よりまとめ)。
Thinornis 属の和名は未定だが、コチドリ属またはイカルチドリ属が考えられる。いずれもタイプ種ではない。
3亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は curonicus (現在ラトビアの地名 Curonia/Courland/Kurland、ロシア綴りでは Kurlyandiya から) とされる。
dubius の由来は Sonnerat (1776) が "Petit Pluvier a collier de l’isle de Lucon" で単なる気候の違いを反映したハジロコチドリの変種で、別種とは区別できないのではと疑っていたことに由来する (The Key to Scientific Names)。基産地はフィリピンのルソン島だった。
Sonnerat (1776) の記述は Voyage a la Nouvelle Guinee... (図版)。解説は1ページ前から始まる。
ハジロコチドリは Brisson が "Petit Pluvier a collier" と呼んでいた。
Sonnerat (1776) は学名を与えていないので原記載は Scopoli (1786) Deliciae florae et faunae Insubricae [...] Pars IIによるものと少し遅れている。ヨーロッパでよく知られたハジロコチドリの記載 (Linnaeus 1758) の方が早い。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Charadrius minor Wolf & Meyer となっており。Aegialitis dubia が別学名に挙がっている。
Charadrius minor Meyer, 1810 (資料) があって、現在は亜種名となっている Charadrius curonicus Gmelin, 1789 のシノニム扱いだったとのこと。
資料によれば新しく付けられた学名であれば無効名とあり、minor は以下にある Wolf and Meyer (1805) が先に用いていたため無効とされた模様。
どちらの命名を採用するとしても minor の意味は現在のコチドリとよく整合する。#シロチドリの備考で調査したようにチドリ類の和名はあまり付いていなかったようで、コチドリはチドリ類の名称が学術的に整理された時代にこの学名由来で名付けられた可能性があるように思える。
Aegialitis minor にこの種小名を用いた Gould の図版がある。Aegialitis の属名は Boie (1822) がハジロコチドリをタイプ種として用いたもので aigialos 浜辺 izo 座る (The Key to Scientific Names)。
同じ名称の属が植物で使われておりマングローブに生育する。
Dement'ev and Gladkov (1951) によればこの学名は Charadrius minor Wolf & Meyer (1805) で、先行する学名 Charadrius minutus と一緒に与えられていたとのこと。亜種 curonicus Gmelin, 1789 と同じものとのこと。
Ogawa (1908) では Aegialitis curonica Gmelin も別学名に載っているので当時は先取権が正しく扱われていなかったらしい。Boie (1822) が Aegialitis 属を与える際に minor の学名で載せているので (The Key to Scientific Names) そのまま踏襲されていたものか。
Boyd では Thinornis dubius。Clements 2024/eBird が採用。
AviList (2025.6) でもこの属名が採用された。
基産地がフィリピンであるように、基亜種 dubius はフィリピン、ニューギニア、ビスマルク諸島に分布するとされる。亜種 jerdoni はインド、スリランカ、パキスタンから東南アジア南部で、これらは留鳥。curonicus は北方型とされる。
Dement'ev and Gladkov (1951) の分布図では日本南部の主に島嶼部が dubius の扱いとなっている。
タイの亜種識別情報: Identifying subspecies of Little Ringed Plovers (ayuwat 2021)。
Gruiformes and Charadriiformes によれば亜種 curonica を種に昇格させる考え方もある [Bahr (2011) and Eaton et al. (2016)] が幅広い支持は得られていない。xeno-canto の音声の比較ではだいぶ違いがあると紹介されているがデータがまだ限られている。
これも分子系統解析待ちか。
フィリピンのチェックリスト (2023) では dubius, curonicus 両者の記載があり普通の冬鳥または留鳥とある。
Hedenstrom et al. (2013) Migration of the Little Ringed Plover Charadrius dubius breeding in South Sweden tracked by geolocators
にジオロケータで明らかにしたスウェーデンからの渡り経路が示されている。アフリカからインドまで広く越冬している。
-
シロチドリ (将来の属学名変更に注意。AviList では従来のシロチドリを2種に分離)
- 第7・8版学名:Charadrius alexandrinus (カラドゥリウス アレクサンドゥリーヌス) アレクサンドリアのチドリ
- AviList 学名:Anarhynchus alexandrinus (アナリュンクス アレクサンドゥリーヌス) アレクサンドリアの後ろ向きの嘴 (のチドリ) と Anarhynchus dealbatus (アナリュンクス デアルバートゥス) 白で塗られた後ろ向きの嘴 (のチドリ)
- 第7・8版属名:charadrius (m) チドリ
- AviList 属名:anarhynchus: ana- 後ろ向きの rhunkhos 嘴 (Gk) 本来はハシマガリチドリのみを指した
- 種小名:alexandrinus (adj) アレクサンドリアの (-inus (接尾辞) 〜に属する) と dealbatus 白で塗られた (dealbo の過去分詞形)
- 英名:Kentish Plover (英国ケント州の) と White-faced Plover
- 備考:
charadrius は#ハジロコチドリ参照。
anarhynchus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-rhyn- がアクセント音節と考えられる (アナリュンクス)。
Alexandrinus (固有名詞) は i が長母音でアクセントもある (アレクサンドゥリーヌス)。ギリシャ語でもこの位置にアクセントがある。
dealbatus は dealbo (白色で塗る) の過去分詞形 (デアルバートゥス)。アクセントと長音は過去分詞の変化形由来。albus は白で、接頭語を付けて動詞語尾形。
基産地は英国ケント州であったが (1787) どんどん数を減らして英国での繁殖もなくなった。現在では英国ではまれな渡り鳥になっており(出典 Focus on: Kentish Plover)、適切な英名とは言えなくなっている。
茂田 (1994) Birder 8(1): 36-40 によればケント州で記載したのは Latham (1801) で Charadrius cantianus (中世ラテン語で Cantia = ケント州) の学名を与えたが、Linnaeus (1758) の Charadrius alexandrinus (原記載) と同一と判定されシノニムとなった。
この学名は (英語圏では?) 一定期間使われていたようで、1896 年でもこの学名を用いた亜種記載がある。Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" もこの学名を使っていた。和名は当時からシロチドリ。
しかし「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710) ではシロチドリの名称はまだ現れず、可能性のある記載として小くびしぎを (?) 付きで挙げている。
飼い鳥中心なので名前が現れないのはやむを得ない感じだが、シロチドリの名称は比較的新しく学術的文脈で付けられたものかも知れない。
シギ類ではいくつか現在と同じか同様のものがあるが、チドリ類では現在の名称と同じものはこの表に見当たらない。「百千鳥」(1799) にも現れない。
英名 (特にイギリス名) はこの学名と基産地をそのまま残したものと考えられる。資料 によれば Kentish Plover, Lewin, Br. Birds pl. 185 を引用したとのこと。
Linnaeus (1758) はエジプト、ナイル川を基産地としているので現在の学名では基産地はこちらになる。Avibase では Egypt, ex Hasselquist となっている。
ケント州の意味を持つ名称は英語以外ではほとんどない。
フランス語名が面白く Pluvier a collier interrompu と "首輪の途切れたチドリ" の意味で特徴を非常によく表している。
和名と英名や学名の関係は特にないと思っていたが、アメリカ名は Snowy Plover だったとのこと。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) の情報による。
wikipedia 英語版の情報をもとにまとめると、Aegialitis nivosa Cassin, 1858 (nivosa 雪の) として 記載 され、この時点では別種扱いで Snowy Plover の英名があった。
1922 年にシロチドリと同種とされ亜種扱い Charadrius alexandrinus nivosus (ただし扱いはリストによる) となったが、アメリカではそのままの英名の方が普通に使われていたよう。
世界の名称統一にうるさい人であればここで種英名は Kentish Plover に乗り換えたか、あるいは全部アメリカ流に Snowy Plover とまとめてしまったかも知れない。
2011 年に再度別種とされ、Avibase で見られる和名ではユキチドリとなっている。
Ogawa (1908) のリストでも学名からはユーラシアのシロチドリを指していると思われるが、アメリカ英語の影響も一定程度入ってあるいは和名成立に関係した可能性があったのかも (アメリカ英語の方がケント州よりは馴染みのある名前になっている)。
日本鳥類目録改訂第7版では亜種 alexandrinus (ハシボソシロチドリ、迷鳥として記録) と dealbatus (シロチドリ) がリストされているが、
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では後者が Charadrius alexandrinus nihonensis (Deignan, 1941 原記載。基産地は青森で1987年4月23日に Blakiston が採集したもの) に変更されている (後述の茂田良光氏の見解参照)。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
Charadrius alexandrinus dealbatus (Swinhoe, 1870) の原記載は On Chinese Plovers で中国南部の沿岸、台湾や海南島の留鳥としている。
同文献では亜種 cantianus (Latham, 1801) が冬季の中国沿岸に多数やってくるとしているが、これは現在亜種 alexandrinus のシノニムとされている。
Dement'ev and Gladkov (1951) では 13 亜種としており、世界の一般的なリストではこれらの大部分が後述のように種に分離された。
この文献では日本付近は亜種 dealbatus となっている。日本鳥類目録 改訂第7版でこの分類が一時的に復活したらしい。Dement'ev and Gladkov (1951) では亜種 nihonensis については言及がなく、情報がまだ伝わっていなかったのかも知れない。北海道より北の分布は分布図になく、当時はまだあまりわかってなかったらしい。
Ryabitsev (2014) も 12 亜種としており、Dement'ev and Gladkov (1951) 時代とほぼ同じ分類を使っているものと思われる。シベリアのものは基亜種としている。
Gluschenko et al. (2023) Breeding birds of Primorsky Krai: the Kentish plover Charadrius alexandrinus (pp. 4403-4424)
ではロシア沿海地方で dealbatus が少数繁殖、alexandrinus が旅鳥の扱い。
IOC 14.1 では dealbatus が分離された結果3亜種のみとなり、後に示す Niroshan et al. (2023) で seebohmi は独立種とされるため、残るのは2亜種のみ (alexandrinus, nihonensis) となるだろう。
dealbatus は現在の標準的分類では別種とされ Charadrius dealbatus Swinhoe, 1870 (カオジロシロチドリ, White-faced Plover, 主な分布域は南中国、北ベトナムでインドシナからスマトラで越冬; HBWでは日本南部、琉球列島、中国東部・南東部に分布、フィリピン、ボルネオで越冬する、と記されている) となるので第7版の学名で整理していた場合は注意が必要。eBird でも2種を別種としている。
比嘉他 (2005) Birder 19(8): 58 は沖縄のシロチドリのものとは違っていることを指摘し、比較写真も掲載している。
一方、日本に分布する亜種は固有亜種の可能性が高く、nihonensis が妥当とも言い切れないとのこと (2016,「山階鳥研ミニレクチャー」茂田良光, 概要; 日本鳥類標識協会全国大会 茂田良光他)。
この中で沖縄県で繁殖するシロチドリは,九州以北のシロチドリより上面がやや淡色で雌雄とも額、過眼線、胸が淡い傾向があり、nihonensis とは異なる亜種の可能性があることが触れられている。
その後の研究で Sadanandan et al. (2019) Population divergence and gene flow in two East Asian shorebirds on the verge of speciation
では日本の大部分を含む北方は Charadrius alexandrinus、南西諸島の台湾に近いところに Charadrius dealbatus が分布している可能性がある。
この論文によれば日本の個体群は遺伝的に結構離れているが、alexandrinus と dealbatus の違いほどではなく、alexandrinus の亜種とするのがよさそうとのことである。
中国沿岸部では一度種分化してまた接触している可能性も指摘されている [Wang et al. (2019) Genetic, phenotypic and ecological differentiation suggests incipient speciation in two Charadrius plovers along the Chinese coast]。
また表現型には差があるのに遺伝子レベルであまり差がないとの指摘もあった [Rheindt et al. (2011) Conflict between Genetic and Phenotypic Differentiation: The Evolutionary History of a 'Lost and Rediscovered' Shorebird]。
Niroshan et al. (2023) Systematic revision of the 'diminutive' Kentish Plover (Charadriidae: Charadrius) with the resurrection of Charadrius seebohmi based on phenotypic and genetic analyses
も参考。
Niroshan et al. (2023) でインド南部、スリランカの亜種とされる seebohmi は独立種と判定された。一般向け記事: Hanuman plover makes a comeback as a species after 86 years。
Hanuman ハヌマーン はインド神話における神猿。今でも民間信仰の対象として人気が高く、インドの人里に広く見られるサルの一種、ハヌマンラングールはこのハヌマーン神の眷属とされてヒンドゥー教寺院において手厚く保護されている。ラーマーヤナ (Ramayana) 叙事詩においてインドとスリランカの間に橋を設けた神とある。この種の分布を考えるとふさわしい名前だろう。
中国に伝わり、「西遊記」の登場人物である斉天大聖孫悟空のモデルになったとの説もあるとのこと (wikipedia 日本語版/英語版より)。
以下のリストではハヌマーンの名前を用いた仮和名 (英名より直訳) を用いている。
AviList では seebohmi を独立種としない扱いとなった。
3953 933 Taxon seebohmi is treated as a subspecies of Anarhynchus alexandrinus, as the evidentiary basis for a split is weak. Vocal differences between seebohmi and alexandrinus have not been documented; there are only minor morphometric differences between the two (Niroshan et al. 2023), for which clinal variation has not been ruled out; mitochondrial DNA divergence is negligible, and there is no support for seebohmi as the earliest-diverged lineage in this complex (Niroshan et al. 2023).
形態的違いは小さく地理的クラインの可能性が否定できない。音声の違いは記述されていない。mtDNA の差異が小さい。
日本のシロチドリは2種 (あるいは旧シロチドリから分離された別の種や亜種も迷行の可能性がある?) になる可能性があり、観察に注意が必要であろう。また海外研究者からも日本の亜種の音声データが熱望されている。写真撮影以外にも音声録音に注意して観察することが望まれ、録音をお持ちの方は国際的音声のオープンデータベース (xeno-canto など) への登録をお勧めする。
上記の seebohmi の音声の違いの記述の不十分さには日本と周辺地域のシロチドリの音声データ不足 (判断できない) も影響を与えていると思われる。遺伝情報も mtDNA のみによる判定のため核遺伝情報を用いれば分離が検討されるかも知れない。
AviList の扱い AviList では2種に分離。属名も変化して Anarhynchus alexandrinus Kentish Plover と Anarhynchus dealbatus White-faced Plover となった。
第7版時代の亜種小名に従えば後者がシロチドリに対応するように見えるが、AviList の概念では日本で繁殖する alexandrinus, nihonensis ともに Anarhynchus alexandrinus の亜種となる。
第8版の概念もこちらに対応する。第8版の亜種には dealbatus は含まれておらず、AviList の分布域にも日本は含まれていないが、南西諸島の台湾に近いところに分布している可能性が指摘されている (Sadanandan et al. 2019) ため2種とも含めておいた。
Lee et al. (2023) Nest-relief behaviors and usage of call types in the Kentish plover (Charadrius alexandrinus)
に韓国のシロチドリの音声について、主に抱卵交代の際に用いる音声の研究がある。
Donegan et al. (2011)
Revision of the status of bird species occurring or reported in Colombia 2011
それまで不十分な記載だったシロチドリ類の音声の比較検討があり、シロチドリとユキチドリで音声が異なることを指摘している。ここで調べられているような点でヨーロッパと日本のシロチドリでどの程度違いがあるか調べることは興味あるだろう (海外研究者がおそらく行っていると思うが)。
Sung et al. (2005)
Breeding vocalizations of the piping plover (Charadrius melodus): structure, diversity, and repertoire organization
でフエコチドリを中心としたチドリ類の音声の共通レパートリーや違いなどを議論している。
シロチドリが複数種に分離されつつあるころで比較に含められている。
コチドリでもニューギニアで越冬中の curonicus と留鳥の dubius で逃げる時の声が異なっていて亜種同定に役立つ可能性も示されている。
フィリピンのチェックリスト (2023) では alexandrinus, nihonensis の両者がリストされており、普通に見られる冬鳥の扱いだが亜種ごとの情報はない。Charadrius dealbatus は記録種に含まれておらず大陸の留鳥の扱いと思われる。
Ivanov (2025) Modern concepts on the systematics of the Kentish plover Anarhynchus (Charadrius) alexandrinus (Linnaeus, 1758) (pp. 2166-2167)
ロシアでの現代的な分類の紹介。国後島やサハリンのものは dealbatus ではなく nihonensis であろうとのこと。新しく採用された属分類の紹介。
[シロチドリ/メダイチドリ亜科? Anarhynchinae の系統分類]
Boyd では最近分割された種を別種扱いではなく Leucopolius alexandrinus に含めているが IOC や Niroshan et al. (2023) に従って別種とした分類を挙げた。
Cerny and Natale (2022) の分子系統樹を用いた Boyd による Anarhynchinae 亜科の分類は以下の通り。
チドリ科 Charadriidae シロチドリ/メダイチドリ亜科? Anarhynchinae
ワキアカチドリ属 Erythrogonys
ワキアカチドリ Erythrogonys cinctus Red-kneed Dotterel (オーストラリア)
マキエチドリ属 Peltohyas
マキエチドリ Peltohyas australis Inland Dotterel (オーストラリア)
メダイチドリ属? Eupoda (Charadrius 属より分離)
ニシオオチドリ Eupoda asiatica Caspian Plover
オオチドリ Eupoda veredus (vereda?) Oriental Plover
オオメダイチドリ Eupoda leschenaultii Greater Sand Plover
メダイチドリ Eupoda mongola Lesser Sand Plover
チャオビチドリ属 Nesoceryx
チャオビチドリ Nesoceryx bicinctus Double-banded Plover (Charadrius 属より分離。ニュージーランドからオーストラリア南部)
ニュージーランドチドリ属 Pluviorhynchus
ニュージーランドチドリ Pluviorhynchus obscurus New Zealand Plover (Charadrius 属より分離。ニュージーランド北端のみ)
ハシマガリチドリ属 Anarhynchus
ハシマガリチドリ Anarhynchus frontalis Wrybill
シロチドリ属 Leucopolius (Charadrius 属より分離)
アカエリシロチドリ Leucopolius ruficapillus Red-capped Plover (オーストラリア)
ユキチドリ Leucopolius nivosus Snowy Plover (南北アメリカ)
クリオビチドリ Leucopolius pallidus Chestnut-banded Plover (アフリカ南部)
シロチドリ Leucopolius alexandrinus Kentish Plover
カオジロシロチドリ Leucopolius dealbatus White-faced Plover (IOC の分離に従う)
ハヌマーンチドリ? Leucopolius seebohmi Hanuman Plover [Niroshan et al. (2023) の分離に従う]
ジャワクロエリシロチドリ Leucopolius javanicus Javan Plover (ジャワ島のみ)
シロビタイチドリ Leucopolius marginatus White-fronted Plover (アフリカ南部)
クロエリシロチドリ Leucopolius peronii Malaysian Plover (マレーシア、インドネシア、フィリピンなど)
ヒメチドリ属? Helenaegialus (Charadrius 属より分離)
マダガスカルチドリ Helenaegialus thoracicus Madagascar Plover
ヒメチドリ Helenaegialus pecuarius Kittlitz's Plover (アフリカ)
セントヘレナチドリ Helenaegialus sanctaehelenae St. Helena Plover
ウィルソンチドリ属? Ochthodromus (Charadrius 属より分離)
ミヤマチドリ Ochthodromus montanus Mountain Plover (北米)
ウィルソンチドリ Ochthodromus wilsonia Wilson's Plover (南北アメリカ)
クロオビチドリ Ochthodromus collaris Collared Plover (中南米)
プナフタオビチドリ Ochthodromus alticola Puna Plover (南米アンデス)
コフタオビチドリ Ochthodromus falklandicus Two-banded Plover (南米南部)
オオチドリの学名は Eupoda veredus (Gould, 1848) によっていると思われるが、Eupoda vereda の表記もある。
Eupoda は eu- よい pous, podos 足 (Gk)。
Leucopolius は leukos 白 polios 灰色 (Gk)。
メダイチドリ属? は日本産種が複数あるため最も身近なメダイチドリを採用した。タイプ種はニシオオチドリ。
ヒメチドリ属? のタイプ種はセントヘレナチドリだが、分布の広さからヒメチドリを採用した。
ヒメチドリを含むの分子遺伝学研究は dos Remedios et al. (2018) Genetic structure among Charadrius plovers on the African mainland and islands of Madagascar and St Helena
にある。ヒメチドリは一夫多妻で一夫一妻のシロビタイチドリ、ミスジチドリ (これらは Boyd の分類ではすべて別属) に比べて大陸と島の間の遺伝的違いが非常に小さい。ヒメチドリ類の3種は遺伝的にはっきり分かれる結果になった。アフリカ南部の広義 Charadrius属は複数回マダガスカルに定着し (Boyd の別属に相当)、そこから新しい種を生み出したと考えられる。
ウィルソンチドリ属? の名称はタイプ種より採用した。
シロチドリ属 Leucopolius は世界に広く分布しており、なぜ英国のケント州やエジプトのアレクサンドリアがもとになっている種類が日本にも分布するか理解しやすい。
かつては Boyd のシロチドリ属 Leucopolius 全体が1種として扱われていたようで、コンサイス鳥名辞典当時ではアカエリシロチドリ、シロビタイチドリも同種とすることがあると書かれている。ユキチドリは当時はシロチドリの亜種扱いだった。
古い図鑑をお持ちの方は分布図を見ていただけばこのあたりの事情がわかりやすい。
シロチドリの和名と Leuco- の相性がよいので、属として認められればこの学名は適切に思える。
メダイチドリ属? Eupoda はユーラシア内陸を中心に繁殖で乾燥環境に適応。一部の種がアフリカに越冬分布する。繁殖分布を考えると Eupoda 属の分離は生物地理学的・生態的にも妥当に思える。他の属は限られた地域に分布。
IOC 14.1 ではこの分類の メダイチドリ属? Eupoda 以降をすべてまとめて Anarhynchus 属としている。
シロチドリも Anarhynchus alexandrinus、カオジロシロチドリも Anarhynchus dealbatus。
まとめる場合にこの属名が優先されるのは Boyd が 亜科 Anarhynchinae に用いているのと同じ理由。
IOC の現行分類に従えばこの分類表に登場する日本産の種類がすべて Anarhynchus 属となり、これはこれで悩ましい。Anarhynchus: ana- 後ろ向きの rhunkhos 嘴 (Gk) で本来はハシマガリチドリ限定の学名なので、多くのチドリ類の属名がこの名前になると名が体を表さなくなって学名の説明に困ることになる。
海外 (wikipedia なども) ではすでに使われ始めているので、なぜ Anarhynchus 属に変わったのかと問われればここに記載した程度の説明が必要になる。簡単なものではない。
AOC も Anarhynchus 属を採用: Chesser et al. (2024) Sixty-fifth Supplement to the American Ornithological Society’s Check-list of North American Birds。
Working Group Avian Checklists は IOC 同様最初から Anarhynchus 属を採用。
まだ満足なものではないが、世界的にはおそらくこの学名に統一されてゆくものと思われる。もし統一しない場合は (現時点までの情報によれば) 上記のような細かな属に分割が必要なので統合の方が選択されたのだろう。
これは Cerny and Natale (2022) の提案に基づくもの [広義 Charadrius 属を扱った dos Remedios et al. (2015)
North or south? Phylogenetic and biogeographic origins of a globally distributed avian clade の影響もあるだろう]
と思われるが、多数の属を含んでいたグループを1属にまとめるのは大雑把すぎる感じがする。多くのリストでまだ Charadrius を使い続けているのはこのあたりが十分解消されていないためかも知れない。生物地理学的・生態的には分けた方が概念的にわかりやすいと思われるが皆さんはいかが考えられるだろうか。
南米の SACC でも議論 (投票) が行われていて Revise the taxonomy of the Charadriidae
によれば、さらに精密なデータが出た将来の分割を前提に暫定的にまとめることには賛成するもののさすがに Anarhynchus の名前はいただけないとの見解も出ている。このグループを代表できるような代わりの名前は詳しく調査してもみつからなかったとのこと。
Bonaccorso のコメントでは Cerny and Natale (2022) の結果はまだ不十分なのでこの論文で提案されている変更を無批判に受け入れてしまわないように moderate (調整役を果たす) すべきであろうとのこと。
しかし現在の Charadrius 属をこのままにしておくことが不適切であることは Barth et al. (2013) ですでに明らかになっているので世界的には分類変更が始まっている。世界の動向をまったく無視するわけにもいかない。
種類も多いグループなので限られた遺伝子のみでの Cerny and Natale (2022) の解析には限界があって (over-interpretation やりすぎ? のような表現もとられることもある)、現在のタカ類程度に詳しい核遺伝情報が出るまで個々の分岐の確実さが判断しきれないとなるだろうか。
しかし種類が多くて誰も手をつけなかったのかも知れないが、Barth et al. (2013) と公開データを用いたいわば "誰でもできる" 研究の Cerny and Natale (2022) の間に、dos Remedios et al. (2015) はあるものの、広範な分類を扱った視点の目立った研究がなされていないのも不思議なところである。
シギ・チドリの保護や渡りルート解明には多くの人が関心を持っているので、誰かが気合を入れて (費用やテクニックは必要だろうが...) Catanach and Pirro (2023) がタカ類 87 種のゲノムを読んだように (#アカハラダカの備考参照) 全ゲノム解析をやれば飛躍的に進展するのだろうが。
Catanach はタカ類の分子系統と保護の両面を行っているが、シギ・チドリ類では保護に関心のある人と分子系統解析専門家の興味の間にオーバーラップが少ないのかも知れない。
Engel et al. (2020) Incubating parents serve as visual cues to predators in Kentish plover (Charadrius alexandrinus)
がカーボベルデ (アフリカの西) の島のシロチドリを用い、抱卵する親の存在が巣の捕食を高めている可能性があることを示した。卵の保護色に加え、親の営巣場所選択と親自身の保護色も重要である。ここでは主な捕食者はチャエリガラス Corvus ruficollis Brown-necked Raven だったとのこと。
チドリ類 (どの種類もそうなのか知らないが) が捕食者に気づくと巣を離れるのもこのような理由で理解できるだろうか。そしてさらに擬傷行動が進化した? (これも調べれば書いてありそうだが)。
-
メダイチドリ (将来の属学名変更に注意)
- 第7・8版学名:Charadrius mongolus (カラドゥリウス モンゴルス) モンゴルのチドリ
- AviList 学名:Anarhynchus mongolus (アナリュンクス モンゴルス) モンゴルの後ろ向きの嘴 (のチドリ)
- 第7・8版属名:charadrius (m) チドリ
- AviList 属名:anarhynchus: ana- 後ろ向きの rhunkhos 嘴 (Gk) 本来はハシマガリチドリのみを指した
- 種小名:mongolus (adj) モンゴルの
- 英名:Mongolian Plover, IOC: (Lesser Sand Plover) 2023 年から Siberian Sand Plover が採用された。AviList も同じ
- 備考:
charadrius は#ハジロコチドリ参照。
anarhynchus は#シロチドリ参照。
mongolus は短母音のみで (mongolicus から推定)、mongolicus の音節区切りから mon-go-lus と区切られると想定され冒頭がアクセント音節と考えられる (モンゴルス)。
5亜種あった (IOC)。IOC 13.2 から2亜種に。日本で記録される亜種は stegmanni (ロシアの動物学者 Boris Karlovich Shtegman に由来) 亜種メダイチドリと、mongolus モンゴルメダイチドリ (かつての名称モウコメダイチドリ) とされる。
Boyd では Eupoda mongola。
IOC 14.1 では Anarhynchus mongolus。英名変更 (IOC 13.2 から) にも注意。HBW/BirdLife v8 (Dec 2023)、Clements, version 2023 もこの英名を採用だが属名の扱いはリストによってまだ分かれている。
茂田 (1992) Birder 6(8): 36-41 にメダイチドリとオオメダイチドリに関する詳しい記事がある。
基産地はモンゴル国境から 40 km 北側だったにもかかわらず、命名者の Pallas はモンゴル高原で繁殖すると考えて mongolus の種小名を与えたもの。基亜種 mongolus はモンゴルでは記録されず、そこで記録される亜種は atrifrons とのこと。
現在の英名も分布に従い、より適切な Lesser Sand Plover が使われている。
メダイチドリ、オオメダイチドリ、オオチドリ、ニシオオチドリ Charadrius asiaticus 英名 Caspian Plover は近縁種グループをなす。
メダイチドリとオオメダイチドリの繁殖分布は重なっておらず、その点からも別種が妥当と考えられている。越冬地分布には重なりがある。第1回夏羽の個体は越冬地に留まるのが普通と書かれている。
嘴の長さは亜種によって異なり、亜種によってはメダイチドリとオオメダイチドリの識別が困難になるが、日本に飛来する亜種はこの点では比較的識別しやすいとのこと。
茂田氏による識別点一覧が表に示されている。
Wei et al. (2022) Genome-wide data reveal paraphyly in the sand plover complex (Charadrius mongolus/leschenaultii)
のゲノム研究で "Lesser Sand Plover" 従来の Charadrius mongolus は単系統でなく、2種に分けるのが適切とのこと:
・Charadrius mongolus Pallas, 1776: 亜種 mongolus, stegmanni はこちらに含まれる。英名 Siberian Sand Plover
・Charadrius atrifrons Wagler, 1829: 亜種 atrifrons, pamirensis, schaeferi はこちらに含まれる。英名 Tibetan Sand Plover
この名称を用いる場合、オオメダイチドリの英名 Greater Sand Plover に対応する Lesser がなくなるため、オオメダイチドリの英名は Desert Sand Plover とするのが適切ではないかとのこと。
オオメダイチドリの方はオオメダイチドリほど詳しい地理的なサンプルを用いた研究はまだなされていない。
AviList では Wei et al. (2022) の提案通り Anarhynchus mongolus と Anarhynchus atrifrons は分離された。第8版の亜種は2つとも前者に含まれる。
英名は前者に Siberian Sand Plover を採用 (Clements 2024 では Siberian Sand-Plover、BirdLife v9 では Siberian Sandplover と少し表現が異なるが実質同じ)。
後者は Tibetan Sand Plover (他リスト英名の表現も Siberian Sand Plover 同様に少し違う)。
-
オオメダイチドリ (将来の属学名変更に注意)
- 第7・8版学名:Charadrius leschenaultii (カラドゥリウス レスケナウルティイ) ルシェノーのチドリ
- AviList 学名:Anarhynchus leschenaultii (アナリュンクス レスケナウルティイ) ルシェノーの後ろ向きの嘴 (のチドリ)
- 第7・8版属名:charadrius (m) チドリ
- AviList 属名:anarhynchus: ana- 後ろ向きの rhunkhos 嘴 (Gk) 本来はハシマガリチドリのみを指した
- 種小名:leschenaultii (属) Leschenault の (ラテン語化して Leschenault -ius を属格化) フランスの植物学者、鳥類学者、採集家の Jean Baptiste Louis Claude Theodore Leschenault de la Tour に由来
- 英名:Greater Sand Plover
- 備考:
charadrius は#ハジロコチドリ参照。
anarhynchus は#シロチドリ参照。
leschenaultii は原語の読みは無視してラテン語読みとした。u にアクセントがあると考えられる (レスケナウルティイ)。
3亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は亜種不明とされる。
メダイチドリとの関係については#メダイチドリの備考参照。茂田氏は学名の由来の説明で語尾の l を発音した表記を示しているが、フランス語ではこれは発音しないのが正しいと思う (例 Renault ルノー)。
Boyd では Eupoda leschenaultii。
IOC 14.1 では Anarhynchus leschenaultii。
-
オオチドリ (将来の属学名変更に注意)
- 第7・8版学名:Charadrius veredus (カラドゥリウス ウェレードゥス) 早馬チドリ
- AviList 学名:Anarhynchus veredus (アナリュンクス ウェレードゥス) 早馬の後ろ向きの嘴 (のチドリ)
- 第7・8版属名:charadrius (m) チドリ
- AviList 属名:anarhynchus: ana- 後ろ向きの rhunkhos 嘴 (Gk) 本来はハシマガリチドリのみを指した
- 種小名:veredus (m) 早馬、駅馬
- 英名:Oriental Plover
- 備考:
charadrius は#ハジロコチドリ参照。
anarhynchus は#シロチドリ参照。
veredus は2つめの e が長母音でアクセントもある (ウェレードゥス)。古代ローマ時代のヨーロッパの地域ガリアで話されたガリア語 (Gaulish) の *weredos 由来で長母音もこれを引き継いでいる。これはケルト祖語 *uphoreidos (馬) に由来し、ウエルシュ語 gorwydd にわずかに痕跡を残しているとのこと (wiktionary)。
単形種。コバシチドリ同様 Oriental Dotterel の英名もあった。
かつてはニシオオチドリ Charadrius asiaticus 英名 Caspian Plover の亜種 (かつての学名 Charadrius asiaticus veredus) とされていた。
オーストラリア北部で Gould (1848) が記載したもの (原記載)。
Boyd では Eupoda veredus。
IOC 14.1 では Anarhynchus veredus。
-
コバシチドリ
- 第8版学名:Eudromias morinellus (エウドゥロミアス モリネルルス) モリニの小さなよく走る者/小さな馬鹿者のよく走る者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Charadrius morinellus (カラドッリウス モリネルルス) モリニの小さなチドリ/小さな馬鹿者チドリ
- 第8版属名:eudromias よく走る者 eu- よい dromos 走る (Gk)
- 第7版属名:charadrius (m) チドリ
- 種小名:morinellus (m) モリニの小さな鳥/小さな馬鹿者 (morio (m) ばか者 -ellus (指小辞) 小さい) 備考参照
- 英名:Eurasian Dotterel
- 備考:
eudromias は外来語由来で発音はわからないが、起源となるギリシャ語は短母音なので長母音は現れないと考えられる。語末に母音が2つあるのでアクセント位置は確定して o にある (エウドゥロミアス)。
charadrius は#ハジロコチドリ参照。
morinellus は morio は2つの o が長母音。
n が入る理由は2つの意味を兼ねているためで、Morini でよく見られるため (Ray 1678) がもう一つの意味 (The Key to Scientific Names)。Morini は現在の英仏海峡のフランス寄りの場所。
古代ローマ時代のヨーロッパの地域ガリアで話されたガリア語の地名。ユリウス・カエサルの時代からある名前で地名の文字通りの意味は "those of the sea" (sea folk, sailors で海の人ぐらいの意味でそのまま地名となったのだろう)。
mori は海の意味 (ラテン語では対応する名詞 mare があり、英語の marine などにつながる。フランス語では mer。ロシア語ではさらに原型が残っていて more モーリェ)。(wikipedia 英語版などより)。
両者の意味があり、Morini の発音もわからないので発音の判定が難しいが n の音が入ることから地名優先で短母音としてみた。アクセント音節は -nel- になる (モリネルルス)。
地名の読みはギリシャ語を参考にすれば o が長母音だが、ラテン語 mare は通常短母音なので決定打がない。冒頭を長母音としてもアクセント移動はないのでどちらでもよい。
英名の Dotterel は 1440 年から鳥や人に対する屈辱語として使われた。現在の英語でも dotard の単語がある。
警戒心がなく簡単に捕まえられ、珍味であるとの記載があった。ロシア名 khurstan にも同じような説明があって抱卵中のオスは触れさせてくれることもある (Kolyada et al. 2016)。繁殖域が比較的限られていることを考えるとそこまでよく知られていたのかやや不思議な感じもする。
wikipedia ドイツ語版には少し異なる記述があり、dotterel の由来は dote (子供っぽい。現在は溺愛するの意味で使われる) の可能性もあるとしている。単形種。
記載は早く Charadrius Morinellus Linnaeus, 1758 (原記載)。Linnaeus 以前から Morinellus の名称が使われていた。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではオスが抱卵し、危険を感じると強力に目をそらさせようとするとある。配偶様式はヒレアシシギ類に似ているとのこと (wikipedia 英語版)。
#レンカク備考の [チドリ目の配偶様式] の Wanders et al. (2024) Role-reversed polyandry is associated with faster fast-Z in shorebirds
によればこの系統 {Charadriinae + Vanellinae + Anarhynchinae} では唯一のようで、ヒレアシシギ類とは違って散発的に生じた配偶様式と思われる。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では単形属の Eudromias 属 (eu- よい dromos 走る Gk) としている。
Howard and Moore でも他のリストでも Charadrius との間を行き来している例がいくつもある。IOC はずっと Charadrius を用いていたが 14.1 より Eudromias 属。
Eudromias を分離する根拠は Baker et al. (2007) (#ミフウズラの備考参照)。
解析に用いられた種類は限られているが、Eudromias を Charadrius に含めると Charadrius が単系統にならない問題のようである。eBird も 2023 年よりこちらの分類を用いている。
HBW/BirdLife もこちらを用いている。
近年の解析情報は #タゲリの備考も参照。
Eudromias は最近の解析の結果提案された属名ではなく、昔から用いられていたもの (Brehm 1830)。IOC などは Charadrius に含める扱いにしていたもの。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)にて Eudromias 属に変更となった。
Working Group Avian Checklists でも Eudromias 属で世界で共通化されそう。
なお1文字違いの Eudromia というシギダチョウ科に属するまったく関係ない属がある。
Boyd では Eudromias morinellus。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES ミヤコドリ科 HAEMATOPODIDAE ▽
-
ミヤコドリ
- 学名:Haematopus ostralegus (ハエマトプース オストゥラレグス) カキを集める血の色の足をした鳥
- 属名:haematopus (合) 血の色の足 (haimat- (接頭辞) 血の pous 足 Gk)
- 種小名:ostralegus (合) カキを集める (ostrea (f) カキなどの二枚貝 lego (tr) 集める)
- 英名:Oystercatcher, IOC: Eurasian Oystercatcher (分離される可能性あり)
- 備考:
haematopus は -pus がギリシャ語の足由来の長母音で他は短母音。-ma- がアクセント音節 (ハエマトプース)。
ostralegus は ostrea は短母音のみ。lego も e は短母音なので長母音は現れないと考えられる。
また -legus の語尾も短母音とあるのでこれを採用する。florilegus (花を集める) なども同様 (wiktionary)。
-tra- がアクセント音節と考えられる (オストゥラレグス)。
4亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は osculans (くっつき合う、キスする < osculari くっつき合う。密集している様子を指す) とされる。
かつてはアメリカミヤコドリ Haematopus palliatus 英名 American Oystercatcher、オーストラリアミヤコドリ Haematopus longirostris 英名 Pied Oystercatcher、
ニュージーランドミヤコドリ Haematopus unicolor 英名 Variable Oystercatcher、アフリカクロミヤコドリ Haematopus moquini 英名 African Oystercatcher などと同種とされ、
汎世界的分布を持った種であったが分割された。少し古い書物 (コンサイス鳥名事典もミヤコドリ科の項目で他の分類もあることを示した上で単形属の取り扱いで記述している) にはこの分類を使っているものがあるので記載を読む時には現代の分類に沿ったものか、
アメリカミヤコドリなども含んだ記述か注意して読む必要がある。南アメリカなどのかつての亜種もアメリカミヤコドリに統一されて、古く使われた亜種名が使われなくなっている。
現代の分類でもユーラシアからアフリカにかけて広く分布する種類で、各国語の名前は「カキなどの二枚貝を集める」かカササギに似た配色からのいずれかが多いようである。カキを食べるかどうかは種にもよるようで、オーストラリアミヤコドリの場合は食べないので名前がやや合っていないとある。
例えばドイツ語では Austernfischer と前者、フィンランド語、デンマーク語、オランダ語、ロシア語などでは後者である。中国語は前者。その意味では日本語の名称は珍しいと言えそうである (語源もよくわかっていないようである)。
[ユーラシア東西のミヤコドリは別種か]
Senfeld et al. (2020) What was the Canary Islands Oystercatcher?
で世界のミヤコドリの分子遺伝学研究が行われて、亜種 osculans を含む極東のグループは種相当の可能性があることがわかった。
その場合は Haematopus osculans とすることになる。系統樹を見ても Haematopus ostralegus は単系統をなしておらず osculans は確かに Haematopus 属の他の種レベルで分離している。
ユーラシアの東西で別種となる形になり、他の亜種はすべてユーラシア西部から中央部に分布。この分離は適切に見える。
この分類群は世界でも孤立した個体群で Haematopus osculans Swinhoe, 1871 と記載されたもので Swinhow の記載、分離されればもとの学名に戻ることになる。
Melville et al. (2014)
Conservation assessment of Far Eastern Oystercatcher
Haematopus [ostralegus] osculans
によれば、Chandler (2009), Livezey (2010) は Korean Oystercatcher の名を用いたが、主な個体群は中国とロシア極東にも分布するため Far Eastern Oystercatcher の英名を提案している (International Wader Studies)。
Boyd の分類では新世界で系統の離れたミヤコドリ類4種を別属 Prohaematopus としている。これらも含めたミヤコドリ類の Boyd による分類は以下のようになる。
Senfeld et al. (2020) はカナリークロミヤコドリは Haematopus ostralegus のグループとしてよいと見解だが、Boyd は別種扱いが適切と考えている。ここでは後者に従っておく。
逆に言えばユーラシア東西のミヤコドリの遺伝的距離はそれだけ遠いことになる。
クロミヤコドリ?/アメリカミヤコドリ?属 Prohaematopus (Boyd の分類による)
マゼランミヤコドリ Prohaematopus leucopodus Magellanic Oystercatcher
ミナミクロミヤコドリ Prohaematopus ater Blackish Oystercatcher
クロミヤコドリ Prohaematopus bachmani Black Oystercatcher
アメリカミヤコドリ Prohaematopus palliatus American Oystercatcher
ミヤコドリ属 Haematopus (Boyd の分類による)
オーストラリアクロミヤコドリ Haematopus fuliginosus Sooty Oystercatcher
アフリカミヤコドリ Haematopus moquini African Oystercatcher
(ニシ? ミヤコドリ) Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher (ユーラシア中・西部の個体群)
カナリークロミヤコドリ Haematopus meadewaldoi Canary Islands Oystercatcher (絶滅種)
ミヤコドリ Haematopus osculans Far Eastern Oystercatcher (極東の個体群。新分類)
オーストラリアミヤコドリ Haematopus longirostris Pied Oystercatcher
チャタムミヤコドリ Haematopus chathamensis Chatham Oystercatcher
ニュージーランドミヤコドリ Haematopus unicolor Variable Oystercatcher
ミナミミヤコドリ Haematopus finschi South Island Oystercatcher
[クロミヤコドリの記録はあるか?]
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によれば当時の学名で Haematopus niger Kurile Is. にクロミヤコドリの和名が与えられている。
Woods (2014) Conservation assessment of the Blackish Oystercatcher Haematopus ater
の記述によればこの学名は現在では Haematopus bachmani (Boyd では Prohaematopus bachmani) に対応するとのこと。
当時の和名と対応がよいのでおそらくこの種に対応するものであろうが現在の日本鳥類目録の検討種には含まれていない。
Dement'ev and Gladkov (1951) のロシアの亜種には含まれていない (千島列島で記録があったならば含められていても不思議でない)。カムチャツカの亜種は osculans。
近年では Lobkov (1995, 2013 再掲) The record of the black oystercatcher Haematopus bachmani on Kamchatka (p. 857) がカムチャツカで迷行例を記録している (写真はない)。
1983 年にはチュコトで記録があるとのこと。いずれも8月前半の記録とのこと。
[ミヤコドリの樹上営巣]
Kotyukov and Nikolaev (2024) Oystercatcher Haematopus ostralegus nest in the tree crown (pp. 5437-5440)。過去には非常に珍しいとされ、近年は事例が報告されているがそれでも珍しい。
Zykin (2025) Oystercatcher Haematopus ostralegus nesting on trees (pp. 2147-2148)。
[和名の由来]
ミヤコドリの和名由来には一般的には定説はないとされている。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3623-3625 のミヤコドリの項目 (内田) では和名由来は全く不明、とすら書かれていた (そこまで強硬に否定しなくとも...)。
これはおそらく「都鳥」をカモメ類ではなくミヤコドリと判定してかつての鳥学者が和名統一に用いたものが誤りであると、複数の論者から反論されたことを反映しているのではないかと想像する。
近年ではもう少し緩やかに古典の「都鳥」由来を取り上げる見解も多く取り上げられている。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 pp. 15-30 (1940 年初出) で詳しく考察されており、万葉学者の豊田八十代氏はミヤコドリ説、東光治氏は万葉集の歌をもとに春 (4月下旬) 汀に下りて鳴く表現から干潟に好んで寄り付く習性からミヤコドリとしたとのことだが、中西氏はこの季節でもユリカモメが残っていることやミヤコドリの数がそもそも少ないことから疑問とし、ユリカモメと解釈できるとのことであった。
かつての鳥学者が採用した「都鳥」の意味は多分間違っていたとみなす方の解釈となっている。
万葉集の大伴家持の「都鳥」の歌はそもそも1首しかなく「都鳥かも」で終わっている (pp. 21-22)。
「都鳥」が1種のみを指していたと考えるならばどちらかを判定する必要があるのだろうが、どうもそこまで断定的ではなさそうに見える。近年は個体数も多く、中西氏が観察されていた時期は狩猟も盛んでたまたま数の少ない時期に当たっていたのではないかとも感じる。
今ではそこまでこだわる必要はなく従来使われた「都鳥」の意味の一つでよいのでは。
[貝を開ける習性]
週間アニマルライフ (1973) pp. 3623-3625 のミヤコドリの項目 (内田) によれば貝を開ける特殊技術が必要で、5週間で飛べるようになってもさらに5週間の給餌を受けてその間に上達するとのこと。
採食様式は親から学ぶため貝を食べる家系とカニを食べる家系があり、貝を食べる家系で育った場合はカニを与えられてもうまく食べられないとのこと。
出典は Norton-Griffiths (1967) Some ecological aspects of the feeding behaviour of the Oystercatcher (Haematopus ostralegus) on the Edible Mussel (Mytilus edulis)。
近年の研究では嘴の形に性的二形があり、雌雄で食物が異なることが知られているとのこと。
Brown and Nol (2024) Diet Overlaps between the Sexes in Breeding American Oystercatchers や参考文献など。
Li and Hokko (2021) Sexual dimorphism driven by intersexual resource competition: Why is it rare, and where to look for it? 雌雄の食物資源の違いによる性的二形はなぜまれかの理論的研究。
これは猛禽類の逆性的サイズ二型 (reversed sexual size dimorphism, RSD) の解釈にもつながる話で、片方の性が主に食物を運ぶ場合に性的二形が進化するメカニズムは考えられるがこの論文の考察では対象外。食物資源をめぐる両性の競争のみから性的二形を説明するのは難しい結果となった。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES セイタカシギ科 RECURUVIROSTRIDAE ▽
-
セイタカシギ (オーストラリアセイタカシギが分離された)
- 第8版学名:Himantopus himantopus (ヒマントプース ヒマントプース) 革ひものような足の鳥
- 第7版種学名:第8版と同じ
- 第7版亜種学名:Himantopus himantopus himantopus (ヒマントプース ヒマントプース ヒマントプース) 革ひものような足の鳥
- 属名:himantopus (合) 革ひものような足 (imantas 革ひも pous 足 Gk)
- 種小名:himantopus (トートニム)
- 第7版亜種小名:himantopus (合) 革ひものような足 (imantas 革ひも pous 足 Gk)
- 英名:Black-winged Stilt
- 備考:
himantopus は -pus がギリシャ語の足由来で長母音。-man- がアクセント音節 (ヒマントプース)。
英名の Black-winged Stilt の由来はおそらく主にアメリカ大陸で複数存在する類似種と区別するため。クロエリセイタカシギ Himantopus mexicanus Black-necked Stilt、ナンベイセイタカシギ Himantopus melanurus White-backed Stilt があるがこれらは英名と学名の整合性が悪い。
クロエリセイタカシギ/Black-necked Stilt は Himantopus nigricollis Vieillot, 1817 (黒い首のセイタカシギ) が由来と思われ、この学名も同じ Vieillot が Himantopus albicollis Vieillot, 1817 (白い首のセイタカシギ) に対比する形で用いたもの。後者は 資料 によるとセイタカシギのシノニムとなった模様。
前者は Charadrius Mexicanus Mueller, 1776 の早い記載が見つかったため使われなくなったが英名や和名に痕跡を残した。また Black-necked Stilt が使われていた都合上対比的に Black-winged Stilt が用いられた可能性が想像できる。
現在は別種とされるが通常はセイタカシギの亜種とされていた。首の色が明らかに違って分布も違うため AOS はずっと別種扱いとしており (wikipedia 英語版より) 主にアメリカ事情による英名ではあったが、本家セイタカシギの英名にも影響を残した可能性がある。英国ではこのような問題が比較的少なく Stilt または Common Stilt でも十分だったのだろうがアメリカの種分離扱いもあり、また迷鳥記録などの表記の問題もあるのでアメリカ流に統一されたものと想像できる。
上記が主な理由と考えたが、Black-winged Stilt にそのまま対応する学名もあった。
Himantopus 属の提唱者は Brisson (1760)。当時の習慣で Linnaeus の種小名から属名に昇格する場合新名が与えられることがあった (#ノスリの備考参照)。
Himantopus vulgaris Bechstein, 1803 (参考) "普通のセイタカシギ" (Common Stilt に対応)、
Himantopus rufipes Bechstein, 1809 (参考) "赤い足のセイタカシギ"、
Himantopus atropterus Meyer, 1810 (参考) あるいは Himantopus melanopterus Meyer, 1812 (参考。上記を改名したもの) はそれらの学名に相当する。
決定打と言えるほどの学名にならず複数提唱され、Meyer はおそらく造語の問題 (ラテン語とギリシャ語が混ざる) からさらに改名も行っていた。
トートニムも許すようになり Himantopus himantopus に統一されるまで Meyer の学名が使われていた可能性があり、1810 年のものは英名を訳した結果不適切な造語となった可能性もありそう。
英名と学名のどちらが先かはわからないが相互に関係していたと想像できる。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
単形種。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版ではオーストラリアセイタカシギが亜種扱いだったが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で独立種となった。
オーストラリアセイタカシギは Himantopus leucocephalus (leukos 白い -kephalos 頭の Gk) 英名 Pied Stilt。単形種。ムネアカセイタカシギの別名があった (コンサイス鳥名事典)。
オーストラリアセイタカシギはインドネシア、オーストラリア、ニュージーランドで繁殖し、一部はフィリピンで越冬するとされる (フィリピンでの繁殖事例もあるとのこと)。そのためオーバーシュートの渡りとして日本にやってくることもあるのだろう。
オーストラリアセイタカシギの原記載。
内田・浜口 (1990) 神奈川県で記録されたオーストラリアセイタカシギ (1986 年の記録)。
セイタカシギとの識別はかなり難しく、非繁殖羽・若鳥は現在の知見では識別できない可能性があるとも記されている (シンガポールの記述)。両種の観察されるフィリピンの識別情報を紹介しておく Ask The Experts: Stilt Identification (birdwatch.ph 2014)。
計測値があればより確実に分離できるようだが野外では形からの識別は難しいこともある。音声は異なるので親しんでおくとよいとのこと。
かつてオーストラリアセイタカシギではないかとされた個体の声を録音したことがあるが (ケッ、ケッ、ケッとケラ類のように鳴いた)、この記事を読んで改めて調べてみるとニュージーランドの音声記録に非常に近いものがあった。セイタカシギでもオーストラリアセイタカシギでもいくつもの種類の音声があるので記録してソノグラムを照合するのが一番であろう。
日本のセイタカシギの音声バリエーションまでは資料がないため確実にはわからないが、このタイプの音声ではヨーロッパのセイタカシギの音声 (ピッ、ピッのように聞こえて 4 kHz 以上) はオーストラリアセイタカシギ (3 kHz 強) よりも音程が高いことがわかった。
ベテランが何と識別するかに頼るのではなく自ら調べるべきであろうことも改めて認識できた。
国松・長島 (2011) Birder 25(7): 65-67 によれば水喜鵲 (すいきじゃく) の名称があり、中国では水辺に住むめでたい鳥と考えたとのこと。Pied Stilt (現在はオーストラリアセイタカシギの英名) はいかにも "カササギのセイタカシギ" の意味になって整合性がよいが、水喜鵲そのものの中国語由来を見つけられなかった。
[世界のセイタカシギ属]
IOC 分類によるセイタカシギ属一覧を示しておく。和名か学名のいずれかに地名が含まれているので分布はすぐわかるだろう。クロエリセイタカシギは学名から推測されるメキシコよりも広く、北部を除いた北米全体に分布する。ハワイの種もクロエリセイタカシギとされる。
ナンベイセイタカシギはセイタカシギまたはクロエリセイタカシギの亜種とされることもあり、Boyd にしては珍しく分離していない。
オーストラリアセイタカシギと学名上で紛らわしい種類があり、現在はムネアカセイタカシギとされるオーストラリア固有種の Cladorhynchus leucocephalus Banded Stilt で、別属ではあるが系統が近く原理的にはセイタカシギ属と1系統にまとめることも可能である。その場合は学名が衝突することになるのであえてそのような分類をとることはないのだろう。
原記載は Recurvirostra leucocephala Vieillot, 1816。
亜種時代のオーストラリアセイタカシギの別名はこの種との混同があったかも知れない。
このムネアカセイタカシギも学名や英名が過去に大きく変遷している。
一時期 Himantopus 属とされたこともあり、その時の学名は Himantopus palmatus Gould, 1837 だった。
セイタカシギ類は2系統がオーストラリアに定着したことになる。
セイタカシギ属 Himantopus (IOC 14.1 分類)
セイタカシギ Himantopus himantopus Black-winged Stilt
オーストラリアセイタカシギ Himantopus leucocephalus Pied Stilt
クロエリセイタカシギ Himantopus mexicanus Black-necked Stilt
ナンベイセイタカシギ Himantopus melanurus White-backed Stilt
クロセイタカシギ Himantopus novaezelandiae Black Stilt (Kaki)
ニュージーランドのクロセイタカシギは南島の限られた地域にのみ生息し、外来種や環境悪化により絶滅の危機にある。IUCN CR 種。オーストラリアセイタカシギとの交雑も大きな問題。最小約 23 個体まで減少した。
飼育下の保全も行われている。Black stilt/kaki (ニュージーランド環境保護局の資料)。100 kaki/black stilt chicks hatch (同ビデオ)。
Forsdick et al. (2024) Maintenance of mitogenomic diversity despite recent population decline in a critically endangered Aotearoa New Zealand bird
によればミトコンドリアゲノム解析から 1960 年代以前のサンプルと比較して過去の交雑の結果を示す introgression が見られていないこと、保全の成果もありミトコンドリアの多様性が保たれているとのこと。
[数の増加]
かつては珍鳥、今では普通種の代表とされるが、個体数や生息域拡大は世界的傾向のよう。世界的なまとめではどうしてもヨーロッパの情報が中心となり、英国ではまだ珍しい鳥のためにそれほど話題になっていないがロシアの情報を見るとむしろよくわかる。
分布の近いロシア沿海地方では Gluschenko et al. (2022) Breeding birds of Primorsky Krai: the black-winged stilt Himantopus himantopus (pp. 2608-2623)
過去 50 年の数の増加が著しいとのことで、日本で言われるように人為環境が好適な生息場所を提供したとは必ずしも言えないよう。
Ischenko et al. (22024) New records of the black-winged stilt Himantopus himantopus and the pied avocet Recurvirostra avosetta in Amur Oblast (pp. 3888-3891)
によればロシアのアムール州ではセイタカシギの繁殖が記録されている。ヒンガンスキー自然保護区の定点観察記録が出ており春には定期的に標行くが記録されている。沿海地方のハンカ湖で過去 50 年で初めて記録されたのは 2012 年。アムール州の方がむしろ早く 2007 年に記録されている。
-
ソリハシセイタカシギ
- 学名:Recurvirostra avosetta (レクルウィローストゥラ アウォセッタ) 反り返った嘴のセイタカシギ
- 属名:recurvirostra (adj) 反り返った嘴の (recurvus (adj) 反り返った rostrum (n) 嘴)
- 種小名:avosetta (合) ソリハシセイタカシギ (avocetta ソリハシセイタカシギ 伊 < ラテン語 avis 鳥 が変化したものか)
- 英名:Pied Avocet (英名もイタリア語起源)
- 備考:
recurvirostra は recurvus は短母音のみ。rostra が冒頭が長母音でアクセントもある (レクルウィローストゥラ)。#イスカも参照。
avosetta は特に長音にする要素は見当たらず、avis も短母音が通常の読み方。-set- がアクセント音節で普通に読めばよいことになる (アウォセッタ)。
単形種。ソリハシセイタカシギ属のいずれの種も単形種で分類も複雑なところはない。
原記載。イタリアへの渡り鳥とある。属名も Linnaeus (1758) によるもの。
ソリハシセイタカシギ属 Recurvirostra (IOC 14.1 分類)
ソリハシセイタカシギ Recurvirostra avosetta Pied Avocet
アメリカソリハシセイタカシギ Recurvirostra americana American Avocet
アカガシラソリハシセイタカシギ Recurvirostra novaehollandiae Red-necked Avocet (オーストラリア)
アンデスソリハシセイタカシギ Recurvirostra andina Andean Avocet
しかしながら属と科の和名は多少注意が必要である。ソリハシセイタカシギ属 Recurvirostra であるが セイタカシギ科 Recurvirostridae で、やむを得ない状況ではあるが属から作られた科の学名が日本語と対応していない。
上科 Recurvirostroidea Bonaparte, 1831 の概念もあり (Boyd)、トキハシゲリ科 Ibidorhynchidae (トキハシゲリ1種)、セイタカシギ科、ミヤコドリ科 からなる。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES シギ科 SCOLOPACIDAE ▽
-
ヤマシギ
- 学名:Scolopax rusticola (スコロパクス ルースティコラ) 狩猟鳥の (田舎に住む) シギ
- 属名:scolopax (f) シギ、ヤマシギ [「とがった物」に由来 (コンサイス鳥名事典)]
- 種小名:rusticola (adj) 田舎に住む (rusticus (adj) 田舎の colo (tr) 〜に住む) または狩猟鳥 (備考参照)
- 英名:Woodcock, IOC: Eurasian Woodcock
- 備考:
scolopax は短母音のみで冒頭がアクセント (スコロパクス)。
rusticola は冒頭が長母音で、-ti- がアクセント音節 (ルースティコラ)。-cola は長音にしない。
単形種。1800 年代前半までは Scolopax は非常に広いものを指していて、各種シギ類、タシギ類、オグロシギ類、チュウシャクシギ類などが含まれていた (The Key to Scientific Names)。シギと訳すことにする。
種小名は語源的には上記の解釈ができるが、"The Key to Scientific Names" では rusticula は Pliny, Valerius Martialis が用いた狩猟鳥の名称。"heathcock" またはライチョウ類 (grouse) を指していたと考える著者もある。
解説に「田舎に住む」の意味は現れず、直接的には上記狩猟鳥の名を用いたもののようである。
年代考証も含まれているのかも知れない。
同様の rusticolus はシロハヤブサの種小名だが "The Key to Scientific Names" では「田舎に住む」意味で別項目となっている。
コンサイス鳥名事典によれば種小名には地上を走る鳥の意味もあるそうで、おそらく上記の Pliny などの語源を指してそうである。学名の訳として狩猟鳥の方を採用し、補足的意味として「田舎に住む」を与えた。
和名別名にホトシギ (母登鴫) があるとのこと。
自分の住んでいる地域 (京都) では冬鳥だが、渡りの時期としては早すぎる8月初めにさえずりを聞いたことがある。チキッ、チキッという声は目立つので繁殖地域以外でも覚えておいて役に立つことがあるかも知れない。
[ヤマシギ亜科の系統分類]
Cerny and Natale (2022) の分子系統樹を用いた Boyd による分子系統分類は以下のようになっている。
ヤマシギ亜科 Scolopacinae
コシギ属 Lymnocryptes
コシギ Lymnocryptes minimus Jack Snipe
オオハシシギ属 Limnodromus
シベリアオオハシシギ Limnodromus semipalmatus Asian Dowitcher
アメリカオオハシシギ Limnodromus griseus Short-billed Dowitcher
オオハシシギ Limnodromus scolopaceus Long-billed Dowitcher
ヤマシギ属 Scolopax
ヤマシギ Scolopax rusticola Eurasian Woodcock
アメリカヤマシギ Scolopax minor American Woodcock
アマミヤマシギ Scolopax mira Amami Woodcock
ミナミヤマシギ Scolopax saturata Javan Woodcoc
ニューギニアヤマシギ Scolopax rosenbergii New Guinea Woodcock
ブキドノンヤマシギ Scolopax bukidnonensis Bukidnon Woodcock (フィリピンのミンダナオ島)
セレベスヤマシギ Scolopax celebensis Sulawesi Woodcock
オビヤマシギ Scolopax rochussenii Moluccan Woodcock (モルッカ諸島の一部)
ハシブトタシギ属? Chubbia (Gallinago 属より分離。南米)
セジマタシギ Chubbia imperialis Imperial Snipe
アンデスタシギ Chubbia jamesoni Jameson's Snipe
ハシブトタシギ Chubbia stricklandii Fuegian Snipe (南米南部。英名はフエゴ島に由来)
ムカシジシギ/ムジシギ/ニュージーランドジシギ属? Coenocorypha (ニュージーランド)
ホクトウムジシギ Coenocorypha barrierensis North Island Snipe (絶滅種)
ムカシジシギ Coenocorypha aucklandica Subantarctic Snipe
チャタムジシギ Coenocorypha pusilla Chatham Snipe
ナントウムジシギ Coenocorypha iredalei South Island Snipe (絶滅種)
スネアーズムジシギ Coenocorypha huegeli Snares Snipe
オオジシギ/ハリオシギ属? Telmatias (Gallinago 属より分離)
ヨーロッパジシギ Telmatias medius Great Snipe
モリジシギ Telmatias nemoricola Wood Snipe (ヒマラヤから中国西部)
アオシギ Telmatias solitarius Solitary Snipe
チュウジシギ Telmatias megalus Swinhoe's Snipe
ハリオシギ Telmatias stenurus Pin-tailed Snipe
オオジシギ Telmatias hardwickii Latham's Snipe
タシギ属 Gallinago
オニタシギ Gallinago undulata Giant Snipe (南米)
ハシナガシギ Gallinago nobilis Noble Snipe (南米北西部山地)
プナタシギ Gallinago andina Puna Snipe (南米アンデス中部)
ナンベイタシギ Gallinago paraguaiae South American Snipe (南米)
マゼランタシギ Gallinago magellanica Magellanic Snipe (南米)
アフリカジシギ Gallinago nigripennis African Snipe (アフリカ南東部)
マダガスカルジシギ Gallinago macrodactyla Madagascar Snipe
タシギ Gallinago gallinago Common Snipe
アメリカタシギ Gallinago delicata Wilson's Snipe (北米)
このグループは広義 Gallinago 属を分割するかどうか程度で IOC とそれほど違いはない。ただし分割すれば種小名語尾が変わるものがかなりある。
これら以外の属名は IOC にも存在するが順序は異なるものがある。
いわゆるジシギとタシギが別の属になるのはむしろわかりやすいかも知れない。
日本鳥類目録 改訂第8版 第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開 (2023年10月) とはオオハシシギ属の配置がだいぶ異なる。
Boyd によれば Cerny and Natale (2022) が用いたコシギの配列はキメラで Limosa 属とクレードを形成する結果となっている。そのため別文献を参照している。
ヤマシギとアマミヤマシギは並んだ方が自然に思えるが、Boyd はその順序でないために上記のようになっている。系統的にはヤマシギとアマミヤマシギの方がアメリカヤマシギより近い。
ハシブトタシギ属? Chubbia の名称はタイプ種を用いた。ナンベイタシギの名称は別の種に使われているので地域の名称は使わない方がよいだろう。
この属名は IOC では未採用だが Cerny and Natale (2022) ではすでに使われている。この属を認め、Cerny and Natale (2022) の系統樹を信頼すれば Gallinago 属は単系統にならない。IOC などではそのため Gallinago 属に内包しているかも知れない。
wikipedia 日本語版 (シギ科) が珍しく英語版に先行してこの属を認めた分類を紹介しているが、これは Boyd の分類を参照したもの。
ムカシジシギ/ムジシギ/ニュージーランドジシギ属? Coenocorypha はこれまでにも存在した属でムカシジシギ属の名前が見られる。他の種の和名にムジシギが複数使われていること、分布がニュージーランドに限定されていることから他の属名の可能性も挙げておく。
オオジシギ属? Telmatias は日本産種が複数含まれるが繁殖種を優先した。タイプ種はハリオシギとのこと。この2種が優先候補になりそうに思える。
日本鳥類目録 改訂第7版時代はアメリカタシギはタシギの亜種だったが分離された。
アオシギは Cerny and Natale (2022) の系統解析には含まれていない (他にも含まれていない種類はある)。紛らわしい英名・学名だがコシグロクサシギ Tringa solitaria Solitary Sandpiper を移動したものではない。
広義 Gallinago 属を含めて 19 種のゲノムの raw reads が公開されている: Capurucho et al. (2023) The Complete Genome Sequences of 19 Species of Snipes (Scolopacidae, Charadriiformes, Aves)
解析は別論文になるのだろうがアオシギも含まれているのでこれらの種の関係は近い将来に明らかになるだろう。データは公開されているので誰かが率先して解析してもよいわけだが...。The Gallinago solitaria whole genome shotgun (WGS) project のプロジェクト名になっているので、やはりアオシギの系統関係は誰もが気になっているのだろう。
GenBank のアオシギの遺伝情報はこれが唯一のもの。標本を使った解読だが、従来手法では生体試料を採取することが難しかったのだろう。
ちなみにゲノムアセンブリについての知識やどのぐらいの計算機が必要になるかは MaSuRCA アセンブラ (macでインフォマティクス 2018) が参考になる。鳥類のゲノム解析には 256 Gb RAM, 32+ cores, 2 Tb disk space のスペックが必要で演算時間は 4-5 日とのこと。通常はスーパーコンピューターを使う程度の計算量になる。
データは存在してやりたいことは明確でもそう簡単な作業でないことがわかる。「計算ならば任せてくれ」という猛者がおられればチャレンジしていただきたい。
属名の由来は Chubbia 英国鳥類学者 Charles Chubb に由来。
Coenocorypha koinosis 混ざっている koruphe 頭頂 (Gk) 頭頂部で色が混ざっているため。
Telmatias telmatiaios 沼の (Gk)。
[ヤマシギの尾の裏先端部の白色]
Dunning et al. (2023) How woodcocks produce the most brilliant white plumage patches among the birds
ヤマシギの尾の裏先端部の白色は他の鳥に比べて反射率が極めて高いとのこと。この著者たちが測定した白色の羽では最も反射率が高かった。微細構造によって光を吸い込む漆黒物質などが知られているが、逆の意味で微細構造が光を効率的に反射する構造色の一種。
薄明時にディスプレイなどを行うので、薄暗い環境下での信号として役立っていると考えられるが役割の研究はこれからに期待とのこと。
[逃げる際に脱糞する? 抱卵中のヤマシギ]
Sladecek et al. (2025) Faeces, Feathers and Flight: Understanding of Escape Behaviour in Incubating Eurasian Woodcocks (Scolopax rusticola)
オンラインの巣の公開画像、チェコの狩猟者などから得た情報による。半数以上の写真に脱糞の証拠が認められ、新鮮な羽毛も高率に見つかった。捕食に対する適応的意義があるのか、身を軽くするため、あるいは fright moulting (単なるストレス、あるいは積極的な防御反応?) などの解釈 (#カタグロトビ備考の [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] に登場の話題参照)、
余計見つかりやすくなるのではなど議論があり他種の過去研究も示されているので参考になる部分がありそう。
他種で捕食者が触れていないのに羽毛の雲 (cloud と表現されている) を放出する事例があるとのこと。
また脱糞と羽毛が抜けるにはよく似たプロセスで起きるとのこと。
[渡りながら繁殖するアメリカヤマシギ]
Slezak et al. (2024) Unconventional life history in a migratory shorebird: desegregating reproduction and migration
によれば、アメリカヤマシギの GPS 追跡により、渡り時期と繁殖時期が分離していない非常に珍しい繁殖様式 itinerant breeding をとっていることがわかった。
渡りで北上しつつ、その途中で営巣して繁殖をする。2回目の営巣は1回目から平均 800 km 離れている。
メスのみが造巣・子育てを行い (早成性)、メスの方がオスより大きい逆性的サイズ二型 (reversed sexual size dimorphism, RSD) を極端に示す。
地上営巣は危険が大きく、条件が悪い場合や捕食された場合に最大6回の再営巣がある。
近くで再営巣するよりも場所を大きく変えた方が有利なのだろうか。また一夫多妻の繁殖様式で渡り途中でも繁殖相手を見つけられ、再営巣のコストも低いのでこのような戦略が発達したのだろうか、とのこと。
このような繁殖様式が部分的に確認されているのは過去 コウヨウチョウ Quelea quelea Red-billed Quelea、サンショクハゴロモガラス Agelaius tricolor、レンジャクモドキ Phainopepla nitens Phainopepla の3種のみ。GPS 個体追跡で確実に確認されたのは初めてとのこと。
疑われている種類を含めても 11 種のみ。我々に関係の近そうなものではヨーロッパウズラ、コバシチドリ、ヨーロッパクイナが含まれている。
URI-led team finds direct evidence of 'itinerant breeding' in East Coast shorebird species (解説記事)。
-
アマミヤマシギ
- 学名:Scolopax mira (スコロパクス ミーラ) 不思議なヤマシギ
- 属名:scolopax (f) シギ、ヤマシギ
- 種小名:mira (adj) 不思議な、驚くべき (mirus)
- 英名:Amami Woodcock
- 備考:
scolopax は#ヤマシギ参照。
mira は冒頭が長母音 (ミーラ)。
単形種。
種小名は驚くべき発見の意味か? [日比 (2000) Birder 14(1): 68-70]。
記載当時はヤマシギの亜種とされた Scolopax rusticola mira。
日本の採集者から Owston の手に渡った標本のようで、記載者はヤマシギに似た色彩の若鳥と思われる別の標本がなければ疑いなく新種としていただろうとある。おそらく留鳥だろうとしている。
記載に of particular interest とあるので種小名には、特に興味がある、あるいはヤマシギと別種かどうか不思議な点があるなどの意味が込められているかも知れない。訳は「不思議な」を採用した。
菊池氏のオリジナルも「不思議なヤマシギ」であった。
-
コシギ
- 学名:Lymnocryptes minimus (リュムノクリュプテース ミニムス) 最も小さい泥に隠れている鳥
- 属名:lymnocryptes (合) 泥に隠れているもの (limus (m) 泥、krypto (intr) 隠れる -tes (接尾辞) 〜するもの Gk)
- 種小名:minimus (adj) 最も小さい
- 英名:Jack Snipe
- 備考:
lymnocryptes は -tes の語尾が長母音。-cryp- がアクセント音節と考えられる (リュムノクリュプテース)。
minimus は短母音のみでアクセントは冒頭 (ミニムス)。
タシギの小型亜種とされ Scolopax gallinago minor の学名も使われたことがあった (#タシギの備考参照)。
単形属で単形種。最も小型のタシギ類。英名の Jack はウエルシュ語でタシギを意味する giach に由来すると言われるが、辞書では人名の Jack に由来するとも書かれる。属名の中央にある kruptes (Gk) は隠れるものの意味の他に、スパイの意味があり、本来はスパルタの秘密部隊を指していた。
茂田 (2000) Birder 14(5): 26-31 によれば属名の Lymno- は Limno- とすべき綴りを誤ったものとのこと。Jack snipe はタシギのオスと信じられたこと由来の名前との説も紹介されている。
コシギのディスプレイ・フライトでは声のみで羽の音は使わないとのこと。
Taxonomy in-flux updates によれば過去に用いられたコシギの塩基配列がキメラだった問題が議論されている。
Charadriiformes (Taxonomy in Flux) によれば Cerny and Natale (2021) の版では誤ったものが用いられていたが、2022 年の出版版では訂正されたとのこと。その他にも塩基配列にかかわるさまざまな問題があり、イカルチドリも影響を受けていたとのこと。
過去に使われたコシギの RAG 遺伝子の一部はアメリカオグロシギのものと全く同じで、これを用いた系統樹は正しい系統を反映していなかった。
Lymnocryptes 属と Limnodromus 属 (オオハシシギ類) は互いに単系統をなさない驚くべき暫定的結果が得られている。
シギ・チドリ類の分子系統解析はこれまで十分なものではなかったため、今後さらに波乱がありそう。
Dufour et al. (2024) Seasonal migration and the evolution of an inverse latitudinal diversity gradient in shorebirds
の Supporting Information (Figure S1) に新しく解析された分子系統樹があるとのことで、この系統解析では Limnodromus 属にも含まれず、Scolopax よりもさらに古く分岐した系統の可能性が示唆される。系統樹サポートはよい。
Dutilleux et al. (2023) Chasing the bird: 3D acoustic tracking of aerial flight displays with a minimal planar microphone array
ノルウェーでのマイクロフォンアレイによるコシギの飛行の3次元追跡。手作業で音をマークしたり結構手間のかかる解析を行っているようだが解析方法も詳細に記載されている。
-
アオシギ
-
オオジシギ
- 学名:Gallinago hardwickii (ガルリーナーゴー ハルドゥウィクキイ) ハードウィックのタシギ
- 属名:gallinago (合) 鶏のような鳥 (#タシギの項目参照)
- 種小名:hardwickii (属) Hardwickeの (英国のタスマニア採集家 Charles Browne Hardwicke ラテン語化 hardwick-ius を属格化) 採取者
- 英名:(Japanese Snipe), IOC: Latham's Snipe
- 備考:
gallinago は#タシギ参照。
hardwickii はラテン読みで -(w)ic- がアクセント音節と考えられる (ハルドゥウィクキイ)。最後に ii が並ぶ。
単形種。英名は Latham's Snipe とされることが多い。John Latham (1740-1837) は英国博物学者、A General Synopsis of Birds (1781-1801) と A General History of Birds (1821-1828) が有名。オオジシギは前者の補遺で記載されたもの。オーストラリア鳥類学の祖父と呼ばれる (wikipedia 英語版から)。
Latham の時代は Scolopax 属で、こちらは#ヤマシギ参照。
[学名・英名の由来]
タスマニアで記載されたもの。
記載時学名 Scolopax Hardwickii Gray, 1831 (原記載)。
Hardwicke への献名であることは明らかだが、この文献によれば Hardwicke が採集したジシギ類は他にもあった模様。当時は採集地を使って Van Dieman's Land Snipe の名称だった。
Van Diemen's Land とはオーストラリアのタスマニア島に設けられた植民地で 1853 年まで流刑地だったとのこと (britanica.com) 不適切な名前で用いられなくなったのだろう。
英名は "タスマニアタシギ" のような名前になってもよかったのだろうが、現在の英語以外の名称の多くで "日本の" が付いている。かつて Japanese Snipe と呼ばれていた時代の名残りだろうが、繁殖地と越冬地が大きく異なり "日本の" と呼ぶことは適切でないと考えて改名されたのだろう。
ここでなぜ Latham の名前が出てくるのかすっきりしなかったが、
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire p. 342 で Scolopax australis 英名 Latham's Snipe、
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によれば当時の学名は Gallinago australis となっていた。
これらは "New Holland Snipe" の英名で Latham (1801) が記載したもの (New Holland = オーストラリアなどの意味)。
この学名は長く使われていたようで Ornithological notes (North 1904)
などに Latham's Snipe の英名とともに用例を見ることができる。
Australian snipe の名称もやはり使われていた。この学名は Scolopax australis Latham, 1801 (参考) に由来するが、
同じ学名が Scolopax australis Scopoli, 1769 (参考) ですでに使われていたため無効となった [参考: Species Gallinago (Gallinago) hardwickii (J.E. Gray, 1831)]。
Gallinago hardwickii が採用されることになったが、最初に記述を行い (記載者とは認められなくなったが) 広く使われていた Latham's Snipe の名称は残して学名のみ変更されたのだろう。
Supplement II to the General synopsis of birds に Latham (1801) の記述が現れるが本文では New Holland Sn[ipe] の名称で示しており、このページには学名は現れない。Richmond Index のカードでは p. lxv とあるのであるいはこのスキャンに含まれていない図版があるのかも知れない。
アメリカを中心に人名の付く英名を排除する方針が広まりつつあるようで、あるいは別の特徴を表す英名に変更されてゆくかも知れない。
Latham が最初に名付けたが学名が変わって...のような話は wikipedia 英語版には他種ではよく記述されているが東洋の種のため記述が不足しているのだろう。
シノニムがよくリストされている Dement'ev and Gladkov (1951) にもこの学名の記載はなく有効な学名ではなかったと考えられる。Dement'ev and Gladkov (1951) にとっても身近な種類ではなかったのだろうか見出しの学名の綴りを間違っている。
なお Latham が記載したジシギにはヨーロッパジシギ/ニシチュウジシギ Gallinago media Great Snipe があり、こちらの英名が "オオジシギ" に対応している (中国名の一つがこの意味に対応する)。この学名の media はジシギとヤマシギの中間の意味とのこと (The Key to Scientific Names)。
ジシギ類は識別のみならず名前も複雑のよう。
オオジシギは Boyd では Telmatias hardwickii。
北海道周辺で繁殖し、オーストラリア東部に渡る。繁殖期に大きな音を立てるディスプレイを行うためカミナリシギの別名がある。
日豪渡り鳥協定の対象種だったが、オーストラリアでは狩猟鳥であったために発効が 1981 年まで遅れたとのこと (コンサイス鳥名事典より)。#タシギの備考にあるように入植者が故郷のタシギ、アメリカタシギ (sniper = 狙撃兵 の語源) のような狩猟鳥を求めたとすれば納得できる話に思える。
狩猟の管理のためには個体数把握は熱心に行われ、数が減ると日本の繁殖地ではどうなっているのかなど関心も高かったが、狩猟鳥でなくなるとあまり熱心に調べられなくなり、日本の減少傾向とオーストラリアの個体数の相関がわかりにくくなった模様。次の項目も参照。
[今やサハリンを代表する鳥]
wikipedia ロシア語版によればロシアはオオジシギの分布のごく周辺で、ロシアに現れたのは 1940-1950 年代と最近のこと。1980-1990 年代に数を増したとのこと。
Yaponskij bekas (2012) によればロシアでは数が増加しており、サハリン南部、千島列島南部で繁殖してもはや日本だけで繁殖する種類ではなくなっている。沿海地方でも繁殖するようになり、サハリン州のレッドデータブックから外す議論もなされている (2012 年段階の記事)。人の接近も許すという。
Yaponskij bekas (2023) によれば保護の結果特にサハリン南部で数が増してきて今では十分広く分布しているとのこと。
Bal'chuk et al. (2016, 2019) History of expansion and current status of the Latham's snipe Gallinago hardwickii on Sakhalin Island
によればサハリンで繁殖北限が 1990-2010 年の期間に北進し、繁殖個体数も増えている様子が記録されている (皮肉にもサハリン開発で問題とされた サハリン-2 の天然ガスのモニタリングステーション周辺で記録され大きく増えている)。日本のような繁殖地南限で減少しており、生息地が北に移動したのでは。
Yaponskij bekas で分布や写真を見ることができる。Bal'chuk et al. (2016, 2019) の検討も含めると、この種の現在の世界の繁殖分布の中心は北海道ではなくサハリン南部になっているらしい。
(サハリンの報告) (2023)
サハリンの鳥類学の歴史も述べられており、Nechaev が 1991 年に「サハリンの鳥」を出したが、その後 30 年を経過して現在ではよく調べられているとのこと。
オオジシギは最初は日本の固有 (繁殖) 種だったが今では繁殖期によく目立つ種類になった代表種 (ロシアではサハリン固有の鳥類相を代表する鳥になりつつあるらしい)。すでにサハリン北部まで到達しており、繁殖地が日本とサハリンで入れ替わってしまったと言える。普通種になっているが分布が狭いために現在もレッドデータブックに含まれている。
シマアオジはかつては普通の種類だったが今では島の北部に限られた数のつがいしかいない。
サハリンハマシギ (600 つがい程度とのこと) の話題、ヨーロッパとはスズメの種類が違う。他所から来た人はスズメの数の少なさに驚くなど他の種類の話も紹介されていてなかなか面白い。
国後島では普通種となっており、映像が出ている Japanese Snipe Display Flights And Drumming in Kuril Islands。
Stefanov (2022) Waders of island Kunashir (pp. 3469-3499)
にも国後島のオオジシギを含むジシギ類の研究データがある。
色丹島の情報は 極東の鳥類43: 千島列島特集 にもあり、2015 年の調査では現在オオジシギは色丹島で最も生息数が多いシギの1種であるとのこと。
プレスリリース:オーストラリアで大規模森林火災を引き起こした異常気象により北海道内のオオジシギの繁殖数が推定で 42% 減少したことを確認 (3.5万羽 → 2.0万羽に!?) (日本野鳥の会 2020)
の分布図も認識が相当異なっていることがわかる。
[タシギ類のドラミング]
日本で繁殖し飛翔ディスプレイ時に音を出す種類はオオジシギのみなのでここで触れておく。
この音を英語では drumming と呼び (キツツキのドラミングと同じ)、古くからどのような仕組みで音を出しているか議論があった。外側尾羽は内側に比べて小羽枝で強力に結合されており、急速降下の際に振動で音を出しているとのこと。翼の形を変えることで尾羽に当たる気流を変化させ、音を変化させているとのこと (wikipedia 英語版より)。
Snipe drumming: how does a snipe drum? にも解説がある。
日本では繁殖しないがタシギなどでも同様。外見は似ているが繁殖行動には種差が見られるとのこと。
#タシギの項目にも情報を追加した。
[羽音と流体力学] 以下#アホウドリの備考 [海鳥の翼先端にはなぜスロットがない?] の *2 から続く。一部重複して紹介する。
ここから読み始めると難解な可能性が高いので、流体力学にかかわるもっと身近な話 (流体力学は実は理学部で物理を専門とする学生にも難しいなど) はアホウドリの備考を先に見ていただくとよい。
まずは鳥や飛行機の翼の揚力や抗力などの話をちょっと見ていただいて、一般に言われる解説の不十分なところなども把握してからこちらを読む順序がよいだろう。
渦抵抗 (カルマン渦列と抗力) の解説もある。
3. 渦動後流と物体が受ける抗力 (円柱の場合) の解説部分も渦の効果が直感的にわかりやすい部分があり参考になる感じがした。
また「流れの中に置かれた弦などは一定の振動数で振動し音を発するが、このような音響的現象は古くから知られていた」の部分は、羽毛と空気の相互作用で音を発生する種類でも起きているかも知れない、がこの話題の発端となる。風で「電線が鳴る」のはこの振動が原因。
上記タシギ類のドラミングの wikipedia 英語版の解説をみると羽の振動によるメカニズムは古くから提唱され、古い文献が引用されているが、以下に述べる2つの対立仮設と現代的な議論を見ていただくと現代ではどのように解釈されているか少しわかっていただけるのではないだろうか。
渦動後流による振動がタシギの音と出すメカニズムとして提唱されたことがあった [van Casteren et al. (2010)
Sonation in the male common snipe (Capella gallinago gallinago L.) is achieved by a flag-like fluttering of their tail feathers and consequent vortex shedding]
が、その後の研究では羽の弾力による aeroelastic flutter ではないかと説明されている:
Clark and Prum (2015) Aeroelastic flutter of feathers, flight and the evolution of non-vocal communication in birds
空気の流れの中で弾性のある羽は2つの状態があり、その間を振動する (これは自分にもわかりやすい limit cycle oscillation リミットサイクル振動。音叉のような単純な振動ではなく、羽の2つの状態の間で行きと帰りで経路が異なって cycle を形成する)。
これが鳥類では一般的なメカニズムと考えられているよう。「機械的雑音」と一括するのは適切でない。
ワキアカアフリカヒロハシ Smithornis rufolateralis Rufous-sided Broadbill や アフリカヒロハシ Smithornis capensis African Broadbill も同様:
Clark et al. (2016) Smithornis broadbills produce loud wing song by aeroelastic flutter of medial primary wing feathers このケースでは P6, P7 が音源とのこと。
ドバトの 700±50 Hz の羽音も P10 由来の音とのこと: Niese and Tobalske (2016) Specialized primary feathers produce tonal sounds during flight in rock pigeons (Columba livia)。
偶然の産物とは考えにくくコミュニケーションのために進化したものと推測している。
Murray et al. (2017) Sounds of Modified Flight Feathers Reliably Signal Danger in a Pigeon
レンジャクバト Ocyphaps lophotes Crested Pigeon では P8 由来で危険を知らせる音になっている。Hingee and Magrath (2009) Flights of fear: a mechanical wing whistle sounds the alarm in a flocking bird も参照。これらも aeroelastic flutter とされる。
ハト類ではかなり一般的なようで、ナゲキバトでも報告がある。
一方キジオライチョウ Centrocercus urophasianus Greater Sage-Grouse の音は羽をこすり合わせて出すものとのこと。
Clark and Prum (2015) のレビューに一覧があるが、この論文では自分たちが風洞実験で調べた音は渦によるものよりは aeroelastic flutter で解釈できると考えている。
大部分は初列風切の外縁側 (P7-P10) またはタシギ類では尾羽の外縁側 (rx = 最外側, rx-1; 一般的なものではなくこの論文での表記) で発生している。
なぜタシギ類で尾羽が識別点になるか考える上でも役に立つだろう。鳴禽類のさえずりが同種へのシグナルとなっていると同様、タシギ類では尾羽を発音器官として用いるために尾羽の進化 (種分化) が速いと読み取れるだろう。
他の形質ではほとんど差のないタシギとアメリカタシギ Gallinago delicata Wilson's Snipe (分類については #タシギの備考も参照) では尾羽のみが有意に異なるとのこと: Rodrigues et al. (2020)
Phenotypic divergence in two sibling species of shorebird: Common Snipe and Wilson's Snipe (Charadriiformes: Scolopacidae)。
ムシクイを外見で識別するのが難しく音声が識別点になっている点がタシギ類では尾羽となっている次第。
Clark and Prum (2015) に戻ると、弾性のある初列風切は emargination の少し近位部位で曲がって flutter を起こしやすく、emargination の形状と音は無関係とは言えない可能性がある。エンビタイランチョウ Tyrannus forficatus Scissor-tailed Flycatcher の P10 は性的二形を示し、大きな音を出すとのこと。
また換羽によって生じた隙間が音を出せる可能性も考えられる。
一覧表も出ているが、我々がよく知っているキビタキの争いの時の音は簡単に調べられる文献になかったためか載っていない。Ficedula 属も出てこないのでキビタキは Ficedula 属の中でも案外特殊なのかも知れない。
ベニマシコも出ておらず、東洋の種は論文も録音も情報不足感が否めない。
他にも単純に音声データベースに (当時の時点で) 録音がないために載っていないだけの種もたくさんありそう。#ホオジロガモはしっかり含まれている。
カモ類は羽音の目立つ種類が多く推定メカニズム aeroelastic flutter に分類されている。
羽によって音を出す能力は少なくとも 69 系統で独立に進化したと推定。
Clark (2021) Ways that Animal Wings Produce Sound にレビューがある。音を出す機構を8種類考えて解説している。
このうち "aerodynamic whistles" が前述の渦動後流による振動に対応する。このレビューによれば動物では今のところみつかっていないとある。"wing whistle" と従来呼ばれてきた用語はあまり正しくない。理論的にはこのメカニズムで音を出すことはあり得るが調べた範囲ではみつかっていないとのこと。
このメカニズムの場合は硬い物体が流体と共振するもので、羽毛の弾性を必ずしも必要としない。
aeroelastic flutter は音を出せる速度の下限値がある。
スズメバト Columbina passerina Common Ground-Dove では P7 に P6 と重なって音を出すための変形がある: Niese et al. (2020) Specialized Feathers Produce Sonations During Flight in Columbina Ground Doves。
打ち下ろす時ではなく打ち上げる時に音が出るとのこと。このような構造は極めて珍しいとのことだが、同じような構造は数種に見つかっており、音を出している可能性があるとのこと。
タテゴトミツオシエ Melichneutes robustus Lyre-tailed Honeyguide の尾羽も爆音のような音を出し、(ハチの巣を壊してもらう) 哺乳類への呼びかけまたは信号との考えがコンサイス鳥名事典に出ている。検索してみると空中ディスプレイらしく aerial displays "bouncing ball steps" などの表現がある (参考 HONEYGUIDES Don Roberson)。
参考までに音源を見ておくと Lyre-tailed Honeyguide (Forbes-Watson) Mechanical sound タシギ類の音とはずいぶん違うが傾向は似ている。これは音声ではなく機械音なのだとのこと。どこがキツツキの仲間なのかと思ってしまう。
-
ハリオシギ
- 学名:Gallinago stenura (ガルリーナーゴー ステーヌーラ) 細い尾のタシギ
- 属名:gallinago (合) 鶏のような鳥 (#タシギの項目参照)
- 種小名:stenura (合) 細い尾の stenos 細い -ouros 尾の (Gk) (The Key to Scientific Names)
- 英名:Pintail Snipe, IOC: Pin-tailed Snipe
- 備考:
gallinago は#タシギ参照。
stenura は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語では stenos の e が長母音、ラテン語化された尾の意味の -ura も冒頭長母音でここにアクセントがある (ステーヌーラ)。
アジサシの sterna とは関係がない。-ura の語尾に注目とともに長音で発音するとよい。
同様の意味の属名に Leptostenura が存在する。エナガカマドドリ Leptasthenura aegithaloides Plain-mantled Tit-Spinetail。
単形種。
Boyd では Telmatias stenurus。
古典的だがハリオシギの繁殖地ディスプレイと音を記述した論文: Byrkjedal (1990) Song Flight of the Pintail Snipe Gallinago stenura on the Breeding Grounds。
ハリオシギが外側尾羽を極限まで細く多く進化させていることは知られており、タシギ類が外側尾羽で音を出していることはわかっていたがハリオシギではそれまで知られていなかったものディスプレイと音の初記述。
#オオジシギ備考の [羽音と流体力学] (特に Clark and Prum 2015) を見ていただくと、流体力学効果でより目立つ (性・社会選択) 音を出すための適応であることがわかりやすい。本数が多いのは音を大きくするため、ほとんど羽軸のみなのは空気の流れを通す隙間を作るため。
比較研究がもっとあってもよさそうなのだが、ロシア北部で繁殖する種なのでどうしても情報が少ない模様。
ジシギ類の識別は日本語でも多くの情報があるが、特にハリオシギとチュウジシギ、およびタシギの識別を取り上げた英語ページがあったので紹介しておく: Pin-tailed/Swinhoe's/Common Snipe (ayuwat 2021)。
[ジシギ類の音声による識別]
この識別の件が気になったのは xeno-canto でハリオシギとチュウジシギは声で識別できるか話題になっていたため。flight call で識別可能と考えている人が多いが似ていると表記されることもあるとのこと。
実際検索してみると xeno-canto に繁殖地も含めた音声が結構多く収録されており少し驚いてしまった。
繁殖地での声や drumming も聞くことができ、オオジシギとどのように違うかなども知ることができる。
さて flight call はやはりかなり違っており、(渡り途中ではあまり鳴かないかも知れないが) 音声のみでも区別可能の結論でよいだろう。
Keep Calm and Study Snipes! Part 2 (2014)
には Leader and Carey (2014) によれば香港では2種類の声があり、2種に共通のカモのような "quack" 声は差異があるが、低いタイプの声があってチュウジシギのものと暫定的に考えているとのこと。
(途中省略) It should be stressed that these calls, although different from the calls of Common Snipe, are sufficiently similar to each other to confuse observers unfamiliar with the calls of Swinhoe’s or Pintail Snipes.
Even to experienced ears, some poorly heard calls can be confusingly ambiguous.
と記述している。
チュウジシギのモンゴルでの録音に XC833993 (Martin Billard 2023) があり、低いタイプの声はこのようなもの指しているかも知れない。
ハリオシギで対応する声は XC840240 (Martin Billard 2023) がコメントにそのように記述している。
-
チュウジシギ
- 学名:Gallinago megala (ガルリーナーゴー メガラ) 大きなタシギ
- 属名:gallinago (合) 鶏のような鳥 (#タシギの項目参照)
- 種小名:megala (合) 大きな (megas, megale 大きな Gk)
- 英名:Swinhoe's Snipe 英国博物学者 Robert Swinhoe が記載した
- 備考:
gallinago は#タシギ参照。
megala は由来となるギリシャ語では女性形で megale で末尾は長音。そのまま引き継げば末尾が長音でもよいが、-e で終わっていないことからラテン語化してから女性形にしたものと考えられる。おそらく短母音でよい。アクセントは冒頭 (メガラ)。
大きいの意味の major は Gallinago を分離する際にすでに使われており、別の単語を用いたものと考えられる (#タシギの備考参照)。
単形種。
Boyd では Telmatias megalus。
The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声) part 2 5:14 チュウジシギ V sumerkakh i noch'yu tokuet lesnoj dupel' (薄明中と夜にチュウジシギがディスプレイ中です) (聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
-
タシギ
- 学名:Gallinago gallinago (ガルリーナーゴー ガルリーナーゴー) 鶏のような鳥
- 属名:gallinago (合) 鶏のような鳥 (gallina (f) めんどり ago 似る) おそらくタシギの褐色のまだらの模様、立ち止まる行動や突然鳴くことを類似点とみなした
- 種小名:gallinago (トートニム)
- 英名:Common Snipe
- 備考:
gallinago は gallina は i が長母音。-ago は両方長母音で a にアクセントがある (ガルリーナーゴー)。-ago の長音は -ax (〜に傾く) の長音に由来と考えられている。-o の長音は名詞を作る語尾。
記載時学名 Scolopax Gallinago Linnaeus, 1758 (原記載)。
Gallinago 属は Brisson (1760) が種小名を属に昇格し、Linnaeus の1種を分割し、タシギを Gallinago major Grosser Graeser とした (The Key to Scientific Names) による。
これは種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる (#ノスリの備考参照)。
種小名から属名に昇格する場合に種小名を変える必要がなくなったとともに、Brisson (1760) は二名法に則っていないためこの学名は無効となった。
そのため major の種小名の Gallinago 属の種はなくなったが、ヨーロッパジシギ Gallinago media Halb-Graeser に当時の学名での大小関係が残っている。
Gallinago minor Kleiner Graeser はタシギの亜種と取り扱われたことがあったが、Avibase のシノニム表記によればコシギのシノニムとして表面上現れなくなった。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 gallinago とされる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によればジシギの別名が挙げられている。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) によれば Bleater の英語別名があるとのこと。bleat はヒツジやヤギなどが鳴く表現に使われ繁殖期のディスプレイ時の音に由来するとのこと。
OED によれば snipe (および類似綴り) の用例は非常に古く 1325 年ごろのものがあるとのこと。当時の綴りは snype (snyte) だった。語源はスカンジナビア言語から借用らしいとされているがよくわかっていない。スカンジナビア言語の snipa がアイスランド語の myrisnipa に残っているとのこと。
中世以降の他言語 (オランダ語の snippe など) との関係はよくわかっていないとのこと。sniper (狙撃兵) の英語はもともとはタシギのように隠れて狙撃する意味で 1824 年の用例があり、タシギを撃つ者の用例は少し遅く 1840 年とのこと。アメリカ英語で金鉱探索者などの意味でも用いられ 1902 年の用例が示されている。
茂田 (2000) Birder 14(5): 26-31 によればアメリカタシギ Gallinago delicata 英名 Wilson's Snipe とは外側尾羽枚数 (左右8対、タシギは7対。#オオジシギの備考も参照)、ディスプレイ・フライト、音声が異なり別種とされるが、ミトコンドリア DNA の違いは 0.6% しかないとのこと。
茂田 (2000) の時代にはタシギの亜種扱いであった。日本鳥類目録改訂第7版時代も同じ扱いだったようである。IOC 分類では現在別種扱い。
参考 Banks et al. (2002) Forty-Third Supplement to The American Ornithologists' Union Check-List of North American Birds。
NC_088447.1 (アメリカタシギのミトコンドリアゲノム) から BLAST を試しておくと確かに別種でよさそうな結果が得られる。むしろオオキアシシギとアオアシシギの分離が微妙に怪しい。
ヨーロッパジシギ Gallinago media 英名 Great Snipe は一夫多妻または乱婚でレック形成を行い、シギ類では他にエリマキシギ (#エリマキシギを参照) で知られているのみとのこと。
アメリカタシギの解説があったので紹介しておく: The Winnowing of the Wilson's Snipe
尾羽で出す音を "winnowing" と呼ぶとのこと (音源あり)。xeno-canto をチェックしてみるとアメリカでよく使われる用語のよう。winnow はもみがらなどをふるい分ける意味から羽ばたきなどにも用いると辞書にある。
"drumming" で検索するとタシギの方が見つかるので英米で異なる用語が使われる例なのだろう (音も違っている)。
アメリカタシギの行動解説はタシギにもおそらく当てはまり、ジグザクに飛ぶのは捕食を困難にするため。ハンターにも難しい獲物で sniper (狙撃兵) という英語も(アメリカ)タシギのような敏捷な鳥を撃てる能力を持つ者として使われたとのこと。アメリカやカナダでは狩猟圧は大したことはないが生息地減少の方がより脅威である。
タシギ以外のジシギ類があまりジグザクに飛ばないのはなぜかと思ったのだが、あるいは発音器官として尾羽がより特殊化しているためなのだろうか。尾羽による特別な発音の必要性のために捕食者からの回避が困難になるならば、尾羽の音を「正直なシグナル」とも捉えることができそうな気もする (誰かが議論してそうだが)。
もっとも尾羽が変形するとジグザク飛行に不利なのかはよくわからないが、ツバメやツバメトビなどでは外側尾羽が制御に役立っていると言われる (ある程度の裏付けがある)。発音器官として尾羽をより特殊化させた種類の尾羽の写真を見ると確かに制御には不向きなぐらいに変形しているように見える。
翼型にも種類によって違いがあることが知られているが、あるいはこの姿勢制御を補う目的 (翼でも姿勢制御が可能) かディスプレイ時の飛行の助けになっているのか。さらに発音器官の尾羽に当てる空気の流れを制御するためか。どれもあってよさそうな気がする。
[この考察は 小田谷 (2021) Birder 35(3): 31 の "翼と飛び立ちでタシギ属を見分ける" 記事も参考にした]。
[Capella 属とは?]
茂田 (2000) Birder 14(5): 26-31 によれば Gallinago 属はしばらくの間 (wikipedia 英語版によれば 1934-1956) Capella 属とされていたがこれは誤った先取権を用いたものとのこと。
Capella 属はタシギをタイプ種として Frenzel (1801) が記載したもので caper, capri (ヤギ) の指小語。ディスプレイ時の音から (The Key to Scientific Names)。
Linnaeus (1758) はタシギを Scolopax Gallinago の学名で記載しており、Scolopax 属の分割に伴って生じた問題のよう。
Gallinago は Brisson (1760) で確かにこちらが早いがあまり自明な問題ではなかったようで、
ICZN Direction 39 (1956) で Capella を用いない裁定を行ったとのこと (The Key to Scientific Names)。
一時は Gallinago Koch, 1816 が採用されていて、Capella Frenzel, 1801 の方が早いことがわかり先取権を与えられたが、Brisson (1760) の記載があることが判明したことがおおまかな経緯のよう。
しかし利用実績もあり、Gallinago の方を用いない裁定を行う案もある。過去の決定を覆す結果となるのでかなり長い議論となっている。最終的には投票で決まった模様。
Peters (1934) "Checklist of Birds of the World" 以外にも多数の用例があり、Peters (1934) より早く 1920 年から用例が見つかっているとのこと。
我々が現在使っている Gallinago に至る経緯は平坦でなく投票で決められたものらしい。Capella の方が採用される可能性もあった。
ぎょしゃ座に Capella の名称の一等星があるがこれも同じ意味とのこと。ギリシャ語でこの星を aix と呼んでいてヤギの意味だったものを訳した名称とのこと (wikipedia 英語版)。
恒星の一般名を決める規則は実は最近までなかったようで、2016 年に Working Group on Star Names が設けられて公認の通称として認められるようになったとのこと。
[分断色]
この項目は川口 (2019) Birder 33(7): 52-53 の「分断色」の記事をテーマに論文を調査してみたもの。川口 (2019) はセグロセキレイを取り上げて分断色は目立つが正体がわかりにくい。砂漠・河原・砂浜など開けた環境でよく見られるとある。分断色は disruptive coloration。
近年の研究などを探してみると Seymoure and Aiello (2015) Keeping the band together: evidence for false boundary disruptive coloration in a butterfly
によれば古くから提唱されているアイデアだが実証研究は少ない。ここで挙げられている古典的例 (Cott 1940) ではタシギの模様が false boundary disruptive coloration に例示されているのでここに挙げておく。
研究対象はやはり観察のより容易な鳥などによる捕食を扱っている。鳥以外の視覚に頼る捕食者として whiptail lizards Ameiva 属トカゲも挙げられている。爬虫類も色覚は良いはずなので考慮すべしということだろう。爬虫類を捕食する鳥にとってもおそらく同様か。
ジャイアントパンダが森林では保護色になるとの研究: Nokelainen et al. (2021) The giant panda is cryptic
背景との類似性を定量的に評価しているが、鳥ではキバシリが含まれている。いろいろな動物を調べると保護色から警告色まで連続的に分布しておりジャイアントパンダは中程に位置して、保護色とされる動物に比べて特に目立つわけではない。
チドリ類では Color of Birds (Ehrlich et al. 1988)
に川口氏のものとほぼ同じような説明がある。
Camouflage and Protective Coloration in Birds
ではアメリカサンカノゴイ Botaurus lentiginosus American Bittern が捕食に役立ている例として取り上げている。サギの擬態はついつい人に対する反応として見てしまうが、両方の意味があって、捕食時ゆっくり移動することも含めて捕食に役立つ役割の方が大きいのだろう。
鳥が食べられる方の研究はあまり見当たらない。分断色はきっと役に立つのだろうがフィールドでの実証は難しいのだろう。
こちらはサルの例だが Nokelainen et al. (2024) Black-and-white pelage as visually protective coloration in colobus monkeys
分断色がチンパンジーの目には有効だが猛禽類にはそれほどでもない。あくまで理論的なもので、猛禽類は解像度が良いので離れてもよいみつけやすいということらしい。実際には捕食者の脳がどのように検出しているかはわからないわけだが。
しかしこのような獲物のカモフラージュの例を多数見ていると捕食者も大変そうなことがわかる。獲物を探す時は脳内のパターン検出回路もフル回転で捕食行動で頭も疲れることが容易に想像できる。我々がタカ渡りで点のような対象を探そう、あるいは背景に対して見つけにくい鳥を探そうとするのときっと同じ。
我々は見つけられなければ残念で終わるだけだが、生活のかかわる猛禽 (に限らないが) 生活はこの面でもおそらくなかなか大変。猛禽類を見ても休憩が多くてずっと獲物を探してばかりでないのは頭も休めないといけないのだろう。ノンレム睡眠もしっかりとって脳内疲労物質も排泄する必要がある。
発端となったシマウマの縞模様は何のため? については Caro (2020) Zebra stripes
に仮説がまとめられている。古典的仮説は捕食者の目を紛らわすものだが、Caro はどのメカニズムも実証できず、ライオンにそもそもよく捕食されていて保護色にも警告色にもなっていないと考えている。
Caro はシマウマの縞模様の専門家で過去にもいくつも論文を出しており、人の目には縞が見えても少し離れると (哺乳類の) 捕食者には模様が見えなくなるので意味がないなど述べている。
シマウマの縞模様は川口 (2019) 氏も (当時のニュースをもとに) 取り上げられていた。関連情報は #アホウドリ備考の [海鳥の翼の上面はなぜ黒い] *1 を参照。
-
アメリカオオハシシギ
- 学名:Limnodromus griseus (リムノドゥロムス グリーセウス) 灰色の沼を走る鳥
- 属名:limnodromus (合) 沼を走るもの (limus (m) 沼、dromeas 走るもの Gk)
- 種小名:griseus (adj) 灰色の
- 英名:Short-billed Dowitcher オオハシシギも参照
- 備考:
limnodromus は#オオハシシギ参照。
griseus は冒頭が長母音でアクセントもある (グリーセウス)。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは亜種不明とされる。
クレチマル・千村 (訳) (1991) Birder 5(7): p.27 に北米からシベリアにアメリカオオハシシギが進出しているとの記載があるが、ロシアではかつてオオハシシギをアメリカオオハシシギの亜種とし、
Limnodromus griseus の学名でロシア名がアメリカオオハシシギだったため、当時は両者が区別されていなかった可能性がある (Dement'ev and Gladkov 1951)。
オオハシシギに相当する当時の亜種は「西アメリカオオハシシギ」に対応する名前となっていた。
現在はオオハシシギは別種とされロシア名では「短い嘴の」が付く (英名に対応)。
Dement'ev and Gladkov (1951) の分布図では「西アメリカオオハシシギ」 = オオハシシギはチュコト半島周辺のみに分布となっていた。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) には特に記載はない。
Scolopax noveboracensis Gmelin, 1789 (noveboracensis はニューヨークの、の意味) Red-breasted Snipe (または Sandpiper) の学名と英名があった。
学名は Pennant (1785), Latham (1785) の用例もあり "New York Sandpiper" とも呼ばれていた (The Key to Scientific Names)。
Scolopax grisea Gmelin, 1789 (原記載) で同じ記載者によるものでこちらは Brown Snipe の英名となっていた。Scolopax noveboracensis はそのすぐ下に出てくる。
容易に想像できるようにこれは夏羽と冬羽を別種として記載し、記載順から冬羽 (griseus) に先取権があってこの学名に統一されたもの。
しかし noveboracensis の学名や英名も広く使われており、Audubon の図版 などに見ることができる。
この当時は Scolopax grisea の方をシノニムと考えていた。
有名な Audubon の図版に描かれているため、この英名は広く使われることになり、オオハシシギがアメリカオオハシシギの亜種となった時代にも影響を与えた。
学名が変わったためかアメリカオオハシシギの現在の英名はちょっと素っ気ないものになっている。
-
オオハシシギ
- 学名:Limnodromus scolopaceus (リムノドゥロムス スコロパーケウス) ヤマシギに似た沼を走る鳥
- 属名:limnodromus (合) 沼を走るもの (limus (m) 沼、dromeas 走るもの Gk)
- 種小名:scolopaceus (adj) ヤマシギのような (scolopax (f) ヤマシギ -aceus 〜に似た)
- 英名:Long-billed Dowitcher
- 備考:
limnodromus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-dro- がアクセント音節と考えられる (リムノドゥロムス)。
scolopaceus は scolopax は短母音のみ。-aceus は冒頭が長母音でアクセントもある (スコロパーケウス)。#オニカッコウ参照。
オオハシシギの和名は英名由来とも考えられ、また種小名とも若干関係があるかも知れないが、最も関連が深いと考えられるのが旧属名 Macrorhamphus の "大きな嘴" でまったくそのままの意味である。属の記載。英名 Longbeak とある。
この属はアメリカオオハシシギ (当時は同種だった) のみを含む属として Leach (1816) が提案したものだったが、Leach の書物は Linneaus の二名法に従っていないため新しく提案した属名はすべて無効と判定された。
Forster (1817) がそれを引用して用いたものが正当な記述とされ、当時の権威であり長く使われていたと想像できる。American Ornithologists' Union 3rd edition (incl. 16th suppl.) まで用いられていた属名。
Limnodromus も同じ種のみを含む属として定義されたもので Wied-Neuwied (1833) で実はこちらの方が遅い (The Key to Scientific Names, Avibase)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Macrorhamphus griseus でオオハシシギの和名が与えられている。scolopaceus は別学名に登場するが当時は Macrorhamphus の属名のみが用いられていたことがわかる。
Seventeenth Supplement to the American Ornithologists' Union Check-List of North American Birds (AOU 1920) で、
Macrorhamphus は Fischer (1813) がすでに用いていたため preoccupied となり Limnodromus と変更する判断がなされた。
この Fischer (1813) の用例は魚に対するもので (rhamphus と言えば嘴を連想する鳥類学者は気づきにくかったよう)、しかもこの用例には先行する Macroramphosus Lacepede, 1803 があってシノニムと判定されたとのこと (#ノジコによく似た事例がある)。和名ではサギフエ属。
この先行用例を指摘したのが Mathews (1911) だったとのこと。つまり Macrorhamphus は現行の学名には現れないにもかかわらず、すでに用いられた属名として無効になった。英名や和名に痕跡を残すことになった。
属名が Macrorhamphus から Limnodromus に変わったことで束縛感がなくなったのか、分離後のアメリカオオハシシギの英名は嘴の長さはそれほど強烈に違うわけでもないにもかかわらず Short-billed Dowitcher とまったく逆の名前になっている。
名前ほど長くないとアメリカでも感じていた人も多かったのでは。
オオハシシギの和名と印象が違うと感じられていた方はある意味正しい (嘴の長い/大きいシギは多種あるのでこれだけに "オオハシ" を付けるのは不自然に感じる)。100 年以上前に無効とされた古い学名とそれに基づく英名に忠実に従った名称を使い続けているためである。
単形種。英名の Dowitcher はイロコイ語 (北米の先住民族の一つ) 由来。Do- は「ドー」と発音する。
Dement'ev and Gladkov (1951) の分布図ではロシア名「西アメリカオオハシシギ」 = オオハシシギはチュコト半島周辺のみに分布となっていたが、Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではもっと広く分布している。
クレチマル・千村 (訳) (1991) Birder 5(7): 27 に北米からシベリアに "アメリカオオハシシギ" が進出しているとの記載に対応するかも知れない (#アメリカオオハシシギの備考参照)。
[オオハシシギの衛星追跡]
Kwon et al. (2025) Strong wintering site fidelity contrasts with exploratory breeding site sampling in a socially monogamous shorebird
アラスカの繁殖地で衛星発信器を付けた個体の追跡。越冬地では同じ場所に執着して戻る傾向が強かったが繁殖地ではそうではなかった。一夫一妻で長距離を渡る鳥ではあまり見られない様式で、繁殖地の年変動が大きく予測困難であることへの適応ではないかと解釈している。
-
シベリアオオハシシギ
- 学名:Limnodromus semipalmatus (リムノドゥロムス セミパルマートゥス) 半分水かきのある足の沼を走る鳥
- 属名:limnodromus (合) 沼を走るもの (limus (m) 沼、dromeas 走るもの Gk)
- 種小名:semipalmatus (adj) 半分水かきのある足の (semi- (接頭辞) 半分の palma (f) 水かき -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Asiatic Dowitcher, IOC: Asian Dowitcher オオハシシギも参照
- 備考:
limnodromus は#オオハシシギ参照。
semipalmatus は#ミズカキチドリ参照。原語義から少し離れ比較的ややこしい。
中国名ではオオハシシギ類は 何とか半蹼鴫 (シギは日本の文字を充てた) とこの種の種小名に基づいている。シベリアオオハシシギは "何とか" が付かないので中国では一番身近なこの種を基本としているよう。
Taxonomy in-flux updates によれば、このフォーラムで新たに解析された分子系統樹ではコシギ (Lymnocryptes 属) とLimnodromus 属の関係が問題となっている。#コシギの備考参照。
さらにシベリアオオハシシギと他のオオハシシギ類の分岐が深く、別属に値する可能性があるとのこと。
これは Cerny and Natale (2022) の系統樹にもすでに現れているが、コシギの従来解析に用いられたデータが誤りで、コシギとヤマシギ類ではなくオオハシシギ類がまとまるならば、この分岐の深さや改めて編成された属内の形態の違いはおそらく議論の対象になるだろう。
別属とみなされる場合はシベリアオオハシシギは Pseudoscolopax 属となる可能性が考えられるとのこと。Pseudoscolopax 属 pseudos 偽の Scolopax ヤマシギ属 の意味なので新しい分子系統解析が確かめられればなかなかふさわしい名前になる。Blyth (1859) がシベリアオオハシシギのみを指して用いた属。
Boyd の最新版 (2024.12.21) ではこの事情を考慮して属を分離。
単形種。
[日本のシベリアオオハシシギの同定経緯]
かつて日本で採集されたオオハシシギ類2標本 (標本はロンドンにあるとのこと) について、学名と種同定に混乱があった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Macrorhamphus griseus の学名でオオハシシギ、場所は Hokkaido, Yokohama とある。
学名別名に Macrorhamphus scolopaceus を載せていた。
高野伸二 (1963) 我国産オオハシシギについて によれば、黒田 (1918) は Macrorhamphus griseus scolopaceus を与えていたにもかかわらず「日本鳥類目録」(1922) ではなぜか Macrorhamphus semipalmatus の学名が与えられてオオハシシギの和名となっていた。
標本が日本にないため (日本鳥学会が目録を作るにあたって) おそらく西方の (亜) 種と判定されたのではないかと推定している。
高野氏は 1955-1962 年日本で観察された個体を検討して、過去に日本で記録されたものは1例を除いて scolopaceus であることを判定しオオハシシギの学名に Limnodromus scolopaceus を用いることを提案した。
Ogawa (1908) は引用されておらず、当時の日本の研究者にもあまり知られていない目録だったのかも知れない。黒田 (1918) はこの学名を引き継いでいたように見える。
また griseus の種小名が長く使われていたのは同種とされていた時代の経緯によるもの (#アメリカオオハシシギの備考も参照)。
現在使われている Limnodromus は Wied-Neuwied, 1833 が提唱したもの (原記載)。属名変更の経緯については #オオハシシギ にまとめた。
Macrorhamphus semipalmatus Blyth, 1848。Jerdon が付けた学名だったが Blyth が記載者となっている。基産地は Calcutta。インドで記載されているので英名の Asian Dowitcher などの方が分布をよく表している。
1972.5.23 高野氏が日本で初の記録を行い、シベリアオオハシシギの和名を提案した
[高野氏自身による経緯の解説は「野の鳥の四季: 高野伸二写真集」(高野伸二 小学館 1974)。「自然読本 野鳥」(河出書房 1983) pp. 122-125 に再録]。
論文は高野 (1972) シベリアオオハシシギ (Limnodromus semipalmatus) の我国への渡来について。
[繁殖分布]
「シベリア」の名が付いているが、他のオオハシシギ類2種が極北で繁殖するのに比べ、この種はユーラシア内陸部ステップ環境や森林ステップの沼地などに繁殖地が点在している。モンゴル、中国東北部にも分布し沿海地方まで分布が及んでいる。しかし全体的にはまれな鳥で繁殖分布範囲もよくわかっていない。
予期せぬ繁殖があったり繁殖地を大きく変えることがある [Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri"]。
和名から受ける印象と繁殖分布は必ずしもよく整合していない。
高野氏が和名を提案した段階の資料は Dement'ev and Gladkov (1951) の分布図に基づくもので、繁殖域の中心はさらに南側であることはまだ知られておらずやむを得なかったと思われる。
#シロハラチュウシャクシギの繁殖分布認識の変遷に似ている。
Melnikov (1998) Population and range fluctuations of Asian
Dowitcher Limnodromus semipalmatus in the central Asian arid zone
はシベリアの繁殖は繁殖域北端で "invasion" と表現している。実際には西シベリアからモンゴル、中国にかけて主な繁殖地が5地域あると考えている。
ステップ地域が中心だがタイガにも広がっている証拠がある: Egorov et al. (2023) Expansion of the Breeding Range of the Asian Dowitcher (Limnodromus semipalmatus, Charadriiformes, Scolopaciidae) into the Tiaga Zone。
Mel'nikov (2023) Dynamics of the Asian dowitcher Limnodromus semipalmatus range - a response of birds of shallow and wet ecosystems to current climate changes (pp. 2557-2567)
にも繁殖地の北進の情報がある。
孫 (2002) (松井訳) Birder 16(6): 50 中国吉林省の向海自然保護区でシベリアオオハシシギが毎年40 羽ぐらいが繁殖しているとのこと。
[渡りと中継地・越冬地の保護]
Yang et al. (2021) Coastal wetlands in Lianyungang, Jiangsu Province, China: probably the most important site globally for the Asian Dowitcher (Limnodromus semipalmatus)
モンゴル東部からの渡り経路追跡: Baldandugar et al. (2023) Autumn migration strategy of Asian Dowitcher (Limnodromus semipalmatus) from eastern Mongolia。
中国の記事 (2023)。
これらの研究から判明した世界のシベリアオオハシシギの個体群のほぼすべてが中継地として利用する江蘇省連雲港市 (Lianyungang) の湿地の開発 (Blue Bay Project) に対して 2021 年に「自然之友」が公益訴訟を行い、2024年1月に開発中断の判決が出たとのこと: (Court Halts Lianyungang's Blue Bay Project)。
インドネシアが最大の越冬地と考えられ、Iqbal et al. (2021) Population Size and Trend of Asian Dowitcher Limnodromus semipalmatus in Banyuasin Peninsula, Sumatra, Indonesia
スマトラ島の南部海岸に越冬地があるが近年では数が非常に減っている。この種に限らず過去 20 年でシギ類が8割減少したと見積もられる。
-
オグロシギ
- 学名:Limosa limosa (リーモーサ リーモーサ) 泥だらけの鳥
- 属名:limosa (adj) 泥だらけの (limosus)
- 種小名:limosa (トートニム)
- 英名:Black-tailed Gotwit
- 備考:
limosa は i, o が長母音で後者にアクセントがある (リーモーサ)。
記載時学名 Scolopax Limosa Linnaeus, 1758 (原記載)。
Limosa 属はこれをもとに Brisson (1760) が導入した。
当時は属が変わる場合に (トートニムを避けるなど) 新名が導入されることがしばしばあり (#ノスリの備考参照)、Limosa melanura Leisler, 1813 (参考)、
Limosa vulgaris Dumont, 1817 (参考) (普通の Limosa の意味)、
Limosa major Brehm, 1845 (参考) (大きな Limosa) のように複数の新名が付けられた。
このうち最初のものが英名・和名と対応しており、この学名または属が変わった Limicula melanura が英名や和名が整理される際に影響を与えたと想像できる。
その後 Linnaeus (1758) の種小名に統一された。
この学名は Dement'ev and Gladkov (1951) でシノニム扱い。
この学名は亜種名に痕跡を残しており、亜種記載の時期 (1846) にはまだ使われていたものと思われる。
Limicula 属は "泥に住む" (limicola の変形) の意味だが、Vieillot (1816) がオグロシギに用い、同じ属名を Foster (1817) がアオアシシギのみに用いた用例がある。
Limosa 属そのものも別のものを指す用例があった [Stephens (1824) アオアシシギ、Boie (1826) アメリカオオソリハシシギ] (The Key to Scientific Names)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Limosa melanura melanuroides の学名でオグロシギの名称がすでに記載されていた。
このように見ると和名は英名や学名起源 (または影響を与えた) ものが結構あるよう。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは melanuroides (オグロシギの過去の学名 Limicula melanura に似た、の意味。melanura は 黒い尾 melanos 黒い -ouros 尾の The Key to Scientific Names) とされる。
英名 Gotwit の語源はよくわかっていない。古英語で godwiht good + wight (生き物) との類似性が指摘されている。鳴き声由来の説もある。
Boyd によるオグロシギ亜科 Limosinae の一覧。IOC や日本鳥類目録改訂第8版と同じ。
シギ科 Scolopacidae オグロシギ亜科 Limosinae
オオソリハシシギ Limosa lapponica Bar-tailed Godwit
オグロシギ Limosa limosa Black-tailed Godwit
アメリカオグロシギ Limosa haemastica Hudsonian Godwit
アメリカオオソリハシシギ Limosa fedoa Marbled Godwit
-
アメリカオグロシギ
- 学名:Limosa haemastica (リーモーサ ハエマスティカ) 血の色のシギ
- 属名:limosa (adj) 泥だらけの (limosus)
- 種小名:haemastica (合) haimatikos 血の (Gk) 胸の赤さを意味する
- 英名:Hudsonian Godwit オグロシギも参照
- 備考:
limosa は#オグロシギ参照。
haemastica 起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-mas- がアクセント音節と考えられる (ハエマスティカ)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
宮崎 (2008) アメリカオグロシギ Limosa haemastica の日本初記録 Strix Vol. 26 pp. 177-180 (日本野鳥の会)。Birder 21(8): 69 (2007) に発見記がある。アジア初記録とのこと。
-
オオソリハシシギ
- 学名:Limosa lapponica (リーモーサ ラプポニカ) ラップランドの泥のシギ
- 属名:limosa (adj) 泥だらけの (limosus)
- 種小名:lapponica (adj) ラップランド地方の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Bar-tailed Godwit (Godwit は#オグロシギも参照)
- 備考:
limosa は#オグロシギ参照。
lapponica は短母音のみで -po- にアクセントがある (ラプポニカ)。学名のみに使われる。
記載時学名 Scolopax lapponica Linnaeus, 1758 (原記載)。
種小名の由来は基産地による。Rudbeck の情報による。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは baueri (オーストリアの自然史画家 Ferdinand Lucas Bauer に由来) 亜種オオソリハシシギ と menzbieri (ロシアの鳥類学者 Mikhail Aleksandrovich Menzbir に由来) コシジロオオソリハシシギ とされる。
Linnaeus (1746) では 記載 (番号 138) と Recurvirostra (ソリハシセイタカシギ) の仲間に分類していた。嘴が上に反った特徴に注目していた。
英名の Bar-tailed の由来があまりよくわからなかったが、Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) によればオオソリハシシギ、オグロシギともに夏羽を指して Red Godwit と呼ばれていたとのこと。1700 年代中期にはすでに使われていたとのこと。
OED によれば 1828 年に Fleming の Bar-tailed Godwit の用例があるとのこと。この時に用いられていた学名が Limosa rufa (赤い、すなわち Red Godwit に対応する)。
この学名の用例は複数あるが最も早いものは Bechstein (1793) (資料 これだけでは何かわからない)。
Dumont の用例は確かにオオソリハシシギを指すとのこと (資料)。
Limosa rufa Leach, 1816 の用例は無効名とある (資料) が、英名 Red Godwit が記されている。
Limosa rufa Forster, 1817 (資料) によれば Scolopax lapponica Linnaeus, 1758 の属を Limosa に変更するにあたって改名された模様 (#ノスリの備考参照)。
Limosa rufa Temminck, 1820 (資料) も用いており、Brisson の学名 (これは無効となった) とのこと。Hartert II (1639) が参考文献に出ている。
当時の雰囲気ではもっと正統的な学名があるので Linnaeus (1758) の怪しげな (?) ラプランド由来ではなく英名に即した学名に変更する流れがあったのかも知れない。
Fleming (1828) が Red Godwit が別のオグロシギも指していることに気づいて英名を整理したのだろうか。オグロシギの現在の英名 (和名にも) に対応する学名が与えられたのが Leisler (1813) なので時代順序は整合している。
オグロシギの方は学名とも関連して Black-tailed Gotwit と概念が分離されたのに伴って、オオソリハシシギは対応する形で Bar-tailed Godwit と整理されたと考えると納得できる感じがする。
英名から整理された思われる中国語名以外に英語に類似する名称がないことから英語特有の事情だったらしいことが想像できる。現在のドイツ語名では Pfuhlschnepfe で Pfuhl (大きな水たまり) のシギになっている。
Hartert (1910-1922) では p. 1639 で、当時は Rostrote Uferschnepfe のドイツ語名の方が先に現れ、英語の Red Godwit に近いが Totanus ferrugineus Meyer, 1810 (参考) の学名の意味よく符合するので、ドイツではドイツ人 Meyer が付けた学名・通称に従っていたものと想像できる。
英国とは流儀が少し違うがどちらも色彩に注目していた点は同じ。ドイツ語 Ufer は岸の意味。
和名のように嘴が上に反っていることを表現した学名やドイツ語名はなかったようだが、Limosa 属の解説 (p. 1636) では軽く反っている (Schnabel sehr lang, leicht aufwaerts gebogen) ことは書かれている。同属のオグロシギとオオソリハシシギで反る程度が異なるので両種に共通の際立った特徴として取り上げにくかったかも知れない。
嘴の反り方ではもっと目立ったソリハシセイタカシギが存在するので、英名などであまり着目点にならなかったのかも知れない。
シギ類の和名が整理されたころはソリハシセイタカシギがそもそも記録されておらず、日本の鳥の範囲ではソリハシシギやオオソリハシシギを "ソリハシ" と呼んでちょうどよいぐらいだったのかも知れない。
ロシア語名ではオグロシギに "大きい"、オオソリハシシギに "小さい" を付けた名称になっており、和名の感覚と異なる。
Limosa uropygialis Gould, 1848 (参考) の学名がありオーストラリアで採集されたもの。Gould の図版。記載は次ページにあり英名 Barred-rumped Gotwit を付けたが、ヨーロッパの Bar-tailed Gotwit Limosa rufa とは似ているが違うと判断していた。
現在ではオオソリハシシギと同種で Limosa uropygialis はシノニムとされる。
ややこしいことに Gould は Numenius uropygialis Gould, 1841 (参考) とシギ類近縁属にも同じ種小名 uropygialis を先に用いていた。こちらはチュウシャクシギを指していた。
オオソリハシシギには Limosa uropygialis Gould, 1848 より早い学名があるので問題が発生しなかったが、同属にまとめられることがあれば preoccupied となっていたケースと考えられる。
最近記述されたばかりの西シベリアの亜種 yamalensis の記載年のついての話題: Latest IOC Diary Updates オンラインの出版物で学名が先に発表されたが公式の ZooBank (ICZN) には登録されておらず、印刷版の 2022 年記載年が正しいとのこと。
海外ではしばしば lapponica group (lapponica/yamalensis/taymyrensis) と baueri group (menzbieri/anadyrensis/baueri)
の区分が使われる: 参考 New unified list of birds - Avilist。
亜種コシジロオオソリハシシギが前者に、亜種オオソリハシシギが後者に含まれる。
分子遺伝学的・亜種分化と渡りの考察は Conklin et al. (2024) High dispersal ability versus migratory traditions: Fine-scale population structure and post-glacial colonisation in bar-tailed godwits
を参照。亜種 menzbieri (コシジロオオソリハシシギ) が中間的な系統 (交雑の結果生じた可能性が示唆されている) となりユーラシア西部と北米およびユーラシア東部が遺伝的によく分離しているわけでもない。氷期サイクルと亜種の分岐年代を関連させて解釈することが可能である。
現状通り亜種扱いが適切なのだろう。無着陸の長距離の渡りで有名なのは亜種 baueri。渡りの一部個体が日本に立ち寄る。
ニュージーランドでもよく研究されていて Genetics of migration timing in bar-tailed godwits: a thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Zoology at Massey University, Manawat, New Zealand (Parody Merino 2018) の学位論文となっていた。
Bom et al. (2021) Central-West Siberian-breeding Bar-tailed Godwits (Limosa lapponica) segregate in two morphologically distinct flyway populations
でも形態的には異なっていても (亜種 taymyrensis) 遺伝的違いは小さく生殖隔離は起きていないことが示唆されていた。
[嘴の形を決める法則]
次の研究で調べられた範囲の種類の中ではオオソリハシシギが例外的な位置のためこの項目に含めておく: Garland et al. (2025) Common developmental origins of beak shapes and evolution in theropods
現生鳥類と化石獣脚類 (theropods) の嘴や口吻の形態を調べたところ、95% の種が power cascade モデルに従っていたとのこと。おそらく脊椎動物に普遍的な法則と考えられる。先端からの距離と厚みの関係 (これがべき乗則に従う。尖りを定量化できる)、アスペクト比をもとに調べたもの。
もう一方の極端な形状にヤツガシラやミサゴ、ダチョウが登場する。ミサゴの嘴の形状はタカ目の中でも特異とのこと。ノガンモドキ類やハヤブサ類もタカ目に似た特性を示す。
ダチョウやカモ類は化石獣脚類に近い位置になるが、ここで挙げた冒頭3種はいずれも遠い位置になりそれぞれ新しく適応進化を遂げたものと考えられる。
嘴は何度も進化したが、これらの数字を見ると現代のこれらの鳥に対応する嘴の使い手は絶滅した獣脚類は存在しなかったのかも。
power cascade モデルは近年提唱されたもので、Evans et al. (2021) A universal power law for modelling the growth and form of teeth, claws, horns, thorns, beaks, and shells を参照。
歯や爪の形にも適用できる普遍的法則とのこと。
-
コシャクシギ
- 学名:Numenius minutus (ヌーメーニウス ミヌートゥス) 小さいダイシャクシギ
- 属名:numenius (合) noumenios Hesychius が記述した鳥で、三日月のような嘴の形からダイシャクシギ類を指すと考えられる [noumenia (伝統的) 新月 < neos 新 mene, menes 月 Gk; 現代的な定義での新月 (= 朔) とは異なる。朔の後最初に見える月のこと]
- 種小名:minutus (adj) 小さい
- 英名:Little Whimbrel チュウシャクシギ参照, IOC: Little Curlew
- 備考:
numenius は由来となるギリシャ語綴りから u, e が長母音と考えられる。-me- がアクセント音節と考えられる (ヌーメーニウス)。ギリシャ語でも同じ位置にアクセントがある。ギリシャ語の mene は e が2つとも長母音 (英語の moon にも対応?)。"new moon" に対応すると思えば発音も納得しやすいし覚えやすい。
minutus は1つめ u が長母音でアクセントもある (ミヌートゥス)。
単形種。
-
チュウシャクシギ
-
ハリモモチュウシャク
- 学名:Numenius tahitiensis (ヌーメーニウス タヒティエーンシス) タヒチのダイシャクシギ
- 属名:numenius (合) noumenios ダイシャクシギ (コシャクシギの項目参照)
- 種小名:tahitiensis (adj) タヒチの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Bristle-thighed Curlew
- 備考:
numenius は#コシャクシギ参照。
tahitiensis は場所の -ensis の冒頭が長母音でアクセントもここにある (タヒティエーンシス)。短母音でもアクセントは移動しないのでどちらでもよい。
原音を考慮して "タヒーティエーンシス" と伸ばしても構わない。
単形種。アラスカの主にユーコン川デルタで繁殖し太平洋の離島で越冬する。BirdLife による個体数見積もりは 10000 で、越冬地での捕食や狩猟により減少中と考えられている。個体数が少ない上に主な渡り経路から離れているため日本での記録は少ない。
[ハリモモチュウシャクの道具使用]
週間アニマルライフ (1972) pp. 2195-2196 のダイシャクシギの項目 (浦本・安部) で紹介があり、南太平洋の島で繁殖中のアジサシ、カツオドリ、グンカンドリの巣をおそい、くちばしで突きさして卵をはこびだし、地面にたたきつけて割って食べる習性が知られているとのこと。おとなしそうなシギ類が、と驚かされる。
wikipedia 英語版を調べてみるとシギ類で唯一知られている道具使用とのこと。日本語版にも別出典で同様の記述があるので文献を調べておくと: Marks et al. (1992) Tool Use by Bristle-thighed Curlews Feeding on Albatross Eggs と何とアホウドリ類の卵も石を投げて割って食べる。
エジプトハゲワシ (#ハチクマの備考 [ハチクマ類の道具使用] 参照) よりも古い系統としては驚くべき。
キョウジョシギが割ったかも知れないアホウドリ類の卵を食べていた観察事例もあるとのこと。
初期の情報は Bailey (1956), Ely and Clapp (1973) があるとのことでいずれも書籍に記述されたもの (探さなかった)。この論文はエジプトハゲワシがダチョウの卵に石を投げて食べる行動が Nature に報告された (1966) よりはだいぶ後の時代で、Ely and Clapp (1973) の記述はエジプトハゲワシの事例を踏まえて書かれているかも知れない。他のシギ類ではなぜ知られていないのか、あるいはハリモモチュウシャクはこのような知的な行動ができるため生き残ったのかなどいろいろ想像させられる。
なお、この解説がダイシャクシギの項目に現れるのはダイシャクシギは英国で繁殖する種類でグループ内で最も馴染みの鳥の一つとして項目に取り上げられたためだろう。
[絶海の離島で越冬する理由?]
太平洋の離島で越冬する渡りの方向感覚には驚嘆させられるが、なぜわざわざ絶海の離島で越冬するのかは猛禽類がいないからではと想像した (繁殖地からそのまま最短距離で南下すれば島にしか到着しないわけではあるが)。
主な越冬地であるタヒチではミナミチュウヒ (Swamp Harrier) のみが記録され、タヒチのリストでは移入種となっている。ハリモモチュウシャクが越冬地に選んだころには捕食者がいなかったのでは?
ミナミチュウヒの離島への分散はおそらく 250-100 万年前ぐらいには起きていて (ニュージーランドの事例から。ミナミチュウヒの分岐年代を考えると 250 万年の見積もりは過大かも知れない)、Numenius 属の分岐年代とまずまず合っている。
ハドソンチュウシャクシギ Numenius hudsonicus Hudsonian Whimbrel のように南米沿岸で越冬する個体群もあったのかも知れないが、沿岸はハヤブサなど外敵も多く生き残らなかったのかも (ただしなぜハリモモチュウシャクは生き残れなかったか理由が必要になるが)。
他のタカ類より外洋への分散に適したチュウヒ類は新しく分岐した系統で、ミナミチュウヒも 100 万年前ぐらい以降に分岐している。
猛禽類の離島への定着は確率的なもので、最初は捕食者がほとんどいなかったが過去 100 万年ぐらいの間に時代を経るごとにだんだん定着した地域や島が増えてきて越冬しにくくなってきたのでは、そして捕食者のいない島のみに残ってゆくともに絶妙な渡りの方向感覚が洗練されてきたとか?
そして猛禽類のいない島で自身が海鳥の巣を襲って猛禽的役割を果たしているのか (!?)。
ハリモモチュウシャクが越冬地で上記の種類の卵を食べることはコンサイス鳥名事典にも示されていたが道具使用まではまだ知られていない段階だった。また渡り前にイチゴなどの植物質も食べると書かれており、この点は#オバシギの繁殖地での驚くべき食性と類似点があり興味深い。
ハリモモチュウシャクはダイシャクシギ類の中で特に離島を越冬地として生き延びたが、潮汐があまり有効でない地域で (#キアシシギ備考の [潮汐の解説] の [補足説明0] の太平洋に於ける潮汐波のアニメーション参照。水深に大きく依存する潮汐波の波長と地形と関係の問題が主な要因)、ダイシャクシギ類の得意とする干潟があまり生じないのだろう。
越冬場所は確保できても食物が不足がちなため、鳥の卵を食べるなどの別解 (知恵) を編み出したのかも知れない (カレドニアガラスが道具を使って食物を捕る賢いカラスとなったのに似ている)。
オバシギも食物の少ない地域で繁殖せざるを得なくなった生態的理由があるのかも。
ハリモモチュウシャクと同じように孤島でも越冬するメリケンキアシシギでそのような話を聞かないのは、岩礁での生活に適応した鳥で、干潟があまりない状況でも食物を得ることができるのだろう。
-
シロハラチュウシャクシギ (IUCN 絶滅種)
- 学名:Numenius tenuirostris (ヌーメーニウス テヌイローストゥリス) 細い嘴のダイシャクシギ
- 属名:numenius (合) noumenios ダイシャクシギ (コシャクシギの項目参照)
- 種小名:tenuirostris (adj) 細い嘴の (tenuis (adj) 細い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Slender-billed Curlew
- 備考:
numenius は#コシャクシギ参照。
tenuirostris は rostrum の o が長母音でアクセントもここにある (テヌイローストゥリス)。#ハシボソミズナギドリやオバシギなどよく現れる種小名。
日本では本州で 1932 年以前に1回 (2羽) の採集記録が残されているが詳細は不明。通常の分布域から大きく外れているために疑問視する見解もある。検証可能な最後の観察記録は1995年2月モロッコでのもの。BirdLife の記事 (日本語版)。
1995 年にイタリアで 20 羽が報告されたが、ダイシャクシギの亜種 orientalis と写真判定された。その後もヨーロッパで散発的な報告があるが確認されていない。
かつてロシアのオムスクで唯一の巣が発見されたが、標本の羽の安定同位体分析から主な繁殖地はもっと南のカザフスタンとロシア南部の草原および草原/森林 (であった) と推定された
[Buchanan et al. (2016) Numenius tenuirostris identified from stable-isotope analysis]。
かつての越冬地も推定される繁殖地も人為的環境悪化が著しい地域で、すでに絶滅したと考える研究者も多い。IUCN では現在絶滅危惧 IA 類にリストしている。
wikipedia 英語版などの一般的情報を見て上記のように記述していたのだが、ロシア語で想像以上に情報があって驚いてしまった。
Ryabtsev (1997) The slender-billed curlew Numenius tenuirostris near the Baikal Lake (pp. 3-4)
1992年8月9-10日にバイカル湖近くの小さな湖で5羽を確認。ダイシャクシギやホウロクシギはよく知っていて上面などが違う。下面には注意していなかった。過去にも記録がありこの地域の迷鳥と位置づけている。
Nanikov (1998) The population of the slender-billed curlew Numenius tenuirostris becomes steady. Monitoring researches are necessary (英文とロシア語要約 pp. 12-15)
絶滅したのではないか、世界で数十羽ではないか、など噂される種類だが 1989-1996 年のブルガリアでは Atanasovsko 湖 (沿岸近くで塩分濃度の高い湖とのこと) で春の渡りで定常的に観察されておりこの時点では減少が止まっていると報告。
Schogolev (2005) On observation of the slender-billed curlew Numenius tenuirostris in northwestern Greece in spring 1997) (pp. 291-297) 1997年4月のギリシャ北西部での観察記録。
Mitropolsky et al. (2012, 2015 再掲) Observations on the migration of the slender-billed curlew Numenius tenuirostris in Southern Kyzylkum in spring 2006 (pp. 3457-3458)。
キジルクム南部ウズベキスタンの Ayak-Agitma [ロシア語で音声表記の一つのようで検索すると Ayakagytma の地名が出てくる。ウズベク語 (テュルク諸語) では Oyoqog'itma botig'i とのこと] 盆地になっていて中央に 15x10 km の塩湖があるとのこと。
この地で 2005 年春の渡りが記録され、2006 年にも同様に記録された。5/1 に始まり最初は 1, 3, 3 羽の3回の記録だったが (同日ダイシャクシギを9羽記録)、5/2 に8回 85 羽 (1-47 羽の集団)、5/3 に4回 54 羽 (5-26 羽の集団)、5/4 に2回 25 羽 (2, 23 羽)、これで観察を終了して翌日移動したとのこと。
ダイシャクシギとは大きさ、嘴、そして特に飛翔時の声で十分区別できたとのこと。両種はしばしば同時に行動していた。最大の群れは夕方 19 時に 47 羽で塩沼で見られたが、翌朝にはいなかった。北方向へ飛んで行ったとのこと。周辺は砂漠で次の休憩地はキジルクム砂漠中央にある 300 km 北側の塩沼と推定され、鳥類学的には事実上調べられていない。
(その後の情報はないが、もしかすると気候変動で砂漠になっているかも知れない...)。
いずれの文献も写真はない。
Wassink (2016) Status of Slender-billed Curlew in Central Asia はこの報告は検証可能なデータがなく疑わしいとしている。文献リストだけを見るとそのまま受け入れてしまいそうだがぜひ原文に当たってみて欲しい。
中東の OSME (2015, 2019) は 21 世紀に記録がなく絶滅したと考えている: Is the Slender-billed Curlew extinct?。
しかし 2017 年には目撃記録を求めていた: Searches for slender-billed curlews by volunteer birders benefits conservation。
Mitropolsky et al. (2012) で報告された環境は極めて特殊で、あるいはどこか人里離れたところで生き残っていないかロマンが残る。Mitropolsky et al. (2012) を検討した資料は声の違いは重要視していないようだが、後述 Ryabitsev も声の違いは気にしている。
Ushakov (1909, 2001 再掲) The slender-billed curlew Numenius tenuirostris Vieill. (pp. 492-495) 1902 年のバルナウル (シベリア中央部でカザフスタン国境に近い) での巣の発見報告の再掲。
Ushakov (1916, 2002 再掲) Nest and eggs of the slender-billed curlew Numenius tenuirostris Vieill. (pp. 426-427)
1914年5月9日に Kraspoperovaya 村 (Tara, Tobol'sk, Omsk の南) の採集者がメス、巣と4卵を持ち込んだので記述した。地元では piskuna の名前で呼ばれていた鳥とのこと。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) にも 20 世紀初頭まではステップ、森林ステップ、タイガ南部で繁殖していた。多彩な声について十分な記載がないが、シベリアの猟師は声から piskunchik の名前で呼んでいたとのこと。
分布は ? で表してある。
かつてはこのぐらい広範に分布していて 20 世紀初頭にバイカル湖周辺でも記録されるぐらいならば、日本に過去の迷行があっても不思議でない印象を受けた (近縁のダイシャクシギの繁殖分布も参照。カラフトワシの分布や分布縮小経緯にも似ている感じがする)。
この卵については Bond and Buchanan (2022)
Eggs of the 'lost' Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris で記述されている。
Hartert (1910-1922) では p. 1645 で、この巣と卵についての言及もある。1909 年までは繁殖地は知られていなかった。1910 年の記述に基づくもので、Hartert のこのシリーズにちょうど間に合った時期にあたる。それまではどのような地域が想定されていたかなど記述もあり、興味ある方には面白い情報であろう。
インドネシアの記録で多少類似点があって議論された写真: Hilda (2020) An unusual Eurasian Curlew Numenius arquata orientalis in Banyuasin Peninsula, South Sumatra, Indonesia。
日比 (1995) Birder 9(7): 80-81 にモロッコで珍鳥として記録されていた時代の現地での行為にまつわる記事があった。当時はモロッコのメルジャ・ゼルガ (Merja Zerga) が世界で唯一知られる定期的越冬地で、多数の海外バーダーが訪れていた模様。1980 年代初頭は数羽だったが、1994-1995 年のシーズンは1羽のみだったとのこと。
現存する唯一の動画記録 (1994、モロッコ; それらしい鳥を見かけた場合の連絡方法なども記されている) と 1990 年に記録された 音声記録 が公開されている。
1994 年のビデオはメルジャ・ゼルガで記録された最後の1羽だったことになる。
日比 (1995) Birder 9(11): 77 に 1994-1995 年のシーズンにイタリアで越冬したとされる報告に関するコラム記事がある。
さらに日比 (2001) Birder 15(6): 36-37 にハンガリーのキシュクンサク国立公園 (Kiskunsag National Park) で 2001.4.15 で目撃した事例が紹介されている。
この事例は Observation of Slender-billed Curlew in Hungary (2001) (Saker Tours) で紹介されている。嘴の折れたダイシャクシギの可能性があるとしてこの報告は 2002 年当初は認められなかったが、2005 年に 21 世紀最初の目撃事例として確認されたとのこと。
Olah and Pigniczki (2010)
New Hungarian record of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in the Kiskunsag (Hungary) が論文。ビデオは Yoshio Ebihara [海老原美夫。人名表記は日比 (2001) による] が撮影。
DNA 解析でダイシャクシギに最も近いが独立種であることを確認した研究 [Sharko et al. (2019)
Phylogenetic position of the presumably extinct slender-billed curlew, Numenius tenuirostris]。
同様に長期間記録がないシギにエスキモーコシャクシギ Numenius borealis 英名 Eskimo Curlew があり、1963 年に撃たれたものが確実な最後の記録。その後も不確かな目撃報告はあったが途絶えている。
Audubon は絶滅宣言を出すべき時期かとの記事を出している。
Tan et al. (2023) Megafaunal extinctions, not climate change, may explain Holocene genetic diversity declines in Numenius shorebirds
の標本を用いた最新の DNA 解析によれば Numenius 属は最終氷期が終わった直後 (約2万年前) から実効個体数を減らし始めていた (近年の減少はまだ反映されてない)。
人間活動が顕著になる以前のことで、メガファウナの動物がツンドラ地域を生息に適した環境に保っていたものが絶滅したためではないかと推測している
(メガファウナについては #カンムリワシ備考の [メガファウナの絶滅] も参照)。
問題の2種が絶滅していれば curlew clade (英名とは対応しておらず系統上のクレード名 #ダイシャクシギ備考の分類参照) の多様性の4割をすでに失ったことになる。
メガファウナの絶滅要因、この系統のすべての種が減少していることを考えると見通しがあまり明るくないグループかも。
[絶滅宣言 (2024.11)]
Buchanan et al. (2024) Global extinction of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) (2024.11.17 発表)
1995 年以降確実な目撃なし。IUCN の絶滅確率モデルで 96.0% の確率で絶滅。IUCN の基準に従い絶滅種とする。
New publication indicates devastating extinction of the Slender-Billed Curlew (BirdLife 解説 2024.11.18)。
Wake-up call as Slender-billed Curlew confirmed likely extinct (RSPB 2024.11.18 英国繁殖のダイシャクシギも危機的状況のため注目度が高い)。
Bird thought to be extinct is first recorded case in mainland Europe (BBC 2024.11.20/21)
島の固有種などの絶滅とは異なり、広域に生息していた種が絶滅したことは重要な意味がある。
ヨーロッパ大陸部で初の絶滅種となった。
-
ダイシャクシギ
- 学名:Numenius arquata (ヌーメーニウス アルクワータ) 弓状に嘴の曲がったシギ
- 属名:numenius (合) noumenios ダイシャクシギ (コシャクシギの項目参照)
- 種小名:arquata = arcuata (adj) 弓状に曲がった (arquatus)
- 英名:Curlew
- 備考:
numenius は#コシャクシギ参照。
arquata は arcuata の別綴りで同じもの。最初の a が長母音でアクセントもここにある (アルクアータ)。arquata の綴りを尊重すれば w の音を添えるとよい (アルクワータ)。こちらを採用した。
arcuata は arcuo (弓のように曲げる。arcus 弓) の過去分詞で所有の -ata ではない。
後述の arquatus 由来の場合でも発音は同じ。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは orientalis (東洋の) とされる。
種小名は通常上記のように解釈されるが、ラテン語で黄疸を意味する arquatus morbus の可能性があるとのこと。皮が虹の黄色に変わるとの言い伝えがある (The Key to Scientific Names)。
arquatus には "虹色の" の意味がある。
[ダイシャクシギ亜科の系統分類]
Boyd による ダイシャクシギ亜科 Numeniinae の一覧を挙げておく。このグループの分類は IOC や日本の分類と同じ。その後ダイシャクシギ属 Numenius は #シロハラチュウシャクシギ備考の Tan et al. (2023) の分子系統樹に従って clades を追加、順序も調整してある。
属は分割されていないが、チュウシャクシギ系統 (whimbrel clade) と ダイシャクシギ系統 (curlew clade) に分けて考えるのが地理分布や保全上もわかりやすい。"チュウシャクシギ" の名くシロハラチュウシャクシギや "コシャクシギ" の名がつくエスキモーコシャクシギがなぜ (たぶん) 絶滅してしまったかなど理解しやすい。
シギ科 Scolopacidae ダイシャクシギ亜科 Numeniinae
マキバシギ属 Bartramia
マキバシギ Bartramia longicauda Upland Sandpiper (北米で繁殖し南米に渡る)
ダイシャクシギ属 Numenius
(whimbrel clade)
コシャクシギ Numenius minutus Little Curlew
ハリモモチュウシャク Numenius tahitiensis Bristle-thighed Curlew
チュウシャクシギ Numenius phaeopus Eurasian Whimbrel
ハドソンチュウシャクシギ Numenius hudsonicus Hudsonian Whimbrel
(curlew clade)
アメリカダイシャクシギ Numenius americanus Long-billed Curlew
エスキモーコシャクシギ Numenius borealis Eskimo Curlew
ホウロクシギ Numenius madagascariensis Far Eastern Curlew
ダイシャクシギ Numenius arquata Eurasian Curlew
シロハラチュウシャクシギ Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew
[ダイシャクシギの亜種]
基亜種 arquata (ダイシャクシギ分布域の西部)、orientalis (ダイシャクシギ分布域の東部 "Oriental Curlew")、
suschkini (南部亜種でカザフスタンのステップで繁殖)。
Oriental Curlews in Western Europe: identification and status (Rodriguez and Gil-Velasco)
によれば orientalis はこれまでのところ西ヨーロッパでは記録されていない。アフリカで越冬するものは大部分中央アジアから来ているとあり、orientalis は西ヨーロッパにも来ているのではないかと考え、スペインで調査したもの。
suschkini は orientalis と似ていて小型とされるが単に緯度の違いを反映していて独立のタクソンなのか疑問も湧いてきたとのこと。
スペインで記録された "Oriental Curlew" に似た個体がシロハラチュウシャクシギの可能性があるのか検討できる資料は持ち合わせていない。
2016 年モザンビークで再発見された "Steppe Whimbrel" Numenius phaeopus alboaxillaris (チュウシャクシギの亜種) の事例を思い出そうとのこと。シロハラチュウシャクシギもまだあきらめていない。
この著者は識別点の考察とともに、ダイシャクシギの北部個体群を分布と渡り習性から4タイプに分け (suschkini は不明で含まれていない)、"Birds of the World" をもとに推定越冬地分布を記している。
これによればアフリカ北部沿岸で越冬するものはシベリア西部 (Central Asian Curlew) にあたり、orientalis はより長い渡りを行い、アジアからアフリカにかけてより南部で越冬することになる。マダガスカルで越冬するのはヨーロッパのものではなく "Oriental Curlew" との描像になる (個体追跡などで明らかになっているものかどうかは知らない)。
これを見ると "Oriental Curlew" に関連の深いホウロクシギがマダガスカルで記録されていても驚かないかも知れない (#ホウロクシギの学名検討参照)。
Tan et al. (2019) Population genomics of two congeneric Palaearctic shorebirds reveals differential impacts of Quaternary climate oscillations across habitats types
の分子遺伝解析では3系統に分けるのが妥当で (既存の亜種分類とも整合する)、suschkini と orientalis の間が最も離れているとのこと。
[英国ダイシャクシギの減少]
Bowgen et al. (2022) Curves for Curlew: Identifying Curlew breeding status from GPS tracking data
英国で繁殖するダイシャクシギの GPS 遠隔データから繁殖状況を調査したもの。
行動記録から繁殖成功の状況が判断できて巣の日々の生存率が 93.5% と低く、ごく一部の個体しかひなを育てることができていない。繁殖成功率の低下が近年の個体数減少に関係していると考えられる。非繁殖個体の割合も 26% と高い。
Ewing et al. (2023) Nest survival of threatened Eurasian Curlew (Numenius arquata) breeding at low densities across a human-modified landscape
も繁殖成功率の低下を問題としており、防御用の柵も用いて増やす試みが行われている。巣の主な捕食者はアカギツネとのこと。
Zielonka et al. (2019) Placement, survival and predator identity of Eurasian Curlew Numenius arquata nests on lowland grass-heath
にも情報がある。
Baines et al. (2022) Lethal predator control on UK moorland is associated with high breeding success of curlew, a globally near-threatened wader
個体群の source となっている重要地域で捕食者数を積極的にコントロールする必要性を提案。
Eurasian curlew recovery (WWT) 英国は世界の個体群の 1/4 を占めている。1970 年に比べて繁殖個体数が 65% に減少。寿命が長いので一見あまり減っていないように見えるがひなが見られなくなっている。
草原やヒースが乾燥してきている要因もあるが、捕食者の密度が高いとのこと。現在英国で最重要の保護対象種となっている。卵を採取して人工繁殖し、再産卵を促すなどの試みも行っている。
-
ホウロクシギ
- 学名:Numenius madagascariensis (ヌメニウス マダガスカリエーンシス) マダガスカルのダイシャクシギ(誤命名?)
- 属名:numenius (合) noumenios ダイシャクシギ (コシャクシギの項目参照)
- 種小名:madagascariensis (adj) マダガスカルの (-ensis (接尾辞) 〜に属する) セレベス島の Makassar をマダガスカルと間違ったものと解釈されている
- 英名:Far Eastern Curlew
- 備考:
numenius は#コシャクシギ参照。
madagascariensis は場所を表す -ensis の冒頭が長母音でアクセントもある (マダガスカリエーンシス)。短く読んでも構わない。
madagascar はフランス語由来で特に長音の入る要素はない。
madagascar そのものもマルコ・ポーロによるアラビア語の誤読とのことで。12 世紀には非常に不正確な地図が描かれていた。Malai は現代のマダガスカルとインドネシアの島 (スマトラ島など) 両方を指していたことがあったと考えられる。またマダガスカルへの2度めの入植に際してマレー出身者も含まれており言語的には一層ややこしくなっているとのと。
マダガスカルの言語名は Malagasy と表記され、古い表記では Malegass と Madegass の2つの方言に分けた用語が使われていたとのこと (wiktionary)。
セレベス島の Makassar に限らずもっと広い範囲でマレーやインドネシアの島と混同されていた可能性もあるのかも。
かつては madagascariensis の種小名を持つ種類が日本のごく近くに存在した。Hypsipetes madagascariensis Madagascar Bulbul の亜種とされていた時代の台湾の Hypsipetes leucocephalus nigerrimus 種英名 (Himalayan) Black Bulbul。
同種時代は台湾からマダガスカルまで広域分布する種で和名クロヒヨドリ。マダガスカルで記載されたものが最も早くこれが基亜種となったため。
単形種。ロシア極東やカムチャツカを繁殖地とする分布域の狭い種類。
原記載 によれば Brisson がこの学名を用いている。
Brisson (1760) Le Courly (= Courlis) de Madagascar がマダガスカルを生息地としており、Linnaeus (1766) がそのまま用いた。Brisson の学名は無効 (書物が二名法に則っていない) とされ、Linnaeus (1766) が記載者となっている。
しかし属の Numenius は Brisson (1760) が有効とされていて、これは Brisson (1760) による新規の属で属記載が存在するためらしい (#ハシグロアビの備考参照)。
Buffon (1783) "de Histoire naturelle des oiseaux" に Courly de Madagascar の絵がある。
The Key to Scientific Names によれば誤って madagascariensis の付いた学名は他にもいくつもあり、古くは地名の混同が激しかった模様。
Dement'ev and Gladkov (1951) を参照すると、Oscar Neumann (おそらく) (1932) の考えによれば、インドネシアのセレベス Makassar (マカッサル) を指すのではとのこと。
"Bemerkungen ueber neue und ungenuegend bekannte Rassen palaearktischer Voegel" Ornithologischer Anzeiger 2(4): 145-150 が該当しそうだが調べた範囲では公開されていない。
Linnaeus が正式に記載を行っているためかつて使われていた Numenius cyanopus Vieillot, 1817 (基産地 New Holland で一般的にはオーストラリアとされる) はシノニムとなるとのこと。
Vieillot (1817) Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquee aux arts, a l'agriculture, a l'economie rurale et domestique, a la medecine, etc では "マダガスカル" で記載されたものとは別種としてリストしている。
"Fauna Japonica" にも日本の鳥として現れる Fauna japonica, sive, Descriptio animalium, quae in itinere per Japoniam, jussu et auspiciis, superiorum, qui summum in India Batava imperium tenent, suscepto, annis 1823-1830 (図版)
ここでは Le Grand Courlis Oriental (東洋の大きなダイシャクシギ) または Le courlis du Japon (日本のダイシャクシギ) Numenius major でスマトラとボルネオの2個体を得たとして紹介されているが、Gould によるオーストラリアの Numenius australis とも合うとのこと。
なお Numenius major の学名はすでに使われており、Nvmenivs major Stephens, 1824 (参考 = ダイシャクシギ)、
これは Nvmenivs = Numenius 属を分離して設けられたもので、種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる (#ノスリの備考参照)。
種小名から属名に昇格する場合に種小名を変える必要がないとなって現在の学名になったものだろう。
madagascariensis の方が先に命名されていたため表立った問題とならなかったが、Numenivs major Temminck & Schlegel, 1849 は無効だった。
同時に記載された Numenivs minor Temminck & Schlegel, 1849 (図版) はコシャクシギで、Temminck and Schlegel は東洋の大小のダイシャクシギを意図して命名したが、こちらも Numenius minutus Gould, 1841 の学名の方が早く、どちらも残らなかった。
同様に Temminck and Schlegel が日本産の鳥を major, minor とセットで記述した例ではヘラサギとクロツラヘラサギがある。#クロツラヘラサギの方の学名は残った。
Numenius cyanopus の学名は特にオーストラリア (現地名で Australian Sea Curlew など) で使われていた: 参考例 1。参考例 2 (1930 年代でも使われていた)。
基産地からはこちらの学名の方がふさわしかったわけだが、同じものと同定されて先に命名されていた学名が有効になったらしい。
Colonel and Legge (1889) によれば当時は Eastern (or Asiatic) Curlew Numenius lineatus (Cuvier)、Australian Curlew Numenius cyanopus の名前が使われていた。
計測値などから Eastern (or Asiatic) Curlew とヨーロッパのダイシャクシギは異なると言える。
当時はヨーロッパのダイシャクシギはあまり渡りをしないとされていて、Eastern (or Asiatic) Curlew はインドシナ、ジャワ島、ボルネオ島に渡るがアフリカ東部にも渡り、南アフリカにとどまる (オーストラリアでも越冬地で繁殖期に渡らずとどまることも多い) ことも知られているとのこと。
オーストラリア・ニュージーランドで越冬する Australian Curlew と分布が重なるが繁殖地は違うと考えていたらしい。
当時の知見では Eastern (or Asiatic) Curlew は分布が広く、アフリカに渡っていると考えられていた模様。マダガスカルとは全然関係ないように見えるが、実は渡っていたと考えても不思議ではなかったかも
(この記事にはマダガスカルのことは現れないので madagascariensis の記載があることに気づいていなかったのか、あるいはこれらの東部グループとは別と考えていたのだろうか)。
Rufescent Curlew Numenius rufescence Gould, 1832 なる別の学名もあって Rufescent Curlew, Numenius rufescens, Gould
日本の Numenius major とは違ってオーストラリアの Numenius australis と合うなどの話も出てきてややこしい。
Eastern Curlew の名前はオーストラリアでホウロクシギを指して現在でも使われている: Numenius madagascariensis: Eastern Curlew。
当時ダイシャクシギグループに多彩な学名が付けられ、越冬地や繁殖地で名付けられたものなど、どれとどれが同じなどの議論がなされていた。我々はその議論を見ていないので現在の分類だけを見て madagascariensis が唐突に感じるだけかも知れない。ダイシャクシギはマダガスカルでも記録されるので誤命名と単純には言い切れないような気もしてきた。
[日本での記載と和名について]
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Numenius cyanopus Vieillot の学名で Horokushugi と当時からホウロクシギの和名があったことがわかる。別学名に Numenius australis, Numenius major, Numenius tahitensis が示され、産地は Hakodate, Yokohama となっていた。
"Fauna Japonica" の図版は 図版 で Numenius major が使われていた。Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば Temminck and Schlegel の本文記述 記述 はダイシャクシギを指しているとのこと [Seebohm (1890) pp. 315-316]。Swinhoe collection に Hakodate から3体、Pryer collection に Yokohama から5体の標本があるとのこと。
Temminck and Schlegel のフランス語名は Le grand courlist oriental で、この小型版に相当する Le petit courlist oriental (Numenius minor) も同時に日本の標本から記載したため学名に "日本の" は入らなかったものと思われる (もし用いていても先取権はなかった)。
この Numenius minor 図版 はコシャクシギのこと [Seebohm (1890) p. 317] で、こちらも先取権はなかった。コシャクシギとダイシャクシギまたはホウロクシギを比較したらしいが、本文はダイシャクシギ、図版はホウロクシギを指していた模様。Temminck and Schlegel は日本にもダイシャクシギが存在することはおそらく知らなかった。
Ogawa (1908) はおそらくこの記述をそのまま採用したものと想像できる。この時点では海外標本以外には国内の確実な事例がなく、国内で新たに得られた標本以前に和名が付けられたらしい。
山階鳥類研究所の標本データベースでも YIO-03727 (静岡 1906) の標本ラベルの学名は新しいもので後から付けられたものらしい。後に種名が同定されたものではないだろうか。
YIO-03723 (東京 1883) は古いラベルが2つあって1枚はダイシャクシギの学名、もう1枚は Numenius cyanopus Vieillot とあるものの大シャクシギとあり (上から訂正されている)、当時は和名が統一されていなかったことがわかる。
YIO-03724 (千葉 1883) や YIO-03725 (千葉 1883) も同様。
YIO-03726 (対馬 1891) はダイシャクシギの学名があるが古いラベルには和名なし。これらのラベルも整理された際に付けられたものかも知れない。
これらから判断すると、文献から2種あることは認識されていたが具体的にどの鳥であるかはまだ明瞭でなくダイシャクシギと混同されていた期間が長かったと想像される。
大橋 (2022) Birder 36(12): 56-57 では食材として台所に置かれたものを焙烙に見立てた考察が紹介されているが、鳥学者の間ですら身近な鳥ではなく標本を見てもダイシャクシギとホウロクシギが区別されていなかったようで、食材説は考えにくい気がする。
Seebohm (1890) に記述があり、"Fauna Japonica" の図版があるので日本産種であることは間違いなく学名もはっきりしているが、具体的にどの鳥を指すのかはまだ明確でなく、"Fauna Japonica" の図版を見てホウロクシギの和名が与えられたのではないだろうか。
ダイシャクシギとホウロクシギを明瞭に区別できなかった理由は Temminck and Schlegel の本文記述がダイシャクシギを指していたためとも考えられる。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 135 では素焼きの焙烙色によります、とある。色彩をもとにするのは比較的知られた由来説と考えるが、"焙烙色" という色があるのか確認しておく必要がある。調べた範囲では見つからなかった。大橋 (2022) によれば「物品識名」(1802) に「ほうろくしぎ」が登場するらしいが、現代のホウロクシギと同一かどうかはわからないだろう。
"素焼きの焙烙色" はこちらを指した意味かも知れない。色彩だけからは別のシギを指したものでも不思議でない感じがする。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば重訂本草綱目啓蒙 (1847) にしゃくしぎ3種、大杓しぎ = だいさくしぎ、中杓しぎ = つるしぎ、そりばししぎ = 小つるしぎ の名称が現れ、現代の名称とは必ずしも対応しておらず、時期的にも海外からの文献が入ってから整理されたものと想像できる。
ホウロクシギはいずれにしても新しい名前で、海外からの文献が入って整理する形で与えられたのだろう。
"Fauna Japonica" の図版と本文の記述の不整合を指摘したのは Seebohm (1890) だったので、それ以前の段階ではホウロクシギの図版を見てダイシャクシギと判断せざるを得なかった。
Seebohm (1890) には多数の種が紹介されていて、日本にそれほどたくさんの種類のシギがいるのかと困惑したであろうことが想像できる。1847 年に使われていた名前を活かすとダイシャクシギ、チュウシャクシギを使うことはできたがツルシギとの区別は曖昧。ソリハシシギもこの名前を活かすことができたが、コシャクシギは新たに与える必要があった。ここで "Fauna Japonica" の2種をダイシャクシギ、コシャクシギとすれば学名やフランス語名ともうまく整合するのでまずはこの名称が採用されたものだろう。
しかし "Fauna Japonica" の図版がダイシャクシギと別物であることが判明して新たに名前を付ける必要が生じ、"杓" から連想して取っ手の長い焙烙に見立てたのだろうか。
和名由来を検討される方は目の前のホウロクシギよりは "Fauna Japonica" の図版を参照いただきたい。長く伸びた首の解釈はおそらく違う。嘴または当時使われた別学名の由来となった青っぽい足以外の特徴は難しいと思う。嘴が第一候補と思うが、青っぽい足に見えるかまどがあって焙烙を乗せるとちょうど図版のように見えたのかも知れない。
[その他]
シブネフ (2000) Birder 14(10): 20 に抱卵中のホウロクシギの写真がある。
植田 (2019) Birder 33(9): 30-31 に「ホウロクシギの不思議な渡り」の記事がある。越冬地からの追跡で渡りを途中で止める個体があることがわかった。北半球の繁殖期にも 20-30% の個体が残るとのこと。前述 Colonel and Legge (1889) でも越冬地 (越冬時期の現地は夏だが "wintering" の用語を使わざるを得ない) にとどまる個体がかなりあることが紹介されている。
-
ツルシギ
- 学名:Tringa erythropus (トゥリンガ エリュトゥロプース) 赤い足のクサシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 < trungas アリストテレスが記述したツグミ大の腰の白い渉禽で尾を振る。具体的には同定されていないが、シギ、セキレイ、カワガラスのいずれかと考えられた (Gk)
- 種小名:erythropus (合) 赤い足の (erythro- (接頭辞) 赤い pous 足 Gk)
- 英名:Spotted Redshank
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
erythropus は -pus が足の意味のギリシャ語由来で長母音。アクセント音節は冒頭と考えられる (エリュトゥロプース)。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) によれば英語別名に Martin Snipe があるとのこと。この Martin は House Martin (ニシ)イワツバメ のことで、(ニシ)イワツバメをそのまま大きくしたような色彩に見えるためとのこと。
単形種。
Scolopax erythropus Pallas, 1764 が初記載とされる。
Linnaeus (1758) の Scolopax fusca (記載。産地アメリカ) は Tantalus fuscus (1766) そして
Guara rubra と同定され (Linnaeus 1758 の同じページにあり) 最終的にショウジョウトキ Eudocimus ruber となったとのことでツルシギと同一ではなかった。
Linnaeus がツルシギを Scolopax fusca と記述 (こちらは産地ヨーロッパ沿岸) したのは 1766 年で、Pallas (1764) の方が早かった。
Richmond (1905)
Notes on the Birds Described by Pallas in "Adumbratiuncula" of Vroeg's Catalogue の同定による。
Linnaeus は同じ学名を別のものを指して 1758, 1766 年に使っていたことになる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" は Richmond (1905) の同定はまだ知らず、Totanus fuscus (Linn.) の学名を用いていた。意外にも他学名は存在しないようで紛らわしい種が少なくてあまり混同が起きなかったのだろうか。
Boyd では Totanus erythropus。
英名の Spotted Redshank は Common Redshank (アカアシシギ) と対比したもの。ツルシギの学名の方が Redshank とよく合っている。
ロシア名 shchegol' も赤い足に注目しており、shchegolyat' (着飾る) に由来するとのこと (Kolyada et al. 2016)。Kolyada et al. は足しか述べていないが夏羽の他部分の色彩も含めた名称だろう。英語だと ornate などに相当しそう。
他言語では長く使われた古い種小名 fuscus が生きているものが多く、灰色や煤色のなどの形容が多くおよそ似つわしくない。ウクライナ語やセルビア語は「黒い」を用いている。フランス語は Chevalier arlequin = harlequin と道化役者の意味。#シノリガモと同様の発想。
現在の和名とロシア語が容姿に対応するよい名前を与えているが、#ホウロクシギの備考 [日本での記載と和名について] にあるように旧名のつるしぎは中杓しぎと同義で、現代のツルシギを指していたかどうかは不明。並びを見ると嘴の長さを指したもので、現代のツルシギの容姿をツルにたとえたというよりは、ツルハシの意味だろう。
[繁殖様式]
Dement'ev and Gladkov (1951) によればロシアでも春の渡りは早いそうで沿海地方で 3/12、気温がまだ -12 ℃ での記録があるとのこと。ほとんどの渡りは5月初めには終わっている。
なぜ早いのか調べてみたが意外なほど情報がない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) でも繁殖生態はあまりよく調べられていないとある。初期はオス・メスが交互に抱卵し、その後メスは去ってしまってオスが世話をするように見えるが、ペアによって違うかも知れないと書かれている。歩くひなを連れているのはオスしか知られていないとのこと。
危険を感じると非常に攻撃的な態度を示し、巣から先に離れて人の目を狙って飛ぶなど模擬攻撃を示すこともある。
夏にはツンドラ以外でも中緯度地域で出会うこともあるが、おそらく非繁殖の1年に満たない個体で、オスを残して北からやってきたメスと合流し、その後繁殖を終えたか繁殖に失敗したオスがやってくる、その後若鳥がやってくるとのこと。
夏の終わりには繁殖域のさらに北側の北極圏沿岸で秋羽の個体に出会うがこれらは非繁殖の若い鳥か成鳥ではないかとのこと。
-
アカアシシギ
- 学名:Tringa totanus (トゥリンガ トタヌス) アカアシシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 種小名:totanus totano アカアシシギ (伊)
- 英名:Redshank, IOC: Common Redshank
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
totanus は下記参照。母音の長短や音節区切りも不明。to-ta-nus と区切ってすべて短母音ならば "トタヌス"。
6亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは ussuriensis (ウスリーの) とされる。
Boyd では Totanus totanus。
かつて使われた (今後復活する可能性もある。もし復活すれば上記のようにタイプ種のアカアシシギの学名は簡単なものになる) 属名 Totanus で過去の文献の至るところに現れる学名であるが、totano の起源は今ひとつわかっていない。wiktionary でベネチア語の totano を見ると由来はラテン語の totanus とあって、どちらが先かわかっていないよう。
イタリア語の totano には別の意味があってイカの European flying squid Todarodes sagittatus を指すとのこと。由来関係はわからないが何か関係あるのかも知れない。ルーマニア語 (ラテン系言語) では古ギリシャ語の tefthis, tefthos との関係が示唆されている (これはイカを指すよう) が、アカアシシギの方は語源不明となっている。
[種学名の問題]
Scolopax Totanus Linnaeus, 1758 の原記載。古くから Totanus と呼ばれていたものをそのまま用いた模様。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Totanus calidris (Linn.) となっていて (和名別名アカガネシギ)、
1766 の方を指しているよう。この文献では Scolopax Calidris と Scolopax Totanus が並んで出てきて嘴が赤っぽく足が赤とあるのでこれが最初に同定できる記載として扱われていたのだろう。
Linnaeus は 1758 年と 1764 年で Scolopax Totanus に異なる記載を与えていた。1758 年の方は足がスカーレット色、1764 年は黒っぽい。1758 年の方は Fauna Svecica (1746) の対応する番号 149 を与えていたが、1764 年には外し、Scolopax Calidris に 167 を与えている。
このような問題点から Scolopax Totanus の学名には問題ありと判断されて Scolopax Calidris の方が採用されていたのかも知れない。
Totanus calidris の学名は十分長く使われていて、1967 年でも用例を見つけることができた。
解消された詳しい経緯は不明。Dement'ev and Gladkov (1951) は Tringa totanus の学名を採用し、シノニムに Scolopax Calidris を挙げているが名称の正当性が確認できないとある。Linnaeus 自身がこの学名でアオアシシギを記述しているとあるので関係があるかも知れない。
[亜種の問題]
亜種 ussuriensis の Avibase の文献名は多分正しくなく、"Polnyj Opredelitel' Ptits SSSR" (Buturin 1934) p. 88 にあった。標本採集地はサハリンの Chajvo。
Dement'ev and Gladkov (1951) は亜種 eurhina, ussuriensis, terrignotae, aralensis をすべて totanus のシノニムとしている。aralensis は世界のリストにも出てこない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではシベリアの亜種はすべて ussuriensis としている。
単形種にまとまっていないのは、Tavares and Baker (2008) Single mitochondrial gene barcodes reliably identify sister-species in diverse clades of birds
の研究があって、COI を用いた DNA バーコディングでアイスランドとベトナム、オーストラリアの間で多少の違いが見つかったことが理由 (の一つ?) のよう。
Baker et al. (2009) Countering criticisms of single mitochondrial DNA gene barcoding in birds、
Kerr et al. (2009) Filling the gap - COI barcode resolution in eastern Palearctic birds
に一覧が出ているが、ユーラシア東西での違いが調べられた種の中でアカアシシギが一番小さかった。次に小さいのがトラフズクでこれはユーラシアの大陸内では単一亜種となっているので、アカアシシギは単形種でもよいように思える。少なくとも6亜種も必要ないだろうと考えるのが自然に思えるが、調査されていない地域が多く、遺伝情報もごく限られたものしか使っていないのでそのまま残しているのが現状だろうか。
[ヒマラヤを越える渡り?]
Li et al. (2020) Shorebirds wintering in Southeast Asia demonstrate trans-Himalayan flights
東南アジアで越冬するアカアシシギとチュウシャクシギの一部がヒマラヤを越えている可能性を示す証拠。
シギ・チドリ類では初めての事例とのこと。
-
コアオアシシギ
- 学名:Tringa stagnatilis (トゥリンガ スターグナーティリス) 池にいるクサシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 種小名:stagnatilis (adj) 池にいる (stagnum 池 -atilis (接尾辞) 〜に住む)
- 英名:Marsh Sandpiper
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
stagnatilis は "池" の意味の stagnum は a が長母音。-atilis の接尾辞で語構成されたとすればこの a も長母音でここにアクセントがある (スターグナーティリス)。-atilis の長音は -atus に由来。stagnum は英語で古くラテン語と同じ意味で使われたが他言語も含めて関連語はほとんど残っていないよう (wiktionary)。
単形種。
Boyd では Totanus stagnatilis。
-
アオアシシギ
- 学名:Tringa nebularia (トゥリンガ ネブラーリア) 霧のようなクサシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 種小名:nebularia (f) 霧の (nebula (f) 霧 -arius (接尾辞) 〜に属する。質を表す、の女性形)。命名当時のノルウェー名意味から。色彩の特徴 (または生息環境) を意味していたと考えられる。
- 英名:Greenshank, IOC: Common Greenshank
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
nebularia は nebula は短母音のみ。-aria は冒頭が長母音でアクセントもある (ネブラーリア)。
一般的には単形種とされるが、
亜種 glottoides も用いられたこともあった。glottis に似た、の意味でこの語義は以下参照。
[学名の歴史的経緯]
現在では Tringa nebularia で統一されているよう (属は変化する可能性がある) で、近年のリストでは他の用例をみかけないが、歴史的にはいろいろな学名があった。
例えば Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Scolopax glottis Linnaeus をアオアシシギの学名として Totanus nebularius Gunner. を別学名に挙げている。
Linnaeus (1758) では Scolopax glottis が与えられていた (記載)。(The Key to Scientific Names はオオソリハシシギのシノニムとしているが wikipedia 英語版では Scolopax glottis をアオアシシギのシノニムとしている)。
過去に用いられた Glottis の学名なども整理したもの。
glottis は不明の鳥でさまざまに同定されてきたが、スウェーデン語では Glutt または Gluttsnappa がアオアシシギを指すとのこと (The Key to Scientific Names)。ラテン語 glottis は別語義があり英語でも同じ綴りで使われる解剖学の "声門" の意味 (< gula のど、glotta 舌 Gk)。
鳥の方に用いられる語源はよくわからないようだが、古ギリシャ語の glottis はウズラクイナの声門を指す意味 (glotta 舌 -is 女性名詞の語尾 Gk) (wiktionary) ここで鳥と関係があるのかも知れない。
Linnaeus (1758) が使ったものはこれだったが glottis はいろいろな形で使われ、Scolopax glottis? (Piller & Mitterpacher 1783) はソリハシセイタカシギのシノニム、Tringa Glottis (Bechstein 1803) はアオアシシギのシノニムとされるなどかなり混乱していたよう (The Key to Scientific Names)。
Glottis はその後もアオアシシギを指すとして他の派生属名にも使われたことがあったため知っておいてよい歴史かも知れない。
Linnaeus (1758) にはもう一つ Totanus littores (記載) があって、これも現在アオアシシギのシノニムとされる。記載順では Scolopax glottis よりこちらが後だが、Fauna Svecica (1746) ではこちらのみを記載している。
Linnaeus (1758) は Scolopax glottis を追加したらしい (#オオタカ備考の Falco gentilis と似た経緯のよう)。
現在の学名規則では 1758 年以前の学名は有効でないが、規則次第では Tringa littorea が最初の記載として認められていたかも知れない。
現在の学名は Johan Ernst Gunnerus (1718-1773。ノルウェー生まれの博物学者でコペンハーゲンで仕事をした) が Beskrivelse over Finmarkens Lapper (1767) p. 271 [英訳され An Account of the Laplanders of Finmark (1808)] で発表した
Scolopax nebularia Gunnerus, 1767 によるもので、Linnaeus の古い学名はなぜ使われていないのか気になるところだが、Johan Ernst Gunnerus の wikipedia 英語版によれば Linnaeus とも交流があり手紙のやりとりは保存されているとのこと。
Gunnerus (1767) の該当ページを見ると Linnaeus の Glarcola, Tringa littorea [それぞれ Fauna Svecica (1746) の 184, 185 これらスキャンは第2版 (1761) から] と比較している。
Gunnerus は Linnaeus (1758) はまだ見ておらず、Scolopax glottis の記述には気づいていなかった模様。
Linnaeus との交流の結果記載者を決めた、あるいは手紙のやりとりから判断された経緯も考えられるが wikipedia にはそこまでは記述されていない。
あるいは後世の者が厳密な先取権の原則から決めた学名ではなかったかも知れない。
アオアシシギの当時のノルウェー名は Skodde-foll [Gunnerus (1767) にも言及がある] で "霧の馬の子"。"馬の子" の意味はおそらく鳴き声から (The Key to Scientific Names)。
skodde の語源は "霧" の意味はドイツ語 Schatten、英語 shade (いずれも影) に関係している (古ゲルマン語 skadwaz) とされている。foll は古ノルド語 fyl 由来で北欧言語のみで使われている (wiktionary)。
ということで、Linnaeus も Gunnerus も当時の現地名を翻訳してラテン語化した学名を用いた模様。現地名の意味が違っていたために学名にも食い違いが発生したらしい。
現在のノルウェー名はスウェーデン語同様の Gluttsnipe で Skodde-foll の名称は今では使われていないよう。フランス名は Chevalier aboyeur で "吠えるシギ"。子犬の鳴き声に似ていると wikipedia フランス語版にある。
ポーランド語では kwokacz で動詞 kwokac ニワトリなどがコッコッと鳴く表現に由来。
音声をどのように表現するか違いはあるが音声はどこでも目立っていたらしい。
wikipedia ノルウェー語版によれば "霧の" の意味はあまり明確でないが、他のシギ類に比べてぼんやりした灰色の外見によるのではとある。"霧の" は生息環境を指すとの説明が多いが (wikipedia 英語版など。元出典が引き継がれているだけのよう)、個人的にはこちらを推したいので学名訳を少し修正した。
ノルウェーの地方名では音声由来の klyvi があるとのこと。
デンマーク語では Hvidklire で hvid (白い、または無地の) シギ。全体的に白っぽくて模様が目立たないためか。
和名と英名の対応がよい (ドイツ語も同様) ので他言語も同じように考えてしまいがちだが、言語間での名称の共通点は意外に少なかった。
なお Gunnerus の記載した学名に他にシロカモメがあるとのこと。鳥はおそらくこの2種のみでいずれも日本産であることは興味深い。
Boyd では Totanus nebularia。
-
カラフトアオアシシギ
-
オオキアシシギ
- 学名:Tringa melanoleuca (トゥリンガ メラノレウカ) 黒白まだらのクサシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 種小名:melanoleuca (合) 黒白まだらの (melano- (接頭辞) 黒い leukos 白い Gk)
- 英名:Greater Yellowlegs
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
melanoleuca は短母音のみで -leu- がアクセント音節 (メラノレウカ)。由来となるギリシャ語も短母音のみ。
北米の単形種。
Boyd では Totanus melanoleuca。
-
コキアシシギ
- 学名:Tringa flavipes (トゥリンガ フラーウィペース) 黄色い足のクサシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 種小名:flavipes (adj) 黄色い足の (flavus (adj) 黄色の pes (m) 足)
- 英名:Lesser Yellowlegs
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
flavipes は a と e が長母音で冒頭にアクセントがある (フラーウィペース)。ほとんど学名のみに用いられる。
北米の単形種。
Boyd では Totanus flavipes。
オオキアシシギに擬態しているとの考えがある。Prum (2014) Interspecific social dominance mimicry in birds (#ハチクマの備考 [擬態と種・亜種の関係] 参照)。
オオキアシシギとコキアシシギの系統の違いは Gibson and Baker (2012) (#ヘラシギの備考) による。
-
クサシギ
- 学名:Tringa ochropus (トゥリンガ オークロプース) 黄土色の足のクサシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 種小名:ochropus (合) 黄土色の足 (ochra (f) 黄土、pous 足 Gk)
- 英名:Green Sandpiper
- 備考:
tringa の読みはわからないが短母音のみであれば "トゥリンガ"。
対応するギリシャ語 trungas は語末が長母音で (ただしアクセントは冒頭) ラテン語でもあるいは伸ばしていたかも知れない。
ochropus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語では okhros (黄土色の) は冒頭が長母音、-pus は足を意味して長母音と考えられる。冒頭がアクセント音節と考えられる (オークロプース)。ただしギリシャ語では冒頭にアクセントはなくラテン語発音規則に基づくもの。
記載時学名 Tringa Ocrophus Linnaeus, 1758 (原記載)
Ocrophus と現在使われる ochropus とは違った綴りになっていた。Linnaeus は後の著書でもこの学名を用いていた。資料 によれば 1788 年の版で訂正された模様。
Tringa ochropus (BirdForum 2025.2) にも話題があり、Commission in Direction 17 で公式に綴りが確定されたとのこと。
Gruiformes and Charadriiformes に記載された種の同定経緯についての解説がある。
Caroli Linnaei Naturae Curiosorum Dioscoridis Secundi Systema Naturae ...
に の見出しで対応するドイツ語名 grosse Sandlaeuffer (大きな砂を歩く者) が記されている。
Tringa 属の定義として Rostrum digitis brevius (嘴は趾より短い) があるためダイシャクシギ類は除外されるなど。
Fauna svecica (146 の番号のもの)、
Fauna svecica... (180 の番号のもの) を見ると Ochropus は Gessner が付けた学名の拝借であることがわかる。Linnaeus (1758) では Gessner が付けた学名のうち Rhodophus (ピンク色の足) と同じとしていたので今ひとつ合っていない。
Linnaeus も pedibus virescentibus (Fauna svecica の記載とは微妙に違う) と記載しているので足の色に注目した種小名と考えられるが、おそらく現物は見ずに学名を整理したものだろう。
Fauna svecica に登場するスウェーデン語名称は Horsgjok。Deutsche Mythologie (Jacob Grimm, Projekt Gutenberg) によればシギ類を指す名前とのこと (hrossagoukr, rossekukuk の別名がある)。
gok (< gukuk) はカッコウなので同じように渡ってくる鳥を指して一連の -gok の名称が与えられたものか (#アリスイ参照)。hors は馬の意味が中心だがシギ類と馬がどのように結びつくかはわからなかった。
現代のスウェーデン語では Skogssnappa で skog は森林を表す。ドイツ語でも同様で Waldwasserlaeufer と森林を意識している。英語の発想も似ていると言えば似ているかも。
足の色に着目した名前は簡単に探した範囲ではみつからなかったが、誰もがおそらくあまり適切な表現でないと考えられていたのでは。
和名の由来もわからなかったが学名をそのまま訳すより適切な命名に思える。Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではすでに現在と同じ名称が使われていた。
ロシア語名が独特で Chernysh と "黒子ちゃん" ぐらいの意味になる。Kolyada et al. (2016) によれば最も近縁の種類であるタカブシギに比べて上面の色がずっと暗色であるためとの説明がある。
双眼鏡もない時代の名前と想像できるので、模様が見えない遠目で見ればそうかも知れない。
単形種。Tringa 属のタイプ種。属を細かく分割する分類でもクサシギの学名は変わらない。
[クサシギ亜科の系統分類]
Cerny and Natale (2022) の分子系統樹を用いた Boyd による クサシギ亜科 Tringinae の分類:
シギ科 Scolopacidae クサシギ亜科 Tringinae
ソリハシシギ属 Xenus
ソリハシシギ Xenus cinereus Terek Sandpiper
アメリカヒレアシシギ属 Steganopus
アメリカヒレアシシギ Steganopus tricolor Wilson's Phalarope
ヒレアシシギ属 Phalaropus
アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope
ハイイロヒレアシシギ Phalaropus fulicarius Red Phalarope/Grey Phalarope
イソシギ属 Actitis
イソシギ Actitis hypoleucos Common Sandpiper
アメリカイソシギ Actitis macularius Spotted Sandpiper
クサシギ属 Tringa
クサシギ Tringa ochropus Green Sandpiper
コシグロクサシギ Tringa solitaria Solitary Sandpiper
キアシシギ属 Heteroscelus (Tringa 属より分離)
キアシシギ Heteroscelus brevipes Gray-tailed Tattler
メリケンキアシシギ Heteroscelus incanus Wandering Tattler
アカアシシギ属? Totanus (Tringa 属より分離)
コアオアシシギ Totanus stagnatilis Marsh Sandpiper
タカブシギ Totanus glareola Wood Sandpiper
アカアシシギ Totanus totanus Common Redshank
コキアシシギ Totanus flavipes Lesser Redshank
ツルシギ Totanus erythropus Spotted Redshank
オオキアシシギ Totanus melanoleuca Greater Yellowlegs
アオアシシギ Totanus nebularia Common Greenshank
カラフトアオアシシギ Totanus guttifer Nordmann's Greenshank
ニシハジロオオシギ? Totanus inornata Western Willet
ハジロオオシギ Totanus semipalmata Eastern Willet
これまでの Tringa を Cerny and Natale (2022) の分子系統に従って複数に分割した点が違うのみ。
馴染みの種類が多く、イソシギ、クサシギ、キアシシギ、アオアシシギなどがそれぞれ別属になるのは受け入れやすいし種類の特徴を把握する時にも役立ちそうな分類だろう。Tringa 属はクサシギがタイプ種なので分割するとクサシギ以外の系統は属が変わる (現在普通に使われている広義 Tringa 属もクサシギ属の名称になっている)。
名称が悩ましいのはこれまでの Tringa 属に代わって多くの種類を含む Totanus 属 (この属名は古くから使われていた) の和名である。タイプ種を優先すればアカアシシギ属になるが足の赤い種類ばかりではないので多少誤解が生じるかも知れない。
アオアシシギが一番身近な種類だろうがこれも足の色の名前が付く、英語のように "shanks" のような総称があるわけでもないので難しいところ。ここではタイプ種を優先した名称としておいた。
Totanus inornata はハジロオオシギ Totanus semipalmata から分離された種で和名が見当たらないが英名より "ニシ" を補った名前としてみた。
少し意外だったのはタカブシギがアカアシシギ、コアオアシシギのグループに入ることで、クサシギに近い印象を持っていたのとは少し違う (この系統樹でもクサシギと系統がそれほど遠いわけではないが)。
カラフトアオアシシギは分子系統樹ではハジロオオシギとグループを作っているがこの解析に使われた遺伝情報には問題が判明している (#カラフトアオアシシギの備考参照。再確認が必要)。
Cerny and Natale (2022) もそれほど精度の高い系統樹ではないので今後の系統研究が必要だろう。
-
タカブシギ
- 学名:Tringa glareola (トゥリンガ グラーレオーラ) 砂利模様のクサシギ
- 属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 種小名:glareola (f) 砂利模様の (cf. glarea (f) 砂利)
- 英名:Wood Sandpiper (由来は備考参照)
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
glareola は1つめの a と o が長母音で後者にアクセントがある (グラーレオーラ)。glarea が冒頭が長母音。-ola は指小辞語尾 (この場合は短母音) ではなく直接派生した単語と考えられる (wiktionary にも語尾語源記述なし)。
似た gladiolus (グラジオラス) では指小辞語尾で短母音となっている。
The Key to Scientific Names では glareola は指小語と解釈しているが発音から判断するとおそらく誤り。The Key to Scientific Names は #アオアシシギ の nebularia と同様に生息環境と推定しているが、これらは少し検討不十分な感じがする (以下も参照)。
単形種。
Boyd では Totanus glareola。
種小名の解釈は多少不明な点があり、砂利 (に住む鳥) と愛媛の野鳥「はばたき」にある。
Linnaeus の原記載。corpore albo punctato と体に白い斑点があることを述べているので模様由来説の方が合っている感じがする。
The Key to Scientific Names によればこの種小名は広く水辺を指していたのではと解釈されていて、Charadrius Glareola Forster, 1844 (現在ではニュージーランドチドリ Charadrius obscurus Red-breasted Plover のシノニム)
では明確に島の小砂利と生息環境を示した記載 (Habitat ad littora glareosa insulae australis Novae Zeelandiae) になっている。
Glareola の属名はニシツバメチドリ (Sand-Vogel と呼ばれ "砂の鳥") をタイブ種として名付けられており、これらは生息環境にふさわしい名前に見えるが、タカブシギとはちょっと違う気がする。
Linnaeus (1746) Fauna Svecica (152.) をチェックすると dorsum nigrum punctis albis adspersum 黒地に散在する白の斑点 とやはり模様をうかがわせる。
生息地が sylvis uliginosis 湿った林または木立 (sylva/silva) となっており、"砂利 (に住む鳥)" はやはりふさわしくなさそう。
英名が生息環境をあまり反映しておらず覚えにくいと感じていたが、(別言語を経由したかも知れないが) 上記ラテン語記述由来と判明した。他言語を調べてみるとドイツ語、ウクライナ語は明らかに "沼地の" を使っている。
フランス語は Chevalier sylvain と "森の精のシギ"。ラテン語からそのまま使っている。
デンマーク語 bosruiter (bos 森)。もっとも "森" が指すものは日本語から受ける印象とは異なるかも知れない。
一方スウェーデン語では gronbena = gron 緑の ben 足 でこれはまだ納得しやすい (そこまで緑に見えないが。また#アオアシシギのスウェーデン名と対比すると面白い)。ノルウェー語も同様。
"沼地の" に相当する英名はコアオアシシギで、タカブシギに "沼地の" を用いている言語でどうなっているか見るとドイツ語で "池の"、ウクライナ語は kolovodnik stavkovij で stavkovij = "池の"。これらは学名由来と考えてよさそう。池も沼もそれほど違わない感じもするが...。
タカブシギの名称については日本語が一番センスがよいように思えた。斑点模様に注目している点では Linnaeus もおそらく似ているように見える。
ロシア語は fifi でこの由来は説明するまでもないだろう。
-
キアシシギ
- 第8版学名:Tringa brevipes (トゥリンガ プレウィペース) 短い脚のシギ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Heteroscelus brevipes (ヘテロスケルス プレウィペース) 短い脚の脚が異なるシギ
- 第8版属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 第7版属名:heteroscelus (合) 異なった脚 (hetero- (接頭辞) 異なった skelus 脚 Gk) ふしょのうろこ状模様による
- 種小名:brevipes (adj) 短い足の (brevus (adj) 短い pes (m) 足)
- 英名:Grey-tailed Tattler
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
brevipes は pes に長母音があり、アクセントは冒頭 (プレウィペース)。
heteroscelus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-ros- がアクセント音節と考えられる (ヘテロスケルス)。分類次第で将来属名が復活する可能性もある。
音節区切りは isosceles を参考にした。この単語では -es がギリシャ語由来の長母音で終わるが scelus は長母音となる要素はないと考えられる。[Heteroscelus 属] 解説も参照。
Heteroscelus 属 (Baird, 1858) は Pereira and Baker (2005) の分子遺伝学研究
Multiple Gene Evidence for Parallel Evolution and Retention of Ancestral Morphological States in the Shanks (Charadriiformes: Scolopacidae) により Tringa 属に統合。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版でも同じ扱い。Tringa brevipes となる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。英名の tattler は騒々しい声に由来。tattle (べらべらしゃべるなど)。
OED によれば tattler の鳥類学の用例は 1831 年ハジロオオシギ 現在の学名で Tringa semipalmata Willet に対して用いられたとのこと。音声を聞いてみると確かに賑やかではある。比較的静かな godwits に比べて音声が目立つためか。
Boyd では Heteroscelus brevipes。
[キアシシギとメリケンキアシシギの記載]
種小名の「短い足」が何と比較したものか気になって原記載を見ると、Le chevalier aux pieds courts と短い足をフランス語名にも付けている。Vieillot (1816) による命名。les pieds sont gris, dans l'oiseau empaille で剥製では足は灰色とある。黄色にはあまり着目していない。
その下に Le chevalier aux pieds jaunes がありこちらが黄色い足になっている。学名から判断すると現在のコキアシシギに相合するもの。この周辺の鳥をみると足の色に注目して名付けていたよう。
百科事典のようなものでアルファベット順のため系統関係を意識しているかまではわからないが、"aux pieds" (足がなんとかの) がしばらく並ぶのでそれほど誤った推測ではないだろう。
キアシシギの一つ上の項目が Le chevalier noiratre (黒っぽいシギ) 当時の学名で Totanus nigellus Vieillot, 1816 と名付けられていたが何者か不明だったよう。
Smith (2018)
The identity of two of Azara's "mystery" waterbirds
によればキョウジョシギの亜種 Arenaria interpres morinella と同定されるとのこと。Azara がパラグアイで測定値などを記述したもので Chorlito pies roxos (足の赤いチドリ plover) と述べていたが長年何かわからなかった。キョウジョシギは近年パラグアイを通過することがわかり、南米で足の赤いシギ・チドリは非常に少なく候補は少数に絞られるとのこと。
Vieillot も書物の記述をもとにリストしたのみのようで、キアシシギの足が短いとしたのは他の (当時) Totanus 属と比較し、特にコキアシシギより短いとしたものと思われる。
メリケンキアシシギの方が記載が早かった (原記載) 当時の学名 Scolopax incana Gmelin, 1789。
東洋の種の記述は遅れたようでキアシシギの基産地は越冬地ティモール島とされる。Vieillot (1816) でもメリケンキアシシギは別種として扱われ Le chevalier cendre (灰色のシギ) として現れる。アルファベット順のため確実ではないがキアシシギとメリケンキアシシギの類似性はあまり意識がなかったものと想像できる。
足の色がそれほど黄色いかなあと思っていた者にとっては、学名・英名・記載時フランス名とも足が黄色い意味が含まれていないのでちょっと納得しやすく感じた。
なおこれらの記載に使われたフランス語 chevalier は普通は騎士の意味で用いられる単語。シギの意味は chevalier によれば第3語義として自然科学の用語としてリストされており、形や色の類似性からか、とある。魚でも chevalier と呼ばれるものがある。鳥類学では 1555-1557 年 Belon が用いたとのこと。魚類では 1814 年の用例があるとのこと。
一方 Totanus griseopygius Gould, 1848 (腰が灰色のシギ) の学名 ("The birds of Australia") があり、同時に付けられた英名 Grey-rumped Sandpiper も使われていた。図版と解説。
これによれば (当時の Totanus 属では) 珍しく背から尾にかけて模様がなく一様に灰色であることからこの名称となったとある。記述では上尾筒も含んでいる。特に腰だけが灰色の意味ではない。
有名な Gould の図版なので比較的使われていた英名だったようだが Vieillot (1816) の記載の方が早いと認定されたために学名が変わった模様。英名には複数の別名があり、Grey-tailed Tattler/Sandpiper, Polynesian Tattler, Siberian Tattler がある [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)]。
現在の Grey-tailed Tattler はおそらくこの Grey-rumped Sandpiper が変形したもの (腰から尾に変わったが上記 Gould の記述ではどちらでもよい感じ。尾というより上尾筒) ではないだろうか。
当時の学名やその後も使われる英名を訳すならば "腰から下がのっぺりと灰色の" が適切な形容と考えられる。
現在の学名も英名も今ひとつしっくりしないと感じられる方が多いと想像するが、このような経緯を考えると納得できる。
茂田 (1991) Birder 5(9): 46 によればキアシシギとメリケンキアシシギの和名は従来逆になっていたが黒田 (1916) が訂正したとのこと。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によれば当時の学名で Totanus incanus (現在の学名でメリケンキアシシギ) に キアシシギ、ミシギ の名称、Totanus incanus brevipes (亜種扱いだった) にメリケンキアシシギの名称を与えていた。
後者は Bonin Islands (小笠原) とあり、基産地ティモール島に引きずられていたのかも知れない。
また同種扱いの場合は記載順からこの学名が妥当である。同種時代であれば Totanus incanus の種和名がキアシシギでもおかしくない。brevipes の分布がまだわからなかっただけで間違っていたと言えるほどではなさそう。
この学名での記述例として Riplay (1947) A report on the birds collected by Logan J. Bennett on Nissan Island and the Admiralty Islands があり、かなり長期にわたって同種とされていたことがわかる。
この記録はパプアニューギニアの島でのもの。
[Heteroscelus 属]
この属名は Baird (1858) が脛骨と足根骨裏目のうろこが他の Totaneae (当時の概念) とは違って六角形でより粗い網目になっているため別属とすべきと記載したもの (Rep. Expl. and Surv. R. R. Pac., 9, 1858, p. xxii, xlvii, 728, 734, The Key to Scientific Names より)。
Oberholser (1919) Heteractitis versus Heteroscelus によれば、この属名よりも Heteractitis Stejneger, 1884 の方が広く使われている時期があった。
これは Heteroscelis Latreille, 1825 (カメムシ目) の属名がすでに存在していたため Heteroscelus は無効と考えられていたもの。
G. M. Mathews がこの問題を指摘し、Oberholser (1919) が規則により同一綴りとは判定されないことを示して先に発表された Heteroscelus が有効な属名と判断され現在に至っている。
Stejneger (1884) は "異なっている" を意味するギリシャ語を用いているいるのみで由来は説明していないらしい (The Key to Scientific Names)。
-scelus の語尾がギリシャ語の形と異なるため発音は類似語との推定による必要があったが、この語尾が生きた背景にはこのような事情があった (-us はラテン語的語尾にしたものと想像できる)。
もしギリシャ語 (heteroskeles) からの変換に際して原音に近い Heteroscelis を採用していればこの属名は生き残らず Heteractitis が用いられていたと考えられる。Baird (1858) はこの点に気づいて敢えて語尾を変えたのか別の理由によるものかは不明。
Heteroscelus 属を認める場合はキアシシギがタイプ種でもう1種がメリケンキアシシギ。ふしょ後面の模様が特徴的である点は共通点があるが、同時にその違いが識別点の一つともなっている。
渡辺・三河 (2007) Birder 21(5): 59-65 の記事中 p. 63 にふしょの拡大比較図が出ている。
現在の通常の扱いでは Tringa 属にまとめられているが、シギ類の精度の高い分子系統解析が進んで Tringa 属が単系統でない、あるいは属分割の見直しがあれば復活する可能性のある属名。
[ロシアのキアシシギとメリケンキアシシギの分布と分類概念]
Dement'ev and Gladkov (1951) を見ると同種扱いでロシアの繁殖地は大部分亜種 incana (属名 Tringa のため性が変わる) で、ロシア東端やカムチャツカ、アラスカからカナダの一部を brevipes としている。
越冬地は前者がインドネシアなど東南アジア、後者が太平洋からアメリカ大陸西岸と考えられていた。
かなりまれな鳥とあり、ロシア繁殖地もあまりよく調べられていなかった。渡りの時は 3-5 羽の群れを作るとのことで、日本で普通種との違いが大きすぎ、まるで別の種の解説を見ているかのよう。
大陸が主な渡りルートと考えられていて日本も渡り時期に通過するとなっている。
この著書の亜種 incana は小笠原、本土、四国、琉球で渡り途中に見られるとある。千島列島はこの亜種と考えられていた。
この文献によれば Portenko (1939) がアナディリ山脈で両者が同所的に繁殖し、それぞれ独立種とする可能性を示したとのこと。同地でいわゆる Tringa glareola (現在の学名ではタカブシギに対応) と呼ばれるものが亜種 incana に属する可能性があると記している。
1950 年ぐらいでもまだ分布境界はよくわかっていなかったよう。
Portenko (1939) は "Fauna Anadyrskogi kraya. Ptitsy" (アナディリ地域の動物相: 鳥) で pp. 178-180 で別種扱いで記述 (違いなども述べられている)。
Portenko (1972) "Ptisty Chukotskogo poluostrova i Ostrova Vrangelya. Ch. 1" (チュコト半島とウランゲリ島の鳥 第1部) pp. 320-322 で同種の亜種扱いで表記しているが、特にコリャーク山地 (アナディリ地域とカムチャツカの間。アナディリ地域とは地理的にやや異なるので注意) で採集した標本によって情報が増えて別種とするよりも同種で違いの大きな亜種と考えるに至ったと述べている (p. 322)。
Lappo and Syroechkovski Jr. (2002, 2018 再掲) On breeding of the wandering tattler Heteroscelus incanus at southern Chukotka (pp. 4555-4557)
がチュコト半島でメリケンキアシシギとキアシシギが同所的に繁殖する新しい報告を行っている (写真あり)。
Portenko (1939) には触れているが Portenko (1972) への言及はなく、メリケンキアシシギがロシア北東部にも広く分布していると考えられていた従来の考え方はしっかりした根拠に基づくものではなく、
Kishchinskij (1980) "Ptisty Koryaskogo nagor'ya" (コリャーク山地の鳥) によればコリャーク山地でメリケンキアシシギの標本は1例 (成鳥 1978.8.17) しか獲られなかったとのこと。
Kishchinskij (1980) は別種扱いで、この地域のものはキアシシギ Heteroscelus brevipes (pp. 122-125) として記述している。標本の1羽はオーストラリアでの標識があった。
メリケンキアシシギ Heteroscelus incanus の記述は pp. 121-122 にあり 1960 年以降で雑種と考えられるものも含めて6例の標本がリストされている。散発的に繁殖する種としている。
Portenko は日本でも有名でよく言及されるが、研究者は他にもおり、コリャーク山地についてはおそらくキアシシギの一部をメリケンキアシシギと考えていて別種とは言えないと判定していた模様。
Portenko (1972) が同種と判定したことは自身の過去の解釈を修正したもので、後から振り返ると分類学上それほど意味がなかった [茂田 (1991) p. 46 で触れられているが当時は理由は不明とされていた]。
研究が進むともにロシアでのメリケンキアシシギの分布は東の端にほぼ限定されることがわかってきたようで、改めてメリケンキアシシギの確かな繁殖事例を探すことになった経緯のよう。
日本語のものも含め、少し古い文献を読む際は記述のニュアンスの解釈も含めて要注意だろう。
Tomkovich (2006) New facts of breeding for the wandering tattler Heteroscelus incanus in Southern Chukotka (pp. 959-961)
にも情報があり、声も違う。キアシシギなのかメリケンキアシシギの白いタイプのものか DNA 解析ができればわかるのだが、とある。少なくとも1例雑種の報告がある (上記参照) とのこと。
コリャーク高地北部のメリケンキアシシギとキアシシギの繁殖状況: Tomkovich and Loktionov (2025) Censuses of broods of the wandering Heteroscelus incanus and Siberian H. brevipes tattlers in the northern Koryak Highlands (pp. 2234-2245)。
2011-2021 年の観察で、年によって変動があるが似た場所 (主に山地の河川) で繁殖が記録されている。この地域ではキアシシギの方が多かった。
[キアシシギの繁殖地]
しかしキアシシギもロシアでも珍しい鳥のようで (ほとんど人の住まないところで繁殖しているらしい) 人里近くで新しい巣の発見などがあると報告が出ているぐらい。
コンサイス鳥名辞典によれば巣の発見は 1959 年とあり、Dement'ev and Gladkov (1951) では繁殖は調べられておらず卵は未記載とある。コンサイス鳥名辞典によればツグミの古巣に営巣した例があるとのことで、人里離れたところで繁殖する種ツグミと似た繁殖分布で、いずれもほとんど調査されていないのかも知れない。
ツグミがごく普通にやってくることを考えると、もし同様の地域で繁殖していればキアシシギは繁殖地であまり記載されないだけで普通種であることも納得が行く。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではメリケンキアシシギの巣は Bent (1929) が記載しているとのこと。
コンサイス鳥名辞典では東シベリアでは両種の繁殖分布が重複していることから別種とみなす説が有力とあり、Portenko (1939) の考えを取り入れているよう [Dement'ev and Gladkov (1951) では亜種扱い]。コンサイス鳥名辞典のメリケンキアシシギの項目では東シベリアでも繁殖と、現代よりも繁殖地を広く見積もっていたらしいことがわかる。
かつてキアシシギが4卵と言われていた時代の情報は、同種時代のメリケンキアシシギの情報が混在しているかも知れない (メリケンキアシシギの方がまだ調べられていて4卵が記載されていた)。
キアシシギの巣が見つからない理由として他のシギ類と違って樹上に営巣するので見つからないのでは、との考えは榎本 (1942) が提案していたとのこと。高野 (1957) で引用されたとのこと [週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973)]。
Vorob'ev (1963) "Ptitsy Yakutii" (ヤクーチアの鳥) pp. 123-127 に記述 (亜種扱い) があり、1958 年撮影の繁殖地環境やひなを見守る親鳥の写真が出ている (巣の写真はない)。Kapitonov の 1955 年の研究でここ (インディギルカ川上流部) では普通に繁殖する鳥と述べられている。この時の記録では 5/23 に現れ、川にはまだ氷が張っていた。5/26 には数が多くなり川にも水が現れた。
p. 126 に Vorob'ev 自身による記録が詳しく述べられていて、巣立ったひなはよく見られて親も採集したが巣の発見は困難で 7/13 に On'uola 川の島で卵の殻2つを見つけたとのこと。「翌年」とあるのでこれが 1959 年の巣の発見を指すのか。ひなの記述は十分あり、卵もこの2卵の色彩が述べられている。
ヤクーチアの河川ではキアシシギは普通に見られるシギとのこと。地上捕食者が近づきにくい中洲などで繁殖しているのだろう。しかし人が普通に訪れる場所ではなさそう。日本からはちょうど北に位置する地域で沿海地方などの大陸で目撃例が比較的少ないことも納得できる (ツグミも主な繁殖地はヤクーチア?)。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) でもキアシシギは全体的には珍しい種類で所により普通となっている。日本では識別基本種になるぐらいなのだが...。
文献はいずれも現状オンラインで読めるので興味ある方は追求してみていただきたい。
参考までにキアシシギの最近の繁殖地の写真記録をみるとシベリアでは Grey-tailed Tattler (Egor Vlasov, Norilsk 2021.8.7) ぐらいしかなく、最果ての地とも言える。
ロシア東部ではもう少し情報があるが個体目撃の写真のみで繁殖に関係する写真は出ていなかった。
コメントでも珍鳥との表現があり、繁殖地のはずのロシアでは今でも珍しい鳥のよう。
メリケンキアシシギは2報告があって Wandering Tattler (Nikolay Yakushev, Meynypilgyno, Chukotka, 2016.8.4) と
Wandering Tattler (Dmitry Nizovtsev, Chukotka, okr. s. Meynypilgyno, 2021.6.6) でいずれもチュコト半島での個体目撃で繁殖の有無は不明。
コキアシシギはカムチャツカの1報告がある: Lesser Yellowlegs (Ekaterina Khudyakova, 2016.7.19)。
キアシシギのロシアでの情報は驚くほど乏しく、Veprintsev の音源ライブラリから編集された "Golosa Ptits Rossii" (Chast' 1, 2007) にも音声が収録されていない。よほど録音困難な種類らしい。
日本ではキアシシギの声ばかりが目立つことが多いのでまさしく所変われば品変わる模様。現代の海外の音声ライブラリにもキアシシギの声は少ない。すなわち繁殖地での警戒音やひなの声などの音声記録はほとんど存在しないと考えると納得がゆく。
キアシシギの春の渡りが遅めなのは世界の寒極と言われる地域が繁殖の中心地であるためかも知れない。
アムール州 Khingan-Bureya 高地のキアシシギの記録: Biserov (2010 初出、2025 再掲) The grey-tailed tattler Heteroscelus brevipes in the Khingan-Bureya Highlands (pp. 717-720)。ここは繁殖地ではないがおそらく漂行中に記録されたものらしい。
ヤクーチア山地で繁殖する普通種であるが、この時点 (2010) では繁殖地の新しい情報は入っていない。アムール州 Khingan-Bureya 高地も繁殖地の候補になり得るが、この地域特有の6月後半のモンスーンの雨がちょうどキアシシギの繁殖期にあたり、増水のため川で繁殖する種には向かないのではと推論している。
参考までに NC_088454.1 から BLAST をやってみると Tringa では新しい方の系統に属する。
カラフトアオアシシギ、ツルシギなどいくつかの種を分岐した後アオアシシギやオオキアシシギを含む系統 (面白いことにこの解析ではアオアシシギとオオキアシシギが単系統の関係にならない) と {キアシシギ + メリケンキアシシギ} の系統の2つに分かれる。この意味では分布範囲の狭いカラフトアオアシシギは遺存的とも考えられる。Biserov の推論のように気候特性からキアシシギがこの地域にあまり進出できなかったので古い系統でもカラフトアオアシシギが残ることができた? (ほんとうか?)。
2つの系統のどちらかが特別に早いわけではないが、このような系統分岐をみると類似種の {キアシシギ + メリケンキアシシギ} は北米由来でやってきたグループのようにも見える。その場合はメリケンキアシシギが分布を広げて地理的隔離でキアシシギが形成されたように見えるがいかがだろうか。ユーラシアではアオアシシギの方が優勢でキアシシギがあまり分布を広げられなかった?
[潮汐の解説]
干潟などのシギ・チドリの観察や生態において潮汐が重要であることはあまりにも当然であるが、雑誌などであまり納得できる説明を読んだことがなかったのでページを紹介しておく。どこに置いてもよかったがさすがに内陸シギ・チドリは避けて普通種のところに記載することにした。
動力学的潮汐理論におけるケルビン波 (1879 年)
タイトルと数式の説明は難しいが、ずっと飛ばして 2. 渤海・黄海・東シナ海 の項目をまず見ていただくとよいだろう。「木浦から仁川に向かって潮汐波が移動するにつれて波高が増大するのは、その方向に向かって水深がだんだん浅くなるからです。それはちょうど津波が海岸に近づくとき、水深が浅くなるにつれて伝播速度が遅くなり、後から来る波が積み重なって波高が高くなるのと同じです」と説明されている。
そして [補足説明0] まで進んで太平洋に於ける潮汐波のアニメーションを見ると事情がよくわかる。
水深の浅いところが水の波 (潮汐波) の速度が遅いため潮汐現象が顕著で、広い太平洋沿岸でも重要湿地がごく限られた地域に密集する (そしてシギ・チドリの東アジアフライウエイとなる) ことが理解しやすい。
そして [補足説明3] を読むとよい。黄海・渤海部分については起潮力強制振動で説明できるとのこと。日本海は共鳴条件を満たす深さや大きさでないため潮汐が非常に弱い (京都にも海はあるがシギ・チドリの記録は限られている)。
なおご存じ有明海も諫早干拓事業によって例えば固有周波数にも変化を及ぼす規模のものであったらしい。
参考までにオンラインで読める論文: 白谷他 (2007) 有明海の潮汐及び潮流の変化とその要因に関する考察。
Birder などの記事などでよく現れる月と太陽の方向に海面が盛り上がる説明はこの中の平衡潮汐理論に相当する (月と反対側の海面が盛り上がるのは平衡潮汐理論で示されるので地球全体で大まかには説明できていると考えてよい)。それでは身近な潮汐現象がうまく説明できないので、どのような説明をすればわかってもらえるか解説がある。
海面の形が十分早く変わることができれば (これは流体の運動が必要なので "平衡" と矛盾するが) おおむね平衡潮汐理論の通りになるが、現実はそうではないので潮汐力による強制振動の効果が顕著となり伝播するケルビン波を考える必要があるとの説明。
潮汐力の原理まで遡るならば、潮汐力 (起潮力)。高校物理を履修していないとあるいは慣性力でつまづくかも知れない。加速度運動をする系の上の観測者 (例えば自転や公転をしている地上の観測者) にとって見える力で例えば身近に使われる遠心力は慣性力の一種。
地球温暖化と異常気象にも同様に慣性力を起源とする波 (ロスビー波 Rossby wave) が関連している可能性が示唆されている: Kornhuber et al. (2020) Amplified Rossby waves enhance risk of concurrent heatwaves in major breadbasket regions、
Chen et al. (2023)
Projected increase in summer heat-dome-like stationary waves over Northwestern North America。
なぜ同じような気象条件が長続きして熱波や異常気象が起きやすくなるのか。天気予報ではなかなか教えてくれないが、温暖化で偏西風が弱まり、ロスビー波が増強されて蛇行をもたらす定在波のような状態が起きやすい条件になっている。ロスビー波は現在キーワードとなっているので日本語で検索してもたくさん見つかる (英語で探せばもちろんもっと多く見つかる)。
-
メリケンキアシシギ
- 第8版学名:Tringa incana (トゥリンガ インカーナ) 薄い灰色のシギ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Heteriscelus incanus (ヘテロスケルス インカーヌス) 薄い灰色の脚が異なるシギ
- 第8版属名:tringa trungas Aldrovandus が 1599 年クサシギに与えた名前 (ツルシギの項目参照)
- 第7版属名:heteroscelus (合) 異なった脚 (hetero- (接頭辞) 異なった skelus 脚 Gk) ふしょのうろこ状模様による
- 種小名:incana / incanus (adj) 薄い灰色の、白髪の
- 英名:Wandering Tattler
- 備考:
tringa は#クサシギ参照。
heteroscelus は#キアシシギ参照。
incana/incanus は -ca- の a が長母音でアクセントもある (インカーナ/インカーヌス)。
Heteroscelus 属 (Baird, 1858) は Pereira and Baker (2005) の分子遺伝学研究
Multiple Gene Evidence for Parallel Evolution and Retention of Ancestral Morphological States in the Shanks (Charadriiformes: Scolopacidae)により Tringa 属に統合。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版でも同じ扱い。Tringa incana (語尾が変わるので注意)となる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。古くは Ash-coloured Snipe (Latham 1785) と呼ばれた (種小名の意味参照)。
種小名はインカを連想してしまいそうだが語源は全く別。ヤマゲラの学名 Picus canus などに出てくる canus (灰白色の) に接頭辞 (特に否定の in- ではない) を付けたものとのこと。加齢による白髪、あるいは古いの意味があるとのこと (wiktionary)。
Boyd では Heteroscelus incanus。
キアシシギとの関係、Heteroscelus 属の由来、ロシアの繁殖情報などについて#キアシシギの備考参照。
-
ソリハシシギ
- 学名:Xenus cinereus (クセヌス キネレウス) 灰白色のよそ者 (変わり者?) のシギ
- 属名:xenus (合) よそ者 (xenon よそ者、客、訪問者 Gk)
- 種小名:cinereus (adj) 灰白色の
- 英名:Terek Sandpiper
- 備考:
xenus は起源となるギリシャ語は短母音なので長母音は現れないと考えられる (クセヌス)。
cinereus は短母音のみで -ne- がアクセント音節 (キネレウス)。
単形属で単形種。
英名の Terek は北コーカサス (ジョージアからロシアに流れる) の川の名前。ロシアのカスピ海の河口付近で採集された。
記載時学名 Scolopax cinerea Guldenstadt, 1775 (原記載)。
Latham (1785) が "Terek Snipe" として紹介し、Scolopax terek Latham, 1790 と名付けた。現在はシノニムとして扱われるが英名に残っている。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Totanus terekius となっている。Dement'ev and Gladkov (1951) によればこれは Totanus terekius Seebohm, 1888 とのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) の時代にも特異性が認められていたようで、Totanus javanicus Horsfield, 1821 (ジャワ島で記録されたものの絵が Gould にある) に対して Trekia Bonaparte 1838 が用いた属が採用されていた。この属名であれば地名が残っていた。
Kaup (1829) の Xenus の方が早いことがかなり近年になって判明したのだろう。
「xenus よそ者」は 記載。Flemdling (よそ者の、外国人) の意味が添えられている。
「長距離の渡りをすることに由来」とコンサイス鳥名事典にあって、渡り途中のよそ者と思っていたのだが、他に比べて特殊の方の意味かも知れない。
同じページで特殊性から単形属がいくつか提案されているうちの一つで、オナガガモ1種に Trachelonetta 属を提唱しているのでそれらしい感じがする (#オナガガモ備考に)。
このページで同時に提案されたほとんどの属名は現在使われていないが、分子系統研究の結果ソリハシシギは確かに他から離れていることがわかって採用されるに至った模様。
他にもシノニムがあって Limosa recurvirostra Pallas, 1811 とソリハシセイタカシギの属と同じ種小名を用いたものもあり、和名の通りでよくわかる。
分布が広いのにこの特徴に注目した他言語名がほとんど見当たらないのが不思議。
ロシア名もあまり馴染みがなく独自のもので morodunka で語源はよくわかっていないが、湿地を指す maapa と don' (dno 底) からだろうかと推測が出ている (Kolyada et al. 2016)。鳴き声由来のシギ類の名前の多いロシアで珍しく音声に注目していない。
-
イソシギ
- 学名:Actitis hypoleucos (アクティティス ヒュポレウコス) 腹の白い海岸に住むシギ
- 属名:actitis (合) 海岸に住んでいる (aktites < akte, aktes 海岸、izo 住む Gk。The Key to Scientific Names)
- 種小名:hypoleucos (合) 腹の白い (hypo- (接頭辞) 下の leukos 白い Gk)
- 英名:Common Sandpiper
- 備考:
actitis は The Key to Scientific Names の解釈を採用した。ラテン語で語構成を行ったものではなくギリシャ語から直接変換されたもの。
そのままラテン語化されると語末は長音になるが、-is と表記にすると単音となる ((aktites) 参照)。
アクセント位置は規則から冒頭になる (アクティティス)。
hypoleucos は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-le- がアクセント位置と考えられる (ヒュポレウコス)。
単形種。
国松・長島 (2011) Birder 25(7): 65-67 によれば「ぴいにすちどり」の名称が現れたことがあったとのこと。「ぴいにす」とは「紅葉雀」(コウヨウジャク) のことで、江戸時代中期に飼い鳥として輸入されたもので、オランダ語の piepen が由来ではないかとのこと。ドイツ語でも同じ単語でぴいぴい鳴くの意味。
イソシギの声としてふさわしい名称ではあるが、江戸時代中期にすでに輸入飼い鳥由来の名称が使われていたことやコウヨウジャクの名称は後に整理されたものらしいことがわかる。鎖国時代とはいえ輸入鳥は結構入っていたのでは。
本稿では飼い鳥や外来種の名称由来は基本的に対象外としているが、紅葉雀がいったい何に由来するのか興味はある。コウヨウジャクは学名 Ploceus manyar で英名は Streaked Weaver。Ploceus 属は英語では Weaver の名称が付くが日本語ではアジアの種のみコウヨウジャクを付け、残りはハタオリを付けている。
アジアの種は飼い鳥時代の名称を整理したものと想像できるが、残りは英語の Weaver を訳しているので微妙に不統一感が否めない。
コウヨウチョウ Quelea quelea Red‐billed Quelea、Euplectes キンランチョウ属やカエデチョウ科 Estrildini も同系統の色彩の発想と想像できるが、ハタオリドリ科の色鮮やかな飼い鳥をすべて紅葉に結びつけたものだろうか。
いずれも学名との関連は特に見当たらず飼い鳥名称由来ではないかと想像する。
ホウコウチョウ Estrilda melpoda Orange-cheeked Waxbill は予想通り頬紅鳥。
ヘビの仲間と熱帯鳥類館の新顔たち (日本平動物園 2013) によればオナガカエデチョウ Estrilda astrild Common Waxbill は「目の周囲が赤色で、嘴も濃い赤色です。腹は赤色です。この赤色から紅葉になぞらえてカエデチョウと名付けられました」とのこと。
カエデチョウ Estrilda troglodytes Black‐rumped Waxbill も目の周囲が赤色で、嘴も濃い赤色が当てはまる。
-
アメリカイソシギ
- 学名:Actitis macularius (アクティティス マクラーリウス) 斑点をつけた海岸に住むシギ
- 属名:actitis (合) 海岸に住んでいる (aktites < akte, aktes 海岸、izo 住む Gk。The Key to Scientific Names)
- 種小名:macularius (adj) 斑点をつけた (macula (f) 斑点 -arius (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Spotted Sandpiper
- 備考:
actitis は#イソシギ参照。
macularius は macula は短母音のみ。-arius は冒頭が長母音でアクセントもある (マクラーリウス)。macula の単語は網膜の黄斑 (macula lutea) の学術用語として英語でもそのまま使われる。鳥の場合はヒトでも用いる中心窩 (fovea) の用語が用いられる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
-
キョウジョシギ
- 学名:Arenaria interpres (アレーナーリア インテルプレス) 砂採取場の通訳 (二重の誤りによる命名)
- 属名:arenaria (f) 砂採取場 (adj) 砂の (arenarius)
- 種小名:interpres (f) 通訳、説明者 (備考参照)
- 英名:Turnstone, IOC: Ruddy Turnstone
- 備考:
arenaria は e と2つめの a が長母音で後者にアクセントがある (アレーナーリア)。arena (アレーナ) が砂。日本語の "アリーナ" も英語の arena を通じてこの単語が起源で長音で発音する意義もわかりやすい。
interpres は短母音のみで -ter- がアクセント音節 (インテルプレス)。
2亜種が知られる (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 interpres とされる。世界的に分布し、もう1亜種 morinella はアメリカ大陸のもの。
Linnaeus が 1741 年ゴットランド (Gotland) 島を訪れた時、現地名 Tolk がキョウジョシギを指しているとの誤った印象を受けた。Linnaeus の母語であるスウェーデン語では tolk は通訳、説明者の意味だが、ゴットランド方言では茎 (ここでは脚を指す) の意味で、実は現地ではアカアシシギを指す名前だったとのこと (Helm Dictionary)。
tolk はオランダ語や中世高地ドイツ語にもあるが現代ドイツ語には残っていない。語源はスラブ言語とのことでロシア語には tolk の名詞があり意味、分別、効用などの意味があるが通訳、説明者の意味は残っていない。
「コンサイス鳥名辞典」にはおそらくラテン語から古い時代の解釈による「見張り番」の意味が記載され、危険が近づくとギョッギョッ...の声を出すためと解説されている。
大橋 (2022) Birder 38(8): 52-53 に和名の解説があるが、むしろ "京女" に込められた意味の解釈が中心となっている。
キョウジョシギの和名の鳴き声由来解釈もある。浦本・安部 (1986)「動物の世界」2版 10 (日本メール・オーダー) pp. 1268-1269 に日没をまわった時などに、とくにさわがしく鳴き合うことがあり、この時の声はキョジョ、キョジョ、キョジョとさえ聞こえ、名前の由来はおそらくこれだろうと記している。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) にも本朝食鑑 (1697) の...呼号京女鴫是言美色乎 (中途半端な区切りになっているのは漢字入力の問題から。性能が低いのでご了承いただきたい) が引用され、大橋 (2022) でも採用されているが、当て字からの逆解釈も考えられるのでこの記述から即断しない方がよいかも知れない。
そのような声を紹介しておくと XC488950 (Lars Edenius スウェーデン 2019.7.25) 時刻 20:00 とある。暗くなった状態まで観察を続ける人はおそらく少ないのであまり知られていないかも知れない。それ以前にさわがしく鳴き合うほどの大群が見られる場面が少なくなっているかも知れない。現在の常識から過去の音声解釈を想像したり真否を議論するのはそもそも難しいかも知れない。
「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) p. 128 に鳴き交わしが収録されており、「キョウキョウキョキョキョ」などと表記されている。
バードリサーチ鳴き声図鑑にある植田睦之 2011-04-19 (2025.5 現在1件) は短いタイプの鳴き声。
自分が過去に記録したのも短いタイプのみで「さわがしく鳴き合う」状況はまだ聞いたことがない。キョウジョシギは見れば一目瞭然なので「鳴くまで待とう」と考える人はほとんどないかも知れない。
大橋 (2020) Birder 34(12): 66-67 で紹介の「鳥賞案子」(比野勘六 1800-1802) の飼育書の表記では京條鴫の表記もあり、"京女" の表記が安定していたわけではなさそう。中国語の用例を見ると京條 = 金條 の意味とありこれは金塊を表す。どちらの漢字も当て字かも知れない。
記載時学名 Tringa Interpres Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe and North America, restricted type locality, Gotland, Sweden (北米も含まれていたが後に Gotland 島に限定)。
interpres を種小名に持つ種にクリガシラジツグミ Geokichla interpres Chestnut-capped Thrush (東南アジア。縁はやや遠いがマミジロと同属) があり、Temminck (1828) が命名した。Merle messager のフランス名が記述され、こちらは黒と白の衣装と赤い帽子が当時の郵便配達人を思わせたためとのこと (The Key to Scientific Names)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Strepsilas 属 (strepsis ひっくり返すこと laas 石 Gk) となっていて、
Arenaria Brisson, 1760 がすでに命名した属名に対して Illiger (1811) が新たに与えた属名 (記述) だった (The Key to Scientific Names)。
ドイツ名 Steindreher 英名 Turn-stone などに合わせて作った属名だった模様。Illiger はラテン語・ギリシャ語由来以外の属名は不適切と考えていた (#アマツバメの備考参照)。
この記述ではキョウジョシギと Tringa Grenovicensis Latham が同属に含まれていて、後者はエリマキシギと同定されたもの。Brisson (1760) を有効とする現代の解釈では先取権もなく、属の記載としてもあまりまとまりのあるものでなかったが一時は有効と考えられていたと思われる。
現代のようにキョウジョシギを含む系統を分割する場合は Arenaria 属が現れる。
さらに Charadriiformes (BirdForum 2025.3) によればキョウジョシギを指した Morinella Meyer, 1810 が記載されている。Morinella collaris Meyer, 1810 (参考) と属提案とともにキョウジョシギを改名していた (#ノスリの備考参照)。
Morinella は #コバシチドリの備考参照。キョウジョシギなどいろいろなものを指して使われていたラテン名だった。Meyer の改名提案の背景には Linnaeus の interpres が語義不明あるいは誤りのため正したかった考えがあったのかも知れない。collaris は "首に特徴のある" でこちらもそれほど特徴ある種小名ではない。
英国にはキョウジョシギ類が他にいないのでイギリス英語では Turnstone だけでもこの種を指す。
英名の Ruddy Turnstone はアメリカにはクロキョウジョシギ Black Turnstone も生息するため区別する必要から。"Ruddy" を補ったのはアメリカ事情と考えてよい。この2種は英名の通り色彩は大きく違う。
OED によれば turn-stone は 1673 年に Ray の用例があり、当時のラテン名で Cinclus Turneri となっていた。Turneri は正規のラテン語ではなく、英語をラテン語風語尾にしたものらしい (一般には人名 Turner の疑似ラテン語属格とされる)。英語 turner はフランス語 tornere 由来でラテン語に直接由来しない。ラテン語では対応する名詞は tornator とのこと。おそらくこのように俗に作られたラテン語風名称もあり、期限を区切ってそれ以前の学名を無効とする理由の一つにもなったのだろう。
1732 年の用例では別名 Sea-Dottrel も挙げられていた。
ruddy turnstone は 1899 年 Palmer が用いたもので当時の学名を Arenaria morinella, (L.). としており、かつては北米の型のみを指していたとのこと。OED によれば現在の学名では Arenaria interpres morinella と亜種扱いとある。
記載時学名は Tringa Morinella Linnaeus, 1766 (原記載) で、Linnaeus の基産地は Sea coast of North America; Europe と北米もヨーロッパも含んでいた。
1766 年のこの版には Interpres も 1758 年版と同じような分布でそのまま載っているので、1758 年に先に記載したはずのキョウジョシギとの関係の理解が怪しかったらしい。
Catesby により coast of Georgia (ジョージア州沿岸) に限定され北米亜種となった (Avibase より)。
やはり ruddy turnstone の名称はアメリカ由来で本来は "アメリカキョウジョシギ" のような概念を指し、ヨーロッパのものは (common) turnstone と呼ぶのが普通だった。世界の英名の共通化傾向に合わせてしぶしぶ (?) 種名が Ruddy Turnstone となったよう。おそらく英国ではわざわざ Ruddy を付ける必要性はあまり感じられていないと思われる。common すら付けたくないかも。
[キョウジョシギ亜科の系統分類]
Cerny and Natale (2022) の分子系統樹を用いた Boyd によるキョウジョシギ亜科 Arenariinae の分類:
シギ科 Scolopacidae キョウジョシギ亜科 Arenariinae
ツアモツシギ属 Prosobonia
クリスマスシギ Prosobonia cancellata Kiritimati Sandpiper (絶滅種)
ツアモツシギ Prosobonia parvirostris Tuamotu (フランス領ポリネシアのツアモツ諸島)
タヒチシギ Prosobonia leucoptera Tahiti Sandpiper (絶滅種)
モーレアシギ Prosobonia ellisi Moorea Sandpiper (絶滅種)
キョウジョシギ属 Arenaria
キョウジョシギ Arenaria interpres Ruddy Turnstone
クロキョウジョシギ Arenaria melanocephala Black Turnstone
オバシギ属 Calidris
オバシギ Calidris tenuirostris Great Knot
コオバシギ Calidris canutus Red Knot (アラスカで繁殖し北米へ渡る)
アライソシギ Calidris virgata Surfbird (アラスカで繁殖し南米へ渡る)
エリマキシギ属 Philomachus (Calidris 属より分離)
エリマキシギ Philomachus pugnax Ruff
キリアイ属 Limicola (Calidris属より分離)
キリアイ Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper
ウズラシギ Limicola acuminata Sharp-tailed Sandpiper
サルハマシギ属 Erolia (Calidris 属より分離)
サルハマシギ Erolia ferruginea Curlew Sandpiper
アシナガシギ属 Micropalama (Calidris 属より分離)
アシナガシギ Micropalama himantopus Stilt Sandpiper
ヘラシギ/トウネン属 Eurynorhynchus (Calidris 属より分離)
オジロトウネン Eurynorhynchus temminckii Temminck's Stint
ヒバリシギ Eurynorhynchus subminuta Long-toed Stint
トウネン Eurynorhynchus ruficollis Red-necked Stint
ヘラシギ Eurynorhynchus pygmeus Spoon-billed Sandpiper
コモンシギ属 Tryngites (Calidris 属より分離)
コモンシギ Tryngites subruficollis Buff-breasted Sandpiper (北米北極圏で繁殖し南米に渡る)
ハマシギ属 Pelidna (Calidris 属より分離)
ミユビシギ Pelidna alba Sanderling
ハマシギ Pelidna alpina Dunlin
ムラサキハマシギ Pelidna maritima Purple Sandpiper (北米・ヨーロッパ)
チシマシギ Pelidna ptilocnemis Rock Sandpiper
ヒレアシトウネン属? Ereunetes (Calidris 属より分離)
ヒメウズラシギ Ereunetes bairdii Baird's Sandpiper
ヨーロッパトウネン Ereunetes minutus Little Stint
アメリカヒバリシギ Ereunetes minutillus Least Sandpiper
コシジロウズラシギ Ereunetes fuscicollis White-rumped Sandpiper
アメリカウズラシギ Ereunetes melanotos Pectoral Sandpiper
ヒレアシトウネン Ereunetes pusillus Semipalmated Sandpiper
ヒメハマシギ Ereunetes mauri Western Sandpiper
Calidris 属より分離としてあるものの中には日本鳥類目録 改訂第7版の属だったものが改訂第8版予定 (IOC などでも) で Calidris 属にまとめられたものが含まれる。統合前の属和名が与えられていたものはそれを引き継いでいる。
新しく分離されているのはサルハマシギ属 Erolia 以降のもので、それ以外は馴染みある属名であろう。
よく知られている通り Eurynorhynchus 属はヘラシギ1種に対して与えられたものでこのタイプ種を優先すればヘラシギ属になる。ヘラシギが特殊と考え、一般的種類を挙げればトウネン属になるだろうか。
Pelidna 属はハマシギがタイプ種で問題なし。
Ereunetes 属は難しく、タイプ種はヒレアシトウネンだが日本産種ではなく検討種のまま。この属は新世界の小型シギ類を表すとして分類的位置づけはわかりやすいが、いずれも日本で普通種ではないので一つには絞りにくい。ここではアメリカで普通の種であること、日本でも一定の知名度があることからタイプ種を属名に選択してみた。
改訂第8版の配列予定にも反映されているが、現在知られている分子系統分類ではトウネンとヨーロッパトウネンはそれほど近縁でない。改訂第8版の配列予定と Boyd のものはコモンシギの位置が異なる。
似たものや地理的特徴を活かした分類とするならば改訂第7版に近い Boyd の分類に近いものになるだろう。少々大きくても単系統にまとめられるものはまとめてしまう考え方だと Calidris 属にまとめてしまうことになる。
キョウジョシギ亜科 Arenariinae もそれほど適当な和名ではないかも知れないが、属名に由来すればこの名前になり和名使用例もある。
属学名由来は Erolia は #サルハマシギの項目に。
Micropalama mikros 小さい palame 手のひら (Gk)。
Pelidna pelidnos 青黒い、土色の (Gk)。
Ereunetes ereunetes 探すもの < ereunao 探す (Gk)。
-
オバシギ
- 学名:Calidris tenuirostris (カリドゥリス テヌイローストゥリス) 細い嘴の斑点のシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:tenuirostris (adj) 細い嘴の (tenuis (adj) 細い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Great Knot (knot はコオバシギ参照。英名由来は備考参照)
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
tenuirostris は rostrum 由来で -ros- の o が長母音でアクセントもある (テヌイローストゥリス)。
単形種。ロシア極北東端のみで繁殖する、主に東洋で記録される種類。
Totanus tenuirostris Horsfield, 1821 が記載時学名。基産地はジャワ島。Keeyo が現地名か。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Tringa crassirostris Temminck & Schlegel の学名 (crassirostris < crassus 厚い -rostris 嘴の) となっていた。現在の種小名とまったく反対の意味。
Fauna Japonica の記載, 図版。
Le becasseau a gros bec 大きな嘴の bekasseau (Calidris 属のシギ) との記載で新種と考えていた。日本の他ジャワ島やボルネオ島でも記録されるとある。この時点の比較対象はコオバシギだった。
Hartert (1910-1922) では p. 1588。
Horsfield (1821) が先に記載していたが記述が短く他種との判別情報が少ないために一時は無効と考えられていたよう。Hartert は標本が本種であることが疑いないのでこちらに先取権があると認められたよう。
Horsfield (1821) を認めない場合は次に早い命名はオーストラリアで採集された Schoeniclus magnus Gould, 1848 (参考) だったようで、Temminck and Schlegel の記載はわずかに遅かった。
Schoeniculus の属名は Rueppell (1845) が Schoeniclus Moehring, 1758 の属名を修正したもの。Schoeniculus minutus の学名で用いていた (ハマシギのこと)。
Gould (1848) の Schoeniclus magnus はこれに対応して "大きい" の意味と考えられ、比較対象はコオバシギではなくハマシギだった。この学名は Ogawa (1908) にも別名として載せられている。
実際に Schoeniclus magnus, Gould., Great Sandpiper (解説は次ページ) があり、英名は Great Sandpiper となっていた。形はハマシギと完全に同じだが大きさはエリマキシギ程度と記されている。
Great はそのまま引き継がれ、Sandpiper より Knot の方に系統的に近い判断から現在の英名になったものと想像できる。OED には great knot の見出しはないのであまり知られていない名称と想像できる。英国からは遠く離れた地域の特産種で英名への関心もそれほど高くなかったものだろう。
コオバシギよりも大きいので英名が Great Knot となる単純な理由ではなかった。
学名に慣れた人はすぐ気づかれるだろうが、Schoeniclus の属名はオオジュリンなどを含むホオジロ類にも使われた。Schoeniclus Forster, 1817。"オオジュリン属" として現在の Emberiza 属を分割することが考えられるが (#アオジの備考参照)、Schoeniclus Moehring, 1758 を有効と判定すればホオジロ類には使えないことになる。
Emberiza 属の分類が世界的にはあまり積極的に検討されていない (現状でロシアは例外) のはこの先取権の問題を解決する必要があるためかも知れない
[The Key to Scientific Names の情報を参考にしたがいずれに先取権があるかについては触れられていない]。
Schaanning (1929)
The nest and eggs of the Eastern Asiatic knot Calidris tenuirostris Horsf.
の4卵の発見報告の中に Johan Koren が採集した標本 (1917) ラベルに Tringa crassirostris が使われていたが、Schaanning のこの報告ではすでに Horsfield の学名が用いられていた。Ogawa (1908) に載せられてた学名は短期間のみ使われていたもののよう。
コンサイス鳥名事典には4卵の巣が知られているとの記述があるが、おそらく Schaanning の報告に基づいていると想像できる。
[巣の発見]
ロシアの繁殖固有種。ドイツ名 Anadyrknutt に現れるように人が比較的近づきやすい繁殖地はアナディリ周辺の限られた場所と考えられていたが、近年の渡り経路調査から実際はもっと広くこの認識とはだいぶ違っているらしいことがわかってきた (後述)。ロシア東北部で他はほぼ人里離れた場所。
Schaanning (1929) に記述されている Johan Koren が採集した4卵の標本 (1917) が最初のもの。
Tomkovich (2001, 2011 再掲) Breeding biology of the great knot Calidris tenuirostris (pp. 451-470) に写真はないが繁殖生態が述べられている。
この論文では Schaaning の記述は 1954 年の論文が引用されており、ロシアでは当初あまり知られていなかったかも知れない。
1970 年代にようやく2、3例目の巣と卵が記載された。その後も少数の巣が発見されたにとどまっていた。Dement'ev and Gladkov (1951) 時代には1例しか知られておらずそれに基づく記述になっている。Grebenistskij は 1885.5.18 に Beringa 島で標本を得て繁殖していると記述したが後の調査では見つからず確かな繁殖記録とは認められていない。
Tomkovich は 1993-1995 年の調査結果を紹介している。
Vorob'ev (1963) "Ptitsy Yakutii" (ヤクーチアの鳥) p. 114 ではヤクーチアの繁殖種とは述べているが巣はまだ発見されていなかった。山地で記録されており、河川上流部で繁殖している可能性も検討されている。#キアシシギの状況に似ている。
日本でもキアシシギよりは見聞の機会が少ないと思うが、ロシアでも珍しい鳥のようで North Eurasia Birds Watch のシベリアの写真サイトにも2024年9月現在まだ写真がない。
日本では普通種と呼んでよいと思うが繁殖実態は歴史的にも現在でも謎が多いよう。
Buyvolov and Baptidanov (2022) About the nesting of the great knot Calidris tenuirostris in goltsy altitudinal belt in Chukotka (pp. 250-251)
にチュコト半島での繁殖地の写真がある (巣などの写真はない)。
[ジオロケーターによる渡り経路、推定される繁殖地と驚くべき繁殖地食性]
オーストラリアからのジオロケーターによる経路論文 Lisovski et al. (2016) Tracking the full annual-cycle of the Great Knot, Calidris tenuirostris, a long-distance migratory shorebird of the East Asian-Australasian Flyway。
Movebank でデータも公開されている Tracking Great Knots along the EAAF。
越冬地で再捕獲が行われたもので、温度ロガーから抱卵時期も推定されている。繁殖時期は果実に大きく依存しており、繁殖地の北限が 70° までで果実が豊富に実る亜高山山地に限定されている可能性がある。
このためコリマ山脈から東とヤクーチアの中央から北部のやや分離した山地2地域の繁殖分布を持っている。過去に知られていた繁殖地のアナディリは分布のごく東端にあたる。
通常のシギ類の繁殖地を想定して低地を探したりなかなか見つからなかったらしいことが想像できる。
中継地や越冬地の食性からは繁殖地の食性は予想外に感じるが、Andreev (1980, 2011 再掲) To breeding biology of the great knot Calidris tenuirostris in Kolyma River Basin (pp. 556-560)
に胃の内容の調査結果が出ており、1羽のオスでは 90% 以上が植物質、実や種で他に昆虫なども入っていた。他の1羽ではヒマラヤスギのくるみの殻が 95% 以上を占めていた (シギなのにホシガラスのような食性!)。ひなの胃には半分以上が草など植物質、動物質のものも各種含まれていたことが記されていた。
Tomkovich (2001, 2011 再掲) ではこの食性のため同じく山地に住むトウネンと分布が異なる可能性も議論されている。
2021-2022 年香港からロシアへの2羽の初の衛星追跡の結果:
The first satellite tracking project - Great Knot Tracking。
意外にもオホーツク海近くのハバロフスク州北部とカムチャツカ北部にとどまっており、知られている繁殖地ほど北には達していない。これら個体はフィリピンやパプアニューギニアに達している。
これら2つの研究の個体は大陸を通る経路で日本は通っていない。
[櫛状の爪 (pectinated claw)]
オバシギの第 III 趾には櫛状の爪 [pectinate(d) claw, または櫛歯] があるとのこと (コンサイス鳥名事典アライソシギの項目より)。
Clayton et al. (2010) How Birds Combat Ectoparasites (#ヨシゴイの備考)
によれば近縁のコオバシギは持っていない (オバシギは調査されていない)。
アライソシギの項目に出てくるのは中継地 (や越冬地?) で好む環境が似ている (オバシギは岩石質の磯を好むので確かに似た点があるが、アライソシギはキョウジョシギに近い系統とのこと) ことを示唆したものだが、もしかするとオバシギの特異な繁殖地や食性にも関係があるのかも知れない。
アライソシギも沿岸部よりも内陸高地の岩石質ツンドラで繁殖するが繁殖生態はあまりよくわかっていないと wikipedia 英語版にある。
Clayton et al. (2010) のリストではシギではオグロシギの多くの個体が持っている。クロキョウジョシギ Arenaria melanocephala Black Turnstone には見られていないことから中継地の好みの環境にはあまり関係ないかも知れない。クロキョウジョシギは沿岸部で繁殖する。オグロシギは内陸の湿地とのこと。
[その他]
Sangster and Luksenburg (2024) Complete mitochondrial genome MK992912 of Great Knot (Calidris tenuirostris) is a chimera with DNA from Pacific Golden Plover Pluvialis fulva (Aves: Charadriiformes)
によれば He et al. (2020) The complete mitochondrial genome of Calidris tenuirostris (Charadriiformes: Scolopacidae)
の発表したミトコンドリアゲノムはムナグロとのキメラとのこと。このデータをもとに He et al. (2020) はヘラシギと近縁としていた。
別のグループの解析があるので MK341548.1 から BLAST を試してみると Calidris 属の中で最も古い分岐となる。次に古い分岐がキリアイ。とはいえ一部の種しか調べられていないのでコオバシギとの関係などはこの解析では不明。エリマキシギやハマシギは新しい系統になる。
特に他種との競合関係などは思いつかないがオバシギが限られた地域でのみ繁殖するのは古く分岐した系統の生態的弱みがあるのかも知れない。キリアイも数の少ない種類。
-
コオバシギ
- 学名:Calidris canutus (カリドゥリス カヌートゥス) カヌーテ王のシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:canutus (adj) デンマークからきた英国王 Canute (Cnut) の (canute -tus (接尾辞) 〜に属する); 音声由来との説もある
- 英名:Red Knot
- 備考:
calidris は由来となるギリシャ語は短母音なので長母音は現れないと考えられる。ギリシャ語同様に ca-li-dris の音節であれば冒頭にアクセントがあると考えられる (カリドゥリス)。ギリシャ語では -li- がアクセント音節。
ca-lid-ris と区切れるのであれば中央アクセントも可能だがやや無理があるかも。
canutus は自明ではないが語源とされる Canute (Cnut) の発音を拝借すれば "カヌートゥス" で落ち着きがよいと思われる。
別語源のラテン語 canutus (canus "白" 由来で "灰色、白髪の" など) があり、この単語であれば a と1つめの u が長母音で後者にアクセントがある。アクセント位置は同じなので冒頭を伸ばすかどうかの違いのみ。Cnut の綴りであれば伸ばしにくい。
シギの方の canutus は非常に起源の古い単語で The Key to Scientific Names によれば史上2つめに学名に用いられた種小名とのこと。起源が明瞭でないのはやむを得ない。
分布域はオバシギよりこちらのほうが広く、北米にも分布する。6亜種が知られる (IOC)。日本で記録される亜種は rogersi (オーストラリアの鳥類学者 John Porter Rogers に由来) 亜種コオバシギ と亜種不明とされる。Calidris 属のタイプ種。
英名 Knot も英国王 Canute (Cnut) 由来と考えられている。
[Calidris 属について]
現在ではごく当たり前に用いられる属名であるが、昔はそうではなかった。
Hartert (1910-1922) p. 1571 の時代には Linnaeus の用いた Tringa 属は多型であるとして複数の属に分割されていた。小型シギ類には Erolia 属 (Vieillot 1816。サルハマシギがタイプ種) の名称に先取権があると考えられて、ハマシギなどの多くの種は Erolia 属とされていた。
現在は Calidris 属にまとめているリストが多いが、Erolia 属と Calidris 属はタイプ種が異なるので分子系統解析で分離すべきとなれば Erolia 属が復活することもある。
Hartert は後に Calidris 属の名称 (著者不明 1804) が先に使われていることに気づき、Oberholser [1920。Richmond (1917) の指摘による] に基づいて Erolia 属は Calidris 属に改名する必要があると記した (p. 2212)。
1920 年ごろの話で、Calidris 属の名称はそれ以前はほとんど登場せず、我々に身近な小型シギ類は Erolia 属に分類されていた次第。
現在ではこの著者は Merrem と判明しており、Calidris Merrem, 1804 の扱いとなる (The Key to Scientific Names)。
Tringa Calidris Linnaeus, 1766 (参考) の学名が存在するので、これをそのまま属名に昇格したように見えるが、事情はそれほど単純でなかった。
Oberholser (1920) Tringa Auct Versus Calidris Anon によれば Tringa Calidris がそもそも何かも自明でなかったが、Calidris 属のタイプ種を決めるに当たってトートニムとなる Tringa Calidris Linnaeus, 1766 を採用すべきと判断した。
Linnaeus (この学名は Gmelin 由来) を引用して Tringa Calidris Bechstein, 1803 があり、記載内容もコオバシギのものと判定された。
この種はすでに Tringa canutus Linnaeus, 1758 と記載されていたため、タイプ種は Tringa canutus Linnaeus, 1758 = コオバシギ となった。
現在の Calidris の属名は種小名から昇格された形にはなっているが提唱された最初の時点では直接の昇格かどうか不明で、またその種小名を持つ種は後行シノニムとなって現在表面上現れない次第。
この文献にはそれ以前の事情も記述されており、Tringa Linnaeus の属名は別のグループを指す提案がなされていた (Tringa Linnaeus は多型なのでどのグループに割り当てるかはタイプ種の指定されていない段階では自明ではなかった)。
この移動の結果コオバシギに属名がなくなった。Canutus Brehm, 1831 の新属名が用いられた時期もあり、1910 年代でもまだ使われていた。
Calidris Merrem, 1804 の属名が発見された結果、Canutus の属名は使われなくなった。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire、Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には Tringa を用いており、Calidris は少なくとも見出しにはまだ現れなかった。Hartert (1910-1922) 以前は属をそれほど細かく分けていなかったことがわかる。
-
ミユビシギ
- 学名:Calidris alba (カリドゥリス アルバ) 白いシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:alba (adj) 白い (albus)
- 英名:Sanderling
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
alba は短母音のみ (アルバ)。
古い属名は Crocethia だった。kroke 小石 < krokale 浜 と theio 走る (Gk) で Billberg (1828) がミユビシギに対して付けた属名だったが現在は Calidris 属に含められた。よほど細かく分けない限り分子系統解析の結果から復活する可能性は低いと思われる。
記載時学名 Trynga alba Pallas, 1764 基産地 Coast of the North Sea (Avibase による)。"Tringa leucophaea" と Vroeg’s Cat. Coll. (1764) に与えられたもの (二名法に基づく文献でなく無効学名) について Pallas (1764) が記載した (参考)。
Hartert (1910-1922) では p. 1929。
ここまで見ると学名由来は単純明快に見えるが、Pallas (1764) の2年後に Tringa Calidris Linnaeus, 1766 (記載) があり、さらに同書に記載された Tringa Arenaria Linnaeus, 1766 (記載) があっていずれもミユビシギと同定された。
後者の方が早く現れるのでシノニムとみなせば Tringa Arenaria Linnaeus, 1766 の方が先行シノニムとなる。当時は Pallas の出版年の扱いが明確でなかった可能性があり Hartert (1910-1922) では 1766 年としている。すなわち取り扱い次第では Tringa Arenaria Linnaeus, 1766 に先取権が発生する可能性があった。
Pallas はバイカル湖で採集した "Sanderling" について Tringa Calidris Linnaeus, 1766 の方を採用し、新たに Trynga tridactyla Pallas, 1827 (現代の解釈では 1811) の新名を付けた (#ノスリの備考参照)。
Trynga と Tringa は綴りが違うので別扱いとの考えもあったかも知れない。Pallas の付けた名称で影響力もあり、tridactyla = 3本指の、は記述的学名として受け入れられていた時期があったかも知れない。
これらは整理されて同じものと判定され現在の学名に落ち着いたものと考えられるが、Tringa Calidris Linnaeus, 1766 が何者か判定されるのも時間がかかっていた (#コオバシギの備考参照)。
"ミユビシギ" に対応する学名や他言語名称が一時的にあったかも知れない。現在 "3本指の" を用いている言語もありイタリア語やスペイン語など。これらの言語では種小名に対応する部分がラテン語に対応する名称となっていて、tridactyla の種小名の学名が使われていた時期に命名されたのではないかと想像できる。
英名 Sanderling は OED によれば 1602 年にすでに用例がある。古英語 sand と古英語 yroling (耕す人) 由来の可能性があるとのこと。Hartert (1910-1922) でもドイツ語名は Sanderling となっていて英語と読み方だけが異なる。
Bechstein 時代には Sandlaeufer (砂を走る者) も用いられていたが現代ではこの用語は Psammodromus 属 (スナカナヘビ属) のトカゲを指す模様。こちらの方が属名の意味そのままなのでより適していて、鳥類学だけで名前を独占するわけには行かなかったよう。
和名は特徴を表したもの、あるいは上記 tridactyla の種小名やこれに由来すると思われる外国語名のいずれの由来も考えられるが、山階鳥類研究所標本データベースには採集年の記載のない古い「埼玉県産チドリ」の標本があり、チドリ (3本趾が一般的) とあまり区別されていなかっただろうことがわかる。
海外情報が入ってきてチドリではなくシギであることが明らかになったため、それまでチドリと考えていた根拠となっていた特徴だった3本趾を表す名称になったのかも知れない。
1889 年千葉県 Shimosa で採集のYIO-10377の標本があり、Stejneger (採集者) による ID とラベルに追記されているので、同定は国内では必ずしも自明でなく海外の採集者からこれはチドリではなくシギであると判定を受けていたのかも知れない。
世界的に分布する。2亜種が知られる (IOC)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種を認めない立場のようである。
Boyd では Pelidna alba。
[筋肉量を急激に増やせるミユビシギ]
Young et al. (2021) Extraordinarily rapid proliferation of cultured muscle satellite cells from migratory birds
muscle satellite cells (myosatellite cells 衛星細胞。筋肉幹細胞) を培養して細胞分裂周期を調べた結果、ミユビシギとエリマキシギは分裂周期が非常に短かったのに対して、ヒメハマシギやスズメ目の渡り鳥ではそのような特徴はなかった。渡り距離そのものではなく、1回の飛翔で飛ぶ距離に関連している可能性がある。
長命の鳥でも加齢に伴ってヒトや他の哺乳類のような筋力低下をあまり起こさない。ミユビシギも長命である証拠があり筋肉の再生機能とも関係があるかも知れないとのこと。
[3本趾の理由?]
#アカゲラ備考 [キツツキの力の釣り合い] で後ろ趾を省略した方が素早い動きが可能かも知れないと少し触れてみた。ミユビシギでは波打ち際で地面が現れた瞬間に急いで採食する行動が印象的だが (ただし開発の進んだ日本の海岸の事情を反映している可能性もあり、本来生態と同じかどうかは知らない)、この際に短時間に多くの食物を得るために素早い動きが可能な方が有利なのではないかと感じた。
#ダイゼン備考の [Squatarola 属] にあるようにチドリ類では一般的でミユビシギはチドリ類への生態的収斂の結果だろうか。
[北米のミユビシギの鳥インフルエンザ感染]
Andreasen et al. (2025) Clade 2.3.4.4b Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Pathology in a Common Shorebird Species (Sanderling; Calidris alba) in Virginia, USA
シギ・チドリ類は小型で死体回収も難しいため研究が難しかったが、基本的な病変は水鳥と同様だった。
2024 年 3-4 月に複数種を含む集団死事例に含まれていたため研究が可能となった。
-
ヒメハマシギ
- 学名:Calidris mauri (カリドゥリス マウリ) マウリのシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:mauri (属) イタリアの植物学者 Ernesto Mauri の
- 英名:Western Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
mauri は人名由来で疑いはないが、同じ綴りの maurus ("黒っぽい" など) の変化形がある。"マウリ" の発音となるが、後述のように Bonaparte が後に訂正したようにもう少し気を配って学名を付けていれば変な意味の誤解は発生せずアクセントも適切な位置となったと思われる。人名由来であることを知らない人には maurus の変化形と受け取られるだろう。
後の訂正だったため原初の綴りが有効となっている。
北米の種で単形種。
Boyd では Ereunetes mauri。
記載時学名 Ereunetes Mauri Cabanis, 1857。
原記載 によれば Bonaparte (1838) が Heteropoda Mauri と名付けていたよう。
The Name of the Western Sandpiper (1906) によれば Bonaparte は名前を与えたが記載をしなかったとのこと。
現在ではヒレアシトウネンと同定されるものを Heteropoda semipalmata Wilson として比較を残しているが不明だったものを、Gundlach (1856) が2種のシギの大きい方に Bonaparte の与えた学名 Heteropoda Mauri を採用したとのこと。原記載は Gundlach の回答を引用する形で Cabanis が記載したもの。
なぜイタリアの植物学者が関係するのかはこの記載からはわからなかったが、Palmer (1931) The Scientific Name of the Western Sandpiper - Whi was Mauri?
が文献調査の結果解明した。Ernesto Mauri (1791-1836) と Bonaparte は友人の関係で魚 Smaris maurii にも学名を与えているとのこと。Heteropoda Mauri の命名は Mauri の死去の2年後にあたる。
ヒメハマシギも Bonaparte 自身が 1856 年に Ereunetes maruii の綴りに訂正したとのこと。
かつては Ereunetes occidentalis Lawrence, 1864 の学名が広く使われていたが Dubois (1904) の指摘で Ereunetes marui に変更されたとのこと。
-
トウネン
- 学名:Calidris ruficollis (カリドゥリス ルーフィコルリス) 赤い首の斑点のあるシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:ruficollis (adj) 赤い首の (rufus (adj) 赤い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Red-necked Stint
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
ruficollis は冒頭が長母音で -col- がアクセント音節 (ルーフィコルリス)。多くの種類の学名に使われる種小名や亜種小名。
単形種。
記載時 Trynga ruficollis Pallas, 1776 でこの記載はヨーロッパトウネンより早い。
トウネンとヨーロッパトウネンが同種とされていた時期もあった。Dement'ev and Gladkov (1951) は別種として現在の学名で記述しているが、解説には亜種とする立場も紹介されおり当時の概念の生物地理学上の姉妹関係 (ロシア語 vikariat) にあるとする研究者もあると述べている。
もし同種にする場合は Calidris ruficollis で、ヨーロッパトウネンはその亜種 minuta とすべきであるが vikariat は当時すでに証拠とみなされなくなっていたとのこと。Portenko (1939) によれば東シベリアで両種が見られるなど分布には曖昧さが残る。Dement'ev and Gladkov (1951) は計測値には明瞭な違いがあることから別種と判定した。
オーストラリアでこの亜種名を用いた報告 (1957) があった Relationship between some Coastal Fauna and Arthropod-borne Fevers of North Queensland。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Tringa ruficollis を用いていた (別種の立場かどうかは不明)。
別名に Tringa albescens Temminck が挙げられているが出典は今のところ不明。Fauna Japonica にはこの種は記載されていない。
少し古い時期であるが Calidris 属は単系統でないと指摘され、「小型オバシギ類」として知られる一部の種 (イギリス英語で stints、アメリカ英語で peeps) を別属とすることもある。
この際にしばしば用いられる属名が Erolia [サルハマシギについて Vieillot 1816 が与えたフランス名 erolie から < erro さまようもの、迷い鳥 (L) lian 非常に (Gk), The Key to Scientific Names] であるが、Erolia 属の元来のタイプ種であるべきサルハマシギの分類的位置づけが確定しておらず、どこまでをこの属にするかがはっきりしていない。
日本の種類で Erolia 属 とも呼ばれる種類は ヒメハマシギ、トウネン、ヨーロッパトウネン、オジロトウネン、ヒバリシギ、コシジロウズラシギ、ヒメウズラシギ である。
またミユビシギを Crocethia (kroke 小石 theio 走る Gk) 属とする考え方もあり、こちらに分類される可能性もあるとのこと (以上 wikipedia 英語版より)。
Thomas et al. (2004) A supertree approach to shorebird phylogeny を参照。
この研究は少し古いのでもう少し新しいデータが出てから再検討されそうである。
Boyd では Eurynorhynchus ruficollis。
-
ヨーロッパトウネン
- 学名:Calidris minuta (カリドゥリス ミヌータ) 小さな斑点のあるシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:minuta (adj) 小さい (minutus)
- 英名:Little Stint
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
minuta は u が長母音でアクセントもある (ミヌータ)。
単形種。別名ニシトウネン。ロシア中部の極北で繁殖し、主にヨーロッパ等を通過してアフリカやインドなどで越冬する。
記載時 Tringa minuta Leisler, 1812 (原記載)。
当時の比較対象はオジロトウネンで同じ文献で記載されたもの。
ロシア名は kulik-vorobej とスズメのようなシギ。英名も学名によく相当している。
Boyd では Ereunetes minutus。
茂田 (1994) Birder 8(9): 42-47 にトウネンとニシトウネン (1) で総論と他の類似種との識別、
Birder 8(10): 45-53 にトウネンとニシトウネン (2) にトウネンとヨーロッパトウネンの識別、初記録とされたヨーロッパトウネンと思われる個体の検討が出ている。
Young Guns (2016) Birder 29(12): 44-47 にもこの2種の識別に関する記事がある。
-
オジロトウネン
- 学名:Calidris temminckii (カリドゥリス テムミンキイ) テミンクのシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:temminckii (属) temminckの (ラテン語化 -ius を属格化)
- 英名:Temminck's Stint (オランダの動物学者 Coenraad Jacob Temminck)
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
temminckii は -ck- を分割する発音も考えられるが原音に近いものを採用した。"テムミンキイ" で最後は ii と並ぶことに注意。
単形種。ユーラシア極北で広く繁殖する。
原記載 Tringa Temminckii Leisler, 1812。Temminck の鳥類学への功績に対して献名されたことはこの前ページ (p. 63) にある。
この種の最初の定義部分に Die drei ausseren Schwanzfederen weiss とあり、これをそのまま訳せば "尾の外側3枚の羽が白い" となり、定義 (この特徴を持つ Tringa 属は他にないの意味の定義) をそのまま和名にすればオジロトウネンとなる。和名は原記載のドイツ語由来と考えてよさそう。
和名と同じ意味の名称を用いているのはロシア語、ウクライナ語など。Temminck の人名をそのまま用いている言語も多い。"小型" を付けている言語もいくつかある。wikipedia 英語版では冬羽はほとんど (ヨーロッパでは最も普通の) イソシギの小型版とあるのでおそらくこの対比を意味するのだろう。
Hartert (1910-1922) では p. 1581。ドイツ語名では "テミンクのシギ" 以外に Grauer Zwergstrandlaeufer: grauer 灰色の zwerg- 矮小の Strand 浜 Laeufer 走るもの、とあまり特徴を捉えた名称でない。Zwergstrandlaeufer がヨーロッパトウネンのドイツ語名なのでその灰色版との扱い。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) によれば英国での識別対象種はヨーロッパトウネン (トウネンは亜種とされた時代の可能性がある) で、現代と特段違うわけではないがオジロトウネンのように尾に白色部がない点が識別点の一つとなっていた。
Leisler (1812) (ヨーロッパトウネンの原記載の一部) にヨーロッパトウネンとオジロトウネンの比較がある。ヨーロッパトウネンを他種と異なることを示すために他の各種と比較を行っている。
声もまったく異なるとの記述がある。pp. 79-80 の比較表に色彩の識別点が出ており、尾についても記載がある (p. 79 の下から2つめ)。オジロトウネンでは尾の羽の外側が純粋な白色でヨーロッパトウネンでは淡灰色となっている。現代の野外識別では別の点に注目することが多いが、標本を見て、あるいは飛んでいる姿を見て識別したポイントの一つになっていたよう。
"純粋な白色" はそれなりに目立つ色彩なので名称に採用されても不思議ではないが、名前からもっと白いのかと想像された経験のある方は多いのではないだろうか。他言語で同様の名称を用いているものは原記載の定義に基づくものである可能性は高いと考えられる。
この名称がさまざまな言語にあまり残っていないのはやはり "オジロ" から受ける印象と実物が異なるためではないだろうか。
名付けられた Temminck 自身による 記述 もあった。フランス語名 Becasseau Temmia とやや控えめな名称になっている感じがある。図版が出ているが尾羽の白い部分がわかるように描いているように見えるが説明も特になく、意味を知った上で意識して図版を見ないとわからないレベルかも。あるいはわかる人にはわかる図版を意識しているとも言える。
別学名に Pelidna gracilis Brehm, 1855 があった (資料) が Leisler (1812) よりはずっと後の時代。gracilis ほっそりした、優雅ななどの意味。
Yet another thread on eponyms... But this one might actually be fun!
に人名の付く鳥の英名から人名を排除した場合にどのような代替名があるか考察がある。オジロトウネンも検討されている種で、White-tailed Stint も候補の一つに登場している (かつて使われたことのある英名なのかも知れない)。
Yet another thread on eponyms... But this one might actually be fun! によれば (広義) Calidris 属の中でこの特徴はこの種が唯一とのこと (記載時 Tringa 属時の特徴記述そのまま)。
スウェーデン語の名称 mosnappa の由来についても説明があり、mo- はヒース (荒れ地) を指す言葉とのこと。
Boyd では Eurynorhynchus temminckii。
[音声]
自分は内陸に住んでいることもあってシギ・チドリとは比較的縁が薄いのであまり大きなことは言えないのだが、皆さんはシギ・チドリを観察される際に音声にどの程度注意を払われているだろうか。
外見や行動、環境で識別が可能で、ムシクイ類のように音声が識別の決め手となる例はあまりないような気がする。外見の識別が比較的難しい種類でも、あまり鳴いてくれないか声が目立たないので (図鑑には書いてあっても) あまり参考にならない気がする。カラフトアオアシシギはアオアシシギと声が全然違うとは書いてあってもそもそも鳴かないと識別材料に使えないし、この組み合わせは姿は似ていても行動の違いが目立つので採食しているところが観察できればあまり悩まないのではと思う。
経験豊富な方は音声が役に立つものにどんな例があるか考えていただけると面白いかも知れない。
図鑑的には音声が識別の決め手となる組み合わせにオオハシシギとアメリカオオハシシギがあるが、後者は珍しい種類なので「鳴くまで待って」識別する必要があった人は少ないのではないかと思う。
その中でオジロトウネンはやや役に立つ気がする。もっとも類似種と好む環境が違い (そのため内陸の冬場で比較的出会いやすい)、外見だけで識別可能なので音声はあまり気にされないかも知れない。
探鳥を始めたころはあらゆる鳥の声が新鮮に思え、探鳥会などで「あの声は何ですか?」「シジュウカラ」、「それではあの声は?」「あれもシジュウカラ」のようなやりとりで納得し難い思いをされた方もあるだろう。しかし慣れてくると身近な鳥をいちいち気にすることがなくなって行くものである。
これを自分は勝手に「ヒヨドリフィルター」とか「スズメフィルター」とか称したりしている。珍しい鳥の声に敏感に気づくためにはこれらのフィルターはやはり大事だと思う。
外国人を案内したるすると彼らにとってヒヨドリの声がいかに珍しいかがよくわかる。「あの声は何ですか?」「ヒヨドリ」というのを延々くり返し、相手も次第に飽き飽きする (いや、こちらが飽きていることを察されているのかも知れない) 様子が見えてきたりする。
これが進むと「シジュウカラフィルター」などができてきて次第に身近な鳥の声は気にしなくなるものであるが (あまりよくないのかも知れない。探鳥会の鳥合わせの時に絶対いたはずの種類をどこで聞いたか思い出せないことは皆さんも経験されているであろう)、オジロトウネンでこれをやってしまった。
ご存じの方はおわかりと思うが、この鳥の声はカワラヒワに似ているのである。つまり「カワラヒワフィルター」が一瞬働いて、いや違うと気づいた時には数少ない録音のチャンスを逃してしまったのである。
オジロトウネンはそれほど頻繁に鳴く鳥ではなく、蒲谷鶴彦・松田道生「日本野鳥大鑑 鳴き声420」にもバードリサーチ鳴き声図鑑にも (今のところ - この部分を執筆当時の状況) 音声が収録されていない (その後 2024.10.6 の記録を簗川堅治氏がアップロードされていた)。音声的にはやや通好みの種類と言えるかも知れない。
その時聞いた声がこれまでで一番大きく聞こえたもので、その後も挑戦しているがなかなかよい条件で記録できず、今も惜しかった思い出になっている。ここまで読まれればオジロトウネンの声がどういうものか確実に覚えていただけるだろうし、また野鳥録音家がどんなことに関心があるかも多少理解していただけるのはないかと思う。
これは中継・越冬地での flight call に相当するもので、繁殖地での求愛飛行の際の声 (song) は少し異なっていて長く続く。wikipedia ロシア語版ではコオロギに似ているとある (音声サンプルもあり)。
配偶システムは特殊でオスがまずテリトリーを確立してメスが産卵してオスがこれを抱卵する。メスは別のテリトリーに移動してつがい、別のクラッチを抱卵する。最初のオスは別のメスとつがうこともできてこの場合はオスのテリトリー内でメスが別のクラッチを抱卵する。ネズミに似た特殊な採食様式で水たまりの縁に沿ってしのび寄って昆虫など小動物を食べる (wikipedia 英語版より)。
wikipedia ロシア語版にも生息地の写真を含めた解説があり文献も記されている。
英語で読める文献では Hilden (1975) Breeding system of Temminck's Stint Calidris temminckii のフィンランドの研究が先駆的で同著者による後続論文もある。ロシアの繁殖地はアクセスが難しく研究が思ったほどない。
-
ヒバリシギ
- 学名:Calidris subminuta (カリドゥリス スブミヌータ) ヨーロッパトウネンに似たシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:subminuta minuta (ヨーロッパトウネンの種小名) に近い、似た (sub-)
- 英名:Long-toed Stint
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
subminuta は u が長母音でアクセントもある (スブミヌータ)。
単形種。学名の subminuta は
ロシアやモンゴルの内陸部や沿岸で局地的に繁殖。
原記載 (Middendorff 1853)。当時の識別対象種はオジロトウネン。基産地はスタノボイ山脈西斜面と Uda ウダ川河口近く (オホーツク海西岸)。
種小名に使われる subminuta/subminutus はこの種類では上記の意味。「やや小さい」の意味で使われる学名もあり、ササフミフウズラ Turnix varius Painted Buttonquail のシノニムに登場する (The Key to Scientific Names。登場する用例はこの2つ)。
これもロシア東部を中心に繁殖する種類で繁殖地情報が乏しい。Dement'ev and Gladkov (1951) では 1930 年に Bering 島で最初の巣がみつかり、1944 年にマガダン郊外で次の巣が見つかったとのこと。
野外識別情報はヨーロッパトウネンと同様とありそっけない。そのためより確実な解剖学的特徴をもとにして英名・ロシア名とも共通の意味になる Long-toed Stint が付いたものと想像できる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Tringa damacensis Horsfield の学名となっており和名は現在と同じ。
Results of ornithological explorations in the Commander Islands and in Kamtschatka (Stejneger 1885)
によればこの学名は Totanus damacensis Horsfield 1821 によるもの (記載) が最初で、Stejneger (1885) が過去に使われた各種学名の同一性などを検討している。
Horsfield (1821) を見ていただいて容易に理解できるように情報があまりに乏しく、同定が不確かなものが多かったようで、後により確実な記述の残る Calidris subminuta が採用されたものと想像できる。
当時はどの学名を用いるか不定性があり、Actodromas damacensis が採用されていたが (Actodromas は#ヒメウズラシギを参照) Long-toed Stint の英名をすでに用いていた。
過去に用いられた学名には "趾が長い" を意味するものはなかった。
damacensis は東インド時代のジャワ島北東部の Damak/Damack (現在の Demak) 由来 (The Key to Scientific Names)。Horsfield (1821) もオジロトウネンとともにジャワ島で越冬地のシギ類を記述したもの。先取権や記載の有効性の解釈次第で damacensis の名前が残っていたかも知れない。
AOU も (途中属名は変わっているが) 3rd edition (incl. 18th suppl.) までこの種小名を採用していた。アメリカとヨーロッパで見解が長い間対立していたが AOU が合わせた模様。
アメリカでは アメリカヒバリシギ Calidris minutilla Least Sandpiper が主な識別対象種で、非常によく似ているが趾が特に長いなどの記述が見られる。
参考: Stint Identification (Dare to Bird 2017)。中央の趾は嘴より長い。
Ogawa (1908) も別学名 Tringa subminuta を載せている。
Boyd では Eurynorhynchus subminuta。
アメリカヒバリシギも国内記録されている: 石橋・城石 (2024) 北海道小清水町におけるアメリカヒバリシギ Calidris minutilla の日本初記録。
種小名の minutilla は「非常に小さい」の意味。
かつてはヒバリシギがアメリカヒバリシギの亜種とされたこともあり、英名もアメリカヒバリシギの Least Sandpiper が用いられていたことがあった (コンサイス鳥名辞典)。アメリカヒバリシギの原記載 (Vieillot 1819) とこちらの方が早い。
Le tringa maringouin のフランス名で、maringouin はカ (蚊) のこと。非常に小さく数も多く、地上でも空中でも近接した群れをなしていることからカのようなシギと名付けたとのこと。現在のフランス名は変更されていて種小名に合わせて Becasseau minuscule と小型のシギに相当する名前になっている。
似た名前ではヒバリチドリ科 Thinocoridae の名称もある。英名は seedsnipes。ヒバリチドリそのものの和名を持つ鳥はいない。コヒバリチドリ Thinocorus rumicivorus Least Seedsnipe を見ると確かに配色はヒバリに似た感じもする。調べた範囲でスズメ目以外でヒバリを冠した名前を持つのはこれらのみか。
-
コシジロウズラシギ
- 学名:Calidris fuscicollis (カリドゥリス フスキコルリス) 黒ずんだ首のシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:fuscicollis (adj) 黒ずんだ首の (fuscus (adj) 黒ずんだ collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:White-rumped Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
fuscicollis は短母音のみで -col- がアクセント音節 (フスキコルリス)。
英名・和名と学名の関係が悪い。無効名となっている Tringa leucopyga Lichtenstein, 1818 (参考) の学名があり意味は一致するがコシジロウズラシギを指すものかどうかはわからなかった。基産地はアメリカなので矛盾しない。
CHARADRIIFORMES Waders, skuas, gulls, and terns (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealand) の情報によれば Heteropygia fuscicollis の学名が与えられていた時期があった。
Coues (1861) による1種のみ (当時は2種だったがシノニムとなった) を含む属で "異なった腰の" の意味。属記載中には white upper tail coverts の表現がある。さらに Delopygia (delos はっきりした puge 腰 Gk) の属名も同時に提案され、もし Heteropygia が preoccupied だった場合の代替名とのこと (The Key to Scientific Names)。
いずれの属名も目立った腰を表したもので、着眼点は最初に記載された Tringa fuscicollis Vieillot, 1819 の学名より適切で、属名を与えることによってより明瞭な特徴を表す意図があったかも知れない。特に分離した系統ではなかったためこの属名は統合されてしまうこととなった。
英名や和名はこの当時の属名や記載に由来していた可能性がありそう。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。北米極北で繁殖し、主に南北アメリカとヨーロッパの種類。
Actodromas bonapartii Cassin の学名も使われたことがあり、ロシア名はこれにちなんで Bonapartov pesochnik。
Boyd では Ereunetes fuscicollis。
-
ヒメウズラシギ
- 学名:Calidris bairdii (カリドゥリス バイルディイ) ベイアードのシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:bairdii (属) baird の (アメリカの動物学者 Spencer Fullerton Baird のラテン語化 -ius を属格化)
- 英名:Baird's Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
bairdii はラテン語読みとした。"バイルディイ" のアクセントと考えられる。原語からはかなり離れる。語末に ii が並ぶことに注意。
単形種。北米とロシア東端の極北で繁殖。
記載時学名 Actodromas (Actodromas) Bairdii Coues, 1861。原記載。
Actodromas bonapartii Cassin (White-rumped Sandpiper コシジロウズラシギのシノニム) と計測値が少し異なることも示されているが当時はまだ関係が明瞭でなかった模様。
当時の属名の Actodromas は akte, aktes 海岸 dromas 走る (Gk)。ヨーロッパトウネンをタイプ種として Kaup (1829) が付けた属名。
Boyd では Ereunetes bairdii。
-
アメリカウズラシギ
- 学名:Calidris melanotos (カリドゥリス メラノートス) 黒い背中のシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:melanotos (合) 黒い背中の (melan- (接頭辞) 黒い nota 後部 Gk)
- 英名:Pectoral Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
melanotos は起源となるギリシャ語 notos の冒頭の長母音を引き継ぎアクセントもここにあると考えられる (メラノートス)。
単形種。
種小名に maculata が用いられたことがしばしばあったが、この2つの学名は Vieillot (1819) が同じ本の中で記述したものでシノニム。melanotos の方が先に現れるのでこちらが使われることになった (Dement'ev and Gladkov 1951)。
CHARADRIIFORMES Waders, skuas, gulls, and terns (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealand) によれば、
過去に使われた学名に Pelidna pectoralis Say, 1823 (参考) や属が変わった Limnocinclus pectoralis などがあり、pectoralis の種小名は長く使われていたと考えられる。
胸がくっきりした境界を持った班をなしていることを表した名称だが、英名はこの学名とよく対応していて相互に関連があると思われる。北米とヨーロッパで別の学名が使われていた時代があったと想像できる。
北米とロシア東部の極北で繁殖。ユーラシア北部で繁殖する個体も北米を経て越冬地に渡るとのこと。
[睡眠時間を限界まで削ってつがい形成]
アメリカウズラシギは極北で3週間のつがい形成時期にほとんど寝なくても能力が維持されていることが示されている: Lesku et al. (2012) Adaptive Sleep Loss in Polygynous Pectoral Sandpipers。
睡眠時間の短い個体ほど子孫を残せる結果となっている (さらなる解釈は#オオグンカンドリの備考参照)。
[Cox's Sandpiper]
オーストラリアで 1955 年 John B. Cox が変わったシギを発見、最初はハマシギと同定されたていたが、1968-1975 年にさらに類似個体の目撃があり、1986 年までに 20 個体以上に達したという。
未記載の亜種との考え方もあったが、1981 年に生きた個体が捕獲され撮影され、Shane Parker が 1982 年に新種 (Calidris paramelanotos) として発表して一度は図鑑にも載った。paramelanotos は para (近い Gk) で、アメリカウズラシギに近縁であることを表した学名。
同様の個体は過去にも見出されていて William Cooper が 1833 年に採集した標本に基づき、Spencer Fullerton Baird が 1858 年に Cooper's sandpiper (Tringa cooperi) と記載していたが、Cox's sandpiper とは別物と考えられた。
2001 年日本の茨城県新利根町でもアメリカウズラシギとサルハマシギの両方の特徴を持つ個体が撮影され Birding World に掲載された [Ujihara (2002) "An apparent juvenile Cox's Sandpiper in Japan". Birding World. 15(8): 346-347]。
この個体は Cox's sandpiper の若鳥と考えられたとのこと。
1996 年に3標本が解析され、cyt b 遺伝子がサルハマシギ、アロザイムはサルハマシギとアメリカウズラシギの両者のパターンを示し、オスのアメリカウズラシギとメスのサルハマシギの雑種と判明した
[Christidis et al. (1996) Molecular Assessment of the Taxonomic Status of Cox's Sandpiper]。
Haldane's rule に従い、記録された大部分はオス個体だったとのこと (以上 wikipedia 英語版より)。Haldane's rule (ホールデンの法則 1922) については例えば 異種ゲノムの不適合性が引き起す雑種の不妊・発育不全現象の遺伝的制御機構 などを参照。wikipedia 英語版の解説も詳しい。
近年でも同様の個体の報告がある。Gunby (2018) First record of Cox's sandpiper (Calidris x paramelanotos) for New Zealand (ニュージーランド)。Ornithological Society of New Zealand は記録として認めたとのこと。
渡辺・三河 (2004) Birder 18(5): 64-65 にもこのシギについてのコラムがあり、数年前 (当時) に御前崎でビデオ撮影され、昨年も出た噂があったとのこと。このコラムでは種、ハマシギの亜種、雑種のいずれの可能性も指摘されていた。
上記のようなアメリカウズラシギの繁殖地での熾烈な配偶者争いを知ると頻繁に雑種ができてしまうのも何となく納得できてしまう。
サルハマシギの繁殖地でのディスプレイ時の声や行動がアメリカウズラシギに似ているとのこと (コンサイス鳥名事典)。
アメリカウズラシギは基本的に北米を経て越冬地に渡る点も興味深い。Cox's sandpiper の目撃例が圧倒的にオーストラリアに多く北米では少ないので交雑によって渡り習性も変わり、サルハマシギの越冬地 (アジア・オーストラリア・アフリカ) を目指すようになったものか、あるいは中間的な方向を目指して一部個体のみが到着できているものなのかなど解釈があってもよさそうな気がする。
アメリカウズラシギにとってサルハマシギよりも近縁な種類が他にもあるので雑種形成が起きているかも知れないが、サルハマシギとの雑種個体に比べて渡りルートが適切な方向を向かないなど生存に不利なのかも知れないなど憶測も思い浮かぶ。
メカニズムがそこまで確実に検証されているとは言えないかも知れないが (スズメ目以外で) カラフトワシとアシナガワシの交雑個体の渡りルートの追跡報告がある (#カラフトワシの備考 [交雑と渡り] 参照)。
Haldane's rule の野外検証
大型カモメ類の雑種における Haldane's rule の野外再捕獲による検証: Neubauer et al. (2014) Haldane's rule revisited: do hybrid females have a shorter lifespan? Survival of hybrids in a recent contact zone between two large gull species
Haldane's rule の通り雑種のメスの生存率が 25% 程度低かったとのこと。法則通り生殖隔離をもたらす方向に働いていると考えられる。
交雑帯での introgression (遺伝子浸透) の研究の多くもこの機構に沿う結果となっている (Z 染色体で introgression がより少ない): Ottenburghs (2022) Avian Introgression Patterns are Consistent With Haldane's Rule。
この検証目的にはゲノム研究は非常に役立つと考えられるとのこと。
Haldane's rule 提唱 100 周年のレビュー: Cowell (2023) 100 years of Haldane's rule。
歴史的に面白いところでは Faster‐male theory (オスの生殖細胞の方が進化が速い。ZW 型の鳥では逆になることが期待される)。Faster‐X theory (X 染色体のほうが進化が速い。鳥の Z 染色体も同様。この時点ではあまり研究がなかった) などがあって理論的説明の限界も指摘されている。XY 型と異なる ZW 型の鳥類で効果を実証的に調べることはやはり大切なよう。
多少関連する話題で Fallahshahroudi et al. (2025) A male-essential miRNA is key for avian sex chromosome dosage compensation
一般的な哺乳類ではオスに X 染色体が2本、オスでは1本と雌雄で異なり、メスでは片方が不活化 (転写調節) されてバランスを保っている機構 (有胎盤類と有袋類では異なる) などが知られている。
鳥ではオスが ZZ で逆のパターンとなっているが、このバランスの機構が不明であった。この研究で Z 染色体のマイクロ RNA (microRNA) miR-2954 をオスのニワトリ胚でノックアウトしたところ早期に胚が死亡したとこのこと。microRNA が鳥のオスの生存に重要な役割を果たしていると考えられる。
マイクロ RNA は 2024 年のノーベル生理学・医学賞のテーマだった。当時の日本語解説も応用ばかり取り上げられてあまりこなれていなかった感じがするが "これまで知られていなかったタイプの遺伝子スイッチ" の表現でほぼよいのでは。DNA から転写されてタンパク質をコードする mRNA とは別の機構。
-
ウズラシギ
-
サルハマシギ
- 学名:Calidris ferruginea (カリドゥリス フェルルーギネア) 鉄錆色のシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:ferruginea (adj) 鉄錆色の (ferrugineus)
- 英名:Curlew Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
ferruginea は u が長母音で i がアクセント母音 (フェルルーギネア)。
単形種。ロシア中部から東部の極北で繁殖。
原記載は Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763 (Danske Atlas)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Tringa subarquata (Guldenstadt) の学名となっている。subarquata は arquata (L) = 英語 curlew で小さなダイシャクシギ類 (curlew) の意味。嘴が少し下に曲がる特徴を捉えたもの。英名 (または古い学名) と和名の両方を把握しておくと識別点の理解にも役立ちそう。
この記載時学名は Scolopax subarquata Guldenstadt, 1775 だった。
ちなみに中国名でも弯嘴が用いられている。ロシア名も覚えやすく krasnozobik (赤いそのうまたは胸) で現地映像などでもよく登場する種類。
Ogawa (1908) ではこの学名を Bruenn. によるものと記述しており、この時点では Pontoppidan の記載がまだ見つかっておらず当時知られていた学名では Scolopax subarquata の用例の方が古かった可能性がある (Danske Atlas については#キリアイの備考参照)。
Tringa subarquata Temminck となっているものもあるが、Pygmy Curlew のように Gould の図版で用いられたため広まった用例かも。Temminck 以前に Guldenstadt が用いていたことはこの時点では知られていなかった可能性がありそう。
古い学名の意味とともに Gould の図版でも英名は小さなダイシャクシギの扱いで、英名に curlew を残して Curlew Sandpiper となったのは自然な流れだったのだろう。
さらに別の学名があって Scolopax testacea Pallas, 1764 の記載があった。testacea はレンガ色のなどの意味。この種小名を用いた Calidris testacea は Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) で用いられていて、BOU が比較的最近まで採用していたことがわかる。
Guldenstadt (1775) よりも古いのでこちらに先取権があると考えられた時代のものだろう。Pontoppidan (1763) の用例が発見されて学名が元に戻ったと推定できる。
Dement'ev and Gladkov (1951) でもこの学名 Calidris testacea が採用されていた。
Boyd では Erolia ferruginea。
-
チシマシギ
- 学名:Calidris ptilocnemis (カリドゥリス プティロクネーミス) 脚に羽毛のある斑点のあるシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:ptilocnemis (合) 脚に羽毛のある (ptilon 羽毛、kneme 脚 Gk。The Key to Scientific Names)
- 英名:Rock Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
ptilocnemis は外来語由来の合成語で発音はわからないが、kneme の e が2つとも長母音。ギリシャ語から作られた解剖用語のラテン語 cnemis も e が長母音でここにアクセントがあると考えられる (プティロクネーミス)。
一般用語でもよく現れる腓腹筋は gastrocnemius muscle。解剖用語を知っているとわかりやすい学名。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは quarta (4番めの) とされる。主にベーリング海峡周辺で繁殖する。quarta はカムチャツカ南部、千島列島とコマンドル島で繁殖するとされる。
かつてはヨーロッパから北米の極北部で繁殖するムラサキハマシギ (現在の名称) Calidris maritima (maritimus 海の) 英名 Purple Sandpiper の亜種とされた。分離される前はムラサキシギの名称があった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" でも分離前の同名のものがあるが、Tringa couesi Kurile Is. にチシマシギの名前を与えている。
これは現在は分離された方のチシマシギの亜種とされる。Arquatella couesi Ridgway, 1880 と別種で記載されていたためそれぞれ和名が与えられていたのだろう。原記載。
quarta の原記載。この亜種の基産地は Bering Island とされる。
アラスカやアリューシャン列島の couesi とは異なる点が記述されているが Hartert (1920) なので Ogawa (1908) にはもちろんまだ出てこない。
Arquatella maritima kurilensis Yamashina, 1929 の記載があるが通常は quarta のシノニムとされる。
Yamashina (1929) On a Collection of Birds from Paramushir Island, N. Kuriles, Japan が文献で、北千島 Paramushir 島のもの。コンサイス鳥名事典ではチシマシギはパラムシル島で採集されたとあるが、これはこの当時記述された亜種を指したもの。
Yamashina (1929) の記載前からチシマシギの名前があったのでこのパラムシル島での採集が和名の由来ではないと想像できる。
また種チシマシギ、あるいは現在シノニムとされる quarta の基産地はパラムシル島ではないので注意。
Boyd では Pelidna ptilocnemis。
-
ハマシギ
- 学名:Calidris alpina (カリドゥリス アルピーナ) (ラプランドの)高地のシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:alpina (adj) アルプス山脈の (alpinus) と解釈されそうだがいかにも違和感がある。Linnaeus の指すスウェーデン・ノルウェー国境近くの Dalecarlian Alps のこと (#ハヤブサと#オオタカの備考参照)。
基産地は Lapland と記述されているので (ラプランドの)高地のシギ とした。原記載。
- 英名:Dunlin
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
alpina は i が長母音でアクセントもある (アルピーナ)。Alpes (ラテン語表記) に -inus (長母音で始まる。〜の) の語尾を付けたため。
世界で 10 亜種が認められている (IOC)。
Boyd では Pelidna alpina。
英名の Dunlin は dun (くすんだ褐色) の色由来 (wikipedia 英語版より)。
ロシア名は chernozobik とそのう (胸も含む) が黒い意味になっているが部位の対応はそれほどよくない。Dement'ev and Gladkov (1951) にも正しくないと書いてあった。#サルハマシギの krasnozobik (赤いそのうまたは胸) があるため対比して区別する形で付けられたものかも。
種小名の解釈に関連して、スウェーデンでは高地で繁殖するのか調べてみると Dunlin Calidris alpina alpina moulting on nest in Swedish Lapland
のページがあり標高 870 m の高地の平原で繁殖中に換羽することが記述されている。
Linnaeus の記述ではヨーロッパ他所は生息場所として知られていなかったようで (越冬分布がありそうなのにこれも不思議)、繁殖または換羽地で記録されたもののよう。
Linnaeus (1758) に出てくる Adlerheim は Per Adlerheim (1712-1789。ドイツ語で "鷲家" さん) のことで、Linnaeus の探検に同行したり科学的情報を提供した鉱山技術者。アカエリヒレアシシギ (当時の学名で Tringa lobata、スウェーデン語ではラプランドのシギの名前になっている) 1748 年に記載したとのこと (wikipedia スウェーデン語版)。
ハマシギの生息情報は Adlerheim の記載によると出典として付け加えてあるのだろう。
中継地や越冬地の干潟で見ていると想像しにくいが、スウェーデンの山間の高地は貴重な繁殖場所なのだろう。
[日本のハマシギはどこから?]
日本で越冬のハマシギ はるばる北アラスカから飛来 (朝日新聞デジタル 2021) によれば、日本で複数の飛来を観察できたのは北アラスカで繁殖するキタアラスカハマシギだけ。
茂田氏は「確実に日本で越冬しているのはこの亜種。サハリンやカムチャツカ半島の亜種はもっと南で越冬する」と記載している。
論文は Lagasse et al. (2020) Dunlin subspecies exhibit regional segregation and high site fidelity along the East Asian Australasian Flyway (各亜種の分布図もあり)。
茂田 (2001) Birder 15(10): 42-47 にも当時の記事がある。後述の Tomkovich (1986) や Nechaev and Tomkovich (1987) が検討した後の時代の記事でこれら文献も亜種記載として引用している。
Todd (1953) A taxonomic study of the American dunlin (Erolia alpina subspp.)
が記載するまでは arcticola に相当するものは sakhalina と考えられていたとのこと (下記 Dement'ev and Gladkov からの追記部分を参照)。
日本のリストでは亜種 sakhalina (サハリンの、の意味だが繁殖地はロシア東部極北からチュコト半島。サハリンで繁殖する亜種は actites) を亜種ハマシギ、arcticola (「北または北極に住む」の意味) をキタアラスカハマシギとしていずれも認めている。
他に亜種不明がある。日本で冬場に普通に見られているハマシギは現在定義されている分布域および和名によれば亜種ハマシギではなくキタアラスカハマシギなのであろう。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種 kistchinski (ロシアの鳥類学者 Aleksandr Aleksandrovich Kishchinskiy に由来) カムチャツカハマシギ、
亜種 actites (aktites 沿岸に住む < akte, aktes 沿岸 izo 座る。よく似た Actitis はイソシギ属) カラフトハマシギの2亜種を検討亜種としている。
カラフトハマシギの和名については茂田 (2005) Birder 19(1): 66-69 を参照。この記事ではサハリンのハマシギの繁殖期の調査や標識、サハリンの個体群の小ささや保全上の問題などについて述べられている。
サハリンのハマシギについて、かつて sakhalina が与えられていたが、Tomkovich (1986) Geographical variability of the dunlin in the Far East (pp. 3-15)
の調査によればこれは渡り途中のもので実際には何を指すかそれほど明らかでないが使われてきた。
Tomkovich (1986) は Vieillot の記述について検討、ネオタイプ標本とともに sakhalina はチュコト・アナディールの亜種にこの名称を与えることとした。
亜種ハマシギが sakhalina と定義されたのは (記載地のサハリンよりは) この分布によるものか。
Nechaev and Tomkovich (1987) がサハリンのハマシギを別亜種として当時 litoralis を与えたがすでに使われていた学名であることが判明して Nechaev and Tomkovich (1988) が与え直したものが actites。
極東の鳥類34:シギ・チドリ類特集 pp. 50-63 に和訳がある。
Tomkovich (1986) の記述で Vieillot に関する部分は Vieillot 原文 par Sakhalin で動作主を指し、"サハリン氏" が出版したロシア語の図版 pl. 85 の意味と思われる (原記載。
この記載では基産地ロシア)。
それゆえ Tomkovich 原文には (!) が付いている。"サハリン氏" を動作主と考えてこの部分の藤巻氏の訳を読めば意味がより通じると思う (Tomkovich も造格を用いており動作主を表している)。
"論文 (「サハリンについて発表された」) の著者" の訳の部分は「"サハリン" が出版した」論文の著者、が適切と考える。
訳文 p. 56 の nomen dubium に関する部分 (原文 p. 10-11) は「形式的にはサハリンを通過する任意の亜種に適用できるので」と訳すとわかりやすそう。次の部分は「従って、広く使われているこの (亜種) 名の有効性に疑義が生じる可能性がある」と訳してみた。「ネオタイプを分ける」はわかりにくいので「ネオタイプを与える」(英語では例えば allot に相当) でよいと思う。
Buturlin (1904) The correct name of the pacific dunlin も読むことができる。Buturlin は該当箇所で最初は Sakhalin を人名 (動作主) と考えて探したことがわかる。
結果的に Adam Johann von Krusenstern (1770-1846) の "Atlas zur Reise um die Welt" の世界一周探検に同行した Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau (1769-1857) による図版との記述 (Tringa Variegata oder der Bunte Sachalinische Strandlaufer)
もあり、Tringa variegata Tilesius, Atlas Krusenstern. Reis., Pl. LXXXIV (1814) と同定された。
訳文 p. 55 に登場するこの図版のサインのロシア語 Turukhtan Pestroj Sahalinskoj を「サハリンの斑入りのエリマキシギ」と訳されているが、少し間違いがある。まず転記されたロシア語の最初の単語の末尾に付いているのは硬音符 (ъ) で軟音符 (ь) ではない。ロシア語の正書法確立前の表記で子音で終わる単語の語尾に付けたもの。
すなわちエリマキシギに相当する単語は男性名詞である (転記されたものでは一見女性名詞のように見える)。現代でもエリマキシギはロシア語で男性名詞。そのように考えると Pestroj Sahalinskoj の語尾が不自然である。男性名詞を修飾する形容詞でこの意味であればそれぞれ -yj, -ij となるところ。
これは Pestraya Sahalinskaya という形容詞語尾の固有名詞の変化形 (主格以外) と考えると納得できる感じがする。固有名詞は地名なのか人名なのかわからないが "まだらのサハリン人の" などの意味が考えられ、"まだら" はエリマキシギそのものを指すものではないように思える。
地名に関係なく Sahalinskaya の人名 (姓でもよいし、サハリン出身を名乗った名前かも知れない) などがあってもおかしくないような気がする。図版からサハリンで採集されたとは言い切れない気がする。
Tomkovich (1986) の記述から 1986 年当時は sakhalina は広義に使われられていたことがわかり、亜種サハリンをこの学名に割り当てたのは (少なくとも当時は) やむを得なかったのだろう。ネオタイプの定義により分類概念が変わったのに引き続き同じ亜種名を使い続けるのは適切でない感じがする。
日本鳥類目録第7・8版の sakhalina は古い概念の亜種名を指していると考えるのが妥当に思える。
Buturlin は Tilesius のこの学名が採用されるべきと考えたが、別のものを指して Tringa variegata Gmelin, 1788 があるとのこと。Tringa とは違う属の鳥を指しているので Tringa variegata はハマシギの学名に譲るべきとの内容になっている。
Tomkovich (1986) はこの学名は長く忘れられていたので使うべきではないと述べているが、忘れられたというより過去に使用例があって無効な学名と扱われたのではないだろうか。
現在のフランス名 Becasseau variable は別の古い学名 Tringa variabilis Meyer (Meyer が最初に用いたとは限らない) 由来で、Dunlin, or purre と Gould (1837) の図版に現れる。
Scolopax sakhalina Vieillot, 1816 の原記載。La Becassine Sakhaline がフランス名。
名称から暗黙でサハリンが想定されていたが、サハリンの特定の場所に同定したのは Tomkovich (1986) と言ってよいだろうか。
図版の背景から場所を特定しているが、写真ではないのですでに描いた風景をそのまま借用した可能性も否定できない感じがする。基産地はサハリンと解釈されていたが明確とは言えない気がする (現在ではネオタイプが与えられているので基産地の解釈の問題は生じない)。
亜種 kistchinski (カムチャツカハマシギ) も上記 Tomkovich (1986) と同じ文献で命名されたもの (Avibase の文献は誤り)。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば従来の解釈、すなわち亜種 sakhalina がユーラシア北東端で繁殖する個体群を指すとしたのは Bent (1927) でタイミル半島からアメリカまでの個体群をすべて sakhalina としたとのこと。
Portenko (1939) はアメリカのものを pacifica としてチュコト半島の sakhalina から分離できる可能性を提案した。
これらをふまえて Dement'ev and Gladkov (1951) はハマシギは2亜種だけでよい可能性も除外できないと述べていた。
これらの扱いが和名に現れているようで、北米のものも sakhalina と考えていた時代ならば sakhalina を亜種ハマシギと呼んでも不思議でないことになる。
しかしこれは先取権の原則によるもので同一亜種とする場合は sakhalina となったもので、亜種が分離された後の亜種和名はそのままである必要はない感じがする。
Ralph (1991) Taxonomic comments on the Dunlin Calidris alpina from northern Alaska and eastern Siberia も原初の sakhalina の扱いについて Tomkovich (1986) に同意するとある。
北米からの渡りについてはさらなる後続研究があり: Lagasse et al. (2022) Migratory network reveals unique spatial-temporal migration dynamics of Dunlin subspecies along the East Asian-Australasian Flyway。
のジオローケーターを用いた研究によれば arcticola が日本を含む東アジア - オーストラリアの渡りルート (East Asian-Australasian Flyway) の東端を利用し、サハリンの sakhalina (新しく定義された亜種分布に基づくチュコト・アナディールの個体群を指す名前) は西側 (中国北部から内陸部) を利用している。
日本で越冬した同じ個体が中国で越冬した、あるいはその逆の例は見つからなかった。ただし亜種間で経路が重複する地域 (サハリン北部、黄海) がある。
kistchinski カムチャツカハマシギのサンプルは少ないが越冬地は黄海周辺 (南西諸島で越冬したと思われる1例がある)。
日本で越冬時期に観察されるハマシギは圧倒的に arcticola (キタアラスカハマシギ) の結論を支持する結果となった。
ハマシギの繁殖地の世界分布を見ると圧倒的に北極圏で、サハリン北部は例外的な位置になる。渡り経路などの歴史的経緯で選択されたのかも知れないが、オホーツク海沿岸の北極圏に似た環境条件が理解できる気がする (この点はカラフトアオアシシギの繁殖分布でも感じる)。
アラスカで渡り途中に捕獲されたハマシギの方位指向性 (古典的定位実験) から提唱されている渡りコンパスを用いた場合のルートの検討: Akesson et al. (2021) Autumn migratory orientation and route choice in early and late dunlins Calidris alpina captured at a stopover site in Alaska
早い季節に記録される pacifica は東寄り向き、遅い時期の arcticola は西寄り向きで越冬分布と合うとのこと。
Arctic shorebird migration tracking study - Dunlin でアラスカ発の渡り経路を見ることができる。
亜種 actites のサハリンの繁殖地での研究: Valchuk and Sotnikov (2014, 2024 再掲)
The protected dunlin subspecies Calidris alpina actites on the northern spit of the Chaivo Bay (Sakhalin): breeding biology, state and number (pp. 2487-2491)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Tringa alpina pacifica と亜種まで与えているのは面白い。名称はハマシギ、別名ハシナガ。
当時は arctica Schioler, 1922 や arcticola Todd, 1953 はまだ記載されておらず、北米の亜種は pacifica Coues, 1861 の時代だった。
別学名として Tringa americana を与えている。
この時代に北米由来と考えていたことになる。Vieillot の記述した sakhalina に気づいていたかどうかはわからないが、Buturlin (1904) の同定の直後なのでサハリンやロシア北東部に生息することはまだ知られていなかったのかも知れない。
-
アシナガシギ
- 学名:Calidris himantopus (カリドゥリス ヒマントプース) 革ひものような足の斑点のあるシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:himantopus (合) 革ひものような足の (imantas 革ひも pous 足 Gk)
- 英名:Stilt Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
himantopus は#セイタカシギ参照。
単形種。
Boyd では Micropalama himantopus。
-
ヘラシギ
- 第8版学名:Calidris pygmaea (カリドゥリス ピュグマエア) 小人族のシギ (IOC も同じ) (命名時は "超小型のヘラサギ" の意味だった)
- 第7版学名:Eurynorhynchus pygmeus (エウリューノリュンクス ピュグメウス) 小人族の広い嘴のシギ (命名時は "超小型のヘラサギ" の意味だった)
- 第8版属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 第7版属名:eurynorhynchus (合) 広い嘴の鳥 (euruno 広げる rynchos 鼻口部 Gk。The Key to Scientific Names)
- 第8版種小名:pygmaea (adj) 伝説の小人族ピュグマエイの (f) 語形も変わっている。備考参照。
- 第7版種小名:pygmeus (adj) 伝説の小人族ピュグマエイの (m) 由来は備考参照。
- 英名:Spoon-billed Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
eurynorhynchus は The Key to Scientific Names のギリシャ語語源を採用すると最初の y と o が長母音の可能性がある。o は動詞語尾なので短音化されて語構成が行われるかも知れない (不詳) が、y は u の文字 (y の長音の発音) からラテン語化される際に音を保存するために y の文字となったと想像できる。
アクセント音節は -rhyn- であることは問題ない。保存されたと推定できる y の長音を採用した (エウリューノリュンクス)。属が分割されると復活するかも知れない属名。
pygmaea は -ma- がアクセント音節になる (ピュグマエア)。
pygmeus は形式的には短母音のみで冒頭にアクセント (ピュグメウス) と見えるが、pygmaeus
(ギリシャ語 pugmaios "こぶしの大きさの" に由来。pugme が "こぶし"。参考: ラテン語で "こぶし" は pugnus で直接の語源は異なるが関連があるとのこと。もしかすると音楽の演奏記号で見られた方があるかも知れないがイタリア語の col pugno も同じ意味。指ではなくげんこつで弾けとプロコフィエフのピアノソナタ第6番に現れる。プロコフィエフの演奏を見た人は格闘技かと思ったとのこと)
が本来の形で、-ae- を -e- に短縮したもの。音は引き継ぐ可能性があり、その場合は "ピュグメーウス" の方が適切な可能性がある。
ほとんど学名にしか出てこない単語なので標準的な発音は不明だが後述のように正しいラテン語ではないと後に判断された模様 (語源などは wiktionary)。
記載時学名は Platalea pygmea Linnaeus, 1758 (原記載)
なのでそのまま男性形にすれば第7版種小名のように pygmeus となる。この形は IOC では 7.1 まで、Birdlife checklist version 06.1 (Feb 2014)、Clements 1st edition と 5th edition - 6th edition (version 6.7 incl. 2012 revisions)、Howard and Moore 3rd edition (incl. corrigenda 8) まで採用されていた。
Calidris 属に変更された後の扱いは両者があり、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2) では pygmea としていたが 4th edition (incl. corrigenda vol.1-2) で pygmaea に修正。IOC は 7.2 - 8.2 で pygmea だったが 9.1 以降 pygmaea。
HBW Alive (2015) の段階で pygmaea、eBird は version 2018 まで pygmea だったが 2019 以降は pygmaea。Clements 6th edition (version 6.8 incl. 2013 revisions) で Calidris 属に変更時点から pygmea で 2018 年まで同様だったが 2019 年に pygmaea。Working Group Avian Checklists, version 0.04 で pygmaea。
H&M4 の記述によれば pygmea は正しいラテン語でなく Peters (1934) で用いられた pygmaeus が正しいとの判断によるものとのこと。
理屈はよくわからないが pygmea ではなく pygmaea で統一される模様。pygmaea であれば発音上の曖昧さも回避できる。
Linnaeus (1758) の種小名の綴りは異なるが、Calidris pygmaea (Linnaeus, 1758) と表記されることになるので、記載時学名を見る時には注意が必要な事例となる。
同様の事例が paradisaea (#キョクアジサシ) と paradisea (ハゴロモヅル) にあるがこちらは問題にならなかったのだろうか。
[学名の由来]
Hartert (1910-1922) p. 1602 の時代には次の Eurynorhynchus 属が用いられていた。Sharpe は綴りを改良して Eurhynorhynchus としたとのことだが採用されなかった。
Platalea pygmea Linnaeus, 1758 からこの属に変更の際、Eurynorhynchus griseus Nilsson, 1821 (灰色広い嘴の鳥) と改名された (参考。属と種記載がある)。
Linnaeus はヘラサギ類に分類していたが、いくら何でもそれは違うだろう (!) ということで改めて小型シギ類に分類したもの。比較対象にオジロトウネンと同じ大きさと出てくる。
ただし Latham (1785), General Synopsis of Birds では Dwarf Spoon-bill の英名を与えているなど一定使われていたらしく、1836 年にも Pigmy Spoonbill の英名が現れる (OED)。
Linnaeus は "超小型のヘラサギ" (一部納得できるところが何とも言えない) と考えてラテン語で意味の通じる学名を与えたが、この考え方が間違っていたため後に適切な属に移され、オジロトウネンと同じ大きさでは "小人族の" では話が合わなくなる。
当時の改名状況は #ノスリの備考参照だが、このぐらい大きく間違っていると pygmea を別のものに改名する十分な理由になると思える。Nilsson は形態を属名で表し、種小名は色彩を表した。しかし後の系統解析で Eurynorhynchus 属が Calidris 属に内包されると形態的特徴が学名に現れなくなった。
種小名に先取権の原則が導入されると元のものに戻され、釣り合いの悪い学名になってしまった次第。どこかで規則で定める必要があるが、この場合は杓子定規的な扱いになってしまった。
最新の学名を見てこれほど特徴のある種にあまり意味のない学名を付けるとは博物学者は何を考えていたのか、と言いたくなるところがこのような背景事情があった。
ただし Calidris 属は広すぎると考えることも可能で、その場合は Boyd の扱いのように Eurynorhynchus 属が復活する可能性もある。
なお Linnaeus は基産地をスリナムと間違っていたとのこと。
griseus のような単純な学名は属をまとめると重複するのではと感じられるが、Calidris grisea Brehm, 1831 が実際にあった。もっと古くからあってもよさそうに思えるが、Calidris の属名が使われるようになったのは新しく、Calidris を属名に用いた記載は非常に少ない (#コオバシギの備考参照) ため重複を免れ無効ではなくシノニムとなった。
単形種。Eurynorhynchus 属は Thomas et al. (2004) A supertree approach to shorebird phylogenyの系統解析により Calidris 属に含められた。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱い。Calidris pygmaea (語尾が変わるので注意) となる。
Gibson and Baker (2012) Multiple gene sequences resolve phylogenetic relationships in the shorebird suborder Scolopaci (Aves: Charadriiformes) の研究では Tringa, Gallinago, Calidris の各属が単系統でないことがわかった。
Chen et al. (2022) Five new mitogenomes sequences of Calidridine sandpipers (Aves: Charadriiformes) and comparative mitogenomics of genus Calidris でも提示されている。
Eurynorhynchus 属およびこの研究で使われている学名 Limicola falcinellus (キリアイ) の属の変更はすでに反映されているため、新たな変更が必要という意味ではおそらくないだろう。
Boyd では Eurynorhynchus pygmeus。
[現状と保護]
絶滅危惧 IA 類 (CR)。IUCN 3.1 CR 種。
世界的にも極めて希少なシギであることは今ではよく知られているだろう。
wikipedia 英語版によれば 2009-2010 年に 120-200 つがいで 2002 年に比べて 88% の減少。越冬地のミャンマーなどで混獲の被害にあったり、重要中継地であった韓国のセマングム (Saemangeum) 干潟の干拓 (1991-2010) が影響を与えた可能性が考えられている。
繁殖地はロシアチュコト半島の一部に限られ、そこでの環境悪化は特にあるわけではないが、将来の個体数減少に対応するため、また保護下で外敵による捕食を避けて数を増やすための飼育施設が設けられている。2011 年からロシアで採取された卵を英国の飼育施設に運んで人工孵化させる取り組みが始まった。2013 年にはロシア現地の飼育施設で 20 羽のひなが誕生したとのこと。
日本語では
ヘラシギ保護の最前線をお届けします! (バードライフの日本語記事 2017)。
日本野鳥の会 ヘラシギ [ティーチャーズガイド・ヘラシギと湿地を守ろう (Spoon-billed sandpiper teaching kit) ができました]
などを読むことができる。渡りの中継地、越冬地各国でも同様のプログラムが進められている。
動画では英国 WWT とロシアの協力の初期段階の映像
The Spoon-billed Sandpiper expedition | WWT、卵の孵化の様子 WWT: Spoon-billed Sandpiper Conservation Breeding などが紹介されている。
ロシアの現地 (Mejnypil'gyno村 非常に読みにくい名前はチュコト語由来) での保護増殖施設の様子と地元小学校でのプレゼンテーションや観察 (2015) Lopaten' (Calidris pygmeus) も紹介されている。
ロシアのヘラシギ保護のサイト。
国際的には Saving the Spoon Billed Sandpiper のサイトにも現地の保護増殖施設の紹介がある。
Green et al. (2021) New estimates of the size and trend of the world population of the spoon-billed sandpiper using three independent statistical models による個体数推定では減少速度は緩和されているが依然危険な状態と指摘されている。
Chowdhury et al. (2022) Accelerating decline of an important wintering population of the critically endangered Spoon-billed Sandpiper Calidris pygmaea at Sonadia Island, Bangladesh
バングラデシュの重要越冬地でさらに数が減っている、などの研究が出ている。
衛星追跡結果は Chang et al. (2020) Post-breeding migration of adult Spoon-billed Sandpipers があり、6個体を追跡。繁殖後に渡りまでの期間を過ごす場所、重要中継地点などが明らかにされている。
これを見ると大陸ルートが主な渡り経路で日本での観察が難しい理由、また石川県などで比較的定常的に観察されている理由もわかる。
富田 (2018) Birder 32(2): 42-43 にも中国で行われた衛星追跡の結果が紹介されている。中国版南部に分散して越冬すること、オホーツク海沿岸にこれまで知られていなかった中継地が見つかったとのこと。
衛星追跡でこれまで知られていなかった繁殖地が明らかに。Transmitter reveals new Spoon-billed Sandpiper breeding grounds (BirdGuides 2024.12.24)。
ロシアの記事 自分では生き延びられない鳥 (2016) 抄訳 ([kbird:01490] ヘラシギのロシアの記事 2016.8.10):
野鳥の卵を巣から盗むというのは恐ろしいアイデアです。これは種が
脅威に晒されている場合にとりわけその通りです。例えばイギリス
では野鳥の卵を盗もうとして捕まった人は禁固6か月に処せられます。
[どのように種を絶滅から救うのか?]
しかしロシア北東部、チュコトカの沿岸の肌寒いツンドラで保護の
ためにまさにこのことが行われています。2012 年からロシアと
イギリスの鳥類学者がヘラシギの巣から卵をつかみ取ります。
ひなが十分に力強くなって自然界で自分で生きて行けるように
なれば自然に放します。
これはこの種を保護するための絶望的な最後のステップなのです。
しかし鳥類学者はこれをやらざるを得ません、というのはヘラシギ
の状況があまりにも絶望的であるためです。
自然界には繁殖しているこの鳥のつがいは全部で 200 しか残って
いません。個体数はこの数十年で急激に現象しました。しかしこの
危機の原因は繁殖するロシア国内にあるのではなく、遠くの南に
あるのです。
[生息環境の破壊]
若いヘラシギは十分な大きさになると黄海沿岸の中国や韓国、そして
東南アジアへと南への渡りを始めます。
この道のりは 8000 km にも及び、スズメほどの大きさしかない鳥が
この長距離を克服するのです。そしてまさしくその道筋において
ヘラシギは自身の最大の問題にぶち当たるのです。黄海のこの鳥の
生息地は事実上なくなってしまっています。この鳥たちは無数の
小さな無脊椎動物のすみかとなっている泥質の砂浜で餌を探します。
しかし中国や韓国ではこれらかつて広大な泥質の砂浜は農業や産業
のために干拓されてしまいました。それはこの鳥の骨の折れる渡りの
時の急速場所が著しく小さくなったことを意味します。
多くの野性の渡り鳥は黄海の生息地の消失の犠牲になっています。
彼らは皆、東南アジアを横切る最大の渡りのルートの一つを通って
ゆくのです。
もう一つの問題は沿岸部の鳥の狩猟、特に東南アジアの国々や中国
におけるものです。猟師にとってヘラシギは価値ある獲物には小さ
すぎますが、暗闇の中でよく網にかかってより大きな種類のために
据えられます。
[子孫を再生産する問題]
この損失を補填するためにヘラシギは多数の子孫を再生産せねば
なりませんが、ここに問題があるのです。卵やひなの大部分は
大きなカモメ類やキツネやリスなどの哺乳類などの捕食者の
餌食になってしまいます。平均的には成熟したつがいは毎年
3-4個の卵を産みますが、その中から2年に1羽のひなが南へと
旅立つことができるのです。
[鳥類学者は何をしているのか?]
まさにここが生態学者が助けをさしのべています。彼らは
卵を集めて孵卵器に入れます。そして孵化したばかりでまだ自分
で生きていくほどに十分強くなっていない間ひなを世話します。
アイデアは産まれ次第卵を集め、そして若い鳥を安全なケージの
中で育てるということです。理論的にはひなが黄海への渡りを
遂げるチャンスが7倍になります。
鳥類学者はこの他に「ノアの箱舟」として知られている23羽の鳥の
集団を設けました。もし自然界で鳥を保護することができなかった
場合、これらの鳥を飼育下で増やそうと願っているのです。
2016年6月にそのうちの2つがいが初めて卵を産みました。
しかしながら今は重大な課題であるこの種を自然界で保護すること
に最大の努力が向けられています。
[飼育下でのヘラシギ増殖の特性]
現在この種の最もよく知られたチュコトカでの繁殖地は漁村の
Mejnypil'gyno です。毎年鳥類学者はここにある8つの巣から
全ての卵を採取します。もし卵をシーズン始めに採取すれば鳥は
再度産卵のためにつがいを作ります。しかしそれは再度採取しません。
しかしながらこのような絶滅しつつある種の卵を採取することは
常に危険を伴います。しかしこの鳥の生物学的特性からこのような
アプローチがうまく行くと予想できる点が2つあります。
一つの好ましい要因はヘラシギのひなは孵化して羽毛が乾けば
すぐに自分で餌をとれることにあります。1時間も経てばひなは
無脊椎動物を探しに歩き回ります。さらに若い鳥はいつ渡りを
始めるか、どの方向に飛ぶ必要があるかを本能的に知っています。
これは例えば親が導かなくてはいけないガン類やツル類が
持ち合わせていないこの種族の自然の防御機構なのです。
[ひなに何を与えるのか?]
しかしながら鳥類学者はさらに一つの問題にぶち当たりました。
飼育下のひなにどのように餌を与えればよいのか。彼らは
ビタミンとミネラルを添加した固形の餌を与えることにしました。
しかしその他に天然の餌である昆虫を与えようと努めています。
ありがたいことに北極の夏には昆虫は不足していません。
ツンドラには非常に大量のカがいて、人間が生活するにはやっかい
なほどですが、鳥が繁殖するには好適な要因なのです。
しかしながら最初の1年間、鳥類学者チームは危機に直面
しました。ひなが乾燥フルーツを食べようとせず、風が強くて
カで餌を保証することもできなかったのです。このため学者
たちは強い風の吹かない遠くの谷間へカを採取に行く必要が
ありました。鳥類学者は真空掃除機、四輪駆動車、ポータブル
発電機のフル装備で遠征に出かけました。彼らは後で雛の餌に
なるかも知れないカを集めるのに掃除機を使いました。今では
プロジェクトチームはその場所で 24 時間体制でカを集めています。
極北の地にはこの季節には夜がなく、ひなは最初の渡りに備える
ために大量に食べる必要があるのです。
[ひなはどのように発育するか]
孵化したばかりのひなは 5 g しかありません。巨大な足を持つ
ハチに似ています。それでも 20 日経つと自然界で生き延びる
ことができるほどに自立します。生まれて 23-25 日後には
自分で渡りを始めることができるのです。
鳥類学者は毎年約 30 羽を育て上げて放しています。大多数は
黄海の方向へと移動を始めます。2014 年、鳥類学者は育てた
鳥を初めて見ました。彼らは生き延びてこちらへ戻ってきた
のです。その後 2015 年、育てられた鳥の何羽かが野性下で
つがいを作りました。今年彼らがうまく繁殖できるかどうかを
語るには早すぎるでしょうが、そうではないと考える理由も
特にありません。
さらに 2015 年夏にその前6年で極めて急速にこの地域の個体群
が減少した後、初めて少し増加が記録されました。データは
飼育下でのひなを育てたおかげで数が増えたことを示しています。
これは鳥類学者の努力が成果につながったことを意味します。
[何のために国際協力が必要か?]
しかしながらチームはこの活動だけで鳥を絶滅から救うことは
できないことはわかっています。実際に採食場所は生息地の破壊
の現実の問題が解決しなければこの種の命運は尽きているのです。
このプロジェクトによってこの種の保護のために十分に強力な
処方箋を作る時間稼ぎをすることができます。現在ミャンマーで
狩猟を避けるため、また中国で生息地の損失を避ける試みのための
仕事がなされています。これはロシアに営巣地で行われている
仕事と同様に大変重要なことです。
結局のところこの小さな鳥を救うには東アジアの渡り経路を
通じた保護が唯一の方法です。ここでの一歩一歩が大変大きな
意味を持ちます。ヘラシギを救うことができるかは渡りの経路での
国際協力にかかっているのです。(抄訳終わり)
ベラルーシの鳥類雑誌 (2012 年号) の p. 22 にヘラシギ調査
に出かけた (2008) 方の手記があった (現在 URL リンク切れ [kbird:01502] ヘラシギ調査 2008, 2016.8.24 紹介)
ある遠征の記録 Pavel Pinchuk
"Ptushki i My" 「鳥と私たち」 (2012) 21(2), 22
私がヘラシギを知るようになったのは 2008 年冬にアレクサンドル
ヴィンチェフスキーからの電話が始まりだった。チュコトカの
2回の遠征に鳥類学者が必要だった: 最初はヘラシギについて
2か月半、2つめはカリガネについて1か月半だった。
迷うことなく最初の方を選んだ。5月終わり、モスクワから
ほとんど9時間の飛行を終え、ベラルーシの夏からチュコトカ
の春へとたどり着いた。春というよりもむしろ冬だった。
6月の始めのチュコトカでは春はまだ始まったばかりで、
アナディルの沿岸の氷の上を「万能車」(訳注:悪魔の車
として有名なもの?) が走っていたが、春の鳥の渡りはもうすでに
真っ最中だった。最初の一週間を我々は Ugolnye Kopi
でヘリコプターを待って過ごした。時間をつぶす (だけでは
ないが) ためかすみ網をしかけ、最初の日には一週間前に Pripyat
(訳注: チェルノブイリで有名な地名だが、もしかしてそこ
での調査?) にいたのと同じ種類を捕まえた:タカブシギ、
ハジロコチドリ、タシギ、エリマキシギ。そしてようやく翌日
ヒバリシギをリストに加えることができた。
総じてヘリコプターを待つのはたいへん退屈な作業だとわかった。
毎朝 11 時に全員が集合して空港に車で行く必要があり、1時間半
待って天候条件が厳しいために便は欠航と聞くのだった。
しかし天候は我々をすぐに哀れんでくれたのか1週間後に
我々は発音するのも難しい Mejnypil'gyno (訳注: よほど
読みにくいのか綴りがかなり間違っていたので修正) という名前の集落
に降り立つことができた。ヘリコプターに乗って初めて鳥類学者
が特別が特別に扱われていることを知った:飛行士は我々がどういう
者かを知って飛行中に撮影用の覗き窓を開けるのを許可して
くれた。その後私は、鳥類学者に至るところで「青信号」
が与えられることに驚かなくなった。例えば学校では自由に
インターネットが使うことや「外出禁止時間」に大人向けの
アルコールを入手することが許されていた。
課題はまずまず単純なことだった:調査区域で繁殖している
すべてのヘラシギのつがいをみつけて記録し、巣を見つけたり
彼らの運命を追跡することを可能にするのだった。
その時はヘラシギに標識をつけることは断念していたが、
昨年カラー標識をつけた鳥を探すことは必要だった。
その他に地域の人々との交流や「ヘラシギ友好クラブ」を作る
ことが我々の仕事になった。ヘラシギの仕事の合間にチュコトカ
南東部の海のコロニーで鳥の調査をすることになっていた。
ヘラシギは到着したその日に見ることができ、集落から十分
近いところにいた。ヘラシギは特に大きなシギではないとは
知っていても、その大きさには驚かされた。ニシトウネンよりも
大きくないのである。ツンドラで探すのはまったく簡単なこと
ではなく、それほど姿を見せようとしないのでなおさらの
ことだった。特徴的なぶんぶん (ジュジュ?) いう声が救いである。
色や外見はヘラシギは見慣れたニシトウネンとあまり
違わない。ここでは普通にいるトウネンとは一層似ている。
しかし嘴に関してはこれはまったく別のことだ。
この鳥にとって何のためにこういう形が必要なのかはよく
わかっていない。このシギの採食行動を観察してもこの形が
役立っているというより邪魔しているような印象を受ける。
ところで地域の学校での講演の準備の途中で明らかになった
のだが、ヘラシギ (lopaten') の名前はシャベル (lopata)
との類似性から来ているのではまったくなく、四輪馬車の
木製の軸の下のすきまにホイールハブに手で穴をあけるために
使われる特別なドリル (lopaten') から来てきることが
明らかになった。
さて仕事にためにやってきたのだからその話に戻ろう。
我々の調査の結果、ヘラシギの数がさらに減少したこと
が明らかになった。2003 年にほぼ 100 つがいを記録した
調査区域で 10 つがいを越えないヘラシギしか生息して
いなかった。我々が見つけたもの全部で6個の巣で
そのうち1つはたぶんイヌが食べてしまっていたが、
他は正常なひなが孵化していた。
天候がヘラシギたち自身にとっても、我々の仕事に
とっても好ましくなかったことは言っておく必要がある。
6月初めには少し雪も降り、その後何時間かかけて雪が
解けた。6月はちょっと寒く、昼の平均温度は5℃ぐらい
だった。雨は少なかったし、降ったとしてもぬか雨ぐらい
みたいだった。7月前半はよく晴れた暖かい日はたった
1日だけで後の日は曇った肌寒い日が続いた。これらの
ことのためにヘラシギが普通営巣する場所が乾きすぎる
ことにつながった。このことがおそらくヘラシギの個体数
が少なかったことにつながり、その証拠は翌年確認する
ことができた。
ヘラシギの巣を見つけるのが難しいとすればひなを見つける
のはもっと難しい。正確な巣の場所を知って定期的に調査
しているのに、巣からそれほど離れていないところに横た
わっている孵化してまもないひなを見つけるのに半時間も
費やした。生まれたばかりのヘラシギの嘴にはすでに
しっかりとした固形の「スコップ」があり、嘴が成長する
につれて一層頭から離れるようになる。
7月半ばには我々は2週間集落を離れて海鳥のコロニーの
調査に出かけた。コロニーの鳥のカウントをする他に
繁殖しているヘラシギを発見する希望を持ってピーク川
地域もまた観察したが成果はなかった。ヒグマたちとの
近接遭遇が風変わりななぐさめになった。ヒグマは人を
恐れるがそれほど強くないことは言っておかねばならない。
しかしセイウチのコロニーのそばにいることと、産卵に
向かう赤い魚 (ベニザケ、カラフトマス) のおかげで
一度に7頭までのヒグマを見ることができた。
そのうち1頭のヒグマ (こいつには良くない呼び名を付けていたが)
が我々のゴムボートをおそらく死んだセイウチと間違って
切り裂いたことで全て終わりとなってしまった。
集落に帰ると我々の乗るヘリコプターの席はなく、その後
もないという嬉しくない知らせが待っていた。そのため
シーズンは「召集されるかされないか」という永遠の
曖昧な希望とともに終わるのだった。最後の日々にはひなに
標識を付けるために近くへの出撃を終えた。知っている
2つがいのコオバシギの3羽のひなに足環を付けることと、
白いフラッグを付けたオスの写真を撮ることに成功した。
この標識はニュージーランドで越冬中に付けられたことが
わかった。
最後の外出のうち1回は我々が標識を付けたひなを訪れる
ために費やした。この時はそれらのひなを見ることが
できないじまいだった。草の中に去ってしまっていた。
しかし両親の行動からは守らなければいけないものが
いることがわかった。そういうことでこれらのひなに
とって少なくとも生涯の門出はうまくいったようだ。
さて8月にモスクワに戻ってくるとグルジアとの間で
始まった戦争のニュースと我々のかつての故郷の首都の
すべての駅にいるおびただしい数の警官が待ち受けていた。
今になって当時 2008 年を思い返してみると、シーズン
が終わってすぐ、ヘラシギの将来はお先真っ暗だったことを
思い出す。5-10 年もすれば最終的に絶滅してしまい、
何をしてももうすでに遅いという意見すらあった。
しかしこの2年でなされた仕事によれば、このユニークな
シギの将来を一定の安堵感 (と言ってよければ)
を持って見守ることができるようだ。(訳文終わり)
この著者の方のものと思われる ブログ がある。
ヘラシギの巣などの映像がある。2009 年当時の記録だが、当時は本当に絶望的で、何かの要因で数が回復してくれると信じたいと結ばれている。
生まれた日のヘラシギ
当時のチュコトカの風景 (5月末) とシギ類: 1, 2。
wikipedia ロシア語版によれば長命で 14, 15年、最低 16 年生きた鳥が記録されているそうで、小型
シギ類では珍しいとのこと。
-
キリアイ
- 第8版学名:Calidris falcinellus (カリドゥリス ファルキネルルス) 小さな曲がった嘴のシギ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Limicola falcinellus (リーミコラ ファルキネルルス) 小さな曲がった嘴の泥に住む鳥
- 第8版属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 第7版属名:limicola (合) 泥に住む鳥 (limus (m) 泥 colo (tr) 住む)
- 種小名:falcinellus (m) 小さな鎌 (falx -falcis (f) 鎌 -ellus (指小辞) 小さい 備考参照)
- 英名:Broad-billed Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
limicola は limus は冒頭が長母音。-cola は短母音のみで -mi- がアクセント音節となるはず (リーミコラ)。属分割で復活するかも知れない属名。
falcinellus は -nel- がアクセント音節と考えられる (ファルキネルルス)。
語構成は見当たらないが falx の単純な変化では n の音は出てこない。
falx + -inus で falcinus が作られ (解剖用語に存在する) + -ellus と考えられるように思える。この場合であれば -inus の i が長母音となる (ファルキーネルルス)。いずれの可能性もあると考えられる。キリアイのファンの方に追求していただきたい。
Limicola 属は Thomas et al. (2004) A supertree approach to shorebird phylogenyの系統解析により Calidris 属に含められた。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版でも同じ扱い。
Calidris falcinellus となる。同文献により Philomachus 属 (#エリマキシギ参照。現在ではこの属も Calidris 属に含められた) となる可能性も提案されている。分子系統に関する文献は#ヘラシギの備考も参照。
2亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は sibirica (シベリアの) とされる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" 時代は独立種扱いで Limicola sibirica となっていた。原記載 (Dresser 1876)。基産地はシベリアと中国。
基亜種の方は Scolopax Falcinellus として Pontoppidan (1763) がリストしたもの。
Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark (p. 727:623)。百科事典的な本。
Falcinellus Ryle eller Domsneppe med et flad og mod Enden nedboyet Nab との記述。
Ryle はハマシギ、Falcinellus Ryle で小さな曲がった嘴のハマシギ。
Domsneppe は sneppe (シギ類) dom は複数の語義がありやや不明。Ryle, Calidris に別名として現れている。
続く部分は平らな嘴の先端が少し下に曲がっている意味で、全体として小さな曲がった嘴と称されていた。
さて Tringa platyrhyncha Temminck, 1815 (参考) があり、この資料ではキリアイと同定している。参考 では Numenius pusillus Bechstein, 1809 と同定されているがこれもキリアイとのこと (参考)。
一方で Numenius pusillus Bechstein, 1812 の用例 (参考) は Numenius pygmaus Latham, 1787 の改名とあり、Numenius pygmaus Bechstein, 1803 (参考) はハマシギのことなど全体的にちょっと怪しい。
Pontoppidan (1763) の学名が早いためにこれらの学名が現在問題になることはないが、Temminck (1815) の学名が英名 Broad-billed Sandpiper の由来と考えられる。
Hartert (1910-1922) では p. 1601 参照。
山階鳥類研究所の標本データベースでも Temminck の学名が用いられていたものがある (YIO-11098)。キリアイの名称の入ったラベルは学名を見ると後に付けられたものと想像できる。
和名のキリアイの由来は今一つよく知らないが、嘴を上から見ると基部の幅が広いとコンサイス鳥名事典にあり、嘴の形由来かも知れない。例えばキリハシチメドリ Wedge-billed Wren Babbler (現在では分離され Sikkim Wedge-billed Babbler の英名が使われるよう) では同書で嘴は円錐状で先端がとがるなどキリアイに似た記述となっている。キリハシハチドリの英名も Wedge-billed Hummingbird。
キリアイの和名が付けられた時代は Temminck の学名がまだ用いられていて、同じような着想から作られた名称を短縮したものだろうかと想像していまう。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 103 p. 17 に時々ジュリー、ジュリーと鳴きながらトビムシやゴカイなどをあさるとあった。形態ばかり注目していたが和名は#キョウジョシギでも考案されているように音声由来も考えられる気がしてきた。例えば嘴の形と関連させてキリを刺しながら回しているような声として解釈された (?)。
繁殖地の音声であるが XC839618 (Stein O. Nilsen 2023.6.26) と大変面白いものがあった。結構よく声を出す種類のようでさまざまな音源がある。XC654080 (Lars Edenius 2021.6.2)。flight call ではあるが、シマアジの声がねじを巻くような音と形容されるならば、キリ回しと形容されてもおかしくない感じがする。
Boyd では Limicola falcinellus。
-
コモンシギ
- 第8版学名:Calidris subruficollis (カリドゥリス スブルーフィコルリス) やや首の赤いシギ
- 第7版学名:Tryngites subruficollis (トゥリンギテース スブルーフィコルリス) やや首の赤いクサシギのようなシギ
- 第8版属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 第7版属名:tryngites (合) tringa に似た鳥 (Tringa クサシギ属 またはギリシャ語 trungas、-ites (接尾辞) 〜に似た Gk)
- 種小名:subruficollis (adj) 多少首の赤い (sub- (接頭辞) 多少 rufus (adj) 赤い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Buff-breasted Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
tryngites は外来語由来の合成語で発音はわからないが、ギリシャ語由来の -ites の e が長母音。他は短母音と考えると冒頭がアクセント (トゥリンギテース)。
subruficollis は -ru- の u が長母音で -col- がアクセント音節 (スブルーフィコルリス)。-collis は英名では -throated, -breasted いずれにも訳される。
少しまどろっこしい種小名になっているのは Tringa ruficollis Pallas, 1776 (参考 トウネンの記載) の用例がすでにあったため。
単形種。Tryngites 属は Thomas et al. (2004) A supertree approach to shorebird phylogeny の系統解析により Calidris 属に含められた。
その後の研究もあり、#キョウジョシギの備考参照。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱い。Calidris subruficollisとなる。
Actidurus naevius Heermann, 1854 (参考) の記載があり、naevius は斑点のある、同時に記載された英名が Mottled Grass Plover でいずれかが和名の由来となった可能性がある。
山階鳥類研究所の標本 YIO-11118 のラベルにはアメリカシギの別名が記されていた。
当時よく使われていた学名は Tringa rufescens Vieillot, 1819 (参考) 由来のもので、属名のみ変えたものが使われていた。しかし Tringa rufescens Bechstein, 1809 (参考。エリマキシギと同定された) の同名の用例がすでにあって無効となった。
Hartert (1910-1922) では p. 1597。
Tringa 属をもし用い、Tringa subruficollis Vieillot, 1819 (Azara のパラグアイの記述をもとに付けた学名 参考) を有効と考えない場合にはその次に古い naevia が有効になる次第。Azara の記述の同定が混乱していた時代もあり、一時期はこの種小名が使われていたのではないだろうか。
Tryngites 属は Cabanis (1857) がコモンシギを指して設けた属で、この属を用いる場合は Tringa 属と衝突しないので、Tringa subruficollis Vieillot, 1819 を有効と考えない立場では Tryngites rufescens の学名でよかったことになる (山階鳥類研究所の 1880 年代の標本に用いられていた学名)。
Boyd では Ereunetes subruficollis。
-
エリマキシギ
- 第8版学名:Calidris pugnax (カリドゥリス プグナークス) 好戦的なシギ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Philomachus pugnax (ピロマクス プグナークス) 好戦的な闘争を好むシギ
- 第8版属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 第7版属名:philomachus (合) 闘争を好む (philos 好む makhe 闘争 Gk)
- 種小名:pugnax (adj) 好戦的な (繁殖期のディスプレイから)
- 英名:Ruff (16 世紀ころのひだの襟から)
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
philomachus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-lo- がアクセント音節と考えられる (ピロマクス)。
pugnax は a が長母音でアクセントは冒頭 (プグナークス)。pugno (プグノー。争う) -ax (長母音。〜に傾いている) に由来する長音。
関連する pugnus については#ヘラシギの語源解説参照。
pugnax が用いられている現行の学名はキムネイロムシクイ Apalis flavida Yellow-breasted Apalis の亜種とエリマキシギのみ。歴史的にはもう少し用例があったが少ない。行動を記述する学名は標本をもとに付けにくいものと想像できる。
単形種。Philomachus 属は Thomas et al. (2004) A supertree approach to shorebird phylogenyの系統解析により Calidris 属に含められた。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱い。Calidris pugnaxとなる。
その後の研究もあり、#キョウジョシギの備考参照。
[旧属名の由来]
かつての Philomachus 属は当時記載者不明の属で 1804 年に用いられたが、記載者不明で有効としない考えもおそらくあったと思われ、同じ属名を Gray (1840) が ツメバゲリ (現在の学名で Vanellus spinosus) Spur-winged Lapwing にが用いた。
かつては Machetes Cuvier, 1817 (makhetes 戦士 Gk)、Pavoncella Leach, 1816 (タゲリのイタリア語名 Pavoncella から) といずれもエリマキシギのみを含む属も提案されたが、これも Philomachus 属が記載者不明だったためかも知れない (The Key to Scientific Names の情報を参照してとりまとめ)。
Hartert (1910-1922) p. 1594 の時代にも Philomachus 属の記載者は不明のままだったが、この属を有効とした。日本鳥類目録改訂第7版でもこの属名が使われていた。
後に記載者は Merrem と判定された (#コオバシギ備考の [Calidris 属について] 参照)。
記載者不明の場合に無効とすると、後に記載者が同定された場合に先取権が変化して大きく変える必要が発生する可能性があるなど難しい問題があったものと想像できる。
Machetes 属を用いた学名で Machetes variabilis Wood, 1837 は納得できる気がする (夏羽と冬羽の変化が大きいなど。#クロジの備考参照)。
この学名については 参考 1, 2。#ノスリの備考のように新属に伴う改名と想像できるが、
Brehm (1831) が Machetes に "2種" (Machetes alticeps Brehm, 1831 参考 と Machetes planiceps Brehm, 1831 参考) を記載したためとも考えられそう。
エリマキシギにはいろいろなタイプの個体があるので、Brehm (1831) は頭の色違いに別々の学名を与えたものかも。Wood (1837) は同種内で違いが大きい (または変化する) の意味で、解釈を訂正する意味合いも込めて Machetes variabilis Wood, 1837 と名付けたのかも知れないが Hartert すら原文献を見ていないとあるので歴史に関心のある人が調べない限り真意は不明のままかも。
ただしこの学名は S.D.W. が 1836 年に用いており (参考。ただし無効学名)、Wood 自身の解釈ではなかったかも知れない。
いずれも現在の分子系統解析では単形属とする必要はなく不要となった。
Hartert 時代のドイツ語名は Kampfhahn (闘争的なニワトリ), Kampflaeufer (闘争的なシギ) と "闘争" を冠し、後者は現在も使われている。フランス語名などでも同様で英名の方が上品な感じ。和名も英名と同様の特徴を指している。
ロシア語名が turukhtan と特殊で普通の人が聞いても耳慣れないとのこと。Kolyada et al. (2016) によればかつては kurukhtan, kurakhtan と呼ばれていて kur (ニワトリ) + petukh (雄鶏または喧嘩好き) の合成から派生したとのこと (原文では語源の表記に正書法以前のロシア語が使われているが現代の綴りを用いた)。ドイツ語名でも闘争的なニワトリが出てくるので発想は同じかも。
[特異な社会構造と遺伝]
繁殖地ではレック lek [語源はスウェーデン語の lek 遊び、leka 遊ぶとのこと (wiktionary)] と呼ばれる集団求愛場のグループを形成する。エリマキシギはオスのディスプレイがメスに対するものよりも、他のオスに直接向けられる点が珍しい。
テリトリーを持つオス (independent, 全体の 84%)、取り巻きのオス (satellite, 16%)、メスのように見えるごく少数のオス (1%) からなる社会構造を持っている。レックを作ることがはっきり確認されているシギはエリマキシギのみ。
これらの特性は遺伝子が決めており、生涯変わらないとのこと。テリトリーを持つオスは翌年は 90% の確率で同じ場所に戻り、他の個体の順位もよく把握している。取り巻きのオスはテリトリーを持たず、テリトリーを持つオスのテリトリーに入って交尾の機会をうかがうとのこと。メスのように見えるオスはオスらしい生殖羽を示さないが、生殖羽を持つオスよりも大きな精巣を持っている。
レックを形成する鳥ではそうでない種類に比べて体サイズでみた精巣が小さい傾向があるが、エリマキシギはあらゆる鳥の中で体サイズに比べて最も大きな精巣を持っている。
このメスのように見えるオスは「隠れオス」、英語では faeder (feader と書かれるのは誤記) とも呼ばれる。進化的にはこれが生殖羽を持つオスの原型と考えられている。この faeder に対して交尾を試みる取り巻きのオスもあるが、この同性間の交尾で faeder の方が上に乗り、相棒はオスであることを認識していると見られている。このような同性間の交尾はメスを誘引する機能があるのかも知れない
2016 年にこれらの3種類のオスを決定する遺伝部位が同定された。380 万年前に起きた 90 個の遺伝子を含む大きな転位によって faeder が生まれた。これだけ多くの遺伝子が含まれるため、この変異を持つ遺伝部位がホモ接合になると致死的である。
50 万年前に起きたまれな組み換えによって取り巻きのオスが形成されたとのことである。
(wikipedia 英語版より。文献や遺伝学的詳細は同ページを参照)。
「超遺伝子」で決まるエリマキシギの恋のアプローチ法 (nature ダイジェスト 2016)
に日本語解説がある (#ベニヒワの備考も参照)。
これほど詳しい研究が行われているのはヨーロッパではエリマキシギが繁殖するためである。
エリマキシギ研究者のページ Ruff Project にもまとめられている。Reproductive strategies in the ruff で3種類のオスの解説と動画が見られる。「
好戦的な」の学名の意味も、この特異な繁殖戦略に由来するものになっている。
東アジアではほとんど極北ツンドラのみで繁殖するため、ご存じのようにオスの完全な夏羽でさえ我々にとっては縁遠い存在である。英語でメスは reeve とも呼ばれる。
テストステロンレベルの制御を行う単一の遺伝子 (HSD17B2) が同定されたとのこと: Loveland et al. (2025) A single gene orchestrates androgen variation underlying male mating morphs in ruffs。
Super enzyme that regulates testosterone levels in males discovered in 'crazy' bird species (一般向け解説記事)。
(#ノスリ備考の [ガラパゴスノスリや他の猛禽類の一妻多夫] と重複掲載):
Marcondes and Douvas (2024) Social mating systems in birds: resource-defense polygamy - but not lekking - is a macroevolutionarily unstable trait
こちらは進化的安定性について。レック形成は進化的に安定でほとんど失われることがないが、resource-defense polygamy (テリトリーを確保して一夫多妻または一妻多夫) は安定でなく一夫一妻に戻ることもしばしばある。予想に反してレック形成は一夫多妻または一妻多夫から進化したより一夫一妻から進化したと考えられるとのこと。
Polygamy is (not) for the birds 一般向け解説 (Alexandra Becker, Rice University 2025.1.13)。
Luzuriaga-Aveiga (2025) Digest: Extremes of the mating system continuum are the most evolutionarily stable こちらは短い解説論文でオープンアクセス。
意外に見えるが一夫一妻とレック形成が進化的に安定で、resource-defense polygamy は不安定で一夫一妻に戻るか、その系統は消滅したかのいずれかと解説している。弱い雌雄の結びつきの場合はオスの子育てへの投資が不確実で、メスにとって適切な戦略となっていない可能性を考えている。
一夫一妻が圧倒的に多い (91%) のは雌雄の結びつきが強くどちらの性にとっても有利な可能性がある。
一夫一妻でパートナーを変える行動は繁殖成功率を上げる戦略の可能性があるとのこと: Culina et al. (2015) Trading up: the fitness consequences of divorce in monogamous birds。
-
アメリカヒレアシシギ
- 学名:Phalaropus tricolor (パラロプース トゥリコロル) 三色のオオバン足のシギ (リストにより三色の水かきのある足の鳥)
- 属名:phalaropus (合) オオバンの足 [phalaris, phalaridos (Gk) は未同定の水鳥で、オオバンと考えられている。鳥類学ではこの意味で使われる< phalaros 白い班のある < phalos 白 (Gk) (The Key to Scientific Names)。pous 足 Gk]
- 種小名:tricolor (adj) 三色の (tri- (接頭辞) 三つの color (m) 色)
- 英名:Wilson's Phalarope
- 備考:
steganopus はギリシャ語由来の -pus が長母音を持つ。-ga- がアクセント音節と考えられる (ステガノプース)。
phalaropus は#ハイイロヒレアシシギ参照。
tricolor は短母音のみでアクセントは冒頭にある (トゥリコロル)。
単形種。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Steganopus 属 (steganopous, steganopodos 水かきのある足の Gk < stegane 水かき Gk podos 足 Gk) としている。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。この場合 Steganopus tricolorとなる。
HBW/BirdLifeでは Steganopus 属、IOC、eBird など Phalaropus 属を用いている方が多く、第8版の最終的な学名が何になるかは不定要素がある。Steganopus 属の場合は単形属。
最終的に Phalaropus tricolor となった。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 では Phalaropus tricolor。
Steganopus は Vieillot (1818) が提唱した属名で Peters (1934) が採用していた (The Key to Scientific Names)。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)にて Phalaropus 属となった。
Boyd では Steganopus tricolor。
Cerny and Natale (2022) の分子系統解析では Phalaropus 属としても単系統となるが、属の分岐年代をどの程度まで反映するかの選択となる。
ヒレアシシギ類の中でもアメリカヒレアシシギのみは系統が少し古いと理解すればよさそう。ソリハシシギがさらに古い分岐に当たると考えると見かけがあまり似ておらず不思議な感じもする。
英名はアメリカの鳥類学者 Alexander Wilson に由来。
北米で繁殖し南米に渡るが、他地域にも分布する可能性がありよくわかっていないようである。
-
アカエリヒレアシシギ
- 学名:Phalaropus lobatus (パラロプース ロバートゥス) 弁足のヒレアシシギ
- 属名:phalaropus (合) オオバンの足 [phalaris, phalaridos (Gk) は未同定の水鳥で、オオバンと考えられている。鳥類学ではこの意味で使われる< phalaros 白い班のある < phalos 白 (Gk) (The Key to Scientific Names)。pous 足 Gk]
- 種小名:lobatus (adj) 葉状の、弁足の (lobus (m) 葉 -atus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Red-necked Phalarope
- 備考:
phalaropus は#ハイイロヒレアシシギ参照。
lobatus は a が長母音でアクセントもある (ロバートゥス)。所有の -atus の長母音由来。
学名と英名の対応が悪いが、これはかつて使われていた学名 Phalaropus ruficollis Pallas, 1811 (参考。首の赤いヒレアシシギ) に由来。下記のように Linnaeus (1766) の Tringa lobata の記載が整理された上で原記載となった。
単形種。
スウェーデンからアラビアまで内陸を通って渡ってゆく研究: van Bemmelen et al. (2015) First geolocator tracks of Swedish red-necked phalaropes reveal the Scandinavia-Arabian Sea connection。
原記載では生息地はアメリカとラプランドと記述されている。ラプランドについては Per Adlerheim が発見 (#ハマシギの備考参照)。
この順序に基づき基産地は優先順からハドソン湾 (下記参照) となっている。
wikipedia 英語版の synonyms によれば Linnaeus が Lobipes lobatus の学名も与えたかのように読めるが、こちらは Cuvier (1816) の学名。
しかし Linnaeus は Tringa hyperborea Linnaeus, 1766 を記載しており (原記載、こちらはアカエリヒレアシシギのシノニムとされる (The Key to Scientific Names)。
この Linnaeus (1766) では Tringa lobata の生息地に英国を追加しアメリカを外した。Tringa hyperborea の方がハドソン湾となっている。
Linnaeus は英国でも生息することを知ったとともに2種に分離した意向がわかる。これを検討した結果シノニムと判定され、曖昧だったアカエリヒレアシシギの基産地がハドソン湾と特定されたよう。
現在は単形種とされるので問題はないが、もしユーラシアとアメリカが別亜種と考えられるならば Linnaeus (1766) の記載は別亜種を記載したことになるのか、それとも Linnaeus (1758) の基産地がアメリカと解釈できるのでシノニムと判定されるのかちょっとわからない。
鳥類全体の配偶様式と地理的関係を調べた論文: Barber et al. (2024) Climate and ecology predict latitudinal trends in sexual selection inferred from avian mating systems
北半球の高緯度地方、北アメリカ、ヨーロッパで一夫多妻または一妻多夫の割合が高い。一方赤道や南半球では少ない。気候の季節変動の大きいところで多い傾向はよく現れている。
-
ハイイロヒレアシシギ
- 学名:Phalaropus fulicarius (パラロプース フリカーリウス) オオバンのような足のヒレアシシギ
- 属名:phalaropus (合) オオバンの足 [phalaris, phalaridos (Gk) は未同定の水鳥で、オオバンと考えられている。鳥類学ではこの意味で使われる< phalaros 白い班のある < phalos 白 (Gk) (The Key to Scientific Names)。pous 足 Gk]
- 種小名:fulicarius (adj) オオバンのような (fulica (f) オオバン -arius (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Red Phalarope
- 備考:
phalaropus はギリシャ語 phalaris は短母音のみ、ギリシャ語の足由来の -pus が長母音。-la- がアクセント音節と考えられる (パラロプース)。
fulicarius はオオバンの属名由来で冒頭を伸ばさない (#オオバン解説参照)。-arius は冒頭が長母音でアクセントもここにある (フリカーリウス)。
学名と和名・英名の対応が悪いが、これはかつて使われていた学名 Phalaropus cinerascens Pallas, 1811 (参考。灰色っぽいにヒレアシシギ) 由来する可能性のある英名別名 Grey/Gray Phalarope もあるため。
和名は英名や学名と対応させたものと想像される。
Phalaropus rufus Bechstein, 1809 (参考) や Phalaropus rufescens Keyserling & Blasius, 1840 (参考) が Red Phalarope に対応する学名であった。
Phalaropus griseus Leach, 1816 (参考) には Grey Phalarope と記されていたので英名と学名の関係は明らかだった (この用例でどちらが早いかは不明)。
この時点の用例は無効とされ、Phalaropus griseus Forster, 1817 (参考) は Linnaeus (1758) の Tringa Fulicaria に新属を与える際にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる。
Phalaropus を冠した前記のいくつかの用例の少なくとも一部も同様と考えられる (#ノスリの備考参照)。後に Linnaeus (1758) の種小名に戻されたと推定できる。
記載順から Phalaropus rufus = Red Phalarope と Phalaropus cinerascens = Grey Phalarope の順ならば Red Phalarope の方が優先して使われていたのかも。言うまでもなく赤い方はメスの夏羽を指していた。
メスの夏羽を指すならばアカエリヒレアシシギよりハイイロヒレアシシギの方がより赤いではないか、と感じるのも自然であるが、おそらく和名成立当時の学名または英名を反映した結果このようになっていると想像できる。
単形種。北半球極北部で繁殖。Phalaropus 属のタイプ種。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES レンカク科 JACANIDAE ▽
-
レンカク
- 学名:Hydrophasianus chirurgus (ヒュドゥロパーシアーヌス キールールグス) 外科医のメスを持つ水キジ
- 属名:hydrophasianus (合) 水キジ (hydro- (接頭辞) 水の Gk、phasianus (m) キジ)
- 種小名:chirurgus (m) 外科医
- 英名:Pheasant-tailed Jacana
- 備考:
hydrophasianus は phasianus の a が2つとも長母音で後者にアクセントがある。hydro- は短母音 (ヒュドゥロパーシアーヌス)。
chirurgus は冒頭の2母音が長母音で後者にアクセントがある (キールールグス)。語源はギリシャ語 kheirourgos が由来で kheir (手) + ergon (働き) とのこと。
単形属で単形種。
種小名は外科医の持つメス (lancet) のように長い趾と爪 (The Key to Scientific Names)、あるいは翼角の突起 (爪) (carpal spur/wing spur) の2説がある。
後者の説は「野鳥の名前」(安倍直哉 2008、再編集されて 2019 年刊行 山と溪谷社)にあるそうである [コンサイス鳥名辞典も同じ。唐沢 (2014) Birder 28(10): 70 に記載されている]。
フランスの探検家 Pierre Sonnerat はこの種を「ルソン島の外科医」("Le Chirurgien de l'Isle de Luzon") と記述し ("Voyage a la Nouvelle Guinee" 1776) 、長い趾と突き出た特殊な構造の初列風切を外科医のメスに見立てたとある。それを受けて Giovanni Scopoli によって 1787 年に記載された (wikipedia 英語版)。前者の説が正しそうである。
ちなみに外科学のことは上記のようにフランス語で chirurgie シリュジー、ドイツ語で Chirurgie ヒルルギー と呼び、日本では過去に主にドイツ医学が入っていたので年配の医師の方であればこの用語を使われているかも知れない。これらの単語を知っていればわかりやすい学名。英語の綴り surgery は違って見えるがフランス語の音と比較すれば同じ語源であることがわかる。
carpal spur を持つ種については Rand (1953) On the spurs on birds' wings がある。
この文献にはそのものずばりの名を持つツメバガン Plectropterus gambensis 英名 Spur-winged Goose は爪で相手を傷付けることもできると言われると書かれている。wikipedia 英語版によればツメバガンの一部に餌のツチハンミョウ類 (blister beetle) 由来の毒を持つものもあるそうである。
レンカク類ではアメリカレンカク Jacana spinosa 英名 Northern Jacana でディスプレイの際に翼角の爪を見せて攻撃のポーズをとると言われている。
Hume and Steel (2013)
Fight club: a unique weapon in the wing of the solitaire, Pezophaps solitaria (Aves: Columbidae), an extinct flightless bird from Rodrigues, Mascarene Islands
には翼角の爪を武器として使っていたらしいドードーのようなハト類の絶滅種があるとのこと。
英名にある Jacana またはレンカク科 Jacanidae (日本には分布しないが Jacana 属がある) の名称は、
ナンベイレンカク Jacana jacana 英名 Wattled Jacana のポルトガル名の jacana に由来。これはブラジル原住民ツピ (Tupi) 族の言語 (絶滅言語) で yassana または yahana で非常に警戒心が強くて騒がしい鳥のこと (The Key to Scientific Names)。
jacana をどのように発音するかは議論があり、ポルトガル語ではジェセネーのような発音になるそうで,、英語ではジェセナーのような発音になるとのこと。3つめの c の文字は本来は下に s のような記号が付き (フランス語のセディーユ、ポルトガル語でセディリャ、日本語名セディラ)、c は k ではなく s と発音される (wikipedia 英語版より)。
Spurs and blades on the wings of jacanas, lapwings, sheathbills and archaeotrogonids (clubs, spurs, spikes and claws part II)
にも面白い解説があり、レンカクを含む数種の鳥は捕食者が現れたときにひなが水中に身を隠して嘴をシュノーケルのように用いるとのこと (#サカツラガンの備考参照)。同様の行動は他のシギ類には見られない。ケリ類の爪についての言及もある。
[チドリ目の配偶様式]
レンカク類はヒレアシシギ類やタマシギと同様にオスが抱卵や子育てをする。レンカク科のほとんどの種は一妻多夫。ほとんどの種は留鳥であるが、レンカクは例外的で一部の個体群が渡りをする (wikipedia 英語版より)。
ナンベイレンカクのような雌雄の役割が通常と逆転し、しかも一妻多夫の場合に Z 染色体の進化が特に速いとの研究が出た: Wanders et al. (2024) Role-reversed polyandry is associated with faster fast-Z in shorebirds
従来は鳥類の Z 染色体の進化が早い理由は遺伝的浮動によるものとされていたが、雌雄の役割が逆転した一妻多夫の場合にはこの効果を打ち消すほどの選択圧がメスにかかるか、あるいは性的二形を強化する遺伝部位がより強い選択を受ける効果が考えられるとのこと。
シギ・チドリ類の配偶様式の系統樹も出ており、どの系統で雌雄の役割が逆転したかも見ることができるが、タマシギのように古い系統で現存している種が少なく、一部の種でのみこの繁殖様式が見られる系統もあって推定しにくい部分もある模様。
レンカクの系統では少なくとも 3800 万年前から、ミフウズラの系統では少なくとも 3100 万年前からこの様式をとっていた可能性が高い (ミフウズラ類は孤立系統の可能性があり、もっと古いかも知れない)。
雌雄の役割が逆転した主な系統は レンカク上科 Jacanoidea (タマシギ科 Rostratulidae + レンカク科 Jacanidae) とミフウズラ類とみなしてよさそう。#タゲリの備考で紹介した系統分類はこのような場面で関連が見えてくることがある。
なお [#鳥類系統樹2024] の Stiller et al. (2024) の結果でもタマシギとナンベイタマシギの分岐が古いことが確認され、姿は似ていても別属がふさわしい。配偶様式も異なる (#タマシギ備考)。
ヒレアシシギ類でのオスによる子育ては有名だが、近縁系統の中ではこの属のみの特性のようで、レンカクやミフウズラより新しく出現した性質のよう。
#コバシチドリの事例は散発的に生じたもののよう。
オーストラリアのマメミフウズラ Turnix velox Little Buttonquail では特に進化速度が早いがこれはおそらく世代が短いためだろうとのこと (ミフウズラ類は他の解析でも同様の傾向がある。#ミフウズラの備考参照)。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES タマシギ科 ROSTRATULIDAE ▽
-
タマシギ
- 学名:Rostratula benghalensis (ローストゥラートゥラ ベングハレーンシス) ベンガルの嘴が目立つ鳥
- 属名:rostratula (adj) rostratus (大きな嘴の、嘴が目立つ) rostrum 嘴 -atus 形容詞に -ula (指小辞) 小さい)
- 種小名:benghalensis (adj) ベンガルの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:(Painted Snipe 分離前の名称), IOC: Greater Painted-snipe
- 備考:
rostratula は rostrum が冒頭が長母音。-atus が形容詞を作る語尾で冒頭が長母音。指小辞 -ula は短母音 (-tula は伸ばさない)。-tra- がアクセント音節と考えられる (ローストゥラートゥラ)。
Rostratula 属は Vieillot (1816) がマダガスカルのタマシギ1種について与えたもの。
当時の慣習によって属が変わる場合に新しい種小名が与えられ (#ノスリの備考参照) て Rostratula viridis Vieillot, 1817 (参考 1, 2)。
記載時学名 Rallus benghalensis Linnaeus, 1758 (原記載) 生息地は Asia とある。
benghalensis は地名の -ensis から長母音を採用した (ベングハレーンシス) が短音でもアクセント位置は変わらずどちらでもよい。
bengalensis と benghalensis の両方の綴りが存在し誤植ではない (むしろ誤記と考えて訂正してしまうリスクがある)。benghalensis の用例は少ない。Linnaeus (1758) が好んで用いていた表記で現存するものでは他の著者による用例はあまりない (The Key to Scientific Names)。
Rallus benghalensis の名称は以前よりあり、Linnaeus が発明した名称ではない。
綴りを気にした人はやはりあったようで、Rallus bengalensis Gmelin, 1789 (参考) と改名提案もあった。
我々は気にしなくてもよいかも知れないが、gh のラテン語読みは特別な規則があるわけではなく、音節区切りを考えると beng-ha-len-sis とも分割されそうに思えるので "ハ" の音を残す発音を採用した。綴りの違いを意識するためにはこの読み方は有用かも知れない。
同じ種小名は植物でよく知られた用例があり例えば ベンガルボダイジュ Ficus benghalensis。Linnaeus は植物学の方が専門なので植物の用例の方が多いよう。
ベンガルはギリシャ語では Beggale (最後の e は長母音) の表記で Beg-ga-le と分け、現代ギリシャ語の発音では冒頭が beng (ng は英語 ng と同じ音) となっている。Linnaeus (1758) はギリシャ語から綴りと音を採用し、-ga- を -ha- として残したのかも知れない。
この綴りの場合 "グ" はあまり強く読まず、英語の -ng に似た発音にするのがよさそうに思える。
rostratula に類似する Rostrata はサイチョウ類の属名。シノニムに Rhynchaea (大きな鼻/嘴の) がある。こちらは Cuvier (1816) が与えた属名。
他のシギ類に比べて嘴が大きいことを特徴と捉えたのだろう。Bec plus long que la tete, un peu grele, sillonne en dessus, un peu renfle vers le bout, lisse et courbe a la pointe (The Key to Scientific Names の情報による)。冒頭に嘴は頭より長く、とある。先端が曲がっている点は最後に出てくる。
愛媛の野鳥「はばたき」には「先端の曲がった嘴の」とあるが、シノニムとなった学名の用例も考慮してここでは "嘴が長い" 特徴を優先することにした。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で亜種 australis を別種 (英名 Australian Painted-snipe) とし、タマシギは単形種となる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
括弧内の英名はこれらの分離される前のもの。
英名の (種を分離する前の) Painted Snipe に相当する学名がある。Rhynchaea varietaga Vieillot, 1825 (参考)。
これは Scolopax capensis Linnaeus, 1766 [記載。基産地南アフリカのケープ。後に Linnaeus (1758) がすでに記載していたタマシギと同一とされシノニムとなった] の属を変えるとともに改名したものとのこと。
Vieillot (1825) はおそらくフランス語の記述と想像されるので Painted Snipe の英名は学名やこのフランス語記載に由来したかも知れない。Linnaeus (1758) の記載したものと同一であることは Hartert が記述したとある。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Rostratula capensis (Linn.) となっており Linnaeus (1758) の記載した benghalensis と同一であることはまだ知られていなかった時代のよう。タマシギの名称はすでに用いられていた。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でも同様に Rhynchaea capensis の方が使われていた。当時は中国、インド、南アフリカから日本では主に南部で繁殖するとされていた。
関連する学名に Rhynchaea varia Horsfield, 1824 (参考) があり、これは R. orientalis Horsefield を改名したものとあるがこちらは何を指していたか不明。
Gallinula orientalis Horsfield, 1821 の用例 (参考) があるがこれを指したものかどうか不明。
Rhynchaea picta Gray, 1831 (参考 基産地 アフリカ、インド、中国) で意味は "絵のような" なのでこれもいかにも英名とよく合っている学名。どちらが先かはわからないが古い時代には英名と学名が対応していたと考えられる。
Rhynchaea variabilis Temminck, 1836 (参考) はその後の名称で #クロジの備考も参照。単語は似ているが Temminck は別の意味で使っていたかも知れない。
尾羽に黄色の水玉模様がある (コンサイス鳥名事典) の記述があるが和名の由来とまでは書かれていない。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) の "はまだら鴫" をタマシギと同定している。その後特に現れない名前らしくタマシギの和名は比較的新しく付けられたもののよう。
タマシギの繁殖様式は雌雄の役割が通常と逆転し、しかも一妻多夫だがナンベイタマシギ Nycticryphes semicollaris American Painted-snipe では役割が逆転しておらず、一夫一妻で弱いコロニー性を示す。
#レンカク備考の Wanders et al. (2024) では同属と扱って解析しているが系統的はかなり古く分岐しており [#レンカク備考。Stiller et al. (2024) の解析による]、姿は似ている点があっても系統的にはやや違っていると見るのがよさそう。
レンカク類とタマシギ類はシギ類の中では比較的近い系統で、雌雄の役割が通常と逆転している種類の多いグループ。
[オーストラリアタマシギ]
オーストラリアタマシギ Rostratula australis Australian Painted-snipe はかつてはタマシギの亜種とされていたが分離された。
研究は Baker et al. (2007) Mitochondrial-DNA evidence shows the Australian Painted Snipe is a full species, Rostratula australis。
Rostratula 属は現在この2種からなる。最新のもの以前の図鑑を見るとタマシギの分布域にオーストラリアが含まれているのはこのため。
それほどよく調べられているグループではないので今後も分離があるかも知れない。
Baker et al. (2007) ではタマシギの東南アジアとアフリカの個体群では 2% の違いであるにもかかわらずオーストラリアタマシギは 10% 違うとのこと。分岐年代は 1900 (95% 信頼区間 1300-2740) 万年前と推定され、かつて亜種とされていたこと自身が驚きの結果となった。
EF632090.1 (cyt b) から BLAST を試みてみると確かにとんでもなく違う。隠蔽種かどうかのレベルではなく別属にしても不思議でないぐらい。
世界のタマシギの解説や分布を見る時はそのつもりで考えていただいた方がよい。特に分離されていない時期に書かれた記述などは要注意。
オーストラリアタマシギはオーストラリアで出会うことが困難な種のトップ 10 に入るとのこと。
In search of our mysterious painted-snipe (Amanda Freeman and Jay Collier, Australian Geographic 2024)。
バードウオッチャーにとっても研究者にとっても困難な種類で、分布が散発的でどこに現れるか予測できない。移動能力が大きく (タマシギより翼も長いとのこと) 遠く孤立した湿地に現れることもあるとのこと。一時的に現れる湿地に依存して生息している
(これは乾燥したオーストラリアの条件と気象条件の変動の大きさを表しているのだろう)。
タマシギ同様に一妻多夫と考えられている (これはタマシギと同種時代の見解に左右されているかも知れない。色彩はオスの方が地味でより小型とのこと)。2021-2022 年の目撃数はゼロだった。2023 年に 25 羽の群れが記録され研究者たちを興奮させた。音声 (さえずり) は重要な発見手がかりとなると考えられるが、これまで録音がなく、またタマシギの音声にも反応しないとのこと (これだけ系統が違えばまったく違ったものになっているだろう)。
気候変動による干ばつでそのような一時的湿地が一層失われる恐れがあり絶滅の恐れもある。生態の基礎的情報が必要で目撃情報の報告が呼びかけられている記事。
xeno-canto には音声登録は1例もなく、Macaulay Library に記録されている唯一の録音は音声ではなく羽ばたきの音のみ Australian Painted-Snipe (Nigel Jackett 2025.3.22)。2025.5 現在、世界に公開の音声音源が一例もないことになる。
変動が大きく一時的に出現するタイプの湿地を得意な環境としているのか、ナンベイタマシギではタマシギと夫婦の役割が逆転していることなど、タマシギの一妻多夫の起源とともに興味深いと思われる。
あるいは系統が違いすぎてオーストラリアタマシギとタマシギの類似性は表面的なものにとどまるかも知れない。
#レンカク備考の [チドリ目の配偶様式] にも関連論文があり、あるいは将来ゲノム解析から配偶様式が推定できたり、あるいは配偶様式の進化経路もたどることができるようになるかも知れない。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES ミフウズラ科 TURNICIDAE ▽
-
ミフウズラ
- 学名:Turnix suscitator (トゥルニクス ススキタートル) 目を覚ましてくれるウズラ
- 属名:turnix (合) 後趾を欠く小さなウズラ [Coturnix 属 (ウズラ属) を短縮して作られた属名。「小さい」の意味と後趾を欠く特徴が込められている] (The Key to Scientific Names)
- 種小名:suscitator (m) 目を覚ますもの suscitare 起こす + -ator (行為者)
- 英名:Barred Buttonquail
- 備考:
turnix は coturnix の短縮形と考えれば短母音のみ (トゥルニクス)。
属名解説には The Key to Scientific Names の解釈を採用したが、IIIe. GENRE. TURNIX, Turnix. ... Les pattes divisees en trois doigts & plus courtes que les rectrices ... の記載部分からと思われる。原意は "小さなウズラ" で十分かも知れない。
Turnix Rafinesque, 1815 は "Tridactilis" (= Tridactylus) Lacepede, 1801 を改名したものとこのこと。Tridactylus (3本指の) は Olivier (1789) がバッタ目の属名にすでに用いており無効だった。
Rafinesque (1815) が "小さなウズラ" 以上に Lacepede (1801) の属名意味まで引き継いだかどうかは不明。
suscitator は -ator の語尾の最初が長母音。アクセントもこの位置と考えられる (ススキタートル)。-or は伸ばさない。英語の語尾に非常に多い行為者を表す -ator も同じ起源。
suscitator によく似た綴りの susceptor のような英単語があるが、sus- の語源は共通 (sub-) しているものの後半の語源は異なる。
ラテン語 suscitator の方は cito (キトー。副詞で "急いで"、"急に") に由来し、英語の susceptor はラテン語そのままに由来し、ラテン語 suscipere に由来する。こちらは capio (カピオー。奪う) が語源。
英語では susceptible の形がよく現れ、生物用語で "感受性のある" など広く使われる。suscitator とは語源も発音も異なる。
16 亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは okinavensis (沖縄の) とされる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" は2種をリストし、当時の学名で Turnix blakistoni Okinawashima にカントンミフウズラ、Turnix taigoor Okino-Erabushima, Miyakoshima, Okinawashima, Ishigakijima にインドミフウズラの名称を与えていた。いずれも現在は亜種扱い。
亜種 okinavensis の記載は遅く Phillips (1947) The Button Quails and Tree Sparrows of the Riu Kiu Islands。
この記述によれば途中に台湾の別亜種 rostratus (原文 rostrata) があるにもかかわらず従来は中国と同じ亜種 blakistoni と考えられていた。台湾の亜種は中国本土とは違い、琉球列島のものはそれとも異なるとして新亜種を記載したもの。
1945 年に採集された標本からとのことでアメリカ軍の占領下時代に入ってからの研究だろうか。
Ogawa (1908) にあるインドの亜種 taigoor については特に触れられておらず、20 世紀初頭にはまだよくわからなかったのだろうか。台湾の亜種は 1865 年に記載されている。
英語の buttonquail にも小さなウズラの意味が込められている。種小名の意味は、Brisson (1760) によれば Reveil-matin (目覚まし時計)、Latham (1783) で Noisy Quail と、声の大きさが由来だそうである (The Key to Scientific Names)。原記載。
ミフウズラの和名、英名の起源の考証 (学名解説は上記と同じ。短縮名は何かが欠けていることを表すとのこと) が大橋 (2020) Birder 34(7): 16-17 にある。大橋氏は英名の button の由来は目がボタンのように見えるからではないかとしている。
中国名は棕三趾鶉で趾が3本であることに対応している。大橋氏による一つの解釈は「三歩」で趾が3本である意味があるとのこと。
wikipedia 日本語版では旧名フナシウズラとあり、この解釈に対応しているように思える。
三斑鶉の表記も使われている。
英語別名に Bustard Quail もあった。一方で Barred Quail Philortyx fasciatus にヨコフウズラの和名が与えられているので、"barred" でない、すなわちフナシウズラは "横縞がない" の意味の可能性もあるかも知れない。
山階鳥類研究所の標本データベースを確認しておくと古くは沖縄の標本に Turnix taigoor の学名を与えていた。taigoor は由来があまりよくわかっていなくて、HEMIPODIUS TAIGOOR. ... Closely resembles the female of Hem. pugnax as described by M. Temminck, but the bill is longer and more slender, and Colonel Sykes has specimens of both sexes (Sykes 1832) との記載で、おそらくヒンディー神話の名前か狩猟鳥の地域名ではないかと Gray (1844) に記されているとのこと (The Key to Scientific Names)。
記載時の属名に使われた Hemipodius は hemi- 半分、小さい podion 足 (Gk) で学名の特徴を解釈すれば足に特徴を見出したと考えるのが妥当だろう。
Hemipodius 属は Temminck (1815) によるもので、Temminck から多くのこと学んだ初期の日本の鳥学者もこの属名を解釈して和名に整合性を持たせたかも知れない。
和名に "ウズラ" が付くのは日本で独立に生まれた概念と考えるより、むしろ英名などの外国語由来かも知れない。
大橋氏の記事によれば江戸時代に少数が輸入されていてこの時代からあった名前とのことだが、博物学者がすでに記述し、"Tridactilis" (= Tridactylus) Lacepede, 1801 の名称がすでに与えられて無効であることが判明していなかった時代であれば輸入先でもすでに学名や外国語名由来の名前が使われていたかも知れない。
ちなみに Ogawa (1908) ではキジ目に含まれていたので "ウズラ" の名が付いていることは不自然でなかった。"Tridactilis" (= Tridactylus) Lacepede, 1801 の時代でも当時所属すると考えられたキジ類としては例外的に趾が3本であることを示す意味があったと考えるのが自然に見える。チドリと考えられていたがシギに分類されることがわかった #ミユビシギの状況によく似ている。
かつてはウズラに近縁の場所に分類されていたり、ツル目に含まれていたこともあったが現在はチドリ目に分類される。例えば
Baker et al. (2007) Phylogenetic relationships and divergence times of Charadriiformes genera: multigene evidence for the Cretaceous origin of at least 14 clades of shorebirds
を参照。シギ類 (Scolopaci 亜目) とカモメ類の間でカモメ類前の分枝に収まるが分子時計に基づく進化速度が例外的に速いとのこと。Berv et al. (2018) Genomic Signature of an Avian Lilliput Effect across the K-Pg Extinction
ではこの理由の一つとして大量絶滅 (K-Pg または K-T 大量絶滅; K/T 境界の大絶滅とも呼ばれる *1) の際に大型種ほど影響を受けやすく、相対的に進化速度が速い小型種が生き延びた効果を考えている
なぜ恐竜は絶滅して鳥は生き残ったかの説明にしばしば使われた仮説。この当時チドリ目グループの祖先はすでに存在しておりこのグループの少なくとも 14 系統が大絶滅を生き延びたとこの論文では考えている。上記 Baker et al. (2007)。もっとも化石証拠は乏しく#ミサゴの備考 [鳥類系統樹2024] Torres et al. (2025) も参照。現生鳥類と別系統ではない Galloanserae の古い系統で現生鳥類の直系の祖先と考えられる最も古い証拠とのこと。
ミサゴの備考で鳥類進化を記述して、Baker et al. (2007) の解析は妥当なのか疑いを持ち、NC_084184.1 (ミトコンドリアゲノム) から BLAST を試してみると Larus 属より分子進化が速い傾向はあるがそれほど極端な違いでない。むしろシギ類の分子進化が遅いことが目立つ。
ミフウズラ と チョウセンミフウズラ Turnix tanki Yellow-legged Buttonquail や マメミフウズラ Turnix velox Little Buttonquail の違いがずいぶん大きく、分子進化が速いのはむしろ Turnix 属の特性で K-Pg 境界以降も分子進化が速いようなので、大絶滅とはあまり関係がないのでは?
Baker et al. (2007) は大絶滅に伴う "Lilliput Effect" (より大きいサイズのものが絶滅しやすいと考えられる化石証拠がある) を鳥でも検出しようとして探した結果見つけたもので、"小型種が大絶滅を生き延びた" パラダイムに沿う結果を得ようとしたものと想像できる (このあたりのニュアンスは上記 [鳥類系統樹2024] の解説参照)。
つまりこの結果は額面通り受け取らない方がよさそうである。ミフウズラ類が K-Pg 境界を生き延びた系統であった推論も上記アイデアを導くために必要な仮定で怪しい感じがする。
あるパラダイムを支持する研究結果に疑問を投げかけるにはこれほど手間がかかるわけである。これら3種のミトコンドリアゲノムが公開されたのは 2023-2024 年のこと [後述の Dey et al. (2023) のミフウズラを含む] なので、Baker et al. (2007) のアイデアはその範囲まで延命できたわけだった。
1種しかデータがなければある程度広い範囲の解釈が可能だが、同じ系統の複数種のデータが得られるとある解釈が必ずしも支持されないことも生じ得る。
ミトコンドリアは細胞内呼吸に関与するので、シギ類は長距離を時にはノンストップや高高度で渡り、代謝まで変えてしまうぐらいなので、ミトコンドリア遺伝情報に対する選択圧が強く働いていてよく保存され、進化速度が遅いのではないだろうか。カモメ類は中間的で、長距離を飛ばないミフウズラ類では選択圧が弱かったため進化速度が速かったのでは ... ぐらいのことは遺伝子に対する選択圧を見ればよいので誰かがすでに調べて報告しているかも知れない。
全ゲノムを解析したはずの Stiller et al. (2024) はミフウズラ類のミトコンドリア遺伝情報以外の進化速度についてもう少し証拠を得ているのではないだろうか。
Berv and Field (2018) Genomic Signature of an Avian Lilliput Effect across the K-Pg Extinction
は現生鳥類全般で小型種ほど分子進化速度が早い効果を検出したと報告しているが、生活史など交絡因子もあるので統計的に物を言うのは思ったより難しい (早い話が代謝率の高い小型種はスズメ目に圧倒的に多いわけだし...)。
小型種の分子進化速度を分子時計にして分岐年代を推定すると古すぎる年代を与える要因となり得るとのこと。中程度の大きさの種の分子進化速度に基づく推定では K-Pg 境界を生き延びたのは限られたものにとどまり、大型種を基準にするとほとんど生き延びていないことになる。
"Lilliput Effect" のように見えるのは K-Pg 境界で選抜されたものか、その後の急激な適応放散に伴って小型化を起こしたのか、さらには人為起源で大型種が狩猟の対象となった影響も関係しているのか、早い話あまりよくわからないということらしい。
この論文の見積もりをある程度信用すれば K-Pg 境界を生き延びた系統または種はこれまで考えられていた以上に少なかったのではないだろうか。K-Pg 境界を生き延びたものがごく少数であったならば統計的ゆらぎの効果も考えられ、なぜ恐竜は滅んでその中で鳥だけが生き延びたかはあまり本質的な問いではないのかも知れない。
Mayr (2011) The phylogeny of charadriiform birds (shorebirds and allies) - reassessing the conflict between morphology and molecules
では形態学 (骨学) と分子系統樹が矛盾することを示しており、ミフウズラ類とカモメ類の系統的近さは分子遺伝学的には支持されても形態的には両者にほとんど共通点がないとのこと。さすがの Mayr (Ernst ではなく Gerald) もこの分類群では形態学による系統解析に限界を認めている。
ミフウズラ科を Lari (カモメ) 亜目に含める分類は問題があり、nonturnicid Lari (ミフウズラ科を除くカモメ亜目) のような名称も使われている。
現代でも位置づけの難しいグループであるが、
Dey et al. (2023) Dataset from genome sequencing, assembly and mining of microsatellite markers in barred-button quail Turnix Suscitator
がゲノム解析を行っている (preprint 段階ではもう少し記載があったが出版論文は上記)。
上記の複数の研究を踏まえると恐竜絶滅の際にも生き延び、独自の進化を遂げたグループと考えてよさそうである (と思って当初読んだが、前述のように [鳥類系統樹2024] を記述していてそうではないかも知れないかと感じた)。
チドリ目ミフウズラ亜目 (Turnices、ツル目に含まれていた時代に使われていた名称) とするのがおそらく適切なのであろう。チドリ目は誕生後かなり多くの系統が失われてミフウズラ科が単独系統のように残ったと考えるのが妥当そう。
ミフウズラ科などいくつかのグループはハトのように水面から直接水を飲むことができる [Fry (1978) Buttonquails in "Bird families of the world"; Drinking Methods in Two Species of Bustards]。
台湾の亜種 rostratus は認められないこともあるようで [Collar (2004) Endemic subspecies of Taiwan birds - first impressions]
多少注意が必要かも知れない (つまり okinavensis との関係がどうなるか。同一亜種であるならば rostratus の方が記載が早い)。
ミフウズラ類は虹彩にある特徴的な模様 (heterochromia) を持つ。#カッコウの備考 [非対称な色彩の虹彩を持つコミチバシリ] 参照。Gutierrez-Exposito (2019) Asymmetric iris heterochromia in birds: the dark crescent of buttonquails は heterochromia の生態的適応についても考察している。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3615 のミフウズラの項目 (安部) によれば抱卵・育雛はオスの役目 (繁殖期の歌はメスが出す)。早成性の鳥で 12-13 日で生まれる。4週間ぐらいで独立。ヒメミフウズラ Turnix sylvaticus Small Buttonquail では飼育下では 3-5 か月で産卵し始めるとのこと。一妻多夫でインドではメスに似せた模型をおとりに使って捕獲するとのこと。
備考:
*1: K-Pg 境界: Cretaceous-Paleogene boundary 中生代白亜紀 (独: Kreide) と 新生代古第三紀 (英: Paleogene) の略。略すと C の文字になる地質年代が多いのでドイツ語の K が使われている。
かつては 第三紀 (英: Tertiary) とされていたので、K-T 境界と呼ばれていたが第三紀が古第三紀と新第三紀に区分されるようになり、1989 年以降国際地質科学連合は「第三紀」の語を正式な用語から外したため名称が変わった (wikipedia 日本語版)。古い人間は K-T 境界の名称に長く慣れていたのでちょっと戸惑う部分もあるが...
wikipedia 日本語版の K-Pg 境界 の記事は多少古いところもあるが、アルバレス (Walter Alvarez) の巨大隕石衝突説の証拠についてはここで改めてまとめるよりもこちらを読んでいただいた方が早いだろう。
Alvarez は別件で 1968 年にノーベル物理学賞をすでに受賞していた。そして世界観を変えるほどの巨大隕石衝突説ということになる。このあたりは後述の Hoyle とはだいぶ異なる。
脚注にある「斉一説」は自然において、過去に作用した過程は現在観察されている過程と同じだろう、と想定する考え方。「現在は過去を解く鍵」という表現で知られる近代地質学の基礎となった地球観。天変地異説に対立する説として登場したもの (wikipedia 日本語)。こちらの歴史的理解の変遷も興味深いので該当ページをお読みいただければと思う。
地質学ではあまりに斉一説に固執したため巨大隕石衝突説をなかなか受け入れられなかったとの反省の見解もあった。
巨大隕石衝突説は意外なところにも影響を及ぼしていた模様。「社会生物学論争史: 誰もが真理を擁護していた」(ウリカ・セーゲルストローレ著 垂水雄二訳 みすず書房 2005) p. 639 によれば (冷戦期の核戦争の脅威に代わって) "ネオ天変地異説的風潮" のもとで、E. O. Wilson の唱えた生物多様性の保護の重要性が受け入れられやすかったとのこと。巨大隕石衝突説も自然環境保護の考え方の進展に一定の役割を果たしていたらしい。
巨大隕石衝突後、ただ1種生き延びた鳥類から現代の鳥類が始まった考えがあったことを知った (今ではもちろんそのように考えられていない)。
Wyles et al. (1983) Birds, behavior, and anatomical evolution。
Emery (2006) Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence に引用されているのだが、始祖鳥からの始まる唯一の生き残りで、スズメ目の出現は霊長類にも匹敵するほど新しいとか。
この論文そのものは知的な鳥類と霊長類がなぜ同じような進化をしたのか説明しようとしている部分で、 その部分は受け入れるとしても、この時代なのに鳥類の起源があまりにも知られていない?
結論部分はよいとしてこう。比較心理学者が (霊長類を求めて) 遠くまで行かなくても、庭に羽の生えた霊長類がいることを認識するきっかけになれば、というレビュー。
巨大隕石衝突説に戻ると、かつて「最新恐竜事典」(金子隆一編 朝日新聞社 1996) で「恐竜絶滅と天文学説の虚偽」と題して論考を述べられていた。「火山説」などと貶めるな! との見出しもある。
「鳥類学者 無謀にも恐竜を語る」(川上和人 技術評論社 2013) では (小天体衝突説は) 2010年に掲載された論文で、その合理性が証明されている、とある。こちらもなかなか断定的な表現で金子 (1996) との違いの鮮明さにやや驚かされる。
おそらくは天文学者が過去にあまりにもくだらない説を多数出しすぎ、またジャーナリズムがそれを面白そうに取り上げたのが金子氏の批判の原因ではないだろうかと想像する。
金子氏の批判の対象となったニュートリノが恐竜を絶滅させたという論文は Collar (1996) Biological Effects of Stellar Collapse Neutrinos。
(恒星爆発によるものとしては) 過去研究では超新星を考えていて、超新星の発生頻度を考えると過去の複数回の大量絶滅には少なすぎる。しかし大質量星の生涯は超新星爆発で終わるとは限らず、そのまま重力崩壊して爆発を伴わないかも知れない (注: 現在ではそう考えられる事例が実際に報告されている *2)。
Bahcall はそのような現象は銀河系で 11.1 年に1回と推定したという (今から考えると少し過大か)。普通のアイデアは恒星爆発で絶滅を起こすのはいわゆる電離放射線で、このような「弱い相互作用」(*3) のみの粒子がどの程度影響を与えるかはよくわからないので見積もってみたとの話 (おそらくこれを考えた研究は過去になかったのだろう)。
電離放射線は地球大気や海の水で遮られるが、ニュートリノならばそのまま到達できる。重力崩壊によるニュートリノなのでエネルギーも高く、high-LET (linear energy transfer 線エネルギー付与率) で生体にとっては重粒子線のようにふるまう (これは確かによいアイデアかも知れない)。ここまで LET の高い粒子の生体への影響はよくわかっていないので作用メカニズムをもとに推定してみた。
通常の電離放射線や加速粒子線 (重粒子線治療などの場合) は皮膚表面や特定の深さに影響を与えるが、ニュートリノならば内側まで均等に到達できるのでより放射線に敏感な骨髄などが侵され得る。被曝量を見積もった。海の水も通過するので海中の生物にも影響を与える (過去の絶滅で海中の生物も絶滅したことを説明できるかもとのアイデア)。
放射線イベントで即死ではなく、放射線による悪性腫瘍が死因となれば大型種ほど細胞数が多いので選択的に失われる可能性があってこれも大量絶滅現象の説明に都合がよい (もっともこれが原因だと死ぬまで時間がかかり、それまでに子孫を残せばほとんど影響を受けないだろう致命的問題がありそう)。
3000 万年から1億年に1回ぐらい無視できないほどの被曝量になる可能性があるとの見積もり (大マゼラン雲の SN 1987A からすでに 35 年以上経過しているが近傍銀河でも起きていないので、11.1 年に1回はおそらく過大すぎ。
爆発を伴わない重力崩壊の頻度がもし1桁少なければ 3-10 億年に1回となってやはりさすがに少なすぎて論文にしにくかったかも知れない)。
この見積もりが正しければ太陽系近くの死にかけの大質量星をマークしておくことはあながち意味がないわけではないだろう、とのこと。論文には恐竜はどこにも出てこないので最初検索しても見つからなかった次第。
アイデアとしては面白いし過去に複数の特徴を説明できるので査読論文として出版されても不思議でない感じがする。恐竜絶滅云々はメディアに紹介する時の後付けらしい。金子氏はニュートリノ衝撃波と書いているが (多分超新星爆発の衝撃波を意図したものであろうが)、そのような衝撃波をほとんど引き起こさない単なる重力崩壊を考えている。
枝葉の部分だけを興味本位で取り上げて報道するので天文学者はアホかバカと誤解されることになる (笑)。
「火山説」と言っても、それは既知の地球物理学の範囲で現象をどこまで説明できるかの立場に立てば別におかしいわけではない。観測事実を合理的に説明できるような地球外からのごくまれな事象がたまたま存在したと言ってよいだろう。
関連する論文が最近出ているので紹介しておく: O'Connor et al. (2024) Terrestrial evidence for volcanogenic sulfate-driven cooling event 〜30 kyr before the Cretaceous-Paleogene mass extinction。衝突の2万年前にはもとの温度に戻っており、巨大火山噴火による寒冷化は K-Pg 絶滅の主たる要因でなかったと推論。
さらにもう一つ、報道記事になると印象がずいぶん違っていた: Quintana et al. (2025) A census of OB stars within 1 kpc and the star formation and core collapse supernova rates of the Milky Way
論文中に超新星爆発が大規模絶滅に関連した可能性を議論している過去研究が示されているので参考にはなろう。過去の絶滅の1つぐらいは超新星由来でもおかしくない、という論旨。この論文では K-Pg 境界の絶滅を "the Cretaceous-Paleogene extinction event ... is commonly believed to have been caused by an asteroid impact in the Yucatan Peninsula"
と表現しているので (commonly believed とは何だ!) 懐疑派らしいことがわかる。自分にとってはそもそもオゾン層が短時間破壊されたぐらいで大規模絶滅が起きるとは思えないのだが...。
ただし意図がわからないわけではなくて、星の分布を調べたぐらいでは多分一般受けしない。もしかしたら大規模絶滅に関連があるかも...と結んでおけば (間違いとは言い切れないので) メディア受けしやすいためだろう。このような論文を専門雑誌に出せば査読者はおそらく天文学者で、生物絶滅の部分にはおそらく切り込まないだろう。
報道記事だけを参考に「こんなことがわかった」と信じてしまうと実際に研究されたものが何だったかまったく判断できないだろう。報道記事をベースに科学の最新話題を追いかけることの危険性もわかる。
「始祖鳥化石の謎」(F.ホイル・C.ウィクラマシンジ著 加藤珪訳 地人書鑑 1988。原著 "Archaeopteryx, the primordial bird: a case of fossil" Hoyle and Wickramasinghe (1986)
も出版当時大々的に宣伝されていたのを思い出す (買わなかったので中身は知らないが)。
Nature も載せていて Archaeopteryx, the primordial bird? 話題性は十分だったということだろう。
「鳥類学者 無謀にも恐竜を語る」p. 54 の脚注にもフレッド・ホイルとして紹介されている。
この話は共著者の C. ウィクラマシンジ (Chandra Wickramasinghe。ホイルの弟子とのこと) の存在も大きいのだろう。wikipedia 英語版によれば 2013 年 Lancet に SARS の原因ウイルスは宇宙からという仮説を出し、即座に反論が3本掲載されたとのこと。2020 年には新型コロナウイルスの起源は宇宙からとの説も述べたとのこと。詳細は wikipedia 英語版を読まれたい。
Fred Hoyle の wikipedia 英語版を見ると "Evolution from Space" (Hoyle and Wickramasinghe 1982/1984) によればパンスペルミア (宇宙から生命の胞子がやってくる) なしで生物に必要な酵素ができる確率は 10 の 40000 乗分の1と見積もったとのこと。
これはほぼゼロなのでパンスペルミアの証拠となるらしいが、"超" (を付けてよいと思う) 古典的な物理学者の発想で、現代ではよく理解されている進化を否定すればこのような数字が必要になるのだろう、ということで意図は理解できる。
これは言うまでもなく独立事象の確率の積の法則の (おそらく意図的) 誤用であるが、このような確率の意味するところは [#鳥類系統樹2024] の補足説明を参照されたい。つまり独立事象ではない。
「進化の特異事象: あなたが生まれるまでに通った関所」のところで ド・デューブ de Duve が挙げている事例は Hoyle や Wickramasinghe が挙げた数字に対してよい反証になるだろう。独立事象の確率の積の法則を同じように用いれば、まったく異なる生物がたまたま同じ姿に見える (擬態) あるいは収斂進化が起きる確率などほとんどゼロに近いものになるだろう。
擬態や収斂進化はごくありふれたものなので、それらの生物が独立に擬態や収斂進化を起こす確率をかけ合わせればほとんどゼロになる。よって生物進化の考え方は間違っている、という結論を導くことができる。
10 の 40000 乗分の1という数字はそのように作られたものだと思えばよい
(しかし生物で起きていることを知らない物理学者はこのような論理を内心信じている人も結構あるのではないかと想像する。現代でも Wickramasinghe の論文の共著者を見ると一端がつかめる気がする。真面目な人ほど意外にも...)。
Hoyle 自身は早い時期に宇宙の元素合成 (#オオワシの備考 [鳥類、特に猛禽類の鉛中毒] 参照) に甚大な貢献をしながら、それを進化とみなさず、宇宙の進化も生物進化も否定してしまった、ということだろうか。
Wickramasinghe の解説によればダーウィンの言うような進化があるかないかは "半々" であって平等に取り扱わなければいけないという。そこでもう一つの説の方を平等に受け持とうというところか。こういう論理は今でもよく見かける気がするがどうだろうか。
Hoyle は 2001 年に死去するまで生涯ビッグバン理論を受け入れなかったと記されている (ただし "Big Bang" の用語は Hoyle が 1949 年の BBC の対談で Gamow への反論として用いたのが最初の用例とされ、まったく BBC の放送に値しないものだったとかその時の逸話もあるらしい)。こちらも詳しくはwikipedia 英語版を読まれたい。
1983 年に William Alfred Fowler が宇宙の元素合成に対してノーベル賞を与えられたが、この説は Hoyle が最初に考えたものなのでなぜ彼が受賞しなかったのか憶測も生んだとのこと。ノーベル賞はある業績に対して与えられるものではなく科学者を全体的に評価して与えられるもので、Hoyle の不名誉で否定されている数々のアイデアがノーベル賞に値しなかった可能性があると後に語られている。
これは「始祖鳥化石の謎」以前の出来事なので、それ以前から数々あったらしい。
ということで、「鳥類学者 無謀にも恐竜を語る」の脚注から感じられる定説への挑戦者の印象とはだいぶ異なる (もちろん Hoyle 本人がどう思っていたかはわからないが)。
一つ前の脚注の BCF [Birds Came First; Came は過去形が正しいと思う。たかが時制と侮ることなかれ。現在形だと「鳥がいつも最初に来るのです」のような意味になりそう] 理論とは生い立ちもまったく違うので等価に読んでしまうと誤読するおそれがある。Hoyle があまりに特殊なのである。
Hoyle は (本人がどう思っていたかはわからないが) ある考えにとりつかれて、その方向のみに突き進んで行ったかのように見える。
インフルエンザなどのパンデミックは太陽活動由来と聞かれた方もあるだろうが、これも彼らの説とのこと。どうも巷に広まりすぎている感じがする。
ここで出てくるような用語で日本語検索すると簡単に怪しいページに行き当たるので、定説に疑いを持って日本語検索するのは危険と改めて実感することになった。知らない話なのでと興味を持ってさらにおすすめ情報などを見るとすぐにトンデモに行き当たってしまう。興味を持ったことは徹底的に調べなさいとこれから学ぶ人に教えるのは図書の時代はともかくネットの時代ではかなり危ない気がする。
英語ではそこまでのことはなく学術的内容や学術論文が普通に表示される (日本語の学術論文は圧倒的に少ないのでそもそもヒットしないのも当たり前とも言えるが)。少なくとも現在では科学的疑問があった場合はまず英語で検索し、査読論文など信頼度の高い情報に当たることを強くお勧めしたい
(ほとんどのサービスは英語で検索しても気を利かせて日本語情報を優先して表示するだろう。個人的なおすすめは OS を最初から英語でインストールして検索は英語で行う。大手検索エンジンではなく日本語に特に対応していない検索サービスを用いる。検索履歴になるべく左右されないようにクッキーは拒否する。あるいは学術系の信頼できる文献検索を用いる)。しかし日本の通常の環境では相当ハードルが高そう。
ただし自分は意識してそういう環境を整備したのではなく、コンピュータを使い始めた時代がまだ英語のみだったので惰性でずっと英語で使っている次第。日本語を扱うのは面倒くさいのである。あまり高尚な理由ではない。
川上氏は巨大隕石が将来飛来する確率はかなり高いと読まれているようだ。報道でもしばしば話題になるのでもう少し解説しておくと、大量絶滅を起こすような巨大隕石 (小惑星) はすでにすべて掌握されており、近未来に地球に衝突することが判明しているものはない。我々が予測可能な範囲ではこのように結論してよいだろう。
日本語では巨大隕石以外の表現が難しく、隕石と小惑星の間に明確な境界があるわけではないのでこの表現が妥当なのだろう。英語では asteroid impact と "小惑星" を使うことが多い。隕石と呼ぶと頻繁にあるかのような印象を与える原因となるかも知れない。
報道で話題となるのは、運悪く衝突すれば都市一つが崩壊程度の小型のものである。この程度の小さいものはまだ未発見のものが多数あるが大量絶滅は当面心配しなくてもよい。それよりも気候変動などの確実なリスクを優先した方がよいのでは? (隕石の話を聞くと気候変動懐疑派が持ち出している話なのかと思ってしまうこともあるが...)。
1994 年に木星に衝突したシューメーカー・レヴィ第9彗星 (Comet Shoemaker-Levy 9) があったではないか、あんなものが地球にぶつかればひとたまりもない、と言われることもあるだろうが、この彗星は木星の重力に束縛されたもの。木星と地球では重力の影響がまったく違う。これほど観測技術が進歩しても地球には月以外の天然衛星が存在しないこともこれを裏付けている。
ということで、シューメーカー・レヴィ第9彗星を持ち出して衝突リスクを訴えた人は「やりすぎ」ということになる。一つにはこの時代に夜空の全天を監視することが技術的に可能になってきていて、他方面の天文学者も非常に期待していたわけだが、地球に衝突する可能性のある小天体を見つけることはあくまで一般受けする目的の一つに過ぎない。
今の時代は売り込みも大事なので一般受けすることも必要だが、そこだけを取り上げて報道すると誤解のもとになる。
なお小惑星の軌道が十分精度良く求まればずっと先の未来まで予測できるのかと言えばこれもまた少し違う。力学法則なので未来まで普通に考えれば十分精度良く予測できるはず。
それが予測できないとなるとこれはカオス理論か ([#鳥類系統樹2024]参照) と思われるだろうが、近未来ではその影響はほとんどなく、小型天体ほど太陽光の圧力を受けて (運動量を受け取る。光の量子性による)、それをどの方向に再放射するか (その方向に運動量を失う) によって生じる力が相対的に大きいことによる。
提唱者から Yarkovsky effect と呼ばれる。おおよそ 10 km より小さい天体で影響が見えるようになるとのこと。
そのため小型天体の場合ははるか先まで衝突しないかどうかを判断することはできず、おおよそ 100 年ぐらい先までとのこと。大量絶滅を起こすような大きな天体ではもっと先まで安心ということになる。
巷で xxxx 年に何 % の確率で衝突の可能性、と言われるのは大部分が発見初期軌道の精度が悪いためで、地球が予測誤差範囲に入ってしまうため。軌道の精度が上がるとすぐゼロになる (そしてその部分は通常報道されない)。
K-Pg 境界大絶滅を引き起こした巨大隕石についてはさらに後日談があって、Bottke et al. (2007) An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor:
衝突時の推定パラメータから軌道を推定することができて、小惑星 (298) Baptistina がかつて別の小惑星と衝突した時にできた破片のうち最大のものが巨大隕石となったアイデアが出された。小惑星にも "族" (こちらは family と呼ばれる) があって Baptistina family と呼ばれる一群の小惑星はかつて単一のものだったものが分裂した結果と判断できる。
これはこれで面白い話でその後も研究されているが、Reddy et al. (2008) Composition of Baptistina Asteroid Family: Implications for K-T Impactor Link
は化学組成が異なるので別物ではないかとの判断。
Misiero et al. (2012) Revising the Age for the Baptistina Asteroid Family Using WISE/NEOWISE Data
で赤外線観測衛星のデータから Baptistina family の分裂時期を 1.4-3.2 億年前と推定。6600 万年前と間が離れすぎているので可能性は低いのではとの話になったが、今のところこの説に対する決着は付いていない模様 (組成から否定的な研究報告が増えている。後述の同位体研究からはおそらく否定的)。
Nesvorny et al. (2021) Dark Primitive Asteroids Account for a Large Share of K/Pg-Scale Impacts on the Earth
の見積もりによると、5 km 以上の巨大隕石の衝突頻度は 10 億年で 16-32 回。10 km 以上だと 2-4 回とのこと。大量絶滅を起こすぐらいの巨大隕石はこの程度の頻度と見ておいてよさそう。この論文によると分裂した彗星の衝突のアイデアもあるが極めて確率が低いとのこと。
小惑星帯から地球軌道へは共鳴でもたらされるらしいとのこと。これは力学計算ができるので頻度を見積もることができることになる。ただし前述のように現実の個々の天体の軌道を 10 億年のような長期に予測することはできないので確率的扱いになる。
このぐらいの数字と思って話を展開するのが現実的ということになるだろう。
Fischer-Godde et al. (2024) Ruthenium isotopes show the Chicxulub impactor was a carbonaceous-type asteroid がルテニウム同位体比からこの小惑星は炭素質であったと推定。メインベルトではなく太陽系の比較的外縁部で形成されたと考えられる。
炭素質であったとの推定はこれが初めてではなく、Siraj and Loeb (2021) Breakup of a long-period comet as the origin of the dinosaur extinction の参考文献などを参照。
Kyte (1998) A meteorite from the Cretaceous/Tertiary boundary、Anne et al. (2006) The nature of the KT impactor. A 54Cr reappraisal など。
月のクレーター年代からも面白い結果が得られているので紹介しておく。Jiao et al. (2024) Asteroid Kamo`oalewa's journey from the lunar Giordano Bruno crater to Earth 1:1 resonance
中国の探査機がサンプル・リターン探査を行う予定の小惑星 469219 Kamo`oalewa は月の組成に非常に似ていて、月のクレーター生成の際に作られ、地球公転と共鳴する形で捉えられのではないかとのこと。
クレーター生成の年代分布も出ていて新しい (1000 万年以内) 大きなクレーターは1個しか知られていない模様 (地球から見えない月の裏側にある)。英文解説。月のクレーターも今ではそれほど頻繁には作られない模様。
この件には少し後日談もあり、生物の学名の話に似ているので紹介しておく: 地球の準衛星「2004 GU9」の命名キャンペーン開始! その意外なきっかけとは 誤読から付いた可能性のある名前が正式に認定され使われているとのこと。
Broz et al. (2024) Young asteroid families as the primary source of meteorites と Marsset et al. (2024) The Massalia asteroid family as the origin of ordinary L chondrites
の Nature 論文がセットで発表された (2024.10.16)。現在の隕石の由来の7割は小惑星の3族に起源を持つと推定されるとのこと。
小惑星が過去に衝突による大分裂を起こして現在の Massalia 族 [中心となる小惑星は (20) Massalia] を作ったが、4.66 億年前の L 型コンドライトによる大規模な隕石衝突がこの分裂に由来するものでオルドビス紀の氷河期をもたらしたとの解釈。この小惑星族は地球軌道面に近い軌道面を持ち衝突確率が高いとのこと。
*2: ちょっとおまけすぎる気がするが、興味を持たれる方もあろうと考えるので紹介しておく。何と言っても恐竜を滅ぼす可能性が議論されているのである。触れておかないわけにはいかないし、過去の書物を読んでそのまま受け止められる方もあるだろう。
金子氏はそれほど膨大なニュートリノを放出できるメカニズムと言えば、タイプ II 型超新星くらいしか考えられない (p. 50) と記しているが、重力崩壊型超新星と書けばもっと正しかっただろう。
太陽系から 20 光年以内で超新星が爆発すれば、地球の生態系などひとたまりもあるまい、と書かれているがこれが本当かどうかは検証の必要があるだろう。Collar (1996) はそういう超新星を考えているわけではないのでここでは気にせずに素通りしよう。
「ご本人の頭の中には、星の外層を吹き飛ばすこともなく、ただ超高密度のニュートリノだけを恒星が放出する何らかの魔法のメカニズムが想定されているのだろうが、それが何であるかは一言も述べられていない」とある。原論文を確認するとしっかり書かれているので、これはある意味報道の問題と言える。
Collar (1996) の論文は著者自身が 1995 年に preprint server に置いて公開されていたので、内容を検証しようと思えばこの時点でできたはずなのだが、当時のコンピュータ環境 (WWW が一部で使われるころの時代) を考えるとアクセスはまだ難しかったかも知れない。
さて重力崩壊型超新星はなぜ爆発するのか。大質量星が進化して鉄のコアができて、それ以上核融合でエネルギーを取り出すことができなくなって星を支えることができなくなり重力崩壊する。その反動で外層が吹き飛ばされて超新星爆発になる、ぐらいのことは書いてあることも多いだろう。
もうちょっと専門的ならば、鉄のコアが圧力を失って自由落下し (すぐに音速を超えて超音速流になる。超音速になると中に壁がある情報が外に伝わらないのでそのまま激突してしまう次第)、コアの中心に作られた硬い原始中性子星にぶつかって衝撃波となり、外に伝わってコアを吹き飛ばしてしまいそうに思えるが、途中の物質と相互作用して衝撃波は途中で失速してしまう。
原始中性子星はあまりにも密度が高く、物質とほとんど相互作用しないニュートリノさえもしばらくの間閉じ込められるが (neutrino trapping) それが出て来るようになると失速しつつある衝撃波に運動量を与え、衝撃波は無事星の外層を吹き飛ばすことができる、と書いてあるかも知れない。
SN 1987A の時代はこれが標準理論だった。その予言通り (主たる目的は別だった。後述) カミオカンデ IIでニュートリノが検出され、小柴昌俊氏を含む3名が高エネルギー天文学への貢献 (ニュートリノはその一部) としてノーベル賞を受賞 (2002) となった次第
(SN 1987A がもし爆発していなければ、現在でも理論的には一番もっともらしい仮説にとどまっていたかも知れない)。
自分も長らくそう思っていたので早い時期の刷り込みというものは恐ろしい。実はニュートリノによる再加速は詳しく計算すると少し足りないらしく、何かもうひと押しのメカニズムが必要らしく現在も盛んに研究されている次第である。逆に言えば重力崩壊で超新星爆発が起きることは必然でないわけである。
超新星爆発をせずに重力崩壊だけすることがあっても理論的には構わない。しかし超新星爆発は実際に観測されている以上、何らのメカニズムでニュートリノによる再加速に上乗せしているらしい、となる。物理学とはいえ自然現象から学ぶわけで、やはり自然科学らしい。
現在では重力崩壊のみをして直接ブラックホールとなる failed supernova (定訳なし。ただし別の意味でも使われるので今後もよい学術語かどうかはわからない) の候補が見つかっている。Raynolds et al. (2015) Gone without a bang: an archival HST survey for disappearing massive stars
ハッブル宇宙望遠鏡が過去に撮影した画像で明らかに大質量星であったと思われるものがある時から消失しているのであった。おそらく重力崩壊のみを起こして消えてしまう大質量星が本当にあるらしい (ただしあまりにも遠いので現在のニュートリノ検出技術ではわからない。爆発を直接観測できないので検証が難しい。単に何かに隠されただけでまた見えてくる可能性もある)。
なお HST のような世界最大クラスの望遠鏡では、観測提案者の一定の優占期間を過ぎたデータは世界の財産として完全公開されている (優占期間すらなく即座に公開されるものもある)。NASA のサイトに行けば全部見られる。このような解析はアイデアさえあれば誰でもできるわけだ。
実際にも画像処理そのものは少し優秀な PC ならば個人レベルで十分行えるもので、スーパーコンピューターが必要というものでもない。天文学の世界が世界の誰にでも門戸を開いていることを学問分野の文化の特徴の一つとして少し紹介しておきたい。
Neustadt et al. (2022) The search for failed supernovae with the Large Binocular Telescope: a new candidate and the failed SN fraction with 11 yr of data
のような後続研究もあって、11 年かけて2例それらしいものを見つけたという
(大学院生や短期雇用の研究者には簡単にできない仕事。ただし関心のある教員が予めデータを取っておいたものかも知れない。同じ研究は日本でもできるかと言われるとやや心許ない。口径 8.4 m の双眼望遠鏡で口径 11.8 m に相当する。すばる望遠鏡は 8.2 m で、10 年間も同じテーマに使えるかと言えば...どうだろうか)。
2例でしかも候補では論文にならないだろうと生物研究者は考えるかも知れないが、そこは天文学らしいところで、もし1例が確かだとすれば (2つ候補があれば片方ぐらいは本物か、ぐらいの感覚) 重力崩壊のみを起こして超新星爆発を起こさない割合を 0.04-0.39 と見積もっている。1例からこのような (もちろんポアソン統計を用いる) 大胆な見積もりが受け入れられるところが実に天文学らしい。
中央値をとって 0.16 とすれば、多くの大質量星の重力崩壊は超新星爆発につながることになる。
銀河系内の超新星爆発の頻度が数十年から 100 年程度に1回 (ニュートリノイベントが少なくとも35年起きていないことなどから) で、上記割合が銀河系でも当てはまると仮定すれば "見えない重力崩壊" は数百年から 1000 年に1回程度となって Collar (1996) が用いた 11.1 年に1回とは桁違いとなる。地球上の大絶滅のよい候補とはならないことがわかる。
最近もう1例有力候補が報告された。しかもアンドロメダ銀河 (M 31): De et al. (2024) The disappearance of a massive star marking the birth of a black hole in M31 (preprint)。スタイルを見るといかにも超有名ジャーナルに投稿したようだが preprint で公開しているところがいかにもこの分野らしい。
2014 年に中間赤外線で明るくなってきたところを検出し、2022 年に可視光では突然暗くなってその後の追観測で検出されなかった。現象の起きる前から変光星として知られており、重力崩壊を起こすにふさわしい天体であった。
ニュートリノの話はもうちょっとあるだろうと言われそうなので少し追加しておくと、SN 1987A の当時はニュートリノに質量があるかどうかはわかっていなかった。古くは質量はほとんどゼロかあるいはゼロと書かれていることもあった。昔は中性微子とも呼ばれていたが訳語の方がむしろ廃れてしまった例。
もし質量があれば光速より遅いはずなので、超新星爆発の光よりもニュートリノの方が遅れて到着する可能性がある。
16.3 万光年離れた大マゼラン雲ではそれを調べる絶好の機会で、ニュートリノが検出された 2-3時間後にはもう可視光で光っている (衝撃波が表面に到達している) から、時間差があってもたかだか3時間と思ってごく大雑把に見積もると、これでも光速の 99.99999% より速いことになる。実際にはニュートリノバーストは全体で 13 秒、最初の 1.9 秒に9イベントが固まっていて時間差はさらに短いはず。
このようにして見積もられたニュートリノ (検出されるものは反電子ニュートリノ) の質量上限は 16 eV/c^2、電子の 1/30000 以下となった。この観測では上限値は得られるがゼロであることを否定することはできない。
ニュートリノの質量が問題となるのは、もし質量があればニュートリノの質量をゼロと予言する理論が排除されるほか、後述のダークマターの候補となり得たため (これは質量上限とともに他の問題点があり現在は棄却されている)。
ニュートリノが質量を持つことが明らかになったのは 1998 年の梶田隆章らによるスーパーカミオカンデの実験や海外他チームの研究によるもの。
ニュートリノ振動 (3種類のニュートリノが相互に転換する) が確認され、太陽ニュートリノが理論モデルの 1/3 しかない従来からの太陽ニュートリノ問題も解決することになった (理論モデルが間違っている可能性はもちろんあったが、太陽の核融合反応が弱まっているのではとの説も流れたことがある)。
梶田氏は Arthur McDonald とともに 2015 年のノーベル物理学賞を受賞されたことは記憶に新しいだろう。でもニュートリノ関係はさすがにこれで終わりかな?
*3: 物理学で言われる4つの力の一つ。わかりやすい方から行くと誰もが知っている重力、そして電磁相互作用 (電磁気力)、原子核を構成する強い相互作用、そしてあまり馴染みでない弱い相互作用、となる。
この辺は受け売りだが、電磁相互作用と弱い相互作用は統一的に記述できる。ワインバーグ=サラム (Weinberg-Salam) 理論 (電弱統一理論) で、もとは同じ力だったものが宇宙がビッグバンから膨張して冷えるに従って別の力に分かれたもの。全然違うものが実はもとは同じものだったというのはノガンとカッコウの関係にちょっと似ている。
この2名を含む3名が 1979 年のノーベル物理学賞を受賞、とまあこれは古くから知られている話である。
この理論に関係したノーベル物理学賞がさらに 1999 年にも与えられている。この2つの力が分かれるメカニズムを明らかにしたのが南部=ゴールドストーン (Goldstone) による自発的対称性の破れ (spontaneous symmetry breaking, 2008 年ノーベル物理学賞)、このころのノーベル賞は説明されても理解が難しい。
そして 2012 年のヒッグス粒子の発見によりワインバーグ=サラム理論は完全実証されることとなった (2013 年ノーベル物理学賞)。
これらの力は宇宙がビッグバンから膨張して冷えるに従って分化してきたものと考えられる。つまり加速器実験なんとかというのは、ビッグバンになるべく近い状態を再現してその性質を見ようというものになる。
{電磁相互作用 + 弱い相互作用} + 強い相互作用 までを統一 (いよいよ生物のクレードに似て来た?) したものが大統一理論 (grand unified theory) と呼ばれるもの。大げさな名前だが物理系の学者はこのような名前が好きなのである。
この理論はまだ確立したものはなくいくつかのアイデアが存在する (しかも力が統一されるエネルギーが高すぎて実験的に確かめられない) が、多くの大統一理論が予言するのは陽子の寿命が有限であること。つまり陽子崩壊を観測することで大統一理論の検証を行おうということになる。
カミオカンデの初期の設置目的はこれだったが超大物の副産物があった次第。陽子崩壊は現在まだ観測されておらず、スーパーカミオカンデのデータによると陽子の寿命は 10 の 33 乗年が下限とのこと (2009 年段階の情報)。
さらに重力も含めたすべての力を統一したものが万物の理論 (Theory of Everything) などと呼ばれる。超弦理論などはこのあたりの話になるが、もちろん自分にはよくわからない。ただ理論の予言する超対称性粒子 (SUSY) はもしかすると観測されるかも知れない。
宇宙の質量のかなりを占めながら未だ正体のわからないダークマター (暗黒物質) の候補の一つともされ、世界の多くのグループが検出を試みている (ちなみにダークマター関連の James Peebles は他グループの系外惑星とともに 2019 年ノーベル物理学賞。これはまだ比較的説明しやすい)。
この関係のノーベル物理学賞がもう一つあってダークエネルギー (Saul Perlmutter 他。2011 年受賞) こちらの方がダークマターより先に受賞とはちょっと不思議ではある。遠方宇宙の超新星 (ここでは重力崩壊型とは異なる Ia 型超新星) の明るさを測定すると、推定距離から予想されるより暗いことを発見。宇宙膨張が加速しているはず、と結論したもの。
アインシュタインの一般相対性理論では宇宙項というもの (ものすごくいい加減に言えば高校の数学で不定積分を習う時に出てくる積分定数 + C のようなもの? さすがにいい加減過ぎか) があって、通常はそれをゼロとして物事を考えてきた。
アインシュタイン (1917) 自身は「まっすぐに進むと元の地点に戻ってしまう」球面状構造を想定し、これがアインシュタインの静止宇宙となる。前述 Hoyle (1948) および Bondi and Gold (1948) の膨張する定常宇宙の考えに近いが、アインシュタインの定常宇宙の方が 1931 年とずっと早かったという。アインシュタインは後にこれを破棄したと wikipedia 英語版にある。
球面状構造の宇宙を実現するためにアインシュタインは宇宙項を入れる必要があったが、後にビッグバンの証拠が見つかり、アインシュタインは「宇宙項を方程式の中に入れたのは人生最大の過ちであった」と言ったとか。
つまり宇宙項が復活したかも知れない、アインシュタインは間違ってなかったとのことで話題となった。当時の Perlmutter 他の超新星の話はリアルタイムでフォローしていたが、正直これほど早く評価されてノーベル賞を与えてよいものだろうかとも思った。その後のより詳細な観測でも矛盾していないことが確かめられてきてやはり実在するのか。
ダークエネルギーの正体はダークマター以上に不明だが、世の中で出てくる宇宙初期の観測などの報道はすべてこれらの標準値を利用しているので知っておいてよいだろう。ダークマターは大絶滅の原因云々の説もあるのでまったく無縁というわけでもない。
ビッグバンから膨張して冷えるに従って対称性が弱まって力が分化してきたことと何か似た現象はないだろうか。
マルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC) (#ハチクマ備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] の系統解析方法、[#鳥類系統樹2024]に登場する) で紹介した生物進化の適応度地図の探索に似ている。
温度が極端に高い条件だとあらゆる場所の適応度が同じで完全に対称的だが、温度を下げると適応度地図にピークが出現してくる。これは生物では適応度ピークに相当し、物理学では力の分化に対応する (とあまり簡単に言うと専門家からお叱りを受けそうだが)。何がなんだかわからない自発的対称性の破れはこのように見ていただけば多少直感的にわかりやすくなるのではないかと思う。
生物学でも実際に類似の概念があって、Takeuchi et al. (2017) The origin of a primordial genome through spontaneous symmetry breaking
生命誕生初期のゲノム進化にも応用されている。マクロ生物学でもきっとあると思うので探してみたい。
やはり応用例があって、1995 年に鳥の群れのメカニズムとして提唱されていた。主に理論研究が進んでいる (#ハイイロガン備考の [鳥の編隊飛行の仕組み] にて紹介)。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES ツバメチドリ科 GLAREOLIDAE ▽
-
ツバメチドリ
- 学名:Glareola maldivarum (グラーレオラ マルディウァールム) モルディブ諸島の (で見つかった) 小砂利にいる鳥
- 属名:glareola (f) 小砂利 (glarea (f) 砂利 -ola (指小辞) 小さい) 広い意味の生息地を反映
- 種小名:maldivarum (複数-属) モルディブ諸島の (基産地は陸地ではない。備考参照)
- 英名:Oriental Pratincole
- 備考:
glareola は#タカブシギ参照。ツバメチドリの場合はタカブシギのような模様の特徴はなく -ola は指小辞で長母音にしないのが正しいと考えられる。
この属名は Brisson (1760) が用いたもので、Glareola = Hirundo pratincola Linnaeus, 1758 (現在のニシツバメチドリ) を指していた (The Key to Scientific Names)。
この "Glareola" を修飾する形の学名が付けられていた。
Glareola austriaca Gmelin, 1789 (参考)。
Glareola naevia Gmelin, 1789 (参考) など。
属を変える際に新しい種小名を与えた当時の用例 (#ノスリの備考参照) では Glareola torquata Meyer, 1810 (参考) があった。他にも "Glareola" が見つかって単に "Glareola" と呼ぶのはふさわしくなくなってきて修飾語を加えた形になる。
torquata は首に特徴がある、首飾りのあるなどの意味。この学名は Brisson 由来のようで、現在のニシツバメチドリの現在の英名 Collared Pratincole にも対応している。
maldivarum は複数属格 (モルディブの島々の) による語尾で a が長母音でアクセントがある (マルディウァールム)。Maldiv- の部分の長短はわからないが伸ばす言語も伸ばさない言語もある。ここでは伸ばさい方を採用したがアクセント位置には影響ない。
記載時学名は Glareola (Pratincola) Maldivarum Forster, 1795 でこれを単独で命名したものではなく、Glareola (Pratincola) Coromanda Forster, 1795 (参考)、
Glareola (Pratincola) Madraspatana Forster, 1795 (参考) とセットになっていた。
つまりインドや周辺のこの地域の標本が手に入るようになってコロマンデル地方、マドラス地域、モルディブを別種として地名を与えたもの。いずれも英名も付いていて Coromandel Pratincole, Madras Pratincole, Maldivarian Pratincole。当時はいかにも西欧の探検・植民地化時代で一般名に地名を多用していた。
Foster (1795) の記載が見出されたのが後になったようで、Glareola orientalis Leach, 1820 (参考 この例は 1821 年だが 1820 年の用例があったよう。図版と説明) の方が使われていたよう。Oriental Pratincole の英名はいかにもこの学名と関係があると思われる。
その後 Forster (1795) の方に先取権があることがわかって改名されたよう。しかし Forster (1795) は3種も記述して、全てシノニムの関係にあると判断されたようで、おそらく最初に登場した maldivarum が採用されたものと想像できる。
記述順序次第で coromanda などになっていてもよかったもので、モルディブに特段の意味があるわけではなかった。
pratincola も旧学名など見え隠れするので音声を調べておくと pratus (牧草地) は a が長母音。incola (住人) は短母音のみ -in- がアクセント音節となる (プラーティンコラ)。こでも最後の -cola を伸ばさないように。
現在または過去にも使われた英名はこの学名の種小名に由来で、学名が変わってもそのまま使い続けられたらしい。
英語の pratincole の読みも一般的に受け入れられているものではすべて短母音で冒頭にアクセントとのこと。co は英語流の2重母音で読むがアクセントは付けない (wiktionary)。
上記の Foster (1795) の記載のように Pratincola 属もあって Pennant (1776) が提唱したもの。Linnaeus の種小名を属名に昇格のケースで、Pratincola krameria Pennant, 1776 の新名を与えていた。(krameria はオーストリアの博物学者 Wilhelm Heinrich Franz Kramer 由来) (The Key to Scientific Names)。
他にも Pratincola glaerola Schrank, 1798 (参考。この場合は Glareola austriaca Gmelin, 1789 からの改名) があり、この方法は属が変わるたびに新しい名前が氾濫する問題があることがわかって改善されたのだろう。
また Brisson (1760) の用例が属を定義するものとみなせるか議論もおそらくあり、Pratincola 属も使われていたと想像できる。後に Brisson (1760) の用例に先取権があると認められて現在の属名に至っていると思われる。英名に旧属名に用いられた名称が残っている。
また "牧草地の住人" ならば他にもいくらも考えられるので Pratincola 属をノビタキ類、特に bush chats に用いた用例もあった (#ヤマザキヒタキの備考参照) が、こちらの方が遅く有効な属名とならなかった。
属名、種小名ともに複雑だった。
さらにややこしいことに Pratincola torquata orientalis Sclater, 1911 (参考。こちらはノビタキの亜種として記載) もあって orientalis を付けているのに場所は南アフリカ。このころはまだ Glareola Brisson, 1760 は有効とされていなったよう。
Glareola orientalis Leach, 1820 とは属が違うので許容された学名だったのだろうか、それとも preoccupied になった? (現代の学名には現れない)。
記載時は Hirundo pratincola Linnaeus, 1758 のようにニシツバメチドリは最初はツバメ類に分類されていた。ツバメチドリよりニシツバメチドリの尾の方が一層ツバメの尾に似ているとのことで納得できる。
ツバメチドリの飛び方や空中採食がツバメに似ている点は違和感がないが、和名はこの旧学名にも関係があるのだろうかと考えていた。おそらく英名とも関係があり Eastern Swallow-Plover の別名があった。漢名 土燕子 とのこと。西側の対応種を Western Swallow-Plover だと想定すればニシツバメチドリは英語の直訳となる。
チドリ類は古い時代の和名はあまりないのでツバメチドリは学術由来の命名かも知れない。
参考: 籾山 (1931) 本邦にては珍しきツバメチドリ 附、飼養法。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Glareola orientalis Leach, 1821 場所は Hitachi とあるが和名はまだなかったようでその後付けられたものだろう。
Seebohm (1890) "The birds of the Japanese Empire" には記述が見当たらない。
単形種。
ツバメチドリは Glareola pratincola (ネズミツバメチドリの旧名もあった) の亜種とされていたが、ハグロツバメチドリ Glareola nordmanni Black-winged Pratincole とともに分離された (コンサイス鳥名事典)。
ハグロツバメチドリはシベリア西部からコーカサスなどで繁殖し、冬は南アフリカに渡る。ニシツバメチドリも中央アジアで繁殖し、主にアフリカ赤道近くで越冬する。アフリカ南部にも夏鳥の繁殖個体群 (別亜種) がある。
ツバメチドリの越冬地はインドネシア、ニューギニア、オーストラリア北部やインドの一部などとされる。
モルディブ諸島で採集されたタイプ標本は海で捕獲され、ハエやパンを与えられてしばらく生きていたとのこと (The Key to Scientific Names)。
ツバメチドリはオーストラリアで最も数の多いシギ・チドリ類とのことで、
Tracking the Oriental Pratincole - Update #24 にオーストラリアのシギ・チドリ類グループによるツバメチドリの渡り衛星追跡が出ている。
Three million pratincoles migrate north (ABC のニュース 2020)。経路は東南アジアまでで、日本に来る個体群の渡り経路はまだ調べられていないようである。
[ツバメチドリ亜科の系統]
アシナガツバメチドリ Stiltia isabella Australian Pratincole は上記のオーストラリアのツバメチドリとは別物だが、ツバメチドリ属と スナバシリ亜科 Cursoriinae との中間の形態を持つ。アシナガツバメチドリやスナバシリ類の特徴を見ておくとツバメチドリの系統・進化的位置づけがわかりやすくなる。ツバメチドリの警戒姿勢は確かに似ている。
[ツバメチドリ類縁種の識別]
wikipedia 英語版によればツバメチドリ、ニシツバメチドリ、ハグロツバメチドリは非常によく似ていて野外での識別が困難なことがあるとのこと。ツバメチドリの英国への迷行例が複数あり、ツバメチドリ類似種もあるいは日本を訪れているかも知れない。
Brazil (2009) によればニシツバメチドリは香港で記録され、さらに東を訪れているかも知れないとのこと。Pratincoles photo ID guide (Tony Prater, Bird Guides 2020)
によれば英国では3種とも記録があり、詳しい識別ガイドがある。ツバメチドリは口角から後ろに伸びる線があるが他種には見られないとのことで、確かに写真を見ると違いがわかる。ツバメチドリを見る時はよく確認していただきたい。
ツバメチドリの分布図でフィリピンの記載は資料によって異なるが、フィリピンのチェックリストによれば広く分布し、おそらく繁殖しているとなっている (旅鳥または繁殖)。
[櫛歯 (pectinated claw)]
ツバメチドリ科では櫛状の爪 [pectinate(d) claw, または櫛歯] があるとのことで分類基準にも使われる (コンサイス鳥名辞典)。#ヨシゴイの備考参照。
ヨタカ類ならば捕食に特に重要な役割を果たしている口ひげ状の羽毛を整える意義としてまだ理解できるが (#ヨタカの備考参照)、ツバメチドリでは何の役に立っているのだろう。
空中で餌をとることが多い点はこの科の特徴であるが口ひげ状の羽毛はぱっと見たところはっきりしない。
Clayton et al. (2010) (#ヨシゴイの備考参照) によれば Glareolidae ツバメチドリ科の保有率が高いことが示されている。ツバメチドリでも 12 個体中 10 個体で見られている。
櫛状の爪の機能は複数あるかも知れないが、あるいは樹木の少ない環境で虫を捕食する種類で捕食後に嘴を樹木を用いて掃除する代替方法として用いられているのかも知れないと考えてみた。乾燥地域に住むヨタカ類とツバメチドリ類では当てはまるかも知れない。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES カモメ科 LARIDAE ▽
-
クロアジサシ
- 学名:Anous stolidus (アノウス ストリドゥス) 愚か者
- 属名:anous (外) 愚かな Gk (船に飛び込んできたり、手で捕まえられることなどがよく知られていた)
- 種小名:stolidus (adj) 愚かな
- 英名:Brown Noddy
- 備考:
anous はギリシャ語由来で長母音はない。母音が3つなので冒頭にアクセントがあると考えられる (アノウス)。ギリシャ語では "アヌス" の読み。
stolidus は短母音のみで冒頭にアクセントがある (ストリドゥス)。
Anous niger Stephens, 1826 (参考) の学名があり、Sterna stolida Linnaeus, 1758 (原記載) の新名とある。
属を変える際に種小名を変えることがしばしばあったのか、Linnaeus の用いた種小名が軽蔑的なのでもっとふわさしい名称にする動機があったのかも知れないが、Anous 属に入れているのでこれは理由になっていない感じがする (未確認)。
おそらく学名直接か他言語名を通じて和名成立に関係したのではないだろうか。
ただしアジサシ類全体を含めると ハシグロクロハラアジサシ 記載時学名 Sterna nigra Linnaeus, 1758 があり、英名の Black Tern はこちらに譲ったものとみられる。
クロアジサシが Sterna 属に含められたことがあって niger はすでに使われた種小名で無効となったのかも知れない (未確認)。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは pileatus (帽子を付けた < pileus フェルトの帽子) 亜種クロアジサシ、pullus (暗色の) リュウキュウクロアジサシ、及び亜種不明とされるが、亜種 pullus は世界の主要リストでは pileatus のシノニムとされる。
リュウキュウクロアジサシが亜種であることを妥当とした文献には三島 (1962)
南部琉球諸島のツミ (新亜種) とクロアジサシの亜種名について がある。現在のこの種の世界の標準的分類ではこのような地域間の違いは亜種の違いとみなさず、紅海、インド洋、太平洋のものを同一亜種としている。
英名 noddy (うなずく者) の由来はオスとメスの求愛行動では首を上下させる行動が見られることから (wikipedia 日本語版より)。
Anous 属のタイプ種。
-
ヒメクロアジサシ
- 学名:Anous minutus (アノウス ミヌートゥス) 小さな愚か者
- 属名:anous (外) 愚かな Gk
- 種小名:minutus (adj) 小さい
- 英名:Black Noddy
- 備考:
anous は#クロアジサシ参照。
minutus は1つめの u が長母音でアクセントもある (ミヌートゥス)。minuo (ミヌオー。縮小する) の過去分詞形の語尾由来の長音。
7亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは marcusi (Marcus 島 = 南鳥島 から) とされる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" には当時の学名で Micranous marcusi Minami-Torishima とあり、トリシマアジサシの和名が与えられていた。
この亜種はインドヒメクロアジサシ Anous tenuirostris Lesser Noddy の亜種とされたこともあったとのこと (コンサイス鳥名事典)。
記載時学名 Micranous marcusi Bryan, 1903 (原記載) Marcus Island Tern。
-
ハイイロアジサシ
- 第8版学名:Anous ceruleus (アノウス ケルレウス) 青灰色の愚か者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Procelsterna cerulea (プロケルステルナ ケルレア) 青灰色の嵐のアジサシ
- 第8版属名:anous (外) 愚かな Gk
- 第7版属名:procelsterna (合) 嵐のアジサシ (Procellaria 属と Sterna (アジサシ) 属の合成。The Key to Scientific Names)
- 種小名:ceruleus / cerulea (adj) 青灰色の #カタグロトビの備考参照
- 英名:Blue-grey Noddy, IOC: Blue Noddy
- 備考:
anous は#クロアジサシ参照。
procelsterna の再編後の現在の Procellaria 属は現在の日本のリストには含まれないが ノドジロクロミズナギドリ Procellaria aequinoctialis White-chinned Petrel がタイプ種で南半球の属になる。アゴジロミズナギドリ属の和名があった。
英語で storm petrels と呼ばれる概念はあるが Procellaria 属は含まれていない。嵐の意味が現れるのは学名由来。
語源となる procella (嵐) は短母音のみ。Sterna 属も短母音であることを考慮すると長母音は現れないと考えられる。-ster- がアクセント音節と考えられる (プロケルステルナ)。
ceruleus/cerulea は短母音のみで -ru- がアクセント音節 (ケルレウス/ケルレア)。
5亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは saxatilis (よく岩にいる < saxum, saxi 石、岩) とされる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では属名は Anous に変更されている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。学名は Anous ceruleus (語尾が変わるので注意)。
-
シロアジサシ (将来の分割・学名変更に注意。AviList では分割)
- 第7・8版学名:Gygis alba (ギュギス アルバ) 白い水鳥の一種
- AviList 学名:Gygis candida (ギュギス カンディダ) 輝く白の水鳥の一種 (該当種)
- 属名:gygis guges Dionysius が述べた想像上の水鳥
- 第7・8版種小名:alba (adj) 白い (albus)
- AviList 種小名:candida 輝く白の < candere 輝く
- 英名:White Tern, AviList: Blue-billed White Tern (該当種)、BirdLife v9: Common White Tern (該当種)
- 備考:
gygis は起源となるギリシャ語 guges は e が長母音だが i の音に変える際に短音化されたと考えると "ギュギス" が想定される。もし長音が保存されてもアクセント位置は変わらない。英語読みでもいずれも短母音で発音しており、2つめの g が "ジ" の音になる点が異なる。英語読みを考慮しても長音でする必要性はないと考えられる。
alba は短母音のみ "アルバ"。
candida は短母音のみ "カンディダ"。
単形属。4亜種あり (IOC)。
日本で記録されるものは candida (輝く白の < candere 輝く) とされる。
独立種 Gygis candida とされることもある。HBW/BirdLife v7 (Dec 2022) ではこの立場だが他の主要リストでは採用されていなかった。
Working Group Avian Checklists では version 0.03 以降 Common White Tern Gygis candida。他のリストと違うので正式版が出るまでまだ様子待ちだろうか。IOC 14.2 ではまだ亜種扱い。
また亜種の1つを Gygis microrhyncha Little White Tern とする分類もあり、分類があまり確定しないようである。
その後 AviList (2025.6) では3種に分離。AviList 英名では Atlantic White Tern, Blue-billed White Tern, Little White Tern。Gygis candida は Blue-billed White Tern (AviList) または Common White Tern (BirdLife v9) の英名がある。
4395 914 Three species are recognized in the Gygis alba sensu lato complex based on differences in size, proportions, bill coloration, and vocalizations (Pratt 2020): monotypic G. alba; polytypic G. candida (including leucopes); and monotypic G. microrhyncha. Mitochondrial DNA data (Yeung et al. 2009; Thibault & Cibois 2017) indicate little divergence among these species, perhaps due to recent introgressive hybridisation; further research needed.
AviList では分離する扱いとなったが、種間の違いが小さい研究結果もあり、近年の introgression の効果が考えられる。
[亜種? 種? の問題]
基亜種を狭義 Gygis alba と独立種 (大西洋のもの) とし、3種に分割する立場もある: Pratt (2020)
Species limits and English names in the genus Gygis (Laridae) に識別点の情報がある。声も違うとの情報がある。
この文献では分離した場合の英名について議論しており、伝統的に "fairy tern" と呼ばれていて (あまりに良く知られた名前なので) 捨てがたいが、現在ではオーストラリア、ニューカレドニアなどに分布するヒメアジサシ Sternula nereis の標準的名称として Fairy Tern が使われている。
この著者は Gygis alba Atlantic Fairytern (大西洋),
Gygis candida Indo-Pacific Fairytern (インド洋、太平洋 Common Fairytern),
Gygis microrhyncha Little Fairytern (Marquesas マルキーズ諸島。フランス領ポリネシアが基産地。フランス領ポリネシアとキリバスに分布)
の名称はどうだろうかと提案している。Fairy Tern と Fairytern は発音も少し違うらしい。
"White Tern" の名称は3種を1種とまとめた時の名称として残してよけばよいとの考え。Sternula nereis を Austral Fairy Tern とすればもっと区別しやすくなるだろうがそこまでは求めないとのこと。
SACC が Pratt (2020) の提案を受けてわかりやすく分類改定提案をまとめている:
Proposal (1032) to South American Classification Committee Change current taxonomy of the genus Gygis: A) recognize subfamilies Gyginae and Anoinae within Laridae; B) split White Tern (Gygis alba) into three species; and C) revise English names for Gyginae。
Gygis 属は分子系統解析から亜科 Gyginae をなすとするのが適切で、かつて近縁とみなされた Anous 属とは縁が遠く、Gygis 属を指して "white noddies" と呼ぶのは不適切である。Anous 属も亜科 Anoinae をなす。
IOC にはもう1亜種 leucopes Holyoak & Thibault, 1976 があるがこの文献では扱われていない。原記載 (p.471)
ピトケアン諸島ヘンダーソン島 (南太平洋イギリス領の無人島) で、通常の分類では candida のグループとされるので狭義 Gygis candida を種と認めた場合は少なくとも当面はこの亜種扱いになるだろう。
candida のシノニムとされる亜種は複数記述されており、あるいは他にも亜種が認められるかも知れない。
Anous 属に分類されたこともある。対応する英名は White Noddy (コンサイス鳥名事典) だが、これはむしろ誤解を招く (Pratt 2020)。
Fairy Tern は実際には現在もどちらの種にも使われている。英文記事や画像などを見る時は地域を確認するのがよい。
さらにもう1つ: Establish English names for three species of Gygis。SACC, NACC とも分割はほぼ定まってきているようで "White Tern" の英名は分離前の総称として残しておく提案。複数の提案があって世界的にはまだ英名の混乱が続きそうな様相。
[縦長の瞳孔を持つ鳥]
系統が近いのでここに含めておく。鳥類の瞳孔はほとんどすべての種で丸いが、数種の例外が知られている。
クロハサミアジサシ Rynchops niger Black Skimmer が有名で
The Vertical Slit Pupil of Black Skimmers (David Sparks 2017)
の写真とかつてどの論文で記述されたかが参考になる。Wetmore (1919) A note on the eye of the Black Skimmer (Rynchops niger) を読むことができる。
Banks et al. (2015) Why do animal eyes have pupils of different shapes? によればハサミアジサシ類の採食様式は水面近く低く飛んで下嘴が獲物に接触すると嘴を閉じる仕組みで、薄明かりの中や夜間に活動する。このニッチは地上性の縦長の瞳孔を持つ短距離の捕食性の動物に似ているとのこと。
網膜面上の像のぼけ具合から距離の見積もりに役立つ可能性が書かれているが今ひとつわからない。
ヘビや哺乳類では比較的多く見られて系統解析もなされているが、鳥では事例が少なすぎてあまりわかっていないよう。
ハサミアジサシ類の採食様式への形態的適応は [ハサミアジサシ類の特殊な採食方法への適応] の項目を参照。
ハイイロチュウヒが瞳孔を開いた写真を見ると縦長に感じることがあるが限られた写真しか見ていないのでこの印象が本当かどうかは不明。瞳孔が縮小すると円形に見え、確認のためには薄暗い条件で撮影する必要があり難度が高いかも知れない。
もし印象が正しいならば薄暗い条件で低いところを低速で飛ぶ点は生態的な共通点があるかも知れない。
リュウキュウヨシゴイ、オオヨシゴイは遠目からは瞳孔が横長のように見えるがこれは虹彩の後方が暗色のため。参考:
Cinnamon_Bittern_7895_eye (alder Chang 2011)。
獲物から目がわかりにくくする隠蔽デザインのような気がするが簡単に調べた範囲では文献を見つけられなかった。
[ハサミアジサシ類の特殊な採食方法への適応]
ハサミアジサシ類の嘴にはサメ肌に似た riblet (リブレット。rib = 肋骨 の小さいものの意味) と呼ばれる構造があり、水中での流体力学的抵抗を減らしている可能性があるとのこと: Martin and Bhushan (2016)
Discovery of riblets in a bird beak (Rynchops) for low fluid drag。
この方式で魚を捕る唯一の鳥のグループとのこと。我々が心配するほど嘴には水の抵抗が働いていないのかも。
田中 (2021) 遊泳生物のリブレット構造の流体摩擦力低減効果と模倣 のなかなか面白い日本語記事がある。
遊泳生物と空中飛行生物の摩擦力軽減効果の違い、遊泳と飛行のどちらも可能なウトウの考察がある。ここでも飛翔と水中のゆっくりした動きとの間でレイノルズ数にあまり差がないことが触れられている (#カンムリカイツブリ の備考も参照)。
水中で抵抗を減らすリブレットは空中でも有効とのこと。
ハサミアジサシ類は空気と水の抵抗を受けるためエネルギー的にはコストの高い採食方法と考えられるが、これまでは水面近くを滑翔する ground effect で抵抗を小さくしていると説明されてきた。
Blake (1985) A model of foraging efficiency and daily energy budget in the Black Skimmer (Rynchops nigra)
がよく参照される論文で、水面近くを飛ぶと ground effect の効果で要するエネルギーと至適速度がともに小さくなる。ground effect がなければこのような様式の採食はエネルギーコスト的に見合わない。文献によって種小名の性が揺れている理由は#メジロの備考参照。1985 年まで確定していなかった。
Mendez and Hedrick (2024)
Wind gradient exploitation during foraging flights by black skimmers (Rynchops niger)
のトラッキング研究で風の速度勾配を利用したダイナミックソアリング的な手法も併用していることが明らかになった。
The Black Skimmer (Optics4Birding) にクロハサミアジサシの適応についての解説があった。下嘴がナイフ状で水の抵抗を減らしているとのこと。獲物に当たると嘴を閉じる。高速度撮影ではその瞬間に首を引いて獲物を確保するとのこと。浅い羽ばたきで非常にゆっくり飛ぶ (当然だろう) ので飛翔が非常に優美で写真家としては見逃せないが、暗くなってから飛ぶのでおそらく難しい被写体と述べたいのだろう。
暗くなってからこの方式で狩りをすれば魚にとっても目立ちにくいことになる。
もちろん顎や首が大丈夫かと気になるわけだが、週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 106 p. 13 には頭蓋と首をつなぐ補強の骨があって、首の筋肉が異常なほどに発達しているとのこと。首がクッションとなって衝撃を和らげているらしい。
出典が見つかり、Zusi (1962) Structural adaptations of the head and neck in the black skimmer: Rynchops nigra だった。
ハシブトアジサシを含む他のアジサシ類やワライカモメとの比較も紹介されている。"補強の骨" とは何のことかと思ったが、どうも第 2, 3 頸椎が特に長くなっていて後突起が発達していることを指すらしい。
しかし hypapophyses (#ウミウ備考 [長い首の水中での役割] 参照) は発達していないとのこと。後ろ向きの力に耐える構造となっている。ハサミアジサシ類は頸椎が太いとともに長く、意外な感じもするが長い首は衝撃に耐えるためにも役立っている。下向きに曲げていると圧縮に耐えられるとのこと (これは衝撃に対して頭部を保護必要がある場合、人でもよく言われる)。衝撃に耐える長めの首はキツツキ類でも同様の役割を想像することができる。p. 74 fig. 32 に他のアジサシ類やカモメ類と筋肉の比較図がある。
顎の筋肉はご期待通り。p. 34 に靭帯の一部が骨化しているとの記述があって "補強の骨" はこちらを指しているのかも。ただし靭帯のように弾性がないために後ろ向きの力に対して保護する機能はあまり期待できないとのこと。比較されている鳥はみな採食方法が違うのでアジサシ類 / カモメ類の構造と採食適応に興味のある方にとっても面白い研究だろう。
さて、#アカゲラ備考 [キツツキの力の釣り合い] と関連させて考えてみよう。
鳥の体で衝撃に対して頭部の保護が必要なのは自明であろう。まさしく命にかかわる。そこで鳥の頭部の力学を木にとまるキツツキ同様に考えてみる。ハサミアジサシ類が獲物を捕える瞬間に働く力を考察してみると、キツツキが木にとまる状況とは多少異なって衝撃力ではあるが、捕えている短い時間の間の釣り合いを考えることは有意義であろう。そこで力の釣り合いが成り立っていなければ、頭部と首の間に加速度差が生じて骨を折ったり脊髄損傷を起こす恐れがある。
頭部と首の関係のみを考えれば頭部の内部の力 (顎の筋肉など) は顎を損傷したりしない範囲で考えなくてよい。この場合頭部に働く力は主に3つで、獲物から受ける衝撃力、脊柱 (頸椎) が頭骨に与える力 (後頭突起 occipital condyle)、後頭部と頸椎を結ぶ筋肉 (この文献では m. complexus) の力である。
なお重力や空気から受ける抵抗力も外力になるが、これは飛んでいる時も獲物を捕える瞬間にも同様に働いており、ここでは獲物を捕える瞬間に特有の差分に相当する部分のみを考察する。
筋肉には origin (起始) と insertion (停止) の解剖学用語があり、ここでは頸椎が origin、後頭骨が insertion の定義となっている (より動かない方を origin と呼ぶのが一般的)。英語で呼ぶ方が簡単なので origin と insertion と覚えよう。ちなみに自分が解剖学を英語の教科書で学んだ時にこの意味、特に insertion の語感が辞書を引いてもすぐにわからなかった。
解剖学の論文として初めて読まれる方にとってもおそらく同様と想像できるのであえて注記しておく次第である。
キツツキの時と同じようにこれら3つの力が「力の釣り合い」と「力のモーメントの釣り合い」の両方をほぼ満たす必要がある。そうでなければ頭部と首の間に加速度差が生じることになる。実際には完全に固定されるわけではないので「ほぼ」と付けた。
獲物から受ける衝撃力と後頭部と頸椎を結ぶ筋肉の力はほぼ後ろ向きなので、頸椎が頭骨に与える力が前向きとなって「力の釣り合い」を満たすことになる。接点はこの点のみなので頸椎に十分な強度が必要で、ハサミアジサシ類の頸椎上部が十分強力で太くなっている理由が理解できる。
「力のモーメントの釣り合い」の方を考慮すると、獲物から受ける衝撃力によるモーメントと釣り合うのものは、後頭突起と後頭部と頸椎を結ぶ筋肉の insertion の距離とこの筋肉の筋力に依存することがすぐにわかる。後頭突起と筋肉の insertion の間が離れているほど有効で、もちろん筋力が強いほど有効である。
この筋肉が特に発達している理由はこの通り自明であるが、十分な筋肉量を確保する、そして後頭突起と筋肉の insertion の間を離すには origin である上部から中部の頸椎と insertion である後頭骨の間隔を広げるのが有利であることが想像できる。これがハサミアジサシ類の頸椎上部が長い理由だろう。
p. 65 (fig. 37), p. 66 (fig. 38) に明瞭に現れている。
この論文の時代には (今でも?)「力のモーメント」の発想は使われていなかったようで、てこの原理などを使った説明となっていて回りくどく感じる。「力のモーメント」を使えば「てこ」の場所を仮想的に想定する必要がないのでより簡単である。
The Black Skimmer (Optics4Birding) で、高速度撮影ではその瞬間に首を引いて獲物を確保すると記述されているのは、この筋肉が収縮する瞬間を捉えたものだろう。獲物を確保するというよりは、「力のモーメントの釣り合い」を満たすために筋肉が収縮していることになる。頸椎そのものはほとんど収縮しないが、筋肉が収縮するすることによって多少なりとも曲がって (曲がりすぎるとこちらも損傷する恐れがあるので頸椎の他の筋肉も同時に収縮して補っているのだろう) 首を引いたように見えるのだろう。
さて、ハサミアジサシ類ほど極端でなくても、飛びながら空中から嘴を使って水面の食物を得る手法は多くのカモメ類が用いている。同じような力の釣り合いがやはり必要になる。カモメ類の上部頸椎が一般的に長いのはこのためと考えることができる (論文の図ではカモメ類に近い種ばかり比べているのでこの点がわかりにくい)。
例えば川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019) でカモメ類と系統的に近いが採食方式の異なる種 (例えばユリカモメとウミガラス) を比べていただければ一目瞭然だろう。残念ながら#ハシボソカモメの骨格標本写真をまだ見たことがないが、こちらはカラシラサギに似た採食方式と関係があるのだろうか。飛び込んで食物を得ることもあるので頸椎のどの部分が長いのか興味がある。
カモメ類、特に広義 (旧) Larus 属の骨格を見る時はこのような点にも着目されると面白い。
これらの比較はある程度まとまった系統の中で行うのが適切で、例えばカモメ類とウ類を直接比べてもおそらくそれほど役立たない。
コンサイス鳥名事典にはカモメ科は「足と頸は短く」とあり、何となく学者が頭の中で考えた話になっている気がする。ハサミアジサシ科は足が短いとあるので記述の上では一応の整合性は保たれるいるが。
特に大型カモメ類では首を伸ばすとかなり長く感じる。漁港で地上でおこぼれを待っているセグロカモメでも結構長く見える。これはすぐ近くなので多少警戒のポーズになっているかも知れないが、Larus 属の骨格の特徴ともよく合致しているように見える。北方で繁殖する種とは思えないぐらい。
アジサシ類でも同様で、普段はあまり気づかないかも知れないが、求愛のポーズなどでこれほど首が長かったのかと感心するような写真もある。
特徴が抜群に現れているわけではないかも知れないが、最近の写真を探してみるとエリグロアジサシで Black-naped Tern (Sam Buttrick 2025.5.4) やクロアジサシ Brown Noddy (Reza Khan 2025.5.3) など。
こちらは採食の瞬間: Brown Noddy (Dixie Sommers 2025.4.25)。力のモーメントの釣り合いから、ハサミアジサシ類ほどなくても上部頸椎が発達していると考えられる。ごく最近の写真を見ただけで、おそらくもっとよくわかる例があるだろう。
飛ぶ時や休息時は首を伸ばしていない (当然ながら流線型にするため) ことや、図鑑で同じようなポーズで並べられたアジサシ類のページを見ているとアジサシ類の首は短いと思い込む原因となるだろう。
離れた系統を直接比べててもそれほど役立たないと書いていながらいきなりであるが、やはり頸椎構造の話の発端となったハチクマの首から猛禽3系統の間の特性を少し比べてみよう。
「鳥の骨格標本図鑑」ではこの系統で最初に現れるのがヘビクイワシで、これは特殊事情がありすぎるのでここでは別扱いとしよう。それにしても隣ページに並んでいるウトウと比べても首が長い。
さて他の猛禽3系統では肉を引き裂いたりするのに首の筋力は当然必要で、どの系統でもウミガラスのように上部頸椎を短縮しておらず後突起も発達している。力学的考察の通りである。つまり猛禽の首は本来は長めのはずである。
猛禽3系統の間で比較するとご承知のようにフクロウ類の首はタカ類に比べてかなり短い。どちらが原因でどちらが結果はわからないが (#ミサゴ備考の [ミサゴは不器用?] で派生したカワセミの話で取り上げたように洞営巣性も一つの要因と考えている)、フクロウ類が獲物を丸のみにして、毛や羽毛をあまり取り除かないので頸椎の力に頼る必要性が低いためかも知れない。
空中捕食型のハヤブサ類もタカ類に比べて首が短めだが (ただし頸椎数はハヤブサ類の方が多い)、速く飛ぶ必要から流線型を保つため? しかしタカ類でも首を縮めて飛んで問題がないし、ハヤブサ類のすべてがハヤブサほどの高速飛行を必要としているわけではないのであまり重要な要因になっていないかも。むしろ営巣特性も関連があるかも。またハヤブサ類の方がたとえば進化初期にタカ類よりも肉食性が弱く、後になってタカ類に収斂進化したため、獲物の解体時にあまり首の筋力に頼らない生活様式の方が得意だったのかも知れない。
首の長さの異なる原因はともかく、現在の地上性でないハヤブサ類はタカ類に比べて頸椎が短く首の筋力に頼りにくいので、タカ類と同じような生活様式をとるならば補うために嘴縁突起が発達したのでは、そう思って骨格を見るとモズも首が短い (こちらは頭に筋肉を集中させたため頭が大きく、首が短くならざるを得ないのだろう)。肉食鳥の嘴縁突起の由来の統一的解釈になるかも、とちょっと期待してしまう (笑)。
この話はもともとキツツキの話題から出発したことを忘れてしまいそう。
-
ミツユビカモメ
- 学名:Rissa tridactyla (リッサ トゥリダクテュラ) 三本指のミツユビカモメ
- 属名:rissa (合) ミツユビカモメ (rita ミツユビカモメ アイスランド語 < 古ノルド語 ryta)
- 種小名:tridactyla (合) 三本指の (tri- (接頭辞) 三つの dachtylo 指 Gk)
- 英名:Black-legged Kittiwake
- 備考:
rissa の発音はよくわからないが短母音とすれば "リッサ"。
tridactyla は短母音のみで -dac- がアクセント音節 (トゥリダクテュラ)。起源となるギリシャ語 tridaktulos も短母音で、語末を伸ばす要因はない。
記載時学名 Larus tridactylus Linnaeus, 1758 (原記載)。
Larus rissa Brunnich, 1764 (参考) や Larus rissa Linnaeus, 1766 (参考) があるが同一と判定された Linnaeus (1758) が最も早い学名として採用されたよう。
Larus rissa Pontoppidan, 1763 (参考) はおそらく後に見つかったが無効とされた。
これらの用例を見ると rissa の名称はすでによく知られていて Larus tridactylus と同一でなければ生きていた学名だっただろう。Larus rissa をタイプ種として命名された属名 (Stephens 1826) に当時の面影が残ることになった。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは pollicaris (親指の < pollex, pollicis 親指。爪/指が一本ないことを示す) とされる。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種 tridactyla ニシミツユビカモメを検討亜種としている (次の記事も参照)。Rissa 属のタイプ種。
茂田 (1991) Birder 5(6): 44-47 にミツユビカモメの亜種についての記事がある。
Pineaux et al. (2023) A gull species recognizes MHC-II diversity and dissimilarity using odor cues
にミツユビカモメがにおいを用いて血縁度を見分けている研究がある。
-
アカアシミツユビカモメ
- 学名:Rissa brevirostris (リッサ ブレウィローストゥリス) 短い嘴のミツユビカモメ
- 属名:rissa (合) ミツユビカモメ (rita ミツユビカモメ アイスランド語 < 古ノルド語 ryta)
- 種小名:brevirostris (adj) 短い嘴の (brevis (adj) 短い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Red-legged Kittiwake
- 備考:
rissa は#ミツユビカモメ参照。
brevirostris は rostrum の o が長母音でアクセントもここにある (ブレウィローストゥリス)。
記載時学名 Larus (Rissa) brevirostris Bruch, 1855 (原記載) 基産地 Northwestern North America (北米北西部)。
この記載によれば Rissa 属全体を指して嘴が短い (明瞭に比較対象になっているものはカモメ) とあり、種そのものの特徴というわけではなさそう。
ミツユビカモメに似ているが die Fuesse sind hoch korallenroth, und der Schnabel ist gelb (足はサンゴのような赤色で嘴は黄色) とある。Larus 属に "足の赤い" に相当する種小名はすでに使われているため足の色を指すのは避けたのだろう。
和名は英名とよく一致している。
単形種。
-
ゾウゲカモメ
- 学名:Pagophila eburnea (パゴピラ エブルネア) 象牙製のように白い氷の友人
- 属名:pagophila (合) 氷の友人 (pagos 氷 philos 友人 Gk)
- 種小名:eburnea (adj) 象牙のように白い (eburneus)
- 英名:Ivory Gull
- 備考:
pagophila は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-go- がアクセント音節と考えられる (パゴピラ)。
eburnea は短母音のみで -bur- がアクセント音節 (エブルネア)。
ebur が象牙、-nus, -eus (いずれも短母音) を付けて語構成されたもの。読み方は違うが英語の ivory にも語幹の綴りの傾向が残っている。
古い図鑑を見ると Pagophila alba の学名がみられ、現在でも時に使われている。参考例: Ivory Gull Facts (Arctic Wildlife 2024)。
American Ornithologists' Union 1st edition (1886) が Gavia alba を用いた。
Kaup (1829) による Pagophila 属の提唱を受け、2nd edition (incl. 9th suppl.) で Pagophila alba に変更、1931 年までこの学名が用いられていたが 4th edition (incl. 19th suppl.) で Pagophila eburnea と変更された経緯がある。
アメリカ流の学名を用いると Pagophila alba が遅くまで残っていた模様。
Kaup (1829) では属提唱時に Pagophila eburnea をすでに用いていた (The Key to Scientific Names) ので Pagophila alba に変更されたのはそれ以降に判断されたものと考えられる。
Larus albus Gunnerus, 1767 (参考) 基産地 Northern Norway (ノルウェー) と記載されたのがこの種の記載の始まりで、要するに "白いカモメ" だった。
その後アメリカではこの種小名のまま Gavia 属に移されていたが、
Larus Eburneus Phipps, 1774 (原記載) 基産地 Spitsbergen (スピッツベルゲン島) が現代では原記載とされる。
Larus albus Gunnerus, 1767 の方が早いので一般的には使われないのは何か理由があるのだろう。
ここから先はあくまで想像だが、ゾウゲカモメが Gavia 属や Pagophila 属 (つまり Larus 属以外) に含まれる場合は、Gunnerus (1767) 以降に Larus albus と記載されている他の学名が複数あるので、これらのうちから記載の古いものが別種の学名先取権を得て Larus albus が有効になる可能性がある。
しかしゾウゲカモメ (見た目はカモメなので十分可能性がある) を Larus 属にまとめる場合はこちらに先取権が発生することになる。
このような分類体系による学名の不安定性を避けるために Larus albus を一律無効とする措置が取られたのではないだろうか。しかし Pagophila 属に分離されているなら問題ないのではなどの見解の対立があったのかも知れない (未確認)。
Dement'ev and Gladkov (1951) にもシノニムとして現れないので無効らしく見える。なおロシア語名は "白いカモメ" に相当して外見そのままか従来の学名に由来するものか。
単形属で単形種。北極圏の島で繁殖する。
-
クビワカモメ
- 学名:Xema sabini (クセマ サビニ) サビンのカモメ
- 属名:xema クビワカモメに対して Leach (1819) が作ったおそらく意味のない造語 (The Key to Scientific Names)
- 種小名:sabini (属) Sir Edward Sabine (英国の北極探検家) の
- 英名:Sabine's Gull
- 備考:
xema の読み方はわからないが短母音と推定すると "クセマ"。xenon なども短母音なのでおそらくこの読みでよいと考えられる。
sabini は人名で読み方がわからないが短母音のみとすれば "サビニ"。
ただしラテン語に Sabina (地名、植物名) の単語が存在し、この発音に似せるならば i が長母音となる (サビーニ)。おそらくどちらでもよい。
和名の由来となると考えられる学名があって Larus collaris Sabine, 1819 (参考)。
このカードによれば Larus sabini Sabine, 1819 (参考) を改名した学名だったが、Larus collaris の名前でウイーンの博物館にある標本はヒメクビワカモメであることが後に判明した模様。
この sabini の命名は自分自身ではなく兄弟を指すものとのこと。
規則はよく知らないが命名者自身を用いた学名は無効とされて改名されたのかも知れない。
Egevang and Boertmann (2008) Ross's Gulls (Rhodostethia rosea) Breeding in Greenland: A Review, with Special Emphasis on Records from 1979 to 2007
に関連情報があって、Larus collaris の学名は実際に使われていたよう。
Etymology of Xema の情報でも Xema collaris と呼ばれていたことがわかる。おそらく当時の英名はこのまま "クビワカモメ" に相当するもので、和名も学名か英名から訳されたと考えると理解しやすい。
collaris は首輪以外に "首に特徴のある" 語義もある (#イワヒバリ参照)。クビワカモメの記載にある torque cervicali nigro (黒い首輪がある) から首輪の語義でよいことがわかる。語義解釈に多少の注意を要する点と言える。
この記載を見て気づいたが、torquatus / torquata は非常によく現れ "首輪のある/首飾りのある" (ノビタキの以前の学名やオオコノハズクなど) の意味で使われるが、torque そのものには首輪の意味はなかった。もとは "絞められた" の意味で、足輪や腕輪など輪のようなもの全般を指すものと考えられる (torquis 腕輪、輪など)。そのため部位を示すため cervicali が付けられている。
collaris と torquatus / torquata は同じような意味のようで多少の違いがある。
単形属で単形種。北極圏の島や大陸沿岸からアリューシャン列島で繁殖する。原記載 "Mr. Sabine's Account of a new species of Gull ..."。種小名は発見者と記述がある。ここで新しい属に置く可能性もすでに提唱されていた。
Xema 属はユリカモメをタイプ種として使われたこともある (Boie 1822)。Zema/Zeme の綴りも使われた。xene (異端者, Gk)、kheima (冬、嵐 Gk) のような類語があり、まったく意味がなかったわけではないかも知れない (The Key to Scientific Names の情報からとりまとめ)。ロシア語の zima (冬。おそらく上記ギリシャ語と同系) も思い当たる。
可能性があるとすれば冬の異端者のような造語だったのかも。
-
ヒメクビワカモメ
- 学名:Rhodostethia rosea (ロドステーティア ロセア) バラ色の胸 (のカモメ)
- 属名:rhodostethia (合) バラ色の胸 (rhodon バラ Gk stethos 胸 Gk)
- 種小名:rosea (adj) バラ色の (roseus)
- 英名:Ross's Gull
- 備考:
rhodostethia は由来となるギリシャ語の stethos の冒頭が長母音でこれに従えばアクセントもこの位置で読みやすい (ロドステーティア)。
rosea は短母音のみで "ロセア"。発見者の Ross の発音にも近い。
単形属で単形種。
英名の Ross は James Clark Ross (英国探検家)。北極圏近くで繁殖するカモメで冬もあまり南下しない。1823 年の Ross による記載後も繁殖地は不明のままで、Sergei Aleksandrovich Buturlin (ロシア鳥類学者)によってヤクーチアの東北部 Pokhodsk 村で 1905 年にようやく発見された。
寒波の激しい年には繁殖しないか1卵しか産まない。極北地域ではレミングなどの齧歯類の年変動が激しく、捕食者であるホッキョクギツネなどはヒメクビワカモメの卵やひなも含めてあらゆるものを食べてしまう。
かつては食物の少ない年にはエスキモーがヒメクビワカモメを狩って食べていた。20 世紀初頭にはアメリカからの猟師などが訪れ、ヒメクビワカモメの詰め物は珍品として高値で取引されたがしばしば色が抜けて単なる白いカモメになったこともあった。家畜による捕食などもあり、繁殖地の限られたヒメクビワカモメの個体数が激減して種の存続も危ぶまれた。
1980 年代にソ連、そしてロシアのレッドデータブックに含まれた。ロシアでも辺境に生息し、ヒメクビワカモメを探す探検は Oleg Kuvaev による小説「キャプテン・ロスの鳥」(Ptitsa kapitana Rossa)に基づく映画「地平線の果てを行って」(1972, Idushchie za gorizont) が作られた (YouTube)。この映画の解説によれば、コリマ川デルタでヒメクビワカモメの巣の発見に人生を捧げた地理学者 Shavanosov の足跡を追った物語である (wikipedia ロシア語版から)。
日本でも記録されると話題になる珍鳥だが、ロシアでも幻のような鳥。
Eugene Potatov による発見物語(1990) (Birds International) を読むことができる。ちょうど日露戦争の時代の物語で、この記事を記載している 20 世紀末ですら、飛行機もヘリコプターも使えない当時に発見できたことは全く信じ難いと記している。
Michael Densley による書籍 "In Search of Ross's Gull" (Peregrine Press 1999) もある。
Rozovaya chajka "鳥の国" というロシアの TV 番組の1つで製作者直々のアップロード。自動字幕も表示できるので翻訳を選択すればある程度内容がわかるだろう。歴史物語から繁殖生態、極北の他の鳥も紹介されている。
北米の極北部 (グリーンランドやカナダの島) にも繁殖地があるが個体数は少ない。現在では部分的な衛星追跡に成功している [Solving the Mystery of Ross's Gulls (カナダ極北);
Gilg et al. (2016) Satellite tracking of Ross's Gull Rhodostethia rosea in the Arctic Ocean (ロシアから北極海)]。
繁殖地にとどまる期間は 60 日に過ぎず、その後は北極海高緯度 (80° 以北) に移動し海氷環境で生活する。おそらく餌資源が豊富であるためと考えられる。秋には南下してアラスカ北西の海上からチュコト半島に移動している。これは高緯度の極夜を避けるためと考えられている。
アンドレーエフ (池内訳) (1992) Birder 6(4): 34-43 に多数の写真を含むこの種の歴史や繁殖地の様子などが紹介されている。
尾がくさび型をしている点は識別点の一つで、ロシア名 vilokhvostaya chajka も vilo- は熊手の意味 (熊手の尾のカモメ)。
和名別名バライロカモメ。
川崎 (2001) Birder 15(4): 54-55 に 2001年1月6日北海道斜里川河口部を訪れた 100 羽の記録が紹介されている。過去の記録のリストも示されている。
Birder 編集部 (2000) Birder 14(1): 10-13 に「谷津干潟にヒメクビワカモメ出現」の記事がある。1999.11.23 に初確認のものを観察に訪れた記事。日本最初の記録は 1974 年1月北海道斜里町だった。
-
ハシボソカモメ
- 第8版学名:Chroicocephalus genei (クロイコケパルス ゲネイ) ジェネの色のついた頭 (のカモメ) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus genei (ラルス ゲネイ) ジェネのカモメ
- 第8版属名:chroicocephalus khroikos 色のついた < khrozo 色をつける Gk -kephalos 頭の < kephale 頭 Gk
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:genei (属) Carlo Giuseppe Gene (イタリアの動物学者) の
- 英名:Slender-billed Gull
- 備考:
chroicocephalus は#ユリカモメ参照。
larus は#カモメ参照。
genei は短母音のみとすれば "ゲネイ"。
ラテン語に genus (生まれ。生物学の属)、genea (世代) などの綴りの類似した単語があるがいずれも短母音。
単形種。現在の分類では Chroicocephalus genei となる。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
属名 Chroicocephalus (khroikos 色のついた < khrozo 色をつける Gk -kephalos 頭の < kephale 頭 Gk) で、ユリカモメなどで繁殖期に頭が黒くなることを表しているがハシボソカモメは黒くならない。
Chroicocephalus 属はユリカモメ属。
Boyd では Gelastes genei となる。
学名の由来を調べてみると原記載 Larus Genei di Breme, 1839 で、友人の Gene への献名となっている。
Carlo Giuseppe Gene (1840-1847) は鳥類学とはそれほど関係なく 1833-1838 年にハシボソカモメの基産地であるサルデーニャ (サルジニア) 島へ遠征し昆虫採集をして新種を記載したとのこと。
イタリア名 Gabbiano roseo のようにピンク色、あるいはスペイン名 Gaviota Picofina のように小さな (細い) 嘴に基づく名前が中心。フランス語では Goeland railleur で railleur は "嘲る、嘲笑する者 (の)" の意味。ユリカモメの学名同様に音声からか。
かつて迷鳥として福岡県に 1984 年から 1992 年までほぼ毎年1-2羽が渡来していたがその後の記録はない (Birder 誌にも当時の記事や回想などあり)。
世界的には地中海沿岸や中東に広く分布しており、分布域ではごく普通の種類。ユリカモメなどを含む小型カモメ類の中では首が長いことが知られていて、集団繁殖地では「パレード (2:23 付近)」と呼ばれる首を伸ばして歩く集団誇示行為が見られる。
韓国語では「キリンの首のカモメ」と呼ばれる (出典)。独特の採食姿勢が見られる。
ソ連時代の古い TV 番組があった 白い鳥の島 (1977) 3:07 あたりからハシボソカモメのコロニーの映像がある (さすがに体型だけでわかった)。他の水鳥やシギ・チドリ類も出てくるのでそのまま見ていても面白い。
ハシボソカモメは当時の黒海自然保護区 (ヘルソン、現ウクライナ) のシンボルでもあって、7:05 あたりから再度登場する (表題の白い鳥はカモメ類やアジサシ類を指すようだが、ハシボソカモメが特に中心であるとのこと)。
7:24 あたりからニシズグロカモメ Ichthyaetus melanocephalus Mediterranean Gull が出てくるが体型がまったく違うことがわかる。その後もアジサシの凶暴な行動やハシボソカモメの繁殖生態なども出てくる。
-
ボナパルトカモメ
- 第8版学名:Chroicocephalus philadelphia (クロイコケパルス ピラデルピーア) フィラデルフィアの色のついた頭 (のカモメ) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus philadelphia (ラルス ピラデルピーア) フィラデルフィアのカモメ
- 第8版属名:chroicocephalus khroikos 色のついた < khrozo 色をつける Gk -kephalos 頭の < kephale 頭 Gk
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:philadelphia (外) 米国のフィラデルフィア
- 英名:Bonaparte's Gull
- 備考:
chroicocephalus は#ユリカモメ参照。
larus は#カモメ参照。
philadelphia はラテン語読みでは語末の i を長母音にしてアクセントはここにあるとのこと (ピラデルピーア)。由来となったギリシャ語 Philadelpheia の語末が3重母音であったため。
単形種。日本鳥類目録改訂第7版で追加。現在の分類では Chroicocephalus philadelphia となる。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
英名、和名はフランスの鳥類学者 Charles Lucien Bonaparte (皇帝 Napoleon Bonaparte の甥)。
Larus bonapartiii Richardson, 1831 (参考) の学名があり、Bonapartian Gull と呼ばれていた。
Sterna Philadelphia Ord, 1815 (原記載) が早かったがここでは目録に並ぶのみ。人名を排して命名している他国語名ではカナダやアメリカを用いているものがいくつかある。
-
チャガシラカモメ
- 第8版学名:Chroicocephalus brunnicephalus (クロイコケパルス ブルンニケパルス) 茶色の頭の色のついた頭 (のカモメ) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus brunnicephalus (ラルス ブルンニケパルス) 茶色の頭のカモメ
- 第8版属名:chroicocephalus khroikos 色のついた < khrozo 色をつける Gk -kephalos 頭の < kephale 頭 Gk
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:brunnicephalus (合) 茶色頭の (brunneus 茶色の < brunius、kephali 頭 Gk)
- 英名:Brown-headed Gull
- 備考:
chroicocephalus は#ユリカモメ参照。
larus は#カモメ参照。
brunnicephalus は外来語を含む合成語で発音はわからないが、brunneus は短母音のみ。-kephalos も同様で長母音は現れないと考えられる。-ce- がアクセント音節と考えられる (ブルンニケパルス)。
種小名、英名、和名はいずれも同じ意味。
記載時学名 Larus brunnicephalus Jerdon, 1840 (原記載)
基産地 West coast of Indian peninsula。記載時は 新種? となっていてやや怪しげ。インド西岸で普通に見られる。現在の英名はここですでに与えられていた。
この記載の前後を見ると 新種? と書きながら学名を与えていないものも多い。"インド半島の鳥のカタログ" の書物なので新種かどうかをあまり追求しなかったのかも知れない。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば Stegmann (Shtegmann) はユリカモメの亜種として扱ったが、"雑種" の特徴を持つ個体が記録されていないことやカモメ類では羽衣の変異が大きいこと、"雑種" に見える個体は個体変異の可能性がある理由から別種として扱っている。
近縁ではあるが、カモメ類の種識別の重要な点の一つである風切羽の色彩の違いからこれらを同種と考えるのは難しいと述べている。
単形種。日本鳥類目録改訂第7版で追加。現在の分類では Chroicocephalus brunnicephalus となる。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
Ratanakorn et al. (2017) Satellite Tracking on the Flyways of Brown-Headed Gulls and Their Potential Role in the Spread of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 Virus
タイで越冬するチャガシラカモメの衛星追跡。
実効個体数は歴史的にもずっと少なかったと見積もられている。#ゴビズキンカモメ備考の Yang et al. (2025) Whole-genome resequencing landscape of adaptive evolution in Relict gull (Larus relictus) 参照。
しかし遺伝的多様性はゴビズキンカモメより高い。
加藤 (2024) Birder 38(12): 48-51 にチャガシラカモメとユリカモメの識別および交雑個体と思われるものについて解説がある。
-
ユリカモメ
- 第8版学名:Chroicocephalus ridibundus (クローイコケパルス リーディブンドゥス) 笑うような鳴き声の (誤命名?) 色のついた頭 (のカモメ) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus ridibundus (ラルス リーディブンドゥス) 笑うような鳴き声の (誤命名?) カモメ
- 第8版属名:chroicocephalus khroikos 色のついた < khrozo 色をつける Gk -kephalos 頭の < kephale 頭 Gk
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:ridibundus (adj) 鳴き声が笑うような (ワライカモメと混同されていた可能性がある。備考参照)
- 英名:Black-headed Gull
- 備考:
chroicocephalus は起源となるギリシャ語の khroikos の1つめの o が長母音。-ce- がアクセント音節と考えられる (クローイコケパルス)。
larus は#カモメ参照。
ridibundus は1つめの i が長母音。アクセントは -bun- にある (リーディブンドゥス)。rideo (リーデオー。笑う) が長音の由来。
ridibundus は本来はワライカモメに付いていてもよい学名だったらしい。経緯は#ワライカモメを参照。Linnaeus の知識 (情報) 不足によりあまりふさわしくない学名になってしまった説明が wikipedia スウェーデン語版にある。
かつてはユリカモメとワライカモメは同一 (ワライカモメの足の赤い版と考えた模様) と考えた Brisson による。文献はワライカモメの方を参照。現行の学名字義を解釈してユリカモメに結びつけるのは無理があるかも。
ドイツ語名は Lachmoewe と学名をそのまま訳しており、こちらが "ワライカモメ" を意味する名前になっている。英名と比べて混乱しないのだろうか...。
日本語のワライカモメに相当するものは Aztekenmoewe と地域名で呼んでいる (Aztek- を使っている点はロシア語名も同じ)。
フランス語名も Mouette rieuse と rieuse (よく笑う、楽しそうな) の意味は近い。ラテン系言語なので学名の影響力が大きいかも知れない。ロシア語名は知っている人もあるかも知れないが (日本のユリカモメはカムチャツカから来るため)、"湖のカモメ" の意味。湖でも繁殖してよく見られるためだろう。
単形種。現在の分類では Chroicocephalus ridibundus となる。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
かつては亜種 sibiricus を認める立場もあり、日本のユリカモメはこの亜種とされていた。
記載時学名 Larus ridibundus sibiricus Buturlin, 1911 (原記載)。基産地は Avibase では Koljma Delta and Ussuriland とされているが、この文献ではカムチャツカも指している。数ページ後に英訳あり。
American Ornithologists' Union 5th edition (incl. 33rd suppl.) までは亜種として認めていた。
亜種を認める場合は先取権が複雑だったようで、Dement'ev and Gladkov (1951) によれば Larus ridibundus var. major Middendorff, 1853 があったがすでに使用されている学名で無効。
Larus erythropus Gmelin, 1789 (基産地カムチャツカと英国)、
Larus naevia Pallas, 1811 (基産地ロシア)、
Larus ridibundus sibiricus Buturlin, 1911、
Larus ridibundus lavrovi Zarudnyj, 1922 (基産地ウズベキスタンの Chirchik) はいずれも当時の学名で、現在は単形種とされる Larus ridibundus のシノニムとされている。
Larus ridibundus sibiricus が一時的に使われたのは先行する記載の地域特定が不十分だったためだろうか。
ユリカモメの学名変更が一番影響が大きいと思われるのでここに含めておくが、旧 Larus 属が単系統でないために属分割を提案したのは Pons et al. (2005)
Phylogenetic relationships within the Laridae (Charadriiformes: Aves) inferred from mitochondrial markers。
今となっては古い論文だがその後の研究でも確かめられている。#カモメの備考 [カモメ科の系統分類] 参照。
茂田 (1995) Birder 9(3): 46-51 によればユリカモメを含む小型カモメ類 (ハシボソカモメも含む) が Hydrocoloeus 属 (hudro 水 koloios 未同定の鳥 Gk #ヒメカモメ参照) にまとめられていたとのこと。
最初の用例は Kaup (1829) で ヒメカモメとワライカモメ (当時の学名で Larus plumbiceps) 2種からなる属であったがその後拡張されたらしい (The Key to Scientific Names)。
その後ご存じのように Larus 属にまとめられて長期間この属が使われてきた。
分子系統解析で属を復活させる必要が生じたが Hydrocoloeus 属は記載時ユリカモメを含んでおらず、ユリカモメを含む最初の記載と判断される Chroicocephalus Eyton, 1836 が採用されるようになった模様。
この属は A history of the rarer British birds が最初の用例でこの時は当時の学名で Larus Minutus Pallas (ヒメカモメ) と当時の学名で Larus capistratus Temminck が含められていた。
Eyton 自身も Larus capistratus と Larus ridibundus を別種と考えていたが、
On the Larus capistratus of Temminck (Thompson 1845) が標本を検討して同一と判定した。Temminck は羽衣の変化に惑わされて別種と考えたらしい。
当時は東洋のことはほとんど未知でユーラシアの東西で別種が存在するのかよくわからず、Eyton もどちらからやってきた迷鳥だろうかと考えたらしい。
Linnaeus (1766) によるユリカモメの原記載。Chroicocephalus 属命名に使われた Larus capistratus Temminck がユリカモメと同じものと判定された結果、こちらがタイプ種となった (The Key to Scientific Names の情報から抜粋)。
もし本当にユーラシアの東西が別種であったならば Larus capistratus と呼ばれたものの方がタイプ種となっていて (ユーラシア東部個体群の学名先取権は要検討)、元祖 Larus ridibundus をニシユリカモメのような名前で呼ぶことになっていたかも知れない。
ワライカモメが別属となったため Hydrocoloeus 属はヒメカモメのみを含む属となった。
ヒメカモメがタイプ種と指定されたのは Gray (1841) による (参考)。
[2023 年ポーランドで H5N1 によるユリカモメへの影響]
Indykiewicz et al. (2025) Impact of highly pathogenic avian influenza virus (HPAIV) on Black-headed Gulls Chroicocephalus ridibundus population in Poland in 2023
成鳥個体の平均死亡率 22.2% だったとのこと。コロニーサイズが大きいほど死亡率が高かった。ポーランドで成鳥 51000 羽が死亡したと推定される。
-
ズグロカモメ
- 第8版学名:Saundersilarus saundersi (サウンデルスィラルス サウンデルスィ) ソーンダースのカモメ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus saundersi (ラルス サウンデルスィ) ソーンダースのカモメ
- 第8版属名:saundersilarus Saunders (Howard Saunders の) larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 第7版属名:larus (m) カモメ (larosがつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:saundersi (属) ソーンダース (英国の銀行家、カモメ類の権威の鳥類学者) Howard Saunders の
- 英名:Saunders's Gull
- 備考:
saundersilarus は人名からの合成なので発音はよくわからないが、larus は短母音のみ。ラテン式の発音規則に従えば -si- がアクセント音節となる。種小名の発音と整合性を持たせるならばすべて短母音で発音するのが読みやすく思える (サウンデルスィラルス)。
larus は#カモメ参照。
saundersi はラテン語読みでは -der- がアクセント音節と考えられる。短母音のみで読めば (サウンデルスィ)。-der- を長母音で発音しても構わないが、統一した読み方にすると属名の読みがやや不自然になる。
単形種。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Saundersilarus 属 [Saunders と Larus 属 (カモメ属) の合成] となる。Saundersilarus 属はズグロカモメ属。
亜属 Saundersia (Dwight, 1925) がすでに他に使われていたため、Saundersilarus の名称がさらに作られた (The Key to Scientific Names)。
HBW/BirdLife, Clements, eBird ではこの属名が使われているが IOC 学名は 1.7 から 13.2 まで Chroicocephalus saundersi。IOC 14.1 以降 Saundersilarus saundersi となった。
Clements (2024) でもこの学名が採用され、eBird も2024年10月現在こちらの学名になっている。
ユリカモメなどは第8版で Chroicocephalus 属になった次第で、ズグロカモメも同じ属で夏には同じような...など説明をすべきところが、ズグロカモメはさらに変更が進んでしまったため。
第7版と第8版の間で2回の学名変更があって、一足飛びに属が変わって現れてもよいはずの Chroicocephalus saundersi の学名になる機会がなかった。IOC や eBird を用いていた方では長く使われていただろうもの。
日本鳥類目録だけを見ていると、ご存じの夏羽の特徴通りズグロカモメとユリカモメが同属で分離されていたことがあることを知らないままとなるのはちょっと惜しい感じがする。
なぜならばユリカモメ夏羽を見てこれこそズグロカモメと呼ぶべきと感じた人は結構多いと思う上、ユリカモメの英名の意味はまさに "ズグロカモメ" である。現在の英名と和名の対応が悪いが、ズグロカモメにも Chinese Black-headed Gull の別名があった。頭の黒くなるカモメ類は多種あるので人名を使って違う系統の名前が用いられたものか。
ズグロカモメが別属になったのは系統的必然性というよりは属境界の定義に基づくものなので、新しい学名だけを根拠に学名の変わる理由に悩むよりは Chroicocephalus 属とほぼ同属に近いことを認識しておくとよいだろう。
上記表示でも第8版学名 / 第7版学名 と並んでいるが、表面上現れないが間に中間段階が存在した。
最新の Dufour et al. (2024) Seasonal migration and the evolution of an inverse latitudinal diversity gradient in shorebirds
の Supporting Information (Figure S1) の分子系統樹を見ると Chroicocephalus 属に含めてしまうと (狭義) Larus 属と単系統の関係にならなくなるので、Saundersilarus 属を分離するのが適切であることがわかる。
Boyd では Saundersilarus saundersi。
他言語名称では Saunders を用いているものがそこそこあるが、地域名を使っているものではロシア語など中国を用いているものが多い。中国名は黒嘴鴎なのでわかりやすい。
-
ヒメカモメ
- 第8版学名:Hydrocoloeus minutus (ヒュドロコロエウス ミヌートゥス) 小さな水の水かきのある鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus minutus (ラルス ミヌートゥス) 小さなカモメ
- 第8版属名:hydrocoloeus hudro- 水の (Gk) koloios 同定されていない鳥の一種 (水かきのある鳥でウの意味か) (Gk)
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:minutus (adj) 小さな
- 英名:Little Gull
- 備考:
hydrocoloeus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。末尾に母音が3つ並ぶのでそのうち最初にアクセントがあると考えられる (ヒュドロコロエウス)。
coloeus は#ニシコクマルガラスの属名も参照。
larus は#カモメ参照。
minutus は u が長母音でアクセントもある (ミヌートゥス)。
単形種。日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Hydrocoloeus minutus となる。
属名 Hydrocoloeus hudro- 水の (Gk) koloios 同定されていない鳥の一種 (水かきのある鳥でウの意味か) (Gk)。属命名の経緯は#ユリカモメの備考参照。
Hydrocoloeus 属はヒメカモメ属。
カモメ類の中で最も小型。
-
ワライカモメ
- 第8版学名:Leucophaeus atricilla (レウコパエウス アートゥリキルラ) 黒い尾の白っぽい灰色の鳥(誤命名?) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus atricilla (ラルス アートゥリキルラ) 黒い尾のカモメ(誤命名?)
- 第8版属名:leucophaeus leukophaios 白っぽい灰色、灰色 (Gk) < leukos 白 phaios 薄黒い (Gk)
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:atricilla (合) 黒い尾の (ater (adj) 黒い cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい。ユリカモメと混同されていた可能性がある。備考参照) -cilla についてはセキレイ科も参照)
- 英名:Laughing Gull
- 備考:
leucophaeus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。末尾に母音が3つ並ぶのでそのうち最初にアクセントがあると考えられる (レウコパエウス)。
atricilla は atri- の冒頭が長母音。-cil- がアクセント音節と考えられる (アートゥリキルラ)。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは亜種不明とされる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Leucophaeus atricilla となる。属名 Leucophaeus leukophaios 白っぽい灰色、灰色 (Gk) < leukos 白 phaios 薄黒い (Gk)。Leucophaeus 属はワライカモメ属。
種小名は atricapilla (髪の黒い。こちらの方が特徴をよく表している) を意図して誤って付けられたものではないかとの解釈がある。
Linnaeus (1758) からある学名で原記載。capite alarumque apicibus nigris で翼の先端が黒いことを指していると思われるので誤命名の解釈でよさそう。The Key to Scientific Names によれば Catesby (1731) の図版を見ると尾が黒い印象を受けるかも知れないとのこと。
英名、和名は鳴き声から。
Mark Catesby (1729-1732) The natural history of Carolina, Florida and the Bahama Islands... にすでに登場する英名で学名以前に英名があった。
ユリカモメはスウェーデンにも分布するのにワライカモメより命名が後になった理由は wikipedia スウェーデン語版 (Skrattmas) によれば ridibundus の名称は Brisson (1760) によるもので、Brisson はユリカモメはワライカモメの亜種 (当時は亜種概念がなかったので同じ種の中に含めたのだろうか) としていたためと解説がある。
Linnaeus はユリカモメのことをよく知らなかったので情報は Brisson の文献に頼っていて、ワライカモメは笑ったような声で鳴くがユリカモメはそのような声では鳴かないのでユリカモメの方にワライカモメに相当する誤った学名を付けたと説明されている。
ワライカモメの原記載にはそのような兆候は見られない (ヨーロッパにも生息する記述になっていない) ので、Linnaeus はカモメ類をよく知らなかった (= カモメ類の情報提供者が少なかった) ということらしい。世界の生物を扱っているのに Linnaeus (1758) では Larus 属の種数も少なかった。
ユリカモメの原記載 (参考) ではこの状況が読み取れて、
・ワライカモメ = Gavia ridibunda (Brisson)。Linnaeus はアメリカとヨーロッパに生息としている。足は黒いとしている。
・ユリカモメ = Gavia ridibunda phoenicopos (Brisson), Linnaeus は Mari Europaeo (ヨーロッパの海) Voce cachinnos aemulatur ("声で笑いを真似る" 程度の意味か)。
となっていて、ワライカモメがアメリカとヨーロッパに生息し、こちらが本家でユリカモメはそのうち足の赤いもの (phoenicopos は "赤い顔" の意味になるが、おそらく phoenicopus "赤い足" を意図したものだろう) の位置づけになる。
Brisson (1760): Gavia ridibunda (No. 13), Gavia ridibunda phaenicopos (No. 14)。
Linnaeus はワライカモメを記載した後に別種記載すべきと判断してユリカモメを後から記載することになったらしい。
そのため分布域などもワライカモメとユリカモメの特徴が混ざったような原記載 (参考) になっている。
ユリカモメを意図した学名を先にワライカモメに付けてしまって学名を修正することはできず、新たに命名したユリカモメにむしろワライカモメにふさわしい学名を付けることになった (Linnaeus は両者を混同していてユリカモメが笑うような声で鳴くと考えたらしい)。
この意味では Brisson (1760) の方が早いが書物全体が二名法に則っていないため有効な学名とはみなされず、この記述を参考にして記述した Linnaeus (1766) の方が記載者となった。
Linnaeus は本家ワライカモメの方の声の記述を行っておらず、ユリカモメが笑ったような声で鳴くと混同していたよう。
このような意味でワライカモメの種小名を考えると atricilla (黒い尾の) はユリカモメの方が合っている (!)。おそらく両者が混同されていて atricilla はユリカモメの尾を意識して付けられたのではないだろうか。
Brisson (1760) にはユリカモメに相当する方に尾の先が黒いと正しく記述されており、ワライカモメに相当する方に Aves istae voce risum quodammodo aemulantur; unde ridibunde nomen と笑い声のような声を出すので ridibunde と名付けるとあり、Brisson (1760) は正しく理解していた。
相前後して出版された形となり、Linnaeus が名付けた atricilla であることも示されていた (別学名を与えていることから、Linnaeus は atricilla と名付けたが勘違いでは、のようなニュアンスも込められていたのかも)。
Linnaeus (1758, 1766) の方が間違って付けてしまったらしい。
Brisson のラテン名にそのまま従えばワライカモメの方が Larus ridibundus となっていたと思われるが、Linnaeus (1758) 年段階では両者を区別しておらず誤解して解釈されていた模様。
また Brisson (1760) の用例が有効な学名とみなされなかったために、後で用いた Linnaeus (1766) の名称が有効となったため起きた現象とも言える。Brisson (1760) の用例が有効であったならば同名の Linnaeus (1766) のユリカモメの種小名は無効となったはず。
他言語ではアステカやカリブ海の地域名を用いているものもある。学名が誤って付けられたらしいことを認識しているところでは地名を使う傾向があるように見える。
Boyd では Atricilla atricilla。
-
アメリカズグロカモメ
- 第8版学名:Leucophaeus pipixcan (レウコパエウス ピピクスカン) (アステカ語の)カモメの一種で白っぽい灰色の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus pipixcan (ラルス ピピクスカン) (アステカ語の)カモメの一種
- 第8版属名:leucophaeus leukophaios 白っぽい灰色、灰色 (Gk) < leukos 白 phaios 薄黒い (Gk)
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:pipixcan (外) アステカ語、ナワトル語のカモメを意味する Pipixcan, Apipipitzcatl, Apipitzin, Apipitztli
- 英名:Franklin's Gull
- 備考:
leucophaeus は#ワライカモメ参照。
larus は#カモメ参照。
pipixcan は外来語で発音はよくわからないが -pic(s)- がアクセント音節と考えられる。すべて短母音で読めば "ピピクスカン"。
単形種。日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Leucophaeus pipixcanとなる。
英名は北極探検家 Sir John Franklin が標本を採取したことによる。
Boyd では Atricilla pipixcan。
-
ゴビズキンカモメ
- 第8版学名:Ichthyaetus relictus (イクチュアーエトゥス レリクトゥス) 遺存種のワシのようなカモメ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus relictus (ラルス レリクトゥス) 遺存種のカモメ
- 第8版属名:ichthyaetus (合) 魚を捕るワシ (ichthy 魚類 aetus ワシ Gk。猛禽類に似た行動を引喩して付けられたもの)
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:relictus (adj) 通常の意味は見捨てられた、手つかずの。ここではニシズグロカモメに対する遺存種の意味 (備考参照)
- 英名:Relict Gull
- 備考:
ichthyaetus は#オオズグロカモメ参照。
larus は#カモメ参照。
relictus は短母音のみで -lic- がアクセント音節 (レリクトゥス)。英語の relic, relict は冒頭がアクセントで異なっている。
単形種。日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Ichthyaetus relictus となる。
属名 Ichthyaetus はオオズグロカモメ Larus ichthyaetus Pallas, 1773 に対して Kaup (1829) が属名に昇格させたもの。
由来等はオオズグロカモメの種小名の解説を参照。
Ichthyaetus 属はオオズグロカモメ属。
種小名、英名ともに遺存種 (英 relic または relict) を意味する: かつて地理的に広い範囲に分布していたものが、現在では限られた地域にだけ生存しているもの (日本大百科)。
1931 年に記載されたが確実な集団営巣地が発見されたのは 1969 年 (後の記述も参照。1968 年の標識調査中に見つかったらしい)。ゴビズキンカモメはモンゴル、カザフスタン、ロシア、中国の数か所の湖で繁殖するのみで、ニシズグロカモメ Ichthyaetus melanocephalus Mediterranean Gull がかつては東方にも分布したものが分断されて遺存種となったものと考えられている。
世界的にも希少なカモメで個体数も減少していると考えられている。数少ない辺境の湖の悪天候なども脅威の一つ。
中国天津沿岸部や韓国で少数が越冬するが正確な越冬分布はわかっていない。Wang et al. (2022) Breeding Population Dynamics of Relict Gull (Larus relictus) in Hongjian Nur, Shaanxi, China に中国繁殖個体群の研究がある。
Liu et al. (2017) Seasonal dispersal and longitudinal migration in the Relict Gull Larus relictus across the Inner-Mongolian Plateau
が内モンゴル平原での衛星追跡の結果を発表している。渤海沿岸で多く多く越冬している。
河北省康保にある湖の個体数が世界の個体数の 60% を占めるとされる。渡りの中継に適した場所がないと思われることも生息を難しくしていると思われる。
モンゴル、カザフスタン、ロシアで保護区が設置され、中国の国家一級保護動物に指定されている (wikipedia 英語、ロシア語、中国語版による)。中国繁殖地の解説ビデオ。
2023 年夏にロシア沿海地方で長期滞在が観察された: Gluschenko and Korobov (2023) Interesting ornithological observations and finds in the southwest of Primorsky Krai in 2023 (pp. 5038-5057)。写真もあり。
国内では1985年1月2日に観察され、オビハシカモメ (クロワカモメ) Larus delawarensis Ring-billed Gull として発表された個体がゴビズキンカモメと同定された。石江他 (1986) 日本におけるクロワカモメの観察記録 が最初の発表。
中村一恵「野鳥」1989年6月号 (No. 514) pp. 40-41 「ゴビズキンカモメについて」の記事があり、海外からの指摘により同定された経緯が述べられている。
[ゴビズキンカモメの発見物語]
「野鳥」の中村氏の記事 (1989) を参考に wikipedia ロシア語版を調べてみると、1929 年にモンゴルの Edzin-Gol 川で Lonnberg が採集した1個体を Larus melanocephalus relictus として 1931 年記載 ("A remarkable gull from the Gobi desert" Arkiv for Zoologi 23B no. 2 p. 2, 5) したのが最初とのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) がチャガシラカモメの異常型と考えたとの記述があるが、原文にあたってみるとニシズグロカモメ Ichthyaetus melanocephalus (現在の学名) の亜種として載っているが、1標本しかなく位置づけは明らかでなく、
ニシズグロカモメでさえなく、普通のチャガシラカモメの羽衣の変わったもの (原文 uklonyashchijsya ot obychnoj okraski ekzemplyar L. brunnicephalus とやや慎重な表現で「普通の色彩から離れつつあるもの」ぐらいの意味) の可能性をまったくもって除外できない、となっている。変種や異常などを意味する単語は使われていない。
u- が離れる + klonit'sya 近づく (英語の動詞の incline の意味が近い。日本語では「〜に考えが傾いている」のような意味の「傾く」に近い表現。逆方向に傾いている、ぐらいに考えればよいだろうか)。
この部分は英訳でニュアンスを的確に表現するのが難しいかも知れない。
根拠は色彩や地理分布から。Dement'ev and Gladkov にとってはニシズグロカモメとはあまりに隔離された分布になるので同種とは信じがたいとの考えだった模様。
モンゴルはそれ以前にも以降にも鳥類学者がよく調べている地域だが、それ以上の記録がないことにも注意を向ける必要がある、とのこと (以前にも以降にも見られていないので意味のあるタクソンとは考えにくいということだろう)。
Dement'ev and Gladkov はニシズグロカモメの亜種として記載通りに置いているが、分布図にも示されているように (?) 付きという解釈でよいと思う。
Vaurie (1962) The status of Larus relictus and of other hooded gulls from Central Asia はオオズグロカモメとチャガシラカモメの雑種と考えた。
この文中に Dementiev rejects the possibility that it is a form of melanocephalus, suggesting that it is an aberrant specimen of brunnicephalus misidentified by Lonnberg と述べられているがこのニュアンスは原文と多少違う ("aberrant" は語源的に確かに原語の表現をよく表しているかも)。
この文献から "relict" は当時から遺存分布と認識されていたことがわかる [以下の Auezov (1971), Potapov (2007a) でも Lonnberg の考えがわかる]。
Auezov (1970) がカザフスタンの Adakul' Taldy-Kurgansk 州の Srednij 湖の島で他種との混合繁殖コロニーを速報したことで状況が大きく変わり、
Auezov (1971, 2015 再掲) Taxonomic evaluation and systematic status of Larus relictus (pp. 4614-4622)
が発見の翌年の分類学的検討の論文。ここで独立種と判定された。1968 年の標識調査中にコロニーが見つかった。Auezov の wikipedia ロシア語版によれば 1963 年や 1967 年にもコロニーが発見されていたが当時はチャガシラカモメと誤同定されていたとのこと (以下の Potapov の論文で歴史が紹介されている)。
この種を同定・研究したことが Auezov の最大の業績として知られるとのこと。
Auezov はその後も研究を続け繁殖生態などの論文を複数出しているので興味ある方は参照されるとよいだろう。
なおこれらの論文や記事で Dement'ev (1951) と引用されているが、この巻は Dement'ev and Gladkov が general editors となっているので同シリーズ他の巻同様に Dement'ev and Gladkov を用いた。
ゴビズキンカモメの発見は旧ソ連で相当大きな事件であったようで、資料が分散しているので雑誌 "The Russian Journal of Ornithiology" 編集部が先導して歴史を振り返る資料がまとめられた。
Gavrilov (2004, 2007 再掲) To history of discovery of the relict gull Larus relictus on Alakol Lake (pp. 515-521)
にカザフスタンの Alakol 湖での再発見 (1968) 物語がある。Auezov は当時先鋭の新人だった。
6月の遠征で明るい色の小型カモメ類のひなを捕獲し、Grachev に聞いたら "ユリカモメ" と答え、誰も疑問も持たずに記録して標識を続けていた。13 羽の "ユリカモメ" を含む多数の鳥に標識を終えて動物学教室に戻って日記を付け終えた。何時間かして「何か違う」ことに気づき、まず「カザフスタンの鳥」を読んでみると標識したものと記述が合わない。
何日か考えて記録をオオズグロカモメに訂正した。しかし何かおかしい。オオズグロカモメのひなには足環
D を付けたが "ユリカモメ" にはもっと小さな E を使ったがそれでも大きすぎるぐらいだった。
真実を明らかにするために死体でも入手できないかと8月に再調査。しかし繁殖は終わっていなかった。
飛んでいるカモメも見たがすべてユリカモメと判明。何も得られず帰り翌年の課題となった。
翌 1969 年は謎のカモメの死体を得ることが課題となり、Auezov が役割を任せられた。Gavrilov 自身は「カザフスタンの鳥」第3版の執筆や Chokpak での調査に忙しくて行けなかった。
Auezov のグループは 1968 年に "オオズグロカモメ" と記録した謎のカモメ 50 羽を含むひなに標識をした。謎のカモメは8羽の成鳥、3羽の若鳥の死体が得られた。
アルマ・アタに戻ってあらゆる資料を調べたが同定できなかった。1971 年に Auezov の発案でこの島に保護区が設けられた。レンジャーが入って漁民が卵を採取することなどを防いだ。Auezov は謎のカモメを独立種のゴビズキンカモメと同定し、この研究で学位を得たとのこと。
この記事の著者 Gavrilov はカザフスタンの著名な鳥学者で、Chokpak の渡り鳥ステーションの所長を務め多くの研究を残している。
Potapov (2007a) To the history of the discovery of a new gull species - the relict gull Larus relictus (pp. 1135-1150)。
Lonnberg は非常に先見の明があり、わずか1標本からニシズグロカモメがかつては広く分布していてその遺存個体群である本質を見抜いていた。そのことは後の研究で確かめられることになった。
さすがの Dement'ev and Gladkov (1951) でも及ばなかった模様。
1934-1935 年に採集されたこの種の標本が 1957 年に3個体もレニングラードに届き、チャガシラカモメとして収蔵された。この時点で世界の4個体の標本だった。1953 年に中国で採集された4標本も後にこの種と判明した。
我が国の偉大な鳥類学者の Stegmann もこれら標本を見ているのに意見を述べなかった。
1963 年にシベリアの動物学者 Leont'ev がかつてのチタ州南端のステップにある Barun-Torej 湖で奇妙なカモメの群れが通過するのを見かけて標本も採集した。1967 年に Khukhan 島でコロニーを見つけたにもかかわらずチャガシラカモメのチベット亜種と記述したとのこと。
Stubbe and Bolod (1971) "Mowen und Seeschwalben (Laridae, Aves) der Mongolei" が出版された。Stubbe は 1969 年に Stockman から新種のカモメの繁殖コロニー発見の知らせを受け取っていたとのこと。出版が 1971 年と遅くなったため Auezov の発見が先んじることになった模様。
Potapov (2007b) The discovery of the relict gull Larus relictus colony in the Lake Barun-Torey も 1970 年に Leont'ev の発見したコロニーの調査に訪れて一般向け雑誌に記事を書いている。
ちょうどこの時期に "新種のカモメ" の情報が広まり、各々が一番乗りを狙おうとしていたらしいが第一記述者になれなかった残念さなどそれぞれの立場で述べられている感じ。記述を見ると Gavrilov も業績として残したかったのかも知れないが都合で行けなかったことを残念に思っているのかも。Potapov も Auezov (1970) の報告は非常に短いと記していて、他の研究者もあわよくばと思ったらしいことが想像できる。
英語で紹介された記事だけでは読み取れない興味深い歴史があった模様。日本のヤンバルクイナの発見に近い状況だったのだろうか。ヤンバルクイナの正式記載は 1981 年なので時期的にもそこそこ近い。
Duff et al. (1991) The Relict Gull Larus relictus in China and elsewhere
の記事では確かに Stubbe and Bolod (1971) も現れていて「情報を伝えてしまった」ためにあるいはわずかの差で第一記述者の座を奪われる恐れがあったことがわかる。表面だけからはわからないが、まだ若い Auezov がすぐには論文を書けず (?) 尻を叩かれる状況だったのかも。
またこの種のカモメは繁殖が安定せず、(カザフスタンで) 翌年訪れても記録できる保証がないことも Potapov が記している。実は冷や汗ものだったのかも知れない (標本はすでにあるので誰かが記述することも可能で、また越冬地で記載される可能性もあった)。
Duff のこの論文でもなぜ見過ごされてきたのかを考察している。石江他 (1986) の論文に対する指摘も、海外研究者が日本でも絶対記録があるはずと目を皿のように探していたのかも知れない。
海外バーダーの識別力がすごいらしいのは確かだろうが背景をよく知って早くから注目していた効果も大きかったのかも。
Ichthyaetus (Larus) relictus (BirdForum) で原記載のスウェーデン語と英訳が読めることを知った。
上述の通り隔離分布に至った経緯も考察されていた。こんなに面白い話ならば wikipedia スウェーデン語版に出ているかと思ったが出典が英語文献由来で、自国の研究者の顕著な業績であるにもかかわらず紹介されていない (2024.12 時点)。
[ゲノム解析と適応に関係する遺伝子候補]
Yang et al. (2021) Genome-wide analyses of the relict gull (Larus relictus): insights and evolutionary implications
にゲノム解析の論文がある。さらに、
Yang et al. (2025) Whole-genome resequencing landscape of adaptive evolution in Relict gull (Larus relictus)
18 万年から 5000 年前の実効個体数の変動を推定、10-8 万年前に個体数がピークで Ne = 100000 程度。現在は 2200-5000 と見積もられる。現在の Ne はトキよりも小さいとのこと。
チャガシラカモメの方がいつの時代も実効個体数が小さかった。しかしゴビズキンカモメは他のカモメ類に比べて遺伝的多様性が低い (チャガシラカモメよりも低い)。
outbreak species の表現が出てくる (バッタのように個体数が増えたり減ったりする歴史を想像している)。分断されたニシズグロカモメの隔離個体群が厳しい環境化で生き延びてきた歴史がゲノムにも現れている模様。また繁殖も安定しないことが Auezov や Gavrilov 時代の繁殖地発見の困難さにもつながっていたのだろう。
嘴の形を決める遺伝子など正の選択を受けている遺伝子候補が挙げられていて、その一つに苦味受容体がある。これは繁殖期に昆虫を主に食べるための適応と考えられ、また視覚よりも嗅覚に頼った採食様式への適応があると考えられる。腫れぼったい目の独特の顔貌もあまり視力がよくないことに対応しているのかも。
カモメ類の採食様式にはかなり多様性があるので、猛禽類同様に視力のよいものから別感覚を主に用いているものまでいろいろありそう。視覚関係の比較ゲノム研究をやってみると面白そう。
チャガシラカモメとの虹彩の色の違いは SPNS2 遺伝子が関係している可能性がある。高所適応の遺伝子候補も挙げられている。
Zou et al. (2025) Comparative Analysis of Gut Bacteria of Four Waterbirds Species in Taolimiao-Alashan Nur (T-A Nur) in Erdos Relic Gull National Nature Reserve, Inner Mongolia, China
がゴビズキンカモメの重要な繁殖地の一つである中国の内モンゴルの Dongsheng District, Ordos City に生息する鳥の腸内細菌叢を調べている。
ゴビズキンカモメでは同所に生息するハイイロガン、アカツクシガモに比べて腸内の代謝に役割を果たす細菌叢の多様性が低いとのこと。また人にとって有害であることが知られている細菌も比較的多く、直接の由来までは議論していないが人にとって有害な細菌がこの場所に存在していることになる。
-
オオズグロカモメ
- 第8版学名:Ichthyaetus ichthyaetus (イクチュアーエトゥス イクチュアーエトゥス) 魚を捕るワシのようなカモメ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus ichthyaetus (ラルス イクチュアーエトゥス) 魚を捕るワシのようなカモメ
- 第8版属名:ichthyaetus (合) 魚を捕るワシ (ichthy 魚類 aetus ワシ Gk。猛禽類に似た行動を引喩して付けられたもの)
- 第7版属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:ichthyaetus (合) 魚を捕るワシ (ichthy 魚類 aetus ワシ Gk。猛禽類に似た行動を引喩して付けられたもの)
- 英名:Pallas's Gull (プロイセンの生物学者 Peter Simon Pallas に由来)
- 備考:
ichthyaetus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、ワシの意味の -aetos は a を長母音で読むためこの場合も同様と考えられる。アクセントもこの位置にある (イクチュアーエトゥス)。
larus は#カモメ参照。
単形種。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Ichthyaetus ichthyaetusとなる。
英語別名に Great Black-headed Gull [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) など]があり、オオズグロカモメの和名はこの英名由来と考えるとわかりやすい。オオカモメ Great Black-backed Gull の英名が紛らわしいので Pallas's Gull とされるようになったものか。
頭の黒いカモメ類では最大の種類で、全カモメ類の中でも3番めに大きい。
Kaup のドイツ語名では Rabenmoeve (略奪するカモメ類)。
獰猛性がより強いことでオオズグロカモメに別属を提案したもの (1829)。Kaup 自身は後にこの属名を猛禽類に与える方がふさわしいと考え、猛禽類のウオクイワシに Ichthyaetus 属を改めて提案した (1844) が、
先に発表したカモメ類に使われることになった (The Key to Scientific Names)。
Ichthyaetus の属名はミサゴにも提唱されたことがあり、その時の学名は Ichthyaetus piscivorus Sweeting, 1837 だった。
現在はカモメ類の方が「魚を捕るワシ」、猛禽類の方が「魚を食べるもの」と属名の意味が逆になってしまっており、Kaup 自身も考えを変更しているが学名の規則によるものでやむを得ない。
なぜ属名にワシが含まれるのかなどの意味を伝える時はこのあたりの事情も説明していただくとよいだろう (The Key to Scientific Names)。
さらにもう1種 (属) 紛らわしい名称があり、カザノワシ Ictinaetus malaiensis Black Eagle。属名の読み方は非常によく似ている ("n" があるかどうかの違い)。こちらの語源は違っていて iktin, iktinos トビ aetos ワシ (Gk)。
Liu et al. (2018) Detours in long-distance migration across the Qinghai-Tibetan Plateau: individual consistency and habitat associations
中国のオオズグロカモメの衛星追跡。青海・チベット高原を避けた渡りになっている。青海湖が重要な中継地となっていることや、他の中継地の環境などもわかる。追跡生データも提供されている。
-
ウミネコ
- 学名:Larus crassirostris (ラルス クラッシローストゥリス) 厚い嘴のカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:crassirostris (adj) 厚い嘴の (crassus (adj) 厚い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Black-tailed Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
crassirostris は rostrum の o が長母音でアクセントもある (クラッシローストゥリス)。
Larus melanurus Temminck, 1828 (黒い尾のカモメ)。
記載 フランス語名 Mouette Queue Noire (図版)。
"Fauna Japonica" 記載 ではフランス語名 le goeland a queue noire (こちらも尾の黒いカモメ)。
図版。
英名はおそらくこの学名 = フランス語名に由来。
日本の海の唯一のカモメと言えるわけではないので先に用いた (1828) この学名を保存しておく (つまり日本を冠した学名を使わない) とのこと。
"Fauna Japonica" に現れるカモメ類はこの1種のみ。採集人が関心を持たなかったためか妙に少ない。
おそらくこの学名が広く使われていたが、Larus crassirostris Vieillot, 1818 の方が早かった (原記載)。フランス名 Le Goeland de Naugasaki 何と "長崎のカモメ" だった。
どちらの学名も特徴を捉えているが Temminck の学名の方が単純だったかも。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Larus crassirostris で英名は Temminck's Gull としていた (当時は人名が広く使われていた)。
単形種。
Boyd では Gabianus crassirostris。
Gluschenko et al. (2023) Breeding birds of Primorsky Krai: the black-tailed gull Larus crassirostris (pp. 4981-5010)
ロシア沿海地方での繁殖生態。
-
カモメ
- 学名:Larus canus (ラルス カーヌス) 灰白色のカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:canus (adj) 灰白色の
- 英名:Common Gull
- 備考:
larus は短母音のみ (ラルス)。古典式では伸ばさないが冒頭を伸ばす読み方も存在するので間違いではない。ギリシャ語でも伸ばさない。
canus は冒頭が長母音 (カーヌス)。
Larus 属のタイプ種はオオカモメ Larus marinus Great Black-backed Gull で今のところ日本産種ではない。
3亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は kamtschatschensis (カムチャツカの) とされる。
日本鳥類目録改訂第7版に記載されていた亜種 heinei (ドイツの鳥類学者 Jakob Gottlieb Ferdinand Heine に由来) ニシシベリアカモメ は検討亜種に移動。
同じく第7版に記載されていた亜種 brachyrhynchus (brakhus 短い rhunkhos 嘴 Gk) コカモメ は IOC では独立種 Larus brachyrhynchus 英名 Short-billed Gull となるが、検討亜種に移動 [日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも亜種扱いのまま]。
Mew Gull の名称もあり、特にアメリカで使われていたが、アメリカの種類が別種コカモメ Larus brachyrhynchus Short-billed Gull と名付けられるようになった。
一般的には Mew Gull の名称は Larus canus complex を指して広い意味で使われる (wikipedia 英語版)。
アメリカでは馴染みの "Mew Gull" がむしろ珍鳥になったと話題になる。
Common Gull の名称にある common は「最も普通に見られる」の意味ではなく中世英語で「最も特徴がない」意味であるとのこと [茂田 (1993) Birder 7(4): 36]。
[亜種学名の問題]
kamtschatschensis の 原記載 (Bonaparte, 1857)
この時点では Gavina hine Larus kamtschatschensis と発表されていた。
Mlikovsky (2012) Nomenclatural notes on the East Asian form of the Mew Gull Larus canus Linnaeus, 1758 (Aves: Laridae)
では kamtschatschensis は nomen nudum (有効な学名でない) で、これよりも早い camtschatchensis (Bruch 1855) が正しい亜種名であるとしている。
Bruch (1855) Revision der Gattung Larus Lin.
が Mlikovsky (2012) が指している論文だが、citrirostris Schimper と camtschatchensis Bonap. を疑いないシノニムとしている (カムチャツカ)。どちらも同等の先取権があるが Bonaparte (1856) が camtschatchensis を採用したとのこと。
世界の多くのリストが kamtschatschensis を用いているが、camtschatchensis を採用しているものもある (HBW/BirdLife)。
Dement'ev and Gladkov (1951) では kamtschatschensis を用いており、Larus niveus をシノニムとしているが、これはすでに使用された学名で無効とのこと。
heinei についても Larus canus var. major Midderndorff, 1853 がシノニムとなっているが、これも使用済み (Laroides major Brehm, 1831) で無効とのこと。
wikipedia ロシア語版も kamtschatschensis を用いている。
参考: Young Guns (2017) Birder 31(1): 44-47。
AOU がこの問題を検討 (2020-2021) しており、AOS Classification Committee - North and Middle America Proposal Set 2021-A (p. 20)
Dick Schodde の見解では camtschatchensis が最も早い名前であるが、kamtschatschensis は 1934 年 (ICZN 最初の規約の1961年より以前) にすでに用いられ、広く使われている名前であるため保護される (ICZN Article 33.3.1: 誤った綴りが広く用いられている場合の規則)。
Larus canus kamtschatschensis (Bruch, 1855) とするのが適切ではないかとの提案
[Bruch (1855) が camtschatchensis を最初に与えたが誤った綴りで使われていて普及しているとの解釈。Bonaparte (1857) を採用するわけではない]。
AOU のこの提案はコカモメを別種として分離するもの。
AOU-NACC Proposals 2021 で議論が行われており、(Bruch, 1855) と変更することは ICZN 規約と合わないとの見解がある。
Bonaparte による Gavina kamchatschensis の用例は 1854 年のものがあるとのことだが、別の投稿者によればこの名称は何を表しているか十分明らかな記述でないとの指摘もある。
このような背景をみると、我々はこのまま kamtschatschensis と呼んでおいてよさそう感じ。
Larus canus var. major Middendorff, 1853 (参考) の名称もあって日本のリストに登場したことがあったとのこと。
[カモメ科の系統分類]
Cerny and Natale (2022) の分子系統樹を用いた Boyd によるカモメ科 Laridae: Gulls and Noddies の分類を示す。
カモメ科 Laridae: Gulls and Noddies
クロアジサシ亜科 Anoinae: Noddies
クロアジサシ属 Anous
クロアジサシ Anous stolidus Brown Noddy
ヒメクロアジサシ Anous minutus Black Noddy
インドヒメクロアジサシ Anous tenuirostris Lesser Noddy (インド洋と沿岸)
ハイイロアジサシ (ソライロアジサシ?) Anous ceruleus Blue Noddy (太平洋中南部)
? Anous albivitta Grey Noddy (南半球太平洋)
カモメ亜科 Larinae: Gulls
アカメカモメ属 Creagrus
アカメカモメ Creagrus furcatus Swallow-tailed Gull (ガラパゴス諸島)
ヒメカモメ属 Hydrocoloeus
ヒメカモメ Hydrocoloeus minutus Little Gull (ユーラシア)
ヒメクビワカモメ属 Rhodostethia
ヒメクビワカモメ Rhodostethia rosea Ross's Gull
ゾウゲカモメ属 Pagophila
ゾウゲカモメ Pagophila eburnea Ivory Gull
クビワカモメ属 Xema
クビワカモメ Xema sabini Sabine's Gull
ミツユビカモメ属 Rissa
ミツユビカモメ Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake
アカアシミツユビカモメ Rissa brevirostris Red-legged Kittiwake
ズグロカモメ属 Saundersilarus (Chroicocephalus 属より分離)
ズグロカモメ Saundersilarus saundersi Saunders's Gull
ハシボソカモメ属 Gelastes (Chroicocephalus 属より分離)
ハシボソカモメ Gelastes genei Slender-billed Gull
ユリカモメ属 Chroicocephalus
ボナパルトカモメ Chroicocephalus philadelphia Bonaparte's Gull
ユリカモメ Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull
チャガシラカモメ Chroicocephalus brunnicephalus Brown-headed Gull
ズアオカモメ Chroicocephalus cirrocephalus Grey-hooded Gull (南米)
? Chroicocephalus poiocephalus Grey-headed Gull (アフリカ)
アフリカギンカモメ Chroicocephalus hartlaubii Hartlaub's Gull (アフリカ南西部)
アカハシギンカモメ Chroicocephalus scopulinus Red-billed Gull (ニュージーランド)
ギンカモメ Chroicocephalus novaehollandiae Silver Gull (オーストラリア)
ハシグロカモメ Chroicocephalus bulleri Black-billed Gull (ニュージーランド)
アンデスカモメ Chroicocephalus serranus Andean Gull (南米中部西岸)
ミナミユリカモメ Chroicocephalus maculipennis Brown-hooded Gull (南米南部)
マゼランカモメ属? Leucophaeus
ハイイロカモメ Leucophaeus modestus Grey Gull (南米中南部西岸)
マゼランカモメ Leucophaeus scoresbii Dolphin Gull (南米南部、フォークランド諸島)
ワライカモメ属 Atricilla (Leucophaeus 属より分離)
ワライカモメ Atricilla atricilla
アメリカズグロカモメ Atricilla pipixcan
イワカモメ Atricilla fuliginosa (ガラパゴス諸島)
オオズグロカモメ属 Ichthyaetus
オオズグロカモメ Ichthyaetus ichthyaetus Pallas's Gull
ゴビズキンカモメ Ichthyaetus relictus Relict Gull
ニシズグロカモメ Ichthyaetus melanocephalus Mediterranean Gull (主にヨーロッパ)
アカハシカモメ Ichthyaetus audouinii Audouin's Gull (地中海周辺)
メジロカモメ Ichthyaetus leucophthalmus White-eyed Gull (紅海周辺)
ススケカモメ Ichthyaetus hemprichii Sooty Gull (アラビア周辺)
ウミネコ属 Gabianus (Larus 属より分離)
ハシブトカモメ Gabianus pacificus Pacific Gull (オーストラリア南岸、タスマニア島)
ペルーカモメ Gabianus belcheri Belcher's Gull (南米中部西岸)
ウミネコ Gabianus crassirostris Black-tailed Gull
アルゼンチンカモメ Gabianus atlanticus Olrog's Gull (南米南東部沿岸)
カモメ属 Larus
オグロカモメ Larus heermanni Heermann's Gull (北米西岸)
オビハシカモメ (クロワカモメ) Larus delawarensis Ring-billed Gull (北米)
カモメ Larus canus Common Gull
コカモメ Larus brachyrhynchus Short-billed Gull (北米北西部)
アメリカオオセグロカモメ Larus occidentalis Western Gull (北米西岸)
キアシオオセグロカモメ Larus livens Yellow-footed Gull (カリフォルニア)
ミナミオオセグロカモメ Larus dominicanus Kelp Gull (南半球沿岸に広く分布)
シロカモメ Larus hyperboreus Glaucous Gull
ヨーロッパセグロカモメ Larus argentatus European Herring Gull (ヨーロッパ)
(カスピアカモメ) Larus cachinnans Caspian Gull (主に中央アジアからヨーロッパ)
(ニシセグロカモメ) Larus fuscus Lesser Black-backed Gull (ユーラシア主に西部)
ホイグリンカモメ (ニシセグロカモメ) Larus heuglini Heuglin's Gull / Siberian Gull
オオカモメ Larus marinus Great Black-backed Gull (ヨーロッパ、北米東部)
(キアシセグロカモメ) Larus michahellis Yellow-legged Gull (ヨーロッパ)
アルメニアセグロカモメ Larus armenicus Armenian Gull (コーカサスから中東)
カリフォルニアカモメ Larus californicus California Gull (北米西部・北部)
アメリカセグロカモメ Larus smithsonianus American Herring Gull (北米)
ワシカモメ Larus glaucescens Glaucous-winged Gull
アイスランドカモメ Larus glaucoides Iceland Gull
モンゴルセグロカモメ Larus mongolicus Mongolian Gull (IOC では 14.2 より別種)
セグロカモメ Larus vegae Vega Gull
オオセグロカモメ Larus schistisagus Slaty-backed Gull
分類は複雑なグループだが、Boyd のものは IOC と大差なく、これまでも問題になっているいくつかの亜種を種としている程度である。ただし順序は IOC とかなり違っている。
Anous albivitta は Anous ceruleus から分離されたものだが、Anous ceruleus には日本産種としてハイイロアジサシの和名が与えられている。
この種をソライロアジサシ、Anous albivitta をハイイロアジサシと表記しているものがあり、英名との整合性はよくなっているが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)を採用するならばこの名前は用いられないだろう。
インドヒメクロアジサシは別名ハシボソクロアジサシ。
カモメ亜科 Larinae の最初の数属は IOC や 日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でもこの通り分離されている。これらはいずれもカモメ亜科の中でも早期に分岐してそれぞれの固有系統をなしているもの。
ズグロカモメ属の分離は日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でもすでに採用されている。
ハシボソカモメ属の分離は同じ意味で Boyd によるものだが、他の Chroicocephalus との違いが大きいのでズグロカモメ同様受け入れやすいだろう。
面白いことにロシア語でも多くのカモメ類は chajka (チャイカ、カモメ) に何かを付ける名前だが、この種は morskoj golubok (海のハトのような意味) と別名を使うことが多い (ハシボソカモメに相当する名称も使われる)。他のカモメ類と違うことを意識しているのだろう。Larus columbinus (これもハトの意味) の学名シノニムもあった。
この次の分岐がボナパルトカモメ1種で、これ以外の他の Chroicocephalus 属は分岐が新しくよくまとまったグループになっている。いわゆる大型カモメ類に比べて系統的にはむしろ古いが、比較的最近種分化を遂げたグループととらえてよい
(例えばタカ類で言えば旧世界ハゲワシの Gyps 属と新しいグループの関係に似ている。Chroicocephalus 属は種分化からの時間が短いのでよく似ていて識別が難しいことが理解しやすい。
比較的新しく生じた環境で適応放散を遂げたグループと考えると生態的にも理解しやすい部分があるかも知れない)。
小型カモメ類の多くが慣れ親しんだ Larus 属から長い属名になってうんざりしている方も多いと思うが、分子系統樹からは Chroicocephalus 属がさらに細分されるなどの恐れはないのでこの名称で固定になるだろう。
Chroicocephalus 属のタイプ種はユリカモメなので、Leucophaeus 属なども含めて全体を Larus 属に戻そうとの強い動きでもない限り属名が変わる心配はない。慣れた方がよいだろう。
分子系統樹のない時期に細分された属を統合した時とは状況が変わっていて Larus 属に統合しようとの動きは多分出ないだろう。これらの属に対して Larus 属の名称が残っているのは古いチェックリストに限られている。
Chroicocephalus poiocephalus は Chroicocephalus cirrocephalus から分離されたもの。分離前の英名は Grey-headed Gull だった。IOC 14.1 では亜種扱い。
Chroicocephalus scopulinus はギンカモメから分離されたもの。IOC 14.1 では亜種扱い。
ニュージーランドでは分離される以前から Red-billed Gull の名前で呼ばれており、アカハシギンカモメの名称がすでに使われているためそれを用いた。アフリカギンカモメも (より早い時期に) ギンカモメから分離されたもの。
アンデスカモメは英語別名 Mountain Gull でアンデス山脈の湖沼で繁殖するとのこと (コンサイス鳥名事典)。wikipedia 英語版によれば繁殖地は標高 3000-5300 m が多いが、分布南部では 1200 m ぐらいのこともある。山岳性カモメと言っても不自然でない [日本で山にカモメという話は 桐原 (2005) Birder 19(2): 59 で書かれていたように普通は間違っているが]。
アンデス山脈のこのような高地は天体観測の適地であるため、各国の多くの天文台が設置されている。アタカマ天文台 (東京大学、標高 5640 m) もその一つで、大学院生が現地調査に向かったりするわけだが、砂漠のような山地で「生き物の気配すらない」とブログに書こうとしたら何と 鳥! と驚かされたと聞いたことがある。
捕食者もほとんど生息しない条件なので環境は過酷だが有利に働いたよう。
リンク先から現地風景を想像していただけるのはないだろうか。
Leucophaeus は日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではワライカモメ属になるが、Boyd はワライカモメなどを Atricilla 属に分離しているため名称が変わる。タイプ種のマゼランカモメを用いた。
広義の Leucophaeus 属でも単系統をなしているのでやや細かく分けすぎかも知れない。地理的分布を考えたものと思われる。
オオズグロカモメ属は日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ですでに使われている。
ウミネコ属 Gabianus が分離されるのは Larus 属との違いが大きいため妥当でわかりやすく思える。この場合のウミネコ属は環太平洋に分布して局地的な固有種のグループとなっている。ウミネコ属をカモメ属に含めても単系統なのでこれも単系統性の要請からの分離ではない。
少し古い分類 (コンサイス鳥名事典など) でも使われており書籍によっては目にすることがあるかも知れない。
ハシブトカモメの和名の由来は英名の別名 Large-billed Gull による。
カモメ属、特にセグロカモメ類の分類は分類学者やリストによっても異なり、種境界の問題は解決が難しいと思われるのでここでは Boyd (IOC に近い) のリストに形式的に対応する和名を振ってある。
種の順序も Cerny and Natale (2022) の分子系統樹で近接しているので (識別が難しかったり交雑が多い理由) 将来データが揃えば順序も入れ替わるだろう。Boyd はこの分子系統樹の順序をそのまま使わず多少入れ替えている。
分子系統樹ではアイスランドカモメやオオセグロカモメが最後に並んでいて大型化への進化方向も感じられるが現状のデータではまだ誤差の範囲だろう。
オオカモメはカモメ科で最大種とのこと (コンサイス鳥名事典)。
キアシセグロカモメの名前は日本鳥類目録改訂第7版で Larus cachinnans に対しても使われた名称であるが現在の英名との対応は悪くなっている、Caspian Gull から作られたと思われるカスピアカモメの名称とともにかっこに入れてある。
ホイグリンカモメは日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではニシセグロカモメの亜種の扱いだが記録されている亜種なので緑で表示してある。Boyd のリストの扱いを用い、ホイグリンカモメ以外の亜種が記録されていなければニシセグロカモメは未記録の種になる。
モンゴルセグロカモメは日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではセグロカモメの亜種の扱いだが記録されている亜種なので緑で表示してある。
ミナミオオセグロカモメ Larus dominicanus Kelp Gull の種小名はドミニカとは関係なく、白黒の衣装を表す Dominican, Jacobin が由来 (#クロシロカンムリカッコウの備考参照)。
アフリカ亜種の vetula は Larus vetula Cape Gull と分離されることもある。分離された場合の和名は見当たらないが アフリカオオセグロカモメ のような名称は考えやすい。
新規属名の由来は Gelastes gelastes 笑う (Gk)。ハシボソカモメに対して von Keyserling & Blasius (1840) が用いた種小名に由来。この属名は Bruch (1853) がハシボソカモメに対して提唱した。
Atricilla はワライカモメの種小名から。Bonaparte (1854) が属名として用いた。The Key to Scientific Names でもこれら2属の名称は近年認識されて再度使われるようになっている記述がある。
Gabianus はフランスのプロバンス地方のカモメを指す名前 Gabian に由来。Bruch (1853) が最初にハシブトカモメに対して用いた属名。
アカメカモメは英名と和名の印象がずいぶん違うが、カモメ類・海鳥の中で世界で唯一の完全夜行性の種類とのこと。眼も目立っていて普通に使われる和名の特徴につながっているのだろう。エンビカモメ [週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 105 p. 4 で用いられていた] の別名もありこちらは英名に対応する。
しかし眼球や眼窩の測定値は他のカモメ類と際立った違いはなかったとのこと: Iwaniuk et al. (2010)
Morphometrics of the eyes and orbits of the
nocturnal Swallow-tailed Gull (Creagrus furcatus)。
かつては眼が大きい、あるいは立体視に適した眼の配置になっていると記述されていたこともあったがいずれの特徴も有意に確認できなかったとのこと (著者はそこまで書いておらず、実測データ不足が原因としているが、かつてはフクロウ類に似た結論を暗黙に導いていたのかも知れない)。ただし形態データだけから立体視の能力がないとは言い切れず、行動実験なども必要だろうとのこと。
この論文ではマゼランカモメ Leucophaeus scoresbii Dolphin Gull の眼の小ささも謎であると書かれている (補足: 瞳孔も小さく解像度もあまり高くないように見える)。
カモメ類はもともと薄明時間帯に活動的で、他の種類 (例えばフクロウ類やヨタカ類) ほど昼行性と夜行性で眼の構造に違いが必要ないのかも知れないとある。
音声やディスプレイは他のカモメ類とは大きく異なっていてミツユビカモメ、クビワカモメに似ているとのこと。ガラパゴス諸島のほぼ固有種だがコロンビア沿岸の小さな島でも繁殖し、エクアドルやペルーに渡るとのこと (wikipedia 英語版)。英名に対応したエンビカモメの名称もある (コンサイス鳥名事典)。
中村 (1998) Birder 12(1): 51-54 にガラパゴスのアカメカモメの生態の記事がある。夜間に船の明かりに集まった魚群に集まり、魚ではなく魚群の食べる食物を食べるとのこと。
グンカンドリ sp. がアカメカモメを追いかけて食物を奪う写真も掲載されている (p. 54)。
アカメカモメが夜行性なのはこのような盗食を避けるためか、アカハシネッタイチョウ Phaethon aethereus Red-billed Tropicbird が高空を飛ぶのも同様の理由からかとの議論が述べられている。
[カモメ類の視力]
カモメ類の視力については (キアシセグロカモメ) Larus michahellis Yellow-legged Gull の研究 [Victory et al. (2021)
Cone distribution and visual resolution of the yellow-legged gull, Larus michahellis (Naumann, 1840)]
があり、視細胞の密度からの推定ではかなり高い数字が出ている。
フルマカモメでも高めの値が出ているが、海鳥でもコシジロウミツバメやマンクスミズナギドリではこれらカモメ類に比べて 1/5 ぐらいのかなり低い値になっている。
これらのカモメ類は小型昼行性猛禽類に近い程度の値で、視力の面では昼行性猛禽類に似た眼を進化させているようである。Mitkus の学位論文 (2015) Spatial Vision in Birds: Anatomical investigation of spatial resolving power
も見られるので紹介しておく。夜行性のヨーロッパムナグロの大きな眼を収めるための余分な構造物の存在や、羽毛を取り去ったアカトビの眼がどれほど大きいかを示す写真も見られる。
ただし#ゴビズキンカモメのゲノム解析のような報告もありカモメ類でも生態次第かも知れない。
[チャイコフスキーとの関連]
カモメ (総称) のロシア語名は chajka (チャイカ) で、これはチャイコフスキーの名前の由来になっている。wikipedia ロシア語版をみると、系譜では本当に「カモメ」だったそうで、ピョートル・フョドロビッチ・チャイカがもとの名前だった。
学校に通うようになって姓の「品をよく」するためにチャイコフスキーと改めたとのこと (「ただカモメ」の名前では学校でかっこ悪かった?)。[この項目は日本野鳥の会京都支部 2023 年 4/5 月号の記事に刺激を受けて調べたものである。日本野鳥の会京都支部の情報に感謝する]。
カモメ類のやってくるところはウクライナにたくさんあるようで、地名 (から派生して姓名) でカモメにちなむ人名がたくさんあるとのこと。
chajka (チャイカ) の由来は古スラブ語の「サイカ」が由来で、声に由来すると考えられているとのこと。
[カモメの漢字と和名の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 105 VII (藤堂) によれば 區 + 鳥 で、區はク・オウと読み、擬声音を表したもの。區 = 区 で新字体では鴎となる。
藤堂氏の解釈ではカモメの日本語は 鴨 + 女 由来ではないかとのこと。中国の黄海沿岸でカモメが若い女性の化身との民話があるとのこと。
Birder 編集部 (2023) 37(12): 27 は水の上に白い泡のように浮かんでいる文字由来説を紹介している。wiktionary をチェックしておくと 區 + 鳥 は形声文字で古代中国語 *qo: 區 との解説になっている。日本語では呉音で "う"、漢音で "おう"。
ベトナム語 (Han character) でも同じ文字を用い、au と音を受け継いでいる。
wiktionary は西洋研究から音声重視の傾向があり、語源はあまり知られていないが音声由来が考えやすいとのこと。
英語の gull の方も OED でチェックしておくと、1430 年ごろの Gullys の用例があるとのこと。初期の gull および類縁語が何を指していたかは多少怪しく、他の水鳥も含まれていた可能性もあるらしい。語源はよくわかっておらずウエルシュ語の gwylan などからの借用とも考えられるが結局はよくわからない。
フランス語の goeland に関連のあるブレトン語 goelann = コーニッシュ語 guilan 由来とも考えられるとのこと。
ドイツ語の Moewe は遡るとゲルマン祖語の *maiwaz とのことだが、ゲルマン語族以外にも存在することからインド・ヨーロッパ語族起源でない可能性が高いとのこと。単に音を真似たものとも考えられるとのこと。英語の mew (Mew Gull に使われる) にも関連がある (wiktionary)。
-
ワシカモメ
- 学名:Larus glaucescens (ラルス グラウケースケーンス) やや青灰色のカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:glaucescens (adj) やや青灰色の (glaucus (adj) 青灰色の) 当時の学名で Larus glaucus = シロカモメ に対比させてやや青灰色
- 英名:Glaucous-winged Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
glaucescens は -ce- の e が長母音でアクセントもここにある。語末も伸ばしてもよい (グラウケースケーンス)。伸ばさなくてもよい。
-escens は "〜のようになっている" を追加する語尾で、動詞語尾 -esco (〜のようになる) の分詞形 (参照)。英語では -ing や "〜に覆われた" のような訳語が対応する。
色彩を語幹としてこの形が多くの学名に用いられている。ほとんど学名のみに用いられる単語。
最初の e が長母音か短母音かは単語による。-esco は -eo + -sco の合成で e と o に長音記号があるので文字通り読めば グラウケースケーンス の方が綴りを反映した読み方になるだろうか。こちらを採用した。
brunnescens は短母音で、brunneus 由来で -eo の e を追加する必要がないためそのままの発音となったものか。この単語の場合も最後の e には長音記号があり伸ばす場合はここを伸ばす。
単形種。
原記載 (Naumann 1840) で基産地は北米。
#アイスランドカモメの備考のように、当時はシロカモメの学名に Larus glaucus が用いられており、外套 (原文 Mantel) の色の比較でシロカモメの方が原文 viel heller oder weisslicher (ずっと明るいあるいは白っぽい) としたもの。
その後シロカモメの学名が先取権のあるものに変わったため関連がわかりにくくなってしまった。中途半端に長い語尾に見える種小名の由来となる。
外套の色の比較だったために英名はこちらを "Glaucous-winged Gull" と訳し分けたようでシロカモメの英名の "Glaucous Gull" と大変よく似たものになっている。当時の種小名ラテン語はほとんど同じような意味で英語ではうまく訳し分けられなかったものと想像できる。
ということで、シロカモメ、アイスランドカモメ、ワシカモメの3種の学名は一緒に把握しておくとよさそう。
-
シロカモメ
-
アイスランドカモメ
- 学名:Larus glaucoides (ラルス グラウコイーデース) シロカモメに似たカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:glaucoides 当時の学名で Larus glaucus = シロカモメ に似た
- 英名:Iceland Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
glaucoides は -oides がギリシャ語由来語尾で i, e が長母音。前者にアクセントがある (グラウコイーデース)。
glaucoides は glaukodes 青っぽい灰色の、銀色の (Gk) とも解釈できるがギリシャ語から直接命名されたものではなく、以下のような経緯から。
Larus glaucoides の学名は Larus glaucus Bruennich, 1764 に似たの意味とのこと。この種は現在はシロカモメ Larus hyperboreus と判定されているとのこと。glaucus に対応してドイツ語で Graumeve 灰色のカモメ類 の概念があった (The Key to Scientific Names の glaucoides の項目より)。
同じ学名 Larus glaucus Pontoppidan, 1763 の用例があり (資料)、すでに使われた学名として Bruennich (1764) の学名は無効となったものらしい。
Pontoppidan (1763) の用例が見つかるまで時間がかかっているはずで、Larus glaucus の学名はかなりの期間使われていたと想像できる。
Pontoppidan のものはカモメ (Larus canus) と同定されたようで、どちらも先取権のない学名となって結局使われなかった。
現在の英名は Glaucous Gull の名称となっている。英名とアイスランドカモメの種小名に命名の歴史が残っている。
さらに Larus leucopterus Faber, 1822 (参考) の学名もあり、Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" はこれを用いていた。和名は Hajiro-kamome となっており、学名 (または他言語名) から訳したものであることが見てとれる。
英語の glaucous はあまり馴染みがなく綴りも覚えにくいが、同一語源の単語に glaucoma (緑内障。ラテン語由来) がある。古い病名で「あおそこひ」と呼ばれた。関連させておくと語尾が少し違うだけなのでおそらく覚えやすい。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 glaucoides 亜種アイスランドカモメ、thayeri (アメリカ鳥類学者 John Eliot Thayer に由来。北米の亜種) カナダカモメ (カナダカモメの項目参照)、及び亜種不明とされる。
日本鳥類目録改訂第7版にリストされていた亜種 kumlieni (アメリカ博物学者で探検家の Aaron Ludwig Kumlien に由来) クムリーンアイスランドカモメは検討亜種に移行。この亜種は glaucoides と thayeri の雑種 (別種とされていた時代) ともされるが、IOC では亜種として取り扱っている。
初野 (2004) Birder 18(1): 47-49 アイスランドカモメの識別の記事がある。
カナダカモメとアイスランドカモメを例として氷河期におけるレフージア、種の形成や遺伝子浸透を扱った解説が NerdBirds (2018) Birder 32(11): 44-47 にある。
-
(旧名種カナダカモメ) アイスランドカモメ亜種カナダカモメ (アイスランドカモメの亜種となった)
- 第8版亜種学名:Larus glaucoides thayeri (ラルス グラウコイーデース タイエリ) セイヤーの青っぽい灰色のカモメ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Larus thayeri (ラルス タイエリ) セイヤーのカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 第8版種小名:glaucoides glaukodes 青っぽい灰色の、銀色の (Gk)
- 第7版種小名:thayeri (属) セイヤー John Eliot Thayer (アメリカの鳥類学者) の
- 第8版亜種小名:thayeri (属) セイヤー John Eliot Thayer (アメリカの鳥類学者) の
- 英名:Thayer's Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
thayeri は原語を無視してラテン語風に読むと "タイエリ" と推定される。この i はヤ行の音だが便宜上このように表記した。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。Thayer's gull とするか、アイスランドカモメの亜種とするかはさまざまな論争がなされたが、アメリカ鳥類学会は 2017 年に独立種であるとの従来見解を取り下げ、アイスランドカモメの亜種とした。海外の多くのチェックリストもこの立場である。この場合の学名は Larus glaucoides thayeri となる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でもこの見解を採用。
Working Group Avian Checklists も version 0.04 までの時点でアイスランドカモメの亜種の扱い。
-
セグロカモメ (AviList ではモンゴルセグロカモメを分離)
- 第8版学名:Larus vegae (ラルス ウェガエ) ヴェガ号のカモメ (IOC も同じ。さらに分離あり)
- AviList 学名:Larus vegae (ラルス ウェガエ) ヴェガ号のカモメと Larus mongolicus (ラルス モンゴリクス モンゴルのカモメ
- 第7版種学名:Larus argentatus (ラルス アルゲンタートゥス) 銀で飾られたカモメ
- 第7版亜種学名:Larus argentatus vegae (ラルス アルゲンタートゥス ウェガエ) ヴェガ号の銀で飾られたカモメ (代表的亜種。他亜種あり)
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 第8版種小名:vegae スウェーデンの北極探検家 Nils Adolf Erik Baron Nordenskjold が探検に用いた船の名前 (Vega) から
- AviList 種小名:vegae スウェーデンの北極探検家 Nils Adolf Erik Baron Nordenskjold が探検に用いた船の名前 (Vega) からと mongolicus モンゴルの
- 第7版種小名:argentatus (adj) 銀で飾られた (argentum -i (n) 銀 -atus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:[旧英名総称 Herring Gull], AviList: Vega Gull と (モンゴルセグロカモメ) Mongolian Gull (備考参照)
- 備考:
larus は#カモメ参照。
vegae の発音はよくわからないが、通常使われる "ヴェガ" の名称から短母音とした (ウェガエ)。"ウェーガエ" と伸ばしてもアクセント位置は変わらないのでどちらでもよい。
vega の語源 (特に恒星の名称) はアラビア語で "落ちる (ワシ)"。アラビア語の "落ちるワシ" の表現から "落ちる" 部分のみが使われたもの。アラビア語の "落ちる" には急降下して襲いかかる (英語 pounce) の意味もある (wiktionary)。
argentatus は -atus の冒頭が長母音でアクセントもある (アルゲンタートゥス)。
mongolicus は は短母音のみで -go- がアクセント音節 (モンゴリクス)。
分割のため第7版学名は代表的亜種まで記した。
セグロカモメ類 (英語通称 Herring gull complex) の分類には諸説あり、現在では (和名なし、元セグロカモメに含有) Larus argentatus European Herring Gull, アメリカセグロカモメ Larus smithsonianus American Herring Gull, セグロカモメ Larus vegae Vega Gull の3種に分割するのが一般的である。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱いとなっている。この場合現在のセグロカモメの学名は Larus vegae となる見通し。海外の分類でも Larus vegae を認めるものが主流。
Larus vegae は2亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は基亜種 Larus vegae vegae 亜種セグロカモメ、Larus vegae mongolicus (モンゴルの) モンゴルセグロカモメ。
日本鳥類目録改訂第7版にリストされていた亜種 smithsonianus (アメリカの James Smithson に由来) アメリカセグロカモメ は検討種に移行。
IOC では独立種 Larus smithsonianus 英名 American Herring Gull で日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱い。
2024.7.25 IOC (14.2) が(モンゴルセグロカモメ) Mongolian Gull Larus mongolicus を分離。Working Group Avian Checklists も version 0.04 より同様。
Mongolian Gull の名称はかつて#ゴビズキンカモメの英名に使われたことがあった。
AviList では、
4608 1136 Four species are recognized in the Larus argentatus complex based on a combination of genetics, plumage, and vocalizations: polytypic L. argentatus (including argenteus); monotypic L. smithsonianus; monotypic L. vegae; and monotypic L. mongolicus. Mitochondrial and nuclear DNA data consistently support separation of L. smithsonianus from L. argentatus (Liebers et al. 2004; Cerny & Natale 2022; Sternkopf et al. 2010; Sonsthagen et al. 2016), an arrangement also supported by differences in adult and juvenile plumage, and apparently vocalizations. Species L. vegae is sometimes considered a subspecies of L. smithsonianus but differs phenotypically at a level more consistent with species status in this complex. Finally, L. mongolicus was previously placed in L. cachinnans but is phenotypically distinct from that species and from L. vegae with which it is sometimes aligned; its vocalizations also appear to be the most distinctive of the species formerly placed in L. argentatus. A comprehensive genomic DNA analysis would be informative given the complex demographic and biogeographic history of this group.
mongolicus を cachinnans に含める従来の扱いは適切でないことが判明。
第8版亜種名はモンゴルセグロカモメだが、もし独立種扱いとなればモンゴルカモメとなる可能性もあるため ( ) に入れておいた。
自分自身は introgession の大きい種の境界はあまり気にしていないが、世界のバーダーの関心はこれらが分離されるかどうかにあるようで AviList の判断をそのまま含めておいた。
Herring gull complex の 遺伝学的研究 (生物地理学や遺伝子浸透など) については例えば Sternkopf et al. (2010) Introgressive hybridization and the evolutionary history of the herring gull complex revealed by mitochondrial and nuclear DNA
(ただしヨーロッパと北米中心)。
セグロカモメの衛星追跡 Gilg et al. (2023) Flyways and migratory behaviour of the Vega gull (Larus vegae), a little-known Arctic endemic。
Vega gull (Larus vegae) - GPS - Russia South Korea Japan で経路が見られる。
カモメ類全体の系統研究では、Viviane Sternkopf の学位論文 (2010, ドイツ語) も参考になるだろう。
和名で一番気になる点は "セグロカモメ" なのに他のカモメ類の方がもっと黒いのがあるではないか。名前がおかしいと文句を言いたくなるところだろう。これは分類の変遷に伴ってかつてはニシセグロカモメの亜種だった時代があったことが由来ではないかと想像している。
Larus fuscus Linnaeus, 1758 はもちろん非常に古い学名なので、関連する種類を亜種とすれば種学名は必ず Larus fuscus になる。fuscus = 黒ずんだ なので英名が Black-backed Gull となって不思議でない。
そのように考えるとかつて同種時代のものが分けられて ニシセグロカモメ (Lesser Black-backed Gull)、オオカモメ (Great Black-backed Gull) と呼び分けるようになった経緯が理解しやすい。
ちなみにセグロアジサシの種小名にもほぼ同じ意味で fuscatus が使われているので、当時はこの学名を "セグロ" と表現するのが一般的だったのでは (?)。
大型カモメ類を種分割する方法は現在も過去も議論のあるところで、たまたま現在の ヨーロッパセグロカモメ Larus argentatus European Herring Gull、当時は広義セグロカモメ (Herring Gull) の亜種であった断面を見ていたために和名と英名が対応していないように見えると思えばわかりやすい。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Larus vegae の学名となっており、これまた 100 年を経て現在の学名が同じものに戻ることなる。
別学名として Larus cachinnans (カスピアカモメに相当) と Larus occidentalis (アメリカオオセグロカモメ) が与えられており、これらと同種と考えられた時代があったことがわかる。
現在のニシセグロカモメでは基亜種 fuscus (最初に記載された亜種。すなわち種小名にもなる) がニシセグロカモメの亜種の中でも非常に暗色で、これならば "セグロカモメ" の名称にふさわしいように見える。基亜種の特性が種全体の特性を必ずしも表していないために種小名の訳名が種全体にあまりふさわしくない例として#オオアカゲラもある。
ニシセグロカモメとセグロカモメが同種であった時代に、当時使われていた英名や学名をもとに "セグロカモメ" の和名が与えられた可能性が十分考えられる。
基亜種 fuscus がどの程度黒いかは写真を確認していただくこととして、さらにおまけとして基亜種 fuscus の分布はどこなのですか? と疑問も出ると想像できる。"Collins Bird Guide" を見るとこの亜種には "Baltic Gull" の別名があり、越冬地も Linnaeus (1758) の記載からちょっと遠い印象を受けるのである。
Linnaeus (1758) の時代は基産地といっても結構曖昧で、この種についてはヨーロッパとしか記載されていない。ではヨーロッパに複数あるどの亜種がこの名前を引き継ぐのか問題になるが、このような場合は後に基産地をスウェーデンに限定する扱いがとられ、スウェーデンで繁殖する個体群が名前を引き継ぐことになった。
スウェーデンの個体群が英国などの個体群よりより東方に渡るため、Baltic Gull の名称も適切なものとなり、基産地がスウェーデンに限定されたため、"たまたま" 最も黒い亜種がニシセグロカモメを代表することになったため、色彩の印象の乖離感がより高まったと言えるだろう。
手塚治虫氏が「鳥人大系」の中でわざわざニシセグロカモメを指そうとして Larus fuscus のカナ表記を使ったのではなく、比較的最近と言える当時の図鑑にこの学名が出ていたのでは (?)。
herring の意味はニシンを指す。中世英語 hering 古英語 haering で西ゲルマン祖語の *haring に遡るがそれ以上の語源は不明とのこと (wiktionary)。
[種小名の由来]
種小名 vegae はスウェーデンの北極探検家 Nils Adolf Erik Baron Nordenskjold が探検に用いた船の名前 (Vega) から (The Key to Scientific Names)。
原記載 Larus argentatus Bruenn. var. Vegae となっている (Vega-Exped. Vetensk. Iakttag. [Nordenskiold], Palmen, 1887)。チュクシ (チュコト) 語で amnunkin-yayak, yayak の名称も紹介されている。
Palmen によるシベリアの鳥類についての 270 ページの資料の一部で、その前に Stuxberg による北極海のノバヤゼムリャ島の動物相の 240 ページ近い資料も含まれている。
関心のある方には大変興味深い一次資料だろう。
「ヴェガ号航海誌」(フジ出版 1988) もあるが上記の翻訳ではないと思われる。
wikipedia 日本語版では船はヴェガ号、1872 年にドイツのブレーマーハーフェンで建造された特注の捕鯨船で、スウェーデン王国の科学者アドルフ・エリク・ノルデンショルド が提督として乗船し 1878 年出港。
北極海航路 (北東航路) の制覇に大航海時代以来史上初めて成功した船であるとある。スウェーデンの科学史上でも高く評価されている。日本にも寄港している [wikipedia 日本語版/英語版。
Journal, gefuehrt am Bord des Dampfschiffes GROENLAND, Captain Ed.
Dallmann, auf der Reise von Hamburg auf d. Walfisch u. Robbenfang an
den Kuesten von South Shetland Islds. Coronation Isld. Trinity Land &
Palmerland, gefuehrt von Rud. Kueper, Hamburg にドイツ語/英語資料あり。
ロシアに渡ったアイヌ資料の歴史的経緯について: A.V.グリゴーリエフのアイヌコレクションを追跡する (鈴木建治 2012) にも関連情報がある]。
最初は Jan Mayen (アイスランド北の北極海の島ヤンマイエン島で人名から作られた名前。捕鯨船時代は基地として使われた) の名前で 1873 年に進水したが、科学者 Nordenskiold が購入して Vega の名前で北極航路開拓と調査に使われたとある。
Vega の意味は簡単に見た範囲ではこれらには記されていないが、wiktionary によると古ノルド語 vega があり、運ぶ、動く、重さを測る (英語 weigh に対応) などの意味が出ている。スウェーデン語でも同系の動詞 vaga (最初の a にウムラウト) があり、英語 weigh に対応する意味か、バランスをとるの意味とのこと。
いずれも船にふさわしい意味に思えるが、有名な恒星の Vega あるいは別の名称にも掛けているかも知れない。
Larus vegae の種小名を和訳する時は (日本でも知られた北極探検船の)「ヴェガ号の」としておくとよさそうである。
これだけの探検なので他にも学名に残っているかと思うが、意外にも鳥の学名ではセグロカモメに使われるもののみのようである。
ヤクーチア北東部のセグロカモメの繁殖: Degtyarev (2025) Materials on the biology of the East Siberian gull Larus vegae in north-eastern Yakutia (pp. 1355-1360)。ツンドラ地域では最も数の多い種類でありながらほとんど調べられていない。
-
(旧名種キアシセグロカモメ) セグロカモメ亜種モンゴルセグロカモメ (セグロカモメに含まれ、第8版ではキアシセグロカモメの和名は消滅。リスト次第で種扱い)
- 第8版亜種学名:Larus vegae mongolicus (ラルス ウェガエ モンゴリクス) モンゴルのヴェガ号のカモメ
- AviList 学名:Larus mongolicus (ラルス モンゴリクス) モンゴルのカモメ (種扱い)
- 第7版学名:Larus cachinnans (ラルス カキンナーンス) 大笑いのような声のカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 第8版種小名:vegae スウェーデンの北極探検家 Nils Adolf Erik Baron Nordenskjold が探検に用いた船の名前 (Vega) から
- AviList 種小名:mongolicus モンゴルの
- 第7版種小名:cachinnans (分詞) 大笑い (cachinno 大笑いする)
- 第8版亜種小名:mongolicus モンゴルの
- 英名:(Yellow-legged Gull)。AviList: Larus cachinnans Caspian Gull と Larus mongolicus Mongolian Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
cachinnans は語末の a が長母音。アクセント音節は -chin- にある (カキンナーンス)。長音は動詞の変化語尾由来。
mongolicus は短母音のみで -go- がアクセント音節 (モンゴリクス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Larus vegae の1亜種 Larus vegae mongolicus となり、Larus cachinnans は削除されている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Larus vegae mongolicus の和名はセグロカモメの亜種キアシセグロカモメのまま、とあるが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではセグロカモメの亜種モンゴルセグロカモメに変更されている。モンゴルカモメまたはモンゴルセグロカモメ (英名 Mongolian Gull) の呼び名も使われるが同じものを指す。
IOC 14.2, AviList では Larus cachinnans Caspian Gull (単形種) と Larus mongolicus Mongolian Gull (単形種) いずれも種扱いで Larus vegae は単形種の扱い。
氏原 (2007) Birder 21(1): 46-49 に「モンゴルカモメってどんな鳥?」の記事があり、セグロカモメとの識別点が述べられている。
この中で北方で繁殖するカモメほどずんぐりした体型で、暖かい地域で繁殖するものは細長い体型であると述べられており、ハシボソカモメを後者の例として挙げている (#ハシボソカモメの備考参照)。セグロカモメより南方で繁殖するモンゴルカモメにも当てはまるとのこと。
現在の分類で "キアシセグロカモメ" の名称に相当する Larus michahellis Yellow-legged Gull は 20 世紀に分布を拡大し、スペインでは他種に影響を与えている:
Ballesteros-Pelegrin et al. (2025) Landscape, Environmental, and Socioeconomic Impacts of an Invasive Bird Species: The Yellow-Legged Gull (Larus michahellis) in the Natural Park Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia, Southeastern Spain)
人為的外来種ではないが invasive species の表現となっている。他の水鳥を守るため個体数のコントロールも行われいるが、人が出すごみや残飯などにも依存しており、それらを減らす必要がある。
-
オオセグロカモメ
- 学名:Larus schistisagus (ラルス スキスティサグス) スレート色の外套のカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:schistisagus schistus スレート < 分離した (lapis schistos 分離した石 sagos 外套 Gk)
- 英名:Slaty-backed Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
schistisagus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。その場合 -ti- がアクセント音節と考えられる (スキスティサグス)。
ラテン語 sagus (sagum の古い形) があり、通常短母音。別語源の sagus があり (意味も違う) こちらは a が長母音。由来が後者ではないため -sagus の a は伸ばしたりアクセントを置かないのがよいと思われる。
単形種。
-
ニシセグロカモメ
- 学名:Larus fuscus (ラルス フスクス) 黒ずんだカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:fuscus (adj) 黒ずんだ
- 英名:Lesser Black-backed Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
fuscus は短母音のみ (フスクス)。
heuglini はラテン語風に読めば "ヘウグリニ"。積極的に伸ばす理由は見当たらないが読みにくい場合は "ヘウグリーニ" も許容されるのではと考えられる。
ドイツ語以外では "ホイグリン" とはなかなか読まれないと想像できるので英語読み (人名は ヒューグリン) でも構わないかも知れない。ちなみにロシア語やウクライナ語転記では "ホイ" ではなく "ゲイ" となっていて "オ" の音は含まれない。
heu- で始まる単語は英語でも限られていて計算機用語などで使われる heuristic 程度。英語読みでは heu- は "ヒュー" が標準的と思われる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。Larus fuscus のうち亜種 heuglini ホイグリンカモメのみが日本で確実に記録された亜種となっている。亜種名 heuglini はドイツの鉱山技術者・鳥類学者の Martin Theodor von Heuglin に由来。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では種 Larus fuscus の和名はニシセグロカモメとしている (ホイグリンカモメの名称は亜種にのみ現れ、亜種ニシセグロカモメの名称は亜種名には現れない)。
ホイグリンカモメに Larus heuglini の種名を用いられることもあるが、現在は通常亜種名として扱われている。
Working Group Avian Checklists も version 0.04 で亜種扱い。
さらに "タイミルセグロカモメ" (英名 Taimyr gull) の名称が使われ、Larus fuscus taimyrensis の学名、またこの亜種名から "taimyrensis" が使われることがあるが、ホイグリンカモメとセグロカモメの雑種の可能性もあるとのこと
[Olsen and Larsson (2003) Gulls Of North America, Europe, and Asia]。 Birds Korea の 解説 (2003) 、 Birds Korea の "taimyrensis" についての補足 (2011) では雑種ではないと考えている。
同資料では Larus fuscus barabensis が定期的に韓国に飛来しており、東アジアでホイグリンカモメのように見えるものの大半は "taimyrensis" であると述べている。ちなみに eBird では 2023 年段階でこれを Larus fuscus taimyrensis としている。
Avibaseは Larus fuscus と Larus heuglini を分けた概念にしているが、heuglini は後者の亜種としている。主要チェックリストで Larus fuscus taimyrensis の分類概念を用いているのは eBird のみ。
日本鳥類目録改訂第7版では "taimyrensis" の扱いは保留とされた。
種として分離するかどうかはともかく、ヨーロッパの研究者にとっては東アジアの個体群を Siberian Gull と呼ぶのは地理的に納得しやすいだろう。フランス語などいくつかの言語が対応する名称を用いている。タイミル半島もシベリアの一部と考えれば Siberian Gull の亜種とするのも納得できないではない。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種 graellsii (カタルーニャの動物学者 Mariano de la Paz Graells y de la Aguera に由来)、intermedius (中間の)、barabensis (ロシアのシベリア西部 Baraba ステップに由来) カザフセグロカモメが検討亜種となっている。前2者の和名はまだ与えられていない。
アメリカでは鳥の一般名から人名を排する動きがあり、ホイグリンカモメについても議論が出ている Yet another thread on eponyms... But this one might actually be fun!。
この機会に実態にふさわしくないカモメ類のアメリカの英名も検討してはどうかなど提案も出されている (誰もがそうだと思っているだろうユリカモメの英名など古い名称由来で今ひとつ合わないものなど)。
ホイグリンを地域名で表すのは難しいなあ、などの議論が出ている。
"Siberian Gull" ならばホイグリンカモメと vegae (日本のセグロカモメの主要亜種) の両方にあてはまってしまう、など。
-
ハシブトアジサシ
- 学名:Gelochelidon nilotica (ゲローケリドーン ニーローティカ) ナイル川の笑うツバメ(アジサシ)
- 属名:gelochelidon (合) 笑うツバメ (gelao 笑う Gk、chelidon ツバメまたはアジサシ Gk)
- 種小名:nilotica (adj) ナイル川の (neilos ナイル川 Gk、-icus (接尾辞) に属する)
- 英名:Gull-billed Tern
- 備考:
gelochelidon は外来語由来の合成語でしかも短縮されているので発音はわからないが、ギリシャ語 chelidon は o が長母音でここは伸ばすのがよいと考えられる。gelao の o は長母音で、-ao- を1文字にまとめたと考えればこの o も長母音がふさわしいかも知れない。-che- がアクセント音節と考えられる (ゲローケリドーン)。
nilotica は最初の i と o がいずれも長母音で -lo- がアクセント音節 (ニーローティカ)。-icus (接尾辞) に属する は短母音。
アジサシ類はドイツ語で Seeschwalbe (単数形) で海のツバメを意味する。属名に現れる chelidon はこれを意図して使われている 。この属のドイツ語名は Lachseeschwalbe (笑う海のツバメ)。Latham (1785) はこの種を "Egyptian Tern" と呼んだ (The Key to Scientific Names)。
Gelochelidon 属は Brehm (1830) が提唱したもので、当時の学名 Gelochelidon meridionalis 1種を指したもの。これはハシブトアジサシを指すものと判定されタイプ種となった。meridionalis は "南方の" の意味 (The Key to Scientific Names)。
Laridae (BirdForum 2025.3) によれば、より早い Viralva Stephens, 1826 の属名があり、ハシブトアジサシをタイプ種とする定義があるのになぜこちらが用いられないのか議論があった。
分子系統解析によって系統が分離され、分離された系統の種をタイプ種とする過去の属名を復活させる必要があって生まれた話題。Brehm (1830) の定義は1種のみを指して明瞭で疑いの余地はなかった。
Viralva は特に意味のあるものではなく当時流行の造語だったらしい。Stephens は新提案の Viralva 属に5種と ? 付きで2種を含め、そのうち1種がハシブトアジサシだった (The Key to Scientific Names)。(無意味な造語の背景は意味のある属名を思いつくのがそろそろ難しくなってきていた時期だろうか)。
Viralva 属のタイプ種は後に定められたが、Gray (1840) はハシブトアジサシを採用、Strickland (1841) はハシグロクロハラアジサシを採用。
Gray の指定の方が早いので一見こちらが優先されそうに見えるが、Gull-billed Viralve? のように Stephens は ? 付きで名付けていたためそもそもタイプ種とは認められないとのこと。Strickland (1841) のタイプ種を採用すればハシグロクロハラアジサシはより早い Chlidonias Rafinesque, 1822 のタイプ種のため Viralva 属は表面に現れなくなる。
ちなみに当時の表記でハシブトアジサシを指して Gull-billed Tern はすでに使われており、対応する学名が Sterna Anglica だった。Anglica は容易に想像可能なように "イングランドの" を指す。Sterna Anglica Montagu, 1813 (参考) に由来し、この時点で "Tern, Gull-billed" の英名がすでに付けられていた。
George Montagu (1753-1815) は英国の軍人で鳥類学者。Sussex で採集した標本にこの英名を付けたとのこと。英国で記載したので Anglica と付けたのはちょっと安易な気もするが、Linnaeus がオガワコマドリに svecica と付けたようなものだろう。また当時の Sterna 属は地名や種小名が付けられたものも多く、イングランドで初めて学名を付けることのできた (未確認) Sterna 属で国名を残して置きたかったのかも知れない。
なお同時に Montagu が命名したアジサシ類ではベニアジサシの学名が現在も使われている。こちらはスコットランドで採集されたものなので Anglica はハシブトアジサシの方に与えたものと推測できる。
ハシブトアジサシは Gmelin (1789) の方が先に Sterna nilotica として記載していたため、Montagu がせっかく付けた自国を指す学名が使われなくなった次第。Stephens (1826) の時代はまだ有効で Montagu の名付けた学名が使われていた。Gmelin (1789) のものと同一であることが判明するまで多少時間がかかっていた模様で Sterna Anglica の学名はしばらく使われていた。
しかし学名字義的には Gmelin の "ナイル川の" や Brehm の "南方の" 方が分布をよく反映しており、"イングランドの" より適切であったと思える。#シロチドリの英名が Kentish Plover で学名が Charadrius alexandrinus となっている関係によく似ている。和名で言えばカラフトワシみたいなものだろうか。
分子系統解析で属名も変わってしまって当時の面影はなくなってしまった。英名のみ、そしておそらく英名由来の和名が現在も使われている。
5亜種ある(IOC)。日本で記録されるものは affinis [(既存の種か亜種の何か、例えば基亜種に) 似ている] とされる。この亜種は中国・モンゴル・ロシアの国境付近で繁殖するグループとされる。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 106 pp. 6, 8 によればハシブトアジサシは魚はあまり食べないとのこと。wikipedia 英語版によれば食性はいわゆる沼アジサシに近く、飛びながら昆虫を捕えたり、両生類や小型の哺乳類を捕えることもあるとのこと。水に飛び込んで魚を捕えることは普通はないとのこと。
-
オニアジサシ
- 第8版学名:Hydroprogne caspia (ヒュドゥロプログネー カスピア) カスピ海の水のツバメ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna caspia (ステルナ カスピア) カスピ海のアジサシ
- 第8版属名:hydroprogne hudro 水の (Gk) < hudor, hudatos 水 (Gk) progne, procne ツバメ < 伝説でツバメに変えられた Progne (Gk)
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:caspia (adj) カスピ海の
- 英名:Caspian Tern
- 備考:
hydroprogne は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語では Progne, Procne の末尾が長母音で音が保存される可能性がある。日本語では Procne はプロクネーまたはプロクネと表記されている。アクセントには影響がないので好み次第でよいだろう。
由来を明確にする意味で伸ばす選択もよいと思う。
ギリシャ語では pro-cne と区切るらしく区切り方を踏襲すればアクセント音節は -dro- になると考えられる (ヒュドゥロプログネー)。
sterna は#アジサシ参照。
caspia はこの形の用例は学名ぐらいのもので、通常は caspica の表記。いずれにしても短母音のみでアクセントは冒頭 (カスピア)。
Progne 属が別に存在し、アメリカでごく普通種のムラサキツバメ Progne subis Purple Martin がタイプ種。こちらは本物のツバメ類で Hydroprogne は Pallas (1770) によるもので、Progne Boie, 1826 より早く、この属名との合成ではない。
ムラサキツバメの種小名の subis の由来が面白いので合わせて紹介しておくと Nigidius Figulus が用いたワシの卵を割る鳥の名前とのこと。巣にいろいろな巣材が用いられており、他の鳥の巣を壊すと考えられた。またムラサキツバメはタカやカラスに対して勇敢で、アメリカの初期の入植者はムラサキツバメの巣箱を用意してタカなどが家畜を襲うのを防ぐことが推奨されたとのこと (The Key to Scientific Names)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Hydroprogne 属 hudro 水の (Gk) < hudor, hudatos 水 (Gk) progne, procne ツバメ < 伝説でツバメに変えられた Progne (Gk); アジサシは二股に分かれた尾から以前は「海のツバメ」として知られていた。
種小名は変化なし。Hydroprogne 属はオニアジサシ属。単形属で単形種となる。将来属統合などがなければこのままの学名で決定となる。
ロシアではこの属名が過去から用いられていて、欧米とロシアで学名が違う例として取り上げられることもあったが分類改訂によって揃うことになった。というよりも、Hydroprogne 属は海外分類でも使われていたので Sterna に全部まとめていた時代が大雑把過ぎたと言えるだろう。
Hydroprogne 属に変更されたのは Clements では 6th edition、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2) ですでに用いられており、IOC では 1.7 以来、
比較的変更が遅かった Birdlife でも checklist version 07 (Jul 2014) と変更されており、日本鳥類目録改訂第7版の出版のすぐ後に世界の足並みが揃っていた。
Dement'ev and Gladkov (1951) では Hydroprogne tschegrava Lepechin, 1770 の学名が用いられ、北米のオニアジサシもこの亜種扱いだった。
記載も古いためロシアではこの学名がおそらく標準だった模様。資料 によればスキャンが切れているが、1898 年の AOU 会合で厳密性を欠くとして欧米では使われなくなった経緯が考えられる。
tschegrava は人名ではなく Chergrava がオニアジサシの地方名とのこと。由来は黒っぽい灰色の意味とのこと (The Key to Scientific Names)。cher- が黒い。grava はちょっと不明でこの解釈はあまり正確でないかも知れない。
現在のロシア名もこの名称が使われているので Kolyada et al. (2016) を調べてみると Dal' によれば chervatyj または charavyj (黒っぽい) 由来で、ウズラのような暗色の、褐色の、と解説がある。cher- の部分は多分問題ないとしてもこれも一解釈の感じ。
ロシア名そのままで定着していたため AOU (1898) の判断は受け入れにくかったかも知れない (日本で言えばアオゲラの記載が別に発見されて学名が変わるようなもの)。
現在使われる学名の記載時学名は Sterna caspia Pallas, (1770) (原記載) で、この中に tjchagrava (chergrava) が出てくるがこれは学名を指したものではなく、色彩の特徴からロシア人はこの名前で呼んでいると紹介したもの。
Pallas の出版物は 1750-1776 に複数巻に分けて出版されたもので、年代の解釈に不定性があったかも知れない。
Hydroprogne tschegrava Lepechin, 1770 とほぼ同じ時期の記載なのでどちらが早いかなど検討があってロシアでは tschegrava が採用されていたものと想像できる。しかし Dement'ev and Gladkov (1951) ではシノニムとして載っていないので経緯には多少疑問が残る。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では世界と同じ学名が使用されている。
世界分布が非常に広いのに単形種なのだろうか気になっている。
北米では3つの個体群があって遺伝的違いが調べられている: Boutilier et al. (2014)
Evidence for genetic differentiation among Caspian tern
(Hydroprogne caspia) populations in North America。
遺伝子交流はある程度妨げられていて、それぞれ保全的に意味のある単位をなしているが、進化的に意味ある単位 (ESU) かどうかまではわからなかったとのこと。
北米内でこの程度の違いがあればユーラシアやアフリカ、オーストラリアのそれぞれの分布ではそれなりの遺伝的違い (例えば亜種レベル) があるかも知れない。
アメリカコアジサシ Sternula antillarum Least Tern
は北米内で3亜種が記載されているがそれほどの遺伝的違いはないとの研究 (Draheim et al. 2010) も紹介されている。
[オニアジサシを襲ったアメリカの鳥インフルエンザの悲劇]
(#インドガン備考の鳥インフルエンザのニュースから重複掲載)
Bird flu has killed nearly 1,500 threatened Caspian terns on Lake Michigan islands
ミシガン州の湖で 1500 羽近いオニアジサシ (英名はカスピ海由来だが北米にも生息する) が犠牲となった。神経症状で震える姿や、それでも抱卵しようとする中で亡くなった姿が記録されている。
多数の経験豊富な成鳥を失い、個体群に与える影響がどれほどのものか想像がつかないとのこと。
関連した論文報告 (地域は異なる): Haman et al. (2024) A comprehensive epidemiological approach documenting an outbreak of H5N1 highly pathogenic avian influenza virus clade 2.3.4.4b among gulls, terns, and harbor seals in the Northeastern Pacific (2024.11.6)
ワシントン州の Rat Island での 2023 年の大発生によってオニアジサシのコロニー個体群の成鳥の少なくとも 56% が死亡。それ以降繁殖に成功していない。
2023 年の発生で太平洋フライウエイのオニアジサシの 10-14% の個体が死亡したと推測している。
もう1種ワシカモメ (雑種とある) も影響を受けたが影響は相対的に小さかった。
オレゴン州のカモメ類での発生が発端と推定され、その後ワシントン州に及んだことが分子系統解析からもフィールドデータからも裏付けられた。この研究では鳥から海の哺乳類への複数回の導入があったと推定される。
(#インドガン備考の鳥インフルエンザのニュースから重複掲載)
カスピ海地域での最も最近の集団感染の事例は 2022 年にあってカスピ海西部沿岸のロシア側でニシズグロカモメ Ichthyaetus melanocephalus、(カスピアカモメ) Larus cachinnans Caspian Gull、オニアジサシやハイイロペリカンが犠牲となったとのこと
[Sobolev et al. (2023) Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus-Induced Mass Death of Wild Birds, Caspian Sea, Russia, 2022 2022年5月]。
この地域で鳥が死ぬことは普通にあるがよく調べられていない。
-
オオアジサシ
- 第8版学名:Thalasseus bergii (タラスセウス ベルギイ) ベルギウスの漁師 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna bergii (ステルナ ベルギイ) ベルギウスのアジサシ
- 第8版属名:thalasseus 漁師 (Gk) < thalasses 海 (Gk)
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:bergii (属) アフリカでの活躍が有名なプロイセンの博物学者 Karl Heinrich Bergius の (ラテン語化 -ius を属格化)
- 英名:Greater Crested Tern
- 備考:
thalasseus は起源となるギリシャ語が短母音なので長母音は現れないと考えられる。-las- がアクセント音節と考えられる (タラスセウス)。
sterna は#アジサシ参照。
bergii は原語にも近い "ベルギイ"。語末に ii と並ぶ点に注意。
英名に "Crested Tern" の付くアジサシ類が何種類かある。これらは Sterna cristata Stephens, 1826 (記載) に由来すると考えられる。
基産地も China and many of the southeastern islands of Asia と広かったが後に中国に限定された。Sterna Bergii Lichtenstein, 1823 (記載) と同種と判定され、この記載の方が早いために種学名はこちらに変わり、cristata は亜種名に残ることになった (属が変わって現在は男性形になっている)。
cristata は英名に残ることになった。単に Crested Tern と呼ばれる時期もあった。
現在の学名からはわかりにくいが、オオアジサシは似た種類の中で比較的大きいために英名 Greater Crested Tern が与えられたと考えられる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代にはすでにオオアジサシの名前はあって Sterna bergii と現在とあまり違わない学名となっていた。当時はオニアジサシはまだ記録されておらず、もっと大きいアジサシが記録されて (ちょっと困って) オニアジサシの名称が選択された経緯が考えられる。
他のアジサシ類は色彩などの特徴を (一部は学名由来で) 和名に与えているものが多いが、アジサシ (チュウアジサシの名前もあった)、コアジサシ、オオアジサシ は大きさで名前を付けていた。大きさを表す接頭語が尽きてしまってその後は別の方法で付けるようになったのでは。
アメリカでコキアシシギ、オオキアシシギに関連した一種のパロディがあって、日比 (1998) Birder 12(8): 76-78 で紹介されている。"A Field Guide to Little-Known and Seldom-Seen Birds of North America" (Sill et al. 1988) が出版されて人気だったとのこと。
チュウキアシシギ Tringa intermedius Least Yellowlegs のような架空の種名・学名まで与えられていた (しかも文法規則に則っていない)。日本で言えばチュウダイサギやダイチュウサギのような感じだろうか。
なぜこのようなことを気にしたかと言えば、自分の地域からそこそこ近い (?) 三重県にオオアジサシが比較的定期的に渡来する場所があり、渡来時期にはカモメ類と一緒にいることが多いのでそれほど大きく感じないのである。
"オオアジサシと言われるほど大きくないなあ" が第一印象だった。見慣れている人にとっては印象が違うかも知れない。
春の渡りでアジサシとコアジサシが同時に見られる時にはそれぞれ納得できる名前ではあるが。
英名の "Crested Tern" に対応する現行和名が日本産のどの種にも付いていないのは多少面白い。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは cristatus (冠羽のある) とされる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Thalasseus 属となる thalasseus 漁師 (Gk) < thalasses 海 (Gk)。Bridge et al. (2005) (#コアジサシの備考参照)。種小名は変化なし。Thalasseus 属はオオアジサシ属。
Thalasseus 属のタイプ種は サンドイッチアジサシ Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern。
-
ベンガルアジサシ
- 第8版学名:Thalasseus bengalensis (タラスセウス ベンガレーンシス) ベンガルの漁師 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna bengalensis (ステルナ ベンガレーンシス) ベンガルのアジサシ
- 第8版属名:thalasseus 漁師 (Gk) < thalasses 海 (Gk)
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:bengalensis (adj) ベンガル地方の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Lesser Crested Tern
- 備考:
thalasseus は#オオアジサシ参照。
bengalensis は場所の -ensis は冒頭が長母音でアクセントもある (ベンガレーンシス)。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Thalasseus 属となる。種小名は変化なし。
森岡 (1999) Birder 13(9): 70-73 に 1998 年富士川河口で記録されたベンガルアジサシの同定の記事があり、アジサシ類の分類や他種の詳しい情報についても触れられている。
-
コアジサシ
- 第8版学名:Sternula albifrons (ステルヌラ アルビフロンス) 白い額の小さいアジサシ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna albifrons (ステルナ アルビフロンス) 白い額のアジサシ
- 第8版属名:sternula Sterna (アジサシ) 属の指小名
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:albifrons (adj) 白い額の (albus (adj) 白い frons (f) 額)
- 英名:Little Tern
- 備考:
sternula は指小辞 -ula は短母音。冒頭にアクセントがある (ステルヌラ)。-nula は伸ばさない。
sterna は#アジサシ参照。
albifrons はすべて短母音でよく、冒頭にアクセントがある (アルビフロンス)。frons は長母音でもよく伸ばしても構わない (アルビフローンス)。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは sinensis (中国の) とされる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Sternula 属となる。この名称は Sterna 属の指小名。種小名は変化なし。Sternula 属はコアジサシ属。Sternula 属のタイプ種。
分子遺伝学に基づくアジサシ類の分類および属名の変更提案については Bridge et al. (2005) A phylogenetic framework for the terns (Sternini) inferred from mtDNA sequences: implications for taxonomy and plumage evolution を参照。系統関係と頭部の模様の関係の図もある。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で新たに現れる属はこの分類による。
英語別名 Least Tern (コンサイス鳥名事典) との記載があるが、これは分離される前のアメリカコアジサシの英名と思われる。#アメリカコアジサシも参照。
茂田・佐野 (1992) Birder 6(7): 18-21 にコアジサシの分布と分類の記事がある。
-
コシジロアジサシ
- 第8版学名:Onychoprion aleuticus (オヌィコプリオーン アレウティクス) アリユゥシャン諸島ののこぎり状の爪の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna aleutica (ステルナ アレウティカ) アリユゥシャン諸島のアジサシ
- 第8版属名:onychoprion onux, onukhos 爪 prion, prionos のこぎり (Gk) 中央の指の爪の側面にぎざぎざがあることによる
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:aleuticus / aleutica (adj) アリュゥシャン諸島の (-icus (接尾辞) に属する)
- 英名:Aleutian Tern
- 備考:
onychoprion は#セグロアジサシ参照。
sterna は#アジサシ参照。
aleuticus / aleutica は外来語で発音はわからないが -u- がアクセント音節と考えられ、短母音のみとすれば "アレウティクス"、"アレウティカ"。場所の -icus は短母音のみ。
Onychoprion 属は男性の扱いだが、aleutica の女性形のままのリストも過去に存在した (British Ornithologists' Union Checklist 7th edition。その後訂正された)。
単形種。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Onychoprion 属となる。< onux, onukhos 爪 prion, prionos のこぎり (Gk) 中央の指の爪の側面にぎざぎざがあることによる。学名は Onychoprion aleuticus となる。
Onychoprion 属はセグロアジサシ属となる。
英語ではこの属の4種を brown-backed terns または brown-winged terns (Bridge et al. 2005) と総称する。
Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" (Birds of Sakhalin Island) pp. 228-239 (No. 177) によれば記載時学名 Sterna camtschatica Pallas, 1811 (参考)
の方が早く特徴を表していたので正統な学名とみなしている。
Pallas は足の色を間違えて記述していたため正当な記載と見なさない扱いが世界では一般的だが Buturlin (1934), Portenko (1973), Lobkov (1976) は Pallas の学名を用いており、Nechaev (1991) もそれに従うとのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) は Baird の aleutica の種小名を採用していた。Bianki (1909) がカムチャツカで繁殖するらしいことを記述していたが後の研究で確認できなかった (Bergman 1935) とある。Dement'ev and Gladkov (1951) は主要繁殖地はサハリン沿岸と考え、より北部は迷行と考えていたので Pallas のカムチャッカ沿海や近くの島に多数との記述は別のものを指していると考えたものかも。
カムチャッカの繁殖個体群については 1972-1989 年には調べられていた。Lobkov et al. (2015 初出、2019) The state of the Kamchatka tern Sterna camtschatica population in Kamchatka (pp. 4176-4177) など参照。
英名で prion と呼ばれるグループは別にあり、ミズナギドリ科 Pachyptila (クジラドリ) 属。かつて Prion 属だった。ギリシャ語語源は同じで、ヒロハシクジラドリ Pachyptila vittata がヒゲクジラに似たろ過式の構造の嘴を持つことから (コンサイス鳥名事典)。英名に whalebird の別名があるので和名は翻訳したものだろうか。
同じ語源の prion を持つ学名は他にもいくつも存在するが嘴以外の特徴を指すものもある。
「プリオン病」などで使われる prion は proteinaceous infectious (particle) からの造語で語源は無関係。牛海綿状脳症 (狂牛病) で有名となった。
コシジロアジサシの越冬地は 1980 年代後半までまったく知られていなかった [Birder 2003年8月「鳥の名前」に出てくる]。現在では多くの個体が西太平洋の赤道付近で越冬することがわかっている (wikipedia 英語版)。日本の図鑑では比較的新しいものでもこの知見がまだ反映されていなかったようである。
ロシアでは現在も Sterna camtschatica Pallas, 1811 の学名 (ロシア名はカムチャツカアジサシに相当) が使われているが、Birds of Northern Eurasia (BirdForum) の議論を見ると、記述がコシジロアジサシと合わないとのことで、自身がカムチャツカで見たものと Steller の記述が混ざっているらしい。
アジサシの若鳥ではないかとの推論がある。Nechaev (1991) が記述するほどには万人を納得させるものとなっていない模様。もっとも Nechaev (1991) などの議論を読まずに Pallas の記載のみを見て議論されているかも知れない。
通常は有効な学名と認められていない Sterna camtschatica Pallas, 1811 (WoRMS)。
この BirdForum のスレッドの後半も面白く、ロシア語の論文タイトル "Vid ili ne vid?" (文字通りだと "種か、それとも種ではないか") はハムレットの有名な "to be, or not to be, [that is the question]" がロシア語では "Byt' ili ne byt'" になるのでその語呂合わせではないかとの解釈が出ている。
調べてみるとロシア語でもハムレットの台詞はよく知られていてこの表現は頻出で、語呂合わせ説はもっともらしい。wikipedia ロシア語版を見るとやはり他の語呂合わせ表現があって、bit' ili ne bit' (打つ), pit' ili ne pit' (飲む) などがあるとのこと。vid も語末は無声音となるので音声的にはよく対応する。機械翻訳ではわからない面白さがある。
-
ナンヨウマミジロアジサシ
- 第8版学名:Onychoprion lunatus (オヌィコプリオーン ルーナートゥス) 三日月斑のあるのこぎり状の爪の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna lunata (ステルナ ルーナータ) 三日月斑のあるアジサシ
- 第8版属名:onychoprion onux, onukhos 爪 prion, prionos のこぎり (Gk) 中央の指の爪の側面にぎざぎざがあることによる
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:lunatus / lunata (adj) 三日月形の
- 英名:Spectacled Tern
- 備考:
onychoprion は#セグロアジサシ参照。
sterna は#アジサシ参照。
lunatus/lunata は u と1つめの a が長母音で後者にアクセントがある (ルーナートゥス/ルーナータ)。luno (ルーノー。三日月型に曲げる) の過去分詞に由来する長音。
ラテン語の "月" は Luna (ルーナ)。これに由来する英語の lunar, lunatic (発狂した) なども冒頭は長母音で発音する。
単形種。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Onychoprion 属となる。学名は Onychoprion lunatus となる。
和名は南洋由来で問題ないと思われるが、山階鳥類研究所標本データベースでは 1910 年に南鳥島の標本が複数ある。当時のアホウドリ乱獲時代やグアノ採取時代にも対応し、時代背景もうかがわせる。
現在の日本産種で "ナンヨウ" が付くのはもう1種ナンヨウショウビン。
-
マミジロアジサシ
- 第8版学名:Onychoprion anaethetus (オヌィコプリオーン アナエテートゥス) 愚か者ののこぎり状の爪の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna anaethetus (ステルナ アナエテートゥス) 愚か者のアジサシ
- 第8版属名:onychoprion onux, onukhos 爪 prion, prionos のこぎり (Gk) 中央の指の爪の側面にぎざぎざがあることによる
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:anaethetus (合) 愚か者の (an- 否定 aisthetos 機敏な、aisthanomai 理解する、感じる Gk wiktionary, The Key to Scientific Names)
- 英名:Bridled Tern
- 備考:
onychoprion は#セグロアジサシ参照。
sterna は#アジサシ参照。
anaethetus は起源となるギリシャ語 anaisthetos の e が長母音で。長母音を保存しアクセントもここに置くと自然な読みになる (アナエテートゥス) のでこれを採用した。
容易に予想されるように英語の anasthetic (麻酔の) などと同語源。"感じない" ので "愚か者" の意味として使われた。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Onychoprion属となる。学名は Onychoprion anaethetus となる。
4亜種あり(IOC)。日本で記録されるものは基亜種 anaethetus 亜種マミジロアジサシと、antarcticus (南極の) インドヨウマミジロアジサシ とされる。
-
セグロアジサシ
- 第8版学名:Onychoprion fuscatus (オヌィコプリオーン フスカートゥス) 黒ずんだ色のアジサシ (新学名で黒ずんだ色ののこぎり状の爪の鳥) (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sterna fuscata (ステルナ フスカータ) 黒ずんだ色のアジサシ
- 第8版属名:onychoprion onux, onukhos 爪 prion, prionos のこぎり (Gk) 中央の指の爪の側面にぎざぎざがあることによる
- 第7版属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:fuscatus / fuscata (adj) 黒ずんだ色の (fuscus (adj) 薄暗い -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Sooty Tern
- 備考:
onychoprion はギリシャ語の prion の o が長母音で忠実に従えば伸ばす可能性がある。アクセント位置には関係ないのでこの表記とした。短音でも構わない。-cho- がアクセント音節と考えられる (オヌィコプリオーン)。
sterna は#アジサシ参照。
fuscatus/fuscata は -atus/-ata の冒頭が長母音でアクセントがある (フスカートゥス/フスカータ)。長音は fusco (フスコー。暗くする) の過去分詞の変化形による。
英名の sooty は種小名とほぼ同じ意味だが、Fauna Japonica Sterna fuliginosa の学名も使われていた。fuliginosa < fuligo すす、なので英名の直接の由来はこちらの学名かも知れない。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Onychoprion 属となる。学名は Onychoprion fuscatus となる。Onychoprion 属はセグロアジサシ属。セグロアジサシがタイプ種。
6亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは nubilosus (曇った < nubis 雲) 亜種セグロアジサシ と oahuensis (オアフ島の) ハワイセグロアジサシ とされる。
英語通称名に wideawake (tern) があり、コロニーで絶え間なく続く声を指す (wikipedia 英語版)。
-
ベニアジサシ
- 学名:Sterna dougallii (ステルナ ドウガルリイ) ダウガルのアジサシ
- 属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:dougallii (属) dougallの (ラテン語化 -ius を属格化) スコットランドの外科医で標本採取家の Peter McDougall に由来と推定 (The Key to Scientific Names)
- 英名:Roseate Tern
- 備考:
sterna は#アジサシ参照。
dougallii はラテン語的に読むと -gal- がアクセント音節となる (ドウガルリイ)。原音とそれほど離れるわけではない。語末に ii が並ぶ点に注意。
Sterna Dougallii Montagu, 1813 (原記載) にもすでに英名 Tern-roseate (現代風に表記すると Roseate Tern で現在の英名と同じ) が与えられていた。嘴の色ではなく繁殖期の胸のピンク色から (wikipedia 英語版でも同様に記述されている)。
OED によれば Montagu (1813) が Roseate Tern の名称で紹介したとのこと。他言語でも同様の名称が多数あり、和名も英名を訳したものと想像できる。
英名と同じ意味の Sterna rosea Forster, 1817 (参考) の学名もあるが Sterna dougallii を改名したもの (Synoptical Catalogue of British Birds)。
色彩を反映したものに改名しようとしたのか元の学名記載に問題があるとみなしたのか、この資料だけからは不明。
5亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは bangsi (アメリカの動物学者の Outram Bangs に由来) とされる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" 時代はすでに Sterna dougallii gracilis の学名とともにベニアジサシの和名が与えられていた。
奄美黄島と石垣島。亜種 gracilis は現在の概念とは異なるが bangsi などの亜種はその後記載されたもの (例えば bangsi は 1912 年) で、当時は亜種 gracilis に含まれていたと考えられる。
気になるのは別学名のリストに Sterna paradisaea Keys. & Blas. が含まれていることで、これは現在ではキョクアジサシの学名になっているが、同種扱いであれば Sterna paradisaea の記載の方が早いのでベニアジサシがキョクアジサシの亜種扱いとなっていた時代 (があったかどうか不明) の学名を反映したものではないかと想定される
(実際に雑種の事例があるよう)。
Dement'ev and Gladkov (1951) のキョクアジサシの記述を見ても Reichienow (1904) 時代はアジサシ類の同定に混乱があったことが推測できる。
Sterna paradisaea の用例は Bruennich (1764) があって Ogawa (1908) の時代にも知られていたかも知れないがその後にさらに早い用例が見つかった。
-
エリグロアジサシ
- 学名:Sterna sumatrana (ステルナ スマトゥラーナ) スマトラ島のアジサシ
- 属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:sumatrana (adj) スマトラ島の (-anus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Black-naped Tern
- 備考:
sterna は#アジサシ参照。
sumatrana は所属の -ana は冒頭が長母音でアクセントもある (スマトゥラーナ)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" 時代の学名は Sterna melanauchen Temminck, 1827 (melanos 黒い aukhen, aukhenos 首 Gk, The Key to Scientific Names) で英名、和名ともによく一致し学名由来と考えられる。和名は英名の意味そのままで英名由来と考えられる。少し珍しい語尾の学名。
図版例。
aukhen, aukhenos から直接派生した単語は思い至らないが trakhelos (Gk) が同義語とのことで、これであれば英語の trachea (気管) が派生する。aukh と ach に類似性が残る。
Sterna Sumatrana Raffles, 1822 (原記載) が早かったために学名が変わったが、Temminck (1827) の学名は長く使われていたようで英語、日本語を初めとする多くの言語に残っている。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でもこの学名が使われていた。
2亜種あり (IOC) だが日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種を認めない立場のよう。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)で多形種となり、記録される亜種は sumatrana となった。
-
アジサシ
- 学名:Sterna hirundo (ステルナ ヒルンドー) ツバメのようなアジサシ
- 属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:hirundo (f) ツバメ
- 英名:Common Tern
- 備考:
sterna は外来語由来で発音は明確でないが短母音のみとすれば "ステルナ"。伸ばしてもアクセント位置は変わらない。
hirundo は語末が長母音で -run- がアクセント音節 (ヒルンドー)。#ツバメ参照。
英語別名に Sea Swallow があり種小名に対応している。
[アジサシの亜種]
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは longipennis (longus 長い -pennis 翼/羽の) 亜種アジサシ 及び minussensis (シベリア中央部のクラスノヤルスク地方南部にある Minussinsk ミヌシンスク地区由来) アカアシアジサシ とされる。
他の亜種は tibetana で、チベットの標本や、かつて Sterna longipennis とされていたバイカル湖の標本から Sterna fluviatilis
(現在では Chlidonias hybrida javanicus?) と嘴と足の色が似ていると記載されたもの (原記載) がある。
バイカル湖の標本あたりがひっかかるが、かつては Sterna longipennis がバイカル湖付近にも分布すると考えられていたのだろう。
現在の分布ではヒマラヤ、モンゴル南部、中国とされている。
アジサシが高地にも分布する点については、週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 106 p. 4 に Schaefer の 1934-1936 のチベット高地の調査で 5000 m の沼沢地域を毎年決まって訪れるという記載があった。なお当時 (1973) はアジサシの和名にチュウアジサシが使われていた。
Dement'ev and Gladkov (1951) でも4亜種で、minussensis がバイカル湖付近から中央シベリア (ロシア名中央シベリアアジサシに相当)、
tibetana が中央アジア高地 (ロシア名チベットアジサシに相当)、
longipennis がシベリア東部、極東 (カムチャツカ、サハリン、千島列島を含む。ロシア名ハシグロアジサシに相当。基産地オホーツクの Kykhtuj 川) としていた (図の番号は間違っていて本文が正しいと思われる)。
longipennis は渡り途中に中国や日本沿岸で見られるとある。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではシベリアで3亜種としており、分布の記述はほぼ同じだが minussensis は基亜種と longipennis の雑種の可能性もあるとしている。
亜種間の違い、分布境界は不明瞭で東に行くほど暗色で嘴の黒色が目立つようになり、足の色も赤っぽいものから黒褐色に変わってゆくとある。ユーラシアで繁殖地があまり分断されておらず、この記述を見ると地理的なクラインに近いのかも知れない。
Sterna 属のタイプ種。
ヨーロッパの亜種の渡り経路: Piro et al. (2022) Revealing different migration strategies in a Baltic Common Tern (Sterna hirundo) population with light-level geolocators。
同一コロニーでジオロケータ装着。越冬地 (アフリカ) によって3グループに分かれる。過去の標識回収記録との比較もある。
Lonca et al. (2024) High genetic diversity yet weak population genetic structure in European common terns 遺伝的違いはあまりなく距離の違いとはあまり相関がない。
[アジサシ科の系統分類]
Cerny and Natale (2022) の分子系統樹を用いた Boyd による カモメ上科 Laroidea アジサシ科 Sternidae: Terns and Skimmers の分類は以下のようになる。
カモメ上科 Laroidea アジサシ科 Sternidae
ハサミアジサシ亜科 Rynchopinae: Skimmers
ハサミアジサシ属 Rynchops
アフリカハサミアジサシ Rynchops flavirostris African Skimmer
シロエリハサミアジサシ Rynchops albicollis Indian Skimmer
クロハサミアジサシ Rynchops niger Black Skimmer (南北アメリカ)
シロアジサシ亜科 Gyginae: White Terns
シロアジサシ属 Gygis
シロアジサシ Gygis alba White Tern (コシロアジサシを含め、複数種に分割される可能性がある。英名も別のものが提案されている。#シロアジサシの備考参照)
コシロアジサシ Gygis microrhyncha Little White Tern
アジサシ亜科 Sterninae: Terns
セグロアジサシ属 Onychoprion
コシジロアジサシ Onychoprion aleuticus Aleutian Tern
セグロアジサシ Onychoprion fuscatus Sooty Tern
ナンヨウマミジロアジサシ Onychoprion lunatus Spectacled Tern / Grey-backed Tern
マミジロアジサシ Onychoprion anaethetus Bridled Tern
コアジサシ属 Sternula
コアジサシ Sternula albifrons Little Tern
アメリカコアジサシ Sternula antillarum Least Tern
ヒメアジサシ Sternula nereis Fairy Tern
アマゾンアジサシ Sternula superciliaris Yellow-billed Tern
アラビアコアジサシ Sternula saundersi Saunders's Tern
ダマラアジサシ (マダラアジサシ: 誤) Sternula balaenarum Damara Tern
ペルーアジサシ Sternula lorata Peruvian Tern
オオハシアジサシ属 Phaetusa
オオハシアジサシ Phaetusa simplex Large-billed Tern (南米)
オニアジサシ属 Hydroprogne
オニアジサシ Hydroprogne caspia Caspian Tern (世界に広く分布)
ハシブトアジサシ属 Gelochelidon
ハシブトアジサシ Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern (主に北半球中緯度に広く分布)
インカアジサシ属 Larosterna
インカアジサシ Larosterna inca Inca Tern (南米西海岸)
クロハラアジサシ属 Chlidonias
クロハラアジサシ Chlidonias hybrida (種小名は#クロハラアジサシ備考参照) Whiskered Tern
クロビタイアジサシ Chlidonias albostriatus Black-fronted Tern (ニュージーランド)
ハジロクロハラアジサシ Chlidonias leucopterus White-winged Tern
ハシグロクロハラアジサシ Chlidonias niger Black Tern
オオアジサシ属 Thalasseus
サンドイッチアジサシ Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern (主にヨーロッパ、北米)
ユウガアジサシ Thalasseus elegans Elegant Tern (南北アメリカ西岸)
カボットアジサシ? Thalasseus acuflavidus Cabot's Tern (南北アメリカ)
オオアジサシ Thalasseus bergii Greater Crested Tern / Great Crested Tern
ヒガシシナアジサシ Thalasseus bernsteini Chinese Crested Tern
ベンガルアジサシ Thalasseus bengalensis Lesser Crested Tern
アメリカオオアジサシ Thalasseus maximus Royal Tern (南北アメリカ)
アフリカオオアジサシ Thalasseus albididorsalis West African Crested Tern (アフリカ西海岸の一部)
アジサシ属 Sterna
メリケンアジサシ Sterna forsteri Forster's Tern (北米)
シロガシラアジサシ Sterna trudeaui Snowy-crowned Tern (南米南部)
キョクアジサシ Sterna paradisaea Arctic Tern
ナンベイアジサシ Sterna hirundinacea South American Tern (南米)
ケルゲレンアジサシ Sterna virgata Kerguelen Tern (インド洋ケルゲレン島周辺)
ナンキョクアジサシ Sterna vittata Antarctic Tern
アジサシ Sterna hirundo Common Tern
エリグロアジサシ Sterna sumatrana Black-naped Tern
ベニアジサシ Sterna dougallii Roseate Tern
シロビタイアジサシ Sterna striata White-fronted Tern (ニュージーランド)
アラビアアジサシ Sterna repressa White-cheeked Tern (アラビア周辺)
カワアジサシ Sterna aurantia River Tern (インドから東南アジア)
インドアジサシ Sterna acuticauda Black-bellied Tern (インド)
個々の種の学名は基本的に日本鳥類目録改訂第8版の変更予定や IOC と同じであるが順序は異なる。
第8版の変更予定ではクロアジサシ属とシロアジサシ属が冒頭にあって他のアジサシ類と分離されているが、この Boyd の分類ではクロアジサシ属をカモメ科 Laridae クロアジサシ亜科 Anoinae に移動し、シロアジサシ属と他のアジサシ類が Boyd が分離したアジサシ科 Sternidae に含まれる点が異なる。
あくまでこれまでの遺伝情報によるもので十分ではないが、全属を分子系統順に挙げてあるので改訂第8版で属名が大きく変わる点の理解には多少役立つかも知れない。
改訂第7版、改訂第8版の変更予定の順序がわかりにくく感じるのはアジサシ類の間にカモメ類がはさまっていることが原因だろうが、分子系統樹を見て判断していただいた上で、この系統分類の方がわかりやすければ (決定版ではないが) 使っていただいてもよいように思える。
途中の系統で単形属のオニアジサシ、ハシブトアジサシがそれぞれ世界に広く分布しているのが特徴。
この2種は系統的には遠い親戚関係になる (1属にまとめても単系統になるが、あまり似ていないので別属とされているのだろう)。
ハサミアジサシ亜科 Rynchopina は ハサミアジサシ科 Rynchopidae と分離されることもあった。アジサシモドキの和名もあった (コンサイス鳥名事典)。
コシロアジサシは IOC (14.1) ではシロアジサシの亜種。分離後の和名はすでに使われているもの。
シロアジサシの中では最も東方の亜種であったが記録されることがないかどうか (識別対象として考慮が必要か) はわからない。
Thalasseus acuflavidus はサンドイッチアジサシから分離されたものだが和名は見つけられなかった。人名 Cabot の標準的な読み方から与えてみたが北米の種類なので英名が変わるかも知れない。
Sternula balaenarum はアメリカコアジサシから分離されたもので eBird などではマダラアジサシと出るがダマラアジサシの和名は以前より使われており (コンサイス鳥名事典では別種扱い) 誤記だろう。
Thalasseus albididorsalis はアメリカオオアジサシから分離されたものだが和名はすでにあったものを使った。
-
キョクアジサシ
- 学名:Sterna paradisaea (ステルナ パラディーサエア) 楽園のアジサシ
- 属名:sterna Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語)
- 種小名:paradisaea (adj) 楽園の (paradisa -ae (f) 楽園 -a 女性形の形容詞に)
- 英名:Arctic Tern
- 備考:
sterna は#アジサシ参照。
paradisaea は paradisus の i が長母音。語末は母音が3つあるので最初にアクセントになる (パラディーサエア)。形容詞の形は paradiseus が普通だが学名で使われる形容詞らしい。
現在の学名で使われるものは2例しかなく、もう1例はホウオウジャク Vidua paradisaea (Linnaeus, 1758) Eastern Paradise-Whydah。
キョクアジサシも Pontoppidan (1763) といずれも古い用例。
Linnaeus (1758) はカワリサンコウチョウでは paradisi、カザリオウチュウ には paradiseus (Linnaeus 1766) を用いるなど paradisaea の用例はむしろ例外的な綴りを使ってしまったものかも知れない。意味は疑いないがラテン語造語の経緯があまりはっきりしない。
paradis- の i を長母音とするのはドイツ語でも Paradies と伸ばすなど他言語にもみられわかりやすい。
学名は Sterna arctica Temminck, 1820 の方がよく知られていて、Sterna paradisaea Bruennich, 1764 の学名が先に付けられていたことがその後判明したものと推定できる。
Hartert (1910-1922) p. 1704、Dement'ev and Gladkov (1951) では Sterna paradisaea Bruennich を用いている。
このころには Pontoppidan (1763) の用例がさらに早いことが判明したものと推定できる。
Hartert の用いたドイツ語名は Kuestenseeschwalbe (海岸の海のツバメ)。
Sterna arctica をそのまま英訳したものが Arctic Tern になる。この学名と英名を含む 図版例 ("The Birds of Europe" Gould 他 1837)。
多言語名でも "北の", "北極の" を用いているものが多く、この学名や英名が広く使われたものがそのまま残っていると考えられる。
OED によれば Arctic Tern の最初の用例は 1824 年で当時の学名 Sterna Arctica と併記され、学名由来であることがわかる。
北極海から南極海に渡ることが早い時期に明らかになって "Arctic" の表現はおそらくふさわしくないとしてロシア語名では和名と同じ "キョクアジサシ" の意味となっている。Dement'ev and Gladkov (1951) にも "arctic" に相当する別名の記載がないのでおそらく早い時期から "キョクアジサシ" だったと想像される。ロシアでの地域名などは別に記述がある。
和名は独自命名なのか、それともロシア語または別言語の影響を受けた (? 不明)。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば Sterna macrura antistropha Reichenow, 1904 の名称があったとのこと (antistropha Gk 対応する、反対のなどの意味)。資料 によれば南極大陸沿岸に生息し、北半球のものの対応種のようにみなしていた模様。
Dement'ev and Gladkov (1951) によればそのため両極に分布する種で北と南が亜種の関係にあると考えられていたことがあったが、キョクアジサシは南極大陸では繁殖しないことが 1934 年に報告され、現代の名前でナンキョクアジサシ Sterna vittata Antarctic Tern の南の個体群を誤認したと結論している。
アジサシ類の一般名を整理するにあたって、北極と南極の対応種でないことを明らかにする意図があったためあえて北極に対応する名称を避けたのかも知れない。
ここで使われている学名 Sterna macrura Naumann, 1819 (尾の大きなアジサシ) はキョクアジサシの学名としてかなり長く使われており 1942 年の用例もある
[参考 Bullough (1942) Observations On The Colonies Of The Arctic Tern (Sterna Macrura Naumann) On The Fame Islands]。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) にもこの学名が使用されていた。解説によれば BOU の名称をそのまま使用しているとのことで、少なくとも 1966 年段階でもこの学名が使われていたよう。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではすでに現代の学名を用いられていたのですでにわかっていたはず。分類学者 (あるいは各国のチェックリスト) の間でもまだ見解の相違があったのかも知れない。
日本で使われた学名にも結構最近まで登場していたかも知れない。
Sterna paradisaea Bruennich, 1764 の用例が認識される前は Temminck (1820) よりも Naumann (1819) の方が早いのでこの学名に先取権があると考えられていた模様。
すなわち現在使われる学名は比較的新しく確定したもので分類学者次第で過去に複数回変わっている。
日本でキョクアジサシが記録されたのは後の時代で、その間に両極を結ぶ渡りの方が有名になったためにこれらの学名や英名の影響を受けにくかったのかも知れない。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
佐々木他 (2004) 静岡県富士川河口のキョクアジサシ。
-
クロハラアジサシ
- 学名:Chlidonias hybrida (クリドニアス ヒュブリダ) 雑種のツバメのような鳥
- 属名:chlidonias khelidonios ツバメのような (Gk) の短縮形 < khelidon ツバメ (Gk)
- 種小名:hybrida 動物の雑種 (f)
- 英名:Whiskered Tern
- 備考:
chlidonias は#ハシグロクロハラアジサシ参照。
hybrida は短母音のみでアクセントは冒頭 (ヒュブリダ)。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 hybrida とされる。
[亜種の問題]
Dement'ev and Gladkov (1951) では中国などユーラシア東部の亜種は swinhoei Mathews, 1912 (原記載、Foochow/Fuzhou 中国福建省福州市。のどがほとんど白く翼は短いとのこと) とされたが現在の多くのリストでは基亜種のシノニムとされる。
ユーラシア東部の個体群は隔離分布となっており、大陸の東西で別亜種として紹介している記述もあるのでヨーロッパのものと違いがあるか気にしておいてよさそうである。
亜種 javanicus Horsfield, 1821 (原記載)
も記載によって分布が異なる。Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" ではシベリアで2亜種が観察され、基亜種に比べて javanicus はより小型で色が淡いとある。
この記載を見るとロシアでは極東付近の個体を javanicus と考えているようである。
Glushchenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraya: Kratkij Faunisticheskij Obzor" でも沿海地方で記録される個体を javanicus としている。
swinhoei を淡色グループ (Dement'ev and Gladkov 1951) としてこの亜種に含めたものかも知れない。
分布の離れたヨーロッパの基亜種とシノニムと考えるか、ユーラシア東部は別にまとめるか見解が分かれる部分かも知れない。
Dayton et al. (2017)
Genetic Diversity and Population Structure of the Eurasian Whiskered Tern (Chlidonias hybrida hybrida), a Species Exhibiting Range Expansion
ではヨーロッパの東西は遺伝的にも差のある個体群で渡り経路や越冬地も別とのこと。それ以上広い地域の遺伝的違いは調べられていない。
チェックリストの亜種分布だけに頼らず亜種を気にしておいてよいのだろう。
[種小名の問題]
種小名はハジロクロハラアジサシ (?) とアジサシの雑種と考えられたため (情報は wikipedia 英語版。The Helm Dictionary of Scientific Bird Names より)。原記載。基産地はボルガ川南部。
原記載では St. fidipede とあり、Sterna fissipes Linnaeus, 1766 = 現在のハシグロクロハラアジサシ と Sterna fissipes Pallas, 1811 = 現在のハジロクロハラアジサシ のいずれの可能性もあるが (The Key to Scientific Names)、同じ Pallas の記載によるものなので後者らしい。
夏羽の頭頂の黒さが (おそらくハジロクロハラアジサシに比べて) アジサシに似ているとのこと。
いずれにしても色彩が現在の Chlidonias 属と Sterna 属の中間的であること意味したものらしく、形態の違いは無視している (Gould 1873) Hydrochelidon leucopareia Whiskered Tern。
Gould はこんなに明らかに違うものをなぜ Pallas が "雑種" と名付けたか理解に苦しむとしている。その上でこれは適切な名前でないので Gould は別学名 (Hydrochelidon leucopareia。この学名も文献にしばしば現れる) を提案している。
また "sea tern" ではなく "marsh tern" に属することは一目瞭然と記している。
調べて行くうちにクロハラアジサシの和名は学名由来ではないかと思えてきた。marsh terns のうち、現在は#ハシグロクロハラアジサシ 記載時学名 Sterna nigra Linnaeus, 1758 の記載が最も早く学名から現在でも 同じ意味の Black Tern が英名となっている。
ハジロクロハラアジサシとハシグロクロハラアジサシが同種とされていた時代はハシグロクロハラアジサシが基亜種となっていたので最も普通の種類に Black Tern を与えるのは妥当だったのだろう。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にはこれらの種に相当するものが見あらたらないが、クロアジサシはすでに名前が付いていたので、Pallas により雑種の相手と考えられた種の学名を考慮し、その後新しく名前を付ける際に区別するためクロハラアジサシが用いられたのではないだろうか。
英名には亜種時代の名称が十分残っており、ハジロクロハラアジサシの過去の英名は White-winged Black Tern だった。この英名はもちろん (亜) 種小名の leucopterus に由来で、和名も英名および学名からと推定される。
ハシグロクロハラアジサシは日本ではまれな種類でおそらく後に確認されたもので、基亜種であっても同種時代にクロハラアジサシの和名を用いたためにこちらの和名に修飾を加えることになったのでは。
英名の Whiskered Tern も学名別名由来の可能性がある。Hydrochelidon leucopareia の学名が広く使われており、この学名と一緒に Whiskered Tern の英名が記載されている。leucopareia は leukos 白 pareion 頬 (Gk) で頬の白色部を whiskered と表現した可能性がある。
Pallas の hybrida とどちらに先取権があるかも自明でなかったようで BOU (1915) は Pallas の学名はタイトルページに 1811 年とあるが実際には 1827 年まで出版されず、1820 年に使われた leucopareia の方に先取権があると認定した。
Hartert (1910-1922) p. 1686 でも Hydrochelidon leucopareia が早いと認定 (Pallas は 1827 年と判定) Weissbaetige Seeschwalbe で "白いひげのあるアジサシ" で英名と同じ。Whiskered Tern もすでに紹介されていた。
その後の Wood (1931) の研究で Pallas の死去 (1811) 直後に文章は出版され、図版は 1834-1842 年に出版されたと判明した (The Key to Scientific Names の leucopareia の項目)。現在では Pallas の記述が早いと考えられ hybrida が使われているが、leucopareia は英名に影響を与えた可能性がある。"雑種" はいかにも通称として与えにくい。
Chlidonias 4種は marsh terns (沼アジサシ) と総称される。
wikipedia 英語版 (Marsh tern) によれば、これら4種の種小名は男性形が通常用いられるが、クロハラアジサシに限って hybrida が元の属時代の形 (Sterna hybrida Pallas, 1811) でそのまま使われることが多いとのこと。Chlidonias hybridus の学名も使われている。
hybridus (Wiktionary) によれば通常の性変化をする形容詞となっている。
Tachyspiza nanus での議論 (#ツミの備考) を見ると hybrida は名詞を意図して使われたものと判定されたものと想定される。
不変化が採用されていることから種小名の語義は形容詞の女性形ではなく女性名詞の hybrida を採用した。
現在使われている学名の中では形容詞と判定できる hybridus が用いられているものは亜種に使われる2例のみ (Tanygnathus lucionensis hybridus と Colluricincla obscura hybridus) で、後者は女性属名にもかかわらず hybrida と変化させていない。
記載時学名が Pinarolestes megarhynchus hybridus であったため生じた末尾で Colluricincla 属に変更になった際に Clements 5th edition (incl. 2005 revisions) までは hybrida と変化させていたがそれ以降は hybridus としている。Howard and Moore 2nd edition までも同様で 3rd edition で hybridus となっている。
おそらくこの間に hybrida, hybridus は変化させないことになったのだろうと推定する (未確認)。
[和名の由来?]
さらに調べてわかったのは Sterna melanogaster Horsfield, 1824 (参考) と Temminck が "クロハラアジサシ" を意味する学名を用いていた。
この記述によれば Sterna javanica Horsfield, 1821 (参考) (ジャワ島のアジサシ) の記載があったがクロハラアジサシと同定されたよう。これに代わる学名とのこと。
当時は Pallas の記載も知られていなかった可能性もあり別個に記載されても不思議ではない。また Pallas の出版物の年代が決められたのも最近のことでこれらの学名に先取権があった時代も続いていたものと想像できる。
Temminck 自身の 記載 Sterna melanogaster Temminck, 1827 (参考) 基産地は Ceylon, Java, littoral India。フランス語名も Hirondelle de mer a ventre noir とクロハラアジサシに相当する名称が与えられていた。
これらを見るとクロハラアジサシの和名は Temminck の学名またはフランス語名由来がもっともらしい印象を受ける。
現在では Temminck のこの記載は インドアジサシ Sterna acuticauda Black-bellied Tern (この英名に学名が残っている) のシノニムとされるようで現在のクロハラアジサシのシノニムを探しても出てこない。しかし歴史的にはクロハラアジサシと同定されていた時期があった。
インドアジサシの方は Sterna acuticauda Gray, 1831 (原記載) とこちらが早いために Temminck の学名は使われなくなったよう。この図版では Javan Tern とともに Brown-bellied Tern の名称でインドアジサシが挙げられているが、Temminck の学名がそれなりに長く用いられて英名に使われていた模様。
実際に Peters' Check-list of the Birds も 2nd edition まで Sterna melanogaster の学名を用いていた。wikipedia 英語版でもクロハラアジサシに似て見えることがあると書かれており混同されていたことがあってもおかしくない (同種とされたことがあったかどうかは見つけられなかった。19 世紀にはあったのかも知れない)。
[識別の情報]
Marsh terns は日本語でも沼アジサシ (ヌマアジサシ) 類と総称され、特に非繁殖羽や幼羽の識別がしばしば話題になる。独断と偏見の識別講座 第29回 Marsh Terns <ヌマアジサシ類> (波多野邦彦) 参照。
海外記事では Andy Stoddart Marsh tern photo ID guide (2018)。
Gould (1873) では Rev. Mr. Tristam (1860) の北アフリカでの採集の際の記録としてクロハラアジサシとハシグロクロハラアジサシは声で簡単にわかる。クロハラアジサシの方が声が鋭くなくより速く反復するとの情報を引用している。
「鳥630図鑑」ではクロハラアジサシはハジロクロハラアジサシより濁った声で鳴くとある。いろいろな種類の声を出すので一概に言えないかも知れないが音声にも注目していただくとよいだろう。
[クロハラアジサシとハシグロクロハラアジサシの営巣環境の違い]
ポーランドの研究で Cieslinska et al. (2025) Nesting niche partitioning between two sympatrically breeding Chlidonias Tern species revealed by remote sensing。
衛星画像から分析し、ハシグロクロハラアジサシの方が開けた水面を好む。この2種の間ではハシグロクロハラアジサシの方が繁殖環境嗜好性が広いとのこと。
和名と学名・英名の対応が悪いので読んでも大変紛らわしい。
-
ハジロクロハラアジサシ
- 学名:Chlidonias leucopterus (クリドニアス レウコプテルス) 白い翼のツバメのような鳥
- 属名:chlidonias khelidonios ツバメのような (Gk) の短縮形 < khelidon ツバメ (Gk)
- 種小名:leucopterus (合) 白い翼の (leuko- (接頭辞) 白い pteron 翼 Gk)
- 英名:White-winged Black Tern, IOC: White-winged Tern
- 備考:
chlidonias は#ハシグロクロハラアジサシ参照。
leucopterus は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-co- がアクセント音節と考えられる (レウコプテルス)。
#クロハラアジサシの和名由来が同項目の考察通りであれば、ハジロクロハラアジサシは種小名または英名から記述的に追加する形で作られた和名のように思える。
単形種。
-
ハシグロクロハラアジサシ
- 学名:Chlidonias niger (クリドニアス ニゲル) 黒いツバメのような鳥
- 属名:chlidonias khelidonios ツバメのような (Gk) の短縮形 < khelidon ツバメ (Gk)
- 種小名:niger (adj) 黒い
- 英名:Black Tern
- 備考:
chlidonias 外来語由来の短縮語で発音はわからないが、ギリシャ語の khelidonios には長母音が現れないのでおそらく短母音のみと考えられる。-do(n)- がアクセント音節と考えられる (クリドニアス)。ツバメの khelidon の o は長母音だが khelidonos の形では短母音となっている。語尾を付ける際に短音に変換されたものと想像される。
khelidonios から最初の e が落ちた理由は後趾が欠けていたためらしい (#ミフウズラ参照)。以上 The Key to Scientific Names の解説から。
短くする意図を持って造語された学名なので長母音を含めないのがよいだろう。
niger は短母音のみ (ニゲル)。Niger (国名) の日本語読みのように語末は伸ばさない。この形容詞の女性形は nigra でナベコウやヨーロッパクロガモなどに現れる。この語形も同様に短く読む。
[属名の問題]
Hydrochelidon は Boie (1822 年 5 月) の与えた属名で hydro 水 khelidon ツバメ (Gk)。ハシグロクロハラアジサシと当時の学名で Hydrochelidon leucoptera の2種を含んでいたが Gray (1841) がハシグロクロハラアジサシをタイプ種と判定した。Chlidonias 属 (Rafinesque 1822 年 2 月) の方がわずかに早く属名シノニムとなった。
Hartert (1910-1922) p. 1682 はこの点を承知していたが、Chlidonias melanops を唯一の種として命名された属だったために種同定の問題があること、Chlidonia (外肛動物) の属名の用例がすでにあるために preoccupied の可能性があり、Hartert はより確実な Hydrochelidon 属を用いたとのこと。
Chlidonia と Chlidonias は別物との判定がなされなければ現在でも Hydrochelidon の属名が用いられていたかも知れない。
Chlidonias 属もハシグロクロハラアジサシを指すものと判定されタイプ種となった (一部 The Key to Scientific Names より)。
[亜種]
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 niger 亜種ハシグロクロハラアジサシ と surinamensis (スリナムの) アメリカハシグロクロハラアジサシとされる。
surinamensis の 原記載 (Gmelin, 1789)。別名 Surinam Tern (Latham)。
"Hirondelle de mer grande espece" (Fermin 1769) (The Key to Scientific Names)。
過去に用いられた学名には "ハシグロ" に相当するものが見当たらないので、クロハラアジサシの和名が確立した後に作られた和名であろうか。日本産亜種のシノニムには Sterna melanops Rafinesque, 1822 (参考) があって多少近いが嘴を直接指したものではない。
初野 (2003) Birder 17(10): 102-103 東京湾におけるアメリカハシグロクロハラアジサシの観察 (2000.7.9 の記録。erect-posture display, courtship feeding が記録されている)。
梅垣 (2020) Birder 34(5): 48-51 に亜種の識別が述べられている。東日本はアメリカハシグロクロハラアジサシが中心か?
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES トウゾクカモメ科 STERCORARIIDAE ▽
-
オオトウゾクカモメ
- 学名:Stercorarius maccormicki (ステルロラーリウス マックコルミクキ) マックコーミックの糞を食べる鳥
- 属名:stercorarius (adj) 糞の
- 種小名:maccormicki (属) マックコーミックの Robert McCormick 英国の軍医、探検家
- 英名:South Polar Skua
- 備考:
stercorarius は#クロトウゾクカモメ参照。
maccormicki はラテン語風読みとした。-cor- がアクセント音節と考えられる (マックコルミクキ)。
単形種。
シノニムに Catharacta matsudairae Taka-Tsukasa, 1922 があった (参考)。
この属名はコンドル類の Cathartes と似ているがギリシャ語文字が異なって直接の関係はない (古く関連があったかも知れないが)。
#クロウミツバメが亜種として記載されたのと同じ年。
オオトウゾクカモメの記載時学名は Stercorarius maccormicki Saunders, 1893 (原記載) とだいぶ早く、"matsudairae" は付かなかった。
当時は Great Skua の一種と考えられたことは見て取れる通りで、現在は Great Skua は キタオオトウゾクカモメ Stercorarius skua (こちらの方が例えば英国ではより一般的な種類で本家と言えるが和名は逆になっている) を指すが当時は集合名詞的に扱われていたと想像できる。オオトウゾクカモメ の "オオ" も英名に対応させたものかも。
-
トウゾクカモメ
- 学名:Stercorarius pomarinus (ステルコラーリウス ポーマリヌス) 鼻孔の覆われた糞を食べる鳥
- 属名:stercorarius (adj) 糞の
- 種小名:pomarinus (合) poma 覆い (Gk) rhinos 鼻孔 (Gk)
- 英名:Pomarine Skua, IOC: Pomarine Jaeger
- 備考:
stercorarius は#クロトウゾクカモメ参照。
pomarinus は綴りだけからは語構成が明確でないが、Pomarinus 属記載 (Fischer von Waldheim 1803) の Die Oeffnungen der Nasenloecher unter einem Deckel gestellt (両鼻孔が1つの覆いの下にある) に由来すると解釈される (The Key to Scientific Names)。
ギリシャ語由来で poma (ポーマ。覆い) に長母音が含まれる。-rinus は rhis, rhinos (鼻孔) の短縮形と考えられるがこれらは長母音を含まない。po- 以外は短母音とすると -ma- がアクセント音節となる (ポーマリヌス)。
属記載時のドイツ語では Pomarin と呼ばれていた。
IOC 14.2 段階で性だけ違うように見える種小名がアシナガワシ Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle に現れるがこちらは地名由来で別語源のよう (#カラフトワシ備考参照)。
トウゾクカモメの記載時学名 Lestris pomarinus Temminck, 1815 基産地 Arctic regions of Europe (Avibase による)。原記載 だが非常に読みにくい。
フランス語名 Stercoraire pomerin。ページ下の方にある Les jeunes de l'annee は1年めの若鳥の記述。属記載の方が古く、属記載の時点では Pomarinus fuscus の名称だった (参考 1, 2)。
種記載として認められなかったか、fuscus はどこにでもある名前なので属統合などで preoccupied となって有効な学名とならなかった可能性がある [過去の学名を見ると Larus 属に入っていたこともあったようで、この場合はもちろん(ニシ)セグロカモメの用例がある]。
Temminck (1815) が新属を用いて命名した Lestris pomarinus が有効な初記載となったものと想像できる。
属名あるいは当時使われていた通称をそのまま用いているため種小名の意味は特に触れられていないと想像できる。Temminck による Lestris の 属記載。
lestris は女性の盗賊 (Gk, The Key to Scientific Names)。
もっともアシナガワシの方の地名は "海のそば" の意味由来で、必ずしも語源の明確でないトウゾクカモメも "海のそば" の可能性はないのかと思ってしまう。
単形種。skua がイギリス英語、jaeger がアメリカ英語の呼び方。skua は キタオオトウゾクカモメ Stercorarius skua 英名 Great Skua のフェロー語での名称 skugvur に由来。
jaeger (イエイガー) はドイツ語 Jaeger (狩るもの) に由来し、英名の発音もドイツ語に近いものになっている。ちなみにドイツ語で jagen (ヤーゲン) 狩る、Jagd (ヤークト) 狩り。
トウゾクカモメの総称としてドイツ語で Raubmoewen ラウプメーヴェン 略奪カモメ (総称なので複数形。日本語名称とほぼ同じ意味) と呼ばれるが、個々の種についてはこの単語も skua も使われていて統一されているわけではないようである。
ドイツ語 Raub- は Raubvogel (ラウプフォーゲル) 猛禽 のような使い方がされるが、タカ類を指す猛禽類のドイツ語名は Greifvogel (グライフフォーゲル、いずれも単数形を挙げた) の方が一般的。greifen (掴む) に由来するが、ワシの頭をライオンの体を持つ伝説の怪獣グリフォンもドイツ語では Greif なので、語から受ける印象はこちらの方がずっと良いのだろう。
またトウゾクカモメは「掴む」ことはできないので Greif- とは呼べないだろうし、どちらにも Raub- を使うよりも使い分ける方がそれぞれの習性をより反映できるということだろう。
これも水鳥の系統的制約の現れで、本格的な猛禽類の登場は近代的な陸鳥の進化を待つ必要があったことを意味するのかも知れない (#ミサゴの備考参照)。
主に労働寄生 (kleptoparasitism, cleptoparasitism) を行うグループの典型例とされる (#トビの備考参照)。
Young Guns (2014) Birder 28(5): 48-50 にトウゾクカモメ、クロトウゾクカモメ、シロハラトウゾクカモメの識別についての記事がある。
-
クロトウゾクカモメ
- 学名:Stercorarius parasiticus (ステルコラーリウス パラスィーティクス) 寄食性の糞を食べる鳥
- 属名:stercorarius (adj) 糞の
- 種小名:parasiticus (adj) 寄食性の
- 英名:Arctic Skua, IOC: Parasitic Jaeger
- 備考:
stercorarius は stercus, stercoris ともに短母音のみ。形容詞を作る -arius は冒頭が長母音でアクセントもある (ステルコラーリウス)。
日本語にすると Larus の発音に似るが無関係で r と l の音も違う。
属名の由来は他の鳥を襲って吐き出させたものを食べる習性があるが、糞を食べていると誤解されていた。以前は Dung-hunter と呼ばれていた。
parasiticus は1つめの i が長母音でアクセントもある (パラスィーティクス)。英語の parasitic (托卵性などに使われる形容詞) も -si- が短母音だがアクセントがある。ご存じのように名詞の parasite の発音は異なる。英語の発音規則の難しいところ。
parasiticus の語源はギリシャ語で para (脇に) sitos (スィートス。食物) で長音の由来となっている。
英名の Parasitic Jaeger は学名と同じ意味でこれはアメリカ英語。Arctic Skua がイギリス英語。
学名シノニムが多数あり、Arctic Skua の由来となったと想像できるのは Lestris arctica Dubois, 1860。
単形種。Stercorarius のタイプ種。
-
シロハラトウゾクカモメ
- 学名:Stercorarius longicaudus (ステルコラーリウス ロンギカウドゥス) 長い尾の糞を食べる鳥
- 属名:stercorarius (adj) 糞の
- 種小名:longicaudus (adj) 長い尾の (longus (adj) 長い caudus (m) 尾)
- 英名:Long-tailed Jaeger
- 備考:
stercorarius は#クロトウゾクカモメ参照。
longicaudus は短母音のみで -ca- にアクセントがある (ロンギカウドゥス)。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは pallescens (淡い色の) とされる。
△ チドリ目 CHARADRIIFORMES ウミスズメ科 ALCIDAE ▽
-
ヒメウミスズメ
- 学名:Alle alle (アルレー アルレー) アレーと鳴く鳥 (誤命名)
- 属名:alle サーミ語 (スカンジナビア半島、および、ロシアのコラ半島に住む先住民、サーミ人が使用する言語。古くはラップ語の名でも呼ばれていたが、現在この呼称が用いられることはほとんどない) によるコオリガモの鳴き声から。コオリガモとヒメウミスズメの冬羽を混同して命名された。
- 種小名:alle (トートニム)
- 英名:Little Auk
- 備考:
alle は The Key to Scientific Names によれば e が長音。ラテン語ではここにはアクセントは置けないので "アルレー" となる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。Alca alle Linnaeus, 1758 と命名されたもので、alle は種小名で使用されたもの。系統解析の結果単形属の Alle 属として分離された。2亜種あり (IOC)、日本で記録されるものは亜種不明とされる。
-
ハシブトウミガラス
- 学名:Uria lomvia (ウリア ロムウィア) ウミガラス
- 属名:ouria Athenaeus が記載した水鳥の一種 (Gk)
- 種小名:lomvia (外) ウミガラス (lomvia ウミガラスまたは潜るもの スウェーデン語)
- 英名:Brunnich's Guillemot, IOC: Thick-billed Murre
- 備考:
uria は#ウミガラス参照。
lomvia は外来語のため発音はよくわからないが、アクセントは冒頭と考えられる (ロムウィア)。
デンマーク語 lomvie の起源となるフェロー語 (Faroese) でもアクセントは冒頭で短母音なのでこの発音でよいと思われる。
4亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは亜種 arra [Pallas (1811) によればカムチャツカでウミガラス類を指す地方名 Ahr'-rah から (The Key to Scientific Names)]。
Guillemot がイギリス英語、Murre がアメリカ英語での呼び方。いずれも William の人名から導かれたフランス語に由来するとされる (フランス語の対応する人名 Guillaume、現在のフランス語での鳥の名前は Guillemot) (wikipedia 英語版)。
-
ウミガラス
- 学名:Uria aalge (ウリア アアルゲ) ウミガラス
- 属名:ouria Athenaeus が記載した水鳥の一種 (Gk)
- 種小名:aalge (外) ウミガラス (aalge ウミガラス デンマーク語 < 古ノルド語 Alka オオハシウミガラス)
- 英名:Common Murre
- 備考:
uria は起源となるギリシャ語をそのまま解釈すると冒頭が長母音となる。アクセントもこの位置にある。wiktionary では伸ばさない発音が挙げられている (ウリア) が語頭のため伸ばさいなものか。伸ばす発音もある (ウーリア) ので誤りではない。
aalge は外来語のため発音はよくわからないが、アクセントは冒頭と考えられる (アアルゲ)。デンマーク語でも現在は Lomvie が種名で現在の発音にも現れない。
5亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは inornata (飾りのない) とされる。
Tiunov et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the common murre Uria aalge (pp. 4247-4260)
ロシア沿海地方での繁殖。
Heather et al. (2024) Catastrophic and persistent loss of common murres after a marine heatwave
2014-2016 年の海水温の異常上昇でアラスカのウミガラスのコロニーで推定 400 万羽が死亡。その後も回復していないとのこと。
Surveys show full scale of massive die-off of common murres following the 'warm blob' in the Pacific Ocean (一般向け英文解説)。ベーリング海東部のコロニーでは 75% も減少した。
この生態系の頂点捕食者であるため生態系のフレームシフトをもたらす可能性があるとのこと。
海水温が 1 ℃上昇した状態が半年続くといろいろな海鳥の大量死につながるとのこと。Jones et al. (2024) Marine bird mass mortality events as an indicator of the impacts of ocean warming、
Marine heat waves caused mass seabird die-offs, beach surveys show (一般向け英文解説)。
この報道に関係して英名の一般名が Common Murre のため「個体数が多い」と誤解されるおそれがあり、地域を指した名称に変更した方がよいとの意見も BirdChat に出ていた。
ウミガラス類は一般的にクラッチサイズが1卵で、小型 (全長 35 cm) のハジロウミバト (検討種) は2卵とのこと。
ウミガラス、オオハシウミガラスとも1卵で、絶滅したオオウミガラスも1卵と記録されている。系統は多少異なるがウトウも1卵。
ミズナギドリ目ほどは遠洋性ではないが、やはり K 戦略的と言えるのだろう (#カワウの備考 [ウの増加と生態系への影響] 参照)。
再生産性が低いので、このような鳥を大量捕獲したり卵を大量採取すると簡単に絶滅してしまうことになる。オオウミガラスはヨーロッパからアクセスしやすい場所で繁殖し、飛べないため分散能力も低く悲劇となった。
体サイズで比較すればはるかに大きいのに2卵を毎年産むイヌワシには r 戦略的な要素があるのだろう (#クマタカ備考 [クマタカ類の隔年繁殖の理由?])。
[ペンギンの名称由来]
現在の penguin の語源ともなったオオウミガラスに対する用例は OED によれば 1577 年が初出とのこと。語源はウエルシュ語の pen gwyn (白い頭) だろうとなっている。フランス語やオランダ語にも類似の単語があるが、いずれも英語より遅く英語由来と考えられるとのこと。
Penguin Island の名称が 1536 年に現れたとの説があるが否定され、伝説であろうとのこと。
ウエルシュ語の pen- は突端の意味もあるためこれを冠した地名由来の可能性もあるとのこと。
脂肪分が多いことが知られていたことから別説のラテン語 pinguis (脂肪) があるとのことで、OED では古くは pin- で始まる用例がいくつかの言語にあることから関連がある可能性がある立場をとっている。ドイツ語では Fettgans (太ったガチョウ) を 18 世紀に penguin にも用いたとのこと。
飛べない翼を表した pin-wing 説は支持されないとのこと。
-
オオハシウミガラス (第8版で検討種)
- 学名:Alca torda (アルカ トルダ) オオハシウミガラス
- 属名:alca (外) 古ノルド語 Alk, Alka オオハシウミガラス)
- 種小名:torda (外) tord オオハシウミガラス スウェーデンのゴットランド方言。スウェーデン本土では tordmule または turmule と呼ばれていたが、Linnaeus が 1741 年ゴットランド島で採集したため (The Key to Scientific Names
- 英名:Razorbill
- 備考:
alca は外来語のため発音はよくわからないが、短母音とすれば "アルカ"。
torda は外来語のため発音はよくわからないが、短母音とすれば "トルダ"。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で検討種に移動。単形属。2亜種があり、日本で記録されたものは islandica (アイスランドの) とされていた。
-
ウミバト
- 学名:Cepphus columba (ケププス コルムバ) ハトを思わせるウミスズメ
- 属名:cepphus kepphos アリストテレス他が記述した淡色の水鳥の一種で現在どの鳥かは不明
- 種小名:columba (外) Klumba ウミスズメ(類) アイスランド語 および columba (f) ハト < ギリシャ語 kolumbao 潜る、(水に) 突っ込む、泳ぐ (wiktionary)
- 英名:Pigeon Guillemot
- 備考:
cepphus は外来語のため発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音なので長母音は現れないと考えられる (ケププス)。
columba は短母音のみで -lum- がアクセント音節 (コルムバ)。
ラテン語でハトを意味する columba はこれに由来し、ギリシャ語ではもとは海鳥だった [ギリシャ語 kolumbao は潜る、(水に) 突っ込む、泳ぐ。wiktionary]。この意味では "ウミバト" の方がハトの本家とも言える。
#コチョウゲンボウの種小名にもハトの方の意味で登場する。
一方モリバトの種小名の由来となるラテン語でモリバトの palumbes (#オオタカの学名とも関係あり) はイタリア祖語の *palwos < インド・ヨーロッパ祖語の *plH-wo- (暗色の、灰色の) < *pelH- (灰色) で羽色を指すとのこと (wiktionary)。ハト類を表すギリシャ語は多数あり、ハト類の属名には困らなかったようだが columba と palumbes の用例と語源が入り混じっていることを見ておくと面白い。
Pallas (1811) によれば Columba groenlandica Auctorum で、Ray (1678) が Columba Groenlandica (グリーンランドのハトまたはウミガメ) と記述したものはハジロウミバト Cepphus grylle。ハジロウミバトが Cepphus 属のタイプ種。
なぜハトまたはウミガメの名が当てられたかはよくわからない。ウミガメの大きさでハトのように2卵を産む点は共通点はあるが。声が似ているのかも知れない、と記述している。
wikipedia 日本語版にはハトを思わせる容貌の写真が出ている。
5亜種が認められている (IOC)。日本で記録されたものは snowi (英国航海士で狩猟家の Henry James Snow にちなむ) 亜種ウミバト と kaiurka [ロシア語でウミツバメ類を表す kachurka を誤ってウミガラス類に付けたもの (The Key to Scientific Names)] アリューシャンウミバト。
kachurka はポーランド語でカモを指す kaczka 由来と思われるとのこと (Kolyada et al. 2016)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では当時の学名で Uria columba Kurile Is., Hokkaido, Yokohama にウミバト、
Cepphus snowi Kurile Is. にチシマウミバトの和名が与えられていた。
-
ケイマフリ
- 学名:Cepphus carbo (ケップス カルボー) 炭のように黒い水鳥
- 属名:cepphus kepphos アリストテレス他が記述した淡色の水鳥の一種で現在どの鳥かは不明
- 種小名:carbo (m) 炭
- 英名:Spectacled Guillemot
- 備考:
cepphus は#ウミバト参照。
carbo は語末が長母音 (カルボー)。短く読んでもよい。
単形種。
ウミバトと遺伝的距離が近い (#カルガモ の備考参照)。
-
マダラウミスズメ
- 学名:Brachyramphus perdix (ブラキュラムプス ペルディークス) ヤマウズラのような短い嘴の鳥
- 属名:brachyramphus (合) 短い嘴の (brachy- (接頭辞) 短い ramphos 嘴 Gk)
- 種小名:perdix (m) ヤマウズラ
- 英名:IOC: Long-billed Murrelet
- 備考:
brachyramphus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-ram- がアクセント音節と考えられる (ブラキュラムプス)。
perdix は i が長母音でアクセントは冒頭 (ペルディークス)。起源となるギリシャ語でも同様に発音されていた。
1998 年まで アメリカマダラウミスズメ Brachyramphus marmoratus 英名 Marbled Murrelet の亜種とされていた。分子遺伝学研究で分離された (wikipedia 英語版)。旧英名 Marbled Murrelet はその時代のもの。少し古い図鑑ではこちらの学名・英名で載っている。
英語 Murrelet は Murre の指小語。単形種。
marmoratus は marbled (大理石模様の) の意味。
ウミスズメ類では珍しくコロニーを作って繁殖しない。1961 年に北海道で繁殖が確認された (コンサイス鳥名事典)。
アメリカマダラウミスズメ Brachyramphus marmoratus Marbled Murrelet について、音声を受動的に録音してニューラルネットで判別する生殖調査が紹介されている。
Duarte et al. (2024) Passive acoustic monitoring and convolutional neural networks facilitate high-resolution and broadscale monitoring of a threatened species
(英文解説)。
IUCN EN 種。海岸から最大 60 マイル離れた内陸部の成熟した林で繁殖するとある (wikipedia 英語版では 90% は 37マイル = 60 km 以内で最大 47 マイル = 75 km とあるのでやや誇張気味の数字か)。
そのため生息確認が難しいが音声モニタリングで分布を調べることができたという研究。
このぐらい単純なソノグラムならば容易に判別できだろうことは想像しやすい。convolutional neural network と言えばわかる人にはすぐわかるだろうし、声が重なっていても判別できるだろうことも想像できる (スズメ目のさえずりはここまでうまく行かない)。
-
ウミスズメ
- 学名:Synthliboramphus antiquus (シュントゥリーボラムプス アンティークウス) 年老いた圧縮された嘴の鳥
- 属名:synthliboramphus (合) 圧縮された嘴の (synthlibo 圧縮する ramphos 嘴 Gk)
- 種小名:antiquus (adj) 古代の、昔の。老人を指す
- 英名:Ancient Murrelet
- 備考:
synthliboramphus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語で sunthlibo (圧縮する) の動詞は i と語末が長母音。語末の o は動詞語尾のため結合で短母音になる可能性があるが i は長母音のままと思われる。rhamphos は短母音のみ。
全体では -ram- がアクセント音節と考えられる (シュントゥリーボラムプス)。"シュントゥリーボーラムプス" の可能性もある。
長い綴りなので長音を入れた方がむしろ読みやすいかも知れない。その場合はこの位置が根拠もありよい候補になる (シュントゥリーボ.ラムプス と少し分ければギリシャ語の音ともよく対応して語調もよい)。ギリシャ語動詞 thlibo の由来は不明とのこと。
ramphus は現代ギリシャ語でも嘴の意味で使われるが語源はあまり明確でないとのこと。rhemphos (口または鼻) は似ているが関係は確実でない (wiktionary)。
antiquus は i が長母音でアクセントもある (アンティークウス)。
英語の antique もほぼ同じ発音でこの発音で違和感がない。
種小名は夏羽の頭部に白髪状の羽があることに由来 (コンサイス鳥名事典)。Pennant (1785) は "Antient Auk" と名付け、後頸部に白く長い羽がまばらにあって、年老いたように見えると記述している。Latham (1785) も "Antient Auk" とした (The Key to Scientific Names)。
#カンムリウミスズメの Temminck の表の中にカンムリウミスズメの学名に対してフランス語名 Vieillard が使われて老人の意味。種小名語義にはこの意味を与えた。
カンムリウミスズメの項目で Pallas の記したウミスズメのシノニムとされるものは Uria senicula Pallas (参考)。クリルやアリューシャンの島近くに多数。カムチャツカ東部沿岸などと示されている。
記載時学名 Alca antiqua Gmelin, 1789 (原記載) 基産地 West of North America to Kamchatka and the Kurile Islands, i.e. Bering Sea (Avibase による)。
Synthliboramphus は Brandt (1837) が提唱した属 (原記載) で後にウミスズメがタイプ種に指定された (The Key to Scientific Names)。Brandt (1837) は属提案に伴って (#ノスリの備考参照) カンムリウミスズメの学名を Synthliboramphus Temminckii と変更していた。
wumizusume はあまりに発音しにくかったのかも知れない。
2亜種あり、日本で記録されるものは基亜種 antiquus とされる。
近くで聞くことができるとまるでスズメのような声で鳴く。
-
カンムリウミスズメ
- 学名:Synthliboramphus wumizusume (シュントゥリーボラムプス ウミズスメ) 圧縮された嘴のウミスズメ
- 属名:synthliboramphus (合) 圧縮された嘴の (synthlibo 圧縮された ramphos 嘴 Gk)
- 種小名:wumizusume (外) ウミスズメ (wumizusume は Temminck による誤記)
- 英名:Crested Murrelet, IOC: Japanese Murrelet
- 備考:
synthliboramphus は#ウミスズメ参照。
wumizusume はそのまま読むしかないがラテン語発音規則から "ウミズスメ" のアクセント位置となる。
単形種。日本野鳥の会が保護活動を行っているように日本近海でしか観察されていない貴重な種類。
天然記念物。絶滅危惧 II 類 (VU)。IUCN 3.1 VU 種。
[学名の話題]
記載時学名は Uria wumizusume Temminck, 1836 (記載)。
この部分ではフランス語名 guillemot wumizusume。
wumizusume は Temminck による誤記と解説される。wikipedia 英語版ではその出典は松田道生 (2001) 蒲谷鶴彦・松田道生「日本野鳥大鑑 鳴き声420」となっているが、
原典は山口隆男 (1994) 日本の鳥類研究におけるシーボルトの貢献 Calanus No. 11 p. 1-150 (熊本大学理学部附属合津臨海実験所) で、「日本野鳥大鑑 鳴き声420」の解説ではオランダ語では s と z の区別が不明瞭であるためと記されている。
wikipedia のオランダ語のページを見ると s と z は現代の標準オランダ語では別の音で、z は一部の方言において [s] として発音されることがあるとのこと。#コゲラの備考で考察のようにフランス語の影響の大きなオランダ語方言かも知れない。z と表記しても s と読んでいた可能性がある。
Wumizusume。Temminck の記載でも huppe (冠) が強調されていて英名の一つの Crested Murrelet (和名と同じ意味) の語源となっているかも知れない。
Uria senicula Pallas, 1811 との比較も述べられていて Pallas の指すものはウミスズメ (この場合シノニムとなる) としている。
senicula は senex, senis 老人の指小形 (The Key to Scientific Names。英訳すると little old woman となっているが属の性に合わせた性別となっている)。
Temminck の記載も朝鮮半島と日本となっており (Avibase の基産地 Shores of Japan and Korea)、現代的な視点では Crested Murrelet の方がふさわしい英名かも知れない。
一方 Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux... の一覧表では同じ学名に対してフランス語名 Vieillard の名称と Brandt が Synthliboramphus の属名を与えたことが示されている。
vieillard は老人の意味。これはウミスズメの学名や英名に相当するため、カンムリウミスズメとウミスズメに混乱があり、和名のウミスズメを種小名に用いた可能性がある。
上記本文の方では Brandt がウミスズメに Synthliboramphus antiquus を与えたと記述されているのでどこかで混線が生じていたのかも。
Mlikovsky (2012) The dating of Temminck & Schlegel’s Fauna Japonica: Aves, with implications for the nomenclature of birds によれば Temminck and Schlegel (1850) は Uria umisuzume と訂正した学名を出していたが、規則によりこれは無効とのこと。
Temminck も綴りを誤ったことに気づいていたのかも知れない。
[音声]
ネットで公開されている音源はごく最近 (2017) までなかった (把握している範囲で現在3例のみ。日本野鳥の会の音源)。船舶の音に紛れて録音も難しく、録音に適した環境で観察できる方はぜひ録音と海外の公開データベースへの登録を行っていただきだい (日本語の動画ページのみだと海外研究者が気づくのは困難)。
出版物では上田秀雄 (1998) 山渓・鳴声CD「野鳥の声283」(英訳版 283 Wild Birds Songs of Japan も発行: 参照) に収録されている(なおウミスズメは収録されていない)。蒲谷鶴彦・松田道生「日本野鳥大鑑 鳴き声420」(小学館 2001) にも収録されているが波の音も混ざっているとのこと。
ウミスズメは世界にそれなりの音源が存在する。世界の野鳥の音声記録を調査している Shaun Peters によるリストでは、カンムリウミスズメはこの2点の出版物がリストされている。
上田ネイチャーサウンド Ueda Nature Sound ではこの2種とも「収録済 未アップの種」となっている (2025.3 現時点)。
[スクリップスウミスズメ]
カリフォルニア沖のサンタ・バーバラ島でスクリップスウミスズメ Synthliboramphus scrippsi Scripp's Murrelet の主な捕食者がメンフクロウだが、エルニーニョ振動の影響で餌となる固有のネズミ (deer mouse Peromyscus maniculatus elusus) 数が減少し、スクリップスウミスズメの被食が 15 倍に増えたという:
Thomsen et al. (2018) El Nino/Southern Oscillation-driven rainfall pulse amplifies predation by owls on seabirds via apparent competition with mice。
同様にこの固有のネズミが干ばつの影響で餌不足となり、スクリップスウミスズメの卵を捕食するとのこと: Thomsen and Green (2019) Predator-mediated effects of severe drought associated with poor reproductive success of a seabird in a cross-ecosystem cascade。
-
ウミオウム
- 学名:Aethia psittacula (アエティア プスィトゥタクラ) 小さなオウムのような海鳥
- 属名:aethia (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:psittacula (f) 小さなオウム (psittacus (m) オウム -ula (指小辞) 小さい)
- 英名:Parakeet Auklet
- 備考:
aethia は#エトロフウミスズメ参照。
古い属名は Cyclorrhynchus で kuklos (輪) rhunkhos (嘴) Gk 由来。特徴ある嘴のウミオウムを指す属名で Kaup (1829) が付けたもの。現在は Aethia 属に含められた。
psittacula はラテン語 psittacus および起源となるギリシャ語の psittakos いずれも短母音のみ。psi- の綴りはギリシャ文字由来。指小辞 -ula も短母音のみ。-ta- がアクセント音節と考えられる (プスィトゥタクラ)。psit-ta-cu-la と分けられるため psit の t を分けているが (本来読み)、tt を t の長音として読む読み方もあるとのこと。
実際上は "プシッタクラ" で問題ないと思われるが (英語読みでは p をおそらく読まないので英語読みというわけでもない) お好みに応じてどうぞ。
オウム病の psittacosis は英語読みでは "スィタコウシス"。
単形種。
-
コウミスズメ
- 学名:Aethia pusilla (アエティア プスィルラ) ごく小さい海鳥
- 属名:aethia (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:pusilla (adj) ごく小さい (pusillus)
- 英名:Least Auklet
- 備考:
aethia は#エトロフウミスズメ参照。
pusilla は短母音のみで -sil- がアクセント音節 (プスィルラ)。
単形種。
-
シラヒゲウミスズメ
- 学名:Aethia pygmaea (アエティア ピュグマエア) ピグミーの海鳥
- 属名:aethia (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:pygmaea (adj) ピグマエイーの (伝説の小人族 pygmaeus)
- 英名:Whiskered Auklet
- 備考:
aethia は#エトロフウミスズメ参照。
pygmaea は -ma- がアクセント音節になる (ピュグマエア)。
#ヘラシギ では原記載の綴りが異なっておりややこしい問題となった。
単形種。
-
エトロフウミスズメ
- 学名:Aethia cristatella (アエティア クリスターテルラ) 小さな冠羽のある海鳥
- 属名:aethia (合) 海鳥 (aithuia 海鳥 Gk)
- 種小名:cristatella (adj) 小さな冠羽のある (cristatus (adj) トサカのある -ella (指小辞) 小さい)
- 英名:Crested Auklet
- 備考:
aethia は起源となるギリシャ語 aithuia は "アイテューア" が元来の読み方で、短縮された読み方でも "エテュア" とアクセントは冒頭。
アクセント位置を重視するか長音を採用するか次第だが "アエティア" または "アエティーア" と考えられる。ここでは前者を採用しておくがどちらも根拠があるのでどちらでもよいと思われる。
cristatella は cristatus の a が長母音で指小辞 -ella は短母音。-tel- がアクセント音節と考えられる (クリスターテルラ)。
記載時学名 Alca cristatella Pallas, 1769 (原記載)。基産地北海道からカムチャツカ。英名と学名はよく対応する。
単形種。Aethia 属のタイプ種。
長谷 (1997) Birder 11(7): 46-54 に油流出事故に遭ったエトロフウミスズメの保護・飼育日記がある。
[においを用いたディスプレイ]
においによるコミュニケーションをとる鳥として非常に有名。コロニーの近くでは強烈な柑橘のにおいがするという。ウミスズメ、柑橘の香りを出してメス誘う、研究 (ナショナルジオグラフィック)。"ruff-sniff" と呼ばれる首の周りの羽毛のにおいを嗅ぎ合うディスプレイを行う。
Hector D. Douglas III による博士論文 (2006): Odors and ornaments in crested auklets (Aethia cristatella) signals of mate quality?。
Hagelin (2007) The citrus-like scent of crested auklets: Reviewing the evidence for an avian olfactory ornament。
これは当初外部寄生虫やカなどの防御のための化学物質 (体臭) と考えられ、その視点を中心に研究が進められていた: Douglas III et al. (2001)
Heteropteran chemical repellents identified in the citrus odor of a seabird (crested auklet: Aethia cristatella): evolutionary convergence in chemical ecology (当時から配偶者選択に関係するアイデアはあった);
Douglas III et al. (2004) Interspecific differences in Aethia spp. auklet odorants and evidence for chemical defense against ectoparasites;
Douglas III et al. (2005) Chemical odorant of colonial seabird repels mosquitoes。
Hagelin et al. (2003) A tangerine-scented social odour in a monogamous seabird のような行動的・実験的証拠から配偶者選択に用いられていることが明らかになってきた(論文中に "ruff sniff" の首の周りの羽毛のにおいを嗅ぎ合う不思議なディスプレイの写真が示されている。集団でもディスプレイを行う。この部位が最も臭気が強いそうである)。
Douglas III (2013) Colonial seabird's paralytic perfume slows lice down: an opportunity for parasite-mediated selection? はさらにその臭気が外部寄生虫防御に役立つことを介して配偶者選択に有益であろうとの仮説を提唱している。
Weldon and Rappole (1997) (#フルマカモメの備考参照) も文献上臭気のある鳥に含めている。
[鳥類の嗅覚]
「鳥たちの驚異的な感覚世界」は比較的新しい本であるにもかかわらず、この面白い話がなぜか記載されていない。代わりに従来は鳥が嗅覚が劣っているが一部の鳥は餌探しに嗅覚を用いていることが判明した経緯などが記されている。古典的には脳の中の嗅球と言われる部分の大きさが嗅覚に関係があることは知られていた。
遺伝子解析が主流となった現代では嗅覚受容体 (olfactory receptor; OR) の遺伝子数を目安とすることが多い。この遺伝子グループは起源が非常に古く、鳥類や哺乳類の獲得免疫のメカニズムとは違って1つの嗅覚受容体が1つの遺伝子に対応するため嗅覚受容体遺伝子数の多い生物ではゲノムのかなりの割合を占める
(例えばヒトで 396 個で、機能しない偽遺伝子を含めると 821 個でゲノム中の全遺伝子の 4-5% を占めているそうである: wikipedia 日本語版より)。この数字は鳥類の嗅覚の話を読む時に参考になるだろう。
#ハチクマの備考に出てくる論文によれば (偽遺伝子を除いて) キンカチョウのようにヒトに近い数の嗅覚受容体遺伝子数を持つものもある。
ハチクマでは偽遺伝子を含めると 283 個で一部調べられた範囲の遺伝子のうち 81.5% が機能していた。ヒトよりは多少劣りそうだがそこそこの嗅覚を持ってそうである。
イヌワシでは偽遺伝子を含めて 57 個とあまり嗅覚を使っていないらしいことがわかる [Policarpo et al. (2024) の研究でだいぶ増えた]。さらに興味ある方はこの文献の引用文献などを見られるとよい。
一般に水鳥は嗅覚受容体遺伝子数が後に進化したタイプの陸鳥より多く、より嗅覚に頼った生活をしていることが想像できる。鳥がどんなにおいの世界を感じているか想像しながら観察するのも面白いであろう。
Policarpo et al. (2024) Diversity and evolution of the vertebrate chemoreceptor gene repertoire
に 2022 年段階の公開ゲノムデータを用いた新しい研究が出ていた。鳥類の甘み感覚などの研究で有名な Baldwin のグループによる。
全脊椎動物を扱い、さまざまな化学受容体を扱っているので膨大な資料があるが、嗅覚遺伝子数については Source Data に個々の種のデータが含まれている。
これにはハチクマはまだ含まれていないが complete OR (完全な OR 遺伝子数) で見ると、オオタカ 275、ハイタカ 46、イヌワシ 119、ソウゲンワシ 57、ノスリ (なぜかヨーロッパでなく日本と同種のノスリ) 49、ハヤブサ 154、シロハヤブサ 60 などとなっていた。近い系統で数がだいぶ違うので個々の種を議論する場合はゲノム精度次第の感じもある。
10 程度の OR 遺伝子数 の低いものも多数あるが、これらはゲノムの精度が低いのだろうと想像する。
オオタカの精度がおそらく高く多くの遺伝子が検出されているのだろう。ハチクマが特に多いとは言えないかも。カリフォルニアコンドルも 183 と特に多いわけではない。
カナダガン 678、オオバン 717 などが多いのはわかるが、ムラサキツバメが 1087 など今ひとつ意味がわからないものもある。ゲノム精度次第かも知れない。
エトロフウミスズメや Aethia 属は含まれていなかった。
Zhou et al. (2019) Comparative genomics sheds light on the predatory lifestyle of accipitrids and owls
の先行研究があって、この研究では昼行性猛禽類は紫外線に晒されるので DNA 修復に関係する遺伝子が正の選択を受けているはずとの動機でゲノムを調べたもので、XRCC5 遺伝子にタカ類固有の変異があるとのこと。嗅覚や味覚の情報が副産物で得られて猛禽類の嗅覚はこれまで考えられていたほど鈍くないことを示していた。
また苦味受容体の TAS2R の偽遺伝子化はなく、草食種ほどではないかも知れないが苦味を情報として用いていることがわかる。ミナミツミとコノハズクのゲノムの初の解読とのこと。
#メジロの備考 [鳥類の嗅覚] にタカ類の苦味受容体の研究が含まれている。新世界ハゲワシ類は苦味に鈍感らしいとのこと。
[Policarpo et al. (2024) に戻る] カメ類、ワニ類、鳥類は鋤鼻器 (vomeronasal organ 別名ヤコブソン器官 Jacobson's organ) を完全に持たないか存在するか議論されている段階だが、フェロモンに関係する V1R, V2R 遺伝子はこれらの系統でほとんど失われていた。形態的知見と遺伝子がよく一致していた。
予想に反して V1R が完全に失われていない鳥もあったとのことだが遺伝子にかかる選択圧は弱く、大した役割はなくて偶然残ったものと考えられるとのこと。「鳥はフェロモンを持たない」はおおむね正しそう。
「鳥のフェロモン」の研究の歴史などの総説は Caro and Balthazart (2010) Pheromones in birds: myth or reality? を参照。
ワニは甘み受容体 (T1R2) を持っているのに鳥類では失われた。一部の系統の甘み感覚は別の受容体の機能を変えることで獲得したもの。
鳥類が他の脊椎動物に比べて嗅覚を含めた化学知覚を比較的失っている傾向は読み取れる。
適応的意義を考えるならば飛翔中は嗅覚などの化学知覚が比較的役に立たないため、とも理解できそうだが、化学知覚は進化が進むにつれて失われる傾向が強く、遺伝子重複で新たに得られるのは脊椎動物の進化の初期段階に限られた。
化学知覚は 1遺伝子 = 1つの知覚 となるため多数の遺伝子が必要で、たとえて言えば古い機械のようなもの。維持コストが高いので必要性が下がれば比較的簡単に失われるのだろう。
視覚や聴覚は少数遺伝子を組み合わせた部品の少ない現代の機械のようなもので、プログラム可能な新しいタイプの知覚と言えそう。こちらは物理知覚である点も異なる。
嗅覚遺伝子は両生類と哺乳類を含むそれ以降の間でかなり失われた (水環境を離れると必要性が大きく下がるのだろう)。爬虫類から鳥類の間でさらに1系統の嗅覚遺伝子が失われた。
このように見ると化学受容体は感覚としては古いもので系統進化とともに次第に失われ、哺乳類が嗅覚や味覚に鋭敏な種類が多いのは古い性質を引き継いでいるためとみると理解しやすい。
鳥類・哺乳類を合わせて高等脊椎動物とまとめるのは少なくとのこの文脈ではふわさしくなさそう。
ヒトがあまり哺乳類らしくないためヒトだけを見ると典型的な哺乳類の特徴がわかりにくい可能性がある。ここでも鳥類とヒトはある程度似たところがある。
Soares et al. (2024a) Volatile organic compounds in preen oil and feathers - a review に鳥類の尾脂腺と羽毛の化学物質についての総説がありこれまでの研究からまとめたリストがあるが、文献検索が十分でないようでアカノドカラカラの研究など載っていない。化学物質一覧などが載っている。
Soares et al. (2024b) Analytical characterization of volatiles present in the whole body odour of zebra finches はキンカチョウ全身から放出される揮発性化学物質を分析したもの。検出された物質のうちにおいのわかるものはどのようなにおい (flavour language) かまで記されている。尾脂腺抽出物との重なりも大きいが全身をサンプルしないと検出されなかったものもある。
アオミズナギドリ Halobaena caerulea Blue Petrel が巣穴に戻るのに嗅覚を役立てているらしい研究: Zidat et al. (2023) Homing and Nest Recognition in Nocturnal Blue Petrels: What Scent May Attract Birds to their Burrows?
古くから嗅覚を利用していることが提唱され、Bonadonna et al. (2004) Recognition of burrow's olfactory signature in blue petrels, Halobaena caerulea: an efficient discrimination mechanism in the dark が実験的に場所を手がかりとしてことを示唆する結果を得ていた。
実際に化学物質を分析してどんな物質が含まれているか調べた。
エトロフウミスズメの wikipedia 英語版には配偶者選択のためのさまざまな信号 (視覚、聴覚、嗅覚) がどのようなメカニズムで進化するかの仮説まで述べて解説してある。これは不自然なほどの信号、例えばクジャクの飾り羽、ニワシドリ類の「あずまや」、サンコウチョウの尾羽などが性選択によってどのように進化したかを考える上でも役立つ一般的なものである。
嗅覚の問題は #オオルリの備考で、[構造色について] から派生して [どの感覚をシグナルに用いるか] に視覚と比較したシグナルの進化や遺伝子進化のことも含めた考察を改めて追加した。
ヒトの嗅覚の脳内メカニズムがある程度明らかになった: Kehl et al. (2024) Single-neuron representations of odours in the human brain 鳥類の場合もよく似ていると考えられるので参考になるだろう。
[信号の進化と性選択]
これに関連した面白い書物があり。Prum (2017) "The Evolution of Beauty: How Darwin's Forgotten Theory of Mate Choice Shapes the Animal World - and Us" で邦訳され、リチャード・プラム著、黒沢令子訳「美の進化」(2020 白揚社) として出版されている。
これはその上記仮説のうち「メスにオスの形質に関する何らかの好みが一旦生ずると、メスの選好性とオスの形質が共進化する」ことを示した (フィッシャーが 1915-1930 年に提唱したもの。#トビの備考 [火を使う猛禽類、森林火災、気候変動] 参照)
という「ランナウェイ過程」に今一度光を当てて生物界のさまざまな現象を統一的に説明しようとする実験的な書物と自分は理解している。
この解釈には理論的問題点があり、進化生物学者 (特に鳥類系統の研究などで有名。#アマツバメの備考参照) である Prum もそれは承知の上で世に出したのであろう。理論的問題点があるとは言え、それもある意味単純化した仮説に過ぎないわけで将来克服される余地はあるのかも知れない。
具体的批判も含めて、内容については The Evolution of Beauty ("shorebird 進化心理学中心の書評など") に非常に詳しい。
この書評から少し引用しておくと「メスの識別コストがわずかでもあるなら、平衡点から進化動態は逆転し装飾と選好性は急速になくなる。ただし装飾に壊れる方向の突然変異バイアスがあれば原点近辺で小さな正の装飾性が残る形で平衡になる」。
「行動・生態の進化」(岩波書店 2006) では p. 161, p. 139 に少し分かれた形で登場する。
出典論文は Pomiankowski (1988) "The evolution of female mate preference for male genetic quality" Oxford Surveys in Evolutionary Biology 5: 136-184 と
Pomiankowski et al. (1991) The Evolution of Costly Mate Preferences I. Fisher and Biased Mutation。
さらに Iwasa and Pomiankowski (1994) The Evolution of Mate Preferences for Multiple Sexual Ornaments
いくつかの信号形質がある場合は最も信頼度の高い、コストの大きな形質が信号として使われることが示されれ、ハンディキャップ理論の一般性を高めることとなった (p. 165)。
進化理論に興味のない方であってもこれら (主に) 鳥類の多様な事例は間違いなく面白いだろう、例えば「なぜ鳥類は祖先恐竜が持っていたはずのペニスを失ったのか (カモなどのペニスは二次的に獲得したらしい)」など。
探鳥会などで「なぜカモはオスが美しいのか」と聞かれることもあるだろう。それに対する一つの仮説または話題を提供していると言えるだろう。このページは鳥類に興味をお持ちの方に一読をおすすめする。
この書評は原書について書かれたものだが、訳書情報 「美の進化」 に同じ著者による和訳版への短い書評がある。プラムの本で言及されているものはいかにもバークヘッドの興味を引きそうなものが含まれているが、博識で「変なもの」好きのバークヘッドがなぜエトロフウミスズメに言及しなかったのか、あるいはプラムの挙げた事例に言及しなかったのか不思議なぐらいである。
あるいはマイコドリ類などは専門家に譲る、他は自身の力量を超えると判断したのだろうか。
このような文脈において、ランナウェイ過程に対する進化仮説として「正直なシグナル」(指標説; 優良遺伝子説、さらに限界に挑むような場合にハンディキャップ説) が有力とされるわけで (上記 "shorebird 進化心理学中心の書評など" を参照)、エトロフウミスズメの説明においても「配偶者候補の質を表す信号として進化したと考える仮説が有力」としておけば多分丸く収まるのだろう。
ただし実験的証拠もあるとは言え、研究者も仮説を裏付けるための実験を行うわけで仮説を裏付ける結果が出た論文が書かれるのは当たり前 (どちらとも言えない結果となった研究は論文になりにくい) で、それは (一般的には) 即座に他の仮説を否定するものではない。
(上記 "shorebird 進化心理学中心の書評など" の脚注にある「プラムは、ハンディキャップシグナルに対してランナウェイ過程は、ちょうど自然淘汰に対する中立説の浮動と似ていて、強い因果的な説明がなくても一般的に生じるもので帰無仮説にふさわしいと主張している」も一応紹介しておこう。
一応抜け道が感じられる上に、プラムのこの本か海外書評では不評な理由もなんとなくわかる気がする。この部分は「独り言」レベルに聞いていただいてよい)。
「羽: 進化が生みだした自然の奇跡」(ソーア・ハンソン著 黒沢令子訳 白揚社 2013。著者はプラムの弟子) にもこのあたりの事情が多少説明されていて、ランナウェイ過程は正直なシグナル/ハンディキャップ説と並列の2大仮説との位置づけ。プラムがランナウェイ過程を気に入っているらしいことは少し想像がつく。
なお日本版「美の進化」的な題材 (鳥による芸術) を扱った本として加藤幸子・浜田剛爾・島田璃里・樋口広芳「鳥たちのふしぎ・不思議」(1993 晶文社) がある。進化云々は述べられていないが、事例として「1.雄は華麗なアーティスト」が似た題材を扱っている。
プラムは鳥類学の範囲を超えて Coevolutionary Aesthetics in Human and Biotic Artworlds
というこれも挑戦的な論文も出している。美についての確立した理論がない以上、共進化をベースに生物進化まで起源を遡りたいという主張はわかる気がする。
プラムやバークヘッドは知らないかもしれないが、自分はハチクマのあの特異なディスプレイがどのように進化したのかも興味がある。生存にはまったく役立たないかも知れない。
自分はこれは一種の過剰な「美」ではないかと感じている。バレエに脚を使った同じような技があり、チャイコフスキーの「眠れる森の美女」で「青い鳥」をソロで演ずるダンサーはその技術を競うのである。ハチクマがオス・メスともに行うのは性選択のみの結果とは考えにくく、それ以上の説明が何か必要に感じる。
もっともメスの間でも競争があってどちらの性でも必要とされるものかも知れない。
「眠れる森の美女」の「青い鳥」について舞台裏の解説や鳥の羽の利用の話題があったので紹介しておく: 富田 (2015) バレエ『眠れる森の美女』の舞台衣装のデザイン・制作。舞台上で青い鳥の超絶技巧を演じるのはなかなか大変なよう。
やはり湿度の低いヨーロッパ大陸部向きなのかも。「青い鳥のパドドゥ」で一度登場してから終幕前に再登場するまで結構間隔があるが、その間に舞台裏で乾かしているらしいことが読み取れる。ここでは羽軸根の用語が使われている。羽を利用した衣装では洗うのも大変なのだろう。鳥が汗腺で体温調節をしない理由も納得できるかも。
この「青い鳥のパドドゥ」のコーダの音楽の速度記号は Presto (急速に) と指示されており、バレエでそんな速度で演奏されることはさすがになさそう。ただしオーケストラのみのバレエ音楽の場合には多少速く演奏される場合もある。
チャイコフスキーの音楽では Prestissimo (最も急速に。表記は版によって違うらしい) は有名なピアノ協奏曲第1番の2楽章の中間部に現れる速度指示で、このような軽快な音楽を期待していたのかも知れない。チャイコフスキーはダンサーがひらひらと鳥のように軽快に飛べると思っていたのではないだろうか (笑)。
Matt Ridley 4th Estate (2025) "Birds, Sex & Beauty: The Extraordinary Implications of Charles Darwin's Strangest Idea" の本が出ているとのこと。Style over substance? What birds' mating behaviours reveal about sexual selection (Nature 書評 Tim Coulson 2025.3.31)。
オジロオナガフウチョウ Astrapia mayeri Ribbon-tailed Astrapia のオスの尾は 1 m を超えることがあって体長の3倍以上になるとのこと。
この紹介記事によれば Zahavi (1975) のハンディキャップ原理は有力であったが Hamilton and Zuk (1982) の good genes' hypothesis (優良遺伝子仮説) が提唱されこれまでのところ両者ともに有力な説明になる事例があるとのこと。優良遺伝子仮説の方がより有力である証拠が増えてきていると記述されている。
エトロフウミスズメには学名・英名の通り冠羽があり、これが配偶者選択に用いられるとの見解が一般的で嗅覚を用いていることは長らく考慮されていなかった。鳥類の嗅覚コミュニケーション研究の草分けとなった発見の一つであろう。
その後スズメ目 (主にアメリカの種類) などさまざまな鳥で配偶者選択に嗅覚が用いられている証拠が見つかり、鳥類は嗅覚の発達が悪いとする従来の見解を覆すものとなっている。鳥の嗅覚研究はあまり行われてこなかったためエトロフウミスズメのようなこれまで想像もされなかった発見があるかも知れない。また新鮮な羽毛を拾った場合などはにおいも調べておきたい。
-
ウトウ
- 学名:Cerorhinca monocerata (ケロリンカ モノケラータ) 一角のある嘴の鳥
- 属名:cerorhinca (合) 角のある嘴 (keras 角 rynchos 鼻口部 Gk)
- 種小名:monocerata (合) 一角をもった (mono- (接頭辞) 一つ keras 角 Gk、-atus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Rhinoceros Auklet
- 備考:
cerorhinca の由来は非常に明瞭ではない。変形である Cerorhina は keras, keros 角 のギリシャ語由来とされる (The Key to Scientific Names)。
keras は短母音のみ。ギリシャ語で monokeros に用いられる際は長音 (モノケロース) となっている。kero- の結合で短音化されると考え (不詳)、rynchos 部分も短母音と考えて -rhin- がアクセント音節と考えれば "ケロリンカ"。
短母音のみで発音するのが音声的にも無理がない感じがする。
monocerata もあまり明らかでなく、monoceros はギリシャ語同様に伸ばすがアクセント位置は -no- にある。-ata を所有の接尾辞と考えて冒頭を長母音でアクセントがあると解釈するのがもっともらしい (モノケラータ)。monoceros そのものも学名に使われるのみとのことで一般的な学名の読みに合わせてこの読み方でよいと考えられる。
単形種。
-
ツノメドリ
- 学名:Fratercula corniculata (フラーテルクラ コルニクラータ) 小角状突起のある修道士
- 属名:fratercula (f) 修道士 (fraterculus (m) 修道士 < 小さな兄弟 frater 兄弟 -cula 指小辞)
- 種小名:corniculata (adj) 小角状突起の (corniculatus)
- 英名:Horned Puffin
- 備考:
fratercula は1つめの a が長母音。-ter- がアクセント音節と考えられる (フラーテルクラ)。frater (フラーテル。兄弟) に由来。英語 brother と語源は共通。指小辞 -cula は短母音のみ。
Fratercula 属のタイプ種は ニシツノメドリ Fratercula arctica Atlantic/Common Puffin。
corniculata は cornu (角) + -cula (指小辞) + 所有の -ata で末尾の -ata の冒頭が長母音でアクセントがある (コルニクラータ)。
単形種。属名の意味はおそらくニシツノメドリの堂々とした体格と白黒の衣装から。Olafsen (1774) によればアイスランドの現地名で祭司を意味する名前だった。Willughby (1676) によればニシツノメドリはコーンウォール語で Pope (教皇) と呼ばれていた (The Key to Scientific Names)。
ツノメドリの和名の由来は知らないが、漢字では角目鳥と書かれる。"ツノ" は英名の Horned または学名の corniculata (目の上にある) と共通由来と想像できる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では現在と同じ学名、和名が使われていたが、別学名の属名に Mormon が挙げられていた。ギリシャ神話由来で、意味的には日本語の「いないいないばあ」に近い。Illiger (1811) が Fratercula に代えて与えたもの (The Key to Scientific Names)。
-
エトピリカ
- 学名:Fratercula cirrhata (フラーテルクラ キルラータ) 巻き毛の修道士
- 属名:fratercula (f) 修道士 (fraterculus (m) 修道士 < 小さな兄弟 frater 兄弟 -cula 指小辞)
- 種小名:cirrhata (adj) 巻き毛の (cirratus)
- 英名:Tufted Puffin
- 備考:
fratercula は#ツノメドリ参照。
cirrhata は -rha- の a が長母音でアクセントがある。
かつてはエトピリカをタイプ種として Lunda 属が与えられていたことがあった (Pallas 1811)。フェロー語 (Faeroese) でニシツノメドリを指す。Gessner (1555) の用例に従った (The Key to Scientific Names)。少し古い図鑑ではこの学名を見ることができる。ツノメドリと別属扱いだった時代に使われた属名。
同属にまとめる際に Fratercula Brisson, 1758 (タイプ種は異なる) の方が早くこちらに統一された。
単形種。
エトピリカの嘴が飛行で発生する熱の放熱器官となっているとの研究: Schraft et al. (2019)
Huffin' and puffin: seabirds use large bills to dissipate heat from energetically demanding flight。体に占める面積は 6% だが 10-18% の熱を放出する。嘴の小さな海鳥に比べて遠くまで飛べるかも知れないとのこと。
△ タカ目 ACCIPITRIFORMES ミサゴ科 PANDIONIDAE ▽
-
ミサゴ
- 学名:Pandion haliaetus (パンディーオーン ハリアーエトゥス) パンディーオーン王の海鷲またはミサゴ
- 属名:pandion (m) パンディーオーン (伝説の王の名)
- 種小名:haliaetus (m) 海鷲またはミサゴ (halos 海 aetos ワシ Gk)
- 英名:Osprey, (IOC: Western Osprey 2種と考えた場合の英名。IOC 14.2 では1種扱いとなったため短い英名に戻った)
- 備考:
Pandion はギリシャ語で i, o が長母音のためこれを採用した。i がアクセントで、ラテン語表記でも同じになっている (パンディーオーン) (wiktionary のギリシャ語ページから)。
ギリシャ語でも次第に長音が失われたが i にアクセントを置く点は変化しなかった。短く読む場合でも "ディ" にアクセントを置く日本語でも自然な発音でよい。
haliaetus は a が長母音でアクセントがある。ワシを表す aetus は同様。
記載時学名 Falco Haliaetus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761 (自身によりスウェーデンに限定)。
Haliaeetus はミサゴの種小名であったがそのまま属に昇格ではなく、de Savigny (1809) がオジロワシのみを含む属として定義した
(微妙に綴りが違うのはかつては合字が含まれていたため。オジロワシはその際に種小名を与えて Haliaeetus nisus Savigny (nisus はハイタカの種小名と同じ) となっていた。#ノスリの備考参照。後に Linnaeus の与えた種小名に戻された)。
Pandion 属は同じく de Savigny (1809) がミサゴに対して与え、ミサゴには Pandion fluvialis Savigny ("川のミサゴ" の意味) の新名を与えた (後に Linnaeus の与えた種小名に戻された)。これらを見ると当時の属の与え方の例がわかる。
ミサゴに付けられた属名は他にも Triorches Leach, 1816 (タカ類を一般的に指す "3つの精巣"。#ハチクマの備考参照)、Balbusardus Fleming, 1828 (フランス語名 balbuzzard から)、
Ichthyaetus Sweeting, 1837 (現代の Ichthyaetus とは別物)、Dalcedo Rey, 1872 (カワセミの Alcedo のアナグラム) があったとのこと (The Key to Scientific Names の情報よりまとめ)。今も昔も人気があったことがわかる。
[ミサゴは何種?]
一科一属一種で汎世界的 (cosmopolitan) な種と考えられてきたが、現在はオーストラリアやインドネシアからニューギニアのカンムリミサゴ Pandion cristatus (英名 Eastern Osprey または Australian Osprey) とミサゴ Pandion haliaetus (英名 Western Osprey) の2種に分けるのが通例 (2024 年までの扱い)。
Wink et al. (2004) Phylogenetic Differentiation of the Osprey Pandion haliaetus inferred from nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene
は相当古い解析で今からみても相当危ない感じがするが、4種への分割を提案している。一番離れている cristatus を別種とみなした扱いが暫定的に採用されたのだろう。
歴史的には 19 世紀は種境界の考え方はさまざまだったが、Gould がオーストラリアのミサゴを Pandion leucocephalus Gould, 1838 White-headed Osprey として別種と主張したのが始まり。The birds of Australia の図版。
記載。現在 (統合される前) の Eastern Osprey とは異なった英名となっていたが、この記載が初のものではなかったと判定された ([カンムリミサゴの学名は正しくない?] 参照) こと、Eastern Osprey はおそらく他亜種を含む過程で作られた名前だろう。
オーストラリア地域とそれ以外を分けるのになぜ Eastern, Western と名付けたのか気になっていたが、欧米を中心とした世界地図ではオーストラリアは世界の東の隅というわけか...。ホウロクシギの英名が Far Eastern Curlew で、古くは Eastern Curlew だったのと同様らしい。
OED には Western Osprey などの項目はないが、eastern の項目には 4.a. Native to the eastern parts of various land masses or regions other than North America, esp. Asia or Australia. ということで比較的新しい語義。
Eastern Golden Plover, Eastern Reef-Heron などの用例 (1876, 1906) が引用されている。この語義から想像するとミサゴで使われた eastern はオーストラリアを指したもので、アジアも eastern ではないのか? のような疑問はあまり表立って出なかったらしい。そもそも極東のミサゴのことなどほとんど知られていなかったので、英語圏だけを考えればオーストラリアを表現できれば十分だったのかも。
Australian Osprey は別名にあるが、なぜ eastern を使いたかったのか考えてみると、Australian にはすでに "南" の意味が含まれているので南米のミサゴのことも考えるとあまり適切でなかったのだろう。
Working Group Avian Checklists では version 0.02 以降同種扱いで統合される見通し。
IOC 14.2 では1種に統合された。AviList も同じ。
日本鳥類目録ではミサゴを複数種に分離した扱いは一度も経験していないと思われるので、日本鳥類目録に従った上でミサゴの種英名に Western Osprey を表記するのはふさわしくない。
ミサゴが2種に分けられていた時代の Pandion cristatus は単形種であったため、統合後の亜種 Pandion haliaetus cristatus を指して Eastern Osprey と呼ぶことは問題ないが、統合前の Pandion haliaetus は複数亜種を含んでいたため、日本で見られる亜種を意味して Western Osprey と呼ぶのはおかしいことになる。
[カンムリミサゴの学名は正しくない?]
カンムリミサゴの学名のもとになっている記載はもしかするとハチクマだったのではないかとの指摘がある (参照先も含め、#ハチクマの備考 [ヨーロッパハチクマとの関係・亜種他] を参照)。
この議論によれば cristatus の名称は有効な学名だがおそらく正しくカンムリミサゴを指したものではない。
これがカンムリミサゴに使えなくなれば次に有効と考えられるのは Pandion leucocephalus John Gould, 1838 だが、これはすでに使用されていた (preoccupied) 根拠がある。
Pandion leucocephalus "N.F." (= "S.D.W." =? S.D. Wood), 1835 で、これは英国のミサゴ (当時別名で呼ばれていた) の改名を意図したものであることはおそらく間違いなく、Gould は 1832 年にも同名の記載をしている。
1832/1835 年の記載が有効とされればカンムリミサゴにふさわしい学名は
Pandion gouldii Kaup, 1847 とのこと。
国際動物命名規約にも先取権の逆転について細かい規約があるらしく、少なくとも 10 人の著者が使用し... などの細かい条項があって、それぞれの学名がいくつの文献で記述されているかを調べる段階でスレッドが終了している。
カンムリミサゴの和名は学名が訳されたものと推定できるが、初期記載の学名がもとになっていて実際に目立つ特徴を正しく表したものではないようで地域を表す名前などに変えた方がよいだろう。
Mees (2006) The avifauna of Flores (Lesser Sunda Islands) (pp. 38-44) にもオーストラリア周辺の "ミサゴ" についての複雑な経緯が記されている。
基産地やラベルの取り違えなどもあったらしいが、Buteo cristatus Vieillot, 1816 がハチクマであった可能性はまだ気づかれていなかったらしい。
カンムリミサゴとハチクマの学名が再検討される可能性が秘められているかも知れないが、カンムリミサゴが別種として扱われなくなり、議論が終息してしまったのかも知れない。
[亜種の問題]
(広い意味での) ミサゴの中でシベリアと日本のグループはこれまで記述されていなかった新系統をなしていることがわかっている [Monti et al. (2015)
Being cosmopolitan: evolutionary history and phylogeography of a specialized raptor, the Osprey Pandion haliaetus]。
アメリカのグループはすでに別亜種の名前 (carolinensis と ridgwayi) を持っているが、シベリアと日本のグループはこれまで亜種として記載されていないとこの論文には書かれている。分類群の名前を与える必要があると思われる (新亜種か。当時はまだ2種扱いだったためその場合どの種の亜種になるのか。さらに別種とする可能性はあるのか?)。
おそらくそれを記述する論文がまだないため、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに亜種 haliaetus となっており、従来分類に基づくものになっている。
なお日本のミサゴについては "Fauna Japonica" で Pandion haliaetus orientalis フランス語名 le balbusard commun oriental (東洋の普通のミサゴ) の名称が与えられていた。当時はすでに北米とオートストラリアのミサゴに別名が与えられていた。
Temminck and Schlegel はインド諸島 (インドネシア) と日本のものはオートストラリアのものに似ているとの記述があるが、Il nous parait par consequent que ce balbusard oriental forme tout au plus une variete locale de celui qui habite l'Europe, et qu'il ne merite pas d'etre regarde comme espece particuliere とあり、ヨーロッパのものの地域変異型で、特段に種とするに値しないと思える、とある。
また Pallas もカムチャツカ近くまでのシベリアのミサゴを地域変異型とは認めなかったと記述されている。
Avibase では Pandion haliaetus orientalis はシノニムで登場するので無効学名だったわけではないように見えるが Richmond Index には現れない。
よく考えてみると Haliaeetus と同属となったことがあるので (例えばサンショクウミワシ African Fish Eagle の地域型 Pandion vocifer orientalis Heuglin, 1863 はこちらで記述されていたがこれは preoccupied?)、
Haliaeetos orientalis Brehm, 1831 (参考) があって orientalis は少なくとも一時期 preoccupied となったものと想像できる。
シベリアと日本のグループに Temminck and Schlegel 由来の orientalis の亜種名称を活かせばよさそうに見えるがそもそも使えなくなっていたと想像できる (現在は別属なので復活可能なのかも知れないがよく知らない)。しかし Temminck and Schlegel 自身が当時の種概念にあてはまらないとし、図版も残していないのでこの時点で有効な学名の記載でなくなっていたのかも (詳しくは知らない)。
カンムリミサゴの学名・和名問題も含め、いろいろと整理された後には世界のミサゴの学名は見慣れないものに変わっているかも知れない。
Boyd によれば friedmanni (Wolfe 1946: A new form of Osprey from northern Manchuria) の名称の可能性があるが、Wolfe は日本のものは大陸のものと異なっていて日本のものは典型的な haliaetus と述べていてどの範囲を指すか判断できないとのこと。
分子系統研究の結果とあまり整合していない。
カムチャツカで基亜種 haliaetus と移行帯があるとのこと。
Monti et al. (2015) の研究で4クレードにほぼ分かれることは認められるが、用いる遺伝子によって系統樹に少し違いがあり、分岐はごく短期間で起きたことが推測される (Boyd)。Boyd はミサゴを1種とするか複数種に分けるかは自明でないとして1種として扱っている
(種より下位の分類は扱っていないので日本を含むグループが亜種に相当するのか、friedmanni が有効な亜種かどうかは判断していない。現時点で Pandion friedmanni を意味がある種と考えるのに十分な根拠がないとの見解であろう)。
ミサゴ科はタカ科から古く分岐したのだが、他の種が現存しておらず、(広義) ミサゴが短期間で (亜) 種分化しているのも不思議な点である。
Monti et al. (2015) の分析から推定される経緯はミサゴは北米で進化し、ベーリング海峡を越えて旧世界に定着し、各地に広がったと想像される。ベーリング海峡を越えるのが難しかったため長らく新大陸にとどまっていたが、一度越えると比較的簡単に分散したのだろうか。
フロリダでミサゴ属の他種の化石が知られている (Pandion lovensis Becker, 1985)。
ミサゴ科ではドイツに化石記録がある: Mayr (2006) An osprey (Aves: Accipitridae: Pandioninae) from the early Oligocene of Germany。他のタカ系統の出所から想像するとおおもとはやはりアフリカから発祥したのだろうか。
世界に分布して種分化をしたが北米で進化した現在のミサゴが一段優れていて過去の少し違った種を短期間で競争排除したのかも知れない。渡りをする種類なので一度地理的障壁を乗り越えれば世界に分布することは比較的容易だったのだろう。
Monti et al. (2018) の研究によれば、アメリカとオーストラリアの (亜) 種は遺伝的に明らかに区別され、最近の相互の遺伝子流入を防いでいると考えられる。地中海とそれ以外のヨーロッパの個体群には多少の違いがある (#イヌワシと似ているかも知れない)。
ただし差がないとの反論もあり: Ferrer and Morandini (2018) The recovery of Osprey populations in the Mediterranean basin むしろ個体群間の交流を増すのに有益ではないか。
Monti et al. (2022) Evolutionary risks of osprey translocations は地理的に離れた個体群を用いて再導入する危険を訴えているが反論も出されている。
Monti et al. (2015) 時代の ND2 遺伝子を使って KT123892.1 を出発点に BLAST を試してみるとこのサンプルとの相同性が 90% を割っているものもあって地理的変異はかなり大きいよう。
広域に分布して世界分布がかなり連続しているため交流が大きくはっきりした種分化を起こすほどではないものの、同程度に相同性の低いものは他分類群では多くは別種扱いとなっているものも多い。ミサゴは1種と現状一応の世界的合意が得られているがまた再検討されるかも知れない。
日本のミサゴ内では遺伝的な個体群構造は認められなかった: Nagai et al. (2021) Genetic Diversity and Structure in Japanese Populations of the Osprey (Pandion haliaetus), Based on mtDNA Cytochrome b, Control Region (archive)。
この遺伝子でもオーストラリアやイスラエルのものと一致率 97% 程度と別種扱いか適切か悩ましいぐらいの数字になる。
暗色型ミサゴが知られている。例: Clark (1998) First North American Record of a Melanistic Osprey、
Nesbitt and McNichols (2003) Observations of a Melanistic Osprey in Southwest Florida。
[つがい外交尾]
Monti はイタリアの研究者で、地中海とそれ以外の個体群の違いに関心が深いよう: Monti et al. (2023) Genetic Variability and Family Relationships in a Reintroduced Osprey (Pandion haliaetus) Population: A Field-Lab Integrated Approach。
イタリア Maremma Regional Park で再導入された個体群の DNA 解析を行った。ビデオ記録でつがい外交尾も観察されているがこの研究では受精には至っていない模様。
密度が高いとつがい外交尾が起きやすい点は他の種類と同様のよう。2暦年で性的成熟に達するが繁殖活動を始めるのは3-5歳で、世代長は平均 9.6 年との文献値がある。非繁殖個体が繁殖個体の近くに存在する semi-coloniality (準コロニー性) を示す (文献より)。
ミサゴで精子競争が激しいのか? (ただしデータが適切でないかも知れない) について、#チョウゲンボウ備考の [アメリカチョウゲンボウの交尾] に比較がある。データが正しければ精子競争が激しい可能性があるが本当だろうか。
関連する文献を示しておくと WidEn and Richardson (2000) Copulation Behavior in the Osprey in Relation to Breeding Density (スウェーデン) 個体密度の高い時は1時間に 0.65 回で低い時の 0.30 回より多かった。
Englund and Greene (2008) Two-Year-Old Nesting Behavior and Extra-Pair Copulation in a Reintroduced Osprey Population
(アメリカ ミネソタ)。ミサゴは DDT や狩猟の影響で一時期全世界的に減少し、再導入されたところも多いため個体群動態がよく調べられている模様。
[ミサゴとタカ科の染色体の違い]
ミサゴではタカ科と同じように染色体レベルで大規模な入れ替えが起きているが、パターンが異なっていて別々の祖先型からそれぞれ独立の進化を遂げたことが示唆される [Nishida et al. (2014)
Dynamic Chromosome Reorganization in the Osprey (Pandion haliaetus, Pandionidae, Falconiformes): Relationship between Chromosome Size and the Chromosomal Distribution of Centromeric Repetitive DNA Sequences] (#クロハゲワシの備考も参照)。
[染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化]
ごく最近、オウギワシの染色体レベルの高精度ゲノムが解読され、タカ類のゲノムから見た染色体再構成や transposable elements (TEs, #ハシボソガラスの備考も参照) の比較研究に進展があった:
Canesin et al. (2024) A reference genome for the Harpy Eagle reveals steady demographic decline and chromosomal rearrangements in the origin of Accipitriformes。
オウギワシのゲノムでは 17.26% が反復配列と判定され、反復配列が特に多いとされていたキツツキ目 (20% 以上) に匹敵し、多くのスズメ目 (7.8%) やオウム類 (9.8%) に近いことがわかった。
[オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] でオウム類の TE 率が高いことを紹介している。オウム類では関連する可能性のある遺伝子欠損候補が挙げられている。
#ツリスガラの備考 [スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン] にスズメ目、キツツキ目の紹介がある。スズメ目では TEs が後に生じた系統ほど蓄積してゆく描像が得られている。
オウギワシでこれほどに高い結果は予想外。36% の TEs の由来は不明で、このうち最も多く見られる2つのうち1つの elements は 1700 (1300-2200) 万年前ぐらいに活発に働いたと推定される。オウギワシが他のオウギワシ亜科 (現在の理解では4種。最も近いものはヒメオウギワシ [高野 (1973) ではカンムリオウギワシ]、そして少し離れたコウモリダカとされ、これらの種との分岐年代に対応する) から分化した時期に対応する。
他のよく知られた TEs では CR1 レトロトランスポゾンがあるがこれは非常に古い時期で 9800-6300 万年前まで (タカ科が分離する以前も含む) 活発に働いていた。6300 万年前ごろに LTR Gypsy がそれに置き換わりはじめ、5400 万年前ごろは CACTA elements が多くの部分を占めた。同じころ不明の TE が広がり始め、4800 万年前にピークに達したとのこと。
スズメ目で話題となった solo-LTRs は 3300-3700 万年前にピーク、CR1 が 3100 万年前に再度小さなピークを示した後活動が沈静化した。
ヘビクイワシの染色体レベルの構成は得られていないが、既知の染色体再構成情報と合わせるとタカ目の中で染色体再構成のほとんどないコンドル科 (この論文での表記。コンドル目と読み直してもよい) がまず分かれ、その後少なくともミサゴ科とタカ科が染色体再構成を行う点において共通した bauplan (ドイツ語由来。body plan ボディプランだがマクロ形態との混同を避けるためにこの用語を用いているのだろう) を持っている。
この研究では CR1 から Gypsy LTR, CACTA elements への移行の年代推定から約 6500 万年前の K-Pg 大絶滅以降にコンドル科と (ミサゴ科 +) タカ科の分離を含む大規模な分岐が発生し、solo-LTRs の大量生成がタカ科内の大規模分岐に先立って起きたと考えている。TEs が多様化に役割を果たした可能性がある。染色体の再構成は生殖隔離にもつながり (#オシドリの備考参照) TEs が種分化に関係しているかも知れない。
スズメ目の進化では solo-LTRs が中心的な役割を果たしたが、LTR Gypsy, solo-LTRs, CACTA の大きな変化のいずれもがタカ科のゲノム進化に関係している。オウギワシでは固有の (スズメ目やイヌワシなどと共通点の見つからない) TE がこの種独自のゲノム構成に関与したと考えられる。ヘビクイワシで同等の研究が進めばタカ類が初期にどのように進化したかさらに手がかりを得ることができるだろうとのこと。
この論文では保全上の意義も取り上げており、過去2万年の実効個体数の減少は人為活動の影響と時を同じくしているなど述べているが TEs がこれまで謎の多かったタカ類進化の解明に役立つことだろうことを示している意義が大きいと感じる。このような研究にはこれまでの低精度のゲノムではなく染色体レベル、かつ反復配列を読める高精度のゲノムが必要で難易度も高い。
染色体レベルのゲノム解析の結果ではあるが、イヌワシとオオタカは共通性が高い。オウギワシはかなり違っている。Catanach et al. (2024) の系統樹ではオウギワシ亜科は Accipitrinae 亜科に近い位置に置かれているが、イヌワシ亜科との位置づけは逆転するかも知れない。
染色体レベルのゲノムではこの3種のうちではイヌワシが祖先的な性質を最も多く持っており、オオタカには他の2種と比べて固有の変化が見られた。この部分だけ見るとタカ科の中でイヌワシが原型に近い結果となるがさてどうなるだろうか。
それぞれ1種しか調べられていない段階なので系統の判定には途中をつなぐ種類の高精度のゲノムが必要なのだろう。反復配列が多いのはオウギワシ特有の現象なのか、オウギワシ亜科で共通なのか、あるいはそれ以外の系統でも見られるのかなどまだまったくわかっていない。
モーリシャスの希少鳥を対象としたゲノム研究が行われ、精度の高いゲノムを用いるとハト目、ハヤブサ目 (ただし Falco 属のみ)、オウム目いずれも従来見積もりより反復配列率が高いことがわかった。ハヤブサ目もオウム目に匹敵している: Wang et al. (2025) Genomic erosion through the lens of comparative genomics (preprint)
研究そのものは絶滅危険度ランクと遺伝的多様性の関係を調べることが主目的だが、精度の高いゲノムが得られたことで副産物の情報もいろいろ得られている。Falco 属は新しい系統なのに染色体再構成や逆位が意外に起きている。一方古い系統のハト目は属が違っても構成はほぼ同じ。オウム目は古い系統でかなり入り組んでいる。
オウム類では関連する可能性のある遺伝子欠損候補が挙げられている、とは簡単に言えなくなってきた。
歴史的な実効個体数 (Ne) 変動も面白く、モーリシャスの希少鳥が低いのは当然としてもモーリシャスチョウゲンボウ (#チョウゲンボウの備考 [離島のチョウゲンボウ類と超希少種の保全] 参照) は人が入植する以前からずっと実効個体数が低かったらしい。面積が小さいことは否めないが同時に調べられたモーリシャスの希少鳥他種よりも少ない。
オウム目が Ne を減らしてきているのは理解できるとしても、ハト目の変動は驚くべき。カワラバトやコキジバトは過去 (10^5 - 10^6 年前) はずっと多かったらしい。多数のハト目の鳥が絶滅したのもハト目が全体的に勢力を失いつつあるためなのかも知れない。ドバトがどこにでもいて一見生命力が強そうに見えるが、自然界では現在はマイナーで繁栄は人為環境あってのことらしい。
ドードーは生存していないので同様の質の解析はできないが、もし解析できれば同じような結果になっていたかも。リョコウバトは博物館標本からの見積もりがあり、#オガサワラカラスバト備考 [リョコウバトなどの絶滅について] に紹介。
ハト類は衰退傾向にあったものに人為が最後の一撃を加えたのかも知れない。
ハヤブサ目は種によって傾向がさまざまでヒメチョウゲンボウは Ne をかなり減らしておりかつては豊富に存在していた種らしいが衰退傾向。ワキスジハヤブサが近年になって Ne が増える傾向が出ている。
Carvalho et al. (2021) Comparative chromosome painting in Spizaetus tyrannus and Gallus gallus with the use of macro- and microchromosome probes
クロクマタカ Spizaetus tyrannus は染色体数 2n = 68 とクマタカ 2n = 66 と似ているが染色体再構成のパターンは大きく違うとのこと。かつては同属とされ姿も似ているが実はかなり異なっているらしい。同じクレードの他のデータがあまりなく染色体再構成がどのように起きたかまだ辿れないとのこと。
[tendon locking mechanism (TLM)]
木にとまった鳥が眠っても落ちないのはなぜかしばしば話題となるが、tendon locking mechanism (TLM) が働いている。腱鞘 (tendon sheath) に横方向のひだ (plicae) があり、接する腱に突起 (tubercles) があって関節を曲げた時に腱と腱鞘の間を固定する機構。この場合は筋力をほとんど使わず体を固定できる。
多くの鳥の足では趾より上の腱・腱鞘の部分にあって上記の場合などに役立っているが、猛禽類では趾にもこの機構があって趾を曲げた状態で筋力をほとんど使わず固定できる。他の鳥は突起が丸いが猛禽類では角張っていてより強固に TLM が働く。
最初に爪を刺す力は必要だがその後は曲げていれば自動的に獲物に食い込むことになる。
上部の腱・腱鞘で TLM が働いた場合、握ると脚を動かせなくなるが (枝にとまって眠る時など)、猛禽類などではこの機構が趾でも働くため獲物を握ったまま脚を動かすことが可能である。
広義 Accipiter 属や Circus 属ではワシ類などに比べて突起があまり角張っておらず、TLM がそれほど強固でなく主な食性を反映している。
ミサゴの高速度撮影では足を閉じる反応は非常に素早く、触覚による反射が関わっていると考えられる。
ミサゴが獲物を運ぶ時も TLM が役立っていて、足に力をほとんどかけずに運ぶことができる (我々が物を運ぶ時とは異なる)。そのため非常に遠くで捕まえた魚を運ぶことがしばしばある [以上 Bildstein (2017) "Raptors" pp. 144-147 より要約]。
ミサゴが内陸で魚を捕らえて双眼鏡でも見えなくなる遠くまで運ぶことをしばしば観察するがこのような仕組みが関わっている模様。
参考となる文献: Einoder and Richardson (2006) An ecomorphological study of the raptorial digital tendon locking mechanism。
最初に考察した研究は枝にとまる機構なども含め、Quinn and Baumel (1990) The digital tendon locking mechanism of the avian foot (Aves)。当時は画期的アイデアだったようでコウモリがとまる機構、齧歯類が木を登る機構などの後続研究が相次いで発表された。
TLM の記述以前の古典的な解剖学文献でよく引用されるものに Goslow (1972)
Adaptive Mechanisms of the Raptor Pelvic Limb があり、図はいろいろな所でご覧になられた方もあるのでは (この図でもやはり第 III 趾を強調している)。
Einoder and Richardson (2006) によればタカ・ハヤブサ類では第 I 趾と II 趾の TLM が発達しており、第 III 趾での発達は比較的小さい (#ハチクマ備考の [カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] の Fowler et al. (2009) なども参照)。第 I 趾と II 趾が大部分の握力を発生している。
フクロウ類ではこの差が小さく、第 I 趾での TLM の発達が悪い。フクロウ類で第 I 趾だけでなく第 IV 趾も後ろに回す対趾足 (zygodactyl) となっている点もよく整合する。
Ward et al. (2002) Functional Morphology of Raptor Hindlimbs: Implications for Resource Partitioning にも解剖学や測定値などが出ているが、フクロウ類の方が握力が強いなど少し異なる結果も出ている。
Galton and Shepherd (2012) Experimental analysis of perching in the European starling (Sturnus vulgaris: Passeriformes; Passeres), and the automatic perching mechanism of birds
はホシムクドリで麻酔をするととまり木から落ちてしまうこと、TLM の一部を阻害しても同じ姿勢で寝ることができることから、TLM だけの作用ではなく自発的な筋肉コントロールを行っていることを示している。
Yapuncich et al. (2019) Vertical support use and primate origins によれば
TLM 類似のものにはいくつかの機構があって鳥類、コウモリ、齧歯類の TLM は収斂進化とされている。
霊長類には TLM は確認されていないが、踵 (かかと) の posterior trochlear shelf (PTF) が似た働きをして垂直に体を支える機能が霊長類の樹上進化に役立ったと考えている。ここでは「噛み合わせ」機構を "cam mechanism" と呼んでいる (これは通俗的な表現)。
長時間の滑翔をする鳥では "shoulder lock" があるとの類推もある: Meyers and Stakebake (2005) Anatomy and histochemistry of spread-wing posture in birds. 3. Immunohistochemistry of flight muscles and the "shoulder lock" in albatrosses
ただし筋肉の性状から推測しているもので TLM のような構造的裏付けは強くない。
TLM に類似した省力化は運動などでも経験されることがあるだろう。ピアニストがピアノを弾く場合も力が入るのは最初の一瞬だけで鍵盤を押さえている間は特に力を加えているわけではない。測定すると力のかけかたにプロとアマチュアで差が出るらしい。とまり木にとまる鳥の筋力の使い方も似たようなものではないだろうか。
[大きすぎる獲物で溺れてしまうミサゴの話は本当か]
ミサゴが大きすぎる魚を獲物にして、一度食い込んだ爪は外すことが難しくそのまま溺れてしまうことがあると言われる。
Osprey struggling to get off the water (Tom of AskaNaturalist.com 2016)
によればこれは古い神話 (myth) で水中でも空中でも捕えたものを離すことができる。巣に戻る時に魚を離して落とす行動も見られる。
もちろん深く刺さり過ぎて抜けずに溺れてしまう可能性までは否定するつもりはないが、構造上食い込んだ爪を外せないとの説明は誤りであるとのこと。
話題となった BBC 動画のページ: Hunting osprey footage viewed 13m times on Facebook (BBC 2016)。いまだに古い神話に基づく解説をしているとのこと。
Goslow (1972) "Adaptive Mechanisms of the Raptor Pelvic Limb" ([tendon locking mechanism (TLM)] 参照) が古い時代で広く使われた説明であったため都合よく解釈されていたのかも。
実際にあきらめて獲物を放す画像: Ospreys Releasing Too Large Fish from Their Talons into the Water (Bartosik 2009)
あまりにも誤った神話が広まっているために写真で実例を示したとのこと。
古い著書 Abbot (1911) や Bent (1937) には神話や逸話通り書かれているが、近年の著書 Poole (1989) や Dennis (2008) は (ミサゴの爪の残っている魚の逸話) 否定しているとのこと。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 pp. 169-171 (1946 年初出。全体はもっと長いが関連部分のみのページを示した) によれば、俗に「ミサゴのお幣束」と呼ばれるものとのこと (p. 170) (幣束または御幣。元々は神に捧げるもので、細長く折り下げた紙を両側に垂らす形式も見られるようになる: wikipedia 日本語版より) 魚にミサゴがぶら下がって連なっている様子を表したものだろう。
中西氏の記述では、外国の生物記録映画にその実写があるとのこと。当時からすでにそのような映像があったのかと驚くとともに、中西氏ですらその映像を本物と考え、世間の俗信を疑うこともなかったことがわかる。現代の文献にまったく触れられていないことや、再現映像が未だに世界に存在しないことから「外国の生物記録映画」は根拠としては受け入れられていないのだろう。
さらに面白い記述もあって、当時の中学4年の国語読本に「うけらがの花」(橘千蔭 1801。参考 うけらがはな 早稲田大学図書館)
「みさごの群れきて水の面に浮かぶるもをかし」との一節があり、学生からミサゴは水禽か猛禽かと中西氏に問い合わせがあったとのこと。当時の国語辞典を引くとミサゴは水禽の一種と出ていたとのこと。
中西氏の返信の一部には「ミサゴは形態容姿は猛禽らしいですが...魚類を食餌としている点からは猛禽という通念には当てはまりますまい」と中庸の表現が行われていた (p. 170) が記述が誤りであることは返答されいた。中西氏自身はこのような教材を用いることをもちろん批判していた。
しかし、「ミサゴは水禽か」は現在の概念では非常に突飛に思えるが、実はタカとの違いがむしろ今よりもよく認識されていたのかも知れない。[近代的な陸鳥の進化] で [2025.6 さらに追記] AviList (2025.6) の配列を見て少し考察を行ってみた。ミサゴはタカだとされるのは、そのように教えられているのを信じているだけで、実は違っているのかも知れないなど考えてみるのは楽しいのではないだろうか。
Husby (2020) Osprey observed when drowned by its prey
こちらは科学者は否定的だが実際に溺れたと思われる目撃事例を報告。Peterson (2002) (ノルウェー語の猛禽類の書籍) によれば飛び立てない場合は通常は獲物を持ったまま岸まで泳ぐという。
"逸話" に相当する古い事例は最近の著書には記述されていないが、スカンジナビアでミサゴの足または骨格を付けた魚の記述があるとのこと。Ferguson-Lees (1968) British birds 61: 465 によればコイ Cyprinus carpio (日本と同種) に刺さったままになっているとのミサゴの骨格は後でノスリ類と判定され、人工的に付けられたものと判定された [Cowles (1969) British birds 62: 542-543]。
この事例もあって "神話" や作り話との考え方が広まったとのこと。
中西 (1946) で紹介されている「ミサゴのお幣束」も現代では忘れられてしまっている程度なので、その後の目撃例も事実上ないのだろう。もちろんいくつかの要因が重なれば発生する確率はゼロとまでは言えないものの、大部分は古今東西共通の (ミサゴすら溺れてしまう) 大物自慢の表現だったのではないだろうか。海外で作り話と判定された事例があるように、適切な物さえあれば組み合わせて簡単に偽造できてしまう。
釣り文化のない地域 (あるのかどうかは知らないが) ではミサゴは溺れなかった、とか (笑)。
Husby (2020) の報告した事例では沈んだ場所をボートで捜索した人はミサゴも漁網も見つけられなかったとのこと (人工物由来で飛び上がれなかった要因をある程度否定しているが回収しない限り完全に否定するのは難しいかも知れない)。
Husby (2020) はこの目撃事例を確かなものと考えているとのこと。いくつかの可能性を考察しているが冷たい水中で筋肉が麻痺した可能性もあるのではとのこと。おそらく水中で "足がつった" 経験をもとにして、鳥類も哺乳類も同じようなものと想像していると考えられる (生理学的には同じようなものとする考え方がここにも表れている。しかし冷水で足の筋肉が麻痺した鳥の例は知られているのだろうか?)。
いずれにしても非常にまれな事例のようで、多くの人や研究者がミサゴの写真を撮ったり研究をしているにもかかわらず報告例はほとんどない。かなり偶発的な事例のよう。
"神話" の根拠となる出典も示されているがいずれも書籍の記述らしく孫引きの可能性が高そう、オンラインで見つけられた具体的記述は Farley (1924) Habits of the Osprey のみだった。
100 年も前に報告されているのに世界レベルでも未だ確実な映像証拠などがないのはやはり相当まれな事象のよう。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3547-3548 のミサゴの項目 (内田) によれば、日本最初の野鳥生態写真家と評される下村兼史「或日の沼池」(東宝教育映画 1951) の記録映画があり、ミサゴがライギョをおそって離すこともできず飛びたつこともできないラストシーンがあるとのこと。同記事ではドイツのオジロワシで大きな獲物を襲った同様の事例が紹介されていたが具体的には不明。
「或日の沼池」で検索してもあまり情報がなく、下村兼史『或日の干潟』 (齊藤聡 2009。間もなくサービス終了で見られなくなると考えられるので早めにご覧を)
にはミサゴの話は出てこず、「静寂を破り、ハヤブサが登場する。群れで牽制されつつも、ハヤブサはガンを攻撃し、食べる。「平和であるべきこの干潟をハヤブサの撹乱に任せておいて良いのでしょうか。」というナレーションはもはや悪乗りだ。それに対する回答はない。前出『海辺の環境学』によれば、ハヤブサが出てくるときだけなぜかプロペラエンジン音が聞こえ、ハヤブサも糸でつながっているという説があるらしい」と解説されている。当時はハヤブサが悪者と教育されていたらしいことが想像できる。
教育映画の位置づけなので、いくつか異なった編集があったのかも知れない。
中西悟堂氏が見たと述べている「外国の生物記録映画の実写」も、教育映画ならばもしかすると付加された可能性もあったのではと考えてしまう。時期的にも近いので、あるいは外国の生物記録映画に似たものを日本でも、という要請があったかも知れない。
塚本他 (2009-2010) 野鳥生態写真の先駆者 下村兼史資料の整理保存 では主に静止画の整理が中心で映画フィルムはそれほど残っていないらしい。ミサゴのシーンが現存すれば世界的に貴重な資料となると考えられるがこの論文にも現れない。
塚本 (2010) Birder 24(12): 16-17 によれば『或日の干潟』は理研科学映画 (1940) とのこと。理化学研究所は 1917 年創設。1940 年は時代的には当時は理研コンツェルン (企業共同体) のころ、1937 年仁科芳雄研究室が日本で最初のサイクロトロンを完成など (wikipedia 日本語版より)。現在の理研から受ける印象とも違うので歴史を見ておくことも参考になるだろう。
時代背景的には戦前に欧米の科学に負けない / 追い越すものを目指していたもので科学映画の要請も強かったのだろう。塚本 (2010) には当時の東京湾のサカツラガンの群れの写真が紹介されていたが、映画のミサゴやハヤブサのシーンについての言及はなかった。
下村氏が描いたものだったかどうかは今となってはわからないが、戦時色が強まる中で教育のためのメッセージとして (ハヤブサが悪者と言うよりも) 後の時代ほど編集が行われたのかも知れない。異なった編集が現存している兆候があまりないのも歴史的時期を考えると理解できるかも。
この映像から当時はハヤブサが悪者だったと考えるのは早計かも知れないが、猛禽類 = 悪 の考え方は映像から植え付けられた可能性がある。そのような考え方を打ち消すには「サントリー愛鳥キャンペーン」などの苦労が必要となったものだろう。猛禽類が多数撃たれたのは戦争の間接的被害者だったのかも知れない。
溺れ死ぬミサゴの映像も、戦前にも存在したならば教育的効果を期待した何かのシンボルだったのだろうか。「外国の生物記録映画の実写」も、現代想像するものではなく何かの教育的効果を期待したものだったのかも知れない。何といってもまだフィルム時代である。高価なフィルムをいつ起きるかわからない現象を待って回し続けるとは考えにくい。
「ドイツのオジロワシ」も、もし象徴的意味があるならば当時の時代背景を考えると微妙にひっかかるところがあるが考えすぎだろうか。空から襲来する猛禽類を敵にたとえるのは大変わかりやすい比喩で、やり方によっては打ち負かすこともできるメッセージ性を持たせたのかも知れない。ドイツが当時 U ボート を多数生産していたのと無縁ではないかも知れない。
アポロの月着陸の際に月面で落とされたハンマーと羽にメッセージ性を読み取るならば (#ハヤブサ備考 [月に行ったハヤブサ])、この程度の読み取り方は可能と思える。
柴田 (2023) Birder 37(12): 54-55 に漫画「釣りキチ三平」(矢口高雄 1939-2020。雑誌連載は 1973-1982) の第 50 巻 (単行本では 1981 年出版) にライギョ VS ミサゴ をテレビの自然番組のクルーが撮影する場面が描かれているとのこと。当時リアルタイムで読んでいた世代なので多分見ているがあまり覚えていない (あったかも知れない程度の記憶。手塚治虫氏の「ブラック・ジャック」ですら覚えているシーンがあまりないので多分漫画の記憶力が悪い)。
それはともかく当時の漫画家がテレビを流しながら (あるいは映画から着想を得て) 仕事をしていたなどは手塚氏がよく振り返っていたので、矢口氏の目にとまる程度の時期に『或日の干潟』でミサゴがライギョをおそって離すこともできず飛びたつこともできないラストシーンが放映されていたのだろう。内田 (1973) も時期的に近い。
当時の漫画家は映画やテレビから着想を得るとともに、一般にあまり知られていない事項を取り上げて独自性を高める場面もあったようなので (手塚氏の漫画で顕著に感じる)、当時はすでに映像として一般に見られなくなっていたが、矢口氏が過去に見た映像の印象が強くてテーマに用いられたのかも知れない。
アニメ版では「第 51 話ライギョ対ミサゴ王者の対決」とのことで、水の王者ライギョと空の王者ミサゴの緊迫した戦闘場面も見所であるとのこと (出典: アニメ釣りキチ三平第51話ライギョ対ミサゴ王者の対決 seesaa.net 2018)。興味ある方はどこまで生物学的に受け入れられる描写になっているか見ていただくのも面白いだろう。
さらに少し調べてみると茜屋 (あかねや) 流小鷹網の巻があるそうで、意外にもタカと縁が深かった。
Husby (2020) が調べた範囲では猛禽類の溺死報告は人工物によって半分溺れかけたミサゴを保護したが間質性肺炎で死亡した1例の文献が見つかったのみとのこと: Anderson (2008)
Late-Stage Granulomatous Interstitial Pneumonia Secondary to Near-drowning in an Osprey (Pandion haliaetus)
ミサゴは原則的に生きた魚しか食物と認識しないので保護療養は非常に難しいと一般に言われる。
大きな魚で飛び上がることが難しく、体を水中に没して首から上だけ出しているミサゴの動画を見ると他のタカ類に比べて長めの首はこのような場合に役立つのかも知れない。頸椎数は平均的なタカ類より1つ多い。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) でも英国猛禽類でミサゴのみ少し長めの記述になっている。#ハチクマの備考 [フィリピンのハチクマの不思議] の項目参照。
魚が生きていて水中に引きずり込まれない限り、魚の体重にかかわらず力学的には水上に頭を出した姿勢を保つことができるので安全な姿勢なのだろう。
Jollie (1976, 1977) のデータを参考に見るとあくまで椎骨数の比で {頸椎 (頸肋骨を含む) / 胸椎} はミサゴで 2.5、この値はヘビクイワシ 2.1 より大きく、イヌワシは 1.8。ミサゴの体躯部が相対的に短いことがわかる。
イヌワシは獲物を捕えるのにより体躯部の力を要して頑丈になっているのかも知れないが、さらに強力なはずのオウギワシでは必ずしもそうでないなどむしろ系統を反映しているかも知れない。
ミサゴの形態は水中に没することのできる捕食方法への適応のようにも見えてくる。
ミミヒダハゲワシが 2.1 で、あくまで数の比だけの比較ではミサゴの方が上回っている。
ミサゴの骨格を例として示し、猛禽類では羽毛に隠れているが首が長いとの説明が Mebs and Schmidt (2005) "Die Greifvoegel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens" にも出ていた。骨格写真を見ると確かにだいぶ長くて体躯部から分離しているように感じる (ドイツ語名では Fischadler なので最初海ワシ類かと思った)。
このように見るとミサゴの首の長さは欧米ではよく知られているのかも知れない。
面白いことに特徴が多い割にはミサゴは自分が持っている2つの骨図鑑の川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019) と 松岡他 (2009)「鳥の骨探」(NTS) いずれにも出ていない。
ネットを軽く探しても同様にマウントされた骨格写真を見つけられずお見せできないのが残念である。
[兄弟殺し] で紹介の兄弟間闘争の映像でもひなの首の長さが目立ち、兄弟間の対立の際に背が高い方が有利に見える。あまり考えたことがなかったが兄弟間闘争で選択され得る形質だろうか。
羽毛の揃った成鳥のミサゴの外見と魚食行動のみからは案外気づきにくい点かも知れない。
調べると長めの首はホバリング中に魚を見つけるのに役立つと書いてあるものがあった: Pandionidae - Discovering the Enchanting Bird Family (Nepal Desk) Ospreys also possess a greater number of vertebrae in their necks than most other raptors, allowing them an exceptional range of movement to spot fish while hovering 本当だろうか?
いわゆる通常のタカ類 (広義のハイタカ類やノスリ類) はこの適応がないので地上をソアリングするのに向いていると説明がある。
尾が短いのは抵抗を減らすためとある。水中を指して記述しているように見えるが、空中も指している? 魚食の海鳥などからの類推かも知れない。どこかに出典となる記述があるだろうと想像するが、もし水中に飛び込んで魚を捕食する適応のために尾が短いならば、空中での低速飛行が難しく (尾による揚力が小さいので失速しやすい) 着地が下手、つまり別項目 [ミサゴは不器用?] の理由につながるかも知れない。
これらの要因が重なって陸鳥系統出身の捕食者にしては海鳥に似た体型に収斂進化しているのかも。
ハクトウワシとの比較ゲノム解析でミサゴの適応に関係する遺伝子が同定されつつあるとのこと。ネパールのサイトで一般向けにしてはずいぶん詳しい。
鳥は物を運ぶ時に重さを目安にするか、シロビタイムジオウム Cacatua goffiniana Goffin's cockatoo / Tanimbar Cockatoo では霊長類以上にも目で見ただけで重さを瞬時に判断する能力が高いという: Lambert et al. (2021) Goffin's cockatoos discriminate objects based on weight alone。
この研究では重さの識別能力の高さは坂を上がる霊長類よりも飛行する鳥の方により求められるとの解釈。
その後の研究で Adelmant et al. (2024) Goffin's cockatoos use object mass but not balance cues when making object transport decisions 実際にバランスより重さで行動を決めている結果が得られたとのこと。重さを手がかりとして運ぶ決断の実験的証拠は鳥では初めてとのこと。
ミサゴ (に限らず獲物を運ぶ鳥) の行動の記録から傍証は得られるだろうか?
[ミサゴはフグ毒に耐性があるか]
ミサゴについておそらく調べられているわけではないが、一般論を#ヤマガラの備考 [ヤマガラの植物毒耐性] (5) 毒鳥ピトフーイなどの対毒性 (BTX 耐性) に紹介しているので参照いただきたい。
フグを食べるヘビなどで テロロドトキシン (TTX) 耐性を進化させているものがあるとのことで、ヘビ類や魚類などで耐性メカニズムや進化もよく調べられている。鳥類はほとんど研究の対象外だが TTX 耐性はそもそもほとんど持たないのでは (毒鳥ピトフーイなど BTX 耐性を持つとされるものは共通メカニズムの部分で多少耐性があるかも)。
TTX 耐性について知りたい場合はヘビ (garter snakes) の研究がよく進んでいるのでまずこれを参考にするとよさそう。哺乳類でも多少知られている。
(記述は重複するが) 鳥は圧倒的に上位消費者が多いので、鳥にとって特に重要そうな運動能力に影響を与えそうな骨格筋 (ヘビについては研究がある) でイオンチャンネルを変異させてまで毒耐性を持つ必要性があまり生じないかも。
毒鳥ピトフーイでも食物中の毒を排泄する役割が大きく、当初考えられていたほど捕食者への防御のためではないだろうとの考察もある [Jonsson et al. (2008) Polyphyletic origin of toxic Pitohui birds suggests widespread occurrence of toxicity in corvoid birds]。
これらは カラス小目 Corvida (corvoid birds) の祖先的な形質と考えられ、雑食の鳥が有毒な甲虫などを食べてしまった時に毒をうまく逃がす機構として進化したものだろうと想像している。何でも食べるカラス小目らしい適応なのかも。
ミサゴではそのような必要性はほとんどなさそうなので、ピトフーイ以上にイオンチャンネルが毒に対応して進化する必要性が薄いと思われる。
ミサゴの場合を考えてみると大きな獲物を丸のみするわけでもなく、食べている最中に嘴や舌の触覚で異常を感じればそこで捨てればよいので、こちらの知覚系と行動を進化させる方がよほど効率的に思える
(猛禽類の系統によって獲物を飲み込む様式の違いはあるいはこのような毒対策の意義もあるのかも。両生類・爬虫類など有毒な可能性のある生物をよく食べるタカ類では細かくちぎって食べるのが安全で、恒温動物を主な食物とする系統ではその必要性が低い? - これも誰かがすでに考えてそうな発想だが)。
イオンチャンネル作用性の毒物は嗅覚・味覚のように特定の受容体と結合する必要はなく、嗅覚・味覚の受容体が分布していなくても一般の末梢神経端末で検知できて不思議でない。
そのうにも一時的に蓄えられるので飲み込んでからでも吐き出すことは簡単にできるだろう。
さらに拡大解釈をすると、獲物を掴んだ時にイオンチャンネル作用性の毒物にもし触れて違和感があれば離しても不思議でないかも知れない (棘の方がより有効かも知れないが)。もしそうであれば獲物にとっても逃れるのに都合がよく、警告のための毒性を進化させる要因にもなるだろう。
鳥の足の裏は羽毛とは異なって α ケラチンで我々のものと似ている (#ライチョウの備考 [鳥類と爬虫類のうろこは別物] 参照)。そのような機能を持つ神経端末は分布しているだろうか。海水浴中に有毒生物に触れて、などの経験のある人がよくご存じかも知れない。
フグを離したミサゴの事例があるらしい点について Birder 2022年9月号 36(9): 28-32 も参照 ([ミサゴの食性など])。
若杉氏の ミサゴは (毒をもつ) フグを食べるか? でも「いろいろな方に聞いてみると、どうも、ミサゴはフグを捕まえても比較的短時間で捨ててしまうらしいです」と記されている。
「こういうふうに膨れた時には体から毒素を放出するそうで、この臭いや毒素を嫌って、ミサゴはフグを捨ててしまうようです」とも書かれている。この部分は想像や伝聞が含まれていると思われるが、鳥の感じている世界と我々の感じる世界が似ていることが (多くの人が承知の上で) 暗黙の前提となっているようでその点も興味深い。鳥と人では感覚が違うだろうから、とわざわざと反論される方も少ないだろう。
ミサゴのゲノムはすでに公開されている (Genome assembly ASM1340127v1 B10K 2020) ので、ヘビ類などで示唆されている変異部位を確認することも可能だろう。興味ある方は調べてみていただきたい。報告が出ていないのはおそらくそのような変異がないからでは?
Mohammadi et al. (2022) Constraints on the evolution of toxin-resistant Na, K-ATPases have limited dependence on sequence divergence にミサゴが含まれていて ATP1A には対毒性候補となる変異はなかった (S2 table)。
参考までに調べてみると、ミサゴのそのうの位置は広義 Accipiter 属や Falco 属とは違って食道下部に位置するとのこと: Preja et al. (2023) The Comparative Anatomy of the Upper Digestive System in 26 Species of Zoophagous-Polyphagous Palearctic Birds。機能的違いはあるのだろうか (ペンギン類、フクロウ類やカモメ類などにはそのうはない)。
この文献によればタカ、ハヤブサ、フクロウ類で舌部の唾液腺開口部がよく発達しているがミサゴは挙げられていない。ほとんど魚食の鳥にはこれらの開口部が見られないとのことでミサゴも同様なのかも知れない。
Jollie (1976, 1977) も見ておくと pp. 282-287 に消化器の比較があるがそのうの位置については特に言及がない。ミサゴの消化器はむしろ腸に特徴があるとのこと (pp. 286-287)。十二指腸より上部の腸の部位がなく、meckelian section (cf. メッケル憩室) が非常に長く複雑な構造となっている。発生学的には卵黄嚢につながっていた部分で鳥の "へそ" にも相当するがなぜそんな部位が発達しているのか??
雑誌 "Birder's World" 1991.2 に Vera M. Walter の北米のミサゴの記事があり、その中で小腸が長く魚のうろこや骨の消化のためと思われるとの紹介があった (p. 26)。この記事自身は野外観察 (水中からの観察など) の紹介で解剖学に関係したものではないが、ミサゴの腸の特殊性や機能の解釈はこの時点ですでに行われていたのだろう。
微妙に気になっているのがフクロウ類の盲腸糞との関係。ミサゴの糞は臭いのだろうか、とか、meckelian section が例えばひなを狙う捕食者対策に役立っていないだろうか。ミサゴは洞営巣性とはまったく関係がないが、#ブッポウソウ [ブッポウソウの巣は臭かった] やミサゴのひなの高度な隠蔽色から類推したもの。
#ミヤコショウビン備考の [ニュージーランドの外来ネズミ類駆除] 関連を調べていて齧歯類は嘔吐反応がないとの記述に気づいた。
Horn et al. (2013) Why Can't Rodents Vomit? A Comparative Behavioral, Anatomical, and Physiological Study
によれば解剖学的な制約よりも脳内の脳幹の嘔吐回路に関係があるのではとの結論。調べた対象は哺乳類のみ。
Huo et al. (2023) Brain circuits for retching-like behavior でも齧歯類は嘔吐反応がないので、とそれ以外の動物の嘔吐に関係する脳ニューロンを調べている。
Zhang et al. (2023) Evaluating proxies for motion sickness in rodent では齧歯類は吐かないが乗り物酔いは起こすとのこと。
鳥で嘔吐反応がない種類があるのか知らないが、上記の研究では肉食哺乳類では嘔吐反応がよく知られている。乗り物酔いで鳥が吐く報告もしばしばあるので鳥の一般的反応は肉食哺乳類の方に近いのかも。
古い研究では Chaney and Kare (1966) Emesis in birds によれば鳥の嘔吐反応の個体差や種差は哺乳類同様に大きいとある。
毒物に接する機会の多い植物食や昆虫食の鳥の方が反応が強くてもよさそうな感じもする一方、哺乳類同様に肉食のものほど反応があってもよさそうな感じもする。実際はどうなのだろう?
参考までに Ullah et al. (2022) Phytotherapeutic Approach in the Management of Cisplatin Induced Vomiting; Neurochemical Considerations in Pigeon Vomit Model ではハトが嘔吐反応モデル動物に使われている。
[ミサゴの世界分布の不思議]
Brown (1976) によれば、(広義) ミサゴはアフリカや南米でも越冬するのになぜかそこでは繁殖しない。南半球でもオーストラリアでは繁殖するので、アフリカや南米で繁殖しない理由が見当たらない。
食物資源の問題ではないと思えると記述している。
アフリカでは海ワシ類が魚を食べているが、南米では他に目立った魚食の猛禽類がなくミサゴノスリが役割を部分的に果たしている。しかしミサゴノスリは小型で大きな魚を捕ることはできない。
系統的にはミサゴの方が古いはずなので先に占拠してしまっていても不思議でないのだが ([ミサゴは不器用?] で考察するように古い系統ゆえ、後発の系統でも特殊化を行わなくても同じような機能が実現できてしまったのかも知れない)。
上記 [ミサゴはフグ毒に耐性があるか] を記述していてミサゴの繁殖分布が毒性の強い魚の分布を避けている可能性も気になった。例えばフグ科レベルだとこの解釈が当てはまるかも知れない (毒起源となる藻や細菌などは低緯度で繁殖しやすい)。
毒性の強い魚が多数生息しているところでは誤って食べてしまう確率も上がり、ミサゴにとっても毒の多い地域は不都合で熱帯地域を比較的避けて北方で繁殖するのかも。
それならば他の魚食の鳥も同様だろうが熱帯でも繁殖するのでは、と言われそうだがタカの系統とウ類などは何か違うのかも知れない。生態的にもウ類に影響を与える可能性のある有毒な魚は存在するのか、また実際に食べるか、毒に反応して吐き出すことはあるのかなどまた別問題になりそう。
また魚食ゆえに魚の寄生虫がミサゴで特に高率に見られ宿主となっているらしい。ミサゴ自身にはほとんど影響がないらしいが、魚由来の病原体や寄生虫も制約要因になっているかも知れない。
参考 Locke etal. (2024) Expanding on expansus: a new species of Scaphanocephalus from North America and the Caribbean based on molecular and morphological data。
Scaphanocephalus 属はほぼミサゴの体内のみで成熟するとのこと。漁業に影響のある寄生虫なのでよく調べられていると想像できるので、あまり調べられていないがミサゴに有害で分布を制約する要因となる寄生虫などもあるかも知れない。
[渡り]
北部ヨーロッパのミサゴの渡り追跡:
Ostnes et al. (2019) Migratory patterns of Ospreys (Pandion haliaetus) from central Norway (ノルウェー)。
8個体の若鳥の追跡で2個体が3暦年で繁殖地に戻り、その後の渡りも記録された。ヨーロッパハチクマ同様に越冬地は同じ場所に戻るが、ミサゴの方が同じ個体が同じ中継地を用いているよう。
Anderwald et al. (2021) Autumn migration of Ospreys from two distinct populations in Poland reveals partial migratory divide (ポーランド。秋の渡りのみ)。
他にも研究がありこの論文に一覧がある。
Hake et al. (2003) Satellite tracking of Swedish Ospreys Pandion haliaetus: autumn migration routes and orientation (スウェーデンの初期の研究)。
DeCandido et al. (2006)
Evidence of Nocturnal Migration by Osprey (Pandion Haliaetus) in North America and Western Europe 予想以上に夜にも渡っている。
ミサゴは海鳥のように海上の上昇気流を用いる: Duriez et al. (2018) Migrating ospreys use thermal uplift over the open sea 猛禽類で確認されたのは初めてとのこと。翼の形状が海上ソアリングに向いている。世界に広く分布することができる理由にもなっているかも知れない。
このような特徴は確かにミサゴ科独特で、他の根拠とも合わせて別科とする根拠にもなり得るのかも知れない。ただしミサゴは海に着水することはできない。
他にもいくつも論文があるので興味ある方はご覧いただきたい。
Ospreys Have A Shocking Spring Migration!
アメリカ東海岸のミサゴの渡りのいくつかの事例について。2015 年の "Wausau" は繁殖地に戻る前になぜか逆行してしまい到着が大幅に遅れ、つがいの相手だったメスはすでに新しいオスとつがいになっていた。しかし追い出すことに成功してこれまで通りのつがいとなったとのこと。"Belle" は6往復が追跡され (発信機が止まったらしい)、最初の年の秋の渡りでは海上を長く飛ぶことになった。
ハリケーンや嵐に何度も耐えたとのこと。
海上を長距離飛ぶのは猛禽類には危険で海上の死亡例が多いとのこと。1羽はポルトガル行きの船に不時着したとのこと。
[ミサゴの食性など]
ミサゴはほぼ完全に魚食であるが、アメリカガラス Corvus brachyrhynchos を捕食して生きたまま食べ、そして巣に運ぶ行動が記録された (記事; 連続写真)。
映像として記録されたのはおそらく初めてであろうとのこと。
魚以外を捕食する例では羽地・籠島 (2015) 沖縄県多良間島におけるミサゴによるミフウズラ採食の観察記録、
冨岡 (2015) ウシガエルを捕食したミサゴ の報告がある。Birder 37(11): 36-37 (秋山) にも紹介がある。
Birder が取り上げやすい種類らしく、Birder 2022年9月号 36(9): 28-32 にも各種獲物を運ぶミサゴの写真が出ている。ウシガエルやフグを運んでいる写真が出ている。写真へのコメントでフグを離したのを目撃したことがあるとのこと ([ミサゴはフグ毒に耐性があるか] や [大きすぎる獲物で溺れてしまうミサゴの話は本当か] の話題に関連)。
ミサゴが貝を落として割る行動も観察されている [Leshem (1985) Shell-dropping by ospreys]が、Lefebvre et al. (2002) (#イヌワシの備考参照) には含まれていない。
川口 (2010) Birder 24(8): 29 によれば紅海のチラン (Tiran) 島での事例のようである。
ミサゴとほぼ同じく、ほとんど魚しか食べない猛禽類がもう1種いるとのこと。
ミサゴノスリ Busarellus nigricollis 英名 Black-collared Hawk。南北アメリカの種類でメキシコからウルグアイにかけて分布する。
That's how you kill two fish with one bird! Predator swoops and snatches a pair of trout in one deadly move
にフィンランドで撮影された2匹の魚を同時に捉えたミサゴの写真が出ている。日本語では「欲の熊鷹股裂くる」というたとえがあるが、これはその上を行ってそうである。記事の英語のタイトルは「一石二鳥」を逆にもじったものだが、日本語のたとえの方が面白い気がする。
ちなみに日本語ではほぼ同じ意味で使える「一挙両得」の表現があり、バーダーはこちらを使おうなど話題となることがある。どうも英語ではバリエーションが乏しいようでどこにでも「一石二鳥」ばかり出てくる (なぜこのようなことが気になるかと言えば、英語の科学論文を "bird" で検索するとこの表現があまりにも多いのである。バーダーの視点から文句が出ないのだろうかと思えるぐらい)。
由来をちょっと追求しておくと、wiktionary によれば Dr. John Bramhall, Bishop of Derry が 1646 年に作った言葉とのこと。意外に新しい。同じく日本語の一石二鳥は英語のことわざの翻訳となっている。中国語でも同じで、「うまく言ったものだ」とすぐに導入されたのだろう。
ドイツ語ではハエ (wiktionary ではドイツ語のこのことわざのページが意外に詳しく、各国語の事例が多数出ている)、ロシア語ではノウサギと対象生物が異なる。英語表現の独自性はどの程度のものであったのか歴史的関係を調べてみると面白いかも。
「一挙両得」は晋書束皙伝と中国の歴史書由来。
ミサゴは第 IV 趾を後ろに回すことができる (semi-zygodactyly)。これが獲物を捉えるのに役に立っているかを検証した研究がある: Sustaita et al. (2019) Behavioral correlates of semi-zygodactyly in Ospreys (Pandion haliaetus) based on analysis of internet images
過去にはフクロウ類の足との類似性から機能が予測されていたが実証研究はなかった。
統計的に有意に獲物を掴む時に用いられていることなどが記載されている。
第 III 趾と第 IV 趾の間の膜が欠如していて趾を後ろにも動かせるとのこと。Bartosik (2009) によれば魚の硬い背骨を避けて両側を掴むためとの解釈がある。
ミサゴが獲物を捕らえたり運ぶ時、左足を前に出す傾向があるとのこと: Allen et al. (2018) Differences between stance and foot preference evident in Osprey (Pandion haliaetus) fish holding during movement。
労働寄生を試みられた時の姿勢の有利性などいくつか可能性が考えられるが、脳の側性を反映している可能性もあるとのこと。
Biggs et al. (2025) Assessment of a Social Media-Based Method for Determining Raptor Diet のソーシャルメディア画像を用いた研究で、オーストラリアのミサゴでは 99.4% が硬骨魚類 (Osteichthyes) だったとのこと。シロハラウミワシ Icthyophaga leucogaster White-Bellied Sea Eagle では硬骨魚類が 71.0%、鳥が 15.9% とミサゴがいかに魚しか食べていないかわかる。
ミサゴでは鳥は 1452 例中1例 チュウヒロハシクジラドリ Pachyptila salvini Medium-billed Prion あったのみで、これは魚と誤認識した程度に思える。
目視よりも圧倒的に効率が良かったが、観察者の偏在や話題の種 (例えばシロハラウミワシがヘビを捕える場面など) が取り上げられやすいなどのバイアスの問題も論じている。現状 (少なくともオーストラリアの) ミサゴは「ほぼ完璧な魚食」と表現して問題なさそう。
これだけの観察例がありながら獲物に引かれて溺死したとされる画像がまったくないのも興味深い。1000 に1つもないわけだ。
この研究は COVID-19 のパンデミックの最中に行われたもので、パンデミック前の 2019 年は観察数が少なかったが、ロックダウン中でも散歩は許されたため、近場の野鳥観察が増加した可能性もあると分析している。
しかし最近の画像を用いると AI 生成画像がある程度紛れ込むのでは?
[ミサゴの「足洗い」]
若杉氏のマーリン通信 ミサゴの「足洗い」は 本当に 足洗いか? の話題から。
雑誌 "WildBird" 1989.10 pp. 40-45 の Millard H. Sharp の北米のミサゴの記事で Osprey have a distinctive habit of "foot washing" (p. 43) の記述を見つけた。英語でも同じ表現が使われていたことがわかった。付随して osprey が s を付けずに複数形で扱われている。"The" も付いていないので種一般を表す名詞ではなく、複数形で不変化とされることもあったのだろう (fish もそうだった)。
当時は日本語の鳥の一般雑誌もなかったので洋書店で気に入った号を買っていた次第。
日本語の用語は独自に名付けられたものか、それとも欧米の書物の翻訳表現か?
この記事では食べた際に付く血やぬめりを除去するためと説明されている。
別項目 [ミサゴは不器用?] をまとめていて少し思い当たることがあったので補足しておくと、獲物の栄養価のためかミサゴの狩りの頻度は高いので食後も短時間でまた狩りに出る必要があると解釈した。普通の食性のタカ類ならば消化して待っているうちに自然に汚れが落ちることもあるだろうが、ミサゴは待ち時間が短いので次に狩りに備えて魚のぬめりによる滑り防止などを行う必要性が高いのでは、と考えた。
オオワシであまり目立たないのは例えばオオワシの方がより大型で、体重あたりの代謝率も低く、そこまで頻繁に狩りをする必要がないためでは?
また翼の特性からミサゴは着陸や離陸が比較的苦手で安全な環境でなければあまり地上に降りたがらないかも知れない。
#オオグンカンドリが睡眠を削ってまで捕食を続ける必要があるのも、獲物の栄養価の問題もあるのではと感じた。捕食してその都度陸に戻って休息していては十分な栄養が摂れないなど。
タカ類について逆に考えればほぼ完全に魚食のタカではミサゴより小さいと効率が悪すぎ、生理的にミサゴが最小サイズとなるかも知れない。南米のミサゴノスリは全長 51 cm と書いてあって (ミサゴノスリは尾が短いので) ミサゴとほぼ同大。ウオクイワシ類はさらに大きい。Raptor Research & Conservation Network (2018) "A Field Guide to the Raptors of Asia" ではウオクイワシにずいぶん小さな全長 (42-52 cm) が記されているが誤りか。
足から飛び込み型の魚食のタカは生理的制約から小型化できなかったのでは? おかげでカワセミ類の一部が別戦略を用いて繁栄することが可能だったのかも。
ウ類では舌に魚のぬめりが付くのを避けて舌を捕食用具として使わずほとんど痕跡器官となっている (?) - 我ながら妙に納得できてしまう統一的解釈にも見えるが、たかが足洗いからなぜこんな話になるのか (笑)。
ウ類が羽を乾かしているように見える行動も、次の狩りまでの間隔が短いため羽の状態を急いで整えていると考えればミサゴの「足洗い」と同様の意義があるのかも知れない。#カワウ 備考のガラパゴスコバネウの進化にも話題を飛ばしてみた。
[ミサゴは苦味を感じないのかも?]
#メジロの備考 [鳥類の嗅覚] にタカ類の苦味受容体の研究が紹介がある: Xiang et al. (2025) Functional decline of a bitter receptor gene in New World vultures。
T2Rs は肉食、魚食などの鳥には少ないとの Niknafs et al. (2023) との結果と合わせると、肉食と魚食で二重の意味で苦味の味覚の必要が薄れミサゴでは失われたのかも。タカ科との分岐後比較的早めの時期に失っていたならばミサゴ系統が現代のタカ科に相当する位置を占めて適応放散できなかった理由の一つになるかも知れない...と勝手に想像。
[兄弟殺し]
Redondo et al. (2019) Broodmate aggression and life history variation in accipitrid birds of prey ではミサゴは兄弟間闘争の強い種類に分類されている。
映像例 Sibling Rivalry on Osprey Nest 07/06/23 (birdsofpooleharbour 2023)。
[ミサゴは巣で餌の殺し方を教えない]
猛禽類がひなや若鳥に獲物の捉え方や殺し方を教えるかはよく議論になるが、ミサゴは巣で餌の殺し方を教えない研究が発表された [Howard and Hoppitt (2017) Ospreys do not teach offspring how to kill prey at the nest]。子供に「教える」行為は共同繁殖をする種のみで見られる証拠があり、行動生態学の理論的な根拠も考えられている。
しかし観察結果はバイアスの可能性がある。子供に「教える」と言い伝えのあるミサゴで調べたが、「教える」ことの知られている共同繁殖種とは逆の傾向が見られた。巣から飛び出しを促して餌を捕まえるのを教えるとか過去には報告があったが、ミサゴは飛んでいるものを捕まえるのはうまくないので、この手法で教えるのはそもそも無理なのではないか。観察題材は巣のビデオ中継とのこと。
[ミサゴは不器用?]
「鳥類の人工孵化と育雛」(原著 "Hand-Rearing Birds" Gage and Duerr (eds) 監訳 山崎亨 文永堂出版 2009)
によればミサゴは空中にいる時以外は不器用なタカで、他のタカは通常巣を隠すのにミサゴは出入りに便利な方を優先しているとのこと。
落ちたひなを戻す時などは高すぎて危険などで元に戻せない場合は別のミサゴの巣でも構わないとのこと。
不器用というよりも、ミサゴは猛禽類の中でも翼面荷重 (wing loading) が特に大きいためではとの指摘を受けた ([kbird:05998] 松原始氏)。
Bildstein (2017) に文献からまとめられていた翼面荷重の資料ではミサゴ (0.48-0.65 g/cm^2) とオオタカ (0.53-0.58 g/cm^2) では大差なかった。翼の形 (アスペクト比など) や尾が短いことにもよるかも知れないがいかがだろうか。
ちなみに翼面荷重はチュウヒ類が小さくこれらの値の半分ぐらい。トビ類もその中間ぐらいで小さめ。いずれも飛び方を見ると納得できる。
次の Gutherz and O'Connor (2022) のデータを見るとミサゴで 0.56、オオタカ 0.664、ヨーロッパノスリ 0.393、ヨーロッパチュウヒ 0.329、トビ 0.294、ヨーロッパハチクマ 0.31、イヌワシ 0.75 のような値が出ている。おおまかには体重で決まっている感じで同程度の体重のものを比べると思ったほど違いがなかった。
#ヨタカに関連して Strisores の進化を考えているうちにミサゴはやはり不器用と呼んでもよいのではと思えてきた。
理屈は同様で古く分岐した系統でありながら適応放散の兆候がほとんどないこと。タカ類の祖先系統の初期にいろいろな試みがあり、そのうち生き残ったものがヘビクイワシとミサゴであったと考えれば Strisores に現生種が1種のみの目がいくつもある状況に似ている。
Strisores がさらに古い系統なのでそれぞれが目扱いが妥当 (これはハチドリ目が Strisores に内包されるので分けざるを得ない事情があった) となっているわけだが、それよりは新しいものの ヘビクイワシ、ミサゴ、それ以外のタカ目は目レベルで分けても構わないぐらい系統的には遠い。
ヘビクイワシとミサゴがそれぞれ1種のみ残っている状況はいかにも Strisores のいくつかの目が生き延びた状況に近い。
Strisores に対比させて考えるとヨタカの系統が一般的なタカ類に対応し、ヘビクイワシやミサゴはタチヨタカやアブラヨタカのような位置づけになる。こちらもヨタカ類に外見が似ているので歴史的に目に分けられていなかったが、ヘビクイワシやミサゴも見かけがタカと判断できるので分けられていなかったに過ぎない。タカ目とハヤブサ目が別目となったのと同様、ミサゴと一般のタカは実際は見かけほど似ていないのだろう。
考えてみると古い時期はまだ Telluraves 系統の小型の陸鳥 (例えばスズメ目などを想定) もまだそれほど豊富でなく、捕食者が当時豊富に存在した資源、つまり魚や爬虫類に依存する選択を行うことも有力だったと想像できる。草原の広がりなどはもっと後の時代なので齧歯類系統もあまり豊富な食料にならかなったかも。
ほどほどのサイズの哺乳類はすでに存在したかも知れないが、当時のタカ類はまだ未熟で哺乳類生体食となるほどのことはできず、哺乳類では死体食 (コンドル目) に特化した程度に終わった可能性が考えられる。
それでも多様な食物を狙っていればまだその後の進化でさまざまな適応放散も可能だったのだろうが、当時としてはおそらく効率のよかった爬虫類食 (ヘビクイワシ) や魚食 (ミサゴ) を専門職として最適化してしまうとそれ以上の進展の可能性がなく進化の行き止まりになったと考えるのが妥当そうに思える。
ミサゴの場合は海鳥に収斂進化して水に体を沈める採食方法をとり、そのために足の骨格も重くなって防水のために尾脂腺を発達させ、飛翔方法も洋上上昇気流を用いるなど海鳥に似せたが、陸鳥出身なのでさすがにそこまで海鳥的にはなりきれなかった。
一時期は専門職が非常に有利だったのだろうが、この特殊化が制約となってその後栄えてきた陸鳥などを獲物とすることができなかった。
魚を食べる猛禽類でも後に進化したものはここまで特殊化を行わず「魚も食べる」機能を追加することで、体も沈めない採食方法 (海ワシ類など) を取り自由度がより高く幅広い食性に適応することができた。
例えばオジロワシではほぼ完全に魚に依存しない生活も可能である。
このように考えるとミサゴは (姿は格好良いが) 進化の行き止まりと考えるのが適切に見えてくる (ミサゴファンの方には申し訳ないが)。フラミンゴの形態を進化の行き止まりと考えるならばミサゴも同様と言ってもよいかも知れない。
生きた魚しか獲物と認識しないのも認知能力のある種の限界を示すものかも知れない。高度な認知能力を必要としなかったのだろう。
つまり生態的にも認知的にもあまり融通がきかないのである。飼育下でも代わりの食物をほとんど食べることがないので早めに放鳥するのがよいとされる。他のタカ類では食物に融通が効く状況とかなり異なる。[ミサゴに魚を捕らせることは可能か?] の項目参照。
魚に特に特化した猛禽類はある程度同じような傾向があるかも知れない。たとえばオオワシがオジロワシほど広域分布できない理由 (#オオワシの備考) や、シマフクロウの生態的基盤が弱いのは特殊な食性にも関係しているのだろうか。ただしこれらの種はミサゴのような古く分岐した独立系統というわけではない。
この考えはヤシハゲワシ (ヒゲワシ亜科) の食性を考察した副産物だった (#クロハゲワシ備考 [採食方法によるハゲワシ・コンドル類の分類])。つまりヒゲワシ亜科には十分多様な食性の種が含まれており、ヤシハゲワシもアブラヤシの実が好みでありながら大型の鳥類も襲い、魚食も行うなど十分ジェネラリスト的なところがある。
ヒゲワシ亜科の段階ではタカ目はすでに万能捕食者的要素を持っていたことが想像できる。チュウヒダカ類も同様でみかけ以上に強力な捕食者とのこと。ヒゲワシ亜科とハチクマ亜科は現状互いに単系統の関係にないのでハチクマ亜科と呼んでもよく、ハゲワシ的性質の強いものをヒゲワシ亜科と呼んでいるだけなので、この2亜科の最も祖先の分岐にあたるチュウヒダカ類が強力な捕食者であれば最初からレパートリーの広いグループだったのだろう。
その次のチュウヒワシ亜科はヘビワシの系統でややヘビ食に特化が見られるがカンムリワシも鳥を食べるようにスペシャリストというほどでもない。次のハゲワシ亜科も生きたものを捕える種類もあり少なくとも最初はレパートリーの広いグループだったのだろう。もっともハゲワシ亜科でも Gyps 属は当時生じた大量の草食獣の死体に依存するようになって進化的には行き止まり感がある。
すなわちヘビクイワシとミサゴより後の系統は基本的に万能捕食者の能力を備えていたと考えられる。ヘビクイワシとミサゴのみが万能捕食者になる前のタカの系統と見ることができる (+ 新世界ハゲワシ類のコンドル目)。
カタグロトビ亜科を忘れているのではと言われそうだが、カタグロトビに十分な捕食性能があるので捕食者能力を疑う人はいないだろう。台湾では同じ食性のチョウゲンボウより優位らしい (#カタグロトビ備考参照)。タカ類の早い系統でもこの関係なので、全般的に見るとタカ類の方がハヤブサ類より高性能と言える気もする。
DDT などの影響の時代は確かにあったが、ミサゴが環境変化に弱いらしいこともこの系統的理由があるのかも知れない (何でも DDT の影響で片付けすぎの傾向もある感じがする)。
現在は保護が進んで少なくとも日本ではどこでも見かける種類になっているが、これも世界全体で魚の捕りやすい人為的条件 (ついでに写真も撮りやすい?) を提供する形になっているためとも言えないこともない (カワウがどこでも増えているのと同様)。内陸進出したというよりも本来好みの生息地であったはずの海岸は人による擾乱が増えて生息地を内陸に移した形になっているのかも。
例えばカワウ対策として魚を捕りにくくすればミサゴはまた減ってしまうかも知れない。
英国では一時絶滅して現在でもそれほど数の多い鳥ではないなど生態的基盤は弱いのかも知れない。海外ではオオタカやオジロワシの増えたところで数を減らしているところもあり、このような系統進化的視点も含めて考えた方がよいと思われる。海ワシがさらに魚食に専念したものとは仕組みがだいぶ違うのである。
水中に潜る割には水深が比較的限定されている (1 m 程度) のもウ類やカツオドリ類のやり方と異なる。おそらく樹上性陸鳥出身ではそれ以上深く潜るのは不得意または無理で、浅いものに特化した (これも生息環境を限定する要因となる) のだろう。どの高さからダイビングするかはどこまでの水深を狙うかで決まることになるが、これがミサゴのホバリングの高さをほぼ決めているのだろう。
この高度に対応した視覚的適応もおそらくあるのだろう (#カタグロトビ備考 [風切羽や雨覆の構造と機能] で翼の構造などとともに視覚特性も考えてみた)。
このカタグロトビ備考でも触れたが、ミサゴもカツオドリ類も基本や自由落下で獲物への到達時間を短縮しているだけで、それほど大したことをやっているわけではない。地上への自由落下はより大きな危険を伴うのでもう少し高度な制御技術が要求されるだろう。
カツオドリ類は深く潜るので減速の必要がなく、ミサゴはあまり潜りたくない (身体の構造上できない) ので直前に減速する必要があり、人の反応速度でも追いつける程度となって、翼も適度に広げるので写真的にはよい題材となる。
カツオドリ類の突入写真をあまり見かけないのは速度が速すぎて人の反応速度で追いつくには限界があり、翼も広げないので写しても単なるミサイルに見えて見栄えがしないためだろうか (そもそも近場で見るのが難しいためかも)。ミサゴの飛び込みはほどほどに人の反応速度向きのタイムスケールと合っているということだろう。
ミサゴがカツオドリ類のような採食様式を進化させなかったのは、もともと樹上性で足でつかむことが得意であったためで、例えば水深の浅いところでかすめるように捕ったのが始まりかも知れない。足で捕らえることをこの段階で選択してしまったため頭から突入型になることはできなかった。
この方法では足から突入するために水の抵抗が大きく、形態を進化させてもさすがにカツオドリ類のように深く潜ることはできなかった。多少の高さから 1 m 程度まで潜水する程度以上の適応はできず、ウ類やカツオドリ類ほど本格的な技は編み出せなかったのだろう。後に海ワシ類、さらにはノスリ類が同じような方法で魚を捕る方法を進化させたが、特殊化があまり必要ない割には有効性は同程度だったのだろう。ミサゴの方が絶対的に有利な場面はあまりなさそうに思える。
ミサゴと同じもともと樹上性の Telluraves であるカワセミ類はそれではなぜ頭から突入型になったのか問われそうだが、これは第一義的には洞営巣性を進化させた Eucavitaves の系統で枝をつかむより洞営巣に適した体のつくりになっていたためだろう。少なくともカワセミ類の足の構造はまったくそうなっている。
ただし [タカ類の初期の適応放散] に述べたように Eucavitaves 系統に樹上営巣性のものがまったく残っていないのも不自然な気がするので、現存している系統だけを見ている先入観が入っているかも知れない。そもそもタカ類は初期は化石もなくどんな形態だったかわかっていないわけで、実は Eucavitaves に似た系統の形態から進化した可能性すらあるわけだ。
カワセミ類は頭から突入することで小型化も成功、というよりあまり大型だと脳への衝撃が大きすぎるのでそもそも大きくなれないのだろう (足から突入のタカ方式は小型化に向かないだろう話も別途検討)。
カワセミ類がなぜカツオドリ方式またはウ方式にならなかったのかもそもそも進化の出発点が違う、小型の体では潜水に不利など (Telluraves 系統の小型の潜水種はカワガラス類ぐらいのもの) の要因もあるだろう。
サギ方式は原理的にあり得たのではないかとも感じるが、Eucavitaves 系統を見ると一足飛びにサギの形になるのはさすがに無理そうに思える。
洞営巣性となった段階で長い足も首も基本的に邪魔になったのだろう。フクロウ類の首が短いのは眼球が大きいためと解釈していたが、こちらの理由の方が先だったのかも知れない感じがしてきた。洞営巣性のハヤブサ類の形も同様でタカ類より突出部が少ない。
#アオバズク備考 [卵の形の進化] のように洞営巣性では卵も丸くなる傾向が強いが、体も丸くなる傾向が強いのでは。
ただしサイチョウ類のように頭部を用いた争いのため、嘴を捕食用具 (ジサイチョウ類では地面のヘビを攻撃して食べるとのこと) や武器として用いる、巣穴にこもって首を出す、一部のサイチョウ類のようにのどの色彩をディスプレイに用いる、あるいはキツツキ類のように嘴を穴をあける道具として用いる系統では道具として二次的に首が長くなる方の進化もあったのだろう (#アリスイの備考にも飛ばしておく)。一方サイチョウ類と似た形態でも頭部を特に争いに用いないオオハシ類の首は長くなっていない。
しかしサギ方式で魚を捕る方向への進化はさすがに無理だろうか。
タカ類でもハゲワシ類が二次的に頸椎数を増やす進化を行っているので形態的進化はまったく不可能ではない感じがするが、この採食方式はすでにサギ類が広範に行っているので、後から進化したグループがたとえ中間的な形態で下手な方式で始めてもきっと追いつけなかっただろう。原理的には可能だったかも知れないが乗り越えるべき障壁が高すぎて別の進化経路をとる確率の方がずっと高かった。
結果的にカワセミ類はまだ使われていない方法でニッチを埋めた形になったのだろうか。
いつの間にかカワセミ類の話になっているが Birder 2025 年 6 月号の表紙を見ているためかも知れない。
ヒゲワシ亜科以降の種類と比べるとミサゴは確かに不器用に見える。海ワシ類の魚の捕り方の方が体をあまり濡らすこともなく、身体に特別な適応を必要とせず汎用度が高いように思える。
海ワシ類が魚に依存せず生きる例としてベラルーシのオジロワシの事例 (#イヌワシ備考 [イヌワシと他のワシとの種間関係] 参照) やサンショクウミワシがフラミンゴを捕食する例がある。
また解剖学などでミサゴを取り上げる場合はタカの1例と考えるよりも別系統のつもりで扱った方がよい。
第 IV 趾を後ろに回せることがよく知られているが、Hartert (1910-1922) でも p. 1191 で Federn ohne Afterschaft! (後羽がない) などあまり言及されない特異性も記されている。
なお Jollie (1976, 1977) p. 41 によれば後羽がない性質はミサゴ科の diagnosis の一つとされていたが deWitte Miller (1915) は後羽を持つ標本を見て驚いたなど記されている。Jollie 自身は reduced aftershaft or none (後羽は退化しているか存在しない) との表現とした。
適応のための進化が考えられるが、「タカの形はしているがかなり別物」のつもりで扱った方が先入観が入りにくくてむしろよいだろう。他の目とタカ目の比較の際に外見や大きさが似ているからと、ミサゴをタカ目の典型例のように取り上げると間違いのもとになり得る。わざわざヘビクイワシをタカ目の代表にする人はいないだろうが、同じぐらいの意味で。
また認知能力などを評価する場合も、ミサゴではできないので他のタカ類でもできないだろうと想像すると早合点になる可能性がある。巣のビデオ中継を記録しやすく人気もあるために研究対象として取り上げられやすいが、[ミサゴは巣で餌の殺し方を教えない] などもタカ類全般に成り立つかどうかは別途調べる必要があるだろう。
このような孤立系統で長い進化を経た経緯の考察は種や亜種の考え方にも影響が及ぶかも知れない。つまりすでにあまりに最適化されすぎたため進化の自由度が少なく、隔離されてもそれほど違った種類が生まれるわけでもない (革新が起きにくい)。現在でも地理的距離の大きさに関連して世界のミサゴは遺伝的にはかなり異なるものとなり、種として扱われたこともあったが、遺伝的には違っていても世界のミサゴはどれも同じミサゴに見える。
亜種を細かく記載する時代があったにもかかわらずミサゴの亜種が遺伝情報が示す以上に過剰に亜種記載がなされていないのは、見かけがほとんど同じで亜種と判断できなかったのではないだろうか。地理的に距離が遠くても、単に遺伝的浮動で遺伝的に異なるものになっただけで適応 (それぞれの個体群に応じた異なる選択圧) を伴っていなければ「何 % 違えば別種」の目安にかかわらず、遺伝的に離れていても同種でよいのかも知れない。
これらは地域による適応や進化速度の加速などの遺伝的証拠を調べれば判断できるかも知れない。結果的に遺伝的には大きく違うがミサゴは1種となってもよいかも知れない。新しく分化したスズメ目の隠蔽種間の遺伝的距離とはおそらく意味が違うと考えるべきなのだろう。
ある意味「完成形」となってしまったために進化速度が遅くなる例は多く知られていて、[染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] 項目で取り上げられている孤立系統のオウギワシが確立したのは 1700 万年前ぐらいでそれ以降は進化速度はおそらく遅くなっている。
#アマツバメ備考の [渡り鳥における磁気定位] で紹介のように、磁気定位がほぼ完成したと考えられる鳴禽類ではそれ以前に比べてクリプトクロム (Cry4) の進化速度が落ちている。
ミサゴも transposable elements の進化を辿れる程度の高精度ゲノムが得られればこの考え方を検証することが可能になるだろう。
さて、さらに考えてみるとタカ類は一般的にむしろ魚を避けているように思える。魚の捕れる場面でも捕ろうとしない種類が多い。海ワシ類 (トビも海ワシ類の系統) はむしろ例外的な感じがする。獲物としては比較的簡単なので魚を捕る習性がもっと進化してもよさそうな感じがするが、これはもしかすると栄養価の問題ではないかとアミノ酸組成を調べてみた。
参考 Mohanty et al. (2014) Amino Acid Compositions of 27 Food Fishes and Their Importance in Clinical Nutrition
硫黄含有アミノ酸ではメチオニンが代わりになるとはいえ、いずれもシステインが非常に少ない。メチオニンは魚の種類によって大きく異なり少ないものもある。
魚ではヒスチジンが多いのはよく知られている。羽毛にシステインが多量に必要な鳥にとって、メチオニンの少ない種類の魚はあまり良質の食材ではないのでは。可能ならばタンパク質源としておそらく自身にもっと近い系統の肉や羽毛を食べた方がよい。しかしそれら獲物を捕えるのは難易度が上がるわけだ。
非常に大量に食べられる食物であることで魚食生活が栄養的に成立しているので、ミサゴもウ類も食べてばかりいるのは栄養価が相対的に低いことの現れなのだろう。ウ類の食性などはもっと調べられてそうな気がするのでこの点に着目した議論があるかも知れない。
日本にいると魚食の方がヘルシーな印象を受けがち (魚を食べなさいと教育されることに影響を受けているかも知れない) だが実際にはどうなのだろう。
ここでは脂質含有量は調べていないが、ヘルシーと言われるのは脂質が少ないためでは。もしそうであればエネルギー的にはあまり効率がよくない。この部分も「和食はヘルシーなはずだから」と結論の方向性が先に決まっていたのかも知れないとかふと思ってしまうがさらに横道に逸れそうなので...。
このアミノ酸組成は#ハチクマ備考の [ハチの子は栄養満点か?] のハチの子とも似た点があって、ハチの子ではメチオニンも少ないらしい。ハチクマ生活も豊富に食べられるならこそ成立している食性なのかも。ただしハチの子は脂質含有量は優れている模様。糖質目的でないことはハチミツを狙わない点から判断できる。
そしておそらく足りない栄養を補うため陸上性の脊椎動物も食べるし、肉だけで生活することも可能 (大発生したネズミ類を食べるのはそちらの方が栄養的に優れているわけだ)。ハチクマも魚はそもそも体に合わないらしい。
ミサゴはおそらくそこまで器用でなかったため陸上性の脊椎動物はほとんど食物にすることができず、魚を大量に食べることで栄養要求を満たしているのだろう。魚は栄養的にはそれほどよい資源ではないため陸上動物食の可能な多くのタカ類は無視し、理屈の上では可能であっても魚食性のタカ類が世界に広く分布することにならなかったのかも知れない。フクロウ類ではもう少し魚食性のものが多いが同じような議論が成り立つかも知れない。
ハヤブサ目では簡単に調べた範囲で魚食性が目立つものはいない模様。ヘビが主な食物となっているワライハヤブサでは食物リストの最後の方に出てくる程度。猛禽類にここまで敬遠されるのはやはり魚食のメリットが小さいのでは。
このような視点で考えると (オオワシ・オジロワシやハクトウワシのファンの方にまた怒られるかも知れないが) 一部魚食となった ノスリ亜科 Buteoninae のトビ族 Milvini は堕落したワシ・タカの系統と言えないこともない。ベンジャミン・フランクリン Benjamin Franklin がハクトウワシがアメリカの国鳥にふさわしくないと考えた理由もわからないでもない (ただしこの部分は通説と異なるところがあり、wikipedia 英語版に書簡が紹介されている)。
種類数はそこそこあるが、トビ属 Milvus、シロガシラトビ属 Haliastur、オジロワシ属 Haliaeetus、ウオクイワシ属 Icthyophaga (ウオクイワシ属はオジロワシ属に含められることもあるぐらいでそれほど分化していない) と、食性が他と異なる割にはあまり多くの属を生んでおらず系統的にも広がりを欠いている感じがする。
魚食がもし優れていたならば複数系統から進化して全世界を占めて競争になっていただろう。
ただしトビ族は後に誕生した系統だけあって食性の可塑性の高いものが多く、オジロワシのように万能捕食者も含まれている。
#オジロワシの備考 [オジロワシ属の系統分類] でも示したように、このグループでは広域に分布することに成功したオジロワシとハクトウワシがむしろ例外で、この系統の典型的な種類はむしろキガシラウミワシと言えるかも知れない。
ミサゴにとっては後に進化したタカ類などの強力な競争者があまり現れず、古い孤立系統であっても生き残ることができたと解釈することができるかも知れない。要するにミサゴは遺存的と言っているわけだ。
なんだか人気あるワシ・タカを片っ端からけなして全世界を敵に回しているような気がしないでもないが、清少納言「枕草子」の系統進化をふまえた現代版とでも捉えていただきたい (笑)。
記述している最中にこのような論文が出た: Varghese et al. (2025) Unravelling cysteine-deficiency-associated rapid weight loss
マウスの実験なのでそのまま当てはまるかどうかはわからないが、システイン制限は体重減少に役立つとのこと。体重減少が健康的であることを意味するのかそもそもよく知らないが、アミノ酸制限の中ではシステインが重要な役割を果たすことがわかったらしい。システインの少ないミサゴの食事が他の猛禽類に比べて健康的なのか...はよくわからない。野生動物にとっては (いや現代人以外でも同じでは) 体重が減る方が不利のような気がするが...。
「2025 年 5 月にネイチャーに発表された研究によりますと、アミノ酸の中でただ一つシステインを減らすだけでマウスの体重が減ることが明らかになりました。魚のタンパク質にはシステインが少ないことが知られています。魚食がヘルシーであることがこれでまた一つ科学的に裏付けられました」のような紹介がすぐに現れても不思議でなさそう。もっともこのぐらいの解説ならば AI がすぐ作り上げてくれるだろうが。
[ひなの色]
ミサゴのひなが他のタカ類に比べて白っぽくないことに気づかれている方もあるだろうが、Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" p. 173 によればミサゴのひなでは "brown down" がやや縞状に生えて多少は隠蔽色になっているのではと解説がある。目立つところに巣を造らざるを得ないためだろうか
(関連情報は #カタグロトビ備考の [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] を参照。フクロウ類のような mesoptile が関係しているのかも知れない)。
同書でゴマバラワシ Polemaetus bellicosus Martial Eagle のひなは黒色と明るい灰色とのこと。Brown (1976) はこれらの時期は親が抱いているのでひなの色はあまり関係ないのでは、と述べている。
ゴマバラワシはイヌワシ亜科の非常に強力なワシだが巣は樹上の開けた環境に造るよう。ひなの色と多少は関係あるのかも知れない。日光が強すぎて真っ白では光が体表に入りすぎるなどの理由も考えられるかも。
イヌワシ亜科のひなはどれも白いわけではなさそう。
(追記) Jollie (1976, 1977)
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part II)
に当時ワシタカ目の羽毛の詳しい情報があった。ミサゴのひなは生まれた時点で protilae と metaptilae の両方が生えているとのこと (p. 41)。真っ白ではない理由となる。ミサゴは他のタカ類に比べて生まれたばかりのひなの綿羽が短く、縞模様になっている点で特異とのこと。他にも異なる点が多く羽毛の面でも科レベルで違うよう。
CJ7 wards off Honey Buzzard from nest 20/06/2025 (birdsofpooleharbour 2025.6.20) 英国のミサゴの巣の中継から。
聞こえるもう1羽の声はオオタカのように思えて、若杉氏にお伺いしてミサゴの声のようにも聞こえます、とのお返事をいただいた。自身でもスペクトルを比較してミサゴの声と判断した。ビデオ表題は映像に現れるメスのみを表すもので、雌雄2羽で追い払いを試みていたのだろうと考えた。ミサゴのひながいかに隠蔽色となっているか非常によくわかる。
ヨーロッパハチクマが他の猛禽の巣のひなを襲うのかどうか違和感もあるが、サギのコロニーを襲うぐらいならばあり得ないことではないのかも。
もう少し調べてみるとメスのヨーロッパハチクマが狙っていたらしい: Harbour Update 20/06/2025 空中戦を演じた後ヨーロッパハチクマは立ち去ったとのこと。
[ポーランドで減少するミサゴ] で紹介されているように、警戒音が近隣個体の防御反応を誘発するのに有効かも知れない。カイツブリの警戒音の役割に似ているかも。
さらに、この警戒の声はあるいは音声擬態の効果があるのではと考えてみた。もちろん学習を想定したものではなく、そのような性質が進化の過程で選抜されてきたと考える。
鳥類捕食者にとってはオオタカのような声は威嚇効果が期待できるかも。狙ってきたのがオオタカやオジロワシであった場合には効果があるのかわからないが、威嚇時の声をオオタカに似せることは一定の防御効果が期待できるのではと感じる。
もしそうであればオオタカや類似の声を持つ種類の生息している地域で有効と考えられるので、ミサゴの声の世界分布を調べればある程度検証可能かも知れない。xeno-canto をチェックすると北欧やアメリカの記録に多い印象を受けたが単に記録バイアスかも知れない。検討課題である。
近年は鳴禽類以外でも音声の違いが分類基準の重要要素とされていて、たとえばアメリカとアメリカオオタカの種レベルの声の違いも不十分ながら検討されていた。上記考察のような音声擬態の効果がもしあるならば少し気をつけないといけないかも知れない。地域の別種または亜種との擬態関係があるならば、ハチクマの色彩や冠羽の有無などの擬態的な可能性のある要素と遺伝的距離との間に必ずしも大きな相関がないことに対応している可能性がある。
世界分布するミサゴは遺伝的距離は遠いが別種に値するとは現在あまり合意されていない。この分離判定基準に音声の違いも含めるならば、音声擬態の効果の可能性も考慮に入れるべきであろう。音声に選択圧が働いて分化する以前に短期間に分布を広げたのであれば地域によって音声にあまり違いがないことも考えられる。
[ミサゴの大腿骨は含気骨でない]
Gutherz and O'Connor (2022) Postcranial skeletal pneumaticity in non-aquatic neoavians: Insights from accipitrimorphae
がタカ類骨格の含気率を調べている。調べられた中でミサゴは唯一大腿骨が含気骨でなかったとのことで、水面突入時に獲物に対する操縦性能を高めるためかとの推論。
他の種類では新世界・旧世界ともハゲワシ類が上腕部先端部まで含気が進んでいてソアリングへの適応か。
広義ハイタカ属や Aquila 属の多くで尾骨に含気が進んでいて操縦のための尾が長いためか、などの考察がある。他の系統でも散発的にあるがノスリ類には少ないとのこと。
系統樹と特徴が図示されている。また解析に使われた種の wing loading などのパラメータも含まれている。全体的にはタカ類の間で期待したほどの差がなく、体重などのパラメータとの相関もあまりなかったらしい。
上腕骨に限ったものだが広い分類を扱った研究がある。Burton et al. (2023) Direct quantification of skeletal pneumaticity illuminates ecological drivers of a key avian trait
潜水性の鳥では含気骨になっていないなどある程度知られている結果を再現することになった。これらは骨皮質が厚くなっている。生態を反映しているが系統 (Elementaves で顕著) も表れている。スズメ目の中にも例外的なものもある。
Moore et al. (2025) When the lung invades: a review of avian postcranial skeletal pneumaticity に新しいレビューがあり、
Gutherz et al. (2021) Postcranial Skeletal Pneumaticity in Cuculidae でカッコウ目が扱われているとのこと。Moore et al. (2025) のレビューではタカ類の上記研究とともに体重が大きいほど含気部が増える予測をそれほど裏付けていないとしている。系統内の広い種を調べた研究はまだこの2例とのこと。
Moore et al. (2025) は含気骨となっても必ずしも体重が軽くなるわけではない (同様の体重で含気度の異なる種類で体重はあまり違わない)、ただし体重比では骨が軽くなっている可能性はあるもののまだ実際に確かめられていない。
長骨の曲げなどに対する強度を予測する直径と骨の厚みの比では、含気骨の種類とそうでない種類が重なっていて含気骨かどうかは強度にはあまり関係がないだろう結果となった。一方で翼竜では極端に骨の薄いものがあって鳥類とは異なる選択圧の存在を示唆する。鳥類の骨は軽さを追求するより時折生じる急激な力に耐える必要があるとの解釈がある (しかし Currey and Alexander 1985 とこれまた結構古い)。
もし含気骨となることで骨の強度が落ちるならば、何か別の利点があると考えられいくつかの仮説が出ている。有力なところでは骨格を軽くすることでエネルギー効率を上げる、骨の構造の最適化のため、があるらしい。空冷効率を上げるためとの仮説もあったが実際にはほぼ効果が期待できないとのこと。
まだ納得できる説明には至っていないよう。セイタカコウ Ephippiorhynchus asiaticus Black-necked Stork では体重がずっと大きいにもかかわらずマガモより頸椎の含気度がずっと低く体重が大きいほど含気部が増える予測と合わないとのこと。μCT + 画像処理 AI で含気部を判別する手法が使われており今後測定例が増えることが期待される。
Klein et al. (2025) Avian air sacs and neopulmo: their evolution, form and function には系統と気のう・含気骨の関係が示されているが、まったく研究のない系統も多数あって傾向は多少知られているものの今ひとつよくわからない。
neopulmo と呼ばれる気のうに関連する細気管支 (neopulmonic parabronchi) も知られていて、原始的な系統の鳥には見られないので進化した形質と考えられるが、進化した系統にあまり一貫性がなく生理的役割もよくわかっていない。
[地上営巣するミサゴ]
Bildstein (2017) p. 121 によれば地上性の捕食者のいない島などでは地上営巣するミサゴがあるとのこと。
例えばメキシコ北西部、紅海の島が挙げられている。砂漠で淡水に囲まれたカリフォルニア湾 (Sea of Cortez) の島では世界でも最も高い営巣密度になっているとのこと。
ミサゴの翼の機能を考えると、地上営巣したくても地上性の捕食者のいないよほど恵まれた環境以外では実現できないかも知れない。
[ミサゴの営巣を防ぐには?]
うらやましい話だがミサゴに営巣されると困る人もあり、このようなスレッドもあった。
osprey problems (Tidal Fish) いろいろ試したがうまく行かなかった。代替営巣場所を用意することで解決したとのこと。もし困っておられる方があれば参考までに。
[ポーランドで減少するミサゴ]
どこでも数が増えているとされるミサゴだが、ヨーロッパで唯一ポーランドでは成鳥の密猟で数が減っているとのこと。Wozniak et al. (2022) Red Spot on the European Green Map: Will the Extra Catastrophic Phenomenon Take the Polish Poaching-Pressured Ospreys to the Brink of Extinction?。
2019-2020 年の巣のカメラモニターにより、ひなのみならず時には成鳥も想像以上にオオタカやオジロワシに捕食されていることがわかった。オオタカによる捕食が卵が孵化しない要因に匹敵する繁殖失敗の要因になっている。生涯の子供の数を下げる大きな要因になっている。
繁殖密度が高い場合は近隣個体が捕食者に反撃する行為が巣を守る効果があるが、個体密度が減少して巣の間の距離が長くなり有効に働かない可能性がある。密猟によって成鳥が死ぬことはさらに大きな打撃がある。
ポーランドでは減少しているが近隣のドイツやベラルーシからの個体の流入がある (生態学的には sink となっている)。もしこの流入がなければ密猟で数を大きく減らしていたはず。絶滅のおそれがあるとも言える危機的状況で、現状は密猟を防止する対策しかない。
Gryz and Kranze-Gryz (2018) Pigeon and Poultry Breeders, Friends or Enemies of the Northern Goshawk Accipiter gentilis? A Long-Term Study of a Population in Central Poland
同じ地域ではないだろうがポーランドのオオタカの推移の研究がある。迫害や DDT、森林伐採で減少した時期があった点は他国と同様。そのころに比べて個体数は増え、1980 年代に密度が高く、近年繁殖つがい数が減少している。
1980 年代は森林被覆率の低い地域に分布して豊富なハト (ドバト) に大きく依存していた。
かつては庭ではニワトリが飼われているのが普通でオオタカのよい食物となっていたが、養鶏場で飼育されるようになり、また鳥インフルエンザで屋外飼育も制限されるようになった。
かつては狩猟も行われていたものの人間活動由来の十分な食物があった。代わりの食物 (ライチョウ類などの狩猟鳥やカラス類) が十分になくて食物不足になっているとの解釈。
[ミサゴに魚を捕らせることは可能か?]
英語で調べていて osprey fishing という表現を見つけ、ミサゴに魚を捕らせるのかと思ったが、これは中国のカワウを使う鵜飼のことだった (中国語をそのまま訳すと fish hawk となり、ミサゴの英名にされたものらしい)。#カワウの備考 [カワウを使った日本と中国の鵜飼] に。
この時はこれで納得していたのだが、何とミサゴに魚を捕らせることが本当に試みられていた。
ミサゴを訓練して魚を捕らせるのは従来と不可能とされていたが、正しくないことが示されたとのこと。
Osprey Falconry。
"Ospreys in Falconry: A falconer's adventures with an osprey" という本まで出している。2022 年の日記が出ているが、半分食べた魚を持って戻ってきたとのこと。
Is An Osprey Considered A Bird Of Prey? によればミサゴを訓練するには十分な経験を必要とするが、利口な (原文 brilliant) 鳥で訓練によく応じるという。哺乳類や水鳥を捕る鷹狩りまで可能であるとのことだが、十分な知識と他の猛禽類での経験が必要とのこと (情報の確かさはよくわからないが)。
(The Modern Apprentice) にも情報があり、ミサゴのリハビリテーションにも特有の技術が要求される。主な食べ物が魚なので獲物の探索像が生きて泳いでいる魚が中心になり、魚を生きたようにみせかけるなど餌を認識させるのに工夫が必要とのこと。
好みも特殊なのでミサゴを用いた鷹狩りの研究は、猛禽類を理解したりリハビリテーションなどの保護にも有用な情報を与えるということだろう (なおアメリカでもミサゴは保護されていて通常は鷹狩りに使うことはできないらしい)。
[ミサゴの体臭]
ミサゴは例えば救護された鳥として届けられた時に、開けなくても種類がわかるほどににおいが強いという。例えば宮崎 (1987)「鷲鷹ひとり旅」には脂肪分の強いヒツジによく似た独特の体臭を持っているとある。
ただしこれは魚食性の鳥なので、という理由ではないようである。尾脂腺の油のようで、その点では他の鳥と変わらないそうであるが、タカ類の中では例外的によく発達しているということのようである。
英語ではミサゴの羽毛を指して "oily" が (oily waterproof coating 防水性のある油のコーティングをした のような表現で) しばしば使われる。
そのためミサゴは水中まで没して魚を捕ることができるが (鼻孔開口部も閉じることができる)、魚を捕るオジロワシは羽が濡れてしまって乾かすのに時間がかかるため水中には没しないそうである (オジロワシの wikipedia 英語版より)。魚食のワシは魚食性の鳥のにおいがするのか、と聞かれたことがあるがそうではなさそうである。
鼻孔開口部も閉じることができる点については Jollie (1976, 1977) A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part III) pp. 119-121
に dorsal and ventral margins of the external naris overlap at the postventral corner と記述がある。開口部の上下の皮膚が重なり合うとのことで、これはハチクマ類でも同様かも知れないとある。
用語を調べてみると operculum の名称があるらしく、潜水する鳥が鼻孔を閉じる際に使われるとある (wikipedia 英語版 Beak の項目より) のでミサゴのものもこの用語でよさそう。
花の蜜を食べる鳥でも花粉が詰まるを避けるため同様の機能がある。Attagis 属 (ヒバリチドリ類) は砂ほこりが入るのを防いでいる。
オーストラリアガマグチヨタカ Podargus strigoides Tawny Frogmouth では鼻腔の乾燥防止や湿度維持に働いているとのこと。ハト類では発達していて上嘴基部を覆い、しばしば cere (ろう膜) と呼ばれるが別物である。Tapaculos (Rhinocryptidae) オタテドリ科 は operculum を動かすことのできることが知られている唯一の鳥 (以上 wikipedia 英語版より)。
ミサゴで operculum を検索するとミサゴの食物の魚のエラにある operculum が検索されてしまい、ミサゴの鼻孔部に対する用例があるかどうかはわからなかった。
おまけで Jollie (1976, 1977) p. 119 によれば Shufeldt (1891) はミサゴは耳管の前方開口部を完全に閉じる機能があると報告されている (水圧への適応を示唆している) が、Jollie 自身の観察ではこの見解は確認できなかったとのこと。
Shtegman (1937) "Faune de l'URSS Oiseaux Vol. I n.5 Falconiformes" (参考文献参照) p. 4 によれば、Stresemann によればミサゴの尾脂腺は同じサイズの他の鳥よりもさらに大きいとのこと。昼行性猛禽類の尾脂腺は中程度の大きさでミサゴのみが例外とのこと。
[ミサゴの体温調節]
Rogalla et al. (2021) Thermoregulation and heat exchange in ospreys (Pandion haliaetus)
がサーモグラフィーなどを用いたミサゴの放熱の研究をしている。嘴の表面近くを動脈が通っていて熱を逃がせる可能性があるが、実測では脚と趾からの放熱が多かった。外気温が上がってくると喘いだり翼を広げる行動を示すが頭部に低温領域が生じて皮膚からの蒸発で放熱していると考えられる。
鳥類の嘴は血管が豊富で、放熱器官として役立っていることについての論文は Tattersall et al. (2016) The evolution of the avian bill as a thermoregulatory organ、
van de Ven et al. (2016) Regulation of Heat Exchange across the Hornbill Beak: Functional Similarities with Toucans?
などが参考になる。湿度の高い熱帯林に住むサイチョウ類などは蒸発による放熱があまり期待できないので蒸発に頼らない放熱の必要があるなど。
Coulson et al. (2024) Non-evaporative heat dissipation across the beaks and casques of large forest hornbills も肯定的な研究。サイチョウ類などで嘴やカスクの温度は外気温より 10-12°C 高く、代謝による熱の 31-83% を放散していると見積もられた。
気温が上がるとあるところから嘴の温度が急に上がる。サーモグラフィー画像も出ている。
タカ類ではアフリカのハゲワシ類3種のデータが使われている。体重が大きいほどより低い温度で嘴の温度が上がる傾向はサイチョウ類などの延長上にあるとのこと。
一方で異なるニュアンスの研究もあった: McQueen et al. (2023) Birds are better at regulating heat loss through their legs than their bills: implications for body shape evolution in response to climate
上記の結果とは違って嘴は外気温に合わせて急上昇が見られておらず、足の方が体温調節に役立っているとの考察。嘴はあまり温度調節ができないので寒冷環境ほど嘴が小さくなる傾向の説明になる (寒冷地ほど出張った部分が小さくなる Allen's rule アレンの法則 に従う理由になるように見える)。
サーモグラフィー画像で比較的簡単に測定できるので手頃な研究テーマになっているかも知れない。
鳥には汗腺がないので皮膚からの蒸発による温度調節はそれほど重要視されていなかったが、Arieli et al. (2002) Cooling by cutaneous water evaporation in the heat-acclimated rock pigeon (Columba livia)
のカワラバトによる実験では暑さに慣れたハトでは皮膚からの蒸発が古典的な呼吸による熱放出 (あえぎ呼吸) に完全に置き換わってしまったとのこと。皮膚からの蒸発の方が水分バランスのためにより効率的であるとのこと。アドレナリン感受性の皮膚の受容体があり、毛細血管を拡張して皮膚血流を増すことで蒸発による熱放出を高めている。
ハト類は乾燥環境に適応したグループなのでこのような熱放出が起きやすい生理機構が特に発達しているかも知れない。
鳥が皮脂腺から脂肪を出して皮膚を防水するよりは水分蒸発で体を冷やす機能の方を優先している点については#フルマカモメ備考の [におう鳥のリスト] も参照。暑さに慣れたハトでは皮膚の脂肪含有量も変化していたとのこと。哺乳類でも汗腺で体温調節を行う種類はそれほど多くなく、鳥も汗腺がなくてもそれに対応する体温調節機構があり風の涼しさは十分感じているはず。
密生した羽毛でハチの攻撃を防いでいるハチクマではどうなっているのだろうか? 足以外にあまり熱が逃げるところがないかも知れない。渡りの時でも口を開けて飛んでいるハチクマはしばしば見かけるがやはり暑いのだろう。海外映像でもハチクマの水飲みの場面はしばしばみかけ、他のタカ類に比べてよく水を飲んで暑さをしのいでいるかも知れない。
口を開けても日本の夏のように湿度が高いと上記サイチョウ類やオオハシ類と同様蒸発による放熱があまり期待できず、ハチクマが西日本に少ないのは暑さにも関係しているかも知れない (近年の暑すぎる夏を体験していると一層そう思えるだけかも...)。もっとも熱帯には留鳥亜種が生息しているので暑さそのものが制限要因ではないかも知れない。
シラコバト (abstract ではジュズカケバトとなっている) のサーモグラフィー画像があった: Crandell et al. (2025) The role of plumage and heat dissipation areas in thermoregulation in doves
体部からも熱を逃していることがよくわかる。風を当てて涼しくすると高温領域が著明に減少する。温度負荷 (飛行後など) では顔、足、翼が特に高温になっている。
ダチョウの体温調節: Svensson et al. (2024) Heritable variation in thermal profiles is associated with reproductive success in the world's largest bird 首と頭に温度差があり、首が頭部の体温調節に用いられていることがわかる。温度調節が優秀なメスほど高温下の産卵能力が高かったとのこと。
サーモグラフィー画像から脚も放熱に用いられていることがわかる。体温調節能力が遺伝とどのように関係するか、亜種の分布域によって異なる気候への適応の遺伝的メカニズムを示唆する最初の研究とのこと。
Monge et al. (2025) What does infrared thermography tell us about the evolutionary potential of heat tolerance in endotherms? この論文へのコメントで、研究の方向性は正しいと考えるがサーモグラフィー画像のみから熱耐性メカニズムを正しく評価できるか疑問も呈している。手軽にできる測定方法の限界も指摘している。
また Svensson et al. (2024) が脚の放熱を考慮していないのは不思議である (おそらく頭部の冷却機能を重視したかったためでは?) など。
この論文にカナダガンの冬場のサーモグラフィー画像があり、嘴を羽毛にうずめた状態でいかに放熱が抑制されるかもわかる。
[英名などの語源]
英名の osprey の語源については 15 世紀中頃に osprai < 英仏語 ospriet < 中世ラテン語 avis prede (bird of prey 猛禽類の意味) と呼ばれていたが、現代英語の osprey はフランス語でヒゲワシを意味した ossifrage (骨を砕くもの) と混同され、音も似ているためこの単語になったものと推測されている (Online Etymology Dictionary)。
os- を見て骨を連想するのは正しいようである。
OED によれば osprey に別語義があり、osprey feather, osprey plume の用法でサギの羽毛を用いた婦人の帽子類の飾りを指し、かなり現代に近い用例もある。この場合は real osprey (1990 年の用例) はミサゴではなくサギを指すのだろう。なぜサギも指すのかについては明瞭な解説はなかった。
英語ではほとんど事例がないが (1601 年の用例があるとのこと)、同系語で orfraie はフランス語で現在もオジロワシを指す。
ドイツ語では Fischadler (魚ワシ) なのでこの単語を見るとつい英語の fish eagle を想像してしまうが、いわゆる海ワシ類はドイツ語で Seeadler (この単語のみでオジロワシを指す)。英語で何とか fish eagle と呼ばれる種類もドイツ語では何とか seeadler の名前になっているようである。
つまりミサゴはドイツ語ではワシの名称 (分類?) になる。日本語では多分タカの方に分類されるのでは。
他の言語ではそこそこバリエーションがありフランス語では balbuzard pecheur (釣り師の balbuzard、balbuzard は英語の bald-buzzard 由来とのこと: 出典。bald はハクトウワシ同様で「頭に白いところのあるノスリ」となる。#ハクトウワシの備考参照)。スペイン語も gavilan pescador (釣り師のタカ)。
ロシア語では特殊で skopa (アクセントは後でスカパーと読む)。語源はよくわかっていないがインド・ヨーロッパ語族の skopiti (削る、剥ぐ) に由来する可能性がある。趾が後ろにも回って二重の「取っ手、かすがい」skoba を形成するとの別の説もある (Kolyada et al. 2016)。
[ミサゴの漢字について]
鶚の漢字が使われるが、由来は何だろうと調べてみた (おそらくどこかでもっと詳しく調べられているだろうが)。
wiktionary によれば形声文字に分類され古代中国語で *na:g とのこと。ミサゴの鳴き声がそのように聞こえるのか疑問の感じもするが、ブッポウソウの表記のように子音の感じ方は様々と言えるのでミサゴの鳴き声の範囲なのだろうか (#ウソの備考 [ウソの漢字の意味] 参照。種が違う可能性がありそうだがウソが hok と聞かれていたらしい)。
...一鶚... によればこの表現は「史記」に登場するとのことで、猛禽を 100 集めても1羽の鶚に満たないとの語句とのこと。平凡な者を集めても非凡な者に敵わないたとえ。ここでは "鶚" が最上の表現となっている。
ミサゴがそれほど優れているのか知らないが、形声文字とすれば実は別の鳥を指していたのかも。あるいは猛禽は一般に黒や茶色っぽいので、白い猛禽は特別に神格視されていたのかも知れない。ミサゴファンの方には朗報かも。もっとも海辺に主に生息する鳥は内陸部の学者にはおそらく馴染みがなく、噂や想像でそのように呼ばれていただけかも知れない。
それはともかく "鶚" の漢字は朝鮮半島にも引き継がれ、こちらでは ak の音になっている (現在のミサゴのハングル表記も同じ)。
"鶚" と同語源とされる文字に 益+鳥 の文字があり、古代中国語で *ngle:g など、中世に ngek と読まれていた。現在は yi の音になっている。古代の意味で水鳥の一種。舳先に鳥を描いた船の意味に使われる。
日本語では呉音でぎゃく、漢音でげき。"げきす" の単語で用いられた。同じ文字は朝鮮半島にも引き継がれ ik の音 (広東語でも jik)。wiktionary では fishhawk bow or prow とあるのでミサゴとつながっていた。魚を捕るタカの舳先の意味だろうか。例えば船に描かれた鳥の絵を見て "げき" とはミサゴのことと理解されたのかも知れない。絵だけ見れば水鳥に見えたかも。
これらの古典に非常に通じた人であれば、ミサゴ = 水鳥 の連想、[大きすぎる獲物で溺れてしまうミサゴの話は本当か] の「うけらがの花」(橘千蔭 1801) のような頭の中で考えたような創作が生まれてもあまり不思議でなかったわけだ。博識で文字は知っていても、具体的に何を意味するかは古典の用例から判断して想像するしかなかったのだろう。
大橋 (2023) Birder 37(4): 50-51 では「かくかのとり」(現代の文字表記では覚賀鳥。最初の文字は旧字体で上は学の旧字になっている) がミサゴの異名として日本書紀に登場するとのこと。大橋氏は声がそのように聞こえないことを気にされていたが、中国古典由来で "学" が形声を表すならばウソと同じように読める。"鶚" の音読みと同じ。「かくかのとり」に関連する用例は「かくか」でも鳥関係でも中国古典には見い出せなかった。
大橋氏の記事によれば、かつては「みさごいる」の枕詞として使われていたものが、1310 年ごろの歌集で「みさご」を詠んだ歌が複数あるとのこと。しかし江戸時代にはほとんど題材にならなかったようで、これも流行現象のようなものだったのではと考える。つまり歌に詠みながらも先人の用例を踏襲しただけのもので「みさご」が何なのかよくわかっていなかったのではないだろうか。
日本語に限らず有名な言語でミサゴの語源が自明でないないものが多い。英語の osprey、ロシア語の skopa、中国語の鶚のいずれも同様である。つまり現地を訪れることもない (昔は容易ではなかっただろう) 中央の学者や文人にとってはわからないままに伝承に基づいて用いられていただけではないだろうか。
なお「かく」の古い文字に "てへん" を付けると新字体では "撹"。古代の推定発音で *kru:? (Proto-Sino-Tibetan language *kruk に由来と考えられる) の発音で "乱す" の意味で、覚醒の "覚" の意味にもつながる (wiktionary よりよりまとめ)。呼び起こすような音声の文字表記と考えるとわかりやすい。#ミフウズラの種小名 suscitator とおそらく同じような意味。
あまり頻繁には鳴かないミサゴの声よりはカモメ類などの方が近いかも。
ミサゴと水鳥の混同は古くからずっとあったのかも知れない。あるいはどこかで中国古典 (猛禽を 100 集めても1羽の鶚に満たない) の知識から猛禽であることと気づいて入れ替わってしまった可能性もあるかも。
[ロシア語の「猛禽類」]
ロシア語では捕食性動物 (哺乳類でも鳥類でも) を指して khishchnik 難しそうな綴りなのだが発音は日本語のヒーシニクで問題なく通じる。もちろん変化形があり複数は -i ヒーシニキ 複数で〜の、〜をは -ov ヒーシニカフ。
特に鳥類の猛禽類を意味する時には pernatyj khishchnik ピェルナーティ ヒーシニク (羽の生えた〜) がよく聞かれる表現。ドキュメンタリーなどでは獲物が出てくることが多いが「獲物を」は dobychu ダブィチュ。これらだけでも聞き取れればロシア語ビデオも案外わかった気になれる。
[feather taxis・頭かき]
川口 (2016) Birder 30(4): 50-51 でミサゴの解剖をもとに扱われているテーマなのでここで紹介しておく。
"feather taxis" と呼ばれる概念で、ミサゴでは次列風切の付着部の S5 に相当するものがない (このタイプを diastataxy と呼び、あるものを eutaxy と呼ぶ)。
と言っても図を見ないとわからないので、川口氏の記事を見ていただくか Bostwick and Brady (2002)
Phylogenetic Analysis of Wing Feather Taxis in Birds: Macroevolutionary Patterns of Genetic Drift?
の図を見ていただくとよいだろう (ここでもミサゴが取り上げられている)。古くから知られていた概念だが、Sibley and Ahlquist (1990) の DNA-DNA 分子交雑法の系統が発表されたのでそれを用いて系統解析をした論文。
何かに対する適応の産物か偶然なのかよくわからないのだが、この論文ではこの系統樹を用いれば多くの回数の出現・消失が起きていて適応の産物よりは遺伝子浮動による偶然ではないかとしている。
川口 (2016) でも「遺伝子の傷のようなもの」のような表現を用いている。
Sibley and Ahlquist (1990) は diastataxy の分類学的価値は限られていると述べているが、この著者は多くの系統でよく保存されているのでこの表現は皮肉に聞こえるとしている。
今ならばもっと多くの形質や生態パラメータとの相関をとったり、新しい分子系統分類を用いて解析するだろう。現代の系統分類に基づいて並べ直してみるとどうだろうか。
Telluraves に限ってみてみると、フクロウ目、タカ目ともに diastataxy、ネズミドリ目、キヌバネドリ、サイチョウ目、キツツキ目は eutaxy だがブッポウソウ目は両方あり。ハヤブサ目、オウム目は原則 diastataxy、スズメ目は eutaxy と系統はかなりよく反映されているように見える。
ネズミドリ目系統で eutaxy が生じ大部分受け継がれたがブッポウソウ目で多少違うものが現れた (何かへの適応であればブッポウソウ目では選択圧が弱いのかも知れない)。
他の系統は diastataxy だが最後に現れたスズメ目のみ eutaxy となった、となってそれほど多くの出現・消失は起きていないように見える (対趾足の出現・消失と同じようなもの)。例えば何らかの航空力学的要請であれば我々が何への適応かよく理解できていないだけかも。どなたか全部チェックしてみられませんか?
川口 (2025) Birder 39(2): 52-53 がアオサギをテーマに再度取り上げられていて大型の鳥はみなそうであると書かれていたので再度見直してみたが、Bostwick and Brady (2002) を見ると必ずしもそうではないことがわかる。
この論文を見ると小型化、飛翔性を失う (クイナ類、カイツブリ類、ウ類で顕著) ことは eutaxy への遷移を起こしやすい。アメリカヤマシギは羽音を出す適応があり、これもこのグループの中では eutaxy となっている。他にアマツバメ類などが取り上げられている。単なる偶然の産物よりは逆方向にも進化し得るが少なくともいくつかの系統では機能的適応と見るのがよさそうに見える。
テーマとなっていたミサゴやアオサギはいずれも大型で翼も長いので diastataxy の傾向が現れてよいことになる (発生学的要請または飛翔機能のための適応?)。
川口氏 (2016) の「遺伝子の傷のようなもの」の表現の意味はどうも上記と少し違うらしく、適応によるものでなければ系統を調べるよい目印になる考えらしい。つまり恐竜化石に diastataxy の証拠が見つかれば鳥類の直系の先祖がみつかる可能性が高いとのこと。この記事では始祖鳥が diastataxy か否かは見解が分かれているとのこと。
だいぶ古くからある話のようで Condon (1957) Neoteny and the Evolution of the Ratites が走鳥類の発生途中で diastataxy の痕跡器官が現れるのは祖先が地上性ではなかったことの証拠であるなどの使われ方がなされている。
なるほど同じ議論が成り立つならば始祖鳥は飛べたのか feather taxis を見ればよいことになる。Bostwick and Brady (2002) にも始祖鳥への言及があり、de Beer (1954) は始祖鳥は eutaxic としたが Steiner (1956) は diastataxic とした。川口 (2016) の記事でも別文献も紹介して同じことが述べられている。
これら議論を行うならば feather taxis が適応の産物であれば困るわけだ。Bostwick and Brady (2002) は (当時の系統情報をもとにした) 系統解析からこの疑問に答えようとしたもの。
#カタグロトビ備考の [風切羽や雨覆の構造と機能] の Hieronymus (2016) Flight feather attachment in rock pigeons (Columba livia): covert feathers and smooth muscle coordinate a morphing wing
の研究を見ても筋肉への付着部位の違いなど機能がグルーピングされていて (例えば S1-S4 と S の後半は異なる) 別個のユニットだと思えば航空力学的要請による適応の産物であってもよいのでは? と感じる。解剖・発生学に詳しい方の検討をいただきたい。
この程度の背景知識を持っておくと単なる豆知識以上に川口氏が何を使えたいのか理解しやすいだろう。
頭かき (直接/間接) の話にも似ているような印象を受けて調べてみたところ、頭かきは種内ではよく保存され、オウム類の系統も反映しているとの研究はあった。
古いものだが ten Cate (1984) Functional Aspecies of Head-scrsatching Methods and Other Preening Movements in Birds
で直接/間接のいずれが祖先形か、分類学的価値はあるか、などの過去の議論も紹介されている。この著者は従来提案された系統 (当時の系統分類) との関係が確認できないので、系統を反映したものよりも機能的、形態的、行動学的要因で決まっているのではないかと考えている。
こちらも成鳥になると間接頭かきになる種類で幼鳥では直接頭かきのものは「機能していない進化の遺物」(以下 Lorenz 参照) 的な捉え方をしている。
鳥の頭かきがなぜそれほど問題になるかに関してあまり説明を聞かないのだが、「本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」(マーク・S・ブランバーグ著; 塩原通緒訳 早川書房 2006 原著 Mark Samuel Blumberg "Basic instinct: the genesis of behavior") という面白い本がある。
Lorenz (1958) が - 大部分の鳥はほぼすべての哺乳類や爬虫類と同様にまったく同じ仕草で頭をかく (間接頭かき)。このようなぎこちない動作が生得的でないならば何と表現したらよいのか見当がつかない。哺乳類と枝分かれする以前の共通の祖先である四足動物の足の位置関係を再現しているに違いない - と述べたことに始まる (訳書 pp. 124-126)。
Blumberg (2017) Development evolving: The origins and meanings of instinct
でこの部分に対応する記述と Lorenz (1958) のイヌと鳥の頭かきの比較絵が見られる。
Lorenz は遺伝子による遺産の一部と考えた。当時は行動は学習か本能 (遺伝) かが問われていて学習が偏重されたため、Lorenz は生得的動作に重点を置くようになったとのこと (pp. 125-126; Lorenz の有名な数々の実験はそのような意図で行われ、生得的なものに重点を置いて発表されたものと解釈するとわかりやすい)。
今から見ると "大部分の鳥は" がおかしいわけだが、当時は間接頭かきの方が古くからあったと考えられていた。現代の系統解析では逆になる。我々はスズメ目が最後の分類に馴染んでいるが、系統解析のやり方次第で必ずしもそうならない。
モリムシクイ (と訳されているが北米のアメリカムシクイ科 Parulidae) は幼鳥では直接頭かきだが成鳥になると間接頭かきになることが知られているとのこと。
Burtt and Hailman (1978) Head-Scratching among North-American Wood-Warblers (Parulidae)
で生得的ではなく姿勢やバランス、体の重心と関係するという Lorenz とはまったく異なる解釈を提示した。同じ系統でも地上性のものは直接頭かきが多く、樹上性のものは間接頭かきが多いとのこと。
Hailman (1969) How an Instinct is Learned
は本能はいかに学習されるか、という刺激的なタイトルの記事を書いている。カモメ類のひなが親の嘴の赤い点をつつく行為も段階的学習によるという。動く点をつつく行動はごく一般的なもので、身近にある動く点が親の嘴にあるという次第。
このように鳥の頭かきは単なる面白い行動以上に動物の行動は本能か学習かの深淵なテーマに結びついていたわけである。今でも研究されて論文が出ている理由である。日本語でネットを検索してもそんな話には行き当たらなかったのだが...。
ちなみにこのあたりの話は分野的には心理学になり、鳥類学の文献にあまり登場しない研究者が多いのは学問分野の違いが現れている可能性がある。
またこの本で批判的なニュアンスで述べられている、行動が遺伝で決まる "生得論" は進化心理学 (社会生物学) の (ある程度の) 前提になっているので、進化心理学 (社会生物学) を基本に考える現代の鳥類学には相性がよくないかも知れない。
進化心理学 (社会生物学) 的に生物行動を説明する時に、行動が遺伝で決まるかどこまでわかっているか議論し始めると収拾がつかなくなるので、あえて単純化して説明を省いているかも知れない (こんなに面白い話なのに)。
また Lorenz などの古典的実験や考え方があまりに古くから図鑑や教科書などで教えられ、我々が刷り込まれているため他の可能性にあまり注意を払わないためかも知れない。渡り鳥の定位の話もそうだったが、古典的実験の話を聞く時には少々疑ってみるぐらいの方がよいのだろう。
頭かきに関連して、普段は間接頭かきをする種類でも飛翔中はそうも行かないので直接頭かきをすることが知られている。上記文献にも記述がある。
しかし撮影事例は少ないという。Gutierrez-Ibanez et al. (2023) (#ハチクマの備考参照)
の著者に両足を使って頭かきをする行動を知っているか聞いたところ知らないとのことであった。
皆さんはご覧になられたことはあるだろうか? 立ったままやるのはもちろん無理なので飛んでいる時の話で、おそらくソアリングする鳥でしか見られないのではと思う。
鳥にも両足を自由に使いたい衝動はあるようで (?)「どうだ、大空を舞うこの爽快感は!」と言わんばかりにハチクマが両足を使ってここぞとばかりに思い切り頭かきをしているのを見たことがある。やっぱりやりたいのだろうな。他の種でもそれらしい写真を見たことがあるが、1枚の静止写真なので両足頭かきかどうかは確実ではない。皆さんにも機会は十分あると思われるので注意して見ていただきたい。
書いているうちに思い出したのだが、#ハチクマの備考 [(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] で翻訳を紹介した [ハチクマのお客さんになって] に登場するヨーロッパハチクマのドルセトは足でなく尻で座って食事をするという (写真あり)。
当時は変わったことをする程度にしか思っていなかったのだが、これはもしかすると両足を利用したいために座って食べているのだろうか。飼育者も意識していないかも知れない。もしそうならオウムより上を行ってないか?! 川上和人様、足をこのように使えば手がなくてもピアノが弾けるかも知れませんよ [cf. 「鳥類学者 無謀にも恐竜を語る」p. 85 技術評論社 2013。文庫版 新潮文庫 2018]。
この姿勢はあまりに無防備なので飼育下で安全を確信しているゆえできる行動だろうが、人知れないところでハチクマが両足を投げ出してこっそりくつろいでいたりするのかも知れない。想像するだけで苦笑してしまいそうだ。ハチクマはやはり面白いのである。
Oriental Honey-buzzard (Sanjiv Khanna 2024.4.20) の写真をみるとヨウムの後ろ姿にもどことなく似て見えて、今にもしゃべってきそうに思えてしまう (気のせいだろうが)。
さらに時間が経てばハチクマからオウムが進化してくる、なんてことはさすがにないかな? ハヤブサ系統からオウム類が進化したならば、タカ類からオウム類みたいな鳥 (タカオウム??) が進化しても別に不思議でないかも知れない。甘い物も好きだし、現在でも実は中間的だったりして。ハチクマはオウムダカだと思って見る (??)。
ある程度大型のしっかりした捕食者で、外敵をそれほど気にする必要がないならこそ両足頭かきする余裕が生じるのだろうし、足を使って器用なことをする余裕も生まれてくるのかも。オウム類がハヤブサ系統から進化したのも祖先がしっかりした捕食者であったことが実は必然だったのかも知れないとか思ってみたりする。
ネズミドリの系統はそれほどの捕食者ではなかったのでそこまで知的なグループが進化しなかった?
このあたりは空想鳥類学ということで...
[ミサゴと他のタカの交配は可能か?]
みさご腹 (鶚腹) という言葉があり、国語辞典などではタカとかけ合わせてミサゴの腹に生まれた子とされる。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) pp. 131-132 に 1254 年にすでに秘蔵のタカとして記述があり、メス親であるミサゴの性質を受け継いで鳥を追わないとのこと。
細川氏は異種交配が試みられていたと考えられているが本当に交配可能なのだろうか。
前述の染色体構成の大きな違いを考えると不可能のように思えるが...。分岐年代約 5000 万年前で科レベルで異なる種同士で交配可能であれば生物学的にも大発見のような気がする。
そもそもミサゴや他のタカの飼育下繁殖技術があったのかどうかも疑問な点だが、単にミサゴのように白っぽい色変わりのタカを自慢する言葉だったのではないだろうか?
探してみると歴史伝承については二本松 (2008) 諏訪流の鷹術伝承 -みさご腹の鷹説話をめぐって- (論究日本文学) という論文があった。
系統の離れた鳥類種の間での交配についての論文があった: Alfieri et al. (2023) Genomic investigation refutes record of most diverged avian hybrid
これまで記録とされたホロホロチョウとチャバネシャクケイ Penelope superciliaris Rusty-margined Guan (分岐年代 6500 万年前と推定) の雑種とされ 1957 年に報告された標本をゲノム解析した結果この同定は誤りで、ホロホロチョウとセキショクヤケイ/ニワトリの雑種と考えられるとのこと。これでも分岐年代 4700 万年前程度でこれまで知られている最も系統の遠い交配例の一つであることは間違いないとのこと。
他に知られている例では 3700 万年前分岐の ショウジョウコウカンチョウ Cardinalis cardinalis Northern Cardinal と コウカンチョウ Paroaria coronata Red-crested Cardinal の例があるとのこと。
哺乳類では分岐年代 2000 万年前、魚では 1.5 億年前の例があるとのこと。全脊椎動物内ではないが鳥類での 4700 万年前は脊椎動物でも最も極端な例と言ってもよいとのこと。
ミサゴとオオタカであれば Catanach et al. (2024) の数字では 5000 万年前を超えるぐらいなので、もし「みさご腹」が本当にあるならば記録的となるはず。http://www.timetree.org/ で見積もってみると 5000 万年前 (3770-5900 万年) となる。
キジ目の間では染色体パターンは保存されているので離れた系統でも雑種形成が起きやすいかも知れない。ミサゴとオオタカの間は染色体再編成のパターンが異なるので単なる分岐年代以上に雑種形成を妨げる要因があるかも知れない。
思いつくところでは #カンムリツクシガモ のゲノムはまだ調べられていないようだが、過去の目撃証拠に基づかず雑種でないことを証明するには現代ではこのような直接検証が欠かせないかも知れない。
[近代的な陸鳥の進化]
日本鳥類目録改訂第7版以降の分類では、このあたり (タカが登場するあたり) 以降の鳥の性質がそれより前の部分とはかなり違うことにお気づきの方もあるかも知れない。
この後では本格的な水鳥は現れず (水辺に住むグループ程度はあるが)、ここからが本格的な陸鳥の始まりである。かつてはタカ類とハヤブサ類は一緒にされ、しかもコウノトリ類と近縁とされた古い研究の影響もあってタカ類 (とハヤブサ類) が変な場所に置かれていたため、図鑑の配列を見てもこのあたりが明確に見えなかった (もっとも、猛禽類の中にはヘビクイワシのような変わった種類もいるので、ツルやコウノトリ類と近縁だったと考えられたのは無理もなかったかも知れない)。
シブリー・アールキスト Sibley and Ahlquist (1990) の DNA-DNA 分子交雑法による鳥類分類の発表があり、従来分類とは違っていていろいろな点で話題となったがこれでもタカ類はコウノトリ目に内包され、根本的な解決には至っていなかった。
Sibley et al. (1988) A Classification of the Living Birds of the World Based on DNA-DNA Hybridization Studies
がオープンアクセスになっているので紹介しておく。
混乱をもたらしただけとの批判もないわけではなかったが、他の分類群については現在に近い結果も多くある。タカ類の位置を見定めるのはそれだけ難しかったということだろう。
シブリー・アールキストの時代には DNA 配列から系統を推定することはできなかったが、その後の分子遺伝学の進歩により現在ではより確かな系統関係がわかるようになっている (その結果日本鳥類目録改訂第7版の分類大改訂につながった)。
現代的な研究の一例として Prum et al. (2015) (#アマツバメの備考) の系統樹を見ていただきたい。
この系統樹は今後少々入れ替わる程度の変化はあると思われるが、今後はこれまでのような大きな変化はなく、おそらく最終版にかなり近いと考えてよいだろう。
この系統樹の2ページめからが近代的な陸鳥のグループであり、日本産の鳥ではミサゴから始まるのでここに説明を入れた。
[追記 2025.3]
この部分を記した後に [#鳥類系統樹2024] や日本鳥類目録第8版が発表され多少事情が変化したので解説を少し追記しておく。
日本鳥類目録の第7版から第8版への移行に際して目の順序が変わった部分があり、新しい配列を覚えるのに苦労されている方も多いと思う。探鳥会リストなどで用いるならば鳥合わせの際に新しい配列を把握する必要があってやむを得ない部分もあるだろう。
しかしこの部分は第7版でかなりよくできていて、順序が変わっているところは系統の前後関係を判定することが難しい部分に限られている。第7版の目順序を使ってもあまり大きな間違いはない。
例えばカイツブリ目は第8版で後に移されたが、[鳥類系統樹2024] の結果を見ると第7版の配列の方が近かった。将来いずれまた戻されることになるだろう。つまりこれら部分の目の配列は一喜一憂するほどのことはない。
ヨタカ目やアマツバメ目も第8版で最初の方に移動されたが、このグループには音声学習を行うハチドリ類が含まれている。#タンチョウの備考 [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] で取り上げた。少なくともこの部分は第8版配列を覚えてしまわない方がよさそうと書いた。
注意深い方であれば第7版から第8版への移行で目の配列が変化しない部分があることにお気づきだろう。つまりタカ目以降は順序を変える必要がないのである。これはタカ目の前とタカ目以降の系統が大きく分かれているため、少々のことでは順序が入れ替わる心配がないのである。この境界がここで示す "近代的な陸鳥" あるいは後述の Telluraves とそれ以前の系統に対応している。
また、第7版から第8版への移行でキジ目・カモ目の順序が入れ替わってしまったが、{キジ目 + カモ目} とそれ以降の部分の順序には入れ替えはない。この境界が Neoaves の出現に相当する。
つまり目の順序を覚える時には {キジ目 + カモ目} / Neoaves (のうち Telluraves でないもの) / Telluraves に3分割すればよい。日本産以外も考えるとさらにダチョウなどの古口蓋類 (古顎類) が {キジ目 + カモ目} の前に並ぶことになる。これらの境界は今後おそらく変わることはないので覚えてしまって大丈夫である。目の順序を覚える必要性はそれほど高くないがどの区分に入るかを把握しておくとよい。
さて、これらの目録に出てくる順序は系統樹を1次元配列にしたもので (linear sequence 線形配列と呼ぶとよいだろうか)、複雑な系統樹を1次元の順序に置き換えるのにそもそも無理があることは理解いただけるだろう。しかし系統樹のままではリストを作る時など扱いにくいので1次元配列に割り当てる必要がある。
ここで系統樹で古い分岐から順に割り振ってゆくわけだが、分岐に含まれる系統数が多い (複雑な系統樹となっている) 場合は往々にして直感に反する順序になることもある。"Neoaves (のうち Telluraves でないもの)" がまさしく該当していて、分岐順に割り振っていった結果類縁性の低いものが隣同士となる場合が生じる。例えば県内の住所一覧を行政区域ごとに分割して1次元配列にすると地理的に離れた地区が隣同士となってしまうことがあるのと同様 (名簿を郵便番号や電話番号順に並べることを想定してもよい)。
しばしば "系統の近いものが並ぶように配置" されていると表現されることがあるが、必ずしもそうなっていない場合が生じる。例えば第7版ではチドリ目とタカ目が並んでいたが、第8版ではペリカン目とタカ目が並ぶ。これらは系統が近いのかと自然な疑問を持たれる通り、系統が近いわけではまったくない。
系統樹の形次第で "Neoaves (のうち Telluraves でないもの)" のグループの最後がたまたまチドリ目になったかペリカン目になったかの違いである。もとを正せばより高次の系統で {キジ目 + カモ目} / Neoaves (のうち Telluraves でないもの) / Telluraves に分けてまずこの順序に並べる必要があるため生じた現象である。同様の現象はいろいろな階層で生じているので、目レベルに限らず順序を覚える際は "何と何がグループを作るか" に注意しながら把握されるとよい。
2つに分かれるだけの枝であればどちらが先になるか明確な規則があるわけではない。キジ目とカモ目の入れ替えはどちらが先になってもよく、これも基づいた分類体系次第となる。一番最初の種類が一番原始的かと問われることがよくあるが (ちなみに昔は図鑑によってはアビから始まっていた)、{キジ目 + カモ目} が最初に分岐した系統であることは問題ないものの、キジ目とカモ目のどちらが早いかはあまり意味がない。
3目あればどの2つが系統を作るなど順序の議論に意味があるが、2目ではどちらが先でも事実上問題ないのである。質問には {キジ目 + カモ目} は古く分岐した系統であることがわかっていますと答えておけばよいのだろう。
その次は {カイツブリ目 + フラミンゴ目} であることはほぼ固まってきている。日本産では {キジ目 + カモ目} (内部順序は入れ替えてよい) の次にカイツブリ目を置くのがおそらく現状妥当だろう。
その次に Columbaves {日本産では ハト目 + サケイ目 + ノガン目 + カッコウ目} (カイツブリ目とフラミンゴ目が近縁であることは化石証拠も見つかったが、ハト目、ノガン目、カッコウ目の何が似ているのか誰もが戸惑いを感じるところ。この部分は第8版で現在の理解に近いものになった) になることもかなり固まってきている。このように見ると第8版の順序そのままは無理に覚えない方がよい感じもする。
それでは第7版から第8版で変化がなかったタカ目以降の順序は固まっているのか、覚えてしまって大丈夫か、と言えば議論の真っ最中で全然固まっていない。
日本産ではフクロウ目以降キツツキ目までが並ぶらしいことはほぼ問題なしで、この内部の順序はおそらく変わらないが後述のネズミドリ目の扱い次第。
日本産では {ハヤブサ目 + スズメ目} がグループを作ることも間違いない。2目ではどちらが先かわからないのでは、と思われるだろうが日本産以外にオウム目があって順序関係に意味があるので、この3目だけを対象とすればスズメ目を最後にしてよい点は問題ない。
さらにまだ系統関係が確定していないノガンモドキ目がハヤブサ目に近いと考えられている。
これらを全部考慮するとハヤブサ目やスズメ目を含むグループ (Australaves) 内部の順序が変わる可能性はゼロではない程度の段階だろうか。
むしろ並列で並ぶ可能性のあるタカ目とフクロウ目のどちらが先にあるべきか議論も実際に行われている。これまでの考えではフクロウ目からキツツキ目までが並ぶらしいので、タカ目とフクロウ目の順序を入れ替えると系統樹の前の方が重くなってしまうのであまり好まれていない次第。現在まさに検討途中の段階で、固まったかのように見えるタカ目以降の順序は将来変わるかも知れない (大きな変更を伴うことになるので変更しない慎重意見が現状は優勢)。
タカ目とフクロウ目の順序を入れ替えると一度は分かれたはずのタカ科とハヤブサ科が (日本産では) 1
次元配列で再び並ぶ珍現象も生じ得る。目レベルでは別であるが先述のように1次元配列の定義による。
また現生鳥類では小さなグループだがネズミドリ目の問題があって、かつては世界的に分布していた証拠があるが現在はアフリカのみに分布。フクロウ目に近い位置に置かれることが多いが見ての通りあまり似ていない。この目をオオブッポウソウ目から始まるグループの冒頭とすると {タカ目 + フクロウ目} と {ネズミドリ目からキツツキ目} が別系統となってフクロウ目からキツツキ目を一連の系統とも言えなくなる。
2系統の順序を入れ替えて {ネズミドリ目からキツツキ目} の後に {タカ目 + フクロウ目} が並ぶ配列も可能で、この場合は日本産ではブッポウソウ目、キツツキ目が猛禽類より先に並ぶことになる。
ノガンモドキ目を考慮に入れるとタカ目とどちらが早いか未解決なので一層ややこしくなる。伝統的な系統樹では優先度が同じならば "数の多いグループを最後に置く" 方が形がよいのでスズメ目を最後に残したい (第7版でもチドリ目の種類が多いので中間グループの最後となるのが好まれた経緯も想像できる) が、分岐順序の評価が変わればもしかするとスズメ目が最後でなくなる可能性もこれまたゼロとは言えない。
もしノガンモドキ目の方がタカ目より早く分岐したことが受け入れられるようになれば、同じ系統のハヤブサ目以降スズメ目までがごっそり移動することも原理的にあり得るのである。これらは科学的検証次第で現状はまだ未確定だが、いずれはより正しい系統順に近づいてゆく過程と言えるだろう。
[2025.6 さらに追記] AviList (2025.6) でこれらの諸問題がかなり本格的に取り扱われ、(大きな系統のみを示す) フクロウ目 - タカ目 - {ネズミドリ目からキツツキ目} - {ハヤブサ目 + オウム目 + スズメ目} の順序が採用された。"フクロウ目からキツツキ目を一連の系統とも言えなくなる" 方が採用された。
これまでの IOC リスト (15.1 まで) に比べると大きな進歩である。
ここでは {ネズミドリ目からキツツキ目} を並べる扱いを紹介しているが、上述のようにネズミドリ目はこの系統の中でも特殊なので、ネズミドリ目 と {オオブッポウソウ目からキツツキ目} を分けて考えた方が妥当かも知れない。ネズミドリ目はかなり古い化石も知られているので、タカ目と順序関係が逆転する可能性も考えられる。
タカ目の祖先がネズミドリのような鳥であったのかは何とも言えないが、おそらく今後の本命はコンドル目とノガンモドキ目のどちらが早かったの問題になるのではないだろうか。もしノガンモドキ目の方が早かったならば、スズメ目まで含めてごっそり前に移動し、タカ目が最後になる可能性が依然残っている。
AviList 配列は系統順序関係に甲乙つけがたい場合は種類の多い方を後にする暗黙の合意に従っているように見える (例えばフラミンゴ目とカイツブリ目の順序関係は定義しにくいが、数の少ないフラミンゴ目を後にすると形が悪くなるなど)。
スズメ目は種類数が多いので誰も最後に置きたいわけだが小型種が多い効果もあるだろう。世界分布や多様性を見てもタカ目とスズメ目は甲乙つけがたいし、種類数でなく主な系統の出現年代に重みを付けると逆転するかも知れない。
何と言ってもタカ目の確実な古い化石がほとんどないのである。出発点では他系統との共通部分があったとしても、タカ目は最後に生まれた系統由来の目の可能性をもやもやと感じてしまうわけである。
[染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] の項目にも関連があって、6300-5400-4800 万年前の数字はタカ目誕生ごろの様子を表しているように思える。
なおここで扱われていた Canesin et al. (2024) 時代の標準的な分類ではコンドル目とタカ目は分離されていなかったので、[染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] の項目で述べられている "タカ科" はここで扱っている "タカ目" とほぼ同じものを指すと読んでいただいてよい。
例えばこの論文でも推定されているようにコンドル目との共通祖先は 6300 万年前ぐらい、ミサゴ科とタカ科の分岐が 5400-4800 万年前 (ミサゴ科以外の系統も誕生したがすべて消滅したと考える) と考えるとなんとなく整合性があるように思える。もっともこの年代推定もいろいろ仮定が入っているので額面通り扱えないかも知れない。
6500 万年前以降に transposable elements の活動のバーストがあったと推定されていることも年代推定の信頼性をある程度裏付けているように思える。
現生系統ではコンドル目とタカ目が最も近い系統となるが、分子系統的にも染色体構成も非常に遠いのでこの2目が単系統をなしていたかどうか怪しいかも知れない (例えばフクロウ系統とタカ系統をまとめるようなもの)。
類縁性はあるがコンドル目とは少し違った別系統からタカ目が生まれた可能性も考えられるかも知れない。4800 万年前にはタカ目の祖先が確立されていたと下限を見積もると、現代の分子系統樹とも整合性がよく見える。(下限値で) 4800 万年前以前には真のタカ目はまだ誕生していなかった、などなど。
フクロウ類の方が古い系統から誕生していて最初は昼の猛禽の地位を占めていたが、タカ目の出現によって夜の猛禽とならざるを得なかった ([フクロウ類はかつてタカの地位を占めていた?] の項目参照) で想定されている順序関係も納得できるかも。
後発でもタカはやはり強かった? もっとも直接勝負で強かった意味ではなく、捕食性能や認知能力で上回っていたのだろう。
フクロウ類はタカに似た生態で始まったので目も最初から前を向く傾向があり、聴覚重視で耳が巨大化するとともに現代のフクロウ類のような形にも進化しやすかった? (半分妄想)。それではなぜフクロウ類で脳が大きくなったのか納得できる理由が欲しい感じがする。
さて、さらなる深読みになってしまうが、フクロウ類とタカ類の順序について AOS Classification Committee - North and Middle America Proposal Set 2025-A の 2025-A-8e では NACC がこの変更を否決したのに AviList (2025.6) がこの配列を採用したのは、NACC と SACC が英語一般名をめぐって決裂した結果の現れと読めば政治問題の方と読めてしまうが、むしろ学術的な問題ではないかと想像する。
実際のところは AviList Core Team に聞いてみれば Stiller et al. (2024) に従ったまでと答えられてさしたる意味はないのかも知れないが、フクロウ類とタカ類をこの順序とすれば [フクロウ類はかつてタカの地位を占めていた?] のようにフクロウ類の方がむしろ原始的な捕食者であった考えがある程度受け入れられるようになってきているのかも知れない。
逆順にするとなぜタカ類が夜の世界にも進出せず、夜行性系統の方のフクロウ類が後になるのか説明が難しい感じもする。
[オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] の項目にあるように、レトロポゾン (またはレトロトランスポゾン) の決定的研究があるのでは (Suh et al. 2011) と言われるかも知れないがこれは1指標と考えた方がよさそうで Gatesy and Springer (2022) では複数の指標を用いて解析を行っている。Cavitaves の系統的連続性を示すなど適用が適切な場合も必ずしもそうでない場合もある。
ここからさらなる推測だがコンドル目を分離した (これは AviList を作ったチームに含まれる SACC が支持していた) のも、単なる分岐年代以上にコンドル目とタカ目の類縁関係は実は遠かった間接的証拠が増えてきているのではないだろうか。さすがに昔主張されたコウノトリ類に近いわけではないが Jollie (1976, 1977) がすでに指摘していたことであった。
旧ヨタカ目が複数の目に分割されたのは単系統性の要請と分岐年代由来であったが、コンドル目の場合は自明な単系統性の要請はないので、別の面から類縁性の遠さが見えてきているのではないかと想像する。つまりコンドル目とタカ目はそれぞれ別々の系統由来なのでは、との疑いが生まれてきているのでは。
それぞれを科のレベルにとどめておくと、系統分類上での目の移動では一緒に移動せざるを得ない。それぞれが別の目であれば原理的には独立に動かすことができる (歴史的経緯から別目だったフラミンゴ目とカイツブリ目のようにもはや一緒に動かさざるを得ない近縁目の関係も存在する)。つまりコンドル目の分離は将来タカ目と同系統から切り離す必要が生じた場合の前準備ではないだろうか。
コンドル目の分布の中心地が新世界で、化石種を含めてもヨーロッパ止まり。コンドル目の方がタカ目より系統が古いはずなので、この系統が Afroaves に含まれる一見矛盾した状況があるが別起源と考えれば解消される可能性がある。
コンドル目を切り離せばタカ目はずいぶん身軽になる。コンドル目と分岐年代があまり違わないヘビクイワシ科を目として独立させることも別に不自然ではない。そのように考えると次の分岐であるミサゴ科も特異な点が多すぎるので実はタカ科と起源が異なるのかも知れない。つまり「ミサゴはタカではなかった」とんでもない結論が出てくるかも知れない。
これは事実上「ハヤブサはタカではなかった」と同じようなもので、そのような結論となっても不思議でない気がする。ヘビクイワシもミサゴも足の形がタカ科とはかなり異なる。
対趾足はオオブッポウソウ目以降の連続する目 (Cavitaves) の間で非常によく保存されていて (ネズミドリ目でも動かせる semi-zygodactyl または pamprodactyl)、エボシドリ目、カッコウ目の関係でも同様なので、ミサゴも足は魚食への適応よりも祖先系統が残っていると解釈することも可能に感じる。
ひなの色にももしかすると祖先形質が保存されているのかも知れない。
もしかしたらフクロウ目と起源に共通性があって、かつてタカのような昼行性の位置を占めていたフクロウ目と起源をともにする系統のわずかな生き残りの可能性もあるのではとふと考えてしまう (フクロウ類の祖先が昼行性捕食者だった時代の名残りが何とミサゴ !? - そんなものは明確に否定されているかも知れない)。
ミサゴのあまりに特化した食性、不器用さなども古い系統の生き残りと考えると理解しやすいかも知れない。
もしヘビクイワシとミサゴを切り離すことができれば、残りは非常によくまとまった誰が見てもタカのグループとなる。ミサゴを切り離せばタカ目の分岐年代は 4500 万年前程度、ミサゴを含めると 5000 万年前程度程度となって [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] の 5400-4800 万年前程度の推定とよく一致し、また確実な古い化石がないこととも整合性がよい。
transposable elements (TEs) を用いるような一段進んだ高精度ゲノム解析が可能になり、分子系統樹だけに頼っていた時代に比べて描像が変わってきていることが AviList (2025.6) の新配列に反映されるようになってきているのかも知れない。B10K のグループ (Stiller et al. 2024 など) ももちろん注目しているはずなので、近年の進歩もふまえた未発表情報が AviList Core Team の判断に影響を与えているかも知れない。
もしヘビクイワシやミサゴの高精度ゲノム解析が行われ、TEs の歴史をたどることができれば、どの時代まで他のタカ類と共通祖先を持っていて、共通の TEs が働いていたか原理的には見積もることができるかも知れない。そのような情報があれば現在用いられている分子系統樹や分岐年代の独立検証ができることになる。すでに進められていてまだ未発表段階かも知れない。
Canesin et al. (2024) はミサゴ科とタカ科には (異なっているが) 大規模な染色体再構成があるため共通した bauplan を想定しているが、染色体再構成はハヤブサ目など他の系統でも複数生じているので、染色体再構成を経験したことのみを根拠として同系統にまとめるのは必ずしも適切でないかも知れない。どのような TEs がどのようなタイミングで働いてそれぞれの科の特性を作り出したかを調べる必要があるだろう。
#シロフクロウ備考の [フクロウ類のゲノム研究] Baalsrud et al. (2024) ではシロフクロウの高精度の染色体レベルのゲノム解析ではオウギワシとパターンが異なり、カリフォルニアコンドルとは染色体レベルで共通性がかなり似ているが再編成もあるなどの結果も得られている。フクロウ類の精度の高いゲノムが得られたのはこれが最初とのことで、目レベルの系統関係はこれから明らかになる部分も大きそう。
2010 年代の方法論はすでに古くなっているかも知れない。
AviList Core Team に入ることができなかったチームは本当にコアな最新情報にアクセスできず、判断に限界があるかも知れない。
現在は目に一緒に含まれている上記のような古い系統を切り離したタカ目が、もし他の系統とは別の起源を持っていたならば、タカ目が配列の最後になる可能性もあるかも知れない。これはあまりにも大きな変化で、すぐに受け入れられないだろうから、まずはタカ目とフクロウ目の順序を入れ替え、コンドル目を独立されることが第一歩となっているのかも知れない。
もしタカ目が最後になるならば David Lack の述べるところの "うがったいい方" [週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 66 VII-VIII に「スズメ目の鳥の < 高等 > であることの意味」(浦本)] によれば専制政治の時代に逆戻りなのだろうか (笑)。昨今の世界情勢を見ると現実の方が先行していて笑い事ではないのかも知れない。
ただしタカ目が専制政治を象徴する鳥であるとはもちろん微塵たりとも考えていない。
またこれもよくある誤解だがこの配列の順序で出現したことを表すわけではない。あくまで系統分岐の順序であって、さらに分かれた先のそれぞれの系統の年代順序まで正しく反映されているわけではない。系統の出現からある地域に分散するまでの時間の考察も必要で、例えば日本のように系統の発祥の地から遠い地域では後に生じた系統が先に到着することもある。これは個々の例で考察する。
[追記終わり]
[2025.7 追記]
(AviList 配列に関係するのでこちらに置いておくが、グループ名などの表記など内容的には後の部分を見ていただいてから読む方がよいだろう)
Gao and Gruenewald (2025) A Maximum-Likelihood Method to Construct Phylogenetic Trees Using Low-Homoplasy Markers: New Insights into Neoaves Phylogeny (preprint)
Laximum Likelihood for Retrotransposed Element (MLRE) を用いた解析では (仮定によって多少異なる結果になるもののの) ネズミドリ類は Afroaves の他の系統から分離される強い証拠がある。つまりフクロウ類や Cavitaves の系統に属さず、この中では最も早く分岐した系統。
フクロウ類を Cavitaves か Accipitrimorphae のいずれに近いと見るかはまだ悩ましいが、冒頭紹介の AviList (2025.6) で採用された Telluraves 冒頭4目の範囲の順序では、ネズミドリ目を最初にして、
ネズミドリ目 Coliiformes
フクロウ目 Strigiformes
コンドル目 Cathartiformes
タカ目 Accipitriformes
となるのがどうも妥当らしい (フクロウ目以下の位置はまだ問題がある)。
Australaves (ハヤブサ、オウム、スズメ目を含む) と Afroaves (タカ、フクロウ目を含む) のいずれがより古い系統かは Australaves の方が古い結果を与えているものが多い。現状まだ不定性が大きく過去の系統樹からあまりに大きく変えるのは避けられているようだが、ノガンモドキ目 Cariamiformes 以降がごっそり Telluraves 冒頭のネズミドリ目より前に移動する可能性がある。
Fig. 9 が一つの例となっているが、これまでの常識とかなり違うかも知れない。少なくともネズミドリ目を動かすことは必須で、Australaves を系統樹の前の方に動かすべきかおそらく悩ましいことになるのだろう (スズメ目が最後でない図鑑になるかも知れない)。可能性を片隅にとどめておいてよいかも。
まだ解かれていない問題とされているが、フクロウ目 + タカ目 が系統を作る可能性はやや支持される傾向があり、Cavitaves とフクロウ目の類縁関係を考えると Cavitaves の後に {フクロウ目 + タカ目} が並ぶ可能性がある [ネズミドリ目を動かすとこれまでの縛りがやや解消される。別に紹介の Ksepka et al. (2017) などの系統議論にも影響を与える。また一見 "小鳥" のような鳥が多系統から生まれ得ることもわかる]。
サンプルに用いる種が多い・少ないによっても系統樹形も変わるので、ここで用いられたサンプルから記述された方法で導かれたあくまで一つの結果で、これらの系統樹の細かい部分まで信頼する必要はないだろう。この研究はネズミドリ目の位置を相対的にほぼ確定したものと言えるだろう。
またパラメータ次第でペリカン目内でペリカンとサギの距離がゼロになる系統樹も生じ、レトロトランスポゾンの挿入頻度を一定 (論文では constant c) と仮定してモデル計算を行うことはよくないことがわかる。この論文の系統樹を見る際は constant c は比較のために示されたもので、variable c が著者推奨のものと捉えてよいだろう。
ただし全体が明らかにされるほど単純ではなくて、ツル目はパラメータ次第で違う位置に入るなどまだ系統関係の判断が難しい。
また一見 "小鳥" のようなネズミドリ目の方が Australaves (ハヤブサ、オウム、スズメ目を含む) よりも後の系統であれば、germline-restricted chromosomes (GRCs) (#ツリスガラ備考の [スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン] 参照) の役割として考えられる種分化機構を鳥類で最初に獲得したスズメ目が多様なニッチを占めることができたため、他系統から進化することも可能であった "小鳥" に類似した系統があまり適応放散できなかったのかも知れない。
ネズミドリ目は系統的順序にかからわずスズメ目の進展以前に世界分布できたため少数が生き残っているだろうかとも想像が膨らむ。
しかしこの preprint は Public Domain になっていて著者を示すことなく再利用しても構わないことになっている。そんことはありなのか? と思ってしまうが一度 Public Domain で発表していまうと撤回できないはず。単なるミスの可能性もあるが、結果が間違っているのではないかとむしろ疑ってしまう要因にもなる。2名とも実在の研究者で Gruenewald は現役教授なので偽情報を意図したものではないだろうと思うが。
あるいは論文投稿の意思はなくて結果を紹介だけの可能性もあり、詳しい検討はこの解析方法が学術論文 (この論文が出版されない場合でも別著者による解析など) として出版されてからの方がよいかも知れない。この部分で述べた解説も少し気をつけて読んでいただいた方がよいかも知れない。
[追記終わり]
この近代的な陸鳥のグループを指して Telluraves という用語がある (対応する日本語名があるのか知らないが、中国語では陸鳥類と訳している)。英語では core landbirds と呼ぶのが一般的。これまでの系統でもハトやキジ類のような陸鳥のグループはあったが、現在の陸鳥の中では非主流と言えるだろう。
観察をしていてもこれ以降の陸鳥は一段進んだグループの印象を受けるでのはないだろうか。そのような意味も込めて higher landbirds という呼び名を使う人もある。
例えば Kuhl et al. (2021) An Unbiased Molecular Approach Using 3'-UTRs Resolves the Avian Family-Level Tree of Life の系統分類も参照。この分類に従えば、
1. Paleaognathae (古顎類) でダチョウなどの走鳥類。日本には該当種なし。
2. Galloanserae カモ類、キジ類
3. Mirandornithes (< miranda 驚くべき ornis 鳥 Gk) Sangster (2005) が提唱した名前。日本語名はよくわからないが、中国語では奇跡鳥類と訳している。カイツブリ類とフラミンゴ類。
4. Basal Landbirds ツル類、チドリ類、ヨタカ類、ノガン類、カッコウ類、ハト類など。これらが古いタイプの陸鳥のグループになる。
5. Aquatic and Semiaquatic Birds アビ類、ペンギン類、ミズナギドリ類、コウノトリ類、カツオドリ類、ペリカン類など。水鳥と水辺の鳥。
6. Higher Landbirds タカ類、フクロウ類、ブッポウソウ類、キツツキ類など。高等な陸鳥と呼んでよいだろう。
7. Australaves (日本語名はよくわからないが、中国語では南鳥類 *1) ハヤブサ類、オウム類、スズメ目など。
6. と 7. の細かい包含関係には後に示すようにまだ議論がある。6. の段階で鳥類に一段の進化 (例えば神経系など) があり、より高度なグループを生み出したと考えられる (そしてさらに 7. の系統でさらに一段の進化があったとみなされている)。1-5 までのグループが K-Pg 大絶滅を生き延び、6. 以降がその後現れたと考えられている。
「足を器用に使う鳥」の研究 (#ハチクマの備考参照) の論文では 6. の段階で足の利用方法が格段に向上している。
足を器用に使う鳥は圧倒的に猛禽類および類縁の種類 (オウム類) が多く、猛禽類として暮らすためには足の利用が不可欠であったのか、あるいは別目的で足の利用が進化したことが猛禽類の出現に結びついたのか面白いところである。
鳥の足はヒトの手のようなものでもあり、足を器用に使うことで脳の発達を促したことも考えられるかも知れない。4. の古いタイプの陸鳥の一部も木にとまるわけだが、これらの中に足を器用に使う鳥が発達しなかったのも興味深い。
ここで Prum et al. (2015) に戻ってみると、最も最後に現れた陸鳥の系統は猛禽型の鳥に始まった。タカ類とフクロウ類、そして残りの (高等な) 陸鳥。猛禽性はそれ以降の陸鳥の系統 (ハヤブサ類、オウム類、スズメ目) にも引き継がれていると書かれている。
猛禽性は例えばカワセミ類でよくわかる、スズメ目でも多くの種類が昆虫を捕まえる、モズ類では特に目立っているなど、猛禽の特徴はスズメ目に至るまで引き継がれていて、時々猛禽らしいグループが顔を出すと考えると納得できるように思える。
この考え方は研究者の間でもかなり共有されているようで、「小鳥の先祖はタカだった」と言ってもそう大きな間違いではないかも知れない (自分はこの考えを気に入っていて、祖先が大変優れた鳥であったために多様で能力の高い陸鳥に進化することができたのではとの「猛禽類ワールド」的な発想で見ている)。
ただし祖先を考える時に猛禽類だけに目を向けるのは、目立つ種類に引きずられすぎているとの指摘もある。
Prum et al. (2015) はさらに、水鳥とシギ類の系統が (生息環境や生活様式など) 限られた生態にとどまっているのは過去に指摘されていなかった系統的制約を意味する可能性を指摘している。
平たく言えばこれらの系統には限界があった、という意味と読んでよいだろう。
(この部分はかなり古く記述したものでこの系統樹は否定的と思われる。詳しくは注釈など参照) さらに次のような興味深い研究が出ている。Ksepka et al. (2017) Early Paleocene landbird supports rapid phylogenetic and morphological diversification of crown birds after the KPg mass extinction
非常に目立たない鳥であるが、ネズミドリの仲間の非常に古い化石が発見され、恐竜大絶滅から 200-300 万年ぐらいで現在の鳥のグループの祖先 (上記 6. 7. に至る) がほぼ現れていたことを示唆する。
この論文に現れる系統樹が斬新で、Telluraves (core landbirds、上記 6. 7.) に3つの系統があり、Australaves、名前は付いていないがフクロウ類とカワセミ類からなる系統、そしてネズミドリを含む Coraciimorphae (例によって中国語訳では仏法僧総目) の系統である。最後の系統にキツツキ類やサイチョウ類などが含まれる、この3つの系統がほぼ同じころに現れたと考えているようである。
現生鳥類だけを使う分子系統樹ではどうしても過去に消滅したグループの情報が含まれないので、このように化石記録も合わせた系統樹は重要である。この論文では (現生鳥類を使った分子系統樹による) 他の研究者の見解とは少し異なり、タカ目を Australaves に含めている。
現生鳥類を使った分子系統樹とは細かな矛盾が生じるのだが、初期に3系統が同じような時期に生じたため現生鳥類を使った分子系統樹で系統の出現順序を正しく解像できていない可能性は十分考えられる (つまりタカ類とフクロウ類、そして Coraciimorphae がどの順序で現れたかはわからない)。
後に発表された同じ著者による Ksepka et al. (2019) Oldest Finch-Beaked Birds Reveal Parallel Ecological Radiations in the Earliest Evolution of Passerines
も参照。ここでは Ksepka et al. (2017) の系統樹作成に使われた分子系統をベースとするが形態的特徴を取り入れる方法次第ではタカ目とハヤブサ目の収斂進化よって枝がまとまったもので、(純粋に) 分子系統的な支持は得られているわけではないと述べている。
分子系統的視点からは斬新な系統樹であったが共著者の助言 (?) もあって批判を呼びそうなトーンを抑えて受け入れられている形にしたのかも知れない。
ただし Ksepka et al. (2017) の論文で示されたタカ目を Australaves に含める系統樹は大変興味深く、タカ系統とハヤブサ系統が並ぶ関係になる (この図によればタカ系統とハヤブサ系統は 6000 万年前以前に分かれていたことになる)。
ハヤブサ類の系統にオウム類やスズメ目が含まれる点はこれまでの見解と同じ。「タカとハヤブサ」のような似たものが同じ系統に乗るならば大変納得しやすい気がする。
「日本鳥類目録改訂第7版ショック」の一つとしてタカ類とハヤブサ類が近縁でなく、後者はオウム類の仲間とされた点があったが、それは従来のタカ・ハヤブサ類の位置があまりにも間違っていたためで、この研究のようにタカ類とハヤブサ類をそれなりに近い位置に置くことも現在の知見とそれほど矛盾しない形で可能であることを示しているのだろうと考える
[ただし上記 Ksepka et al. (2019) が述べている解析の限界なども参照]。
もしこの系統樹が真実に近いのであれば、「小鳥の先祖はタカだった」と一層強く言えることになる (もちろん現代見ているタカは長い時間をかけて進化、選抜されてきたものであり、祖先となったタカのような鳥は現在のタカとはだいぶ違うものだったであろうが)。
現生鳥類を使った分子系統樹に忠実に従えば、タカ類と {ハヤブサ類 + オウム類 + スズメ目} の間は少し距離がある (現在の世界のチェックリストの分類順、日本鳥類目録改訂第7-8版もこれに従っている)。この系統概念でタカ類とフクロウ類、ブッポウソウ類、キツツキ類などを広く含む分類を Afroaves
[Jarvis (2014) Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birdsで提唱。
Sangster et al. (2022) Phylogenetic definitions for 25 higher-level clade names of birds の系統樹と引用文献も参照]
と呼ぶこともあるが、必ずしも系統性が再現できない理由で使用しない研究者もある。
もし Ksepka et al. (2017) の系統樹を採用すれば鳥類分類の最後はスズメ目にならず、スズメ目はタカ類やハヤブサ類の後に並ぶことになる。ここでは一応「別の可能性」程度に考えておくこととしよう。
なお、後述のように #フクロウの備考の Jarvis et al. (2014) のレトロトランスポゾンのデータを知ってこの考えは多分否定的であることに後で気づいたが、話としては面白い可能性だったのでこのようなことを考えたこともあった古い記述として残しておく。
レトロトランスポゾンのデータからはタカ類とフクロウ類は初期に十分近い関係であったはずである。
([初期のフクロウ類とタカ類は交雑していた!?] に記述あり)。
しかしフクロウ類と共通のレトロトランスポゾンが存在する Eucavitaves (キヌバネドリ類、サイチョウ類、カワセミ類やキツツキ類を含む) の系統とタカ類のレトロトランスポゾンの類縁性は見つかっていない。現象的にはまだまだ不思議である。
レトロトランスポゾンを用いた系統関係の確定については後の項目の [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] を参照。
現生鳥類の標準的な分子系統樹はフクロウ類よりタカ類の方が早く生じたことを示唆するが、
タカ類やフクロウ類は古い化石証拠に乏しいため、化石から系統関係に制約を付けにくいため両者のギャップが埋まっていない。
タカ類の可能性のある最も古い化石 (といっても指一本の断片) は 5050-5200 万年前とされる: Mayr and Smith (2019)
A diverse bird assemblage from the Ypresian of Belgium furthers knowledge of early Eocene avifaunas of the North Sea Basin
で分子系統樹から示唆される年代まではとても遡れていない。もっと確実な化石証拠はさらに後のものになる (フクロウ類の化石記録については興味深いので別に分けた。この項目の後を参照)。
なおここで述べた「近代的な陸鳥」とそれ以前の系統の間に位置する可能性のある極めて変わった種類がある。ツメバケイ Opisthocomus hoazin 英名 Hoatzin で、まるで草食哺乳類のように植物を発酵させるそのうを持つ。ひなは翼に爪を持ち実際にそれを使って木の枝を登る。
鳥類のゲノムの中には恐竜の前肢の爪 (例えばシソチョウは翼に3本の鉤爪を持つ指がある) を形成する機能が残っていて「先祖返り」が可能であるとも解釈されている。
近縁の現生種もなく系統関係はよく解明されていない。2014 年の研究ではツル類やシギ類に遠くつながる枝にあるとされたが最新の B10K の暫定結果をもっても未だに決着していない The Bizarre Bird that's Breaking the Tree of Life (Crair 2022, in the New Yorker)。
Prum et al. (2015) ではタカ類の手前の最初の「近代的な陸鳥」の位置に置いている。
2024 年になって [鳥類系統樹2024] のように修正された。
「鳥の生活」ブライト著 丸武志訳 平凡社 1997 p. 445 によればツメバケイは目立ったディスプレイを行わないが、なわばり境界で大声で攻撃的な交尾を数十回行ってテリトリーの所有者であることを示すという (関連研究を見つけられず)。
Hoatzin には "They display ritual copulations, assume aggresive postures, and emit loud noises to inform others of their territory" とある (出典は不明)。儀式化された交尾なのだろうか?
ツメバケイの生態全般については The Hoatzin (Joel Cracraft 2022) は参考になるかも。
Giant hoatzins of doom では南米のノガンモドキからハヤブサ類につながる系統の初期の可能性を考えていたが、現代の分子系統研究ではかなり違う結果となった。
骨格など形態に興味のある方ならば Pages (2019)
Compared and functional morphology of the hoatzin (Opisthocomus hoazin) (学位論文) も面白いだろう。
Sauropods still didn’t hold their necks in osteological neutral pose
の画像にもあるが、骨格と外見があまりに違うことも有名。この博物館の骨格展示ではキジ目になっているが骨格を見るとそのようにも感じられる。
ツメバケイはそのうで食べ物を発酵させるため、足以外にそのうも枝に乗せて体を支え、その部分の皮膚が厚くなっているという (コンサイス鳥名事典)。
手の骨の話なのでここに含めておくと、川口 (2024) Birder 38(6): 52-53 でエミューでは手羽第 II 指のみが残っているとある。
Kawabata et al. (2019) Evolution of the avian digital pattern に関連研究があり、こちらでは発生学的な番号では第3指でよいとしている (他の鳥と同様)。第2、4指の痕跡が一時的に現れる。
Newton and Smith (2020) Regulation of vertebrate forelimb development and wing reduction in the flightless emu
に指の発生のレビューがある。古口蓋類 Palaeognathae ダチョウ類で4系統で独立に翼の飛翔機能を失ったとのこと。エミューを含むそれぞれの系統の上腕骨格の比較も出ている。エミューには第 IV 指の痕跡を個体のもあるとのこと。
Feduccia and Nowicki (2002) The hand of birds revealed by early ostrich embryos が指番号が異なるので恐竜と鳥は別の系統と主張していた。
Alan Feduccia "The Origin and Evolution of Birds" (1996, 1999)「鳥の起源と進化」(アラン・フェドゥーシア著 黒澤令子訳 平凡社 2004) でもこのことは触れられているが、原著初版はこの論文が書かれる前に書かれたもの。
Burke and Feduccia (1997) Developmental Patterns and the Identification of Homologies in the Avian Hand もある。
日本の報道では
鳥は恐竜から進化した - 論争についに終止符 (nature ダイジェスト 2011)
や 恐竜の前足の指と鳥類の翼の指は同じもの
で確定したかのように読める (発生初期に番号がずれる frame shift フレームシフト) が、後述のようにそれほど簡単ではなかった模様。この論文は Tamura et al. (2011) Embryological Evidence Identifies Wing Digits in Birds as Digits 1, 2, and 3。
なおフレームシフトのアイデアは Wagner and Gauthler (1999) 1,2,3 = 2,3,4: A solution to the problem of the homology of the digits in the avian hand に現れる。
Young et al. (2011) Identity of the avian wing digits: Problems resolved and unsolved
恐竜と鳥で前肢の指番号が同じかどうかは古生物学、発生学、分子機序によって解釈が異なっており、まだ議論されているとのこと。
古生物学的には3つのパターンが考えられていて Posterior Digit Loss Model (PDL, 後の番号のものが失われる)、Bilateral Digit Loss Model (BDL, 両側が失われる)、Developmental Variability Model (DV, フレームシフト)
があるとのこと。この文献では慣習に基づき発生学的な指の位置にアラビア数字の 1-5 を用い、指番号をローマ数字で表している。
指を失う順序は Morse's Law (1872) として知られていて鳥類も例外でない。発生学的位置は 2-3-4 だが、残る指番号は I-II-III として古生物学的証拠と現代の鳥類の発生との間の矛盾を説明するフレームシフトを考えた解釈を行っている。
Stewart et al. (2019) Evidence against tetrapod-wide digit identities and for a limited frame shift in bird wings
は鳥の前肢の指は 1, 3, 4 ではないかとの可能性の解釈も行っている。
de Bakker et al. (2021) Selection on Phalanx Development in the Evolution of the Bird Wing
に系統ごとの主な種で指の骨の数の比較が出ている。
後肢は比較的よく保存されているがヨーロッパアマツバメのような例外もある。前肢ではもっと変化が大きい。この論文では古生物学的証拠と現代の鳥類の発生との間の矛盾を説明するために導入された (パラダイムシフトでもあった) フレームシフトのアイデアは必要なく、鳥の前肢は始祖鳥も含めて II-III-IV でよいだろうとしている。
ツメバケイの前肢の指骨式 (phalangeal formula) を X-2c-3c-1-X (c は鉤爪がある意味) としており系統的に合わないように感じる。この点は次の [鳥類系統樹2024] の最新結果を取り入れてもツメバケイの位置は変わるが基本的結論は変わらない。ツメバケイ以前に分岐した系統でも数の少ないものがある。
失われた骨を回復する "先祖返り" がないとすれば、この論文で主張されているように、指の骨の減少や指の消失は必要に応じて独立に起きると考えてよい印象を受ける。これを受け入れれば鳥の前肢は II-III-IV でも特に矛盾があるわけではない模様。
また現代では他の証拠が増えて指の同定問題は鳥と恐竜の類縁関係を考える上ではあまり重視されなくなっているらしい。
参考までに哺乳類の祖先型の後肢の指骨式は祖先となる単弓類 (Synapsida) で 2-3-4-5-3、獣弓類 (Therapsida) でもしばしば同じものがある
[Rowe and Heever (1986) The hand of Anteosaurus magnificus (Dinocephalia: Therapsida) and its bearing on the origin of the mammalian phalangeal formula]。
哺乳類の祖先型とされる 2-3-3-3-3 はその後生じたものと考えられるとのこと [哺乳類の指骨式については川口 (2010) Birder 24(7): 60 も参照]。
de Bakker et al. (2021) の表を見ると鳥類の基本形は 2c-3c-4c-5c-X だがダチョウのようにさらに失って X-X-4c-5c-X となっているものや、ヨーロッパアマツバメのように 2c-3c-3c-3c-X となっているものもある。
鳥類では後肢で体を支えるため指の骨は哺乳類ほど簡単には減らせなかったが、ヨーロッパアマツバメのように後肢の役割が小さい場合は哺乳類との収斂進化が見られるらしい。
鳥類・哺乳類で根源的な違いがそれほどあるわけではなく、生態的違いから骨や指の減らしやすさが異なっていたと考えるのが妥当そう。
#サケイでは外見では足が哺乳類によく似ているとのこと。
ダチョウの趾が減っている遺伝的制御機構の候補: Li et al. (2025) ZIC3 shapes digit morphogenesis in avian
ダチョウでは他の鳥と違って Zic3 が強く発現しているとのことで、ニワトリでこの遺伝子を強く発現させるとダチョウに似て I, II 趾が短い表現型となったとのこと。
ニワトリでは5本や6本の趾を持つ品種がある。Chu et al. (2017) Association of SNP rs80659072 in the ZRS with polydactyly in Beijing You chickens で Beijing You chickens で余分の趾を持つ個体の遺伝的基盤や解剖学を検討している。[ヨーロッパの品種にもあるがこれは北京のものを扱っている。参考 Zhang et al. (2016) Parallel Evolution of Polydactyly Traits in Chinese and European Chickens]。
指の同定は 4-3-2-1-2’, 4-3-2-1-1’, 4-3-2-1-2’-2’, 4-3-2’-2’-2’, 4-3-2-2’-2’-3’ が与えられている (指骨式とは異なる)。第 V 趾が復活したものではなさそう。
Dunn et al. (2011) The chicken polydactyly (Po) locus causes allelic imbalance and ectopic expression of Shh during limb development によれば発生途中に Shh が異所的に発現した結果とのこと。
関連する遺伝子の研究: Huang et al. (2025) Integrated genomic and transcriptomic analysis of polydactyly in chickens。
de Bakker et al. (2025) Changes in Evolutionary Developmental Control Points in the Amniote Limb May Explain Hyperphalangy に羊膜類の指や爪の数を決める発生的因子の提案がある。指の数が増える例はカメ類、ワニ類、イルカ類の一部で知られているとのこと。
チュウゴクスッポン Pelodiscus sinensis Chinese softshell turtle は足に角質を持たない (爪もない)。"softshell" の英名の由来。指や爪を形成する遺伝子発現制御次第で指や爪の有無はあまり系統の目安にならないのかも知れない。
[鳥類系統樹2024]
最近になって2本の論文がセットで発表された。鳥類の全系統樹は Prum et al. (2015) がこれまでのある種の標準であったが、約 10 年近くを経て大幅に躍進した B10K の系統樹が発表された。
スーパーコンピュータを用いても計算機処理能力の限界から各分類群を代表する 363 種を選択して解析 (別の深淵な背景があるかも知れない。後述)。92% の科をカバーした。目レベルの系統関係は一部を除いてこれでほぼ固まっただろう。
塩基配列数で比較すると Prum et al. (2015) の 300 倍以上、Kuhl et al. (2021) の 100 倍程度のデータを使用。これまで最大だった Jarvis et al. (2014) の塩基配列数で6倍、アラインメントで 50 倍とのこと。
近代的な陸鳥の進化からは少し離れるがここに含めておこう。「鳥類系統樹2024」とでも呼ばれるものになるだろう。
Stiller et al. (2024) Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes (オープンアクセス)
系統樹とデモンストレーション動画は A new family tree revises our understanding of bird evolution
で見ることができる。
中国語解説。
Neoaves (現生鳥類から古口蓋類 Palaeognathae ダチョウ類と Galloanserae キジ類 + カモ類を除いたもの) のうちまず (1) Mirandornithes (フラミンゴ類 + カイツブリ類) と (2) Columbimorphae (ハト上目に相当) がそれぞれ分岐した後の2グループ (3) Elementaves と (4) 「近代的な陸鳥」Telluraves 系統となった。つまり Neoaves はこの順に出現した4系統となる。
名称の扱いについては後にもう少し触れる。
キジ類 + カモ類 まではこれまでの理解と同じ。「近代的な陸鳥」の部分もこれまでの理解でよいが、中間部分の関係が変わる。
大まかに見た全体で7段階ある点は Kuhl et al. (2021) と同じ。図に示された系統数は12となっている。
Elementaves (新系統名。中国名 "元素鳥類") は
(1) ツメバケイ
(2) Cusorimorphae (ツル目: #アネハヅル備考、チドリ目: #タゲリ備考 を含む。中国名 "鶴形鳥")
(3) Strisores "夜鳥類" (ヨタカ、アマツバメ、ハチドリ系統)
(4) Phaethoquornithes (Phaethonimorphae ネッタイチョウの系統 + Aequornithes カモ類でない "水鳥類"。中国名 "鷺形鳥") (#クロトキ備考)
の4系統からなるグループ。
水・土・気は古典元素 (四元素 しげんそ。古代ギリシア、古代インド、仏教など) なので Elementaves "元素鳥類" となったとのこと。火または太陽を意味する名称は Phaethonimorphae ネッタイチョウの系統 で使われているので揃うとのこと。
現生鳥類の中で陸・海・空すべてに放散し、地球の生態系を形作る基礎となった初めての系統である。祝福しようではないか。
英語では "基礎" に相当する "basal" (Basal Landbirds など。系統的により古いものを指す) のような表現があるが、物質を構成する元素、あるいは世界を形作る elements (構成要素) を充てたことになる。洋の東西の価値観の違いを問わず通じる古典に基づくことになる。これ以上大きな現生鳥類の分類群はもう現れないだろう。日本語にそのまま当てはめにくいが、最後の命名として何と含蓄のある比喩だろうか。
Boyd の Taxonomy in Flux Checklist 3.50 にも最近採用された。
このアイデアは Murray Gell-Mann マレー・ゲルマン (クォークの提唱者。人となりは wikipedia など見ていただきたい) が素粒子の対称性に注目して仏教から拝借した概念「八道説」に通じるところがある感じがする (*2)。
ツメバケイは「近代的な陸鳥」の冒頭ではなく、Elementaves の冒頭となった。
Neoaves の出現は 6740 万年前程度と見積もられた。
全ゲノム解析でもタカ系統の位置関係は自明とならなかった。鳥類系統の中でも最も難しいものの一つだろう。Telluraves の中で Australaves (ノガンモドキ目、ハヤブサ目、オウム目、スズメ目) は分けられるが、残りの系統の関係はまだ確定的でない。タカ目だけを別系統とするものと {タカ目 + フクロウ目} で系統を作るものの確からしさが解析方法によって異なる。
他の目では3種のサンプルで十分系統が確認できるが、タカ目とフクロウ目は 10 種以上をサンプルしてようやく系統として認められる難しいグループだった。系統樹の形もスズメ目を何種取り入れるかによって変わってくる。
初期の交雑、incomplete lineage sorting (不完全遺伝子系統仕分け)、long-branch attraction (長枝誘引) などが系統樹構築に影響を与えた可能性がある。
Mirarab et al. (2024) A region of suppressed recombination misleads neoavian phylogenomics
の最新の B10K の結果から、大絶滅後の鳥類放散の初期 (6500 万年前ごろ) に染色体の一部の組み換えが極度に抑制される現象が生じたと判定された (#ベニヒワの備考も参照)。
この結果はこれまでの分子系統解析にも影響を与えているとみられ、研究によって (目より上位レベルの) 系統関係が異なっていた原因も説明できるかも知れない。これまでは Mirandornithes と Columbimorphae が系統 Columbea をなすと考えがあったが、染色体の逆位の解析の結果別系統と判定された。
Mirandornithes は単独系統をなし、Columbimorphae (ハト上目に相当) と Otidimorphae (ノガン類やカッコウ類などを含む) が系統を作る結果となった。
これを支えたのが高速新アルゴリズムとサンディエゴにあるスーパーコンピューターセンター "Expanse" の計算機資源とのこと。スーパーコンピューターの世界ランキングで見ると2023年11月段階で「富岳」(この時点で PFlop/s で世界4位。2020 年で1位)
の 1/100 を下回るぐらいでそれほど大きなものではなく、大学が扱うスーパーコンピューターぐらいの規模だろうか。さらに多数の種を高速に扱えるように改良中とのこと。
Algorithm Helps Evolutionary Biologists See Where Bird Species Are Perched on Phylogenetic Tree。
Computational tools fuel reconstruction of new and improved bird family tree。
使われたアルゴリズム ASTRAL の初期論文 ASTRAL: genome-scale coalescent-based species tree estimation。現在はこの3世代目とのこと。
松井 (2021) 分子系統解析の最前線 にも解説があり、Olivier Gascuel と Tandy Warnow (ASTRAL はこちら) は、革新的なアルゴリズムの開発と高品質な実装を両輪として進めているとのこと。
コンピューターの性能を2倍にするのは費用もものすごくかかるが、革新的なアルゴリズムの発明によって何倍も早い解析ができればそれに匹敵する効果がある。
Catanach et al. (2024) のタカ類系統解析にも書かれているように、古い系統樹の枝の構築と例えば種か亜種かの判定レベルの計算を同時に行うのは計算機資源的にも得策でない。ここでは少数の代表種を用いることで全系統関係を明らかにしたもの。枝の詳細はこれからさらに明らかにされてゆくことだろう。
参考のために「鳥類系統樹2024」に従った目以上の分類を紹介しておく。今後の世界のリストの配列順もこれを参考にすることになるだろう (並列で並んでいるところの順序は任意性がありここで示した順番の限りではない)。番号は Stiller et al. (2024) の系統樹記載の系統番号。最後のかっこ内の系統番号は同じく 12 系統とした場合の番号。
系統によっては科か目かの扱いの分かれているものがあるので全目の名前があるわけではない。
目和名は 山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類 に従っている。
新顎類によるとパーカー, スティーヴ著、日暮雅道・中川泉 訳、養老孟司 日本語版監修 編「生物の進化大事典」三省堂 (2020) が高次分類の和名を提案しているらしい。
賛鳥類 Mirandornithes、水禽類 Aequornithes、陸鳥類 (これは中国名と一致) Telluraves とのこと。「陸鳥」の概念は昔からあるので使い方が難しいところ。
古口蓋類 (古顎類) / 新口蓋類 (新顎類) の名称は 日本鳥学会「日本鳥類目録改訂第7版」の「高次分類体系の解説」(山崎ほか 2013) と
冨田他 (2020) 恐竜類の分岐分類におけるクレード名の和訳について で後者がかっこ内のもの。鳥学と古生物学で少し異なる名称を用いている。
Galloanseres, Neoaves は山崎ほか (2013) では「ガロアンセレス類」「ネオアヴェス類」としているとのこと。冨田他 (2020) ではキジカモ類、新鳥類を採用。日本鳥類目録には目より上の分類群は載っておらず、「キジカモ類」は日本鳥学会による公式な名称ではないが鳥類関係者の間では従来から広く使われている用語 (ほんとう?) との認識。
和田 (2004) Birder 18(7): 77-79 では (当時明らかになってきた) 系統として、キジ・カモ類の名前は使っているが、日本語の用法としてこれは系統名とは言えないと思う (タカ・ハヤブサ類と同様)。
この記事は 日本鳥類目録 改訂第5版 で用いられた分類と、Sibley and Ahlquist (1990) の知見および当時明らかになってきた少数の遺伝子による系統を比較したもの。当時の知見の紹介として適切な記事に見える。
家禽類の祖先が示す現生鳥類の初期進化 (Nature ダイジェスト 2020) では キジカモ上目を使っている。この分類群は「家禽類」と見なすことができる、とのことだがある意味言い得て妙にも感じる。あまり日本語らしくない「キジカモ類」よりもふさわしいカモ? 家禽類は野鳥の名前を指すにはふさわしくないとも言われそうだが。英語でも一般名 fowl で、この2目を含むとある。
もっと積極的に "家禽" を表す poultry も日本では一般的にはあまり馴染みがないのでこれらに関係する語彙が日本語にあまり豊富にないかも知れない。
参考情報: Torres et al. (2025) Cretaceous Antarctic bird skull elucidates early avian ecological diversity 6920-6840 万年前の南極から大絶滅の前の鳥類 Vegavis iaai 化石の頭骨の解析。
現生鳥類と別系統ではなく Galloanserae の古い系統に含めることができた。足のひれで推進するカイツブリ類やオオハム類のような深い潜水採食生態だったと考えられ、対応する生態を持つ現生のカモ類はいない。一般向け解説。
現生鳥類の直系の祖先と考えられる最も古い証拠とのこと。当時の南極は気候も温暖で小惑星衝突地点からも遠く、避難所として機能したのではとの考え。
Galloanserae の系統と考えられ、キジ類とカモ類の特徴を併せ持つ古い化石 (6680-6670 万年前) Asteriornis maastrichtensis がヨーロッパで見つかっており、この系統がゴンドワナ大陸以外にも生息していたことを示す結果となっていた: Field et al. (2020) Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds。
「野鳥」2025 年 7・8 月号 (No. 877) pp. 2-9 の対談記事 小林快次×上田恵介 を読んで、小林氏の気に入られている考え方の基本は思ったより単純らしい印象を受けた。
上田氏の応対と対談記事編集によるバイアスが入っているかも知れないが、K-Pg 境界を生き延びた恐竜系統は歯を持たないもののみ。これを説明できるアイデアとして巨大隕石の衝突によってもたらされた暗黒時代がある程度長く続き、種子は数年は保存されるだろうから種子食のものが残ったと考えることが可能。
歯を失って嘴とし、歯の機能は消化管機能が代替した恐竜系統が生き残ったと理解することができる、というのが大まかなストーリーだろうと読んだ。この記事は鳥と植物の関係をめぐる生態学に詳しい上田氏が受けやすいテーマとして取り上げられた可能性もあり、小林氏のアイデアの全貌を把握した上のコメントではないことをまずお断りしておく。
この仮説については、後に登場する Larson et al. (2016); 小林 (2020) Birder 34(8): 30-32 を紹介している部分の Louchart and Viriot (2011) From snout to beak: the loss of teeth in birds を参照。これを紹介した時点では系統名の表記のために参照したが、「野鳥」2025 年 7・8 月号の記事があったためここに改めて追記した。
まず思い浮かんだ疑問は (1) 種子以外の食物は長期間残らないのか (すべての生物が絶滅したわけではないので他の食物もあるのでは?)。
(2) 地球全体が大きな影響を受けてどこもある程度同じように被害を受けたことがある程度前提となっているようだが、あまり被害を受けなかったところもあったのでは。
Torres et al. (2025) の発見はこの2点の疑問に答えてくれているように思える。つまり他にも食物はあった場合に残ることができるものがあった可能性がある程度に食性が多様化していた。また全球が同じように影響を受けたわけではなかったらしく、衝突地点から遠い地域にも K-Pg 境界以前の現生系統につながる鳥が生息していたことが幸いした可能性がある。
地球の歴史で全球凍結を経験しているが生物が生き延びられる場所がどこかに残っていたのと同じような考え。火星はそのような条件を断続的にしか保つことができず、少なくとも現在の表面は居住不可能となっている [#トビ備考の *3: ミランコビッチ・サイクル で紹介の Kite et al. (2025) の数値計算とアイデア参照]。
他の考え方にどのようなものがあるのか少し調べてみると Torres et al. (2021) Bird neurocranial and body mass evolution across the end-Cretaceous mass extinction: The avian brain shape left other dinosaurs behind
によれば歯を失って嘴となるとともに顎関節の可動性が高まったことが多様化に役立ち適応放散に有利であった考え方がある。現生の2系統である Palaeognathae (古口蓋類/古顎類) に比べて Neognathae (新口蓋類/新顎類) が急激な適応放散を行った理由の説明として考えられていたが、それだけでは他の系統の恐竜が絶滅した理由まで説明することは不十分である。
この著者は他の系統に比べて脳が進化していたらしい点に注目している。Torres et al. (2025) の執筆と同じチームなので、Vegavis iaai をカモ類に近いグループと位置づけていた。
また小型種が生き延びた説明は古くからあったが、体重の進化はサンプルに非常に敏感で小型種が選択的に生き延びた根拠は薄くなっているとのこと。
以下自身の補足: 小型種が生き延びた説明は現生鳥類と恐竜の系統関係がよくわかっていなかった時代のもので、いわゆる "小鳥" も含む鳥類の大部分は大絶滅以前に登場していて、大型の恐竜が劇的な気候変動に耐えられず絶滅したと考えればうまく説明できるとして一般に用いられていた。
現生鳥類と恐竜の系統関係が明らかになるとともに、分子系統解析も進んで "小鳥" は新しい系統であることが判明するとこの発想はやや下火となったが、K-Pg 境界以前に現在の系統が出揃っていたか、Stiller et al. (2024) と Wu et al. (2024) の議論、Springer and Gatesy (2024) と Wu et al. (2024b) の議論の再燃のように Angiosperm Terrestrial Revolution (cf. 後述「花に追われた恐竜」参照) にも絡めて水面下でくすぶっているらしい (こういう表現を用いる場合はパラダイム論争を意味していると読んでいただいてよい)。
K-Pg 境界以前に "小鳥" が出現していれば "小型種が生き延びた" 古い時代の説明が延命できる可能性があることになる。
この話は #ノガン 備考の [Otidimorphae の系統分類]、#タゲリ 備考の [チドリ目の系統分類]、ミサゴ備考 (この項目) の [オウム類・ハヤブサ類の年代推定]、似た形態と習性のチュウヒダカとセイタカノスリの間および新世界と旧世界のハゲワシ類の間に直接の系統関係があるのではと考えられたことにもつながっている。
これらの隔離分布の説明に提唱された、K-Pg 境界以前にこれらの系統が連続分布していた証拠は分子系統解析が否定的結果を与えている。
オウム類の Wright et al. (2008) A Multilocus Molecular Phylogeny of the Parrots (Psittaciformes): Support for a Gondwanan Origin during the Cretaceous の研究がまだ評価されていたように現代のような系統関係がわかるようになったのはやはりこの時期以降。この研究は "現代の鳥の系統は古くからあった" パラダイムを支持する論者であったことがわかる。
ものごとが明瞭になってきたのは 2010 年ごろからの急速な分子系統研究の進歩以降のことで、分子系統研究の進歩は鳥類の系統関係を明らかにしただけのものではなく、K-Pg 境界との関係を解きほぐすにも役立っていたわけだ。タカ類とハヤブサ類が分けられたことだけが取り上げられがちだったが、もっと大事なところを明らかにして行くことになった。この変革はごく近年のことなので、現在でも "現代の鳥の系統は古くからあった" 方を信じたい人たちもあって、異なる系統解析の方法が好まれるなど混在した議論が存在していることになる。
見ていただいての通り現存系統については新しい理解と大きな矛盾点が見つからず、大筋は多分正しい理解に近づいているのだろう。極めてまれにしか起きない巨大隕石の衝突時期と鳥類の爆発的な適応放散が偶然一致するとは考えにくい。巨大隕石の衝突前に爆発的な適応放散が起きていたとするのはやはり無理があるだろう。
もっともゲノム情報がわかるのは現生種に限られる問題はあって、現生種のゲノム解析では K-Pg 境界以前に適応放散したが絶滅した系統の情報がわからないだけに伴うバイアスの可能性は完全には捨てきれない。もっと早い時期に鳥類の爆発的な適応放散が始まっていたが、生き延びた現在の系統に反映されていないために古い時代の多様性を適切に評価できていない可能性は残る。それにしてはあまりに化石証拠が少ないなど面白い部分だろう。
"現代の鳥の系統は古くからあった" + "小型種が生き延びた" かどうか、このようなある意味古いパラダイム論争をやっていたところに Louchart and Viriot (2011) が一石を投じた経緯だろうか。この論文以降だけを見ると歴史的議論の背景が見えにくくなるかも。それ以前の論争が (今から見れば) 古くさい印象を受けるものだったために、にわかに興味を引く仮説として浮かび上がった状況だったかも知れない。
パラダイム論争といえば K-Pg 境界大絶滅要因を巨大隕石衝突に求めるか、巨大火山活動に求めるかも同じくパラダイム論争だった。2つとも有力なシナリオを描けるのでパラダイムとなり得る。こういう論争はみんな好きだったのだ。
パラダイムができると支持者 (信奉者?) のグループも生じ、そのパラダイムに都合のよい証拠を探すことになる。そのようにしてあるパラダイムを支持する多数の証拠が選択的に示されて、いかにももっともらしく見える。
そのパラダイムに疑問を持った場合も、それらの膨大な証拠に対して反証するのは大変で、新しいパラダイムはよほどの証拠が集まらないとなかなか提示されないのが一般的。つまりパラダイム・シフトは起きにくい。
グループ内で複数のパラダイムを戦わせるのが理想的だろうが、小さなコミュニティではなかなか難しく、どうしても主流のパラダイムに乗る方が簡単で労力も使わないことになる。
巷で流行っているパラダイムの方が有力なのかどうかは実はよくわからない。純粋な自然科学であればまだ対等に競わせることも可能であろうが、社会的評判や研究費が獲得できるかなど一方のパラダイムに別の力が有利に働くこともあるだろう。集団が小さいほど物の見方は一方向に進みやすい。
パラダイム論争も一般的にはいつまでも続くわけではない。巨大火山活動と巨大隕石衝突の論争も今や巨大隕石衝突の証拠が圧倒的に強まり、少なくとも以前のように活発に行われる状況にはなっていない。パラダイム論争に乗って生活していた人は別の話題に乗り換えるか活動を終えることになる。
K-Pg 境界大絶滅でなぜ鳥だけが生き残ったのかも (例えばゲノム解析など古生物学とあまり関係ないところから発展する可能性が十分考えられる) 次第に明らかとなって、想像する以上に早くパラダイム論争が終わってしまうかも知れない。「恐竜から鳥」がテーマとして取り扱われるのも、長い目で見ると羽毛恐竜の発見に始まった流行現象と記憶されることになるかも知れない。
Torres et al. (2021, 2025) は、多分 "小型種が生き延びた" のような単純なことが要因ではないだろう、もっと別のより大事な要因があるだろうと見ていると読める。歯を持つか持たないかの1要因で解釈するのも "小型種が生き延びた" 仮説と同様の構造かも知れない (種子食を要因と考えるのも Angiosperm Terrestrial Revolution の延長上かも知れない)。
前述の (1), (2) がいずれも肯定されるならば食性や形態はそれほど大きな要因ではなく、他のもっと本質的な要因の相関の形で見えているものかも知れない。
Torres et al. (2021) の提唱する脳が一段進歩していた仮説はその後の鳥類進化の経緯をみてもよりもっともらしい気がする。
脳が他の系統より進歩していたため、生き残った食物を食べることができた幸運な一部の系統が大絶滅を生き延びた。大絶滅を生き延びるハードルは極めて高く、子孫を残せるレベルの個体密度が残存したのはごくわずかの種類で、ほとんどの種類はそもそも生き延びることができなかったか、生き延びても創始個体群となるレベルの個体数に達しなかった。ハードルをかろうじて乗り越えることができたのは選りすぐりの優秀な系統に限られたのだろう。
このように説明するともっともらしく聞こえる。この議論を延長すれば現生鳥類の脳の機能や習性を絶滅系統に当てはめるのは危険とも言える。K-Pg 境界の大絶滅という極めて強い選抜を受けた種類のみが残っていて、選抜を受けたものの性質をそのまま用いるとバイアスが非常に大きい可能性があるわけである。
同じような形をしていても脳の能力は想像以上に違っていたかも知れない。つまり絶滅恐竜の能力は現代に生き延びた鳥類に比べてかなり劣っていたのかも知れない。
化石動物では脳の体積や脳の構成要素の比率や外部形態しかわからないが、現生鳥類でも脳の機能を外観からどこまで予測できるかはかなり怪しい印象を受ける。例えば化石しかなければフクロウ類は知能が高いと判断されただろう。同じような食性のタカ類とフクロウ類を化石だけから比較すれば、フクロウ類の方が脳が大きく生態的も優位に立っていたと判断されるのではないだろうか。
嗅球のサイズのように機能がほぼ現れてそうな古い部位 (これも実際はみかけと異なるかも知れない) に比べると、新しく進化した方の脳の部位は外部形態よりニューロンの密度や内部ネットワークの構造により大きく左右されると思われる。嗅球のサイズが嗅覚とよい相関があったから他の部位も同様とは言い切れない可能性がある。
化石から脳の内部構造や機能まで推定することは難しいだろうから Torres et al. (2021) の推定も限界があるだろうが、"脳が一段進歩" 仮説を直接検証することは難しく脳の形態に頼らざるを得ない。
しかしそれでも食性よりよい仮定のように思える。同じ地域・食性であっても脳の機能のより高いものが生き延びた。さてどうだろうか
#ミフウズラ備考の系統分類の部分でも一部議論を行っており参照。
ミサゴ (この項目) 備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] にあるようにゲノムに残された "化石証拠" から鳥類の適応放散の年代上限値をある程度知ることができるようになってきた。9800 万年前は現代的な鳥のゲノムから読み取れる上限値の一つと考えてよいのではないだろうか。
Early Cretaceous (前期白亜紀) 1.45-1.00 億年前よりは以降で、Angiosperm Terrestrial Revolution は 1.25 億から 5000 万年前ぐらいとの年代関係ぐらい。
上記のような "少数の種が極めて高いハードルを乗り越えた" 考え方であれば、K-Pg 境界以前に現生鳥類の祖先がすでにある程度多様化していたことで、完全絶滅を避けることができたとも考えることもできる。
もし巨大隕石の衝突が数千万年早ければ、現生鳥類の祖先に生き延びることのできるものがなかったかも知れない。恐竜も鳥類も全部絶滅生物となっていて、残ったわずかな系統の爬虫類と哺乳類が繁栄することになったのだろう。
哺乳類から空を制覇したのは現生動物ではコウモリ類であるが、翼の構造も呼吸器も鳥類とは大きく違っていて、現代の鳥類ほどは活躍できなかったかも知れない。哺乳類の系統は β ケラチン (CBPs) を持たないため羽毛のような構造を作り出すことはできず、あくまで飛翔能力のある哺乳類にとどまっていて現代の鳥のように多様な世界に進出することはできなかっただろう (「羽毛は我々の毛と同じケラチンが成分」とする説明ではこのような場合に困る)。
呼吸器もすでに初期の進化の設計を終えた後で、もはや大幅なモデル変更はできなかっただろう。
ということで鳥類が絶滅し、飛翔能力のある哺乳類が空を制覇していたとしても、現代の鳥のように多様な役割を果たすことはできなかったのではないだろうか。肉食性のものは当然進化してしかるべきであるが、コウモリの構造を考えると猛禽類に対応するほどの性能のものは進化できなかったのではないだろうか。
巨大隕石の衝突がもっと後であれば鳥類系統はさらに多様化していたかも知れないが、地上性の恐竜がすでに広範に支配していたため鳥類系統の進化はある程度で落ち着いて、いつ衝突しても状況はあまり違わなかったかも知れない。
では現生鳥類の祖先がすでにある程度多様化した段階で巨大隕石が衝突したのはなぜだろうか。単なる偶然であろうか。天文学的には地球の生命進化段階に合わせて衝突する理由はないので完全な偶然となるのだろうが、我々のような観察者が進化できたバイアスを無視することはできない。
つまり飛翔能力のある哺乳類が空を制覇していた世界があったとしても、高度な科学技術文明を発達させた人類が進化しなければそのような世界は観察されないことになる。今後の科学が明らかにしてくれそうな気がするが、もし鳥類が空を制覇していなければ人類が進化できる環境が整わなかったのではないだろうか。
例えば空からの捕食者が現れなければ生態系や例えばサル類のような哺乳類はどのような進化を遂げていただろうか。
空からの捕食者がなければ、現代のダチョウのように地平面に特化した視覚系が発達したかも知れない (視覚も脳も、必要ない部分にはわざわざ投資しない)。つまりサル類も上を見る必要がなく目線の高さか下ばかり見る生活で構わない。このような視覚特性であれば現代見るようなサル類とは異なった生態や社会構造を発達させていたかも知れない。
上を見上げる必要がなければヒトでは音声コミュニケーションの進化に必要だった喉頭の発達も起きなかったかも知れない (#ウミウ備考 [長い首の水中での役割] にて紹介の霊長類のポートーのような事例を考えてしまう)。
このような観点からみると、現生鳥類の祖先がすでにある程度多様化したタイミングに合わせて巨大隕石が衝突したのは観察者が存在するためによる必然と言える可能性がある。この考え方は弱い人間原理 weak anthropic principle として知られている。もともとは宇宙がなぜこのような法則に従っているのかを説明する宇宙論から出発したが、むしろより現実的なこの問題の方に当てはまるかも知れない。
もっとも発端となった物理学の方ではこの考え方はあまり人気がない。というのは "宇宙がなぜこのようにできているのか" を人間が進化して観察できているためと説明すればそこで解釈が止まってしまい、もっと普遍的な法則があることを見逃してしまうおそれがあるためである。
生物に対する扱いについても同様で、物理や化学は普遍的な学問であっても、生物学はたまたま人間を生んだ特殊な世界を記述しているだけで本質的ではないと考えられがちである理由となり得た。現代ではもう少し理解が進んで生命の起源や化学進化にある程度の必然性があって、それを探ることが重要な科学の分野と考えられるようになってきている。
巨大隕石の衝突規模が大きすぎたり、それ以外のタイミングであれば哺乳類が生き延びても人類が誕生しなかった可能性も考えられる。もし数種でも鳥類 (特に Neognathae の系統) が生き残れたことが我々の運命を決めていたとすれば大変ロマンチックな話ではないだろうか。
現生鳥類の祖先の多様化がこのタイミングで起きたことは、もしかすると我々の誕生に鳥類の存在が深くかかわっていたことと、弱い人間原理がある意味で成り立っていることの両者の根拠になるのかも知れない。また、もし人類が誕生していても上方への視力が悪ければ宇宙の存在を認識するにも時間がかかっただろう。例えば天空の神は思いつかなかったかも知れない。
現生鳥類がどのように生き延びて進化したのかを知ることは、もしかすると我々自身の進化を理解する手がかりになるのかも知れない。あるいは生物進化と巨大隕石の衝突のタイミングが合致する、我々のまだ気づいていない必然性があるのかも知れない。
もし我々が恐竜または鳥系統から進化していたならば別の解釈を考えていたかも知れない (挿入終わり)。
なお冨田他 (2020) で使われている Aves の概念は #ハヤブサ備考「鳥の起源と進化」で紹介している川上・江田 (2018) で示されている系統樹と異なる。
Wikipedia 英語版 Bird で Stiller et al. (2024) はすでに採用されている。
Psittaciformes の和名は山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類ではオウム目、日本鳥類目録 改訂第7版や日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)ではインコ目で異なっている。
1. 古口蓋類 (古顎類) Palaeognathae (1)
ダチョウ目 Struthioniformes
以下2系統。合わせて Notopalaeognathae (中国名 "南方古顎類") の名称がある
(系統 1。Novaeratitae の名称があったが 系統 2 と単系統の関係にないことがわかった)
ヒクイドリ目 Casuariiformes
キーウィ目 Apterygiformes
(系統 2)
レア目 Rheiformes
シギダチョウ目 Tinamiformes
これ以降が 新口蓋類 (新顎類) Neognathae
2. Galloanseres (キジカモ類) (2)
カモ目 Anseriformes
キジ目 Galliformes
これ以降が現在 Neoaves (新鳥類) と呼ばれる
3. Mirandornithes (中国名 "奇跡鳥類") (3)
フラミンゴ目 Phoenicopteriformes
カイツブリ目 Podicipediformes
4. Columbaves
大別して2系統
系統 1 Columbimorphae (4)
系統 1a
クイナモドキ目 Mesitornithiformes
サケイ目 Pterocliformes
系統 1b。系統 1 内部の分岐はこちらの方が早い
ハト目 Columbiformes
系統 2 Otidimorphae (5)
系統 2a
エボシドリ目 Musophagiformes
系統 2b
ノガン目 Otidiformes
カッコウ目 Cuculiformes
5. Elementaves (中国名 "元素鳥類")
系統 1 ツメバケイ目 Opisthocomiformes (6)
ツメバケイ目 Opisthocomiformes
系統 2 Cursorimorphae (7)
ツル目 Gruiformes
チドリ目 Charadriiformes
系統 3 Strisores (8)
(全体でヨタカ目 Caprimulgiformes とすることも、全体でアマツバメ目 Apodiformes とすることもあり、あるいはさらに目に分けられることもある)
系統 4 Phaethoquornithes (中国名 "鷺形鳥")
系統 4a Phaethontimorphae (9)
ネッタイチョウ目 Phaethontiformes
ジャノメドリ目 Eurypygiformes
系統 4b Aequornithes (10)
4b-1 アビ目 Gaviiformes
4b-2a
ペンギン目 Sphenisciformes
ミズナギドリ目 Procellariiformes
4b-2b (4b-2 の分岐はこちらが早い)
ペリカン目 Pelecaniformes
(一般的に用いられるコウノトリ目 Ciconiiformes, カツオドリ目 Suliformes はここに位置する。目レベルの分類は複雑で #クロトキ の備考参照。十分な種数の解析がなされていないために議論のある目レベルの分類は扱わなかったのだろう。クロトキの備考に科レベルも含めた考察を少し加えた)
6. Telluraves (中国名 "陸鳥類"。この解説で「近代的な陸鳥」と読んでいるもの)
系統 6a Afroaves (11)
(この解析では2系統になるが全体の関係はまだ自明でない)
6a-1
フクロウ目 Strigiformes
タカ目 Accipitriformes
6a-2。以下は系統順に分岐。
ネズミドリ目 Coliiformes
(以下の系統は大部分は穴に営巣する特徴があり、Cavitaves のクレード名がある)
オオブッポウソウ目 Leptosomiformes
キヌバネドリ目 Trogoniformes (ここから Eucavitaves のクレード名がある)
サイチョウ目 Bucerotiformes
ブッポウソウ目 Coraciiformes
キツツキ目 Piciformes
系統 6b Australaves (12) 以下は系統順に分岐
ノガンモドキ目 Cariamiformes
ハヤブサ目 Falconiformes
オウム目 Psittaciformes
スズメ目 Passeriformes
以下の話では Neoaves を指して日本語で「新鳥類」と記述することを避けて Neoaves と呼んでおく。Telluraves についても同様。
これは「新鳥類」の訳名が別の概念にも使われている (いた) ためで、例えば青塚 (2017) Birder 31(3): 28-29 にある。この記事の引用文献を見ると Chiappe and Dyke (2006) から "Modern birds" に対応するものが新鳥類となっている。
"Modern birds" と同じ意味の Neornithes のクレード名が存在して、[冨田他 (2020) "恐竜類の分岐分類におけるクレード名の和訳について" では表に含まれない、これを区別する場合には「鳥」と「禽」を使い分けて新たに定義し直す必要があるかもしれない、とある] それをそのまま和訳した結果同じになったものの可能性がある。
青塚 (2017) で引用されている Larson et al. (2016) Dental Disparity and Ecological Stability in Bird-like Dinosaurs prior to the End-Cretaceous Mass Extinction
では Neoaves が現在と同じ意味で使われているので記事中の訳語の対応がよくない。
なお Larson et al. (2016) の論文は種子食の鳥が系統のどこに分布するか示されておりなかなか面白い、別の意味でも興味深いので一見をおすすめする。
小林 (2020) Birder 34(8): 30-32 でも Neornithes を新鳥類、また始祖鳥を含むクレードを Aves と呼んでいる (このクレード名については #ハヤブサの備考「鳥の起源と進化」の部分も参照)。複数の日本語記事で紹介されているため、"新鳥類" の名称はある程度市民権を得ている可能性があるが、ここで扱う Neoaves とは異なる概念であることに注意。
小林 (2020) の記事で引用されているのは Louchart and Viriot (2011) From snout to beak: the loss of teeth in birds
で、鳥類が嘴と砂嚢を獲得して歯を失うことにより成功した仮説のレビューとなっている。
Birder に紹介されている系統樹は (From snout to beak: the loss of teeth in bird: Figure 2) で見られる。
この文献を引用している Wang et al. (2017) Heterochronic truncation of odontogenesis in theropod dinosaurs provides insight into the macroevolution of avian beaks
でも、Yand and Sander (2018) The origin of the bird's beak: new insights from dinosaur incubation periods でも、
Louchart and Viriot (2011) で使われる始祖鳥を含むクレード Aves に代えて Avialae (鳥群) を用いているので、始祖鳥を含むクレードを Aves と呼ぶことが現在の世界の常識というわけではない (続きは #ハヤブサの備考へ)。
Stiller et al. (2024) との比較のために Wu et al. (2024) Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous
も紹介しておく。これは Aquaterraves の概念を提案して上記の 4. Columbaves と 5. Elementaves を合わせたものに対応している。Stiller et al. (2024) ではこれは単系統をなさないのでおそらく使われないだろう。
5. Elementaves に類似した分類に相当する Litusilvae を提唱しているが、ツメバケイ目の包含関係が異なり 3. Mirandornithes を 5. Elementaves の水鳥類と合わせて Aequorlitornithes と呼ぶなどかなり異なる結果となっているので別物と考えた方がよいだろう。
扱っているデータ量が Stiller et al. (2024) とは圧倒的に違うので、こちらの方がより信頼されることはないのではと思う。B10K が結果を発表する予定があったので先取権を確保すべく急いで出した論文かも知れない。
[ここから追記 2024.7.8 論文に基づく] その後再解析がなされた: Springer and Gatesy (2024) A new phylogeny for Aves is compromised by pervasive misalignment and homology problems 問題点が発覚。Aquaterraves は確認されず。
Wu et al. (2024) の使ったアルゴリズムでは例えば反復配列部位の処理が正しく行われず、種間で相同でない遺伝部位を拾い上げる。同じようにやってみるとまぜこぜの結果が出てきた。
この論文の fig. 1 (ASTRAL species tree based on Wu et al.'s cleaned dataset) を見るとさらに興味深いことになっていて、ノガンモドキ目がハヤブサ目から離れてしまった。Stiller et al. (2024) の解説で振った系統番号だと ノガンモドキ目 - 6a-2 (ネズミドリ目) - 6a-2 残り + 6b の ハヤブサ目以降 の順になっている。
ノガンモドキ目が実は Telluraves 祖先系統の可能性も考えられているのでこの結果は面白い [ただしデータ量は Stiller et al. (2024) よりもずっと少ない]。今度はタカ類とフクロウ類が離れる結果になり、以下の Hieraves もサポートされない (ただし矛盾するとまでは言えない)。Mirandornithes の位置関係も Stiller et al. (2024) と異なるのでどこまで信じてよいか?
Wu et al. (2024) の結果にはライバルグループから疑問が持たれ再検証が行われたのだろう。
この論文では研究者は適切な手段で正しさを検証することが本質的であると相当批判的に結んでいる。
Wu et al. (2024b) Reply to Springer and Gatesy: The impact of long branches and misalignments on phylogenetic analysis is minimal
が反論があり、指摘された部分を除いて再解析してみた。2つのアルゴリズム NJst と ASTRAL で結果が違う。指摘された部分を除いても NJst では形は変わらないが、ASTRAL では変化するので自分たちの使った NJst の方が信頼度が高い (あまり反論になっていない気がするが)。
ASTRAL の正確性はまだ検証が必要であると反論。これを見ると過去にもこのグループの間で批判が行われていた模様。Wu et al. (2024) のデータを使って ASTRAL で解析した系統樹がこれまでの理解と異なる結果になっているのでさらに原因究明が行われることだろう。
アラインメントの誤りはともかく、アルゴリズムの優劣 (さらにはコードのバグなどの可能性もあるだろう) を競い合うレベルになっておりこれは相当高度。Sibley and Ahlquist (1990) の DNA-DNA 分子交雑法時代と比較するととんでもなく高度が議論がなされていると思ってよい。
[追記終わり]
ライバルが巨大データを用いてスーパーコンピューターで時間を費やしている間に、より小規模なデータで結論の出せる部分を先に発表して名称の先取権を得ることも可能であろう。しかしこちらもスーパーコンピューターを用いている (ただし独自アルゴリズムの改良までは行っていない)。
いずれのグループにとっても公募提案の審査を受けて利用するような超大型スーパーコンピューターよりもまだ手軽に使える小型のスーパーコンピューターはこのような競争には都合がよいのだろう
(しかしそれはそれですごいレベルの競争であるが)。
Stiller et al. (2024) が種数を絞ったのもこのような熾烈な競争のためかも知れない。
この研究でも Elementaves に類似した系統が見出されたので、この系統の存在はおそらく支持されてゆくのだろう。
Wu et al. (2024) はタカ類とフクロウ類を合わせた系統として Hieraves の名称を提案しており、もし将来この系統が認められればこの名称が使われるかも知れない (B10K でもまだ判然としない)。
Hieraves の Hier- は学名では通常タカのことなのでそのまま訳せば "鷹鳥類" (なんだそれは?)。中国語風に訳せば "鷹型鳥類" みたいになるが、それでは Accipitriformes や Falconiformes の原意とほとんど同じになってしまう。
"鳥は恐竜である" ように、"フクロウ類はタカだ" と考えてよいのではないかとの名称意図が見えないこともない
(タカファンにはまぁ...構わないが、フクロウファンからは文句はないだろうか?)。
鳥類学では hier- は学名を作る際にほぼタカの意味で用いられるが、原意 hier-, hiero- ギリシャ語 hieros (神聖な) に立ち返れば「神聖な鳥」。「聖鳥類」でもよいかも知れない。英語でも hierarchy のような単語で使われ、鳥類学の学名での用例に詳しくない者はこちらの意味が先に出てくるのが普通だろう。
あるいは通常の hier- を含む学名を作る際にもそのような意味を想定しているかも知れない。
hierophant 最高祭祀 のような単語もあって、「最高位の鳥」の位置づけ (すごい) だと思えば古来から畏敬の念の対象であった通りでなかなかよい名前にも思える。
学問の一時的進展でカモの付近に置いたりしたのが多分よくなくて、古い図鑑を見るとカモ・タカ (含ハヤブサ)・キジ類と呼べるような配列になっている。現在ならばキジカモ類の仲間で、つまり家禽類や狩猟鳥の扱いに相当する。食用には向かないだろうがタカはどんどん撃ってしまっても構わない認識になってもおかしくない。こんな分類を考えたのは誰だ (笑)。
ほんの少し前までは猛禽類は原始的な系統の鳥で頭も悪く獰猛なだけと認識されていて、我々の頭の中にもこの印象がおそらくインプットされ、無意識のバイアスは保全や文化面も含めきっといろいろなところに現れていたことだろう。
今や分子系統学的にも古代からの認識通り最高位の鳥だったことが裏付けられ、まったく逆だった。
もちろん hieroglyph ヒエログリフ のことも忘れてはいけない。神聖文字とも訳されている [日本語の漢字を指して hieroglyph と言われる (だから日本語は難しいとか面白いとか) こともあって、まあそうかも知れない]。エジプトでは神の言葉とも呼ばれていた (wikipedia 英語版)。
我々が普通に使っている "a" の文字もワシの姿が由来で [この出所は、Jeff Watoson "The Golden Eagle" 邦訳と日本語版追記「イヌワシの生態と保全」文一総合出版出版 (2006) だが、調べてみるとエジプトハゲワシと書いてあるものが多い。ハヤブサ類を挙げてものも少数ある] 確かにタカ類と非常に縁が深い。「神の鳥」系統もよいかも知れない。
もう少し凝ってみると「霊鳥類」はフクロウ類にもふさわしく両方の系統を含むのによいかも。万物の霊長と並ぶ空の霊長だぞ、どうだまいったか (笑)。中国古典では「霊鳥」が現れ「霊妙な力をもつ鳥。瑞祥をもたらすめでたい鳥。尊く神聖な鳥」とのこと (霊鳥)。具体的な鳥には同定されていないようで鳳凰などともある。
正月には夢にも出てきて欲しい鳥。めでたいことこの上なし。
学術的な文脈で使うと「霊鳥類による霊長類の捕食」とか、巣ならば逆に「霊長類による霊鳥類の捕食」とか、何を言っているんだと言われそう (笑)。「霊鳥類学会」などできると実に紛らわしそうだが、蝶と鳥もすでに音の上では十分紛らわしいので (日本蝶類学会という組織もあって音だけではどちらかわからないかも) まあよいかも知れない (勝手に遊んでしまっているが...)。
さらに、英語ならば hier-aves と分けて発音すれば higher Aves と同じような発音になり、音の上では「高等鳥類」にも聞こえて印象もよい。このような言語的センスはぜひ競い合って欲しいところ。
含蓄のある命名の和訳は工夫を要することになるのだろう。ちなみにちなみにだが、Pluto に対する「冥王星」の訳名は野尻抱影が与えたとのこと。この名称は京都天文台 (現在は京都大学) ではすぐに採用されたが、東京天文台 (現・国立天文台) では英語のままの「プルートー」が用いられたとのこと。
当時は東京と京都で見事に競っていたよう。
カタカナ語が禁止された 1943 年に東京天文台も「冥王星」を採用したとのこと (wikipedia 日本語版より)。
なんだか「ネオアヴェス類」等の名前の話と似ているなあ...とふと思ってしまう。
和名は通称なので理屈の上では何種類もあってもよいわけだが、日本の鳥学関係者にも頑張って欲しいところ。
近年の複数の研究が示すように、フクロウ類の系統がカワセミやキツツキの系統に順次つながっているという Prum et al. (2015) 時代の見方
[例えば 山崎 (2019) Birder 33(1): 16-19 の解説参照。この中でもネズミドリ類は生態的にもあまり似ていないように見える]
は次第に支持が弱くなってきているのだろうか。ただし #フクロウ備考にあるようにフクロウ類とカワセミやキツツキの系統に共通のレトロトランスポゾンが存在するので系統的に関係していることは間違いない。
タカ類との関係もまだはっきりしていないので {タカ類 + フクロウ類} を単系統と認めるかはまだ議論が続くのだろう。
さらに重要な点は、この Wu et al. (2024) の研究では分岐年代がかなり古く、6600 年前の大絶滅 (K-Pg 境界) の前に全ての系統が出揃っていたことになって、大絶滅付近で大規模な放散があった現在では標準的な描像と異なっている。
大絶滅で一時停止はしたものの、ゆっくりとした進化と分化が進んでいたと主張しており、Stiller et al. (2024) とは大きく異なる点である。
この論文では化石証拠なども用いて、大規模な放散は隕石の衝突よりも鳥類・哺乳類 (8100-8600 万年前) ともに Angiosperm Terrestrial Revolution (Cretaceous Terrestrial Revolution) に関連しているとの議論をしている。隕石の衝突の影響は大したことはなかった (?)。
知る人ぞ知る「花に追われた恐竜」(NHKスペシャル 地球大進化 46 億年・人類への旅 2004) の現代版か?
[cf. 今更ですが「花に追われた恐竜」 せつなりつと (2020) に詳しい解説あり]。
Angiosperm Terrestrial Revolution にかかわる新しい論文もあるので引いておこう:
Benton and Sauquet (2021) The Angiosperm Terrestrial Revolution and the origins of modern biodiversity。
Llyod et al. (2008) Dinosaurs and the Cretaceous Terrestrial Revolution。
Dilcher (2000) Toward a new synthesis: Major evolutionary trends in the angiosperm fossil record と時期も合うので「花に追われた...」はこの説を大々的に取り入れたのだろう。
ということで、Stiller et al. (2024) は鳥類系統樹を改訂したこともあるが、Angiosperm Terrestrial Revolution は鳥類においては支持されないことをこれまでよりも強力に示したことが重要なのだろう。
「大絶滅で一時停止はしたものの、ゆっくりとした進化と分化が進んでいた」については、上記の鳥類論文でも書いてある通り哺乳類でも同様の主張がなされている: Liu et al. (2017) Genomic evidence reveals a radiation of placental mammals uninterrupted by the KPg boundary。
このあたりは隕石衝突が大絶滅をもたらしたか否かの従来議論の延長線上にあるパラダイムの違いなのだろうと理解しておく。
比較のために "正統派" な方も取り上げておくと、
Field et al. (2018) Early Evolution of Modern Birds Structured by Global Forest Collapse at the End-Cretaceous Mass Extinction
こちらは K-Pg 境界の隕石衝突と引き続く環境激変で森林が一度完全に失われ、樹上性の鳥も恐竜も姿を消し、現在の樹上性の鳥も地上性のものから改めて進化したとの自分には納得しやすい仮説。
Wu et al. (2024) の論文は ゲノム、化石、そして白亜紀後期における現生鳥類と被子植物の同時的な出現 (恐竜パンテオン 2024)
に日本語解説があって (鳥の名前がかなり間違っているが AI 翻訳も併用?)、「Hieraves の発見は、タカ目とフクロウ目の共通祖先が夜行性であった可能性を示唆している」とあるのだが論文になぜか見つけられない。
もしどこかに書いてあるなら、ものすごく大胆な (いくつも既知知見に反する) ことを言っているわけだが。当時は強い恐竜がまだいたので現在の猛禽類の祖先系統は夜行性だったとの解釈か (?)。書いてないがすごい大胆仮説を考えていたのかも知れない。さらに悪乗りすれば「ほら鳥類は肉食恐竜だと言っているだろうが。猛禽類はその肉食恐竜がそのまま生き残って進化したんだぞ」...一般的にはこちらの方が受けがよいかも知れない (?)。
それとももしかしたら AI が要約するとこういう解釈を付け加えてくれるのかも??
もし AI が与えた解釈であればこれはこれですごいことで、生物学者の推論能力を上回っている? (なんてことはないだろうが) ...本当のところはわからないが。
Hieraves はなんと wikipedia 英語版にすでに登場している。Houde and Braun (2019) Phylogenetic Signal of Indels and the Neoavian Radiation (こちらは B10K グループ) がこの系統をサポートする結果も出していたが名前は付けなかった。
Wu et al. (2024) は Braun et al. (2019) Resolving the Avian Tree of Life from Top to Bottom: The Promise and Potential Boundaries of the Phylogenomic Era
は引いているものの Houde and Braun (2019) は参照していない上にこの系統のサポートになる過去研究にも触れていない。皆が慎重に扱っていただけなのに突然現れた Hieraves をこのまま取り入れて大丈夫か?
[ここから追記 2024.9.16 論文に基づく]
Wu et al. (2024) の年代推定には問題があるとの指摘:
Claramunt et al. (2024) Calibrating the genomic clock of modern birds using fossils。
Wu et al. (2024) は年代推定に化石種 Ichthyornis dispar の年代を用いているが、Ichthyornis は Neornithes の直接の祖先でも姉妹関係にもないので Neornithes の起源の直接の年代推定には使えない。
Wu et al. (2024b) の反論も掲載されている: Reply to Claramunt et al.: Robustness of the Cretaceous radiation of crown aves。
Claramunt et al. (2024) はいくつかの化石の年代下限を無視している。自分たちには Claramunt et al. (2024) の結果が再現できない。
この論文に掲載されている系統樹では鳥類の大規模な適応放散は K-Pg 境界のはるか前で、K-Pg 大絶滅は系統樹の形のほとんど影響を与えていない。タカ類やハヤブサ類の系統、そしてスズメ目の祖先系統さえ K-Pg 大絶滅の前に出現していたとの大胆な解釈になっている。この解析では Wu et al. (2024) の系統樹を一貫して利用しており、Hieraves などの名称もそのまま使っている。
化石の年代下限をどのように取り入れるか、それらはあくまでわずかにサンプルされた点に過ぎないので確率的な扱いを取り入れるとどのように変わるかなども焦点になっているよう。
Claramunt et al. (2024) では化石の年代下限を厳格な値として制約を設けた結果と確率的扱いの両者の結果が示されており、前者でも多くの系統が K-Pg 境界前後に現れたことになるが、後者ではさらに新しい時期を示す推定となって Neoaves 出現は K-Pg 境界直前になる。
Wu et al. (2024b) では確率的な扱いは行っていないが、Ichthyornis の年代は上限ではなく下限を示すとの見解の相違を述べている。
(さらなる追記 2025.7 論文に基づく): Wu et al. (2025) New fossils imply a deeper origin of modern birds in the Mesozoic。こちらは引き続き鳥類の大規模な適応放散は K-Pg 境界のはるか前と主張している。
New fossils というのは Vegavis iaai と Asteriornis maastrichtensis とのこと。どちらも Galloanserae の古い系統と考えられているので、Galloanserae より以降の系統 (つまり Neoaves) は K-Pg 境界以前に現れた証拠がむしろまだ見つかっていない。
ここで Angiosperm Terrestrial Revolution のレビューとして引用されている論文は Benton and Sauquet (2022) The Angiosperm Terrestrial Revolution and the origins of modern biodiversity。
この論文でも鳥の証拠はそれほど出ていない。それぞれの系統の代表に現生種のイラスト (鳥ではノスリ類?) が挙げてあるのでいかにも古くから存在したように見えて紛らわしい。この論文の Fig. 2 で対数スケールで種数変化を表示しているが、一見 K-Pg 境界はほとんど影響を与えていないように見える。
図の注には extinct diversity (e.g. fossils) is not counted here とあり絶滅した種は数えない。つまりダチョウ? が生まれたら1種、次の現生種が出現したら2種、のカウントになる。
図だけから判断すると種数に影響を与えるような大絶滅はなかったように見えてしまうがこの定義のため。
鳥の出現年代の出典は Claramunt and Cracraft (2015) A new time tree reveals Earth history's imprint on the evolution of modern birds とのこと。この論文の主著者の Claramunt が 2024 年に Wu et al. (2024) を否定する論文を出しているので相互の論理関係はまずまず読み取れる。
さらに Benton and Sauquet (2022) が引いている (現生の鳥の直接の祖先系統ではないが) そのうが発達して種子を蓄えられるようになった化石証拠の論文は Zheng et al. (2011) Fossil evidence of avian crops from the Early Cretaceous of China。
Stiller et al. (2024) の鳥類新系統樹が出る直前に Angiosperm Terrestrial Revolution 仮説 + そのうを持つ鳥に似た恐竜化石の発見 + Louchart and Viriot (2011) が種子食と嘴、絶滅を免れた理由のアイデア が注目を集めたらしいことがわかる。
K-Pg 境界以前の Neoaves の確実な化石証拠が出れば状況が変わってくるだろうが、現状では K-Pg 境界以降に現生鳥類の大部分の系統が誕生したとみなしてよさそうに見える。
[追記終わり]
[2024.9 追記]「野鳥」2024 年 9・10 月号 (No. 872) p. 11 に鳥類系統樹が出ているので比較しておくと、この系統樹はおそらく日本鳥類目録改訂第8版の配列順と同じもの = IOC 13.2 を想定していると想像できるがツメバケイの位置を見ると Prum et al. (2015) が使われ続けている可能性が高い。
IOC の "A higher classification of modern birds (June 28, 2019)" では Prum et al. (2015), Suh et al. (2015) をベースとして、Kuhl et al. (2020) を少し取り入れているとのこと。Kuhl et al. (2020) を部分的に取り入れてツメバケイの位置を Prum et al. (2015) 時代から変えている。
「野鳥」誌の記事では日本鳥類目録改訂第8版の配列は Prum et al. (2015) と同じと想定してそのまま用いられている模様 (ツメバケイは日本産の鳥ではないので日本鳥類目録にあまり関係がない)。
この系統樹は 10 年近く前の知識に基づくもので多少注意して見ていただくとよいだろう。細かいところは意見の相違があるものの Stiller et al. (2024) と Wu et al. (2024) の結果は Prum et al. (2015) と異なる部分があるので IOC もいずれかの時期に入れ替えるだろう。
ツメバケイの入れ替えだけならば影響が小さいので IOC も簡単に取り入れたものと思われるが、2024 年の系統樹はかなりの順序変更を必要とするのでまだ本格的には取り入れにくいのだろう。
[追記終わり]
Birder 編集部 (2025) Birder 39(1): 38 に 特別展「鳥 〜ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統〜」の取材写真があり、ツメバケイ目とタカ目が隣り合っている拡大写真が紹介されている。何も議論の多い部分をわざわざ紹介しなくても... (笑) と思ってしまうが、この順序が見られるのはこれが最後の記念として実は奥が深いのかも知れない。真意は知らない。
これも後に追記: Chen et al. (2025) Towards a comprehensive anatomical matrix for crown birds: phylogenetic insights from the pectoral girdle and forelimb skeleton (preprint)
骨格形態学的特徴 (特に上肢と pectoral girdle 胸帯) による系統樹と近代的な分子系統樹が一致しない問題を解決できないかとの試み。系統に強く相関する形態形質は判定でき、重みを変えて系統樹を作ってみたが分子系統樹との整合性があまり高まらなかった。
多様な系統で形態の収斂進化が起きたためと推定される。古生物を骨格形態で系統解析する限界も現れている感じ。なお気になるタカとハヤブサはこの解析では比較的うまく分かれているが、どの分岐に収まるかを見ると分子系統樹との整合性は必ずしも良くなくそれほど成功していない印象。
相互羽繕いの有無と系統の関係を調べたもの: Jensen et al. (2023) The selfish preen: absence of allopreening in Palaeognathae and its socio-cognitive implications
古口蓋類 Palaeognathae ダチョウ類 では詳しいビデオ観察の結果相互羽繕いが見つからなかったとのこと。相互羽繕いは多くの科で記録されているが、Galloanserae キジ類 + カモ類 の事例は少ないとのこと。
ハゲワシ類が相互羽繕いをする印象はあまり持っていなかったのだが映像記録がある。#クロハゲワシ備考 [首の羽毛を失う理由] でズキンハゲワシの事例がある。同じく [ハゲワシ亜科の系統分類] でクロコンドル (新世界ハゲワシ類) とカラカラが異種間の相互羽繕いが知られているとの文献を紹介。
Bearded Vulture pairs in captivity are already busy with the new breeding season に人工繁殖中のヒゲワシの相互羽繕い。
ヘビクイワシでも相互羽繕いらしい写真を見たことがあるので、タカ目で相互羽繕いは古い系統でも一般的に存在するのだろう。
#ハチクマの [マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] のハチクマ親子の相互羽繕いから重複掲載しておくと、鳥類全体で相互羽繕いを調べた研究: Kenny et al. (2017) Allopreening in birds is associated with parental cooperation over offspring care and stable pair bonds across years。
(韓国のハチクマの繁殖に登場する文献の再掲) タカ類も含めて猛禽3系統いずれも相互羽繕いが意外に知られている。
広義ハイタカ属など日本で通常見られるタカ類では記録例がない (日本はタカ類の発祥の地から遠く、種多様性があまり高くないことを思い出そう) ので例外的に見えるらしい。社会性のある種 (モモアカノスリなど) ではあまり系統に関係なく記録されているよう。
ハゲワシ類など社会性のある種で多く見られているが、ハゲワシ類は想像以上に知的である可能性も考えられているので矛盾しないかも知れない。
ちなみに preening (羽繕い) と grooming (毛づくろい) はほぼ同義のように使われるようで、まとめて用いる場合は grooming と呼ばれることもある: 参考 Bush and Clayton (2023) Grooming Time Predicts Survival: American Kestrels, Falco sparverius, on a Subtropical Island
アメリカチョウゲンボウで毛づくろい頻度が高いほど生存率が高かった報告。
他の論文でもどちらも使われている。鳥を指して "毛づくろいしている" と表現された時、「鳥では羽繕いと呼ぶ」などと用語を訂正しがちだがあまり気にする必要はないかも知れない。言うまでもないだろうが鳥類と哺乳類の収斂進化の一例だろう。
McTavish et al. (2025) A complete and dynamic tree of birds 基本的には過去の文献からまとめたものだが、今後はこのように計算機にとって扱いやすく更新の容易な系統樹ツールが用いられることになるのだろう。さまざまな階層の系統研究が発表されているので全貌を調べるのはもはや人力では限界があり計算機に任せるようになってゆくのだろうか。
大きな部分の系統の扱いに違いがあるが、Stiller et al. (2024)、Wu et al. (2024)、Prum et al. (2015) はおおむね同じような系統関係を再現している。Jetz et al. (2012) The global diversity of birds in space and time (オープンアクセスでない) の系統樹はやや違いが生じている。
Clements 2021 では Muscicapidae (ヒタキ科), Turdidae (ツグミ科) は単系統をなしていなかったが Clements 2023 で解消された。Laniidae (モズ科) が単系統になっていない問題はまだ残っているなど。
Jetz et al. (2012) の影響を受けた分類体系は最新のもの違いがあるかも知れないと把握しておくとよいだろう。
示されている多様性の分布地図は基本的に eBird のデータをもとにした多様性評価で、例えば中国などの多様性が適切に評価されているかやや怪しいかも。
Stiller (2025) Synthesizing decades of research into one tree for birds が McTavish et al. (2025) へのコメントを述べている。この研究がこれまでのものと異なるのは個々の系統でなく全部を扱って data-centric approach (あるいは data-driven science) であることなど。手間はかからないかも知れないが、サンプリングが圧倒的に不足している系統も多く、全部を同一の枠組みで扱うのことに多少難色を示しているのだろうと読んだ。
日本の鳥ではないためこの項目にしか登場しないのでここに含めておく。シギダチョウ科のゲノム解析が行われて分子系統樹も新たに描かれ、いくつかの種や属名の変更が予想される (種に昇格のものもある):
Musher et al. (2024) Whole-genome phylogenomics of the tinamous (Aves: Tinamidae): comparing gene tree estimation error between BUSCOs and UCEs illuminates rapid divergence with introgression (preprint)
著者にはタカ類最新分子系統樹を解明した Catanach も含まれている。理論的に考えられる通りゲノムを読んで長い UCEs を用いるのが科内レベルの分子系統推定には一番精度が高い結果が得られたとのこと。
複数の遺伝子を用いる伝統的方法は意外にも間違い率が高かった。
Neoaves 関係でヒットしたさらなる情報: Ng et al. (2023) Gene purging and the evolution of Neoave metabolism and longevity
分枝鎖アミノ酸 (branched-chain amino acids, BCAA) ロイシン、イソロイシン、バリンが筋力増強や疲労回復に有効であることはよく知られているだろう。しかし筋肉中のこれらのアミノ酸を直接代謝すると酸化ストレスが発生し、血中濃度が高いとインスリン抵抗性が増して寿命が縮むという。
Neoaves ではこれらのアミノ酸の輸送にかかわる遺伝子を選択的に失うことで代謝経路を変え、これらの弊害を回避して寿命も伸ばしているとのこと。エネルギー供給は肝臓で作られたケトン体で行うという想像通りのことが書いてある。
なお鳥の "ミルク" には炭水化物はほとんど含まれない。哺乳類でもミルクで子育てする鳥でも成長にケトン体が大きな役割を果たしている。ケトン体はかつては悪者にされていたが Kolb et al. (2021) Ketone bodies: from enemy to friend and guardian angel のように評価は変わってきている。
論文でも鳥のことを知ると医学にも役立つかも、のような書いてあるがここまで説明すれば後は想像にお任せしたい。
「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) p. 143 にハトの飼育について述べられていて、トウモロコシは炭水化物を多くふくみハトをふとらせ... 他の食物でタンパク質や脂肪の多いものがそれぞれ有益な作用を示すことがすでに記されていたのを見つけた。
何だはるか昔からわかっていたのか (笑)、太る原因は脂肪との説はどこから出てきたのかと思ってしまった。
Ng et al. (2023) に戻ると飛行への適応のための強い選択圧で遺伝子がこれほど変わる。鳥類の遺伝子はどれもニワトリ (Neoaves でない) と同じようなものと思ってはいけないらしい。
Neoaves でないカモ類が羽ばたき飛行で長距離を渡るのは大変だろうなと感じるが、Neoaves ではそれがより容易にできるようになったと思ってもよいだろう。カモ類も渡りをするが、本格的な渡りは Neoaves で一層洗練されたものになり、ソアリングのような効率のよい渡り形態も一般的になったのだろうか
(Neoaves 以外でソアリングで渡りをする鳥類を思いつかないがこの見方であっているだろうか → クロエリサケビドリ Chauna chavaria Northern Screamer が行うことがわかった。#ノスリ備考 [呼吸以外の気のうの機能] Schachner et al. (2024) に含まれていた)。
哺乳類に比べて鳥類のタンパク質をコードする遺伝子数がかなり少ないことがわかっている。カナリアで 15281、ヒトで 22389。ほぼ同じ数とされていたニワトリゲノム初解読時代からだいぶ見方が変わっているらしい。遺伝子を失うこと自身は悪影響を与えていないらしい。
もっともこの数字はヒトゲノム初解読 (2001) 時代のヒトでも同様で、それ以前は 8-14 万と見積もられていたのが解読されて発表時は 31000。2年後には 25000 に減少し、ショウジョウバエの2倍にも満たなかった (数字出典は「本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」ブランバーグ 2006, p. 64)。万物の霊長のはずなのにいったいどうなっているんだ、となった。
ニワトリゲノム初解読時代はほぼ 25000 が脊椎動物共通の (必要な) 遺伝子セットと考えられたこともあったが、この考え方もどうも正しくなかったようだ。
代謝のように複数の遺伝子がかかわるネットワークが複雑系としてどのように進化するかなどの理論も引用されている: Prud'homme et al. (2007) Emerging principles of regulatory evolution
この論文ではハエの翅の模様の進化パターンなども挙げて紹介されている。形態進化は遺伝子の調節部位のネットワークの機能的変化で起きる圧倒的証拠が積み重なってきている。この機構による進化はアミノ酸変異の場合の適応度低下の影響をかなり免れることができる。
鳥の模様や形態の進化などもおそらく同じような機構が関係しているだろうし、代謝機構ネットワークのようにゆとりのある機構が存在するものにはこのような進化が比較的短期間でも起きるのだろう。Ng et al. (2023) に書いてあることをちょっと補えば鳥が尿酸排泄の方向の代謝経路を選択していったことも同様に説明でき、水分喪失を避けるとともに尿酸による抗酸化作用も役立っている (#カワウの備考も参照)。
複雑系の特徴である創発 (emergence) が進化のさまざまな過程で役立っているのだろう。断続平衡 (punctuated equilibrium) 的に見える現象も複雑系の特徴で説明できるかも (生物進化に限らなければたくさんみつかる。以下 *2 のゲルマンの話も参照)。
Neoaves 関係でもうひとつ。こちらも難しい論文だが Castiglione et al. (2020)
Adaptation of the master antioxidant response connects metabolism, lifespan and feather development pathways in birds
では Neoaves の段階で酸化ストレスに関係するマスター遺伝子 (KEAP1) の機能に変化があり、代謝率が高くなると酸化ストレスが発生して寿命が短くなるトレードオフ問題がそれまでの系統に比べて改善され、高い代謝率と長い寿命を両立させることができるようになった。
興味深いことに fig. 1 を見ると我々哺乳類も古い系統のままで、脊椎動物の中で Neoaves のみがこの能力を得たことがわかる。Neoaves が脊椎動物の中で一番進化したグループに見えてしまう。
抗酸化物質のカロテノイドを羽毛の色彩に用いるのは生存に不利になるため性選択において「正直なシグナル」としばしばみなされるが直接的な実験的証拠はまだまだではある。それがあるとすればそのしきい値が Neoaves になって大幅に上がった。すなわちそれまでの系統よりも抗酸化物質を豊富に色彩などの表現形に使えることになった。
実験的証拠が得にくいのは Neoaves の生理的機能に十分な余力があって、例えば放射線事故の影響も想像したほどはっきり現れない結果にもつながっているのかも知れない。
生活史戦略も変わってくる (生存率が低ければ多産せざるを得ないが、より少産の戦略が有利になってくる。いわゆる r/K 戦略の問題。だからこそ理不尽に見えるイヌワシの兄弟殺しのような現象も生じ、進化的には親が介入しない戦略を取らざるを得ないわけだろうが...)。
(適当に読みすぎかも知れないが) 表現形の自由度も増して色彩も鮮やかに、自由度が広がったことで適応放散にも役立ち、より広い領域で活躍できるようになったということだろう。
Neoaves 以前の系統で赤系統を使っている鳥を調べれば赤の構造色が見つかるかも知れない。誰か調べていないだろうか。
青塚 (2023) Birder 37(8): 32-33 で恐竜では羽毛にカロテノイドがあまり使われていなかったと推定する研究が紹介されている: Davis and Clarke (2022)
Estimating the distribution of carotenoid coloration in skin and integumentary structures of birds and extinct dinosaurs
この系統樹 (非スズメ目のみ) を見ると (現生鳥類では) Neoaves 以前の系統では羽毛着色にカロテノイドはほとんど使われていない。フラミンゴのように資源が豊富な場合を除き、貴重な資源を使い捨ての羽毛に大量に用いるのはもったいない?
Telluraves で皮膚着色も含めた全体的に利用率が一段と高まっている。一部の系統 (特にキヌバネドリ類、キツツキ類など) では羽毛にも利用されている。猛禽類系統では羽毛の着色は見られないが皮膚裸出部、特に足の着色は多く見られる。
顔の着色はタカ・ハヤブサ類では多く、羽毛にはおそらく隠蔽色の必要性や耐久性などの制約もあって使いにくいが、つがい相手などに見えやすいところに投資か。嘴や虹彩の着色もタカ・フクロウ類の特徴。なるほど。猛禽類の "おしゃれ" 感覚が何となくわかるかも (?)。
虹彩の着色は獲物への威圧感とも言われることがあり、もちろんその意味や巣を守る時に捕食者の威圧感などの効果もあるだろうが、これだけ多系統に普遍的に存在すると別の意義もあってもおかしくなさそう。カロテノイド色彩が「正直なシグナル」として働くならば健康状態を表すにも使えるだろう。
猛禽類の足はなぜ黄色いのか、そういう疑問も聞いた覚えがないが生物学的には面白い問いなのかも知れない。
Why do so many raptors have yellow feet? (BirdForum 2014)
と気にしていた人はあるようで、この時点では有力な答えは出ていない (研究もなされていない?)。
目につく2つの仮説は、ひなが黄色い足と爪で捕食者を威嚇する。なるほど。これは猛禽類に共通する特徴だろうし、幼鳥で足が黄色い理由になる Hawks and yellow legs (BirdForum 2011)。
2011 年の時は紫外線でどう見えるかが話題になっていたが、後半でひなが足で攻撃してくることが述べられている。
虹彩の色と同様、選択においては栄養状態のシグナルか。もちろん両方の働きをしていてもよいだろう。
2014 年の記事にあるようにアカアシチョウゲンボウの足の色はこの極端な場合と考えてよさそう。
Understanding the Bird of Prey (Nicholas Fox 1995 原著, reprint) がこの問題を扱っているとの記述があったが、今の円レートではちょっと衝動買いしにくい (笑)。
他に猛禽類では繁殖期の化粧色は足やろう膜、虹彩には現れないが目の周囲の皮膚の色が鮮やかになるとの話もみかけた。
そういえば日本のカッコウ類も足が黄色いがこれもタカへの擬態? #カッコウの備考 [カッコウのタカへの擬態] を参照。黄色い足も擬態項目に挙げられている。
カッコウ類にそれほど強力な爪はないだろうし、爪を誇示するためには使えないように思える。
ということは猛禽類の成鳥でも黄色い足だけで威嚇効果が期待できるのか?
あるいはカッコウ類の祖先が猛禽性を持っていてその時の性質が簡単に顔を出す? 単純にカロテノイド色彩の「正直なシグナル」でよいのかも知れないが。
Davis and Clarke (2022) では系統樹の形が他のものとまた微妙に違うので周囲の鳥の絵との対応がどうもすっきりしない系統もある。タカとフクロウの間の絵はヨタカだろうか?
ベースとなっている Thomas et al. (2014) Ancient origins and multiple appearances of carotenoid-pigmented feathers in birds
も役立ちそう (オープンアクセスではないが)。羽毛着色のみだが系統樹はこちらが見やすい。Davis and Clarke (2022) に含まれないスズメ目はこちらにあり、羽毛着色はスズメ目で圧倒的に増加したのがわかる。
カロテノイドかどうかは高速液体クロマトグラフィー (HPLC) とラマン分光で科レベルで確認したとのこと (後者は非破壊的に判定できる。ラマン散乱はコヒーレント散乱云々のところで出てくるもう一つの概念分類で、波長が変わるコヒーレントでない方の散乱になる。ややこしい)。見た目の色との整合性がよいので種レベルのカロテノイド有無の判定では写真を用いたとのこと。
羽毛のカロテノイド着色は 13 目で独立に進化した結果になった。オウム目はハヤブサ目同様羽毛にカロテノイドを使っていない系統に分類されているが、オウム目全般に対する文献による情報由来なので間違いがある種もあるかも知れないとのこと。
カロテノイドかどうかの判定が意外に難しいものがある。
ジャノメドリ Eurypyga helias Sunbittern の初列風切、
ヒノドハチドリ Panterpe insignis Fiery-throated Hummingbird の喉の赤色などにはカロテノイドが検出されず。
キンケイ Chrysolophus pictus Golden Pheasant の黄色はラマン分光では検出されたが HPLC では検出されず。化学形によって抽出できないものもあるらしい。
サザナミオオハシガモ Malacorhynchus membranaceus Pink-eared Duck のピンク色の "耳"、ベニキジ Ithaginis cruentus Blood Pheasant の血のような胸、
ヒムネバト Gallicolumba luzonica Luzon Bleeding-heart の胸の赤色、アメリカササゴイの粉綿羽はいずれもカロテノイドだった。
ニシアマサギの着色にも含まれており、サギ類は比較的普通に使っているよう。
個々の種のデータを見るとやはり日本と共通種が少ないので、個々の事例をカロテノイドかどうかを判定するのは少し注意が必要そう。スズメ目はほぼ見た目通りに考えてよい。世界のレンジャク類は3種とも過去研究でカロテノイド着色と確認されている。他の分類群では必ずしもそうではない。
例えばアオショウビンの褐色にはカロテノイドが含まれていないがアカショウビンはどうなのかはこの研究では直接的にはわからない。系統解析ではアカショウビンはカロテノイドでない判定を行ったデータが使われている。嘴と足以外はそれほど赤くないので羽毛には使っていないかも知れない。実際には誰かが測ってみるまでわからないだろう。
コアオバト Treron vernans Pink-necked Green Pigeon では含まれている。
古い系統のものほどカロテノイドが含まれていないものが多いので、黄色・褐色系統は多分違うと考えた方が当たってそう。例えばヨーロッパムナグロの背中には含まれていない。
カンムリヅルの黄色の尾にも含まれていなかった。アカオネッタイチョウの尾は含まれている。
ショウジョウトキ Eudocimus ruber Scarlet Ibis はカロテノイド。
ヒオドシジュケイ Tragopan satyra Tragopan satyra は赤でも含まれていなかった。
アメリカホシハジロ Aythya americana Redhead も含まれていなかったのでホシハジロもそうだろう。カモ類で現在知られているのはサザナミオオハシガモの1例のみとにこと。ホシハジロぐらいの色彩だと明らかな構造色のカモの頭の色から連続的に変化しても作れそうな感じもする。
作業そのものは楽しそうだが生物の研究はなかなか大変そう。
Neoaves 関係でヒットした2本の論文ともたまたまその領域にターゲットを絞って研究した結果かも知れないが、いずれも酸化ストレス関係であることが興味深い。Neoaves の出現は (他の要因もあるかも知れないが) 酸化ストレス克服を一段高めた新グループの鳥類と見てよいかも知れない。"高等な" 系統の鳥類の生理・生態を考える上でもおそらく重要なのだろう。
現生の猛禽類のような高度な身体・知的能力の必要な鳥は Neoaves まで出現できなかったかも知れない。さらに Telluraves でもう1段階の飛躍があるようなので、本格的な猛禽類の出現はここまでお預けかも (本格的でない猛禽類への進化はそれ以前にも挑戦があったのかも。#カッコウの備考参照)。
Neoaves への進展につながる変異は鳥類の何系統で独立に発生しているような事象ではない。鳥類進化における非常にまれな特異事象なのだろう。
肉食恐竜がそのまま残っていたとしてもすぐに猛禽類になれるわけではない、きっと。
これに関係する興味深い発見があった。Clark et al. (2024) New enantiornithine diversity in the Hell Creek Formation and the functional morphology of the avisaurid tarsometatarsus
6800-6600 万年前の enantiornithine birds (エナンティオルニス類。歯を持つものが多い) の化石で現代の猛禽類に似た部分骨格 (tibiotarsus 脛足根骨) が見つかり、これまで原始的と一般に考えられていた enantiornithines (この用語は適切でなく enantiornithean を使うべきとの指摘もある。wikipedia 英語版より)
の生態が想像以上に多様だった可能性を示唆するとのこと。この系統は K-Pg 境界の大絶滅で絶滅したと考えられている。
enantiornithines に肉食のものがあったとの推論は Sanz et al. (2001) An Early Cretaceous pellet にあり、ペリットと考えられる化石証拠によるもの (wikipedia 英語版より)。
もう少し新しい論文では Miller et al. (2024) Synthetic analysis of trophic diversity and evolution in Enantiornithes with new insights from Bohaiornithidae の総説的なものが読め、脊椎動物食 (魚食も含まれる) の系統 (特に新しく出現した Avisauridae のクレード) の存在を積極的に支持している。
Clark et al. (2024) の発見から近代の猛禽類に近い生態を持った古い系統の鳥類はすでにあったのだろうか。
ただ証拠が tibiotarsus の形態なので、現代の鳥では猛禽類に似ているためこのような推定となった部分もあり、足である程度の重量のものを掴んで運ぶ鳥が本当に出現していたか (現代の鳥では Neoaves の中でも Telluraves に限られる)、猛禽類的な足の使い方をしていたかなど今後も議論の対象となるのだろう。
Neoaves と別のクレードでさらに以前に似た進化はあったのだろうか (DNA を調べることはできないので現代の鳥と同等の議論はできないが)。猛禽類的な足の使い方を進化させていたならば、足でものをつかむ現代の Telluraves に相当する猛禽類的でないグループもあっておかしくないように思える。Miller et al. (2024) の解析は多少答えてくれている感じもする。
猛禽類であることが可能な系統や遺伝的な必要条件を考える上で面白い題材と思える。
Duchene et al. (2025) Drivers of avian genomic change revealed by evolutionary rate decomposition これまた難しい論文だが B10K の成果の一つ。近代の鳥の進化はどの系統・どの時期が速かったか、それを促した要因は何かを広範囲の系統を網羅した全ゲノム解析から分析したもの。
それぞれの性質との相関はぱっと見てよくわからない (世代の長さやクラッチサイズなど) 感じもするが、遺伝子レベルで見るともう少し見えてくる。K-Pg 境界の大絶滅の後、Neoaves はリボゾームの効率が高く新しく生じた広大なニッチに適応放散することを可能にした可能性がある。適応放散後は進化速度が低下したという。
微小染色体 (microchromosomes) の急速な変化も K-Pg 境界後の特徴の一つで変異率すなわち進化速度の加速に役立っていると考えられる。ダチョウなどの基本形は微小染色体の多い染色体数 2n = 80 だがいくつかの系統で大きく変化しており
(cf. [タカ類の初期の適応放散] の項目のタカ・ハヤブサ類などやオウム類 [オウム類・ハヤブサ類の年代推定] など参照。タカ類では 2n = 66-68 が標準的だがミサゴは 2n = 74、オオタカは 2n = 78、ヒメオウギワシは 2n = 54 とかなり異なるものがある。ハヤブサ類でも違いが大きく数がかなり減っている)
急速な進化による適応放散を可能にするメカニズムの一つと考えられる。
この研究で微小染色体全般に GC 含量 (DNA 塩基中のグアニンとシトシンの比率。wikipedia 日本語版も参照) が多いことが確認された。また大型染色体を構成する要素 (building blocks) となる。微小染色体が大型染色体に融合すると大型染色体の方が再構成を起こしにくく、また転写頻度が下がるとのこと (つまり小型染色体の存在が進化速度を速める機構となり得る)。
いずれも相互に関係しているので#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] など盛んに進化を起こしていた時期も参照。
Duchene et al. (2025) では現在の主な科が揃って以降の進化速度は落ち着いているとのこと。
またアホウドリ類、タカ目の3科で代謝などにかかわる遺伝子の進化速度が大きく大型化を可能にしたなどの推論も示されている。ゲノムデータが膨大でまだまだ相関などから手がかりを掴みつつある段階だが他の研究とも合わせて次第に描像が現れつつある感じ。
備考:
*1: 南半球3大陸で近代的な陸鳥 [Kuhl et al. (2021) の 6. 7.] が進化したらしいことについては Ericson (2011) Evolution of terrestrial birds in three continents: biogeography and parallel radiations
の研究を参照。現生鳥類の遺伝情報をもとに組み立てたものだが、オーストラリアでスズメ目とオウム類が生き残り (現生鳥類のデータをもとに記述するため「生き残る」のような表現になる)、南アメリカからハヤブサ目とノガンモドキ類、
アフリカからはより多くの系統でブッポウソウ類 + オオブッポウソウ、キツツキ類、フクロウ類、ハヤブサ目を除く昼行性猛禽類、新世界ハゲワシ類、キヌバネドリ類、ネズミドリ類が生き残ったとされる。
もちろんこれら3大陸にいろいろなグループが分布するまでの過程があるわけだがそこまでは対象にしていない。
この意味では近代的な陸鳥はすべて南起源と考えてよいわけであるが、アフリカで主に放散した系統を Afroaves、それ以外を Australaves とすれば概念的にはまとまったものになる。
おそらくあまり想像されないであろうが、スズメ目の起源はオーストラリアと考えられる。
これをテーマにした Tim Low "Where Song Began" (Yale University Press 2014) という興味深い本が出ている。スズメ目はなぜアフリカやユーラシアでなくオーストラリアで適応放散したのであろうか。
ハヤブサ類・オウム類・スズメ目が近縁であることがわかってきた時期に並行して書かれた本とも言える。
副題が "how they changed the world" とあり、もしスズメ目が生まれなければ、世界は我々が現在見聞きするものと大きく違っていたかも知れない。
現在日本野鳥の会会長の上田恵介氏が 1997 年に著した対談も関連して興味深いだろう。
生物のサバイバル戦略 - 共進化。
「鳥がいなければこの世界はどれだけ単調であっただろう」などもよく言われるが、記憶能力の高い鳥がいなければ世界もまったく違っていただろう。スズメ目のアフリカ進出とヒトの進化も時期的には重なっていて、あるいは言語の進化なども含めて関係があるのではと思ってしまう。
今後も「野鳥」誌で上田氏の話を読めるかも知れない、いや期待したい (しかしあまり大風呂敷は広げにくいかも知れないが...)。
オーストラリアの鳥は他大陸に比べてより知的で長命の傾向があるとしている。
世界のどこよりもオーストラリアでは鳥が生態系を形作っており、行動も多様である。
北半球の住人はどうしても北半球にバイアスをかけがちでオーストラリアでの進化に気づきにくい。
"Where Song Began" の内容を一部紹介しておくと、鳥の進化については
当時の欧米の知見から Ernst Mayr の大御所の
見解による、スズメ目などの新しいタイプの鳥は北半球で比較的新しく生ま
れて、空白だった南へと進出していったとのパラダイムが広く受け入れられ
ていて、それに対する反証も多少はあったものの、Sibley による
DNA-DNA-hybridization による系統の見直し、その後の塩基配列から
より直接に系統関係が明らかにされる中で、このパラダイムが書き換わっていった。
欧米のデータだけを見ているとスズメ目は最近にしか化石に現れないので、
新しく生まれた (創造説によれば人間と一緒にあるものは最終段階で創ら
れた) と考えるのももっともだが、現在のスズメ目の共通祖先に相当する
系統がオーストラリアの鳥だった (コトドリ、ニュージーランドの wren
など) とのことで、スズメ目はオーストラリアで生まれて長い進化を経て
様々に分化し、その後北半球へと分布を広げた。そして北半球の在来の
鳥を圧倒していった描像が明らかになってきたことが描かれている。Ernst Mayr は新しい
研究を高く評価しつつも自説を生涯曲げなかったとのこと。
これらとさらに共通する祖先を持つグループがオウム類やハヤブサ類。
コトドリの歌 (模倣) は最上のものとみなされているが、オウム類の
知性とともに、何千万年もの間オーストラリアの鳥が地球で最も
知的な動物だった可能性もある (これらの部分についての知見は後に紹介するオウム類の祖先と
思われる化石種以降も参照。オウム類はかつて北半球にも広く存在していた証拠がある)。
その後進化したスズメ目に比べて、
これらの祖先型の鳥は興味深いことに鳴管の構造はより単純なのに
出す音はもっと多彩である。その後進化したスズメ目は種認識 (種分化)
のためにそれぞれは狭い種類の範囲の音しか出さないようになった?
音声模倣能力のある鳥は知的能力も優れている?
オーストラリアで進化した鳥はたいへんのんびりした生活史で、
卵の孵化や成熟などに大変時間がかかる (小鳥なのに成熟するのに7年かかるのもある)。
北半球でその後進化して逆にオーストラリアに入ってきた種類はこれが早い。
北半球の生存条件の過酷さ、渡りの必要などで生活史を急ぐ必要が
あるのでは。しかしオーストラリアの鳥は個体としては大変強力で、
ニュージーランドの Kea (ミヤマオウム) は有名だが、カササギの破壊力なども
すさまじい。また鳥のサイズもスズメ目としては大変大きい。
婚姻形態も北半球の鳥に比べて多様。北半球の鳥だけ見ていて
鳥類の一般的特性と考えるのは誤解かも知れない。
音声学習をする動物は非常に限られている。もしスズメ目が
いなかったら世界の音ははるかに単調なものだっただろう。
鳥の声は西洋音楽の音階に近い音程が多く (オクターブを使う
鳥もある)、音楽における美意識の根底に関係があるかも知れない
(補足私見: 収斂進化かも知れないが)。
なぜオーストラリアだったのか (なお当時はゴンドワナ大陸の一部だった。
南極大陸とつながっているとはいえ寒冷な部分で実質上隔離されていた)
については、6600 万年前の隕石衝突が北半球だったために、大絶滅を免れたのが
南半球だったこと、その後小型哺乳類による捕食の影響を受けずに "のびのびと" 進化した
可能性が挙げられている (補足私見: いたずらに競争をさせれば最終的によいものが
生まれるというわけではないだろう)。
スズメ目ほど証拠は明確でないものの、
いろいろな種類がオーストラリア由来と考えるともっともらしいとのこと。
北からオーストラリアに進出してきたムクドリの仲間は非常に粗雑な巣を
作ってよく落ちる。これはムクドリの仲間はもともと隙間に
営巣して丸い巣を作らないのが、樹洞などの制約のために巣作りをする
ようになったもののまだうまくないらしいとの推測が出ている。
北半球とオーストラリアに同じ植物がある (途中に空白がある) ことが
謎だったが、シギ類が種子を運んでいる可能性が示唆されている。
胃内容を調べてみると結構種子が見つかるとのこと
(なおこのあたりは近年渡り鳥による長距離運搬としてよく研究されている)。
本のタイトルもなかなか洒落ていて、地球で「歌」と呼べるものが誕生したのはどこだろうかと問うている。もちろん他の鳥類や他の動物も声を出すが、人類の「歌」の出現するはるか以前のスズメ目が生まれなければ多様で華麗な歌声を聞くこともなかっただろう。
スティーブン・フェルド Steven Felt 著; 山口修ほか訳「鳥になった少年 - カルリ社会における音・神話・象徴」(平凡社 1988) という書物もある。現地の鳥の声がメッセージ伝達に使われるとのことで、「鳥の歌」からヒトが進化の過程で学んだこともあるのではないだろうか。
Steven Felt の研究のきっかけについては 宮沢賢治の宇宙 編集日誌 の2000. 8.10 編集日誌 のところでも触れられている。
猛禽類の解説部分でスズメ目の出現に触れる形になるがタカ類をはじめとする近代的な陸鳥の進化を見る上で南半球の果たした役割の大きさを改めて認識しておきたい。
この話とは直接関係はないが、12000 年以上前に作られた猛禽の声をまねたらしい笛が発見された報告がある。Davin et al. (2023) Bone aerophones from Eynan-Mallaha (Israel) indicate imitation of raptor calls by the last hunter-gatherers in the Levant
鳥の声を通信などに用いるのは極めてあり得る感じがする。
*2: ゲルマンは将来は鳥類学者 (または言語学者か考古学者) になりたかったが、それでは貧乏生活になると親に諭され、物理学の道を歩んでノーベル賞も受賞、というレベルの話ではなく別人であればそれぞれノーベル賞になりそうなぐらいの多くの業績を残している
(Murray Gell-Mann)。
ちなみに鳥類化石に革命を起こした古生物学者 Xing Xu 徐星 はまったく逆だったという (「羽: 進化が生みだした自然の奇跡」より)。
ゲルマンの著書には有名な「クォークとジャガー: たゆみなく進化する複雑系」(The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex 1994; 野本陽代訳 草思社 1997) があり、「選択と適応度 (生物の進化などで働いている選択)」「多様性と持続可能性 (脅威にさらされている多様性)」の章もある。
今となっては古典となっているが、彼自身も「世界がなぜこのようになっているのか」を説明したい望みがあったのだろう。また生命へのまなざしも彼自身のサブテーマの一つとして息づいていたことがわかる。
次に出てくる複雑系研究で有名なサンタフェ研究所の設立者のひとり。
あるいはこの「鳥類系統樹2024」の研究グループにゲルマンの若い時の夢を叶えようとした人がいたのではないだろうか。
複雑系と生物進化、生物多様性にかかわる日本語の本では「持続不可能性」(Simon Levin サイモン・レヴィン著 原著 1999 重定南奈子・高須夫悟 訳 文一総合出版 2003) がある。
これも今となっては古典かも知れないが、ここで述べている話にも関係するので少し紹介しておこう。
文一総合出版がなぜこの書籍を取り上げたのかはよくわからないが、「環境保全のための」の部分だけを見て内容を読むとちょっとがっかりするかも知れない。基本的には複雑系として生態系を考える理論的基盤を一般向けに解説したものと考えるのがよいだろう。
当時は「べき乗則」がまったく無関係に見える事象 (例えば地震の規模と頻度の関係など) になぜそれほど普遍的に成り立つのかに関心が持たれていた。種数面積関係も生態学で最もよく知られた関係の一つであって保全生物学でも重要な意味を持つが、この関係がなぜ生じるのかは必ずも自明でない。
複雑系の法則性を考えることでこれを説明できるのではないかと考えるのは自然な発展方向だろう。
ここではこの話は深入りはせず、Neoaves 関係で出てくる遺伝子の調節部位のネットワークなどの複雑系の進化をどう理解すればよいかの方面から取り上げる。
ご存じのように生物進化はさまざまな変数 (古典的には嘴の長さや高さ、遺伝子レベルだと例えば調節部位の働きなど) で表される適応度空間の中を変異の結果で移動するうち、より適応度の高い点が自然選択で選ばれてゆく過程とも表すことができる。
調節部位のネットワークなどは自由度の非常に高い (変数が多い) 適応度空間の最適化問題となる。選択圧はもちろん個々の個体にかかって適応度のより高いものが相対的に多く生き残ることで実際上最適化問題を解いているようなものである。
このような表現をすると何か類似の例に気づかれないだろうか。これは多変数関数の極値を求める問題とほぼ相同である。1変数関数ならば微分をとって0になる点を探せば極値を求められるが、変数が多くなるとこの方法はほぼ使えなくなる (完全に線形な問題で連立一次方程式にでも帰着しない限り3変数でさえすでに困難になる)。
この問題を解くために従来からさまざまな方法が考案されていて、「持続不可能性」(p. 201 の脚注 7) にも出ているような simplex 法、Nelder-Mead 法などがよく知られたアルゴリズムだった。
いずれも高次元空間の中で「より高い (低いでもよい) 点」を (乱数を用いずに) 探索してゆくものである。これらは「決定論的」な手法で、初期値が同じならば誰が行っても同じ結果になるはずである。
「持続不可能性」には確率的最適化法 (芸術的な解法とある) が紹介されていて、生物の進化にならって最適解を探す方法とある。
つまり突然変異のように乱数で変数の値を変えて最適解を探す方法である。Levin が言及した具体的なものはもう少し限定した問題 (例は巡回セールスマン問題) を解く古いタイプのもののようにも見えるが、
今では マルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC) (#ハチクマ備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] の系統解析方法に登場する)
が有名になっている。
おそらく Levin も馴染んでいた統計物理学では単にモンテカルロ法とも呼ばれる。この名前では乱数を用いて何かを求める方法 (例えば乱数で円周率を求めるなど) と区別がつかないが、「マルコフ連鎖」を加えることで用語が非常に明確になる。要するに一つ前の状態に (突然変異に相当する) 乱数を加える生物進化とほとんど同じような原理になる。
「決定論的」な手法から決別してどちらへ進むかは乱数に頼る。一見頼りないようだが...
乱数を加えていって最適解を探す方法ならば誰でも何らかのやり方を思いつくだろうが (よりよい点に当たればそれを採択して先へ進むなど)、MCMC はベイズ統計学と組み合わせると特に有益な確率分布を求める点が異なる (最適解一つを求めるのではなく確率分布を求める。ベイズ統計学では事後確率 posterior probability の概念になる。適応度に対応するものは尤度になる)。
ピーク一つを探すだけであればそれほどややこしい話ではないが、確率分布を再現したいとなると少し厄介で詳細釣り合いの条件などが必要になる。適当に乱数を振ったり結果を適当に採択したりしていては正しい確率分布にならない。そこで MCMC の出番である。この計算で最もよく知られて基本となるアルゴリズムがメトロポリス・ヘイスティングス (Metropolis-Hastings) 法である。
この手法を確立したのは Metropolis (1953) で統計物理学者、Hastings (1970) が一般化してさまざまな分野に使われるようになったが Hastings の Monte Carlo Sampling Methods Using Markov Chains and Their Applications
は何と生物学雑誌である。この手法の学際的色彩がもはや現れている。
Metropolis の方は初代の電子計算機 MANIAC I (1952) に実装されたもので、これはロス・アラモス研究所、すなわち原子爆弾の開発のために使われたもの。今からみてもこの時代にこのような計算が行われていたことはただただ驚嘆である。
さて生物進化の話の方に戻ると、こういう高次元空間の最適化問題には「局所解」の問題が出てくる。つまり高次元ではいたるところにちょっとしたピークがあって簡単にそこに陥ってそれ以上動かなくなるのである。
Levin の時代にはまだ主流だった simplex 法、Nelder-Mead 法などを扱われた経験のある方ならばこの問題は痛いほど体験されているだろう。2000 年代前半ぐらいまではこちらが普通だった。
そのためにたくさんの初期値から出発してなるべく大局的な最適化を探したいわけだが今度は膨大な計算時間がかかる。
では生物はこの局所解問題をどのように乗り越えてより大局的な最適解にたどりついているのだろう。
ここで MCMC を使うと物事の理解が圧倒的に明快になる。それまで simplex 法で苦労していた問題が解けてしまう。大学院生が苦労していた問題を学部学生の演習でも解けてしまうのである。
つまり "よりよければそれを採択して先へ進む" だけではなく、"よくなくてもある確率で採択する" が肝で、MCMC では確率分布を再現するためにここに工夫を施している。生物進化でも同じようなことが起きているのではないだろうか。
このように書くと MCMC が魔法の道具のようにも聞こえてしまうが生で使うには数変数 (次元) ぐらいが適当で、もっと多次元になるとやはり局所解問題が効いてくる。ここで出てくる一つの技法が生物に例えれば "選択圧のレベルを弱めて進化させたグループと、本来の選択圧で進化させたグループを適宜とりまぜる" (一般に多段階を用意する)
に相当するレプリカ交換モンテカルロ法 (英語では parallel tempering の名称がよく用いられる) である。最初の提唱者は Swendsen and Wang (1986) だが手法の発展には日本の統計・物理学者が大きく関係している (1990 年代)。
実際のレプリカ交換モンテカルロ法では上記のような曖昧な表現ではなく、確率分布を正しく再現するための詳細釣り合い条件も満たすべく数学的に厳密な記述がなされている。実際の生物進化ではもっと曖昧な手段でも十分役立つだろう。
なお Levin (1999) (訳本 p. 205 脚注 11) によれば生物進化において局所解問題問題を逃れるこれに近いアイデアが Sewall Wright (1931) Evolution in Mendelian Populations ですでに提唱 (shifting balance theory) されていたとのこと。
ただしアイデアは萌芽的なもので、他の解釈には影響を与えたものの進化において重要な因子としては捉えられていないとのこと (wikipedia 英語版より)。複雑系の進化を考えると事情が変わってくるかも知れない。
Levin (1999) ではレプリカ交換モンテカルロ法の話はまではまだ出てこず、当時先端的な方法であった Simulated Annealing (焼きなまし法) が紹介されている (p. 205 脚注 10)。当時は 遺伝的アルゴリズム などが話題となっていたが MCMC の定式化と組み合わせることで一層価値が出てきた、というところだろう。
wikipedia 日本語版の MCMC の解説では何が何なのかほとんどわからないが、「計算統計 II マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺」(統計科学のフロンティア 伊庭他 岩波書店 2005) が出て普及が始まったと言えるだろう。
出版社による本の紹介では "マルコフ連鎖モンテカルロ法は、近年の計算統計学で最大の話題のひとつであり..." とまである。現在はオンデマンド出版で手に入るらしい。
この種のものを理解するには書いてある通りに計算機を使って実際にプログラムを書いてみること (あまりにも簡単で R ですぐに書ける。古い BASIC でも一向に構わない)。大学入試が終わると演習問題をやってみなくなるものなのだが食わず嫌いをやめてとにかく触ってみるとよい。
数学好きの人でなくても面白そうな話題としては N × N の魔法陣の解はいくつあるかが紹介されている。3 × 3 ならば1種類はご存じの通り。N が少し増えるだけで計算機でもすぐに厳密に求められなくなる (厳密な値は N=5 までしか知られていない) が、レプリカ交換モンテカルロ法を使ってよい近似値を求めている。N=5 で上位4桁まで一致する数が推定されている。
魔法陣は 1 から N^2 までの整数だけが許された極端な連立方程式だが、"選択圧のレベルを弱めて進化させたグループ" に相当する条件を緩和した進化を解くことを組み合わせて厳密解の数が推定できる
[cf. Kitajima and Kikuchi (2015) Numerous but Rare: An Exploration of Magic Squares]。
そんな問題が突然変異の積み重ねのようなもので解けてしまうのかと思うが、実際に解けるのである。
wikipedia 英語版では従来の方法で求めることは不可能だったとある。
何が言いたいかと言えば、「遺伝子などのネットワークが複雑系としてどのように進化するか」などの具体的イメージを得るにはほぼ相同である MCMC を使ってみるのが今ならば早道である (Levin の時代には紹介することは多分無理だったが今の時代ならばおそらく誰でも使える) ということである。アルゴリズムも「こんなに簡単でよいのか」と思えるぐらい単純で手持ちの計算機でもすぐ走るものがあるだろう。
何よりも MCMC は生態学のパラメータ推定などですでに馴染まれている (苦しまれている?) 方もかなりおられるだろう、話が通じやすいだろうことを前提に書いている。
松井 (2021) 分子系統解析の最前線 でも分子系統解析に MCMC が広く取り入れられていることもわかる。この解説で Metropolis-coupled MCMC と紹介されているものがあるが、説明を見る限りではレプリカ交換モンテカルロ法とほぼ同様の概念でないかと思う。
Mueller and Bouckaert (2020) Adaptive Metropolis-coupled MCMC for BEAST 2 BEAST 2 での実装。
このような名前を付けているのは、略すと MCMCMC と大変語呂がよいため。
レプリカ交換モンテカルロ法にしても parallel tempering にしても語呂のよい略名がなくて今ひとつ紹介しにくい。(MC)^3 と書いてあるのはその意味。
生物進化を模倣したアルゴリズムで生物進化系統を探る (?) ... 直接の関係はないかも知れないが面白い話である。
2000 年前後からに急速に広まり、今や分子系統解析を初めとする生物学の屋台骨を支えているのである。何と学際的な話だろうか。
分子系統解析ではそこまで専門家が関与していないように感じるので、数理科学の専門家が本腰を入れてスーパーコンピューター用に最適化すればすごいものができそうな気がする。
昔から哲学的議論の対象となっていた事項に、「なぜこんなに複雑なものが進化できるのか」。ダーウィンは眼の進化を取り上げた。(今ならば遺伝子のことがわかっているが) これほど多数の遺伝子を同時に操作して思い通りの形質を得る確率などほとんどゼロである。神による創造としか考えられない。のような議論がしばしばなされる。
今ならばこの問題にある程度の回答を与えることができる。ネットワークが複雑系としてどのように進化するか、理論は多分難しいが手早く感触を得たいならば MCMC がなぜこれほど単純な原理で全体的な最適化を行え局所解問題を乗り越えることが可能なのかを体感してみるとよい。
適当に数を割り振るだけで魔法陣ができる可能性はほぼゼロである。N=7 でも 10 の -28 乗の確率と、すでにアボガドロ数回試行しても無理になっている。
多少は意味が違うが、生物の場合では同じぐらいの数の調節部位を同時に操作するようなものと考えてもよいだろう。普通に考えれば解に相当するものに偶然行きあたるには宇宙年齢をかけても無理だろう。しかし適切なアルゴリズムさえあれば乱数を使うだけでできてしまう。
最初の Metropolis (1953) の時代には変数を1個ずつ動かしていた。これは1遺伝子なり1調節部位に変異を加えることに相当する。後には複数の変数を同時に動かすことでより高速の計算が行えるようになり、変数をブロックで動かすなどこの方面の技術も進歩している。
どの方法でも得られる結果が同じであることは数学的に証明されている。個々の遺伝子や調節部位を変えてゆく方法でも、おそらくもっと上等な方法で最適化をする方法でも進化速度が違うだけでよい解に到達できる。先に高い適応度を得た方が選択されるだろうから何か上等な方法で最適化する方法が選抜されるのだろう。このあたりは生物の知見からアルゴリズムの改良に結びつくかも知れない。
生命誕生もおそらく同じで、(古典的な?) 生物学者の視点からは「生命誕生は地球でただ1回しか起きなかった現象で、ほぼゼロの確率の幸運が積み重なったもの」と認識されている印象も受ける。あまりにもうまくできすぎているのである。
「天文学者はどこででも生命が誕生しているようなつもりで探そうとしているが、ハビタブルゾーンとか何を馬鹿なことを考えているのか」とか内心思われている方もあるだろう。
実際に見つかってみるまでは何とも言えないが (ここは形而上学的議論でなく自然科学たる部分)、生命誕生は普遍的であっても不思議でない理由が後述の Kauffman が想像しているように複雑系の観点からはあり得る。それは実証に値する仮説であるとの認識に基づくものと理解している。そして近年急速に進展した太陽系や惑星の進化シナリオ (#ハヤブサの備考 [月に行ったハヤブサ] の *1 参照) とも関連している。
科学の世界もいろいろなところでつながっているのである。
関連する話題が出ていた: Mills et al. (2025) A reassessment of the "hard-steps" model for the evolution of intelligent life
生化学・分子生物学者とはまた違った視点よりマクロの現象を扱っているが、知的生命の誕生に必要な複数の困難な段階 (確率の積とすると起こりそうもない) と考えられてきたものはもっと自然に実現できるとの解釈。生物学の知識があまりなくても読めるように古くから唱えられていたフェルミのパラドックスなど宇宙生物学的視点が主になっている。
あまり何か新しくわかった感じではないがここで述べているような話の体系化の試みと言えそう。知りたいのは "ヒト" が生まれるかではあるが、ヒトが特別な存在ではないことを示すところにカラスが出てくる。哺乳類とそれ以外の区分は宇宙生物学者にはまあやむを得ないところだろう。
この論文で初めて紹介されたものではないと思うが、親星 (太陽) も進化するので生物の生存できる期間には限られた window がある。その window の期間内に複雑な生物を生み出せるかどうかはそれほど楽観的ではないかも知れない。我々はその window のかなり最後の期間に位置している。
これは親星の進化速度次第なので太陽より少し軽い星の周囲の惑星ならばもう少し猶予期間があるだろう。
「進化の特異事象: あなたが生まれるまでに通った関所」(クリスティアン・ド・デューブ Christian de Duve 原著 "Singularities: landmarks on the pathways of life" 中村桂子監訳 一灯舎 2007) にもより明確な形で同じような主張がなされている。
ただしド・デューブは複雑系や自己組織化を意識しているというより非常に低い確率でも生物では膨大な数の試行が行われているので適切な解に到達している見方をしている。
ここで注目すべきと考えるのは、生物がこのような (偶然で考えればほとんど起きないような) 最適化を日常的に行っている顕著な例として収斂進化や擬態を取り上げていることである (訳書 pp. 216, 230 など)。
つまり異なった系統から出発して違う経路を歩んでも結果的に同じような最適化に至っていることになる。これは進化の特異事象にも匹敵する現象とのこと。
収斂進化や擬態はあまりにも普遍的に見られるので当たり前のことのように感じそうだが、出発点が違うのに突然変異と自然選択でそこまで似たものを作り出せるのか考えてみると確かに不思議である。
以下に紹介するような複雑系や自己組織化の性質によって、通常想像するより少数のステップで収斂進化や擬態が生じるのかも知れないし、擬態の生じやすい系統ではそのような性質を内在する遺伝子や制御ネットワークを選択圧によって選択されてきたのかも知れない。
鳥の擬態や隠蔽色を調べることは、一見全然関係のないことに見えても実は宇宙の生命現象解明とつながっているのかも知れない
(ド・デューブの考えで多少気に入らないところがあるとすれば生命始原物質を宇宙に求めすぎているように思えることで、宇宙で普遍的な化学反応ならば地球で起きる場所があってもよいのではと思う)。
Neoaves の解説のところで「特異事象」の語を使ったのもこの本の表題を少し連想してみたもの。もし我々が Neoaves から進化したものであったらならばこれらのポイントを指して同じように「あなたが生まれるまでに通った関所」と呼んでいたかも知れない。
ちなみに生物学者もかなり昔から "自己組織化" は知っていた。有名なところではタンパク質を合成する最も重要な細胞内小器官であるリボゾームで、リボゾームの RNA (rRNA) と 33 個のタンパク質 (小サブユニット) + 49 個のタンパク質 (大サブユニット) (数は真核生物の場合で wikipedia 日本語版を使っているが、昔習った時とはちょっと数が違う?) から組み上がる。
それぞれをばらばらにしても合体再構成されることが示されたのが 1960-1970 年代の話。驚くほどうまくできているとしか言えなかった。
ウイルスなどでも同様で、インフルエンザウイルスを複数ユニットからあっさり合成できた河岡グループの研究 (#インドガン備考参照) もウイルス粒子の自己組織化の産物と言えるだろう。
インフルエンザウイルスの場合はこのような複数ユニットを自己組織化で組み合わせる戦略が対宿主戦略として一番適応的だったのだろう。ウイルス自身に意思があってとは誰も思わないだろうから自然選択の産物とか言えないだろう。
より小規模な数のユニットから進化してきたのかも知れない (調べれば書いてありそうだが)。
リボゾームでも事情は同じで、Reuveni et al. (2017) Ribosomes are optimized for autocatalytic production
のような魅力的な進化仮説があるとのこと。自己複製のために最適化された構造を持っている。
しかしながら 1970 年代ぐらいでは「なぜこれほどうまくできているのか」の背景を理解するには時代がまだ早すぎたのだろう。
目に見える形で最初に世に出たのはロシア出身のプリゴジン (Ilya Prigogine 1917-2003。エフゲニー・プリゴジンとは別人) によるもので "散逸構造" として紹介されたもの
[Glansdorff and Prigogine (1971) "Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations"「構造・安定性・ゆらぎ: その熱力学的理論」みすず書房 1977] (1977 年ノーベル化学賞)。
物理学の世界の話で関係がないと思われていても不思議ではないが、今や生物がなぜそうなっているのか理解するのに一番役立ってきているかも知れない。
またまた余談だが優れた人は多方面で活躍するようでゲルマン同様言語学や考古学 (考古学博士) にも秀でていたという。ピアノも超一流でウラディーミル・アシュケナージ (泣く子も黙る?ピアニスト) の父に師事したという。
複雑系ではいかにもありそうな話だが脳の同じ回路を多方面に使っていたのかも (ピアニストは指が器用に動く能力が重要で指の訓練を日夜行っている話題がよく述べられるが、実はそれをコントロールしている中枢神経回路を鍛えている。その回路は他の目的に用いられても不思議でない。
ピアノで脳トレーニングも意味があるだろうし、他の習い事に比べて脳機能の発達に圧倒的に有効との研究結果も出ているらしい。足を器用に使う鳥で知能が発達している可能性を調べる動機にもつながるだろう)。
さらに兄 (Alexandre Prigogine) は鳥類学者になったという (Alexandre Prigogine (1913-1991) Ibis誌の訃報)。
なお、ここでは生物進化との類似が非常にわかりやすいため (今や身近にある) MCMC を紹介しているもので、まったく同じというわけではない。
Levin は生物進化では同じ適応度空間 (適応度地形図) の中を探索しているわけではなく地形図が時間とともに変わったり、他の個体の存在によって変わったりすることなどの違いを挙げている。例えば生態系の場合には適応度空間の同じ点を他の個体が占めればその点の適応度は下がる (頻度依存メカニズム) (pp. 205-206) のですべての個体が全く独立に適応度空間を探索しているわけではない。
しかしながら進化のプロセスを理解する上で適応度地形図上の探索、すなわち MCMC のような挙動を思い浮かべることは有益であろうし、このプロセスを受け入れれば適応度地形図を変化させる効果は副次的に取り入れることで理解できるだろう。
Levin の本を読むならば当時明らかになったばかりで注目を帯びていた事項2つを把握しておくと話の背景が理解しやすいだろう:
(その 1) 一つはカオス理論 (chaos theory) で、wikipedia 日本語版から引用すれば「ある初期状態が与えられればその後の全ての状態量の変化が決定される系を力学系と呼ぶ」。この項目の最初の方で「決定論的」の表現を用いたの理由のはここにある。
つまり決定論的であれば初期値さえ十分精密に与えれば将来の状態 (時間進化) はほぼ正確に記述できるはず。この常識を打ち破ったのがカオスの発見である。最初に気づいた一人は ローレンツ (Edward Lorenz。動物行動のローレンツとはもちろん別人) で気象モデルで 1961 年に見出した現象であったが長らく注目されなかった。
1976 年ロバート・メイ Robert McCredie May が生態学で個体数を記述する方程式であるロジスティック方程式 (logistic equation) がこの挙動を示すことを示し、1990 年ごろには研究が進み急激に注目を浴びるようになった (wikipedia 日本語版に十分詳しいので詳細は参照されたい)。
初期値のわずかな違いが時間とともに指数関数的に増大するのである。数理科学者がこれに注目しないはずはない。
大学に入って初めて学ぶだろう数学で、至るところ微分不可能な連続関数とか「有理数の濃度は整数の濃度と等しい」とか意味不明の話を習ったりすることもあるだろう (数学者は高校数学では習わない数学の面白さを伝えようとしているのだが、それで大学の数学が嫌いになるとの話もないではない...)。
そんなことは数学者の世界だけの特別な話で関係ないと思っていたら生態学を記述する関数になんとその性質が含まれていたのである。
ある力学系がカオス状態にあるか否かはその力学系によるが、ロジスティック写像の場合にはあるパラメータを境にカオス状態が出現する。この境界にあたる状態がカオスの縁と呼ばれるが、自然選択の結果生命現象はカオスの縁状態になっているのではとの考えがあり Levin の本でもこれが紹介されている
(上記の古典的なカオス理論は決定論的な問題であってもカオスが出現することが斬新で、乱数が入るような非決定論的な場合とは多少違うので類似の意味での延長線上の使い方だろう)。
カオスの縁状態にあればわずかな摂動で別の状態を生み出すことが容易で、さまざまな進化を理解できるのではないかとの考えになる。
本文中で Neoaves での代謝の進化を記述した Ng et al. (2023) にも複雑適応系を指して "Assuming most species are near this type of boundary condition," のような表現があり、"カオスの縁" との関連性を暗に示唆しているのだろう。
"カオスの縁" のような状態にあれば、(一見不利に見えるのに) 複数の遺伝子を失って違った環境に適応することも可能かも知れない、といった読み方になるのだろうか。
(その 2) もう一つが自己組織化臨界 (self-organized criticality, SOC) で、地震の規模と発生頻度がべき乗則に乗る説明などでしばしば用いられる。Levin の本でも砂山に砂を1粒ずつ加えていった場合にいつ崩れるか (なだれが発生するか。その規模と頻度の関係は?) との砂山モデルを取り上げている。
SOC の用語は Per Bak (1996) が考え出したもので、著書 "How Nature Works" で自己組織化で生物群集を説明するアイデアを出している [Levin (1999) 訳書 pp. 96-98, p. 290。Levin はこのアイデアを一定評価しつつ個体ではなく群集への選択圧を暗黙で仮定する点などを疑問視している]。
Levin (1999) 訳書 p. 287 脚注 9 に断続平衡と SOC の関係が述べられている。
自己組織化と進化・生態系に関してはそのものずばりの名前の書籍もあり、スチュアート・カウフマン (Stuart Kauffman)「自己組織化と進化の論理 - 宇宙を貫く複雑系の法則」(米沢富美子監訳、森弘之・五味壮平・藤原進訳 筑摩書房 2008)。原題は "At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity" (1996) とかなり感触が異なる。
Levin (1999) ももちろん Kauffman (1995) を引用している。
「持続不可能性」の訳書では SOC とカオスの縁がほぼ同様の概念である注釈がなされている。
Kauffman の著書について At Home in the Universe - The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity で書評を見ることができるが、
"If, as he argues, life were bound to arise, not as an incalculably improbable accident, but as an expected fulfillment of the natural order, then we truly are at home in the universe".
Kauffman の考えるところでは、生命がとんでもない偶然の中で誕生したものでなく、自然の法則の産物して生まれるべくして生まれたのであれば、我々はしかるべき所にいるのである。"At Home in the Universe" はここに由来。
進化的適応の産物であれば我々が環境に一番適した状態で存在していることは理解しやすい。生物としては今の住処が一番適しているのである (宇宙に出れば地上の問題が解決できるかも知れないような考えは、我々は自然選択の産物ではないと言っているかのように自分には感じられる)。
「持続不可能性」の原題は "Fragile Dominion" (訳書では「はかない住処」) である。もちろん地球のことを指していて、我々の環境破壊や気候変動などに痛めつけられている生態系のことである。
Kauffman の "At Home in the Universe" に呼応した表現だろう。
生態系はそのような条件でも形を変えて存続するだけだが、その生態系は我々にとって住みやすい環境にはならないだろう。Kauffman の言葉によれば自然の法則の産物として我々はしかるべき住処を占めることになったが、自らの手でそのはかない住処を失いつつあるのである。
しかしこの本はその部分よりも複雑系科学が生命や進化の不思議を (当時の最先端の情報で) どのように説明できるかを伝える方が中心となっていると見た方がよいだろう。Levin の本と Kauffman の本 (いずれも易しい内容ではないが...) はセットで読むべきものであろう。
英語論文や本でも構わなければもっと新しい仕事も読めて、Vattay et al. (2015) Quantum Criticality at the Origin of Life など。
Sansom (2011) "Ingenious Genes: How Gene Regulation Networks Evolve To Control Development. Life and Mind: Philosophical Issues in Biology and Psychology"
は Kauffman のアイデアをもとに遺伝子制御ネットワークを考察。
Kauffman (2016) "Answering Descartes: Beyond Turing"。
Kauffman (2014) Beyond the Stalemate: Conscious Mind-Body - Quantum Mechanics - Free Will - Possible Panpsychism - Possible Interpretation of Quantum Enigma
心や意識といった概念も既知の物理学で説明できるのでは? シュレーディンガー Schroedinger "What is life?" (1944) [エルヴィン・シュレーディンガー 著、岡小天、鎮目恭夫 訳「生命とは何か: 物理的にみた生細胞」岩波書店 1951 初出版] DNA の仕組みなどもまだ見つかっていない時代の著作である (そしてこのアイデアが 1953 年のワトソン・クリックによる DNA の構造の解明につながったとも言われる)。
この中の有名な文章 ...living matter, while not eluding the "laws of physics"
as established up to date, is likely to involve "other laws of physics"
hitherto unknown, which however, once they have been revealed, will form
just as integral a part of science as the former (wikipedia 英語版より)
生命はこれまで知られているところでは既知の物理法則に反するわけではないが、生命活動を説明するためにはこれまでの物理学では不足で、まだ知られていない新しい法則がかかわっているだろうと著したもの。これはさまざまな意味で憶測や誤解にもつながっているが、今は複雑系科学がこれに答えようとしている。
この話は実は渡り鳥の磁気定位 (#アマツバメの備考) にもつながっており、真の意味で量子生物学と呼んでよさそうな分野が生まれつつある。量子生物学の名称は過去にもあったがかつては量子化学の生物への応用と大した違いはなかった。
心や意識にはもしかすると渡り鳥の磁気定位と共通の機構があるのか。
まだ萌芽的で真に生命現象を解明するアイデアが出てくるのはおそらくこれから。ただし自分にはついて行けそうもないが...。
(非常に古くから量子力学と意識を結びつける考えはあったが) Smith et al. (2021) Radical pairs may play a role in xenon-induced general anesthesia、
Zadeh-Haghighi and Simon (2022) Radical pairs may play a role in microtubule reorganization
が最近の進展の発端の一つとなったアイデアの論文。渡り鳥の磁気定位に出てくるラジカル対がかかわるメカニズムを提唱 (医学に関連する論文に渡り鳥の磁気定位の研究が紹介されている!)。
そもそも全身麻酔がなぜ意識を消失させるのかわかっていなかった (そんなこともわかってなかったのかと思われるだろうが、一部の麻酔薬が何を標的としているか判明したのはようやく 2020 年になってから。ほぼ 100 年間不明だったとのこと。この研究ではキセノンの麻酔効果を考えている)。偉そうに書いているが渡り鳥の磁気定位を調べる過程で副産物として初めて知った (笑)。
渡り鳥の磁気定位におけるラジカル対が今や最有力仮説となっている現在、渡り鳥が使っているなら生物の別のところで普遍的に使われていても不思議でない気もする。
例によって大風呂敷を広げておくと、もしこれらが実証されればノーベル賞あるいは類似の賞の対象とされるのではないだろうか。テーマとしては「生命におけるマクロ量子現象」のようなものが想定できる。
分野は何だろうか、マクロ量子現象というといかにも物理学賞のタイトルのようだが、扱っている現象は化学なので化学賞? いや、医学も含む生物だから医学・生理学賞か? 最初に確立されるのが渡り鳥の磁気定位の可能性が高い気がするので鳥類学からノーベル賞か。渡り鳥がなぜ正確に戻って来ることができるか解明できればノーベル賞ものだよ、とか冗談で言ったことがあるが、考えてみるほどに本当にそうなのかも知れない。
受賞者は誰になるのだろうか、と考えると面白い。もちろん大風呂敷、妄想ですよ (笑)。
カオス理論と鳥の発声メカニズムの相性がよい可能性が出てきた: #エゾビタキ備考の *1: 発声と非線形現象 を参照。
[オウム類とフクロウ類のモザイクのような化石鳥]
オウム類とフクロウ類のモザイクのような化石鳥が知られている。Mayr (2021) A partial skeleton of a new species of Tynskya Mayr, 2000 (Aves, Messelasturidae) from the London Clay highlights the osteological distinctness of a poorly known early Eocene "owl/parrot mosaic"
この化石属とともに化石属 Messelastur Mayr (2005)
The postcranial osteology and phylogenetic position of the Middle Eocene Messelastur gratulator Peters, 1994 - a morphological link between owls Strigiformes) and falconiform birds?
があり、後者の発見の時点ではハヤブサ目とオウム目の類縁性がまだ知られていなかったため、当時のワシタカ目 (当時ハヤブサ科を含む) とフクロウ目をつなぐ化石かと注目されたもの。
属名に "astur" が付いているようにタカの仲間と意識されていたことがわかる。
2008 年以降ハヤブサ目とオウム目の類縁性が明らかになってきて、(少なくとも現時点では) 幻の "ミッシングリンク" となった。
Mayr (2010) Well-preserved new skeleton of the Middle Eocene Messelastur substantiates sister group relationship between Messelasturidae and Halcyornithidae (Aves, ?Pan-Psittaciformes)
の論文で Messelastur と Tynskya の関係がより明らかになったが、Messelastur gratulator の方がより猛禽的な足のつくりになっている。
この2属は現代の昼行性猛禽類のように目の上の骨性の supraorbital ridge (processus supraorbitalis) が発達しており (猛禽的な生活様式だった? #カタグロトビの備考 [カタグロトビ類の系統分類] も参照)、嘴も猛禽的である。
この研究の時点ではタカ目と {ハヤブサ目 + オウム目} の違いが明らかになる途上で、もし今後の研究でこれら化石グループがオウム類の祖先であることがはっきりすればオウム類の祖先は猛禽的な鳥であったことを裏付けると結んでいる。
Mayr (2021) で Tynskya 属のより完全な化石が見つかって、この時点ではハヤブサ目とオウム目の類縁性が明らかになっていたため再検討も行われた。この化石の足のつくり (semi-zygodactyl feet) はオウム類に似ている。
形態学的には現生の猛禽類やオウム類との共通点はあるが、どの系統に位置するか確定的なことは言えなかった。分子遺伝学による制約 (ハヤブサ目とオウム目がまとまった系統をなす) をつければオウム類かスズメ目に近いことが示唆されるのだが...
(制約をつければそうなることは計算してみなくても自明なのであまり詳しく説明していないのだろう。制約をつけなくても形態学的に独立に同じ結果になればお互いの確かさを裏付けることになるのだろうが)。
頸椎の構造が特殊で現生のすべての鳥の鞍状の関節面 (saddle-shaped または 異凹型 heterocoelous #フクロウの備考 [フクロウ類の首の動き] 参照) と異なる。
第4頸椎 (C4) の後方突起は現生のフクロウ目とタカ目にみられる (注: 一般的には肉を引きちぎる力を伝えるのに適した形態と思っていたが、ぱっと見たところでは肉食でもヘビクイワシにはない? *1)。
顎の特異性も合わせて現生の鳥には存在しない生態的地位を占めていたのではないか、とのことだが系統的位置づけがよくわからない。
後述の [猛禽類の分類など] の「オウム類の祖先と思われる約 5400 万年前の化石種」の部分も参照。
備考:
*1: Shtegman (1937) "Faune de l'URSS Oiseaux Vol. I n.5 Falconiformes" (参考文献のところで shtegman1937_dnev_hischniki.djvu のファイル名で入手可能) p. 6 に記述があった。後ろの突起を os dorsale と呼び、頸椎の前方で長く伸びた突起に processi spinosi anteriores の名称があって [松岡他 (2009)「鳥の骨探」(2009) では proc. costalis の名称] 猛禽類では肉を引き裂くための強力な筋肉の付着部位となっているとのこと。
そう思って川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019) のヘビクイワシの骨格を見ると processi spinosi anteriores は長いが細い。ウミウの骨格でも細い。カモやカイツブリではほとんど目立たない。サギは力が必要そうに見えるがあまり目立たない (実は力はそれほど必要ない?)。やはり肉食性の強い猛禽類で目立った特徴のよう。オジロワシやオオワシでは突起は短めで太い。トビは細いなど食性をかなり表しているように見える。
ハチクマは中間的だがトビより太く、この特徴はハチの幼虫のみを食べていたらあまり必要なさそう。やはり肉もそれなりに食べているタカらしく見える。巣材の枝を折るなどにも役立っているかも知れない。
頭骨の骨格はネットにもよくあるがこのあたりはあまり出てこないので比べてみると確かに参考になる。
#クロハゲワシ備考 [採食方法によるハゲワシ・コンドル類の分類] の Boehmer et al. (2020) Gulper, ripper and scrapper: anatomy of the neck in three species of vultures にハゲワシ類の頸椎と筋肉の付き方の写真があるが、前方・後方の突起とも肉食性の強いタカ類より目立たない。
腐肉食ではあまり力を必要としないのかも知れない。食性を考える時には嘴の形などのみでなく首の骨にも注目、ということだろう。
なおこの Shtegman (1937) は当時のソ連の鳥を扱っていて各論も詳しい (もちろん当時の知見に限られる) が国外の種類も含めた猛禽類総論が結構詳しく、足の形の比較などもあって現代的な猛禽類の総説より詳しい部分もあるかも知れない。カザノワシ Ictinaetus malaiensis の足は鳥の卵が主食のために爪がほとんど曲がっていない図になっているが本当だろうか。
参考写真: Black Eagle 爪は長いがその割には曲がっていないということか。
網膜の temporal (shallow) fovea が正面視の方向を向いている模式図は現代の知見とは異なっているが、過去このように考えられていたことを念頭に読むと従来の書物に示されていた常識も理解しやすいかも知れない。
[フクロウ類はかつてタカの地位を占めていた?]
タカ類よりフクロウ類の方がむしろより古い (約 5500 万年前) 良質の化石が知られている: Mayr et al. (2020) Skeleton of a new owl from the early Eocene of North America (Aves, Strigiformes) with an accipitrid-like foot morphology;
解説記事例 (現代のシロフクロウとの骨格比較が出ている) Scientists describe the most complete fossil from the early stages of owl evolution。
著者たちは当時のフクロウ類は現代のフクロウ類 (趾は相対的に弱く、最後の一撃を嘴で加えるとのこと) とは異なり、現代のタカ類のように足で獲物を殺していたと考えている。
著者たちは約 3400 万年前に昼行性猛禽類が広がった結果 [後述 Catanach et al. (2024) の系統樹では {(チュウヒダカ亜科) + ヒゲワシ亜科 + ハチクマ亜科} の共通祖先が生まれたころ] 昼行性猛禽類との競争の結果フクロウ類の採食方法が特殊化して夜行性に移行した可能性もあると考えている。
フクロウ類が Strix グループ と Tyto グループに分かれたのはこの前にあたるので微妙に整合しないかも知れない (こういう議論は「猛禽類観」にかかわるので面白い)。
Mayr et al. (2020) の考えに従えばタカ類が現在のような昼行性猛禽類の地位を確立するのに意外に長時間 (例えば 2000 万年) を要しておりそのため古い化石も少ないのかも知れない。
ミサゴ科が分かれたのが約 5000 万年前で [Prum et al. (2015) ではもっと若く 2700 万年ぐらい前になるが Mayr et al. (2020) の解説と合わないのでおそらくこちらの数字は使っていない。
Fuchs et al. (2015) の値を使っている可能性があり、この文献では 3400 万年前は (おそらく地上性だが) ハヤブサ系統の祖先、Mindall et al. (2018)
Phylogeny, Taxonomy, and Geographic Diversity of Diurnal Raptors: Falconiformes, Accipitriformes, and Cathartiformes
では同時代はカタグロトビ類と現在の他のタカ類が分かれたころ。
タカ科の祖先系統で 2400-2600 万年前にそれなりに強力な森林性捕食者の化石証拠もある Mather et al. (2022) (#ハチクマの備考参照) ので Catanach et al. (2024) の系統樹は少し古く見積もり過ぎかも知れない]。
当時の地上のタカ類はまだそれほど強力な捕食者を生み出せなかったが、その後生まれた {(チュウヒダカ亜科) + ヒゲワシ亜科 + ハチクマ亜科} の祖先系統は十分強力な捕食者で当時のフクロウ類を凌駕する昼行性猛禽類の能力を持っていたと解釈すればよいだろうか。
わずか1例の化石からは飛躍し過ぎであるが、少しばかり大風呂敷を広げて進化史を考えてみよう。現在のフクロウ類の祖先 (現在のような形態は考えてはいけない) は昼行性猛禽類として現在のタカ類の祖先よりも優位だったと考えることができるだろう。しかしタカ類の祖先も脇役ではあるが途絶えることなく共存していた。
現在のフクロウ類の祖先が昼の陸上で優位だったために、タカ類の祖先の一部は特殊化してニッチを占めたのであろう。
以下の年代の数字は別項目 [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] のオウギワシの染色体レベルの高精度ゲノムからたどる (transposable elements の歴史からみた) タカ類の進化と対応させて見ていただくと面白いだろう。
高精度ゲノムがさらに読まれるようになると描像が明らかになって行きそう。
まずごく特殊なヘビクイワシ科が 6000 万年ぐらい前に分岐 (現在の分布はアフリカ限られているが古くはもっと広く分布していたらしいようでヨーロッパの化石もあるらしい。1科1属1種しか残っていないのは不自然なので研究者は同系統の化石がもっとみつかることを期待している)。
なおこの前に新世界ハゲワシ類 (コンドル類) が分岐しているが、これ以降のタカ類とは染色体の入れ替えがまったく違っていて (#ミサゴ、#クロハゲワシの備考参照)、タカ目に含める必要はないように思える。
ハヤブサ系統の出現もほぼ同じころと推定されているが Falco 属など捕食性の強いグループの出現はかなり後になる。ただしタカ類が地位を確立するよりは早かったようである [Ksepka et al. (2017) の系統樹でもコンドル類とタカ類が分かれる前にハヤブサ系統が分離していれば染色体にかかわる矛盾は起きないと書いたが、後述のようにレトロトランスポゾンのデータからは多分否定的でありこの部分は削除]。
次に魚食専門家としてのミサゴ科が 5000 万年ぐらい前に分かれ陸のフクロウ類の祖先と異なる環境に適応し、全世界に分布を広げた。
次に現れたのが 4500 万年ぐらい前に分岐したカタグロトビ科 (通常の分類ではタカ科の亜科とされるが) で、昼の陸を制覇したフクロウ類 (矛盾した表現に感じるが) の祖先の支配下で夜行性にも適応し、現在のフクロウ類に似た特性を持ち (例えば網膜の紫外線感受視細胞を欠く)、これまた (寒い地域を除いて) 汎世界的に分布を広げた。このような視点で考えるとやはりカタグロトビ類は "科" 相当に感じられる。
これらの特殊化、特に夜行性のタカ類の進化には昼を制覇したフクロウ類の圧力があったのだろう。
少なくとも 4500 万年ぐらい前ぐらいまでは陸の昼間はフクロウ類の祖先の天下だったのではないだろうか。
そして約 3400 万年前にタカ類の真打登場 (前述のように少し古く見積もりすぎの可能性がある。ここからをタカ科とするのは理にかなうように思える) でフクロウ類と立場が逆転。フクロウ類は夜の世界に生きることになる [現代の Ninox (アオバズク) 属のようにタカに近い特徴を持つグループや、昼行性も示すコミミズクなどもあるので昼行性のフクロウ類も長く共存していたかも知れない]。
タカ類の先駆者は現在では {(チュウヒダカ亜科) + ヒゲワシ亜科 + ハチクマ亜科} の共通祖先となるが、この系統の猛禽類には現在もさまざまな特性のものがあるように、当時すでに種分化を遂げて世界に進出していたフクロウ類が昼の世界に残れないぐらいに優れた能力を生み出し多様な適応放散を遂げて昼の陸を制覇したのであろう。
このタカ類の先駆系統も全体として現在も汎世界的に分布している。
「原始的なタカ類」のような表現は失礼であり (笑)、どこかで一線を突破してタカ類の進展を確立したパイオニアと考える方がふさわしいだろう。この系統から分岐してもう少し後 (2800 万年前ぐらい) にヘビワシ類や (強力ではあるが生態的には森林や山岳地、開けた地域など次第に特殊化した放散が見られる) クマタカ/イヌワシなどに至る系統を生み出すことになる。
ただしこの先駆者グループでも少なくともクロハゲワシは網膜の紫外線受容視細胞を欠き、一部の系統では祖先が夜行性生活を行っていたことを意味するかも知れない。
このようにみると猛禽類の中ではタカ類はむしろかなり後発だったように見える。タカも「下積み」時代が長かったのだ。系統順に「場所取り」をしていったような捉え方は間違いなのだろう。
タカ類がフクロウ類をどのような点で凌駕したかを現生種から推測するのは無理があるかも知れないが、みなさんも考えてみていただきたい。
学説も固まっているわけでもないので特に猛禽類好きの方は "えこひいき" (笑) でもよいので自由に想像を膨らませていただいてよいだろう。
以上あくまで「大風呂敷」なので全然違う結果になるかも知れないが。
フクロウ類がかつては昼行性で二次的に夜行性になったと考えると他にも都合のよい点がある。系統関係をどう考えるかによって異なるが、Prum et al. (2015) のような系統樹を考えるとフクロウ類と祖先を共通にするグループが夜行性を体験せずに済む (実際に網膜の4原色が保持されている)。
Ksepka et al. (2017) の系統樹であってもフクロウ類とカワセミ類からなる系統に分離されるだけでスズメ目はタカ類につながり特に矛盾が発生するわけではない (後述のようにレトロトランスポゾンのデータからは多分否定的でありこの部分は削除)。
もう一つ、夜行性の系統は渡りの磁気定位にかかわる分子の遺伝子として最も有力とされる Cry4 を失う傾向にある (#アマツバメの備考参照)。
フクロウ類が祖先段階で夜行性であればその後フクロウ類との共通祖先から分かれた系統も Cry4 を失う可能性があるが現実にはそうなっていない (ただし渡りの必要がないなど二次的に失なった/失いつつある系統はそれなりにある)。フクロウ類が祖先段階で昼行性であればこの問題も回避できる。
後述のようにヨタカ類の系統 (アマツバメ類、ハチドリ類など) で Cry4 が不完全になる傾向が少し見られておりこの系統は初期から部分的に夜行性だったかも知れない。
ヨタカ類の系統は古いが、フクロウ類が祖先段階で昼行性であったと思われる時代に複数の系統を分岐しており、夜行性に回ったのはあるいは昼行性フクロウ類との競争もあったもかも知れない。
タカ類は調べられた範囲で Cry4 を完全に保持しており、フクロウ類の天下の時代にもおそらく主に昼行性生活をしていたのだろう。
[初期のフクロウ類とタカ類は交雑していた!?]
Jarvis et al. (2014) (#ミサゴの備考参照) では、
フクロウ目と Eucavitaves (キヌバネドリ類、サイチョウ類、カワセミ類やキツツキ類を含む) の単系統性を示すの 22 遺伝子座 (レトロトランスポゾンの挿入) を発見したが、一方で他の 15 遺伝子座はフクロウ目とタカ上目 (タカやコンドル等) の単系統性を示した。にもかかわらず、Eucavitaves とタカ上目の単系統性を示す挿入遺伝子座は報告されていない。
Jarvis et al. (2014) は種間交雑の可能性について結論付けてはいないが、蔵本らは上記3つの系統群が分岐した後にフクロウ目とタカ上目との間で種間交雑が起きたと考えている
[蔵本多恵 2016 博士論文より抜粋と付記, Kuramoto et al. (2015) #クロトキの備考参照。後述 Gatesy and Springer (2022) は少し異なる描像も提示しており Eucavitaves とタカ上目が先にあって遺伝子浸透を通じてそこからフクロウ目が生まれたとのアイデアがある]。
[タカ類の初期の適応放散]
Mayr and Hurum (2020) A tiny, long-legged raptor from the early Oligocene of Poland may be the earliest bird-eating diurnal bird of prey
が 3000-3100 万年前のポーランドに小型のタカ類の化石を発見し、Aviraptor longicrus と名付けた。形態的には現代のハイタカ類に似ており、現代のタカ類の最小サイズに相当する。小鳥食と考えられるが、広義 Accipiter 属との類似性は収斂進化の可能性もある。
著者は広義 Accipiter 属を含むクレードの出現推定年代より倍近く古い。古い系統の現存猛禽類でふしょの長いものは特殊な採食習性のもののみで、このような小型種はいない。系統についてはそれ以上の議論は行っていない。現代の分子系統樹に従えば最初に適応放散した猛禽類の中に現代のハイタカ類に似た小鳥食のものも含まれていた可能性もあるのかも。
この時期にポーランドで最初のスズメ目やハチドリの化石が見つかっており、小型の鳥の出現と猛禽類の適応放散の共進化の最初の段階を表している可能性がある。
Catanach et al. (2024) を用いれば分岐年代が少し古くなり、3000 万年前ぐらいにタカ類の系統がいくつか出現している可能性があるが、広義 Accipiter 属を含むクレードは 2300 万年前ぐらいで存在したとしても原始的な進化段階と思われる。
それ以前の系統も広義 Accipiter 属に似た種類を生んでいたのかも知れないがなぜ現存していないのか?
Mayr and Perner (2020) A new species of diurnal birds of prey from the late Eocene of Wyoming (USA) - one of the earliest New World records of the Accipitridae (hawks, eagles, and allies)
は北米で初期のタカ類の適応放散と考えられる化石を見つけている (暫定で Palaeoplancus 属に含めている)。こちらはノスリ類に似ていて哺乳類を捕食していた可能性を考えている。
Mayr (2022) Accipitriformes (New World Vultures, Hawks, and Allies), Falconiformes (Falcons), and Cariamiformes (Seriemas and Allies)
が総説を書いていて、Cariamiformes (ノガンモドキ目) の古い化石はアメリカやヨーロッパで比較的多く見つかっていて、タカ類の化石の方が遅い。
分子系統解析からの示唆とは整合しないが、全ゲノム解析を用いても確実な系統関係が得られていない。
{ノガンモドキ目 + ハヤブサ目} が猛禽類の初期系統と考えるのは化石証拠からは依然魅力的なようで、2022 年段階でも {ノガンモドキ目 + ハヤブサ目} とタカ類の関係は議論の対象になっている。
Gatesy and Springer (2022) Phylogenomic Coalescent Analyses of Avian Retroelements Infer Zero-Length Branches at the Base of Neoaves, Emergent Support for Controversial Clades, and Ancient Introgressive Hybridization in Afroaves
の解析も面白いので紹介しておく。例えば fig. 10 参照。解析手法次第ではノガンモドキ目が最初の系統にもなり得る。
レトロポゾンを用いた解析でも決定打とはならず確率的にどの系統関係が確からしいかを議論する現状は程度問題となっている。どの項目にどのような重みをかけるか次第で結果も変わる。初期のフクロウ類とタカ類は交雑していた!? も考えられる仮説だが、タカ類と Eucavitaves (キヌバネドリ類以降のよくまとまった系統) が先にあり、遺伝子浸透を通じてフクロウ類が後に生まれた可能性も提唱している。
しかし樹上性のタカ類祖先と、少なくとも現在では洞営巣性の Eucavitaves が果たして交雑していたのだろうか?? 洞営巣性はその後獲得されたとも考えられるが、Eucavitaves 系統に樹上営巣性のものがまったく残っていないのも不自然に見える。タカ類の祖先がどんな鳥だったのかまだわからない部分があまりに多い。
分子系統解析でもこのような状況なので、出現順序の理解に古生物学的知見が役に立つ可能性が改めて議論されているのだろう。[#鳥類系統樹2024] で改良されたが、これらの難しい系統関係まではまだ結論が出せない状況。
遺伝情報からみるとなぜこのようになっているのかなどの仕組みの理解にまだ到達できていないのだろう。
AOS Classification Committee - North and Middle America Proposal Set 2025-A
によれば NACC (北米の鳥の系統分類の委員会) で Stiller et al. (2024) の系統順序を取り入れる議論が始まっているのがわかる (p. 53)。
いくつかの系統は最新知見に基づく入れ替えが採択された。フクロウ類系統とタカ類系統の順序を入れ替えるか (2025-A-8e) は採用されなかった。まだ新知見でサポート率も高くないため。
これまでに発表された系統樹によって形の異なる部分で、タカ類の方が後になると印象がずいぶん異なる。
フクロウ類系統とタカ類系統のどちらが先かはまだ証拠待ち段階。
かつて水鳥の近くに置かれていたタカ類の位置があまりにも違っていて、今では系統樹の一番最後の部分のどこを占めるか議論が進められる段階とすらなっている。
ノガンモドキ目の染色体研究: Souza et al. (2025) Cytogenomic analysis in Seriemas (Cariamidae): Insights into an Atypical Avian Karyotype。
染色体数が 2n = 80 と大きく基本形らしい (ダチョウやコンドル類も同じ数) と考えられるが、Z 染色体は染色体逆位を繰り返しているもののエミューのものと相同性が高かった。反復配列も Z 染色体に蓄積しており、祖先的な鳥のパターンとはまた違うとのこと。
ノガンモドキ目とハヤブサ目に共通のレトロトランスポゾンがある一方で Z 染色体はエミューと相同性が高いのは謎の感じがするが Abstract を見ただけなのでエミュー以外と類縁性を調べたかなど詳細は不明。
参考: ハヤブサで 2n = 50、チョウゲンボウで 2n = 52、コチョウゲンボウで 2n = 40 (特に小さいので有名) [Nishida et al. (2008) Characterization of chromosome structures of Falconinae (Falconidae, Falconiformes, Aves) by chromosome painting and delineation of chromosome rearrangements during their differentiation]。
タカ類は Nie et al. (2015) Multidirectional chromosome painting substantiates the occurrence of extensive genomic reshuffling within Accipitriformes の一覧と系統研究も参照。このような特異なパターンはタカ目とハヤブサ類で特に顕著。
#カッコウ備考 [カッコウ類の足と近縁系統] の参考文献も参照。
[猛禽類の分類など]
古い方の分類に戻るが、かつてはタカ類とハヤブサ類を合わせて Falconiformes ワシタカ目 (後にタカ目と改名) とされていたことはご存じであろう。その中にワシタカ科 (後にタカ科。英語では古くから Hawk Family だった) とハヤブサ科があった。問題は Falconiformes が現在の分類ではハヤブサ目のみを指すことである。つまりいつ書かれた文章か、何を出典にしているかによって意味が変わってしまう。ネットの情報でも混在している状況なので特に注意が必要である。
「まえがき」に相当する部分で階層構造でファイルを整理する時の注意として挙げたものだが、この例がまさしく当てはまっている。Falconiformes/ワシタカ目 を階層に使っていた場合などは個々の種を判断した上での大規模な移動が必要になる。両方使われるからと「Falconiformes または Accipitriformes」のような階層を作ってあったりすると事情はさらややこしくなる。
古い図鑑でもある意味 "賢明" だったものもあり、系統分類順ではなく水鳥と陸鳥に分けているものもあり、この場合は水鳥と猛禽類が混じらなくて都合がよかった。しかし古いタイプの陸鳥も一部後者に入るので分類学上は若干都合の悪い部分もないとは言えない。
動物園などのネームプレートなどでは、受け入れた時の分類や学名がそのまま使われていることも多いので (入れ替えには費用もかかるのでやむを得ないところもあると思うが...)、ワシタカ目などの名前はまだまだ目にすることがある。受け入れ時の分類名がその後分割された場合などに反映されていないこともあり、ネームプレートを見ても分類が変わっていないか、本当にその種かは確認しておいた方がよい。例えばソウゲンワシとアフリカソウゲンワシ (サメイロイヌワシ) は典型例である。
普通の意味で「猛禽類」と言った場合、我々が思い浮かべるのはタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目であろう (タカ目から分離されることもある新世界ハゲワシ類も含む)。
新世界ハゲワシ類を指すコンドル目 Cathartiformes は南米の South American Classification Committee, SACC は別目としており、そのように扱われることもしばしばある。コンドル目を分離する場合の {コンドル目 + タカ目} の名称はタカ上目 Accipitrimorphae となる。
The Peregrine Fund ではこれに南米のノガンモドキ科を加えたものを猛禽類として扱っている(資料)。
参考文献: McClur et al. (2019) Commentary: Defining Raptors and Birds of Prey。
なお目の命名は Falconiformes Sharpe, 1874, Accipitriformes Vieillot, 1816 と実際には Accipitriformes の方が早かったようだが、Falconiformes が市民権を得て使われていたよう。
Analyse d'une nouvelle ornithologie elementaire
この文献内では Vieillot (1816) は Accipitres, Linn., Lath. の目の名称を使っていた (Linnaeus 時代からある名称だが Linnaeus はモズ類など多様なものを含めていた)。
Falconiformes の方は Catalogue of the Birds in the British Museum が由来と思われ、ここでは亜目 Falcones として登場する。この文献でも Vieillot (1816) 同様に目の名称は Accipitres だった。
おそらく亜目を目と読み替えることは有効で、これらの古典的な目の名称は有効としてどこかの段階で鳥類の目に -formes を付けて統一する改名が行われたのだろう。より広まった名称としてトキ科が Threskiornithidae となった経緯と似たようなものかも知れない (詳しい規則や経緯は知らない)。
正確な経緯はわからないが、Falconiformes の名称は Peters (1931) "Check-list of the Birds of the World" で使われており、これを基本文献として引き続き同じ分類が使われていたのかも知れない。旧 Falconiformes が分割される際に Falconiformes の名称はハヤブサ類に譲った、などの表記がある。比較的新しい話なので調べれば 旧 Falconiformes の命名由来などもどこかに書いてあるかも知れない。
Bock (1994) History and nomenclature of avian family-group names (pp. 95-96) によればタカ科 Accipitridae は Accipiter 属に基づくともラテン語の一般名 accipiter のどちらに基づくとも解釈され、後者であれば有効な科名にならないとのこと。
ACCIPITRIFORMES Kites, hawks, and eagles (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealand 2019) によれば ICZN (1999) の規則では Linnaeus の属名をもとにした Vieillot (1816) の科名はいずれも有効なものではないとのこと。
科レベルより上を規定しておらず、Vieillot (1816) が科を意識して用いた Accipitrini を現代の科名語尾に変換したものである Accipitriformes は原理的にはタカ科とヘビクイワシ科いずれにも用いることができる (may be used の書き方になっている)。
この解説に従えば適切な (おそらく) 概念が過去に提唱されていなかったため古い名称を拡張して新しい概念を包含する形の名称 Accipitriformes としたため、記載は古くても過去にこの名称は現れず Falconiformes が使われていたと想像できる。タカ目とハヤブサ目を分離する必要が生じ、適用可能な Accipitriformes がタカ目に用いられたと解釈できる。
ヘビクイワシはタカ目に含まれるので (ミサゴ同様に独立科) 分類上はあまり気にならないかも知れないが、ヘビばかり食べているわけでもない。2 Secretary Birds Attack Rabbit にウサギを仕留めるヘビクイワシが紹介されており、猛禽類らしさがよく現れている。
この足で物を掴めるかは議論が分かれており、掴めると解説している資料もある (元出典は不明)。
ちなみにヘビクイワシは学名 Sagittarius serpentarius 英名 Secretarybird (IOC 名は1単語。一般に使われる時は secretary bird と2語にすることが多いようである)。学名の由来は属名は別のところで見た人もあるかも知れない。12 星座にも入っている「いて座」と同じ。sagitta が矢 (これも星座にある) で、矢を射るものの意味。
種小名もヘビのことでこれも星座にあり、星座を知っている人には即刻わかってもらえる学名 (英語でも serpent だが)。
日本語で書記官鳥とも呼ばれるように「書記官鳥のペン先に似た冠羽」が英名の由来と一般に考えられているが、これに挑戦する仮説もある。Hilary Fry (1977) によればアラビア語で saqr et-tair が「半砂漠のタカ」または「飛ぶタカ」を意味するそうである。
地上を歩いているばかりの印象を受けるが、飛行もしっかり行い求愛ディスプレイもある (これはタカらしい感じがある)。どんな声を出すのかは海外音源やビデオなど探して聞いてみて欲しい。タカの声とはとても思えない。
Glenn (2018) Shoot the Messager? How the Secretarybird Sagittarius serpentarius got its names (mostly wrong)
はこの説が歴史的・言語学的に正しくないとしている。Fry (1977) の説で名前を説明している古い日本語記事を見たことがあるが、日本語での説明のオリジナル出典がどこにあるかは分からなかった (現在は wikipedia 日本語版・英語版ともに解説あり)。
現在の標準的ドイツ語名は Sekretaer だが、かつては Kranichgeier (ツルハゲワシ) だった。日本でも中国でもかつてはサギタカに相当する別名があって似ている。
ヘビクイワシのキック力の測定: Portugal et al. (2016) The fast and forceful kicking strike of the secretary bird。195±34 N だったとのこと。接触時間は 15 ms と大変短かった。
日本でよく聞くのはヘビに体を噛まれないように脚が長い解釈だが [川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019)]、どうも一般的に受け入れられている説はやや異なるらしい。脚が長いために高速のキックが可能。また回転に関係するモーメント (慣性モーメント) が大きいことが全身を使った逆振り子状の運動を可能にしている。
モデル計算も行われており力学的には驚異的な性能で、絶滅した恐鳥 (terror birds、以下にも登場) の解釈にも役立てられるのではないかとのこと。
ヘビに体を噛まれないように、はおそらく副次的効果で (脚が短い猛禽類でもヘビを食べ、ヘビ毒への特異的な耐性は持たないらしいので)、キックに最適化することでこの形状に進化したのだろうか。
どの骨を長くするとキックに有利かなどは力学的なモデル計算などで推定できる可能性があり、なぜ現在の形態に進化したかを説明できるかも知れない (誰かやってみませんか?)。
ヘビクイワシがタカ類の中でも新世界ハゲワシ類の後、最初に分岐した系統である点もあるいは関係するのかも知れない。後に分岐したより高性能 (?) のタカ類は長い脚を使わなくても効率的にヘビを殺すテクニックを "発明" し、極端な特殊化の必要がなかったのかも知れない。
ヘビクイワシは特殊化で生き残ったがそれ以上の適応放散を見せることはできなかった、など。
そのような視点からタカ類の最新系統樹を見てみると、ヘビ食はさまざまな系統で見られ、いわゆるヘビワシ類も比較的古い方の系統で、ご存じの通りハチクマやサシバもヘビを食べる。
ヘビ食がこれらの系統で独立に進化したと考えるよりも、共通祖先段階で特殊な装備なしにヘビを殺すテクニックが "発明" されたのだろうと考える方が自然に見える。ミサゴがヘビを殺すことがあるのか知らないが、ミサゴ科から分離した段階のタカ類ですでにこの能力があったのでは。つまり共通祖先段階で採集生活者というよりすでに活発な捕食者の能力があったと考えられる。
最初は動きの遅いトカゲ類などを食べていて (例えば現存の古い系統のマダガスカルヘビワシの主食)、足の形を大幅に変えるより、制御する神経回路 (中枢神経) などが洗練されて次第に動きの速いヘビ類 (動きの遅い鳥類や哺乳類も) を食べる能力を発展させ、その機能がさらに進化してさらに敏捷な鳥類や哺乳類を捕食するようになったと考えれば現在の食性を説明できそうな気がする。
旧世界ハゲワシ類、チュウヒ類、ノスリ類 (特に Buteo 属) の食性は乾燥地や草原の広がりに合わせて急速に数を増やした草食哺乳類に特化して二次的に進化したものと考えれば理解しやすい。ノスリ類は系統的にも新しく機能的には万能選手だが、豊富な資源となった齧歯類を主な食物とするようになった、など。
ハヤブサ類でも捕食性能が独自に進化したと考えられるが、早く分岐した系統のワライハヤブサがヘビ食でタカ類と共通点があるように見える (#ハヤブサの備考参照)。ハヤブサ目でも南米でタカ類に似た形態や生態を示すクビワモリハヤブサ Micrastur semitorquatus Collared Forest Falcon も (食性はカエルから中型の鳥までと広いが) ヘビも食べるとのこと。
ヘビ類を捕えられるかあたりが猛禽類の分岐点?
#カンムリワシ備考の [猛禽類のヘビ毒耐性] にも関連解説あり。
Carril et al. (2024) Evolution of avian foot morphology through anatomical network analysis
にあるように全鳥類を比較しても一部の特殊化した足の使い方を行うものを除いて足 (踵から先の部分) は比較的よく保存されている。足を器用に使う鳥でも足の構造はあまり違わない。
系統樹を見てもフクロウ類はさすがに特殊化があるが、タカ類、ハヤブサ類では想像するほどの特殊化が見られない。
この論文の著者は体を安定に支えるための基本機能が必要なのであまり大きな変化がなかったと推定しているが、鳥の足は基本的に十分な機能があって上位の神経による制御系 (つまり主にソフトウエア) の進化だけでいろいろな役割を果たせたのかも知れない。
ノガンモドキ科 Cariamiformes で2属 (Cariama, Chunga 2種を含む。いずれも seriema が種小名となっており、いずれも現地名に由来する。英語では Cariama, Seriema のいずれでも呼ばれる。
このグループは古くはツル類に近縁と考えられ、ヘビクイワシと外見が似ているため (これは収斂進化と考えられている)、タカ類が水鳥に近縁と考えられた原因の一つにもなっていた。
ノガンモドキ類は肉食性の巨大な飛べない鳥であった恐鳥類 Phorusrhacidae フォルスラコス科の生き残りとの考えもある。これは恐竜絶滅後南アメリカ大陸で頂点捕食者であったが、南北アメリカが陸続きになって食肉目の哺乳類が到達するようになり、競争で絶滅したとの考えが優勢であった。
しかし最近の研究で最後のフォルスラコス科と初期の現生人類が共存していた可能性は高まってきているそうである (wikipedia 日本語版より)。恐鳥類とノガンモドキ類との系統関係はまだ明らかとは言えないようである。
Worthy et al. (2017) The evolution of giant flightless birds and novel phylogenetic relationships for extinct fowl (Aves, Galloanseres)
によれば植物食の多くの巨大絶滅鳥は Galloanserae (キジカモ類) で、Neoaves に属する雑食・動物食のものは Patagornis と Brontornis 属と考えている。ノガンモドキ科に近いと推定しているがなかなか難しそう。巨大絶滅鳥はさまざまな飛翔性の系統から独立に大型化したと考えられる。
LaBarge et al. (2024) The evolution and ecology of gigantism in terror birds (Aves, Phorusrhacidae)
(出版社サイト)
は南米の恐鳥類の新しい系統解析。このような系統関係とすれば1系統だけが巨大化した結果になる。骨格しか情報がないがノガンモドキ類とハヤブサ類の分岐はより古いものになる。ノガンモドキ類は巨大化した系統には含まれない結果となった。
ノガンモドキ科は現生鳥類の系統樹ではハヤブサ目・オウム目・スズメ目からなる Australaves [Ksepka et al. (2017) とは異なる一般的な呼び名で] の古い枝に属する。ハヤブサ目も古くはこのような種類に似ていたのかも知れない。
Mayr and Kitchener (2022) New fossils from the London Clay show that the Eocene Masillaraptoridae are stem group representatives of falcons (Aves, Falconiformes)
によれば、ハヤブサ目・オウム目・スズメ目の関係は分子系統からは示唆されるが、形態や生態面でハヤブサ目に似た種類が現存していないのが問題であった。
ハヤブサ目とノガンモドキ類の関係を補強する化石種がヨーロッパで見つかったとこと。
分子系統からハヤブサ目などの祖先が現れたのは 3420 万年前と推定されているが (Fuchs et al. 2015)、この化石 (約 5500 万年前) よりもずっと新しい年代になっている。
またハヤブサ系統は南米で進化したと考えられる点など細かい矛盾点がある。
[しかしハヤブサ類の系統から後に生じたはずのスズメ目やオウム類の祖先らしい化石は古いものが世界にみつかっているので、ノガンモドキ類からハヤブサ目への分岐は想像以上に古く、ハヤブサ目の過去の系統がまったく痕跡を残していないだけかも知れない。古い時期に存在したはずのタカ類の化石がほとんどないことも含めてミステリーである。この部分は私見]。
この化石種は脚が長くカラカラ類のように地上で獲物を探していたと考えられるが、ハヤブサ類でもワライハヤブサ類 (Herpetotherinae) のような例外もあって断言はできない。
ハヤブサ目・オウム目・スズメ目の祖先は猛禽的な性格を持っていたらしい点の補強材料となるだろうとのこと。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 114 V-VII と 115 V-VI に「ワシタカ目のおもなグループとその生活」(浦本) のなかなか意欲的な記事があり、Brown and Amadon "Eagles, Hawks and Falcons of the World" (1968-1969) が出たばかりであったため、その国内向け紹介を兼ねたものと思われる。後半に当時のハヤブサ科が含まれていた。
おそらく国内では意見を述べられるほどには咀嚼されていない段階で、Brown and Amadon の分類に従ったものとなっている。
この当時の記述を見るとかつての分類の基本的な方法論がかなり理解できる。つまり似たものをまずまとめてグループとしてゆき、残りは中間的な場所に置いたり分類不明として後回しにしておく形となっていた。認知的にはいかにも考えられるプロセスで (分別などと同様、人にとって把握しやすい)、必ずしも系統を踏まえたものになっていなかったことは後の分子系統解析で示された通り。
他の系統で言えば、「ゴミ箱」状態になっていたツル目やチメドリ科などがこのプロセスの産物に該当するだろう。ツグミ類、ヒタキ類とヨーロッパやアメリカのまとめやすいところからまとめたために後世を悩ませる結果となった。
この状況はタカ類でもまったく同じで、まとめやすいところ、すなわち旧ハイタカ属、ノスリ類、チュウヒ類などをまとめたため、現代に至っても旧ハイタカ属が分割されるべきなのに非常に抵抗感があった。まとめにくい種類は後回しだったのでどこにに入ってもあまり違和感がなく、分類変更が簡単に行われた。一種の認知バイアスと言えるだろう。
当時も旧ハイタカ属が多くの種を含んでいて巨大な属となっていることは気にされていて、オオタカ類とハイタカ類に分けるかつての分類も検討されていたが決定打とならなかった。当時の概念で分割したハイタカ類が後にさらに2分割されることになることを想定していなかったことも理由の一つだっただろう。
日本で旧ハイタカ属が3種も繁殖しているのは不自然な感じもすでに持たれていたようだが、分割する解剖学などの根拠が十分になく食物が違うことによる同所的な「すみわけ」(原文にはこの表現は直接使われていない) 的な解釈がなされていた。この状況は北米でも同じだったため同様に理解できると考えられたのだろう。
まさか3系統が入り日本ではそれぞれ1種のみ定着した歴史があったとは予想されていなかった模様。
旧ハイタカ属に近縁と考えられるウタオオタカ属 (Melierax) の3種の中でチュウヒ属やカンムリワシ属に似たものと、明らかに旧ハイタカ属に似たものの両者があることも挙げられていた。
ウタオオタカ属は現在では3種だがそのうち2種は後に分離されたはず、と見てみると、当時は カワリウタオオタカ [高野 (1973) ではモリウタオオタカ] 現在の学名で Micronisus gabar をウタオオタカ属に含めていた (色彩は似ている。また和名も当時の分類を引き継いでいる)。つまりウタオオタカ属に系統や習性の異なるものが混ざっていたため、旧ハイタカ属を分割しにくい理由の一つとなっていたわけだった (この点は浦本氏の記事には直接触れられていないが、取り上げられ方から Brown and Amadon の解釈を読み取ってみた)。
明らかに旧ハイタカ属に似たものとはカワリウタオオタカ [高野 (1973) ではモリウタオオタカ] を指していると思われる。ハイタカ的な小鳥食の習性は多少異なった系統でも何度も進化できたわけだった。
ただし当時のウタオオタカ属の中でチュウヒ属に似たものがあるため、旧ハイタカ属はチュウヒ属に近縁なのではないかと思わせるとの記述もあって、これは現代の知見にもつながっている。この件は#チュウヒの備考 [チュウヒ類の首は長いか] で取り上げ、現代の Accipitrinae 亜科 のうちで Tachyspiza 属や狭義 Accipiter 属をむしろ特殊化した形態と考えれば素直に理解できることを紹介した。
カワリウタオオタカ [高野 (1973) ではモリウタオオタカ] はアフリカとアラビア半島の留鳥だが、同じく小鳥食の習性を獲得した Tachyspiza 属や狭義 Accipiter 属は渡りの小鳥の移動を追跡した結果、小鳥の移動に従った渡り習性も獲得したと考えるとこれらの系統の関係が一層理解できる感じがする。渡りの小鳥は多いので留鳥より渡りの小鳥を狙った方が進展の自由度が高まった可能性がある。
旧ハイタカ属類縁系統に類似する別系統が別にある例として、アカオオタカ Erythrotriorchis radiatus Red Goshawk (当時和名なし) はオオタカよりもさらに大きく開けた場所にすみ、おもに地上で鳥を捕えるという点でハイタカ属と異なり、飛翔型もむしろノスリ型である、と書かれていた。旧ハイタカ属に近くてもノスリに近い種類もあるので、旧ハイタカ属を分けにくい理由の一つとなっていた模様。
つまり当時のウタオオタカ属の一部のようにチュウヒ属やカンムリワシ属に類似点のあるものも、ノスリ類に似た種類もあるものがあったため、それらに比べれば旧ハイタカ属はよくまとまっている、ということになる。
#ハイタカ備考 [オーストラリアのタカ類] 参照。ノスリ類不在のオーストラリアでノスリ類に似た形態や生態となったものだろうが、さすがに分子系統解析がなされるまでどこに分類すべきかわからなかったらしい。
解説の全体的傾向を見ると、当時の日本の鳥学者には当時のワシタカ目に詳しい人があまりいなかったのではないかと想像する (115 p. 3 のオオタカの項目でも、日本での密度や生息地はよくわかっていないとあった)。
この記事の個々の系統の解説は本稿では取り上げず、Brown and Amadon および後継の書物を見ていただきたいとしておく。南米のノスリ類の解説などもおそらく Brown and Amadon をそのまま用いたものだろう。和名を付けるのも難しかったようで学名だけの表記も多かった。
例えば現在は Spizaetus 属の代表種となっているアカエリクマタカも当時は和名がなかった。
海外標本が豊富に手元にあるわけではないので国内ではやむを得ない状況だったのだろう。
ただし与えられていた和名には現在と若干違って面白いものがあるので少し紹介しておこう (114-V)。
チュウヒワシのことを当時はハラジロワシと呼んでいて #カンムリワシ備考の [分類と系統] のようにおそらく古い学名由来。
本稿で問題として取り上げた Circaetus spectabilis (現代の分類による学名) はヘビワシと呼ばれていた。
Polyboroides は当時メガネダカ属。
Elanoides は当時アメリカエンビトビ属 (エンビトビ部分は英名の和訳)。
Chelictinia は当時アフリカエンビトビ属 (これも英名からの和訳)。この2属は "エンビトビ" が現在では "ツバメトビ" に変わった程度でそれほど違いがない。
115 p. 14 ではヨーロッパクマタカの名称が登場し、何かと思ったが ヒメクマタカ [高野 (1973) ではケアシクマタカ] Hieraaetus pennatus Booted Eagle を指していた。クマタカのヨーロッパ版との位置づけだったがクマタカの亜種名のようにも読めるので使われなくなったのだろう。
これは当時アフリカクマタカ属だったが現代の分子系統解析の結果で別属となった。アフリカクマタカが Aquila 属に含まれることになったためアフリカクマタカ属の名称の意味がなくなった。
Rostrhamus は当時ニシクイトビ属。その後は タニシトビ [高野 (1973) ではカタツムリトビ] となって、タニシは漢字では田螺。日本語では単独で使われることのほとんどない文字なのでカタカナにすると何のことかわからない、となって名前を変えたのだろうか。
この記事ではまだ和名がなかったが Ictinia plumbea を ムシクイトビ [高野 (1973) ではナマリイロトビ] と名付けたのは当時ニシクイトビの名称を付けた対比の産物だろうか (#トビ備考の [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] も参照)。
この2種については 高野 (1973) の和名の方が適切な感じがする。
Ichthyaetus は当時ハイガシラウミワシ属。現在では通常ウオクイワシ [高野 (1973) ではハイガシラウオクイワシ] で、ハイガシラウミワシ (コンサイス鳥名事典はこちらを採用していた) もハイガシラウオクイワシも英名 (Grey-headed Fish Eagle) 由来と思われる。#オジロワシの備考 [オジロワシ属の系統分類] 参照。
さらに深読みすれば、この英名は英語圏の2種 (オジロワシ、ハクトウワシ) に対する英名で、ハクトウワシの種小名 leucocephalus に対応する white-headed に対して灰色 (おそらく白い方が偉かった) と名付けたものと想像できる。
ウオクイワシはおそらく属名由来だが、Fish Eagle (または Fishing Eagle - こちらの方が対応がよい) の訳と理解することもでき、概念的には総称名に近くむしろ後退してしまった可能性がある。当時の慣習から推定すると、属を代表する種に、種を特定するには不足であっても最も短い名称を与える規則があったのかも知れない (付けられた順序はおそらく逆順だろうが、カモメの和名が種名か総称か区別しにくくなっているのと同様)。
現代では分類が変わってしまい、結果的に統一性の悪いものになってしまった。この点は英名も同様だが英名では種に総称的名称を与えることは避けている。
Brown and Amadon はイヌワシ類をタカ類進化の頂点に位置づけ、それに向かって進化段階を進む描像となっていたが、後の分子系統解析で見事に打ち砕かれた次第。当時の考え方はまず進化段階が最も高いものを定義し (例えばヒト) それに近い形質を持つものから順次上位に置いていた。タカ類ではイヌワシ類に似た形質を持つものが上位に置かれ、そうでないものほど原始的と位置づけられた次第。
興味深いことに週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 66 VII-VIII に「スズメ目の鳥の < 高等 > であることの意味」(浦本) の記事が先に出されており、その中ではかの David Lack が書いた "うがったいい方" (原文) が紹介されていた。
専制政治の時代には鳥の王はワシ、黒いコートを着たブルジョワの共和制の時代にはカラス、今は平民の庶民の主権があり、スズメやヒワがトップとなった。将来の宇宙時代がやってくればアマツバメになるだろうとのこと (現在まだなっていない)。
この見解には David Lack が "Swifts in the Tower" (1956) を著しているようにアマツバメに対する思い入れも含まれているように思える。
分子系統解析が示されるようになって "分類学の権威" の主観ではなく、客観的立場から "平民" が分類学を議論できるようになったのは大きな進展だろうか。そう、現代では分子系統解析こそ "平民" のためのものなのだ (笑)。敬遠しているのはもったいない。
世界のリストが統一化されつつある現状も、誰でも同等のことができる分類学となって "分類学の権威" の個性を反映しにくくなり (専門家にとっては一言で言えば面白くない)、世界の権威が次第に手を引きつつある状況を反映しているのかも知れない。日本鳥類目録第7版から第8版への流れの傾向もこの世界情勢とおそらく無縁ではないだろう。この流れが戻ることはもはやないだろう。
世界のリストの統一化に際して BirdForum などで盛んに議論されているのは、統一化が行われても IOC リストのような透明性が維持されるか懸念があること。
中西悟堂 (「定本・野鳥記 5」収録) がすでに 1940 年にいみじくも指摘していたように (#ホトトギスの備考 [ホトトギスの「忍音」] 参照)、専門家が権威を保つのに有力な方法は手の内を隠して仲間内にしか教えないこと。杞憂であることを願いたい。
この「世界動物百科」の配列は「高等」なものから逆に遡る形となっており、哺乳類は霊長類でゴリラから始まっていた。鳥類編ではアトリ類から。号数の 66 と 114 の順序関係を見てもわかるようにワシタカ目は後 (すなわち下等) の位置づけだった。
ただしアトリ類を高等とする理由付けは難しかったようで、声のよさや巣造りの上手さなどは出てくるがあまり積極的に解説されていなかった。
スズメ目をアトリ類から始めるならば、ワシタカ目の中の配列はイヌワシ類から始まっていてもよさそうだが、なぜか Brown and Amadon の配列に準じて進化段階を進む順序になっていて典型的なタカ類を含む最初2冊の中ではワシ類が最後。逆順では落ち着きが悪いと感じられたのだろうか。
浦本氏のこの解説に対して週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 82 V で森岡弘之氏が反論 ""カラス科の鳥の分類的位置" を述べられていて、系統進化の概念を述べて頭骨や形態的特徴からカラス科は祖先型に最も近い。分類学上の高等・下等と優秀・繁栄は別物と記されていた。
当時は分類学上の高等・下等の表現にはまだ盛んに使われていたが誤解を招きやすいので次第にあまり使われなくなったのだろう。
高等・下等の表現は英語では higher, lower に対応するが higher vertebrates のような表現は今でも使われているので高等脊椎動物と訳さざるを得ない。しかし higher birds とは英語でもさすがにあまり呼ばないらしい。advanced birds とも普通呼ばない。primitive birds とか呼ぶと「始祖鳥のことですか?」となりかねないので表現が専門的になっても系統名を用いて呼ぶのがよいだろう。
[オウム類・ハヤブサ類の年代推定]
オウム類の祖先と思われる約 5400 万年前の化石種 Mopsitta tanta がデンマークで見つかったとの報告があった: Waterhouse et. al (2008) Two new parrots (Psittaciformes) from the Lower Eocene Fur Formation of Denmark。
Mayr and Betelli (2011)
A record of Rhynchaeites, Threskiornithidae) from the early Eocene Fur Formation of Denmark, and the affinities of the alleged parrot Mopsitta
は Mopsitta がオウム類に近縁かを疑問視しており、新たに発見したトキ類らしいより完全な化石からこれと同属と考えている。その場合 Rhynchaeites tanta と改名すべきとある。
時期はこの前になるが Dyke and Cooper (2000) A new psittaciform bird from the London Clay (Lower Eocene) of England
はより完全な約 5500 万年前の化石種 Pulchrapollia gracilis をロンドン近くで発見している。
当時は現代的な分子系統は知られておらず、ハヤブサ系統に関する言及はない。
Mayr (2001) Comments on the systematic position of the putative Lower Eocene parrot Pulchrapollia gracilis
はオウム類ではなく Pseudasturidae Mayr 1998 (現在では Halcyornithidae に含まれるとされる) ではないかと述べている ([オウム類とフクロウ類のモザイクのような化石鳥] を参照)。Ksepka et al. (2019) はこの系統をノガンモドキ類とハヤブサ類の後の分岐でオウム類以前の系統と捉えている。小型種であるがハヤブサ類のように眼窩上の「ひさし」が発達している。
これらはオウム類の祖先の研究であるが、ハヤブサ系統に近縁と考えられているオウム類の祖先がいつどのように生まれたかの情報はハヤブサ系統の出現時期や猛禽類の系統関係についても示唆を与えるだろう。
Zelenkov (2016) The first fossil parrot (Aves, Psittaciformes) from Siberia and its implications for the historical biogeography of Psittaciformes
にも 1600-1800 万年前にシベリアでオウム類の祖先と思われる化石が報告されており、温暖な気候のもとでオウム類が世界的に分布していた時期があることを示している。
これらの化石はオーストラリアのオウム類の最も古い化石よりも古いとのこと。オウム類の起源や古い時期の放散を主なテーマとしている。
(以下は #ヤマセミの備考でカラフルなオウム類の色彩には隠蔽色か警告色の可能性があるのか、の話題からハヤブサ類の出現時期にも関係するためこちらに移動した。一部重複する)
オウム類の天敵を軽く探してみると一般的な記述ばかり目立って具体的にどのような種に捕食されるかあまり書かれていない。アフリカのヨウム (色彩の目立たない数少ない種類だが) を捕食する鳥は少なく、 重要な捕食者の一つはヤシハゲワシ (これまたちょっと意外な種類) とあるページがあった (wikipedia 英語版でも引用されている) が裏付けとなる資料を見つけられなかった。
大型のオウム類の成鳥ではそもそも捕食者があまりないのかも。警告色である必要性もあまりないかも。
オウム類はハヤブサ目に近い系統とされるが分岐したのはかなり古い模様で、オウム類は早い時期 (南半球に広く分布する理由は後述のようにゴンドワナ大陸時代に遡るとの考えがあった。現代的な証拠からは否定され気味) から分布を広げていたが全体としてみるとタカ類、ハヤブサ類の方が新参者。
フクロウ類が昼行性だった可能性は残るが、オウム類が世界に広がっていった時代には昼間に成鳥を捕食する鳥はいなかったかも。
オウム類の研究者の一部はかなり古い年代を考えているようだが、[#鳥類系統樹2024] などの新しい結果とはやや整合性が悪いように見える。
ニュージーランドの飛べない夜行性のオウムのフクロウオウム (カカポ) の色彩二形が絶滅した猛禽類によって維持されていたかも知れないとの興味深いアイデアもある: Urban et al. (2024) The genetic basis of the kakapo structural color polymorphism suggests balancing selection by an extinct apex predator。
かつて絶滅に瀕したこの種は 1995 年に 51 個体まで減少を経験している。2023 年段階で捕食者のいない島に 247 羽が生息している。
絶滅したハーストイーグル Haast's Eagle (#イヌワシの備考 [ハーストイーグル (Haast's Eagle)] 参照) やアイレスチュウヒ(仮名) Circus teauteensis Eyles's harrier (#チュウヒの備考 [チュウヒ類の離島への定着、ニュージーランドの鳥の定着と衰退] 参照) が考えられる。
これら2種の猛禽類はどちらも 200-250 万年前ぐらいにそれぞれ別の系統から種分化し 600 年前ぐらいに絶滅。
色彩二形 (緑とオリーブ色) の違いは紫外線によく現れていて構造色に関係する遺伝子の変異を想定しているが捕食者の色覚を考えると面白いアイデアかも知れない。緑が祖先型でオリーブ色が推定 193 (59-452) 万年前に変異で現れ、捕食者とのバランスで維持されていたと考えている。
もし捕食圧に関係して維持された色彩二形であれば今後遺伝的浮動で 33 (10-94) 世代で失われる計算になるとのこと。緑色のオウムは例えば地上など条件によって鳥類捕食者には多少目立ちやすいことを示唆しているのかも知れない。
この論文は植村・岩間 (2025) Birder 39(2): 66-67 で紹介されている。こちらの方が専門的用語 (頻度依存選択 frequency-dependent selection) を用いていてより難しい気がするぞ (笑)。
頻度 (の用語を使うと絶対数の概念と区別が付かないが、ここでは総対比率のこと) の少ない表現型に比率が少ないことによって有利な点があるならばそのような表現型が維持される可能性がある。選択圧の存在下で実際にどうなるかは数値シミュレーションをしてみないとわからないので、この論文では維持される条件を調べてみた。
関連して役立ちそうな論文を見ておくと Brisson (2021) Negative Frequency-Dependent Selection Is Frequently Confounding 総論。
インフルエンザウイルスの抗原性の変化は比率によるものではなく、このメカニズムによるものではない (wikipedia 日本語版の例はいきなり間違っている。英語版にこの論文を引用して誤解であるとの説明がある。2025.1 段階)。
Clarke et al. (1988) Frequency-dependent selection, metrical characters and molecular evolution
頻度依存選択の効果を取り入れるとしばしばランダムな遺伝的浮動よりも進化を駆動する主要な効果となり得る。
この話題はカッコウ類の赤色型にも関連する (#カッコウの備考 [カッコウ類雌雄の擬態の進化] 参照) のでこちらにも取り上げておく。Merondun et al. (2024) の Abstract にカッコウ類の赤色型の存在は negative frequency-dependent selection (NFDS) 説と対立仮説があったが色彩多形は W 性染色体で決まっていることがわかり、上記の balancing selection の効果で説明できるとの論文であった。
Urban et al. (2024) の論文はいくつもの要素が含まれており、簡単に実行できないのは多くの個体の全ゲノム解析で色彩にかかわる遺伝部位を同定し、その進化をたどった部分と言えるだろう。
頻度依存選択は2形の存在を説明する有力とされる考え方で、捕食者が由来と想定して絶滅猛禽類と関連づけたのはアイデア勝負の部分。いや実はもっと別の役割があるかも知れませんよ (?)。
年代の一致は偶然かも知れないが論文のストーリーとしては面白い (現在は消滅した別の色彩多形があって進化は実はもっと複雑だったかも知れないが、現在の遺伝情報からは知ることができない)。
個人的にはこれら猛禽類がなぜ生まれ、また人が入ったことで絶滅したのか興味深いのでハーストイーグル、アイレスチュウヒの項目を見ていただきたい。他の系統との分岐年代だけで議論してもよいのかなあ、と感じないわけではない。
猛禽類の離島環境への定着や既存生態系の影響など大変奥深い。チュウヒ類に関心のある方は分散能力に注目。人為環境の広がりでミナミチュウヒが進出して競争排除された説は本当か、など面白い点がいくつもある、ということで結局猛禽類の話題になる (笑)。
ニュージーランドへの鳥の定着に関係した新しい研究が出ていた: Lubbe et al. (2025) Plio-Pleistocene Environmental Changes Drove the Settlement of Aotearoa New Zealand by Australian Open-Habitat Bird Lineages
(Repeated invasions shape NZ's bird life 一般向け解説)。
ニュージーランドに定着した各種の鳥の分岐年代を調べると 1000 万年前以降に増え、250 万年前ぐらいから固有種が特に増えた。必ずしも開けた環境に適応した種ばかりではないが、開けた場所の混在する環境に適応して分布を広げた可能性がある。乾燥化にオーストラリアで前適応してニュージーランドへの定着に役立った可能性が議論されている。
関連のある種類をピックアップしておくと、ニュージーランドからみて海外近縁種との分岐年代はアイレスチュウヒ(仮名) Circus teauteensis Eyles's harrier 237 (140-354) 万年前、
ニュージーランドハヤブサ Falco novaeseelandiae New Zealand Falcon 200 (140-440) 万年前、ハーストイーグル 222 (141-325) 万年前など時期が集中していることがわかる。イヌワシの日本への定着にも同じような気候変動に関連して森林内に開けた場所が生じた経緯などが関わっていたのかも知れないとふと考えてしまう (イヌワシはそれほど古い種ではなく他種との分岐年代は 500 万年前より若い。クマタカの分岐も 250 万年前ぐらいでどちらも同じような時期に日本にやってきたのかも)。
オーストラリアからニュージーランドへの飛来は現在でも続いており、論文著者は人為起源の乾燥環境がそれらの定着を容易にすることでニュージーランドの固有種が一層失われてゆく可能性も危惧している。
ちょっと寄り道になってしまったが捕食者のサーチイメージ (探索像) 形成 (論文にも例としてこの記述がある: For example, NFDS through search image formation in the avian predators can theoretically maintain such polymorphisms) は解釈の一つである意味おまけとも言える。
ハーストイーグルやアイレスチュウヒが紫外線色彩に頼る探索を行っていたのだろうか。捕食者が2種いればそれぞれ違う獲物の好みがあっても不思議でないかも。いずれも現存の近縁種から推測することはできるかも知れない。
捕食者のサーチイメージ形成で隠蔽色や色彩多形が生じる議論の総説は例えば Bond (2007) The Evolution of Color Polymorphism: Crypticity, Searching Images, and Apostatic Selection
(ResearchGate; University of Nebraska のサイト)
探しにくいもの2種類をサーチイメージとするより1種類に絞った方が効率的との仮説は魅力的だが検証が難しかった。この議論は他の捕食者でも行えるので猛禽類より他の分類群で進んでいる。
動物行動学的には Tinbergen 時代のアイデアに由来している部分もあり、歴史的背景 (#ハイイロガンの備考 [首の短い鳥は危険?] など参照) も実験結果の解釈もなかなか難しそう
[predators switch among attentional states in response to short-term changes in prey (中略) detection perceptual switching can promote and maintain cryptic color polymorphism とあり、短時間の間の探索像の切り替えが隠蔽色の色彩多形の形成を促す可能性がある 程度の表現にとどめている]。
#カタグロトビ備考の [カタグロトビは偏食家?] を見ると獲物の頻度分布は種にもよるようで、必ずしも特定のサーチイメージに頼っていないかも知れない。一定の種の獲物に偏るより多様性傾向が強い傾向が得られている。いかがだろうか。
サーチイメージの概念だけが取り出されて独り歩きをすると危ない気もする。
Heracles inexpectatus というニュージーランドの巨大オウムの化石種 (1600-1900 万年前) が知られており、体重 7 kg と推定されている。
Worthy et al. (2019) Evidence for a giant parrot from the Early Miocene of New Zealand を参照。記録されている最初の巨大オウム。2008 年に骨が記載された時はワシのものと考えられた。哺乳類のいない島で哺乳類のニッチを占めて巨大化したと考えられる。
フクロウオウム (カカポ) や Nestor 属 [こちらは飛べる現生のオウムであるミヤマオウム (ケア) と カカ を含む]、や Nestor 属に近縁の Nelepsittacus 属とともに最も古い系統のオウム類である Strigopoidea 上科を形成する。現生種については分子系統解析で確かめられている。
フクロウオウムと Nestor 属の分岐は 2700-4000 万年前と推定されている [Smith et al. (2023) Phylogenomic Analysis of the Parrots of the World Distinguishes Artifactual from Biological Sources of Gene Tree Discordance fig. 4 参照]。
古い系統かつ失われた系統も多いためオウム類の内部でも系統関係を探るのが難しかった模様。
この巨大オウムはフクロウオウムの祖先にあたる可能性も示唆されている。
なおニュージーランドとゴンドワナ大陸の分離は 8200 万年前と推定され、オウム類の起源を古く見積もる根拠となっていた。cf. Wright et al. (2008) A Multilocus Molecular Phylogeny of the Parrots (Psittaciformes): Support for a Gondwanan Origin during the Cretaceous。
この考え (Nature に発表された) は過去かなり受け入れられていろいろなところで紹介されている。
この時代はオウム類とハヤブサ類の近縁性が明らかになりつつあったころで、この結論を受け入れるとハヤブサ類も K-Pg 境界以前から存在した系統であることが示唆されることになる。
肉食恐竜のそのままの生き残りが恐鳥類であってノガンモドキ類のような猛禽類を生み出した、のような歴史認識にもつながってくるわけである。
この Wright et al. (2008) に先立って白亜紀の化石記録からオウム類の起源は古いとの考えがあり、川口 (2022) Birder 36(10): 54-55 で紹介されていた。論文は Stidham (1998) A lower jaw from a Cretaceous parrot (Parrot Fossil from the Cretaceous Pushes Back Origin of Modern Land Birds 大学のプレスリリース)。
Dyke and Mayr (1999) Did parrots exist in the Cretaceous period? が早速反論。
Stidham (1999) Did parrots exist in the Cretaceous period? が再反論。川口氏の記事は Dyke and Mayr (1999) の反論まで触れられているがその後はわからないとなっていた。分子系統研究については触れられていないため、この記事だけを読むとまだわかっていないことが多いのだなと思ってしまいそう。
一方 Schweizer et al. (2011) Macroevolutionary patterns in the diversification of parrots: effects of climate change, geological events and key innovations
はこれまで考えられていたほどは古く種分化が起きたものではなく、海を越えた移動がなければ説明できないパターンと示しているとした。
そして上記の Smith et al. (2023) のような近代的な分子系統研究によってやはりもっと若かった見解が一般的となった模様。
Hunag et al. (2022) Recurrent chromosome reshuffling and the evolution of neo-sex chromosomes in parrots の見積もりでは Strigopoidea 上科とそれ以外の分岐は 3180 万年前程度とやはりそれほど古いものではなかった。この図を見るとオウム類は新しく種分化したグループに見える。
参考までにこの研究は全ゲノム解析を行っておりオウム類には transposable elements が多く (#ハシボソガラスの備考参照)、染色体再編成も頻繁に起きている (染色体数も種ごとの違いが大きい)。オウム類に特有の DNA 修復遺伝子 ALC1, PARP3 の欠損が原因である可能性が高いとのこと。
このように見るとニュージーランドへのオウム類はかなり古い時期の定着のみで複数回の定着があったわけではなさそう。海を越えた定着はやはり難しかったらしい。
この時代には (知られている範囲で) 猛禽類もいなかった。オウム類の方が猛禽類よりも早く定着したのは、ニュージーランドはオウム類が進化した地域に近い一方、タカ類はアフリカ起源と考えられるようにニュージーランドへの到着に一層の時間がかかったためだろう。
ニュージーランドで長年のびのび暮らしていたオウム類にとって、200-250 万年前の大型猛禽類の定着は青天の霹靂だっただろう。わずかな種類しか残っていないのはその影響もあったのかも知れない。それら大型猛禽類も今はいなくなってしまったが。
フクロウオウムの wikipedia 日本語版には 100 万年ほど前にニュージーランドにやってきたとある (2025.5 現在も同様) がこの情報は相当古いものかも知れない。「フクロウオウム保護計画」の項目は最新データが入っているのに (?)。
Halcyornithidae などの位置についてはまだ議論があり、Mayr and Kitchener (2022) Psittacopedids and zygodactylids: The diverse and species-rich psittacopasserine birds from the early Eocene London Clay of Walton-on-the-Naze (Essex, UK)
によれば骨学による系統分類 (化石種ではそうならざるを得ないが) では、現生種を同様に分類した場合に分子遺伝学が示唆するようにオウム類がハヤブサ類が近くではなくネズミドリ、キヌバネドリ、あるいはブッポウソウ類やキツツキ類系統に近くなってしまうなどの問題があり骨学による系統分類は注意して見る必要があることが述べられている。
Psittacopasseres (オウム類 + スズメ目。以下参照) の祖先的形質と考えられる対趾足 (zygodactyly) の特徴を示す Zygodactylidae が単系統である証拠は得られていないとのこと。
[人語を理解し用いるヨウム]
ヨウムの話はあまりに有名で特段取り上げてこなかったが、関連論文が出ているので紹介しておく。日本産種ではないのでどこに入れるか悩ましいがオウム類つながりで暫定的にここに置いておく。
Roubalova et al. (2024) Comparing the productive vocabularies of grey parrots (Psittacus erithacus) and young children
チェコとスロバキアで複数のヨウムを用いて発声 ("単語") の多様性を言語学習中のヒトの幼児と比較したもの。幼児は発声は物や状況、感情を表すラベルがより多かった (実はあまり違わなかった) が、ヨウムの方は挨拶などの会話の複数語からなるものが多かった。
この論文に対して Pepperberg (2024) Comments on "Comparing the productive vocabularies of Grey parrots (Psittacus erithacus) and young children" がコメントを寄せている (もちろんあの有名な Pepperberg)。
人とヨウムの違いを調べたというより、Their emphasis might instead be on how amazing it is that pet parrots actually can acquire so much given the impoverished input they received. とのこと (極めて乏しい入力からヨウムがこれほど多くのことを獲得できることは驚くべきである)。
I agree that some species-specific predispositions toward acquisition of a conspecific communication code in parrots do exist, and that I would find it very unlikely that any parrot, whatever the input it received, would acquire all the elements of full human language ...
(ヨウムの同種間のコミュニュケーションを獲得する種特有の code はある程度あるだろうが、どれほど情報を与えてもヨウムが人の言語のすべての要素を獲得できるとはさすがに思えない。ただし人の言語を学ぶ際の最適な code が何であるかは我々はまだ知らない) などと書いている。詳しくは原文をどうぞ。
[英語 "birds of prey" の由来]
猛禽類は英語では birds of prey と呼ばれるが、なぜ "of" なのかを疑問に持つ人はやはりあるようで、Why do we call predator birds "birds of prey"?
に議論がある。いろいろな説が現れているが、prey は古フランス語の proie, preie, praie に由来し、"of" は "〜に関係した" の意味との解釈が出ている。
猛禽類のフランス語でのかつての名称は oiseau de proie (単数形) でこれを直訳したのではないか。
フランス語では属性を表す意味以外にも英語の "of" 以上に "de" をよく使うので直訳されたものとしても驚かない。
このフランス語も中世ラテン語 avis praedae を訳したもの。ラテン語 praeda には奪略などの意味があって狩猟の獲物は第2語義となっている。"奪略する鳥" (この意味では現在は改名されたドイツ語の Raubvogel と同じ) の意味だったよう。
現在の英語名詞の prey はラテン語の第2語義の方が一般的で、そのため "of" を用いることに違和感を感じるのだろう。辞書を調べると英語名詞にも奪略の意味は残っていて数えられない名詞とのこと。そのため bird of prey の prey の前には冠詞が不要。しかし獲物を表す語義の場合は数えられる名詞で catch a prey のような使い方になる。
英語の prey も動詞の方には捕食するの意味が残っている。自動詞なので目的語には前置詞が必要で prey on のような使い方になる。
英語では形容詞の predatory の方にラテン語の第2語義も単語の形もよく残っている。
[オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか]
従来の Falconiformes (タカ類 + ハヤブサ類) が単系統でない可能性は卵白電気泳動パターンから Sibley (1990) The electrophoretic patterns of avian egg-white proteins as taxonomic characters
が提案したが、それ以前にハヤブサ類は他の昼行性猛禽類に近くないかも知れないとの示唆がなかったわけではない。
Jollie (1976, 1977) の論文
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part IV) (総括部分)、
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part II)
は羽毛、骨格、筋肉、内蔵、外部形態からタカ類とハヤブサ類は共通祖先を持つと解釈できないと述べていた。タカ類・ハヤブサ類内部では現在の分子系統に近いものを導いていた。p. 306 から "Phylogeny within the Falconiform Groups" を参照。p. 323 から "The Place of the Falconiforms in the Class Aves"。
なお Jollie は 1953 年に Are the Falconiformes a monophyletic group? (オープンアクセスではない) の論文を出しており、単系統性に疑問を抱いていたことがわかる。
冒頭はフリーで見ることができて、Theressa Clay (1951) はハジラミの研究から Falconiformes は単系統と主張していた。Garrod, Gadow, Fuerbringer, Forbes も Falconiformes 内部の形態的類似性が乏しいため Cathartidae (ハゲワシ類)、ヘビクイワシ、Falcones (残りすべてのタカ・ハヤブサ類) と分けていて、ミサゴの特異性には誰もが注目していた。これらの著者によれば Falconiformes は単系統でないとの合意が得られていたとのこと。
#イヌワシの備考 [ハーストイーグル (Haast's Eagle)] で紹介の Holdaway の学位論文 (1991) は Jollie の数値データも用いて現代的なアルゴリズムで系統解析したもので、もし Jollie (1976, 1977) の時代に同じような計算機やソフトウェアが使えていたならば同じような結果を出すことができていただろう。
と思ったのだが、Holdaway の学位論文 (1991) は Jollie (1976, 1977) と結果が異なる部分もあり、Jollie の方が (現代のものと比較して) 正しい結果を導いている部分も見られるので計算機やソフトウェアが使えた方が正しい結果が得られるというわけでもなさそう。
Jollie (1976, 1977) p. 327 では従来提唱されたワシタカ目は人工的に作られた寄せ集めで (以下現代の名称があるものはそれに合わせて表記)、ヘビクイワシ目 Sagittariformes、コンドル目、タカ目、ハヤブサ目に分類され、それぞれの間の違いは他の目の間の違いと同程度であると述べている。
ただし当時の知見では他の鳥類と関係はあまりよくわからず、ヘビクイワシ目、コンドル目は水鳥や水辺の鳥に近いと考えていた。ヘビクイワシとノガンモドキ類の関係は検討されていたが当時は資料がほとんどなかった模様。むしろ収斂だろうと考えられた (p. 233)。
p. 230 ではヘビクイワシの嘴がコウノトリ類から進化可能かを考察しており、Jollie はコウノトリ類の一部はハゲワシに似た生活様式をとっているが嘴の形は変わっていない。足についても同様。
コウノトリ類の嘴は進化の行き止まり (dead end) で、タカ類の生活様式に合わせて進化させることはできなかったであろう。ヘビクイワシは猛禽類型の鳥から派生して地上型になったと考える方がよりもっともらしいと述べていた。
当時のワシタカ目、特にタカ類と従来言われていたコウノトリ類の類縁関係には懐疑的見解を示していた。
一方ハヤブサ目は樹上性の鳥類に近い。フクロウ類やオウム類との骨格の関係も検討されたが類似性は高くないとされた (p. 233)。
タカ目は残りのグループからは際立っていて地上性のスカベンジャーや捕食者の最初の系統だろうと考えていた。
ハヤブサ目とタカ目は共通性が乏しく、よく似て見えるのは収斂進化だと述べている。
Sushkin (1905) はモリハヤブサ類 Micrastur がタカとハヤブサの中間型 (#ハヤブサの備考 [ハヤブサ目の系統分類] で紹介) でハヤブサ目とタカ目は連続していると主張したが、Jollie はその可能性を否定した。
Jollie による一貫した主張はハヤブサ類はタカ類よりも当時のワシタカ目以外と類似性がある。従来の分類は形態学的類似性よりも捕食性の生態に頼ったものである。現代の知見からみると極めて先見の明のある結論を下していた。現在の各種資料などであまり言及されていないのが不思議。
Brown and Amadon (1968-1969) "Eagles, Hawks and Falcons of the World" が大家だったために議論することすらはばかられていたのかも知れない。
一方で Griffiths (1994) Monophyly of the Falconiformes Based on Synringeal Morphology は鳴管構造から従来の Falconiformes はこれまでの考え通り単系統と主張していた。
ただし鳴管構造は Jollie (1976, 1977) もすでに調べており、系統分類には (他の多くの特徴を凌駕するほどには) 有用でない結論を下していたので Griffiths (1994) にそれほど目新しい内容が含まれているわけではなかった。
Bildstein (2017) "Raptors" でも参考文献は Griffiths (1994) を挙げており、本文でも Jollie への言及はない。当時の研究者にとっては Griffiths の方が影響力が高かった模様で、Bildstein も分類学や系統学が専門というわけではないのでやむを得ないところだろうか。
想像をたくましくしておくと、鳴管構造がそれほど重視されたのはスズメ目が最も "高等" とされ、スズメ目の分類に鳴管構造が役立ったため、また系統を考える上では (進化の最後の段階のはずの) スズメ目とどの程度近いかが重視されたためではと思える。従って Jollie (1976, 1977) が意図的に無視されていたのでなければ、さまざまな点を調べるよりも鳴管構造のみに着目した研究の方が受けがよかったかも知れない。さまざまな分類で鳴管構造と出てくれば、スズメ目を頂点に置く価値観が背景にあるかも知れないと思っておいてよいだろう。
[猛禽類の分類など] の「スズメ目の鳥の < 高等 > であることの意味」(浦本) の項目も参照。
Bildstein (2017) では Brown and Amadon (1968-1969) でほとんど結論されていたような書き方でその次は分子系統学による進展まで飛んでいる。
一般書を参照しつつ総説をまとめるとこのような形になりがちなのだろう。
系統に関する記述は一般書でも Brown (1976) の方が詳しかったが、Jollie の論文の出る前なので成果は紹介されていない。
Mayr and Clarke (2003) The deep divergences of neornithine birds: a phylogenetic analysis of morphological characters も形態学から旧 "Falconiformes" (Cathartidae, Sagittariidae, Accipitridae, and Falconidae) が単系統でないことを示していたが、タカ科とハヤブサ科はまとまると考えていた。Holdaway の学位論文同様、形態学的類似性のスコアだけで見るとそのように見えてしまうと考えられる。
この研究でも Jollie にはほとんど言及がなく真面目に検討されていなかったらしい。この時代にはフラミンゴ類とカイツブリ類の類似性が分子系統研究からすでに示唆されていて形態学でも再現できるとのこと。
茂田 (2007) Birder 21(10): 68-70 「ハヤブサとタカはどう違う」の記事で Jollie (1976, 1977) は引用されていたが分類の試行錯誤のステップのひとつとしか捉えていなかった模様。Jollie が非常に詳しく調べているのに比較表には含まれておらず、情報は山階 (1941)、Johsgard (1996)、Ferguson-Lees and Christie (2005) を参照している。
形態学は山階 (1941) によるものと思われる。
Ferguson-Lees and Christie の書物は分類学には詳しくないので、生態的比較はともかくあまり適切な引用先ではないだろう。
茂田氏の記事の中でもモリハヤブサ類とワライハヤブサは原始的なハヤブサ類で中間型の見解が紹介されているが、引用文献は Jollie (1976, 1977) となっている。Jollie はこの考えを否定している点が重要なのだが茂田氏は過去の記述に引きずられたのか誤解している。
Jollie の分類提案は非常に正しかったのだが (ハヤブサとタカが別系統であることは各セクションでくり返し述べられている)、論文が大部のため結語だけを中心に読むと印象が薄いのかも知れない。結果的に先駆的研究が適切に紹介されることなく終わっていた。Birder の茂田氏のものは 2007 年とかなり新しい記事だが、その直後に分子系統研究でひっくり返ってしまった次第。
この記事と直後の認識の変化だけを見ると、形態学はやはり役に立たないではないかのように思えてしまうが、これは Jollie (1976, 1977) の知見が正しく紹介されていないためであった。
特に筋学の知見は重要で、ある筋肉の配置は進化しても別の系統の配置にならないだろう推論は比較的確実に行いやすい。軟部組織の残っていない化石のような骨学では筋学は推定に頼る必要があり判断しにくい部分とも言えるだろう。
分子遺伝学によってハヤブサとタカの関係が急に変わったかのように思えるが、過去の研究が適切に紹介されなかっただけで実はそうではなかった。分子遺伝学の結果が出る前から議論が連続的に進められていてもまったく不思議でなかった。
この時代の形態学による上位 (高次) 分類としてしばしば取り上げられる Livezey and Zusi (2007) Higher-order phylogeny of modern birds (Theropoda, Aves: Neornithes) based on comparative anatomy. II. Analysis and discussion
では Fig. 16 に該当部分があるが、タカ、ハヤブサ、フクロウ類をまとめて Falconimorphae としており、Falco + Polyborus が Pandion から始まる枝に含まれていた。
全体的には現代の分子系統研究の結果に近い部分もあり、そうでない部分もある。
タカ、ハヤブサについては Jollie (1976, 1977) についても言及があるが "largely limited to anatomical phenetics and influenced by suspicions of functional convergence" との言及で、おそらく論文の個々の項目をあまり吟味せず重視していなかったらしい。この Livezey and Zusi (2007) から孫引きしてしまうと Jollie (1976, 1977) の主張の新規性が簡単に歴史に埋もれてしまうだろう。
Livezey は形態学で系統研究を極めていたが、#カイツブリの備考 [フラミンゴ目とカイツブリ目の関係] にも現れるように自身の信念をなかなか捨てられなかったのかも知れない。異なる結論を導いた Jollie (1976, 1977) をあまり読まずに一蹴してしまった可能性がある。
当時始まりかけていた分子系統学も自身の結論をサポートする部分を選んで取り上げている印象があり、分子系統学でも収斂現象があるので形態学より正しいとは言い切れないなど書かれている。新しいものを受け入れない理由でよくあるタイプの批判。
当時の Falconiformes が Sibley and Ahlquist (1990) の唱えるようにコウノトリ科に含まれるのではないことは示されている。過去なぜコウノトリ類に近縁と考えられたか文献も紹介しているのでこの部分は参考になると思われる。
引用文献を頼りに少し後の進展を見ておくと (古い論文はオンラインで見られないものが多いので)、新世界ハゲワシ類とコウノトリ類が近縁である主張は、初期の分子系統研究でもなされていたが手法上の問題点も指摘されていた: Johnson et al. (2016) Multi-locus phylogenetic inference among New World Vultures (Aves: Cathartidae)
の導入部分を参考。新しい方の研究では Kimball et al. (2013) までは系統が近いと見ていたが、それ以降の研究では系統が遠い結果を与えるようになっていた。これを見るとタカ、ハヤブサの関係以上に比較的最近まで決着していなかった。
Mundy (2023) Commentary : The correct names of Old World vultures and their sequence ではハゲワシ類の現代の知見を紹介し、従来の Falconiformes が単系統でない主張は Jollie (1976, 1977) に遡ると正しく紹介されていた。参考までに。
Livezey and Zusi (2007) の結論のフクロウ類がヨタカ類に近縁でなく Falconiformes に近い系統である点は正しい結果だった。
他の分類群も見ていただくと面白いだろう。よい線を行っていると思える部分もあれば、伝統的分類やみかけの類似性に引きずられたのかまったく異なっている部分もある。
ノガンモドキ類も Jollie (1976, 1977) とはまったく違う場所に置いている。Jollie を批判しているのに自身が収斂に引きずられていたのだった。
この問題は共通するレトロポゾンの存在で 2011 年に明確な結論が出て Livezey (ただし 2011 年事故死) も文句を言えなかっただろう。この時期あたりから高精度の分子系統研究の優位性が確定的になってきた。
Livezey and Zusi (2007) を当時の最新鳥類全系統の分類と捉えた人はおそらく Jollie (1976, 1977) の業績を適切な形で知ることなく終わって若干不幸だったかも知れない。特にタカ、ハヤブサについてはその直後に分子系統研究でひっくり返ってしまったので落差が大きかっただろう。
分子遺伝学の方では、オウム類とスズメ目の系統が近いことは Hackett et al. (2008) A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History
による核 DNA 解析で示された。そしてこのグループとハヤブサ類が近いことがわかったのが一番驚きの発見であった。用いる遺伝子によって結果は多少異なったが、これらのグループが近縁である点は疑いなかった。
この論文に先行して Ericson et al. (2006) Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils
がハヤブサ類を除いたタカ類がまとまることが示されたがハヤブサ類とオウム類、スズメ目との関係は明瞭でなかった。系統樹も現在使われているものとはやや異なって、これら陸鳥のグループは大絶滅前に分岐して大絶滅を生き延びた形態になっている。
また Gibb et al. (2007) Mitochondrial Genomes and Avian Phylogeny: Complex Characters and Resolvability without Explosive Radiations
がミトコンドリアのコントロール域の重複現象のパターンから系統推定を行っている。当時からハヤブサ類の位置が問題であったことは認識されており、2001 年ぐらいにはすでに問題となっていたことがうかがえる (古く DNA-DNA hybridization の時代でも落ち着いていたわけではなかった)。
この研究ではハヤブサ類とタカ類に距離がある傾向は出ているがコウノトリ類などの水鳥と同じグループに入ることは DNA-DNA hybridization 時代とそれほど違いがなかった。オウム類 (ここではフクロウオウム) はこちらの方のグループに入っている。これらはスズメ目とはまったく違う枝になっている。
核 DNA のある程度詳しい解析が行われるまでまったくわからなかった関係性だったのだろう。
新世界ハゲワシ類はかつてコウノトリ類の近くに置かれる扱いもあったが、この論文で (タカ類を含む) 陸鳥グループに属することがわかった。
Suh et al. (2011) Mesozoic retroposons reveal parrots as the closest living relatives of passerine birds
で共通するレトロポゾン (またはレトロトランスポゾン。ゲノム上の位置を転移することのできる塩基配列。そのうち転写と逆転写の過程を経る RNA 型でレトロウイルスの起源である可能性もある) の存在から Psittacopasseres (オウム類 + スズメ目。中国名では鸚雀総目) の概念が導入された (そしてこの文献で音声学習の起源が共通祖先である 3000 万年以上前に遡る可能性が示された)。
ハヤブサ類を含めて共通するレトロポゾンも存在して {Psittacopasseres + ハヤブサ類} を Eufalconimorphae (中国名では真隼形鳥、ロシア名では sokolopodobnye でハヤブサ類縁類。eu- の意味を考えると前者の訳の方が良さそうである) とする概念も導入された。
このグループが系統的にまとまっていることにはおそらく疑問の余地がない (ハヤブサ類がオウム類に近縁と証明されたのはこの時点と言ってよいだろう)。
ノガンモドキ類も含めて共通するレトロポゾンがあるのでここまでの系統関係はおそらく問題ないだろうが、それ以外の近代的な陸鳥の系統にはそのような決定的なマーカーがなく、この方法で {Eufalconimorphae + ノガンモドキ類} がどの系統につながるかは判定できない。通常の系統分類ではこのグループが前述の Australaves になる。
いずれにしても分子系統学によるオウム類とハヤブサ類の近縁性は 2008-2011 年に解明されたもので最近の出来事である。ハヤブサ類の特集などは Birder でもたびたび行われたが、少し古い時代の記事の時代はこの近縁性がまったくわかっていなかった (電気泳動に触れている記述はわずかにあった) ことを意識して読むのがよいだろう。
山崎 (2017) Birder 31(1): 8-9 "タカとハヤブサ、どこが違う?" の記事があり、歴史にも触れられている。タカとハヤブサの関係は従来考えられていたより遠いとの認識が広まった記述があるが具体的には触れられていないので、文献にも現れる考えであったのか、あるコミュニティー内の認識であったのか区別できない。
タカとハヤブサは同じ系統だが非常に古く分かれたもの、との認識であれば現状の理解と大きく違うわけではない。現代ほぼ確かと考えられているのはタカとハヤブサの間に直接の分子遺伝学的関係がみつかっておらずおそらく単系統をなさない点で、"非常に古く分かれた" だけであれば現在の理解とあまり違わない。
興味深いのはオウム類の方が早い時期から世界的に化石が豊富で、ハヤブサ類の祖先からオウム類が分かれた現代の描像と微妙に異なる。山崎 (2017) は Prum et al. (2015) (#アマツバメの備考参照) の解釈がベースにあると思われるが、共通祖先が捕食者であったかどうかはまだ議論の余地があるところだろう。
なお [タカ類の初期の適応放散] の項目にある Gatesy and Springer (2022) の研究によればレトロポゾンを用いた解析でも決定打とは言い切れない可能性がある。ノガンモドキ類が最初の系統であればノガンモドキ類からハヤブサ類、タカ類、フクロウ類が生じた可能性も残り、{ノガンモドキ目 + ハヤブサ目} とタカ目が独立した系統とならないかも知れない。
[#鳥類系統樹2024] でもタカ類の位置づけは依然難しい問題で、{タカ類 + フクロウ類} のクレードを確固たるものとみなしていない。
Catanach and Johnson (2015) Independent origins of the feather lice (Insecta: Degeeriella) of raptors
はタカ・ハヤブサ類のハジラミの分子系統樹からタカ類とハヤブサ類の系統が分離していることを示し、両者が近縁でない証拠の一つとしている。ハヤブサ類のハジラミはキツツキ類のものと類縁性があり、タカ類のハジラミはハチクイ類のものと類縁性があるとのこと。
現代の標準的な分子分子系統樹ではキツツキ類もハチクイ類もブッポウソウ類系統になるので他の分類群との関係については何とも言えないかも知れない。
日本産であるため (+ 猛禽類ひいき) ハヤブサ類の位置が特に気になるわけであるが、それではオウム類はかつてはどこに配置されていたのか日本産リストを見てもわからない。ちょっと古い方の分類に当たってみるためにコンサイス鳥名事典を見ると (いずれも当時の名称で示す)、ハト目、オウム目、ホトトギス目の順序で、フクロウ目、ヨタカ目、アマツバメ目と続いていた。
ハヤブサ類 (タカ類も同様) の位置が現代とは大きく違っていたが、オウム目の位置もまったく違っていた。ハヤブサ目とオウム目が近いことが判明したことは衝撃であったが、それらは従来の見解と全く異なりスズメ目の系統の方に入ることの方がより衝撃的であったかも知れない。
第7版、第8版のこの部分の目配列を見ると第7版時代の方がむしろ先進的で現代の知見に近く、第8版はオウム目こそ移動されているものの過去の考えが少し復活しているように見える。いかがだろうか。
非特異的免疫遺伝子から見る系統関係・哺乳類との比較
他の項目にも関係するがハヤブサ類とオウム類の近縁性がさらに明らかになった: Gonzalez-Acosta et al. (2025) Exploring Diversity in Avian Immune Defence: Insights from Cathelicidin Clusters (オープンアクセスでない)
公開ゲノムデータを用いて非特異的免疫に関与する Cathelicidin Clusters の研究 (カテリシジンまたはカセリサイディン cathelicidin antimicrobial peptide, CAMP 抗菌ペプチド。いわゆる白血球が細菌を殺す。wikipedia 日本語版より。英語版にはニワトリでも知られている記述がある)。
通常の鳥類では第 1, 2 染色体の末端に存在するがハヤブサ類とオウム類は例外とのこと。
Galloanserae キジカモ類は cath1 を持っている点で他の鳥類と異なる。cathB1 はカモ目で偽遺伝子化していると考えられる。cath3 はスズメ目で失われており、ハヤブサ目では偽遺伝子となっているとのこと。cathelicidins の遺伝子が多数見つかりよく保存されている。鳥類の免疫に重要な役割を果たしていると考えられるとのこと。
まだ同一目内では少数の種 (26 目 72 種) を用いた研究で、遺伝子の喪失や偽遺伝子化は系統によって独立に起きた可能性もあるため、今のところ状況証拠が増えてきている段階と解釈すればよいだろうか。
この分野の少し前の論文を見ておくと: van Dijk et al. (2023) Evolutionary diversification of defensins and cathelicidins in birds and primates (レビュー論文)。鳥類と霊長類の host defense peptides (HDPs) に類似点が多いとのこと。
β-defensin 遺伝子はゲノムサイズの制約から鳥類の方が少ないが、cathelicidin は複数の系統で保存されていて霊長類よりレパートリーが広いとのこと。鳥類と霊長類の間で β-defensin のタンパク質の β-シート構造が保存されており免疫受容体を介した収斂進化の考え方を支持するとのこと。
この論文はオープンアクセスで見られ、上記論文よりサンプルは少ないがほぼ相当する系統関係を見ることができる。(この論文の表記に従う) CATH-2 では {ハヤブサ類、オウム類、スズメ目} とキジカモ類は分かれる。CATH-3 で見ると {オウム類、タカ類} がまとまる (スズメ目では欠損。ハヤブサ類は偽遺伝子のためこの図には含まれていないと思われるがおそらくオウム類と同じ枝に乗るのだろう)。CATH-B1 で見るとオウム類とハヤブサはあまり近くないなど系統関係の判定に用いるにはまだまだ検討を要しそう。
ヒトで知られている cathelicidins である LL-37 と他の霊長類、鳥類のもののタンパク質立体構造の比較が出ている。ハヤブサ類と言っても調べられているのは Falco 属のみなので系統関係を議論する際にはおそらく注意が必要。ハヤブサ目の他の系統では偽遺伝子化していないかも知れない。
鳥類と霊長類の比較では、鳥類では霊長類に比べて皮膚の defensins が少ないが、羽毛に守られているためとの解釈がある。哺乳類の脂腺機能からの類推から尾脂腺から defensins を分泌している可能性がある (この時点ではまだ調べられていない)。哺乳類では defensins の不足による皮膚疾患 (アトピー性皮膚炎や乾癬 psoriasis) が知られているが不思議なことに鳥類での報告はないとのこと。
β-defensin は鳥類・霊長類とも生殖器に広く分布していて卵管から総排泄孔に至るまで多数の AvBDs (ここでは鳥類タイプの総称) が発現しているとのこと。卵や胚を病原体から守る機能があると考えられる。ヒトの膣・子宮・胎盤でも同様 (HBDs。H は Human のこと) とのこと。オスでも精巣や精巣上体に多数発現している。β-defensin は鳥類・霊長類ともに確実な受精のためや病原体から防御機能を果たしていると考えられるとのこと。
cathelicidins は鳥類・ヒトともにやはり生殖器に広く分布しているとのこと。
哺乳類・鳥類で進化は少し違っており、哺乳類ではゲノムサイズの制約が小さいため β-defensin をあまり失わなかった。cathelicidins は霊長類では1種類のみ (ヒトでは LL-37) で広くカバーしているが鳥類では遺伝子重複で複数の遺伝子を獲得したとのこと。
参考までに van Hoek et al. (2019) The Komodo dragon (Varanus komodoensis) genome and identification of innate immunity genes and clusters によればコモドオオトカゲでは 66 種の β-defensin の遺伝子が見つかったとのこと。
β-defensin を多数持っている点では哺乳類の方が爬虫類的だったりして (笑)。
共通祖先段階に遡るものだが K-Pg 境界の絶滅後の適応放散に合わせて2種類の非特異的免疫遺伝子族をそれぞれ進化させ、共通の選択圧のもとで似ているが違いもあるシステムを構築した描象でよいだろうか。羽毛があるために鳥類では皮膚免疫の役割が相対的に小さくなっているのかも。
Peel et al. (2025) Marsupial cathelicidins: characterization, antimicrobial activity and evolution in this unique mammalian lineage
では cathelicidins は鳥類・哺乳類の共通祖先段階からあり、classic cathelicidins は哺乳類が分岐してから誕生したもの (現在まで鳥類で見つかっていない) との仮説を示唆するとのこと。
鳥類型の non-classical cathelicidins は祖先型に近く、哺乳類の真獣類では失われたと考えているが、有袋類や単孔目が持っている可能性も考えられれさらなる検証が必要とのこと。
鳥類はなぜウイルス性肝細胞がんにならないか: Kaur et al. (2025) Comparative structural insights of X protein across species and the "lost" BH3-like domain that may explain the absence of hepatocellular carcinoma in birds
系統関係に直接及ぶわけではないが紹介。鳥類でも肝炎ウイルスは存在するがなぜか哺乳類のような肝細胞がんは報告されていない。鳥類ではストップコドンへの変異のためにがん化に関連するタンパク質が作られず、がん化能力が失われたと考えられるとのこと。もとあったものを失って逆に役立った例。ウイルスの系統樹を見ると宿主の系統順序とあまり対応していないように見えるが、これはおそらくサンプルが少なすぎるためだろう。
鳥類・哺乳類以外ではどのようになっているのか、単なる偶然なのか何かの適応的意味があるのかなどは今後調べられて行くだろう。
ゲノム精度の問題はやはりあって、従来キジ目が失ったと考えられていたインターフェロン制御因子 (IRF3, IRF9) が発見されたとのこと: Ungrova et al. (2025) Avian interferon regulatory factor (IRF) family reunion: IRF3 and IRF9 found。読み取りの困難なゲノムの部分にあったとのこと。
アヒルでの実験ではウイルスによる細胞死を避けるために IRF9 が不可欠であったのこと。
[日本産タカ類を新しい分類で見る]
Catanach et al. (2024) の分類 (#アカハラダカの備考参照) を取り入れて日本産タカ類の一覧を作ってみた (第8版で検討種になるものも含めている)。
系統が少し離れるところに空白行を入れてある。現 Accipiter 属の分割結果もふまえた分類と学名になっている (これら学名は海外の主要リストにはまだ現れていないが論文でもすでに使われている)。
順序は Catanach et al. (2024) の系統樹に合わせているが、属内の違いはわずかなこともあるので今後細かいところで多少入れ替わるかも知れない。(当初は 2023 年の preprint を用いていたが 2024 年のもので入れ替わった部分は発生した)。
大きなところでは (a), (b) の順序は逆になるかも知れない。新属の和名などは私案である。
約 10 年後 (?) の改訂第9版はきっとこのようになっているだろうと推定したもので、ごく近い将来の分類では日本産タカ類はこんな感じになるらしいことを感じ取っていただければと思う。またこの分類はタカ類個々の種の備考を読む上でも参考になるだろう。
この分類は近年の海外動向や文献などを調査した上で作ってあるので、日本鳥学会の目録にこだわる必要のない方は学名などをすでに使っていただいて構わないだろう (近い将来に変わることが予想されるため)。
wikipedia 英語版は最新情報をかなりよく取り入れていて (東洋の種は相対的に手薄だが) 属内の順序が変わる程度でこの分類とそう大きく違わない。現 Accipiter 属の細分については wikipedia 英語版説明の中では触れられているが Catanach et al. (2024) は執筆現在ではまだ触れられていない。
(追記: 2024年8月に IOC 14.2 で採用され、wikipedia 英語版も IOC に合わせて修正された)。
世界のタカ類を全部入れると世界の種類との関係もわかってもっと面白いかも知れないが、さすがに数が多いので日本産に限った。
ミサゴ科 Pandionidae
ミサゴ属 Pandion
ミサゴ Pandion haliaetus
タカ科 Accipitridae
カタグロトビ亜科 Elaninae (カタグロトビ科 Elanidae が提唱されている。科になる場合はミサゴ科とタカ科の間になる)
カタグロトビ属 Elanus
カタグロトビ Elanus caeruleus
ハチクマ亜科 Perninae
ハチクマ属 Pernis
ハチクマ Pernis ptilorhynchus
カンムリワシ亜科 Circaetinae
カンムリワシ属 Spilornis
カンムリワシ Spilornis cheela
クロハゲワシ亜科 Aegypiinae
クロハゲワシ属 Aegypius
クロハゲワシ Aegypius monachus
イヌワシ亜科 Aquilinae
クマタカ属 Nisaetus
クマタカ Nisaetus nipalensis
カラフトワシ属 Clanga
カラフトワシ Clanga clanga
イヌワシ属 Aquila
カタシロワシ Aquila heliaca
イヌワシ Aquila chrysaetos
(a)
(古典的名称のハイタカ亜科 Accipitrinae *1) [Lerner and Mindell (2005)。この概念は単系統でない]
ツミ属またはアカハラダカ属 (タイプ種を優先すれば後者) Tachyspiza
ツミ Tachyspiza gularis
アカハラダカ Tachyspiza soloensis
ハイタカ属 Accipiter
ハイタカ Accipiter nisus
オオタカ属 Astur
オオタカ Astur gentilis
(古典的名称のチュウヒ亜科 Circinae)
チュウヒ属 Circus
ウスハイイロチュウヒ Circus macrourus
ハイイロチュウヒ Circus cyaneus
マダラチュウヒ Circus melanoleucos
ヨーロッパチュウヒ Circus aeruginosus
チュウヒ Circus spilonotus
(b)
ノスリ亜科 Buteoninae
トビ族 Milvini
トビ属 Milvus
トビ Milvus migrans
オジロワシ属 Haliaeetus
オジロワシ Haliaeetus albicilla
ハクトウワシ Haliaeetus leucocephalus
オオワシ Haliaeetus pelagicus
ノスリ族 Buteonini
サシバ属 Butastur
サシバ Butastur indicus
ノスリ属 Buteo
ケアシノスリ Buteo lagopus
オオノスリ Buteo hemilasius
ノスリ Buteo japonicus
このように見ると新しい視点も生じる。日本で繁殖するタカ類は1属につき1種に限られるのである。つまり1回の導入で到達して定着したものは1種のみで、同属の類似種を複数種持つほどの国土面積がなく、また環境の多様性がそれほど高くなかったと考えることができるかも知れない。
備考:
*1: Catanach et al. (2024) 論文の訂正論文 (2024年6月。参考文献参照) で Accipitrinae はこれまでよりも広く、チュウヒ属も含む概念になった。古典的名称のチュウヒ亜科の名称はおそらく使われなくなってゆくだろう。
[タカ類を新しい分類で見る]
日本産タカ類の一覧を紹介したが、ハヤブサ目で全種を紹介するとやはり便利であったこと、Catanach et al. (2024) の論文が無事出版されたため、長くなるがタカ類全種一覧を系統順に並べてみることにした。
日本鳥類目録 改訂第7版の分類順だと系統順がかなり入れ替わってしまって探しにくいことも理由の一つ。
* のある種名は核遺伝情報の UCE なし、** は遺伝情報なし。
ほとんどは個々に記述した部分のコピーになっているが、全分類を見やすくするために亜科以上の分類階級を青字、族を緑字で示した。種の緑字は日本鳥類目録改訂第8版で日本産種に含まれるもの。
Catanach et al. (2024) が ウタオオタカ族 Melieracini, トカゲノスリ族 Kaupifalcini, ツミ?/アカハラダカ?/アフリカオオタカ?族 Aerospizini とすべて族としているのは、名称はないがカンムリオオタカ亜科 Lophospizinae に対応する亜科相当の系統を考えそれに属する族と判断しているものだろう。相当する「亜科相当」の概念を補った。
Accipitrinae (ハイタカ亜科の名称に相当) の名称も従来や他所で用いられているが、チュウヒ類を内包するので適切な名前と考えられなかったかも知れない。チュウヒ類を除いた Accipitrinae の名称は Circinae (チュウヒ亜科) と並列して Lerner and Mindell (2005) で用いられていた。
Lerner and Mindell (2005) の Accipitrinae の概念では単系統をなさない。Catanach et al. (2024) はチュウヒ類を含めた上で単系統となるこの系統にはこの名称を積極的に用いなかったと考えられる。論文中では広義 (s.l.) Accipitrinae の使い方をしている。
その後 2024年6月に訂正が発表され Accipitrinae は広義と定義されてこの問題は解消した。
この分類に従えば {アカオオタカ属からチュウヒ属} までのグループは族相当になるので補ってある
[伝統的チュウヒ亜科 Circinae (wikipedia 日本語版にもあるが記載されている概念は非常に古い) の名前は残してあるが現代的な分子系統分類では亜科相当に当たらないことに注意]。
古い名前で {Accipitrinae + Circinae} のグループ以外は (ほぼ) きれいに亜科に分けることができるのだが、ハイタカ類、チュウヒ類があまりにも古くから名前を持っていて分子系統を見るまで系統関係が明らかでなかったため自然なグループ名と感じられないのだろう。
オウギワシ亜科には見た目がかなり異なるものも含まれているので、同様に古い分類はとらわれず少々の違いには目をつむってチュウヒ類も含めた (広義) ハイタカ亜科の概念に馴染んで行くことになるのだろうか。
上位分類は一般的なものを利用している。コンドル目 Cathartiformes については #クロハゲワシ の備考参照。Catanach et al. (2024) もこの目を採用している。
猛禽類好きの方にとってはこれらの分類や進化経路はもちろん興味深いだろうが、最上位の捕食者の一つとして (特に陸上では) タカ類などの猛禽類が生態系を形作り、あるいは他の鳥の生活様式や形態などの進化に与えた影響は非常に大きいだろう。猛禽類の性質を知らずして陸鳥の生態を深く知ることはできないと言っても過言ではないだろう。
猛禽類学は鳥類学の必修項目 (?) の一つに置いてもよいぐらいなのかも知れない、と少し偉そうに言っておこう。Catanach et al. (2024) の挿絵を見ているとどれも色も地味だしとまっている姿を並べると不気味そうな感じさえしないでもない。動物園でも立ち止まる人はあまり多くない。
色鮮やかな小鳥好きの人にとってはいったい何がそんなによいのかと言われそうだが、まあタカ信者の独り言と思って聞いていただくぐらいでよいだろう。
*** タカ上目 Accipitrimorphae
** コンドル目 Cathartiformes
* コンドル科 Cathartidae
カリフォルニアコンドル属 Gymnogyps
カリフォルニアコンドル Gymnogyps californianus California Condor
コンドル属 Vultur
コンドル Vultur gryphus Andean Condor
トキイロコンドル属 Sarcoramphus
トキイロコンドル Sarcoramphus papa King Vulture
クロコンドル属 Coragyps
クロコンドル Coragyps atratus Black Vulture
ヒメコンドル属 Cathartes
ヒメコンドル Cathartes aura Turkey Vulture
キガシラコンドル* [高野 (1973) ではキガシラヒメコンドル] Cathartes burrovianus Lesser Yellow-headed Vulture
オオキガシラコンドル* [高野 (1973) ではオオヒメコンドル] Cathartes melambrotus Greater Yellow-headed Vulture
** タカ目 Accipitriformes
* ヘビクイワシ科 Sagittariidae
ヘビクイワシ属 Sagittarius
ヘビクイワシ Sagittarius serpentarius Secretarybird
* ミサゴ科 Pandionidae
ミサゴ属 Pandion
ミサゴ Pandion haliaeetus (Western) Osprey
カンムリミサゴ Pandion cristatus Eastern Osprey/Australian Osprey (IOC 14.2 ではミサゴの亜種となった。学名・和名ともに適切でない可能性がある)
* タカ科 Accipitridae
カタグロトビ亜科 Elaninae (ハイイロトビ亜科の名称もあり: #ハチクマの備考参照) [#カタグロトビ備考より]
シンジュトビ属* Gampsonyx
シンジュトビ [高野 (1973) ではシロクロトビ] Gampsonyx swainsonii Pearl Kite
アフリカツバメトビ属* Chelictinia
アフリカツバメトビ [高野 (1973) ではアフリカツバメハイイロトビ] Chelictinia riocourii Scissor-tailed Kite
カタグロトビ属 Elanus
オジロトビ* [高野 (1973) ではオジロハイイロトビ] Elanus leucurus White-tailed Kite
カタグロトビ [高野 (1973) ではハイイロトビ] Elanus caeruleus Black-winged Kite
クロオビトビ* [高野 (1973) ではクロオビハイイロトビ] Elanus scriptus Letter-winged Kite
オーストラリアカタグロトビ [高野 (1973) ではオーストラリアハイイロトビ] Elanus axillaris Black-shouldered Kite
ヒゲワシ亜科 Gypaetinae (単系統でない可能性がある。チュウヒダカ類2種が別亜科となる可能性がある) [#ハチクマ備考より]
チュウヒダカ [高野 (1973) ではアフリカチュウヒダカ] Polyboroides typus African Harrier-Hawk
マダガスカルチュウヒダカ Polyboroides radiatus Madagascar Harrier-Hawk
ヤシハゲワシ* Gypohierax angolensis Palm-nut Vulture
エジプトハゲワシ* Neophron percnopterus Egyptian Vulture
ヒゲワシ* Gypaetus barbatus Bearded Vulture
ハチクマ亜科 Perninae [#ハチクマ備考より]
マダガスカルヘビワシ属* Eutriorchis
マダガスカルヘビワシ [高野 (1973) ではマダガスカルオナガヘビワシ] Eutriorchis astur Madagascar Serpent Eagle
カギハシトビ属 Chondrohierax
カギハシトビ Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite
キューバカギハシトビ Chondrohierax wilsonii Cuban Kite
ハイガシラトビ属 Leptodon
ハイガシラトビ Leptodon cayanensis Grey-headed Kite
シロエリトビ Leptodon forbesi White-collared Kite
カッコウハヤブサ属 Aviceda
アフリカカッコウハヤブサ Aviceda cuculoides African Cuckoo-Hawk
マダガスカルカッコウハヤブサ Aviceda madagascariensis Madagascar Cuckoo-Hawk
チャイロカッコウハヤブサ [高野 (1973) ではジェルダンカッコウハヤブサ] Aviceda jerdoni Jerdon's Baza
カンムリカッコウハヤブサ Aviceda subcristata Pacific Baza
クロカッコウハヤブサ Aviceda leuphotes Black Baza
ハチクマ属 Pernis
ヨーロッパハチクマ Pernis apivorus European Honey Buzzard
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Crested Honey Buzzard
ヨコジマハチクマ Pernis celebensis Barred Honey Buzzard
フィリピンハチクマ Pernis steerei Philippine Honey Buzzard
ツバメトビ属 Elanoides
ツバメトビ [高野 (1973) ではツバメハイイロトビ] Elanoides forficatus Swallow-tailed Kite
クロムネトビ属* Hamirostra
クロムネトビ Hamirostra melanosternon Black-breasted Buzzard
シラガトビ属* Lophoictinia
シラガトビ [高野 (1973) ではアカムネトビ] Lophoictinia isura Square-tailed Kite
オナガハチクマ属 Henicopernis
クロハチクマ [高野 (1973) の別名はガーニイオナガハチクマ] Henicopernis infuscatus Black Honey Buzzard
オナガハチクマ Henicopernis longicauda Long-tailed Honey Buzzard
チュウヒワシ亜科 Circaetinae [#カンムリワシ備考より]
カンムリワシ属 Spilornis
スラウェシチュウヒワシ* [高野 (1973) ではセレベスヘビワシ] Spilornis rufipectus Sulawesi Serpent Eagle
フィリピンカンムリワシ* [高野 (1973) ではフィリピンヘビワシ] Spilornis holospilus Philippine Serpent Eagle
カンムリワシ Spilornis cheela Spilornis cheela
以下3種はまだ遺伝学的データなし。上記のどの位置かはわからない。IOC 順に並べておく。
ニコバルカンムリワシ [高野 (1973) ではニコバルヘビワシ] Spilornis klossi Great Nicobar Serpent Eagle
キナバルカンムリワシ Spilornis kinabaluensis Mountain Serpent Eagle
アンダマンカンムリワシ [高野 (1973) ではアンダマンヘビワシ] Spilornis elgini Andaman Serpent Eagle
フィリピンワシ属 Pithecophaga
フィリピンワシ (旧名サルクイワシ) Pithecophaga jefferyi Philippine Eagle
ダルマワシ属 Terathopius
ダルマワシ Terathopius ecaudatus Bateleur
チュウヒワシ属 Circaetus
ミナミオビチュウヒワシ* Circaetus fasciolatus Southern Banded Snake Eagle
オビチュウヒワシ Circaetus cinerascens Western Banded Snake Eagle
オナガヘビワシ* Circaetus spectabilis Congo Serpent Eagle
ムナグロチュウヒワシ Circaetus pectoralis Black-chested Snake Eagle
チャイロチュウヒワシ* Circaetus cinereus Brown Snake Eagle
チュウヒワシ Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle
以下1種はまだ遺伝学的データなし。上記のどの位置かはわからない。
ボードワンチュウヒワシ** Circaetus beaudouini Beaudouin's Snake Eagle
ハゲワシ亜科 Aegypiinae (ハゲワシ族 Gypini ともされる) [#クロハゲワシ備考より]
ミミハゲワシ属* Sarcogyps
ミミハゲワシ Sarcogyps calvus Red-headed Vulture
カオジロハゲワシ属* Trigonoceps
カオジロハゲワシ [高野 (1973) ではシロガシラハゲワシ] Trigonoceps occipitalis White-headed Vulture
ミミヒダハゲワシ属* Torgos
ミミヒダハゲワシ Torgos tracheliotos Lappet-faced Vulture
クロハゲワシ属 Aegypius
クロハゲワシ Aegypius monachus Cinereous Vulture
ズキンハゲワシ属* Necrosyrtes
ズキンハゲワシ Necrosyrtes monachus Hooded Vulture
ハゲワシ属 [高野 (1973) ではシロエリハゲワシ類] Gyps
ベンガルハゲワシ* Gyps bengalensis White-rumped Vulture
インドハゲワシ* Gyps indicus Indian Vulture
ヒマラヤハゲワシ* Gyps himalayensis Himalayan Vulture
コシジロハゲワシ* Gyps africanus White-backed Vulture
シロエリハゲワシ Gyps fulvus Griffon Vulture
マダラハゲワシ* Gyps rueppelli Rueppell's Vulture
ハシボソハゲワシ* Gyps tenuirostris Slender-billed Vulture
ケープシロエリハゲワシ Gyps coprotheres Cape Vulture
イヌワシ亜科 Aquilinae [#クマタカ備考、#カラフトワシ備考より]
カンムリクマタカ属* Stephanoaetus
カンムリクマタカ Stephanoaetus coronatus Crowned Eagle
マダガスカルカンムリクマタカ** Stephanoaetus mahery Malagasy Crowned Eagle (絶滅種。分子系統樹にはもちろんないが追加)
クマタカ属 Nisaetus
ウォーレスクマタカ* Nisaetus nanus Wallace's Hawk-Eagle
レッグクマタカ* Nisaetus kelaarti Legge's Hawk-Eagle
クマタカ Nisaetus nipalensis Mountain Hawk-Eagle
ジャワクマタカ* Nisaetus bartelsi Javan Hawk-Eagle
カオグロクマタカ* [高野 (1973) ではブリスクマタカ] Nisaetus alboniger Blyth's Hawk-Eagle
セレベスクマタカ* Nisaetus lanceolatus Sulawesi Hawk-Eagle
ピンスカークマタカ* Nisaetus pinskeri Pinsker's Hawk-Eagle
フィリピンクマタカ* Nisaetus philippensis Philippine Hawk-Eagle
フローレスクマタカ* Nisaetus floris Flores Hawk-Eagle
カワリクマタカ Nisaetus cirrhatus Changeable Hawk-Eagle
アカエリクマタカ属 Spizaetus
クロクマタカ Spizaetus tyrannus Black Hawk-Eagle
セグロクマタカ [高野 (1973) ではチリーワシ] Spizaetus melanoleucus Black-and-white Hawk-Eagle
アカクロクマタカ* Spizaetus isidori Black-and-chestnut Eagle
アカエリクマタカ Spizaetus ornatus Ornate Hawk-Eagle
アカハラクマタカ属* Lophotriorchis
アカハラクマタカ Lophotriorchis kienerii Rufous-bellied Eagle
ゴマバラワシ属* Polemaetus
ゴマバラワシ [高野 (1973) ではゴマハラワシ] Polemaetus bellicosus Martial Eagle
エボシクマタカ属* Lophaetus
エボシクマタカ [高野 (1973) ではカンムリクロクマタカ] Lophaetus occipitalis Long-crested Eagle
カザノワシ属* Ictinaetus
カザノワシ Ictinaetus malaiensis Black Eagle
カラフトワシ属* Clanga
インドワシ Clanga hastata Indian Spotted Eagle
アシナガワシ Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle
カラフトワシ Clanga clanga Greater Spotted Eagle
ヒメクマタカ属 Hieraaetus
ヒメイヌワシ* [高野 (1973) ではコイヌワシ] Hieraaetus wahlbergi Wahlberg's Eagle
シロハラクマタカ Hieraaetus ayresii Ayres's Hawk-Eagle
コビトクマタカ* Hieraaetus weiskei Pygmy Eagle
ヒメクマタカ [高野 (1973) ではケアシクマタカ] Hieraaetus pennatus Booted Eagle
ハーストイーグル/ハルパゴルニスワシ* Hieraaetus moorei Haast's eagle (絶滅種)
アカヒメクマタカ [高野 (1973) ではヒメアカクマタカ] Hieraaetus morphnoides Little Eagle
イヌワシ属 Aquila
(系統 1。ソウゲンワシ属 Psammoaetus とする分類学者もある)
ソウゲンワシ Aquila nipalensis Steppe Eagle
アフリカソウゲンワシ* [高野 (1973) ではサメイロイヌワシ] Aquila rapax Tawny Eagle
ニシカタシロワシ* Aquila adalberti Spanish Imperial Eagle
カタシロワシ* [高野 (1973) ではカタジロワシ] Aquila heliaca Eastern Imperial Eagle
アフリカクマタカ Aquila africana Cassin's Hawk-Eagle
(系統 2)
イヌワシ Aquila chrysaetos Golden Eagle
ボネリークマタカ Aquila fasciata Bonelli's Eagle
モモジロクマタカ Aquila spilogaster African Hawk-Eagle
コシジロイヌワシ* Aquila verreauxii Verreaux's Eagle
モルッカイヌワシ* [高野 (1973) ではガーニイイヌワシ] Aquila gurneyi Gurney's Eagle
オナガイヌワシ Aquila audax Wedge-tailed Eagle
オウギワシ亜科 Harpiinae [#カンムリワシの備考より]
パプアオウギワシ属 Harpyopsis
パプアオウギワシ [高野 (1973) ではニューギニアオウギワシ] Harpyopsis novaeguineae Papuan Eagle
コウモリダカ属 Macheiramphus
コウモリダカ Macheiramphus alcinus Bat Hawk
オウギワシ属 Harpia
オウギワシ* Harpia harpyja Harpy Eagle
ヒメオウギワシ属 Morphnus
ヒメオウギワシ* [高野 (1973) ではカンムリオウギワシ] Morphnus guianensis Crested Eagle
[以下2属は Catanach et al. (2024) 本文記述に従ってここに置くが分子系統上は場所に問題があるかも知れない。それぞれの部分の解説参照]
ヒメハイタカ属 Microspizias
ヒメハイタカ Microspizias superciliosus Tiny Hawk
ナンベイアカエリツミ* Microspizias collaris Semicollared Hawk
ハバシトビ属 Harpagus
ハバシトビ [高野 (1973) ではアカハラトビ] Harpagus bidentatus Double-toothed Kite
モモアカトビ* Harpagus diodon Rufous-thighed Kite
[#アカハラダカ備考より]
カンムリオオタカ亜科 Lophospizinae
カンムリオオタカ属 Lophospiza
カンムリオオタカ Lophospiza trivirgatus Crested Goshawk
セレベスオオタカ** Lophospiza griseiceps Sulawesi Goshawk
亜科 Accipitrinae (以下チュウヒ属までを含むグループ。2024年6月に Accipitrinae 亜科 の概念を拡大すると発表された)
ウタオオタカ族 Melieracini
カワリウタオオタカ属 Micronisus
カワリウタオオタカ [高野 (1973) ではモリウタオオタカ] Micronisus gabar Gabar Goshawk
オナガオオタカ属* Urotriorchis
オナガオオタカ Urotriorchis macrourus Long-tailed Hawk
ウタオオタカ属 Melierax
ウタオオタカ Melierax metabates Dark Chanting Goshawk
コシジロウタオオタカ Melierax canorus Eastern Chanting Goshawk
ヒガシコシジロウタオオタカ Melierax poliopterus Pale Chanting Goshawk
トカゲノスリ族 Kaupifalconini [系統 1: Catanach et al. (2024) で命名。2024年6月に綴りを訂正]
トカゲノスリ属 Kaupifalco
トカゲノスリ Kaupifalco monogrammicus Lizard Buzzard
ツミ?/アカハラダカ?/アフリカオオタカ?族 Aerospizini [系統 2: Catanach et al. (2024) で命名]
アフリカオオタカ属 Aerospiza
ワキアカハイタカ [高野 (1973) ではワキアカオオタカ] Aerospiza castanilius Chestnut-flanked Sparrowhawk
アフリカオオタカ* Aerospiza tachiro African Goshawk
ムネアカオオタカ* Aerospiza toussenelii Red-chested Goshawk (IOC 15.1 でアフリカオオタカと同種に)
ツミ属またはアカハラダカ属 Tachyspiza [#ツミ備考より]
アフリカツミ* Tachyspiza minulla Little Sparrowhawk
ニシアフリカツミ* Tachyspiza erythropus Red-thighed Sparrowhawk
ミナミツミ Tachyspiza virgata Besra
ツミ Tachyspiza gularis Japanese Sparrowhawk
レバントハイタカ Tachyspiza brevipes Levant Sparrowhawk
タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia Shikra
アカハラダカ Tachyspiza soloensis Chinese Sparrowhawk
シロハラハイタカ* Tachyspiza francesiae Frances's Sparrowhawk
ハイガシラオオタカ* Tachyspiza poliocephala Grey-headed Goshawk
カワリオオタカ Tachyspiza hiogaster Variable Goshawk
ハイイロオオタカ [高野 (1973) ではカワリオオタカ] Tachyspiza novaehollandiae Grey Goshawk
シロクロオオタカ* [高野 (1973) ではニセマダラオオタカ] Tachyspiza imitator Imitator Goshawk
クロアカオオタカ Tachyspiza melanochlamys Black-mantled Goshawk
アカハラオオタカ [高野 (1973) ではオーストラリアオオタカ] Tachyspiza fasciata Brown Goshawk
ムナグロオオタカ Tachyspiza haplochroa White-bellied Goshawk
フィジーオオタカ [高野 (1973) ではフィージーオオタカ] Tachyspiza rufitorques Fiji Goshawk
以下遺伝情報なし
シラボシオオタカ** [高野 (1973) ではシラホシオオタカ] Tachyspiza trinotata Spot-tailed Sparrowhawk
セレベスツミ** Tachyspiza nanus Dwarf Sparrowhawk
ムネアカツミ** [高野 (1973) ではアカムネツミ] Tachyspiza rhodogaster Vinous-breasted Sparrowhawk
モルッカツミ** [高野 (1973) ではハイノドツミ] Tachyspiza erythrauchen Rufous-necked Sparrowhawk
アカエリツミ** Tachyspiza cirrocephala Collared Sparrowhawk
シロハラツミ** Tachyspiza brachyura New Britain Sparrowhawk
チャバラオオタカ** [高野 (1973) ではグレイオオタカ] Tachyspiza henicogramma Moluccan Goshawk
ニコバルハイタカ** Tachyspiza butleri Nicobar Sparrowhawk
ノドジロオオタカ** [高野 (1973) ではマダラオオタカ] Tachyspiza albogularis Pied Goshawk
アオハイタカ** Tachyspiza luteoschistacea Slaty-mantled Goshawk
オオハイガシラオオタカ** Tachyspiza princeps New Britain Goshawk
族相当 [系統 3] (以下チュウヒ属までを含むグループ。名前はない)
アカオオタカ属 Erythrotriorchis
アカオオタカ Erythrotriorchis radiatus Red Goshawk
カタアカオオタカ* Erythrotriorchis buergersi Chestnut-shouldered Goshawk
ハイタカ属 Accipiter [#ハイタカ備考より]
セグロオオタカ* Accipiter poliogaster Grey-bellied Hawk (Dinospizias 属とする分類学者もある)
サバンナハイタカ* [高野 (1973) ではオバンポハイタカ] Accipiter ovampensis Ovambo Sparrowhawk
マダガスカルハイタカ* Accipiter madagascariensis Madagascar Sparrowhawk
アシボソハイタカ Accipiter striatus Sharp-shinned Hawk (学名が変わる可能性は解説参照)
ムナジロアシボソハイタカ(*) Accipiter chionogaster White-breasted Hawk
フナシアシボソハイタカ(*) Accipiter ventralis Plain-breasted Hawk
モモアカアシボソハイタカ(*) Accipiter erythronemius Rufous-thighed Hawk
ムネアカハイタカ* [高野 (1973) ではアカムネハイタカ] Accipiter rufiventris Rufous-breasted Sparrowhawk
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk
オオタカ属 Astur [#オオタカ備考より]
(系統 1: クーパーハイタカ属 Cooperastur の名称も提案されている)
モモアカハイタカ Astur bicolor Bicolored Hawk
チリハイタカ(*) Astur chilensis Chilean Hawk
ズグロハイタカ* Astur gundlachi Gundlach's Hawk
クーパーハイタカ Astur cooperii Cooper's Hawk
(系統 2)
オオタカ Astur gentilis Eurasian Goshawk
マダガスカルオオタカ* [高野 (1973) ではヘンストオオタカ] Astur henstii Henst's Goshawk
オオハイタカ [高野 (1973) ではシロクロオオタカ] Astur melanoleucus Black Sparrowhawk
シロハラオオタカ* Astur meyerianus Meyer's Goshawk
アメリカオオタカ(*) Astur atricapillus American Goshawk
(伝統的チュウヒ亜科 Circinae に相当したもので拡張されたが: 現在は Accipitrinae に吸収) [#チュウヒ備考より]
パプアオオタカ属 Megatriorchis
パプアオオタカ [高野 (1973) ではドリヤオオタカ] Megatriorchis doriae Doria's Goshawk (Doria's Hawk に変更)
チュウヒ属 Circus (S: steppe ステップ型, M: marsh 沼型)
(系統 1)
アイレスチュウヒ(仮名)* Circus teauteensis Eyles's harrier (絶滅種)
ウスユキチュウヒ Circus assimilis Spotted Harrier (S)
(系統 2)
クロチュウヒ* Circus maurus Black Harrier (S)
ウスハイイロチュウヒ Circus macrourus Pallid Harrier (S)
ハイイロチュウヒ* Circus cyaneus Hen Harrier (S)
アンデスチュウヒ [高野 (1973) ではナンベイハイイロチュウヒ] Circus cinereus Cinereous Harrier (S)
アメリカハイイロチュウヒ Circus hudsonius Northern Harrier (S)
(系統 3)
ハネナガチュウヒ* Circus buffoni Long-winged Harrier (S)
ヒメハイイロチュウヒ* Circus pygargus Montagu's Harrier (S)
マダラチュウヒ Circus melanoleucos Pied Harrier (S)
ヨーロッパチュウヒ* Circus aeruginosus Western Marsh Harrier (M)
アフリカチュウヒ* Circus ranivorus African Marsh Harrier (M)
チュウヒ* Circus spilonotus Eastern Marsh Harrier (M)
パプアチュウヒ* Circus spilothorax Papuan Harrier (M)
ミナミチュウヒ* Circus approximans Swamp Harrier (M)
マダガスカルチュウヒ* Circus macrosceles Malagasy Harrier (M) (和名修正)
レユニオンチュウヒ* Circus maillardi Reunion Harrier (M) (和名修正)
(以下2属は重複して挙げる)
(ヒメハイタカ属 Microspizias
ヒメハイタカ Microspizias superciliosus Tiny Hawk
ナンベイアカエリツミ* Microspizias collaris Semicollared Hawk
ハバシトビ属 Harpagus
ハバシトビ [高野 (1973) ではアカハラトビ] Harpagus bidentatus Double-toothed Kite
モモアカトビ* Harpagus diodon Rufous-thighed Kite)
この2属はオウギワシ亜科 Harpiinae (#カンムリワシの備考参照) で述べているように、Catanach et al. (2024) の本文解説ではオウギワシ亜科に入るように思える。しかし系統樹はやや遠いもののノスリ亜科と単系統をなす形になっているので、こちらにも括弧を付けて含めておく (系統樹的には独立亜科としても構わない)。
後述のようにハバシトビ属をノスリ亜科に含めている分類も存在する。
ノスリ亜科 Buteoninae [#トビ備考より]
トビ族 Milvini
トビ属 Milvus
アカトビ Milvus milvus Red Kite
トビ* Milvus migrans Black Kite
キバシトビ** Milvus aegyptius Yellow-billed Kite
シロガシラトビ属 Haliastur
シロガシラトビ Haliastur indus Brahminy Kite
フエフキトビ [高野 (1973) ではフエナキトビ] Haliastur sphenurus Whistling Kite
オジロワシ属 Haliaeetus
オジロワシ Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
ハクトウワシ Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle
オオワシ Haliaeetus pelagicus Steller's Sea Eagle
キガシラウミワシ* Haliaeetus leucoryphus Pallas's Fish Eagle
ウオクイワシ属 Icthyophaga
マダガスカルウミワシ* Icthyophaga vociferoides Madagascar Fish Eagle
サンショクウミワシ Icthyophaga vocifer African Fish Eagle
ソロモンウミワシ* [高野 (1973) ではサンフォードウミワシ] Icthyophaga sanfordi Sanford's Sea Eagle
シロハラウミワシ Icthyophaga leucogaster White-bellied Sea Eagle
コウオクイワシ* Icthyophaga humilis Lesser Fish Eagle
ウオクイワシ [高野 (1973) ではハイガシラウオクイワシ] Icthyophaga ichthyaetus Grey-headed Fish Eagle
ノスリ族 Buteonini
サシバ属 Butastur [#サシバ備考より]
チャバネサシバ* [高野 (1973) ではアカハネサシバ] Butastur liventer Rufous-winged Buzzard
アフリカサシバ Butastur rufipennis Grasshopper Buzzard
メジロサシバ* Butastur teesa White-eyed Buzzard
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard
ムシクイトビ属 Ictinia (和名はタイプ種を優先した)
ムシクイトビ [高野 (1973) ではナマリイロトビ] Ictinia plumbea Plumbeous Kite
ミシシッピートビ* Ictinia mississippiensis Mississippi Kite
セイタカノスリ属 Geranospiza
セイタカノスリ [高野 (1973) ではセイタカチュウヒ] Geranospiza caerulescens Crane Hawk
ミサゴノスリ属 Busarellus
ミサゴノスリ [高野 (1973) ではミサゴワシ] Busarellus nigricollis Black-collared Hawk
ハシボソトビ属 Helicolestes
ハシボソトビ Helicolestes hamatus Slender-billed Kite
タニシトビ属 Rostrhamus
タニシトビ [高野 (1973) ではカタツムリトビ] Rostrhamus sociabilis Snail Kite
ヨコジマノスリ属 Morphnarchus
ヨコジマノスリ Morphnarchus princeps Barred Hawk
ヒメアオノスリ属 Cryptoleucopteryx
ヒメアオノスリ [高野 (1973) ではクロアオノスリ] Cryptoleucopteryx plumbea Plumbeous Hawk
カニクイノスリ属 Buteogallus (和名はタイプ種を優先した)
アオノスリ* Buteogallus schistaceus Slate-colored Hawk
クロノスリ* [高野 (1973) ではクロヌマワシ] Buteogallus anthracinus Common Black Hawk
キューバノスリ Buteogallus gundlachii Cuban Black Hawk
カニクイノスリ [高野 (1973) ではヌマワシ] Buteogallus aequinoctialis Rufous Crab Hawk
サバンナノスリ Buteogallus meridionalis Savanna Hawk
シロエリノスリ Buteogallus lacernulatus White-necked Hawk
オオクロノスリ* [高野 (1973) ではオオクロヌマワシ] Buteogallus urubitinga Great Black Hawk
カンムリノスリ [高野 (1973) ではハイイロカンムリワシ] Buteogallus coronatus Chaco Eagle
オグロカンムリノスリ [高野 (1973) ではオグロカンムリワシ] Buteogallus solitarius Solitary Eagle
オオハシノスリ属* Rupornis
オオハシノスリ Rupornis magnirostris Roadside Hawk
モモアカノスリ属 Parabuteo (和名はタイプ種を優先した)
モモアカノスリ Parabuteo unicinctus Harris's Hawk
コシジロノスリ Parabuteo leucorrhous White-rumped Hawk
シロノスリ属 Pseudastur (和名はタイプ種を優先した)
ハイセノスリ* [高野 (1973) ではシロハラノスリ] Pseudastur occidentalis Grey-backed Hawk
セグロノスリ* Pseudastur polionotus Mantled Hawk
シロノスリ Pseudastur albicollis White Hawk
ワシノスリ属 Geranoaetus (和名はタイプ種を優先した)
オジロノスリ Geranoaetus albicaudatus White-tailed Hawk
ワシノスリ* [高野 (1973) ではハイイロオオノスリ] Geranoaetus melanoleucus Black-chested Buzzard-Eagle
セアカノスリ Geranoaetus polyosoma Variable Hawk
カオグロノスリ属 Leucopternis (和名はタイプ種を優先した)
セアオノスリ* [高野 (1973) ではウスアオノスリ] Leucopternis semiplumbeus Semiplumbeous Hawk
シロマユノスリ* Leucopternis kuhli White-browed Hawk
カオグロノスリ [高野 (1973) ではクロガオノスリ] Leucopternis melanops Black-faced Hawk
ノスリ属 Buteo [#ノスリ備考より]
ミナミハイイロノスリ* Buteo plagiatus Grey Hawk
ハイイロノスリ Buteo nitidus Grey-lined Hawk
ハネビロノスリ Buteo platypterus Broad-winged Hawk
ヒスパニオラノスリ* [高野 (1973) ではリッジウェイノスリ] Buteo ridgwayi Ridgway's Hawk
カタアカノスリ Buteo lineatus Red-shouldered Hawk
オビオノスリ Buteo albonotatus Zone-tailed Hawk
ハワイノスリ* Buteo solitarius Hawaiian Hawk
アンデスミジカオノスリ Buteo albigula White-throated Hawk
ミジカオノスリ* Buteo brachyurus Short-tailed Hawk
ガラパゴスノスリ* Buteo galapagoensis Galapagos Hawk
アレチノスリ [高野 (1973) ではスウェイソンノスリ] Buteo swainsoni Swainson's Hawk
ナンベイアカオノスリ Buteo ventralis Rufous-tailed Hawk
アカオノスリ Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk
ケアシノスリ Buteo lagopus Rough-legged Buzzard
アカケアシノスリ Buteo regalis Ferruginous Hawk
アカクロノスリ* Buteo rufofuscus Jackal Buzzard
ヨゲンノスリ* Buteo augur Augur Buzzard
アフリカアカオノスリ* Buteo auguralis Red-necked Buzzard
ソマリアノスリ* Buteo archeri Archer's Buzzard (現在は通常ヨゲンノスリの亜種とされる)
マダラノスリ [高野 (1973) ではヤマノスリ] Buteo oreophilus Mountain Buzzard
モリノスリ* Buteo trizonatus Forest Buzzard
ヨーロッパノスリ Buteo buteo Common Buzzard
ニシオオノスリ [高野 (1973) ではオオノスリ] Buteo rufinus Long-legged Buzzard
オオノスリ [高野 (1973) ではヤマオオノスリ] Buteo hemilasius Upland Buzzard
ヒマラヤノスリ* Buteo refectus Himalayan Buzzard
ノスリ Buteo japonicus Eastern Buzzard
以下遺伝情報なし
マダガスカルノスリ** Buteo brachypterus Madagascan Buzzard
ケープベルデノスリ/ケアプベルデノスリ** Buteo bannermani Cape Verde Buzzard
ソコトラノスリ** Buteo socotraensis Socotra Buzzard
△ タカ目 ACCIPITRIFORMES タカ科 ACCIPITRIDAE ▽
-
ハチクマ
- 学名:Pernis ptilorhynchus (ペルニス プティロリュンクス) 羽毛で覆われた嘴のタカの一種
- 属名:pernis アリストテレスが Historia Animalium (9.36) に記述 (英訳, pternis と記載されている) したタカの一種。現在どの種類に対応するかは不明。
- 種小名:ptilorhynchus (合) 羽毛で覆われた嘴の (ptilo 羽毛 rynchos 鼻口部 Gk)
- 英名:Oriental Honey Buzzard, IOC: Crested Honey Buzzard
- 備考:
pernis は語源が確かでなく原語次第では長母音を含む可能性がある。ここでは短母音を採用した (ペルニス)。
アリストテレスのギリシャ語の綴りそのままであれば pernes は末尾が長母音であるが音も変わっていること、冒頭アクセントしか考えられないため長音は採用しなかった。
pternis 由来であれば短母音のみ。pernix 由来であれば i は長母音。
ptilorhynchus は ptilon も rhunkhos も短母音のみで -rhyn- がアクセント音節と考えられる (プティロリュンクス)。読み慣れた発音の正統性を確認できた。
日本の亜種名である orientalis は a が長母音でアクセントもある (オリエンターリス)。
後の [ハチクマの学名は正しくないかも?] で詳しく述べるが、他の種の多くの英名から推定すると現在一般的な英名 Crested Honey Buzzard は過去に使われていた学名 Pernis cristatus に由来すると考えられる。
比較的最近までヨーロッパハチクマの亜種とみなされることも多かったがかつては別種扱いの時代があり、"インドのハチクマ" を指してこの学名と英名が用いられていた。アメリカやイギリス本国からは縁の遠い種類で、英国植民地時代に使われていた英名がそのまま引き継がれたものと想像できる。
日本のハチクマでは冠羽がそれほど目立つわけではないが、亜種によってはしっかりした冠羽を持つものもある、しかし日本のハチクマでも実際は冠羽があるなどの解説は英名をふまえたものだが、この英名がかつての学名由来と考えるとより納得しやすい。もとは冠羽の目立つ熱帯の個体を指して付けられた学名であった。
この事例のように (特に英語圏から遠い地域の鳥については) 学名由来の英名は多く、種全体の特徴を表して付けられた名前でない場合がある。英語圏から見て異国の鳥に付けられた英名を解釈して "英語ではこれこれの意味で" とあまり読みすぎない方がよい場合もある。
この当時に用いられていた種小名は誰の記述によるものかは明瞭ではないが、Buteo cristatus Vieillot, 1816 が最初の用例で、この記載は現在ミサゴの亜種とされるカンムリミサゴ (IOC 14.1 では種扱いだった) を指すものとして使われ、誤りの可能性がある。
Vieillot (1816) は Crested Honey Buzzard に相当するフランス名 La Buse-bondree Huppee を紹介しており、当時から Crested Honey Buzzard / La Buse-bondree Huppee が標準的な英語・フランス語名だったと考えられる。つまりこの学名の意味がハチクマの英語・フランス語・ロシア語名などに残り、カンムリミサゴの現在の学名・和名も同じ学名に由来することになる。
[属名の考証]
Pernisについては Le regne animal distribue d'apres son organisation, pour servir de base a l'histoire naturelle des animaux et d'introduction a l'anatomie comparee p. 322 Les Bondrees (Pernis Cuv.) (1817)
で導入された (pernis または pernes とある)。
Pierre Belon, L'histoire de la nature des oyseauxも参照。ここでは Pernes の表記が使われている。ハゲワシやワシよりは小さな猛禽類の一種とされる (Bird Watching Blog: Pternis Pternes)。
Pernis のシノニムに Pterochalinus があり、pteron 羽 khalinos (くつわの) はみ (Gk) で嘴と目の間が密生した羽毛で覆われていることに基づく名前。
基亜種 ptilorhynchus はジャワ島の留鳥 (Temminck, 1821) でこれが採用された理由は後述。種小名 ptilorhynchus はしばしば ptilorhyncus とも綴られるが、前者が正しいと考えられている。
よく似た綴りの Ptilonorhynchus 属 (意味は同じ) は有名なアズマヤドリ類の属名。アオアズマヤドリ Ptilonorhynchus violaceus Satin Bowerbird など。ハチクマとアズマヤドリの共通性は超難問のクイズになりそう。
属名綴り (Gk) は pernes, pernis, pternis, perknes の諸表記あり。
日本野鳥の会京都支部の副島猛氏による写本、印刷本、現代誤訳本などを調査と時代考証の結果、次のような結論が得られている: (1) アリストテレスのオリジナルは pternis (2) 印刷本 (1497-) 以降、ギリシャ語では pernes、ラテン語ではそれに対応する pernis というオリジナルとは別の語に改変
[t が落ちたのは、単なる誤植がきっかけだったのかもしれませんし、ほとんど目にしない pternis (アリストテレスの著作でも一箇所しかない) という語を意図的に「正した」ということなのかもしれません (副島の考察)] (3) Cuvier はそれを採用して pernis を属名に (4) 19世紀以降の批判校訂版ではギリシャ語 pternis に戻る (5) オリジナルの原義や、それが指す種については未だ不明 [kbird:06852 (2023.9.17)]。
Theodorus Gaza 訳 (1476) は独自解釈で pernix (Gk)「敏捷な」を語源と考えた。
pternis をタカの意味で用いた属名は他に存在する (Leucopternis, Poecilopternis)。
[以下完全に私見: Acropternis という属名もあり、これはタカとは無関係。副島猛氏によればこれはタカの pternis とは異なる語でアリストテレス「動物誌」などで用いられた pterne (女性名詞の「かかと」) とのこと (Helm Dictionary)。
この2つの語の間に語源的な関係があるかどうかはわからないが、学名にする時のラテン語化で同じ綴りになったと考えられる [副島猛 kbird:06862 (2023.9.23)]。
この「かかと」の単語は語源が推定されていて、インド・ヨーロッパ祖族語 tpersneh に遡り、さらに t(s)perH- (かかとで蹴る) が由来の可能性があるとのこと。これならば猛禽類の習性としてあり得そうである。タカの方の pternis も遡ればもしかすると同じ語源にたどりつくのかもしれない。
アリストテレスはタカ類の記述でノスリが一番強力と述べ、以降タカ/ハヤブサ類の種類を列記して pternis は6番目の種類。本来は (ヨーロッパ) ハチクマ (当時ノスリと区別されていたかも怪しい) よりももっと小型のタカ/ハヤブサ類を指していたのかもしれない。興味をお持ちの方の語源究明に期待したい]。
[属名の変更に伴った新名]
(ヨーロッパ)ハチクマ (同種時代) に Linnaeus 時代の Falco 属から Pernis 属への移動に伴って Pernis communis Lesson, 1831 (普通のハチクマの意味) の新名が付けられた (#ノスリの備考参照)。
参考。Hartert (1910-1922) p. 1181 も参照。
他にも Pernis larvivorus Hogg, 1845 (参考) も同様に属移動に伴う改名でハチより幼虫を食べるため。
Pernis mellivora Morris, 1837 (参考) は英語の "Honey Pern" から付けた改名の学名。一般名の "pern" は属名 Pernis 由来なので早い時期から属名由来の英名が使われていたことがわかる。
Pernis 属以外の属にも移動された名称があって Aquila variabilis Koch, 1816 (参考)。なんと "変化する? ワシ" 扱い (#クロジの備考参照)。
Accipiter lacertarius Pallas, 1811 は [ハチクマの学名は正しくないかも?] で紹介。
これらは(ヨーロッパ)ハチクマに対するもので、熱帯のハチクマは最初から Buteo 属で命名されたものもあった (ハチクマの学名は正しくないかも?])。
[ハチクマ類の系統分類]
ハチクマには日本産の他のタカ類に系統的な類縁種がないため、ハチクマ亜科の全種を#ミサゴの備考のように示しておく。Catanach et al. (2024) の分子系統分類による。
全種は調べられていないので、Catanach et al. (2024) に含まれていない種は属内で IOC 順に並べてある。系統が少し離れるところに空行を入れてある。
この項目で種または属名の和名の後に * が付いているものは従来の少数遺伝子によるもので付いていないものよりは精度が低く (従来の系統解析と同じ)、今後の精度の高い全ゲノム解析で多少前後するかも知れない。
新分類では従来含まれていた Macheiramphus (コウモリダカ属) がハチクマ亜科から外れ、むしろイヌワシ亜科 Aquilinae の後のオウギワシを含む系統に属する。
コウモリダカはアフリカとアジア赤道部に隔離分布しており、Aviceda (カッコウハヤブサ) 属の分布に似ているためハチクマ亜科に近縁と考えられたのかも知れない。
ハチクマ亜科に先行する (カタグロトビ亜科が科となればタカ科の先頭になる) ヒゲワシ亜科 Gypaetinae にはこれまで [Catanach et al. (2024) の系統順による]
チュウヒダカ [高野 (1973) ではアフリカチュウヒダカ] Polyboroides typus African Harrier-Hawk
マダガスカルチュウヒダカ Polyboroides radiatus Madagascar Harrier-Hawk
ヤシハゲワシ* Gypohierax angolensis Palm-nut Vulture
エジプトハゲワシ* Neophron percnopterus Egyptian Vulture
ヒゲワシ* Gypaetus barbatus Bearded Vulture
の4属5種が含まれていたが、Catanach et al. (2024) の研究によれば Polyboroides属のチュウヒダカ [高野 (1973) ではアフリカチュウヒダカ]、マダガスカルチュウヒダカを含むと単系統にならない。
Polyboroides 属を別亜科として分離するか、これら5種も含めてハチクマ亜科とするかのどちらかになるだろう。
wikipedia 日本語版 (2023 に参照。分類は IOC 2.6 準拠?) の「タカ科 属と種」によればチュウヒダカ亜科 Polyboroidinae、ヒゲワシ亜科 Gypaetinae の名前はすでに存在するのでこれが踏襲されるかも知れない (なおハイイロトビ亜科 Elaninae の名前を与えている)。
ただしチュウヒダカ亜科 Polyboroidinae は形態・生態には類似するが縁の遠いセイタカノスリ類2種を含めた名前であった (Brown 1976)。現在では分離されており、1属のためにチュウヒダカ亜科の概念が妥当かどうかはわからない (そのためチュウヒダカ亜科の名称は以降括弧付きにする)。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) 時代ではこれらをまとめてチュウヒ類に含めていた。
これまでの取り扱いではハチクマ類とこれらも含めてヒゲワシ亜科 Gypaetinae とし、ハチクマ族 Pernini と ヒゲワシ族 Gypaetini と分ける名前もあった [Howard and Moore 4th (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) はこちらを採用だが用いている資料は古い]。
Catanach et al. (2024) でもこの部分はまだ今後の研究が必要とあるが現状ヒゲワシ亜科 Gypaetinae となった。
後々も出てくるがこれらの種類はどれも非常に個性のある猛禽類である。個性がありすぎて全体を1亜科にするのはむしろやりにくいかも知れない。また注目すべきは (従来からわかっていたが) 旧世界ハゲワシには異なる複数の系統がある。エジプトハゲワシには捕食性のタカ類の性質もあり、小動物を捕らえて食べる。
エジプトハゲワシの属名に使われる Neophron の性は一時女性とされたことがあったが、1955 年に男性と規定されていたとが見過ごされていて ICZN リストに誤った性が示されていたとのこと。2024/2025 年に ICZN が公式に訂正した。
AviList (2025.6) では 7982 N-73 The gender of Neophron has long been controversial because the entry in the ICZN’s Official List from 1987 stipulated a feminine gender while the previous ICZN Direction 26 from 1955 fixed it as masculine. The entry in the Official List was an error. In 2024/2025, the ICZN issued an Official Correction that establishes the gender as masculine.
文献によっては種小名が女性の形で現れるかも知れない。
Polyboroides の学名は若干混乱しやすいので補足しておくと、容易に想像できるように Polyborus に -oides 似たの意味で、Polyborus
(ハヤブサ目ハヤブサ科の) カラカラ属の旧名であった < poluboros がつがつ食べる、貪欲な < polus 非常に -boros むさぼり食う (Gk)。複雑な経緯を経てカラカラ属の属名ではなくなっている (#ハヤブサの備考 [ハヤブサ目の系統分類] を参照)。
系統は違うがどちらも猛禽類の学名で雰囲気も似たところがあるので学名混同に注意。
これらはタカ類の中で最初に現れたもので (ハチクマが原始的なタカ類と言われることがあるのは同様の意味。その意味であればミサゴはもっと原始的となるが、機能的にはおそらくそのようには感じられないだろう。「原始的」はあくまで系統上の表現と考えるのがよさそうである)、
タカ類が現れた当初はいろいろな種が現れたのだろうが、後に現れたより高性能のタカ類が同じ生態学的地位を占めたために特殊な技能 (食性面ではスペシャリストが多い) を持つ種類が残ったものと考えるとわかりやすそうである。
さらに古く分岐した種類も入れて特徴をまとめておく:
・(コンドル科または目: スカベンジャー)
・ヘビクイワシ科: ヘビ食 [捕食性 (捕殺性) の猛禽類らしくなるのはここから。#ミサゴの備考参照]
・ミサゴ科: 魚食
・カタグロトビ類 (科?): 夜行性にも適応。フクロウ類類似の適応あり。
・チュウヒダカ類: "二重関節" で脚を反対にも曲げられ器用に食物を捕ることができる (#クロハゲワシの備考参照。文献も記載)。
・ヤシハゲワシ: ヤシの実を食べる最も果実食的な猛禽類 (#クロハゲワシの備考参照)。
・エジプトハゲワシ: 石で卵を割る行動で有名。バルカン半島でカメを食べる (#イヌワシの備考参照)。
・ヒゲワシ: 骨髄を主に食べる唯一の猛禽類。バルカン半島でカメを食べる (#イヌワシの備考参照)。
この視点を延長するとハチクマ類の強い点はハチの子食になるかも知れないが、ハチクマ類の前後の種類がそれほど特殊化していないこと、分岐時期も推定された系統樹で見るとタカ類のグループとの競争が生じる時期にはまだハチの子食に適応していなかったと考えられることから、ハチの子食は二次的なものでそれ自身が過去の他の猛禽類との競争に決定的に役立ったわけではない印象を受ける。
後の事例で示すようにハチクマ類の系統は知的な行動を可能にする別の意味で優れた点があったのではないかと感じている。オウム類やカラス類のような系統を生み出す性質がこの段階で備わっていたとすれば面白い (例えばタカ類とスズメ目の古い共通祖先段階で生み出されていた? #ミサゴの備考も参照)。
自分がハチクマにこだわっている一つの理由であるが、自身が生きているうちに解明されることはないかも知れない。一種の「予言」として聞いておいていただきたい。
Barrowclough et al. (2014) The Phylogenetic Relationships of the Endemic Genera of Australo-Papuan Hawks
によれば狭義のハチクマ亜科の中で
Hamirostra, Lophoictinia,
Henicopernis には RAG-1 遺伝子 (recombination-activating gene で DNA の切断を行い免疫細胞遺伝子再構成に関与する。
#インドガンの備考参照。RAG-1/2 は脊椎動物が獲得免疫を獲得する過程で最も重要なステップだったとの仮説がある) に他のタカ類に見られない3塩基の欠如があり、これらが同系統であることは間違いない。
1属にまとめてしまってもよく、その場合は先取権の原則から Hamirostra 属になるとのことである。
ハチクマ亜科 Perninae
マダガスカルヘビワシ属* Eutriorchis
マダガスカルヘビワシ [高野 (1973) ではマダガスカルオナガヘビワシ] Eutriorchis astur Madagascar Serpent Eagle
カギハシトビ属 Chondrohierax
カギハシトビ Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite
キューバカギハシトビ Chondrohierax wilsonii Cuban Kite
ハイガシラトビ属 Leptodon
ハイガシラトビ Leptodon cayanensis Grey-headed Kite
シロエリトビ Leptodon forbesi White-collared Kite
カッコウハヤブサ属 Aviceda
アフリカカッコウハヤブサ Aviceda cuculoides African Cuckoo-Hawk
マダガスカルカッコウハヤブサ Aviceda madagascariensis Madagascar Cuckoo-Hawk
チャイロカッコウハヤブサ [高野 (1973) ではジェルダンカッコウハヤブサ] Aviceda jerdoni Jerdon's Baza
カンムリカッコウハヤブサ Aviceda subcristata Pacific Baza
クロカッコウハヤブサ Aviceda leuphotes Black Baza
ハチクマ属 Pernis
ヨーロッパハチクマ Pernis apivorus European Honey Buzzard
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Crested Honey Buzzard
ヨコジマハチクマ Pernis celebensis Barred Honey Buzzard
フィリピンハチクマ Pernis steerei Philippine Honey Buzzard
ツバメトビ属 Elanoides
ツバメトビ [高野 (1973) ではツバメハイイロトビ] Elanoides forficatus Swallow-tailed Kite
クロムネトビ属* Hamirostra
クロムネトビ Hamirostra melanosternon Black-breasted Buzzard
シラガトビ属* Lophoictinia
シラガトビ [高野 (1973) ではアカムネトビ] Lophoictinia isura Square-tailed Kite
オナガハチクマ属 Henicopernis
クロハチクマ [高野 (1973) の別名はガーニイオナガハチクマ] Henicopernis infuscatus Black Honey Buzzard
オナガハチクマ Henicopernis longicauda Long-tailed Honey Buzzard
[ハチクマ亜科の他種]
マダガスカルヘビワシは非常に変わった種類で、保全上もよく取り上げられるので別項目とする。
過去の目撃情報のみから、"50 年記録がない" IUCN の絶滅条件を一時的に満たした。
GenBank でも3遺伝子 [Catanach et al. (2024) の "legacy markers"] しか情報がなく (2025.2 時点)、BLAST を行ってみるといずれの遺伝子も他の種類からも遠く、早い時期に分岐した種類らしいことがわかる。Catanach et al. (2024) の結論通り "ヘビワシ" 類に含まれる遺伝的証拠はないことが確認できた。
今後全ゲノム解析などで系統上の位置がさらにはっきりすることを期待したい。
カギハシトビはカタツムリ類を主に食べていて嘴の形はそのための適応。
同じ習性を持ちかつては近縁と考えられたカタツムリトビ Rostrhamus sociabilis Snail Kite はそのものずばりの名前だが、現代的な研究では系統は全く違ってこちらはノスリの系統に近い。これは収斂進化と言ってよいだろう。
Temminck (1824) 参考 に Falco uncinatus フランス語名 Cymindis bec on croc (嘴の先端が曲がっている Cymindis) があり uncinatus は uncus, unci (鈎) -atus (持つ)。
原記載は先に出版された 1822 年の図版 (1, 2, 3) となっている。
本文。
解剖学をご存じの方ならば肋骨の鉤状突起 uncinate process (ちなみにこの構造はヒトにはないため人体解剖学では出てこないが同じ名称の解剖学用語は膵臓など他にもある) で目にかかられているだろう単語。フランス語名、英名ともに対応している。
同じ文献に Falco unicinctus Temminck, 1824 が出てきてこちらはモモアカノスリ (ハリスホーク)。ものすごく紛らわしく自分も最初は混同していたのでご注意を。
モモアカノスリ (ハリスホーク) の unicinctus は尾の基部の太い白い帯を指したものだが、この説明はカギハシトビのオス成鳥にもそのまま当てはまってしまうので誤解していても気づきにくい。
何か不審な点が残ったらよく調べてみるべき好例となった。
ヨーロッパのハチクマと似た点があることはかなり注目されているが目先に羽毛がない点など異なる部分もある。
趾の間に膜の痕跡がある (なるほど)。嘴の嘴縁 (突起) の形はヨーロッパハチクマとそっくりで他の種ではハバシトビ [高野 (1973) ではアカハラトビ] Harpagus bidentatus 英名 Double-toothed Kite、モモアカトビ Harpagus diodon 英名 Rufous-thighed Kite の嘴縁突起の例があるとして比較している。
それぞれ違いがあるのでいくつかの属に分けたいが、そこまでの資料が得られていないので Falco 属にまとめていた。しかし自身の分類も反映してフランス語名では扱いを変えていた。
Le bec de cette espece est large et comprime ... la pointe fortement recourbee en Croc et tres-longue とあって嘴先端の鈎が長く目立つ点はこれらの種類と異なってフランス語名の由来となっているよう。
飛翔時の模様はオオタカやクマタカ類を思わせる点もあり、ハチクマで議論されるような擬態も提案されている [Sazima (2010) Five instances of bird mimicry suggested for Neotropical birds: A brief reappraisal]。
嘴に注目すればハチクマの仲間にも見えるが他の点は違っていて分類学者を悩ませた次第。
キューバカギハシトビはカギハシトビの亜種と考えられていたが、種相当の違いがあることがわかり別種となったもの。カタツムリ類に依存しているが生息地が非常に限定されており、1960 年代以降 10 例未満の目撃例しかなく絶滅の恐れの最も高い猛禽類 (IUCN CR 種) とされる。
Kirwan and Kirkconnell (2023) Cymindis wilsonii Cassin, 1847 (= Cuban Kite Chondrohierax wilsonii): Original Description, Types, Collector, and Type Locality
および wikipedia 英語版より。2010 年が最後の目撃で迫害も受けていて簡単に撃たれてしまうとのこと。
北米の委員会 NACC は 2024 年に独立種と判定。Johnson et al. (2024)
Comments on the species limits of certain North American birds, part 1
北米の他の種の境界変更も含め、明らかに Avilist/WGAC の世界的なリスト統一化に呼応する動きであるとのこと (参考 NACC, North American birds。今後も引き続き同様の提案が出されることを期待しているとのこと)。
ハイガシラトビは南北アメリカ大陸の普通種でそれほどの特殊化はないようである。シロエリトビはかつてはハイガシラトビの1型と考えられていたが独立種になったもの。こちらは生息地も限定されて生態もほとんどわかっていない。
この2種の恐竜を思わせるような名前の属名 Leptodon は leptos よい、ほっそりした odon, odontos 歯 (Gk) 上嘴にハヤブサ類にあるような「歯」(嘴縁突起 tomial tooth) が1つあるため。
ハバシトビ [高野 (1973) ではアカハラトビ] Harpagus bidentatus 英名 Double-toothed Kite、モモアカトビ Harpagus diodon 英名 Rufous-thighed Kite も嘴縁突起が2つあり、
Harpagus 属の種小名、英名や和名の一部はいずれもそれに由来している。
項目が大きくなったので [タカ類の嘴縁突起] を独立させた。
なお学名に関しては Leptodon cayanensis の種小名は cayannensis が正しいか議論となっていたとのこと。本来は地名 Cayenne (フランス領ギアナのカイエンヌ) 由来なので -nn- となるのが自然で Gmelin (1788) は -nn- を用いていた。
この種ではないが Linnaeus の記載 (鳥では IOC 14.2 で3種ある) では一貫して -n- の方が使われており、Latham (1790) は -n- の綴りを用いたとのこと。複数の名称を同じ方法で変更しているので単なる綴りの誤りではなく意図的な訂正とみなすことができるとのこと。
記載時の学名で記すと Falco cayanensis Latham, 1790 (修正された学名) と Falco cayennensis Gmelin, 1788 の2種類の学名が存在する状態で 20 世紀初頭には後者が広く用いられていたとのこと。
Falco cayennensis の名称はミサゴの変種の記載に使われた cayennensis (記載) があってその後 preoccupied と判定され、前者の名称が使われるようになった (現在も使われている) が実際には preoccupied ではなかった。
現在は通常 Latham (1790) が記載者とされているが、ICZN 規則を当てはめると Gmelin が記載者でこちらの学名を使うべきと議論されている (https://www.birdforum.net/threads/accipitridae.183825/page-7)。
よく似た綴りを同じものとみなすか、違った綴りを改名として有効とするかなどの各種問題が絡み合っていた模様。
カッコウハヤブサ類はこの中で比較的馴染みのあるグループであろう。東南アジアにタカの渡り観察に行かれる方ならば普通に見られる。
Mindell et al. (2018) では Aviceda 属が多系統となる結果に問題があったが、Catanach et al. (2024) による解析で解消された。
カンムリカッコウハヤブサの繁殖生態の研究があり、ハチクマとの比較も興味深いので別項目とした。
カッコウハヤブサ類には特有の臭気があると書かれていたが出典が不明だった。クロカッコウハヤブサの wikipedia 英語版に見つけた。Birds are said to have a disagreeable odour which has been described as "bug-like" (甲虫のようと言われる不快な臭気がある)。
A revised list of the birds of Tenasserim (Hume and Davison 1878 - ここまで遡らないと記述がないのか...) によればこの鳥は非常に特異で不快な臭気があり、カエルのような、あるいは甲虫のようと例えたらよいだろうか。皮をある程度空中に晒さないと消え去らないという W. Davison の経験を紹介している。
気にしているのは臭気があるともないとも言われるハチクマとの関係で、ハチが嫌う臭気があるかとの関係で [死体をおとりに使うか?] [ハチの幼虫を主食とする猛禽類・ハチの巣の蜜蝋を食べる鳥] のところでも取り上げている。
食べたものがそのまま体臭になるわけではないだろうが (昆虫食の種類は他にもたくさんあるし)、ロシアの (ヨーロッパ) ハチクマ飼育者フォーラムでは比較的知られているようで、それを指せばわかるらしい。「臭くないか」などのやりとりがなされていた。
断片的情報であるがエキゾチックな臭気があるとのことで、ある人は甲虫のようと表現していたのであるいはカッコウハヤブサ類と共通性があるかも知れない。もっとも飼育者によってはまったく気にならない人もあるようでにおいは特にないと答えている人もあった (これほどたくさんの動物を飼っているのに臭わないと来訪者が驚くぐらいとの表現があった)。
もちろん糞を始末せずに放っておくと大変なことになるが...、とかの記述はあった。
これらを一部抜粋して [(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の ロシアの飼育フォーラムから: Ingrid に紹介した。
甲虫だとカブトムシ飼育者 (採集者) では匂いはよく知られているが、排泄物とエサなどの腐敗臭が原因とあるのでちょっと違うかも知れない (カブトムシの匂いでもある・ないの議論が盛り上がるようなので感度の個人差、慣れなどもあるのかも)。
ロシアのハチクマ野生個体の保護経験のある人に聞いてみたが特に該当する回答もなく、気にしないとわからないレベルなのかも知れない。ロシアのアパートでは寒冷対策に気密性を高めてあって、部屋で飼っていていつも近くにいると気になる人もあるということだろうか。保護個体の放鳥時に嗅いでいる人のビデオは見たことがあるので、あるいは何か気づかれている方もあるのかも。
系統進化を見ればハチが嫌う臭気の進化にも関係するかと思って調べたのだが、今のところ手がかりはつかめていない。
この程度の臭気だとそれほど役に立たないかも、と思ったのだがテントウムシ (ladybug) などの臭気 (化学防御) にピラジン誘導体 (pyrazines) が含まれているとの記述を見つけ、
調べてみると Silva-Junior et al. (2018) Pyrazines from bacteria and ants: convergent chemistry within an ecological niche
アリなどで広く使われるフェロモンとのこと。虫自身が合成するわけではなく共生細菌が合成するとのこと。アミノ酸のスレオニンから合成される経路も見つかった: Motoyama et al. (2021) Chemoenzymatic synthesis of 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine by L-threonine 3-dehydrogenase and 2-amino-3-ketobutyrate CoA ligase/L-threonine aldolase。
広域スペクトル (もし関係するならこれが大事だろう) の昆虫で使われるとのことで、ピラジン誘導体は幅広い生物で警告化学シグナルとして使われているらしい [Woolfson and Rothschild (1990) Speculating about pyrazines]。
Osada et al. (2015) The scent of wolves: pyrazine analogs induce avoidance and vigilance behaviors in prey ではオオカミの尿にピラジン誘導体や類縁物質が含まれており、化学物質に対してシカなどが警戒反応などを示すとのこと。この論文では肉食動物が食物からピラジン誘導体を合成できる可能性も提唱していた。
Romero-Diaz et al. (2020) Structural Identification, Synthesis and Biological Activity of Two Volatile Cyclic Dipeptides in a Terrestrial Vertebrate。マウスやツパイがフェロモンとして利用しているとのこと。
ピラジン誘導体は鳥も警告化学シグナルとして感受する報告もある [Guilford et al. (1987)
The biological roles of pyrazines: evidence for a warning odour function]。
鳥避けにも関係してハゴロモガラスで調べられたりしている。
ガが用いるアリやクモなどの捕食者よけ: Burdfield-Steel et al. (2020) Testing the effectiveness of pyrazine defences against spiders。
このぐらいならばハチクマでも可能かも知れない。
ハチクマやカッコウハヤブサが使っているかどうかはわからないが、Cherniienko et al. (2020) Antimicrobial and Odour Qualities of Alkylpyrazines Occurring in Chocolate and Cocoa Products
によればピラジン誘導体は抗菌・抗真菌作用もあるとのこと。虫ではもともとは非特異的な抗菌・抗真菌作用から始まって捕食者対策やフェロモンに用いるようになったのかも? 生物活性が高いので哺乳類も用いている? 比較的最近注目を浴びるようになったようなのでハチクマでは過去考慮されていなかったかも知れない。今後の進展に期待したい。
このような窒素の入ったヘテロ芳香族ならば分光で非破壊で羽から検出できるかも?
アフリカカッコウハヤブサの幼鳥はアフリカオオタカ Accipiter tachiro (新分類で Aerospiza tachiro) 英名 African Goshawk に似ている (擬態か?) との指摘がある (コンサイス鳥名事典)。
Bildstein (2017) "Raptors" にはクロカッコウハヤブサがより弱い鳥であるカッコウに擬態することで捕食を容易にする説が紹介されているが本当か? (南米のオビオノスリは弱い鳥である新世界ハゲワシに擬態している説がある: #ノスリの備考参照)。
カンムリカッコウハヤブサに第 III 趾と第 IV 趾の間の膜が欠如して趾をミサゴのように後ろに回せる能力があるとのこと [Tsang (2012): #カタグロトビの備考参照]。
ツバメトビがスズメ目を巣ごと持ち去って捕食した例が知られている: Coulson (2001)
Swallow-tailed Kites Carry Passerine Nests Containing Nestlings to Their Own Nests
個々のひなを捕食して運ぶよりも時間も手間も節約できるとのこと。2つの繁殖コロニーで 14 個体以上で見られた行動とのこと。翼面荷重が小さく、低くゆっくりした飛行で樹冠や茂みの中の獲物を探すとのこと。
食べた後の巣は通常捨てるが自身の巣に残されることもある。
系統的に近いハチクマに似てハチの幼虫も食べるが、記述を見ると樹上性のハチの巣を枝を折って捕食するよう。枝を折るため足は強力とある。
Swallow-tailed Kite (Linda Fell 2024.7.20), Swallow-tailed Kite 飛びながら水面で水飲みらしい画像。
Swallow-tailed Kite (Mark Gorday 2024.6.8) ハチの巣を運ぶ。
Swallow-tailed Kite (Bob Sicolo 2024.5.29) 鳥のひなを相棒に渡す。
ツバメトビの写真を見ていると翼面荷重が小さいので尾羽の揚力があまり必要なく、この尾羽の形状で十分だったのだろうかと考えてしまった。
クロムネトビは道具使用が特徴に挙げられる ([ハチクマ類の道具使用] 参照)。
シラガトビ [高野 (1973) ではアカムネトビ] の Lophoictinia は lophos 冠 (Gk) + Ictinia Vieillot, 1816 ムシクイトビ [高野 (1973) ではナマリイロトビ] に与えた属名 (現在も使われる)。iktin はギリシャ語でトビで -ia を付けて属名語尾としたもの。
種小名の isura の方が難関だが、同種を指すもう一つの形があって isiurus (Milvus 属の時代)。これは isos 等しい (英語でも接頭語によく使われる iso- の語源) -ouros 尾 (Gk) と解釈される (以上 The Key to Scientific Names の情報から)。
トビ類、特にヨーロッパで通常見られるトビやアカトビは凹尾だが、その仲間 (ではなかったことが分子系統解析で判明した) でありながら角尾であることから "等しい尾" の種小名となったと考えられる。
この角尾の特徴が英名の Square-tailed Kite の由来と考えられる。実際の種小名ではさらに短縮された形となっているが、Isurus 属が魚に存在して (和名アオザメ、バケアオザメ) 同じ意味の解釈がなされている。
isura の読みは上記語源から "イスーラ" と考えられる。
シラガトビ [高野 (1973) ではアカムネトビ] の和名の命名者は学名や英名の由来などはあまり考慮しなかったと思われ色彩から独自の名前を付けている。オーストラリアにはクロムネトビ (この名称は英名や学名に対応する) がいるので、それに対する名称としてアカムネトビが与えられたのかも。
対応する他言語の名称は見つけられなかったのでおそらく学名由来ではないのだろう。
写真を見る限りでは "シラガトビ" の名称の方が少しふさわしいかも。ロシア名も独自で "前髪のあるトビ" となっていて着眼点はシラガトビに近いかも。
"トビ" と名付けられたのは尾や翼の形にも関係あるだろうが、風切羽にタカ班が見えるなどいわゆる "トビ類" とは印象が異なる部分がある。ハチクマに少し近い種類と思って見ると類似性が多少見えて面白いかも。高野 (1973) = Lloyd and Llyod (1969) によればチュウヒのように低く飛んで獲物を捉えるとのこと。
オナガハチクマ属に使われる Henicopernis は henikos 特異な (Gk) に由来。前述のようにこの属はクロムネトビ属 Hamirostra に吸収されてなくなる可能性もある。
こちらの由来は hamus 鉤 rostrum 嘴。
クロムネトビは嘴が長くろう膜部分が特に長く嘴の半分を覆うことが特徴とのこと。意外にもオナガイヌワシと結構混同されて掲載されていることがある。
ハチクマ系統の "トビ" と呼ばれる種類とカタグロトビ類を Brown (1976) では aberrant kites とも称している (primitive kites とも呼んでいる。古い分類時代なので多少注意が必要だが)。aberrant は辞書的には「異常な」「異常型の」などの意味がある。"通常の経路から逸れる"、"所属するグループとやや異なる"という意味。これは、ラテン語の aberrans から派生 (etymology online)。
医学用語でも不整脈の原因となる心臓内の変行伝導 aberrant conduction、本来以外の場所にある (異所性) 甲状腺組織 aberrant (or ectopic) thyroid のように使われる。使用例を知った上で aberrant kites を見るとわかりやすい表現に感じる (もちろん他の分類群でも使われる用語)。
英語の kite とギリシャ語 iktinos は以前はトビ/アカトビのみを指す用語であったが、フランスの鳥類学者は milan をカタグロトビ類も含む名前として用いたなど言語による概念の違いも多少ある。「真正トビ類」(true Milvus) のような表現も使われた (Elaninae の wikipedia 英語版から)。
Brown (1976) によればオーストラリアにはノスリ類が分布しないので (aberrant を含む) "kites" がノスリ類の地位を占めているとのこと。
なお、オーストラリアの化石種ではあるがカタグロトビ類 (科?) とタカ科の間に位置する、(カタグロトビ類が科として分離されれば) タカ科の中で最も古い (2400-2600 万年前) 系統が見つかっている:
Mather et al. (2022) An exceptional partial skeleton of a new basal raptor (Aves: Accipitridae) from the late Oligocene Namba formation, South Australia。
この著者たちは Archaehieraxinae 亜科を創設し、Archaehierax sylvestris Archaehierax (arkhaios 古い hierax タカ Gk) sylvestris (森林に関係する < silva 森林) の学名を与えている。
当時のオーストラリアは現在よりずっと湿潤で森林に覆われていたとのこと。
大きさはオーストラリアの現生種クロムネトビとオナガイヌワシとの中間だがオナガイヌワシよりずっと華奢な造りになっているとのこと。クマタカ類のように森林に適応した翼を持ち、現代の森林性猛禽類ほどは強力でないもののクマタカ類に近い生態を持つ種類がこの段階ですでに現れていて小型の哺乳類 (例えばコアラ) や鳥類を捕食していた可能性が考えられるとのこと。
ハチクマの祖先系統に対して選択圧を与えた可能性があるかも知れないなあ、とぼそっとつぶやいておく (笑)。
ハチ類の出現はいつごろ?
参考までにハチクマの好きそうなハチ類はいつごろかいたのかも調べておいた。Tang and Vogler (2017) Evolution: Taking the Sting out of Wasp Phylogenetics
によれば1億年前には主な系統は出揃っていた模様。
Harrison et al. (2018) Hemimetabolous genomes reveal molecular basis of termite eusociality
の研究でも社会性シロアリ類は 1.5 億年前に誕生、我々が普通にみかけるハチやアリは 5000 万年前に出現とのことでハチクマの進化の方が後になる。
Hellemans et al. (2025) Termites became the dominant decomposers of the tropics after two diversification pulses (preprint) によれば 1.32 億年前に誕生とされるが多様化が進んでシロアリ類が熱帯の主な分解者となったのは始新世/漸新世境界 (Eocene-Oligocene transition 3390-3340 万年前) の寒冷化に伴うものらしいとのこと。
この時期はタカ類の適応放散の時期と一致し (適応放散の理由も同じように解釈されている)、社会性シロアリ類の進化はタカ類の適応放散とほぼ並行して起きていたらしい。
当たり前のような感じもするが、イヌワシ属 Aquila (あるいはその中の系統 ソウゲンワシ属 Psammoaetus と分けることもある) のようなワシでもシロアリは好むので、タカ類の祖先系統でもよい食物だったかも知れない (もっとも系統分岐時期しかわからないので食物として多量にあったかまでは不明)。
チンパンジーもシロアリを食べるしヒトでも好んで食べるフィールド研究があった (URL は失念)。タカ類の祖先系統にも都合のよい食物がすでに存在していたことになる。
過去の人類の食物はハチクマ的だった?!
窒素の安定同位体 (15N) 解析からネアンデルタール人が日常的にハエなどの幼虫を食べていた可能性が発表された: Beasley et al. (2025) Neanderthals, hypercarnivores, and maggots: Insights from stable nitrogen isotopes この中にも文化人類学的記録が多数あることが紹介されている。
値は現在の肉食動物を超えるぐらいだが、そこまで 15N が多い食物は少なく、豊富に存在して人が食べることが食物はハエなどの幼虫が非常によい候補になるとのこと。我々はハチクマやイヌワシ類の一部に近い食性から進化したものだったのかも知れない。Mystery food in Neanderthal diet might be maggots (Jenna Ahart Nature news 2025.7.25)。
[ハチ類の行動とタカ類などの共進化]
Detoni et al. (2021) Evolutionary and Ecological Pressures Shaping Social Wasps Collective Defenses
にハチ類の行動 (攻撃防御など) の進化と捕食者の関係が議論されている。ハチ類が最初に進化したころには単独行動で刺す行動は獲物を麻痺させるために進化したと考えられる。真社会性ハチ類は捕食者が現れる前にすでに進化していたが、次第に強力な相手が現れて防衛能力を高める (軍拡競争)、あるいはあきらめる行動も進化したのではなど議論が行われている。
あきらめる行動は温帯の Vespula 属や Dolichovespula 属のコロニーではほとんど見られないが、これは繁殖可能な季節の幅が狭く、あきらめて別の場所にコロニーを作る行動が進化しにくいためと考えられているとのこと。
アリの毒に対して小型捕食者のツノトカゲ属のトカゲ Horned lizards (Phrynosoma 属) は対毒性を獲得してその毒を代謝して自身の毒として用いる (一部の種は目から毒を噴射する) 特異な経路を獲得したが [参考: Sherbrooke and Kimball (2024) Antipredator Blood-Squirting Defense in Horned Lizards (Phrynosoma): Chemical Isolation of Plasma Component(s), Pogonomyrmex Ant Dietary Origin, and Evolution]、
これはまれな事例で他にはほとんど知られていない。アリやハチ類の集団攻撃に対して捕食者側が抵抗力を得る軍拡競争においては小型捕食者側にはあまり勝ち目がないので、おそらく毒への抵抗性はあまり進化しないと考えているように読める。哺乳類や鳥類のような後に現れた大型捕食者は強力で体も大きく、哺乳類捕食者は複数回刺されても抵抗力がある観察事例があるとのこと。おそらく特別な毒抵抗性を持っていないと考えているのでは。
fig. 5 の時系列も面白く、ハチの子の栄養価の高さに気づいたタカ類 (ハチクマ以外にすでに消滅した系統もあるだろう) やスズメ目とともに集団防衛行動 (あるいはあきらめる行動) が共進化した可能性がある。Vespa 属は 2700 万年前と新しく、タカ類の放散時期とかなりよく合っている気がする。
Pernis と Henicopernis 属が分岐したのはほぼこの年代ぐらい。
Catanach et al. (2024) の分子系統樹を見ながら読んでいただきたいが、それ以前のタカ類の系統にあまりハチの子食が目立つものがないので、このあたりから栄養価に着目したタカ類による捕食圧が次第に高まってきたのだろうか。反撃が進化するとともにタカ類も襲う戦略や羽毛の機能などが次第に高性能化したのかも。
それ以前のタカ類の系統で散発的にもハチの子食が現れないのは、ハチの子食のために何かの機能 (生理的なもの、中枢神経の機能など要因はいろいろ考えられる) が必要で、Pernis 系統で初めてその線を超えることができたなどの理由を想像することができる。
系統がかなり異なる Henicopernis 属がハチの子も食するのは、ハチの子食を可能にする機能が (ハチの子食以外の面でも?) 有利であったため失われることがなかったのかも知れないが、ハチの巣盤を嘴でくわえる (Pernis) か足で掴む (Henicopernis ではそのように言われている) か違いも多少あるようなので、あるいはある程度の共通基盤のもとにそれぞれ進化させた行動かも知れない。
オナガハチクマ類がいったいどのようにハチの巣を壊すのか観察した人はおそらくおらず、行動にどの程度の類似性があるのかおそらく不明。
もう少し系統樹を見ておくと、Pernis 属と Henicopernis 属の分岐は古いが、それぞれの属内 (または近縁属) との分岐は比較的新しい。
Pernis 属と Henicopernis 属の分岐はウォレス線 (Wallace's Line) の西と東に対応しており、分散能力の高いグループでも陸続きにならなかった障壁を乗り越えるのは難しく系統間の隔離が生じたと考えられる。
もっとも途中に位置するツバメトビ [高野 (1973) ではツバメハイイロトビ] Elanoides forficatus Swallow-tailed Kite はアメリカ大陸に分布しているので、ハチクマの後の系統でもほぼ陸続きの北回りで分布を広げているものがある。
ツバメトビでは樹上性のハチの巣を枝を折って捕食する情報がある ([ハチクマ亜科の他種]、[ハチの幼虫を主食とする猛禽類・ハチの巣の蜜蝋を食べる鳥])。共通祖先段階 (2800 万年前程度) でハチの子に目をつけて様式は異なるが捕食能力も獲得しつつあったと思われる。
Pernis 属に最も近い Aviceda 属 (Pernis 属の前の分岐で特にハチの子食の傾向はない) のアフリカとアジア・オセアニアの2系統の分岐は 1800 万年前とだいぶ古く、もし Pernis 属が同じような進化を遂げていて同様に中東地域の乾燥化で隔離されたものであれば同じような分岐年代となってもおかしくないような気もする。
実際はハチクマとヨーロッパハチクマの分岐年代は 1000 万年前ぐらいと新しいのでハチの子食に特化したのは Aviceda 属の東西分岐より後の時代のように見える。
Vespa 属の初期進化に影響を与えた系統があったとすれば現代のハチクマとは少し異なる類縁系統で、現代のハチクマの方が高性能だったため競争排除されて残存していないのかもなどの解釈を考えたくなる。
1800-1000 万年前程度の時期には Circaetus, Spilornis, Nisaetus, Tachyspiza (主に南方系で競争の生じそうな属を取り上げた) などタカ類の主要属はほぼ揃っており、これら猛禽類との競争の結果ハチクマがハチの子食により特化して行ったのかも知れない。
とは言えオオタカもノスリもこの地域に分布しないのでハチクマの生息を決定的に制限するほど強力な系統があまりない。ヘビ食ならばスペシャリストの方が上かも知れない程度の問題。
現在もハチクマ類と同じようなところに分布している Nisaetus 属はよい競争者だったかも。それぞれ違う食物を中心とすることで共存している感じで、ハチクマ類を排除することは過去にもなかったのでは。
もう少し後の時代の種分化を考えてよいならば、ハチクマの祖先系統にあたるものが一度適応放散し、後に生じたハチクマが優勢だったために吸収されてしまった可能性も考えられる気がする。これはセグロセキレイとハクセキレイの関係 #セグロセキレイ備考の [近縁種との関係] をもとに考察したものだが、ハチクマに多様な色彩型があるのは祖先系統を吸収してしまった結果と考えればハクセキレイの亜種の豊富さ同様に統一的に解釈できるかも知れない。
[ハチクマ色彩の遺伝的背景] の Ono et al. (2024) で MC1R のハプロタイプが他種との交雑でもたらされた可能性に対応するかも知れない。
小野 (2020, 2023) の mtDNA とも2起源?、「ハチクマという種がごく最近二つ以上の遺伝子プールの雑種形成から生じたことを示唆していると考えられる」に対応するかも知れない。
この解釈が成り立つためにはハチクマの祖先系統と交雑可能な程度の分岐年代の必要がある。あまり古すぎては交雑が難しく、おそらく 1000 万年前程度はよさそうな数字ではないだろうか。ヨーロッパハチクマにも morph が存在することから共通起源段階ですでに祖先系統と交雑して吸収していたかしつつあったのではないだろうか。
これらの数字から推定すると 1800-1000 万年前ぐらいの段階でハチクマの祖先系統がたとえばアジア熱帯や亜熱帯で適応放散し、その中で特に機能の高かった後発のハチクマが残ったのではないだろうか。移動能力が大きいのでアジア程度の広さでは種分化するほどの隔離は起きず、遺伝的には混ざっているものの個体間の遺伝的距離は大きいと解釈できる。いかがだろうか。
さらに想像を膨らませるとハチクマ類はもともとは真面目な (?) タカをやっていたが、2700?-1800 万年前ぐらいには南方系で競争の生じそうなタカ類の主要属はほぼ揃ってくるようになり、うまくハチの子食を見出すことができて真社会性ハチ類の Vespa 属に圧力を加えつつ共進化することで他のタカ類と競争を避けることができてハチの子食に主な食性をシフトさせたのかも知れない。
フィリピンのハチクマ ([フィリピンのハチクマの不思議]) に遺存的要素はないのか気になる要素が増える。系統解析を行った Gamauf はフィリピンのハチクマに色彩多様性がないのは少数の創始個体群の特徴が残った創始者効果と考えていたようだが、何と言ってもミトコンドリアの短い断片のみなので過去の交雑を想定するならば核ゲノムではどの程度違うのか知りたいところである。
独自にある程度のハチ攻撃への適応を進化させたミツオシエ科 (アフリカやアジアのキツツキ目) があり、図鑑などの配列ではキツツキ目の方が後の方に並ぶので新しいように見えるが年代関係を確認しておいた。Dufort (2016) An augmented supermatrix phylogeny of the avian family Picidae reveals uncertainty deep in the family tree がキツツキ目の系統解析、
生物地理学を合わせた分岐年代解析では Claramunt and Cracraft (2015) A new time tree reveals Earth history's imprint on the evolution of modern birds
が現状信頼されている模様で (Supplementary Material の 1501005_sm.pdf をダウンロードしておくとよい)、ミツオシエ科は 3600 万年前ぐらいの分岐が想定される。予想通り? タカ類の方が全体的に新しい。
なおインドミツオシエ (キゴシミツオシエ) Indicator xanthonotus Yellow-rumped Honeyguide では人の手を借りずに Apis laboriosa Himalayan giant honey bee の蜜蝋を食べ、ハチにあまり妨害されないとのこと。
オオスズメバチ Vespa mandarinia の Apis laboriosa への攻撃を利用して蜜蝋を得たとの報告もあるとのこと。この場合はスズメバチを利用してハチの巣を襲わせていることになる (wikipedia 英語版より)。
インドミツオシエがハチにあまり妨害されない要因も調べてみると面白いかも。
ミツオシエ科の狙いは蜜蝋とハチの子で蜜は目的でないらしい。蜜はほとんど炭水化物なので栄養価が低く重視されていない点はハチクマの場合と同じ。
ハチ攻撃対応ではハチクマと多少の類似性がある。鳥類ではタカのような大型種出現まで真社会性ハチ類に決定的圧力をかけるまで至らなかったのかも。
ミツオシエ科はキツツキの系統で武器も持たず、体も小型で積極的な防御を行うほど強力なグループではなかったので、一部の種類では他の大型動物にハチの巣を壊させる方の進化が進んだのだろうか。オオスズメバチが主にタカ類と共進化の結果凶暴化したのであればインドミツオシエは間接的にタカの恩恵を受けているのも (ほんとうか?)。
インドミツオシエがハチクマを誘導してハチの巣を壊してもらえばよさそうにも見えるが、これは自身が食べられる恐れがあってこの行動は進化しなかったのかも (おとぎ話の中のような世界と思って読んでいただければ...)。
スズメバチに襲われる方の人間にとってはたまったものではないが、これも哺乳類やタカ類がよってたかって捕食した過去の痕跡が残っているのかも (?) と考えるとロマンも漂う。
「ハチ類の行動とタカ類などの共進化」と言えば何となくわかったような気になってしまうが、ハチの側の視点からも少し見ておこう。そもそも飛翔能力で昆虫は鳥類に勝ち目はなく、軍拡競争と言っても圧倒的にハチ側に限界がある。
タカ類のような能力の高い大型鳥類に目をつけられたところで進化の行方は決まったようなものではなかっただろうか。
その場合いたずらに攻撃能力を増すより適当な段階で退散する方が効率がよく、ハチクマもすべてのハチの巣を破壊するわけでもないので、やり直しを行うこの行動は進化できると思われる。大筋で Detoni et al. (2021) の議論をそのままたどっているだけだが。
ここでハチの側にとって大事なのは、攻撃すれば撃退できる相手とそうでない相手を早めに見分けて最適戦略をとることだろう。素手のヒトのように攻撃すれば撃退できる相手ならば攻撃のためのフェロモン (alarm pheromone) を出すなどそのまま攻撃するのがよい。一方でハチクマのように無理な相手は早い段階であきらめた方がよい (もちろんそのように考えて行動するようになったというより、そのようなプログラムを持った、あるいは持てる性質が自然選択で選抜された)。
撃退できる相手とそうでない相手を見分けるにはいくつか手がかりが考えられる。触覚でタカの羽毛のようなものに触れた場合、あるいは化学物質を検知してタカ類のようならば早めに退散した方が有利。このように考えると別にハチクマでなくても大型鳥類らしさが検出できればそれで十分のような気がする。種特異的な化学物質でなくても「タカ類のような臭気」(があるならば) を検出できる能力を少しでも持てば無駄な攻撃を避けることができてハチ類にとって有利かも知れない。
ハチクマが防御物質を出していると考えるよりも、ハチの側が見分け能力を進化させた程度かも知れない。
まだ羽毛の防御機能な未熟だった時期はもう少し原始的だったかも知れないが、この状況でタカの方が行うべき行動は最初の攻撃で退散するのではなく相手の攻撃力が弱ってくるまで待つことだったのだろう。
そのためには反射的に反応するだけでなく状況判断をして再挑戦する能力が必要で (このあたりは追い払われてもゴミ漁りを執拗に繰り返すカラスの行動に似ている。いずれ人間があきらめるのを知っている?)、そのための認知能力が必要だった (この解釈は賢さの進化の説明もできるかも?) と考えればハチクマの系統で一線を超えることができたのかも知れない。
ふと思い出したのが、[(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の Ingrid の項目で「ハチクマの気性は頑強です」が何を意味しているのかよくわからなかったのだが、少々妨害されても行動をあきらめない性質を示しているのかも知れない。この点に思い至ったのは、モビングを積極的に行うスズメ目の種類の解説で猛禽類が諦める性質を利用しているとあったため。
簡単に諦めない性格がハチの子食となる以前からあったものかハチの子食と一緒に進化したものかどうかはわからないが、ハチにあきらめさせるのに役立っていることは間違いないだろう。
集団で空中の巣を襲うハチクマの映像を見るとある程度先読みができているのではないかとも感じる。
妨害されてもまた巣を造るハト (場所への執着) とはまた仕組みが違うだろう。
一度タカが優位に立てば後は相手が早々にあきらめる能力を進化させるのが得策で、いずれは現在のような関係が安定な状態になるのだろう。またハチクマの系統で初めて一線を超えて一定の身体的適応が進めば、同所的には後の系統で後追いで身につけても追い抜くことが難しく、ハチクマ以外の系統でハチの子食がそれほど進化しなかった理由になるかも知れない。
ただこの解釈では世界の他の場所でハチクマと対等の種類が進化しなかったことが十分に説明できない。アメリカ大陸ではハヤブサ目のアカノドカラカラが後発で身につけたと言えるがハチクマほど高性能にならなかった理由はあるのだろうか。
[ハチの幼虫を主食とする猛禽類・ハチの巣の蜜蝋を食べる鳥] に登場する中南米のヒメキヌバネドリ Trogon violaceus Guianan Trogon が熱帯産スズメバチの巣を横取りして成虫も幼虫も食べ自分の巣にするとのこと。こちらもある程度壊されればハチの側があきらめると解釈すると理解できる気がする。
キヌバネドリ目の属する Eucavitaves のクレードにミツオシエ類 (キツツキ目) が含まれることは偶然ではないかも知れない。ヒメキヌバネドリは食料目的より巣穴が欲しいもので、あるいはミツオシエ類ももともと巣穴を探すためにハチの巣を訪れるうちに食料として活用するようになったのかも知れない。
樹洞営巣性の鳥はハチの巣に出会う頻度が高かったのかも。
これらの系統にみなハチ毒耐性があるとちょっと考えにくいので (多少はあるかも知れないが)、鳥類捕食者に対してはハチの側が一方的にあきらめる行動を進化させたのかも。
ヒメキヌバネドリは (この種に限ったことではないが) 目先の裸出部はなくて羽毛に覆われており、ハチクマ同様そもそも刺せる部分が少ないだろう。
Eucavitaves のクレードはハチクマよりも早い時期に出現しているので、あきらめる行動はタカ類以前から始まっていて、タカ類にとっては最初から有利な条件で、食物として完全に目をつけてしまったハチクマ系統の出現でハチの行動も一層洗練されたのかも。
改めて考えてみると、少なくとも鳥類では、ハチの巣を壊してその場で食べることができても、食べられる量も限られていて、ひなに常食として与えるためには運ぶ必要がある。ハチの巣を壊す能力をたとえ身に着けても、ハチの巣資源はそれほど高密度で存在するわけでもなく (特にハチクマの好む肉食ハチ類は高次捕食者である)、運搬方法がなければ効率の悪い資源となっていまう
(資源の埋蔵量と資源量は異なるのと同様。貯蔵したり運搬できる穀物の栽培が行われるようになって文明が進歩したのも似ている。近いところにある資源の方が有用なのでヨーロッパやロシアから見てウクライナが特別な位置を占める理由にもなる...なんて話にも応用できる)。
昆虫食のスズメ目が虫の多い場所の近くに営巣するのと同じようなもの。虫の多い場所が近くになければ営巣場所があってもツバメも繁殖できない。
遠すぎるともはやあまり有効な資源にならない。従ってハチの巣を壊して常食する特別な習性は進化しにくい。
地上性鳥類も古い時代から多種存在し、鳥類で原理的には何度でも進化可能な性質ではあったが、重量物を遠距離運べる足を持ったタカ類系統の出現によって、ハチの子食がようやく労力に見合う意義のある進化を遂げた性質である説明になるかも知れない。
アメリカ大陸のアカノドカラカラも攻撃力はあるが重量物を遠距離運ぶのに適した足の構造ではないため、ハチクマほど洗練されたハチの子食になる必要がなかったのかも知れない。アメリカ大陸には旧大陸ほどタカ類の系統が多様でないので、ハチの子に頼らなくても他にも食物資源が残っている。
こういう話はハチの巣を運ぶハチクマを見たことがあれば現実味が湧く。姿勢が悪いと落としかけそうになったり、両足で抱えるように運ぶのはやはりそれなりに重いのだろう。持てるだけ持ちたい気持ちは買い物で買いすぎて運ぶのに困ることのある我々にもよくわかる (狙い撃ちで1点のみ買い物にくる客は販売する側にはあまりありがたくないわけだ、そして習性を利用して巧みに...とか始めると話が明後日の方に行きそうなので程々にしておく)。
刺せる部分がほとんどなければある程度以上の大きさの鳥では原理的にはいずれもハチの巣を狙えたが、タカ類の基本形態は目先が露出しているので、どんなタカでもハチの巣を狙うわけには行かず、視界を遮らない目先の羽毛の進化など多少の形態適応の必要があったのだろう。
樹洞営巣性のフクロウ類でもハチの巣を狙えたかも知れないが、ほぼ夜行性のためハチを追跡してハチの巣を探すのは無理だったかも知れない。
ハチの針の構造を参考までに調べておいた: Ramirez-Esquivel and Ravi (2023) Functional anatomy of the worker honeybee stinger (Apis mellifera)
によればセイヨウミツバチの針がどこまで刺さるか調べたところ 1.3 mm 程度だったとのこと。ヒトの皮膚であれば真皮に毒を注入するには十分な長さであるが、皮下組織までは届かないとのこと。
研究の関心事は哺乳類の皮膚で鳥の羽毛は対象外だが、この数字ならば羽毛を通して届きそうもない?
なぜもっと細長くできないか理由もあって、刺す際に抵抗で挫滅してしまう (折れてしまう) 制約がある。哺乳類の皮膚の強度に抵抗する必要があるためあまり細長くできないわけで、羽毛で覆われた鳥にはあまり効果がなさそう。
ハチクマがハチの毒に耐性がある、あるいは何か物質を出して防御していると言われればそのように思えてしまうが、同じようにハチの巣を壊すラーテル (Mellivora capensis Honey badger) はなぜあまり話題にならないのか。
Ratel/Honey Badger (Mellivora capensis) Fact Sheet: Taxonomy & History (San Diego Zoo Wildlife Alliance Library) によれば
・Thick, loose skin helps protect against bee stings, but individuals have been found stung to death by honeybees (Begg and Begg 2002)
・Ratel do have some degree of resistance to snake venom; as do some other mustelids (Begg and Begg 2004; Voss and Jansa 2012)
・Possibly due to the thickness of its skin; when bitten, only small amounts of venom are likely injected (Vanderhaar and Hwang 2003)
・Myth: ratels fumigate beehives with their scent glands (Begg and Begg 2002); Descriptions of ratels anaesthetizing bees or emptying hives by performing handstands and spraying have not been confirmed by scientists working in the southern Kalahari
とのことで、毒耐性がある、臭腺から物質を出してハチを無力化させる、などのハチクマで提唱されているような仮説 (鳥の尾脂腺はかつては哺乳類の臭腺と同様の機能と考えられていた) は一通り出ていて、いずれも神話であるとのこと。
皮膚に針が刺さりにくい、皮膚が厚いので毒が入っても少量になる、しかしミツバチに刺されて死んだ例があるらしいので毒耐性はあまりなさそう。ヘビ毒に多少の耐性があるなどの報告がある。
ヘビ毒の特異耐性は鳥ではまだ報告されていないのでこちらは哺乳類特有かも。ラーテルに対する仮説の方が先に否定されてしまって、同じような発想の仮説が検証されないままハチクマに残っているだけかも知れない。ハチクマも羽毛が針をほぼ通さないだけで仕組みはラーテルとほとんど違わず、それ以上特殊な話は何もなかった、で終わるかも知れない。
体重はラーテルの方が 5-10 倍大きい (飛ぶ鳥と比較すればもちろん重い) が1桁違うほどでもない。哺乳類の毛の方が性能が低そうなので程度問題の違いだろう。
なおラーテルの Mellivora 属の分岐年代は 1200-1300 万年前、イタチ科 Mustelidae まで遡れば 1610 万年前ぐらいとのこと。ハチクマの祖先系統がハチの子に目を付けたのとどちらが早いかを考えるとなかなか微妙な前後関係かも知れない。1000 万年前より少し古い時代ぐらいにハチ資源が急激に増えたことを表しているのかも。
[目先の羽毛の役割] (#オオモズ [目先の剛毛 rictal bristles の役割と進化] より重複掲載とともに考察を発展させた)。
この部分の羽毛がハチクマではうろこ状になって覆いを作っているのはもしかするとヒントになるかも。ハチクマでも単なるハチが刺すことへの保護のためだけではなく、もっと積極的に感覚器の役割を果たしている可能性もありそうに思える (この点はコウモリダカも同様)。虫からの振動を感じて顔をそむけるぐらいのことはできるかも知れない。
ハチクマといえどもこの部位の羽毛は比較的薄いため刺されるのを避けるための虫センサーの役割は有効かも知れない。1か所だけ接触があればよけるなり頭を振るなりすればよさそう。複数の接触が同時にあって対処できないレベルになれば一度離れればよいなどの危険密度センサーの役割が考えられる気がする。それ以外の場所はほとんど刺さる危険性はないと想像すればこの点だけ注意すればよい。目の直前なので視覚的にも判断しやすい。
もう少し考えてみると哺乳類の皮膚ならば痛点にたまたま当たらなければおそらくハチに刺されてから痛みで気づくだろう。痛点も高密度に分布しているわけではないので、毒液が浸潤するまでの時間が必要である。気づいて対処するまでに時間がかかって多少毒液が注入されることになる。ラーテルではその弱点を厚い皮膚で補っていると想像できる。
鳥類でも痛みで気づくことは可能だが、羽毛をセンサーとすれば1枚の羽毛で痛点より広い範囲を感知できる。刺される前に気づくことが可能なので、顔をすぐにそむければたとえ刺されたとしても毒液の注入量もごくわずかで事実上影響がないだろう。
細い針ではそれほど高速に毒液を注入できないのは粘性があるためで、日常生活でもなぜホースはある程度太くなくてはいけないか、注射針はもっと細くてもよいのでは、などにも現れる。詳しく知りたい方はハーゲン・ポアズイユ流れ (Hagen-Poiseuille flow) などを検索していただければ具体的な数値もわかる。このテーマはおそらく大学1年程度の物理実験でよく扱われる。圧力をむやみに増しても流量がそれほど劇的に増えるわけでもない。
センサーとなる方の鳥の羽毛も、この程度の形状変化は簡単に生じさせることができて、飼育ハトならば品種レベル。他の部位の形態をハチ対応のために進化させるよりずっと簡単だろう。
羽毛が二次的に変化してうろことなるのも足など限られた部位で、ハチ避けのために爬虫類のうろこに戻せばよい、というわけには多分行かない。このあたりは鳥のうろこを爬虫類のうろこと同じように考える発想からは理解しにくいことになる。
また二次的にうろこに変化させることがもしできたとしても、頭部のような部位では固定したうろこよりは体温調節などのために動かせる羽毛の方が圧倒的に高機能で、上述のような刺される前の触覚センサーとなり得るのでより都合がよい。このように見ると哺乳類の皮膚より鳥の羽毛の方が防御面でも高機能と言えるだろう。
刺される前の触覚センサーとしての羽毛、そして毒を注入する方の流体力学的制約によってハチクマはハチ刺されを防いでいると考えると納得しやすい。
[タカ類の嘴縁突起] ([ハチクマ亜科の他種] より独立項目とした) ハイガシラトビは南北アメリカ大陸の普通種でそれほどの特殊化はないようである。シロエリトビはかつてはハイガシラトビの1型と考えられていたが独立種になったもの。こちらは生息地も限定されて生態もほとんどわかっていない。
この2種の恐竜を思わせるような名前の属名 Leptodon は leptos よい、ほっそりした odon, odontos 歯 (Gk) 上嘴にハヤブサ類にあるような「歯」(嘴縁突起 tomial tooth) が1つあるため。タカ類にも嘴縁突起を持つものがあり、ハヤブサ類やモズ類だけの特権ではない。
他にカッコウハヤブサ類
[英名でもハヤブサの名が付いているのは嘴の類似性のためか。Swainson (1836) にも嘴縁突起の記述があり、当時はタカもハヤブサも Falco 属だったが、足の形態は調べた限りのハヤブサ類とは似ていないと記されている]、
ハバシトビ [高野 (1973) ではアカハラトビ] Harpagus bidentatus 英名 Double-toothed Kite、モモアカトビ Harpagus diodon 英名 Rufous-thighed Kite も嘴縁突起が2つあり、
Harpagus 属の種小名、英名や和名の一部はいずれもそれに由来している。
川口 (2021) Birder 35(12): 54-55 で嘴縁突起 (この記事では刻歯) がハヤブサ類とモズ類に見られるのは従来は収斂進化と考えられていたが、分子系統研究でハヤブサ類とスズメ目の関係が近いことがわかって系統の近さを反映している可能性も示唆されている。それではなぜスズメ目の他種では見られないのかを問題提起している。
タカ類にも嘴縁突起が見られることはタカ類とハヤブサ類の系統の近さを表すのだろうか。
それともやはり収斂進化なのだろうか。
川口氏によるとモズ類の刻歯は嘴の骨の構造ではなくケラチン質とのこと。昆虫程度であればこの強度で十分なのだろうとの考えが示されている。
トビ類に近いと考えられていたため Double-toothed Kite の名称が付いていたが、
Harpagus 属もハチクマ亜科とは系統的には遠く、現代の研究では Macheiramphus (コウモリダカ属) 同様にむしろイヌワシ亜科 Aquilinae の後のオウギワシを含む系統に属する。
これらの例を見ると嘴縁突起は少なくともタカ類においては必要に応じて比較的簡単に進化できるもののようである。
Jollie (1976, 1977) p. 101 (fig. 82) に図がある。Harpagus, Ictinia では骨の構造 (tomial groove and septal bar) もはっきりしている。Leptodon, Chondrohierax では浅め。
によればハヤブサ類の嘴縁突起は骨の構造に従って形成されるが、タカ類の嘴縁突起はハヤブサ類に匹敵するほどではないとある。
その後「アニマルライフ」(日本メール・オーダー 1974) p. 248 に嘴縁突起のはっきり見えるオオタカの写真が載っていることに気づいた (1974 年のこのシリーズはフランスで制作されたものの翻訳)。
ハヤブサ類と同じぐらい深い突起になっているが下顎には対応するへこみはない。顔写真のみで日本のオオタカと少し違う印象を受けるが、ヨーロッパのオオタカは見かけが少し違うのかも知れない。ハチクマと思われる種類をサメイロイヌワシと説明した ([ハチクマと他種猛禽類との識別] 参照) シリーズなので種同定に誤りがある可能性を否定できないが、嘴縁突起のあることで知られる他種猛禽類の顔には見えないので、オオタカにも嘴縁突起が生じることがある、ということだろうか。
気になって探してみれば Featured Feature: Tomial Teeth and Cranial Kinesis (Infinite Spider 2014) が見つかり、何だ、例がたくさんあるのだった。アシボソハイタカでもはっきり見える例が紹介され (上記写真のオオタカではさらにはっきりしている)、切れ込みは浅いがクーパーハイタカで2つある例が紹介されている。
この記事の解説文章には伝聞で情報鮮度がちょっと古いものも含まれてそうなので写真のみ見ていただけばよい。
A Red-tailed Hawk's beak... (The and the Peanut 2012) にアカオノスリの写真が紹介されている。下嘴に対応する凹みがない点が違うとのこと。
骨の構造かケラチン質か程度の違いはあるだろうが、嘴縁突起はハヤブサ類やモズ類の専売特許とは言えそうもない。
「ハヤブサと違ってタカには嘴縁突起はない」も、誰かが言い出したと思われる事柄を疑ってみることもなく伝承されてきた、ワシの視力のような「伝説」に近い話だった。
多少気になるので関連して紹介しておくと Louryan et al. (2022) Evolution and development of parrot pseudoteeth
によれば発生途中のオウム類に見られる pseudoteeth には爬虫類や哺乳類の歯の発生で見られる遺伝子の発現が見られるとのこと。歯を取り戻しつつある、というよりは共通の制御パターンは歯を失っても保持されていると読めばよいだろうか。嘴縁突起の形態形成にも関わっているかも知れない。
[60 年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)]
マダガスカルヘビワシの学名の一部に使われるように triorchis という名前がタカ類にしばしば現れる。語源的には treis, tria 3つ orkhis 精巣 (Gk) の意味で、精巣が3つあると考えられたようである。副腎を精巣と見間違えたのではないかとの解釈がある。
triorkhes はアリストテレス等の用いたタカの一種で、ヨーロッパノスリを指していたのではないかと考えられている。Triorchis をタカ (特にノスリ) の一種とみなし、接頭語を付けて作られた属名がいくつもある。日本産の種類には出てこないが知っておいてよい語源である (wikipedia 英語版より)。
個々の種の解説で3つの精巣の語源が示されていることがあるが、これはあくまで Triorchis の語源を説明しているもので、学名で使われる時点ではその意味はなくタカ (特にノスリ類似) の意味で使われるもの。個々の種が3つの精巣を持つと勘違いされたものではないので注意を要する。
マダガスカルヘビワシはアフリカの東方沖合のマダガスカル島の固有種であり、かつてはカンムリワシなどを含むヘビワシ類と考えられたためこの名前が付いた。
マダガスカル島は様々な分類群の固有種が豊富であることが有名で、鳥類では「アカオオハシモズの社会」(山岸哲 京都大学学術出版会 2002) の研究が有名。霊長類の固有種も豊富でアイアイ、多数のキツネザル類などで有名で多くの研究者が訪れている。WWF によると2009年3月に起きたクーデターとその後の政治的混乱などにより、森林の大部分が失われこれら固有種の生息を脅かしている。
マダガスカルヘビワシの種小名の astur はオオタカのこと。
1930 年代の標本 11 点があるのみで一度は絶滅したと考えられた。
1988 年 Sheldon and Duckworth (1990) が目撃。
1990 年死体が見つかる (Raxworthy and Colston 1992)。
1993-1998 年に複数回目撃されて生存が確認された [後に紹介する Thorstrom and de Roland (2000 より]。
研究者にとっても研究が非常に困難な種で、海外データベースにもごく限られた写真しかない。
論文: Sheldon and Duckworth (1990)
Rediscovery of the Madagascar Serpent-Eagle Eutriorchis astur 目視情報のみ。
Madagascar Serpent-Eagle Captured for First Time in 60 Years (The Peregrine Fund 1994) この種の写真はこの時に史上初めて撮影された。
Thorstrom et al. (1995) Repeated sightings and first capture of a live Madagascar Serpent-eagle Eutriorchis astur。
First Madagascar Serpent-Eagle Nest Discovered (The Peregrine Fund 1998) 初めての巣の発見。
Scientists Race to Uncover the Secrets of Madagascar’s Treasure-Filled Forests (Audubonの記事 2019)。
Sutton et al. (2022) Extensive protected area coverage and an updated global population estimate for the Endangered Madagascar Serpent-eagle identified from species-habitat associations using remote sensing data
により詳しい情報があり、プレイバック法で従来考えられていたよりは個体数が多いことがわかったが成鳥は250-999羽と見積もられている。
Thorstrom and de Roland (2000)
First nest description, breeding behaviour and distribution of the Madagascar Serpent‐Eagle Eutriorchis astur
が初めて発見された巣と繁殖生態を記述している論文で、名前にはヘビワシと付いているが食物の 80% はカメレオンやカエルとのこと。ヘビも少数食べている。獲物はすべて頭部を食いちぎってあったとのこと。
クラッチサイズは1だった。巣立ち後も餌運びが観察された。巣立ち後6週間で独立したとのこと。
この研究で目撃されたマダガスカルヘビワシはいずれも非常に臆病で、Sheldon and Duckworth (1990) にある比較的人を恐れない記述とは異なる。Thiollay (1998) はよく見ようと近づくとすぐ隠れてしまうと記述している。営巣期は特に顕著で巣に入る時も出る時も極めて目立たないように行動して巣の近くで声を出すことはほとんどない。
巣の周辺で騒々しいマダガスカルオオタカ Accipiter henstii Henst's Goshawk) と大きく違うが、マダガスカルオオタカのひなはマダガスカルチュウヒダカに捕食されることもある (後述)。
マダガスカルヘビワシが捕食者対策として巣の周辺で目立たないように行動している理由は理解できるが、それ以外の場面でなぜそこまで隠れようとするのか理由がわからないと書かれている
(プレイバックなども用いた現代の技術でもそれほど観察困難な種類を 1930 年代にどのように 11 個体も標本にできたのだろうと気になるところである)。
目につかない場所に巣を作ることと合わせて巣を見つけることが極めて困難である。
この巣を見つけるのに4年かかった。最初は通常の大型猛禽類のように外から見える巣を探していた。
オスも半分ぐらい抱卵を行う。この点は多くのタカ・ハヤブサ類と異なって、系統に関係しているかも知れない (当時はトビ類はこのグループに近縁と考えられていたのでその点では現代の知見と多少異なる)。
系統の近いカッコウハヤブサ類は同様とのこと (ご存じのようにハチクマも同様)。
抱卵中に緑の葉のついた枝を運んだのはオスのみで、メスはほとんどひなのいる時期のみに運んだとのこと。
巣造りは産卵してから行う部分が多く、これも捕食者対策であろうとのこと。
緑の葉のついた枝を運ぶ理由はいくつかの仮説があるが (Newton 1979)、湿度を保つ、巣を見つけやすくする、衛生のためなどの仮説はいずれも当てはまりそうにない。熱帯雨林では排泄物はすぐに雨で流れてしまう。著者は断熱効果を考えているようである (この研究では同様の言及はないが台湾のハチクマの中継では初期はひなの糞を親が食べていた。若葉は糞受けに役立っているように見えた)。
マダガスカルヘビワシの孵化から巣立ちまでの期間は同じ程度の大きさな他の猛禽類や、同所的に生息するマダガスカルオオタカ (42-48 日) より長く 62 日だった。
熱帯の猛禽類と同様の少数産卵、長い巣内期間、長寿命の戦略をとっていると考えられる。
ひなへの給餌はメスだけが行い、オスは後期に食物を落とすのみでひなには給餌しなかった。
足の構造は爬虫類食に適応した点が見られるが状況に応じてさまざまなものを食べているようである。
成鳥も若鳥も地上で獲物を探しているらしい行動をしばしば目撃している。
"The Eagle Watchers" (Cornell University Press 2010) に Sarah Karpanty がマダガスカルヘビワシの研究を紹介している。1997 年ごろで再発見されて間もない状況で分布を調べたり巣をみつけようとしている段階の話である。当時 Karpanty は大学院生でマダガスカルヘビワシの巣を見つけることなど学内では「見込みのない計画や話」または「骨折り損」(wild-goose chase) と言われていたとのこと。
霊長類研究者によればキツネザル類ほか (lemurs) が猛禽類に捕食されるところが目撃されていないのに大型猛禽類 (マダガスカルノスリ Buteo brachypterus Madagascar Buzzard、マダガスカルチュウヒダカ、マダガスカルオオタカ
を見ると警戒音を出すのが不思議とされていて、例えば 500-1000 年ぐらい前にキツネザル類を捕食できる猛禽類が生息していたが絶滅してその名残ではないかとの仮説があったそうである
[Goodman (1994a)
The enigma of antipredator behavior in lemurs: Evidence of a large extinct eagle on Madagascar;
Goodman (1994b)
Description Of A New Species Of Subfossil Eagle From Madagascar - Stephanoaetus (Aves, Falconiformes) From The Deposits Of Ampasambazimba]
熱帯の猛禽類研究者共通の寄生虫によるジアルジア症や暑さなどの苦労があったとのことで、冬には回帰熱マラリアが流行してメンバーもやられたとのこと。
同行の現地の自然に最も詳しいガイドに持参した猛禽類の音声のテープを聞いてもらうと、ほとんどの種はたちどころに答えてくれたがマダガスカルヘビワシの音声はわからなかった。マダガスカルヘビワシと告げると信じられない表情を示し画像を見せると数年前にオオタカのような鳥がミルンエドワーズシファカ (6 kg ぐらいある島で2番めに大きな霊長類) を襲ったが失敗したのを思い出したとのこと。
声は過去に聞いたことがあることを思い出したが姿は見られず正体はわからなかったとのこと。
日記には熱帯雨林では「あまりに静かで行っても行っても猛禽に出会わない」とある。
5週間後になって早朝にようやく声を聞いたがあまりに疲れていてすぐに動けなかった。ガイドとともにテントから出ると大きな猛禽が飛び去るのが見えた。しかしその後4週間まったく気配がなく
「幽霊の鳥」となっていた。11 週間後にはどうやって帰るかを考えていた。数日前からマダガスカルヘビワシの声を聞いていて、どこか近くにいるはずとわかっていても姿を確認できなかった。
その日は祭りの日で見ると川辺の 100 m ぐらいの距離にマダガスカルヘビワシがとまっていた。急いでテントに戻ってカメラを取り川に走って戻った。飛んでゆく短いビデオを記録できたが種の識別に耐えるものではなかった。
この夏の間に視認または音声で何度かの確認ができて原生林以外に人の手の加わった森林にも生息することがわかった。
最後の残された時間で国立公園と近傍の猛禽類の調査を行い、マダガスカルヘビワシ以外の3種の猛禽類の巣を 10 個発見した。そのうち5個は国立公園の外側にあった。学務のために大学に戻る必要があって2か月この場を離れた。現地では農地を得るために伐採が行われつつあり、住民に営巣木を切らないように頼んで大学に戻った。
学務を済ませて戻ってきた時の現地の変貌ぶりは、訓練を受けた研究者にとっても感情を抑えきれないものであった。まさかわずか2か月の間にこの地域の猛禽類の半数が失われるとは。しかし農民を責めることもできない - 農民に食べ物などあるはずもなかった。
国立公園外にあった最後の1巣は営巣木のみを残して切られており、周囲の木の日陰になることもなくひなは生き延びなかった。
Karpanty は調査の合間にマダガスカルオオタカ、マダガスカルチュウヒダカがキツネザル類を捕食するのを幸運にも目撃することができた - 小型のネズミキツネザル類 (32 g) から大型のベローシファカ (3.5 kg) に至るまでひなに餌として与えた。
これまでの猛禽類研究者も霊長類研究者も目撃したことのないことであったがキツネザル類はちゃんと知っていて、猛禽類の巣で粘り強く観察する人が事実を証明する時を待っていたのだった。
この研究は Karpanty and Wright (2007) Predation on Lemurs in the Rainforest of Madagascar by Multiple Predator Species: Observations and Experiments
の学術論文となっている。この中でマダガスカルヘビワシが成獣のヒガシアバヒ Avahi laniger Eastern Woolly Lemur を捕食する場面が目撃されたことがあると伝えている。この研究ではマダガスカルヘビワシの巣は見つからなかったので巣に運ばれる食物の研究はできなかった。
マダガスカルヘビワシを含む猛禽類の4種の音声のプレイバック実験ではキツネザル類の反応はマダガスカルオオタカに対するものが最も長続きしたとのこと。
猛禽類が霊長類の群集構造や信号の進化に与える影響を議論した論文として McGraw and Berger (2013) Raptors and Primate Evolution
があり、この中でマダガスカルを含む世界の猛禽類による霊長類の捕食の一覧がある。タカ類の霊長類食に関心のある方には興味深いリストであろう。驚くべきことにハチクマに近い種類であるマダガスカルカッコウハヤブサやハイガシラトビも霊長類を捕食している (トビの名前から先入観を持ってはいけないようだ)。
クマタカによるニホンザルの捕食については Iida (1999) Predation of Japanese Macaque Macaca fuscata by Mountain Hawk Eagle Spizaetus nipalensis が引用されている。
東洋の種はもっと事例がありそうだが、研究されていないかあまり論文になっていないのだろう。
マダガスカルチュウヒダカ (#クロハゲワシの備考参照) もタカ類の中でも最も古い系統に属し、どちらかと言えば採集生活に近い印象を受けるがそれでも敏捷な霊長類を襲うとは驚きである。猛禽類の能力を改めて思い知らされる。
マダガスカルオオタカはオオタカ類の中でも最も大型のものの一つで現在のマダガスカルの生態系の頂点を占める。しかし親鳥不在中にひながマダガスカルチュウヒダカに捕食されることがあるとのこと。
マダガスカルヘビワシがマダガスカルオオタカに擬態しているとの指摘もある (wikipedia 英語版より)。後者出典は Negro (2008) (#イヌワシに出てくるアフリカクマタカのところ参照)。
マダガスカルヘビワシの営巣写真は例えば Aguia-cobreira-de-Madagascar (Eutriorchis astur) でも見ることができる。
数少ない写真: Madagascar Serpent Eagle (Ken Behrens 2021)、
Madagaskar slangenarend、
Madagascar Serpent Eagle (Eutriorchis astur) nestling (Russell Thorstrom 2019、巣内ひな)。
[ハチクマの学名は正しくないかも?]
Kaup (1844) (#イヌワシの備考参照) はハチクマ類をハイタカ/オオタカ型ノスリと分類していたが、インドのハチクマを cristatus (cristatus 冠羽のある) の種小名で呼んでおり、すでに別種と考えていた。Pernis cristatus の学名も使われていたことがあった。
例えば The Zoologist, 4th series, vol 6 (1902) ではこの学名とともに現在使われている英名 Crested Honey-Buzzard も使われている。この場合は学名と英名の対応がよい。
Wallace (1868) によるマレー半島の猛禽類の報告も読める: On the Raptorial Birds of the Malay Archipelago
この中では学名 Pernis cristatus が用いられていて、Falco ptilorhynchus Temminck, 1821 と同一と考えていたことがわかる。
これらの Pernis cristatus は後で示すように Bonaterre and Vieillot (1823) に出てくるもので Cuvier が命名したのもののようにも読める学名が由来と思われる。
Wallace (1868) はこの時点でセレベス島の変種 (現在では別種ヨコジマハチクマ) とセレベスクマタカ Nisaetus lanceolatus の模様が全く同じで「擬態」を指摘していることは興味深い ([ヨーロッパハチクマとの関係・亜種] の項目も参照)。
Osprey taxonomy (BirdForum) に興味深い記述がある (2009.5.6 のところ)。
最初に使われたのは Buteo cristatus Louis J. P. Vieillot, 1816 であり (原記載)、
記述は一見オーストラリアのミサゴを指しているようにも見えるが、ろう膜や足が黄色 (la cire et les pieds jaunes) などミサゴと合わない部分もある。
この投稿者によればオーストラリア (と言っても広範囲を含む) の場所の不自然さが残るが、あるいはハチクマの若鳥だったのではないかとの疑念が残る
Falco ptilorhyncus Temminck, 1821 と Buteo cristatus Bonaterre & Vieillot, 1823 のタイプ標本はいずれも Buteo cristatus Vieillot と記述されているとのこと。
Falco ptilorhyncus Temminck, 1821 の方が早いのでこちらが優先されることになった模様 (後述の情報も参照)。
もし 1816 年のものが 1823 年と同種を意図していたならば Buteo cristatus がハチクマの初記載となる可能性も残る。
Buteo cristatus Louis J. P. Vieillot, 1816 は現在では
カンムリミサゴ (IOC 14.2 などで亜種扱いに戻された) Pandion cristatus Eastern Osprey
の初記載として採用されているが、1816 年の記述はもしかするとハチクマだった可能性を否定できないという話。後の方の議論で代わりになる適切な名称をどう提唱するべきかなど挙がっている。
もしこの見解が認められればハチクマとカンムリミサゴの学名が変わることになるが、さて?
ミサゴを何種に分割するかの検証が終わってから、となるかも知れないが面白い話である。
この BirdForum の議論を最初に読んだ時は淡色型 (morph を指す名前でこの解説内で "型" と "形" のどちらも出てきてあまり統一していないのご了承を。どちらの表記も使われている。"性的二形" を変換すると使っている辞書ではこちらしか出てこず書き換えていない)
の若鳥だと専門家でもミサゴと間違えるぐらいなので...また地理的にもここまで渡っても不思議ではない。オーストラリアと言っても赤道近くの島しょ部を指しているかも知れない。
ハチクマの多彩な色彩が知られていない時代に記載者が間違えても不思議でない...と思ったが、原記載を確認してみると: 頭は白と褐色、後頭部から始まる冠羽が垂れている。上面の羽はすべて褐色で赤い縁取りがある。下面は白くて首の前に褐色の斑点があるが胸で消えている。
初列風切は黒い。尾は上面が褐色で下面は白っぽい。黒いバンドが目を通り、喉の両側に下っている。
嘴と爪は黒い。ろう膜や足が黄色。
体は我々の balbuzard より少し頑強である、とある。
ちょうどこの記載の前の部分にヨーロッパハチクマの記述があり、鷹匠にはこの種類は飛ばして使う役に立たないが肉は美味とのこと。これまでにこの種類を捕らえて (食べて) きたことでフランスでは数を大きく減らしてしまった [19 世紀初めのフランスではヨーロッパハチクマを食べすぎて数が減ったらしい (日本でも彼岸鷹と呼ばれて食べられていたが...)]。
対照的にロシアのクラスノヤルスク (シベリア) の湖では多くみられ、トカゲやカエルを食べている。Pallas はこの種類をむしろ lacertarius (トカゲの) と呼ぶべきだと言っている (現代の知識で見ればクラスノヤルスクのものはハチクマの方になるが、Pallas は違いに気づかなかったのだろうか)。
Accipiter lacertarius Pallas, 1811? (参考) で現代の年代同定だと 1811 年になる。Pallas は Linnaeus の Falco apivorus
のシノニムとして挙げているが、地域的にはハチクマと思われるのでもしこの記述が有効な学名と認められればハチクマの初記載になり得るのかも (Pallas の意図はそのようにも呼べると記述したもののようで有効な学名とは呼べないのだろうが)。"Pernis lacertarius" 幻の学名である。
Hartert (1910-1922) p. 1181 によればこれは Falco 属から Accipiter への属変更に伴う新名で Falco apivorus と同じものとしている。
その後ヨーロッパハチクマの狩りとあるので、ヨーロッパハチクマが獲物を捉えることが書いてあるのかと思ったら逆だった (標識のための捕獲などには役立つかも知れない情報だが省略する)。農作物に害を与える小動物を食べるので迫害するのもよくないともある。
1816 年の時代背景を考えるとやむを得ないところか。本の目的も農業との関係が中心で、どのように人や産業に役立つかなどの視点を重視したものになっているのだろう。
どの部分を見てもヨーロッパハチクマの記述で間違いないと思われる。
さて、このヨーロッパハチクマの記述の後に問題の Buteo cristatus が出てくるわけだが、表題は何と La Buse-bondree Huppee で、ミサゴでなくて明らかに「冠のあるハチクマ」(!) を意図している。
全体の構成でも BUSE (ノスリおよび類縁の鳥) のいろいろなタイプの説明の1項目の中にヨーロッパハチクマと一緒に挙げられている。"B. Lorum couvert de petites plumes tres-serrees, en forme d'ecailles. Tarses a demi vetus" がこの項目の表題で、"lore (眼先: 眼と嘴の間) は尖った小さな羽毛で覆われうろこ状。ふしょは半分覆われている" タイプのノスリに似た鳥。ハチクマ類以外あり得ないだろう。
ミサゴの眼先が羽毛に覆われているかと確認してみたが、少なくともハチクマと誤解するようなことはなさそうに見える。オーストラリアのミサゴに垂れ下がるほどの冠羽があるのかと見てみたが、逆立つとぼさぼさした感じに立っている程度ではっきりしたものはなさそうで、日本のミサゴと大差なく見える。他の地域のミサゴに比べて小型であるなどと記載されている。
少なくとも東南アジアでよく見られる長い冠羽のあるハチクマとは全然違って見える。
ちなみにミサゴは同書 p. 159 (第3巻) に BALBUZARD Pandion Veill. とあり、自身が名付けた属名としているが de Savigny (1809) が使った名称を使っているので Pandion の属名は現在は de Savigny の方に先取権があるとされる。
Vieillot はこの属に複数の記載があると細かく記述している。南北アメリカ、アフリカに生息していることは記述されている。この中に Falco arundinaceus, Latham がシベリアで記録した balbuzard des roseaux (葦原のミサゴと呼ばれていた) も含まれているが、ミサゴ類ではないかも知れないと述べている。この種は現在の (ヨーロッパ) チュウヒに対応する模様である。
これらを見る限りではミサゴと Buteo は混同していないように見える。
原記載では Nouvelle-Hollande で見つかったとある。Nouvelle-Hollande はオーストラリアと解釈されていた。同名の地名は諸外国にあるようだがここで関係するものはおそらく Abel Tasman (1644) が用いた名称で、
同地図によれば Nouvelle-Hollande (Australie) ニューギニアなどの北方の島も描かれている。
カンムリミサゴの初記載と考えられた時には記載場所がタスマニアと解釈され、タスマニアではミサゴの記録はほとんどないのでなどの議論もあったが、Tasman の地理的発見に引きずられた解釈だったかも知れない。
Nouvelle-Hollande の前に、オーストラリア発見以前の La Grande Jave (大ジャワ) の名称があり、大ジャワでの記載に Nouvelle-Hollande が使われていても不思議でないかも知れない。
次の C. の先頭にある種類は Falco connivens Latham で、Vieillot は Buteo connivens, Vieillot の学名に変更している。
この種類は現在のオーストラリアアオバズク Ninox connivens で Ninox 属はタカにも似たところがあるのでノスリの仲間に入れていたのだろう。この種も Nouvelle-Hollande の種類とある。現代の分布ではオーストラリア、ニューギニアとモルッカの一部となっている。
BUSEは A. B. C. のグループに分類されていて、例えばケアシノスリは C. (ふしょがほぼ趾まで羽毛に覆われている) のグループに属する。
B. に記載された「冠のあるハチクマ」をオーストラリアのミサゴと解釈したのは何かの誤りだろう。途中に比較に balbuzard = ミサゴが出てくるので、ハチクマ若鳥の容貌を知らないものが解釈したらオーストラリアのミサゴになってしまったのだろうか。
「黒いバンドが目を通り、喉の両側に下っている」はミサゴの特徴では? と思われる方もあろうと思うが、戸塚 (2004) Birder 18(10) の付録にあるほとんど白色の若鳥の写真ではこの通りに見えていて (頭頸部のバンドの色彩だけ見るとほぼミサゴに見える)、多様なハチクマの色彩にはこのようなものが存在するようである。
この写真は代表的写真として他の記事でも使われていることがあるので目にされた方もあるだろう [Birder 24(10): p. 52 (2010) にもあった] 。
「下面は白くて首の前に褐色の斑点があるが胸で消えている」についても日本のハチクマの標本でもいわゆる喉の斑紋がほとんどなくて斑点のみに見える個体もある。特に若鳥ではあまり目立たない。
YIO-08841 (山階鳥類研究所標本データベース) のような標本もあって、ミサゴの斑紋と似ている点は特に問題ないように思える。なおこの標本のラベルは5月4日に山梨県で採集されたオス若鳥となっており、現代の知見からはオス若鳥がそのような時期に来ているのか不思議である。
オスかどうかはわからないが嘴の基部の色は若鳥で良さそうなので採集日が違っているのかも知れない。
シンガポールの個体だが Oriental Honey-buzzard (Kok Hui Tan 2023) も下面はミサゴと同じような模様になっている。
大胆に書いてみると、
ハチクマ Pernis cristatus (Vieillot, 1816) Crested Honey Buzzard
これがハチクマの正しい学名かも? 英語ともよく対応する (これら及び以下の文献を引用して使ってしまえばよいとも思えるが...。ミサゴの亜種の初記載として採用されているので、ハチクマでは初記載とならない理由はないように見える)。
参考までに BirdForum でリンク切れになっている Liste des types d’oiseaux
des collections du Museum national d’Histoire naturelle de Paris. 8 : Rapaces diurnes (Accipitrides), premiere partie (Voison and Voison 2001)。
このリストに Falco ptilorhyncus Temminck, 1821 と
Buteo cristatus Bonaterre & Vieillot, 1823
の両者の記載がある。実はどちらも同じ標本で Leschenault (#オオメダイチドリ参照) によるものでジャワ島。
Bonaterre & Vieillot (1823) は Buse Bondree huppee de Java としており、
Voison and Voison (2001) によれば
Cuvier の言うところの Pernis cristatus
Les Grandes-Indes (この "大インド" も #サシバのようにインドネシアのことだろう) としているがこの引用は正しくなく、Cuvier の初版 (1817) には出てこない。
第2版 (1829) に出てくるので、Bonaterre & Vieillot (1823) を見て Cuvier
が名前を付けたのだろう、cristatus の命名権は
Cuvier (1817) でなく Bonaterre & Vieillot (1823) にあるとしている。
Voison and Voison (2001) は Vieillot (1816) に気づいていなくて誤読している可能性がある。ただし Pernis cristatus, Cuvier の学名は広く使われたので注意を促す意図もあるかも知れない。
Buteo cristatus の名前は Vieillot (1816) ですでに用いているので周知のこととして Bonaterre & Vieillot (1823) では Cuvier (1816) に合わせて属名 Pernis を用いた Cuvier 流に示した場合の学名をかっこつきで用いたということだろう (Cuvier 1816 にある図版がこの種類と示している)
[なお一般的には Pernis Cuvier, 1816 が記載年になっている。複数の巻からなる本で Pernis は 1816 年。本の出版年は 1817 年となっているので Voison and Voison (2001) は 1817 年と記している模様]。
1816 年の本では学名の後に自身を命名者として入れているが、1823 年の記載では学名の後に名前を入れていないので、この文献で命名権を主張しているわけでないことがわかる。
Cuvier の記述では 1816 年の段階ですでにヨーロッパハチクマに加えて La Bondree huppee de Java (ジャワ島の冠のあるハチクマ) の項目があるが学名は未記載。
これは Leschenault が報告したもので全身が茶色だがヨーロッパハチクマ同様頭は白っぽい。尾は黒いなどとある。こちらはタイプ標本の記述と一致する。
この問題を多少検討したと思われる文献があり、Dickinson et al. (2022)
Temminck's new bird names introduced in the early parts of the Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux in 1820-22
Buteo cristatus by Vieillot (1823) よりも Falco ptilorhynchus Temminck, 1821 を受け取った記録が1週間以上早いので Temminck の名前が優先されるとある。この2文献だけを比較する場合は同じ標本を用いた記載なので時間差だけの問題なのだろう。
脚注に Sharpe (1874) が Baza lophotes 現在の学名で Aviceda lophotes クロカッコウハヤブサ のシノニムとみなした記載がある (もちろんまったく違う種類だった)。
Sharpe は「1816 年の名前は Baza subcristata 現在の学名で Aviceda subcristata カンムリカッコウハヤブサ のことでは。ただし確認できなかった」との Strickland の見解を紹介しているが、Sharpe もおそらく詳しくは調べていない模様で、
クロカッコウハヤブサと間違えるぐらいなので Sharpe (1874) の記述の信頼性も怪しいかも (オーストラリアと解釈された場所の記載につられてしまったのかも。ただしそれぞれの種を取り上げた色調の特徴は理解できる。"オーストラリア" だけで考えると該当種がないので「確認できなかった」となったのだろう)。
さらに [カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] で紹介のように、カンムリカッコウハヤブサの種小名があまり素直でない。別に cristata / cristatus と付く種があり、別物であってより小さいために subcristata と付けたとすれば解釈しやすい。
Falco ptilorhynchus Temminck, 1821 = Buteo cristatus Bonaterre & Vieillot, 1823 のタイプ標本は暗色型なので、
Vieillot の 1816 年 Buteo cristatus の表記は別の個体を指していると思われる。Leschenault が 1807 年に採集したものが 1821, 1823 年文献記載のタイプ標本になったことは確実であるが、他にも別の標本なり何かを得ていた可能性がある。
Bonaterre & Vieillot (1823) が色調の異なるものを指して違いにあまり言及なく同じフランス名と学名で記述しているのも不思議なところである。
目先の羽毛や長い冠羽など他にも十分特徴があるので色調のことは重視しなかったのかも知れないが、Vieillot はあるいはしっかりした標本が得られたので 1823 年に別のものを指して (他者も同じ標本を使って別に記述したことを知らず) 自分が先に用いていた学名で記述したのだろうか。
ヨーロッパハチクマの記述との構成関係も 1816 年の本と同じ配置なので 1816 年と同じものを意図しているように見える。
1816 年に記録した Nouvelle-Hollande も 1823 年の記載では de Java とあるようにおそらく具体的には ジャワ島 (など) を指しているのだろう。参考までに#ハシブトガラスの macrorhynchos も記載は "Nova Hollandia, Nova Guinea et in insulis Sumatra et Java" でジャワ島が基産地になっている。
かつてはハチクマはオーストラリアで記録のない種類とされていたことは上記の Dickinson et al. (2022) の判断根拠にもなっていると思われるが、近年は定常的に記録されるようになってきている。19 世紀後半から 20 世紀の狩猟圧や環境破壊の影響の少なかった 1816 年ごろにはジャワ島に限らずオーストラリアも訪れていた可能性もあるかも知れないと思えてきた。
参考までに Temminck (1824) がハチクマにヨーロッパとジャワ島で2種あるとしている部分 参考。新世界のハイガシラトビ Leptodon cayanensis Grey-headed Kite を記述している部分。
タカ好きの方はこのあたりの図版を見てゆくだけでも何の鳥か考えるだけできっと面白い。Temminck and Schlegel が "Fauna Japonica" を記述するはるか前から世界の鳥に (標本のみとはいえ) 親しんで分類を考察していたことがわかる。Temminck and Schlegel が何を知っていて何を考えたのかは "Fauna Japonica" をいきなり参照するとわからない部分があると思われる。
Hartert (1910-1922) p. 1183 では面白いことにロシアの個体は大きい (!) (Menzbir のデータ) とコメントされていた。
この時代にはすでに亜種 orientalis は記載されていて Seebohm の日本の個体は小さいとしていた。当時熱帯の種類を指して Pernis cristatus (Vieillot, 1823) 3月または Pernis ptilorhyncus (Temminck, 1823) 7月の名称が使われてきたが、Pernis elliotti Jerdon, 1839 を採用していた。
orientalis がシベリアから渡ってきたものではないかとの議論をしている。一方で Pernis cristatus (Vieillot) のもう一つを別扱いにしてスンダ列島、フィリピン特にミンダナオ、パラワン島などの種類としている ("冠のある" の語義は現代の留鳥個体の特徴とあまり合わない)。Pernis tweeddalii との関係はどうなっているのかなど疑問点が残っていた。これらの亜種の名称については別項目参照。
1816 年の個体との関係はまだ気づかれていなかったように見える。
[ヨーロッパハチクマとの関係・亜種]
しかしその後、比較的最近までヨーロッパハチクマ (Pernis apivorus) の亜種と考えられていた。(apivorus apis ハチ -vorus 食べる < voro, vorare。Linnaeus が整理して付けた学名だがこれは少し不適切だった。英名の由来の部分参照。またこれ以前に Linnaeus はオオタカと混同していた: #オオタカ備考)。
日本の鳥を記述した Temminck and Schlegel (1844) も実は日本のハチクマを取り上げていた。
参考。Pallas はシベリアにも生息するとしており、日本からの2羽のメス成鳥は色彩や計測値などでヨーロッパハチクマと区別できない (ちょっと信じがたいが) のでヨーロッパのものと同一種と考えたとのこと。ヨーロッパ、エジプト、アラビアからシベリア全域、日本、ギニアに広域分布する種と捉えていた。
"冠のあるハチクマ" は Temminck and Schlegel (1844) 以前にすでに知られていたはずなので Pallas が同じだと考えた先入観のなせる技だったのかも。しかし ptilorhynchus の名称は Temminck (1821) が付けたものだった。自身が名付けたこの種類と同じとは考えなかったのだろうか。
Temminck and Schlegel は (ヨーロッパ)ハチクマのことをあまり知らなかったのだろう。また英語圏の情報 (インドや "New Holland = オーストラリアなど) で記述されていた "冠のあるハチクマ" の情報があまり入っていなかったのかも知れない。
書物や比較的最近の論文でもハチクマを指してこちらの学名 Pernis apivorus が使われていることがあるので注意。
ヨーロッパハチクマと同種とされていた時代には日本の種類には ptilorhynchus は亜種名としても現れることはなかったはずで、海外図鑑などからいきなり Pernis orientalis が使われたことがあったことも納得できる。
ヨーロッパハチクマと同種と考えられていたため、図版の特徴 (特に飛翔図) もヨーロッパハチクマと混同されているものもある。図鑑などで一般に使われている翼開長の 121-135 cm (出典: 榎本『野鳥便覧』: 日本野鳥の会大阪支部の資料) もヨーロッパハチクマの値に近い。
数字の上ではハチクマの方がノスリより翼開長が小さく実際と合わない問題は叶内 (2001) Birder 15(9): p. 90 でも指摘されていた。
飛翔図については「野鳥識別ハンドブック」(高野伸二 日本野鳥の会 1980) を念頭に置いている。この書籍をもとにした後続の "A Field Guide to the Birds of Japan" (WBSJ 1982) (「フィールドガイド日本の野鳥」1982 に先行して刊行された英文図鑑) では若干改善されていて、ヨーロッパハチクマの carpal patch が削除されているが、全体的なパターンはヨーロッパハチクマのまま。
飛翔図は海外図鑑をかなり参考にして描かれたものと思われる。とまっている図では当時は雌雄差や齢差が明らかにされていなかった。ヨーロッパハチクマ成鳥にはない暗色虹彩の図も描かれている。オス成鳥の尾羽模様となっていないため幼鳥を示しているようにも見えるが、顔の色彩はオス成鳥の特徴も混じっているように見える。海外図鑑との相違を気にされつつも判断できなかったのであろう。
オス成鳥の尾羽模様で黄色の虹彩が描かれた当時の学習用鳥類図鑑よりは改善されていた。
[ハチクマの性と年齢の識別] の項目にあるように、日本で初めて公表された確かな野外識別方法は ハチクマの雌雄と幼鳥の識別 (川田隆)「野鳥」1988年10月号 だった。
現代的な測定値はオス 1266-1434 mm (平均 1358, n=45), メス 1310-1506 mm (平均 1406, n=32) 全長はオス 520-630 mm (平均 573, n=46), メス 551-645 mm (平均 598, n=32) [出典: 久野 (2006) Birder 20(10): 20-27] で、タカの渡りの解説などでは注意が必要。
ちなみに Brazil (2009) "Birds of East Asia" では 128-155 cm, 全長 54-65 cmとしている。全長 68 cmの測定値もあり、大きさを識別要素とする場合は注意が必要。
ロシアの図鑑では Ryabitsev (2014) のように翼開長 150-170 cm としているものもあって、これは別の意味で誤った記載が引き継がれているのかも知れないが、同図鑑ではトビが 160-180 cm、ミサゴが 145-170 cm となっており測り方が違うのかも知れない。しかしヨーロッパノスリは 100-130 cm、ソウゲンワシ 175-260 cm となっていて、さすがに何かおかしいところもあると気づかれそうなものだが?
6亜種がある (IOC)。orientalis 以外は長距離の渡りをしないと言われている。
ハチクマの中で長距離の渡りをする (日本に来る) 亜種 orientalis を別種扱い (Pernis orientalis) にしている図鑑 [例えば Brazil (2009) "Birds of East Asia"] もあり、この学名が使われた日本語記事もある。
Swann (1920) がこの種学名を用いたとのこと (次の Kuroda, 1925)。
日本の亜種は大陸とは別に亜種 japonicus Kuroda, 1925 動物学雑誌 37 (440): 221-226 とされたこともある。中国のものより少し小さく、喉に "w" 模様があるとの記載。
この論文では雌雄を判定していて雌雄の大きさの違いへの言及はある。尾はほぼ必ず3本の黒帯があるが帯がなくて不規則な模様のものもあるとのこと。
大陸のものは大陸を渡り、日本のものは大陸に渡らず南下して越冬すると想定されていたため亜種が違うと考えられたのかも知れない。
この亜種名はかなり長く使われていたようで、山階鳥類研究所標本データベースの先述の標本ラベルにも出て来る。1980 年代少なくとも最初のころはまだ使われていたようだ。
現在は亜種 orientalis Taczanowski, 1891 のシノニムとして扱われている。
亜種分類にかかわる参考情報: Vaurie and Amadon (1962) Notes on the Honey Buzzards of Eastern Asia
この中で長距離の渡りをする (日本に来る) 亜種 orientalis の尾の模様で性と年齢の識別の図が示されていた。
この文献では Stresemann (1940) によれば亜種 ptilorhyncus は "原始的" で成鳥と若鳥にあまり差がないと述べ orientalis, ruficollis は成鳥と若鳥が大きく異なり、尾のパターンで区別できることが示されていた。
Vaurie and Amadon (1962) は Kuroda, 1925 記述の2亜種 (japonicus と neglectus) は通常認められていないことが述べられ、計測値からも亜種とは認められないとのこと。Austin and Kuroda (1953) 中に Austin は japonicus を亜種とみなす意義が認められないと書かれていた。
Stresemann も japonicus を亜種と認めず、Checklist of birds of the world (1931) の原稿ですでにシノニムとしていた。
Stresemann (1940) はジャワ島で多数採集された翼の短い個体を orientalis が越冬したものとみなしていたが、Vaurie and Amadon (1962) はこれは ruficollis と区別できず、インドからのものではないかも知れないものの ruficollis の越冬個体ではないかと考えていた。
Vaurie and Amadon (1962) は 冠羽の長い torquatus は中間型がなく別種に値する可能性があり、その場合は亜種 ptilorhyncus、記載以降新しい情報のない philippensis, palawanensis も一緒に含まれる可能性を述べている。
これらの亜種と ruficollis とは明瞭に区別できるとしている。
台湾では一部留鳥となっているが、これも亜種 orientalis と考えられている。
亜種 orientalis を別種とする考えは、Gamauf and Haring (2004)
Molecular phylogeny and biogeography of Honey-buzzards (genera Pernis and Henicopernis)
の分子遺伝学研究では支持されていない (もっとも使用された塩基配列が短く、将来の研究で改訂されるかもしれない。ハチクマの中に隠蔽種がある可能性を考えている人は結構ある。亜種区別も標本ラベルをもとにしていると思われるのでまだ検討の余地があるように感じる)。
別種とする考えに従って英語表記で亜種 orientalis を Oriental Honey-buzzard (Northern)、渡りをしない東南アジアの複数の亜種を Oriental Honey-buzzard (Indomalayan) と区別されている場合があり eBird、海外図鑑などを利用する場合は注意が必要 (将来別種とされた場合を見越し、分割の手間を省くためにデータベースなどではこのように分けてあるのだろう)。orientalis はハチクマの中でも最大亜種の一つ。
英名で Oriental Honey Buzzard (よく OHB と略される) の名称は非常によく使われるが、IOC 名が現在 Crested Honey Buzzard としているのはこのような分類上の混乱を防ぐためと思われる。ただしハチクマの亜種には冠羽を持たないものもあり、この英名にも一長一短がある。
Crested Honey Buzzard に相当する表現はすでに用いられていたもので、IOC などが最近の分類を受けて考案した名前ということではない。
Oriental Honey Buzzard - BirdForum Opus によれば、Eaton et al. (2021) Birds of the Indonesian Archipelago (Greater Sundas and Wallacea), Second Edition では P. orientalis を別種とし、狭義 Oriental Honeybuzzard の名称を用いているとのこと。
Gamauf and Haring (2004) の後の出版物なので、あるいは他に遺伝情報が得られているのだろうかと調べてみた。
GenBank には Yamamoto et al. (2020) (山階鳥類研究所) Pernis ptilorhynchus orientalis HN0387 mitochondrial DNA, complete genome
にミトコンドリアゲノムの解読結果が出ている。Journal of the Yamashina Institute for Ornithology に Mitochondrial Genome Project on Endangered Birds in Japan の一連のシリーズ論文があり、Yamamoto et al. (2023) Complete Mitochondrial Genomes of Endangered Japanese Birds
に報告されている模様であるが、他の亜種は Gamauf and Haring (2004) 以降のデータがないので、少なくとも公開データの範囲では Eaton et al. (2021) は新しい遺伝情報に基づくものではないように見える。
P. p. palawanensis, P. p. torquatus, P. p. ptilorhynchus
の3亜種を Sunda Honey Buzzard とする呼び方もある (上記 BirdForum Opus 参照。eBird もこのカテゴリーを設けている)。
さて、[ハチクマの学名は正しくないかも?] の話題を思い出してみると、P. p. ptilorhynchus がジャワ島の亜種とされるのは、Temminck (1821) [もしくは Vieillot (1816)?] が基産地ジャワ島で記載したためであるが、これはおそらく Leschenault がそこで採集したからに過ぎない。
ジャワ島の固有亜種かどうかは多分あまり調べられていなくて、ジャワ島の留鳥を P. p. ptilorhynchus と記録しているように見える。
他の亜種では、現在の理解ではインドやスリランカからマレー半島以外の東南アジア大陸部の亜種として P. p. ruficollis Lesson, 1830 (フランス名 "首の赤いハチクマ" インドのハチクマの種として記載) は亜種として認められ、
同じ文献にある P. albigularis Lesson, 1830 (フランス名 "喉の白いハチクマ" に相当) は P. p. ruficollis の一つの変種として亜種とは認められなかった。
P. p. torquatus Lesson, 1830 も同じ文献でフランス名 "首の黒いハチクマ" (torquatus 首飾りのある、首輪のある)、こちらも種として記載され後に亜種となった。
つまり Lesson (1830) は主に首や喉の色に着目して3種を記載し、そのうち2つが現在亜種として認められていることになる。この文献では Temminck の記載したハチクマ (別種と認識している) はジャワ島とスマトラにいるとある。多彩なハチクマの色彩を考えると生態的情報がなければ何種に分けても不思議でない。
これらの種 (後に亜種) はジャワ島とスマトラでの発見以来初の記述なので、当然のことながら我々が普通に見る渡りのハチクマのことは知らずに記載したものだろう。つまり "首の赤い" というのは Lesson から見て3種に分けた場合の着眼点、およびジャワ島とスマトラの種との違いを表すものであって、後に名前の付けられた日本のハチクマと比べて特に首の赤さが目立つわけではない。
ruficollis, torquatus は他種の種小名などにもよく出てくるので命名者にとっては使いやすい呼び方なのかも知れない。前者はおそらく褐色の意味で使っているのだろう。
有効な学名が付けられた後は変えられないため後の亜種の色調と整合性が悪くなることもある。Lesson も極東のハチクマを見て比べていればこのような種名を与えなかったかも知れない。
時期的にはこの間に Pernis celebensis Wallace, 1868 が記載されているが現在は別種となっているため後述する。ジャワ島とスマトラの近く (セレベス島) にもう1種違うハチクマがいると考えたもの。
後述のように見かけの違いは共存する他の猛禽類 (主にクマタカ類) との種間関係の結果生まれた "擬態" の産物の可能性もある。島しょ部でクマタカ類が多数の種に種分化しているが、それぞれに対応する別の容貌のハチクマがいてもおかしくない。日本のクマタカは冠羽がそれほど発達していないのでハチクマもそれ相応になっている? そのため一見容貌が違っていても別の種や亜種に値するかは必ずしも自明でない。
個体群の間の交流がどの程度あって、種分化がどこまで進んでいるか次第であろうが、当時はまだそこまでは認識されておらず見かけが異なるものは別個に記述されていた。
この解釈に従えばジャワ島ではジャワクマタカ Nisaetus bartelsi Javan Hawk Eagle が固有種となっていて、若鳥の見かけは褐色味が強く Leschenault が採集して亜種 P. p. ptilorhynchus のタイプ標本となった個体と似ていると言えば似ている。成鳥の体下面の模様はそれほど似ていない。
後に示すようにジャワ島の繁殖期に容貌の異なるハチクマも撮影されているので、亜種 P. p. ptilorhynchus に淡色型もあるのか、あるいは概念的に別亜種なのかよくわからない。
カオグロクマタカ (ブリスクマタカ) Nisaetus alboniger Blyth's Hawk-Eagle) はマレー半島、スマトラ島、ボルネオ島に生息するがハチクマの P. p. torquatus は似ている。
これらと同所的にカワリクマタカ Nisaetus cirrhatus Crested Hawk-Eagle/Changeable Hawk-Eagle も生息するがハチクマとはそれほど似ていない印象を受ける。
セレベス島のハチクマは遺伝的にも種相当異なっていて後に別種となった。対応するクマタカはセレベスクマタカ Nisaetus lanceolatus Sulawesi Hawk-Eagle/Celebes Hawk-Eagle。これらは両種の (とまっている) 写真を見るとどこが違うのかと思えるほど似ているものがある。セレベスクマタカの若鳥は白っぽいがこれはまたヨコジマハチクマの淡色型によく似ている。
セレベスクマタカがジャワクマタカなどとかなり異なるため、ヨコジマハチクマは他のハチクマと容貌も異なる形に進化して種レベルで分化したのかも知れない。
「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) p. 107 にもこの擬態が取り上げられていて当時はカワリクマタカとカワリハチクマの名前になっていた。
黒田氏による記述であろうが明らかに小学生でも読めることを意識した学習図鑑としては驚くべき知見が取り上げられていたことになる
[この図鑑の改訂版 (もちろん出版よりずっと後) を見て育った世代だが、このことはまったく覚えておらず後の鳥への興味に直結したわけではない (笑)。今になって見てみると非常に意欲的な内容である。
同社の刊行物リストにもう少し高度と思われる学習科学図鑑シリーズも載っていて全12巻。鳥に特化したものはない。その1つに "エネルギーと原子力" (1967) という巻があって当時の原子力推進の情勢も想像できる。当時は科学に関心のある子供には原子力は必須事項でさえあった]。
Amadon (1961) Relationships of the Falconiform Genus Harpagus
に記述があり、Meyer and Wiglesworth (1898)
The birds of Celebes and the neighbouring islands は両種ともまれなので擬態と考えにくいと考えていたとある。擬態あるいは祖先形質にかかわる主要な論点はこの時点でほとんど提示されていた模様。
どちらがどちらに似せているか、共通の祖先形質から収斂進化かなどすでに 1898 年の段階で双方議論されている [#アホウドリの備考 [海鳥の翼の上面はなぜ黒い] 参照。Poulton (1890) "The Colours of Animals" や Thayer (1896) "The Law Which Underlies Protective Coloration" が出たばかりで当時も擬態はホットなテーマだった]。
ハチクマ類でも強いタカに擬態してもカラスのモビングを受ける。獲物の方からは模様よりも動きを見ている。そもそも模様が見えるぐらい近くに来る前に逃げるなど。
ハバシトビがモモアカハイタカに系統的に近いか議論している部分で使われているもので、Amadon は巣のハバシトビが卵を捕食するオオハシに驚いて逃げることを記しており、強いタカへの擬態の役割を果たしていないようだが系統が近いのではなく擬態だろうとしているもの。こういう文献が容易に読める今の時点こそ振り返るとよいかも知れない。黒田氏はどの文献を参照されたのだろうか。
さらに少し考えると、成鳥・若鳥がそれぞれ擬態する必要はないような気もしてくる。より強いタカに擬態して攻撃を避けるならば若鳥の段階でセレベスクマタカの成鳥に擬態すればよいのではないか? わざわざより弱いだろう若鳥に擬態する必要があるのだろうか。
若鳥があまりに成鳥に似ていると同種内で攻撃される可能性があるため? それならば成鳥と違う特徴があればよいだけだろうが、違う種類なのに若鳥同士がなぜこれほど似せているのか? セレベスクマタカの成鳥が若鳥をあまり攻撃しないだろうからそれに便乗している可能性は考えられるかも。セレベスクマタカにとっても同種若鳥のように見えている? 本当だろうか?
しかしセレベスクマタカの若鳥の方がより無害な (?) ヨコジマハチクマの若鳥に似せている可能性はあるかも知れない。この場合だと aggressive mimicry の方になるのだろう。
クマタカ類の方がおそらく親元を離れるのに時間がかかるなど生育が遅い (これは日本のクマタカとハチクマからの類推だが留鳥種のハチクマ、熱帯のクマタカ類ではどうなっているだろうか)、すなわちハンターとして未熟なまま長期間過ごすこともハチクマ類の若鳥に似せる由来になり得るかも知れない。
もしこの解釈が成り立つならば、普通に言われるようなハチクマがクマタカに擬態と逆の可能性もあることになる。若鳥はあるいはそうかも知れない。日本のクマタカの若鳥はハチクマ淡色型に似ているといえば似ているようにも見える。日本ではハチクマ若鳥は長期間滞在しないが類似性を検討してみる価値もありそうな気がする。
別に紹介する ISDM 仮説では (主要な食物は違うが) この組み合わせは含まれている。
Tweeddale morph? Origins of the name for a uniquely plumaged Oriental Honey Buzzard (Pernis ptilorhyncus)
によれば、スマトラ南東部で Arthur Hay が非常に変わったハチクマを採集したがハチクマの個体変異が大きいので別種とはせず Pernis ptilorhyncus の学名で 1877年に標本を残したとのこと。
しかし他に似た標本が2体得られ、別種として Pernis tweeddalii Hume, 1880 として 9th Marquis of Tweeddale の名前でも知られる Arthur Hay にちなんで記載された。Note on a Malayan species of Pernis distict from P. ptilorhyncus "Malayan Honey Buzzard"。
今はこの学名は残っていないが亜種 torquatus の morph の名称 (tweeddale morph) として使われている。"tweeddale" はよく出てくるのだが英語の辞書を引いても意味はわからない。固有名詞だった。
1880 年のこの文献にはすでに Pernis celebensis Wallace, 1868 との比較が出てくる。
この辺の歴史を追っておかないと現在の名称や分類がなぜそうなっているのか理解しにくいところ。
この文献には Pernis brachypterus (翼の短い) Blyth の名前も出てきてこれは単にハチクマの若いオスではないかとしている。
現在使われる亜種でその次に記載されたものは
P. p. orientalis Taczanowski, 1891 でシベリア東部での記載になっている。オスの計測値が出ているが確かに日本で言われる数字よりも大きく見える。
(この間に前述の japonicus Kuroda, 1925 が入る)。
P. p. philippensis Mayr, 1939 と
P. p. palawanensis Stresemann, 1940 がその後新たに記載されたがこれらの原資料は現状オンラインでは見られないようで歴史を遡った分析はできていない (原記載をもとにしていると思われる図鑑の記述については後述)。
Pernis celebensis Wallace, 1868 が別途 Pernis cristatus の変種 (var.) として提唱され、Schlegel がすでに記述したが学名を付けなかったため命名したとある。
現在はヨコジマハチクマ (セレベス島)、さらに近年ヨコジマハチクマからフィリピンハチクマ Pernis steerei (パラワン島を除く。後述のようにハチクマのフィリピンの亜種と非常に紛らわしいので注意を要する) が分離されたものに対応する別種となっている。これに対応するのはフィリピンクマタカ Nisaetus philippensis Philippine Hawk-Eagle で、フィリピンクマタカの若鳥に確かに似ている。
Sulawesi Honeybuzzard (Mike Nelson - Birdtour ASIA) 参考映像。尾を横に振るのはハチクマもよく行うが多分機嫌がよい状態。
On the Birds of the Philippine Islands―Part IX. * The Islands of Samar and Leite
でフィリピンのサマール、レイテ島で採集された鳥が Pernis tweeddalii (現在の P. p. torquatus の tweeddale morph) に似ているとの記載がある。
冠羽が長いとあり、フィリピンハチクマ (ハチクマのフィリピンの亜種ではない) と思われるが、当時はマレー半島の種類に似たものがフィリピンにもいるとの報告になった模様である。
腹部模様などの記述は例えば現代の写真 Philippine Honey-buzzard と合っているように見える。ネットで見るフィリピンハチクマは淡色のものが多いが、このような暗色のものもある模様である。
Philippine Honey-buzzard で長い冠羽が見られる。
Philippine Honey-buzzard は暗色と淡色の飛翔。
この文献でもハチクマの学名をめぐる混乱が見られ、フィリピンのものをインドで呼ばれているように Pernis ptilorhynchus と呼んでよいのか Pernis cristatus なのかよくわからないとある。
Oriental Honey-buzzard はジャワ島の繁殖期の写真で P. p. ptilorhynchus のタイプ標本の記載に似ていてそれらしく見える。
スマトラ島の繁殖期の写真は Oriental Honey-buzzard があってオスの目が暗色の点は上記ジャワ島の個体と異なる。別亜種でよいのだろうか。
同じくスマトラ島の繁殖期の写真があって Oriental Honey-buzzard (Sunda) こちらはオスの目が黄色い。
コメントには亜種 torquatus とあるが、基亜種 ptilorhynchus と書かれているジャワ島の 写真
(Crested Honey-buzzard (Pernis ptilorhyncus) ssp ptilorhyncus. In flight from below / Garut - West Java / Sungsang Toto Suprapto) とよく似ている。この写真のリンクは The honey-buzzard から。ジャワ島の情報がまとめられていて同亜種とされる他の写真、他の亜種の写真もある。
Sikepmadu Asia のインドネシアの猛禽のサイトで P. p. orientalis とある2番めの写真は日本で見かける orientalis とは異なって見える。
ざっと見ただけだがインドネシアの亜種は記述されている分布通りにはきれいに分かれていない感じがする。
HBW (書籍版) でも図版があるが、基亜種 ptilorhynchus は見事に記載の通りの色彩 (暗色型) で描いてあって、実物を見て描いたのかタイプ標本から想像したのかはわからないが限られた情報からよくここまで描けるものと感心する。
これら図版や亜種記述を見て識別すれば我々のハチクマの暗色型は亜種 ptilorhynchus に一番似ているなどと判断されそうにすら思える。
インドなどの亜種 ruficollis は日本の亜種と比較的似て見える。2024年2月、交尾中のインドの画像 があり、少なくともこのつがいは現在外見上で判定すればあるいは日本の亜種と同一とされるかも知れない。
インドは実は2亜種生息しているのかも知れない。
マレー半島の留鳥亜種の torquatus の tweeddale morph と呼ばれるものは冠羽も長く日本の亜種と印象が相当異なる。
成鳥オスの虹彩が暗色かどうかは亜種あるいは地域によって異なるが基本形は黄色の虹彩で、一部のグループのみ成鳥オスの虹彩が暗色になったらしい。久野 (2006) Birder 20(10): 37 には熱帯亜種は黄色とあるが現在の知見では必ずしも正しくない。インドには繁殖個体でオスの虹彩が暗色のものと少し明るい色のものの両者が存在する。
インドのハチクマのオスのクローズアップ映像: Oriental Honey Buzzard male in closeup, in forest of central India, June, 2024 (Sanjay Nafdey on Behavior of Birds & Animals 2024)。
日本のものとどの程度似て見えるだろうか。おそらく暑い中で舌をあえぎに使っているのが記録されている。
久野 (2009) Birder 23(11): 48-53 に「マレーシアでハチクマの渡りウォッチング」の記事があり、2009.3.2-16 の春の渡り。p. 50 に留鳥ハチクマとされる個体の写真がある。足が巨大で全体に小ぶりで頭が大きめとある。熱帯で見るハチクマは痩せているとの記述がある。
そう思って熱帯の留鳥ハチクマと考えられる写真を見ると足が多少目立つものがある Oriental Honey-buzzard (Ramesh Shenai 2024.7.18 インド)。
Oriental Honey-buzzard (Wilbur Goh 2024.6.10 マレーシア) は足は特に大きくない (亜種は? 何かを運んでいるので繁殖個体だろう。日本のハチクマと比べると尾はオス成鳥タイプ、虹彩は黄色、全体的には暗色型と言ってよさそう)。
Oriental Honey-buzzard (Lim Ying Hien 2023.11.23 マレーシア) はもう少し白っぽい個体で尾のパターンはオス成鳥タイプ。翼が短めでいかにも留鳥らしく見えるが足は特に大きくなさそう。
マレーシアの子育て映像にもあるように繁殖時期の食物事情が悪いわけではなく、春の渡り時期には食物が少ないのかも。
形態の違いも含めて引き続き要調査。海外のハチクマの写真を見るのは面白いのでおすすめしておく。
インドで撮影された大変淡色の個体: Oriental Honey-buzzard (Ramachandran 2024.9.14)。
亜種との関連でここに紹介しておくが、ハチクマはインドの Nagpur 市の鳥となっている。
Bird of Nagpur
どのように決まったのかはわからないがなかなか渋いところに目をつけたもの。
しかし都市化で林が減って近年は珍しくなって保護すべきとの報告も: Shukla et al. (2024) Chapter 17 - Shrinking urban green spaces, increasing vulnerability: solving the conundrum of the demand-supply gap in an urbanizing city。
[擬態と種・亜種の関係]
ハチクマがクマタカに似ているのは偶然ではなく、強いタカに擬態 (mimicry) することで他種からの攻撃を防いでいるとの考え方がある。
van Balen et al. (1999) は擬態相手として想定される種類をリストしている (
Juvenile plumage of Javan Crested Honey Buzzard, with comments on mimicry in south-eastern Asian Pernis and Spizaetus species)。
これによれば次の組み合わせが出ている(以下 P. p. は Pernis ptilorhynchusの略):
・P. p. orientalis (日本にも来る亜種) とクマタカの亜種 Nisaetus nipalensis orientalis
・P. p. ptilorhynchus (ジャワ島の留鳥亜種とされる) とジャワクマタカ Nisaetus bartelsi
・P. p. torquatus (マレー半島の留鳥亜種。スマトラ島、ボルネオ島も同亜種とされる) とカオグロクマタカ Nisaetus alboniger
・Pernis steerei (フィリピン留鳥の種フィリピンハチクマ) とフィリピンクマタカ Nisaetus philippensis
・Pernis celebensis (スラウェシ島留鳥の種ヨコジマハチクマ) とセレベスクマタカ Nisaetus lanceolatus。
・これらとは別にカワリクマタカ Nisaetus cirrhatus (及び Nisaetus limnaeetus も独立種とされることがある) も高地を除くインド亜大陸に広く分布しており、ハチクマの若鳥の模様に似ていると言われる。
これらについては [ヨーロッパハチクマとの関係・亜種] でも少し述べた。ただし前述のようにハチクマの亜種分布は図鑑の記載通りなのか、ジャワ島の留鳥亜種はタイプ標本で記載されたものと同じタイプのものだけなのかなどはっきりしない点も多い。種レベルで異なり分布もよく把握されているヨコジマハチクマ、フィリピンハチクマは対応が比較的はっきりしているように思える。
P. p. torquatus はボルネオ島にも分布するとされるが記録も少ない (どこでも他種の誤認らしい画像もしばしばあるので注意)。
Oriental Honey-buzzard ssp torquatus tweeddale morph 2, Borneo は間違いなさそうである。
スマトラ島は torquatus とされるがこちらも画像は少なく類似性もあまりよくわからない。
繁殖期の画像は少なく、渡り個体の越冬時期は orientalis がむしろ多く記録されているように見える。
島に固有のクマタカ類には似ているが成鳥がカワリクマタカとそれほど似ていないのも不思議に思える。
インド亜大陸のハチクマは擬態を行うならば対象種はカワリクマタカになるだろうが、ハチクマ若鳥の淡色型以外はそれほど対応していないように見える。
インドネシアやフィリピンハチクマでは非常に対応がよいがこれは何か意味があるのだろうか。一般的にはハチクマがクマタカに擬態しているとされるが、クマタカ側にもお互いに似ているメリットはないのだろうか。
獲物がクマタカを無害な (?) ハチクマと誤認することで捕食効率を高める? (本当ならば aggressive mimicry の一種と呼べそうだがどちらも怖い鳥に見えそうであまりありそうにない?)。これは後に ISDM 仮説で紹介する Prum (2014) の冒頭で紹介されている古い解釈の一つに相当する。
あるいは同じ森林性環境で収斂進化の可能性はないのだろうか
[後に紹介の Jonsson et al. (2016) によれば (この例ではないが) Stresemann (1914) は擬態のアイデアをそんなものは収斂進化 (Resultat unabhaengiger Convergenz der Entwicklungsrichtungen 直訳で "進化による独自の収斂の結果") だと批判していたという]。
クマタカ類がなぜあのような容貌になっているか、現在の Aquila 属の一部がクマタカ類に似て理由など、まだわからない点がありそうに思える。
タカ類にとって出しやすい模様の可能性もあるかも知れない。
後述の ISDM 仮説がハチクマ類とクマタカ類の関係にもし当てはまるのであれば、クマタカ類の方は擬態から逃れる方向に進化し、ハチクマ類は似せる方向に進化した可能性が考えられる。この場合ハチクマ類による擬態がクマタカ類の種分化を促した可能性すらあるかも知れない。
一方模倣される側にも利益があるならば、ISDM 仮説とは逆に両者はより似る方向に進化することも考えられる。
後で気づいたのだが、日本のクマタカは大きいが東南アジア島しょ部のクマタカ類はそれほど大きな鳥ではなかった。ハチクマ類とそれほど違いがなく状況によっては逆転している。
ウォーレスクマタカ Nisaetus nanus は全長 46-49 cm、ハチクマ亜種の torquatus ( [マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] で映像紹介しているもの) の分布と一致してモデルともされるカオグロクマタカ [高野 (1973) ではブリスクマタカ] Nisaetus alboniger で 50-58 cm。渡りのハチクマ亜種よりむしろ少し小さい。
ハチクマ類がクマタカ類に擬態しているとそこまで強く言えないかも知れない。
これも後で気づいたのだが、ハチクマ亜科 Perninae のカッコウハヤブサ属やハチクマ属の前の系統である北米から南米のカギハシトビ Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite、
南米のハイガシラトビ Leptodon cayanensis Grey-headed Kite は翼が実に見事なタカ斑模様となっていて、尾もまるでハチクマのオス成鳥のような太い縞がある。
同じくシロエリトビ Leptodon forbesi White-collared Kite も翼がタカ斑模様となっている。
尾のパターンがここまでハチクマに似ているとこの系統が出しやすい模様のようにも思える。
しかしハイガシラトビもハチクマ同様に色彩の多形があるとのことで、
Menq (2013) Mimicry in birds of prey
(translated) でハイガシラトビの若鳥のアカエリクマタカにそっくりな写真を見ると驚かされる。
和名にひきずられてはいけないが、これが "トビ" (?) の若鳥とは信じ難い。普通に見れば色彩の多形はほとんど別種に見えるぐらいである。擬態は若鳥で見られ (ハチクマ若鳥が攻撃的な相手に擬態していないことはこの点では異なる)、他のタカ類や霊長類による捕食を避けるためと説明している。
Lima et al. (2020) Distribution and identification of the White-collared Kite Leptodon forbesi and the juvenile plumages of the Gray-headed Kite Leptodon cayanensis
にシロエリトビ、ハイガシラトビの両種を扱った論文がある。黒色型は クロクマタカ Spizaetus tyrannus への擬態の可能性があるとのこと。ハチクマだと暗色型で済ませそうだがこちらでは対応種がいる模様。ハチクマでは対応種はないのだろうか。
カギハシトビは北米にも分布して Spizaetus 属の分布と合わない部分もあるためか擬態の話は簡単に探した範囲で見当たらない。
(島では?) 天敵はほとんどいないとある (Chondrohierax uncinatus (Hook-billed Kite), The Online Guide to the Animals of Trinidad and Tobago)。
絶滅した可能性すらあるキューバカギハシトビも同様の模様で、こちらは対応種がそもそもないのでやはり系統的に出しやすい模様なのだろう。
Prum (2014) Interspecific social dominance mimicry in birds
により大型の別の種に擬態する Interspecific social dominance mimicry (ISDM) の総論がある。タカ類では
・モモアカトビ Harpagus diodon (オウギワシ亜科 Harpiinae) がモモアカハイタカ Astur bicolor に、
・マダガスカルヘビワシ Eutriorchis astur (ハチクマ亜科 Perninae) がマダガスカルオオタカ Astur henstii に、
・セグロオオタカ Accipiter poliogaster の若鳥がアカエリクマタカ Spizaetus ornatus に、
・オナガヘビワシ Circaetus spectabilis (チュウヒワシ亜科 Circaetinae) がアフリカクマタカ Aquila africana に、
・ハイガシラトビ Leptodon cayanensis (ハチクマ亜科 Perninae) の若鳥がセグロクマタカ Spizaetus melanoleucus に。セグロクマタカは擬態する側にもリストされており、Menq (2013) の記述も用いればここは アカエリクマタカ Spizaetus ornatus Ornate Hawk-Eagle や クロクマタカ Spizaetus tyrannus の方がさらによさそう、
・カザノワシ Ictinaetus malaiensis がカワリクマタカ Nisaetus cirrhatus に、
・ウォーレスクマタカ Nisaetus nanus、チャイロカッコウハヤブサ Aviceda jerdoni、カンムリオオタカ Lophospiza trivirgatus それぞれがカオグロクマタカ Nisaetus alboniger
の組み合わせが文献から紹介されている (記述時期から分類が変わっているので学名はここで用いるタカ類の新しい分類に基づくものに揃えた)。Menq (2013) の記述や写真も参照。
それほど似ているのか、という組み合わせもないわけではないので参考までに写真を見ていただくとよいだろう。クマタカ類がクマタカ類に擬態しているとは本当か、とも思えるわけだがこの2種の分布は実際に同所的である。系統的にはウォーレスクマタカの方が古いのでカオグロクマタカが別途日本と同じ系統のクマタカグループから分布を広げ、ウォーレスクマタカは新しく来たより大型の方に合わせたのだろうか。
モモアカトビとモモアカハイタカはほぼ同じ時期 (300 万年前ぐらい)。
マダガスカルヘビワシとマダガスカルオオタカでは前者が圧倒的に古いなどになる。
マダガスカルにはもっと上位の捕食者であった絶滅種のマダガスカルカンムリクマタカ Stephanoaetus mahery が存在したので、マダガスカルヘビワシの擬態形成にはこの種の影響も考える必要がありそうに思える (#クマタカの備考参照)。
マダガスカルカンムリクマタカは色彩など不明で証拠はないが、マダガスカルオオタカもマダガスカルカンムリクマタカに擬態していた可能性もあるかも知れない。
タカ類に擬態がかなり見られるのは ISDM 仮説では食物資源に重複があって生態的な競争が大きいためだろう。Prum (2014) も小型種の方が食物を得る競争では一般的に有利としている。
この解説ではコキアシシギがオオキアシシギに擬態していることになる。この例では2種はシギ類内で系統が異なるのに見かけが非常に似ている。
タカ類に関しては歴史的には大きい方の種が小さい種を真似ることで小さい方の種が大きい方を同種と見誤らせて捕食しやすくするとの考えもあったらしい。
Prum (2014) の考えでは (必要とする資源が似ている場合) 真似られる方にも真似る方にも選択圧がかかり、前者は擬態されることによって資源などを失うことを避けるためにより見かけが異なる方向に進化し、真似る側はより似せる方向に進化する共進化が働くとのこと。
まだタカ類の関係部分しか調べてみていないが、この関係にノスリ類がまったく関わっていないのも興味深い。ノスリ類とそれ以前のグループとの間で食物などがかなり異なるので競争があまりなかったのか、もし後から来たノスリ類の方が大きくてもあまり目立つ模様のないグループなので擬態対象にされなかったのか。
ここには出てこないがサシバとオオタカの若鳥が似ているのは擬態に関係あるのだろうか。両者のサイズはあまり違わない。
しかしなぜか Prum (2014) のリストにはハチクマ類が入っていない。いくつかの理由が考えられるが Prum が単に知らなかった (他の知名度の低いタカの例をいくつも出しているので考えにくい)、ハチクマとクマタカの組み合わせは食物資源に重複があまりなくて ISDM 仮説には当てはまらないと考えた (他に ISDM 仮説に当てはまらない擬態の例示があるのでこれもやや考えにくい)、
ハチクマは亜種レベルなので扱わなかった、ハチクマとクマタカを擬態として含めると ISDM 仮説がむしろ弱くなる、などの理由があるかも知れない。Prum に聞いてみればよいのだろうが。
ハチクマの亜種 orientalis (日本にも来る亜種) とクマタカの亜種 Nisaetus nipalensis orientalis
の類似性は van Balen et al. (1999) のリストにあるが、これは日本では成り立つ話であるものの、インドの留鳥ハチクマの成鳥がなぜ日本のクマタカに類似しているのかは説明できない気がする。インドで擬態するならばカワリクマタカや別のワシに擬態する方が効率的だろう。
カワリクマタカとハチクマの若鳥の模様が似ているとも書かれているがいずれも淡色型若鳥のことで全般に当てはまるわけでもない。
別のグループだが昔から典型例に挙げられていたコウライウグイス属による攻撃的なハゲミツスイ属 Philemon (friarbirds) へ島ごとに擬態している関係が見事に示されている: Jonsson et al. (2016)
The evolution of mimicry of friarbirds by orioles (Aves: Passeriformes) in
Australo-Pacific archipelagos。
日本に渡来するコウライウグイスは含まれていない。ハゲミツスイ属の方が少し先に適応放散をしていたため後から到達したコウライウグイス属が真似る関係がうまく成立したのだろう。
カッコウがタカに似ているのは通常宿主を欺くためと説明されているが、Prum (2014) によればハイタカによるカッコウの捕食は少なく、タカがカッコウを避けている可能性があってさらに研究が必要とある。
カワリクマタカの分布域と大きめのタカであるハチクマ及びカンムリワシの分布域は重複しているが互いに寛容であり、カワリクマタカの通常の攻撃的な性格を考えると驚くべきことであるが、主な食物はそれぞれ異なっているとの記載がある (カワリクマタカの wikipedia 英語版)。日本でもクマタカとハチクマの種間関係を観察する時にこの知見は役立つであろう。
なおハチクマの容貌は (巣を狙う) 哺乳類にも有効である。台湾のビデオ「九九蜂鷹」([ヨーロッパハチクマとの関係・亜種] の項目も参照)。哺乳類の中でも色覚に優れたサル類に有効であろう。
また動物園でも幼少児がオジロワシよりハチクマに怯える様子を複数回観察したことがある。ハチクマの習性を知らない人が見ると、目が黄色くて体に模様のある鳥の方が襲われると怖く見える可能性は十分ありそうである。
巣の外でもハチクマがタイワンザル Macaca cyclopis の集団を襲い、群れが散り散りになって逃げる様子が 映像記録・報道 されている。飼育下の (ハチクマより一回り小さい) ヨーロッパハチクマが犬にめっぽう強いことも報告されている ([飼育下の行動] 参照)。
ヨーロッパハチクマにおいては若鳥がヨーロッパノスリに似ていて、これも擬態の可能性があるとの提案もある。
#カッコウの [カッコウのタカへの擬態] より重複掲載:
Kuroda (1966) 猛禽斑とカッコウ類のタカ斑の起原について。
(和文抄訳) ハチクマはヂバチを食べる弱い種でありながら、タカ斑を示す (とくに尾) 例外といえるが、これは他の猛禽とくに大型のクマタカの攻撃に対する予防的擬態であると考えうる (中略) セレベスのクマタカ Spizaetus lanceolatus とハチクマ Pernis celebensis は、幼鳥は幼鳥、成鳥は成鳥に極めて類似している。この鳥では、後者はその擬態によって種を維持できたとさえ考えられる とまで書いてある。
「鳥類の図鑑」p. 107 に示唆されているものと同じ考えだが、クマタカは強く、ハチクマはよほど弱くて擬態に頼らなければ生きて行けない鳥と思われていたことがわかる。
もっともこの部分は Warncke (1961), Maerz (1954), Meyer and Wiglesworth (1898) を組み合わせたらしい。このようにして伝えられて "ハチクマ観" が熟成されて行ったのだろう。
さて、コンサイス鳥名事典にハチクマは「ジバチと呼ばれるクロスズメバチの幼虫を好んで捕食すると言われるが、このハチの巣を掘っているハチクマの姿を観察した者は少ない」と書かれていた。単なる事実説明と思っていたが、黒田氏にしても、「定本・野鳥記」の中西悟堂氏にしても、あたかも見てきたかのようにハチクマの生態を記述していることに不満を表明されたものだったのではないかと思えてきた。
「定本・野鳥記」にはハチクマの生態観察の場面は出てこないので、中西氏にもあまり馴染みの種類ではなかったらしいが、タカらしくないとしたミサゴのところで比較してハチクマをけなしている: 「定本・野鳥記」3 pp. 167-168 (1943 年初出) 「地蜂の巣ばかり嘴や脚で掘り起こしているハチクマよりはよほど見ごたえがある」。
そのようにして過去にも数々の「神話」が生まれてきたのでもっと謙虚になるべし、と言われたかったのではないだろうか。そして中西氏が中央の鳥学者が各種の鳥の生態や声を知らないらしいことをそれとなく記述されてきたことに対して、鳥学者側が一矢を報いたのかも知れない。
「定本・野鳥記」3 p. 166 のハチクマの項目もちょっと怪しい。尾羽にある V 字形の三条の黒色横帯がいちじるしい、とある。オス・メス・若鳥の区別ができていなかったので本数を混乱したとも読めるが、中西氏自身も尾の帯の本数がはっきりわかるほど近くでは観察していなかったのではないだろうか。
「鳥 630 図鑑」(1988) の飛翔図もそのような絵が描かれており、ヨーロッパハチクマの特徴が混ざったような図版となっている。中西氏も同種だと考えてヨーロッパハチクマの記述を参考に「見てきたように」書いてしまったのではないだろうか。
さらに亜種 japonicus Kuroda, 1925 動物学雑誌 37 (440): 221-226 では尾はほぼ必ず3本の黒帯があるが帯がなくて不規則な模様のものもあると述べられており、黒田氏の記述を借用したのかも知れない。
さらに「定本・野鳥記」の 1943 年の記述に先立つはずの YIO-08851 のフィリピン産の標本 (1934) を中西氏が保有していたようなので、尾羽の三条の黒色横帯の記述はなおさら怪しい感じがする。
さらに邪推すれば、もし捕食時の目撃証言があったとしても、今でもハチクマとクマタカの区別は怪しいぐらいなので、ハチの巣を掘っていればハチクマ (これは多分正しい)、例えばヘビなど小動物を捕食していればクマタカと自動的に判断され、ハチクマはハチの巣ばかり掘っていると考えられてきたのではないだろうか。先入観の入らない観察が先にあったとは限らない。
もっとも現代の我々がハチクマの姿をある程度知っているのはタカの渡り観察が普及した以降のことで、図鑑の絵が間違っていても気にする者はそもそもあまりいなかったのかも知れない。
ハチクマのクマタカへの擬態解釈の再検討
さて、ハチクマがクマタカに擬態してより強いタカからの攻撃を防いでいる説はポピュラーになっているが、本当なのだろうか疑問も湧いてくる。[マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] の 2025.5.5 のところでササゴイの巣を襲うハチクマが記録されている。
他にも [セーシェルのハチクマ初記録] にあるようにアオサギのコロニーを襲う、[北米のハチクマ初記録!] のアリューシャン列島に到着したハチクマがウのコロニーを襲う、[ヨーロッパハチクマの繁殖地行動・ディスプレイ] のヨーロッパハチクマによるヨーロッパヒメウの捕食例など、ハチクマにとって中型のサギ (アオサギは中型とは言えないが) やウのコロニーは実は魅力的なのではないだろうか。
主要な食物ではないとはいえ必要な時には襲うのだろう。この場合は巣を守る親鳥に対する威嚇効果が有効なのではないだろうか。つまり獲物に対する威圧感 (そのような意味があるのかずっと疑問に思っていたが) よりも巣や子を守る親鳥に対する威圧感と考えれば納得できる気がする。
ハチクマはハチの子を主に食べるので獲物に対する威圧感が必要でなく、消去法的により強いタカからの攻撃を防いでいる論理が出てきたものだろうが、中型の鳥の巣を襲う時には有効なのではないだろうか。もちろんすでに述べたように自身が巣を守る時にも有効であろう。
系統的順序から考えてもハチクマ亜科の祖先が現れた時代にはすでに中間系統の Elementaves グループの水辺の鳥や水鳥が適応放散している一方陸鳥はまだそれほどでないころで、繁殖期の食物として目を付けるのに適切な相手だったのではないだろうか。このように比較的大きな鳥を相手にする場合は威圧感をもたらす色彩は有効だったかも知れない。Elementaves グループも自身が生きた動物の捕食者のものが多く、必然的に体サイズも大きくなる。
クマタカ類が現れたのは少し後の時代になり、実はクマタカ類がハチクマ類に擬態したのかも? よく似た種類がいればより効果の高い方の色彩が有利な形質として選抜され (いわゆるトップランナー方式のようなもの)、相互に影響を及ぼしながら進化して結果的に模様が収斂したのかも。もちろん森林性で隠蔽色として有効だった生態的類似性の効果もあるだろう。
ハチクマ類とクマタカ類の主な食物が違う異なる形となる方向に進化したが、祖先的な性質も残っていてハチクマ類も中型の鳥の巣を襲うこともできるのではないだろうか。
両者が似せ合う理由の解釈もさらに検討してみた。多くの鳥 (または視覚の優れた哺乳類) にとってはタカに襲われる機会はそこまで多くないだろうと考えると、別の種ですでに学習していてくれればタカにとって都合がよい。クマタカ類もハチクマ類もお互い似せることで獲物 (ハチクマ類では巣を襲う際の親鳥の反応などを想定) が学習しておびえる確率を増すことができる。それぞれ別個に学習してもらうよりも効率がよい。
おそらくより数の多い (あくまで推定) ハチクマ類を通じて事前学習しておいてくれることでクマタカ類もきっと利点を得ているのだろう。これは ISDM とも呼べないし、より強いタカへの擬態 (ベイツ型擬態) にも aggressive mimicry にも該当しないように思える。
クマタカ類が強いので、と考える人にとってはいかにも受けの悪そうな仮説である (笑)。
オナガヘビワシが目立たない生活をしているアフリカクマタカに擬態しているとの従来の考えも、この解釈ならばより素直に説明できるかも知れない。アフリカクマタカの方が数の多くて目立つオナガヘビワシに合わせたとなる。オナガヘビワシも生態があまり知られていないだけで、おそらくヘビばかり食べているわけではないだろう。
ミゾゴイがハチクマを用心棒にするするのは危ないかも知れない。大西 (2009) Birder 23(5): 13-15 DISCOVER BIRDS 鳥たちの私生活、再発見! #14。ミゾゴイはサシバが友達?! (p. 15)。ミゾゴイがサシバの近くで営巣するらしい事例について。他にハチクマやオオタカの巣の近くでも営巣したが、オオタカには雛を食べられてしまったとのこと。あるいはハチクマは日本では子育て季節が遅いので大丈夫だったのかも。
少し気になる画像に気づいたので紹介: Oriental Honey-buzzard (Cescly Chen 2025.7.14)
中国 Shaanxi で内陸部。地域的には渡り亜種が想定されるが、日本のハチクマとやや印象が異なる。尾のバンドが3本。翼が短く見えて風切のタカ斑の入り方が細かい。carpal patch は見えないのでヨーロッパハチクマとの雑種ではなさそう。
分布や大きさがぴたり一致する種類は見当たらなかったが現代の Accipitrinae 亜科 (東アジア限定ならば旧 Accipiter 属と呼んでもよい) に似ているのではないだろうか。
[ハチクマにはなぜ多様な色彩型があるか?]
ハチクマの亜種が遺伝的にあまり異ならないとの Gamauf and Haring (2004) の結果をそのまま信じれば、ハチクマに多様な色彩型 (morph) が存在するのは、比較的短期間で必要に応じて模倣対象種に似た模様を生み出せることを可能にする遺伝機構が有利に働くためかも知れない (私見仮説)。
[多様な色彩を生み出す遺伝機構はもちろんまだわかっていないが、例えば #鳥類系統樹2024 で紹介の Prud'homme et al. (2007) Emerging principles of regulatory evolution などは参考になるかも知れない]。
Prum (2014) はハチクマは扱っていないが mimicry polymorphism (擬態に伴う多形) が進化的に安定である言及はある。この仮説を述べてから上記ハイガシラトビの事例を知ったのだがこの考え方は有力のように思える。地域だけで見ていないで地球規模で考えるべきなのだろう。
ハチクマになぜ色々な模様があるのかについてはこの系統 (ハチクマ亜科) で一般的に見られる現象で、擬態も含めて適応度を高めることを可能にする機構として暫定的に挙げてよいのではと考える。
系統的な出しやすさと擬態に伴う多形の両方が関係している? 擬態の機能が実際はあまりないものでも似た種類がいれば擬態と解釈している可能性もありそう。
ヨーロッパハチクマでは繁殖地域対応型の擬態関係は見られていないが色彩型は存在するので、擬態にかかわる色彩多形は当てはまらないかも知れない。ヨーロッパハチクマでは異なる越冬地によって違う種類のワシがいるのでそれに擬態しているため色彩の多形があるアイデアも出されているが [Bildstein (2017) "Raptors" pp. 29-30 参照]、あまりすっきりした対応関係は出されていないように見える。
これはヨーロッパハチクマの色彩が多様なことを説明する仮説として最初考えられていたものかも知れない。
Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" p. 339 にそれらしい記述があった。旧北区ではヒメクマタカ [高野 (1973) ではケアシクマタカ] Hieraaetus pennatus Booted Eagle、チュウヒワシ Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle、
越冬地のアフリカでは ヒメイヌワシ [高野 (1973) ではコイヌワシ] Hieraaetus wahlbergi Wahlberg's Eagle、シロハラクマタカ Hieraaetus ayresii Ayres's Hawk-Eagle、アフリカクマタカ Aquila africana Cassin's Hawk-Eagle、
エボシクマタカ [高野 (1973) ではカンムリクロクマタカ] Lophaetus occipitalis Long-crested Eagle、チュウヒワシ類、アフリカオオタカ Aerospiza tachiro African Goshawk、
オオハイタカ [高野 (1973) ではシロクロオオタカ] Astur melanoleucus Black Sparrowhawk の名前が登場する。"models" の表記で擬態対応種を意味するようにも読めるが、ここでは識別対象種として取り上げている。
越冬地に限らず正面から向かってくる場合には大型の旧 Accipiter 属、例えばオオタカに非常に似た印象を受けるとのこと。ヨーロッパハチクマとオオタカの識別 ([ハチクマと他種猛禽類との識別] 参照) が特に話題になるのはこのような場面らしい。日本ではあまり話題になっていないので興味深い。共通点の一つに "broad chest" とあるので正面から向かってくるのを見るとオオタカのように広い胸に見えるらしい。翼を水平に保つ点も同じ (トビの飛び方があまり強そうに見えないのは翼の先が下がるためかも知れない)。獲物から見ればおそらく区別が付かない。
ここで挙げられた種類を見ると "生物の模様は擬態で決まっている" そしてハチクマ類は弱いので強いタカに擬態して生き延びているパラダイムが全盛だった時代に取り上げられた印象を受ける。ヘビ食専門に近いチュウヒワシに擬態する必要はあまりなさそうに思える。これは東洋ならばハチクマがカンムリワシに擬態していると考えることに対応するが、そのような解釈はあまり聞いたことがない。
タカはそもそもよく似ているので色と大きささえ合わせればいろいろな組み合わせが可能だったが、その後あまり支持する研究がなく "models" にニュアンスを残しつつ識別対象種どまりの扱いとなったと思われる。
Ferguson-Lees and Christie (2001) の時代には系統関係がよくわかっていなかったのでハチクマ類とトビ類は近い位置に置かれていて余計に他のタカへの擬態が意識されていたのかも知れない。
上記見てきたようにハチクマ亜科 Perninae には模倣種がいないと思われるところでも多様な色彩型を持つものが多いようでこれが祖先的な形質かも知れない。
しかしながら ISDM 仮説で述べられている種類の系統を見ると結構様々で、aggressive mimicry とされるものも含めるとハイイロオオタカに見事に存在するし、カワリクマタカでも名前の通りである。タカ類全般に普通に見られることで程度問題の違いだけかも知れない。
タカ類の中でも特に複雑な模様を持つものは森林性タカ類に多く (これは複雑な景色の中で隠蔽色となるのだろう)、開放地に適応したイヌワシ属やノスリ亜科 Buteoninae (トビ、海ワシ、ノスリ類) などには比較的少ない。これらは開けた環境が背景になるので隠蔽色の必要性があまり高くなく、複雑な模様も生み出す必要が少ないのだろう。
ハチクマ亜科で多いのは多くの種類が込み入った森林に生息することに由来する選択効果かも知れない。
ハチクマ亜科の中でも開けた空間で滑翔で獲物を狙うツバメトビ Elanoides forficatus Swallow-tailed はタカ斑を持たないし、多様な色彩型も持たないように見える。
森林性タカ類では隠蔽色的な色彩とともに多様な模様を生み出せることはおそらく適応的なのだろう。
なぜタカ類なのかを考えてみると共通の性質として高い地位の捕食者であることが挙げられるだろう。捕食者を模倣することで採食を有利にする (ISDM 仮説)、もちろん他の捕食者から逃れることも適応的だろうがこれはタカ類に限った話ではない。
森林性タカ類でこのような形質が進化したのは、視力や色覚がよく、記憶力にも優れた鳥類 (特に Telluraves) が捕食対象になったためと考えることもできそうである (小型霊長類でもよいだろう)。ハチクマ亜科でも現在は鳥類をよく食べるものはあまりいないが鳥類も捕食しないわけではなく、以降の系統のタカ類が現れる前は主に鳥類食の種類もいたのかも知れない。
色彩の進化では食べられる側の適応として語られることが多いが、特に鳥類を食べる場合は捕食者側の適応もおそらく同じぐらい重要なのではないだろうか。色覚に劣る哺乳類食の大型の種類にとってはむしろあまり必要がない?
ハイタカグループの猛禽類でも色彩の違いと生息環境の関係 (熱帯地域で赤っぽい下面の種類が増える) などもこの面から追求してみると面白いかも知れない。
ハチクマでは巣内ひなの段階で色彩型がすでに現れることが知られているが、生涯同じ色彩型かどうかは確証が得られていない。
Thomsett (2007) A record of a first year dark plumage Augur Buzzard moulting into normal plumage
は飼育下のヨゲンノスリ Buteo augur で暗色型だったものが通常の羽衣に変化した例を報告している。ヨゲンノスリでは 16% が暗色型とのこと。
[ハチクマ色彩の遺伝的背景]
(この部分 2024.8.1 追記)
Ono et al. (2024)
Dark Morph of the Oriental Honey-Buzzard (Pernis ptilorhynchus orientalis) is Attributable to Specific MC1R Haplotypes
他の種でも色彩を決める要因として報告されていた MC1R 遺伝子のハプロタイプ解析でハチクマ暗色型も関連があることを示した日本の研究。暗色型に一致するハプロタイプを認めた。ハプロタイプ B1, B2 (この論文でのタイプ名) は淡色型、中間型には見られなかった。
D119G の置換は暗色型を生み出す候補と考える。ASIP 遺伝子の調節部位 (structural mutations も含む) が部位に対応した色彩発現や淡色型に関係している可能性も考察があるがいずれも仮説段階。
動物園個体の ASIP 調節部位も調べているが色彩多型に関連する遺伝的な多型を同定するのは難しいだろうとのこと。
海鳥で MC1R のハプロタイプが他種との交雑でもたらされた可能性が提唱されているそうで、あるいは Pernis 属でも類縁種や亜種間で同様の状況もあり得るかも知れないとのこと。
著者も述べているが調べた暗色型 (縞模様2個体、縞模様なしが2個体) は4個体で B1 が3個体、B2 が1個体でまだサンプルが少ないよう。なお動物園個体の情報もある。
以下の報告書が上記 Ono et al. (2024) の概要解説に対応する。
小野 (2019) ハチクマ (タカ目タカ科) の羽毛色バリエーションに関与する遺伝子の研究。盛岡市動物公園 (以前飼育されていた個体か) のハチクマの全ゲノムドラフト配列はすでに得られているとのこと。
小野 (2020) ハチクマ (タカ目タカ科) の羽毛色バリエーションに関与する遺伝子の研究 で関連する日本語概要 (mtDNA とも2起源?) が読める。
小野 (2023) ハチクマ (タカ目タカ科) の腹側淡色化に関わる ASIP 遺伝子多型の研究
「ハチクマという種がごく最近二つ以上の遺伝子プールの雑種形成から生じたことを示唆していると考えられる」とある。mtDNA についてはまだ論文化されていないよう。「二つ以上の遺伝子プールの雑種形成」のアイデアは論文中では海鳥からの類推として挙げられている。
LC579777.1 が Ono et al. (2024) の該当データの一つで、これを用いて BLAST を行ってみるとハチクマの多様性の高さがわかる。orientalis の中でも別種相当ぐらい違いがあるがよく混ざっているため系統を分離することはできない模様。ただし日本のサンプルのみなので分布西部や熱帯亜種などを調べるとまた違った結果になるかも知れない。
MC1R と色彩の関係、なぜ MC1R がさまざまな色彩を生み出すのに適しているのかなどについては例えば Mundy (2005) A window on the genetics of evolution: MC1R and plumage colouration in birds のレビューがある。
他種では #ミヤマモリフクロウ の Baltazar-Soares et al. (2024) で調べられているように MC1R をコードする部分ではない遺伝部位に違いが報告されているものもある。
ハチクマの (高精度ではないものの) ゲノム情報はすでに得られて公開されていることがわかった: SRX3628415: Sequencing for Oriental honey-buzzard genome by Illumina HiSeq4000 with insert size 500bp (Birds of prey genome 2018, 2019。韓国のチームによる)。
Catanach et al. (2024) の系統解析にはこれが用いられていた。
(2025.4.30 追記) [ハチ類の行動とタカ類などの共進化] の項目で、ハチクマの多様性を説明するアイデアを思いつたので議論を加えてみた。ハチクマの亜種または近縁種個々に対応するクマタカ類が存在するようなので擬態は何かに役立っていると考えられるが、もしハチクマの遺伝的多様性の起源の方が古ければクマタカ類がハチクマ類を模倣している可能性もあり得る気がする。
系統的にはクマタカ類の方が後発のはずだが種分化時期は結構近いかも。どちらにしても相互に影響を与えながら進化してきた2系統だろう。
[フィリピンのハチクマの不思議]
この話はしばらく調べてきた題材なのだがおそらく本邦初紹介となる (2024.3.14 初出、謝辞部分まで)。
ハチクマの特徴と言えば「他のタカに比べて首が長い」と決まり文句のように使われることがあるが、実際はどうだろうか。ノスリのように丸っこく見えるタカに比べればハチクマのスタイルは独特なのでこの場合の比較には正しいと言えるだろう。
ノスリ好きの方にとってはハチクマの形は気持ち悪いと言われることもある (ちょっとかわいそう)。
丸っこい鳥の好きな方、かっこいい猛禽類のイメージが崩れることを懸念される方は以下の話は完全に飛ばしていただいた方がよいかも知れない (笑)。
ハチクマも首を伸ばして飛んでいるとは限らないので全然長く見えないこともある。ハチクマならば首が長いはずなのでこれはいったい何だろうと問われることも複数回経験している。海外の写真を見ても実に紛らわしいものもある。
サシバとは大きさがだいぶ異なっていてタカ渡りで一緒に飛んでいる時は全然紛らわしくなく、全体的な形も異なるので、ハチクマの首が特別に長いと感じられていない方もあるのではと思う。
頭が小さい、あるいはペン先にように尖っている (これは解剖学的にも確かめられいる) などの表現も使われているが、こちらは納得できる感じがする。他のタカに比べて相対的に頭が小さくて尖っているため、相対的に首が長いように見えるだけではなかろうか、など (大型種ほど相対的に頭が小さいため。オオタカもハイタカより首が長いと言われるのと同じような理由)。
細かくみれば顔のみかけも違うし、嘴は細長いなど他の特徴の方が信頼できるので「第一印象」以外は首の長さはハチクマの飛翔時の識別点としてそれほど有用でないかも知れない。識別を記述したものでも翼の前縁に出る頭部が長いなど慎重な表現も見られる。
クマタカも悠々舞っている場合は翼の広さから間違えようがないように思えるが、(あまり機会はないかも知れないが) 追われて先を急いで飛んでいる場合など翼の広さがわからない角度のシルエットだどハチクマとよく似て見えることがある。
先崎・伊関 (2014) Birder 28(9): 6-9 にもシルエットでは大変似たハチクマとクマタカの写真が出ていて識別の紹介が取り上げられていたこともあり、ぜひ実際にご確認いただきたいところ。
こちらも大型種でより小さなタカに比べると相対的に頭が小さく首も長く見える。舞っている場合はあまり首を伸ばして飛んでいないのでわからないだけとも言える。
同様のことはイヌワシにも言える場合がある。
そうするとハチクマの特徴とされる「他のタカに比べて首が長い」は単に頭が相対的に小さく尖っていることによる視覚的効果が主で、実は首そのものは言われるほど長くないのではと釈然としない思いを持っていた。クマタカでもそうだが、羽毛に隠れている上に縮めていることも多いので (小型サギ類の首と同様) 見かけの長さはあまりあてにならない。
この疑問を払拭してくれたのがフィリピンのハチクマの映像である。まずこのページをご覧いただきたい。
The Tanay Honey Buzzards (Trinket 2016)。当時はビデオも見られたのだが現在はすでに公開されていないのは残念なところ
[この後の説明は少し細かいので画像だけを先に見ておきたい方は Me with HONEY a honey buzzard eagle (Pautastics 2015) やその先の Oriental Honey Buzzard (George So 2018) のところまでいったん飛ばしていただいてもよい]。
"Look at that long neck and pale yellow eye, December 2016" の写真は日本のハチクマでこの長さはさすがに見たことがない。
"A pair of Crested Honey Buzzards perched near the raptorwatch site, September 2014" につがいと考えられる (枝運びも見られたとのこと) 画像が出ているが、首を縮めると "たるみ" が生じているように見える。
この記述の時点では "Often described as having a long, pigeon-like neck" とあり、地元のバーダーの間では (後述のようにハチクマ全般を指して) 長くてハトのような首と記述されていたらしい。
同じ画像を用いているが Crested Honey Buzzard, Pernis ptilorhynchus (Raptorwatch Network Philippines 2016)
は "Will this resident raptor be elevated to another endemic?"
と記述しており、(おそらく他のハチクマと見かけが異なる留鳥のために) 新固有種になるのだろうかとの見解を紹介している。これはフィリピンハチクマ (Pernis steerei) が近年別種に分離されたことを受けたものと思われる。フィリピンハチクマとは容易に識別でき、特徴もまったく違うので別種になるだろうか、ということだろう。
Oriental Honeybuzzard (Pernis ptilorhynchus), philippensis (Wild Birds of the Philippines, Daniel Persia Galvan 2016)
には "Distinct from other races because of its extra long neck and tail" とあって他のハチクマの亜種より首と尾が一層長いとあるが、フィリピンで見られる他の亜種に比べて、の意味かも知れない。
亜種まで記述した一般的図鑑 [HBWの書籍版や Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World"] にはフィリピンの亜種についての形態的な違いの記述はなく、色彩や冠羽の有無の違いを記述してる。これは標本などに基づく記載と思われ、図版も同じ形の色違いのものになっていて他亜種に比べて首が長いことはこれらの著者には (まだ) 伝わってなかったのだろう。
Robert Kennedy et al. "A Guide to the Birds of the Philippines" (Oxford University Press 2000) にはハチクマは poorly known (よく知られていない) とあった。
この図鑑の記載には渡りのものも含めたハチクマ全体を指して Note long slender 'chicken' neck (現地観察者の言及もおそらくこの記述由来) とあるが、フィリピンハチクマ (当時はヨコジマハチクマと同種) も long neck, smallish head とあって首の長さの違いはあまりしっかり認識されていなかったかも知れない。
飛翔図はハチクマ全体で首を多少長めに描いているが、とまっている姿は philippensis とフィリピンハチクマ (ヨコジマハチクマの亜種として記載) を描いてあって冠羽以外は同じような形になっている。実際とはだいぶ異なる。
さらに原記載に近い記述と思われる John E. duPont (1971) Philippine Birds でも計測値と色の記載のみで、
亜種 philippensis には冠羽がない点は plate 9 (p. 37) の D が該当するはずだがあまり似ていない。
philippensis の頭頸部はバフ色っぽい白、初列風切は濃い褐色で先端が白い、尾は5本以上の濃い褐色の帯があって先端は白い、下面は白いが標本によっては胸に多少縦縞があるとなっていて当時はセブ島、レイテ島、ミンダナオ島、ネグロス島の固有亜種とされていた。ルソン島にも生息することは当時知られていなかったらしい。
特徴は現在フィールドで撮影されているものにあまり似ていないように見えるが...。写真を探してみると淡色型の幼鳥にはそのような特徴 (先端にわずかに白い部分がある) のものもあった。日本のハチクマのメスでもオスに似た黒いバンド (オスよりは細い) が次列先端や尾にあって先端が白いものもあった。
フィリピンでも似た特徴を持つ個体があって、亜種の違いというよりハチクマ全体にそのような個体もあるということだろう。タカ類の他種でも同様の特徴があるものが見られる。バンド先端部が白っぽく見えるのはあるいは擦れて脱色したものかも知れない。
写真を改めて見ていると見逃していた特徴にも気づいてハチクマはやはり奥が深い。識別やカウントだけして終了とすべきではないだろう。
亜種 palawanensis は philippensis に比べて小さな冠羽があること、下面はずっと暗色で濃褐色の縞があって少し小型とある。
渡りの亜種 orientalis は philippensis に比べて上面がより暗色で冠羽ははっきりしている。下面は明るい褐色で少数の暗色の縦縞がある。philippensis に比べて尾のサブターミナルバンドは倍ぐらい太いとのことと記述されている。
現在のフィリピンで philippensis と考えられているものと合っているのは冠羽がない点と少し大型である点程度で一般的な色彩はそれほど似ていない。原記載はそれぞれの亜種の色彩の多形や性別、年齢による違いに惑わされているかも知れない。
これら記載の情報をもとにフィールド識別していると冠羽ぐらいしか識別点がなく、図版を見てもさっぱりわからなかったことだろう。生息地域に頼るしかなかったかも。
同じ時期の日本の図鑑を考えても納得できるが、他の種の図版を見ても何かわからない種類がしばしばある。
原記載が何を表現したかったかを知る参考にはなるだろう。フィールドでの写真がネットでも簡単に見られて比較できる現代とは事情が全然違っていただろう。
問い合わせや図鑑での記述などとは相前後するが、最初に紹介したページの次に見つけて首が長い印象を決定的にしてくれたのが動物園個体の次の画像である (亜種は同じと想定する): Me with HONEY a honey buzzard eagle (Pautastics 2015)。
いかなるタカ (ハゲワシ類を除く) が首を伸ばしてもここまで長く見えることはないのではないだろうか。
これらの映像や画像に 2017 年前半に気づいて撮影者などに問い合わせなどをしていた。当時の情報によればフィリピンで猛禽類の観察が始まったのは比較的最近のことで、猛禽類観察者の間では首の長さが大きく違うことはよく知られていたが、一般のバーダーは出会う機会も少なくあまり知られていなったとのことであった。
当時の図鑑も 20 年近く前のものであまり情報もなかったらしい
(これらのやりとりの結果現地観察者にもあるいは関心が高まったかも知れない)。
現地の観察者にも実際にそれほど知られていなかったようで、分類が最近変わったので識別には自信がないなどの返事ももらった。
亜種間の研究もあまりなく、フィリピンの亜種全体を称して虹彩が暗色などの話も最初のころは聞いた。別に紹介するように日本でもハチクマの性や年齢識別が確立されたのはそれほど遠い昔ではなかったので、亜種や成鳥・幼鳥が区別されていなかった可能性もある。
ハチクマについては少なくとも近年では日本の知識の方が少し先行していたこともあって (目が肥えていて?)、海外からの視点で「これは違う」ことに気づきやすかったかも知れない。
次も驚くべき画像でサムネイル画像を見た時は何かわからなかったが拡大してみると:
Oriental Honey Buzzard (George So 2018)。
猛禽類は似た種が多いので識別が難しいことはよくあるが、知っている種のはずなのにあまりに違っていて何者かわからないことなどあるだろうか!?
他の写真など:
An Oriental Honey buzzard that flew overhead
while we were waiting for the Kalaws to appear (Henrick Tan 2021)、
"Indomalayan Honey Buzzard" or Oriental Honey Buzzard in a flyby
(Henrick Tan 2023)、
Oriental Honeybuzzard (Romy Ocon 2008)、
Oriental Honeybuzzard at Bacsil Ridge (La Union, Philippines) (Romy Ocon 2012 ビデオ)、
Oriental Honey-Buzzard or Crested Honey Buzzard (Pernis ptilorhynchus) (Loel Lamela 2019) 交尾。
Crested Honey Buzzard/Oriental Honey Buzzard (Pernis ptilorhyncus) (Ralf Nabong 2019) 換羽中のためか翼指が7に見える個体。伸長すれば6になるのだろうか、それとも7の個体もいるのだろうか。
これらは首の長さの特徴がわかりやすいものを抽出したもので、いつも首を伸ばして長く見えるわけではない。撮影者も特徴の現れている写真を出すことが多いと思われるので、平均的な見かけの印象とは異なる可能性は十分にある。
現地の詳しい方に問い合わせた 2017 年当時は、一般的図鑑には書いてなくても記述のある本も探せばあるかも知れないとのことだったが、
最近出版された一般的図鑑の Desmond Allen "Birds of the Philippines" (Lynx 2020) で Indomalayan Honey-buzzard Pernis (ptilorhynchus) ptilorhynchus
と記述され、亜種 palawanensis (フィリピン西部のカラミアン諸島、パラワン島)、philippensis (フィリピン北部と東部)
と分けられている。これらを総称して "Large, long-winged raptor with small head, long, almost vulturine neck, and shortish shaggy crest on nape and hindneck"
となっていて首が長い (ニワトリの首の記述からほとんどハゲワシのような首に変わった) ことは両亜種共通のように読める。この部分は従来の図鑑を多少踏襲しているかも知れない。両亜種を含めて雌雄の色彩の違いはおそらくなくて、メスは大きいだけか? としている。
少なくとも philippensis は交尾写真などもあるので体上部の雌雄の色の違いはほとんどないことは確かに見える。
この図鑑には区別して書かれていないが、尾の模様は太いものもやや細いものもあり、交尾写真を参考にすると尾の模様の太い方がオスかも知れない。メスの方が内側のバンドが細めで本数が多いように見える。
他の飛翔写真などで見られるバンドの細いものは非成熟個体も含まれているかも知れない。
Allen (2020) によれば亜種 palawanensis はあまりわかっておらず、亜種記載時と思われる色彩の記載はあるもの、渡りの亜種 orientalis と野外で区別できないかも知れないと述べている (両亜種共通で首が長い書き方とは内部的に多少矛盾する)。
亜種 philippensis の典型的の成鳥が幼鳥とともにいることがパラワン島で記録されているが、亜種 palawanensis の特徴を示す繁殖個体はパラワン島で観察されておらず、ボルネオ島から漂行している可能性があるとの記述になっている。
学術的には亜種 palawanensis が記載されているものの、どの個体を指すのかあまりよくわかっていないのかも知れない。
Birding by the road: Buenavista-Tagabinet-Cabayugan
(Trinket 2017) に繁殖期のパラワン島での写真があるが、philippensis と異なるように見える。
Oriental Honey-buzzard (Miguel Rouco 2012) にパラワン島でハチの巣を運ぶ写真がある。尾に2本の太い帯がある個体で虹彩は濃い黄色。
首は philippensis ほどは長くなく、観察者も注記しているように亜種 palawanensis かも知れない。
philippensis に比べて下面はずっと暗色との記述とは合致するが、単に暗色型かも知れない。orientalis とは明らかに異なっている。
亜種 palawanensis の特徴を示す繁殖個体はパラワン島で観察されていないとの Allen (2020) の記述と合わないがあるいは著者がこの記録を見逃しているのか。
philippensis にも尾のバンドが太いものもあるように見える: Oriental Honey-buzzard (Indomalayan) その1, その2 (Bob Natural 2023)。尾のバンドより首の長さが決定的識別点に見える。
次も尾のバンドが太いが内側は orientalis ほどではない: Oriental Honey-buzzard (Indomalayan) (Robert Hutchinson 2024)。Oriental Honey-buzzard (Robert Hutchinson 2023)。
フィリピンで撮影されていても次は orientalis: Oriental Honey-buzzard (Kevin Pearce 2022。ミンダナオ島西端)。
Allen (2020) の図鑑では渡りの種類 Eastern Honey-buzzard (Oriental Honey-buzzard) (亜種 orientalis) に比べて Indomalayan Honey-buzzard は羽衣の変異が少なく、首が長く頭が茶色で翼は丸いとある。
亜種 philippensis は際立っていて種に値する可能性があるとしている。
Allen (2020) のこの図鑑では philippensis は描き分けてあり、HBW 書籍版などとは違って、とまっている姿も飛翔時も明瞭に違う形態となっている。広く手に入る図鑑では初めてかも知れない。
今度は orientalis (日本のハチクマと同一) の絵では翼の模様はよいのだが、頭頸部はノスリとあまり違わない感じで描かれていてこれまた実物とちょっと印象が違う。首の長さの違いを強調するためにこうなったのだろうか?
フィリピンハチクマ (Pernis steerei) の項目で識別点は Indomalayan typically finely streaked below, not barred, with much longer vulturine neck とある。模様の記述からは philippensis の方を意識していると思われる。Indomalayan Honey-buzzard は首がずっと長くハゲワシのようとなっている。
Eastern Honey-buzzard (日本のハチクマと同一) はオスの眼が赤い点、尾のパターンが異なる点を挙げている。クマタカ類との識別点はクマタカ類の方がずっと強い太くて長い足、翼指が6ではなく7である点を挙げている。
興味深いのは Gamauf and Haring (2004) の分子遺伝学研究ではハチクマ亜種間の遺伝的な違いがあまり存在しないことで、(これほど形態の違いがあるのに) philippensis も他とあまり違わないことになる。
博物館標本を用いた研究なので標本ラベルに亜種まで正しく同定されていない可能性も考えたが、
Gamauf et al. (1998)
Distribution and field identification of Philippine birds of prey. I. Philippine Hawk Eagle (Spizaetus philippensis) and Changeable Hawk Eagle (Spizaetus cirrhatus)
で野外識別についても触れられていて Gamauf はフィリピンのハチクマの観察経験もあるのだろう。
しかし、The larger Oriental Honey-buzzard
Pernis ptilorhyncus philippensis has
the appearance of a typical honey-buzzard. Because of its 'cuckoo-like'
long neck. In many cases flying Barred Honey-buzzards do
not show a long neck compared to the other congeneric species.
と書いている。亜種 philippensis は "典型的なハチクマの形" をしていて首が長いと書いてあって、フィリピンハチクマ (Pernis steerei) は飛翔時それほど首が長く見えないとあるものの亜種 philippensis がハチクマの中で特異な形態を持つことまでは 2004 年の分子遺伝学研究の時点では認識していなかったかも知れない。
標本が philippensis の記載と矛盾しないことは確かめているのだろうが、複数の亜種の存在するフィリピンなので本当に現在の首の長いグループと同じなのか確かめる必要はあるのだろう (アメリカのスミソニアンの標本を使っている。別途調査するとここで調べられた他にも標本はあるものの骨格標本は調べた範囲ではないらしい)。
新しい標本を得るのは難しいだろうが飼育個体などからサンプルを得てさらに現代的な方法で系統を確認した方がよいのだろう... ということは誰でも思いつけるわけで、何とかならないかとやっていたわけだが、飼育個体の出所などは多分よくわからず科学的な協力は得られないのではなかろうかとの現地のバーダーの感触だった。
日本では最近心理的障壁が減ってきているように見えるが、現地の伝統的なバーダーにとっては (保護思想からも) 飼育個体にはあまり関わりたくない、見たくない印象も受けた (今でも野外鳥学者の飼育個体への障壁を感じることがある。鳥学や自然保護にあまり深く関わっていない者の方がそこまで障壁を感じることなく両方の視点から見られてむしろよいのかも知れない)。
猛禽類はいずれも CITES Appendix II 以上でサンプルの国外持ち出しも双方からいくつもの書類が必要で相手の積極的協力なしでは難しい。動物輸入業者ならば慣れているかも知れないが、研究者や動物園にとっては相当な障壁になるので、標本を使ってできる研究ならばその方がよいのは確かである。
あるいは Gamauf もすでにコンタクトを取って同じような結果になっているかも知れない。
分子系統解析なども詳しくフィリピンとも縁の深い共同研究者のフィリピン訪問調査の可能性なども検討していたのだが、そうするうちにコロナですべてがリセットされてしまった状況である。しかしハチクマのフィリピン繁殖亜種の面白さは現地観察者にも共有された部分もあろうと思えるので、今後何かの進展があることに期待したい
(これらのことを調べていたのが #コブハクチョウ の [鳥類の頸椎] のような情報に詳しい理由の種明かしになる)。
さて、もし亜種 philippensis が種になった場合どのような英名・和名がふさわしいのかも興味あるところである (現在でも亜種に和名があってもよい)。
Philippine Honey Buzzard, フィリピンハチクマ の名前はすでに使われているので亜種学名をそのまま名前にはできない。この点を考えると Gamauf and Haring (2004) はフィリピンからハチクマがさらに1種分離される可能性は想定しなかったと考えられる。
もし将来分離される可能性があるならばより "フィリピン" と名付けるにふさわしかっただろう philippensis が他のハチクマとこれほど違っていることに Gamauf もおそらく気づいていなかったのではなかろうか。
模様の特徴などで差し障りのないタテジマハチクマのような名前は考えられるが、そのような特徴は他の種や亜種にも見られそうで (フィリピンハチクマ成鳥も縦縞が目立つ)、philippensis でも胴体部は縦縞が見えない、あるいは横縞の見えるものもあるのでもっと明確に区別できる特徴を表した方がよいと思う。
"クビナガハチクマ" としか呼べないような気がする [そのまますぎてあまり品がないかも知れないが、それはいったい何者だ、クビナガリュウの新種かと興味を持つ人もきっと出てきそうな名前に思える (笑)]。
亜種にも多分現在和名がないので、亜種 philippensis とかフィリピンのパラワン島以外の繁殖亜種のハチクマとかややこしい名前でなく亜種クビナガハチクマと呼べば簡潔になるように思える。
クビナガ... の付く種名は北米の有名なクビナガカイツブリ Aechmophorus occidentalis Western Grebe がある (カンムリカイツブリと別属でこの属は現在は2種。そのままの意味の英名はあまり使われないようだが Swan Grebe, Swan-necked Grebe の別名もある)。
ここでは今後この名前で呼んでみよう。
上記の図鑑などの記述でほとんどハゲワシのような首とあるが、これは主に飛んでいる時に首を下げる様子を指している印象を受ける。ハゲワシとハチクマが系統的に近いのかと最初は思ったが、これは最近の分子系統研究で否定的となった。現代の分類のハチクマ亜科でも他のタカ類に比べて首の長いと言えるような種類は他にいない。共通祖先系統の特徴を表すものではなさそうである (後述)。
なおハゲワシの首が長く見えるのは頭頸部に羽毛がないことも影響があるだろう。羽毛をまとったらそこまで極端に見えないかも知れない。この点は Katrina van Grouw からも指摘をいただいた。
種・亜種混ぜて書けばフィリピンにはフィリピンハチクマ、"クビナガハチクマ" (philippensis)、いま一つ正体不明の亜種 palawanensis (これは和名亜種パラワンハチクマで問題なしで異論も出ないだろう)、そして渡ってくる亜種ハチクマ (越冬期または非成熟個体) が混在することになる。
分布上問題となるのはフィリピンハチクマがパラワン島に分布しないとされていることで、繁殖個体群ではパラワン島は亜種パラワンハチクマ [ただし上記 Allen (2020) の示唆するように "クビナガハチクマ" がパラワン島にも生息しているかも知れないが亜種同定が正しいかどうかわからない]、それ以外はフィリピンハチクマと "クビナガハチクマ" とほぼ地理的に分かれていることになる。
これは生物地理学的な区分がある程度反映されていることになる。パラワン島はボルネオ島と関連が深く、フィリピンでもパラワン島の固有種がいくつもある。
ハチクマのように飛翔力の強いものにとってパラワン島と例えばミンドロ島、ルソン島との間に障壁があるのは不思議ではあるが、何か越えにくい部分があるのだろうか。
日本のハチクマの衛星追跡でもパラワン島どまりで戻ってきているので理由があるのだろう。あまり北まで戻るとわざわざ迂回して南に渡って来た意味がなくなるとはっと我に返って戻ったのかも知れない、というのは冗談だが不思議なところである。島伝いに行くのは得意でないのかと思ったがミンダナオ島まで行った個体やインドネシアではそうでもない。
パラワン島より先に行くとフィリピンハチクマや "クビナガハチクマ" の競争相手が周年生息しているので、ハチクマ類の生息密度の低いたとえばスンダ列島東側で越冬する方が有利なのかも知れない。
パラワン島を除くフィリピンではフィリピンハチクマと "クビナガハチクマ" が同所的に繁殖個体群として生息していることになるが、Gamauf and Haring (2004) の示すような遺伝的距離の近さでは交雑は当たり前に起きておかしくないように思える。行動や生態など他の点で完全に種分化しているのだろうか。
Gamauf and Haring (2004) の書き方では "クビナガハチクマ" が最後に分化した形になるが、
フィリピンハチクマの存在下で "クビナガハチクマ" はいったいどのように分化できたのだろうか。あるいは限られた系統解析が正しい分岐順序を反映していないのだろうか。
これら2種または亜種の関係だけを考えて分岐順序を考えなければ、2種または亜種のニッチが異なる可能性が考えられるが、どちらもほとんど調べられていない。
Raptor Research & Conservation Network (2018) "A Field Guide to the Raptors of Asia" によればフィリピンハチクマは巣立ちびなが1例知られているのみでクラッチサイズは1とある。
これも産卵初期からの継続観察ではないと思われるのでは実際は2かも知れない。論文があるかどうかもよくわからない。我々のハチクマと同様繁殖時の巣の発見や調査は難しいのだろうと思われる。
よほど熱心に研究する者がいれば別だろうが、フィリピンにはフィリピンワシのような人気鳥も多種生息しているので、ハチクマ類をわざわざ研究しようという人は現れにくいのかも知れない。
"クビナガハチクマ" については巣の発見記録はあるのだろうか?
"クビナガハチクマ" がハチの巣を運ぶ映像は得られている: Oriental Honey Buzzard (Pernis ptilorhynchus) with honey catch,
Another shot of Oriental Honey Buzzard (Pernis ptilorhynchus) with honey comb catch (Virgilio Gales 2020),
ORIENTAL HONEY BUZZARD (Cora Lopez 2022)。
これらを見ても飛翔時でも首が長く見えることがわかるが、子育て時はハチの巣が主食になる点は我々のハチクマと同様なのだろう。交尾も記録されており餌運びが観察されて繁殖は間違いないが、どこで営巣しているのか突き止めるのが難しいのは日本などの事情と同様なのだろう。
The Continuing Saga of Bees (DashKleyn 2011) にフィリピンで樹のハチの巣 (giant bees オオミツバチ類) を食べた跡が紹介されている。このタイプのハチの巣は大陸南・東南アジアでおそらく大陸型のハチクマに食されている映像が紹介されている。
少し脱線するが関連して食性も少し考察しておきたい。
樹のハチの巣などの食物は非繁殖期などにはちょうどよいのだろうが、ひなに与えるために巣に持ち帰るのに適したサイズではない。巣に持ち帰るには地バチの巣盤や小動物が向いているだろうから、巣に持ち込んだものだけを調べて食性を把握すると適度な大きさで運びやすいものに限定されてしまう可能性がある。
日本のハチクマでもきっと同様の事情と思われるので、ハチクマ類が何を食べて生活しているのかはおそらくまだまだ情報不足、あるいは偏って解釈されているだろう。ハチクマ類の捕食シーンは非常に観察しにくいようなので解明は簡単には進まないかも知れない。
飼育下ではいろいろなものを食べるようで、甘い物好きなので案外いろいろなものを食べているかも知れない。飼育下個体では肉は好きだが古くなった肉は捨てるようなので (別項目にあるようにタカ類の中では嗅覚遺伝子が発達している。嗅覚や味覚で食べられるものを判断しているかも知れない)、肉についてはおそらく新鮮な獲物しか食べていないように思える。
トビのように死肉食を (ほとんど) 行わないので冬場も繁殖地にとどまることができないのかも知れない。
断片的な越冬地の記録では、我々が「典型的なスペシャリスト」と呼んでいるよりはいろいろなものを食べるようで、甘いハチの子が大好きであっても実はジェネラリスト的な本質を持っているように感じる。
繁殖時期の巣の記録だけを見ていると食性を正しく把握できていない可能性を示すために付記してみた。
本題に戻ると、我々のハチクマも首が長い点がハチの巣食への適応とされるが、フィリピンハチクマの首の長さでもおそらく十分なのでなぜこれほど長いのか理由がわからない。首の長さで食物 (ニッチ) が微妙に違っているのだろうか? この写真を見る限りでは日本のハチクマと同じようなものを食べてそうに思えるが...。
フィリピンハチクマの方がむしろ "差別化を図る" (?) ために短めの首になっているようにも見える (かつて同種とされたセレベス島のヨコジマハチクマの方にむしろ首の長めの写真がある)。
assortive mating (この場合は簡単に言えば首の長さの似た個体とつがいになる、模様の似たものとつがいになる) なども考えられるが、首の長さで選り好みするなどはさすがに聞いたことがない。
そもそも交雑個体らしい中途半端なものを見かけない気がする。もっと縁の遠いハチクマとヨーロッパハチクマでの交雑があるならばあって当たり前なのだろうが。
しかし選り好みはまったくあり得ないことではないかも知れない。性選択で長い首が進化した可能性は魅力的だが、しばしば話題にされるキリンでも長い首の選り好みの結果ではないのであまりに突拍子ないかも知れない。
なお大きさはフィリピンハチクマの方がわずかに小さい。"クビナガハチクマ" は留鳥で、渡りをする我々のハチクマよりも相対的に翼が丸くて短い印象を受けるが、計測値では我々のハチクマよりもむしろ大きな翼長になっている。"クビナガハチクマ" は首は長いが尾も我々のハチクマよりも長い。数字を見る限りではハチクマの最大亜種と思える (ただし計測値は古いもの)。
ハチクマ亜科全体でも一番大型の模様。Pautastics (2015) の画像で "eagle" とあるのも (現地語でワシ・タカが区別されていない可能性はあるが) わからないこともない。
また少し脱線するが関連してハチの巣食への適応についても追記しておくと、地下のハチの巣を捕るのは嘴か足かの二択になるだろう。
ハチクマが嘴で捕る方を選択して、おそらくそのための適応として首を伸ばしたのはある意味正解で、現在の繁栄につながっているのだろう。
狭いところを足で捕るとおそらく不自然な姿勢になるか、チュウヒダカ類やセイタカノスリ (#クロハゲワシの備考 [変わった餌の捕り方をする猛禽類]) のように脚の関節を特殊化 (と言えば聞こえはよいが単純化である) させると、猛禽類本来のしっかりした脚の機能は多少なりとも犠牲になっているだろう。
ハチクマの足は弱々しいとしばしば言われるが、クマタカのように中型の哺乳類も相手にする種類と比べた場合の話で、近くで見るとなかなかしっかりした脚で爪も想像以上に立派である。
動物園ぐらいの近さでないとわかりにくいかも知れないが、最近のマレーシアの繁殖個体の下からのビデオのおかげで野外でも成鳥、若鳥ともこの印象を確認できた。鳥類学者はすり減った爪の標本ばかり見てニワトリの足のような絵を描いているのかも知れない (失礼)。
趾は細くて長いので実際にどれほどの力が出せるかはわからないが、かつて食用に撃たれていた時に死んだと思った個体に掴まれて爪が手を貫通した話を読んだことがある。
日本の動物園の飼育員の方は手に乗っても痛くないと言われたが、慣れた鳥が手を踏み台にしたもので多分手加減してくれているのだろう。
オナガハチクマ類 (Henicopernis 属) は足でハチの巣を捕るらしいとの記述があるがあまりにも知られていない種類なので実際どのようにしているのかはよくわからない。
系統的には Pernis 属からやや離れていて、実は想像するほどハチクマと似た生活をしていないのかも知れない。分布はニューギニアで (真性) ハチクマ類の分布からは外れている。
オナガハチクマ類はハチクマ類に似てはいるが、機能的には (真性) ハチクマ類には敵わないかも知れない。
写真を見ると羽の擦れた個体もあって地上でも食物を捕っているのだろうと想像できる。前述のように首はハチクマのように長くない。脚は短いように見えるので足でハチの巣を捕るのは本当だろうか?
もう一つ擬態の問題がある。フィリピンハチクマでは前述のようにフィリピンクマタカへの擬態があると考えられているが、同所的に繁殖する "クビナガハチクマ" には必要ないのだろうか。
フィリピンハチクマにははっきり見られる冠羽もなく、もし "クビナガハチクマ" が祖先型のハチクマから同様に進化したならば、すでに持っていた擬態できる機能を捨てたことになる。擬態できる方が生存には有利と思えるがわざわざ捨てるだろうか。あるいはタカ類の擬態の我々の解釈は誤っているのだろうか。
ただし "クビナガハチクマ" の顔つきが怖い鳥に見えないわけではない: A Crested Honey-buzzard, Pernis ptilorhynchus perched on a high tree (Birding Philippines 2021)。
fierce light yellow eyes とあるように黄色い目は怖い目つきに見えるらしい。
piercing eyes とも呼ばれ、URL を失念してしまったが比較的暗色の "クビナガハチクマ" で頭部にあまり模様がなく褐色背景と白っぽい黄色の虹彩のコントラストが特に著明さがわかる画像もあった。"怖い" というより "不気味" かも知れない。特に首を伸ばして突き刺すような目つきだと見たこともないような鳥に見えて一層 "不気味" かも知れない。
(Avilon Zoo 2019) は保護飼育個体だろうが (単に過去の写真の紹介かも知れない) 虹彩の色も完全に変わっておらず非成熟 (2年めぐらい?) 個体と思われ顔もあどけない。
このような画像を見ると性的成熟を終えて虹彩が黄色く怖い顔になるのは巣での防衛目的が第一義のように感じる。若鳥の方が他のタカからの攻撃に無防備と想像できるが、若鳥のうちから怖いタカに見せていないのはよく言われるような他の種類のタカへの擬態には他の種類のタカからの攻撃を防ぐ意義があまりないのかも知れない。
また性的成熟すると同種の他個体との競争が発生し得るので成熟した兆候を早くから示さないのだろう。
この議論は日本で繁殖するハチクマについても成り立ちそうな気がするので、性的成熟と巣を守るようになる時期が一致することは解釈しやすい気がする (#トビの備考の [猛禽類の逆性的サイズ二型] も参照。この備考でもハチクマ雌雄の巣での役割について考察している)。
そう言えば魚食のミサゴの怖い顔は何のためなのだろう。獲物に対しては関係なさそうなのでやはり巣での防衛のため? トビはあまり怖い顔に見えないがこの種にはあまり必要ないのだろうか。
先に日本のハチクマの衛星追跡でパラワン島、ミンダナオ島どまりなっている理由としてフィリピンハチクマ、"クビナガハチクマ" の競争相手が周年生息しているので、ハチクマ類の生息密度の低いたとえばスンダ列島東側で越冬する方が有利なのかも知れないと述べた (生態学的にも理解されやすそうな仮説で究極要因の方になるだろう)。
日本のハチクマの衛星追跡ではセレベス島では越冬しているので、同所的に生息するヨコジマハチクマ Pernis celebensis についてはこの解釈は当てはまらないかも知れない。ヨコジマハチクマとフィリピンハチクマは同種に近いぐらい縁が近いので、これらの種が同所的に生息することはあまり制約になっていないかも知れない。
ミンダナオ島にも "クビナガハチクマ" は生息するが、追跡された渡りハチクマもあまり深く入り込んでいないように見える。
あるいは渡りハチクマは "クビナガハチクマ" を避けているのかも知れないと解釈してみよう。自分たちと同じような種類であることはわかるが経験のない容貌なので、本能的に「危険かも知れない、ここは別世界みたいなので避けておこう」(半分冗談) となっているのかも知れない (至近要因? 例えばそのような効果で結果的に競争が避けられているなど)。
別の意味で興味深い写真がある。先述のものと同じ動物園の飼育個体 (足環からは同一個体ではない?) であるが Steve & Marcia on the Rock: Corregidor Journal の Day 6, April 10 (Subic Bay) のところ (クリックで画像拡大)。
これを見ても驚くほどの首の長さがよくわかるが、縦縞も含めてあるいは樹木や竹林への擬態も考えられるかも知れない。サギ類ならばまだわかるが猛禽類でそのようなことはあり得るのだろうか? (もし猛禽類が首を伸ばして木に擬態し、外敵の目を欺くとなれば鳥類学の常識を覆しそうだが?)。
サギに擬態ということはないだろうが、首の長い鳥は危険との常識がタカ類の遺伝子に書き込まれていればもしかすると避ける理由になるかも知れない。
獲物を襲う時目立たないようにする効果はあるかも知れないが、その場合の獲物は何だろうかと不思議なところが多々ある。
頸椎の構造はどうなっているのだろう。最初に紹介した Trinket (2016) The Tanay Honey Buzzards でも首を縮めると "たるみ" が生じているように見える画像が出ているが、例えば次も同様 S-neck pose (Liza Del Rosario 2023)。
他のハチクマでもこのような "たるみ" は多少見られるが通常はあまり目立たない: Oriental Honey-buzzard (Mayank Mishra 2024.3.9 インド)。
おそらくほとんどの鳥で実際はこのように首を S 字型に曲げているのが通常の姿勢だが羽毛に隠れてわからないだけだろう。"クビナガハチクマ" では "たるみ" のように見えるのはおそらく小型サギ類と同様に折り曲げた頸椎が羽毛の中に収まりきらずに突出しているもの。
"クビナガハチクマ" の場合は外見からも曲げているのが目立つが、他のタカ類ではそこまで首が長くなくて実際は曲げていても目立たないだけだろう (先述のハゲワシとの比較にも関係)。
このような姿勢が鳥にとっては一番リラックスしている状態と思われるが、首を S 字型に曲げて頭の位置を維持するのにむしろ疲れないのだろうかとも感じる。とまって周囲を見渡している一般的な猛禽類の基本姿勢はおそらく同じで、外からわかりにくいだけで首をS字型に曲げつつ周りを見渡していることになる。
この姿勢だけを見て猛禽類の首は一般的に短いと考えると誤解の原因になり得る。
ハチクマの頸椎数が他のタカ類より多いかどうかはあまり資料がない。古い解剖学の話題なので誰かが調べてそうに思うが成書になかなか見当たらない (日本のハチクマは骨格標本もあるのでその気になれば調べることは可能だろう。山階鳥類研究所のオンラインの標本データベースには含まれていない)。
Holdaway の学位論文 (1991) (#イヌワシの備考の [ハーストイーグル (Haast's Eagle)] 参照) によれば日本でお馴染みの猛禽類では頸椎数はだいたい 14 個 (これは他の資料でもそう書かれているので馴染みの種はほぼ全種同様と考えてよさそうに見えるが単に出典が同じだけかも知れない)。
この論文で使われた結果は Jollie (1976, 1977)
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part IV) によっているとのこと。
15 個なのは (当時の分類体系順) ヘビクイワシ、ミサゴ、ヨーロッパハチクマ、ミシシッピートビ (Ictinia 属)、ヤシハゲワシ、ヒゲワシ、ズキンハゲワシ、クロハゲワシ、
ダルマワシ、オウギワシ。現在の分類で Gyps 属のハゲワシ類のみもっと多い (17 個)。
ヘビクイワシ、ヤシハゲワシ - クロハゲワシ のように首が長めのものは確かに含まれているが、15 個でも特に首が長いわけではないものもある。ミサゴの首は長く感じられるだろうか? - 自分には多少そのように思えるのだが。山階鳥類研究所の標本データベースでミサゴの骨格画像が出ていて頸椎は 13 cm ぐらいで確かにトビ (10 cm 強) より少し長い。
かつて洋書店によく置かれていた Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) には全長も含め、識別のために体の各部位の長さを S-L (vL) で表していた。全長をベースに並べてあった面白い図鑑。
この一つに "neck ratio" (頭頸部を合わせた全身に対する比率) があった。英国猛禽類でミサゴのみ MS (カモメ類ぐらい) となっていて他は S だったので見かけの違いに気づいていた観察者もいたのだろう。
ちなみにハヤブサ目も 15 個で、カラカラ類を見ると確かに首が長めに見える。しかし我々の見かけるハヤブサ類ではその印象はまったく受けない。
この数が {ハヤブサ目 + オウム目 + スズメ目} の Eufalconimorphae (#ミサゴの備考 [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] 参照) の一般型なのだろう。オウム目は数を減らしているがスズメ目ではかなり受け継がれている。
スズメ目のヒロハシ科のみが頸椎数 15 個で原始的な特徴と言われるのもそれを反映しているかも知れない (#ズグロヤイロチョウの備考参照)。
Eufalconimorphae の前、Australaves の最も早い分岐にあたるヘビクイワシと似た形のノガンモドキ目 Cariamiformes はかつては別のグループ (ノガン類やツル類) になっていたためか書籍では資料があまり見当たらないのだが 14-15 個とある情報があって、頸椎数はノガン類とかなり違い、Eufalconimorphae と同様のよう。
Boehmer et al. (2019) ではアカノガンモドキとミナミカラカラは同じ数になっているが数え方の定義が異なるので1個単位の直接の比較は難しい。ここまでが同一と考えれば Australaves (南鳥類) の基本形は頸椎数 15 個であろうか。現在の知識ではこれ以上は類縁系統を遡れない。
ヒロハシ科以外のスズメ目と系統の新しい大部分のタカ目は 14 個だがこれは偶然の一致なのか、それとも何か意味があるのだろうか。もっとも近代的な陸鳥 (Telluraves) の系統はだいたいこのような値なのでこの2グループだけが特別似ているわけではない。
このように見るとハチクマもおそらく 15 個ではないかと推測している。Jollie (1976, 1977) の骨盤より前方の脊柱の分類ではヨーロッパハチクマはミサゴ、(意外にも) オウギワシと同じグループになっている。
ハチクマの近縁種が必ずしも似ているわけではなく一番近いと考えられるカッコウハヤブサ類 (Aviceda 属) は 14 個になっている。
ハチクマ亜科ではカギハシトビ 14 個、ハイガシラトビ 13 個、ツバメトビ 14 個となっていて系統的にタカ類の中で頸椎数の多いグループというわけではなさそうである。
"クビナガハチクマ" はいったいどうなっているのか気になるところだが亜種レベルではおそらく調べた人もおらず知る限りで骨格標本もなく、今のところお手上げ状態である。猛禽類の (普通の数え方で) 頸椎数 16 個は知られていないので、もしハチクマよりも1個多ければおそらく新発見となるわけだが。
だたしこれは伝統的文献によるものなので Boehmer et al. (2019) の頸椎数に機械的に2を加えればハゲワシ類の一部は 16 個になる。
"The Unfeathered Bird", "Unnatural Selection" の著者である Katrina van Grouw に問い合わせたのもこの点で、"Unnatural Selection" (当時ネットで紹介されたサンプルページ) に鑑賞バトの品種のである Maltese は突然変異の結果頸椎が多く、それを品種として人為的に固定したものとの記述があり、
同書籍にはさらに shaker pigeon (Stargard Shaker, ドイツ名 Zitterhals) では頸椎が上部で2個多く、そのため頸椎のS字が通常より下方に移動して見えるとある (面白い画像や映像もあるのでドイツ名も含めて検索してみていただきたい)。
頸椎/胸椎の境界が変化して結果的に頸椎数が増えることはあるが [先述 Jollie (1976, 1977) 参照]、頸椎上部に骨が追加されるとは考えにくいように思えたためである。
結果的にはこちらがどうなっているのかは骨格標本だけを見てはおそらく判明せず、発生がどう進行して遺伝子発現がどうなっているのかなど調べないとわからないのだろう。Jollie (1976, 1977) では発生時に上腕の神経根が何番目の頸椎から始まるかに注目している。
ハト類は飼育されていて実験もやりやすいと思われるので誰かが興味を持って調べてくれることを期待しておくことにする。
飼育のハトでは突然変異のケースもあるようだが、カワラバトの遺伝子プール内に頸椎数を増やす機構が存在することを意味するのかも知れない。
もし Gamauf and Haring (2004) の解析が正しく、"クビナガハチクマ" とハチクマはミトコンドリア遺伝領域では同種と考えられるほど近い関係であるならば、ハチクマの遺伝子プールの範囲で頸椎数を増やせるか頸椎を長くできることを意味するのかも知れない (数が増えているのか頸椎が長くなっているのかはまだわからないが)。
ハチクマが嘴でハチの巣を捕る適応として首を伸ばせたのもその機能が役立っていたのかも知れない。
しかしながらフィリピンハチクマと "クビナガハチクマ" の生殖隔離があるように見えるのでこの解釈は正しくないかも知れない。
"クビナガハチクマ" のゲノムレベルの解析が行われれば、あるいはミトコンドリアはよく似ているが核ゲノムのどこかの調節部位は大きく異なっているなど見つかるかも知れない。これは相当高度な解析なので (サンプル入手の問題もあり) 簡単にはできないかも知れない。
興味深いことに Dement'ev and Gladkov (1951) は "クビナガハチクマ" をすべてのハチクマ類 (おそらくオナガハチクマ類も含む) の中で最も原始的としている。標本をもとにしているはずで首の長さは知らないはず。冠羽やはっきりした模様がない点、あるいは色彩に変化が少ない点を指しているのだろう。
この点で我々の渡りのハチクマが最も特殊化しているとしており、Gamauf and Haring (2004) の分子系統解析とはまったく逆になる。
ハチクマ類を用いた行動などの仮説の実験的検証はおそらく困難で、野外生態的にもほとんどわかっていない現状では (あまり見込みのなさそうなものも含めて) 仮説を提唱することも意義があると思われるので、要約に代えて "クビナガハチクマ" の首がこれほど長い理由として思いついた仮説をまとめておこう。
これらは必ずしも排他的ではない:
(仮説1): 食物にかかわる生態的適応。長い首で他のハチクマ類と異なる食物のニッチを開拓した。(反論) それほど首が長くないフィリピンハチクマが同所的に生活できているので長い首の必要性がわからない。
巣に運ぶ食物は通常のハチクマと同じように見える。
(再反論) それぞれの生態がよくわかっていないだけ。
(仮説2): assortive mating (性選択) で似た容貌を持つものをつがい相手に選ぶ結果、首の長さで好みが (?) 分かれた。フィリピンハチクマが同所的に生息するため違いを強調する方向に種分化が働いた? (反論) そんな好みなどあるだろうか? 分化する前に交雑で特徴が消滅しそうである。このメカニズム単独では多分無理で、何らかの生態的違いがあるのだろう。
(再反論) 鳥の好みなど我々にはわからないので...ニワシドリなど見てみよ。
(仮説3): ディスプレイが異なり種分化が進んだ。"クビナガハチクマ" のディスプレイは現状映像証拠が見つからないので通常のハチクマとは違うのかも。長い首を目立たせたディスプレイなどあるのかも。(反論) こちらもこのメカニズム単独では難しいだろう。フィリピンハチクマではハチクマと同様のディスプレイ飛行が知られているので同じようなものなのでは。
(仮説4): 外敵への防御。首が長く鋭い目つきは異様な雰囲気で巣での防衛に役立ち、形態的違いが食物以外でも生態的な違いをもたらしているかも。(反論) 営巣中の行動が知られていないので役に立っている証拠に乏しい。
(再反論) 間接的証拠で大いに想像を交えたものだが、渡りのハチクマは "クビナガハチクマ" の生息地を避けているのでは? 営巣中のものでなくても異様な雰囲気を感じ取っているかも。
(仮説5): 草原の鳥、ガン類や哺乳類などでは外敵に気づくのに長い首が役立つことはよく指摘される機能なので念のため挙げておこう。水鳥では採食行為の目的の方が大事で外敵に気づくのは二次的なものかも知れない。
ハチクマは草原の鳥でというわけでもないし、木の上から見渡す時はあまり関係ないかも知れない。
(仮説6): 木など周囲環境への擬態。(反論) サギならばわかるが猛禽類が捕食者対応でそのような擬態をするだろうか? 捕食する側として身を隠す効果とすると獲物はいったい何か?
(仮説7): サギへの擬態。自分は近づくと危ない鳥である。猛禽類なら知っているだろう。(反論) そこまでサギに似ていないし、嘴を見れば違うことはすぐわかるだろう。
(再反論) そこまでは似せきれなかったが一定の効果はあるのでは。
(仮説8): 実は "クビナガハチクマ" がハチクマ類の祖先系統に近く、最初はこんな形をしていたのだろう [Dement'ev and Gladkov (1951) 流儀]。
色彩の性的二形もほとんどないし冠羽もない。Gamauf and Haring (2004) の系統解析は正しくないのでは。
別系統とすればフィリピンハチクマやハチクマ他亜種との交雑が明瞭でないことが説明しやすい。
(反論) フィリピンが発祥の地とはさすがに考えにくい。大陸が発祥の地だろう。生殖隔離の証拠もはっきりしない。
(再反論) 生殖隔離は首の長さに明瞭な違いがあってはっきり区別できることに基づくが、実際には遺伝子を見ないとわからないだろう。
もとは大陸に分布していたのだが、後に進出したハチクマの系統が代替してフィリピンにのみ残っているのでは。現在使われる大陸の亜種分類も色彩をもとにしたもので妥当かどうかわからない。フィリピン以外でも "クビナガハチクマ" 系統のものが隔離分布しているかも知れないがほとんど調べられていないのでは。
フィリピンは現在は島だが海水面が下がっていた時期はほぼ陸続きで大陸の一部だったと言えないこともない。
Gamauf and Haring (2004) の系統解析とは合わないが、現在の大陸部ではなく、現在の島しょ部に相当する地域がハチクマの起源地域だったならば特異な渡り経路の進化も理解しやすいかも知れない。
系統関係は確実に "クビナガハチクマ" と言える個体の DNA をさらに調べないと結論できないだろう。
[謝辞: フィリピンのハチクマを調べるにあたって多くの方にお世話になった。
Richard Holdaway, Pieter Pelser は Holdaway への学位論文についての質問以来議論いただき、博物館へなどの問い合わせや標本などの調査を行っていただいた、
Trinket and Adrian Constantino, Neil Konrad Binayao, Steve and Marcia Kwiecinski, Peter Quakenbush, Christian Perez, Robert Hutchinson より画像などの情報をいただいた。
Alex Tiongco はフィリピンのハチクマ類の各種の違いの情報を提供いただいた (いずれも2017-2018年当時)。
Katrina van Grouw も相談に乗っていただいた。
Cristina R. Cinco (Records Committee Wild Bird Club of the Philippines) も観察者への問い合わせと Desmond Allen からの返事の資料を送っていただいた (2023年)]
***
フィリピンのハチクマについての初公開の情報は以上までとする。修正・補足があれば以下に記述する予定である。
皆さんにも考えていただきたいのだが、以下の鳥は何に見えるだろうか:
山階鳥類研究所の標本データベースに "ハチクマ" とされる "フィリッピン、ザンボアンガ" (原文のまま) の仮剥製標本の 画像 (1934年5月。採集者等: 中西悟堂。所有者だったかも知れない) が1つ公開されている。場所はミンダナオ島にあたる。
標本ラベルは Pernis apivorus japonicus KURODA とある。
[ヨーロッパハチクマとの関係・亜種] で紹介したように japonicus の喉に "w" 模様があるとの原記載とは合わない。
中西氏はあるいは日本の個体がフィリピンで越冬すると考えてこの学名を与えたのかも知れないが、当時の知見の範囲ではどのように日本の亜種と同じと判定できたのだろうか。
この個体は日本のハチクマと同亜種と考えられるだろうか。
尾の2本の帯 (尾の全長が見えているわけではないので定かではないが) は日本のハチクマと同亜種のオス成鳥のパターンに似ているように見えるが嘴の基部がまだ黄色いように見える。5月なので成鳥であれば越冬地にはもういないだろう。
下面の白さから最初見た時はフィリピンハチクマ (Pernis steerei) の淡色型の亜成鳥かと思ったのだが、尾の縞模様は違うように感じる (帯が3本あって3本目が見えていないだけかも知れないが)。
場所からはフィリピンハチクマ、日本のハチクマと同亜種、"クビナガハチクマ" のいずれの可能性もあり得るが調べた範囲では "クビナガハチクマ" で尾の帯がこのタイプのものはないように見える。
他の標本と比べると日本のハチクマに比べて尾が相対的に長いように思える。
識別対象種としてフィリピンクマタカも含まれるが、同様に淡色のもので尾の帯のパターンの似たものは見つけられなかった。足が見えれば違いは明らかなのだろうが、嘴の形はハチクマ類のように見える。
もしフィリピンハチクマであれば山階鳥類研究所の標本データベースに含まれていない種になる。
可能性は低そうな印象だが "クビナガハチクマ" ならば日本に標本が存在するのかも? - もしそうならば遺伝情報解析には有利なわけだが。
皆さんの識別眼を駆使し、写真記録なども見て考えてみていただきたい (ここまで 2024.3.14記述)。
追加 (仮説9) ハゲワシ類では長い首は放熱に役立っているという。これも生理的役割の可能性として考えられるが、羽毛に覆われているのでハゲワシ類ほどは有効でないかも知れない。ハチクマ類が翼を半開きにして放熱している姿は見られる。
タカ類で放熱の可能性のある例として、オーストラリアのオナガイヌワシや南アフリカのコシジロイヌワシは参考になるかも知れない。
いずれも首が長い記述がある [Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World"; オナガイヌワシの wikipedia 英語版では long, almost vulturine neck (ほとんどハゲワシのような首) とまで書かれている]。飛んでいる時はそこまで明らかでないが地上に降りている時などはイヌワシとの形態の違いがわかりやすい。
Nos rapaces (Les Aigles du Leman) に各種が並んでいて体型の違いがわかりやすい。
オナガイヌワシの研究者によれば首を伸ばして獲物の距離感を確かめるような行動は野外ではほとんど観察されないとのこと。
オナガイヌワシは顔に裸出部が目立ち、かつてはスカベンジャーの役割のために顔が裸出して首も長い解釈もあったが、wikipedia 英語版にあるように死肉を食べないコシジロイヌワシにも同様の特徴があるため、北方系統のイヌワシ類の高温環境への適応と考えられるとのこと。
オオハシやサイチョウ類の嘴もそうであるようにたとえ別の要因で発達したものでも二次的に適応的意義を持つことはあるだろう。
もっともこれらイヌワシ属の2種は首が長いとは言ってもそれほど極端ではなく "クビナガハチクマ" までは顕著ではない。桐原氏がかつて Birder 連載されていた記事 (2003) 17(9): 55 にあったアジサシ類の足の長さ比べぐらいに見ていただいたらよいだろう。
(仮説3, 8関連) "クビナガハチクマ" のペアの可能性のある写真 Oriental Honey-buzzard (Djop Tabaranza 2017)。飛びながら足を出している。ディスプレイ飛行の一部かも知れない [クマタカなどでも見られる疑似攻撃など。若尾 (2023) クマタカ生態図鑑 pp. 230-233 など] が撮影時状況はよくわからない。
左の個体が尾のバンドが太くてオスかも知れない。山階鳥類研究所の標本データベースのフィリピンの標本と尾のパターンはそれなりに似ているかも知れない。
日本のハチクマのオスでも尾のバンドの幅には個体差もあって個体による違いの範囲かも知れない。
系統的に早い分岐で首が長い例として#ハシボソカモメ (系統については #カモメの備考) も思い当たる。この種では首を伸ばして行進するディスプレイが知られており、採食以外にも役立っているように思える。"クビナガハチクマ" が他のハチクマよりもし先に分岐した系統ならばこの対比は興味深いわけだがどうだろうか。
クマタカでもディスプレイ飛行中に首を後ろに反らす行動も記録されているので、ハシボソカモメ同様 "クビナガハチクマ" でも誇示行動に使われているかも知れない。
関係があるかどうかはわからないが海ワシ類も他のタカ類より首が長く [例えばオオワシとイヌワシの飛翔型を比べると違いは明らか。Ferguson-Lees and Christie (2001) にもオジロワシに関する記載がある]、ディスプレイの一種としても使われる反り返って鳴く行動 (サンショクウミワシがよく知られていて誇示行動で白を目立たせているかも知れない) など長めの首に意義があるかも知れない。
そういえばコルリも誇示行動で白を目立たせるとか考えたりするが、多くの鳥が喉に目立つ模様を持つことやカモ類のディスプレイなど喉や首を誇示することは一般的に意味があるのかも。
(仮説4関連) "クビナガハチクマ" で役に立っている直接的証拠はないが、巣で捕食者の意欲をそぐことは大変重要である。
Caterpillar bird:
解説。
ハイイロモンキタイランチョウ Laniocera hypopyrra Cinereous Mourner で論文は Londono et al. (2015) Morphological and Behavioral Evidence of Batesian Mimicry in Nestlings of a Lowland Amazonian Bird。
猛禽類は防戦できるだろうから攻撃に晒される無防備な小鳥ほどのことはないだろうが、怖いあるいは気味悪い鳥に見せ、狙われて無駄に労力を使うのを防ぐ価値はあるだろう。
(仮説2関連だが機構が違うため分離して仮説10としておく) 猛禽類の首の長さの雌雄差について興味深い記述があった。赤 (1994) Birder 8(11): 40-41 ハヤブサ、オオタカとも個体差もあるかも知れないがメスの方が全体的に首が長く見えるとのこと。
「大型種ほど相対的に頭が小さいため。オオタカもハイタカより首が長いと言われるのと同じような理由」と先に記したが、相対的なみかけだけではなくあるいは性差があるのかも知れない (多分まったく調べられていないだろうが)。
ハヤブサ、オオタカとも逆性的サイズ二型が著明なグループで (#トビの備考の [猛禽類の逆性的サイズ二型])、雌雄で異なるサイズの獲物を捕るための適応などの解釈があるが、Schoenjahn et al. (2020) は広い分類群を対象に巣の防衛にかかわる能力を重視した説明を行っている。
メスの方が首が長くても巣の防衛には関係ないかも知れないが、首の長さを決める遺伝部位とたとえば防衛能力にかかわる身体的機能を決める遺伝部位が連鎖あるいは (例えば成長ホルモンの働きなども通じて) 共通している可能性があるかも知れない。人でも例えば一部のスポーツの能力と関連があることが "経験則" であろうが言及されることがある。
一部の鷹匠は首の長さによる (適性の?) 違いに気づいているようで、#イヌワシの備考 [亜種・中央アジアの鷹狩り歴史] のような呼び分けがあった。
ジョージアでタカ渡り途中の違法な猛禽類の捕獲 (鷹狩り用、あるいはペットとして) が行われていたが、ハイタカでは細身で首の長いタカが好まれる [van Maanen et al. (2001) Trapping and hunting of migratory raptors in western Georgia]
とのことで、狩りの能力と相関があるのかも知れない。
"クビナガハチクマ" の首の長さも例えば餌を捕る能力 (優良遺伝子) の「正直なシグナル」になっている可能性もあるかも知れない。(ここまで 2024.3.21 追記)
2024.3.21 追記分に修正を加えた。サイチョウ類の嘴が体温調節に役立っている研究は van de Van et al. (2016) などがあるがよく研究されているのはオオハシ類なので追記した。#ミサゴの備考の [ミサゴの体温調節] にも関連情報がある。
表面上は羽毛に覆われているとはいえ、空気の流れがあれば一定の放熱が期待できるので前述の "クビナガハチクマ" 写真も首を伸ばして夕涼みなどしているのかも知れない (かっこいいタカのイメージが一層損なわれるかも知れないが...)。水浴び後などは特に有効だろう。
よくご存じの通り恒温動物にとって脳のオーバーヒートを避けることは非常に重要である。「あくび」が脳を冷やす機能がある仮説がある: Massen et al. (2021) Brain size and neuron numbers drive differences in yawn duration across mammals and birds
で鳥類、哺乳類のあくびの時間の長さを公開映像などから調べている (過去研究なども多数引用されている)。
あくびには他の機能もあるので Why Do Birds Yawn: The Science Behind This Behavior (Shivam Desa, Bird Facts 2024) も面白い記事だろう。あくびついでに寄り道をしておくと、
Gallup (2022) The causes and consequences of yawning in animal groups
かつてあくびが伝染するのはヒトだけと思われていたが社会性のある動物で進化したと考えており、哺乳類ではそれなりの例があるとのこと。哺乳類以外はあまり調べられていないがセキセイインコでそれらしい行動が知られているとのこと。ワタリガラスでは観察されなかったとのこと。いろいろな動物で温度を上げるとあくびの頻度は上がるとのことで脳の冷却仮説を裏付けるとのこと。
ハチクマであくびが脳の冷却にそれほど役立っているのかはわからないが、首を伸ばしたり縮めたりして温度調節ができるならば確かに都合がよいだろう。
スポーツの能力との関連について出典を見つけることができた。他でも読んだことがあったかも知れないが、「くびは何のためにあるか」(山田宗睦編 風人社 1995) に「プロ野球選手の頸」(戸部良也) の章がありスカウトが投手を獲得する時は頭と頸を見る、とある (p. 154)。他にも俊足選手の特徴はジョージアのハイタカの好みの話にも似たところがある。
この本そのものは医学に関係した内容が多くて動物の話はあまり出てこないが、エリマキシギのことやエリマキトカゲが襟巻きを広げて体温調節を行うことへの言及がある (p. 140)。
なおこの本は扱うテーマの特性上 "首" と "頸" の漢字を使い分けているが、我々が使う場合は (誤解の心配のない場合は) 漢字では日常的にも圧倒的によく使われる "首" を使えばよいと思う (どちらの文字も読み方は同じなので)。医学でもわざわざ "頸" とは書かないと思う。
厳密に意識して使い分けたい場合は頭部、頸部の学術語があるのでそこで使い分ければよいだろう。英語 (に限らずヨーロッパ言語のおそらく多く) では学術語も日常語も neck なので問題は特に発生しない。頭頸部も英語では head and neck で特別な概念があるわけではない。中国語では頸には (月へん = にくづき に孛)子 の別名があり、ハチクマの巣の中継の時はこちらが使われていたのでより日常的な語なのだろう。
新規情報: フィリピンのパラワン島で 2024.3.27 のハチクマの記録。Napsan - Apurawan Road, Puerto Princesa PH-Palawan (Paul Fenwick, eBird 2024.4)。
我々の見慣れているハチクマに比べて首がやや長い印象を受ける。尾の太い縞は我々のオス成鳥と似ているが、太い縞の間に細い縞がほとんど見えない。
首から下面の縦縞模様は見られず philippensis ("クビナガハチクマ") の特徴とは合わない。喉にわずかに gorget が見えるようで、この点は orientalis に似ている点があるが (torquatus でも見られる)、ろう膜の色は成鳥で虹彩が黄色の点は合わない。
越冬中の orientalis ではないだろうと想像する。冠羽が少し見られる。あるいは亜種 palawanensis の淡色型であろうか。同定の議論対象として面白い種類だろう。palawanensis の首の長さは中間的なのだろうか。
同日に飛翔中の別個体の写真があるが、これは特に首が長く見えない (距離が遠くて細かいところがわからないが亜種は別か?)。
Mt. Polis, Ifugao (ルソン島北部) Oriental Honey-buzzard (Indomalayan) (Lars Mannzen 2024)。これは種識別も問題とされているようだが、そのうの膨らみのように見えるのはあるいはサギが首を曲げて飛んでいるようなもの?
Oriental Honey-buzzard (Sean Melendres 2024) に頭かきの動画がある (ルソン島)。
Crested Honey Buzzard - male (Yvonne Blake 2024) のマレーシアの頭かきの映像と比べると確かに首が長いことがわかる。
遺伝的距離の近さにもかかわらずフィリピンハチクマと "クビナガハチクマ" が同所的に繁殖個体群として生息して生殖隔離があるように見えるのには、あるいは "great speciators" (#メジロの備考 [Great Speciator] 参照) で考えられているようなものに似た遺伝的な隔離機構が存在するのかも知れない。
メジロ類同様に、遺伝的には極めて近いグループ内で、ほぼ完全に渡りを行う亜種と留鳥の亜種が存在する点も似ている (渡りを行う能力は十分ありそうなのに留鳥はあまり島を出ないように見える)。
クマタカ類は留鳥で海は渡りたくないだろうが、クマタカ系統でもハチクマ類に相当する種分化が起きておりこちらも同様の観点で見るのも興味深そう。フィリピンクマタカとピンスカークマタカはフィリピンで2種に分かれているので (しかもフィリピン南部ではカワリクマタカが同所的)、対応するフィリピンハチクマの2亜種ももしかしたら同じように別かも、の感もある。
メジロ類では "個性" に関係する遺伝子などとの関連が指摘されている。
同じメカニズムは多様な色彩表現型にも関係する可能性があり、全ゲノム解析で調べられば面白いだろう。
もしメジロ類同様のメカニズムが関与しているならば分岐年代だけで種か亜種かの判定を行えない可能性もあるだろう。ハチクマの全部の亜種がそれぞれ種に相当する (tweeddale morph は?) 可能性もあってもおかしくない。
そのつもりで Gamauf and Haring (2004) の分子系統樹を見てみると、ハチクマを少なくとも2グループに分けることは適切に思える (分岐年代 100-200 万年ぐらい?)。Gamauf and Haring (2004) がフィリピンハチクマを別種としたのはヨコジマハチクマと同種にすると単系統をなさないためだが、もう一歩踏み込んでもよい感じがする。
グループ1 (clade 5) は東南アジア留鳥の torquatus, ptilorhynchus, palawanensis でこれらは地理的にもまとまっている。
もしこれを1種とするならば Pernis ptilorhynchus はこちらのグループの名前となる。Pernis cristatus の学名が早いと認めるならば、これも地理的にはこのグループにふさわしい。
グループ2 (clade 4) は ruficollis, orientalis, philippensis で地理的にもやや分散している。
前述の通り philippensis はあまりにも似ていないので別種の可能性が高いと考えるが、我々の orientalis とインド・スリランカの ruficollis は共通点が多く、遺伝的な近さは納得できる。
Ceylon Bird Club, Birds of Sri Lanka, sri lankan birds, endemic birds によればスリランカで少数の渡りの orientalis が越冬するが ruficollis とほとんど区別できないとの記述がある。
長距離の渡りを行うか留鳥かが生態的な主な違い。orientalis の西部 (シベリア) 個体の越冬域は ruficollis の分布域と重複がある。
生殖隔離についてはわからないが、グループ2を別種とするならば ruficollis の方が記載が早いので Pernis ruficollis となりそう (philippensis は記載が遅いのでどちらにしても影響がない)。
このグループを別種にするならば Pernis orientalis を分けてもらった方が我々としては納得感がある。
従来の Pernis orientalis の概念 (Brazil 2009 など) はハチクマの中で長距離渡りをするものだけを別扱いとしたものだが、熱帯亜種間で生殖隔離機構があるとすれば別の観点から分ける意味が出てきそう。
いずれにしてもメジロ類の亜種レベル同様の詳しい遺伝情報研究が必要となるだろうが、ハチクマ熱帯亜種の移動分散能力や個体群の遺伝的構造などを調べるのは相当難しそう。
van Grouw の記述の "shaker pigeon では頸椎が上部で2個多く、そのため頸椎のS字が通常より下方に移動して見えるとある" との記述はあるいは Solounias (1999) The remarkable anatomy of the giraffe's neck (雑誌サイト)
の記述に倣っているのではないかと感じた。この論文ではキリンで C2-C6 の間に頸椎が一つ余分に挿入されていると述べている。「キリン解剖記」(郡司芽久 ナツメ社 2019) を参照した。Solounias (1999) の考えは少なくとも当時は受け入れられなかったようだが (挿入説はその後もおそらく否定的)、
Gunji and Endo (2016) Functional cervicothoracic boundary modified by anatomical shifts in the neck of giraffes
でキリンの第一胸椎 (T1) が機能的に頸椎の役割を果たしている研究は広く受け入れられることとなったとのこと (日本語解説はいろいろ読めるので参照いただきたい)。Hox5 または Hox6 の変異が関係しているのではとの考察が論文にある。
参考に探してみると Williams (2016) Giraffe Stature and Neck Elongation: Vigilance as an Evolutionary Mechanism
にキリンの首が長い理由の仮説がまとめられていた。Wilkinsons and Ruxton (2011) を修正したものとのことで (1) 高所の食物を食べる、(2) 性選択、(3) 体温調節 [cf. Mitchell et al. (2017) Body surface area and thermoregulation in giraffes でレビューされている]、(4) 気候変動、(5) 足の長さに伴って、(6) 地平線の監視 (horizon vigilance) を挙げている。
(2) はキリンのオス同士の争いに利用されることから注目を浴びていたが、性差が乏しいため根拠に乏しいとのこと。(3) は高くするより横に広げた方が有効ではなど。(6) は高いほど遠くがよく見えるので捕食者対策に有効との考え。ラクダやリャマは (1) に当てはまらないが開けたところに住む動物にとって首が長いことは有利で、ダチョウは (6) のよい例であるとのこと。
この論文では遠くまで見渡せることによって個体間の距離を大きくすることができてより広い範囲を安全に採食できて同種または他の草食動物との競争が避けられる可能性を考えている。
性選択は現在でも議論が続いているようで、Wang et al. (2022) Sexual selection promotes giraffoid head-neck evolution and ecological adaptation
は化石研究から (なお C4 植物が優勢になってサバンナが広がるまでこの属は現れなかったとのこと) オス同士の争いが進化の主要因と考えている。
ゲノム解析で違いがわかりそうに思えるが Agaba et al. (2016) Giraffe genome sequence reveals clues to its unique morphology and physiology
ではさまざまなものが関わっていて Gunji and Endo (2016) で考えられたほどは簡単ではなさそう。FGFRL1 (線維芽細胞増殖に関わる受容体) が他の哺乳類と違う点は何となく納得できる。
Liu et al. (2021) A towering genome: Experimentally validated adaptations to high blood pressure and extreme stature in the giraffe
ではマウスにキリン型の FGFRL1 を導入すると高血圧抵抗性を示したという。
高血圧でも大丈夫!? キリンがもつ「強心臓」の秘密 の日本語記事もある。
なお FGFRL1 はニワトリの軟骨で最初に見つかったものとのこと [Trueb et al. (2003) Characterization of FGFRL1, a novel fibroblast growth factor (FGF) receptor preferentially expressed in skeletal tissues]。その後他の脊椎動物にも相同のものが見つかったとのこと。
鳥でも同じような機能がありそうなので今後の注目点かも知れない。
日本のハチクマ (盛岡市動物公園 ZOOMO) でも首がどこまで伸びるか撮影された: (日頃の体重測定トレーニングの成果を発揮し初めて公開測定してくれたハチクマの"はっちゃん"です!)。
野生の写真ではフィリピンの方がずっと長く見えるが、この映像を見るとそこそこよい線を行っている感じも受ける。
また正面を見るために眼球を少し寄せているのか、虹彩の外側の「黒目」が少し見えている。
飼育員の方が片手にハチの巣らしいものを隠し持っておられるのも面白い。
インドのハチクマでもこの姿勢だと普段は首を S 字に曲げていることわかりやすい: Oriental Honey-buzzard (Muthirulan 2024.9.14)。少し姿勢を変えるだけでわからなくなる。飛行時もこの形が見えることがあり、そのうの膨らみと混同しないよう注意が必要。
"クビナガハチクマ" のディスプレイ飛行と思われる貴重な画像が紹介された (2024.7.17 追記)。大型でなかなか立派。
Oriental Honey-buzzard、Oriental Honey-buzzard、Oriental Honey-buzzard (Ravi Iyengar 2024.6.23)
撮影地 Jariel's Peak-Restaurant, Bgy. Magsaysay, Infanta, Quezon, Philippines
とありレストラン? 換羽も多少進んでおり、繁殖期半ばぐらいなのだろうか。
Oriental Honey-buzzard 同じくこちらは飛翔中。換羽が必要なほどに相当ボロボロになっている。瞳孔が非常に縮小しており炎天下の明るさではここまで小さくなるのか。首を下げて飛んでいるのもわかる。
THE ENDEMIC ORIENTAL HONEY-BUZZARD AT LMEP (Ferdie Llanes de AvesFlores 2024.10) とまった姿。目撃状況や同定などの詳しい解説あり。最初はフィリピンカンムリワシと考えたとのこと。
2019 年に初めて庭で出会った時は凍りついたとこと。これまで何度かニアミスをしてこの方にとって初めての撮影とのこと。ちょっとボロボロでやつれた感じがあるがこの写真を選んだとのこと (写真を見慣れているとむしろ "クビナガハチクマ" らしさがよく現れている感じがする)。
少し気になる画像。Philippine Honey Buzzard (Pernis steerei) (Kevin Manila 2024.12.14) 撮影地 Zamboanga (ミンダナオ島西端にあたる)。飛翔中。
Philippine Honey Buzzard (Pernis steerei) (Kevin Manila 2024.12.14) こちらはフィリピンハチクマ (ハチクマの亜種ではない) とされている。形態の違いがわかりやすい。繁殖中のようで葉のついた枝を運んでいる。成鳥2羽と若鳥1羽が記録されたとある。
とまっているのは暗色でフィリピンハチクマと違うようにも見えるが葉のついた枝を運んでいるのは淡色でこちらはフィリピンハチクマの記述と合っているように見える。暗色型も存在するのか?
なかなかしっかりした爪も見ていただける。
Oriental Honey-Buzzard or Crested Honey Buzzard (Pernis ptilorhynchus) (Loel Lamela 2024.12) これはもしかすると "クビナガハチクマ" の飛翔中真正面顔かも。
参考比較: インドのハチクマの飛翔中正面顔 Oriental Honey-Buzzard (Vinit Bajpai 2024.12.28) このように見るとタカらしい顔つきに見える。
Oriental Honey-buzzard (Bart De Schutter 2024.12.20) Ambulong Island, Occidental Mindoro 一見してそれとわかる "クビナガハチクマ" の飛翔。ミンドロ島から南に少し離れた島。
首に "出っ張り" が見え、他の写真と比較するとサギのように首を折り曲げていることがわかる。
日本のハチクマを見慣れているとびっくりするような飛翔形だが、比較してみると羽毛に隠れてわからないだけで日本のハチクマ (おそらく他の種類も) も折り曲げているよう。飛び立ちの直後の写真などを比べるとわかることがある。"クビナガハチクマ" は首が長い分目立つよう。
Oriental Honey-buzzard 同じ個体の写真。遠目で見ると気づきにくいがこの写真でも折り曲げている部分がわかる。
Oriental Honey-buzzard (Mathieu Soetens 2024.12.21) Northern Mindanao, Bukidnon, Philippines
これも識別上興味深い。のどの模様など日本と同じ渡りの亜種に似て見えるが翼が短く形態的には留鳥のように見える。しかもこの時期に初列風切の換羽を行っているので、渡りの亜種の越冬中とは解釈しにくく思える。しかしフィリピンの繁殖種・亜種に似たものがいない (首が長く見えず、下面の模様も異なるのでおそらく "クビナガハチクマ" ではない)。
同じ場所で撮影された個体: Oriental Honey-buzzard (Mathieu Soetens 2024.12.19) 色彩が異なるので別個体と思われるがこれも初列風切の換羽中。斜め向きで確実ではないがこれも翼が短く感じる。
一見すると日本と同じ亜種のメスに見えるが換羽時期が不思議であり、また衛星追跡で知られている越冬域からやや離れている。何者?
これまた気になる写真: Oriental Honey-buzzard (Norman Marigza 2025.3.3)。ルソン島。越冬時期で渡りの亜種の可能性もあるがこの時期に次列風切の換羽中。渡りの亜種であればメスか若鳥タイプの尾の模様に見えるが虹彩は暗色に見える。まだ完全に成熟していない渡りの亜種の越冬期の画像なのだろうか。
次列風切の膨らみ方は若鳥タイプの方だろうか。日本からの衛星追跡ではルソン島まで北上したものはないはずなので、渡りの亜種なのか興味あるところ。
頭かきの際の首の長さに関連してインドの個体の頭かきの写真もあった: Oriental Honey-buzzard (Atul Dhamankar 2025)。
フィリピンの個体はやはり首がだいぶ長く見える。このインドの写真では第 I 趾の爪の曲がりがよく見えるので紹介させていただいた。全体的な羽毛の様子からは水浴び後だろうか。
比較参考画像。マレーシアでおそらく越冬中の渡りのハチクマのオス (日本と同じ亜種)。首を伸ばしているところ, 縮めているところ (Joseph Morlan 2025)。
フィリピンのものはやはりだいぶ長い。首を縮めている時に "そのう" のような部分の羽毛が盛り上がって見えるのは頚椎を S 字型に曲げたものが突出して見えるため。日本の個体でも遠目で見るとそのうが膨らんでいるようにも見えるので注意。
Oriental Honey-buzzard (Jeorge Lacson 2025.4.19) フィリピンの個体の画像。
ノガンモドキの頸椎についての補足情報: Buchmann and Rodrigues (2025) Flesh and bone: The musculature and cervical movements of pterosaurs
にノガンモドキの計測値が出ていた。やはり 15 個らしい。そもそも大きな鳥 (wikipedia では全長 75-90 cm とある) だが計測値を見ると頸椎のみ足し合わせて 28.5 cm あり、確かにかつてノガン類に近いと考えられた、あるいはかつてはツル目に入れられていた (ノガン類もかつてツル目に入っていた) のもおかしくない感じ。かつてのツル目の頸椎数の記述などを見る場合はこれらの種類も混ざっているので注意が必要。
フィリピンで巣材運び中の画像: Oriental Honey-buzzard (Scott Watson 2025.3.18 撮影)。一見してわかる形態。
久しぶりに見たとまり画像 Oriental Honey-buzzard (Jomar Guzman 2025.5.2 撮影)。遠目に見ると何かと思ってしまう。
少し気になる画像 Oriental Honey-buzzard (Roberto Yniguez 2025.6.2 撮影)。
場所はフィリピンのルソン島で、一般的なハチクマより多少首が長く思える。しかし下面は暗色の横縞で典型的な "クビナガハチクマ" とは異なる。翼はあまり長く見えず換羽も行っていて留鳥個体か。渡り亜種の滞在中の画像ではない感じがする。
フィリピンハチクマの典型的な模様ともまた違い、記述の乏しいフィリピンハチクマの暗色型、あるいは雑種の可能性もあるかも知れない。
これまた気になる画像 Oriental Honey-buzzard (Jeremy Ang 2025.6.22 撮影)。
ハチの巣らしきものを運んでいて繁殖個体と思われるが、形態・色彩的に "クビナガハチクマ" に見えない。フィリピンハチクマの暗色型の可能性も考えられるがこれほど暗色の個体が存在するのだろうか。画像は1枚で獲物で尾の模様が隠れて見えない。
Owls (BirdForum 2025.1) の方法で自分でも cyt b を用いた系統樹を描いてみた (GenBank から Pernis celebensis を検索してその1つに Run BLAST を適用。全ゲノムデータのあるものも自動的に探してくれた)。
問題となる地域の亜種については Gamauf and Harring (2004) の時代から情報が増えているわけではないが実際にやってみると Pernis celebensis と Pernis steerei がきれいに分離されてなるほどと感じた (紹介する系統樹の2つめを参照)。この2種はかなり異なる種類だった。
簡易系統樹の作り方 以下の簡易系統樹は AY424379.1 の配列に Run BLAST を行ったもの。こちらは Gamauf and Haring (2004) の結果が再現されている。
作り方はこの配列のページからメニューで Run BLAST → BLAST ボタンを押して実行 → 結果が表示されたら Distance tree of results をクリック → 系統樹が表示されたらその上で右ボタンクリックで Expand all を選択 → メニューから [TXT] ボタンを選んでサンプル情報の表示 → 必要に応じて画像スクロール (2025.2 現在のサービスに基づく)。
海外の利用時間帯を考えて混まない時間帯 (日本時間だと昼間の早いうちぐらい) に利用すると反応が早いので参考までに。
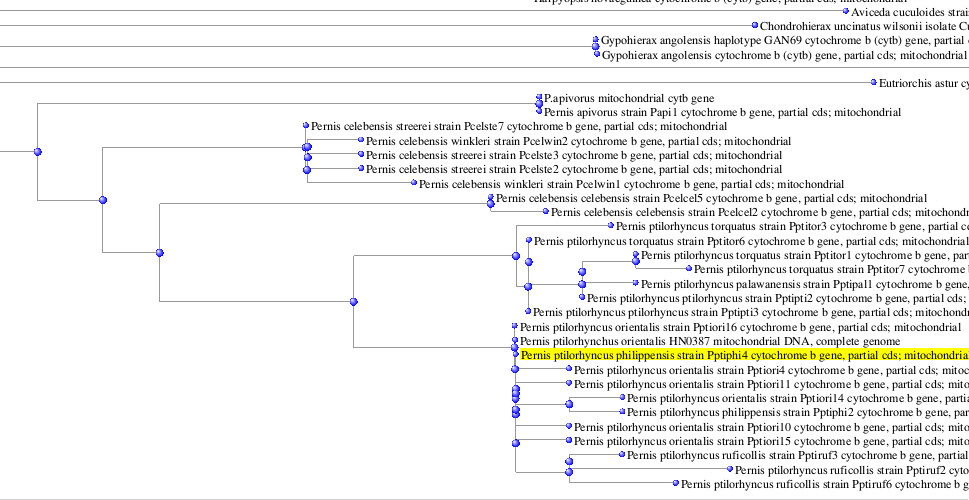 次は AY424395.1 を出発点としたもの。この場合は多少の系統樹形の相違も生じ、ハチクマとヨーロッパハチクマのどちらが祖先型かはこのデータからは判断できないことになった。出発点によって結果が異なる理由は BLAST がまず類縁配列をデータベースから探すため、この段階で出発点次第で母集団の集合が異なるため。
少し違う種を使って複数の出発点を試してみるとよい。本文の解説はこちらの系統樹をもとにした。
次は AY424395.1 を出発点としたもの。この場合は多少の系統樹形の相違も生じ、ハチクマとヨーロッパハチクマのどちらが祖先型かはこのデータからは判断できないことになった。出発点によって結果が異なる理由は BLAST がまず類縁配列をデータベースから探すため、この段階で出発点次第で母集団の集合が異なるため。
少し違う種を使って複数の出発点を試してみるとよい。本文の解説はこちらの系統樹をもとにした。
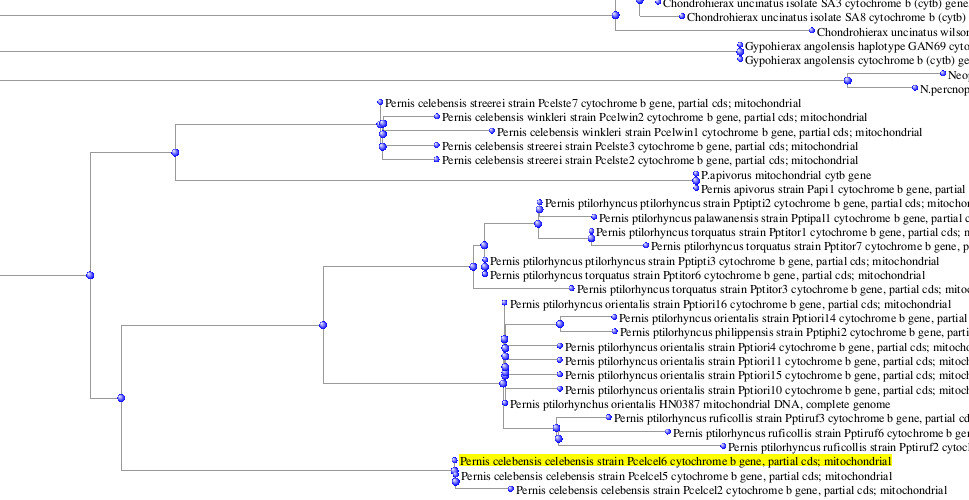
ハチクマ内部の2系統 (orientalis グループと ptilorhynchus グループ) も前述のようにかなり分離されており、Gyps 属内の距離ぐらいの違いはあるので確かに別種扱いも可能に見える。実際に作ってみると Gamauf and Harring (2004) の論文系統樹を見るよりもよくわかる。
なぜか philippensis が orientalis グループに内包される。この地域の亜種のデータはもう少し欲しいところ。
ただしこのようなグループで2系統を種に分けると orientalis グループの中では ruficollis の記載の方が早いので日本のハチクマの種学名が Pernis ruficollis となってしまう (前出の議論と同じ)。Pernis orientalis の種学名とするためには近い分岐でも意図的に分離するなど少し無理をする必要があり、この遺伝情報からこの種学名採用は少し難しそうに見える。
Anita Gamauf (1962-2018)
ハチクマ類の分子系統の研究を行った Anita Gamauf (オーストリア) は猛禽類の専門家でヨーロッパハチクマ、オオタカ、ヨーロッパノスリの種間関係が学位論文、1993-1995 年にフィリピンの猛禽類の研究に従事、各地を遠征してヒメコウライウグイス Oriolus isabellae Isabela Oriole (IUCN CR 種) を 1993 年に再発見したとのこと。
ハチクマ類は好みだったようで 2009 年に始まった "BORN TO BE WILD" プロジェクト (Auf der Spur von Sakerfalke und Wespenbussard) でワキスジハヤブサとヨーロッパハチクマの衛星追跡を行ったとのこと。
アジアも含めたハチクマ類の系統解析を行ったのも、地元で馴染みのヨーロッパハチクマがどこからやってきたのか知りたかったのだろう。フィリピンでの観察や研究に従事したのもあるいは祖先の候補地の一つと考えたためかも。フィールドワークを機にフィリピンの観察者には著名な研究者とのこと。
Gamauf and Haring (2004) の分子系統研究で逆の結果となり予想が外れたかも知れない。
我々は日本のハチクマを見慣れているのでフィリピンの個体の特殊性がすぐわかるが、まだ識別点も明確でなかった 1990 年代にヨーロッパハチクマを見慣れた目にはフィリピンのハチクマは単にヨーロッパハチクマとアジアのハチクマの違いとして映ったのかも知れない。
自身が 2004 年の分子系統研究で独立種としたフィリピンハチクマ Pernis steerei Philippine Honey Buzzard には亜種 winkleri Gamauf & Preleuthner, 1998 の記載を行っている (記載)。
標本をもとに計測値などから分離したもので、標本の中にもフィリピンクマタカおよびピンスカークマタカ (この当時は亜種扱い) との誤同定はしばしばあったとのこと。
Dickinson et al. (1989) Notes on the birds collected in the Philippines during the Steere Expedition of 1887/1888 が読めるので紹介しておく。Steere (1890) によってフィリピンクマタカと判断されていた標本をなんと Sclater (1919) がフィリピンハチクマ (当時はヨコジマハチクマの亜種) のタイプ標本として記載していたとのこと。Steere (1890) の間違いだろうと判断されている。
専門家にとってすら紛らわしい (さらに学名も英名も紛らわしい)。
Gamauf and Preleuthner (1998) ではこれらの類似性が擬態による可能性については別所で議論の予定とある (どこかに論文があるのだろうか?)。
これぐらい調べられていればフィリピンのハチクマ類の中で首の長さに違いがあることが気づかれそうなものだが、仮剥製 (skins) になってしまうと判断できなくなってしまったのかも。
ピンスカークマタカの記載者の一人で、クマタカ類における貢献は#クマタカの方に記した。
Anita Gamauf がすでに故人であることを知って wikipedia ドイツ語版より調べた。フィリピンのハチクマの特異性はここに示すほどご存じだっただろうか。自分とは別の出発点から未検証の類似のアイデアに到達されていた可能性もあり、研究の着想なども含めて存命中に情報交換してみることができればよかったのだろうが。
しかし 20 年前の限られた分子系統樹である。改めてゲノムレベルで調べる価値は十分あるだろう。
Anita Gamauf 1962 - 2018 (Winkler et al. 2019 の追悼文)。
Anita Gamauf (1962-2018) (Hans-Martin Berg, BirdLife Oesttereich 2018 の追悼文)。
[よく誤認されるハチクマ若鳥淡色型]
ハチクマ若鳥淡色型は渡り中に飛んでいる時はよいが、とまっている時や保護された時などは専門家ですらしばしば識別を誤らせる。
韓国の参考映像。
救護された場合、図鑑を見ても似た種類が見つからなくて別種にされてしまうこともしばしばあるそうである。
次はロシア沿海地方の話 (英語記事): East of Siberia: An Osprey, Until It Wasn't (Wildlife Conservation Society 2017)。
専門家が判定したのにもかかわらず、ミサゴと間違われて何週間も魚を与えられていたようである (ただし若鳥淡色型の容貌を知らずに調べるといかにも間違いそうである。さらにヨーロッパハチクマではさらに真っ白のがいるそうである)。
セルゲイの腕におとなしくとまっていたとのこと。
正体が判明してからハチの巣を買ってきて与えると大喜びで食べた。
食べ終わるとまるで犬のようにもっと欲しいとこちらを見つめたとのこと。
ヨーロッパハチクマでも同様で、ペテルブルグで救助されたものが最初はミサゴとされていた。あまりに白いので間違った、とのこと ペテルブルグで保護されたミサゴはハチクマと判明。専門家が誤同定 (2019)。
Oriental Honey-buzzard (Paul Anderson 2024.12.1) タイで撮影された非常に淡色の若鳥。Oriental Honey-buzzard とまっている写真。
[ヨーロッパ諸言語のヨーロッパハチクマの名称と英語語源]
久野 (2006) Birder 20(10): 20 では、英語で honey buzzard と呼ばれることから、ヨーロッパハチクマもヨーロッパの養蜂家にとってお馴染みと推測しているが、ヨーロッパハチクマは養蜂場を訪れないとの記述もある。
(旧 URL なので直接のリンクは張らない https://twitter.com/WMGVs/status/1425025233401098242) ヨーロッパハチクマはあまりミツバチを狙わない。ヨーロッパではヨーロッパハチクマが集団でハチの巣を襲う報告はないとのこと。越冬地でどうしているのかはわからないが、とも書いてある。
むしろ庭にやってきて (日本の庭の広さを想像してはいけない...) ハチの巣を掘ることはしばしば目撃されている、あるいは庭で他の鳥が騒いでいて見に行ってみると大きな鳥が飛び立ち、ハチの巣があったので駆除業者を呼んだなどの話を身近に聞いたことがある。
また多くのヨーロッパ言語ではちみつ honey の方ではなく、直接にハチを意味する名称が使われている。ドイツ語 Wespenbussard (Wespen ハチ = 英語 wasp, スズメバチ科 Vespidae に対応; ミツバチはドイツ語で Honigbiene)、
オランダ語 wespendief (dief は英語 thief と同じで盗人。面白いことに -dief の付くオランダの他の猛禽は kiekendief のみ。チュウヒ類を指し kieken はひよこの意味)、
ハンガリー語 darazsolyv (ドイツ語同様とのこと)、
フランス語 bondree apivore (後半は学名の種小名と同じ意味)。
フランス語の bondree の語源はよくわかっておらず、bondree によれば 1534 年にすでに用例があり、色彩の似たツグミ類を指していたブルトン (Breton) 語 bondrask 由来説があるとのこと。
スウェーデン語 bivrak (bi- は英語 bee と同語源)、
デンマーク語 hvepsevage (hveps ハチ = 英語 wasp と同語源)、
イタリア語 Falco pecchiaiolo (pecchia ハチ ではあるが現在通常にハチの意味で使われる apis から派生した単語のよう)、
チェコ語 vcelojed lesni (vcela ハチ類全般)、
ロシア語 osoed [osa スズメバチ; ロシア語ではミツバチは pchela と別単語になる。ハチクマにも pcheloed の別名があるが、これは通常ハチクイ類を指す (英語の bee-eater も同じ)。
「幼虫を食べる」の意味の lichinkoed はサンショウクイ類を指す。Cuckoo Shrikes の食性に合わせた名前だろう #アサクラサンショウクイの備考参照]、
ウクライナ、ブルガリア語も同様。
ポーランド語は trzmielojad (trzmiel マルハナバチ属、ミツバチ科ミツバチ亜科)。
ミツバチを直接意味するものは少なく、ハチ類の総称か、ロシア語やドイツ語のように積極的にミツバチではないハチを指すものも多い。
スペイン語 abejero は養蜂家を指すようで例外的だが、ヨーロッパハチクマの wikipedia スペイン語 の見出し語は学名になっていて、そもそもあまり知られていない種類かも知れない (渡り経路ではあるが繁殖地は国内のごく一部)。
英国では比較的珍しい種類でヨーロッパハチクマの本家は大陸だろうことも考えると「英語の名称はハチミツノスリである」とかあまり強調しない方が良さそうである。
English and scientific names of the Honey-buzzard
Brian Groombridge (2011) に英語語源や別名の考察があり、"honey buzzard" は
Willughby (Willoughby) が Buteo apivorus sive vespivorus (ミツバチまたはスズメバチ科のハチを食べるノスリ)
の名前で 1676 年の Ornithologiae で英名とともに用いたもの。英国初記録とのこと。巣での行動を観察した結果で養蜂場とは関係なかった。
当時の記述は生態的には正しかったが、付けられた英名はふさわしくなかった。スズメバチ科のハチはハチミツ (honey) は作らない。
Gilbert White (有名な "The Natural History of Selborne" 1789。邦訳され「セルボーンの博物誌」 講談社学術文庫 1992) もハチミツ目的ではなく幼虫であることを正しく解釈していたが、Willughby and Ray の英名 "honey buzzard" も的確としていた。White 自身は後にハチミツ目的でないことはわかっていたのになぜ間違えてこのように記述してしまったのかと記しているとのこと。
通称が "honey buzzard" だったために White も引きずられてしまったのかも知れないとのこと。
Willughby and Ray の用いた "学名" は Linnaeus 以前だったため Linnaeus は前半の apivorus はそのまま拝借して Falco apivorus の学名に整理したとのこと。Willughby and Ray の "学名" 後半の vespivorus の方が結果的にはより適切であったことになる。
"Capped Buzzard" そして "Bee Hawk" (Macgillivray 1836。この英名は "honey buzzard" よりも一層不正確だった), "Honey-Kites" または "Perns" (Sharpe 1896) などの名称も提唱されたことがあるがまた "honey" に戻ってしまった。"Honey-buzzard" は発音もしやすく (バーダーの間では) 省略しても意味が通じやすいので他の名前は定着しなかった模様。
"honey" の発音のしやすさや音の親しみやすさは英語特有の部分もあって、英語なので定着した名前と言えるかも知れない。
"pern" は現在の辞書でもヨーロッパハチクマの別名とされるが、Cuvier (1817) の学名が由来とのこと (wiktionary)。OED でも最初の用例が 1840 年 Blyth et al., Cuvier's Animal Kingdom で学名から作られた英語であることがわかる。OED では pernis のギリシャ語語源に pterna かかと + id の可能性を挙げている ([属名の考証] 参考)。
(ヨーロッパ)ハチクマ観察者は冬場は余裕ができるので文献に当たったりするのは大変よく理解できる。
もっとも、養蜂場らしいところにとまっている、あるいはミツバチらしいハチが周囲を飛んでいるヨーロッパハチクマの写真がないわけでもない。
写真の例 Trzmielojad。
ポーランドの写真なので、ポーランド語の名称も考慮するとポーランドでは養蜂場を訪れるのかも知れない。
"honey buzzard" のような誤解はハチクマに限った話ではなく、セイヨウミツバチ Apis mellifera の種小名 (蜂蜜を運ぶ) にも同様の誤解があり、Apis mellifica (蜂蜜を作るハチ) とは一度は訂正された経緯がある (wikipedia 日本語版より知った)。ラーテルの属名の Mellivora (蜂蜜を食べる) は蜂蜜も食べるらしいので問題はなかった。
このように見ると人は自身の食物を基本に物事を考え過ぎているようにも見える。
#オオタカの備考にも記したが、Linnaeus (1746) は(ヨーロッパ)ハチクマとオオタカを混同していた。66.を参照。
まだ学名が有効となる前の時代だが、過去に使われた Buteo apivorus s. vespivorus と Accipiter palumbarius (後にオオタカの学名となり、その後シノニムとなった) を同じ項目に入れていた。学名を見れば特色ある "ハチを食べる" と "モリバト (を食べる)" では全然違うので気づきそうなものだが (?)。これは当時のスウェーデン語で区別されず Slaghok と呼ばれていたことに起因する模様。Willughby and Ray の記述をもっと気に留めていれば、という場面。
名称の歴史にも学名成立にも関連する話で、この時点では Linnaeus はオオタカのことをよく知らなかった。続きはオオタカと#ハヤブサの備考参照。
参考までにスラブ諸語の名称について少し追記しておく。-ed, -yad, -jad などはすべて共通の語源で、「食べる」を意味する。英語は eat、ドイツ語は essen なのでどことなく似ている点は把握しやすいと思う。
この後の種類でタカ類のロシア語名をいくつか紹介するが、この語尾を把握おいていただくとよい。-yatnik のように -nik を付けるのは「行為者」をさらに積極的に表現しているものである (例えば okhota 狩 okhotnik 猟師; オホーツク海も同じ語源で我々はロシア語の単語を実は意外に知っている)。
日本では馴染みのない種類であるが、ヘビを食べる種類にチュウヒワシ Circaetus gallicus 英名 Short-toed Snake-Eagle があり、ヘビはロシア語で zmeya なので普通に造語すると zmeeed になる。
これは間違った名称でなく実際にこのようにも呼ばれるが、同じ母音が3つ並ぶと発音しにくいためか (ロシア語の e はヤ行音で、ィエと読む。英語のようにまとめて伸ばして発音したりしない)、一般に使われる名称は zmeeyad となっている。
英語でも別の単語を並べた結果たまたま同じ文字が3つ並ぶことがないわけではないが、このように正規の造語方法で3文字並ぶ単語はロシア語でも非常に珍しいようである。もう一つ別の単語を思いつく人があれば相当の博識だろうと想像する (最初見た時は感嘆語と思ってしまった)。
脱線ついでに豆知識を紹介しておこう。stervyatnik というロシア語名もある。-yatnik はもうおわかりであろう。前半な何か難しそうだが実はこれはドイツ語の sterben (死ぬ) が由来。ドイツ語のこの単語を知っている人であればハゲワシのことかと納得できると思う。
ややこしいのはこう呼ばれるのはハゲワシ類すべてではなく、エジプトハゲワシのことである。日本にもやってくるクロハゲワシは grif と呼ばれて豆知識が直接役に立たないは少し残念なところであるが、系統分類のところで述べたように旧世界のハゲワシ類は複数の系統からなり、もう一つの Gyps 属 (#クロハゲワシの備考参照) は sip と呼ばれ系統の違いごとに別名になっていることがわかる。
[ハチクマの性と年齢の識別]
[ハチクマとヨーロッパハチクマの識別] の話題の前に振り返っておくことにする。
ハチクマの雌雄と幼鳥の識別 (川田隆)「野鳥」1988 年 10 月号 (No. 506) pp. 4-5] がおそらく日本で初めて公表された確かな野外識別方法と思われる (この件や当時の状況については若杉稔氏のお世話になった)。
1983 年から7つがいと5巣の観察によるもので、餌渡し、夜間の抱雛の担当なども根拠に含まれている。
なお「野鳥」の同じ号 (pp. 20-21) に大丸秀士氏による広島 (市) の渡りのハチクマ自慢がある。「止まっている姿がタカらしくなくやさしいだの、飛んでいる姿が首が長くてどうもだのとは言わせない。蚊のごとくちっぽけなサシバでなく、...」とあった。当時からそのような印象も持たれていたらしく面白い。
亜種 japonicus Kuroda を記載した前記論文でも飼育実験まで行われているものの虹彩や尾の模様については注意していなかったのか、尾の性差は現代の記述とあまり整合してない。バンドの太さよりも本数を気にしていた可能性もあるだろう。Dement'ev and Gladkov (1951) ではオス成鳥の尾の帯は「3ではなく2本」と記載がある。
もしかすると japonicus Kuroda の記載を訂正する意図があったのかも知れない。
内田 (1871) 誤られたるハチクマ Pernis apivorus
の記事ではサシバをハチクマと誤って呼ばれていた話とともに、第2図に日光産のハチクマ幼鳥とされる写真が出ているが、これは明らかにオス成鳥であろう。
ハチクマの雌雄と幼鳥の識別は早い時期からかなり混乱があったものと想像できる
[なおこの文献の引用の中に八雕 (雕はワシを表す漢字) が出ていて、背に八の模様が出るので八雕の話が紹介されている。ハチクマはクマタカして流通していたとか。(ハチクマ) とふりがながあって鷲で終わる名称の漢字は現在検索するとオオワシの意味が出てくる。(クマタカ) とふりがながあるのは中国語でワシのこと。クマタカの中で老いて大きくて黒いものをハチクマと呼ぶと書かれていた]。
ハチクマの和名の検討 多少割り込み的になるが、この文献を見ていると "ハチクマ" の名称は複数起源があって:
・クマタカの中で老いて黒く最も大きいもの (そもそもクマタカとハチクマが区別ができていなかった可能性もあり、ここで示される "クマタカ" も現代と同じものかどうか不明)
・満州より蝦夷の地方に渡来る。大型種。まだ (鷹狩りに?) 使えていない。これは冬鳥のワシを指すのでは?
・八雕はワシ類で黒く、尾に白黒の模様がある。背に八の字があるので八雕。しかし蜂雕の表記もあって微妙に混乱がある模様
・観文禽譜 (1794) では「...努て蜂を養ふよし...蜂クマの羽には八の字の様なる文ありと云八字の文ある故ハチクマと云に非ず」と八の字由来説を否定している
当時は野生のワシ・タカの成長などはよくわかっておらず、成長するとより大きくなるなどの誤解もあったかも知れない。例えば大きいのは別種ではなく年老いた鳥であると考える説も可能である。また当時は種の概念は現在と異なっていて外見上見分けのできるものを "種類" としてそれぞれ名前を与えていたものと想像できる (ウソやドバトなどいくつも例がある)。
観文禽譜は語源に複数説がある中でおそらくやや強引に結論を出したものではないかと思う。
内田氏はこれらに当てはまる種として Pernis apivorus (当時は同種) を考えられたが、どの記述も同じものを指すと考えられたため apivorus = ハチの巣を襲って食べると観文禽譜の「蜂を養ふよし」(内田氏も意味が今ひとつ明瞭でないとしている。蜂が巣を作って共生していると読むこともできるので食物としているか自明でない) にうまく対応すると結論付けられたのだろう。
かつては今のようにハチクマの多様な色彩型が把握されておらずいろいろな混乱があった (今でも?) だろうことは十分予想できる。暗色型をイヌワシなどのワシと区別できていなかった可能性も考えられる。イヌワシをハチクマと呼んだならば大型の "クマタカ" であったり満州より渡るなどの記述があっても不思議でない。
「帰らぬオオワシ: 猟師七兵衛の物語」(遠藤公男 偕成社 1975) の 2002 年再版にて著者追記部分によれば、古くは (と言っても 1970 年代でもまだ通じていた) オジロワシの若鳥とイヌワシの若鳥は混同されていたらしい。これらが古い文献記述をもとにかつては "ハチクマ" と呼ばれていても不思議でない。
内田氏による確実な識別点は標本となった場合の顔の羽毛の特徴。
内田氏のこの文献によれば、誤解の発端は Blakiston の標本ではないかと推定している。Seebohm (1890) "The birds of the Japanese Empire" では p. 197 に Captain Blakiston has recorded in the 'Chrysanthemum' the capture of a fine male (without crest) by Mr. Jouy at Chuisenji, in Tokio, during August とある。
内田氏の時代の札幌博物館にある Blakiston 採集の2例は函館と千島? (Snow 氏採集) とあるのでこれとも異なる (?)。
事の発端は松平氏の標本に大型の見慣れないタカがあったので標本を調べると現在呼ぶところのハチクマだったが、日本の札幌博物館にある2標本とはまったく別物とわかったことに始まる。
過去のハチクマの名前は誤った種に付けられたもので誤用ではないかと文献検討を行い、「蜂を養ふよし」の記述があるので過去の名称は誤用とも言えない。ここで正しく Pernis apivorus = ハチクマ と呼んでよい、と判定したものと言える。
apivorus は "ハチの巣を襲って食べる習性に起因して附せられた" (外国では古くから知られて居るとあるので、日本ではまだ習性が知られていなかったことが読み取れる) とあるが、apivorus の種小名は実は不適切で ([ヨーロッパ諸言語のヨーロッパハチクマの名称と英語語源] 参照) Willughby and Ray が誤解して用いたものを Linnaeus がそのまま用いたことに由来している。"ハチの巣を襲って食べる" は学名ではなく別の出典が由来と考えられる。
ということで、"ハチクマ" の和名は古くは何を指していたかは必ずしも明確でなく、標本ですら誤って付けられていたが、外国の記述と日本の記述を組み合わせて蜂を由来として "ハチクマ" を Pernis apivorus に使ってよいのではないだろうかとここで決められたとも言える。つまり主に「観文禽譜」の記述をもとに内田清之助氏が再定義したと言えることになる (挙げられている他の文献の記載は必ずしも現代のハチクマと整合しないかも知れない)。
日本では (少なくとも鳥学者には) 習性が知られていなかったので、習性と蜂を結びつけたのは海外の記述と学名が由来。たまたま (?) 当時はハチクマとヨーロッパハチクマが同種だったのでヨーロッパでの習性を参考にして名付けて構わなかったが、ハチクマはサシバの異名とも解釈可能だったわけで、ここで学名とヨーロッパ (現在のヨーロッパハチクマ) での習性と合わせて決められたものと考えてよさそう。
これ以前にハチクマ Pernis apivorus の対応関係が与えられていたはずなので、習性を必ずしも知らないにもかかわらず学名との整合性から最もそれらしい既存の名前が選ばれたものだったかも知れない。
内田氏のように明瞭な考察が残されているわけではないので、他の種の状況から推定すると "Fauna Japonica" では日本で採集され、本文の記載のみで図版のない Pernis apivorus はいったい何だろうかと同定を試み (図版がないので想像に頼る部分が大きい)、Pernis apivorus の学名と他の書物の記述をもとに既存の名前の中から "ハチクマ" を選んだものではないだろうか。
しかも当時はハチクマとヨーロッパハチクマは区別されておらず、他の書物のヨーロッパハチクマの記述や計測値に頼るしかなかった。ヨーロッパハチクマの方が小型なのでより小型のサシバと混同されやすかった可能性があるかも知れない。計測値の大きいのは小型のクマタカだと考えられたなど (内田氏の時代でもまだ分離されておらず、巷では翼開長などヨーロッパハチクマの計測値が長年使われてきたらしい状況をみても、サイズが合わないことは国内ではあまり注目されていなかった模様)。
実際には "ハチクマ" は Pernis apivorus を指して使われていたとは限らず、実際にも間違って使われていたが、内田氏は別の和名を新しく考えるよりは過去に間違って使われたものであってもハチクマの名前を使い続けよう、としたものだろう。
"ハチクマ" の名称の由来は複数あっても構わず (八の字の出る大型の黒いタカ)、"ハチ" を蜂の意味に限定的に結びつけたのは鳥学者ということになる。"クマ" の部分は大型のタカを全般にクマタカと称していたのが由来と解釈することになるだろう。和名の字義解釈は "ハチを食べると言われている大型のタカ" (1871 年定義) でよいのではないだろうか。
少し嬉しいのは田中某氏所蔵の標本を「極めて美しき鷹にして」と記述されている点 (第1図が対応する図になっているがこれはヨーロッパ産の図版で本文のものとは色彩が少し異なるとのこと)。ハチクマを「美しき猛禽類」とすることに違和感のある読者がいるかもしれない [cf. 水谷 (2025) Birder 39(8): 65] の読者とは誰なのだろうか (笑)。かつては美しい鷹とされていたものが、その後いろいろな先入観が導入された結果ではないだろうかと思う。
標本中心に物事を考えておられた黒田長久氏の影響も大きいのではないだろうか。当時は系統関係がよくわかっていなかったので、クマタカへの擬態説 (#カッコウ備考の [カッコウのタカへの擬態] の カッコウのタカへの擬態の黒田氏の論文 参照) の補強材料に 擬態によって種を維持できたとさえ考えられる (セレベスのハチクマ) など、折りに触れてハチクマが原始的でつまらないタカであると主張された認識がタカの観察者にとってすら浸透してしまっているのではと想像する。
なお、うろこ状とされる模様を原始的なものに結びつけるのは、これまた鳥類が爬虫類に似た点を残していると思われる感覚的なものではないだろうか。アリスイはキツツキ類の中では最も古い独立系統でキツツキ類の範囲では原始的と言ってもよい部分があるかも知れないが、同じような意味でヨタカ類を古い方の系統に分類するのは現在の知見からは正しくない (アマツバメ類、ハチドリ類も類縁系統に含まれる)。
ハチクマも適応によるもので原始的特徴というわけではない。羽繕い映像など見ていただければそれほどうろこ状の羽毛でないこともわかる。配列が密なのでうろこ状に見えると表現されたのだろう。ヨウムでもうろこ状の配列に見えるが原始的特徴と言う人はいないだろう。
かつては剥製にして販売されていたぐらいなのでそもそも美しい鷹とみなされていたのである。世界でも一般に立派な美しい鷹と評価も高く、日本での低評価は植え込まれたものの可能性が高い。首が長くて云々も海外ではそれほど話題にならず、日本で渡りのタカの識別点として取り上げられたものが独り歩きしている部分もあるかも知れない。
これももしかするとヨーロッパハチクマの計測値が長年使われてきたことが由来かも知れない。見た目の大きさは図鑑通りでないので別の識別点に注目する必要があった。例えばハチクマはサシバより大きく、ノスリより翼が長い、とすればよいところが、図鑑の数字と合わなくなってしまうので頭部の形の方がより信頼できるとされたなど。
ヨーロッパハチクマとの混同もあった高野伸二氏時代の識別情報がもとになっているかも知れない。"A Field Guide to the Birds of Japan" (WBSJ 1982) で long-necked, medium-sized hawk とあり図にも識別点として示す矢印が付くが「フィールドガイド日本の野鳥」(1982) も見ての通りあまり明確でない。これらの表現がそのまま引き継がれて使われているものかも知れない。
Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" にも特にそれらしい表現はなく、projecting head (ハチクマ)、narrow head projecting from shoulders (ヨーロッパハチクマ) とある程度で、これは他の種にも使われる表現なのでハチクマに特有ではない。"首が長い" は日本独自に与えられた印象の可能性がある。そしてもしかするとそれもヨーロッパハチクマとの違いの情報があまり入っていなくて大きさなどが長年混同されていた結果に遡るかも知れない。
Dement'ev and Gladkov (1951) にはヨーロッパハチクマより明らかに大きいなど示されていて翻訳版などは当然日本の鳥学者が目を通せたはずだが、ハチクマは鳥学者にもあまり注目されていなかった種で特にページを開くこともなく、アマチュアの識別情報にもあまり口出しもしなかったのかも知れない。
海外では首の長さがあまり意識されていなかったためか、フィリピンのハチクマが特異的である点を説明するのに最初多少苦労した。単に緊張して首を伸ばしているだけではないのかと言われた... (挿入ここまで)。
世界に目を向けると [ヨーロッパハチクマとの関係・亜種] にあるように Vaurie and Amadon (1962) が亜種 orientalis = japonicus の尾のパターンで性と年齢の識別を識別できることを図版とともに示していた。直接文献には当たれなかったが Stresemann (1940 他) でもすでに区別されていたのかも知れない。
これらは標本に基づくものであり虹彩色はわからないが、尾のバンドのパターンは現在でも最も重要な識別点であり、尾のバンドを用いた識別方法は 1962 年までには明らかになっていたと考えるべきであろう。
それ以降に描かれたはずの日本の図鑑や記述が曖昧なものにとどまっていたのはこれらの海外情報が十分入ってきていなかったか、当時は同種とされたヨーロッパハチクマの図版や記述を参考にしていた要因もあるだろう。
現代の知識で東アジアフライウエイの野外識別の英語論文ならば Decandido (2016)
Flight Identification of the Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhynus orientalis in Thailand and Malaysia
が引きやすい。
[ハチクマとヨーロッパハチクマの識別]
ハチクマとヨーロッパハチクマは繁殖域が一部重なっていて雑種形成の可能性があり、雑種と思われる個体も中東を中心に報告されている [Forsman (2016) Flight identification of raptors of Europe, North Africa and the Middle East 2nd edn. 他]。
ただし、ハチクマとヨーロッパハチクマは従来想像されていたほど近い系統ではなく、雑種がしばしば観察されるノスリ類の間よりも類縁関係は遠い (#ノスリ、#チュウヒの備考参照)。ヨーロッパハチクマがハチクマの分布地域にも渡来している可能性もあるが、東アジアの渡りルートで雑種と思われる個体は報告がない。
インドではヨーロッパハチクマの記録がある。Anand et al. (2015) The European Honey-Buzzard
Pernis apivorus in India, and notes on its identification。
この文献の中では亜種 orientalis はインドではまれに見られるとある。さらに Munderi Kadavu Bird Sanctuary (Abdul Raheem Munderi 2020) を雑種と紹介している
(インド初記録のヨーロッパハチクマかどうかが問題となって純粋な種とは認めなかった模様。ハチクマに類似していると指摘されている点はなかなか微妙に見える)。
以下のオンラインセミナーが大変役に立つ (このセミナーは越冬地の視聴者も対象としているため、アフリカの種類との比較が多い):
Honey Buzzard Hybridization and Identification (Better Birding Webinars)。
分布の重なっているところは人も訪れないところで (これは正しくない)、雑種のつがいのいる巣を見た人はいない。DNA 解析も行われていない。ハチクマまたはヨーロッパハチクマの多様な個体変異の一部が雑種によるものの可能性は? 中東やアフリカで越冬するハチクマの事例が増えてきている。これは種そのものの変化によるものか、あるいは雑種形成の結果アフリカ方向に向かう渡りの衝動が生じるのか。
ヨーロッパハチクマの南アフリカでの記録は大変まれだったか最近 25-30 年の間で増えた。アフリカでも大部分の期間は樹冠の下で生活していて地面をひっかいている。ハチ類が主食だが日和見主義的 (opportunistic) な採食行動 (その時に簡単に得られるものを食べる) をとっている。南アフリカで観察されるものの大部分がメスである。
ヨーロッパハチクマは成鳥の羽衣になるのに3年かかる。最初の2年間はアフリカで過ごす。ヨーロッパの図鑑を見ても中間の年齢がどう見えるのかはわからない。オスの方が遠くまで渡らない仮説として、オスはなるべく繁殖地の近くで越冬することで繁殖地に早く戻れてよい場所を確保する意義があるとするものがある。
53:15 あたりからハチクマの識別:
* ハチクマの方がヨーロッパハチクマより足や爪がずっと大きい。
* 飛翔時ハチクマの方がずっとワシに似た印象を受ける。アフリカのアフリカソウゲンワシ (サメイロイヌワシ) Aquila rapax 英名 Tawny Eagle のように見える。ヨーロッパハチクマを見慣れた目にはまるでワシのように見えるそうだが、日本でもよい出会いをすると大変立派に見えるのでこれは納得できる。
日本でも飛翔時のシルエットが Aquila 属 (イヌワシ属) のように見えると指摘する人もある [cf. 先崎・伊関 (2014) Birder 26(9): 9 に識別対象種としてイヌワシが出ている]。
* 翼下面の横縞がヨーロッパハチクマでは揃って並んで見えるが、ハチクマではばらついている (この点は自分もハチクマのイラストを見る時に気にしている部分。よく特徴を把握せず描かれたイラストではヨーロッパハチクマのようにきれいに並べているものも多い)。
* ハチクマには手根部のいわゆるノスリ班のような "carpal patch" がない。
* 「よだれかけ」みたいな喉の模様 (gorget) があればハチクマ。
* 翼指はヨーロッパハチクマで5枚、ハチクマで6枚。
* ヨーロッパハチクマはオスでも虹彩は黄色。
これらの特徴が混ざっている個体は雑種の候補となるが、1:19:10 あたりに雑種ハチクマ判定の注意点:
* 英名の "crested" (冠羽)については、とまった姿でハチクマはチュウヒダカに似た印象を受ける (がよい識別点ではない)。
* 足が大きいと言っていたが獲物は違うのか? - 知らない。
* carpal crescent (carpal patch より小さい手根部の三日月型の模様) を雑種の特徴と主張している人もあったが、東アジアフライウエイの個体 (ハチクマ) でも見られており、雑種を表すものではなく個体変異の範囲だろう。
* 若鳥の次列風切の横縞がヨーロッパハチクマでは4本、ハチクマでは5-6本だが、ハチクマでも少ないのがいる。
以下の個体は雑種と判定されているがいかがだろうか: Crested or Oriental Honey Buzzard and hybrids (Batumi Raptor Count 2013)。
尾のバンドがハチクマほと太くないなど挙げられているが、この程度の個体もあるような気がする (外側のバンドは擦り切れて細くなっているものもあるのでそこまで判断材料にならないかも知れない)。
次列風切の模様のパターンは確かにハチクマとしては違和感があるように思える。
カザフスタンのハチクマ Oriental Honey-buzzard (Northern) (Charley Hesse 2024.5.18 Taukum Desert)。
渡り亜種のはずで、日本のものとよく似て見えるがいかがだろうか。尾のバンドが少し細い気がするが個体差の範囲か。
1羽のみがハチクマとのこと (カザフスタン) この拡大率では難関: Oriental Honey-buzzard (Andrey Averin 2025.5.10)。
[ハチクマと他種猛禽類との識別]
ヨーロッパハチクマとの識別の後にこの項目が出てくるのは変な気もするが、あまり予想しないような誤認がしばしばある。
日本では最もよく間違えられるのがクマタカというのは納得できる話で、流通が許されていた時代にはハチクマがクマタカの名前で流通していたのも不思議な感じがしない。
ハチクマの名前がほとんど知られていなかった時期のような古い書籍などではクマタカに近い種類とまで書いてあったりする (しかし生態的には実は近そう)。トビに近いと書かれるようになったのはその反動か? 今ではこれも間違っていることがわかっている。
クマタカを見慣れた人にはどこが似ているのかわからないと言われることもあるが、翼の幅広さがわからない条件では確かに似て見えることもある。
タカ渡りなどではトビ、ノスリとの区別が問題となるのはご存じの通り。また飛翔形がイヌワシ属に似ていることもしばしば取り上げられる。シルエットしか見えない場合は識別対象になることは他所でも触れた。
「野鳥」2010年10月号 (No. 750) p. 39 に福田氏のエピソードが紹介されている。
ここで取り上げたいのは海外事例で、日本ではハチクマとカンムリワシは同所的ではないのでほとんど問題にならないが、海外ではカンムリワシとの誤認が非常に多い (ベテランの写真ですら間違っていることがある)。尾の帯模様などが似ているからだろう。
この誤認の問題は写真であればまだ見て判断しやすいが、誤認された結果が音声ライブラリ (Macaulay Library など) にも紛れ込んでいると思われるので要注意。カンムリワシの音源だと思って解析に用いたが実はハチクマだった、ということも十分あり得る。もちろんカンムリワシやハチクマに限った話ではない。
とまっている時に多く見られる誤認はクマタカ類で、海外ではクマタカ類に擬態している (とされる) ハチクマ類やハチクマの亜種もあるのである程度やむを得ないところもある。人でも間違えるぐらいの擬態は効果もあるのだろう。カワリクマタカとの誤認もよくある。
ミサゴとの誤認は [よく誤認されるハチクマ若鳥淡色型] で述べた。もっともこれ以外にも何にでも間違えられるようで、広義ハイタカ属やワシ類なども含め「どこが似ているのか」と思うような誤認を見かけることがある。亜科レベルではハゲワシ亜科など特別なもの以外の誤認をほとんど見たことがあるように思う。
この項目を設けたのは過去の書物を見ていて「あれっ?」と思う事例に遭遇したためである。
「アニマルライフ」 デラックス 「動物の世界」35 (日本メール・オーダー 1983; 週刊版は 1974 が初版だったらしいがこの号に相当されるものが初版に含まれていたかどうかは不明) をぱらぱらと見ていて p. 507 (アジアの山岳地帯の動物) でこんなところにハチクマが、と (いわゆる jizz で) 思った写真があったが、
キャプションには「サメイロイヌワシ。中世ヨーロッパにおいて、鷹狩りのとき王侯しかつかうことのできなかったといわれるイヌワシ類は、"王" の威厳にふさわしいすばらしい翼をもっている」とある
(お持ちの方もあろうと思われるので見ていただきたい。図書館にもよく入っているだろう)。
なおサメイロイヌワシは Tawny Eagle の過去の名前で、アフリカソウゲンワシの名前が現在よく使われる。この記事の時代はおそらくソウゲンワシ Steppe Eagle が同種とされていたころで、地域からは今でいうソウゲンワシのことを意味していると考えてよさそう。
ワシだと言われると爪も確かに立派でそのようにも見えてしまうのだが (もうちょっと隠しておいた方がよいらしいよと余計な助言もしておく)、ここまで書いてあると識別点を確認しておかねばならない。
虹彩が黄色で全周が丸く見えていることはソウゲンワシとは合わない。目と嘴の間 (lore) が羽毛で覆われている点もハチクマでよい。鼻孔もワシのように開いていない。ろう膜は暗色。他にも口角の色などソウゲンワシと似ていない点がいくつもある。
これらの特徴をみるとハチクマの亜種 ruficollis のメス成鳥でよさそう。背景も森林環境でソウゲンワシの好む環境と合っていない。
なぜイヌワシ類と考えられたか想像してみると、ふしょのかなりの部分が羽毛で覆われているためで、全体の色調からソウゲンワシと判定されたのではないだろうか。
ハチクマを横顔で見ると十分かっこよくて爪もしっかりしていて (鳥類学者の描くニワトリのような爪はやはり間違っている模様)、イヌワシ類とされても疑いが持たれなかったのかも。[ハチクマとヨーロッパハチクマの識別] でハチクマはアフリカソウゲンワシのように見えると紹介されているので鳥類学者にとっても似て見えたのかも。
著者は主にフランスのチームのようで (フランスの鳥類学者 Jean-Jacques Barloy 1939-2013 が冒頭に出てくる)、ヨーロッパハチクマに慣れた目にはハチクマはソウゲンワシに見えた? (ほんとうか?)。
影の写りこみの様子から複数人で投光器を用いて撮影したものと思われるが、なぜそんなに注目されるのか不思議に感じていたのではないだろうか (笑)。
このシリーズは世界同時発売だったはずで、誰も指摘しなかったのだろうか?
なお同書 pp. 528-529 でイヌワシが扱われ、p. 531 に捕食場面の写真がある。写真サイズが小さいためかイヌワシよりハチクマの方が立派に見えるし、イヌワシの方がむしろ首が長く見える。ハチクマは首が長くてタカらしく見えない云々は緊張させた条件で撮影された画像 (つまり一般に言われる特徴がよく現れているとされる瞬間の写真が選ばれやすい) の印象に引きずられすぎだろう。
後で気づいたが、とまり画像と捕食画像を出すことでイヌワシ類のかっこよさを多角的に表現したかったものだろう。片方がハチクマだったとは夢にも思わず...。
ふしょが大部分羽毛で覆われている写真はインドの Oriental Honey-buzzard (Atul Dhamankar 2025.4.19) もあった。こちらに目をつけると何の種類かと思ってしまう。
なお目先 (lore) が羽毛で覆われているタカ類はコウモリダカがあるとのこと (Jollie 1977, p. 297)。系統的にはまったく異なる。参考画像: Bat Hawk (Reece Dodd 2024)。
顔がハチクマに似ているかと考えれば多少似ている感じもする (目が大きいのは夜行性が強いため)。翼型など他は似ておらず共通点は目先の羽毛だけか。コウモリの捕食で目先が羽毛に覆われるのはどのような適応だろうか (#トラフズク備考の [コウモリを主に食べる北京郊外のトラフズク] で考察してみた)。
オウギワシ亜科というのも容貌からは理解しにくいがオウギワシは特有の transposable elements があるなど独自の進化を遂げたらしい (#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化])。コウモリダカもこの精度でゲノムが読まれれば共通点や進化経路の違いなども議論の対象になるのだろう。
近年の識別話題例では Eagle in Central Asia 一緒に写っているのはワタリガラスとのこと。投稿者もワシばかり考えて思い至らなかったとのこと。
これも最近の識別話題: Honey Buzzard? Poland
ヨーロッパハチクマとオオタカの区別がつかない。どこに注目すればよいのか教えて欲しい。
「そんなものは全然似ていない。見れば一目瞭然だろう」しかし議論は続き「どこが似ているか敢えて挙げてみよう」などの手助けをする人も。「もっとフィールド経験を積みなさい」(まったくその通りではあるが) との発言もあるが、「ビデオを探して見なさい」の助言も。でも識別方法を言葉で説明して欲しい。それは確かになかなか難しい。
続きがあって Question about identifying raptors
ヨーロッパハチクマとヨーロッパノスリの識別はどこにも書いてあるが、ヨーロッパハチクマとオオタカの識別は出てこない。書いてあるそれぞれの特徴を並べると同じようなものになってしまうとのこと
[ハイタカに比べたオオタカの識別点、(ヨーロッパ) ノスリに比べた (ヨーロッパ) ハチクマの識別点をそれぞれ列挙すると確かにそうなるかも知れない]。感覚的でなく絶対的な識別点が知りたいとのこと。
2024.9.28 の新聞広告に Birder Special タカの渡り観察マニュアル (久野公啓 文一総合出版 2024) が出ていて、紹介写真のキャプションにクマタカとあった。文一でも間違えるのか !? かつて Kbird で動物園のハチクマのネームプレートがクマタカになっていても一般の人は 90% 以上は気づかないのではと書いたことがあるが、おそらくその通りらしい。
なおハチクマは秋の渡りで見る機会が圧倒的に多いので、個体によっては脂肪を蓄えて非常に太っていることがある。体格が良ければ一層クマタカのように見えても不思議でないかも。秋の渡りだけ見ていると印象を誤る恐れが多分にあり。写真図鑑なども飛翔写真は秋の渡りのものが多く平均的にはやや太っているかも。
スマートなハチクマが見たければ (お好みであれば) 春から夏に観察するのがよい、となるだろうか。
とまっている姿は養蜂場で撮影されたものもかなり含まれているらしいためか、海外で撮影されているとまった写真と少し違う印象を受ける。地上近くでは多少なりとも警戒している可能性がある。
ハチクマに限った話ではないが写真図鑑のポーズが必ずしも典型的なものとは限らないのでこの点も注意して見ていただくとよいだろう。
Oriental Honey Buzzard from BR Hills, Karnataka (Think Wildlife Foundation 2024)。見ていただければすぐわかっていただけるだろう。特徴まで記述してあるのだが...ビデオの取り違えかも知れない。
さて、このあたりまで書いてから最近のビデオにはかなり怪しいものが含まれていることに気づいた (これまで紹介していない)。単に他人のビデオを継ぎ接ぎしてアクセスを狙ったものかと思っていたが、ハチクマ類に見えない種類はハチの巣を襲っている映像などが見られる。これは AI が作成した「ハチの巣を襲うタカ」の映像で、タカは何でもよかったのでハチクマ類以外が使われてしまったものがあるかも知れない。
この状況になると単なる誤認や取り違えとも言えず、自然の映像か合成映像か個々に疑う必要がある。ハチクマの習性のビデオとして紹介されていても必ずしも本物とは限らない。古い時期からあるものは大丈夫なのだろうが。
[幼鳥の次列風切が幅広いのはなぜ?]
#カタグロトビ備考 [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] の Zuberogoitia et al. (2018) Moult in Birds of Prey: A Review of Current Knowledge and Future Challenges for Research
より。猛禽類では一般的に亜成鳥の羽は幼鳥より短く成鳥より長い。この傾向は特に次列に顕著とのこと。ハチクマの次列風切が幅広いのは幼鳥の識別点となっているが、おそらくこの羽毛構造の齢差に関係しているのだろう。
この機能は尾羽の機能と組み合わせて考えるとよりはっきりするかも知れない。ハチクマが尾羽をしっかり広げると次列風切と連続面をなして航空力学的にもいかに有利なように見える。特に春の渡り中のハチクマがしばしば尾羽をしっかり広げている印象を受ける。春は相対的にまだ気温が低く、上昇気流も弱めで体重の大きなハチクマが渡るためには尾羽を活用する必要性がより高いかも知れない
(自分の場合はまだ気温が上がる前で風の少ない朝の記録が中心である選択効果が現れているかもしれない。日中も含めてよく観察されている方の印象も伺いたい)。
ノスリ類のソアリング中の尾羽の役割と同様でノスリ類の方がより目立って見える。クマタカでも同様かも知れないがクマタカは体重が一層大きいので (森林性のため) 翼を長くせずに面積を拡大するにはこの方法しかないかも。またクマタカサイズの鳥が森林性かつ渡りをするのは形態的には無理があるかも。
ハチクマで幼鳥のみ次列風切が幅広いのは、まだ飛翔能力が十分でない段階で秋の渡りを行う必要があるためではと考えてみた。飛翔能力の高い成鳥よりも尾羽の効果と組み合わせて上昇気流を捕まえる能力が成鳥以上に必要なのでは。また平均的に幼鳥の方が渡りが遅いため、気象条件がより不利になる効果を補えるかも知れない
(成鳥が幼鳥を待って渡らないのは別件でも紹介のように生活史戦略からも妥当で、寿命の長い成鳥が自身の生存率を高める行動の方が進化しやすい。ではなぜツル類やガン類がそのような戦略にならないのかと問われそうだがいずれも古く誕生した系統で系統的制約なのかも知れない)。
[ハチクマとヨーロッパハチクマの識別] にあるように、ハチクマとヨーロッパハチクマの識別点で若鳥の次列風切の横縞の数も体重差を反映しているかも知れない。
渡りを行わない留鳥亜種の幼鳥の翼型と比較すれば検証できるかも知れない。
参考画像: Oriental Honey-buzzard (Nick 6978 2025.5.12 マレーシア) これは留鳥亜種? 一見別種かと思ったほど相対的に翼の幅が広く尾は短く大きく広げていた。幼鳥の翼型の議論とは必ずしも符合しないかも知れない。
ここまではタカ類の次列風切の話であるが、ご存じのように飛んでいる鳥を下面から見ると下雨覆で覆われる範囲が系統によってずいぶん違っている。ハチクマでは下雨覆で覆われる範囲が狭いために次列風切の横縞の数が識別点に使える次第である。
カモ類では飛翔時下雨覆が翼のかなりの部分を覆っているように見える。カモ類では常時羽ばたいていないと落ちてしまうので下雨覆で補強する必要があるのでは?
同じ説明はコウノトリ類には当てはまるような気がするがミズナギドリ類には必ずしも当てはまらないようにも見える。おそらくミズナギドリ類はタカ類とソアリング方式が異なるので、翼はもっと幅が狭く次列風切が短い方がよいのだろう。
すでにどこかに議論がありそうな気もするが検討材料として提供。
[目を隠す模様は何のため?]
(#カワウの備考 [ウの虹彩はなぜ緑色?] から移動およびタカ類を対象とした追記):
アメリカチョウゲンボウなどで後頭部に偽の目 (false eyes) の模様があると言われていたが最近この話をあまり聞かない。説を知っている現役世代があまりいなくなったのか、あるいは実験的証拠に乏しいのか。チゴハヤブサの事例 (高野 1974) を#チゴハヤブサに示した。
Negro et al. (2004) Do Eurasian Hobbies (Falco subbuteo) Have "False Eyes" on the Nape が論文にしていた。
次の Deppe et al. (2003) とも時期が近く、この当時話題となっていたのかも知れない。
この論文に機能に関する過去の議論も取り上げられているので歴史を遡るのに参考になるだろう。攻撃を防ぐ説は Clay (1953) によるもので、「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) p. 107 でも取り上げられていた。Deppe et al. (2003) の言及している Glaucidium 属については del Hoyo et al. 1994 の HBW にもすでに記されていたとのこと。
高野氏も英語論文を書いていれば参照されていたことだろう。
「鷲鷹ひとり旅」(宮崎学 平凡社 1987) p. 32 にハイタカの頭のうしろに白い目玉模様があるのがおもしろいとの写真と記述があった。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 115 p. 2 におそらくヨーロッパのものと思われるハイタカの写真の後頭部に白斑が見え、同じく p. 4 のウタオオタカ Melierax canorus Eastern Chanting Goshawk の写真でも同様に白い部分が見える (当時はまだ種が分離されていなかったかも知れない)。
いずれも横向きの画像なので真後ろからどのように見えるかまではわからない。
このような写真を見ると Accipitrinae 亜科 (現代の概念で) に比較的現れやすい模様なのかと思えた。現代のウタオオタカの写真を探しても対応する模様があまり見当たらない。若鳥はチュウヒ類に似た色彩で (チュウヒ類に似て腰の白い個体もあった)、チュウヒ類の顔盤の後側に位置する模様に相当するのかも知れない。
さらに言えば英名の由来としばしば誤解されるイヌワシの後頭部の色彩も類似点があるのかも知れない。
These Birds of Prey Have Eyes in the Backs of Their Heads (Audubon の解説) では見ているように見せかけて攻撃を避けているとのこと。
比較的新しい論文があって Deppe et al. (2003) Effect of Northern Pygmy-Owl (Glaucidium gnoma) Eyespots on Avian Mobbing メキシコスズメフクロウではモビングを避ける機能があるとの実験結果。これが本当ならば被食者が捕食者の視線を見ている? しかしこの論文でアメリカチョウゲンボウに一言も触れていないのはなぜだ?
モビングを避けるならばどの種にも有効そうだが、限られた種にしか同様の模様が見られないのはなぜだろうか。
Negro et al. (2007) Deceptive plumage signals in birds: manipulation of predators or prey?
に総説があり、Falco 属内で見られる系統まで示されている。
しかしなぜ Falco 属や Glaucidium 属なのだろう。論文には少しそれらしい記述があって、ハヤブサ類がフクロウ類のように錯覚されるのは首が短く顔が丸いためとある。一部の (旧) ハイタカ属やコウモリダカでも後頭部に対になった淡色部分があるとのこと。多くのタカでは後頭部に白っぽい部分があっても目のようには見えないとのこと。
考え方の起源は古く、ガや幼虫のの目玉模様など (かの Cott 1940 が引いていある)。
Clay (1953) というのは Protective Coloration in the American Sparrow Hawk。
当時すでに議論がなされていて Zahavi and Zahavi (1997) が "The handicap principle" で述べた攻撃を防ぐ説は "an insult to the intelligence of predators" (捕食者の賢さに対する侮辱である) 考えに同意するとのこと。さすがに猛禽類研究者だけのことはある (笑)。Zahavi and Zahavi がそんなことを述べていたのだ。
Negro et al. (2007) で Hypothesis 5: Mobber Manipulation で逆にモビングを誘発して食物となる小鳥を襲う説も述べられていた。
The Function of Ocelli (false eyes) In Raptors (Ron Dudley 2014) でも紹介されており、この著者は小鳥も食べるスズメフクロウが偽の目を持つ傾向があると説明している。
タカ・ハヤブサ類の種類によっては目をむしろ隠すような模様があるものがあるがどちらが有効なのだろう。ミサゴやハヤブサは反射光を防ぐ解釈ができるが、ハチクマのメス淡色型や若鳥の模様は何のため? Mobber Manipulation の仮説に乗ればハチクマは小鳥を (たぶん) 襲わないのでモビングを誘発する必要がない (?? 多分関係なさそうだが)。
#ハシブトガラ備考の Poecile 属の意味や #オオヨシゴイ備考の虹彩の模様など、捕食する際も対捕食者に対しても目を隠す手法は多分有益なのだろう。タカ・ハヤブサ類の場合はカラスなどに見つけられてモビングされるのを避けるのに役立つかも知れない (アメリカチョウゲンボウの場合の発想とは逆になる)。
これは特に森林性の猛禽類が待ち伏せ猟をしている場合、カラス類などに見つけられて騒がれると狩りが台無しになってしまうのを防ぐ効果があるのでは、とカラス類に追われてやむを得ず森林から飛び出す猛禽類をしばしば見て感じた (そんなところにいたのか、とかカケスが妙に騒ぐのできっといるぞ、など)。すなわち獲物に色覚や高い視力がなくても成り立つ可能性がある。
猛禽類の場合はおそらく森林性・待ち伏せ猟タイプに特に有効なのでは。草原性や飛びながら獲物を探すタイプは目を隠す必要は高くないかも。ハチクマの模様は前者に当てはまる感じがする。クマタカでもカラス類がよく騒いで移動を余儀なくされることもあるのできっと同様だろう。
日本やインドのオス成鳥のハチクマの黒い目は目立つのではとも思えるが、むしろ黄色の目ほどは目立たないかも。カラス類から見てとまっている時はタカに見えずハトと思われて無視されている、なんて可能性も (?)。
下のオオタカの事例を見てから、ハチクマの成鳥オスの順光でない写真を調べてみると、顔が灰色っぽいので目があまり目立たないことがわかった。顔の凹凸で適度に陰影が生じていると黒い目が隠蔽色になっているかも知れない。順光の完璧な写真ばかり見ているとむしろ解釈を誤ってしまうかも。
獲物が反撃する場合に目を狙われないように目を隠す効果もあるだろう。ハチクマでもサギ類などの巣を襲う場合に親鳥の反撃が危険かも知れない。さまざまな場面で目を隠すことは役に立ちそう。
オオタカの方がサギ類を襲いそうなので、オオタカの目が目立っていることと矛盾する感じもするが、オオタカの逆光写真を見ると目が全然目立たないことに気づいた。サギの方から見ればほぼ逆光条件なので目を通る黒い帯があれば目を隠す効果が十分期待できる。
オオタカとハチクマで狙うものは違うかも知れないが、狙われるサギの側にとっては同じようなものだろう。
そう、図鑑やインターネットの写真などはわざわざ逆光のものや目がはっきり写っていないものを載せないので、これらの写真だけを見ていると気づかないのであった。古い本の写真ではそこまで完全な条件で撮影されていないものも多かったので目が目立たないことに逆に気づくことができた次第。
そのように考えるとオオタカの目の上の "ひさし" も陰影を付けるために役立ってそうに思える (生物の構造には往々にして複数の機能がある)。
さらにハヤブサ類の目を通る模様もほとんどそうではないか? ハヤブサ髭も日光の反射を抑えると言われるが、遠目で見ると目を隠す役割の方が大きいように見える。攻撃を受ける側の獲物は距離も遠く、視力もそこまで高くないので図鑑写真のように見えているはずがない。
獲物を襲う際に目を隠すことが役立っているかまではわからないが。チョウゲンボウ類などの模様は特に顕著に思える。
[モビングを受けるタカの行動観察のすすめ]
[(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の [ハチクマのお客さんになって] で記録されたダンボールの箱の固まりをもぎ取って落とし、後に丸めた紙を与えられて同じ行動を繰り返す行動は遊びと考えられるが、野生でも遊んでいないかふと気になった。
タカがカラスに追われていると「モビングを受けている」でおしまいになってしまいそうだが、これも先入観がだいぶ入っている可能性がある。タカがカラスを遊び道具に使っている事例はないだろうか - のような疑問を投げかけるのはそういう場面に遭遇しているためである。
モビングを受けて嫌ならばすぐにその場を去った方が効率的と思われるが、長時間一緒に空にいる場面が結構多いのである。また並んで飛んでいるなど必ずしも追われていない写真も多い。
本気で飛べばタカの方がもちろん速いので (カラスの翼にはスズメ目なりの限界がある)、わざと速度を落としているのではないだろうか。
タカのプライドが許さないのですぐには立ち去れない (笑) わけでは多分なくて、「くそカラス」と思いつつも、うまく利用して飛ぶ (飛ばせる) 遊びに使っている可能性はないだろうか。カラスの方が頭がよいので、と先入観を持ってしまうとタカをからかっているように見えてしまうが、タカの方が賢ければカラスが遊ばれている可能性もあるのではないだろうか。
「カラスしつこいですね」と思っていたら実は逆で、タカを見ればモビングせざるを得ないカラスの気質を見抜いて反復利用して満足を得ているのかも。カラスの方も終わってみたらしまったと思っているかも知れないし逆に満足しているかも知れない。
相手の反応があり、何と言っても自身が得意とする空中の話で、狭い環境で人工物を落とすよりも一層面白いのではないだろうか。タカが体力的に弱っていない限り、一対一で直に勝負すればもちろんタカが圧倒的に有利なので余裕を持って遊んでも大丈夫。実はどちらも結構よい頭脳勝負を行っているのかも知れない。
[目を隠す模様は何のため?] でモビングされるのを避けるためではと議論しており一見矛盾するようだが、これは我々自身を想像してみるとあまり不思議でない。真剣に取り組んでいる時に話しかけられるのは邪魔であっても、そうでなければ気分転換のおしゃべりになってしまうのと同様に状況次第だろう。
そう思ってみると、オーストラリアに進出したハチクマ ([オーストラリアのハチクマ] 項目) がモモイロインコの群れと一緒に飛んでいる写真があるが、これも群れを飛ばして楽しんでいるのではないだろうか。捕食目的とは考えにくいし、例えば小さい子どもが地上に群れているハトを飛ばすのと同じような感覚なのかも。
余裕があって腹も減っていない時は、カラスを見つけたらモビングを誘発してみるなどの行動もあるかも知れない。
渡りを控えた若鳥のハチクマがクマタカに挑む行動も報告されているが、これもモビングというわけではないだろう。#カッコウ備考の [カッコウのタカへの擬態] に登場する Kuroda (1966) "猛禽斑とカッコウ類のタカ斑の起原について" の解釈ではあり得そうもない話となる。そのようにお互い半分遊びながら (?) 挑戦して行動力を高めて行くのだろう。渡りに備えて必死で食べているばかりではない。
そういえば、カラスやハトの追い払いに鷹匠が活躍する場面が知られているが、肝心のタカの方は報酬がもらえるとはいえ、面倒くさければわざわざ長時間追い払いをするだろうか (自分ならば多分手抜きをする)。やはり相手の反応を見て楽しんでいる部分があるのではないだろうか。数ある動物の中でも食用以外に家畜化できた種類はわずかで、鷹狩りが早い時期に成立したのは、タカやハヤブサがそれだけ賢く、満足を与えることのできる共同作業ができたためではないだろうか。
[目を隠す模様は何のため?] の記述途中で Negro et al. (2007) Deceptive plumage signals in birds: manipulation of predators or prey? の総説に気づいた。モビングの意義の議論も述べられていた。モビングは危険が伴うので、なぜそのような行動が進化し得るのかもちろん行動生物学 (社会生物学) の議論になる。理解には程遠いとのこと。
モビングする側については猛禽に別の場所に移動してもらう説、Zahavi and Zahavi (1997) "The handicap principle" のハンディキャップ原理を述べた書物ではモビングすることで同種内の社会的地位を高める効果が期待できる説があるとのこと。なんとなく人の行動から類推かな。
からめ手を重視して一枚上手を行く Zahavi and Zahavi の発想の方向性がわからないでもない。行動生物学者は他人の説を復唱するのではなく、このような点で想像力豊かでなけばいけない、ちゃんちゃん。
この Negro et al. 論文ではモビングが猛禽に負の影響を与えることは確かで、その視点を述べた研究は多数あるとのこと。猛禽の方が遊びに使う発想は猛禽の能力を高く評価しているさすがの Negro も思いつかなかったのかも。
そもそもそのような行動解釈が本当かどうかわからない段階だが、もし遊びならばなぜそのような行動が進化したか考察するのも面白いかも。上手にモビングに対応したり小物相手に遊ぶ行動を同種個体に見せることは社会的意味があるかも知れない。同種個体を例えば観客に見立てるわけだ。認知能力の高い生物でないと成り立ちそうもない。動物行動学とはかくも複雑なものである (笑)。
さらに悪乗りしておくと、Zahavi and Zahavi (1997) も発想がサルなどの哺乳類寄りではないだろうか。カラスは霊長類なみに知能が高いのは当時も知られていたと思うが、サルとカラスでは決定的に異なる点がある。サルはあくまで地上の動物であって2次元の世界に生きている。樹上も登るので 2.5 次元ぐらいと言ってもよいかも知れない。
しかし空中を自由に舞う鳥のように完全に3次元の世界ではない。我々が4次元の空間を想像しにくいのと同様、2次元の世界に生きる生物には完全に3次元で行動できる生物の戦略を把握できていないのではないだろうか。サルと同等で考えるのは不十分かも知れない。
例えば四方を取り囲まれた場合は2次元では逃げ道がなくなるが、3次元ならば自由度がまったく違う。
トンネルに営巣する鳥 (1次元) と開放空間に営巣する鳥では防衛戦略が異なるのと同様。
モビングに対する戦略も、モビングする側の行動も3次元効果を考慮すべきであろう。サルならば空間の次元の制約のため同種内の社会的地位につながるかも知れないが、カラスではそうならないかも知れない。
[目を隠す模様は何のため?] の Negro et al. (2007) 論文で Zahavi and Zahavi (1997) の (擬態模様をモビングを避けるためと解釈することは) "捕食者の賢さに対する侮辱である" 考えに賛同すると述べられているが、2次元空間の生物の認識力で3次元空間の生物の認知能力を議論するのはまことに侮辱的ではないだろうか (笑)。
もちろん飛ぶ鳥でもテリトリーは2次元的なもので行動がすべて3次元というわけではないが、空中でのディスプレイや争いなどは3次元効果がいかんなく発揮される部分だろう。
このようなことを考えた背景には過去の天文学の進歩の経緯がある。計算機能力の乏しかった時代には1次元モデルが使われていた。星であれば自転しない球対象な理想的な形状の星ということになる。1980 年代初頭はまだこの時代で、超新星の爆発の計算などでも1次元モデルが使われていた。大マゼラン雲の SN 1987A がちょうどその時代にあたる (#ミフウズラ備考 *2 に小史を紹介している)。
当時は1次元が標準モデルであったため、当時の日本の X 線天文衛星の「ぎんが」が想定よりずっと早い時期にこの超新星からの X 線を検出したため大きなニュースとなった。レイリー・テイラー不安定性 (Rayleigh-Taylor instability) が一躍脚光を浴びることになった次第。
1次元モデルでは扱えなかった現象が起きていることが白日の下に晒されることになった。特に回転を含む場合は必然的に2次元以上の取り扱いが必要となる。
工夫して1次元モデルで扱う時代も長く続いたが (回転している場合でも例えば降着円盤)、その後計算機の進歩とともに2次元が扱えるようになるとジェットが発生することなどが自明となり (1次元では逃げ道がないのでそもそもジェットの出る場所がない)、超新星爆発でもジェットが発生することからガンマ線バースト (GRB) の理解につながったり、星の合体現象も理解が進んだ (#オオワシ備考の [鳥類、特に猛禽類の鉛中毒] に小史あり)。
要するに天文学のこの時代の目覚ましい進歩はモデルが1次元から2次元や3次元に拡張されたことによってもたらされた部分も大きい。すでに3次元に到達してしまっている以上、この時代のような目覚ましい進歩はもう望めないのではないだろうか (汗)。
つまり同じように2次元から3次元に拡張されることによって生じる行動生物学のコペルニクス的転回があっても不思議でない。たとえ恐竜マニアであっても及ばない、他の生物にはない飛ぶ鳥独自の研究視点がいくらでもあるかも知れない。鳥の知能はサルと同程度なのでサルの理屈をそのまま適用すると考えるのはよい近似になっていない可能性がある。
次元の違いが与える効果は個々の個体にとってはわずかな相互作用の違いであっても、微小な選択圧が示す進化の多くの顕著な事例に見られるように、行動戦略や個体群構造の進化には大きな影響を与えるかも知れない。
集団の扱いについてもおそらく2次元に慣れ親しんでいる我々の認識の制約を受けているだろう。飛んでいる鳥の群れを見て、本来3次元的なものを画像のような2次元として認識してしまうため、飛んでいる鳥の側から見ると視点がまったく異なるかも知れない。
距離方向の感覚がなく2次元にしてしまうと高い密度のように見えてしまうが、実際はそうではない事例として星空を思い浮かべればよい。宇宙は星だらけのように見えてしまうが、3次元でみると空間だらけである。月に行ければ次は火星に行けるのではないかとの錯覚も同じように生まれるのだろう。
鳥の群れでも入ってみれば案外混雑していないかも知れない。2次元空間の生物が例えば満員の列車ホームの群衆の中で身動きが取れない状況とはおそらくまったく異なる。個体間相互作用もまったく異なるだろう。
普段群れないタカが渡りの時は群れても争いにならないのだろうか、など考えられることもあるかも知れないが、当のタカにとっては個体間距離も十分あって群れているように感じられていないかも知れない (と一応ハチクマらしい話に戻しておこう)。
さて先程の、次元によって行動が変わる事例を念頭に置くと、動物を捕獲するとは次元を下げる行為そのものである。飛んでいる鳥は3次元なので捕獲は非常に難しい。従ってヒトが銃を発明するまでは主要な食料となりにくかった。銃を発明するまでは鷹狩りが重要だった文化的理由もわかる。
2次元空間の生物による捕食圧が働きにくいので捕食に対する防御行動もあまり進化しなかった。従って2次元空間の生物にとって鳥の行動は "ばか" のように見えがちである。
3次元空間の捕食者が後の時代になって現れるとさすがに飛んでいる鳥もそこまで無防備にはなれず、飛ぶ捕食者に対する行動が必要となったが、空からの攻撃のみに気を配ればよいので他のパターンの攻撃への対応行動はあまり進化する必要がなかった。
さてヒトは賢かったので、3次元を2次元へと次元を減らすことで相手に逃げ道を用意しない方法を発明した。つまり餌などを使って地上に降りさせれば2次元の問題となって捕獲は一層容易になる。すぐに飛び立てない鳥ならば猟犬などで囲めばよい (もっとも2次元の囲い込みはそれほど高度ではなく、カモ類やペリカン類も行っている)。
その上で逃げ道をふさいで追い込めば1次元の問題となる。1次元で追い込まれることを進化の過程で経験していない鳥にとっては大した対策が進化していない。そのような鳥の行動は "ばか" のように見えがちである。そして0次元になれば捕獲成功となる。
少なくとも我々にとっては、次元を減らす方が扱いやすくなる点は進化の過程で認知プロセスに組み込まれているだろう。3次元の問題でも2次元で扱える範囲の問題に制約することで理解がやさしくなる (#アカゲラで紹介のキツツキのバランスの問題など)。
主成分解析など偉そうな用語を使っているが、次元が高い問題を最もわかりやすい2次元に縮約する道具である。系統解析でも系統樹を用いるがこれも2次元化するためのもの。実際にはもっと複雑なはずと3次元系統樹なども試みられているがあまり流行しない。
3次元の問題を2次元に減らしたり、あるいはさらに1次元で扱うテクニックを身につけるのが受験数学だったり物理というもので、公式はそのためにあるようなもの (さすがに言い過ぎかも知れない)。次元を減らす方向への写像は簡単なので受験数学や物理を AI が簡単にマスターできる理由もわかってしまう。
こちらは問題を簡単化するために次元を減らすもので、先述の天文学の例にあるように次元を減らすことによって失われてしまう性質もあるので手加減を注意すべきである。
動物を捕獲するために次元を減らす戦略に数理的に類似する現象は日常世界にはないだろうか。受験偏差値は学力を1次元の量として表そうとしたもの。これほど扱いやすい指標はないかも知れないが、弊害も古くから指摘されている通り。どの時代に始まったのかは知らないが、受験産業にとっては動物を捕獲するのと同様、極めて有効な指標だっただろう。
とらえどころのない多次元の「学力」から次元を落とすことで、なんだ我々は追い込み猟の対象になっていたのか、と理解しなおせば何となくもやもやした感じから多少開放されるかも知れない。
今となってはもはや縁を切ることもできないだろう金銭も1次元の量である。我々は2次元空間を得意とする生物で低次元の扱いに適応した認知能力ともよく整合していたため発達したものだったのかも知れない (金銭による追い込み猟は何に該当するかなど、この先の応用的解釈は考えてみていただきたい)。
3次元空間が普通である飛ぶ鳥ならば別の認知的アプローチを取ったかも知れないとも考えてしまう。次元を落とした方が理解しやすい点は鳥でも共通なのだろうか、それとも違いがあるのだろうか。
もし違いがあるならばそれに適した神経回路の進化など、脳科学にもつながるかも知れない。
次元を変えることで扱いやすくなったり理解が容易になる場合や、あるいは同じような原理が別の場面に応用できることを考えるのは、物理学者や数理科学者が最も喜びを見出す場面だろう。
次元を上げることでわかりやすくなる場合もあり、単なる数から複素数 (2成分) や行列を派生させたことが挙げられるだろう。複素数が用いられていなければ現代生活に欠かすことのできない基礎となっている量子力学の理解ははるかに難しくなっていただろう。
空間の点の配置も2次元座標だと考えず、複素数1変数で扱えば圧倒的に見通しがよくなることがある。例えば R は複素数に対応しているので、2次元をメッシュに分けるのは単に round() でできてしまう。2次元で分布の集中しているところを探すのはさらに table() を使えばよいなど、空間生態学への実用的な応用範囲も広いのではないだろうか。
次元の概念の鳥の世界への応用も、分野の枠にこだわらない物理学者や数理科学者の方が興味を示す題材になるかも知れない。
鳥の研究が社会にとって何の役に立つのかと問われた時の一つの回答となるだろうか。
次元が面白い効果をもたらす例を思いついたので追加で紹介しておく。かつて商品名プラパズルというパズルが流行したことがあった (現在は「脳ブロック」の名称で同じくテンヨーから発売されている)。ペントミノなどの一般名ならば理解できる方もあるかも知れない。
タイルを2次元に敷き詰めるパズルで今でももう少しやさしいパズルの題材にある程度使われている。5個の正方形からなるピースを埋めるのがペントミノで最も流行し、当時は「電子計算機」がすべての解をすぐに見つけたと話題 (宣伝?) になっていた。
次には6個のものや正方形でなく正三角形を基本としたものが商品化されたが期待ほどは売れていなかったらしい。難しすぎるのである。それでもパズルのマニアの間で誰よりも多くの解を見出そうと競われていたわけだった。6個になると「電子計算機」でさえ、とてもすべての解を見つけ出せないことが判明したのはその後になる。そうなると自由度が膨大すぎてパズルの面白さが少し失われるわけだ。
そして立体ペントミノがほぼ「究極のパズル」のように発売された。こちらはマスの数は2次元の場合と同じで、計算機にとっては同じようにすべての解をすぐに見つけることができた。しかし人にとってはあまりに難しく、1つの解を得ることさえほとんど不可能となり、パズルの面白さが次第になくなってしまった。
ブームの消退も同時に目にすることとなった。
同じマスの数で計算機にとっては等価であっても、2次元と3次元でこれほど難しさが異なるわけである。これらパズルはヒトの知能を測るのに実に適した題材のように思えてしまうが、実はヒトの知能はごく限られた状況にのみ適応して進化したもので、別角度から見ると全然大したことない可能性が十分にある (しかしそのような別角度を自身で簡単に思いつくことができないのでわからないだけである)。
人間の心を「空白の石板」と捉え、「君たちには無限の可能性がある」と説くのは進化心理学でしばしば議論の対象とされる通り。そのようなスピーチを新入生に行っているらしいと聞くと自分はむしろがっかりしてしまう (もっとも多忙な学長の中で、スピーチ原稿を自らゼロから書き上げる人は少ないかも知れない)。
3次元の問題すら簡単には解けない (誰にでもできるわけではないからこそ空間造形が美術的に高く評価されたり、3次元の数学の問題が学力の判別に使われるわけだ) ことは我々が経験してきた進化経路の制約が見事に現れているのだろう。
3次元の数学の問題が解ける人は偉い、とか考えがちだが、多くの部分は3次元の問題を2次元や1次元に落とすもので、勉強とはそのような次元を減らすパターンを学習しているわけである。大学入試もそのようなパターンをどこまで学習しているのかを評価しているようなもので、パターン学習の得意な AI の方が高い成績を示してもまったく不思議でない。
鳥ならばパズルが解けるのかどうかは知らないが、2次元中心の認識力で鳥の行動を解釈するには限界があるだろうことが容易に想像できる。我々が理屈で考える想像よりも鳥の方がはるかに高度なことを行っているかも知れない。カラスが水道の蛇口を自力でひねったなど、我々には高い認知を必要とするように見えるが実は大したことはないのかも知れない。
巣造りなど空間造形の発想や技術はもしかすると鳥の方が上かも知れない。
次元や空間的囲い込みに関係した物事では囲碁や将棋を思いつくこともできる。空間を区切る点など囲碁も2次元よりも1次元要素が多く含まれ、次元を減らす写像の得意な計算機にとっては簡単に克服できたのだろう。AI 以前は人がアルゴリズムを開発していたので、自らの認識能力の限界から有効なアルゴリズムを思いつくことができなかったのだろう。
囲碁の方が先に人を追い越した理由もわかる気がする。将棋でも駒の動きは1次元要素が多く、これまた計算機にとっては次元を減らす写像でうまく対応できるのだろう。駒の動きに制約を設けているのも、それ以上難しいゲームは人に理解できず面白くないためだろう。また同様の意味で、これら現在のゲームは長い年月をかけて洗練されたもので (淘汰と言ってもよい)、人の思考にとって最適化されてきただろう。
新しいゲームを開発してもおそらくほとんどの場合は AI の方にとって有利で、AI より人の方が有利なゲームを開発することは容易でないだろう。
他人同士の対決であっても、追い込んで捕獲するゲームを見て面白いと感じるのは狩猟生活で我々が獲得した認知が反映されているのだろう。
おそらくこのような数理的構造はすでに広く議論されていて、なぜ AI の方が有利なのか答えてくれていることだろう。
計算機に圧倒的に追い越され、今後はさらに差が開くであろう状況でどこまで楽しみを味わい続けることができるだろうか。
人の知能テストに相当するものを動物に与えて動物の知能を推定することが行われているが、例えば空間把握に強い鳥の方にとって有利な課題を我々が考えつくことは、AI より人の方が有利なゲームを開発することと同様におそらく難しい。鳥の方が人を上回っている側面を見つけ出すことは、あるいは今後 AI を用いた鳥類学研究で有効かも知れない。
もっとも人の創作したものを学習させた AI にも人と同じ弱点があるかも知れない。次元を上げる方向の問題設定は案外難しいかも。研究してみていただきたい。
文章も圧倒的に1次元となっていて (より複雑な構造となると読みにくいとお叱りを受けることになったり作文では減点となる)、この点はおそらくほぼすべての言語に共通で、音声に意味を持たせることで始まった進化経路の制約の結果とも言える。これまた AI には扱いやすい構造で、1次元同士の写像が自然に翻訳となっているわけだ。2次元の言語がもしあったならば AI ももう少し扱いに苦労していたかも知れない。
鳥の個体の音声は周波数に分ければ2次元とも言えるだろう。複数個体によるコーラスなどはもっと複雑だろうが、我々も音声1次元しか慣れていないのでもっと高い次元で何が起きているのか想像しにくい。
そうでなくても音声に意味を持たせる (聞きなしなど) ことによって周波数空間では2次元のものを1次元に落としがちなので、単独個体の声に本来含まれている情報さえうまく聞き取れていないことになる。
もともとは何から始まったのかと振り返ってみるとハチクマが丸めた紙を落とす話題だった。(本当かどうか知らないが) 木からリンゴが落ちるのを見て万有引力を考案したニュートンの事例に近い (← こういうの自画自賛と言う)。話がこれほど飛ぶのは自身の本生がおそらく鳥で、概念空間を飛び回りたいのだとご理解いただきたい。
[ハチクマの嘴はあまり曲がっていない?]
ハチクマの爪や嘴はあまり鋭くないとよく書かれているが、こんな嘴の写真もある。Oriental Honey-buzzard (Vivek Sharma 2025.4.26) インドの画像で亜種はおそらく日本のものと異なるがよく似ている。
これほど嘴が曲がっているとハチの子を引き出すのにむしろ支障があるのではと感じてしまうがあまり問題にならないのだろうか。オス成鳥でおそらく食料には不自由せず生きてきたものと考えられるが何を食べているのだろう。Oriental Honey-buzzard 同じ個体で爪が見える画像。
[ハチクマとノスリの骨の強度比較]
一般的にはハチクマに比べてノスリの方ががっちりした体のつくりになっている印象を受けるが、骨の内部構造を見ると必ずしもそうでもないらしい: Bertuccelli et al. (2021) Predisposing Anatomical Factors of Humeral Fractures in Birds of Prey: A Preliminary Tomographic Comparative Study
いずれもヨーロッパの種を扱っているがおそらく東洋の対応種にも適応できるのだろう。以下それを前提に書くと、上腕骨 (humerus) の強度はハヤブサとハチクマの方がノスリやフクロウ類を上回る可能性があるとのこと。ハヤブサの強度が高いのは当然のように感じるがハチクマが高いのは意外な感じがする。
ソアリングにはそれほど骨の強度は必要ないとも言われるが実際にはそうでもないのかも。骨格の外見だけを見るとわからない部分かも知れない。悪天候時のハチクマの飛翔力が強いと言われるタカ渡りの観察者の知見の方が (gross anatomy あるいは肉眼解剖学の) 解剖学者の感覚より正しいのかも。
ふと気になったのでメモ的に残しておくが、初列風切の翼指 (fingers) の数とも関係があるかもしれない。ヨーロッパハチクマで5枚、ハチクマで6枚なのは単純にサイズの違いを反映したものと思っていたが、ノスリは5枚なのでちょっと少ない感じがする。
そう思ってオオノスリを調べてみたところ、飛翔写真を見る限り5枚に見える。体重や翼開長はオオノスリとハチクマは同等かオオノスリの方が少し重く大きいぐらいなので、ノスリ類ではサイズの違いが翼指数にあまり影響を与えないのかも知れない。
それならばもっと大きい種類を調べておかなければ、とワシノスリ [高野 (1973) ではハイイロオオノスリ] Geranoaetus melanoleucus Black-chested Buzzard-Eagle の写真を見てみると翼型は全然違うがやはり5枚に見える。
ワシノスリの尾がかなり短いことを見ると、開けた環境で生息するノスリ類は加速度を要求する敏捷な操縦性能があまり要求されないのかも知れない。
森林性のより強いハチクマの翼の方が操縦性能が必要で、翼もノスリ類より相対的に長いと考えれば強度が要求されるかも知れない (だからこそ? ハチクマの尾羽は強度が買われて弓矢に重宝されるのかも)。ハチクマは例えばオオタカほどではないかも知れないが森林内を自在に飛んでいるが、我々が出会う頻度が低すぎて気づきにくいだけかも知れない。偶然出会った場合に込み入った林を巧みに抜けて飛び去るのを見ることもあるので操縦性能は高いのだろう。
逆に言えばノスリ類の方が相対的に後発なので、森林性猛禽類がすでに占めてしまった森林内より開放環境を得意としたのかも知れない。
クマタカが7枚なのも単に大きいからだけでなく、同様に森林内の操縦性能の要求があるかも知れない。
直接関係ないかも知れないが、ハチクマは樹上のハチの巣などを捕食する際や片足で獲物を持っている場合に翼を支えに使っている映像をしばしば見かける。我々が腕で体を支えるのと似た使い方になっている。もし本当に手ならば使いたいところだろう。このような場合に上肢と下肢の統合がどのように行われているのか神経科学的にも面白いかも。
純粋に飛翔のみに翼を用いるタカ類に比べて要求水準が高い可能性もあるかも知れない。
渡りの際にものすごく欠損の大きいハチクマを見かけてよく飛べるものだと感じることもあるが、こんな写真もあった Oriental Honey-buzzard (Charlie Bostwick ブータン 2025.5.20)。初列風切は対称的に近い欠損なので通常の換羽だろうし次列風切も派手に欠損している。いずれにしても飛翔力には相当の余裕があると見てよいのではないだろうか。
[ハチクマの繁殖行動]
繁殖行動は成書にも詳しいので主に有益な文献を紹介しておく。
計測値のところでも引用した久野 (2006) Birder 20(10): 20-27 は日本のハチクマの比較的新しい基本文献と言ってよいだろう。いろいろな側面からの情報が述べられている。Birder のこの号はハチクマの特集で、衛星追跡によってハチクマの渡りが明らかになって一般的にも話題になっていた時期であった。
少し古いバックナンバーで入手が難しいこと、日本語のため海外に紹介しにくいのは難点である。ハチクマの英語論文は限られた視点のものしかなく、海外の研究者にとってはハチクマは生態がほとんど知られていない種と考えられているようである (ヨーロッパハチクマの論文は多数あるのでこれはある意味正しいが)。この特集号に相当する英語論文があってもよい気がする。
佐伯・堀田 (2014) Birder 26(9): 16-17 に「日本で過ごすハチクマの暮らし4か月」の記事があり、ここでは抱卵は雌雄がほぼ 24 時間交代で行い、抱卵していない方の個体はほぼ1日フリーで遊びに行ける印象を受けるが、久野の記事ではペアによって様々なパターンがあるとのこと。
近場に養蜂場があるかどうかにもよるかも知れない。
ひなは兄弟をいじめることもしないとある ([兄弟殺し] の項目も参照。韓国で確実な兄弟殺しの事例が記録された)。
また 2006-2012 年の7シーズンに同じオスがメスを変えることが3回あった (つまり4羽の違うメスとつがいになった) との報告がある。この事例は「日本のタカ学: 生態と保全」(東京大学出版会 2013) でも紹介されているが、ヨーロッパハチクマの追跡結果ではあまりつがい相手を変えない印象を受ける。
ハチクマで一般的性質なのかはよくわからない。マレーシアの事例ではつがい関係が長期継続されているが渡りを行う亜種かどうかにも依存するのかも知れない。
「アニマ」1988年2月号 (pp. 84-99。オオタカの記事内)
宮崎学氏によるとオオタカはなかなか姿を姿を現してくれないがハチクマはよく姿を現す。オオタカとハチクマは割合近い位置で営巣していることが多い。宮崎氏はオオタカを見つける際にまずハチクマを探す。「ハチクマのいる所にオオタカあり」と記述している。
皆さんの印象と比べていかがだろうか? ハチクマは繁殖地で見ることが通常なかなか難しいとされるが、宮崎氏のフィールドとされた地域はハチクマが多いのかも知れない。また宮崎氏はタカの観察に声を重視しており、通常の観察者があまり訪れない夜明け時間帯などの音声情報などの手がかりも使われているかも知れない
(後に紹介するマレーシアのハチクマの事例ではつがいの音声コミュニケーションについても述べられており、想像以上に声を使っているかも知れない)。
オオタカはハチクマのひなも狙うのでハチクマがわざわざ選んで近い位置で営巣しているならば興味深いところである。
同記事にはオオタカの古巣 (複数持つ巣のうち使用していないもの) をハチクマや他のタカ類が利用した事例も紹介されていた。
宮崎 (1987)「鷲鷹ひとり旅」でもこの記事で紹介されているものと同一と思われる、同じ山の狭い範囲にオオタカ、ハチクマ、トビ、ノスリが営巣した例が紹介されている。
「ハチクマのいる所にオオタカあり」は一般的記述と思われるので、この事例だけを指したものではないだろう。
他項目 [ロシアのハチクマとヨーロッパハチクマの研究のための情報] や [音声] および#オオタカ備考にも関連情報を取り上げた。
[擬態] の項目で示したように南から東南アジアではカワリクマタカ、ハチクマ、カンムリワシも同所的に生息しているが、互いに近い距離で営巣しているかまでの情報はわからない。
カワリクマタカで提案されているようにオオタカ、ハチクマ、トビ、ノスリは主な食物がそれぞれ違うので互いに比較的寛容なのかも知れない。
オオタカ、ノスリはヨーロッパでもアジアでも大きさはあまり違わないが、ヨーロッパハチクマに比べてハチクマが大型なのはアジアにはクマタカ類がいるためかも知れない。
「アニマ」1989年1月号 (#トビの備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] 参照) にも宮崎氏の対談「童話に生きる鷹少年」があり、ここでも (なかなか出会えない) タカの世界に声から入ることが紹介されている (海外研究者の事例だが [60 年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)] の記述を見てもまったくその通りである)。
宮崎氏によれば種ごとに違った声でコミュニケーションをとり、声 (鷹語) の意味もわかるとのこと (表題の「童話に生きる」はこの部分を比喩したもの)。
別に紹介するマレーシアの繁殖ハチクマの映像や記述では声でコミュニケーションをとっていて観察者も声で行動を聞き分けていることは確かなので、タカにも豊富な音声レパートリーがあって使い分けているのかも知れない。
自分も #オオルリ で一部紹介するような音声レパートリーを把握して行動も理解しているが、この把握にもかなりの年月を要している。数も行動頻度も少ない猛禽類で把握するのは相当の期間と経験が必要だろう。スズメ目とは違う点もあるだろうが地鳴きがいろいろな意味を伝える機能はタカでも実はそれほど違わないかも知れない。
「アニマ」のこの号は「日本の鷲鷹」特集なので関心のある人には大変興味深いであろう記事がたくさんある。
ジャーナリストの坂本正治氏による「追跡! ワシタカ密輸ルート」の記事がある。前半は恐らく皆様も時代から期待されるような密輸ルートの解明の記事となっているが (当時は剥製がまだ売られていたがそれほどの需要はなかったとのこと)、かなり意外な展開に結びついている。
著者も「結末は最もつらいものになってしまった」とサブタイトルに挙げているので読みたくない方は以下飛ばしていただいてよいだろう。
上述の宮崎氏 (この記事では M 氏としているが記述より実名は明らかであるが) が密猟者疑いとして日本野鳥の会の一部からマークされていたことがあったことが記されている。
当時は日本野鳥の会がオオタカ保護運動を進めており特殊鳥類に指定されるなど一定の成果を挙げていたが、インタビューで市田則孝氏 (後にバードライフ・アジア初代代表となり、現在バードライフ・インターナショナル東京) は「日本古来の鷹匠術を文化財として認めない考え方にたってオオタカ保護運動を進めたのか?」の質問に対して
「滅ぼしてしまおうとしたものではなく、なくなっても仕方ない、残すに値するものがないと聞いている」
と返答している。
(この質問はここでは唐突に見えるが、密猟者、鷹の飼育者などの複雑な関係が取材により明らかになってゆく途中の過程を紹介しきれないためである。この部分は実話や聞き取り調査などもあるが実名は伏せられている。上記 M 氏の扱いもそれに合わせたものと思われる)。
保護関係者から得られた情報は事実上2種類しかなかったとのことで、今で言われる偽情報に相当するものがグループ内で拡散していったものらしい。
この記述やその後に述べられる解釈には坂本氏独自のものが含まれていると思われるが、結果的に限られた情報に伴う視野の狭い運動が日本の自然保護を歪めてしまった部分はあるように感じる。
これは市田氏個人や日本野鳥の会への批判のつもりではないが、その後の歴史が当時提起されたさまざまなことを物語ってくれているように感じ、歴史を読み解くつもりで書いている。
日本野鳥の会の古くからの会員の方はこれ以降の時代に起きたことをご存じであろうし、鷹匠術に対する当時の価値観を引き続き保ち続けられている方もあるだろうと思う (鷹狩りはさまざまな側面の事項があり一筋縄ではないわけだが)。
しかし日本野鳥の会の若手会員減少や、なぜ海外諸国のように関連団体がまとまっていないのかなど「これ以降の時代」に起きた出来事、そしてこの時代に示されていた遠因と無関係とは考えにくく、結果的に坂本氏の指摘は正鵠を射ていたのではないかと感じる。今となっては関連団体間の障壁はそれほどではないかも知れないが。
興味ある記事の詰まっている号なので何らかの手段で読むことができれば一読をお勧めしたい。
#コマドリの備考、[コマドリと少年、手塚治虫さんとかつての日本野鳥の会のこと] キューソクさんのコラムなども関係。
同項目にある「アニマ」1984年5月号の特集「創立50周年を迎えた<日本野鳥の会>」にも対談があるが、当時の日本野鳥の会の会員数は 13000 人。5年も経過しない時期に「結末は最もつらいものになってしまった」と書かれるに至ったのは何が問題だったのだろうか。
[死体をおとりに使うか?]
Birder 2003年7月号 (該当記事を読めていないのでこれに対する回答のみからの考察になるが) のバーダー質問箱に小野氏が巣のカエルやトカゲの死体をおとりに使ってハチをおびき寄せているのではとの質問があったようである (人間の行うハチ追いには同様のものを用いる)。
久野 (2004) Birder 18(2): 82-83 がハチクマのひなはカエルなどを食べるのが苦手でハチの巣が運ばれてくると食べ残しになることがあるため、おとりよりも単なる食べ残しなのではと回答している。またハチクマにハチ忌避の臭気があるならばハチが寄り付かないだろうことの述べている。
ハチクマ7個体を捕獲時嗅いでもらっても誰も特別なにおいを感じなかったとも記載されているものの、ハチの行動変容からハチの巣を襲う時のみハチをおとなしくする臭気を出す可能性も検討されている。
小野氏によれば片方の翼を開いて真上を覆うようにして巣盤をついばむ様子が観察されており、口かあるいはどこかから臭気を出している可能性も挙げられている。
久野氏のこの回答に対するコメントを述べておく。
動物園個体を観察した印象では、片方の翼を開く行動はバランスを取るため (片足で掴んで食べることもあるので片足だけでのバランスが難しい)、あるいはマントリングの一種ではないかと思う。
台湾のハチクマの巣のビデオ中継では前述のように巣ではハチ忌避の機能 (臭気) はないように見え、湿度の高い時はハチが訪れていたので食べ残しの死体が副次的にハチを誘引している可能性はありそうに見えた。飛び立つ時にそれを追いかける様子はなかったので意図的なおとりとしては役立っていないのではないかと思う。
後で気づいたのだが、「スズメバチの科学」(小野正人 1997 海遊舎。この本は表紙がスズメバチの巣をひなに運ぶハチクマの写真で、Birder の書評によれば宮崎学氏ともつながりがあったそうである) の著者の講演で
「ハチクマはスズメバチの巣を襲い、幼虫やサナギを食料としています。まず自分の巣にカエルやヘビなどを運び込み、それらに近づいてきたスズメバチを追跡し、巣を発見します」とある (社会性ハチ類の知られざる生態-ミツバチ、マルハナバチ、スズメバチと私たちの生活との関わり 玉川大学 読売新聞社立川支局 共催 2018)。
あるいは宮崎学氏の観察結果なのかも知れない。ここに記されている社会性昆虫におけるハミルトンの血縁選択は生態学理論 (社会生物学) の花形でもあるので興味ある話題が詰まっている。
韓国のドキュメンタリーでカエルの死体をおとりにクロスズメバチ Vespula flaviceps をおびき寄せると説明されている (英語字幕あり):
(ENG SUB) What would happen if birds of prey evolved to hunt bees exclusively? (EBS Documentary 2025)。2022 年放映の DocuPrime - The Relentless Attraction, Part 1: The Nesting and Hunting Scenes of the Honey Buzzard and Various Seasonal Changes in Nature から。
0:14 付近。そのまま待っていればハチが巣に戻る。クロスズメバチは通常では地下の隠れた場所に巣を造るので探すのは容易ではない。ハチクマは賢くハチが巣に戻るのを追いかけて巣を見つけると説明されている (確かに賢そうな表情を映している)。巣を掘る様子も紹介されている。ハチにまとわりつかれて追い払っている映像。体や翼でもハチの不快感を感じているのか振り払っている。そしてあきらめて一度退散した。
しかししばらく退避して再度挑戦する。これは獲物を見つけた猛禽類の習性とのこと。再度の挑戦までに待機しているうちにハチの攻撃が弱まるのか (?) その場で食べている。[ハチの幼虫を主食とする猛禽類・ハチの巣の蜜蝋を食べる鳥] で紹介のアカノドカラカラで提唱されている absconding に似た反応があるのかも知れない (アカノドカラカラでは化学防御物質を出していないらしい)。
ただし映像化で編集されているはずで実際の時間経過は不明。なおこれは若鳥。
その後巣で子育ての映像が続く。初の産卵の際には通常1卵とのこと (ハチの巣を掘っている個体と繁殖個体は別なので要注意)。
7:05 17 日齢のひな。肉を与えるオス。このつがいもオスが主に食物を運び、メスがひなの世話や巣の掃除をするとのこと。
再びハチの巣の捕食映像では、ハチの天敵は少ないが地中のものは他の哺乳類にも食される。空中のスズメバチの巣はハチクマ以外に外敵がないとのこと。
ハチに刺されない体の特徴、嘴や爪の鋭い猛禽類の特性がハチの巣捕食を可能にしている。11:47 再度おとりを使ってハチの巣を見つける知能があると説明されている。猛禽類が本気でハチの子食に専念したらこれほどの適応が可能であるとの文脈で紹介されているように見える。他の系統でここまでハチの子食に適応した種類がないのはやはりタカ類特有の優れた能力が随所に現れるためだろうか (知能がある説明も自分はある程度納得したい)。
韓国では深山の鳥とのこと。後半の解説には多少正しくない部分もあり、一般向けに脚色されていると思われるが、カエルの死体をおとりに使う部分の映像は実際の生態を反映したものだろうか。
生きた獲物の貯食の役割? その後週間アニマルライフ (1973) p. 3730 モズヒタキの項目 (斎藤) に面白い情報を読んだ。
カンムリモズヒタキ Oreoica gutturalis Crested Bellbird (オーストラリアの種類) が生きた獲物を繁殖期に蓄える習性があるとのこと。巣にチョウやガの幼虫を、巣のへりの上や、巣に卵のあるときは巣のなかにおいておく。くちばしで幼虫を殺さないていどに強くはさみ幼虫の神経を麻痺させる。幼虫は生きてはいるが正常にはいでて巣から逃げるほどでもない。
つまり彼らはえさを腐敗させず新鮮なまま蓄えていることになるとの記述。
(#アサクラサンショウクイ備考にも紹介)。
ヨーロッパハリモグラ (現在の種名不明) がミミズの頭部だけをかみきって生きているが動けない状態で地下にたくわえる習性があると言われており、類例として紹介されていた。
ただし毛虫の幼虫は孵化したひなの食物ではないらしい (コンサイス鳥名事典) のようにおそらく反論があるのだろう。
ハチクマがカエルを完全に死なない状態で巣に持ち込むのは同様ではないかと思えた。台湾のハチクマの巣の中継でもカエルが運び込まれる状況がしばしばあったが、まだ動いていて時には逃げてしまうことがあった (その場合逃げるのを捕えに行かずただ見ているだけなのがまた面白かった)。半分いわゆる "脊髄ガエル" 状態になっていて反射だけで逃げることが可能だが脳はやられている状態。
獲物が鳥の場合にはその状態ではおそらく完全に死んでしまうが、カエルならばしばらくは新鮮な状態が保たれるのかも。
カエルはひなの好物ではないかも知れないが、悪天候などで狩りに出にくい場合は親がちぎって与えればよい、生きた保存食となり得る (食物が現在ほど豊富でなかった昔、子供は好きではないが保存食も食べさせられた経験と重なってしまう)。
カエルは毛虫ほどは外敵侵入防止にならないかも知れないので、ハチクマの事例の方が「保存食として生かしておく」よりよい候補になるかも。付随的にハチのおとりの役割も果たすのかも知れない。
[ハチクマの哺乳類食]
Gluschenko et al. (2020) Breeding birds of Primorsky Krai: the crested honey buzzard Pernis ptilorhynchus (極東の鳥類42「沿海地方の繁殖する鳥類 2」 で訳文が読める)
によればロシア沿海地方南東部では「ネズミの当たり年」にはネズミも捕食し、タイリクヤチネズミ Clethrionomys rufocanus は多い年 (原文複数形) に食物の 22.9% を占めたという。しかし全体としてはおそらく哺乳類は (数が多い状況で) たまたま食べるものと解釈している (原文 sluchajnyj たまたまの。英語では facultative に対応しそうである)。
この点はトビの哺乳類食にも似ているようである (同じく Gluschenko et al. の #トビの備考参照)。
[ロシアのハチクマとヨーロッパハチクマの研究のための情報]
Karyakin (2004) "猛禽類の調査方法" (参考文献参照) に興味深い情報があった。この地域はヨーロッパハチクマが中心でハチクマの情報が少しある。ヨーロッパハチクマと共通の部分はヨーロッパハチクマの方にのみ記載しておく。
ハチクマとヨーロッパハチクマの識別 (pp. 175, 180-181)。
ヨーロッパハチクマの飛行シルエットはノスリ類とハイタカ類の中間型 (p. 176)。
ヨーロッパハチクマのところに特にウラル地方南部ではヨーロッパノスリやオオタカの古巣も用いるとある (p. 178)。「ハチクマのいる所にオオタカあり」([ハチクマの繁殖行動] の項目) との宮崎学氏の見解もこのような生態的理由もあるのかも知れない。ヨーロッパハチクマと他のタカの種間関係の研究はスカンジナビア半島や西ヨーロッパのものが中心だが、ロシアでは多少状況が違うかも知れない。
ヨーロッパハチクマでは新鮮な青葉の付いた枝を必ず使う点が他のタカの巣と異なる。他のタカの巣ではひなが生まれた後周囲に糞が飛散するがヨーロッパハチクマではひなが大きくなっても外に出さない。ハヤブサ類の方に似ている (別項目 [ハチクマ類が糞を飛ばさない理由?] で検討した)。
産卵時期はヨーロッパノスリやオオタカより1か月遅い。巣間距離は生息密度の高いところで 0.5-3 km で平均 1.5 km。低いところで 3-10 km で平均 5 km。ヨーロッパハチクマは十分普通に生息するが隠蔽的なためあまり調べられていないだけである。
巣を守っているメスは飛び立つとすぐに下方に飛んで木々の間に隠れてしまう。時に巣の上空でデモンストレーション旋回を行って樹冠を通して見ることができることがある。このような場合にヨーロッパハチクマの声を真似ると返事してくるとのこと。
ハチクマの歩き方 ヨーロッパハチクマの足跡を見ることもあり、ワタリガラスのものに似ているが爪はずっと長い。ヨーロッパハチクマが歩く時は羽の生えた部分のふしょを支えにするため後趾の痕があまり残らないが、第 II, III 趾の痕は強く残る。
注記: これは捕食性タカ類の強力な 第 I 趾は生存に必須だが歩くにはあまり適さないことを示唆しているように思える。しかしハチクマは歩く時の足の使い方まで人に似た部分があるのか [半分冗談? 川口 (2021) Birder 35(2): 54-55 参照]。やはり異色のタカだ。
ハチクマ類ではふしょのかなりの部分を羽毛で覆うことでハチによる攻撃を避けつつ、歩行にも有効で一挙両得だったのだろう。足のうろこは羽毛の変化したものと考えれば羽毛で覆うことはわずかの遺伝的変化で簡単に実現できるのだろう (#ライチョウの備考 [鳥類と爬虫類のうろこは別物] 参照)。
2本趾の対趾足だとむしろ安定性が増して地上性カッコウ類、例えばミチバシリのような生活形態に都合がよいのかも知れない。
他の動物によるハチの巣食痕との違いなど生活痕の解説部分もあり、ヨーロッパハチクマはしばしばハチの巣を近くに運んで樹上に置いて巣盤を取り出す。この場合は残りはそのまま地面に落ちるか枝にひっかかっていることもある。このようなハチの巣には特有の "割れ目" がある。
ヨーロッパハチクマでペリットはまれで、小型のスズメ目や齧歯類のような複雑なものを食べた時に出されるとのこと。ヨーロッパノスリのものに似ているが褐色味が少し強く多少小さく、明るい灰色のことが多い。
ハチクマの音声への反応 到着したばかりの5月には定点観察でも生息を確認できることがあるが、音声のプレイバックが最も役立ち最大 90% の率でつがいを発見できる (同書 p. 104 にタカ類全般の音声のプレイバック法の情報あり) 開けた地域で場所が十分特定されていれば徹底的な調査で巣が発見できることもある。
長期間雨が続いた後の雨上がりの際に複数のテリトリーからのメスが集まり、河川渓谷やさらには大きな平原や沼地の上空を高空を旋回しながら声を出すことがある。その後分かれてそれぞれの方向に向かうものを追跡すれば通常何日もかけて行う巣の探索よりも多くの巣を発見できることがある (p. 180)。
ヨーロッパハチクマに比べてハチクマは混合林を好み、暗色の針葉樹林は避ける。森林の開けた場所から 100 m 以内に造る。ヨーロッパハチクマ同様に他のタカの古巣も利用するだろう (p. 182)。
p. 183 にハチクマの生息状況の調査にも音声のプレイバックが最も役立つとある。面積が広いので通常の巣の探索方法は徒労に終わるとのこと。
目視での探索が徒労に終わった [60 年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)] の事例を見るといかにもと納得できる。
オオタカとハチクマの音声反応の比較 興味深いことに p. 210-211 にオオタカではプレイバック法が(ヨーロッパ)ハチクマよりもずっと成績が悪いとある (ワシミミズクの声も用いている)。オオタカはより近距離でないと反応しないとのこと。(ヨーロッパ)ハチクマの方が音声をより積極的にコミュニケーションに用いているらしい。
これも(ヨーロッパ)ハチクマの生息環境が見通しの悪い森林であることにも影響があるのでは。姿の見えない相棒を呼ぶには声はぜひとも必要なのだろう。おそらく調べられていないだろうが(ヨーロッパ)ハチクマの方が聴力がよいのかも知れない (以下 [音声] の項目へ)。
同じく [ハチクマの繁殖行動] の項目の宮崎学氏のタカの観察に声を重視していることも述べられており、森林性タカ類の研究には音声は非常に重要なのかも知れない。
Karyakin (2004) のこの部分ではオオタカの繁殖証拠を見つけるのが難しいことが述べられている。越冬時期に見つけるのはさらに難しいとある。p. 215 ではハイタカは繁殖期の巣からの声で結構見つけられるとのこと。ハイタカは孵化後よく鳴くのでより容易になるとのこと。強力な猛禽類のオオタカでも生息を隠して明らかにしないのか。
宮崎学氏の「オオタカはなかなか姿を姿を現してくれないがハチクマはよく姿を現す」記述とも整合しているように見える (#オオタカの備考に)。
同書 p. 104 に巣に観察者が近づいた場合の反応の違いが述べられている。50-300 m 程度に近づくと警戒音を出し始めてさらに近づくと鳴きながら上空を舞う種類もあるが、例外はイヌワシ、ヨーロッパハチクマ、一部のカタシロワシとカラフトワシが挙げられている。もっともこの書物で取り上げられている種類にはよく鳴くハヤブサ類も一緒に含まれているのでそれらに比べれば違いが目立つのだろう。
イヌワシや(ヨーロッパ)ハチクマは近づくと通常警戒音を出さずに巣を去るとのこと。
p. 140 にカタシロワシは繁殖確認が最も行いやすいワシ類の1種とある。イヌワシと性格がだいぶ違うよう。
[ハチクマ類が糞を飛ばさない理由?]
[ロシアのハチクマとヨーロッパハチクマの研究のための情報] の Karyakin (2004) から派生したもの。これはおそらく巣を明らかにしないための戦略の一つなのだろうと想像する。
ひなの糞をどう処理するかはおそらくどの種でも問題だが、巣の衛生を保つために多くのタカ類は外に飛ばし、ハチクマは飛ばさない代わりに青葉を敷いたり親が食べてしまうことで衛生を保つ別の方法を選択したと考えれば理解しやすそう。
異なる戦略はそれぞれ有力な方法で独立に進化し得たが、ハチクマ系統が熱帯出身でより早い時期に分岐したことに関係あるかも知れない。熱帯では競争者も捕食者も多く、なるべく所在を明らかにしないのが有利なのだろう。我々が普通に比較するタカ類は比較的北方型が多く、開けた場所に巣を造る習性が進化しやすかったのかも知れない。
さらに "被写体に選ばれやすい" 選択バイアスも入っていると思われ、要するに海ワシなど開けた目立つところに営巣しやすい種とハチクマを比較すると違いが目立つのでは。
また目立つ巣は必ずしも持ち主が強力であることと関係ないかも知れない。一般的に考えれば隠した方が適応度は高まりそうで、目立つ巣はそれを上回るメリットがある場合のみ進化するとも考えられる。
同種内の社会的順位を示す信号や性・社会選択が思い当たる。#トビ備考の [トビの巣の飾りは同種への信号?] の考え方は面白いと思う。トビの場合は同種に積極的に見せた方が有利な側面があって比較的目立つ巣を造るのかも (トビは海ワシに近縁なことも思い出そう)。
ヨーロッパハチクマでは巣の近くでの捕食が圧倒的 (central forager behaviour) ([ヨーロッパハチクマによるオオスズメバチの巣の捕食] の項目参照) とのことで、巣の近くに同種の営巣を妨げる理由になるだろう。トビの場合はそこまでで資源集約的ではないと思われ、緩いコロニーに近い繁殖も可能で社会的信号に選ばれやすいかも知れない。ハチクマではそのような生活様式は採用されずディスプレイ飛行などを性・社会選択のために選んだのだろうか。
ミサゴの巣が目立つのは海ワシ類と同じような理由とともに、海鳥に似た飛行性能特性が最も考えられるだろう。タカ系統の出身でありながら海鳥に部分的に収斂進化していると考えるとわかりやすい。
いずれにしても見やすい、あるいは写真撮影に好まれる種を標準として生態の一般論を考えるとバイアスが入りがちだろうと思う。見つけにくい種は理由があるはずで、その生態的理由はおそらくかなり一般的に当てはまる。見つけやすい種はむしろ例外的で、目立たせる特有の理由があると考える方が自然に思える。
見つけにくい種は写真的成果が少ないので調べられにくいならば大変もったいない。
ではタカ類とハヤブサ類の排泄習性の違いは何が原因かと問われるとあまり理由を思いつかないが、単に系統の違いなのだろうか。ハヤブサ類は開放環境が中心で自身で複雑な巣を造らないので衛生上の問題が少ないのかも。
糞を飛ばす/飛ばさないは生理的には何が違うのか多少気になるところだが、ハチクマも遠くまで届く声を出すので体腔内圧の違いではなさそうな気がする。
あるいは括約筋の働きの違いの違いも考えられそうだが、こんな情報もある Gee et al. (2004) Reproduction in nondomestic birds: Physiology, semen collection, artificial insemination and cryopreservation
(出版社リンク切れ? ResearchGate)
この論文は人工授精の技術を扱ったもので、p. 60 によればコンドル類やワシ類 (ここではハクトウワシ) の総排泄孔の筋肉は強力で強力なマッサージが必要とのこと (pp. 63, 64, fig. 11 のキャプションも参考)。
カリフォルニアコンドルの排泄場面: California Condor Pooping 巣の外には飛んでいないので巣を汚さない目的にはあまり役立っていないかも。自身の羽毛を汚さない程度の飛ばし方か? この研究もあくまでアメリカの野鳥を扱ったものなのでワシ・タカ類全般に当てはまる話かどうかは不明。
巣のビデオ映像からの推測だがハチクマはおそらく抱卵・抱雛中に巣の中では排泄せず飛び立って外で用を足しているだろう。親はちょっと外に出ればよいだけなので。
筋力が関係するとするならば、の場合の参考資料として紹介しておく。
もっと簡単な話で糞を飛ばさない鳥は単に力の入れ方を手加減しているだけかも知れない。巣の外に排泄しない生態的適応とともに食物の違いに伴う糞の水分量の違い (例えば魚食の種は水分量が多いかも?) など別要因もあるのかも知れない。タカ類の糞の飛ばし方の系統研究など行うと面白いかも知れないが排泄映像のサンプル数が少なくて難しいかも。
マレーシアのハチクマ若鳥が糞をする映像があった: Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7284 (Sein Chiong Chiu 2025.6.16 撮影)。
この映像ではしっかりした量を出していて下に落としている。尾は思ったほど上げていないがしゃがんでいる。小鳥のように自然に出るのではなく体腔内圧をかけているように見える。
淡色の個体で、とまっている映像では淡色型のカワリクマタカによく似て見える。Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" で大きさを確認しておくと、この地域のカワリクマタカ (亜種 limnaeetus) で翌長オス 380-430 mm、メス 405-482 mm、体重メス 1.36-1.81 kg とある。全長は出ていない (カワリクマタカは亜種間の大きさの違いが大きいので個々に調べる必要がある)。
ハチクマの方の torquatus (亜種として扱う場合。留鳥亜種なので渡り亜種ほど翼は長くない) ではオス 398-000 mm、メス 000-455 mm となっていて、この亜種の体重記述はない (最小・最大の数字しかなく、オス・メスに仮に割り振った表記と思われる)。
日本のハチクマの体重から推定するとカワリクマタカの方が体格を反映しておそらく少し重いが、大きさはハチクマとおそらく大差なし。日本のハチクマとクマタカの関係とは少し異なる。
バードウォッチャーでも間違えるぐらいなので捕食される側からはどちらも同じに見えるのではないだろうか。
Oriental Honey-buzzard (Haemoglobin Dr 2025.6.14) はインドの画像。飛び立つ前の姿と思われるが尾を上げているので直前に糞をしたところかも知れない。この姿勢ならばあるいは飛ばしていたのかも。
[大部分肉で子育てをするハチクマ]
日本とは異なる亜種だがマレーシアで 90% は肉を与えて子育てをしているハチクマが紹介されている。同じつがいの過去のひなに比べて成長が早いとのこと。[マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] の項目に考察も加えて紹介。
Oriental Honey Buzzard busy to eating his prey (Wild trekker Chandan 2020) おそらくインドと思われるが獲物は何だろうか。
木の枝の上で赤身の肉を食べているハチクマはあまり想像しにくいかも知れないが、少し考えてみると世の中に出回っているハチクマの食事映像のおそらく大部分はカメラをセットできるような場所 (場合によっては "やらせ" 的なセットもあるだろう) あるいは巣のライブカメラによるもので、このような生態はなかなか記録されないのであまり知られていないだけかも知れない。GPS 追跡をしてもこのような生態までわからないだろうし。
ハチの巣の捕食シーンや巣に小鳥のひなを運んでくる映像ばかりを見て判断すると先入観が入りすぎるかも知れない。
Oriental Honey Buzzard eating its prey (a small bird) (Passion of Nature and Wildlife 2025.5) こちらは小鳥を食べているハチクマのオス (インド)。口を開けた息づかいの様子からはちょうど捕らえたところだろうか。
Oriental Honey-buzzard (Peter Christiaen 2025.7.19) 鳥を運ぶタイのハチクマ。尾のパターンは日本の亜種ではオス成鳥に相当、しかし虹彩は黄色。尾の白い部分はメラニンが少ないため強度が低いようで摩耗が激しいことがわかる。何の鳥かは記述なく記録種一覧を見ても判然としない。
Oriental Honey-buzzard (Peter Christiaen 2025.7.19) 同一個体。それにしても尾の傷みは相当のもの。
[兄弟殺し]
(ヨーロッパ)ハチクマでは兄弟殺しあるいは兄弟間闘争はほとんど見られないとされているが (しかし#イヌワシの備考も参照)、Siblicidal behaviour in Honey buzzard Pernis apivorus という映像は紹介されている (猛禽類研究家 Valentijn van Bergen による)。傷つけておらず、単なるつつき合い程度のものであるとのコメントがある。
なお Pukinskij (2003) の観察によると「食物不足だと大きな幼鳥が小さな幼鳥より常に多くの餌を得て、小さい方を攻撃する。大きな幼鳥の攻撃性は6〜7日齢から 14 日齢までにとくに強いが、15〜17 齢ではまったくなくなる」との記述を残している (Gluschenko et al. 2020。原文・訳文は上記項目参照)。
[中国のハチクマの繁殖生態] で紹介されたビデオ (2024.10.24 公開) で明瞭な兄弟殺しが記録された。同項目の "Honey Buzzard, the big brother wants to eat the little eagle" のビデオと考察を参照。その後さらに追加の映像が紹介されており、どのような段階を経てで小さい方のひなを食物として与えるようになったか経緯も記録されている。
これまでのハチクマに関する一般的常識を覆すような映像資料であり、一連の映像をぜひご覧いただきたい。
Gluschenko et al. (2020) の記述が正しかったとも言えるだろうし、食物量に依存するのかも知れない。また大陸と日本で習性が異なる可能性もあり得ないと言い切れないかも。
#ヤツガシラのように食物が豊富でも最後の子を食物とするものとは異なるようにも見える。ヤツガシラの嘴では肉を引き裂けないが、ハチクマの嘴ではある程度成長しても食物とできるよう。
Gluschenko et al. (2020) の同文献には「雛は1日目から大きさや体重が違い、これは多分性差 (雄が小さく、雌が大きい) によるものである」との記載がある。この考えは (ヨーロッパハチクマも含めて) ロシアの研究者の間で共有されているようで、巣内びなでも大きさで性が識別できると考えているらしい (クリミア初のヨーロッパハチクマの営巣ビデオで性別が述べられていたので聞いてみたところ、このような回答を得た)。
ヨーロッパの研究者のヨーロッパハチクマの研究では巣内びな段階で外見で性が識別できるとは考えられていないようである。
非同時孵化にもかかわらず兄弟間闘争が少ない理由として、抱卵最初から全力で抱卵するのではなく、ヨーロッパハチクマでは抱卵開始時点で 29 ℃ で徐々に上がって8日後に 39 ℃ で安定するとあり (出典)、
産卵に間隔があっても孵化時には日齢差が縮まっているとのことである [Der Wespenbussard (1955/2004)]。
オオタカでも同様の現象が知られており、広義の Accipiter 属で相対的に兄弟殺しが少ないのはこのような回避メカニズムも影響している可能性もあるのかもしれない。
[韓国のハチクマの繁殖]
First Breeding of the Oriental Honey Buzzard in Korea
(ARRCN Newsletter December, 2010) にあるように2009年8月16日に巣にいるひなが目撃されたのが繁殖の初確認だったとのこと。意外にも最近の発見で渡りルート上、気候的にも日本と大きく違わないのに繁殖例が少ないのは不思議でもある。
Oriental Honey Buzzard (birdsee3496 2024) 子育て映像例。ひなは自分でついばめそうだが親から幼虫をもらっている。
Oriental Honey Buzzard (birdsee3496 2024) 子育て映像例。上記より少し成長して肉の破片も自分から食べている。与えている肉はカエル? このメスは獲物を右足で掴んでいる。日本同様にセミの声の背景音が大きいことがわかる。
Honey Buzzard Nesting ひなを抱くメス。
Oriental Honey Buzzard オスがひなにハチの幼虫を与えているところ。唾液も与えているように見える。
(Siberian honey buzzard) (K birds 2024.10) 韓国ハチクマの巣とひな。オスが巣にいるところにメスがハチの巣を持って戻ってきた。オスはその後飛び出す。ひなはあまり空腹でないのか食物を与える場面は出てこない。
(ひなを羽繕いする親?) メス自身も途中で頭かきを行っている。成鳥の相互羽繕いではきずなの維持や社会的役割が主に論じられるが、この事例では親と子であまりに非対称で古典的に説明される社会的役割によって進化した行動とは考えにくい気がする。
外部寄生虫などを除去する行動は適応度を上げると考えられるので進化する可能性がある。これは相互羽繕いの生態学的解釈として古くから知られているが異論がないわけではない
[例えば Kenny et al. (2017) Allopreening in birds is associated with parental cooperation over offspring care and stable pair bonds across years]。
興味深いことに古い系統の鳥ではほとんど見られないとのこと ([#鳥類系統樹2024] Neoaves 解説の Jensen et al. (2023) を参照)。
疑い深い人 (?) は自身も途中で頭かきを行っているので自分がかゆくなって転位行動でひなをかいたなどと解釈するかも知れないが、自分の頭かきの後にも続けている。愛情表現とは考えられないだろうか。子育ての早い段階でオキシトシン (*1) もよく分泌されているだろうから我々における役割と相同と考えてもおかしくないように思える。
親がひなの体に触れ、ひなが rattling call を出して応じている状況は 2021 年の台湾の巣の中継でも観察されていた。
備考:
*1: かつては鳥類などでは Mesotocin メゾトシン [由来は脳下垂体中葉から分泌されるためと聞いたが、Kamkrathok et al. (2017) Distribution of mesotocin-immunoreactive neurons in the brain of the male native Thai chicken を見ると違うかもしれない。
分泌は後葉からのようで eminentia mediana (median eminence) の方が由来かも?
哺乳類のオキシトシンとは1アミノ酸が違うのみ]
と呼ばれていた。生理学の解説でもおそらくこの名称が残っているだろうし過去の記事・論文などを読むと出てくる。
現在では哺乳類同様にオキシトシンと呼ばれる。cf. Theofanopoulou et al. (2021) Universal nomenclature for oxytocin-vasotocin ligand and receptor families。
この提案の背景には比較ゲノム学の進歩があったとのこと Researchers propose a new universal nomenclature for vasotocin and oxytocin genes (Emily Henderson, News Medical Life Sciences 2021)。
生物の学名以外にも分子系統解析はこのような分野にも影響を及ぼしている。
ヒトで使われる名称に合わせることは鳥類の生理学者もおそらくあまり抵抗がなかった。
この論文では Vasopressin バソプレッシンのグループも哺乳類以外に合わせて Vasotocin バゾトシン とする提案を行っているが、Vasopressin バソプレッシンの名前はあまりにも普及しているために統一はあまり進んでいないよう (もし統一すれば医学における表現を至るところ書き換える必要がある)。むしろ哺乳類以外でも Vasopressin バソプレッシンを用いる用例が出てきている。
いずれも同一系統のホルモンで電解質・浸透圧調節が最初の役割であったが機能が分化したもの。子育てを行う鳥類・哺乳類では現生爬虫類とは役割がある程度違うのでは? つまりオキシトシンの生理的役割は系統を反映するよりも鳥類と哺乳類の方が近いのではと想像したくなる。
Oriental Honey Buzzard 韓国のハチクマの巣の映像。オスが帰ってきて枝や葉の場所を整えている。巣の外側に広がった葉を配置するのは巣を目立たなくするためと考えれば行っている行動が解釈しやすい。この行動はハチクマ亜科に比較的共通している印象を受ける。
また首を伸ばして上方にある枝をちぎろうとする姿も記録されている。
Oriental Honey Buzzard 韓国のハチクマの巣の映像。オスが葉のついた枝を持ち帰った。飛び立って同様の別シーンが記録されている。腹で巣の内装を整えるなど。
Oriental Honey Buzzard 韓国のハチクマの巣の映像。オスが葉のついた枝を持ち帰り巣に配置。オスの飛び立ちまで。その後メスが戻って巣を整えている映像もある。
メスの方は日本で一般的な個体よりのどの模様が淡い (淡色型と呼べそうだが少し雰囲気が違うように感じる。クマタカの分布しない地域なので擬態効果を考えると色彩型に違いがあるのかも知れない)。比較的早く飛び立った。
[死体をおとりに使うか?] の項目に韓国のドキュメンタリー (EBS Documentary) の映像を紹介しているので参照いただきたい。
Oriental Honey Buzzard 韓国のハチクマの巣の映像。オスが巣に戻ってきた。0:34 rattling call あり。細かく体を震わせている (1音ごとに息を吐いて出していると思われる)。この声を断続的に3分程度続け、しばらく下を向いて何かの作業をした後音声を再開。7:09 飛び立つ。
途中カットあり、7:39 に小枝をくわえて戻る。しばらく作業をして 9:33 飛び立つ。途中カットあり、11:02 小枝を運んで戻ってくる。その後枝の位置を整えたりしたがまた飛び立った。
解説によるとオスがメスを呼ぶ声を初めて聞いたとある (rattling call のこと)。
Oriental Honey Buzzard 韓国のハチクマの巣の映像。オスが巣に戻ってきた。この映像でも rattling call を出している。メスの姿が見えていて声を出していたのかも。0:44 にメスがやってきた。少し顔を見合わせて (相談?) オスが飛び出す。この間もオスの体が震えていて rattling call を出していたことがわかる。
声が小さくて遠方のカメラからでは音声記録が難しいぐらいかも知れない。何かの感情の伝達?
しかしメスも飛び出したオスの動きを追っていたようでメスも飛び出した。
次の別角度のシーン (抱卵中?) で 3:35 に何かの声 (ツグミ類?)。3:59 に遠ざかった声がする。5:00 にメスが巣から頭を上げて 5:19 に飛び立つ。5:20 にケラ類らしい声がした (当地京都ならばアオゲラを想像しそうな声。音源を探してみるとヤマゲラか?。ハチクマが飛んで驚いたのかも)。
A Baby Crested Honey Buzzard is Challenging Its First Flight (EBS Beyond Eye 2024)。
[マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態]
以下は亜種 torquatus (tweeddale morph) の繁殖記録。
Wee (2007) Oriental Honey-buzzard: 1. Nesting
ゴルフクラブの敷地内に営巣して、1998-2005 年の間に 10 回子育てをした。1年に2回繁殖したのは2年。オスが巣材をくわえて場所を示してメスを待つ。
同じ巣を使ったのは2回のみ。前年の若鳥が巣造りを手伝うのが目撃されているが親から必ず反撃された (これは日本のハチクマ若鳥が翌年なぜ戻ってこないかの解釈にも役立つ情報かも知れない)。
Wee (2007) Oriental Honey-buzzard: 2. Nestlings
抱卵は主にメスが行う。木の高いところで辛抱強く獲物が現れるのを待つことが多い。
Wee (2007) Oriental Honey-Buzzard: Successful breeding of 2 chicks on third attempt
ほとんどの年にひなは1羽しか育たない (要因はさまざま)。ハチの子だけでなくハチの巣も食べるのが観察された。
巣立った若鳥が枝に逆さまにぶら下がったり元に戻ったりを 20 分続けていたことがあった。
筋肉の力を付けるためのような書き方になっているが、カラスがこれをやれば遊びと解釈されてもおかしくないように思える。ハチクマの遊びは飼育下で観察されている ([飼育下の行動] 参照) ので、若鳥が遊びながら筋力を付けていたのであろうか。
なお以下の映像を紹介するにあたり用語がやや悩ましい。巣立ち前は英語でも nestling で「ひな」で構わないだろうが、巣立った後の名称は英語では fledgling で fledge (巣立つ) から推定するとタカ類でもスズメ目でも巣立ちびなに相当する用語で読んでいる。
ここでは若杉氏の見解 (鷹隼類に「巣立ちビナ」はいない) に従って若鳥と表記することにする。
本記事全体では若鳥、幼鳥、亜成鳥などの用語はあまり吟味して使っておらず、論文などで使われている英語の表現をそのまま訳しているだけのことも多いので厳密性や統一性を欠く点はご容赦いただきたい。
なお「巣立ちびな」に相当するロシア語は sletok (単数形の主格 スリョータク と読む) で「飛び出た者」ぐらいの感じ。
同じ単語はスズメ目に対しても用いられ、ロシア語でも英語同様にスズメ目と区別していない。用例ではタカ類のその年生まれの若鳥に相当するものも sletok と呼んでいる (若鳥の用語も用いられる) ようなので英語の fledgling よりも利用範囲が広いかも知れない。地上性や水鳥の場合は podletok と別の単語が用いられる。
ただしこれらは狩猟用語で、普通の人はあまり知らないかも知れない。辞書にも載っていないこともある (日本語でも「巣立ちびな」の用語はそれほど知られていないかも知れない)。
野鳥を捕えて飼育していた時代にはスズメ目の巣立ちびなを指して「飛びっ子」と呼ばれていたとのこと。これはロシア語は sletok とほぼ完全に同じ意味。"飛びっ子" ではあまりにも学術用語らしくないので「巣立ちビナ」と呼ぶことになったものの、今度は "ひな" の語句が入るために鷹隼類にはむしろふさわしくなくなってしまった。ロシア語では狩猟用語をそのまま学術用語として用いたため齟齬が生じなかった次第。この場合は英語由来の概念よりもロシア語の方が対応関係がよい。
マレーシアのハチクマが街路樹で繁殖している映像も出ているが、騒々しい人為環境に慣れている姿はとても日本と同じ種類と思えないぐらいである。
Oriental Honey Buzzard nest site, Malaysia. 20210316 (1),
(2),
(3)。
最近 Yvonne Blake がマレーシアの留鳥の繁殖ハチクマの映像を YouTube に多数アップロードしているのでこちらも参考になる ([音声] の項目にも紹介)。
Crested Honey Buzzard mating
(2023.10.6 撮影) に珍しい下のアングルから撮影された交尾の映像が出ている。
上から見ているとどうやっているのか疑問に思うのだが、下からみると交尾で何が起きているのか若干よくわかる。
こちらは同日の別方向からの交尾映像 Crested Honey Buzzard couple mating
他のタカ類同様1日複数回の交尾を行うのだろうか。オスの方が大きいように見えるが気のせいだろうか?
なお Cramp and Simmons にあるヨーロッパハチクマの記述では交尾は日に最大5回、10-12 日続くとある。
同じく Yvonne Blake による映像で、前回生まれた若鳥が繁殖を手伝っている (ヘルパー) という:
Crested Honey Buzzard juvenile。同じ個体の映像 Crested Honey Buzzard juvenile。
この行動は興味深い点がある。ヘルパー行動は他の種類でもいくつも知られており、血縁個体のヘルパーは生態学理論の解釈もよく知られていて行動そのものは不思議でないが、ハチクマの観察例は過去になかったのではないだろうか。
(1) サシバの幼鳥が繁殖を行わないのになぜ日本に帰ってくるのか、若杉 (2014) Birder 28(9): 24-25 で取り上げられている。追い払われることもあるがヘルパーのような行動のある事例もあるとのこと。若鳥が繁殖行動について学ぶなど何か意義があるのだろうかなど考察されている。
一方ハチクマは若鳥は帰ってこない。マレーシアの事例を見るとハチクマはヘルパー気質があるらしく、サシバ同様若鳥も帰ってきても理屈の上ではおかしくないように見える。帰ってきて得られる利益よりも渡りのリスクの方が上回るのだろうか。
ハチクマの方が寿命が長く、親のなわばりが空くまで時間がかかるだろうから、戻ってきても将来のなわばりの確保にあまり役立たないかも知れない。
ヨーロッパハチクマは熱帯留鳥の個体群はないので熱帯地域でヘルパー行動があるかどうかはそもそも調べられない。ヨーロッパハチクマではできない、ハチクマならではの研究テーマになる可能性があるが渡りのハチクマの越冬地の衛星追跡の情報はまだほとんどなく、よく調べられているヨーロッパハチクマと同様かどうかもわからない。
台湾では留鳥なので調べられる可能性があるが、いずれにしても海外の情報も参考にしながら今後の進展に期待したい。
マレーシアの観察も進行形の状態なので今後の進展を楽しみにしたいところ。
この件についてその後 [ヨーロッパハチクマはいつ繁殖地に戻るか] の情報が得られた。ヨーロッパハチクマでは地中海を渡る春の渡りのリスクが非常に大きい。まだ少数例だが初めて繁殖地に戻る年は帰還時期が遅く繁殖に間に合わない。出生地に戻るわけではなく、ヘルパーとなっていない。戻って最初の1年は場所探しや経験を積むための役割があると考えられている。
長距離の渡りを行う上で生活史の制約があるのだろう。
(2) 渡りのハチクマの場合は渡りの前に親子の縁が切れてしまうが、留鳥の場合は必ずしもそうではなさそうで前回巣立った若鳥が近くで観察されている模様。
クマタカの子離れに非常に時間がかかるのに比べてハチクマの場合はあまりにも早いことがしばしば対比されるが、これは限られた季節しか滞在できない渡り個体しか見ていないことによる印象かも知れない。
ヨーロッパハチクマの事例は [ヨーロッパハチクマはいつ繁殖地に戻るか] の項目も参照。
留鳥ハチクマの場合も、クマタカのように餌まではねだらないにしても追い払われることもなく近くで生活しているのだろうか。マレーシアではこれを書いている現在で少なくとも半年は滞在している。
クマタカは大きめの動物を捕えるため習熟に期間を要するためなどの説明もあるが、このハチクマの事例を見ていると必ずしもそうとは言い切れない感じがする。早い時期に子別れを行うイヌワシなどの方がむしろ例外的なのかも知れない。
(3) 人への恐怖は "生得的" (この表現は微妙なので注意を要する。#カンムリワシ備考の [霊長類はなぜヘビを恐れるか] などを参照) でないことがわかる。
人を恐れないガラパゴスノスリ Buteo galapagoensis Galapagos Hawk と同様に人を外敵と教わるか認識しないと恐れないのだろう (もちろん猛禽類に限った話ではないが、一般的に猛禽類は警戒心が強いと言われるので注目している)。
このマレーシアのハチクマの場合は親も人を恐れず (巣での繁殖行動のみならず、腹を水に浸して涼んでいるなど普通は撮れそうもない映像が多数紹介されている)、子供も人を恐れる機会がないので自然な行動を見せてくれるのだろう。このハチクマ家系で人を恐れない "文化" が育っているならば面白い。
2024年5月の映像でオスがコウライウグイスの若鳥を巣のひな (孵化後6-7週間) に与えた映像と解説があった (#コウライウグイスの備考も参照)。置いてそのまま飛び去りひなが自身で羽むしりをして多少は食べたこと、ハチの巣を運んできたメスがハチの巣ではなく先にコウライウグイスの方を処理したとある。
Crested Honey Buzzard chicks Part 1 of 4 から始まる一連の映像参照。確かに黄色い羽が見える。
Crested Honey Buzzard mummy feeding chicks がメスが鳥をちぎって与えている映像か。
このマレーシアのつがいはひなに鳥をしばしば与えている。コウライウグイスに毒性があるのか、鮮やかな色は警告色になっているのかも併せて興味深い。
Crested Honey Buzzard chicks tearing small chick ではまだ小さな小鳥のひなを与えたところ。ハチクマはあまり丸のみしない印象を受けるが、この例ではひなをまるごと飲み込んでいる。ひっぱりあいの様子も人と遊ぶ時の様子 ([(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど: ハチクマのお客さんになって] 参照) に似ている。
Crested Honey Buzzard mummy with her chicks ひなが食べ物をもらった後羽ばたき練習中。巣立ちとも言えるぐらい巣の端まで移動している。
なお小鳥が無害なハチクマを見分けて警戒しないと書いてある本もあるがそんなことはない。実際に小鳥も食べられているし、モビングを受けている写真もいくつも発表されている。福丸 (2010) Birder 24(7): 36 に2008年7月香川まんのう町でハチクマがとまって餌を探している時にサンコウチョウのモビングを受ける写真がある。頭に蹴りを入れたという。この写真を見るとハチクマも後ろはあまり見えていないよう。
参考: Orientale Honey Buzzard Threaten by Lapwing Bird ケリ類のモビングを受けているハチクマ (撮影地は不明)。
Oriental Honey Buzzard? Singapore にも興味深い記載がある。ハチクマがクマタカに擬態しているというのは本当か? の議論があり、ある観察者によれば繁殖中のチゴハヤブサを観察するとヨーロッパノスリには反応しなかったがヨーロッパハチクマやオオタカにはパニックになるとのこと。
別の投稿者はチゴハヤブサがヨーロッパノスリにモビングするのはいくらでも見たことがあるとのこと。
Crested Honey Buzzard juvenile Part 1 前回巣立った若鳥が枝を折ろうとしているところ。
Crested Honey Buzzard juvenile biting through twig for insects Part 2 同上。枝を (自分の印象では空のハチの巣を壊すように) くだいて昆虫を探しているとある。
足で上手に枝を持っているが遊びのようなもので本気の餌探しではないかも。オウムが同じように枝を持つと器用と言われるだろうが、タカではあまり注目されないかも知れない。
この映像では趾3本が前を向いていてタカ類の足の基本形になっているが、別のマレーシアの枝運びの写真で趾1本が後ろに回っているのを見つけた (URL 記録忘れ。326976912_962599568224857_2747320672287037010_n.jpg のファイル名で Facebook の画像か)。
たまたま趾の間に入ってしまったのかも知れないが、semi-zygodactyly に近い特性があるのかも知れない。ミサゴは有名だがカタグロトビ類、ハチクマと系統的に近いカッコウハヤブサ類でも知られている (#カタグロトビの備考 [系統とフクロウ類との収斂進化] も参照)。
III, IV 趾の間の膜 (いわゆる水かき) が顕著でなく足を広げてハチの巣を掴むのに有利などの適応が考えられるが、タカ類全体ではどうなっているか調べると面白いかも。
ハチクマが枝などを掴んでいる時に趾がこのような配置になっていないか注意して見るべきだろう。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 72 Part 1 若鳥が足で掘る練習中。
Crested Honey Buzzard fledgling 同上若鳥 82 日。まだ食べ物をもらっているとのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 83 after breakfast Part 2 of 4 同上若鳥 83 日。親に食べ物をねだって鳴いている (まだひな同様の声)。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 83 after breakfast Part 3 of 4 同上若鳥 83 日。ねだりながら自分でもかじってみている。
Crested Honey Buzzard juvenile B flying with daddy
その後状況はさらに複雑になっているようで、まだ巣立っていない個体も含めて若鳥が4羽いるとのこと。前回 (半年前) 生まれの2羽のうち年長の1羽は子育てを時々手伝う。この映像の個体はオスと一緒に飛んでいるところで、親の飛び方をよく真似ているとのこと。
オスが巣に姿を見せなくなっていたのだが、この若鳥 (Crested Honey Buzzard juvenile B とまって親を呼んでいる映像) を構っていたらしいとのこと。この若鳥の兄弟にあたる年長の個体が時々ヘルパーとなっていたとのこと。
これらの記載を見ると半年経過してもまだ子別れしていない様子。
日本ではハチの子の栄養価が高いので成長が早いとよく言われるが、留鳥ではそうでもないようで日本のハチクマの独立が早いのは本当はもっと甘えたいところが、親の生存率を高めるために早く渡り、生活史を (やむを得ず?) 切り詰めているのだろうか。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 9 この映像は若鳥だが正面顔が見られる。頭蓋骨の形状から他のタカ類より正面の両眼視野が狭いだろうが、両眼で見ているらしい場面が見られる。サギのように両眼視の視線は下向きではなく、正面から少し上向きがよく見えているよう。成鳥 (特にオス) の正面顔から受ける印象と少し違う。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 9 calling 上記と同じ若鳥が鳴いているところ。成鳥の声に似てきた。
Crested Honey Buzzard juvenile A approx 6 months old の解説によれば生後6か月の若鳥が小さなハチの巣を巣に落とし、現在養育されていて巣立ったばかりの若鳥の年上の方が巣にいたため食べた Crested Honey Buzzard fledgling Day 12 とのこと。
ヘルパーとして食物も与えている模様。古典的な血縁個体のヘルパーの解釈でよさそうな感じ。
その後親がハチの巣を運び、年下の巣立ったばかりの若鳥が食べた Crested Honey Buzzard mummy returns to nest。年上の方は先に6か月の若鳥からもらったものを食べた後。
Crested Honey Buzzard fledgling C Day 12 巣立って 12 日の若鳥。枝を握って遊ぶ練習中?
Crested Honey Buzzard fledgling Day 14 地上に降りるかどうかを思案中の若鳥。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 14 on the ground, bathing & drinking for the first time Part 1
巣立ち後 14 日で初めて危険な地上に降りて、親や同胞の行動を見ていた通りに真似て (aping) 水を飲んだり腹を冷やしたとのこと。もう1羽もやはり巣立ち後 14 日で同じことを行った。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 14 on the ground, bathing & drinking for the first time Part 2 こわごわ水を眺めている。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 14 on the ground, bathing & drinking for the first time Part 3 初めての着水。思ったより冷たかったのか一瞬で飛び退く。しかし2回めは水も飲んで次第に大胆に水浴び。瞬膜がよく動いていて何かの感情の表れ?
Crested Honey Buzzard fledgling Day 14 on the ground, bathing & drinking for the first time Part 4 だんだん慣れてきた。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 14 on the ground, bathing & drinking for the first time Part 5 水浴び後少し歩いてみる。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 4 stretching 若鳥の「伸び」。尾を左右に振るのは機嫌の良さの現れと思う。
Crested Honey Buzzard mummy hydrating 後日の映像だが親 (メス) の方は水飲みも慣れたもの。
Crested Honey Buzzard juvenile approx 6 months having a drink 前回生まれの若鳥 (2番めの個体) の水飲み。なかなか見られない行動かも。
Crested Honey Buzzard juvenile approx 6 months old flying down for a drink 同上、周囲を見渡して水飲みに降りるところ。首がどのように動いているかよくわかる。
これらの動画にも背景に他の個体の声が入っている。現在前回巣立った子供も含めて6羽の家族となっている模様。新しい方の巣立ちびながまだ巣で餌を受け取っているので親も忙しく、前回巣立った子供はあまり構ってもらえない。
Crested Honey Buzzard juvenile approx 6 months old preening 生後半年だが尾の模様はまるで成鳥のように見える。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 10 moaning 巣立って 10 日目の若鳥。巣にいた年長の方の若鳥がハチの巣をもらって食べている間に上から見ていた。時々このように鳴いていた。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 20 年長の個体で巣立って 20 日。このように休むのが好みとのこと。
Crested Honey Buzzard older fledgling Day 20 Crested Honey Buzzard older fledgling Day 20 同上。お腹いっぱいで翼を半開きで枝に腹ばいになっているような姿勢。
Crested Honey Buzzard older fledgling Day 20 - tennis ball breast 満腹状態。枝葉で遊ぶ。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 10 年下の方。暑くてあえぎ呼吸中?
Crested Honey Buzzard fledgling siblings Day 20 and Day 10 2羽の若鳥が一緒に。年上の方はそのうが重くて枝に腹ばいになっているのかも。まるでそのうを枝に乗せるツメバケイみたいだが、そのうを枝に乗せて休むタカとは何だ (巣立ってまだ幼くタカの自覚がまだできてないかも知れないが。笑)。それにしても警戒心がない。
Crested Honey Buzzard fledgling siblings Day 20 and Day 10 同上。少し消化が進んだ?
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 23 初水浴びから9日後でこれが2回めとのこと。降りる前の見回し中。頭かきでバランスを崩す。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 23 Part 1 of 5 そして地上へ。だいぶ自信が付いてきたとのこと。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 23 Part 2 of 5 しかししばらく思案中。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 23 Part 3 of 5 水は飲んだが入るのはまだこわごわ? 足で水温を確認?
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 23 Part 4 of 5 また水を飲んでようやく決心、と思ったらまた陸に上がってしまった。しばらく歩いて悩んで? 今度は決心したよう。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 23 Part 5 水浴び中。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 23 drying after a bath 水浴び後乾かしているところ。頭かきとあくび。
A group of honey buzzard quenching thirst in hot weather こちらはインド? 暑い中ハチクマの集団水飲み・水浴び。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Male & Chicks) @ Chiu S C DSCN7456
こちらは別の観察者によるもの。ヘビをちぎって与えている。ひなに与える時に瞳孔が収縮するが、近くを見るのにピントを合わせているのだろうか。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 15 Part 1,
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 15 Part 2 こちらは若い方の巣立ち後 15 日の若鳥。前日に続き地上に降りたのは2回めとのこと。しばらくためらいつつも歩いて水場に。
途中で思案してその後水に近づくも水を飲むには勇気が必要なようでなかなか決心がつかない。水面を眺めたりしているのはまるでためらっている人間の行動を見るよう。
rested Honey Buzzard younger fledgling D Day 15 Part 3 ようやく水を飲む。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 15 Part 4 なかなか水に入れない。草をくわえて捨てたのは悩んでいる時の転位行動のようにも見える。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 15 Part 5 まだ決心できず水路をはさんで行き来する。ちょっと移動して水を飲んだりする。これも決心が付かない時の転位行動なのかも。
ハチクマは親が「早く入りなさい」とか急かしたりしないのでのんびりした性格に育つでしょう (笑)。
そのうち親が別の若鳥に食べ物を運ぶ声が聞こえて自分もねだる声を上げる。結局入れず?
Crested Honey Buzzard mummy having a drink after delivering food Part 1 こちらは若鳥に食べ物を運んだ後のメスの水飲み。背景によく声が入っていて親を呼んでいるのか?
Crested Honey Buzzard mummy having a drink after delivering food Part 1 同上。そのまま飛び立つ。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 25 playing in the rain Part 2, Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 25 playing in the rain Part 3 突然の雨を楽しむ年上の方の若鳥。鳴きながら翼を広げて雨浴び。そのうはまたたっぷり入ってそう。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 25 playing in the rain Part 4 同上。セッカのように細い枝2本に両足を乗せたら落ちてしまった (体重が違いすぎ)。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 25 drying after the rain その後乾かし中。
Crested Honey Buzzard fledgling siblings drying after the storm 親子で乾かし中。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 Part 1
下の子は空腹で地上で食べ物を探そうとするがまだ動けない。後ろ姿は羽縁の白が目立っている。
上記より8日後の状況のようで、数日親 (メス) が姿を見せず空腹とのこと。一つ前の繁殖で生まれた6か月年上の個体が巣に食べ物を運ぶ (まさしくヘルパー) ハチクマのヘルパー が上の子供が食べてしまう。
オス親の役割の変化、ヘルパーが実際に子育てをしているところなど他では得難い情報になっている。
猛禽類の共同繁殖やヘルパーの例や一般的解釈については#ノスリ備考の [ガラパゴスノスリや他の猛禽類の一妻多夫] に情報をまとめておく。
ハヤブサ目のアカノドカラカラ Ibycter americanus (Red-throated Caracara) はハチの巣主食で有名だが、群れを作って行動し、大きな食べ物は分かち合ったり時には他個体への給餌 (allofeeding) を行うことも社会の維持に役立っているとのこと:
Thiollay (1991) Foraging, home range use and social behaviour of a group-living rainforest raptor, the Red-throated Caracara Daptrius americanus。
猛禽類では珍しい行動とのこと。樹冠部の果実食の鳥のあるものはアカノドカラカラと混群を作ることもあって外敵から身を守っているとのこと。
アカノドカラカラとハチクマは食物に共通性があるので類似点があるのかも。Dawson and Mannan (1991) ではモモアカノスリでは allofeeding は記録されていないとある。ハチクマはそこまで群れを作って行動していないかも知れないし、allofeeding の有無はよくわからないがアカノドカラカラの社会との類似性も検討の価値がありそう。
他個体をとがめず大きな食べ物は分かち合う点は似ている感じがする。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 Part 2 地上を探して何か見つけたがハチの巣ではなく泥の塊だった。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 Part 3 少し行動が上達して掘ってみるがやはり泥の塊で食べられなかった。
ハチの巣を掘る行動をどのように段階的に習得してゆくのか考えながら見ると興味深い。飛ぶ昆虫とハチの巣の関係は学習する必要があるのだろうか。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 Part 4 掘るのはいったん諦めて別の食べ物を探す。草をくわえてみるが食べられない?
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 Part 5 プラスチック袋の破片をくわえる。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 checks out plastic Part 6 気になるが食べなかった。歩いて何か見つけたが食べ物ではなかった。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 餌を期待して巣に戻った。
Crested Honey Buzzard younger fledgling Day 23 餌は運ばれず食べ物を探して飛び出して別の場所に。今度は樹上で。解説によれば前回の繁殖で生まれた2羽を含めて若鳥は4羽とも夕方には水場を訪れたとのこと。
Crested Honey Buzzard couple こちらはまた別のつがい? 4回めの繁殖で 4/23 に産卵したが5月中旬に放棄とのこと。その後やり直したのだろうか? ひなが産まれた (6/20)。ここまで紹介してきた幼鳥4羽のつがいとの関係はよくわからない。
Crested Honey Buzzard daddy collecting leafy twigs to cushion nest for newly hatched chick 同上。産座に使う枝を折ろうとしているオス。なかなかうまく行かない。両足で持って嘴で折ろうとしている場面もある。
先の家族はしばらく映像がなかったので大丈夫かと心配していたが、
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 26 年下の新しい方の若鳥はずっと1羽でいた。地上にいるところ。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 26 Part 1 1羽で退屈していて、食べ物がもらえないかと時々巣に戻る。食べられないが枝先を分解しているところ。途中で足で持つ。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 26 Part 2 続き。あくびも出ていた。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 27 ここからは翌日。巣にいて呼んでいる。声は大きくなったか。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 27 何時間も鳴いていたとのこと。途中で上空を見ていたが親ではなかった模様。
Crested Honey Buzzard juvenile A 上記と同日。ヘルパーになっている一つ前の繁殖の年上の若鳥が見つかった。背景で呼んでいる若鳥の声が聞こえる。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 27 年下の新しい方の若鳥が巣から出てねだっている。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 27 同上。
Crested Honey Buzzard younger fledgling D Day 27 同上。最後は鳴きながら飛び出し。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 37 Part 1 年上のヘルパーと年上の新しい方の若鳥が戻ってきた。年上の新しい方の若鳥は水場へ。あまりためらわずに水に入った。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 37 Part 2 同上続き。背景で年下の新しい方の若鳥が呼んでいるが特に反応していない。そのうは膨れていてどこかで食べるか食べさせてもらったいたのだろうか。しばらく歩いてまた水に入る。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 37 Part 3 同上続き。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 37 同上水飲み後。枝にとまって少し歩く。こちらは腹は減っていないよう。
Crested Honey Buzzard juvenile A after delivering honeycomb 年上のヘルパーが先の年下の新しい方の若鳥にハチの巣を運んだとのこと。生後半年なのに尾のバンドが目立つ。
Crested Honey Buzzard juvenile A Part 1 同上その後水場へ行くか考え中から飛び降り。
Crested Honey Buzzard juvenile A Part 2 同上水場で続き。イヌが近くに来て追い払ったが効果なく飛び去ったとのこと。
水があまり流れていないとのこと。
Crested Honey Buzzard older fledgling C has a sore throat 年上の新しい方の若鳥。口内に異物? (polyp とあるが?) があるようで声が枯れている。
Crested Honey Buzzard juvenile A 年上のヘルパーの若鳥。水場でイヌに邪魔されたので再度考え中。背景で年下の2羽が鳴いている。
Crested Honey Buzzard juvenile A and sibling fledgling C Part 1 そして降りたが、すぐに年上の新しい方の若鳥が降りてきたねだったので飛び去った。
Crested Honey Buzzard elder fledgling C Day 37 Part 2 同上水場で続き。ちょっと飲んだが水がほとんどない。新しい方の若鳥は2羽とも鳴いている。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 37 Part 3 同上続き。著者のすぐそばに降りて来たという。すっかりお馴染み? 途中に頭かきあり。
Crested Honey Buzzard older fledgling C Day 37 同上続き? 飛び立つところまで。すぐそばで撮っている? 人もあり。
Crested Honey Buzzard juvenile A plus siblings C and D Part 4 年上のヘルパーの若鳥が再度水場へ。別のところにもう1羽。年上ヘルパーの若鳥が飛ぶと新しい方の若鳥は2羽ともねだる。特に樹上にいる年下の新しい方の若鳥は翼も開いて大きなねだり声を出す。水場の年上の新しい方の若鳥はその場で鳴いている。
ヘルパーは若鳥だがほとんど親のような役割か。3羽で鳴きあっているよう。若鳥4羽のうち1羽だけ見かけないのは残念とのこと。親はもう現れないのか? 若鳥だけの家族ができているよう。
その後しばらく映像が出ていなかったが6月26日撮影 (上記4日後) のものが出ていた。上記の表現で A, C, D の個体が撮影されており、無事に育っているよう。巣にあまり依存しなくなって観察機会が減っているのかも。D は巣立ち後 31 日め。
Crested Honey Buzzard chick 17 days old being fed meat by mummy こちらは新しい方のつがいの巣でひなが肉をもらっているところ。
Crested Honey Buzzard chick 17 days old and mummy 同上。親 (メス) の正面顔もよく見える。
Crested Honey Buzzard chick 17 days old trying to catch a nap 同上。ひながちょっと居眠りかけ。
Crested Honey Buzzard chick 17 days old trying to catch a nap 同上。どちらもちょっと不自然な姿勢で居眠りかけ。
Crested Honey Buzzard chick 21 days old with mummy 生後 21 日目のひな。こちらは "4" の名前をもらっている。先ほどで長く居眠り中だったとのこと。肉をもらった後とのこと。別の映像によれば前回のひな "3" に比べて肉中心に与えられているとのこと。
日本ではひなが小さい時はハチの巣がまだ多くない時期になるだろうが、ハチの巣が豊富かどうかよりも小さい時に必要な栄養源として肉を与えるのかも知れない。要検討か。
親の瞳孔がよく変化しているのを見るように、とのこと。リラックスすると瞳孔が開くとの一般的傾向があるそうだがこの場合はどうだろうか。
Crested Honey Buzzard chick 43 days old 久しぶりの映像で生後 43 日目のひな。これまでの子育てに比べてひなの成長が非常に早いのこと。今回は 90% は肉を与えられて育っているそうで、意外にもハチの子より栄養価が高いのか? ハチの巣がなくても子育てができる? これならば食性も肉食と呼んでもおかしくない。[ハチの子は栄養満点か?] の項目を独立させた。
Crested Honey Buzzard chick 43 days old 同上羽ばたいているところ。巣立ちも早いのかも。
Crested Honey Buzzard female 同上。巣のメスで、近くで高いところにとまっているオスに対してだろうか少し鳴いている。
Crested Honey Buzzard/mummy ちょっとくつろいでいるメス。趾や爪などが見やすい。
Crested Honey Buzzard/mummy 同上。オスに呼びかける声とのこと。
Crested Honey Buzzard male/daddy メスが呼ぶと戻ってきたオスとのこと。正面視で見ている様子がわかる。日本のハチクマのオスより正面視に適した目の構造の印象を受けた。
Crested Honey Buzzard chick 48 days old 48 日目。すでに巣立っていた。この1週間は巣の外縁で過ごしていたとのことで、巣立ちはもう少し早かったのかも。趾も爪も十分たくましくなっているとのこと。
2024.8.5 の映像なのでこのペアの子育て時期は日本のハチクマに近い。
Crested Honey Buzzard chick 50 days old preening 50 日目にすでに枝にとまって羽繕い中。
オスの正面像。動きなどの参考に。構造を知って見るとこの姿勢は頸椎を S 字に曲げていて中間部分を前方に動かしたらしいことがわかる。
Crested Honey Buzzard chick 51 days old 51 日目。大部分は巣の外にとまっていて食物をもらう時のみ巣に戻るとある。
Crested Honey Buzzard chick 53 days old 53 日目。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 56 日目に巣から離れて外にいた (2024.8.24)。同じつがいの前のひな2羽は 63 日で7日早いとのこと (主に肉で育った効果?)。オスが小さなハチの巣を巣に落としたのを食べに行ってその後の羽繕いの場面とのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 同上。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 これが巣にいた時の映像。
Oriental Honey-buzzard (Female & Male) @ Chiu S C DSCN1808 別の方による親の主に羽繕いと伸び。
Oriental Honey-buzzard (Female) Chiu S C DSCN9776 同上メスの羽繕い。上下のまぶたが閉じているように見える。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 9 with mummy 巣立ち後9日目の若鳥とメス。解説によればカラスの群れがやってくるとメスが飛び出した。このつがいの以前の若鳥はカラスを怖がったがこの若鳥はメスと一緒にカラスを追いかけたとのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 9 with mummy 上記続き。最初に別の1羽の声が聞こえて2羽との声を気にしていた。解説によるとオスがハチの巣を巣に置いたので若鳥が食べに戻った時点のよう。
メスも続いて飛び出しておりこちらはありはカラス対応?
Crested Honey Buzzard fledgling Day 9 若鳥のクローズアップ。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 9 after breakfast 同上食後。趾や爪の構造もわかりやすい。最後に飛び出し。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Male & Chicks) @ Chiu S C DSCN7468
別の方による少し前 (2024.5.6) の映像でメスがひなに食物を与えている。引きちぎっているようなので肉を与えていることろか。2:03 に何か細長いものを与えた。
Crested Honey Buzzard mummy with food for fledgling 食物を握って若鳥を待つメス。かなり暑いらしい。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 10 巣立ち後 10 日目の若鳥のクローズアップ。羽毛を膨らませる表情などがよくわかる。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 10 同上。後半は飛んでいる何かを追いかけている視線。前半で正面顔も見られる。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 10 同上。頭かき。何かに気づいて視線を固定している場面も見られる。少し前のめりになるなど動きを見ると正面視で見ているように見える。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 28 巣立ち後 28 日目だいぶ成長してきた。正面でこちらを見ているらしいなどタカらしい動きを示す。最後飛び立ち。こちらのハチクマは若鳥でも白い眉班が目立つ。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Female) @ Chiu S C DSCN6983 別の方の映像でメス。前半で正面を見ている場面がある。正面少し上方向から見るとタカらしい顔に見える。後半に羽繕い。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 28 drying after the storm 巣立ち後 28 日目の若鳥が嵐の後翼を広げて乾かしているところ。途中で頭かきが見られる。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Male & Chicks) @ Chiu S C DSCN7469 別の方の映像 (2024.5.6) 肉をさいてひな2羽に与えているオス (日本の亜種とは容貌が相当違う)。ひな2羽で引き合う場面が少しあったが争うほどではなかった。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 25 Part 1 of 3
巣立ち後 25 日目の若鳥 (2024.9.5)。オスが巣から呼んでいた。若鳥とメスが一緒に飛んできてメスは前回の繁殖で使われた巣に入る。若鳥は外でとまっていたがオス・メスは交尾したとのこと。オスは飛び出して戻った。若鳥は外で小声で鳴いていてメスが呼び戻し若鳥が巣に戻った。メスもしばらくいたが飛び出してまた戻った。
若鳥は両親と一緒に前回の繁殖で使われた巣にも馴染みになった。両親に対してさまざまな声で鳴いて幸せそうにしていた。その後食事をしたとのこと。この時が (育った) 巣の外での初めての給餌になったとのこと。代替巣を食物を与える場所として用いた 事例のよう。猛禽類の代替巣の役割の一つとなりそう (#イヌワシ備考の [猛禽類が代替巣を造る理由] も参照)。
子育て中に次の繁殖の準備を始めるのか? やや早すぎる感じの交尾は誇示行為や若鳥に対する何らかの信号になるのかも知れない (本当に次の繁殖を始めていた!)。
またこの若鳥が将来ヘルパーになることを期待して別の巣に誘導したのかも知れず興味深いところ。若鳥がヘルパーの役割を果たせるならば早い時期に次の繁殖が可能で有利な生活史戦略なのかも知れない。
ハチの巣があまりなくても肉で子育てできるようなので熱帯では繁殖時期はそれほど限定されないのかも知れない。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 25 Part 2 (後日アップロードされた) 2024.9.5 の映像。解説は上記も参照。午後 2:10 ごろにオスが呼んだとのこと。オスはずっと鳴いていて 10 分後 (?) ぐらいにメスと若鳥が一緒にやってきたとのこと。
別巣での行動の記録。rattling call に近いタイプの発声がある。
2日前にメスの方が巣にいてオスを呼んだ行動と関係があるのか、とコメントあり。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 25 Part 3 (後日アップロードされた) 上記続き。
Crested Honey Buzzard couple Part 1 (後日アップロードされた映像) (2024.9.3 撮影) 上記の2日前にメスの方が巣にいてオスを呼んで交尾の映像。
その際の交尾について記述があり、メスの方が要求したとのこと。連続2回の交尾を行い、このペアで観察された中で最短の間隔だったとのこと。
メスはずっと鳴いていたがオスは交尾の絶頂 (orgasm と表現している) 以外は声を出さなかったとのこと。映像で鳴いている声がメスとすれば rattling call を出している。オスの声 (?) はもっと柔らかく長い声。
Crested Honey Buzzard couple Part 2 上記交尾その2。上に乗っている時はオスの方が大きく感じるのがちょっと不思議。
オスの瞳孔が少し小さくなっている印象を受けるが、これは性的に興奮したセキセイインコなどでも見かける (目が暗色の日本の亜種のオスではわかりにくかも)。
その後メスが出している rattling call が聞こえる。腹部の動きからメスが出している声とわかる。
細かく呼吸を繰り返して出している音らしい。オスはその後羽繕い。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 48 遡って後日アップロードされたもの (2024.9.28 撮影)。巣立ち後 48 日の若鳥。食後でもまだねだって鳴いているところ。この声に似たフレーズは動物園個体でよく聞く (甘えているのか?)。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 48 ほぼ同じ。
Crested Honey Buzzard daddy taking a break from collecting twigs 遡って後日アップロードされたもの (2024.9.28 撮影)。オスが巣材を集めていた後の休憩中とのこと。巣立ち後 48 日の若鳥が巣でねだって鳴いている。
Crested Honey Buzzard male 久々のアップロード。成鳥のオスが逆さまにぶら下がっている。そして飛び立つ。カラスがやれば遊びと呼ばれそう。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 54 巣立ち後 54 日の若鳥 (2024.10.3)。同年齢の日本のハチクマならばすでに渡り途中の時期のはず。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 54 preening 同上羽繕い。白い眉斑がある。
Crested Honey Buzzard - female preening メス成鳥の羽繕い (2024.10.16)。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Female) @ Chiu S C DSCN1924 別の撮影者による映像 (2024.2.1) さまざまなポーズや飛び出しなど。
以下は渡り途中の個体 (おそらく日本と同じ亜種) だが近くで撮影された映像なので紹介しておく。Oriental Honey Buzzard take-off (2024.10.18) 足がどこまで羽毛に覆われているか、しっかりした爪などがよくわかる。飛び立ちまで。
Oriental Honey Buzzard drying after the rain こちらは雨の後に乾かしているところ。渡って行ったハチクマの 10 月中旬ぐらいの生活。マレーシアではこの時期が渡りのピークごろでしばしば見られる模様。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Male) @ Chiu S C DSCN2173 (Chiu S C 2024.2.3) こちらはマレーシアの留鳥亜種のオス。のどの模様など日本でも生息する亜種と多少共通点があるが虹彩の色が違い、冠羽がはっきりしている。途中頭かき。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 74 巣立ち 74 日の若鳥 (2024.10.23)。途中で頭かき。最後の方で視線で何かを追いかけている。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 74 同上。少しクローズアップ。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 74 同上。別ポーズ。片足でとまってくつろいでいる様子。
Crested Honey Buzzard - male (後日アップロードされた映像) (2024.10.23 撮影) オスが巣立った若鳥の世話を終えて休憩しているところか。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN1999 (Chiu S C 2024.2-3 月の映像) マレーシアの留鳥亜種の若鳥。羽繕いや頭かきなど。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Female & Juvenile) @ Chiu S C DSCN2308 (Chiu S C 2024.2.5 の映像) 巣立った若鳥とメス。枝の上でねだっている。
あまり聞かないタイプの発声がある。声だけ聞くとハチクマとわからないかも。他の個体もいるようで別方向から同じ声が聞こえ、メスは飛び出した。家族で行動している時期の模様。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Female) @ Chiu S C DSCN3933 過去映像 (2024.2.5) から。メスがおそらく食後に嘴を掃除している場面や後ろから見た羽繕いの様子など。
Crested Honey Buzzard - male (2024.10.29) オス親がとまって休憩しているところ。正面視で何度かこちらに視線を向けた。上空を飛んでいるものを追う姿も見られる。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Male) @ Chiu S C DSCN2320 (こちらは過去映像のオス 2024.2.5) ハチの巣らしきものを持ってとまっている映像、おそらく貯水塔のようなもので水を飲むところ、森林内で頭かきや羽繕いなどいくつかの場面を紹介。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Male) @ Chiu S C DSCN2366 こちらはオス成鳥の過去映像 (2024.2.5)。狩りの後か息遣いが荒いが掴んでいる獲物は何?。コウモリのような形に見えるが? そのうち落としてしまった。おそらく途中からの映像で食後の最後の部分か?。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 85 in the drizzle 小雨の中で巣立ち後 85 日の若鳥。翼を半開きで雨を浴びている。途中にフンをする場面がある。尾は上げるがほぼ下に落とす (おそらくあまり飛ばさない)。
その後頭かき。親が飛んでいるのか周囲を見て声も出している。まだ子供らしい声? 最後に飛び立ち。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 85 in the drizzle 同上その2。
Crested Honey Buzzard - male オス成鳥の羽繕いと頭かき。
Oriental Honey-buzzard (Juvenile) @ Chiu S C DSCN2012 これも過去映像 (2024.2.1) で枝にとまって翼を広げて震わせてねだっている若鳥。他のポーズなど。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN2039 (2024.2.29) 枝にとまっておそらく親が食物を運ぶのを待っているところか。クローズアップのスローモーション映像もあって瞬膜の動きがわかりやすい。表情がややうつろで多少眠いのかも。
Oriental Honey-buzzard (Juvenile) @ Chiu S C DSCN3940 これは上記の続きのよう。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Chicks) @ Chiu S C DSCN7391 こちらも過去映像 (2024.5.6) で2羽のひなが巣で育っている。そのうも膨らんでいて食物事情はよさそう。
冠羽が見えるのでひなのうちから性別がわかる? 後半は枝で翼を広げていたところ。日光浴というほどでもなさそう。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7699 (Sein Chiong Chiu 2024.5.15 の過去映像) 若鳥。冠羽がはっきり見える時は多少クマタカ類に似て見える。羽繕いなど。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7731 (Sein Chiong Chiu 2024.5.15 の過去映像) 巣に2羽のひなのいる映像。この程度成長すると争いもなく仲良く並んでいる。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus toquatus - Juveniles) @ Chiu S C DSCN7760 (同上 2024.5.15 の過去映像) 巣にいる2羽のひな。後半に羽繕い。
Oriental Honey buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7927 (同上 2024.5.18 の過去映像) 巣にいる2羽のひな。羽ばたき練習中。後半に羽繕い。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Female) @ Chiu S C DSC8142 (Sein Chiong Chiu 2024.5.26 の過去映像) 水路で水飲み。
尾の1枚が折れているのか、白い部分が擦れてなくなってしまっている興味深い映像。メラニンが羽毛強度を高めていることがわかる。模様を作ることは強度を落とす弱点にもなり得ることが考えられる。
ハチクマのオスの尾の太いバンドの間に細い模様があるのは強度を高めるためかも知れない。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN8138 (Sein Chiong Chiu 2024.5.26 の過去映像) 巣にいる2羽のひな。食事中。
Yvonne Blake の繁殖事例に戻ることになるが、なんと再度繁殖。
Crested Honey Buzzard nesting Part 2 (2024.10.17 撮影) 上記の Crested Honey Buzzard fledgling Day 74 と同じペアと若鳥で。
巣立って 68 日目に新しい巣にメスが卵を産み、オスが巣材を集めるのを若鳥が手伝ったとのこと。オスが巣材を持ち帰り、交代でメスが飛び立つ。3羽いるのでどの個体の声かわかりにくいが、rattling calls (コゲラのキキキ...に多少似ている) を巣で出しているのがメスのよう。他個体の声は若鳥の甘え声らしい。
Crested Honey Buzzard nesting Part 3 続き。オスが交代して抱卵 (に入る前の映像?) で若鳥は近くにとまって甘え声を出している。若鳥はその後飛び立ったメスを探しに飛び立ったとのこと。
Crested Honey Buzzard nesting Part 4 続き。オスが交代して抱卵に入った。
Crested Honey Buzzard nesting Part 5 同じく続き。巣に体を沈めると外からはあまり見えなくなる。外装はまだあまり青葉に覆われていない。
Crested Honey Buzzard nesting shift change 遡って後日アップロードされたもの (2024.10.23 撮影) 抱卵交代。巣にいるメスが交代を要請してオスを呼ぶ。オスの返事らしい声と巣立って 74 日目の若鳥の甘え声らしい声もある。そうするうちにオスが戻ってきてここでメスも声を出す。
オスが実際に抱卵を始めるまでに多少かかった。
Crested Honey Buzzard - daddy and fledgling Day 74 Part 1 of 3 遡って後日 (2024.12.26) アップロードされたもの (2024.10.23 撮影)。暑い中の抱卵でのどが渇き交代後の水飲み中のオス。2:01 足をふみ外す。水浴びをしたかったようだが呼ばれた (2:05)。
そして巣立って 74 日目の若鳥がやってきて甘え声を出している。若鳥に場所を譲った形となってオスは飛び立つ。若鳥はその後も甘え声を出していた。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 74 having a bath Part 2 of 3 同上続き。若鳥の水飲みから水浴び。水浴びには多少の決心が必要なようで少しためらっている (足で地面をひっかくような行動はまだ迷っている時の転位行動かも。動物園個体でも同様のためらいが見られる)。
Crested Honey Buzzard male having a drink Part 3 同上続き。若鳥の後の順でオス親の水飲み。水浴びの前に水を飲んで渇きを癒すのが通例とのこと。0:26 あたりで水しぶきが飛んでいて舌で味わっているらしいことがわかる。小鳥のように水飲み中の外敵をそれほど気にする必要がなくじっくり味わっている感じ。
巣造りを手伝うハチクマのヘルパー若鳥
Crested Honey Buzzard fledgling Day 86 being relieved of nesting duties by daddy Part 1 of 4 遡って後日アップロードされたもの (2024.11.4 撮影) 巣立って 86 日目の若鳥が巣材集めの後メスと交代して巣にいる状態。オスが巣材を持って戻ってきた。若鳥は撮影者の方を見ていたのでオスが帰ってきて驚いたとのこと。そして交代して若鳥が飛び出す。その後オスが巣に入って巣材の配置をしているところか。
Crested Honey Buzzard daddy settling down for nest duty Part 2 続き。巣で仕事中のオス。
背景でメジロの地鳴きに似た声が聞こえるが Zosterops 属のいずれかか。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 85 collecting twigs Part 3 続き。オスが巣に入って飛び立った後、枝を集める若鳥。若いのに結構上手に枝を折っていて、その後足も使っているのであるいは枝を整形しているのかも。
日齢の表記が1日違っているが撮影日は同じよう。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 85 back at nest with twig Part 4 続き。枝を巣に持ち帰る若鳥とのこと。
オスのそばに寄る前に長く会話していたとのこと。その時の音声を記録したものではなさそうだが、あるいは 0:16 あたりの声はそれかも。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 87 collecting twigs 遡って後日アップロードされたもの (2024.11.5 撮影) 巣立って 87 日目の若鳥が巣材集め。最初は太い枝を折ろうとしてさすがに無理。考え直してちょっと移動し、別の枝をこちらも嘴で折ろうとするがこれも太すぎた。朝の食事前の出来事とのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 87 preening in the morning 朝にメス親と一緒に起きた後の日々の日課の羽繕い。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 87 with mummy nesting 巣にメス親と一緒にいるところ。これまで3羽を育てたペア (この若鳥が4羽め) だがこの子だけは扱いが特別だったとのこと。そして繁殖を手伝っている。
若鳥に嘴を接して対してささやくような声を出すメス親。若鳥がメス親を少し羽繕いして愛情表現たっぷりとのこと (なんとこんなタカの家族もある!)。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 87 with mummy nesting 同上続き。若鳥がメス親を明瞭に羽繕いしている。
後半は逆にメス親が若鳥を羽繕い (ハチクマ親子の相互羽繕い)。一緒に巣にいて幸せそうにしているとのこと。
擬人的な見方だが手伝いもしてくれる我が子を可愛く感じているのかも。
鳥類全体で相互羽繕いを調べた研究: Kenny et al. (2017) Allopreening in birds is associated with parental cooperation over offspring care and stable pair bonds across years。
(韓国のハチクマの繁殖に登場する文献の再掲)
タカ類も含めて猛禽3系統いずれも相互羽繕いが意外に知られている。
広義ハイタカ属など日本で通常見られるタカ類では記録例がない (日本はタカ類の発祥の地から遠く、種多様性があまり高くないことを思い出そう) ので例外的に見えるらしい。社会性のある種 (モモアカノスリなど) ではあまり系統に関係なく記録されているよう。
ハゲワシ類など社会性のある種で多く見られているが、ハゲワシ類は想像以上に知的である可能性も考えられているので矛盾しないかも知れない。
ワタリガラスなどの事例では一般的には社会性を学習した個体が行っているようで、親子はあまりないかも知れない。
Migratory ORIENTAL HONEY BUZZARD sunbathing, Singapore (kidowmer 2024.11.27 アップロード) こちらは別の方によるシンガポールで日光浴中の渡りのハチクマ。10 月に渡来するとのこと。羽繕いも少し記録されている。この時期には初列風切の換羽は完了しているよう。
Crested Honey Buzzard nesting (2024.11.6 撮影) 巣でヘルパーとなっている若鳥 (右側。巣立って 88 日目) がメス親が枝を配置しているのを見ているところ。以下の一連の映像は必ずしも時系列順ではないと思われる。
Crested Honey Buzzard nesting 同上。若鳥 (左側) が枝集めを手伝ったとのこと。その後の巣で一緒にいる映像と思われる。向き合った時は親の方が声を出している (投稿者によれば特別な子で愛情たっぷりとのこと)。
Crested Honey Buzzard nesting 同上。枝を集めてきた若鳥。枝集めのために尾羽が乱れている。後ろにメス親 (抱卵中らしい) が一緒にいる。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 88 collecting twigs 同上。枝を集めている若鳥。朝から3時間近く枝集めを行っていたとのこと。どうやって枝を折るか、まだ経験不十分で格闘しているところ。
メス親が暖めている卵はそろそろ孵化する時期とある。
Crested Honey Buzzard nesting 同上。枝を集めてきた若鳥 (右側) とメス親。2羽が同じ枝をくわえて共同作業をしている (?) 場面がある (ハチクマ親子の共同作業?。このような行動は他の鳥で見られているだろうか)。
Crested Honey Buzzard nesting 同上。2羽で巣にいるところ。雨が降ってきてメス親が卵が濡れないように覆っている。
Crested Honey Buzzard nesting 同上。2羽で巣にいるところ。若鳥の方は雨宿り中か。
Crested Honey Buzzard nesting 同上。2羽で巣にいるところ。若鳥の伸びと少し羽繕い。
Crested Honey Buzzard nesting 同上。2羽で巣にいるところ。雨が激しくなってきて若鳥はメス親のために場所を空けたとのこと。雨が強くなると 15 分後若鳥は飛び立って自分の雨宿りの場所を探したとのこと。
Crested Honey Buzzard nesting 巣立って 89 日目でヘルパーとなっている若鳥。この日は朝に枝を一つ運んで巣でリラックスしているところ。映像はオス親が隣の木にとまった後巣のそばに入って歓迎 (?) しているところ (0:22 に rattling call が聞かれる)。
若鳥はその後飛び立ってオス親がとまっていた枝にとまったとのこと。オスは巣に入ったが抱卵はせず卵が孵化するのを見ているようだったとのこと。
Crested Honey Buzzard nesting 同上続き。巣にいるオス。
Crested Honey Buzzard nesting こちらは先に若鳥が持ち帰った枝をメスが巣に詰め込んだところとのこと。
Crested Honey Buzzard nesting 若鳥が自分で食物を探しに行く前に巣にいるオス親のところに立ち寄った。オス親の仕事をかなり肩代わりしており、オス親はずいぶん楽ができて2日間巣を離れることもできたとのこと。
オス親もこの特別な若鳥に愛情満点で 0:15 付近で嘴を合わせたりしている。その後若鳥が立ち去った。なるほど 別れ際のキス? だったのか (!)。もし同じ機能があるのならばこの行動をヒトと独立に進化させたことになる。
Crested Honey Buzzard daddy feeding chick that hatched this morning/last night (2024.11.8 撮影) ひなが生まれた。巣で肉を食べてひなに与えるオス。抱卵期間は 24 日とのこと。
Crested Honey Buzzard mummy arranging cushion for newly hatched chick 同上。生まれたひな用に青葉のついた枝をメスが整えているところ。なかなか納得できないようで何度も置き直している。
Crested Honey Buzzard mummy feeding chick 同上。自分も食べながら生まれたひなに肉を与えるメス。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 90 (2024.11.8 撮影) 同上。こちらは巣立って 90 日めの若鳥。メスがひなに食べ物を与えるのを見て近くの木にとまっていた。メスが与え終わってから巣に戻った。この晩は巣でメス親と一緒に過ごしたとのこと。3世代同居中。
Crested Honey Buzzard mummy with fledgling Day 90 同上。巣でメス親と一緒にいる若鳥。親はおそらく生まれたひなを抱いている。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7906 別の方による過去映像 (2024.5.18 撮影) 2羽の若鳥 (ひな) のいる巣。2羽の成長段階はかなり違っている。
この地域で繁殖するハチクマにとっては人は外敵とみなされていないのだろう。
Crested Honey Buzzard nesting (2024.11.9 撮影) ひなが生まれ2日め。同居しているヘルパー若鳥 (右側。巣立って 91 日目) が朝からひなに肉を与え、ひなの羽繕いを手伝ったとのこと。メス親が水浴びに行ったところで若鳥が代わってひなを暖めた。
2分後にオス親がハチの巣を持って帰って来て若鳥は声を出した。若鳥がひなに食べ物を与えているのをしばらく見ていたオス親は近くの木に枝探しに出かけた。メス親が戻ってきて一緒にひなに食べ物を与え、自分たちも食べた。オス親が枝を持って戻り、メス親の指示でオス親は飛び立ったとのこと。
以下の映像には巣で親子が一緒にいる時の行動の一部のみ記録されている。
この映像では 1:29 にメスが枝をくわえて若鳥に渡し、若鳥が配置しようとしている。メス親も参加して共同作業になりかけていた。手伝ってもらいながら教えているのかも? (血縁個体が繁殖技術を向上させれば包括適応度の上昇につながる可能性があるため、教えることが可能ならばそのような行動は進化できるだろう)
Crested Honey Buzzard nesting (同上)。
Crested Honey Buzzard nesting (同上)。
Crested Honey Buzzard nesting (同上)。わかりにくいが親子一緒にひなの面倒を見ているところ?
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchis Orientalis - Juvenile) @ Chiu S C DSCN3976 (Sein Chiong Chiu 2025.1.26 撮影)。こちらは渡りのハチクマの若鳥の映像だがマレーシアなのでこちらに含めておく。日本など北方で 2024 年に生まれた個体は越冬地でこのようにのんびり暮らしているのだろうか。
0:55 近くの枝をくわえて羽ばたいてみる。1:06 尾を上げて戻してからフンが落ちた。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus orientalis - Juvenile) @ Chiu S C DSCN3984 (Sein Chiong Chiu 2025.1.26 撮影)。こちらも越冬地でくつろいでいる渡りのハチクマの若鳥。しばらく正面で撮影者を見つめているところなど記録されている。頭かきや飛んでいるものを追っている視線の動きなど。
Crested Honey Buzzard chick approx 6 weeks old (Yvonne Blake 2025.2.12) 久々のアップロードで、ひなが育っているがなかなか見えなかったらしい。生後6週間程度のひなの羽ばたきの様子。
なんとヘルパーと育てていたひなは 2024.11.11 に死んだとのこと (詳細は不明)。そのためアップロードが止まっていたのか...。説明からは9日かけて新しい巣を造ったらしい。
前回アップロードは 2024.11.8 撮影でその時点で生まれたひなに食物を与えていたのでそのまま育っていれば生後6週間とはならない。何かが起きて再営巣したのだろう。
メスはオスに甘やかせてもらって (おそらく食物を運んでもらっている意味だろう) 巣にとどまっているとのこと。
このペアに限った話かも知れないが、繁殖失敗にもかかわらず留鳥亜種ではつがいのきずなは保たれているらしいことがわかる。
Crested Honey Buzzard female eating larva-comb Part 1 of 3 (Yvonne Blake 2025.3.8 撮影) 久々のアップロード。若鳥 (上記と同じ。生後8週間) は3日前に枝渡りをするようになってこの日に巣の外で初めてハチの巣をもらってその残り物を食べている親のメス。
Crested Honey Buzzard female eating Part 2 of 3 続き。Crested Honey Buzzard female finishing meal Part 3 食べ終わって嘴の掃除。残り物は気にせずそのまま落とした。
遡ってヘルパーと育てていたひなが 2024.11.11 死んだ後の状況が紹介されていた。
Crested Honey Buzzard mummy (Yvonne Blake 2024.11.14 撮影) 死んだひなは生後3日だったとのこと。2024.11.13 には強力な嵐があって (ひなが死んだのにも関係するのかも?)、ほとんどの枝が落ちてしまったとのこと。
メスは新しい営巣場所を選んだが巣を造りにくい場所のようで立腹しているオスをなだめているとのこと。巣材を掴んで運ぶメス。
日本のハチクマの雌雄識別をそのまま当てはめると尾のパターンが違う。このペアでは眉斑がよく見える方がメスらしい。冠羽が見えれば長い方がオス。
Crested Honey Buzzard couple at new nest site 新しい営巣場所で2日め。メスはオスの羽を引っ張った。これが "なだめる" 行動か。
Crested Honey Buzzard daddy looking for twigs 枝を探すオス。
Crested Honey Buzzard couple building nest 巣を造るつがい。メスのいるところにオスが戻ってきて (0:10) rattling call が聞かれる。結構近接してとまっている。その後メスが飛び出し (交代の合図?)、オスが巣材を配置している。置きにくい場所で落としてしまった。その後頭かきで "落としちゃった" というところか。
巣造りがうまく行かないのでオスが立腹するようになったのかも。
なんだか不器用そうにも見えるが立体構造のある枝をうまく組み合わせて強度のある構造物を作るのは我々が考えてもそれほど簡単でないだろう。適当に重ねるだけならばすぐ崩壊してしまい、配置に悩んでいるのも納得できる。
Crested Honey Buzzard daddy building new nest 巣を造るオスとのことだが結局羽繕いのみして飛び出す。
Crested Honey Buzzard female Day 4 of nest building 巣造り4日めとのこと。メス。嵐で風が強くて巣造りに時間がかかっているとのこと。
Crested Honey Buzzard male Day 4 of nest building 同上。こちらはオス。
Crested Honey Buzzard couple building new nest Day 6 巣造り6日め (2024.11.24 撮影) とのこと。
メスがオスを羽繕いしている。触ってもらっていて体は振れているのに視線はメスよりむしろ外を見ていた。
このつがいの過去の巣造りに要した時間は 5-7 日が最大で終わるとすぐに産卵したとのこと。今回は強風と嵐のために進行が遅れている。
このつがいは子育てが好きなようで次々と営巣し、「繁殖期」の概念が通用しない。そのため季節によって枝や葉の得やすさが異なるとのこと。巣のタイプも決まった形がなく小さい巣も使うとのこと。
これだけ聞くとまるでキジバトのような印象を受けるが、まさしくそうなのかも知れない。
高温湿潤な熱帯地域では巣の耐用期間が短く、必要最小限で繁殖して次は別のものに乗り換えてしまうのが最も効率的なのかも知れない。また我々が想像する以上に暴風などもあって巣の崩壊なども頻繁に起きるのかも知れない。粗雑な巣を作るのはそのための適応ではないかと思えてきた。
また大部分肉で子育てした事例も報告されているが、ハトのひなは格好の食物のようで食物を選ばず例えば年中繁殖するハトを食物とすればいつでも繁殖可能なのかも知れない。
温帯や亜寒帯では寒い冬の時期があるので巣の衛生はある程度保たれ、熱帯より長年反復使用可能なのかも知れない。
巣を新たに造るコストはそれほど大きくないかも知れないが、渡りのコストがかかっても温帯や亜寒帯では食物資源の豊富さ以外にも (他種の巣の借用も含めて) 巣を反復利用できる利点もあるかも知れない。もし巣の立派さが性・社会的信号となっているならばなおさら当てはまる感じもする。
日本の南西部にハチクマが少ない、あるいは定着していないのは都合よいハチ資源がないなど理由もありそうだが、台風の影響を受けやすいことも理由の一つかも知れないと少し深読みしてみた。
ハチクマは繁殖季節が遅いのでより影響を受けやすそうだが、樹上に営巣する他のタカ類にもある程度当てはまる可能性も考えられる。ノスリが小笠原に定着しているのに南西諸島には定着しにくい背景事情の一つになり得るかも知れない。
Crested Honey Buzzard male Day 6 building new nest 同上。巣にいるオスがかゆいのかこすっているところ。
Crested Honey Buzzard couple Day 8 into building new nest 同上巣造り8日目。2羽でそれぞれ枝を配置したりしているところ。
Crested Honey Buzzard Day 2 nesting 同上巣造り9日目 (2024.11.23 撮影)。あまりにもまばらで卵が落ちそうとのこと。オスが巣の縁にいてメスが巣の中にいる。
Crested Honey Buzzard nesting shift change こちらはひなの方 (2025.2.18 撮影)。生後6週間少しとのこと。オスがちょうど戻ってきてひなの見守り。交代でメスが飛び出すところ。ひなの声らしいものも聞こえるが他の鳥かも知れない。
Crested Honey Buzzard chick approx 6+ weeks old 同上ひなの映像。撮影者にとって6番目の孫とのこと。
Crested Honey Buzzard chick approx 8 weeks old 同上。生後8週間の巣立った若鳥 (2025.3.5 撮影)。枝渡り中。この日はとても勇敢で冒険的だったとのこと。翼を下がっているのはなぜ、との疑問が記されている (運動後暑くて半分開いているようにも見える)。
Crested Honey Buzzard chick approx 8 weeks old 同上。こちらは翼をさらに広げているように見える。胸の上が膨らんだように見えるのは頸椎を S 字に曲げているのが出張って見えている。
Crested Honey Buzzard chick 8 weeks old 同上。生後8週間の巣立った若鳥 (2025.3.8 撮影)。まだ枝渡りをして3日めとのこと。翼が下がっているように見えるのを気にされている。
Crested Honey Buzzard chick 8 weeks old 同上。
Crested Honey Buzzard mummy Part 1 of 5 同上。ハチの巣を持って屋根にとまっているメス。一仕事して暑かったのか少しあえいで休憩中。真後ろを超えて首を回して少しこちらを向く場面もある。以下に続く。
Crested Honey Buzzard mummy with food for chick 8 weeks old. First out of nest feeding Part 2 of 5 同上。初めて巣の外で食物が与えられた。
屋根の上から木へと飛んだとのことでよく隠れた場所にいる。過去の4羽のひなでは枝渡りをして最速でも 30+ 日目ぐらいにようやく巣の外で食物が与えられたとのことだが今回は非常に早くまだ太っていない段階。メスがハチの巣を与えるが、丸ごと与えるのでなく若鳥の足の成長に合わせて断片にして与えたとのこと (巣立ってるが確かに足がまだ貧弱で持つのも立つのも下手)。
記述から想像すると前のひな (4羽めでヘルパーになっていた個体) の時は丸ごと与えておそらくうまく行かずに教訓としたらしい。若鳥が食べている間はメスは残りの部分をくわえたまま飛び立った。
Crested Honey Buzzard mummy with food for chick 8 weeks old. First out of nest feeding Part 3 of 5 同上続き。食べ終わって足元もまだ不安定。食後の嘴の掃除など。
向きを変えて 1:44 あたりから小さい声で鳴いている。近くでメスがハチの巣の残りの部分をくわえてとまっていた。そこへ若鳥が飛んできた! メスと若鳥がハチの巣を引っ張りあうところ。[(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の [ハチクマのお客さんになって] で保護個体が著者と食べ物を引っ張り合う行動が描かれているが、あるいは人が食べるパンがハチの巣を食べているように見えたのかも知れない。
メスはそのまま飛び出してしまった。
Crested Honey Buzzard mummy with food for chick 8 weeks old. First out of nest feeding Part 4 of 5 同上続き。引っ張りあってできたハチの巣の破片を食べる若鳥。これが投稿者の指す少しずつ与えているところだろう。結果的に若鳥の訓練になっているのかも。
斜めにとまると足元が安定するようで片足でつかんで食べた。その後幹を使って嘴の掃除。
鳥は上を向かないと飲み込めないとしばしば言われるが下を向いたまま食べている。
Crested Honey Buzzard mummy with food for chick 8 weeks old. First out of nest feeding Part 5 同上続き。食べ終わった後の若鳥。枝渡りの練習中。
Crested Honey Buzzard mummy with honeycomb for chick 8weeks old Part 1 同上 (2025.3.9 撮影)。
ハチの巣を持ってとまって休憩しつつ若鳥を探すメス。若鳥は前日にあまりに遠くに外出し、この日は近くにいるようにと言いつけられたのではとの推察あり。くわえて運びにゆく。このような映像を見ると人がパンを食べるのは外見上いかにもハチの巣をくわえて食べているように見えるかも知れない。
Crested Honey Buzzard mummy delivering food Part 2 同上。若鳥は巣の近くにいてメスがハチの巣を巣に落として飛び去った。巣で食べる若鳥。
こちらはシンガポールでハチの巣を掴んで食べているところ。関連して紹介: Oriental Honey Buzzard having meal (Little Penguin "Mini Adventures" 2025.3)。亜種・年齢不明だが冠羽がないように見える。渡り亜種の越冬または移動中? 片足で器用に掴んで持ち上げて食べている。
Yvonne Blake のマレーシアのハチクマ親子に戻る。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 Part 1 of 3 (2025.3.11 撮影)。著者はこの日を巣立ちとみなしている。自信を持って別の木に移ったとのこと。その後枝を探検して過去に育った若鳥と同じような行動を示す。親は周囲にいなかったとのこと。葉などくわえようとしてみている。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 Part 2 of 3 同上続き。糞をする瞬間も後ろから記録されており、尾を上げてその後尾を下げる時に糞を落している。糞が小さいので糞を飛ばすタカより水分量が少ないのかも。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 Part 3 同上続き。ほぼ後ろ姿だが後半にほぼ真後ろを向いた正面顔。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 同上別映像。頭かきなど。しばしば撮影者の方向を見ていてほぼ真後ろを向いた正面顔がよく見られる。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 Part 1 of 3 同上これも別映像。こちらは正面向き。上空を時々気にしている。後半は片足を引っ込めたりして片足でも長時間立てるようになってきたよう。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 Part 2 of 3 同上続き。これも正面顔がよく見られる。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 1 Part 3 同上続き。人家の近くなので生活音や人の動きにも反応しているよう。最後に動き出して枝を足でひっかくような動作を多少見せた (ハチの巣を掘る行動の練習か)。
Crested Honey Buzzard mummy cleaning beak after delivering food to nest こちらは巣に食物を運んだ後のメス。柱にとまって嘴の清掃中。メスは巣に食物を置いて飛び出たが別の木にいる若鳥は気づいてなかった。
メスが呼んだが若鳥が聞いていないようなので、再度巣のある木に戻ったところ今度は若鳥が気づき、メスのとまった枝にとまって興奮して枝も移ってねだったとのこと。メスは巣に誘導して若鳥は無事食物にたどり着けた。興奮して鳴きまくっていたとのこと。これはその後のメスの映像。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 3 同上巣立って3日め (2025.3.13 撮影)。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 3 同上。主にこちらを見ているところ。時々上も気にしている。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 5 同上巣立って5日め (2025.3.15 撮影)。左右の頭かき。足が少しふらつく。
Crested Honey Buzzard mummy after delivering food (2025.3.24 撮影) 若鳥がメスの運んできた獲物を奪い取って巣に持ち帰って食べたとのこと。映像はメスの趾にできた傷 (表皮が剥がれてしまったらしい)。若鳥とはいえ親と同じ大きさなのでなかなか危ない。傷は治りつつあるとのこと。
中国のビデオで巣でオスがメスに獲物を渡す際に嘴に持ち替えているのはあるいはこのような危険を避けるためかも知れない。
Crested Honey Buzzard mummy after delivering food 同上続き。食物を運び終えた後で嘴の掃除。趾の傷はあまり気にしていない感じ。
オスをこの 17 日見ていないとのことで懸念されている (2025.4.3 掲載されたものだが日数はこの映像が撮影された時点のものらしい)。これまでも巣立ち後オスが休暇をとったことがあったが最長で5日だったとのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day14 巣立ち後 14 日の若鳥 (2025.3.24 撮影)。これまでよく過ごしていた木に止まらなくなって探すのに苦労している。食物はほぼ巣でもらっており、巣の外では1回のみとのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day14 同上。羽繕い。
Crested Honey Buzzard fledgling Day14 同上。枝にとまって片足を途中まで上げている。
Crested Honey Buzzard fledgling Day14 同上。枝上を移動してやはり尾を左右に振っている。その後頭かきや枝の先端をつついてみる。
Crested Honey Buzzard fledgling Day14 おそらく同上続き。枝の上を移動し尾を左右に振っている。
Crested Honey Buzzard fledgling Day14 おそらく同上続き。頭かき、翼を広げたり伸びなど。見つけるのが難しくなってきているとのこと。
Crested Honey Buzzard daddy (2025.3.26 撮影 2025.4.13 掲載)。大変心配させられたオスは 18 日間不在で、ようやく姿が見られたとのこと。MIA = missing in action の略。何事もなかったかのように戻って羽繕い中。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 17 Part 1 of 2 (2025.3.27 撮影 2025.4.16 掲載) 巣立ち 17 日後の若鳥。
長らく不在になっていたオスがハチの巣を近くの新しい巣に運んだが若鳥が見当たらず、10 分連続で呼んでいたとのこと。若鳥がついに近くにやって来たが、オスは反対方向を向いていて気づかなかったとのこと。
声に反応してやってきたと思われるが巣が隠れた場所で若鳥が巣に戻るところは見られなかった。オスはずっと鳴いていて若鳥はどこから声がするのか探していたとのこと。新しい巣は新しいテリトリーにあるとのこと。例えばヘルパーになるのを期待するなど、若鳥を新しい巣に呼ぶ習性があるのだろうか。
オスの不在中もメスが無事に育てていた模様。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 17 Part 2 同上続き。0:28 あたりから親が rattling call で呼んでいると思われる。この声を聞いて反応して飛び出した様子がわかる (これがハチクマの声であることを知らなければ背景で何が起きているのか全くわからないかも)。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 17 同上食事後。羽繕いや頭かき。巣立ってそれほど日数が経っていない若鳥でも尾の縞模様は立派で冠羽もある。日本の亜種の若鳥とはなぜ尾の縞模様が違うのだろう。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 17 同上続き。小枝をかじってみたりしている。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 20 (2025.3.30 撮影 2025.4.17 掲載) 前日に何かが起きて新しい巣からあまり遠くに行かなくなったとこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 20 同上続き。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 21 in the rain (2025.3.31 撮影 2025.4.20 掲載) 巣立ち後 21 日の若鳥。強い雨が長く続いた後に小降りになった状態。頭の羽毛は先端部のみ着色であることがわかる。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 21 drying after the rain 同上雨上がり後。この日は遠出はしなかったとのこと。片足を持ち上げて握っている。
Crested Honey Buzzard drying up after the storm (2025.4.3 撮影 2025.4.20 掲載) 嵐の後に乾かしているところ。
なんと若鳥が巣立ってわずか 20 日 (しかもオスが姿を見せなかった?) なのにもう次の繁殖に入っていて巣にいたメスをオスが交代し、メスが外に出て乾かしているところ。目つきはなかなか精悍。
Crested Honey Buzzard female drying after the storm 同上前後の映像か。こちらは正面を向くとややとぼけた感じに見える。
Crested Honey Buzzard female drying after the storm 同上先行する映像か。見つけた時の状況が記されていて、まずオスが見つかり若鳥が飛び出したのでじっくり探すとメスが見つかったとのこと。
Crested Honey Buzzard female drying after the storm 同上。
Crested Honey Buzzard female drying after the storm 同上反対側から。趾の傷は治った?
Crested Honey Buzzard male preening and drying up after the rain 同上こちらはオスが乾かして羽繕い中。
Crested Honey Buzzard male preening and drying up after the rain 同上。巣のメスに交代した後再度交代してオスが出て乾かして羽繕い中。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 24 (2025.4.3 撮影 2025.4.20 掲載) 同上こちらは巣立ち後 24 日の若鳥が乾かしているところ。一人前に (?) 尾を完全に広げたりしている。新しい繁殖に入った段階で若鳥もまだ一緒にいる。渡りのハチクマが熱帯地方の留鳥ハチクマから進化したのであれば (逆の過程も考えられる) 繁殖時期に若鳥も一緒にいるのがハチクマの本来の性質なのだろうか (繁殖が始まっても若鳥がまだねだっているクマタカとの類似性を考えてしまう)。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 24 almost dry after the storm 同上若鳥。ほぼ乾いた段階。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 38 巣立ち後 38 日めの若鳥 (2025.4.17 撮影)。枝の上を探索中。
こちらは日本と同じ亜種の渡りのハチクマの若鳥越冬中の映像: Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus orientalis - Juvenile) @ Chiu S C DSCN5918 (2025.4.23 撮影)。羽繕いや頭かきなど。
こちらは現在紹介中のもとのは別個体で、2023.3.28 以来の観察となるメスとのこと: Crested Honey Buzzard female (2025.5.3 撮影) 0:13 に相棒のオスの呼ぶ声 (rattling call) が聞こえた。声を聞いて向きを変え尾も左右に振った。
Crested Honey Buzzard female 同上。相棒の声は 0:59 付近で聞こえた。
これも別ペアの方の映像で Crested Honey Buzzard female avoids mating with male (2025.5.4 撮影) 巣は完成しているとのことでオスの交尾をメスが拒んだとのこと。最後にその瞬間が撮影されている。
Crested Honey Buzzard - male after mating rejection 同上、交尾を受け入れられなかったオスの映像。
Crested Honey Buzzard female avoids mating with male again 同上、再度の交尾の試みも受け入れらなかった。ビデオの早い段階でオスが飛んで来たが逃げてしまった。
Crested Honey Buzzard - male とまって多少羽繕いをするオス。真後ろからの撮影で首が半回転以上回るのがわかる。
Crested Honey Buzzard male (同上 2025.5.5 撮影) 羽繕いから飛び出すオス。遠くてよくわからないが 0:12 あたりから相棒が鳴いているような気がする。
Crested Honey Buzzard female 同上、こちらはメス。周囲を見渡しているところ。
Crested Honey Buzzard male 同上オス。しばしば撮影者の方を見ている。
Crested Honey Buzzard female 同上。頭かきをしているメス。
Crested Honey Buzzard male 同上オス。日の当たるところで羽繕いなどくつろいでいる感じ。
上記と同じペアの珍しい映像。ササゴイの巣を襲うハチクマ
Crested Honey Buzzard female attacking Striated Heron nest (2025.5.5 撮影) メスがササゴイの巣を攻撃したとのこと。3回攻撃をしたがその都度ササゴイの親が攻撃を逸すことに成功したとのこと。見物人が多数おり、多くの人はササゴイの方に加勢してササゴイが叫び声を上げると手を叩いて妨害しようとしたとのこと。弱い鳥を襲うけしからんタカと映っているだろう。現地語のわかる方どんな話がなされているか聞き取ってください。
カメラが追いきれていないが、この映像は羽繕いをして一見平静にしているハチクマが3回めにササゴイの巣を襲う場面。映像の一番最後に。飛び立つ時の顔つきは眉斑もくっきりして他のタカと同じように見える。
この行動から考えられる解釈は [擬態と種・亜種の関係] にまとめた。
Crested Honey Buzzard female after 3rd attack on Striated Heron nest 3回めの攻撃の後のメス。人の手打ち音も聞こえる。ここであきらめた。
Striated Heron nest that survived 3 attacks by a Crested Honey Buzzard 攻撃に耐えたササゴイの巣。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old (2025.5.6 撮影) こちらはずっと紹介していた方の先のペアの先の子供 (Four) でヘルパーをやっていた個体。眉斑もくっきり立派になって里帰り。268 日は生後の日数か。
先のペアは見えにくいところで子育てしているらしいが、巣立った若鳥 (Six, 57 日目) が繁殖中の両親が忙しいので子育ての手伝いにきたのではないかとも (なお Five は巣立つ前に死亡)。
この個体を最後に見たのは Five の死んだ日で 93 日目だったとのこと。撮影者にとって半年ぶりの再会。半年ちょっと前に親と添い寝をしていたあの個体。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old 同上。正面映像。周囲を眺めつつも途中で頭かき。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old close-up 同上。正面拡大。羽繕いや頭かき。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old preening 同上別の場所で羽繕い。熱心に尾を羽繕いしている。
Crested Honey Buzzard Six fledgling Day 57 (2025.5.6 撮影) こちらは 57 日目 Six の方。幼さがまったく違う。親か Four を見つけたのか典型的な甘え声を出した後飛んで行った。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old (2025.5.6 撮影) 後日アップロードされた続き。268 日の Four の方。
Crested Honey Buzzard Four 269 days old (2025.5.7 撮影) こちらは翌日の Four の映像で Four is showing Six how to hunt shrubbery for chicks とあり、Six に下生えでどのように獲物を捕まえるか教える訓練の2日めとのこと。
親が繁殖のために巣立った Six の面倒を見られなくなったので、忙しい親に代わって Six を教育中との解釈のよう。これもヘルパーの形態の一つなのか。Four はよほど面倒見のよい個体らしい。
Four と Six に直接の面識があったかどうかは不明だが、親の育てている子らしいことはわかるのだろう。Six の方も知らない個体がやってきているのに手伝いに来ていることがなぜわかるのだろうか。
いずれにしても一度親元を離れた個体がまた手伝いに戻ってきていることになる。
Crested Honey Buzzard Six fledgling Day 59 (2025.5.8 撮影) こちらは 59 日目 Six の方。行動範囲が広がったとのこと。とまって羽繕いとフンをするところ。やはりハチクマのフンは水分が少なくて固まっているように見える。熱が逃げにくく暑いところで体温調節のために水分量が不足しがちで尿から積極的に水分再吸収を行っているのでは?
Crested Honey Buzzard Six fledgling Day 59 同上。とまりながら何かを視線で追いかけている。
Crested Honey Buzzard Six fledgling Day 59 同上。墓地によい場所を見つけて羽繕いや頭かきなど。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 50 drying after storm (2025.4.28 撮影) こちらは少し前の映像で直近の若鳥 (Six, 50 日目)。嵐の後に乾かしているところ。頭かきや rousing が見られる。
(2025.5.8 撮影) 2家族が同時紹介されて複雑になっているが、こちらは 2023.3.28 以来の観察となるメスのつがい で 2005.5.4 に交尾の拒否などの映像のあったつがいの方。メスに食物を与えた後のオスの姿とのこと (求愛給餌と呼ばれるものだろう)。羽繕いや頭かき。
Crested Honey Buzzard female preening Crested Honey Buzzard female preening 同上、メスの羽繕い。
Crested Honey Buzzard couple 同上、朝に交尾の試みが2度失敗した後とのこと。メスが羽繕いしてくつろいでいたところにオスがやってきたが逃げられた。瞳孔サイズを変えているので感情が現れているのだろうがさすがにそこまでは読み取れない。
Crested Honey Buzzard male 同上、最後にメスを追って飛び出したが再度失敗とのこと。
Crested Honey Buzzard male 同上、交尾失敗後のオス。気分転換して (?) 羽繕いに。
Crested Honey Buzzard male 同上、4回めの失敗の後それぞれ別の方向へ飛んだとのこと。オスの正面表情。
Crested Honey Buzzard female (2025.5.18 撮影) このペアの羽繕い中のメス。
Crested Honey Buzzard female 同上。最後に飛び出し。
ハチクマの先生と生徒!?
こちらはまた Four と Six の関係で「何だそれは?」のような話が多数。映像順序が不明のまま並べておく。
Crested Honey Buzzard Four lecturing Six (2025.5.6 撮影) Four (268 日) が Six (57 日) に教えているところでしばしば呼ぶ声を出している。解説によるとああせよこうせよと小うるさい (nagging) (指導が厳しい) らしい (笑)。Four の翼は親のメスより長くなっていて風格はまるで親鳥。Six も時々応答しているとのこと。羽繕いや rousing あり。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old lecturing Six fledgling Day 57 同上。書かれている解説は間違っているかも知れないが、Four の行動を Six がよく模倣している。Four が降りた場所に Six が降りる、Four が枝を集めるとそれに従うなど。Four は非常に優れた教師で Six の習得は非常に早く、3日で教育が終わって離れたとのこと。
これは鳴いている Four と、別の場所にいる Six の映像。呼ばれて Four がとまっていた場所に移動した映像。
Crested Honey Buzzard Six fledgling Day 57 and sibling Four 同上。こちらは Six が羽繕いをしていると Four に呼ばれた。Six が応答しながら近くまでやってきた。Four の行動 (この部分は映像にない) をまねて? Six が枝を折っているところ。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old Four が枝の折り方を教えて見せているところとのこと。そして飛び出す。記述から推定するとそして上記の映像に続くのかも。しかし枝を折るのは先生にしてはあまり上手でない (それではやってみろと言われると我々でも難航するかも知れない)。
まだ生後1年にも満たない若鳥なので当たり前かも知れないが、他の映像から判断してもハチクマは新鮮な枝を折るのはあまり得意でない感じがする。だからこそ嘴の細い樹上性タカ類で嘴縁突起が発達しやすいのかも。
ペンチと同様、荷重のモーメントは嘴の幅に比例するはず。幅の広い嘴を持つ種であればあまり問題がない。新鮮な枝でなくてもよい種類、あるいはそもそも巣材に枝を使わない種類では嘴縁突起が必要がない理屈になり得るかも。代わりに足を使うなど異なるテクニックを用いる種でもこの目的の嘴縁突起はなくてもよいことになる。
[カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] あるいはどこかで触れたつもりだったが、「カッコウハヤブサ類の嘴縁突起は枝を折るためぐらいしか用途を思いつかないが、その程度の目的だけのために進化するものだろうか」と書いてあるものがあった。
ただしハチクマには嘴縁突起はない。折れない時は足を使って体重をかけられるためだろうか。少し遡って Crested Honey Buzzard daddy collecting leafy twigs to cushion nest for newly hatched chick の部分も参照いただきたい。
Crested Honey Buzzard Six fledgling Day 57 同上。Six が枝をくわえている。Four が声を出して指示しているとのこと。
Crested Honey Buzzard Six fledgling Day 57 replying to Four 268 days old 同上。こちらは Six が声を出して応答しているところ。そして飛び出す。
Crested Honey Buzzard Six 同上。Four は生まれた巣を経てかつて食物をもらっていた古い巣に戻り (場所をよく記憶していることもわかる)、Six を呼んでここが食べる場所と教えているとのこと (Four はメスで自身の繁殖に備えた練習も兼ねているかも? 巣で居心地よさそうにしている)。Six は指示に従って飛んできたとのこと。
Crested Honey Buzzard Four 268 days old 同上。指示に従って巣に入った Six。なんと2羽一緒に巣にいる。
学術的に表現しようとすると難しくなるが「ままごと」と言えばよいのだろうか。「ままごと」の英訳を探してみると play pretend があった。なるほど。しかし自明に書かれていなければ霊長類の行動について記述しているのかと思われるのではないだろうか。ハチクマの「ままごと」!? と表題にまとめたかったぐらいだが、さすがに何のことか想像も付かないだろうと断念した (笑)。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 63 (2025.5.12 撮影)。Four は3日間の教育を施した後去ったとのこと。"スズメの学校" ならぬ "ハチクマの学校" の全教科修了。個別指導・短期集中型と言える (笑)。
Six はまた1羽に戻って頭かきなどしているところ。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 63 同上。
ところで、血縁個体の育児を助けるヘルパー行為は行動生態学的にも進化し得る性質であるが、他の個体の行動を模倣するのはなかなか高度なのではないだろうか。さらにその見本を示す行動はどのようにして進化するのだろうか (教育行動の進化?)。模倣する方は直接的利益が得られるだろうが、見本を示す個体は何か利益を得ているのだろうか。弟子が技術を習得することによる満足感を得ているならばほとんどヒトのような話になってしまう。
技術を教える場合に模倣させ、教師から見て正しくできていなければ介入し、教師から介入がなくなれば習得したとみなせるならば言葉がなくても技術の伝授は可能だと思ってしまう。言葉のわからない外国人教師から通訳なしで技能を習うのとあまり違わない気がする ... まるでヒトの行動の進化を議論しているのか (?!)。
もっとも親が子に教える場合は生存率を上げるなど有利な形質として選択される可能性があり、血縁個体ではその延長で考えられないこともない。
この Four の場合は将来の繁殖行動に備えたリハーサルのような位置づけが考えられるかも知れないが、枝の折り方まで模倣させるのは繁殖行動のメニューに含まれていないような気がする。それとも普段も夫婦で教えあっているのだろうか。
Four は Six ともしかするとつがいになりたい衝動から一緒に巣に入るなど上記のような行動を起こした可能性も考えられそうだがよくわからない。最も知的とされるカラスでもこのような行動は知られているのだろうか。
また Four はなぜ3日であっさり離れたのだろうか。つがいになりたい衝動だけでは説明できない気がする。もしかすると次の生徒となるよそのハチクマの子を探しに行ったのかも (??)。もし出前授業 (?) になっていれば利他的互恵行動が発生しているのかも。
ヒトの行動進化を議論した研究で「xx の行動 (資源の分配など) はヒトや類人猿のみ知られていて他の哺乳類や鳥類では知られていない」などと書かれていることがあるが、鳥類ではカラスを想定した記述になっているかも知れない。カラス以外を見渡せばあるかも知れない状況をうかがわせる。
またカラスの知能は食物を得るために特に進化しているように見えるが、カラスの知能の方が雑な印象も受ける。ハチクマは大きな鳥なのでカラス並みの知力を持っていてもそもそも驚くに値しないかも知れない。
「動物の世界」2版 5 (日本メール・オーダー 1986) pp. 667-669 のオウム類の項目 (浦本) で、オーストラリアのクロオウム類 (当時の表記)、ここでは具体的にアカサカオウム Callocephalon fimbriatum Gang-gang Cockatoo (現在ではクロオウム属ではない) で理由なく木の枝を折るのが好きでおもしろいからやっているとしか思えないことが紹介されていた。
オウム類は木の枝を折って巣材としないと考えれば "オウム類は賢いので" 目的のない「遊び」を行っていると解釈できるわけだ。ハチクマは木の枝を巣材に用いるので、繁殖に備えて枝を折る練習 (?) と考えた解釈がなされているわけだが、おもしろいからやっている可能性はないだろうか。
オウムやカラスが行えば遊びで、タカならば訓練と解釈するのは先入観の入り過ぎでは (?)。
そう言えば [飼育下の行動: 韓国の事例] で雪だるまに指した枝を抜く映像があった。とんがったものをいじったり抜いたりするのがそもそも好きなのかも知れないが (インコに紙を破られるのはいやというほど経験した)、目的のない「遊び」の要素も含まれているかも知れない。マレーシアの先生ハチクマも真面目に折るところまで行っていないので明確な目的のない「遊び」のレベルかも。おもしろいから真似てやってみるのを教えているとすれば遊びを教えている (??)。一層「ままごと」的に見えてくる。
ハチクマとは何かをそもそも知らない人が聞いたら「ハチクマというのはもしかしてクマのことでしょうか?」と恐る恐る聞かれても不思議でない気がする (笑)。
Crested Honey Buzzard male (2025.5.30 撮影) 休憩中のオス成鳥。足元が狭くすべりかける。まっすぐこちらを見ている時の正面視が見られる。日本のハチクマのオス成鳥とは顔がだいぶ違う。
Crested Honey Buzzard male preening (2025.5.30 撮影) オス成鳥羽繕いと頭かき、大きく口を開いたところ。
Crested Honey Buzzard female (2025.6.2 撮影) こちらは最近のメス。
Crested Honey Buzzard mummy nesting (2025.5.6 撮影) 日付が少し戻っているが Four が Six に教えていたのと同じころ。巣のひな (Seven) を抱いているメス。孵化後1週間少しとのこと。
Crested Honey Buzzard daddy with chick (2025.5.7 撮影) オスとひな。この説明では孵化後 13 日。ひなに唾液か何かを与えているところか。ずいぶん経験豊富なペアのはずだが熱帯の留鳥ではひなは1羽が普通なのかも (その代わり繁殖回数が多い)。
Crested Honey Buzzard daddy doing nesting duty 同上。オスがドリアンの木から葉をもぎとって敷いているところ。におい物質が豊富なのでその効果を用いているのかも。
Crested Honey Buzzard daddy with chick 同上。オスとひな。何を行っているのか見えない角度だが、下を向いて巣の中を何か掘っている?
Crested Honey Buzzard delivering breakfast (2025.5.19 撮影) ひなは孵化後 25 日とのこと。ハチの巣を運ぶ途中の休憩中。
Crested Honey Buzzard mummy feeding chick 25 days old 同上。メスが巣でひなに与えているところ。
Crested Honey Buzzard mummy feeding chick 25 days old 同上。ひなに与える時は近くに焦点を合わせるためか瞳孔が少し収縮する。
Crested Honey Buzzard parents and chick when daddy brings breakfast 同上。こちらはオスが食物を運び、両親が巣にいる状態からオスが飛び立つ。上記4映像は時系列順でないかも知れない。
Crest Honey Buzzard daddy (2025.5.21 撮影) 巣にいるオスとひな (27 日齢)。オスは枝を持ち帰ってメスと交代、メスは羽を乾かしに出たとのこと。オスは持ち帰った枝を配置している。3次元の枝をどのように配置するのかそれなりに苦労しているように見える。
Crested Honey Buzzard daddy feeding check 27 days old 同上。オスは鳥のひなを運んできた。1羽のカラスに追われていて一緒に舞っていたがカラスが諦めたとのこと。オスがひなに与える。メスは外で羽を乾かしていてその後狩りにでかけたとのこと。もしかするとカラスのひなをさらってきたのかも。
Crested Honey Buzzard daddy feeding check 27 days old 同上。
Crested Honey Buzzard mummy preening 同上。外で羽を乾かして羽繕い中のメス。オスが巣で与えているうちにメスが外で羽を乾かすのはこの日2回目とのこと。尾の手入れ中。
Crested Honey Buzzard mummy back in nest 同上。映像の順序関係は不明だが、メスが戻ってきてオスが狩りに出ている。
0:07, 1:10 にひなの声らしい rattling call 的な音声が聞かれる (ただし他の鳥の声かも知れない。親の足元が若干危ういので自分に注意しろと存在主張の音声かも)。その後メスが唾液または何か残り物を与えているように見える。
マレーシアのハチクマ若鳥が糞をする映像があった: Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7284 (Sein Chiong Chiu 2025.6.16 撮影)。
この映像ではしっかりした量を出していて下に落としている。尾は思ったほど上げていないがしゃがんでいる。小鳥のように自然に出るのではなく体腔内圧をかけているように見える。
淡色の個体で、とまっている映像では淡色型のカワリクマタカによく似て見える。Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" で大きさを確認しておくと、この地域のカワリクマタカ (亜種 limnaeetus) で翌長オス 380-430 mm、メス 405-482 mm、体重メス 1.36-1.81 kg とある。全長は出ていない (カワリクマタカは亜種間の大きさの違いが大きいので個々に調べる必要がある)。
ハチクマの方の torquatus (亜種として扱う場合。留鳥亜種なので渡り亜種ほど翼は長くない) ではオス 398-000 mm、メス 000-455 mm となっていて、この亜種の体重記述はない (最小・最大の数字しかなく、オス・メスに仮に割り振った表記と思われる)。
日本のハチクマの体重から推定するとカワリクマタカの方が体格を反映しておそらく少し重いが、大きさはハチクマとおそらく大差なし。日本のハチクマとクマタカの関係とは少し異なる。
バードウォッチャーでも間違えるぐらいなので捕食される側からはどちらも同じに見えるのではないだろうか。
(以下の映像は [ハチクマ類が糞を飛ばさない理由?] 脱糞風景に紹介していたがこちらに再掲した):
マレーシアのハチクマ若鳥が糞をする映像があった: Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7284 (Sein Chiong Chiu 2025.6.16 撮影)。
この映像ではしっかりした量を出していて下に落としている。尾は思ったほど上げていないがしゃがんでいる。小鳥のように自然に出るのではなく体腔内圧をかけているように見える。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7294 (Sein Chiong Chiu 2025.6.16 撮影)。同じ個体の続き。枯れ枝を壊したりして遊んでいる。もぎ取った枝を足で器用に掴み直している。
Large billed Crow & Oriental Honey-buzzard (Pernis p. torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7326 (Sein Chiong Chiu 2025.6.18 撮影)。上記と同じ個体と思われるが日付が異なる。ハシブトガラスが同じ枝にとまって羽繕い、ハチクマもちょっと頭かきをした。そこで隙を見てハシブトガラスはちょっと牽制した場面があったがハチクマが飛ぶことはなく本格的なモビングとはならなかったよう。最初の方の場面ではハチクマが少し翼を広げると身を引いた。
カラスの羽繕いもあえて気になるタカのそば (ハチクマとカワリクマタカの区別はカラスにとってもおそらく難しい) にとまって緊張感から転位行動的 (例えばちょっかいを出すべきか逃げるべきか両方の衝動がある) な部分があるかも知れない。
タカの方も常時反応できる体勢はとっているがそこまで緊張感を示した姿勢にはなっていない。さてどちらの方が賢いのでしょう?
種名はハシブトガラスだがやはり日本のハシブトガラスは大きい感じがする。
Large-billed Crow & Oriental Honey-buzzard (Pernis p. torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7330 (Sein Chiong Chiu 2025.6.18 撮影)。上記映像と同じ日付。とまっていたハチクマが上空のカラスに気づいて翼を広げた場面。そして同じ枝にとまってカラスが羽繕い。カラスがちょっかいを出そうとしたところで、別の鳥 (カラス? ともう1羽別の鳥) が飛んできたのに合わせて飛び出さたところ。
こちらは同じ撮影者による渡りのハチクマの若鳥。繁殖後少なくとも1年は繁殖地に戻らない時期の夏場の生活: Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus orientalis - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7174 (Sein Chiong Chiu 2025.6.8 撮影)。木にとまって他の鳥が飛ぶのを視線で追っているらしい。
Yvonne Blake の子育て中の巣の映像に戻る:
Crested Honey Buzzard chick 36 days old (2025.5.30 撮影) ひなは孵化後 36 日とのこと。カラスのひな? を失敬したのではないかと思われるが、カラスが巣を見つけてしまったとのこと。カラスの集団を追い払ってメスが戻ってきたところ。巣のひなの安全を確認して飛び立ったとのこと。
Crested Honey Buzzard chick 36 days old 同上。映像順序は不明。メスが巣に帰ってきたところ。
Crested Honey Buzzard chick 36 days old 同上。こちらはひなのみの時の映像。
Crested Honey Buzzard chick 41 days old with mummy (2025.6.4 撮影) ひなは孵化後 41 日。カラスは大丈夫だったよう。メスがはちみつ滴るオオスズメバチの巣盤を持ち帰ってひなに与える。まだ親からもらっている。10 分後にオスが中型のハチの巣盤を持ち帰ったとのこと。
Crested Honey Buzzard chick 41 days old with mummy 同上。
Crested Honey Buzzard chick 41 days old with mummy 同上。鳥の綿羽のようなものも与えていて自身も食べている (以下も含めて映像の順序関係不明)。
Crested Honey Buzzard chick 41 days old 同上。ひなの映像。前半でメスは空になった巣盤を捨てに行った。0:21 にひならしい声 (rattling call 的) が聞こえるが合図か、メスが動き出したので踏まないように注意か。ひなも口を開けていて暑いよう。
Crested Honey Buzzard chick 41 days old 同上。巣盤を捨てに行ったメスが戻ってきた。巣内のものを何か拾って食べている。メスが歩くとついバランスを崩してひなに当たりそうになる。
Crested Honey Buzzard chick and mummy (2025.6.9 撮影) 巣にいるメスとひな。ひなは孵化後 46 日。
Crested Honey Buzzard chick and mummy 同上。最後にメスが撮影者を覗き込むような形になっているが特に何も起きなかった模様。
Crested Honey Buzzard chick 54 days old (2025.6.17 撮影) 54 日齢の若鳥。すでに巣立っていた。途中であくびや頭かき。
Crested Honey Buzzard chick 54 days old 同上。
Crested Honey Buzzard chick 56 days old (2025.6.19 撮影) 56 日齢の若鳥。頭かき。耳羽に相当する部分の色が先に変わっていて面白いパターンになっているが、これは外耳穴が露出しているとハチが入りやすいので優先して防御されているのだろうか。
Crested Honey Buzzard chick 56 days old 同上。
Crested Honey Buzzard and chick 59 days old with mummy (2025.6.22 撮影) 59 日齢の若鳥。メスが巣で若鳥にハチの巣を与えているところ。空になった残骸をくわえてメスが運び出す。メスの飛び立つ瞬間も写っているのでどこに力を入れて飛び出しているか判断できるかも知れない。その後も若鳥は残りを食べていた。
Crested Honey Buzzard and chick 59 days old 同上。巣で翼を広げているところ。その後頭かきをしてバランスを崩す。何かをみつけて向きを変えたが親が近くを通っているのかも。尾をしばしば左右に振ってご機嫌 (?) で、満足感が現れている感じ。
Crested Honey Buzzard chick 59 days old preening 同上羽繕い中。その後少し歩いて外に出る。
Crested Honey Buzzard chick 59 days old 同上。もう少し外に出た。枝をかんでみたりしている。
Crested Honey Buzzard chick 60 days old (2025.6.23 撮影) 翌日の 60 日齢の若鳥。枝渡り途中の休憩中。これまで翼の訓練はほとんどしていなかったとのこと。
Crested Honey Buzzard chick 60 days old 同上。
Crested Honey Buzzard - male/daddy (日付は遡るが 2025.6.20 撮影) ハチの巣を運んできた後のオス。羽繕い? で嘴に羽毛が付いてしまった? 正面から見るとなかなか立派。
Crested Honey Buzzard - male/daddy 同上。後ろ向き。
Crested Honey Buzzard fledgling Day1 (2025.6.29 撮影) 撮影者はここで巣立っていると判断して巣立ち後 1 日と呼んでいる。巣立つと fledgling と呼び方は変わるが、すでに巣から出ていたのでどの時点で巣立ったかは定義や呼び方次第。
撮影者は飛んだことで巣立ったと判断した模様。この定義では 66 日目に巣立って、一つ前のひなの 63 日より少し遅いとのこと。
あまり機嫌がよくないらいしく、のどの右側が腫れていて嘴を完全に閉じることができないとのこと。
虫がよくやってきていて虫よけの臭気などはあまりなさそうに見える。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 3 (2025.7.1 撮影) 巣立ち3日目とのこと。これまでの他の若鳥に比べて不活発であまり探索活動や羽ばたきをしないとのこと。やはり腫れていて嘴を完全に閉じることができないとのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 3 flying back to nest 同上。近くの枝から巣に戻ったところ。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 3 同上。枝にとまっている姿で嘴が閉じない。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 3 feeling sleepy 同上。眠そうにしているところ。病気なのではないかと心配されている。
Crested Honey Buzzard - male daddy (2025.7.3 撮影) オス親の映像。この映像は早い時期に掲載されていて、かなり間が空いているが繁殖映像は撮りにくいのかも - と思ったら巣立った後だった。経緯は上記と下記。とまりから飛び出しまで。
以下は後日掲載されたもの。Crested Honey Buzzard fledgling Day 6 (2025.7.3 撮影) 巣立って6日目。下嘴が長くて閉まらないことに気づいたとのこと。
正面からみるとのどの右側が腫れており目にも欠陥があって腫れているとのこと。巣立った時以来飛んでおらず、両親が励ましているがこの数日飛べていないとのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 6 同上。左目に生彩がない。
Crested Honey Buzzard mummy with fledgling Day 6 Part 1 同上。こちらは巣にすでに食物があるのにメスにねだっているところ。
Crested Honey Buzzard mummy with fledgling Day 6 Part 1 同上。20 分ねだってようやくメスが哀れに思った (原文 relent) とのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 7 (2025.7.4 撮影) 巣立って7日目。のどの右側の腫れと嘴が閉じない症状がより目立つが右目の腫れは少しましになったとのこと。
Crested Honey Buzzard fledgling Day 7 showing deformed beak 同上。嘴が変形している。
Sein Chiong Chiu の撮影 Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7292 (Sein Chiong Chiu 2025.6.16 撮影) こちらは別個体の若鳥。主に羽繕い。真正面もしばしば向くが確かにカワリクマタカの淡色型にそっくり。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7346 (Sein Chiong Chiu 2025.6.18 撮影) 同上。クローズアップでいろいろな方向を向いているところと全体像の両方がある。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7342 (Sein Chiong Chiu 2025.6.18 撮影) 同上。最後に飛び出しあり。
Oriental Honey buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile & Male) @ Chiu S C DSCN7811 (Sein Chiong Chiu 2025.7.8 撮影) 近くにいるオス親を大きな声で呼ぶ別個体の若鳥。
Oriental Honey-buzzard (Pernis Ptilorhynchus torquatus - Juvenile) @ Chiu S C DSCN7817 (Sein Chiong Chiu 2025.7.13 撮影) 同じく若鳥。枝皮を剥いでくわえたり足で掴み直したりしている。ハチの巣をくわえる行動もこれに近いものかも。
[中国のハチクマの繁殖生態]
こちらは日本と同亜種の中国のハチクマの巣のビデオ ([音声] の項目でも別映像を紹介。Nature bird。中国で話題となっているようでそれぞれのビデオの再生数が結構すごい)。
The male bird returns to incubate eggs オスが戻ってきて抱卵するまで。
(以下最初の数件は [音声] の項目に含めていたが定期的アップロードが行われるようになり移動した)
中国で日本と同じ亜種のハチクマの巣のビデオで抱卵中のメスが戻ってきたオスと抱卵交代の際の発声: Honey Buzzard, the male bird brings back leaves to change shifts and incubates eggs。
Honey Buzzard,Male bird hatches eggs, female bird returns to change shifts メスが戻ってきてオスと交代。映像を見る範囲ではどちらが出している声かわからないが抱卵交代と関係が深い声のよう。
Honey Buzzard, the male bird brought a string of leaves back and incubate eggs でも同様に戻ってきたオスと抱卵交代の際の発声。
Honey Buzzard, the male bird came back to change shifts and didn't bring anything オスが戻ってきた時に発声があり、最初は一般的なタカの発声パターンに似ている (?) 感じがするが途中から rattling call に変わっていった。
倍音成分が少ない点が例えばオオタカの声とは異なって聞こえる。カワリクマタカに似た声があったがハチクマの方が音が高い。ヨーロッパハチクマでは類似の声を未確認。
思いつく種類を調べただけなのでタカ類の一般的な声か、他にも似た声の種類があるかどうかはさらに調査が必要。
Honey Buzzard, the bird bring back a string of leaves to incrase humidity for incubating eggs でも同様の発声が見られる。
Honey Buzzard, the mother bird caught a little bird and didn't give it to the male bird to eat
これも抱卵交代の際に rattling call が聞こえる (巣にいたオスの体が少し振動しているように見えて、オスが出している声か)。
メスが鳥を捕まえてきたがオスには与えなかったとある。オスはメスに食物を運ぶことはあるかも知れないが逆はないのでは、と想像するがいかがだろうか。
捕まえた鳥は何だろうか? 頭部が食いちぎられているように見える。
Honey Buzzard, mother bird bring back fresh leaves to incubate eggs これもオスが抱卵中、戻ってきたメスに気づいて声を出しているよう。飛び立つ前にちょっと不器用に卵を踏んでしまっている。環境汚染物質などの影響で殻が薄いとこういう場面で割れたりするのだろう。
行動を少し擬人的に解釈してみると、飛び出すことに気が先走りして足元に注意を払っていない? 触れた触覚で「あ踏んじゃった」と気づいて下を見る、というところか?
Honey Buzzard, the male bird really looks like the turtledove
典型的な rattling call とまでは呼べないかも知れないがメス抱卵中で帰ってきたオスに反復音を出している。rattling call の要素は含まれている。
オスはまるでキジバトと書かれているが、もしかしてハトへの擬態?は何か意味があるだろうか。簡単に調べた範囲ではハトへの擬態説は見つけられなかった。
ハチには関係なくても、地上で採食する時ならばハトと間違えられて脊椎動物の小動物に警戒されないなど (この場合は aggressive mimicry となる?)。この解釈がもし成り立つならばまさしく爪を隠したタカとも言えそうだが?
そう思ってキジバトの分布を見るとハトに似たオスのハチクマのいる繁殖分布と合っているようにも思える。
東南アジア大陸部はベニバトがいるが模倣種としては少し小さすぎるかも。東南アジア島しょ部は Streptopelia 属はかなり少ない。
アオバトのような樹上性のハトは他にも生息するが地上行動はあまりよい模倣相手にならない気がする。
ヨーロッパハチクマのケースを考えておくと、ヨーロッパでは Columba 属が中心で模倣するならモリバトかヒメモリバトか? Streptopelia 属とは生態が少し違うかも知れない。あまり模倣するとオオタカに獲物と間違えられてしまうかも知れない (笑)。
ハトの姿で巣は狙われないのか、と言われそうだが翼を広げればハトでないことが一目瞭然なので、ハトだと思って油断して近づいた捕食者もびっくりして逃げるだろうか ("変身" 仮説?)。逆に襲われかねない。我ながらよくできた解釈である (笑)。もちろんオスだけが擬態する理由が必要で、RSD と同じような解釈または性選択を考える必要があるだろう。
ハトへの擬態説が本当ならば、ハトへの擬態、クマタカへの擬態と状況に応じて併用していることになる (ほんとうか?)。
Honey Buzzard, the male gently flipped the egg, afraid of breaking the egg これも同様中国の映像の続きだが声は出していない。オスが転卵した後何かやっているとメスが帰ってきて交代。
Honey Buzzard, father bird brought back bee pupae to feed the little eagle 同上。ひなが孵化してオスが小さなハチの巣を持ち帰る。メスは声を出していたが rattling call というほどではない (むしろ begging call に近い)。餌渡しは口で行った。
ひなが孵化しているがオス・メスが交代した。メスも足元を見ていないようでもう一つの卵を踏んでしまった。映像が部分的だがどちらがひなに与えたのか。
Honey Buzzard, Daddy Eagle brought back the pupae to feed the baby eagle 同上。ひなが孵化してオスが小さなハチの巣を持ち帰る。メスは声を出していた。この映像ではメスがひなに与えている。
Honey Buzzard, a baby eagle has hatched from her nest 抱卵・抱雛中のオスにメスが葉のついた枝を持ち帰る。声は特に出さず交代。
Honey Buzzard, mother feeds the little eagle, full of maternal love これは早送りで音声 (セグロカッコウ) は関係ないがメスがひなに食物を与えているとことろ。オスも途中少し与えたように見える (次のビデオ参照)。
Honey Buzzard, the baby hatched, the father brought back the pupae to feed the baby
に上記の部分映像や早送り部分を含む少し長い映像が出ていた。交代時のメスの声、ひなの声も入っている。オスが与えているのは唾液か。その後小さなひなと卵をオスが暖めている。メスが交代して青葉を敷く様子など。
前半に入っている声はコガラの大陸と共通のものか (#コガラの備考参照)。
後半はフレーズはオオルリに似た印象を受けるが断片的で判定できず。もしオオルリでも日本と亜種が異なると考えられるのでわかる方聞いてみていただきたい。
Honey Buzzard's mother guards the baby in her nest, father sends back the pupae オスが小さなハチの巣を運んで受け渡す。メスの rattling call も入っている。オスはしばらく巣にいてひなを見ていた。
Honey Buzzard, The second one has also hatched, and Eagle Dad brought back food
2卵めも孵化。オスが鳥のひなを運んできた (種類は?) 両親ともにちぎってそれぞれ別のひなに与えている。親の声はなし。ひなの声が入っている。ひなの声にも rattling call に似た成分がある (台湾の中継でもみられた)。
獲物を扱う時に第 II 趾をよく使うのが捕食性のタカらしい特徴とのこと ([カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] の Fowler et al. (2009) Predatory Functional Morphology in Raptors: Interdigital Variation in Talon Size Is Related to Prey Restraint and Immobilisation Technique 参照)。
この映像ではオス・メスとも第 II 趾を用いている。鳥の利き足の話題もありタカ類は右足優位とのことがオスは右足、メスは左足で掴んでちぎって与えている。しばらくオス・メスで足で引き合う形になった。よく見るとなかなか面白い映像。
Honey Buzzard, Eagle mother takes out stored food to feed two little babies
こちらはメスが鳥の残りの肉を与えているところ。今度は右足で掴んでいる。ひなの声は結構大きい。
Honey Buzzard, Eagle mother stays at home, Eagle father returns from foraging
オスが小さなハチの巣を運んで受け渡す。帰ってくるオスに気づいて鳴く (これはタカらしい感じの声) メス。またおそらくひなのフンを食べるメスが写っている。
Honey Buzzard, It's really a type of eagle that eats bees 2羽のひなにハチの幼虫を与えるメス。ひなの日齢差があまり感じられず仲良く食べている。
Honey Buzzard eats honey and indulges it, but the little eagle is hungry 巣のひなは空腹だが自分ばかり食べているメス。
Honey Buzzard, the female eagle came back, but she didn't bring any prey オスがひなを抱いている途中でメスが帰って来た時に rattling call が聞かれる。立ち上がったオスがひなの糞を食べるところが記録されている。
Honey Buzzard, Eating bee pupae, the mother eagle is very gentle メスがひなにハチの幼虫を与えているところ。オスもしばらく巣にいた。
以下少しまとまって一連のアップロードがあった。
Honey Buzzard, two little eagles are so hungry that they want to fight オスがひなを抱いている途中でメスが帰って来た。食べ物はない。空腹でひなが争いかけるとの記述だが大したことはない。
Honey Buzzard, Eagle Dad brought a large piece of bee pupae to feed two little babies
オスが大きなハチの巣を持ち帰りメスが与えているところ。オスはそのままとどまり見ている。
Honey Buzzard, two eagles fight, the big one overturns the small one 軽い兄弟争いが見られるが深刻なものではなく、メスも巣にいてひなにも少し触れている。兄弟争いに全く介入しない種類とは少し行動が違っているかも。
Honey Buzzard, Eagle Dad's movements are very light, afraid of stepping on the child おそらくひなを抱いていたメスとオスの交代。オスは傷つけないように用心しつつひなを抱いた。
Honey Buzzard, Eagle Mom feeds her child, Eagle Dad wants to accompany her
両親が巣にいてメスがひなにハチの幼虫を与えているが、自分も小さいハチの巣は丸ごと食べてしまった。オスもしばらく一緒にいたが飛び立つ。
Honey Buzzard, Eagle Dad couldn't find food and brought back a bunch of leaves メスがひなを抱いているところにオスが青葉の付いた枝を運ぶ。メスが受け取ってひなに被せる。小さな声が聞こえるがどの個体が出しているか判然としない (ひな?)。
Honey Buzzard, as the name suggests, grew up eating bee pupae ひなに給餌しているメスだが自分も食べている。
Honey Buzzard eats honey, Eagle Mama grabs a large piece of honey and eats it メスが自分ばかり食べているところ。ひな2羽が向き合った場面もあったか目立った争いはなかった。
Honey Buzzard, Eagle Dad returned with the beehive and fed the pupae to the little eagle メスが大きなハチの巣をくわえているところに背面からオスが小さなハチの巣を持って帰ってきた。直前まで気づいてなかったようで多少驚いた感じ。
両親ともひなに給餌。オスは左足から右足に持ち替え。メスはずっと右足で持っていた。少し右利き傾向?
以下少しまとまって一連のアップロードがあった。
Honey Buzzard, the children are all full. Eagle Dad keeps the little eagle warm オスが肉を与えようとするがひなは満腹状態で自分で食べた。様子を見ていたメスが飛び出し、オスはその後座ってひなを暖める。
オスは獲物を左足から離したように見えたが右足に血が付いていて右足で掴んでいたのか。
Honey Buzzard, Eagle Dad caught a little bird and brought back a bunch of leaves オスが最初に青葉を運び、その次に何かの鳥のひな? を持ち帰ってきたところ。この時は左足で掴んでいた。その後はメスがひなに与える役割でオスは飛び去った。
Honey Buzzard, Daddy Eagle brought back a beehive, hungry little eagles waiting to be fed オスがハチの巣を持ち帰る。オスは左足で持ち帰り、メスは嘴で受け取った (この時に聞こえる声は別の鳥のものか?) が左足に持ち替え。メスがひなに与えるがひなはあまり空腹でないよう。オスはひなの糞? を探すような動作を示している。
Honey Buzzard loves to eat bee pupae, Eagle Dad brings the beehive back to the nest オスが小さなハチの巣を持ち帰る。オスは左足で持ち帰り、メスは嘴で受け取った。メスがひなに与えるが左足で掴んでいる。オスも何か (残り物?) を少し与えた。オスが葉の間をぬって飛んでくる様子もある程度わかる。
Honey Buzzard,Eagle Dad caught a beehive, the children love to eat bee pupae オスが小さなハチの巣を持ち帰る。オスは左足で持ち帰り、メスは嘴で受け取った (0:04 に弱い声あり、あるいはハチクマの声?)。メスは右足に持ち替え。オスもとどまって唾液を与えている?
これらの映像を見ていると (擬人化は好ましくないのだろうが) "愛情たっぷり" と表現しても過言でないように思える。
以下少しまとまって一連のアップロードがあった。
Honey Buzzard eats honey, mother eagle is full that it's the little eagle's turn to eat まずメスが自分で食べその後ひなに与えた。しかし自分の食欲が勝っているよう。今回は右足を使っている。バックでカッコウが鳴いている。
Honey Buzzard, Eagle Dad brought back a honeycomb and fed two little eagles メスが巣にいてオスが小さなハチの巣を持ち帰る。オスは左足を使い、メスは嘴で受け取った。この時に弱い声がありハチクマのものか。
巣には何かの肉の食べ残しがある。
間が飛んで次のシーンはメスの飛び立ち。どの個体が出しているかわからないが (ひな?) メスの飛び立ち前に rattling call に似た声が聞こえる。
その後オスが左足で保持して肉を裂いて与えている。唾液も少し与えているように見える。
Honey Buzzard, Is the strange behavior of Eagle Dad giving water to the little eagle? 奇妙な行動でオスが水を与えているのか? とある。与えているものまで見えないが唾液? バックでトラツグミのような声がする。次のビデオの状況を見ると雨っぽい日だったのだろうか。
Honey Buzzard, Mother Eagle was drenched in heavy rain, but Father Eagle brought back the pupae
雨の中でメスがひなを抱いていたところにオスが小さなハチの巣を持ち帰る。オスは左足で持っていたが嘴に持ち替え右足を添えた。多少 rattling call に似た声が聞こえる (ひな?)。左足はメスを踏んでいた (笑)。メスは嘴で受け取ってひなに与えているようだが裏側で見えない。オスも何か拾って与えた。
間を置いて次のシーンで濡れねずみとなったメスの飛び出し。冠羽が少し立つとまるでクマタカのように見えてかっこいい。この時もひならしい rattling call に似た声が聞こえる。
Honey Buzzard, Eagle mother only brings a string of leaves home every time オスが巣にいてメスが葉の付いた小枝を運ぶ。この時ははっきり rattling call が聞こえた (オス?)。ひなはオスの下でもぞもぞ。しばらくしてからオスの飛び出し。これにもコガラらしい声 + トラツグミ?
Honey Buzzard's family, Eagle Mom feeds her child, Eagle Dad goes out to search for food メス不在の巣にオスが葉の付いた小枝を運ぶ。
その後のシーンでメスが戻り、やはり rattling call が聞こえる (オスが出している?)。
その後オスの飛び立ちシーンに続いてメスが肉を引き裂いて与えている。獲物は左足で掴んでいるよう。
以下少しまとまって一連のアップロードがあった。
Honey Buzzard, eagle mother is going to give up youngest child and not feed it ハチの巣を左足で保持している。まず自分が食べてからひなに与えるメス。小さい方のひなに与えていないことが話題になっている。
最後はくわえて捨てに行くがまだ食べるところありそうに見えた。ひなをずっと抱いている必要はなくなったのか。
Honey Buzzard eats bee pupae, the mother eagle only feeds the big eagle これも小さい方のひなに与えていないと話題になっている。メスが今度は右足で保持。やはり自分が先に食べてから与えている。途中でひなのものらしい rattling call 類似の声が聞こえた。
Honey Buzzard, mother eagle only feeds the big baby, and the little baby is so hungry おそらく上記の続き。
小さい方のひなが大きな声でねだった時に少し気にする様子はあったがやはりもらえていない。
Honey Buzzard swallowed a large piece of honey メスが大きなハチの巣の断片を飲み込むところ。大きかったので結構苦労している。
自分が食べる方に夢中で (?) なんと抱いていた大きい方のひなを爪で踏みつけている。ひなも声を出している。このあたりが時にどんくさいと言われる所以かも (笑)。自分が食べるのに熱中している時は注意がお留守になる感じもあるが、注意して視線を向けないと下はあまり見えていないのかも。
と思ったが自分たちも歩く時足元は見えていなかった。我々がつまづくのと大差なし。
この映像は動物園個体でよく見られる食べ方 (おそらく与えられる肉の断片が大きいため。簡単に飲み込めてしまわず自分で工夫できるようにエンリッチメントの一種とのこと)。バックで鳴いているのはコイカル? 考察は [タカ類のひなが白い理由?] に分離した。
Honey Buzzard, Eagle Dad and Mom feed their eldest child with bee pupae オスが戻ってきた。オス・メスとも同じひなに与えている。
Honey Buzzard, Daddy Eagle caught a little turtledove and fed it to his own child オスがキジバトの羽に生えたひなを運んできた。右足で掴んでいたが少し休憩して左足に持ち替え。やはり大きい方のひなに与えている。
Honey Buzzard, Eagle Dad feeds meat to the youngest child おそらく上記の続き。オスが小さい方のひなに与えて少し安心。そこそこのサイズの肉片は飲み込んでいる。"調理" には左足を使っていた。最後にメスがてぶらで帰ってきた。
Honey Buzzard, both Eagle Dad and Mom brought back fresh leaves まずオスが右足で、その後のシーンで再度オスが左足で青葉のついた枝を運ぶ。ひなは rattling call に近い方の声で鳴いている。どこに置くか思案している時にまたひなを踏みかけた。ひなはそれほど空腹でないよう。
残り物をみつけて食べようとしているところでメスが嘴で青葉のついた枝をくわえて戻ってきた。
以下少しまとまって一連のアップロードがあった。
Honey Buzzard, Eagle Dad brings back the pupae and feeds the baby eagle with Mom
メスがひなと一緒に巣にいたところ、オスがハチの巣を持ち帰る。小さめで嘴から嘴へ渡している。メスは自分で丸ごと食べてしまった。その後のシーンでオスが左足で持ってひなに与えている。メスも残り物を右足で持って別のひなに与えている。夫婦同時の給餌風景。
Honey Buzzard, Daddy Eagle brings back the pupae, and Mommy feeds the pupae to the baby eagle
巣にいたメスが声を出した。これは甘え声と言ってよいだろう (動物園個体では普通の声)。オスが左足でハチの巣を持ち帰る。メスがひなに与えオスは早めに飛び出した。
Honey Buzzard, Eagle Dad brought a small beehive back and fed the baby eagle
これもメスが (甘え) 声を出していてオスが小さなハチの巣を嘴から嘴へ渡した。受け取る前にオスもいるため狭くてメスは足の置き場に困っていた。
オスは少し何か探したかちょっと与えた (メスの背後になって見えない) 後飛び出す。
メスといる時にひなは rattling call に近い方の声で鳴いていた。ここでまたメスが甘え声のような声を出す。オスの飛ぶ姿が見えているのかも。
以下少しまとまって一連のアップロードがあった。
Honey Buzzard also eats meat, and Eagle Dad feeds the baby eagle bird meat オスが小鳥の肉をひなに与えているところ。左足で持っていたが右足に持ち替えてみたりしている。ひなは鳴いているが思ったほど空腹でないのかあまり食べない。肉をちぎる音も少し記録されている。
ハチクマのひなは静かとしばしば言われるがよく鳴いている。
Honey Buzzard, the Eagle Dad brought back a huge beehive メスが巣にいたところにオスが大きなハチの巣を持ち帰る。
おそらくメスが近づく途中から rattling call を出していた。大きな獲物に気づいて興奮したのかも。
嘴から嘴に渡す。メスは左足で持って両方のひなに与えるが。オスも残り物 (小鳥の残骸?) をくわえてちぎって与えるがあまり食べようとしない。食べてくれないためかオスは両足を使って思案するように持ち替えている。
Honey Buzzard, mother eagle feeds her child pupae and then takes away the hive おそらく上記の続き。オスは引き続きちぎっているがどうも食べてくれない。
メスが与えている合間に rattling call に近いタイプのひなの声もあった。最後のシーンで空になったハチの巣をメスがくわえて飛び去る。
これ以降隠れて2羽目のひなが見えにくくなるが声は2羽とも聞こえる。
Honey Buzzard, mother eagle, plucking feathers from a little bird メスが小鳥の残骸 (?) をちぎっているが自分が食べている。小鳥をちぎる時は両足を交互に使うよう。持ち替えた方が都合がよさそう。
ひなは rattling call に近いタイプの声も含めて結構鳴いていた。
Honey Buzzard, the eagle that truly loves honey 小さめのハチの巣をくわえたメス。自分が食べてまとめて飲み込もうとするがやや大きくて飲み込みに苦労している。途中で右足を出して手助けし、多少食べて小さくなったところで飲み込んだ。ひなも鳴いているがもらえなかった。
Honey Buzzard, mother eagle feeds her child in the nest, while father bring back a string of leaves
メスがひなに肉 (小鳥?) を与えているところ。一緒にいたオスが飛び出し葉のついた枝を左足で持ち帰る。足も使ってくわえた直したが、足を離して前に歩こうとしてひなを踏んでしまい、ひなが rattling call に近い声をだした。やはり足元が見えていないのか?
Honey Buzzard, Daddy Eagle has caught a little bird and feed eldest child first
メスが巣にいるところにオスが羽の生えた鳥のひなを右足で持ち帰る。オスが一度嘴にくわえ直し左足で押さえてちぎって与えている。オスが与えている合間になんとその鳥からメスも一部嘴で取り出して右足で押さえてちぎって一緒にひなに与えている。引きちぎるのはそれなりに硬いよう。
Honey Buzzard shreds bird to feed children, Eagle Dad likes to feed the youngest child 上記の続きか? 獲物本体はメスが右足で持ってちぎって大きい方のひなに与えている。オスは小さい方のひなに残り物を与えたがその後飛び出す。小さい方のひなもそのうはそれなり膨れている感じ。
Honey Buzzard, Eagle Mom feeds 2 little eagles with bird paws 上記の残り部分か。メスが鳥の足を与えている。右足で持っていたが左足で掴み直す。腱などもあって硬いようでひねってちぎる音が聞こえる。
Honey Buzzard, mother eagle eat honey in big gulp メスが帰ってきて小さめのハチの巣をひなが欲しがっているのに自分で食べている。飲み込みにくい時に右足で手助けしている。rattling call に近いタイプのひなの声も聞こえる。
最初に飛んでくる光景が記録されているが林の合間をぬって飛び、操縦性能は案外高いのではないだろうか。
Honey Buzzard's voice, Eagle Dad has returned with the beehive ハチの巣を運んで戻ってくるオスに対して甘え声に近い声でひなを抱えていたメスが巣で鳴く。オスはハチの巣を左足で持っていたものを嘴に持ち替え嘴で渡してすぐ飛び立つ。メスが左足で押えてひなに与える。メスはひなを踏まないように避けて歩いているように見える。
Honey Buzzard, Eagle Dad feeds the baby eagle, but it only feeds strong eldest son 大きい方のひなのみに肉を与えているオス。餌乞の声は出しているが満腹に近いのかあまり食べようとしない。
大きいひなは途中で rattling call に近いタイプの声を出して、もういらないと言っているのかも。
オスは左足で掴み直してようやくひなが食べた。最後にひなの兄弟間の対立らしい光景 (音声もあり) が見られる。
Honey Buzzard, Eagle Dad caught a bird and feed the little eagle メスがひなと一緒にいるところにオスが左足で小鳥 (巣内びなか) を持ち帰った。一度嘴にくわえて右足に持ち替え、小さい方のひなに与えた。
仕事は巣内を歩いてメスが引き継ぎオスは飛び立った。
Honey Buzzard catche bird to feed the baby, and youngest son also eats meat, doesn't to go hungry
これもメスが巣にいてオスがまだほとんど羽の生えていない右足で小鳥を運んできた。嘴でくわえて左足で押さえてちぎり小さい方のひなに主に与える。大きい方のひなにも与えるがそれほど腹が減っていないよう。
見ているだけのメスもハチクマはこんな模様だったかと思えるぐらい胸から腹の鷹斑が格好良く見える。
Honey Buzzard, the eagle father feeds two young eagles, and the eldest son eats more おそらく上記の続きで大きいひなの方がたくさんもらっている。見ていたメスが飛び立つ。オスが左足を使って握っている様子も見られる。その後オスの飛び出しあり。
Honey Buzzard truly eats bees, the mother feeds the youngest child first メスが巣に飛んでくるところも映されている。林の合間を真正面向いて飛んできた。渡りの時にみかけるゆっくりした飛翔時のハチクマの頼りない羽ばたきの印象とは大きく違う。
その後オスの飛行も捉えられており、左足で比較的小型のハチの巣を持ち帰った。すぐに嘴に持ち替え、嘴でメスが受け取った。小さいひながそれをくわえたが自分ではまだうまく食べられない。メスが最初右足を出しかけて少し移動して左足に持ち替え両方のひなに与えた。より近くの小さいひなに多く与えた。
オスは落ちているものを少し与えたがメスの与えている合間に飛び出す。
Honey Buzzard, the little eagle is starving, but the mother only feeds her eldest son メスが巣にいるところにオスが小さいハチの巣を左足で掴んで帰ってきた。枝の間の空間を飛んでくる姿も記録されている。
小さいひなは嘴で受け取ったが食べられない。
メスはそれを嘴で拾って右足に持ち替え、さらに左足に持ち替え。小さいひながねだっているのもかかわらず大きい方にひなのみに与える。オスはすぐ飛び出した。
Honey Buzzard loves honey, the mother eagle eats honey with baby eagle 巣で小さなハチの巣を食べるメス。自分がほとんど食べてしまったが少しはひなに与えた。
Honey Buzzard, Eagle Dad caught a beehive and handed it over to Eagle Mom to feed the baby eagle
メスが巣にいるところにオスが左足でハチの巣を持ち帰る。飛んで帰るところも写っている。嘴に持ち替えてメスも嘴で受け取る。メスが左足で押さえて与えるが大きい方のひなしかもらえていない。
Honey Buzzard, The eccentric eagle mother only feeds the strongest eldest child メスが巣にいるところにオスがやや小型のハチの巣をで左足掴んで持ち帰る。
メスはオスの足から嘴で直接受け取り、オスも少し未練を示していたよう。小さい方のひなが食いついているにもかかわらずメスは右足で押さえて大きい方のひなにのみ与えている。オスはすぐに飛び出した。
食物が不足気味なのかも。
Honey Buzzard, Eagle Dad brings his children a beehive every day 巣のメスとハチの巣を運ぶオス。左足で持ち帰ったか (素早い飛行であまりわからない)。
小さい方のひなは相当空腹のようで小さな翼で羽ばたきながら食らいついている。残り物から小さい方のひなも多少はもらっている。メスは途中から右足で押えた。オスは早く飛び去った。
Honey Buzzard has insufficient food, and the youngest child only has to go hungry メスが巣にいるところにオスが小さなハチの巣を左足で持ち帰る。オスが嘴にくわえ直すと大きい方のひなが食らいついて受け取る。ひなはどちらも空腹のよう。メスがそれを嘴で受け取り左足で押さえて大きい方のひなに与える。
食物不足とのことで小さい方のひなは盛んに鳴くがもらえる機会がない。
Honey Buzzard, Eagle Dad brings back a little lizard for the children メスが巣にいるところにオスがトカゲをくわえて持ち帰った。オスからメスへは嘴で渡した。オスはすぐ飛び立った。メスは左足で掴んだが扱いにくいらしく右足に持ち替え。結構硬いようで引き裂く音も聞こえる。大きい方のひなに与えた。
小さい方のひなも欲しがって鳴いていたがもらえなかった。
大物をあまり持ち込まないのでやはり食物不足なのか、オスの捕食技術があまり高くないのか。
Honey Buzzard, the Eagle Dad, specializes in feeding the youngest child 少しほっとさせてくれる映像。小さい方のひなに肉を与えるオス。左足で押さえている。一連の映像は時系列順ではないかも知れないが。風で巣のある木が大きく揺れている。
Honey Buzzard, mother eagle feeds her youngest child sweet honey メスが小さい方のひなにハチの子を与えている。つついていて小さな塊を飲み込むなど自分でも食べられるよう。大きい方のひなは抱いてもらっている。
食物事情が多少よくなったのかも。
Honey Buzzard, Eagle Dad Capture a Little Bird to Feed His Child メスが巣にいる時にオスが羽毛の生えた小鳥のひなを右足で掴んで持ち帰る。嘴に何度もくわえ直し、ちぎる時はどちらの足も使っているが左足を使う方が多い。オスがひなに与えている間にメスは飛び出す。模様が目立つが獲物は何の鳥?
Honey Buzzard, Eagle Dad feeds 2 baby eagles and takes care of the youngest child 上記の続き。オスが2羽のひなに食物を与える。左足で空中で持ってちぎった時に音もした。
Honey Buzzard, Eagle Dad brought back a beehive and fed the larvae with pupae メスが巣にいるところにハチの巣を左足で持ち帰ったオス。オスが戻ってくるのを見てメスは場所を空けた。ひなは食欲旺盛のようで食らいついているがオスが嘴で取り上げた。
小さい方のひなにも成羽が見えるようになってきた。
大きい方のひなは自分で食べようとしたがメスが嘴で受け取って与えた。ハチの巣は2片に分かれたので小さい方のひなも食べられそう。オスは早めに巣を飛び出した。
Honey Buzzard, eagle dad feeds the cubs, but the youngest child dare not eat メスが巣にいるところにオスが羽毛の生えた小鳥のひなを持ち帰る。
メスは巣のわきに移動しすぐに飛び出す。オスは左足で押さえてひきちぎって与えるが、小さい方のひなは声は出すが食べに行かない。
Honey Buzzard, the youngest child is probably a backup food and dare not eat food メスが巣にいるところにオスが左足で小さなハチの巣を持ち帰る。
メスが受け取って左足に持ち替えてひなに与え、小さい方のひなも羽ばたいて声も出してねだるが食べに行かない。投稿者コメントによれば小さい方のひなは予備の食料となるのか、とのこと。オスは合間に飛び出した。ハチの巣も小さくやはり食料不足なのか。
Honey Buzzard, father sent food back in the rainstorm 雨の中でひなを抱くメス。オスが左足で羽の生えた小鳥のひならしい獲物を持ち帰る。メスはその際に口を開けて弱い音声を出した。
オスが獲物を嘴でくわえると大きい方にひなが食いついた。落ちた獲物をメスは右足で押さえてちぎってひなに与えるがオスはすぐ飛び立った。小さい方のひなは生きてメスに抱かれていたが食べられないよう。
Honey Buzzard's mother feeds two baby eagles in the rain 雨の中獲物 (小鳥?) の肉をちぎってひなに与えているメス。少し大きな肉片になったものは右足で掴んで調理。小さい方のひなもねだって受け取りかけたがうまく受け取れず結局大きい方のひなに。
あまり見込みのないひなに対して親がどのようにふるまうか知ることができる貴重な映像かも知れない。
Honey Buzzard's nest, male eagle sends beehive back to female eagle 遡って抱卵期の映像。メスが抱卵中で転卵のような行動も見られる。
オスがハチの巣を運んできてメスが甘え声を出していた。メスは嘴で受け取ってオスはすぐ飛び出した。メスはそのハチの巣をくわえて飛び出す。別の時間帯と思われるがメスのいない巣にオスが戻ってきてしばらく巣の外の枝で周りを見渡し (メスが帰ってこないか確認している?)、巣の縁でしばらく思案? してから中に入って抱卵を始めた。後半はオスの抱卵中のカットをいくつか。
Honey Buzzard's mother caught a little bird and came back to eat これも過去映像。抱卵時期オスが巣にいるところへメスが羽の生えた鳥のひなを持ち帰る。この繁殖段階では rattling call を出していた。オスはすぐ飛び立ち、抱卵交代の時に小鳥を持ち帰るとは面白い。
メスは右足を主に使って巣で食べる。足の腱などが硬いようでちぎる音も聞こえる。基本的にはタカの食事風景。巣の近くでは我が子を殺してしまわないように攻撃行動は抑制されるとよく言われるが、食べる行動は抑制されないらしい。羽毛も食べているので不消化物が含まれて後にペリットになりそう (ハチクマはペリットを吐かないと言われるが多分そうではない)。
6:18 に少しコルリに似た声が聞こえて気になったがこれはもしかしてシマゴマ?
10:19 ごろから翼 (結構成長したひなのよう) を丸飲みしようとしたが飲みにくくて断念。
羽毛も結構食べていて何か役に立つのかも。
15:23 左足に持ち替え。19:33 片足を丸ごと飲み込む。左足でちょっと手伝いも入る。結局飲みきれずにちぎって食べる。卵の上に落としてしまったが獲物のみを食べた。
抱卵そっちのけで食べるのに熱中していたがその後卵を嘴で動かして抱卵姿勢にはいった。
21:40 に弱い声があるが他の個体がいる気配は見えないのでこのメスが出しているもの? 抱卵姿勢に入る直前に何か一言つぶやいた?
背景でオオルリの大陸亜種のような声が聞こえるが途中に警戒音らしい鳴き方が何度もあったのが気になるところ。近くに観察者がいてハチクマの巣外行動を観察しているのかも。
いずれにしても野生のハチクマ成鳥が獲物の鳥を食べる様子を記録するのは相当難しいと思われるのでぜひ見ておいていただきたい。他のタカが獲物を食べ始めると熱中するのと基本的に同じよう。特にマントリングのような行動を見せないのは我が巣であまり横取りされる心配がないから?
Honey Buzzard, the big brother wants to eat the little eagle 何とこの時点で兄弟殺しが始まっている。
食物が少なくひなの体格差が大きい場合にはハチクマでも兄弟殺しが起きることを確実に示す貴重な映像。これまでの一連を状況を見てきて生き残るためにやむを得ない印象を受ける。そのまま死んで無駄になるよりも適応的なのだろう。
ひなが動かなくなった時点で食物とみなす、あるいは親が殺して与えるのではない点も興味深い。
メスが巣にいるがさらに早い段階では年長のひなによるつつきが発生した場合にひなに触れる行動が見られ、時期によっては多少の介入をするのかも知れない。
この映像では介入せずおそらくひなの糞か残り物を拾うような行動を示しているが、これはもはや介入できないことに伴う葛藤から生じた文脈的な意味のあまりない一種の転位行動のようなものかも知れない。
動物園の飼育ハチクマではまるで心の動き (葛藤、決断をためらうなど) が読めるような明瞭な転位行動と思われるものを示すこともあり、同様の行動の可能性があるように見える。
子供を保護する行動はもちろん進化したに違いないが、一方で兄弟殺しに介入しない行動も生態学的意義があって進化可能である解釈は可能だろう。この場合生態学的にはそれぞれがともに適応的な行動であっても対立 (矛盾) が生じることもあり得るだろう。
特に脳のような "アルゴリズム" が進化する場合は形態などに比べて異なる適応に対して対立 (矛盾) が生じやすいかも知れない
(これはプログラミングを行う者にとっての実感。初期設計で構造がすべて決まっているわけでなくそれぞれの部分を進化させると往々にして都合の悪いことが生じがち。
生物の初期設計は先のことまで考えて行われているわけではないので、継ぎ接ぎプログラムのような進化をしている可能性が大いにあると考えられる。現実のプログラミング言語のように、初期設計の段階でたまたまよい選択になっていた系統がより生き延びたなどの可能性もあるかも知れない。
我々でも同じかも知れない。脳を継ぎ接ぎプログラムのように進化させた動物の宿命でいろいろな矛盾した適応的な行動が存在して、それは時には大規模な争いのような事象につながるのかも知れない。それを避けるためには数々の苦い経験をもとに倫理や規則が必要で...となってくるのだろうか)。
このような場合に脳が指示する行動に対立や矛盾が発生して転位行動につながる可能性が考えられる。片方の行動を抑制するためにはおそらく脳内の抑止機構が働いていて、ヒトで言えば前頭前皮質が関わっていることが知られている。
鳥でもすぐ手に入る報酬をあえて避けて後により多くの報酬が得られる場合には後者を選択するなどの行動が知られ、実験的にもそのような行動に関連していることが知られている鳥類の "前頭前野" (prefrontal area) の表現も使われている。このビデオの事例でも関わっているかも知れない。
転位行動を行うことによって脳の指示する行動の対立・矛盾に伴うストレスの悪影響を多少とも緩和できるならばそれも適応的な反応として進化するかも知れない。
兄弟殺しの行動が進化することそのものは生態学的には理解可能であっても、その時に親が何を感じているのかほとんど手がかりがない。もしこの映像の親の行動が転位行動であれば、兄弟殺しに介入しない猛禽類の親の感情を多少なりとも読み解くヒントになるかも知れない。
カッコウの声が聞こえて季節もある程度推定できる。
Honey Buzzard, the first baby eagle has hatched, and Dad brought back a beehive
こちらは遡った映像で1卵めが孵化したところ。すでに紹介した映像と重複あり。コメント欄に英語でひなをつぶさないようにどのような適応があるか説明がなされている。
Honey Buzzard, the second baby eagle has also hatched, and Eagle Dad has sent back food
これも遡った映像で2卵めが孵化したところ。すでに紹介した映像と重複あり。この時期の方が食物が豊富だったかも知れない。
Honey Buzzard, Eagle Dad sent back a lizard これは兄弟殺しの場面の後のものと思われる。メスが巣にいるところにオスがトカゲを嘴にくわえて持ち帰ったところ。大きい方のひなが嘴で受け取ったが落としてしまう。
小さい方のひなは死んでしまったように見え、大きい方のひなが与えられたトカゲより先に食べようとしている。メスは早々に飛び立った。トカゲも少し食べようとしたが小さい方のひなをつついている。
オスは左足でトカゲを押さえてちぎろうとするがその合間にも大きい方のひなが小さい方のひなを食べようとしている。大きい方のひなのそのうはある程度膨らんでいてそれほど空腹でないかも知れない。
ひながねだらないためかオスもあまり熱心に与えようとしていないように見える。メスが飛んでいるのか周囲を気にしている感じ。
こちらは過去映像でメスが2羽のひなに食べ物を与えているところ (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, the mother eagle fed the pupae to two young eagles。
Honey Buzzard, the little eagle wants everything it can eat これは兄弟殺しの場面の後の映像の続きと思われる。オスがトカゲを与えようとしたところ大きい方のひなは一度捨てて小さい方のひなをつついていた。
その後トカゲを拾い直したがやはりそのままでは食べられず、オスが再度受け取って渡す形になった。
大きい方のひなが小さい方のひなをつついている間はオスは一度はそちらに注意したがよそを見ている様子。
オスは再度受け取ったトカゲは引き裂こうとしたが、映像に現れる範囲では小さい方のひなを食物とする行動は示さなかった。
Honey Buzzard, Eagle Dad feeds lizard to the baby eagle この映像は上記の続きのよう。オスがトカゲを左足で押さえて引き裂いている。硬いようで音も聞こえる。ひなはしばらくあまり欲しがらなかったがその後食べるようになった。映像に現れる範囲では小さい方のひなを食物とする行動は示さなかった。
Honey Buzzard, Eagle Dad wants to feed the meat of his child to his eldest son オスがついに死んだ小さい方のひなを肉として大きい方のひなに与えようとしているところ。
親が我が子を食物とする初めての映像。
大きい方のひながそこまで要求しないためかも知れないが少しむしっている程度。(これはひいき目の見方だが) 持ち上げてみるなど本当に生きていないか確認したり多少抵抗感があるようにも見える。
ひなだけではちぎって食べられないよう。
Honey Buzzard, the mother eagle feed the lizard to the little eagle 少し時期の経過した後の映像と想像できる。
ひなのみ巣にいたところにメスがを青葉の付いた枝を運んできた。まずは枝の置き場所を選択している。
小さなトカゲを右足でつかんでちぎって与えているところ。後ろに小さい方のひなの死体が見える。あまり本格的には食べなかったのか。
Honey Buzzard, the mother eagle feeds the baby eagle pupae メスが巣にいてオスが左足で持ち帰った小さなハチの巣をメスが与える。オスはひなに渡して飛び立った。メスはまず右足、そして左足でハチの巣を掴んでいる。
映像の最初の方や途中で小さい方のひなの死体らしきものが少し見えるが大部分は隠れて見えないよう。
それほど食べられなかったのか例えば足をちぎって飲み込んだようには見えない。
Honey Buzzard, Daddy brings back beehive hive, Mommy feeds baby eagle これも上記と同様の場面と思われる。メスが巣にいてオスが小さなハチの巣を持ち帰る。ひなは嘴で受け取ったが自分では食べられず、メスが与え、オスはその間に飛び去る。
小さい方のひなの死体はやはりほとんど食べられていないようでひなもその上に乗っている。実際にはほとんど予備の食料とはならなかったよう。
Honey Buzzard, Eagle Dad caught a little bird and fed it to the little eagle メスが巣にいてオスが羽の生えた小鳥のひなを右足で持ち帰る。オスがひなに与えて途中でメスが飛び立つ。メスも下を向いていたがひなに隠れて何をしていたか不明。小さい方のひなの死体はひなに隠れてほとんどわからない。
Honey Buzzard, the mother eagle feeds her baby's meat to the chick ようやく決心したのか、食物が少なすぎるためか小さい方のひなの死体を肉として与えるメス。優先順位は低かったようだが食物とみなしたらしい。
オスが最初に試みた時とは違ってためらいなく与えているように見える。
Honey Buzzard, eagle mother feeds her eldest child, survival of the fittest 同上続きの映像と思われる。完全に迷いなく食料として与えている。硬いようでちぎる音も聞こえる。
確かにだいぶ小さく、経緯を知っていないと運ばれてきた獲物とあまり違わないように見える。
オスが最初に試みた時に比べて白い羽毛がかなり失われているが除去したのか。
Honey buzzard the mother eagle took action on the stored food and fed Ermao's meat to Damao
これは別の方による映像で同じ巣かもわからないが (ヨーロッパハチクマの該当映像かも知れない) 貯めておいた肉を与えているところとのこと。
Honey Buzzard, the mother eagle fed the remaining part to her child おそらく1つ前の映像の続きで死んだ小さい方のひなを残ったひなに与えているメス。途中で少し動かしたため白い羽毛がまだ残っているのがわかる。
ひなも自分で食べようとするがさすがに無理なよう。メスは結構周囲を見ていてオスの帰りを待っているのか。
Honey Buzzard, Eagle Dad caught a beehive and let the little eagle eat it 巣にはひなのみ。オスが左足で小さなハチの巣を持ち帰った。嘴でひなに渡し、ハチの巣ならば自分でも飲み込めるよう。オスはそのまま飛び立つ。
映像の前半で背景に死んだ小さい方のひなの残骸がまだ残っているのが見える。
Honey Buzzard,Dad caught a little bird and fed it to the little eagle 時期的には上記の続きのころらしい。メスが巣にいるところにオスがまだ羽の生えていない小鳥のひなを持ち帰った。小型なのでオスは嘴でくわえた。
メスはすぐ飛び立った。オスは右足で掴んで押えてちぎって与えた。これは柔らかいよう。側方に小さいひなの残骸らしきものが見える。
Honey Buzzard, Eagle Dad feeds his own child's meat to the little eagle これまでの映像との前後関係は明らかではないがオスが小さい方のひなの死体の肉をひなに与えているところ。翼の白い羽毛はまだ残っているが体の肉はかなり食べた後のよう。
Honey Buzzard, Eagle Dad brings back food and eats honey with the little eagle 少し成長したひなにオスが羽の生えていない小鳥のひなを左足で持ち帰る。オスは一度嘴に移した後に右足で掴んだがひなはなかなか食べさせてもらえず足元のハチの巣をついばんでいる。
オスの方もつられたのか小鳥を掴んだまま同じハチの巣をついばんだ。
小さい方のひなの死体は隠れているかも知れないが見当たらない。
Honey Buzzard, Eagle Dad and Little Eagle Eating Sweet Honey Together 上記続きのようで食べ物を運んできたはずのオスがひなと一緒になって食べている。自分も食べているがひなにも与えている。掴んでいる小鳥のことはしばらく忘れているよう。
Honey Buzzard, the mother bird brought back food with only one child メスがネズミ? を持ち帰って少し成長したひなに与えているところ。左足で持ち帰ったが嘴に移した。
Honey Buzzard, the father eagle sent back the pupae, and the little eagle looked very hungry メスが少し成長したひなと巣にいるところへオスがやや小さなハチの巣を左足で持ち帰った。ひなは食らいついている。メスに渡してオスはすぐ飛び立ち、メスがひなに与えた。
Honey Buzzard,likes to eat bee pupae more than meat メスが少し成長したひなと巣にいるところへオスがやや小さなハチの巣を左足で持ち帰った。上記同様オスはすぐ飛び立ち、メスがひなに与えた。肉よりハチの幼虫の方が好きとのこと。
Honey Buzzard likes to eat bee pupae これもメスが少し成長したひなと巣にいるところへオスが小さなハチの巣を左足で持ち帰った。メスが別の小さなハチの巣をひなに与えようとしたが小さいためひなが受け取った。オスは飛び立つ。メスはオスの持ち帰ったハチの巣を拾ってひなに与えた。
複数の場面が合成されているがひなも自分で食べられるよう。
Honey Buzzard, chick start eating food without the need for mother to feed 小鳥のひなを食べるひな。自分でも柔らかい部分は食べられるようになってきた。メスが一緒にいるが手助けはしていない。
Honey Buzzard, Eagle Dad is responsible for hunting and feeding the baby eagle メスが少し成長したひなと巣にいるところへオスが鳥のひなを左足で持ち帰る。嘴にくわえた。メスが飛び立った後オスがひなに与えるいくつかのカットが紹介されている。
Honey Buzzard, Eagle Dad is responsible for foraging メスが少し成長したひなと巣にいるところへオスが鳥の小さなひなを持ち帰る。嘴にくわえた後足で押さえてひなに与えた。途中まで様子を見てメスは飛び立った。
Honey Buzzard, the little eagle will crawl into its mother's arms and sleep 少し成長したひなが単独で巣にいるところにメスが右足で葉の付いた枝を持ち帰る。羽音は結構大きく聞こえる。オスの方の飛び方が敏捷な気がするが気のせいかも。ひなはねだるが食べ物ではない。
次のカットでメスの下に潜り込むひな (ひなの音声はねだる声ではなく rattling call 的)。
Honey Buzzard, mother eagle and baby eat bee pupae together, delicious food 巣でハチの巣を食べているメスとひな。メスは自分も食べているがひなにも与えている。ひなが落とした場合はそれを拾って与えた。
Honey Buzzard, the mother eagle fed all the pupae to the little eagle 今度は食料がたっぷりあるようでハチの巣が複数ある (もっと早い時期に食料があれば2羽育ったのだろうが...)。巣でひなに与えるメス。端の方にある幼虫から順次与えている。
Honey Buzzard, the pupae are difficult to obtain, the mother feeds all the food to the baby eagle 上記映像の続きか。メスも食べている。ひなは満腹に近いように見えるがよく食べている。
Honey Buzzard, the mother eagle took away the beehive 上記映像の続きか。メスが空になったハチの巣をくわえて捨てに行く。
Honey Buzzard, the little eagle picked up the beehive 親は不在中。ひなは自分でもハチの巣をついばんでいる。
Honey Buzzard, the mother eagle easily carries away a large honeycomb メスが空になったハチの巣をくわえて捨てに行く。ひなが自分でついばんでいる映像もある。
Honey Buzzard,Daddy Eagle feeds the baby eagle pupae オスがひなにハチの子を与えているところ。自分でも食べられるが甘えている。唾液も多少与える意義があるらしい場面も見られる。
Honey Buzzard, the mother eagle has returned with a large piece of pupae メスが少し大きなハチの巣を右足で持ち帰った。自分も食べるがひなにも与える。ひなも自分が持っている方のハチの巣もついばむ。
Honey Buzzard, the baby eagle is full, and the mother eagle eats the bee pupae herself 2つのシーンがあり2つめはオスが大きなハチの巣を持ち帰ったところのよう。ひなは満腹でメスが食べている。オスは飛び立つ。ひなが少し羽ばたき練習をしている。
Honey Buzzard, the little eagle has started practicing flapping its wings おそらく上記の続きでひなが少し羽ばたき練習をしている。メスが空になったハチの巣を捨てに行く。その時にひなは少し違った声 (rattling call に多少類似点がある) で鳴く。
Honey Buzzard, Eagle Dad brought back food and went out again メスとひなが一緒にいるところにオスが小さなハチの巣を持ち帰る。飛んでくる時にメスが少し避けた。メスがひなに与えてオスは再度飛び出す。
Honey Buzzard, the capable eagle dad brought back another beehive ほぼ同上。オスは左足で持ち帰った。飛んでくる時にメスが少し避けた。小さなハチの巣でメスが自分で食べたそうだったがひなに与えた。嘴から左足に持ち替えたり後に右足も使っている。
The little honey buzzard thought mom was back with food and nibbled at her toe メスが巣に戻ってきたところ。ひなは食べ物と思って反応したが枝運びだった。ひながしばしば rattling call のような音声を出している。メスは翼を半開きにしたが意義は?
The honey buzzard. Father eagle brought back a small piece of beehive メスとひなが一緒にいるところにオスが左足で小さなハチの巣を持ち帰る。嘴にくわえ直してメスに渡す。メスもしばらくくわえていたが左足で掴み直してひなに与える。合間にオスが飛び立ち、メスはしばらく動きを見ていたよう。
As for the honey buzzard, the daddy eagle brought back yummy food オスが右足でハチの巣を持ち帰る。ひなはだいぶ成長してきて自分でも食べられるが親からもらう方がよいらしい。オスは早めに飛び出した。
こちらは過去映像でメスが2羽のひなに食べ物を与えているところ (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, Eagle Dad brought back food to feed two little eagles この時は2羽とも食べることができた。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, the mother feeds two baby eagles honey, the eagle that truly loves honey。メスが自分が食べて2羽のひなに食べ物を与えているところ。
このかわいかったひなが死んでしまったことにショックを受けられたらしいコメントあり。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, Eagle Dad brings food back to feed the baby eagle, Eagle Mom takes away the beehive ひなが2羽の時点でオスがハチの巣を運んできた。
メスは自分ばかり食べて空の巣をくわえて飛び去る。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, the father caught a little bird and fed it to his own child ひなが2羽の時点でオスが小鳥を運んできてちぎって与えているところ。このころは小さい方のひなも食べ物をもらっていた。
メスは合間から自分が肉片を食べるなど結構食い意地がある (?)。その後メスは飛び立つ。巣を守っていてそろそろ空腹になってきたころか。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, Eagle Dad came back with breakfast, a small honeycomb メスがひなを抱いていたところにオスがハチの巣を持って戻る。メスの甘えこえらしい声がある。このころは小さい方のひなも食べ物をもらっていた。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, Eagle Dad retrieves a beehive and feeds two baby eagles オスがハチの巣を持ち帰ってメスが2羽のひなに与えるところ。このころは2羽のひなの体格差も小さかった。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, the mother eagle feeds two baby eagles pupae
ひなが2羽で大きなハチの巣をもらっていたころ。
メスは自分もよく食べていたが小さい方のひなにも与えていた。後半に兄弟間闘争が見られるがメスはハチの巣をくわえたまま捨てに行くところで特に介入していない。このころは背景の鳥の声も多かった。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, the mother eagle eats honey and feeds the baby eagle pupae まだひなが2羽でハチの巣をまずメスが食べてオスも鳥のひなを捕まえて戻ってきたところ。後半でメスがひなに与えている。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard, the mother eagle came back and saw the big chick bullying the little chick オスがひな2羽を抱いて巣にいるところにメスが戻る。
オスが飛び立った後、大きい方のひなが小さい方をつついているところ。このころはそれほど深刻な兄弟争いではなくメスがそのまま2羽を抱いた。
複数の場面が合成されているようで、3:27 に弱い声で鳴いたがおそらく帰ってくるオスに気づいたもの。その後オスがハチの巣を運んで戻ってきた。メスはもっぱら大きい方のひなに与えている。
4:42 ごろからオスが足踏みをするがこれは何か。隠れて見えにくいがオスが主に小さい方のひなに与えている。
ちょっと大きな破片はひながうまく飲み込めずメスが自分で食べている。途中からメスが移動し (8:20 ごろ) 小さい方のひなにも与えている。オスも引き続き与えているのでこのまま食料が豊富ならば2羽とも育ったのだろうが。その後メスがまた位置を変えてもっぱら大きい方のひなに与えている。
オスの尾が真後ろを向いていないので手前に枝があってそこにカメラが付いているのかも。オスはその後飛び出す。後半に雨が降ってきたようでメスが2羽を抱く。
ひなの小さい声 (rattling call に近い) もしばしば記録されている。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): Honey Buzzard eats honey, Mama is a bit biased and only feeds strong children メスがハチの巣をまず自分が食べ、大きくて簡単に飲み込めず、姿勢を変えようとして下を見てなくてひなを何度も踏んでいる。
食欲の方が勝っているのか踏んでいるというよりひなにつまづいている。
踏まれた時にひなが声を出している。メスは結構苦労して飲み込んだ。
その後もまず自分が少し食べてから主に大きい方のひなにのみ与えている場面。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): This is the Honey Buzzard. The father brought back a huge beehive まだ小さなひなが2羽いた時点のもの。オス・メス共同でひなに食物を与えていたころ。rattling call も聞かれる。
こちらも過去映像: The male honey - buzzard brings back a small green bird, then some leaves to fix the nest まだ小さなひなが2羽いた時点のもの。
獲物は羽毛の生えた鳥のひなか。オスが頭を食いちぎった (0:27 やはり力がある)。メスが胴体を受け取ってオス・メス共同でひなに食物を与えた。ひなはあまり空腹でなかったのかそれほど食いつきがよくない。
メスが後ろから与えようとしてもひなが後ろが見えてなく気づかないのか、あまり向かずにオスからの肉をもらっていた。メスは自分で食べていた。途中からひなが向きを変えてメスからもらうようになった。その後オスが飛び出す。
後半のシーンは葉の付いた枝を持ち帰るオス。メスはまだひなに与えている時で少し rattling call が聞こえた (5:52 ごろ)。ひならしい。オスが足で食べ物を処理しようとして爪がひなに触れたのかも知れない (6:10 ごろからの映像参照)。
ひながあまり食べないためかメスが飛び出した。オスが見送る。メスが飛び出すと他の鳥の声が聞こえ、やはり少し騒ぎになったよう。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): The male honey - buzzard catches a small bird and plucks it clean まだ小さなひなが2羽いた時点のもの。
オスが鳥のひなを持ち帰り、オス・メス共同でひなに食物を与えた。小さい方のひなももらっている。
獲物をちぎる時の頭の動かし方にも注意。筋力も結構要するはず。獲物へのとどめを指す行為は足の爪で行っているようだが、頭をちぎり取る行動はハヤブサの食べ方に似ているかも知れない。
鳥類では occipital condyle (頭骨と脊椎の接点) は1つで、哺乳類や両生類の2個とは異なるが、このような動きを見ると occipital condyle は1つである利点もわかる感じがする。
この食べ方であれば嘴縁突起 (tomial tooth) があっても役に立ちそう。[ハチクマ亜科の他種] にあるように、カッコウハヤブサ類やハイガシラトビ、シロエリトビ (何度も書くがいずれも和名のハヤブサやトビとは系統が違う) のようにハチクマに近い系統に時々見られる嘴縁突起は同じような食べ方に役に立っているのかも知れない。[カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] で祖先は小鳥食だった可能性も少し検討している。
本体はオスが押えていたが途中からメスが持つようになった。その後小さい方のひながオスの嘴を盛んにつつく。食べ物は持っておらず唾液を与えているところかも知れない。その後オスが飛び出す。
メスは後半に小さい方のひなにも食物を与えるようになった。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり): The smallest crested honey buzzard doesn't actively fight for food, which is concerning まだ小さなひなが2羽いた時点で、小さい方のひながあまり食物をねだらなくなって懸念される時点。メスが小さい方のひなにも与えようとしたが最初食べなかった。
メスは大きい方のひなに主に与えているが小さい方のひなにも時々与えた。大きい方がある程度満足したら小さい方にも与えるなどそれぞれ行動の適応的意義が感じられる映像。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり?): The male honey buzzard brought food back. This time, the mother eagle fed the youngest chick more まだ小さなひなが2羽いた時点。オスが右足でトカゲを持ち帰った。メスが受け取ってオスはすぐ飛び立った。まず頭からちぎった。
小さい方のひなにより多く与えていた映像。この時はどちらのひなにも食欲があった。
7:30 ごろからしばらく周囲を気にした。
こちらも過去映像: The male honey buzzard shows favor to the youngest eaglet, which has a full meal for the first time まだ小さなひなが2羽いた時点。オスが右足で羽の生えた鳥のひなを持ち帰った。小さい方のひなに与える。
メスはすぐに飛び出した。大きい方のひなは足1本を丸ごともらって飲み込もうと格闘していた。途中で吐き出したが再度飲み込んで成功。オスの方は小さい方のひなにつききりで肉をひきちぎる様子などそれぞれに面白い。鳥のひなは全般に柔らかいようだがところどころ硬いところもあって力を入れている部分もある。
小さい方のひなも満腹となってそれ以上あまり食べなくなった。満腹になるとねだる声から rattling call 的な小さな声に変わった。ひな2羽とも満腹状態の珍しい映像。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり?): Honey buzzard: The eldest gets fed even lying sideways, unlike food reserves まだ小さなひなが2羽いた時点。オスが右足で小さな鳥のひなを持ち帰った。少し調理しようとしたがメスが奪ってひなに与える。どちらのひなも与えてもらった。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり?): Honey buzzard dad brings hive, youngest chick in corner starves まだ小さなひなが2羽いた時点。オスがハチの巣を持ち帰る。小さい方のひなの食いつきがなく飢え始めた時期。
このような映像で見ると巣に運ばれた青葉は衛生的な食卓を提供しているようにも見える。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり?): Honey buzzard dad brings prey. They like meat besides beehives まだ小さなひなが2羽いた時点。オスが羽の生えた鳥のひなを持ち帰る。様子を見ていたメスが飛び立ち、オスがひなに与える。大きい方のひなのみがもらっていたが途中鳥の足をまるごと飲み込み、しばらく食欲が落ちた時点で小さい方のひなも食物をもらえるようになった。
途中でひなが飲み込めず落とした鳥の足を拾って引き裂くなど細かい行動もある。
こちらも過去映像 (すでに紹介した映像と重複あり?): Mom hawk didn't feed the smallest honey buzzard. Why? Doesn't it deserve to be full? まだ小さなひなが2羽いた時点。オスが左足でハチの巣を持ち帰る。
メスは大きい方のひなのみに与えた。オスが小さい方のひなに与えるチャンスもあったが飛び立ってしまった。兄弟間闘争の兆候が少し見られた。
こちらも過去映像: After the downpour, the tiniest honey buzzard appears feeble and is trembling faintly
大雨の後で小さい方のひなは弱く震えているのみとのこと。大きい方のひなは食べ物をねだっている。メスは残り物のハチの巣を探す。大きい方のひなが結構大きなハチの巣を飲みこもうとして無理で、足も手助けに使うようになった。大きい方のひなは自分でも十分食べられるが親からももらっている。
こちらも過去映像: The male honey buzzard returns, spots the honey, and feasts happily with its young
ひなは1羽になってかなり成長していた時点。メスは不在。オスが小さな鳥の裸のひなを持ち帰ったがすぐに与えず、ひなが気づいて食べ始めた巣にあったハチの巣を一緒についばんでいる。時々は親からもらっている。
ひなにとって大きすぎた場合はひなも足で食物を中空で握るなど親に似た行動を示すようになってきた。
オスは獲物を掴んだままで、何のために帰って来たのかしばらく忘れているよう (我々も忘れてしまうぐらい)。時々周囲に注意しているのはメスが帰るのを待っているのだろうか。
The mother honey buzzard and her chick are having a hearty feast with countless bee pupae ひなと一緒にハチの子を食べているメス。この時は食料豊富だった。
ひなが落としたものを拾って与える場面もある。ひなが食べていることを確認し、与えた食物の行方を把握していることがわかる。ひなが飛ばしてしまったものを拾いにゆく行動もあり行動が細かい。ハチクマの行動は我々とって大変理解しやすい印象が強いが他の鳥でもこのような行動をするのだろうか。
新たに次のものを取り出して与えてもよいので、落としたものを拾うのは必ずしも自明な行動ではなく思える。
最後の方はひなも自分で食べられるので2羽で別々に食べていた。
4:02 あたりで舌で食べ物を口の中で動かして確かめているような場面がある。これは結局捨てたが食べられるか味や食感を確認して食べたり与えたりしているのだろうか。
A young honey buzzard picks up a beehive and gorges until its crop swells like a ball
メスが空のハチの巣を捨てに飛び立つ。満腹のひなのそのうは膨れ上がっている。1羽になっても自分でハチの巣をついばんでいる。足も多少使っていて、足を使うためには片足で立てるバランス感覚が成長する必要があるよう。ひなの尾はまだ短い。
そしてメスが戻ってきたが特に何も持たず。2つめの空のハチの巣をくわえて捨てに行こうか多少思案したが、食べられるところが少し残っていたようでひなと一緒に少し食べる。しかしやはり捨てに行きたかったようで結局くわえて飛び出して行った。多少思案するのはハチクマらしさがよく現れている。
Honey buzzard, the father brings back a beehive and gives it to the mother to feed the eaglets
メスとひなが巣にいるところにオスが少し小さいハチの巣を運んできた。オスはすぐ飛び立つ。メスがひなに与える。ひなのそのうは膨れ上がっている。
少し大きめの破片をもらったひなは自分で足で掴んで食べようとしたが飲み込めず。メスは次のハチの子をくわえたまま少し待っていた。結局親からもらって食べ続けた。その後ひなが飲み込めず落したものを拾って今度は飲み込めた。ひなが満腹になって移動した後、メスがひなの下を掘る。糞の始末? ひなはその後横たわって rattling call のような声を出す (7:14-)。
The mother honey buzzard is feeding bee pupae to the little honey buzzards with great patience
メスとひなが巣にいるところにオスが小さなハチの巣を運んできた。帰ってくる方向をひなも見ていた。オスはすぐ飛び立つ。メスがひなに与える。かなり食べた後のハチの巣をひなに渡し、ひなも自分で食べる。
メスがそれを失敬してひなにまた与えるようになった。ひな自身ではあまりうまく食べられなかったのか。
メスは途中から自分でも食べ始める。
The honey buzzard, a bird fond of bee pupae, is a wonder of nature
メスとひなが巣にいるところにオスが小さなハチの巣を運んできた。帰ってくる方向をひなも見ていた。オスはすぐ飛び立つ。ハチの巣はひなに渡したがメスが受け取ってひなに与える。小さい破片が残っておそらく捨てようかとメスが動き出したがまだ食べられる部分があって与え始めた。
破片の一部はメスも食べて結局なくなってしまった。まだ残り物を探していたぐらい。
The father honey buzzard brings back a lizard and feeds it to the chick
ひなのみが巣にいるところにオスが小さなトカゲを右足で運んできた。オスがそのまま与えるが引き裂く時の頭の動きに注目。結構硬いようでそこそこ苦労している。ちぎる音も時々聞こえる。足を上げた時にふしょのかなりの部分が羽毛で覆われているのがわかる (この羽毛が後ろに長く伸びていて結構立派)。途中で持つ足を替えたりしている。尾の部分は握りにくいのか何度か持ち替えている。
ハチの子の方がだいぶ食べやすそう。周囲をよく見回しているのはメスが帰ってくるのを期待しているのかも。
背景に聞こえるセンダイムシクイの出だしやキマユムシクイを思わせる声はフタオビムシクイ Phylloscopus plumbeitarsus Grey-legged Leaf Warbler (?) このあたりの声はよく知らないので想像で挙げてみたがいかが?
The father honey buzzard is awesome! He brings back a large piece of honeycomb for the honey buzzard
ひなのみが巣にいるところにオスがハチの巣を左足で運んできた。ひなも喜んで食らいついている。ひなは自分でも食べながら親からももらっている。
ひなは別の残り物のハチの巣を自分でも食べていてかなり大きいのに飲み込んでしまった。足も使えるようになってきた。ひななのに足がずいぶん大きいことがわかる。その間はオスは少し待っていたが引き続き与える。ハチの巣をひなに渡すとひなは十分自分で食べることができ、オスが与えようとしたものを食べないので少し思案してオスが飛び出した。
その後メスが持ち帰ったのは木の枝だった。ひなは期待外れ。メスが枝を配置する際にひなが少し避け、メスはひなが出した糞らしいものを食べた。さすがにこれはひなに与えなかったが、その後何かを掴んで与えた (前半はひなに隠れて見えず)。硬さなどからハチの巣ではなさそうで何かの動物 (トカゲ?) の残りものか。肉片らしいものを与えている。オスより少し力があるように見える。
7:38 トビのような声が聞こえて周囲を少し注意する。
[ハチの子は栄養満点か?]
(ほとんど肉で子育てしたマレーシアのハチクマ子育ての項目に記載していたがこちらに分離した)。
Hasnan et al. (2023) Insects as Valuable Sources of Protein and Peptides: Production, Functional Properties, and Challenges
によれば、昆虫は種類によってシステインやトリプトファンなどが非常に少ないものもあるとのこと (ただし牛肉に比べて低いわけでもない)。人のタンパク源としての研究でハチクマの食べているものの成分はわからないが、システインは羽毛の重要成分なので少ないと成長が遅れるかも知れない。カルシウムも気になるところ。
Brede et al. (2018) Does the Optimal Dietary Methionine to Cysteine Ratio in Diets for Growing Chickens Respond to High Inclusion Rates of Insect Meal from Hermetia illucens?
に成長期のニワトリの食材として昆虫の栄養の研究がある。検討されているものはアメリカミズアブで、システイン含有率は低いとのこと。硫黄含有アミノ酸は家禽の栄養制約要因になっている。メチオニンは主に筋肉、システインは主に羽毛に分布する。メチオニンはメチル基の供給源になる。
Jeong et al. (2020) Nutritional Value of the Larvae of the Alien Invasive Wasp Vespa velutina nigrithorax and Amino Acid Composition of the Larval Saliva
は韓国で外来地バチのツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax が人の食用になるかを調べたもの。これはハチクマの食事に近そう。韓国ではまだ食品に加えることは認められていないが、日本などでは食べられていると紹介されている
[もちろん日本語資料はたくさんあるだろうが、この論文では Payne and Evans (2017) Nested Houses: Domestication dynamics of human-wasp relations in contemporary rural Japan
を引用している。日本ではクロスズメバチの幼虫が食されている。過去に日本語で発表した内容に対応する英語論文らしく十分詳しく、フリーで読めるのはありがたい。さすがにハチクマと奪い合いになることまでは書かれていない]。
総タンパク質量ではドライミルクを大きく上回ってタンパク量は優秀。
必須アミノ酸の多くは 70 kg の成人で1日に幼虫 100 g を食べれば WHO の要求を満たしているとのことだが、硫黄含有アミノ酸他いくつかのアミノ酸の量は多くない模様で、メチオニンは検出されていない。
ハチクマは体重 1 kg ぐらいでも 100 g ぐらいは食べているのでは、と思ったが、代謝率も違うし WHO の人の基準はタンパク質の最小必要量だけでエネルギーは別の栄養素を想定しているのでこのような違いが生じるのだろう。
ハチクマでもこれだけでは硫黄含有アミノ酸などが不足しそうで、特に成長期のひなには足りないのでは? ハチの子ばかりでなく脊椎動物も食べる必要がある理由になるだろう。いくらハチの子好きでもタカらしい本質は捨てることができないのだろう。
食物さえ十分獲られるならば脊椎動物を食べた方が成長が早いのかも知れない。ただし感染症を考えるとハチの子の方が安全性は高いかも。
これらを見ていると肉食は栄養面だけを見れば大変優れていて、捕食にコストがかかっても肉食動物が生じるのは当たり前のように感じる。
「肉食が人類初期の進化にとって重要や役割を果たした」も有力仮説の一つなので、猛禽3系統を含む Telluraves でも同じようなことが言えるのかも知れない。まあ大風呂敷ということで...。
「ハチの子は栄養満点なのでハチクマのひなの成長が早い」はアミノ酸組成まで考慮すると正しくないかも
知れない。
従来考えられていたほどハチの子ばかり食べているわけではなく、必要な栄養から推定すると実は肉を中心にもっと広く食べているのでは。繁殖フェーズによっても異なるかも知れない。
Conde-Aguilera et al. (2025) Effects of a methionine deficiency on chicken tissue protein turnover: comparative analysis of methionine source ニワトリにおけるメチオニン制限実験。成長も筋肉の成長やタンパク質代謝 (ここでは tissue protein turnover) が阻害されるとのこと。
猛禽類が死活問題である筋肉の成長をわざわざ阻害するとは思えないので、ハチクマにとってもハチの子は食欲は満たせるもののあくまで代替食なのでは。良質の栄養を別に摂取しているはず。
かさばるので巣に運ぶ量は多いように見えるが、食べている部分の栄養成分を調べれば他の獲物の方がむしろ主要な役割を果たしているかも知れない。ほとんど肉で子育てしたマレーシアのハチクマ子育ての事例ではむしろ成長が早かったことから考えても肉の方が良質資源なのだろう。
このように栄養素の面から考察すると、ハチクマも肉の方が良質資源であることは知っていて、目前に大きなハチの巣がある時や、子育て時期で多量に食物を必要とする時以外はむしろ肉を優先して食べているのではないだろうか。肉がある間は肉を優先して食べればその間にハチの巣も育ち、一見ハチの巣が大きくなるのを待っていて狙うかのように見えるだけかも知れない。
温帯であれば例えば鳥のひなの生育が一段落した時点でハチの巣資源がちょうど増えてくるようなタイミングになる。
Phalen et al. (2005) Naturally occurring secondary nutritional hyperparathyroidism in cattle egrets (Bubulcus ibis) from central Texas
も関連した興味深い研究で、アメリカのテキサスで(ニシ)アマサギが昆虫食に頼りすぎてカルシウム不足となり、二次性副甲状腺機能亢進症を起こしていたとのこと。ひなの骨量不足、変形、骨折などが見られた。
脊椎動物をほとんど食べない食事ではこのような問題が発生する。
純粋な肉だけですら問題があり #クマタカ備考の [飼育クマタカの栄養不良死事例] を参照。
昆虫ではカルシウムは必要量の 1/3 しかないとのこと。ハチクマが大部分ハチの子で子育てをするとはやはり考えにくい。
[ハチの巣の効用]
しかしハチの巣の効用はアミノ酸組成だけでは語れない部分があるらしい。Chen et al. (2023) Dietary supplementation with honeycomb extracts positively improved egg nutritional and flavor quality, serum antioxidant and immune functions of laying ducks
ハチの巣抽出物をアヒルにサプリメントとして与えると健康によいらしい。フラボノイドやポリフェノールなど抗酸化物や抗菌作用のある物質なども含まれている。この研究はおそらく養蜂業の副産物の有効利用を想定したものだろうが、ハチクマがハチの巣をそのまま放置したり時々食べたりしている理由にもなりそうで、ハチ自身が繁殖のために抗菌作用を物質を利用していて、それを横取りしていると思えばよいだろうか。
Xu et al. (2011) Protective and antioxidant properties of wasp (Vespa magnifica) honeycomb extract: a potential inhibitor against acidified ethanol-induced gastric lesions によればオオスズメバチの巣の抽出物が胃への酸化ストレスを防ぐ作用がある可能性があるとのこと。
中国のハチクマの営巣ビデオでも親がしばしば残り物のハチの巣の破片を食べたり、埋もれていたものを掘り出したりしておやつのように利用している。食べても栄養にならないのではと思ってしまうが実はなかなか健康によいものらしい。おいしいかどうかはわからないが...。
ハチの子が当初は目当てであっても、副産物としてハチの巣も食べる行動が適応度を高めるなら確かに進化してもよさそうな感じ。
ハチの巣ならず食べられる鳥の巣に含まれるペプチドやシアル酸にも効用があるとのこと。研究は多数あるが1つ紹介しておく: Nguyen et al. (2024) Uncovering the Antibacterial Potential of a Peptide-Rich Extract of Edible Bird's Nest against Staphylococcus aureus。
唾液の抗菌作用らしい。ハチでも鳥でも子を育てる環境には共通する病原体対策が進化しているらしい。
すぐには役に立たないかも知れないがスズメバチ類の毒のペプチド成分の総説: Luo et al. (2022) Bioactive Peptides and Proteins from Wasp Venoms。
抗菌作用のある物質もある。BK (ブラジキニン)-related peptide (BRP) が痛みを誘発する。vespakinin M が最初に単離された物質。参考 Zhao et al. (2022) Vespakinin-M, a natural peptide from Vespa magnifica, promotes functional recovery in stroke mice 医学への応用の興味が持たれている。
G protein-coupled BK receptors (GPCRs) kinin B1 (B1R) and kinin B2 (B2R) を通じて効果を発揮するが、GPCRs は化学知覚も含み、味覚 (酸味など) にも関係するもの。
ハチクイ類やハチクマ類で塩基配列などを比較すればハチ毒への適応が調べられるかも (精度の高い全ゲノムがあればできそうな研究題材。時間の問題で判明するかも)。
[タカ類のひなが白い理由?]
([中国のハチクマの繁殖生態] の項目に記載していたがこちらに分離した)。
タカ類のひなが白いのは生える羽毛が neoptile (幼綿羽) である構造的な理由 (#ミサゴの備考 [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] 参照) や、色素を用いるとコストがかかる生理的理由が考えられるが、ミサゴのような保護 (隠蔽) 色らしいひなもあるのでこれだけが理由ではないかも知れない。
どうもタカ類が前を見る時は下があまり見えていないようで、白い色にはあるいは誤って踏む可能性を減らす認識色の役割もあるのかも。
保護色だと誤って踏む可能性がさらに高まりそう。ハチクマでも他の鳥のひなや若鳥を捕まえてくるので爪がささればひなにとって致命的になることもあり得るだろう (巣を歩く時は爪を立てないよう注意しているようには見えるが)。猛禽類以外はその心配はあまりかも知れないのでタカ類でほぼ共通して白い生態的要因になり得るかも。
我々も道路に白線が引いてあると避けて歩くのは学習によるものかも知れないが、本能と矛盾する学習は成立しにくいと想像できるので本能的要因もある程度あるのかも知れない。白いひなは道路の停止線みたいなものかも (?)。
さらにあるいは獲物と似た色だと自分の子供と獲物の区別が難しくなるかも知れない。この場合も認識色と言えることになる。そう考えるとミサゴでは食性から我が子を獲物と誤認するリスクは低いかも知れない。
隠蔽色にして捕食リスクを下げる効果と認識色にして他のリスクを下げる効果の兼ね合いで決まっているのかも。積極的に防御を行う猛禽類では捕食リスクは相対的に低く、認識色の利点の方が勝っているのかも知れない。
[中国のハチクマの繁殖生態] で見られた兄弟殺しと、その後に親が死んだひなを食物として認識してゆく様子 (すぐには与えなかった) を見てゆくとひなの白い色彩には親が食べてしまわない一定の抑止力があるように感じる。
例えば白い子供は中枢神経の子育てに関連するホルモン分泌を促すなど (かわいいと思っているかどうかはともかく、ホルモンの働きでそれに近い脳内感情が生み出される可能性はあってもおかしくない)。
見ていただいていかがだろうか。
[ヨーロッパハチクマの繁殖地行動・ディスプレイ]
McInerny and Shaw (2018) The honey-buzzard in Scotland: a rare, secretive and elusive summer visitor and breeder の英国スコットランドの研究によれば、ヨーロッパハチクマはオオタカなどの他の森林性猛禽に比べて、テリトリーの重なりを許すらしい。
産卵が通常より4-5週間遅れたケースがあった。繁殖年齢には2-3歳で達するが1年めは帰ってこない。非繁殖個体も多く、比率が 50% を超える個体群も報告されている。非繁殖個体は飛び回ってよく目立つ。
ディスプレイの羽打ち合わせ行動 [wing clapping、定訳があるわけではないが日本語ではスカイダンスなどさまざまな用語で呼ばれる。Bildstein (2017) "Raptors" によれば猛禽類のディスプレイ飛行を指して広い意味で sky-dancing と呼ばれるそうで (p. 113)、スカイダンスは必ずしも的確な用語ではないかも知れない。
東方蜂鷹 Oriental Honey-buzzard によれば中国語で空中拍手と表現されている]
も長く連続で行うことがある。
繁殖個体はそれほど長く行わない。ヨーロッパノスリはヨーロッパハチクマを追い回すことがあり、ヨーロッパハチクマが羽打ち合わせ行動を行うことも何度か観察された。
ミサゴもちょっかいを出すことがあってヨーロッパハチクマが羽打ち合わせ行動で応答した、とありハチクマ・ヨーロッパハチクマ独特の羽打ち合わせ行動はディスプレイ以外の目的で使うことがあるらしい。
日本のハチクマも同様の行動を示すか注意が必要であろう。なおイヌワシも同所を利用していたがヨーロッパハチクマと目立った種間関係はなかったとのこと。
A taste of honey: an introduction to the Honey-buzzard にヨーロッパハチクマのオンラインセミナーがあり、英国では地域にもよるがなかなか出会えない鳥で関心を持つ人も多いらしい
(どこでも出会える可能性があるが、どこへ行けば見られると特定できるタイプの鳥ではないのでこの1種を増やしたいとか確実に写真を撮りたいなどの人には悩ましい種類だそうである。日本のハチクマでも渡りの時期以外はそうかも知れない)。
このセミナーは生態の解説が中心。27:45 に獲物として鳥を運んでいるヨーロッパハチクマの画像がある。
Hungry beautiful Honey Buzzard - Mahlzeit schoener Wespenbussard に肉をちぎって食べるヨーロッパハチクマの映像がある。
Ziesemer and Meyburg (2015) Home range, habitat use and diet of Honey-buzzards during the breeding season
GPS を用いた繁殖地でのヨーロッパハチクマの行動研究 (Meyburg については#イヌワシの備考も参照)。
1時間に1点とれるようで、よく滞在する場所にハチの巣を掘った後なども見つけられている。
地図も出ていて行動の様子もわかる (農地に囲まれた結構小さな森林にも生息している)。
99% の時間は巣から 4 km 以内を行動していた (日本のハチクマの事例では非常に遠くまで外出する印象を受けるが、種による違いなのか、日本の情報は特殊事例を強調しすぎているのか不明)。
天気のよい日は夜明け前からも動き出す。ひなが成長してくると、メスが餌探しに遠くまで出かける傾向がある。van Diermen et al. (2013) によれば 124 km の遠征をした記録がある。
オランダ van Manen et al. (2009) Ecologie van de Wespendief Pernis apivorus op de Veluwe in 2008-2010
も参考になるだろう。最後にそこそこの長さの英文要約がある。図を見るだけでもさまざまな情報がわかる。
fig. 16 巣にいる時間と飛んでいる時間の割合
fig. 18 巣に親鳥がいる確率。孵化してからは次第に下がってゆく。
fig. 20 採食域の変化。5月は狭くてオスメス同じような場所にいるが季節が進むと範囲が広がり、オスメスが違う場所を使うようになる。
fig. 21 季節が進むと遠くまで餌探しに出るようになる。この例ではメスの方が遠くまで行っている (6km)。
fig. 25 あるオスの採食域。年によって結構変わっているが home range は広がっていない。
fig. 27 4羽のオスの採食域。重なっている部分もある。単なる丸は非繁殖個体のよう。
fig. 29 オスメスが夜にいる場所。産卵のころは一緒に巣にいる。その後はメスがとどまるようになる。
p. 57 捕食されたメス。雛は 30 日齢だったがオスが最後まで育て上げた。雛の捕食で多いのはオオタカ (日本のハチクマと同じよう)。
p. 66 餌をめぐる争いの例
ハンガリーのヨーロッパハチクマ追跡プロジェクト 2018 年に始まり、リアルタイムで場所が公開されたとのこと。
Bela et al. (2021) Kifejlett darazsolyvek (Pernis apivorus) jelolesenek tapasztalatai (gyuruzes es jeladozas)
ハンガリーの研究。home range も調べられているが、越冬地では繁殖地よりかなり狭い。個体にもよるが年によって渡りルートがまったく違う (次の渡りの項目も参照)。ハンガリーで最も調べられていない種類の猛禽とある。
ヨーロッパハチクマによるヨーロッパヒメウの捕食例: Heubeck et al. (2009) Predation of a brood of European Shag Phalacrocorax aristotelis chicks by a Honey-buzzard Pernis apivorus
春の渡りの最中のできごとで、巣で 45 分にわたってひなを食べていたとのこと。
この文献ではヨーロッパハチクマはコウライキジやニワトリサイズまでの獲物 (主にひなか巣立った若鳥) を捕食することが知られている。多くの個体は通常の渡り経路の途中は食べ物をとらないが、一部は食べていると考えられている (Panuccio et al. 2006。次の項目参照)。
この事例では渡りのコースを外れてやむなくそこにあるものを捕食したと考えられるとのこと。
ノルウェーのオスロで非常に遅い時期の子育ての映像が紹介されている:
Honey Buzzard nest Oslo 2023 (Simon Rix)
9月に入ってもまだ巣で餌をもらっている。9/13 にもまだ若鳥が巣にいたとのこと。
ヨーロッパハチクマの方がハチクマより早く子育てを終えるのが普通なので、これはかなり遅い時期の記録と考えられる。2024 年の記録もあり後にビデオが紹介されている。後述のビデオ一覧参照。
日本のハチクマでも井上他 (2011) 熊本市金峰山における非常に遅いハチクマの繁殖例
の例が報告されている。この事例では孵化直後の時期に大雨があり繁殖に失敗し、再び産卵して2度目の繁殖に入った可能性を考察している。
Some Honey-buzzard behaviour (Brian Groombridge 2018)
にヨーロッパハチクマのメスが小型哺乳類らしきものを捕らえて運ぶ最中に wing clapping (スカイダンス) を行った報告が出ている。ああ、これは自分も理解できる (!) と思った。よい獲物が捕れた時は自慢や満足感の表明もあるのだろう。勝手な解釈だが人が行う喜びの行動とあまり違わないのでは?
(飼い鳥も含め) 鳥の自慢や喜びの行動を体験されている方ならば賛同していただけるかも知れない。
wing clapping は必ずしもテリトリーの主張だけではないだろう。
Honey-buzzard and Golden Eagle! (Brian Groombridge 2013)
にヨーロッパハチクマとヨーロッパノスリが一緒になってイヌワシを追いかけた記録が出ている。ヨーロッパハチクマは適切な距離を保っていたがヨーロッパノスリは果敢にも突進したとのこと。
久野 (2006) Birder 20(10): 25 にハチクマがイヌワシを見ると慌てて逃げる話が紹介されているが必ずしもそうではないらしい。
Groombridge のこのサイトは "ヨーロッパハチクマ観察日記" になっており、興味ある方にはおすすめ。よほど気に入っているらしい (その気持ちもよくわかる)。
このサイトの情報によれば Bijlsma がヨーロッパハチクマのモノグラフを出版する予定 (2012) だったが他の仕事が多くて実現していないとのこと。
The Honey Buzzard によれば出版キャンセルとのこと。
Rob Bijlsma: Mijn Roofvogels. Zeer leesbaar boek waar je ook nog wat van leert
によれば代わりに (?) "私の猛禽類" という本を2012年に出版している。英文モノグラフまでは大変だが自国語で自伝的な本を出版した模様。
世界のハチクマ類まで含めたモノグラフが出るのはいつのことになるだろうか。
Groombridge もヨーロッパの海外情報を収集しているがさすがにロシアや周辺言語での情報はない。
なおヨーロッパハチクマの世界的大家と言えば Bijlsma か先述の Gamauf が挙がるらしい。
Bijlsma (1999) Do Honey Buzzards Pernis apivorus produce pellets?
にヨーロッパハチクマがペリットを吐くかについての研究がある。巣で観察したが確実な記録はなかった。飼育下個体ではネズミのみを与えると小さなペリット (毛のみで骨はない) を吐き、ペリットを作る能力があることは確認されたが野外ではネズミを食べることはそもそもまれで、脊椎動物を食べる時は大きな骨や羽、毛などは慎重に避けているのでほとんどないのではとのこと。
ハチクマがあまり羽の生えた鳥を食べたがらないのはこのような調理が面倒であることも関係ありそうで、マレーシアの繁殖ビデオでもそのような解説が出ていた。柔らかくてすぐ食べられるハチの子を食べ慣れてしまうと柔らかいものを先に食べる (動物園個体でも同様で硬い肉は後に残しておく) のは我々のファーストフード感覚にも似たところがある (?) ように感じる。
[(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の [ハチクマのお客さんになって] でも不消化物をペリットとして吐く記載があり、ロシアの飼育者には比較的知られた行動らしい。
ディスプレイの wing clapping (スカイダンス) についてはハチクマ類縁種で共通らしいと言われるが Raptor Research & Conservation Network (2018) "A Field Guide to the Raptors of Asia" によればヨコジマハチクマ (スラウェシ島留鳥) ではまだ知られていないとのこと。
高く舞い上がって爪を掴みあう行動は知られているとのこと。
ヨコジマハチクマと極めて近いフィリピンハチクマでは最近はスカイダンスが知られているとのことで、以下のような写真もある Philippine Honey-buzzard (Louis Bevier 2017) display flight, raising wings vertically over back and cocking tail upwards, legs slightly dropped while held together と記述されている。
Philippine Honey-buzzard (同上その2)。
記載論文 Gewers et al. (2006) First observation of an advertisement display flight of 'Steere’s Honey-buzzard' Pernis (celebensis) steerei on Panay, Philippines。
翼を震わせるような行動は十分強力で空中に止まったように見えるとのこと。なかなか用語が難しいようで論文表題では advertisement display flight、行動の記述には wing-quivering と称している。
30 m ぐらい上昇飛行をして翼をほぼ閉じて急降下。頂点付近でこの行動が見られた。同所的に生息するピンスカークマタカ (全長はフィリピンハチクマと大差ない) との識別点にもなる。なおフィリピンハチクマは日本のハチクマとほぼ同じ大きさか少し小さい程度。
Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" の時点ではこの行動は未記載。久野 (2006) Birder 20(10): 36 にもまだ知られていない言及があるが当時のこの出典が由来か。
"wing clapping" の用語は英語でも必ずしもよい用語とは考えられていないよう: Honey Buzzard wing-clapping: a misnomer? (BirdForum 2010.7) ヨーロッパハチクマについての質問で、英語語義のように本当に音がするのか。モリバトが翼を打って音を出すのを指す方に使う方が合っているのでは。butterfly display または sky dance とも呼ばれる (いずれも日本語でも使われる表現)。
Martn-Avil et al. (2023)
The trophic strategy of the European honey buzzard Pernis apivorus during breeding: extravagant specialization or genius solution? (preprint)
にスペインのヨーロッパハチクマの 24 巣をビデオ記録したとのこと (2018-2021)。
渡り経路の調査もそうだが、やはりヨーロッパハチクマの研究は規模が違う。
在来のハチの次に多く外来種のオオスズメバチも運んでいたとのこと。ハチ類以外では他所で報告されるようなカエルではなくトカゲが主だったとのこと。
調理不要で素早く与えられるのでひなを育てるには効率がよい。ひなも早くから自分で食べられるものなのでメスが巣を早めに離れることができる (書いてないがしかも多分おいしい)。
ハチの攻撃さえ避けられれば消費者に対する資源量も多く (これはハチクマ類があまり争いをしない要因になるだろう。資源量も豊富だと都会のカラスのように暇で遊べる時間も生まれるかも?)、「ぜいたくなスペシャリスト」または「天才的解決」とも表現している。渡りをする必要がある点はマイナスかも知れないがそれを十分に補える利点があるということだろう。
脊椎動物の獲物は巣内ひなの時期に多いが、これはカルシウムなどの補充のためかなどの前述のような議論も出ている。
スウェーデンの Amcoff et al. (1994) Nest site choice of Honey Buzzard Pernis apivorus (後半に詳しい英文要約がある) によれば、ハチの巣は偏在しておらずヨーロッパハチクマは長距離を飛ぶのでハチの巣の分布はあまり要因になっていないと考えている。
ハチの巣が多くない5-6月の食物の方がむしろ営巣場所を決めているのではと考察している研究。
ここでは両生類はあまり食べていないようで、繁殖期の早いうちはスズメ目のひなや幼鳥をよく与えているとのこと。ハチクマ/ヨーロッパハチクマでも地域によって食性がだいぶ誓っている可能性がありそう。
Bos (2017)
Aanvallende Wespendief Pernis apivorus bij nest (英文要約あり)。オランダの子育て中のヨーロッパハチクマの巣を訪れた人が 20 分に5回の (擬) 攻撃を受けたとのこと。警戒音も出したとのこと [英文サマリーに feign-attacked とあるので (擬) を入れておいた。原文では schijn aanval とある]。
メスが攻撃してオスは少し離れたところでみかけた。
その間掴んでいたハチの巣を離さなかった。写真を見るとしっかり正面視をして向かってきており想像以上に迫力がある。他にネズミを持ったまま飛んできた事例も紹介されている。
このような (擬) 攻撃は森林性猛禽類では比較的まれで、起きるとすればオオタカやハイタカ (これらは実際の攻撃もある) でヨーロッパハチクマでは珍しい。
古い文献には 9月9日とされる事例があって執拗に攻撃を受けて棒でやり返したとのことだが時期が合わないので日付が間違っているのでは?
別の例で巣から 8 m のところにブラインドを設置していたが、巣のある木に登る時に 7月18日に巣の下 8 m まで来るとオスに翼で頭を打たれたという。7月25日にも攻撃を受けたがそこまで近くに来ず、羽ばたきの風が感じられた程度。この程度ならばよくあるとのこと。
別のスロバキアの記述ではヨーロッパハチクマはつがい形成期と造巣時期に攻撃的だが子育て時期はそれほどでないとのこと。ただしどのような条件で攻撃されたかは書かれていないとのこと。
van Nie (2002) Schrikrui bij Wespendieven Pernis apivorus オランダで夏に悪い栄養状態で保護されたヨーロッパハチクマが短い期間の間に尾羽を脱落させたとのこと。地上で採食時間が長いので捕食者対策で急性ストレスによって尾羽を抜けやすくする戦略 (尻尾切り) があるのではとの議論
(飼育下ストレスで羽が抜ける他の猛禽の例もあるのでほんとうか?)。
Bijlsma (1998) Invloed van extreme voedselschaarste op broedstrategie en broedsucces van Wespendieven Pernis apivorus
オランダの記録。1997 年の5-6月の雨量が記録的で地バチの数が非常に少なかった。ヨーロッパハチクマの繁殖成績も悪く、遠くまで獲物を探しに行く必要があった。1970-1980 年代はモリバトが多く、同様の気象条件の年にはヨーロッパハチクマはモリバトのひなに獲物を切り替えたとのこと。
作物が穀物からトウモロコシに変わったためモリバトの数が大きく減少して、地バチ資源が少ない時にヨーロッパハチクマのよい代替食物がなくなってしまったとのこと。そのような年は成鳥の換羽も遅れ、繁殖滞在中に換羽しなかったとのこと。
Bijlsma et al. (2012)
Demography of European Honey Buzzards Pernis apivorus
が 1974-2005 年のデータからオランダのヨーロッパハチクマの個体群動態を調べている。現在測定されている値では将来的な個体数が維持できない結果となった。観察されたり標識される数とは必ずしも整合していない。しかしオランダ北部の個体数は減っており、繁殖成功や生存率を低めるさまざまな要因があるので懸念されるとのこと。1970 年代にはほとんどなかったオオタカによる捕食 (別記) も要因の一つに挙げられる。
越冬地は繁殖地に比べて移動範囲が狭く、食物は豊富と考えられるが生息環境は人為的要因で悪化していると考えられる。
IUCN は個体数が安定しているとしているが、半数の個体はロシアで繁殖するので状況はよくわからない。ヨーロッパでは減少が報告されているところも多い。フィンランドでは 1982-2008 年の期間にテリトリー数が年率 2.8%、巣は年率 4.2% で減少したと報告されている。
ドイツ西部の Nordrhein-Westfalen では 1972-1998 年の期間にほぼ半減したがその後一部回復したとのこと。セルビアでは 1980 年代からむしろ明らかに増加。
渡りの観察数はそれほど年変動がない。
Bijlsma (1997) Zon-gedrag van een Wespendief Pernis apivorus
はヨーロッパハチクマの日光浴の状況を記述。翼を半開きにして背から日光を受け、首を伸ばして目は半分閉じていかにも楽しんでいる様子とのこと。平均で5分程度。オランダでは日光浴をするヨーロッパハチクマは普通に見られるが、オオタカ、ハイタカ、ヨーロッパノスリでは観察されていないとのこと。
日本でも広義ハイタカ属では聞いたことがない気がするがどうだろうか。
Bijlsma (2016) Foerageersucces van een multitaskende Wespendief Pernis apivorus
は働きバチの動きを見張ったり、観察者の動きに反応したり、郵便配達の音を聞いて反応し、羽繕いをするといった複数の作業を同時に行えるヨーロッパハチクマの能力の高さを報告している。
UK のヨーロッパハチクマの繁殖調査のための情報がある:
Honey-buzzard (Raptors: a field guide for suvreys and monitoring 2014)。
ヨーロッパノスリの巣の近くに営巣することもあるがオオタカからは距離を置くとのこと。ヨーロッパハチクマが後にやってくるので古巣をヨーロッパノスリやオオタカが使ってしまうこともあるかもとのこと。
巣造りは非常に速く、3日でできた巣がある。非繁殖個体による "summer nests" (ドイツ語で Spielnest 遊びの巣 とも呼ばれた) と呼ばれる7-8月に造られ、翌年使用される可能性のある巣もあるとのこと。
summer nests についてオランダで Vis et al. (2019)
Summer nests of Honey Buzzards Pernis apivorus and their subsequent use, with notes on breeding and natal dispersal
の情報がある。翌年使われる事例が多く、ヨーロッパハチクマの生活史にとって重要な役割があると考えられる。オスが食物を運ぶ行動などもあって summer nests を造る行為が資質を表している可能性があり検討に値する。非繁殖のオスや繁殖中に巣やつがい相手を失った個体が獲物を持って樹冠の上をしばしば高く飛ぶことがある [誇示行為? 別記 van Manen (2020) も参照。ハチクマの行動を解釈する上でも役立ちそう]。
Santing (1994) Vervolglegsel bij Wespendief Pernis apivorus? 証拠不完全だが一度失敗して再産卵を行った可能性のある事例。
Potters (2009) Molt Wespendief Pernis apivorus een Mol Talpa europaea?
ネズミの残骸が巣にあった。また穀類も見られたがハトの体内にあったものか。
van Barneveld sr. and van Barneveld jr. (2006) Oog in oog met de Wespendief Pernis apivorus: waarnemingen bij een nest op de Utrechtse Heuvelrug
ペアの入れ替わりはそこそこある模様。ひなはカエルはあまり好きでなく自分では食べない。脊椎動物を引き裂くのは親の仕事。抱卵はほとんどメスが行い、オスは昼間 1-4 時間程度の抱卵を行う。抱卵交代はメスが誘導し、オスが近づくと ticking-call (rattling call) を出す ([音声] の項目参照)。
ひなの頭が腫れたことがあっておそらくハチに刺されたのだろうとのこと。兄弟争いの兆候はなかった。
巣立ってからも遅くまで巣に戻って食物を待っていたとのこと。
青葉は地上から巣が見える方向に集中して置いたとのこと。
UK の Northumberland (ノーサンバーランド) で見られる個体がヨーロッパハチクマかヨーロッパノスリかの議論が毎年のようになされていたとのこと。"Northumberland Honey Buzzard" on video
ヨーロッパハチクマの若鳥かヨーロッパノスリか議論が続いていたようで、そのぐらい識別が難しいとのこと。ビデオを見てもヨーロッパノスリが優勢だが確実な判定に至っていない模様。どうなったかはスレッドの後続メッセージにあり。
この話に気づいたのは Honey Buzzard ... or Honey-buzzard? のスレッドから。
このスレッドは英名にハイフンを入れるか入れないかで、IOC は "buzzard" を広い意味で捉えている。BTO の名称では真の buzzard ではないのでハイフンを入れるべきとの見解の両方があるが、とはいえ半分はノスリみたいなものでは? Northumbrian の "ヨーロッパハチクマ" に至っては特異な食性で知られていてウサギやハト、カラスも食べるとの話題から。冬眠動物を巣穴から追い出して食べることもするらしい (笑)。
そういえば... Honey Buzzard Calls にヨーロッパハチクマのさまざまな声のバリエーションが載っているページがあるが、信頼性が低そうなので参照するのをパスしたのだった。問題の "Northumberland Honey Buzzard" らしいことを知って納得した次第。
本物の声も含まれているだろうが、このページの情報は注意して扱った方がよさそう。
このようなことが起きるのは UK ではヨーロッパハチクマはなかなか出会えない種類で、特に繁殖時に見ることは難しい。ヨーロッパハチクマであって欲しい願望から...?
9月に子育て中のヨーロッパハチクマ
オスロ (ノルウェー) でヨーロッパハチクマの繁殖生態がまとまってアップロードされた (Simon Rix 2025.1。2024 年の撮影):
Honey Buzzard nest Oslo 17.7.24,
Honey Buzzard nest Oslo highlights,
Honey Buzzard nest Oslo 29.7.24,
Honey Buzzard nest Oslo 27.7.24,
Honey Buzzard nest Oslo 1.8.24,
Honey Buzzard nest Oslo 5.8.24,
Honey Buzzard nest Oslo 13.8.24 この段階でまだ白いひな。
Honey Buzzard nest Oslo 11.8.24,
Honey Buzzard nest Oslo 16.8.24 食物を持ち帰る。
Honey Buzzard nest Oslo 19.8.24,
Honey Buzzard nest Oslo 27.8.24 だいぶ大きくなってきたひな。
Honey Buzzard nest Oslo 31.8.24 2羽のひな,
Honey Buzzard nest Oslo 5.9.24,
Honey Buzzard nest Oslo 8.9.24 かなり成長した2羽のひな。
Honey Buzzard nest Oslo 10.9.24,
Honey Buzzard nest Oslo 12.9.24 巣から出つつある。
Honey Buzzard nest Oslo 13.9.24,
Honey Buzzard nest Oslo September 2024 こちらは撮影時遠景で望遠鏡にビデオカメラで撮影されている。
日付を間違えたのか思うぐらいにとんでもなく遅い時期の繁殖映像 (秋の渡りはヨーロッパハチクマの方がハチクマより先にピークを迎える)。9月中旬なのにまだひなが巣にいる。
近年はかなり遅い時期の繁殖も見られるようになった話は聞いていたがここまで遅いとは驚き。
2023 年にも同じ記録者による映像記録があり、あるいは毎年遅く繁殖するつがいなのかも。
[ヨーロッパハチクマと他のタカの種間関係]
森林性猛禽類の種間関係に関するフィンランドの研究があった。Bjorklund (2015)
The effects of habitat changes, conservation measures and interspecific interactions on forest-dwelling hawks (学位論文)。ヨーロッパノスリやヨーロッパハチクマが他の猛禽類を捕食した例は知られておらず (ただし以下も参照)、お互い近くでも営巣できる。ヨーロッパハチクマが後にやってくるのでオオタカの少ない場所を選ぶことができる。
ヨーロッパハチクマの好む環境はオオタカの存在に影響されている可能性があり、最良の条件でない場所を選んでいる可能性があるとのこと。
スウェーデンではヨーロッパハチクマは池の近くの良質な森林を好み、小鳥が多いためとの解釈があるとのこと。フィンランドのオオタカも水辺を含むが、こちらは水鳥を捕食するためとある。
Bjorklund et al. (2015) Habitat Effects on the Breeding Performance of Three Forest-Dwelling Hawks が発表論文。
大学院生でこのような研究が成り立つ背景には衛星追跡が組織的に行われていて、統計解析が可能なぐらいの数の巣が発見されている恵まれた事情もあるのだろう。
Bjorklund et al. (2016) Intraguild predation and competition impacts on a subordinate predator
によればヨーロッパノスリはオオタカの多い (ライチョウ類が豊富) 場所は避けていると考えられ、自身にとっての食物の豊富さとオオタカによる捕食とのバランスで繁殖分布が決まっていると推論している。
ヨーロッパノスリとフクロウは競争関係にある。
ヨーロッパハチクマがオオタカの巣の近くを避けているらしい論文は Gamauf et al. (2013) Honey Buzzard Pernis apivorus nest-site selection in relation to habitat and the distribution of Goshawks Accipiter gentilis
オーストリアではヨーロッパハチクマの環境嗜好性はあまりなかったが、オオタカの巣との距離は統計的に有意な関係があった。ヨーロッパハチクマは森林性ではあるが人の居住区の近くで営巣することでオオタカによるひなの捕食を避けている可能性がある。
ラトビアではそれほど顕著でないが、ヨーロッパノスリ、ハイタカ、オオタカの巣間距離に似た関係が見られている: Rebollo et al. (2011)
Spatial relationship among northern goshawk, Eurasian sparrowhawk and
common buzzard: rivals or partners?
ヨーロッパハチクマに限らず、互いに捕食関係にない猛禽類の巣はオオタカの巣との距離に比べて近接する傾向がある模様。
Bijlsma (2004) Wat is het predatierisico voor Wespendieven Pernis apivonis in de Nederlandse bossen bij een afnemend voedselaanbod voor Haviken Accipiter gentilis
(What is the predation risk for European honey buzzards Pernis apivorus in Dutch forests inhabited by food-stressed northern goshawks Accipiter gentilis? 詳しい英文要約あり)
一時は数を減らしたオオタカが個体数を回復し 1980 年代から、特に 1990 年代からオランダ北部の砂の多い地質地域でオオタカの食物が不足している。かつては同地域に営巣していたヨーロッパハチクマのひながオオタカに捕食される事例はほとんどなかったが最近は急に増えている。
この文献ではヨーロッパハチクマのメスが途中から姿を見せなくなり、オスだけで子育てしていたがひながオオタカに食された事例が報告されている。この時点ではオオタカによる捕食がヨーロッパハチクマの個体群に深刻な影響を与える状況にはまだなっていないとのこと。
Bijlsma (2014) Van wieg tot graf: natale dispersie en het te korte leven
van een vrouwelijke Wespendief Pernis apivorus
では過去にすでに繁殖に成功した成鳥が捕食されたとのこと。
Drenthen and van Manen (1994) De Wespendief Pernis apivorus van Boswachterij Schoonloo
も同様の事例を報告している。
van Tuijl and van Vroenhove (2003) Wespendief Pernis apivorus gebruikt drie jaren achtereen hetzelfde nest
では3年連続で同じ巣が使われたが個体が違う可能性がある。2003 年にオオタカが 300 m の距離でひなを巣立たせたとのこと。
Vroege (2016) Broedgeval(len) van de Wespendief Pernis apivorus in de duinen bij Castricum in 2015
で 2005-2014 年のうち近隣のオオタカが1つがいだけだった3年に繁殖成功。オオタカが2つがい以上の場合は成功していなかった。2015 年は特別でオオタカが2つがいとヨーロッパハチクマのおそらく2つがいが繁殖に成功で、この年は地バチが豊富だったとのこと。
Waggershauser et al. (2021) Lethal interactions among forest‐grouse predators are numerous, motivated by hunger and carcasses, and their impacts determined by the demographic value of the victims
が哺乳類を含む森林捕食者の種間捕食関係のレビューを行っている。この研究では鳥類捕食者としてヨーロッパノスリ以上のサイズの猛禽類の関係を考察している。
これによればヨーロッパノスリによる他の猛禽類の捕食もないわけではない。オオタカの捕食者としてワシミミズクとイヌワシが挙げられている。
オオタカによるヨーロッパノスリの捕食例は多少報告がある。UK ではオオタカが捕食する猛禽類の主なものはチョウゲンボウ。オオタカの近くでヨーロッパノスリの繁殖成功率が下がっている報告もいくつかある。
オオタカの餌不足が原因の可能性が示唆されるがヨーロッパノスリの繁殖成功率への影響は直接捕食によるものよりも間接的要因が中心と思われる。
UK でヨーロッパハチクマの巣のビデオ記録中にひながオオタカに捕食された事例: Goshawk kills rare buzzard chick (BBC 2005)。あまり好ましい光景ではなかったためか広く報道されていない模様。
Hoy et al. (2017) Density-dependent increase in superpredation linked to food limitation in a recovering population of northern goshawks Accipiter gentilis
によれば英国のオオタカの食物不足の要因は2種類の主要食物の減少によるとのこと。モリバトなどハト類 [Bijlsma (1998) にあるように作物の変遷に伴っており、モリバトの減少はヨーロッパハチクマの代替餌不足につながっている] とキジ類。現在ではオオタカは食物量で制限されており、餌不足により他の猛禽類も捕食するようになった模様。
Rutz and Bijlsma (2006) Food-limitation in a generalist predator
はオランダのオオタカの食物不足の研究。ジェネラリストの猛禽類が食物で制約を受けるのは珍しい。1975-2000 年ごろにオオタカの主な食物 (レース鳩、モリバト、ウサギ) が同時に大きく減少した。
オオタカが他の食物を求めたことがチョウゲンボウ、コチョウゲンボウ、ハイタカの個体数減少にも関わっている可能性があり、すでに減りつつあったモリバトにもさらなる打撃を加えた。オオタカ自身も繁殖成功率低下で減少してきている。
他の研究については #オオタカ備考の [ヨーロッパの局地的なオオタカの減少・オオタカによる他猛禽類の捕食] にまとめた。
日本のハチクマの場合ではオオタカの餌不足はおそらくそれほど顕著でなく、さらにクマタカがいるので種間関係が多少異なっているかも知れない。
例えばオオタカがクマタカを忌避するならば、似た容貌のハチクマのメスは巣の防衛に際してヨーロッパハチクマより有利かも知れない。ただし大陸部はこれはあまり成り立たないので、亜種 orientalis 全体がクマタカに似ている説明にはならないかも知れない。
これらの研究はヨーロッパハチクマとハチクマの営巣場所の嗜好を比較する時に役立つ部分があるかも知れない。
Vroege (2015) Overlevingsstrategieen bij de Wespendief Pernis apivorus en de invloed daarvan op het aantal broedgevallen in de zes deelgebieden van het Noord-Kennemerlands Duin
ではオランダのヨーロッパハチクマの繁殖失敗率は近年高い (40-45%)。2例 (8%) はオオタカによる捕食でオオタカの繁殖との関係に注目した記述になっている (ヨーロッパの一部ではオオタカによる捕食がおそらく近年増えているために話題になっているのだろう)。
この論文ではヨーロッパハチクマが熱帯で繁殖しないのは他の捕食者の攻撃を避けるためと解釈しているが、アジアのハチクマでは熱帯繁殖するものがたくさんあるのでほんとうか? なおアフリカでは Hieraaetus 属に擬態しているとしている。
最近の統計ではまた成功率が上がっているようで一時的なものだった可能性もあるかも。
van Manen (2020) Mogelijke vervanging van mannetje Wespendief Pernis apivorus tijdens de jongenfase
オランダのつがいのヨーロッパハチクマが子育て中 (12 日齢のひな) にオスがおそらくオオタカに襲われて捕食され、メス単独となったが2日めにはすでに2羽のオスが見られたという。個体群中の非繁殖のヨーロッパハチクマの比率は 50% 近いとされ、他の猛禽類とは異なって非繁殖個体がよく目立つ行動を行う。しばしば繁殖つがいの周辺を訪れてディスプレイ飛行 (羽打ち合わせ) を行って能力を示すとのこと。
こんなニュースもあった: Photographer convicted for disturbing honey buzzard nest (BirdGuides 2024.7.2) ヨーロッパハチクマの繁殖妨害で罰金。詳しくはリンク先を。
関連情報として UK では希少種で BBC のドキュメンタリー Iolo's Valleys でヨーロッパハチクマの巣のモニターが紹介されたとのこと。写真家のマナーに関するコメント欄も参照。
[カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較]
現生種の中でハチクマに系統が一番近い (といっても分岐は古い) カッコウハヤブサ属の Aviceda は avis 鳥 -cida 殺すもので、さまざまなものを捕食し、食性面ではハチクマのようなスペシャリストではない (しかし越冬地ではハチクマもいろいろ食べている可能性もある)。
ハチクマと同様に果実も食べるそうで、カンムリカッコウハヤブサでは飼育下でレタスを与えないと繁殖しなかったとの報告がある (wikipedia 英語版)。
文献 Fleay (1981) Looking at animals with David Fleay: a selection of topical nature notes from the writings で一部見ることができるが、
Perhaps the most extraordinary discovery eventually to prove vital in the sought after outcome was, in fact dietary.
It occurred the day one of the handsome birds seized a fallen lettuce leaf and in eating it showed every evidence of enjoyment.
Ever since then such leaves have been part of the daily handout.
Fancy a vegetarian inclination on the part of a hawk!
It's up to bird observers to observe, now, what vegetation in bush or rain forest is favoured for far from being the aberrant taste of an individual the cellulose leaning is common to all.
との記載がある。レタスの葉を喜んで食べる行動が発見され餌に与えるようになったとのこと。ベジタリアン志向のタカとは一体何たることか!? 当時の解釈はセルロースを要求としているとのことだったのだろうか。
Bell (1984) New or Confirmatory Information on Some Species of New Guinean Birds。
Fisher and Hill (2023) Breeding biology and behaviour of the Pacific Baza Aviceda subcristata in subtropical coastal New South Wales
にカンムリカッコウハヤブサの繁殖生態の論文がある。ひなへの餌は昆虫 (特にセミ類、ナナフシ類)、カエルが多かったとのこと。植物食については見当たらない。
空中ディスプレイの深い undulating (波状) 飛行があり、この表現だけだと他の猛禽類でも行うものと共通に見えるが (若杉氏の オオタカのスカイダンスは 間 (ま) が魅力 との興味深い記事がある。ハチクマはこの 間 (ま) を上手に利用するようになったのか?) 、
そのピークでの写真 (Fig. 4) が出ている。あるいはこれが進化すればハチクマのディスプレイのようになるのだろうか。
写真を見ると翼下面の模様はハチクマとも多少共通点がある (Fig. 3 にあるように個体差も結構あるとのこと)。
ハチクマの空中ディスプレイの進化を考えてみると、カンムリカッコウハヤブサのこの飛び方が原型で、例えば並列で横向きに飛んでいる時はあまり見えない翼下面の模様を波状飛行の頂点で目立たせる意味があるかも知れない。
翼を打ち合わせる行為も、他の鳥でも尾を振るなどと同様誇示したい部分をより長時間強調する行動になっているとすればわかりやすい気もする。ハチクマの場合はオスの下面模様はよく目立つので (我々が見てもあでやかに見える) これは優良遺伝子を示すシグナル、あるいはつがい外の個体へのシグナルとなっていても不思議ではないだろう。
スカイダンスで 間 (ま) を翼の打ち上げに利用する個体が現れ、それが何らの理由 (社会、性選択) で好まれれば、#オウチュウ備考 [さえずりの進化] で紹介した Schwark et al. (2022) が仮説として取り上げているような脳内回路を通じて強化され、
脳と行動が共進化してもおかしくない感じがする [このあたりは #エトロフウミスズメ で紹介のリチャード・プラム著、黒沢令子訳「美の進化」の発想に近い]。
ハチクマの wing clapping と思われる興味深い写真があったので紹介しておく。Oriental Honey-buzzard (Aamir Nasirabadi 2024.4.14 インド)。
この写真だけ見ると何なのかわからないかも知れないが、翼の先端の黒色はこの姿勢だとこれほど目立って見える。写真の順序や尾の欠損から想像すると次の写真が同じ個体の普段の姿か: Oriental Honey-buzzard。こちらを見ると普通のハチクマに見える。
写真の特性にもよるかも知れないが翼の先端の黒色模様は魅力を増すのに役立っているかも (摩耗しやすい先端を守るなど別の適応もある)。これだけ形が違って見えると鳥とは思えない形に変身するフウチョウのディスプレイすら連想させてくれる。
オスの模様をメスがどう判断しているかに関連して、動物園個体 (メス) に遊んでもらっていた時に写真集を持って行って見せたことがある。「今日はいったい何?」というちょっと身構える表情はインコが新しい刺激に対して示したものと同じようだった。
サシバがとまっている姿の写真には特に反応はなかったが、青空バックに鮮やかなハチクマのオスの飛んでいる写真には明瞭に興味を示した。渡り中の写真などには特に反応はなかった。
実物やビデオでなく写真を見てもわかるのだろうか。
オスの模様はメスを引きつける刺激になっているのではないかと想像する。一部始終をビデオに収めておこうとセットしておいたのだが、後で見てみると自分が写野から外れてしまっていて鳥に本を見せている珍奇な映像は記録されていなかった。飛行中のオスの写真を見せた時に首をにゅうと伸ばす鳥が写っているだけでこれでは何なのかわからない (笑)。
前飼育員の方には (多分苦笑をこらえつつ) まるでインコみたい...と言われた。
この事例やカンムリカッコウハヤブサとの比較を考えるとハチクマのオス下面の派手な衣装はクマタカへの擬態よりも空中ディスプレイを発展させる経緯で進化した (選択された) と考えることもできそうに思える。
翼や尾の縞模様はタカが作りやすい模様で、タカらしい容貌が同種にもよいシグナルになるので (意外にも我々の審美眼と似ているのかも知れない。タカもかっこいい相手が好きなのかも知れない?) 結局クマタカと同じような模様になったとか。獲物や外敵への威圧感は二次的な役割でも構わないだろう。
同種間でも翼の縞模様を誇示する行動は争いを避けるなど優位性の表現になり得るのかも知れない。
カンムリカッコウハヤブサはそれほど模倣相手になる種もなさそうだし、Prum (2014) ([擬態と種・亜種の関係] で紹介) のリストにも出てこない。シラガトビやオナガハチクマ類にも風切に同じような模様があるので、タカ班模様はこの系統の原型的な性質かも知れない。
"トビ" と名前の付く方でノスリ・海ワシ系統のトビ類 (我々のトビも) はタカ班がほとんど見られないが、これも系統を反映した結果と考えれば納得ができる。
カンムリカッコウハヤブサでは抱卵はオス・メスともに行い抱卵分担はほぼ同じ。オスが夜間抱卵を行うのを初めて確認した。
猛禽類でオスの夜間抱卵はあまり報告がないそうで、見過ごされているかも知れないが、シラガトビ Lophoictinia isura Square-tailed Kite の事例があるとのこと。いずれもハチクマ亜科である点が興味深い。
特徴的な声は2種類あって1つは2音節の声 (この論文では wee-choo call と呼んでいる)。タカ類によくある whistling call に相当するだろうか。
他に ticking call (あるいは clucking call ニワトリなどのコッコ...の声を指す表現らしい) と呼ばれる音声があって、この表現からは短い音を繰り返すように思える。(ヨーロッパ) ハチクマの rattling call ([音声] の項目参照) に似ている感じがするが実際の音が示されていない。
Cramp and Simmons (1980) "Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa, Volume II: Hawks to Bustards" ではヨーロッパハチクマの音声を ticking call と呼んでいるのでほぼ同じものかも知れない。
抱卵交代などつがいが関係する繁殖に行動に関係が深く、対立行動の時にも聞かれるとのこと。日光浴やモビングを受けた時にも聞かれたとのこと。機能的には (ヨーロッパ) ハチクマの rattling call と結構似ているのかも知れない。
巣での発声が多いことや発声時に体が揺れる点も (ヨーロッパ) ハチクマに似ている。記述からはハチクマよりよく発声しているように読めるが、ハチクマの音声観察記録が少ないだけかも知れない (台湾のハチクマ子育て中継も音声チャンネルが早々に壊れてしまって最初の部分しか記録されていないが、体の動きから後にも発声していたと思われる)。
こちらの外敵はハイイロオオタカ Tachyspiza novaehollandiae Grey Goshawk、アカハラオオタカ Tachyspiza fasciata Brown Goshawk とのことで外敵への攻撃的行動も示したとのこと。外敵の方は "オオタカ" と名前が付いても Tachyspiza 属で日本のオオタカとは異なってツミの方の系統。
カンムリカッコウハヤブサに系統的に近いハチクマに似ている点がいくつもあるが類似点や比較は述べられていない。著者が知らないこともあるのだろうが、ハチクマの繁殖時行動などは海外ではほとんど知られていないのではないだろうか?
少なくともオスの抱卵の役割については比較があってもよさそうに感じる。カンムリカッコウハヤブサはハチクマよりもかなり小さい種。日本のハチクマは渡り鳥だがこちらは留鳥。熱帯の留鳥ハチクマ類もいるのでこれは本質的な違いではないだろう。食性は大きさも反映してそれなりに異なる模様。
カンムリカッコウハヤブサやクロカッコウハヤブサに付けられた属名 Lepidogenys があり、Gould (1838) が当時の学名で Lepidogenys subcristatus (カンムリカッコウハヤブサ) をタイプ種、Selby (1840) が当時の学名で Lepidogenys indicus (クロカッコウハヤブサのシノニム) をタイプ種としてそれぞれ名付けたもの。
lepis, lepidos 鱗 genus, genuos 頬など (Gk) だが目先を指していたようで、ハチクマの(亜)種小名に使われる ptilorhynchus と意味がかなり近い。Gould (1838) も The form is somewhat allied to Pernis とハチクマ類との類縁性を意識していた。
クロカッコウハヤブサには従来 Lophotes Lesson 1831 の属名が使われていた (冠のある) がすでに他で使用されていた属名だったために新しく提唱されたもの。
クロカッコウハヤブサの記述は Falco indicus Lesson, 1830 があったがこれはなんとサシバの記載時学名と同じで preoccupied となったもの。Lesson 1830/1831 の学名は属名、種小名ともに残らなかった。
参照: Voisin and Voisin (2001) Liste des types d’oiseaux des collections du Museum national d’Histoire naturelle de Paris. 9: Rapaces diurnes (Accipitridae), seconde partie に Lesson (1830) のホロタイプの記述がある。
種小名は Falco lophotes Temminck, 1823 = Falco leuphotes Dumont, 1820 で後者の方が早く採用されたもの。属名に意図されたものと同じ種小名でいかにもどこにでもありそうな意味の学名だが衝突しなかったよう。
leuphotes は意図するものは同じだが綴りを誤っているよう (あるいは重複を避けるために意図的に語構成を変えたのかも。フランス語読みだとほとんど同じ音になる)。
(The Key to Scientific Names の Lepidogenys, Lophotes の項目などよりまとめた)。
これが気になったのはカンムリカッコウハヤブサの種小名が subcristatus/subcristata と控えめな名前になっている点から。なぜ cristatus/cristata としなかったのかはおそらく Falco cristatus Gmelin, 1788 (Crested Falcon) の用例があったためではないかと想像している (この学名も無効名となって残っていない)。
もしかすると Buteo cristatus Vieillot, 1816 (現在ミサゴ亜種の学名に用いられるが実はハチクマかも、というもの) があったためかも衝突を避けたのかも知れない (分類変更などで同属となれば preoccupied となる)。ただし英名は遠慮なく Crested Baza/Crested Hawk が用いられていた。
"Crested Hawk" 日本語風ではカンムリダカのような印象で好意的に受け止められている種類のよう。研究者もとても気に入っている鳥で、優れていると考える点をいくつも挙げてもらえた (このような点もハチクマに近いかも)。
この英名はカンムリカッコウハヤブサの由来となっているが、現在の通常の英名は Pacific Baza で、英名と和名の関係が見えないが学名でつながっていた。
Briggs (2018) Breeding biology and behaviour of a pair of Pacific Bazas
Aviceda subcristata in central-coastal Queensland over 10 years が1つがいを 10 年以上観察した記録がある。ワライカワセミやミナミガラス Corvus orru Torresian Crow も巣の捕食者となる可能性があるとのことで、再営巣の例がある。
フエガラス Strepera graculina Pied Currawong のつがいがカンムリカッコウハヤブサを追い払って卵を捕食したのを目撃した。しかし繁殖成功率は 73% と高かった。
フエガラス亜科 (または科): Cracticinae の系統的位置づけについては #アサクラサンショウクイの備考参照。
Mayr and Hurum (2020) A tiny, long-legged raptor from the early Oligocene of Poland may be the earliest bird-eating diurnal bird of prey
にちょっと面白い情報がある。第 II 趾の近位の骨が長いのは現存のタカ類では Pernis, Aviceda の2属に限られるという。他の種では短縮されている。
両者の現在の主食はそこまで似ていない (ハチクマが特殊なだけだろうが) ので系統を反映したものだろうか。Pernis と Aviceda の類縁性が骨格面にも存在するよう。
関連話題が#トビの [トビなどの第 II 趾の骨の癒合] の項目にある。
Mayr and Hurum (2020) が扱っているのは、知られている最古 (3000-3100 万年前) に近い小型のタカ類で、現代の最も小型の広義ハイタカ属に似ているとのこと。小鳥食を想定している。
そのつもりでハチクマの趾の骨格を見ると大型種 (ワシ類など) や哺乳類食の種類よりむしろツミに似ているように見える。もしかすると Pernis と Aviceda の祖先は小鳥食だったのではと思ってしまった。
現代のタカ類では小鳥食のものは脚が長いが Mayr and Hurum (2020) によればその役割はよくわかっていないとのこと。生体力学的な考察もさらに必要だろうとのこと。
Fowler et al. (2009) Predatory Functional Morphology in Raptors: Interdigital Variation in Talon Size Is Related to Prey Restraint and Immobilisation Technique
に猛禽類の趾・爪の形態の解析が出ていた。主成分解析でタカ類、ハヤブサ類、フクロウ類はよく分離されそれぞれ特徴ある領域を占める。
タカ類でもミサゴはフクロウ類に近い位置にくる。コンドル目やヘビクイワシは地上性の鳥に近く、タカ類とは似ていない。
系統関係も出ていて {コンドル目 + タカ目} で第 II 趾が第 III 趾と同等あるいはそれ以上となり、タカ科 (ミサゴ科は含まれない) で第 I 趾、第 II 趾が肥大した (カタグロトビ亜科以降すべてが含まれる)。広義ハイタカ亜科 (チュウヒ類も含む) で趾が長くなったとのこと (derived 派生した/進化した 形質の可能性があるとのこと)。
ハチクマ亜科、ヒゲワシ亜科も含まれているが基本的にはタカ科と同じ特徴。
ハヤブサ類の趾・爪の形態はスズメ目とも多少の重なりがあるが、通常は 第 II 趾が第 III 趾と同等あるいはそれ以上で、スズメ目では第 II 趾が第 III 趾より必ず小さいとのこと。
第 II 趾の大型化は猛禽類のそれぞれの系統で独立に進化したと考えられる。ハヤブサ類とフクロウ類でふしょが短いのは収斂進化かも知れない。
広義ハイタカ亜科の捕食方法と関連があるか多少の考察がある。獲物がまだ生きている間に食べ始めることが多く、その間に動かれないように固定する必要がある。
ハヤブサ類の方が脚が短いので最初の一撃の衝撃が大きく、獲物を殺すのに嘴の tomial teeth を使うので大きな趾を発達させる必要が少なかったと考えている。
広義ハイタカ亜科の足の特徴は過去にも研究されており、例えば Einoder and Richardson (2007) Aspects of the Hindlimb Morphology of Some Australian Birds of Prey: A Comparative and Quantitative Study
(オーストラリアではそれほど多様な系統の猛禽類が定着していないので分析は限られている。カタグロトビ類やハチクマ亜科は分析に含まれていない)。
Jollie (1976, 1977)
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part IV) pp. 299-300 にも記述があり、Astur (現在の学名で復活) と Accipiter を区別する点は第 III 趾と IV 趾の比較があるとのこと。
また第 IV 趾の方が第 II 趾より短いのはカザノワシ、チュウヒダカ類、セイタカノスリとのことで、これらの種類の特異な採食習性からも納得できる (#クロハゲワシの備考 [変わった餌の捕り方をする猛禽類] 参照)。カザノワシは巣ごとひなを持ち去って捕食することがあるらしい。
Fowler et al. (2009) によれば魚食に特化したものを除いてすべての猛禽類は小型の獲物を殺す能力を持っている。
タカらしい捕食の特徴は第 II 趾で獲物を捕らえているかを見るとよいらしい。両足の第 II 趾で獲物を押さえていることが多いとのこと。参考資料ではハチクマ亜科でもハイガシラトビでそのような写真が紹介されている。写真や映像もこの視点で見ると面白いかも。
日本の放鷹術用語では第 II 趾の爪は「内爪」(うちづめ)。名称は季刊アニマ 2「鷲と鷹」(1975) 付録の「暁斎 絵本鷹鑑 鷹ノ名處」を参考にしている。
若杉氏のマーリン通信から: 江戸時代の鷹狩り(5) 鷹の羽 その2 によれば「打爪」で、機能的にはこの名称がふさわしい気がするが、精選版 日本国語大辞典では鳥搦 = 打爪は中の指とある (元亀本運歩色葉 1571)。少しわからない。
第 III 趾は「鳥搦」(鳥がらみ) は多くの辞書にもこの表記になっている。若杉氏は「ハイタカの鳥がらみは小鳥には脅威」と解説されている。
"搦" の文字は今ではあまり使われないが、搦め捕る (からめとる) に使われる。探してみると中国語で捕搦の単語があり、あるいはこれが "とりがらみ" となったのかとも感じた。「鳥搦」の表記が完全に安定しているわけではなかったので当て字の要素も含まれていたのかも。
日本の名称からは第 II 趾より第 III 趾を重要視しているようにも見える。
タカ類に共通の第 II 趾の機能と、ハイタカ (類) の第 III 趾にはタカ類一般に加えて別の役割が派生したものだろうか。
第 IV 趾は「かいるこ」。若杉氏は「一番外側で、後ろに返るほど動く」と説明。#ミサゴ、#カタグロトビの備考 [系統とフクロウ類との収斂進化] やカンムリカッコウハヤブサで出てくるが、ハイタカ (類) でもある程度共通性があるのか。
「暁斎 絵本鷹鑑」では第 IV 趾は「帰籠」の旧字体となっている。
若杉氏よりこれらの和名は爪を指して使われるものとの教示をいただいた。「暁斎 絵本鷹鑑 鷹ノ名處」でも爪を指す印になっているが、趾も含めた用語として使われるかどうかまでは確認はできなかった。
「鷹匠の技とこころ」(大塚紀子 白水社 2011) でも厳密に区別されておらず両方の意味で使われているように読める [p. 92 では爪を指しているが、p. 171 (中指) のような表記もあり指も指して使われるように読める]。
オオタカでは "とりがらみ" を上方向に起こすと全ての指がゆるむがハヤブサはそうではないのでオオタカのように扱って爪や趾を傷めないように注意が必要ともあった (p. 171)。
なおかつては海外でも第 II 趾より第 III 趾が注目されていた記述があった (Brown 1976)。
ハイタカ類の趾はヘビを掴むのは苦手との記述もあった (Brown 1976, p. 104)。
Tsang et al. (2019) Raptor talon shape and biomechanical performance are controlled by relative prey size but not by allometry
に Fowler et al. (2009) の後続とも言える研究があるが、こちらは爪の形しか調べていないので異なった主成分解析の図になっており、分類群ごとに分離される形にならない。爪の形は獲物サイズと相関がある結果となっている。
Csermely (2004) Lateralisation in birds of prey: adaptive and phylogenetic considerations
昼行性猛禽類はまず片足で獲物を掴む時に右足を使うことが多い。夜行性のフクロウ類ではこの傾向は見られず昼行性に共通の適応か。獲物を扱う時に脳の左半球が役立っている可能性があるとのこと。
ハチクマの臭気の再検討 [ハチクマ亜科の他種] で取り上げたカッコウハヤブサ類には特有の臭気がある、について、カッコウハヤブサ類になぜ特別な臭気があるのか再度考えてみた。
これはハワイミツスイ類 (Drepanidinae) ではほとんどの種の羽毛ににおいがある #フルマカモメ備考 [におう鳥のリスト] を見ているうちに気づいたもので、ハワイミツスイ類では嗅覚に優れた捕食者がいないためにおいを消す必要がなかったのだろうと想像できる。この点はニュージランドで地上性で飛べない鳥でも同様。
同じ説明がカッコウハヤブサ類に適用できないだろうかと考えた次第。ほとんどの鳥にとって嗅覚で営巣場所を知られるのは不都合なはずなので、カッコウハヤブサ類が臭気をわざわざ出すのは不自然と感じた。
もしかして巣を狙う哺乳類捕食者の少ない場所に生息するのではと考えてみると、特別な臭気が記載されたクロカッコウハヤブサの記録された場所は Tenasserim でヒマラヤからマレー半島の高地にあたる。
あくまで日本からの想像でイタチ類が重要な外敵ではないかと探ってみると Mustela 属ではこの地域に分布するのは Mustela nudipes Malayan Weasel で wikipedia 英語版によれば分布密度が低く、主に地上性で木に登るのはあまり得意な形態をしていないとのこと。Mustela lutreolina Indonesian Mountain Weasel は分布が限定的でカッコウハヤブサ類にはあまり関係なさそう。
イタチ類は北方型なのでこのような結果となったが、他の捕食者は調べていないので暫定として見ていただきたい。日本では北方型の哺乳類捕食者をまず思いつくので大事なものを忘れているかも知れない。
サル類は視覚優位なので捕食者となってもにおいはあまり関係ないかも知れない。
カンムリカッコウハヤブサは主な分布がニューギニアからオーストラリアで、オーストラリアでは特に樹上の哺乳類捕食者が少ないかも知れない。セキセイインコのインコ臭もそれゆえ可能なのかとも少し考えてみた。
ヘビ類はもう少し分布が広いようなのでこれらの点は現状考慮不十分段階。
仮定を重ねた考察になっているが、カッコウハヤブサ類、特にオセアニア地域のものが臭気を持っているのは嗅覚に頼る重要な捕食者がいないか少ないためかも知れない。
カッコウハヤブサ類に特有の臭気がある + カッコウハヤブサ類とハチクマは比較的近い + ハチクマがハチに刺されないのは臭気を出しているのでは、の論法でハチクマに特別な臭気がある説が誕生したのではないかと思えてきた。クロカッコウハヤブサの臭気のしっかりした記述も 1878 年まで遡る必要があり、それ以降いくらでもありそうなのに見当たらない。オーストラリアのカンムリカッコウハヤブサの研究者 (Fisher) も特にご存じでないらしく、伝説的な部分があるのかも知れない。
ハチクマ側からみると、ロシアで言及されている(ヨーロッパ)ハチクマの臭気もそれほど強いものではなさそうで、これは飼育条件に由来するのではないかと思えてきた。つまり本来肉食の種類に餌を工夫してオートミールなどいろいろ混ぜることで逆に消化を悪くしているのではないだろうか。ハチクマからは味は工夫されたハチの子みたいに見える穀類は喜んで食べるかも知れないが、人の食物でいえば「もどき」であって、消化の遅いものばかり食べさせられていると消化機能に障害を起こしそうな気がする。
飼育下のハチクマの臭気はあまり参考にできないかも知れない。
北半球の温帯から寒帯に住む、イタチ類など巣を狙う哺乳類が多い地域の典型的なタカ (ハイタカやオオタカなど) に比べれば臭気を消す必要性が多少和らぐかも知れないが、鳥自身あるいは巣の臭気は想像されているほど他のタカ類と違わないのでは? [(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の Ingrid の項目では飼育下でカラス類と同程度、あるいはむしろ臭わないとの記述もあった。
例えばハチクマは実は他のタカとそれほど違うわけではなく、針を通さない羽毛構造 (これは小羽枝を密にすればよいだけなので遺伝制御的には比較的簡単に実現できる。逆に小羽枝をなくせば例えば蓑羽のようになる) や、顔面を密生した羽毛で覆う点程度の簡単な特殊化で乗り切っているのでは? 熱帯や雨の多い時期に繁殖するので例えば尾脂腺の成分は雨への適応のため多少違い、湿度の低い時期や地域で繁殖するオオタカなどに比べて濃厚になっているかも知れない。しかし基本的にはタカのにおいの範囲では? 悪臭物質も薄めるだけで香料になることがあるなど嗅覚も結構いい加減なところがある。
自力でハチの巣を積極的に壊せる能力を持っている以外の点は他のタカとそれほど違わない感じがする。ヘビもクマタカと同じようなものを食べているし。日本で広域に繁殖するタカ科ではクマタカに次いで3番めに大きい立派なタカだと思えばハチクマの評価ももう少し上がるかも知れない。
特別な化学物質があるかと調べても、あららら...、アカノドカラカラのように期待はずれ (徒労) に終わるかも知れない。あくまで無責任な想像の範囲で、実際には予期せぬ結果も出ることも期待したい。
[ヨーロッパハチクマの渡り]
ヨーロッパハチクマでは衛星追跡の他に GPS-GSM (Global System for Mobile Communication)を用いた追跡も行われ、詳細も公開されている。Honey buzzard 620 の若鳥 (2020) の例では地中海を夜に渡る途中に多分ボートに不時着したらしい。
サハラ砂漠を 11 日かけて渡った。基地局がないので、サハラ砂漠でのデータが送られて来たのがマリに入ってからとのこと。砂漠を飛ぶ時は最高 3133 m まで上昇したそうである。
途中で水を飲んだと思われるのは渡り初めて5日め (10/5)。食物を食べたと思われるのはさらに3日め (10/8-9)。ヨーロッパハチクマではサハラ砂漠で食物を捕れないため、脂肪を蓄積して渡るようである。
英国で発信器を付けられたヨーロッパハチクマが海上を4日飛びつづけて絶命した記録がある(BBC の記事)。英国からの渡りは海に向かって飛ぶ必要があり、若鳥の初めて渡りでこのように方向を誤ると致命的になり得ることも英国でヨーロッパハチクマが少ない理由になるのだろう。また (ヨーロッパ) ハチクマの夜間飛行能力、連続飛行能力を知る上でも貴重な事例となっているだろう。
この事例ではさまよっているうちに低気圧に遭遇してしまったようで、方向感覚を失ったものと思われる。海上でもしばらくの間発信器からの信号が発せられて船や漂流物などに不時着しているのではとの期待も持たれたが、その後の動きは (船の動きとは異なる) 海流に乗ったもので、しばらくして信号も途絶えたため海に落ちて死亡したものと判断された。
アイルランドを越えてスペインに下りられるかと期待したが、アゾレス諸島を見過ごしてしまった(資料) [注: アゾレス諸島のポルトガル語の由来の acor はオオタカの意味だがオオタカは生息していない。現在生息しているタカはヨーロッパノスリの固有亜種 rothschildi のみ]。
次はフィンランドの同一個体を6年連続で追跡した例。Satellite tracked birds。
シーズン毎に経路が結構違っている。越冬地は同じ場所であった。繁殖地に戻るのは6月に入ってから。8月下旬にはもう動き出す (動画にして楽しむ機能も付いている)。
少なくともヨーロッパハチクマでは繁殖地と越冬地は固定しているが、その間は結構融通が利き、おそらく偶然どのグループと一緒になるかで渡りの経路が違ってくるのだろう。それでも最後には正しい場所にたどりつける感じである。日本のハチクマでも同様なのか興味あるところである。同じページから他の個体なども見られるのでお試しいただきたい。
Agostini and Panuccio (2015) Is the water-crossing tendency of adult European Honey Buzzards influenced by a time minimization strategy during spring migration?
春の渡りでは目的地への到達を急ぐためにより直接的なルートを選ぶのでは。
Nourani et al. (2020) Dynamics of the energy seascape can explain intra-specific variations in sea-crossing behaviour of soaring birds
では秋の渡りで地中海を渡る時のエネルギー消費を考察。
成鳥と若鳥では渡り時期がほとんど重なりがなく、成鳥がアフリカに達するころに若鳥が渡るそうである。若鳥は一般に生存率が低いものの、地中海を渡る時に命を失うことは少ない。早い季節に渡る成鳥は地中海を渡る時に風はあまりよくないが、若鳥が渡るころは条件がよくなっていて風に助けてもらうこともあるようだとのこと。
Saying "Kesobb talalkozunk!" to the Honey Buzzards!
(Williamson 2020) のヨーロッパハチクマの渡りの記事によれば若鳥が生き残る確率は 1/3 だそうである。若鳥は最初の渡りは本能的に、繁殖地に戻れば他の成鳥から安全な渡りのルートを学ぶとのこと。
親が子供に付き添って渡るやり方だと親自身の生存確率が下がる。子供にとっては単独で渡るリスクが大きくても親が長生きしてより多くの子供を残す方が有利なので、もし一緒に渡る戦略があってもそれは不利になって残らないそうである。著者はハンガリーの方で参照文献へのリンクもある。
ヨーロッパハチクマの衛星追跡はかなり行われているが、2暦年の個体が繁殖地に戻ることがないのかはまだ確実に明らかでない → その後の衛星追跡により、もう少し詳細が明らかになってきた [ヨーロッパハチクマはいつ繁殖地に戻るか] 3年目には一部戻り始めたとのこと。
Corso et al. (2012) The status of second-calendar-year Honey-Buzzards in Europe 過去にそのような個体が春の渡りで観察された報告はあるが、多くは年齢判定に問題があったのではとのこと。標識調査からも少し証拠が出ているが、情報は私信レベルで論文にはなっていない。
3例があるが情報は意外にも結構怪しく、渡りの途中で死んだ個体がみつかっただけの例が含まれてそう。
春の早すぎる時期の回収で、あるいはヨーロッパで越冬したものが少数あるのではとの話も含まれている。
Bildstein (2017) "Raptors" p. 25 によればヨーロッパハチクマ以外にもミサゴやエジプトハゲワシの1年目も繁殖地に戻らないとのこと。これは繁殖地で成鳥との競争を避ける、繁殖可能になる前に経験を積むなどの意味もあると考えられるが、渡りを行うことによってエネルギーを大量に必要とする換羽期間が短くなるのを避けてゆっくりした換羽を可能にする意義もあると述べられている。
Panuccio et al. (2006) Does the Honey-buzzard feed during migration?
によれば渡りの時に帆翔を主に行うヨーロッパハチクマでは体重を減らすため、また到着を早めるために渡り途中で食物をとらないが、羽ばたき飛行をするミサゴ、トビ、チュウヒ類は途中で食べるとの解釈があるとのこと。
アメリカのハネビロノスリ Buteo platypterus 英名 Broad-winged Hawk では 100 g の脂肪で帆翔ならば 20 日以上飛行できるが、羽ばたき飛行では5日以内に使い果たしてしまうと見積もられている。
この論文ではそのうの膨らんだヨーロッパハチクマも複数観察され、一部の個体は途中で食べていることがわかったというもの。
Becciu et al. (2021) Groping in the Fog: Soaring Migrants Exhibit Wider Scatter in Flight Directions and Respond Differently to Wind Under Low Visibility Conditions
で霧の中のヨーロッパハチクマの春の渡りをレーダー観測 (イタリア) した結果がある。霧の中では平均的渡り経路から外れる傾向が高くなり、風が強まると飛行速度を上げ、横方向に流される結果が得られた。
霧の中での飛行経路を定量的に調べた初めての研究であるとのこと。観測中に高度を下げて地上の目標を確認しにくる個体もあったとのこと。
視界のよい時は風の影響を補正できるように飛行できるが、視界が悪いと補正が不十分になる。視界の悪い中で速度を上げることは霧の中から逃れるなどの効果が期待できるが、建物や風車などへの衝突の危険性も高まる。霧の中での渡りの目視観測はほとんど不可能であるが、レーダー観測はその点で有利である。
[ヨーロッパハチクマはいつ繁殖地に戻るか]
フィンランドでヨーロッパハチクマの若鳥の渡り追跡が研究されている: Mirski et al. (2024) Natal dispersal and process of recruitment in a long-lived, trans-continentally migrating bird (preprint)
29 羽を衛星追跡。76% が越冬地に到着 (最初の渡りの生存率は結構高い)。翌年戻ってきた個体はなかった。1年目の冬は越冬地を広範囲移動するが、2年目は動きが比較的少なかった (個体差もあり)。
3年めは11羽のうち6羽が繁殖地に戻ろうとしたが成功したものは半数だった。
この年に渡らなかったものは翌年もすべて生存し、5羽中4羽は繁殖地に戻ろうとした。最後まで残った個体は5年目に戻ろうとしたが地中海を越えられず、6年目に戻ったとのこと。
全体では6個体 (21%) が 3-6 年後に繁殖地に戻ることができたとのこと。冬季はテリトリーを持たない。
繁殖地に近い地域に戻ってくるが (最初の帰還では 5-177 km 離れていて平均 53 km) 渡りのコースは秋と異なっていた。年を追うごとに生まれた場所に近づき、帰還も早くなったとのこと。6羽のうち4羽は生まれた場所から 10 km 以内に近づいたとのこと。オスの2羽は巣を造ったが繁殖成功は確認できなかった。
オスの1羽は3回目の帰還となった5年目に出生地から 16 km 離れた場所に巣を造った。もう1羽のオスは最初の帰還となった6年めに 出生地から 189 km 離れた場所に巣を造った。翌年も同じ巣を用いたが、その翌年は場所を変えたと思われる。いずれの例でもつがい形成や繁殖成功までは確認できなかった。
最初の渡りでの死亡率は 25%、越冬地での最初の年の死亡率は 32%、さららに翌年は 3.5% だったとのこと。春の渡りまで至った個体 11 羽のうち5羽 (45%) は途中で死んだとのこと。1羽は途中で戻った。
一度繁殖地までの渡りを完結するとその後の死亡率は減るとのこと。繁殖の試みまで至ったものは2羽 (11%)。実際に繁殖できるまでにはよい場所を見つける必要があって帰還の年にすぐ繁殖できるわけではない模様。
性成熟年齢を超えても越冬地にとどまった個体がいたことは驚くべきことだが、早くから繁殖を始めることと渡りの生存率の間にトレードオフが存在するのだろうと述べられている。#オオタカの備考 [クーパーハイタカの繁殖開始年齢] も参照。
おそらく体調や環境要因により成鳥でも繁殖地に渡らないケースも知られている。
ヨーロッパハチクマでも知られている ([越冬地で休暇をとった?ヨーロッパハチクマ] の項目) が、Sorensen et al. (2017)
Rare case of an adult male Montagu's Harrier Circus pygargus over-summering in West Africa, as revealed by GPS tracking のヒメハイイロチュウヒの論文がある。
ヨーロッパハチクマの中にも繁殖開始が早いもの、遅いものが含まれていると想像される。このような戦略が可能な一つの要因として、同じサイズの他の猛禽類よりヨーロッパハチクマの寿命が長い (野外最長寿記録 28 年) ことも要因か。生活史戦略はむしろ海鳥やハゲワシに似ているとも考えられるとのこと。
参考までに見ておくとオオミズナギドリの繁殖開始年齢は4歳以上とのこと: しまぐに日本の海鳥 (8) 繁殖と長生きとを両立するオオミズナギドリの戦略【寄稿|島と鳥を愛する研究者・平田和彦@千葉県立中央博物館 】。
文献値では体重は平均値で 489 (メス) - 569 (オス) g (Yamamoto et al. 2016) とある。ヨーロッパハチクマの半分強ぐらい。
ヨーロッパの研究者にはマンクスミズナギドリが念頭にあるかも: 例えば Wynn et al. (2022) Early-life development of contrasting outbound and return migration routes in a long-lived seabird。こちらは3年めから繁殖地に戻るとのこと。
ヨーロッパハチクマにとっては秋の渡りの方がむしろ安全で、春の渡りの方が条件が厳しいとのこと。完全な成鳥でない個体の到来は6月中旬から遅いものは7月中旬になることもあり、繁殖のタイミングには間に合わないので最初はあぶれ個体として他個体などから営巣地や採食場所を学んだりして過ごすことになる。
渡りの経験を重ねると早く戻ることができるようになるとのこと。3回目ですでに成鳥と同じ期間繁殖地で過ごす。
最初の繁殖地への帰還は場所探しや経験を積むための役割があると考えられる。多くの個体は繁殖まで 6-8 年かかると推定している。42% が2年で繁殖を始めるオオタカ (留鳥)、平均 3.5年 のヨーロッパノスリ (短距離の渡り)、3.6 年のアカトビ (短距離の渡り)、2-8 年の長距離の渡りをするトビとは対照的である。
若鳥の方が成鳥より 1-2.5 週間遅れて繁殖地を出発するが、この期間が生まれた場所の刷り込みに役立っているかも知れない。
死因もある程度判明していて、力尽きた、捕食されたなどがある (死因はかなりのものが推定で、越冬地ではあまりわからない。捕食が確認できた例はなく推定)。撃たれたものもそれなりの数があって一部は確認されている。個体群動態に与える狩猟圧の影響は思ったより高いよう。
(ヨーロッパ) ハチクマの衛星追跡研究は10年がかりの仕事で、しかも若鳥に標識をしないと全貌はなかなかつかめない模様。ハチクマの場合は春の渡りの障壁はそこまで高くない感じがするが、ヨーロッパハチクマと比べてどうなっているのだろうか。
ハチクマで時々報告される6-7月ごろの意外な場所での出会いには、あるいは最初に帰還した年の遅く渡ってきた個体が含まれているかも知れない。行動圏が広い印象をもとに解釈されがちかも知れないが、遅く渡ってきた、あるいはあぶれ個体の可能性もありそう。
ドイツからの成鳥の渡り追跡 (2001-2011) と信号が途絶えた原因の考察: Meyburg and Ziesemer (2024)
Where and when does mortality occur in adult European Honey- buzzards
Pernis apivorus breeding in Germany, based on satellite telemetry?
同じ場所に戻ってくるので一部は再捕獲も可能だったとのこと。追跡が終わった後でも送信機を付けているものもあってアンテナがなくなっているなどの情報も得られた。
渡り途中で力尽きた (速度が落ちるなど) と思われる事例は想像より少ない。こちらは秋の渡りで失われたものの方が多かった。
越冬期に信号が途絶えたものがそこそこ数があり、例えばフクロウ類や昼行性猛禽類による捕食もあるが情報は少ない。少なくとも一部は狩猟によるものではないか。
Wright et al. (2023)
Photographic evidence of a 2nd calendar-year female European Honey Buzzard
Pernis apivorus on autumn migration in the Western Palearctic
は2暦年のメスをヨーロッパの秋に渡りで記録したとの写真が紹介されているがいかがだろうか。
[ハチクマの渡り]
ハチクマの渡りはよく知られているので周辺情報が中心。[中東やアフリカに進出するハチクマ] などもご覧いただきたい。
日本も含まれる東アジアのルートの他に西ルートもある。
意外に感じられるかも知れないが、ネパール西部にもタカ渡りの観察ポイントがある Raptor watching at Thoolakharka Nepal 標高 2050 m とのこと。
渡り観察シーズンは 10/15-12/15 だそうで、ハチクマのピークは 10 月第3週でここではノスリの渡りと同じ時期とのこと。Decandido (2014) Autumn 2013 Raptor Migration in Nepal にさまざまな種の情報がある。ソウゲンワシが多いのが特徴。
中央アジアでは近年定常的な渡りが見られるようになってきた。Schweizer and Mitropolskiy (2008)
The occurrence of Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhyncus in Uzbekistan and Tajikistan and its status in Central Asia。
久野 (1996) Birder 10(10): 78-84 に白樺峠のタカの渡りが知られるようになった当初の記載がある (当時は伊良湖岬などが有名で、内陸のタカの渡りは少しずつわかってきた段階であった)。
1989年9月に同所で大規模な渡りが発見されたのがきっかけ。
同記事には成鳥と幼鳥の両方の特徴を持つ個体が記録され、暫定的に若鳥と記録しているとの記載がある。
「野鳥」1992年2月号 (No. 543) pp. 29-30 に織田氏による韓国済州島でのハチクマの渡りの発見 (1991年9月23日) の手記がある。志村氏のコメントがあり、長崎から先の経路が不明であったが、予想を裏付けるものとのこと。この観察時は夕方近い時間帯であったとのこと。
ヨーロッパハチクマが海上迷行に関連して、日本でもハチクマの本来の渡り経路とは異なる長距離海上飛行の例として、千葉 (1998) Birder 12(10): 10-15 に小笠原で衰弱保護されたハチクマ (1997年10月) があり、小笠原でのハチクマ初記録だったそうである。同文献には 1998年3月のオオタカの記録も記されている。
秋の与那国島/石垣島紀行 その4...(2018) に与那国で秋の渡り時期のハチクマの記録が紹介されている。幼鳥が本来ルートを外れてしまったのであろうか、それとも台湾を渡りで通過する個体群に関係するのだろうか? 同記事にはマダラチュウヒなどの記録も掲載されている。
また冬期のハチクマ成鳥の観察記録がある: 村上・秋山 (2016) 神奈川県における真冬のハチクマの観察記録。
冬期は何を食べて過ごしていたのだろうか?
よく知られているが日本の衛星追跡の論文を列挙しておく:
Higuchi et al. (2005) Migration of Honey-buzzards Pernis apivorus based on satellite tracking
Shiu et al. (2006) Route and site fidelity of two migratory raptors: Grey-faced Buzzards Butastur indicus and Honey-buzzards Pernis apivorus
Yamaguchi et al. (2008) The large-scale detoured migration route and the shifting pattern of migration in Oriental honey-buzzards breeding in Japan
Yamaguchi et al. (2012) Real-time weather analysis reveals the adaptability of direct sea-crossing by raptors
Mardiyanto et al. (2015) Spatial Distribution Model of Stopover Habitats Used by Oriental Honey Buzzards in East Belitung Based on Satellite-tracking Data
Nourani et al. (2017) Climate change alters the optimal wind-dependent flight routes of an avian migrant
Syartinilia et al. (2017) Landscape Characteristics of Oriental Honey Buzzards Wintering in Western Part of Flores Island Based on Satellite-Tracking Data
Sugasawa and Higuchi (2019) Seasonal contrasts in individual consistency of oriental honey buzzards' migration。
中国の山東省長島県での秋のハチクマ渡りの記録 Yu et al. (2022) Population Dynamics and Autumn Migration of Pernis ptilorhynchus in Changdao of Shandong Province, China
1987-2019 年の秋の渡り調査。個体数は増加傾向。2019 年に2個体を GPS 追跡で秋の渡りのみ調べられている。
インドネシアのモルッカ諸島には日本からの衛星追跡で渡った例はないが、ある程度の記録があり移動時期から渡りの個体と想像されるものの年中滞在している可能性もあるらしい [Mittermeier et al. (2015)
The status of Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus in
Wallacea, with a description of the first record for Ternate]。
この文献によればフィリピンの衛星追跡でパラワン島に渡った記録があるが、それまでは現地で記録例がなかったとのこと。おそらく留鳥のヨコジマハチクマと混同されてきたのではないかと書いている。
ただしヨコジマハチクマはパラワン島に分布しないと通常の解説にあるので、P. p. palawanensis のことか? この島の亜種はフィールド観察ではよくわかっていない。
パラワン島で越冬中らしい画像: haralddahlby 2024 iNaturalist 197460775。
ミンダナオ島も訪れているように見え、衛星追跡の例とも符合する: notoriousbiologist 2023 iNaturalist 188153108。
[台湾で留鳥化したハチクマと渡りの謎]
台湾では渡り個体と留鳥個体の両方がみられる。
留鳥個体は冬場は養蜂業に依存して生活しているらしい (The Oriental Honey Buzzard of Ninety-nine Peaks; 九九蜂鷹(英語版))。
台湾でハチクマが留鳥化したいきさつ、冬場の行動の記事がある
ハチクマの記事 (科学発展 2013年11月)。
遺伝子および安定同位体解析により台湾には2グループがあることが示されており、渡りの個体群が留鳥になったことが示された。時期は 1970-1990 年代で、
台湾では 1970 年代から養蜂業が活発になり、1980 年代にピークに達したそうで、それがハチクマが留鳥化した要因になっていると考えられる。
ヨーロッパでは小鳥が給餌で越冬地を変えたことが知られている。これほど大型で猛禽類の渡り鳥が本能的習性を変えることは考えにくいとされていたが、ハチクマの事例は渡り行動の可塑性を明らかにするものであるとのこと。
日本から追跡されたハチクマは台湾を通らない。中国本土からやってきてフィリピンに向かう個体群なのかまだわかっていない。
フィリピンの渡り研究ではハチクマの渡りは比較的少数しか観察されていない。
台湾でもハチクマの衛星追跡が行われたが、追跡された 12 個体は年中台湾を離れなかったとのこと [Chien-Hung and Severinghaus (2014)]。
Ferrer et al. (2011) Why Birds with Deferred Sexual Maturity Are Sedentary on Islands: A Systematic Review
この論文で大陸から比較的離れた島に完全な渡りをして繁殖する猛禽類の例でケアシノスリとヒメハイイロチュウヒが取り上げられているが何を指しているのかよくわからない。
Gangoso et al. (2013) Ecological Specialization to Fluctuating Resources Prevents Long-Distance Migratory Raptors from Becoming Sedentary on Islands
によれば大陸の個体群は渡りをするが、島に定着したものに留鳥個体群がある種類があるとの解説がある。
ケアシノスリとヒメハイイロチュウヒについてはどの島の個体群を指しているのかわからないが、完全に渡りをする亜種ハチクマでの台湾での留鳥化はむしろ当てはまるかも知れない。
著者の関心はエレオノラハヤブサ Falco eleonorae の特異な渡りなので東洋の種はあまり詳しくないかも知れない。
猛禽類では島に定着してなおかつ渡りをするものは非常に少ないようで、古く島に定着したものも留鳥になる傾向が非常に強いとのこと (インド洋のハヤブサ類やメラネシアの島の Tachyspiza 属がまず思い当たる)。
サシバやハチクマは日本にもやってくるが、基本的には大陸種の分布が少し広がったものとみなしてよいかも知れない。さすがに日本の冬は寒すぎて留鳥化までは至らなかった (?)
ツミも該当するかも知れないが「部分的な渡り」の方に分類されて留鳥化のカテゴリーに入らないかも知れない。
ミサゴも (カンムリミサゴを別とすれば) 世界的には渡り個体群が一般的だが、いくつかの島では留鳥になっている。日本のミサゴも留鳥傾向が強いのは関係があるかも。
トビが南西諸島でまれなのもあるいは大陸から離れすぎているためかも知れない (#トビ備考 [亜種と渡り] で東アジアのトビの起源で考察あり)。
他に可能性のあるものとして #ハヤブサ [ハヤブサ亜種の分子系統解析] 亜種のシマハヤブサも挙げられるだろうか。#ノスリの備考 [ノスリの亜種] でフィリピンの個体群の考察を行っている。
台湾ではタカ柱のことを鷹球と呼んでいるらしい 東方蜂鷹的蜂鷹球 Oriental honey-buzzard (20210502) 4K
日本の衛星追跡では台湾を通っていないので、これらの個体はどこから来てどこに行くのだろうか。
ついでにタカ柱は英語では kettle と呼ぶことはある程度知られているだろう。要するに "やかん" である。OED もチェックしておくとさすがに業界用語すぎるようで見出しがない。a kettle of fish の用語はあるが意味も違いおそらく関係ない (魚の群れを示す集合名詞は school of fish。他の言い方もある)。"hawk pillar" は日本以外の用例を見つけられなかった。
さて少数個体の場合は boil と呼ばれることを知った。こちらの方が語源的には古い可能性があり、OED によれば魚が突然疑似餌に飛びついてくる用例がある (1893-)。いずれにしても "湧き上がってくる" 状況を表現したものであろう。
大陸の渡り個体群と考えられる集団が台湾で留鳥化した理由として 1970-1990 年代の養蜂業との関係が挙げられているが、#サシバの備考にあるように、1970 年代までは捕獲圧が異常に高かったことも起因していないだろうか。
それまでもハチクマが散発的に渡ってきていたが、大型で目立つため剥製業者の格好のターゲットとなって (当時どこへ輸出されたかはサシバの備考参照) 繁殖集団を形成することもできず撃たれて消滅してしまっていたのではないだろうか。
それ以前は猛禽類全般への迫害の時代でもあり個体数も減っていたかも知れない。そして近年のハチクマの世界分布拡大の好調さにも助けられているかも知れない。
平野 (2014) Birder 28(9): 22-23 に 2013-2014 年の台湾で冬に集団で巨大スズメバチの巣を襲うハチクマの取材の記事がある (冬場も養蜂業以外に自然の食物がある)。15 羽以上が訪れたとのこと。
九九蜂鷹のビデオもそうだが、集団で巨大なハチの巣を襲うのは (動かない獲物だが他個体の動きを見るなど社会性が必要だろう) 猛禽類の共同ハンティングと呼んでもよい印象を受ける。
モモアカノスリの共同ハンティングは #トビの備考参照。
#ハヤブサの備考 [オナガハヤブサの共同狩猟]。
#ハヤブサの備考 [タカ目、ハヤブサ目、オウム目の脳の比較] に Harrington et al. (2023) のフォークランドカラカラの問題解決能力が高さが示されているが、社会性があって新しいものを怖がらない (動物園個体の観察や韓国の飼育個体、UAE の保護個体、ヨーロッパハチクマの飼育情報など) 点、越冬地ではジェネラリスト的でもある点でハチクマはこの条件を満たしているかも知れない。
Snake v Oriental Honey Buzzard! 01 August 2021 (Arlene Beech 2021)
に台湾のビデオ中継から巣にヘビを運んできたものの途中で引っかかってしまい外そうとしているハチクマの映像がある (mom とあるがオスである。またこの時期にはすでに巣立った後で、食物をもらう時のみ巣を使っていた。子供は自分で食べられるので親は通常食物を置いてすぐに飛び立つ)。
あまりにも人間の行動を見ているようで違和感を感じないのだが、この時期に食物を運ぶハチクマがこれほど長く巣に滞在することはまずない。ひっぱってもだめとわかると中程を引いてみようとか、引っかかっている場所はわかっていて外そうとするがそこまで届かずバランスを崩して落ちそうになる。
一度はあきらめて (しかし飛び立たない) しばらく考えて再挑戦している。同じ状況なら人でも同じようにしていたかもしれない。
問題解決能力の高さを示しているように思う。カラスがこのような行動をすれば賢いと言われそう。
ひなが親と同じように引っ張った映像を見た記憶があるが見つけられなかった。考えたら同じような結果になったのか、それとも親の行動を見て学習したのか? 翌日の映像にはヘビが見られないようなので何とかして食べたのかも知れない。
[中東やアフリカに進出するハチクマ]
ハチクマの世界的分布は近年広がっており、中東では普通に観察されるようになっている。ヨーロッパやアフリカでも少数観察され、例えば Kennedy and Marsh (2016) First record of Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus for Kenya and East Africa (ケニアでの初記録。他所での記録への論文も記述されている)、
南アフリカ共和国で 2021 年に初の (越冬) 個体が記録された。この南アフリカの記録は面白いので当時の記録を紹介しておく。
What A Bird! Finding the Crested Honey Buzzard (観察者のブログ)。こんなに「大物」の迷鳥はめったにあるものでなく、大変な人気であったとのこと。ただし待ったものの見られなかった人も多かった。
Rare sighting of a crested honey buzzard in Somerset West has birders abuzz にも報道記事がある。
国内中から観察者が押し寄せているとのこと。雑種ではなく純粋なハチクマと判定されているとのこと。この地域に2週間ぐらいいることはわかっている。ある方はトゥィッチ歴に残る忘れることのない出会いになったと述べている。なお当時は南アフリカは真夏。
[ついに北欧でも?]
PRESUMED - Crested Honey Buzzard (Pernis ptilorhynchus) 11.9.2024 Mattby, Kirkkonummi, S Finland (Mika Ilari Koskinen 2024.10)。
2024.9.7 にフィンランドで目撃されごくわずかなバーダーが見られたが後日目撃あり、エストニア方向に向かったとのこと。不明のワシのような鳥として記録された模様。
アフリカで越冬するならばそのまま北に向かっても不思議でないかも知れない。
このところハチクマに勢いがある印象を受ける。気候変動による分布の変化を反映しているのかと考えていたが、あるいは狩猟圧が高くて数を減らしていた可能性も含まれるかも知れない。狩猟圧が生じる前に分布を広げていなかったらしい点を考えると気候変動の影響の方が大きいかも。
もし本格的にヨーロッパに定着すればヨーロッパハチクマと競争が生じるかも。微妙にニッチが違うかも知れないが完全に競合すればハチクマの方が大型なのであるいは、との印象もある (いつの時代になるかわからないが)。
[デンマークの記録]
2025 年、春の渡りでデンマークでも目撃され映像となっている: First record for Denmark. Crested Honey Buzzard (Pernis ptilorhynchus) at Skagen May 1st 2025 (Alex Sand Frich 2025.5.1 撮影)。デンマーク初記録とのこと。
解像度の限界もあって虹彩色などがわかりにくいが、(6 枚は問題なし) 初列風切先端の黒さは日本で見る個体ではメスのように見える。それにしては虹彩色が見えているような気がする (暗色?)、尾のバンドの先端が結構太い感じがする。
Tophvepsevage i lyd og billeder over toppen af Danmark, den 1. maj 2025 こちらはデンマーク語の音声も入ったより長いビデオ。最初は何かわからなかったらしく、大きいのでワシの1種かなどの議論や他の方はハチクマならば別に観察経験がある、おそらく野生個体だろうなど (音声英語翻訳で意味を一部解読)。
みなさんの判定はいかが?
英国 BirdGuides の海外珍鳥コーナーにも報告されているが、フィンランドではともかくデンマークならばかなり近い。あるいはそのうち英国にもハチクマがやってくることを期待しているのかも。
またデンマークを通っているならばこれまで未記録だった国をおそらく通過してきたはずでこれも各国で話題となりそう。
近年ハチクマに勢いがあると感じられる報告が多いがおそらくその通りなのだろう。
[セーシェルのハチクマ初記録]
インド洋セーシェルでの初記録: Levorato et al. (2022) First confirmed record of Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus for Seychelles
2020 年遅くに訪れ、少なくとも2021年12月の段階でまだ滞在中とのこと。2暦年の個体 (幼い特徴の残るオス) で営巣中のアオサギを何度も攻撃していたとのことで典型的な食物がないためだろうとのこと
[セーシェルには固有種の mud dauber wasp Sceliphron fuscum というハチがいるらしいが外来種に置き換わりつつあるとのこと。このような巣を食べ物と認識するだろうか?]。
ハチクマもいざとなればアオサギを襲うらしい。
ヨーロッパハチクマは過去に何度も記録があるそうだが、どちらの種類でも海上を相当飛ばないと到達できないはず。ハチクマの方はまるでアカアシチョウゲンボウのようにインド洋を横切ったのだろうか。
セーシェルのチェックリストは Les oiseaux des Seychelles で見られるが、タカ類の比較的大型種ではヒメクマタカの記録がある。
ヒメクマタカの方が小さいぐらいなのでハチクマは同島を訪れた最大のタカ類かも知れない (ミサゴ、トビの記録はあって体重的にはハチクマとよい勝負だが鳥はめったに襲わないかも知れない)。同島の鳥にとっては普段気にする必要もなかったはずの突如現れた猛禽類になるだろうか。
ちなみにこちらはシロアジサシのモビングを受けるヨーロッパハチクマ: Amur Falcon, Red-throated Pipit and Western Honey Buzzard at Alphonse
(Seychelles Bird Records Committee 2016)
インド洋渡り途中のアカアシチョウゲンボウの記録も出ている。
[オーストラリアのハチクマ]
オーストラリアでは現地の夏季にディスプレイ飛行をする個体も記録されている (Oriental Honey Buzzard - Lake Joondalup, Western Australia; eBird の分布図)。オーストラリアで繁殖する前触れであろうか?
2000 年代前半はまだオーストラリアのハチクマの初記録などが出ていた。
Clarke (2003) Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhyncus on Christmas Island, Indian Ocean, Australia
この記録は正式認定されたそうで、目視記録のみからいかに種や亜種の判定などを行ったかなどの付随情報も役に立ちそう。クリスマス島はジャワ島南に位置するオーストラリア本土から離れた場所なので、ここで迷鳥記録されることはまだ理解できたが...そのうちオーストラリア本土の北部でも記録され、ここもスンダ列島に近いので、とまだ思われていた。
Gregory (2007) Second Mainland Australian Record of the Oriental Honey-Buzzard Pernis ptilorhyncus。
もう少し新しい記録では Jackett et al. (2019) Oriental Honey Buzzard - Christmas Island。
現在ではオーストラリア本土のさらに南部でも地域限定で結構見られるようになってきている模様。
まだ数個体の記録だった時代のブログ: Perth Buzzard Twitch (Jennifer Spry 2015.2.15)。
2羽現れたとのニュースを知ってオーストラリア南東部ビクトリアから 2700 km 飛んでパースの空港から1時間車に乗って来たのに、15 分前に現れたがその後は見てないとの返事だったとのこと。その後は幸い見られたとのこと。
WESTERN AUSTRALIA NOVEMBER 2018 (Sue Taylor 2018)。初日は見られなかったが翌日に見られた。
Oriental Honey-buzzard (Allison Archer 2022.1.21) オーストラリア西部でオーストラリアチョウゲンボウに対する威嚇の背面飛行。Oriental Honey-buzzard が背面飛行への移行途中の体勢と思われる。
Oriental Honey-buzzard (Rachel Olsen 2022.1.14) 現地のオス (すでに複数のよう) と渡りのオスの意味だろうか。
Oriental Honey-buzzard (Samuel Gale 2023.3.11) 初記録された若鳥。
Oriental Honey-buzzard (Samuel Gale 2023.3.11) 同所でのオス成鳥。モモイロインコと飛んでいていかにもオーストラリアらしい。
Oriental Honey-buzzard (Geoffrey Groom 2018.12.6) 12 月のディスプレイ飛行。
10 月の写真は見られず、11 月には換羽していない姿が撮影されているので渡ってきているのか?
4月に若鳥の写真はあるが 5-7 月の写真はなし。2019.8.30 に北部オーストラリアで大きく換羽中の個体が撮影されている。
Oriental Honey-buzzard (ladyrobyn 2020.12.14) によればここ 7-10 年毎年見られている。羽衣の違いから少なくとも5個体が記録されている。
オーストラリア西部のパース近郊で夏鳥となっていて繁殖の兆候十分ありだろうか。2024 年初頭の北半球の冬にも複数個体の写真がある。
まだまだまれな存在だが、オーストラリアはハチクマの新天地となりつつあるのか?
参考までに比較でヨーロッパハチクマの背面飛行。相手はタカサゴダカとのこと: European Honey-buzzard (Gavin Ailes 2024.11.17 ガーナでの撮影)。
これも参考までにインドのハチクマの急降下姿勢 Oriental Honey-buzzard (Haemoglobin Dr 2024.12.22)。ハチクマも急降下の時にはこのような姿勢になる。
Oriental Honey-buzzard (Mel Mitchell 2015.2.7) 一緒に飛んでいるのはアカヒメクマタカ [高野 (1973) ではヒメアカクマタカ] Hieraaetus morphnoides Little Eagle で小型のヒメクマタカ属とは言えイヌワシ亜科である。ハチクマの大きさがわかる。
Oriental Honey-buzzard (Jose Teixeira 2024.12.14) Dili, Timor-Leste オーストラリアではないが近くのチモールでのハチクマ。
Oriental Honey-buzzard (Stephen Corcoran 2025.1.2) 2025 年もオーストラリアでこれまでの記録地でハチクマが観察され獲物を運んでいる。半年違うと思えば日本では 7/2 に相当でいかにも繁殖個体のよう。
Oriental Honey-buzzard (Sheila Rowlands 2025.1.10) 獲物を運ぶオーストラリアの個体。
Oriental Honey-buzzard (Emma Geary 2022.8.2) こちらは冬季の映像。もしかすると留鳥になっている? 日本のハチクマによく似て見える。
[北米のハチクマ初記録!]
なんとアラスカのアリューシャン列島でハチクマが記録された。2024年5月にアメリカ初記録。
Shemya Island-Eareckson AS (restricted access) (Brad Benter and Zak Pohlen 2024.5.27 eBird)。
最初はウのコロニーで見られたとのことで、ハチクマが高度を上げるたびにすべてのウが巣を離れ、カモメ類は集まって追い払っているような行動をとったとのこと。初記録なので観察者も追いまくった様子が記されている。同定は最初は悩ましかったがハチクマと判定。
ハチクマとオオワシ、シジュウカラガンが同じ観察リストに出てくるなど想像し難い。
Rare Bird Alert (ABA 2024.7.12)。
[UAE の事例]
大変興味深い写真が報告されている: Checklist S201837101
(Mohamed Almazrouei 2024.11.9 Western Mahadir, Al Dhafra AE-Abu Dhabi, UAE)。
大きなハチの巣らしきものを掴んで舞うハチクマ若鳥。
写真事例 1, 事例 2 (出典は上記と同じ)。
このような光景を見れば普通は繁殖期の行動に見える。しかしこの季節かつ若鳥である。たまたま大きなハチの巣をわざわざ運んでいるところか、それとも繁殖行動に関係しているのか。
通常は渡り個体の地域だが、インドの繁殖個体群が分布を広げているのか、渡り個体だったのものが定着して若鳥も繁殖に参加しているのだろうか。
渡り個体群が繁殖する地域ではハチクマの繁殖開始年齢は遅いとされるが、もし若鳥も繁殖に参加しているならばマレーシアで観察されているようなヘルパーの可能性もあるかも。
さらに考察を巡らすと測位点が必ずしも多くない衛星追跡では越冬地の行動まではなかなかわからない。
越冬地で単に越冬して成熟を待っているだけでなく地域個体群の繁殖行動に何か関与している可能性はないのだろうか。
[ハチクマの越冬地での行動]
渡りのハチクマ (日本と同亜種) のインドネシアでの生態の情報がある。
Kahono et al. (2020) First report on hunting behavior of migratory Oriental Honey-buzzard (Pernis ptilorhynchus orientalis) towards migratory giant honeybee (Apis dorsata dorsata) (Hymenoptera: Apidae) on Java Island, Indonesia。
ハチクマは 8-11 月にやってきて 2-3 月に渡ってゆく。渡りの時期には林や耕作地の高い木にとまるが、郊外で高い木のあるところにも滞在する。
Apis dorsata (オオミツバチ, Giant Honey Bee) は移動性で乾季の始まりのころにジャワ島にやってくる。(地バチのように地下ではなく木の枝や建物に) 巣を作り、それを狙ってハチクマがやってくる。ミツバチの一種だがスズメバチに匹敵するほどの獰猛な性格とのこと (wikipedia 日本語版)。
ハチの巣を発見すると近くで偵察飛行し、まだできあがっていない巣は攻撃しない。
ハチクマはハチの巣にまっすぐ飛んで巣の下部を攻撃する。多くのハチが飛び出してハチクマの敏感な部分 (目など) を攻撃する。
ハチクマによる巣の攻撃を受けて5分程度はハチはまだ攻撃的で人なども襲う。ハチクマはよろめくように数百メートル飛んで足でもぎとったハチの巣を食べるとのこと。
使われているハチの巣よりもハチの移動によって空になった巣を好むとのこと。この場合攻撃を受けることはない。巣にぶら下がって足でもぎ取り、少し離れた枝で食べる。ただし栄養価は低い。空になってまだ時間の経っていない巣ではまだ未成長の幼虫、貯蔵されている花粉 (タンパク質などが豊富)、はちみつなどの栄養物質がある。はちみつの匂いのする蜜蝋の部分だけを選んで食べる。
使われているハチの巣は栄養豊富だが攻撃も受ける。
ハチクマがハチの巣の近くを舞うのに気づくとハチはフェロモン (酢酸イソペンチル; 他の物質もあって alarm pheromones と呼ばれはっきりした芳香臭を持つとのこと) を出して他のハチをパニックに陥らせる。それらのハチは近くで動くものは何でも攻撃する。
現地の人によれば経験豊富な (若くて経験の浅い個体でないものの意味) ハチクマは賢くて自身がハチに刺されるのを避けて人のいる方にわざと飛んでハチの攻撃を人に向けさせるとのこと (wikipedia 英語版にも紹介されているが、研究者による観察ではそのような行動はまれで、
ハチの生息地が減少して都会近くに住まざるを得なくなり人とハチの遭遇機会が増えていることが原因ではないかと解釈している)。
攻撃に失敗し、多数のオオミツバチに攻撃されて横たわっていたハチクマの記録が一度あるが、これは経験の浅い若鳥ではないかとのこと。過去にこのような報告はなされていない (ハチに襲われて死んだらしいハチクマの初めての報告とされることがあるが、因果関係やそれらのハチが実際に刺しているかなどの記述はあまり明瞭でない)。
McCann et al. (2013) のアカノドカラカラの論文 ([ハチの幼虫を主食とする猛禽類・ハチの巣の蜜蝋を食べる鳥] の項目参照) ではミツバチの反撃で死んだ可能性のあるハチクマの記録について
Thapa R, Wongsiri S (2003) Flying predators of the giant honey bees; Apis dorsata and Apis laboriosa in Nepal. Am Bee J 143: 540542 が引用されているが中身は読めないので詳細はわからない。
ハチクマはヨーロッパハチクマで記録されているようにオオスズメバチの巣を捕食するのは観察されていないとのこと。
なおこの論文ではハチクマを eagle と呼んでいるが、インドネシア語ではワシとタカを区別しないためであろう。
おそらく越冬地で撮影されたと思われるハチクマ若鳥がパパイヤを食べる画像がある: Crested honey buzzard eat papaya with different pose。
飼育下の記録にあるようにハチクマが果物など甘いものを好むことはよく知られているが野外での撮影は珍しい。もっとも果物を食べるのはハチクマに限らないようで、他の猛禽類でも知られている (#クロハゲワシの備考 [猛禽類の植物食] 参照)。
[ヨーロッパハチクマによるオオスズメバチの巣の捕食]
Macia et al. (2019) Exploitation of the invasive Asian Hornet Vespa velutina by the European Honey Buzzard Pernis apivorus。
Martin-Avila et al. (2025)
The European honey buzzard (Pernis apivorus) as an ally for the control of the invasive yellow-legged hornet (Vespa velutina nigrithorax) のトレイルカメラと GPS を用いた研究もある (スペインの西端部)。
ヨーロッパハチクマの巣からの平均 (代表値に何を用いるかで値が異なる。統計の扱いに注意) 距離は 1234.7 m で、攻撃されたハチの巣の 89.3% は破壊されたとのこと。
ヨーロッパハチクマの親鳥の捕獲方法まで書いてあり、若い方のひなが保温を必要としない 14 日齢に達した時点でワシミミズクの剥製やオオタカを地上のおとりにして音声を流して呼び寄せたとのこと。巣から見える場所とのことで危ないものがいれば当然追い払いに行くのだろう。
ハチの巣を同定するには GPS が必須とのこと。ヨーロッパハチクマの巣の近くでの捕食が圧倒的 (central forager behaviour) この事例では遠くまで行くことはほとんどなかったが繁殖後期で資源が枯渇していくるとやや遠くを訪れる機会が増えるとのこと。いずれも生態学の理論の通り。
この侵略的外来種のハチが減ったかどうかの検証はヨーロッパハチクマがオオタカの巣の近くを避けるとの知見に基づく対照区となっていて統計的には有意な差があるが個々に見るとうーんの感じ。
オオタカの巣の近くは統計的に有意にハチの数が多い結果となっているがなぜだろうか。
半径 1 km ぐらいの範囲のハチを少し減らす程度の効果はあるらしい。2.5 km を超えると効果はほぼゼロになる。
2014 年にこの地域にオオスズメバチが定着してからヨーロッパハチクマにとって2番めに重要な食料となっているとのこと。
実用的観点よりはヨーロッパハチクマの生態の方が面白い。
Supplementary Information のファイルに追跡例や写真が出ており、巣とハチの巣を往復する場合に経路が多少異なってもほとんど正しい位置に到着している。驚くべき方向感覚。渡りの時のような遠距離の場合は磁場情報から目的地に向かうことも可能だろうが、この場合は目視で景色を覚えているのだろう。おそらく似た場所を多少間違えることもあるようで少し探索した経路も1つ記録がある。
学習でより確実に到達できるようになるかなどは別論文で考察されるのだろう。
Avila et al. (2025) Encouraging native predators of invasive yellow-legged hornets: breeding habitat preferences of European honey buzzards in exotic Eucalyptus plantations
に後続研究がある。ヨーロッパハチクマの好みの環境を調べ、複雑な構造のある森林のパッチの大木に営巣するのを好むとのことだが好む環境と繁殖成績とは逆相関となった。ユーカリのプランテーションは適切に管理すればヨーロッパハチクマに良好な生息環境を提供する可能性があるとのこと。
[越冬地で休暇をとった?ヨーロッパハチクマ]
(旧 URL なので直接のリンクは張っていない https://twitter.com/WMGVs/status/1452608122380500994/photo/1) ヨーロッパハチクマのつがいを衛星追跡したもの。
GPS ロガーを付けたメスが3年間行方不明になった後再発見され、3年分のデータが無事取得できていたとのこと。ルートが毎年異なるのはその年の天候に左右されているらしい (先述推測のように別の渡りの群れに入ったのかも知れない)。2009 年に繁殖したが、2010 年は相棒が繁殖期もアフリカにとどまったまま (休暇?) で、メスは他のオスとつがいになることもなくさまよっていたそうである (赤点)。
2011 年は無事にオスが戻ってきてつがいになったとのこと。
日本で観察された相棒を変えたハチクマの例と比べると婚姻形態は少し違うのかも知れない。
[ハチの幼虫を主食とする猛禽類・ハチの巣の蜜蝋を食べる鳥]
ハチの幼虫を主食とする猛禽類にはハチクマ類の他、ハヤブサ目のアカノドカラカラ Ibycter americanus (英名 Red-throated Caracara) が知られているが、
この種では化学防御物質を出していないことが確認されている [McCann et al. (2013) Strike Fast, Strike Hard: The Red-Throated Caracara Exploits Absconding Behavior of Social Wasps during Nest Predation]。
狩猟習性もハチクマとは異なって空中のハチの巣を繰り返して襲い、ハチがあきらめる (absconding) のを待つ。地下のハチの巣は襲わないらしい。Ibycter (研究者 Sean McCann のページ)。Red-throated Caracara predation behaviour (ハチの巣攻撃の YouTube 映像)。
ハチへの防御能力はハチクマの方が優れていると思われる。
生息地が南米なので研究するのも大変とのことである。
ハチに襲われて死んだらしいハチクマの報告があると言われる ([ハチクマの越冬地での行動] を参照)。
再生回数もすごいのでおそらくすでにご覧になられている方が多いだろうが、比較のために日本のハチクマの捕食動画:
ハチクマ VS スズメバチ VS ツキノワグマ。
ヨーロッパハチクマで鮮明な捕食動画があったので紹介しておく。
The European honey BUZZARD | Bordeaux, France | Wild Animal Behaviour
フランスの映像であるが説明は英語。平均で9年生きるとのこと。
エストニアの方による地バチの巣をくわえ上げてその場で食べるヨーロッパハチクマの映像。食べ終わると再度取りに入った: Pernis apivorus... (Valery Zmachynski 2024)。左右両方の足を使っていて特に利き足がある感じではない。
Ferguson-Lees and Christie (2001) によれば、ハチクマの名は付くが前述のオナガハチクマ類 (Henicopernis は主に足を使ってハチの幼虫を取り出すそうで、Pernis 属との採食方法に違いがあるかも知れない。
Macaulay Library の写真では Long-tailed Honey-buzzard, Long-tailed Honey-buzzard (Charley Hesse 2019.8.20) のように獲物を運んでいるものがあるが、ハチの巣盤を運んでいる画像をまだ見たことがない。脚が長い種類でもないので「主に足を使ってハチの幼虫を取り出す」は本当だろうかとも思う。
Fetisov (2015) The three-toed woodpecker Picoides tridactylus in food
of the European honey buzzard Pernis apivorus in Sebezh Poozerie (pp. 1889-1893)
にミユビゲラの巣内ひなを捕食したヨーロッパハチクマの論文がある (写真あり)。ミユビゲラの営巣そのものがここでは大変珍しい。キツツキの巣穴から巣内ひなを捕食したヨーロッパハチクマのハンティング技術の多彩さがわかるとのこと (この場合は足を使ったのだろうか?)。
ヨーロッパハチクマが鳥をどの程度食べるかは地域差が大きく、レニングラード州ではほとんど鳥を食べていないがベラルーシのある地域では食物の 11.5% が鳥であった (Ivanovskij 2012) とのこと。
ハチの幼虫が主食というわけではないが、ハチクマに近い系統でハチの巣食の観察例がある:
Optland (2015) More on the Square-tailed Kite as Australia's honey-buzzard (ハチクマ類が事実上分布しない) オーストラリアのシラガトビ Lophoictinia isura (ハチクマよりやや小型)。
ツバメトビ Elanoides forficatus 英名 Swallow-tailed Kite の ハチの巣食の写真 (ハチクマと同程度の大きさ)。これらの場合は主にほぼ使い終わってハチの攻撃を受けにくい巣を捕食しているのかも知れない。
カラス類もたまにはハチの巣を食べることもあるらしい。American Crow feeding on a wasp nest
アメリカガラス Corvus brachyrhynchos の事例。
カンムリアリモズ Frederickena viridis のハチの巣食も報告されている: McCann et al. (2014) Black-throated Antshrike preys on nests of social paper wasps in central French Guiana。
猛禽類以外でキツツキ目のミツオシエ類 (Indicator 属) がハチの巣の蜜蝋を食べることが知られているが、ハチの幼虫や蜂蜜はほとんど食べない。溶けた蝋の匂いに集まってくることが知られていて (バークヘッド「鳥たちの驚異的な感覚世界」; Steiger の 1966 年の実験) 鳥類における嗅覚利用の一例となっている。
Friedmann (1955) The Honey-Guidesに詳しい生態解説などがあり、p. 82 と p. 83の間のプレートにはまるでハチクマのようにハチの巣に乗ったり食べたりしている写真がある。
「コンサイス鳥名前事典」には皮膚が特に厚くハチ防御に役立っていることや臭気があることが記されている。これは Friedmann (1955) "The Honey-Guides" pp. 87-88, p. 170 にも記載があるが、著者は臭気を確認できなかったとある。Chapin (1939) The birds of the Belgian Congo. Part 2 がかび臭い臭気について報告したもの。
ミツオシエ類にはハチ毒耐性はなく、皮膚による防御も完全でない。特に嘴の付け根 (lore) が狙われるそうで、ハチクマがこの部分を念入りに羽毛で覆っている理由にもなるだろう。鼻孔がスリット状になっている点もハチクマと共通した防御機構であろう。
なおミツオシエ類は托卵性で、習性など非常に変わった点が多い。
「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 156 によればハチの巣は希少な資源であり、インドミツオシエ (キゴシミツオシエ) Indicator xanthonotus Yellow-rumped Honeyguide ではオスがハチの巣を含むテリトリーを防衛し、ハチの巣に採食に来るメスと交尾するという。18 羽のメスと交尾した例が知られているとのこと (ミツオシエは托卵性でメスの行方はあまり心配する必要はない)。
"resource-based non-harem polygyny" と呼ばれる繁殖様式とのこと (Cronin and Sherman 1976 "A resource-based mating system: the orange-rumped honeyguide". Living Bird 15, 5-52)。
Feeney and Riehi (2019) Monogamy without parental care? Social and genetic mating systems of avian brood parasites に解説あり。托卵種のミカドスズメ Vidua regia Queen Whydah (こちらは水が資源) でも知られているとのこと。
ハチクマの臭気は記載している書物や飼育者の報告もあるがまだよくわかっていない。
ロシアの飼育者による記述は [(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の Ingrid の項目参照。
台湾のハチクマの巣のビデオ中継では雨の降った後の朝に、巣を守っていたメスがハチにまとわりつかれて睡眠不足になっている様子が記録されている。ハチクマの巣そのものにはハチ忌避の機能 (臭気) はないようである。
#エトロフウミスズメ備考の [鳥類の嗅覚] に Soares et al. (2024) Analytical characterization of volatiles present in the whole body odour of zebra finches の研究を紹介している。
これまでは尾脂腺抽出物、羽毛や皮膚のサンプルが揮発性化学物質の研究に主に用いられていたが、全身をサンプルするとそれ以外の物質も検出されるとのこと。ハチクマでも同様に全身サンプルすればあるいはハチが忌避する臭気物質が見つかるかも知れない (あるいは逆に見当たらない結果になるかも)。
Mridula (2020) Experience with an Oriental Honey Buzzard
家がハチクマのなわばりにあって、居ながらにしてハチの巣を襲う様子が記録できたとのことだが、怒ったハチがあらゆるものに猛攻撃をかけて飼っていた牛がたくさん刺されて死にかけたとのこと。
翌日はしっかり対策しておいたとのことで、近所の人には外に出ないようにと伝えた。
逆に捕食者対策にハチの巣近くに営巣する鳥もあるとのこと。ブラジルの研究 de Carvalho et al. (2023)
Nesting of birds associated with social wasps (Hymenoptera, Vespidae) in Brazilian Cerrado。
#カッコウ備考 [托卵鳥の同種認識] も参照。
南米のカザリドリ科 Cotingidae (スズメ目 Tyrannida に分類。ヤイロチョウの遠い親戚に当たる) がハチやアリと共同して肉食哺乳類から身を守っているとの説がある (コンサイス鳥名事典)。
中南米のヒメキヌバネドリ Trogon violaceus Guianan Trogon (3種に分離され、この名称は分離後のもの) は空中のスズメバチの巣を占拠して成虫スズメバチを食べ、残った巣を掘って空洞にして営巣するという [「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 169]。
Trogons Nest with Wasps (BirdNote 2022)。
Wasps' Nest Ideal Place for One Bird to Lay Its Eggs (BirdNote/Audubon 2013) すべてのハチを駆逐しないので捕食者が近づけないとのこと。
「動物の世界」2版 9 (日本メール・オーダー 1986) pp. 1244-1245 (浦本・斎藤) にも記述があり当時有名な話だったらしい。こちらでは熱帯産スズメバチの巣を横取りして成虫も幼虫も食べ自分の巣にする。ハチの針に対して免疫があるようとのこと。
キヌバネドリ目は Eucavitaves のクレードで洞営巣性。このクレードには他にサイチョウ目、ブッポウソウ目、キツツキ目が含まれる。ヒメキヌバネドリは全長 23-25 cm とそれほど大きな鳥でない。
「動物の世界」2版 5 (日本メール・オーダー 1986) pp. 664-665 (浦本・安部) のオウチュウの解説ではオウチュウ類はスズメバチ類を含む各種ハチ類が好物とのこと。ハチの針に刺されない秘訣があるらしいと記述されていた。ハチ類を食べる程度であればハチクイ類も食べているのでそこまで不思議ではないかも知れない。
[嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ]
ハチクマは採食に嗅覚も利用している可能性の実験的報告があり、嗅覚に関連する遺伝子数もイヌワシなどに比べて多い [Yang et al. (2015) Stop and Smell the Pollen: The Role of Olfaction and Vision of the Oriental Honey Buzzard in Identifying Food]。
この論文の実験では同じ色のものでは花粉を付けたものが有意に高く選ばれた。黄色の食物を好む結果も出ており、嗅覚と視覚を用いた採食を行っているのではとの結果である。栄養成分あるいは砂糖を入れたかどうかは差がなかったそうである。
なお花粉はハチの子への重要なタンパク質、脂質、ミネラルの供給源であり、ハチの巣の中でも蜜と別個に保管されるとのこと。栄養成分の豊富なにおいを弁別できるように進化してきた、あるいは学習した可能性があるとのこと。
まだあまり調べられている段階ではないが、タカ・ハヤブサ類の嗅覚の文献レビューが Potier (2020) Olfaction in raptors; 雑誌サイト。
にある。嗅覚遺伝子数はハヤブサとワキスジハヤブサで 63 とのことだが機能しているのは 28 個のみとのこと。ハチクマの嗅覚遺伝子数 283 で調べられた範囲の嗅覚遺伝子のうち 81.5% が機能しているのはやはり高い (ただし #エトロフウミスズメ備考の [鳥類の嗅覚] によれば必ずしもそうではない可能性がある)。
嗅覚の優れた動物はにおいを持つ傾向があることが指摘され、ハチクマに独特の体臭があっても不思議でないかも知れないが、実際に嗅いだ人の見解は分かれている。
嗅覚を用いて食物を探すことが確実に示されている新世界ハゲワシ類は脳の嗅球が大きいことがわかっているが遺伝子数は調べられていないようである。
Roeder et al. (2014) Chicks of the Great Spotted Cuckoo May Turn Brood Parasitism into Mutualism by Producing a Foul-Smelling Secretion that Repels Predators
によればマダラカンムリカッコウ Clamator glandarius 英名 Great Spotted Cuckoo はハシボソガラスに托卵するが、ひなが悪臭を放ち捕食者であるハヤブサ類などのカラスの天敵を追い払う効果があるとのこと。この結果托卵が相利共生となる珍しい例となっている
[#カッコウ備考でも紹介]。
実験によればこのにおいを付けた肉をハヤブサ類は食べないとのことだが、におい付けで食物の見かけが変わってしまう要因の考慮も必要とされるとのこと (実験的証拠が思ったほど得られていない点について #ヤツガシラの備考も参照)。
Slater and Hauber (2017) Olfactory enrichment and scent cue associative learning in captive birds of prey
によればハゲワシ類やワシ類で食物と関係のないにおい物質 (ペパーミント) と食べ物を関係づけて学習できることが示され、タカ類も嗅覚識別ができるらしいことを示している。
最も植物食の特殊な種類ではあるが、ヤシハゲワシが霊長類同様に果実のにおいを食物探しに使っている可能性が指摘されている [Dominy (2004) Fruits, Fingers, and Fermentation: The Sensory Cues Available to Foraging Primates]。
トビで尾脂腺分泌物の組成が季節変化し、スズメ目で同様に知られるような個体や血縁認識に役立っている可能性がある [Potier et al. (2018) Preen oil chemical composition encodes individuality, seasonal variation and kinship in black kites Milvus migrans]。
ヨーロッパハチクマの網膜細胞の研究から視力は他のタカ類同様に良いと考えられるが、正面視に適した側方窩 (lateral fovea または temporal fovea 側頭窩) は認めらない
[Mitkus et al. (2017) Specialized photoreceptor composition in the raptor fovea (PubMed Author manuscript)] (#イヌワシの備考も参照)。
これはハチクマが敏捷に移動する獲物 (小鳥など) を正面視で獲る必要は少ないが、ハチの動きや渡りの際などに遠方のタカ (広く分散して飛ぶことで他の個体の動きから上昇気流の場所を探る説がある。例えばケリンガー「鳥の渡りを調べてみたら」p. 202) を側方視で見つけるのに役立っていると思われる。この知見を前提に渡りの際に視線にも注意して観察すると興味深いと思われる。
捕食性鳥類の temporal fovea 側頭窩 = shallow fovea の役割について#シロハヤブサ備考 [シロハヤブサの獲物追跡] に考察を追記した。
渡りのタカではないが、ハゲワシ類を用いて他個体から上昇気流の位置を知る実験が行われている: Sassi et al. (2024) The use of social information in vulture flight decisions
飼育個体を放してトラッキングすると他個体の情報を観察して上昇気流に乗っている。飛行条件の悪い時は最初のチャンスはパスしたり、社会的順位の低い個体は他個体からの情報を無視する傾向があった。これは競争を避けるためと考えられるが、最初に来た電車やバスに乗るか、次のを待つか、まるで人間の行動を見ているような感じがする。
タカの渡りでも気付かれていないだけであるいは同じような現象があるかも知れない。
前述のようにカッコウハヤブサ類 (Aviceda 属) は現生種の中ではハチクマ類と比較的近い類縁関係にあり、ハトを思わせる顔つきなどがよく似ている。
カンムリカッコウハヤブサはオーストラリアのタカ類中相対的な眼球の大きさが最も大きいそうで、(それが理由かはともかく) 眼球が横向きに付いているとのこと。「待ち」の狩猟方法で樹冠の複雑な背景の中で獲物の動きに気づくのに有利との解釈もあるが網膜の構造などはまだ調べられていない
[Keirnan et al. (2022) #カタグロトビの備考参照]。
ハチクマは頭をハチの巣に突っ込むために頭骨の形が尖っていて眼球の向きが制約されるのかも知れない。
Rare Footage: Crested Honey Buzzard Brave Honey Raid | Intense Bee Battle! の映像を見ると飛翔時ペン先とも比喩される尖った細長い頭部を持つ意義がよくわかる。羽が非常に傷んだハチクマをしばしば見るが、この姿勢で頑張っていれば羽が傷むのもわかる。頭にハチがまとわりつくのか、猛烈な勢いで頭かきも行っている。
Pernis apivorus (Honey Buzzard) (Skullsite) にヨーロッパハチクマの頭骨があるが、他のタカと比べると細長い形状が目立っている。
ハチクマの頭骨の特徴や目の位置などについての議論は Sievwright and Higuchi (2011) Morphometric Analysis of the Unusual Feeding Morphology of Oriental Honey Buzzards
にあるが視野の実測値や眼球の大きさへの言及はない。
カッコウハヤブサ類は学名が示す通り鳥も捕食するため、眼球が比較的側面に付いていることは動く動物の捕食行動に必ずしも不利になっていないかも知れない。
その後鳥類の眼球と脳サイズの一覧を見つけた (#イヌワシの備考の [鳥類の眼球と脳サイズのデータ] 参照)。
これによるとカッコウハヤブサ類は体重 194-323 g と小さいのに眼軸長 21-23 mm と際立って大きい。
(当時はハチクマと同種だったが、おそらく現在の分類では) ヨーロッパハチクマでは 754 g, 21.5 mm と中型のタカの標準的な値で眼球が大きいわけではない。目の配置は頭骨の形による制約なのだろう。
ハチクマは他のタカ類に比べて頭が小さい特徴がよく挙げられるが、脳も小さいのか妙に気になってくる (笑)。この表を見ると (分離された後の種名ではおそらく) ヨーロッパノスリの体重 759 g、眼球 20.8 mm、脳ともに同じような数字で、全然体型が違うのに頭骨が細長いだけで心配 (?) 無用だったようである。
オオタカはこの2種より少し大きめだがほぼ似た値になっている。ハヤブサもだいたい同じような数字。
このぐらいの中型のタカでは脳は体重の 1% 程度となる。体重や脳の構造も全然違うので無茶な比較であるが、ヒトの脳は 1.2-1.4 kg とされ体重の 2% ぐらい。体重比ではタカの脳はヒトの2倍しか違わない。100 kg 近い体重の方はそれで割ってみていただきたい
(さらに鳥類の脳は哺乳類に比べて細胞が小さいなどの理由で哺乳類に比べて小型の脳で同等の機能を持つと言われる。もっともヒトの場合脳重量で知能が決まるとは通常は考えられていないので、重量はあくまで荒い指標に過ぎない)。
眼の発達した鳥類では眼と脳がほぼ同等の量の血液供給を受けているらしいので、ヒトで言われるように大食いの脳 (+ 鳥類ではさらに眼) を養うのはなかなか大変であることがわかる。頸動脈の比較については #フクロウの備考の [フクロウ類の首の動き] にある。
トビとアカトビの体重が結構違うが、トビの体重はここまで挙げた中型のタカと同じぐらいで眼球もほぼ同じ、体の割に脳がちょっと小さめ。
日本のハチクマはヨーロッパハチクマより一回り大きいはずなのでこれら中型のタカを少し超える程度だろう。
面白いので皆さんも見ていただければと思う (ここで学名で読める重要さがわかる)。
このデータを使って気になるタカ類の脳サイズを作図してみた。後述の Sayol et al. (2017) のデータも知ったので追加改訂してある。
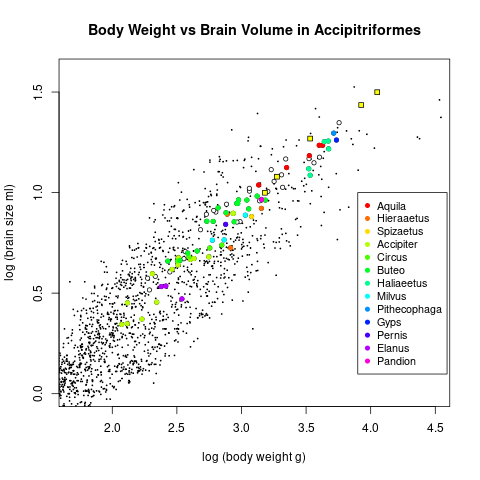
縦軸・横軸ともに対数スケールである。タカ目全体では脳の容積は体重の 0.54 乗 に比例する結果となった。詳細は一部属のみ示すがタカ目全体は白抜きの丸、それ以外は黒い点で示してある。
タカ目は鳥類中では体重比では中ほどか少し高めに位置する。
系統が近い分類が似た色となるようにしているが思ったほどの違いはなかった。
海ワシとトビのグループは陸のグループより若干低いように見える。
猛禽類としては "原始的" と言われるグループも脳の大きさにはあまり違いがない。あれほど体型が違うのに旧世界ハゲワシもフィリピンワシ、イヌワシはほぼ同じ。ヨーロッパハチクマも中ほどに位置していてハチクマ亜科の他の種類 (図では分けて示していないが白抜きの丸になる) も脳の大きさは他のタカ類とほぼ違いがない。
ヘビクイワシも測定されているが (青の四角)、あれだけ体型が違うのに他とあまり違いがない。
唯一カタグロトビ類だけは体重が小さいにもかかわらず脳が相対的に小さめ (別科にする見解もあるので他のタカ科と違っていても不思議ではないが)。系統の分かれるミサゴも他のタカ同等だった。
黄色の四角は新世界ハゲワシ (コンドル) で、こちらの方が脳が相対的に小さそうな印象を受けるが実はそうではなかった。小型種はタカ科と同じぐらい、大型種はむしろ上になるぐらいで、10 kg 近い大型の鳥の中で最も大きな脳を持つ結果となった。つまり頭脳の面では巨大なニワトリのような鳥ではなかった。
ハチクマも大きなハトのような鳥 (笑) ではなかった。
ちなみにこのリスト [Liu et al. (2023) + Sayol et al. (2017)] に載っている鳥を脳の容積 (ml) 順にいくつか並べると (かっこ内は体重 g)、* を付けた種類は Sayol et al. (2017) から。
ダチョウ 40.23 (111000)、
ヒクイドリ 36.35 (44000)、
オオハゲコウ* 33.52 (7458)、
コンドル 31.56 (11236)、
エミュー 28.88 (34093)、
カリフォルニアコンドル 27.25 (8443)、
ミナミジサイチョウ 26.15 (3744)、
スミレコンゴウインコ 24.73 (1331)
のようになる。体重比ではもちろんオウム類が大きいが、飛べない鳥を除けばオオハゲコウに続き大型コンドル類が最も大きな脳を持っている。これらの調査では調べられていないがトキイロコンドルが上位に入るのではないだろうか。
この図をさらによく見るとコンドル類を除いたタカ目では体重 1 kg ぐらいまでは傾きが急であるが、それ以上の体重では傾きが緩やかになり、少し段差 (頭打ち?) があるように見える。
この現象はより頭脳の大きなオウム類でははっきりせず (#ハヤブサの備考 [タカ目、ハヤブサ目、オウム目の脳の比較] 参照)、
タカ目、ハヤブサ目に見られる特徴のようである (ハヤブサ目にはそれほど大型種はいないが)。
タカ目については多少思い当たる点があり、大型種を生み出した系統が2系統 (イヌワシ・クマタカ類 Aquila + Hieraaetus + Spizaetus および海ワシ類 Haliaeetus) に偏っているため全体として見ると系統間の違いが効くのかも知れない。
体重による制約 (例えば飛翔筋に投資する必要があるなど) もあるかも知れないがコンドル類にあまり制約が見えないのでどうであろうか。
この調査ではもしかしたらハチクマの脳は小さいのではとの素朴な疑問からタカ類の中での脳サイズの違いがあるかマニアック (?) な点にこだわったものだが、
鳥類全体での脳のサイズの研究は過去にもよく行われていて、Marugan-Lobon et al. (2021) Beyond the beak: Brain size and allometry in avian craniofacial evolution
など。この著者は脳化 (encephalization) の進んだグループにフクロウ類、タカ類、オウム類、カラス類を挙げて脳化の進んでいないハト類やシギ類と比較している。導入部分にスズメ目や猛禽類には霊長類に匹敵する性質を示すものがあると書いている。
Ksepka et al. (2020) Tempo and Pattern of Avian Brain Size Evolution
にも鳥類の脳のサイズの系統進化の研究がある。古いタイプの水鳥からカッコウなどの含まれるグループに一段めの進化があり、近代的な陸鳥の段階でさらに一段の脳の進化があった結果になっている。
この論文でも猛禽類 (全グループ含めて) の脳の容積は体重の 0.5 乗強程度の値を得ていて (ここで示したものと関連する図も出ているので比べていただきたい)、肉食の哺乳類にも同じような関係があるとのこと。好みの獲物が関係に関連している可能性を示唆している。
カラスが猛禽類によくつきまとうが、脳のサイズの関係はどうなっているのか調べてみた。昼行性猛禽類の日本産種または近いものを系統順に並べてみた。(Sayol) は Sayol et al. (2017) から。
| 種 | 脳重 (g) | 体重 (g) |
| ニワトリ (参考) | 3.53 | 751.72 |
| カワラバト (参考) | 2.04 | 354.20 |
| ミサゴ (Sayol) | 9.24 | 1432.25 |
| ヨーロッパハチクマ | 6.95 | 754.37 |
| アカエリクマタカ | 7.60 | 1197.40 |
| アフリカソウゲンワシ | 13.31 | 2236.06 |
| イヌワシ | 17.19 | 4247.97 |
| タカサゴダカ | 2.83 | 131.15 |
| ハイタカ | 2.85 | 220.79 |
| オオタカ | 7.88 | 866.04 |
| ハイイロチュウヒ | 4.78 | 392.98 |
| ヨーロッパチュウヒ | 5.48 | 704.07 |
| トビ | 5.82 | 734.10 |
| トビ (Sayol) | 5.80 | 595.26 |
| アカトビ | 7.72 | 1071.77 |
| オジロワシ | 16.50 | 4729.27 |
| ハクトウワシ | 18.04 | 4700.58 |
| メジロサシバ | 4.73 | 325.00 |
| ケアシノスリ | 9.20 | 949.76 |
| ヨーロッパノスリ | 7.94 | 759.10 |
| ヒメチョウゲンボウ | 2.71 | 152.06 |
| チョウゲンボウ | 3.87 | 183.21 |
| チゴハヤブサ | 3.59 | 208.17 |
| ハヤブサ | 6.19 | 759.95 |
| シロハヤブサ | 9.43 | 1431.72 |
| カケス | 3.91 | 159.46 |
| ハシボソガラス | 8.51 | 570.00 |
| ハシボソガラス (Sayol) | 8.10 | 536.46 |
| ハシブトガラス | 12.66 | 513.14 |
| ワタリガラス | 14.45 | 927.97 |
脳重の測定値は骨を使えるのでかなり正確らしいが、体重は文献値や個体の栄養状態、性差などでかなり怪しいものも含まれているだろう。あまり納得できない体重 (例えばハシブトガラスの方がハシボソガラスよりと軽いのは不思議) も含まれているので目安的に見ていただきたい。
このように見ると小型から中型のタカ類はそもそも体重面で Corvus 属のカラス類に及ばず、カラス類より劣っていてもやむを得ないかも知れない。ツミの分布がカラスの影響を受けるのもこれほどの体格差があれば仕方ないだろう。
ハシボソガラスでは中型のタカ類の脳重が匹敵するぐらい。
中型以上の猛禽類だと脳重でも大型カラス類と結構よい勝負になっている感じがする。みかけのサイズの割にはトビが妙に軽いのだが、アカトビでも体重比が小さいので海ワシ類も含めてこの系統は脳が少し軽いよう (Sayol のトビはずいぶん体重が小さいが)。クマタカ類は1種しか測定値がないので傾向がはっきりしないが、体重の割には脳重がやや小さい印象を受ける。
日本のクマタカはもっと大きいのでカラス類よりもきっと上になるだろう。
イヌワシは海外亜種なので日本のものを考える時は少し割り引いていただくとよいだろう。ハチクマはヨーロッパハチクマの2-3割増しぐらいと考えればなかなかよい線を行っている。少なくともトビよりは知恵がありそう。ハヤブサ目は体重が軽めなので脳重では大型のカラスには及ばないよう。
猛禽類とカラス類のいずれが優位かは脳重がかなりよく近似している感じがする。
カラス類の研究者はニワトリやカモなどと比較してカラスの脳の立派さをよく語るが、猛禽類相手だとそこまで差が顕著でないかも。
上記の表ではハシブトガラスの体重が小さいので特別に脳化が進んでいるように感じてしまうが、ハシボソガラスを比較に用いるとそれほどでもない。
Chiappe et al. (2022) Fossil basicranium clarifies the origin of the avian central nervous system and inner ear
の比較研究があり、ニワトリとタカの間で脳の向きや内耳の前庭器官の再配置が起きているという。論文の趣旨に沿っているかどうかは不明だが、図を見ると猛禽類が直立姿勢に近いのは脳の向きの変化を反映しているよう。
この論文ではタカでは拡大した脳 (視覚関連部位) に圧迫されて前庭器官の形が変わっている解釈に基づく図が出ているが、Benson et al. (2017) Comparative analysis of vestibular ecomorphology in birds
にも鳥類各種の比較図があってウズラでも曲がっているのでこの解釈はちょっと怪しい気がする。こちらの論文の比較で載せられている中で一番大きく曲がっているのはイソシギ。系統的には近いはずのヤマシギとも形が異なる。
哺乳類では Grunstra et al. (2024) Convergent evolution in Afrotheria and non-afrotherians demonstrates high evolvability of the mammalian inner ear
が前庭器官の形は哺乳類の方が多様性があり、選択圧による適応進化の結果と導いているがどうだろうか。
コンドル、旧世界ハゲワシ類が想像以上に大きな脳を持っていることは、van Overveld et al. (2022) Vultures as an overlooked model in cognitive ecology
でも注目されていて、これらのグループの採食様式には知能が必要で、集団知能などが要求されるなどの可能性も検討されている。新世界・旧世界ともにハゲワシ類の知的な行動 (道具使用やさまざまな逸話なども記述されている) や認知機能をもっとよく知る必要があることが述べられている
(これらは #クロハゲワシの備考に紹介)。
鳥類各グループごとの脳のサイズの図も出ているのでご覧いただきたい。
Ellison et al. (2015) Testing problem solving in turkey vultures (Cathartes aura) using the string-pulling test
がヒメコンドルを使い、紐を引き上げて食物を得る課題を実験している。6羽のうち2羽は見ただけで解いた、1羽は他の鳥の行動を見て問題を解いたとのこと。紐を引く時はカラスやオウムは足で押さえるが、ヒメコンドルでは生態的に足を使うのは得意でないらしく、舌を上手に使っておそらくそのうに紐を格納し、カラスやオウムと異なる問題解決を行ったとのこと。
モモアカノスリの実験もある: Colbert-White et al. (2013)
String-pulling behaviour in a Harris’s Hawk Parabuteo unicinctus
こちらは1羽だけの実験だが新しいものに興味を示し、攻撃的な態度もとったとのこと。複数回の試行でオウムやカラスのように餌の獲得に成功したとのこと。
なお Lamarre and Wilson (2021) Waterbird solves the string-pull test
オビハシカモメ (クロワカモメ) が水鳥で初の同様の実験 (水平の紐を引く) の成功例を紹介している。ワシカモメで過去に実験されたことがあったが問題解決には至らなかったとのこと。水鳥は認知能力が低いと考えられ、実験もあまり行われて来なかった。
この文献には過去の他種の実験も紹介されているので参考になるだろう。ワタリガラスでも成功率は思ったより低い (26%)。バルバドスアカウソ Loxigilla barbadensis Barbados Bullfinch の問題解説率が意外に高く (43%)、42 羽のうち2羽は1回の試行で成功したという。
Brainy Birds Know How to Reel in Food With String (解説とバルバドスアカウソの動画あり)。
コクロムクドリモドキ Quiscalus lugubris Carib Grackle 31 羽のうち1羽も1回の試行で成功したとのこと。オビハシカモメでは1回での成功率が 21% と成功率の高い種に匹敵するという。
ただしオビハシカモメでは成功の再現性が高くなく、同じ設定で成功しない個体も多いとのこと。再現性が高い個体は理解して行っているのか、低い個体は偶然引いただけなのかはさらに検討が必要とのこと。
問題解決のできたヒメコンドルでは学習効果も現れ、レベルはもう少し高そうな記述になっている。
Garcia-Pelegrin (2025) Causal affordances shape Hornbills' problem-solving strategies (preprint)
キタカササギサイチョウ Anthracoceros albirostris Oriental Pied Hornbill では紐を引き上げる実験の成功率が高く、短時間で洞察で解いているらしい。足の構造が紐を押さえるのに向いておらず、嘴と舌を使って実現したとのこと (ヒメコンドルの例に似ている)。
過去に調べられていなかった分類群でも問題解決の能力が高いことを示す。
サイチョウ類と同じ目ではないが同じ Eucavitaves に属するオオオニハシ Ramphastos toco Toco Toucan の認知能力の高さが北條 (2023) Birder 37(4): 46-47 で紹介されている。
このように見ると Telluraves のすべての系統で認知能力を進化させた種類があるらしいことがわかる。
コンドル、旧世界ハゲワシ類の知能はもしかすると飼育者の方がよく知っているかも知れない。「猛禽類の医・食・住」(パンク町田 どうぶつ出版 2003) pp. 130-131 によればコンドル、旧世界ハゲワシ類は少し距離感のある犬のように慣れるという。犬は家畜化のために選抜されたものであることを考えると野生種がそこまで慣れるのはかなり驚異的ではないだろうか。
過度な擬人化に注意とのことで、一緒に風呂に入る (鳥と風呂に入ることはまったく想像もしなかった!)、撫ですぎる、寝る時に布団をかけるなどは鳥に負担をかけることになると忠告されている。人の子でも犬でもない。ここまで擬人化可能な鳥のよう。鳥かごでなく外で布団をかけるのは自分もインコでやったことがあるが (笑)、期待に応えるためか? 寝たような姿は見せてもそのまま寝ないので大丈夫だった。
またビスケットやどら焼きのような甘いものを大量に与えるのはよくないとのこと。そんなものを喜んで食べるとは甘い物好きなのか。#メジロ備考の [鳥類の味覚] に肉食の鳥 (ハヤブサ類やフクロウ類も) も一般的に甘い液体を受け入れる (Niknafs et al. 2023) とあるように、肉食の鳥は案外甘さに感度があってハチクマが甘い物好きに進化しても特別驚きではないかも知れない。
肉も好き、甘い物も好き、というわけだが...これはファーストフードで好まれる味付けそのものでは (?)。味覚は案外我々の好みに近いのかも。
ペットの猛禽類が好むからと甘い物を大量に与えているときっとメタボリックシンドロームなどを引き起こすのだろう...おそらく報告されている症例の一部は該当するのでは。
ニワトリの甘みへの感度が低かったことや、キジ目の鳥で植物毒への味覚の方がより重要だろうことに伴う鳥類全体への過小評価、味覚は我々のものを基準に考えがちで鳥には甘み知覚がないと考えられがちだったが、鳥では {旨味から甘み} が混ざった形で快く感じていて甘い方に好み (感度) をシフトさせる選択圧は簡単に働くのかも知れない。
こんな映像があった (インドネシア): caring for eagles from chicks until they fly into the wild (LINTANG TV9)
種類が書かれていないがウオクイワシ (?) 鳥と風呂に入るとはこのようなことを指すのかと納得 (一緒に水浴びしている)。抱き合っても大丈夫のよう。一緒に寝そべったりしている。若いうちはかかとまでつけて歩いているなど行動面も面白い。
かつて見つけたイヌワシの実験映像を発掘した: Gifts of an Eagle - Testing Lady's Intelligence (Durden Films 2012)。
改めてこの映像を見ると結構成功しているようだが (4分で解いたとのこと。初見で解いたならば結構優秀かも) 完全に引っ張ればよいことまではすぐに洞察できていない印象を受ける。このような行動が想定されていない動物で驚くべきだとのこと。
後半の方の実験はどの容器に隠した肉かを1時間後に覚えているかを調べたもの。どれかはすぐわかったようだが容器をひっくり返すのはあまり得意でないようで少し手間取っている。
しかし何と言っても 50 年前 (!) の実験。当時のアメリカ車もいかにも時代物。
"Gifts of an Eagle" Kent Durden 著作 (1972)。Gifts of an Eagle (ウエブサイト)。訳本「ワシと人間の季節」(ケント・ダーデン著 ; 佐藤高子訳 日本リーダーズダイジェスト社編集部 講談社 1981)。昔はよく置かれていた懐かしい本。
鳥類の目レベルの脳のサイズの違いでは、Sayol et al. (2017) Environmental variation and the evolution of large brains in birds
の fig. 4 が最もわかりやすいかも知れない (論文の趣旨とは無関係に見ているが)。系統順序は我々の見慣れているものと違うが目名とシルエットが描かれているので見やすいと思う。
ちなみにこの円形系統樹は3時の方向から半時計回りに系統が進み、1周して3時の方向で終わる。
黒い線で表されている長さが相対的な脳の発達程度を表す。
やはり近代的な陸鳥が生まれたところで格段の飛躍がある。
タカ目 (一般の配列順でなく後の順序になっている) とハヤブサ目は分けてあるが、ハヤブサ目がチドリ目、ネズミドリ目の後に並ぶ配置になっていて若干わかりにくい。その次に並ぶオウム目は高い種類があるが平均的にはハヤブサ目の間に著明な段差が生まれていないのは興味深い。
スズメ目になってもカラス類以外はそれほど脳が大きくないものが大半らしいことがわかる (カラス類以外にも少しピークがあるがシルエットが描かれていないので何かはすぐにわからない)。スズメ目は音声学習を行うように脳の能力が高そうに思えるが、全体としてはそれほど脳を発達させたグループでないことがわかる。
タカ目とフクロウ目の比較ではフクロウ目の方が少し高いが科内のばらつきも見るとタカ目も十分高い。フクロウ類と共通祖先があるキツツキ目、ブッポウソウ目などでむしろ小さいのが面白い。
Marugan-Lobon et al. (2021) の述べるように、猛禽3系統 + オウム目 + カラス類 が脳を特に進化させたグループと捉えておおよそ間違っていないように思える。つまりカラス類とスズメ目の他の種を比較してカラス類のみが鳥類の中で特別とするのはカラス類の過大評価につながる恐れがある。
猛禽類の中でカラス類やオウム目に相当する行動を見出しても神経科学的には驚くに値しないであろう。知的な行動記録があればぜひ残して発表していただきたい。
爪を隠すことはできないが「能ある鷹」は本当だった (*1)。
鳥類全体では脳が相対的に大きいほど種分化速度が大きい傾向があるという。Sayol et al. (2019) Larger brains spur species diversification in birds
モデル計算によれば、脳が相対的に大きいほど絶滅確率が下がる効果よりも種分化速度そのものが早まる効果の方が効いているらしいとのこと。
Eliason et al. (2021) Accelerated Brain Shape Evolution Is Associated with Rapid Diversification in an Avian Radiation もカワセミ類を研究して脳が相対的に大きいほど新しいニッチの開拓能力が高い仮説を提唱。
Sayol et al. (2017) の論文で用いられている系統樹の系統順では ネズミドリ目、{ハヤブサ目 + オウム目 + スズメ目} 系統、{フクロウ目 + キツツキ目 + ブッポウソウ目など} 系統 [この系統が2つに分かれるために Prum et al. (2015) とは違ってフクロウ目の方が後になる]、タカ目 となっていて、何とタカ目が一番最後に出てくる (#ミサゴの備考 [近代的な陸鳥の進化] も参照)。
昔の図鑑でハヤブサ類も含んだワシタカ目がカモ類の次で、比較的原始的なタイプの鳥と考えられていたのは大違いである (ちなみにロシアの図鑑では今でもその順序になっている)。
系統樹は Bird Tree project [Jetz et al. (2012) The global diversity of birds in space and time; 2014 年に改訂 cf. Jetz et al. (2014)
Global Distribution and Conservation of Evolutionary Distinctness in Birds] を用いてこの論文で調べた種をもとに作成されたもの。ベースとなる系統樹は Ericson または Hackett (#ミサゴの備考 [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] にあるそれぞれの文献) に準拠した約 10000 種を含むものとなっている (*2)。
著者 (監督?) にはバードウォッチングも鳥の脳も大好きな神経生理学者 Iwaniuk が入っているので神経生理学者の目からみても不自然なところのない系統ということだろう。
系統樹の解釈の方法次第だろうが、タカファンにとっては大喜びの系統順となっている - というのは一般的には図鑑などの並び順はより進化した (より後に分岐した) ものが後に出てくるため。スズメ目グループが最後にならないと印象がまったく異なる。昔はカラス類が最後になっていたのも、スズメ目内の系統もよくわからなかったので最も進化したものと見られていたのだろう。
タカ目を最後にする図鑑をもし作ったとすれば、何と日本のノスリが光栄にも世界の鳥のリストの最後を飾ることすら考えられる (#ノスリの備考参照)。
必ずしも IOC などの標準分類順準拠でなくタカファン向けにこんな図鑑があってもよいかも知れない。オーダーメイド図鑑もオンデマンド出版ならばできるかも知れない [文一あたりがマニア心をくすぐる図鑑として作ってくれないだろうか (笑)]。
ハヤブサ目を最後にしたくてもその場合はスズメ目が最後になるので夢は叶わない。フクロウ目はこの図を見ると最後に置くこともできるようである。猛禽類の中ではタカ (あるいはフクロウも?) ファンのみが見られる夢の図鑑である。
系統順序の解釈のわずかな違いによるものだが、スズメ目グループが最後になる分類や系統樹を見慣れ過ぎて先入観にもつながっているかも知れないので、そうでないものも見ておくとよいだろう。この順序は現在でも研究者の間で意見が一致しているわけではないので違ったものがあっても別に悪くない。
この研究でも用いられたデータをダウンロードできて個々の種の値を見ることができる。Liu et al. (2023) Evolution of Avian Eye Size Is Associated with Habitat Openness, Food Type and Brain Size
(#イヌワシの備考 [鳥類の眼球と脳サイズのデータ] の項目参照) と種の構成は違っているが日本周辺のデータがない点は共通している。ミサゴは Sayol et al. (2017) には入っている。
スズメ目でも Turdus 属のツグミ類に比べて Muscicapa 属のヒタキ類や Phylloscopus 属のムシクイ類は脳が小さいことがわかる (いずれも日本周辺の種ではないので注意は必要だが)。
Kaplan (2020) Play behaviour, not tool using, relates to brain mass in a sample of birds
はオーストラリアの種のみだが行動と脳の大きさの関連を調べたもの。社会的な「遊び」を行うこととの脳の大きさに相関があるが、道具使用とはそれほど関係なかったとのこと。
一般向け解説 Birds that play with others have the biggest brains - and the same may go for humans
(Kaplan, The Conversation 2021)。この記事によるとトビの道具使用は火のついた枝を運ぶ行為が挙げられている (#トビの備考 [火を使う猛禽類、森林火災、気候変動] 参照)。
気になるところでタカ類の情報を見てみると、遊びを行う種類にトビ、行わない種類にハイイロオオタカ、オナガイヌワシ、道具を使う種類にトビ、オナガイヌワシ、(カンムリ)ミサゴ、使わない種類にハイイロオオタカ (ただし Tachyspiza 属) を挙げている。行動が目撃や記録されたかどうか次第のような気もするが、広義ハイタカ属は確かにあまりこのような行動は行わないかも知れない。
Griesser et al. (2023) Parental provisioning drives brain size in birds
が脳のサイズと子育ての相関を調べていて、早成性 (半早成性を含む) ではクラッチサイズが大きくなるほど相対的な脳のサイズが小さくなる傾向があるが、晩成性 (半晩成性を含む) では逆の傾向があるが弱い。晩成性では餌運びの頻度が高いほど脳のサイズが大きい傾向があるとのこと。
表示されている系統樹 (ただし用いられたツールの関係で最新のものではなくヨタカ類がフクロウの隣になっているので見方に注意) との関係を見ながら結果を見るとなかなか面白い。ヨタカ類は半早成性とは知らなかったのだが、現代の分類で Strisores に属するもの (系統樹で別の場所に分割して現れる) は近い系統に比べて脳のサイズが明瞭に小さい。
同じ傾向がノガン類にも現れている。今では Otidimorphae としてまとめられるカッコウ類、エボシドリ類はこれまた分離して配置されているが、これらは平均的な脳のサイズ。托卵性カッコウ類は晩成性に分類せざるを得ないが子育てはしないので一緒に相関をとってしまうとちょっとまずい気もするが...。
カッコウのクラッチサイズは9が採用されている。1繁殖シーズン全体の値を用いているのかと思ったが他の種はそうではなさそう。
早成性の種類では多くの場合脳のサイズが小さいことはかなりよく現れていて、Elementaves に含まれる水鳥では系統が近い間でも傾向が顕著に出ている (カモ類はもっと古い系統でいずれも低い)。
晩成性が最初に現れたハト類は晩成性にもかかわらず脳のサイズが小さい。
このように見ると近代的な陸鳥のグループの Telluraves で脳のサイズが増加したのは、Telluraves の祖先系統が捕食者で (あったとすれば) 子育てに手間がかかり脳の進化が必然の結果だったのかも知れない。そこで獲得した能力がその後のオウム類やカラス類に引き継がれているのかも (ほんとうか?)。
面白いことに Telluraves の系統でも (猛禽類以外の) 樹洞営巣系統となった Cavitaves (ブッポウソウ類の系統) やスズメ目のカラス類 (カラス小目 Corvida に含まれる) 以降の系統には脳を発達させた系統が特にない。音声学習は脳をそれほど要求しないのか。
キツツキ類は衝撃の関係で脳が相対的に小さい方が有利かと思ったが Cavitaves 全体が脳を発達させていないので適応よりは系統を反映しているのかも。しかし飛び込むカワセミ類がこの系統から進化したことも関係があるかも (#カワセミ備考の [飛び込むカワセミ類の収斂進化] 参照)。脳の大きいグループではキツツキ類やカワセミ類のような系統は進化しにくかったのかも。
スズメ目でもカラス小目以前の早めの系統では散発的に脳のサイズが大きいグループがあるが後半の系統には見られない。古めの系統でも脳力があるものが選択的に生き残った (?)。もっとも後半の系統には新世界で適応放散したホオジロ類が含まれるので既存の競争相手があまりなかったためかも知れない。
似た傾向はタカ類でも少し感じられる。早めの系統と最後のノスリ系統が比較的高めだが途中のグループ (海ワシなど) がそれほど高くない。
オウム類も系統が進むと脳のサイズが小さくなる傾向がある。Telluraves 以前では見られない傾向なので何か意味があるのだろうか。後の系統ほど脳が進化しているのはカラス小目だけのよう。
脳のサイズのデータが公開され、系統関係もわかるようになってくるといろいろな性質と脳のサイズの相関関係の研究がたくさん出るようになっている。あくまで相関なので因果関係があるかは自明でない。
Chen et al. (2021) Large brain size is associated with low extra‐pair paternity across bird species 脳の大きい鳥ほどつがい外交尾率が低い。このグループはこの路線で考えているよう。
Hooper et al. (2022) Problems with using comparative analyses of avian brain size to test hypotheses of cognitive evolution これらの脳のサイズとの相関を調べる最近流行の手法に問題点を指摘している論文も多い。
Smeele (2022) Using relative brain size as predictor variable: Serious pitfalls and solutions 体重比の相対的な脳重を用いて議論している研究が多いがこの選択は必ずしも自明でなく、脳重そのものを用いても議論できるはず。
皆が同じパッケージを用いて解析しているので相対的な脳重が標準的方法のように見られがちだが両方を用いて議論している研究もある。我々も結果を見る時は注意した方がよさそう。
前述の猛禽類とカラス類の脳重比較もこの点も意識した形になっている。
こちらはキジ目の脳が後の系統の鳥類より構造的に劣っているかを調べたもの: Kocourek et al. (2025) Cellular scaling rules for brains of the galliform birds (Aves, Galliformes) compared to those of songbirds and parrots: Distantly related avian lineages have starkly different neuronal cerebrotypes
同じ重量あたりのニューロン数ではキジ目の脳はオウム類やスズメ目の半分程度だったとのこと。キジ目の脳は終脳のニューロンの比率が低く小脳の比率が高い点でむしろ霊長類でない通常の哺乳類の構成に似ていること。
キジ目では同じサイズの脳でも前脳のニューロン数はオウム類やスズメ目よりずっと少なく、認知能力の制約要因となっていると考えられる。セキショクヤケイはヨーロッパシジュウカラの 50 倍の体重だが脳のニューロン数はほぼ同じとのこと。
一方で霊長類以外の哺乳類のニューロン数と同程度なのでキジ目でも多くの哺乳類に匹敵する認知能力を持っていても不思議でないとのこと。
小脳がどの程度認知に役立っているかは不明な部分が多いが medial spiriform nucleus は知的な鳥でよく発達していて小脳と外套を結んでいる。しかし最も知的なグループは終脳を発達させているので鳥類では終脳が知能に関係が深いのではとのこと。
頭脳の面では鳥類の中であまり発達していない系統が哺乳類一般に近いらしい。
オウム類では脳サイズと寿命の相関が調べられている (動物園個体が多いのでデータが十分ある): Smeele et al. (2022) Coevolution of relative brain size and life expectancy in parrots
cognitive buffer hypothesis (脳の予備力が大きいほど環境変化に適応できて長命である)、expensive brain hypothesis (発達期間が長いほど脳も大きくなり長命である) の仮説がよく知られている。この研究からは前者の仮説の方が結果をよく説明できるとのこと。
哺乳類、特に霊長類では後者の仮説を支持する結果が出されているが、鳥類では父親やヘルパーも育児に参加する種類が多く発達期間を短縮できる効果があるのではとの解釈もあるとのこと。ここではオウム類がほぼ洞営巣性で、捕食に対して open-cup nesters (おわん型の巣を造る鳥) より安全であるため巣立ちまでの期間を短縮する必要が小さくて済むなどの要因も考察されている (洞営巣性ならではの捕食危険性もあるような気もするが...。詳しくは引用文献参照)。
この分野は鳥類の方がよく調べられているようで Kilili et al. (2025) Maximum lifespan and brain size in mammals are associated with gene family size expansion related to immune system functions の研究が最近出た。哺乳類では免疫関連遺伝子族の拡大と寿命や脳サイズの関連がある。
鳥類では免疫関連遺伝子を減らす傾向があるのでもしかすると相関が逆になるかも?
長い寄り道をしたがハチクマの目の話に戻ると、ハチクマをごく近く (動物園個体) で観察すると瞳孔が目の中央でなく前方に寄っていることがわかる。これは眼球が他のタカ類よりも側面に付いているが (斜め) 前方視野を重視していることを意味すると思われ、眼球の位置の違いを瞳孔の方向の違い (眼軸の方向) で補っている部分があるのだろう。
ハチクマの眼球を野外でこれほど詳しく観察することは難しいと思われるが、サギ類でも同様の瞳孔の配置を観察することができるので注意して見ていただきたい。サギ類でも採食手法への適応から頭部が尖った形状になっていると考えられるので、正確な捕食に欠かせない前方視のために瞳孔の方向の違い (眼軸の方向) で補っているのだろう。
瞳孔のよく見える他のタカ類でも同様の非対称性が見られることがある。
ハチクマが歩く時もハトに似た印象を受けるがハトのように首は振らず、視線の向きが違うのだろう。
Murphy et al. (1995) Raptors lack lower-field myopia
という研究もあって、ニワトリ、ハト、ウズラなどは他のことを行いながら近くの地面に焦点を合わせる (近視になる) ことができるが、ここで調べられた猛禽類 (メンフクロウ、アレチノスリ、アメリカチョウゲンボウ) はでは地面に焦点を合わせる目の調節は見られなかったとのこと。地上で食物を探す種類に発達している能力ではないかとのこと。
Gutierrez-Ibanez et al. (2012) Functional Implications of Species Differences in the Size and Morphology of the Isthmo Optic Nucleus (ION) in Birds によれば脳の isthmo-optic nucleus (ION) の発達している鳥がこの能力を持つことを示唆している。従来は他の機能が考えられていた。
ハト類、キジ類、嘴で探索を行わないシギ類、クイナ類、キツツキ類など系統的にあまり関係のない種類で発達し、スズメ目でも多様性があるが発達している。ペリカンや海鳥ではまったく見られない。猛禽類でも昼行性・夜行性とも発達していないがおそらくこれらの鳥は主に遠くを見ているのでは。
我々が身近に歩いているのを見るのは前半の種類が多く、ハト類やキジ類でこの核が特によく発達しているため鳥は首を振って歩く印象を受けがちなのかも知れない。
Wylie et al. (2015) Integrating brain, behavior, and phylogeny to understand the evolution of sensory systems in birds にもこの仮説も含めたレビューがある。なお Wulst の大きさは両眼視、おそらく立体視と相関がある多くの証拠があるとのこと
[Iwaniuk and Wylie (2006) The evolution of stereopsis and the Wulst in caprimulgiform birds: a comparative analysis だがフクロウ類とヨタカ類に類縁関係がある古い系統樹に基づいている]。ION ほどは関連がすっきりしない感じ。
ホシムクドリは両目でヒトのように左右完全に揃ったものではないが yoked saccades と呼ばれる左右が同時に動くが振幅の異なる眼球運動で地上で食物探しなどを行うとのこと: Tyrrell et al. (2015) Oculomotor strategy of an avian ground forager: tilted and weakly yoked eye saccades。
南北アメリカのオナガクロムクドリモドキ Quiscalus mexicanus Great-tailed Grackle は両目を別々に動かすことができるとのこと: Yorzinski (2021) Great-tailed grackles can independently direct their eyes toward different targets。
Lapsansky et al. (2025) Hummingbirds use compensatory eye movements to stabilize both rotational and translational visual motion ハチドリでは左右の目が独立に動いて飛行中の体の動き (後ろ向きにも飛ぶので) による視線の変化を補償しているとのこと。鳥類で初めて見つかった。両眼の神経的なつながりが少ないことで可能になっている。
種類によって眼球運動は異なった適応を示しているよう。
ハチクマでは詳しくは調べられていないが、近くの地面に焦点を合わせる能力の有無が首を振って歩くかどうかを決めているかも知れない。
関連した観察と考察を #アオバト備考の [アオバトは歩く時首を振らない?] に追記した。
フクロウ類では正面視の視力がそれほど良くなく、タカ類に比べて近くへの調節能力が弱いが、これは獲物を丸のみする性質に関係していると言われる (#イヌワシの備考参照)。
タカ類は獲物を解体するために近くに焦点を合わせる能力が高いと言われるが、ハチクマもハチの幼虫を取り出すなど細かい作業を行うためおそらく前方では近くに焦点を合わせる能力が同様に高いのではないかと考えている。鳥類の正面視や立体視や捕食性鳥類でどのように役立っているかについてはまだわかっていないことも多く、研究が望まれる分野であろう。
Wylie et al. (2015) のレビューでは principal sensory nucleus of the trigeminal nerve (PrV) 三叉神経の感覚に関係する核が嘴で探索を行うシギ類、水鳥 (特にろ過して食物を得るカモ類など)、オウム、キーウイなどでよく発達しており、嘴の感覚が鋭敏であることとよく対応している。
この関係をみるとタカ、フクロウ、サギのいずれも嘴の感覚が最も発達しておらず、感覚器よりも獲物を捕らえたり調理する道具として用いていることがよくわかる。獲物を突き刺しても嘴は痛くないのだろう。
オウムと猛禽類は嘴の形が似ているが感覚的にはおそらくまったく違うようで、オウムの嘴の感覚が猛禽類にも当てはまると考えてはいけない模様。嘴のろ過機能と感覚が関連しているのは面白い。
PrV の出典は Gutierrez-Ibanez et al. (2009) The independent evolution of the enlargement of the principal sensory nucleus of the trigeminal nerve in three different groups of birds。
この核のサイズを見れば採食に触覚をどの程度用いているか推定できる模様で、直感的にもわかりやすい結果になっている。
備考:
*1: 余談ついでに「能ある鷹...」は英語では何と言うのか調べてみた: 「能ある鷹は爪を隠す」を英語で言うと?。英語では鷹が出てこないが類似のものがある。日本語で鷹が出てくるのはそれだけ身近な存在だったのだろう。
*2: この系統樹作成には BEAST 2 の TreeAnnotator が用いられている。
系統解析にはさまざまな方法が用いられてきたが、松井 (2021) 分子系統解析の最前線 の日本語レビューがあり BEAST の位置づけや系統樹作成の本質的な困難さもわかる。このソフトもオープンソース。マルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC) を用いた系統樹のベイズ推定を行う。
可能な系統樹は多数存在するが (系統樹空間) MCMC を用いてその空間を探索して複数の系統樹形態とその事後確率を求める。過去の日本語資料でよく紹介されていた単一解を求める近隣結合法、最大節約法に比べるとかなり現代的な方法である。
Bird Tree を用いて鳥類の形質の比較研究を行う方法について Rubolin et al. (2016) Using the BirdTree.org website to obtain robust phylogenies for avian comparative studies: A primer
に解説がある。
BirdTree では Ericson et al. (2006) および Hackett et al. (2008) の2種類の系統樹をベースにしているがこの2つは β-フィブリノゲンの遺伝情報を含むかどうかの違いだけであり、この遺伝子が系統解析が適切かどうかは議論があったとのこと。ちなみに Ericson et al. (2006) は近代的な陸鳥の大きな系統の間には系統順を付けていない。
タカ目とハヤブサ目が別系統になっている点は両者に共通している。
BirdTree では他の系統情報や制約も含めて BEAST で MCMC を用いた 10000 種類の系統樹を予め作成してあり、その中からランダムにダウンロードできるサービスになっている。
Sayol et al. (2017), Liu et al. (2023) では調べた種に対してこの方法で得た系統樹セットから事後確率の高いものを BEAST (2) に探させたものだろう。タカ目が最後になるのは BirdTree の出力する系統樹の傾向や BEAST による選択や作図の際の配列順の特徴が現れているかも知れない。
また限られた種だけで系統樹を作ることによるバイアスなども考えられるが、ここではタカ目が最後になっても構わない方が夢があるので (?) これを前提としておく。
[ハチクマ類の道具使用]
ハチクマ類の系統にクロムネトビがあり、石を使って卵を割る道具使用が知られている数少ない猛禽類である。
これはオーストラリアの種類で、石を使って卵を割るショーが動物園などでよく紹介されている。例えば Black-breasted Buzzard opening an "Emu Egg" (タカ類には芸を教えられない話とやや合わない。#ベニマシコの備考参照)。
Pepper-Edwards and Notley (1991) Observations of a Captive Black-Breasted Buzzard Hamirostra melanosternon Using Stones to Break Open Eggs
が飼育下での初めての記録を紹介。この行動は John Gould (1865) がすでに注目しており、エジプトハゲワシの同様の行動より先に知られていたとのこと (「世界の鳥 行動の秘密」バートン 1985)。
エジプトハゲワシの方は van Lawick-Goodalls and van Lawick-Goodalls (1966) Use of Tools by the Egyptian Vulture, Neophron percnopterus とさすがに Nature 論文。
Goodall (1964) Tool-Using and Aimed Throwing in a Community of Free-Living Chimpanzees でチンパンジーが "狙って石を投げる" 行動が Nature 論文として発表された直後で衝撃の発表だった模様。
チンパンジーは今では accumulative stone throwing と形容詞を付けて記述されているが、二足歩行では不十分なので直立二足歩行と呼んでいるようなものか。最初の論文の表題と比べるといかにも後付けだが、ヒトに最も近い霊長類が行い、ヒトの行動の起源かと Nature で大々的に発表するほどの高度な行動を鳥にそんなに簡単にやってもらっては困るわけだ (笑)。この当時の活気や困惑を多少なりとも体感できる気がする。
道具使用の例が哺乳類より増えてしまってどこまでを道具使用とみなすか困るようになった次第。そして定義が厳格化されて行くことになる。"準" 道具使用を含めるとやはり鳥が多い。「世界の鳥 行動の秘密」p. 57 では道具使用の定義は難しい。定義次第では巣造りも道具使用になり得るがさすがに納得する人はいないだろうとのことだが、縫い上げて巣を造る鳥は果たして道具使用なのかと問うと境界が怪しくなってくる。
この本では転位行動 (転嫁行動) が石を投げる道具使用の起源ではないかとも記している。転嫁行動でやけくそに投げたらたまたま当たって、という理屈だがどうだろうか。
なおエジプトハゲワシの上前をはねる鳥もあってチャエリガラス Corvus ruficollis Brown-necked Raven は放棄されたダチョウの卵があると待機してエジプトハゲワシが卵を割るのを待ち、卵が割れると集団でエジプトハゲワシを追い払うとのこと:
Yosef et al. (2011) Set a thief to catch a thief: brown-necked raven (Corvus ruficollis) cooperatively kleptoparasitize Egyptian vulture (Neophron percnopterus)。
道具を使う鳥を道具として使う (?) 知恵もの同士の比べ合い (?)。卵はなかなか手に入らずそれほど栄養価が高い。
その後も次々と鳥の道具使用が見つかる。ほぼリアルタイムで話題を追っていたが、道具を作る鳥も見つかって霊長類学者も驚き、それでは道具を "選ぶ" とか "保持する" とかだんだん要求条件が複雑になって行ったのを覚えている。チンパンジーにできて鳥にはできないことがあるかをわざわざ探す必要があるぐらい鳥の道具使用はチンパンジーに似ていたわけだ。
自分もオオルリ (小枝?) をくわえて地面をつついているのを見たことがあって (おそらく渡り中の個体で冷え込んだ朝のこと) が棒のようなもの、どこかで見たヨーロッパのクロウタドリ (だったと思う) の道具使用の写真に似ていたのだが、クロウタドリ? の出典が見つけられなくなってしまった。
オオルリは双眼鏡で見ただけで映像記録が残っていないので証拠にはならないが、 転位行動 (転嫁行動) の可能性はあるかも知れない。しかし木の枝を普段使う種類ではないので何だったのだろうか。この程度のことは想像以上に多くの種類が行っているのかも知れない。
エジプトハゲワシは現生種ではハチクマと同じ亜科か別のより古い亜科というもので、ハチクマ類の議論に含めてよいだろう。
エジプトハゲワシの行動の記述の歴史については Baxter et al. (1968) A Nineteenth Century Reference to the Use of Tools by the Egyptian Vulture に詳しく、Wood (1877) にすでにそれを示唆する記述があるとのこと (記述はここに引用されている)。ここではヒゲワシが物を持ち上げて落として割ることからの類推がある。
この文献によれば Chistholm (1954) The use by birds of "tools" or "instruments" でクロムネトビの石投げ行動 (アボリジニおよびヨーロッパ人の目撃者がある) が記述されているとのこと。同文献にはオナガイヌワシが空中で枝やウサギを落として着地前に捉える行動も記されており、遊びと解釈された (アボリジニは枝遊びと呼んでいたとのことで、トビも同じ行動をするとのこと)。
「動物の世界」2版 5 (日本メール・オーダー 1986) pp. 642-644 のエミューの項目 (浦本・安部) にも解説があり、当時の名称でムナグロノスリ (英名をそのまま訳したもの = クロムネトビ。オーストラリアにはノスリ類が生息せず、トビの方が系統が近いと考えられて新称が与えられたのだろうがこちらの系統解釈も誤りだった。同じ項目内で現在のオナガイヌワシをクサビオワシと表記しており、こちらも英名をそのまま翻訳したもの)
は抱卵中のエミューのオスを巣から追い出して上空から石を落として卵を割って食べるという伝聞が紹介されていた。当時はおそらくまだ伝聞時代で後に行動が飼育下でも確認された次第だろう。
しかしエミューを追い出すとはなかなかすごい能力なのでは。
クロムネトビはハチクマ亜科にしてはかなり黒っぽい印象を受けるが、もしかするとひなを襲うオナガイヌワシのような暗色の捕食者に対するものと似た反応を引き起こすのかも。過去に襲われた経験があれば似た色の上空からの捕食者から予防的に逃げる可能性が考えられる。
オーストラリアは進出しなかった (できなかった) 猛禽類の系統が多いので (#アカハラダカ備考の [オーストラリアのタカ類] 参照)、後に現れた猛禽類の系統との競争の結果でハチクマ亜科の中では限られたクロムネトビのような種類のみが残ったものとは考えにくい。道具使用 (認知能力?) などの面ではタカ類の中でハチクマ亜科はそもそも優秀なのでは。
ヨーロッパハチクマで道具使用と思われる行動が報告されているが [Camacho and Potti (2018) Non-foraging tool use in European Honey-buzzards: An experimental test] 行動の解釈は定かでない。
ハチクマはタカ類の中では足を器用に使う種類である [Gutierrez-Ibanez et al. (2023) Online repositories of photographs and videos provide insights into the evolution of skilled hindlimb movements in birds]。
ハチクマに系統的に近いカッコウハヤブサ類も足を器用に使うことが知られており、タカ類中で食物を足で嘴に運ぶことのできる数少ないグループである。
永井 (2023) Birder 37(4): 61 にハチクマが足で持った食物にかじりついている写真が掲載されているが、タカ類でこのような行動のできる種類はごく少ない。
ビデオ映像や動物園等でのハチクマの観察でも、つい足が (まるで手のように) 出てしまうことがしばしば見られる。嘴だけでうまく食べられない場合に手助けをしたり、動物園では隣のケージを覗く際に足でケージをつかんで体を乗り出したり、帰ろうとすると近くのとまり木から片足でケージをつかんだりすることがあった。これらの行動はオウム類を思わせるものがある。
ハチクマ類の系統に道具使用を行う種類がある点からも行動にもっと注意を払って記録すべきであろう。
そういえば思い出したのだが、動物園のハチクマが訪問2回めにして愛着を示すような行動を示したのはケージの前で食べた時だった。この時に声を出した。
後日「つられ食い」(前で人が食べるのを見てお腹が空いたのか自分も食べ物を探した。こちらは与えるわけにはいかないので...) を観察したので人が食事することが自分と同じであることを理解していると思われる。
まったく違うものを食べているのに食べていることがわかっていると驚かれた話は手乗りのインコ類で聞いた。食べると自分も欲しがったとのこと (似た光景は自分も記憶があるが当時は特別なことと意識していなかった)。
他の鳥で人が食べているのを見て自分も食べたくなる例は知られているだろうか。
ここで興味深い共通点に気づいてしまった。オウム/インコ類もハチクマも足でつかんで食べるので、人の手が自分の足と同じようなものと認識しているのではないだろうか。自分と似たようなものと認識してくれているならちょっと嬉しい。
この解釈が正しければ猛禽類は程度の差はあれ該当しそうな気がするので、トビも人が食べていることを認識した上で食物を狙うのかも。
ここでついでに触れておくと「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 56 にヘビクイワシが草の束を放り投げてその後空中に飛び上がる写真が紹介されている。Gutierrez-Ibanez et al. (2023) に関係して議論した時は証拠を思い出せなくて (写真があったのは覚えていた)、まさかあの足では掴めないだろうとの話だったが掴んで投げることができる模様。
この本ではこれも遊びではないかと紹介している。遊びは通常幼鳥に見られるとあるがこの個体は成鳥のよう。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 114 pp. 6-7 にも3枚組の同じ写真が紹介されており、クレジットは J. Burton となっているので出典は上記と同じよう。同様の写真がその後あまり発表されていないことからみて、まれにしか見られない行動なのだろう。
#ミサゴの備考の [猛禽類の分類など] で取り上げた鳥類の足の使い方について、Carril et al. (2024) Evolution of avian foot morphology through anatomical network analysis を引きながら鳥の足は基本的に十分な機能があって上位の神経による制御系 (つまり主にソフトウエア) の進化だけでいろいろな役割を果たせたのかも知れないと書いた。
改めて考えてみるとハチクマの足は非常に多機能ではないだろうか。獲物を殺す、掘る、地上の物を蹴る、裏返す、空中のハチの巣を崩す、押える、掴む、食事の手助けをする、ぶら下がる役割をすべて果たしている。これほど多機能な足の使い手の鳥を簡単に思いつかない。
[カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] に紹介するように第 II 趾の骨の構造にも特色がある。器用な足のためには#トビの [トビなどの第 II 趾の骨の癒合] のように第 II 趾の骨を癒合させるのはあるいは強度が増すのかも知れないが自由度が下がって不都合だったのかも知れない。
そのような視点で見ればカンムリカッコウハヤブサ類とハチクマ類の共通祖先の段階で器用な足が獲得されていたのだろうか。
もし我々がこの系統から進化していたならば、進化の歴史を振り返り、祖先の横向きの足が直立に近くなって自由度が上がり、器用な足を手に入れてそれに伴って頭脳が進化した、とか説明していたかも知れない...どこかで聞いたような説明だが。
[音声]
ハチクマの声としてよく知られるものは、ピーエーとノスリの声に少し似たもので、英語では whistling call とも呼ばれる。警戒の際や離れた他個体との鳴き交わしなどさまざまな場面で使われる。警戒の際の声と考え alarm call とされることもあるが、基本的には同じ声である。
野鳥録音をしている人はご存じだろうが、(少なくとも日本では) ハチクマの声の録音は意外に難しい。西日本では数が少ないこともあるが、もともとそれほど頻繁に鳴く種類ではないことや声をよく聞く時期がセミの最盛期に当たるのでなかなかチャンスがない。「野鳥大鑑」鳴き声 420 でも繁殖地での録音ではなく渡り前の集結期のものになっている。
東日本で数の多い地域ではまた事情が違うだろうが、普通に出会える夏鳥の声は一通り録音できてもハチクマは最後の方になってしまった。ハチクマの前の「声のライフリスト」(録音版) を挙げてみるとセグロカッコウ、オオコノハズク、ブッポウソウ、ヤイロチョウ、マキノセンニュウ (いずれも地元記録) などの方が先になっている
(夏鳥の記録をされている方ならばこのリストはふむふむと納得いただけるだろう。もちろん標準的な夏鳥はずっと早く録音できている。ヤイロチョウももっと早くから持っているがまだテープ録音の時代だったので後回しになった)。
行くべきところへ行けば記録できるウチヤマセンニュウ、コノハズク、ホシガラスなどはその後になっているがまだハチクマはまだ出てこない。姿は見られることはあってもそう鳴いてくれるわけではない。
地元でもサシバやノスリ (ここでは多分繁殖していない) の声は複数回記録できているがハチクマはまだ記録したことがない。
セミの声が背景になる録音も PCM で記録して高音域を取り除けば使えるが倍音情報がわからなくなるのでできれば静かな背景で録音したいもの。
皆様もハチクマの声に注意してみていただきたい。渡りの時に明らかに鳴きあっていると見える映像は記録したことがあるが声は聞こえなかった。
セミの声が背景でもビデオで音声も一緒に入っているので大丈夫、と思っていたら音声情報は圧縮の結果ほとんど失われている場合もあるので要注意 (#ヒクイナの備考参照)。ハチクマはまさにこのような季節が多いのでぜひ PCM 録音をおすすめしたい。
近傍個体などに対してはこの声を弱めたり「鼻にこもった」ような音質に変えたりしてさまざまな声を出す。動物園個体で聞かれる声はこれである (おそらく餌乞いの声 begging call の一種)。
ヨーロッパハチクマのみが持つと考えられていた rattling call という別種の声がありヨーロッパハチクマの例、普通に聞くととてもタカの声とは思えない。
台湾の巣のビデオ中継やロシアの飼育個体 (リンク先にロシア文スクリプトと英訳あり) がこの声を出し、ハチクマでも rattling call が存在することが明らかになった。
Kato et al. (2023) Rattling Call of Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus (オープンアクセスとなった。電子付録に映像などへのリンクもあり)。
台湾の巣のビデオ中継では外敵 (タイワンザルの群れ) が巣に近づいた時 (1, 2) や、つがい相手が餌を持って飛んでくる時に記録されており、声の役割はヨーロッパハチクマに似ていると思われる。
「九九蜂鷹」のビデオもよく聞けばこの声が入っている (タカの声に聞こえないのでおそらく誰も気づかなかった)。
Yvonne Blake のマレーシアの留鳥の繁殖ハチクマの YouTube 映像の中にも同じ声を出しているものがある。
Crested Honey Buzzard - mummy back at previous nest and calling daddy Part 1 (2023.10.3) 巣でメスがオスを呼んでいる模様。
Crested Honey Buzzard nesting shift change Part 1 of 2 (2023.10.27) 抱卵交代の時にこの声を出すとのこと。rattling call の一部分またはその変形のような声に聞こえる。産卵は 2023.10.11 とある。
解説によれば、自宅から (うらやましい!) この声が聞こえるらしく、声がしたら交代を観察しに行っているとのこと。"I want a stretch call" 「羽を伸ばしたいから代わって」と聞きなし (?) ている。
オスにも声は遠くから聞こえていて5分以内には帰ってくるがすぐに来たことはない。
オスもいつも近くにいるわけではないので、と説明がある。同種の声に対する聴力は良いのだろう。
Crested Honey Buzzard nesting shift change Part 2 が続きで前半に少し声があるが音質は異なっている。
マレーシアの巣立った若鳥の発声記録: Crested Honey Buzzard juvenile preening (0:18 付近)。
その後マレーシアの留鳥の繁殖ハチクマでメスがこの声を出してオスを交尾に誘った事例があった。発声の様子もよく記録されている。交尾後もメスはこの声をしばらく出していた。
交尾の際のオスの声は rattling call とは異なっていた。
またマレーシアのハチクマの項目で 2025.3.27 撮影のもので、オスが食物を運んだが若鳥が見当たらず呼ぶ時もこの声を用いていた。
インドのハチクマでの記録 Santharam V 2023.12.26 (eBird)。
[韓国のハチクマの繁殖] 項目のビデオにも巣でオスが長く rattling call を続けた記録を紹介している。この例では撮影者はメスを呼ぶ声とコメントしている。
(中国のハチクマの巣での抱卵交代時の音声記録情報をここにまとめていたが、生態記録が増えてきたので別項 [中国のハチクマの繁殖生態] にまとめた)
ヨーロッパハチクマではよく知られた声で、cycle-wheel call, ticking-call などの別名があり、前者は自転車のスポークに硬いものを当てて車輪を回した時に出る音に似ているためこの名前が付いたものである。ヨーロッパ大陸のいくつかの言語で対応する意味の用語がある。ヨーロッパハチクマでは巣の外での発声も記録されており、日本でも野外で聞くことができる可能性がある。
他に Panov (1973) が長く続く "tyo-tyo-tyo-tyo-tyo-" の声を求愛の声として記録しているが、以上に述べた声のどれかに類似のものかはよくわからない (極東の鳥類5「南ウスリーの鳥類1」に和訳あり。対応する音声は先述の Gluschenko et al. (2020) にも引用されており極東の鳥類42で和訳を読むことができる)。
Oriental Honey Buzzard Raiding A Beehive For Food!
では最近の映像だがインドでの食事風景が詳しく捉えられている。餌をめぐって争ったりしないようで行儀よく順番を待っている。
小さい声で鳴いているが近隣個体間のコミュニケーション (甘え声もほぼ同じような声) であろうか。
翼を半開きで食べる (他のタカ類同様の mantling か) 光景も記録されている。
Buzzard Calling & Eating Honey: Wild life Documentary in Hindi (Birdindia 2024.12) の 1:25 から枝にとまって rattling call を出す映像。この例ではメスと記されている (映像では虹彩がわずかに見えた)。
巣の外でも木にとまってこの声を出すことがある。
その後性別や年齢の説明があるが最初にオスと説明されているものは若鳥。最後にメジロサシバとの識別がある。解説では舌が長くて溝があって幼虫を引き出す適応があると説明されている。英名の通りハチミツを食べるとの説明はあまり正しくない。
これらを記述した後に週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 114 pp. 14-15 のハチクマの項目 (当時は分類に諸説があったが、少なくとも日本版では全ハチクマ類を同種扱いとする扱いで記事が書かれていた。この分類ではユーラシアのほとんどの地域に分布する広域種だった) に、現在の分類でヨーロッパハチクマと考えられる「テッ、テッ、テッ」と1秒間に 4-5 回「テッ」を繰り返すほど早く鳴く。鳴くのはオスだけのようで、決まって巣の近くで鳴くとあった。
現在の知識で考えればこれは rattling call のことと考えられる。翻訳者も音声がわからないので文字をそのままカタカナ表記したものと想像できるがほとんど伝言ゲームのような世界。
フランス語版ではおそらく最後に発音しない子音文字が置かれていたのだろうがカタカナ表記に変換するとそれも消えてしまう (どんな音を表現したかったのかよくわからない)。
Panov (1973) の "tyo-tyo-tyo-tyo-tyo-" も、もしかすると同じ音を表したかったのかとも思えるが今となっては不明。出版時期が妙に近く、実は当時はよく知られていたが今では忘れ去られたなど元となる別の原典があって、文字の異なる各自の言語で表現した可能性もあるのではとも思えてしまう。
他の鳴き声は知られていなかったのだろうかと不思議に思える - 他にももっとタカらしい音声があるでしょうが (笑)。
日本語版で紹介されているので少なくとも当時の鳥類学者や読者に一度は周知されていたと思われるが、ハチクマの知名度が低く完全に忘れ去られてしまったのだろうか。日本のハチクマで誰も聞いたことがなかったので、そもそも何のことかわからなかった可能性もありそう。
その後別種に分離されたのでヨーロッパの知識がそのまま適用できるとは必ずしも言えなくなったわけではあるが。
この記事ではさらに「飛行しながら巧みにハチ類をくちばしで横にくわえ、針のついている虫の尾部をくちばしでちぎって飲み込んでしまう」の記述があり、聞いたことがないが見られた方はあるだろうか (ここまで読むと全体の情報の信頼度も疑問に思えてしまう。ハチクイ類と混同されていないか?)。ハチの巣を襲うことに関連して、ハチ類の針で刺されていることは確かであるが、ハチ類の毒に対しては免疫になっているようですと説明がある。
どこまでが事実で、どの部分が想像なのかよくわからないが、このような説明が伝え続けられて現在の「ハチクマ観」が熟成されてきた可能性もある。
どの部分が原著にあってどの部分が日本版で修正や追記されたのかもよくわからない。
原著の巣の写真も紹介されており、2羽のひなは孵化して 24 時間ほどとあるがこれも誤り。
日本のハチクマの清棲幸保氏による写真が紹介されており、羽毛の色の違いは別種とするか亜種とするか議論が多いと記述されていた。まだ暗色型と淡色型 (および中間型) があることは知られていなかったらしい。日本に生息することは知られていたが研究はまだなされておらず、いろいろな色彩は別種か亜種かと議論されていた模様。
Bird Call: ORIENTAL HONEY BUZZARD, Singapore (kidowmer 2025.2) シンガポールで記録されたとまって鳴く越冬中のハチクマの映像。一番よく聞くタイプの声で大きく口を開けて鳴く様子や舌の位置 (食べる時とは違って舌を引いている) がよく記録されている。ここでは相棒 (越冬地なのでつがい関係ではないだろうが) が上空を舞っていて同様に鳴いている。
ねぐらをキタカササギサイチョウ Anthracoceros albirostris Oriental Pied Hornbill に妨害されて抗議しているとのこと。この鳥はハチクマと同じぐらい大型。
Oriental Honey Buzzard Call (AromaWorld [Ramanand Tripathi]) こちらはインドの映像。日本で聞くハチクマの声に比べて倍音成分が多いような気がする。口を開けて鳴く様子など記録されている。ヒヨコの鳴き声のようなクマタカよりタカらしい感じの声に聞こえるが気のせいか (笑)。
大きい声を出す時は舌を引いているのは我々でもそうかも知れないが、口腔を共鳴要素として利用しているようにも見える。
[ロシアのハチクマとヨーロッパハチクマの研究のための情報] の項目で Karyakin (2004) に(ヨーロッパ)ハチクマの音声に対する反応に関する興味深い情報があったので、一般的な whistling call について再度取り上げておく。同所の考察を再掲しておくと、
「興味深いことに p. 210-211 にオオタカではプレイバック法が(ヨーロッパ)ハチクマよりもずっと成績が悪いとある (ワシミミズクの声も用いている)。オオタカはより近距離でないと反応しないとのこと。(ヨーロッパ)ハチクマの方が音声をより積極的にコミュニケーションに用いているらしい。
これも(ヨーロッパ)ハチクマの生息環境が見通しの悪い森林であることにも影響があるのでは。姿の見えない相棒を呼ぶには声はぜひとも必要なのだろう。おそらく調べられていないだろうが(ヨーロッパ)ハチクマの方が聴力がよいのかも知れない。」
上記 AromaWorld [Ramanand Tripathi] のビデオにもある通り近場で正面を向いた時に聞くとよく通るよい声である。側面、後ろ向きの場合はそれほど強くは響かないが、whistling call の冒頭に強いアクセントがあってこの音の成分が反響のように長く続く。
Kato (2021) A code for two-dimensional frequency analysis using the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (Lasso) for multidisciplinary use にハチクマの whistling call のサンプルのソノグラムがあるのでご参照いただきたい。
よく似た種類の声との識別にも使える特徴と考えている。日本ではノスリの声が似ているがハチクマほど音声冒頭がシャープでなくもっと平坦な感じ (ハチクマでも正面を向いていない発声の場合はノスリのようにも聞こえる)。
日本では識別対象種となることはあまりないだろうが、同所的に生息している地域ではカンムリワシの声のレパートリーの一つがハチクマのこの声に似ていて誤認要因ともなり得る。ソノグラムを描いてみると違いがよくわかり、カンムリワシの方が立ち上がりのゆっくりした丸みを帯びた波形になる。
ハチクマのこの鋭い声は遠方まで届き、直接姿の見えない相棒を呼ぶ目的にかなっているのだろう。例えば地上で採食中など音の聞こえにくいところでも、音声冒頭の鋭いピークに気づいて注意を集中すれば呼ばれていることに気づきやすいなど。我々が鳥の第一声に気づき次の音声を待って確認するのと同じようなものだろう。ノスリのような平坦な声はもっと開けた環境に適しているなど音声の環境適応も考察の対象となり得るだろう。
ハチクマがいろいろな方向を向いて発声するのも相棒がどの方向にいるかわからないためだろう。
ハチクマの声は基本的に同種に向けたものだろうが、オウギワシのように隠れている獲物を追い出して捕える戦略もある (#カンムリワシ 備考の [霊長類はなぜヘビを恐れるか] 参照)。
[(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど]
(ヨーロッパ)ハチクマはロシアやベラルーシなどでしばしば保護・飼育されている。これはロシア人などにとって、きのこ狩りが秋の恒例の楽しみで(ヨーロッパ)ハチクマの巣立ち時期ごろに林内をよく散策し、まだあまりよく飛べない鳥を保護 (あるいは保護する必要のない巣立ちびなかも知れないが) することがあるのが一つの要因になっている。
渡り途中に庭を訪れた鳥が地面を掘って途中に人がなでても気にしていない動画も紹介されている (ベラルーシのビデオ)。タカ類の中でも特に多く動物園に運ばれてくるとのこと。
ロシアのハバロフスク地方のブレインスキー保護区でのそのような記録の一つ (2010-2011 年で執筆進行中に知って翻訳を ML Kbird にて紹介した) の日本語訳を紹介しておきたい [ハチクマのお客さんになって] (残念ながら原文は現在読めない)。
ハチクマの温厚な性格や屋内での遊び、果物が好きで個体ごとに好みがあることなどなども読み取れる。
室内で加速するだけで窓を破ってしまうあたりはハチクマの飛翔力の強さもわかる。
この中で著者の食べるパンを食べにきた事例が報告されているが、[マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] の映像を見ていて人がパンを食べているのがハチの巣に見えたのではないかと想像してみた。ハチの巣を知らない人が見るとハチクマがかじっているのがまるでパンのように見える (!)。
遊び行動から [モビングを受けるタカの行動観察のすすめ] の項目を独立させた。
次はロシアの沿海サファリパークで 2017 年にナホトカの住民が幼鳥で保護したハチクマ。以下のビデオを撮影時点で4暦年となるがろう膜にまだ黄色の部分が残っているように見える。
沿海サファリパークの猛禽類が熱帯の果物を狩る
おやつとしてバナナを喜んで食べるとのこと。
スイカで沿海サファリパークの猛禽類をもてなす
ふれ合い動物園になっているようで、ハチクマが来園者からスイカをもらってなでてもらっている。
クロハゲワシは長い時間スイカを調べてひっくり返したり、かじったりしたが果肉の部分は食べなかったとのこと。
Blagosklonov (1960) による野鳥飼育の本 飼育下の鳥 があり、猛禽類も取り上げられている。
ヨーロッパハチクマの項目が大変面白いので大型猛禽類の部分をまとめて紹介しておく。
ノスリは現在の分類ではヨーロッパノスリ。
オオタカの行動も紹介されているが、動物園で見る人に慣れないオオタカの行動はまったく
この通りであった。
「室内での大型昼行性猛禽類」
(訳注: 当時は有益な小鳥を食べる鳥は害鳥、有害なネズミを食べる鳥は益鳥とされており、害鳥の駆除は推奨されていた)
猛禽類の中で、飼育下に置くことへの関心の観点から、2つのグループを
区別する必要があります: 小型猛禽類と大型猛禽類。小型猛禽類である
チョウゲンボウ、そしてとりわけニシアカアシチョウゲンボウは愛らしく、
観察すると多くの有益なものが得られます。大型猛禽類はたぶんハチクマを
除いて飼育下で退屈です。
猛禽類の大多数がネズミ類の齧歯動物の駆除に非常に役立つことを忘れては
なりません。すなわちそれらをケージに保持することは経済的損害を引き
起こします。しかし、野生生物の学校の社会・文化活動の部屋においては、
猛禽類は、それを例として、若い博物学者が大きくて重要な鳥のグループに
慣れるために常に非常に必要です。
益鳥である猛禽類を飼育することは、観察が行われ、実験が行われ、
その生物学のさまざまな側面が明らかにされれば、完全に正当化されます。
猛禽類の中でも有害な鳥を必要なだけ飼育下に置くことは禁じられて
いないことは自明のことです。さらにその上、活用することもできますが、
これについては後で説明します。
オオタカは一度だけ私たちのケージにいたことがあります。それはこのような
強盗を飼いたいという願望を思いとどまらせるのに十分なことでした。
捕まったオオタカは成鳥でした。オオタカは非常に大きいことがわかった
ニワトリをひきずり出しました。オオタカはニワトリを捕まえて飛び上がれ
ませんでしたが、人々がオオタカに向かって走っているのを見ても、ニワトリを
爪から解放しませんでした。それからオオタカは羊皮のコート (フードで
しょうか) で覆われることになりました。
この鳥は、苛立ちと敵意の感覚しか引き起こしませんでした。オオタカはよく
食べましたが、とても野性的でした。人が近づくと、タカはケージの格子に
飛びつき、時には激しくぶつかりました。そしてオオタカはケージにいくら
いても野蛮なままでした。餌を与えて育てることには比較的慣れています。
昔はオオタカやハヤブサで狩りをし、今でもコーカサスでハイタカで狩りを
しているのもちゃんとわけがあります。
この猛禽類もちゃんと役に立ちます。アメリカの飛行場で最初に使用されました。
ここで餌を食べる鳥は、飛行機が離陸したときに衝突することがあり、事故の
恐れがありました (イギリスでは、鳥の群れにぶつかった1機のジェット機が
燃え尽きました)。鳥を追い払ったり、餌を破壊したりする手段は役に立ち
ませんでした。しかし縛られたタカがポールに置かれたとき、鳥は飛行場を
訪れなくなりました。捕食者への恐れは鳥にとってとても大きいです!
オオタカを使って作物をミヤマガラスから守れないでしょうか?
ハイタカは、ムクドリやスズメからのキビや小麦の作物からの桜の果樹園や
ブドウ園の保護を請け負うことができます。試してみてください。
これらのタカは両方とも害鳥であることを忘れないでください。巣からひなを
穫るときは何も残さないでください。しかしこれを行うことができるのは、
猛禽類に精通していて、それらを正確に同定できる場合のみです。
国の中央部に住む農夫の友人であるネズミの駆除者であるノスリは、
他の猛禽類よりも頻繁に人の目を引きます。そしてその巣は見つけやすく、
トウヒやカバノキ、通常は古い混合森で、端からそれほど遠くない (1 km 未満)、
捕食者が獲物であるネズミを探している牧草地や野原の近くに造られます。
ひなで捕らえられ、肉、ネズミ、スズメ、カエルを与えられたノスリは
人間にはよく慣れていますが、飼育下ではとろくて、鈍重で、あまり
面白くない鳥のままです。
ノスリは独特の、非常に騒々しくて迷惑な叫び声を持っています。
鳥がお腹を空かせるとすぐに、長く続く「キャイイイイイ、キャイヤイ」が
遠くからでも聞こえてきます。ノスリは物乞いをしているようで、哀れな声
でうるさくせがみます (それ故に「せがみ屋」kanyuk という名前を
もらいました)。私たちは通常、ノスリをケージに入れずに、彼らがずっと
過ごしていた支柱に足で縛りました。単に野外にいるように保つようにしました。
この場合、成長するにつれて、彼らはますます人々を避けるようになり始め
最終的には彼らは完全に私たちの世話を離れました。
そのような「野生」で育てられた子は、映画「翼ある防衛」でノスリの役割
の一部を果たしました。ズヴェニゴロド生物ステーションで育ち、彼は長い間
建物の近くに滞在しました。ノスリはまた台所を訪れ、そこで肉片を受け取り
ました。彼はモスクワ川のほとりに沿って、しばしば地面で狩りをし、
草の中のイナゴを捕まえ、そばで水を浴びる人々を恐れませんでした。
しかし、彼はますます目につかなくなり、7月中旬までに完全にみかけなく
なりました。そして秋、駅の近くで何度か彼に会いました。彼は野生のノスリ
よりは近くにいて、人々が近づくこともできましたが、以前の信じ込みやすさは
ほとんど残っていませんでした。
人が 20-30 歩も近づくと鳥は木から飛び出して消え去りました。この距離からは
この子の右足にあるアルミニウムの足環が完全に見えました。これによって彼は
簡単に識別されました。それでもノスリは人々をあまり恐れないことで、おそらく
不利益を被っていたのでしょう。彼は腕のよい長距離ハンターの目を引くことに
なりました。ハンターの中には、くちばしが曲がって、鈎爪を持ったすべての
鳥が有害であると今でも考えている人がたくさんいます。彼らはこのようなタカを
撃つことによって彼らが善行をしていると思います。いずれにせよ、翌年は誰も
私たちの子に会いませんでした。私たちが知っている2つの巣を双眼鏡でどの
ように見ても、脚に目立つアルミニウムの輪が付いた鳥はその中にいませんでした。
飛んでいるトビを他の猛禽類と混同することはありません。切り欠きのある尾
があるのはトビだけです。
獲物を持って飛ぶトビがどこに行くかを丘から追跡すると、巣を見つけるのは
難しくありません。それは比較的低く、ほとんどの場合他のいくつかの巣が
近くにあります (そのようなコロニーはモスクワの Sokolnicheskaya Roshcha
(= 鷹匠の木立) にさえありました)。したがってトビを手に入れることは難しく
ありません。しかし、飼育下ではこの鳥はノスリよりもさらに退屈です。
とまり木に偶像のように一日中とまっており、餌を与えた瞬間にのみ生き返ります。
かつて私はヴォルガデルタのトビの巣から取ったひなを育てなくてはなりません
でした。ここでは彼らは猛禽ではなく、ウや他の魚を食べる鳥のコロニーで
繁殖する掃除屋であり寄生者です。ひなのためにたくさんの魚を捕まえているウは、
時々それを地面に落とし、トビはすぐにそれを拾います。満腹になったひなが
食べ残しの魚を巣に残すことがよくあります。トビはそれを引きずり出されます。
このようにトビはこでは完全に鳥に頼って生きています - 魚奪いの達人の仕事です。
私はトビの羽が生え始めるところで引き受けましたが、綿毛のひなよりも白かった
です。彼は非常に大胆で騒々しかったです。トビの声は一種の口笛、振動する口笛
またはきしむ音であり、かなり大きな声です。空腹になるとひなは絶えず叫び
ました。トビの子は通りで育ち、そこからどこにも行きませんでした。彼にはあらゆる
種類の残り物を与えられました。ひなの好みはここに住んでいた
ニシアカアシチョウゲンボウやチョウゲンボウが食べなかったニワトリの内臓でした。
トビが成長したとき大きなケージに入れられました。ここでは、トビは同じサイズの
他の猛禽類、つまりノスリとハチクマと一緒に平和に暮らしていました。かつて
ハチクマのひなが私たちの生物ステーションに運ばれました。背中はすでに羽で
覆われていましたが、頭には厚い白い綿毛しかありませんでした。ハチクマは
若いノスリとチョウゲンボウがすでに入っていた屋外のケージに入れられ、
彼にはオシクという名前を付けました。
名前からして変ですが、この鳥のすべてが奇妙でした。確かに、なぜそれは
「ハチ食い」(= ロシア名) なのでしょう? こんな大きな鳥ではハチクイ
やヒタキのように食べ物のハチを捕まえないでしょう? 実際ハチクマは
ニワトリとほぼ同じくらい背が高いのです。ハチクマはケージの隣人に似て
見えませんでした。ちょっと見ると猛禽類ですが、よく見ると似ていません。
くちばしはかぎ状ですが、ほとんどニワトリのように鈍いです。爪も他の
猛禽類よりも短いです。そのような爪で獲物をつかむのではなく、
ニワトリのように地面を掘るのです。
すぐに食べ物に問題が発生しました。私たちの猛禽類には肉を与えていましたが、
ハチクマは食べません。ハチクマの口に一片を詰め込みましたが、頭を振って
吐き出します。しかし、カエルが提供されたとき、ハチクマはそれを
貪欲に食べました。私はハチクマを養うためにカエルを捕まえなければなり
ませんでした。数日後、最も驚くべきことが偶然発見されました - 彼の好きな
食べ物は...イチゴとラズベリーでした。ベリーを手に持ってケージを通り過ぎる
とすぐにオシクはそれらに気づきました。彼の視力は本当の猛禽類のよう
でした。彼は興奮して叫び始めました - 餌を懇願するために。ひなは
喜んでスイカ、トマト、その他の果物を食べました。それで彼は私たちの
ところで半分菜食主義者として育ちました
私たちのオシクは完全に飼れました。彼が成長して飛べるようになった時、
私たちは心配なく彼を生物ステーションの森の中で散歩させました。
空腹になれば、鳥はいつも戻って食べ物を求めました。
あるとき、朝に放したハチクマが、夕食に戻ってこないことがありました。
いつもならば「オシク!」と一声呼べば飛んできて頭にとまるのですが、
呼んで見回してもみつかりません。
私たちは長い間探し、この鳥の好きな木をすべて調べました。私たちがすでに
ハチクマを見つける希望を完全に失っていたとき、私は何か茶色が茂みの下を
動いているのに気づきました。行ってみました。目の前には、イタチの穴に
似た、掘りたての大きな穴があり、少し震える鳥の尾が突き出ていました。
疑いの余地はありません。何かが私たちのオシクを穴に引きずり込みましたが、
それでも彼は抵抗しています。鳥が動いているということは生きているという
ことなので、私はすてばちになって鳥を引き抜くことにしました。
私は鳥を尻尾と足を持って穴から引き出しました。オシクはすべて土で汚れて
いましたが、奇妙なことに血や傷もなくまったく無事だったのです。
鳥があまりに激怒して反撃し、自由になった足で引っ掻いたので、
私は持っていることができず放しました。鳥は地面に飛び降りてまた穴に急いで
戻りました。あっという間に鳥は地下に姿を消し、尾だけが外に突き出ました。
そして私は穴の上を飛んでいる黄色い虫に気づきました。地バチでした。
ここに鳥が発掘して破壊したハチの巣があったのです。ついに何とかハチクマ
は本来の食べ物を見つけ、本能は彼にそれを手に入れるには何が必要かを
教えたのです。
私のケージにとどまったすべての大型猛禽類の中で、オシクは最もよく慣れ、
行動も最も興味深いものでした。彼は飛行の研究に大いに役立ってきました、
もっとも、私が説明した他の鳥の多くも同様ですが。学者たちはオシクと
特別の研究を行い、彼はすべての課題を無事にこなし、彼の飛行技術を喜んで
示しました。
私は、モスクワのバウマン・ハウス・オブ・パイオニアの野生生物の
社会・文化活動の部屋に住んでいて、おそらく今も生きているハチクマを
知っていました。この害鳥でもない鳥は、無学なハンターによって
撃たれました。翼が壊れていることがわかりました。その後翼は
成長しましたが正しくはならず、鳥は永遠に飛ぶ能力を失いました。
4年間の飼育生活で、ハチクマは人々に非常に慣れて、人々に愛着さえも
示しました。ミシェンカは出された手に喜んでとまり、撫でられることを
許しました。下に新聞が敷かれた椅子の背もたれによく陣取っていました。
このハチクマもまた、自分が菜食主義者であることを示しました。
彼は非常に空腹なら肉を食べ、それでもしぶしぶ食べました。鳥は
チーズケーキの塊がはるかに好きで、まず最初にすべてのレーズンを
慎重に選びました。ジャムも拒否しませんでした。
ミシェンカのおおらかな性格はの部屋のすべての鳥によく知られていました。
ハチクマがレンジャクやイスカのケージに登って、羽繕いをし、
鳥たちを眺めている時、鳥たちはまったく恐れる態度をとりませんでした。
しかし、カササギがケージにとまるとすぐに、鳥の間で騒ぎが起こりました。
ハチクマはハチの刺傷に対して興味深い適応を持っています。
すべての猛禽類では、くちばしの付け根(頬)の皮膚がまばらな髪の毛
のような羽で覆われ、それらを通して輝いています。側面に鎧のある頭
を持っているのはただハチクマだけです - 鱗のように小さくて
密度が高く、灰色の羽です。それらは、捕食者の頭を昆虫の刺傷から
確実に保護します。
注: 翻訳中に出てくる一声呼べば という部分は「一回動詞」という一回の動作を表す動詞を
訳出したもの。必ずしも一回というわけではないかも知れないが、何度も繰り返す必要はないのだろう。
ロシアのヨーロッパハチクマの事例: 新年の干支に出会う (2019)
動画 0:55 あたりから、動物園ではちみつを与えている。
「ほらはちみつよ、おいしいでしょ」とか声をかけながら与えている。
動物園でははちみつで甘やかされ、夏にはなんとアイスクリームまでも、と紹介されている。
この記事は日本で言う「干支の引継ぎ式」で干支が「白いワシ」だそうである。白いワシに一番近いヨーロッパハチクマに登場いただいた、ということのようである。
(スクリプトから翻訳) 新年の干支を訪れて
東洋のカレンダーではイノシシの年、そしてスラブのカレンダーでは
白いワシの年がやってきました。「子供と若者の創造の会館」の
動物たちの中に新年の干支の親戚がいます。同僚のマリア・コンスタンチノワ
が飼育場の住民の習性に親しんできました。
若いナチュラリストたちはどんな天気でも自分たち後見人のところへ急いで
行きます。1つのおりの中にどれほどのモルモットがひしめいているか
数えることもほとんど不可能です。新しい子孫は2か月ごとに生まれます。
かわいい動物たちはブタの金切り声に似たおもしろい声でピーピー鳴き
食べ物に大して足ることを知っています。生野菜と種子がスキニーと
アビシニアン品種のペットのモルモットの好物です。
500 年以上前モルモットはロシアにやってきました。その当時は
ザモルスキー (舶来の) と呼ばれていたのですが、時間とともに接頭語
が取れて現在の名前モルスキー (海の) になりました。
悲しいかなモルモットは泳ぎ方を知りません。それでもここでは
飼育場の住人で、グッチ小学校の生徒たちの寵児は暖かい風呂が好きです。
この子の毛は鼻面にしかありません。そのため暖かいケージで飼います。
「ほら、みなさん、はちみつが欲しいでしょう? はちみつおいしいですよ。はちみつ」
そしてこちらは白いワシの直接の親戚であるハチクマです。
本来の環境ではこの猛禽は有剣類の巣を壊し、そこからこの名前が
付きました。しかし動物園でははちみつで甘やかされ、夏には
なんとアイスクリームまで! 彼ら隣人のハヤブサは喜んで生の肉や
魚に舌鼓を打ちます。ただ翼を痛めているだけです。
ハヤブサはおびえていて、そのためたいへん控えめに行動します。
動物園の飼育環境で生きることにすでに慣れている猛禽にはすでに
ファンができています。
エレナ・ベロウソワ(若いナチュラリスト)
「もう2年もここに通っています。一番好きなのはトビです。
かまないので好きです」
エレナ・ラフマニナ (「子供と若者の創造の会館」主任)
「今の時点では本当の大きなワシはここにはいませんが、親戚がいます。
2種類のハヤブサたち: レッドデータブックにも載っているハヤブサと
チョウゲンボウです。ハチクマとトビもいます。ワシの仲間と呼べる
のはこれで全部です。
このようにイノシシと白いワシ (原文は多分言い間違い) のミニチュアが
暮らしていて、かわいい動物たちをいつでも暖かく世話することのできる
若いアンガルスクの人たちにたくさんの喜びを与えているのです。
ブラーツクのハチクマの事例: アフリカからシベリアへ
(日本と同じハチクマ。アフリカからと書いてあるのはヨーロッパハチクマと誤解しているものと思われる)。
アフリカからシベリアへ:ブラーツクではるばるやってきたお客さんを介抱しています
アフリカに飛んで行きますが、この鳥はここシベリアにとどまりました。ブラーツクの人
は珍しい弱った鳥を介抱しています。
この鳥がどのようにしてここにいるのか、すでに誰と仲良くなったのかをマリア・グルシ
ェンコが伝えます。
この美男子は少し前からエネルゲチク (Energetik) に住んでいます。彼は世話好きの住人
たちに助けられました。住民たちは線路にいたまだらの鳥を拾い上げました。彼にとって
の危険は列車だけではありませんでした。ワタリガラスたちが襲い始めていました。
珍しい鳥の介抱をしているエカテリーナ・イラリノワ「鳥は右の翼を怪我していました。
月曜に地域の獣医に連れて行きました。獣医は翼を調べて骨折はすでに古くて治っている
と言いました。もう翼が元通りにならないので全て癒着してしまっていました。もしそれ
を元に戻したとしてもだめになって鳥は生きて行けないだけでしょう。痛みながら死んで
いくだけでしょう。すぐに誰かに食べられてしまい、自分で食物も得られないでしょう」
地域の鳥類学者が鳥を調べました。普通でないお客さんはハチクマとわかりました。鳥の
通常の食事は昆虫の幼虫です。そのためハチクマはシベリアで越冬せず暖かい地域、特に
アフリカに飛んで行くのです。それがハチクマがバナナも好きな理由です。珍味に舌鼓を
打つことも厭いません:生の肉です。さてこれは彼の新しい隣人であるシロフクロウ
(注: ではないように見えますが言い間違い?) の普通の食べ物です。このフクロウはちょっ
と前に乗馬クラブに住み着きました。これも行きがかり上です。
珍しい鳥の介抱をしているエカテリーナ・イラリノワ「このフクロウは知り合いからもら
いました。知り合いは街で見つけました。女性が子供たちと幼稚園に行きました。玄関の
そばに座っていたのがこのフクロウです。猫が食べたりカラスがついばんだりするのを避
けるために持ち帰ることにしました。カラスが襲おうとしているのが明らかでした。よく
食べてくれましたが手からしか食べません。こうやって餌を置いてやってみたのですが触
ろうとしません」
フクロウはシベリアでは普通の鳥だと鳥類学者のアラ・ハルガエワは言います。見たろこ
ろでは怪我していないようです。しかしぶつかって脳震盪を起こした可能性はあります。
それで動きがないのでしょう。この鳥がすでに屋内で飼われていた可能性も否定できませ
ん。ハチクマもこの地域で生息していますが南の方だけです。極東やサハリンでも生息し
ています。これらの地域ではレッドデータブックに記載されています。イルクーツク州で
は生息数が減少しています。それゆえこのような素晴らしいものを手許に置けることは、
大成功なのです。
鳥類学者のアラ・ハルガエワ「ハチクマを野外で識別するのは大変難しいです。よくノス
リと間違われます。色合いがよく似ています。しかしハチクマは他の猛禽からちょっとか
け離れた点があります。すなわち<ハチ食い>と
呼ばれるように主な食事はハチなのです。ハチクマはハチ、マルハナバチ、野生ミツバチ
の幼虫を食べます。爪が非常に鋭くないことは見ていただけるでしょう。それゆえ素手で
据えています。爪は肉を引き裂くのにはあまり向いていませんが巣を壊すのには向いてい
ます。見ての通り頭に冠があります (注: 英語やロシア語では冠のあるハチクマの名前に
なっている)」
ハチクマが生まれるのは遅いです。6月終わりにようやく飛べるようになります
(注: 7月終わりの間違い?)。そのため9月終わりから10月にかけて渡去してゆきます
(注: もう少し早いと思います)。我らがヒーローも怪我さえなければ喜んでアフリカを訪れた
ことでしょう。
幸いなことに寒くなる前に助けられました。そうでなれば凍え死んでいたことでしょう。
今では「松林の乗馬クラブ」が彼の生家になっています。ここで鳥は力をつけるだけでな
く訪問者の目を楽しませています。
実際にわかったことは、アフリカのお客さんは大変友好的であることです。シベリアの
フクロウだけでなくモスクワサーカスからやってきたラクダともよい関係を築くことができたのです。
ベラルーシのヨーロッパハチクマの事例:
リダの新聞記事 (2019)
朝には暖かい風呂、朝食にはジャムと米。リダで助けられたヨーロッパハチクマは
フロドナ (グロドノ) 動物園でどう
暮らしているか?
「すばらしい」の一言に尽きる。オシャと名づけられたハチクマは
世話を受けて可愛いがられている。彼はあらゆる友情に応えて
なでさせてくれ、喜んで手にとまっていつも自分の鳥の言葉で
つぶやいている。こんなに行いよく社交的なのはたとえ控えめに
言ってもタカ科の猛禽の特徴とは言えない。
しかし全てが違うようになっていたかも知れない - もしこの夏に
木の下でうずくまっている鳥をリダの住民が見つけていなければ。
「鳥を助けた人の名前は知らないが、心の広い行いに感謝している」
とフロドナ動物園の「オウムと猛禽類」課の主任インナ・ヤコフチュク
が語った。「リダの人がハチクマを偶然見つけたことは基本的に大成功
だった。第一にこれは大変珍しい鳥でベラルーシのレッドデータブック
にも載っている。第二にハチクマはふつう人目につかない生活を
しており人から離れて住んでいる。木の下にどうやって来たのか?
多分飛べるようになった若鳥か単に巣から落ちたのだろうか」
リダの人がひな鳥を見つけた時、親鳥が何とかしてみつけるだろうと
期待して、何日かは近寄らず、鳥を動かそうともしなかった。
このアプローチは非常に正しい。しかし何日か経過してもひな鳥は
哀れに鳴きながら同じ場所にうずくまっていた。そこで鳥を家へ
連れて帰ることになった。ここで鳥は1か月餌を与えられ、
強くなって自分で野生に戻れることを期待された。しかし鳥は
弱ってしまい、8月にフロドナ動物園に連れて来られた。
ここでリダの人が目の前の鳥が何という種類か知らなかった
ことは注目に値する。「我々も実は何なのか知らなかった。
動物園に搬送する段階になっても猛禽類の何かとしか知らされ
なかった。鳥の<人格>はこの場でようやく明らかになった」
と専門家は付け加えた。
すぐに社交化したこと、食べ物の変更と新しい習性について
「リダの人はチキンフィレを与えていた。これは控えめに言っても
ハチクマの餌ではまったくない。栄養不良のため彼が来た時は
大変やせていた。体重は標準よりも低かった。しかし致命的な
ほどではなかった。状態は正常化することができた。
たとえどうであったにせよリダの人は全て事を正しく行った。
すばらしい! 感謝する」フロドナ動物園の獣医エレナ・コマレツ
はコメントした。
新しい住人にはオシャと名前がつけられ検疫室に入れられた。
最初の間は慣れたチキンフィレを与えたが、次第にハチクマの
餌にふさわしいものに変えていった。
「最初にオシャが生きたワーム、カブトムシ、幼虫の<ミックス>
を与えられた時、本当の胃腸の有頂天を経験したのです」
獣医のベロニカ・ジャトチク (写真) は写真を思いだしながら
ほほえみをこらえることができなかった。
「すぐに虫を片足いっぱいつかみとって、サギのように
片足で立って休むことなく 10 分ぐらい食べたのです。その後は
チキンフィレは<ノー>のカテゴリーとして拒絶しました。
りんごジャムを付けたチーズを試してみたら、なんと
<注文する>ようになったのです」(ほほえみ)
オシャは米も好きです。他のかゆ (シリアル) のどれよりも
好きです。ひきわりは鳥の一番の好物である幼虫に似ている
と専門家は考えています。ハチクマという名前もハチの巣を
壊して幼虫を食べることでまさに名付けられたものです。
実際に別のおもしろい事例があります。専門家たちは
オシャを子ヤギに馴染ませてやろうと考えてケージの中で
子ヤギのそばに置いたのです。いろいろな野菜や混合飼料
が置いてありました。オシャは迷うことありませんでした。
見渡して、ゆでたポテトを的に足でつかみかかり、まるで
リンゴのように噛んだのです。しかしベラルーシ人
(ポテト好きで有名なようです) にはなれなかったので
その後はもう触らなくなりました。
「オシカ (= オシャ) が馴染みでない場所でどのように
振る舞うか、他の動物を怖がるか見たかったのです。
しかし彼は確信に満ちた以上の行動をしたのです。
反対に子ヤギが敬遠したのです」ベロニカ・ジャトチク
は後見人をなでながら、ほほえんで付け足した。
動物園で家のように
4か月オシャは新しい場所を完全に自分のものにしました。
構ってくれたり、餌を与えたり、喜んで走って会いにくる
人をよく知っています。つまるところ、手にとってなでて
確実におしゃべりしてよいのです。鳥は飛んでみようと
しますが今のところまだ成功していません。
朝にはハチクマの若鳥が暖かい風呂に入りかけるのを
見ることができるかも知れません。オシカは水浴びが
特に好きなのです。
動物園に来る人は、彼がこれほど社交的で行いよいので
好きにならないはずがないと言います。彼がもしこれほど
飼いならされていなければ野生に放そうとしていたかも
知れません。でも彼は私たちと一緒にいます。
人に餌を与えられて、人に愛着を覚えた鳥はもはや野外で
自分で暮して行くことはできず、死んでしまうかも知れません。
ところで、オシャは私にはとても控えめです。肩に
乗せようとするとあからさまにそっぽを向けて
獣医のベロニカ・ジャトチクの手に戻りたいと言います。
これもわかります。彼は本物の紳士で自分の<女性たち>に
忠実だったのです。そのうえこの時は我々の奥の隣の
ケージから彼のできたてのガールフレンドのカーチャが
じっくりと彼を観察していたのです。
動物園では彼女はすでに 16 年以上生きていて、ここに
オシャが現れるまでは唯一のハチクマだったのです。
「誰にもわかりませんが、あるいは私たちのオシンカ (= オシャ)
が若鳥から大人の鳥に変わった時、友情がちょっと
増して... とりわけ彼女を補完する形で新しい家族が
できれば私たちは大変嬉しいです」フロドナ動物園で
新年の願いを分かち合いました。
オシャは「リダ新聞」のための私のわがままを許してくれません
でした。そしてこんな風に...
オシャはあまりに人に慣れているため、人がいる時でないと食事を
しません。人と嬉しそうにしゃべり、ビデオを撮る理由を無数に
与えてくれます。例えば水遊びは彼の大好きな仕事で、そばに
誰かがいる時、特に電話でしゃべっている時に水浴びをするのが
何よりも好きです。
ロシアでバナナを食べるハチクマ:
アフリカからシベリアへ、ブラーツクに珍しいお客さん
ブラーツク (バイカル湖の西側) で飛べないのを住民に救助されたもの。
線路の上にいてカラスに襲われていたそうである。
翼が折れて骨折は治癒していたがまともに飛べないとのこと。
ハチクマは大変友好的で、フクロウともラクダとも友達になったとのこと。
Skalon (2015) "Monitoring Researches of the Vertebrates Included in the Red Book of Kemerovo Region (2014-2015)" Vestinik Kemerovoskogo Rosudarstvennogo Universteta 4(64) T. 3 (ケメロボ国立大学報文) におそらく種ハチクマが保護された経緯がある。
RDB をまとめるための近年の情報として記述されたもの:
2014年8月24日ケメロボ国立大学動物学および生態学部に
ケメロボ郊外のトム川の右岸で近くで見つかったハチクマの巣立ちびなが
連れてられてきました。ひなはまだ飛べず、ひどくやせ衰え、
弱っていました。実験室の鳥小屋では、ハチクマはより強くなり、羽に覆われ、冬を乗り切ることに
成功しました。最初から人に非常に寛容で、散歩のために囲いから出ました。
2015年3月、鳥は突然死にました。剖検の結果は肝臓に炎症と破壊がありました。
ハチクマの顕著な食べ物の好みは、一日齢のひよこの死体を特に喜んで食べ、
次にマウス、次に果物で、甘いものを好みました (バナナ、ブドウ、ネクタリン、
熟した梨、オレンジ)。昆虫 (コオロギ、ゴキブリ、ズーフォバス) はしぶしぶ
食べ、しばしば捨てました。魚は拒否しました。
(注: 昆虫食がしばしば強調されるが必ずしもそうでもない模様)
2015年9月9日ケメロボ地域ウポロフカ村近くの道路で非常に明るい色の
若いハチクマが見つかりました。犬がうずくまっている鳥を攻撃していました。
鳥を見つけた女性は1週間鳥にソーセージを与えましたが、その後鳥は
大きく衰弱し、やせ衰え、腎臓と肝臓に損傷を与えておそらく慢性的に
下痢をしていました。ケメロボ国立大学動物学および生態学部に移送
されましたが救うことはできませんでした。鳥は見るからに弱っていました。
最初の日は自分で歩いてひよことネズミの肉をついばんでいました。
次は飼育個体ではないがロシア関係で Galushin「猛禽類」よりヨーロッパハチクマの記述:
ハチクマ (ヨーロッパハチクマ。以下ハチクマと表記) は
例外的にのろのろしていてぎこちないが、これもまた理解できる。そのような
「狩り」においては辛抱強さが特に必要で、敏捷性は特に必要ない。
ハチクマは猛禽類の中で「待ち」のチャンピオンに挙げられるだろう。
筆者がブラインドから最初に観察した時からすでに動じないことに気がついた。
巣にいる他の鳥を観察しても、絶え間なくいろいろな方向を見渡して羽繕いをし、
産座の上で何かをあちらからこちらへと移動するのを見ることになるだろう。
ハチクマは実際まったく動くことなく 20 分、30 分、さらには 40 分も座り、あるいは
立ち続けることができる。巣にじっと立っていたハチクマの記録は2時間47分である。
この記録はおそらく猛禽類だけでなくあらゆる鳥類の中でも最高のものだろう。
考えてみれば、このようなハチクマの特性はもちろん独特の「狩り」の
能力であって怠慢さでないことにちょっと驚かされる。この能力はハチクマにとって
例えばハチが巣の近くのどこかで飛ぶ方向を追跡する時に大変重要である。
そして巣に入る(巣は地上にあることも多い)時にもできるだけ正確に
見つけ出し、その前に巣のハチを騒がせるべきではないのである。
「ためらわずに」どこかに立ち続ける能力はなかなか役に立つのかも知れない。
器用さの点でもハチクマは抜きん出ることはない。ハチクマついてはちょっとした
特徴がある。巣に飛んで来る時や単に枝から枝へと飛び移る時に雑音を出して、
我々も鳥が近づいてくることを聞いて簡単に知ることができる。
ハチクマが森の中を飛ぶ時、絶えず翼を枝に当てながら樹冠を貫いてまっすぐに
飛ぶ印象を受ける。
ハチクマの「気性」についても、その言葉が比類なき鈍重さを指すものであっても
多少述べておかねばならない。ハチクマは何時間も微塵とも動かないだけでなく、
まったく安全でないものを含めたあらゆる外部刺激にほとんど反応しない
ことがある。何よりも注目されるのはハチクマが驚くほど人に無関心である
ことである。巣の下で騒々しく歩き回るキノコ採りの集団や、道を歩く伐採人、
牧夫は言うに及ばず、ハチクマがまったく注意を払わなかったことを我々は
ブラインドから何度と見ている。その上、大部分のハチクマは我々にさえ注意を
払わないのである。何度も訪れて彼らを十分飽き飽きさせているかも知れないが。
観察者が営巣木のほとんど半分ぐらいまで登った時にようやくハチクマが飛び立つ
こともしばしばである。巣のすぐそばにブラインド小屋があってもハチクマは
まったく気にしない。
雛を育てる時期に親鳥を観察小屋から追い払うこともそれほど簡単でない。
せきをしたり大声でしゃべったりしてもハチクマはあまり気にしない。
観察者の交代の際に出て行こうとする際に、小屋からジャケットをハチクマの
文字通り嘴の前に投げ出しても、鳥は冠羽をちょっと逆立てて嘴を開け、
翼を羽ばたきかけて...そのようなばかげたポーズで固まってしまうのである。
しかし人間が出てくるとハチクマはそれでもやはりちょっと離れたそばの木に
飛び移るのである。
このような猛禽類としては普通でない行動には最初は戸惑わされる。
しかしよりよく考えてみればこの森の中ではこうやって最低限の声も出さずに
警戒するのが鳥にとってはより安全なのかも知れない。そこではもっと強い
猛禽類が大抵は舞っているだろうし、声を出したり音を立てることは
人を巣に近づけるだけである。
ハチクマのこのような行動を見ていると、ジュネーブの公園でハチクマ
のつがいが営巣してすっかりすぐに人慣れしてしまったことを読んでも
もうちっとも驚かない。
ハチクマの行動と食性はこのように極めて特異であるが、他の点では
他の猛禽類とほとんど違いはない。
出典: Khishchnie ptitsy (猛禽類) Vladimir Mikhajlovich Galushin (1970)。ヨーロッパハチクマ。
他の種に比べて解説が詳しく、著者にとっても面白い鳥だったのだろう。
ロシアの飼育フォーラムから: Ingrid (ヨーロッパハチクマの保護個体飼育記事 2013)
(臭気と行動に関係する部分を抜粋訳。口語なので訳があまり正確でない部分もあると想像する。皆さん興味津々なのがよくわかる)
Lilit
それからもう一つ、ハチクマの糞についてはいろいろ言われていました。
臭いは家族にとって耐えがたいか、あるはそうでないか、カラス類を飼っている
自分の経験からも知りたいです。
pepetka94
うわ、何という大きさ。最初の写真を見た時はハチクマはもっと小さいかと
思いました。自分が思うに強情さだけではなく (注: 牛のように強情、などの
慣用句があるようです)、大きさもほとんど雄羊ほどもあるではないですか。
これからもこのテーマを楽しみに読みます。
ハチクマのことをもっと書いてください。カラス類とどれほど、
どのように違うのか興味があります。もちろん写真は歓迎です。
この写真は実に驚くべきです。鳥があまりに大きいのでフレームに入りきって
ないです。翼の端が画面から切れています。
p.s. 床は走りますか? ハチクマは座ったままどこへも行きたがらない
ようです (フォーラムを読んでそう思っています)。
p.s.s2 ビデオをぜひ。鳥がどう動くのかとても興味あります。
Lerois (飼育者の鷹匠)
to Lilit: 糞はまったく臭わないです。ところで、他のタカ類のように糞を
遠くへ飛ばさないです。カラス類のように下へ落とします。イングリッド
には1日に1回、夕方に餌を与えています。ほとんどの時間夜の間、糞は
とまり木の下に残っています。ハチクマの糞はカラス類よりだいぶ少ないです。
少なくとも今のところ。というのもイングリッドは今は食べないです。
おそらくは怪我や治療、運搬の後のストレスに関係しているのでしょう。
早く回復して自分で食べられるようになって欲しいです。
to pepetka94:
はい、カササギの後ではイングリッドは巨大に思えます。これは娘が撮った
写真で、なのでこの程度の出来上がりになっています。
はい、アパートの中全体をよろよろしています。だいたいは高いところに
いますが、時によって床を歩きます。だいたいは靴下を探してです。
私の縞模様の靴下に興奮して、靴下をけちらしてしまいます。
それにしてもハチクマはまったく猛禽類ではありません。
ビデオをすぐに撮ることは無理です。カメラは友人と旅に出ています。
帰ってきたらすぐに撮ります。
pepetka94
食べるのも少なくて糞も少ない? その上カラス類のようにコンタクト
できるとは、まさしくすごい鳥 (super bird。原文で英語の super がそのまま使われているので形式的に訳してみたが、文脈から "理想の飼い鳥" と訳してもよいかも知れない) ではないですか。そんなのが欲しいです。
1日に1回でたくさん食べるのですか? とまり木の横であなたと
一緒に過ごしているのですか? これほどの大きな鳥には最低でも 1.5 m
の部屋かケージが必要そうなのに。
p.s. こんな鳥が欲しいです。でもすぐには実行できません、妻が鳥とともに
追い払ってしまうでしょう。
p.s.2 とまり木の生活は最初のメッセージで読みました。さらに質問です。
とまり木につないでいないですか。アパートの中で何も壊さないですか。
p.s.3 水浴びは、これほど巨大なのには水場を作る必要があるでしょう。
Lerois
いいえ、食べるのが少ないわけではないです。今は強制的に食べさせる
必要があるだけです。コンタクトはカラス類と同じというわけではないです。
ずっと少ないです。1.5 m でも小さいでしょう。というのもイングリッドは
とまり木で生活しているからです。私たちが家にいる間はつないでいます。
リードを付けています。今日は初めてリードをつけたままでひとりにして
おきました。そして何も壊さず何もだめにしません。翼で投げ捨てる程度です。
いまのところ水浴びしません。普通ハチクマは給水器でさえも水浴び
するぐらい好きなのですが。
実際のところハチクマを飼育するのは十分難しく、チョウゲンボウ類よりも
難しいです。初めて HP に載せるならばチョウゲンボウがよいです。
ハチクマはとても優しく臆病です。気性はとても優しいです。
Lerois
イングリッドは渡りの衝動が強まったのです。いつもどこかへ飛び立とうとし、
餌を拒否してよく鳴きます。最終的にどこかに「たどりつく」のを待って
いますが、待ちきれていません。餌を何度も置いてやりますが必ずうまく
行きません。食べないだけでなく、餌台をひっくり返してしまいます。
ついでに混ぜもので足から頭から汚し、とまり木をわざとらしい柄に
染めてしまいます。カエルも運悪く全部隠れてしまいました。
今日も探したのですが一つ見つけただけでした。夕方またカエル探しに
行きます。
SleepingSun
養い子たちおめでとう。糞が臭わないのは面白いです。うちのハチクマはみんな
臭いやつでした。糞は臭って、ストレスを受けた時はまるでスカンクのように
どこかジャコウ臭のような臭いを出していました。すべての臭いが不快という
ほど簡単ではないですが、比較すると、例えばオオタカは私の考えではまったく
匂いません。直接に鼻をあててかいでも羽の匂いがするだけです。ハヤブサ、
特に大きいのは少し稚魚の匂いがします。そしてハチクマは、おぇっ、くさっ!!!
しかしお宅にカラス類がいるなら比較してみると、同程度の臭いか、あるいは
一層臭わないかも。臭いに気をもむこともないです (注: カラス類よりも臭わないらしい)。
餌については子供をあやすようにすることは止めた方がよいです。自分で食べるか、
器からか、あるいは飛んで来させる訓練をするならばグローブから食べる
ようにさせます。生ぬるい状態で、腹も減っておらず、甘やかさせると
あなたの後を追って「ママ、ニャムニャム!」と歩いて来てしまいます。
ハチクマの気性についても同意しません。他のものはどうであれハチクマの気性は頑強です。
どんな猛禽でも薬を与えたり、リードを付けるときなどは手でつかむことは決して
やってはなりません。全てはフードをかぶせて、誰がなぶりものにしているのか
聞こえさえしないように静かにする必要があります。そうすればハチクマは
無関心になります。自分がくちばしや爪を切る時は何の策略もせず、足指をつかんで
タオルを巻き動かないようにして鳥を前へ置きます。処置を施してから腹を立てる
のは最初の 15 分だけです。その後足をひっぱり出すなどなどすればよいです。
ところでハチクマは歩くのが好きです。
Lerois
to SleepingSun
ありがとうございます。いえ、恐れている時にはちょっと臭いが感じられます。
しかし簡単に言えば臭わないです。うちのカラス類も臭いません。
お客さんが来た時でさえ、こんなに動物がいるのに臭いがしないと驚かれます。
もちろんサボって1、2日掃除をしないと、もちろん臭いは華々しくなります。
もし無理でなければもっと詳しく教えてください。単に自分から食べないのです。
まったく。混ぜものの入った器の前に2日とまって、まったく手をつけませんでした。
私のところに十分やつれた状態でやってきて、竜骨がつかめるほどでした。
今では多少筋肉が付いてきました。満杯の器を前にしたまま飢えて死んで
しまわないでしょうか? ハチクマにはとまり木はどんなものがよいか
よくわかっていません。切り株タイプがよいでしょうか、それとも枝でしょうか。
アドバイスを受けて切り株にしました。試してみるとイングリッドは尾を
擦れさせ始めてしまいました。床を歩かせてやる方がまだ悪くないです。
端の方はもう擦りきれています。
その上鳴き声です。誰かがイングリッドの生活の見えない境界に入り込むと
頭の羽毛を立てて大声で鳴くのです。ずっとこういうままなのでしょうか?
Lerois
やった! 自分で食べてます!
Larkha
おめでとう! このような種類の鳥で、このような状況だと上出来でしょう。
Lerois
ありがとう! この鳥の自分を目立たそうとする行動にどれほど神経を使うことでしょうか。
SleepingSun
おお、餌は解決したのですね。すばらしい。しかしながら春と秋にはハチクマ
はハンガーストライキを見せることがあることに注意するとよいです。
たぶん渡りの不穏を表しているのでしょう。
とまり木についてはハヤブサ用のタイプが一番よいです。つまり切り株ということです。
尾が擦れるのはとまり木が低いのでしょう。尾で台座か床を掃いてしまうのです。
(とまり木がどのような作りなのかわかりませんが。写真でもあれば)
そんな風に羽根で床を擦ってはいけません。
糞についてはよく知りません。ハチクマでは一度まっさらのおしめに糞をして
くれたことがあります。未だに臭いがします。自分は気難しがりやなのかも知れないが、
もちろんそうですが。たまたま、ハチクマはいつもすぐすぐそばにいて、
とまり木がコンピュータのそばにあったのです。
Lerois
to SleepingSun
お返事ありがとうございます。ハチクマの情報がとても少なくてちょっとずつ
集めています。とまり木は切り株タイプで、尾は床に届かず、擦ったりしていません。
床に腰を下ろしながらアパートの中を散歩するという悪い癖が出ているのです。
驚いてそうしているような感じです。ネズミを見つけたかのように驚いた様子で
尻をついてしまうのです。
とまり木は部屋の中に立てています。興奮した時や何かを恐れているときに
確かに十分臭いを感じることを言っておかねばなりません。そして糞は..臭いません。
臭いにうるさい母でさえも怒りません。
昨日は散歩に行きました。イングリッドはグローブに乗って初めてバスに乗りました。
最初のうちは少し興奮して鳴いていました。しかし頭を手で覆うとすぐに
静かになりました。10 分ぐらい「夜」のままにして、また周囲が見えるように
するともう鳴きませんでした。グローブから肉をとるようにもなりました。
夢中になって私を指でつかみました。とても痛かったです。
さらに、歩いている途中、突然私の頭によじ登りたくなりました。
道を行く間に爪が首や耳や頬に当たりました。その結果、残りの散歩の間
耳は傷だらけで恐ろしい恰好でした。これもまた最初の試練です。
気を抜かず、鳥は正しく持つ必要があります。なぜならばこれはカササギとは
まったく違うからです。
そう、ペリットは出しません。これが正常なのか自信がありません。
一日に一回食べます。夕方でだいたい同じ時刻です。
ペリットのために混ぜものにはにんじんを入れ、砕いて粉にした首の骨や
2-3 日に一回毛や骨の付いたネズミを与えています。確かにネズミは
大部分の皮や骨はそのまま残るようにかじっていますが。
しかし残りの全てはペリットになるはずなのですが。
SleepingSun
尻をつくのは普通で正常です。同時にどうやって羽根を守ればよいかは知りません。
単純に換羽を待つことでしょうか。うちにも同じような成鳥のハチクマがいて尻をついて
いましたが羽根は理想的な状態でした。ハチクマはほとんどペリットを出しません。
ちょっとした小さな何かの塊を時々出す程度です。多くの場合気がついていません。
Lerois
すでに書きましたようにイングリッドは一人で食べ始めています。
確かに今は自分に差し出された食べ物を食べるだけでなく、指、手、足、
鼻や、人間にとって極めて重要でない体の突出した部分も食べようとします。
ハチクマのそばをソックスなしで通るのはごめんです。目標まで「ターミネーター」
のような頑強さで歩いて行きます。伸びきった xxx に注意を払うこともなく。
5 分か 10 分歩いて一ヶ所で踏みつけます。その後怒って自分の切り株に
戻って、30 分ぐらいたったらまた「獲物」を求めて「大遠征」をします。
さらに新しいことです。グローブに飛んでくる訓練を始めました。
今のところ、数メートル離れたところから呼び笛で喜んで飛んできます。
もちろん無償で飛んでくるわけではありません。グローブから落ちることは
ほとんどなくなりました。散歩の時に何回も落ちていたのですが、
一日に一回も落ちなくなりました。水浴びは期待していません。というのも
水の入った器を完全に無視するのです。そのため餌を与える前に肉を
ちょっと水につけるようにしています。
[飼育下の行動: 韓国の事例]
韓国で保護されたハチクマの映像を Chungnam Wild Animal Rescue Center (忠南野生動物救助センター) がいくつか紹介している。ここでは大学 (韓国忠清南道の公州大学 Kongyu National University) と共同で行動研究なども行っていたようである (現況はわからない)。
2012 年に保護された個体の記事
これによると人に非常によく慣れて、餌を与えることも容易で飼育は楽だったとのこと。
「大きなインコ」のようだとのこと。飼育することで動物に与えるストレスを考える必要があるが、この鳥の場合は空腹になると鳴くために、むしろ飼育する方がストレスを受けるぐらいだった。
本当に純真で穏やかな鳥であるとある。水を飲む姿を見ると間違いなくオウムに見えるとのこと。
他の個体の行動を見てエンリッチメントのための新しい餌箱の使い方を学ぶ様子。メスの「爪」さんはこのツールに習熟しているが、新しく入ったオス (2015 年に救助された個体とのこと) はまだ使い方を知らない。動物の観察力や思考力を調べているとのこと。
おもちゃのように見える物の中に餌が隠してある。
それを食べているところ。
レンコンの穴にブルーベリーが埋めてあるそうです。夏場には凍ったブルーベリーやいちごを与えていて大好きだそうです。元獣医スタッフだった方からの情報では大変友好的で愛らしい鳥であるとのこと。
同上。
以下はより最近の映像:
Me hummingbird, Claw. I prefer berry juice the most.
(都合上英訳でタイトルを示す)。「爪」さん (タイトルの Claw) で、いちごジュースが大好き。自分はハチドリだよ、と言っている。
It's a great curiosity to make a snowman for friends who are relatively unfamiliar with snow than other species.
雪だるまを壊すハチクマ。野生下では雪とはほとんど縁がないはずだが興味津々?
[飼育下の行動: チェコのヨーロッパハチクマ]
次はチェコで保護されたヨーロッパハチクマの話。Vcelojed vcely nerad! Zato lipanky...。最初は自然の食べ物にハチの子をまぶしたものを与えていたが、最後には子供のおやつである lipanek を食べるようになった。
1日に2パッケージを平らげるとのこと。lipanek だけでは不十分なので虫も与えているが、虫も高価で
うちでは一番餌代がかかるやつだとのこと。
冬で放せないので翌年に放鳥する予定とある。lipanekとはクリーム+コッテージチーズのようで、子供のおやつに最適とある。
[飼育下の行動: ドイツのヨーロッパハチクマ]
Nahrungsspezialist Wespenbussard (ドイツの猛禽類保護組織 greifvogelhilfe.de の情報)
食べ物のスペシャリスト ヨーロッパハチクマ (Sylvia Urbaniak 著から)。
機械翻訳で多分意味がわかると思うが、個体の一時保護に重要そうな情報も含まれており、保護施設にも有益と思えるため抜粋訳を提供しておく。ヨーロッパハチクマの若鳥が保護されることがしばしばあり、問い合わせもあるので FAQ 的に記述された文章ではないかと考える。この訳文内ではヨーロッパハチクマをハチクマと略した (おそらくどちらの種にも通用すると思われるため)。
(前略) [鳥小屋での飼育]
ハチクマは自然界でと同じように、鳥小屋の床を傷つけ始めました。
最大地下 30-40 cm の最大深度はすでに報告されています。従って
いつかある時に彼が鳥小屋から自分自身を掘り出せないようにすることが
重要です。
ひなを親の巣や発見された場所に戻すことはこの種では逆効果であり解決策に
なりませんが、他の猛禽類やフクロウ種にとっては正確に正しい方法です。
通常は巣も見つかりません。ハチクマは巣を緑で覆い、届かない高いところに
巣があるためです。
[間違ったインプリンティングに注意!!]
ハチクマは非常に賢い猛禽類です (*1)。毎日食べ物を持って来る人を見ると、
間違ってインプリンティングされてしまいます。兄弟と育てることは間違いなく
この種にとっての解決方法です。より大きな猛禽類ステーションに連絡する
ことができるならば間違ったインプリンティングを直接防ぐ良い方法でしょう。
私たちは連絡を歓迎します、そして私たちは一緒にどうするかを議論する
ことができます。手で餌をやるのは避けるべきで、鳥が自分で立てるように
なった時点から不要になることが重要です。2019 年には、病棟に合計4羽の
ハチクマ患者がいました。私たちは育てかた、飼育方法、越冬に精通しています。
この猛禽類では放鷹術の訓練は必要ありません。実際に幼鳥をそのまま
冬を越して手元に置くことは完全に間違っています。
例外は、翼の骨折が治癒した場合、または非常に長期間の休息を伴う越冬が発生
した場合にのみです。ハチクマは上昇気流で飛ぶ鳥です! リリースは適切な日
にのみ実行する必要があります。10 月以降のリリースは、渡り去るのに十分な
上昇気流がないことが多いため、この種にとって高いリスクを伴います。
[越冬]
ドイツでの越冬は絶対に避けなければなりません。尾の羽毛の欠陥は、
ハチクマを越冬させる理由にはなりません。何らかの理由で羽毛が破壊された
場合、通常は羽毛を接ぐこと (英語 imping; 放鷹術の技術) ができます。そのような鳥を越冬
させる方が問題ははるかに大きいです。ほとんどの場合、深刻な羽の問題に
つながり、それがこの長距離の渡りする鳥をにとってまさに問題になる可能性が
あります。さらにこの暖かさを愛する猛禽類は氷点下の気温に備えていません。
ここでは冬には換羽が起きません。翼の浮腫のリスク (*2) は、モモアカノスリ (ハリスホーク) や
トビなどの場合と同じであり、最悪の場合、鳥の命にかかわる可能性があります。
冬の間、この猛禽類をフライワイヤーシステム (Flugdrahtanlage、吹きさらしの屋外飼育施設) で
飼育することは、時限爆弾と見なされるべきです。このタイプの飼育施設を
用いないよう強く勧めます。しかし放鷹術の手法は、鳥を落ち着かせて、
逃げようとして羽が損傷しないようにするのに役立ちます。
(中略) 若いハチクマは、自然の渡り時期に野生に放鳥されるべきです。
上昇気流で飛ぶ鳥なので天気と天気予報が正しいはずです。これは越冬中の
鳥には適用されず、夏に放鳥すればよいです。このために鳥は必ずしも
健康状態のトレーニングを受ける必要はありませんが、特に優れた
栄養状態を持っている必要があります。越冬した鳥が野生に放たれるとき、
天候と昆虫の状況は最適でなければなりません。鳥はハチクマも生息している
ことが知られている適切な生息地で放鳥されることが望ましいです。
これは、若鳥(KJ2 動物: 2暦年 calendar year の意味と思います)
にとって特に重要です。なぜなら、彼らはほとんど経験がないからです。(中略)
しかし、7月と8月には、養蜂家からミツバチの子を入手するのはもはや簡単
ではありません。したがって、養育のためにハチクマを定期的に受け取る
ケアステーションは、適切な時期に在庫を確保する必要があります。(中略)
与えることのできた他の食物は、1日齢のひよこ、げっ歯類、ワックスウジ、
ミールワームとその蛹、前もって殺したハエの幼虫とバナナの断片を細かく
切ったもの、熟したサクランボと熟した梨程度です。
ミツバチの子の贈り物の受け入れは最高であり、すぐに受け入れられます。
可能な限り、ハチクマは強制給餌されるべきではありません! (中略)
注意: ケアステーションでの越冬は、あらゆる状況下で避ける必要があります。
試行しないでください。したがってハチクマは専門家の手にのみ属します。
わら、干し草、削りくず、樹皮マルチ (mulch)、さらには新聞紙の上に置いては
いけません。鳥の羽は非常に繊細で、飼育下で簡単に損傷します。(後略)
備考:
*1: 原文で使われている単語は pfiffig。辞書訳では狡猾な、ずる賢いとあるが、対応する英語を調べると smart, cute, foxy、他の辞書では「抜け目のない、ちゃっかりした」とあり、次に挙げる文章を翻訳いただいた笠井氏に聞くと「賢い」でも構わないだろうとのこと。「ちゃっかりと人に慣れる」ぐらいの意味と思ってよさそうな感じがする。
日本の動物園の個体も飼育員をよく見分けていて、単に餌をくれるだけの飼育員にはあまり愛想がないが、時々遊んでくれる人には餌をもらわなくなってから年単位経過しても甘え声を出していた。インコでも餌を与えている人より遊んでくれる人に懐く印象があるがそれに近い。
この飼育員の方とハチクマのケージの前で立ち話をしていた時、ハチクマはキューキューとよく鳴いていた。ちょうど犬を連れて散歩中に他の人と出会って立ち話をすると犬がこちらにも構って欲しいと鳴く様子に似ていた (タカがそんなことをするのか!?)。
あるいは一緒に会話に参加しているつもりだったのかも知れない。「ハチクマのお客さんになって」にも同じような記述がある。ハチクマの社会性を考える上でも興味深い。
*2: Wing tip oedema in raptors
典型的には本来暖かい地域に住む猛禽類が寒気に晒されると発症することがあるとのこと。
(手根骨付近に炎症が生じる)。その年生まれの鳥に多い。
日本語では翼端浮腫 WingTip という (以前は獣医師による日本語ブログがあったのだが現在は存在しないようである)。
普段野鳥観察をしている時に、翼を閉じた状態で「手」にあたる部位がどこにあたるかあまり考えることはないかも知れないが、少し考えると寒風を受けやすい場所であることがわかる。足先や嘴のように羽毛にうずめて暖めることができない場所なので寒さに弱い種類では凍傷を起こしてしまうことがあるのだろう。
ドイツの Alfred Brehm 「ブレーム動物事典」(Brehms Thierleben 世界では有名な本だが和訳本は出ていないようである) の該当ページ Unterfamilie Busarde (Buetoninae)
(1893 年初版; 当時はノスリ類として扱われていた) からヨーロッパハチクマの興味深い行動の部分をスイス在住の笠井潔氏に翻訳いただき、自分で少し修正と注釈を入れたを紹介しておく。(注: 当時はヨーロッパハチクマとハチクマは同種とされていた。文章で扱われている種類は現在はヨーロッパハチクマであるが、ハチクマと記載する)。
Behrends によると、ハチクマは飼育していて大変に楽しませてくれるようです。
「私が捕まえた飛べるオスは、数週間後には彼が知っている人や私の犬達に対して非常に
信頼し、それどころか甘えるぐらいになりましたが、知らない犬すべてに対しては攻撃的な姿勢を
とり、羽を逆立てて攻撃しました。 彼はある小型犬が特に好きになりました。
その犬が横になると、彼はその足の間に座って遊んだり、くちばしで毛をかき回したりし、
犬もそれを好意的に我慢していました。
ハチクマは食べることに関してのみ油断ならない性格で、自分に
逆らわない犬は食べ物から追い払い、しばしば自からは食べないで
長い間食べ物を見はっていました。 彼は家の内外を走り回り、あるドアがロックされて
いるのを見つけたときは、ドアが開くまで全力で叫んだのです。
夏に彼は毎日私のアパートの近くの公共の庭を訪れました。そこでは彼は人気のある
ゲストであり、いつも何かを投げてもらいました。夏の終わりから秋にかけて、
彼は刈り取られた畑で食べ物を探して半日歩き回ることがよくありました。
彼は「ハンス」という呼びかけを聞いても、ご機嫌か空腹のときにだけ来ました。
機嫌が良い時は、女性の膝の上にジャンプしたり、翼を持ち上げてその下を
引っ掻いてもらって明らかに心地よさそうにに目を閉じたり、肩に座って髪の毛で遊んだ
りしていました。誰かが彼を傷つけた場合、彼は長い間それを覚えていて、その人を避けま
した。
お腹が空いたとき、彼はいつも彼に餌をくれるいるメイドを家中叫びながら追いかけ、
彼女の服を引っ張ったりしました。彼女が彼に抵抗すると、彼はひどい声でなき叫び、
立ち上がって身を守りました。彼の好きな食べ物はロールパンとミルクでした。
しかし、彼はまた、肉、穀類粉の食べ物、ジャガイモ、そして時には小鳥など、
他ものをなんでも食べました。
庭の茂みからぶら下がっているハチの巣は、これっぽっちも彼を魅了しませんでした。
彼は頭を振って頭の周りを飛んでいたハチを撃退しようとしました。
もし彼のくちばしの前でハチをみせても、彼はそれらを噛み殺しましたが、
決してそれらを食べませんでした。彼は寒さにとても敏感でした。
冬になると、彼はしばしばストーブの下に隠れ、
彼が室内にいることはあまり皆に喜ばれなかったので、自分がいることを
さとられないように静かにしていました。
一般的に、彼の態度は猛禽類というよりはカラスのようでした。
しかし彼の動きは (カラスより) 悠然とし、慎重で、すり足で歩き回り、
決して飛び跳ねず、追いかけられているときだけは、
数回飛び上がりました。彼は3年後に亡くなりました。
ずっと以前に捕らえたメスは、ハチの幼虫が大好きでした。
メスの前にハチの巣を持っていくと、目に見えて興奮し、熱心にそれを
突いて、ハチの幼虫を丸飲みしました。空になったハチの巣を今度は幼虫を探して、
バラバラに引き裂きました。それ以外の点では、前述のオスと同様に、彼女の好きな食
べ物はロールパンとミルクでした。しばしば死んだ鳥は手つかずのままにしました。
メスはそれよりカエルを好みました。コフキコガネ (訳注 こちらで5月によく見られる
昆虫です) も一応食べましたが、特に好きではありませんでした。
ハチクマは私の他のペットに対して非常に協調的でした。
ハチクマがペットたちと一緒に、つまり2匹のモルモット、ムクドリ (注: 現在の和名では
ホシムクドリ)、
ヨーロッパムナグロ、2羽のウズラと一緒に一つのボウルから食事をしているのを見る
のはそれは楽しかったです。 言及された動物のどれもが彼へのほんのわずかな恐れすら
も示しませんでした。ええ、、せんさく好きなムクドリはしばしば
餌に対する妬みから彼を噛んだり、顔にミルクをはねかけたりしましたが、
しかし彼は全く落ち着いてそれを甘受していました。
時々、そういう場合でも彼は非常に威厳を持って立ち上がって、誇らしげな表情で
彼のごちゃまぜの食事仲間のグループをを見渡しました。
ある時ハトを受け取ったので、ハチクマの隣に置いたら、
ハトが恐怖を示さずにタカ (ハチクマ) の近くに寄り添ったとき、少なからず驚きを覚え
ました。
ハトはそれどころか決してハチクマの側を離れようとはしないほど、ハチクマへの
愛着を示しました。ハトがハチクマの隣にとまっていたとまり木から食べ物に飛び降りた場合、
ハトは飛ぶことができなかったので、ハトは我々がまたとまり木に乗せてやるまで、
ハトの友達 (ハチクマ) の下をウロウロ行ったり来たりしました。
ハチクマが落ち着いて行動しなかった場合、
ハトはしばしばハチクマをつつきましたが、それでもこれはハチクマをまったく怒らせ
なかったようです。
ハチクマは人間や前述の動物に対してかくも気さくに振る舞うのに、、
犬が近づいたときはとても意地悪でした。
矢のように速く、大変に怒って犬の頭を撃ち、爪足を立て、噛み、翼で
引っ叩きました。彼は羽を逆立て、猫のようにシューッと唸り声を立てました。
犬は、最強で最も悪質なものでさえ、最大の恐怖に陥り、遠くに逃げました。
犬が逃げ出したあとも、彼はすぐには落ち着かず、しばらくは近くに来るもの全てに
やたらめったら怒り任せに噛みつきました。
彼は太陽の光がとても好きだったので、翼を広げてくちばしを開いて開いた窓べに
座ったり、隣近所の屋根に飛んだりすることがよくありました。 彼は雨をとても嫌がり
ました。
突然雨にあったりしたら、彼はすぐに近くの隅に逃げ隠れました。
彼はまた、寒さに非常に敏感だったので、冬の間は作業室に保管しなければなりませんで
した。
[飼育下の行動: ドバイ (UAE) で保護されたハチクマ]
これは一時保護個体であるが内容は大変面白い (ビデオあり):
Video: A rare migratory bird rescued by Dubai resident (2021)
ハチクマの分布が西に広がって中東も渡り地域になってきていることもわかる。
(前略)「午後4時のことで Damac Hills の自宅でリモートワーク中でした。
忙しくコンピュータに向かっていると突然大きなどすんという音を
聞きました。文字通り椅子から飛び上がってびっくりしました。
何者かがバルコニーの窓に飛び込んでいたのです」
と Michael は語りました (中略)
外はものすごく暑く、鳥は深く早い息をして
いてすっかり憔悴しているようでした。すぐに何か、とにかく何か
しなければ死んでしまうと思いました、と付け加えました。
Michael はドバイの熟練した鷹匠の友人の Hendry に電話をかけました:
Hendry に写真を送ってぶつかった鳥は何かを聞きました。
Hendry は鳥をすぐに日光から遠ざけて日陰に入れるように
と指示しました。何だって! ニワトリでさえ生きたのを掴むのは怖いのに! (中略)
「そっとタオルをかけて翼を片側ずつ掴んで鳥をゆっくりと浴室に
運びました。鳥は安心したようで一気におとなしくなりました。
照明は点けたままにしてドアを閉じました。時々何をやっているかを
覗いていました」
「浴室に猛禽を入れた人なんてあるでしょうか? 多分ないでしょう。
しかし鳥は手洗い場に堂々ととまっていました。鏡に写る自分の
姿にほれぼれしているかのようでした」、そして Michael は冗談の
ように「鳥はさらにやらかしてくれました。どうやったのか
"偶然に" 蛇口を開けてしまったのです」と付け加えました (後略)。
囚われの身でありながらいきなり気になるものを触ってしまうハチクマのいたずら好き (初めてのものを怖がらない) の様子がわかるが、
カラスがこれをやれば天才と言われそうな気がする。
GPS タグを付けて放ち渡りを追跡するとのことで、救護体制とともにこのような準備が整っているのは素晴らしいと思う。
本稿では蛇口を開けるカラスの話題は現状取り扱っていないのでここに含めておくが、Klump et al. (2025) Emergence of a novel drinking innovation in an urban population of sulphur-crested cockatoos, Cacatua galerita
オーストラリアのシドニーでキバタンが給水場の蛇口をひねって水を飲む行動が発明され、複数個体で少なくとも2年にわたって続いているとのこと。過去の報告事例を知らないとのことで、日本のカラスの事例は目に触れる形で論文化されているのだろうか。UAE のハチクマは因果関係を理解し、機会があれば継続して利用しようと果たして試みただろうか。タカがそんなことをするはずがないと考えられ、検証も行われていないかも知れない。
改めて考えてみると UAE で保護されたハチクマも救護されるまでは炎天下で、水を与えたとは書かれていないので、落ち着いてみると猛烈に水が飲みたくなったのではないだろうか。
鏡の中の自分を見ていたのではなく、何とかして水が飲めないか考えていたのではないだろうか。試してみたらたまたまうまく行ったのかも知れない。器具は説明がなくても人が初めて見て使える程度には工夫されていると思われる。つまり操作法がわからない場合でも一番簡単な操作が正解になっている。いわゆる人間工学だな。そうなっていなければ設計が悪いと文句も出る。鳥にとっても自然な発想の範囲で試してみることができたのかも知れない。人間工学ならぬ鳥工学になっていた (?)。
オーストラリアも乾燥地で飲水要求が非常に高いゆえキバタンが行動を編み出したのだろうと考えると共通性が感じられる。
さらに考察を巡らしてみると、手洗いに鏡を設けてあると、鏡像の自己認識ができるかを問わず同種の姿に関心を持つだろう。つまりランダムに行動しても自動的に手洗い場に引きつけられることになって水を出せてしまったのかも。
手洗いに鏡を置く本来の目的は別かも知れないが、結果的に人間 (鳥) 工学とうまく合うことになったのだろう。手洗いと反対側の壁に鏡が置いてあれば設計が悪いとおそらく文句が出るだろう。
ハチクマが自分で蛇口を開けてしまった話を動物園の飼育員の方に伝えると、それは納得できるとすぐに反応された。動物園のハチクマを一時的にフクロウ類のケージに入れていた時、さわって器具を動かしてしまったとのこと。以来ハチクマを入れるケージに動かせるものを入れるのは危険と撤去されたとのこと。
あくまで一面の評価に過ぎないが、フクロウ類のケージに入れてあっても大丈夫だったことは両者の知的能力の違いを反映していないだろうか。フクロウ類の脳は大きいが認知にはあまり役立っていないとの見方をある程度裏付ける事例のようにも思える。
[飼育下の行動: 中国のハチクマ]
An injured crested honey buzzard recovered with help from humans (英語音声と字幕) 北に渡る途中のハチクマが撃たれたが手術で救われた。牛肉にハチミツをかけて与えると驚くべきことに喜んで食べたとのこと。かなり淡色のメス成鳥。
中国のハチクマ関連ビデオがあったのでここに紹介しておく: The Crested Honey Buzzard, a medium-sized raptor and a second-class protected species in China (Guizhou Echo 2024。英語音声と字幕)
重慶市 (Chongqing) は "ワシの街" の名称でも知られるとのこと。ハチクマに関心を持ってもらうための啓発ビデオのよう。
このビデオでは特別な虹彩がハチへの武器になっているとの説明があるが瞬膜のことかも。ハチ食で多分弱いとの文脈と思われるが、他の動物にいじめられることもあると紹介されている。映像が不鮮明でよくわからず (次に出てくる映像は別種。タカサゴダカのようにも見えるが何でしょうか)。
[飼育下の行動: インドネシアのハチクマ]
飼育下の映像 Caring For Eagles From Chicks Until They Fly Into The Wild おそらく日本と同じ亜種の若鳥で何らかの理由で飼育され放鳥されたらしい。短いビデオだが他のタカと同じような反応を示しているよう。
[飼育下の行動: 日本のハチクマ]
ハチクマ保護日記。
現在盛岡市動物公園 ZOOMO にいるハチクマ (はっちゃん) の保護経緯。
ひなを運ぼうとしていた猛禽が何だったのか (親鳥? それとも#イヌワシの備考にあるように捕食しようと自身の巣に運ぶ他の猛禽?)。
人に慣れてしまって同種を見ても渡る意思が起きなかったらしいのも興味深い。
ハチクマにハチの巣を与えてみると (多摩動物公園 2016.5.20)。
動画では最初は嘴で受け取ったが足で掴み直す。静止画で足で受け取るらしい画像が出ている。
-
カタグロトビ (第8版で検討種)
- 学名:Elanus caeruleus (エラヌス カエルレウス) 青っぽいトビ
- 属名:elanus (elanosトビ Gk)
- 種小名:caeruleus (adj) 青い < caelum (天上、空) 備考参照
- 英名:Black-winged Kite
- 備考:
elanus は起源となるギリシャ語 elanos は短母音のみ。ラテン語規則からアクセントは冒頭 (エラヌス)。
現代ギリシャ語でも "エラノス" と呼んでいる。ギリシャでも記録される鳥。
caeruleus は短母音のみで -ru- がアクセント音節 (カエルレウス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動 (文献で同属の類似種が明示的に否定されていないため)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも検討種。
Rene Louiche Desfontaines (1789) が Falco caeruleus の学名で記述したもの。基産地は Algiers (アルジェリアのアルジェ) ははるか遠く。
複雑な歴史があるため関連種もここで合わせて説明する。
現在の名称でオーストラリアカタグロトビは Latham (1801) の記述 (Falco axillaris) が最初で、1790 年代の Thomas Watling の図版を元に記述された。
Latham (1801) の方が早かったが Latham の記述はクロオビトビ Elanus scriptus Letter-winged Kite を指すものとの議論が Gregory Mathews から出され (1916)、図版も不明瞭だったため Elanus notatus Gould, 1838 を使うべきと提案された。
1980 年に Richard Schodde and Ian J. Mason が Mathews の指摘を論破し、Elanus axillaris の学名が使われるようになった。
1959 年に Kenneth C. Parkes は現在の名称でカタグロトビとオーストラリアカタグロトビ2種は同種とするべきと唱え、先取権の原則に従って Elanus caeruleus に一旦落ち着いたが、その後の研究で 1992 年に再度分離されて現在に至った複雑な歴史がある
[Clark and Banks (1992) The taxonomic status of the White-tailed Kite] (オーストラリアカタグロトビの wikipedia 英語版より)。
そのため現在のオーストラリアカタグロトビを指して Elanus notatus とされていた時代があり、高野 (1973) がこれに相当する (この書物では2種を別種扱い)。
2種を同種とする立場であれば Elanus caeruleus となる。
古くはアメリカのオジロトビ [高野 (1973) ではオジロハイイロトビ] Elanus leucurus White-tailed Kite も含めてすべて "black-shouldered kite" と呼ばれていた (wikipedia 英語版)。
オジロトビは Audubon (1840) "Birds of America" Black-shouldered Hawk の名前ですでにアメリカの鳥として登場していた。この時の学名は Elanus dispar Temminck だった。
別名に Black-winged Hawk もあった。
記載時学名 Falco dispar Temminck, 1825 (記載, 図版, 参考)。
dispar は "違った" などの意味。フランス語名 Milan a queue irreguliere (不規則な尾のトビ) で "尾の最外側の羽が短く尾が不揃いな発達段階に見える" との Azara の記述に基づく。トビ類にしては最外側尾羽が短い特徴を表現したものと思われる。
記載時学名で Milvus leucurus Vieillot, 1818 に先取権があったため Temminck の学名は使われなくなった。
つまりカタグロトビの名前はそもそもアメリカの鳥に対して付けられた英名由来で、おそらく後にオーストラリアのもの (現在の Elanus axillaris) と同種扱いとされ、その場合はどちらを基亜種とするか次第で学名が異なることになる。前述のように Latham (1801) と Gould (1838) の記載のどちらを採用するか議論されていたため、Gould (1838) の記載を正統とする立場であればオーストラリアのものはアメリカのオジロトビの亜種となる。
すなわちその時代の産物として種英名が Black-shouldered Hawk でその英名が現在のオーストラリアのものに引き継がれ、現在のカタグロトビと同種時代は Black-shouldered Kite と呼ばれていたものと考えられる。カタグロトビの和名は同種時代のアメリカのオジロトビに起源があったことになる。
現在ではカタグロトビの原記載がこの中で最も早いと判定され、もし同種とする場合はカタグロトビの亜種となるが、古い時期には逆転していた時期があった。
高野 (1973) ではカタグロトビ類をハイイロトビ類と呼んでいた。高野の名称とカタグロトビの名称のどちらが早かったのかは不明。
猛禽類分類の事実上の「標準」とされていた Brown and Amadon (1968-1969) "Eagles, Hawks and Falcons of the World" では、Elanus caeruleus Black-shouldered Kite と Elanus notatus (現在は Elanus axillaris) Australian Black-shouldered Kite の英名となっていた。
Elanus notatus Gould, 1838 (参考 1, 2) でこの学名も記載が十分でなかったことがわかる。Brown and Amadon (1968-1969) は Gould (1838) を正統として分類していたがこの時代にはアメリカのオジロトビは分離していた。
時代背景的にはこれがそのまま和訳されたものが現在に至っているのかも知れない。
時代や採用した分類により名称が交錯しているので過去の文献を見る際は要注意。
カタグロトビの学名のシノニムに Elanus caesius Savigny, 1809 があり、caesius は青灰色 (元素セシウム Cs の語源と同じでこちらは炎色反応のスペクトル線の色)。現在の種小名 caeruleus も同様。他のトビ類に比べて青っぽく見えることが学名の由来だろう。
#ハクガンの種小名 caerulescens にも同系のラテン語が使われるが、ギリシャ語、ラテン語とも本来 "青" を意味する語彙がなかったとのこと。例えばギリシャ陶器には青は現れない。
これらの単語は cera (蝋) が語源で、白と茶と黄色の間の色を指していたものが語義が次第に変化し、緑か黒っぽい色、そして青っぽい色を指すようになったとのこと。「青の歴史」(ミシェル・パストゥロー著; 松村恵理, 松村剛訳 筑摩書房 2005; 原著 "Bleu: histoire d'une couleur" Michel Pastoureau) pp. 24-25 による。
青っぽい色彩を指すラテン語はいくつかあったが多義的で色彩も漠然としており、用法もまちまちだったとのこと。caeruleus が最もよく使われたとのこと。ハイイロチュウヒの種小名に現れる cyaneus もそのような単語の一つ。
キリスト教的中世の著作家が青色にあまり関心を示さなかったためとのこと。青系統の語彙も貧弱で、赤や茶系統の色に多彩な学名が存在するのとは対照的である。日本のアオサギの "アオ" 同様、ヨーロッパでも曖昧に使われていたらしい。日本産の種の種小名には出てこないが、azureus はアラビア語から後に導入された語とのこと。
フランス語でも bleu はドイツ語 blau から (ゲルマン語由来で blavus がラテン語にも入った) でラテン語系統の単語ではなかった (以下 #カワセミの備考に続く)。
「セグロハヤブサ」の名前で古くから鷹狩り用に輸入されていた (YouTube などでは BWK の略称で海外の訓練ビデオを見ることができる)。「セグロハヤブサ」の名称は英語の Black-winged Kite 由来か。
英語では BWK とそのまま略しているようなので日本では「トビ」から「ハヤブサ」と付け替えたものかも。
なおトビ Milvus migrans と近縁の種類ではなく、ハチクマとも近縁ではない。
3亜種あり (IOC)。
日本で初記録時代には迷鳥としてフィリピンの亜種 hypoleucus が想定されたことがあったが、現在は日本で記録されるものは東中国、インドシナ、マレーの亜種 vociferus (「騒々しい」の意味) であると考えられている。[分布拡大] の項目も参照。
小山他 (1995) Birder 9(3): 85 に 1995.1.6 の石垣島のカタグロトビが hypoleucus らしいとする記述あり。
(フィリピンの写真) (Jun Jose 2024.10) と比べていかがだろうか。
Vagrant Kite No Visa Needed (Joel Dayao 2025.1.12 撮影) はフィリピンだがこちらは迷鳥のオーストラリアカタグロトビ Elanus axillaris Black-shouldered Kite とのこと。
オーストラリアカタグロトビも齧歯類など獲物の豊富な農地へ分布を広げつつあるとの見解が示されている。
[カタグロトビ類の系統分類]
カタグロトビには日本産の他のタカ類に系統的な類縁種がないため、カタグロトビ亜科の全種を#ミサゴの備考のように示しておく。順序は Catanach et al. (2024) の分子系統分類による。
この項目で種または属名の和名の後に * が付いているものは従来の少数遺伝子によるもので付いていないものよりは精度が低い (従来の系統解析と同じ)。
ここでは日本鳥類目録改訂第7版の順序なのでハチクマ亜科の後に登場するが、現代の分類では #ミサゴと#ハチクマの間になる (分類位置はこれらそれぞれの備考参照)。
"トビ" の名の付く種類も複数の系統に分散しているが、カタグロトビ亜科は和名でも英名でもすべての種に "トビ" の名が付いている。
ミサゴ科からハチクマ亜科は眼窩上の張り出し supraorbital ridge を作る骨 (os lacrimale 涙骨の processus supraorbitalis) が発達しておらず (解剖学的な分類根拠にもなっている)、あまり険しい目に見えないと言われるが、カタグロトビは羽毛で supraorbital ridge を作っているとのこと。
Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" にカタグロトビの説明と写真も載っているが、Lerner and Mindell (2005) Phylogeny of eagles, Old World vultures, and other Accipitridae based on nuclear and mitochondrial DNA
によればカタグロトビ類は骨が眼窩上の張り出しを作っており、ハチクマ類と区別できる点としている。
Elanus caeruleus (Black-shouldered Kite) (Skullsite)
では該当の眼窩上の張り出しを作る骨があり、Brown (1976) の早合点かも知れない。
Brown (1976) はこの骨の張り出しがないものを原始的系統の分類根拠として挙げているが、必ずしもそういうわけではなさそうである。この後に出てくるクロオビトビはこの骨の張り出しがないが夜行性なのでそもそも必要なく、必要なければ簡単に失われるものなのだろう。
同サイトの他のタカ類と比較するとヨーロッパハチクマとケアシノスリは骨の張り出しは小さいが大差なく、チュウヒ類も比較的小さい。ハチクマ亜科に近いヒゲワシ亜科でもヒゲワシでは骨の張り出しが発達していてノスリ類でも種差が大きいので必ずしも系統を反映するものではなさそうに見える。
What are pernine kites? (Honey Buzzard stuff 2012)
にも同様の解説があり (ヨーロッパハチクマが中心のサイト)、Amadon の言う原始的特徴ではないとの考えを述べている。
カタグロトビ亜科 Elaninae (ハイイロトビ亜科の名称もあり: #ハチクマの備考参照)
シンジュトビ属* Gampsonyx
シンジュトビ [高野 (1973) ではシロクロトビ] Gampsonyx swainsonii Pearl Kite
アフリカツバメトビ属* Chelictinia
アフリカツバメトビ [高野 (1973) ではアフリカツバメハイイロトビ] Chelictinia riocourii Scissor-tailed Kite
カタグロトビ属 Elanus
オジロトビ* [高野 (1973) ではオジロハイイロトビ] Elanus leucurus White-tailed Kite
カタグロトビ [高野 (1973) ではハイイロトビ] Elanus caeruleus Black-winged Kite
クロオビトビ* [高野 (1973) ではクロオビハイイロトビ] Elanus scriptus Letter-winged Kite
オーストラリアカタグロトビ [高野 (1973) ではオーストラリアハイイロトビ] Elanus axillaris Black-shouldered Kite
カタグロトビ属の4種は高精度の分子系統樹が描けているものが2種なので、4種の順序には現状はあまり意味がない。ただしこれら4種は非常に近い系統というわけでもなく、亜種レベルに近い違いではない。
かつて同種とされた (Parkes 1959) カタグロトビとオーストラリアカタグロトビの間もそれほど近いわけではない (ハチクマとヨーロッパハチクマ程度には違っている)。
ツバメトビとアフリカツバメトビは和名が示唆するような近縁の種ではない。どちらも優美な種類だが尾の形は収斂進化の結果なのだろう。
属名 Chelictinia は khelidon, khelidonos ツバメ iktin, iktinos トビ (Gk)。
シンジュトビは南米の小型の種類で南北アメリカで最小の猛禽類。ヒメハヤブサ類 Microhierax (極小のタカの意味) と配色がそっくりなためハヤブサ類に分類されていたこともある。換羽様式がハヤブサ類様式でなくタカ類様式であること、骨格の特徴からタカ類に移動となった。
属名 Gampsonyx は gampsos 曲がった onux, onukhos 爪 (Gk)。
[系統とフクロウ類との収斂進化]
Elanus 属はミサゴ科が分岐した後に他のタカ類と早期に分岐したグループで、この中には夜行性のクロオビトビがいる。この習性のため観察は非常に難しいことで有名。
最近になってようやく高い周波数まで含まれた公開音源が報告された XC924861 これは昼間の録音。
Elanus 属は羽音を出さずに飛べる [Clark and Liu (2020) Evolution and Ecology of Silent Flight in Owls and Other Flying Vertebrateにも記載がある]、
大きな目が前方に付き暗所視に優れる、網膜の紫外線感受視細胞を欠く (つまり3原色型。#ハヤブサの備考参照)、足指をミサゴのように後ろに回せる、胃の酸性度が低くペリットはフクロウ型、この属の少なくとも1種は左右の耳が非対称でフクロウ類のように音源定位をしている可能性があるなどフクロウ類との収斂進化が見られる
[Negro et al. (2006) Elanus Kites and the Owls。
さらなる参考 Perez et al. (2019) Elanio comun - Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)]。
カタグロトビ科 (Elanidae) として独立させる意見もある [Starikov and Wink (2020) Old and Cosmopolite: Molecular Phylogeny of Tropica-Subtropical Kites (Aves: Elaninae) with Taxonomic Implications]。
さらにはカタグロトビ目 (Elaniformes) すらも提唱されている [Debus (2004) Relationships of the Elanus kites. Boobook 2004, 22, 8] が、分子遺伝学や (染色体) 核型の研究からは独立科として認められる段階には至っていない。
AviList (2025.6) では独立科として認めるには不十分としてタカ科 Acciptridae に含めた。
7961 1172 The family Elanidae is subsumed in Accipitridae. Although forming a distinctive sub-group at the base of the Accipitridae phylogeny (e.g., Catanach et al. 2024), they are more appropriately treated at infra-family rank pending a more thorough comparative analysis of trait divergence among sub-family groups within Accipitridae.
趾をミサゴのように後ろに回せる能力については Tsang (2012) Facultative zygodactyly in the Black-shouldered Kite Elanus axillaris
に写真などがある。ミサゴ同様に第 III 趾と第 IV 趾の間の膜 (人の指で言われる「水かき」に相当) が欠如している。
カンムリカッコウハヤブサ Aviceda subcristata Pacific Baza
にもこの能力がある。系統的な特性なのか、例えば薄暗い中で哺乳類を確実に捕まえるのに役に立っているのかなど役割は検討されている段階。
Tsang et al. (2019) Raptor talon shape and biomechanical performance are controlled by relative prey size but not by allometry
によればカタグロトビ類とフクロウ類の爪の形状にも共通点があるとのこと。
網膜の視細胞の構成はタカ類としては特殊であるが、Moroney and Pettigrew (1987) (#ハチクイの備考参照) ではカタグロトビも両眼視の視力がよいと考えられている。
クロオビトビの頭蓋骨の研究は Keirnan et al. (2022)
Not like night and day: the nocturnal letter-winged kite does not differ from diurnal congeners in orbit or endocast morphology
にある。形態的には昼行性タカ類と大きな違いはないが視神経は細いようで、Elanus 属は全般的に視覚の分解能は犠牲にしているらしい。顔つきはしっかりして見えるが視力はそれほどよくない?
この研究ではクロオビトビが Elanus 属の中で唯一の夜行性と考え、分岐年代から夜行性への移行は大きな解剖学的変化を伴わなく短期間で達成できる性質であると考えている。
Elanus 属の網膜の紫外線受容体細胞の欠如を考えるとこの種の分岐前から夜行性であったことも考えられ、この解釈には問題があるかも知れない。
この文献によればクロオビトビはオーストラリアで Tyto 属 (メンフクロウ類) の地位を占めていることが紹介されている。
Scheibler (2007) Food partitioning between breeding White-tailed Kites (Elanus leucurus; Aves; Accipitridae) and Barn Owls (Tyto alba; Aves; Tytonidae) in southern Brazil
によればブラジルではオジロトビ [高野 (1973) ではオジロハイイロトビ] Elanus leucurus White-tailed Kite がメンフクロウと同所的に生息し、どちらも齧歯類が主食とのこと。活動時間帯は違いがあるが食物はよく似ているとのこと。オジロトビの方がもう少し大きな哺乳類の獲物も食物としているとのこと。
見事に競合しているがメンフクロウ類との共存は可能な模様。
これらの研究ではカタグロトビ類の特異性が強調されている印象があるが、ミトコンドリアの CRs (control regions) の解析でミサゴ、カタグロトビ、ハチクマにむしろ共通性が見つかる結果も出ている:
Sonongbua et al. (2024) Insights into Mitochondrial Rearrangements and Selection in Accipitrid Mitogenomes, with New Data on Haliastur indus and Accipiter badius poliopsis
で、過去の解析 (カタグロトビは含まれていない) でミサゴのみがタカ科と異なるとした結果と異なるとのこと: Urantowka et al. (2021) Mitogenomes of Accipitriformes and Cathartiformes Were Subjected to Ancestral and Recent Duplications Followed by Gradual Degeneration。
この研究では CRs の重複現象はタカ類とフクロウ類の共通祖先段階で起き、ヘビクイワシを分岐した後 CR1 が CR2 の役割を置換する進化が起き、その後系統特異的に CR1 と CR2 の間で塩基配列の収斂や役割の置換があったと考えていた。
ただ Sonongbua et al. (2024) が比較対象に用いているのが大部分 (現代の概念で) トビ族 Milvini と Accipitrinae なのでむしろこれらの特殊な適応が現れているのかも知れない。個々に見るとだいぶ違いがあるのでカタグロトビとハチクマはそこまで似ていないかも。
Perninae, Circaetinae, Aegypiinae, Aquilinae の4亜科を指して four primitive subfamilies ("原始的な" 亜科) と表現しているのでイヌワシ好きの方には叱られそうである (笑)。これらのグループには ATP8 遺伝子に共通性があるが Elaninae, Buteoninae, Circinae では異なっているとある。原始的なというよりも系統的に混ざってしまっているような気がする。
論文にも指摘があるがエネルギー代謝にかかわる遺伝子なので、タカ類全体の系統順序を反映したものというより生態や食性への適応かも。
ミトコンドリアの CRs で描いた系統樹では カンムリオオタカ Lophospiza trivirgatus Crested Goshawk が他の広義 (旧) Accipiter とは大きく離れていて間にソウゲンワシが入る形になっている。
系統樹形はもっと広範な遺伝情報を用いた Catanach et al. (2024) の方が信用できると考えられるが、カンムリオオタカが相当違うらしいことはこの研究からも読み取れる。
この研究の行われたタイは種類数も多く渡りの要所でもあるためかタカ類への関心が高く、系統にもアマチュア・プロを問わず興味が持たれている印象を受ける。
Catanach et al. (2024) の論文 (preprint 段階は知っていてわずかな修正で受理まで把握していたが) が雑誌に実際に出版されたのを最初に知ったのもタイの猛禽類サイトに紹介された情報からだった。
[分布拡大]
カタグロトビの分布拡大は世界的傾向で、台湾では 1998 年に初確認以来 2001 年に初繁殖で急激に数が増えている。ヨーロッパでは 1970 年代から分布を広げている。長距離に分散する能力が高く、年に複数回繁殖できる (齧歯類が爆発的に増えることがあるのに適応できる能力である)。
Podsokhin et al. (2023) The black-winged kite Elanus caeruleus on the border of Moscow and Tver Oblasts (pp. 3724-3726)
によれば伝統的分布より北進しており、モスクワ近郊でも観察された。ザバイカルでも記録があり内陸にも進出している。
人為的な環境にも適応力が優れている。チョウゲンボウ (台湾では冬鳥) と生態が似ていて留鳥のカタグロトビの方がより攻撃的。数の上でも逆転現象が発生しており、将来チョウゲンボウの個体数減少の心配がある:
Chen et al. (2022) Competition between the black-winged kite and Eurasian kestrel led to population turnover at a subtropical sympatric site。
台湾の個体群は人為的に導入されたもので自然分布ではない (その場合は日本の記録は二次的人為分布となる) 説 (参照) もあるが、台湾の研究者によれば初記録から数が増える過程が詳しく記録されており、中国南部から自然分布を拡大したものと広く受け入れられている。
齧歯類を食べる益鳥としてとまり木を設置するなどの試みも行われている (wikipedia 中国語)。北京にも分布を拡大している (参考)。
台湾での研究 Lin et al. (2014) Distribution Trend and Prediction of Black-winged Kite (Elanus caeruleus) in Taiwanによれば猛禽類の渡りの時期以外には競争種がなく、豊富な齧歯類によって個体数が大幅に増えた。
前述のフィリピンの写真のようにオーストラリアカタグロトビも分布を広げているらしく、カタグロトビ類は人為環境の広がりによって世界的に勢力を広げているらしい。
橋本 (2007) Birder 21(10): 20 に2007年7月13日に台風通過後に沖縄本島で記録されたカタグロトビの報告がある。この当時は迷鳥だったがすでに分布拡大傾向を反映したものだったのかも。
川野 (2017) Birder 31(3): 40-41 に石垣島の初繁殖時期の記事がある。2015 年に繁殖に挑戦、2016 年に初繁殖したとのこと。
韓国でも観察例が増えており、日本でもこれまでより広い地域で記録されるようになるかも知れない。
澤田他 (2024) 波照間島におけるカタグロトビの記録
が日本の繁殖個体が同属の他種ではないことを明示的に示した国内のカタグロトビの初めての学術報告となった。
鳥を食べる報告もある。Wee (2015) 映像もあり Black-shouldered Kite eats a Javan Myna。
Black-Winged Kite subadult (Yvonne Blake 2025.3.21 撮影)。止まり場でネズミを食べているところ。他個体への反応らしき尾を上下する行動も記録されている。
Brown (1976) p. 81 によればカタグロトビ類とチョウゲンボウ類は頻繁に羽ばたきながら採食する行動に共通点があるとのこと。採食のために羽ばたき飛行を続けるには大きなエネルギーが必要だがこれらの種はそのための生理的適応があるのだろうと記述している。
[タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式]
ドイツの鳥類学者 Erwin Stresemann (エルヴィン シュトレーゼマン 1889-1972) は換羽様式を中心に鳥類の分類を提案した
("Die Mauser der Voegel", Stresemann and Stresemann 1966, 448 pp.)。
それによればタカ・ハヤブサ類の初列風切 (9枚と書いてあり換羽の説明図もそうなっている。Brown の他所には通常 10 枚とあるので Stresemann の説明に合わせているのかも知れない) の換羽様式を ascendant (P4 から対称的に換羽)、
descendant (P1 から外側へ)、irregular (いくつかの部分でそれぞれ中央から対称的に換羽)
に分けていた。irregular なものは若鳥で descendant で成鳥で irregular のものと、生涯 irregular のものに分けられる。
Stresemann は descendant が原型 (原始的) で ascendant はその変形と考えた。
descendant がタカ類に相当、ascendant がハヤブサ類に相当。
ヒメコンドルなどが irregular に分類される。旧世界ハゲワシも新世界ハゲワシもこの分類では同じグループに入る。
Stresemann の分類ではタカ類の中でトビ類、ハチクマ類、海ワシ類が進化の最高段階とされ、一般的な考え方と異なっている。
ハゲワシ類が旧世界、新世界ともに同じ分類になるのは遺伝的な系統を反映したものより翼荷重の問題ではないか (以上 Brown 1976 より)。
Brown (1976) が参考文献として選択しているのは Stresemann and Stresemann (1960) Die Handschwingenmauser der Tagraubvoegel (一般書なのですべての文献が記載されているわけではない)。
猛禽類の換羽の新しいレビューは Zuberogoitia et al. (2018)
Moult in Birds of Prey: A Review of Current Knowledge and Future Challenges for Research
がある。情報は主にヨーロッパの猛禽類で、フクロウ類も含まれている。以下 moult はアメリカ英語の molt に統一して表記する。
換羽戦略については #ライチョウの備考 [ライチョウの換羽]、#キタヤナギムシクイの備考 [渡りと換羽戦略] も参照。
この論文をもとに、途中に他の研究をはさみながら簡単に紹介する。
上記の irregular は換羽が1シーズンで終わらないために複数の換羽開始点 (molt foci) が生じるため。Stresemann の用語では Staffelmauser (英語 staggered molt)。
ヨーロッパのハイタカではひなの巣立ち時期 (7月) に 18.75% のメス、55.5% のオスが換羽を中断する (arrested molt)。親にとっても負担の大きい時期で納得できる数字と性差が現れている。
このような現象はおそらく繁殖期に限られたものではなく、条件の悪い時に換羽を中断し、条件が改善すると再開すると考えられる。
換羽に時間のかかるシロエリハゲワシのような大きな鳥で傷んだ羽を自身で抜いて換羽を行うことが観察されており、イヌワシでも同じようなことがあるとのこと。
Rohwer et al. (2009) Allometry of the Duration of Flight Feather Molt in Birds
によれば初列風切の換羽に要する時間は体重の 0.14 乗に比例するとのこと。この数字を説明するための簡単な生理的モデルも提案されている。体重の大きな鳥は1シーズン内にすべて換羽できないことを説明できるとのこと (この論文で特に気にしているのは 70 kg の絶滅した最大の飛べる鳥 Argentavis magnificens がどのように換羽しただろうか)。
なお段階的換羽は比較的大型の鳥が中心と考えられていたが、40 g のスズメバト Columbina passerina Common Ground-Dove でも起きることが分かった: Rohwer and Rohwer (2018) Breeding and multiple waves of primary molt in common ground doves of coastal Sinaloa
この例ではピジョンミルクを生成するために換羽を中断すると考えられるとのこと。大型の鳥では P1 から始まった換羽が P10 に達する前に P1 からの換羽が再度始まってしまい、内側が2回換羽されて非効率である。ウ類や大型のサギ類では "omissive" molt が知られていて、一部の若鳥は P8-P10 のいずれかを換羽順でなく失いこの問題を克服しているとのこと。
特に傷んだ初列風切を優先的に交換する能力があることが最近わかったとのこと。
スズメバトでは新しい方法でこの問題を克服しており、P9/P10 に換羽が達する前に P1 から新たに換羽が始まるのを防いでいるとのこと。
タカ・ハヤブサ類の風切の換羽様式はそれぞれの系統の基本的パターンがあるが、フクロウ類は属による違いが大きいとのこと。
Buteo 属以外の猛禽類の大部分は2回めの換羽 (second prebasic molt 第2回基羽への換羽) で初列の換羽を優先し、初列の換羽がある程度進んでから次列の換羽が始まる。
ハヤブサの換羽は地域により異なり、留鳥または短距離の渡りのものは連続した換羽を行うが、北極に近いもの (亜種 calidus) は繁殖地で換羽を開始し、渡り時期に中断して越冬地で換羽を完了する。ハヤブサ類は1シーズンで換羽が終わり、多くのものは秋には換羽を終えている。
1シーズンで換羽を終えるタカ類では、アカトビのように中・長距離の渡りを行う種でも渡り前に換羽を大部分完了しているが一部は中断して越冬地で完了する。中型の渡りを行う種ではヨーロッパハチクマは渡り前に換羽を中断するが、ヒメハイイロチュウヒ Circus pygargus Montagu's Harrier は中断しないとのこと。
ヨーロッパノスリでは全体の換羽に2シーズンを要する。多くの個体は前年に中断した場所から換羽を再開し、換羽順序の規則に従って進む。このため、また部分的に抜けた羽などによって個体にさまざまな換羽状態が見られるとのこと。
より大型種では2-3シーズンを要し亜成鳥の羽は幼鳥とも成鳥とも異なる。亜成鳥の羽は幼鳥より短く成鳥より長い。この傾向は特に次列に顕著 (ハチクマの幼鳥の次列が幅広いのも同様か? #ハチクマの備考 [幼鳥の次列風切が幅広いのはなぜ?] に続く)。
1シーズンで換羽を終えず、かつ渡りをすることで冬季に換羽を再開するパターンはより複雑で、ミサゴ、ヨーロッパノスリの亜種 Buteo buteo vulpinus は渡り前に換羽を中断する。
ヒメクマタカ Hieraaetus pennatus Booted Eagle、チュウヒワシ Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle は渡り中に換羽を中断しない。これらは比較的短距離の渡りのためこのようなことが可能との考えもある。
ミサゴは生まれたその年の秋に2回めの換羽を開始し、22-29 か月後に繁殖地に旅立つまで換羽を継続するとの観察がある。これらのミサゴ若鳥は初列内側を1年で2回換羽することになるとのこと。
若杉氏の ミサゴ幼鳥の換羽は すごく早く 始まる! にも関連した記事がある。
ヒメハイイロチュウヒが渡り中に換羽を中断しないのは、チュウヒ類は渡り時にそれほどソアリングを多用せず、低く羽ばたき飛行をして獲物を捕りながら進むためと考えられる。
(フクロウ類の換羽は個人的興味から大部分省略したがご容赦いただきたい)。
成長段階を戻るとひなが孵化した段階の羽は neoptile (幼綿羽と呼ぶらしい)、一部の種 (特にフクロウ類) は2段階目の綿羽が生じて mesoptile (第二幼綿羽の用語があるらしい) と呼ばれる。
ひなに飛翔羽 (flight feathers *1) が発育してくると栄養が体の生育よりもこの羽の成長に使われる。
幼綿羽による覆い (downy cover と記されているが特に学術用語というわけではなさそう) が取れて幼鳥羽 (juvenile plumage) に置き換わる現象を first prebasic molt (第1回基羽への換羽 または first prejuvenile molt) と呼ぶ。
幼鳥の羽は成鳥とは違ってまとめて生育するため強度も弱く密な構造になっていない。幼鳥の飛翔羽は成鳥に比べて細くて長く、先端がより尖っている。
neoptile の構造は系統によるとのことで、Foth (2011) The morphology of neoptile feathers: ancestral state reconstruction and its phylogenetic implications
によれば Neoaves 以前の系統と Neoaves で構造が異なり、後者は無構造だが前者は対称性を持った構造が neoptile の段階で現れる (ニワトリやエミュー)。この違いは単純に Neoaves で卵内の発育期間が短いためかも知れない。
卵内での neoptile の成長が調べられている種はごくわずかなのでより広い範囲の系統を調べる必要があるとのこと。教科書などの記述はほとんどが家禽の知見に基づくものと思われるので、新しい系統の鳥では教科書と違っている可能性もあることを念頭に読むのがよさそう
(羽毛研究の関心事は羽毛の起源や羽毛恐竜に向いているので新しい鳥の研究は思ったほどない)。
Ng and Li (2018) Genetic and Molecular Basis of Feather Diversity in Birds のレビューによればスズメ目では 25 番染色体の β ケラチンをコードする遺伝子がニワトリより少なく、スズメ目が natal down を持たない遺伝子レベルの要因となっているとの考えがある
[Greenwold and Sawyer (2010) Genomic organization and molecular phylogenies of the beta (β) keratin multigene family in the chicken (Gallus gallus) and zebra finch (Taeniopygia guttata): implications for feather evolution]。
生態要因は晩成性の鳥のひなは羽毛を持たずに生まれるために熱の伝わりがよく、より多くのエネルギーを発育に使えると解釈されている [Starck and Ricklefs (1998) "Avian growth and development: evolution within the altricial-precocial spectrum"]。
早成性の鳥では neoptile の発育で生じる模様が隠蔽色となっている証拠がある: Rohr et al. (2011) Neoptile feathers contribute to outline concealment of precocial chicks。
フクロウ類のひながタカ・ハヤブサ類に比べて灰色と言われるのは mesoptile を見ているためのよう。
Holt (2016)
Mass Growth Rates, Plumage Development, and Related Behaviors of Snowy Owl (Bubo scandiacus) Nestlings にシロフクロウの発育の報告がある。この論文では幼綿羽に相当するものを protoptile down と呼んでおり、やはり白くて大変よく目立つとのこと。
系統の新しい鳥の neoptile は古いものとは異なって無構造な down のためおそらく白色にならざるを得ず (構造を作るための遺伝子発現の順序にも関係してそう)、フクロウ類が mesoptile を進化させたのはやはり目立つため隠蔽色とするためだろうか (どこかに書いてありそうなのだが見つけられなかった)。
タカ・ハヤブサ類ではなぜ mesoptile を進化させなかったのか [Zuberogoitia et al. (2018) では主にフクロウ類とあるので例外があるのだろう。文献は挙げられていなかった] 理由が必要だろうが、この時期は主に巣に親が大部分の時間いて守っているので十分だったのだろうか。
白いひなが目立つのは昼間なので、夜行性のフクロウ類の親は同じような状況でも昼間は守りきれない? 巣の構造が違うため? しかしハヤブサ類は巣を造らないため前者の説明の方が当てはまりそう? (いかにも適応的意義の議論がありそうなのだがみつけられなかった)。
もし古い時代に生態的意義があまり議論されていなかったとすれば、過去の系統分類ではタカ・ハヤブサ類が古いグループに置かれていてニワトリと同じようなものと考えられていたためかも知れない。
換羽の名称については茂田 (1993) Birder 7(3): 36-40 で異なる流儀の名称が紹介されており、この Zuberogoitia et al. (2018) の論文は Humphrey and Parkes (1959) An Approach to the study of molts and plumages の用語を採用しているよう。Humphrey-Parkes system の用語があるらしい。
Howell et al. (2003) The First Basic Problem: A Review of Molt and Plumage Homologies
には prejuvenal downy plumage の用語が紹介されていて、多くの鳥はこの downy plumage (natal down の用語もある) の段階があるが、キツツキ類では裸で生まれるが最初から juvenal plumage になるとのこと。ペンギン類では2種類の prejuvenal downy plumage があるとのこと (上記 mesoptile に対応と思われる)。
Zuberogoitia et al. (2018) が downy plumage を細かく分けた用語を採用しているのは猛禽類全体のレビューのためと考えてよさそう。
換羽戦略についてはタカ類・ハヤブサ類は似ていてフクロウ類やオウム類など他の系統に類似したものがない。この文献では生まれた年を暦年で year 1 と表記しているので年齢表示はやはり難しい。
ツミの換羽に異なったタイプがあることも報告されている。
Kang and Hur (2016) New moult pattern in diurnal raptors: primary moult pattern of the Japanese Sparrowhawk Accipiter gularis、
Iseki et al. (2021) Unique and Complicated Wing Molt of the Japanese Sparrowhawk Accipiter gularis (独特で複雑なツミの風切の換羽様式)。
2011, 2012 年の学会発表がある ツミは複数の換羽様式を持つ非常に稀な鳥だった - ツミには2つのグループがある? (2012)。
2023年度日本鳥学会内田奨学賞選考報告 (伊関文隆) に解説がある。
言及されている先行論文が上記 Kang and Hur (2016) である。タカ類換羽に関連した近年のニュースであり、研究の進展経緯も日本語で興味深く読める。
最新提案の分類でツミやアカハラダカが Tachyspiza 属とハイタカやオオタカと別になることも踏まえて調べると面白いかも知れない。
Tachyspiza 属は熱帯の種が多く、熱帯種は換羽様式が調べられていないものも多いので、系統的な特性があっても同属とされてきた時代には温帯種のみを調べて違いが見過ごされてきていたかも知れない。
換羽と系統の関係: Kiat et al. (2020) Sequential Molt in a Feathered Dinosaur and Implications for Early Paravian Ecology and Locomotion
論文目的は羽毛恐竜の換羽様式の推定だが、順次換羽を行う sequential molt とそうではない non-sequential molt (同時換羽や不規則なもの) の系統関係が示されている。
祖先形質は sequential molt と推定。non-sequential molt は生態 (飛行能力の必要性に関連) に対応して独自に進化したもの。飛べない鳥には sequential molt のものはない。irregular molt は飛べない鳥にしか見られない。
飛行能力の必要性から sequential molt の形質が維持されている。sequential molt を維持するためのコストが存在し、飛ぶ必要がなくなれば失われることを意味する。
最近の論文らしく使われたデータも公開されていて、クイナ亜目 Ralli を含むツル目 Gruiformes では non-sequential molt が一般的。これはクイナ類が多数含まれるためかと思ったのだが、ツル類の中でも両者が混ざっている。ナベヅル、アネハヅルは sequential molt で飛翔能力を失わないが、マナヅルは non-sequential molt で飛翔能力を一時的に失う。
Grus 属の中でも混ざっているのでこの系統は全体的に sequential molt を失いやすい模様。
カモ類は一般に non-sequential molt で一時的に飛べなくなるが、飛べないカモも結構ある (渡りをしないので馴染みがないだけのよう)。Terrill (2020) Simultaneous Wing Molt as a Catalyst for the Evolution of Flightlessness in Birds のように翼の同時換羽は例えば島や開けたニッチで迅速に飛翔性を失う前適応か、との議論がある。
猛禽類はこのリストでは例外なく sequential molt (当たり前か?)。
続編があって Kiat et al. (2021) Body mass and geographic distribution determined the evolution of the wing flight-feather molt strategy in the Neornithes lineage。
この論文の定義で "absent molt" と分類している最初の1年で風切羽を換羽しない例にオオタカが出ている (タカ類で一般的、他にも多数ある)。
Supplementary Table 1 に一覧があるので見ていただくと面白いだろう。ツミが "partial molt" となっている他、タカ類ではミサゴ、カタグロトビ、ヨーロッパハチクマ、チュウヒワシが含まれている。
ハヤブサ目ではニュージーランドハヤブサ Falco novaeseelandiae New Zealand Falcon が "complete molt" になっている。ムシクイ類ではさまざま。
ツグミ類は absent。コサメビタキで absent、サメビタキで complete。Ficedula は absent。
Kiat (2017) Divergent primary moult―A rare moult sequence among Western Palaearctic passerines divergent primary molt という換羽様式もあり、P1 から始まって次は P2 ではなく離れた点からも2方向に換羽が進むものもある。
スズメ目の少数で知られており (#シベリアセンニュウ で報告された)、この論文では旧北区西部のスズメ目を調べている。
P1 からは始まらないが初列の途中から始まって両側に進む形式 divergent sequence molt にハヤブサ目やウミガラスが含まれている。
スズメ目の divergent primary molt については換羽速度を早める一方、飛翔能力が低下して捕食の危険が増す。スズメ目では非常にまれな換羽様式であることは、おそらく換羽に必要なエネルギーが大きいためだろうと推論している。
この議論を延長すればハヤブサ目では換羽速度を早めることが有利なのだろうか。多くのタカ類ではソアリングの必要性がより大きいためこの換羽様式が選択されなかった? などの想像も可能に思える。
前述のように換羽様式は系統のよる関係もあるが生態の影響を受けやすいので、タカ類とハヤブサ類の違いは系統より生態の違いの方にむしろ関係しているのかも知れない。生態的必要性次第でタカ類の中にもハヤブサ類のような換羽様式を持つものがあってもおかしくなさそうだし、逆もあるかも知れない。ツミはそのような例なのかも。
翼の年1回の逐次換羽様式は鳥類進化の比較的後の段階で進化したのではないか: Kiat and O'Connor (2023) Rarity of molt evidence in early pennaraptoran dinosaurs suggests annual molt evolved later among Neornithes。
標本の換羽状況の分布から。同時換羽様式は羽毛を持つ恐竜で従来考えられていたより一般的だったのではないか、あるいは逐次換羽を行っていたが1サイクルは1年より長かったのでは、の2つの可能性を検討している。化石羽毛の摩耗度を考えると後者の可能性も考えられるが情報も乏しく難しいよう。
初列風切の換羽の証拠は 1.25 億年前のものがある: Wang et al. (2024) Earliest evidence of avian primary feather moult。著者が共通するが1サイクルは1年より長かった方を示唆するとのこと。
アメリカチョウゲンボウで換羽期間外に人工的に flight feather を抜いて新しい羽が成長するかを調べた実験がある: Delnatte et al. (2014)
Assessment of regrowth of flight feathers after manual removal in American kestrels (Falco sparverius)
4か月の観察で、尾羽は 2-3 週間で新しい羽が成長し始めたが風切羽が生えることは少なく、特に初列風切はほとんど生えなかった。抗炎症作用のある物質 (次硝酸ビスマス) を塗布しても成績は変わらなかった。
風切羽、特に初列風切は骨の periosteum 骨膜と強固な結合組織で結合しているが尾羽は R1 を除いて繊維・脂肪組織からなる rectricial bulb の中にあり体の他の部分の羽毛より結合が弱いとのこと。"fright molt" と呼ばれる現象は捕食から逃げるための適応とも言われている。
猛禽類でも尾羽は抜けやすいよう。尾羽を完全に失った猛禽類を見かけることもあり抜けた原因はともかく納得できる話ではある。#ハチクマの備考 [ヨーロッパハチクマの繁殖地行動・ディスプレイ] に van Nie (2002) が飼育下で尾羽を脱落させた事例もある。
初列風切を人工的に抜くと皮膚の乳頭部 (dermal papilla) の組織を傷付ける可能性があり、新しい羽が生えなかったり異常の原因になり得る。この実験ではおそらく傷つけたため新しい羽が生えなかったのではないか。
ハトでは人工的に初列風切を抜くと新しい羽が正常に生えた報告があるとのこと。
古く矢羽に用いるために尾羽が抜ける直前に捕獲した猛禽類で尾羽を抜いて自然に返していたのでは、と宮崎学氏が推測されていた (「アニマ」1989年1月号「童話に生きる鷹少年」の対談中 p. 46。宮崎氏はさらに毎年捕らえられて警戒心の強さが遺伝している "新説" を紹介している)。尾羽を抜いて自然に返すのは合理的で生理学的には納得できる。
柴田 (2011) Birder 25(12): 26-29 に (ハトなどで) 筋肉が緩んで羽が抜けやすくなり、尾羽を抜いて逃げてしまう説明があるが、筋肉の働きよりは解剖学的特徴の方がより関係しているかも知れない。
一方ワシが傷んだ羽を自分で抜いて換羽を促進する話は初列風切についてはあまり当てはまらないかも知れない。
捕食から逃げるための適応仮説 (主に獲物となる側) は古くからあり、Moller et al. (2006) Losing the last feather: feather loss as an antipredator adaptation in birds (ResearchGate)
がまとめている。背中側の方の羽毛の方が小さな力で抜けるとのこと。
この文献で引用されているものでは Dathe (1955) Ueber die Schreckmauser (恐怖による換羽について) があり、この当時話題となっていたようで複数の文献が出ている。wikipedia ドイツ語版では Schockmauser ともあって、ショックによる換羽の別名になっている。ニワトリやハトで尾が抜けやすくなる例があるとのこと。
この論文では尾は調べていないが背中、腰、胸の羽毛を抜くのに必要な力を測定している。小型の鳥が中心だがハイタカやヨーロッパノスリも測定されていてさすがにタカ類は抜けにくいよう (同じ体重の他の鳥に比べて倍ぐらい)。トラフズクは他の鳥とあまり違わない。ハトはやはり抜けやすい。
ハイタカは仮説通り背面の方が抜けやすかったが、ヨーロッパノスリは逆傾向になっていて腰の羽毛はむしろ抜けにくかった。研究そのものはハイタカに食べられる方の種類の相関を調べている。尾の抜けたハイタカの割合は 0.1% となっているがさて (?)。
現象としてはあるとはいえ、相関関係からの結論はさすがに強引な感じもあり、査読者も否定的意見を述べたらしいことがわかる。このような数字を測った研究は多分なくて貴重だが (話題にはなりそうだが) 話は半分ぐらいに聞いておくのがよさそう。
Moller は比較免疫学が専門領域らしい。ヒトの免疫の研究でも (ご存じの通り) すっきりした結果が出ることは少ないので相関を取れば出てくる研究には全体的に少し眉に唾をつけて見てしまう。一般的に否定はできないがそれほど肯定もできないのではと感じる。これは個人的好みの問題として聞いていただく程度でよい。
少し古めだがオープンアクセスでハトの尾羽の構造とコントロールする筋肉の活動を調べた論文: Gatesy and Dial (1993) Tail Muscle Activity Patterns in Walking and Flying Pigeons (Columba livia)。
尾羽を自由に動かすために骨に直結させず rectricial bulb に収めているため抜けやすくなっているのかも。
O'Connor et al. (2016) An Enantiornithine with a Fan-Shaped Tail, and the Evolution of the Rectricial Complex in Early Birds
は新しい化石から現代の鳥の尾の進化を考え、"rectricial complex" と呼んでいる。現代の鳥の尾と同様の構造は Pygostylia (尾端骨類) 以降に3回独立して進化したとの見方。
ニワトリの品種に腰から先がない形質 (tailless, rumpless) を持つものがある。遺伝的基盤も調べられている。参考: Chen et al. (2024) Molecular genetic foundation of a sex-linked tailless trait in Hongshan chicken by whole genome data analysis;
Guo et al. (2023) Mapping and Functional Dissection of the Rumpless Trait in Piao Chicken Identifies a Causal Loss of Function Mutation in the Novel Gene Rum に X 線写真もある。
比較的簡単な変異で失われるらしく、椎骨も含めて尾部は形質の変化しやすい可変部位となっているのかも知れない。尾の構造は鳥類進化の上でも比較的新しく生じたものと考えてよいのだろう。
備考:
*1: しばしば風切羽と訳されるが英語では尾羽を含めた総称らしいのでこの名前にしておく。学術語では風切羽が remix (複数 remiges) 尾羽が rectrix (複数 rectrices) となるので確実に区別したい場合はこれらの用語を用いた方がよいのだろう。
remix はラテン語の「こぎ手」、rectrix はラテン語の「操舵手」とのこと。
英語の用語表現も案外いい加減なところもあって初列風切に相当する primary feathers には "remiges" の意味は含まれない。初列風切の番号を P、次列風切の番号を S で表すのは英語の primary (primaries), secondary (secondaries) 由来だが、尾羽の R は rectrices 由来とのこと。
primary の番号順は内側から1番とする (descendant numbering) のが一般的で、多くの鳥の換羽順序に合わせている。外から1番とする順序は ascendant numbering と呼ばれる (wikipedia 英語版より)。
英語の一般的表現でも rectrices をしばしば見かけるのは "tail" と言った場合クジャクのように尾筒も含まれる可能性があるので厳密に呼びたいためだろう。
ヨーロッパ言語でも扱いに違いがあり、ドイツ語では primary, secondary に対応するものを Handschwinge, Armschwinge (いずれも単数形) で、手と腕なので意味はわかりやすい。Remiges primarii, Remiges secundarii と初列、次列に相当する名称は解剖学名としてラテン語表記されるよう (wikipedia ドイツ語版より)。
辞書によれば Schwinge は翼 Fluegel に相当する詩語。風切羽を指す鳥類学用語とは特に出てこない。独立に付けられた名称としても違和感はないが、上記ドイツ語をそのまま英訳すれば hand wing, arm wing となり、これら現在も使われる用語はドイツ語由来かも知れない。
フランス語ではラテン語ほぼそのままの名称が使われている。翼 aile に対応する用語はあるが、英語同様に風切羽を指す用語は特にないよう (wikipedia フランス語版より)。
Svensson の母国語であるスウェーデン語では handpennor, armpennor とドイツ語に近い表記。尾羽は stjartpennor と、全て英語の feather に対応する pennor を付けている。
ロシア語では風切羽を指す用語があって makhovye (複数形形容詞または名詞)、日本語同様に初列、次列を付けて表現する。
wikipedia を見てもこれらの記載されている言語はあまり多くなく、世界的に見ても相当マニアックな話題なのだろうと思われる。
用語に関連して alula はドイツ語では Daumenfittich (親指の翼) などの名称がある。系統発生研究がなされる以前から解剖学的解釈も含まれていたわけである。
羽弁はドイツ語では Fahne で旗などの意味。この単語には植物学で旗弁 (きべん) の用語がありおそらくドイツ語を訳したものではないだろうか。鳥類学用語も起源が同じかも知れない。以下 OED によれば英語の vane には植物学用語の意味はない。
羽毛のこの構造は英語では web とも呼ばれる。vane のこの意味の用例は 1713 年にすでにあったが、現在の vane を指す解剖学用語として特定の構造を指すものに用いられるようになったのは案外新しいかもしれない。1835-1836 年の Todd's Cyclopaedia of Anatomy & Physiology では barbs とともに The vane [of the feather] consists of barbs and barbules と紹介されているのでこの意味であることは間違いない。
barb は本来の意味はひげ (1450-1500? の用例がある。別の語義でさらに早いものもある) のことで現在はほぼ廃れている。派生して動物のひげのような付属物を指すようになった (1486 年初出)。タカの嘴の下の羽毛など (現在は廃れている)。語源はフランス語 barbe < ラテン語 barba (ひげ) からの借用とのこと。その後フランス語とは独立に意味が派生したとのこと。
このような例を見ると羽毛の他の用語もドイツ語を訳したものではないかと多少想像して辞書を見てみると、風切羽全体を指すものは Schwungefeder (単数形) と少し形が異なっていた。辞書訳では飛羽、翼羽、風切羽となっていてかつては前者の訳語が用いられていたことが想像できる。風切羽はむしろ新しく付いた用語なのかも? 翼羽の用語があったので alula は小翼羽と名付けられたとしても納得できる
[藤井 (2023) Birder 37(12): 28-29 を参考に考察した]。
他にも (いずれも単数形で表記) Ast (枝から羽枝)。Deckfedern (= tectrices、辞書訳で蓋羽。Decke = 覆い)。Schulterfedern (Schulter 肩)。
Oberschwanzdecken (上尾筒)、Unterschwanzdecken (下尾筒)。"筒" の概念はドイツ語には現れない。直訳すれば上尾蓋、下尾蓋になる。部位の名称はドイツ語とよく対応している。
wikipedia ドイツ語版の Konturfeder の図を参考にした。さらに Hartert (1910-1922) XII (ドイツ語の部位名称図)。
この図を見てさらに気になったのは趾はドイツ語で Zehe で英語の digit では手足どちらも指す。手足で用語を使い分けるのはドイツ語の影響があったのでは? (英語でも足の指に toe の用語があるが、どちらかと言えば一般用語)。
羽軸もドイツ語では2つの概念があり、Schaft (これは羽軸とそのまま訳せる) と Spule (辞書には羽幹とある。かつてはこの用語が使われていたらしい)。
ネットを探してもあまり見つからなかったが羽軸根の用例がある。学術用語ではラテン語で calamus。calamus を指して "羽根" (日本語で "うこん" と発音するもの) と呼ぶ用例はむしろ中国語にあった (参考: 脊椎動物の皮膚)。
日本語では大塚・和田 (2001) Birder 15(10): 27-30 の「換羽の生理学」で羽根 (うこん) が用いられていた。また和田 (2002) Birder 16(2): 71-73 でも羽根 (うこん) が振り仮名なしで用いられていた。茂田 (1997) Birder 11(8): 27 でも振り仮名付きで用いられており、この時代は一般的用語だったのではないだろうか。
参考までに Feder のドイツ語辞書訳を見ておくと羽、羽毛となっており、羽根の訳語はもっぱら羽根飾りや羽根ぶとんに用いられていた。確かに "羽ぶとん" では読み方も不詳でまとまりが悪い。当時の訳語用例を見ると「羽根ぶとんなどの羽根が抜ける」(ドイツ語 federn) のような場合は羽根を使っていた。同じ動詞でもふとん以外は羽が用いられていた。
留鳥の Standvogel も気になった用語で (#ホトトギスの備考参照)、鳥類学用語にはドイツ語からの訳がかなりあるのではないだろうか。
#ヨシゴイの [粉綿羽と櫛状の爪] も参照。
OED を調べると英語の名詞の molt (moult) は意外に新しい用語で鳥では 1819 年の用例が最初とのこと。もっぱら in the moult と状態を示す用語として使われていた。1894 年の Sharpe, Hand-book to Birds of Great Britain に first moult の現代と同じ用法があった。
動詞の方の用例は古くからあり 1425 年ごろの用例があるとのこと。語源は突き詰めればラテン語の mutare とのこと。l が挿入されたのは 16 世紀終わりごろで、末尾の -t の前に最初は無声の l が挿入されたものとのこと (類例 fault < フランス語 faute)。
[風切羽の枚数と尺骨の長さの関係の系統による違い]
鳥類全般で風切羽特に secondary (次列風切) の枚数と尺骨 (ulna) の長さ、系統との関係を調べた研究: Deeming et al. (2023) Maintaining the avian wing aerofoil: Relationships between the number of primary and secondary flight feathers and under-lying skeletal size in birds
secondary の枚数と付着する尺骨の長さによい相関があることはよく知られているが、その関係は体重や系統によってどのように変わるかを調べたもの。一般的には大型になって羽毛が比例して大きくなると航空力学的に必要な強度が保てないために枚数を増やしていると解釈されるが、単純に体の大きさと枚数が比例するわけではない。
例えばタカ類はスズメ目より何倍も大型だが枚数はあまり違わない。
fig. 3 によれば面白いことにハヤブサ目 (オウム目、スズメ目でも同様) などでは尺骨の長さが違っても secondary の枚数はあまり変わらない。何か系統制約的なものがあるらしい。
新しい系統の鳥の特徴かと言えばそうでもなく、キジ目、ハト目も同様。一方タカ目 (これはコンドル・ハゲワシ類が含まれるため生じた相関かも知れない気がする)、ツル目、ペリカン目、ミズナギドリ目などは secondary の枚数はかなり変化する。カモ目は中間的。詳しくは論文を見ていただきたい。
fig. 4 に体重と secondary の枚数の関係があり、チドリ目やカモ目は相対的に多い。羽ばたいて長距離を一気に渡るタイプの鳥では多いのかも。スズメ目やオウム目は少なく、ハヤブサ目も少なめ。
全系統の凡例が出ていないようで一番軽いのはハチドリ類のよう。体重比では secondary の枚数が多い。
primary (初列風切) の方は広い系統で体サイズに比べてほぼ固定 (10-11) されていて、ダチョウでは 16 もあることと比較すると飛翔のために枚数に強い制約が存在する可能性が考えられるらしい。
[風切羽や雨覆の構造と機能]
長大な論文なので存在のみ紹介: Hieronymus (2016) Flight feather attachment in rock pigeons (Columba livia): covert feathers and smooth muscle coordinate a morphing wing
雨覆の構造と機能についてはこれまでほとんど注目されてこなかった。ここで解剖・組織学や制御機構や生体力学が一気に扱われている。
通常のハトの羽ばたきでも筋肉制御のみで実現するには速すぎる。神経による制御 (neuromotor control) 以外に、構造そのもに由来する受動的な制御も用いているはずである。そのための解剖学的な基礎情報が必要である。ここでは鳥の皮膚の平滑筋や弾性組織の構造や機能に特に注意を払い、風切羽や雨覆の付着部位などを記述している。初列風切のそれぞれの羽毛の付着部位の構造も記されている。
次列風切も近位部と遠位部で付着様式や機能が異なる。P1-P5 は同じような構造だが P6-P10 は1枚ごとに付着部の構造が異なる。
関連する研究がいくつか行われているがオープンアクセスでないものが多いので以下を紹介:
Gong et al. (2024) Position-dependence straight-wing experiments of artificial coverts in flow separation control at a high Reynolds number
これは実際の鳥ではなくモデルを用いた研究だが、弾性のある雨覆があると流れに剥離が起きた場合に受動的に振動を (流れに反応して passive flap を起こす) 起こして剥離の悪影響を防ぐ。結果的に例えば失速を防ぐ効果がある。
Zekry et al. (2023) Covert-inspired flaps: an experimental study to understand the interactions between upperwing and underwing covert feathers (出版社サイト)
翼上面の雨覆と下雨覆の相互作用。体を起こした状態で飛び立ったり着地する鳥 [high angle of attack; angle of attack 迎角 (むかえかく) この論文ではハクトウワシやオオタカを例に挙げている] で特に力学的要請が厳しい。これまでは関節の構造などで巧みな機能を実現することが主に研究されてきたが、雨覆のような小さな構造も大きく影響を与えることができる。
流体力学的な吸引力の働く面と圧迫力の働く面で自然界での記録と同じような状況が実現でき、片側だけ (例えば翼上面の雨覆のみがある場合) より制御能力が高かった。
Murayama et al. (2021) Flexible Flaps Inspired by Avian Feathers Can Enhance Aerodynamic Robustness in low Reynolds Number Airfoils
(以下コメント。論文のどこかや過去に触れられているかも知れない) おそらく雨覆の位置は流れの剥離場所に対応する形になっているのだろう。複数列の雨覆が存在するのは速度や角度などの条件によって流れの剥離場所が異なるためでは。また雨覆が階層的になっていることの構造力学的利点もおそらくあるのだろう。
雨覆の材質の曲げ強度も上記のような機能を最適化する (passive flap の振動数など) ような最適化が行われているのだろう。骨組織のような硬い構造を突出させて変形しない、あるいは皮膜のような弾性のない構造ではおそらく効果を発揮せず、ヒステリシスを伴って変形できる鳥の羽毛はおそらくちょうどよいのだろう。
なぜそれほどまでの機能が "腕 + 羽毛" から進化できたのか驚異としか言いようがないが、たまたま四足動物の腕の骨格にそれだけの自由度があり、羽毛にはこれほどの機能を支える構造や物性特性があり、絶妙の組み合わせで最適化が可能だったのだろう。異なる要素の組み合わせが必要で、鳥ほどすぐれた飛翔性動物が独立に何度も進化しなかった理由ともなるのだろう。
そのような視点で考えると、たとえ羽毛を持っていても初期設計がうまくなく、十分な機能に到達できず消滅した "失敗作" のような系統が多数あっても不思議でないと思える (始祖鳥もきっとそうだ? *1)。現在の鳥類の系統につながる系統のみが、たまたま十分な機能の組み合わせに唯一成功した可能性があるかも知れない。
雨覆の機能は体を起こした状態で飛び立ったり着地できる鳥と得意でない鳥 (海鳥など。ミズナギドリ類の飛び立ちや着地を考えていただきたい。翼竜などもおそらくできなかっただろう) では最適化の条件が異なっているのだろう。
ミサゴは海鳥に似た最適化が行われていて着地が器用でない結果 (#ミサゴ備考の [ミサゴは不器用?] 参照) となっているかも知れない。
ホバリング時の雨覆の役割はまだ実験されていないようなので、ミサゴなどではそちらの機能を果たすように最適化されているのかも。
もし雨覆がなければ...おそらく体を起こした状態で飛び立ったり着地できず海鳥のような動きになり、少なくとも狩りをする猛禽類には向かないだろう。
ミサゴはなぜホバリングから獲物を狙うことが中心なのか、つまり海ワシ類の魚の捕食とは何が違うのか多少考えてみた。ミサゴは海鳥に似た飛翔羽の最適化のため止まり場から飛び込む行動はあまり得意でなく、アジサシ類同様に空中から狙う戦略に特化したのかも。もっともミサゴは海ワシ類より体重が軽いのでホバリングが可能などの要素もあるかも知れない。
アジサシ類は垂直方向に直接飛び立てる (迎角が大きい) ので、ホバリング能力と迎角が大きい離着陸を行う能力が排他的というわけではなさそう。
他のホバリングを行って獲物を狙う種類では翼の構造はそれ以外の種類と違うのだろうか。チョウゲンボウやノスリ類、特にケアシノスリがホバリングしながら獲物を狙うのは見事な気がするが、ホバリングしている捕食者を見つけると獲物は逃げてしまわないのだろうか (捕食者側にとってホバリングするメリットは?)。
そういえば O'Rourke et al. (2010) Hawk Eyes I: Diurnal Raptors Differ in Visual Fields and Degree of Eye Movement の研究があって、アメリカチョウゲンボウでは眼球があまり動かないので、ホバリング時に眼球を固定するのに有利かも知れないとの視覚生理からの考えがあった。フクロウ類も眼球があまり動かないのでホバリングを使う...かどうかは知らない。
ミサゴの眼球もあまり動いていない印象を受けるがいかが? - 獲物の性質によるかも知れない。#ハイタカ備考の [ハイタカの急降下による捕食行動] で考察したが、小鳥は相対的に目がよいので遠くから見つける必要があり、遠方あるいは隠れたところからの襲撃が必要になり獲物の探索時と攻撃時で視線が異なるため眼球を動かす必要性が高まる。
魚ではそのようなことを考えなくてよいのでずっと正面に見据えて近くから急降下 (と言っても自由落下みたいなものではあるが) すればよいので眼球を動かす機能が発達する必要がなかった、この方法だとハンティングのテクニックもそこまで必要としない - の解釈でいかがだろうか。
ミサゴのデータは知らないが、眼球を動かすタカはそれだけ複雑なことを行っているとみなしてよいのでは。
ミサゴの場合には水中の魚からはそもそも鮮明に見えないので、ホバリングからの捕食でもあまり影響はないかも知れない。止まり場から飛び込む行動とホバリングからの捕食のいずれが有利とも一概に言えない気がするので、行動に必要なエネルギー消費なども見積もる必要があるのだろう。体重が大きいほどホバリングにエネルギーを要して不利になるだろう傾向は予測できる。
さてミサゴの行動は捕食上有利だったのか、それとも翼の機能によって選択された捕食方法のいずれだろうか。
備考:
*1: 始祖鳥を取り上げたら早速研究が出ていた: O'Connor et al. (2025) Chicago Archaeopteryx informs on the early evolution of the avian bauplan
(UV light and CT scans helped scientists unlock hidden details in a perfectly-preserved fossil Archaeopteryx一般向け解説)。
上肢の骨が長く、次列風切と体の間に隙間があれば揚力を失ってしまう。現代の鳥では三列風切で間を埋めることでこの問題を回避している。この始祖鳥化石では三列風切の証拠が初めて見つかり、始祖鳥に飛ぶ機能があったのではとの解釈が行われている。恐竜は飛翔能力を複数回進化させた魅力的な仮説の裏付けともなるとのこと。
#カワラバト備考 [家禽ハト品種の形態に関連する遺伝子] で Microraptor の新化石の研究 を紹介。
どこに入れてもよさそうだが、現代の鳥以前の段階で子育てが行われていた新証拠 (?)。Bert et al. (2025) Neonatal state and degree of necessity for parental care in Maiasaura based on inferred neonatal metabolic rates
成長に伴う代謝率の変化を骨化石から読み取る、あるい意味で古典的な方法。Maiasaura が晩成性に近いと主張しているが、Fig. 4 を見ると比較対象となっている早成性で特別な成長率を示すのはカモ目と走鳥類だけで、他の鳥は早成性でも晩成性でも大差ないのでは? 統計解析で言えば外れ値に引かれる効果になると言えるだろう。
Maiasaura の誤差棒も考えるとあまり証拠になっていない気がする。「マイアサウラ (Maiasaura) が子育てを行っていた証拠がまた一つ明らかになりました」とは短絡的に考えない方がよさそう。
[ケラチンの進化]
羽毛と大変関係が深いので換羽の後に含めておく。哺乳類の毛も鳥類の羽毛もケラチンが構造形成を行っていることはよく知られている通り。α ケラチン はすべての脊椎動物にあるが鳥類・爬虫類には β ケラチンがある。
β ケラチンの方が β シートを作るアミノ酸配列を持ち、硬い構造を作るのに向いている。羽毛や嘴、爪に多く含まれている (近年では corneous beta-proteins と呼ばれることも多く、β ケラチンが歴史的な名前)
[cf. Calvaresi et al. (2016) The molecular organization of the beta-sheet region in Corneous beta-proteins (beta-keratins) of sauropsids explains its stability and polymerization into filaments]。
哺乳類の毛を構成するのは α ケラチン (別名 cytokeratins) の方。
森本 (2024) Birder 38(10): 30-33 に解説があるが構造形成におけるこの違いに触れて欲しかったところ。
Greenwold et al. (2014) Dynamic evolution of the alpha (α) and beta (β) keratins has accompanied integument diversification and the adaptation of birds into novel lifestyles
は比較的最近のケラチンの進化のレビュー論文。哺乳類に比べて鳥類では α ケラチンの遺伝子は一部を失ったものの一部を獲得している。
β ケラチンの遺伝子数は種差も大きく、メンフクロウでは6遺伝子しかみつからなかったがキンカチョウでは最大 149 個もあったとのこと。ただしこの数字は例外的に大きい。ニワトリも 133 個とのこと
(ゲノム精度にも影響されているかも知れないが家禽化の影響も考えられるとのこと)。この研究で調べた結果では鳥類平均で 33.81 だったとのこと。
β ケラチン遺伝子はいくつかに区分され、scale beta-keratins (爬虫類と共通)、feather beta-keratins (鳥類のみで羽毛に見られる) に大別され、さらに claw beta-kerains (爪) と keratinocyte beta-keratins (爬虫類と共通) があり、種類によっては一部の系統を欠いているものもある。
猛禽類では claw beta-kerains の割合が高く、生態に対応した爪の進化と関係していると考えられる。
水鳥では keratinocyte beta-keratins の割合が高く、feather beta-keratins の割合が低い。防水性に優れるなどの適応と関係している可能性がある。
β ケラチンは爬虫類の祖先型から遺伝子重複で種類を増やし、鳥類とワニ類の共通祖先の段階以降 (羽毛の進化) に遺伝子重複で種類を増やし、さらに水鳥型と陸鳥型に分化したと考えられるとのこと。
Li et al. (2013) Rapid Evolution of Beta-Keratin Genes Contribute to Phenotypic Differences That Distinguish Turtles and Birds from Other Reptiles によれば、鳥類とカメ類で β ケラチン遺伝子の進化が早いとのこと (ただし調べられた種類は少ない)。
ゲノムの1部位の重複が独自に起きて複雑な構造を生み出したと考えられる。
Alibardi et al. (2009) Evolution of hard proteins in the sauropsid integument in relation to the cornification of skin derivatives in amniotes
α ケラチンの祖先型ではグリシンとセリンが多いが、羽毛の β ケラチンではグリシンを多く含む 52 アミノ酸領域の欠失で羽毛にみられる整列した長い構造を作るのに適しているとのこと (この知見は古くから知られていた)。グリシンの多いタンパク質は疎水性が高くてうろこを作るのに向いているとのこと。
羽毛の β ケラチンでは末端部にシステインが多く含まれてジスルフィド結合で強度を高めるのに役立っていると考えられる。
Alibardi (2025) Keratinization and Cornification of avian skin appendages during development. Insights from immunolabeling and electron microscopic studies
特にダウン形成のおける α ケラチン (IFKs) と β ケラチン (CBPs) の相互作用。IFKs の形成を追い抜く形で CBPs が蓄積して行くが、IFKs は酸性で CBPs は塩基性のため静電相互作用が働き、CBPs がジスルフィド結合を作って構造を作る過程が推定されるとのこと。羽毛から抽出されるタンパク質の大部分は CBPs (feather CBPs) だが少量の IFKs も含まれるとのこと。
[カタグロトビ若鳥の色彩メカニズム]
Negro et al. (2009) Porphyrins and pheomelanins contribute to the reddish juvenal plumage of black-shouldered kites
若鳥の赤っぽい色彩にメラニン系統の色素以外にポルフィリン類の coproporphyrin III (フクロウ類やカタグロトビのひなの色彩に関係している) が関与していることを示した。成鳥の羽毛にはこの色素はないとのこと。ポルフィリン色彩は日光で退色するため一時的に必要となる機能に向いているのでは、また赤外線を吸収しないため体温調節に有利との考えもある。
ポルフィリン類を色彩に用いている鳥は知られている範囲で少なく、フクロウ類、ヨタカ類、ノガン類とのこと (当時知られていた範囲)。この著者はカタグロトビ類とフクロウ類の収斂進化を示す要素とも捉えている。
Camacho et al. (2019) Correlates of individual variation in the porphyrin-based fluorescence of red-necked nightjars (Caprimulgus ruficollis)
によればポルフィリン類を色彩に用いている鳥で色素が同定されたものはこの時点ですべて coproporphyrin III だったとのこと (#オオルリ備考の [蛍光を用いる鳥] でも紹介)。
[カタグロトビは偏食家?]
DeLong et al. (2024) The global diet diversity spectrum in avian apex predators
が面白いデータベースを提供している。猛禽類 (ここではタカ、ハヤブサ、フクロウ類をすべて含む) が何種の獲物を食物としているかを調べたもの。
データベースそのものは jpdelong/OSPrey-database からダウンロード可能で OSPrey-database "Omnibus study of prey" の略とのことだがミサゴの osprey に合わせたものと想像できる。解凍して raptor_ds_20.txt のファイルを参照。名付け方や面倒そうなデータベース保守を行われている点、かなりの猛禽好きの方が含まれているのではないかと想像している。
それはともかく、この論文でカタグロトビ類縁の オーストラリアカタグロトビ [高野 (1973) ではオーストラリアハイイロトビ] Elanus axillaris Black-shouldered Kite は少数の種類の獲物に頼っている代表種となっている。好みの獲物があればそればかり食べていると言い換えてよい。
もっと極端なものがタニシトビ [高野 (1973) ではカタツムリトビ] Rostrhamus sociabilis Snail Kite でこれはほぼ特定の獲物しか食べない。(研究で調べられた) オーストラリアカタグロトビは4種のみ獲物としていたとのこと。
近年のカタグロトビの分布拡大傾向などから想像できるように齧歯類ならば何でも食べる状況ではないのか、研究で調べられた地域で1種類の獲物が卓越しているのかなどはこの研究のみでは何とも言えない。
論文そのものは苦労して集めた OSPrey-database の紹介目的が半分ぐらいありそうだが、猛禽類全体として統計的にも興味深い結果になっている。
あくまで仮定だが獲物の種ごとの個体数 (相対優占度) が lognormal distribution (対数正規分布) に従うとした場合、ランダムに獲物を捕える (出会い頭に捕えるなど) 場合には獲物の分布も獲物の相対優占度分布を反映すると考えられるが、獲物の多様性指数 (ここでは Shannon entropy シャノンのエントロピー) で評価すると獲物の種類の多い猛禽類の食事は軒並みこの予測を上回っていた。
つまり獲物はランダムな捕獲から予想されるよりも各種を種個体数によらず均等に捕獲する選び方に近いものになっていた。
参考で示されている中で特に獲物の種類が多かったものはハヤブサで 40 種以上を獲物にしていた。
意外にもコウモリダカ Macheiramphus alcinus Bat Hawk の多様性が高く (データを見ると 36 回の捕食で 22 種)、マダガスカルチュウヒダカ Polyboroides radiatus Madagascar Harrier-Hawk も高い (63 回で 19 種。器用のような不器用なような種なので意外)。
コウモリダカはいかにもスペシャリスト (論文ではこれら用語は複数の意味に解釈できるので避けている) の印象を受けるがコウモリ類の種多様性の高さを反映しているのだろうか。
この場合でもランダムな捕食から予想されるものを上回っていて多様な獲物を選んでいる傾向が出ているが、マダガスカルチュウヒダカや広義 Accipiter 属 (データは多数ある) ではランダムでも説明できる範囲だった。
また体が大きいほど食物の幅がが広がる予想ができるがその傾向は認められなかった。
獲物の種類数とその数分布 (ここではエントロピー) は異なるものとして評価する必要があるとのこと。
分岐の古い系統に偏食家? の種類が多いのか気になるところだが、マダガスカルチュウヒダカで多様性が高いならばあまり関係ないかも。食物データベースは限られた種に偏っているためか (あまり知られていない種はほとんど入っていない)、あるいは系統解析であまり関連が見られなかったか取り上げられていない。
分岐の古い系統に特定の食物にこだわる種類が多い印象を受けるのは、特異性が有名な限られた種に注目しがちなためかも知れない。
著者は猛禽類が特定の種の獲物に偏るより多様性傾向が強いため、食物網が単純で例えば獲物が特定の種に偏る場合に生じやすい捕食者 - 被食者の共振動が生じにくくなり、食物網の安定化をもたらすと推論している。獲物の数分布が対数正規分布に従っている仮定に問題があるのでは、など考えられる方はぜひ論文を読んで検討して著者に挑んでいただきたい。
[カタグロトビのまぶたの機能]
Shawki et al. (2024) The Role of the Eyelids of the Black-Winged Kite, Elanus caeruleus in the Immune Protection of the Eye
まぶたの粘膜や瞬膜に多数の免疫細胞が認められ (conjunctiva‐associated lymphoid tissue, CALT) 目を保護しているとのこと。
Langerhans cell (ランゲルハンス細胞。皮膚免疫に関与する。膵臓のランゲルハンス島とは別物) も認められる。鳥類皮膚の Langerhans cell の記載は比較的新しく 1990 年代ぐらいから酵素活性などを用いて同定されたらしい。
まぶたのメラニンは反射光を防止するにも役立っているのか。
カタグロトビ類は古く分岐した系統で眼窩上の骨の張り出しが少ない ([カタグロトビ類の系統分類] 参照) と言われるが bony shelf (lacrimal process) がしっかり見られるとのこと。
[備考]
Elanus 属に以前所属していて、これから派生した属名に Elanoides (「Elanus に似た」の意味) があり、こちらはハチクマと近縁の種類である。紛らわしいので注意が必要。
例 ツバメトビ Elanoides forficatus 英名 Swallow-tailed Kite (#ハチクマの備考にハチの巣食の写真がある。系統分類もハチクマの備考を参照)。
-
トビ
- 学名:Milvus migrans (ミールウス ミグラーンス) 渡るトビ
- 属名:milvus (m) トビ
- 種小名:migrans (分詞) 移住する、渡りをする (migro (intr) 移住する)
- 英名:Black Kite
- 備考:
milvus は i が長母音 (ミールウス)。
milvus そのものの語源は不詳 (wiktionary)。派生語に milvinus (トビのような、猛禽的な) の単語があり "ミールウィーヌス" とやはり長母音で読む。
migrans は a が長母音だが mi- にアクセントがある (ミグラーンス)。動詞 migro の分詞形の単数・主格。
日本の亜種名の lineatus は i, a が長母音でアクセントもある (リーネアートゥス)。linea (線) の冒頭が長母音であることと形容詞語尾の発音による。
Kessler (1851, 参考文献参照) によれば当時の学名 Milvus niger Kessler (黒いトビ) で英名その他の言語名はこれまたは後述 Milvus ater 由来と考えられる。
英国では Kite と言えばアカトビ Milvus milvus のことで [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)]、学名からもこれが "kite" の本家であることがわかる (しかし一度は絶滅して再導入された)。
英国にはトビは生息しないのでこれで紛らわしくなく、大陸のより黒っぽいトビを指して学名ないし他言語例えばフランス語から英名を付けたものだろうか。英国からみると海外の鳥のことなのであまり真剣に名前を検討しなかった可能性がある。
OED を調べてみると 1575 年 Turberville, Booke of Faulconrie の用例がありフランスでは Mylan Noyer と呼ばれるとのことで Blacke Kyte の名称が与えられていた。フランス語由来と考えてよさそう。red kite の用例は意外に新しく、1792 年 Owen のものがある。英国内では kite で十分だったので海外のことを記述するようになり black kite, red kite を使い分ける用例が出てきたよう。
kite の用例は鳥の方が古く 1400 年ごろにはすでに使われていた。凧を指す比喩的用例は 1556 年ごろが最初とのこと。
英国からアメリカやオーストラリアに入植すると本家の "kite" は生息していないが、例えば尾が似た形で同じように飛んでいる鳥がいるのでそれらを "kites" と名付けたと考えるとその後の英名が大変納得できる (ちょうど英国の Robin と同じ名前がアメリカで使われたように)。特にアメリカには本家の "kite" の系統が存在しないのでこれでまったく紛らわしくなかった。
これらの "kites" は系統的にはアカトビやトビとは近縁でなかったが、英名では総称して "kites" と呼ばれたために分類学にもその影響が残ったことがタカ類の分類がごく近年まで混乱していた一要因ではないだろうか。現在でもタカ類の包含範囲を英語で記述する際に hawks, kites, ... などの形で使われている。
ハチクマがトビと同じグループ (kites に含められることもある) と考えられたのもこの影響が間接的に及んでいると想像できる ... と思えば発端は英国にアカトビ1種しかいなかったためだったのかも。
鳥の分類や名称概念のいろいろなところに英国事情が現れている。
ドイツ語やフランス語ではだいぶ様相が違うので ["トビ" 類のドイツ語名] も参考に。
現在のドイツ語名は英名に合わせて Schwarzmilan (黒いトビ) が一般的だが、Braune Milan (褐色のトビ) も使われていた。こちらの方が色彩をよく反映しているように感じるが。
wikipedia 英語版の Kite_(bird) の項目によれば Vigors (1824) は Milvina (kites, Elanus と Milvus の2属)、
Swann (1922) がカッコウハヤブサ類 (Aviceda 属) とハチクマ類を Milvinae 亜科に含めたとのこと。ハチクマ類がトビ類に分類されていたのはこのあたりが起源だったよう。
Peters (1931) "Check-list of Birds of the World" では Elaninae (カタグロトビ亜科)、Perninae (ハチクマ亜科。現代の概念より狭い)、Milvinae (トビ亜科。現代の概念より広い)、Polyhieracinae (シンジュトビ亜科。現代ではカタグロトビ亜科に含まれる) と分けていて思ったより現代の分類に近かった。
英語 kite の由来は中世英語 kyte, kite, kete、古英語 cyta (トビまたはサンカノゴイ)、さらに祖西ゲルマン語 *kurijo でこれは祖ゲルマン語 *kuts (猛禽類) に由来するとのこと。この語源は祖インド・ヨーロッパ語 *geweH-d- (鳴く、叫ぶ) とのこと。語源的にはフクロウを指す現在のドイツ語 Kauz に関係がある (wiktionary)。
猛禽類の英名の多くが遡ると音声由来で、行動の方はむしろあまり注目されていなかったのだろうか。
英語の同義語に glede があるとのこと。これは glide と関係し、現在でもアイスランド語 gleda、スウェーデン語 glada に残っているとのこと (wiktionary)。
[トビの学名の変遷]
Linnaeus はアカトビを Falco Milvus Linnaeus, 1758 と命名 (原記載)。
トビの Falco migrans Boddaert, 1783 の 原記載 (No. 472; mihi と自身による命名であることが示されている) に先取権があることが認められたのは後の時代と想像され、Milvus niger や Milvus ater の学名が長く使われていたのだろう。
Milvus niger Bonaparte, 1838 の用例があり、Kessler (1851) 以前に使われていた。
Milvus ater は Falco ater Gmelin, 1788 が由来のよう (記載。参考1 ここに Black kite. Lath. や Milan noir. Buff. が出てくる。前者は現在の英名と同じ。後者はフランス語名)。
もう1件あり参考 2。こちらは同じ学名を Gmelin (1788) が用いながら Falco communis (ハヤブサに用いられたことのある学名), Falco columbarius (現在ではコチョウゲンボウに対応) などが挙げられている。
Falco migrans Boddaert, 1783 は Buffon (1770) Histoire naturelle des oiseaux に基づくもの。
Buffon (1770) ではここで il y a une autre espece encore plut voisine & qui se trouve dans nos climats comme oiseaux de passage, que l'on a appele milan noir と記していた。アカトビに非常によく似ているがもう1種あって、我々の気候帯では渡りの時期に見られるとある。
p. 288-289 には Belon のエジプトへの渡りや越冬の記述もあり、当時から渡り鳥であることが判明していた模様。しかし Buffon (1770) はフランス語で milan noir と呼ばれることを述べたのみで本文にも図版にも学名を記さなかった。そのため Boddaert (1783) が学名を与えた経緯となっている (wikipedia 英語版より情報を知った)。
現代の学名はこの種小名を用いているため、"さまよう" (愛媛の野鳥「はばたき」などではこちらが採用されている) よりもより積極的に "渡る" の訳語を採用した。
意味の上ではどちらでも誤解を生じるものではないが、"渡りをする" ことも知られていた記述論文とそれに基づく種小名の記載を実際に確認できたため。
なお Linnaeus (1758) のアカトビの記載でも渡り鳥とあり、スウェーデンで夏鳥であることから判定したものだろう。アカトビも渡りをするのにトビに migrans が付いたのはフランス事情由来と言えるだろう。
migrans の種小名が用いられている種は IOC 14.2 ではトビのみ。実は珍しい種小名である。亜種小名まで含めても他にもう1つあるのみ。migratorius / migratoria はコイカルに用いられているがこちらもあまり用例が多くない。"渡りの" を意味する学名は習性を記述するため、標本のみで生態がわからないものには比較的使いにくかったのだろう。
北米で普通種のコマツグミ Turdus migratorius Linnaeus, 1766 American Robin もある。
migrans は動詞 migro の分詞形で英語ならば migrating に相当する。一方 migratorius / migratoria は migratory に相当する。同じような意味ではあるが英語でも migrating と migratory は微妙な違いがある。例えば "渡り鳥" は migratory birds で、同じ意味でも使われるが migrating birds は "渡っている鳥" の意味が近い。migrating birds は birds on migration と言い換えてもよいだろうか。
Bildstein (2006) の本が "Migrating Raptors of the World: ..." となっているのも、"渡りをする猛禽類" 一般を静的に記述する本ではなく、"今渡っている" 臨場感を出すホークウオッチャーの視点で書かれたものなのだろう。
このような視点から見ると、トビに付けられた migrans は Buffon (1770) の oiseaux de passage に対応するもので、日本語の用語では旅鳥が近いと思われる。現代の分布を見るとフランスでは夏鳥になっているが観察地次第では渡り途中しか観察されなかったものかも知れない。
Milvus 属を導入したのは Lapacede (1799) で Falco Milvus の Milvus を属に昇格とともに Milvus vulgaris の種小名を与えた ("普通のトビ" の意味。ここではタイプ種を意味するような役割となっている)。
(The Key to Scientific Names の Milvus の情報から)。
この経緯はヨーロッパノスリの場合と同じ (#ノスリの備考参照) で、属への昇格の場合種小名を新たに与える必要はない規則となって Linnaeus 由来の Milvus milvus に戻されたものと考えられる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも Milvus ater melanotis (黒いトビの黒い耳の亜種とされた)、
Milvus melanotis Temminck & Schlegel (Fauna Japonica で用いられた学名:
本文 フランス語名 le milan a oreilles noires (耳の黒いトビ)。
この時点でヨーロッパのアカトビ以外に Milvus 属がすでに4種記述されており [Buffon (1770) の記述は気づいていなかったのかも知れない] "アカトビの日本版" の名称はふさわしいと考えなかったかも知れない。この時点では別属であったがノスリに japonicus を用いたため遠慮があったかも知れない。
図版 1, 図版 2),
Ogawa (1908) には Milvus major Hume が並んでいるものの Milvus migrans はまだ現れていない。
melanotis は melas, melanos 黒い -otis 耳の (Gk) で英語別名の Black-eared Kite に対応する。この名称も図鑑などによく登場する。
おそらく Gmelin (1788) の Falco ater の用例は種同定不明として使わない立場もあったと思われる。その場合は Milvus niger が優先されたり、これもあるいは種同定不明な部分があるなど確実性の高い Milvus melanotis が優先されていた時代があったと思われる。
Milvus melanotis の用例は多数ありこれも広く使われていた学名のよう。記載年は 1847/1848 とされる模様 [Dement'ev and Gladkov (1951) では 1844 となっている]。その後 Milvus migrans Boddaert, 1783 のさらに早い記載 (一覧リストの中に含まれているものでいかにも気づきにくい) が見つかったのだろう。
現在の学名からは想像しにくいが、英名などいろいろなところに過去に使われた学名の痕跡が残っている。
melanotis は中国を基産地とする lineatus のシノニムとされ、記載年が遅かったため日本で記載されながら亜種名にも残らなかった。
古い用例を見ると英語では Milvus ater 由来が多いようで、ドイツ語やフランス語では Milvus niger が見られる。
しかし広く使われていた Milvus melanotis の種小名はいかにもありそうなもので、Buteo melanotis Jerdon, 1841 の用例がある。
近いグループなので同属にまとめられることがあれば衝突のおそれがあったが、トビ類とノスリ類は異なると認識されていたためか実際には衝突が起きなかったようで、この学名は現在はカンムリワシの亜種に使われている。
ちなみに種小名に使われる melanotis とよく似た melanotos (#アメリカウズラシギなど) もあって一見同じものに見えてしまうが語源が異なる。前者は -otis 耳の だが後者は -notos 背中の (いずれも Gk) に由来する。"黒い" の場合は melanos と n の文字が含まれるために似た綴りとなってしまったもの。
melanotus も使われ (ナンヨウセイケイなど)、これはラテン語化される際にラテン語形容詞の語尾に変換されたもの。意味は melanotos と同じ。これらよく似た (亜)種小名 (一部属名) を混同すると意味が通じなくて悩む原因となり得る。
[Milvus korschun は何だったのか?]
トビに Accipiter korschun Gmelin, 1771 の学名が使われたこともあり、Dement'ev and Gladkov (1951) など古い書籍ではこの種小名が使われているものもある (Milvus korschun)。korschun はロシア語のトビの意味で古インド語の karsati に由来すると考えられる (Kolyada et al. 2016)。
この当時はロシア語現地名を学名種小名に用いることがしばしば行われていたようで、カタシロワシでも用例 (Aquila mogilnik) があったがソウゲンワシとの区別が曖昧だったようで現在は残っていない。
cf. Spotted eagles; #ソウゲンワシの備考。
#メジロガモ、#セグロサバクヒタキなどロシア語由来の学名はその時代の名残りだろう。まだ早い時期なので過去の種小名との重複を避ける目的があったかどうかは不明だが理由の一つにはなり得ただろう。
Falco migrans Boddaert, 1783 の方が新しいので、korschun の方は無効な種小名だったのだろうかと考えて調べてみた。
The Nesting of the Black Kite (Milvus migrans) in the Territory of Verona, Arrigoni Degli Oddi
に多少の情報が見られ、Milvus korschun を用いたのは Sharpe であったとのこと。
Milvus milano Gerini, 1767 のさらに古い学名の可能性も指摘されたが、これはトビではなく Buteo vulgaris (ヨーロッパノスリのシノニム) であると大方が認めているとのこと。
資料ではおそらく何らか理由があって Hartert (1914) が Milvus migrans を用いる判断を行ったように見える。この時期までは多くの亜種が Milvus korschun の種学名で記載されておりこの時代が判断の分かれ目だった模様。
Mlikovsky (2011)
Nomenclatural and taxonomic status of birds (Aves) collected during the Gmelin Expedition to the Caspian Sea in 1768-1774 (p. 87)
の記述で判明。Gmelin (1771) は学名から明らかにトビを念頭に置いていたが、記載されている図版は分離される前のチュウヒ (基産地 Tanain = Azov アゾフ海沿岸) 現在ヨーロッパチュウヒ のもので、Nilsson (1817), Blanford (1876), Hartert (1914) が正しく指摘していたが Dement'ev や Portenko はこの学名を使い続けていたとのこと。
Nilsson (1817) や Blanford (1876) の方はあまり完全に浸透していなかった可能性があるが、大きな図鑑であった Hartert (1914) の指摘で正しい学名がロシア語圏を除いて浸透したらしい。その後亜種命名に使われなくなった経緯がわかる。
ということで Accipiter korschun Gmelin, 1771 は種小名は "トビ" の意味だがヨーロッパチュウヒのシノニムと判断された。
おそらく Gmelin の単なる勘違いで、種小名がロシア名と一致するため Dement'ev も疑念を持たずに使っていたのだろう。現地名を使って間違えて学名を付けた点ではコマドリにアカヒゲの名前を付けたのとほぼ同等。我々もコマドリとアカヒゲの学名を見ているとしばしば混乱してくる。
なおこの学名を有効として、Falco 属 (わざわざ Falco!) に改名の際に新名を付けた例もある (#ノスリの備考参照): Falco russicus Daudin, 1800 (参考)。korschun がロシア名だったので russicus としたらしい。
この用例が早いため、ロシアのタカ・ハヤブサ類の種小名や亜種小名に "ロシアの" を付けることが事実上できなくなった。
現在ではトビの学名は安定しているが過去は必ずしもそうではなかった。英名も見て歴史を振り返ってみて欲しい。
[ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類]
日本産のタカ類ではノスリ亜科の最初がトビになるのでここに記述する。
別所でも述べたようにトビは海ワシ類に近いグループで、現代の分子系統樹順ではイヌワシ、クマタカよりも後になる。ハイタカグループとノスリ亜科のどちらが先になるかの違いは微妙であるが、これまでのようにトビが日本産のタカ類の前の方 (例えばタカ類としては原始的のようにも読める) に位置するわけではない。
これまでと同様 Catanach et al. (2024) の順序による。日本産種のない属は全種掲載。
(ヒメハイタカ属 Microspizias
ヒメハイタカ Microspizias superciliosus Tiny Hawk
ナンベイアカエリツミ* Microspizias collaris Semicollared Hawk
ハバシトビ属 Harpagus
ハバシトビ [高野 (1973) ではアカハラトビ] Harpagus bidentatus Double-toothed Kite
モモアカトビ* Harpagus diodon Rufous-thighed Kite)
この2属はオウギワシ亜科 Harpiinae (#カンムリワシの備考参照) で述べているように、Catanach et al. (2024) の本文解説ではオウギワシ亜科に入るように思える。しかし系統樹はやや遠いもののノスリ亜科と単系統をなす形になっているので、こちらにも括弧を付けて含めておく (系統樹的には独立亜科としても構わない)。
後述のようにハバシトビ属をノスリ亜科に含めている分類も存在する。
ノスリ亜科 Buteoninae
(ノスリ亜科 トビ族 Milvini)
トビ属 Milvus
アカトビ Milvus milvus Red Kite
トビ* Milvus migrans Black Kite
キバシトビ** Milvus aegyptius Yellow-billed Kite
シロガシラトビ属 Haliastur
シロガシラトビ Haliastur indus Brahminy Kite
フエフキトビ [高野 (1973) ではフエナキトビ] Haliastur sphenurus Whistling Kite
オジロワシ属 Haliaeetus (4種 + ウオクイワシ属6種に分離。#オジロワシの備考参照)
(ノスリ亜科 ノスリ族 Buteonini)
サシバ属 Butastur (4種。#サシバの備考参照)
(かつては トカゲノスリ属 Kaupifalco がこの位置にあったがハイタカグループの先頭に移動された。和名・英名ともに過去の系統概念を引き継いでいるので注意)
ムシクイトビ属 Ictinia (和名はタイプ種を優先した)
ムシクイトビ [高野 (1973) ではナマリイロトビ] Ictinia plumbea Plumbeous Kite
ミシシッピートビ* Ictinia mississippiensis Mississippi Kite
セイタカノスリ属 Geranospiza
セイタカノスリ [高野 (1973) ではセイタカチュウヒ] Geranospiza caerulescens Crane Hawk
ミサゴノスリ属 Busarellus
ミサゴノスリ [高野 (1973) ではミサゴワシ] Busarellus nigricollis Black-collared Hawk
ハシボソトビ属 Helicolestes
ハシボソトビ Helicolestes hamatus Slender-billed Kite
タニシトビ属 Rostrhamus
タニシトビ [高野 (1973) ではカタツムリトビ] Rostrhamus sociabilis Snail Kite
ヨコジマノスリ属 Morphnarchus
ヨコジマノスリ Morphnarchus princeps Barred Hawk
ヒメアオノスリ属 Cryptoleucopteryx
ヒメアオノスリ [高野 (1973) ではクロアオノスリ] Cryptoleucopteryx plumbea Plumbeous Hawk
カニクイノスリ属 Buteogallus (和名はタイプ種を優先した)
アオノスリ* Buteogallus schistaceus Slate-colored Hawk
クロノスリ* [高野 (1973) ではクロヌマワシ] Buteogallus anthracinus Common Black Hawk
キューバノスリ Buteogallus gundlachii Cuban Black Hawk
カニクイノスリ [高野 (1973) ではヌマワシ] Buteogallus aequinoctialis Rufous Crab Hawk
サバンナノスリ Buteogallus meridionalis Savanna Hawk
シロエリノスリ Buteogallus lacernulatus White-necked Hawk
オオクロノスリ* [高野 (1973) ではオオクロヌマワシ] Buteogallus urubitinga Great Black Hawk
カンムリノスリ [高野 (1973) ではハイイロカンムリワシ] Buteogallus coronatus Chaco Eagle
オグロカンムリノスリ [高野 (1973) ではオグロカンムリワシ] Buteogallus solitarius Solitary Eagle
オオハシノスリ属* Rupornis
オオハシノスリ Rupornis magnirostris Roadside Hawk
モモアカノスリ属 Parabuteo (和名はタイプ種を優先した)
モモアカノスリ Parabuteo unicinctus Harris's Hawk
コシジロノスリ Parabuteo leucorrhous White-rumped Hawk
シロノスリ属 Pseudastur (和名はタイプ種を優先した)
ハイセノスリ* [高野 (1973) ではシロハラノスリ] Pseudastur occidentalis Grey-backed Hawk
セグロノスリ* Pseudastur polionotus Mantled Hawk
シロノスリ Pseudastur albicollis White Hawk
ワシノスリ属 Geranoaetus (和名はタイプ種を優先した)
オジロノスリ Geranoaetus albicaudatus White-tailed Hawk
ワシノスリ* [高野 (1973) ではハイイロオオノスリ] Geranoaetus melanoleucus Black-chested Buzzard-Eagle
セアカノスリ Geranoaetus polyosoma Variable Hawk
カオグロノスリ属 Leucopternis (和名はタイプ種を優先した)
セアオノスリ* [高野 (1973) ではウスアオノスリ] Leucopternis semiplumbeus Semiplumbeous Hawk
シロマユノスリ* Leucopternis kuhli White-browed Hawk
カオグロノスリ [高野 (1973) ではクロガオノスリ] Leucopternis melanops Black-faced Hawk
ノスリ属 Buteo (29 種。#ノスリの備考参照)
例によって系統が離れるところに空白行を入れてある。
ノスリ亜科 ノスリ族 では日本産種を含むサシバ属、ノスリ属を除いて圧倒的に南米のグループである。少数が北米にも分布する。これらは基本的に留鳥であまり移動する必要もなく、少数が北米にも分布した程度なのだろう。つまりノスリ族は南米で放散を遂げたグループと言ってよいだろう。
南米には広義ハイタカ属も少なく、イヌワシ類や海ワシ類もいないためノスリ族が適応放散するのに十分なニッチが存在したのだろう。なお代わってハヤブサ系統は南米が進化の中心と考えられている。
南米のタカの写真を見ると全体的にぼてっとした印象を受けるが、これは主な系統を反映しているのだろう。
ヒメハイタカとナンベイアカエリツミは和名が示すように広義ハイタカ属と考えられていたが、ノスリ亜科の系統となった。ハバシトビとモモアカトビも同様である。これら2属はトビ族 Milvini には含まれない系統をなすが系統間の距離は遠い。この2属内の2種の順序には意味はない。
ヒメハイタカ属の名称はハイタカ属と関係があるような誤解を受けそうだが、属名や英名も近い意味なのでやむを得ないところだろう。外見がハイタカ属に近くても必ずしも系統的関係がない事例となる。
ハバシトビの名称は嘴縁突起を表すもの。高野 (1973) はこのことを解説には書きながらもこの形態的特徴はあまり気にしなかったか、あるいは以前に存在したアカハラトビの名前を使ったのだろうか。モモアカトビとともにタカ類中で嘴縁突起を持つグループ (#ハチクマの備考 [ハチクマ亜科の他種] 参照) をなす。
少し気になって調べてみるとコンサイス鳥名事典の見出しはアカハラトビになっていた。ハバシトビはおそらく英名か学名から新しく訳し直した名称のよう。現在の英名では対応するものがないが、アカハラトビに対応する他言語名があってドイツ語では Rostbrust-Zahnhabicht (胸の赤い歯のあるオオタカ)。ロシア語名はこれをそのまま訳したものか "胸の赤い" 部分を省略したものになっている。
ヒメハイタカ属やナンベイアカエリツミの同様に広義ハイタカ属に近いと考えられていた形跡がドイツ語名から読み取れる。翼が短めで丸く尾が長くて全体的にはオオタカやハイタカに似て見えるとのこと (wikipedia ドイツ語版から)。
wikipedia 英語版でも accipiter-like kites (ハイタカ類に似たトビ) と何ともわからない表現になっている。これは英語の一般用語の kite が非常に広義のものを指すためだろう (前述のように英語特有に近く、例えばドイツ語ではこのような表現にはならない)。
トビ類には近くなく "true" hawks ("真正" タカ類。英語の呼び方でも何が真正なのか悩ましい) に近縁であると紹介されている。
南米には Tachyspiza 属が分布しないのでその位置を占めている部分もあるのだろうか。
原記載にも胸と腹は赤っぽいと記されているので、原記載をもとに付けられたドイツ語名かも知れない。アカハラトビもドイツ語や原記載をもとに命名された和名のように思えてきた。
wikipedia 英語版によれば胸の赤っぽいのは基亜種の方で、そのため種全体の和名にアカハラトビ、ドイツ語で Rostbrust- を付けるのはふさわしくないと考えられ名称から色彩が外される傾向があるのかもしれない。
気になっている理由はアカハラダカの和名由来で、もしかするとアカハラトビと対比する形で命名された可能性もあるかも知れない。
嘴縁突起を持つハチクマ亜科カッコウハヤブサ類 Aviceda 属とは類縁がない。
ハバシトビ属に使われる Harpagus はオウギワシの Harpia (harpy) と同様の意味。Vigors (1824) による命名で嘴縁突起を持つこれらタカ類2種に対して命名したもの。嘴縁突起は種小名にすでに現れるので別の意味の属名を挙げた模様 (タカ類に多数の属名があって新しいものがあまり思い浮かばなかった印象を受ける)。
このころは共通特性を持つ種類もあることからタカ類とハヤブサ類はそれほど区別されず、Swainson (1837) はモモアカヒメハヤブサ Microhierax caerulescens Collared Falconet のハヤブサ類を含めて Vigors の提唱した属を (たぶん) 再定義した。含まれている H. rufipes が何を指しているかちょっとわからないがハバシトビは含まないように見えるので不思議。
Swainson の定義した属のタイプ種はモモアカヒメハヤブサと Gray (1840) が定めた (The Key to Scientific Names の情報よりまとめ)。
Boyd はハバシトビ属のみを含む Harpagini 族を用いているが、ヒメハイタカ属 Microspizias の位置が Catanach et al. (2024) 以前のものなのでここでは検討しないでおく。
ご存じの通り、現在のトビ族 Milvini に相当する分類は過去はハチクマ類の後あたりに置かれていた。
ハチクマ類にもトビに似た種類が存在する (ハチクマ類も英名ではノスリの名が付いているが、分類される時は kites に入れられることもある。ただしこれもわかりにくいため kites and honey-buzzards のような英語分類も使われる) ため一緒にまとめられていて、類縁の海ワシ類がその後に置かれていた。現在のトビ族 Milvini のトビ類が「真性トビ類」とも呼ばれるもの。
トビ属ではキバシトビは従来トビのアフリカ亜種とされていたものが分離されたもの。体重はトビの半分程度とのこと。この解析でのトビ属の3種の位置関係には意味がないが、キバシトビの遺伝情報も含めればトビとキバシトビが並ぶはずである。
シロガシラトビ属に使われる Haliastur は hali- 海の (Gk) astur タカ、オオタカ。
高野 (1973) = Grenys and Llyod (1969) で用いられていた伝統的分類は Brown and Amadon (1968-1969) に基づくもので、Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" でも小さな修正のみを加えたものが紹介されている。
この分類は分子系統研究がなされるようになるまで事実上の標準とされており、一世代前の図鑑 (日本鳥類目録 改訂第7版でもハヤブサ目を分けたもののタカ類の分類の基本は同様だった。本稿も改訂第7版に基づく順序のため、属の順序などは現代では相当入れ替わっている。ノスリ亜科の分類がこの位置に出てくるのは本来不自然なのだがやむを得ない) などはこれに基づいているはずである。
40 年以上使われていたのはさすがに長過ぎる気がするが、多くの人がその順序に慣れきっておられるだろうので改訂第8版の順序、そしてこの記事で改めて知識をリフレッシュしていただければと思う。
現在のノスリ亜科で使われる属名も大部分は当時存在していたもので、属内の種の位置づけや属の間の関係が従来と違っている。別属とされて過去に使われていた属名が再登場したものが少数ある。
ここでは理解を助けるために Brown and Amadon (1968-1969) 時代の分類順序を示しておく。属に含まれる種は現在と異なるものもあるので属名の和名は省いておく:
Butastur
Kaupifalco (ハイタカグループに移動)
Leucopternis
Buteogallus
Harpyhaliaetus (現在は統合され消滅)
Heterospizias (現在は統合され消滅)
Busarellus
Geranoaetus
Parabuteo
Buteo
Morphnus (オウギワシ亜科に)
Harpia (オウギワシ亜科に)
Harpyopsis (オウギワシ亜科に)
Pithecophaga (チュウヒワシ亜科に)
これを見ながら読んでいただければ高野 (1973) 時代の和名の由来などや分類変更の解説がわかりやすくなるだろう。
Butastur がノスリ類の冒頭に来るのは現在と同じで、属名もノスリとオオタカの中間的な特徴を表している。昔から "buzzard-eagles" と呼ばれていたよう。Brown (1976) もあまり適切な名称とは考えていなかったようで "so-called" (いわゆる) を付けていた。#サシバの備考参照。
Morphnus (ヒメオウギワシ)、Harpia (オウギワシ)、Harpyopsis (パプアオウギワシ)、Pithecophaga (フィリピンワシ) は大型種でかつてはノスリの遠い仲間に (便宜上?) 含められていたわけだが、後にこの4属4種でオウギワシ類として独立させてまとめて移動となった。
当時の分類では "sub-buteos" (ノスリ類の前段階のグループと考えられたもの) → ノスリ類 → booted eagles (イヌワシ・クマタカ類) の進化系列が想定されていたため次にイヌワシ類が続いていた。ノスリ類とイヌワシ類を結ぶ中間グループの位置づけだったものと思われる。
そのうちフィリピンワシのみが別系統とわかって分離された次第である。
オウギワシの和名はおそらく古くからあって、それぞれ近縁を意味する名前が付けられたものだろう。
位置づけが従来あまりよくわからなかったが分子系統解析でハイタカグループに移動された Kaupifalco (トカゲノスリ、分布もアフリカでノスリ類と違っていた) を除く残りの属の種は現在もノスリ類の主要なグループになっている。
Buteo がノスリ類中で最も進化の進んだグループとの概念は現在と同じで、その前段階に相当するグループ ("sub-buteos") を配置する形になっている。
これは現在のイヌワシ・クマタカ系統で Aquila の前段階の位置に Spizaetus が大所帯で存在していたものとほぼ同等の位置づけになる。
ノスリ類でも Leucopternis、Buteogallus が大所帯であった。Spizaetus が大きく分割・再編されたのと同じように、分子系統解析の結果これらが前段階とされた属が単系統でないことがわかって相互で種の移動が行われて現在の形となっている。
do Amaral et al. (2009) Patterns and processes of diversification in a widespread and ecologically diverse avian group, the buteonine hawks (Aves, Accipitridae) を参照。
この研究の後にさらに再編されているが生物地理学、渡りの進化などへの示唆もある。
過去の Leucopternis 属はほぼ森林性のグループで、南米の森林性猛禽類とあってほとんど研究がなされていなかった。おそらく爬虫類食との記載があった程度。
分割・再編後に Buteogallus は大きな属になったが Leucopternis は小さな属となった。
ムシクイトビ、ミシシッピートビ、ハシボソトビ、タニシトビはもともと (旧) トビのグループに入っていたものがこちらに移動されたもの。
セイタカノスリはチュウヒ類からこちらに移動。少しややこしく後の解説参照。
Harpyhaliaetus と Heterospizias は Buteogallus に統合。
ヨコジマノスリ、ヒメアオノスリ は Leucopternis からの分離。
オオハシノスリは Buteo からの分離。
シロノスリなどの3種も Leucopternis から分離。
ムシクイトビの和名がなぜ付いたか (なぜ改名されたか) の由来はわからなかった。多くの言語では灰色などの色を意味する名称が付いている。中国語でも鉛灰鳶などが使われ、多くが学名や英名の plumbeous
を利用しているように見える。属名に使われる Ictinia は iktin, iktinos トビ (Gk)。
食性は飛びながらあるいは止まり場から昆虫を捉えるとあるので、改名された和名はあるいはそれに由来するのか。しかし小動物も食べる。この種にも嘴縁突起があると Vieillot (1816) の記載にあるがそれほどはっきりしたものではない感じである。
近縁のミシシッピートビの写真 Mississippi Kites (BirdNote) も同様の形態が見える。この2種の順序には意味はない。タイプ種に従った属名和名を採用しているが、ミシシッピートビの方が知名度が高そうなのでこちらでもよいかも知れない。
ミシシッピートビは若鳥は前面が縦縞、尾は広義ハイタカ属のような縞模様、かつ翼先の風切羽の分離があまりなく何の仲間か判断に悩むぐらい。写真を探して見ていただきたい。このような模様を比較的簡単に作るメカニズムがあるのだろう。かなり小型の種類。
ムシクイトビは南米の種。両種とも顔つきがカタグロトビに多少似た印象を受ける。収斂進化があるかも知れない。南米で数少ない (部分的な) 渡りをするタカ類。
系統的にはノスリ族 Buteonini の中で最初の分枝で系統がやや離れたサシバ属とノスリ類の間に位置するが、やはりやや独立した系統をなす。
ノスリ類は南米で種分化を遂げたが、系統の発祥の地はアフリカやユーラシアであったはずで、南米に至るまでの途中の種類があるべきだが、ムシクイトビ [高野 (1973) ではナマリイロトビ] や ミシシッピートビ がそれに対応することになる。これらは開放環境に適応したものと考えらえる。
中米や北米の一部に クロノスリ [高野 (1973) ではクロヌマワシ] などが生息するが、これらが南米の同属の祖先系統ではないので、南米で種分化を行って中米や北米に分布を広げたものと考えらえる。ユーラシアから南米に到着する途中の系統には該当しない。
ミシシッピートビは小型の種で、先行したカタグロトビ亜科やハチクマ亜科由来の "トビ" 類似種と似た生態的位置を占めると考えらえるが、少なくとも初期系統のノスリ類はあまり強力でなかったようでほとんど現存していない。
セイタカノスリ [高野 (1973) ではセイタカチュウヒ] は脚を反対にも曲げることができる (#クロハゲワシの備考 [変わった餌の捕り方をする猛禽類] を参照)。
チュウヒダカ類とともにかつてはチュウヒ類として扱われていた。
属名に使われる Geranospiza は geranos ツル spizias タカ (Gk) で英名と同じ。脚の長さを表している。
この属 (種) は別所から移動されたもので、結果的にほとんど同じような意味の Geranoaetus (ワシノスリなど) がノスリ類のグループに共存することとなって学名的には大変紛らわしい。
-spiza の語尾は Kaup がタカ類の属名に -spizias の代わりにしばしば用いたもので (The Key to Scientific Names)、現代の学名として他所にも現れる。spiza (Gk) は本来フィンチまたは小鳥の意味なのでスズメ目の属名にも -spiza がよく現れ紛らわしい (Spiza 属もある)。同じ -spiza でもタカ類についてはタカ、スズメ目ではフィンチまたは小鳥と訳し分ける必要がある。
本稿では#アカハラダカ備考に示すように意味を発音で区別する試みを導入している。
以降で取り上げる種もほぼ南米から中米の種である。高野氏にとってもまったく馴染みのない地域の多数の種に和名を与える作業は大変だったと想像できる。
ミサゴノスリ [高野 (1973) ではミサゴワシ] はほぼ完全に魚食の珍しいタカ (#ミサゴの備考参照)。ただしミサゴよりは他のものも食べるらしい。
属名に使われる Busarellus は buse ノスリ rayee 縞のある (仏)。かつての英名は Fishing Buzzard だった。南米には海ワシがおらず、ミサゴ類もなぜかあまり分布せず北米から越冬に来る程度である (同じことはアフリカのミサゴにも言える)。ミサゴノスリはそれに代わる位置を占めたノスリ類。
英名の Black-collared Hawk は種小名の nigricollis 由来だが、これは首に黒い部分がある意味で使われているもので、"首輪のある" の英名はいかにも誤解を招きそう。フランス語の Buse a tete blanche (頭の白いノスリ) の方が色彩をよく表している。ドイツ語では Fischbussard で魚のノスリ。過去の英名由来かも知れない。和名はなかなかよいところを捉えていると思う。
セイタカノスリ、ミサゴノスリ、ハシボソトビ、タニシトビ [高野 (1973) ではカタツムリトビ] はいずれも単形属で、この4属は単系統をなすが特徴の違いが大きく、遺伝的距離も離れているのでそれぞれ単形属が妥当な扱いだろう。Buteogallus 属などジェネラリスト的なグループが適応放散する前に分岐した独特の種類と言える。
#ハチクマ備考の [ハチクマ類の系統分類] の現象と似ている。とはいえノスリ類の方が系統的にはずっと新しい。
これら4種は形態など特殊な点が多いので Catanach et al. (2024) も全ゲノム解析を行っている。系統樹の信頼性も高い。
嘴の形と食性に特徴が特異なハシボソトビとタニシトビが並列に並ぶのは興味深い。
ハシボソトビの属名に使われる Helicolestes は helix, helikos らせん、巻き貝 leistes 盗むもの (Gk)。
タニシトビの属名に使われる Rostrhamus は rostrum 嘴 hamus 鈎 (Gk)。
これらの "トビ" の付く種類はかつては現在ハチクマ亜科のものを含むトビの系統とされ、分子系統解析によってノスリ類に近いことがわかった。他所でも述べておりが、"トビ" 類はいろいろな分類群に散在する多系統の名前である。
タニシトビでは在来のカタツムリに代わってより大型の外来のカタツムリが増加すると 10 年も経過せずに嘴の形が変化したとのこと。Cattau et al. (2018) Rapid morphological change of a top predator with the invasion of a novel prey
大型で寿命の長い捕食者でも獲物に応じた形態変化を短期間で起こせることを示した。
急速な小進化が起きているというよりは表現型の可塑性を示しているのではとのこと。
この事例も含め、表現型をもとに亜種などを決める限界も指摘されている: Cadena and Zapata (2021) The genomic revolution and species delimitation in birds (and other organisms): Why phenotypes should not be overlooked。
論文そのものは遺伝情報だけで分類を決める危険性を主張したもので、選択圧など別の効果もある、しかし表現型の可塑性などもあるので表現型で二峰性を示すことが必ずしも適切な種や亜種の判別基準にならない文脈に登場する。
このリストで残りの種類の多くは過去の分類では大枠ではノスリ類とはされていたものの、いろいろな場所に混ざっていた。高野 (1973) で "ヌマワシ"、"カンムリワシ" と付くものは系統的位置づけがはっきりせずこのような名前になっていたものと思われる。ノスリ類であることがはっきりするように改名されたと思われる。
以下高野 (1973) = Lloyd and Llyod (1969) で用いられていた伝統的分類との比較を主に行う。現代の IOC 分類などはこれまでの研究も取り入れられていて、新しい分子系統解析の結果と順序まで含めてほとんど違いがない。ノスリ類は外見などでの伝統的分類は難しかったが、分子系統解析で比較的安定した結果の得られるグループだったのだろう。
高野 (1973) で "カンムリワシ" と付くものは Harpyhaliaetus 属とされていて、Harpia オウギワシ属の名称と Haliaeetus オジロワシ属の名称からの合成で、何物かわからないことを告白しているような学名であった。
高野 (1973) = Lloyd and Llyod (1969) の時代には Buteogallus 属 [これもノスリ 属と Gallus 属 (ヤケイ) の合成] はこれら "ヌマワシ" 3種のみを指していた。
高野 (1973) = Lloyd and Llyod (1969) の時代には南米の熱帯性ノスリ類9種を Leucopternis 属 [leukos 白い pternis タカの一種 = ハチクマの Pernis と同じものを指す別の綴り Gk (#ハチクマの備考 [属名の考証] を参照] とまとめていたが3種のみを残して他の系統に分類された形になっている。
Leucopternis 属から Buteogallus 属にも複数の種の移動があった。元来の属名の由来の白いタカだったシロノスリなどは Pseudastur 属 (pseudos 偽の Astur オオタカ Gk) に移動となった。
これらの地理的関係は Lerner et al. (2008) Molecular Phylogenetics of the Buteonine Birds of Prey (Accipitridae) にある。
シロエリノスリも典型的な "白いノスリ" で Leucopternis 属に含まれていた。当時知られていたはずだが高野 (1973) には載っていない。
これは Buteogallus 属に移動されて色と系統にはそれほど関係が深くなかったようである。名前から想像する以上に前面はほとんど白い。
ブラジルに局地的に生息し、個体数も少なく絶滅のおそれがある。生態もほとんど知られていない。
音声の文字による記述すらもなされていないとのことであるが xeno-canto で音声を聞くことはできる (wikipedia 英語版より)。
保全上重要な種類であることもおそらく意識して Catanach et al. (2024) も全ゲノム解析を行っている。
ヨコジマノスリも Leucopternis 属からかなり離れて独立した系統になった。現在の属名に使われる Morphnarchus は morphnos 黒い arkhos 支配者 (Gk)。
かなり大型のノスリ類であるにも関わらず翼は短く、森林環境に適応したものと考えらえるとのこと (wikipedia 英語版より)。ノスリの仲間でも Buteo 属から想像する以上に熱帯森林適応種があった。次のヒメアオノスリ [高野 (1973) ではクロアオノスリ] も同様。
ノスリ類が到達する以前はタカ類発祥のアフリカから遠く、あまり多くの系統が南米に到達していなかったためまだいろいろなニッチが残っていたのだろう。
Spizaetus 属も似た時期に中・南米で種分化を遂げているが、森林では Spizaetus 属の方が優勢だったようで熱帯森林に適応したノスリ類は少数に限られたものと想像できる。
ヒメアオノスリ [高野 (1973) ではクロアオノスリ] も同様。現在の属名に使われる Cryptoleucopteryx は kruptos 隠れた leukos 白い pterux, pterugos 翼 (Gk)。この2種は系統上は Buteogallus 属に含めても単系統となるが、少し遺伝的距離があってこれまでも別属で扱われていたためそれぞれ単形属が妥当とされるのだろう。
ヒメアオノスリの種小名はやはり鉛色のことで、英名もそれに由来する。「隠れた白さ」というのは雨覆の下面にあって、飛んでいる時などしか見えないようである。
サバンナノスリは Heterospizias 属 (異なったタカ) の単形属から Buteogallus 属に移動されたなどかなり大きく変わっている。
Buteogallus 属は現在では比較的大きく、系統的にもまとまりのよいグループをなしている。
Buteogallus 属の中ではサバンナノスリ以降の5種がその前の4種と系統が少し分かれるがそれほど深い分岐ではない。"ヌマワシ" は両者に現れるが。"カンムリワシ" と付いていた最後の2種は近い関係にあり、外見は他のものとかなり異なって見える。
オオハシノスリに使われる Rupornis は rhupos 汚物 ornis 鳥 (Gk) と語感的にはよい意味でない。
南米で普通種で Roadside Hawk と呼ばれるように道端によくいるようで、属名の意味は日本語の "馬糞鷹" (ノスリ、チョウゲンボウの異名) に近いかも知れない。もとは Buteo 属だった。
Rupornis 以降は Buteo と単系統を作ることもできるが多少系統が離れていることや、これまで別属扱いの Parabuteo があって、Parabuteo を残しつつ Rupornis を Buteo に含むと Buteo が単系統にならないためそれぞれ別属とされているのだろう。
モモアカノスリなどに使われる Parabuteo は para 近い (Gk) Buteo 属に (ノスリに近い) の意味。
モモアカノスリの種小名 unicinctus は uni- 一つの cinctus 縞 (Gk)。
モモアカノスリの和名で基本的に通っているが、英名由来のハリスホークもよく使われる。
和名の由来は何だろうかと調べるとこの種も Temminck が記載したものだった: Falco unicinctus Temminck, 1824 (原記載)。
ラテン語属名は Falco を用いているがノスリ類 (Buse) とは別グループである認識を持っていてフランス語名では Autour a queue cerclee (円形の尾のオオタカ)。
記述は Autour a queue cerclee にある。ヨーロッパの種で比較すると細かな点ではノスリ類よりオオタカの方に似ているためこの名称となったよう。
les cuisses sont d'un roux de rouille tres-vif と腿の赤さが鮮明とのことで、この部分はモモアカノスリに対応する。
和名はモモアカトビ (こちらは英名そのまま) とセットで付けられたものかも知れない。腿部 (解剖学的には脛) の赤っぽいノスリ類は他にもあるのであまり限定的な記述となる和名ではなかったかも。
"モモアカ" の付く種は他にもいくつもあり、モモアカヒメハヤブサ (旧英名 Red-legged Falconet。red-thighed となっていない分解剖学的にはより正確?)、モモアカアシボソハイタカ (これは学名、英名の通り)。英語でも日本語でも当時の命名者の好みだったのかも知れない。
種小名は une tres-large bande blanche, disposse vers l'origine de la queue, traverse toutes les pennes 尾の基部の太い1本の白い縞に対応。かつて英名に Bay-winged Hawk (bay 鹿毛色の) が使われていた。学名に対応した One-banded Buzzard の英名もあった。
大変紛らわしいことに同じ Temminck (1824) に 参考 に Falco uncinatus フランス語名 Cymindis bec on croc (嘴の先端が曲がっている Cymindis) があり、こちらはカギハシトビ Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite を指している (#ハチクマ備考の [ハチクマ亜科の他種] 参照)。
モモアカノスリの unicinctus は uni- (一つの) cinctus (帯) で尾のバンドを指す。
カギハシトビの uncinatus は uncus, unci (鈎) -atus (持つ) で非常に似ているが語源は異なる。正しくアクセントを置いて読めばまったく違う発音になる。
解剖学をご存じの方ならば肋骨の鉤状突起 uncinate process (ちなみにこの構造はヒトにはないため人体解剖学では出てこないが同じ名称の解剖学用語は膵臓など他にもある) で目にかかられているだろう単語。フランス語名、英名ともに対応している。
Harris's Hawk の方の英名は Buteo harrisi Audubon, 1837 に対応学名があり、これは現在は亜種扱いとなっている。Audubon の "The Birds of America" の図版に現れる学名。図版の英名は Louisiana Hawk となっていた (図版)。
北米でも南部開拓が進んで新種が記述されていった時代を反映したものだろう。
Falco harrisii Audubon, 1839 の名称もあったらしい (参考 1, 2)。
図版の方が出版が早かったためその学名が優先されたよう。
Edward Harris は米国の農家で博物学者、Audubon と一緒に探検をした (The Key to Scientific Names)。
"Birds of America" (1840) 本文では Harris's Buzzard の名称で登場。こちらの図版は Harris's Buzzard となっていて Audubon が考えを変えたらしい。
p. 29 に経緯が記されていて、標本はルイジアナの紳士が撃ったもので、ラベル以外に何の情報もなかったため採集者人名もわからず英名は最初 Louisiana Hawk としていた模様。一緒に仕事をした Edward Harris の方への献名となって標本採集者そのものではなかった。1837 年の図版にすでに学名が付いているので事後説明のようなものだろうか。
過去はそれほど注目されていた猛禽ではなかったが、集団で共同狩猟を行うことが発見されて大変話題となった (#ハヤブサの備考 [オナガハヤブサの共同狩猟] も参照)。
Bednarz (1988) Cooperative Hunting in Harris' Hawks (Parabuteo unicinctus)
から読める。同一だがオリジナルの Science 論文のサイト。
1980 年代らしい手描きイラストでどのように共同狩猟を行ったかを図示している。
モモアカノスリがなぜ共同狩猟を行うようになったかを議論した論文: Coulson et al. (2013) Reexamining Cooperative Hunting in Harris's Hawk (Parabuteo unicinctus): Large Prey or Challenging Habitats?
獲物が大きいためか、生息環境が厳しいためか?
「アニマ」1989年1月号のニュース欄 (p. 9) に「モモアカノスリの共同ハンティング」の記事があり、自分はこれを読んで知った。
なお同じ号の特集は「日本の鷲鷹」で海野氏による北海道のハチクマの子育て報告があり、兄弟の2羽が淡色型、暗色型とそれぞれ違っていた。この報告はその後もよく引用されている (この号については #ハチクマの備考 [ハチクマの繁殖行動] にも関連情報を紹介)。
当時は鳥の社会性が脚光を浴び始めたころで、「アニマ」1986年10月号のニュース欄 (p. 10) では 「鳥を見てサルを知る」が話題になっていた。ヤブカケスの社会 (ヘルパー制) がタマリンと類似しているなど、国際霊長類学会でサルの社会性の理解には鳥に学ぶのが有益であるとの発表がなされたことが話題になっていた。
なお同じ号の特集は「渡り鳥」「道具を使う動物たち」(鳥では「道具を使う鳥カタログ」の記事もあり、ササゴイも含めて現在知られている種類も多数取り上げられている。ハクトウワシも飼育下でコオロギやカメに石を投げつける行動が記録されたとのこと。
オオツチスドリ Corcorax melanorhamphos White-winged Chough は貝で貝を割るとのこと。
道具を使って羽繕いする鳥も紹介されていて、ミミヒメウ Nannopterum auritum Double-crested Cormorant は尾脂腺をぬぐうのに抜けた風切羽を使うそうである。同様の目的に他のものを使う種類もある)。
鳥の能力が科学会でも次第に認知され、その後神経科学や心理学でも裏付けられるようになってきたさきがけぐらいの時期だろうか。
モモアカノスリはこのような特性もあって鷹狩りでよく用いられている種類であることはご存じの通り。「ハリスは賢い」と動物園の飼育員の方などがよく言われるが、おそらくオオタカなどが慣れにくいことと比べた話で確かに人によく慣れるらしい。
行動を見ているとどの人にも同じように反応しているように見えて、あまり人を見分けている感じはしなかった。そのためかよく慣れた鳥ならば知らない人でも相応の相手をしてくれた。
飼育オウム類では自傷行為が知られていて、猛禽類ではまれだがモモアカノスリの報告例が多いとのこと。
Smith and Forbes (2009)
A Novel Technique for Prevention of Self-mutilation in Three Harris' Hawks (Parabuteo unicinctus)
他の猛禽類に比べて非常に賢く刺激がないと飽きてしまう、オウムのように刺激が必要と書いてあるが、単に飼育数が非常に多いためかも知れない。ここでは嘴の先を歯科用材料で加工することで防ぐことができたとある。
クロコンドルでもあったらしい: Swartout (2021) Self-Injurious Behavior in a Captive, Malimprinted Coragyps atratus。人に性的にインプリントされた個体で起きた性的葛藤、あるいはクロコンドルは家族を守る利他な攻撃行動が知られていて、人を同種個体のように扱って攻撃的になるのではなどの考察が出ている。
こちらでは鳥類一般を指して認知能力が高いので適切な神経活動を保つために適切な刺激が必要であるが、この個体は食物を与える際にパズルなどエンリッチメントは行われていなかったとのこと。クロコンドルのカラスのような行動 (#クロハゲワシの備考参照) を知ると知的刺激不足もうなずける気がする。
ワシノスリ [高野 (1973) ではハイイロオオノスリ] などに使われる Geranoaetus は geranos ツル (灰色を指す) aetos ワシ (Gk)。
Geranoaetus も Geranospiza も Kaup の命名。高野 (1973) 時代の名称は属名の色を活かしたものになっていたが、外見や学名の由来から改名されたのだろう。
属名の確定には紆余曲折があったようで、Buteo とされたこともあったが、分子系統研究で単系統でないことが判明して別属とされた
(Amaral et al. (2010) Priority of Geranoaetus Kaup, 1844 over Tachytriorchis Kaup, 1844 (Aves: Accipitridae) based on the first reviser principle)。
セアカノスリの種小名に使われる polyosoma は polios 灰色 soma, somatos 体 (Gk)。
セアカノスリにはかつて別種とされた、高野 (1973) でガーニイノスリ (種小名 poecilochrous) とされる種類があった。
Brown (1976) によると当時の英名は Red-backed Buzzard と Gurney's Buzzard だったので高野 (1973) ではそのまま訳したものと思われる。
Farquhar (1998) Buteo polyosoma and B. poecilochrous, the "Red-Backed Buzzards" of South America, are Conspecific
によれば、当時の知見では事実上 Stresemann の翼式 (#カタグロトビの備考も参照) しか違いがなく、同種とすべきであるとの提案がなされて現在に至っている (当時はいずれも Buteo 属の扱い)。
しかし博物館標本や限られたデータをもとにした実験室の判断には限界があり、分布の違い [セアカノスリはアンデスに沿って南米南端まで、ガーニイノスリはより北部。Brown (1976) によれば南米南端に生息する猛禽類はごくわずかしかいないらしい] 長年の野外観察で雑種が観察されていないこと、動物園個体の観察の結果、遺伝情報も含めて別種とすべき提案が出ている: Stiles (2009)
Re-split Buteo poecilochrous from B. polyosoma。
南米の検討委員会は別種とする十分な根拠がないと判断を下したが反論も出ている。
HBW、Gaudin など少数のリストはこの提案を受け入れ別種としているが、IOC などは採用していない。
Boyd も採用していないが、おそらく遺伝情報から別種を妥当とする論文が出ていないためであろう。
この Stiles (2009) で述べられている中で albicaudatus は現在別種とされて Catanach et al. (2024) では全ゲノム解析も行われ、大きな違いが見つかっている。
カワリオオタカでもそうであったように、改めて表現型で多型 (polymorphism) を示す種類の扱いの難しさを理解できる。
poecilochrous は別種扱いではないため少なくともこの研究には現れなかったものと想像できるが、亜種か種かの扱いの違いは分類学上の興味以外にも研究が行われるか否かにも影響を与えるのだろう。これだけ大きな違いが見つかるとこのグループを詳しく研究する動機になるだろうが。
[亜種と渡り]
世界で5亜種(IOC)。
・migrans European Black Kite ヨーロッパ中部、南部、東部、アフリカ北部からパキスタン北部まで繁殖分布、サハラ砂漠以南のアフリカに渡る。
・lineatus Black-eared Kite シベリアからヒマラヤ、インド北部、インドシナ北部、中国南部、日本。大陸内陸部の北のものは中東から東南アジアへ渡る。
・govinda Small Indian Kite パキスタン東部から熱帯インド、スリランカ、インドシナからマレー半島までの留鳥。
・affinis Fork-tailed Kite スラウェシ島やパプアニューギニアなどの一部の島、オーストラリアの留鳥。
・formosanus Taiwan Kite 台湾と海南島の留鳥。分布は限られている。
以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種記載もわかる範囲で含めた。
Milvus melanotis は亜種扱いではないが年代関係がわかりやすいように含めておいた。キバシトビに分離される亜種は含んでいない。
・Falco migrans Boddaert, 1783 o (原記載) 基産地 Restricted type locality, France, apud Hartert, ex Daubenton, pi. 472 (Hartert がフランスに限定)
・Haliaetus lineatus Gray, 1831 o (原記載) 基産地 China (中国)
・Milvus Govinda Sykes, 1832 o (原記載) 基産地 Dukhun = Deccan, India (インドのデカン地方)
・Milvus affinis Gould, 1838 o (原記載) 基産地 Australia = New South Wales, fide Mathews, antea, p. 171 (オーストラリア南東部 NSW)
・Milvus melanotis Temminck & Schlegel, 1844? 1847/1848? * 基産地 日本 = lineatus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Milvus ater glaucopus Severtzov, 1875 * (参考) 無効名? 詳細不明
・Milvus korschun reichenowi Erlanger, 1897 * (参考 基産地 Sidi Ali-ben-Aooum, Tunis (チュニジア) = migrans
・Milvus korschun rufiventer Buturlin, 1908 * (参考) 基産地 Murrab, Turkmenii (トルクメニスタン) = migrans (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Milvus korschun napieri Mathews, 1912 * (参考) 基産地 Napier BroomeBay, north-west Australia (オーストラリア北西部) = affinis
・Milvus korschun furghaneneis Buturlin, 1913 * (参考) Gul'chi から南の Lyangar = lineatus [Dement'ev and Gladkov (1951) 記載年は 1908 としている]
・Milvus lineatus formosanus Kuroda, 1920 o (原記載) 基産地 Gyochi, Nanto district, Taiwan (台湾)
・Milvus korschun tianshuieus Buturlin, 1928 * 基産地 Naryn = lineatus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Milvus migrans tenebrosus Grant & Mackworth-Praed 1933 (原記載) 基産地 Beoumi, Ghana (ガーナ) = migrans
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。 * は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。 = 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
大まかにはユーラシアでは西部亜種が migrans、東部亜種が lineatus、インド周辺が govinda の形になっている。
オーストラリアを別亜種として大陸との境界をどこにするか悩ましいこともわかる。Dement'ev and Gladkov (1951) はフィリピンは affinis と考えていたがまれに見られる種類で現在では通常 lineatus とされている。
このように並べると結構多数の記載があるが亜種記載は通常小型種の方が多い。大型種は標本を送るのに費用がかさむためあまり好まれず小型種が優先された経緯があるとのこと。
亜種英名の Fork-tailed Kite はアフリカツバメトビ [高野 (1973) ではアフリカツバメハイイロトビ] Chelictinia riocourii Scissor-tailed Kite (カタグロトビ亜科) の別名にもなっている。
Small Indian Kite は過去 Pariah Kite と呼ばれていたがカースト制度由来の名称で廃止された (wikipedia 英語版より)。govinda はヒンズー神話で牛を見つけるもの。
日本ではトビはあまり渡りをしないが、種小名が示すように世界的には渡りをする地域が多い。ヨーロッパや中東のタカ渡り観察地などでは渡りをする主要なタカの一つでカウントが行われている。日本の亜種は lineatus (「線で縁取られた」の意味。「分類学の父」 Carl Linnaeus と似た綴りだが関係ない) とされる。
lineatus を独立種と提案する考えもあったが (Peters' Check-list of the Birds) 最近はあまり出てこないようである。亜種名 (または別種とした時の種名) として Black-eared Kite も使われる。
独立種とした場合は formosanus が亜種の扱いになる。
lineatus その他の亜種の遠方への迷行例もある。2006 年 lineatus が英国で記録された。太平洋やハワイの記録もあるがおそらく lineatus と考えられる (wikipedia 英語版より)。
オーストラリアからニュージーランドへの迷行例も時々あり、Renwick 近くの個体は 2015 年まで約 23 年同地域にいたとのこと Black kite (New Zealand Birds Online)。
亜種 lineatus は近年北コーカサス地方からロシア南部に大規模に進出中とのこと: Lipkovich (2023)
Siberian subspecies of the black kite Milvus migrans lineatus in the North Caucasus and in the steppes of southern Russia: stages of mass invasion (pp. 1413-1415)。1990 年代からこの地域でシベリア型とヨーロッパ型の2亜種が越冬するようになった。
[ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] にもあるように分類的にはよく一緒にされるハチクマと近縁でなく、オジロワシなどの海ワシ類の系統。アカトビ Milvus milvus の種小名として Falco milvus Linnaeus, 1758 で使われ、後に属名に昇格された。
西シベリアのトビの渡りの研究: Literak et al. (2022) Black Kites on a flyway between Western Siberia and the Indian Subcontinent
ロシアのアルタイ地域からの追跡で、ヒマラヤを超えて最大 6256 m の高度まで記録され、パキスタンからインドで越冬した。若鳥の巣立ち後の移動や越冬地での移動も記録されている。若鳥 19 羽中5羽が複数年追跡された。
翌年には繁殖地に戻るが、生後数年は生まれた場所より北側に戻ったとのこと。
この研究で遺伝子研究も行われ、いずれも lineatus に属することが判明した。東西亜種の中間的な地域が広がっていることが知られているが、ユーラシア東西の遺伝的構造を知るにはさらにデータが必要である (lineatus が独立種であることもこの段階でまだ否定できない)。
逆にインドのデリーからの追跡も行われており、lineatus がやはり高所を通る渡りを行っている: Kumar et al. (2020) GPS-telemetry unveils the regular high-elevation crossing of the Himalayas by a migratory raptor: implications for definition of a "Central Asian Flyway"
インドガンやアネハヅルのような羽ばたき飛行の鳥がヒマラヤを越えることは知られていたが、ソアリングで渡る鳥でもこれまで考えられていた以上にヒマラヤを越えているらしい。
これらの研究を通じて中央アジアルートの猛禽類の渡りがかなり解明されてきた。2年追跡された1羽は渡りルートを大きく変えていた。越冬期のデリー地域は世界一トビの密度の高いところだろうとのこと。
西ルートに進出中のハチクマもこのルートを使っているのだろうか。
主に日本の個体群を中心とした cyt b 遺伝子ハプロタイプを用いた研究: Nagai and Tokita (2022)
Analysis of Genetic Structure and Genetic Diversity in Japanese Black Kite Population Using mtDNA
日本の個体群は大陸 (lineatus) 由来で定着したと考えられる。遺伝的には少なくとも2系統からなる (複数回の導入が示唆される)。ただし用いられた大陸個体のサンプルは数も分布も限られている。
#ハチクマ備考の [台湾で留鳥化したハチクマと渡りの謎] の考察も多少参考になるかも知れない。世界的には日本はトビの分布の東端で、大陸にも留鳥個体群があるが渡り個体が日本に定着して留鳥化した可能性もあるように思えた。トビが南西諸島でまれなのもあるいは大陸から離れすぎているためかも知れない。
台湾のトビ (formosanus とされる) も数が減少し、殺虫剤 (Carbofuran など)、殺鼠剤のため危機的状況だったとのこと。現在は保護努力が行われている。
参照: The Black Kites of Taiwan (Mary Ann Steggles 2021)。
formosanus は亜種に値するか議論もある: Andreyenkova et al. (2023)
Genetic relatedness of the black kite (Milvus migrans) populations of Asia, Taiwan, Japan and Australia: does Taiwanese subspecies exist? (発表スライド)。
台湾の南北に離れた個体群があり、ハプロタイプも異なっているとのこと。系統的には govinda より lineatus に近い。海南島と中国のデータを解析する必要がある。台湾への定着経路も含め、大きめの猛禽類の大陸から島への定着メカニズムの視点からも興味深いところ。
Andreyenkova et al. (2024) Genetic relationships of populations of the Black Kite Milvus migrans (Accipitriformes: Accipitridae) in the east of its range in Asia and Australia
に日本のトビも含めた上記発表の論文がある。日本のトビは遺伝的に均一性が高く大陸とは隔離があるかも知れない。台湾のトビは2系統が認められ記載されてきた南北に隔離分布した亜種に対応するが、亜種 lineatus の方が分布を広げている。
フィリピンでもトビは珍しい。Black kite taken in Laoag, Ilocos Norte (Richard C. Ruiz 2024.11.2)。
このように見ると日本では当たり前に見えても近傍の島の様相はやや違うこと、つまり日本のトビの特殊性がわかる。フィリピンのチェックリスト (2023) では亜種 lineatus でルソン島の迷鳥となっている。学名は渡るトビなのに日本ではなぜ留鳥なのかしばしば話題になるが、サシバのように海を超える渡りは得意でなく、フィリピンにも簡単には到達できないのだろう。
大きさは似ているがハチクマの飛翔力とはだいぶ違いがあるよう。
Black kite taken in Laoag, Ilocos Norte on November 9, 2024 (Richard C. Ruiz 2024.11.9) 同様の写真。かなり珍しいものと思われる。
世界的にもキバシトビも含めて大陸から離れた島にはあまり分布していない。マダガスカル、カーボベルデ (アフリカの西沖合) に分布する。カーボベルデではアカトビ (Milvus milvus fasciicauda Cape Verde Kite。独立種とされることもある) も少数分布していたが 2000 年以降トビとの雑種のみとなり事実上絶滅した
[wikipedia 英語版; Johnson et al. (2005) Prioritizing species conservation: does the Cape Verde kite exist?: そもそも独立した分類概念ではなかった?]。
Hille and Thiollay (2000)
The imminent extinction of the Kites Milvus milvus fasciicauda and Milvus m. migrans on the Cape Verde Islands トビも絶滅寸前。住民の誤解による毒殺なども要因の一つ。
Hille and Collar (2011)
Status assessment of raptors in Cape Verde conrms a major crisis for scavengers
人口は増えていてあらゆるスカベンジャーの猛禽類、特にトビ類が危機的状況。
Andreyenkova et al. (2018) New Haplotypes of the Mitochondrial Gene CytB in the Nesting Population of the Siberian Black Kite Milvus migrans lineatus Gray, 1831 in the Territory of the Republic of Tyva
ロシア Tuva (モンゴル北方) の lineatus と考えられる繁殖個体群の中に migrans 型のハプロタイプがあることがわかった。
これらはもちろん渡る個体群。
Andreyenkova et al. (2021) Phylogeography and demographic history of the black kite Milvus migrans, a widespread raptor in Eurasia, Australia and Africa
に続報の研究がある。キバシトビ Milvus aegyptius Yellow-billed Kite は種レベルの差があると考えてよい証拠が増えている [Catanach et al. (2024) では同種としていたため解析されていない。またこの解析は亜種レベルを同時に扱う判定には向いていない]。
mtDNA の cyt b の一部のみを用いたもので解析上の限界はあるが最初のステップとしては有用ではないだろうかとのこと。
キバシトビの 原記載 で由緒ある名前。aegyptius は基産地のエジプトから。IOC 14.2 では別種扱い。
AviList (2025.6) ではキバシトビはトビに含められることになった。8466 361 Taxon aegyptius (polytypic, including parasitus) is treated as conspecific with Milvus migrans pending further research. Although the aegyptius complex is morphologically distinctive, mitochondrial DNA data (Johnson et al. 2005; Andreyenkova et al. 2021) do not recover the group as monophyletic, and geographic patterns do not align with currently recognized subspecies. All taxa are retained within a single species until more comprehensive nuclear or genomic data are available.
より確実な核遺伝子またはゲノム研究が出るまで暫定的扱い。
キバシトビはヨーロッパでの記録が散発的にある: Yellow-billed Kite: wild or escape? (Sam Viles, BirdGuides 2023)。
日本はほぼ純粋な lineatus で、大陸ともある程度の交流があると考えている [Nagai and Tokita (2022) の解析も参照]。現在のトビはツンドラ域には生息しないので、最終氷期に lineatus と migrans は一度隔離されたが再接触したとの描像でよさそうとのこと。
台湾の亜種と中国の個体については分析されていない。著者たちの主な興味はユーラシアの大陸部の生物地理学なので東・東南アジアの生物地理学は別途調べる必要がありそう。
トビの繁殖開始年齢は 3-5 歳とされ、繁殖年齢前の個体は大きく分散するが性成熟すると生まれた場所に戻る傾向があるのこと。未成熟または非繁殖の成鳥の大きな群れが夏のシベリアで観察されている。
Karyakin (2017) Problem of Identification of Eurasian Subspecies of the Black Kite and Records of the Pariah Kite in Southern Siberia, Russia
ユーラシアのトビの亜種の識別。写真を見ると確かに印象がだいぶ違う。また分布図で日本がいかにトビの世界分布の端に位置するかわかる。
fig. 5 に足や虹彩の黄色い rufous morph の写真が紹介されている。
亜種 migrans の渡りなどの生態研究は特にスペインでよく行われている。
Sergio et al. (2017) Migration by breeders and floaters of a long-lived raptor: implications for recruitment and territory quality
のよれば渡りのトビは 1-7 歳で繁殖を始める。あぶれ個体は渡りの時期が行き・帰りとも繁殖個体より遅いが、より急いで渡って風の条件はよくない。それでも早く着く方が有利とのこと。
遅く渡る個体はあぶれ個体または生存率が低く選択的に失われてゆくとのこと。
Santos et al. (2021) Black kites of different age and sex show similar avoidance responses to wind turbines during migration
で成鳥 77 羽、若鳥 58 羽と研究規模も大きい (2012-2013 年に捕獲とのこと)。
Evans et al. (1998) Successful breeding at one year of age by Red Kites Milvus milvus in southern England
英国で再導入されたアカトビに1歳で繁殖する個体がある確実な証拠。23 個体が繁殖を試み、1歳個体を含む3つがいが記録された。アカトビでは生まれた翌年に繁殖可能年齢に達しているよう。
Literak et al. (2022) A lifelong floater: the Red Kite female that never met a mate スロバキアで標識されたメスのアカトビ幼鳥のうち1羽は7年の生涯で繁殖できなかった。
最初2年はクロアチアやルーマニアに探索に出かけたがその後はほとんどスロバキアの別地域やハンガリー北部で過ごした。越冬時は常に孤独で他個体は見られなかった。個体密度が低いために繁殖時期に先立ってつがい相手を見つけることができなかったのでは。
Blas et al. (2011) Experimental Tests of Endocrine Function in Breeding and Nonbreeding Raptors によるトビのあぶれ個体のホルモンを調べた研究がある。あぶれオスも繁殖能力があるだろうとの結果となった。
ウクライナのトビ類渡り研究もある。GSM 発信機によるアカトビの渡り追跡の軌跡 (2021)
ウクライナ語でトビ類は shulika と他言語と大きく違うが語源は不明だった。
トビとヨーロッパノスリの雑種の報告がある: Corso and Gildi (1998) Hybrid of Black Kite and Common Buzzard in Italy in 1996。
[トビとアカトビの交雑個体の渡り]
Literak et al. (2025) Evidence of genetic determination of annual movement strategies in medium-sized raptors (近年の論文はこのような一般向けの抽象的なタイトルが多く、Abstract まで読まないと研究対象がわからないことが多い。良いのか悪いのか...)
F1 個体の渡り特性はトビ (より長距離の渡りを行う) のものに似ているものが大部分だった。渡り特性の基盤は遺伝的なもので顕性 (優性) 遺伝を示すと考えられるとのこと。
#カラフトワシ備考 [交雑と渡り] でも同様の事例が報告されているが一般化した議論が行えるまでには至っていない。
アカトビよりトビの方が移動能力が大きいため、地域に執着のより強いアカトビのような個体数ボトルネックを経験せず遺伝的多様性が高いことも議論されているとのこと。この部分は Andreyenkova et al. の仕事が参照されており [亜種と渡り] の項目参照。
アカトビとトビの分岐年代はかなり新しいが、このような結果を見るとアカトビが祖先型で (だとすれば...)、長距離渡りに関係する遺伝子が生じて隔離も進み、有利な性質だったためトビの方が広範囲に分布するようになり、トビ属が栄えるようになった。そうでなければトビ類はマイナーな存在にとどまっていたと解釈できる進化経路も考えられそうな気がする (どこかですでに議論されているかも)。
分散能力と表裏一体だが、トビ内の亜種分化もそれほど進んでおらず、渡り特性が新しく生じたものとの解釈に合う気もする。海ワシやノスリ類の系統の中では古く分岐していたものの、トビそのものは多くの地域では新参者となったと考えられる。ただし過去に消滅したトビ系統はすでにあったのかも知れない。
トビに似たニッチは先発の Elanus 属などがかなり占めてしまっていて進出しにくかったかも知れない。日本は分布の東端でそもそも猛禽類の種類が少なく、競争相手もあまりなかったのでトビにとっては天国のような存在だったかも知れない。
「春の鳥」(小学館 1984) p. 138 おそらく大都市圏の話と想像されるが「下水道の普及により最近では市街地で見られなくなってきている」とある。環境は改善されたと言えるだろうが、過去の日本のトビの密度は人為廃棄物のおかげで過剰に高く、[亜種と渡り] にある「越冬期のデリー地域は世界一トビの密度の高いところだろうとのこと」の状況に近かったかも。
しかし全国鳥類繁殖分布調査の報告書でも減少率の高い種に挙げられており (pp. 70, 160) 実はあまり安泰と考えるべきでないのかも知れない。繁殖成功率の変化もおそらくあまり調べられておらず、個体寿命の長さで個体数が保たれている部分もあるかも知れない。
しかしトビそのものは高緯度帯に分布するほどではないため新大陸まで到達することができず、新大陸では同じようなニッチを先発の系統やノスリ類、あるいはハヤブサ目が占めることになっていたと想像できる。
アカトビとトビの関係はツミとアカハラダカの系統関係 (こちらは分岐関係がよりよくわかっている) にも似ていて、少なくともタカ類にとっては長距離渡り習性を獲得することは進展の大事なステップだったのではないだろうかと感じられる。
#アマツバメ備考の [渡り鳥における磁気定位] にもあるように磁気定位能力はタカ類全体で保持されているようで、必要であればいつでも渡りを進化させる潜在能力を持っているように見える。昼行性猛禽類では磁気定位に関係すると思われる紫外線受容体が保持されていたことも有利に働いてそう。
旧広義の Accipiter 属全体を見渡しても同様で、古い系統で移動能力のあまり高くない Aerospiza 属はアフリカに局地的な比較的マイナーな系統にとどまっているが、渡り能力の大きい Tachyspiza, 狭義 Accipiter, Astur, Circus の各属は複数回に渡ってアジアや北半球に適応放散している。
もう少し解析が進めば、どの遺伝部位がどのように変異して長距離渡りを可能にするようになったか、共通の遺伝的基盤があるのかなど一般像が得られるのかも知れない。
ハチクマの熱帯地方の留鳥と渡り亜種の関係は、など興味ある話題にもつながるかも知れない。
ヨーロッパのアカトビの保全プログラム (LIFE EUROKITE) による GPS 追跡、死体回収と死因の特定など: Panter et al. (2025) A LEAP Forward in Wildlife Conservation: A Standardized Framework to Determine Mortality Causes in Large GPS-Tagged Birds
LEAP は LIFE EUROKITE Assessment Protocol の略で leap (跳躍) と意味をかけている。
かなりの割合で射殺や毒殺があるらしい。
["トビ" 類のドイツ語名]
英語では全部 kites としているが、ドイツ語ではさまざまな名称があることがわかった。
ドイツの鳥学会世界の鳥のドイツ語リスト (2022) Die Voegel der Erde によると:
カタグロトビ亜科の "トビ" を Aar。
ハチクマ亜科の "トビ" を Weih。英名は kites でなくてもマダガスカルヘビワシ、カッコウハヤブサ属、オナガハチクマ属も Weih としている。
ヨーロッパハチクマはドイツにも生息して昔から名前があるので Wespenbussard でハチクマ属も同様だが、オナガハチクマ属は真のハチクマ類ではないと考えている模様。この部分は後述のフランス語名と違っている。
ハバシトビ属は Zahnhabicht 歯のあるオオタカ。
トビ属、シロガシラトビ属は Milan。
ムシクイトビ属、ハシボソトビ、タニシトビは Bussard とノスリ類の名前。
と単純に英名から訳すだけでなく、系統や習性なども取り入れているらしいことがわかる。和名よりも凝っている感じ。
辞書を見ても同じような訳語が並ぶのだが、Aar はワシの同義語に近く、詩的な用法 (雅語)、あるいは Aar は英語の erne に相当してオジロワシの意味、ドイツ語で普通にワシを指す Adler は Adel-Aar (高貴なワシ) の短縮形らしいなどの情報が出ていた (#ノスリの [英名の語源] 参照)。
Weihe はチュウヒ類を指すなどある。Kornweihe がハイイロチュウヒ。"トビ" 類のは Weih と使い分けているようだが Weih は辞書では Weihe と同義とある。チュウヒの尾をちょっと短くして Weih に短縮した、とか考えるのは多分想像しすぎだろうが (笑)。Weih- は接頭語で「神聖な」などの意味があるので悪い語感ではないだろう。いずれもなかなか高貴な扱いとなっている。
なおチュウヒやトビの Weihe は「神聖な」とは別語源とのことでインド・ヨーロッパ祖語の *weyh1- (追う、追跡する) からドイツ祖語の wiwo に由来するとのこと (wiktionary)。
アフリカカッコウハヤブサは Kuckucksweih でカッコウの Weih、シラガトビは Milanweih と Milan (トビ) と Weih の合成になっている。
マダガスカルヘビワシ (#ハチクマの備考参照) の Geckoweih は Gecko (ヤモリ) で英名などより適切な名称かも知れない。
なおドイツ語の凧は Drachen でまったく異なる。
フランス語は概念がだいぶ違って kites に相当する分け方はない。フランス語はラテン系言語なので学名と相性がよく、属名などをしばしばそのまま取り入れている。
トビ属、シロガシラトビ属が milan である点はドイツ語と同じ扱い。
アカトビに milan royal (王のまたは立派なトビ) の名前を付けているのは面白い。
ツバメトビの名称に naucler という見慣れない単語が出てきて辞書を見てもまったくわからないが、これは形は似ているが系統がまったく違うツバメトビとアフリカツバメトビがかつて同属 Nauclerus と考えられた時の名残りとのこと (wikipedia 英語版より)。
ラテン語の意味は船長 < naukleros (Gk) とのこと。英語同系語に nautical (航海の) があり、nautical clerk のように解釈すれば意味が通る。海上を優雅に飛ぶ姿から名付けられたのだろう。
フランス語名もじっくり見ると面白そうである。
"トビ" 類の名称とは関係ないが、フランス語ではチュウヒ類が busard、ノスリ類が buse である。
#ノスリの備考 [英名の語源] にあるように、-ard はワシを表しているかも知れない (別説)。
フランス語 busard はドイツ語の Bussard の語源になり、こちらではノスリ類を表している。
[トビなどの第 II 趾の骨の癒合]
川口 (2024) Birder 38(12): 54-55 で取り上げられていたので紹介しておく。Jollie (1976, 1977) (最後の参考文献参照) では p. 228 に調べた範囲で Milvus、Ictinia (ムシクイトビ属)、Haliaeetus の各属でみられ、
Haliaeetus 属では癒合が不完全なものもあるとのこと。Shufeldt (1891) が Ictinia, Haliaeetus 属で癒合を報告しているとあり、ここまで文献を遡っていることを見るとトビ属で癒合していることを報告したのは主な文献では Jollie (1976, 1977) が最初なのかもしれない。
Milvus と Haliaeetus 属は現代の分子系統樹でも近い関係で系統的特徴が現れているのだろう。Milvus + Haliaeetus のクレードの祖先段階で生じた形質と考えるとわかりやすい (タカ類分子系統樹を見ながら読んでいただくとわかりやすい)。
Ictinia は多少系統が離れているが孤立系統でノスリ亜科 Buteoninae の古い方の系統であることは共通している。途中に Butastur (サシバ) 属があるのでサシバ属で癒合が見られないのであれば Ictinia では独立に進化した形質と言えることになる。
川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019) を見るとサシバでは癒合していないように見える。
第 II 趾の役割については #ハチクマ備考の [カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] の参考文献 Fowler et al. (2009) なども参照。
この点だけでもトビとハチクマはあまり似ていないことがわかる。
同じくハチクマ備考の [ハチクマ類の道具使用] にも関連した考察がある。
なお (骨について) fusion の定訳は癒合でないかと思う (医学分野ではこの用語が主に使われている。参考用語集 Skeletal Anomaly 骨格異常)。
癒着は adhesion の方ではないだろうか。川口氏も記事の中で紹介される suture (縫合) の用語もあり、こちらも病態などの名称には通常は癒合がよく使われている。医学と例えば古生物学では訳語が違うのかも知れない。
[猛禽類の逆性的サイズ二型]
図鑑などでトビの項目を見ると全長がオス 58.5-59 cm、メス 68.5 cm とあってこれは榎本「野鳥便覧」
の数字が由来と思われる (#ハチクマの備考 [ヨーロッパハチクマとの関係・亜種他] 参照)。小鳥食の猛禽類ほどメスの方が大きい逆性的サイズ二型 (reversed sexual size dimorphism, RSD) が際立っているとの過去の一般的解釈から考えるとトビの雌雄サイズの違いが大きすぎる疑問をずっと持っていた。
とはいえ海外文献にも全長の数字はあまり出てこないし、日本の個体群とは違うかも知れないのであまり役に立たないかも知れない。それを前提として Dement'ev and Gladkov (1951) を見てみると、
ミサゴの全長がオス 560-598 mm (中央値 574 mm)、メス 575-615 mm (中央値 595 mm) とあって 3-4% 程度の違いになる。
トビのヨーロッパの亜種 migrans では全長はないが翼長中央値でオス 453.6 mm、メス 464.6 mm で 2.4% の違い、日本と同じ亜種の lineatus (ヨーロッパ亜種より少し大きい) では同じく 476.7 mm と 489.1 mm とあり、2.6% の違いになる。
アカトビでは雌雄ほぼ同じように見えるとあるが雌雄別の中央値は出ていない。
これらをみるとトビ類では雌雄差が 2.5% ぐらいではないかと推測する。オス 58.5-59 cm、メス 68.5 cm は 17% に相当し、ちょっと違いが大きすぎると思う。他にも資料はあると思われるので記事などで記載される場合はご確認いただければと思う。
さて昔から「小鳥食の猛禽類ほどメスの方が大きい」と言われてきて、比較的ポピュラーな解釈として雌雄で異なるサイズの獲物を捕るための適応、よく獲物を運ぶオスが小さい方が小回りがきくなどがある。
Schoenjahn et al. (2020) Why female birds of prey are larger than males
に最近の論文があるので少し見ておきたい。
これによれば 20 以上の仮説が提唱されているとのことなので参考文献を見ていただければよいだろう (*1)。
この論文では、系統的に離れたタカ目、ハヤブサ目、フクロウ目に共通してみられる性質で猛禽類以外の他の系統ではほとんど見られないことから、一つの共通要因で説明することが可能かを考えたもの。
例えばモズ類も猛禽的であるが RSD を示すものはごく少ない。グンカンドリ類やトウゾクカモメ類は RSD を示す。
この著者によれば猛禽類においてはメスによる巣の防御が大きいほど有利であることが共通仮説になり得るのではないかとのこと。
雌雄で異なるサイズの獲物を捕るための適応 (食物を巡る雌雄の競争を避ける) であればオスが大きくても構わないのではないか (なお #ミヤコドリ備考の [貝を開ける習性] で紹介した理論研究では食物を巡る雌雄の競争を避ける単独要因では性的二形はむしろ進化しにくいとのこと)。
獲物を捕るための適応については実証的研究があまりない。アラスカのシロハヤブサでは雌雄差が大きいのに雌雄ともに同じ獲物を捕る。フクロウ類でも同様の結果がある。
小さい方が小回りがきく仮説も実証的研究は得られていない。
猛禽類は武器も備えているので他のグループに比べて巣やひなをより攻撃的に守ることができる (グンカンドリ類やトウゾクカモメ類はそうではないが) ので、(従来から言われる仮説の一つの言い換えに過ぎないが) 巣を守る行動が RSD の主要因ではないかと考察している。
猛禽類の繁殖失敗要因として、人為によるものを除けば外敵による捕食が最も大きい。
オスが遠くへ出ていることも多いので、メスが単独で防衛する必要がある種が多い。
この機構はオスには直接関係しないのでオスのサイズを制約するものではない。
これまで「巣を守る」役割が RSD の機構として軽視されてきた理由は、巣を守る種類は他にも多数あるのに RSD を示さないなどがある。これは猛禽類が攻撃的に守る能力が高いことを軽視している。
どちらの性がより重要な「巣を守る」役割を果たすかはあまり調べられていない。
巣を守る行動は主に観察者の人間に対する情報が中心で、他の捕食者に対する行動はあまり知られていない。
著者は多少変わった例を調べて仮説の妥当性の検証を試みている。これまでの仮説はこれらをうまく説明できない。
新世界ハゲワシ類 (コンドル類) は RSD を示さないが、これらは卵やひなの捕食が繁殖失敗の重要要因なのに卵やひなを守る行動をあまりとらない。
旧世界ハゲワシ類 (シロエリハゲワシ) ではごくわずかな RSD で、コロニー性で雌雄が同様に抱卵をする。コロニーでは他の個体による防衛も考えられるが観察は十分でない (注: 給餌場でのシロエリハゲワシの行動ではイヌワシを駆逐するほどの力があるので足に武器がなくても十分攻撃ができているかも知れない #イヌワシの備考 [イヌワシと他のワシとの種間関係] 参照)。
ヘビクイワシは RSD がごく弱いが雌雄が同様に抱卵や子育てをする。
フクロウ類では大型の Ninox 属の種でオスの方が大きいものが知られている: アカチャアオバズク Ninox rufa Rufous Owl、オニアオバズク Ninox strenua Powerful Owl、オーストラリアアオバズク Ninox connivens Barking Owl
でいずれもオーストラリア地域のもの。あくまで人への反応だがオスもメスも同様に攻撃するとのこと。
オスが昼間に餌を提示する "prey holding" 行動が知られる唯一のフクロウ類だが、このディスプレイはオスを大きくする方向に働くかも知れない。一方メスの大きさは樹洞サイズで制限される。
これらの事例は雌雄が同様に防衛に関わるもので、「巣を守る」仮説を補強するとしている。
もちろん巣を守ることとメスの大きさは原因か結果か両方どちらも考えられる。
読んでみての感想だが、このような議論は通常さまざまなパラメータで多変量解析を行うのが最近の流行であるが、巣の防衛行動などは広範な種のデータがないので多変量解析に向かないのだろう。
そうするとどうしてもデータのある食性 (小鳥食の猛禽類ほどメスの方が大きい) の相関が強く出るのではないかと感じる。巣での役割分担なども考慮した相関を調べる必要がありそうに思う。
古賀・白石 (1987) トビ Milvus migrans の育雛行動
抱雛は主に雌の役割であるが、育雛初期には雄が抱雛を分担することもあると記されている。トビを日本語で探しただけだが思ったほど情報がない。皆さんの観察ではいかがだろうか。自身の観察ではオスが結構子育てに関与している印象を受けたが (巣にいる時によく鳴く片方の個体がいてどちらが巣にいるかわかりやすかったのだが、役割分担のことを意識していなかったので数値的な記録を残していない)。
食性からあまり RSD が期待できないように思えるハチクマで雌雄の違いが結構大きいのは抱卵は平等に分担していても育雛初期はほとんどメスが巣を守るためかも知れない、とか考えながら見てゆくと面白そうである。オスが遠くまで餌を捕りにゆく種類は巣でメスが必死で呼んでもオスが帰ってこないなど。
Brown (1976) によれば (広義の) Accipiter 属ではオスは抱卵に関与しない。オスは餌を運ぶがひなが餌乞い鳴きをしても餌を与えることはなく、ひなに餌を与えるのは完全にメスの役割とある。このグループは RSD が最も顕著なので「巣を守る」仮説とは整合しているように見える。
もちろんこれも何が原因で何が結果かはこれだけでは明らかでない。小鳥食では捕獲後の "調理" に手間がかかるので役割を切り分けた方が効率がよいかも知れない。RSD と食性の関連解説に最もよく使われるのが (広義の) Accipiter 属なので雌雄の役割分担なども含めて広い視野で見た方がよさそうである。
哺乳類で性的サイズ二型 ("逆" ではない SSD) と遺伝子の関係を調べた研究が発表された: Padilla-Morales et al. (2024) Sexual size dimorphism in mammals is associated with changes in the size of gene families related to brain development
(Size doesn’t matter for mammals with more complex brains, according to new study リリース記事)。
より脳の発育に関する遺伝子ファミリーの大きいものほど SSD が小さい傾向がみられた。また嗅覚遺伝子は逆の傾向になった。哺乳類の場合はおそらく事情が異なるだろうが、脳がより発達するとサイズをもとにした性選択よりもっと複雑な手がかりを用いるようになったのではとのこと (カラスの雌雄差が小さいことに関係がある?)。
また精巣サイズとゲノムの関係も調べたいと考えているとのこと。
公開ゲノムデータはすでにある程度あるはずなので、鳥類の SSD/RSD を議論する際も生態要因以外にもこのような比較ゲノム学が用いられるようになるのだろう。誰か挑戦してみては?
備考:
*1: まとめておくと便利そうなので主要文献を挙げておくことにした。提唱時の論文や本は古いものが多くオンラインでオープンアクセスでないのが残念なところ。以下のような "ストーリー" は作られているが、例えば役割分担が生じた場合その行動が進化するかまで検証することは難しい ("適応的" との表現は自然選択できっと進化するだろうなどの意味合いで使われているのだろう)。
進化を実験することは難しいので比較解析などで説明変数との相関を探り、進化要因になり得るかを調べるアプローチが古くからも一般的だった。異なる生活史を持つ個体群などが見つかった場合の比較、また本当に "適応的" になっているかを生涯の子供の数などで調べるのは正攻法だが猛禽類では長期研究を要し、統計的に有意なサンプルを得ることは現実的は容易でない。
生涯の子供の数は難しいので、採食効率が推測される通り上がっているかなどを間接的に調べる比較的短期間で可能な研究が中心になる。トラッキング技術が進歩すれば細かい行動なども遠隔で記録できてあるいは採食効率の研究などに進展があるかも知れない。
これらの難しさが古くからアイデアが出されているもののなかなか検証されない要因となっているだろう。これに比べると配偶様式や繁殖様式 (コロニー性など) はまだ調べやすいとも言える。
分子遺伝学の方からは何かアプローチがあるだろうか。RSD の最も顕著な広義 Accipiter 属の系統が判明したので系統と組み合わせた解析は以前より行いやすくなっているかも知れない。
(1) 'food-niche' hypotheses (雌雄で食物のニッチが違う):
Snyder and Wiley (1976) "Sexual size dimorphism in hawks and owls of North America";
Andersson and Norberg (1981) Evolution of reversed sexual size dimorphism and role partitioning among predatory birds, with a size scaling of flight performance (別サイト)
警戒心の強い獲物の場合雌雄が共同で狩りをしても効率が2倍にならないので効率が悪く、猛禽類では役割分担をするのが適応的。役割に分担が生じるとメスが巣を守り、オスが食物を探す傾向が生じる。巣を防衛する能力の高いメス、狩りの能力の高いオスが選択される方向に働く。
鳥を専門に食べる種類ではそこまで敏捷でない他の食物に比べておのずと適切な獲物サイズが決まるので、雌雄で獲物に違いがあることが有利に働く、といろいろな仮説を組み合わせたもの。
von Schantz and Nilsson (1981) The reversed size dimorphism in birds of prey: a new hypothesis
Deshler (2021)
Higher reversed sexual size dimorphism among nesting pairs of Northern Pygmy-Owls (Glaucidium gnoma) in northwestern Oregon than among specimens collected at the range-wide scale
メキシコスズメフクロウ Glaucidium gnoma Northern Pygmy-Owl でアメリカオレゴン州北西部で RSD が強かったが、その地域ではオスが鳥をよく食べていたとのこと。食物が RSD に影響を与える可能性がある。
(2) 'small male' hypothesis (オスが小さい方が敏捷で採食効率が良い):
Andersson and Norberg (1981);
Mendelsohn (1986) Sexual size dimorphism and roles in raptors - fat females, agile males
比較研究の例: Krueger (2005) The evolution of reversed sexual size dimorphism in hawks, falcons and owls: a comparative study
タカ類では3変数でかなり説明できる [獲物サイズ、狩りの方法 (分類は論文参照)、翼長]。
ハヤブサ類では同様に3変数 (狩りの方法、クラッチサイズ、色彩の性的二形)、
フクロウ類では狩りの方法または獲物サイズでそれほどよく説明できていない。
狩りの方法が共通するので敏捷な動きが必要とされる種類と相関がある、との論理になっている。
(3) intersexual behaviours (つがい間の行動、特にメスが大きい理由):
(3a) to control or dominate the male (メスがオスより優位に立つため):
Andersson and Norberg (1981)
(3b) to prevent the male from harming the female or from killing the young
(オスがメスやひなを殺さないため):
Amadon (1959) The significance of sexual differences in size among birds
(3c) to force the male to supply food for the family (オスに家族への食物を運ばせるため):
Cade (1982) "The falcons of the world"
(3d) to facilitate pair formation (つがい形成を容易にするため):
Amadon (1975) Why are female birds of prey larger than males;
Cade (1982)
(4) 猛禽類全体を説明することを意図していないが、配偶システムに焦点を当てたもの:
(4a) 一夫一妻の場合: Smith (1982) Raptor "reverse" dimorphism revisited: a new hypothesis (一夫一妻の鳥では通常メスが優位。雌雄の闘争を防ぐため猛禽類では RSD が有利になる);
Mueller (1990) The evolution of reversed sexual dimorphism in size in monogamous species of birds (他の要因も合わせて考察)
(4b) 一夫多妻の場合: Snyder and Wiley (1976)
(5) 'nest defence' hypothesis (巣の防衛):
Snyder and Wiley (1976); Andersson and Norberg (1981)
参考までに一夫一妻のシギ・チドリで見られる RSD についての仮説: Figuerola (1999) A comparative study on the evolution of reversed size dimorphism in monogamous waders
(1) 'energy storing' hypothesis 産卵に備えてメスがエネルギーを貯める, (2) 'incubation ability' hypothesis, (3) 'parental role division' hypothesis, (4) 'display agility' hypothesis の4つがあるとのこと。(4) は性選択に関連する。敏捷なディスプレイは能力の「正直なシグナル」となり得てオスが小型化する。
(1) は長距離の渡りをするシギ・チドリには重要な要因。(2), (3) は猛禽類とも共通性がある。
Danel et al. (2024) Sex predicts response to novelty and problem-solving in a wild bird with female-biased sexual dimorphism
は野生のトウゾクカモメ類 (RSD を示す) で学習能力などは差がなかったがメスの方が問題解決能力が高く、新しいものを嫌わなかったとのこと。
[視覚特性]
Poiter et al. (2016) Visual abilities in two raptors with different ecologyによれば、最大視力(側方視)はモモアカノスリ (ハリスホーク) がトビより少しよい程度であまり大した違いはない。
正面視に関してはモモアカノスリは2つめの視力のよい場所(側方視より悪い)を持っているが、トビはそれがない (しかし網膜の構造が違うだけで正面視にかかわる神経細胞は多いのかも知れない)。ハゲワシ類などのスカベンジャーの網膜構造はトビと同様。正面視の能力は動く獲物をとるのに必要なものらしい。
面白いのは、視覚弁別実験に対する反応時間はトビの方が圧倒的に長い。これはモモアカノスリが正面視と側方視を両方使って判断しているためで、トビは左右の側方視を交互に用いて課題をこなしているため (右で見て左で見てを繰り返す) その分時間がかかる。
トビの行動を見て「とろい」と感じる人もあると思われるが、これはこのような生態に合わせた視覚特性に由来しているもので、必ずしも頭の反応速度を意味しているものではなさそうである。トビの方が視野が広く、これは同種他個体を見つける (餌の探す時に他の個体を探す、渡りをする個体群では渡りの時など) のに役立っていると考えられる。
Osik et al. (2022) Nicotinamide adenine dinucleotide reduced (NADH) is a natural UV filter of certain bird lens
の研究で、いくつかの鳥で NADH (ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 生物界で広く使われる電子伝達体) が紫外線フィルターとして働いていることを明らかにした。調べられた中ではトビが特に顕著だったとのこと。レンズに紫外線フィルターを持つことが知られている種類はこの時点で数種にとどまっていた。
ヒトを含む霊長類でも紫外線吸収物質が知られているが哺乳類では kynurenine の別の物質を使っている (こちらはトリプトファン由来。昼行性の種類に見られると考えられるので哺乳類では少ないのだろう)。
紫外線フィルターが猛禽類の優れた視力に役立っているのでは。
この記述だけを要約すれば「トビはサングラスを付けて餌を探す」となるだろうか。
ヨーロッパチュウヒのレンズは NADH 濃度が低く紫外線をよく通す。ヨーロッパノスリは中程度でアオサギと同様とのこと。アオサギは NADPH 濃度が高く、これが同様に働いている可能性がある。
トビは高い位置から獲物を探すので視力が必要、ヨーロッパチュウヒは低い位置で狩りを行うので視力はそれほど必要ないのではと議論している。カンムリカイツブリ類 Podiceps 属も濃度が高いが生態的意義はよくわからない。しかしカモメ類では低いとのこと。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3936-3938 のリスの項目 (今泉) によれば、リス類や多くのサル類でレンズが黄色で (人間でも黄色で加齢とともに濃くなる、というのは白内障のことか?)、昼行性で色覚が発達している共通点があるとのこと。
リス類では青空のタカを見分けるのに役立つのではとの解釈も出ていた (なるほど黄と青は補色関係となるわけか...)。
当時の論文を少し探してみると Cooper and Robson (1969) The yellow colour of the lens of the grey squirrel (Sciurus carolinensis leucotis) があり、この文献でも色収差軽減のためか、視細胞が紫外線を感受するため、紫外線による劣化の抑制などの議論があった。
新しい方では Douglas and Jeffery (2014) The spectral transmission of ocular media suggests ultraviolet sensitivity is widespread among mammals では多くの哺乳類の眼球が紫外線を通すのは、紫外線を感受する色素がなくても紫外線に感度があるためでは、との示唆もあった。
この論文に哺乳類での紫外線透過率の一覧が出ていてリス類は低い方からほとんど通さないものまで。しかし同様に低いものも多数あって紫外線をよく通す方がむしろやや例外的な感じ。夜行性のものはよく通す傾向がある。色収差軽減や紫外線による劣化の抑制など論点は昔とあまり異なっていないよう。
青空のタカを見分けるのに役立つアイデアはここには載せられていない。
Mougeot and Arroyo (2006) Ultraviolet reflectance by the cere of raptors ではヒメハイイロチュウヒのろう膜は紫外線を反射して、性選択のシグナルになっている可能性を指摘しているが、この点はヨーロッパチュウヒのレンズが紫外線をよく通すことと整合する可能性がある。
ただし波長がやや短すぎるので猛禽類の紫外線知覚の現代の知見と整合するかどうかはあまり明瞭でない。
鳥類が紫外線を見ていることが判明して初期になされた研究で (チョウゲンボウが齧歯類の尿の跡を見ると同様)、後続研究もなくやはりカロテノイドの方が重要だろうと認識されている印象を受ける。
[トビの労働寄生]
労働寄生 kleptoparasitism, cleptoparasitism: 宿主の体から直接栄養を得るのではなく、宿主が餌として確保したものを餌として得るなど、宿主の労働を搾取する形の行動を取ることを指す。盗み寄生とも言う (wikipedia 日本語版)。
Belyaev (2021) An unsuccessful attempt at kleptoparasitism of the black kite
Milvus migrans against the grey heron Ardea cinerea (pp. 3237-3239)
はアオサギから餌を奪おうとして失敗した報告。トビによる労働寄生の相手としてカワウ、ミサゴ、ウスハイイロチュウヒ、カラス類などが挙がっている。大型の鳥からも奪うことがあるそうでアフリカハゲコウ、海ワシ類、エジプトハゲワシ、ズキンハゲワシ、ハヤブサの記録がある。
タカ類では海ワシ類に多くみられる。海ワシ類は大きなトビのようなものとも言われることがあるが、系統的にも近く半分当たっている感じもする。
アフリカソウゲンワシ Aquila rapax Tawny Eagle もハゲコウがネズミを飲み込もうとする時に大声で鳴いて騒がしくして動揺させ、獲物を奪うとのこと [「鳥の生活」ブライト著 丸武志訳 平凡社 1997 p. 515]。
動物園でも Aquila 属としては悪声で、またよく鳴くのだがそのような意味があったのかと認識した。あまり鳴かない方が賢く見えるのだが (笑) これは単なる個人的好みかも知れない。
[生きた動物を食べるトビ]
Balcony Birding: The Hunter (Black Kite) & The Hunted (Rock Pigeon) という町中でハトを生きたまま食べるトビの映像が紹介されている。
Vinuela et al. (1992) Importance of Rabbits in the Diet and Reproductive Success of Black Kites in Southwestern Spain
スペインの研究でウサギをたくさん食べている報告。食べている鳥の種類も書いてある。おもにひなか若鳥であるが (早成性の鳥のひなはよい獲物になるのだろう) オオバン、カモ、カササギ、ニシコクマルガラス、アカアシシギ、セイタカシギ、ソリハシセイタカシギ、クロハラアジサシなど比較的大きな鳥も含まれている。イエスズメや他のスズメ目も含まれる。
Sergio and Boto (1999) Nest dispersion, diet, and breeding success of Black Kites (Milvus migrans) in the Italian pre-Alps
はイタリアの例で、巣に運ぶ食物では魚と鳥が主食とある。
Glushchenko et al. (2020) Breeding birds of Primorsky Krai: the black kite
Milvus migrans (pp. 4961-4972)
(和訳は 極東の鳥類39: 非スズメ目鳥類特集 収録) のよればロシアのビキン地方のトビが魚より鳥をよく食べているとのこと。ネズミ類が大繁殖した年はよい食料になるとのこと (#ハチクマ備考の [ハチクマの哺乳類食] も参照)。主にスズメ目だがオナガなども含まれている。
沿ハンカ湖低地ではネズミ類が多く、鳥ではタゲリ、シマアジ、キジなども含まれる。
他の地域だがオオルリのオスの捕食例もある。
先崎 (2018) Birder 32(2): 29 にシメが採食に集結していた際 (2012-2013 の冬)にさまざまな猛禽類が食料として利用した事例が紹介され、シメを奪い合うトビの写真が出ている。
一方オーストラリアのトビがアボカドを食べることが観察されている。過去に報告された同様の事例はアフリカのみとのこと。猛禽類による植物食のレビューを含め #クロハゲワシの備考 [猛禽類の植物食] を参照。
[胃液の発見]
胃が食物を消化する仕組みを発見したのは レオミュール (Rene-Antoine Ferchault de Reaumur 1683-1757) と説明されている本があり、自分も生物で習ったような気がする。
レオミュールは飼育しているトビに金網に入れた肉片を与え、ペリットを吐き出す習性を利用して史上初めて胃液を採取したと説明されている。
昔からこの「トビ」は何だったのか気になっていたのだが、今では文献を見ることができる:
Reaumur (1752a)
Premier memoire. Experiences sur la maniere dont se fait la digestion dans les Oiseaux qui vivent principalement de graines et d'herbes, et dont l'estomac est un gesier、
Reaumur (1752b) Deuxieme memoire. De la maniere dont elle se fait dans l'estomac des Oiseaux de proie
1本目が鳥類の消化についての一般的考察、実験の具体的な記述があるのは2本目 (Oiseaux de proie = 猛禽類, proie = 英語 prey) のようで、p. 464 で une buse d'une grosse espere & commune とあってヨーロッパノスリを指してそうに見える (そのまま読めば 大型の種で普通のノスリ となる。単数形。18 世紀の話なので現代の種名とはそのまま対応しないかも知れない)。
日本語にする際に "ノスリ" はあまり馴染みのない名前なので誰かがよりわかりやすい "トビ" に直し、それが伝承されてきているのではないかと想像する。
[兄弟殺し]
トビでも兄弟間闘争が起きる報告がある (#イヌワシの備考参照)。
アカトビの兄弟殺しの映像が最近撮影されたSiblicide in Red Kites (猛禽類研究家 Valentijn van Bergen による)。オジロワシなどの海ワシの仲間と考えれば見かけから想像されるより凶暴な行動が納得できるかも知れない。
[トビの巣の飾りは同種への信号?]
Canal et al. (2016) Decoration Increases the Conspicuousness of Raptor Nests
トビの巣に人工的に飾りを付けると同種がより容易に見つけるようになった実験。
Sergio et al. (2011) Raptor Nest Decorations Are a Reliable Threat Against Conspecifics
による同種にとって巣が目立つことが「正直な信号」となっている (同種間の無用な闘争を防ぐなど) 仮説に基づくもの。
トビの巣にしばしば持ち込まれる人工物もこのような飾りの一種なのかも知れない。
[死んだふりをするアカトビ]
Martin-Jurado et al. (2011)
Bispectral Index Reveals Death-feigning Behavior in a Red Kite (Milvus milvus)。
猛禽類の中で長時間保定と続けるとアカトビが人に対して死んだふりをする行動が知られていたが、性別判定のための麻酔下での腹腔切開から目覚めても sternal recumbency (起き上がれない状態) で生理学的測定値も死んだふりをしている可能性を示唆するとのこと。
この文献で引用されている死んだふりは、ニワトリの Rovee et al. (1976) Periodicity of death feigning by domestic fowl in response to simulated predation、
脊椎動物で Hoagland (1927) Quantitative Aspects of Tonic Immobility in Vertebrates。
アカトビが死んだふりをするのは獣医にとって周知の事項のよう。
岩見 (2010) Birder 24(8): 30-31 に巣の中のトビのひなが身を寄せて隠れる様子、保護されたトビでよく見られる「死んだふり」について言及がある。死んだふりはしているが目は開けて様子を見ているとのこと。
最小の猛禽 (スズメ大) として知られるサボテンフクロウ Micrathene whitneyi Elf Owl の死んだふりがよく知られているとのこと (wikipedia 英語版)。
広い範囲の動物を扱った新しいレビュー論文 (オープンアクセス) では Humphreys and Ruxton (2018) A review of thanatosis (death feigning) as an anti-predator behaviour
があった。
主な関心はヒトの死んだふりだが行動の進化を検討したレビュー: Peinkhofer et al. (2021) The evolutionary origin of near-death experiences: a systematic investigation。
すべての系統に存在するとのこと。鳥ではネコに対するウズラ、キツネに対するカモ、闘鶏におけるニワトリの研究が引用文献に紹介されている。
Bjelica et al. (2025) The Slithering Dead: Does locomotor performance affect post-capture death feigning in dice snakes (Natrix tessellata, Laurenti 1768)?
こちらはヘビ類 (dice snakes) が捕獲された後に示す死んだふり行動。速い個体ほどすぐ逃げるが遅い個体は死んだを行う傾向がある。哺乳類捕食者のいない島では行動が遅く、死んだふり行動が多いとのこと。逃げる行動を発達させるには運動器能力が必要で、その維持にコストがかかるためということらしい。
"死んだふり" は上記の学術用語の他に英語で playing possum と表現される。OED によればアメリカ口語とのことで、1832 年の用例 (possuming, 1828 年に oppossuming) がある。動物のオポッサムなどを含む opossum (1610 Apossouns, 1612 Opassom などの用例がある) の名前の方が古く、バージニアのアルゴンキン族 (Virginia Algonquian) 言語 (Powhatan language) の opassom (op- 白い -assom 犬) 由来とのこと。
[トビの獲物攻撃速度]
Santer et al. (2012) Predator versus Prey: Locust Looming-Detector Neuron and Behavioural Responses to Stimuli Representing Attacking Bird Predators
ビデオでバッタの大群 (オーストラリアの Chortoicetes terminifera) への攻撃速度を測定。10.8 (±1.4) m/s だったとのこと。ここではバッタのニューロンが接近する物体にどのように反応して逃避反応を示すか調べている。
行動も比較的詳しく記述されており、捕食を試みる間隔は 6.4±3.5 s だった。成功すれば上昇して飛びながら食べるが落としてしまった例も記録され、落としてしまったのに食べようとする行動が見られた。
[トビの人への攻撃性]
インドのデリーでの研究: Kumar et al. (2018) Offspring defense by an urban raptor responds to human subsidies and ritual animal-feeding practices
ここでは人の出すゴミ以外にも宗教的理由で餌付けが行われている。人馴れもあって子を守る行動は基本的にはカラスの話と同様のよう。よい "餌場" は上位個体が占拠する傾向があってより攻撃的な可能性なども議論されている。
[トビの遊び?]
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 197 (1941 年初出) によればアドバルーンに3メートルほどの鋼が垂れたところにトビが嘴でぶら下がる行動が観察されたとのこと (戸田達雄氏報告となっている)。
[トビの白内障治療]
Sritrakoon et al. (2021) Bilateral cataracts extraction by lens aspiration and foldable intraocular lens implantation in a black kite (Milvus migrans)
タイで両眼白内障のトビのレンズ吸引と眼内レンズを入れた。術後2か月で飼育下ではあるが衝突することなく十分飛べて動くマウスを捕えるとることができたとのこと。両眼視に反応している証拠がある。3年後でも予後良好とのこと。
検査の結果トビの水晶体の屈折度はヒトのものに近く、ヒト用の眼内レンズを使うことができた。他に数例の猛禽類の報告があるが両眼手術のケースは知る限り初めてとのこと。
[火を使う猛禽類、森林火災、気候変動]
オーストラリアの先住民アボリジニの言い伝えによれば山火事の際に意図的に火を広める行動をとる猛禽類があるとのことで、2018 年初頭に研究が発表されて "firehawk" の名前で一躍有名になった。例えば
Australian "Firehawk" Raptors Intentionally Spread Wildfires
の記事を参照。
山火事の際に逃げ出す動物を餌として利用する習性は猛禽類でしばしば知られているが、燃えている枝を運んで意図的に火を広め、獲物を追い出すという。
科学者が実際にそのような現場を映像記録することはできていないが、聞き取り調査による目撃例を集めた。
火の付いた枝を運ぶのが目撃された種類はトビ、フエフキトビ Haliastur sphenurus 英名 Whistling Kite (2種ともノスリ亜科トビ族)、チャイロハヤブサ Falco berigora 英名 Brown Falcon の少なくとも3種。
まれな事象であり、目撃者も一度か多くても数回しか見たことがないとのこと。
意図的なものか偶然運んだものかが問題となったが巧みな質問への回答から研究者は意図的に運んでいると考えているとのこと (住民が伝統的に山火事を制御するのと同じやり方で行う。人の方が鳥から学んだ可能性すらあるとのこと。さすがに鳥が火を起こすことまではできないらしいが)。またアボリジニ以外の観察例もあるとのこと。
研究者グループも煙の出ている枝を拾って燃えていないところに落とすトビやフエフキトビを観察している。
嘴で拾って足に持ち替える行動も観察されている。他の著者がさらに2種に言及していてシラガトビ (ハチクマ亜科)、アカハラオオタカ Accipiter fasciatus (新学名で Tachyspiza fasciata) 英名 Brown Goshawk (ハイタカグループ) も可能性があるとのこと (先の3種は数も多く、聞き取り調査で種の識別が容易であったものに限られている)。
トビの名が付くと同じようなものに思えてしまいがちだが、亜科の異なるさまざまな系統の猛禽類がこのような行動を行うらしいことも注目に値するだろう。
一名の研究者は比較的頻繁に観察できたが他の観察者はほとんどみかけなかったなど、地理的にどのような範囲で見られる現象なのかはよくわかっていない。
カラスが火のついたロウソクを運ぶ話で、カラスは賢いので火を恐れないことを学習するなどの解説もあるが、それならばこれらの猛禽類も同じぐらい賢いのでは (笑)?
論文は Bonta et al. (2017)
Intentional Fire-Spreading by "Firehawk" Raptors in Northern Australia。
この話は興味本位な尾ひれが付きがちなのでメディア情報などは用心して読んだ方がよい。
自然に起きる山火事は生態系にとっても重要で、小規模な山火事は大規模な山火事を防ぐ役割もある。
人工的に制御された火災によって生息地が維持されている種類もある (参考: Set With Care, Fire Creates Habitat for Many Declining Bird Species。
ここで言及されている種類はヤブスズメモドキ Peucaea aestivalis 英名 Bachman's Sparrow だが人名付きなのでそのうち改名されるだろう、と ホオジロシマアカゲラ Leuconotopicus borealis 英名 Red-cockaded Woodpecker)。
森林火災が生態系に重要な意味を持つ研究は例えば、
He et al. (2019) Fire as a key driver of Earth's biodiversity、
Stephens et al. (2023) Forest restoration and fuels reduction work: Different pathways for achieving success in the Sierra Nevada。
シベリアの森林火災の増加がハチクマにとって好適な環境を生み出して分布が広がっている可能性なども指摘されている。
しかしながら近年の気候変動に伴う制御不能の大規模山火事はしばしばそのような役割を超えている。
オーストラリアの 2019-2020 年の山火事は破局的なもので、このために絶滅した種類もあるかも知れないとされている。
この時も "firehawk" が火を広めているデマがあったが、大規模火災にはとても生物が近づけるものではなく、一見平常に見えた景色が逃げる余裕もない短時間で大火災に変わってゆく映像も紹介されていた (車を使ってももちろん逃げることはできない)。
そしてまた夏を迎えつつある 2023 年年末の現状は Australia fires: Dreaded bushfire season turns deadly
のように報道されている。"Black Summer" (暗黒の夏) と呼ばれるそうである。
2019-2020 年のオーストラリアの山火事の生物への影響がまとめられた: Driscoll et al. (2024) Biodiversity impacts of the 20192020 Australian megafires (2024.11.13 オープンアクセス)。
鳥は移動能力が大きいため他の分類群に比べて影響は比較的小さかったようで、哺乳類への影響が大きかった。しかし生存基盤の脆弱な種については注意が必要である。
カナダの 2023 年の大規模山火事も記憶に新しい。報道される断片部分だけ見ていると一つの火災がまだ広がっているのかと感じがちだが、報道されているものは実はすべて別の火災で、至るところで森林火災が発生して制御不能の状態となっていたようである。
秋分を過ぎると高緯度では白夜になる地域が生じるが、白夜の中でも燃え続ける森林の映像は気候変動の目撃者であり責任者でもある我々が記憶にとどめておかなければいけないであろう。
カナダの火災が鳥に与えた可能性: How Do Wildfires in Canada’s Boreal Forest Affect Birds Across the Continent? (Audubon の記事)。
カナダのような北方林では地上に出ている森林自体のバイオマスはそれほど大きくないが、長年にわたって堆積した土壌のバイオマスをどこまで燃やしてしまったのかが問題となる。例えば 10 年分の堆積物を燃やしてしまえば過去 10 年に森林吸収で固定された CO2 を一気に放出したことになる
[Shingler (2023) What the trees are telling us]。
人新世 (Anthropocene。wikipedia 日本語版に十分読める解説がある *1) に代わる用語といて "Pyrocene" (火の世紀) を提案している研究者もあるほどである (Welcome to the 'Pyrocene,' an Epoch of Runaway Fire *2)。
Byrne et al. (2024) Carbon emissions from the 2023 Canadian wildfires によれば 2023 年のカナダの森林火災で放出された CO2 は世界の大国の年間放出量に匹敵 (アメリカ、中国、インドのみが上回る)。
2050 年代には 2023 年の特異気象は当たり前になっていると予測され、カナダの森林が炭素吸収源にならなくなる恐れがある。
もはや CO2 吸収源でないアマゾン森林 Trounle in the Amazon (Daniel Grossman 2023 Aug. Nature のオープンアクセス記事) より部分抄訳:
2010-2018 年の観測でアマゾン南東部はすでに CO2 排出源になっている
ことがわかった。違法伐採なども横行しており、温暖化と合わさって
tipping point (*2。ここでは生態系のレジームシフト regime shift のことを主に
指しているようである) を迎えるのではないかと 2016 年に予測されていたが、
新しい観測はその兆候を示している。20-30 年で見られるだろうと予測
していた変化がすでに始まっている。
森林から劣化したサバンナへと後戻りできない遷移が進むと見られる。
気候変動のペースを落とし、伐採を止めて劣化した土地を回復することで
でアマゾンをまだ救うことをできるのか、との問いに対する答えの中
には可能であるの文言もあった、ぐらい。
アマゾン森林で CO2 吸収が減少した要因の一つに、過去数十年の間は
大気の CO2 濃度上昇の結果、植物の CO2 吸収も高まっていた効果が考え
られるが、この効果は一時的なもので、数年しか続かなった実験結果も
ある。
気候変動がアマゾンに与える影響を初期の研究では過小評価していた
ようだ。アマゾン全体としてはまだ tipping point には達して
いないが、到達はもう時間の問題かも知れないことを確信している。
tipping point という用語を使うのはあまり好きでないが、アマゾン
を調べている研究者の多くは深刻な問題があること点では一致している。
2019-2020 年に保護のための法律が弱められた時に猛烈な勢いで
破壊活動が行われ、地域の CO2 排出は倍増した。
林を調査するための塔に登るとまだ熱帯林が見渡す限りに広がって
見える。しかし熱帯林は病んでいるのだという。「我々は直接的、間接的に
生態系を殺しつつあるのです。これほど恐ろしいことがあるでしょうか。
ここへ来るたびに林が死んでゆくのを観察し、涙が溢れてくるのです」
しばらく前、現在の温暖化は太陽活動によるもので、むしろ太陽活動がこのまま低下してミニ氷河期に入ることを心配せよとの話があったことを覚えておられる方もおられるだろう。
例えばその一例: Cap Allon (2020)
Professor Nils-Axel Moerner: 'The approaching grand solar minimum and little ice age conditions'。2030 年に予想される寒冷化に備えよ、と 2020 年に予言。
太陽活動が強くなったら今度は Record number of sunspots observed in June has solar scientists worried
この記事ではミニ氷河期とか信じているやつらはまだ残ってるかね、と皮肉つき。あくまで個人的印象だが、メディアではよく取り上げられるが太陽関係に近い物理・天文学者による気候変動への言及はあまり信用する必要はないと思っている (単なる対立仮説の提唱以上に人為起源温暖化論の根からの懐疑者がかなり含まれていた/いると思っている)。
地球温暖化に言及する場合に、これらの見解にわざわざ気を使って控えめに記述する必要はないだろう (*3)。
衛星データを用いて大規模森林火災が世界規模で圧倒的に増えていることが示された: You're not imagining it: extreme wildfires are now more common。図は消失面積ではなく発生した熱を測定したもの。
北方林の森林火災が特に増えており、20 年で 7.3 倍になった。
温暖化との関連は直接は述べていないが、間接的な影響の理由はいくつもある。夜間に温度が下がらないことで火災が収まりにくいとのこと。
2019-2020 年に大規模火災のあった地中海沿岸、オーストラリアではまだ長期傾向は明らかでないが、傾向が現れるのは時間の問題と考えている。
2020 年に船舶の硫黄酸化物排出制限が設けられた結果、確かに船舶航行経路の大気汚染の減少が観測されたが、特に北半球の温暖化に影響を与えている可能性: Gettelman et al. (2024) Has Reducing Ship Emissions Brought Forward Global Warming?。
Kim et al. (2024) Abrupt increase in Arctic-Subarctic wildfires caused by future permafrost thaw
永久凍土が解けることで北極から亜北極地方の森林火災が非線形的に増えるモデル計算。2030 年ごろには永久凍土の表面温度が 0°C に達し、2050 年ごろにはこの温度が 1-3 m まで達し、表面の水分が地中に潜って表面は乾燥化が急に進む。乾いた土は熱容量が小さいので大気温度の上昇が簡単に起きて湿度も低下する。突然の変化は数年で起き得る。
土壌の水分が 40% 減少すれば7月の西シベリアやカナダの温度が 5°C 上昇し、一方アラスカは温度が下がる結果が得られている。
大気中に増えた CO2 を植物が固定すればそれは新たな火災のための燃料となる。
Geyman et al. (2024) Permafrost slows Arctic riverbank erosion 永久凍土が河川による侵食を抑えているが、完全に融解すると北極圏の河川流量は 30-100% 増すと推定された。
Kazlou et al. (2024) Feasible deployment of carbon capture and storage and the requirements of climate targets
気温上昇を 1.5°C に抑えるには程遠いが、CO2 回収・貯留技術 carbon capture and storage (CCS) で 2°C 上昇に抑えるためには 2000 年代の風力発電と同様に大規模な導入が必要で 2040 年代には石油ショックで 1970-1980 年代に原子力が体験した以上の増加率が必要である。
過去の他のプロジェクト達成率を考慮するとなかなか厳しい要求水準である。
なお現在十分使える技術は発電時などに発生する CO2 を回収するもので、大気中の CO2 を吸収する有望な技術はまだまだである (still in their infancy と言われる)。
Don’t overshoot: why carbon dioxide removal will achieve too little, too late (Nature editorial 2024.10.9) にも関連記事があり、一時的に上限を超えただけでも影響は長期に及ぶ可能性がある:
Schleussnar et al. (2024) Overconfidence in climate overshoot。
Overshooting global-warming limits is a risky idea (Nature news 2024.10.9) 一時的に超えても将来の CO2 吸収技術で引き返せるとの考え方は甘い可能性が示唆されている。
Thirumalai et al. (2024) Future increase in extreme El Nino supported by past glacial changes
氷河に残された過去の気候の解析により 1982, 1997, 2015 年に起きたような極端なエルニーニョ振動は気候変動によってより頻繁に起きるようになると考えられる。
壊滅的な気候変動の影響を避けるためには 1.5 °C 上昇に抑える緊急の対応が必要である。
急速に "緑化" の進む南極半島: Roland et al. (2024) Sustained greening of the Antarctic Peninsula observed from satellites 衛星観測のデータから。
2000 年以前はほとんど見られなかったが 2015 年以降は特に顕著。南極とは思えない光景になっている。外来種などの侵入を促し生態系への脅威となる可能性がある。
Jones et al. (2024) Global rise in forest fire emissions linked to climate change in the extratropics
(Global CO2 emissions from forest fires increase by 60 per cent 一般向け英文解説。2001 年以降熱帯以外の森林火災による CO2 排出は 60% 増えた)。
Jarvis and Forster (2024) Estimated human-induced warming from a linear temperature and atmospheric CO2 relationship 南極氷床データと CO2 濃度との相関関係から 2023 年時点で産業革命前より +1.49(+/-0.11) °C 上昇と見積もられ、すでに 1.5 °C の目標を超えてしまった可能性がある。
Reich et al. (2024) High CO2 dampens then amplifies N-induced diversity loss over 24 years
24 年の研究から高い CO2 濃度は窒素量の増加と合わさって草地の生物多様性の減少をもたらすことが判明。植物にとって栄養が増えることは優占種を選択的に増やす可能性がある。
Rodell et al. (2024) An Abrupt Decline in Global Terrestrial Water Storage and Its Relationship with Sea Level Change
地球観測衛星によって大陸の淡水含有量が減少し乾燥化が進んでいることが判明。2014-2016 年のエルニーニョ現象以降が淡水のレベルは低いままとどまっている。極端な降雨があっても地下水として蓄えられず流れ去ってしまう。また温暖化によって大気が水蒸気を蓄えられる容量が増えた。大陸の淡水のレベルが 2015 年以前に戻るかどうかは不確かだが、最も気温の高い年が続いていることと突然生じた乾燥化は偶然の一致ではないと考えている。
Sippel et al. (2024) Early-twentieth-century cold bias in ocean surface temperature observations
1900-1930 年代の世界の温度はその後に比べて低めで、太陽活動との相関がしばしば話題になっていたが、海と陸のデータを用いて再構成してみると過去に言われていたほど低くない結果になった。
地球温暖化の太陽活動起源説を唱える人たちはしばしば 20 世紀後半の太陽活動の活発化を取り上げるが、この研究によれば根拠がさらに薄くなった印象を受ける。
2023, 2024 年の夏の猛暑は記憶に新しいが、日本も "熱波" に見舞われた地域と認識されている: Kornhuber et al. (2024) Global emergence of regional heatwave hotspots outpaces climate model simulations 最近の日本も含め、このような地域的な熱波の出現は気候モデルを上回るペースで起きている。
Heuze and Jahn (2024) The first ice-free day in the Arctic Ocean could occur before 2030
夏に事実上氷のない北極海の状態は 2030 年代にはほぼ間違いなく起きるおそれがある。早ければ 2027 年ぐらいにも発生する可能性がある。+1.5 °C の目標達成を維持できるならばこの事態が発生しない確率はゼロではない。
Goessling et al. (2024) Recent global temperature surge intensified by record-low planetary albedo 2023 年の高温はこれまでの理屈だけでは説明できない部分 (約 0.2 °C) があり原因が調べられてきた。
低緯度帯で雲の量が減衰して太陽光を反射する効率が落ちたためではないかとの推論。一般向け英文解説。
低い雲は日光を反射するので温度を下げる効果があるが、大気上層の水蒸気量 (または雲) が増えると温室効果ガスの役割を果たすので同じ雲でも地球温暖化への寄与は異なっている。
環境汚染物質規制で大気に放出される人為起源のエアロゾル (雲形成の核になる) が減ったことは原因の一つとして考えられが、それだけでは説明できないのではないか。地球温暖化によって低い雲が減少するフィードバック効果を予測している研究がある。もしそうであれば将来もっと強烈な温暖化が起きることを考えなければいけない。これまでのモデルで予想されたより早く +1.5 °C に達してしまう可能性がある。
Earth shattered heat records in 2023 and 2024: is global warming speeding up? (Nature news 2025.1.6)
2023, 2024 年の高温は一時的なものか、それとも科学者の予想以上の地球温暖化の加速傾向を示しているのか。2024 年 12 月の American Geophysical Union (AGU) の会合でエルニーニョ効果と汚染物質の減少だけで説明できるのか議論がなされた。
Earth breaches 1.5 °C climate limit for the first time: what does it mean? (Nature news 2025.1.10)。
2024 年の公式発表で +1.55 °C。+1.5 °C の目標を決めたパリ協定は 2015 年 (10 年も経っていない!)。1年ではあるが初めて目標を超えた。+1.5 °C は政治的目標であって数値には特別の意味があるわけではないが、目標達成のためにはさらに厳しい努力が求められることを意味する。
Saros et al. (2025) Abrupt transformation of west Greenland lakes following compound climate extremes associated with atmospheric rivers
2022 年秋の高温以降グリーンランド西部の湖は CO2 吸収源から発生源に急激にシフトした。
Terhaar et al. (2025) Record sea surface temperature jump in 2023-2024 unlikely but not unexpected 2023-2024 年の海水温が 2015-2016 年に比べて 0.25 °C 高かったのは現在の温暖化モデルのしミューレーションでは 500 年 (95% 信頼区間 205-1185 年) に1回ぐらいの確率と見積もられ、モデルの範囲で不可能な現象ではなかったが、もし地球温暖化がなければ事実上不可能とのこと。
図では 2023-2024 年の日本東方は世界でも最も顕著な異常高温であったことがわかる。
気候モデルでは 2020-2021 年に逆の傾向が現れており、地域レベルの異常高温を予測することは現在でもまだ難しいことがわかる。2023-2024 年の記録では日本より南方、東南アジアでは顕著な温度異常はなく、夏鳥にあまり変化がなかったのはそのためかも知れない。
秋は異常高温で出発をためらった鳥もありそうな気がするが、本来の渡り時期に渡ってしまえば行く先ではそれほど暑くなかったかも。
Data centres will use twice as much energy by 2030 - driven by AI (Sophia Chen, Nature news 2025.4.10) データセンターが世界の電力の 1.5% (2024 年) を占め、AI 用が 24% で急成長中とのこと。
再生可能エネルギーで賄おうと考えればおそらく必然的に風力や太陽光発電を大幅に増やす必要があるだろうが、今後は「AI は野鳥の敵」と言えることになるのかも。
Web-scraping AI bots cause disruption for scientific databases and journals (Diana Kwon, Nature news 2025.6.2) 悪質な "ボット" が匿名 IP から世界の学術サービスや論文誌などを食い物にしている。技術力の限られたところでは攻撃に対応できず消滅せざるを得ないところも。
いくつか事例はすでに見聞しており、音声データベースの xeno-canto も何度も悩まされており、その都度管理者が対応しているが、そのために割く労力は知的資源の無駄遣い以外の何者でもない。発信元と推測されるものに「さもありなん」と思える大手サービスも挙がっていた。
xeno-canto の Latest News June 6, 2025 に妨害の歴史と現状が触れられていた。ブロックしても規則を無視してくぐり抜ける、サーバー機能を向上させても相手も向上させるなどいたちごっこ状態になっている。
学名の原記載調査などに用いている複数のサービスもしばしば機能停止が発生しているが、同様の理由ではないだろうか。
Is a monster web of ocean currents headed for collapse? The race is on to find out (Tim Kalvelage Nature news 2025.6.18)。大西洋南北熱塩循環 (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) の減退に関する研究の現状。
観測が始まってからまだ 20 年程度で結論を出すには至っておらず、現状は物理モデルと組み合わせた推定が行われている段階で研究者の見解も分かれている。兆候が誰の目にも明らかになった段階では手遅れかも知れないが...。
Xu (2025) China's fossil-fuel challenge - how to build a bridge to renewables (Nature news 2025.7.22) 現在世界最大の CO2 排出国である中国のエネルギー事情の現状。再生可能エネルギー比率を高めたいが不安定性や天候要因に悩まされており、化石燃料に頼らざるを得ない。2024 年段階で再生可能エネルギーは 19% にとどまっている。
Liu et al. (2025) China reins in the spiralling construction costs of nuclear power - what can other countries learn? (Nature news 2025.7.28) アメリカやフランスでは原発の建設コストが上昇したため 1990 年代に新設をほとんど取りやめたが、中国では自国で供給網を確立するなど低コストに抑えている (あくまで建設コストの評価で、各国の比較は為替レートやインフレーションにも影響を受けるので注意せよとある)。2030 年までに中国は世界最大の原子力エネルギー利用国になるだろう。
1990 年代から 2005 年ごろはフランスの技術を原型として独自の開発を進め、福島事故後はアメリカやフランスとも共同研究してより安全性の高い炉を採用したとのこと。韓国は中国に似た建設コスト削減方法に成功したが、フランスはアメリカ型から離れて自国独自の型を採用したためコストが増大したなど分析されている。
原子力エネルギーの利用には賛否あるだろうが現状分析として紹介した。
備考:
*1: 自分が最近改めて気候変動問題に関心を持ったきっかけは 2023年1月にエクソンモービルが 1970 年代にすでに現在のものに近い気候変動モデル計算の結果を知っていたにもかかわらず隠蔽して地球温暖化を否定していたことが明らかになったことによる [Supran et al. (2023) Assessing ExxonMobil’s global warming projections]。
もちろんそれ以前にも十分関心を持っており 2000 年代冒頭に地球温暖化問題が大きく取り上げられたのもフォローしていた。
2000 年代冒頭に科学者たちは結果は 10-20 年もすればもっと明らかなものになるだろうと予言していたが、現在まったくそのようになっており、例えばパリ協定が目標を達成できないことは誰の目に明らかになってきている。2000 年ぐらいからしっかり取り組んでいれば現状も違ったのかも知れないが...時すでに遅しの感がある。
「人新世」wikipedia 日本語版に地球温暖化問題の技術的な解決策としてジオエンジニアリング (climate engineering, geoengineering) が紹介されている。太陽光を反射して気候を冷却する太陽放射管理と二酸化炭素の吸収が挙げられているが、工業規模の大規模な二酸化炭素の吸収技術はいまだなく、地球温暖化問題の解決に間に合うとは考えにくい。
太陽放射管理の技術的に有望なアイデアとして成層圏エアロゾル注入 (SAI) があり、これは現在の技術で実現可能な範囲にある。しかしながら wikipedia 日本語版にも書かれているようにさまざまな予期不能な副反応が考えられ、世界的な合意も得られるか疑わしい。
またこれは対症療法に過ぎず一度始めると少なくとも数百年単位で続ける必要があるという (数百年という数字はそれ以上長期の数値計算ができなかったためで、長期の数値計算が行えるようになるとさらに必要な期間が伸びているようである)。
途中で中断するとそれまで以上の地球温暖化に襲われるとのこと。
また開始後例えば数十年は恩恵を受けられず逆に高温に襲われる地域もあるとの計算結果もある。
SAI を本格的に用いたとしても「今すぐ始めない限り」南極の氷床コアの融解を最終的に防げないとの研究もある [Sutter et al. (2023) Climate intervention on a high-emissions pathway could delay but not prevent West Antarctic Ice Sheet demise]。
現在技術的に一番有望視されているのは硫黄酸化物の散布であるが、役割を終えると硫酸の雨が降ることになり、いずれにしても酸性化は避けられそうもない。生態系への影響もまったくわからないが他に考えられる方法がほとんどないので単なる地球温暖化の生態系への影響以外にもこのような適応策の影響も検討しておく必要があるだろう。
数百年あるいはそれ以上、「空というものは昔は青かった」と伝えられる時代が来るのであろうか。
地上の光の天文学はこのような形で終焉を迎えるのであろうかと天文学のメーリングリストで真面目に議論をしたこともある。
昔の人の出した CO2 と格闘するために成層圏までジェット機を飛ばして硫黄酸化物の散布を続けるのだろうか。
再生可能エネルギーへの移行はもちろん必要不可欠のものであるが、そのために必要な金属資源の量は人類がこれまでに採鉱した量を超えており、そもそも短期間で地球規模でエネルギー源を電力に移行することが可能か疑う専門家もある。電線に必要な銅についてすでに peak copper (意味は下記 peak oil 参照。ただし鉱物とエネルギーは別物なのであくまで類似の用法) の概念がある。
Mark Mills: The energy transition delusion: inescapable mineral realities: 電気自動車で問題が解決できる幻想を示している (ここでは電極材料のコバルトなどを特に問題としている)。
自分が地球温暖化など環境問題に関心を深めていた 2000 年代前半に環境関連でよく話題となっていたのは peak oil (石油ピーク) で、従来よく言われていたような「石油枯渇」(埋蔵量を消費量で割って後何年もつなど計算するなど) の印象は間違いで、
より重要なのは {生産されるエネルギー}/{投入したエネルギー} [= かつては energy profit ratio (EPR) が使われていたが、現在は energy return on investment (EROI) の用語がよく使われるようである]
(wikipedia 日本語版では "エネルギー収支比" の項目だが英語版の方が情報豊富)
であり、EROI が下がってゆくことが根本的問題。EROI < 1 になればもはやエネルギー資源ではない。
これを無視した議論が世の中ではよくなされているので多少なりとも環境に関係する、あるいは関心を持つ者は知っておくべきであろう。
"peak oil" が問題になっていたころ、いわゆるシェールオイルが使われ始めており、EROI = 1.4-1.5 などの数字 (wikipedia 英語版より。当時の数字は多少違っていたが) を見てため息をつくしかなかった。こんな資源に依存している文明など考えられない...。
太陽光発電は当時は低かったが現在はかなりよい数字になっており 8.7-34.2 (30 年寿命の場合。算出の根拠となる日照時間などは日本の場合と異なるかも知れないが) と書かれている。
風力は同じ資料で 19.8 となっている (日本語版では 5-54 とある)。
風力発電は投入エネルギーに見合うエネルギーを生み出せないとの主張は誤りと言える。
当時は気候変動よりも peak oil がむしろ話題となっていたが、現状では化石燃料の EROI 低下よりも温室効果ガスの排出量限界によってある程度以上の化石燃料を使えないことの方がより大きな制限となっているようである。
メタンハイドレートも一時期話題になったが結局使えないだろう。
この EROI の概念は原子力発電にも適用できる。発電時 CO2 を出さないとして原子力発電の推進が進められているが、もし世界のエネルギー需要を原子力発電のみでまかなったならばどうなるかの試算もある。
こちらも peak oil 同様の "peak uranium" が発生し、ある見積もりでは 2089 年までしか十分な資源がないとのこと (Peak Uranium and the Sustainability of Nuclear Energy)。
もちろん現在は再生可能エネルギーが大きな割合を占める状況になりつつあって (日本は遅れているが) この通りにはならないであろうが、原子力発電に頼ることのできる期間は人類史的には極めて限られたものである基礎資料として知っておいてよいだろう。福島原子力発電所の事故の後は語られたが忘れ去られているかも知れない。そして核廃棄物の問題もいつまでも残ることだろう。
核融合については解決困難な問題がいくつもあるが、Nature の最新ニュースに現状の紹介があるので参考までに: Conroy (2024) Inside China’s race to lead the world in nuclear fusion。
*2: ここで用いられている runaway は「暴走」の意味。
「暴走」と "runaway" は日本語英語ともいくつかの少しずつ異なった語義がある。
日本語では車や機械の暴走、少し古い時代の PC を使われた方はコンピュータの暴走 (現在でも CPU 温度が上がりすぎて異常動作を起こすことを熱暴走と呼ぶこともある) などを思いつかれるだろう。
科学、特に物理学や工学ではもう少し限定した意味で用い、何かが起きた結果それがさらに起こりやすくなる現象 (正のフィードバック、例えば温度を上げると反応が強まるような場合、反応で出た熱で温度が上がってさらに反応が強まる場合など) に使われる用語。
暴走温室効果 runaway greenhouse effect のような表現は温室効果ガス濃度がある程度を超えると例えば水の蒸発が強まって強力な温室効果を持つ水蒸気が空中に増え、温室効果がさらに強まるような正のフィードバック現象を指す (いったんこの暴走が始まってしまえば介入の余地はほとんどないゆえに恐れられているものである。
気候問題ではこのような正のフィードバックは複数のメカニズムによるものが知られていて臨界点は tipping points と呼ばれる。いくつかの tipping points はすでに超えてしまっている可能性もある: Climate tipping points are nearer than you think - our new report warns of catastrophic risk)。
この意味では日本語と英語 runaway ともまったく同じように用いられ、科学の文脈ではこの意味で用いれば理解に曖昧さがなく安全である (他にも「逃走」の意味で使われることもある)。
車や機械の暴走は上記の正のフィードバックではなくても日常用語として用いられており、英語辞書にも runaway の語義の一つのようである (昔の辞書にはなかったので最近使われるようになったのかも知れない)。
この記事の "Runaway Fire" は後者の広い意味の暴走を指しているかも知れないが、森林火災が温室効果ガスを増やし、結果的に森林火災をさらに増やす正のフィードバックの意味も込められているのであろう。
正のフィードバックによる "runaway" は生物学でも、特に進化生物学で時々現れる。#エトロフウミスズメの備考 [信号の進化と性選択] にあるフィッシャーのランナウェイ過程 (Fisher's runaway process of sexual selection; runaway hypothesis; Fisherian runaway) は正のフィードバックを考えたもので物理学などと同じ概念である。
wikipedia 英語版によれば Fisher (1930) に the speed of development will be proportional to the development already attained, which will therefore increase with time exponentially, or in a geometric progression
の表現があるので指数関数的、あるいは幾何級数的に形質が進化することを述べており "runaway" を正しく表現していることがわかる。Fisher はこのアイデアを 1915 年に提唱し、Fisher (1930) 自身が "runaway process" と呼んだとのこと [Gayon (2010) Sexual selection: Another Darwinian process]。
日本語書籍では例えば巌佐「数理生物学入門」(共立出版 1998) 17 章で扱われており、「セクシィな息子」仮設の死などの項目ではランナウェイ過程が現実的に働かない批判やどのような条件下ならば働くかなどの解説がある。数学を扱っている以上読みやすい本ではないが...。
物理学などでいつごろ導入された概念かはわからないが、Fisher のものは用例としてかなり先駆的なものであったかも知れない。
*3: ミランコビッチ・サイクル 他の項目で種分化年代に関係して wikipedia 日本語版を見ていたところ ミランコビッチ・サイクル (Milankovitch cycles) に対してかなり怪しげな説明がなされていることに気づいた。地球の公転運動の計算の難しさはさすがにないだろう。Milankovitch (Milankovic 原語に基づく表記の場合) の時代は計算機もなかったのでもちろん大変だったわけだが。
英語版の方がまだよいがあまりまとまりがよくない、実は Milutin Milankovic (現在のセルビアで死去) の wikipedia 英語版ページ Milutin Milankovic に彼がどのような着想に基づいて研究を進めたかよく記述されていてむしろわかりやすい。
概略を説明したページや本を読むよりまずこのページをおすすめする。
基本的には天体力学の基盤から始まり、日射量の惑星への影響を考察したのがその次。氷河期の周期性を天
文学的要因から説明しようとしたアイデアが斬新であったことがわかる。検証段階を経てこの着想が本命であること確かめつつ Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf das Eiszeitenproblem (1941) を出版した経緯となる。
この本が英訳され Canon of insolation and the ice-age problem として出版されたのが 1969 年。ここでも何度も登場の Dement'ev and Gladkov (1951-1954) が英訳出版されたのと同じ翻訳プロジェクト (Israel Program for Scientific Translations) による。
ちなみにこの翻訳プロジェクトは (現在のネットには関連する記述が見当たらないが) おそらくスプートニク・ショックなどで先を越されたアメリカが、当時のほとんど知られていなかった東側諸国の科学文献を収集・翻訳したものではないかと想像する。この想像が本当であれば、Dement'ev and Gladkov のソ連の鳥の英訳版が読めるのはこのおかげとも言えるのかも。
日射量と気候の関係や応答の非線形性などは現在も深海堆積物や氷床アイスコア材料やモデル計算をもとに多くの研究が行われているが、惑星レベルの天体力学の部分 (軌道離心率の変化、後に述べる公転面の変化など) には不定性が事実上ないことは押さえておいてよいだろう。あまり議論するまでもないのである。第一近似はここまでで十分。
ミランコビッチは極点の移動にも注意して Milankovitch's theorem (ミランコビッチの定理) も導いている。ケチを付ける部分がない。
地球全体としては外部 (慣性系) から見れば回転軸が変わるわけではないが、アイソスタシー (isostasy) の平衡状態に近づくために地殻の移動が起きて地球表面の観測者には自転軸が移動するように見えるとの説明を残したとのこと。
この影響は小さなもので事実上影響がない。外部の天体の重力の影響による地軸の変化と混同してはならないと wikipedia 英語版 Polar motion のページにある。
一般的な解説で忘れ去られているように思えるが、地球の公転面が太陽系の公転面であるとの地球中心主義とも言える誤解がある。太陽系全体で見ればもちろん木星・土星の運動が支配的で、その面から傾いている地球の公転面の向きや角度が変わってゆくことになる。この効果が地球上の観測者からどのように見えるか考えるとよい。
Invariable plane (不変面。日本語版でもよい) の数字が参考になる。木星の影響が最も大きく、木星の公転軌道はこの面から 0.5° 以内とのこと。現在の地球の軌道は 1.57° 傾いているので軌道の向きが変わるとミランコビッチ・サイクルの説明に出てくる地軸の傾き 22.1 - 24.5° の変化に対応することになる。
さらに詳細を知りたい方は Secular evolution of planetary orbits に解析的な (数値計算に対比した表現) 近似で地球の軌道離心率や軌道面の傾きの変化 (この計算では 2.95°) が導かれている。この変動 (secular evolution 永年進化。これも天体力学の用語) のタイムスケールが 5 万年のオーダーであることも説明できる。
Muller and MacDonald (1997) Spectrum of 100-kyr glacial cycle: Orbital inclination, not eccentricity に the inclination of the earth's orbit to the invariable plane of the solar system, should be associated with the 100-kyr glacial cycle と本質を的確に表現した解説がある。
wikipedia 日本語版の "10万年問題" のページで "不変面" が出てくるところを見ていただけば完全に間違っていることがわかる (2025.1 時点)。当時何が議論されていたか理解されていなかった可能性がある。wikipedia 英語版が訳されて要約されている感じだがこちらも間違っている。ということは引用されている Hays et al. (1976) が間違っているのか? (オープンアクセスでないので確認できない)。
ミランコビッチ・サイクルが 1970 年代に再評価されたらしいが、ここまで見ると "不変面" が (天体) 力学の概念であることを理解して議論している人がほとんどいなかったのではないか? 何とミランコビッチ・サイクルの理屈そのものも理解されていなかったということか...。
Muller and MacDonald (1997) を見てみると、惑星間ダスト云々というのは Culbe (1987) の説で、この論文内ではむしろ逆説的に取り上げている。極めつけはその次で、Hoyle and Wickramasinghe (!) が惑星間ダストの降着が温室効果を生み出して...という部分。
このあたりの人名を見てピンと来られる方もあるだろう。本稿では#ミフウズラ備考に登場する始祖鳥化石を否定し、パンスペルミア説を推進し、宇宙の元素合成を唱えたにもかかわらず宇宙の進化も生物進化も否定してしまったという当人である。もしこれらの説を前面に出して語られていたとしたら、氷河期の周期性の天文学的要因説は天文学者の怪しげな説として片付けられていても不思議でない。
Hoyle and Wickramasinghe はこんなところでも困ったことをしていないのだった。少なくとも一般の理解を遅らせたことは間違いないだろうし、今でも誤った認識の由来の一つとなっていると考えられる。
wikipedia 英語版の解説や参考文献引用はこれら背景を理解しておらず、Muller and MacDonald (1997) 論文そのものの論理もおそらく読めていない。参考文献が表示されているからといって信頼性が高い記述とは限らない好例である。
Milutin Milankovic の wikipedia 英語版ページの研究経歴を読んで、彼がなぜこの順序で考察したかも推測してみよう。火星や金星への影響をまず検討し、知りたい地球がなぜ出てこないかと言えば火星や金星は大きな衛星を持たない (金星は衛星を持たない) ので、自転軸の向きの扱いが単純で天体力学の応用を最初に示すのに好適だったからであろう。
もちろん火星や金星に水があるか興味が持たれていたことはこのページの示す通りだろう。
また彼が地球の北緯 65° に注目した理由も理解できる。この値は {90° - 地軸の傾き} であり、地軸の傾きの変動による影響が最も現れやすい緯度となる。氷河形成に関わる当時の知見や提唱されていたアイデアを組み合わせて論理体系を構築したことになる。
ちなみにミランコビッチ・サイクルのもう一つの構成要素である歳差運動 (precession。地球の北極の向きが天空上で変化することなど。こまの味噌すり運動) も天体力学で解析的に導かれる (Forced precession and nutation of Earth)。
太陽だけを考慮すれば 79400 年周期となるが月の引力を取り入れると 24800 年と導かれ実測値もよく再現する (わずかな違いは細かな近似が入っているためとのこと)。
北半球・南半球のどちらの夏がより日射を浴びるか歳差運動で変動する。これは地球の公転軌道が楕円であるため、太陽により接近する時期 (近日点) が現在は南半球の夏にあたるが歳差運動の半周期後には逆になる。
Milankovitch (Orbital) Cycles and Their Role in Earth's Climate (NASA の解説ページ)
によれば地球の公転の長軸の方向が変わる周期と組み合わせると平均 23000 年の周期性となる。この部分は wikipedia 英語版の解説でよい。
公転の長軸の方向が変わるのも天体力学の効果で、このページでは一般向けの比喩的表現となっている。apsidal/perihelion precession 近日点移動などの概念がある。他の惑星の重力により複雑に軌道が変わり...とうやむやに理解されがちだが、ケプラーの法則のように公転の長軸の方向が変わらないのは中心力が逆二乗則に従う場合。この法則から外れると公転の長軸の方向が変化する。
Perihelion precession of planets に取り扱いがある。
近日点移動は十分遅いので、他の惑星は同じ質量の太陽まわりのリングの重力場をもたらすと考えて扱ってよい。Gauss (天文学者・数学者のガウス) が扱った方法。
(しばしば「木星の公転の方向にひきずられて地球の軌道方向が移動する」タイプの説明があるがこれは正しくない)。この方法で求められた水星の近日点移動速度と実測値の違いを説明することが一般相対性理論の検証材料の一つとなったのは有名な話。
この歳差運動は地軸の傾きの変化 (実際には地球の軌道面の変化) をもたらすものではなく別の効果である点も注意。ミランコビッチ・サイクルの要因のうちでは歳差運動はそれほど主要な要因ではないと考えられている。
ミランコビッチ・サイクルは大変天文学的な話だと思うが、現代の宇宙の科学を扱う日本語教科書などであまり見かけないのもある意味不思議である。スーパーフレアなどは好んで取り上げられているようだが、もっと大きな現象を説明する理論、かつ現代の喫緊の課題である気候変動問題の理解にも関わるので天文学の成果としてもっと取り上げられてもよい気がする。
あるいは懐疑感も残っているのだろうか、それとも天文学の話題とあまり認識されていないのだろうか。
ミランコビッチサイクル と日本天文学会の天文学辞典を見ても天文学の記述の部分がずいぶんあっさりしている (2025.1 段階)。天体力学のような他の項目との関連性を示してこそ専門団体の用語集にふさわしいのだが (まあ内輪みたいなものなので気軽につぶやいておこう...)。
火星で少なくとも表面に生物が住めなくなった要因: Kite et al. (2025) Carbonate formation and fluctuating habitability on Mars
地球では少なくとも 35 億年生物が住める状態が続いているが火星ではそうならなかった。その理由を説明する仮説。液体の水が炭酸塩を形成して封じ込められてしまう考えが提唱されているが、その過程を火山による CO2 放出を加えて現在知られている知見で再現しようとしたもの。
太陽の進化によって光度が増した効果、火星軌道のカオス的ふるまいも重要要因となっていて、これらの要因が複合的なフィードバックを形成して死の惑星となった。経緯は過去の地質学的歴史に刻まれているはず。断続的に生物が住める状態が存在したと考えられるが、連続的なものとはならなかった。条件が水の三重点 (気体・液体・固体が共存できる点: 273.16 K = かつては 0 ℃の定義とされた、611.657 Pa = 0.006 気圧程度) に近づくと液体の水の安定性が低下して生物が住める環境も不安定となった、とのシナリオ。
-
オジロワシ
- 学名:Haliaeetus albicilla (ハリアエエトゥス アルビキルラ) 白い尾の海鷲
- 属名:haliaeetus (m) 海鷲またはミサゴ (halos 海 aetos ワシ Gk)
- 種小名:albicilla (合) 白い尾の (albus (adj) 白い cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい -cilla についてはセキレイ科も参照)
- 英名:White-tailed Eagle
- 備考:
haliaeetus はミサゴの種小名と綴りが1文字違う。ee が並ぶため ae が2重母音とみなされ a は長母音にならない。アクセントはこの位置にある (ハリアエエトゥス)。
Kesller (1851。参考文献参照) を見ると古い学名ではギリシャ語から転記の際にワシを表す語尾の -aetus の ae の e の上に点を2つ付けている ("トレマつき e" と呼ぶとのこと。この表記は現在でもたまに見られる。通常の e とは音が違う。イヌワシの種小名でも同様)。
ミサゴの種小名とオジロワシの属名はもともとの綴りでは同じで、記号を省く際に aae とするか aee とするかの扱いの違いが生じたらしい。前者では a を長音とした -aetus、後者では ee を重複させる代わりに a を短音とした -aeetus の表記となったものと推定できる。事実上どちらも同じように発音してよさそうで、"アエ" 全体で長母音的に少し伸ばして発音すると原音に近くなりそう。
albicilla はすべて短母音で -cil- にアクセントがある (アルビキルラ)。
de Savigny (1809) による属記載時学名は Haliaeetus nisus (参考で、nisus はハイタカの種小名に現れるようにタカ類を指す。
オジロワシの Falco Albicilla Linnaeus, 1758 (原記載) に新属を与えるとともに改名したもの (#ノスリの備考参照)。この種のみを指していたため自動的に Haliaeetus 属のタイプ種となる。
de Savigny によるフランス語名は L'Aigle de mer (海のワシ)。現在でもドイツ語では Seeadler がそのままの意味の名称となっている。他言語でもいくつか例がある。
興味深いことに現在のフランス語名は Pygargue a queue blanche と "山ワシ" と "海ワシ" を大幅に使い分けている (尾の白い海ワシの意味)。ヒメハイイロチュウヒの学名が Circus pygargus であることをご存じの方もおられるだろう。現在のオジロワシ類のフランス語名を見るとチュウヒ類に見えてしまうのである。
Pygargus Koch, 1816 はハイイロチュウヒを指して与えられたもの (Pygargus dispar Koch, 1816 と改名) であったが、
Pygargus vulturinus Forster, 1817 (参考) と Forster がオジロワシを Pygargus 属に編入する [どこが似ているのか!? と思えるが Linnaeus (1758) では連続した項目に現れる] とともに改名を行った結果による。"ハゲワシのようなハイイロチュウヒ" の学名になっている。
de Savigny (1809) の属記載が発見されたのが後の時代になったようで、Pygargus の属名に先取権があると考えられていた時代には Pygargus vulturinus Forster, 1817 由来の学名がオジロワシにそれなりの期間使われていたよう。
チュウヒ類の Circus は de Lacepede (1799) が早かったので Pygargus の属名は結局どこにも残らなかったが、オジロワシ類のフランス語名やスペイン語などのラテン系統の言語にかつての痕跡を残している。
スウェーデン語の havsorn は hav (海) orn (ワシ) 由来でドイツ語名と同じ意味。デンマーク語やノルウェー語でも同様。ポーランド語の bielik は "白いもの" を指す。
Kaup (1844) Classification der saeugethiere und voegel では Falkenseeadler (タカまたはハヤブサのような海ワシ) に分類されていた。
参考までに当時使われていた命名時の学名で Falco pondicerianus Gmelin, 1788 (参考) 現在のシロガシラトビ Haliastur indus Brahminy Kite は Weihenseeadler でトビのような海ワシ。
Kaup (1844) はこちらに Selby が提案した Haliastur の属名は適切でないとして Ictinoaetus 属を提案していた。Kaup がオジロワシやオオワシをどのように捉えていたかわかる資料となっている。
[オジロワシ属の系統分類]
ノスリ亜科 トビ族 Milvini オジロワシ属とウオクイワシ属の現代的な系統分類を示す。ウオクイワシ属も含んでいるのは (広義) オジロワシ属に含まれていた (いる) ため。
ノスリ亜科内での位置は #トビの備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] を参照。トビ族中で最後のグループになる。
これまでと同様 Catanach et al. (2024) の順序による。(2023 年 preprint 版と順序が少し異なっていたので入れ替えた)
ノスリ亜科 Buteoninae
オジロワシ属 Haliaeetus
オジロワシ Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
ハクトウワシ Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle
オオワシ Haliaeetus pelagicus Steller's Sea Eagle
キガシラウミワシ* Haliaeetus leucoryphus Pallas's Fish Eagle
ウオクイワシ属 Icthyophaga
マダガスカルウミワシ* Icthyophaga vociferoides Madagascar Fish Eagle
サンショクウミワシ Icthyophaga vocifer African Fish Eagle
ソロモンウミワシ* [高野 (1973) ではサンフォードウミワシ] Icthyophaga sanfordi Sanford's Sea Eagle
シロハラウミワシ Icthyophaga leucogaster White-bellied Sea Eagle
コウオクイワシ* Icthyophaga humilis Lesser Fish Eagle
ウオクイワシ [高野 (1973) ではハイガシラウオクイワシ] Icthyophaga ichthyaetus Grey-headed Fish Eagle
Brown (1976) ではこの位置に ヤシハゲワシ Gypohierax angolensis Palm-nut Vulture を置いている。Vulturine Fish Eagle の別名のように当時はウミワシ類の異端と考えられていたが、現在はヒゲワシ亜科 Gypaetinae に移動: #ハチクマ [ハチクマ類の系統分類] を参照。
例によって系統が離れるところに空白行を入れてある。
オジロワシ属はかつてこれらがまとめられていて、ウオクイワシ、コウオクイワシのみを分けて Icthyophaga 属 (ikhthus, ikhthuos 魚 -phagos 食べる Gk) と長年呼ばれていた。
Catanach et al. (2023) ではオオワシとキガシラウミワシが系統を作り、オジロワシ + ハクトウワシ のクレードと並ぶ形になっていたが、2024 年版で逆順となった。それぞれ2種で2系統を作るので順序は任意性があるが、オジロワシ系統からオオワシやキガシラウミワシが種分化したのか、あるいはオオワシやキガシラウミワシは遺存的なのか解釈も微妙に反映されている印象を受ける。
オオワシやキガシラウミワシの分布が限られていることから個人的にはこちらの方が遺存的な印象を受けるが、このリストは 2024 年版に従ってオオワシの方が後に並ぶ形となった。
オジロワシ属とウオクイワシ属の順序も入れ替わっていて、これも2分岐なので任意性があるとは言え、ウミワシ類が熱帯地域起源と考えればウオクイワシ属の方が前になる順序がよい感じがする。
古いが参考: Seibold and Helbig (1996) Phylogenetic relationships of the sea eagles (genus Haliaeetus): reconstructions based on morphology, allozymes and mitochondrial DNA sequences。
この文献で使われた情報は古いが、他のタカ類の起源もアフリカなど赤道地域のものが多いので、この系統でも北東の種類ほどより derived (派生した) ものと考えるのは理にかなっているように思える。
Catanach et al. (2024) の現在の配列順ではオジロワシの出所が不明になる感じがする。IOC 15.1 ではこの部分は 2023 年版を用いているようでオオワシ、オジロワシの順になっている。一方オジロワシ属とウオクイワシ属の順序は新しい方が採用されているようでどうも扱いが一貫していない。
2023 年版を用いて暫定版を作ったものの 2024 年版に変更する際に作業もれがあったのかも知れない。
2024 年版に忠実に従えば上記リストの順序となる。
この2種は近縁だが Haliaeetus 属に内包されるために属名を変え、全体でオジロワシ属とする扱いがしばらく続いた。IOC で言えば 3.3-13.1 の期間である。
IOC 13.2 になって上記オジロワシ属と別系統をなす上記ウオクイワシ属系統を Icthyophaga 属と呼ぶことになってごく最近学名が変わった。
全体を Haliaeetus 属としても単系統であることには変わりはないので、このあたりは属をどこで区切るかの問題である。Catanach et al. (2024) では IOC 13.2 で変わる前の分類となっている。
IOC 14.2, Clements/eBird ともに Icthyophaga 属を採用。Working Group Avian Checklists, version 0.02 以降も同様でおそらくこちらに統一されると思われる。
AviList (2025.6) では Icthyophaga 属を採用。
8474 360 Haliaeetus is split into two genera based on genetic evidence. Mindell et al. (2018) identified two deeply divergent clades based mostly on mitochondrial DNA sequences: a northern Haliaeetus group consisting of the species leucocephalus, albicilla, leucoryphus, and pelagicus; and a southern Icthyophaga group consisting of the species leucogaster, sanfordi, vocifer, vociferoides, humilis, and ichthyaetus. A two-genus arrangement is also supported by genomic DNA data (Catanach et al. 2024).
単系統性の要請によるものではなく分離の深さによるもの。
個々の種でみれば元の学名に戻ったもの (ウオクイワシ、コウオクイワシ) や慣れた学名が変わったもの (シロハラウミワシ、サンショクウミワシなど) がある。いずれにしてもどれも最近の変更なので過去に知った学名が変わっていないか注意が必要である。
ウオクイワシがタイプ種であり、日本でも知名度がある種類なので属名和名はこれを採用した
(2種だけだった時代もウオクイワシ属だったはずだが分類概念が変わっている)。世界的に見るとサンショクウミワシの方が知名度が高いかも知れない。
オジロワシ属は何種か、なども時代によって変わったことになる。ウオクイワシ類などの画像検索などでも学名が変わったことを意識して複数探さないとうまく見つからないかも知れない。
オジロワシ属の中でもオオワシは少し孤立系統になるが分岐年代はそう古くない。ご存じの通り、このグループでも世界分布が非常に限られている。オジロワシとハクトウワシは分布も広く、系統もそれなりに近い。
キガシラウミワシは南から東アジアの他、夏鳥としてユーラシア内陸部のステップ地域やシベリアにも生息する種類で渡りも行う。個体数は少ない。Raptor Research & Conservation Network (2018) "A Field Guide to the Raptors of Asia" によればかつては広範に分布していたが現在の分布は限られている。かつての分布は文献の図の印象をもとに判断されていた可能性があり、Dement'ev and Gladkov (1952) でも広範な分布が示されているが、分布は散発的であることが述べられていた。
遺伝情報は不十分だがこの系統に属すると考えられる。
先述の解説の通りキガシラウミワシとオオワシは比較的近い関係にあり、オジロワシの主な分布の外縁部に生息している。このような系統関係にあるものが地理的に遠い地域に限定して生息しているのは#セグロセキレイや#ルリカケスの事例でも見られ、かつて少し古い系統が広域に分布していたがその後卓越した系統が現れて大部分置き換わってしまった経緯が考えられる。
セグロセキレイの項目でセグロセキレイのような少し大型の種類のみが残っている可能性を考察したが、大型のオオワシとオジロワシの関係にもあるいは当てはまるかも知れない。旧系統のうちで大型のオオワシが残り、オオワシ自身に十分な漂行能力があるが、オジロワシの方が生態的に優位で、オオワシはオジロワシの優勢な地域に分布を広げることができなかった可能性を考えることができる。
オオワシが沿岸部で魚食にかなり特化して生き残った一方、オジロワシは食物の範囲が広く内陸環境への適応度の高さも生態的優位性につながっているのだろう。
通常の分布より南 (本州) で越冬するオオワシの越冬地への執着性の高さも、あるいはそのような種間競争の結果選択された生存のための形質なのかも知れない (オオワシはどこでもやって行ける種類ではおそらくない)。
そういえばかつて川内で越冬していたカラフトワシが毎年同じ場所に戻ってくるのも Aquila 属内での生態的弱さを補うための戦略であると考えれば納得できる感じもする。
オジロワシと分岐して北米に分布を広げたハクトウワシの場合は海ワシ類の既存の競争相手はなかった。イヌワシと競合する部分があるがイヌワシより生態的に優位であるとのこと (#イヌワシ備考参照)。
キガシラウミワシは IUCN EN 種で 2500 羽未満とのこと。生態的も弱いようでオジロワシの主な分布域より南側に限局して細々と散発的に生息している模様。遺伝情報がまだ不十分なため狭義 Haliaeetus 属と Icthyophaga 属をつなぐ位置にある種類かどうかは不明だが狭義 Haliaeetus 属では最も南に分布するのでその可能性もありそうに思える。
キガシラウミワシの遺伝情報は2遺伝子しか調べられておらず (GenBank 2025.4 段階)
Z73469.1,
AY987135.1 のいずれから出発して BLAST を行っても狭義 Haliaeetus 属の中で最も古い系統となる。前者の遺伝子ではオオワシと系統をなし、後者ではキガシラウミワシが独立した古い系統になる。この場合でもオオワシが {オジロワシ + ハクトウワシ} に比べて古く分岐した系統になる。
今後全ゲノム解析が進めば系統関係がもっとしっかりしたものになるだろう。
これらを考慮するとこのグループ内の配列は Catanach et al. (2023) と IOC 15.1 の中間的なものが妥当に思える。
高野 (1973) のハイガシラウオクイワシは英名に忠実な名称、ウオクイワシは学名の意味を表したものになっている。
英名は亜種 plumbeiceps Baker, 1927 (鉛色の頭) に由来と思われる。
Falco Ichthyaetus Horsfield, 1821 の (記載 でミサゴ類の1種としていた) は当時すでに種として認められており、その亜種扱いで記載された。
亜種まで含めて学名を英語に訳せば Grey-headed Fish(ing) Eagle となって不思議でない。英名が亜種を指しているとすれば確かにウオクイワシの名称の方が種和名にふさわしいかも知れない。
東南アジアや南アジアに生息して我々にも馴染み深い種類である。映像検索などをするとシンガポールに有名な撮影地があるらしく多数の動画が撮影されている。
種小名の ichthyaetus は ikhthus, ikhthuos 魚 aetos ワシ (Gk) とほとんど自明のことを表しているだけだが、実はこれがややこしいのである。同じ名称の属名がカモメ類にあって Ichthyaetus は日本産の種でもオオズグロカモメ、ゴビズキンカモメ (オオズグロカモメ属) に現れる。
どこかで見たような学名だなあと思っていると、実は綴りまでまったく同じなのである。検索時は要注意。
「魚を食べるワシ」はオオズグロカモメ属よりウオクイワシ属の方がふさわしいと思えるが、経緯は #オオズグロカモメの備考参照。
ややこしいことに同じ属名はかつてミサゴにも使われたことがあった。要するに考えることは誰も似たようなものと言えるわけだが。
さらにややこしい話としてこれまた同じ意味の属名で綴りが1文字違うだけの Ichthyophaga がウズムシ綱にあった。
Sluys and Kawakatsu (2005) A Replacement Name for Ichthyophaga Syromiatnikova, 1949 (Platyhelminthes: Prolecithophora), with a Nomenclatural Analysis of its Avian Senior Homonym
によれば、ウオクイワシ属で用いられた方が早かった (Ichthyophaga Lesson, 1843) のだが、その後は誤記で1文字短い学名が正当化されないまま使われてきておりその扱いが問題となっていたとのこと。鳥類学者がもし原典を重視して Ichthyophaga Lesson, 1843 が正しいと変更するとウズムシ綱の属名が使えなくなってしまう恐れがあった。
混乱を防ぐために Sluys and Kawakatsu (2005) はウズムシ綱の属名を
Piscinquilinus に改名する提案を行ったが反対意見も強く、ICZN が 2017 年最終的に別名であるとの裁定を下した (wikipedia 英語版より)。ウズムシ研究者側が名前を譲る提案があったものの、ウオクイワシ属の学名は実はここまでは必ずしも安泰ではなかったことになる。
学名の面白い歴史の側面の一つと言えるだろう。
このグループではアフリカのサンショクウミワシが有名だろう。英名の方は素っ気ないが、サンショクウミワシの和名は色をよく表しているとそのまま使われてきているようである。ワシ類では色鮮やかな種類で人気も高い。他言語で同様の名称は見当たらないので日本独自の命名の模様。
種小名に使われる vocifer は騒々しいの意味 (#イカルチドリの備考参照。カタグロトビの国内初記録当初の亜種名にもあった)。
ビデオ映像などでサンショクウミワシの「雄叫び」を見ていただければ納得いただけるだろう。行動を見るとオジロワシやハクトウワシ、オオワシに系統が近いことも理解できる。
しかしながら Fish Eagle に対応するものを "ウミワシ" としているために海岸に生息する印象を持ってしまう。実際は主に内陸の種で淡水魚を主に食べている。オジロワシと同属であった時代の命名で属名をそのまま訳せば和名はそのようになるが、生態を必ずしも反映していないことは注意が必要であろう。
これは#イソヒヨドリが Monticola 属だから山に住む解釈するのと同じような問題。属は系統を表すもので習性などと必ずしも対応するわけではない。オジロワシを代表とする Haliaeetus 属の一部が内陸に住まないわけではないのも同様。
"ウミワシ" よりは Fish Eagle の方が指す範囲が広いので英名の方はある意味融通がきく。
このように考えると和名の "ウミワシ" の起源も多少気になってくる。これは特にオジロワシを指して使われていた Sea Eagle (White-tailed Sea Eagle) を訳したものではないだろうか。この時代のオジロワシの英名はある意味学名そのままである (どちらが先かはわからないが)。現在のオジロワシの標準的な英名からは "Sea" が落ちているが、オオワシの方には残っている (分布からこちらは適切と言える)。
ウオクイワシ類の Icthyophaga 属は早くから分離されていて 高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) でも別項目となっている。これらに fish eagles の名前を与えるために、Haliaeetus 属は sea eagles と分けざるを得なかったのであろうか。
現在標準的な英名で Sea Eagle の残っているのは Haliaeetus 属ではオオワシのみ。Icthyophaga 属の方にむしろ多くあって、これらはかつて Haliaeetus 属だったが分子系統解析で Icthyophaga 属に移動となったもの。
現在のところ日本産種ではないので、英名で Fish Eagle で "ウミワシ" の和名の付く乖離の目立つものは系統関係も確定した現在、和名再検討の価値があるかも知れない。
Ferguson-Lees and Christie (2001) では Haliaeetus 属と Icthyophaga 属を分けて扱っており、前者に Fish-eagle、後者に Fishing-eagle の名称を使い分けていた (その結果あまり標準的でない英名が使われていると言われる要因となっている)。"Sea Eagle" は意図的に避けたものと思われる。
積極的な試みだったとはいえ、分子系統解析の結果は入り組んでしまい使い分ける価値が薄れてしまった。
シロハラウミワシはアジア南部からフィリピン、インドネシア、オーストラリアにかけて分布する海ワシで、これも我々に近い地域に生息している。和名、英名ともに学名そのままだが見た目もその通りである。
(ミサゴを除けば) オーストラリアに分布する唯一の海ワシ。南米にはこれらグループ (広義オジロワシ属) の種は分布せず、ミサゴノスリが対応する役割を果たしている。
ソロモンウミワシはシロハラウミワシとほぼ同種レベルに遺伝情報が近く、分離したのは 20-30 万年前ぐらいと推定される (wikipedia 英語版より)。1935 年に記述されるまでシロハラウミワシの幼鳥と混同されていたとのこと。
いずれも大型で見応えのある種類なので画像や映像を検索して確認してみていただきたい。
[亜種と生物地理学]
オジロワシの現存の亜種は基亜種 albicilla とグリーンランドの亜種 groenlandicus が有効とされている。日本の亜種は前者に所属。
Hailer et al. (2007) Phylogeography of the white-tailed eagle, a generalist with large dispersal capacity によれば基亜種 albicilla とされる旧北区に広く分布するグループは2つの個体群に分けられ、氷河期にユーラシアの少なくとも2か所のレフージアで生き延びたと考えられるが、いずれも太平洋岸ではなかったと考えられる。
太平洋岸には氷河期後にヨーロッパから分布を広げて定着したと考えられる。氷河期に太平洋岸に残らなかった理由として、生態学的により優位なオオワシとの競争が考えられるがはっきりしない。
氷河期におけるこの生物地理学はセグロカモメ類に対して提唱されているものと似ているとのこと。オジロワシはさまざまな食物を利用できるジェネラリストで分散能力が高いことが次のハワイの絶滅 (亜) 種やこの分布にも現れている。
分子遺伝学的にはグリーンランドの個体群を亜種と強く示唆する結果は得られなかったが、解剖学的に差があるとの報告があり、地理的にも隔離度の高い個体群であるため亜種としての扱いを続けることは保全上の意義もあると考えられる。
[ハワイの絶滅 (亜) 種]
ハワイにもかつて海ワシ (英名 Hawaiian eagle) がいて 3500 年前の骨格標本がある。この個体は洞窟に残っていて、出られなくなった個体が亜熱帯でありながらよい保存状態で残っていたものらしい
[Fleischer et al. (2000) Identification of the Extinct Hawaiian Eagle (Haliaeetus) by mtDNA Sequence Analysis];
Hailer et al. (2015) Distinct and extinct: Genetic differentiation of the Hawaiian eagle]。
系統的にはハクトウワシよりオジロワシに近い。オジロワシの絶滅亜種とするか Haliaeetus属の別種とするかはまだ情報不足のよう。10 万年以上はハワイ諸島で生息して頂点捕食者であったと考えられるが絶滅原因は不明。後者の論文にはハクトウワシ、オオワシを含む系統樹が出ている。ハワイのワシ類については#イヌワシの備考も参照。
兄弟殺し (#イヌワシの備考参照) の映像もある。この例ではかなり成長したひなを巣から落としてしまった。
オジロワシとイヌワシの種間関係については#イヌワシの備考も参照。
小宮 (2018)「野鳥」2008年12月号 (No. 830) pp. 24-25 に大型猛禽類の足拓が紹介されている。
体の大きなオオワシ、オジロワシはイヌワシよりも小さく、トビやカラスと一緒にゴミを漁るオオワシは大きなトビか、とある。なおトビの足はハイタカより小さいとのこと。足サイズの特徴は現代の分子系統的な位置づけとよく合っている。生態的な優位性は体のむしろ大きさを反映しているように見えるので面白いところ。
Shevetsov and Ilyukh (2023)
The collapse of the populations of the white-tailed eagle Haliaeetus albicilla and the imperial eagle Aquila heliaca in the eastern part of Stavropol Krai (pp. 3306-3313)
によれば、ロシア西部のスタヴロポリ地方ではオジロワシは全然心配ないと考えられていたが、なんと 2022-2023 年に壊滅的な個体群の激減があった。カタシロワシ、クロヅル (2500 羽以上)、哺乳類など他の種も被害を受けた。
2022 年の秋が記録的に高温であったため齧歯類に好適な環境となり大増殖し、農家が殺鼠剤を使わざるを得なかった結果らしいとのこと。2023 年も巣の大部分で繁殖が見られなかった。この時代に、と思える事象だが、温暖化の影響が間接的にこんなところにも。
[海ワシ類の眼圧は高い]
Hongjamrassilp et al. (2022) Glaucoma through Animal’s Eyes: Insights from the Evolution of Intraocular Pressure in Mammals and Birds
によれば、オジロワシとハクトウワシの眼圧が高くトビ類は高くなく系統的なもののよう。
ペンギン類は全般に高く、これは潜水に必要なためと考えられる。眼圧の測定されている種類は猛禽類が圧倒的に多いが、フクロウ類は低く、ハヤブサ類やオウム類も同様。タカ類はこれらより高めイヌワシは少し高いなどの結果が出ているが広義ハイタカ属・チュウヒ類もそれほど高くなく、むしろノスリ類にやや高い種類がある。
高い視力を必要とする系統の眼圧がやや高めの印象を受けるが、ハヤブサ類が低いのはちょっと意外。
ヒトは高い方には入っていない (哺乳類で高い系統はいくつかあり、海に住むもの、ウマやサイ、イノシシなど)。こちらは視力とはあまり関係なさそう。
ダチョウが中程度だが、大きな目を支えるために多少圧力が必要なのかと感じた。
この論文ではこれらの眼圧の高いグループに緑内障抵抗機構があるのでは想像している。
[オジロワシは美味?]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 82 I の知床半島の取材記事 (上田) で、現地の方がかつてはオジロワシの2卵めのひなを失敬して飼育すると放し飼いでき、呼べば餌を食べにやってくるほどになったという。
飼育するとホウレンソウも喜んで食べたとのこと。
冬場は与える餌がなく人が育てたオジロワシは自分で魚を捕れないため食用にしていたとのこと。オジロワシの肉はうまかった、シマフクロウはもっとうまかったと別の方が証言されていた。
この記事は当時進行中の知床半島の国立公園 (1964 年指定)、観光地化と開発の問題を取り上げたもので、密猟監視人の言葉によれば数が減ったのは剥製目当ての密猟、カメラマン、いたずらするハイカーによるもの。特に車で来る人がひどかったとのこと (道路を作ったので自然が破壊された、あるいは入りやすくなったとはおそらく立場上言いにくい)。取材記事なのでいずれの証言や立場もある程度誇張されて表現されていたかも知れない。
今から振り返ると世界的にも数が減っていた時期で、オジロワシは今では回復が著しい (地域によっては成功しすぎている?) 種なので、この時代の延長線上で物事を考えない方がよいかも知れない。シマフクロウに比べてタカ類の適応力の高さも感じられる。
-
ハクトウワシ
-
オオワシ
- 学名:Haliaeetus pelagicus (ハリアエエトゥス ペラギクス) 海の海鷲
- 属名:haliaeetus (m) 海鷲またはミサゴ (halos 海 aetos ワシ Gk)
- 種小名:pelagicus (adj) 海の
- 英名:Steller's See Eagle
- 備考:
haliaeetus は#オジロワシ参照。
pelagicus は -la- にアクセントがある (ペラギクス)。
pelagos (海) が語源で英語にも pelagic などの同じアクセント位置の単語がある。
英名の Steller はドイツの博物学者 Georg Wilhelm Steller に由来 (ドイツ語読みであればシュテラーとなる)。ロシアやアラスカを探検した。
鳥にあまり詳しくない人に英名で説明すると stellar (星の) とよく勘違いされるので、わかりにくそうであれば Steller が人名であることを補うとよい。アメリカであればステラーカケス (英名 Steller's Jay) はよく知られている。
この話が見事に出ていた: Yet another thread on eponyms... But this one might actually be fun! Steller を Stellar と書き間違える人がしばしばあるとのこと。
Falco leucopterus Temminck, 1830 (翼に白いところのあるワシタカ類) の学名があり日本で記載されたものだった (資料)。"white winged eagle" の記述が 1824 年にあるとの記載が wikipedia 英語版にある。上記資料より早く登場したようだが、
参照されている図版ではフランス語表記 Aigle leucoptere で解説と学名は次ページにある。図版と本文の出版年が異なっていれば図版のみには学名が現れないので記載年の扱いの相違の原因となっているかも知れない。
Aquila pelagica Pallas, 1811 (原記載) 基産地 Islands between Kamchatka and America の方が早かった。
Falco imperator Kittlitz, 1832 の学名 (資料 1, 2) もあった。
東洋特産の種類なのですでに記載があることに気づきにくかったのかも知れない。
オオワシを指して与えられた Thalassoaetus Kaup, 1844 の属名があった。thalasses 海 + aetos ワシ (Gk)。記載。ドイツ語名 Bussard oder Geierseeadler でノスリまたはハゲワシ型の海ワシと表現していた。
現代のドイツ語名では Riesenseeadler と巨大な海ワシの意味。
Kaup (1844) が海ワシ類をどのように分類したかはこの前のページを参照。ほぼ 1-2 種ごとに属名が与えられており、属分割されても使える属名がたくさんある状態となっている。{オジロワシ + ハクトウワシ} と別属にされることはおそらくないと思われるがその場合でも使える属名が存在することになる。
Kaup (1844) は種小名を与えなかったがこの属名を用いた学名が存在して Thalassoaetus macrurus Menzbier, 1900 (Dement'ev and Gladkov 1952)。macrurus は長い尾の (Gk)。楔形の尾が確かに目立つ。
ユーラシアの北側に事実上どこにでもいるオジロワシ及び北米のハクトウワシと比べてオオワシはロシアと日本の固有種と言ってよい。もちろん繁殖地を訪れることは容易ではないので世界のウオッチャーも日本を訪れるわけである。
オオワシと {オジロワシ + ハクトウワシ} の関係の考察は#オジロワシ備考の [オジロワシ属の系統分類] を参照。
豆知識としてオオワシのロシア語名も紹介しておこう。beloplechij orlan で「肩の白い海ワシ」の意味で (和名も英名もそうであるが) 大して凝ったものではない。
Dement'ev and Gladkov (1952) は別名 kamchatskij orlan とともにこの名称は正しくない (白い部分は肩ではない。またカムチャツカのみに生息するわけではない) として tikhookeanskij orlan (太平洋の海ワシ) の名称を見出しにしていたが「肩の白い海ワシ」の方が知名度が高くて残ったらしい。
ロシア語では山ワシと海ワシを呼び分ける。前者が orel (アリョールと読む。なぜそんな読み方になるかと思えるような綴りだが、ロシア語の読み方を少し勉強すればすぐわかる。複数形は orly アルルィ でアクセントは後ろに。これまたなぜ形がそれほど変わるのかと思うが、規則をちょっと知るとそれほど難しいものではない。もちろん英語と同じように R と L の音の区別があり、R を少し巻舌っぽく読めればロシア語らしく聞こえる)、後者は orlan (アルランと読む。アクセントは後ろに)。オオワシのロシア語での読み方はベラプレーチイ アルランとなる。
ワシとタカの区別が曖昧なのは分類学でも現実の言語でも同じで、ロシア語ではクマタカもワシになる。khokhlatyj orel ハフラーティ アリョール となって、「冠のあるワシ」(その前に「山の」または「東方の」を付けることもある。冠のあるワシの種類はたくさんあるためであろう)である。
[オオワシの遠方への漂行]
ハクトウワシが北海道で記録されたことは有名だが、逆にオオワシも 2022-2023年 北米を訪れ、各地を漂行しているようである [
Steller's sea eagle sighting in N.S gets stellar reaction from bird watchers (表題で Steller と stellar をもじった表現がなされていることに注意);
Pease et al. (2023) The Steller's Sea-Eagle in North America: An economic assessment of birdwatchers travelling to see a vagrant raptor]。
「野鳥」2024年7・8月号 (No. 571) p. 57 の会員フォーラムに 1994年11月でオオワシ成鳥とオジロワシの若鳥に出会った記事がある。クジラの周囲にそれらしい足跡もあったとのこと (大澤氏)。
ハワイの#イヌワシ迷行例 [亜種と遺伝子からみた保全・長距離の迷行例] などを考えれば驚くべきことではないのかも知れないが。
[亜種]
オオワシの亜種として朝鮮半島で記録されて 1968 年以降観察記録のない niger (「黒い」の意味)が提唱されており、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では当初この亜種を認める立場だったようである。
亜種 niger は朝鮮半島で留鳥であり、尾以外に白い部分が認められないとのことである。
亜種 niger に該当すると考えられる飼育個体がドイツの Bayerischen Jagdfalkenhof で 2001 年に孵化し、Tierpark Berlin に移送された。この個体の両親は典型的な通常のオオワシの色彩であり、niger は亜種というより特に暗色の型 (dark morph) と考える方が適切であろうことを示している
[wikipedia 英語版; Kaiser (2011) A living specimen of the dark form of Steller’s Sea Eagle, Haliaeetus pelagicus ("niger") in captivity;
Dark Steller's sea eagle solves 100 year debate (BBC) 肩の白くないオオワシ2個体の写真あり]。
現在は世界の多くのリストで亜種を認めない単形種として扱われており、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種が削除され、単形種の扱いとなっている。
この「亜種」疑いについては、Lobkov and Neifel'dt (1986) Distribution and biology of the Steller's eagle Haliaeetus pelagicus pelagicus
(Pallas) にも詳しい説明があり、極東の鳥類30-1 で和訳が読める。
Dement'ev and Gladkov (1952) によれば記載時学名 Haliaeetus niger Heude, 1887 (niger はいかにもありそうな種小名だが当時 Haliaeetus 属にすでに分けられていたため重複しなかったらしい)、
Haliaetus Branickii Taczanowski, 1888 (参考 1, 2) がシノニムとのこと。
Branickii はポーランドの Wladyslaw Michal Graf Branicki (1848-1914) 由来とのこと (The Key to Scientific Names)。
1952 年当時知られていた朝鮮半島の繁殖情報などは日本のチェックリスト (1932) からとのこと。当時は一般的には亜種扱いとされていたが Dement'ev and Gladkov (1952) はそもそも地域型 (亜種) でも種でもなく色彩変異だと考えており、オオワシを単形種として扱っていた。Austin (1948) によればこのタイプは 18 標本があるとのこと。
[ハヤブサの捕食事例]
大館 (1993) Birder 7(5): 67 にオオワシ成鳥によるハヤブサ幼鳥の捕食例が紹介されている。
[オオワシの形態の特殊性]
日本産のタカ類ではオオワシのみが尾羽 14 枚だが、他に Gyps, Neophron が 14 枚とのこと。Jollie (1976, 1977)
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part II) (p. 38)。
カリフォルニアコンドルは 12 枚または 14 枚だが、14 枚の形質は常染色体劣勢遺伝とのこと: Pryor and Ralls (2017) Fourteen tail feathers: An autosomal recessive trait in california condors (Gymnogyps californianus)。
オオワシやフィリピンワシの大きな嘴を肉を引き裂くための適応と説明されることがあるが、大型のオウギワシやカンムリクマタカでは普通の形状なので、食性への適応ではなくディスプレイのためとの説明が Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" p. 76-77 にある。
オオワシとフィリピンワシの両種の嘴が平たいのは前面視界を確保するためとある。
雪の降った後の琵琶湖のオオワシが山麓にとまっている条件では黄色い嘴で存在がわかることもあり (肩の白さは雪景色では目立たない)、確かに色とともに存在を示すのに役立っている印象を受けた。
[アムール州北部内陸部で見つかり保護された衰弱したオオワシ]
Dugintsov and Ivanov (2024) An emaciated Steller's sea eagle Haliaeetus pelagicus was found in the north of the Amur Oblast (pp. 5219-5220)。
2024.11.14 に Dugda 集落近くで若鳥を発見。この時点で健康状態がよくないように見えた。人が近寄っても逃げなかった。翌朝地上で凍死しかけていたワシを救出し、暖かいところで肉を与えると食べたとのこと。数日でかなり回復し、2024.11.26 に 570 km 離れた Blagoveshchnsk への輸送 (長く困難な道のりだったとのこと) に耐えて獣医学的手当を受けることになったとのこと。いずれ野外に戻すことができるだろうとのこと。
なぜアムール州北部内陸部にやってきたのか。若鳥が食物を求めて漂行中に川に沿って遡っているうちに凍結してしまったのでは。最後の力で集落の近くまでやってきたのではと推論している。
[鳥類、特に猛禽類の鉛中毒]
いくつもの種類が影響を受けているが、よく報道される種類としてここに含めておく。
なぜ鉛中毒が起きるのかなどはよく知られているのでここでは割愛することにして、鉛中毒の生化学的側面を主に取り扱ってみたい。
ヒトにおける鉛中毒は古くから知られていて労働衛生上も大きな問題となり、早い時期から規制が進められるようになった。ヒトではそれほど古くから知られて規制されているのになぜ野生動物では認識にそれほど時間がかかるのか不思議ではあるが、ヒト医学でのエビデンスは他種の直接の根拠として使えないので事例を集める必要があるということだろうか。
単体の鉛はほぼ毒性を示さないが、化合物になると毒性が現れる。
非常に昔聞いた時代には、鉛イオン (Pb 2+) の毒性は生体中のカルシウムイオン (Ca 2+) を置換することによるなど説明がなされていた (そのため骨に影響を与え、重要な所見の一つとされる)。放射性ストロンチウムが生体内ではカルシウムと同じような挙動を示すことは納得できても、鉛のメカニズムとしては納得できるように思えなかった。
仕組みがある程度わかるようになったのはおそらく自分が学んだ時以降のことらしい。wikipedia 英語版を見て知ったのだが、Pearson and Schonfeld (2003) の本に出ているらしい。
-SH 基は酵素の活性中心に広く現れるが、そこに結合しやすいとのこと。化学を多少知っているとこれはなるほどと思える。水素イオン (H+) と水酸化物イオン (OH-) は酸塩基反応の基本だが、これを拡張した広義の酸塩基反応があり、ルイス (Lewis) 酸・塩基の概念がある。ルイス酸・塩基において「軟らかい酸」「軟らかい塩基」の概念が使われる。
HSAB則 (Hard and Soft Acids and Bases) があり、軟らかい酸と軟らかい塩基は非常に結合しやすい。鉛イオン (水銀も同様) は代表的な軟らかい酸で、-SH 基から H+ を失ったもの (チオレート) は代表的な軟らかい塩基である。原子番号が大きいと電子の軌道も広がって (イオンの化学形にもよるが)「軟らかい酸」になる傾向があり、重金属毒性の原因の一部を説明するだろう。
高校の化学で硫化物で金属イオンが沈殿する実験をされた方なら納得いただけるだろう (廃棄物処理の必要があるので最近はこのような実験はあまり行われていないかも知れないが)。
PbS は非常に強固な結合でご存じの通りごく微量のイオンでもすぐに沈殿する。PbS の溶解度積は 8x10^(-28) と極端に小さく、酵素に鉄イオンや亜鉛イオンがくっついていても少量の鉛イオンがあれば化学平衡の原理から優先して置き換わってしまう。
酵素における仕組みはこれでわかった感じがする。古典的なルイス酸・塩基の法則ではこのように推定されるが、Gourlaouen and Parisel (2007) Is an Electronic Shield at the Molecular Origin of Lead Poisoning? A Computational Modeling Experiment
のように、亜鉛イオンが鉛イオンに置き換わることによって酵素活性中心に大きな構造変化が起きることが量子化学計算で示された。
ここで用いられた酵素は δ-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD: δ-アミノレブリン酸脱水素酵素) で、この酵素はヘモグロビンの中心となるヘムの合成に重要な役割を果たしている。ヘムが合成されなければ貧血になるし、レブリン酸がたまれば急性ポルフィリア症のような毒性を示す (wikipedia英語版より)。
この研究はターゲットとなる主要酵素について計算を行ったものだが、鉛イオンの影響はそれ以外にも多岐に渡り、様々な酵素やイオンチャンネルを阻害したり活性酸素を発生させるという。
Gurer and Ercal (2000) Can antioxidants be beneficial in the treatment of lead poisoning?
によれば、やはり -SH を持つ主要抗酸化物質であるグルタチオンと結合することで酸化ストレスを増大させることも書かれている。-SH など由来の「軟らかい塩基」は非常に効率的なフリーラジカルのスカベンジャーである。
微量必須元素とされるセレンも硫黄と同族元素で、生体内の化学形はそこまでわかっていないようだが硫黄がセレンに置き換わったセレン含有タンパク質がある。セレンは一層「軟らかい塩基」でフリーラジカルの強力なスカベンジャーとなる。周期表でもう一つ下のテルルでは金属性 = 軟らかいルイス酸 が強くなってむしろ毒性を示す。
鉛イオンは生体にとって有害な機能しか持たないのである。微量でも慢性中毒になる。
自然界では鉛はほとんど不溶の形で存在し、生物とはほとんど無関係だったのだろう。人が鉱物として利用を始めたゆえに起きた問題である。
毒性の分子機構も徐々にわかってきているようである。他の毒性元素の機序は一般にはそこまでわかっていなくて、例えばベリリウムやタリウムの毒性の項目を見ても大したことは書かれていない。それだけ鉛の健康被害は重大でよく調べられているということであろう。
またルイス酸・塩基の基本的性質はわかっているので研究のよい手がかりにになるのだろう。
wikipedia 日本語版には現時点ではそこまで詳しくは書かれていない。
タリウムによる野生動物被害についてはミヤマガラスが報告されている: 安田他 (2007)
タリウム中毒による野鳥の死亡例。氷山の一角なのかも。
殺鼠剤として使われてきたこともあり、かつてはヨーロッパのフクロウ類や他の猛禽類に高いレベルで検出され、死因と考えられた: Clausen and Karlog (1977) Thallium loading in owls and other birds of prey in Denmark
ちょうどこのころに規制が始まった。
参考までにタリウムの慢性毒性についてはいくつかの作用ポイントがあるらしい: Chang and Chiang (2024) The Impact of Thallium Exposure in Public Health and Molecular Toxicology: A Comprehensive Review
生体に重要な +1 価のイオンの類似物質として、また軟らかいルイス酸の両方が関係しているよう。
例えば -SH を持つグルタチオンと結合することで酸化ストレスを生み出す。
wikipedia 英語版では Lead poisoning in raptors の項目もあって猛禽類の鉛中毒についてかなり詳しい記述がある。基本的にはヒト医学と同じ仕組みが書かれている。
この問題は人が注意して行動するだけでほぼ 100% 防ぐことが可能であると書かれている。
鉛弾に代えて銅弾を用いた場合、90% 以上のハンターは効果は同様または鉛弾よりよいと答えている研究があり、合金も使えるとのこと。
De Francisco et al. (2003) Lead and lead toxicity in domestic and free living birds
が非常に有用なレビューで特徴的な症状や臨床経過なども記されているので引いておこう。
水鳥が小石と誤って飲み込む、猛禽類が獲物と一緒に飲み込むと単体の鉛が pH の非常に低い胃酸で溶ける。胃酸の塩化物イオンは「硬い塩基」なので鉛イオンと結合せず鉛イオンは体内に吸収され生体にとって重要な役割を果たしている「軟らかい塩基」と結合してゆくことになる。この移動は化学平衡の自然な産物である (そこまで論文に書いてあるわけではないが)。
鉛の毒性に関する知見について (厚生労働省) によればヒトの場合 30 μg/dL = 0.3 ppm で神経伝達速度の低下が起き、300μg/dL = 3 ppm を超えるような高濃度の暴露では明瞭に観察される影響として脳症が挙げられるとのこと。
De Francisco et al. (2003) では鳥において 0.2-0.5 ppm 以上で影響が現れる。40 ppm あれば鉛中毒と確実に診断できるとことだが、ヒトの場合と比較するととんでもない高値である。500 ppm では運動機能を司る神経系が障害されるという。8 ppm 以上ならば中毒と診断してよいとの見解もある。
The cloacal feathers turn green as a result of intense green-coloured diarrhoea
総排泄孔の周囲羽毛が下痢により緑色に着色するのは非常に特徴的な症状とある。
ヒトでも "lead lines" と呼ばれる歯肉着色が知られており、メカニズム (例えばポルフィリン代謝など) に共通するものがあるかも知れない (Lead Toxicity - Clinical Assessment Signs and Symptoms)。
音声も変わり、vocal changes (high-pitched honk) とあり実にいたたまれないのだがヒトの症状ではあまり思い当たらない。ヒトでは鉛疝痛の症状が知られていて急性腹症 (acute abdomen の英語の方がニュアンスがわかりやすいかも知れない。急激な腹痛を伴う緊急事態の総称) や虫垂炎としばしば間違われるとある。あるいは耐えきれない痛みを表す声なのかも知れない。
ヨーロッパハチクマで鉛中毒の報告がある。Lumeij et al. (1985) An unusual case of lead poisoning in a honey buzzard (Pernis apivorus)。
食性 (動物の死体を食べる報告は多分ない) からは考えにくいものだったが、臨床所見と X 線所見から鉛を疑い、胃内異物をカテーテルで確認。血中鉛濃度は 80 μg/dL = 0.8 ppm で、極端に高いわけではなかったが鉛中毒と診断した。翼にもう1つ鉛らしき破片があった。
麻酔下で透視下に気管支鏡を入れ、砂嚢にある異物の採取に成功。最初1週間は強制給餌が必要だったが、その後は自分で食べるようになり、予想通り幼虫の入ったハチの巣を好んだという。キレート剤治療を行って2週間後鉛濃度が 16 μg/dL まで下がり、渡り時期も近づいていてすでに成鳥であったため放鳥となった。
折れた風切羽はヨーロッパノスリのものを用いた羽接ぎ (imping) を行った。
通常のルートで鉛の破片が入るとは考えにくく、翼にも弾があったことからこの鳥は撃たれて偶然破片が胃に入ったものと想像される。マガモを使った実験では砂嚢に4弾 (1.4 g) で致死的であるとのこと。
この例では1つでも胃に破片が入ると致死的になり得ることを示すものだろう。
人でも特に関節内など軟部組織で吸収が起きることが知られているが、結合組織に囲まれているうちは無害とのこと。翼の弾は関節と関係ない場所であり、結合組織に囲まれていると考えたため取り除かなかった。
血中鉛濃度は一般的に言われる診断基準よりも低く、血中濃度だけに頼って判断するのは危険である。
それほど酸性度が高くなくてもよさそうなヨーロッパハチクマの胃でも鉛弾を溶かす模様である。
さらにありそうもない例としてオオアカゲラの鉛中毒が報告されている: Morner and Petersson (1999) Lead Poisoning in Woodpeckers in Sweden
原因はよくわからないが散弾が木にささってそれを食べてしまったのでは?
ナミビアでチーターの事例が報告されている: Hauw et al. (2025) Case Report: Acute lead poisoning from bullet ingestion in a captive cheetah (Acinonyx jubatus) in Namibia: implications for wildlife management
捕獲収容はできず、最初の症状が観察されてから 48 時間後に死亡したとのこと。中枢神経症状など猛禽類の場合と似ているように見える。チーターでの報告は2例目とのことで報告された神経症状は似ているとのこと。
Blanchette et al. (2024) Extreme lead tolerance in an urban lizard (preprint)
Cuban brown anole lizard Anolis sagrei (ブラウンアノー。トカゲ) が汚染の高い地域で驚くべき鉛耐性を示したとのこと。これまで脊椎動物で知られている中で最も耐性がある。
鉛暴露で遺伝子発現の制御反応もあまり見られなかった。環境毒に対する耐性は比較的容易に進化できるとのことで Anolis 属もそのような耐性の知られているトカゲ類。
人為起源の都市の鉛濃度のもとで耐性が進化したものかとのこと。Fig. 2 に各種動物の平均鉛濃度が出ているが地上性のものが高い (ワニ類も高いものが知られている)。本来は地上の毒物にほとんど接するはずのない樹上性のタカ類などはそもそも耐性が低いのかも知れない。
では鉛はなぜそのような特性を示すのか元素の性質から少し振り返ってみよう。周期表マニア (科学好きの人はほぼ馴染みであろう) の方ならばご存じだろうが、元素には族があって同じ族では化学的特性に類似性がある (高校化学で習う)。それは最外殻電子の配置によることも多分習う。
鉛は現在の名称では 14 族元素に属する。これがまたピンとこない名称で、古くは典型元素・遷移元素で 4A, 4B 族の名前を使っていてこちらの方が酸化数と合っていて覚えやすかった。族の名称定義の変更によるものなのでやむを得ない。
14 族元素は C (6 炭素) - Si (14 ケイ素) - Ge (32 ゲルマニウム) - Sn (50 スズ) - Pb (82 鉛)。数字は原子番号。で典型元素だとちょうど中央で、原子価は4価が標準。例えば CO2, SiO2 などは酸化数4。
原子番号が大きいと (典型元素では) {最外殻電子の数 - 2} の酸化数が安定になる傾向があって、鉛では +2 が一般的 (PbO2 は非常に酸化力が強い)。この酸化数では最外殻電子が2個余ることになる。鉛イオンの毒性の解説に出てくる lone pair (孤立電子対) というのはこの2個の (s 軌道) 最外殻電子による電子対を指す。
原子番号の小さい元素ではこの酸化数はあまり安定でないので、完全に最外殻電子を奪われたイオンはあまり悪い振る舞いをせず、一般にそこまでの毒性は示さない。原子番号が大きい主に典型元素の重金属でよく見られる現象である。
第3周期元素 + α (18 Ar, 20 Ca) までは非常に単純で、電子の s 軌道と p 軌道に順番に電子が詰まってゆくことになる。この場合は s 軌道と p 軌道のエネルギー差が小さく、炭素などで見られる sp3 混成軌道のような概念がうまく適用できる。高校の化学で系統立って出てくる元素はだいたいここまで、ということになる。
その先は 3d 軌道が存在して、4s が埋まった後それまで同様に 4p が埋まるのでなく先に 3d 軌道に埋まってゆく。これが遷移元素で周期表で一段下がったところに対応する。3d 軌道は 4p 軌道よりも (主に) 内側に存在するので化学反応への関与が弱まり、一般に最外殻電子の数 = 酸化数 とならない。
この辺で法則性が敗れるので高校化学が嫌いになる一つ要因かも。鉄とか銅などの性質を個々に覚える必要が生じるのはこれが原因と言える。4s → 3d → 4p の順で埋まるので、4s (2個) と 4p の違いが発生してくる。
この傾向は第6周期元素 (鉛もここに含まれる) でさらに顕著で、これは 4f 軌道がさらに存在してさらに内側が先に埋まるため。普通の周期表ではこの部分を分けてランタノイド系列としている。
4f 軌道はさらに内側にあって、15 個の元素がほとんど同じような化学的特性が極めて似ているため一つの枠に入れてしまってもよいぐらいであるため。
第6周期元素の 81 Tl (タリウム) や 82 Pb はこの影響を大きく受けて {最外殻電子の数 - 2} の酸化数が安定になる次第
(高校化学は暗記科目的なところが多いが、このような背景にある規則性を知るとずっとわかりやすくなる)。ということで毒性が強くなる理由もこのあたりが背景にある (*1)。
もう一つの要因は、環境問題になるほどの量の鉛が天然に存在することである。もっと希少で高価な金や白金を銃弾に使ったりしないだろう。これにはなかなか深遠な理由がある。元素や周期表に関心の深い方ならば魔法数をご存じだろう。原子核を構成する陽子や中性子がこの数の場合は特別に安定 (エネルギーが低い) になる。
50 Sn, 82 Pb ともにこの魔法数を満たしている。鉛の同位体 Pb-208 は陽子・中性子ともに魔法数で特別に安定である。これが自然界に鉛がかなり大量に存在する主な理由である (もっと原子番号が小さく、量も多くてもよさそうな 78 Pt 白金、79 Au 金 などはずっと少ないので高価ということになる)。
ただしこれだけでは天然に鉛が多く存在することを説明する理由の半分ぐらいしか行っていないだろう。
科学好きで「理科年表」などをよく見られる方なならばお馴染みの放射性元素の崩壊系列がある。
つまりかつては鉛より大きな原子番号の元素がもっと存在したのだが、それらが放射性元素で崩壊するために最終的に鉛か 83 Bi ビスマス に落ち着くことになる。
鉛が終着点になっている理由は魔法数で特別に安定であることに起因するので、前半だけでも半分ぐらいは説明されていることになるだろう。ウラン系列が特に有名で、92 U ウラン、(90 Th トリウム-230) 、88 Ra ラジウム といった名前は有名な放射性元素が並ぶ。終着点が鉛-206である。
昔はウランがもっと多かったのだが崩壊して現在は鉛になっている。他にもトリウム系列があって終着点が鉛-208。あと2系列がある。この原理を利用したウラン-トリウム法は古い方の年代測定に用いられ古生物でもよく知られている。これが鉛がそこそこ豊富にあるもう一つの理由。
この話は地球が誕生した時点で鉛、トリウム、ウランなどの元素が存在したことが前提になっている。もっとも現在も存在するので存在したことそのものは間違いないわけだが、この理由はごく最近になるまで実はわかっていなかった。現在でもよくわかっているかと言えはまだまだと言える。
これも元素に関心のある方ならばよくご存じと思うが、元素は合成されてきたもの。
宇宙の始まりであるビッグバンで 1 水素と 2 ヘリウムが作られ、3 リチウムが少量、4 ベリリウムと 5 ホウ素はごく少量で無視してよいぐらい (現在あるベリリウムやホウ素の大部分は別の過程で作られたもの)。重要な点は 6 炭素は作られなかったこと。つまりビッグバン元素合成だけでは生命は作られない。
ここで宇宙好きの人ならば必ず話題にするだろう3α (トリプルアルファと読む) 反応がある。これはヘリウム原子核3個がほぼ同時に衝突することで起きる核融合反応で、それほど簡単に起きるものではない。
星の内部の高温高密度状態でようやく起きるもので、太陽中心部ですらまだその状態に達していない。ロシア人科学者ガモフにちなむ Gamow peak (または Gamow window) と呼ばれる極めて詳細な条件のもとにようやく進む反応で、もし "物理定数がほんのわずかでも違っていれば" 炭素は作られずに宇宙は終わっていたかも知れない。
この部分が偶然であったか (この場合物理定数は一意に決まるものでなく別の宇宙では別の結果になっている可能性がある)、自然の法則に従う必然であったのか (物理定数を決めるもっと根本的な法則がある) は現代の物理学もまだ答えることができない。
3α 反応で作られた炭素に対する核融合反応は比較的容易に進む。ヘリウム原子核 (α 粒子) が順次反応に加わる反応経路があり、この場合は原子番号が2増える (α 元素と言われる)、原子番号が偶数の元素の方が奇数のものより存在量が多い理由である。
よく知られるように重い星が超新星爆発を起こす寸前では鉄 (および原子番号の近い元素) までが合成されるが、これは鉄 (および周辺) の原子核が一番安定でエネルギーが低く、これ以上核融合が起きてもエネルギーが取り出せないため。これには 28 が魔法数であることも関係している。
鉄までの元素は基本的にこのように作られ、超新星爆発で放出される。我々がしばしば「星の子」と呼ばれるのはこれが由来。
それではもう少し原子番号の大きな元素はなぜ存在するのだろう (鉛の原子場号のまだ 1/3 ぐらいにしかならない)?
この部分の元素合成は主に s (slow) 過程と呼ばれる反応で、やはり星の中、しかも赤色巨星でミラ型変光星のような進化段階、しかもその一部の時期に間欠的に起きる。中性子が豊富に存在する条件で原子核に中性子が捕獲され、質量数が1増える。それが放射性同位体で β 崩壊すれば原子番号が1増える過程になる (他の過程もあるがここでは主なものを示した)。(*2)
このようにして徐々に原子番号の大きな元素が作られて行くが、あるところまで行くと放射性同位体の半減期が短くなりすぎてそれ以上反応が進まなくなる。この過程で作られるのはおおよそ 56 Ba バリウムぐらいで、その先の元素も多少できるが主要な経路ではない。鉛も半分ぐらいはこの経路で合成されたと見積もられている (非常に安定なのでこれ以上は反応が進まない)。
鉛よりも原子番号の大きな元素はこの過程ではほとんど作ることができず、また途中の元素でもこの過程から予測される量と合わないものが多数ある。
これらの元素は r 過程と呼ばれる反応で作られたに違いないと考えられてきた (放射性同位体が崩壊する前に中性子と結合する rapid な過程の r を意味する)。そのような過程が存在しないと元素の存在量が説明できないわけだが、具体的にどこで起きているかはずっとわからなかった。
そういう高エネルギー現象はきっと超新星爆発ぐらいしかないだろうと想像されて (あまり根拠があったわけではないが) 大きな原子場号の元素は超新星爆発で作られると教科書にも長く書かれていた。
この定説を打ち破ったのが 2017 年の連星中性子星の合体が発見である。この現象は重力波としてまず2台の重力波望遠鏡で検出され (GW170817。重力波の信号がわかれば合体した天体の質量がわかり中性子星と判明する)、位置がある程度絞られた方向に明るくなってくる天体が確認されたのである (現在は kilonova の名称がよく使われる。超新星ほどの規模ではないが、ぐらいの意味合い)。
この天体のスペクトル観測によって大きな原子場号の元素が実際に作られていることが確認された。
中性子だけでできたような天体である中性子星が合体すれば、もちろん大量の中性子の中で核反応が進むわけである。
ちなみにアインシュタインの予言した重力波が直接観測されたのは 2015 年 (ブラックホールの合体) のことで、なんと 2017 年には早速ノーベル賞受賞となった。GW170817 の発見はこの受賞の直前のことで、いかに画期的な発見であったかがわかる (*3)。重力波の直接観測ではないがアインシュタインの予言した通りの重力波の効果が見つかっており、これにも 1993 年のノーベル賞が与えられている。
この発見が周期表の歴史を書き換えることになった。現在はウランなどの超重元素はこのように作られたと考えられている。野鳥の鉛中毒もこんなとことで宇宙とつながっているのである。
我々にも馴染みの 53 I ヨウ素 なども (そして有名なところでは白金族元素) はほとんど r 過程反応で作られていると考えられている。連星中性子星の合体がなければ生物が甲状腺にヨウ素を使うこともなかっただろう。
最近のものでは Pognan et al. (2024) Actinide signatures in low electron fraction kilonova ejecta (preprint) があり、超重元素生成の直接の確認はまだ得られていないらしい。生成率はモデルによってかなり変わる。
...と書いていると、これはもともと学名の記事でないのかとお叱りを受けそうなので、元素名と鳥の学名は縁が深いことも紹介しておこう。だいたいは色に関係するもので、学名日本語解説で意味の通じるもの、英語でも似た単語が使われるものは元素との関係は省略し、気になったところには注記してある。
身近な鳥では ノジコ Emberiza sulphurata、ヤナギムシクイ (身近ではないか...) Phylloscopus plumbeitarsus などがあり、意味が共通するものでは カワウ Phalacrocorax carbo、ソリハシシギ Xenus cinereus など。
応用編として「日本産鳥類の学名で元素と共通の語源を持つものを挙げよ」を演習問題としておこう。
Te テルルと Telluraves も共通語源。元素名と共通の語源を持つ英語もたくさんあり、Kr クリプトン と cryptic など。学名の理解にも英単語 (特に専門用語) の理解にも役立つ。周期表や元素の名前は (特に理系の好きな人には) 科学常識の宝庫として知っておくと役に立つことも多い。
備考:
*1: このあたりの話は文字だけではわかりにくいので、電子のエネルギー順位の配置図などを見ていただきたい。s, p, d などの軌道名も多分高校化学で出てくる。フントの規則 (Hund's rules) は高校化学でも習ったような気がする (いずれも昔の教育課程なので今は高校では出てこないかも知れない)。
もし中学・高校生の方がこれを読まれているならば (あまりないかも知れないが...)、今後の勉強の参考にしていただくとよいと思う。
自分が習った時は化学の先生が大変意欲的で、程度が高すぎることも承知しつつこれらの原子軌道に電子がどの順番で埋まるか (構造原理 Aufbau principle というらしい。人名も使われるがこれらの名称は習わなかったと思う) を説明された。そこだけ覚えれば後の理解がずっと易しくなることを伝えられたのだと思う。
これらは (軌道のもともとの名称はスペクトル線の特徴を表すものだが) 量子力学から出てくる概念で、量子力学を学ぶ前の段階ではそのような規則があると知っておけば理解するには十分。高校生でも十分理解できると思う。本格的に知りたい場合は大学で量子力学を勉強すればよいことになる。
実はここに多少の落とし穴がある。これらの原子軌道の概念はおそらく「水素原子の構造」の項目で学ぶこととなる。水素原子の構造は量子力学で厳密に記述できるもので、量子力学の応用なり初等段階の仕上げとして勉強する場合もある。物理学全般で用いられる量子力学では他の粒子なども扱うためにより一般化した形式の話が最初にあって、具体的な水素原子の構造は後の方に出てくる (と思う)。
そして大学でこの順序で学ぶと往々にして途中で挫折するのである。
むしろ化学への応用のために量子力学を学ぶ場合、結合に関係するのは電子だと考えて最初から水素原子の構造を勉強しても構わない。シュレーディンガー方程式を最初のうちに習うが、1個の点電荷と1個の電子だけからなる系として方程式を適用して腕力で計算すれば解が求まり、高校化学で習うことをなるほどと納得できる次第。面倒な数式なので誰かが計算して教科書に書いてくれたものを追いかければよい。
また必ずしも数式を追わなくても、このようにすれば原子軌道が導かれることがわかれば十分。
大学で量子力学を勉強するなら物理学の専門の先生の講義を受けて、となりそうだが、利用分野が化学・生物に限られるならば水素原子の構造や分子を早いうちに取り上げてくれる講義を選ぶとよいだろう。
#ヨーロッパコマドリの備考に出てくる [渡り鳥における磁気定位] の話も同様で、こちらは分子軌道の概念を学んでいるとよく理解できるが、物理の先生は分子軌道をあまり教えてくれないかも知れない。
大学で数学を勉強する場合も同じで、専門の数学者から習うよりも応用重視の先生から学ぶ方がわかりやすいこともある。
*2: 超新星爆発に至る星の進化 (および元素合成) は非常にわかりやすいのでポピュラーサイエンスの本でもよく紹介され、日本にも専門家が多いこともあって日本語情報も多くて知っている人も多いだろう。科学に関心のある小中学生でも知っていても不思議でない。
しかし s 過程による元素合成を説明できる人は相当少ないだろう。内容的にもかなり難しい部分があって一般的には大学生後半か大学院生で扱う題材になるだろう (中性子がくっついて原子場号が増えてゆく部分の説明はわかりやすいが、星の中の特殊な条件でどのように起きているのかを説明するのが難しい)。
天文学を勉強している人 (きっとないとは思うが...) が身近にいれば s 過程について聞いてみていただくとよいだろう。大部分の人はどのように星の中で起きるか説明できないのではないかと想像する。
星の中で元素合成が起きているのは驚くべき発見がきっかけで明らかになったもなので紹介しておこう。周期表を見ると奇妙な「穴」があることがわかる。最初の穴が 43 Tc テクネチウム で、現在は安定同位体の存在しない最も原子場号の小さな元素であることがわかっている。
この穴を埋めるために多くの研究者が捜索を行った。その中には日本の研究者小川正孝による発表もあり、
ニッポニウム (nipponium, 元素記号 Np を提案) と命名したが後に取り消され、幻のニッポニウムとなった。これは当時未発見だった 75 Re レニウムだったと考えられ、日本人による最初の新元素発見のチャンスを失うことになった (wikipedia 日本語版より)。
この元素は 1936 年に加速器によって人工合成され、それにちなんでテクネチウムと名付けられた。
この元素の同位体の半減期はいずれも 420 万年以下で、地球が作られた時代にもし存在したとしても消滅してしまっていることになる。Merrill (1952) "Technetium in the Stars" Science 115, 484
がある種の星のスペクトル中にテクネチウムが存在することを発表した。
参考解説
Elements from the stars: The unexpected discovery that upended astrophysics 66 years ago (Spyrou and Schatz 2018, The Conversation)。
これは星の中で実際に元素合成が起きていて、しかも半減期の数倍程度の時間以内に表面に運ばれていることを示している動かぬ証拠となった記念碑的研究である。
テクネチウムは現代では核医学診断 (シンチグラフィー) で Tc-99m が最もよく使われるなど生活にも関係している。この (準安定) 同位体は β 線を出さずエネルギーの低い γ 線のみを出し、半減期6時間と放射線による影響を最低限に抑えるのに理想的な性質を示すため用いられている。
*3: 最短距離で書けばこのような歴史になるが、科学では往々にして背景に面白い歴史が含まれていることがある。せっかくなので少し寄り道してみよう。
連星中性子星の合体 (中性子星やブラックホールは超新星爆発の産物として有名。少なくとも中性子星は別の生成経路もある) は必ずしも新しい概念ではないが、超新星爆発でできた 20 km ぐらいのサイズの中性子星2個を合体できるほどの距離の軌道に近づけることがそもそも可能なのか長年議論されていた。純粋に理論的にはわからない。実際に見つけるしかなく、ある意味これは空想の産物だったと言える。
理解が進展したきっかけがガンマ線バースト (GRB) の発見であった。これは大気圏内核実験が行われていた時代、核実験監視衛星が偶然発見したもの。地球の方向からではなく、宇宙方向からガンマ線が降り注ぐ現象があることが見つかった (最初の発見 1967 年)。
これは長らく宇宙でもトップクラスの謎の現象で、1970 年代の技術でガンマ線の飛来方向 (ガンマ線の飛来方向を知ることはできなかった (現在でも容易でない)。当時は複数の惑星間探査機による到達時刻の差による三角測量を行った) を確かめても、そこには何も見当たらなかった。太陽系内からはるか遠方の宇宙まで、あらゆる仮説が提唱されたと言って過言でないだろう。
1990 年代に入って事例が増えて GRB があらゆる方向で均等に発生している (等方的) 証拠が高まってきた。これは GRB が近くで起きているか宇宙のはるかかなたで起きていることを示唆する。
当時の日本のX線天文学業界では、銀河系のハローの古い中性子星が起源とのアイデアがあった (これには相応の理由もあったが割愛する)。その中でポーランドの研究者 Bohdan Paczynski (故人) は 1990 年代のデータが出る以前から宇宙論的距離の天体で起きる現象のモデルを提唱し、連星中性子星の合体や超新星爆発を想定していた (1986)。
この考えが正しいことは GRB 970508 (1997年) にX線残光が見つかり、その位置に遠方銀河があることで実証されることとなった。1998 年の GRB 980425 では該当位置の誤差範囲に変わった超新星 (SN 1998bw) が見つかり、やや特殊なケースだったが GRB と超新星の関係が脚光を浴びることとなった。
この時期ごろには GRB 研究は天文学の主流となって GRB の光学対応天体を見つけるさまざまなプロジェクトが始まった。
2003 年の GRB 030329 はその研究の中でも一つの歴史を作ったと言えるだろう。この天体は光で見える残光の中に後日超新星が現れ、GRB と超新星の関連が揺るぎないものになった。
この結果は Nature の特集号となって、我々のグループも一つ貢献している [Uemura et al. (2003) Structure in the early afterglow light curve of the γ-ray burst of 29 March 2003]。筆頭著者は当時大学院生。
なぜかわからないが当時の BBC がうちのサイトの GRB の解説ページにリンクを張って回線がパンクしかけたことがあった。
GRB がガンマ線で観測されていた古い時期から、GRB には2種類あって、大まかには長いもの (long GRB)、短いもの (short GRB) に分けられることが知られていた。超新星との関係が明らかになったのは long GRB の方であった。
それならば short GRB の方が連星中性子星の合体と想像するのは極めて自然であるが、なかなか直接証拠に結びつかなかった。そして本文につながる。合体を起こすような連星中性子星が実際に存在することが証明されたのである。
GRB の話は生物絶滅と関連して語られることもあり (ほんとうかなあ?)、
Melott et al. (2003) Did a gamma-ray burst initiate the late Ordovician mass extinction?。
少しアンテナを張っていただくとよいかも知れない。(大部分の人は生物を知らない) 天文学者のこういう話は面白半分のことも多いのであまり真に受けない方がよいだろうと思う。
"Dark Matter and the Dinosaurs: The Astounding Interconnectedness of the Universe" (Lisa Randall, HarperCollins 2015) という本も出ていて、Randall and Reece (2014) Dark Matter as a Trigger for Periodic Comet Impacts
で preprint も見ることができる (Physical Review Letters, accepted) 注の "no dinosaurs" は報道で話題になって見にきた人に "恐竜のことは書いてありません" の意味か。
太陽系が銀河系円盤を横切る時に大絶滅が起きるタイプの説は昔からあって Schwartz and James (1984) Periodic mass extinctions and the Sun's oscillation about the galactic plane はなんと Nature 論文。
この手の話はほぼ眉唾で聞いておくのがよさそうだが、物理学雑誌では面白いと思えばアイデアだけでも評価される点は評価してよいのだろう。
脱線ついでに宇宙・天文にちなんだ話をもう一つ紹介させていただくと Alfaro et al. (2024) Ultra-high-energy gamma-ray bubble around microquasar V4641 Sgr (2024.10.16)
[arXiv バージョン (天文の世界では Nature 論文でも著者バージョンが preprint 形式で公開されることは珍しくない)]
これはすごい。自身もこの V4641 Sgr の発見に関わっており、銀河系に1つしか知られていない SS 433 と相同であろうと当時から想定していたが何とその通りだった。
2024 V4641 Paper が研究チームの公開データのページ (ニュースのページが別にあるが直接のリンクがないためこちらを紹介した)。
見ての通り検出器の名前が HAWC と我々には嬉しい名前。もちろん "鷹の目" で宇宙を見ていることも示唆している。
このチームのカタログの名前が HWC なので "タカ" の名前が天文の世界にもずっと残ることになる。アメリカとメキシコの組織が中心となったチームだが、好きな人がいるのではないだろうか。
SS 433 は光速の 26% のジェットを出している天体として 1970 年代末に正体が明らかになったもの。cf. Margon et al. (1979) Enormous periodic Doppler shifts in SS 433;
Martin and Rees (1979) A model for SS 433: precessing jets in an ultra-close binary system; SS 433 伝説: 謎の天体を追う天文学者たちの群像 (D. H. クラーク著; 福江純訳 恒星社厚生閣 1987) の日本語の本もある。
V4641 Sgr は 1999 年の大爆発で一躍注目を浴びた天体だが、我々は SS 433 発見の四半世紀ぶりの再来と受け止めていた (しかもどちらもロシアの研究者に不思議なほど縁があった)。V4641 Sgr の発見以来四半世紀を経過するが類似の天体はまだ見つかっていない。
Stubbings et al. (1999) GM Sagittarii and SAX J1819.3-2525 = XTE J1819-254 が発見報告。
鳥の学名と同様に、変光星であることが最初に報告された当時 (Goranskij 1978) は近くの星と混同があって別の名前が付いていたが、その後別天体を指していたと判明して新名称が与えられた。
古い文献を用いた鳥の種の同一性に相当する議論を行った論文もある: Hazen et al. (2000) GM Sgr - Now Two Different Variables。
Goranskij (1978) 以来この時点までまさかブラックホールであろうと考えた人はいなかった模様。
この爆発の検出に成功したのは、"たまたま" 注目していて変動を追いかけていたため: Kato et al. (1999) Preoutburst Activity of V4641 Sgr = SAX J1819.3-2525: Possible Existence of 2.5-Day Period。
古いページだが発見当初のものがまだ残っているので紹介しておく: Giant outburst of V4641 Sgr (previous GM Sgr) = SAX J1819.3-2525
(外部リンクなどは完全に切れているが極めて珍しいことに可視光での発見が X 線での検知に先行したことが海外ニュースでも紹介された。当時は太陽系に最も近いブラックホールの可能性も示唆されていた)。
Uemura et al. (2002) The 1999 Optical Outburst of the Fast X-Ray Nova, V4641 Sagittarii が我々のグループの論文 (なぜかオープンアクセス版がない?)。
植村誠 博士学位論文 (2004)
Optical Observations of Three Black Hole X-ray Novae: V4641 Sgr, XTE J1859+226, and XTE J1118+480 (中身は読めない...また日本の論文システムは探しづらい)。
V4641 Sgr について我々のグループもいくつも論文を出しているので、天文学の学位とはどんなものかなどさらに興味ある方は探してみていただきたい。
こぼれ話をしておくと (本人も多分笑って読んでくれるだろう) 植村氏は当時修士課程に入ったばかりの大学院生で、V4641 Sgr (当時は旧名 GM Sgr) は "よくわからない天体だが正体を解明してみないか" とテーマとして与えられた対象だった。ここまで大化けするとは (!)。
本人の担当テーマであったため、修士課程1年にしていきなり Nature への投稿を任されることに (しかも自身の専門分野で初めて書く論文だった) ...
当時の Nature はすでに周知のことはあまり好ましく感じておらず、我々が逐一情報を公開して世間に知られていたために査読者が否定的コメントを返したなどの事情もあった。
この慣習は現在では改善されている模様で、今ではそのようなコメントを受け取ることはなく、突発天体などの情報をかなり安心して公開することができる。まあ査読者側は先を越された方に違いないので難癖を付けたくなるのも理解できる。
安価な装置が数百万ドルを要するプロジェクトを凌駕することを示した、などの肯定的な査読コメントもあった (これはあくまで昔の話で今ではそう簡単ではない)。
"たまたま" 注目していたのも理由があって、先鋭なアマチュア観測家であった渡辺努氏が眼視観測でこの天体の活動を捉えたことに始まる (論文共著者にも入っている)。渡辺氏も年に数回たまに見ていた程度だったがたまたま捕まえることができたもの。
渡辺氏の論文もある: Watanabe (1999) Outburst of Goranskij's variable near GM Sgr (p. 3)。忘れていた背景事情なども記されていて論文の形で残す重要性もわかる。
渡辺努氏が時々見ていたのも偶然ではなく、その前 1980 年代後半にちょうどこの「新・野鳥の学名入門」の天文版のようなものを作成して (当時は自身もアマチュアだった。インターネットはもちろんなく印刷物による配布だった) 当時知られていた激変星を網羅し、この天体については歴史を紹介して見て欲しいと観測を促していたことに始まった。熱心なアマチュア観測家は隅々まで読んでいたとのこと。
資料はもちろん日本語だったが電子メールも使われだしたころで、一部の先進的な海外のアマチュアも情報を入手して 1990 年代初頭には内容は海外でもすでによく知られていた。
結果的に銀河系に2個しか知られていないものの片方だった。価値が判明してきたのはより後になってからで、当時の Nature も惜しいものを逃したと言えるだろう (と偉そうに言っておこう)。アマチュアとプロがどのように学問を進めるか、また情報公開にも関連して他分野の事例として見ていただければ幸いである。この「新・野鳥の学名入門」からも何かを見出す人が現れることを期待したい。
-
クロハゲワシ
- 学名:Aegypius monachus (アエギュピウス モナクス) 修道士のハゲワシ
- 属名:Aegypius aigupios ハゲワシ (Gk) 語源は諸説あるがよくわかっていない (wikipedia)
- 種小名:monachus (m) 修道士
- 英名:Eurasian Black Vulture, IOC: Cinereous Vulture
- 備考:
aegypius の発音はよくわからないが、原意のギリシャ語には長母音は含まれていないので、"エ" にアクセントが来ると想像できる。ギリシャ語 aigupios では末尾にアクセント。起源は明らかでなくギリシャ語以前からあった単語と考えられる (wiktionary)。
monachus は冒頭にアクセント (モナクス)。語源はギリシャ語 monakhos (一人、孤独) から。種小名の意味は "孤独" よりは外観から "修道士" として用いられていたと考えられる。#ナベヅルにも同じ種小名の女性形が使われている。
英名の cinereous の意味は灰色 (< cinereus < cinis 灰)。一般にはあまり使われる単語でなく、主に鳥の色の指して使われる。
Monk Vulture とも呼ばれる。これは学名と同じ意味になるが、ドイツ語 Moenchsgeier (見かけが頭巾付き修道服と似ているため) からの訳とのこと。もと Black Vulture と呼ばれていたが南北アメリカのクロコンドル (American) Black Vulture Coragyps atratus と区別するために改名されたものとのこと。
現在の和名は外観的にはふさわしく見えるが命名時は旧英名の影響も受けていたかも。
Eurasian Black Vulture (European Black Vulture も使われた) の英名はその対比のために使われていた時代のものだろう。
「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) ではハゲワシの名称で登場していた。かつては日本あるいは統治下の地域で最初に記録された種に代表的な短い名称を与える習慣があったらしくその時代の名残りか。その後世界の鳥に名称を付ける必要が生じてクロハゲワシのような修飾的な名称に統一されたのだろう。
クロハゲワシの和名は比較的新しいものと考えられる。
記載時学名 Vultur Monachus Linnaeus, 1766 (原記載) 基産地 Arabia (アラビア)。
Aegypius 属は de Savigny (1809) が導入。Vultur 属の名称はいかにもそれっぽく見えるが、複数の系統を含んでいたため後に分割されたよう。The Key to Scientific Names によれば近代的な命名が確立して以来最初に diagnosis が与えられた属とのこと。
Vultur 属の用例はかなり長くあって (1900 年以降にもある)、分割が受け入れられたのはかなり後の時代のよう。
イヌワシ属のオナガイヌワシも記載時学名は Vultur audax Latham, 1801 (原記載。英名 Bold Vulture とある) だったので大型猛禽類はかなり何でもあり状態だった模様だが、オーストラリアにはハゲワシらしいものが他に見当たらないので死肉に集まっているところがそのように評価されたのかも。
ハゲワシにしては勇敢の意味で audax が使われたのかも知れないが、Aquila 属に編入されると少し名前負けしてしまったかも。現在の学名だけでなく記載時学名も考慮すると意味がよりよく理解できる例と言えるかも知れない。
クロハゲワシには Vultur cinereus = gemeine Geyer (ドイツ語で "普通のハゲワシ") の名称があった (参考 Raubvoegel verschiedener Art)。
学名の方は Vultur cinereus Gmelin, 1788 (参考) が出典のよう。
Gmelin (1788) が過去の用例をまとめたものだが、Vultur cinereus はそれ以前から使われており、英名では Cinereous or ash-coloured Vulture も記されており、現在改名後の英名は新しく名付けたものではなく古くからあった英名とわかる。
"普通のハゲワシ" の方はシノニムの Vultur vulgaris Daudin, 1800 (参考) に対応するかも知れない。ヨーロッパから見て "普通のハゲワシ" の感覚だろう。
これは種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる (#ノスリの備考参照)。
種小名から属名に昇格する場合に種小名を変える必要がないとなって現在の学名になったものだろう。
単形属で単形種。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば東アジアのものは西部 (ヨーロッパ) のものより大型に見えて亜種 chincou を分ける考えがあるが自身は十分な情報を持たないのとある。
この奇妙な名称は Vuture chincou Daudin, 1800 (参考) が記載したもので基産地は "中国" とあるとのこと。
古い記載なのでもし東西で亜種を分けるならば真っ先に有効になる名前の可能性がある。
The Key to Scientific Names の記述によれば Chine (フランス語で中国。Daudin の故郷とされる) + Oricou (フランス語で oreille 耳 と cou 首 から合成) を短縮したもので、彼が名付けたミミヒダハゲワシとの類似性からとのこと。
ミミヒダハゲワシには Vultur auricularis Daudin, 1800 = Vultur tracheliotus Forster, 1791 (後者の記載が早いため種小名が採用されている) の学名があり、両者を合わせればなるほど "耳と首" になる。
Daudin はハゲワシのことを Oricou と呼んでいたようで、"中国のハゲワシ" を意図したものになるのだろう。
亜種の可能性のある chincou はフランス語読みだと "シンク" となるがさすがにラテン語読みから離れすぎる。ラテン語らしくない綴りだが "キンコウ" と読まざるを得ないだろうか。
なおフランス語の読みは知っていれば奇怪ではないが、ou は "ウ" なので cou は "ク"。尾の意味の queue は綴りは長いのに "ク" だが音が違って "ウ" と "エ" の中間のような音。フランス語をカタカナで書くのは難しい次第。"尾が長い" が名称に入っている鳥は想像通り非常に多い。例えばエナガはフランス語では Mesange a longue queue (英名と全く同じ意味) で、この queue を適切に発音しないと "首の長い" の意味になってしまう。鳥名ではいかにも起きそうな話。
oeuf (最初の oe は合字) も "オ" と "エ" の中間のような音の中間としか表現できない音と f の音で、これは卵のこと。oeij (最初の oe は合字) は目のことで、単語が短いのはよいが鳥で普通に出てくる語彙が (少なくとも日本人にとっては) 軒並み発音しにくいのである。
フランス語は水は eau ("オ") とこれまた短い。複数形になって eaux でもやはり "オ"。知らないとだまされたような気になってしまう。なぜそれほど短くても混乱しないのかと言えば母音の種類が多いのである。
この程度の基礎知識があればフランス語で鳥を表す oiseau が "ワゾ" でも驚かれないだろう。複数形の oiseaux でも "ワゾ"。"美しい" と英語で It's beautiful. となるところが、同じことをフランス語では C'est beau. "セボ" と大変短くなる。このカタカナ発音で十分通じるのでこれまた不思議な感じがする。
[ハゲワシ類の位置づけ]
クロハゲワシは日本産鳥類の中では特に近縁の種類はないが、大きく見るとカンムリワシの属する系統に含まれると考えられる。旧世界ハゲワシ類は複数の系統から進化したものと考えられ、クロハゲワシもその一つ。新世界ハゲワシ類 (コンドル) とは大きく異なった系統である。
古い時代の研究だが、cyt b 遺伝子を使って現代の系統樹とかなり近い結果を得ていた Seibold and Helbig (1995) Evolutionary history of New and Old World vultures inferred from nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene
当時としては先進的で、分子系統研究で新世界ハゲワシ類は {タカ類 + ハヤブサ類} に含まれないことを示していた (この時期は一般的には タカ類 + ハヤブサ類 が系統をなすと考えられていた。Jollie の論文も引用されている)。コウノトリ類とも特に近いわけではない。
Sibley and Ahlquist (1990) の DNA-DNA hybridization の次の段階に入っていた。
"New World vultures are not birds of prey" (新世界ハゲワシ類は猛禽類ではない) とまで書いていてなかなか刺激的である。新世界ハゲワシ類は似て非なる収斂進化の絶好の例と考えていた。しかし後の分子系統研究でまたタカ類に近づく逆転劇となった次第だが、旧世界ハゲワシ類の系統についての結論は正しく両者が収斂進化である指摘は正しかった。
さすがにハヤブサ類とオウム類との系統関係までは考えておらずまだ調べられていなかった。
なお cyt b 遺伝子は属の関係ぐらいを見る程度までに用いるのがよく、目や科レベルの関係にはもっと置換速度の遅い遺伝部位を用いるのがよい。一部現代と異なる系統関係が導かれていたのは当時ようやく可能になった手法でまだ多少やむを得ない部分があった。Livezey が分子系統学をすぐに受け入れたくなかったのもこのような背景があったのだろう (#ミサゴ備考の [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] 参照)。
現代では新世界ハゲワシ類はコンドル科 Cathartidae に分類され、さらにコンドル目 Cathartiformes とする提案もなされている。新世界ハゲワシ類はタカ類で見られるような特異な染色体構成を持たず、現生鳥類の原型に近いと考えられるニワトリの染色体構成と違わない。ヘビクイワシやミサゴの染色体構成はタカ類との中間的性質を持っている。
参考までに新世界ハゲワシ類の系統研究: Cortes-Diaz et al. (2023) Bridging Evolutionary History and Conservation of New World Vultures
によれば2系統があり、かつては北米由来も考えられていたが南米が発祥の地で北米に広がったと考えられる。アマゾン盆地が新世界ハゲワシ類の遺伝的多様性の 70% を占めている。示されている系統樹はそれほど新しいものではなく Johnson et al. (2016) なので少し注意。
旧世界ハゲワシと新世界ハゲワシの類似性は収斂進化の結果。コンドル類と比較すれば、クロハゲワシは「ワシのようなハゲワシ」と呼んでよい (旧世界ハゲワシとイヌワシの強さの比較については#イヌワシの備考も参照)。
クロハゲワシに系統の近い種類にはアフリカのカオジロハゲワシ (またはシロガシラハゲワシ) Trigonoceps occipitalis (英名 White-headed Vulture) があり、この種類はハゲワシ類では珍しく生きた哺乳類、爬虫類などを捕食することが知られている。
高野 (1973) (Lloyd and Lloyd 1969 の翻訳) では他のハゲワシに比べてハゲワシ的な点が少なく、ずっとワシ的である。小型のカモシカの子どもや、若いコガタフランミンゴのような鳥を殺すことができる、と記載されている。
機動性を持ち、足は強く、レイヨウの幼獣や鳥類を殺す (コンサイス鳥名事典)。
なおGyps 属のシロエリハゲワシも従来襲わないとされた家畜を襲う事例が報告されている: Margalida et al. (2011) European vultures' altered behaviour。
[ハゲワシ亜科の系統分類]
クロハゲワシには日本産の他のタカ類に系統的な類縁種がないため、ハゲワシ亜科の全種を#ミサゴの備考のように示しておく。順序は Catanach et al. (2024) の分子系統分類による。
この項目で種または属名の和名の後に * が付いているものは従来の少数遺伝子によるもので付いていないものよりは精度が低い (従来の系統解析と同じ)。
ここでは日本鳥類目録改訂第7版の順序なのでオジロワシ亜科の後に登場するが、大きくまとめると#カンムリワシのグループになり、カンムリワシ亜科の次になる。
ハゲワシ亜科 Aegypiinae (ハゲワシ族 Gypini ともされる)
ミミハゲワシ属* Sarcogyps
ミミハゲワシ Sarcogyps calvus Red-headed Vulture
カオジロハゲワシ属* Trigonoceps
カオジロハゲワシ [高野 (1973) ではシロガシラハゲワシ] Trigonoceps occipitalis White-headed Vulture
ミミヒダハゲワシ属* Torgos
ミミヒダハゲワシ Torgos tracheliotos Lappet-faced Vulture
クロハゲワシ属 Aegypius
クロハゲワシ Aegypius monachus Cinereous Vulture
ズキンハゲワシ属* Necrosyrtes
ズキンハゲワシ Necrosyrtes monachus Hooded Vulture
ハゲワシ属 [高野 (1973) ではシロエリハゲワシ類] Gyps
ベンガルハゲワシ* Gyps bengalensis White-rumped Vulture
インドハゲワシ* Gyps indicus Indian Vulture
ヒマラヤハゲワシ* Gyps himalayensis Himalayan Vulture
コシジロハゲワシ* Gyps africanus White-backed Vulture
シロエリハゲワシ Gyps fulvus Griffon Vulture
マダラハゲワシ* Gyps rueppelli Rueppell's Vulture
ハシボソハゲワシ* Gyps tenuirostris Slender-billed Vulture
ケープシロエリハゲワシ Gyps coprotheres Cape Vulture
マダラハゲワシの英名中の ue は u にウムラウトであるが、原語がドイツ語のため ue の表記としてある。
ミミハゲワシからクロハゲワシまでの4種は系統的には少し離れているが単系統をなしており1属にまとめることも可能である (この論文では特にそのような示唆は与えていないが)。個々の種に差異があるためそれぞれ単形属が妥当との判断であろうか。
もしまとめるならばクロハゲワシの記載が最も早いため、Aegypius 属になる。
Buthasane et al. (2024) Comprehensive genome assembly reveals genetic diversity and carcass consumption insights in critically endangered Asian king vultures
でミミハゲワシ (英名を Asian king vulture としている) のゲノムが報告された。
ミミハゲワシとそれ以降の系統との分岐年代は 1313 万年前と推定された。種固有のレトロウイルス起源の配列がいくつも見つかったとのこと。実効個体数も少なく個体群ボトルネックも存在した。
インド亜大陸に個体群がある (こちらはジクロフェナクの影響を大きく受けた) が、東南アジアに隔絶した個体群がある。
現状かなり危うい保全状態で、タイでは繁殖個体の平均年齢が 25.4 (±3.6) 歳と高齢化が進み、平均2年に一度しか産卵しない。飼育下では産卵するのは 7-9 歳、ひなが生まれるのは 8-10 歳とのことでこのまま行けば次の世代は founder effect crisis (創始者効果の危機) に直面すると考えられる。
同じような研究でミトコンドリアゲノムの結果が出ていて Buthasane et al. (2025) Complete mitogenome of the critically endangered Asian king vulture (Sarcogyps calvus) (Aves, Accipitriformes, Accipitridae): evolutionary insights and comparative analysis
新世界ハゲワシ類とは系統が遠く、Gyps 属にむしろ近いなど当たり前のことが書かれているような気がするが。
Gyps (ハゲワシ) 属8種は系統的にも近くよくまとまったグループである。ここに並べた順序もそれほど意味があるわけではない。Catanach et al. (2024) の研究での推定ではこの系統が現れたのは比較的最近で 270 万年前と推定された (過去の他の文献では 110-370 万年前)。
旧大陸ハゲワシ類の祖先の起源はタカ類の中では比較的古い方だが旧大陸ハゲワシ類の中心となる Gyps 属8種 (英語で総称して griffons と呼ばれる) が現れたのは最近で、Gyps 属は古めの系統のタカ類の中では最も新しく発展を遂げたグループの鳥と言える。
もとは捕食性のタカだったのが専門職のスカベンジャーに特殊化した感じである。逆の進化の順序が考えやすそうだがここでは特殊化したスカベンジャーが二次的に進化している。
Thom van Dooren "Vulture" (Reaktion 2011) によればこれらの種類は脊椎動物中唯一の「完全な死体食」(obligatory scavenger の表現を使っている) の可能性がある。
他の猛禽類も必要に応じて死体も食べる (facultative scavenger) ものも多いが、ほぼ死体しか食べないという意味である。
死体は非常に密度が低く、まれにしか発生しない。この本では ephemeral の表現を用いているが言い得て妙である。一般の英語ではあまり出てこない単語かもしれないが、スプリング・エフェメラル (主に植物で用いられる「春のはかないもの」) のエフェメラルのことである。ハゲワシ類といえども古い肉は適さず、死後すぐの食用に適した状態は短期間しかない。
完全な死体食になることは簡単でなく、大型の体で (ヒマラヤハゲワシでは 12 kg にも達する) 長時間の帆翔に適したつくり、集団行動で広い範囲を探索して餌のありかを見つけだすなど (集団ねぐらを作るのは情報を伝えているかも知れないとのこと) 実は高度な能力を必要とする。
そのため完全な死体食の猛禽類は後の時代になって進化したものと考えられる (生きた獲物を殺す能力と引き換えに、とある)。
この本によれば有蹄類の分布が広がり、その季節移動のルートに合わせて Gyps 属が種分化を遂げたのだろうとの説があると説明している。
有蹄類の移動中に特定の時期 (乾季の終わりなど) に自然死が生じやすいという。そのような有蹄類の移動ルートは現在では人間の進出で大きく分断されてしまっているが、家畜の死体が代わりの役割を果たすようになった。
Pirastru et al. (2021) Anthropogenic Drivers Leading to Population Decline and Genetic Preservation of the Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvus)
にも Gyps 属のレビューと主にシロエリハゲワシの生態や近年の人間との関わりなどが述べられている。この文献ではシロエリハゲワシの出現が最も新しく 75 万年前としている。ウシ類の種分化の時期に一致するとのこと。
ドキュメンタリー番組などではライオンなどの食べ残しを食べている印象を受けやすいが、そのような食物は 5% 程度で、ほとんどの食物は自然死由来のものとのこと。
有蹄類の分布の広がりは#チュウヒの備考にあるように C4 植物の発展によって草原が広がったことに対応しているのかも知れない (文献を探せばどこかに載ってそうだが)。
Gyps 属の種分化の時期が、タカ類中でも最も新しく分化を遂げたものの一つであるチュウヒ類の適応放散の時期とほぼ一致するのは偶然ではなく、そのような背景があるように思える (その点はノスリ類と齧歯類の場合も同じかも知れない)。
Maliet et al. (2019) A model with many small shifts for estimating species-specific diversification rates (執筆者レポジトリ)
によればタカ類では種分化速度の遅いものから速いものまで多様であることが示されているが、これはおそらく Gyps 属や Circus 属、Buteo 属のように近年に急速な種分化を遂げたグループが存在することが反映されているのだろう。一方でチドリ類やオオハシ科などはグループ内の種分化速度がほぼ一定。
シギ類は種分化速度がさらに遅い。
古い系統ほど種分化速度が遅いのかと感じるがカモ類はタカ類同様の分布を示す。カモ類、タカ類ともに近年出現した新しい環境に適応して種分化したものらしい。
集団行動で餌のありかを見つけだす行動 (これは渡りのタカ類が上昇気流を見つけ出す手法としても提案されている: #ハチクマ備考の視覚のところ参照) は個体数が少ないと急激に効率が悪くなる。
この本の書かれた当時 (2011) は後述のジクロフェナクによるハゲワシ集団死で個体数が激減し、絶滅も心配されていたころで、個体数激減によってハゲワシ類の従来方法の集団での餌の発見効率が落ちて生存率が低下することが懸念されていた。
またスカベンジャー scavenger は語の印象が悪いので、"purifier" がよいのではと唱える研究者もあるとのこと (新世界ハゲワシ/コンドル類の Cathartes の属名はこの意味)。
ハチクマ亜科にまとめることも可能とされるヒゲワシ亜科 Gypaetinae でもエジプトハゲワシが進化しているようにスカベンジャー的な性格の強い種類が入り込めるニッチは結構あったのかも知れない。
クロハゲワシは Gyps 属に比べると古めの系統となり、カンムリワシ属との共通祖先が持っていた捕食性の性質を残し、上記のような死体だけに頼る生活様式にはなっていないのだろう。
カオジロハゲワシについても同じことが言える。
ハゲワシ類 (旧世界、新世界とも) は脳が発達しており、上記のような集団での餌の発見などの高度な採食習性のために脳が進化した可能性も検討されている (#ハチクマの備考 [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] でも紹介の van Overveld et al. (2022) Vultures as an overlooked model in cognitive ecology も参照。
この文献によれば (個々の情報出典は論文参照) クロコンドル Coragyps atratus Black Vulture (Turkey Vulture) の逸話として死んだり傷ついたりした魚を疑似餌に用いて魚を釣るという。水に飛び込んで体を完全に水中に沈めることもあるとのこと。
Bildstein (2017) "Raptors" p. 159 によればクロコンドルは硬いクルミを車にひかせて中身を食べるという (コスタリカでの Bildstein 自身の観察)。カラスにしかできない行動ではないらしい。
集団で車にいたずらする行動はフォークランドカラカラも思わせる Black Vultures and Vehicle Damage。
家畜にも被害を与える可能性が問題視されている
Federally Protected Black Vultures May Be 'Eating Cows Alive' in the Midwest
生態的位置や行動などを映像で見ると我々のハシボソガラスそっくりに見える。カラス同様に黒くて怖いと思われているのかも?
Get to know the not-so-scary black vulture (Erin Fisher 2020)
人に対しても社交的で、賢くて他の鳥を追い払うような方法は有効でないとのこと。まったくカラスそっくりである。
Are black vultures friendly to humans? (Megan Holzman 2024)
にも記事があって、まるで「カラスとの共生は可能か?」のような表題や内容になっている。餌となるゴミを残すななどほぼカラス対策と同じ。自己防衛のために攻撃的になってまれに人を襲うこともある点もカラスによく似ている。
狂犬病リスクのことも書かれていて、鳥も狂犬病に感染することがあるのかと調べてみたが実験室では感染が成立するとのこと。猛禽類が狂犬病の宿主となっているかを調べ、狂犬病の生態には意味のある役割は果たしていないとの研究まで存在する。狂犬病に感染した哺乳類を食べて抗体ができた例があり、感染は起きることもあるらしい (wikipedia 英語版 Rabies in animals)。
Bildstein (2017) "Raptors" p. 57 には狂犬病に感染した動物を食べて猛禽類が感染することがあり、自然治癒することもあればそうでないこともあると書かれていて、これも出典がわからないが本当であれば (ヒトの場合は致死率ほぼ 100%) どちらも驚くべきことのように思える。
クロコンドルの場合の可能性は低いが、宿主の可能性のある動物に噛まれたりひっかかれて傷を負った場合は医学的対処を受けるべしとある。日本は現在清浄国となっている。
The Role of Birds in Rabies Transmission: Investigating Behaviors and Interactions
(Nature Blog Network) のようなページもあって、こちらも出典となる研究はわからないが科学者の間でも見解が分かれているように見える (哺乳類と鳥では免疫系や脳の構造が違うと説明しているがあまり関係なさそうに思える)。
クロコンドルではアシカの臍帯をちぎって胎盤を食べる行動もあるなど多様な採食行動が記述されている。カラカラと異種間の相互羽繕いが知られている。ゴミ捨て場や最近では海水浴客の放置したカバンを開ける行為を学習したとのこと。都会近くにも進出し、街中のゴミを漁ったり住人を驚かせて食べ物を盗むこともある。ハゲワシ類の中でも特異な行動であるとのこと。
トキイロコンドルやミミハゲワシは単独で獲物を探すが、見え隠れする地上の肉食動物を追跡して死体にたどりつく能力を持っていたり、嗅覚で獲物を見つける他のハゲワシ類の行動から情報を得たりしているらしい。
シロエリハゲワシで集団で協力して単独個体では得られない食べ物を得た報告があるが集団による問題解決を理解して行ったものかはわからない。ミミヒダハゲワシが集団でフラミンゴを追い込む捕食行動が記録されており、共同狩猟をする肉食哺乳類に似ている。
Gyps 属の集団構造や採食行動についても紹介されている。行動は原始的かも知れないが問題解決能力のカラス類との比較研究も興味深い。
エジプトハゲワシとヒゲワシで道具使用が知られている。カメを落として割る行為については確かな文献証拠が見つけられなかったとのこと。
戸塚 (2018) Birder 32(10): 40-42 に韓国南部の クロハゲワシ越冬地の記事がある。1997 年より給餌を始め、多い年には 500 羽を数えるという。越冬期間は12月中旬-3月中旬。ロシア、モンゴル、韓国でそれぞれ異なった色のウイングタグで標識された個体も混じっているとのこと。
戸塚 (2023) Birder 37(12): 36-37 に続報があり、よく知られた場所になっていたとのこと。越冬数は 400-800 羽とのこと。
BirdLife による最新の個体数見積もりではアジアで 5500-8000 つがいとされており、上記韓国の最大越冬数 500 はかなりの割合になる (wikipedia 英語版を参照)。
日本でも散発的に記録があり、吉野 (2023) Birder 37(2): 61 に2022年12月に八ヶ岳山麓に飛来したクロハゲワシの例が紹介されている。
渡辺 (2007) Birder 21(1): 59 に「クロハゲワシと鳥インフルエンザ」の記事があり、朝霧高原の養鶏場にクロハゲワシが訪れていたが、2004年12月にはトビ柱すら見られなかったとのこと。
富士山周辺には二度と出現しないかも知れないと記載されていた。
モンゴルで標識され韓国で記録されたクロハゲワシについては Batbayar et al. (2008) Migration and Movement Patterns of Cinereous Vultures in Mongolia,
Kenny et al. (2008) Dispersal of Eurasian Black Vulture Aegypius monachus fledglings from the Ikh Nart Nature Reserve, Mongolia
の論文がある。
シンガポールで 2021 年末に救護されたクロハゲワシの記事 After 3 hours under the hot sun, rescued Cinereous vulture finally flew 50m before landing again さすがに暑すぎるのかも知れない。抱えられた映像もあり大きさがよくわかる。
[採食方法によるハゲワシ・コンドル類の分類]
ハゲワシ・コンドル類は採食方法により3種類に分類されることがある (Kruuk 1967 が最初に提唱したもの)。
次の文献は読みやすく情報も新しい:
Linde-Medina et al. (2021) A revision of vulture feeding classification。
"gulpers" (英語では「ひと飲みにする」から) は死体の中に頭を突っ込んで内部を食べる種類、
典型的にはシロエリハゲワシ Gyps fulvus 英名 Eurasian Griffon または Griffon Vulture のように首が長く、頭から首にかけて裸出している (短い羽毛に覆われている)。典型的なハゲワシ類として思い浮かべる Gyps 属の多くはこのグループに属する。
"rippers" は表面を剥ぎ取るように食べる種類、トキイロコンドル Sarcoramphus papa 英名 King Vulture、ミミヒダハゲワシ Torgos tracheliotos 英名 Lappet-faced Vulture など。
"scrappers" は死体周囲の主に残り物を食べる種類であり、この分類に属するものはジェネラリスト (何でも食べる) のスカベンジャー性が強い。ヒメコンドル Cathartes aura 英名 Turkey Vulture など。
それぞれの採食方法に適した骨格や筋肉の特性がある。Boehmer et al. (2020) Gulper, ripper and scrapper: anatomy of the neck in three species of vultures (#コブハクチョウの備考も参照)
では頸椎数が違うだけでなく、筋肉の付き方も違っていて採食時にどの筋肉が重要な働きをするかが解剖学的にも反映されているとのこと。gulpers では頭骨も細長い。
クロハゲワシは ripper に分類される。通常のハゲワシ類は帆翔を主に行うが、クロハゲワシは羽ばたき飛行にも適した構造となっていて、時に生きた獲物を捉えることにも対応している。
ヤシの実を食べる、猛禽類としては珍しい習性のヤシハゲワシ Gypohierax angolensis 英名 Palm-nut Vulture または Vulturine Fish Eagle は従来は gulper とされてきたが新しい研究では形態的には scrapper であり、この分類はヤシの実を食べる時に必要な採食行動にも合致するとのこと
[この属名は gups, gupos ハゲワシ と hierax, hierakos タカ (Gk) で、形態的にもタカとハゲワシの中間であることをよく表している。顔つきもハゲワシよりもタカに似た感じがある。種小名は地名アンゴラから]。
系統的には英名の別名が示唆するような海ワシに近いものではなく、タカ類で最初のころに分岐したグループの一つ (#ハチクマの備考の系統参照)。
顔だけ見ると特に Gyps 属のハゲワシ類にまったく似た点がないため、海ワシのような名前が付いたのであろう (魚なども少々は食べるらしい)。十分強力な猛禽類で足も爪も強く哺乳類など生きた獲物を十分捕えることができるとのこと。単純に一般的なハゲワシ類の scrappers に当てはめない方がよいかも知れない。
典型的なハゲワシ類の scrappers では生きた獲物を捕える種類はほとんどない ([病原性細菌への適応] の項目も参照。典型的な scrappers の採食様式はニワトリに似ている)。
Macaulay Library でヤシハゲワシの写真を探してみると確かに魚を運んでいる画像が見つかり、"fish eagle" との中間型と考えられた理由が理解できる。しかし他にも陸上性脊椎動物を運んでいる画像も同様に見つかるので特に魚食が目立つわけでもなさそう。
とまっている時の写真を見ると足が立派で十分な捕食能力があることも想像できる。ほぼ完全にスカベンジャーのハゲワシ類のように足の弱そうな種類には見えない。
オウムの捕食者と書いてあるページもある (#ミサゴ備考の [オウム類・ハヤブサ類の年代推定] 参照) が探した範囲では鳥を運んでいる画像は見つからなかった。
本来は強力な猛禽類だったものが好物ができて趣味に走ったものかも知れない (笑)。この種の嗅覚や味覚も研究の意義がありそうに思える。
Linde-Medina et al. (2021) によれば、また他の scrappers にも時に果実食を行うこととも合致するとのこと (時に果実食を行うジェネラリストからヤシハゲワシのような特定の食物に特化したスペシャリストが進化したと考えると理解できるのかも)。gulpers にはこのような習性は観察されていない。rippers には例外的に果実食を行う種類もある。
一般的にも関心の深そうなヒゲワシ Gypaetus barbatus 英名 Bearded Vulture (#イヌワシの備考も参照) もこの研究で従来分類の gulper から ripper に再分類された。
前述のように Gyps 属のハゲワシ類は捕食性のタカ類の系統から二次的に死体食に特化したものと考えられ、形態的にはずいぶん違って見えるが Jollie (1976, 1977) によれば頸椎数が多い (最大 17) 代わりに胸椎 (肋骨) が少なくなっており、頸椎数を増やしたというより頸椎と胸椎の境界が変わったと理解できるとのこと。
Gyps 属のハゲワシ類でも基本的なタカ類の基本形はあまり変わっていないとのことで、新世界ハゲワシ類でも同様の変化 (収斂進化) が見られる [Jollie (1976, 1977) p. 208, 211 など。胸部が短くなる点は仙骨や尾骨の境界を変えることで補われている (p. 212)。またこの点はタカ類とハヤブサ類を区別する有用な情報ではないとのこと]。
ハゲワシ類では雑種の報告がなぜ少ないのか問題提起もある: Ottenburghs (2025) Commentary: Why is Hybridization So Uncommon in Old World and New World Vultures?
古い系統だから? (しかし Gyps 属はそれほど古いわけではない)、野外ではディスプレイの違いなど接合前生殖隔離 (この論文では prezygotic barriers) が強く働いているのではなどの考察。
[変わった採食方法を用いる猛禽類]
日本に関係する種類ではないが、変わった採食方法を用いる猛禽類としてアフリカのチュウヒダカ Polyboroides typus 英名 African Harrier-Hawk (フランス語由来の別名の Gymnogene もよく知られている。これはラテン語由来とのことで、起源はギリシャ語の gumnos 裸の、はげた + genus, genuos 頬などの意味。顔が裸出していることを意味する。
この属にはマダガスカルにもう1種マダガスカルチュウヒダカがある) と南米のセイタカノスリ Geranospiza caerulescens 英名 Crane Hawk がある。
いずれも樹洞の獲物を足で捉えるが、二重関節 (double joint) で脚を反対にも曲げることができる (ひざ関節ではないが、つまり我々のひざと同じような方向にも曲げることができる) という。
Burton (1978) The intertarsal joint of the harrier-hawks Polyboroides spp. and the Crane Hawk Geranospiza caerulescens
に解剖学的な研究がある。Burton (1978) で PDF が見られ (Burton 自身によるアップロード)、関節の画像もある。
ここで比較したチュウヒ類に比べて関節部分の骨が小さく接触範囲が狭いために関節の可動域が増しているらしい。アルコール保存された骨格標本なので保存処理の影響を受けていてあくまで概略比較だが、前方 130°、後方 75° 曲げられる結果となった。
ハイイロチュウヒではそれぞれ 180°、5° で前方に曲げる機能は多少犠牲になっているとのこと。横方向にもよく曲げられて内側に 40°、外側に 50° でハイイロチュウヒではそれぞれ 20°、5°。
靭帯や筋肉はヨーロッパチュウヒと特に違いはなかった。
図や解説を見る限りでは「二重関節」という表現は誤解を招くかも知れない。
趾も第 IV 趾が小さく、第 II 趾が第 III 趾の横側よりも後ろ側を向いているなどの特徴があり、狭い場所から獲物を引き出すのに適している。
カザノワシも趾がチュウヒダカに似た点があり検討の価値があるとのこと。
このような採食方法ができるのは猛禽類でこれらの種のみで、系統的は異なっているため収斂進化のよい例と考えられている。猛禽類の中でも面白い習性として知っておいて損はない。
ビデオ例: African Harrier-hawk (previously Gymnogene), Gymnogene hunting for geckos, An African Harrier Hawk Finds What its Looking For。
Portugal et al. (2023) Anomalous binocular vision in African Harrier-Hawks によればチュウヒダカの視野は他のタカ類と異なる特徴があり、上方も両眼視できて採食習性とも整合するとのこと。論文中に YouTube からいくつかのビデオが掲載されている。
一見弱そうな感じがするが大型で強力な猛禽とのこと。Gymnogenes Sedgefield (birdwatcher.co.za) 南アフリカの映像で2羽の鳥を掴んで飛んでいるところ。鳥の巣やねぐらを容赦なく襲うとのこと。飼い犬も襲ったことがある話があるらしい。
Sutter et al. (2001) Diet and Hunting Behavior of the Crane Hawk in Tikal National Park, Guatemala
にセイタカノスリの食性や狩猟行動の研究がある。多くの獲物は夜行性で昼の隠れ場で捕食しているらしい。樹洞のような他の猛禽類が採食できない領域をカバーすることで他の猛禽類との食性の競合を防いでいると考えられる。この種では関節を後側に 34° 程度曲げられたとのこと。
獲物は主に足で捕り、嘴で捕ることは少ない。
AVONET (#ハイタカの備考と同じ方法) で脚の長さをみるとこれらの種類はやはり脚も長く、採食方法に応じた形態をしていることがわかる。
カワリウタオオタカ Micronisus gabar 英名 Gabar Goshawk もこのような脚の構造は持たないが、捕食者対策に造られたハタオリドリの空中の吊り巣にぶら下がって内部を襲う変わった採食方法をとる (オオタカに多少近い仲間であるがこの場合嘴で獲物を捕る)。
Autour gabar [この文章はおそらく "Raptors of the World" Ferguson-Lees and Christie (2001) からの抜粋翻訳に画像を入れたもの]。
映像例: Gabar goshawk raid on weaver nest。さすがに小鳥はその間は逃げているようである。
[ヒゲワシの食物]
ヒゲワシの主な食物は骨 (+ 骨髄) で、栄養価を調べた研究がある: Margalida and Villalba (2017) The importance of the nutritive value of old bones in the diet of Bearded vultures Gypaetus barbatus
乾いた骨の栄養価は肉と遜色なくエネルギー面では 140 g の骨が 111 g の生肉と同等とのこと。この論文ではヒゲワシの胃液の酸性度はまだ測定されていないが Gyps 属からの推定ではおそらく 1 を下回っているのではないか。
ヒゲワシは古い骨を好むが、これは乾燥して重量が減り運びやすくなるためとのこと。
Margalida et al. (2020) What do minerals in the feces of Bearded Vultures reveal about their dietary habits? によれば糞の分析からそれでも少なくとも 15% は肉由来で小型哺乳類や鳥を食べていると推定される。しかし多くの部分はウシ類などの骨由来であることが確認された。
ヒトも古くから洞窟に骨髄を保存して食料としていた考古学的証拠がある: Blasco et al. (2019) Bone marrow storage and delayed consumption at Middle Pleistocene Qesem Cave, Israel (420 to 200 ka)。ヒトの進化に "ヒゲワシ的生活" は重要な役割を果たしていたよう。
次の [ヒゲワシの化粧色] で紹介の論文では、ネアンデルタール人やヒトも同様の鉄染色を行っていたことが知られており、大型動物の死体食などヒトとヒゲワシの行動が共通していて、鳥の行動を真似たのではとの興味深い仮説も考えられている。
Marin-Arroyo and Margalida (2011) Distinguishing Bearded Vulture Activities within Archaeological Contexts: Identification Guidelines。古代のヒトとヒゲワシの分布や採食習性が似ていて遺物の同定には注意を要する。
[ヒゲワシの化粧色]
ヒゲワシは酸化鉄を用いて羽毛を着色することが知られている。鳥で各種の "浴び" が羽毛のメンテナンスに役立つ可能性が提唱されているが (#カワセミ備考の [カワセミの嘴先端の形・鳥の寄生虫対策] の総説参照)、ヒゲワシの化粧では細菌による羽毛劣化を防ぐ機能は今のところ見つかっていない
[Margalida et al. (2019) Cosmetic colouring by Bearded Vultures Gypaetus barbatus: still no evidence for an antibacterial function]。
研究者も機能を理解するのに悩んでいるようで、社会的序列を高めるためではなど考察されている: Margalida et al. (2023) New Insights into the Cosmetic Behaviour of Bearded Vultures: Ferruginous Springs Are Shared Sequentially。GPS 追跡で "鉱泉" とも言えるが "鉄泉" を利用に来るとのこと。
この行動を目視で捉えることは極めて困難でほとんど観察例がなく長年の謎だった。鉄泉の場所も特定され浴びる行動も映像記録された。GPS 追跡ならではの成果。この結果は鉄泉の保全などにも活用可能とのこと。
ヒゲワシの目の写真を見ていて虹彩の外側が赤いことを思い出した。#カワウ備考の [ウの虹彩はなぜ緑色?] で鳥の目の色の役割の総説論文を紹介しており、ヒゲワシの事例を検討してみた。色彩は同系統で酸化鉄を用いた化粧色とも関連があるかも知れない。
[捕鯨の影響を受けて習性を変えた? コンドル]
Lambertucci et al. (2018) Tracking data and retrospective analyses of diet reveal the consequences of loss of marine subsidies for an obligate scavenger, the Andean condor
現在のトラッキングと 1841-1933 年の羽毛の安定同位体解析によって、パタゴニアのコンドルはかつては現在より沿岸の獲物 (死体) に頼っていて (約 33%、現在は 8% 未満) 、沿岸漁業や捕鯨などの最盛期に沿岸に漂着する獲物が極端に減った (クジラ類のバイオマスで 80% 減少) ことで少なくとも一部の個体群は地上のステップの死体に頼る必要が生じたと考えられる。
現在のデータでは個体によっては営巣地から長距離を移動して食物を探す必要があるとのこと。
Duda et al. (2023) A 2200-year record of Andean Condor diet and nest site usage reflects natural and anthropogenic stressors はこの研究をグアノ研究を用いてさらに遡ったもの。
1650-650 年前に営巣率の低下があり火山活動に伴ったものと考えられる。650 年前にもとの営巣地に戻ったが沿岸の獲物の減少や開発、入植者が持ち込んだ家畜により食物や行動を大きく変えた。
糞の記録から水銀や鉛が見つかり、家畜を襲うとして毒殺されたり撃たれたり、あるいは食物からの鉛を摂取していたと考えられる。現在でも鉛濃度の高さは懸念材料。
週間アニマルライフ (1972) pp. 1668-1672 のコンドルの項目 (浦本・内田) によればペルー沿岸で海鳥のグアノが重要な資源だった地域で、海鳥の卵やひなを捕食するとの理由でコンドル類 (ヒメコンドル、クロコンドル) が害鳥として駆除されていたとのこと。様々な理由で迫害されまくっていたわけだ。
[食性と視覚特性]
クロハゲワシに近い仲間は Gyps 属に比べて両眼視の視野も広く生きた動物の捕食に対する適応と考えられる [Portugal et al. (2017)
White-headed Vultures Trigonoceps occipitalis show visual field characteristics of hunting raptors]。
この研究の対象はカオジロハゲワシ Trigonoceps occipitalis 英名 White-headed Vulture であるが Aegypius 属にも言及がある。
ハゲワシとワシの中間的な性質を示していると考えられる。先述のミミヒダハゲワシもクロハゲワシに近い系統の種類だが生きた動物の捕食については特に触れられていない。
網膜の紫外線感受視細胞を欠く (つまり3原色型。#ハヤブサの備考参照)。ハゲワシ類の夜間行動も記録されており、暗所視が発達している可能性がある
[Peshev et al. (2022) Nocturnal activity of Griffon Vultures at a feeding site in Kresna Gorge, Bulgaria]。
ブルガリアのハゲワシ給餌場 (以下参照) でのシロエリハゲワシでの記録。これまでは夜間の行動を得ることが難しかったが、装置の進歩で記録できるようになった。夜間の採食活動が結構記録されていた。
夜間採食は肉食哺乳類による危険が伴うが、給餌場は襲われる可能性が低い場所に設置してあるのでその影響もあるかも知れない。しかしこれらの行動は実は想像以上によくあることなのかも知れないとのこと。
[ハゲワシ類は聴覚でも食物を探す?]
ハゲワシ類などのスカベンジャーが食物を探すのに嗅覚を使うか、視覚を使うかは古くから議論されており一定の結論が出ているが、聴覚についてはあまり考えられてこなかった。
Jackson et al. (2020) A dead giveaway: Foraging vultures and other avian scavengers respond to auditory cues
肉食動物が草食動物を捕食する際の音を再生する音声刺激 (普段はライオンやハイエナのために夜間に行っていたが、昼間に試してみたとのこと) のみでスカベンジャーの鳥が集まり、哺乳類 (ハイエナ、ジャッカル) よりも到達が早く、哺乳類スカベンジャーの数とは逆相関があったとのこと。
実験条件は十分整ったものではないがスカベンジャーの鳥が音刺激も用いて食物を探している可能性がある。聴力は意外に高いのかも知れない。
ここではあまり深追いはしなかったが、ハゲワシ類の中で旧世界ハゲワシ類は主に視覚、新世界ハゲワシ類が嗅覚に頼っていることは現在はよく立証されている。
歴史的にはそうではなく、あの有名な Audubon や Bachmann が実験を行いヒメコンドルが嗅覚ではなく視覚を用いていると立証した報告があったため長年信じられていた。
その定説を打ち破った時代の論文があったので紹介しておく: Sayles (1887) The Sense of Smell in Cathartes aura。
あの Audubon や Bachmann でも間違うのだ、と衝撃をもって受け止められたことがあった。この論文の結語がすごい "in this case, I feel that they are merely human" (Audubon や Bachmann もこの点ではただの人に過ぎない - 当時のアメリカで言論の自由がしっかり尊重されていたことがわかる)。
Audubon が思い込んで間違った事例として#カンムリカイツブリの備考 [アメリカにもカンムリカイツブリが生息していた?] を紹介しておく。いずれの時代でも神格化は禁物。
[猛禽類の植物食]
What do Golden eagles eat?
に他のワシは肉しか食べないがイヌワシは果物や野菜を食べることもあるとある。特に獲物がない時に何でも食べられるとある。嗅覚で探すこともできて、必要があれば食べるとある。本当だろうか? (#イヌワシ備考より移動)
Meet the Raptors That Eat Avocados (and Other Fruit)
(Hausheer 2021) によればオーストラリアのトビがアボカドを食べることが観察され (ビデオあり)、
オーストラリア以外では過去アフリカ以外で記述されていなかったのは不思議であるとのこと。
観察された 2002 年は干ばつで獲物も少なく、猛禽類は代替脂質として植物食を行った可能性がある。
しかしアボカドには有毒物質のペルシン (persin) が含まれ特に葉に多いとのこと。ヒトにとってはアボカドの熟した果実は通常有害と考えられていないが鳥類、特に cage birds (スズメ目やオウム・インコ類) は感受性が高くニワトリやシチメンチョウはより抵抗性がある。ペットには決して与えてはいけないと wikipedia 英語版にある。
鳥への毒性は Avian Avocado Toxicosis (Burmeister and Yunker, Veterinary Technician) の情報がある。ペットでこれほど症例があるということは、これらの鳥は甘みなどを感じて好んで食べているのだろうか。
ヒトには特異的に毒性が弱いらしく、アイアイ Daubentonia madagascariensis には毒性が強いらしい [Greene and McKenney (2018) The inside tract: The appendicular, cecal, and colonic microbiome of captive aye-ayes]
種差がかなり大きいようで毒性や対毒性の機構の研究は今ひとつ進んでいないよう。タカ類は抵抗性がある方のグループなのかも知れない。含まれる物質にはペルシン以外もあり、脊椎動物に対する植物の化学防御や種子散布の機構とも関係がありそうで面白そうだがよくまとまった論文が見当たらず調べきれていない。
Fitzsimons and Leighton (2021) Frugivory in Raptors: New Observations from Australia and a Global Review
によれば猛禽類による植物食はそれなりにあってイヌワシに近い種ではエボシクマタカでも野外報告がある。以下参考までにこの文献からリストしておく。なるべく系統を反映するように少し並べ直した (どれも二次情報や又聞きも多いようなので注意):
・コンドル (新世界ハゲワシ) 亜科または科:
トキイロコンドル Sarcoramphus papa King Vulture
クロコンドル Coragyps atratus Black Vulture
・ヒゲワシ亜科 Gypaetinae:
チュウヒダカ Polyboroides typus African Harrier-Hawk: 存在する時はヤシの実を食べるが分布は一致しておらず依存しているわけでもない。アイボリーコーストでは 86% の食物がヤシの実だった記録あり。
マダガスカルチュウヒダカ Polyboroides radiatus Madagascar Harrier-Hawk
ヤシハゲワシ Gypohierax angolensis Palm-nut Vulture: 成鳥の 58-65% の食物、若鳥の最大 92% の食物が植物との記録あり。アイボリーコーストで 50% 以上の数字もある。
エジプトハゲワシ Neophron percnopterus Egyptian Vulture: 腐った果物や野菜との記載あり。
・ハチクマ亜科 Perninae
ハイガシラトビ Leptodon cayanensis Grey-headed Kite: この論文にはないが見つけてしまったので追記。Gaviao-gato (Leptodon cayanensis) se alimentando
カンムリカッコウハヤブサ Aviceda subcristata Pacific Baza: ニューギニアでは比較的普通に枝にぶらさがって果実を食べる。
クロカッコウハヤブサ Aviceda leuphotes Black Baza: ヤシの実1例あり。
ヨーロッパハチクマ Pernis apivorus European Honey Buzzard: まれに果実や冬にヤシの実。
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Crested Honey Buzzard: ここでは誰かが見た話を聞いたレベルの話で、ヨーロッパハチクマと混同があるかもとのこと。
ツバメトビ Elanoides forficatus Swallow-tailed Kite: 熱帯では果実も食べるがアメリカ合衆国では報告がない。主に樹冠部、まれに地上のものを食べる。
・ハゲワシ亜科 Aegypiinae
ズキンハゲワシ Necrosyrtes monachus Hooded Vulture: 時々ヤシの実を食べる。
・イヌワシ亜科 Aquilinae
エボシクマタカ Lophaetus occipitalis Long-crested Eagle: まれに果実を食べる。
・ノスリ亜科 Buteoninae
トビ Milvus migrans Black Kite: 西アフリカでヤシの実、オーストラリアでアボカド。
フエフキトビ Haliastur sphenurus Whistling Kite: オーストラリアでアボカド。
ムシクイトビ Ictinia plumbea Plumbeous Kite: 果実
オオクロノスリ Buteogallus urubitinga Great Black Hawk: 果実
ヨーロッパノスリ Buteo buteo Common Buzzard: リンゴを食べた例、果実
・ワライハヤブサ亜科またはモリハヤブサ亜科 Herpetotherinae
ヨコジマモリハヤブサ Micrastur ruficollis Barred Forest-Falcon: 果実の例あり。
・カラカラ亜科 Caracarina
カラカラ (広義) Caracara plancus Crested Caracara: ココナッツやヤシの実などの事例あり。
アカノドカラカラ Ibycter americanus Red-throated Caracara: 果実をよく食べる。ナット類、ヤシの実の種。
キノドカラカラ Daptrius ater Black Caracara: ヤシの実。
キバラカラカラ Milvago chimachima Yellow-headed Caracara: ヤシの実など。
チマンゴカラカラ Milvago chimango Chimango Caracara: 腐ったリンゴなど。ペリットに植物成分が大量にあったとのこと。
マダラコシジロカラカラ Phalcoboenus carunculatus Carunculated Caracara: 穀類や植物の報告あり。
・ハヤブサ亜科 Falconini
ハイイロチョウゲンボウ Falco ardosiaceus Grey Kestrel: 時にヤシの実。
コウモリハヤブサ Falco rufigularis Bat Falcon: 未確認報告で小さな果実。
ニュージーランドハヤブサ Falco novaeseelandiae New Zealand Falcon: 果実事例1例あり。
このように見ると系統的にはかなり傾向があって、ヒゲワシ亜科は大部分が植物食の記録がある (ヒゲワシのみ記録がない)。ハチクマ亜科も比較的多いがあまりしっかりした記録がない。
特にハゲワシ類でも Gyps 属は意外にも記録がない。スカベンジャーと言ってもむしろワシ的なのだろう (味覚に関係するかも知れない。#メジロの備考の [鳥類の味覚] も参照)。
ハイタカグループ (気軽に亜科と呼べない) はこれまでのところ出てこない。イヌワシが食べるかどうかはこの文献で調査された範囲ではあまり手がかりがなかった。ハヤブサ目では地上性でスカベンジャー的なカラカラ亜科がやはりよく食べている。ハヤブサ亜科では系統が比較的まとまっているのが興味深い。
このリストを見ると猛禽類の植物食のトップはよく知られるようにヤシハゲワシで次点がチュウヒダカだろうか。チュウヒダカは食物の分布とは一致しないのでヤシハゲワシのように主に食べるというわけではないらしい。
エボシクマタカについては週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 115 p. 13 にも言及があり、植物質のもの、特にイチジクも食べるようであると記されていた。
#オジロワシ備考 [オジロワシは美味?] ではオジロワシが飼育下でホウレンソウも喜んで食べたとのこと。
通常は肉食と考えられてあまり注目されないが、猛禽類に種子散布者の役割もあるとのこと: Silva (2022) Frugivory and primary seed dispersal of Elaeis guineensis by birds of prey
ブラジルでアブラヤシの主な種子散布者であるとのこと。カラカラ類、ヒメコンドル Cathartes aura Turkey Vulture、オオハシノスリ Rupornis magnirostris Roadside Hawk の採食中の写真が出ている。
アブラヤシはメガファウナ (#カンムリワシの備考 [メガファウナの絶滅] 参照) に対応したもので、現在の果実食の動物には見合ったサイズのものがないとのこと。猛禽類は壊して食べられるのでその役割を果たしている。
Dracxler and Kissling (2021) The mutualism-antagonism continuum in Neotropical palm-frugivore interactions: from interaction outcomes to ecosystem dynamics や
Stevenson et al. (2022) Oilbirds disperse large seeds at longer distance than extinct megafauna によればこの見方は少し古いかも知れない。
肉食動物に関連してここで紹介しておく。アビシニアジャッカル Canis simensis Ethiopian Wolf が花 (Ethiopian red hot poker Kniphofia foliosa シャグマユリ属) の蜜を食べて受粉も行っている可能性があることが明らかになった:
Lai et al. (2024) Canids as pollinators? Nectar foraging by Ethiopian wolves may contribute to the pollination of Kniphofia foliosa。
哺乳類の方が甘み知覚は保存されてそうだが、肉食動物が甘い物好きになるのは案外簡単なのかも (#ハチクマ参照)。
意外な動物が種子散布者であったり受粉に関与していたりする。
猛禽類が通常は植物由来で必須のビタミン E をどこから得ているのかあまりよくわからなかったが、多分獲物、草食動物の腸などに含まれるものなので限られた資源だろう。Barton et al. (2002)
Vitamins E and A, Carotenoids, and Fatty Acids of the Raptor Egg Yolk の
文献にもウズラを丸ごと与えていたハヤブサで野生個体に比べてビタミン E 血中濃度が非常に低く、人工的に添加する必要が述べられている。
Schink et al. (2008) Alpha-Tocopherol in Captive Falcons: Reference Values and Dietary Impact
ではワキスジハヤブサ (雑種) に商用のシチメンチョウの胸肉ばかり与えているとビタミン E 濃度が大きく下がるとのこと。
Avian Nutrition によれば飼育ミサゴに多価不飽和脂肪酸の多いツナ (マグロ族) ばかり与えているとすぐにビタミン E 欠乏になるともある。
猛禽類が時々植物食をする一つの理由なのかも知れない (上記および #ハチクマの備考 [ハチクマ亜科の他種] のカンムリカッコウハヤブサの事例など)。
ちなみにビタミン C は多くの鳥が合成できるので植物食をする理由にはならないだろうし、ヒトの場合でもビタミン C の "エビデンス" は古い話で腸内細菌も合成するので普通の生活で不足することはないのではとも言われる。
霊長類では尿酸をアラントインまで酸化せずに抗酸化物質として用いることでビタミン C の合成能力を必要としなくなった (直鼻猿亜目) との解説が wikipedia 日本語版にある。この出典は Similar Functions of Uric Acid and Ascorbate in Man (Proctor 1970) と古いので要検証かも。
かなり昔の話になるがポーリング (Linus Carl Pauling) が大量のビタミン C や他の栄養素を摂取する健康法を提唱した ("エビデンス" をあまり要求しない時代の話で、当時の根拠はイヌはそのぐらいの量を体内で合成しているのでヒトでもそれぐらい必要だろうなどであった) ことがあった。ノーベル賞学者の言うことは何でも正しいわけではないよい事例となった (wikipedia など参照)。
糖質制限と大量のビタミン C 点滴がガン細胞に与える影響を聞かれた方もあるだろうが、これはまた別の性質 (ビタミン C の細胞毒性) を利用したものなので少し意味が異なる。興味深いメカニズムがかかわっているがこれ以上は触れないので興味ある方は調べていただきたい。
ビタミン C を食物から十分摂取できる場合はビタミン C 合成能力を失う系統があることにはビタミン C の両側面の役割もかかわっているのだろう (以下の文献などにもある)。
鳥類でも多系統で合成能力を失ったり再獲得もしている [Drouin et al. (2011) The Genetics of Vitamin C Loss in Vertebrates 系統樹は Sibley and Ahlquist ベースで現代のものと相当違うので注意]。
ビタミン C を体内で合成する場合には反応副産物もあるため、食物中の存在量によってどちらの方向の進化もあり得るらしい。猛禽類での研究はあまり見当たらず、おそらく体内で合成能力を持つ模様だが種差も考えられるので実際には遺伝子を調べてみないとわからないだろう。
Gradinaru and Popa (2025) Vitamin C: From Self-Sufficiency to Dietary Dependence in the Framework of Its Biological Functions and Medical Implications
にもう少し進化史も出ており失う理由の仮説もいくつか紹介されている。ビタミン C の合成能力は脊椎動物が水から陸に上がる際に酸素の肺への毒性を克服するために獲得したと考えられるとのこと。系統の古い鳥では失われていない。
失う方の仮説は (i) 生合成が比較的高コストであること (ii) 食物から得られる (iii) 遺伝的浮動 で昔とあまり変わっていないが、(iv) ビタミン C の合成遺伝子に他の機能があって保持することで不利になる場合がある、が仮想的に挙げられている (脊椎動物ではまだ実証されていないとのこと)。
イヌでは突然変異で合成能力を失っているが (出典によって書いてあることが違う?)、祖先のオオカミも完全な肉食ではなく果実も食べる。肉にはあまりビタミン C が含まれないが獲物の臓器、特に肝臓にある程度含まれているなどの情報が出ている。
イヌで合成能力を失ったことで多様な環境に適応できることにつながったとの議論もあるとのこと。
ビタミン E の話に戻ると猛禽類の植物食に多く現れるナッツや他の実、アブラヤシの実もビタミン E が非常に豊富なことはヒトの食べ物としてもよく知られている。単なる脂質の代替物以上の栄養的意味があって、ヤシの実をそこそこ食べる猛禽類は実はものすごく健康的な食事をしているのかも知れない。
ハチの子はどうかと見てみると鉄や亜鉛は高いもののビタミン E, A は少ない (「日本食品標準成分表」に載っている数字だがおそらくハチの種類にもよるだろう)。
これを見るとハチクマはハチの子だけではおそらく栄養が偏り、何か別に食べる必要がありそうに見える。カルシウムのために脊椎動物を食べるのはこの意味から理解できるが、ビタミン E などはどこから得ているだろうか。ハチの子がまだ多くない時期は植物食の脊椎動物? 観察事例は少ないが植物食は一つの候補のように思える。
他種の鳥の卵もよい資源になるだろう。石で卵を割る猛禽類など卵を食べる鳥は多いが、これもそれだけ栄養学的価値が高いのかも知れない。
さまざまな食性の鳥がビタミン E をどのようなタイミングで必要で、どのように得ているかを調べることも (特に生殖にかかわるトレードオフや免疫とも関係して) 十分面白い研究になるのではないかと思う。
クロコンドルについては #クロハゲワシの備考で硬いクルミを車にひかせて中身を食べるという Bildstein 自身の観察も紹介したが、家畜の糞も食べるという。これも草食動物の食事から必要な栄養を得る意味があるかも知れない。
ミサゴがカナリー島で海藻を集めて食べたという [Bildstein (2017) "Raptors" p. 159]。
フォークランドカラカラは草なども食べ、ペリットにはそれらの不消化物が多く含まれるとのこと (同書 pp. 161-162)。この本では草食も行ってペリットを出す際に消化管を掃除する役割が挙げられているが、栄養面の役割もあるかも知れない。ロシアの (ヨーロッパ) ハチクマ飼育の典型的な食事にニンジンなども含まれているがこれは栄養面なども考慮したものかも知れない。
#チョウゲンボウの備考 [アメリカチョウゲンボウの交尾] の考察中に気づいたもので、ここにまとめなおした。
さらに血糖、アルブミンの糖化、抗酸化物質濃度の研究があることを知り、#ハクトウワシ備考に含めておいた。チョウゲンボウなどハヤブサ目は調べられていないが、タカ類、フクロウ類では血糖値が特に高いわけでもないのにアルブミンの糖化度が高いとのこと。
肉食ではカロテノイドやビタミン E が不十分な可能性も少し触れられていたがまだ情報不足であまりわかっていないよう。
Negro et al. (2002) Coprophagy: an unusual source of essential carotenoids の報告があり、エジプトハゲワシの黄色い顔の着色に用いられるカロテノイドは有蹄類の糞を食べることで得ているとのこと。間接的な植物食とも言える。少なくともこの時点では初報告とのこと。
肉食ではカロテノイドが不足しがちで、羽毛着色に使うよりもっと大事な部分に重点的に使うのだろうか。
[ブルガリアでの再導入]
ブルガリアでは一度絶滅したクロハゲワシの再導入が行われ、給餌ステーションが設けられてソフトな野生放鳥が行われている。放鳥されたクロハゲワシに装着された GPS に状態を知らせる機能があり、緊急信号を受けて捜索隊が撃たれた鳥を発見して収容し、ICU で獣医師ができる限りの救命措置を施したが数日後に息絶えたとのこと (記事)。
ブルガリアのハゲワシの増殖プロジェクトの母体は Green Balkans で 1988 年創設、野生動物救護センターは 1992 年に設置された。
ブルガリアの 鳥類保護団体 Bulgarian Society for the Protection of Birds とも連携しており、この団体は SmartBirds というデータベースサイトを運用して驚くほどのデータが集まっている。
近年は5年刻みぐらいの詳しい繁殖分布メッシュ (10 km) 情報が出されている。希少種の情報をここまで公開するのは日本とは文化や背景が異なることもあるだろうが、鳥類 (特に猛禽類) の保護や個体数回復に向けた取り組み方法として参考になる部分が多いと思われる。
Petrov and Dicheva (2024) Successful captive breeding of vultures due to the double clutching method 自然条件では1卵しか産卵しないが、取り去ることで人工飼育下で1シーズン2回の産卵がこれまで3例記録された。
Cotorogea et al. (2025) Using GPS and accelerometer data to precisely record egg laying, incubation and chick hatching of Cinereous Vultures (Aegypius monachus) in-situ
同じくブルガリアの GPS と加速度計による研究。抱卵時期や孵化前後での体の向きの変化などのデータが記録された。ひなの養育や巣の補修などに関連する変化と考えられる。leg-loop harness と足まわりのハーネスで背に取り付けている。記録された生データも付けられている。
クロハゲワシのデータは得られ始めたばかりだが、過去にシロエリハゲワシのデータがあって比較されている。
[ハゲワシ類の集団死とジクロフェナク]
1990 年代初頭からインドでハゲワシ類の謎の集団死が発生するようになり、全個体数が 99% 減少するなど絶滅の危機に瀕した。
伝染病、農薬中毒なども疑われたが原因がなかなかわからず、2004 年になって家畜に使われる鎮痛剤ジクロフェナク (diclofenac, 人の医薬品としても使われ商品名ボルタレン。人の医薬品が大量製造され家畜用に転用された) がハゲワシ類に強い毒性を持つことが明らかになった (*1)。
インドで家畜用に使われるようになったのは 1990 年代からで時期もちょうど符合する。
この医薬品 (非ステロイド性抗炎症薬 NSAIDs の1種) はシクロオキシゲナーゼを阻害し、プロスタグランジン合成を抑制する作用機序を持っている。ハゲワシ類はこの感度が特に高く、
腎臓のシクロオキシゲナーゼが阻害されることで腎不全を起こしたとされている。
鳥類は窒素を尿酸として排出するため、尿酸が臓器に蓄積する内蔵痛風を引き起こしたものである。
2005年3月、インド政府はジクロフェナクを段階的に排除することを発表した。
ハゲワシの数が減少したことで野犬が増え、野犬を通じて狂犬病が広まる生態系のカスケード効果も起きた。(wikipedia 日本語版/英語版の情報に追記。英語版では Indian vulture crisis という別項目がある)
最新の調査でハゲワシの採餌による死亡数が致死性薬物の使用禁止以後3分の1減ったことが判明 (BirdLife の日本語記事 2014)。
この集団死で最も影響を受けたのは Gyps 属であったが、ジクロフェナクは現在でも利用されている地域もあり、
アジアのハゲワシを絶滅から救うための戦いに大きな進展 (BirdLife の日本語記事 2015)、
最新研究で確認: スペインでのハゲワシ減少の主因は獣医薬の可能性大 (BirdLife の日本語記事 2016)。
再導入されたクロハゲワシがヨーロッパで犠牲になった報告がごく最近あった。Diclofenac claims first official victim in Europe: the Cinereous Vulture (BirdLife 2021)、
Herrero-Villar et al. (2021) First diclofenac intoxication in a wild avian scavenger in Europe。
これらを見るとクロハゲワシにも毒性が高いようである。
インドでハゲワシ類の集団死後に保護対策は進められているが、個体数は現在でも低く、インドにのみ生息する種類は IUCN CR 種となっている。
ベンガルハゲワシ、捕獲数増加の必要性 (ナショナルジオグラフィックの日本語記事 2008)、
アジアの絶滅危惧IA類ハゲワシに初めての回復の兆し (BirdLife の日本語記事 2012)、
ネパールで人工飼育されていた絶滅危惧IA類のハゲワシが放鳥へ (BirdLife の日本語記事 2018)。
現在でもまだ進行中の問題である。
Thom van Dooren "Vulture" (2011) は本が書かれた時期のためかも知れないが、たとえ人工増殖などの保護活動が進んでも時すでに遅く、例え数十年後に個体数が回復しても家畜の死体の処理方法は大きく変わっているだろう。
かつてのようなハゲワシの大群が見られることや、ハゲワシがインドの生態系に占めていた役割や文化を取り戻すことが二度とないことは確実だろうと述べている (かつての北米の DDT の悲劇なども念頭にあるのだろう。たった一つの過ちが生態系に取り返しのつかない影響を与え得る警鐘と考えてよいだろう)。
備考:
*1: 例えば Hassan et al. (2018) Could the environmental toxicity of diclofenac in vultures been predictable if preclinical testing methodology were applied?
ではでは血中半減期も長く、ウズラに比べて 4000 倍も毒性が強いとのこと。ハトではさらに耐性が高く、カラスやヒメコンドルも影響を受けないとのこと。
Gyps 属がこれほど敏感なのは種特異的な代謝によるものと考えられるとのこと。数種の実験動物に使われる鳥類で事前に試験を行っていても予見できなかったと考えられる。
Locke et al. (2022) Effect of cytochrome P450 inhibition on toxicity of diclofenac in chickens: Unravelling toxicity in Gyps vultures
によって P450 (代謝、特に薬物解毒で有名) が関連している可能性が高いことが示唆されていた。
Gyps 属ではおそらく何かの酵素が欠損しているのではと考えて探されたのだろうが、全ゲノム転写の解析で
Adawaren et al. (2024) A premature stop codon in the CYP2C19 gene may explain the unexpected sensitivity of vultures to diclofenac toxicity
CYP2C19 に生じた1塩基変異による終止コドン (stop codon) が種特異性にかかわっている可能性が高いことを示した。この変異を持つ酵素はジクロフェナクの代謝能力が低い。Gyps 属8種にこの変異が保たれているとのこと。
CYP2C19 は P450 の酵素の一つでヒトでの機能はよく調べられている。
グレープフルーツジュースと一緒に飲んではいけないと言われる薬も P450 のうち CYP3A4 が関係するなど、この場合とほぼ同じようなメカニズムが起きていたと考えてよい。
[高病原性鳥インフルエンザ感染を生き延びたシロエリハゲワシ]
(#インドガン備考の [野鳥と鳥インフルエンザ] と部分重複掲載)。
2022 年のヨーロッパでの発生時のフランスのシロエリハゲワシの GPS 追跡の結果、成鳥の多くは感染しても生き延びたがひなの大部分は死んだ。罹患中は巣で平均 5.6 日間動かなかったとのこと: Duriez et al. (2023) Highly pathogenic avian influenza affects vultures’ movements and breeding output。
成鳥のうち2羽は過去の感染を示す抗体があったとのこと。
繁殖期中に起きた流行であったため巣を養生場所に用いることができたのだろう。渡り鳥で越冬地の場合は適切な場所がないかも。成鳥は病原性のあまり高くない鳥インフルエンザに過去に暴露経験があってある程度の交差免疫が働いていたのかも知れない。
病原性は異なると思われるが治癒期間なども我々の場合と大変よく似ている。
この研究は感染した鳥が移動することで他の鳥に病気を広げるかを調べる研究目的となっているが、病気の時に巣に籠もるのはヒトの場合同様に適応的な行動なのだろう。他の鳥ではどうなのだろうか。ハゲワシの行動は "賢い" のだろうか。
このような詳しい研究が可能なのは、シロエリハゲワシはフランスに再導入されて生態がよく調べられているため。wikipedia フランス語版に詳しい解説がある。かつては迫害されていた種類のため啓発活動も重要であったが、偽情報も拡散しており問題となっている。
我々には想像しにくいが、この研究は再導入されたシロエリハゲワシの増加が病気を広げていないことを検証する社会的任務もあったと考えられる。
[ハゲワシ類の名称や迫害、改名]
ハゲタカという名称は俗名で (wikipedia 日本語版で vulture に対応する項目となっているがあまり適切でないように思う)、死骸を漁る彼らの食餌習性から転じて、窮地に陥った者を食い物にする強欲な人物・組織を「ハゲタカ (vulture)」と表現することがあると wikipedia 日本語版にある。
ハゲタカファンドは英語でも vulture fund と呼ばれるが、ハゲタカジャーナル (学術界ではよく知られる用語で、ご存じでなければ検索してみていただきたい) は英語では predatory journal である。
"vulture" に誤った負のイメージを与えることを避けるために最近はこの意味で "vulture" を使わなくなっているのではと想像している。
vulture journalism の用例はないわけではないので使っている人もあるということだろうが、日本のジャーナリズム用語の貧困さを感じてしまう。いくつかの言語をチェックしてみたがハゲタカジャーナルのような名称を使っているところは見当たらなかった。単純に英語語彙が貧困で predatory の単語に馴染みがないだけかも知れないが。
Thom van Dooren "Vulture" (2011) によればハゲワシ類は上記のような誤解から忌み嫌われずっと迫害の対象であった。ヨーロッパのヒゲワシは家畜を襲い、時には幼児を襲うとの誤認から迫害の対象となり、銃器が普及する以前の 19 世紀においても極めて残忍な方法で殺されていた。20 世紀初頭にはヨーロッパではヒゲワシは事実上一度絶滅し、ようやくアルプスの再導入個体が定着しつつある段階である。
絶滅原因の大部分は直接の迫害によるもの。そして現在でもまだ続いている。
著者はヒゲワシに付けられた名称 lammergeier (または lammergeyer) は最悪であると述べている。
これはドイツ語由来で原語では Laemmergeier レマーガイアー (ae は a ウムラウト)。
Lamm が子羊 (Laemmer が複数形) の意味で Geier がハゲワシ (辞書ではドイツ語で Geier が卑語として使われるとのことだが現在でもそうであろうか?)。子羊を襲うハゲワシと信じられて誤って名付けられたものが普及し、他のヨーロッパ言語や英語圏 (分布域の南アフリカ共和国も英語圏) にも波及してしまった。
ドイツ語では現在改名され Bartgeier (ヒゲハゲワシの意味) が通常の名称となっている。容貌がワシに似ているため Bartadler (ヒゲワシの意味) などの別名もある [wikipedia ドイツ語版より。Laemmergeier の名称は迷信に基づくためとの説明もある。Mebs and Schmidt (2005) "Die Greifvoegel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens" にはドイツ語別名すら出てこない]。
英語でも同様の理由から現在は Bearded Vulture (和名と同じ意味) が通常の名称として使われている。British Birds に掲載された D. Andrew の意見と編集部のコメント (2008) Lammergeiers and lambs。決して古い話ではない。オランダ語では未だに改められていないと記している。
歴史を考えると「別名に lammergeier があり、発音が難しい」とか安易に説明するのは慎重になるべきであろう。
ロシア語でも lammergeier の訳に相当する yagnyatnik (子羊を食べるもの) の名称もあるが (辞書を見ると「大はげたか」と和訳してあったりして認識不足がよくわかる)、通常は borodach (あごひげを生やした人) の貫禄ある名前になっている。Dement'ev and Gladkov (1951) でも borodach が使われており、西洋語からの訳に相当する yagnyatnik は生態的に誤りであることが述べられている。
日本で1羽のみ飼育されているヒゲワシを動物園で見たが大変立派な鳥である。
ヒゲワシ学名の種小名 barbatus はひげのあるの意味。学名をそのまま訳せば何の問題もなかったはず。
著者 Thom van Dooren はヒゲワシの事例から得られる教訓として、鳥の名前は恐ろしいほどに意味を持つとしている (原文 there is an awful lot in a name: さしずめ「名は体を表す」、ちょっと凝って「名は口ほどに物を言う」と訳してみようか)。
アメリカでも以前よく知られた名前であった California Vulture は 20 世紀初頭に California Condor と改名されたとのこと。
もちろん vulture を別の名称に変えるだけでは問題解決にならないため、「vulture を正しく知る」運動がなされている。2010 年に International Vulture Awareness Day (世界ハゲワシ啓発の日) が設けられ、ハゲワシの誤ったイメージの払拭や生態系における重要性の一般の理解は次第に進みつつある。誤った意味で vulture が用いられなくなってきているのもこれらの活動の成果なのかも知れない。
日本では文部科学省自らがハゲタカジャーナルの名称を使っているぐらいなので (学術情報流通に係る懸念すべき事例への対応状況アンケートについて) 何をか言わんやであるが...。
ヒゲワシの場合はオランダが名指しされているが、あの素晴らしい albatross を指して「アホウ」と呼んでいる国があるのだそうだ、と話題になっているかも知れない。
アホウドリ--優雅に飛んで長生き...なぜ「阿呆」? (朝日新聞社 2015)
によれば "日本鳥学会は一昨年、日本鳥類目録改訂第7版を出しましたが、アホウドリの和名は変わりませんでした。(中略) 日本鳥類保護連盟元理事で目録編集委員会委員長の柳沢紀夫さん (73) は
「今回は変えたほうが良いという意見はなかった。変更するとなればさまざまな法律名などにも影響が及ぶ。10年をめどに次の改訂の努力をするが、改称について論文が発表されるなど提案があれば検討するかもしれない」"
とあった (論文至上主義?)。「10 年をめどに次の改訂の努力をする」と述べているのでヒゲワシに際して述べられた British Birds (2008) のような意見論文でもよいのではないだろうかと感じる。
日本鳥類目録第8版の編集について [西海功 (目録編集委員長) 日本鳥学会 鳥学通信 2022] を公式見解と考えてよいだろう。
差別語かどうかの判断よりも母国語に対する我々自身の感性の問題のように思えるがみなさんはいかがお考えだろうか。
[尿で体を冷やすコンドル]
同じくハゲタカの wikipedia 日本語版で「また自分の体を冷やす手段として自身に尿を掛ける」と紹介されているが、これはハゲワシ類全般の習性ではなく新世界ハゲワシ類 (コンドル科) の特徴。
この習性はコウノトリ目に似ているためにかつてワシタカ類をコウノトリ目に置く一つの要因となっていた。
Cabello-Vergel et al. (2021) Urohidrosis as an overlooked cooling mechanism in long-legged birds
によればこの行動 (urohidrosis) は開けた環境に住むコウノトリ類、新世界ハゲワシ類 (コンドル科)、カツオドリ類に見られるもので、多系統性を示す (系統が近い根拠にはならない)。
この行動のためには水分を常時とることができる必要があり、鳥類ではまれにしか見られないとのこと。
別項目 [病原性細菌への適応] の Lobello et al. (2025) のレビューによれば尿による抗菌機能も期待できるとのこと。
[旧世界ハゲワシ類の進化]
旧世界ハゲワシ (多系統) の化石と年代一覧は Li et al. (2016) A new Old World vulture from the late Miocene of China sheds light on Neogene shifts in the past diversity and distribution of the Gypaetinae
で見ることができる。
扱われているものは ヒゲワシ亜科 Gypaetinae (ハチクマ亜科の前でタカ科の古い系統にあたる。単系統とは限らない)、ハゲワシ亜科 Aegypiina で、ヒゲワシ亜科は北米に豊富な化石記録があるが現存種はない。南米では記録されていない。これまでユーラシアやアフリカの完全な化石はほとんどなかったが、中国北西部で Mioneophron longirostris が発見された。
ヒゲワシ亜科はユーラシア、北米で草原が広がり開けた環境の出現した 2400 万年前ぐらい程度の時期から広く分布し、1500-1700 万年前の Middle Miocene Climatic Optimum (特に温暖だった) の時期に哺乳類とともに種分化を遂げた。
北米では地質年代的にはごく最近 [11000 年前程度と見積もられている: Zhang et al. (2012) A Late Miocene Accipitrid (Aves: Accipitriformes) from Nebraska and Its Implications for the Divergence of Old World Vultures] 絶滅した。
ユーラシアには現在のヒゲワシ亜科の数系統が残っている。
現在の分布からはユーラシアやアフリカに主に分布していたように見えるが、北米の中緯度からやや高緯度地域で繁栄していたことは興味深い。熱帯森林地帯を超えて南米までは進出できなかったのだろう。
一方ハゲワシ亜科は C3 から C4 植物への遷移に伴いユーラシアからアフリカで分布を広げたと考えられ、ヒゲワシ亜科からハゲワシ亜科が中心となった。
従来はコンドル類との競争によって絶滅したとの見方もあったが環境要因の変化の方が納得できる気がする。
開けた環境に従って分布を広げたグループに南米から北米に分布を広げたハヤブサ類、ムクドリ類などが挙げられている (チュウヒ類でも提唱されている)。
こちらは新しく 700 万年前ぐらい以降だが地域によっては植生の遷移が遅れ、遅くまでヒゲワシ亜科系統が中心だったと見られる。旧世界の良質の化石が見つかったことでコンドル類との競争説は根拠が薄くなった。
なおオーストラリアにもかつてハゲワシ亜科の Cryptogyps が生息していた。
メガファウナ絶滅 (#カンムリワシの備考 [メガファウナの絶滅] 参照) によって資源を失ったことも旧世界ハゲワシ類の衰退に影響を与えたと考えられるとのこと。
人類の進出も近年の衰退に関与していたのかも知れない。
ヒゲワシ亜科の新しい化石の発見については Marco (2022) Two New Gypaetinae (Accipitridae, Aves) from the late Miocene of Spain も参照。
ヒゲワシ亜科は現生のタカ類の祖先系統にもあたるので、猛禽性の獲得経緯を考える上で注意を払っておいてよいだろう。
しかしオーストラリアでカタグロトビ類 (科?) とタカ科の間に位置するクマタカ類に似た森林性猛禽類が 2400-2600 万年前の化石種として見つかっている (#ハチクマ備考 [ハチクマ亜科の他種] 参照)。旧世界ハゲワシ類の適応放散よりも早い時期である。
旧世界ハゲワシ類のようなスカベンジャー的な性格の強い猛禽類からもっと強力な猛禽類が進化したとみるのはむしろ古典的な見方かも知れない。
旧世界ハゲワシ類は化石の残りやすいところに生息していたため目立つだけで、草原の広がる前の森林に覆われていた地域では森林性猛禽類がそれなりの進化を遂げていたのかも知れない。これほど最近に見つかるぐらいなので化石も見つけにくいのだろう。
よく言われるハゲワシ類が肉食の原点かどうかはそれほど明瞭でない感じがする。
なお現在の新世界ハゲワシと呼ばれるコンドル類 (科) はさらに古い系統だが南北アメリカで化石が出土するのは新第三紀 (2300 万年前より) 以降で、新世界の現生種の分岐年代も 1700 万年程度。
分子系統的にはタカ科と分かれたのは 6000 万年前ぐらいと推定され、現在のタカ科の祖先とは関係が薄い [フクロウ類よりは直接の関係がはっきりしている程度とされるが #シロフクロウ Baalsrud et al. (2024) にあるように多少状況が変わってきている]。
フランスなどでこの系統と考えられる化石が知られていて (Diatropornis "European vulture" フランス; Cathartidae gen. et sp. モンゴル) 起源は旧世界と考えられているが、新大陸に至るまで途中をどのように過ごしたのかはタカ科の出現同様によくわかっていない。
[病原性細菌への適応]
新世界ハゲワシ類のコンドルの腸内細菌とそれに対する宿主の適応を調べた研究: Martinez-Hernandez et al. (2023)
First metagenomic analysis of the Andean condor (Vultur gryphus) gut microbiome reveals microbial diversity and wide resistome
普通の動物にとって病原性を示す細菌に抵抗性があることは確かなよう。どのように対応しているかはまだ明らかでないがいくつかの候補遺伝子が発現していて、広域の細菌に抵抗力を示す cationic antimicrobial peptides (CAMPs) が関わっている可能性が指摘されている。
Chung et al. (2015) The first whole genome and transcriptome of the cinereous vulture reveals adaptation in the gastric and immune defense systems and possible convergent evolution between the Old and New World vultures
クロハゲワシのゲノム解析で旧世界/新世界ハゲワシ類に特有の胃や免疫に関係する遺伝子候補を探したもの。
Zhou et al. (2019) Genome-wide analysis reveals the genomic features of the turkey vulture (Cathartes aura) as a scavenger
ヒメコンドルの比較ゲノム解析で特有の変異があり、非特異免疫に関わる β-defensin 遺伝子にも変異があるとのこと。
Panis et al. (2025) Chromosome-Scale Genome Assembly Provides Insights Into Condor Evolution and Conservation でコンドルのかなり高精度なゲノムが読まれたことが発表されているがオープンアクセスでないため系統関係など新たに判明したことがあるのかどうか Abstract からは不明。むしろ生態に適応するための遺伝的特徴を調べた論文のよう。
Lobello et al. (2025) The Role of Vulture (Accipitriformes) Cutaneous Microbiota in Infectious Disease Protection
ハゲワシ類の皮膚細菌叢が有害細菌を抑制したり免疫を制御するなどの働きをすることが期待されるが、これまでの研究のレビュー。前半にはハゲワシ類の生態全般のレビューも含まれていて参考になる。体温調節機能などの生理も含まれている。日光浴の役割や羽毛を損傷する細菌への対応など視点は多彩。
ハゲワシ類の生態的分類では rippers が最も捕食性が強く、採食の際も足で掴むことができて生きた獲物もしばしば捕る。翼の構造にも特徴があり逃げる獲物を追うことができる。特にカオジロハゲワシとミミヒダハゲワシの捕食性が高い。gulpers も生きた獲物を多少捕ることができるが scrappers の捕食能力はニワトリに似ているとのこと。gulpers は形態的特殊化を遂げて新しいニッチを開拓したものだろう。
現代の分子系統樹ではカオジロハゲワシとミミヒダハゲワシはハゲワシ亜科 Aegypiinae の祖先系統に近い位置なので、ハゲワシ亜科は捕食性が強い猛禽類から進化したらしいことが想像できる (これは論文には書いていない)。クロハゲワシはもう少し後の系統でここまでがハゲワシ亜科の中で1つの系統を作る。
ハゲワシ亜科に入らない旧世界ハゲワシもあり、ヒゲワシ亜科 Gypaetinae のエジプトハゲワシなど。エジプトハゲワシは scrapper に属する。
頭の皮膚細菌叢の方が腸内細菌叢より多様性が高く、有害なペスト菌 Yersinia pestis の定着を抑制する Hylemonella gracilis が顔に存在することが知られている。抗菌などの作用を持つ細菌もいくつも同定されていて詳細は論文の表参照。ただし研究が進んでいるのは新世界ハゲワシ類が多く系統の異なる旧世界ハゲワシ類とは多少違いがあるかも知れない。
ハゲワシの肉は食用に適さないのではと思ったが、アフリカでは薬効が信じられるなど肉が食用に流通して保全上の問題となっているとのこと (ズキンハゲワシの wikipedia 英語版より)。ズキンハゲワシは代表的な gulpers である Gyps 属の祖先系統にあたるので、ハゲワシ類ともっと捕食性が強い系統の中間はどのような形態や習性から進化したのか気になって探してみた結果。
ズキンハゲワシは残り物を食べるタイプなので、Gyps 属の直接の祖先系統にあたる捕食性が強い系統はおそらく現存していないのだろう。
[首の羽毛を失う理由]
ハゲワシ類、ハゲコウ類、ダチョウなど首に羽毛を持たない鳥はいくつかの系統でみられ、それぞれ独立に獲得したものと考えられている。生態的適応理由はわかりやすいが、なぜそのようなことが可能なのか。
Mou et al. (2011) Cryptic Patterning of Avian Skin Confers a Developmental Facility for Loss of Neck Feathering
首の羽毛と胴体の羽毛は発生上異なる点があり、簡単な制御機構の変化で首の羽毛を失うことができる (ニワトリなどに首に羽毛のない品種がある)。首の裸区 (apterylae) は体温調節に役立っているとのことで、首の羽毛をわずかな遺伝的変異で変化させやすいことは役に立っているのかも。
Ward et al. (2008) Why do vultures have bald heads? The role of postural adjustment and bare skin areas in thermoregulation
シロエリハゲワシで熱収支を調べたもの。姿勢を変えるだけで外気に晒される区域を 32% から 7% に変えることができ、寒冷下では 52% の放熱を抑えることができるとのこと。首が放熱器官になっていることを改めて認識。我々も同じようなものだが。
#ハチクマ備考の [フィリピンのハチクマの不思議] の (仮説 9) でも放熱に関係する可能性を取り上げている。
Heller (2011) How Bird Necks Get Naked (解説記事)。
Gyps 属の祖先系統にあたるズキンハゲワシで頭と首の前面に羽毛がないが後部にはある (ズキン = hooded の名称の由来でクロハゲワシと共通点がある。種小名も同じで、もし同属にまとめられればズキンハゲワシの方が命名が新しいので変える必要が生じるが大きく違うのでおそらく心配ないだろう。ズキンハゲワシの命名者は Temminck, 1823 だった)。
どこに羽毛が生えているか Hooded Vulture (David Barnett 2024.4.13) の画像がわかりやすかった。Jollie (1976, 1977) p. 32 fig. 23 にちょうどこの種の羽域の図がある。一般的に見られる lateral cervical apterium (裸区) がより腹側に広がっている。
この種で側面が羽毛に覆われない理由はハゲワシ類同様に衛生・放熱などの役割もあるだろうが、紅潮した時に顔も首も赤色になるので信号伝達目的もありそう。首の前面がうろこに覆われたような写真になっているが、個体によってはしわになっていたり、いわゆる「うろこ」とは異なりそう。
上記図をみるともともとは羽区で (ただし個体の年齢など標本によって異なるかも知れない) 反復刺激や紫外線などで角化が進んでうろこ状に変形したものなのだろうか。性的成熟とも関係があるのかも知れない。
羽毛からうろこへの遷移過程が見られるかも知れないと少し気にしてみた。
参考画像 Hooded Vulture (Gopi Krishna 2024.1.24) 所々羽毛が見られる。
ひなではもっと広く羽毛に覆われているよう Hooded Vulture (Maciej Kotlarski 2024.2.11)。
ハゲワシ類でも相互羽繕いがあった: Hooded Vulture (Necrosyrtes monachus) pair mutual preening (Warren Photographic)。相互接触でつがいの絆を強めるのに裸区が役立っている可能性があるのか...知らない。
頭頸部と体部の羽毛の制御機構が異なる点については#カワラバト備考の [家禽ハト品種の形態に関連する遺伝子] を参照。冠羽の形成メカニズムに関係している。
家禽ハトに様々な品種があるが、体部の羽毛より別の部位の特徴が多く (飼育下で好まれた選択効果もあるかも知れないが) 体部の羽毛は少々の変異ではあまり変化しない頑強な遺伝子メカニズムがあるのかも知れない。これは体部の羽毛の起源が古いことを示している可能性があり、羽毛の進化は装飾のためよりは保温のため機能が先行したのではないかと感じる (このような議論は多分どこかの本や論文に書いてあるだろうが)。
#ライチョウ備考の [換羽・換毛の共通機構] も参照。同項目の [鳥類と爬虫類のうろこは別物] にも発生途中を阻害しても足の「うろこ」が羽毛になってしまうことを示す研究がある。
[ハゲワシ類のソーシャルディスタンス?]
D'Bastiani et al. (2024) Social interactions do not affect mycoplasma infection in griffon vultures
によればイスラエルのシロエリハゲワシの GPS トラッキングのデータを分析し、社会的な関係や集団内の地位とマイコプラズマ感染率の相関が見られなかったとのこと。この種の場合にはソーシャルディスタンス (? なお英語での social distance の用語は日本語で使われるものとは多少違う。social distancing が感染症予防を指すもの) と感染率はあまり関係なかった?
[異所性の翼を持った鳥の事例]
Osofsky et al. (1990) An ectopic wing in a wild black vulture (Coragyps atratus)
クロコンドルで異所性の翼を持った野生個体が保護され、切除が予定されていたが感染で死亡したとのこと。余分な翼は指2本もあって初列・次列の風切羽もあるなどほぼ完全な形態だったが運動機能はなかったとのこと。発生学的プログラムが一度始まれば翼の全構造は意外に簡単に作られるものらしいが、野生個体で生き延びていたのは珍しそう。
翼の進化メカニズムを考察する上で参考になるかも。
[新世界ハゲワシ類の生態的位置]
Monar-Barragan et al. (2025) Vulture dominance in a scavenger assemblage in the Neotropical dry forest
エクアドルで実験的に死体を置いて映像記録したところ、死肉食専門の新世界ハゲワシ類が圧倒的に多く現れ、時に死肉を食べる哺乳類がそれに次いだ。時に死肉を食べる鳥類は記録されなかったとのこと。
少なくともエクアドルの乾燥した森林ではスカベンジャーとして新世界ハゲワシ類が圧倒的に重要な役割を果たしている。
-
カンムリワシ
- 学名:Spilornis cheela (スピロルニース ケエラ) 斑点のある鳥ケーラ
- 属名:spilornis (合) 斑点のある鳥 (spilo 斑点 ornis 鳥 Gk)
- 種小名:cheela (合) カンムリワシ (cheel トビ ヒンディー語)
- 英名:Crested Serpent Eagle
- 備考:
spilornis は -ornis の i が長母音。スピロルニースのアクセントと推定される。
cheela の発音は不明だが "ケエラ" または "ケエーラ" が考えられる。
日本の亜種名の perplexus は短母音のみで -plec- がアクセント位置 (ペルプレクスス)。英語の perplex も同じ位置にアクセントがある。
IOC などでは採用されていないが、種カンムリワシをどのように分割するか多少の議論がなされているようで、Avibase では perplexus を独立種とした概念も用いている。
Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" では独立種扱い。
カンムリワシ類は最も複雑なグループの一つで、特に島の亜種のついてどこまでを種とするか扱いが著者により異なる。標準的な分類では日本や台湾から最も近いフィリピンは別種扱い。
Avibase で Spilornis cheela を引くとミナミカンムリワシの和名が出るのは日本のカンムリワシとは遺伝的に遠いことを反映したものなのだろう。
種記載時学名 Falco Cheela Latham, 1790 (原記載) 基産地 India; restricted to Lucknow by W. L. Sclater, 1919, Bull. Brit. Ornith. Club, 40, p. 38 (Avibase による)。Latham が Cheela Falcon の英名を用いていた。
cheela はヒンディー語でトビを指す Chil 由来だったが誤ってカンムリワシの名称となったとのこと (Blanford 1895, The Key to Scientific Names)。
かつて Haematornis Vigors, 1832 の属名が用いられたことがあった (haima, haimatos 血 ornis 鳥 Gk)。Falco Cheela からの属独立に際して Haematornis undulatus Vigors, 1832 の学名が与えられた (The Key to Scientific Names の Haematornis の項目) (#ノスリの備考参照)。undulatus は波模様のある、の意味。
Spilornis Gray, 1840 は Haematornis 属の当時3種記載されていた種に対して与えられたもの。Haematornis holospilus は全身に斑点があり、H. bacha は腹のみ斑点、H. undulatus は雨覆のみ斑点と記述した (The Key to Scientific Names)。
属名の "斑点のある鳥" の意味はこれが由来。
日本の亜種は記載時学名 Spilornis cheela perplexus Swann, 1922 (原記載) 基産地 'Triomate Yayeyama, S. Loo Choo Is.' = Yayeyama, Iriomote Island, Riukiu Islands。
これによれば Ogawa (1905) のリストに載っていて、Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Spilornis pallidus Walden 場所 Iriomote-shima と載っているものと同一とある。
Spilornis pallidus Walden, 1872 (参考) 基産地 Sarawak。
pallidus は現在も有効なカンムリワシの亜種となっている。
日本でも知られていたが海外の種と同一とみなして亜種記載が行われなかった模様。
[島の亜種としてのカンムリワシ]
熱帯アジアに広く分布し、非常に多く 21 (IOC) の亜種がある。かなりの亜種は島の固有亜種。小さな島で生物が島嶼化 (フォスターの法則 Foster's rule) によって巨大化するかあるいは矮小化する考えがあるが、カンムリワシにおいては矮小化 (insular dwarfism) が顕著に見られる。
例えば小さな島である琉球の亜種 perplexus (perplexus 曖昧な) は典型的な insular dwarfism を示して小型であるが (ワシと名が付くのにタカとあまり違わない)、台湾の亜種 hoya (hoya 台湾での地方名) は大きく、中国語で大冠鷲と呼ばれる。日本で使われる亜種名でもオオカンムリワシ。
種全体では eagle と呼ばれても不思議でない。
最大亜種はインドの基亜種で cheela で 1.8 kg に達するという。最小亜種はアンダマン諸島の davisoni で最小 420 g という (数字は Raptor Research & Conservation Network (2018) "A Field Guide to the Raptors of Asia")
[island syndrome について Michal et al. (2023) The island syndrome in birds の新しいレビューがある]。
大陸のカンムリワシと他の猛禽類の種間関係については#ハチクマの備考も参照。
[分類と系統]
日本の猛禽類の中では比較的孤立した系統であり、ユーラシアに広く分布するヘビワシ類 (snake eagles / serpent eagles) の系統に含まれる。ヨーロッパに分布するチュウヒワシ Circaetus gallicus (#ハチクマの備考にも少し登場) もこの系統。
Catanach et al. (2024) の分子系統分類に従って記述すると、
大きく分けた場合はヘビワシ亜科 Circaetinae + ハゲワシ亜科 Aegypiinae が一つの系統をなし、イヌワシ亜科 Aquilinae、オウギワシ亜科 Harpiinae から始まる系統がそれに続くことになる。
イヌワシ亜科とオウギワシ亜科のどちらが先かは微妙な違いで順序は変わるかも知れない。
以下これまでと同様に並べると
チュウヒワシ亜科 Circaetinae
カンムリワシ属 Spilornis
スラウェシチュウヒワシ* [高野 (1973) ではセレベスヘビワシ] Spilornis rufipectus Sulawesi Serpent Eagle
フィリピンカンムリワシ* [高野 (1973) ではフィリピンヘビワシ] Spilornis holospilus Philippine Serpent Eagle
カンムリワシ Spilornis cheela Spilornis cheela
以下3種はまだ遺伝学的データなし。上記のどの位置かはわからない。IOC 順に並べておく。
ニコバルカンムリワシ [高野 (1973) ではニコバルヘビワシ] Spilornis klossi Great Nicobar Serpent Eagle
キナバルカンムリワシ Spilornis kinabaluensis Mountain Serpent Eagle
アンダマンカンムリワシ [高野 (1973) ではアンダマンヘビワシ] Spilornis elgini Andaman Serpent Eagle
フィリピンワシ属 Pithecophaga
フィリピンワシ (旧名サルクイワシ) Pithecophaga jefferyi Philippine Eagle
ダルマワシ属 Terathopius
ダルマワシ Terathopius ecaudatus Bateleur
チュウヒワシ属 Circaetus
ミナミオビチュウヒワシ* Circaetus fasciolatus Southern Banded Snake Eagle
オビチュウヒワシ Circaetus cinerascens Western Banded Snake Eagle
オナガヘビワシ* Circaetus spectabilis Congo Serpent Eagle
ムナグロチュウヒワシ Circaetus pectoralis Black-chested Snake Eagle
チャイロチュウヒワシ* Circaetus cinereus Brown Snake Eagle
チュウヒワシ Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle
以下1種はまだ遺伝学的データなし。上記のどの位置かはわからない。
ボードワンチュウヒワシ** Circaetus beaudouini Beaudouin's Snake Eagle
カンムリワシ属はこのグループの最初の分枝にあたり、他とは比較的離れている。
カンムリワシ自身に非常に多くの亜種があり、カンムリワシ属の他種も分布の狭い島の固有種的なもの。カンムリワシ属自身が分散性が低く、東南アジアの多くの島で独自の進化を遂げたものであろう。
カンムリワシの亜種からも同様の種が今後分離される可能性がありそうである。
分散性の低いグループが島で多くの種に分化している点は Nisaetus クマタカ属に似ている。
クマタカ属では2系統に分かれ、それぞれが複数種に分化しているがカンムリワシ属ではカンムリワシが大部分の地域に生息している点が異なる。カンムリワシ属の分岐年代は (調べられている種が少ないが) 比較的新しく (2000 万年前ぐらい)、地理的分布は広いが比較的新しく適応放散した模様でそれほど種分化を遂げていない。
分岐年代背景的にはコウモリダカ (別項目参照) に近い。同じような議論が当てはまる可能性があり、ハチクマ亜科あるいはカタグロトビ類の系統がカンムリワシ属初期の競争相手だったかも知れない。どれもヘビを食べるがカンムリワシ属系統では特化したものか。現在の食性は後発のクマタカ類との競争の結果も影響を与えているかも知れない。
Artuti et al. (2020) A phylogenetic analysis of Crested Serpent Eagle (Spilornis cheela) based on cytochrome-c oxydase subunit I (COI): a stepping stone towards genetic conservation of raptors in Indonesia
によれば東アジアと東南アジアの3地点のみだが遺伝的にはあまり大きな違いがない結果となっている。
たくさんの亜種が記載されているが分子系統研究が進めばさらに整理される可能性があるかも。
フィリピンワシとダルマワシは比較的孤立した系統で容貌もかなり異なり、分布もフィリピンとアフリカと大きく異なる。
チュウヒワシ属はヨーロッパからカザフスタンで夏鳥でアフリカで越冬、インドで留鳥のチュウヒワシが分布域の広い種で、他はアフリカで留鳥。系統がそれなりに遠くこれらの種の多くは同所的にも生息している。カンムリワシ属よりもより積極的にヘビを捕食しており最も典型的なヘビワシ類と呼んでよいだろう。
系統的にも進化の進んだグループと考えて差し支えない結果となっている。
属名の Circaetus はほとんど自明であろうが、Circus (チュウヒ) 属 + aetus (ワシ) を付けたもの。-ae- が長母音であることを考慮して "キルカーエトゥス" の読みでよいだろう ("エ" の方を伸ばしてもよい)。
和名のチュウヒワシはこの属名が由来と想像される。別名にハラジロワシがあるとのこと (コンサイス鳥名事典)。この和名はおそらく学名 Accipiter hypoleucus Pallas, 1811 (下面の白いタカ。基亜種は不詳だがアジア地域のロシア) 由来と想像される。
現在は基亜種シノニムとなっているが、Falco gallicus Gmelin, 1788 (基産地フランス) と同一と認定されて学名が変わる前に使われていたのだろう。
種小名に使われる gallicus はニワトリを意味する印象も受けるが、Gallia (フランスの古名ガリア。元素ガリウム Ga の名称由来。フランスはフランシウム Fr と2つの元素名を持っている) 由来とのこと (The Key to Scientific Names)。
Kessler (1851, 参考文献参照) によればチュウヒワシに Aquila brachydactyla Meyer (趾の短いワシ) の学名もあり、英名 (かつては Short-toed Eagle で Snake は後に追加された) はこれが起源と考えられる。ドイツ名も同じ意味の Der kurzzehige Adler が用いられていた。
Hartert (1910-1922) では p. 1188 でヨーロッパやアジア中北部に分布するチュウヒワシのみが対象で、南部に分布するカンムリワシ属は扱われていない。
チュウヒワシをミサゴの前に配置しており、図版からはふしょや足のうろこの類似性に注目してこの位置に置いたように見える。チュウヒワシのドイツ語名 Schlangenadler で "ヘビワシ" の意味。1種しか対象種がない場合はこの名前でよかったのだろう。英名も Snake-Eagle を別名に挙げていた。ヘビワシ類全体の系統を議論していれば面白かったのだろうが当時の資料では難しかったのだろう。
もっとも南方に分布するサシバ属は扱われているので種類が多いヘビワシ類全体を扱うのは回避したのかも。
#ハチクマの備考に登場するマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科) はかつてはこれらのヘビワシ類の系統に属すると考えられていた。
高野 (1973) 時代以降にかなり改名が行われているが、snake eagles (Circaetus 属) と serpent eagles (Spilornis 属) にそれぞれ別系統の和名を与える目的と考えられる。提案和名が付けられた当時の分類を反映しているかも知れないが、現在の系統分類を見ると必ずしもすべてが一貫した名前になっていない。
Spilornis 属をカンムリワシに統一するならスラウェシチュウヒワシよりもスラウェシカンムリワシの名称の方がよいだろう。
ダルマワシは尾が非常に短い (相対比では猛禽類中最も短い) 独特の形態で有名。Terathopius < teras, teratos 驚き ops, opos 容貌、顔貌 (Gk)、ecaudatus < ex- ない -caudatus 尾が。英名はフランス語由来 (同名) で軽業師、大道芸人などの意味 (アクロバティックな空中ディスプレイやバランスを取りながら飛ぶ姿が棒を持ってロープを渡る軽業師に比喩された)。
例によって余談になるが軽業師から思いついて「道化師の朝の歌」(Alborada del gracioso スペイン語) というモーリス・ラヴェルの名曲があるので紹介しておく。この曲もクラシックにあまり縁のない方でも十分楽しめるだろう。この「道化師」は「笑わせてくれる人」を指しているようである。
この曲は「鏡」(Miroirs) という曲集の1曲で、他に「悲しげな鳥たち」(Oiseaux tristes) がある。このフランス語の題名はチフチャフの学名 (亜種) をご存じならばすぐ理解できるであろう。曲集の中ではそれほど際立った曲ではないのだが。第1曲の「蛾」(Noctuelles) も不安定で不規則な飛び方を描写しているようで面白い。
ダルマワシに戻ると足は短いが翼は独特の形で先端が長い。次列風切も 25 枚とのこと。
形態的には一見不器用に見えるが、さまざなまハンティング方法を用い、多種の猛禽類が生息して競争の激しいアフリカでさまざまな獲物を獲っているとのこと。ヘビワシに近い仲間だがヘビの割合はそれほど高くない。また毒のあるヘビも嫌わないとのこと。
主な採餌形態はハゲワシ類に近く、猛禽類としては特殊な翼の構造は食物探索の際にミズナギドリ類のような長時間の帆翔飛行を可能にするとのこと。時速 55-90 km で1日に 300-400 km も飛行するそうである (道路もないようなアフリカで行動を追跡することは研究者にも困難とのこと)。
ただし翼のアスペクト比は8とフルマカモメ類の 12 には及ばず、シロエリハゲワシの7と同程度である [Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology"]。
空中では方向転換などハヤブサや他のワシ同様に十分に器用で、そして戦闘機のアクロバット飛行にも似た一種不安定な飛翔をするが、尾が非常に短いため減速が難しく、地上への急降下的な捕食方法には向いていない。
比較的開けたところに巣を造るがこのような着地の際の飛行性能の制約によるものかも知れない。
獲物には霊長類やジャッカルも含まれる。猛禽類さえも捕食することも知られていて、クロワシミミズク Bubo lacteus 英名 Verreaux's Eagle-Owl の捕食例もある
(Bateleur kills a Giant Eagle Owl in Kruger National Park)。
野生では人には用心深く人による繁殖への影響も出やすいが飼育下では非常によく慣れるという。
以上 wikipedia 英語版や Richard T. Watson (in "The Eagle Watchers" 2010) などからの情報だが wikipedia 英語版に様々な興味深い生態が記録されており、他の鳥の行動の解釈にも有益な可能性もある。興味ある方は一読をおすすめする。
オナガヘビワシ (#イヌワシの備考で視力検査に出てくる) は Avibase 等では和名がヘビワシと出るが、高野 (1973) でオナガヘビワシの名前が与えられている。コンサイス鳥名辞典でも同じなので、Avibase 登録時の誤りかも知れない。山階鳥類研究所の標本データベースではヘビワシ属となっているのである時点で短縮されたのだろうか。
独立属 Dryotriorchis (< drus, druos 木 triorkhes タカ; triorchis についてはハチクマの備考参照 Gk) とされていた。尾が長いため最初はオオタカの仲間と考えられ (記載時学名 Astur spectabilis Schlegel, 1863)、その後異なることが判明してこの属名が与えられた。
日本で使われることのある ヘビワシ属 Dryotriorchis (wikipedia 日本語版 タカ科 2024.10.26 の記述による) はこの属そのものが Circaetus のシノニムとなり和名は消滅の見込み。この属のタイプ種がチュウヒワシであるとともにこれまでの同属の他種和名にはすべて "チュウヒワシ" が付いているために チュウヒワシ属 の和名は適切と考えられる。
種名についてはオナガヘビワシの和名は特徴をよく表しており、Dryotriorchis 属の記載もこの点は強調されている。
"ヘビワシ" の名称は "ヘビワシ類" (snake eagles) の概念と紛らわしく記述的な特徴を欠くのでオナガヘビワシの名称を残すのが望ましいだろう。一般的な英名を翻訳するならばコンゴヘビワシの可能性も考えられるが地理的分布はもう少し広い。
鳴管構造はクマタカ属に似ているとのこと。分子遺伝学研究で一度はチュウヒワシ属に含まれるとされたが、2018 年の研究 (この著者グループの一つ前の研究) でオナガヘビワシを含むと Circaetus 属が単系統にならない (この研究ではオナガヘビワシがダルマワシより先に分岐する結果となった) ことがわかり、IOC は 2022 年に元の学名に戻した。
Catanach et al. (2024) では再び Circaetus 属に含まれる結果となり、属名を再度戻すことを提案している。この2種について新たな遺伝情報が追加されたわけではないが、Circaetus 属の他種の核遺伝情報を用いることで Circaetus 属の系統樹がよりしっかりしたものになった結果のようである。
IOC 15.1 (2025) でこの変更が反映される予定。
AviList (2025.6) では Circaetus 属を3分割して Dryotriorchis の名称を残すことは可能であることも示しつつ、Circaetus 属に含めた。
8115 354 Taxon spectabilis is placed in Circaetus, rather than in Dryotriorchis, based on genomic DNA evidence (Catanach et al. 2024) that recovered Circaetus as paraphyletic. However, a three-genus arrangement could also be tenable if a generic name becomes available for the basal clade containing C. cinerascens and C. fasciolatus; this would render Circaetus as monophyletic and allow retention of Dryotriorchis for spectabilis.
3分割する場合は2種に対して新しい属名を考案する必要があるため Circaetus 属にまとめる方が採用された。
チュウヒワシ属中のミナミオビチュウヒワシとオビチュウヒワシは類縁関係が大きく、詳細な遺伝情報は後者のみだが、この2種がグループをなすことは確実。
世界で最も強いワシの一つとされるフィリピンワシもこの系統に含まれていることは注目に値する (なおフィリピンワシはかつては世界最強のワシであるオウギワシ Harpia harpyja に近縁と考えられたことがあったが系統解析の結果否定された)。
属名の Pithecophaga は pithekos サル phagos < phagein 食べる (Gk) と旧英名の Monkey-eating Eagle も旧和名も属名を表していた。jefferyi は Jeffery Ludlam Barton Whitehead 由来: 原記載。Jeffery Whitehead の標本記述が引用されている。
フィリピンは大陸からかなり離れていてイヌワシ系統の大型猛禽類が進出しなかったので比較的古い系統でも頂点捕食者となったのだろうか。
猛禽類では史上3番めに大きく、比較的近年絶滅したオーストラリアの巨大猛禽類 Dynatoaetus gaffae
[Mather et al. (2023a) A giant raptor (Aves: Accipitridae) from the Pleistocene of southern Australia];
解説記事] も類似系統 (ヘビワシ亜科 Circaetinae + ハゲワシ亜科 Aegypiinae; Dynatoaetus gaffae は後者の早い段階の分枝に相当する) に属することも注目に値する。
同属と考えられるオーストラリアの巨大猛禽類 Dynatoaetus pachyosteus の化石も最近新たに記述された。
Mather et al. (2023b) Pleistocene raptors from cave deposits of South Australia, with a description of a new species of Dynatoaetus (Accipitridae: Aves): morphology, systematics and palaeoecological implications
によれば
ヘビワシ亜科 Circaetinae + ハゲワシ亜科 Aegypiinae 系統だが、系統的にはハゲワシ亜科により近いとのこと。
発見がなぜこれほど遅くなったのかは、骨が見つかってもオナガイヌワシのものと考えられて検討されず見過ごされていたらしいとのこと。
オーストラリアの大陸の大きさを考えると現在の大型猛禽類1種 (オナガイヌワシ) は少なすぎ、また現在はハゲワシ類がいない。これらの大型猛禽類が共存していた時期は他の大陸と比べられる種類数の大型猛禽類がいたと考えられ、新しく見つかった種類はオナガイヌワシより強力であったと考えられる。
これら3種や当時存在したハゲワシ類 Cryptogyps lacertosus
はそれぞれの生態的地位を占めていたと考えられ、オナガイヌワシの生態的地位を現在より狭いものにしていたと思われる。
これらの化石ワシ類のかつての食物の推定に役立つと思われるオナガイヌワシの習性については #イヌワシ の備考 [オナガイヌワシと共同ハンティング] を参照。
自身よりずっと大きな獲物を捕食する猛禽類はないわけではないが少ない。カンムリクマタカは同程度の大きさの猛禽類よりしっかりした体のつくりで、自身の2倍の体重を持つと推定されるウシ科 Cephalophus harveyi ハーヴェイダイカー の幼獣を捕食したとのこと。
オーストラリアの過去の大型猛禽類もカンガルーを捕食する能力は十分あったと思われる。
ヘビワシ亜科 Circaetinae + ハゲワシ亜科 Aegypiinae もイヌワシ属を超える十分強力な猛禽類を生み出せる系統であったことがわかる。
これら大型猛禽類やハゲワシ類の絶滅後はオナガイヌワシ1種がこれらの種全ての生態的地位を占めることになったが、森林内を器用に飛ぶのに向いた翼ではなく、また真のスカベンジャーの役割は十分果たすことはできていないとのこと。
比較的近年に起きた大型猛禽類の絶滅の影響は生態学的にまだ十分緩和されていないかも知れない。
Bildstein (2017) "Raptors" (pp. 120-121) は他の大陸では普通に存在する崖に営巣する猛禽類がオーストラリアには非常に少ない特徴を取り上げている。オーストラリアの猛禽類研究家の Oslen はいくつかの仮説を挙げているがいずれもあまり説得力のないものとのこと。
あるいは過去に大型猛禽類が複数繁栄していたが突如絶滅した歴史的経緯が残っているのかも知れない。
Catanach et al. (2024) の系統順ではオウギワシ亜科 Harpiinae はイヌワシ亜科の後になるがわずかな違いであり、IOC ではイヌワシ亜科の前になっている (#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] の結果も参照。オウギワシよりイヌワシの方が染色体レベルの遺伝情報が原型に近い結果が得られている)。
イヌワシの項目の情報量が多いので、オウギワシ亜科 Harpiinae はこちらで紹介しておく。{ヘビワシ亜科 + ハゲワシ亜科}、イヌワシ亜科、ハイタカグループのいずれとも近い関係にはなく独立した系統である。いずれも日本と縁の少ない種類でオウギワシ以外は名称もあまり知られていないかも知れない。
以下 Catanach et al. (2024) に従ってこれまでと同様に並べると、
オウギワシ亜科 Harpiinae
パプアオウギワシ属 Harpyopsis
パプアオウギワシ [高野 (1973) ではニューギニアオウギワシ] Harpyopsis novaeguineae Papuan Eagle
コウモリダカ属 Macheiramphus
コウモリダカ Macheiramphus alcinus Bat Hawk
オウギワシ属 Harpia
オウギワシ* Harpia harpyja Harpy Eagle
ヒメオウギワシ属 Morphnus
ヒメオウギワシ* [高野 (1973) ではカンムリオウギワシ] Morphnus guianensis Crested Eagle
ヒメハイタカ属 Microspizias
ヒメハイタカ Microspizias superciliosus Tiny Hawk
ナンベイアカエリツミ* Microspizias collaris Semicollared Hawk
ハバシトビ属 Harpagus
ハバシトビ [高野 (1973) ではアカハラトビ] Harpagus bidentatus Double-toothed Kite
モモアカトビ* Harpagus diodon Rufous-thighed Kite
となる。いずれも系統的には離れているが、パプアオウギワシ、オウギワシ、ヒメオウギワシが共通の系統にまとまることは BF-I7 (β-フィブリノゲンのイントロンの一つ) に8塩基の欠損が共通して見られることから確かである [Lerner and Mindell (2005) #カタグロトビの備考参照]。
ヒメオウギワシがこの系統の最初の分枝であることは Catanach et al. (2024) の核遺伝情報も用いた解析から支持される。この属名の Morphnus は morphnos ワシ < morphnos ワシ (Gk)。morphnus をワシの意味で含む属名は他にも存在する。
Accipitridae (BirdForum 2025.3) によれば Morphnus と類似綴りの Morphinus Fleming, 1822 の属名があり、こちらのタイプ種が現在採用されているとのこと。Morphnus Dumont, 1816 が最初の属記載で、タイプ種は Morphinus の綴りが用いられた以降に決められたとのこと。
最初に用いられた Morphnus は当時の学名で Morphnus dubius = 現在のエボシクマタカ Lophaetus occipitalis Long-crested Eagle とのことで、綴り通りの Morphnus 属のタイプ種を問われると困る要因になるとのこと。
Morphinus の綴りを用いればタイプ種の問題は解消するが、同一の綴りの訂正であると判断される場合は Morphnus の方が早く使われたことになる。
誰かが公式に問題を持ち出さない (例えば Morphinus の方が正しいと訂正した学名が使われるなど) 限り現在の学名が使われるであろうが、とのこと。
コウモリダカは特徴も多いので別項目とした。
Harpagus 属と Microspizias 属も古い分枝で、Catanach et al. (2024) の系統樹でもオウギワシ類と別図に入っているので要注意である。
Catanach et al. (2023) の解説ではこれらを (独立亜科を作らず) オウギワシ亜科のメンバーと認識するとの記述に基づいてここに含めておく。
ただし Catanach et al. (2023) の系統樹はこの2属を含めるとオウギワシ亜科は単系統にならない。これら2属の解説は #トビの備考の [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] に記載している。
なお名称の先取権については Gregory et al. (2024) Falling through the cracks: a family-group name for a clade of hawks and eagles (Accipitridae) including Morphnus Dumont, 1816, Harpia Vieillot, 1816, Harpyopsis Salvadori, 1875 and Macheiramphus Bonaparte, 1850
が一世代前の Mindell et al. (2018) の分子系統樹に基づく議論を行っている [2024.2.29 出版なので Catanach et al. (2024) の分子系統樹を用いていない理由になるが Tachyspiza 属の名称は正式に認められる前から用いている]。
オウギワシ系統は Thrasaetinae Blyth, 1850 の名称が存在していて、Harpiinae Verheyen, 1959 (1850) に置き換えられたと考える場合に Harpiinae の名称が正当化されるとのこと。ただし Catanach et al. (2024) の研究で包含関係はかなり変わってしまった。
オウギワシの英名や学名の由来となるラテン語 harpyia はギリシア神話に登場する女面鳥身の伝説の生物。食欲が旺盛で、食糧を見ると意地汚く貪り食う上、食い散らかした残飯や残った食糧の上に
汚物を撒き散らかして去っていくという、この上なく不潔で下品な怪物である。
ダンテの叙事詩『神曲』地獄篇の中では、地獄第七圏第二の環・「自殺者の森」において、自ら命を絶った者が変容した樹木を啄ばむ怪鳥として描写されている。
本来は風の精で、つむじ風や竜巻の様な、地上の物体や人間を攫って空に持ち上げ運ぶ現象を具象化した存在である。また、墓場においてハルピュイアに供物を捧げる習慣があり、死者の霊とも見做された様である (これらを見るとそれほどよい印象ではないが。wikipedia 日本語版より)。
和名のオウギワシの由来はよくわからなかった。オウギアイサのように最初は冠羽を広げた姿を指すのかと思ったが、オウギバト (コンサイス鳥名事典。現在ではオビオバトの方が使われ、オウギバトは別種に使われる) Band-tailed Pigeon の過去名があったので、むしろ尾の模様を指したように思えてきた。"ワシ" なのに "タカ" のような帯のある尾を持っているのでワシらしくない特徴として取り上げたのかも知れない。
和名では帯のある尾を持つものは大きさにかかわらず圧倒的に "タカ" の名前を与えており、オウギワシはさすがに例外となったが名称に特徴を残したのかも。
記載時学名 Vultur Harpyja innaeus, 1758 (原記載) といかにもふさわしくない属に分類されていたため、属変更がいくつもあってその都度種小名が新たに設けられていた (#ノスリの備考参照)。
Falco destructor Daudin, 1800 (参考) は破壊者。
Harpyia maxima Vieillot, 1817 (参考) は Latham の Falco destructor, cristatus をもとに "最大の harpy"。
Harpyia ferox Lesson, 1839 (参考) "凶暴な harpy"。他の例もあった。
ヨーロッパの多くの言語で harpy に相当する名称を使っている。中国語では角鷲に相当。
フランス語では harpie feroce とわざわざ "獰猛な" を追加しているが、これは Harpyia ferox Lesson, 1839 と関連する名称と考えられる。
スペイン語・ポルトガル語では単純にワシタカ・ハヤブサ類を集合的に表す gaviao に real (英語 royal に相当) を加えているだけで単純である。イヌワシが同言語で aguila real となるのとほぼ同じ。
なお harpy はヨーロッパチュウヒにも使われる名称。Falco harpyja Boddaert, 1783 (参考) はこちらを指す。この用例があるため Daudin (1800) が Falco 属に含める場合に種小名を保存することはそもそも無理だった。
このような例もあったので属変更の際に種小名を新たに与えることが当たり前になって行ったのかも知れない。
Gregory (2024) Further notes on family-group names introduced as substitute names under Article 5 of the Regles (1905) between 1931 and 1960 inclusive
によれば系統名に Harpiini Verheyen, 1959 が用いられることがあるがこれは疑問点があるとのこと。
相当する Harpiinae は Morphnus, Harpia, Harpyopsis, Macheiramphus を含むとあるが、Harpagus, Microspizias は含めていない。
この論文では Catanach et al. (2024) の定義は検討されていない。
Microspizias 属はかつては Accipiter 属に含まれていたが、分子系統解析の結果で縁が遠いことがわかり分離された。
分布も他の広義 Accipiter 属の放散経路と異なって南米の種で、Accipiter と縁が遠いことも納得できる。
Sangster et al. (2021) (#アカハラダカの備考参照) による属名で意味は「超小型のタカ」。
IOC 12.2 以降もこの分類をすでに採用している。AOU, eBird も 2022 年より同様。より広義のハイタカグループからさえも外れる結果になった。
このために和名が変わることはないだろうがハイタカの名が付くといかにも混乱しそうである (同様の問題を抱えるイヌワシ/クマタカの名前のある種類とは違って系統はもっと離れている)。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) ではかなり保守的で Accipiter のままにしている。2008 年以降の新しい研究をフォローしていないように見える (保守的というより遅れて検討も行われていないだけかも知れない。少なくともタカ類に対しては一見して情報が古く、分類の基礎に使うには適切でなさそうである)。
Harpagus 属はかつては (広い意味の) トビ類に含められ、ハチクマ類やカッコウハヤブサ類と近い関係にあると考えられていたが大きく違っていた。ハチクマ系統トビ類でないトビ亜科 (従来分類での名称) Milvinae に含められたこともあった。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) ではウタオオタカ類とチュウヒ類の間に置いており Accipiter に近いと考えているようであるが文献は示されていない。検討の結果この場所に置いたというより文献検討が遅れている可能性がある。
ヒメオウギワシはオウギワシと分布が似ていてオウギワシの方が数が多いとある。オウギワシのひなに給餌した事例がある (wikipedia 英語版)。熱帯森林性の猛禽で研究が難しくあまりわかっていないようである。英名をそのまま訳すとこちらがカンムリワシになってしまう。crested eagle で画像検索しても別の種類が圧倒的に多く出てくるので要注意。
Brewer et al. (2023) The visual fields of the Harpy Eagle (Harpia harpyja)
によればオウギワシの視野の測定では見えない範囲が広く、両眼視の範囲が比較的狭かった。
獲物を捉えるよりも複雑な光景の林内での行動における役割に関係しているかもとのこと (他の森林性タカ類にも当てはまるかも知れないので注意しておいてよいだろう)。
なかなか目にすることのない話と思われるので一緒に紹介しておくが、ベネズエラの原住民がオウギワシを捕まえて矢羽根に使っていた (報道記事は見たことがあったが) 論文がある:
Viloria et al. (2021) Ethno-ornithological notes and neglected references on the Harpy Eagle Harpia harpyja in western Venezuela。
[コウモリダカ]
コウモリダカは #ハチクマの備考 [ハチクマ類の系統分類] にも示したが、かつては形態・生態的に類似するカッコウハヤブサ類 (カッコウハヤブサ類も薄明中の狩りを行い、コウモリも捕食する) と近縁と考えられいたが大きく違っていた。
属名の Macheiramphus は makhaira ナイフ rhamphos 嘴 (Gk)、種小名の alcinus は alcinus < Alca ウミガラス/ウミスズメ類由来とされるが Clark and Davies (2018) によれば alkimos 強い、頑強な、勇敢な (Gk) がなまったものとも解釈される (The Key to Scientific Names)。
記載時学名も Macheiramphus alcinus Bonaparte, 1850 (原記載) 基産地 Malacca。
Bonaparte は比較的細かく記述しておりアメリカ大陸のタカ類の Cymindis に対応するものだが嘴が極端に小さく、圧縮された形となっており、Schlegel 自身が Alcae (ウミスズメ類) に属を与えたように種小名に与えるとよいと考えた模様。この記述を見るとウミスズメ類の中でも Synthliboramphus (圧縮された嘴の) を指しているように見える。
命名者の語義的にはタカ類にしては極端な嘴の細さをウミスズメ類に例えたらしい。標本からは生態などはわからないため形態から命名するしかなかった模様。コウモリをほとんど丸のみするため肉を引き裂く必要性が少ないのかも。
ちなみにフランス語名では Alcin des chauves-souris (chauves-souris = コウモリ) が用いられていて Alcin の由来を調べると Alkides = Alcaeus の子孫の意味で、Alcaeus は強さと勇気の象徴とのこと。こちらは後付けの名称かも知れないが Clark and Davies (2018) の解釈に対応している。
各国語の名称も分類がわからなかったため苦労しているようでトビ類に入れているものが多い (中国語でも)。英語や日本語は "タカ" で表せたので楽だった。そう見るとドイツ語は Fledermausadler と "コウモリワシ" の意味になっている。結果的には系統的にはこれが最も近かったのかも。
すでに解析論文は出ているが、試しに EF078745.1 をベースに BLAST をやってみるとかなり古い分岐であることはわかる。
ハチクマ亜科とは縁が遠く、むしろイヌワシ類の系統に近いことがわかる。同時に示される系統樹には最強のワシの一つであるゴマバラワシの分岐後に最弱 (?) のワシの一つカザノワシが分岐していて、近い系統からそれぞれ適応次第で最強のワシも最弱のワシも生まれるらしいことがわかる
[同様のことは Catanach et al. (2024) を見てもわかり、こちらは UCEs も用いていてより確実な結果を得ている]。
そこまでコウモリ食に特化したのは昼間は競争相手があったためと想像できるがどの系統と競合していたのだろう。他の強力な系統がまだ現れていない時期に分岐した古い系統なので、現存する系統の中ではハチクマ亜科あるいはカタグロトビ類の系統が競争相手だったのかも知れない。
現在では同じような地域に分布しているハチクマ亜科の Aviceda 属などの系統の方が少し勝っていたのかも。
このような試行錯誤の後にオウギワシやイヌワシ類が地位を確立したのではないかと考えると面白い。
なおコウモリ類の方が出現時期は早く、起源は 6000 万年前以上に遡るとされて 4000 万年前ぐらいには多くの系統が出現していたのでタカ類の方が後になる。初期のタカ類にとっては都合よい獲物だっただろう。
#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] で現生の近縁 (と言ってもかなり遠いが) 系統のオウギワシの transposable elements が調べられていてコウモリダカとの分岐 (2300 万年前ぐらい) や ヒメオウギワシ [高野 (1973) ではカンムリオウギワシ] との分岐 (1700 万年前ぐらい) のころ、オウギワシのゲノム中で transposable element の一つが活発に働いたと推定されている。
この時期にオウギワシらしさを確立したと考えれば、コウモリダカらしさも同じような時期に確立されたのかも知れない。先行するタカ類の他にもこの時期には広義 Acipiter (ハイタカ) 属の祖先も現れ始めていた。ただこれらはアフリカからまだ出ていなかったと想像できる。
コウモリダカがアフリカとアジアに分布していることから、コウモリダカらしさは広義 Acipiter 属の出現以前の時期に獲得されたのではないだろうか。コウモリダカやオウギワシの祖先の主な競争相手がハチクマ亜科だった可能性はありそうに思える。
コウモリダカの高精度ゲノムが読まれてオウギワシと同様の議論ができるレベルになればこのあたりもよりはっきりしてくるかも知れない。コウモリダカの研究者に期待しよう。
コウモリダカは他項目に多数現れるのでまとめておくと、
#カタグロトビ備考の [カタグロトビは偏食家?]: コウモリダカは意外にいろいろなものを食べている。
#トラフズク備考の [コウモリを主に食べる北京郊外のトラフズク] コウモリダカの捕食習性や成功率など。若干の考察あり。
#ハヤブサ備考の [視覚特性・薄明かりや夜間の狩り] ヨタカ類やアマツバメ類との形態の類似性、捕食行動の特性など。
#ハチクマ備考の [ハチクマと他種猛禽類との識別] で目先 (lore) の羽毛の類似性、[ハチクマ類の道具使用] で紹介の Gutierrez-Ibanez et al. (2023) Online repositories of photographs and videos provide insights into the evolution of skilled hindlimb movements in birds
では preprint 段階 (bioRxiv で見られる) ではコウモリダカはあまり資料がなかったが発表論文で飛びながら食べる項目などを追加してもらった (経緯は論文と Peer Review File を参照)。明るい時間帯にあまり活動しないため市民科学データベースにそのような映像があまりなかったためだった。
紹介した映像は Tadashi Shimada and NHK's "Wildlife Films" in Sabah, Borneo "Flying Hunters of Borneo" (Borneo Safari 2013。NHK 番組の取材)。
a slow-motion: Bat Hawk hunting bats ... Bat Hawk (liewwk Nature)。ハヤブサ類に似た飛翔形、飛びながら次々食べていることや飛行操縦性能の高さがわかる。
論文紹介以外の映像も紹介しておくと Bat hawk of Borneo.mov (cede prudente)。光量が少ないので撮影は困難なよう。足で捕えるのが見える。
Bat Hawk: Adopt a raptor nest protection (Siam Avifauna)。翼の形状から予測できるように森林内ではなく開けた樹上に営巣するらしい。ハチクマ亜科の営巣習性とはだいぶ違うが、コウモリ食に特化したしたためコウモリのねぐら近くに営巣する二次的な産物かも知れない。イヌワシ類の系統の方に近いと思えばあるいは開放環境に営巣する点に共通点があるのかも。
ひなに与える時はさすがに嘴を使って細かくする必要があるので嘴にタカらしさが残っているのだろうか。
[カンムリワシの生態]
宮崎 (1987)「鷲鷹ひとり旅」によれば「日本に生息するワシタカの仲間でカンムリワシほど不器用なやつはいない」とあるが、この性質もカンムリワシがこのグループで最も古く分岐した系統的なものかも知れない。もちろん小さな島で競争者がいないためそのような性格になったのかも知れないが。
しかしながら五百沢 (2007) Birder 21(6): 11 にバンを捕食したカンムリワシの観察例がある。
同じ号で山形 (2007) Birder 21(6): 26 にカンムリワシが道路の死体 (シロハラクイナ、カエル、トカゲ、ヘビ) を捕食するにあたって死体を片足で触って死んでいることを確かめるような動作をすることがある記述がある。
橋口 (2003) Birder 17(11): 21 にカンムリワシによるヨシゴイの捕食写真 (頭部を掴んで飛び立とうとしている) がある。
吉見 (1991) 日本の生物 5(3): 4-15 にカンムリワシの繁殖生態記録がある。カンムリワシは羽音がせず羽も雨をはじかないとある。
カエルの声を真似すると敏感に反応し、音源を確かめようとするがなかなか見つけられず、そのうち目が合って正体がばれてしまうとのこと。子別れ後成鳥羽へと換羽を済ませた若鳥が成鳥のところに戻ってきたとの話が記述されている。
同記事 p. 13 にはひなの孵化 49 日の段階で、オスがカエルを運んで来た時にメスが不在で、オスがちぎって与えたという。この著者によればオスのこの行動が観察されたのはこの一回のみとのこと。
佐野 (2003) 石垣島におけるカンムリワシの繁殖生態 の論文がある。
Tobe et al. (2024) Seasonal diet partition among top predators of a small island, Iriomote Island in the Ryukyu Archipelago, Japan
に糞の DNA 分析による食性解析がある。小さな島でカンムリワシとイリオモテヤマネコの2種の頂点捕食者がなぜ存在し得るのか。大きく見ると両者で重なりがあるが種レベルではあまり重なりがない。
カンムリワシの食物にカニが多く含まれるのは特徴的。昆虫やムカデ類も多い。冬場は爬虫類も多い。
夜行性のカニもよく食べるがイリオモテヤマネコは昼行性の鳥が休んでいる夜の捕食が多いなど活動時間帯も違う。インドのカンムリワシは爬虫類が中心で両生類はあまり食べていない。鳥はインドの方がよく食べている。哺乳類はどちらもほとんど食べていない。
インドとの違いは獲物の豊富さにもよるのだろうが、体格差も現れているかも知れない。
Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" p. 80 によればヘビワシ類がネズミを食べる時はそのうに一時的に蓄えるが、ヘビを飲む時は刀飲みのように直接胃まで入れる (原文では intenstine とあるので腸まで?) とのこと。
台湾の亜種オオカンムリワシ (亜種 hoya) について、Raptor Research & Conservation Network (2018) "A Field Guide to the Raptors of Asia" によればタイワンザル Macaca cyclopis などが巣を荒らして繁殖失敗に至ることがあるとのこと。
#ハチクマ備考の [擬態と種・亜種の関係] も参照。台湾のハチクマがタイワンザルに敏感なのはこのような妨害を受ける可能性があるためなのだろう。カンムリワシよりハチクマの方がより積極的に防御・攻撃しているように見える。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 79 III の出版社の取材記事 (田島) によれば、警戒心が少なく動作が比較的ゆっくりしているため西表ではハンターの絶好の的になった。
琉球大学池原教授によれば、復帰前は琉球政府の天然記念物に指定されていなかったので乱獲されたのが減少の最大要因とのことだった。
「九州・沖縄の鳥」(小学館 1985) 収録の本若博次氏の解説 (pp. 144-145) によれば、交尾が初めて撮影されたのが 1978.3.16 島袋憲一氏によるもので、巣の発見が 1984.4 宮崎学氏によるものとのこと。
[カンムリワシは空中でヘビを食べるか]
チュウヒワシで Short-toed Snake-Eagle (Ella Slinn 2025.5.3) の写真があったので問題提起として挙げておく。
Gutierrez-Ibanez et al. (2023) (#ハチクマの備考参照) では、チュウヒワシ属 Circaetus は空中で足から嘴に物を運べる分類に含まれているがカンムリワシ属は含まれていない。
[猛禽類のヘビ毒耐性]
ヘビを食べる猛禽類は多数存在するが、これまで調べられた範囲では、哺乳類とは異なり鳥類ではヘビ毒に対する nicotinic acetyl choline receptor (nAChR) の変異による耐性を持つ種類はみつかっていない
[Khan et al. (2020) Widespread Evolution of Molecular Resistance to Snake Venom α-Neurotoxins in Vertebrates;
Khan (2022) Evolution of molecular resistance to snake venom α-neurotoxins in vertebrates (学位論文);
van Thiel et al. (2022) Convergent evolution of toxin resistance in animals]。
鳥類にはヘビが噛みやすい場所があまりないことと、十分敏捷でヘビ毒に対する耐性を持つ必要がなかったためであろうと解釈されている。
ヘビに噛まれたタカの救命措置を行った論文もある。Heckel et al. (1994) Apparent fatal snakebite in three hawks。
吉見 (1991) 日本の生物 5(3): 8 がカンムリワシが採食行動中に誤ってハブに脚をかまれた事例が紹介されている。かまれたあたりを盛んにつついていたが、翌日も元気だったとのこと。
その後南米のカンムリノスリ Buteogallus coronatus Chaco Eagle 血清のヘビ毒中和機能が調べられている:
Regner et al. (2022) Neutralization of "Chaco eagle" (Buteogallus coronatus) serum on some activities of Bothrops spp. venoms
多少の中和機能があり、グロブリン分画でなく抗体の作用ではないとのこと。いくつかのヘビや哺乳類で報告されている PLA2s, SVMPs の阻害物質と機能が似ているとのこと。
nAChR の変異によるヘビ毒耐性やいわゆる特異抗体ではないが、別の作用機序で多少のヘビ毒抵抗性を持っているらしい。
ヘビに噛まれた鳥類に関するレビュー: Cummings and Eisenbarth (2024) Snakebite Envenoming in Avian Species: A Systematic Scoping Review and Practitioner Experience Survey。検索エンジンなどで調べたもので地域的にはかなり偏っている (アジアの報告はない)。
猛禽類の事例が多いのは鷹狩り用のものが多いためで (興味本位で無理にヘビを狙わせる例もおそらくあるだろう)、
アカオノスリでは噛まれる場所によって症状が違って筋肉部分を噛まれるとやはり重症で致命的なこともあるとのこと。局所の症例写真などあり。
鷹匠の言い伝えではふしょより上を噛まれるとまず死ぬとされるとのこと。足先の血流は少なくて毒も回りにくいとの理由も挙げられている (後に検討)。ヘビを食べるタカでもヘビ毒耐性は一般的にあまりなさそう。
トカゲ類では様相がだいぶ違っていてヘビ毒耐性に関連した nAChR の変異が軍拡競争的に進化している: Chandrasekara et al. (2024) A Russian Doll of Resistance: Nested Gains and Losses of Venom Immunity in Varanid Lizards
しかし一度耐性を獲得したトカゲ類の系統で毒ヘビが少ない地域で進化した種では耐性を二次的に失ったことがわかり、ヘビ毒耐性の維持にはコストがかかる (適応度を下げる) ことも示唆する [この点は Khan et al. (2020) にも触れられている]。
トカゲ類では大型種では皮膚も厚くなってヘビ毒耐性も弱まるらしい。
敏捷な運動の必要な鳥では運動能力を落とす可能性のあるイオンチャンネルを変異させる変異は進化しにくいのでは。#ミサゴの備考 [ミサゴはフグ毒に耐性があるか] や #ヤマガラの備考 [ヤマガラの植物毒耐性] (5) 毒鳥ピトフーイなどの対毒性 (BTX 耐性) も参照。
Khan et al. (2020) のデータを見てもこの部分のアミノ酸配列が鳥類で非常によく保存されていることから変異に対する選択圧が高いと想像できる。
その後発表されたゲノムデータも増えているので鳥で本当にヘビ毒耐性がないか同様に配列を調べてみると面白そう。論文になっていないのは調べてもまだ見つかっていないのかも?
また前適応的な機能かも知れないが鳥の羽毛はヘビ対策に相当役に立ってそう。
Cummings and Eisenbarth (2024) で "足先の血流は少なくて毒も回りにくい" のような説明を聞くとなるほどと思ってしまいがちで、「それみろ、鳥のふしょより先は爬虫類そのもの」と言いたげな人もありそうだが、足先を噛まれても全身に毒が回りにくい理由はコンパートメント構造のためではないかと想像した。
解剖経験のある人ならご存じだろうが体内には膜構造が非常に多い。腱鞘や筋膜 (fascia)、他にもなんとか膜と呼ばれるもの。発生的、機能的に必要なものもあるが、感染などが他の部位に簡単に波及しない構造にもなっている。
足先を噛まれたタカの足が局所で腫脹する程度にとどまるのは局所で炎症を起こして周囲に簡単に波及していない (= 血流に乗りにくい) 現れでないだろうか。炎症を起こして腫れると周囲の血管を圧迫して毒物が他の部位に回るのを防ぐ機構になっているのでは。そのように時間稼ぎをしているうちに代謝で毒活性が弱まれば生き延びることになる。
人の手の感染症ではこのような機構が知られていて [cf. Rigopoulos et al. (2012) Closed-space hand infections: diagnostic and treatment considerations。日本語でも手の外科の解説はいくらもありそう]、
手は外界に最も接する部位なので、毒や感染を局所にとどめて生命に危険となるのを避ける機能などがあるのだろう。もちろん限られた空間の炎症なので痛みは激しく、障害を与えないためにも医学的には重要な課題である。ヘビに噛まれた猛禽類の症例写真を見ても鳥の足が同様の適応を遂げていてもまったく不思議でないと思える。
トカゲ類でもヘビ毒耐性機構があることから、うろこがあれば大丈夫というわけではなさそう。鳥のふしょなどのうろこは爬虫類に似て見えるが、羽毛から進化したうろこは爬虫類型のうろこより一層高性能なのかも知れない (#ライチョウの備考 [鳥類と爬虫類のうろこは別物] 参照)。
Khan et al. (2020) の研究は科学ニュースにも登場して話題を知っていたが、後の方の論文は別件からの副産物で、#ミヤコショウビン備考の [ニュージーランドの外来ネズミ類駆除] で抗凝固薬をチェックしていて引っかかった。神経毒の他にヘビ毒には凝固不全 (促進 procoagulant と阻害 anticoagulant の両方がある) をもたらす毒もあって関連情報として浮かび上がった次第。いわゆる出血毒の方に対応する。
野外の猛禽類へのネズミ類駆除の抗凝固薬の環境影響を調べるために Russell's viper venom time (ヘビ毒による血液凝固時間) も使われているので基本的にはヒトと同じように作用しているらしい。神経毒のイオンチャンネルの方は塩基配列から調べやすいので研究が進んでいるよう。凝固にかかわる方はまだ手がかりが難しくてゲノムから簡単に推測できず、毒耐性の研究は遅れている可能性がある。
一般向け解説だが Birds That Eat Snakes: The Fearless Snake-Slayers (Silva in Bird Venue 2023) にヘビを食べる鳥やさまざまな狩りの方法、有名な毒ヘビを食べる鳥が紹介されている。
個々には一次文献をチェックした方がよさそうだが、タカサゴダカ Tachyspiza badia Shikra がマングースを食べて Mongoose bird と呼ばれるとのこと。
ちょっと探した範囲では他のページに見つからないので本当か...? と思って探すと SNAKE_HUNTING_WITH_SHIKRA (Punjabi Falconers) の映像があった (題名は GOSHAWJ に変更された模様。タカサゴダカの若鳥?)。
Shikra, the leopard of avian kingdom (Ragoo Rao 2022)
独立前のインドの鷹狩りで最も多用された種類とのこと。日本で言えばツミに対応する種だがハトより少し大きいにもかかわらず勇敢であるとのこと ("空のヒョウ" とも呼ばれる)。また獲物の習性をよく知った狩りを行うなど知的だと大変褒めている。薄明中の暗い中でコウモリを捕えることもできるとのこと。
都市にも順応しているとのことでツミと似た面がある。
訓練したタカサゴダカで敢えて毒ヘビを攻撃させるなどの事例が知られているのかも知れない (ヘビ対マングースが見せ物になるならばいかにもありそう)。
Balchan et al. (2025) Raptors without resistance: No evidence for endogenous inhibition of rattlesnake venom metalloproteinases in a Great Plains raptor assemblage
北米の猛禽類 (タカ、ハヤブサ、フクロウ類) の血清がガラガラヘビの毒を中和するか調べたがほとんど証拠がなかった。生理学的なヘビ毒への適応はほぼなく、形態・行動面での適応で毒を防いでいる。毒への暴露による獲得免疫による効果は多少考えられる。やはり猛禽類にヘビ毒耐性は一般的にない結論となりそう。
カンムリワシの写真を見ていて気づいたが鼻孔がかなり狭くなっている。ハチクマのスリット状鼻孔はハチ対策 (ハチが入らないように、あるいはハチの巣を食べる時に鼻孔が詰まらないように) と言われるが、こちらはヘビ毒対策? 少し系統の異なるチュウヒワシの画像も見ておくと確かに多少狭いように感じる。
こちらはヘビの側からの研究 (ハンガリー): Radovics et al. (2023) Hide or die when the winds bring wings: predator avoidance by activity shift in a mountain snake
Vipera graeca (Greek meadow viper) 有毒とのこと。
観察結果を見ると「捕食者がヘビを襲う時には頭部を狙う」はどうも俗説らしい (もっとも生き残った個体しか調べられないが)。体の後ろ半分に傷が多いとのことで 12.5% の個体に傷があったとのことでかなり高率。またこの環境には猛禽類が多数種生息している。
直接捕食が観察されたのはチュウヒワシとチョウゲンボウ、ハシボソガラス (ズキンガラス) とのこと。温度の高くなる真昼は捕食危険性が高まるので日光浴 (basking) の活動を避けていて、ヘビにとっては体温調節機会のジレンマになっているとのこと。
ヘビ毒ではなくクモ毒についての研究: Lyons et al. (2025) Spider venom potency exhibits phylogenetic prey specificity but does not trade-off with body size or silk use in prey capture
(一般向け解説)。
こちらはクモの捕食する動物への毒性と相関があったとのこと。無脊椎動物のみを捕食するクモでは哺乳類への毒性が弱かった。"クモの巣" を張るタイプのクモは毒性が弱かった。クモ毒は獲物を動けなくするために役立っていて、"クモの巣" はその代用になる。ハチ毒も獲物に対するものとしてまず進化した (#ハチクマ備考 [ハチ類の行動とタカ類などの共進化] 参照) のと似ている。
捕食者への防御は副次的な効果で、クモでもハチでも捕食者への効果は限定的で比較的簡単に突破できるのだろうか。
[カンムリワシの強心配糖体への耐性変異]
日本のカンムリワシで Na+/K+-ATPase に強心配糖体への耐性変異が見つかったとのこと。Tobe et al. (2025) Evolutionary insights into Na+/K+-ATPase-mediated toxin resistance in the Crested Serpent-eagle preying on introduced cane toads in Okinawa, Japan
カンムリワシの分布地域には植物毒を防御に用いる Rhabdophis 属のヘビ (keelback snakes。例えばヤマカガシ) が在来種として存在して食物となっている可能性がある。
有毒な移入種 (1978 年移入) の オオヒキガエル Rhinella marina Cane toad を食べることができるが在来種にはこの毒ステロイドを分泌するものはいないとのこと。
石垣島、西表島、インドネシアの Simeulue Island のカンムリワシ、およびムナグロチュウヒワシ Circaetus pectoralis Black-chested Snake Eagle (東から南アフリカの種でチュウヒワシと上種 superspecies を形成するか、同種とされることもある)
の ATP1A に共通の Q111E 変異が存在したとのこと。有毒なオオヒキガエルが導入されてから獲得されたものではなく Circaetinae (チュウヒワシ亜科) の系統内ですでに存在していたとのこと。ただ調べられている種はごく一部なので系統に散発的に現れたものか共通形質かまでは不明。
この部位はタカ類の祖先型からは1塩基変異。より一般的な共通形質か否かはさらに調べる必要がありそう。なお論文の系統樹はこの部分の配列に基づくもので、Catanach et al. (2024) のような一般的タカ類系統樹に乗せているわけではないので注意。近いものはだいたい近くにまとまっているが系統順序などは別資料を見る必要がある。
ATP1A Q114E については#ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] (1) 強心配糖体への耐性 を参照。Mohammadi et al. (2025) の preprint によれば Q114E はスズメ目のモチーフの中で特に有効そうで、さらに複数の変異があると一層有効との結果となっている。
タカ類のモチーフの上で Q114E のみで効果があるかどうかはそこまで自明ではないかも知れない。
ちなみに Tobe et al. (2025) によればカンムリワシではこの研究で調べたタカ類の中で最も変異数が多かったとのこと。
ヘビ毒耐性とはメカニズムが違ってカンムリワシにヘビ毒耐性があることを意味するわけではない。むしろ植物毒とそれを食べた動物が (化学防御のために) 含有する毒への耐性ということになる。
Tobe et al. (2025) の読み取ったこの部分の配列は GenBank ですでに公開されており、サンプル LC850561.1。
他の生物と比較するにはここから BLAST をして Alignments を見ればよい。CDS feature をチェックするとアミノ酸配列も表示される。
確かに論文に書かれている範囲の種類にとどまっていて比較対象種が少ない。
他に公開されているゲノムアセンブリから自前で構築すればよいのだろうが手間がかかりすぎるのだろう。
タカ目ではないので論文には取り上げられていないが、似た食性のノガンモドキには Q114E の変異がないことも興味深い。他の部位にはかなり違いがあるので、あるいは他部位の変異で耐性を持っているのかも知れない。詳しく調べれば Q114E 以外の変異で耐性を持つ事例になるかも知れない。
ATP1A は重要な遺伝子のため一般的には極めてよく保存されているが、カンムリワシ系統では変異が加速しているように見える。ただしサンプル種数が少ないことと BLAST で表示される系統樹が本来の系統を反映していないためによる見かけの効果かも知れない。
オオヒキガエルの在来分布は南北アメリカの熱帯から亜熱帯で、この地域の両生類食のタカ類の配列情報があれば系統との関係がもう少しわかるかも知れない。この地域に分布するものは主にノスリ亜科 Buteoninae となる。
ノスリは Q114E は持たないがそこそこ他の変異があるので、論文でも可能性が指摘されているように多少の耐性があるのかも知れない。ノスリは北回りでユーラシアに到着して植物毒を持つ動物が比較的少ない地域で分散したため、身体能力を犠牲にする可能性のある毒耐性への選択圧が弱まり、祖先的な形質が一部失われているかも知れない。よく調べられているタカ目も北方に非常に偏っているので、毒耐性を持たないものが選択的に読まれている効果があるかも知れない。
南北アメリカの熱帯から亜熱帯のオウギワシにはまったく変異がないが食性もまったく違う。オウギワシはイヌワシに近い系統ゆえ毒耐性を持っておらず、生態的にはたとえ可能であってもこの地域で両生類食などの多様な食性の種類は進化できなかったかも (オウギワシが孤立系統である理由の一つになり得るかも)。
Circaetinae にはフィリピンワシも含まれているので、同じような変異を引き継いでいるのか興味あるところ (生態的関係や孤立系統である点はオウギワシに近い)。
参考までに 111-122 部分のアミノ酸配列を見ておくと
ESVLEDGSNKDN (カンムリワシ)
QSVMEEEPNNDN (イヌワシ)
QSVLGEEPNNDN (ノガンモドキ)
QSAMEEEPNNDN (ハヤブサ)
QSVIEE-ANKDN (ノスリ、この論文から。英国のヨーロッパノスリ NC_134178.1 の配列も同じ)
QSVMEEEPNNDN (フクロウ、参考比較)
QSVMEEEPNNDN (ハイイロペリカン、参考比較)
でカンムリワシの変異がかなり多いことがわかる。ノガンモドキは基本的にハヤブサのモチーフに似ているが、114-116 の3か所が異なっており、カンムリワシと似たパターンを示していることがわかる。系統的にはハヤブサよりノガンモドキの方が古いのでこちらが祖先型配列に近く、ハヤブサの配列がノガンモドキに似た配列から適応によって進化したのか、ノガンモドキが特異的に変異を進化させた両方が考えられそう。
ノスリは南米で進化した系統の特徴が残っているのかも。カンムリワシとノスリは系統が異なるので祖先段階から共通の変異を持ったまま進化したとは考えにくい。
この部分の配列が系統の相当異なるハイイロペリカン、イヌワシ、フクロウでまったく同じなので、いかによく保存されているかがわかる。逆に言えばこの部分を見てもタカとフクロウの系統関係を議論するのは難しい。
Q114E は異なるが、カンムリワシ (+ ノスリ系統) とノガンモドキで毒耐性へのある程度の収斂進化があるのではないだろうか。これらの配列の違いがどのような立体構造の違いとなって耐性に影響を与えるだろうか、AlphaFold が活躍してくれそうな場面。
[霊長類はなぜヘビを恐れるか]
ヘビを食べる猛禽類が多数あるので一見問題にならないのだろうが、哺乳類では話が多少違ってくる。本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」(マーク・S・ブランバーグ著; 塩原通緒訳 早川書房 2006) (#ミサゴの備考 [feather taxis・頭かき] で紹介) pp. 179-181 によれば、
Ohman and Mineka (2003) The Malicious Serpent: Snakes as a Prototypical Stimulus for an Evolved Module of Fear
は多くの哺乳類がヘビを恐れるのは "生得的" なもので、恐竜支配下の哺乳類の爬虫類恐怖症を引き継いでいるのではとも述べているとのこと (なかなか大胆な考え)。一部の哺乳類では変異してヘビ恐怖症が失われている可能性なども議論しているとのこと。前述の Khan et al. (2020) のように有毒のヘビを食べる哺乳類は何種類も存在する。
ブランバーグはヘビと恐竜はそもそも縁が遠いことも触れている。
ブランバーグによれば爬虫類好きな人もあるし、そもそも前提が間違っているのではとの考え。Ohman and Mineka (2003) にもサル用の餌で育てたリスザルはヘビを恐れないが、生きた虫を餌にして与えると恐れると記述しているとのこと。
Ohman and Mineka (2003) の主旨を見ると、一度恐怖に晒されると遺伝的な「恐怖モジュール」が活性化されるとの解釈としているようだが、ブランバーグはこのようなモジュールの存在には否定的。
Landova et al. (2012) Human responses to live snakes and their photographs: Evaluation of beauty and fear of the king snakes
のヒトのヘビに対する反応実験でも Ohman and Mineka (2003) がベースとなっており、進化的に関連のない種類の警告色にも反応するとの結果となっている (心理学ではモジュール仮説に人気があるらしい)。ブランバーグはそんなに単純なことではないと考えていると思われるが、警告色への反応など普遍的に見られそうなことも再検討の必要があるのかも知れない。
Radlova et al. (2019) Snakes Represent Emotionally Salient Stimuli That May Evoke Both Fear and Disgust
はさまざまなヘビの写真をヒトに見せて何が恐怖を起こすかなどを調べている。
Prokop et al. (2018) Aposematic colouration does not explain fear of snakes in humans
はヒトの子供で警告色そのものは恐怖を起こさなかったとの実験がある。ヒトと捕食性のヘビと長期間暮らしてきたためヘビに敏感な注意バイアスを進化させたのではないかと説明している。
Coelho et al. (2019) Are Humans Prepared to Detect, Fear, and Avoid Snakes? The Mismatch Between Laboratory and Ecological Evidence
はモジュール仮説に合わない点などを指摘している。いくつか挙げられいる中で、ヒトはヘビよりも進化的にもっと新しいはずの銃に強く反応する、ヘビの色彩は捕食者に対する隠蔽色 [ここで鳥の出番になるが鳥はヘビに恐怖感を持たないのか? 恐竜支配下の哺乳類の爬虫類恐怖症がなかったから? (笑)] として進化したもので、ヘビ捕獲の専門家でも見つけるのは難しいなど鳥が "警告色" をどう捉えているのかにも関係して面白い。[紫外線で見たヘビの色] の項目も参照。
ヒトが恐怖を感じる神経機構 (扁桃体) は他の哺乳類に似たもので、捕食される側でもする側でもあまり違わない可能性がある。無意識に反射的にヘビに反応しているわけではなく対象物を意識して始めてヘビから逃げる証拠があるなど。
selective habituation hypothesis (Schleidt 1961) の古い仮説があって、さまざまな刺激に対して警戒したり恐怖を感じるが、慣れで警戒や恐怖を失ってゆく考え方がある。ヘビという特定の刺激ではなくもっと広い範囲の刺激への警戒や恐怖から始まって必要ないものを失ってゆくアイデアも再評価されるべきでは。
またほとんどの実験は室内で行われているので野外の状況を的確に表しているとは限らない。この著者もモジュール仮説に懐疑的。
扱っている対象はヒトなのでこういう議論になるが、ヘビを捕食する鳥ではどうなっているのだろう。捕食者も最初から完璧なものではなかったはずで、もっと原始的な段階ではヘビを恐れていなかったのだろうか。
日本語で調べるとこんな記事があった ほとんどの人がヘビを嫌う理由 秘密は 6500 万年前の太古にあった (2016)
川合信幸准教授 (当時) の発表資料のコメントを引用しておくと「人間の祖先は 6500 万年前から樹上生活を始めました。当時、樹上のサルを捕食できるのは、ワシやタカの猛禽類とネコ科の動物、そしてヘビですが、30 メートルを超える枝の生い茂った場所まで近づけるのはヘビだけだったでしょう。
そのため、サルはヘビのカモフラージュはすばやく見つける必要がありました。脳内でヘビに敏感に反応する領域が発達し、すぐに恐怖を感じ対応できるよう進化したと考えられます」。
Kawai and He (2016) Breaking Snake Camouflage: Humans Detect Snakes More Accurately than Other Animals under Less Discernible Visual Conditions
がその論文の模様。上の報道資料とはだいぶ雰囲気が違って、見分け率は ヘビ > ネコ > 魚 > 鳥 で数字は報道と同じなのでどこかで入れ違いがあったのだろう。鳥を認識する能力が特に低かったが理由がよくわからないとのこと。鳥はよく知っている (つまり無害) ことは説明にならないとのこと。
この論文でもモジュール仮説をベースとした導入があり、ヒトで特に進化しているとの見方のよう。
樹上のサルはそれほど古い時期にいたのかとちょっと感心したが、ほぼその程度に見積もられていて 5700 万年前の化石があるとのこと (wikipedia 英語版)。あまり本質的問題ではないかも知れないが、少なくとも現存系統ではサルを捕食できるワシやタカはまだいなかったのでは? ワシやタカはよほど昔からいると思われていたらしい
[もっとも一般的に明らかにされたのは Prum et al. (2015) 以降だが]。
Telluraves 以前の系統には多分なさそうだし、フィリピンワシの祖先系統で 2200 万年前ぐらい。かつての系統に強力な捕食者があったことは否定できないが、タカ目の放散が 3000 万年前ぐらいなのであるとすればフクロウ目の方か? もし鳥類捕食者がいたならばそれは十分脅威だったのではないだろうか。
その後別の学術書ではない書物でワシやタカは Tyrannosaurus rex の時代にもいたと書いてあるのを見つけた。「鳥類は恐竜の生き残り」が強調されてその印象だけが独り歩きするとワシやタカは大型恐竜の時代にもいたものと思ってしまうのかも知れないと納得した。
しかしながらこのような目で見ると、#ハチクマ備考の [60年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)]と #クマタカの備考の [Nisaetus 属のクマタカ類の系統分類 (イヌワシ亜科その1)] の、
有力な猛禽類捕食者がマダガスカルに現在いないと思われていた時期に、霊長類学者がキツネザル類に絶滅した猛禽類に対する警戒の痕跡が残っていると考えた理由も想像できる。
古い時代の "猛禽類警戒モジュール" が上記報道資料のように遺伝的に受け継がれていると考えたわけだろう。ヒトが猛禽類を目立って恐れるわけではない (しかし #ハチクマ備考も参照。あながち否定できない) ので猛禽類画像を用いた研究はなされていないのだと想像するが、古い時代に "猛禽類警戒モジュール" が存在して、上記の説明の通りならばヒトが猛禽類を恐れてもよいように思える (むしろかっこいいと思うのは学習によるものなのだろうか)。
マダガスカルのキツネザル類では当初からこの説に懐疑的な議論もなされていたようだが、実験室のヒトでは違うということだろうか。
日本語で ヘビ 恐怖 本能 などで調べると本能的な説明が多数あってそのまま受け入れてしまいそうだが、「科学する目」ならばもう少し疑って冷静に見た方がよいように感じる。
こんな研究もあった。これまでの実験は主に西洋で教育を受けた産業文明のヒトを被検者に用いているが、もっと人類発祥の地に近いソマリアで調べたもの。Frynta et al. (2023) Animals evoking fear in the Cradle of Humankind: snakes, scorpions, and large carnivores
データはあくまで自己申告によるものだが、最も恐れを感じない動物グループは鳥で、クラスター解析をすると温血動物 (とあるのでそのまま訳しておく) を恐れない傾向にあるなど出ている。ハトも調査対象に入っていて誰がそんなものを恐れるか (笑)、という感じもする (比較的小型の鳥類も多く含まれているので温血動物を恐れない傾向が出るのだろう。ただしダチョウも入っている)。
ソマリアではセレンゲティに比べて大型哺乳類への恐れが小さいが、ソマリアでは早く乾燥化が進んでメガファウナの動物が残っていないので刺激として用いなかったのが原因か、とある。
トカゲが高い位置に来るのは地域文化のためか、とか実際に何が明らかになったのかあまりよくわからない気がする。
こちらの著者はそもそも恐怖とは何か: LoBue and Adolph (2019) Fear in Infancy: Lessons From Snakes, Spiders, Heights, and Strangers
ここに Ohman and Mineka (2001 の書籍の方に出てくるらしい) の先述の言葉 (恐竜支配下の哺乳類の爬虫類恐怖症) が出てくるので引用しておこう: "the predatory defense system has its evolutionary origin in a prototypical fear of reptiles in early mammals who were targets for predation by the then dominant dinosaurs.
Thus, because of this system, contemporary snakes and lizards remain powerful actual fear stimuli".
恐竜支配下で羽毛恐竜に対する恐怖症はなかったのかとかツッコミたくなるが、2001 年段階ではまだわからなかったとしておこうか。しかし Ohman and Mineka はあまりに誰もが引用しているので、羽毛恐竜が見つかった現在でも誰もが学ぶ説になっているのだろう。
LoBue and Adolph (2019) は上記のような文脈の recurrent evolutionary threats (進化的な昔の恐怖がよみがえる) 説には否定的。高所恐怖症も幼児に本当にあるのか (鳥にもあるのだろうか? 巣立ちの映像を見るとあるような気もする)。幼児の表情は恐怖のしっかりした証拠ではない (上記ハチクマで体験した話にも関係する)。幼児が知らない人を怖がるというのも本当か。
この著者は古典的な「ヘビ・クモ、高所、知らない人への恐怖は適応的である」見方は間違っていると主張。それらの刺激に直接恐怖を覚えるよりも、新しい物事を探索して何が危ないのかを文脈に応じて意味を理解して行動できる能力の方がより適応的だと述べている。
このような議論が行われている話は鳥類学の研究を見ても出てこないし、日本の報道ではほとんど聞かないので新鮮な感じがする。もしかすると霊長類学では今でも恐竜支配下の哺乳類の爬虫類恐怖症は有力仮説なのだろうか?
鳥が模様の何に驚いているのか (そもそも実験は今から見ても正しいのか?)、タカ類の間、あるいはタカへの擬態が何の役に立っているのかの解釈にも関わりそうなのでご覧いただくと面白いだろう。
同じような時代で「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) はもう少し現象的中立な書き方で、昆虫の捕食者対策のところで警告色の虫を放置する傾向があり、ヨーロッパヨシキリ幼鳥はスズメバチなど黒と黄色の縞模様を恐れると生得的なことも多少は匂わせつつも、昆虫のこの防御も完全ではなくハチを食べる鳥も多くあって、いかに対処するかを学習した後恐れなくなっているのか、のような書き方になっている (p. 87, *1)。
スズメバチを食べる鳥もあるので黒と黄色の縞模様が鳥にとって普遍的に恐怖を引き起こすとは推論できないわけだ。なぜこううまくハチクマに戻るのか自分でもよくわからない (笑)。
鳥類には進化的な昔の恐怖がよみがえるような恐怖はなくて多分学習によるもの、恐竜支配下の哺乳類には本能的にある、と解釈されていたように読める。ヒトから逆に進化を遡るとこういう推論になるのか?
霊長類はそもそも恐がりで、それゆえに大脳を発達させてヒトを生んだのか - なるほど。ほんとうか? ここはぜひとも川上氏に 鳥類学者 無謀にも 霊長類を語ってほしいところだ。
Gil-da-Cos et al. (2003) Rapid acquisition of an alarm response by a neotropical primate to a newly introduced avian predator
の興味深い研究もあって、パナマで 50-100 年前にオウギワシが絶滅した地域に再導入された鳥の声に対するマントホエザル Alouatta palliata Mantled Howler Monkey の反応を調べた。オウギワシの再導入から1年ぐらい後に調べたものだが、オウギワシの声を流すだけで逃避行動をとったが、50-100 年間被食経験のない対称群では逃避行動をとらなかったとのこと。
50-100 年間で捕食者の声への反応が失われたことを示すとのこと。同様の結果がヘラジカとオオカミの関係でも知られているとのこと。日本の生態系ではニホンオオカミへの反応はすでに失われていることだろう。
"猛禽類警戒モジュール" 説には不利な結果である。サルに限らずタカの声を聞いて警戒するのは学習によるもの?
捕食者が絶滅して長期間に及ぶ場合はすぐに被食を受け再導入に注意が必要であることも示す。オウギワシの声は predator-assessment call (獲物の質を見極める声) で、相手の反応を見て襲うかどうかを決断しているらしい。試しにオウギワシの声を聞いてみると一般的なタカの声と極端に違わない感じもするが獲物を追跡する時の声と同じかどうかまではわからない。
Belin et al. (2018) Influence of early experience on processing 2D threatening pictures by European starlings (Sturnus vulgaris)
という研究があった。ホシムクドリのひなを用いたところ、モニターに映されたヒト、猛禽類、ヘビを区別できていなかった。育つ途中の若い時期 (実験では人が育てたものと野生のもので違いがあった) か後の時期に本当の外敵を学ぶ必要があるのでは、とのこと。
鳥に文化はあるのか、特に「累積文化」(cumulative culture) と呼ばれる個体ごとに行動が修正され、その中でより洗練された行動が集団内に伝播し定着する様式はヒト以外では証明されていないとのこと。
霊長類で主に研究されているが、ハトを使った実験で他個体を真似ることで累積的に飛行経路が洗練できることが数値モデルも含めて示されている: Dalmaijer (2024) Cumulative route improvements spontaneously emerge in artificial navigators even in the absence of sophisticated communication or thought。
これを cumulative culture の一種と呼べるのか、渡り経路などを他個体から教わることは cumulative culture ではないのか、あるいはヒトで cumulative culture とされている現象は実はそれほど高度な認知や思考の産物ではないのでは、などさまざまな視点から見ることができるだろう。
補足:
*1: この部分は昆虫の捕食者対策について述べられている。葉や枝への擬態もあるが、見破られると今度は小枝や葉をつつくようになり、食べられる虫が少なくなってきて食べられないものばかりつついているとわかると探索像が弱まって他に移るという。
昆虫の捕食者対策も完璧ではない、という文脈の後に昆虫の警告色について言及があるもの。
この書籍は 1985 年の日本語訳の出版で、いかに古い時代から "探索像" (サーチイメージ) の概念があったかわかる (#ミサゴ備考の [オウム類・ハヤブサ類の年代推定] にて紹介の Urban et al. (2024) の項目参照。(Lorenz-)Tinbergen の歴史的背景の影響を十分に受けている)。
Zhang et al. (2024) Nature's disguise: Empirical demonstration of dead-leaf masquerade in Kallima butterflies 枯れ葉への擬態がどれほど役立っているのか初めての実験室条件での実証研究とのこと。
枝への擬態については Skelhorn et al. (2010) Masquerade: camouflage without crypsis。ここで実験方法が確立された。
隠蔽色でないカモフラージュも有効であることを示した。
Skelhorn and Rowe (2016) Cognition and the evolution of camouflage は仮想的な探索像形成の概念に則った考察。
最近の研究も1つ紹介: Kelley et al. (2025) A leaf-mimicking moth uses nanostructures to create 3D leaf shape appearance (一般向け解説)。
カモフラージュが役に立っていることまでは示していないが、fruit-sucking moth (Eudocima aurantia) がどのような微細構造を用いて枯れ葉に似せるか。
直接関係がないが面白いので紹介しておく。黒地に赤は目立たないか、クモを使った実験: Gerfen and Tedore (2024) Hidden in red: evidence for and against red camouflage in a jumping spider (Saitis barbipes)
実験的には逆の結果が得られて赤い方が多く捕食された。色覚から予想される結果と異なる。足を黒くすると鳥の探索像から外れるのではなどの議論でもやはり使われている。赤と黒の組み合わせは (少なくともクモを捕食するタイプの) 鳥にとって特に警告色となっていないのかも。
[紫外線で見たヘビの色]
Crowell et al. (2024) Ecological drivers of ultraviolet colour evolution in snakes
ヘビの視覚は2色型で、1つは紫外線にピークがあるとのこと。種類によって紫外線反射率が異なり、紫外線を模様に用いている種類ではヒトの目で見るよりもヘビの視覚で見た方がはっきり模様が見える (同種間の信号として利用しているかどうかは不明)。人の目に色鮮やかな種類は一般に紫外線では鮮やかでないが、一見隠蔽色に見える種類が紫外線に色彩多形を示すものがあるとのこと。
3色型のトカゲも紫外線の受容体があり、ヘビが見るのと同様に模様が見える。
ヘビでは紫外線で見ても色彩の性的二形は認められず、紫外線での色彩は性的な役割をあまり果たしていないと考えられる。
鳥の目にはもっと鮮やかに見えると予想され、紫外線の役割は主に捕食者に対するものではないか。ヘビの色彩進化にも鳥の視覚が関与している模様。
["ヘビワシ" 類のクラッチサイズ]
Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" p. 167 によれば serpent eagles (ヘビワシ類) のクラッチサイズは当時知られている範囲で1卵とのこと。
日本のカンムリワシを調べてみるとやはり1卵と記述されている。
よく調べられているはずと思われるチュウヒワシ Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle もそのようだが、wikipedia ロシア語版を見ると例外的に2卵のこともあるが、1卵目が孵化すると抱卵を中止するので必ず育たないと説明がある
(英語圏にほとんど分布しないので web の英語情報が乏しい。Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" にもこの記述はない)。
カンムリワシの他亜種では2卵のこともあるが1卵しか育たないとある (wikipedia 英語版)。チュウヒワシと同様のメカニズムだろうか。余剰卵の "保険仮説" や兄弟殺しの起源との関係も含めて調べてみると興味深いと思う。
Brown (1976) は食性が同じワライハヤブサ Herpetotheres cachinnans Laughing Falcon も1卵でないかと予言していた。wikipedia 英語版によればやはり1卵で時に2卵とある。
ヘビ食専門の猛禽類のクラッチサイズが特別に小さいのは何か生態的理由があるのだろうか。
ちなみに体重で規格化したクラッチサイズが大きな猛禽類はチュウヒ類が知られている。広義ハイタカ属も大きい方に属する。
Olsen and Marples (1991) Geographic Variation in Egg Size, Clutch Size and Date of Laying of Australian Raptors (Falconiformes and Strigiformes)
がオーストラリアの猛禽類のクラッチサイズを調べているが体重が主な要因で、他に亜種の違いに由来する程度。オーストラリアにはヘビワシ類が分布しないのであまり話題にならなかったかも知れない。
猛禽類に限らなければ緯度とクラッチサイズの相関は古くから知られていて、Ashmole (1961) の仮説がある。Lundblad and Conway (2021) Ashmole's hypothesis and the latitudinal gradient in clutch size。
Griebeler and Boehning-Gaese (2004) Evolution of clutch size along latitudinal gradients:
revisiting Ashmole's hypothesis。
猛禽類のデータは現在は多少は揃っていて系統樹もしっかりしたものになっているので、系統や分布緯度を考慮した食性との相関などを研究してみると面白いかも。
[メガファウナの絶滅]
前述のような巨大猛禽類が生存していた時期は世界中に哺乳類も含めた巨大動物が生息していたメガファウナ megafauna の時代に相当している。Megafauna (wikipedia 英語版)
に種類も含めて詳しい。マダガスカル島のエピオルニス Aepyornis もその一つで、#クマタカの備考にある Stephanoaetus mahery Malagasy Crowned Eagle とともに伝説のロック鳥のモデルの一つとされる。
ハーストイーグル (Haast's Eagle) (#カラフトワシの備考参照) の Holdaway の記事にあるようにメガファウナの絶滅に気候変動が関与した説はよく取り上げられてきた。
しかし大陸ごとの絶滅時期が異なることや、この絶滅に合致するような特別な CO2 濃度変化が記録されていないことなど関連性に疑問がある。またこの程度の気候変動の変化率には適応できるとも考えられる (現在の人為起源の気候変動は、絶対値にもまして変化率が過去に例をみない大きさであることが問題視される)。
Saltre et al. (2016) Climate change not to blame for late Quaternary megafauna extinctions in Australia
はオーストラリアのメガファウナの絶滅の最も重要な要因は気候変動ではなく、むしろ人類が到達した時期によく一致することを示している。
一方で Hocknull et al. (2020) Extinction of eastern Sahul megafauna coincides with sustained environmental deterioration
では人類の到達時期に伴って急速に起きたわけではなく、気候変動や不安定 (極端気象など) が原因ではないかと考えている。
Lemoine et al. (2023) Megafauna extinctions in the late-Quaternary are linked to human range expansion, not climate change
は人為起源の見解を述べているが、発表されている雑誌が Anthropocene なので多少のバイアスはあるかも知れない。読んでいただいて判断していただくのがよいだろう。
この著者の言葉によればメガファウナの絶滅には長い時間がかかっているが、人類が到達したすぐ後から影響が現れ始めた可能性がある。人為由来のメガファウナの絶滅が生態系に及ぼす影響は今後何百万年も続くだろう。
しかし原因がわかっている今ではその影響から回復・減速させることはまだ可能である (現存するメガファウナを絶滅から防ぐ。現存するメガファウナというのは何のことはない動物園の人気者たちのことである) と述べている。
Chatters et al. (2024) Mammoth featured heavily in Western Clovis diet
北米原住民の祖先にあたる Clovis の安定同位体解析からマンモスを主食としていた可能性を示した研究。一般向け英文解説。
-
ヨーロッパチュウヒ (第8版で検討種)
- 学名:Circus aeruginosus (キルクス アエルーギノースス) さびた色のチュウヒ
- 属名:circus (m) チュウヒ (circus (m) 円弧、求愛の時の旋回行動からチュウヒ)
- 種小名:aeruginosus (adj) さびた
- 英名:Western Marsh Harrier
- 備考:
circus は#チュウヒ参照。
aeruginosus は u と o が長母音で後者にアクセントがある (アエルーギノースス)。
aerugo (アエルーゴー。さび) に由来。さらに aes (銅やブロンズなど) + -ugo (u, o いずれも長母音。表面にコートがある状態を指す) で構成された単語。この名詞を -o で動詞化 (aerugino アエルーギノー) したものに形容詞語尾 -osus (冒頭が長音) を付けたもの。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版や日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では検討種リストに移動となっている。2亜種あり、リストに記載されているものは基亜種。Circus 属のタイプ種。
昼行性猛禽類の多くは眼球が紫外線をあまり透過せず強烈な日光から網膜を守る、紫外線による色収差で像がぼやけるのを防いでいるらしい [Potier et al. (2020) #チョウゲンボウ の備考参照]。
知られている範囲ではヨーロッパチュウヒが例外で、薄明中の紫外線を積極的に利用して採食行動を行っている可能性がある (#フクロウの備考参照)。
他のチュウヒ類も同様かも知れない。(聴覚利用の可能性については#ウスハイイロチュウヒの備考も参照)。
[生涯メスの羽衣のままのオス]
一部の鳥では delayed plumage maturation でオスがすぐにオス成鳥の羽衣を獲得せず、メスの羽衣で過ごすものがある。female mimicry とも呼ばれる。
Sternalski et al. (2012) Adaptive significance of permanent female mimicry in a bird of prey
によれば permanent female mimicry と呼ばれる現象があり、一部のオスが生涯をメスの羽衣のまま過ごす。
非常にまれな現象でこれまでのところエリマキシギとヨーロッパチュウヒのある個体群のみで知られている (エリマキシギは遺伝で決定されている #エリマキシギの備考)。
ヨーロッパチュウヒの permanent female mimicry では2年めに獲得した羽衣のまま生涯を過ごすとのことで delayed plumage maturation とは呼べない。
メスの羽衣のオスは虹彩の色、大きさの違いでメスと区別できるとのこと。フランス西部のこの個体群では 40% のオスが permanent female mimicry を示すという。
デコイを用いた攻撃を調べてこのような羽衣が存在する意義を検討したもの。delayed plumage maturation で一般に考えられる他のオスからの攻撃を弱める効果の他に、繁殖に必要な資源を守る場合にメスのように行動するとのこと。オス・メス間の攻撃性が高い場合は生涯メスの羽衣のままの表現型も適応的だろうとのこと。遺伝的な背景などはまだ今後の研究課題。
-
チュウヒ
- 学名:Circus spilonotus (キルクス スピロノートゥス) 背中に斑点のあるチュウヒ
- 属名:circus (m) チュウヒ (circus (m) 円弧、求愛の時の旋回行動から)
- 種小名:spilonotus (合) 背中に斑点のある (spilo 斑 noton 背面、-os 形容詞語尾に Gk)
- 英名:Marsh Harrier, IOC: Eastern Marsh Harrier
- 備考:
circus は短母音のみで冒頭にアクセント (キルクス)。
circus の語源はギリシャ語 krikos (輪) でインド・ヨーロッパ祖語の *(s)ker- (曲がる、曲げる) に由来するとのこと (wiktionary)。
ラテン語 notus の意味は "背" とは異なるが o は長母音。ギリシャ語 noton は原初は no- は長母音。対応するラテン語 natis は長母音ではない。
ギリシャ語の同様の造語 (一般に学名の由来になる) では -no- の長音は保存されているので "背" の意味では長母音とする解釈とした。
この解釈を採用すれば -notus で終わる学名のアクセントが統一されて覚えやすいと考え採用した。
[分類と亜種]
チュウヒ類は、現代の分子遺伝学的解析では従来の Accipiter 属に内包されることがわかった。個々の単系統性を保ちつつ単系統でまとまりのよいチュウヒ (Circus) 属を残すため、Accipiter 属の分割が提案されている (#アカハラダカの備考参照)。
この分割を採用する場合、チュウヒ属に最も近縁な属はオオタカなどを含む Astur 属となる。チュウヒ類はオオタカ類の系統から比較的新しく生じたものと考えられ、観察の際にも共通性が感じられることがあるかもしれない。オオタカ類から齧歯類を主食物とするグループが進化したと考えるとよいのかも知れない。
Catanach et al. (2024) の分子系統樹では Astur, Megatriorchis, Circus をまとめて1属にすることも可能である。
この場合は Circus 属に加えてMegatriorchis 属の属名も変える必要が生じ、Megatriorchis の特徴ある属を改名するのはふさわしくないとも言えるだろう。
もしこの統合を採用した場合は別の問題がある。Astur と Circus は Lacepede (1799) の同じ文献に登場するもので先取権の問題が発生する。チュウヒ属をオオタカ属に統合、というほど簡単ではないのである。
裁定者次第ではオオタカの学名が Circus gentilis (!) となる可能性すら考えられてしまう。Circus 属の方が種数が多いので、属名の変わる種の数を最小にする論理ならばこちらになってしまう可能性がある。
これら複雑なことを検討するより分離した方がずっと自然な解決であり、分岐年代的にも Aquila 属や Spizaetus 属 (これは単系統性の要請から分割されたもの) の扱いにも合わせて
Astur, Megatriorchis, Circus を別属にするのが自然となる。
C4 植物の出現によって草原が広がったことに応じて分布を広げ種分化を起こしたとする考え方がある [Oatley (2015)
A molecular phylogeny of the harriers (Circus, Accipitridae) indicate the role of long distance dispersal and migration in diversification]。
#ハイイロチュウヒの備考 [渡りをするタカ類の系統] も参照。
かつては2亜種あり、日本の亜種は spilonotus (日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版での扱い)だった。
亜種 spilothorax はニューギニアに分布し、パプアチュウヒ Circus spilothorax (英名 Papuan Harrier) として別種とされることが多い (IOC 2.1 以降、HBW/BirdLife 2014 以降、Clements 2021 以降など)。
この場合チュウヒは単形種となり、亜種の記載は不要になる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではこの扱いとなっている。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では当時の学名で Circus aeruginosus をチュウヒ、Circus spilonotus をシベリアチュウヒとしており、分布の記述などを見ると現代とは学名が逆転していた。
この当時は広義ハイタカ属、チュウヒ属をまとめて Accipitrinae 亜科に分類されており、何と現代の分子系統解析と合っている。チュウヒ属を別亜科としていない。
チュウヒは以前はヨーロッパチュウヒと同種と考えられていた (分離される前の学名のため現在ではヨーロッパチュウヒを指す Circus aeruginosus)。東シベリア/モンゴルでこの2種が同所的に生息する地域 (イルクーツク付近など) があり、雑種も知られている
[Fefelov (2008) Comparative breeding ecology and hybridization of Eastern and Western Marsh Harriers Circus spilonotus and C. aeruginosus in the Baikal region of Eastern Siberia。
ディスプレイや繁殖様式の違いなども記されている]。
現在はヨーロッパチュウヒと別種とされるため、英名は Eastern Marsh Harrier がよい。
さらに古くはチュウヒの概念はもっと広く、Dement'ev and Gladkov (1951) ではヨーロッパチュウヒ (基亜種)、チュウヒ、アフリカチュウヒ、マダガスカルチュウヒ、レユニオンチュウヒ、ミナミチュウヒをすべて含んでいた。
当時の分類では亜種 spilonotus は東アジアのチュウヒの繁殖地と越冬地が含まれていた。
「鳥630図鑑」 (1988) では Asian Marsh Harrier の英名が与えられ、ヨーロッパチュウヒから分離されている。上記 Dement'ev and Gladkov (1951) の亜種 spilonotus の分布の他にニューギニア島も含まれており、現在の分類でのパプアチュウヒを含んでいたと考えられる。
「コンサイス鳥名事典」ではもっと広く、オーストラリアやポリネシアのチュウヒ類も含む記述になっている。これらの区分の考え方の違いは現代の分子系統分類での系統の近さを考えるとやむを得なかったであろう。
Circus spilonotus Kaup, 1847 (原記載) は基産地があまり明らかでなく Asia となっている。参考 によればタイプ標本の産地は Sharpe によればフィリピンとのこと。
フィリピンを産地とする記載もあって Circus philippinensis Steere, 1890 (参考)。おそらく "アジア型" としてシノニムとなったと想像される。
チュウヒ類は主に2つのグループに分けられる: 草原性の steppe harriers と沼地性の marsh harriers [Simmons (2000) "Harriers of the World"]。日本の種で前者に属するものはハイイロチュウヒ、ウスハイイロチュウヒで、後者に属するものはチュウヒ、(ヨーロッパチュウヒ) である。
マダラチュウヒは両者の中間的な性質がある (生態等からの従来分類で steppe 型、分子遺伝学的で marsh 型の系統との中間的位置にある)。特にハイイロチュウヒと、その他のチュウヒ類の好む環境や採食行動の違いを理解する上でこの分類は役立つであろう。系統的には marsh 型の方が新しいグループに属する。
以下 Catanach et al. (2024) に従ってこれまでと同様に並べる。英名の後の (S) (M) は steppe harriers と marsh harriers に対応する。
(伝統的チュウヒ亜科 Circinae に相当したもので拡張されたが: 現在は Accipitrinae に吸収)
パプアオオタカ属 Megatriorchis
パプアオオタカ Megatriorchis doriae Doria's Goshawk (Doria's Hawk に変更)
チュウヒ属 Circus
(系統 1)
アイレスチュウヒ(仮名)* Circus teauteensis Eyles's harrier (絶滅種)
ウスユキチュウヒ Circus assimilis Spotted Harrier (S)
(系統 2)
クロチュウヒ* Circus maurus Black Harrier (S)
ウスハイイロチュウヒ Circus macrourus Pallid Harrier (S)
ハイイロチュウヒ* Circus cyaneus Hen Harrier (S)
アンデスチュウヒ [高野 (1973) ではナンベイハイイロチュウヒ] Circus cinereus Cinereous Harrier (S)
アメリカハイイロチュウヒ Circus hudsonius Northern Harrier (S)
(系統 3)
ハネナガチュウヒ* Circus buffoni Long-winged Harrier (S)
ヒメハイイロチュウヒ* Circus pygargus Montagu's Harrier (S)
マダラチュウヒ Circus melanoleucos Pied Harrier (S)
ヨーロッパチュウヒ* Circus aeruginosus Western Marsh Harrier (M)
アフリカチュウヒ* Circus ranivorus African Marsh Harrier (M)
チュウヒ* Circus spilonotus Eastern Marsh Harrier (M)
パプアチュウヒ* Circus spilothorax Papuan Harrier (M)
ミナミチュウヒ* Circus approximans Swamp Harrier (M)
マダガスカルチュウヒ* Circus macrosceles Malagasy Harrier (M) (和名修正)
レユニオンチュウヒ* Circus maillardi Reunion Harrier (M) (和名修正)
チュウヒ類とオオタカ類の中間に位置するパプアオオタカ Megatriorchis doriae (英名 Doria's Goshawk)という単形属の変わった種類がある。
(広義) Accipiter 属に含まれると考えられたこともあったが、現代の分子系統研究はこれを支持せず、チュウヒ類からはやや離れているがオオタカ類からチュウヒ類が分岐したころの系統に近いと考えられる。
英名も分子系統を反映して Doria's Hawk と 2024 年変更された。
系統が少し離れるところに空行を入れてある。ここでは便宜上3系統に分けたが、それほど類縁関係が遠いわけではない。(系統 3) は最初2種はそれぞれ小さな別系統だが残りの種はよくまとまっている。
絶滅種の Circus teauteensis の和名は見つけられなかったため英名 (ニュージーランド古生物学者 Jim Eyles) から仮に与えてある。下記 [樹上営巣するチュウヒ類] に少し解説がある。
(系統 3) の最後の5種は同種に近いぐらい系統が近い。
レユニオンチュウヒとマダガスカルチュウヒの和名はどこかで逆になってしまっているようなので入れ替えてある。おそらく IOC 掲載の和名が逆になっているためと思われる。
分布は Circus maillardi が英名の通り現在レユニオン島のみに生息。Circus macrosceles はマダガスカルとコモロ諸島に生息。
かつては同種とされていた。さらに以前はヨーロッパチュウヒとチュウヒ以降の4種はすべて Circus aeruginosus の亜種とされていた。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) ではメスが褐色の上面と白い腰、下面には縦斑のあるグループとしてマダラチュウヒ、ハイイロチュウヒ、アンデスチュウヒ [高野 (1973) ではナンベイハイイロチュウヒ]、
ウスハイイロチュウヒ、ヒメハイイロチュウヒの5種をグループにまとめていたが分子遺伝系統的には特にまとまったグループではなさそうである。
チュウヒ類は比較的新しく種分化を遂げ、種間の違いが小さい。
この点はノスリ類と同様であり (#ノスリの備考参照)、雑種形成も起きやすいと考えられる。
マダラチュウヒはリスト最後の7種 (marsh harriers) より少し前 (250 万年前ぐらい) に分岐したと考えられ、多少異なっているが系統的にはやはり近いグループである。marsh harriers は単系統におさまるが、steppe harriers は多系統となる。
チュウヒ類の識別がしばしば困難であることにはこれらの類縁性もおそらく関係している (チュウヒ類で世界のデータベースの画像検索をすると、あまりに似た種が多くて正しく検索できているのか、あるいは識別が正しいのか悩まされるぐらいである)。
ヨーロッパチュウヒ (およびチュウヒ、他のチュウヒ類でも同様) では分布が広範であるにもかかわらず、ミトコンドリア遺伝子の多様性が低い。これはチュウヒ類の主な食物が齧歯類であり、獲物の個体数の大幅な増減が見られる特徴に関連している可能性がある。
獲物の個体数の減少が歴史的に何度も起きたことで捕食者の個体数が減少し、個体数のボトルネックを体験するなど遺伝的多様性が減少したことが考えられる [Oatley (2015); Simmons (2000)]。
"ringtail" harriers という表現があり、一部の種で若鳥、メスで種類を正確に識別しにくいものを指す。Forsman (2016) "Flight identification of raptors of Europe, North Africa and the Middle East" 2nd edition にも同じ表現が使われており、一番識別の難しいグループであるとも記されている。これは上記のようにチュウヒ類が系統的に近く似た特徴が現れやすいことに起因するのだろう。
歴史的には The Ringtail の名称がみられ、学名からはヒメハイイロチュウヒを指していたよう。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) の時代にはチュウヒダカ類 (Polyboroides属。ハチクマ亜科の前にあたるヒゲワシ亜科に類縁。#ハチクマの備考 [ハチクマ類の系統分類] 参照)、セイタカノスリ Geranospiza caerulescens もチュウヒ類に含まれていたが、系統関係はいずれもまったく違っていた。
Brown (1976) によれば南米とアフリカの距離が近かった時期の関連も考えていたが関係なかった。
[樹上営巣するチュウヒ類]
ご承知のようにチュウヒ類は地上に営巣するが、チュウヒ類の中で1種だけ樹上営巣のものがある。
ウスユキチュウヒ Circus assimilis 英名 Spotted Harrier というオーストラリアの種類。
チュウヒ類はクラッチサイズが大きいが、この1種はクラッチサイズが小さく、地上営巣がクラッチサイズが大きい要因になっていると考えられるとのこと [Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology"]。
Gabb (1984) The evolution of Tree-nesting and the Origin Spotted Harrier。
この著者はこの種ももともと地上営巣だったのが樹上性に移行したと考えている。樹上の巣の作り方も他の猛禽類に似ていないとのこと。
当時はチュウヒ類の進化系統はまだあまりわかっていなかったが、Catanach et al. (2024) の分子系統樹によればウスユキチュウヒは 広義の Accipiter 属からチュウヒ類が分岐する最初の枝 (あるいは前述の Megatriorchis 属の分岐の後) に当たり、
あるいは地上営巣だったのが樹上性に移行したのではなく、まだ樹上営巣習性のあるタカ類の性質を残したチュウヒ類なのかも知れない。
[チュウヒ類の離島への定着、ニュージーランドの鳥の定着と衰退]
系統樹でウスユキチュウヒと同じ枝にニュージーランドの絶滅種 Eyles's Harrier (Circus teauteensis) が含まれているが営巣習性はわからない。
島でしばしば見られる巨大化 (island gigantism) の典型例とされ、メス成鳥は体重 2.5-3.0 kg と推定されている。
ニュージーランドにはコウモリ以外の哺乳類がいないためオオタカのように主に鳥を狩っていたのではないかとの考えがある (チュウヒ類はオオタカ類から派生した系統で一種の先祖返りとも言える?)。
ニュージーランドを含めオセアニア離島には現在ミナミチュウヒが生息しているが、遺物の推定年代が 1000 年を超えない。Eyles's Harrier はミナミチュウヒの競争によって絶滅した可能性も考えられている [wikipedia 英語版より。Eyles's harrier のページでは過去の Worthy and Holdaway (2002) "The lost world of the Moa: Prehistoric Life of New Zealand" も引用しており、少しニュアンスが違う]。
ニュージーランドには過去2回の大きな導入の波があったとのこと: Rawlence et al. (2019) History Repeats: Large Scale Synchronous Biological Turnover in Avifauna From the Plio-Pleistocene and Late Holocene of New Zealand。
Anas 属のカモ類、ゴイサギ類、カオジロサギ Egretta novaehollandiae White-faced Heron、オーストラリアツバメ Hirundo neoxena Welcome Swallow、ノドグロカイツブリ Tachybaptus novaehollandiae Australasian Grebe
は人が定着して島を覆っていた森林が減少した結果定着可能になったものと考えている (約 1000-500 年前)。
1回めの大きな導入は 250-100 万年前ぐらいの森林の衰退期で、Eyles's harrier、
タカヘ (ノトルニス) Porphyrio hochstetteri South Island Takahe などの系統、ハーストイーグル Harpagornis moorei Haast's Eagle などはこの時代に定着して島で独自の進化を遂げたが人為活動により衰退または絶滅した可能性が考えられる。
Eyles's harrier も人為的な森林減少で空間が生まれてチュウヒ類が再度定着可能になり、ニッチが非常によく似たミナミチュウヒが定着した結果競争排除された可能性がある。
250-100 万年前ぐらいにニュージーランドで起きた環境変化に似た変化を短期間で人為活動がもたらしている (論文表題の「歴史はくり返す」の意味するところ)。
Knapp et al. (2021) Ancient Invaders: How Paleogenetic Tools Help to Identify and Understand Biological Invasions of the Past
もこの仮説を取り上げ、分子遺伝学 (準化石を含む) がこのような生物の侵入や衰退にどのように役立つか紹介したレビュー。
文献は How a giant eagle came to dominate ancient New Zealand (Boyce Upholt 2022) の記事から知った。
Brown (1976) pp. 81, 84 によればチュウヒ類は系統の近い Astur 属 (現在の分類で記述する) に比べて羽ばたきに適応しているとのこと。ソアリング中心の種類とは違って離島や海上遠方 (フィジーやニュージーランドなど) に分布するチュウヒ類があるのはそのためと説明している。
自力で海を越えて分布を広げる能力があり適切な環境があれば定着できるのだろう。
ミナミチュウヒは他にも離島に分散しており、哺乳類捕食者のいないフィジーでは固有のイグアナの脅威となっているとのこと:
Harlow et al. (2022) Predation of the critically endangered Fijian crested iguana (Brachylophus vitiensis) by the swamp harrier (Circus approximans)。ミナミチュウヒが爬虫類を主な食物とする初めての記録とのこと。
ミナミチュウヒは比較的強力な捕食者と思える。食性はジェネラリストのようで冬場は死肉も食べ、ロードキルの死体を食べて自身も犠牲になることがしばしばある (wikipedia 英語版より)。
日本のチュウヒともオオタカともまた少し違った点があるよう。
志村 (1997) Birder 11(2): 76-79 でミナミチュウヒのことが触れられており、森林の密生した環境では採餌できないが、山が放牧地となって標高の高いところまで生息地を広げた。日本で言えばチュウヒ、ノスリ、カラスに相当する位置を占めるとの説明がある。
人為導入された種ではないが広範に分布を広げた要因は人為活動が関連している。
チュウヒ類は亜種が非常に少ない。近年分離されて単形種とされたものがあることも理由と考えられるが、それ以外の種でも亜種が非常に少ない。離島に分布を広げたミナミチュウヒも IOC 14.2 では単形種となっている。
東南アジア地域を中心に多数の種に分化している Tachyspiza 属とは様相がかなり異なる。Tachyspiza 属の東南アジア地域は渡り能力の高いアカハラダカ (の祖先) が渡り能力を活かして分布を広げたと考えられるが、ミナミチュウヒでは種分化が起きない程度に海上を移動して遺伝的交流があるのだろうか。つまり多くの種類で見られるように島に定着して分散能力を失う傾向が少ないのだろうか。
それとも分岐年代が浅いだけで種分化の途中段階を見ているのだろうか。
ここでは長距離の渡りを行う点で Tachyspiza 属と比較したが、定住性の強い Spilornis 属 (カンムリワシなど) との違いはより顕著である。
チュウヒ類のこのような特性は大陸との違いを考える時に参考になるかも知れない。「大陸型チュウヒ」と言われる割には亜種に分かれていないのは分岐年代の浅さだけでなく、チュウヒ類固有のこのような分散特性に基づくのかも知れない。また分散特性が違うならばチュウヒ類はなぜ特別なのだろうか (→ 次の項目につながってしまった)。
[チュウヒ類の食性と生活様式の関係]
週間アニマルライフ (1973) pp. 2846-2847 のチュウヒの項目 (浦本・安部) では、当時はチュウヒを広く扱っていたため、ニュージーランドやオーストラリアの亜種の表現が登場する。現在ならばミナミチュウヒに対応する。
この地域に生息するノウサギ (外来種) を兎粘液腫 (ミクソーマ) ウイルス (これも個体数管理のために導入されたウイルス) に感染してほとんど全滅するまで主食としていたとのこと。
またアフリカに分布するチュウヒ類はしばしば大発生するトビバッタ類の大群に集まるとのこと。
これらの記述を見ると、チュウヒ類は r 戦略的な獲物 (#クマタカ備考の [クマタカ類の隔年繁殖の理由?] 参照) を得意としているように見える。
湿地もそもそも年による変動が大きく移ろいやすいものであり、特定の地域にとらわれず獲物を求めて移動する生活様式をとっているのでは。渡り能力の高さやクラッチサイズの大きさもこのような生活様式を反映しているように見える。例えば分散能力が特に高くなったものがミナミチュウヒとも言えるだろう。
従って特定の樹木やテリトリーにこだわる樹上営巣はあまり向かなかったと考えると、チュウヒ類の環境嗜好が見えてくるような気がする。生活史戦略は次の [タカ類の一夫多妻] にもおそらく関係がありそう。
地上では繁殖失敗が多いのでメスがより多く卵を産めるように...はタマシギの説明にしばしば使われるがチュウヒでは雌雄の役割が違うのでそのままでは使えないかも知れない。しかしナンベイタマシギでは雌雄関係がタマシギと逆なのでどちらの性でもよいのかも知れない。猛禽類ではもっぱらオスが食物を捕るので雌雄の役割に著しい違いさえあれば同じような説明でよいのかも。
この特性 (推定) を考慮するとチュウヒ類が同じところにとどまってくれるものと想定し、場所を決めて保護区とする保護手段はあまり向かないかも知れない。そもそもある年に現れて別の年には現れない、あるいは年によって繁殖したりしなかったりするのはチュウヒ類の本質であって、一喜一憂するほどのことはない。しかしチュウヒ類に適した生息場所が一定以上の割合で広域に存在しなければ、いくら特定地域で保護を行っても数が減ってゆく可能性があるなど想像できる。
もしチュウヒ類自身が r 戦略的であれば、個体寿命はあまり長くなく、繁殖率が低下すると r 戦略的でない種よりも効果が顕著に現れるかも知れない。逆に好適な条件が整備されれば急速に数を増やす可能性もある。
上記週間アニマルライフの記事によれば英国では湿地の干拓、そして殺虫剤の使用によってチュウヒ (現在のヨーロッパチュウヒ) は急激に数を減らし、この記事の時点で6つがいとなって、そのうち半数が RSPB の保護区内に生息する状況となっていたとのこと。
その後は殺虫剤の禁止によって順調に数を増やして現在では危ない状況にはないとのこと: Marsh Harrier (Hawk and Owl Trust)。この記事を見ても成鳥の年生存率が 74% とあまり高くないことを示唆する。しかし #ハクトウワシ備考の [猛禽類の寿命記録] ではヨーロッパチュウヒで 20.1 年の事例があるのでそこまで短命ではないかも。
殺虫剤の禁止によって英国では順調に数を増やしたにもかかわらず、日本ではなぜそうなっていないのか問う必要があるのだろう。
[タカ類の一夫多妻]
タカ類では珍しく、チュウヒ類ではしばしば一夫多妻がみられる。
日本のチュウヒでも「基本的に一夫一妻制であるが、各地で一夫二妻の事例が確認されている
(日本野鳥の会岡山県支部 2002, 中川 2006, 千葉ほか 2008, 小栗ほか 2009, 多田ほか 2010)」
(出典) [橋本 kbird:06051 (2023.5.22)]。
北海道におけるチュウヒ Circus spilonotus の生態
その原因として以下のような仮説がある。Altenburg et al. (1982) Polygamy in the Marsh Harrier, Circus aeruginosu: Individual Variation in Hunting Performance and Number of Mates。
この説明ではオスの方が成熟が遅く、獲物を狩る能力の個体差が大きいので実効性比が偏るアイデアを述べている。
Into the Nest: Home, home on the range (northern harrier style) では
営巣できる環境が狭いので、巣の間隔が狭いことも要因になっているらしいとの解説がある。
Hayes et al. (2022) Typical Polygyny and Cooperative Polygyny in Ridgway's Hawk (Buteo ridgwayi)
ノスリ類でも複数の種類でば一夫多妻が知られている。
Driscoll and Rosenfield (2015) Polygyny Leads to Disproportionate Recruitment in Urban Cooper's Hawks (Accipiter cooperii)
都会に進出したクーパーハイタカでも知られている。
Wang et al. (2019) Polygyny in the Eurasian Kestrel (Falco tinnunculus): Behavior, Morphology, Age, Heterozygosity, and Relatedness
チョウゲンボウの一夫二妻。一夫二妻のオスはより翼開長が小さかった。2巣めのメスは若くてより小型だった。2巣を持つオスの餌運びは通常の2倍であった。
Ille et al. (2002) Paternity assurance in two species of colonially breeding falcon: the kestrel Falco tinnunculus and the red-footed falcon Falco vespertinus
コロニー営巣性、あるいはその傾向のある種類であるニシアカアシチョウゲンボウ (#アカアシチョウゲンボウの備考参照)、チョウゲンボウではつがい外交尾への防御行動もあるとのこと。
Bildstein (2017) "Raptors" p. 122 によれば、おそらく Simmons の記載を踏まえたものと思われるが、チュウヒ類が地上営巣性になったのは樹木の少ない環境に進出したためで、地上の捕食者のいる環境で地上営巣する弱点もある (#ミサゴの備考 [地上営巣するミサゴ] 参照)。
その欠点を補うべく loose colony 弱いコロニー性を持っていて、外敵に対して集団防衛 (モビング) を行うとのこと。雌雄の餌渡しが空中で行われるのも巣の位置をわかりにくくするため、との解説が出ている。
これらの記述に基づくと繁殖期のチュウヒ類は積極的に営巣場所を隠すようで、他のタカ類以上に観察圧に敏感かも知れない。
ヒメハイイロチュウヒ Circus pygargus Montagu's Harrier では警戒音が他個体を引き寄せるとの実験がある:
Arroyo et al. (2001) Colonial breeding and nest defence in Montagu's harrier (Circus pygargus)。
#オウチュウ備考の [警戒音の本質は何か] も参照。
Korpimaki (1988) Factors promoting polygyny in European birds of prey-a hypothesis
に当時ヨーロッパの猛禽類 (フクロウ類も含む) での一覧と考察が出ている。一夫多妻は齧歯類を食べる種類で多く、鳥を食べる種類では少ないとのこと。ハヤブサの事例があるとのこと。[Newton (1979) に
Weir の報告が出ているとのこと]。
松村 [kbird:06062 (2023.5.22)] によれば日本のハヤブサのでも未遂事例があったとのこと。チュウヒ類で巣の間隔が狭いことが理由に挙げられているが、このハヤブサの事例でも巣間距離が 320 m 程しかなかったとのことである。
先崎・先崎 (2015) Birder 29(10): 22-23 でも北海道のチュウヒの一夫多妻に触れられている。同じ個体でも年によって繁殖様式が異なることもあるそうである。
この記事では道央8月初旬 (秋の移動前) にカエルを食べに集まるチュウヒの記録が紹介されている。
浦 (2015) Birder 29(10): 26-27 に 2009 年よりチュウヒに GPS を装着して行動圏や渡りを調べた結果が紹介されている。
[ロシアのチュウヒ]
「大陸型チュウヒ」の表現はよく使われるが、ノスリとは異なり日本と大陸とで(少なくとも現在は)亜種は同じである。North Eurasia Birds Watchで大陸のチュウヒの写真を多数見ることができる (分布付き, 写真一覧)。
eBird でもロシアで撮影された写真が見られ、顔と風切先端のみが黒くて他はほぼ白い個体も記録されているがいかが考えられるだろうか。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では、「オスには2種類の色型 (morph) があり、中間型もある。黒色型のオスでは頭とのどが黒く、背中と上部雨覆は黒いが明るい色か灰色っぽい縁取りがある (マダラチュウヒのオスでは背中と上部雨覆は完全に黒い。ヨーロッパチュウヒのオスでは頭頂は褐色)。翼下面と腹は白い (ヨーロッパチュウヒでは褐色)。
淡色型のオスでは色彩がより不明瞭で、頭、背中、上部雨覆は暗色と淡色のまだらになっており、しばしば黒よりは褐色が基調。初列風切と尾の縞が明瞭で腹と翼下面に斑点がある。オスは3歳で成鳥の色となり、亜成鳥は成鳥より暗色だが若鳥よりは明るい色をしている」と記載している (オスの色彩のみを抜粋。原文説明を読むことができる)。
ロシア沿海地方での繁殖: Shokhrin et al. (2020) Breeding birds of Primorsky Krai: the eastern marsh harrier Circus (aeruginosus) spilonotus (pp. 4745-4755)
(極東の鳥類42:沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める)。代表的な写真も収められており、ヨーロッパチュウヒとは色彩が明らかに異なるとのこと。
[フィリピンのチュウヒ]
Eastern Marsh Harrier (for ID confirmation) (Gid Ferrer 2024.10)
ずいぶん印象が違うがいかが判断されるだろうか。
調べてみると東南アジアのチュウヒにはこのように白っぽいものが多く見られる。
フィリピンの画像を調べると日本のチュウヒに似た色彩とこのような色彩のもの写真の両方がある。フィリピンのチェックリスト (2023) では亜種は記載なし。
Eastern Marsh Harrier Pampanga (Jopet Sy 2024.10) に2羽の写った写真もある。
Eastern Marsh Harrier (Jopet Sy 2024.10) こちらは白くないタイプの下面の画像。
[チュウヒ類の飛翔形]
チュウヒ類が飛翔する時に翼が浅い V 字型の形をとることはよく知られている。この飛翔タイプを英語では (positive) dihedral flight (dihedral は航空用語で上反。数学的には "2平面からなる"、の意味)。negative を付ける (あるいは anhedral) と逆 V 字型を指す。
いかにも不安定そうに見えるが、乱流などを受けて傾くと下がった方の翼はより揚力を発生するので実は力学的に安定していて効率がよいとのこと。rocking flight とも言われる (rock は岩ではなく、ロック音楽の由来となる "揺れる" の意味) [Bildstein (2017) "Raptors" pp. 37-38]。
ただし航空力学的にはそれほど簡単な話ではなさそうで、翼は可動部分も多く、鳥が姿勢を上手にコントロールしていることも含める必要があるのだろう。チュウヒ類については明確に記述した論文は見つけられなかった (他の実験動物に比べてチュウヒ類を扱うのは難しい点もあるだろう)。
Durston (2019) Quantifying the flight stability of free-gliding birds of prey (学位論文)。
この p. 182 に "dihedral effect" として dihedral は傾きを復元するモーメントを生じるとあるが、飛行機のような固定翼に対する概念でもあり議論はそう簡単ではない模様 (p. 194)。p. 199 に左右非対称な風切羽の開き方で生じる体軸まわりの回転の不安定性 (roll instability) を翼を dihedral に保つことで補正している記述とヒゲワシの写真があるがまだ仮説段階の模様。
航空力学では wikipedia に解説があったので引いておく Dihedral (aeronautics)。
Dihedral Effects in Aircraft Flight (Peterson 2013)
によれば正の dihedral angle は roll に対する安定性を増し、負の場合は操縦性 (機敏な運動を可能にする) が高まるとのこと。いずれも目的に応じて航空機に応用されている。
Control and Stability of Aircraft (aerospace engineering 2016) にも図解入りの説明がある。
一般的傾向はチュウヒ類の飛行の説明に当てはまるように見える。低速で失速しやすく低いところを飛ぶのでこの翼形が適切なのだろう。羽ばたいて姿勢を回復するのは音も出て獲物に対して目立ちやすくなるので自動安定の方が選ばれたのだろうか。
Bildstein (2017) では more efficient と書いてあったので最初に読んだ時はエネルギー効率が良い意味と想像したがそのような記述は文献には見つけられなかった。一般向け書籍なので広い意味で「より有効」の意味で使っている模様。
チュウヒ類は系統はオオタカ類に非常に近いが、(もちろん食物の応じて) オオタカ類が高速飛行かつ操縦性を高め、チュウヒ類が低速飛行で安定性を高めたため外見がかなり違って見えるようになったのかも。
positive dihedral の傾向も体重云々よりもゆっくり飛んで獲物を探すかどうかに関係が深いかも (イヌワシなど)。とまって獲物を探すハンティング法ではおそらくあまり必要でない。
なおチュウヒ類のように低くゆっくり飛んで獲物を探す飛行を "slow quartering" (quarter くまなく捜索する。英語辞書では意味は crisscross とある。もともと猟犬などに使われる用語) や "coursing" (こちらも猟犬用語) とも呼ぶとのこと (Bildstein 2017)。
カタグロトビなどのハンティング法も同じように "quartering" と呼ばれる [Black-winged Kite (The Peregrine Fund)]。
#カタグロトビ備考の Keirnan et al. (2022) でも共通点としてこの用語 (low, continuous forward flight over tall grasses and marshes with the beak pointed downwards と説明) が紹介されているがカタグロトビ類はホバリングを好む点でチュウヒ類と多少異なるとのこと。
Cheney et al. (2021) Raptor wing morphing with flight speed のように翼の形と飛行速度の関係の研究などはあって、フクロウ類とオオタカが使われている。尾の角度を調整することで抵抗を最小にする結果は他の研究でも得られている。
[腰の白いタカ類]
論文になっているわけではないが、Garcia et al. (2022) がポスター発表を出している Phylogenetic Signal of White Rump in Accipitriformes
タカ類の中で腰の白いものはチュウヒ類が特に多い (属のうち 81%)。例外はウスハイイロチュウヒ (ほんとう?)、ウスユキチュウヒとしている。
ウタオオタカ、オナガオオタカの系統もまとまっている。アフリカツミ、ニシアフリカツミもまとまっている。トカゲノスリも含まれる。このポスターは 2018 年の系統樹を用いて系統との関係は薄いと述べているが、最新のものを用いると 2024 年の新概念の亜科 Accipitrinae は腰の白いものが生じやすいよう。
他にも散発的にあるがノスリ亜科でやや目立つ感じ。サシバも含まれているが腰は白いのか?? 散発的な方ではコシジロイヌワシは名前の通り。
間違っているものも結構ありそうで、同じ種でも一部白いものもあるので文献を鵜呑みでなくしっかり調べることができ、個々の種に関心のある人も検討すべき課題だろう。
コシジロイヌワシの腰はなぜ白いのか、改めて考えると確かに不思議でもある。
チュウヒ類は系統的に近く、たまたま生じた白い腰が多数の種に共通しているように見えるだけかも知れない。
Brooke (2010) Unexplained recurrent features of the plumage of birds
鳥類全体でしばしば見られるが統一した説明はない。
捕食される側では Santos et al. (2015) Personality and morphological traits affect pigeon survival from raptor attacks
は捕食者を紛らわす可能性も考えているが効果が確かめられているわけではなくアイデア段階。
松本 (2007) Birder 21(10): 31 になわばりに侵入したトビを攻撃するハヤブサの写真があり、腰らしい部分を攻撃して羽毛が飛び散り、ハヤブサも少し羽毛を掴んでいた。
この場合は本格的な攻撃ではないだろうが、あるいは背中を攻撃 (モビングを含む) 鳥に対して腰の白斑がよい目標となって致命的な影響を受けずにすむ可能性を考えてみた。
#ワキスジハヤブサ備考の [ワキスジハヤブサによるペルシャのワシの狩り] "Husam al-Dawlah Timur Mirza" によればワキスジハヤブサに大型の鳥を狙わせる場合は背中を目標にするとのこと。特にハヤブサ類 (に限らないかも知れない) は背中に攻撃を加える習性があるかも知れない [Brown (1976) にも確かにそのような記述がある]。
チュウヒ類、ウタオオタカ類、オナガオオタカ、トカゲノスリも生態的に比較的弱い方の猛禽類なので攻撃に対して身を守る役割の可能性はあり得る気がした。
特にチュウヒ類、ウタオオタカ類は wing loading が小さく、ゆっくりした飛翔で食物を探すためより高速で飛ぶ猛禽類に狙われやすいかも知れない。
タニシトビ [高野 (1973) ではカタツムリトビ] Rostrhamus sociabilis Snail Kite も採食習性を考えるとこの説明が当てはまるかも。
名前の通りのコシジロノスリ Parabuteo leucorrhous White-rumped Hawk は生態がよくわかっていないとのこと (写真を見る限りではチュウヒ類ほどは白い腰は目立たない感じ)。同属のモモアカノスリにも腰の白い個体があるが、集団生活をするための社会的信号になっているかも。
#カタグロトビ備考の [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] で獲物になる鳥は腰の羽毛が抜けやすい傾向にあるとのこと。チュウヒ類などでも同様の傾向が見られるか調べてみる価値がありそう。
[チュウヒ類の首は長いか]
水谷 (2025) Birder 39(6): 75 でチュウヒの仲間はすべて首が長いが、その首をすぼめて下を向くと必然的に首の周りの羽が大きくふくらみ、パラボラアンテナ状に広がるとのこと。
ここではマダラチュウヒが取り扱われている。表記は "頸" が使われているが原著者が意図したものか判断できないのと、本稿では一般的表記を "首" としているためこちらを使用した。
機能に準じる形態が見えたとの表現で、水谷氏は首の羽毛が顔盤状に広がって集音装置の役割を果たしていると考えられていると読める。
チュウヒ類の首の長さは気になっていた点で「チュウヒの仲間はすべて首が長い」と書かれると「我が意を得たり!」と感じたが、これまでそのような記述を読んだことがなくあまり自信を持って触れることができなかった (ついでに "おしなべて" ならば一層よく合う感じがする。古い言い回しで読者に伝わりにくいかも知れないが、"すべて" と書くと英語では all harriers have ... ぐらいの感覚。"おしなべて" ならば harriers generally have ... ぐらい。"おしなべる" に平均化・平滑化のニュアンスが現れる)。
骨格も含めて本当に長いのかどうかは例によって確認できていないが、少なくとも地上にとまっている時の外見上はそのように感じる。地上で営巣や食事をする際の警戒のための適応と考えていた (近縁のグループに対する関係ではツバメチドリもそのような印象を受ける)。
水谷氏の記述により別の機能が考えられることになる。
#ウスハイイロチュウヒの備考 [チュウヒ類の音源定位] で紹介のようにチュウヒ類が聴覚に依存した音源定位を行っている証拠は各方面で集まりつつあり、外見的にも顔盤が見られる。
フクロウ類では羽毛の研究から顔盤に集音機能があることを示唆する研究がある (#ヒガシメンフクロウ備考 [フクロウ類の音源定位] Hausmann et al. (2009) 参照)。
チュウヒ類ではそこまで知られているかどうかは不明。[チュウヒ類の音源定位] の Citron et al. (2025) では頭骨の構造、脳の神経核の構造ともフクロウ類と類似性が認められた。
関心のある方であれば Jollie (1976, 1977) p. 34 fig. 24 を見ていただければハイイロチュウヒの解剖図で非常に大きな外耳開口部分が描かれており、顔盤はフクロウ類に似ていて外耳開口部分周囲の羽区・裸区の配置が顔盤の形成に役立っているらしい図が描かれている。
この図を見る限りでは首の羽毛は集音機能にはあまり役立っていないかも知れないが、あくまで Jollie の解釈による図版なので実際には役立っているかも知れない。
チュウヒ類の後頸の羽毛の音響特性を調べればよいので、(新鮮な羽毛をどのように手に入れるかの問題があるが) 検体さえあれば実験的検証はおそらくそれほど難しくないのではと想像する。海外では数の多いチュウヒ類もあるのでアイデアさえあれば可能なのでは。
個人的にもう一つ気になったのは [チュウヒ類の音源定位] の Citron et al. (2025) にあるように脳神経科学的にはチュウヒ類はフクロウ類に比べて上下方向の音源定位能力が低い可能性があり (ただし確かめられていない)、行動によって補っているアイデアが提唱されている点が挙げられる。チュウヒ類は飛びながら頭を動かして音源定位のためのスキャンを行っているのではないだろうか。
フクロウ類に耳の左右差は別になくても頭をちょっと傾ければよいのではとの指摘があるが、これも解釈があって、齧歯類の出す音は短いので頭を傾けなくても済むならばそちらの方が有利との意見がある [フクロウ類の音源定位] (Norberg 1968, 1978)。チュウヒ類はまさしくそれを行っているのでは?
フクロウ類に比べてタカ類の方がもともと首が長いのでチュウヒ類はもっぱらそちらを利用し、フクロウ類は頭骨や羽毛に左右差を設けることで上下方向の音源定位を行う方に進化したのでは? など考えてしまう。この機能を用いているならばチュウヒ類の首が多少長くなるのは有利かも知れない。
参考までに週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 93 p. 6 でフクロウ類が首をかしげるのも左右の音の位置を調べるためと解説されていた。
#チョウゲンボウ備考の [チョウゲンボウはなぜ頭を上下左右に動かすか] にあるようにチョウゲンボウが頭を上下左右に動かすのはチョウゲンボウ類では眼球の動きが少ないことも理由に挙げられていた。チュウヒ類も音源を用いる定位とともに視覚による遠近感も併用していると想像すれば、頭の移動などに伴う視差 (motion parallax) も首が長い方が有利かも知れない。
ミサゴでも飛びながら獲物を探すのに有利とのちょっと怪しげな説もある (#ミサゴ備考 [大きすぎる獲物で溺れてしまうミサゴの話は本当か] Pandionidae - Discovering the Enchanting Bird Family に登場)。
チュウヒ類はオオタカ類と系統が非常に近い。オオタカ類も首が長い傾向はあるのだろうか (識別点にも出てくるが定量的には不明)。もしオオタカ類の系統ですでに首が長い傾向が現れていたならばチュウヒ類を進化させるのに多少役立ったかも知れない。
そのような考えから改めて Catanach et al. (2024) の分子系統樹を見ると、我々が旧 (広義) ハイタカ属は首が短いと感じてしまうのは、ツミなどの Tachyspiza 属やハイタカなどの狭義 Accipiter 属 (世界の分類がすでに変わってしまっているので "狭義" などいちいち付けなくてもよいかも知れない) にとらわれすぎかも知れない。
現代の Accipitrinae 亜科 (和名不明) はチュウヒ類も含んでいてむしろ話がしやすいが、Accipitrinae まで範囲を広げるとウタオオタカ族 Melieracini も含まれるので、Accipitrinae はそもそも長めの首が祖先形質だったと考えてよいのだろう。
Tachyspiza 属 (と言っても我々に馴染みの種類の範囲で) や狭義 Accipiter 属は飛翔性小鳥食に適応したため採食行動に応じて首を短くする選択圧が働いていたが (方向転換の際の空気抵抗を減らすため突起を減らす? 小鳥を追う際に視線を安定させる? 理屈はよくわからない)、
オオタカ類の系統では食性の幅が広がって小鳥食の制約からかなり開放され、首を短くする選択圧が弱まって (学術的には relaxed selection の表現がよく使われる) Accipitrinae 本来の形質が戻ってきたと考えればよいのではないだろうか。
北米では Astur 属のクーパーハイタカと狭義 Accipiter 属のアシボソハイタカの重要な識別点の一つに首の長さが挙げられる (とまっている際にアシボソハイタカではほとんど首がないように見える)。やはり Astur 属の特徴と言ってよいのだろう。
チュウヒ類ではその傾向はさらに顕著となり、ウタオオタカ類に似た形態になってきた。系統の異なるチュウヒダカ類 (Polyboroides 属、Harrier-Hawks) との類似性は収斂進化のようなものかも知れないが、どちらにしても環境や生態に応じて似た形態を作る遺伝的基盤があるのではないかと感じる。
現代の Accipitrinae 亜科は一見あまりに茫漠として特徴をまとめにくい感じがするが、ウタオオタカ類やチュウヒ類が本来形態で、ツミなどの Tachyspiza 属やハイタカはむしろ特殊化の産物と考えれば理解しやすい気がする。
Tachyspiza 属の種数が多い (これは島の固有種が多いのも要因の一つ) ため古い分類では圧倒的に Tachyspiza 属が主要系統に見え、チュウヒ類が特殊化の産物のように見えるが必ずしもそうではないかも知れない。
オオタカ類とチュウヒ類をつなぐ位置に相当するパプアオオタカ Megatriorchis doriae Doria's Hawk の形態はヒントになりそうだが希少種で写真が少ない。しかし画像を見ると模様はオオタカ類の若鳥に似ているがほっそりして首が長い印象を受ける。ついハチクマと比べてしまう習慣があるが、嘴周辺を除いた全身の形態はハチクマ亜科にも見えてしまう。
この考察を通じて Accipitrinae 亜科は寄せ混ぜではなく、なぜ系統的にグループにまとまっているのかある程度理解ができた感じがする。チュウヒ類を特殊化の産物と考えず考察することが鍵になると思える。
またカンムリオオタカ属 Lophospiza が Accipitrinae 亜科から外れて カンムリオオタカ亜科 Lophospizinae となることも興味深い。姿は似ているがオオタカとは相当異なるグループで、上記のような視点で見ると Accipitrinae 亜科との共通性は弱いだろうか。検討課題である。
オオタカ類とチュウヒ類の関係を考える際には、オオタカやアメリカオオタカでは高音の音への感度がそれほど高くないので聴覚の感覚生理がどのように進化したのか若干不思議なところもある。もっともこれも Astur 属の代表種がオオタカやアメリカオオタカと思っているだけのことなので、別種では別の適応を示しているかも知れない。
[ヒメハイイロチュウヒの渡り研究]
Kannan et al. (2025) Detour migration to circumvent the Himalayas in the Montagu's Harrier Circus pygargus
カザフスタンの繁殖個体の5年間の追跡結果。中央アジアの渡り経路で最短距離より 1245 km も遠回りの渡りとなって春・秋ともにヒマラヤを避けている (4000 m 以上に相当)。風で経路を決めているとは考えにくい結論となり、それぞれの季節で食物の得られるところ (春にアムダリヤ川、秋にタール砂漠) を通っている模様。
原理的には高所を渡ることができるはずだが、V 字型の飛翔型のため高度を稼ぐのに適していない、また羽ばたき飛行が多いので空気密度の低い高所は避ける傾向がある議論が紹介されている。
チュウヒ類は比較的風の助けを受けて渡っていない印象で、「チュウヒ類の渡り観察ポイント」などがあまり話題にならないのは風向きによって集中する効果が小さいためだろう。チュウヒ類が羽ばたき飛行で分布を広げる能力が高いこととも整合性がよい (因果関係の前後はどちらが先とはただちに言えないが)。
[チュウヒの和名検討]
チュウヒの和名由来もあまり定説がないようで、中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 121 (1940 年初出) では自説として音声由来を挙げられていた。
中西氏は他の種類の他者の解釈も取り上げて音声由来の鳥名が多いとされており、フクロウも音声由来の自説を展開されていた。現代の視点で見てみるとカッコウなどのよくわかる種類を除いて音声由来はむしろ少ないのではと思う。
古名や地方名に音声由来のものはいくつもあったようだが、中西氏ほどは鳥の声に馴染みのない鳥学者が整理する際に大部分を落としてしまったのだろう。
それはともかく、チュウヒの音声を知っている人は案外少ないのではないだろうか (少なくとも自分が案内したことのある鳥学者も知らなかった)。
繁殖時期の声は "チュウヒ" のようには聞こえず (#マダラチュウヒ の求愛の声がタゲリに似ているのと同様)、主に越冬地での声を指したものだろう。個体密度の高い所でないとむしろあまり聞くことができず、多くの人にとっては姿だけの鳥ではないだろうか。
獲物のネズミのような声ですねと言われた方があるが、"チュウヒ" と聞こえるとすれはこのタイプの声だろう。個体密度の高い所 (例えば関西地方からでは石川県の河北潟を思いつく) ではもう少し多様な声を聞くことができる、と思ったが求愛の声も "ウ" を高くすれば "チュウヒ" と書けないこともない気もしてきた。カタカナで音声を表しても区別できない限界をまさしく露呈している。
それはともかく、バードウォッチャーでさえあまり知らない声を名前に用いるとは少し考えにくい。海外でも(ヨーロッパ)チュウヒでそれらしい事例を知らない。
おそらく飛翔行動を指したものだろうと皆が想像するわけだが、どこでも議論されている通り決め手を欠いている感じがする。
そこで「新・野鳥の学名入門」らしく学名との関連を考えてみたい。
チュウヒは Circus 属で、非常に昔 Falco や Accipiter 属などだった時代を除いて、少なくとも和名に結びつきそうな他の属名が使われたことはなかったよう。Circus はラテン語読みでキルクス、ドイツ語読みでツィルクスで似ていると言えば似ている点もあるが音だけでは決め手を欠く感じがする。
日本は過去どのような名称が使われていたのだろうかと山階鳥類研究所の標本データベースを見てみると古い標本が案外存在する。やはり的が大きいので小鳥より採集しやすかったのだろうか。
古いラベルの見られるものでは
YIO-09138 (東京都 1883) にチウヒ、YIO-09058 (神奈川県 1884) にハイイロチウヒがあり、当時からチウヒの名前があり、ハイイロチウヒも区別されていたことがわかる (この場合は色も違うので別種であることは明瞭だっただろう)。
学名はすでに入っていた時代と考えられるので、鳥学者が Circus にチュウヒを与えたのはこの前と想像できる。
さて Circus の名前が入ってきて、おそらくそれは何の意味だ、となったことだろう。現在でも語源を明確に示せないのと同様、当時もよくわからなかっただろう。普通に考えればサーカスをまず思いつく。
英語で circus = サーカス の語源は OED によれば比較的新しいが、古くは円形競技場を指していたものが舞台の場所から派生して Royal Circus が 1791 年にはすでにあって 19 世紀ならば日本にも入っていただろう。
ドイツ語の Zirkus も同じ意味で鳥学者がなぜ鳥と関連があるのか悩んだことだろう。
ドイツ語鳥名由来辞典の Die deutschen Vogelnamen: eine wortgeschichtliche Untersuchung (Suolahti 1909) p. 356 を見ても Weih か Weihe で別名がほとんどなく、早い話がトビやノスリと一緒にされていたらしい。日本でもおそらく同じで "茶色のタカ" は一律に扱われていても不思議でない。
探鳥地でしばしばある話が「今のはチュウヒですよね」で、多くの場合は「トビやノスリではないですよね」のニュアンスで使われることが多い。バードウォッチャーにとってトビでないタカは値打ちがあるということである。一般の人が見たら全部同じに見えるか、よくわかる人でもトビとそれ以外を分ける程度であろう。基本的に "茶色のタカ" である。
ドイツ語以外の他言語も事情は似たりよったりで、渡りのハイイロチュウヒが目立つところでは特別の名前が付いていた場合があるが、チュウヒ類を指す名前は Circus 属が認識されて以降のことらしい。英語でも harrier は Willughby & Ray, Ornithologiae (1676) に現れたもので、総称として現れるのは 1828 年に Bonaparte が Circus 属とともに紹介し、今後は Harrier と呼ぼうと提案したもの (OED。#ハイイロチュウヒ備考も参照)。
英語もドイツ語もあまり参考にならず、Circus の意味はサーカスだと判断したと思えば、サーカスに関連した鳥の動作を考えると主要演目の空中ブランコはまさしく「宙飛」である。飛行形態を知っている人であれば不安定にバランスを取る姿を綱渡りに見立てたかも知れない。
後者は前例がないわけではなく、ダルマワシの Bateleur がまさしくこの意味である。ダルマワシもチュウヒ類も gust soaring を用いていると考えられる共通点もある (#アホウドリ備考 [ソアリングの分類] 参照)。
ここでは属名 Circus からサーカス、そしてサーカスの主要演目と飛行様式の類似性から「宙飛」を推薦しておきたい。
ひとたび Circus = チュウヒ と訳すと決めてしまえば話は簡単で、Circaetus はチュウヒワシと英名とは関連性のわからない和名の定訳もできる。
チュウヒダカの方は英名の Harrier-Hawk 由来でもよいし、かつては Circinae (伝統的チュウヒ亜科) に含まれていた (英名もこちらが由来かも知れない) いずれも考えられる。古い学名由来も考えるのは、山階鳥類研究所の標本データベースにこれらの種類の標本が (もちろん海外由来で) かなり古い時代に含まれていたため。手元に標本があることは和名を与える動機になっただろう。
ロシア語名は lun' と独特で、Kolyada et al. (2016) の語源辞典でもやはりよくわかっていない。
ロシア語話者でも "lun' を見に行く" と言っても「それ何」となるらしく、日本語で「チュウヒを見に行く」と言ってもわかる人がほとんどないぐらい知名度が低いらしい。
luna (月) と関係があるのではとの説があるらしいがこれまた関連がわからない。日本よりはハイイロチュウヒ類縁種が中心で白い模様のあるものが多いので月になぞらえた (?) との推測も出ている。しかし sedoj kak lun' (チュウヒのように白髪の) の慣用句もあるとのこと。
別語源は lupit' から、現在ある言葉の同義語で表せば grabitel' (略奪者) 説もあるとのこと。
ロシア人でも気づかなかったかも知れないが、月ならば「狂っている」(英語の Hen harrier の OED 解説のように) あるいは腰の白斑を月型と考えた (例えばイスラム圏で moon-tailed #ワキスジハヤブサ 備考の [ワキスジハヤブサによるペルシャのワシの狩り]) 可能性もあるかも知れない。
-
ハイイロチュウヒ
- 第8版学名:Circus cyaneus (キルクス キューアネウス) 青っぽいチュウヒ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:第8版と同じ
- 第7版亜種学名:Circus cyaneus cyaneus (キルクス キューアネウス キューアネウス) 青っぽいチュウヒ
- 属名:circus (m) チュウヒ (circus (m) 円弧、求愛の時の旋回行動から)
- 種小名:cyaneus (adj) 青っぽい
- 英名:Hen Harrier
- 備考:
circus は#チュウヒ参照。
cyaneus は冒頭が長母音。アクセントは a にある (キューアネウス)。
cyaneus は青にも使われる単語だが、一般にはもっと曖昧な色も指す (#カタグロトビ備考参照)。
ハイイロチュウヒの和名で色彩的には違和感がないが、種小名の cyaneus とは少し合わない感じがする。
現在のヒメハイイロチュウヒ類似種の概念に対して古く Circus cineraceus (灰色っぽいチュウヒ) の学名が存在し、Dement'ev and Gladkov (1951) によればヒメハイイロチュウヒのシノニムに Circus cineraceus abdullae Floericke, 1896 が存在するとのこと。
かつてはハイイロチュウヒ類の種概念は曖昧で、19 世紀末でも分類学者によっては Circus cineraceus の学名を用いていたことがわかる。
つまり当時この学名や対応する英名が日本に入って訳されてハイイロチュウヒとなった可能性もあるように思える。
Kessler (1851) では Circus cineraceus とハイイロチュウヒは別種扱いだったので分類学者によって見解が異なっていたものと想像できる。cineraceus の種小名の初出はこの文献からはわからないが Mont. とあり、少なくとも Montagu はこの種小名を用いていたよう。
Falco cineraceus Montagu, 1802 (参考) 基産地 Wiltshire, England (英国) で冬の記録だった模様。
Montagu の用いた Falco cineraceus に由来する "Gray Falcon" の英名もあった。Pouchet (1860) Researches on the Corpuscles introduced by the Atmosphere into the Respiratory Ornags of Animals
などに用例 (この場合は訳例) がある。"Ash coloured falcon" のような英名、
The Montagu Harrier Morris's British Birds 1891 によれば cinerarius の綴り (参考。無効名とのこと) もあり、Buteo cineraceus と属を変えた用例もあったとのこと。
Falco cinereus Pennant, 1776 (参考) 基産地 Anatria (トルコ) の用例がすでにあったためと想像できる。
これが何を指していたのかはわからないが、Falco cinereus Piller & Mitterpacher, 1783 (Falco cinereus Gmelin, 1788 (参考) の同名の用例は Ashcoloured Buzzard でハドソン湾が基産地となっていてこちらはアメリカハイイロチュウヒらしい印象を受ける。
Falco cinereus では何を指しているか明瞭でなかったため少し語尾を追加した学名が与えられたらしい。
Falco fuscus Miller, 1777 (参考), Falco fuscus Gmelin, 1788 (参考) の名称があり後者の記載からはハヤブサを指したものと想像できる。
Bechstein はこの名称はすでに用いられていると考えて Falco cinerascens Bechstein, 1811 (参考) と新名を与えたが、このカードの記載によればすでに用いられていたのは通称の方で学名ではなかったとのこと。チュウヒ、タカ、ハヤブサ類すべてを含め、Falco にまとめられていた時代に名称が混乱していたことがわかる。
この時代より後でも Circus cinereus Vieillot, 1816 (参考) などの用例があった。
pygargus の方の種小名は Linnaeus (1758) にすでに記述されたものだったが、類似したチュウヒ類のうち何を指しているか明確でなかった (pygargus の語源にも関係する。#ヒメハイイロチュウヒ備考参照) ため、後の学名の方が使われていたのかも知れない。cyaneus の方は Linnaeus (1766) 由来。
つまり pygargus, cyaneus の両者を有効と認めてこれらの類縁チュウヒ類を同種とみなすならば cyaneus は pygargus の亜種となることになる。Naumann は pygargus を基亜種とみなしたらしいことは Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" から判断できる。
さまざまな立場の扱いがあっただろうことは想像できる。
また学名が変わっても英名はしばらく引き継がれていた可能性もある。
Ogawa (1908) のハイイロチュウヒの扱いは現在と同じ (チュウヒは異なる) で、この資料からは和名と古い学名の関係は読み取れない。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第7版では亜種 cyaneus となっていたが日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で亜種名が削除されている。
これはかつてアメリカハイイロチュウヒ Circus hudsonius (英名 American Harrier/Northern Harrier) がハイイロチュウヒの亜種となっていたため。
分子遺伝学研究が発表される前ではあるが、AOU は 1886 年第1版ですでにアメリカハイイロチュウヒを別種扱いでそのまま現在に至っている。IOC は少なくとも 2.10 の時点、HBW はオンラインで Alive となった 2015 年に別種とした。
一般的には次の分子遺伝学研究を待って別種とされたようで、Clements, eBird は 2016 年までは亜種扱いだった。
アメリカハイイロチュウヒの Linnaeus (1766) による記載時学名は Falco hudsonius (原記載)。
ハイイロチュウヒも同じ文献で記載している (原記載) がアメリカハイイロチュウヒと類似していると考えていなかったのか配置場所が違う。アメリカハイイロチュウヒはむしろチョウゲンボウに近いと推定していたように読める。
ハイイロチュウヒとアメリカハイイロチュウヒの分類の歴史や違いについては Etherington and Mobley (2016)
Molecular phylogeny, morphology and life-history comparisons within Circus cyaneus reveal the presence of two distinct evolutionary lineages も参照。
ハイイロチュウヒには別に亜種 taissiae が提唱されていた。ヤクーチア-サハのコリマ川地域で採集された2個体に基づき Circus taissiae Buturlin, 1908 と記載されたもの (参考)
[BirdForum taissiae は Kolyma の女医 (原文に基づき表記する) Tassia Michailovna Akimova への献名だが人物像がわからないとのこと。
Tat'yana Michajlovna Akimova の名前の医師の名前はあるが綴りが違い、1898 年生まれと時期も合わない。
ここからコメント: Tat'yana の親称の一つに Tasya があるので、Tat'yana でも構わないかも。ポピュラーな名前なので同姓同名は多数ありそう。
原記載]。
これは Dement'ev and Gladkov (1951) でも現在でも cyaneus のシノニムとされる。現在では多くのリストが分割後のハイイロチュウヒを単形種としている。
志村 (1995) Birder 9(9): 76-78 によればハイイロチュウヒのフランス名に聖マルタンの鳥の名称があり、11月11日の同名の祝日前後に渡りが見られることから名付けられたとのこと。
Busard Saint-Martin (oiseaux.net) でフランス名を見ることができる。
現在でもフランスの標準的名称のよう (2024 年のリストでも同様)。フランス語ではチュウヒ類は bussard とノスリ buse に似た名前で呼んでいる。
OED によればチュウヒ類を指す harrier の英語はハイイロチュウヒの Hen harrier で用いられたのが最初で、Willughby & Ray, Ornithologiae (1676) に登場した。語源は harry (戦争などで荒らす、侵攻する) + er とのこと。猛禽類を指すため自然な造語だったのかも知れないがあまりよい意味ではなかったよう。Hen harrier (語義通りならばニワトリを荒らす者) がいつまでも迫害される遠因ともなっているのかも。
Circus 属 (当時は亜属) を指して Harrier と呼ぼうと書いたのは Bonaparte, American Ornithology (1828)。1834 年の用例では very indefatigable in their hunting, and highly destructive of the feathered tribes とあり非常に破壊的など記され、相当誤解されていたらしい。
[チュウヒ類の兄弟殺し]
チュウヒ類ではほとんど兄弟殺し (#イヌワシの備考参照) は見られないが、Fernandez-Bellon et al. (2018)
Video Evidence of Siblicide and Cannibalism, Movement of Nestlings by Adults, and Interactions with Predators in Nesting Hen Harriers に確実な記録が紹介されている。
Redondo et al. (2019) Broodmate aggression and life history variation in accipitrid birds of prey によればハイイロチュウヒはスコア0になっている。チュウヒ類に類縁のオオタカでは3になっているが、(広義の) Accipiter では全体的にスコア低め。
これはこの論文の結論の一つであるクラッチサイズが小さいほど兄弟殺しが起きる傾向が高い (相関は一番強い) 根拠となるデータになっているようである。
なおこの論文の冒頭の方に兄弟殺しが起きる傾向を高める7つの要因が挙げられている:
(1) 専有できるタイプの食物、(2) 一腹のひなの数が少ない、(3) 食物を運ぶ頻度が低い (大きな食物を少数回運ぶ)、(4) 成長の早い段階で攻撃能力がある、(5) 食物を与える速度が遅い、(6) その後の競争にも影響が及ぶ場合、(7) ひなの期間が長い。
[ハイイロチュウヒのメスの begging call の役割]
Redpath et al. (2017) Female begging calls reflect nutritional need of nestlings in the hen harrier Circus cyaneus
によればハイイロチュウヒではメスが子育て、オスが食物を運ぶ分担があり、空中で餌渡しがよく行われるためオスにはひなが空腹かどうか直接わからない。
メスが出す begging call がひなの要求を反映したものか (Offspring Need Hypothesis) メスの要求を反映したものか (Breeder Need Hypothesis) の仮説が考えられていた。大きな声で人が 1 km 離れていても聞こえるとのこと。
この研究ではメスの体重が子育て中に減るため後者の仮説ならば begging call が次第に増えるはず、ひなの成長は中盤が一番盛んなので前者の仮説ではこの時期が最大になると仮定した。
ひなの要求を反映したものと解釈できる結果となったとのこと。メスの声が必要性を正直に伝えていると解釈するのがもっともらしい。
しかしひなが食物要求をするとメスの begging call が増えているだけに過ぎないなどの不明な点もある。
[渡りをするタカ類の系統]
Nagy and Tokolyi (2014) Phylogeny, historical biogeography and the evolution of migration in accipitrid birds of prey (Aves: Accipitriformes)
渡りをするタカ類の系統研究がある。どこに入れてもよいのだがチュウヒ類の渡り傾向が系統的にも目立つためここで紹介しておく。タカ類のそれぞれの系統の祖先は熱帯か亜熱帯に近いところだが、独立して何回も渡りの習性を身につけたとのこと。
どこでいつ渡りの習性が始まったのかは系統樹をじっくり見ていただくと面白いと思う。
これはタカ類で磁気定位に関連が深いと考えられる Cry4 遺伝子がよく保存されていることにも関係がありそうに見える (#アマツバメの備考参照)。
Cry4 遺伝子を失った系統もあったかも知れないが、Cry4 を持っている方が分布拡大に有利であったためにそのような系統が中心に残っている可能性もあるかも知れない。
ノスリ類も渡り傾向の強いグループ。
中新世 (2300-500 万年前) 中期には何度も寒冷化イベントが起きて森林が衰退し、草原が広がるなどタカ類にとって新しい生息環境が出現しやすかったと考えられる。タカ類の系統はこの前に現れていて (#ミサゴの備考の [近代的な陸鳥の進化] 参照) 渡りの習性を利用して生活圏を広げたと想像できる。逆方向への進化はずっと少ない。
予想に反して温血動物または死体への食物依存と渡りはあまり相関がなかった。渡りをするかしないかには別の因子も働いていると考えられる。
[英国のハイイロチュウヒ迫害]
Hen Harriers feared dead after vanishing at Cumbrian reserve (BirdGuides 2025.6.3)
ライチョウ類の狩猟家がハイイロチュウヒを敵視し、現在でも密猟あるいは疑われる事例が相次いでいる。
2018 年以降でも少なくとも 138 例が密猟されたり失われている。
-
ウスハイイロチュウヒ (第8版で検討種)
- 学名:Circus macrourus (キルクス マクロウールス) 大きな尾のチュウヒ
- 属名:circus (m) チュウヒ (circus (m) 円弧、求愛の時の旋回行動から)
- 種小名:macrourus (合) 大きな尾の (macro- (接頭辞) 大きな Gk、-ouros 尾の)
- 英名:Pallid Harrier
- 備考:
circus は#チュウヒ参照。
macrourus ギリシャ語由来で尾を意味する -urus で終わる学名は発音とアクセントが共通になり覚えやすいため同様に最初の u を長母音とする解釈を採用した。
由来となるギリシャ語の oura は "ウーラー" が原初の読み方。
かつて用いられた Circus pallidus Sykes, 1832 (参考。基産地 Dukhun とインドのデカン高原) があり、この学名での図版も登場するので、英名はこの学名の意味と同じと考えてよさそう。和名も英名からの訳が想像される。
Pallid/pallidus を "ウス" と訳したものではウスアマツバメ Apus pallidus Pallid Swift の例がある。
Accipiter macrourus Gmelin, 1770 基産地 Voronezh, southern Russia (ロシア南部) の記載の方が早いのでこの学名が採用されている。
Falco pallidus Schlegel & Sysemihl は Circus pallidus と後に同定されたが、#コチョウゲンボウ の亜種学名に一時的に影響を与えていた。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動(文献で類似種との識別点が明確に示されていないため)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも検討種。単形種。
カリブ海、西インド諸島のバルバドス島で 2014 年に記録されていた個体が本種と判明したとのこと: Pallid Harrier in Barbados is first for Americas (BirdGuides 2025.7.5)。撮影者の John Webster はアメリカハイイロチュウヒと報告していたが、写真に気づいた Paul Buckley が Forsman に写真を送付して判明し、南北アメリアで初記録とのこと。
[チュウヒ類の音源定位]
チュウヒ類の中でも小型齧歯類への依存性が最も高い種で、顔盤がよく発達している (聴力がよいことを示唆している)。
チュウヒ類がフクロウ類同様に音源定位を行えることを示した研究がある:
Rice (1982) Acoustical Location of Prey by the Marsh Hawk: Adaptation to Concealed Prey。
論文記載の学名からはハイイロチュウヒに見えるが現在の分類ではアメリカチュウヒ Circus hudsonius であろう。いずれにしてもハイイロチュウヒに近い仲間である。
この実験ではアメリカチュウヒ、コミミズク、アカオノスリ、アメリカチョウゲンボウを使って水平方向の音源定位能力を調べている。コミミズクは 1-2°、アメリカチュウヒで 2°、他の猛禽類では 8-12° を得ている。
小西他の研究 (#ヒガシメンフクロウの備考参照) のころの研究で特に垂直方向の定位能力が高すぎる印象を受けるが (実験方法も小西他の研究ほど厳密なものではなさそうに見えるので結果も多少違うのだろう)、基本的にはフクロウ類と同程度の音源定位能力があるものと思われる。
鳥類の感覚の比較研究をまとめた Wylie et al. (2015) Integrating brain, behavior, and phylogeny to understand the evolution of sensory systems in birds でも引用されているがチュウヒ類の神経科学的研究はまだ行われていないようである。
Pecsics et al. (2021) The possible occurrence of cranial asymmetry in three harrier (Accipitridae: Circus) species はヨーロッパチュウヒ、ハイイロチュウヒなどの頭骨を測定し、聴力に関係すると思われる左右の非対称性を調べている。
Citron et al. (2025) The evolution of an "owl-like" auditory system in harriers: Anatomical evidence
(一般向け解説)
チュウヒ類は頭骨の構造、脳の神経核の構造ともにフクロウ類と類似性が認められたが、耳の左右の非対称性や内耳の拡大は認められなかった。左右の時間差を検出する神経核が発達している (nucleus magnocellularis, nucleus laminaris が他の同じサイズのタカの 3 倍と 12 倍とのこと)。
水平方向の角度分解能は高いことが期待されるが、垂直方向は非対称性な耳を持つフクロウ類ほどではないだろうとのこと。独自の獲物を探す方法 (quartering flight) で効率を高めている可能性がある。ただしいずれも実験的検証は行われていない。
オーストラリアのウスユキチュウヒ Circus assimilis Spotted Harrier やカナダのアメリカハイイロチュウヒ Circus hudsonius Northern Harrier が取り上げられている。脳科学の視点からもチュウヒ類が聴力を使っていると考えてよさそう。
祖先系統がオオタカに近いので系統的制約もあるので、古くから適応したフクロウ類ほどではないとしても頑張っているところだろうか。逆に言えばオオタカに近い系統でも聴力の余力はあると考えられるのでチュウヒ類に限らず活用している種類があるかも知れない。
[音を出さない羽毛構造]
聴覚に頼って獲物を探すフクロウ類が飛行時音を出さない羽毛構造を持っていることはよく知られているが、同様の構造はチュウヒ類にも存在するとのこと。
Clark et al. (2020a) Evolutionary and Ecological Correlates of Quiet Flight in Nightbirds, Hawks, Falcons, and Owls
によればガマグチヨタカなどの一部ヨタカ系統、ゆっくり飛ぶタカ類の一部、聴覚を使って獲物を探すことは知られていないがゆっくり飛ぶチョウゲンボウなどに同様の構造が存在し、聴覚で獲物を探すのに雑音にならない、また獲物に気付かれない仮説を支持する結果となっている。
反響定位 (echolocation) を行う鳥ではみられず、反響定位のために進化した特徴ではない。
Clark et al. (2020b) Evolution and Ecology of Silent Flight in Owls and Other Flying Vertebrates (オープンアクセスでこちらをおすすめする) はフクロウ類を中心に無音飛行の系統関係や意義をまとめている。
多くのフクロウ類はほぼ無音に近いが、マレーウオミミズク Ketupa ketupu Buffy Fish-Owl、アカウオクイフクロウ Scotopelia ussheri Rufous Fishing Owl などは羽音を出して飛ぶ。
タカ類ではアメリカハイイロチュウヒとオジロトビ [高野 (1973) ではオジロハイイロトビ] Elanus leucurus White-tailed Kite に見つかったとのこと (カタグロトビに近縁。薄明時に活動する) が同様の構造を持つ例として挙げられているが羽音の超音波成分を記録した資料は存在しないとのこと。多くはバットディテクターを用いて測定されているが超音波に感度のあるマイクロフォンを利用した録音も用いられている。
同様の構造はヨタカ系統の一部でもみられ、ヨタカ属も含まれている。系統の近いアマツバメ類には見られない。
無音飛行は複数の系統で独立に進化したもの。
音の出る鳥の羽音のスペクトル測定結果も出ており、鳥の可聴域を超えるものが多いのでどちらかと言えば哺乳類の獲物に対する対策かも。周波数が高いのでこすれによる音と考えられる。
フクロウ類では velvet 構造が発達しているが、これが抑制しているのは上記飛行音の出るタカ類などの音の性質から流体力学的機構で発生する音 (タシギ類の drumming などに対応。この部分の話は予備知識として #オオジシギ備考の [羽音と流体力学] を参照していただくのがわかりやすい)
ではなく、擦れによる structural noise の方との結論になった。
上記では silent flight を無音飛行と訳したがそこまで音が出ないわけではないらしい: Wagner ete al. (2017) Features of owl wings that promote silent flight
に文献から測定値が紹介されている。人が主に羽音を聞くような低い周波数帯では 5-10 dB 低い程度で思ったほど無音ではなかった (おそらく超音波領域の無音効果の方が生態的は役立っているのでは?)。
この論文ではよく言われる前面 (leading edge) の serrations セレーション (新幹線にも応用され有名だがこちらはむしろ流体力学効果か) が音の抑制に役立っているかどうかは複雑でまだよくわかっていないとある。過去の実験では除去しても音はあまり変わらず、着地近くのみ違いがあったなどの報告もある。
5 dB 程度は減弱効果があるとの研究もあるが、研究の主な焦点は応用のためで高速飛行に相当する状態で調べたものが多い。生態学的には夜間活動する種類ほど音の影響が大きいと考えらえるが、serrations は夜行性の種類の方が発達している傾向があり消音に役立っている証拠ではとのこと。
serrations が音に影響を与えることは確かだが、航空力学効果もあって渦の消滅が早く、低速で翼を向かい角の大きい飛行で失速しないことにも役立っている。
Clark et al. (2020b) にもあるように velvet 構造が音の発生を抑制している点はむしろ確実。この構造は航空力学的にも影響を与え、摩擦による効力で揚力/抗力比を下げる可能性がある。しかし低速飛行を安定させる効果があるとのこと。velvet 構造を実際に応用した事例は知らないとのこと。
フクロウ類の翼の後ろ側 (trailing edge) の羽毛は hooklet (細突起?) の絡み合いがなく fringes となっている。状況によってこれは最大 10 dB の音の減弱に役立つとのこと。
ということで、フクロウ類の無音飛行における羽毛の役割として serrations だけに焦点を当てて説明するのはあまり適当でない模様。
LePiane and Clark (2020) Evidence that the Dorsal Velvet of Barn Owl Wing Feathers Decreases Rubbing Sounds during Flapping Flight
がメンフクロウにヘアスプレーをかけて velvet 構造を失わせると 0.1-16 kHz の全範囲で音が大きくなったとのこと。打ち上げの時の音がより大きな影響を受け、羽ばたき時の音のかなりの部分は羽同士の摩擦による音の仮説を裏付けるとのこと。
Lawley et al. (2019) Flow Features of the Near Wake of the Australian Boobook Owl (Ninox boobook) During Flapping Flight Suggest an Aerodynamic Mechanism of Sound Suppression for Stealthy Flight
オーストラリアのミナミアオバズク Ninox boobook Southern Boobook を使った研究では、スズメ目の鳥に比べて羽ばたき飛行時に整列した wake (後流または伴流) がほとんど見えない。
前述のような翼の羽毛の構造の効果の組み合わせで流れのスケール長が小さくなっているのでは。圧力勾配を小さくする効果があるので音の減弱にも役立つ可能性がある。
Krishnan et al. (2020) Turbulent Wake-Flow Characteristics in the Near Wake of Freely Flying Raptors: A Comparative Analysis Between an Owl and a Hawk
もフクロウとタカを風洞内を飛ばせる実験で同じような結果を得ている。
Schalcher et al. (2024) Landing force reveals new form of motion-induced sound camouflage in a wild predator
メンフクロウが着地の際に速度を落として着地音を減弱している (音そのものを直接測っているわけではなく加速度計による力の測定から推定)。とまり木にとまる時は硬い人工物にとまるより衝撃が小さい。
着地の衝撃が小さいほど次の狩りの成功率が高まる。繁殖期のオスとメスで行動が異なり、オスの方がゆっくり飛びとまり木をあまり使わなかった。オスは頻回に獲物を運ぶ必要があるため待ち時間の長いとまって待つ方法を採用していないのではないかとのこと。
解釈の部分はともかく、力を測定できるぐらいの高時間分解能の加速度データ、GPS データを野外で取れるようになって可能となった研究と考えてよさそう。
おまけ情報としてヘビクイワシは体重の 5.1 倍の力を筋力だけで出しているとのこと (ヘビクイワシの続きは #ミサゴ備考の [猛禽類の分類など] の方に)。
脚がかなりの部分羽毛で覆われていて音を消しているなどあるいは書いてないかと思ったが特に触れてなかった。
Liu and Clark (2024) Acoustics of rubbing feathers: the velvet of owl feathers reduces frictional noise
が 17 種の猛禽類などの羽をこすって音を調べた。アカオノスリやアメリカチョウゲンボウのようにかつて知られていなかった種に有意に消音機能があるが何に役立てているかは不明。
調べられた種を見ると齧歯類の鋭敏な聴覚対応のようにも見える。コンドルの羽が一番うるさかったとのこと。またここで調べられた中では4系統で消音機能が独立に進化した。猛禽類以外ではプアーウィルヨタカ Phalaenoptilus nuttallii Common Poorwill。
かつてヨタカの飛び出しの羽音を録音しようとしてほとんど記録されなかったのを思い出した。前述の Clark et al. (2020b) にも載っているが、日本のヨタカも消音機能を持つ方に分類されるのだろうか。
系統は異なるが、ハジロヨタカ Eleothreptus candicans White-winged Nightjar は積極的に羽音を使うようで珍しい音声と羽音が記録された White-winged Nightjar (xeno-canto)。
カワラバトの羽音が大きいのは消音していないというより羽音を積極的にコミュニケーションに用いているためかも知れない。アオバトでも羽音は大きく団体で突然飛ぶと結構驚くことがある (#オオジシギ備考の [羽音と流体力学] も参照)。
アカオノスリやアメリカチョウゲンボウの風切羽には実際に velvet 構造があることもわかった。過去に消音機能がフクロウ類と収斂進化があると報告されたカタグロトビ類 (#カタグロトビの備考 [系統とフクロウ類との収斂進化] 参照) では オジロトビ [高野 (1973) ではオジロハイイロトビ] に見つかったとのこと。
この研究ではチュウヒ類は調べられていないのでこれも含めるとおそらく少なくとも5系統となりそう。
タカ・ハヤブサ類で消音機能のあるものはかなりの性能で (特にアメリカチョウゲンボウ)、消音機能はフクロウ類の専売特許ではなかった。
齧歯類を捕食する猛禽類では消音機能は意外に簡単に進化させることの可能な形質なのかも知れない。
また逆に消音していない猛禽類では羽音に積極的な威圧効果があるかも知れないとふと思ってしまった。聴覚のよい哺乳類には有効かも知れない。羽音を用いたコミュニケーションは案外奥が深いかも。
研究対象はアメリカ大陸の種だが同様の研究 (特に羽の構造を見る) ならば他所でもできそうな感じ。どなたか調べてみられませんか。
ツバメ類でも消音機能らしい機構 (こちらは serration) がある種があるとの報告もある: Hasegawa (2023) Sexually dimorphic leading-edge serrations evolved in silent swallows (preprint) 性的二形があり飛行時音を出さないオスが好まれる? 先行研究の議論が引用されているので参考になるかも。
この報告を参考に挙げておくと、学名・英名のいずれにも serration を意味する語が含まれている。例: Stelgidopteryx serripennis Northern Rough-winged Swallow (キタオビナシショウドウツバメ)、Psalidoprocne pristoptera Blue Sawwing (ムネジロクロツバメ)。
Stelgidopteryx stelgis, stelgidos あかすり器 pterux 翼 Gk、serripennis serra のこぎり状の pennis 羽根、Psalidoprocne psalis, psalidos はさみ procne ツバメ (Gk)、pristoptera pristos のこぎりでひいた ptera 翼 (Gk) など。
実際に消音機能が捕食行動に役立つかは疑問もあり、ツバメ類のごく一部の系統のみが持っている理由もよくわからないとのこと。
-
マダラチュウヒ
- 学名:Circus melanoleucos (キルクス メラノレウコス) 黒白まだらのチュウヒ
- 属名:circus (m) チュウヒ (circus (m) 円弧、求愛の時の旋回行動から)
- 種小名:melanoleucos (合) 黒白の (malano- (接頭辞) 黒い leukos 白い Gk)
- 英名:Pied Harrier
- 備考:
circus は#チュウヒ参照。
melanoleucos は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-le- がアクセント位置と考えられる (メラノレウコス)。
和名は英名の pied に関係があるかも知れない。同様の事例としてマダラヒタキの用例がある (European Pied Flycatcher。おそらく単に Pied Flycatcher と呼ばれていた時期に付けられたと想像できる)。
和名で "マダラ" は Pied や Spotted の訳としてしばしば登場する。
単形種。
秋の渡りはハイイロチュウヒより早いとされ、サシバ・ハチクマの渡りピーク時期に小型のチュウヒ類の渡りが観察された場合は本種の可能性がある。
マダラチュウヒは中国東北部・極東ロシアの限られた地域で繁殖するため情報が少ない。
山形 (1992) Birder 6(1): 34-43 (マダラチュウヒは 40-43) に 1989 年愛知県田原町でメスが単独で営巣・産卵を行った記録が紹介されている (写真あり)。
浦野・中川 (2001) 石川県本土おけるマダラチュウヒ雄成鳥の初記録 - とくに巣材搬入行動について - 1979年5月10-24日、石川県河北潟でオス単独で巣材運びが観察され、ディスプレイ飛翔と発声が記録されている。当時の過去の記録一覧もまとめられている。
[繁殖地のマダラチュウヒ]
ロシア沿海地方の情報をまとめたものに Shohkrin et al. (2020) Breeding birds of Primorsky Krai: the pied harrier Circus melanoleucos (pp. 4871-4883) があり、極東の鳥類 42: 沿海地方の繁殖する鳥類2 で和訳が読める。
繁殖地での生態が主で、渡り途中の個体の識別に役立つ情報はあまり含まれていない。
Panov (1973) の南ウスリーの鳥類1 (極東の鳥類5で和訳が読める) にも記載があるが、上記 Shohkrin et al. (2020) にほぼ含まれているようである (引用の際に原典を明示する必要がある場合などは出典に注意)。
20 世紀前半に沿海地方では普通の鳥であったが生息数が非常に減少したとのこと。最近の 5-10 年間におもに広大な休耕地が出現したことにより、マダラチュウヒは徐々に回復してきたと記載がある。
開けた環境に生息する (チュウヒが優占する場所にはいないようである)。採餌にも繁殖にも古い休耕地、特に水田のあった所を好んで利用するとのこと。
5月前半末にはすでに産卵があり、日本で5-6月の渡りはやや遅いようである。
マダラチュウヒの渡去は8月末〜9月と早く、これは日本で秋の渡りの観察時期が早いことに符合する。
Panov (1973) によれば、外見がメス同士の2個体が繁殖初期に見せるようなディスプレイ飛行を行っていた観察例があるが、他のチュウヒ類同様に完全な生殖羽になる前に性成熟するならばこれはつがいであった可能性があるとのこと。
(極東の鳥類 42、5の訳文に情報を少し付記)。
他の文献も少し追加しておく。Dul'kejt (1928) の再掲が To the biology of the pied harrier Circus melanoleucos in southern part of Ussuri Land (pp. 937-941)
にある。ハイイロチュウヒの方が必ず少し早く渡来するとのこと。
4月中数が増加し、メスもすぐに飛来する。5月初めから6月初めにかけてディスプレイ飛行が見られる。ペアはいつも一緒に行動するわけではなく、一日中違う場所を狩場とすることもある。
ディスプレイ飛行の時期、夜明けごろ太陽は少し顔を出したところで上空からしばしばオスの声がし、特有の羽ばたきで翼の白黒を誇示し、最後に "ムーゥイ" と 鳴き、小型であるためや飛び方などタゲリの行動とだまされることすらある。まったく猛禽類らしく見えないとのこと。
オス・メスは旋回して互いに急降下しあい、大きな波を打つように空中をあちらこちらへ移動し、鳴き続けながら両者は次第に降下してメスが地上に降りる。メスは高く上げていた翼を次第にたたみ、そこへオスが舞い降り翼でバランスを取りながら交尾する。
5月終わりから6月初めに産卵を始め、7月中旬まで抱卵が続く。7月終わりから8月初めにひなが地上に現れ、8月に飛べるようなって自分で狩りを行い始める。9月には移動を始め、10 月にはまったくいなくなる。
若鳥は 11 月や 12 月初めでさえも満州国境付近で見られることがある。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) には時に 200-500 m ぐらいの範囲で小さな (2-3ペア) グループで繁殖し、狩りは巣から 100-200 m ぐらいの範囲でのみ行われたとのこと。
一夫一妻であるが、1羽のオスのなわばりに2羽のメスがいて、シーズンに2回、おそらく3回の繁殖をしたと考えられるケースがあるとのこと。
シブネフ (2000) Birder 14(10): 16 に巣にいるマダラチュウヒのオスとひなの写真がある。
繁殖地でのマダラチュウヒのディスプレイの音声は世界で1例のみが公開されている。確かにタゲリの声に似ていて、チュウヒの声をずっとまろやかにした (倍音が多い) 印象になっている。
森岡 (1996) Birder 10(2): 71 にマダラチュウヒのメスと類似種の識別の情報がある。
Karyakin (2004) "猛禽類の調査方法" (参考文献参照) p. 220 (fig. 220) にハイイロチュウヒ、マダラチュウヒ、ヒメハイイロチュウヒの翼式の違いが図示されている。
[North Eurasia Birds Watch の紹介]
2024年6-7月現在、古い north.eurasia.birds.watch のサイトでセキュリティ警告が出る。
ドメインの変更があり、https://north.eurasia.birding.day に変わったよう。
以下のリンクは .birding.day に修正してある。
地域ごとのサイトも維持されているようなので、例えば極東ロシアであれば https://fareast.russia.birding.day/index.php?l=en からたどってみて欲しい。
種名を選ぶと、in other projects に他の地域のリンクが出る。
以下 North Eurasia Birds Watch からの画像。このサイト及び関連のサイトはカザフスタンの Aksar Isabekov が創始した
(birds.kz) もので、
「諸外国では楽しそうにオンラインで議論しているのでロシア語圏でも議論できる場が欲しい」として最初はカザフスタンで、そして旧ソ連圏や近隣諸国にそれぞれにデータベースを作り、各地域に働きかけてコミュニティを構築して行ったもの。
ブログのように単に投稿するだけでなく、検索可能なデータベースを目指したのが特徴。
eBird とは異なり、ここは写真記録をベースとしているので同定に疑問があった場合に調べられる情報量が多く、また場所も詳細に公表されている (ここ以外にも海外では詳細場所をリアルタイムで公開しているところも多く、日本のような制限を取らざるを得ないところは世界的にも比較的珍しいかも知れない)。
しかしこの方は志半ばにして新型コロナ感染で2021年4月に亡くなってしまわれた。
亡くなる直前まで精力的に野鳥観察を続けられていて、いつものように観察されていたレポート (英語版) を見ることもできた。どこへでも出かけられている頑強そのもののような方であったが、最後の観察からわずか 10 日以内に帰らぬ人となってしまった。
現在は有志が引き継いで管理が行われているようだが、時に動作が不安定であったりするのは上記のような状況から察していただければと思う。
Aksar Isabekov の没後にロシアによるウクライナ侵攻があった。Isabekov は野鳥観察を通じて国境を越えたつながりを深めて行く趣旨であったため、同サイトのウクライナのページにロシアのユーザーから「うちの国がおたくで行っていることが恥ずかしい」趣旨の投稿もあった。
[Pied Harrier by Oleg Katugin] に2022年8月11日に撮影されたマダラチュウヒ? 若鳥の集団飛翔がある。上から見た写真はないのかとの質問にはないとのこと。
同フォーラムで同定の議論があり、一番よくある識別対象はチュウヒで、
[Alexander Rogal'の写真]
これはチュウヒではないのかとの議論がなされている。特に腰の白さが議論されていて、チュウヒでは白い部分がもっとはっきりしているので、これはマダラチュウヒの1暦年個体との意見が出ている。参考までに (鮮明な画像や意見の付いているものを主に) 他の事例を挙げておく:
[Max Logunovの写真] 鮮明な飛翔写真がある;
[尾の前部に少し褐色味のある個体];
[これもチュウヒではないかと識別が問題となっている];
[これもチュウヒだろうとのこと];
[同じく];
[これもチュウヒかハイイロチュウヒか意見が別れている。おそらくマダラチュウヒらしい];
[これはあまり疑問がなさそう]。
少し古いがこんな議論 (英語) もあった。Harrier identification revisited!。
Identification of harriers in Thailand タイのチュウヒ類の識別について。
Yonok Harrier Roost; Pied Harrier & Eastern Marsh Harrier | Birding in Thailand タイの集団ねぐらの映像。
-
アカハラダカ (将来の属名変更に注意)
- 第7・8版学名:Accipiter soloensis (アクキピテル ソロエーンシス) ジャワ島のソロのタカ
- AviList 学名:Tachyspiza soloensis (タキュスピツァ ソロエーンシス) ジャワ島のソロの速いタカ
- 第7・8版属名:accipiter (m) タカ (accipere 掴む Gk)
- AviList 属名:tachyspiza (f) 速いタカ takhus 速い spizias タカ (Gk)
- 種小名:soloensis (adj) ソロの [solo ジャワ島のソロ (Solo = Surakarta スラカルタ) -ensis (接尾辞) 〜に属する]
- 英名:Chinese Goshawk, IOC, AviList: Chinese Sparrowhawk
- 備考:
tachyspiza は -spiza の音声はわからなかったが、起源であるギリシャ語 spiza / spizo の i は長音でないので -spiza の i も長音ではないと想像できる。この場合 tachyspiza は y にアクセントがある (タキュスピザ)。
Kaup がこれらの属名を造語する際に -spizias (タカ) の語尾を用いずあえて短くした (スズメ類の方の綴りと同一になる) のは音声的なものがあるのではと考えている。ドイツ語経験があれば spiza は "シュピツァ" とつい読んでしまうと思う。ドイツ語では同じような音の spitz (尖った、鋭利ななど) の単語があり (犬の品種名にもある)。ドイツ語風に読むと語感的には非常によい。
また嘴の先端を Spitze と呼ぶらしく (オオモズ亜種の記載で見つけた) 鳥類学用語としても大変整合性がよい。さらに Spitze には最上のものや頂点の意味もある。形容詞の spitze は現代ドイツ語語義ではあるが英語の great, awesome, super などに相当する意味で使われるとのこと。
ただしドイツ語の spitz は語源的にはまったく関係がない。
Kaup はドイツ人なのでドイツ語読みすればタカ向きの単語であると認識して使っていたのではないだろうか。調べてみるとラテン語のドイツ式読み方が実際に存在してこのように読む。
古典ラテン語読みの束縛を離れ、あえて Kaup が想定して使っていたただろう "タキュスピツァ" と読んで満足感を得るのも一つの楽しみ方ではないかと思う。日本産の属でこの事例はこの1件のみなので例外として扱っても許されるだろう。
実は自分もクマタカの古い属名の z を "ツ" の音で読んでいた (ドイツ語風に解釈すれば "鋭利なワシ" の意味になる)。
語末の -spiza は対象によって "フィンチ または 小鳥" と "タカ" を訳し分ける必要がある (#トビの備考参照) こともすでに問題になっているので、ここでは Kaup の考えたであろうことも想定して "タカ" の方は "スピツァ" と読み分ける発音を実験的に採用してみることにした。音で分類を区別可能な利点があり、また音にタカの鋭さが現れるのではないだろうか。
accipiter は#ハイタカ参照。
soloensis は場所を示す -ensis で e が長母音でここにアクセントがある (ソロエーンシス)。長音でアクセントを置いた発音に慣れておけば o の文字を落としてしまうなどの誤りも起きにくい。
Dickinson et al. (2022)
Temminck's new bird names introduced in the early parts of the Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux in 1820-22
の調査によれば Temminck (1822) がアカハラダカを Falco cuculoides の学名 (カッコウのようなハヤブサまたはタカ) で記述していた。
Temminck 自身はフランス語で Autour coucoide と呼んでおり、カッコウのようなオオタカの意味。
記載 (図版 1, 2)。
Horsfield の Falco soloensis の学名も紹介していたが、
Horsfield の記載は簡潔過ぎるとして別学名を与えたもの。Horsfield のもの 原記載。ジャワ島では Allap-allap lallar の現地名とのこと。インドネシア語は単語を重ねることが多く、Allap-allap はおそらくタカ・ハヤブサ類を指す。この文献を見るとウミワシやトビ類は呼び分けられていたことがわかる。
Horsfield が soloensis を用いた理由は Falco javanicus Gmelin, 1788 (参考 サシバのことか? とのこと) の用例がすでにあったため、"ジャワ島" を冠した学名を使いたかったものの使いにくかったのだろう (Horsfield が命名した他の属の種類では Javensis を種小名に用いているものがある)。
"東インド" (会社) を意味する Falco indicus Gmelin, 1788 (現代のサシバ) もすでに使われていたので地名を用いる選択肢が少なく、より局地的な地名を用いたと想像できる。種小名の地名から意味を深刻に考えるは可能だろうが、用いた理由は次に思いついたものなど案外単純なものだったかも知れない。
Horsfield (1821) の記載は有効と認められて現在の学名になっている (Temminck の与えた学名はシノニム) が、もし Temminck の学名が採用されていればややこしいことになっていた。
アフリカカッコウハヤブサ Aviceda cuculoides が同じ種小名を持っており、こちらに カッコウハヤブサ (cuckoo hawk/cuckoo falcon) の名前が含まれるように例えば Falco 属にまとめられるなど同属になれば衝突するおそれがあった。
その場合はアフリカカッコウハヤブサの Aviceda cuculoides Swainson, 1837 の方が新しいので学名を変えるなどの措置が必要となり得た。アフリカカッコウハヤブサは最初から Aviceda 属で記載され、Temminck の学名は別属でしかもシノニムと判定されたためこのような事態は避けられた。
もう一つあって Cymindis cuculoides Swainson, 1837 は現行のカギハシトビ Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite。
こちらは Falco uncinatus Temminck, 1822 の記載 (参考。学名は尾に太い模様が1つあること、フランス語名は Cymindis bec en croc と英名の起源となったと考えられる。同じ) の方が早く使われなかった (The Key to Scientific Names の Cymindis の項目より)。
Cymindis はギリシャ語 kumindis でおそらく架空の鳥でフクロウか猛禽類を指したものとされる。タカ類の学名で人気があったようで複数人が異なる定義で用いていた。カンムリワシの亜種などこの属に含まれていたことがあった。
カギハシトビ/キューバカギハシトビの論文で最近でもこの属を用いているものがある。
しかしアカハラダカのどこが "カッコウのような" なのかは考慮が必要だろう。アフリカカッコウハヤブサ (なおハヤブサとは系統的に関係ない) については目の容貌および縞模様ではないかと感じている。カギハシトビはとまっている姿を見るとカッコウ類のような目の容貌および縞模様に見える。
カギハシトビは南北アメリカの種類で旧世界のカッコウ類はいない。カッコウ類への擬態よりは系統的な顔つきや模様なのだろうか (縞模様は別の猛禽類への擬態もあるかも知れないが顔つきは多分系統的なもの? wikipedia 英語版によれば色彩や模様の多形が極めて著しいとのこと。#ハチクマ備考の [擬態と種・亜種の関係] でも少し考察している)。
アカハラダカは (?) メスや幼鳥だと風貌が多少似ている (?)。あるいは "カッコウのような" は図版にあるようなオスの上面の色彩由来?
同じ文献で Temminck が名付けたミナミツミ Falco virgatus Temminck, 1822 = Tachyspiza virgata は現在も採用されているので Temminck のアカハラダカの学名が採用されるか否かは紙一重の違いだったのだろう。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではアカハラダカが当時の学名で Accipiter badius ロシア名 tyuvik の亜種または関連のある種の可能性を考えていた。この種は当時は現在の Tachyspiza 属のユーラシアからアフリカ北部の種を含んでいた。
現在の分類での構成種は レバントハイタカ Tachyspiza brevipes Levant Sparrowhawk と
タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia Shikra になるが、タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] の方が記載が早いために Dement'ev and Gladkov (1951) ではこちらの亜種扱い。
アカハラダカは種扱いで Accipiter soloensis の学名で分布図に破線で表してあった。タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] の東部亜種 poliopsis と分布が類似する。
tyuvik は古くから使われている名前で 1774 年の文献にもすでに記載があるとのこと。語源は不詳だがおそらく音声由来ではとある。
ロシア名はかつては kitajskij perepelyatnik (中国のハイタカの意味) だったが、Tachyspiza 属となったことでロシア名 tyuvik から kitajskij tyuvik となる取り扱いが www.balatsky.ru の 2023.8 の分類に示されている。
こちらでは属変更に伴って慣用名も変わる可能性がある。
wikipedia ロシア語版では学名は変更されているが項目名は従来名のまま。しばらく両者が併用されるのだろうか。
なおアカハラダカのロシア語別名 korotkopalyj yastreb (趾の短いタカの意味) があるが、記述的に付けられた名称か、学名由来かはよくわからなかった。Accipiter brachydactylus Swainson, 1837 と対応する意味の学名は存在して Senegal sparrow hawk の名称が見られるが何かのシノニムとなって残っているわけでもなく関連は不明。
意味が少し違って "足の短い" だがレバントハイタカの種小名 brevipes に近い。もしこの学名由来であればアカハラダカとレバントハイタカが同一種とされた時代がしばらくあって、現在の タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] の先取権がまだ判明していなかった時代に種学名として用いられたものの可能性も考えられる。
あるとすれば 19 世紀ごろと推定されるがさすがに調べられなかった。注記: Menzbier (1882, 参考文献参照) の記述で確認できた。
なお "アカハラダカ" ほとんどそのものの意味を持つ学名の種類がある Accipiter rufiventris。訳すならばこちらの方が "アカハラダカ" にふさわしい。ムネアカハイタカ [高野 (1973) ではアカムネハイタカ] 英名は Rufous-breasted Sparrowhawk なので英名からの訳と思われるが、アカハラダカの和名の方が先にあったためだろうか。
調べると面白いことがわかった。Falco exilis Temminck, 1830 参考 (図版) の記載がほぼ同時になされていて、かつての判定ではあまり根拠なくシノニムとして無視されてきたが、詳しい年代判定の結果 Temminck の方が早いことが判明した。
すでに使われてきていた Accipiter rufiventris の学名を保存するために ICZN が裁定を行った
Falco exilis Temminck 1830: proposed invalidation under the plenary powers in order to conserve Accipiter rufiventris Smith, 1830 (Aves). Z.N. (S.) (1956) とのこと。
Temminck の用いたフランス語名 Autour menu は小さいオオタカの意味。ハイタカとほぼ同じぐらいとのこと。Accipiter rufiventris は長く使われていてよく知られた種類だったよう。
以上はアカハラダカの和名由来を考察した途中の副産物だったが、山階鳥類研究所の標本データベースに過去の別名があった。YIO-09221 (1924 年 京畿道楊州郡議政府 朝鮮) のラベルに Wakidiro-daka の名前が記されていた。学名は現在と同様だが Astur soloensis と Astur 属となっていた。
YIO-09207 (1935 年 Halmahera I., Moluccas Is.) では Accipiter erythrauchen (Gray, 1861 の学名は 参考 1, 2) のラベルが付いていて同時に記入されたものか不明であるが (ペレアゲレ) と書かれている。
Accipiter erythrauchen は現在ではモルッカツミ Tachyspiza erythrauchen Rufous-necked Sparrowhawk に対応する。
eruthros 赤 aukhenos 首、のど (Gk) で、英名ならば (存在したかどうかは不明だが) Red-breasted Hawk などの名称となっても不思議でない。
これらを見ると、少なくとも 1930 年代までは "アカハラダカ" の和名は確立した形では使われていなかったようで、種同定もさまざまでツミやミナミツミと同定されていたものも多かった。
Dement'ev and Gladkov (1951) の時代でもよくわかっていなかったようなので、アカハラダカに相当する概念そのものがほとんど認知されていなかった可能性が考えられる (Horsfield や Temminck の標本は日本にはないし)。
後の時代 (しかも思ったより遅い) に整理された段階で付けられた和名ではないだろうか。
Accipiter erythrauchen の学名が用いられた標本があることをみると、やはり Accipiter rufiventris との関係が気になるところ。これらの赤道地域の小型で下面の赤い "ハイタカ属" をまとめた概念が存在していた時期があったのではないだろうか。
当時はすべて Accipiter 属であったためまとめても不自然性があまりなく、Accipiter rufiventris ならば red-breasted sparrowhawk の別名もあった。ただし記載年はアカハラダカの方が早いので Accipiter rufiventris の亜種になったとは考えにくい。
あり得るとすれば一般名で red-breasted sparrowhawks のような仮想上の総称があり、モルッカツミやアカハラダカも含まれていたなども想定できるがどうだろうか。胸または腹の赤いハイタカ属のグループの中で最初に和名が付けられたのでこの名前になった、など。アカハラダカ自身も腹が赤いというより胸が赤いと呼ぶ方がふさわしそうだが、ツグミ類のアカハラなどの名前もあって合わせたのかも。
和名がもっと後の時代に命名されたものであればこのような分類的概念とは関係なく、身体的特徴や海外種を比較した上で名前が整理されたものかも知れない。
単形種。Tachyspiza 属のタイプ種。
[属名の由来・属名和名は?]
Kaup (1844) の Tachyspiza 属記載。ドイツ語の属名は Weiheweihsperber または Flugsperber。Kaup は当時の Nisus 属 (ハイタカに対応する) をドイツ語で Weihesperber と呼び、広義の Weihesperber をさらに分割し、そのうち Hieraspiza を Falkenweihesperber と呼んでいた。
Hieraspiza はこの文献では極めて単純な記述でグループの名称 (どちらかと言えばゴミ箱的) と判定され、後の Hieraspiza Kaup, 1845 の属記載が有効と判定された。このタイプ種は後にミナミツミと指定されており、もし Kaup (1844) の記述を属記載相当のものであったならば Hieraspiza も現在の Tachyspiza 属に代わる名称候補となっていたことがわかる。実際には属記載には値しないものだった (The Key to Scientific Names)。
多分あり得ないだろうが、Tachyspiza 属がさらに分割されるならばツミはミナミツミと同一系統に入るのでこの2種からなる Hieraspiza 属となりアカハラダカと別属となることがも考えられる (あくまで仮想的な話だが考えてみると面白い)。
用いられたドイツ語名から Kaup が細分化にあたって何を考えていたか多少判断することができる。Hieraspiza の方は Falken- とむしろハヤブサ的またはタカ的な名前を付けていたが、Tachyspiza の方は weih を補っているようにチュウヒやトビを意識していたと想像できる (#トビ備考の ["トビ" 類のドイツ語名] 参照)。
一方で別名 Flugsperber の名称があったようなので博物学者の間で飛翔に着目されていたことは確かだろう。初列風切の3番めが最も長いなど翼式を気にしていたと考えられる (飛翔性が高いと見ていた? 結果的に現在の Tachyspiza 属のうちで長い渡りをするものを形態からグループ化できていた模様)。
Flug は飛行などの意味があり、im Fluge で比喩的に "すばやく" などの意味 (日本語で「時が飛ぶように過ぎる」と同様) がある。Tachy- はこの意味の接頭語と考えてよさそう。おそらく翼の比較からそこまで想像していたのだった。
逆に言えば生態的適応の影響を受けやすい形態学 (特に翼式を重視する場合) から現代の分子系統研究が明らかにした系統を導くことは困難だったのだろう。Accipiter 属内の系統関係が確立するまで長い時間を要し、多系統であることは認識されつつもこれまで合意が得られにくい理由となっていたのだろう。
なお次ページ (p. 117) で Kaup は本家の Nisus 属をこれらから分離したものを Adlerweihsperber または Finkensperber と呼んでいた。Adler- はワシでこのグループの中では大きいの意味だろう。Finken- はフィンチなのでフィンチを食べるの意味だろう。
p. 118 ではオオタカを Adlersperber と呼んでいて、こちらも大きいの意味と想像できるが、ハイタカの方は weih が付いているのでオオタカよりはチュウヒやトビを意識した名前になっている。
p. 119 に属名を Tachyspiza と争った (以下参照) Leucospiza があり、このドイツ語名は Bussardhabicht ノスリのようなオオタカ。オーストラリアのハイイロオオタカ [高野 (1973) ではカワリオオタカで後に分割された] の白色型を意識しているので [オーストラリアのタカ類] の項目も参照。オーストラリアにはオオタカ系統もノスリ系統も到着しなかったので Tachyspiza がオオタカとノスリの役割を果たしたと考えれば Kaup のドイツ語名は本質をよく表していた。
超・超マニアックな話になるが、Hieraspiza Kaup, 1845 の存在は後の属名に影響を与えていた。Ierospizia tinus Bonaparte, 1857 の用例があってこれは現代のヒメハイタカ 現在の学名で Microspizias superciliosus Tiny Hawk (アメリカ大陸) に対応。
分子系統解析の結果この系統の2種が旧 Accipiter 属から遠く離れていることがわかり属名を付ける必要が生じたが、Ierospizia は Hieraspiza の綴り違いとも判断できるために Sangster et al. (2021) が新たな属名 Microspizias を提唱して受け入れられた (The Key to Scientific Names)。
形式的には Ierospizia を保存することも可能であったが、Hieraspiza Kaup, 1845 を用いる必要が生じた場合にあまりに紛らわしくなるので著者判断で新たに提案したのだろう。
Kaup (1844) 自身がアカハラダカを Tachyspiza 属のタイプ種に指定しているので曖昧さがない。ツミの記載の方が遅いのでタイプ種にはなり得なかった。
これら歴史的経緯やツミに他の候補属名が存在することは、日本の分類で新しい分類が採用された場合ツミ属と呼ぶかアカハラダカ属と呼ぶか微妙に影響を与えるかも知れない。Kaup の与えた属ドイツ語名も判断材料に検討いただきたい。
以下の項目にも関係するが、Tachyspiza 属に和名を与える必要性がいずれ生じるであろう。現在の日本産種ではツミとアカハラダカが候補になり得るが、Kaup (1844) を検討した結果、アカハラダカ属とした方が好ましいように思える。
上記からまとめると、アカハラダカ属の名称とした場合の
利点:
・Tachyspiza 属のタイプ種であり世界的観点からふさわしい。
・アカハラダカはこの系統の世界進展の中核となった種類 (例えばオーストラリア) で、生物地理学的にも系統を代表する名称としてふさわしい。
・Kaup は翼式から想像されるアカハラダカの特性を反映して Tachyspiza の名称を与えた。属学名とアカハラダカの特性の整合性がよい。
・当時はツミは未記載であったが、Kaup はツミに最も近縁なミナミツミに Hieraspiza の属名を与えている (有効な記載と認められる Tachyspiza の翌年)。つまり Kaup はツミとアカハラダカは別属相当と考えていた。
・分子系統上ツミに適用可能な属名が別途存在することから、もし分離されればツミの属名が変わる可能性がある。現状では属まで変わる可能性はほとんどないと想像されるが、例えばツミとミナミツミを指して亜属などの概念で用いられる可能性がある。アカハラダカ属としておけば将来分類概念変更があっても変える必要がない。
欠点:
・属和名が多少長くなる。
・ツミは日本で繁殖する種類としてより有名。ただし日本の繁殖固有種ではなく大陸にも分布している。
・上記欠点にもかかわらずマンクスミズナギドリ属のようにタイプ種を優先して名付けられた属和名もあるので本質的問題ではないはず。マンクスミズナギドリは第8版では検討種。
[広義 Accipiter 属の分割]
Accipiter 属が単系統でないことは以前からも指摘されていた。例えば Oatley et al. (2015)
A molecular phylogeny of the harriers (Circus, Accipitridae) indicate the role of long distance dispersal and migration in diversication を参照。
この文献によれば Accipiter 属が単系統でないことは Griffiths et al. (2007) Phylogeny, diversity, and classification of the Accipitridae based on DNA sequences of the RAG-1 exon ですでに指摘されており、後続研究も複数ある。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に対してアカハラダカの分類へのパブリックコメントへの回答で参照されている文献は Accipiter 属の分類のみを対象としたもので、単系統性を議論するには不適切な論文であった。
現在までの Accipiter 属は Circus 属 (チュウヒ類) を内包している。
以下の解説を読むにあたって系統樹の入った チュウヒは ハイタカ属のタカだった! (マーリン通信 2024.11) を見ていただくとわかりやすいだろう。
Circus 属はよくまとまった特徴のある属で、分岐年代も他の属と同程度なので Accipiter 属に改名しない方が望ましいと考えられ [後述 Catanach et al. (2024) も参照]、その場合は Accipiter 属を分割する必要が生じる。
Mindall et al. (2018) はタカ類分子系統分類の基本文献。Mindall はこの分野の権威で、この文献ですでに Accipiter 属の分割の必要性に言及しているが、まだ系統サンプルが不十分で分割した場合の属名は言及されていなかった。
その後現代的な核ゲノム解析も進んでおり、
Catanach et al. (2023)
Enigmas no longer: using Ultraconserved Elements to place several unusual hawk taxa and address the non-monophyly of the genus Accipiter (Accipitriformes: Accipitridae) (preprint 段階)
が Mindall et al. (2018) の後継にあたる論文でタカ類の全分類を扱っている。
この論文は 2024.2.7 に受理され 2024.3.22 に公開された。以下 Catanach et al. (2024) と記す。
この研究では冒頭で述べた次世代シーケンサー (Next Generation Sequencer, NGS) を用いて新たに 88 種の全ゲノム解析
[ゲノムアセンブリ、全ゲノム解析には何段階があり、読み取って計算機でつなげた raw reads と言われるもの。Catanach and Pirro (2023) The Complete Genome Sequences of 87 Species of Hawks (Accipitriformes, Aves)も参照]
と UCEs (*1) に絞った解読8種を行い、これまでの結果と合わせてタカ類の 90% の種の何らかの遺伝情報が得られたことになる。
この結果これまで系統的位置が不明であった独特なタカ類の位置が明らかになるとともに、これまで分類に問題があることは把握されつつも、膨大すぎて手をつけることが難しかったこれまでの Accipiter 属の分類提案に至ったものである。
伝統的手法では十分な解析には生体試料が必要であったがその点も改善されており、標本の組織サンプルで十分に読み取れるようになったとのことである。
後述の系統分類にあるように Accipiter 属に対して提唱されている新分類によれば Tachyspiza 属となる見通し。
この属名は Tachyspiza soloensis Kaup, 1844 で最初に使われたもので、アカハラダカがタイプ種となる。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Urile 属の和名に必ずしもタイプ種にこだわらずヒメウ属が採用されているように、日本鳥類目録で将来 Tachyspiza が採用される時にはツミ属になるかも知れない。
一部の小型 Accipiter 属への属名提唱は Sangster et al. (2021)
A new genus for the tiny hawk Accipiter superciliosus and semicollared hawk A. collaris (Aves: Accipitridae), with comments on the generic name for the crested goshawk A. trivirgatus and Sulawesi goshawk A. griseicepsも行っており、
この系統樹を見ると、現在までの Accipiter 属と関連属がいかに混在していたかを見ることができる。この論文の Appendix 1 にこれまで Accipiter のシノニムとして提唱された多数の属名がリストされている。
Sangster et al. (2021) の提案は多くのリストで早い時期に取り入れられた。どのリストも旧 Accipiter が単系統でないことは問題視しており、情報の揃った古い分岐から順次新分類を取り入れていった。
旧 Accipiter は種類も多く全種 (特に次の Tachyspiza 属) をカバーすることは現実的に不可能なので、情報が大部分揃って分子系統樹の形も疑いない段階となったところで現在の提案に至った次第。
現在 Accipiter 属の半数近くが Tachyspiza 属となる見通し。takhus 速い (Gk) spizias タカ (Gk) (#クマタカの備考も参照)。
この属名については先取権の問題が残っている。Tachyspiza soloensis Kaup, 1844 と Leucospiza novaehollandiae Kaup, 1844 と Kaup が出版した同じモノグラフの中に現れるからである (Boyd Afroaves I)。
Boyd はいずれ誰かがどちらかを決める必要が生じると述べているが、Leucospiza (白いタカ) は事実上ハイイロオオタカ (これまでに通常使われてきた学名で Accipiter novaehollandiae 英名 Grey Goshawk) の白色型にのみ相当するものなので Tachyspiza のほうが望ましいと考えているとのこと。
Accipitriformes (birdforum.net) の 2023.7.30 のところにも議論があり、大方の期待通り Catanach et al. (2023) が初めての判断を下したことに安堵しているようである。
Catanach et al. (2024) では Tachyspiza の方が Leucospiza よりもこのグループの特性に広く当てはまることからこちらを優先するとしている。自身を "acting as first reviser" (規則のみから先取権が決まらない場合に行う最初の裁定者) と記述しているので意図は明確である。
自分もこの属名はよい名前と思う。takhus 速い は日常でも使われる用語の語源でもあり (タコグラフなど) 一般にも馴染みがある。何と言っても「光より速い」仮想粒子の名前がタキオン (tachyon) なのである。解釈次第で「光より速いタカ」大変かっこいい学名である (将来学名解説をされる方はこの話をぜひ入れて欲しい *2)。
同じ意味で和名の語源の一つに挙げられる「はしたか」= ハイタカ が Tachyspiza 属に含まれないのは玉に瑕というところだろうが、こちらは引き続き Accipiter 属 (いつの間にかメンバーがずいぶん減ってしまったが) の代表になるので「はしたか」様にはご満足いただけるであろう。
また過去クマタカの属名に使われていた Spizaetus はクマタカに使われることはもうないだろうが、この学名に親しみを持たれていた方も多いと思う。この学名の面影が Tachyspiza に多少とも残ることもファンとして喜ばしいところがある。
女性名詞の属名であるため一部の種小名・亜種小名が変わるが、日本産の種類・亜種には (これまで記録されている範囲では) 影響がない。
他の -spiza の学名を見慣れていると自然に思えてしまうのだが、
Latest IOC Diary Updates では Tachyspiza は Sparrowhawk ならぬまるで sparrow のような名前だと指摘がある (-spiza はフィンチ類でよく使われるので。こちらで訳せばすばしこいスズメのような意味になる)。IOC のこの決定を待っていたとのコメントも出ている。
Catanach (とても若い人) がなぜそれほど猛禽類に思い入れがあるのか 2023 年のインタビュー記事がある: Studying New Hawk Communities Through Genetics and Collections
"What is so special about hawks?" タカ類 (猛禽類全般を指しているよう) のどこがそんなに特別なのですか、のような質問があるとちょっと嬉しい。Catanach は主に保護に関わる返答を行っている (優等生すぎ?) が、それ以外にも十分面白い点があることは承知の通り。
このような系統研究を行うとともに、高校時代からテキサスのリハビリテーションセンターのボランティアをするなどずっと猛禽類関連に関わってきて、自身でも頻繁に観察をしているホークウオッチャーとのこと。
2つの学位 (イリノイ大学で Ecology, Evolution, and Conservation Biology とテキサス A&M 大学で Wildlife and Fisheries Sciences) をとってこの研究の時点で鳥類学研究室のポスドクとのこと。「好き」から始まって最先端研究に進める恵まれたアメリカの鳥類学の環境もわかる。
Catanach et al. (2024b) The Complete Genome Sequences of 31 Species of Hawks (Accipitriformes, Aves) 31 種のタカ類のミトコンドリアゲノムの解読結果を出している。新しい系統樹などは示されておらずデータ提示のみ (新しい学名を用いていないのは Genbank に合わせるため)。
いくつかの種は新規で、他の種もこれまで過去の遺伝子情報のみを用いていた部分がより確かになりそう。
このレベルになるとサンプルが入手できるか次第のようで、やはり東洋の種は難しいらしい。
2024 Taxonomy Update-COMING SOON (eBird の解説 2024.9.24) に属分離に関係してそれぞれの属の特徴 (特にディスプレイ飛行) が述べられている。日本に関係する属だけ挙げておくと:
・Astur: 大型でディスプレイ飛行ではゆっくりした翼の動き (slow languid wing flaps) で似た声を出す
・Tachyspiza: 小型で羽ばたきが断続的で速く (snappy flaps in flight) ディスプレイ飛行をあまり行わない
Lophospiza, Aerospiza にはそれぞれ固有のディスプレイや行動様式がある。
分子生物学以前に旧ハイタカ属とチュウヒ属が近縁であることを示唆した先行研究があるか、また Jollie (1976, 1977。URL は参考文献の項目参照) にご登場いただこう。
p. 319 にある系統樹 (fig. 208) では旧 Accipiter に内包されるとまでは言っていないが、Accipiter, Urotriorchis, Erythrotriorchis, Circus
がまとまった枝を作っている。形態学からここまで議論されていたのである。これを見ればチュウヒ亜科はすでに意味をなさないことがわかる。当時は別と考えられていたので "core accipitrin" には Circus は点線で含まれているが、形態的な系統解析からはこのように考えられるとしていた。
Jollie は Circus は Accipiter の早い時期の分岐にあたると考えていた。Jollie によればこの枝に含まれる Erythrotriorchis には原始的な形質があり、Accipiter より先に分岐したと考えていたよう (p. 320)。
Geranospiza (セイタカノスリ属) が "core accipitrin" に含まれると考えられていたようでこれも点線でつないであるが、Jollie はノスリ類の系統に含めており、これも現代の見解と一致する。
現在はハイタカグループとなった Kaupifalco (トカゲノスリ属) の位置はさすがにわからなかったようで分子系統解析を待つ必要があったのだろう。
形質マトリックスを用いた Holdaway (1994) の解析では Circus と Accipiter はまったく別の場所に置かれていたとのこと。多くは Jollie のデータを用いているはずなので数値的に取り扱うか、解剖学的視点から系統を考察するかによって異なる結果となったのだろう。
Holdaway (1991) の学位論文 [Systematics and Paleobiology of Haast's Eagle (Harpagornis moorei)] (p. 83, 5.5 Classification of the Acciptridae - Based on the Phylogenetic Tree Presented Here 参照)
でも同様となっており、Circus と Geranospiza を含む Circinae (チュウヒ亜科) と当時の Accipitrinae (ハイタカ亜科) は間に Milvinae (トビ亜科) などが入った別の場所に分類していた。これらの点では解剖学の詳細を熟知した Jollie の方が一段上だった模様。
Sibley and Ahlquist (1988) を用いてコウノトリ目に含めているのも時代を反映していて興味深い。タカ類の系統分類に興味のある方はこれらの論文や該当部分の一読をおすすめする。
Gregory et al. (2024) Falling through the cracks: a family-group name for a clade of hawks and eagles (Accipitridae) including Morphnus Dumont, 1816, Harpia Vieillot, 1816, Harpyopsis Salvadori, 1875 and Macheiramphus Bonaparte, 1850
が一世代前の Mindell et al. (2018) の分子系統樹に基づく議論を行っている [2024.2.29 出版なので Catanach et al. (2024) の分子系統樹を用いていない理由になるが Tachyspiza 属の名称は正式に認められる前から用いている]。
この論文では Mindell et al. (2018) に従って Tachyspiza などの属は Accipitrini に含まれていない (!)。属レベルで広義の Accipiter 属が分割されたのみならず、族レベルでさえ分離できるぐらいに系統が違う (トビ類とノスリ類程度異なる) ことを意味する。
十分な種数の解析が行われるまで分割が難しかった理由は Choi et al. (2021) Complete mitochondrial genome of a hen harrier Circus cyaneus (Accipitriformes: Accipitridae) from South Korea
の系統樹でも見ることができる。この程度の種類数のサンプルであればミナミツミ (現在の Tachyspiza) とカンムリオオタカ (現在の Lophospiza) のグループを分離すればオオタカをAccipiter 属に残すことも可能であった。
Catanach et al. (2024) の結果がこのようにならなかった理由はおそらく現在の Astur 属4種と狭義 Accipiter 属3種、そして Circus 属7種の UCEs が読まれたことで 狭義 Accipiter 属と現在の Astur 属がクレードを形成しないことが明らかになったためだろう。
種サンプルが不十分だと誤った系統樹の形になり得る例とも言える。
Circus 属を Accipiter 属に編入しなかった理由は前述の通りと考えられるが、属統合が学名の衝突をもたらす問題点もある。
現行の学名で調べてみるとマダラチュウヒ Circus melanoleucos をもし Accipiter 属とすれば オオハイタカ [高野 (1973) ではシロクロオオタカ] (Astur 属が採用される前の学名で) Accipiter melanoleucus の学名と同一と判定されるか問題が発生する。
もし同一でないと判断されれば極めて紛らわしい1文字だけ違う学名が生じることになる。
(どちらが正しいのか詳しい規則は知らないが) もし同一と判断されるならばマダラチュウヒの命名の方が古いのでオオハイタカ [高野 (1973) ではシロクロオオタカ] の学名を変える必要がある。
この種は南アフリカで色彩二形のメカニズムも調べられていて学名もよく知られているので、見慣れない学名への変更の影響は大きいだろう。どちらにしても不都合となる。将来の判断で Circus 属を復活すべきとなればまた学名を変える必要が生じるかも知れない。
ちなみにこの種は現在は Astur 属なので、Circus 属と Astur 属を統合する (#チュウヒ備考の [分類と亜種] 参照) だけでも同じ問題が発生する。
他にも過去に使われたことのある種小名やシノニム化されて一見表面に現れない亜種小名などに衝突しているものがあるかも知れない。これらの調査はおそらくかなり大変なので誰もやりたいと思わない。すなわち Circus 属は残して Accipiter 属を分割する方が賢明と言える。
それではそもそも Accipiter 属のタイプ種がなぜオオタカでなくハイタカだったのかの疑問も生じる。Brisson (1760) Ornithologia sive synopsis methodica sistens avium divisionem in ordines... に属定義がある。
ここに登場するのは Accipiter (Brisson は1単語で種を表していた。英語で Sparrow-Hawk とある) と Accipiter minor の2つだった。
前者には Accipiter maculatus の名称 (縞/斑点のある Accipiter ぐらいの意味) が派生型として出てくるが何者とも特に同定された記述を見かけない (参考。よくわからないがハイタカの方は確実なのでこちらが採用されたものと想像できる)。
オオタカは同じグループに含まれていたが Astur の1単語で種を表していた。
さらに Falco などもこのグループに含まれていてこちらは Falco などを属名として用いた表記があるが、古い時代の話でもあって、Falco は Linnaeus が先に用いているので深入りはしないでおこう。
一覧表も参照。
面白いことに Accipiter major (Gessner の用いた学名。まだ有効な学名とされない時期) があって、これがオオタカを指していた。
Accipiter minor も同じく Gessner の用いた学名で、Brisson (1760) はこの学名をそのまま用いていた。Falco nisus Linnaeus, 1758 と同じものと判定されてハイタカが Accipiter 属のタイプ種とされた模様。
Gessner はオオタカ・ハイタカを大・小と考えていて、Brisson (1760) がそれぞれに別の名称を与えた。すなわち Astur の方が大、Accipiter の方が小。ヨーロッパに限ればこれは大変わかりやすく、現在のような分類になったのはヨーロッパ主要部に広義ハイタカ属が2種しかいなかったためのヨーロッパ事情とも言える (そして分離の妥当性はようやく今になって分子系統解析で確認された次第)。
長年 Accipiter 属が使われてきたのは、Brisson (1760) では Genus Accipitrinum の表現なのでこれが属を明確に表す最初の
ものとなったものと想像できる。
一方で各種種小名の方は Brisson は二名法による分類を採用しておらず有効な学名とみなされなかったと考えられる (#ハシグロアビの備考参照)。
この判断は時代にも依存したと考えられ、Brisson の用いた学名 (例えば Accipiter 属の major, minor など) は現在は無効だが意識的に避けられる要因となっていたかも知れない。
Astur は Brisson (1760) の記述では属とみなされず Lacepede (1799) が属の提唱者となっている。
そのため1属にまとめる場合はより早く定義された Accipiter 属の名称となった。
ちなみにハヤブサがどうなっているのか見てみると Falco Gentilis の部分に Falco gentilis と Falco peregrinus が並んで出てくるので、やはり gentilis はハヤブサを指して使われていた種小名らしいことがわかる (#オオタカと#ハヤブサの備考参照)。
ただしこれらの学名もやはり無効で、Falco peregrinus は挙げてあるものの学名記載とはみなされない。
もし Brisson (1760) の記した学名を有効とするとハヤブサと思われる種に peregrinus より先に登場する多数の名称があって [#オオタカの備考の Gesneri (1555) をほぼ引き継いでいる]、これはこれで大問題となっていただろう。
Linnaeus (1758) が定義上 Falco gentilis の原記載となるが、記述が混乱していてオオタカらしい特徴も挙げてしまったため歴史的名称をオオタカに持って行かれたことになる。
備考:
*1: UCEs: ultraconserved elements。参照: Ultraconserved Elements (UCEs)。
Cummins et al. (2024) The Evolution of Ultraconserved Elements in Vertebrates もわかりやすく、2004 年に提唱された概念 [Bejerano et al. (2004) Ultraconserved elements in the human genome]
で最初はヒト、ラット、マウスの間で 100% 合致する遺伝領域を指していた。
その後概念の拡張が行われて広い系統に使われるようになった。タンパク質をコードする遺伝子より 10 倍ぐらい進化速度が遅い。哺乳類・爬虫類・鳥類の間でも 89% 一致していて、これらが分岐する以前にほぼ固定されたと考えられる。多くの UCEs は神経や骨格に関係するタンパク質をコードする遺伝子のイントロンに含まれており胚の発育中に発現する調節領域にあたる。
*2: またまた余談だが "faster than light" (光より速い。faster-than-light とも綴る。真面目な物理学用語に superluminal という同義語があり、仮想でない現象の記述にも使われる) は英語でもしばしば非常に高速である比喩に使われる。
かなり昔の時代の方はかつて FTL Modula-2 (FTL Pascal の名前もあったように思う) というプログラミング言語があったことをご存じかも知れない。この FTL は faster than light の意味で、light は当時のライバル言語だった C 言語 (c は光速を表すので) よりも速いとの触れ込みであった。
どちらが生き残ったかは現状を見れば明らかなのだが。
新幹線も「ひかり」を使ってしまったためにそれより速いものの名称が悩ましかっただろうことは容易に想像ができるが...。wikipedia 日本語版によれば「ひかり」は公募で選ばれたそうで2位が「はやぶさ」だったとのことでさすがハヤブサである。
現在では新幹線でも「はやぶさ」号が走っているが、ロシアの超特急の名前もサプサン号 (sapsan) でやはりハヤブサである (最初のころだろうと思うが超特急なのに踏切があって世界にこんなのはないと住民がぼやいているニュースを見たことがある。実話かどうかは知らないが)。
ちなみに「光より速いものはない」のは真空中の話で、真空中以外では光速は {真空中の光速}/{屈折率} となり (真空の屈折率は1。屈折率が1より小さい状況はあり得るが話がややこしいので省略する。光速より速く情報が伝わることはない) 真空中より遅い。このため水面やレンズでの光の屈折が起きる。
水鳥の瞬膜が水中で近距離に焦点を合わせる能力を持たないことや、猛禽類の深い中心窩が凹レンズのように働く機能がないことは屈折率の概念を用いれば簡単に理解できる。
真空中以外では光速よりも速い速度は可能で、荷電粒子ではチェレンコフ放射が見られる (1958 年のノーベル物理学賞)。ニュートリノ観測 (2002 年小柴昌俊氏のノーベル物理学賞) に用いられ、原子炉の水中の青い光の正体はこれ。
真空中の光速より速いニュートリノの報告が 2011 年に発表されたが翌年に撤回された。
真空中の光速は 299792458 m/s と定義されている (1983 年以降)。これと1秒の長さの定義を組み合わせることで長さの単位が定義されている。1メートル = 真空中で光が 1/299792458 秒で進む距離。
秒は現在セシウム-133 の超微細構造遷移周波数で定義されている。キログラムの定義は 2019 年に変更され
国際キログラム原器に頼る必要がなくなった (特殊相対性理論の E=mc^2 と量子力学の E=hν に基づき、h を定数と定義することになった)。
科学好きの方ならおそらくご存じの話題で、実用上は特段何も変わることはないが。
余談の余談になるが、上記のような単位は SI 単位 (International System of Units; Systeme International d'unites 仏) と呼ばれ、多くの生物学論文誌でもこの単位の使用が求められ、科学の世界では統一されていると想像される方も多いだろう。
しかしながら天文学やその周辺分野 (物理学の一部でもそうであろう) では今でも CGS (cm, g, s) 単位系が普通に使われており、例えば日本天文学会の投稿の手引を見ても単位に関する規定がない。
世界の科学雑誌、例えば Nature でも SI 単位またはその分野で共通で使われる単位を使えとあり、科学全体で統一されているわけではない。エネルギーの単位は天文学では今でも通常 erg (エルグ) が使われ、生物の論文や本で厳格に kJ (キロジュール) と書いてあるのはむしろ斬新に見える。
一つには天文学では扱う値が大きすぎて SI でも CGS でもべき乗の部分が少し違う程度で大して変わらない理由もあるだろう。例えば太陽質量は 2x10^(30) kg であるが、2x10^(33) g としても大した違いがあるわけではない。昔から親しんできたべき乗の数字を変えるとむしろ間違いの元というのがおそらく本音だろう。
10 のべき乗の表現は英語では ten to the x-th となるが、日本語では 10 の 33 乗のようになる。口語では「10 の」を付けるのが煩わしいためしばしば略されて「51 乗エルグ」のような表現になり (この数字は超新星の爆発エネルギーぐらい) 知らない人が聞くと何を言っているのかさっぱりわからないと思う。共通語となってしまっているので CGS を使うのはやむを得ないのだろう。
距離の方も太陽系ぐらいはともかく、m や km, cm などで表さないことの方が多い。大きな値を用いるに小さな単位を使うのは変な話ではあるが、太陽までの距離でもやはり CGS を用いて cm で表している人も多い。
天文学で太陽系ぐらいの距離で一般的に使われる距離の単位は天文単位 AU で、もともとは地球と太陽の距離をもとにしたものだった。これには理由があって km 単位で測るよりも AU 単位で測る方がより精度が高かったため。km で十分な精度で書けるようになったのは探査機が飛んで光が届く時間などを実測できるようになってから。
物事のつながりを知ると話はより面白くなると思えるので紹介しておくが、2004 年と 2012 年に金星が太陽面を通過する現象があった。いずれも日本で観測可能なもので特に 2012 年はよく晴れてフィールドスコープで投影法で観察することができた (金星の太陽面通過は軌道の関係で6月か12月にしか起きず、この2回はいずれも6月で日本ではほとんど梅雨の時期にあたる)。
この現象は最近ではほぼ 243 年のパターンで繰り返し、12月に8年間隔で2回起きて、105.5 年後の6月に
8年間隔で2回起き、次は 121.5 年後という周期性がある。この現象を地球上の離れた点から観測して時刻差などを調べれば金星までの距離、そして1天文単位が実際は何 km なのかを測定することができる (なぜできるのかは天文ファンの方への宿題としておこう)。
前回のサイクルの1回めに当たる 1874 年の太陽面通過では、日本で経過の全過程を観測可能で、欧米から観測隊を受け入れることになった。ちょうど文明開化の時期にあたる。
この海外からの観測隊を受け入れによって近代天文学や経緯度の測定方法などを学ぶことになり、斉藤国治は「科学における黒船」と評している (金星の太陽面通過 wikipedia 日本語版より。他にもいろいろ情報がありこのページは面白い)。日本の経度原点 (東経 135°) が定められたのもこの出来事による。宇宙の距離を測ることも文明開化に一役買っていたのである。
日本初の鳥の目録が作られたのはこの後の時代。科学の他分野の出来事と比べると日本の鳥学の歩みも理解が進む気がする。
当時は km で表した太陽までの距離は3桁めでも怪しいぐらいの精度だった。
かつては定義が変遷したが 2009 年以降は定数として定義されて SI 単位で厳密に表せるようになった (のでこれも案外最近の話である)。太陽までの距離はほぼ 1 AU となる
[参考までに SI 単位 の wikipedia 英語版を見ると非 SI 単位で SI 単位と一緒に使うことが許されている単位に 日 (d) 時間 (h) 分 (s) 天文単位 (ここでは au となっている) や角度の単位、面積のヘクタール (ha)、リットル (l)、重量のトン (t)、音圧などのデシベル (dB) などが含まれているが、月や年は含まれていない。
日本鳥学会誌の投稿規定の投稿の手引 (2022年10月19日) にある単位の事例はすべてが SI 単位および派生単位、SI 単位と一緒に使うことが認められている単位に収まっている。SI 単位使用のこと、だけで済みそうだが投稿者にわかりやすく例示したのだろう。強いて挙げれば kJ/g は SI 基本単位で kJ/kg と書けるので SI 基本単位ではこちらの方が推奨される、という程度であろうか]。
太陽以外の恒星までの距離は桁違いに大きいためやはり CGS, SI はまず用いられず、パーセク (pc) が標準的な単位である。光が1年かかって進む距離である光年 (1 pc = 約 3.26 光年) も一般用語としては使われるが学術用語ではあまり使用されず pc やその 1000 倍の kpc, さらに Mpc, Gpc があって宇宙の距離を表現する時はここまでで十分である。
pc そのものは SI 単位で厳密に表すことができる (2015 年に厳密な値が定義された) が、Mpc を超えるぐらいになってくると別の問題が重要になり直接に距離で表すことは少なくなる。用いられるのは宇宙膨張の結果光の波長が長くなる効果に伴う赤方偏移 (z) である。この z は観測値から直接求められるものなので距離に代わって用いられる。
別の問題というのは宇宙膨張のことで、早い話が相手から光が出た時点と我々に届く時では宇宙の大きさが違うので現在観測する時点と光が出た時点が同じ座標系に乗っているわけではない。そのため通常考えられるような距離を単純に定義することができない。
わかりやすいのは相手から光が出てから我々に届くまでの時間 (lookback time) を計算して xx 光年と言えばよさそうに思える。また物の大きさが距離に反比例して小さく見えることで距離を定義してもよいだろう。さらに物の明るさが距離の2乗に反比例して暗くなることで定義してもよいだろう。
他にも使われる距離の定義があるが、これらはいずれも宇宙膨張のパラメータ (宇宙モデル) 次第であるとともに、定義によってそれぞれ大きく異なった値となる 赤方偏移と宇宙年齢および距離 (日本天文学会 天文学辞典) 参照。
「距離に反比例して小さく見える」定義を使うと、あるところから z が大きくなるのに距離が逆に小さくなってしまう。
これらの問題があるために天文学者に例えば最も遠い銀河の距離を聞いても答えにくいわけである。z ならばずっと正確な値を示すことができるわけである。
遠い天体の距離について
によれば国立天文台の発表などでは光路距離 (lookback time に対応) を用いているとのこと。
もう少しわかりやすい図の入った説明は 遠くの銀河を見るということ (pp. 3-5) にある。他にも使われる距離の定義と書いた中で共動距離 (もし現時点で巻き尺を当てて測れるならば、に多分近い) は一番よく使われるだろうが、これで測るととんでもない数字になる。
我々に届くまでの時間で定義することにすれば何の問題もないのではと思われるかも知れないが、赤方偏移では重力によっても起きるので、もしブラックホールまでの距離を「光が出てから我々に届くまでの時間」で定義すればブラックホール近傍まで近づけばいくらでも大きな値になり得る。
これは困るのでブラックホールのずっと外側 (ブラックホール自身による重力赤方偏移が問題にならない程度に) から重力の中心はどこにありますよ、を調べてその仮想的な点からの距離を使うことになる。
赤方偏移は宇宙膨張や重力がブラックホールほど強くなくても生じるもので、地球の重力場でもやはり微小な赤方偏移が生じる。GPS 衛星がもしこの効果を無視すると1日で 1 km ぐらいの誤差が生じてしまうらしい。
GPS と物理 によれば 10 m の精度を出すためには相当細かい配慮が必要になるようである。
もうちょっと近いところでは、野外観察などで星空を眺めて「あの光は何万年 (もっと大きな数字でも結構) も前に出たものを見ているのですね」などの説明を聞き、ロマンチックな雰囲気を味われている方も多いだろう。実際には肉眼で目立つ恒星はせいぜい数十から数 100 光年程度のものが多く、実はそれほど昔のものではない。
個々の星として見分けられない天の川でも 10000 光年ぐらいと思ってよい。
北半球から肉眼で見える最も遠い天体はアンドロメダ銀河で 250 万光年ぐらいとされる。肉眼ではこれより遠い天体は見ていないと考えてよいので、例えば何千万年前などの表現はさすがに過剰と言える。
望遠鏡を使えばもっと遠くの天体を見ることができて、市販されている程度の望遠鏡で普通に観察できるものではクエーサーを除いておとめ座銀河団が最も遠いものだろう。これが 5400 万光年程度で、我々に最も近い大規模な銀河団である。我々の住む銀河系はこの銀河団を含むおとめ座超銀河団の外れに属すると考えられている。偶然だが生物の分類階層にも似ている。
次に近い銀河団は 1.4 億光年、北半球から見える大規模銀河団のかみのけ座銀河団で 2.9 億光年となり、アマチュアの望遠鏡ぐらいでは見ることさえ困難になる。つまり我々がおとめ座超銀河団という大都会の郊外のアンドロメダ村 (局所銀河群) に所属しているからこそそこそこ近くの銀河が見えるのである。宇宙はおとめ座超銀河団の先こそが闇が深いのである。
もし銀河団の間に身を委ねることができるならば、肉眼はもちろん小型望遠鏡ですら何も見えない無重力、漆黒の真空の世界である。
大型の精密な観測装置がなければ方向も進んでいる方向すらもわからないだろう。自然の熱源となるものはもはや何もなく、ビッグバンの名残である絶対温度 2.7 K の放射とわずかな宇宙放射線が空間を満たしている極寒の世界である。SF 漫画などでよく描かれる銀河が肉眼でもたくさん見える宇宙の印象とはあまりに異なっている。
おとめ座銀河団ぐらいの距離で鳥類が大規模に進化を遂げたのと同じような時期に出た光を見ていることになり、宇宙の時間・距離感覚と鳥類進化の時間感覚の関係が多少わかっていただけるのではないだろうか。
市販の望遠鏡で目で見えるぐらいなので、ものすごく遠い話には感じない。
しかし宇宙のスケールに照らすと恐竜などの大絶滅の 6600 万年前と数億年の単位の時間はあまりにも違うのである。
[ハイタカグループの分類]
今後も分類が出てくるのでハイタカグループの新しい属名と系統分類を紹介しておく。Catanach et al. (2024) による。日本産のないグループは全種掲載。日本産のあるものは属まで掲載。チュウヒ属は属名は違うが (系統 3) に含まれ、(系統 3) は5つの属から形成されることになる。
(かつてこの位置にあった Accipiter superciliosus と Accipiter collaris はハイタカグループからは外れ、Microspizias 属に移動: #カンムリワシの備考参照)
カンムリオオタカ亜科 Lophospizinae
カンムリオオタカ属 Lophospiza
カンムリオオタカ Lophospiza trivirgatus Crested Goshawk
セレベスオオタカ** Lophospiza griseiceps Sulawesi Goshawk
ウタオオタカ族 Melieracini, トカゲノスリ族 Kaupifalcini, ツミ?/アカハラダカ?/アフリカオオタカ?族 Aerospizini とすべて族としているのは、名称はないがカンムリオオタカ亜科 Lophospizinae に対応する亜科相当の系統を考えそれに属する族と判断しているためだろう。
亜科 Accipitrinae (以下チュウヒ属までを含むグループ。2024年6月に Accipitrinae 亜科 の概念を拡大すると発表された)
ウタオオタカ族 Melieracini
カワリウタオオタカ属 Micronisus
カワリウタオオタカ [高野 (1973) ではモリウタオオタカ] Micronisus gabar Gabar Goshawk
オナガオオタカ属* Urotriorchis
オナガオオタカ Urotriorchis macrourus Long-tailed Hawk
ウタオオタカ属 Melierax
ウタオオタカ Melierax metabates Dark Chanting Goshawk
コシジロウタオオタカ Melierax canorus Eastern Chanting Goshawk
ヒガシコシジロウタオオタカ Melierax poliopterus Pale Chanting Goshawk
[系統 1: Catanach et al. (2024) でトカゲノスリ族 Kaupifalconini 2024年6月に綴りを訂正]
トカゲノスリ属 Kaupifalco
トカゲノスリ Kaupifalco monogrammicus Lizard Buzzard
[系統 2: Catanach et al. (2024) で ツミ?/アカハラダカ?/アフリカオオタカ?族 Aerospizini と命名]
アフリカオオタカ属 Aerospiza
ワキアカハイタカ [高野 (1973) ではワキアカオオタカ] Aerospiza castanilius Chestnut-flanked Sparrowhawk
アフリカオオタカ* Aerospiza tachiro African Goshawk
ムネアカオオタカ* Aerospiza toussenelii Red-chested Goshawk (IOC 15.1 でアフリカオオタカと同種に)
ツミ属またはアカハラダカ属 Tachyspiza (27 種。#ツミの備考参照)
族相当 [系統 3] (以下チュウヒ属までを含むグループ)
アカオオタカ属 Erythrotriorchis
アカオオタカ Erythrotriorchis radiatus Red Goshawk
カタアカオオタカ* Erythrotriorchis buergersi Chestnut-shouldered Goshawk
ハイタカ属 Accipiter (9種。#ハイタカの備考参照)
オオタカ属 Astur (8種。#オオタカの備考参照)
パプアオオタカ属 Megatriorchis
パプアオオタカ [高野 (1973) ではドリヤオオタカ] Megatriorchis doriae Doria's Goshawk
チュウヒ属 Circus (チュウヒなど 16 種。#チュウヒ備考参照)
セレベスオオタカ** は遺伝情報がまったくないが、形態的に (Mayr 1949; Wattel 1973) ここに分類されることが適切とのこと。
この解説の初期バージョンでは ハイタカ亜科 Accipitrinae の名前を用いていたが外した。
Catanach et al. (2024) の論文で preprint (2023) 段階に比べて亜科の扱いが多少変化し、Accipitrinae の名称を積極的に利用しない理由が生まれたためである。
Catanach et al. は preprint (2023) 段階ではウタオオタカ亜科 Melieraxinae の名称を使っていた。当初は (ハイタカ亜科) Accipitrinae と並列となる分類を想定したいたものと考えられるが、(2024) 発表論文で族 Melieracini となり、他の系統にも族名が新たに与えられた。
ウタオオタカ族からチュウヒ属までを含むグループ全体を亜科と位置づけたと考えられる。この亜科を "ハイタカ亜科" Accipitrinae と呼ぶことは可能だが、Accipitrinae が従来さまざまなグループに対して用いられた概念のため (チュウヒ類を含むかどうかも問題) Catanach et al. (2024) ではこの名称の利用を控えているように見える。
(その後 2024年6月に訂正が発表され、Accipitrinae の包含範囲をここで示したように広めることとなった。末尾の参考文献に追加)。
Catanach et al. (2024) ではチュウヒ類を含むものを Accipitrinae (s.l.) 広義ハイタカ亜科に相当する名称で呼んでいるが、過去にはもっと広義の Accipitrinae が存在したためどのように使い分けるかは非常に複雑である。
例えば NCBI Accipitrinae ではミサゴ亜科 (ミサゴ科になる前の名称) を除くタカ類をすべて Accipitrinae と呼んでいた分類を用いている。
SACC では Part 4. Opisthocomiformes to Strigiformes のようにタカ科を3系統に分割し Elaninae, Gypaetinae, Accipitrinae とする扱いもある。この分類ではクマタカ・イヌワシ類やチュウヒ類、ノスリ類などもすべて Accipitrinae と呼ばれることになる。
これら場合だと "(広義)ハイタカ亜科" とすら訳すのは適当でないだろう。"タカ亜科" とすれば SACC 分類ではトビは "タカ亜科" だが、それでは「自分はタカでないのか」とハチクマ殿から苦情が来かねないことになる。「ははあ、そういうつもりではございませぬが...」。ミサゴ殿は別格ですので。
true "hawks" のような一般名も使われることがあって、"真正タカ類" に相当するがこれはあくまで一般名であり、何をもって "真正" とするのかもわかりにくい。昔はふしょまで羽毛に覆われた booted eagles を "真正ワシ類" と呼んでいたことがあったが [高野 (1973)]、今はあまり聞かない。ハチクマ殿より「自分は偽のタカか」とまた叱られそうである。
Add subfamilies to Accipitridae
に図示されているが、Peters (1931) では8亜科に分けていて分子系統が判明した現在では大きく入り混じっていたことがわかった。Lerner and Mindell (2005) は単系統にするべく 14 亜科。
それでも「ハイタカ亜科」と「チュウヒ亜科」の問題は解決されないことがわかった。
「チュウヒ亜科」をどうしても残したければ「オオタカ亜科」のように細かくわければよいわけだが分岐年代が新しすぎることなどからさすがにその解決法はとらなかった。
チュウヒ類はオオタカ類が特殊に進化した形、と理解して行くことになるだろうか。セキレイ科とスズメ科やアトリ科がわかりにくいように、いつまでも直感的に捉えにくいまま残るかも知れない。
上位系統名は徐々に市民権を得ていくようなので、新しい分子系統が判明した現在から次第に整理したものが使われるようになってゆくだろう。
Catanach et al. (2024) が発表したものは単系統になる属までで、一部の上位系統名を与えた。それを採用するかどうかは分類学者の考え次第ともなるのだろう。チェックリスト次第で単系統になる属を必ずしも採用しない立場もあり得るが、分子系統学的な根拠の強さの問題、同一のチェックリスト内での他のグループの基準との整合性の問題性になるだろう。
亜科などの中間階層は必須ではないのでまったく取り入れない立場もあり得る。しかしかつてツグミ亜科、ヒタキ亜科の名称を使っていたので過去にも一般的に全然使われていないわけではない。
この解説では系統構造の理解しやすさを優先し、亜科などの中間階層の分類も文献に基づいて積極的に利用している。
Aerospizini 族の和名は Tachyspiza 属の和名が確定していないのでわからないが、日本産種を優先した名前とするとツミ族またはアカハラダカ族となるが、タイプ属の名称からは離れてしまう。これはやむを得ない部分もある。イワヒバリ科とカヤクグリ属のような和名関係になる可能性がある。
[系統 3] に族名称が与えられていないのはハイタカ属、オオタカ属、チュウヒ属などを含んで自然な名前にならないためかも知れない。Boyd は Accipitrini の名称を [系統 2] + [系統 3] に対して用いており、Catanach et al. (2024) の系統概念と異なるので注意。
形式的には [系統 3] を Accipitrini と呼ぶことはおそらく可能だろうが現段階ではおそらく非公式名 (記載者がまだない) になると思われる。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) ではパプアオオタカ [高野 (1973) ではドリヤオオタカ] とアカオオタカをこのグループの冒頭に置き、近縁であるとしていた。
ほとんどわかっていない地域の種類で Berryman and Eaton (2020)
The avifauna of the Mekongga Mountains, Southeast Sulawesi, Indonesia, and notes on a vocally distinct Locustella grasshopper warbler
に比較的最近の調査情報がある。この報告ではすでにここで示された新しい学名を用いている。
2020 年段階では属名の2つの可能性の選択はまだ確定されていなかったが、ツミやアカハラダカも新学名で記述されている。
論文には新種と考えられるセンニュウ類の音声記録もある。
このリスト中の日本産でない種類ではカンムリオオタカの分布が近く、台湾で留鳥。中国東部にも少数生息するところがある。#オオタカの備考参照。
Lophospiza < lophos 冠 spizias タカ (Gk)。trivirgatus < tri- 3本の virgatus 縞のある。
わざわざ "3本の" と付けたのはこの種は Falco trivirgatus Temminck, 1824 と記載されたもので、ミナミツミを Falco virgatus Temminck, 1822 と自身がすでに命名していたので区別するためと考えられる。
Temminck の命名したタカ類は模様や色彩に基づくものが多かった。当時はヨーロッパ以外の種類を命名する時代となっていてヨーロッパの種類のように通称などの歴史がなかったため標本のみから判断できる外見の特徴を多用したものと想像できる。学名の由来の理屈を考察する場合はあまり面白みがないかも知れない。
広義 Accipiter から Aerospiza 属の分離は以前にも行われていて (Roberts 1922; Wattel 1973) 新 (狭義) Accipiter とは形態的違いがある。
Roberts (1922) によればアフリカオオタカ (新分類で) Aerospiza tachiro を含むアフリカの数種は初列風切の外弁欠刻が5枚、5枚めの初列が最も長い、最外側の初列風切が次列風切より短い、尾は翼の 3/4 の長さなどの点で他と異なるとのこと。この属名はここで提案された。
狭義 Accipiter 属は主に鳥を捉える種類。
この研究で暫定的に 狭義 Accipiter 属に分類した種類のいくつかは過去の研究で違う位置に置かれていた。
セグロオオタカ Accipiter poliogaster Grey-bellied Hawk は Megatriorchis 属に近い位置の結果もあった (Mindell et al. 2018)。形態的には Accipiter 属に置く結果は支持されない (Wattel 1973)。
マダガスカルハイタカ Accipiter madagascariensis Madagascar Sparrowhawk と サバンナハイタカ Accipiter ovampensis は Breman et al. (2013)
DNA barcoding and evolutionary relationships in Accipiter
Brisson, 1760 (Aves, Falconiformes: Accipitridae) with a focus
on African and Eurasian representatives (広義 Accipiter のみを扱い、DNA バーコーディング領域のみを用いたもの。Circus 属との関係についてはまったく言及なし)
がオオタカのクレードに含めたが系統樹サポート率は十分ではなかった。この2種は狭義 Accipiter 属の基本的な形態 (長く細い足根中足骨 tarsometatarsus と趾、比較的小型の嘴と第 I 趾、相対的に小型の体型) を満たしている。
これらについては遺伝情報が十分揃うまでは暫定的に Accipiter に置くとのこと。
ウタオオタカの Melierax は melos 歌 hierax, hierakos タカ (Gk) (学名をたくさん見ているとこのあたりは見ればすぐわかってしまう)。音楽的な声に由来する。
ウタオオタカの metabates は飛び跳ねるもの (< meta 変わる bates 歩むもの)。
コシジロウタオオタカの canorus はカッコウの種小名と同じで「声の美しい」を意味する。Thunberg, 1799 の記載が早いために現在の学名になっているが、Falco musicus Daudin, 1800 のシノニムがあり、音楽的であることが古くから着目されていたようである。
参考 Voisin and Voisin (2001) Liste des types d’oiseaux des collections du Museum national d’Histoire naturelle de Paris. 9: Rapaces diurnes (Accipitridae), seconde partie。
ヒガシコシジロウタオオタカ はかつてコシジロウタオオタカと同種 (とはいえコシジロウタオオタカがヒガシコシジロウタオオタカの亜種とされていた) とされたが polios 灰色 -pteros 翼の (Gk)。
英名の方がむしろ馴染みがある。chant は歌うの意味だが、吟遊詩人のようなイメージがある。同系語に canto があり、cantabile はわかる方もおられるだろう。
フランス語でも chant が歌。chanson (シャンソン) が名詞。
これらウタオオタカ類はアフリカ探鳥では最も普通に見かける猛禽類で旅行記の写真にもよく出てくる (行ったことはないが)。
樹上でも地上でもとまっている姿がスマートでかっこよく自分も気に入っている種類。
他言語でもイタリア語 astore cantante、ドイツ語 Singhabicht、ポルトガル語 acor-cantador、中国語 歌鷹 のように同じ意味ものが多いが、フランス語 autour sombre (くすんだ色のオオタカ)、スペイン語 azor lagartijero (トカゲタカ) のように別の特性に着目しているものもある。
Shaw et al. (2024)
African savanna raptors show evidence of widespread population collapse and a growing dependence on protected areas
によればアフリカのサバンナでほとんどの種類の猛禽類が壊滅的とも言える数の減少を示しており、これまでより一層保護区に依存するようになっている。ヒガシコシジロウタオオタカとコシジロウタオオタカは例外的に数を増やしている。
ウタオオタカは他の猛禽類同様に数を減らしている。モモジロクマタカ、ソウゲンワシ、ゴマバラワシ、ダルマワシのような大型種ほど減少率が高い。
Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" p. 104 によればウタオオタカ類は爬虫類を中心に食べるが、それでも飛翔中のホロホロチョウやウズラ類を狩ることがあるとのこと。
カワリウタオオタカ [高野 (1973) ではモリウタオオタカ] の Micronisus は問題ないだろう。小さなタカの意味。gabar の方はあまり明確でなく garde ガードマン barre 帯のある (仏) または コエ語 (Khoi) から Levaillant が与えたものか、ただし意味不明 (The Key to Scientific Names)。
Gabar Goshawk Melierax gabar (BirdForum 2025.3) によればこの解釈は不詳とのこと。Lavaillant が "l'espece d'epervier que j'ai nommee Gabar" (自分が Gabar と名付けたハイタカ類) と記述しているので自身が名付けた名称で、Levaillant の名付けた名称に語源不詳のものがたくさんあるとのこと。他の事例を見てもフランス語をもとにした造語 (言葉遊び?) らしく、外国語からの借用ではないだろうとのこと。
epervier はフランス語でハイタカ類のことだが投網の意味もあるとのこと。gabar(r)e に網を指す意味もあるがかなり違うもので関連性はよくわからないとのこと。
多くの言語で gabar を用いているが、中国語では 紅臉歌鷹 と少し違う視点に着目している。
通常はシノニムとされる亜種 defensorum が記載されており、Sir Reginald and Lady Champion の貢献を讃えて、Champion の名前から defensorum (defending Champion) と命名されたとのこと 。
特殊な餌の捕り方については #クロハゲワシ備考の [変わった餌の捕り方をする猛禽類] を参照。
オナガオオタカは極端に長い尾で有名で、翼よりも尾の方が長い。Urotriorchis は oura 尾 triorkhes タカ (Gk) [#ハチクマの備考参照; uro- については #イヌワシの備考 (オナガイヌワシ) 参照]。
macrourus < makros 長い oura 尾 (Gk) と尾の長さを二重に強調している。ウスハイイロチュウヒの種小名にも現れる。
全長 56-65 cm だが尾は 32-35 cm を占めて独特の飛翔型となる。猛禽類中で全長に対する尾の比率ではアンデスチュウヒ Circus cinereus Cinereous Harrier に並ぶ (wikipedia 英語版より)。
トカゲノスリの Kaupifalco は Kaup (ドイツの動物学者で分類学者 Johann Jacob Kaup) と Falco (当時はタカ・ハヤブサ全般を指した) の合成。
monogrammicus < monos 一本の grammikos 線 (Gk)。
これも英名、和名ともノスリの名が付くのにハイタカに近い分類になるのは紛らわしい。ハイタカグループでは最も早く分岐したもので、ウタオオタカ属と残りのハイタカグループの間になる。
名前から想像されるよりは哺乳類 (齧歯類) を主に食べているが Mabuya 属 と Agama 属のトカゲが好きとのこと。
短く尖った翼で混んだ森林内を飛ぶのに適している (wikipedia 英語版より)。
他言語では英名から訳したと思われるトカゲを含むものもいくつもあるが、ドイツ語 Kuckuckshabicht (カッコウオオタカ)、フランス語 autour unibande (一本帯のオオタカで種小名由来だろう) のような独自路線もある。
アフリカオオタカ属の Aerospiza はおそらく説明するまでもないだろうが「空のタカ」。
女性名詞の属名になるが、Boyd のリストでは種小名を変化させているものはない。
ワキアカハイタカ [高野 (1973) ではワキアカオオタカ] の castanilius は castaneus くり色 + ilia/ilium わき腹。
アフリカオオタカ の tachiro は2説あり、tache 斑点 rond 丸い (仏) か tachiro (Gk) 速い (The Key to Scientific Names)。
Aerospiza toussenelii はアフリカオオタカから分離。和名は使用例を用いた。toussenelii はフランスのジャーナリストで博物学者の Alphonse Toussenel から。Verreaux が命名したもので Toussenel にさらに真剣に自然史を研究することを勧める目的があった (wikipedia 英語版)。
2024.12.12 IOC 15.1 でアフリカオオタカに統合。DNA には違いがあるが形態的に重なりがあり、音声や行動が似ているためとのこと。Catanach et al. (2024) の分子系統樹では結構違いがある (ただし Aerospiza toussenelii は伝統的マーカー遺伝子のみ調べられている)。
この程度の遺伝的違いがあっても同種とされるならばチュウヒ類などすべて同種となるぐらいなので、生態的な隔離の情報も必要で DNA だけでは別種相当かどうかを決めていないという意味だろう。
Latest IOC Diary Updates では遺伝情報的には賛同できない意見も出ている。
toussenelii の全ゲノムレベルの解読も望まれる。Aerospiza 属は2種となる。
アカオオタカの Erythrotriorchis もここまで読まれたらすぐわかるだろう。erythro 赤 triorchis タカ である。
アカオオタカの radiatus は一般には「縞がある」意味で使われることが多い。
オナガオオタカとは対照的にタカ類中尾が相対的に最も短いものの一つ。
wikipedia 英語版 (2025.3 時点) によれば、かつてはクロムネトビ Hamirostra melanosternon Black-breasted Buzzard および シラガトビ [高野 (1973) ではアカムネトビ] Lophoictinia isura Square-tailed Kite と合わせてオーストラリアのハチクマ亜科の系統と考えられていたことがわかる。
アカオオタカに関連する考察を [オーストラリアのタカ類] に分離した。
カタアカオオタカの buergersi はドイツ人でニューギニアを探検した外科医 Theodor Josef Buergers にちなむ。
Astur Lacepede, 1799 の名称は先取権の原則による (Sangster et al. 2012)。この属の特徴は比較的大型の嘴と長い第 I 趾。
astur の名前は代表的なタカまたはオオタカの名称として非常に多くの場面に現れる (cf. サシバの属名、マダガスカルヘビワシの種小名、使われなくなった属名など多数)。
ラテン語の起源や読み方は#オオタカの備考の方に移動した。
Astur 属は2系統からなり、gentilis オオタカを含むクレードと北米のクーパーハイタカ Accipiter cooperii (英名 Cooper's Hawk) を含むクレードをを独立の属とすることも考えられる。その場合の属名として Cooperastur 属を提唱している (新称ではなくかつて使われた属名)。
gentilis クレードの特徴は cooperii クレードに比べて比較的大型の体、短めの tarsometatarsus、短めの第 III 趾である。
クーパーハイタカにかつてヒメオオタカの名称が提案されていたことがあった [日本鳥学会「鳥」32(4) 世界の鳥の分類和名 (4) (1983)。この情報は若杉氏のマーリン通信の 2012 年記事 世界のタカ類・ハヤブサ類 標準和名 で知った]。
"オオタカ" の方が系統的には近かったのだがクーパーハイタカの名称が定着している模様。クーパーハイタカがハイタカ的に感じられるのは、Astur 属の2系統の違いが現れているのだろう。
Cooperastur 属 の属名を直訳するとクーパーオオタカ 属となる。上記の属の特徴を参照するとこの2系統は「大型オオタカ類」「小型オオタカ類」のような印象でよいだろうか。
十分定着した名称なので和名を変える必要はない感じがするが、英名および学名は鳥類学者 William Cooper にちなむもので、個人名の付いた英名を AOU (AOS) は今度どう扱うだろうか。
若杉氏の「せっかく高野伸二さんがつけて、やっと定着してきた和名が、十分な議論もなく変わってしまいました」にはまったく同感だが、自分も高野さんの本に馴染みすぎているためかも知れない。
ヒメオオタカの名称はちょっと小さすぎる感じがするが、ある意味時代を先行していたのかも知れない。
参考までに他言語の名称を調べておくと、Cooper を使っているものが多いがそうでもないものもいくつかある。ドイツ語は Rundschwanzhabicht と 尾の丸いオオタカ または Rundschwanzsperber 尾の丸いハイタカ。ノルウエー語 trostehauk はツグミのタカ。ウクライナ語、ポーランド語などは頭の黒いタカ。
英語別名の Chicken Hawk に相当するものもいくつかある。"ヒメオオタカ" に相当するものは見当たらず、他言語を訳したわけではなさそう。
AOS to discard patronyms in English names
によれば AOS の提案を受け、スウェーデンは AOS 地域のスウェーデン名を変更したとのこと。
新名は trasthok (ツグミのタカの意味。ノルウエー語に合わせたかも)。モモアカノスリの和名があるので日本では問題がないが、ハリスホークのスウェーデン新名は kaktusvrak (サボテンノスリの意味)。
他のグループで和名に個人名が入っているものでは、ボナパルトカモメの新名は tradmas (木のカモメ)、ウィルソンアメリカムシクイは svartkronad skogssangare (黒い帽子のムシクイの意味) とのこと。一部新名を募集中としている。このように他国の事例も紹介してアイデアを出し合うのは非常に健全なプロセスに見える。
AOS to discard patronyms in English names
ではクーパーオオタカに Pale-naped Hawk を提案している人がある。
別項目で人の名前よりも特徴が入った名前の方が識別点を記憶しやすい意見もあった。
クーパーオオタカはかつて鳴管の構造からオオタカと北米のアシボソハイタカ Accipiter striatus (英名 Sharp-shinned Hawk) の系統の近さが述べられたこともあったが、これは収斂進化だろうとのこと。ちなみにクーパーハイタカとアシボソハイタカは北米のタカの見分けで一番問題となる組み合わせである。
パプアオオタカ [高野 (1973) ではドリヤオオタカ] の Megatriorchis も簡単にわかるだろう。大きなタカの意味。doriae はイタリアの博物学者 Giacomo Marchese Doria にちなむ。
最大全長 69 cm に達し広い意味でタカの中で最も大きい部類という。
チュウヒ類とオオタカ類の中間に位置する。#チュウヒの備考参照。
チュウヒ類の中では祖先的な系統で、オオタカ類からチュウヒ類が分岐するに当たって他種も生まれたが、後続のより高性能なチュウヒ類による競争排除の結果大型種のみが残存した可能性が考えられる。
Mindell et al. (2018) では違う位置になるが、これは最も近縁になったものと解析に使われた遺伝子に共通のものがなく人工産物と考えられるとのこと。
Barrowclough et al. (2014) はチュウヒ類に近い位置に置いたが、これも Astur 属を扱っていない欠点がある。Catanach et al. (2024) の解析では核遺伝情報が使われており信頼性が高い。
生態的な情報はほとんどない。
[渡り]
池長 (1991) Birder 5(10): 30-35 の当時のアカハラダカの知見について詳しく述べられている。
渡りの発見は 1980 年で、現地古名でスズメダカとして知られていたとのこと。なぜ最近まで発見されなかったかの理由としてこの季節はシギ・チドリの渡りの時期でベテランは海岸や平地に出向くことが多かったことや先入観などの要因を挙げている。Birder のこの号は当時の知見によるタカ渡りの特集で、現在の知見と比べてみると面白い。
「アニマ」1992年10月号に鴨川氏による「アカハラダカの渡りルートを探る」の記事がある。アカハラダカが日本産種に認められるに至った事情や詳しい経緯などはこちらの記事の方がより詳しい。
当時はタカ渡りの観察と言えば 10 月で、9月の早い時期は考えられていなかった模様。
鴨川 (1997) Birder 11(5): 62-68 にそれまでの経緯、九州西部の渡りルート、本土初のねぐらの発見の記事がある。
アカハラダカの衛星追跡はすでに行われている [Min et al. (2021) Annual Long-Distance Migration Strategies and Home Range of Chinese Sparrowhawk (Accipiter soloensis) from South China。オス・メスとも調査されている] が、
日本を通過するアカハラダカの個体群の渡り経路はまだ衛星追跡で調べられていない (#ツミの備考も参照)。
台湾でのレーダーを用いた春の渡り観測が報告されている: Sun et al. (2010)
Spring Migration of Chinese Goshawks (Accipiter soloensis) in Taiwan。
Bildstein (2004) Raptor Migration in the Neotropics: Patterns, Processes, and Consequences は中南米の ムナジロアシボソハイタカ Accipiter chionogaster White-breasted Hawk、
フナシアシボソハイタカ Accipiter ventralis Plain-breasted Hawk、
モモアカアシボソハイタカ Accipiter erythronemius Rufous-thighed Hawk
は正しい方向に渡らなかったか渡らなかったアシボソハイタカから進化したことはほぼ確実であろうと述べている (migration-dosing speciation 仮説)。
同様にメラネシアの島の Tachyspiza 属の多くの種は同様にしてアカハラダカから生じたと提案しており、エルニーニョの風で飛ばされて、などのメカニズムを考えている。
Catanach et al. (2024) でも Tachyspiza 属の島の固有種は希少性も高く、解析に適した標本を扱えないためかあまり含まれていないので近縁性はよくわからない。
アカハラオオタカ (オーストラリア)、ムナグロオオタカ (ニューカレドニア)、クロアカオオタカ (ニューギニア)、フィジーオオタカは近いグループをなすのでアカハラダカから個別に "migration-dosing" を受けた進化経路とはおそらく異なるのだろう。祖先系統がアカハラダカであることは間違いないが、定着と種分化の過程はもう少し複雑なのだろう。
しっかりした系統樹が手に入るとこのようなことも考える楽しみも増える。
渡り個体が島に定着して固有種を形成する傾向を系統的に調べた研究もある: Dufour et al. (2024) The importance of migratory drop-off for island colonization in birds。
系統別にみるとタカ類は渡りをする種類も多いが、migration-dosing によって固有種形成が一番多いグループとなっている (別の視点で見ると海鳥が高い。Supplemenetary Information 参照)。ハヤブサ目はなぜか入っていない。
新環境での生存確率も高いのかも知れない。猛禽類の渡りを考える時にこのような視点で見るのも面白い。
日本周辺 (全分類群を含む) ではフィリピンがそのような種類のホットスポットとなっており、琉球がそれに次ぐ。世界的に見てもカリブ海に匹敵するぐらい migratory drop-off が島の固有種形成に関係が深い地域となっている。
ただし SupplemenetaryData2 を見ると琉球で該当するものはリュウキュウキビタキ、ホントウアカヒゲ、アマミヤマシギ、アカコッコ (琉球ではないが)、オオトラツグミを入れているよう。これらがみな migratory drop-off にふさわしいかどうかは ? の感じもある。
[食性]
アカハラダカは Grey Frog Hawk とも呼ばれていてほとんどカエルのみを食べているとのこと。繁殖地での主な食事がカエルである珍しい種類だそうである。Ferguson-Lees and Christie (2001) をみると韓国では繁殖期にほとんどカエルを食べていて、他には昆虫。
主に地上採餌をする (飛翔して探すこともある) など、小鳥を食べるのが中心の (これまでの広義の) Accipiter らしからぬ種類である。越冬地ではもう少し鳥も食べるらしい。
中国での繁殖生態研究: Ma (2016)
Breeding Biology of a Little-Known Raptor in Central China: The Chinese Sparrowhawk (Accipiter soloensis)
こちらではトカゲが7割だったとのこと。韓国では水田地域で観察されたためで、この中国の研究ではもっと森林地域での観察である点が異なる。繁殖失敗率はかなり高く韓国、中国とも4割程度だが韓国の研究は事例数も少なく孵化失敗が多かったが理由不明。この研究ではヘビによる捕食が最も多かった。
巣立ち後 17-18 日で分散を始めるが、このように早い理由は捕食が容易なトカゲや昆虫を主に食べるためかと推測している。
日本では繁殖しない種類だが、日本産種のタカ類ではアカハラダカが巣立ち後最も短時間で自立するものだろうか。
Choi (2013)
Morphometrics and Sexual Dimorphism of Chinese Goshawks (Accipiter soloensis)
にアカハラダカの逆性的二形の研究がある。測定値のみで十分雌雄判別が可能だが、翼長でみると性比 95% と確かにツミ 85%、ハイタカ 83% などに比べると雌雄差があまりない。現代の分類でもツミと同属になるが、系統よりも食性が現れているのだろうか。ノスリやチュウヒに近い値になっている。
[オーストラリアのタカ類]
アカオオタカの系統に関連してオーストラリアのタカ類について調べてみた。オーストラリアでは最大種のオナガイヌワシが非常に有名だが他のタカ類はあまり知られていないのではないだろうか。
#ミサゴの [日本産タカ類を新しい分類で見る] と同様に作ってみた。
資料は 2023 Australian bird species checklist (IOC) から。(V) は迷鳥。
ミサゴ科 Pandionidae
ミサゴ属 Pandion
ミサゴ Pandion haliaetus Osprey
タカ科 Accipitridae
カタグロトビ亜科 Elaninae
カタグロトビ属 Elanus
クロオビトビ [高野 (1973) ではクロオビハイイロトビ] Elanus scriptus Letter-winged Kite
オーストラリアカタグロトビ [高野 (1973) ではオーストラリアハイイロトビ] Elanus axillaris Black-shouldered Kite
ハチクマ亜科 Perninae
カッコウハヤブサ属 Aviceda
カンムリカッコウハヤブサ Aviceda subcristata Pacific Baza
ハチクマ属 Pernis
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Crested Honey Buzzard
クロムネトビ属 Hamirostra
クロムネトビ Hamirostra melanosternon Black-breasted Buzzard
シラガトビ属 Lophoictinia
シラガトビ [高野 (1973) ではアカムネトビ] Lophoictinia isura Square-tailed Kite
オナガハチクマ属 Henicopernis
オナガハチクマ Henicopernis longicauda Long-tailed Honey Buzzard
イヌワシ亜科 Aquilinae
ヒメクマタカ属 Hieraaetus
アカヒメクマタカ [高野 (1973) ではヒメアカクマタカ] Hieraaetus morphnoides Little Eagle
イヌワシ属 Aquila
モルッカイヌワシ [高野 (1973) ではガーニイイヌワシ] (V) Aquila gurneyi Gurney's Eagle
オナガイヌワシ Aquila audax Wedge-tailed Eagle
亜科 Accipitrinae
ツミ?/アカハラダカ?/アフリカオオタカ?族 Aerospizini
ツミ属またはアカハラダカ属 Tachyspiza
ツミ (V) Tachyspiza gularis Japanese Sparrowhawk
アカハラダカ (V) Tachyspiza soloensis Chinese Sparrowhawk
ハイイロオオタカ [高野 (1973) ではカワリオオタカだが分離あり] Tachyspiza novaehollandiae Grey Goshawk
アカハラオオタカ [高野 (1973) ではオーストラリアオオタカ] Tachyspiza fasciata Brown Goshawk
アカエリツミ (系統位置暫定) Tachyspiza cirrocephala Collared Sparrowhawk
族相当
アカオオタカ属 Erythrotriorchis
アカオオタカ Erythrotriorchis radiatus Red Goshawk
チュウヒ属 Circus
(系統 1)
ウスユキチュウヒ Circus assimilis Spotted Harrier
(系統 2)
ミナミチュウヒ Circus approximans Swamp Harrier
ノスリ亜科 Buteoninae
トビ族 Milvini
トビ属 Milvus
トビ Milvus migrans Black Kite
シロガシラトビ属 Haliastur
シロガシラトビ Haliastur indus Brahminy Kite
フエフキトビ [高野 (1973) ではフエナキトビ] Haliastur sphenurus Whistling Kite
ウオクイワシ属 Icthyophaga
シロハラウミワシ Icthyophaga leucogaster White-bellied Sea Eagle
日本産でない種類が多いので和名はよく使われるものを挙げてある。属和名なども一部は仮に与えたもの。
古いリストなどを見ると順序があまりに違うのでどこに入るのか悩むぐらい。現代の分子系統的考えではイヌワシ類がタカ類進化の最終段階ではない。
このように眺めると日本と大きく違うのは Tachyspiza 属以外の広義 (旧) ハイタカ属が到達していないこと、ノスリ類がいないことだろうか。代わりにカタグロトビ亜科とハチクマ亜科が頑張っている。ただしハチクマはかつて生息していた証拠は知られておらず近年の新参者。2023 年リストでは (V) になっているが繁殖兆候が十分高いので勝手に (V) を外させてもらった。
大陸の面積の割には猛禽類の種類が少ないと言われるがこの表をみてもそのように感じる。かつてはハゲワシ類も生息していたが絶滅してしまったなど消え去った系統もあるだろう。
カタグロトビ亜科は近年は世界的にも好調なのと同様、生態的にも優勢なようでオーストラリアでも重要な位置を占めている。古く分岐した系統なので生態的に弱いというわけでもない。
#ハチクマ備考の [ハチクマ亜科の他種] に登場するカタグロトビ類以降のタカ科の中で最も古い (2400-2600 万年前) 系統の化石がオーストラリアで見つかっている: Mather et al. (2022) An exceptional partial skeleton of a new basal raptor (Aves: Accipitridae) from the late Oligocene Namba formation, South Australia。この著者たちは Archaehieraxinae 亜科を創設。
現代の森林性猛禽類ほどは強力でないもののクマタカ類に近い生態を持つ種類がこの段階ですでに現れていて小型の哺乳類 (例えばコアラ) や鳥類を捕食していた可能性が考えられるとのこと。
オーストラリアではさらにもう1系統の化石猛禽類が見つかっていて (Pengana robertbolesi)、系統を判断する資料が乏しいがチュウヒダカ類やセイタカノスリ Geranospiza caerulescens Crane Hawk に似た骨の特徴があるとのこと [Boles (1991) Pengana robertbolesi, a peculiar bird of prey from the Tertiary of Riversleigh, northwestern Queensland, Australia]。
チュウヒダカ類はヒゲワシ亜科 Gypaetinae、セイタカノスリはノスリ亜科 Buteoninae と系統はまったく異なり形態的な類似性は収斂進化によるものとされているので Pengana robertbolesi の系統を判定する材料に乏しいことになる。
ヒゲワシ亜科であればハチクマ亜科に先行する系統なので順序的には興味深いがヒゲワシ亜科の現生種はヒゲワシがユーラシアに分布する程度でアフリカ以外にあまろ分布していない点は解釈上悩ましいかも。
ヒゲワシ亜科ももしかすると現在よりも広範囲に分布していたのかも知れないが、後続系統の方がより優秀で限られたものしか残らなかったのかも。Pengana robertbolesi をノスリ亜科と考えるのはオーストラリアにノスリ類が到達していないので否定的に見える。
その次となった可能性のあるハチクマ亜科はアメリカ大陸にも分布するのでかつては世界的に分布していたらしい。このうちクロムネトビとシラガトビ [高野 (1973) ではアカムネトビ] はオーストラリア固有種で、クロムネトビは道具を使う鳥として有名。
カンムリカッコウハヤブサとハチクマは顔つきが似ているが、クロムネトビはどう見てもノスリのように見えてハチクマとどのような類似点があるのかわかりにくい。英名も悩ましいようで、Buzzard は分類上正しくないので Kite と付けてみたり、Buzzard-eagle となっていたりする。ノスリ類がいなければ代わりの系統が進化してノスリ類の役割を果たせる次第。
我々は北半球の鳥を見てオオタカやハイタカがタカ類の代表種のように捉えがちだが視点を変えると様相がだいぶ変わる。
チュウヒワシ亜科 Circaetinae に対応する可能性のある種類では、比較的近年絶滅したオーストラリアの巨大猛禽類 Dynatoaetus gaffae と Dynatoaetus pachyosteus が 2023 年に発見された (#カンムリワシの備考参照)。
絶滅したハゲワシ類 Cryptogyps lacertosus (#カンムリワシの備考参照) が知られており、ハゲワシ亜科 Aegypiinae もかつてオーストラリアに進出していたことがわかる。ただし系統はそれほどわかっていない。これも古く分岐した系統で生態的はむしろハゲワシ類がいないことが不自然だった。
メガファウナ動物の死体に依存していたがメガファウナの絶滅により絶滅したと考えられている。ご存じの通りオーストラリアの哺乳類は系統が限られており、絶滅によって食物が突然大幅に減少することもあり得た。
ついでながら Australian megafauna の wikipedia 日本語版を見ると現生の megafauna にオナガイヌワシが含まれているが英語版では含まれていない。やはり他言語版もチェックした方がよい。
ここまで一通りの系統がオーストラリアに到達していたらしいことがわかる。チュウヒワシ亜科やハゲワシ亜科が絶滅したのはユーラシア・アフリカで他系統との競争によって特殊化が進んだ後だったため、生態的にあまり柔軟性がなく環境変化に適応できなかったのだろうか。
さて問題のアカオオタカであるが、この現生種の表を見ても一番近そうに感じるのはハチクマ亜科で、かつてはハチクマ亜科が多様に種分化したものの1種を見ていると考えられ、Australasian old endemic raptors として含められていたことがあった [wikipedia 英語版 (2025.3 時点) でも同様。Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" では分類不明に分けられていた]。
オオタカ類との類似性は収斂進化によるものと解釈されていた。音声はオオタカ類とある程度似て聞こえる。
アカオオタカはオーストラリアでもおそらく最もまれな猛禽類で数の減少が懸念されている (IUCN EN 種) 生態的にはあまり強力ではないよう。目撃も難しい種類のようで eBird/ML にもあまり画像がない。
オーストラリアへの入植に伴う土地改変によって数が減少し、Ferguson-Lees and Christie (2001) によれば南部を中心にすでに絶滅した地域も多いと考えられるとのこと。一方トビが増えたのはこのためとのこと
[Gaff (2002) The fossil history of the family Accipitridae in Australia (修士学位論文) も参考とした]。
Gaudin "List of the birds of the world" は Catanach et al. (2024) 以前の情報により 2022 年段階で Tachyspiza 属に含めていた。
同じ Erythrotriorchis 属のカタアカオオタカはニューギニアの種類だがほとんど知られていない。日本のオオタカも含めて後に現れた系統の猛禽類は一般的には保全上あまり心配ないのではと考えるがこれらの種はやや危ない感じがする。
現在ではむしろオオタカ類に近縁で、狭義ハイタカ属 Accipiter が分岐する前の系統となる。ニューギニアのカタアカオオタカとともに狭義 Accipiter 属や Astur 属がユーラシアに分布する以前にこの系統の一部がおそらくアフリカから熱帯を経由してオセアニアに分布していたことがわかる。
上記の表では Tachyspiza 属の分岐が早いためこちらが先に分布していた印象を受けるが、オーストラリアの Tachyspiza 属はアカハラダカ以降の系統で、アカハラダカの祖先系統が長距離の渡り能力を活かして分布を広げたと想像できる
(オーストラリアの Tachyspiza 属ではハイイロオオタカが有名で広く分布する。近年分割が行われて英名・和名ともに複雑な関係になっている。分割の結果オーストラリア固有種となる。この属の種は#ツミの備考の方に)。
分岐年代的には新しくアカオオタカの方がずっと早くから分布していたはず。
この点はここに現れるチュウヒ属もアカハラダカ類同様である。
ハイタカやオオタカの系統も初期は広域進出を試みていたが他の系統 (例えば Tachyspiza 属や当時存在していたハチクマ亜科などが候補?) によって競争排除され、競争種の少ないオーストラリアなどにわずかに残っている形になったものだろうか。
古い系統にもかかわらずアカオオタカとカタアカオオタカの分岐が新しいことも注目に値する。この2種は比較的最近まで連続分布していたが両者とも衰退した結果地理的隔離が発生したのだろうか。いずれも遺存固有と考えてよさそう。
もう少し考えてみるとハチクマ亜科が世界的に優勢だった時代は温暖・湿潤で森林が連続して存在していたと思われる。その後乾燥化が進んで中東などに乾燥地帯が広がり、森林に依存する種類ではアフリカなどから出生の系統は南回りでは簡単に分布を広げることができなくなったと考えられる。カッコウハヤブサ属 Aviceda の分布がアジア・オセアニアとアフリカに分断されているのも乾燥化で途中の分布がなくなったのだろう。
ハイタカやオオタカの系統の大部分の進展は温暖・湿潤な時代には間に合わず、初期系統の一部のみが Erythrotriorchis 属のように分布を広げることができたのだろうが、現代のハイタカやオオタカのような生態的強さをまだ持ち合わせていなかったためあまり生き残ることができなかったと想像できる。
その後乾燥化が進み、草原や開放地が好みの Aquila 属 (モルッカイヌワシ [高野 (1973) ではガーニイイヌワシ] とオナガイヌワシ) もニューギニアからオーストラリアまで到達することが可能になった。チュウヒ類も乾燥化による草原の広がりに合わせて分布を広げ、こちらは渡り能力を利用してオーストラリアに2系統が定着したと思われる。
Aquila 属に近いグループではクマタカ類 (Nisaetus 属) は海を越える分散能力が低く分布できなかったが、アカヒメクマタカ [高野 (1973) ではヒメアカクマタカ] はこの系統で唯一分布を広げた。しかし大変小型の種類。
この Hieraaetus 属は絶滅したハーストイーグル (Haast's Eagle) (#カラフトワシの備考参照) も含まれアカヒメクマタカが最も近縁な種類。この系統はオーストラリアでかつてある程度栄えていたことを示唆する。Hieraaetus 属がオセアニアで種分化したのは約 200 万年前と新しく、オーストラリアに乾燥地が広がった時代に対応する。
ハーストイーグルの巨大化は島に隔離されたことで何らの大型化への選択圧 (種内?) が働いたものと考えられるが (モアを捕食するために大型化するかどうかはよく知らない)、最も近縁なアカヒメクマタカが非常に小型なのは他種が存在するため種間競争による選択圧の結果 (例えば大型化してもオナガイヌワシ相手では競争にならないなど?) も想像できる。ハーストイーグルの巨大化はオナガイヌワシがいなかったため可能になった?
オナガイヌワシの進出も同じころで、Hieraaetus 属や Aquila 属は飛翔能力の点では分布を広げることは十分可能だったが、密生した森林環境が開けるまでは容易に定着できなかったものと想像される。
ハイタカやオオタカは乾燥化が進んでからアフリカを出発し、北回りで分布した結果ユーラシアでは現在の成功につながっているが、もともと北方に進出した系統であったこと、海を超える分散能力がそれほど高くなくウォレス線を越えてオーストラリアまでは遠く分散できなかった描像が考えられる。ノスリ類も同様。
ただしハイタカやオオタカが進出しなかったのは北方系統だけが理由ではなく熱帯に先に分布していた他の猛禽類との競争も要因の一つではないかと想像する。
また熱帯の森林を通じて分布を広げることができたハイタカやオオタカの初期系統がオセアニア以外に残っていないことから判断して、ハイタカやオオタカの祖先系統は生態的にあまり強力ではなかったのではないだろうか。より祖先系統には古い分岐がいくつもある (ウタオオタカ類など - 好きだけど) が、格段に強力な種類ではない。ハイタカやオオタカの祖先を遡るとこのような鳥だったのかも知れない。
南米の遺存的なセグロオオタカ (#オオタカ備考の [Astur (オオタカ) 属の系統分類] も参照) もハイタカやオオタカの祖先を考える上で参考になりそう。
Tachyspiza 属 (例えばタカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ]) のようにタカ類の中でもとりわけ攻撃的な性格を発達させることでようやく広域進展が可能になったのかも知れない。
ハチクマ亜科、カンムリワシ類、クマタカ類などが温厚と言われるのも、先行した系統の強みで攻撃的な性格をもたらす選択圧がかかる必要性がなかったからではないだろうか。
また、現在は地域によって生態系の最上位捕食者であるはずのオオタカが、なぜそれほどまで生息を明らかにしないのか (#オオタカ備考 [オオタカの生息確認は難しい?] 参照)、このような苦難の進化の歴史が背景にあるのかも知れない。ハイタカの方が先行したため、後から分布を広げたオオタカの方がより一層隠蔽的な性質が必要だった? (かどうかわからないが)。
一方で先行した Tachyspiza 属ではそこまで隠蔽的になる必要がなかったために都市に近い環境にも適応しやすいのかも知れない (もっともツミが都市鳥になっているのはほぼ関東平野限定の話で、こちらでは依然幻のタカに近い)。
日本の種類に閉じない考察はいろいろな意味で有効なのではないだろうかと感じる。
-
ツミ (将来の属名変更に注意)
- 第7・8版学名:Accipiter gularis (アクキピテル グラーリス) のどに特徴のあるタカ
- AviList 学名:Tachyspiza gularis (タキュスピツァ グラーリス) のどに特徴のある速いタカ
- 第7・8版属名:accipiter (m) タカ (accipere 掴む Gk)
- AviList 属名:tachyspiza (f) 速いタカ takhus 速い spizias タカ (Gk)
- 種小名:gularis (adj) のどに特徴のある (gula (f) のど -aris (接尾辞) 〜に関連する)
- 英名:Japanese Lesser Sparrowhawk, IOC, AviList: Japanese Sparrowhawk
- 備考:
tachyspiza は#アカハラダカ参照。少し例外的な読みを採用している。
accipiter は#ハイタカ参照。
gularis は a が長母音でアクセントがある (グラーリス)。-aris の発音に由来。
現在 Accipiter 属に対して提唱されている新分類では Tachyspiza 属となる見通し。#アカハラダカの備考参照。
記載時は l'epervier a gorge rayee 原記載 で学名は Astur (nisus) gularis, Temminck & Schlegel, 1845 で Astur は当時のオオタカ属。
この記載ではオオタカ類を2つに分け、ハイタカとツミには Nisus (亜) 属を提案している (1ページ前も参照)。記載時のフランス名からのどにある線が学名由来となっていることがわかる。
記述では sur le milleu de la gorge, une fine raie longitudinale (のどの中央の細い縦線)。
オス、メスともにのどの線が見られるとある。La raie de la gorge est aussi prononcee que dans le male (メスの方がのどの線が目立っている)。(図版)。図版を見る限りは雌雄同定は誤っていないよう。
非常に珍しい鳥で2体しか標本を持っていないとのこと。
個体によってはのどの線が目立たないものもあるので、たまたま手にした2標本が雌雄とものどの線が目立つ個体であったため付いた学名と言えるかも知れない。
gularis は非常に多くの鳥の学名に使われており、IOC 14.2 の種で修飾のない gularis を持つ種は 28 で、修飾されたもの (atrogularis など) も含めると 129 種もある。Temminck もツミに先立って 1815 年の用例がある。首を意味する collis は修飾されたものも含めて 102 種で gularis の方が多い。
Temminck and Schlegel が用いた gularis の用例ではオオルリのメスがあった (すでに使われており無効名だった。#オオルリの備考参照)。
Temminck and Schlegel が過去の何かの学名との重複を気にしたとすれば、この記載の Astur 属ではあまり問題なく、Accipiter 属まで含めても特に気になるものはない。
ノスリやチョウゲンボウに japonicus を使っており似た名前が並ぶのを避けて、比較的記述しやすい特徴があり、よく使われる種小名だったので用いたのかも。
のどに縦線のもっと目立つタカの種類は他にもあると言われそうだが、この記載は日本に生息する2種を述べたもので、ハイタカに比較するとのどに縦線が目立つことを意味したと理解してよいだろう。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば Accipiter nisoides Blyth, 1847 ("ハイタカに似た" の意味。参考) マラッカでの記載、
Accipiter stevensoni Gurney, 1863 (参考) の中国の記載もあり、当時は中国の由来の方がよく知られていたようで Seebohm (1890) は Chinese Sparrow-Hawk の英名を用いていた。Temminck and Schlegel の記載が早かったので現在の学名となった。
ツミに最も近縁の鳥はミナミツミ Accipiter virgatus (英名 Besra の名が有名) で、かつてはツミはこの亜種とされていた。Dement'ev and Gladkov (1951) では8亜種あり、その1つがツミだった。
現在では系統が比較的離れていることがわかっている。顔つきもだいぶ違う。
Japanese Lesser Sparrowhawk の英語旧名はミナミツミと同種とされていた時代由来らしい。まとめて Lesser Sparrowhawk と呼ばれていた。ミナミツミの方が記載年代が古く、これも記載時学名 Falco virgatus Temminck, 1822
(一覧表。記載。図版にはフランス語名のみ現れる) 基産地 Java と Temminck によるもの。
ツミの記載の方が新しいのでミナミツミと同種の場合はミナミツミの亜種となる。つまりツミの種英名が Lesser Sparrowhawk とされていた時期があったが、その後種分割に伴って地名などを使うようになったらしい。ツミの学名はうまく対応する英名がないため使われなかった可能性もある。
ミナミツミの方は記載時学名で Accipiter Besra Jerdon, 1839 (現在はミナミツミの亜種) があり、分布も広いためヒンディー語の Besra がそのまま使われたと想像できる (統合前のものも含めて Asiatic Sparrowhawk, Besra Sparrowhawk, Philippine Sparrowhawk などの名称もあった)。
ツミの方は Seebohm (1890) が Chinese Sparrow-Hawk の英名を用いていたがこれはおそらく同種とされる前の名称で、同種時代にこの古い名称が一度失われ、再度分割する際に基産地をもとに命名されたものと想像できる。現在の英名に含まれる Japanese はこの時代の名残りと言えるかも知れない。
英国では Goshawk と Sparrowhawk のみなのでそれより小さいものは適切な名前がなく、広義ミナミツミを指して Lesser Sparrowhawk となったのも安易な名称ではあるがやむを得なかったのかも (#ホトトギスが Lesser Cuckoo の名称となった経緯は少し事情が違うと思われる)。
ミナミツミもツミも英国・米国の種ではないので英名にはあまりこだわらなかったかも知れない。
Accipiter 属に含めるのが妥当とされた期間が長く続いたのもタカ類をオオタカ、ハイタカの視点で見るヨーロッパの影響が大きかったのかも知れない。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば同種扱いで、ロシア語でもミナミツミは英語 Lesser Sparrowhawk と同じ意味の名称になっている。そのうち亜種ツミに "シベリアの" を冠していた。ロシアでも極東の種はあまり知られていなかったようで現地名なども出てこない。
Karyakin (2004) "猛禽類の調査方法" (参考文献参照) でも Accipiter virgatus となっており、ロシア語名も上記と同じ (p. 215)。ツミとミナミツミが同種とされた時代が後々までかなり長く続いていた模様。やはり分割に際して Japanese が与えられたものと想像できる。
後述の [ロシアのツミの論文] Frolov et al. (2025) で状況がよりよくわかって、タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] 現在の Tachyspiza badia が tyuvik と呼ばれていたが、{ツミ + アカハラダカ} は別概念で "小型のハイタカ" の名称 (英語 Lesser Sparrowhawk と同じ意味) があった。
ツミとアカハラダカを分離するに当たって後者に "中国の" を付けた。ツミはロシアにも分布するために "小型のハイタカ" の名称のまま残した。分子系統解析の結果 tyuvik と同じ属に入ることがわかり、"ハイタカ" を外して "小型の" tyuvik、"中国の" tyuvik と改名することになるのではないかとの推測が出ている。英語も同種時代は Lesser Sparrowhawk だったが、英語の習慣として分割する場合に分割前の名称は残さず、分離後はそれぞれ代表的な地名で呼び分けたものと考えられる。
英語圏とは関連の薄い種なので Japenase, Chinese に分けてもあまり問題なかったのだろう。
これは過去の分類で Astur と Accipiter 属は分けていたが (現代の概念とは異なる)、それより小型の種に別属を与える習慣があまりなかった (ヨーロッパやアメリカから身近ではない地域だった) ため、そのまま Goshawk, Sparrowhawk と引き継がれた経緯が残っているのだろう。フランス語でも autour, epervier でも同じ。
北方のオオタカとハイタカを出発点に物事を考え、より南方の主に小型の種類を分ける発想があま生まれなかったため別系統 (Tachyspiza 属など) の認識も遅れ、分子系統解析があっと驚く結果を導くことにつながったのだろう。このあたりは鳴禽類でもヨーロッパのツグミ類などから順次分けていったため "ゴミ箱" 状態の分類群が残った事情に似ている。
ミナミツミが広義に使われていた時代は現在の分類ではもう1種 ムネアカツミ [高野 (1973) ではアカムネツミ] Tachyspiza rhodogaster Vinous-breasted Sparrowhawk が含まれていた (Dement'ev and Gladkov 1951 の広義分類)。
これは記載時 Nisus virgatus rhodogaster Schlegel, 1862 (原記載) と当初より亜種扱いで種英名などは分離後に後から付けられたものだろう。
Schlegel (1862) のこの文献にもツミが別種扱いで登場するが名称は特に挙げていない。"Fauna Japonica" の時代よりは知見も増えていたようで日本からインド大陸に分布するとあり、ネパールの標本も挙げられていた。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に記載の亜種はツミ gularis (ロシア極東部も同亜種とされる)
と八重山地方の留鳥のリュウキュウツミ iwasakii (気象学者、生物学者の岩崎卓爾 Takuji Iwasaki 由来。原記載)。
世界的には他に亜種 sibiricus (「シベリアの」の意味。Tachyspiza 属になれば女性形の sibirica になる。モンゴル、中国から台湾で繁殖) がある。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では前2亜種と亜種不明がリストされている。
[Tachyspiza (ツミまたはアカハラダカ) 属の系統分類]
順序は Catanach et al. (2024) で解析された 16 種に加え、遺伝情報のない種類を Boyd AFROAVES I (Taxonomy in Flux) に従って列挙。
種小名語尾も Boyd による。ツミの wikipedia 韓国語版で Tachyspiza の属名が使われている。
wikipedia スロバキア語版 Jastrabovite の分類も Catanach et al. (2023) 段階のものに従い、これまでに使われたクレード名が何を含むかの解説もあって役に立ちそう。
古い分類はこちら、とのリンクもあってなかなか親切。しかし広義ハイタカ類に始まりハチクマ類で終わる分類 (2011 年の記事らしい) は相当古いものかも?
亜科相当 (ハイタカグループ)
ツミ属またはアカハラダカ属 (タイプ種を優先すれば後者) Tachyspiza
アフリカツミ* Tachyspiza minulla Little Sparrowhawk
ニシアフリカツミ* Tachyspiza erythropus Red-thighed Sparrowhawk
ミナミツミ Tachyspiza virgata Besra
ツミ Tachyspiza gularis Japanese Sparrowhawk
レバントハイタカ Tachyspiza brevipes Levant Sparrowhawk
タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia Shikra
アカハラダカ Tachyspiza soloensis Chinese Sparrowhawk
シロハラハイタカ* Tachyspiza francesiae Frances's Sparrowhawk
ハイガシラオオタカ* Tachyspiza poliocephala Grey-headed Goshawk
カワリオオタカ Tachyspiza hiogaster Variable Goshawk
ハイイロオオタカ [高野 (1973) ではカワリオオタカ] Tachyspiza novaehollandiae Grey Goshawk
シロクロオオタカ* [高野 (1973) ではニセマダラオオタカ] Tachyspiza imitator Imitator Goshawk
クロアカオオタカ Tachyspiza melanochlamys Black-mantled Goshawk
アカハラオオタカ [高野 (1973) ではオーストラリアオオタカ] Tachyspiza fasciata Brown Goshawk
ムナグロオオタカ Tachyspiza haplochroa White-bellied Goshawk
フィジーオオタカ [高野 (1973) ではフィージーオオタカ] Tachyspiza rufitorques Fiji Goshawk
以下遺伝情報なし
シラボシオオタカ** [高野 (1973) ではシラホシオオタカ] Tachyspiza trinotata Spot-tailed Sparrowhawk
セレベスツミ** Tachyspiza nanus Dwarf Sparrowhawk
ムネアカツミ** [高野 (1973) ではアカムネツミ] Tachyspiza rhodogaster Vinous-breasted Sparrowhawk
モルッカツミ** [高野 (1973) ではハイノドツミ] Tachyspiza erythrauchen Rufous-necked Sparrowhawk
アカエリツミ** Tachyspiza cirrocephala Collared Sparrowhawk
シロハラツミ** Tachyspiza brachyura New Britain Sparrowhawk
チャバラオオタカ** [高野 (1973) ではグレイオオタカ] Tachyspiza henicogramma Moluccan Goshawk
ニコバルハイタカ** Tachyspiza butleri Nicobar Sparrowhawk
ノドジロオオタカ** [高野 (1973) ではマダラオオタカ] Tachyspiza albogularis Pied Goshawk
アオハイタカ** Tachyspiza luteoschistacea Slaty-mantled Goshawk
オオハイガシラオオタカ** Tachyspiza princeps New Britain Goshawk
系統が少し離れるところに空行を入れてあるが、いずれも深い分岐ではない。2種のみが並んでいる3系統において2種の順序は意味がない。
ツミとアカハラダカはそれほど近い関係ではない。
Tachyspiza 属は南方系と言って差し支えないだろう。
シラボシオオタカ [高野 (1973) ではシラホシオオタカ] 以降は遺伝情報がなく解析されていないが、上記 Boyd (根拠となる文献は Boyd のページ参照) によりこの属に属すると考えられるもの。Boyd の系統順とそのうち Catanach et al. (2024) で調べられたものの結果に多少違うものがあるがおおよそこの順でどこかに収まると考えられる。
セレベスツミの学名は扱いが分かれていて IOC 14.2 では Tachyspiza nanus となっている。Boyd は nana、Gaudin は nanus と古くから Tachyspiza を用いているリストでも違っている。
ラテン語で nanus (小人) は名詞。nana (同じ意味で女性を指す名詞) がある。
Linnaeus は植物には nanum を形容詞として用いていた証拠があるそうで植物学では変化させることもあるらしいが植物学と動物学では規則が異なる。ICZN Article 34.2.1 では名詞は変化させないとの規則があるそうで nanus が正しそう
cf. Change the species name of Dwarf Jay from Cyanolyca nana to C. nanus (N&MA Classification Committee 2020)。これは属変更に伴って一度変えられた種小名が戻された事例。
原記載が形容詞を意図したことが明らかでなければ nanus, nana は名詞扱いとのこと。
やはり気づいて指摘した人があり Latest IOC Diary Updates
nanus は名詞で用いられたもので対応する中性名詞が存在しないので (属名のラテン語は中性のものがある) かつては行われていたが性の合致は行われないとの説明がある。インドネシアのフィールドガイドでは早くから分割を取り入れておりすでに nana で印刷したものがすでに出回っているのこと。
また H&M checklist には不変と記述があり、この点については非常に信頼できる出典であるとのこと。
英語の dwarf は形容詞的にも使われるので、意味を dwarf と意味を書くと誤解を招きやすいとの見解があった。
レバントハイタカ Tachyspiza brevipes と タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia は同種扱いのこともあった。高野 (1973) では別種扱い。
タカサゴダカの和名の由来はタカサゴモズ同様と想像できるが、主要語義となる台湾は分布域から離れており地理的分布の広さをうまく洗わせていない気がする。一方ミナミハイタカの名称もミナミツミが存在してミナミハイタカは現在の系統的にはあまりふさわしくない名前になってしまう。
[小型種で小鳥食の猛禽類は都市化に向いている?] の項目も参照。
シロクロオオタカの和名は高野 (1973) では Accipiter melanoleucus = Astur melanoleucus に対して付けられていたものだがこの種 Astur melanoleucus Black Goshawk にはオオハイタカの名前が与えられているようである。
Tachyspiza hiogaster はかつて Tachyspiza novaehollandiae の亜種とみなされていたため、分離に従ってこの2種の名称が与えられたものと思われる。この2種には遺伝的には結構大きな違いがある。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) には当時の名称でカワリオオタカの3つの型の図が出ている。
そのうち2型がハイイロオオタカの白色型 (White Goshawk) と灰色型 (Grey Goshawk)
を表しているようである。
もう一つが現在の名称でカワリオオタカに対応するようである。
novaehollandiae Gmelin, JF, 1788 の方が hiogaster Mueller, S, 1841 よりも古いので両者を統合した場合は前者の学名になるはずだが、The Peregrine Fund では2種を分離していないようで Accipiter hiogaster Variable Goshawk として3つの morph がある説明になっている。
もともとの variable の意味が3つの morph を指していたのであればそのうち2つの morph のある Tachyspiza novaehollandiae の方が variable の名前にふさわしい感じもするが、Tachyspiza novaehollandiae の灰色の morph にすでにあった英名 (Grey Goshawk) を活かしたのであろう。
分離された Tachyspiza hiogaster も多数の亜種と morph があるので、variable の名前をこちらに引き継いだようである。
ハイイロオオタカの和名は英名の種名に対応する。白色型 (White Goshawk) は亜種とはされておらず通常の分類群の名前としては現れないかも知れないが、もし和名を付けるならばどうなるだろうか。
シロオオタカはオオタカの亜種名としてすでに存在するのでそのまま訳すことはできない。
高野 (1973) でさえも「マックロ」を和名に付けるのは躊躇したらしいあとがきがあるので、ここでは「マッシロオオタカ」を提案してみようか。ハイイロオオタカの白色型と長々と言うよりも簡単明瞭である。
なお Grey Hawk という種が別に存在する Buteo plagiatus ので注意が必要。
なおこのハイイロオオタカの白色型は白色のオウム類 (cockatoos) の大群に紛れることで自らを隠し捕食を容易にしている擬態と考えられるとのこと。白色のオウム類のいない島には白色型がいないとも記されている [Bildstein (2017) "Raptors" p. 29]。aggressive mimicry については #ノスリの備考 [オビオノスリはヒメコンドルに擬態?] も参照。
関連して気になるところでシロノスリ Pseudastur albicollis White Hawk という南米の森林性の種がある。捕食者なのにそれほど目立っていてもよいのかと気になるところだが、空を飛んでいると白は案外目立たないかも知れない。
シロハラハイタカは高野 (1973) には登場していないようだが、マダガスカルハイタカ Accipiter madagascariensis が同じ学名で2種類出ており、配置や全長の数値などから2つめの種類がシロハラハイタカに相当すると思われる。その意味で高野 (1973) では和名が与えられていない。
広義の Accipiter は多くの種を含んでいて英名にも似た名前が多く、さすがの高野氏にも校正漏れがあったのだろう。
[オオハイガシラオオタカ New Britain Goshawk の初撮影]
オオハイガシラオオタカ New Britain Goshawk は IUCN VU 種だが、Search for Lost Birds によれば 1969 年以来目撃がないとのこと。パプアニューギニアのニューブリテン島に生息するが調べられていないようで、言われているより個体数が少ないのではとの考えから 2008 年に VU 種となったもの。シロハラツミも同所に生息で 1994 年の記録が最後とのこと。
いずれも観察情報の少ない地域のため実際に絶滅に近い状態とは考えられていないよう。
2024 年に 55 年ぶりの再発見のニュースがあった。初めての写真撮影に成功: Raptor species 'lost' for 55 years photographed (BirdGuides 2024.10.2)。撮影時は価値を知らなかったとのこと。
撮影時は種類不明で iNaturalist で撮影者自身の同定が提案されたが過去に写真がないために最初は却下され、他の人から写真はないが目撃記録はあるなどの議論がなされていた: New Britain Goshawk。
同定者が2名あり、過去の写真はなくても同定可能な観察経験者があってこれも驚くべき。公式記録はなくても見ている人は見ていた。
Hawk-eyed photographer snaps threatened bird feared lost (別記事 phys.org 2024.9.13)。
Lost bird for 55 years: rare goshawk photographed for the first time in Papua New Guinea (WWF Pacific 記事)。
55 年観察されていなくても絶滅を心配する人があまりなかったのは、人為のあまり及んでいない地域の猛禽類は一般的に大丈夫と思われていたのだろう。
アオハイタカも 2009 年の観察が最後でパプアニューギニアのビスマルク列島。IUCN VU 種。
いずれも他種との類似性などから現在の Tachyspiza 属に含まれるが英名でも Sparrowhawk, Goshawk の両者があるように多少の違いもあるらしい。いずれも Tachyspiza 属であれば近縁系統が2回導入されてしかも生殖隔離が起きているらしい。分子系統解析で確認すべきものなのだろう。
意外に感じるがタカ類で種レベルで近年目撃がない種類はほとんどなく、最も絶滅のおそれがある種類は キューバカギハシトビ Chondrohierax wilsonii Cuban Kite とされる (#ハチクマ備考の [ハチクマ亜科の他種] 参照。近年分離された種)。
Bildstein (2017) の言うように猛禽類は resilient (柔軟性がある、回復力がある) で種レベルの絶滅が想像以上に少ない (#クマタカの備考 [クマタカと鷹狩り] 参照) 考えを裏付ける結果となっている。Search for Lost Birds にはハヤブサ目は出てこない。
[ツミとアカハラダカの衛星追跡]
ツミとアカハラダカの衛星追跡は Pierce et al. (2021) Determining the migration routes and wintering areas of Asian sparrowhawks through satellite telemetry にある。これらは渡り中にタイで標識されたもの。ツミの1羽はロシアの繁殖地に戻るまで追跡された。
最新の追跡結果は
Khieo, our GPS tagged Japanese Sparrowhawk, is well on her way back to Thailand ロシアで繁殖期を過ごしてタイに戻ってきた (2023) コースが報告されている。春と秋の渡りでコースにはそれほど差がないようである。
ボルネオ島に渡るツミ The first Japanese Sparrowhawk, Janjao arrived in Borneo。
タイの渡り研究の裏話 Winged migration
衛星追跡用のデバイスは 1 km 以内の精度が出るそうである (サシバ、ハチクマの追跡時代よりだいぶ良くなってそうである)。ただし大変高価で1つあたり 4000 ドル以上かかるとのこと。
論文によれば発信器は 5 g で、大型であるメスにしか装着できなかったとのこと。オスの経路はまだ未解明。
この裏話では渡りのツミは日本で繁殖するものと信じてられていたがロシアに行ったのは鳥類学の常識を覆すと書いてある。
DNA 型も異なるので (ロシアで繁殖するのは) 新しい亜種だろうと書いてあるが、論文ではそんな話は出てこないので報道上の誇張かと考えたが遺伝子解析は別に論文があった。
Nagai et al. (2020) Genetic Structure in Japanese and Thai Populations of the Japanese Sparrowhawk Accipiter gularis
に情報があり、mtDNA Control Region のハプロタイプ解析で日本とタイのツミには差が認められるとのこと。リュウキュウツミも遺伝的にまとまっているとのこと。
LC541470.1 のデータで BLAST 結果を見るとツミ (このデータはリュウキュウツミ) とミナミツミが遺伝的に相当近いことがわかって面白い。
[ロシアのツミの論文]
ロシアのツミの論文:
Shokhrin (2009) The Japanese sparrowhawk Accipiter gularis on Southern Sikhote-Alin pp. 2236-2240 (2009 初出、2019 再録)、
Zhukov and Balatsky (2011) The Japanese sparrowhawk Accipiter gularis in the Novosibirsk Oblast: in nature and in zoological collections pp. 327-334、
Voloshina and Myselenkov (1974) To breeding biology of the Japanese sparrowhawk Accipiter gularis pp. 652-653 (1974 初出、2010 再録)。
沿海地方だけでなく、ノボシビルスクまで分布している。ツミの分布はハチクマとよく似ているように思える。
Nechaev (1983 初出、2024 再録)、Distribution and biology of the Japanese sparrowhawk Accipiter gularis on Sakhalin (pp. 4951-4953) サハリンのツミについて。
ヨーロッパロシア (沿ヴォルガ連邦管区に含まれるペンザ州) ペンザ (Penza) でツミが記録されていた: Frolov et al. (2025) The Japanese sparrowhawk Accipiter gularis - a new bird species for the European part of Russia: the story of one photograph (pp. 2571-2576)。
2013 年 8 月にハト小屋に飛び込んできたとのこと。当人は "ワキスジハヤブサ" だと思って望まざる来客の写真だけ撮っておいたもののしまわれていた。数年後に "ワキスジハヤブサ" とはとんでもなく異なっていて、(広義) Accipiter 属の1種と判明したが当該地域に生息・飛来する種類にうまく該当するものがない。
ただしハイタカのオスに非常に小型のものあることは知られている。
ツミかアカハラダカが迷行したかも知れないが可能性は低いと思われた。特にアカハラダカの若鳥の羽衣はあまり十分に知られておらず文献からの判断は困難だった。
まずは中央アジアやカザフスタンのタカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia Shikra の亜種が検討されたが、2021 年に同じペンザでタカサゴダカの繁殖が 50 年ぶりに確認され (Frolov et al. 2024。同じ号の pp. 2588-2592 に収録) 若鳥の模様は撮影された個体と異なることが明らかになりようやく事態が動いたらしい。
ロシア東部で繁殖するツミとの比較やアカハラダカの識別情報 (De Candido et al. 2014 のタイの識別情報を参考にしている) などからツミのオスの若鳥と判定されたとのこと。Menzbir 鳥類学研究所が記録を認定したとのこと。識別で検討されている点もなかなか微妙でこの2羽が異なる点に重点を置きすぎの感じがする。もしかするとまだ覆る可能性もあるのでご検討を。
若杉氏とも相談し、ロシアのツミの写真を調べたところシベリア中央部で iNaturalist に投稿されている画像の範囲では確実にツミと言えるものはないのではと考えた (この判断部分は自身に責任がある)。iNaturalist の投稿や議論されている内容を見ると、識別点よりも Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) の記述や分布図を判断材料にしている傾向が感じられた。
iNaturalist はアマチュアによる投稿が主体で専門の研究者の判断と同じではないかも知れないが、識別情報や写真図鑑の質では日本は恵まれている印象を受けた (もっとも日本以外の鳥の情報は限られてしまうが)。もちろんロシアでも日本の図鑑を参考にすればよいだけのことだが、英語図鑑や論文を見るのはともかく、日本とは言語障壁があまりに大きいのだろう。情報は蓄積されているにもかかわらず日本発で英語で書かれたオンラインの識別情報が少なすぎることも要因の一つだろう。
ロシアのリストではツミ、アカハラダカはまだ Accipiter 属のままだったが、AviList や IOC 15.1 では Tachyspiza 属に変わっているのでおそらく早晩 (現在 "ハイタカ" を修飾する名称となっている) ロシア語名も変わるだろうが、今のところ分類学の専門家に任せるとなっている。AviList を見ていながら Catanach et al. (2024) を引いていないので分類学にはあまり詳しくない著者と思われる。
[小型種で小鳥食の猛禽類は都市化に向いている?]
ツミそのものとは直接関係がないが、オーストラリアの研究で小型猛禽類 (体重 172-370 g) は都市化に抵抗性があるとのこと: Headland et al. (2023) Smaller Australian raptors have greater urban tolerance。
この研究では最も都市化に適応しているのが シロガシラトビ Haliastur indus Brahminy Kite (トビよりも少し海ワシに近い)、ハヤブサ、オーストラリアチゴハヤブサ Falco longipennis Australian Hobby、アカハラオオタカ Tachyspiza fasciata Brown Goshawk、
アカエリツミ Tachyspiza cirrocephala Collared Sparrowhawk などで、アカハラオオタカやアカエリツミはツミと同属。
最も非寛容なのは オナガイヌワシ と チャイロハヤブサ Falco berigora Brown Falcon とのこと。オナガイヌワシの傾向はイヌワシとよく一致するとのこと。
White et al. (2018) Raptor nesting locations along an urban density gradient in the Great Basin, USA がアメリカの研究。
こちらでは クーパーハイタカ Astur cooperi Cooper's Hawk、アシボソハイタカ Accipiter striatus Sharp-shinned Hawk、アカオノスリ Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk が寛容とのこと。
生息環境や獲物への要求もあるが、食物面でジェネラリストかどうかは必ずしも関係がなかった。体サイズとよい相関があるのは生活史も関係があるのでは。例えば子供の数が少なく発育速度の遅いものが非寛容な傾向があるなど。
オーストラリアの都市はモザイク状なので、小鳥を追う小型猛禽類には魅力的かも知れないとのこと。
面白いことにトビ (同種) やミサゴ (カンムリミサゴ) はそれほど寛容でなく、トビはむしろ忌避している。フエフキトビ Haliastur sphenurus Whistling Kite も同様。
これらの結果を見ると、小型種で小鳥食の猛禽類は都市化に向いている? ツミは好適な条件を備えているのかも。
アジアに分布するタカサゴダカも都市環境に順応しているとのこと。
#カンムリワシ備考の [猛禽類のヘビ毒耐性] にもインドにおける鷹狩り、ヘビの捕食などタカサゴダカの話題がある。ツミよりは大型だがツミに対してよく言われるように気が強い種類のようでインドの鷹匠に気に入られているとのこと。
[ツミの換羽]
ツミの風切羽の換羽に関する研究について #カタグロトビの備考 [タカ・ハヤブサ類の初列風切の換羽様式] の紹介も参考。
[過去のツミの系統樹に注意]
Sangster and Luksenburg (2021) Scientific data laundering: Chimeric mitogenomes of a sparrowhawk and a nightjar covered-up by forged phylogenies
によれば Liu et al. (2017) の発表したツミのミトコンドリアゲノムはキメラで、同じグループによるヨタカもキメラだった。このデータを使っている過去のツミの系統研究は間違っているので注意。
ほとんど系統樹の "捏造" に近いとの表現になっている。
どこかで見た系統樹でツミが不自然になっていたならばこのデータを使っていないかチェックすべし。
Liu et al. (2019a) のエゾビタキも種類が間違っている (#エゾビタキの備考参照)。
Liu et al. (2019b) のカラフトアオアシシギもキメラだった (#カラフトアオアシシギの備考参照)。
Hu et al. (2020) のオバシギもキメラ (#オバシギの備考参照) ですでに少なくとも4つの系統樹に用いられている。
[和名について]
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 78 では "墨鷹" がなまってツミとなった説が紹介されていた。河合氏はオオタカ、ハイタカ、ツミのすべてが色彩由来で説明できる考えを好まれていた。
大橋 (2022) Birder 36(9): 52-53 によれば すずめたか、ずみ の古い名称が小さい鷹の意味で紹介されている。これらの名称が短縮されたりなまってツミとなったとの考え。
同記事によれば "えっさい" の意味は不明で、これらが同種であることは江戸時代になってから一部の人に知られるようになりましたとの記述になっていた。
本草食鑑 (1697)、大和本草 (1709) にも (同種であることをうかがわせる) 指摘が見えます、とのことで、江戸時代の数々の鳥類図譜には「えっさい」は載っていてもツミの雄だという指摘は見当たらないとのこと。
若杉氏の 小形ながら最も気の強いタカ ツミ (マーリン通信 1996) では 一部の書籍を見ると、「別種と思われて..」などの記載がありますがこれは間違いです。ちゃんと同じ種の雄と雌と認識されていました。とあり、大橋氏の情報と両方を勘案する必要があるかも知れない。若杉氏に問い合わせ、少なくとも鷹狩りに関連する一部の人が知っていたのではないだろうか、程度の印象を受けた。「一部の人に知られるようになりました」表現はおそらく正しかったのだろうが、広く知られるほどではなかったのではないだろうか。
Temminck and Schlegel (1845) はオス・メスのわずか2体の標本をなぜ同種と判定できたのか気になってくるが、原記載を見ると送られてきた標本をもとに判断したようで日本の情報由来ではなかった。
Temminck and Schlegel はヨーロッパのハイタカ、そしてアカハラダカ (Temminck 自身の記載で Falco cuculoides Temminck, 1822 フランス語名 Autour coucoide)、l'epervier de Dussumier 現在の学名で Tachyspiza badia dussumieri タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] のインド亜種をすでに見ていたため、雌雄差が大きいことは経験済みだったらしい。
またミナミツミ Tachyspiza virgata Besra も Temminck (1822) がすでに記載していた。
同種と考える理由は明確には述べてはいないが、記述を見た範囲ではのどの中央の細い縦線が共通で見られることが決め手となったように読める (そして学名の由来にもなる - 些細な特徴と考えて学名の意味を軽視してはいけないのだった)。どちらかの個体がこの縦線を欠いていれば (オオルリの雌雄を別種としたこともある) Temminck and Schlegel も悩んだかも知れない。
細かく調べてあってオス標本には幼羽が一部残っていること、メス標本はおそらく成鳥であろうと書かれている。
原記載ではツミの方がアカハラダカやタカサゴダカに比べて足や趾の長さや頑強さは及ばないとある (ces organes sont loin d'etre aussi gros et aussi lourds que dans l'epervier coucoide et l'epervier de Dussumier)。アカハラダカよりツミの方が大型と考えているとやや意外な感じがする。
このように考えると "つみ" と "えっさい" が同種であることは Temminck and Schlegel の記述を見た鳥学者にとって初耳で、あっと驚いたかも知れない。そしてこのようなことを結論できる西洋の優れた科学を導入しなければ...となった (ほんとうか?)。
ウグイス (オス) とコウグイス (メス) を別種と考えていた時代のことなので別種と考えられていても不思議でなかったかも。ウグイスも巣からひなを採取したならば、現代の視点からは同種であることは明らかだが、そのようになっていなかったのも鳴かないウグイスは捨てていただけで、同種の雌雄の認識は弱かったのではないだろうか。
ちなみに Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではオスを Essai、メスを Tsumi と併記でまだ種全体を指す名称の表示になっていない。
念のため "悦哉" の "哉" の文字を調べておくと、要するに強調や感嘆符のようなものと思えばよいらしい (中国語・日本語とも)。当て字かも知れずやはりよくわからなかった。雀 "鳥 + 戎" の漢字の表記もあるようなので、後者を見ておくと武士、武器、野蛮などの意味があるらしい。すなわちこちらも雀鷹の意味? ただし "えっさい" の音と漢字は中国語をみても対応がない。
マーリン通信の上記ツミのページでは "えっさい" に 雀 "多+缶 + 鳥" の表記が紹介されており、この後者の文字を見ておくと中国語ではハイタカ、チュウヒ、トビに対応するとのこと。形声文字で古代中国語では *lew, *lews、現代の標準的読み方では yao (鷹の文字の "よう" の読みに相当)。日本語では訓読みで "はいたか" とのこと。この語形は "スズメ" + "ハイタカ" を意味することになる。
中国語ではは別語源で読み方が違う使い方もあって、この場合はキジを意味していて音は同じ。現在この語義は使われていないとのこと。韓国語では Hanja でこの文字を yo と読む。ハングル文字でこの音に対応するものは現在ではタカの意味は残っていない。漢字を用いていた時代は意味が区別されていたのだろうが日本語同様に同音異義語が多く、ハングル表記となってタカの意味は失われてしまったらしい。
中国語でこの文字と鷹 (yaoying) でハイタカを意味する。漢語から入った文字由来と考えられるが、上記表記と "えっさい" の音は無関係のよう (以上 wiktionary より)。
多少気になっているのは、タカの古語に "くち" があり、日本書紀 (720) に倶知として現れ、百済から伝来とされる点。"くち" の知られている最も新しい用例は 1128 年ごろとのこと (wiktionary, 出典は日本国語大辞典)。「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) では 1116 年の「くちの羽」を含む歌が紹介されている。
この "くち" の名称は日本で見慣れぬ鳥を百済の人に問い、ここから鷹狩文化が伝来したと言われる。wikipedia 日本語版より紹介しておくと: 『日本書紀』巻第十一には、以下のような説話が掲載されている:
仁徳天皇 43 年 9 月 (推定 353 年)、依網屯倉の阿弭古が、「異しき鳥を捕りて」天皇に献上した際に、「私は、いつも網を張って鳥を捕りますが、未だかつてこのような鳥の類を得たことがありません。そこで、奇妙に思い、献上しました」と申し上げた。天皇は 2 年前にとあることがきっかけで来朝した百済王族の酒君を呼び出して、鳥を示して「これは何という鳥だ」と尋ねた。酒君は「この鳥の類は百済に多く存在し、馴らすことができれば人によく従い、またはやく飛んでもろもろの鳥を捕ります。百済の人はこの鳥を名づけて『倶知』(くち) と言います」と答えた。
"くち" は他の表記 "久知" もあるがこれは日本独自のものらしい。"倶知" は wiktionary フランス語版に項目があって百済の言葉 (Baekje) となっている。これ以上の語源は不明だが、Alexander Vovin (2013) の From Koguryo to T'amna, Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean p. 227 が出典に挙げられている。
"くち" の名前が百済から伝来されるぐらいであれば、鷹狩文化を学ぶ途上で他のタカの名前も同じように問い合わせたのでないかと考えてしまう。小型のタカが別に存在することに気づいて何と呼ぶのか問い合わせたなどあり得るのではないだろうか。サギの音との関連性も示唆されている (wiktionary) 朝鮮半島言語の sae (鳥) との関係が気になる。この語は "賽" の文字で朝鮮半島で最初に用いられた記録があるとのこと (さい = sae の音対応がある)。ただし漢語の意味は鳥とは異なっていて競争する、競争などの意味 (日本語の賽はこちらの意味に関係する)。
つまり何とか鳥を意味する朝鮮半島言語の語末が "えっさい" に残ったのではないか、との想像である。"えつ" に相当する朝鮮半島言語を知らないので対応するのかよくわからないが。"悦" の文字はハングルでは yeol の音になるとのこと。"悦" の文字の由来もそれほど簡単ではない。興味をお持ちの方の追求に期待したい。
山階鳥類研究所標本データベースでも古く付けられたと思われるラベルでもすでに Accipiter virgatus の学名が付けられており、学名が整理された以降に付けられたものと考えられる。西洋の学問が導入される以前の名称の手がかりは乏しかった (またハイタカ、サシバとの混乱があったこともわかる)。
YIO-09296 (高知県 1905) の標本ラベルがやや興味深く、チゴハヤブサの名称を訂正してエウサイズミとなっている。エウサイズミで1語なのか、エウサイまたはズミの意味なのかは判断が難しいが、"ツミ" の読みは "スミ" (連濁の場合) または "ズミ" だったらしいことが読み取れる。性別はオスと判定されているがラベルの記号は後に追記されたように見える。
またタカ・ハヤブサ類の種類判定は鳥学者にも難しかったらしいこともわかる。
YIO-09301 (高知県 1931) は籾山コレクションで、Accipiter gularis を独立種として扱っているのでかなり新しいと言えるが、ラベルに Essai とあるのでこの時代でもオスのツミを指して Essai と呼ぶのは健在であったことがわかる。
つまり学名は比較的簡単に記せても、むしろ和名を記す方が難しく性別を確認する必要があったわけだ。性別不明の標本に和名が付いていない理由も説明できる。鳥学者も名前を問われても性別がわからないと答えられないのでは不便なので雌雄に統一した種和名を与えるようになっていったのだろう。統一されたのは 1930 年代以降のかなり新しい時代と思われる。
Hartert (1910-1922) p. 1161 では特に問題はなく、Temminck and Schlegel の記載をそのまま引き継いでオス・メスを記述している。この記述は日本の鳥学者も目を通していたはず。
改めて考えてみると、同種かどうかが問題になるのは生物学の進展以降の話ではないかと思った。
我々と同じように雌雄があってそれぞれの役割がある、というのは一部の身近な種では気づかれていただろうが、一般性があることまでは十分認識されていなかったのでは。
現代でも性はなぜ2つなのか議論しなければいけない問題ぐらいでもあり、雌雄同体だったり単為生殖をする生物もあるので、そこまで自明ではなかったのではないかと想像する。ツミでも飼育下繁殖をさせているわけでもなかっただろうし。
中世のヨーロッパはガンは貝から生まれるとか (#コクガン備考)、渡り鳥は冬は別の生物になる、東洋でもワシが犬の子を生むとか、要するにあまりわかっていなかった時代の方が長かったのではないだろうか。
「つみ」と「えっさい」は語源が違うだけで漢字別表記を見る限り事実上同義語で小さい (雀のような) 鷹の意味。おそらく鷹狩りのタカにも、巣から得て素性の明らかなひな以外は外見からいろいろな名前がついていたのではないだろうか (これは西洋でハヤブサに多数の名前があったことからの類推。地元産のものを gentilis と呼べて、これは現在はオオタカの種小名として使われているが、渡りのものを捕獲したものはいろいろな名前があった。#ハヤブサの備考)。
英語の鷹狩り用語でも Peregrine Falcon と Peregrine の用法には使い分けがあって、前者はメスのみを指すのが正しいとされている (ハヤブサの備考 [英名の由来] 参照)、のように鷹狩り用か、あるいは流派などで雌雄の表現の揺れや使い分けがあっても不思議でない感じがする。
巣から採ってきたツミのひなが成長して期待通りでなかった場合はそのまま逃していたのだろうか。
なぜメスしか用いられていなかったのかを考えてみると、ツミ、ハイタカ、オオタカについてはすべて Accipiter 属だった時代の認識もあって3種がすごく似ているように感じがちだが、現代の視点では属 (系統) が違うので得意とする獲物や狩りの手法が (そしてよく知られている通り性格も) 違い、同じ属内で優劣が明瞭だったためと考えれば納得できる。日本では各属が1種のみなので、必然的に体の大きなメスの方が好まれた。
鷹匠は属レベルの性質の違いには気づいていたが、同じ属内で最も優秀なものを選んでいただけで、同種の雌雄かどうかはあまり気にしていなかった可能性もあり、日本にもし同属の2種が存在していたならばオスを使う事例が生じるなど事情が違っていたかも知れない。
現代の鷹狩りなので歴史を考える上で参考にならないかも知れないが、北米ではクーパーハイタカ (Astur 属) はオス・メスともに使われていて鷹匠によって好みが分かれるとのこと。参考 Cooper's Hawk Male vs Female: Differences Every Falconer Should Know (falconryadvice.com)。
北米にはアシボソハイタカ (狭義 Accipiter 属) が生息するが、管理などが難しくあまり用いられていないよう。参考 Sharp-Shinned Hawk For Falconry (falconryadvice.com)。
アシボソハイタカの管理が難しいため、より飼育の容易なクーパーハイタカを用い、オスもメスと異なった技能を買われて使われていると考えることができるかも知れない。
このように考えてみると、江戸時代の数々の鳥類図譜でも外見からは区別できても同種の雌雄である認識は弱かった、あるいは同種判定の必要もなかったのかも知れない。各属に1種しか存在しなかったため鷹狩りでも選択肢がメスに限られたもので、必ずしも雌雄を意識する必要はなかった可能性がある。
西洋から文献が入ってきて対応する和名を決める必要が生じ、複数の和名が存在するが西洋の学問で同種であると判明した場合は、用例も検討して割り振って定義したと考えると自然な感じがする。あるいは皇室に身近な鷹匠に図版のタカの名前を聞いた結果かも知れない。
つまり「つみ」と「えっさい」を同種のメスとオスの名称と "定義" したのは鳥学者だったと言えるかも知れない。
文献主義を採用するならば、確実に存在する雌雄を記述した文献は鳥学者の作った目録なので、ここで定義されたと言えないこともない (そうであればおそらく Temminck and Schlegel の判定由来と言えることになる)。
しかし上述の標本にあるように鳥学者にとってもメスとオスの区別は難しかったようで、和名を1種1つに統一する機運ともなったのかも知れない。鳥学者が手元に標本がなくても海外文献をもとに名称を定義したと考えると納得のできる事例は #センダイムシクイ や #ホウロクシギ などにも見ることができる。いずれも過去にあった名前を活用した可能性もあるが、新たに付けたものかも知れない。
Linnaeus などが過去にあった学名を整理して1つを選んだ過程と同様のものだったかも知れない。Linnaeus の場合は典拠を残しているので出典をたどることができるわけだが、日本の場合は残さない習慣があったのだろうか。
「野の鳥の生態」(下村兼史 1931 初出。「日本野鳥記」1 講談社 1985 収録より) p. 60 にコノリ、エッサイも鷹狩りに使われたことは確かな方に入れられていた。この部分は種名を並べる表記となっていて、ツミとエッサイが同種などは特に触れられていなかった。
ツミとエッサイが同種のメス、オスであることはわかっていたものの、1931 年でも種として統一名を用いずそれぞれ呼び分けていたいたことが読み取れる。当時の標本ラベルの表記とも合致するように見える。
下村氏が紹介されていた海外の鷹狩りについての記述は現在から見ると不自然な部分もあり、必ずしも正確でない伝聞資料をもとに語られていたらしいことがわかる。
-
ハイタカ
- 学名:Accipiter nisus (アクキピテル ニースス) ニースス王のタカ
- 属名:accipiter (m) タカ (accipere 掴む Gk 備考参照)
- 種小名:nisus (m) ニースス (タカの姿に変えられたギリシャ伝説メガラの王の名)
- 英名:Sparrowhawk, IOC: Eurasian Sparrowhawk
- 備考:
accipiter は短母音のみで -ci- がアクセント音節 (アクキピテル)。
nisus は i が長母音 (ニースス)。ギリシャ語 Nisos も同様 (ニーソス)。
日本産あるいは近くの亜種の読みも考察しておくと、nisosimilis は nisus + similis で後者は短母音のみ。nisus の冒頭が長母音であることを考慮すると "ニーソスィミリス" (similis 単独でもアクセント位置は同じ)。
pallens は "パルレーンス"。動詞 palleo (白くする) の分詞形から形容詞に。
accipiter の語源と考えられる accipere の本来の語源は「理解する」(英語の grasp にもこの意味がある)。aci 速い (Gk) pertrum 翼 (Gk) の解釈もあるが、accipere の解釈の方が一般的。
ただし WordSense Dictionary によればインド・ヨーロッパ祖語の *h2ekus (尖った) + *peth2r (翼) とのこと。対応するラテン語で書けば acus + penna となる。-cc- の綴りは accipio (掴む) の影響を受けた可能性があるとのこと。
ラテン語 acutus は英語の acute の語源ともなっており、インド・ヨーロッパ祖語の *ak- (尖った) は多くの語に使われる接頭語とされる (英語の acid 酸など。学名でも acro- は多数ある)。
古ギリシャ語で同様に構成された okupteros (okus 速い pteron 翼 Gk) と類縁とされる (WordSense Dictionary, wiktionary ともに記載がある)。accipere 由来とすると t の音の由来の解釈が難しいのだろう。
対する accipere < accipio の方の語源は ad- (方向を指す) + capio (取る) とされる。
直接関係する英語は accept でタカのような素早い動きは含まれていないよう。
語義を見てゆくと「尖った (または速い) 翼」が「受け取る」の影響を受けてこの綴りになったものと考えるのがもっともらしい気がする。
現在 Accipiter 属に対して提唱されている新分類では日本の種類ではハイタカのみ Accipiter 属となる見通し (#アカハラダカの備考参照)。
これは Accipiter nisus Brisson, 1760 で最初に使われた属名で、ハイタカは新分類の Accipiter 属のタイプ種となる。
種小名の nisus は転じてタカの意味でさまざまな場面で使われる (クマタカ、アオバズクの属名参照)。ハイタカに最も近縁の鳥はアフリカのムネアカハイタカ Accipiter rufiventris でかなり近縁である。
ラテン語の accipiter の読み方は "-ci-" にアクセントがあるそうなので、アクキピテールで "キ" にアクセントを置くとよい。カナ書きで最後の長音にはアクセントは来ない。
アッキピテールの表記でもよいが、アクセント音節の前に子音があるので分離した表記を採用した。
英語の accept が発音できれば、2つめの c を k の音に変えれば accipiter に近い発音になる。
ここではラテン語としての accipiter の読み方を記載しているが、英語の単語としても同じ綴りで使われてこちらの発音は想像されるだろう通り "アクシピター" (アクセント位置はラテン語と同じ) となる。複数で アクシピターズ で英語読みの方が素直な気がする。
おそらく英語圏ではこの学名も同様に英語読みしていると想像できるので学名もラテン語読みにあまりこだわる必要はないかも知れない。
オリオン座 (学名で Orion) を英語でオライオンと読むのと同様、しかしこれもオリオンでも通じるし、
英語以外のヨーロッパ言語ではこちらの読みが普通。属格で用いられることが多く (Orionis、例えばベテルギウスの名称は α Orionis である)、どちらの読み方でもそれほど違和感なく理解されているだろうと想像する。
Accipiter も他の言語圏では事情がおそらく異なっているだろう。
かつてハイタカ、ムネアカハイタカ、マダガスカルハイタカ Accipiter madagascariensis が上種を形成するとの考えがあった [Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World"]。
分子系統解析でムネアカハイタカをハイタカと同種とするぐらいの類似性が確認されたが、マダガスカルハイタカは異なっていることが示され Ferguson-Lees and Christie (2001) の見解は否定された。
ハイタカとムネアカハイタカの類似性については Lerner et al. (2008) Molecular Phylogenetics of the Buteonine Birds of Prey (Accipitridae) も参照。共通のマーカーとなる変異が認められるほどに近縁。
Catanach et al. (2024) の分子系統解析でも調べられたタカ類中最も近縁な組み合わせの一つ。ノスリ類だと同種扱いが議論されるレベル。
[亜種]
ユーラシアに広く分布し、7亜種が認められている (IOC)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で日本の亜種は nisosimilis (ヨーロッパの基亜種 nisus に similis 似た)この亜種は中央から東シベリア、カムチャツカ、日本から中国北部で繁殖する。
カムチャツカの個体群にはかつて亜種 pallens (淡い色の) が与えられていたが、現在は nisosimilis のシノニムとされる。この亜種は完全に渡りをすると考えられ、パキスタン、インドから東南アジア、中国南部、朝鮮半島から日本で越冬し、一部はアフリカまで渡るとされている (wikipedia 英語版)。
過去は多数の亜種が記載されており、Avibase に載っている範囲でも 基亜種 nisus に4亜種が統合、granti に1亜種が統合などヨーロッパを中心に統合が進んだ。
nisosimilis は nisus に似ていると名付けられたもので、その程度ならば同亜種でよいのではとの見解もあってもおかしくない。
記載時学名は Falco Nisosimilis Tickell, 1833 (記載) Jungle Sparrow-Hawk。基産地は Marcha, Borabhum, India。
ユーラシアの東西あるいは南北でどの程度違うのか、また分けるとすれば境界はどこかの問題になる。
分化が進んでいると想像できるカムチャツカがユーラシア大陸東部と同亜種にまとめられるならばもっと広範に亜種統合があるかも知れない。
現在は広義 Accipiter 属の分割が終わった程度の時点だが今後はハイタカの分子系統研究が出てくるかも。#オオタカの Kunz et al. (2019) の分子系統研究も参照。旧北区のオオタカで連続した遺伝的分布を示している兆候がある。
狭義 Accipiter 属の分岐年代と分布をみるとアフリカ起源で主に熱帯で種分化したが最後にムネアカハイタカとハイタカが分岐して一方はアフリカに分布、一方は北に広く分布を広げたことがわかる。この状況は#ホトトギスや#カッコウに似ており、カッコウの北方型が現在では1亜種にまとめられたことを考えると同様になるかも知れない。
なおカッコウの分布がハイタカと似ているのは偶然ではなく擬態に関係するかも知れない (#ホトトギスの考察参照)。
ハイタカの一部がアフリカまで渡るのであればカッコウに一層似ている。
狭義 Accipiter 属全体を見るとハイタカは広域分散能力を高めたと思われ、そしてほとんど同種に近いぐらいの種類がアフリカに存在する (つまり種ハイタカ内部の遺伝的違いがさほど大きくないことも示唆する)。ハイタカを細かく亜種分割する必要性をあまり感じなくなってしまった。
分子遺伝学解析に期待だが、北方型は全部亜種 nisus でよいのかも。そうなれば複雑な考察も必要なくなって覚えやすくなりそう。ハイタカは種としてはかなり一様で、日本から見た "大陸型" の色の違いは微妙な色彩遺伝子頻度の違い程度で本質的なものではない、など。
Avibase でわかる範囲の亜種記載を見ておくと (記載時学名で表示)、
・Falco Nisus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761 ヨーロッパから Linnaeus 自身によってスウェーデンに限定
・Falco Nisosimilis Tickell, 1833 (原記載) 基産地 Marcha, Borabhum, India
・Accipiter Melaschistos Hume, 1869 基産地 Interior of the Himalayas
・Accipiter Granti Sharpe, 1890 (原記載) 基産地 Madeira (ポルトガル領マデイラ諸島)
・Accipiter pallens Stejneger, 1893 基産地 Hitachi, Japan = nisosimilis
・Accipiter nisus punicus Erlanger, 1897 (原記載) 基産地 Ain-bou-Dries, Tunisia (チュニジア)
・Accipiter wolterstorffi Kleinschmidt, 1901 (原記載) 基産地 Lanusei, Sardinia (イタリアのサルデーニャ島)
・Accipiter nisus teneriffae Laubmann, 1912 基産地 Vilaflor, Tenerife (スペイン領カナリア諸島) = granti
・Accipiter nisus peregrinoides Kleinschmidt, 1921 基産地 Rossiten, East Prussia. Migrant = nisus
・Accipiter nisus hibernicus Swann, 1924 基産地 Hillsborough, Ireland = nisus
・optimi Kleinschmidt, 1940 = nisus
・Accipiter nisus Salamancae Jordans & Steinbacher, 1941 基産地 Linares de Riofrio, Salamanca, Spain = nisus
・Accipiter nisus dementjevi Stepanyan, 1958 基産地 Issyk-Kul and Fergana, Asia
= の後は現在の一般的取り扱いではこの亜種の先行シノニムとなっているもの。
この表を見るとわかるように、ヨーロッパでは離島とアフリカに分布するものを除いて nisus にまとめられた。中央アジアのものはよくわからないので特にとりまとめずそのまま残されているのだろう。
亜種 punicus はムネアカハイタカとの関係からも興味深い。アルジェリアのハイタカで検索すると Eurasian Sparrowhawk (khaled Ayyach 2018.5.5) のような下面の赤い個体があり、ムネアカハイタカの色彩に近い (アルジェリアはムネアカハイタカの通常の分布域には含まれていない)。
このように見るとハイタカとムネアカハイタカは実質的にはほとんど同種で、色彩を決める遺伝部位が主に違っているだけのようにも思えてくる。
ムネアカハイタカとハイタカの祖先形はアフリカに住んでいて、かつては地理的障壁が少なかったが、サハラ砂漠の拡大で地理的隔離が起きてそれぞれ進化したが、ハイタカの遺伝子プール中にもムネアカハイタカの色彩タイプが含まれていて、時折見られる赤みの強い個体はムネアカハイタカに近い色彩遺伝子を持っているなど。
さらにカッコウが擬態しているならばカッコウの赤色型頻度の地理的違いもハイタカの色彩遺伝子頻度に関係があるかも知れないとふと思ったりした。
赤みの強い色彩遺伝子は北方林では不利で次第に頻度が下がって行ったなども考えられるが、環境によっては有利にも働く可能性があるのでこの色彩型が残っている、またそのような遺伝子頻度がユーラシアからアフリカにかけて異なり、極東や北方ほど白いものが多くて西や南に行くほど赤みの強い遺伝子頻度が増えるなど想像できる (極東から見ているのでこの部分は進化や分布拡大経路を遡った表現になっている)。
一部のハイタカの越冬地とムネアカハイタカの生息地には重複があり、長距離の渡りを行うハイタカの中には祖先の生息地にまだ固執しているのかも知れない (長距離の渡りを行う種ほど祖先の生息地に固執する傾向が知られている)。
Movebank のデータによればバイカル地方のハイタカの追跡が行われたようなので (まだ非公開) ユーラシア東部地域の渡り経路がそのうち発表されるかも。ハイタカの追跡事例は思ったほど多くなかった。
このような観点から見ると pallens の位置づけなどは議論するほど重要な問題ではないかも知れない。日本を基産地とする亜種記載で、しかもかなり古いので他亜種のシノニムになりにくい点で貴重ではあるが。
単に Sparrowhawk と言えばこの種を指すことに誰も疑念を持たないだろうが、他にも Sparrowhawk の名前を持つ種類が複数あるため、学術的な文脈では Eurasian Sparrowhawk を使うのが望ましいであろう。
なおアメリカチョウゲンボウ Falco sparverius (英名 American Kestrel) を指して "sparrow hawk" と呼ぶこともある。いずれもスズメのような小型種の意味に由来している。アメリカへの入植者がアメリカチョウゲンボウをハイタカと誤認していたためとの解釈もある。
ハイタカはロシア語名では perepelyatnik で「ウズラを食べるもの」。ウクライナ語では malij yastreb で「小さなタカ」であるが、両国でどちらの表現も通じるようである。ドイツ語 Sperber もスズメに由来し、他のヨーロッパ言語の多くで同様。
叶内 (2003) Birder 17(10): 20 は対馬の春の渡りで朝鮮半島から渡ってくるハイタカに赤みが強いものがいて、ヨーロッパタイプの可能性を検討している。国内の冬期の写真でも赤みの強いものがいて「ハイタカ大陸型?」と記している。
赤 (2003) Birder 17(4): 60-61 にハイタカのメスの赤色タイプとも呼べる個体をスケッチしている。オスを大きくしたような感じで胸の縞模様は羽の外縁が茶褐色とのこと。
[ロシアの個体について]
三島 (1960) ハイイロハイタカについて があった。この亜種の記載地は日本なので、亜種を認めるならば当然日本産亜種となる。Dement'ev and Gladkov (1951) によればカムチャツカのハイタカは非常にまれであまり記録がないとある。
日本ではハイタカはまれで (nisosimilis は珍しくないとある) 鷹匠が高く評価しているとある。標本が非常に少ないので亜種に値するかは確認が必要で、nisosimilis の個体変異の大きいものに過ぎないかも知れないとある。
日本で記録された pallens とカムチャツカの繁殖個体が同じ亜種とする扱いも推測に過ぎず、Lobkov (1986) の "カムチャツカで繁殖する鳥" を見てもほとんど情報がない。Gerasimov (2018) のカムチャツカのレッドデータブックにも載っておらず情報がほとんどない。
Lobkov (1986b, 2013 再掲) Kamchatka as a center of taxa formation in birds (pp. 2128-2129) によれば多数の種にカムチャツカ亜種があり、種分化 (白い亜種) の分化の中心地ではないかとの考え。
カムチャツカのハイタカにも言及があり亜種に値するか議論があることが述べられている。オオタカもシロハヤブサもカムチャツカのものが最も淡色である。
近年のカムチャツカでは
Common Sparrowhawk (Pogodina 2021.12.12) もしかして飼育個体? との質問があり、3 m の距離で窓を通して撮ったものとのこと。小鳥の水場があるとのこと。
確かに北ほど白っぽい傾向があるかも知れない。
Common Sparrowhawk (Kovaleva 2021.11.16)、
Common Sparrowhawk (Ivushkin 2021.9.10)
の3例の写真が出ていた。まれではあるが見られているよう。
カムチャツカ以外で日本の北方に位置する地域の写真では、マガダン周辺で、
Common Sparrowhawk (Petrunina 2019.8.17 オオタカとの識別が問題となっていたよう)、
Common Sparrowhawk (Basik 2024.6.10)、
Common Sparrowhawk (Petrunina 2019.8.22 これもオオタカとの識別が問題となっていたようだが小さかったとのこと)
の3例がある。
択捉島の写真で Common Sparrowhawk (Barkanova 2020.4.30)、
サハリン (通常は nisosimilis の分布域とされる) の写真で Common Sparrowhawk (Korobov 2019.9.6 飛翔中で上面が見える)、
Common Sparrowhawk (Korobov 2019.9.11)。ゴジュウカラを掴んで飛翔中。結構色が濃く褐色味も目立つ。
Common Sparrowhawk (Bobkov 2024.7.3 とまっている姿。これもオオタカとの識別が問題となっていた)、
Common Sparrowhawk (Shukov 2022.6.1 とまっている姿)、
Common Sparrowhawk (Parkhaev 2021.6.17 飛翔中下面)。
大陸の写真も同サイトから見られるので興味ある方は参照してみていただきたい。例を1つ挙げておく。
Common Sparrowhawk (Dugitsov 2021.2.7)。気温 -29 ℃ とのこと。5階建て建物の中庭での出来事で最初の2枚は 7-8 m の距離からとのこと。
沿海地方で繁殖するハイタカについては 極東の鳥類 42: 沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で翻訳を読むことができる。
最初に繁殖が確認されたのは 1950 年代だったが、21 世紀に入って数が増え、現在では広く繁殖する種になっている。
[ロシアのハイタカ子育てのドキュメンタリー]
ロシア関係なのでこちらに関連して含めておく。ロシアのシベリア中央部オムスク地域のハイタカ子育てのドキュメンタリー Bespokojnoe leto v Grankinom lesu "鳥の国" というロシアの TV 番組 (シリーズを製作者が公開されているのでそれに字幕を入れたものと想像できる)。字幕も表示できるので翻訳を選択すればある程度内容がわかるだろう。巣での映像はハイタカ。取り扱われている猛禽類は他にヨーロッパノスリ (だと思う)。
音声と飛行映像を合成しているのでストーリーは作為的なところがあり、ちょっと誤解を生みそう。
最初6羽いたひなが2羽まで減少。強い嵐で巣が落ちてしまった。1羽のひなを地面で発見。最も小さいひなだけが残った。大きいひなは大きくてよりおいしいので先に捕食されてしまい、真新しい捕食痕が残っているとの説明。
人工の巣に入れて持ち帰り育てることにした。まだ未熟な段階で野外放鳥まで記録されて終了となっているが大丈夫なのだろうか...。若い鳥ののどにこれほど赤い部分があるのは初めて知った。
しかし他の小鳥の繁殖映像も見られるので種類判定なども含めて楽しんでいただけそう。
[狭義 Accipiter (ハイタカ) 属の系統分類]
順序は Catanach et al. (2024) による。
亜科相当 (ハイタカグループ)
ハイタカ属 Accipiter
セグロオオタカ* Accipiter poliogaster Grey-bellied Hawk (Dinospizias 属とする分類学者もある)
サバンナハイタカ* [高野 (1973) ではオバンポハイタカ] Accipiter ovampensis Ovambo Sparrowhawk
マダガスカルハイタカ* Accipiter madagascariensis Madagascar Sparrowhawk
アシボソハイタカ Accipiter striatus Sharp-shinned Hawk (学名が変わる可能性は解説参照)
ムナジロアシボソハイタカ(*) Accipiter chionogaster White-breasted Hawk
フナシアシボソハイタカ(*) Accipiter ventralis Plain-breasted Hawk
モモアカアシボソハイタカ(*) Accipiter erythronemius Rufous-thighed Hawk
ムネアカハイタカ* [高野 (1973) ではアカムネハイタカ] Accipiter rufiventris Rufous-breasted Sparrowhawk
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk
系統が少し離れるところに空行を入れてあるが、いずれも深い分岐ではなく、オオタカ属 Astur ほどの違いはない。
Gaudin "List of the birds of the world" ではセグロオオタカを Dinospizias 属 (deinos 恐ろしい spizias タカ Gk) としている。Catanach et al. (2024) 以前の研究によるものだが単独系統ともできる点は新しい研究とも整合している。
セグロオオタカは南米の種で、北米のアシボソハイタカと系統関係がない点でも狭義 Accipiter 属と異なった進化過程を示唆する。生物地理学を考慮して将来属名が変わるかも知れない。
Catanach et al. (2021) Systematics and conservation of an endemic radiation of Accipiter hawks in the Caribbean islands
に核 DNA の UCE 領域も用いたカリブ海周辺の Accipiter属の分子系統研究がある:
アシボソハイタカ Accipiter striatus の Vieillot (1807) による原記載は1標本のみによるもので、Hispaniola (イスパニョーラ島) 西部 (現在のハイチ) で得られたもの。色彩の記述から大陸のアシボソハイタカが渡ってきたものではなく現地の留鳥であることが明らかであり、アシボソハイタカの記載としてもふさわしくない。
カリブ海の島に多数の固有種の存在を明らかにした。
正しい大陸のアシボソハイタカの記載であり分子系統や先取権もふまえて Accipiter velox (Wilson, 1812) とするのがふさわしいとのこと。
ムナジロアシボソハイタカ、フナシアシボソハイタカ、モモアカアシボソハイタカはおそらくこの研究もふまえてアシボソハイタカから分離されたもので IOC 13.2 に従った分類とした。
アシボソハイタカからさらに亜種 venator Puerto Rican Hawk、 fringilloides Cuban Hawk、striatus Hispaniolan Hawk を分離することも提案されている。
Catanach et al. (2021) ではアシボソハイタカグループの分布が広く、中央アメリカや南アメリカの個体群の解析がまだ行えていないのでこれらはまだ Accipiter velox の亜種としておくのがよいとの記述で、明瞭にアシボソハイタカの学名改訂を提案している。
これら3分類群を種として扱っているリストがまだないためここでは分離していない。
英名は Boyd による (このあたりを読むと見たことも聞いたこともない学名や英名が並んでいて間違ったところを見ているのかと思うぐらいだが、将来はこれが標準になるかも知れない)。
Catanach et al. (2024) ではこれらは分離して扱われていないので (種を分割することが目的の論文ではないので) アシボソハイタカの後に暫定的に配置した。
アシボソハイタカのように日本でも有名な種類の分類がすでにかなり変わっていて、将来的にさらに変わってアシボソハイタカの学名も変わる可能性が予想される。島の固有種を分離するのは抵抗が少ない上、保全上も有益であるが、アシボソハイタカのように有名な種の学名が変わると影響が大きいので各リストでまだ慎重に判断されているところであろう。
AviList (2025.6) ではこれらを分離せず、学名もそのままと判断された。まだ分子遺伝学的研究が不十分との考え。
8374 358 Accipiter striatus is treated as a single species based on available data; sometimes treated as four species (monotypic A. erythronemius, A. ventralis, and A. chionogaster, and polytypic A. striatus). Genomic and mitochondrial DNA data consistently identify erythronemius as the most divergent lineage (Breman et al. 2013; Oatley et al. 2015; Mindell et al. 2018; Catanach et al. 2021), but a comprehensive genetic review of all taxa is needed to better define species limits in this group.
前述のようにムネアカハイタカ (アフリカに離散的に分布) とハイタカは同種にして構わないぐらい近い。この2種は並列になって系統樹では順序には意味がないが分散の順序を考えるとハイタカを後に置くのが適切に見える。この2種の関係はムネアカハイタカは名前の通り下面の赤色が特徴で、同じ関係は新大陸のいくつかの留鳥の熱帯種が下面の赤色が特徴的である点と対応している (Bildstein 2004)。
[他の事例については Astur 属または Cooperastur 属の クーパーハイタカ Astur cooperii Cooper's Hawk と ズグロハイタカ Astur gundlachi Gundlach's Hawk の関係、
狭義 Accipiter 属のアシボソハイタカと熱帯種との関係
(#アカハラダカの備考 [渡り] 参照) がある]。
北方森林に生息する場合は目立った色彩がない方が隠蔽色になるのだろうか。
アフリカ熱帯に生息するオナガオオタカ Urotriorchis macrourus Long-tailed Hawk もとても派手な色彩の鳥で、参考 Long-tailed Hawk (Bradley Hacker 2021)。Long-tailed Hawk (Daniel Lopez-Velasco 2021)。
Accipitrinae 亜科 はもともとこのような色彩を出しやすい系統で、北方のハイタカやオオタカで二次的に白っぽくなったと考えるのが妥当そうに思える。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 115 p. 3 によれば暗くなってから高速で飛行し、小鳥の不意を突いてつめで捉えるとのこと。いかにも見てきたように書かれているが、Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" によれば生態はあまりよくわかっていないらしい。
Accipitrinae 亜科にしては足が短いが (足はハチクマに少し似ている)、ハイタカの長い足も、もとはこのような形態であったものが、飛翔中の小鳥食に特化するために進化したものかも。オナガオオタカのような鳥を見るとハチクマの祖先時代はこのような生活様式だったのかも知れないと感じてしまう次第。
このグループでは前述のようにセグロオオタカ (熱帯南アメリカ) の位置が従来系統樹とやや異なる結果になった。残りの種は過去の分類でも近い位置に置かれていた。
サバンナハイタカとマダガスカルハイタカもクレードを作る。この2種の順序には意味がない。
マダガスカルハイタカは IOC では単形種。wikipedia 英語版では雌雄の色のパターンの違いで3亜種が知られていて、このうち Sensu Palmer Sparrowhawk は 1972 年に絶滅したとあるが対応する情報は見つけられなかった。
アシボソハイタカはよく知られた北米の種。
セグロオオタカの poliogaster は polios 灰色 gaster, gastros 腹 (Gk)。
サバンナハイタカの ovampensis はアンゴラの Ovampo/Ovambo 川から (The Key to Scientific Names)。wikipedia 英語版では現在ナミビアに含まれる Ovamboland とある。
英名からは地域限定の種類のようにも感じるが実際はアフリカにもっと広く分布している。
アシボソハイタカの striatus は線条のある。
ムネアカハイタカの rufiventris は rufus 赤っぽい venter, ventris 腹。
この結果を見ると狭義ハイタカ属はそこまで北方型ではなく、やや高緯度に分布を広げているが基本は中緯度系の系統と言ってよさそうである。低緯度は比較的少ない。
ハイタカとムネアカハイタカが非常に近縁であることは、例えばかつて分布が連続していたか、熱帯の留鳥が北方に分布を広げたかまたはその逆の過程が考えられる。ムネアカハイタカの分布が限られているので、かつて分布が連続していたもののハイタカがあまり得意としない熱帯地域の分布が競争で消滅した可能性もありそうに思える。
ムネアカハイタカの各地域個体群もよく調べればアシボソハイタカのもと亜種や現在の亜種のように種相当のものがあるかも知れない。今後の研究が待たれる。
狭義ハイタカ属は大陸ごとに主なものが1種ある感じと捉えてよい (これは単系統であることの現れでもある)。アフリカを代表する狭義ハイタカ属はサバンナハイタカとなるだろうか。他の種類は島に定着して進化した固有種と見ることができる。
Tachyspiza 属ほど細かな生態的地位に適応した種分化を遂げていないようだが、これは Tachyspiza 属の方がより熱帯に適応しているようかつ小型種が多いためのように思える。
Tachyspiza 属はクラッチサイズが3程度のものが多く、より大型の狭義 Accipiter 属の方がむしろ大きめ (3-4が普通でもっと多いこともある)。これは温帯で生き残る厳しさを表しているのだろうか、あるいは生活史戦略の違いであろうか。
ハイタカ属の分類見直しによって Tachyspiza 属と混ざっていた従来の「ハイタカ観」も少し変える必要がありそうである。
大陸ごとに主なものが1種ある状況は Astur 属でも同様で、日本産に関係する属では Tachyspiza 属、狭義 Accipiter 属、Astur 属の3系統がそれぞれの属に適した少しずつ違う環境に適応してそれぞれ世界分布したと考えてよいだろう。
#ハイイロチュウヒ備考の [渡りをするタカ類の系統] も参照。
[日本と北米の広義ハイタカ属比較]
東條 (1991) 日本の生物 5(3): 30-31 で「ハイタカ属3種入門」の一環として「日本産3種と北米産3種」の記事がある。繁殖する広義ハイタカ属で日本産3種は雌雄のサイズの違いを含めて6段階あるが、日本ではツミのメスとハイタカのオスのサイズが近く、ほぼ5段階になっているとのこと。
新しい分子系統分類による学名を用いて検討してみる。
| 日本 | 学名 | | 北米 | 学名 (系統) |
| ツミ | Tachyspiza gularis | | アシボソハイタカ | Accipiter striatus |
| ハイタカ | Accipiter nisus | | クーパーハイタカ | Astur cooperii (系統 1) |
| オオタカ | Astur gentilis | | アメリカオオタカ | Astur atricapillus (系統 2) |
このように日本産3種は新分類ではすべて別属になり起源や系統が異なることがわかる。体型や好む生態的環境などもそれに応じて差があるため (南方起源で主にアジアのグループ Tachyspiza 属) ツミのメスと (北方森林に適応 Accipiter 属) ハイタカのオスの間にサイズから期待されるほどの競争が生じず共存可能なのかも知れない。
北米も Accipiter あるいは Astur 属内部の2系統となり、3回にわたる導入があったことがわかる。最も新しく入った系統が北方森林起源のアメリカオオタカとなる。
Astur 属の系統 1 (クーパーハイタカを含む) は南米熱帯林にも分布するように北方型というわけではない。
アフリカ起源と考えられる ツミ?/アカハラダカ?/アフリカオオタカ?族 Aerospizini (Tachyspiza 属も含む) が新大陸のニッチを占めなかったため Astur属の系統 1 が代わって対応する位置を占め、北方森林起源かつ競争種の多いユーラシアで選抜されたアメリカオオタカがさらに入る余地があったと解釈すればわかりやすく思える。
狭義 Accipiter 属は空いているはずの新大陸ではあまり種分化を遂げなかったようで何か理由があるのだろう。この属の古い系統であるセグロオオタカが南米の珍しい種類であるように、環境など何かが向いていなかったのだろうか。このような狭義 Accipiter 属の新大陸での挙動もユーラシアのハイタカの特性を理解する上で役立つだろう。
ホオジロ類の系統から新大陸のさまざまな小鳥が生まれたと同様、広義ハイタカ属でも Astur 属が新世界で主な系統となっている。ホオジロ類とは違ってそれほど多数の系統に分化したわけではないので Astur 属に自然にまとめられ、ホオジロ類ほど悩ましい状態にはなっていない。
このように系統を反映した属学名を用いると話がわかりやすくなる場合も多い。広義 Accipiter 属ではいろいろなものが混ざってしまっているので属レベルで地理的分布などを概観することが難しい。
IOC などで新しい分類を早く導入してもらって (14.2 で導入されるのことになった) wikipedia などにも反映してもらえばこのような点も調べやすくなるだろう (2024年8月に反映され調べやすくなった)。
Northern hawk-owl (オナガフクロウ、Surnia ulula) の wikipedia 英語版によれば姿や行動がタカに似ており、飛翔形もクーパーハイタカに似ていて昼行性捕食者として北米でタカのニッチを占めている考えが紹介されている。
Sonerud (1992) Search tactics of a pause-travel predator: adaptive adjustments of perching times and move distances by hawk owls (Surnia ulula) が出典。
下面もハイタカに似た模様になっている。
北米の広義ハイタカ属の上記分析を見ると北米では小型タカ類の系統がユーラシアに比べて不足しているためかも知れない。
「世界の鳥 1」(小学館 1985) p. 136 によればハイタカに似た声でキッキッキッと鳴き、夜も昼も狩りをする。寒帯に住み夏はネズミやレミングなど、冬は鳥を捕獲することが多いとあった。姿も声もタカに似ているとなると、偶然ではなくカッコウのタカへの擬態で提唱されているように何か役立つのかも知れない。
なお英語で Hawk Owl と言えばオナガフクロウを指した (あるいは指す)。#アオバズクの備考参照。古くはタカ類とフクロウ類は連続したもので中間型とみなされていたらしい。生態や進化を考える上でも面白い。
そのように思って調べてみるとオナガフクロウは単形属 Surnia をなし、近縁の Glaucidium 属との分岐年代は 4800 万年前程度 (timetree.org) とかなり古い。出典は Roquet et al. (2014) One tree to link them all: a phylogenetic dataset for the European tetrapoda とのこと。
年代はあまり精度良く定まっていないようだが、かなり古くから存在していた系統で、Accipiter や Astur 属の出現 (2300 万年前程度) 以前にタカ類の地位を占めて昼にも狩りをしていたが、昼行性のタカ類が分布を広げるのに合わせて北方にのみに分布を消退させたのかも知れない。Tachyspiza 属はそれほど北に分布を広げなかったので主な競争相手はハイタカとオオタカ類であったと想像できる。
オナガフクロウはタカ類の位置を占めていた昼行性のフクロウだったものが次第に北方に限定されるようになった遺存的系統と言えるのかも知れない。現在冬に鳥を捕食するのは、高緯度では冬には鳥か哺乳類しか食物となる動物が活動していない必然的な部分もあるだろう。
後から進出してきたハイタカに似せることで一定の利益を得ているかも知れない。フクロウ類の進化を読むにもタカ類の知識は欠かせないのだろう。
また、同様に Hawk-Owl の名称の付く別系統の Ninox 属も分岐は古く、あるいは同じような説明が可能なのかも知れない。あまりフクロウ類らしくない顔つき、聴覚による音源定位よりむしろ視覚を用いているらしいことなどかつてはタカのような昼行性捕食者であった時代の名残りなのかも知れない。
[渡り中のハイタカ・アシボソハイタカの食性]
DNA バーコディングを用いたアシボソハイタカの食性解析: Bourbour et al. (2019) Messy eaters: Swabbing prey DNA from the exterior of inconspicuous predators when foraging cannot be observed。
表を見ていただくとどんな鳥を食べているかわかって興味深いだろう。
Belik (2024) The food of migratory sparrowhawks Accipiter nisus in desert areas of the Ural-Emba interfluve (North-Eastern Caspian region) (pp. 3935-3939)
こちらはカスピ海北東にあたる砂漠地帯で渡り中のハイタカが何を食べているか。渡り途中の小鳥を主に捕えているようでトップはウタツグミ。他は表の学名を参照していただけば判断できるであろう。
朝から夕方まで狩りをするとのことで日没後にキクイタダキを捕えた事例も出ている。
これはどこかに書いてあるような気がするが、広義ハイタカ属、特にハイタカやツミの渡りは小鳥の渡りと相関しているように思える。サシバ・ハチクマはむしろ天候や風向きで決まるだろうが、広義ハイタカ属では小鳥が大きく動いた時のの目撃例が多いと感じる。特に都市部ではアトリ類やホオジロ類、そしてツグミ類がやってくるピークに合わせて現れている感じがする。
渡りの小鳥を追いかけて渡っているのでは? 小鳥が大きくのは寒冷前線の通過する時なので広義ハイタカ属でも天候や風向きとの相関が見られると予想できるが小鳥の渡りの方が主要因か。
広義ハイタカ属の渡り時期が遅いのは繁殖地で食物が遅くまで得られることもあるだろうが、渡り中の食物量も関係しているかも。
赤塚 (1996) Birder 10(11): 66-71 で伊良湖岬での観察からツミやハイタカは小鳥類にくっついて移動をくり返しているのではとの考察があった。
上記 Bourbour et al. (2019) の後続研究となるが、Bourbour et al. (2024) Feeding en route: Prey availability and traits influence prey selection by an avian predator on migration
によればアシボソハイタカの爪付着物の DNA 解析と eBird の記録情報から秋の渡りでは最も多く消費される種の渡り時期とよく合っているとのこと。またオス・メスによる食物の違いも見つかり、逆性的サイズ二形が食物選択に反映されていることも明らかになった。北米では eBird の記録情報が豊富なので小鳥の渡りとの相関を調べることが可能のよう。
概ね自分の考えていた通りで納得しやすい結果。
Padro (2024) Integrating eDNA metabarcoding and citizen science enhances avian ecological research
上記論文の解説。逆性的サイズ二形の存在のため渡り中に雌雄で異なった採食戦略をとることができる (渡り観察をされている方の結果では雌雄の渡りの違いなど現れていますでしょうか)。eDNA と市民科学を組み合わせることで移動能力の大きい種類の採食生態研究に役立つ。
渡り関係でどこに入れてもよい話だがここに紹介。深層学習による天気予報が従来の物理学モデルベースの予報を超えつつある: DeepMind AI weather forecaster beats world-class system (Nature news 2024.12.4)
現代では複数の企業が天気予報を競っているとのこと。挙げられている例が Huawei (中国)、Nvidia (アメリカ)、Google も 2024 年に NeuralGCM (物理モデル + AI のハイブリッド) を発表したとのこと。
新しく発表された GenCast [Price et al. (2024) Probabilistic weather forecasting with machine learning] は 12 時間おきの 0.25° のメッシュの天気予報を 8 分で行えるとのこと。
現在の世界最高度の中期予報の ENS (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) の精度を上回ったとのこと。
今後もさらに進化して従来の天気予報を置き換えてしまうかも? - さらに考えると物理モデルによらず機械学習で天気予報ができるならば、天気の読みが生死にかかわる渡り鳥が類似の類似の気象予測システムを進化させていても不思議でないかも知れない。
局地的な豪雨や台風発生などは予想困難かも知れないが、秋の渡り時期の寒冷前線のタイミングのような規則性のある中規模スケールならばかなり予測できるのでは。局所的な気象現象を動物が予知していないからと言っても、別のスケールの気象現象も予測できない理由にはならないと思う (この部分は想像をたくましく)。
[ハイタカの急降下による捕食行動]
若杉氏が ため池上空でハイタカが高空から急降下し小鳥を捕った で興味深い観察記録を紹介されているので考察してみたい。
身を隠す場所から不意打ちのように攻撃する方法が使えない、開けた場所で獲物に気づかれないように上空から降下する戦術は十分効果があるのだろう。
上空から降下する場合にどのぐらいの高さが適当か考えてみた。空気抵抗のない完全な自由落下であれば時間 t での移動距離は h = g * t^2/2 となる (g は重力加速度)。速度は g * t。抵抗がある場合は終端速度が上限となるので、この値は理論的上限値のように見ていただくとよい。
h = 400 m とすると t = 9.0 s で速度は 88 m/s (319 km/s でさすがにそこまで速くならないだろう)。
h = 1000 m とすると t = 14.3 s 速度は 140 m/s。
#シロハヤブサ備考の [シロハヤブサの急降下速度] を参照すると数値的には似ているが定速度の時間はシロハヤブサの研究例では短時間 (数秒以内) しか続かない。そのまま激突すると自分も死んでしまうので減速期間が必要である。逆向きの重力加速度に相当する減速を加えれば時間がどのように伸びるかなどいかにも数学の演習問題なので試みていただきたい。
シロハヤブサでも最大 500 m 上空から急降下とのことで値は似ている。
この高度から獲物が見えているのか検討してみると、1000 m の距離から 15 cm のものが 30" の大きさになるのでヒトの視力 2.0 に相当する分解能の限界となる。1000 m より高いと獲物が多分見えないのでこの高さが実質的上限となると考えられる。若杉氏の観察結果とよく合っている印象を受ける。
狙われる小鳥の方から見ると、真正面に向かうと翼は広がって見えないので体の断面積程度と考えると視力 1.0 (小鳥の視力上限として推定) ではその方向を注視している最もよい条件でもおそらく 150 m ぐらいまで接近しないと気づかないだろう [この部分を記述してから赤塚 (1996) Birder 10(11): 66-71。該当記述は p. 71 に同様の考察があることを知った]。
400 m で狩りに失敗したのは例えば正面方向を向いていない時は小鳥からタカの姿がずっと見えていて動きを追跡できていたのかも知れない。高い位置からだと遠方から獲物に対して真正面に近い角度を保つことができて見つからずに接近することができると思われる。
シロハヤブサの最高速度 52-58 m/s を想定すると、気づいてから逃げるまで 2-3 秒の余裕しかなく、気づくのに少し遅れると捕食されるかも知れない。これはもちろん理論的上限値で実際にはもう少し余裕があると考えられる。
この解釈にも少し問題が残り、鳥の正面視力 (lateral fovea 側方窩 または temporal fovea 側頭窩を用いる) は一般的に斜め前方の側面視 (central fovea 中心窩) に劣るため、真正面に見据えると最大視力が発揮できない可能性がある。
#シロハヤブサ備考で紹介の Tucker (2000) Gliding flight: drag and torque of a hawk and a falcon with straight and turned heads, and a lower value for the parasite drag coefficient
ではそのためハヤブサ類は分解能の高い斜め前方の側面視で獲物を追跡するためらせんを描くような軌跡となると説明している (なお後の研究でそうではないらしいことがわかった)。
しかしこの場合は斜め方向になるので獲物からは体がより大きく見えて気づかれやすくなる可能性がある。
ハイタカが真正面を見据えて獲物に接近するならば、例えばハイタカの正面視力はハヤブサ類より高い、あるいは眼球を動かせる範囲が広くて真正面を向いたまま解像度の高い領域で獲物を見ることができるのかも知れない。
#イヌワシ備考の [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] で紹介の Plochocki et al. (2018) Extraocular muscle architecture in hawks and owls や
Potier et al. (2020) Visual adaptations of diurnal and nocturnal raptors のようにタカでは眼球をかなり動かすことができるようで正面でもよく見えているのかも知れない。
ただし正面の像を結ぶのはやはり temporal fovea 側頭窩と解釈されている。
アカヒメクマタカ [高野 (1973) ではヒメアカクマタカ] Hieraaetus morphnoides Little Eagle の眼球が 24° 動かせるとの報告は少し古いが Wallman and Pettigrew (1985) Conjugate and disjunctive saccades in two avian species with contrasting oculomotor strategies (オープンアクセス) が出典で図から可動範囲を読み取れる次第。
ただしこの研究はサッケード運動における眼球の動きを記録したもので正面で獲物を狙う状況までは再現できていないかも知れない (しかしタカの眼球の動きはヒトの場合と似ている印象を受ける)。
正面を向いていても両眼視の視野が重なっている程度で両眼球の視野中心を真正面に向けているわけではない点はフクロウ類と異なるとのこと。temporal fovea は central fovea に比べてずっと浅いが、central fovea の限られた部分のみ最高の解像度を維持しつつ飛ぶのではなく、立体視はある程度犠牲にしつつ両眼である程度広い範囲をカバーした方が飛びながら獲物を追跡する場合は役立つのかも知れない。
遠方から獲物を発見するのに役立つだろう central fovea から temporal fovea に視線を移動する際に視力があまりよくないギャップが生じる可能性も考えられる。
このような生理学や解剖学も念頭に置いて考察しつつ観察・記録されると面白いだろう。
この部分を記述してから気づいた#トビ備考 [トビの獲物攻撃速度] にある Santer et al. (2012) Predator versus Prey: Locust Looming-Detector Neuron and Behavioural Responses to Stimuli Representing Attacking Bird Predators
の議論を獲物となる小鳥の側にも適用できるような気がした。迫ってくる物体は外敵や衝突の可能性があるのでバッタに限らず逃避反応がいかにも起きそう。物体が猛禽かどうかも必ずしも見分ける必要はなく反射的なものだろう。視覚系を持つ動物ならばいずれにも備わってそう。
この論文では l/|v| という指標 (looming disc の概念として図で示されている) を用いている。"物が迫ってくる" ように見えるタイムスケールに相当する値になる。loom は "巨大な姿を表す" などの意味。
このバッタの実験では l/|v| が 15 ms より短くなるとニューロンの発火頻度が上がり、この程度の値の場合には衝突の 100 ms ぐらい前に移動反応を起こす閾値に達するとのこと。同じような定量化は小鳥の反応にも適用できそうに思える。
#オオタカ備考の [オオタカの獲物探索の視線の動き] に関連情報がある。オオタカの場合は状況が異なっているかも知れないが、像は網膜上の2つの fovea の位置とは一致していなかったとのこと。さらに上記 looming effect を獲物が捕食者に対して利用している可能性も議論されている。
Matilda et al. (2020) Camouflage in predators に motion camouflage の概念が取り上げられていた。
獲物から見て一見動いていないように見せかけて接近するとのこと。
Kane and Zamani (2014) Falcons pursue prey using visual motion cues: new perspectives from animal-borne cameras のシロハヤブサなどにカメラを装着した研究の経路の結果もこの motion camouflage の概念に合うとのこと。
camouflage の概念は広く歴史も長いので (一種のパラダイム?) 多くの現象を包括的に呼べてしまえるのかも知れない。
Tucker (2000) の議論との対比も示されているが獲物が動く場合への拡張版と言えるとのこと。シロハヤブサなどの場合は lateral fovea 側方窩 または temporal fovea 側頭窩 = shallow fovea 近くに像を固定するとのこと。Tucker (2000) は deep (= central) fovea の方と考えていたが実証実験ではそうではなかったとのこと。
Kane and Zamani (2014) の研究は#シロハヤブサ備考にまとめた。ベースとなる追跡理論があり、その最適値に近い方向に視線を向けていて、その方向がだいたい shallow fovea に当たっているとの解釈。#シロハヤブサ備考にさらなる解説と考察を追記した。
[障害物がある場合の獲物追跡アルゴリズム]
実験はモモアカノスリ (ハリスホーク) に対して行われたものだがテーマに関連してこちらに挙げておく。ハイタカでもオオタカでも当てはまるのではないだろうか。
Brighton et al. (2023) Obstacle avoidance in aerial pursuit
動く獲物に対して2つの障害物をどのように避けるかを高速度ビデオ撮影で解析。単純な獲物追跡 (連続的な closed-loop 制御) と障害物回避アルゴリズム (単発の open-loop 修正) を導入して運動をどこまで再現できるかを調べた。実験ビデオもあるが想像通り敏捷な動きになっている。
翼1つ分程度の距離に障害物を検知した場合に方向転換すると解釈できるとのこと。実験設定でも翼先端はある程度の頻度で障害物に触れているが自然条件下では羽毛を傷付けない程度のものとのこと。
飛び立ちも獲物の方向でなく障害物の合間を向いている。#ハシボソガラス備考の [鳥の知能行動] のケーラーの迂回実験など問題にならないぐらい障害物を回避した先読みした行動を行っているよう (古くは鳥は頭が悪いことが暗黙の前提になって結論を導いていた可能性あり)。
この実験を見て思い出したが、姫路の動物園でモモアカノスリ (ハリスホーク) の飛行デモンストレーションがあった (鳥インフルエンザや主にコロナ以前の話)。輪をくぐって餌に飛びつく実演だったが、本番以外も見る機会があって輪の位置を変えた場合の反応を知ることができた。
飛行経路の途中に置いた場合は輪をくぐってくれないことが多く避けて飛んで笑いを誘っていたが、おそらく輪をくぐること自身は目的になっておらず (輪をくぐることを楽しんでいるわけではなさそう)、餌の直前に置かれた輪はうまく通ることができるものの、経路の途中にある場合は障害物とみなしていたと考えられる。
餌の直前では輪を通らないと餌に到達できないので迂回しなかった、あるいはすでに減速していたので障害とみなさかったが、飛行速度の高い経路途中では回避可能でかつ衝突するとリスクがあるのであえて最短距離を選ばなかったとも解釈できそう。いかに猛禽類でも能力の限界に挑戦しているわけではない?
Brighton et al. (2023) では通り抜けられ、かつ同一物体が障害物にもなるような実験条件は選ばれていないので、相対速度 (または相対角速度) など実験条件をうまく選べば面白い結果が得られるかも知れない。
[ハイタカの巣内ひなに食物を与える実験・巣の乗り換え]
Newton et al. (1999) Post-fledging behaviour, dispersal and survival in Eurasian Sparrowhawks
がハイタカの巣内ひなに人工的に食物を与えることで巣立ちや若鳥の分散が遅くなるかどうかを調べた。
結果的には人工的に食物を十分供給すると通常巣立つよりも遅くまで巣にとどまる結果となった。
この実験は親が巣に運び入れる食物を減らすことで巣立ちを促す仮説を検証することが目的で、その点のみを捉えると多少裏付けられる結果とも読めるが、実際には親が突然食物を与えなくなる、あるいは子に対して攻撃的な態度を示すことは観察されなかった。巣立ってから子が十分に技術を身に着けたと判断できる時点で給餌を中止するように見えるとのこと。
親は単に食物を置いてゆくだけで誰が食べるかは関知しない。そもそも巣で自身の子とそうでない個体を区別しない。そのため他所の若鳥が寄生することも可能である (post-fledging brood-parasitism と呼んでいる。brood parasitism は托卵の意味で使われることが多いが本来の意味に戻ることになる)。
一緒にいる若鳥は大抵兄弟で、他の個体を排除する行動がもしあれば自分の子を殺しかねない。
この点を考慮すると早く繁殖を開始することは遅く繁殖を始めたつがいを利用できる可能性が高まり、早く繁殖を開始する戦略が有利となる。早く巣立った個体が (依存する) 巣の乗り換え行為 (nest switching) はオオタカやミサゴなどでも指摘されているとのこと。
ハイタカで直接に議論した論文は Frumkin (1994) Intraspecific brood-parasitism and dispersal in fledgling Sparrowhawks Accipiter nisus。
nest switching が実際に記録され、早く繁殖を開始したものの方が生存率が高かった。こちらも人工的に食物を与えることで巣立ちが遅くなったとのこと。上記 Newton et al. (1999) は研究会集録だが共著者の Frumkin (1994) の研究をさらに続けたものだろう。nest switching が主要因というわけでもないだろうが、生存率向上には役立っても不思議でない。
ひなや若鳥の成長期が食物の豊富な時期になるように繁殖スケジュールが最適化されるのだろうが、それにしても早すぎる印象を受ける猛禽類の繁殖時期はこの要因も関与しているのかも知れない。
この点については巣をめぐる種内、種間競争もあり#イヌワシ備考の [猛禽類が代替巣を造る理由] も参照。
他種の文献 (引用されているもの以外も含めた):
オオタカ: Kenward et al. (1993) Post-nestling behaviour in goshawks, Accipiter gentilis: II. Sex differences in sociality and nest-switching
ミサゴ: Poole (1982) Breeding Ospreys Feed Fledglings That Are Not Their Own,
Gilson et al. (2000) Facultative Nest Switching by Juvenile Ospreys,
Bierregaard et al. (2016)
Long-distance Nest Switching by a Juvenile Osprey (Pandion haliaetus)
アメリカチョウゲンボウ: Lett and Bird (1987) Postfledging Behavior of American Kestrels in Southwestern Quebec
エジプトハゲワシ: Donazar and Ceballos (1990) Acquisition of food by fledgling Egyptian Vultures Neophron percnopterus by nest-switching and acceptance by foster adults
トビ、アカトビ: Bustamante and Hiraldo (1990) Adoptions of fledglings by black and red kites
スペインカタシロワシ: Ferrer (1993) Natural adoption of fledglings by Spanish Imperial Eagles Aquila adalberti
とイヌワシ属でも報告があった。
巣にひなが3羽いるミサゴ A raucous display: How five grown Ospreys fit in a single nest? (Anders Gyllenhaal 2024) 親鳥を含めて5羽が巣にとまっている。
#オオタカ備考の [クーパーハイタカの種内托卵] のように托卵もあったのかも知れないし、他の若鳥が混ざっているのかも?
個体標識や遺伝子解析などをしないとわからないだけで、猛禽類では (まれとはいえ) 巣の乗り換えはそこそこ起きているのかも。巣のビデオ中継でも巣の外の出来事までは見えないので巣立ってからの行動は盲点かも知れない。
[ハイタカの巣の再利用]
Otterbeck et al. (2019) The paradox of nest reuse: early breeding benefits reproduction, but nest reuse increases nest predation risk
がデンマークとノルウェーで調査した結果、再利用の場合起きやすい巣の捕食を避けるために毎年新しい巣を造る戦略が進化し、再利用は主に経験の浅いオスによる繁殖開始の遅れを取り戻すために行われる可能性がある結果となった。寄生虫を避ける可能性もあるがこの研究では捕食リスクが主要因ではないかとのこと。
[猛禽類の脚の長さ]
広義ハイタカ属は猛禽類の中でも脚が長いと感じられると方が多いだろう。このような特徴を定量的に見るには#コブハクチョウの備考で紹介した AVONET を使うのが便利である。極めて参考までにそのような図を描くにはどうすればよいかサンプルを示しておく。
library(traitdata)
data(avonet)
plot(log10(avonet$Wing.Length),log10(avonet$Tarsus.Length),pch=19,
xlim=c(0.5,3.5),cex=0.2)
genus <- c("Accipiter","Aquila","Nisaetus","Butastur","Haliaeetus","Circus",
"Sagittarius","Buteo","Gyps","Gymnogyps","Melierax","Falco","Caracara",
"Ibycter","Milvus","Pandion","Pernis")
pal <- rainbow(length(genus))
for (i in 1:length(genus)) {
a <- subset(avonet,Genus==genus[i])
points(log10(a$Wing.Length),log10(a$Tarsus.Length),pch=19,col=pal[i],cex=0.6)
}
legend(0.5,2.7,legend=genus,pch=19,pt.cex=0.6,col=pal[seq(1:length(genus))])
AVONET のデータをダウンロードして(そのためには R が必要)、R で上記を実行 (例えばコピーアンドペーストで) すれば図が描ける。背景の小さな黒い点は他の鳥類すべてのデータ。
横軸が翼長の対数、縦軸がふしょ骨の長さの対数である。
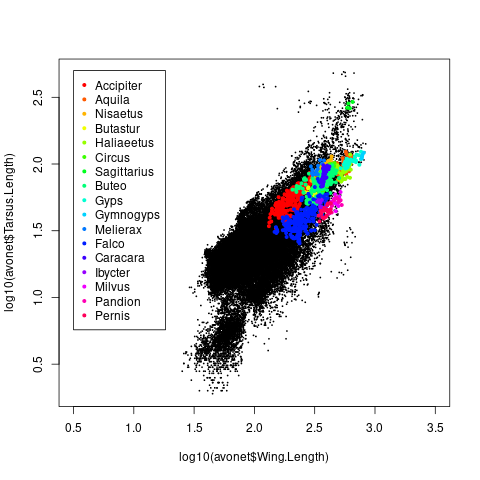 脚の長いグループを前半に (Melierax まで)、短いグループを後半に (Falco 以下) に並べてみた。はっきり2つに分かれるのは面白い。広義ハイタカ属とハヤブサ属は脚の長さですみわけている? (そんなことはあるのだろうか?) クマタカの脚も長い。
ウタオオタカは広義ハイタカ属より一段脚が長い (思った以上に大きい鳥だった)。カラカラはハヤブサ類の中でも脚は長い (地上を動き回るから?)。カラカラの中でも Ibycter (ハチクマとともに唯一のハチの子主食の猛禽) はハチクマ同様に脚は短い。などが読み取れる。こういうことを調べるのは専門家の領域と思われがちだが、現代ならば (ソフトさえインストールすれば) 誰でもできるようになっている。
Fowler et al. (2009) Predatory Functional Morphology in Raptors: Interdigital Variation in Talon Size Is Related to Prey Restraint and Immobilisation Technique
に広義ハイタカ属とハヤブサ属の獲物を殺す方法の違いなどに関連した考察があった (#ハチクマの備考から)。
脚の長いグループを前半に (Melierax まで)、短いグループを後半に (Falco 以下) に並べてみた。はっきり2つに分かれるのは面白い。広義ハイタカ属とハヤブサ属は脚の長さですみわけている? (そんなことはあるのだろうか?) クマタカの脚も長い。
ウタオオタカは広義ハイタカ属より一段脚が長い (思った以上に大きい鳥だった)。カラカラはハヤブサ類の中でも脚は長い (地上を動き回るから?)。カラカラの中でも Ibycter (ハチクマとともに唯一のハチの子主食の猛禽) はハチクマ同様に脚は短い。などが読み取れる。こういうことを調べるのは専門家の領域と思われがちだが、現代ならば (ソフトさえインストールすれば) 誰でもできるようになっている。
Fowler et al. (2009) Predatory Functional Morphology in Raptors: Interdigital Variation in Talon Size Is Related to Prey Restraint and Immobilisation Technique
に広義ハイタカ属とハヤブサ属の獲物を殺す方法の違いなどに関連した考察があった (#ハチクマの備考から)。
次は日本で識別上話題となるチュウヒ類の例 (この例では生物関係の作図によく使われる ggplot2 を使ってみた)。マダラチュウヒの脚は長いと言われるが、ハイイロチュウヒに比べて長いわけではなく、脚の長さは識別点にならないことがわかる。
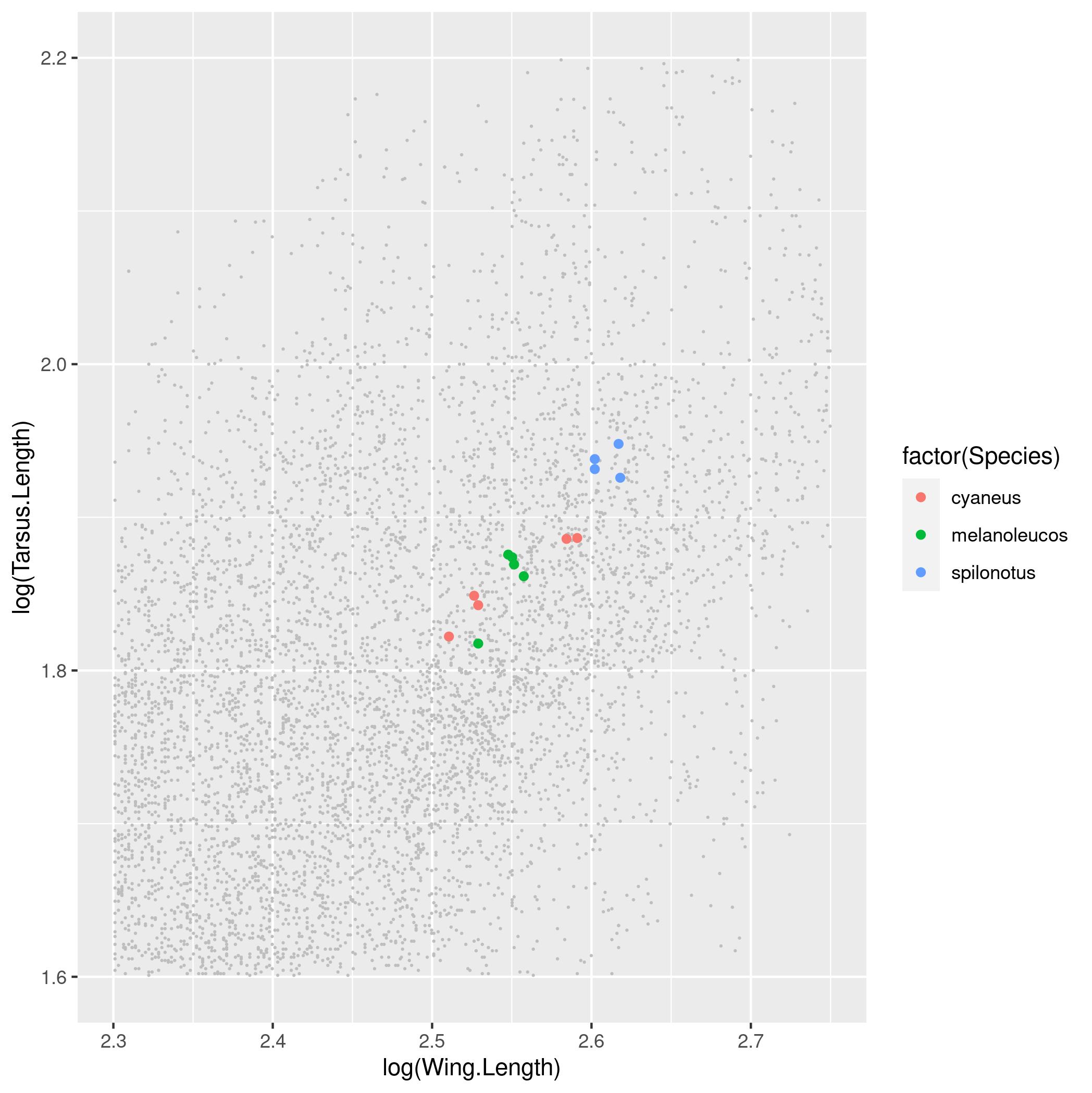 R とパッケージのインストールの詳細やトラブル解決はここには書ききれないので R 利用経験のある人に聞いてみていただきたい。AVONET は AVONET にある。論文に書いてある通り、
R とパッケージのインストールの詳細やトラブル解決はここには書ききれないので R 利用経験のある人に聞いてみていただきたい。AVONET は AVONET にある。論文に書いてある通り、
install.packages("remotes")
remotes::install_github("RS-eco/traitdata")
とやればインストールできるはずである。
[ハイタカとオオタカの識別関連]
フランスのサイトに飛翔中のオオタカとハイタカの識別の記事があったので紹介しておく:
Autour des palombes et Epervier d'Europe: page comparative (Valery Schollaert 2022)。
カワセミの捕食に失敗したハイタカの写真も出ている。日本語資料は十分あるので海外のページを見に行くまでもないが、フランスでは識別点をどのように捉えているか、どのように表現しているかなど見るのも面白いかも。
オオタカの方で触れた方がよいかも知れないがオオタカの備考も多いのでこちらで述べておく。
Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology" p. 88 によればオオタカは ulna 尺骨 が短く、次列風切も少ないので他の猛禽類に比べて止まっている時に "shoulder" (肩のように見える部分) が目立たないとのこと。オオタカの識別点で静止時の (みかけの) 首の長さが取り上げられることがあるがこれが関係しているかも知れない。
[両方の卵巣が発達していたハイタカ]
Red'kin and Shatokhina (2006, 2024 再掲) Finding paired ovaries in a female sparrowhawk Accipiter nisus (pp. 2398-2399)。
若鳥でモスクワの Malenkovskaya マレンコフスカヤ駅で2004年9月14日に死体で見つかった。ハトの追跡中に透明な隔壁に衝突したのではとのこと。左右の卵巣が対称的に発達していた。
Jollie (1976, 1977)
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part IV) (pp. 287-288) によれば広義 Accipiter と Circus はタカ類の中で右の卵巣の発達が特によいとのこと。
例えばミサゴや大型のハゲワシ類は右の卵巣を持たないとのこと。他のタカ類でもほとんど発達していないものが多く (トビ類や海ワシ類、ノスリ類、イヌワシ類なども同様)、広義 Accipiter と Circus の卵巣の特性は際立っている。
Stieve (1924) によればオオタカで両方の卵巣が機能しており、右に1つの卵胞、左に2つの卵胞があって3卵を産んだ例を報告しているとのこと。
ハヤブサ類内では多少変化があるよう。
-
オオタカ (将来の属名変更に注意)
- 第7・8版学名:Accipiter gentilis (アクキピテル ゲンティーリス) (同一民族の) タカ (本来の学名はモリバトを捕らえるタカだった可能性がある。備考参照)
- AviList 学名:Astur gentilis (アストゥル ゲンティーリス) (同一民族の) オオタカ (本来の学名はモリバトを捕らえるタカだった可能性がある。備考参照)
- 第7・8版属名:accipiter (m) タカ (accipere 掴む Gk)
- AviList 属名:astur (m) オオタカ 由来は備考参照
- 種小名:gentilis 同一民族の、氏族の (gens, gentis 氏族。しかし本来はオオタカではなくハヤブサを指していて、よく訳される「高貴な」意味は含まれない可能性がある。備考参照)
- 英名:[Goshawk, Northern Goshawk 分離前の名称], IOC, AviList: Eurasian Goshawk
- 備考:
astur の読み方はラテン語では冒頭の "ア" にアクセントがある。そのつもりで "アストゥル" と読むと何となくそれっぽい感じがする。語末を伸ばす発音は後の時代にもないので伸ばさないのが正しい。astur も accipiter も短く読むとタカの鋭さにふさわしい...かどうかは知らない。
英語の goshawk でもアクセントは冒頭なので同じようなアクセントにすればよいことになる。
なおラテン語の aster (星) はギリシャ語由来で末尾を伸ばす (アステール)。ホシムクドリの sturnus は伸ばさない [系統と分類] の項目参照。
音声面では星よりはホシムクドリの方が語源に影響があるかも知れない (例えばホシムクドリを狩る鳥?)。
accipiter は#ハイタカ参照。
gentilis は最初の i が長母音で中央にアクセント "ゲンティーリス" と読むとよいらしい。gens (民族) + -ilis (形容詞語尾で冒頭が長母音) に由来。
gens は e に長音記号が付くが実際にはほぼ短音で読まれる (長音の読み方 "ゲーンティーリス" もある) (wiktionary)。
別種となったアメリカオオタカの学名 Astur atricapillus (アメリカではもはや Accipiter 属でない) の読みは "アストゥル アートゥリカピルルス" でよいと思われる。黒い髪毛の意味 (#キガシラシトド参照)。
よく出てくる亜種名も考察しておくと、fujiyamae はラテン語風に j を i と読んでもよいが世界にもよく知られた富士山の読みを用いて "フジヤマエ" でよいだろう。
albidus は短母音のみで冒頭にアクセント (アルビドゥス)。
schvedowi はラテン語風だと "スケウェドウィ" となると思われる。
原語は Shvedov で普通に考えれば "シュヴェドフ" の読みになって語末にアクセントが生じる理由はない。ロシア由来の学名でしばしば使われるようにドイツ語読みを前提に作られた可能性があり、原語に音も近い "シュウェドウィ" でよいと思われる。
[オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑]
gentilis (adj) はラテン語本来は「同一民族の」の意味で使われるが、中世鷹狩りではオオタカ (gentle falcon) は位の高い人のみ飛ばすことを許されていたことから「高貴な」訳が適切と考えられている (The Key to Scientific Names) ...
これまでこのように記述してきたが、調べてゆくと上記はあまり正しくなくもっと複雑であることがわかった。
(1) Linnaeus (1758) 「自然の体系」時代の Falco gentilis は何を指していたか
原記載。Linnaeus が文献として挙げているものでは、Falco gentilis の学名が Will. ornith. 46. Raj. av. 13. (1676) に現れていた。
Linnaeus の記述には Habitat in Alpibus, victitans Tetraonibus. Ars capiendi Falcones Columbis & Lanio, instituendi, his venandi Gazellas, Ardeas, Aviculas & c. propriis artificibus.
アルプスに住み、ライチョウ類を食べる。ハトやモズを使ってこの "Falcones" (複数形) を捕える技術があり、ガゼル、アオサギ、小鳥などを獲物にすることができる、ぐらいの意味か (単語を追いかけただけなので誤訳があれば失礼)。
この記述の一部は後で問題となるハヤブサよりオオタカに合っているようにも見えるが、生息地の記述も他種と異なるところがあり (後述) 鷹狩りの記述は他に出てこないので、ここでは一般的な鷹狩りの記述として紹介している可能性がありそう。
#ワキスジハヤブサ備考の [ワキスジハヤブサによるペルシャのワシの狩り] によれば中東でワキスジハヤブサ (ハヤブサも) ガゼルやサギ、ツルの狩りに使われていたとの具体的情報があり、ハヤブサで問題ないかも。
以降は Linnaeus (1758) 以降、しかも英国の記述であるが、
Pennant (1776) "British zoology" Falcon Gentil から始まるページの記述は「虹彩が明るい黄色」(irides light yellow) とあり、翼と尾の長さの比較など、これはオオタカを指しているようにも見える。2つある図版の最初の方はオオタカ若鳥でよさそうだが、2つめはどちらにも今ひとつ似ていない。
Goshawk が Pennant (1776) による Goshawk (オオタカ) のページでこちらはそれっぽく見える。
この文献も過去に使われた名称を挙げていて、Falcon Gentil については Linnaeus (1758) から Falco gentilis を採用している。しかしフランスの Belon (1555) L'histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naifs portraicts retirez du naturel / escrite en sept livres
から L'Autour を採用している His. d'Oys. の該当ページ (絵が抽象的でどちらか今ひとつわからないが現在見ればオオタカの方か)。
同書 p. 116 に Faucon Gentil と Faucon Pelerin が別に出てくる。
絵や記述順序を見ると Belon (1555) は L'Autour をオオタカの方に用いていたと思われる。
Pennant (1776) の Goshawk の項目には Linnaeus (1758) から Falco palumbarius を採用。しかし Autour. Belon av. 112 (上記ページ) も記されているので、同じ Autour を2回紹介していることになる。
Goshawk の項目に L'Atour, Astur. Briffon av. i. 317 を初めとする一連の Autour も採用されているので、Goshawk = Autour = Astur と認識しており、Faucon Gentil に L'Autour を含めたのはおそらく Pennant が混乱したのではないだろうか。Goshawk の項目でドイツ語名 Grossergepfeilter Falck (大きい矢のようなタカぐらいの意味か) も紹介されている。
Bewick (1809) "A history of British birds: the figures engraved on wood" The Gentil-Falcon も同様で Goshawk とは分けているが、虹彩や翼と尾の長さの比較などは Pennant (1776) と同じ書き方になっている。
Latham は Common Falcon を 12 の変種に分割しているが不必要に細かすぎるとのこと。
Buffon によれば Gentil (Buffon は Common Falcon と同じで季節だけが違うと考えた) と Peregrine or Passenger Falcon の2種類でよいとのこと。Bewick は後者は英国では珍しいものであまり知られていない。ろう膜と虹彩は黄色などとある。
この本では The Goshawk にオオタカが出てくる。この項目に中国皇帝が狩りの際に使ったと言われるとの記述がある。
英国では古くは Hawk を据えることのできるのは階級の高い男性に限られていたとのこと。貴族でなければ鷹狩りに必要な広い土地を所有できなかった。この Hawk が何を指すかは自明でなく、同じ段落の最後に (ここで紹介したオオタカ以外に) 多くの種類が貴族の楽しみに高く評価されたとある。後の記述を見るとおそらく Hawk はタカ・ハヤブサ類全般のことか。
それらの鳥は Jer-Falcon (シロハヤブサ), Falcon, Lanner (ラナーハヤブサ), Sacre (Falcon-Gentil の換羽をしていないある特定の色彩を指すと注釈している), Hobby (チゴハヤブサ), Kestrel (チョウゲンボウ), Merlin (コチョウゲンボウ) が含まれ、これらは Long-winged Hawks と呼ばれる。
翼の短い Goshawk, Sparrowhawk (ハイタカ), Kite (トビ類), Buzzard (ヨーロッパノスリ) と区別される。これらは動きが遅く、より怠惰で、Long-winged Hawks よりも勇敢でないとある。
過去の記述などを伝聞している部分もあると思われ、特徴なども混乱があるよう。この記述はオオタカの項目にあるにもかかわらず、オオタカなどの方が劣っている記述になっている。おそらくオオタカの項目がハヤブサより先に出てくるのでこちらで鷹狩り全般を紹介したのだろう。
英国で紹介される時点で名前や実態 (虹彩の色など) が混乱してしまっていた可能性がありそうだが、これらの著書でも "gentil" はオオタカを意図していたものでないことは明らか。
(2) 「鷹狩りの書」(フリードリッヒ二世著) の「高貴なハヤブサ」は何か
"Peregrine Falcons of the World" (Clayton et al. Lynx 2014) の書評 Bell (2015) Peregrine Falcons of the World
によれば Frederick II の時代にはハヤブサが "Falcon Gentle"、ラテン名で Gentilis peregrini または Falco gentilis absoluteと呼ばれていて、もし Linnaeus の学名システムが採用されなければまだこのラテン名を使っていたかも知れないとある。
これらの話を見て「鷹狩りの書」(フリードリッヒ二世著 吉越英之訳 文一総合出版 2016) を読み直してみると、訳本で「高貴なハヤブサ」(p. 187 など) とあるのはこのこととようやく理解した。
以下邦訳に基づくが翻訳原本の英語版は The art of falconry: being the de arte venandi cum avibus of Frederick II of Hohenstaufen (Wood and Fyte 1943) で見られる。
Manuscript - Pal.lat.1071 に 1071 年写本のスキャンがある。56v に De falconibus gentilibus absolute: falcones gentiles absolute というのがこれを指すよう。
文中では単に falcones gentiles とも記されている。表題の falconibus, gentilibus はいずれも複数形 (単数形主格は falco, gentilis) で、前置詞 de (〜に関して) が付いて奪格となっている。absolute は副詞で「完全に」。
英訳では the true (gentle or) noble falcons となっている。しかし gentilis の本来の語義からは実は「高貴な」意味は入っておらず、類似の英語から英訳でそのように扱われただけの可能性もあるかも。「同一民族の」「同族の」方と捉えれば、海外からのよそ者の (渡りの) peregrinus と自然に対応するような気もする。
地元のハヤブサを gentilis、遠くからやってくるハヤブサを peregrinus と呼んでいた、などの解釈も考えられるように思える。absolute も "正真正銘" 地元で生まれ育った、という意味かも。
The Key to Scientific Names (peregrinus) によれば、少なくとも英国では遠くからやってくるハヤブサの方が巣から捕えるハヤブサの方が鷹狩りに適していたと考えられていたとの文献が出ている。gentilis は「うちのハヤブサ」、peregrinus は「よそ者」のほうがよい?
写本でオオタカには astur が用いられているよう (56r) で特別な扱いはなさそう。
訳本に戻ると Frederick II によれば「高貴なハヤブサ」はハヤブサのような種だが、やや小さく体の各部の形状も多少異なり、色調はハヤブサほど輝いておらず、美しくもないとある。訳注で漠然と混乱した記述をしているとある。これは英訳の脚注通り。意味を「高貴な」と解釈しなければ必ずしも混乱した記述になっていないかも?
「高貴なハヤブサ」は最初の羽が生え変わると、風切り羽はハヤブサの風切り羽に非常に似ているとあるので、オオタカを指しているものではないだろう (Frederick II 自身も別にオオタカの本を著していたようで、この本にもオオタカの記述があるので混乱していたとは考えにくい)。背中や尾羽に小斑点があり、そのためハヤブサほど美しくないとある。
「高貴なハヤブサ」はハヤブサより秋の渡り時期が遅い (p. 217)。また一般に開けた草原で捕獲され、主として陸鳥を餌として生活するため (p. 219) とある。
ハヤブサは Falco peregrinius (peregri 海外から 飛翔することから) (p. 168)。多くの人は「高貴なハヤブサ」とハヤブサは別の種と信じているが、Frederick II は同じ種と考えている (p. 169) 出生地の気候の違いが表れていると考えた記述になっている。
この本の中では「高貴なハヤブサ」とハヤブサはしばしば並列で現れる。
「高貴なタカ」は Frederick II の元来の用法ではハヤブサを指していたという Bell (2015) の見解とは少し異なっている。英訳されて伝えられる過程で意味が変わって行った可能性もあるかも?
(3) Linnaeus (1758) およびその原典の Will. ornith. 46 (1676) の記載順序からの検討
Linnaeus の記述では Falco Gentilis の1つ前がツバメトビとされるもの (ここまでがアカトビとともにトビ類) 、次がチゴハヤブサ、ヨーロッパノスリ、チョウゲンボウと続いていて、ヨーロッパノスリの位置が変だがチゴハヤブサは subbuteo なので buteo の隣にしたのだろう (後述 Gesneri 1511 も参照)。
この部分に現在のハヤブサ科が固まっている。もっとも Linnaeus 時代の Falco 属にはモズ類が含まれているのであまり厳密な分類の議論はできないかも。
記載順を見ると Linnaeus はろう膜の色を特に気にして分けているよう (チゴハヤブサまでは黄色となっている)。ツバメトビとされるものはアメリカの種類で尾が二股に分かれるとあるのでこの種類しか該当するものがないかも知れないが、ろう膜があまり黄色に見えない感じもする。
現在受け入れられているハヤブサの学名は Falco peregrinus Tunstall, 1771 なので Linnaeus が名付けた学名ではない。ハヤブサのように目立った種類を Linnaeus が見逃すとは考えにくいような気がするとともに、当時の文献も参考にすると Linnaeus はハヤブサの方を "Falcon Gentle" と呼んでいたのではないだろうか。
Linnaeus が引用している Will. ornith. 46 (1676) ではハヤブサ類の場所に置かれていて、Frederick の言う Imperator Falcones gentiles in peregrinos と absolute gentiles とは違っているとの議論のよう。
peregrinus よりは (複数奪格で比較対象を指す) より小型で、頭はより丸く、嘴はより小さく、体に比べて脚はより小型 (短いの意味か)。
風切羽が生え変わると羽はより細く? (貧弱に?) なる一方尾や背にはより多くの斑点が現れるなどの違いが記されている。
同書 p. 43 Falco peregrino が別途扱われており、分離して新種の扱いのよう。
同書 p. 45 Falco montanus (山のハヤブサの意味) が問題の Falco gentilis の一つ前に出てきて、Linnaeus は Falco gentilis と同一として一つにまとめている。
Falco montanus は虹彩が黒っぽいなどとあるのでやはりオオタカではないのでは? その一つ前の項目がシロハヤブサ。
同書 p. 51 De Accipitribus brachypteris (翼の短いタカについて) のグループに De Accipitre Palumbario があり、the Goshawk となっている (Linnaeus でもこのまま出てくる)。
p. 46 の Falco gentilis はオオタカとは別物で、ハヤブサから分けて新種として記載しただけではないだろうか。
Gessner (1555)
Conradi Gesneri Historiae animalium liber III qui est de Avium natura - 1555
にも当時の鳥の一覧があり、
Falco in genere (ハヤブサ属) Falcones diversi, Falco sacer (セーカー), Hierofalchus (シロハヤブサ類), Falco montanus, Falco peregrinus, Mediani, Gentiles, Falco gibbosus, Falco niger, Falco albus, Falco rubeus, Falco cui pedes coerulei, Lithofalcus et dendrofalcus, Lanarii (ラナー), Falcones mixti (雑種のこと?)
となっていて意味のわかるものが多い。現在使われていない学名がたくさん並んでいるのはハヤブサを細かく分けた結果のよう (検討は #ハヤブサの備考に)。
同じ文献で、同じく Accipiter には複数の属があってオオタカ関係を抜粋すると チュウヒ類の後に Accipiter fringillarius, Accipiter palumbarius, Sperverius vel nisus recentiorum が出てくる。当時は Subbuteo, Tinnunculus は Accipiter 類に入っていてハヤブサの仲間とは考えられていなかったよう。Accipiter 類はこれらを含む多彩なグループを包含していた模様。
これを見ると Falco montanus, Gentiles は明らかにハヤブサを示す一群に含まれていて、montanus と Gentiles はおそらくハヤブサをいくつかに分けたもので、「山の」「地元の」そして peregrinus「よそ者の」と推定出身地とわずかな外見の違いを手がかりに分けていたのだろう。
オオタカはこの当時から Accipiter palumbarius で呼ばれていたことがわかる。
(4) Accipiter palumbarius の位置づけ
1911 Encyclopdia Britannica/Gos-hawk の百科事典によれば当時の学名は Astur palumbarius で、ヨーロッパではオオタカでガンや大型の鳥を捕る伝統がなかったので (後記も参照)、
goshawk (= goose + hawk) はもともとは翼の長い (森林性のタカ類と比較してハヤブサ類を指す用語だった。現在の鷹匠用語では "longwings") 大型のタカかハヤブサ類の一種に使われていた名称がオオタカに転用されたものではとある。
Goshawk (Gould 1837) によれば原学名は Falco palumbarius で図版も入っておりこれは明瞭にオオタカを指したものと解説されている。
この学名も同じ Linnaeus によるもので、Falco palumbarius の原記載で見られる。こちらはろう膜が黒とある。
記述は明瞭ではないが並び順はヨーロッパチュウヒがその前、ハイタカがその次になっている。系統分類的にはこちらの方がオオタカのあるべき場所に近い。
Turberville and Gascoigne (1611) The booke of falconrie or havvking
も読むことができる。この時代にオオタカが鷹狩りに使われていて goshawke と呼ばれていたことは問題ないよう。
Gray (1855) Catalogue of the Genera and Subgenera of Birds contained in the British Museum では palumbarius を Astur属 (Lacepede 1799) のタイプ種としているなど、
オオタカに対する palumbarius の種小名は長く使われていた模様で、gentilis がオオタカを指す用法は想像以上に新しいものかも。
(5) Falco gentilis Linnaeus, 1758 は Falco palumbarius Linnaeus, 1758 のシノニムとの解釈について
Sangster et al. (2021)
A new genus for the tiny hawk Accipiter superciliosus and semicollared hawk A. collaris (Aves: Accipitridae), with comments on the generic name for the crested goshawk A. trivirgatus and Sulawesi goshawk A. griseiceps
では Falco palumbarius Linnaeus, 1758 を Falco gentilis Linnaeus, 1758 のシノニムとしている。
どこかの段階で両者は同じものと判断され、Falco gentilis の方が先に現れるので優先されたのだろう。
palumbarius は palumbes モリバト (を捕らえる) の意味。The Key to Scientific Names (palumbarius) によれば BOU (1915) は Linnaeus described the Goshawk twice under the names Falco gentilis and F. palumbarius on pp. 89 and 91 of the 10th edition.
As the first name has been entirely passed over and ignored until quite recently, the Committee have forborne to make a change, and keep the older-known name as a "nomen conservandum"
とあり、Linnaeus はオオタカを2か所に登場させているとの解釈。Falco gentilis は最近まで長年忘れ去られていおり、オオタカの名前を変えるのは控えて palumbarius の方を使い続ける判断としたとのこと。
1911 Encyclopdia Britannica/Gos-hawk で Astur palumbarius が使われていた状況とも合う。
Hartest (1917) Notes on Game-Birds が厳密に先取権の原則に従うべきだとして Accipiter palumbarius よりも Accipiter gentilis を優先し、
Anas boschas よりも Anas platyrhynchos (マガモ) を優先すべきと述べた。BOU (1915) を受けた見解かも。この意見が契機かどうかはわからないが、これらは現在使われている学名になっている。
Accipiter palumbarius で検索すると図版もみつかり、The Pigeon Hawk の名前でよく知られていた模様。対応する学名も素直に意味がわかるのでこちらの方がよく使われていたのだろう。
これらから推定すると Accipiter palumbarius (または別の属名) の方が少なくとも 1555 年以前から 1910 年代までは使われていた由緒あるオオタカの学名らしい。
亜種記載の学名などを見ると 1920 年代でもまだ使われていたよう。
Linnaeus はオオタカを2か所に登場させたとの誰かの解釈から先取権の原則によって Accipiter gentilis となったのが真相のよう。
しかし Linnaeus がそのような過ちをするだろうか? ハヤブサのつもりで記載したが混ざってしまった可能性もあるのか真実はわからないが、後日の研究者の解釈の誤りの可能性もありそう。
オオタカの歴史的学名は「モリバトを捕らえる」で主な食性とも一致し、英語の Pigeon Hawk にもよく対応する。
gentilis は実は Frederick II の時代も含め今で言うハヤブサに与えられていたのではないか。現在の学名はあくまで先取権の原則に基づいた微妙な判断によるもの。
そのように考えると「モリバトを捕らえる」は特徴をよく表しているように思う。
さまざまな辞書でも falcon-gentil は主にメスのハヤブサを指すが、鷹狩りに用いるメスのハヤブサ類 (タカ類も含まれていた可能性あり) にも使われるとの説明が多い。
Webster 1913 年版で 第3語義に The female or young of the goshawk (Accipiter gentilis, formerly Astur palumbarius) が見られ、このあたりで学名の扱いや用例に変化が生じてきたらしいことをうかがわせる。
このころから両方の学名が使われ、BOU が 1915 年に判断を出した流れだろうか [後述 Lonnberg (1906) によると思われる]。
Grassby (1997) The Decline of Falconry in Early Modern England でも 17 世紀には falcon, falcon gentle, tiercel gentle (オス) はほぼ種ハヤブサのみを指して使われたいたとのこと。peregrine の名はほとんど使われなかった。
当時 "falconry" に使われていたのはハヤブサ、シロハヤブサ、ラナーハヤブサ、コチョウゲンボウ、チゴハヤブサで輸入されたものも使われていた。主に貴族の楽しみ (sports) の見世物となっていた。
ハヤブサ類にサギやツルを襲わせる場合には訓練したイヌで獲物を空中に追い出させた。goshawk の語源で「ガンや大型の鳥を捕る」部分とハヤブサ類の習性との関連が気になる部分だったのだが、このような "falconry" の手法を考えるとハヤブサだったのかも知れない。
これらの項目を記述してから西海 (2012)「野鳥」2012年7月号 (No. 766) pp. 4-14 「鳥の分類」の記事の記述に気づいた (なお「野鳥」のこのページには他の方が記述した部分も含まれる)。
この記事によれば代表的な誤りの例として「偉人リンネでさえ、マガモのメスやオオタカの幼鳥を異なる種とみなして種名を付けてしまった」を挙げている。リンネ (当時は Linnaeus) はマガモやオオタカに新たな学名を導入したのではなく過去の文献の学名を整理してまとめただけなので「種名を付けてしまった」表現は語弊を招く気がするが、どちらが幼鳥でどちらが成鳥なのかも気になるので再度チェックしてみた。
Falco gentilis の記載は:
F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. Fn. svec. 60.
Falco gentilis. Will. ornith. 46. Raj. av. 13.
Falco montanus. Will. ornith. 45. t. 5. Raj. av. 13.
Habitat in Alpibus, victitans Tetraonibus.
Ars capiendi Falcones Columbis & Lanio, instituendi, his venandi Gazellas, Ardeas, Aviculas & c. propriis artificibus.
となっている。
この記述ではろう膜、足は黄色、体は灰色で褐色の斑点があり、尾は褐色で4本の黒い帯がある、となる。尾の帯のみハヤブサと整合しない。
"Fn. svec." は Linnaeus (1746) "Fauna Svecica" で付けられた番号。
Fauna Svecica で見られ、60. の項目の記述は "Systema Naturae" (1758) よりも少し詳しい。
足、ろう膜、虹彩は黄色、体は全体に灰色で褐色の斑点がある。尾は灰色で4本の褐色の横帯がある。首、背中、翼上面はくすんだ色で羽の先端は鉄さび色。下面は黄色みを帯び、のど、首、胸、腹の下面に褐色の長楕円形の斑点が散在する。腿部ではさらに細いものになる。
風切羽は外側が褐色で内側は白色で灰褐色の斑点があり、褐色の 5-6 本の縞がある。尾羽の外側と下面は全般に褐色で 5-6 本の黒い等間隔の縞がある。先端は擦れていて尾羽下面は白-黄色っぽい縦縞が散在する褐色。
ぐらいの感じで、この記述はオオタカの幼鳥の方が合うよう。
基産地についてはこちらを見ると確かに生息地は Dalecarlian Alps でドイツ人が捕獲する話 (#ハヤブサの備考参照) の通りとなっている。
Carl Linnaeus and the Falcon Catchers
(Linnaeus の足跡をたどる旅) によればハヤブサを捕まえるのに有名な場所があって [Linnaeus (1758) 記載の生息地について の項目参照]、地名 (Falkhojden, Falkfangarhogda) にも意味が残っているとのこと。ここで捕まえたものはフードを付けてドイツ、オランダやアラブに長旅で売られていたとのことで、
Linnaeus が実際に 1734 年にハヤブサ捕りの現場に同行しているとのこと。ハトやオオモズをおとりにハヤブサを網で捕まえると記述しているとのこと。この話は Falco gentilis の "Systema Naturae" の記載に非常によく合っている。
現在でもハヤブサ捕りに使われた洞窟の利用痕跡が残っているとのこと。スウェーデン語ではドイツ語と違ってハヤブサとタカを区別していたのでこれらの記述や現存する地名などはハヤブサ (タカも捕まえたかも知れないが) を意図していたものだろう。
Falco palumbarius の記載は:
F. cera nigra margine pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis palllidis, superciliis albus
ろう膜は黒で足は黄色、体は褐色、尾羽は褐色で白っぽい、眉斑は白、というところか。
こちらは Fn. svec. の番号はないが、66. に Alb. orn. 2. p. 8, t. 8 の Accipiter palumbarius の学名が現れる。引用されている他の学名を見るとこれはヨーロッパハチクマを指していることがわかる (どちらも学名に習性が含まれているのでオオタカとヨーロッパハチクマの学名を誤認するのは非常に不自然)。
当時のスウェーデン語では Slaghok となっており、slag は古ノルド語以来 "打つ" などの意味。攻撃するタカを想定したものと考えられ、オオタカを指してよさそうな名称。
"Systema Naturae" (1758) のヨーロッパハチクマの記載に 66 が出ているが、Alb. orn. 2. p. 8, t. 8 は引いておらず、別種と判定して別項目の Falco palumbarius を設けたことがわかる。
Linnaeus (1746) "Fauna Svecica" の記載だけを見ると Falco gentilis はオオタカの幼鳥を示しているようにも見えるが、オオタカの成鳥が別の項目として現れないので幼鳥を異なる種とみなして種名を付けてしまったとも言えない感じがする。
1746 年当時は Linnaeus にとってオオタカ、ハヤブサ、ヨーロッパハチクマの間の混同 (または記載ミス) があったと考えられる。よりによってオオタカ成鳥であるべきのものとヨーロッパハチクマを混同するとは! ヨーロッパハチクマに含まれているぐらいなので、オオタカ成鳥がどういう姿かも認識していなかったのだろう。
Linnaeus は "Systema Naturae" (1758) をまとめるまでの間にこの誤りに気づき、オオタカをヨーロッパハチクマからこっそり (?) 分離したのではないだろうか。"Fauna Svecica" の "ヨーロッパハチクマ" の記述には "眉斑は白" は出てこないので "Systema Naturae" に後から書き足したものだろう。
"Systema Naturae" の記載には "Fauna Svecica" を訂正したとも書かれていない。
つまり "Systema Naturae" が "Fauna Svecica" を参照したとしていても、Linnaeus の考えがその間に変わった可能性があり (明記されていない)、"Fauna Svecica" の記載をもって "Systema Naturae" の記載と読み替えることは必ずしも正当とは限らないだろう。つまり "Fauna Svecica" への引用が1対1対応するスタイルになっていない。
むしろ "Systema Naturae" (1758) は Will. ornith. 46. Raj. av. 13. (1676) の分類によく整合しているので、スウェーデンの種類しか扱っていない "Fauna Svecica" よりもこちらを参照にまとめ直した印象を受ける。
[オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑] どころでなく、なんと [オオタカとハヤブサとヨーロッパハチクマの学名の関係は複雑] だった。
Falco gentilis が幼鳥、Falco palumbarius が成鳥との解釈は wikipedia スウェーデン語版にあった Duvhok。
Lonnberg (1906。ドイツ語文献だがスウェーデン人なのでウムラウト表記はスウェーデン語に合わせた。Einar Lonnberg)
Einige Nomenklaturfragen が提案した文献で、Falco gentilis が幼鳥、Falco palumbarius が成鳥と判定した
[なお Lonnberg は #ゴビズキンカモメ の初記載において驚くべき慧眼を示している]。
前者の冒頭の記述からオオタカの幼鳥であることは明らかと書いており、それ以上に文献を当たるあるいは Linnaeus はハヤブサをどのように考えたのか検討は行っていないが大丈夫か? (現代の研究ならばもう少し歴史的検討が記述されるだろう)。
両者をシノニムとしてページの記載順から gentilis に先取権があるとした。
Hartert (1910-1922) でも p. 1146 で Linnaeus の gentilis は基産地がおかしいとの指摘が出ていた。
Linnaeus の時代にはスウェーデン語でそれぞれ falck, slaghok が与えられていたが、slaghok の名称にはヨーロッパノスリやヨーロッパハチクマも含まれていた (Slaghok) ので古くからあった duvhok の名前になったとのこと (wikipedia スウェーデン語版)。
Linnaeus (1746) がオオタカとヨーロッパハチクマを混同したのはスウェーデン語に引きずられてしまったためらしい。ヨーロッパノスリは "Fauna Svecica" の 65. で Upland 語で Quidfogel とあり、ヨーロッパノスリと {ヨーロッパハチクマ + オオタカ} は区別していたよう。ただし "Systema Naturae" (1758) にはこの番号は出てこない。
falck はやはりハヤブサを意図したかっただろうと想像できるが、情報に錯綜があってオオタカ幼鳥と区別できておらず、後世にオオタカ幼鳥と判断される記述になってしまったのだろうか。
Linnaeus が実際に捕獲に立ち会っているように、ハヤブサには馴染みがあって第一に出てくる種類だっただろうが、オオタカはそれほど馴染みがなかったのだろう。
Linnaeus (1758) の脚注にある鷹狩りを記述した本 (1617。Falco gentilis の項目の補遺として記されている模様) は
La fauconnerie de Charles d'Arcussia de Capre, seigneur d'Esparron, de Pallieres, et du Revest, en Provence のことか。
Falco gentilis がハヤブサであればもう一つ波及的効果があり、Falco 属のタイプ種に影響がある可能性がある。
Linnaeus の記載順で現在 Falco 属の最初のものはチゴハヤブサでこれがタイプ種との取り扱いがなされた (なおハヤブサとする立場もある。#チゴハヤブサの備考参照)。もし Falco gentilis がハヤブサであればハヤブサの配列の最初に現れ文句なくタイプ種としてふさわしい。こちらの方がすっきりする感じもする。
(6) 鷹匠用語の noble / ignoble
A Description and History of Falconry (WINGMASTERS) のようなページもある。こちらでもシロハヤブサやハヤブサがアオサギやクロヅルを捕える能力が称賛されたとのこと。
翼の短いタカ (現在の鷹狩り用語で "shortwings" 広義ハイタカ属) は "ignoble hawk" (高貴の反対の意味で、高貴でないタカ) と呼ばれていてこの用語は実際に広義ハイタカ属 accipiter の意味で辞書にも載っている。
オオタカは獲物を確実に捕えることから中世の鷹匠により "the cook's bird" (料理人の鳥) とあだ名が付けられていた (あまり身分の高い表現ではなさそう)。ただし英語の情報が当時の全貌を表しているかまでは不明。
全体的にはオオタカよりハヤブサの方がより貴族向けで、タカ類を用いる鷹狩りはもう少し庶民的?
なお、英語辞書では鷹狩り用語として noble, ignoble が出てきて、急降下で襲うハヤブサ類の行動を noble と称していたよう (また貴族も好んでいた)。
(記述してから後に wikipedia 英語版のオオタカの項目に同様の記述があることに気づいた。貴族よりは庶民の食卓のタカというところ。
現代の鷹狩りではハヤブサとオオタカは同等の地位が与えられているとあり、かつてはハヤブサの方が格上だったことが読み取れる)。
ignoble は機動性の高い飛翔により獲物を捕らえる森林性のタカを指しており、必ずしも悪い意味というわけではない。「イグノーベル賞」のように別の意味の称賛が入っているかも知れない。
しかし ignoble hawk のような用例を見るとオオタカの学名を「高貴な」とは訳しづらく、gentilis はハヤブサの方がふさわしい気がする。
Eversman (1866) "Estestvennaya istoriya ptits Orenbugskogo kraya" を見ると当時のハヤブサ類を指して Falcones nobiles (ロシア名では貴金属の "貴") と Falcones ignobiles (卑金属の "卑") に分けられていた。チゴハヤブサまでが前者で後者には (ニシ)アカアシチョウゲンボウ など。現代言われる Hierofalco とも違っていた。
noble/ignoble の位置づけも字義通りであったらしいことが推定できる。
Linnaeus のちょっとした不確実さ (または後世の不適切な解釈) で、本来ハヤブサに付くべき学名だったのだろう。あくまで現在は幻の学名だが Linnaeus が付けたかったと思われるものは (現代の分類で表記すると)、
ハヤブサ Falco gentilis Linnaeus, 1758 "同一民族のハヤブサ"
オオタカ Astur palumbarius (Linnaeus, 1758) "モリバトを捕らえるタカ"
になるだろうと想像 (夢想?) しておくこととする。あるいは識者が検討すればこの名前が復活する可能性もゼロではない気がする。特に後者は十分に正当な由来・理由がある。
オオタカの学名と意味を解説される方はぜひこれらの歴史を解説していただければと思う。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではオオタカの学名は属名も含めて上記の通りとなっていた。
(7) Linnaeus (1758) 記載の生息地について (#ハヤブサの備考と重複あり)
Linnaeus の「アルプスに住み」が気になったので調べておくと、Falco gentilis をオオタカとする解釈ではスウェーデンのダーラナ地方 (Dalarna) にも Alps と呼ばれるところがあり (Dalecarlian Alps) 一般的にはここが基産地と解釈されるとのこと。
Falco palumbarius がオオタカを指していたことは疑いないが、こちらの生息地 (基産地) はヨーロッパとなっている。同所に記されているヨーロッパチュウヒ、ハイタカも同じ生息地の記載になっているので整合性がよい。
他の種と見比べると Falco gentilis の生息地はヨーロッパと記さず局地的で特殊な記載になっている。
Lindberg (2008) The fall and the rise of the Swedish Peregrine Falcon population では歴史的分布も再現されているが、かつてはスウェーデンに広く分布していた。
迫害、有機塩素化合物、水銀汚染で一度はほぼ絶滅して再導入され、現在では南西部の山岳地の崖と北部ではタイガにある崖で沼地が近いところを好むとのこと。崖好みの習性からは Dalecarlian Alps の表現は整合性がよいと思える (#ハヤブサ備考に追記)。
British zoology (Pennant, Thomas 1768-70) によれば FALCON GENTIL は鷹匠が高く評価した種で、ドイツの鷹匠は Dalecarlian Alps (Denmark in Jutland and Norway) に求め、英国の鷹匠はスコットランドに求めたとある。 Dalecarlian Alps は特にドイツの鷹匠には上質の Falco gentilis の産地として有名だった模様。
1734 年の Linnaeus の同地の足跡の記述とよく合っている。
古くスウェーデンに分布していて鷹狩りに使われていたこと:
Bellamy-Dagneau (2015) A Falconer’s Ritual に特に北欧の鷹狩りの考古学的証拠がレビューされている。
西暦 500 年ぐらいにはすでに鷹狩りが行われていたと考えられる。埋葬品の中に猛禽類や獲物となる種類が含まれている研究がいくつもある。地位の高い者を埋葬する場合の伴侶の生贄も含まれているのでは。
鷹狩りに用いられる用具もみつかっているが、副葬品からも地位の高さがわかる。
オオタカ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、ハイタカなどの骨が見つかっており、これらの種類が古くから鷹狩りに用いられていたことを示唆する。キリスト教伝来以前の鷹狩りは霊的な、シャーマニズム的なあるいは儀式的な側面があったと考えられる。北欧特有の文化背景もあり、より南部のヨーロッパ大陸部でも同様であったかはわからない。
シャーマニズム的にはいろいろな側面があり、鷹匠は肉体的には鳥になることはできないが魂は鳥になることができ、猛禽を放す時に肉体を離れることができる。野生動物は戻らないが猛禽は戻ってくることができ魔術的なものと考えられてもおかしくないなどの考察がなされている。
この鳥は何? 古い図版でまた面白いものを見つけてしまった。Falco dubius Sparrman, 1787 (図版。記載) 産地スウェーデン。"疑わしいタカまたはハヤブサ" の学名。
Hartert (1910-1922) p. 1146 によれば Sundevall は質の悪いオオタカの若鳥の図版だとみなしたとのこと。Hartert はオオタカのシノニムとしている。
しかし目先の羽毛 [Hartert もこんな所を見逃してはだめですよ (笑)] や嘴、ろう膜と鼻孔の形はヨーロッパハチクマの若鳥にも見える気がする (その年生まれとすると虹彩色がちょっと合わない)。ふしょの露出部はヨーロッパハチクマに比べて長過ぎる感じもするが趾の描写はヨーロッパハチクマ的な感じがする。いかが?
オオタカもヨーロッパハチクマも 1758 年にすでに記載されているので学名に影響は与えないがスウェーデン語でオオタカとヨーロッパハチクマが区別されていなかった理由もわかる気がする。
記載の備考部分によればスウェーデンは時折みられるが頻繁ではない。シロハヤブサに変わると根拠なく考える人たちもある (最後部分は訳にあまり自信なし)。この記述の訳を信用すれば多分冬場はいないのだろう。サイズは確かにシロハヤブサと同じぐらい。
[系統と分類]
現在 Accipiter 属に対して提唱されている新分類では Astur 属となる見通しで (#アカハラダカの備考参照)、かつてオオタカに使われていた学名 Astur gentilis に戻ることになる。
記載時学名は Falco gentilis Linnaeus, 1758。
Astur 属の記載は Lacepede (1799)。
astur タカまたはオオタカ < asterias タカ (Gk)。
ラテン語の起源は複数説があり、主に3説: (1) acceptor 受け取るもの。accipiter からの影響を受けたと考えられる、(2) aster 星 < aster 星 (Gk) < インド・ヨーロッパ祖語 の *h2ster、(3) (ホシ) ムクドリを表すインド・ヨーロッパ祖語 の *(h2)stornos (wiktionary)。
(2) と (3) は似た感じに見えるがインド・ヨーロッパ祖語段階の起源が別のようである。
The Key to Scientific Names では原義を aster 星 (Gk) と示している。 ちなみに植物では Aster 属 (シオン属) があり、こちらは形態から語源は明瞭であるが、星とタカの関連は自明でない。みなさんも考えていただきたい。
フランス語の autour は古フランス語 (h)ostur でラテン語 auceptor < accipiter 由来とあり (wiktionary) 上記 (1) 説に対応する。結果的には accipiter から派生した名前だったのかも知れない。 フランス語ではもともと h が付いていたが発音しなくなって落ちた、p も途中で抜けたと考えれば納得できる感じもする。hawk と形は似ているがこちらはドイツ系で語源は異なる模様。
現在の (広義) Accipiter 属はかつては Accipiter (脚が長く趾は短めで小鳥を捉えるのに適する。ハイタカが典型) と Astur (脚が短めで趾が強力で小型哺乳類食にも向く。オオタカが典型) に分割されていた。
この分類は例えばフランス語で健在で、それぞれ epervier、autour と呼ばれている。
ほぼ同じ意味の分類がハヤブサ類ではチゴハヤブサ (hobby) とチョウゲンボウ (kestrel) の違いに当てはまるとのこと [Brown (1976) "Birds of prey: their biology and ecology"]。
世界で 10 亜種が認められている (IOC 13.1 まで)。IOC 13.2 でアメリカオオタカが分離され7亜種となった。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に記載の亜種オオタカは fujiyamae (富士山の。fujiyama に -e を付けて属格) でオオタカの亜種では比較的小型。亜種シロオオタカ albidus (「白い」の意味) は検討亜種とされている。
シロオオタカは北東シベリアとカムチャツカで繁殖し、多くの個体はバイカル湖の東、モンゴル北部、ウスリー地方に渡るとされる。比較的大型亜種とされ、オオタカの亜種の中では最も白っぽい (ほとんど白色の見事な個体によるマガモの捕食シーンがカムチャツカで撮影されている: 参考論文 p. 687)。
亜種チョウセンオオタカ schvedowi (ロシアの採集家 Ivan Grigor'evich Shvedof に由来) はウラル地方からアムール地方、ウスリー地方、中国東北部から中央西部、時にサハリンや千島列島で繁殖するとある。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種オオタカと亜種不明がリストされ、亜種シロオオタカと亜種チョウセンオオタカが検討亜種となっている。
wikipedia ロシア語版で亜種分布が異なっていることに気づいた。schvedowi の分布を北海道までとしており、fujiyamae を本州としている。wikipedia 日本語版にもかつてこの扱いであったことを示唆する記述がある。
この部分を記述してから 「日本動物大百科 鳥類 I」(日高敏隆監修 樋口広芳・森岡弘之・山岸哲編集 平凡社 1996) の記述に気づいた。当時は「北海道で繁殖するとされるチョウセンオオタカ A. g. schvedowi (異論も多く、今後再検討を要する)」と認識されていた。
日本鳥類目録第6版はでこの扱いであったらしい。
Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" (Birds of Sakhalin Island) (p. 86) ではサハリンのオオタカの繁殖個体について Dement'ev and Gladkov (1951) や Portenko (1951) は fujiyamae、Vaurie (1965) や日本鳥学会 (1974) では schvedowi と判断が分かれていたことを述べている。
Nechaev (1991) 自身は博物館標本を測定して fujiyamae の方だろうと考えていた。渡りの時期は疑いなく schvedowi が見られ、Stepanyan (1975) は繁殖期に albidus を記録しているとのこと。
wikipedia 英語版では 9-10 亜種と本文にあり、アメリカオオタカの分離に伴う変更もれが残ってそう (2025.1 時点)。
北海道のオオタカの亜種の扱いが2通りあったということは、この2亜種はゲノム解析などによる将来的な再検討によって統合される可能性も考えられることも意味するのかも知れない。以下の「オオタカ識別マニュアル 改訂版」にも計測値に重なりがあることが示されている。
ヨーロッパにはかつてもっと多くの亜種が認められていたが整理された (wikipedia 英語版から) ことを考慮するとあり得るかも知れない。
その場合は亜種 fujiyamae の方が記載が遅い (現行のオオタカの亜種のうち記載が最も遅い) のでシノニムとなって表に現れなくなるかも知れない。
分子遺伝学を用いた解析と従来の亜種概念が対応しない事例は#イヌワシでも知られており、今後再検討されるかも知れない。
後述の Kunz et al. (2019) によればデータがそれほど十分ではなくミトコンドリア遺伝情報しか使われていないが、fujiyamae が単系統をなしていないことがうかがえる。schvedowi に特に非常に近いわけではないが buteoides に近いハプロタイプを持つものが多い。
もしこの3亜種が統合されることになれば、schvedowi と buteoides はいずれも Menzbier (1882) の記載なのでどちらを採用するかおそらく判断が必要となるだろうが、記載論文 (参考文献参照) pp. 439-440 では schvedowi が先に現れよりしっかりした亜種記載となっているので統合されるならばこちらだろう。
サハリンの亜種がどちらか判断が分かれるぐらいなので3亜種にそれほど大きな違いはなく分子遺伝学、形態にも重なりがあるとすれば現代的な亜種概念には合わないかも知れない。
ユーラシア東部の中緯度からやや高緯度のグループと思えば統合された後のヨーロッパの亜種とも対応がよい感じがする。
buteoides の名称は "ノスリに似た" の意味だが、1866, 1868 年に Sabaneev が典型的なヨーロッパのオオタカとは違って (ここでは現在使われるロシア語名の他に golubyatnik と当時の学名 Astur palumbarius に合わせて "ハトを食べるもの" の名称も紹介している)、
ヨーロッパノスリ (当時の学名で Buteo vulgaris。Buteo vulpinus のことであると注釈) に似ていると述べたことに由来するもの。
Astur と Buteo の中間型ではないかとの見解も述べられていたとのこと (p. 441)。そのため Sabaneev も Astur sp.? としていた。
当時のロシアの猟師はオオタカとハイタカの他に3種めがいると考えて yastreb-gushyatnik (ガンを食べるタカ) の名前で呼んでいたが、オオタカの大型個体ではないか。Danilov は Astur major の名称も用いていたがこれはハイタカを指して使われたことを知らなかったのだろう (誤用) との注釈あり。
Menzbier (1882) 自身は Sabaneev の言うところの "ノスリに似た" については何とも言えないが、自身の持っている2標本は Buteo vulpinus よりケアシノスリにより似ていると記している。
Hartert (1910-1922) p. 1149 は buteoides を亜種として認めず、標本によるわけではない型の記述のみで学名に値しないとして schvedowi のシノニムとした。
Menzbier の記載を "ロシア語!" としており、少なくとも当時は記載言語には適さないと考えられていたことがわかる。
参考までに同ページでカムチャツカの albidus は ? 付き。Pallas が最初に用いた Accipiter astur, varietas no. 3 を改名したものとある。白いものは他所にも存在するではないかと亜種に値するかだいぶ怪しげに見ていた。
buteoides はもともとそれほどしっかりした亜種記載ではなく、Dement'ev and Gladkov (1951) などはシベリア西部の亜種と認めて位置づけたものと考えられる。同書では基亜種よりずっと明るい色で、白っぽい個体は東方の alibidus と区別できないとあり、このような淡色の個体はおそらくタイガの森林限界や森林ツンドラで繁殖するのではと考えていた。
buteoides は白っぽくても alibidus までは脱色が進むことはないとしている (上記 Hartert の議論を受けたものと思われる)。
alibidus の方が少し大きい。これらオオタカの白色型の分布関係はシロハヤブサ (ちなみにシロハヤブサは現在単形種扱い) によく似ている。シベリア北東部では半数が白いが亜種として分けるほどの根拠はないとのこと。
schvedowi はもともと Darasun とザバイカルで記載されたもので、Dement'ev and Gladkov (1951) はシベリア中央部型と位置づけた。
トルキスタン地方の鷹匠は buteoides のまれな白色のものを tujgun と呼んで高値が付いていた。明るい色でまだらの buteoides を tundzhir、schvedowi と suschkini を kush と呼んでいたとのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) は fujiyamae は大陸東部にも分布していると考えていたが、schvedowi と本当に区別できるかどうかは意見が分かれている (日本鳥学会 1932; Hertert and Steinbacher 1936)。分布もよくわからないが日本とサハリンで分けるのが通例となっている。プリアムールと沿海地方の少数の標本では schvedowi より少し小型で色が濃いとのこと。
schvedowi と分離するならば同じようなサイズ・色彩のチベットや中国甘粛省の khamensis と同亜種とすることもできるかも知れないとのこと。
緯度によるクラインで亜種間にあまり違いがないことをある程度暗示していた。
現在では khamensis も suschkini も schvedowi にまとめられるのが通例。
khamensis は繁殖隔離分布となっているのでこれが schvedowi にまとめられるならば fujiyamae も同様に考えられるのかも知れない。
オオタカ識別マニュアル 改訂版 (環境省 2016) も参照。違法取引と違法飼育、および違法捕獲の防止が目的とある。国内希少野生動植物種 (古くは特殊鳥類) 指定にかかわる歴史的経緯は #クマタカ備考 [クマタカと鷹狩り] も参照。
指定解除に関連して 東京オオタカ・シンポジウム
(日本野鳥の会 2014) の情報がある。
世界の亜種分布 (オオタカ上種) の地図は Kunz et al. (2019) Mitochondrial phylogenetics of the goshawk Accipiter [gentilis] superspecies で見ることができる。この解析の結果からオオタカ上種間で系統が入り組んでいることが示唆される結果になった。
つまりシロハラオオタカ Accipiter meyerianus (英名 Meyer's Goshawk、ニューギニアなど)、マダガスカルオオタカ Accipiter henstii (英名 Henst's Goshawk)、オオハイタカ Accipiter melanoleucus (英名 Black Goshawk、中央から南アフリカ) がこれまでのオオタカに内包されていた
(論文中の学名を用いている。これらはいずれも現在の標準的分類では Astur 属)。
そのためこれまでの "オオタカ" から3亜種を アメリカオオタカ Accipiter atricapillus (英名 American Goshawk) として独立種に分離されることになった (IOC 13.2)。
ユーラシアと北米の旧オオタカが別種となったのは、ユーラシアと北米の違いが認識されたこともあるが、すでに種命名のあったオオタカ類他種に対して単系統性を保つ必然性があったことが大きな要因と理解してよいだろう。シロハラオオタカやオオハイタカなどを改めてオオタカの亜種と定義するには遺伝的にも外見的にも違いが大きすぎた。
オオタカとアメリカオオタカを "オオタカ上種" のように扱うならば、シロハラオオタカ、マダガスカルオオタカ、オオハイタカもオオタカ上種に含まれることになる。
Sangster (2022) The taxonomic status of Palearctic and Nearctic populations of northern goshawk Accipiter gentilis (Aves, Accipitridae): New evidence from vocalisations の音声などを用いた研究もこの結果を支持するものであった。
AviList (2025.6) では 8407 710 Taxon atricapillus (polytypic, including laingi and apache) is treated as a species separate from Astur gentilis based on mitochondrial DNA data (Kunz et al. 2019) that recovered A. gentilis sensu lato as non-monophyletic. The split of A. atricapillus is supported by nuclear DNA evidence (Geraldes et al. 2019), vocalizations, plumage, and iris color (Sangster 2022), although the analysis of vocalizations suffers from incomplete sampling.
とまとめている。単系統性を保つ必然性が最も重要な要因で、この点は核 DNA でも支持された。Sangster (2022) は表現型の違いを扱ったもの。アメリカオオタカの "赤目" も一つの要因に含まれているが、根本的な判断は単系統性の要請から。
Astur gentilis と表記することはもはや当たり前で、Accipiter gentilis の学名を使い続けるのはむしろ海外とのコミュニケーションの障害になるかも。
Kunz et al. (2019) が旧北区のオオタカの連続した遺伝的分布を示しているように、旧北区では音声面でも亜種判別はできなかった。亜種というより地理的なクラインを形成していると考える方が適切かも知れないが、音声記録は限られているためより多くの亜種を含め、さらに多くの音声を記録する必要がある。
Clements 2023、eBird 2023 のリストではオオタカとは別種となっている。北米の "オオタカ" を扱う時、あるいはオオタカ全体を扱う時に北米の分布をどう記述するかなど注意が必要であろう。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)ではアメリカオオタカを別種とする扱いになり、最終的に日本の扱いでも分離された。
[Astur (オオタカ) 属の系統分類]
順序は基本は Catanach et al. (2024) によるが、オオタカ以降は Kunz et al. (2019) を加味して少し入れ替えてある。
亜科相当 (ハイタカグループ)
オオタカ属 Astur
(系統 1: クーパーハイタカ属 Cooperastur の名称も提案されている)
モモアカハイタカ Astur bicolor Bicolored Hawk
チリハイタカ(*) Astur chilensis Chilean Hawk
ズグロハイタカ* Astur gundlachi Gundlach's Hawk
クーパーハイタカ Astur cooperii Cooper's Hawk
(系統 2)
オオタカ Astur gentilis Eurasian Goshawk
マダガスカルオオタカ* [高野 (1973) ではヘンストオオタカ] Astur henstii Henst's Goshawk
オオハイタカ [高野 (1973) ではシロクロオオタカ] Astur melanoleucus Black Sparrowhawk
シロハラオオタカ* Astur meyerianus Meyer's Goshawk
アメリカオオタカ(*) Astur atricapillus American Goshawk
前述のように Astur 属は2系統に分かれる。全体を Astur 属とする分類で表示している。
チリハイタカはモモアカハイタカから分離されたもので Catanach et al. (2024) に含まれていないので (*) を付けてこの場所に追記しておく。IOC (version 1.0 から)、eBird 2022 以降、Clements は別種扱いだが分離していないリストもある。
モモアカハイタカとの中間型のような亜種 pileatus があり、通常はモモアカハイタカの亜種とされるがどちらの種に属するか決着していない (wikipedia 英語版より)。
Catanach et al. (2024) は最初の系統 (チリハイタカも含めて4種) が Cooperastur 属 (Cooper + Astur の合成。ラテン語式に読めば "コーペラストゥル" となるだろうか) となる可能性も示している。分岐年代的には他の属の分岐 (例えばイヌワシ亜科内の属の分岐) とさほど違わない。もし分離されるならばクーパーハイタカ属となるだろう。
クーパーハイタカの記載は Cooper's Hawk American ornithology; or, The natural history of birds inhabiting the United States。
記載時学名 Falco cooperii Bonaparte, 1828 で長い前置きの後に p. 9 ニュージャージー州で標本を採集した。Mr. William Cooper がロングアイランドで採集した標本と詳細な記述を提供したことへの献名であることが示されている。
Linnaeus の述べた Falco gentilis によく似ているが、これはオオタカの若鳥を指した学名 (と当時すでに解釈されていたたらしい) で、混乱要因となることを未然に防ぐために新しい学名を与えることにした (p. 8) とある。我々のタカ (クーパーハイタカ) は "若いオオタカ" とされるものによく似ているが微妙な違いがある。
Catanach et al. (2024) の段階ではアメリカオオタカは分離されていなかった。論文を検討した結果、日本の愛知の個体で読まれたゲノムを用いており、Catanach et al. (2024) の系統樹における分離前の "Accipiter gentilis" はアメリカオオタカではなくオオタカであることが確認できた。
Kunz et al. (2019) ではミトコンドリアのコントロール域と cyt b を用いたもので核遺伝情報を用いた Catanach et al. (2024) と用いた遺伝情報が異なるため単純比較はできないが、アメリカオオタカ以外の系統樹形態は一致しており、Kunz et al. (2019) の系統樹ではアメリカオオタカは別の分岐にあたる。
ここではこの系統樹を用いてアメリカオオタカをオオタカの隣ではなくこの系統の最後に置いた。
Kunz et al. (2019) のハプロタイプのネットワーク図から受ける印象と少し異なるが、系統樹を見るとアメリカオオタカ1種と残りの4種が少し離れた系統に属することがわかる。どちらが早いかは微妙なところだが4種の系統の方が若干早い分岐になっているのでその順序を採用した。
簡易解析でも試すことができる MK433189.1 を出発点に BLAST を実行すると cyt b の系統樹が得られ、これだけでもオオタカとアメリカオオタカが大きく違うことがわかる。この解析では (2025.2 時点) オオタカとシロハラオオタカがまとまる結果となったが用いた塩基配列が短いのでこの程度の精度なのだろう。
この解像度の系統樹ではヨーロッパとシベリアのオオタカは事実上同じと出る。
改めて系統を見てみるとアメリカ大陸の Astur 属の 系統 1 (クーパーハイタカを含む) はどこからやってきたのか気になる。オオタカを含む 系統 2 はアフリカにも分布するのでアフリカや赤道付近から分布を広げたと理解することが可能だが 系統 1 がユーラシアから到達した痕跡がわからない。
この中で系統的にはクーパーハイタカより古いはずのモモアカハイタカは現在中南米に分布。ただし Astur 属全体では最も普通の種類とある (wikipedia 英語版)。
狭義 Accipiter 属の最も古い系統がセグロオオタカで南米に生息するのが気になるところ。しかし狭義 Accipiter 属が南米出身でユーラシアからアフリカに分布を広げたとすると、中間に分布するハイタカが新しい系統であることと整合しない。
すべてがアフリカや赤道付近から分布を広げたと考えると、ユーラシアから北米に セグロオオタカ / セグロオオタカを除く狭義 Accipiter 属 / Astur 属 系統 1 / Astur 属系統 2 の少なくとも4回の導入が起きたと解釈するのが妥当なのだろうか。セグロオオタカのように競争力が弱いなど、比較的古い系統は途中段階の分布が競争などで消滅したなど考えることができる。
セグロオオタカの系統がアメリカ大陸に分布した時期は分岐年代から 2000 万年前ぐらいと想像でき、アメリカ大陸にはまだ Spizaetus 属やノスリの系統も到達していなかったためまだ強力な競争相手もおらず分布を広げられた可能性が考えられる。当時の競争相手はカタグロトビ亜科やハチクマ亜科、そして現生種が少ないので系統関係や到達時期がわかりにくいがオウギワシの系統が考えられる。
"オウギワシらしさ" が作られたのは 1700 (1300-2200) 万年前ぐらいと推定される (#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化]) ので、セグロオオタカの祖先系統とオウギワシの系統に競争があったかも知れない。
セグロオオタカがアカエリクマタカに擬態しているならば後から到着した Spizaetus 属に擬態していることになる。年代順序関係はハチクマ類とクマタカ類の容貌の類似関係にも近いので相互擬態による収斂の可能性も考えてしまう (#ハチクマの備考 [擬態と種・亜種の関係] ハチクマのクマタカへの擬態解釈の再検討 参照)。
Astur 属の 系統 1 と 系統 2 のどちらが先なのか考察した結果気づいた問題だが、アメリカ大陸の Astur 属 系統 1 の方が先に定着し、その後により強力なアメリカオオタカがやってきてクーパーハイタカと北米を分け合う形になったが、クーパーハイタカが先に占拠していて十分に競争能力があったため、北方から回ってきたアメリカオオタカをそれ以上南下させなかったなどの過程が考えられる気がする。
主要食物が違って分け合っているのかも知れない。アメリカオオタカの方がユーラシアのオオタカより少し小さい理由など何か提唱されているだろうか。
オオハイタカ [高野 (1973) ではシロクロオオタカ] の和名変更が行われた理由は、Great Sparrowhawk の英名が使われていてこれを訳したためと想像できる。高野氏の名称は学名から訳したものに対応する。Astur 属に変更となり遺伝的にもオオタカと非常に近いことが明らかになったので、"ハイタカ" の名前を消して、改めて "オオタカ" 系統の名前を付けてもよい感じがする。
マダガスカル以外のアフリカには他の Astur 属は存在しないので、アフリカオオタカでも構わない感じがする。ただし暗色型・淡色型の morphs が存在することで有名で、遺伝的背景などもよく研究の対象になっているので、地理分布よりこの特徴を反映した "カワリオオタカ" も可能そうに思えるが、これは Tachyspiza hiogaster または Tachyspiza novaehollandiae にも使われるので混乱要因となるかも知れない。
高野氏のシロクロオオタカは実はよい名前かも知れない。"カワリオオタカ" の Tachyspiza hiogaster または Tachyspiza novaehollandiae の和名を Tachyspiza 属を反映すべく整理した方がよいかも知れない。"カワリオオタカ" (Variable Goshawk) はそもそも別種・morphs の区別ができていなかった時代の名称なので、現在でもふさわしい名前とは限らない。
シロクロオオタカは Tachyspiza imitator に使われるなど過去の用例と整合性が取れておらず和名が混乱している状況にある。属分離が確定した現状で海外種の和名を整理するよい機会かも知れない。
[カンムリオオタカ]
これまで Accipiter 属に含まれていたカンムリオオタカ (または旧名タイワンオオタカ) Accipiter trivirgatus (英名 Crested Goshawk) は台湾に生息し (亜種 formosae)、台湾産亜種が日本で観察される可能性があるとのことである (資料)。この種も台湾で巣のライブ中継が行われていた。
名前から想像するほど大きなタカではない。オオタカとは系統がかなり異なり、Accipiter 属に対して提唱されている新分類では Lophospiza 属
(lophos 冠 spizias タカ Gk。読みのカタカナ表記は#アカハラダカ考察より、Kaup の他のタカ類の -spiza に合わせて "ロポスピツァ" を採用しておく)
となる見通し
[Sangster et al. (2021) で提案された]。
IOC 14.2 のようにこの分類をすでに採用しているところもある。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 でも採用されているので今後はこちらに統一されるだろう。
唐沢 (2014) Birder 28(11): 68-70 に台湾での記事がある。
CRESTED GOSHAWK--POWER LIFER! (Ferdie Llanes de AvesFlores 2024.11.18) フィリピンのパラワン島での撮影。この島では亜種 palawanus が知られている。
Mayr (1949) Geographical Variation in Accipiter trivirgatus が各亜種を記載して既知亜種も含めて比較している。パラワン島のものは固有亜種でボルネオ島とも異なるとのこと (#ハチクマなど他種もパラワン島は特異な分布を示す傾向がある)。
台湾の formosae もこの文献で記載。
地理的クラインの観点も示しているが遺伝的にもある程度違うのかも知れない。
[クーパーハイタカの繁殖開始年齢] の項目に Lin et al. (2015) のカンムリオオタカの繁殖生態の研究を紹介している。
[英語他のオオタカの語源]
単に Goshawk と言えばこの種を指すことに誰も疑念を持たないだろうが、他にも Goshawk の名前を持つ種類が複数あるため、学術的な文脈では American Goshawk を別種とする現在の立場で Eurasian Goshawk がよいだろう (IOC 13.2 以降英名 = 日本鳥類目録改訂第8版も同じ)。
Northern Goshawk はオオタカとアメリカオオタカが分離される前の名称。今後は使わない方がよいと思われる。
なお広義 Accipiter 属以外の属にも Goshawk の名をもつ種類がある。例えば Melierax 属のウタオオタカ類 (Chanting Goshawk の名を含む種類が3種ある) が有名である。
英語の goshawk は goose-hawk (ガンのタカ) を意味する goshafoc が短くなったもの (Online Etymology Dictionary)。[オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑] にある 1911 Encyclopdia Britannica/Gos-hawk 百科事典によればハヤブサ類の誤用の可能性がある。実際にガンが獲物となることは少ない (wikipedia 英語版より)。
アメリカでは Chicken Hawk の別名 (他の中型タカ類も同様に呼ぶ) があるように、家禽を襲う猛禽類としてあまりよい意味で使われていなかった模様。もちろんバーダーには実態を反映しない名称とされている。
オーストラリアでも チャイロハヤブサ Falco berigora Brown Falcon が同じ別名を持っており、意味するところは同じだろう。
アメリカの政治の俗語では臆病を表すチキン (鶏) とタカ派を表すホーク (鷹) を合わせたもので「臆病な強硬派」を意味するとのこと (wikipedia 日本語版より)。
英語で noble hawk は「孤高のタカ」のようなよい印象で使われるが、特にオオタカを指すわけではなくタカ類一般に使われる。
noble goshawk の用例を探してみると A Noble Goshawk とウタオオタカだった。
この意味の用例はあまり見当たらず、少なくとも英語圏ではオオタカを「高貴な」と呼ぶのは伝統的学名から (正しいかどうかわからないが) 先取権に基づく学名に変更され、意味を合わせるために解釈が後付けされたように見える。「高貴な」の語義はハヤブサ、オオタカいずれにも実はどこにも出てこなかったかも知れない。
ドイツ名は Habicht で英語と全然違うが遡れば英語 hawk と同じ語源になる (なおドイツ語ではタカは Falke。ハヤブサ類と区別されない)。フクロウのドイツ名 Habichtskauz (オオタカのフクロウ) のような合成語にも使われるので知っておくと面白い。
ドイツ地方名ではやはり家禽を襲うことから英語同様の Huehnerraeuber, Stossvogel のような名称がある。もっともドイツ語では猛禽類全般の名称の一つが Raubvogel (盗っ人鳥) なのでオオタカだけが特別というわけではない。
有名なハプスブルク (Habsburg) は城を建てるとオオタカが住み着いて Habichtsburg と呼んだとの伝説があるが、実際は古ドイツ語の hab/haw (川を横切る) 由来と考えられる。
ポルトガル沖のアゾレス (Azores) 諸島の旗にオオタカが描かれているが、オオタカは生息せずーロッパノスリの固有亜種が生息している。この件は #ハチクマ備考の [ヨーロッパハチクマの渡り] にも関連情報あり (wikipedia ドイツ語版より)。
アゾレス諸島が紹介されるのは、これだけよく知られた鳥なのに国鳥にしているところがないためだろうか。wikipedia 英語版によればインドのパンジャブ州の鳥になっているとのこと。
オオタカもロシア名が面白く teterevyatnik (ライチョウ類を食べるもの)。このようなところからロシア語の鳥名の世界に入るのも面白い。ウクライナ語では beliki yastreb と単に「大きなタカ」であまり面白みがない。ちなみにベラルーシ語では shulyak-galibyatnik で「ハトを食べるもの」。ラテン語族では Astur から派生するものが多い。
フランス語は Autour des palombes と Accipiter palumbarius の学名が生きている [オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑] 参照。ルーマニア語も同様。
フランス語別名に epervier bleu (青いハイタカ) がある。
他言語でも「大きい」か「普通」を冠するものが普通あるいは、英語と同じくガン (ノルウェー語など)、森の (チェコ語など) などで、「高貴な」を意味を用いた言語は見当たらなかった。
[タカとハヤブサの握る力と噛む力]
タカ類とハヤブサ類の握る力と噛む力を実測した論文があったので紹介しておく。
Sustaita and Hertel (2010) In vivo bite and grip forces, morphology and prey-killing behavior of North American accipiters (Accipitridae) and falcons (Falconidae)
北米の種なのでタカ類はクーパーハイタカ (新分類ではオオタカ属) とアシボソハイタカ (新分類でハイタカ属) なので日本のそれぞれの種に相当する程度の数値として見ていただくとよいだろう。
ハヤブサ類はアメリカチョウゲンボウ、コチョウゲンボウ、ハヤブサ、ソウゲンハヤブサ。
飼育個体を用いて多くは野生から救護されてリハビリテーションの最終段階の個体とのこと。
鳥を検者が抱えて足や嘴の前に掴める/噛める装置を提示して握力などを測定した。多くの鳥は熱心にやってくれたが一部の鳥は協力してくれなかったとのこと。握らせたりくわえさせて腹や口に刺激を与えて反応させた場合もあった。
おとりを捕まえさせて測定する方が現実に近いように思われるかも知れないが、これはどちらかと言えば防御反応の能力を反映するもので最大値をあまり表さないとのこと。
測定値は表にあるのでお楽しみいただきたい。クーパーハイタカ、アシボソハイタカではメスの方が 1.5 倍ぐらい力が強いがハヤブサ類では 1.3 倍程度。クーパーハイタカのメスの最大値で 10 N = 1 kg重ぐらい (N ニュートン → kg重 または kgf には 9.8 で割ればよい) の握力。ハヤブサのメスの最大値で 13 N ぐらいが出ている。
噛む力は同じ組み合わせで 3 N と 13 N と、タカ類では握る力の 1/3 ぐらいなのに対してハヤブサ類では握る力と噛む力がほぼ同じぐらいか、ソウゲンハヤブサでは2倍以上 (同サイズのタカの握る力よりも大きい)。
獲物を殺す方法の違いに対応する違いが現れる結果となった。
ハヤブサ類では握る力以外にも飛翔時の相対速度で効果的に力を加えている可能性もある。咀嚼筋 (翼突筋 m. pterygoideus。ここでは m. は musculus 筋肉のラテン語。解剖学名もラテン語がそのまま使われることが多い。翼突筋は実際には単一の筋肉ではなく筋群をなしている) が役立っていることも判明している。顎関節もそれに耐える適応があるとのこと
(注: その分ハヤブサ類の方が頭部が多少重くなるだろうし表情も豊かになるだろう)。
ハヤブサ系統から進化したオウム類の噛む力が強力な理由にもなっているかも知れない。
猛禽類では趾の腱や腱鞘に力を逃さない適応が見られるとのこと [Einoder and Richardson (2006) An ecomorphological study of the raptorial digital tendon locking mechanism]。
解剖学データ (筋肉の太さや腱の構造など) から予測される値よりは3割ぐらい小さいとのことで、解剖学から予想される値は多少過大評価になっている可能性があるが、実際に獲物を殺す時ほど熱心に力を出していない可能性が考えられる (ただし数割の違い程度なので馬鹿力を出しても何倍も大きくなることはないだろう)。
タカ類の握る力は体重の 0.8 乗ぐらいに比例とのことで、広義ハイタカ属と同じ関係がそのまま使えるとすれば、4.0 kg のイヌワシを想定すれば 5.7 kg重ぐらいになる。人の指1本では負けるかも知れないが大人の力で動かせない数字ではないように見える。
「ワシ 握力」で検索するとすぐ 100 kg などの数字が出てくるがこれも「神話」の一種なのだろう。
試しに 100 kg の力を出すためにはどの程度の筋肉の太さが必要か逆算してみた。
この文献で用いられている値は筋肉1平方センチメートルあたり 25 N なので、直径 7 cm ぐらいの筋肉が必要になる。さすがにそんなところに過剰投資をする余裕はないだろう。
Dickinson et al. (2025) Ecomorphological correlates of grasping forces in strepsirrhine primates
哺乳綱霊長目曲鼻亜目 (キツネザルなど) の握る力の測定。大きな親指を持って木の枝を巧みに移動するが握力が他の哺乳類より勝っているわけではない。樹上性の鳥とも比較すると体重あたりではオウム類の方がずっと上だった (タカ類は対象になっていないが負けることはなさそう?)。
strepsirrhine primates はビタミン C 合成能力を失っているなど霊長類と樹上性の鳥の収斂進化も少し垣間見える気がする。
[2種類の鷹匠]
鷹狩り関連の英文を読まれる方であれば「鷹匠」に相当する単語が2種類あることに気づかれているかもしれない。よく使われる方の falconer は主にハヤブサを使う鷹匠。austringer がオオタカを使う鷹匠であり、ここにも語源の Astur が見え隠れする。ちなみにハヤブサの方がずっと人によく慣れ訓練もやさしいが、オオタカは気難しいと言われる (オオタカの方が頭が悪いと言われる方もあるが、野生の生活を観察されている方であれば反論されるかも知れない。
ただし系統分類的にはハヤブサはオウム類に近いため頭がよいのも理解できる。#ベニマシコの備考も参照。ロシアで記載された飼育下のタカ類と小型ハヤブサ類の行動の違いは#ハチクマと#チョウゲンボウの備考も参照)。
初心者 austringer が初めてオオタカを飼って苦労した White (初版 1951) "The Goshawk" (Penguin Modern Classics) という本がある。古典的に有名な本であるが、「このように飼育してはいけない」反面教師ともされる。The Goshawk (1969年 の BBC 映画) の元になっていると言って大きな間違いはないだろう。
この本は近年再評価され書評は The Goshawk, By TH White - book review: Avian classic finds its second wind
にある。中に出てくる "H is for Hawk" も和訳されていて「オはオオタカのオ」(ヘレン・マクドナルド著 山川純子訳 白水社 2016)。「ドはドーナツのド」の歌があるが上記英語表題も同様の使い方で和訳タイトルも同様。
[兄弟殺し]
イヌワシ類ほど顕著ではないが、オオタカでも兄弟殺しが起きることがある。Chick kills his sibling. Loch Garten Goshawks. 22 June 2023 の映像が紹介されており、こんなに激しいのは見たことがない。餌が運ばれてきたばかりなのに見向きもせず兄弟殺しが起きたとのこと。
[ハトを襲うオオタカの戦略]
Rutz (2012) Predator fitness increases with selectivity for odd prey
によればオオタカは群れの中の変わった個体を狙うとの研究結果がある。その結果目立つ表現形の個体が排除されてゆきそうだが、ハトは自分と異なる色の個体とつがいを作る傾向があり、多様なハトの表現形が維持されているだろうとの話。
[オオタカの成鳥・幼鳥の色彩]
川口 (2020) Birder 34(9): 54-55 で、ハイタカの成鳥・幼鳥の色彩の違いについて、紫外線の見える鳥には一目瞭然に違って見えるのか問題提起がある。
ハイタカのデータは見つけられなかったが、オオタカのものがあったので紹介しておく:
Spicka et al. (2024) Function of juvenile plumage in the northern goshawk (Accipiter gentilis): aggressive mimicry hypothesis
の Fig. 2 によれば下面の白色部分の反射スペクトルの違いが一番大きく、オオタカの成鳥で紫外線から青にかけて反射率が高い。タカ類の紫外線受容体のピーク波長が 430 nm ぐらい、ただしタカ類の目は紫外線透過率が悪くて 400 nm より短い光はあまり感知されていないはず。
このことを考慮に入れても成鳥・幼鳥の紫外線の反射率にはかなり差があって下面の白色部分は成鳥の方が 1.5 倍ぐらいよく反射する。下面の暗色模様の反射スペクトルには成鳥・幼鳥にあまり違いがなく、我々も下面の白色 (背景) 部分の青の反射率の低さを褐色味として認知している模様。紫外線の見える鳥にとっては一層明らかな色の違いになっているだろう。
この論文ではヨーロッパノスリの色彩がオオタカの成鳥と幼鳥の中間になっている。
オオタカ幼鳥がメス成鳥の色彩を真似て同種内の攻撃を防いでいる仮説も、オオタカでは他の広義 Accipiter とは違って成鳥の色彩の性的二形が小さいため否定的。オオタカ幼鳥の色彩には何らかの適応的が意味があるだろうが、オオタカが捕食されるケースはまれ (大型フクロウ類による夜間捕食) なので幼鳥の色彩が保護色として働いている可能性は低いのではないか。
ハイタカでも同じことが当てはまるかは実際に調べる必要があるだろう。
オオタカの色彩が食物量に影響される可能性を示す論文: Galvan et al. (2019) Pheomelanin synthesis varies with protein food abundance in developing goshawks
システインが細胞のライソゾームに蓄積すると有害なため CTNS 遺伝子が働いて排出する機構がある。
食物量が豊富だとこの遺伝子が働いて羽毛のメラニン合成を抑制すると想像されるが成鳥では相関が認められなかった。ひなの色彩には関係がある可能性を示す結果が得られたとのこと。
[オオタカの生息確認は難しい?]
#ハチクマ備考 [ロシアのハチクマとヨーロッパハチクマの研究のための情報] で紹介の Karyakin (2004) "猛禽類の調査方法" (参考文献参照) pp. 210-211 によればオオタカの繁殖証拠を見つけるのが難しいことが述べられている。
ほとんどのタカ類同様に隠蔽的で生息を明らかにすることが難しい。大部分の森林地帯では(ヨーロッパ)ノスリの密度より低くないが、一見(ヨーロッパ)ノスリより何十倍も少なく見える。多少は適した時期はつがい形成の時期の4月。
(ヨーロッパ)ハチクマでは音声プレイバック法で生息確認を行いやすいが、オオタカはつがい形成時の音声、警戒音、ワシミミズクの音声いずれもあまり有効でなく、より近距離でないと反応しないので成功率が低い。(ヨーロッパ)ノスリのように車で後を追いかける方法も難しいとのこと。
越冬時期に見つけるのはさらに難しく、生息密度の現実的な数字を知ることはさらに難しい。都市域の緑地で獲物の生息する森林地域に近いところの方がむしろ見つけやすい。そのような地域では巣からあまり遠くない地域に 1-3 羽のオオタカが越冬するのが普通である。特に漂行するカラス類はオオタカを惹きつける。越冬時期のオオタカの行動圏を調べるのは春がよく、獲物の痕跡が雪が解けて現れるのを探すとよいとのこと。
p. 215 ではハイタカは繁殖期の巣からの声で結構見つけられるとのこと。ハイタカは孵化後よく鳴くのでより容易になるとのこと。
オオタカは頂点捕食者のはずなのに意外にもかなり隠蔽的な種類らしい。
状況はおそらく日本でも同様だったのではないだろうか。ある程度まとまった面積であれば結構どこにでも住んでいるが簡単な調査では繁殖を確認することができず、自然保護団体が丁寧に調べれば営巣が確認されたなどの背景事情が想像できる。おそらくその場所だけが特別で重要だったのではなく、同程度の面積で似た環境であれば同じような重要性となっていたのだろう。
Karyakin (2004) のこの文献では vyyavlenie の単語が使われており、辞書訳では (見えなかったものを) 現わす・示すこと; 暴露する となるが "猛禽類の暴露方法" では意味不明なので訳すならば少し工夫が必要となる。ここでは "生息を明らかにする" と訳してみた。単語を見れば意味がわかるが日本語になりにくい例。
vy- は行動の達成や内部からの運動を示す接頭語、yavno が "明らかに"、対応する動詞が yavlyat'sya などなのでスラブ言語の語構成的には意味が取りやすい。英語だと ex- を類似の意味の接頭語として expose / exposure が近いだろうか。
[英国のオオタカ]
英国ではオオタカが一時野生絶滅だったことを知った。「動物の世界」2版 5 (日本メール・オーダー 1986) pp. 698-700 (浦本) の解説によれば狩猟家から狩猟鳥を捕まえると敵視され、19 世紀末にはほとんどいなくなった。Sussex で 1938-1951 年に 2-3 つがいが繁殖していたがこれも狩猟家に撃たれて絶滅したとのこと。原本の "Purnell's Encyclopedia of Animal Life" の発行されたのは 1968 年で英国では野生絶滅状態だった時代だった。
しかし鷹狩り用のオオタカが逃げたり放されたりして個体数が回復してきたらしい。Goshawk (wildlifetrusts.org から)。
英国の現在のオオタカにはこのような背景があって、バーダーから必ずしも完全に歓迎されていないらしい事情が理解できた。飼育個体が逃げて個体群を形成したならば人為導入ではないかと悩ましいわけだ。とはいえ (おそらく) 渡ってきた個体由来の個体と原理的に区別困難なため野鳥扱いとなっている。
上記の 1938-1951 年のことも書かれていないものも多く、飼育個体由来とみなして無視される場合もあるのかも知れない。
英国ではアカトビやオジロワシなど再導入による復活がメディアなどで宣伝されている割にはオオタカには冷淡である。個人趣味や任意団体由来だと「お墨付きの」再導入とはみなしにくいのだろう。
Goshawk reintroduction to the UK のページによれば 1971 年にフィンランドやスウェーデン由来のオオタカが British Falconers Club をパートナーとして行われたとのこと。
Goshawk (Scottish Raptor Study Group) にも歴史の解説があり、保護団体によるものではなく鷹匠やタカの飼育者が再導入したとのこと。関連部分を紹介しておくと:
They were reintroduced from the 1960s onwards, not by any conservation organisation, but by falconers and hawk-keepers who brought birds into the country initially from Poland and Germany, then subsequently in the 1970s from Finland (Petty 1996). Some of these imported birds escaped from captivity and others were deliberately released, to establish wild populations for harvest.
この記事では reintroduced の表現も使っているが、他の記事では deliberately released とのみ記されているものもあり、再導入 (reintroduction) とは呼びたくないことを暗に示唆しているように思える。鷹匠グループが新たな個体を野生から獲得するために野生個体群を復活した、ということらしい。野生個体に育ててもらったひなが欲しいわけで意図はよく理解できる。
確かに狩猟のために狩猟鳥を放鳥するのと何が違うかと言えば区別が難しい。では「お墨付きを得た」再導入と何が違うかと言えば人側の目的が違うだけでこれまた本質的な違いはないように思える。
オオタカの基亜種は Linnaeus (1758) 記載のもので基産地スウェーデン (原記載では Dalecarlian Alps。既述のように Hartert によりスウェーデンと認定。Linnaeus はおそらくハヤブサの産地を意図していたと考えられる) と定義されており、多くの種で行われたように英国は大陸と別亜種扱いであったならば亜種を絶滅させたことになっていたはず。
Hartert (1910-1922) p. 1146 でも英国で記載されたオオタカがシノニムとされた形跡が今ひとつ見当たらない。英国はオオタカの場合は自国の亜種は別と主張しなかったのだろうか。
当時は害鳥扱いなので、英国独自の害鳥はおりませんとの主張か、あるいは自国亜種を絶滅させたとすれば格好悪いので積極的に主張されなかったか、さらにあるいは鷹狩りで大陸から輸入物がすでに使われていて亜種を認めがたかったのかも。
さらに Hartert の時代には英国では事実上絶滅しており当時の分類学で過去の状況まで議論するにも値しなかったのだろうか。
Dement'ev and Gladkov (1951) も見ておくとこれまですごいことになっていて、アイルランドが現在の別種アメリカオオタカに相当する亜種が越冬する分布で、英国諸島にはオオタカの大陸の亜種は分布しない扱いとなっていた。
どうも亜種概念を認める近代的な分類学で議論される以前に事実上絶滅していてうやむやになっていたように思われる。他種ではある程度英国と大陸との違いを認めていても、英国のオオタカが別亜種とは特に大陸の者にとっては考えにくく、英国から積極的に主張が出て過去の標本を調べて別タクソンだと言わない限り誰も取り上げないのだろう。
[猛禽類の声変わり]
オオタカ、ワキスジハヤブサなどでひなから成長するにつれて音声がどのように変わるかを調べた論文があった。Marchenko et al. (2018)
Ontogeny of vocalization in diurnal birds of prey (Falco cherrug, Accipiter gentilis)
(ロシア語。英文要約は最後に)。
カモ目やキジ目のあるものは発育中に音声が連続的に変わるものが知られているが、ツル目、ブッポウソウ目、ハト目では不連続に変わるものが知られているとのこと (引用文献参照)。"不快" を表す方の声は変わらなかったが、餌ねだりの声は連続的に変わったとのこと。孵化後 30 日程度まで調べられている。
ちなみにロシア語でも begging call に相当する名称になっている。"不快" を表す方の声は "tvit" と表記されていてオオタカでは1-4回の音声からなるとのこと。
[猛禽類のホルネル (Horner) 症候群・鳥の目の閉じ方]
LaChance et al. (2019) Horner Syndrome in Birds of Prey
という論文があった。目に関わる運動を支配する交感神経の麻痺によるもので、中脳からのニューロンが脊髄を通って胸椎近くの神経核を通ってから頭部に向かうとのこと。経路が長いので途中で骨折などの影響を受けるとこの症状が出やすい。
最もよく見られる症状が上瞼の眼瞼下垂で哺乳類と同じである (通常は目を閉じる時は下瞼が上がるように見えるのだが違うようである)。縮瞳も見られることがあるが哺乳類とは瞳孔散大筋の構成が少し違うので (フクロウ類の Bubo virginianus では哺乳類とあまり違わないとの報告もあり、種差もあるかも知れない) それほど信頼できる症状ではない。
受診した猛禽類の 0.4% ぐらいに見られており、従来言われていたほどまれではない (ハヤブサ目では少ない)。
論文本文を読める方ならば眼瞼下垂を起こしているオオタカの写真などを見ることができる。原因の多くは外傷とのことでこの症状の出る個体の予後は良くないものが多かったとのこと。
このような疾患にかかわらず、鳥 (主に猛禽類) の瞳孔反応を詳しく見ていると興味深いので皆さんにも観察をおすすめする。瞬膜が通るだけでも瞬間的に瞳孔が少し散大することがある。
ハチクマだがこんな映像がある An oriental honey-buzzard (Pernis ptilorhynchus ptilorhynchus) in Jakarta, Indonesia (学名と場所との対応は判然としないが #ハチクマ備考の亜種についても参照)。
眼を閉じた瞬間に逆に瞳孔が小さくなるように見え、これは明るさに対する反射ではなく別の自律神経の作用が現れているのだろうか。
鳥の目の閉じ方には3種類あるとの論文があった: Morris and Parsons (2023) The Various Ways in Which Birds Blink
上瞼を閉じる鳥もあるようで、上下両方を閉じることもある。瞬膜のことはもちろん述べられており、瞬膜と瞼の動きにも関係があるらしい。瞼を閉じる運動は phasic (急速運動。瞬膜 + 一部の種で上瞼) と tonic (ゆっくりした運動。瞬膜 + 下瞼) に分類され、後者は眠い時や羽繕い時に目を保護する。
上瞼を閉じる動作は爬虫類では見られず Neoaves で進化したものとのこと。特に4目で知られており、ハト目、フクロウ目、オウム目、ヨタカ目とのこと。オウム目と共通の枝のハヤブサ類は上瞼を閉じないとのこと。なぜ進化したのかなど考察しているが想像の域を出ないよう。上瞼の動きは進化途上なのか、それとも退化中なのか? なおワニは眼球を引くとのこと。
長時間目を閉じている時は角膜上皮が空気に晒されなくなるが、瞬膜の血管が酸素を供給しているのか。
この論文ではタカ類は上瞼を動かさない方に分類されているが、(盛岡市動物公園 ZOOMO 2024.7.2-1),
(盛岡市動物公園 ZOOMO 2024.7.2-2) のくつろぎ中のハチクマの画像では上瞼も動かしているように見える。
ちなみに目をしっかり開くと両眼視の顔になって正面顔の印象はまったく違ってみえるので1枚の写真からの判断は危険。正面顔も見せている参考ビデオ: ハチクマの "はっちゃん" ... (盛岡市動物公園 ZOOMO 2024.9)。正面顔でも見る方向次第で瞳孔の見え方が結構変わる。声は甘え声。
猛禽類のホルネル症候群があることからタカ類でも上瞼も普段は筋力で開いているのだろう。
ハチクマの"はっちゃん" です。... (盛岡市動物公園 ZOOMO 2024.10)。顔の拡大映像。声は甘え声。
ハチクマの "はっちゃん" です。... (盛岡市動物公園 ZOOMO 2024.10)。顔の拡大画像と解説。においも他の猛禽類と異なる示唆あり。
同上 (盛岡市動物公園 ZOOMO 2025.2)。
羽毛の膨らませ方次第で顔の印象が大きく変わる。Birder 2025 年 1 月号の表紙のカンムリワシとも比較いただきたい。
[クーパーハイタカの繁殖開始年齢]
(この部分はマーリン通信の記事 オオタカ 雌幼鳥と雄幼鳥の繁殖例 に刺激を受けて調べたもの)
クーパーハイタカは、既述のように "ハイタカ" の名前は入っているが日本の猛禽類ではオオタカにより近い。
Millsap et al. (2019) Demographic consequences of sexual differences in age at first breeding in Cooper's Hawks (Accipiter cooperii)
の繁殖開始年齢の興味深い論文がある。生活史理論では繁殖可能年齢に達すればすぐに繁殖を開始することが期待されるが、タカ類では繁殖開始を遅らせる方が一般的。逆性的サイズ二形の目立つ猛禽類では雌雄に差があることが期待される。
オスが獲物の大部分を捕獲する種ではメスに比べて繁殖成功のためにオスの方がより経験を必要とすると考えれば、(1) メスの方が早い年齢で繁殖を開始する、(2) 低い年齢で繁殖を開始したオスの適応度 (自身の生存率を含めて生涯に残す子供の数に対応。詳しくは論文参照) は低いことが予想される。アメリカのニューメキシコ州でクーパーハイタカを調べたところ、1年めで繁殖したメスはオスより 79% 多く、予想 (1) を裏付けた。
1年めで繁殖したメスの適応度は1年めで繁殖したオスより 21% 高いと推定された。
1年めで繁殖したオスは獲物の密度が特に高いテリトリーに定着したが、1年めの繁殖にはコストがかかり、1年めに繁殖しなかったオスに比べて2年めの生存率が 37% 低かった。生涯の適応度はあまり差がなかった。生活史戦略としてどちらかが選択的に進化するよりも、状況に応じてそれぞれの戦略が有利になることがあると考えられる。
1年めで繁殖したメスは、比較的高い年齢のオスとつがいとなった場合、若年のオスとつがいとなった場合に比べて2年め生存率は 33% 高く適応度も 16% 高いと見積もられた。
この個体群では1年あたりの増加率が 1.08 となり、オスの生命表モデルから期待される値 (1.02) に一致した。メスの生命表モデルから期待される値は 1.21。雌雄で繁殖開始年齢が違う場合は遅く繁殖を開始する性の動態を反映する予想通りの結果となった
(つまりオスの生存が十分有利な条件になれば、メスの生命表モデルから期待される値に近づいて個体数が増加すると考えられる)。
これまでの研究ではメスの生命表モデルを用いて繁殖戦略を議論しているものが多いが、性差を考慮する必要がある。なお lifetime reproductive success (LRS。上記の fitness に相当) で評価すると繁殖開始年齢が遅い戦略の影響があまり現れないが、増加率で評価すると違う結果になることがあるとのこと
[cf. Krurger (2005) Age at first breeding and fitness in goshawk Accipiter gentilis ドイツのオオタカの研究例の導入部分参照]。
質のよいテリトリーが得られる場合に1年めで繁殖する割合が増える効果はハイタカ (Newton 1976 の有名なモノグラフだが持っていない) で知られており、同様の状況が考えられる。オスが1年めで繁殖する行動に対する強い選択圧は繁殖後の生存率と考えられるが、メスが経験の深いオスを選択するため若いオスがメスを得られない効果も否定できない。
この論文の導入部分には、猛禽類で若鳥が繁殖に参加する事例は成鳥の個体の回転率が高い場合や、個体数の増加期によく見られるとの先行事例の報告が述べられており、考察の参考になる部分もあるかも。
参考: ヨーロッパのアオガラで年上のオスを除く実験で若鳥オスのつがい外交尾の成功率が高まった研究 Schlicht et al. (2024) Removal of older males increases extra-pair siring success of yearling males。
クーパーハイタカが都市に定着を始めた時期の研究もある: Stout and Rosenfield (2010)
Colonization, Growth, and Density of a Pioneer Cooper's Hawk Population in a Large Metropolitan Environment。
Millsap (2017) Demography and metapopulation dynamics of an urban Cooper's Hawk subpopulation
同じ研究者による先行研究だが、こちらではオスが1年遅く繁殖を開始するためオスが不足してメスが離れて都市外に移住する割合が 31% とのこと。都市では冬場の獲物が豊富なのでメスが越冬可能だが都市外の個体は大部分渡りをする。都市外に移住するメスは渡り個体が帰ってくる前にテリトリーを作るため渡り個体と直接の競争にはならない。
都市への進出はハジロバト Zenaida asiatica White-winged Dove に定着に伴って 1980 年代に始まったと考えられる (それ以前は DDT の影響もあった)。1980 年代には個体数が9年で倍増だったとのこと。
都市で繁殖した個体は渡る必要が少ないため移住しても有利のようで、環境変化の激しい時期に都市の個体群が多様性の reservoir (source) となっていることを裏付ける。渡りをする都市外の個体群を次第に駆逐しつつある状況のよう。なお都市に進出して渡りを行わなくなる傾向はアシボソハイタカでも同様とのこと。
Millsap et al. (2023) A two-sex integrated population model reveals intersexual differences in life history strategies in Cooper's hawks
がさらにモデル計算を行っている。Millsap et al. (2019) では都市から都市外への移住の効果は詳しくは取り入られていなかったが、この研究で生存率と移住効果の両方を取り入れてもう少し詳しく検討。
Millsap et al. (2024)
Causes of Death of Female Cooper's Hawks from an Urban Setting in New Mexico, USA が死因の研究。人工物との衝突がかなりある。捕食はイヌやワシミミズクなどによるものが知られ、人に撃たれたり、捉えられて殺されたものも捕食と同じぐらいあった。ヨーロッパでは違法な迫害は減っているようだがアメリカでは法律や教育が整備されているのに減っていないとのこと。
その年生まれの鳥の早い季節の死因は衝突が多いが、春はメスの間 (オスもおそらく同様) の闘争によるものが多く、結果的に衝突死につながっている。
Millsap et al. (2019) の記述しているような北米のクーパーハイタカの状況は都市近郊にオオタカが進出する過程の日本の状況に似ているかも知れない。ラトビアの幼鳥のつがいも環境改善が進んで個体数増加のフェーズに相当しているのかも ([ヨーロッパの局地的なオオタカの減少・オオタカによる他猛禽類の捕食] のミサゴやアシナガワシの捕食事例にも関係があるかも)。
成鳥の個体の回転率も (特に成鳥への) 狩猟圧などが高い時期には高かったかも知れない。
Margalida et al. (2008)
Breeding of Non-Adults and Effects of Age on Productivity in the Spanish Imperial Eagle Aquila adalberti および
Ferrer et al. (2004) Density-dependent age of first reproduction as a buffer affecting persistence of small populations はスペインカタシロワシの事例。
北米のアメリカオオタカの研究もあり、Reynolds et al. (2017) Long-term demography of the Northern Goshawk in a variable environment
では最初の繁殖は2歳で平均の繁殖開始年齢はオス・メスで違わなかった。この研究では気象変動など食物量が大きく変化している (irruption の渡りが見られるように年変動の大きい食物を利用している) のでその影響を主に扱っている。現状ではテリトリーが埋まっている状況とのことで、個体群増加率は 1 を少し下回っているがこの 20 年の個体数は安定していたと考えている。
北米のクーパーハイタカの動態とは違うようで、またヨーロッパのオオタカの動態とも多少異なっている。
Lin et al. (2015) Breeding performance of Crested Goshawk Accipiter trivirgatus in urban and rural environments of Taiwan
台湾で最近都市に進出したカンムリオオタカ (新しい分類では Lophospiza 属) の事例。
都市では郊外に比べて 34 日も繁殖時期が早かった。このため繁殖に有害な雨季を避ける効果もあることにもつながっている。
ここでも幼鳥を含むつがいが認められ都市の方が多かった、メスが幼鳥の事例が逆よりも多かった。例数は少ないが郊外ではオスが幼鳥の事例はみられなかった。
都市での食物は豊富でスズメとベニバトが主な食物とのこと。都市の方が幼鳥を含むつがいが多い理由として成鳥の死亡率が高い、食物と営巣場所が豊富で幼鳥が繁殖に参加する機会が増えるの2要因を検討し、食物が豊富なことから前者は考えにくいとしている。
クーパーハイタカで8卵のクラッチ例が報告されている: Stout (2009)
First Documented Eight-egg Clutch for Cooper's Hawks
孵化は失敗したが途中で大雨もあり、卵を覆いきれなかった仮説を考えている。7卵の事例は次の項目で。
Taylor et al. (2025) Social context and the evolution of delayed reproduction in birds (preprint) で鳥類全体の繁殖開始年齢と社会様式の関係が調べられている。共同繁殖、コロニー性、レック形成を示す種の繁殖開始年齢が遅いことはさまざまな系統で認められた。
タカ類でも後の系統のものは全般的に一夫一妻で繁殖開始が早い点はクーパーハイタカやオオタカなどにも当てはまるのかもしれない。タカ類でもクロコンドルでは複雑なねぐら社会構造を持ち8歳まで繁殖しないとのこと。
オオタカなどの繁殖開始年齢が体格から想像される以上に早いのは社会構造に由来するのかも知れない。
[クーパーハイタカの種内托卵]
一夫一妻の猛禽類で種内托卵が起きるとはあまり想像されていなかったが、少なくともいくつかの地域のクーパーハイタカで高率で起きていることが判明:
Rosenfield et al. (2024) Combined high rates of alternative breeding strategies unexpectedly found among populations of a solitary nesting raptor。
#チョウゲンボウ備考の [アメリカチョウゲンボウの交尾] で Rosenfield et al. (2015)
High frequency of extra-pair paternity in an urban population of Cooper's Hawks 13.9% のひながつがい外交尾で生まれ、34% の巣につがい外交尾のひながいたという研究を紹介した (背景には都市への進出途中の特殊事情がある。営巣密度が高く食物が豊富。該当部分もお読みいただきたい) が、研究を続けた結果高率 (15-26%) に種内托卵のある巣が存在したとのこと。
つがい外交尾と種内托卵を合わせると 42-46% の巣で起きていたとのこと。これらの事象にかかわったはずのあぶれ個体はほとんど見つけられなかった。
つがい外交尾によるひなの割合はコロニー性の Falco 属で測定されている値より高かった。
巣の繁殖ペアのメスが交尾の際に食物を受け取ることと引き換えにこの戦略をとっている証拠は見つからなかった。かつて Ellis and Depner (1979) A Seven-Egg Clutch for the Cooper's Hawk
が異常に大きなクラッチサイズの原因として複数のメスが産んだ可能性も考えたがあり得ないことではなくなった。近年複数のメスがなわばり内にいる事例や若鳥による巣の乗っ取り事例 [Maione (2024)
Post-Incubation Intrusion and Possible Nest Usurpation by a Second-Year Female Cooper's Hawk (Accipiter cooperii)]
なども報告されており、複雑な繁殖システムを持っている示唆があった。
つがい外の個体を捕獲したり同定することが極めて難しいために生態的要因の判定が難しい (またこのような結果を予測して研究をデザインしていなかったので観察も不足していた)。
クーパーハイタカはおそらく特殊と思われるが、猛禽類ではこれまでこのような代替戦略はほとんど調べられておらず今後の進展 (つまり生態や行動の進化の解釈) が期待できる。
この著者によれば猛禽類での種内托卵は過去2つ報告があり、ヒメチョウゲンボウ: Costanzo et al. (2020) Extra food provisioning reduces extra-pair paternity in the lesser kestrel Falco naumanni (こちらも意外に高率)、
ニシアカアシチョウゲンボウ: Magonyi et al. (2021) Extra-pair paternity, intraspecific brood parasitism, quasi-parasitism and polygamy in the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) (こちらは家族単位では 2.7% に見られた)
がいずれもコロニー性の種である。
これらの種で研究が進んでいる背景にはヒメチョウゲンボウが都市鳥になっていること、ニシアカアシチョウゲンボウはハンガリーでミヤマガラス駆除の副産物で絶滅の危機に陥った (#アカアシチョウゲンボウの備考参照) ことがある。個体群動態がよく調べられている。
Brouwer and Griffith (2019) Extra-pair paternity in birds の総説の情報 (この論文にはクーパーハイタカのつがい外交尾率の高さも含まれている) によれば、
Rodriguez-Martinez et al. (2014) High Urban Breeding Densities Do Not Disrupt Genetic Monogamy in a Bird Species
のアナホリフクロウ Athene cunicularia Burrowing Owl の研究が引用されており、都市部で高密度で営巣しているが婚姻形態は変わらなかった。つがい外交尾によるほな (1.47%) は比較的少なかったが、種内托卵がより高率 (8.82%) に認められたとのこと。
この論文によれば種内托卵はこの時点で 234 種で知られていたがほとんどは早成性の鳥で、この時点ではフクロウ類では知られていなかったとのこと。コロニー営巣性のヨーロッパハチクイ (9-12%) に匹敵する値とのこと。
この論文で紹介されている過去研究によれば戦略としての種内托卵はあまりよく理解されておらず、繁殖地への固執がメスに偏っている場合や、宿主と托卵個体が近縁関係にある場合などの議論があるとのこと。
これからは猛禽類の研究者も托卵やその進化について学ぶ必要があるのだろう。猛禽類では種内托卵が例外的なのであればなぜ例外的なのか、どのような種が種内托卵が可能なのか、他種への絶対托卵性の猛禽類は進化しなかったのかなど。
保全のために他種を仮親に用いた増殖例もあり絶対托卵性も原理的には不可能ではなさそう。托卵性の早成性の鳥やカッコウ類に比べて親から学ぶことが多いためとも理解できそうだが、音声学習をするスズメ目でも托卵系統が複数あるので絶対的な条件にはならない気がする。
托卵に訪れて攻撃されると親の身に危険が及ぶ恐れがあるため進化しにくい性質かも知れないが、クーパーハイタカはなぜ許しているのかなど論点はいくらもありそう。自身の危険を犯してでも托卵する利益があるとすれば何だろうか。排除行動を行うと宿主側にも危険が及ぶので抵抗せず受け入れる方が得策? (ほんとうか?)。
別種を育てたワシ・タカの例があり、通常は食物のつもりで持ち込んだ他の巣のひなを育ててしまったものとされるが托卵例も実際にあるのかも知れない。
#ハイタカ備考の [ハイタカの巣内ひなに食物を与える実験・巣の乗り換え] も関連する。この項目では托卵そのものではないが巣立ち後に別の親の世話になる行動 (post-fledging brood-parasitism) が扱われているが、
自分の子以外を排除する行動は自分の子を殺してしまう可能性があるために進化しなかった (カッコウ類などに托卵される鳥が一般的にひなの識別能力を進化させない理由の一つに取り上げられるのと同様) などの考察もある。
[クーパーハイタカとリョコウバト]
絶滅する前のリョコウバトは広義 Accipiter 属の格好の獲物であったとのこと。"pigeon hawk" の通称は特にこの習性に由来する。特にクーパーハイタカは狩りの成功率の高さから "great pigeon hawk" と呼ばれていた。渡るリョコウバトを追いかけて移動していたと言われている。
ハトの群れが大きいために希釈効果が働いて個々の個体は大部分が繁殖に成功した。"predator satiation" (捕食者の飽食) がリョコウバトが非常に社会的で大群を作って繁殖する理由の一つと考えられる (wikipedia 英語版の Passenger_pigeon の項目から)。
リョコウバトなど絶滅したハト類の話題は#オガサワラカラスバトにまとめた。
それだけ豊富だった食物資源が絶滅すると捕食者の方にも影響したのではと想像できるが、その代わりとなったのが世界中で栄えているドバトということだろうか。
[ヨーロッパの局地的なオオタカの減少・オオタカによる他猛禽類の捕食]
(#ハチクマ備考の [ヨーロッパハチクマと他のタカの種間関係] から再掲を含む):
英国北部ではチョウゲンボウ (コミミズクも可能性がある) 繁殖可能になる前にオオタカに捕食され、主な減少要因になっていると考えられる: Petty et al. (2003)
The decline of Common Kestrels Falco tinnunculus in a forested area of northern England: the role of predation by Northern Goshawks Accipiter gentilis。
Rutz and Bijlsma (2006) Food-limitation in a generalist predator
はオランダのオオタカの食物不足の研究。ジェネラリストの猛禽類が食物で制約を受けるのは珍しい。1975-2000 年ごろにオオタカの主な食物 (レース鳩、モリバト、ウサギ) が同時に大きく減少した。
オオタカが他の食物を求めたことがチョウゲンボウ、コチョウゲンボウ、ハイタカの個体数減少にも関わっている可能性があり、すでに減りつつあったモリバトにもさらなる打撃を加えた。オオタカ自身も繁殖成功率低下で減少してきている。
Hoy et al. (2017) Density-dependent increase in superpredation linked to food limitation in a recovering population of northern goshawks Accipiter gentilis
によれば UK のオオタカの食物不足の要因は2種類の主要食物の減少によるとのこと。モリバトなどハト類 [Bijlsma (1998) にあるように作物の変遷に伴っており、モリバトの減少はヨーロッパハチクマの代替食物不足につながっている] とキジ類。現在ではオオタカは食物量で制限されており、食物不足により他の猛禽類も捕食するようになった模様。
生態系の遷移過程と考える他に、英国ではオオタカが一時絶滅しチョウゲンボウが増加したが、オオタカの個体数が回復し、チョウゲンボウが好みの獲物となった過程で起きている現象との見方も考えられる。また単に捕食されて数が減る以外に繁殖をあきらめる効果もある。どちらも保全の対象となっている種である。
Hoy の学位論文 (2015)。
これらの研究によればオオタカが "出会い頭" (確率) 的にチョウゲンボウを捕食するわけではなく、チョウゲンボウが減少したにもかかわらず捕食割合が増えている。コミミズクも数が増えていないのにオオタカによる捕食割合が増えている。
夜の短い高緯度でコミミズクが昼間にも狩りをする必要があってその時間帯に捕食されるのだろう。
コミミズクのひなの声が大きいために目立っている可能性もある。捕食者が競争者を減らす、あるいは潜在的な捕食者を減らすために捕食する仮説があるが、これらは裏付けられなかった。消去法的に食物不足仮説となっているようで実際にはあまり確かでないかも知れない。
オオタカが継続的にチョウゲンボウを捕食するようになり、英国のチョウゲンボウは大陸からの "sink" 個体群となっている。これはコミミズクについても同様。
アメリカチョウゲンボウの渡りカウントが経年減少しており、一時期増えたものが以前の水準に戻っている状態とは考えにくい。Farmer and Smith (2009)
Migration Monitoring Indicates Widespread Declines of American Kestrels (Falco sparverius) in North America
草原が植林されたり開発された時期とも重なるが、クーパーハイタカ (オオタカ近縁の北米の少し小型の Astur 属で都市環境にも適応している) が数を増してきており捕食の影響も考えている。条件の異なる広範な地域で似た時期に減少してきており何か共通要因があるはず。
McClure et al. (2017) Commentary: Research Recommendations for Understanding the Decline of American Kestrels (Falco sparverius) Across Much of North America
によれば、Mallwood et al. (2009) はクーパーハイタカによる影響仮説を除外したが、クーパーハイタカ仮説がもっともらしいと考える専門家も市民科学者も多い。殺虫剤などの影響では減少時期が説明できない。樹洞営巣性で適した樹洞が減少している可能性もあり、越冬地の環境悪化も考えられ要因分析のための研究指針を示している。
クーパーハイタカはこのように増えているようだが、オオタカと同種とされたこともあった北米のアメリカオオタカは少し事情が違うようで、When Goshawks Ruled the Autumn Skies
ホークマウンテンでかつては大規模な渡りが見られた (ここでは約 10 年ごとに起きる irruption) が、近年はそのような現象が見られない。温暖化の影響か、あるいはカナダ北方林の状態が悪くなっているのかもとも心配されている。
フィッシャー Pekania pennanti fisher (イタチ科) によるアメリカオオタカの巣の捕食、北米に悪質な外来ウイルスとして入った入った西ナイル熱ウイルス (West Nile Virus。病原性が高く変異した株だった) の影響も考えられるが、フィッシャーは在来種で適応できているはず。しかし西ナイル熱ウイルスどの複合要因があればアメリカオオタカの繁殖に制限を与える可能性も考えられる。
カナダの森林管理をアメリカオオタカに適したものに変えてもっと多様性の高い天然林に戻すなども提案されている。ヨーロッパ、あるいは日本のオオタカとは状況が異なる模様で、他の猛禽類への影響を考える場合は北米ではアメリカオオタカよりクーパーハイタカの事例の方がより参考になりそう。
Goshawks and impact on the ecosystem (BirdForum 2022-2023)
風力発電のための調査の結果、英国では本来いるべきハイタカが減少しており、オオタカ分布の周辺域にしか見られなくなってきているとの話がある。ヨーロッパハチクマ以外にもハイタカの減少もオオタカの食物不足の影響の可能性がありそう。
イベリア半島の研究でオオタカとハイタカがどのように共存しているか: Rebollo et al. (2017) Spatial relationships and mechanisms of coexistence between dominant and subordinate top predators
いくつかの要因を挙げていて (1) オオタカの種内競争が激しい。空間的には安定している。いずれもハイタカが生息場所を得るのに有利に働く (2) ハイタカの方が繁殖時期が約3か月遅く、繁殖場所も距離を置いている (3) オオタカが活発に活動していないなわばりを利用している (4) ハイタカの方が巣を隠している (5) 食物の違い。
しかしオオタカの生息密度が上がり、より質の低いテリトリーも利用するようになるとハイタカにとって厳しい条件になるかも。
Krueger (2002) Analysis of nest occupancy and nest reproduction in two sympatric raptors: common buzzard Buteo buteo and goshawk Accipiter gentilis
ドイツでのオオタカとヨーロッパノスリの関係。ヨーロッパノスリの営巣選択がオオタカの影響を受けている可能性がある。情報が少し古いので参考程度か。
Goshawk diet によれば 2006 年段階で英国でオオタカの捕食によってよりまれなヨーロッパハチクマが絶滅してしまうのではとの懸念も出されていた。
一方でもしある地域でヨーロッパハチクマがオオタカに対応できず絶滅したとしても単に不幸だっただけだ、という見解も出ていた。英国では珍しい種類でも大陸ではヨーロッパハチクマは普通なので英国でも時間とともに増えてくるのでは。現状の動向は珍しい種類ではあるが大丈夫のようで、そこまで心配することはなかった模様。しかし選択的に狙われているかも知れないチョウゲンボウは心配かも。
日本では野中 (2014) Birder 28(9): 18-19 で栃木県東部でサシバの雛を襲うオオタカの記事がある。この時点で近年傾向が目立っており、オオタカの主な食物である中型の鳥類の減少が背景にある可能性も示唆されている。
「日本のタカ学: 生態と保全」(東京大学出版会 2013) p. 243 (13 章 東 淳樹) に埼玉県の里山では、かつてのサシバの繁殖地が、オオタカのそれらと置き換わってきているらしい (内田 博氏私信) との記述がある。
大阪のサシバの現状 (大西 2020; 初出は「都市と自然」2016年3月号) にもオオタカやノスリがサシバの生息環境に進出することで、営巣地の乗っ取りやオオタカによりサシバが捕食される。府下では 2000 年頃からオオタカの低地への進出が目に付き始めたとある。
温暖化でサシバの分布が北上している傾向もあるかも知れないが、オオタカ向きの環境か増加しつつあり、世界の他種猛禽の報告例と比較しても全国的なオオタカの増加が日本のサシバの個体数に影響を与えている可能性もありそうに感じる。
これはオオタカの餌不足とは関係ないかも知れないが、シロハヤブサのひなを捕食した事例: Moen et al. (2023) Wildlife Camera Monitoring Revealed the Northern Goshawk as a Predator on Gyrfalcon Nestlings。
温暖化でオオタカの生息可能な地域が極北にも広がっている可能性がある。
シロハヤブサの若鳥の生存率も低く、環境変化とともにオオタカによる捕食が新たな不定要因になる可能性がある。
ラトビアのミサゴのひなが捕食された事例: Latvian Osprey nest - A goshawk attacks the nest and kills the chick - 18.06.20。
同様アシナガワシの事例: Goshawk kidnaps little eagle chick Latvia 2020-07-05。
ポーランドではミサゴが急減し、オオタカによる捕食率が大きな要因となっているという。#ミサゴの備考 [ポーランドで減少するミサゴ] 参照。かつては豊富だった人間活動由来のオオタカの食物が不足するようになったことが背景にあるのかも。
こちらは "sink" 個体群となっておりよい状況ではない。
タカ類ではないが、関東でコサギの減少とオオタカの増加の関連を議論した研究: 内田 (2017) 埼玉県東松山市周辺でのコサギ Egretta garzetta の減少。サシバの繁殖地がオオタカに置き換わりつつあることを報告されたのと同じ研究者による。
ドイツの研究では Mueller et al. (2016) Intraguild predation leads to cascading effects on habitat choice, behaviour and reproductive performance
がワシミミズク (近年再定着した)、オオタカ、ヨーロッパノスリの数を調べている。ワシミミズクが加わったがこの3種とも個体数は増えている。ただしオオタカ、ヨーロッパノスリともに繁殖失敗率は高まっている。
この研究はワシミミズクが新たに加わることでどのような影響があったかを調べるもので、他の猛禽類は調べられておらずこれらによる捕食の影響がどのように現れているかはわからない。
歴史的にはフィンランドでワシミミズクによるオオタカの巣の捕食事例が増えたなどがあった: Tella and Manosa (1993) Eagle owl predation on Egyptian vulture and northern goshawk: Possible Effect of a Decrease in European Rabbit Availability
この当時は野ウサギの減少が問題となっていた。フィンランドでは 1980 年代までオオタカは法的に保護されていなかったとのこと。
1980 年以来アメリカチョウゲンボウの個体数が 40% 減少し、コチョウゲンボウを含めた他の猛禽類は DDT の禁止後数が回復しているのにアメリカチョウゲンボウは減少している。クーパーハイタカの増加が要因の一つと言われている。
参考 Sharma and Kwon (2024) Modeling American Kestrel Decline Using Spatiotemporal Subsampling to Improve eBird Data Reliability (preprint)。
この論文そのものは関連性を議論したものではなく eBird などの目撃記録をどのように信頼度の高い値として扱うか、またモデルによる近未来の予測などを取り上げている。
過去の個体数推定は出ていて 2000 年代後半からクーパーハイタカの増加が目立つ。
オオタカではないが関連情報をこちらに紹介しておく。カリフォルニアの Channel Islands (チャンネル諸島 太平洋岸に点在する島) でハクトウワシの保全が行われている。過去の食性解析からかつては豊富な海鳥を主な食料とし、その後人為導入されたヒツジを食べていたが後者は駆除され海鳥も減少したため食物不足が発生している。ハクトウワシが増えることで海鳥の個体数回復や希少なキツネへの影響が懸念される:
Newsome et al. (2010) Pleistocene to historic shifts in bald eagle diets on the Channel Islands, California。
Cruz et al. (2019) Top-down effects of repatriating bald eagles hinder jointly recovering competitors
Voyageurs National Park (アメリカ ミネソタ州) では 1990 年以降ハクトウワシのみが個体数を回復し、競争関係にあるミサゴやサギ類は減少している。ハクトウワシの巣が増えるに従ってミサゴやサギ類の巣が減っている。数字を見るとミサゴやサギ類の減少率は個体群絶滅の恐れがある程度のかなり危ないレベル。
頂点捕食者のみに注目した個体数増加プログラムは注意が必要であると述べられている。
一方で Piper et al. (2020) Plunging floater survival causes cryptic population decline in the Common Loon 北米のハシグロアビは減少が続いていて、要因の一つにハクトウワシの増加が挙げられていたがウイスコンシン州のこの研究では、ハシグロアビのひなに体重減少が見られることからハクトウワシによる要因はむしろ否定的で食物不足が主な要因と考えられるとのこと。
Solonen (2025) Vulnerability of Prey Species to Predation by Two Sympatric Accipitrine Hawks in Rural and Peri-Urban Landscapes in Southern Finland
フィンランドで郊外と都市部でのオオタカ、ハイタカの獲物の違いの研究。ハイタカの主な獲物はオオタカにとってはそれほど重要でないらしい。それほど重要な知見を提供している印象はないが、獲物を通じた種間関係の研究。オオタカの学名に最新の Astur gentilis が使われている。PubMed で検索できる論文ではこの学名が初めて使われた。
GenBank に PQ049665.1 の配列があり mitochondrion Astur gentilis (Northern goshawk) とあるので、
いよいと採用かと論文を見てみると Lopez et al. (2024) GoEnrich: creating high quality genomic DNA resources from limited voucher specimen tissues or museum specimens of at-risk species for conservation-friendly use in the validation of environmental DNA assays
で論文中では Accipiter gentilis となっている。サンプルは北米のものでアメリカオオタカに対応すると思われるが、論文執筆当時は同種時代で、その後属名が変わったので属名のみ変えて GenBank に登録したらしい。
調べてみると GenBank Taxonomy はすでに Astur gentilis に移行しており、どちらで検索しても結果が得られる。Accipiter gentilis の方が多少多くの検索結果が得られるのは鳥そのものの遺伝情報だけでなく鳥由来生物などの遺伝情報も含まれるが、こちらの学名までまだ対応できていないためだろう。
Reynolds et al. (2025) Fidelity to territory and mate and the causes and consequences of breeding dispersal in American goshawk (Astur atricapillus)
アリゾナ州のアメリカオオタカの分散の研究でも Astur の属名がすでに用いられている。これまたすごい数のテリトリーが同定されて地図にも表されており、テリトリーの位置関係などもよくわかる。20 年でのべ 1688 の巣を調べて一部に個体標識をしたとのこと。GPS 研究ではなく目視同定によるもの。
繁殖失敗とつがい解消との関係はほとんどなかった。全体的に相関を見つけるの難しく、あまり強い結論が出せなかった感じがする。詳しくは論文をどうぞ。
[フィンランドとアメリカのオオタカの人に対する行動の違い]
Wright et al. (2019) Comparison of Nest Defense Behaviors of Goshawks (Accipiter gentilis) from Finland and Montana
(この研究の時点ではフィンランドとアメリカのオオタカは同種扱い)
アメリカのオオタカは巣の防衛で人に対する攻撃的行動が目立つ。フィンランドでは 1980 年代後半まで狩猟対象だったため、攻撃的な個体は撃たれてしまった、あるいは撃たれても生き延びた個体がリスクを学習したのかなどの考察がある。フィンランドの個体は人よりも天敵のワシミミズクに反応するとのこと。
現在では別種で種の違いがどの程度行動に関係するものだろうか。
[オオタカの獲物探索の視線の動き]
Kane et al. (2015) When hawks attack: animal-borne video studies of goshawk pursuit and prey-evasion strategies
小型カメラを取り付けて頭の方向を追跡した。眼球があまり動かないとすると網膜上の一定の位置に動く獲物を固定していたが2つの fovea の位置とは一致していなかった。#シロハヤブサ [シロハヤブサの獲物追跡] でもある程度似た結果が得られている (同じ著者なので同じような結論が出ている可能性もある)。
獲物が急に横に動くことことが視線を外すのに役立っている。過去の獲物の逃避反応の研究とよく合っている。
#ハイタカの [ハイタカの急降下による捕食行動] および #トビの [トビの獲物攻撃速度] を記述してからこの論文に気づいたが、獲物に等速で近づくと (獲物から、あるいは獲物が) 急に大きく見えるため一定速度で大きく見えるようになるよう速度を調整している可能性も議論されていた (論文の τ 関数のところ)。
この "急に大きく見える" 効果は距離知覚によらないとのことでさまざまな動物で見られる。衝突を避けるための反応と考えられるが、獲物が翼や尾を急に大きく見せて驚かせる効果 (startle effect) を示すのはこの反応を利用しているとも考えられる。古くから知られているアイデアで Edmunds (1974) にも記述がある。他の互いに排他的でない説明もあるとのこと。
motion camouflage 効果については #ハイタカの [ハイタカの急降下による捕食行動] の方にまとめた。
[鷹と雁の漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 86 VII (藤堂) によれば難しいとあるので、あまり定説になっておらずあくまで一つの解釈として見ていただくのがよさそう。
广 (囲う) から人が囲って飼育する意味。陰と同系語と解釈され、鷹の文字は胸板の中に擁 (= 鷹の音読み) してかくす鳥の意味であるとのこと。
雁の漢字と似ており、鷹の方は尾の長い鳥の意味で鳥を添えたのかとも思ったがどうも違うらしく、週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 96 VII (藤堂) によれば 厂 は直角にかどったことで、音は ngan/ngai とのこと。岸や崖の文字にも含まれ、ガンが群れをなして飛ぶ際の形をたとえたものらしいとのこと。ガンは中国では古代は ngan と読まれ現在では yan となっているが、日本語は古代の音を音訳したものと考えられるとのこと。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) を見るとカリの名称の方が古くから使われ、日本語ではガンの読み方は比較的新しい。この本では 1485 年の事例が出ている。
藤堂 (1973) によれば中国ではガンは礼物 (しんぶつ、れいもつ、贈り物) として用いられ、行儀正しい仲間のシンボルとして用いられたとのこと。
ということで鷹と雁の文字は "鳥" が多いかどうかの違いではなく、广 (囲う) の意味はガンよりもむしろタカに当てはまることになる。
参考までに他出典を見ておくと、鷹 では音声を示す文字 (雁の文字の上に点を付けたもの) と鳥の合成となっている。音は jing で wiktionary によればチベット語 glag などと同系とされている。中国語圏でも定説がなくて猛禽類を指す音声由来を考えているらしい。なぜその文字が選択されたのかは書かれていない。
-
サシバ
- 学名:Butastur indicus (ブータストゥル インディクス) (東インド会社の時代の) インドのノスリオオタカ
- 属名:butastur (合) ノスリオオタカ Buteo 属 (ノスリ属) と Astur 属 (オオタカ属) から合成
- 種小名:indicus (adj) インドの (-icus (接尾辞) に属する) ただし現在のインドには分布しない。備考参照。
- 英名:Grey-faced Buzzard-eagle, IOC: Grey-faced Buzzard
- 備考:
butastur は -(t)as- が子音で終わる音節のためここにアクセントがあると思われる。bu(t)- は buteo 由来で u は長母音と考えられる。(ブータストゥル)。astur の読みは#オオタカ参照)。
indicus のアクセントは冒頭 (インディクス)。
Gmelin (1788) が記載したのは Falco indicus "Javan Hawk" とされていた。原記載。
Latham (1781) Javan H. の記述がもとになる。Latham は学名を与えなかったので Gmelin が与えたらしい。これもハヤブサとされる日本近海の2個体 (#ハヤブサ備考 [亜種と系統] 参照) と同様船に飛び込んできたもので "ジャワ島に住むと考えられる" との記載になっている。
植民地時代のオランダ東インド会社の時代、ジャワ島を含むインドネシアの一部がオランダの支配下にあった時はジャワ島も「東インド」(オランダ領東インド) と呼ばれたことに起因すると推定する (オランダ語で Nederlandsch-Indie = 英語で Dutch East Indies)。
現在の名称インドネシアも Indos + nesos (Gk, インドの島々) が由来であり、インドネシアはインド諸島と同義で用いられていたとのこと。オランダの学者の間では Indonesia は長いので Indie と略すのが普通であった (19 世紀に遡るとある。wikipedia 英語版より)。
しかしややこしいことに Falco (?) indicus Gmelin, 1788 なる同じ学名があり、こちらはインドが基産地となっている。Falco communis (現在ではハヤブサに相当するよう) の変種であり、Falco ruber indicus Briss に基づくとある。
こちらは基産地的には学名と符合するがおそらくハヤブサ類の1種のインド個体 (red indian falcon) を指しているものでサシバの由来とは関係なさそうに見える。
もうひとつ Falco javanicus Gmelin, 1788 (記載, 参考) と Gmelin 自身による "ジャワ島" を冠した学名があるがこれはサシバと同じものか? との注釈がある。
Gmelin 自身もおそらくあまりよく判別していなかったようで、同種? に同じ地域名を指す別学名を用いたり、同じ学名を別種にも用いていたりしたよう。
The Key to Scientific Names の indicus の項目では古く「東インド」(オランダ領東インド) にも使われたとあり、上記推測で正しかった模様。「西インド」やニューギニアを指す用例はさらにまれとのこと。
さらに面白い誤用があって、ハジロバト (これは英名 White-winged Dove とも一致) はアメリカ大陸の種類なのに学名がなぜ Zenaida asiatica とアジアになっているのか非常に疑問に見える。wikipedia 英語版によれば asiatica はおそらく広義のインドを指したものだが、「西インド」にあたるジャマイカを指すつもりで誤訳したのだろうとの解釈が紹介されている。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば Javan Buzzard の名称が使われていた。
英名 Grey-faced Buzzard の由来がわかりにくいが、Falco poliogenys Temminck, 1825 (polios 灰色 genus, genuos 頬など Gk) 由来と考えられる。後の解説参照。
単形種。
[Butastur (サシバ) 属の系統分類]
Catanach et al. (2024) の分子系統樹 (#アカハラダカの備考参照) によればサシバ属は海ワシ類とノスリ類の中間に位置する。属名の由来や若鳥の類似性から想像されるようにオオタカの仲間に近いわけではない。
これまでと同様 Catanach et al. (2024) の順序による。
ノスリ亜科 Buteoninae ノスリ族 Buteonini
サシバ属 Butastur
チャバネサシバ* [高野 (1973) ではアカハネサシバ] Butastur liventer Rufous-winged Buzzard
アフリカサシバ Butastur rufipennis Grasshopper Buzzard
メジロサシバ* Butastur teesa White-eyed Buzzard
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard
Butastur 属に分類されるもののうち日本のサシバ以外は亜熱帯から熱帯に分布する留鳥。ハチクマ同様サシバもやはり南方由来の種類と呼んでよいと思われる。
南アジアから東南アジアに分布する種類はインドなどに分布するメジロサシバ、インドシナのチャバネサシバ [高野 (1973) ではアカハネサシバ] で、分布はサシバの越冬域とも重なる。この2種はサシバにかなり近縁のようで、音声もよく似ている。サシバ属のタイプ種はメジロサシバ。
チャバネサシバの種小名にある liventer は青黒い、土色の (英語 livid)。
アフリカサシバの種小名にある rufipennis は rufus 赤い、赤っぽい -pennis 翼の、でむしろ チャバネサシバ [高野 (1973) ではアカハネサシバ] の和名に対応している。高野 (1973) 時代はすでに別種だったがあるいはさらに古い名前を引き継いでいるのかも知れない。
Temminck and Schlegel の "Fauna Japonica" (1833-1850) には Buteo poliogenys の学名で登場した 記述。フランス名 la buse a joues grises (灰色の頬のノスリ。このフランス語名称は現在も使われている)。フィリピンで発見されたものだが日本にも生息するとの記述。
(自分たちが) Falco poliogenys と名付けたものであるとの記述もある。
さらに Buteo pyrrhogenys (次ベージ 記載) (pyrrho purrhos 炎の色の genys genus, genuos 頬など Gk) がともに現れ、以下の Bolau (1881) ではこの名称は同じものを指した不的確記載とみなしている (図版 この絵はサシバの若鳥か)。
図版には学名が登場するが、この学名はシノニムとされていないようで英名にも対応しない。
Kaup (1844) が Poliornis 属 (polia 頭の灰色の ornis 鳥 Gk) を提唱していて、その時はドイツ語で Bussardsperberadler (ノスリのハイタカのワシ) と称してメジロサシバ、liventer、poliogenys (現在のサシバ) を属のメンバーとしていた。
Ueber Voegel aus dem Suifun-Gebie (綏芬河の鳥。Bolau 1881) にあるように
Poliornis poliogenys が当時のサシバの学名だった模様。
現在は Poliornis は Butastur のシノニムとなっているが、Buteo poliogenys や Poliornis poliogenys の学名は一定程度使われていた。しかしこれを見てサシバの学名と感じられる人はいったいどのぐらいいるだろうか。
Schlegel On Nisus rufitorques and N. poliocephalus でも比較対象としてこの学名が登場している。
Hume (1873) Stray Feathers 1 (2, 3 & 4): 318-319 に Notes - Poliornis liventer の記事があり、この中でも現在のサシバを含む Poliornis 属3種のインドからビルマ、マレー半島西部の分布が紹介されているとのこと。
アフリカサシバは Poliornis rufipennis Sundevall, 1850
と記述されたので、Kaup (1844) 時代には未記述であった Poliornis 属の新種として記載したもののようである。
属名については Butastur Hodgson, 1843 (タイプ種メジロサシバ) の方が早かったのでこちらに先取権があったことが判明したのであろう。1873 年の文献でも Poliornis が使われているように両者が共存していたのか、あるいは後に先取権が明らかになったのだろう。
メジロサシバの種小名にある teesa はヒンディー語でメジロサシバを意味する tisa 由来。
メジロサシバの分布域に関する wikipedia 英語版の文章の記述は多少気になる点がある。
インドネシアの初事例が Shagir and Iqbal (2015)
White-eyed Buzzard Butastur teesa, a new species for Greater Sundas and Wallacea
に報告されている。この個体がサシバに似ている点や識別に関する記載もあるので気になる方は見ておかれてよさそうである。本来遠くの留鳥の個体がなぜここにいるのか、サシバと似ているのはなぜなのか。新亜種なのか?
アフリカサシバもやはり亜熱帯から熱帯に分布する。
この4種は遺伝的にもよくまとまったグループを形成しており、それほど目立った遺伝的分岐もない。
いずれも単形種。The Peregrine Fund のページには supercpecies を形成するとある
(Grey-faced Buzzard)。
同ページによれば Kaupifalco 属 (新分類ではハイタカグループ) と類縁関係があるとされたのは鳴管構造の類似性から (Griffiths 1994)。
Lerner et al. (2008) Molecular Phylogenetics of the Buteonine Birds of Prey (Accipitridae)
の分子遺伝研究で Kaupifalco 属とノスリ類は近縁でなく、むしろウタオオタカ類などの系統に近いことがわかった。
さほど大きなタカでもないのに過去の英名で Buzzard-eagle が使われたのは Kaup (1844) の総称名 (またはドイツ語属名) Bussardsperberadler に含まれるワシ (Adler) が由来ではないだろうか。
つまり英名が付いた当初は Poliornis の学名が使われていたと想像できる。ただし直接の語源由来の記述は見当たらなかった。
ロシア語名は yastrebinyj kanyuk/sarych (タカのようなノスリ)。kanyuk は#ケアシノスリの備考参照。sarych はチュルク語起源で同じくノスリのこと。「タカのような」は腹に多くの (広義) Accipiter 属と同じような縞があることに由来するとのこと。属名 Butastur の由来も同じように解釈できそうである。
[暗色型サシバ]
暗色型サシバは非常に珍しいと言われるが、赤勘兵衛 (2006) Birder 20(12): 52-53 によれば新潟県愛鳥センターで暗色型が多く保護されていたとのことで、スケッチが示されている。
Kaup (1844) が Poliornis 属 (polia 頭の灰色の ornis 鳥 Gk) を提唱し、Falco poliogenys Temminck, 1825 (polios 灰色 genus, genuos 頬など Gk) の学名が提唱されて使われていたように、灰色を強調した学名が目立っていた。
写真を見たところではチャバネサシバ [高野 (1973) ではアカハネサシバ] Butastur liventer Rufous-winged Buzzard の方がむしろ灰色の目立つ個体があるように思える [個体次第というのは複数の morph が存在するか、あるいは年齢などによるものか。Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" では Butastur liventer について特に morph として述べられていない]。
またメジロサシバも若鳥の頭が灰色に見える写真がある...と思っていたが、もしかすると Falco poliogenys は暗色型サシバを指して名付けられたのではと思えてきた。暗色型サシバがとまっている写真を見ると確かに相対的に顔の灰色が目立つ。
Temminck がそう考えたかどうかはわからないが、別種に見えても不思議でないかも知れない。後に同種の色変わりと判定され古い方の学名に統一されたのかも。
他のサシバ類 (Poliornis と名付けられるほどの) 容貌と比べると暗色型サシバの方がむしろこの属の原型に近いかも知れない。
ではサシバではなぜ暗色型が少ないのか、と考えると生息地が一定競合するオオタカの影響が大きいのではと思える。少なくとも若鳥は非常によく似ているのでオオタカ若鳥への擬態、特に ISDM 仮説が当てはまるのでは (#ハチクマ備考の [擬態と種・亜種の関係] 参照) ではないか。
成鳥でもそこまで似ていないとはいえ、暗色型よりは有利なために暗色型の遺伝子頻度が非常に低いのではないだろうか。
[生態や渡りなど]
Kojima (1987) Breeding Success of the Grey-faced Buzzard Eagle Butastur indicus
大阪河内長野での 1977-1980 年のサシバの繁殖成功率の研究。兄弟間闘争も記録されているが死亡例は2例と少なかった。捕食による繁殖失敗にも言及されているが詳細は不明。
日本のサシバの遺伝的多様性については Nagai et al. (2019) Analysis of the Genetic Diversity and Structure of the Grey-Faced Buzzard (Butastur indicus) in Japan, Based on mtDNA
に研究がある。ここ 40 年で数が減少したとされているが遺伝的多様性は十分高い。(過去のことではあるが) おそらく日本の里山環境の拡大の結果個体数が増加したことも遺伝子解析の統計からも読み取れ、過去に個体数のボトルネックを体験したことはないと考えられるとのこと。
中国東北部における 1996-1998 年の繁殖生態の研究がある。Deng et al. (2004) Breeding Biology of The Grey-faced Buzzard (Butastur Indicus) in Northeastern China。
Gluschenko et al. (2020) Breeding birds of Primorsky Krai: the grey-faced buzzard Butastur indicus
にロシア沿海地方でのサシバの繁殖生態の論文がある。極東の鳥類42: 沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める。
動物園での一時保護の例 差羽 2019年5月14日 京都市動物園救護センターブログ。
動物園での飼育個体数の変動からサシバの個体数減少を示唆する論文: Kawakami and Higuchi (2003)
Population Trend Estimation of Three Threatened Bird Species in Japanese Rural Forests: the Japanese Night Heron Gorsachius goisagi, Goshawk Accipiter gentilis and Grey-faced Buzzard Butastur indicus
があり、川上 (2005) Birder 19(6): 30-31 にも紹介がある。サシバは 1950 年代より記録があるが飼育個体数は減少傾向 (ただしさまざまな因子があり個体数変動そのものとは言い切れない)。論文によればゴイサギも減少、オオタカは顕著に増加しているが個体数増加を表しているものかどうかはわからない (#クマタカの備考でも関連して少し考察を加えて紹介している)。
サシバの渡りルート、特にフィリピン周辺の天候の安定しない海域の渡りコストのモデル計算: Concepcion et al. (2020) GIS-Modeling of Island Hopping Through the Philippines Demonstrates Trade-Offs Migrant Grey-Faced Buzzards During Oceanic Crossings
海上飛行をなるべく短くするのが合理的でルソン島北部で越冬するのは理にかなっている。ハチクマのインドネシアからの春の渡りはフィリピンを避けるのが風やリスクの面では合理的だが、サシバは渡りに要する時間を短縮するために秋と同じルートを用いているかも知れない。
Wu et al. (2024)
Night Landing of Grey-Faced Buzzards (Butastur indicus) on a Ship During Migration
渡り途中の夜間のサシバの船への不時着の記録。台湾南方で春の渡り途中 30 羽以上。特に疲れ切っているようではなかった。
[台湾のサシバの狩猟]
2006 年に台湾でのサシバの密猟の報道があった。Hunting of Grey-Faced Buzzard-Eagle in Taiwan
"The Ongoing Hunting of Grey-Faced Buzzard-Eagle" の記事に歴史的経緯が紹介されている。古くはスタミナ剤として食用にされていたが、日本の台湾統治時代に剥製用として日本に大量輸出されるようになった。日本人は高貴な生き物が福を呼ぶとして猛禽類の剥製を欲しがった。
1960-1970 年代に中国 (本土) からの独立性が強まり、環境面でも規制が及ばなくなって日本への剥製輸出が急激に増えた。
1976-1977 年に剥製用サシバの6万羽が日本に輸出された、1978-1979 年に3万羽を輸出。1978年10月の Echo magazine にこの種の悲劇が取り上げられ、保護の出発点となった。台湾、日本と国際協力でこの種を救う活動が始まった。
1983 年に台湾が East Asia Bird Conservation Union に加わることが認められ、1989 年にサシバの保護の法律が通って狩猟は急激に減少したが、台湾を無事通ってもフィリピンで密猟される (この件はご存じの通り)。
2006 年に台湾で再度密猟が発覚。サシバのような種がこのような破壊行為にいつまでも耐えることはできない。現在は当局が法律を徹底できていないことが問題でかつてほど効果的な対策を当局に期待できない。
Gray-faced Buzzard (Birding in Taiwan) にも上記出典と思われる英文の歴史の記事があった (文献の紹介もあり)。
日本の台湾統治時代の鳥類学者はおそらくサシバが台湾を通って渡ることに気づいておらず、標本も3点しか残していないとのこと。現地名では "Nan-lu Ing" と呼ばれていて South-road Eagle の意味で南へ向かうことは知られていた。
「野鳥」1991年7月号 (No. 538) pp. 22-23 に市田氏の「台湾のサシバ」の記事がある。
市田 (2005) Birder 19(4): 76-78 に「環境保護, 激動の 30 年」の連載の一つがこのテーマになっている。1978 年の輸出業者の調査の生々しい報告、1979年10月にサシバ調査隊が台湾に向かったことなどの歴史が述べられている。市田 (2004) Birder 18(8): 46-47 にもワシントン条約に関連した記事で台湾の剥製業者やサシバに関連する情報がある。
過去の歴史も少し取り上げている最近のニュース (台湾のサシバの渡りの季節到来)
台湾猛禽研究会の衛星追跡の結果も紹介されている。ルートを見ると大陸からの個体も結構多いのかも知れない。秋と春で渡りルートが結構異なっていて、春は遠回り傾向がある。日本にやってきたものもある。
1982 年ごろは日本での剥製需要があって経済的価値が高かった。狩猟圧も下がって個体数は近年は増加傾向で、2020 年の秋の渡りは特に多かったとのこと。
2023 年のニュースではこのところ年平均 10 万羽とのこと (鷹河) 前年のサシバ2万羽の渡りの映像が紹介されている。
[サシバ類とは何者か]
属名の紹介のところでオオタカとノスリの中間の意味を紹介したが、確かにそれぞれに似た点があるように見える。食性はノスリに近い点があるかも知れない。
系統的にはそこそこ難しいグループで、#トビの備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] で紹介したが、ノスリ亜科 ノスリ族 Buteonini の先頭グループ、すなわち最も分岐が早いと位置づけるのがもっともらしい。ただしノスリ族の他のメンバーとはやや離れているのでサシバ族と分けてもよいぐらいである。
何が言いたいかといえば、サシバ類は (一般的な表現で言えば) ノスリ類の中で最も原始的なグループと位置づけることができるかも知れない [ただし分岐は 1700 万年前ぐらいと古いがサシバ類が種分化したのは 700 万年前ぐらいとかなり後の時代になる。いずれも Catanach et al. (2024) の数字]。
あるいは "サシバ族" とみなせるぐらいであれば、海ワシ類 + "サシバ族" + ノスリ類 という共通祖先を考えてもよい。ノスリ類と合わせて考えるよりも、海ワシ類とノスリ類を生み出した系統に似たものがサシバ類を生み出したということである。海ワシ類とはだいぶ違うので通常は分けて考えられるわけだが。
そのようなノスリ亜科 Buteoninae の中で、熱帯で主に地上性の小型動物を捕食する系統として一足早く生まれたのだろうか。このぐらい古い時期だと同様の食性を持つ猛禽類はまだあまりおらず、主な競争相手はカンムリワシ属が考えられる。ご存じの通りこのグループはそれほど強力な種類ではない。
チュウヒワシ属 (ヘビワシ類) は有力な競争相手だが、現在はアフリカからヨーロッパが中心で、サシバ類の分布とあまり重複がない。これらの種の存在のためサシバ類の分布が南・東南アジアから東アジアに限定されているのかも知れない。
カタグロトビ亜科または科もすでに存在していて競争相手になっていたかも知れないがこれらは比較的小型種なのであまり問題なかったかも知れない。
ハチクマ類もすでに分布していた可能性があり、まだハチの子食に特化していなければ競争相手だったかも知れない (ただしカンムリワシ亜科もハチクマ類も現生種の種分化年代は比較的新しく当時はあまり主要な種ではなかったかも知れない)。
もっと大型種の系統のクマタカ類も分岐年代は比較的新しく、食性が違うのであまり競争が生じなかったかも知れない。広義 Accipiter 属は古くから存在したが食性が違うので食物面ではあまり競争が生じなかったかも知れない。
オオタカ類から新しい系統として分岐したチュウヒ類は異なる生息環境に進出したが、生息環境の違いから競争は生じにくかっただろう。
一番問題となり得る相手は系統的にも近いノスリ族 Buteonini だろうが、これらは長期間南米で進化を遂げ、旧世界に戻ってきたのが遅くなりかつ北方系が中心となったためサシバ類は競争を免れたのかも知れない (これが主な論点のつもり)。
アフリカやユーラシアから北米・南米へと分布を広げたはずのノスリ族 Buteonini の祖先系統はそれほど目立った種類ではなかったようでユーラシアには現存せず、北米・中米にわずかに残っている程度。
#トビ備考の [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] を参照。ミシシッピートビが該当する。この程度の種類であれば競争熾烈であったユーラシアにもし生息していても競争排除されたかも知れない。トビとの競争も考えられるが、トビの中で長距離の渡りを行う遺伝型が生まれてユーラシア全体に分布を拡大した後になった可能性があり、この時代の間隙をぬうようにノスリ族の祖先系統が北米に分布を広げることができたのかも知れない。
もしサシバ類のような系統が南米で生まれていれば新しいノスリ類との競争に勝てなかったかも知れない (サシバ類と南米系統のノスリ類の間に相当の系統差、時間差があるので、実際にそのような系統が例えば南米にあったが消滅した可能性もあるかも知れない)。
このように考えるとサシバ類はノスリ類の大部分が南米で進化したために、この中では比較的古い系統であるながら残り得たグループと言えるのかも知れない。
渡りの時は数多く見られて有り難みが若干薄いかも知れないが、里山のような人為環境のないところでの生息密度は高くなく、食性的には幅広く生活できそうなのに世界的に広い地域に進出していないなどノスリ類などに比べて生態的には弱いところを抱えたグループなのかも知れない。
サシバの繁殖分布が日本周辺に限定されているのも、大陸の最も東側で競争相手の猛禽類が少ないためとも解釈できる。
「野鳥」1993年4月号 (No. 557) p. 9 にいわむろかずお氏による「チャボを襲ったサシバ」の記事がある。3日連続で通って食べていったとのこと。
[サシバの幼鳥はなぜ日本に帰ってくるのか]
若杉 (2014) Birder 28(9): 24-25 で取り上げられている。最近になってヨーロッパハチクマの衛星追跡から興味深い状況が明らかになったのでこちらにも取り上げておく。
#ハチクマの備考 [ヨーロッパハチクマはいつ繁殖地に戻るか] を参照。
ヨーロッパハチクマの場合は初めて繁殖地に帰還する時の到着は遅く、繁殖には間に合わない。出生地に戻るわけではなく、ヘルパーとなっていない。一度渡り全体の経験を積むこと、戻って最初の1年は場所探しや経験を積むための役割があると考えられている。
サシバでも遅い時期の幼鳥の春の渡りが知られていて (伊良湖ではハチクマの春の渡りの時期にサシバの幼鳥が渡るとのこと)、ヨーロッパハチクマと同じような意義があるのかも知れない。いわゆる春のタカ渡りの観察ピーク時期からは外れるので初めて渡りを体験する個体があまり目視されていないだけかも知れない (この点はハチクマも同様だろう)。
サシバの方がヨーロッパハチクマに比べて生活史戦略が短いかも知れない (また系統的にもオオタカに類似点があって短い年月で成熟できるのかも知れない)。
サシバでもヨーロッパハチクマ同等の幼鳥の衛星追跡を行えば出生地近くに戻ってくるのか、初めて戻った年の行動、いつ繁殖を開始するのかなどが解明できるのだろう。
ハチクマの備考 [マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] ではハチクマの生後半年の若鳥がまだ自立せず時々ヘルパーの役割を果たしている事例がある。日本のハチクマの生態は長距離の渡りを行う制約に伴うものと解釈するとよさそうに思える。
三上 (2015) 青森県青森市におけるサシバの 2013 年・2014 年の繁殖について -抱卵の交替・ヘルパーの存在・餌生物- では成鳥によるヘルパー行動が報告されていて、過去にも1例の報告があるとのこと。
前澤 (1990) サシバの複数雄をともなった繁殖例。
一方最近クーパーハイタカで種内托卵が明らかになった (#オオタカ備考の [クーパーハイタカの種内托卵] 参照)。この場合は繁殖能力を持ちながらあぶれ個体となっているものが関与しているはずで、サシバでもあるいは、との感じもする。
上記のヨーロッパハチクマの衛星追跡ではつがい外交尾のためには到来時期がさすがにちょっと遅すぎるだろうか。サシバについては検討の余地がありそう。
[レーダーによるサシバ渡りの予備研究]
Kamata et al. (2024) Field validation of effects of species and flock size on echoes in avian radar surveys
X バンドレーダーで 2022 年に行われた性能調査。検出率が半分になる距離はサシバでは 750 m かそれ以下だった。徳島の鳴門で猛禽類の渡り、新潟の聖籠で水鳥の渡りを調べたもの。"ornithodolite" 1970 年代に Colin James Pennycuick が発明した装置 [cf. Spedding and Hedenstrom (2021) Colin James Pennycuick. 11 June 1933-9 December 2019。
1960 年には名前はまだなかったが使用されていた: Pennycuick (1960) Gliding Flight of the Fulmar Petrel]
で同時に光学的に経路を測定。
猛禽類ではないが気象レーダーで小鳥の渡りの研究が進み始めたオーストラリアの報告: Shi et al. (2024) Distinctive and highly variable bird migration system revealed in Eastern Australia。
[ハブの谷渡り]
「九州・沖縄の鳥」(小学館 1985) 所収の "南九州の鳥" (椋鳩十) pp. 22-23 でサシバを襲うハブの項目があり、奄美諸島ではハブがサシバが来るのを待っていてかみつく。サシバは空高く舞い上がって狂ったように飛び回る。地元では「ハブの谷渡り」と呼ばれているとのこと。
現在検索しても見当たらないが、もし本当ならば現在知られているヘビとタカの関係に関する考えとはかなり異なる。
[伊豆諸島の猛禽類の減少]
オープンアクセスではないので具体的にどの種を指すのか読めていないが、サシバも含まれると想定してこの項目に含めておく: Iijima et al. (2025) Ongoing collapse of avifauna in temperate oceanic islands close to the mainland in the Anthropocene
(伊豆諸島全体で鳥類の多様性が過去 50 年の間に低下した 〜一部の島に導入された捕食者の影響が海を越えて波及した可能性〜 一般向け解説) また、猛きん類が多くの島から消失しました とのこと。
サシバの項目に含めたのは次の論文から: 長谷川他 (1996) 北伊豆諸島におけるサシバ Butastur indicus の行動圏の分布。
この論文ではかつてノスリとトビが繁殖しており、チョウゲンボウが繁殖期に目撃されたが繁殖は確認されていない。ハヤブサも目撃されたが繁殖は確認されていないとのことだった。
これらがいずれも消失した結果が得られたのだろうか。トビは人為環境に依存して数を増やしていた可能性もあり、近年本土でも衰退傾向なので要注意だろう。ノスリは本土では数が増えているようだが移動力の大きい種類なのでこの解釈にどの程度あてはまるものだろうか。
サシバは夏鳥なのでこれらの種とは事情 (要因) が違うかも知れない。論文の存在の紹介まで。
[サシバの漢字]
コンサイス鳥名事典に難しい漢字が使われていたので何かと調べてみると、(shuang jiu) のようで、「本草綱目」に現れるタカの一種とのこと。其性爽猛 なのでこの名前が付いた記述がある。旧字体で 爽 + 鳥。
この漢字は鳩と組み合わせてのみ用いられるらしく、(shuang) に英語版説明がある。同中国語版ではこの漢字は日本で使われた借用文字で、タカを指すとのこと。具体的にどのタカを指すまでは書かれていない。"鳩" が付くので比較的小型の丸っこいタカ (??) (#ウソの備考 [ウソの漢字の意味] 参照)。(春秋正義の用例)。
「本草綱目」を輸入する際にどのタカかわからないのでサシバと解釈されたのかも。西洋で pernis がどのタカかわからないのでハチクマに割り当てた程度のものかも知れない。
-
ノスリ (分割された)
- 第8版学名:Buteo japonicus (ブーテオー ヤポニクス) 日本のタカの一種 (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Buteo buteo (ブーテオー ブーテオー) タカの一種
- 第7版亜種学名:Buteo buteo japonicus (ブーテオー ブーテオー ヤポニクス) 日本のタカの一種 (代表的亜種。他亜種あり)
- 属名:buteo (m) タカの一種
- 第8版種小名:japonicus (adj) 日本の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 第7版種小名:buteo (トートニム)
- 第7版亜種小名:japonicus (adj) 日本の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:[Buzzard 分離前の名称], IOC: Eastern Buzzard
- 備考:
buteo のラテン語は u, o ともに長母音。アクセントは冒頭 (ブーテオー)。wiktionary によれば語源は声を真似たものではないかとある。
japonicus は o に長音記号が付くが実際には短音で読まれることが多い (長音で読んでもよい)。
いずれの場合も -po- がアクセント音節 (ヤポニクス または ヤポーニクス)。日本を表すラテン語は Iaponia (または Japonia) でこの場合は o はほぼ長音で読まれるとのこと。お好みでどうぞ。
分割のため第7版学名は代表的亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第7版ではヨーロッパノスリと同種とされていた (上記古い英名もその時代のもの)。
Buteo 属はヨーロッパノスリ Falco buteo Linnaeus, 1758 で使われた種小名を de Lacepede (1799) が属名として昇格したもの (Discours Ouv. Clot. Cours Hist. Nat.) "BUSE, Buteo. Bec, tete et base du bec des Eperviers; ailes des Aigles; tarse gros et court":
嘴と頭はハイタカ、翼はワシ、ふしょは大きく短いとの記述。フランス語で buse がすでに使われていたのでそれに対応する属名を与えたのだろう。
ただし Buteo 属が設けられて以来ヨーロッパノスリの学名が Buteo buteo であったかと言えばそうでもなく他の学名が一般的に使われていた。後の解説参照。
Boie (1826) も当時の Buteo tachardus (後に無効名と判定された) をタイプ種として Buteo 属を設けた。
Buteo tachardus の有効な学名は The Key to Scientific Names では Buteo buteo trizonatus Rudebeck, 1957 を採用しいかにもヨーロッパノスリの亜種で問題がないように見えるが、現在ではモリノスリ Buteo trizonatus Forest Buzzard に分離されているので別種となる。
日本のノスリは現在別種とされて Buteo japonicus となった。
海外リストでは IOC では 1.5 段階で採用されていた。Howard and Moore 4th edition でも同様。wikipedia 英語版によれば 2008 年以降は別種と考えられるようになって一部のリストがそれに従ったが一部は亜種のままであったとの記述がある。
Falco Buteo Japonicus Temminck & Schlegel, 1844 の原記載。la buse commune du Japon の名称が使われていた。
当時の時代背景を考えると亜種としての命名よりも "la buse commune" (ヨーロッパノスリ) の日本版の位置づけの学名と考えられる (他の学名でも同様のものが多い)。
Falco Buteo と Linnaeus (1758) の学名を用いてその後に Japonicus を付記していることとも話が整合する (この Falco が残っていたことで後述のように Falco 属ですでに使われた Japonicus がある問題も発生した)。
同じページで Buteo japonicus や Buteo capensis があるなど Buteo 属を意図して扱っていたことは明瞭。
なお本文中には La Buse du Japon と大文字表記があり (p. 17) 固有名詞的に "日本のノスリ" とも表現している。この前のページでは buse が小文字となっていてこの段階ではまだ種名を意識したものではないが、当時の概念で別種に対応する型 (forme une espece differente) と記述した後に大文字表記が現れるので、単に日本にいるノスリの意味ではなく別種を明確にする意味で使われていると考えられる。
表題にはこの名称は現れないので la buse commune du Japon が正式で、別種を示すための略称であったと考えられる。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) によれば 2008 年のこの分離の出典は Kruckenhauser et al. (2004) Genetic vs. morphological differentiation of Old World buzzards (genus Buteo, Accipitridae) とのこと。
Penhallurick and Dickinson (2008) The correct name of the 'Himalayan Buzzard' is Buteo (buteo) burmanicus も参照。この時点では (buteo) が付いているように別種の取り扱いは暫定的とされていた。
なおこれ以前からも Buteo japonicus の概念は使われていた。
Buteo japonicus toyoshimai Momiyama, 1927 はこの学名を用いている。
もう少し新しい分子系統解析は後の Mindall et al. (2018), Jowers et al. (2019), Nagai et al. (2019, 2020) を参照。大陸のノスリ近縁種全体を考えると分岐年代の浅いグループで種境界をどこに置くか自明と言えるほどではないので、リストによって新しい分類がすぐに取り入れられなかったことは不思議でない。
オオタカとアメリカオオタカが別種とされた事情とは異なっている (#オオタカの備考参照)。
'Himalayan Buzzard' (Birdforum 2009) によれば事情はさらにややこしかったようで、
Buteo plumipes ('Parbattiah' [= Hodgson], 1836) の名称 [もとは Circus plumipes Hodgson, 1836 (鉛色の足の意味。参考 基産地ネパール。ノスリもチュウヒもよく区別されていなかったことがわかる] の方に先取権があったはずだが、Falco plumipes Daudin, 1800 の名称 (参考) がすでにあり、
Hartert (1914) が Daudin の用例を Buteo lagopus lagopus のシノニムとしたために Buteo 属となり、Hodgson による Buteo plumipes の方は preoccupied で無効な学名となった。そのためこのグループを指して Buteo burmanicus Hume, 1875 とする名称が最も古く先取権が発生するとのこと。
Buteo burmanicus を別種としない立場では Faclo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 = 現在の Buteo japonicus の方が Daudin (1800) より遅いので、
もし Daudin (1800) の用例を Hartert (1914) が念入りに Buteo 属に編入していなければ Buteo plumipes の学名は有効で、日本のノスリもこの学名になっていた可能性がある。
ただし Daudin (1800) の用例をそのまま見過ごすわけには行かず、どの種か判定して必要ならば優先順位を考える必要がある (古い用例なので何かの学名の先行シノニムとなる可能性がある)。たまたま Buteo 属と判定できた
(先行シノニムとなって話が複雑になるのを避けて単に整理したしたのかも知れない。ケアシノスリのシノニムならば先行シノニムにならず安全である。しかしケアシノスリの足が鉛色かと言えばちょっと違う気もする...)。
Hartert (1914) の記述: 参考。何と基産地南アフリカと間違っているとのこと。
現在の日本のノスリの学名は紙一重のところで決まったとも言える。
なお "Himalayan Buzzard" を別種とする立場であれば問題なく Buteo japonicus となる。
このページによればもう一つ悩ましい学名があって Buteo pygmaeus Blyth, 1845 (参考) とのことで、記述からは Buteo とは思えず、サシバの若鳥では、などのコメントがある。
サシバの通常の分布域からやや遠いのでサシバ類の別種、あるいは迷鳥だった可能性もあるかも。
当時のインドに3種のノスリ類が知られていて、canescens がヒマラヤから北部地域、longipes が西部から南部、rufiventer が南部とのことだったが、当時は Buteo と Circus の区別が曖昧で、
配列順から Circus pectoralis Vieillot, 1816 (参考) = Accipiter ferox Gmelin, 1771 (参考 = チュウヒワシとされるが無効な学名とされる。#オオノスリ備考参照) が混ざっているのではなどの考察が出ている。
個人的にさらに気になっているのは longipes の名称を持つものが
インドワシ Clanga hastata (かつては アシナガワシ Clanga pomarina と同種扱い) と混同、または Buzzard よりも大きいの Eagle とされたなどで、英語の Long-legged Eagle (アシナガワシの和名の由来と思われる) の名称につながっていたのでは? 分布的にはよく合っている。
Long-legged Eagle に対応する有力な学名がこれまでのところあまり見当たらないので、あるいはと気になるところ (#カラフトワシ備考参照)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版でも同じ。長くヨーロッパノスリと同種とされていたため、書物等の記載でヨーロッパノスリの特徴が混ざっているかも知れないので注意 (大きさについてはヨーロッパハチクマとハチクマほどの大きな違いはない模様)。新しい分類でのヨーロッパノスリの英名は Common Buzzard となる (IOC)。4亜種ある (IOC)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Buteo vulgaris Leach とあり (和名別名にアカノスリ)、列挙されている学名からも Temminck and Schlegel (1844) とは異なってヨーロッパのものと別種とは考えていなかったことがわかる。
Leach の記載年は現代の資料では 1816 年とされる。Linnaeus (1758) に Falco Buteo がすでに登場する (原記載) のに当時から比較的最近まで (1950 年代の用例もあった) 広く用いられていた学名で現在ではシノニムとされる。
Linnaeus (1758) にも Linnaeus 以前の学名として Buteo vulgaris が載せられており、古くから使われていた慣性のようなものがあったかも知れないが、
Ramles in Florida にあるように同じものを指して別の研究者がそれぞれ別の名前で呼んでいた経緯もあった模様 (Pennant は Buteo vulgaris Great Hen-Hawk)。
この記述をみるとアカオノスリの若鳥を指していたように見え、
Common Buzzard にあるように Audubon の色彩画で "Common Buzzard" Buteo vulgaris (別名に Falco buteo が現れる) と称したものは アレチノスリ [高野 (1973) ではスウェイソンノスリ] Buteo swainsoni Swainson's Hawk とのこと。
"vulgaris" と英語 "common" の対応がよいので間違われたのかも知れないが、ノスリ類がどれもある程度似て見えることの表れかも知れない。北米の用例で混乱が発生し、後に先取権の扱いも現代のものとなって現在のヨーロッパノスリの学名に落ち着いたのかも知れない (詳しい経緯は未確認)。
英語 buzzard は OED によればフランス語 busart からの借用で 1300 年ごろから用例があり、鷹狩りには使えない劣ったものを指し、フランス語 buse にも同様の意味があるとのことだが両者の関係は不明とのこと。両言語ともラテン語の buteonem (buteo の対格) から派生したと考えられているが、どのように語形変化を起こしたのか不明のこと。
少なくとも英語・フランス語ではノスリを表す単語には劣った意味があるらしい (アメリカでは同じ種でも hawk を用いる一つの理由になり得るだろう)。
比喩的な用例は 1377 年のものが知られているとのこと。between hawk and buzzard の古い成句があり同種のものの良いものと悪いものの中間を指すとのこと。転じて薄明中を指す用例もあった。
[Buteo (ノスリ) 属の系統分類]
これまでと同様 Catanach et al. (2024) の順序による。
ノスリ亜科 Buteoninae ノスリ族 Buteonini
ノスリ属 Buteo
ミナミハイイロノスリ* Buteo plagiatus Grey Hawk
ハイイロノスリ Buteo nitidus Grey-lined Hawk
ハネビロノスリ Buteo platypterus Broad-winged Hawk
ヒスパニオラノスリ* [高野 (1973) ではリッジウェイノスリ] Buteo ridgwayi Ridgway's Hawk
カタアカノスリ Buteo lineatus Red-shouldered Hawk
オビオノスリ Buteo albonotatus Zone-tailed Hawk
ハワイノスリ* Buteo solitarius Hawaiian Hawk
アンデスミジカオノスリ Buteo albigula White-throated Hawk
ミジカオノスリ* Buteo brachyurus Short-tailed Hawk
ガラパゴスノスリ* Buteo galapagoensis Galapagos Hawk
アレチノスリ [高野 (1973) ではスウェイソンノスリ] Buteo swainsoni Swainson's Hawk
ナンベイアカオノスリ Buteo ventralis Rufous-tailed Hawk
アカオノスリ Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk
ケアシノスリ Buteo lagopus Rough-legged Buzzard
アカケアシノスリ Buteo regalis Ferruginous Hawk
アカクロノスリ* Buteo rufofuscus Jackal Buzzard
ヨゲンノスリ* Buteo augur Augur Buzzard
アフリカアカオノスリ* Buteo auguralis Red-necked Buzzard
ソマリアノスリ* Buteo archeri Archer's Buzzard (現在は通常ヨゲンノスリの亜種とされる)
マダラノスリ [高野 (1973) ではヤマノスリ] Buteo oreophilus Mountain Buzzard
モリノスリ* Buteo trizonatus Forest Buzzard
ヨーロッパノスリ Buteo buteo Common Buzzard
ニシオオノスリ [高野 (1973) ではオオノスリ] Buteo rufinus Long-legged Buzzard
オオノスリ [高野 (1973) ではヤマオオノスリ] Buteo hemilasius Upland Buzzard
ヒマラヤノスリ* Buteo refectus Himalayan Buzzard
ノスリ Buteo japonicus Eastern Buzzard
以下遺伝情報なし
マダガスカルノスリ** Buteo brachypterus Madagascan Buzzard
ケープベルデノスリ/ケアプベルデノスリ** Buteo bannermani Cape Verde Buzzard
ソコトラノスリ** Buteo socotraensis Socotra Buzzard
系統が分岐するところに空行を入れてある。ノスリ属は分岐年代も若く大きな分岐ではないが、地理的にみると系統的なグループを形成していることがわかる。ノスリ属内に目立った大きな系統はない。
これまで Buteo 属に含まれていたものが分離されたものもある。
Rupornis (オオハシノスリ) 属1種、Geranoaetus (ワシノスリ) 属3種がそれに相当する。この属に属するセアカノスリには隠蔽種の可能性が指摘されて議論されている (#トビの備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] 参照)。
Buteo bannermani、Buteo socotraensis ともに高野 (1973) の時点では記載がない。
ケープベルデノスリ/ケアプベルデノスリの名称が見られるが、国名の日本語表記はカーボベルデ (外務省) とされるため、国名を用いるならばカーボベルデノスリの名称の方が適切であろう。
ソコトラ島 (イエメン) の表記はあまり揺れがないのでこれでよさそうである。いずれもアフリカ近くの島の固有種。
ソコトラ島は種の固有性は極めて高く、「インド洋のガラパゴス」とも呼ばれている (wikipedia 日本語版より)。
Clouet and Wink (2000)
The buzzards of Cape Verde Buteo (buteo) bannermani and Socotra Buteo (buteo) spp.: First results of a genetic analysis based on nucleotide sequences of the cytochrome b gene
によればこの2種は近縁でアフリカ大陸東西の島にそれぞれ定着したものと考えられ、分岐年代は9万年前程度とされるとこのこと。アフリカに分布するニシオオノスリが近縁種とのこと。上記系統分類ではヨーロッパノスリを含む最後の系統に含まれると考えてよいだろう。
ソコトラノスリは非常に攻撃的との報告がある。
AviList (2025.6) ではカーボベルデノスリはヨーロッパノスリに含められることになった。
系統を順を追って見ていただければすぐわかるが、Buteo 属も起源は南米で、北米にも分布を広げたことがわかる。
そのうち {アカケアシノスリ + ケアシノスリ} 1系統がまず北方に適応してケアシノスリがユーラシアに到達したと読める。
この系統と独立にユーラシアに到達したか、あるいはケアシノスリの祖先から進化したかどうかはわからないが、もう1系統のグループがユーラシア中緯度からアフリカにかけて広く分布した。
我々が普通みかけるノスリ類はすべて後者のグループで、北方型のケアシノスリが越冬南限近くで少数が訪れている考え方でよいだろう。
Buteo 属は分散能力が高いようで、大陸から遠く離れた離島に分布するものもある。
例えばガラパゴスノスリ Buteo galapagoensis (英名 Galapagos Hawk) があり、これはアレチノスリ
[高野 (1973) ではスウェイソンノスリ。コンサイス鳥名事典でもこちらの名称が使われていた。慣用名から人名を廃する近年の北米の動きを考慮するとアレチノスリの方がふさわしいだろうか。しかし南米はこの限りでないので引き続き Swainson's Hawk と呼ばれるかも知れない]
Buteo swainsoni (英名 Swainson's Hawk) から 30 万年前に分岐したと考えられている:
Bollmer et al. (2006) Phylogeography of the Galapagos hawk (Buteo galapagoensis): A recent arrival to the Galapagos Islands。
ダーウィンが訪れた時、人を全く恐れなかったことでも有名。#ハチクマの備考アゾレス諸島の猛禽類 (ヨーロッパノスリ) についても参照。
この分岐年代はガラパゴスに定着した鳥の中では最も新しいとのこと。ちなみにカケスとサドカケスの分岐年代も同じぐらい。サドカケスの場合は環境が本土とそこまで大きく違わなかったが、ガラパゴスノスリでは生態系の頂点に立ってしまったため表現型の変化も大きかったのかも。
アフリカの4種アカクロノスリ、ヨゲンノスリ、アフリカアカオノスリ、ソマリアノスリは比較的近縁で北半球のノスリグループと並ぶ系統をなす。ヨゲンノスリ、ソマリアノスリは高野 (1973) の時点では記載がないがおそらくアカクロノスリの亜種として扱われていたのだろう。Brown (1976) ではヨゲンノスリは種として扱われ、本文にもアフリカの代表種として何度も記述がある。
ヨーロッパノスリも一部アフリカで越冬するため、ヨーロッパノスリのグループがこれらの地域に分布を広げて進化したと考えることができる。
ヨゲンノスリ、アフリカアカオノスリの augur, auguralis はラテン語・英語ともに augur で avis (鳥) 由来で、鳥などの動きを用いて占いを行う鳥占い師 (アウグル) で卜鳥官 (ぼくちょうかん) などとも呼ばれる。ワシなどの飛行の観察は特に重要だったとのこと (The Key to Scientific Names)。"ヨゲン" はその意味からであろう。
ソマリアノスリは IOC 12.2 以降ヨゲンノスリの亜種扱いとなっている。遺伝的には多少の違いが見られるが古典的遺伝子しか調べられていないので決定的なことは言えない模様。現在独立種としている主要リストはないようである。ヨゲンノスリの色の違う morph との考えもある (ノスリ類は分岐年代が新しいのでどこでも分類がややこしいのだろう)。
ソマリアノスリの種小名に使われる archeri は当時英国領ソマリランドの探検家 Geoffrey Francis Archer に由来。
AviList (2025.6) では種分離しない扱いとなった。
8639 363 Taxon archeri is treated as conspecific with Buteo augur, as the evidentiary basis for a split is weak. Sometimes treated as a distinct species, variation in plumage characters suggests it is a rufous color-morph (Clark 2003) or subspecies of B. augur (Clark 1996). Genetic data for archeri are uninformative, being limited to a short section of mitochondrial DNA (Riesing et al. 2003) of uncertain provenance; although aligned with a group that includes augur and rufofuscus, the position of archeri remains poorly resolved.
ソマリアノスリの遺伝情報がまだ乏しいことも背景にある。
ヨゲンノスリはアフリカでも目立つ猛禽類で飛行する姿は妙に尾が短く翼が広く見えるが、とまっている姿は白黒がはっきりしてなかなかハンサムに見えてよく被写体に選ばれている。
ノスリの名前から想像する印象とはだいぶ違うので画像検索をしてご確認いただきたい。(ここで調べるまで和名を知らなかったのだが) 私的になかなか好みの種類の一つ。
他のところでクラシック音楽をよく話題にしているのに、ここでなぜロベルト・シューマン作曲の「予言の鳥」が出てこないのか不思議に思われている方もあるだろう (多分ないかも...)。この曲は「森の情景」Waldszenen という曲集の1曲で、この中では際立って有名な作品である。
「予言の鳥」は原題 Vogel als Prophet で「預言者としての鳥」の意味。昔聞いた時にはフクロウの意味だと教わった気がするのだが (暗い雰囲気はそのような感じもするが)、以下のような資料をみつけた Robert Schumann, "The Prophet Bird" (No. 7 from "Forest Scenes" op. 82)
(Wolf-Dieter Seiffert 2010) この曲は描写音楽 (表題音楽) の側面はほとんどなく、シューマン得意の霊感を昇華させたということだろう。ゲーテの詩集 Gesellige Lieder の中の Fruehlingsorakel (春の予言) の中に「預言者の鳥よ、花盛りの歌い手、カッコウよ!」と出てくるそうで、実はカッコウを指しているらしいとのこと
(#カッコウの備考にあるようにヨーロッパでは日本よりずっと早い時期にカッコウが渡ってくる。初夏というより春を告げる鳥の位置づけなのだろう)。音楽の中にもカッコウの声を借りたと思われるモチーフが出てくるらしい。
深い森の奥に住み、声はするが姿は見えない鳥で鳥の声を借りて神の啓示を与えるという。興味ある方は読んでみていただきたい。
シューマンの曲で同じように鳥を連想されるものに「飛翔」があり、こちらは幻想小曲集 Phantasiestuecke の1曲で原題は Aufschwung で比喩的な飛翔、躍進などの意味らしい。英語では "Soaring" とよく訳されているが原意は "Upswing" に近い。いずれにしても比喩的な意味で、有名な曲ではあるが鳥そのものとはあまり関係がないらしい。タカ柱などを想定して "Soaring" も許容範囲かも知れないが、意味は「上昇」の方が近いかも知れない。
Schumann's Fantasy Pieces, Opus 12 (Edward Baxter Perry 1906) に解説があり、Longfellow の有名な詩 Excelsior (1841) こちらは「もっと高く」と訳されているが、同じようなテーマを扱っているとのこと。ご存じの方もおられると思う。
ラテン語 excelsus の比較級由来で独立革命を達成したアメリカの喜びと希望を体現する言葉だったとのこと ('エクセルシア'考 寺内孝 2003)。シューマンとは背景が異なるが同時代の 19 世紀の雰囲気を多少なりとも伝えているかも知れない。
シューマンの音楽には平易で有名なもののあるものの、彼一流の霊感性はファンでないと理解が難しいのかも知れない。有名な曲で構造は単純であるが「交響的練習曲」の終曲などは演奏効果も高くてわかりやすく一般にもお勧めしてよいと思う。
ノスリの話題に戻るとモリノスリとヨーロッパノスリは同種でよいぐらいに非常に近い。これらとマダラノスリ [高野 (1973) ではヤマノスリ] の3種でまとまったグループをなす。
マダラノスリの種小名に使われる oreophilus は oros, oreos 山 philos 好む (Gk) で、エチオピアの 3000 m 近くまで生息するというが、熱帯雨林にも生息するため和名が変更になったのだろうか。
マダガスカルノスリもこれらの種と superspecies を形成するとの記載もある。マダガスカルノスリは伐採地を好むようで、ほとんどの種類の猛禽類の減少が懸念されているマダガスカルで人間活動のために数はむしろ増える傾向にあるとのこと。
マダラノスリとモリノスリはしばしば同種とされるが、遺伝研究で単系統でないことが示され、Clark (2007) Taxonomic status of the Forest Buzzard Buteo oreophilus trizonatus
ではモリノスリは通常ヨーロッパノスリの亜種とされる steppe buzzard Buteo buteo vulpinus の越冬地に分布しているためこの亜種から進化した可能性を考えている。[北京で記録されたヨーロッパノスリ?] の項目も参照。移動能力が高いために越冬地に適切な環境があれば定着する可能性があるかも知れない。
モリノスリと Buteo oreophilus の系統が近く、英名は山と森になっているのでヤマノスリの方がふさわしかったかも。参考までに他言語の用例をチェックしておくと「山」を使っているものが多い。ウクライナ語はマダラノスリに近い名前になっているが例外的。
ヤマノスリの名称が別のものと混同されるおそれがあるならば、いくつかの言語で使われている「アフリカヤマノスリ」に相当する名前はよいかも知れない。
これらのノスリ類のグループは遠いアフリカの話だが、steppe buzzard では日本でも記録されている可能性があるためフォローしておくとよさそうである。
ユーラシア中緯度帯に西からヨーロッパノスリ Buteo buteo、
ニシオオノスリ Buteo rufinus、
オオノスリ Buteo hemilasius、ノスリ Buteo japonicus が重複を持って連続して分布する形となっている。
種分化年代が比較的新しいため、異なる種の間の遺伝子浸透や雑種形成も記録されている。この分布関係を知っておくと日本を訪れる頻度の大小が理解しやすい。
ノスリに最も近縁な種類は西ヒマラヤから中国に分布するヒマラヤノスリ Buteo refectus で遺伝的にはほとんど同種にしてもよいぐらい近い。Buteo 属内では同程度に近い種ペアは他にもある。
ノスリとヨーロッパノスリが特に近縁というわけではない。
結果的にこのリスト順では日本のノスリが最後になっているが、ヨーロッパノスリからノスリまでの分岐年代はあまり違わず、中緯度帯ノスリグループの終端とみなしてよいだろう。東の端なので到着がわずかに遅くなった程度の違いである。
Mindall et al. (2018) ではこの順序ではないが最後のグループが1系統をなす点は同じ。ノスリが最後になったのは「たまたま」程度に思っていただいてよい。
なお Mindall et al. (2018) は Buteo vulpinus (後述の steppe buzzard)、Buteo burmanicus (カラノスリ)、
Buteo refectus をすべて種として解析しているがこれらの系統関係を明らかにするほどの分解能は出ていない模様。
Jowers et al. (2019) Unravelling population processes over the Late Pleistocene driving contemporary genetic divergence in Palearctic buzzards
に大陸のノスリ類についての種分化の研究がある。
この研究を受け、North African Buzzard is not a Long-legged but an allospecies of Common Buzzard (MaghrebOrnitho 2019)
によればアフリカ北部の "ノスリ" はニシオオノスリよりもヨーロッパノスリに近いため、これまで使われてきた Atlas Long-legged Buzzard ではなく Buteo buteo cirtensis North African Buzzard (亜種 cirtensis) の名称を提案し、OSME (中東からコーカサスのグループ) はニシオオノスリから分離してこの名称を採用したとのこと。
IOC 14.2 でもまだニシオオノスリに含まれたまま (ヨーロッパノスリの亜種に分離すると IOC ではニシオオノスリは単形種となる)。このページによれば OSME は大部分 IOC に従っているが新しい研究結果が現れた場合は取り入れているとのこと。建設的な扱いに思える。
コメント欄では Portenko (1929) も検討しておりレベルの高い議論となっている。IOC の扱いは少し遅れているだけにも見える。
種レベルのオオノスリとニシオオノスリの和名変遷は#オオノスリ備考にて検討した。
The Red-tailed Hawk Project is a multifaceted research effort that aims to understand one of the most abundant, yet mysterious, raptors on Earth (Scott Weidensaul 2025, from Living Bird)
によれば北米のアカオノスリも DNA と渡り経路研究の結果ややこしいことになっている模様。
Accipitridae (BirdForum 2025.4 の情報による)。
この著者は地理的に大きく離れているがナンベイアカオノスリはアカオノスリと同種と考えているらしい。1個体のみをサンプルした Catanach et al. (2024) の系統樹ではかなりはっきり分かれていた。
この記事にもあるようにアカオノスリにあまりの多くの亜種があり、それぞれに色彩 morph がある (ない亜種もある) とのことで、外見のみで判断すれば何種に分かれるのかと感じるぐらい。論文はまもなく出版されるらしいが、アカオノスリが遺伝的に多様でナンベイアカオノスリを内包してしまうのだろうか。
Wild Wonders: Bryce Robinson on The Red-tailed Hawk Project | October 27 2024 (Lake Tahoe Wildlife Care - Education) に登場する Join Bryce Robinson によるアカオノスリの YouTube 解説。
北米は渡り経路で4系統がある。35:40 付近から系統樹が登場。問題のナンベイアカオノスリはアカオノスリの西系統に属する。ナンベイアカオノスリが古く分岐した系統ではなく最も近い系統は最も広く分布する亜種 calurus (この研究ではアイダホの個体のみを用いたとのこと) であった。
系統樹では亜種はかなりきれいに分かれている。東系統のカリブ海の亜種は新しい分岐というわけでもない。西系統でもしナンベイアカオノスリを種と認め、単系統性を厳格に保つならば西系統のアカオノスリを少なくとも 5-6 系統に分割する必要が生じるが亜種 suttoni が単系統をなさないためこの解決方法も使えない。ナンベイアカオノスリをアカオノスリの亜種とするのが最も受け入れいられやすいものと想定できる。
37 - 38 分あたりで西系統の一部が渡りで南米にも到着して定着した考えを示している (驚きの結果となったが種の進化史を考えればそれほど驚きではないかも知れないと述べている)。他にもメキシコの孤立した亜種にも同様の状況がみられる。migratory drop-off については #アカハラダカ備考の [渡り] 参照。
過去から考えられていた機構で、ノスリ類は新しい系統なのでまだ種に値するほど分化を遂げていないだけかも知れない (また現在でも南米まで渡っている個体があるのかも知れない)。
質疑応答の部分でこの研究者はガラパゴスノスリとアレチノスリ (スウェイソンノスリ) も似た関係と述べており、ミトコンドリア遺伝子で系統樹を描くと互いに単系統の関係にならないが、形態的にも生態的にも大きく違って独自の進化を遂げていることから同種と考えないのが一般的 (分岐年代などガラパゴスノスリのところに既述)。
ガラパゴスノスリのような有名種ならば遺伝情報が豊富かと思ったがそうでもないようで、GenBank に長い配列が登録されていない。参考までによく使われる ND2 AY870891.1 から BLAST を行ってみると確かに言われる通りの関係になり、アレチノスリ (スウェイソンノスリ) との一致率は 99.7% となる。やはりノスリ類は分岐が新しいことを実感できる。
cyt b GQ264783.1 から行うと互いに単系統の関係が得られるが一致率は 99.8%。
ヨーロッパノスリと burmanicus の関係の方がむしろ遠い (["Himalayan Buzzard"] 参照)。
Bollmer et al. (2011) Reduced MHC and neutral variation in the Galpagos hawk, an island endemic ガラパゴスノスリの起源となる大陸のアレチノスリ (スウェイソンノスリ) に比べて免疫の MHC 多様性が低い。創始者効果と暴露される病原体の少なさの両方が関係していると考えられる。もっとも今となってはやや古典的な研究で 255 bp の短い配列が使われていた。
Koop et al. (2014) Birds are islands for parasites もガラパゴスノスリの面白い研究で定着している島ごとに鳥もハジラミもハプロタイプが異なるとのこと。ガラパゴスノスリにとってはこの程度の距離でも海を越えるのはよほど抵抗があるらしい。
ガラパゴスノスリは Santa Cruz, San Cristobal, Floreana の島にかつて定着していたが絶滅したとのこと。Genovesa 島はかつて定着した証拠はないとこと。wikipedia 英語版によれば人間活動で生息地が破壊されたり外来捕食者 (ノネコ) の導入、人による迫害によって食物不足となったと書かれている。
「世界の鳥 2」(小学館 1985) p. 140 によればまた少し違うことが書いてあって、ニワトリを盗むことから大量に殺されて当時わずかの島に 150 つがいが残っているに過ぎないとのことであった。どちらが本当か知らないが外来種を悪者にするのは簡単なのでおそらく直接的にも殺されていたのだろう。この件は英文で検索しても簡単に見当たらない。
昼行性猛禽類で唯一近年絶滅したグアダルーペカラカラ Caracara lutosa Guadalupe Caracara の絶滅要因には、島のみに住み、子ヤギを襲う害鳥とされて (警戒心がなかったため) 簡単に駆除され、鳥類学者の標本採集が最後のとどめを刺して 1911 年絶滅とあり (wikipedia 日本語版。英語版では記述が少し異なり、続きは #ハヤブサの備考の方に)、時代背景的にも状況は似ていたのではないだろうか。
全ゲノムが読まれればまた状況が多少変わってくるかも知れない。ガラパゴスノスリはまさしく離島の隔離分布の進化途上と言えるのだろうか。遺伝的にはガラパゴスノスリとアレチノスリ (スウェイソンノスリ) にはほとんど違いがないのでガラパゴスノスリの一妻多夫 ([ガラパゴスノスリや他の猛禽類の一妻多夫] 参照) は行動の可塑性を表している可能性も考えられるかも。同じような状況ならば他のノスリ類で同じような様式が選択されても不思議でない。属は違うがモモアカノスリもそうかも。
ナンベイアカオノスリとアカオノスリの関係はユーラシアのノスリ類を考察するにおいて注意を払っておいてよさそう。
ナンベイアカオノスリの遺伝子が GenBank に2個あるので AY213024.1 から BLAST を試してみるとアカオノスリで 100% 一致するサンプル (USA: New Jersey。東系統に属しそうな位置だが...) がある。この解析は短い配列のみだが Catanach et al. (2024) では核ゲノムも扱った結果相当の遺伝的距離があったものと想像できる。
しかし Catanach et al. (2024) ではアカオノスリの1サンプルのみを用いている (種よりも高いレベルの系統を調べるためで亜種か種かレベルの評価には適していない) のでアカオノスリの地理的な多様性が反映されていないため生じた違いだろう。
この問題は広域分布して種内多様性の高い種に共通の課題だろう (タカ類では例えばカワリクマタカやハチクマなどを想像することができる。旧ノスリでは暫定で分けられている部分もあって詳しく調べると同様の問題が発生するかも知れない)。
北米のカタアカノスリを東西に分離する提案がなされていた。研究は Barrowclough et al. (2019) Phylogeography and species limits in the red‐shouldered hawk (Buteo lineatus): Characterization of the Northern Florida Suture Zone in birds
論文著者は3種に分割を提案。AOS の AOS Classification Committee - North and Middle America Proposal Set 2024-B で検討がなされた。北米の種なので AOS の判断次第となるが、Bryce W. Robinson は2種への分離を提案。計測値も異なる。
日本のノスリ類から想像する以上に体重が軽い印象を受けたが、アメリカ大陸ではノスリ類がいろいろなニッチを占めているためユーラシアで他の系統の役割に相当する種類が存在するためかも知れない。
ミトコンドリア1遺伝子で種レベルの分離を判定するのは難しいと考えるが他の系統では例がある。
西の elegans は音声も違うことはバーダーも研究者も気づいているとのこと。分離する場合は Red-bellied Hawk (Buteo elegans)
の英名を提案 (学名は "優雅なノスリ" となかなかよい。ユウガアジサシの名称があるので英名を訳すよりユウガノスリでよいかも)。結局は採用が見送られ IOC 15.1 では亜種扱い。将来採用される可能性があるが現状ではまだ幻の種学名。情報が揃えばいずれ採用されるのでは?
この提案ではコガモとアメリカコガモ、ベニヒワ、タヒバリの分離など身近な話題も扱われていた。
北米でこの段階であればユーラシアのノスリ類分類問題の決着にはさらに時間がかかるかも。
[ノスリの亜種]
日本産ノスリはこれまでは3亜種がリストされていて、japonicus ノスリ、toyoshimai (Yoshikiyo Toyoshima 由来) オガサワラノスリ (天然記念物。絶滅危惧 IB 類)、
oshiroi (Masao Oshiro 由来) ダイトウノスリ (1970 年代から確認がなく絶滅したと判定された: ダイトウノスリの国内希少野生動植物種からの削除について。また標本も剥製も存在しないそうである) となる。
ダイトウノスリの記載は Kuroda, Nagahisa, 1971 で 南大東島のノスリ新亜種について、個人飼育個体に基づく記載直後に絶滅したことになる。
「日本本土産のものが渡行した起源と考えられる」とある。この論文では詳細な比較の後続論文の予定が記されているが該当するものは見当たらなかった。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で burmanicus カラノスリが追加された。以下の ["Himalayan Buzzard"] に紹介する。
オガサワラノスリを遺伝的に別の集団とする根拠は Nagai et al. (2019)
Genetic Structure and Diversity of Two Populations of the Eastern Buzzard (Buteo japonicus japonicus and B. j. toyoshimai)
に示されている。
ノスリは日本では東日本で多く繁殖し、西日本では冬鳥の個体が多いので海外でも同様と考えがちだが、フィリピンのルソン島に繁殖しているらしい個体群がある (資料; フィリピンの鳥のチェックリスト 2022)。亜種は不明。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) June 13, 2024 (Pardo de Leon) の写真があるがちょうど換羽を開始したところか。ずいぶん白い個体。
Eastern Buzzards (Buteo japonicus), right before impact に2羽の空中争いの写真が出ている (ルソン島 の Benguet)。
Japanese Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.8.13) にとまった写真がある。脛の羽毛に縞状の模様があり、ふしょがあまり露出していない感じがする。
ケアシノスリと似た特徴がある? Macaulay Library にフィリピンの少数のとまりの写真はあるが、同様の特徴の個体は見当たらなかった。
フィリピンの亜種とダイトウノスリなどとの関係が気になるところだが、いずれ遺伝的関係などが調べられることを期待したい。写真から日本の個体との違いは見つかるだろうか。
#ハチクマの備考 [台湾で留鳥化したハチクマと渡りの謎] の紹介のように、あるいは大陸の渡りのノスリが overshoot/offshoot して島に定着した可能性もあるのではと考えてしまう。
Japanese Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.8.16) に飛翔中の上面の写真が紹介され換羽の進み方がわかる。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.8.13) にも飛び立った直後だろうか飛翔中の写真がある。脛部の縞模様がよく見える。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.9.3) に飛翔中の上面の写真。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.9.9) 飛翔中の側面写真。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.9.27) 飛翔中の上面の写真。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.9.27) とまる直前の画像。翼の両面が見える。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.9.27) 上面の画像。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.9.3)。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.10.29)。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.10.29)。
Eastern Buzzard (Buteo japonicus) (Pardo de Leon 2024.12.1) 時期的には繁殖個体か渡り個体かわからないところ。
[ヨーロッパノスリの亜種]
参考までにヨーロッパノスリの亜種は IOC 14.1 = 13.2 で6亜種で以下の通り: buteo (ヨーロッパに広く分布する留鳥)、rothschildi (アゾレス諸島)、
insularum (カナリア諸島) [かつての arrigonii (コルシカ島、サルジニア島) を含む]。
Rodriguez et al. (2010) Density, habitat selection and breeding biology of Common Buzzards Buteo buteo in an insular environment
にカナリア諸島のテネリフェ島での研究がある。島の亜種として特殊性があるか (insular syndrome) 調べられたが大陸のものとあまり違わなかった。繁殖成功率は高い。競争種はバーバリーハヤブサ Falco pelegrinoides Barbary Falcon (ハヤブサの亜種とされることが多い)。
harterti (Madeira 島) の概念もあり一部のリストで使われているが現在では通常基亜種のシノニムとされる。
一方で Fuerteventura 島のものは色彩に特徴があり、別亜種 lanzarotae と考えるのが適切とのこと: Rodriguez et al. (2017) Phenotypic characteristics of Common Buzzards on Fuerteventura。
この文献では Long-legged Buzzard (一般的な分類ではニシオオノスリ Buteo rufinus) をヨーロッパノスリの亜種 (cirtensis) としており (前述 MaghrebOrnitho 参照)、lanzarotae はヨーロッパノスリの基亜種と Long-legged Buzzard の過去の交雑の結果と考えている。
島ごとに違いがあるのはガラパゴスノスリに似たところがあるが、大陸から比較的近いため複数系統の導入や交雑が起きているのだろう。
pojana は arrigonii のシノニムとされるリストもある。ちなみに poiana はヨーロッパノスリのイタリア名。
ヨーロッパノスリの東部亜種は vulpinus (steppe buzzard、ソウゲンノスリ。vulpinus はキツネに似たの意味だが色を意味するのだろう) がスウェーデン東部、フィンランドなどからコーカサス北部、カザフスタンやキルギスタンの北部、東部を除くロシア、天山山脈からモンゴル西部で繁殖し、長距離の渡りをして大部分がアフリカ東部や南部などで越冬する。
vulpinus を独立種とする考えは古くからあるが、ヨーロッパノスリの基亜種と遺伝的には区別できないそうで広範な交雑が存在する。これらにかつて亜種名が複数 (intermedius など) 与えられていたが vulpinus に整理された。
現在では vulpinus を独立種とする主要リストはない模様。
menetriesi (クリミアからコーカサス、イラン北部の亜種とされ留鳥とされてきたが一部はアフリカに渡るらしい) (主に wikipedia 英語版より)。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではシベリアでは西部 (エニセイ川まで) と東部で vulpinus と japonicus の2亜種としているが、後者を独立種とする文献もあることが紹介されている。亜種ごとの絵は示されていない。
steppe buzzard は渡り鳥として中東を多数通過するため研究もいろいろある。Yosef et al. (2019) Footedness in Steppe Buzzards (Buteo vulpinus)
では利き足を調べ、他の鳥類でよく見られるように右足を先に出すものが半数以上だったとのこと。この論文では独立種の扱いとしている。
["Himalayan Buzzard"]
大陸のノスリの亜種 [burmanicus (ビルマの)] も越冬時に観察されているのではないかとの推測 ("大陸型ノスリ") はあったが、近年の GPS ロガーによる追跡とミトコンドリア DNA の遺伝子解析で確認された
[Nakahara et al. (2022) GPS tracking of the two subspecies of the eastern buzzard (Buteo japonicus) reveals a migratory divide along the Sea of Japan; 長崎大学の発表資料]。
亜種 burmanicus が過去の学名変遷の経緯からヒマラヤノスリと呼ばれていることもある。もしかすると将来同一種となる可能性は否定できないものの、日本鳥類目録第8版の和名が確定すれば少なくとも日本国内での名称問題は解消するだろう。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でカラノスリとして掲載された。
Nakahara (2022) A migratory divide in the Far East (BOU) に英文解説がある。
Nagai et al. (2020)
Discovery of a Novel mtDNA Sequence in the Eastern Buzzard (Buteo japonicus) in Japan
では Buteo japonicus japonicus (亜種ノスリ) が単系統でなく、日本の B. j. japonicus とオガサワラノスリ B. j. toyoshimai を含む Eastern Buzzard group (fig. 3 では外群にあたるヨーロッパノスリ、ケアシノスリも含まれている) と、
中国、ロシアの B. j. japonicus および "Himalayan Buzzard" B. refectus を含む Himalayan Buzzard group の2系統に分かれることが示された。分岐年代は 81 万年前程度と推定される。
かつての広義ノスリからユーラシアで3分割されたうちの1種である Himalayan Buzzard は現在の通常の学名で Buteo refectus だが、ノスリとよく似ている。かつては (ノスリとヨーロッパノスリが分離されない時代の) 亜種 B. b. burmanicus として扱われていたが、独立種 Buteo burmanicus として扱われることもある。
この論文での引用は IOC 9.1 だが IOC 2.7 - 11.1 の期間 Buteo burmanicus とされ、その前後は Buteo refectus となっていた (いる)。
Himalayan Buzzard は中国、ネパール、ブータンが分布の中心と考えられ、ロシアや日本での報告はなかった。Nagai et al. (2020) によってロシアのサンプル1例が Himalayan Buzzard と判定され、従来考えられているより分布が広いことが示唆される。
しかし東アジア地域のノスリの系統研究や種・亜種の分類には限られた mtDNA 部位以外の遺伝情報の解析や、地理的にもより広いサンプルが必要である。
現在は Boyd のみ Buteo burmanicus の種名を用いているが、前述の名称変遷の経緯に基づく可能性がある。
しかし Nagai et al. (2020) の系統樹に基づいて (いずれも現在の IOC 学名準拠で記す) B. j. burmanicus と Buteo refectus を同種に含めたかも知れない。burmanicus の方が記載が早いので種学名は Buteo burmanicus となる。
この扱いの場合は "Himalayan Buzzard" が大陸東側に広く分布し、ヒマラヤ周辺では留鳥で北方の個体群が渡りを行う描像になる。Boyd は分子遺伝学を第一に分類しているとのことなので、渡り習性や越冬地の違いなどは考慮していない可能性がある。
この扱いの場合は日本にすぐ近い大陸部にノスリと別種が生息して少数が冬鳥として渡ることになる。
いずれが正しいかは今後の研究を待つ必要があるだろうが、日本のノスリは1種増えるかも知れない。
名称もカラノスリが適切かどうか、今後さらなる判断が必要になるかも知れない。
少し歴史を遡ると、Dickinson and Svensson (2012) A new name for a buzzard from the Himalayas は burmanicus が満州で繁殖して南に渡る亜種の扱いで満足だが、
Portenko (1935) の名付けた refectus も burmanicus も Hodgson (1836) が plumipes と呼んだヒマラヤの黒い個体とは異なるとの考えを示し
Circus plumipes Parbattiah [= Hodgson], 1836 に代わる名称として Buteo (buteo) hodgsoni を提案している。
plumipes を用いることができない理由は先述の通り。
burmanicus はシベリア、モンゴル、中国北部、北朝鮮で繁殖し、東南アジアで越冬とされていた。
IOC 11.2 以降は burmanicus をノスリの亜種とし、大陸で渡りを行う個体群を指すとしている:
Recognition of burmanicus as the migratory mainland
Asia subspecies of B. japonicus rather than
the name associated with Himalayan Buzzard is based on James (1988).
Race japonicus is limited to the form that breeds on the main Japanese islands (James 1988; Nagai et al. 2020).
とのことで、IOC ではこの時点から大陸で繁殖するものは B. j. japonicus
とは呼ばないとした。同時に Himalayan Buzzard の学名が Buteo refectus に変更され、現在の扱いに至っている。
refectus の意味は再建された、復興されたなど。Voous and Bijleveld (1964) A note on Himalayan Buzzards, (Aves)
によれば、かつては日本のノスリの亜種とされ Buteo japonicus saturatus Portenko, 1929 (暗色の) (参考) 基産地 Ju-tsuchou (Kham), Central Asia = Tibet チベット) と命名されたが、
Asturina saturata Sclater & Salvin, 1876 (参考 = 現在はオオハシノスリ Rupornis magnirostris Roadside Hawk の亜種) がしばらくの間 Buteo 属に統一されていた時期に preoccupied で無効となったらしい (参考)。
そのため Portenko (1935) が改名したもの。refectus にはそのような経緯が含められているのだろう。亜種の学名字義だけを見ていると命名理由までわからない難解な事例と言える。
saturata / saturatus は性による変化のある形容詞なので Buteo 属にまとまった場合は同一名となる上記事例はまだ理解しやすいが、
Accipitridae (BirdForum 2025.1) によればさらに複雑な事例があるようで、Accipiter ruficaudus Vieillot, 1807 (= Buteo borealis boralis (Gmelin 1788) のシノニム) があるため、
van Rossem (1935) は Buteo magnirostris ruficauda (Sclater & Salvin 1869) を preoccupied と考えて B. magnirostris petulans に改名したとのこと (オオハシノスリの亜種。Buteo 属だった時代の問題。現在が属が変わっていて Rupornis magnirostris)。
しかしこれらの ruficaudus, ruficauda はいずれも合成語で性によって変化する形容詞とみなされないため、この2つの綴りは異なると判定できる。つまり現在の規則では実は preoccupied ではない可能性がある (つまり van Rossem が語形変化を誤解していた可能性がある)。
1961 年以前に preoccupied のため改名された学名は永続的に無効とする規則があるため現在は改名された学名が使われているが、そもそも preoccupied でなかったならばこの条件を満たさない可能性があるとのこと。
現実の事例とはなっていないが、さらにもし別属で ruficaudus と ruficauda の種小名が用いられた種があり、属統合によって同属となった場合は一見男性形と女性形の同じ形容詞に見える2つの種小名が共存可能となる理屈となる (未確認)。
Buteo refectus の場合は preoccupied となった相手の種は現在別属で saturatus は重複しないことになるが、この理屈によれば 1961 年以前の改名のため元に戻さないものと考えられる。
Portenko 自身が気づいて改名したため記載者が変わる問題は起きなかった模様。
ほとんどパズルのような世界だが、Buteo refectus に本来使いたかった学名は Buteo saturatus で "暗色のノスリ" の意味となるので、色彩を考察する場合は記載者が何を考えたかも考慮に入れておくとよい。
Voous and Bijleveld (1964) 当時から Buteo buteo の亜種にするか見解がすでに分かれていたようである。
B. j. burmanicus と Buteo refectus (およびヒマラヤ周辺の個体の遺伝子構造) の関係は十分に解明されているとは言えないので、将来同種扱いの可能性も残るだろう。
ノスリの分類、学名を見る時には最新の文献を参照する必要がある。
Peng et al. (2014) Complete mitochondrial genome of Himalayan buzzard (Buteo buteo burmanicus)
の分子遺伝学研究があるが、前述の BirdForum の指摘によれば Wu et al. (2014) の結語部分をコピー・アンド・ペーストしたことは明らかで直し忘れがあるとのこと (Abstract を見るだけでわかる)。編集委員も査読者も真面目に読まなかったのでは? このグループの論文があまり信頼されていない一端がうかがえる。反面教師のような論文となってしまった。
KM364882.1 が発表された塩基配列で BLAST で処理してみると確かに Buteo buteo とは距離があってヨーロッパノスリとは別種 (GenBank では Buteo japonicus burmanicus となっている) が適切とわかる。ヨーロッパノスリとオオノスリぐらい違っている。
AY423068.1 (韓国で Buteo japonicus japonicus となっているサンプルの cyt b 遺伝子。投稿は 2004 年なので当時の分類を反映していると思われる) をベースに行ってみると burmanicus とは結構違いがある (#オオノスリ備考にもミトコンドリアゲノムを用いた関連情報あり)。
McClure et al. (2020) Towards reconciliation of the four world bird lists: hotspots of disagreement in taxonomy of raptors
にもこの種の学名の扱いを統一 (例えば ICZN による裁定) する提案が出ているので再掲しておく。
分子遺伝学情報が固まらないと種境界が決まらない問題はあるかも知れないが、保全を優先するならば分類上は多少の曖昧さが残っても学名を統一する裁定を行う方が利益があるかも知れない。
さらに古く遡ってみると Dement'ev and Gladkov (1951) ではノスリもヨーロッパノスリの同種で世界的に広く取り扱っている時代であるが、バイカル湖以東の東シベリアから日本に至る亜種を B. b. burmanicus (Oates 1875) と扱っており、インドから東南アジア、中国の一部に渡るとしている。
japonicus (Temminck and Schlegel 1844-1845) もシノニムとして載っているが、すでに使用されている名称 (nom. praeoccupatum) なので burmanicus が優先される扱いとなっている。
'Himalayan Buzzard' (2009.1.26) の記事によれば
Collin and Hartert (Nov. Zool., 34, 1927, p. 51) がこの問題を指摘したとのことで、
Nomina Mutanda (Collin and Hartert 1927) によればチョウゲンボウの亜種に Falco tinnunculus japonicus (Temminck and Schlegel 1844) があってこちらが先に使われたとの判断だった模様。チョウゲンボウの種・亜種の名前については複雑なため #チョウゲンボウ に記した。
Falco と Buteo の属が違うのでよさそうにも見えるが、記載時はどちらも Falco が付いていたことが問題視されたようである。
他の種の記載でも反復して現れるが、Temminck and Schlegel の時代は亜種概念がまだ明確でなく一貫した記法はまだなかった。Falco Buteo Japonicus の名称は (Linnaeus の記載した) Falco Buteo の日本版の意味で使われたと考えられ、Falco Buteo の亜種を現代の三名法で表したものではないと判断できるだろう。
この記載を現代流に文字通りに読めば Falco 属の種に亜種小名 Japonicus を付けたもので、その場合は Falco tinnunculus japonicus の用例が先にあるため Falco 属内で preoccupied になる。
しかし "Falco Buteo の日本版" の意味で Buteo を属名として用いたものと考えれば preoccupied ではない。Temminck and Schlegel の記述を現代の三名法に合わせて解釈してよいかの判断も含まれ大変複雑である。
Portenko (1929) Ueber den taxonomischen Wert der Formen der palaearktischen Bussarde. Erster Teil (p. 642)
はこの件を議論して Buteo japonicus が同じ文献内に述べられているので Buteo japonicus が正当であるとしている。
Temminck and Schlegel が本文中で Buteo japonicus と言い換えを示していなければ Falco 属内で preoccupied となっていたのかも知れない。
もっともこの話も完全に明快とは言い切れず、Le Buteo japonicus のように定冠詞を付けて表している。同じ解説内に現れる Falco tachardus には定冠詞を付けず、Buteo のみ定冠詞が付いているのでこれは学名扱いではなくフランス語で Buse を言い換えたものと主張することも可能なように感じられる。ラテン系言語なのでラテン語の表現を借用することも不自然でない。
同書のサシバの記載のところには Buteo polyogenys またはかつて用いた学名の Falco polyogenys の表現が現れるので、Falco 属と Buteo 属の区分にまだ若干の不定性を感じていたのかも知れない。
ここでは他の著者がサシバ類に Buteo 属を用いていたのでそれに合わせたように読める。
Portenko のノスリ類解説の第2部も同じページからダウンロードできる。
Dement'ev and Gladkov (1951) はこの論文は当然承知していただろうと思われるが重複と判断した理由はよくわからなかった。Portenko (1929) 以降に再度考察されたのかも知れない。
山階鳥類研究所の標本データベースを見ると 1893, 1905 年などの国内の標本ラベルには Buteo vulgaris が用いられていた。
1907 年の中国河北省の標本では Buteo buteo burmanicus。
1923 年の八丈島の標本では Buteo buteo japonicus。
1926 年の新潟の標本では Buteo japonicus japonicus とあるのでこの時は Buteo japonicus に先取権があって大陸のものもこの種の亜種とみなしたらしいことがわかる。
しかし 1929 年の国後島の標本では Buteo burmanicus となっており、japonicus が無効と判断された経緯が反映されていた模様。
1930 年の小笠原の標本では Buteo buteo burmanicus が用いられ、同年の朝鮮半島の標本も Buteo buteo となっていた。
ノスリの分類は昔から変遷を繰り返していたことがわかる。主な理由は japonicus を有効と認めるか、そして種境界の判断である。
過去の文献に Buteo burmanicus の記載があっても現代の burmanicus と同じものを指しているのか、japonicus が無効と判断されて先取権の原則からその学名が用いられていたのか注意する必要がある。
Dement'ev and Gladkov (1951) では東シベリアから日本に至る亜種は現在はヨーロッパノスリの亜種とされる vulpinus に近いとみなされていた。
toyoshimai も載っているが地図の場所は琉球になっており (解説文は正しい) 何かの誤解があった模様。refectus もチベット・ヒマラヤの亜種としてすでに載っていた。
自身が海外画像を見たところでは、モンゴルなどの繁殖期の個体と狭義の "Himalayan Buzzard" は非常によく似て見える。渡りを行うかどうかの形質は種境界の判定には必ずしも有効でなく (例えばハチクマの orientalis)、"Himalayan Buzzard" の分布は実は北方までずっと広がっているのではないだろうか。
分布の類似性についてはトビの亜種 lineatus も参照。
#ワキスジハヤブサと#シロハヤブサの関係については近年高精度のゲノム研究が行われており、性染色体に種を特徴づける遺伝的特徴が見つかっている (シロハヤブサ備考の [シロハヤブサとワキスジハヤブサの関係、"Altai falcon" とは何か])。
この場合は両者が鷹狩りに使われるため、また "Altai falcon" が独立したタクソンに相当するかの長年の疑問もあって詳しく研究されたもの。ノスリの方が遺伝的にはよく混ざってそうだがノスリも高精度のゲノム研究が行われると意外な結果も得られるかも知れない。高地に生息するノスリは遺伝的に少し違うかも知れない可能性を少し考えておきたい。burmanicus がどちらに入るか次第で日本産ノスリ類が1種増えるかも (?)。
日本のノスリの衛星追跡研究: Hijikata et al. (2022)
Satellite Tracking of Migration Routes of the Eastern Buzzard (Buteo japonicus) in Japan through Sakhalin。
サハリンまで渡り、国内の移動経路も記されている。
Eastern buzzard (Buteo japonicus) で経路が見られる。
AviList (2025.6) では Buteo refectus を種と認め、英名は主要3リストでいずれも Himalayan Buzzard で、この名称で確定と思われる。burmanicus は Buteo japonicus の亜種の扱いで IOC 14.2 や日本鳥類目録第8版と同じ。現時点で特に扱い変更の必要はない。
[関連亜種一覧]
ノスリ、ヨーロッパノスリ、"Himalayan Buzzard" について、以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種またはシノニム記載もわかる範囲で含めた。
・Falco Buteo Linnaeus, 1758 o1 (原記載) 基産地 Europe; restricted to Sweden by Hellmayr and Laubmann, 1916 (Hellmayr and Laubmann がスウェーデンに限定) ヨーロッパノスリ
・Falco desertorum Daudin, 1800 * (参考) 基産地 アフリカ = vulpinus (+ 他種?)
・Buteo vulgaris Daudin, 1802 * (参考) = Falco Buteo Linnaeus, 1758?
・Buteo mutans Vieillot, 1816 * (参考 1, 2) = Falco Buteo Linnaeus, 1758? 同定不詳
・Buteo fasciatus Vieillot, 1816 * (参考 1, 2) = Falco Buteo Linnaeus, 1758
・Buteo variegatus Billberg, 1828 * (参考) = Falco Buteo Linnaeus, 1758
・Buteo communis Millet, 1828 * (参考) = Falco Buteo Linnaeus, 1758
・Falco pojana Savi, 1831 o1 基産地 Tuscany, Italy (イタリア)
・Falco vulpinus Gloger, 1833 o1 (原記載) 基産地 Africa. Type from Cape Province (アフリカ。タイプ標本は南アフリカ)
・Buteo fuscus Rylands, 1837 * (参考) = Buteo vulgaris = Falco Buteo Linnaeus, 1758
・Buteo fuscus MacGillivray, 1840 * (参考) = Falco Buteo Linnaeus, 1758 に新名を与えたものと判定
・Faclo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 o2 (原記載) 基産地 Japan (日本) Faclo は誤記
・Buteo capensis Temminck & Schlegel, 1844 * 上記と同ページに現れる。Portenko (1929) では desertorum の改名で = vulpinus と判定
・Buteo rufiventer Jerdon, 1844 * (参考) 基産地 Neilgherries? (インド) Portenko (1929) では = vulpinus と判定
・Buteo minor Brehm, 1855 * (参考) Portenko (1929) は無効と判定
・Buteo anceps Brehm, 1855 * (参考) 基産地 北東アフリカ Portenko (1929) では = vulpinus に入れているが他種と判別は判定困難とのこと
・Buteo minor Heuglin, 1856 * (参考) 基産地 Nubien, Fazoglo?, Abyssinien (アフリカ東部) = Falco Buteo Linnaeus, 1758 と一度は判定された模様。
参考 によれば Buteo tachardus = 現在の Buteo oreophilus と判定。The Key to Scientific Names の情報をもとに判断するとその後分離され = 別種 Buteo trizonatus となると考えられる
・Buteo vulgaris var. etrusca Pelzeln, 1862 * (参考) Falco pojana の新名 = pojana
・Buteo vulgaris var. obscura Pelzeln, 1862 * (参考) 基産地 オーストリア = ?
・Buteo Delalandi (Delalandii) Des Murs, 1862 * (参考) 基産地 アフリカ Portenko (1929) では vulpinus と Buteo brachypterus Madagascar Buzzard の混合と判定
・Buteo auguralis Salvadori, 1865 * (参考) = Falco desertorum Daudin, 1800 = vulpinus (+ 他種?)
・Buteo burmanicus Hume, 1875 (原記載) 基産地 Thayetmyo, Pegu, Burma. Migrant (ビルマ。渡り鳥) = refectus (Dickinson & Svensson 2012)
・Buteo linnei Malm, 1877 * (参考) = Falco Buteo Linnaeus, 1758
・Buteo menetriesi Bogdanov, 1879 o1 (参考) 基産地 Caucasus (コーカサス) vulgaris に含まれたことがあった
・Buteo vulpinus ruficaudus s. typicus Menzbier, 1889 * 基産地 トルケスタン = vulpinus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Buteo vulpinus typicus Menzbier, 1889 * 基産地 ロシア = vulpinus 同上
・Buteo vulpinus intermedius Menzbier, 1889 * 基産地 ロシア = vulpinus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Buteo vulpinus fuscoater (fusco-ater) s. fuliginosus Menzbier, 1889 * 基産地 ロシア = vulpinus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Buteo zimmermannae Ehmcke, 1893 (原記載) 基産地 ドイツ? = vulpinus
・Buteo buteo insularum Floericke, 1903 o1 (参考 1, 2) 基産地 Grand Canaria (カナリア諸島)
・Buteo buteo Arrigonii Picchi, 1903 基産地 Sardinia (サルデーニャ島) = pojana
・Buteo buteo lanzaroteae Polatzek, 1908 * (参考) 基産地 Lanzarote, Canary Ids. (カナリア諸島) = insularum? (亜種認定される可能性あり)
・Buteo buteo harterti Swann, 1919 (原記載) 基産地 Madeira. Type from Santo Amaro (マデイラ島) = buteo
・Buteo buteo rothschildi Swann, 1919 o1 (原記載) 基産地 Terceira, Azores (アゾレス島)
・Buteo buteo bannermani Swann, 1919 別種 (原記載) 基産地 St. Vincent, Cape Verde Islands (ケープベルデ) ケープベルデノスリ かつてはヨーロッパノスリ (ノスリ) に含まれていた (未確定)
・Buteo japonicus toyoshimai Momiyama, 1927 o2 基産地 Okimura, Coffin Island, Bonin Islands (小笠原)
・Buteo japonicus saturatus Portenko, 1929 * (参考) 基産地 Ju-tschou (Kham), Central Asia = 無効名で refectus の新名に改称
・Buteo japonicus refectus Portenko, 1935 o3 (原記載) 基産地 Ju-tschou (Kham), Central Asia (saturatus の新名)
・Buteo buteo meridionalis Trischitta, 1939 * (参考) 基産地 Italia centrale-meridionale e Scicilia (イタリア中央部、シシリー島) = pojana?
・Buteo vulgaris hispaniae Jordans, 1939 基産地 Linares de Riofrio, Salamanca, and Mosqueruela, Teruel, Spain (スペイン) = buteo
・Buteo buteo oshiroi Kuroda, 1971 o2 (原記載) 基産地 Minami Minamidaito, Daito islands (南大東島)
・Buteo socotraensis Porter & Kirwan, 2010 別種 (原記載) 基産地 Socotra (ソコトラ島) ソコトラノスリ かつてはヨーロッパノスリ (ノスリ) に含まれていた
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。o1 = ヨーロッパノスリ、o2 = ノスリ、o3 = Himalayan Buzzard の亜種。別種 は IOC 14.2 で別種。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
Menzbier (1889) の記した3つは Dement'ev and Gladkov (1951) によれば色彩の型を表したものとのこと。
この学名一覧だけを見ると Buteo vulpinus が独立種扱いされて亜種があったように見えるが、この時点では単なる色彩表現で亜種とみなすのは適当でないだろう (当時は亜種概念もはっきりしていなかった)。intermedius は2つの型の間の色調の意味。
Portenko (1929) によれば Kleinschmidt が Buteo vulpinus を独立種としていた。
Buteo desertorum (Daudin, 1800) の名称はかなり使われていたようで、英国での記録や、Buteo desertorum Daud. のように登場する。
この記事ではドイツ語名で Steppenbussard, Wuestenbussard (ステップノスリ、荒れ地のノスリ Wueste は英語 waste に対応) と表現している。シノニムに Buteo tachardus = (現在の Buteo oreophilus か分離された Buteo trizonatus)、Buteo cirtensis = 現在の Buteo rufinus が含まれているように単一種の概念ではないと判断され古い学名だが無効となったものと想像できる。
それ以前は先取権がある名前と考えられていた模様。
当時も英語で steppe buzzard と呼ばれていたが現代の steppe buzzard ソウゲンノスリ よりは広い意味で使われていたよう。通常のヨーロッパノスリとは違うものが訪れていることは古くから気づかれていた模様。
Falco Buteo Linnaeus, 1758 を用いなければ、ヨーロッパのノスリは基本は Buteo vulgaris ("普通のノスリ" の意味で英語 common buzzard, フランス語 buse commune に対応) と Buteo desertorum ("荒れ地のノスリ": desertum 砂漠 の複数属格) の2種になっていた時代があったらしい。
当時の規則や慣習があったのだろうと想像するが (未確認)、何でも含んでいた Falco 属の中で Buteo 属を独立させるのが適切と考えられるようになって、代表種である Falco Buteo をグループととらえ Buteo vulgaris のように種小名から属に昇格とともに新しい属の中で新たに種小名を与えたものと想像できる。
他の属の例をみると新しい属の中に複数種がある場合は代表的な種に過去にも使われていた vulgaris を付けた、あるいは英語やフランス語の一般名に対応する形にしたのではないかと想像できる。
当時はトートニムとなることが積極的に避けられていたようで、学名の成り立ちからも納得できる。
名詞 + 形容詞 の形であればごく自然だが、名詞 + 名詞 はラテン語的にはあまり自然でない。特に2つの名詞が同一 (トートニム) では同じものを重ねる必要性がなく不自然である。そのため種小名から属に昇格の場合は同じ単語が並ぶことを避けて別名を与えたのだろう。
この用法はかなり長く使われていたようで 19 世紀の長期にわたって用例がある。属を提唱する、あるいは変わった時に新しい種小名を与えることは提唱者にとっても自身の名前を後世に残すのに役立ち、属が乱立したり複数の新名が生じる要因ともなっていた模様。
現在のようにトートニムを認め、属に昇格しても種小名を変えない規則は後から作られたものではないだろうか。その結果 Buteo buteo に戻されたのではないか。
[北京で記録されたヨーロッパノスリ?]
A possible Steppe Buzzard in Beijin (2021) によればヨーロッパノスリはまだ北京で記録されたことはないが、この個体はそのように思える (ノスリと並んだ画像で小さいなど)。
steppe buzzard (Buteo buteo vulpinus。上記 [ノスリの亜種] 参照) というヨーロッパノスリの亜種ではないかとのことで、専門家の判断を仰いだところ純粋な亜種ではないと思われるとのこと。ノスリ属はまだ歴史の浅いグループで種分化が不完全のため、雑種の可能性も考えられるとのこと。
この記事の解説ではヨーロッパノスリの個体差は非常に大きいが、ノスリではそうではない。そのためにノスリの中に変わったものが混じっていると見分けやすいとのこと。
先崎 (2015) Birder 29(10): 20-21 では赤茶のノスリが Buteo buteo vulpinus である可能性を検討している。
Kappers et al. (2018) Inheritance patterns of plumage coloration in common buzzards Buteo buteo do not support a one-locus two-allele model
の研究ではヨーロッパノスリの色彩は1遺伝子でメンデル遺伝をするものではなくポリジーン由来と考える証拠が見られた。従来は中間型の morph の適応度が高いため色彩多形が維持されているとの見方があったが、ポリジーンの場合にはおそらくそれでは説明できず環境との関係で色彩多形が保たれているのだろうとの考え。
Weiss and Yosef (2010)
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) Hunts a Eurasian Buzzard (Buteo buteo vulpinus) While in Migration over Eilat, Israel
イスラエルで渡り中の Steppe Buzzard がソウゲンワシに捕食された事例。
ヨーロッパノスリの渡り経路。個体により異なり比較的短距離を渡っているのがわかる。
Common Buzzard, Southern Sweden (スウェーデンの事例)、
Common buzzard (Buteo buteo) Lithuania CORPI (リトアニアの事例)。
[英名の語源]
遡ると古フランス語 busart, busard で、古フランス語 buison, buson (現代フランス語でノスリを表す buse) でラテン語の buteo 由来の可能性がある。これに接尾辞 -ard (ゲルマン祖語 *harduz 硬い に由来) を付けたもの (wiktionary)。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば古ドイツ語 Bus-aro に由来とのことでミャーと鳴くワシとの記述がある。ロシア語の kanyuk に類似の意味で興味深いとの文脈で出てくる。
aro は Aar (#トビ備考の ["トビ"類のドイツ語名]) と関係がある。aro = arn (高地古ドイツ語でワシ) で Aar はこれから派生したもの (wiktionary)。こちらは buzzard 語源の別説となる。
aro, 古ノルド語で orn は他言語にも現れるので理解する上の参考になるだろう。イヌワシのデンマーク語 kongeorn、スウェーデン語 kungsorn など。ロシア語の orel も似ているのだが語源は諸説あるらしい (Kolyada et al. 2016)。
[ノスリの漢字の意味]
中国語でも同じ漢字が使われているためおそらく出典があるのだろうと調べてみると
中国神話の奇妙な鳥を集めてみた。怪鳥特集3 (*、狂鳥、鳴鳥、黄、青、鳥、蕃鳥) (プロメテウス 2017)
狂鳥というのはもともとは鳳凰だったとのこと。中国語のページでも同じように書かれている (そこで使われる名称をもとに探すと日本語での解説があった次第)。
狂った鳥ではなくおめでたい神鳥と理解しておけばよいのだろう。
日本の記事で検索すると ノスリ 馬糞鷹の汚名返上 (高橋 コウノトリ文化館 2006) のような記述があり、やはり日本語のみで探すと話が違う方に行ってしまうかも知れない [大橋 (2024) Birder 38(2): 50-51 にこの解釈に基づく説明があり、出典はいずれも同じかも]。
"狂" の文字の由来を wiktionary で調べておくと 犬+表音文字 (王は簡略表記) とのこと。表音文字の部分は往 (行く) の古い形とのこと。いろいろな意味があって "狂暴" などの単語には確かにつながるが、"熱狂した" の狂にあるように "興奮した"、"野性的な" などの意味もある。
そう思ってみると rhapsody の狂想曲/狂詩曲 の意味はどんぴしゃに見える。狂想曲は中国語でも同じで朝鮮半島や日本語の表現は中国語由来となっている。狂想曲/狂詩曲 の別名は capriccio で別に凶暴や狂った曲ではなく自由な曲想を示したもの。
野性味があり、渡り個体も多いなど移動能力が大きく自由に動き回るノスリを表したものと考えてふさわしそう。文字を置き換えると、"鷹" が人とともにある文字とすれば、(猛禽類の中では) むしろ "野の鳥" の意味に近い。"ラプソディックなタカ" と言えばノスリにもケアシノスリに生態的にもよく合う感じがする。
鷹狩りに使おうとした人は世界的にもいなかったのだろうかとも思うが、ちょっと野性味が強くて使いにくかったのかも知れない。今ではモモアカノスリ (ハリスホーク) が広く使われているように、ノスリ類がまったく使えないわけではおそらくない。ハヤブサやオオタカなどに比べると手間をかけて訓練しても、獲物の好みなども関連して見返りが小さかっただろう。
派生した沢 狂+鳥 (チュウヒ) が湿地のノスリの意味になるが、これは日本語で作られた表現のようで中国古典には登場しない。
現代の中国語ではこのノスリの漢字は kuang と読むが、古代には犬の声らしい g の音が冒頭に残っていた。
朝鮮半島では中国語由来のこの文字は使われておらず、現在ノスリを指して使われるハングルの冒頭2文字 (malttong) は馬糞とのこと。ダンゴムシの名前にも使われる。独自に作られたのかそれとも日本の馬糞鷹と関係があるのか。地上にとまるワシを墓に関連されせる用例はステップ地域の大陸にもあるので大陸由来かも知れない。
ハングルの後半2文字は kari/kali の発音で漢語由来を示唆するが (同音異義語があるので難しいらしい) 済州島では独自に時間、機会の意味があるとのこと (以上 wiktionary よりとりまとめ)。
東南アジアではあまり特別視されていなかったのか中国語から伝来しなかった模様。もっとも我々もノスリとトビは違うなどと習うまでは似た色のタカの違いはあまり気づかないかも。
[タカも動脈硬化になる!?]
Shrubsole-Cockwill et al. (2008) Atherosclerosis and Ischemic Cardiomyopathy in a Captive, Adult Red-Tailed Hawk (Buteo jamaicensis)
によれば少なくとも 19 歳の飼育下のアカオノスリが剖検により動脈硬化で小規模な心筋梗塞 (虚血性心疾患) を繰り返していたことがわかったとのこと。ノスリ属では初事例とのことであるが、オウム目ではよくある (10-15%) とのこと。
猛禽類ではハヤブサ、ハクトウワシ、イヌワシ、ソウゲンワシ、ボネリークマタカ、ヘビクイワシで報告事例があるとのこと。
論文では高コレステロールの餌や野外に比べて極端な運動不足を原因に挙げている。食事由来のコレステロールの役割についての認識はヒトでは近年はだいぶ変わっているが、ここでは古い方に認識に基づいたものになっているかも知れない。猛禽類の代謝 (糖新生が中心となる) を考えると肉食では動脈硬化が起きにくいように思えたので取り上げてみた。
[オビオノスリはヒメコンドルに擬態?]
アメリカ大陸のオビオノスリ Buteo albonotatus Zone-Tailed Hawk はより弱い鳥であるヒメコンドル Cathartes aura Turkey Vulture に擬態 (通常の擬態は自衛のためであるが、ここでは逆の aggressive mimicry 攻撃的な擬態) することで自身の捕食行動を有利にしているとの解釈がある。
Willis (1963) Is the Zone-Tailed Hawk a Mimic of the Turkey Vulture?。
Mueller (1971) Zone-tailed Hawk and Turkey
による反論があり、擬態よりも航空力学的要請の結果 (つまり収斂進化) では。
Zimmerman (1971)
Comments on Feedng Habits and Vulture-Mimicry in the Zone-tailed Hawk
ではオビオノスリの行動や他種の反応から擬態よりも航空力学的要請の方がそれらしいが擬態の可能性は排除できず興味深い事例として研究に値するとしている。
その後も多数の観察報告があり、Bildstein (2017) "Raptors" では aggressive mimicry の可能性のある種類として最もよく調べられているとのこと。
Willis (1963) は同様の可能性のある例として モモアカハイタカ Astur bicolor が モモアカトビ Harpagus diodon にを挙げているが Amadon (1961) は結論できないとした。
タカがハゲワシ類に擬態している可能性として クロノスリ Buteogallus anthracinus がクロコンドル Coragyps atratus も挙げているがあまり似ていない点もあると述べている。
Willis (1963) の時点はオビオノスリが唯一の事例の可能性があるとのこと。
モモアカハイタカとモモアカトビの関係については Prum (2014) (#ハチクマの備考 [擬態と種・亜種の関係]) は逆の可能性を考えている。
オビオノスリとヒメコンドルの関係については Aggressive mimicry にも紹介されているが鳥類では他にあまり例がない模様。Bildstein (2017) "Raptors" にはハイイロオオタカの白色型が白色のオウム類に擬態している (#ツミの備考参照) 事例を含めて猛禽類で指摘されているのはこの2例だけと解説している。
クロカッコウハヤブサがより弱い鳥であるカッコウに擬態することで捕食を容易にする説の可能性も紹介されている (#ハチクマの備考 [ハチクマ亜科の他種] 参照)。
Matilda et al. (2020) Camouflage in predators 鳥の話は少なめだがさまざまな動物群について提唱されている aggressive mimicry のレビュー。上記のタカ類の話は古く提唱されているものの根拠はあまりはっきりしないとのこと。
オオタカの幼鳥がヨーロッパノスリに擬態 (この場合 aggressive mimicry を想定) しているかどうかを調べた研究がある: Spicka et al. (2024) Function of juvenile plumage in the northern goshawk (Accipiter gentilis): aggressive mimicry hypothesis
カササギは2種を見分けていてこの仮説は当てはまらない結果となった。
[ヨーロッパノスリの morph の意義]
Pauli et al. (2015) De novo assembly of the dual transcriptomes of a polymorphic raptor species and its malarial parasite
ヨーロッパノスリの色彩多形では morph によって寄生虫の傾向が異なり、暗色型は Carnus haemapterus に寄生されるが、淡色型はより強力なマラリアに似た原虫 (Leucocytozoon buteonis) に寄生される傾向が知られている。
このチームはドイツ西部のヨーロッパノスリのひなからサンプルを得て、色彩多形を持つ猛禽類で初となるほぼ完全なトランスクリプトーム解析を行った (Buteo 属でも初とのこと)。Leucocytozoon のトランスクリプトームも副産物として得られた。1羽は落下して死んだ個体で複数の臓器や皮膚のデータを得た。
臓器に比べて羽毛に発現する遺伝子が圧倒的に多く、羽の成長中であること反映している可能性がある。
背面の暗色部位には免疫に関係する6遺伝子が検出されたが腹面の淡色部位では1つのみだった。提案されていたメラニン色彩と免疫との関係を裏付ける遺伝的証拠
[南アフリカのオオハイタカ Astur melanoleucus Black Sparrowhawk で提唱されている: cf. Lei et al. (2013) Differential Haemoparasite Intensity between Black Sparrowhawk (Accipiter melanoleucus) Morphs Suggests an Adaptive Function for Polymorphism] となるとのこと。
どの遺伝子が関与しているかを議論するにはまだ早いがいくつかの候補シグナル経路を提案している。
morph によって候補遺伝子の背面/腹面の遺伝子発現の違いがあることがわかった。
ひなから低侵襲でサンプルが得られることが判明したので今後に期待できる。
タカ類の morph の寄生虫に対する免疫との関係を調べるパイロット研究となりそう。
[ガラパゴスノスリや他の猛禽類の一妻多夫]
上田 (2024) Birder 38(3) 28-29 に晩成性で一妻多夫の例としてガラパゴスノスリが取り上げられいる。関連文献をいくつか紹介しておく。
Faaborg et al. (1995) Confirmation of cooperative polyandry in the Galapagos hawk (Buteo galapagoensis)
1羽のメスに複数 (2羽が多いが最大8羽まで) のオスがつがいになり、すべてのオスがメスと交尾し餌運びを行う cooperative polyandry の繁殖形式をとる。この文献で DNA フィンガープリント法で実際に複数のオスの子供が確認された。繁殖にかかわったオスは特に血縁関係にはなく、血縁選択を必要とする仮説は棄却される。
同一のオスが複数年にわたって同じグループにとどまり、"通りすがり" の個体が繁殖に参加しているわけではない。
Dawson and Mannan (1991) Dominance Hierarchies and Helper Contributions in Harris' Hawks
では共同繁殖をするモモアカノスリで社会的劣位 (ホルモンレベルが低い?) 個体によるヘルパー行動が記録されている。
Kimball et al. (2003) Occurrence and Evolution of Cooperative Breeding Among the Diurnal Raptors (Accipitridae and Falconidae) のレビュー論文では
cooperative polyandry に区分される他の猛禽類に モモアカノスリ Parabuteo unicinctus Harris's Hawk、ヒガシコシジロウタオオタカ Melierax poliopterus Pale Chanting Goshawk
が挙げられているがグループに無関係のオスなども含まれている可能性があるとのこと。
これらの一妻多夫の要因として、ガラパゴスノスリの場合は共同防衛の必要性 (後に別の説を紹介する)、モモアカノスリでは共同ハンティング (#トビの備考参照)、ヒガシコシジロウタオオタカでは一妻多夫のペアがシーズン2回めの繁殖をする傾向があり、共同防衛や共同ハンティングに役立つ可能性が挙げられているとのこと。
Kimball et al. (2003) によれば猛禽類 (タカ・ハヤブサ類) で複数の個体が繁殖にかかわる事例は実はもっと多いが、標識研究がなされることが少ない、テリトリーが広大で観察が難しいなど見逃されてきた可能性があると考えている。
複数の個体が繁殖にかかわっている可能性のある報告を含めると多くの分類群に見られることから、実はもっとありふれた現象なのではないか。報告された事例では余分な個体の多くはオス成鳥である (ただしグループ全個体の性別を判別できない場合もある)。
他に cooperative polyandry の可能性のある種類として挙げられているものにヒゲワシ Gypaetus barbatus Bearded Vulture、エジプトハゲワシ Neophron percnopterus Egyptian Vulture、セアカノスリ Geranoaetus polyosoma Variable Hawk から別種扱いにする場合の Geranoaetus poecilochrous
(いずれも現在の学名で記す) が挙げられている。
若鳥の参加するヘルパーの形式もあってコチョウゲンボウでは過剰個体を判定できたものはオスだったが、ハヤブサではメスだった。ミシシッピートビ Ictinia mississippiensis Mississippi Kite でもヘルパーが知られているが性別は不明。
若鳥がヘルパーとなるケースは主として渡りをする種類か、独立後の若鳥の分散範囲が大きいもの。それ以外の共同繁殖は留鳥種とのこと。
ごくまれだが複数のメスが同一の巣に産卵するケースが知られていて、ハイタカ、ハイイロチュウヒ、ヒメチョウゲンボウ。これらの種は一夫多妻になることがしばしばあるが、メスは通常は大きく離れた巣で繁殖する。一夫多妻の場合でもメスの間の競争が相互の巣の間隔を広げていると考えられる。
共同繁殖をする鳥類では一般的に巣立ち後の分散の遅い個体にとって有益である説明がなされるが、猛禽類ではモモアカノスリでしか知られておらず猛禽類一般には当てはまらないだろう。
他の要因として (1) 資源の年変動が大きい、(2) 適切なテリトリーの数が限られている、(3) 共同ハンティング、(4) つがい相手の不足、(5) ペアのみの場合の繁殖成功率が低い、(6) 集団の方が生存確率が高まる、(7) 温度調節
が挙げられ複数の要因が関係していてもよい (これら要因は猛禽類以外に対するものも含まれている)。
若鳥の分散の遅れは有力とみられるがあまりすっきりした結論は得られず、他の鳥類の共同繁殖の利点と違いがあるのかよくわからないらしい。
Hagler et al. (2022)
Nest Provisioning and Sociality at Harris's Hawk Nests in South Texas
ではモモアカノスリの巣のビデオモニターによって、つがい外の個体が加わることで餌運びが増える結果は必ずしも得られなかった。
Bildstein (2017) "Raptors" (p. 110) ではガラパゴスノスリの場合は離島のため若鳥が遠くに分散して新しいテリトリーを得ることが難しいためこの行動が進化した可能性が挙げられている。
同様に若鳥の分散が妨げられているアルプスのイヌワシ (#イヌワシの備考 [同種間争い] を参照) と挙動が異なるのは食物の違いやイヌワシの場合は食糧事情の厳しい冬を越す必要があるため、あるいは同種への攻撃性の違いなど系統差があるのかも知れない。
ガラパゴスノスリはアレチノスリ Buteo swainsoni Swainson's Hawk に非常に近縁で最近 (30 万年ぐらい前) ガラパゴスに定着した個体群から進化したと考えられる (#ノスリの備考参照)。
ノスリ類ではこのような婚姻形態が比較的短期間で生まれるのだろう。
ジェネラリスト性の強いノスリ類でモモアカノスリのような種類は共同生活に向いている可能性があるかも知れない (さらに考えを巡らすとフォークランドカラカラも離島で同様な制約から共同生活を営み、結果的に高い知能を生み出したのかも知れない。このぐらいのことならば誰かが考えているだろうが)。
Bildstein (2017) ではモモアカノスリでは共同繁殖と共同ハンティングを同一集団で行い、因果関係がある記述となっている。
Spottiswoode et al. (2004) Co-operative breeding in the Pygmy Falcon Polihierax semitorquatus
でコビトハヤブサ Polihierax semitorquatus Pygmy Falcon での事例報告があり、cooperative polyandry も認められ、若鳥の分散の遅れがあるとのこと。
Bolopo et al. (2019) Helpers improve fledgling body condition in bigger broods of cooperatively breeding African pygmy falcon ではこの種でヘルパーの存在が子供の質を高めるとのこと。さまざまな組み合わせが存在しており、共同繁殖の進化にかかわる選択圧はこれまで考えられていた以上に多彩である可能性がある。
ハヤブサ類は自身で巣を造らずこの種はもっぱら社会性ハタオリドリの巣に依存するため、良好な営巣環境に限りがある点も要因になっているかも知れない。
この種ではつがい相手とテリトリーをめぐる同種内の致死的な争いも報告されている:
Lowney et al. (2017)
Mortal Combat: Intraspecific Killing by an African Pygmy-Falcon (Polihierax semitorquatus) to Acquire New Mate and Territory。
この報告では同種内の致死的争いはまれであると書かれているがイヌワシでいくつか記録がある (#イヌワシの備考 [同種間争い] 参照)。
Zuberogoitia et al. (2003) Two Cases of Cooperative Breeding in Eurasian Hobbies
がチゴハヤブサの共同繁殖事例を報告。一妻多夫かヘルパーかは判別できなかった。
共同繁殖と言える可能性のある事例はもっと強力な猛禽類でも報告されていて Gonzalez et al. (2006)
Cooperative breeding in the Spanish Imperial Eagle Aquila adalberti: a case of polyandry with male reversed sexual behaviour?
スペインカタシロワシでつがいのメスが姿を消した後に2羽の亜成鳥がテリトリーに加わりメスに代わる役割を果たした可能性がある事例報告がある。
#ハチクマ備考の [ヨーロッパハチクマと他のタカの種間関係] に登場する van Manen (2020) の事例を見ると寿命が長く繁殖開始年齢が高く、亜成鳥が多数いる環境になっているかも知れない (島のガラパゴスノスリはいかにも生活史が長そう)。同じくハチクマ備考の [マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] では血縁ヘルパーが見られていて、本格的な繁殖開始までは時間がかかるが子育て能力はかなり早期から見られるよう。
同じ項目にハチの巣を主食とするアカノドカラカラの社会的行動にも触れている。
鳥類全般についての入門レビュー: Kempenaers (2022) Mating systems in birds。
ガラパゴスノスリは polyandry with biparental care (一妻多夫で両親が子育てに参加する) 代表種として示されている。鳥類全体では一夫一妻が基本形でそれからの派生型の扱い。反対側に進化した polygyny with biparental care (一夫多妻で両親が子育てに参加する) の例としてアオガラ。レックやハーレムはこの発展型の位置づけ。
ガラパゴスノスリのように別のオスとメスを共有する形態が進化する理由の説明は難しく、子育てに複数のオスが必要である、あるいはオス1羽よりも複数の方が重要な資源の確保に役立つなどの説明があるが満足できるものではない。
Marcondes and Douvas (2024) Social mating systems in birds: resource-defense polygamy - but not lekking - is a macroevolutionarily unstable trait
こちらは進化的安定性について。レック形成は進化的に安定でほとんど失われることがないが、resource-defense polygamy (テリトリーを確保して一夫多妻または一妻多夫) は安定でなく一夫一妻に戻ることもしばしばある。予想に反してレック形成は一夫多妻または一妻多夫から進化したより一夫一妻から進化したと考えられるとのこと。
Polygamy is (not) for the birds 一般向け解説 (Alexandra Becker, Rice University 2025.1.13)。
[タカ類の聴覚]
McGee et al. (2019) Auditory performance in bald eagles and red-tailed hawks: a comparative study of hearing in diurnal raptors
がハクトウワシとアカオノスリの聴覚を調べている。いずれも 2 kHz 付近の感度が高く、ハクトウワシでは周波数上限が 5.7 kHz、アカオノスリでは 8 kHz となった。
風力発電において猛禽類にどのような警告音を与えればよいかを調べるための研究の模様で、Goller et al. (2024) Selecting auditory alerting stimuli for eagles on the basis of auditory evoked potentials
に後続研究があり、ハクトウワシとイヌワシが調べられている。音の高さの変化する刺激に対してはハクトウワシの方がイヌワシより敏感であるとのこと (サイレンのような音で危険を知らせることを想定している模様)。
Ordiway et al. (2024) Revisiting the Chicken Auditory Brainstem Response: Frequency Specificity, Threshold Sensitivity, and Cross Species Comparison
音に対する脳幹反応はニワトリは比較的単純な波形を示し、哺乳類では 5-7 個のピークが観察されるのに対して鳥類の方がピークが少なく、5個のピークが記録されているものはハクトウワシとアカオノスリとのこと。鳥類の方が音源定位に左右の耳の時間差により頼っていることも反映しているかも知れないとのこと。種間比較はまだ始まったばかりの感じ。
聴覚全般の話題 (タカ類も含まれる) は #ヨタカの備考 [反響定位を行うアブラヨタカ] を参照。
[アカオノスリの消音飛行]
フクロウ類ほどではないがアカオノスリの羽毛に消音機能があることが明らかになった。#ウスハイイロチュウヒ備考 [音を出さない羽毛構造] Liu and Clark (2024) を参照。
齧歯類を狙うための適応のように思えるが、上記 [タカ類の聴覚] でアカオノスリの聴覚周波数上限が高めなのは齧歯類の音を聞くなどにも役立てているのかも知れない。獲物に羽音を気づかれないため、また自身の羽音が音で獲物を探す邪魔にならないように、などの解釈が考えられる。
タカ類での羽毛消音機能は他にチュウヒ類やカタグロトビ類で知られている。ノスリ類では初めての事例。
[タカに襲われた事例]
Ehrensperger et al. (2018) Tularemia in a jogger woman after the attack by a common buzzard (Buteo buteo): A "One Health" case report
2017年3月7日、スイスでジョギング中にヨーロッパノスリに襲われて引っかき傷を負い、ツラレミア症 (野兎病) を発症した事例。通常は齧歯類に多いが他の哺乳類も感染する。病原体が単に付いていたと考えられるが、ヨーロッパノスリが感染していた可能性も否定できない。その後同じ場所で他のジョガー3人も攻撃を受けて1人がツラレミアに感染したという。営巣場所で若鳥を守るための行動で5月から6月に多いとのこと。
こちらは種類不明だが、フロリダで後頭部をタカに急襲されて意識を失い、目に障害が残った事例: Tenewitz et al. (2021) Traumatic central retinal vein occlusion following a hawk attack to the posterior cranium。
タカではなくモリフクロウ Strix aluco Tawny Owl の声を真似して襲われた事例がある: Leifert et al. (2004) Imitation of Typical Birdcall Causes Ocular Perforation by a Tawny Owl Attack
この人は夏場に声を真似ていた時は鳴き返してきていただけだったが、冬に行ったところ突然襲われ過去にこれほど攻撃的だったことはなかったとのこと。眼球穿孔まで生じたとのこと。つがい形成期で突然のライバルとみなされたのだろうか。
鳥に目を襲われたというと猛禽類やカラス類を想像しがちだが、イランでの調査によれば (家禽のニワトリを別にして) 一般に言われるフクロウ類ではなく mynah ハッカチョウ類が大半だったとのこと。
鳥による損傷は眼球穿孔が多かったとのこと: Bahar et al. (2025) Animal and bird-related ocular trauma: a decade of experience from a tertiary referral eye hospital of Iran。
[呼吸以外の気のうの機能]
Schachner et al. (2024) The respiratory system influences flight mechanics in soaring birds
飛翔筋の間にある subpectoral diverticulum と呼ばれる気のうは調べられた中でソアリングを行う鳥のほとんどに存在し、行わない鳥には見られなかった。関連があることは疑いない。
この構造はソアリングを行う鳥で少なくとも7回独立に進化したとのこと。
ノスリ属の鳥を用いモデル計算で機能を調べた。この気のうは呼吸に関与していないが膨らませるとソアリング中の筋肉がてこの原理で力を発揮できるとのこと。呼吸をしながら自発的にこの気のうを膨らませたり縮めたりできるとのこと。
またソアリングを行う鳥では胸筋の解剖学的にも特徴があるとのこと。英文解説。
(pdf from svpow.com)。
これまでは羽ばたき運動が呼吸を助けることが知られていたが、呼吸器にまったく別の機能も存在することがわかった。アカオノスリの飛び立ち画像が Nature 2024.6.20 号の表紙となっている。
この論文に系統解析も出ているが、古い系統の種類ではクロエリサケビドリ Chauna chavaria Northern Screamer がソアリングを行い、この気のうも存在しているとのこと。他の古い系統ではツル類の一部、海鳥、ペリカン類 (ウ類も含む)、カモメで発達しているがアビ類はない。
ショウジョウトキ Eudocimus ruber Scarlet Ibis はソアリングを行うがこの気のうは持たない例外とのこと。
昼行性猛禽類はいずれも持っているが、フクロウ類にはない。夜間は上昇気流が起きにくいと考えれば納得できるが、夜間渡りをするフクロウ類は長距離を羽ばたくのだろうか。コミミズク (ソアリングと言ってよいと思う) は調べられていないがフクロウ類にも例外があるかも知れない。この種の同様の解剖 (CT) も興味深いだろう。
フクロウ類に留鳥種が多いのもソアリングによる低コストの移動が難しいことも理由の一つになるだろうか。
Telluraves で昼行性猛禽類以外にソアリング能力を持つものがほとんどないのも興味深い。ブッポウソウ系統にはかなり大型の鳥も含まれているが羽ばたきのみか (フクロウ類に近い系統的制約かも知れない)。ハヤブサ類は持っているのに近縁のオウム類が持たないのも興味深い (とはいえハヤブサ類のうち調べられているのは Falco 属のみで、飛翔性の高いハヤブサ類がオウム類と分岐してから独自に能力を持った可能性もありそう)。
論文では例外としてワタリガラス (ソアリングを行う) が挙げられている。カラス類のソアリング (日本で普通に見られるカラスはソアリングというより滑空か?) は解剖学的には少し無理をしている?
これだけ明確な対応関係があり (見ただけでわかる対応関係はそう出るものではない)、しかもこれまで誰も着目しなかった構造は確かに Nature 論文にふさわしい発見に思える。古生物学にもインパクトがあるだろう。
Meyers and McFarland (2016) Anatomy and histochemistry of spread-wing posture inbirds. 4. Eagles soar with fast, not slow muscle fibres
によれば、長時間のソアリングを行う鳥 (アホウドリ類やハゲワシ類など) では胸筋に長時間の姿勢を保つのに役立つ slow muscle fiber (遅筋) が含まれていることが知られていたが、ハクトウワシ、イヌワシの飛翔筋にはほとんどなかったとのこと。fast fibers (速筋) で姿勢を保っているはずだが理由はこの時点では明らかでなかった。
猛禽類に一般的なのかどうか解剖学的にもまだあまり調べられていない。
Walker and Meyers (2019) The anatomy and histochemistry of flight hindlimb posture in birds. II. The flexed hindlimb posture of perching birds
も関連して興味深い話で、(ふだんあまり疑問を持たれないが) スズメ目の鳥は脚を曲げて飛ぶのに、猛禽類やシギ・チドリはなぜ伸ばして飛ぶのか。伸ばして飛ぶ方が筋力が必要。筋肉中の slow muscle fiber の量は飛行形式と合っているがなぜ伸ばすかの説明は特にない。
放熱のためや空気抵抗を減らすなどの目的が別にあるかと思ってみると、Sachs (2007) Tail effects on yaw stability in birds によれば脚を伸ばした方が飛行の安定化効果があるとのこと。
[猛禽類の爪が曲がっている理由]
Zhang et al. (2024) Curving expectations: The minimal impact of structural curvature in biological puncture mechanics
目的は同じでも他の動物の捕食用具に比べて猛禽類の爪の曲がりは非常に大きい (100° を超える)。
この研究ではまっすぐな爪を刺した場合と曲がった爪の場合で組織に与える損傷に違いがあるかを有限要素法で評価したもの。結果的にはほとんど差がなかった。かつて言われていた曲がっているほど強力との結論は支持されなかった。
論文タイトルは爪の曲がり (curve) と予想が外れるの意味をかけている。
[痛みを感じている鳥の兆候]
骨折などでアカオノスリで通常行う頭の動きが減少する Mazor-Thomas et al. (2014) Pain-Suppressed Behaviors in the Red-tailed Hawk (Buteo jamaicensis)
頭の動き以外にも嘴で音を立てる (beak clacks)、足の交代、rouse (鷹匠用語で羽を膨らませて身震いをする行動で他の鳥にも用いられる) いずれも怪我をした鳥で減少する。オピオイドの buprenorphine (日本の商品名レペタン、ノルスパンテープ) の鎮静作用で多くの行動が減少するが頭の動きは鎮静作用との関係が薄く、痛みを感じているか一番よい指標になると考えられるとのこと。
[ヨーロッパノスリの繁殖時期の年変動]
この論文そのものは統計的手法に関するものだが、ヨーロッパノスリの繁殖時期の年変動が触れられているので紹介: Baumeister et al. (2025) Early and Late Buzzards: Comparing Different Approaches for Quantile-Based Multiple Testing in Heavy-Tailed Wildlife Research Data
気温が高く齧歯類の多い年には繁殖活動が早くから始まる傾向があると一般的に考えられている。2019 年以降の最初の一腹ひなの孵化日の変化傾向を見ていて、2019 年は "早い年"、2022 年は "遅い年" の代表となったがこの印象は正しいのか、もしそうであれば何を指標に "遅い" (例えば中央値) と判断すればよいのか、要因は何かを検討する途中で気づかれた統計的扱いの問題を議論したもの。
例えば人為的影響や温暖化との相関を見る場合に注意すべきとのこと。このような論文が出てくるのは、逆に言えば温暖化との有意な相関を見つけられなかったのではないか。
"早い年" や "遅い年" は渡り鳥の初認などでもしばしば話題となるが、これだけのサンプルがあってこのような議論が行われていることも参考にするとよいのだろう。ヨーロッパノスリの繁殖時期でも均質な 20 年近いデータの蓄積がある。
-
オオノスリ
- 学名:Buteo hemilasius (ブーテオー ヘーミラシウス) 半分毛深いノスリ
- 属名:buteo (m) タカの一種
- 種小名:hemilasius (合) 半分毛深い (hemi- (接頭辞) 半分 lasios 毛深い Gk)
- 英名:Upland Buzzard
- 備考:
buteo の読みは #ノスリ参照。
hemilasius の読みはわからないが、ギリシャ語 lasius には長母音は含まれない。
hemi- はギリシャ語 hemi- に従えば e は長母音。hemisphaerium の事例を見つけたので同様に長母音とした。
規則通りでは -la- にアクセントがあるものと想像される (ヘーミラシウス)。
興味深いことに Buteo hemilasius Temminck & Schlegel, 1844 が原記載となって、基産地日本となっている。図版。
日本では珍しい種類で大陸で先に記載されている方が自然な感じがする。
同じ Buteo 属で現在ノスリに japonicus を与えているのでこちらでは重複して使えなかった。オオノスリの方が記述的特徴が目立つのでこちらに記述的種小名を与えたものと想像できるが、もし逆になっていれば後の世代は学名と生息域の相違に悩んでいただろう。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば英名は Siberian Buzzard となっていた。日本からの2例めの標本がなく Temminck and Schlegel は迷鳥を記録したものだろうと述べている。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" オオノスリの名称はすでにあって4学名が載っており、主見出しでは Buteo leucocephalus Hodgson, 1845 (白い頭のノスリ) を用いていた。
もう一つが Buteo aquilinus Blyth, 1845 (ワシのようなノスリ) でこれらは Temminck and Schlegel (1844) より後のためにシノニムと認定された模様。
[Dickinson and Walters (2006) Systematic notes on Asian birds. 54. Comments on the names proposed by Hodgson (1845) and their priority]。
この場合は発表年だけの違いで問題はなかったらしい。
Portenko (1929) Ueber den taxonomischen Wert der Formen der palaearktischen Bussarde. Zweiter Teil (p. 48) も最も早い名称が Temminck and Schlegel (1844) によるものであることを示している。
さらに一つある Buteo ferox はもともと Accipiter ferox Gmelin, 1771 で ferox は恐ろしい、勇敢ななどの意味 (英語 ferocious など同系)。Latham (1781) は "Fierce Eagle" として用いたとのこと。現在の分類でニシオオノスリ (またはステップオオノスリ) Buteo rufinus Long-legged Buzzard と同定され、オオノスリとニシオオノスリの分離が不明確な時代であったためにこの学名が使われていたようだが、同定誤りと判定された。
Buteo ferox の種名を用いて複数の亜種が記載されていた。
実際には Buteo ferox はチュウヒワシ Circaetus gallicus Short-toed Snake-Eagle を指していると判定されたが ICZN 1957, Direction 83 の裁定により (有効であれば先取権があるが) 使用されない学名となった (The Key to Scientific Names)。
同種扱いは Hartert (1933) の提案があって地域型とみなしたが、Dement'ev and Gladkov (1951) はニシオオノスリは平地で、オオノスリは山岳型であることから異なるとの考えを示していた。
Portenko (1929) は両者の分布の接点で雑種個体があると報告しているが、分布が大きく違うので Dement'ev and Gladkov は別種と考えるとのこと。
ニシオオノスリも基産地はアフリカ北部 Falco rufinus Cretzschmar, 1829 (原記載) と遠く離れていた。もしオオノスリと同種であればこちらの記載年が早いためにオオノスリは亜種扱いとなって学名も現在と違ったものになっていたところ。
高野 (1973) ではオオノスリはニシオオノスリを指し、現在のオオノスリにはヤマオオノスリが与えられていたのも、Ogawa (1908) にオオノスリの名称がすでにあったことから、一時はオオノスリがニシオオノスリの亜種となって広い意味で種名オオノスリが採用されていたが、2種に分離するに当たって新しい名称を用いる必要が生じたためと想像できる。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 104 (内田) で対馬の迷行例が紹介されていて、この当時の学名は Buteo rufinus とされていた。高野 (1973) の記述とも整合して公式には同種と扱われていたらしい。なぜか Temminck and Schlegel については触れられていなかった。
現代の分子系統解析では種扱いで構わない結果になっているが、ノスリ類の分岐年代が若いこともこのような学名や和名の扱いの複雑さにも現れている印象を受ける。
英名の Upland Buzzard に対応する学名は見当たらないようで起源はよくわからない。Temminck and Schlegel (1844) で用いられたフランス語名では La Buse Demi-pattue (脚に半分羽の生えたノスリ) で学名と同じ。
フランス語別名で Buse des montagnes があって英語と直接関連しないので山岳地のノスリであることは知られていたよう、ドイツ語で Mongolenbussard, Hochlandbussard の名称があり、生息地のモンゴルから高地が連想された可能性もあるが後者は英名からの訳 (あるいは逆) かも知れない。
#マキノセンニュウ備考でマキバシギの英名・他言語名からオオノスリの英名由来を考察してみた。北米にプレーリーがあるからとの推定。
OED には Upland Buzzard の項目はないが、upland の語義を見ると必ずしも高地の意味ではなく海から離れた内陸部が最初の語義だった模様。高地に住む意味は現代では鳥でよく使われるとあるが、マキバシギの他言語名からおそらくプレーリーを指していたと想像できる。
結果的に記載年のわずかな違い、かつ系統分類上で別種とされたために日本が基産地となった (日本にとっては) 幸運な種だったのだろう。現在のフランス語名は Buse de Chine (中国のノスリ) と生息地を主に反映した名前になっているが半分合っているようないないような。
ニシオオノスリの英名 Long-legged Buzzard は Buteo longipes Jerdon, 1839 に由来 (The Key to Scientific Names, Limnosalus の項目。参考 Jaulnah はインドの Jalna ジャールナー のことか)。当時広く使われた学名由来ではあるが実体の表現としてはあまりすっきりしない。
単形種。
2021 年に広範囲で侵入的渡り (irruption) があったことは記憶に新しい。日本に限らず、東アジアで広く irruption が起きたようで、上海で 78 年ぶりの記録、台湾など日本よりさらに南の地域でも記録された。
この年の irruption はおそらく正月ごろの大陸の大寒波のためと思われる。モンゴルを中心としたステップ地域に生息する鳥だが、同地域の猛禽類が軒並み数を減らしている中で増加している数少ない種類。
分布地域も広がっており、バイカル湖周辺のステップでも普通に繁殖するようになっている (解説動画) (ノスリと少し違ったホバリングが見られる)。昔はまれだったがバイカル湖西側の森林ステップの特徴的な鳥になっている。
厳冬の減少でここでも越冬するようになった。一番好きな場所は柱の上。ネズミや鳥を食べる。「ケアシ」の足でよく歩く。大きいにもかかわらずハタリスはほとんど食べない。感電事故で多数が犠牲になっているとのこと。
モンゴルより北方のロシアのイルクーツク州では 2010 年ぐらいから繁殖するようになって、都市にオオノスリが住み着いているのは見慣れた光景になっている (記事)。
イルクーツク州では 1990 年代半ばになって出現するようになった。かつてはレッドデータブックに含まれていたことがあったが今は入っていない。イルクーツク州では雪が多くてハタネズミが簡単に地表に現れない。
都市にはハトを餌にするためにやってきている。ネズミ類も多いかもしれない。イヌやネコにとっては危険ではない。
都市ではハンターや感電の危険がある。イルクーツク州で営巣するようになってからここでも越冬するようになった。都市生活に慣れたのはこの 8-10 年のことである (記事は 2018 年)。
ロシアのトゥバで人工巣塔に営巣したオオノスリのビデオ。
Bliznetsov and Baranov (2016 初出, 2023 再掲) Breeding of the upland buzzard Buteo hemilasius in arid conditions of Central Asia (pp. 2649-2651)
でトゥバ南部山岳地帯のオオノスリの繁殖地の研究。ワキスジハヤブサと同所的に繁殖し競争相手になっている。
Dugintsov and Ivanov (2024) Expansion of the range and breeding habitats of the upland buzzard Buteo hemilasius in the anthropogenic landscapes of the southwest of the Zeya-Bureya Plain (pp. 1231-1242)
アムール川流域の中国国境部に近い Zeya-Bureya Plain の人為環境へのオオノスリの分布拡大。
モンゴルを代表する鳥だったが、急激に極東に近づいてきている感じ。
同じく Dugintsov and Ivanov (2023) Long-term dynamics of the number of birds of prey in agricultural landscapes of the Zeya-Bureya Plain (pp. 4277-4283)
に同地域の農地の昼行性猛禽類の数の変化。1986-1990 年と 2023 年を比較してオオノスリの増加が目立つが、他にトビが目立って増え、ハイイロチュウヒ、オオタカも増えている。
減っているのはチュウヒ、ハイタカ (かなり減っている)、チョウゲンボウ (絶対数は多いが大きく減少)。マダラチュウヒ、チゴハヤブサ (数はそう多くない) は安定している。アカアシチョウゲンボウは数も多く代表種となっている。現在の個体数ではトビ、アカアシチョウゲンボウが多く、マダラチュウヒ、オオノスリがそれに次ぐ形になっている。
2020年12月にイルクーツクで越冬中のオオノスリの映像。
バイカル湖東側ウラン-ウデの報道では、南方で越冬することの方が多いが、暖かい冬には若鳥がそのまま越冬する。2020-2021 年初頭の寒波で動けなくなって救助された個体も複数あった
(報道映像) 。
個体数や生息域の拡大も irruption が起きたり記録数が増える原因になっている可能性があり、今後も以前ほど珍しい鳥ではなくなるかも知れない (が、地球温暖化の進行であまり南に渡ってこなくなる可能性もあるかもしれない)。
寒さには強く、中国内モンゴルで -40 ℃ になる中でも獲物を探している映像 (2021年1月) が記録されている。
[ニシオオノスリの分布拡大]
オオノスリに合わせるかのようにヨーロッパではニシオオノスリ Buteo rufinus Long-legged Buzzard が分布を広げている。
Kassinis and Charalambidou (2022)
The Long-legged Buzzard Buteo rufinus in Cyprus: three decades of presence and range expansion
違法狩猟で悪名高いキプロスだったが状況が改善しているよう。耕作放棄地が増えて森林化が進むなど、ニシオオノスリに適した環境が増えるなどの効果もあって 1990 年代に初繁殖以来急激に数を増やして 2021 年には 115 つがい。過去 17 年で3倍に増えた。
かつては崖に営巣していたが今では樹木に営巣するものが増えた。
かつてはワタリガラスが重要なライバルだったが数を減らして絶滅に近い。シロエリハゲワシもほとんど絶滅に近い状況でニシオオノスリに古巣を提供することになっているとのこと。ヨーロッパ北西に分布を広げているのは温暖化の影響も考えられる。
キプロスでは他の猛禽類への影響は今のところ明らかでないとのこと。
Kassinis et al. (2022)
Feeding Ecology of the Long-Legged Buzzard and Diet Overlap with Sympatric Bonelli's Eagle On Cyprus
ニシオオノスリの増加に伴い、ボネリークマタカ Aquila fasciata Bonelli's Eagle との競合がやや心配だったが食物はあまり重複していない。
ボネリークマタカはイヌワシ属だが生態的にはそれほど高い地位になく、少し心配されている種類。#イヌワシの備考 [ボネリークマタカの分布] も参照。
[分子系統解析]
NC_029377.1 (オオノスリのミトコンドリアゲノム) から出発して BLAST を行ってみると、広義に捉えれば Buteo buteo に収めることが可能 (一致率 98% 程度と結構高い)。
(この系統樹に現れる範囲であれば) オオノスリを独立種として互いに単系統の関係とするためには Buteo burmanicus を分離する必要が生じる。
研究されていない亜種も含めた種境界と先取権のややこしい問題がある (#ノスリの備考 ["Himalayan Buzzard"])。この配列は Nagai et al. (2020) より後に発表されたもので新たに見ておいてよいだろう。オオノスリを認めるならば旧ノスリを少なくとも東西で分けた方がよいらしいことはわかる。
-
ケアシノスリ
- 学名:Buteo lagopus (ブーテオー ラゴープース) ノウサギの足をしたノスリ
- 属名:buteo (m) タカの一種
- 種小名:lagopus (合) ノウサギの足 (lagos ノウサギ pous 足 Gk)
- 英名:Rough-legged Buzzard
- 備考:
buteo の読みは #ノスリ参照。
lagopus は o, u ともに長母音で o にアクセントがある (ラゴープース)。ギリシャ語 lagos も o が長音。-pus は#ナンキンオシ参照。
lagopus は古くからあるラテン語 (ライチョウ類の属名にもなっている) で "足" の意味が明瞭なため -pus を伸ばす読み方が定着していたのかも。
lagopus は他にも現れてもよさそうな単語だが、現在使われる用例はケアシノスリとライチョウ類のみ。
よく話題になる亜種名も考察しておくと、menzbieri はラテン読みでは "メンズビエリ" (意識的に伸ばせば "メンズビエーリ" の可能性はある) と考えられる。原語の音からはそれほど離れないが原語では冒頭がアクセントとのこと。Menzbir はロシア語綴りだがラテン文字表記では Menzbier と綴っていたよう (wikipedia 英語版より)。
この綴りに基づく学名と考えられる。テンザンマーモット Marmota menzbieri Menzbier's marmot の学名にも残っている。
e はラテン文字表記のために追加されたもので、原語の音を考えると "ビ" にアクセントを置く方 (メンズビエリ) が素直に思える。
kamtschatkensis は -ensis の長母音のみ注意して "カムチャトゥケーンシス" でよいと思われる。
sanctijohannis は綴り上は -han- にアクセント位置となる。sanctus は冒頭が長母音。John に対応するラテン語の Ioannes は -an- がアクセント音節で短母音。これらを総合すると "サーンクトヨハンニス" が古典式発音と考えられる。長くなるのでアクセント位置のみ採用して冒頭は伸ばさなくてもよいだろう。
Brehm (1831) が Archibuteo 属を導入したことがあった。archon は支配者や首領 (Gk) の意味から (この意味の arch は monarch 君主 クロエリヒタキ の英名に登場する Monarch サンコウチョウの含まれるカササギヒタキ科 Monarchidae, 英語の -archy で終わる単語など広く登場する。デザインや建築の architect, architecture も同語源)。
Brehm 自身は属の構成種に Archibuteo planiceps Brehm と Archibuteo alticeps Brehm を挙げていたがいずれもケアシノスリのシノニムと判定され、無効な属名とされたとのこと (The Key to Scientific Names の Archibuteo の項目から)。
ノスリ類の首領と考えられた時期の属名、また語源を同じくする単語の理解の補助のためにも記憶にとどめておいてよい名前だろう。
Oberholser (1919) The Status of the Genus Archibuleo, Brehm。
Archibuteo を含む学名も文献にしばしば見かける。
亜種 sanctijohannis の記載にもこの属名が用いられていた。
世界に4亜種 (IOC)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に記載の亜種は menzbieri (ロシアの鳥類学者 Mikhail Aleksandrovich Menzbir が由来)。
亜種 kamtschatkensis (カムチャツカで繁殖の亜種カムチャツカケアシノスリ) は検討亜種となっている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
亜種クロケアシノスリ sanctijohannis
(sanctus 聖なる = saint, Iohannis は John から。この亜種名はカナダニューファンドランドの Saint John's = ニューファンドランド・ラブラドール州の州都が由来) も検討亜種となっている。
ケアシノスリは北極圏で広く繁殖するため、ユーラシアだけでなく北アメリカにも分布している。アメリカでは Buteo 属を buzzard でなく hawk と呼ぶため、Rough-legged Hawkと呼ばれる (世界共通の英名を決める必要性はよく理解されているが現実には難しい!)。
さらに簡略化した roughleg の名称も使われる。
ケアシノスリに最も近縁の種類は北米のアカケアシノスリ Buteo regalis (英名 Ferruginous Hawk)。
以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種記載もわかる範囲で含めた。
・Falco Lagopus Pontoppidan, 1763 o 基産地 no locality = Denmark (デンマークと判定)
・Falco S. Johannis Gmelin, 1788 o (原記載) 基産地 Hudson Strait and Newfoundland (ハドソン海峡とニューファンドランド。カナダ) クロケアシノスリ
・Archibuteo lagopus var. Sibirca Severtzow, 1875 * Dement'ev and Gladkov (1951) によれば無効学名 = menzbieri
・Archibuteo pallidus Menzbier, 1888 基産地 Russian Turkistan (トルキスタン地方のロシア。越冬地記載) = menzbieri (Dement'ev and Gladkov 1951) または kamschatkensis? (Avibase)
・Buteo lagopus kamschatkensis Dementiev, 1931 o (原記載) 基産地 Kikhchik River, Kamchatka (カムチャツカ) カムチャツカケアシノスリ
・Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951 o (シベリア北部ヤマル半島からアナディリまでなど。範囲は示されているが基産地は明瞭でない) 亜種ケアシノスリ
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
sanctijohannis は最初からこの表記ではなく略されていたことがわかる。Dement'ev and Gladkov (1951) では sancti-iohannis と表記されていた。
kamschatkensis は pallidus とは明らかに違うので新亜種として記載したもの。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではオホーツク海沿岸までこの亜種としていた。
pallidus の方が記載が早いので先行シノニムになるように見えるが、Buteo 属となった時に Buteo pallidus Lesson, 1830 の用例が先にあって無効となったものらしい。
Lesson (1830) の指していたものは チャバネサシバ Butastur liventer Rufous-winged Buzzard のシノニムとなってこちらも表面上現れなくなった。
シノニムとする場合は Dement'ev and Gladkov (1951) のように menzbieri か Avibase の表示のように kamschatkensis のシノニムとされる模様。越冬地記載で分布を考えると多分前者の可能性の方が高そう。
Hartert (1910-1922) p. 1130 の時代にはこのことはまだ知られていなかったのか pallidus としてカムチャツカまでこの亜種で日本 (Jesso) も同じとしていた。
Dement'ev and Gladkov (1951) では lagopus の記載者を Bruennich としており、Pontoppidan の書物はまだ発見されていなかったと考えられる。
後述のように色彩変異があるにもかかわらず北米ではアラスカからカナダ東部まで1亜種として扱っているので、北極圏から広域を渡る種でユーラシアに複数亜種を認めるのが妥当か微妙な感じもする。日本で主に問題になるのはカムチャツカと思われるので、カムチャツカがどの程度地理的に隔離されているかによるのだろう (まとめてしまうと亜種識別の楽しみが減ると言われそうだが)。
亜種が再編成されるならば Buteo lagopus menzbieri の記載が最も新しいため亜種学名が変わる候補となる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Aquila 属になっていた。文献は調べていないがふしょに羽毛があるため Aquila 属に分類されていたことがあるのだろうと想像する。
[暗色型ケアシノスリと亜種の問題]
Young Guns (2014) Birder 28(2): 48-50 にケアシノスリの性差と亜種の記事がある。この中で暗色型の記録があり、北米の亜種の可能性を検討している。写真調査の結果では北米亜種はむしろ白っぽいとのこと。亜種ケアシノスリには黒い個体はいないのか?
Glushchenko et al. (1990) About melanistic specimens of the rough-legged buzzard Buteo lagopus in Southern Primorye
(2020 に再掲 pp. 3007-3009) がロシア沿海地方の黒っぽいケアシノスリの標本の検討を行っている。
この論文ではイヌワシ亜成鳥を思わせる色合いで、止まっていると遠くから見るとほとんど黒く見えるとのこと。
野外での遭遇記録などもまとめられており、標本の検討もなされている。暗色型は全体の 2% 程度とのこと。これらの個体がどこから来たのは明らかでない。亜種 sanctijohannis に暗色型がある。Yamashina (1929) がこの亜種ではないかと思われる標本をパラムシル島 (千島列島北部) で採集している。
Stepanyan (1975) によればカムチャツカの亜種が最も暗色のものからなっており、アジア北東部の繁殖地で暗色型の個体を探すのが望ましいとある。
北米ケアシノスリの色については Cade (1955) Variation of the Common Rough-Legged Hawk in North America で読める。さまざまな色調の標本の写真も出ている。亜種命名についても言及があるが、古い論文なので現代の知見とは異なっているかも知れない。
最も淡色のシベリア型は pallidus と名付けられていた。すでに使用された preoccupied な学名だったことは Wetmore et al. (1948) が気づいたとの記述がある。
現在ではこれは menzbieri または kamtschatkensis のシノニムとされているようでリストによって扱いが異なっている。
まだ pallidus と呼ばれていた時代にアラスカで記録があった。
色の個体差は大きく、白いものから黒いものまで連続的に存在し、"morph" のような表現は適切でないだろうとのこと。
この著者は kamtschatkensis はシベリア型と区別できず、シベリア型全体を最も早く命名された亜種名である kamtschatkensis にすべきと考えており、また sanctijohannis は氷河期に孤立した個体群であったと考えられるカナダ東部の繁殖個体群にのみ適用すべきと主張していた。
アラスカの個体群はアジア型との交雑帯にあたると考えられるので独立した亜種を与えるのは適切でない。
また menzbieri は kamtschatkensis のシノニムとすべきとの主張。
Korobov et al. (2014) On the question of polymorphism of the rough-legged buzzard Buteo lagopus wintering in the south of the Russian Far East (pp. 3829-3834)
によれば従来は暗色型は亜種 sanctijohannis 由来と考えられており、北米から渡ってきていることの根拠とされていた (Nazarenko and Glushchenko 2005) が、
2007年にカムチャツカの繁殖地で暗色の個体が見つかった (Lobkov et al. 2008) とのこと。
亜種 menzbieri にで暗色の個体があるかどうかはまだ明らかでない。
1975-1985 年の先述のデータでは 2% 程度の割合であったが、1986-2004 年の 2300 羽のデータでは 0.7% 以下と減少した。2004-2013 年では 5863 羽中 1.35% であったとのことで年変動もあるとのこと。
その後は 2014 年 11 月にアムール州で最初の暗色型の記録があった。
暗色の個体はオスが圧倒的に多くて 88.6% (性は大きさ、それに対応した飛行パターンの違い、色合いから判断できるとのこと)、また成鳥が中心で 77.2%。それぞれの写真も掲載されている。
Petrovichi 村で 2003-2013 年にほぼ連続で飛来した暗色のオスがあった (額の白色斑の同一性から同一個体と判定された)。
Lobkov et al. (2008) は
Research and Conservations of the Raptors in Northern Eurasia (Materials of the 5th Conference on Raptors of Northern Eurasia. Ivanovo, Feb. 2008) pp. 264-266
で読むことができる (写真はない)。この文献によればカムチャツカの亜種は北米の亜種に似ているが、これまでは北米のような暗色型はないと考えられてきた。35 年カムチャツカで 500 例程度を観察してきたが夏場に本当に暗色型と呼べるものは見られなかった。
Lopatka 観察ステーションで 1987 年秋に 43 羽のケアシノスリを観察し、多少なりとも黒っぽいものはは 4.6% だったが「暗色型」と呼べるものはなかった。
食物となる齧歯類の個体数は大きく年変化して特に齧歯類の個体数ピークが数年続くとケアシノスリの個体数も大きく増える。ケアシノスリの個体数が少なくとも5-7倍に増える年があり、2007 年はまさしくそういう年で、この年は春から夏の期間ずっとケアシノスリの繁殖シーズンに注目していた。そのうち4個体はまさしく暗色型だった。このような個体はこれまでカムチャツカで見たことがなかった。
北米の亜種が数の多い年にカムチャツカで繁殖した可能性もあるが、暗色の表現型は遺伝的に劣性でカムチャツカではこの遺伝子の頻度が低く、数が多い時でないと観察できる確率が低いのかも知れないと推定している。
地域は違うが 2007 年にヤマル半島でハタネズミが豊富だった報告もある: Fufachev and Sokolova (2019) Population numbers, breeding success, and food of the rough-legged
buzzard Buteo lagopus in the shrub tundra subzone of the Yamal Peninsula (pp. 1798-1799)。
なおタカ類の淡色型/暗色型はオオハイタカ Accipiter melanoleucus (新学名で Astur melanoleucus) 英名 Black Sparrowhawk でよく調べられており、
Nebel et al. (2021) Multigenerational pedigree analysis of wild individuallymarked black sparrowhawks suggests that dark plumagecoloration is a dominant autosomal trait
によると野外での家系図解析から暗色型が常染色体優性遺伝と判明したとのこと。
Rodseth et al. (2024) Plumage polymorphism in the black sparrowhawk (Accipiter melanoleucus) is strongly associated with expression level of agouti signalling protein
によればオオハイタカで MC1R や ASIP のタンパク質をコードする領域には多形は認められなかったが ASIP の発現量と色彩にはよい相関があった。色彩を制御する機構は調節部位が関係するなどもう少し複雑なよう。
ノルウェーでケアシノスリとヨーロッパノスリの異種間のつがいと雑種の若鳥が記録されている: Gjershaug et al. (2006) Hybridisation between Common Buzzard Buteo buteo and Rough-legged Buzzard B. lagopus in Norway。
この場合は親の種を同定できるので確実な事例となった。若鳥の begging call はケアシノスリの方に似ていた。羽衣は中間的だったとのこと。
一方で北米でノスリの雑種と考えられる個体の DNA を調べたところ外見と違っていた事例が報告されている: Clark et al. (2017) Contrasting molecular and morphological evidence for the identification of an anomalous Buteo: a cautionary tale for hybrid diagnosis
こちらは外見からの雑種判定は要注意との結果となっている。
[ケアシノスリの侵入的渡り (irruption)]
ご承知の方も多いだろうが、日本では 2008 年初頭に大規模な irruption (低緯度まで侵入的渡り) があった。いくつかの出版物に記載があるが、例えば「日本のタカ学」(2013) pp. 196-201 に久野氏が記載されている。
この記事によれば 2008 年1月下旬に山口県で1羽、3月上旬に三重県で3羽に送信機が取り付けられ (すべて幼鳥)、渡り経路の追跡が行われた。山口の個体は朝鮮半島を北上して 68N 166E 付近のカムチャツカよりさらに北のロシアで越夏したとのこと。
三重の個体は本州を北上して北海道まで追跡され、1羽はアムール川まで追跡されたとのこと。
[環境省自然環境局 渡り経路による衝突の影響分析業務報告書 (2008, 2009, 2010) の平成 19 年度から平成 21 年度版に記載されているとのこと]。
ケアシノスリ 日本への大量飛来 2008 年 (若杉氏の「マーリン通信」の記事)。湖北地方を多数渡っている移動途中の姿も目撃された (日本野鳥の会滋賀の記事より)。
日本の 2008 年初頭の前に韓国でも記録されている Birds Korea: irruption 2007 年 11 月から 2008 年2月にかけて何十羽のケアシノスリが東西海岸にとどまったとのこと。
ちなみに上記 Korobov et al. (2014) ではこの時期の観察結果もあり、極東ロシア南部で越冬するケアシノスリは 2007/2008 の冬に個体数が極端に多いわけではないが多い方の年であり、暗色型はこの年が一番多かったことが示されている。
2007 年にカムチャツカ (あるいは北極圏の他地域でも?) で大繁殖したケアシノスリが 2007/2008 年の冬にやってきたと考えると非常に整合性がよいと思われる。極東ロシア南部で暗色型が多かったことも、カムチャツカの繁殖個体が越冬に来たと考えると納得できそうな感じがする。
日本で記録されるケアシノスリの亜種は主に menzbieri とされるが、このような事象をみると kamtschatkensis が関わっているようにも見える。当時の写真をお持ちの方は再検討されていかがであろうか。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" でも亜種分布についてはやや不明瞭な書き方をしており、日本で記録されるケアシノスリの亜種は多分 menzbieri であろうと記しているが中国東北部で越冬するものは大部分 kamtschatkensis とも書かれており、全体にやや含みを残した記述になっている。
なおヨーロッパでは 2010-2011 年に大規模なケアシノスリの irruption があったとのことで現象には地域差もあるようである。ヨーロッパでの越冬数は長期的な減少傾向があるとのことで、やはり温暖化が影響しているのであろうか。
[齧歯類がいない島で繁殖したケアシノスリ]
Pokrovsky et al. (2015) Rough-Legged Buzzards, Arctic Foxes and Red Foxes in a Tundra Ecosystem without Rodents
ロシア北極地方の Kolguev 島 (バレンツ海) には齧歯類がいないがケアシノスリが繁殖に成功。ガンの子やライチョウ類を捕食していた。かつてはケアシノスリは記録されておらず、観測空白期間があったが繁殖するようになったのは近年のことと思われる。齧歯類を専門とする種と考えられていたが食物の変化に柔軟に対応できることを示す。
[ケアシノスリの渡り追跡]
北極圏の齧歯類の獲物の年変化が大きく、個体数が多い年や寒波が強烈な年には irruption が起きることは日本と同じ。
ヨーロッパでのケアシノスリ衛星追跡の例。
Rough-legged Buzzard in variable environment (スカンジナビアの衛星追跡)。
Notes From the Field: The Rough-legged Hawk Project 北アメリカでのケアシノスリ衛星追跡の結果 (2020)。膨大な数の追跡が行われていることがわかる。
同一個体が数年間追跡されており、渡りのルートは年によってあまり変化しない結果が出ている。
個体数が年によって大きく違い、irruption もあるためケアシノスリは放浪的な生活様式が考えられがちだが、少なくとも北米に関してはそうではなく同一個体は同じ渡りのルートを用いているようである。
Yamaguchi et al. (2017)
Migration Routes of Satellite-Tracked Rough-Legged Buzzards from Japan: The Relationship between Movement Patterns and Snow Cover 日本の研究例。
Pokrovsky et al. (2021) Longer days enable higher diurnal activity for migratory birds
がロシア西部で標識されたケアシノスリの追跡を行っている。北極圏で繁殖することで長い昼を有効に利用しているとのこと。データも公開されていて Data from: Longer days enable higher diurnal activity for migratory birds [rough-legged buzzards]
から取得できる。
Pokrovsky et al. (2024) Foxtrot migration and dynamic over-wintering range of an Arctic raptor
ロシア西部北極圏からのケアシノスリの越冬期の移動。積雪に応じて 1000 km 程度の範囲を移動する。時々戻りつつ移動する渡りを "foxtrot migration" と呼んでいる。
オランダの 40 年間の研究でケアシノスリの減少が記録されているが、おそらく温暖化に伴って積雪地域がより北側に移動したため。2011 年にはオランダで 12 月遅くに多数の渡り個体が観察されたが、北欧の大雪の影響と考えられる。
ケアシノスリのロシア語名は zimnyak でこれは大変わかりやすく、zima (冬) にやってくることが由来。ノスリ類 kanyuk (単数形) の名前を付けて kanyuk-zimnyak あるいは mokhononogij kanyuk とも呼ぶ。後者は英語名、和名と同じ意味。ノスリ類 kanyuk の語源はせがむように鳴く声から。
[鳥インフルエンザの影響を強く受ける北米のケアシノスリ]
Paprocki et al. (2025) Increased Mortality Rates Caused by Highly Pathogenic Avian Influenza Virus in a Migratory Raptor
GPS-GSM で追跡をした結果、渡り途中の死体が回収されて死因も明らかになり、2022-2023 年の HPAI H5N1 の大発生に対応する高い死亡率 (47%。致死率とは異なるので注意。とんでもなく高い数字) が明らかになった (通常は年死亡率 3-17% とのこと)。
繁殖前の春の渡り (2022 年 4 月) に顕著だった。感染した水鳥の死体を食べたためではないかと考えられる。
わずか1年で北米のケアシノスリの個体数が 28% 減少するなど危機的状況である。
2023 年 4 月はまだこの研究の対象外だが、2023 年 1 月にある程度 HPAI H5N1 による死亡個体が記録されている。
調べられた中で死因不明 (回収できなかった、保存状態が悪かったなど) と判定されたものにも HPAI によるものも含まれている可能性がある。死因不明とされた2例の若鳥は死の前に逆方向への渡りを示していたとのこと。GPS-GSM と早期の死体回収の威力のわかる研究となっている。
北米のケアシノスリの主要4ルートのすべてで HPAI による死亡例が確認された。
ウイルスのゲノム解析からアジアから太平洋ルートで北米への導入も 2022-2023 年に検出されており (Damodaran et al. 2024。#インドガン備考の [野鳥と鳥インフルエンザ] で紹介) ユーラシア北部ではいったいどうなっているのだろう。
-
カラフトワシ
- 第8版学名:Clanga clanga (クランガ クランガ) ワシの一種 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Aquila clanga (アクィラ クランガ) ワシの一種
- 第8版属名:clanga klangos (Gk) ワシ
- 第7版属名:aquila (f) ワシ (aquilus 暗色の 由来との解釈がある)
- 種小名:clanga klangos (Gk) ワシ
- 英名:Greater Spotted Eagle
- 備考:
clanga は語源もあまり明確でないが、ギリシャ語の klange (音を表す名詞) は末尾が長母音でアクセントがありそのまま音訳すれば伸ばす可能性もある。klangos 由来ならば短母音。ラテン語では末尾アクセントにはならないので音韻的にも素直な短母音を採用した (クランガ)。
aquila は#イヌワシ参照。
単形種。
BirdForum: Bird Name Etymology clanga にギリシャ語語源の考察がある。声や色彩も候補に上がっているが確かな結論は出ていない。
過去の Aquila 属が単系統でないことが判明して属に分けられた。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版以降は Clanga 属 (備考参照) となり、世界で使われる分類に一致する。Clanga 属はカラフトワシ属。
このような解説を見ると属名はすんなり受け入れられたように見えてしまうが、実はややこしかったとのこと。Spotted eagles によれば、
Wells and Inskipp (2012) A proposed new genus of booted eagles (tribe Aquilini)
が分子系統解析に基づく3種を含む新属 Aquiloides を提唱した。しかし過去の文献の検討が不十分だった。
現在受け入れられているものは Rev. et Mag. de Zoologie (Adamowicz 1857) で、
Clanga naevia, C. fasciata, C. macrodactyla の3種 (当時の学名) としたもの。
Clanga naevia は古い学名で、naevius 斑点のある などの意味。
Clanga fasciata は現在では ボネリークマタカ Aquila fasciata に対応する。Clanga macrodactyla は何を指していたか不明 (誤植の可能性ありとのこと)。
この記載では clanga の種小名から直接昇格したものでないことがわかる。
Tyzenhaus (1858) が Clanga 属を定義し、Falco maculatus Gmelin, 1788 = Aquila clanga Pallas, 1811 をタイプ種としてこちらは新学名からのトートニムによる。Tyzenhaus (1858) は2種 Aquila clanga, Aquila pomarina (アシナガワシ) を含むとした。
しばらくは Tyzenhaus (1858) が Clanga 属の命名者とみなされていたが、Gregory and Dickinson (2012) Clanga has priority over Aquiloides (or how to drop a clanger)
がこの問題を検討し、実際の出版年月の推定を行い現在使われる名称に至ったとのこと。
"drop a clanger" はもちろん Clanga と引っ掛けているが、英国俗語で「大きなへまをする」の意味とのこと。clanger は大きな音を出すベルなどを指す。それを落として大きな音を立てることを例えたもの。
人名の関係の記述はわかにくいので次の文献の方が読みやすい。Tyzenhaus の名前は追悼文の中で未発表原稿の著者として出てくるもので記載者にはならないとの判断。
しかしこの問題はまだ解決しなかった。Hordowski and Gregory (2018) The avian genus-group name Clanga Adamowicz dates from 1854
の論文を発表し、由来はもっと古く遡れることがわかった。記載年は 1854 年とすべきとのこと。
この最も早い記述によれば Falco maculatus Gmelin, 1788 = Aquila clanga Pallas, 1811 を Clanga naevia と名付けたことになる。maculatus も 斑点のある などの意味。
Adamowicz 自身は Pallas の学名を用いて記述していなかったが、Aquila clanga Pallas, 1811 と同一と判断されたため結果的にトートニムになった。
この 1854 年の属記載であれば種小名から属名への昇格ではなく、後の分類整理によって属名と一致する種小名の種が含まれることになってカラフトワシがタイプ種となった。
もう少し検討してみると Falco maculatus Gmelin, 1788 (参考 Spotted Eagle) はカラフトワシの種小名となってもよかったが、Falco maculatus Tunstall, 1771 (参考 Spotted Falcon) の用例が先にあって無効となった。
また Gmelin (1788) の用例の最初のものは複数種に分割された Aquila naevia と同定されたため種の概念として不適切でもあったのだろう。
この学名はさらに複数の概念を含み 参考 1 はシロハヤブサのアイスランドの変種、参考 2 は Spotted Sparrowhawk と斑点のあるハイタカ。Gmelin (1788) だけで少なくとも3つの異なる概念に対してこの学名を与えていたこととなり、先に用例がなくても無効となっていたかも。
複数種に分割された Aquila naevia が現在では Clanga 属に含まれるので属定義としては構わないのかも知れないがあまり釈然としない点も残る。
Hordowski and Gregory (2018) では Falco maculatus がカラフトワシのシノニムのように見えるがそれほど簡単ではないようで多少注意するのがよさそう。
Brooks (1873) Indian and European Eagles
にワシ類の当時のさまざまな学名が現れ、互いに似ていることや若鳥、渡りもあって相当混乱していたことがわかる。Clanga naevia についても議論があり、インドで見かけるものと別のものをヨーロッパの学者が同じ名前で呼んでいるなど。Aquila orientalis との学名もあって、その若鳥ではないかとの提案もあったが違うとのこと。
Dresser (1873) On certain Species of Aquila
も Pallas が名付けた Aquila clanga が何者かを議論している。
さらに
Brooks and Assensole (1873) On Aquila bifasciata and Aquila orientalis
Aquila orientalis の標本はあるが古い記載の記述からの同定は難しいよう。Aquila bifasciata (2本の帯のあるワシの意味) はインドのワシを指す名前であった。
この著者は Aquila bifasciata と Aquila orientalis は同一であると判断し Aquila bifasciata の方に先取権があると考えた。
脚注に Aquila bifasciata の標本と比べて完璧に同じとの連絡があったが標本ラベルが正しいかどうかは必ずしも確かではない。もしこれが本当ならば同種説を裏付けるとのこと。
Pallas の Aquila clanga は Klein (1750 とされる) が用いたもので Pallas はそれを Aquila naevia のシノニムとして用いた。この著者はヨーロッパのものを指して Aquila clanga と呼ぶのは間違いであると考えた。
なおここで指されているものは Aquila bifasciata Gray (1830 年代?) (参考) が 1802 年にインド Cawnpore (現在のカーンプル) で採集した標本に基づくもの (英名 White-banded Eagle が付いていた) と考えられるが、
Aquila bifasciata Brehm, 1824 (参考 基産地ヨーロッパまたはドイツ の用例があるようで Gray の用例は有効にならなかったかも知れない。現在はこの学名はソウゲンワシ [Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) の方が新しいが。#ソウゲンワシの備考参照] に吸収されている。
Aquila orientalis Cabanis, 1854 も現在はソウゲンワシの亜種となっている (こちらは年代順からも妥当)。
Pallas の Aquila clanga は異なるとの判断となったよう。
orientalis は "東洋の" と訳したくなるが、この例のようにヨーロッパ西部から見て "東側" を指していることもあり用例によって意味が異なる場合もある。
[なぜ "樺太" ワシ?]
日本では珍しいが、主に東欧から極東ロシアに広く分布する。和名の樺太は通常の分布域に含まれていない。
園部 (2003) Birder 17(8): 78-79 によれば当初は樺太、朝鮮半島にも記録があったとのこと。
Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" (Birds of Sakhalin Island) p. 96 に記述があり、サハリンで採集されたカラフトワシがサハリン博物館のリストに載っているとのこと。出典は Takahashi (1937) で当時日本領であった時代に記録されたものだった。
文献は Takahashi T. (Tazo Takahashi 高橋多蔵) A list of the birds from Saghalien, depended on the descriptions to arrangement of birds on the specimens in the Saghalien locality Museum. Toyohara. Vol. 1, N 1 とのこと。樺太産鳥類目録。
p. 60 にカラフトワシ 樺太鷲 Aquila clanga fulvescence Gray となっている。採集地樺太となっているが樺太産の新種のマークは付いておらず、これ以前から樺太で知られていたものを載せた模様。
Nechaev (1991) ではサハリンの鳥のリストでズグロカモメやイワミセキレイの記録も同様に樺太産鳥類目録由来とのことで詳細はわからないとなっている。
Aquila clanga fulvescence の学名を調べてみるとこれは Aquilla fulvescens Gray (参考) 基産地 Cawnpore (インドのカーンプル)。
Tawny Eagle, Aquilla fulvescens とあり、この学名は現在のカラフトワシではなくソウゲンワシ (ここでは分離される前の英名) になっている (おかげで Tawny Eagle の英名由来もわかってしまった)。
当時はワシ類の分類がまだ混乱していた時期で、本当に現在の Clanga clanga だったのだろうか?
亜種まで記されていることから見て、例えば Gray の図版を色調の比較対象とした可能性が考えられるが、この色調はたとえカラフトワシの若鳥でも合わないのでは。学名の字義は当然知られていただろう。
さらに調べると Menzber (1882, 参考文献参照) p. 393 に情報があった。当時は Aquila clanga に5型があると考えられ、色彩で分けていてカラフトワシとソウゲンワシが混ざった形で Aquila clanga と呼ばれていた。アシナガワシは別扱いでこの文献では Aquila naevia の学名となっていた。
現在のソウゲンワシに相当すると考えられるものは Aquila orientalis (p. 385) と Aquila bifasciata (p. 386) と2か所、さらに Aquila glitschii (p. 387) に現れている。
p. 388 に分布に関する総論を述べている。Aquila orientalis と当時の概念でカラフトワシ (さらにアシナガワシ) を Aquila glitschii と同種と考える見解も述べられていた (p. 389)。
Menzber の考えでは Aquila clanga fulvescence はカラフトワシ (またはアシナガワシ) の色素欠乏型と分類されていたらしい。p. 394 では異常型として var. fulvescence の呼ぶのがよいと考えていた。
clanga の記載が早いため、これらの記載を1種にまとめる場合は clanga が基亜種 (つまり種学名) となる次第。
ということでカラフトワシ 樺太鷲 Aquila clanga fulvescence は見事にこの学名を用いており、種学名に Aquila clanga と付いているのは先取権の原則によるもので、現代の Clanga clanga と同じとは言い切れない。
Hartert (1910-1922) では Aquila maculata (カラフトワシに相当) と Aquila naevia (アシナガワシに相当) の学名を用いて記述していた。
この標本は p. 1106 に記述がある。カラフトワシの若鳥の色彩変異と考えたが大きさはアシナガワシの方に近いと考えていた。はっきりした結論は出していない。
当時の Aquila clanga は現代では少なくとも2種に分離されることになる。
Aquila fulvescence Gray の指していたものや使われている字義の色調を考えるとむしろ現代の概念のカラフトワシではなかったのではないだろうかと感じる。
Shtegman (1937) "Faune de l'URSS Oiseaux Vol. I n.5 Falconiformes" (参考文献参照) pp. 181-182 では当時の Aquila maculata のシノニムとしており Hartert を引き継ぎ、まれに見られる黄金色の異常型と考えていた。このタイプは1年めの若鳥に多いが成鳥でもまれに見られるとの記述になっている (この解釈は現在でも認められているのだろうか?)。
色彩変異の扱いで Menzber のように亜種扱いとはしていない。
Karyakin (2004) "猛禽類の調査方法" (参考文献参照) p. 150 (fig. 42) に淡黄色の morph (palevyj morf) の図版があり関係するかも知れない。この図版では成鳥となっている。
同書 p. 149 にはワシ類の中で最もよく鳴くとある (それゆえ clanga ということか)。
なお pp. 153, 159 ではカラフトワシ、アシナガワシともにワシ類の中で最も目立たず、(繁殖時の) 生息確認も難しいとのこと。ワシ類の中では隠蔽性が強い。
標本などで確認できない限り樺太時代の目録に載ったものは確実な種同定は不明とならざるを得ない感じがする。
Nechaev (1991) によればサハリンで最初に記録されたのは Dobrotvorskij (1870) と Mitsul' (1873) とのこと (この記録については後述)。Nechaev (1991) 自身は一度も見たことがないとの記述となっている。
Dement'ev and Gladkov (1951) にはこの分布は含まれていない。
Gizenko (1955) "Ptitsy Sakhalinskoj Oblasti" (サハリン州の鳥) によれば、サハリン、モネロン島、千島列島に少数、繁殖は記録されていないとある。
Gizenko が1947年9月16日にウルップ島の北西部でエトピリカのコロニーの上で旋回しているのを見つけた。1948年6月23日に Terpenie 岬の近くで、1949年5月29日にサハリンの Kuzunetsov 岬の先端で見つけた。
過去にはサハリン南部の Susui 川流域の森林に多数生息していたという。Mitsul' (1873) が多数観察したという [Nikol'skij (1889) に記述]。ウルップ島でも小型のワシが観察されカラフトワシと思われるとのこと。近いところではアムール流域で採集されている (Schrenck 1861) との記述がある。
文献は Nikol'skij (1889) ["O prirode ostrova Sakhalina" (サハリン島の自然)、
"Ostrova Sakhalin i ego fauna pozvonochnykh zhivotnykh" (サハリン島とその脊椎動物)、の2つの出版物がある] なので Dement'ev and Gladkov (1951) が目を通していてもおかしくなさそうだが出てこない。
Nikol'skij (1889) の後者の文献では p. 220 に記述されているが上記とほぼ同様。サハリン島の標本はない。過去の情報をまとめているもので、「多分」などの表現が多くちょっと怪しい。Mitsul' によればサハリン南部で古い学名で Aquila naevia (Spotted Eagle) が多数見られ、沿岸部に多いとのこと。Menzber (1882) で用いられた学名を見るとこれはかなり怪しい。
これら記録からヨーロッパ南東部からシベリア全域に分布していると結論している。Mitsul' によればサハリン南部でオオワシ、オジロワシも多数見られ、沿岸部に多いとそれぞれの種でカラフトワシとほとんど同じ記述になっている。
大きさが相当違うはずだが、あるいはオオワシ、オジロワシの若鳥と混同されていたのではとの印象も受ける。Dement'ev and Gladkov (1951) が分布にカラフトワシのこれらの情報を採用していないのは不自然な点を感じていたのかも知れない。
それともあるいは 20 世紀に分布が縮小したのだろうか。
Belik (1999 初出、2020 再掲) Likely causes of the disappearance of the great spotted eagle Aquila clanga in Russia (pp. 2731-2734)
によれば、主な生息地であるヨーロッパロシアの東部 (この種の世界の個体の 80% がロシアで繁殖するとのこと) の情報が中心だが、急激な個体数減少が報告されており、20 世紀前半は現在の 5-10 倍の個体数で普通種で広範な環境の森林に生息していたという。数が減ってからは沼地のツンドラ性森林ステップが主な生息地となってしまった。
1960 年代に特に減少が著しく狩猟や古い木の伐採などが影響していたと説明されてきた (1950-1960 年代に猛禽類撲滅運動があった) が、同様のサイズのカタシロワシはそれほど影響を受けていないので、カラフトワシに特有の理由があるはず。毒物の影響が表れやすい生活史戦略や生態などを要因として取り上げているがあまりすっきりしない。
Dement'ev and Gladkov (1951) がまとめた情報と時期的にちょっと合わない印象を受けるが、個体数減少前には分布がもう少し広く、サハリン州でもある程度観察されていたのかも知れない (19 世紀の数が多いとの記録はちょっと ? だが)。
分布図には含まれるが最近の文献を見る限りではバイカル湖以東の情報はほとんど出てこず、極東ではほとんど記録されていない。圧倒的にシベリア西部の種類に見える。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では沿海地方まで分布するとなっているがほとんどの場所でまれで絶滅した地域もあるとのこと。場所により比較的普通とある。
Greater Spotted Eagle によればハンカ湖やアムール川流域など極東でも少数の記録例がある。
2023年9月28日に Max Logunov による 記録 があって同定が議論されている。撮影者はカタシロワシと考えたが多くの人がカラフトワシと判定したとのこと。イヌワシ類のような嘴でなくエレガントで "カラフトワシ属風嘴" との造語も出ている。
若鳥で背や翼上面の白っぽい羽毛が特徴的とのこと。
世界的個体数では Clanga 属では最も少なく、アシナガワシ Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle はヨーロッパ東部中心でカラフトワシの一部と同様にアフリカに渡りをするが個体数は1桁大きい。
インドワシ Clanga hastata Indian Spotted Eagle の個体数はカラフトワシ同程度だが分布域の広さを考えるとカラフトワシの個体数はかなり少なく見える。
1950-1960 年代の迫害や森林伐採などの影響をより多く受け、個体数が減少した地域に他のワシ類が進出し、以前の生態的地位を取り戻せなくなっているのだろうか。Clanga 属そのものも Aquila 属より古く分岐した系統で、イヌワシ亜科内で競争があった場合に若干の生態的な弱さがあるかも知れない。
カラフトワシは現在のサハリン州の情報 (Nechaev 1991) によれば迷行種の扱い。1970-1980 年代には観察されていない。千島列島では記録がない。「カラフトワシ」は現在の分布にはあまりふさわしい和名になっていない。
Greater Spotted Eagle "Threatened birds of Asia" (The BirdLife International Red Data Book 2001, 2002) にアジアの情報がまとめられており、サハリンは歴史的記録にも含まれていない。文献に記録されている場所の地図もある。
アシナガワシの和名の由来はおそらく英語別名由来ではないかとのこと (若杉氏私信)。日本鳥学会「鳥」32(4) 世界の鳥の分類和名 (4) (1983) のリストに Lesser Spotted (Long-legged) Eagle とある。
Indian Spotted Eagle (The Peregrine Fund) には インドワシ Clanga hastata Indian Spotted Eagle の別名として現れる。
Lesser Spotted Eagle と Indian Spotted Eagle はかつて同種とされたもので、Lesser Spotted Eagle の別名に Long-legged Eagle が含まれていた可能性があるが、英名の関係は見つけられなかった。
Dement'ev and Gladkov (1951) ではカラフトワシの項目にふしょが比較的長いとあるが、アシナガワシの方には特に出てこない。あるいはカラフトワシと一緒にまとめられたいた時代の名称なのかも。
学名の中にこの英名に相当するものがあり、Aquila longipes Hornschurch & Schilling, 1837 参考 によれば無効学名とされており何を指したものか判明しなかった。
あるいは "アシナガワシ" を指して使われていた時期があって Long-legged Eagle につながっていたかも知れないが文献も用例も見当たらず不明。
Talassemtane National Park (モロッコ) の野生動物のところに long-legged eagle の用例があった。何を指しているかは明瞭でないが地域的には Clanga pomarina に対応するかも知れない。
Clanga hastata に至る経緯は大変ややこしく、
採用された記載は Morphnus hastata Lesson, 1831 と別属に含められていた。黒っぽいやや大型のワシを何に分類するか紆余曲折があった。
Brooks (1873) にあるようにカラフトワシの旧学名でもいろいろな混乱があったが、Messrs, Gurney aud Dresser はヨーロッパのカラフトワシ (当時学名 Aquila naevia) と Aquila hastata は区別できないと述べたとのこと。
Die Voegel der palaearktischen Fauna systematische Uebersicht der in Europa, Nord-Asien und der Mittelmeerregion vorkommenden Voegel (Hartert 1910-1922) では Aquila pomarina hastata と亜種の扱いとなった。
どこかの段階で Long-legged Eagle の名前があったのかも知れない。
シノニムに Liminaetus unicolor Blyth, 1843、Spizaetus punctatus Jerdon, 1844 が挙げられており、要するにどのグループに属するかも判然としなかった。この文献は当時の鳥の分類を垣間見ることができ、他の部分を読むのも有用だろう。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば、カラフトワシよりアシナガワシは少し小型で、ふしょは比較的長く (これがアシナガワシの由来?)、嘴は弱いなどとある。
Indian Spotted Eagle (インドワシ) と Lesser Spotted Eagle (アシナガワシ) を分離する根拠となった研究は Parry et al. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata
特に Indian Spotted Eagle では口角 (gape) が大きいとのこと。ふしょの長さ (tarso-metatarsus length) も挙げられているが、カラフトワシに比べてアシナガワシが相対的に長い結果にはなっていないので、この文献では Dement'ev and Gladkov (1951) の記述は裏付けられなかった。
この文献では Indian Spotted Eagle でもあまり差がないので、Indian Spotted Eagle の別名としての Long-legged Eagle もふさわしくなさそう。
Markus et al. (2011) First confirmed record and first breeding record of Indian Spotted Eagle Aquila hastata in Indochina
にこれらの数字が引用されているのでご覧いただきたい。この論文はカンボジアで繁殖した個体の DNA 解析で Indian Spotted Eagle と判定したもの。計測値を見ていただくと面白いのだが tarso-metatarsus length が長く、Indian Spotted Eagle よりも体の大きなカラフトワシの標本に匹敵する結果となっている。
Parry et al. (2002) はどのように測定したか述べていないので、標本になった後の収縮が生じている可能性があるとのこと。この数字と DNA による確実な同定から Indian Spotted Eagle のふしょは相対的に長いのかも知れないが、比較された他の種の標本でも収縮効果はあると思われるので実際には確実でないかも知れない。
カラフトワシとアシナガワシで違いがあったとしても差はあまりにもわずかなので「アシナガワシ」の和名はやはりふさわしくないと思う。証拠はまだ不十分だが Indian Spotted Eagle の方が「アシナガワシ」にふさわしく、Long-legged Eagle と呼ばれた理由になっていたかも知れない。
参考までに Indian Spotted Eagle で脚の長さがわかりやすい画像をピックアップしてみた: Indian Spotted Eagle (Martin Allen 2024)。
Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" ではLesser Spotted Eagle と Indian Spotted Eagle は分離されていないが、long-looking legs とカラフトワシに比べてちょっと長めの表現。当時の記述で亜種 hastata の方に longer-legged とある。やはり Indian Spotted Eagle の方が Long-legged Eagle に少しふさわしいか。
桐原氏がかつて Birder 連載されていた記事 (2003) 17(9): 55 にあったアジサシ類の足の長さ比べぐらい。
中国名は小烏鷲に相当。spotted eagle を烏鷲としている。
上記を記述した後、週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 97 「日本迷鳥録 31」にカラフトワシの項目 (内田) があるのを見つけた。
和名の由来となった地名には旧領土も含まれており、シベリア産の亜種であるタイワンハクセキレイはたまたま台湾で捕獲されただけだし、カラフトワシも樺太は迷行の地でしかないと専門家ですら疑問を呈していたぐらいであった。
日本の鳥の命名慣習についてはここに登場する [カザノワシ] の項目 (台湾の外部サイト) 参照。日本の過去の慣習について中国語だが詳しい情報がある。翻訳ツールなどで見ていただきたい。
統治地域の地名に基づく命名は他国でも同様であったが、世界語となっている英語では見直しの際には旧統治時代の地名を避けるなど配慮される事例も出てきている。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 115 p. 23 にアシナガワシの項目が登場し、「その名のとおりきわめてあしが長い」とある (!)。当時はアシナガワシが分割される前でインドの亜種の表現も出てくるが、少なくとも訳文からは「あしが長い」はインドの亜種よりも種全体を指したものと読める。
この部分は日本版で追加されたものではなく原著 (または訳文 / 抄訳) が間違っていたのでは。
現在探しても対応する表現を見つけることができていないが、Long-legged Eagle はもしかするとフランス語由来かも。
いくつか候補を当たってみると、
Aigle tachete - aigle < marcheur によれば
aigle < marcheur > (健脚家のワシ)、歩きながら獲物を探すので足が長く見えた?
L'aigle pomarin semble avoir une queue plus longue: 尾がイヌワシ同程度に長い、とあるが尾と間違えたわけではなさそう。
これを見ると、フランス語由来かまではわからないが、「健脚家のワシ」のフランス語表現があるので、地上を歩く時は足が長く見える解釈が当たっている感じがする。
もしかすると博物学者による伝聞記述でヘビクイワシと混同していたのかも。「世界動物百科」の原著著者も翻訳監修者も現物や写真を見ていなかったのでは (?)。「きわめてあしが長い」の表現はヘビクイワシについても同じように使われていたので、あるいは本当にヘビクイワシを指したものだったのかも。
ヘビクイワシの名称と混同された解釈から少し当たってみると、現代のヘビクイワシの各国言語名はほとんど Secretarybird 由来となっていて語源がわからないが、スロバキア語で Hadozrut nohaty と呼ばれることを知った。
これまた辞書にない語が用いられていて意味が少しわかりにくいが、nohaty はほぼ間違いなく足が目立つ (長い) の意味 (ロシア語では足は noga)。Hadozrut はどうもヘビを食べる者の意味らしい (スラブ言語の類似性からなんとなく理解可能。ロシア語とは逆順になっている)。訳すとおそらく「足の長いヘビクイ」の意味になると想像できる。スロバキアに生息するわけではないので例えば動物園に導入する際にかつてあった外国語名を翻訳したものでは。
"アシナガワシ" と勘違いされるような名称がかつてあったのかも知れない (和名もあるいは古い外国語名由来かも)。
ちなみにヘビクイワシのアイスランド語名は orvi で or (英語 arrow に相当) でこちらは学名由来。
Long-legged Eagle の名称が積極的に使われた形跡がないのは、どこかの段階で間違いに気づかれたのかも知れない。
さらにドイツ語由来を疑って調べてみると、Langbeinadler (足の長いワシ) が複数種に使われていたことを知った:
・ニシオオノスリ [高野 (1973) ではオオノスリ] Buteo rufinus Long-legged Buzzard
・エボシクマタカ [高野 (1973) ではカンムリクロクマタカ] Lophaetus occipitalis Long-crested Eagle
・インドハゲワシ Gyps indicus Indian Vulture
ニシオオノスリは現在の英名にも残っているので由緒あるものだろう。ノスリはワシではないとしてドイツ語名から外されたものと想像される。
しかし "アシナガノスリ" に相当するドイツ語の Langbeinbussard セイタカノスリ [高野 (1973) ではセイタカチュウヒ] Geranospiza caerulescens Crane Hawk にも使われていた。この和名 "セイタカノスリ" は他の用例と比較するとドイツ語からの翻訳かも知れない。
画像を見るとエボシクマタカは多少長いかも知れない。飛翔中は足の先が尾の先端にかなり近い。
インドハゲワシは絶対的にはそれほど長く感じないが Gyps 属は尾が短いので飛翔中はやや目立つかも知れない。こちらもハゲワシはワシではないとしてドイツ語名から外されたものと想像される。
アシナガワシの飛翔写真を見ても Clanga 属は尾が短いにもかかわらずこららの種ほども目立たないので間違い感が強い。分離された Clanga hastata Indian Spotted Eagle でもそれほど違わない。
さらに見つけたものでは "Falco longipes" なる学名があって (Nilsson, Ornithologia svecica. I-II. Copenhagen, H. F. Popp, 1817-21) が新種として記載していた (図版)。
解説によれば、この美しい際立った鳥は、あるいは Falco leucopsis Beehsteinii (チュウヒワシのシノニム) はそうかも知れないが、どこにも記述されていないといのこと。
Bookplate of the Swedish naturalist and painter Gunnar Brusewitz. Friesen p. 11. Nissen Die illustrierten Vogelbuecher 677. Contains, among other things, a plate depicting the apocryphal bird "Falco longipes", which Nilsson presents as a new species. In reality he had been fooled by a forgery in a collection of natural-history specimens.
(AbeBooks auction 2025.7 取得。売却されれば見られなくなるかも知れない) とのことで、何とこの "新種" は捏造を見抜けず命名してしまったものだったとのこと。
同じ部分のスウェーデン語の紹介 NILSSON, SV. Ornithologia svecica. I-II 英語はこの翻訳かも知れない。
当時の Falco 属は何でも含んでいたので "アシナガワシ" に相当するかどうかまでわからないが、博物学者の間で引き継がれて各国語に訳されて行ったかも知れない。longipes の種小名がタカ・ハヤブサ類に出てこないのはここで使われてしまったためらしい。
GBIF には Falco longipes Lichtenstein, 1818 の項目があったが 2021 年削除されたとのこと (Falco longipes Lichtenstein, 1818)。
Lichtenstein, M.H.C. 1818. Verzeichniss von ausgestopften Saeugethieren und Voegeln, welche am 12ten October 1818 u. folg. Tage im zoologischen Museum der Koenigl. Universitaet zu Berlin durch den Koenigl. Auctionscommissarius Bratring dem Meistbietenden oeffentlich verkauft werden sollen. Berlin.
に現れるものとのこと。これは博物館標本の商品カタログに登場したもの。古い話で有名な種でもないので詳細を調べることは難しくなっているが標本を販売した結果捏造が判明したものかも知れない。
Hartert (1910-1922) の時代のチュウヒワシの項目にもシノニムとして現れないのは、この時代にはすでに捏造であることが判明して無効となっていたのだろう。
捏造なのでどの種とは判定できないが、このような経緯があったため世界のほとんどの言語で "アシナガワシ" に相当する名称はたとえ別種であっても過去に使われた捏造名と区別が付かないので排除されたものと想像できる。
ヨーロッパでは当時よく知られた捏造事例であったが、日本で和名を付ける時代にはすでに忘れ去られていて、どこかの言語に保存のために残っていた古い名前 (またはヘビクイワシとの混同。いずれにしてもおそらくその後排除されたか経緯が忘れられて残ったままになっている) を訳してしまったものかも知れない。
「最初に記録された産地に基づいて命名する」かつての一般的規則によっていなければ、#マダラチュウヒ にあるように、Pied, Spotted を "マダラ" とする用例はしばしばあるので "マダラワシ" となっていてもおかしくなかった。マダラチュウヒがあるならマダラワシでもよかったのでは?
英名に限らず、整理される前の古い学名では Aquila naevia だったので "マダラワシ" は学名とも対応していた。この和名を用いていて分離されれば "(オオ)マダラワシ" と "コマダラワシ" となって英名とよく対応する。日本産でないウオクイワシとコウオクイワシの名称は実際そのようになっている。
産地にこだわった命名 (これも分布を考えると適切でなかった) が由来となって、出所もあまり明らかでない (実は誤りかも知れない) アシナガワシの名称を使わざるを得なくなったと考えることもできるだろう。
カラフトワシは冬期アフリカ北東部では昆虫食となり、バッタ、シロアリなどを食べる (#カタシロワシの備考参照)。
Vali et al. (2019) High genetic diversity and low differentiation retained in the European fragmented and declining Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) population
によればヨーロッパでカラフトワシの生息地は断片化しているが遺伝的多様性は保たれているとのこと。
[鳥にちなむ小惑星の名前]
なんとなんと Greater Spotted Eagle にちなんだ星 (小惑星) の名前が付けられていた (wikipedia ウクライナ語版に載っていた)。
8979 Clanga (3476 T-3) によれば Discovered 1977 Oct. 16 by C. J. van Houten and I. van Houten-Groeneveld on Palomar Schmidt plates taken by T. Gehrels.
Named for the bird Aquila clanga, or greater spotted eagle.
となっている。あるいは発見者が熱心なバードウォッチャーだったのかも?
命名は 1999 年とのこと。同時期に名前の付けられた小惑星に鳥の名前がたくさんある。参考までにリストしておくと (学名は当時のものなので注意。この学名が天文学の正式記載に使われている):
8959 Oenanthe (Oenanthe oenanthe) ハシグロヒタキ
8960 Luscinioides (Locustella luscinioides) ヌマセンニュウ
8961 Schoenobaenus (Acrocephalus schoenobaenus) スゲヨシキリ
8962 Noctua (Athene noctua) コキンメフクロウ
8963 Collurio (Lanius collurio) セアカモズ
8964 Corax (Corvus corax) ワタリガラス
8965 Citrinella (Emberiza citrinella) キアオジ
8966 Hortulana (Emberiza hortulana) ズアオホオジロ
8967 Calandra (Miliaria calandra) ハタホオジロ
8968 Europaeus (Caprimulgus europaeus) ヨーロッパヨタカ
8969 Alexandrinus (Charadrius alexandrinus) シロチドリ
8970 Islandica (Bucephala islandica) キタホオジロガモ
8971 Leucocephala (Oxyura leucocephala) カオジロオタテガモ
8972 Sylvatica (Turnix sylvatica) ヒメミフウズラ
8973 Pratincola (Glareola pratincola) ニシツバメチドリ
8974 Gregaria (Chettusia gregaria) マミジロゲリ
8975 Atthis (Alcedo atthis) カワセミ
8976 Leucura (Oenanthe leucura) クロサバクヒタキ
8977 Paludicola (Acrocephalus paludicola) ハシボソヨシキリ
8978 Barbatus (Gypaetus barbatus) ヒゲワシ
8979 Clanga (Aquila clanga) カラフトワシ
8980 Heliaca (Aquila heliaca) カタシロワシ
小惑星を番号のみで記述する場合は (8979) のように ( ) に入れるのが普通。(8979) Clanga と表記してもよい。
これらの鳥の共通点を述べよとノーヒントで出題されて答えられる人は世界に何人いるだろうか?
さらに見ると WGSBN Bull. 2, #8 にまとめて訂正があった。学名をイタリックで記載していなかったための訂正だが、他の鳥も小惑星の名前になっていることが判明。驚くほど多数ある。
8589 Stellaris など「星」の意味かと考えてしまいそうだが、なんとサンカノゴイの意味とは!
単独で名前だけ見ると鳥の学名由来とは気づかないものも多いかも知れない。
wikipedia ドイツ語版で、(8585)-(8600) は頭文字を並べるとラテン語の Per aspera ad astra の意味となるとあったのでリストしてみた。英語で書けば "through hardships to the stars" となり、標語としてしばしば使われるとのこと。日本語では「苦難を乗り越えて星々へ」。栄光ともとれるとのこと (wikipedia 日本語版より)。
全部調べたわけではないが、発見者のオランダの RDB 記載種に含まれるとのことで、これらの鳥たちに栄光あれ、の意味が込められているのかも知れない。星に名前を付けるので "ad astra" はそのものずばりの表現と言える。自分もかつて Toki の名前を付けられないかと提案して実現可能に近いところまで行ったことがあるが思わぬ事象のため実現しなかった。
8433 Brachyrhynchus (Anser brachyrhynchus) コザクラバシガン
8434 Columbianus (Cygnus columbianus) コハクチョウ
8435 Anser (Anser anser) ハイイロガン
8436 Leucopsis (Branta leucopsis) カオジロガン
8437 Bernicla (Branta bernicla) コクガン
8438 Marila (Aythya marila) スズガモ
8439 Albellus (Mergus albellus) ミコアイサ
8440 Wigeon (英語から) ヒドリガモ
8441 Lapponica (Limosa lapponica) オオソリハシシギ
8442 Ostralegus (Haematopus ostralegus) ミヤコドリ
8443 Svecica (Luscinia svecica) オガワコマドリ
8585 Purpurea (Ardea purpurea) ムラサキサギ
8586 Epops (Upupa epops) ヤツガシラ
8587 Ruficollis (Tachybaptus ruficollis) カイツブリ
8588 Avosetta (Recurvirostra avosetta) ソリハシセイタカシギ
8589 Stellaris (Botaurus stellaris) サンカノゴイ
8590 Pygargus (Circus pygargus) ヒメハイイロチュウヒ
8591 Excubitor (Lanius excubitor) オオモズ
8592 Rubetra (Saxicola rubetra) マミジロノビタキ
8593 Angustirostris (Marmaronetta angustirostris) ウスユキガモ
8594 Albifrons (Sterna albifrons) コアジサシ
8595 Dougallii (Sterna dougallii) ベニアジサシ
8596 Alchata (Pterocles alchata) シロハラサケイ
8597 Sandvicensis (Sterna sandvicensis) サンドイッチアジサシ
8598 Tetrix (Lyrurus tetrix) クロライチョウ
8599 Riparia (Riparia riparia) ショウドウツバメ
8600 Arundinaceus (Acrocephalus arundinaceus) ニシオオヨシキリ
8601 Ciconia (Ciconia ciconia) シュバシコウ
8602 Oedicnemus (Burhinus oedicnemus) イシチドリ
8603 Senator (Lanius senator) ズアカモズ
8750 Nettarufina (Netta rufina) アカハシハジロ
8751 Nigricollis (Podiceps nigricollis) ハジロカイツブリ
8752 Flammeus (Asio flammeus) コミミズク
8753 Nycticorax (Nycticorax nycticorax) ゴイサギ
8754 Leucorodia (Platalea leucorodia) ヘラサギ
8755 Querquedula (Anas querquedula) シマアジ
8756 Mollissima (Somateria mollissima) ホンケワタガモ
8757 Cyaneus (Circus cyaneus) ハイイロチュウヒ
8758 Perdix (Perdix perdix) ヨーロッパヤマウズラ
8759 Porzana (Porzana porzana) コモンクイナ
8760 Crex (Crex crex) ウズラクイナ
8761 Crane (英語から) クロヅル (ヨーロッパで存続が危ぶまれていたため。Grus は星座名にあるので使えなかったのだろう)
8762 Hiaticula (Charadrius hiaticula) ハジロコチドリ
8763 Pugnax (Philomachus pugnax) エリマキシギ
8764 Gallinago (Gallinago gallinago) タシギ
8765 Limosa (Limosa limosa) オグロシギ
8766 Niger (Chlidonias niger) ハシグロクロハラアジサシ
8767 Commontern (英語から) アジサシ (706) Hirundo がすでに使われていたため英語から (wikipedia ドイツ語版より)
8768 Barnowl (英語から) メンフクロウ
8769 Arctictern (英語から) キョクアジサシ
8770 Totanus (Tringa totanus) アカアシシギ
8771 Biarmicus (Panurus biarmicus) ヒゲガラ
8772 Minutus (Ixobrychus minutus) ヒメヨシゴイ
8773 Torquilla (Jynx torquilla) アリスイ
8774 Viridis (Picus viridis) ヨーロッパアオゲラ
8775 Cristata (Galerida cristata) カンムリヒバリ
8776 Campestris (Anthus campestris) ムジタヒバリ
8777 Torquata (Saxicola torquata) (ノビタキ。おそらく分離前の学名)
[逆性的サイズ二型とアシナガワシとの交雑]
カラフトワシ (Greater Spotted Eagle) はイヌワシ亜科の中でも逆性的サイズ二型が著しいとのことで、平均的な数字では大きさでメスはオスより 26% 大きく、体重は2倍近い。この系統の中ではゴマバラワシに次ぐとのこと。ただし雌雄のサイズには重なりもあるとのこと (wikipedia 英語版より)。
鳥を捕える種類では敏捷さが必要なので逆性的サイズ二型が発達する説にとってはやや都合が悪い。
wikipedia 英語版の記述では飛びながら獲物を探すことが多いが、比較的低空を飛びチュウヒ類に似たところがあるとのこと。とまったり歩いて獲物を探したりすることもあるとのこと。
この部分の行動を見て [なぜ "樺太" ワシ?] のアシナガワシを指す aigle < marcheur > (健脚家のワシ) の名称が付けられたのかも知れない。
より小型のアシナガワシ (Lesser Spotted Eagle; 英名の方が話がわかりやすい) としばしば雑種を作るという。イヌワシ亜科の中では遺伝的に比較的近縁な2種と考えられる。
Maciorowski et al. (2015)
Hybridisation Dynamics between the Greater Spotted Eagles Aquila clanga and Lesser Spotted Eagles Aquila pomarina in the Biebrza River Valley (NE Poland)
がポーランドでの交雑状況を報告している。より大型のカラフトワシのメスと小型のアシナガワシのオスのペアの事例が多く、逆性的サイズ二型の利点を利用する傾向が考えられる (Vali et al. 2010)。
カラフトワシ類のメスは繁殖地の固執度が低く広範囲に移動するとのこと。成鳥オスが少なく、繁殖期の負荷が高いため大型猛禽類にも関わらず死亡率が高い可能性があり、メスが新しい相手を求める必要性が理由に挙げられるが死亡率の情報不足で詳しくはわからない。
東ヨーロッパでよく調べられており、2種の間の遺伝子浸透も調べられている。Backstrom and Vali (2011) Sex- and species-biased gene flow in a spotted eagle hybrid zone
によれば常染色体だけでなく Z 染色体でも遺伝子浸透が見られ、これまで調べられた鳥の交雑の中でも種分化の初期段階を表していると考えられる (これまで考えられていた以上に遺伝子浸透が起きやすい。また Z 染色体の方が進化速度が速い仮説 faster-Z hypothesis があり、Z 染色体の方が先に遺伝子浸透が見られにくくなる)。
分岐年代が短いため、あるいはスズメ目 (ヨーロッパの Ficedula 属でよく調べられている) に比べて1世代が長いことの影響が考えられるとのこと。
[交雑と渡り]
渡りを行う種で、渡り特性に違いがあるため雑種個体の渡り特性にも興味が持たれる。Vali et al. (2018) Genetic determination of migration strategies in large soaring birds: evidence from hybrid eagles
が雑種の若鳥を追跡。全体的にはカラフトワシの越冬域に近いところを選択した。渡りの個々の戦略 (渡り時期、越冬地) に顕性 (優性) 遺伝の影響が現れていると考えられるが、ペアの交雑は主にカラフトワシが好む環境で起きており、社会的影響を受けている可能性もある。複数年の渡り経路も追跡されており、ここまで調べられているのかと驚かされる。
2種が雑種を作ることや保護対象種で追跡が数多く行われていることをうまく活用した研究と考えるが、渡り戦略や越冬地が遺伝で制御されている根拠とするのはやや危ない感じがする。スズメ目で実験のように定位方向が中間を向くものではなく、渡り途中に合流した個体群との関係で決まっている可能性も考えられる。
どのような個体群に合流するか遺伝的な好みも現れている可能性もあり、何が決めているかは慎重に評価した方がよいのだろう。
アシナガワシで、ほぼ 100% 兄弟殺しの犠牲となる (#イヌワシの備考 [兄弟殺し] を参照) 2羽目のラトビアのひなを用いて人工的に育てて放ち渡り経路が調べられた:
Meyburg et al. (2017) Orientation of native versus translocated juvenile lesser spotted eagles (Clanga pomarina) on the first autumn migration
ラトビアで放されたものは成鳥の渡り経路で渡ったが、ドイツ (過去に個体数が大きく減ったため個体数を増やすために兄弟殺しの犠牲となる若いひなを活用している) で放たれたものは6日も早く出発し南へ渡った。多くは地中海地域で死亡したと考えられる。出生地で成鳥と一緒に渡ることのできたものは渡り経路を学習する機会が多かったはず。
しかしどちらで放たれたものも大部分がその年のうちに死んだという。それでも生き残ったドイツで放鳥の若鳥は地域の個体数増加に役立っているとのこと。
[イヌワシ類の系統分類 (イヌワシ亜科その2)]
Catanach et al. (2024) の分子系統樹に基づく分類を示す。#クマタカの備考の [Nisaetus 属のクマタカ類の系統分類 (イヌワシ亜科その1)] の続きになる。
系統的にはイヌワシ亜科 Aquilinae は {Stephanoaetus 属 (現生は1種のみ) + Nisaetus 属} (クマタカの備考部分) と Aquila 属などを含むそれ以外に分かれる。
ここで扱う後者のみで単系統をなす。
イヌワシ亜科 Aquilinae (の後半) (前半は#クマタカ備考)
アカエリクマタカ属 Spizaetus
クロクマタカ Spizaetus tyrannus Black Hawk-Eagle
セグロクマタカ [高野 (1973) ではチリーワシ] Spizaetus melanoleucus Black-and-white Hawk-Eagle
アカクロクマタカ* Spizaetus isidori Black-and-chestnut Eagle
アカエリクマタカ Spizaetus ornatus Ornate Hawk-Eagle
アカハラクマタカ属* Lophotriorchis
アカハラクマタカ Lophotriorchis kienerii Rufous-bellied Eagle
ゴマバラワシ属* Polemaetus
ゴマバラワシ [高野 (1973) ではゴマハラワシ] Polemaetus bellicosus Martial Eagle
エボシクマタカ属* Lophaetus
エボシクマタカ [高野 (1973) ではカンムリクロクマタカ] Lophaetus occipitalis Long-crested Eagle
カザノワシ属* Ictinaetus
カザノワシ Ictinaetus malaiensis Black Eagle
カラフトワシ属* Clanga
インドワシ Clanga hastata Indian Spotted Eagle
アシナガワシ Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle
カラフトワシ Clanga clanga Greater Spotted Eagle
ヒメクマタカ属 Hieraaetus
ヒメイヌワシ* [高野 (1973) ではコイヌワシ] Hieraaetus wahlbergi Wahlberg's Eagle
シロハラクマタカ Hieraaetus ayresii Ayres's Hawk-Eagle
コビトクマタカ* Hieraaetus weiskei Pygmy Eagle
ヒメクマタカ [高野 (1973) ではケアシクマタカ] Hieraaetus pennatus Booted Eagle
ハーストイーグル/ハルパゴルニスワシ* Hieraaetus moorei Haast's eagle (絶滅種)
アカヒメクマタカ [高野 (1973) ではヒメアカクマタカ] Hieraaetus morphnoides Little Eagle
イヌワシ属 Aquila
(系統 1。ソウゲンワシ属 Psammoaetus とする分類学者もある)
ソウゲンワシ Aquila nipalensis Steppe Eagle
アフリカソウゲンワシ* [高野 (1973) ではサメイロイヌワシ] Aquila rapax Tawny Eagle
ニシカタシロワシ* Aquila adalberti Spanish Imperial Eagle
カタシロワシ* [高野 (1973) ではカタジロワシ] Aquila heliaca Eastern Imperial Eagle
アフリカクマタカ Aquila africana Cassin's Hawk-Eagle
(系統 2)
イヌワシ Aquila chrysaetos Golden Eagle
ボネリークマタカ Aquila fasciata Bonelli's Eagle
モモジロクマタカ Aquila spilogaster African Hawk-Eagle
コシジロイヌワシ* Aquila verreauxii Verreaux's Eagle
モルッカイヌワシ* [高野 (1973) ではガーニイイヌワシ] Aquila gurneyi Gurney's Eagle
オナガイヌワシ Aquila audax Wedge-tailed Eagle
系統が分岐するところに空行を入れてある。必ずしも大きな分岐ではない。
中南米のアカエリクマタカ属 Spizaetus でよくまとまった単系統をなす。3種類の核遺伝情報が十分得られており、これらの間の分岐は精度が高い。
アカクロクマタカとアカエリクマタカは並列に並び順序に特に意味はない。
アカクロクマタカはかつて Oroaetus 属 [< oros, oreos 山 aetos ワシ (Gk)] とされていたが Spizaetus 属に内包されることがわかり統合された。
Spizaetus は spizias タカ (< spiza フィンチ + piazo 捕まえる) aetos ワシ (Gk)。
アカエリクマタカの wikipedia 英語版によればアメリカやメキシコに Spizaetus 属のいくつもの化石があり、ユーラシアからベーリング陸橋を通じてアメリカ大陸で適応放散したと考えられるとのこと。そのうち Spizaetus willetti (化石種) はオウギワシに近い大きさまで成長したと考えられるとのこと。
現代の分子系統解析ではアジアの Nisaetus 属とまとまったクレードをなすわけではない点は興味深い。
参考: Howard (1962) Bird Remains from a Prehistoric Cave Deposit in Grant County, New Mexico。化石の検討で Aquila 属とSpizaetus 属は共通点も多いが尺骨や手根骨などに違いがあるなど。
Nisaetus 属は系統的には少し離れるのでそこまで似ていないかも知れない。
アジアの Nisaetus 属はこのグループの中でも比較的早く分岐したが適応放散の時期が約 1000 万年前以降とやや遅い (中南米の Spizaetus 属の方がむしろ早いぐらい)。
これはアジアで Nisaetus 属に競争相手があり簡単に適応放散できなかったためかも知れないが、もしそうであれば競争相手は何だったのだろう。
同じくアジアで適応放散した Hieraaetus 属や Aquila と関連属の祖先も考えられるが前者は比較的小型。ただしハーストイーグルを生み出した系統なので案外強かったのかも。後者は主に草原環境だが系統的には比較的新しく 1000 万年前以降に種分化している。
現在の Nisaetus 属は主に熱帯から亜熱帯の森林に特化することで生態的地位を確立したのかも知れない (共通祖先がアメリカ大陸まで分布を広げた以降の話)。
もちろんさらに以前の系統とも競争があったかも知れない。例えばチュウヒワシやカンムリワシを含む系統にフィリピンワシのような強力な種類が存在するので競争相手の候補になり得たかも (#カンムリワシの備考参照)。
イヌワシ亜科 Aquilinae は系統的にはそれほど新しいグループではないが適応放散の時期が他系統 (例えば 亜科 Accipitrinae) に比べて比較的遅く、何か乗り越えるべきハードルがあったのかも知れない。
日本にクマタカがいるのは競争種がもともと少なかった (タカ類発祥の地より遠く種多様性も低い) ためと解釈できるかも知れない。クマタカは結構生息していると感じるが、生態的にはオオタカより少し脆弱な印象を受けるのは進化にも現れているようなクマタカ類の適応範囲の狭さを反映しているのかも知れない (他種との競合関係にかかわるもので、南方系なので性格がおとなしい、とはまた違う話に感じる)。
Spizaetus 属と Nisaetus 属はもと同属だったこともあって一緒に考えられる機会も多いかも知れないが、実はかなり違うものと考える方が正しそう。前者の方がイヌワシ類により近い。
クロクマタカの tyrannus は 暴君。それほど恐ろしい名前ではなく鳥の世界では Tyrant flycatcher もある (タイランチョウ科 - 太蘭鳥の漢字もあるがこれは英語の発音をそのまま用いた当て字のよう。コウウチョウ = Cowbird と同じようなもの)。
セグロクマタカの melanoleucus は英名と同じ意味。高野 (1973) のチリーワシは分布を表したものと想像されるがチリは主な分布域から外れている。
最初は Buteo melanoleucus Vieillot, 1816 と記述 (参考) されたがワシノスリが Spizaetus melanoleucus Vieillot, 1819 と記述されていて、一時期両種が Buteo 属とされた時に学名が一致してしまう問題が生じた。
そのため 20 世紀半ばにはセグロクマタカを Buteo fuscescens と呼んでいたことがあったが
[Wetmore (1956) A check-list of the fossil and prehistoric birds of North America and the West Indies. Smithsonian Miscellaneous Collections らしい p. 42 に改名したことが記されている]、セグロクマタカの方に先に使われた種小名であったためこの扱いは誤りで後に正された。
これにも別の問題がかかわっており、Spizaetus fuscescens Vieillot, 1819 (参考) と命名されたものを使っていたがこれは Vieillot がセグロクマタカの若鳥を別種と考え別の学名を与えてしまったもの。
fuscus は非常に頻繁に用いられる種小名なのであえて少し形を変えたものを付けたと思われるが、それでも別の人が同じようなことを考えて同じ種小名になってしまったものらしい。
現在は通常別属に置かれて当初の種小名に戻されている: Geranoaetus melanoleucus と Spizaetus melanoleucus なので衝突しないが、(今後まずないだろうが) 分類学者の捉え方次第で同属で取り扱うことがあれば種小名を変える問題が復活することもあり得る
(wikipedia 英語版より。Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816) にさらに説明がある。1963 年に規約が改定され、1961 年以前に同名となって改名されたものは同名が使われていなければ永久に無効とはしないとのこと。現在は別属にあるのでどちらも有効となる)。
アカクロクマタカの isidori はフランスの動物学者 Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire にちなむ。Isidor's Eagle の英語別名がある。
アカエリクマタカの ornatus は「着飾った」の意味。キマユムシクイの種小名と逆の意味。この属のタイプ種でもあり、英名では同意味 (非常に凝った、華美な。同系語に adorn がある) のよい名前が与えられている。種小名の意味も考えると和名はもう少し凝って欲しかった。ornatus/ornata の種小名を持つ他の鳥も和名は地味なので日本の鳥類学者はこのような訳語をあまり好まなかったのかも知れない。
Falco ornatus Daudin, 1800 (原記載) でこの当時のフランス語名では autour huppe (冠のあるオオタカ) または aigle moyen de la Guiane (ギアナの普通のワシ)。
Restrepo-Cardona et al. (2020) Human-raptor conflict in rural settlements of Colombia によれば南米コロンビアでニワトリに被害を与えるとして迫害されているとのこと。
アカハラクマタカの属名の Lophotriorchis は lophos 冠 triorkhes タカ; triorchis についてはハチクマの備考参照 (Gk)。
kienerii はフランスの動物学者 Louis-Charles Kiener にちなむ。
容貌は Hieraaetus 属にも似ていてこちらに置かれることもあった。あるいは Aquila 属に置かれることもあった (wikipedia 英語版)。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば Stresemann (1926) が ヒメクマタカ [高野 (1973) ではケアシクマタカ] Hieraaetus pennatus Booted Eagle の亜種としたが、趾やふしょの長さが全く違うと記している。
現代的な分子系統樹では Lophotriorchis 属以降をすべて Aquila 属としない限り単系統にならないので、おそらくそれでは分類が少し荒すぎることで別属になっているのであろう。
これらをもし Aquila 属にまとめれば Clanga 属 (カラフトワシなど) も Aquila 属となる日本産の種だけ見れば従来の扱いと同じとなる。
分岐年代もそこそこ古く、途中にゴマバラワシやエボシクマタカのようにいかにも別属に分けたい種類があるので現在のような分類になっているのであろう。wikipedia 英語版の解説では形態や生態に明らかな違いがあるため Aquila 属にまとめないとのこと。
その次にゴマバラワシ属 Polemaetus (1種) が分岐する。
属名の由来は polemos 戦い、戦争 aetos ワシ (Gk)。英名もこれに由来している。
bellicosus も 闘争的な < belli 戦争。こちらはラテン語。
名前の通り世界で最も強力なワシの一つ。
エボシクマタカ属 Lophaetus 以降は単系統をなすが、エボシクマタカ属 (1種) が最初の分枝。属名は lophos 冠 aetos ワシ (Gk) で、アカハラクマタカの属名と大変紛らわしいので注意 (要するにカンムリワシとかカンムリダカのような名前が至るところに出てくる)。
外見は非常に特徴的で crested eagle で検索するとこの種が圧倒的に多く出てくる。Crested Eagle の英名を持つより知名度の低いヒメオウギワシが別にあるので要注意。
occipitalis も後頭部の意味なので冠羽がよほど目立つのでこの学名になったのだろう。
アフリカの代表的猛禽類として写真やイラストなどでもよく見かける。
エボシクマタカ属 Lophaetus (1種)、カザノワシ属 Ictinaetus (1種)、カラフトワシ属 Clanga で単系統をなす。これら3属は1属にまとめてしまっても構わない関係にあるが (遺伝的距離は後のヒメクマタカ属と同程度である)、それぞれに特徴があるため別属としているのであろう。
まとめる場合には Lophaetus 属となるがこの分類はまだ使われていないようである。
この系統はなぜか全ゲノム解析がほとんど行われていないが、既存遺伝子情報で系統樹はよく描かれているようである。
これを見るとカラフトワシ属の位置がよくわかるが、Aquila 属からはかなり離れていて、本格的なイヌワシ類の前段階にあたる。
アカエリクマタカ属 Spizaetus から始まるイヌワシグループをタカ全体類に例えればカラフトワシは例えばハチクマのような位置になる。
カザノワシの属名は iktin, iktinos トビ aetos ワシ (Gk)。トビ類のように浮くように飛ぶことから。malaiensis はマレーシアから。カザノワシの名称由来は別項目とした。
インドワシの hastata は (葉などが) ほこ状の。
アシナガワシの pomarina は北海の地名 (Pomerania。犬の品種名となっている。ドイツ語で Pommern) で現在はポーランドとドイツの間。Aquila Pomarina Brehm, 1831 (原記載) にドイツ語名 pommersche Schreiadler で Er libt in den grossen pommerschen Waldern で Pomerania の大きな森に生息するとの記述からこの語義で間違いなさそう。
Pommern の語源はスラブ祖語 *po mori (海のそば)。ロシア語などを知っているとなるほどとそのまま理解できる名称。
この Brehm (1831) の記述では Unedle Adler Aquilae ignobiles (p. 24) "高貴でないワシ" の仲間に現在ソウゲンワシやカラフトワシに対応するものとともに含めていた (言いたいことはよくわかる気がする)。
共通の綴りとなる #トウゾクカモメの種小名では pomarinus は鼻孔の覆われたと解釈されており語源が異なっている。
アシナガワシはかつてはインドワシと同種とされた。これらの spotted eagle の英名は若鳥の飛翔時に翼に白斑が見えることが由来とのこと。ロシア名ではこれら spotted eagle は podorlik < pod- (英語 sub- に相当) + orel ワシ + 接尾語で「少し小さい (または劣った) ワシ」の意味。「亜ワシ」や「準ワシ」のように訳してもよさそうな語感。
アシナガワシはほぼ確実に兄弟殺しが起きる (obligate siblicide) ことで有名 (#イヌワシの備考 [兄弟殺し] を参照)。
これら "spotted eagles" の祖先はおそらくアフガニスタン周辺に生息していたものが氷河期で北系統と南系統 (インドワシ) に分かれ、北系統が 200 万年前ぐらいに東系統 (カラフトワシ) と西系統 (アシナガワシ) に分かれたものと推測される。系統が近いため現在でも交雑がある (wikipedia 英語版より)。
アシナガワシは森林性の種類とのこと。
ヒメクマタカ属 Hieraaetus は属とされていることから明らかであるが単系統をなす。名前の通り小型種中心であるが、その中に絶滅したニュージーランドの巨大猛禽のハーストイーグルが含まれていることが注目に値する。
ハーストイーグルは関心のある方も多いと思われるので項目を別にした。
Catanach et al. (2024) では Hieraaetus 属を Aquila 属の前に置いているが分岐年代はほぼ同じでどちらを先にしてもよい誤差の範囲。たとえば Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では Aquila 属の方を先にしている。
最も進化が進んだように思われて種数の多いグループを最後にすると落ち着きがよいので Catanach et al. (2024) では Aquila 属の方を後にしているかも知れない。
ヒメクマタカ属 Hieraaetus を イヌワシ属 Aquila に統合しても単系統となり、Hieraaetus 属を Aquila 属に改名する提案がある。
たとえば英国の British Ornithological Union (BOU) は 2005 年にヒメクマタカを Aquila に移したが海外の種については変えなかったとのこと。
ヒメクマタカが Hieraaetus 属のタイプ種であるため、この1種だけを移動すると他の種の属名を変える必要が出てきてしまう。BOU は 2014 年に元に戻したとのこと (wikipedia 英語版)。
Christidis and Boles (2008) は Hieraaetus 属、Aquila 属をそれぞれ単系統にすることを諦めて一部の種のみ移動とした。
Clements Checklist は 2001-2009 年の間 Hieraaetus 属全体を Aquila 属に入れる扱いにしていたが元に戻したとのこと (wikipedia 英語版)。
かつてこの属に含まれていた種はモモジロクマタカ、ボネリークマタカ (いずれも現在 Aquila 属。色合いからは過去の分類はやむを得ない点があったと思われるが分子系統解析により移された)、アカハラクマタカ (単独の Lophotriorchis 属、こちらは大きく違っていた)。
The Peregrine Fund は Hieraaetus 属全体を Aquila 属に入れる立場をとっている。
Debus et al. (2007) Breeding Biology and Diet of the Little Eagle Hieraaetus morphnoides in the New England Region of New South Wales。
にアカヒメクマタカを Hieraaetus 属とするか Aquila 属とするかに関連して
Hieraaetus 属と Aquila 属を分離する根拠を挙げている。Hieraaetus 属は小型で羽色に二形 (dimorphism) がありサイズの二形 (性的とは書いていないがその意味だろう) も著しい。音楽的な笛のような声を出す。Aquila 属は大型で冠羽がなく二形の違いが大きくない。音声も "yelp" あるいは吠えるような声。
このような観点で捉えれば Hieraaetus 属はよりまとまったグループをなすとしている。ソウゲンワシ類も独特の声を持っており、タカ類の分類において声の系統的違いは結構よい指標になるかも知れない。
Hieraaetus 属の中でヒメイヌワシは一番最初に分岐したものでアカヒメクマタカのグループ4種 (ハーストイーグルを含む) からは少し離れている。Aquila 属で記載され長く Aquila 属とされていたが遺伝系統解析の結果 Hieraaetus 属に移されたもの。
特にアフリカのリストではこの変更を受け入れず Aquila 属のまま取り扱っていたものがあるが、前述のような Hieraaetus 属と Aquila 属を合体させる意味ではなく、Hieraaetus 属を認めながらヒメイヌワシをそちらに移動することに抵抗があったらしい。
この種は小型にもかかわらずクラッチサイズが通常1卵で人工操作実験で2羽を巣立たせることができなかったことが示されている (#イヌワシの備考 [兄弟殺し] を参照)。
主に鳥を狩る種類とのこと。種小名と英名はスウェーデンの博物学者 Johan August Wahlberg にちなむ。
シロハラクマタカの学名はかつて Hieraaetus dubius であったが、これはヒメクマタカを指していたものとされ改名された。この種類もヒメイヌワシに次いでアカヒメクマタカのグループ4種から少し離れている。種小名と英名の由来は南アフリカの鳥類学者 Thomas Ayres にちなむ。
この2種は写真を見ていただければなぜそのような名前になったのか理解しやすい。
コビトクマタカは 1900 年に Anton Reichenow により記述され、アカヒメクマタカ (和名から印象が浮かびにくいが英名の Little Eagle を考えれば小型種同士を亜種関係にしたことが理解しやすい) の亜種とされている期間が長かった。
Gjershaug (2009) Taxonomy and distribution of the Pygmy Eagle Aquila (Hieraaetus) weiskei (Accipitriformes: Accipitridae)
により別種とされた。英名の Pygmy Eagle は世界最小のワシであることからこの著者が提案したもの。
この論文の fig. 4 にヒメクマタカグループの世界分布を示している。
ヒメクマタカはアフリカ、インド、東南アジアの一部で越冬し、その延長としてニューギニアに分布したものがコビトクマタカ、オーストラリアがアカヒメクマタカ、そして絶滅したニュージランドのハーストイーグルとなったと考えられる。
Catanach et al. (2024) の系統樹でもこの4種は Hieraaetus 属の中でもまとまりがよく、近年種分化を遂げたと考えられる。
#カンムリワシの備考にあるようにオーストラリアにはかつて先に分岐した系統の大型猛禽類が複数種存在していたことがわかっており、アカヒメクマタカの進出したころにはそれら大型種との競争もあってニュージランドのように大型化しなかったのかも知れない (この部分は私見)。
イヌワシ属 Aquila は主に2系統に分かれ、ソウゲンワシの系統とイヌワシの系統、そして後者の最初の分枝にあたる (やや遺伝的距離のある) アフリカクマタカが途中に位置する。
ソウゲンワシの系統はよくまとまった (分岐年代が若い) 単系統をなす。Aquila 属の中でも特に草原 (砂地のような半乾燥地域) の拡大に適応したグループと言ってよいだろう。
Gaudin "List of the birds of the world" はこの系統を Psammoaetus 属 (psammos 砂 aetos ワシ Gk) としている。IOC 他では用いられていないが系統をまとめる概念としては役に立ちそうである。和名を与えるならばソウゲンワシ属でよいだろう。
{アフリカクマタカ + イヌワシの系統} で単系統をなす。
イヌワシの系統だけでも単系統となるため、Gaudin "List of the birds of the world" はアフリカクマタカ単独で Cassinaetus 属 (Cassin + aetus ワシ Gk) としている。
この付近の種は全ゲノムのドラフトが得られているものが多く、この系統樹は信頼度が高い。
ソウゲンワシやアフリカソウゲンワシの英名の由来については#ソウゲンワシ備考に。
#イヌワシの備考でも現れるが、容貌が最も似ているイヌワシ、コシジロイヌワシ、(あまり知られていないが) モルッカイヌワシ、オナガイヌワシだけでまとまったグループを作るわけではなく、ボネリークマタカ、モモジロクマタカと色彩や生息環境が必ずしも似ていない種類が同じ系統に含まれることは興味深い。
これもイヌワシの備考で出てくるが、Aquila 属で英名に Hawk-Eagle を持つ種を Eagle と呼ぶ提案が出ている [Lerner et al. (2016) Phylogeny and new taxonomy of the Booted Eagles (Accipitriformes: Aquilinae)]。
この項目で扱ったイヌワシ亜科 Aquilinae (の後半) の分類は Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) も Catanach et al. (2024) も順序が入れ替わる程度で本質的に差がない。種の概念にあまり曖昧なところがなく分子系統データもよく得られているためであろう。
ニシカタシロワシとカタシロワシを同種と扱うかどうかの問題はあるが、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) も特に問題視していないようである。保全の視点からは明らかに別種扱いが適当であろう。
Kessler (1851, 参考文献参照) ではヒメクマタカが現在と同じ種小名で Aquila 属に含まれている。生活様式はヨーロッパハチクマに大変似ているとあり興味深い。
[カザノワシ]
カザノワシの記載時学名は Falco malayensis Temminck, 1822 (原記載) 基産地 Indian Archipelago; restricted to Java by Swann, 1922, Synop. Accipitres, ed. 2, p. 115 (Avibase より。ジャワ島に限定)。
フランス語名 Aigle Malais (マレーのワシ) で Reinw. が用いた学名 (原記載にはなっていない) がすでにあったためそのまま用いている。色が黒っぽいことは書かれているが、英名の Black Eagle の直接語源とはあまり結びつかないよう。
おそらく当時 Black Eagle (黒いワシはいくらもあるので) と一般的に呼ばれていた名称があって Asian Black Eagle, Indian Black Eagle のような別名を通して生き残ったのか。
ロシア語名が面白く orel-yajtseed (卵を食べるワシ)。カザノワシは巣ごとひなや卵を持ち去って捕食することがある (#ハチクマ備考の [カンムリカッコウハヤブサの生態とハチクマとの比較] で Jollie (1976, 1977) の記述を紹介、#クロハゲワシ備考 [変わった餌の捕り方をする猛禽類] にも登場する。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) にも鳥の巣を運ぶイラストが採用されており、古くからよく知られていた習性らしいことがわかる。
巣ごと持ち去って捕食するのは効率がよいことはツバメトビで議論されている (#ハチクマ備考の [ハチクマ亜科の他種]。wikipedia 日本語版にも記述があるが英語版の訳と思われる)。ロシア語名は生態をふまえた命名と言える。
和名は「風野鷲」と記されるが、人名 (風野鐵吉。台南州立教育博物館長で新種を記載) 由来だった: 風野鷲 (RRGT 台湾猛禽研究会 2018)。当時の日本領内 (統治下) では台湾で最初に記録された。風野氏が台湾が発見して報告した鳥の報文の中には含まれていなかった。同定できなかったものと思われるとのこと。
台湾の博物館を訪れた山階芳磨氏が判定しカザノワシと命名して 1940 年に和名を発表。西洋では発見者の名前を冠することは普通だったが民間人の名前を冠した和名は珍しいと説明されている。
台湾の留鳥では最後に発見されたものとのこと (近年のカタグロトビは除いている)。
第二次世界大戦中の 1945.3.1 に激しい戦火でこの博物館も破壊され風野氏もこの日に死亡したとのこと。
終戦後台湾で風野鷲の名称が使われた期間はわずか数年で、日本の目録からも台湾の名称からも風の中のワシのごとく消え去ったとのこと。そして 林の(周 + 鳥 で鷲に相当する漢字) の名称 (林のワシ) に変更され、現在も台湾の山の上を飛び続けているとのこと。
戦火に見舞われる前の 1940 年博物館を訪れた少年があって風野氏とも言葉を交わしたという。将来もっと大きな博物館を建てたいとの夢を持っていたとのこと。2015 年にその夢が実現し台南市に奇美博物館が開館したとのこと。
ブッポウソウ問題が解決したとされるのは 1935 年とされるので、この当時の台湾での仏法僧発見 (1928) というのはどちらの種のことだろうか。台湾の現在の鳥名では仏法僧はブッポウソウを指している。
(林文宏 2016) によれば台湾でも知られておらず現地名もなかったとのこと。
wikipedia 日本語版に名称や風野氏に関する日本語情報がある。
wikipedia 英語版ではインドの Soliga people のカザノワシの地方名 Kaana Kattale があり、黒い色で森林に住むことを表現しているとのこと。Kattale Kaanu によれば地名で Katthale Kaanu は Dark Forest を意味するとのこと。
コシジロイヌワシ Aquila verreauxii の方の現地名 black eagle が残らなかった理由までは解明できなかったが、コシジロイヌワシを指すと考えられる "黒いワシ" の学名は存在した。Aquila nigra Jameson, 1835 (参考 1) 基産地は南アメリカとなっているがアフリカのこととのこと (南アメリカとアフリカの区別がついていなかったよう)。
参考 2 でも基産地が間違っているのではと指摘がある。Aquila verreauxi Lesson, 1831 の方が早かったためコシジロイヌワシの学名として使われている。人名の付く学名となったためわざわざ "黒いワシ" を使うまでもなく、この英名はカザノワシに譲ったのかも。
なおクロコシジロイヌワシの名称が使われていたこともあった [「世界の鳥 1」(小学館 1985) p. 138 など]。"クロイヌワシ" の名前でもよかったのではと思えるがこの用例も実際に見つけることができた。
しかし黒いイヌワシ類は他にもあるので、より記述的に "コシジロ" を補ったら今度は長くなりすぎて短縮されたものだろうか。
古い時代はコイヌワシ、イヌワシ、オオイヌワシ、クロイヌワシ と短い名称が一部の種に付けられていて、当時の動物名としていかにも簡素で好まれたのかも知れない。
"国内産" の範囲が広がってカラフトワシの名称が使われるようになり、名称に一貫性が失われるようになり、さらにもっと広い範囲の種に名前を付ける必要が生じると記述的な名前を用いる必要が生じてきたものだろう。
[ハーストイーグル (Haast's Eagle)]
人間が入植する前の 700 年ぐらい前までニュージーランドには鳥類 (陸上哺乳類はコウモリ類のみ) を中心とした動物相があり、その頂点に位置していた。
体重は 10-14 kg と推定され、現存最大のオウギワシより 30-40% 重く羽ばたき飛行の限界に近かったと考えられている。
絶滅した飛べない鳥モア (最大 200-230 kg にも達する) を捕食していた証拠がある。マオリ族が hokioi, pouakai (poukai) と呼んでいた鳥と推定されており、伝承記録とこの種と考えられる壁画のみが残っている。現在の復元図の色はこの伝承に基づいている。Julius von Haast が 1871 年に死体骨格に基づき Harpagornis moorei の学名で記載した。
Haast は比較できる猛禽類の骨格を4体しか持っておらず、最初はチュウヒ類に似ていると考えていたがハヤブサとも似た点があるとした。後の研究者は海ワシやイヌワシ類に近いとし、特にアフリカから東南アジアに分布するイヌワシ類に近いと考えた。事実オーストラリアにはオナガイヌワシが現存する。
イヌワシ類であったが森林に適応した環境で異なる色彩になったと考えられた。
11000 年前の温暖化でニュージーランド西海岸は湿潤化が進み、一部のモアの種は絶滅しハーストイーグルも乾燥した東部に逃れたと想像される。わずかに残った生息地でポリネシア人が火を使って森林を破壊し獲物を絶やしたことでハーストイーグルも最終的に消え去ったと考えられる。
ハーストイーグルはマオリ族の集合知にも影を残すぐらい長期間生存していたのかも知れない
[Holdaway (1989) Terror of the Forest New Zealand Geographic Issue 4 から抜粋]。
著者の Richard Holdaway はタカ類の系統研究で学位を得た研究者で古生物、放射性年代測定、渡り鳥のトラッキングなどで活躍している。
Bunceet al. (2005) Ancient DNA Provides New Insights into the Evolutionary History of New Zealand's Extinct Giant Eagle
(Holdaway も最終著者として含まれる) で DNA 解析の結果、通常は小型の Hieraaetus属に属することがわかり世界を驚かせた。近傍の現存種は Holdaway (1989) が想像したオナガイヌワシではなく非常に小型のアカヒメクマタカ (Little Eagle) であった
[後で聞いた話によると、アカヒメクマタカの骨格標本は比較的近くの国外にあったにもかかわらず Holdaway の時にはアクセスが許されなかったとのこと。そのためイヌワシ類が優先的に検討されたとのこと]
島で短期間で巨大化が可能 (island gigantism) であることが示された。
参考までに island syndrome について Michal et al. (2023) The island syndrome in birds の新しいレビューがある。
Holdaway の学位論文 (1991) のテーマは実はハーストイーグルの分類学的位置づけに関するもので [Systematics and Paleobiology of Haast's Eagle (Harpagornis moorei)]、
他のタカ類の骨格とも比較する必要があり広く調べられている。表題から想像する以上に全タカ類の系統分類が扱われている。骨学は独学でマスターしたとのこと。当時の計算機環境を考えると系統推定は想像以上に大変な仕事だったのではないだろうか [聞いてみるとやはりパソコンでは当然無理で大型計算機 (当時メインフレームと呼ばれていたもの) でも1時間以上かかったとのこと]。
188 の骨格形質をもとに描いた 44 属のタカ類の系統樹が出ている。現代の分子系統樹と細かい点で違う点もあるが主な特徴はかなりよく一致している。
また Appendix 5.2 に形質マトリックスも示されており、役に立つ方にとっては大変有益な情報源であろう。ただしこの結果はこの学位論文以外では発表されなかった模様で、通常の学術論文のように引用される機会が少なくなってしまったよう。タカ類の系統改訂が分子遺伝学が取り入れられるまであまり行われなかった遠因にもなっているように思われる。
同属2種めの Harpagornis assimilis Haast, 1874 として記載されたものはこの種のオスであろう (シノニムとなる)。Holdaway (1989) にも記述初期の同定状況が出ているので読み物としてはこちらの方が面白いかも知れない。
この学位論文ではハーストイーグルは Aquila 属に隣接する場所に置いており、Oliver (1945, 1955) や Duff (1949) が想定したようにオナガイヌワシに近いとした。
Brathwaite (1986) が提唱した Spizaetus 属に属するとの仮説は東南アジアの Spizaetus 属 (現 Nisaetus 属) の情報が不足していて否定も肯定もできない。しかし南米の Spizaetus 属はハーストイーグルに隣接する枝になっている。
後から聞いた話だが、Holdaway はこの研究で広義 Spizaetus に近い可能性にも気づいていながら現在の分類に思い至らなかったことを残念がっていた
van Heteren et al. (2021) New Zealand's extinct giant raptor (Hieraaetus moorei) killed like an eagle, ate like a condor
に嘴、頭骨、爪を現代の猛禽類と比較して生活様式を探る研究がある。爪は現代の協力なワシに似ているが頭部や嘴はハゲワシと類似性がある。マオリの壁画の絵も頭部や首に羽毛がなかったことを示唆するのでは? との解釈がある。
[紛争と野生動物]
ロシアとウクライナの戦争によってカラフトワシが渡りルートを変えたとの論文
Russell et al. (2024) Active European warzone impacts raptor migration
があり、一般受けするニュースであったためいろいろなところで取り上げられているが、統計的にどれほど物が言えるのかは論文を見て判断していただいた方がよいだろう。
海外でも取り上げられる例をみかけるが「もうたくさん」の反応が一般的の模様。あまり話題になっていない。またこのニュースはロシアにとって都合が悪く取り上げないだろうとの推測も当たっておらず普通に報道されていた。
紛争と野生動物についてはウクライナよりも長期の紛争の続いているアフリカの方が深刻で、特に哺乳類への影響が大きいとのと。ブラジル、ベネズエラ、ニジェール、アンゴラ、カンボジアが紹介されている。
カンボジアでは武器を手にする人が増えたため野生動物の違法取引が増えたとのこと。
Conservation policies must address an overlooked issue: how war affects the environment (Weir et al. Nature comment 2024.10.16)。
このコメントにウクライナ東部の地図が出ておりどの部分の森林が焼けたかなどの客観的データを見ることができる。著者の保護への関心は大型哺乳類に向いているかも知れないが上記の Russell et al. (2024) の研究は紹介されていない。
-
カタシロワシ
- 学名:Aquila heliaca (アクゥィラ ヘーリアカ) 太陽神ヘーリオスのワシ
- 属名:aquila (f) ワシ
- 種小名:heliaca (adj) 太陽神ヘーリオスの (heliacus)
- 英名:Imperial Eagle、IOC: Eastern Imperial Eagle
- 備考:
aquila は#イヌワシ参照。
heliaca の読みはわからないが、語源のギリシャ語 heliakos は冒頭が長母音で太陽を表す helios も長音なので長音を採用した。冒頭を伸ばすかどうかにかかわらず綴りからアクセントは -i- と考えられる (ヘーリアカ)。
太陽に由来する helium もラテン語 (古典式発音) では冒頭が長母音となっている。
記載時学名 Aquila heliaca de Savigny, 1809 (原記載) 基産地 Upper Egypt。フランス語名 L'Aigle de Thebes で Thebes (テーベ) はエジプトのナイル川沿いの地中海から 800 km 南、新王国時代のエジプトの首都 (wikipedia 日本語版より)。エジプト由来で太陽神を用いたらしい。
Kessler (1851, 参考文献参照) では Aquila imperialis Bechstein, 1812 の学名があってこちらが使われていた。こちらは基産地がドイツで、英語の Imperial Eagle もこの当時の学名そのままで、由来と考えると理解しやすい。The Birds of Europe (1837) にこの学名と英名で登場している (もちろん分離前の概念・学名)。
OED によれば英名の語源はラテン名からとのことで、初期には Aquila imperialis はオウギワシと混同され南米の種として紹介された (Shaw 1809) 現在は用例が廃れたが第一語義となっている。Latham (1821) "General History of Birds" でエジプトやアビシニアに生息、チロル地方と正しく指すようになっていた。
Hartert (1910-1922) では p. 1092。ドイツ語名も Kaiseradler または Koenigadler と英名同様。
分離後は単形種。
主に東欧からロシア東部に分布するが、極東や中国東北部は通常の分布域に含まれない。
和名はカタジロワシと記載されることもあった。
[和名の由来? など]
和名の由来とも考えられる学名 Aquila leucolena Dresser, 1873 (参考) があり、leuco 白 lena < olene 肘 (Gk)。記載。
Hartert (1910-1922) p. 1094 では現在分離後のニシカタシロワシ (イベリアカタシロワシ、スペインカタシロワシ) の方のシノニムとしていた。上記 Richmond index の記述とは少し違ってスペインと記述されている。
実際の記載では Richmond index の東ヨーロッパからインドの記述は多分誤り。スペインとモロッコの地中海沿岸のみで知られており、東ヨーロッパからインドのものとは大きく異なる。当時のドイツの鳥類学者は Aquila adalberti Brehm (現在ニシカタシロワシに用いられる学名) と Aquila naevoides Cuvier を同一とみなしていて、その場合は (シノニムとなって) 学名がなくなるため新たに提案した学名だった。
英名は White-shouldered Imperial Eagle で確かに同種時代は "カタジロワシ" と訳されても不思議でない。オオワシの名前にふさわしいと思ってしまう名前だが由来はここにあった。ニシカタシロワシを指すとすれば確かに肩が白い Spanish Eagle (Marcos Lacasa 2025)。
カタシロワシでは白い部分の位置が少し違い翼角まで白くないよう Imperial Eagle (MKBP Mahapatra 2025)。
[系統]
Aquila 属であるが、イヌワシ類とは系統的には少し離れた中型 Aquila 属のグループに属する。
イベリア半島で絶滅の恐れのあるニシカタシロワシ (イベリアカタシロワシ、スペインカタシロワシ) Aquila adalberti、アフリカソウゲンワシまたはサメイロイヌワシ Aquila rapax、ソウゲンワシ Aquila nipalensis と共通したグループを作る。
ソウゲンワシやサメイロイヌワシは動物園で飼育しているところも多く、イヌワシ類との見かけの印象や声の違いもわかりやすいだろう。ソウゲンワシは越冬地ではアリが好みで、アリ塚を壊して食べるなどあまりイヌワシ類らしくない捕食行動も行う [ワトソン「イヌワシの生態と保全」(2006)。原著 1997 年]。
Eagles feasting on termites (Liaan Lategan 2025) に南アフリカで撮影された興味深い映像がある。ビデオ部分は少なくスナップショットが中心。解説も参照。
全部で数百のキバシトビ Milvus aegyptius Yellow-billed Kite、Brown Eagle というのはヒメイヌワシ [高野 (1973) ではコイヌワシ] Hieraaetus wahlbergi Wahlberg's Eagle のことか、アシナガワシ Clanga pomarina Lesser Spotted Eagle とアフリカソウゲンワシがアリ塚を壊して食べていたとのこと。
典型的なワシとされる Aquila 属または類似属とはいえ豊富な資源を求めて昆虫食にもなる。ハチクマの食性が例外的というわけでもない。
イベリアカタシロワシはカタシロワシが一時は広く分布していたものの遺存種 (#ゴビズキンカモメの備考参照)とも考えられている。
ニシカタシロワシ (イベリアカタシロワシ、スペインカタシロワシ) とアカタシロワシが同種かどうかは以前より議論の対象になっているが近年は別種とするのが一般的。IOC 英名もそれに従っている。
[ロシア名と関連する学名]
カタシロワシのロシア名 mogil'nik は「墓守人」の名前で、墓の盛り土によくとまっているためこの名が付いたものだが、他の多くのヨーロッパ言語では高貴な名前が付いているのでもっとよい名前 (例えば太陽のワシ、皇帝のワシ) への改名運動も行われている。カタシロワシの巣のライブ中継も行われており、「太陽のワシ」の名前が使われている。
Belik and Galushin (2019) (Aquila 属のいくつかのワシ類の歴史的名称について) によれば
Falco mogilnik Gmelin, 1788 が記載したものはカタシロワシではなくソウゲンワシを指していると考える。mogil'nik がカタシロワシのロシア語通称名なのでそれに従っていると解釈され、研究者によってはソウゲンワシとの区別が曖昧だったために無効な学名とみなされた。
もしソウゲンワシを指していることが確認できればこれが最初の学名 [Aquila mogilnik (Gmelin, 1788)] となる可能性がある。
ただし ICZN 23.9.1 の規則によればこのことが確認されても学名が変わらないとの判断だが、無効な学名 (nomen dubium) から nomen oblitum (忘れられた学名) に変更することは検討に値するとのこと。
測定値は出ているものの、Gmelin (1771) のイラストから何者かを判定するのは確かに至難だろう。
ここにも不適切なロシア名の改名の動きが触れられているが公式判断を待つとのこと。ドイツ語で猛禽類は Raubvoegel (略奪する鳥) だったが 20 世紀前半に Greifvoegel (掴む鳥) と改名された経緯も紹介されている。
[ソアリング中の wing tuck]
ソアリング中の大型猛禽類でしばしば軽く翼を持ち上げる行動が見られる (wing tuck)。ソウゲンワシを使って調べた研究:
Reynolds et al. (2014) Wing tucks are a response to atmospheric turbulence in the soaring flight of the steppe eagle Aquila nipalensis
が加速度計と地上からの測定を用い、wing tuck の起きる直前に風速が増していることが多く、乱流 (gust 突風) に対応して起きるらしいがどのように安定性を保つかなどの詳細なメカニズムまでは不明。
ソウゲンワシのソアリングについては Gilles et al. (2011) Soaring and manoeuvring flight of a steppe eagle Aquila nipalensis
があって Gilles の学位論文になっているとのこと。
-
イヌワシ
- 学名:Aquila chrysaetos (アクゥィラ クリューサーエトス) 金色のワシ
- 属名:aquila (f) ワシ
- 種小名:chrysaetos (合) 金色のワシ (chrysos 金色の aetos ワシ Gk)
- 英名:Golden Eagle
- 備考:
aquila は -ui- は2重母音ではなく -wi- の音と解釈される。アクセントは冒頭の a にある (アクゥィラ)。aquila を語彙として持つイタリア語でもアクセントは冒頭。
英語の aquila, 形容詞 aquiline もアクセントは通常冒頭で、apple の a と同じ発音になる。
英語圏の話者も学名の Aquila は冒頭にアクセントを置いて読んでいると考えられる。
-aetos は a が長母音でアクセントがある。chry- の y も長母音で上述のような発音で "サー" にアクセントを置くのが原音に近い (クリューサーエトス)。語源のギリシャ語の khrusos, aetos ともに対応する音が長音のため。
広く使われている学名なので英語読みでも実用上は問題ないだろう。
記載時学名 Falco Chrysaetos Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, ed. 2, p. 19 (Linnaeus がスウェーデンに限定)。
Aquila 属は Brisson (1760) が名付けたもの (参考)。Brisson は Genus Aquilinum と与えて属定義をした。
最初の種に Falco fulvus Linn., Falco canadensis Linn. とあってタイプ種はイヌワシとなったのは自然な成り行きだった。
この属新設に伴って、Aquila vulgaris Sprungli, 1784 (参考) "普通のワシ" の意味 も Falco fulvus Linnaeus, 1758 = 現在はイヌワシの基亜種のシノニムとされる の新名として与えられている (#ノスリの備考参照)。
天然記念物 (1965 年 4 月指定)。絶滅危惧 IB 類 (EN)。1972 年 6 月に特殊鳥類に指定。
中西悟堂氏の 1950 年年代の著作によれば当時はまだ狩猟鳥だったらしい。
石川県 (1965 年イヌワシを県鳥に指定) の記録では イヌワシの分布及び生息環境 の県内過去のアンケートがあり、捕獲及び保護例が紹介されている。
全世界の個体数は多く、IUCN 3.1 LC 種。
[英名の由来など]
英名 Golden Eagle の由来はどこにでも書かれているので出所を調べてみることにした。
OED によれば 1600 年代後半にはすでに使われていた英語だそうだが、遡れる用例は Willughby (1676) Ornithologiae libri tres ...
とのこと。ラテン名 Chrysaetos (Aldrovandi) でここに英名の Golden Eagle が示されている。
ラテン語の説明的学名では Aquila fulva seu (または) aurea となっている。
The ornithology of Francis Willughby of Middleton in the county of Warwick, esq (1678) に英訳版がある。
よく言われる後頭部や後頸部の羽毛の色彩はほとんど記述がなく (英訳版で The feathers of the neck are rigid and ferrugineous とある。ラテン語原書も同じ意味)、古くからの Chrysaetos の名前をこの鳥に同定した理由は Ulisse Aldrovandi (1522-1605 はイタリアの博物学者) が述べているとのこと。同じく Pygargus と述べられていたものはイヌワシの尾に白いリングのあるものと同定したとのこと。
イヌワシは襲ってきてとても危険なのでケージに近づき過ぎるのは危ないなど書かれている。
Aldrovandi (1599) Vlyssis Aldrovandi philosophi ac medici Bononiensis historiam naturalem in gymnasio Bononiensi profitentis, Ornithologiae, hoc est, De avibus historiae libri XII ... : cum indice septendecim linguarum copiosissimo
に登場。このページに Chrysaetos Ornithologi 次ページに Chrysaetos Bellonii の図版。
p. 110 に記載。他にもいくつも図版あり。
冒頭だけ見てみるとギリシャ語語源であることはその通りで、quasi auream seu fuluam Aquilam Latine dicas, merito iure appellata fuit, quod colore fit aureo, aut salte ad hunc caeteris propius accedat:
と続いている。ロシア語への機械翻訳で読んでみると、意味は金色または黄褐色 (fuluam = fulvam。英語 tawny などに相当) のワシに近い。この名称は適切で、金色の色彩を帯びていて、少なくとも他のワシよりもより金色に近い。
ということで他のワシよりも黒色が薄くて黄色っぽく見えることが由来のよう (これは Aquila fulva または aurea のラテン名にもに一致する)。他のワシと言えばオジロワシなどなので確かにイヌワシの方が黄色 (褐色) 味が強い。言い換えに fulva(m) を挙げていることから金色と言っても黄褐色を意識していたものと考えられる。
このように見ると Golden Eagle の英名はラテン名 Chrysaetos をそのまま訳したもののように見える。またヨーロッパのイヌワシ (基亜種) の方が北米より色が淡くて黄色みが目出つ。Golden Eagle はヨーロッパ亜種の色彩を基準に付けられた名称と言えるかも知れない。
よく言われる英名の解釈も後付けの可能性が十分ありそう。英語用例が Aldrovandi (1599) 以降に現れることからもラテン名を訳したものが妥当に思える。
OED でも with golden-brown feathers on the back of the head and neck と記述しているが語源は Aldrovandi のラテン語を採用している。
意味もまったくそのままで、二名法成立以前は学名を1単語で示しても十分でこれはその例と言えるだろう。Linnaeus (1758) は二名法で Falco 属として後に Aquila となったが Chrysaetos にすでに Aquila の意味が含まれているので重複していることになる。
それゆえに Falco fulvus Linnaeus, 1758 由来の Aquila fulva の学名の方がしばらく好まれたのかも知れない (#アトリの学名の事例参照)。
シートン・ゴードン「イヌワシの生態」(大原総一郎訳 平凡社 1973、原著 Seton Gordon 1955 年 "The Golden Eagle, King of Birds") 訳書 pp. 19-21 にも従来の博物学者はイヌワシとオジロワシを区別しておらず、Ray や Willughby が 1658 年や 1662 年に英国ウエールズ地方のイヌワシの繁殖地を訪れたことが記されている。Willughby (1676) の記述はこの後に行われたことになり上記年代とも合致する。
aurea の方は aurum (金) 由来だが、学名で色彩を表す場合は#シマアオジなども参照。
fulva の方もインド・ヨーロッパ祖語の *bhlwos < *bhel- (輝く) 由来で意味は近い。同系語 fulgeo (光る、輝く) があり、稲妻の fulgor もこれから派生する (wiktionary)。いずれも語源的に近いと思ってよいだろう。
寿命に関する逸話
これが気になった理由はゴードン「イヌワシの生態」(訳書 pp. 55-56) にイヌワシの寿命が長いことを示す逸話として取り上げられていた個体の名前が FULGOR (稲妻) だったため。
この個体は 1845 年にフランスで撃ち落とされ、金の首輪に CAUCASAS PARTIA: FULGOR NOMEN: BADINSKI DOMINUS MIHI EST; 1750 (故郷はコーカサス、名前は FULGOR、主人は Badinski) と刻まれていて、ゴードンはイヌワシが 95 年以上生きる証拠と考えていた。
FULGOR (稲妻) は行動を指して名付けたのかと思っていたが、上記のような語源関係を考えるとラテン語ではむしろ色彩を指していたのかも知れないと感じた (fulvus / fulva と fulgor は語源的に近い)。例えば "稲妻のように輝くワシ" など。
この話はゴードン氏のお気に入りだったようで、別出典のものもあった (出典は失念)。大原総一郎氏の訳されたものと違う部分を紹介しておくと、When I was looking through an old newspaper-cutting book belonging to a friend, I came across a contemporary account of the shooting of a golden eagle. This bird was shot in France in the year 1845.
とのことでゴードン氏は知人の新聞スクラップブックでこの記事を知ったとのこと。
The inference is that the eagle was used in falconry (as I believe it still is in the Caucasus) and may have been taken from the eyrie and trained for this purpose.
It had travelled far from its native land, but there was nothing in the newspaper report to show that it was old or failing in health.
ゴードン氏は鷹狩り用のイヌワシで巣から手に入れたものだろうと推定 (そのため年齢推定まで行っている)。新聞記事には老齢あるいは弱っていたなどの記述はないと記していた。「イヌワシの生態」にはこれらは出てこない。
古い言い伝えが紹介されていて "Thrice the life of a dog the life of a horse, Thrice the life of a horse the life of a man, Thrice the life of a man the life of a stag, Thrice the life of a stag the life of an eagle, Thrice the life of an eagle the life of an oak."
馬の命は犬の3倍、人の命は馬の3倍、鹿の命は人の3倍、ワシの命は鹿の3倍、樫の木の命はワシの3倍。ワシが古巣を引き継いで新しい個体が同一場所で子育てをするため長生きすると考えられていたのだろう。
この表現で検索すると Hull (1932) The Hawk of Achill or the Legend of the Oldest Animals の民間伝承の記述があった。
"The Golden Eagle, King of Birds" (1955) はゴードン (1886-1977) の著作では晩年のもので表現を少し控えめに修正したのかも知れない。
この話題は英語圏以外でも知られているようで、Pfeffer (1985) "Ptitsa na ruke" (アルマ・アタで出版されたロシア語の鷹狩りの読み物) にも登場するが引用元は示されていない。
大原総一郎氏の訳されたものと同一と思われる出典があった: The Golden Eagle: King of Birds by Seton Gordon (Citadel Press, New York. 1955): p. 35 からの引用 Golden Eagle - Aquila Chrysaetos (過去の Carnivora 2012 のアーカイブから)。
該当部分を紹介しておくと:
In the early part of the nineteenth century, according to reliable contemporary evidence, sportsmen shot a golden eagle in France. Round its neck this bird had a collar of gold. On the collar was engaged the following inscription:
Caucasus Patria: Fulgor Nomen: Badinski Dominus Mihi Est; 1750
This may be translated; "Caucasus my native land, Lightning my name, Badinski my master, 1750." The eagle was shot in 1845, and thus at the time it was killed, far from its home, it had reached the age of 95 years, even if it had been a young bird when the collar had been placed round its neck... I see no reason to doubt this evidence, which was printed in the Aberdeen Free Press in the year 1845. After studying the golden eagle for fifty years and more, I am convinced that the eagle's natural life can be more than a century.
とのことで地方紙の名前は Aberdeen Free Press (1845) だった。大原氏の訳は十分正確だった。
The British Newspaper Archive で記事を一部検索できるが、系列誌に 1844 年 10-11 月に掲載された記事のようでたくさんの新聞に見つかる当時話題の記事だった模様。1951 年にも掲載された記事があった。
もちろん現代の知見からはイヌワシがそれほど生きるとは考えにくく、"Eagles" (John Love 1989 Whittet Books。多分どこかの書店で買ったもの) では、ペットのワシにわざわざ金の首輪を用意したら自分ならば死んだら次の個体に再利用するだろうといかにもそれらしい見解を述べている (p. 81)。
しかしペットのワシに金属製の首輪を付けたら食べ物を飲み込む時にそのうが膨らむと鵜飼いのウ状態になりそうな気もするし、ペリットを吐く時に困るのでは。現実にあまりあり得ないかも。地方紙に掲載されたよくできた作り話だったのではないだろうか。
ドイツ語名の Steinadler (石のワシ) は岩場に住むワシの意味だろう (wiktionary ドイツ語版にも岩場の生息環境を示すとある)。Kaup (1829) がコチョウゲンボウを含む属 Aesalon を提唱した時のドイツ語名は Steinfalke (石または岩のハヤブサまたはタカ) だった (#コチョウゲンボウの備考)。スロバキア語の orol skalny、チェコ語の orel skalni (崖のワシ) は意味が近い。
18 世紀のロシアの文献では "石のワシ" と "黄金のワシ" の両者が見られるそうで、おそらくドイツ語名由来だろうとのこと。後者に対応するドイツ語名は Goldadler (Dement'ev and Gladkov 1951)。
Menzbir や Severtsov の時代には berkut (後述) と khalzan の2つの名前が用いられており後者は成鳥を指していたとのこと。これらの著者が中央アジア由来で berkut などの名前を導入したためドイツ語由来の名称が廃れてしまったのかも。
スロベニア語で planinski orel (山のワシ)。
フランス語名の Aigle d'or は英名と同じ意味。Aigle fauve は Aquila fulva に対応している。いずれもラテン名由来でおかしくない。
ポーランド語は orzel przedni (第一のワシ) など。真のワシ、王のワシの名称は多くの言語で使われている。
セルビア語では suri と呼ばれるそうで Suri (orao) によれば灰色や石の色、暗色などこちらも色彩などが由来のよう。
英名と同じ使い方は意外に少なく (ラテン名をほぼそのまま使える言語で見られる程度)、万国で受け入れられる名前のように思いがちだが英語以外ではあまり普遍的な比喩でないことがわかる。
[亜種]
世界で6亜種が認められている (IOC)。
日本 (および朝鮮半島、半島内の分布はよくわかっていない) 亜種 japonica (日本の) はイヌワシ中最も小型。英名 Japanese Golden Eagle。
一方最大亜種は中央アジアの daphanea。Hodgson (1844) が Aquila daphanea (1898 年に解説された本の説明) と記述したもの。
Hodgson (1844) では "Catalogue of Nipalese Birds, collected between 1824 and 1844" 一覧の中に名前 A.? Daphanea のみ出てくる。
Hodgson (1846) ("Catalogue of the specimens and drawings of mammalia and birds of Nepal and Thibet")
によれば Dapheny of the Nipalese とのこと (The Key to Scientific Names)。語源はこれ以上調べられなかった。
Hartert (1910-1922) p. 1091 に少し解説があり、Hodgson (1844) の学名は無効名 (description がない) で Menzbier (1888-1893) Ornithologie du Turkestan et des pay adjacents I (1888), p. 75 が初記載 "Haute-Asie" ("アジアの屋根" の意味で生息地のこと?)。原文も見られないのでこれ以上の判断はできない。
英語でブーツにたとえられる脚の羽毛はドイツ語では Hosen と呼ぶらしい。非常に長くて密集しているとのこと。
Taczanowski (Faune Orn. Siberie orient. p. 10) はカムチャツカの個体のメスの翼長は 73 cm でこの亜種と考えたとのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) では (Hartert の判断に従えば) 正しく Menzbier (1888) が記載者になっており、記載時学名 Aquila fulva daphanea だったとのこと。
しかし Avibase では Severtsov (1888) となっている (記載) これは中身を読むことができて (Menzbier も Severtsov もフランス語で記載)、
Aquila daphanese, Hodgson を用いている (学名表記を用いなかったのは "Hodgson の Aquila daphanese" の意味で学名を指したものでないと考えられるため。当時はイヌワシ他亜種と別種扱い)。ここに (p. 195) l'aigle de la Haute-Asie があり、やはり "アジアの屋根のワシ" の意味らしい。
しかし daphanese の表現を見ると地名のような気もしてきた。
Avibase の原記載としてリンクされているこの出版物 (Nouveaux memoires de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou モスクワの帝国博物学協会紀要ぐらいの意味) は 1898 年に出版されたものだが、Dement'ev and Gladkov (1951) を見ると出版年は 1888 年のよう。
前文にはもっと早い年を示した表紙ページがあるので再掲して出版されたものを現在見ることができる、ということだろうか。
Review: Menzbier's Ornithology of Turkestan (Auk 1890 年の書評 by J.A.A.) によれば、この本はこの地域を 21 年探検した Severtsov (Sewertzow) の膨大な標本に基づくもので、不幸にも途中で亡くなってしまい (Nikolai Severtsov 1827-1885)、Menzbier に後を託したものとのこと。
Menzbier の wikipedia ドイツ語版によれば Severtsov の仕事を死後に多数世に出したとあり、1888 年の出版物もその一環かも知れない。Menzbier は特に猛禽類の専門家だったとのこと。我々も学名などに彼の名をしばしば見かける (#ケアシノスリ参照。オオソリハシシギの亜種にもある)。
Menzbier の生涯について Ognev (1946, 2025 再掲) Mikhail Alexandrovich Menzbier (1855-1935) (pp. 2133-2145) が見られる。
Menzbier 自身による 1895 年のロシアの鳥の書物があり、ここには "daphanea" は出てこない (ネパールが基産地なのでロシアに分布すると考えていなかったかも) が Ornithologie du Turkestan... の著者を Sewertz. et Menzb. と表記しており Menzbier は共著の扱いと考えていた模様。
Menzbier 自身による猛禽類の本が後年出版されているが、現在オンラインで見ることができるものはハヤブサ類の巻のみでイヌワシ類の扱いを調べることができないのが惜しいところ。
Aquila daphanea のカードによれば Menzbir の文献が記されていて、同名の書物は現在見ることができたが出版年は 1882 と記載されている。記載されているページはカラフトワシ類の記述の周辺だが同書のイヌワシの項目にも daphanea を見つけることはできなかった。
この文献は Berez. + Bianchi (1891) の文献に引用されているとのことだが引用が間違っている可能性が高いと推定した。
Dement'ev and Gladkov は両方の文献を調べていると考えられるので彼らの判断の方が正しいかも知れない。この判定によればイヌワシのユーラシアの主要亜種の中で daphanea のみは記載者 Menzbier のよう。あるいはその後記載者を決める規則などによって Severtsov と判定されるようになったのかも知れない (初記載の文献の判断が一定していない可能性もある)。
いずれにしても Severtsov の記述では daphanese/daphanea の意味までは載っていないよう。
HBWAlive Key; mission accomplished or mission impossible? によれば語源不明の学名の一つにリストされている。
Dapheny (nameslook) によれば人名では Pioneer 先駆者、Sacrificer 犠牲者/いけにえを捧げる祭祀、Respectability 立派さ、尊敬すべき人 の意味があるそうだがそのような意味で使われたものかはわからなかった。
Dapheny (names.org) では人名ではユーザー投稿でギリシャ由来で、Laurel (月桂樹、栄誉) との情報がある。
ギリシャ神話の Daphne であれば我々にも馴染みの名前であるが、Daphne は ギリシア語で月桂樹の意味 (wikipedia 日本語版)。語源的関係はどうだろうか。
ネパール人にとっての尊敬の対象、と仮に訳しておく。ネパール人がイヌワシをそのように呼んでいた以上の情報はわからない模様。
もう一つヒントが見つかった。ニジキジ Lophophorus impejanus Himalayan Monal がネパールでは danphe / danfe と呼ばれているとのことでネパールの国鳥 (Monal はインドでの名称)。
ネパールでは最も美しい鳥の一つとして知られる。綴りが少し違うがあるいは関連があるかも知れない。
#ソウゲンワシ備考にこの亜種の学名の命名由来に関連するさらなる考察がある。
Hartert (1910-1922) (先述) の時代にはイヌワシは3亜種となっていて (アメリカ大陸は扱われていない)、基亜種、daphanea、occidentalis だった。最後のものはスペイン、アルジェリア、モロッコ。この亜種記載は 1889 年で、現在は homeyeri の名称 (1888) に含まれている。
daphanea はヒマラヤやチベットからアルタイ、モンゴルに分布するとされていた。前述のように Taczanowski がカムチャツカで得た標本は daphanea としたとのこと。この当時の分類が今でも痕跡を残していて daphanea と、その後名付けられた亜種の地理的境界が不明瞭になっている。
daphanea は古い記載なので亜種をまとめる場合はこの亜種になる傾向が強い。
後の分子系統研究からはこの Hartert ぐらいの亜種数とするのが実は適切だったのかも知れない。
英名 Asian Golden Eagle, Himalayan Golden Eagle。
よく Berkut (日本語でベルクート) と呼ばれる。これは現在のロシア語でイヌワシの意味だが (ただしこの亜種のみを指すものではない)、発音はビェルクト (アクセントは冒頭) の方が近い。このロシア語もチュルク語由来で、タタール語で birkut (berket)、カザフ語で burkut などチュルク語圏で似た単語が使われている。
YouTube などで中央アジアのイヌワシフェスティバルの報道などを見ることができるが、たとえ知らない言語であっても「ブルクト」のような単語を聞き取ることができる。
Berkut のキルギスの記事によれば berkut/burkut は「雨の主でアラーの神自身との争いに挑む神」を指すとのこと。
Severtsov (1888) は日本の亜種も記載した。Avibase による Aq.[uila] fulva japonica? 原記載。こちらは Sev. と Severtsov の命名であることを明らかにしているので記載者は不明確な点はない。
Blakiston による江戸の Keyoica Hakabusakan の博物館標本をもとにしたもので函館の商人から得たもの。カムチャツカのものよりかなり小さい。
Dement'ev and Gladkov (1951) でも亜種 japonica はこの記載を採用して記載者 Severtsov 記載年 1888 年としている (当時は亜種 kamtschatica のシノニム扱い)。
他の亜種は基亜種 chrysaetos 英名 European Golden Eagle (ヨーロッパからイランまで)、
canadensis (カナダの) 英名 North American Golden Eagle (北米)、
homeyeri (プロイセンの軍人、鳥類学者の Alexander von Homeyer に由来) 英名 Iberian Golden Eagle (イベリア半島から地中海周辺、中東などに局地的に分布。アフリカの個体群もこの亜種と考えられる)、
kamtschatica (カムチャツカの) 英名 Siberian Golden Eagle, Kamchatkan Golden Eagle (シベリア西部からカムチャツカ) でこの亜種は canadensis と同亜種とされることもあるが、北米のイヌワシに比べるとずっと大型とのこと。
参考までに亜種の原記載の一覧を示しておく。基産地は Avibase。
・Falco Chrysaetos Linnaeus, 1758 o (原記載) 基産地 Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, ed. 2, p. 19 (Linnaeus 自身によりスウェーデンに限定)
・Falco fulvus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe = England (ex Willughby, 1676, Ornith., p. 28, and Ray, 1713, Synop. Method. Avium Piscium, p. 6, note 2) [ヨーロッパと記載されたがイングランドに限定。Dement'ev and Gladkov (1951) は英国のイヌワシを別亜種として扱っていた] = chrysaetos
・Falco canadensis Linnaeus, 1758 o (原記載) 基産地 Hudson Bay (北米のハドソン湾)
・Aquila nobilis Pallas, 1811 * (参考) = Falco fulvus (記載者による) = chrysaetos (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Aquila chrysaetos melanastur Pelzeln, 1862 * (参考) 基産地 オーストリア = chrysaetos
・Aquila fulva intermedia Severtzov, 1873 * 基産地 トルキスタン地方 fulva? (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Aquila fulva var. alpina Severtzov, 1882 * (参考) = chrysaetos?
・Aquila fulva Homeyeri Severtsov, 1888 o (原記載) 基産地 Balearic Islands and Algeria (バレアレス諸島とアルジェリア)
・Aquila daphanea Severtsov / Menzbier, 1888 o (原記載) 基産地 Russian Turkistan, Transbaicalia, etc. (ロシアのトルキスタン地方など)
・Aquila fulva japonica Severtsov, 1888 o (原記載) 基産地 Japan
・Aquila fulva kamtschatica Severtsov, 1888 o (原記載) 基産地 Kamchatka (カムチャツカ)
・Aquila chrysaetos obscurior Sushkin, 1925 (参考 1, 2) 基産地 central Altai and Sailughem ranges (アルタイ山脈、Saylyugem Mountains アルタイ共和国とモンゴル国境付近) = kamtschatica (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Aquila chrysaetus hodgsoni Ticehurst, 1931 * (参考) 基産地 Hazara, N. W. India (インド北西部) = daphanea (Dement'ev and Gladkov 1951)
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
見ての通り Linnaeus はヨーロッパのイヌワシは2種と考えて学名を2つ付けた。基産地で分離も試みられたがヨーロッパの大陸とイングランドを別と考える必要があり、Dement'ev and Gladkov (1951) は別亜種としたが現在は通常シノニムとされる。しかしこれらの種学名はどちらも亜種記載などに使われていた。
Linnaeus は北米のイヌワシも記載していた。Severtsov (1888) が残りのユーラシアの亜種を記述して現代認められている亜種はこれで出揃ったことになる。
Latham (1781) Ring-tailed E.の学名に Falco Fulvus Linn. が挙げられており (同一性はよく検討されたものではないかも知れない)。Golden Eagle, with a white ring about it's tail, Ringtail Eagle の別名が出ていて、表現からイヌワシの若鳥を指すものと思われる。
しかし亜種の分布境界は自明なものではなく、Dement'ev and Gladkov (1951) は fulva を南ヨーロッパ型の亜種としていた。
Sushkin (1925) の obscurior は kamtschatica のシノニムとされる (Dement'ev and Gladkov 1951) ものの分布的には daphanea に含まれる可能性があるなどすっきりしない。
同じ Dement'ev and Gladkov (1951) が japonica を kamtschatica のシノニムとしているので、あまり亜種を認めず、ユーラシア東端は kamtschatica にまとめられると考えていたと思われる。
Aquila fulva intermedia Severtzov, 1873 はさらにややこしく Dement'ev and Gladkov (1951) は fulva にまとめたが分布的には現在の daphanea に対応しても不思議でない。
ユーラシアは広くて環境も多様だからと多くの亜種が記載されたものがあまりまとめられずそのまま使い続けられている状態とも言える。
現在通常使われていない亜種のシノニム化も Dement'ev and Gladkov (1951) は少し違う形で行っていた。一部がそのまま引き継がれてユーラシアの亜種境界がすっきりしない形になっている。
分子系統解析で判明するかと期待されたが後述のようにこれまでのところ遺伝子レベルではむしろあまり亜種分化がない結果になっている。
[中央アジアの現代のイヌワシ匠]
松尾 (2025) Birder 39(1): 6-15「モンゴル西部の大地と鷹匠文化」のグラビアがあり、「ブルクッチュ」が現地の言葉で鷹匠の意味と紹介されている。綴りを見るとキリル文字で (モンゴル語の文字表記の歴史などは wikipedia に詳しい)、ロシア語でも berkutchi (辞書訳ではイヌワシ匠) と事実上同じ用語が使われる。
格変化などのない名詞で外来語由来と考えられる。おそらく berkut / burkut 同様にチュルク語系統言語に由来するものだろう。
この単語は行為者を示すのみではなく、技術全般を指して英語の falconry のようにも使われる。中央アジアのイヌワシを用いた鷹狩りの映像などを探したい時には、この単語のロシア語表記を用いると多数見つけることができるのでお試しいただきたい。
参考までにキルギスの 1990 年のビデオ: The Eagle Hunter (1990, Kyrgyzstan) (ソ連時代のドキュメンタリー)。ロシア語字幕も表示できるので (ちょっと苦しいが) 機械翻訳で意味をとることも可能と思われる。
この時代の映像ならばもう少し伝統的な側面が見られるかも。
Kyrgyzskij berkutchi (Telekanal Planeta 2014)。こちらもキルギス。あまりよくできていない "やらせ" 的な感じだが...。オオカミの幼獣はうまく行かずイヌワシが地面に降りてしまった。こちらもロシア語で単語をコピーして検索に使うこともできる。
もっと新しい観光用 PR 用動画ではモンゴルなどのイヌワシフェスティバルの様子なども多数見ることができる。
カザフスタンの記事で Istoriya dinastii berkutchi (Solntseva and Sariev, Tengri News 2021) があり、伝説混じりの部分もあるが、10 歳を過ぎると子孫を残せるように野生に戻す。
カザフスタンのイヌワシ匠によればイヌワシは 45-50 年生きる。学者は 100-150 年生きると言うが学者は 150 年も生きていないのでどうやってわかるのだ?
Chem berkutchi iz Mongolii luchshe kazakhstanskikh
カザフスタンの "イヌワシ匠" への聞き取り。イヌワシを用いた鷹狩りはツーリズム的にはモンゴルの方がはるかに成功していてイヌワシ匠も多い (カザフ人のイヌワシ匠によるツーリズムが盛んに行われている) とのこと。ソビエト時代はイヌワシは使えず、イヌワシを使うのは馬鹿者のすることとされていたとのこと。
この "イヌワシ匠" はキャリア 20 年強とのことで出会いは巣から落ちたひなを助けたことでその時の傷が残っている。そして動物園で働いているイヌワシ匠を知ったことに始まるとのこと。モンゴルではツーリスト用のイヌワシが用意されていて、母国の身近な環境にイヌワシのいない外国人は大変喜ぶとのこと。鷹狩りがユネスコの世界文化遺産に登録されたことも人気の背景にある。
女性や子供にイヌワシを与えることは昔のカザフ人ではなかったことで、メディアで取り上げられる女性イヌワシ匠などはツーリズムの産物 (とまでは言っていないがそれに近い)、また現代のイヌワシ匠は伝統的なものとは異なる点もあることなど取材者も注意すべきニュアンスで語っている。
かつてのカザフ人は秋にイヌワシを捕獲して 10-15 日で仕上げて (そんなに短期間で!) 狩りに使い、春には放して翌年また捕えていたと言われているとのこと。
[中央アジアの鷹狩り歴史]
Yrsaliev (1966) によれば「東洋の人々は古き時代から鷹狩り用の鳥を広く狩りに用いてきた。そのような鳥としてタカ類は、シロハヤブサ、ハヤブサ、ワキスジハヤブサ、オオタカ、イヌワシなどである。
大型のハヤブサ類やオオタカでノガン類、キジ類、白鳥、カモ、ヌマライチョウ、サギなどが狩られ、イヌワシはキツネやオオカミに放たれ、時にはアイベックス、サイガ、コウジョウセンガゼル、ノロに放たれることもあった。
銃が現れてから鷹狩りはそれほど重要でなくなり、今では主にスポーツの性格を帯びている。しかし鷹狩りは特にキルギス、カザフスタン、トルクメンの所々では現代でも商用の獲物を獲るのに大きな意味がある。オオタカによる狩りが第二の位置を占めている (中略)。
ハヤブサ類のみで狩りをしていたヨーロッパの人々とは違って、中央アジアやカザフスタンではハヤブサ類 - シロハヤブサとハヤブサの他に、イヌワシ、オオタカ、コチョウゲンボウを鷹狩り用の鳥として用いていた。
特にキツネやオオカミを狩り、時にはノロや他の野獣を狩るイヌワシを使った狩りは商用の獲物を得る意味があったことに注意しなければならない。
ハヤブサ類やタカ類を用いた鷹狩りはより愛好家的な性質を帯びていた。M. N. Bogdanov (Dement'ev による) の情報によれば、19 世紀後半にはトルクメンでヒビンスキー (Khvinskij) オアシスに住むカザフ人の間で鷹狩り用の鳥を使った狩りは幅広く広まっていた。
トルクメンの人々はイヌワシをオオカミ、サイガ、コウジョウセンガゼルの狩りに用いた。トルクメンの人々はよいイヌワシのためにラクダ1頭を払った。狩りのためのイヌワシの他にここではハヤブサ類やオオタカも使用された。
S. Flerike と Loudon (Dement'ev 1952 による) の情報は、この時期にトルクメン、特にトルクメンのプレアムダリア地域 (北東部のウズベキスタン国境近く) で鷹狩りが幅広く広まっていたことをさらに裏付ける。
革命前のキルギスでは鷹狩り用の鳥を使った狩りは主にスポーツ、愛好的特徴を帯びていた。それはたいての場合封建貴族の気晴らしの役割を演じていた。そしてごくわずかの数の農民がイヌワシを使った狩りを行っていたに過ぎない。
普通は捕獲者 (サヤトチ sayatchi) は捕獲されたハヤブサ類やタカ類を強いマナプ (部族指導者) たちに贈ったり売ったりした。あるものはハヤブサ類を訓練した後に贈り、別のものは捕獲後すぐに贈った。サヤトチが自分で鷹狩りをすることはまれだった。このことについては最も年長の猟師たちの語りが証言している。
例えば最も優れた鷹匠の一人である Karabek Osmonaliev は捕獲されたハヤブサ類やタカ類を地域の富豪に贈り、他の多くも同様にふるまったことを伝えている。封建領主の間で鷹狩りはたいへん幅広く広まっていた。これには獲物の動物相の豊かさが寄与していた。
春先に水に浸かる草地の林には多数のキジ類、ノウサギ、ヌマライチョウが住んでいた。それぞれの湖にはおびただしい数のカモ、ガンや他の水鳥が営巣していた。当時のすべての上質の狩場は名門のマナプの手にあった。それらのうちいくらかの者は狩場を動物で豊かにすることに関心があった。
そしてアタルチャト (Aktalchat) 地域のナリィン (Naryn) 川の草地はマナプ Musakozho Ismailova の管理下におかれ、1908 年この地域にキジが放鳥された。
キジは増えて草地全域に広がり、今でもそこに住んでいる。アト-バシ (At-Bashi) 川の草地の林を所有していたマナプのチョジョ (Chozho) もまた 1911 年に自分の区域にキジを放鳥した。しかし鳥はマナプ自身か友人が狩るだけで、他人には狩りは許されなかった。同様の現象はキルギスの他の地域でもみられた。
キルギスでのソビエト政権の樹立によって以前マナプに属していたすべての狩場は国家の所有物となり全ての国民の共有物となった。狩猟は次第に国家の法的枠組みに入っていくようになった。すなわち法律や鳥や動物の猟期が制定され、動物の繁殖期の狩猟は禁止された。
この魅力的な仕事の全ての愛好家が鷹狩りに携わることが可能になった。特に発展したのがイヌワシによるキツネやオオカミの狩りである。イヌワシ使いの猟師はイヌワシの助けで得た毛皮を国営の調達物供出場所で公定価格で引き渡すようになり、イヌワシによる鷹狩りは次第に市場向けになっていった。
ハヤブサ類やタカ類を鷹狩り用に用いる猟師の数も増えた。主に鷹狩りが行われたのはキルギスの北半分、特にイシク・クル盆地、タラススカヤ (Talasskaya) 谷と天山山脈である。キルギスの南部では広範には広まらなかった。キルギスの北部は大きな湖や川の存在で際立っており、川の草地には林が続いている。
このような湿地にはいつも多数の水鳥が群れており、河畔の草地の林にはキジ、ヌマライチョウ、ノウサギが住んでいる。そのためこれらの地域での鷹狩りはより広まった (後略)」とあまり知られていない中央アジアの鷹狩りの歴史を記している。古くはイヌワシを使った鷹狩りは少数の農民が行っていたのみだが、ロシア革命後は獲物を市場に出すルートができて一般に広まったことがわかる。
ちなみにウクライナ語でも berkut であり、ウクライナ鳥学会の機関誌の名前にもなっている。しかしかつてウクライナ内務省に存在した警察機動隊の名称が berkut であり、クリミアではロシア占拠後に事実上ロシアによる監視部隊となり、イヌワシの名前に対する市民感情は好ましいものではないようだ。
日本語では、
相馬 (2016) カザフ騎馬鷹狩文化におけるイヌワシ捕獲術と産地返還にみる環境共生観の民族誌
の研究がある。この引用文献から過去の研究をいくつもたどることができる。これらの文献にも年齢に応じたイヌワシの名前があることが触れられていて日本語で読むことができる。
Yrsaliev (1966) の表記を紹介しておくと、
バラパン (balapan) - 雛 (若鳥)、
ボズム (bozum) - 2歳、
タシ-ツロク (tash-tulok) - 3歳、
クム-ツロク (kum-tulok) - 4歳、
ニム-ツロク (nym-tulok) - 5歳、
バルチン (barchyn) - 6歳。
この後は ビル-バルチン (bir-barchyn)、エキ-バルチン (eki-barchyn)、ウチ-バルチン(uch-barchyn) などと続く (すなわち1バルチンが6歳、2バルチンが7歳などの意味になる)。
これとは別に色、大きさ、外見、爪のつくり、嘴と足の色に応じたイヌワシの名前があることを Yrsaliev (1966) が記していてこれまで見た範囲の日本語資料には見当たらないので紹介しておく:
「キルギスで著明なマナスチであり最も年長のイヌワシ猟師である
S. カララエフ (Karalaev) はイヌワシを18の異なる種類に分類している。
全てを取り上げる必要はないので、一番広く知られているもののみを取り
上げる。
ジャンボズ (zhamboz): 色は褐色-灰色から茶褐色を帯びる。翼と尾は
短く丸い。脚は強力。首は他のイヌワシより長い。目は赤い。
ケレボズ (keleboz): 胸は広く額は広い。翼と尾は切形で丸みを帯びる。
色は灰色-褐色。頭は白い。止まっている鳥の翼の先端はハヤブサのように
重なる。猟師たちの情報によればこの種類のイヌワシは山ヤギやアリガリ
を攻撃する。
カラチク (karachyk): 後頭部に伸びた黒っぽい色の羽が背まで続いている。
大きさでは他のイヌワシよりはるかに大きい。このイヌワシの訓練には
長い時間を要し、獲物の質は際立っている。山ヤギを捕らえる。
チョル-サリ (chol-sary): 色は冷めた褐色、時に黄色っぽい、脚は
青っぽい (ワキスジハヤブサのように)、足指は力強くで爪は強く、
曲がっている。目は赤っぽい褐色。
サリ-ウンクイ (sary-unkuj): 全般的な色は黄色っぽく「サリ」の名前
を意味している。目もまた黄色で、「眉」は高く、脚は太い。
イヌワシ使いの猟師たちの見解ではこの種類のイヌワシはアリガリにも山ヤギ
も攻撃する。しかし見られることは非常にまれである。K. オスモナリエフ
(Osmonaliev) の話によれば「モロル」(molor) と名付けられているさらに
1種類のイヌワシがいる。この種類のイヌワシの嘴の先は細く、後ろ指が長い
(中指と同じ長さ)。色は茶褐色。カシュガルとの国境に近い天山山脈の東部
にいる。アト-バシンスキー (At-Bashinskij) 渓谷でボソゴ (Bosogo) 区画の
オシ-タプ (Osh-Tap) に営巣している。そして「ムズ-ムルト」(muz-murut)
の種類のイヌワシがいる。彼らはイヌワシ使いの猟師たちの見解では高い山の
雪の地帯に営巣する。鼻孔から嘴の先端に達する硬い剛毛のような毛が突き
出ている。脚は太く爪は強力である。翼は長く、目は大きく青い。この種類
のイヌワシは非常に強い。
「シルガコブ」(syrgakov) に属する「バシュ-シルガコブ」(bash-syrgakov)、
「アヤク-シルガコブ」(ayak-syrgakov)、「ジェドゥウ-シルガコブ」
(zheduu-syrgakov) もまた分けられるが、お互いに違っていて見分けること
は簡単である。上面からの鼻孔はひげの形で伸びてお互いつながる。足指の
上面には筋目がある。
このほかに「ベレノブ」(berenov) とそれから一連の「ボシュ-ベレン」
(bosh-beren)、「オルト-ベレン」(orto-beren) その他が分けられる。」
[亜種と遺伝子からみた保全・長距離の迷行例]
イヌワシの亜種に戻ると、シベリアからカムチャツカの亜種 kamtschatica と北米の亜種 canadensis は区別できず同一亜種であるとの見解は古くからあった。
Nebel et al. (2015)
Mitochondrial DNA analysis reveals Holarctic homogeneity and a distinct Mediterranean lineage in the Golden eagle (Aquila chrysaetos) の遺伝系統解析でも明確に区別できるのは地中海系統 (亜種 homeyeri に相当) とユーラシア、北米を含む北方系統だけで (ただし亜種 daphanea の含まれる中央アジア、シベリア、カムチャツカなどは調べられていない)、日本のイヌワシも北方系統に分類されることがわかった。
北方系統は大きく広がっているが、その分多様というわけでもない。これまで記述されてきた亜種はこの研究で分離できなかったが、これは使った遺伝部位の性質によるものかも知れない (亜種の存在を肯定も否定もできないが、文献によっては既存の亜種を疑問詞する根拠ともなっている)。
日本のイヌワシの遺伝的多様性は Masuda et al. (1998) が報告しているが、異なる遺伝領域 (ミトコンドリア擬コントロール域) を使っていたため直接の比較はできない。
考えられる可能性として (1) 日本と大陸の個体群で遺伝的交流が何度もあって、個体群の少なくなった時期の遺伝的多様性の低下を防いでいる (2) そのような交流が現在も続いている (3) 氷河期のアジアに残った遺伝的に異なった複数の refugia レフージア (待避地) から日本に定着した を挙げている (複数の要因が重なっていてもよい)。
たとえばニホンイヌワシという独立した亜種が実はなくて、遺伝的には大陸の個体群の混合物ようなものである、また体サイズや渡り習性などは必ずしも大きな遺伝的違いを反映するものではないので、それをもって遺伝的に明らかなグループとまでは言いきれない、などの可能性があり、保全上も重要な示唆である。
Sato et al. (2020) Population history of the golden eagle inferred from whole-genome sequencing of three of its subspecies では上記 Nebel et al. (2015) の結果の解釈として氷河期に北米と東アジアの間で交流があったことを考慮すると話が合うとの表現になっている。
Genetic research into the Japanese golden eagle (Aquila chrysaetos japonica) for conservation managenemnt (ニホンイヌワシの保全を目指した遺伝解析) (2019)
の日本語概要がある。
この論文では、(少なくとも過去に北米と遺伝子交流があったことも背景として) 非常に慎重な考察が必要だろうが、日本のイヌワシを救うために北米の亜種を導入することも選択肢として考えられるとの記載がある。ロシア東岸部や中央アジアの個体群を調べることも重要である。
イヌワシ亜種の間の遺伝型と表現形の機能的な違いを明らかにすることも、もし導入が行われた場合に環境に適応できるかを調べるためにも重要である。
同グループによる遺伝的多様性を調べた論文があり、Naito-Liederbach et al. (2021) Genetic diversity of the endangered Japanese golden eagle at neutral and functional loci 上記とは異なる DNA 領域を調査して、絶滅の恐れの低いとされている猛禽類よりも多様性は低いが、個体数の割には遺伝的多様性は高い結果になっている。
日本の個体群で近親交配の傾向は見られないが、若鳥が古いペアや死亡した個体を代替することが減少していて、繁殖ペアの高齢化と繁殖能力の低下が示唆される。世代交代が起きると個体数が急激に減少し、遺伝的多様性が失われ近親交配が進む可能性がある。遺伝子レベルからみた保全のために飼育個体群を増やすことや飼育個体の放鳥も提案している。
国内個体のみでの保全を念頭に置いた保全戦略も発表されている:「ニホンイヌワシの保全学: 現状と将来展望」[原文 (2020)、訳文 (2021)]。
ユーラシア北端、北米北端のイヌワシは渡りをする (アラスカで繁殖する個体群は GPS 発信機で渡り経路もよく調べられている) が、北米のイヌワシが海を越えて遠くに渡る能力があることを示す事例として、1967-1984 年ハワイにすみついたイヌワシの例がある:
Pyle and Pyle (2017) Golden Eagle in "The Birds of the Hawaiian Islands: Occurrence, History, Distribution, and Status. B.P. Bishop Museum, Honolulu, HI, U.S.A. Version 2"。
1967年1-2月に発見され、当時は 1-2 歳の若鳥だった。主にヤギとニワトリを食べていた。1969 年には観光用ヘリコプターを攻撃するようになって、1984 年にヘリコプターとの衝突事故で死んだとのこと。北米のイヌワシが海を越えてユーラシアに (もしかすると日本にも?) 渡ることも十分可能であろうことを示す事例であろう (逆にユーラシア北端のイヌワシが北米に渡ることも考えられる)。
その後新しい研究が相次いで発表された:
(1) Nebel et al. (2023)
Genetic Analysis of Golden Eagles (Aquila chrysaetos) from the Mongol-Altai: A Hotspot of Diversity and Implications for Global Phylogeography
哺乳類などの事例から中央アジアのモンゴル高原やサヤン-アルタイ山地が氷期の Holarctic タイプのレフージアであった可能性がある。
氷期にこの2系統に分離し、氷期の終わりとともに Holarctic タイプが北方への分布を広げ、ヨーロッパ北部の分布を形作っているとすれば現在の分布を説明できる。中間の地域ではハプロタイプの混合があるが、ヨーロッパでは Mediterranean タイプと Holarctic タイプを evolutionarily significant units (進化的に意義のある単位: ESUs) と考えた保全を行うのがよいのではないか。
ここでもヨーロッパのミサゴの地中海系統とそれ以外の系統の関係との類似性が取り上げられている (ミサゴも地中海をレフージアとしたとすると都合がよい。しかし異論も出ている #ミサゴの備考 [亜種の問題] 参照)。
ミサゴの場合は渡りを行うかどうかで系統が分かれる説明もできるが、イヌワシはそれほど渡りを行わないので同じ説明は適用できないかもとのこと。
日本と大陸はそこそこ地理的隔離があるが、日本の個体群には大陸の遺伝子型も混ざっている。日本の個体群に固有の遺伝型は見つからなかった。
大陸の遺伝子型の導入が1回の導入イベントで説明できるか、大陸からの分散が頻度は低いものの起きているのかは現在のデータ (1個体しかない) からは区別できないが日本の個体群の保全上では重要な意味を持つ可能性がある。
(2) Sato et al. (2023) Genomic data reveal strong differentiation and reduced genetic diversity in island golden eagle populations
は日本のイヌワシのゲノム解析を行い、スコットランド、大陸ヨーロッパ、アメリカとは遺伝的にはっきり分離できる結果を得て大陸レベルの亜種が区別できる結果を得ている。この解析では日本の個体群はアメリカに近縁のグループとなった。Nebel et al. (2023) (こちらはマイクロサテライトを用いたものでゲノム解析ではない) で調べられた地理的に中間に位置するアジアの個体群は含まれていない。
Sato et al. (2023) は日本やスコットランドの島の個体群の遺伝的多様性が従来の研究で見積もられたものより低く、近交度が高いことを示している。
Nebel et al. (2023) の研究はマイクロサテライトによるもので限界もある。Sato et al. (2023) では大陸からの明らかな流入はなく、大陸からの自然な遺伝的多様性の流入に期待することはできないとしているが、アジアの大陸部の個体群は調べられていない。分布の他地域のデータ解析は進行中とあるので亜種の問題はいずれ解決されるだろうか
(動物園個体が日本の亜種かどうか、飼育個体も含めた保全戦略にとって遺伝データからの亜種判定の必要性は高い)。
Sato et al. (2023) では日本では近親交配の影響がすでに現れつつある可能性もあるとしている。
Nebel et al. (2023) はユーラシアのイヌワシの生物地理学を明らかにすること、及びヨーロッパのイヌワシの研究が主目的なので両者の研究の力点は少し異なっている。
(3) 日本を除くユーラシアのイヌワシの遺伝的研究 (これもマイクロサテライトの解析): Karabanina et al. (2024) A renewed glance at the Palearctic golden eagle: Genetic variation in space and time
日本の個体群は以前の研究で Holarctic タイプに分類されていたが、"Far East" (ロシア東部、中国東部・中部) の個体群も同じく Holarctic タイプと判定された。
北米も Holarctic タイプに含まれ、ユーラシアとは多少分離している。過去に北米のみで認められたハプロタイプがカムチャツカでみつかり、北米に集積していたハプロタイプが極東、中央アジア、コーカサスにも認められた。
北ヨーロッパの個体群の遺伝的多様性は低いが、中央アジア、コーカサスの個体群の多様性は高い。
ユーラシア本土の個体群は 19-20 世紀の個体数ボトルネックの効果が現れているが、世代の長さと分散能力の高さに救われている可能性がある。
以下で問題になるアフリカ個体群はデータが公開されておらず調べられていない。
これら最新の研究を総合解釈すると、イヌワシは2または3系統 (日本を含む Holarctic + 北米、Mediterranean) で、分散能力が高いので十分はっきりした地理的系統に分かれていない。
Holarctic は分布域が広いのでユーラシア東西 (例えば日本と英国) では違いが現れているが全体的にみると連続的。多くの亜種が記述されているがこの解析の範囲では遺伝的にはそれほど違いがない模様。
Nebel et al. (2023) は氷河期中央アジアのレフュジヤの役割を想定している。中央アジアが現在のイヌワシの遺伝的多様性ホットスポットであること、[亜種・中央アジアの鷹狩り歴史] にあるキルギスの鷹匠がイヌワシを形態や色彩で分類していたように表現型にも多様性が表れている可能性がありそうで、中央アジアがイヌワシの遺伝的多様性のソースになっている可能性が高い感じがする。
また Aquila 属 (狭義、広義いずれでも) アジアの種多様性が高く、やはりユーラシア起源 (さらにはアフリカ) で大陸全体に広がったものは中央アジアにホットスポットを持つと考えるのが妥当そうで、現在の多様性もそれが反映されているとみなすことができそうに見える。
[イヌワシ類似の大型イヌワシ類] でもう少し系統を考えた考察を紹介する。
北米に分散したのはイヌワシ1種で、アジア個体群との交流がそれほど容易でないため、現在の個体数は多いにもかかわらず北米個体の遺伝的多様性や過去の有効集団サイズが小さいと解釈できるように思える。
日本の個体の過去の有効集団サイズが大きいのは、2020 年の研究のように北米の集団とまだ分離していなかった状態を反映しているというより、アジア大陸の個体群とまだ分離していなかった状態を反映しているのではないだろうか。
現在は朝鮮半島にはほとんど生息していない状況だが、過去には中央アジア個体群の分散経路となっていたことも想像でき、人為活動により分断されるようになったと理解できるような気がする。
日本のイヌワシの大陸に比べた体のサイズの縮小はどの時期に起きたのだろう? ヒトでも体格差があるように同一タクソンでも個体サイズは違っていても不思議でない。体のサイズと色調だけで亜種に分けるならばヒトも多数の亜種に分けることができてしまうだろう。
遺伝的に日本と大陸のイヌワシにあまり違いがないならば、日本のイヌワシはそもそも栄養不足の可能性もあるのではないかと感じた。体のサイズの縮小は遺伝的基盤もあるとも考えられるが、表現形の可塑性由来かも知れない (戦後日本人の体格が向上したのは別亜種になって行ったわけではない)。
遺伝的にほとんど違いがないのであれば、大陸の大型のイヌワシ亜種を例えば遺伝的多様性を増すために日本に連れてくれば、あるいはそもそもその体格では生き延びられなかった、あるいは小型化した、などの結果もあり得る気がする。
イヌワシの日本の亜種もそもそも大型のカムチャツカの個体 (これは Bergmann-Allen の法則通り) と比較した結果記載されたもので、地理的に離れていたためにたまたま大きさの違いが目立っただけかも知れない。多くの亜種を記載した Severtsov の記載も古い上に細分主義的で、イヌワシの亜種は現在ある程度そのまま使われているものの Dement'ev and Gladkov (1951) が示したように批判的立場もある。
遺伝的な研究も進んできているので、イヌワシは生物地理学的には実は2亜種で十分で、日本の個体群は気候または食物に応じた小型個体であるとみなしてもよいのかも知れない。
[ウラル地方のイヌワシ]
ロシアのイヌワシの情報が少ないと思われるので、かつて訳したものから多少修正して抜粋紹介しておく。
Karyakin (2004) "猛禽類の調査方法" (参考文献参照) にもイヌワシの以下の記述はこの文献にも一部盛り込まれている。
I. V. Karyakin (1998)
イヌワシ (Aquila chrysaetos L.)
「ウラル地域の猛禽類. タカ目とフクロウ目」
ペルミ: ウラル動物保護連盟野外研究センター/社会環境連盟 483 p より。原文。営巣写真などが見られる。冒頭の歴史的記録の部分は省略。
[営巣分布と数]
現代ではイヌワシはまれに営巣する留鳥であり、さらに森林地帯ではワシ類の中で最も数が多い。
森林ステップ地域ではイヌワシの分布は大なり小なり均一である。
ウラルの山岳地帯ではその生息に最も適した条件にあり、そこでは山脈や河川渓谷
に面した岩場の山塊に沿っている。
南部ウラルには、この種の数の最大の源がある。ここでは 111 の営巣区域があり、
そのうち 99 は Bashkiria 領域にある。南ウラルの山岳森林地域の西部では広葉樹が
優勢で数世紀にわたって伐採されておらず、イヌワシは最大の密度で営巣している。
いくつかの営巣集団 (Bel'ck, Nugushsk, Zilimsk) における、異なるつがいによって
利用されている巣の間隔は 4-12 km で、最小は 4 km (Uryuk)である。南ウラルで
イヌワシが営巣している地域での密度は 1000 平方 km で 4-13 つがいである。
南ウラルの南端 (Zilairsk 台地, Shaitan-Tau, Prisakmar'e) ではイヌワシの数
は急激に減少している。そこでは森林に覆われた地域の 50% 以下でこのワシが営巣
し、密度は 1000 平方kmに 1-3 つがいである。山岳森林地域の周辺で、イヌワシの
分布にはマーモット類のコロニーや大型のミヤマガラスが大きな役割を果している。
ウラルの北に向かってでイヌワシの数は減少している。中央ウラルでは
このワシは一層まれになっている。ここではおそらく集中的な皆伐がイヌワシの数
に影を落している。これはイヌワシが繁殖するにあたって大なり小なり、天然の
開けた環境と交代で存在する古く成育した森林に頼っていることに関係があり、
これらは通例高い山の斜面である。中央ウラルでは我々は 19 のイヌワシ営巣区域を
知っているが、そのうち 15 が Sverdlovsk 州に存在し、Perm' 州ではわずか4つ
しかない。ウラル東斜面でイヌワシの数がより多いことは、松やカラマツの林相が
優勢であることに原因があるように見える。これらは暗色針葉樹に覆われた西斜面
と比較してこの地域での営巣適合度を何倍にも高めることになる。中央ウラルでの
異なるつがい間の巣の間隔はふつう互いに 20-40 km 離れている。
北部ウラルでは大部分で中央ウラルと同様の密度で営巣しているが、ここでは
より保存された森林のおかげで営巣集団が保たれてきた。ここではつがいの営巣
間隔は 8-14 km である。北部ウラルで調査された地域の範囲で 14 の営巣区域が
知られており、そのうち8が Perm'州、6が Sverdlovsk 州にある。北側、Komi
共和国と Tyumensk 州の領内ではイヌワシの数は何倍も高く、Kozhdym, Kos'yu,
Narod 川の分水嶺、Telposiz, Nepoika 山塊のような未開の環境では特にそうで
ある。ここでは 17 の営巣区域が知られており、異なるつがい間の巣の最小間隔は
10 kmである。
Ufimsk 台地 (13000 平方 km) は同様の山岳地域で、南ウラル同様イヌワシはかつて
はまったく普通の種類であったが、ここではイヌワシの個体群は皆伐によって損な
われた。現代ではここでは 18 つがいの営巣が知られており、そのうち 15 つがいは
台地のうち Bashkirsk 領内で繁殖し、Sverdlovsk 州領内の Karatau 山脈の2つがい、
Perm'州の1つがいを含んでいる。台地でのイヌワシの営巣密度は 1000 平方 km あたり
2つがいである。
広葉-針葉樹林地域の集中的な開拓と景観の分断の結果、ここではイヌワシは丈の
高い森林が一部区域にある分断された大型の島状の森林にのみ残された。結果は
明らかである: その 90% が葉の小さな二次林若木に覆われた Tulvinsk 台地 (Perm' 州)
では 40000 平方 km の広さに3つがいが営巣。Pribel'sk 平野の領内ではイヌワシの
営巣は9区域知られている: 7つが Bashkiria の北西部で2つが Perm'州の南西部
である。
森林平原地域では、イヌワシの主な営巣集団は水ごけに覆われた沼地上流に富んだ
地域に集中している。西部ウラルではこれは Veslyansk 低地で、Verkhnekamsk 低地
と北部ウラル (Verkhnekamsk 沼地) の周辺地域を含んでいる。東部では Kondinsk
低地で Tavda 流域を山麓まで全て含んでいる (Tavdinsk 沼地)。Verkhnekamsk 沼地
では 34 のイヌワシのつがいが知られている (Veslyansk 低地領内で 25 つがい、その
うち 22 つがいが Perm' 州に営巣。Verkhnekamsk 台地領内で9つがい)。Tavdinsk
沼地では 27 つがいが知られている (Pelym 川流域に 17 つがい、Vagil'sk 水-沼地群に
2つがい、Tavda 川流域に8つがい)。この地域でのイヌワシの営巣密度は 1000 平方 km
に1つがいである。
森林ステップ地帯ではイヌワシは非常にまれで、密度は 1000 平方 km に 0.2-0.1
つがいである。基本的には全ての既知の巣は、大きな森林塊か森林ステップの周辺
地域に合わせられている (森林の境界か山岳森林領域)。
ステップ地域ではイヌワシは事実上絶滅してしまい、ほとんどの地域で密度は
1000 平方 km に 0.1 つがい以下である。イヌワシは大きな島状の松林 (外ウラル =
ウラル以東で) か、カシの林 (前ウラル = ウラル以西) に営巣しており、しばしば
マーモットの大きな生息地に隣接している。
我々は、中央ロシアの森林ステップやステップでは、山岳地域から残りの地域へ
の若鳥の流出によって孤立したつがいがまだ残っているウラル地域でのみイヌワシ
が保たれているのではないかと思うようになっている。Tataria, Ornburgsk,
Samarsk州や北部カザフスタンでの観察が示すように、天然の開けた空間がこの種
を失わせてしまい、おそらく回復しないだろう。
1998 年の現状では、ウラル地域で 276 のイヌワシの営巣地域が知られている。
Perm' 州 (16.06 万平方 km) に 66、Sverdlovsk 州 (19.48 万平方 km) に 65、Bashkortostan
共和国 (14.36 万平方 km) に 129、Chelyabinsk 州に 16 つがいである。
この地域のイヌワシの概数は 500 つがいと見積もられる: そのうち Perm' 州に 120
つがい、Sverdlovsk 州に 200 つがい、Bashkortostan 共和国に 150 つがい、Chelyabinsk
州に 30 つがいである。
調査地域の範囲の他でのこの種の状態は以下のように思われる。
すでに述べたように、Orenburgsk, Samarsk州、Tatarstan 共和国のステップ、
森林ステップ地域では、イヌワシの巣を見つける全ての試みは成功しなかった。
Sanarsk Luki地域 - 森林ステップ内の島状森林で、ミサゴや海ワシ類、多数の
森林性の種類の営巣が保たれている - でさえもイヌワシは見出されなかった。
Zavolzh'e ではアンケート調査をした全てのワシの巣や鳥類学者によってイヌワシ
の巣とされていたものはカタシロワシの巣と判明した。
Udmurtia ではイヌワシの営巣場所は基本的に Kirovsk と Perm' 州の境界で、
Kama, Vyatka 川の上流の大きな森林塊、Kama 川下流、Kil'mez' 川流域、Votka 川
に沿って知られている。
Komi 共和国の平野部では巣は Lokchim Voch', 北 Kel'tma, Nem 川の上流、
Vychegdeに沿って、Pechora 川流域で、平野部にも、山岳部にも知られている。
Tyumensk 州では全ての森林に覆われた地域で大なり小なり均等に営巣しており、
Kondinsk低地で最も数が多い。
[営巣環境、巣、繁殖特性]
平野林では、イヌワシは水ごけに覆われた沼地に富む成熟した丈の高い森林
(通例は純粋な松林、あるいは上層で松や白樺の優勢な混合林) に従っている。
分水嶺は渓谷の森よりも明らかに好まれている。大きな水ごけ沼地面積 100 平方 km
以上) で、イヌワシが狩り場として占拠していないものを我々は知らない。
最近ではこの鳥の営巣は広い伐採地の中で観察されることがますます多くなって
いる。食物基盤からはおそらく沼地に勝るように思える。農業地区ではイヌワシ
は大きな森林塊の内部に営巣する。森林ステップ地域では島状の松林、起伏の
多い窪地あるいは河川渓谷の険しい崖に居を構える。
島状の森林では、大きさに関わらず、イヌワシは森林塊の奥に巣を造る。
森林ステップでは、イヌワシの営巣は、森林の他に、マーモットの生息地、
ミヤマガラスのコロニー、水-沼地性の野鳥が集まる場所に合わせられている。
森林地域では、イヌワシの分布は、その分布の基準は森林と食物基盤であるが、
生息場所 (стация = habitat) の視点ではより広いように思われる。
イヌワシがその大きな巣を構えることができる場所の制約は、イヌワシの分布
を制限する主要要因である(ここでは狩猟や人為的な巣の破壊などは考慮しない。
というのは、この要因は地域によって様々であり、人々の集団の文明の程度や
数に依存し、分布地域の多くの場所ではイヌワシの分布に影響を与えていない
ためである)。
山岳地帯ではイヌワシは山間渓谷(河川渓谷の森の向こうの山の崖、丈の高い
森林に覆われた山脈の間の渓谷)に従っている。
イヌワシが巣を造るにあたって、多くの場合木が選ばれている。第一には
高い (20-30 m) 松、ヤマナラシ、白樺、カシ、カラマツであり、森林の種類によっ
てはまれにモミや杉(後者はウラルの西斜面に特徴的である)が使われる。
もちろん、イヌワシの営巣する全ての木の中で松が一番よく利用されており、
この点では総じて普遍的である。島状の森林塊や山地ではワシが巣に飛んで来る
のを容易にする小さな開けた場所の近くの森林の奥にある木が選ばれている
(林道、小さな草地、古く一面に草の生えた道の近く、強く起伏に富んだ場所で
は険しい谷間の崖)。密林では沼地と伐採地がまだらに交代する、幹の高い松の
疎林が好まれている。疎林のない場合は沼地の縁に成育する、あるいは沼地の
中の島状の林の高い木が選ばれている。皆伐の中では、伐採後の播種用に残さ
れた木、あるいは伐採地の縁に巣が造られている。総じて木に営巣するに
あたって、下部と中央の枝がワシの巣に持ちこたえられるように(イヌワシは樹冠
の下部と中央に巣を造る)、またこの大きな猛禽が容易に巣に飛んで来ることが
できるように(獲物を巣に運ぶ滑空が自由にできる、木のない小さな空間)選ばれて
いる。
イヌワシの営巣する第二の種類の場所として、測地塔 (いわゆる三角測地点) が
ある。イヌワシは塔の中央と高い踊り場 (それぞれ高さ 15m, 20m に位置している)
に巣を造り、よりまれには約 8m の高さの低い踊り場に造るが、これは伐採地や沼地
の中、苔の生えたあまり高くない (5m まで) まばらな松や白樺の林分の中に造られる
ものがよく観察される。通例、塔には中央と上のプラットフォームに2つの巣が
ある。イヌワシが住みつく塔は、大なり小なり伐採されておらず、開けた場所
(沼地や伐採地) から少し離れた (1-8 km) ところにある森林(昔からのものとの条件
付きで)に面した林道や道に沿ってある。あるいは沼地や伐採地の中央に直接あるが、
これはよりまれである。観察が示すように、イヌワシの塔への移住は、水ごけに
覆われた沼地に富み、この時点で事実上 80% が伐採されている、中央、北方タイガ
林の分布地域で観察されている。
このような正常でない営巣は、おそらくは、成熟した林の大規模伐採の結果に
他ならない。山脈の崖や峡谷湿原で高い幹の森林の残されているウラル山岳林の
すべての事例で、塔への営巣を一例も知らない。全ての巣は木に据えられており、
イヌワシが木のみに営巣する南タイガ林や森林ステップ地域についても同様であ
ろう。とはいえこれらの地域で塔が不足している結果の可能性もある。塔はそこ
ではまれにしか所在しない。
現代では、個体の 95% (我々のデータで) が塔に営巣している2つの拠点がある:
Verkhne(上)-Kamisk と Kamisko-Vychegodsk 森である。また Pechorsk 平野
タイガでも、第一の拠点が Verkhne-Kondinsk 森であり Priob'ya 森が第二である。
よりまれには、イヌワシは川の、垂直の 100-200 m の崖の露頭に営巣する (近寄り
難い棚や崖の上 1/3 の半窪み)。これはウラル山地の他の地域よりも南ウラルにより
特徴的である。
巣の建造についてもいくらか述べておく必要がある。塔に造られる巣はあまり
大きくなく、直径で 100-150 cm、高さが 10-20 cm で普通は 20 cm ぐらいである。
巣は支柱の継目に設けられた踊り場に設けられ、平らな雑然と積み上げた山で
平らな産座を伴う外観をしている。低い踊り場に設けられた巣については、高い
ところのものよりも大きな直径を持つ特徴があり、120-150 cm に達する。これは
崩壊した踊り場の巣にも特徴的である (踊り場の一部が壊れて巣の産座が沈下する
と、鳥は巣を活発に高く増築し始めるように見える。春には同じ状況でも鳥はわず
かな小枝を巣に敷くのが普通である。というのも造巣する刺激がなくなるからで
ある)。
高さ 10-18 m の木に造られる巣はより大きなサイズである: 直径は 1-2 m, 高さ
0.9-1.5 m, 明らかに建築されたばかりの巣はより小型であるが、古く何年も続けて
使われてきた巣はより大型である。類似の建築サイズは崖に営巣するつがいに
おいても認められる。
ウラル地域に知られている 330 の巣 (276 の営巣場所において) で、206 は木にあり、
97 は塔に、12 は 崖にあった。
中央タイガの松林の成育地域である平野の北方林では、それらが伐採された後
ワシが事実上測地塔にのみ営巣する拠点が形成される。巣を造るにあたって、
イヌワシは通例塔の2つの高い踊り場の一つを用いるが、圧倒的に多くの場合
20-25 m の高さにある最も高いものを用い、よりまれに 5-8 m の高さの低い方の踊り場
を用いる。すでに述べてきたように、塔での営巣は多くの場合もろくあまり大きく
ない。高いところでは特にそうで、木に造られる巣とはこれらの点で違っている。
Verkhnekamsk 沼地では 40 の既知の巣のうち、34 は塔に、6つのみが木にあった
(すべて松であった)。
Tavdinsk 沼地では 65 のうち 63 が塔で、2が松であった。
山岳ウラルではイヌワシはほぼ木にのみ営巣する。210 の既知の巣のうち、
198 が木に造られ (137 が松、43 が白樺、12 がカラマツ、11 がカシ、6 がヤマナラシ、
3 が杉、1 がモミ)、12 が 80-120 m の垂直な崖にあった。崖に造られた巣の全ては
南ウラルであった (Belaya 川 7、Nugush 川 3、Zilim 川 2)。
以前は Vishera 川や Chusovaya 川の崖にも巣が知られていたが、この 10 年では
Perm', Sverdlovsk 州でイヌワシの崖への営巣は途絶えてしまった。これについて
はちょうどワシの抱卵期のに川を訪れたり崖を登ったりする旅行者によってもたら
される不安要因が決定的な役割を果したように思われる。
南部の平野地帯では 15 のイヌワシの巣が知られており、5 が松に、4 が白樺に、
2 がヤマナラシ、2 がカシ、カラマツとニレに1つずつであった。
大多数の地域で、イヌワシは人の居住地区から 10 km かそれ以上離れたところに
営巣しているが、南ウラルだけがこの距離が 1 km まで縮まっており (6 例)、200 m の
例すらある (Kuznetsovsk 山脈、Belaya 川)。
巣にはほとんどの場合1羽の雛がいる。研究の全期間を通じて2羽目の雛の
孵化と巣立ちが成功したのは6例に過ぎず、すべて南ウラルでのことであった。
調査した 23 のクラッチのうち、20 で1卵から、3つで2卵からなっていた。
繁殖の早い段階の巣の多くは Verkhnaya Kama と Kamsk 貯水場で調べられた。
ウラル全体としては、イヌワシでは2卵のクラッチがずっと多い可能性を否定
できない。おそらくはるかに多くの巣で2羽めの雛が孵化しているが、6月まで
に2羽めの雛の存在痕跡が消えさってしまう (年長の雛が食べてしまうのか、ある
いは巣から投げ出されて、そこでテンやキツネが雛を拾い集めるのか。イヌワシ
の巣の下には非常に頻繁に食べ物の食い残しが観察される)。
我々は1卵からなる 14 の巣において繁殖の成功を調査することができた。11 の
巣で雛の孵化し、そのうち 10 の巣で巣立った。つまり繁殖成功率は 71% であった
(卵の死亡が 22%、雛の死亡が 10%)。
年によっては 10-80% のワシの個体が繁殖に取りかかることができないか、営巣に
成功しなかった。
我々の考えでは、イヌワシの巣における死亡の主な要因は人間の経済活動で、
不安や密猟によって多くの卵や雛が死んでいる。最近ではイヌワシの巣のある
塔の倒壊事例も増えてきている。我々もそのような例を6つ知っている (4つは
Perm' 州、2つは Sverdlovsk 州)。
[フェノロジー]
ウラルにおいてイヌワシは留鳥で、若鳥とパートナーを失った成鳥のみが
大なり小なりの距離を漂行する。
成鳥は3月中旬から下旬に巣に現れる。北では4月初めである。
産卵は4月1日から5月5日の間である。産卵が主に行われるのは4月の最後
の5日である。最も早い産卵は南ウラルで知られており、1998年3月27日である。
最も遅いのは中央ウラルで1996年5月11日である。極圏地域ではイヌワシの繁殖
時期は 10-20 日遅くなる。3月27日以前の時期に産卵があることは否定できない、
というのは Perm' 動物園では3月25日にすでに産卵するからである。
雛の孵化は5月5日から6月8日で、6月10日以降は調査した巣の全てに雛が
いあた。最も早い孵化時期は 1997 年 Sakmar 川で、ここでは5月25日に 30 日齢の
雛が記録された。
雛が飛べるようになるのは7月20日から8月10日で、8月15日には調査した営巣
地域の全てで十分飛べる巣立ち若鳥がいた。巣立ちの後は大部分の地域で 10-30 日間
巣立ち若鳥は巣で、あるいはその近くで夜を過ごす。この期間に人が巣に現れると
巣立ち若鳥は声を出すが、成鳥が巣で声を上げることはずっとまれで、これは南の
地域により特徴的である。
9月から10月にイヌワシは活発に漂行を始める。ステップ地域ではこの時期に、
マーモットの大きな生息地や、渡りのガンの集団や、動物の死体に集まる多くの
若鳥が現れる。
[行動特性]
このワシの研究の過程で、この種か個々の集団に特徴的な一連の行動特性が認め
られた。
特に、北の平野地域の事実上全ての鳥は、彼らへの不安要因のために、巣の下に
人が現れるずっと前に気づかれないように巣を去り、不安要因がなくなるまで巣に
現れない。巣を去った鳥は離れた木の樹冠に隠れるか、巣からずっと離れたところ
を高く帆翔して、樹冠が観察者から隠してしまうようにする。
南ウラルではイヌワシは人をそれほど恐れず、巣に人が現れるとその上を頻繁に
帆翔し、叫び声 (猛禽特有の断続声) を時々上げて抗議する。さらにこの行動は崖に
営巣する鳥により特徴的である。
1988-89 年、我々は Kamsk ステーションで巣やつがいの狩猟場所から離れたブライ
ンドから観察を行った。繁殖の早い時期には成鳥のうち1羽が食物を持って巣に
2-4 回現れ、孵化の後はずっと頻繁になった。獲物は巣の近くにある見張り場で解体
されるか、よりまれにはすでに解体されて運ばれた (87 のうち 8 回)。通例一日に雛は
運ばれた獲物の 2/3 を食べた。主な獲物はクロライチョウ 45.6% であった。イヌワシ
の狩りが最も頻繁に行われるのは7時から 10 時および 15 時から 17 時で、20 時以降に
運ばれる獲物はそれほど多くなかった (87 のうち 18)。最も早い獲物を持って巣への
飛来は 5:50で、最も遅いのは 23 時だった。
急襲の成功は開けた沼地上流にある木の梢づたいに低く飛ぶ時に主に記録された。
鳥は飛びながら森から獲物を追い立て、沼の上の地面に押しつけて脚で打った。
営巣時期の狩の際に人に遭遇するとイヌワシは森に深く逃げ去り、木の間を迅速に
旋回して広く開けたところで、非営巣時期でもよくあるように上空へさっと舞い
上がった。まれにワシは帆翔から急襲を行ったが、これは通例効果がなかった。
異なる時期、異なる地域で我々は興味深い狩の事例を観察した。
Permisk 州の Kishertsk 地域で1988年7月 28-30 日の草刈りの時期にイヌワシが
何度も森から平野中央に飛び立ち、機械の騒音を恐れず、刈り取った草から追い
出したあるいは傷ついた動物を奪い取った。このワシはトラクターから 20-30m の
距離で後をついて飛行した。
Perm' 州の Gajnsk 地域で、1989年2月15-18日、1羽のイヌワシが 8-9 時ごろに
わなの列を飛び回り、4日でわなで死んだ5匹のノウサギ、2匹のキツネを食べた。
Bashkiria で 1995-1997 年、我々は家禽のガチョウを意図的に狙った狩に遭遇した。
居住地区から 200-800 m 離れた岸辺で休息しているガチョウを1羽のイヌワシが見張
り場に運ぶのを3回観察した。
1996年6月、我々は Bashkortostan 共和国の Meleuzovsk 地区、Belaya 川で、1羽の
イヌワシが放し飼いにされた 25 頭の群れから1頭のヤギを崖から突き落し、ばらした
動物をつつき、後ろ脚を巣に持ち去ったのを観察した。さらにほとんど全てのヤギは
ワシの急襲の際に崖の突出部の下やくぼみに隠れた。このワシの巣の下には3頭以上
のヤギの食い残しがみつかり、おそらく死体 (を食べたの) ではなかっただろう。
1997年、Kuvatovo 市の住民が2羽のイヌワシが居住区の上で、崖から引き下ろした
若い子ヤギを引き裂いたことを物語った。
イヌワシと他の猛禽類の関係については以下のようにみられる。イヌワシは自身の
営巣地域において全ての猛禽類を攻撃する: 小型のオオタカやノスリはしばしばイヌワシ
の食料になってしまう。大型の海ワシやミサゴはふつう無傷でのがれ、出会った
場所から退却する。南ウラルではイヌワシは営巣地域の近くに営巣するカタシロワシ
にしばしばつきまとわれる。マーモットの大きなコロニーに対する狩が同時に行われ
る場合、イヌワシとカタシロワシの間で獲物をめぐる衝突がしばしば発生する。その
際にはカタシロワシが常に負け、イヌワシからなるだけ遠くへ早く去ろうと努力する。
Sakmara 川で 1997 年に我々はイヌワシが1日に6回、近くに営巣する2つがいの
カタシロワシを軽くあしらうのを観察した。ワタリガラスに追われて巣のある崖の近く
まで飛んで近づいた時にカタシロワシが攻撃され、さらにワタリガラスはイヌワシが
目に入ると方々へ飛び去ったが、イヌワシが去ると後でカタシロワシの周りに再び
集まった。
[食料]
イヌワシの食料は個体によってさほど多様ではない。イヌワシの食料の性質に常に
特徴的なのは、大型の哺乳類や鳥類が含まれていることである。
森林帯ではユキウサギ、クロライチョウ、ヨーロッパオオライチョウが主要な食料
である。森林帯のいくつかの地域ではクロライチョウが、場所によってはヨーロッパ
オオライチョウが首位を占めるが、全体としては食料の構成は安定している。
地域の森林ステップ、ステップ帯では大型のカラス類 (ミヤマガラス、ハシボソガラス、
ワタリガラス)、ウサギ類 (ユキウサギ、ヨーロッパノウサギ) が餌の多くを
占める。場所によってはマーモットが首位を占める。
冬期には食料に顕著な割合で死体が含まれる。大きな集落や町の近くに定期的に
営巣するいくつかのワシはカラス類や野犬が十分に多く集まって餌をとるゴミ捨て
場に集まる。
1987 年、Perm' 州 Usol'sk 地域で越冬した2つがいのイヌワシのペリットや食べ
残しを 60 採取した。その中には 45 の動物の食痕がみつかり、そのうちペット (家畜)
動物とシナントロープ種が 15.5% を占めており、その中には以下のものが含まれる:
犬 6.7%, 鶏 2.2%, ズキンガラス (ハシボソガラス) 2.2%, コクマルガラス 2.2%,
カワラバト 2.2%。興味深いことに、これらの鳥の巣においてもやはりペット (家畜)
動物の食痕がみつかり、獲物全体のうち 8.4% を占めていた: 犬 5.0%, 猫 1.7%,
鶏 1.7%。
1995 年 12 月から 1996 年3月にかけて Zhabrej (Perm' 地域) にある崖で 74 の
ペリットや食べ残しの中に 82 の獲物の食痕が観察された。その中には以下のものが
含まれる: ズキンガラス (ハシボソガラス) 33 (40.2%), コクマルガラス 2 (2.4%),
ドブネズミ 10 (12.2%), ユキウサギ 7 (8.5%), 犬 4 (4.9%), 猫 2 (2.4%) および
さまざまな死体や残骸 20 断片 (24.4%)。
面白いことに、Bashkiria 地方の南部で、8-10月にイヌワシは山麓地域に位置する
家畜の野営地や動物の埋葬所をよく訪れている。そこでは死んだ家畜の残骸を食べ、
骨さえも嫌うことはない。1996 年、我々は1羽のイヌワシが夏の家畜野営地から
300 m 離れた崖に位置する見張り場に一日かけて毛皮や筋のついた大きな骨を約 10 個
運ぶのを観察した。崖下の骨の山から判断するにこのイヌワシは飛ぶたびにこれを
定常的に行ったのだろう。
(食物表 省略)
イヌワシには天敵はいない。我々はイヌワシの雛が猛獣(猛禽)の餌になった事例を
2回しか知らない: Perm' 州 Gajnsk 地域でイヌワシの巣立ち若鳥を熊が食べた例と、
Bashkorstan 共和国の Burzyansk 地域でワシミミズクの巣に食べ残しの羽がみつかった
例である。
タイガでの主な食物競争者はヤマネコであり、ステップ地域や森林ステップ地域
では他のワシ類である (カタシロワシ、ソウゲンワシ)。
ワシが地域住民によって撃たれている。Perm' 州領域で 10 個の使われている巣から
たった1羽の巣立ち若鳥が生き残っただけである。さらに主な死亡は巣立ちの1週間
前から巣立ち後数週間の期間に観察された。
1996 年に行ったアンケート調査が示すところでは、Perm' 州の北部地域では事実上
全ての狩猟者がワシを撃ったことがあり、それは事実上いつも巣においてであった。
過去 10 年の間に Perm' 州で 250 羽のワシが捕獲され、そのうち 180 が撃たれたもの、
70 がわなで捕獲されたもの (さらに送電線での死亡例が2例ある)。
この数値は、ワシに対していかほどに野蛮な態度になれるのかショッキングであるが、
ただ厳然たる事実に過ぎない。
皆伐もイヌワシに損害を与える。一面で皆伐は広い狩場と食物基盤の生息場所と数
の増加を提供することで有利なところもあるが、別の側面で営巣に適した木を制限
してしまう。巣のある木が伐採されなければ、この影響による状況は総じてそれほど
壊滅的ではない。Perm' 州だけでもイヌワシの巣の損傷が 25 例知られている。
西ウラル、東ウラルの平原タイガで塔に営巣するワシの個体群の状況は心配で
複雑な状況にある。彼らの新しい巣作りの場所に関連してほかならぬ巣の作り方
が変化してしまった。90% の事例で塔の板張りのプラットフォームの上に小型の
小枝の寄せ集めのような巣に見える。結局これらのワシは大きな巣を作る能力を
事実上失ってしまった。そして 1950 年代に建設された塔は現在では朽ちて倒壊して
いる。この5年間でこの結果既知の6つがいが営巣を止めてしまった。これらの
ワシが巣作り用の板張りのプラットフォームを見つけられなければ、彼らの運命
はかつては広大なロシアの多くの場所で生息していた鳥と同じようになるだろう。
Kamsk ステーションのイヌワシ営巣地域の活用状況の特性を表 (省略) に示す。
これまで 13 年で3つがいが 21 羽を巣立ちさせることができた。理論的には Kamsk
のワシは 39 羽を巣立たせることができるはずだが、実際には 21 羽の若鳥が巣立った
のみである。つまり期待される子供の数の 53.8% であった。ここは営巣場所が保護
されておりワシが撃たれることのない地域ある (ここでは不安要因のみが働いている)。
述べてきたことからこの地域でのイヌワシ個体群の主要な損失は狩猟とさまざま
な要因による巣での死亡がもらたしているように見える。
疑獲物を通じて鳥の体内に入りこんだ農薬もまた影響を与えることは疑いないが、
S. Bystrykh の見解によればイヌワシにとって現在大部分の生息地域で目に見える
要因にはなっていない。
[数の動向、この種の状況の分析、近い将来の状況の予後]
イヌワシは他の猛禽類と同様負の状況をまぬがれていない。
イヌワシの数の減少過程は 1960 年代に特に顕著であったが、多くの地域で 1920-1930
年代にはすでに減少が始まっていた。ヨーロッパとロシアにおいてこの過程は
何らかのはっきりした違いなく、ほとんど同時に起きた。
1980 年代までに多くの西ヨーロッパ地域、ロシアのヨーロッパ中央地域の州、
旧ソ連の森林ステップ、ステップ地域の国でイヌワシは営巣しなくなった。
ヨーロッパではイヌワシの安定した個体群は山岳地域 (そこでは数は大なり小なり
均等に分布しており、危険な状況にない) にのみ残っている: アルプス、ピレネー、
ギリシャ、オーストリア、英国の山岳部。西ヨーロッパの平野部ではイヌワシの
数は減少を続け、その理由で広大な地域で完全なワシの絶滅や大半の個体群の
孤立が危険視されている。いくつもの国の平野部の個体群の衰退にもかかわらず、
特にノルウェー、フィンランド、スイス、フランスではこの種の数が安定している
ことが観察されている、いくらかの増加も記録されている (Galushin 1980;
Bauser 1977; Bergman 1977; Garzon 1977; Willgons 1977; Nilsson 1981;
Saurola 1985; Krol 1987)。
現在、いくつかの個体群に好転があるにもかかわらず、種の個体数においては
現在もなお減少プロセスが続いている。ヨーロッパではこの種のある程度の大きさ
の孤立個体群が散在しているが、それはこの種が本質的に脅威に晒されていること
をすでに示すものであり、ロシアの多くの地域ではイヌワシの分布域の南限は
何百 km も北に偏移し、その結果一体をなす地域の自然生態網から切り離された。
ウラル地域ではイヌワシの数の減少プロセスは、厳しい政策 (=強制収容地のこと)
に変えられた地域や森林伐採に特化した ITU (= Ispravitel'no-Trudovaye
Uchrezhdeniya, 強制労働機関) ネットワークとともに始まった。1950 年代終わりまで
には平野部の事実上全ての地域と山岳部の多くの地域はさまざまな年齢の伐採地に
変わった。1950 年代に最初の急激な数の低下が起きたと思われ、イヌワシは広範な
地域で消滅した。
皆伐はイヌワシにとって二面的に影響する。タイガの伐採の結果イヌワシの主な
餌であるノウサギやクロライチョウに富んだ土地が現れる一方、営巣樹木の制約
要因にもなる。まさにこの時期 (1950 年代) ワシの数の減少を背景に、広範な伐採地
に現れた塔で営巣への適応傾向が現れたように見える。
1960 年代には測地塔が建てられなかった山岳地域では広範な森林伐採を背景に
数の減少プロセスが続いたが、平野部では新しい営巣場所を身につけたつがいの
おかげで数はある程度安定した。数の増加は続かなかったが、これはこの時期
ロシアに広く展開した猛禽撃ち落とし会社の結果のように思われる。
これらの全ての傾向の結果、山岳部では集中的な山岳森林伐採のためにイヌワシ
は急激に数を減らし、農業地域では完全に消滅し、平野林でもほぼ完全に消滅した。
1990 年代まではこの種の広範な生息域で、あまり開拓されていないか経済活動
で損なわれなかった山岳地域 (ピレネー、アルプス、コーカサス、南ウラル、
北部や極圏ウラル、天山、アルタイ ほか) で一連の原住個体群と、一方向性の人の
経済活動に適応した一連の個体群 (Kamsko-Vychegodskie 森, Kondinsk 低地など)
が残された。
南ウラルではイヌワシ個体群に有利な一連の要因が働いてきた - それは
"Bashkir人のイヌワシに対する態度" (Bashkir では最近まで鷹狩りが行われて
きて、Bashkiria は現在中央ロシアでワシが撃たれない事実上唯一の場所である),
"Bashkirでの伝統的な自然の利用方法" (集中的な畜産、山岳森林地域における
もの、平坦な分水嶺のモザイク状の松林伐採地を含む), "起伏の激しい土地と
レクリエーション利用の少なさ" (南ウラルの Bashkir のみで崖に営巣する個体群
が残っている。これはウラル水準でも最も近づきがたい崖が豊富で、旅行者に
よる川の利用が少ないことによると思われる)。
北ウラルでワシが保存されている原因は一つであった - 未開発と到達しにくさ
である。
タイガ内部林や北部タイガ平野林については、またしてもこの種の手つかずの
残存生息場所 (レフージア) として知られる -
水ごけに覆われた広い沼地上流に面した松林の島や周辺のおかげでイヌワシが
保たれた。沼地がモザイク状のため一帯の伐採を阻み、ワシが繁殖できる手つかず
の地域として残った。一方向性の土地の開拓 - 1950-1960 年代の森林伐採と閉鎖
- "厳しい政策" 地域と住民による利用の制限のある、所轄官庁の (内務省管轄の)
森 - の結果、残存生息場所から個体の流出のおかげでイヌワシに新しい条件へ
適応する可能性が生まれ、ワシが皆伐された広大な地域へ移住し、そこでは営巣
に適した木が限られていた結果、塔に営巣するようになった。
南部タイガ林でも同様の (すでに特徴を述べたが) プロセスが進み、住民の数の
多さ、中央ヨーロッパ地域から移住させられたさまざまな階層の人々による数の
増大、森林地の強度の分断、総合的な経済強化を背景に伐採場所の土地を農業用地
に転換すること、さまざまな領域の狩猟活動、そして猛禽類撃ち落とし会社による
ワシの駆除の結果、南部タイガではこのプロセスがイヌワシを事実上ゼロに追い
やった。
森林ステップ、ステップ地域ではこの時期、松やカシの林の伐採、ステップの
開墾、そして主要食物であるマーモットの根絶の結果、イヌワシは壊滅的な早さで
絶滅した。
1990 年代までに、イヌワシはステップ、森林ステップ平野地域で絶滅し、南部
タイガ帯や山岳ステップ地域で広い開墾地に分離された不定期に繁殖する単独の
つがいのいくらかが残り、山岳-森林ステップ地域と一連の山岳森林地域で、
山岳森林地帯からの個体の流出によってのみ保たれている孤立個体群に変わった
いくらかの地域的なイヌワシ集団が保たれた、中央・北部タイガの大部分では
イヌワシは数を減少させたが、沼地に富んだあまり開拓されていない地域とに
それなりに集中する、均一に分布する鳥としては残った。あまり開拓されず人間の
経済活動で傷つけられていない一連の山岳森林地域においてのみイヌワシは適正
数が残された。
現代では場所によっては保護の結果、しかし大部分の地域では経済活動の低下
を原因として、ヨーロッパでもロシアでもこの種の数の安定化や、いくらかの地域
では増加の兆候が認められた。
ウラル地域で、我々はイヌワシの数のなんらかの著明な増加には記録していない。
地域全体としては数は一定水準でバランスしている。個体群の繁栄 (南ウラル) が
あるが、また減少もある (Prikamsk)。繁栄したイヌワシ営巣集団の子孫が皆、
順調でない地域の個体の穴を埋めているように思われる。
南ウラルではおそらくなんらかの数の増加が観察されているが、長期にわたる
定常的な観察が欠けているためこの過程は見届けられていない。より広域での
イヌワシの数の動態を評価するとしても、それは安心させられるものではなく、
逆に用心するものである。Sushkin and Sabaneev の時代 (19世紀末) からイヌワシ
の生息域は2倍以上縮小し、南限は北に移動した。以前はイヌワシの見本市が
開かれモスクワの買い手のために Bashkir 人がイヌワシを捕まえていた場所でも
イヌワシは営巣せず、全域がカタシロワシが住み着いている。カタシロワシは
かつての住人のいなくなった典型的なイヌワシの生息場所を占め、現在では北へ、
森林地帯の奥へ進出している。
我々が定期的なモニタリングを行っている Chsovaya 川では 1988 年にはまだ2つ
がいのイヌワシが持ちこたえていたが、不安から営巣には着手しなかった。
1990 年には2つがい目のが河川渓谷で記録されなくなった。1995 年からはイヌワシ
のつがいが再び Chsovaya 川に現れたが現在に至るまで営巣が確かめられていない。
Kamsk ステーションではこの 10年イヌワシの数に変化はない - 3つがいが営巣。
新しいつがいの出現は外ウラルでのみ記録されている。以前の生息地に再び
現れたワシの興味深い特徴として、全く異なる食物との結び付きがあることが
注目される: ノウサギ、クロライチョウ、あるいはマーモットに特化した鳥は
基本的に消え去り、再び現れたものは事実上カラス科と死体のみを食べている
(同様のプロセスは開拓された南部タイガの北側の森林地帯に進出したカタシロワシ
についても起きている。彼らはハタリスあるいはマーモットから事実上カラス科、
死体、クマネズミ、キスゲネズミのみに切り替えている)。
イヌワシがより手に入りやすく数の多い餌に方向転換することは十分よい進歩
である。それはワシへの忠実な態度によってワシが農民の中に住むよう導くもの
である。結果的に我々はこの猛禽の数はまさにこのプロセスのおかげで増加を
始めると考えるようになっている。
ロシア経済のなんらかの重大異変 (注: この記事が書かれたのはロシア経済が崩壊していたころ)
がなくとも、急速な数の増加は明らかにはならないにしても、
2000 年には南タイガ林でのイヌワシの数の増加傾向が明らかに
認められるだろう。今後 3-5 年でこの地域でのイヌワシの数は 500 つがい程度で
バランスがとれるのではないかと我々は考えるようになっている。
[保護の手段]
イヌワシは森林帯の多くの地域で生態学的ピラミッドの頂点にある。ステップ、
森林ステップ地域でイヌワシの生態的地域を占めることのできる種類のワシは
存在するとしても、北ユーラシア森林では食物連鎖でイヌワシに取って代わる
ことのできる種類はない。生態系の全体的な安定のためにはこの種が地域の 80%
の領域に、1000 平方 km に 2-3 つがい(最低でも1つがい)の密度で営巣する必要が
ある。
この地域でイヌワシ保護のための主な手段は以下のものである:
1 - テリトリーの保護。この地域でこの種の保護を保証するだけの統一された特別自然
保護地域ネットワークを設けること
2 - この種の営巣に適した場所の、この地域のタイガ内森林地域の全ての領域で
緊急の生物工学的対策を組織すること
3 - さまざまな住民グループの間、特に自然と直接の関係のある範疇の人々の間
にこの種の保護を訴えること
イヌワシの領地の保護には以下のものが含まれている必要がある:
1 - イヌワシの営巣数が最も多い場所 (5-50 つがい)、あまり開拓されていない地域、
高度に開拓された地域いずれにも (原住個体群および人に依存した個体群)、保護区
(大きな OOPT かその複合体) を設ける。第一種の生息場所。
2 - 人為的景観における地域営巣個体(1-2つがい)にサイズの大きくない自然保護
地域 (OOPT, 注: 国定公園などを含むいろいろカテゴリーの保護地域の総称の
よう http://en.wikipedia.org/wiki/Protected_areas_of_Russia
ロシア独自の概念のようで以下 OOPT とそのまま記す) を整える。
第二種の生息場所。
3 - 前2種のカテゴリーに入らない地域でイヌワシ営巣場所での経済活動の厳しい
制限。
経済活動の結果、この種が分断されている地域では特に注意が必要である。
そこではまず第一に生息地に対する負の影響を排除する必要がある - イヌワシが
生息している地域も、類似したイヌワシが存在しない地域も -
そのようにして分断地の間にある種の回廊を設け、
それらの間に営巣環境に類似した保護を行うことで、分断された生息地を持つ
この種を保全することができるかも知れない。
イヌワシの生息地において、地域の保護を計画する、また OOPT を計画するに
あたって、つがいの営巣場所では半径 500 m から 1 km では完全な禁止に至るまで、
経済活動を規制する必要がある。もし営巣場所が何らかの大きなサイズの地形
(崖、島状の林、茂った丘のある沼地) で天然に区切られた環境の中心にあれば、
全域を一つの営巣環境として完全な保護の下に置く必要がある。イヌワシに
とってその狩猟環境を保全することは緊急に必要である。それゆえこの種の
保護地域を設けるにあたって、特に北部タイガにおいては、つがいの狩猟環境
を、経済活動を特別に制限した形で含むように OOPT を設けることは理に
かなっている。
中央、北部タイガ森林の平野部では約 90 %のつがいが測地塔に営巣している。
これらの塔はすでに 1950 年代に建設されたもので、現代では寿命を終えて倒壊
している。そして、営巣に適した木の全体的な制限と、多くのつがいの塔の
板張りのプラットフォームでの営巣への遺伝的適応の結果、北半分の地域
全体でイヌワシの生存の未来に問題を投げかけている。複雑な状況からの一つ
の出口としてイヌワシを人工プラットフォームに誘致することがある。試み
が示すところでは、塔に営巣してきたワシは古い巣を残したままでも喜んで
プラットフォームに移住する。
1989 年から野外研究センターによって6つの区域で 29 のプラットフォーム、
1区域あたり 4-6 個、を設置した。2区域ではイヌワシが定期的に営巣した
(1992 年に最初のつがい、1994 年に第2つがい)。最初の例では5つのうち2つ
を定期的に利用し、2つめの事例では4つのうち2つを利用した。その後巣の
ある塔が倒壊した。2つの区域では古巣を塔に残したままでプラットフォーム
に定期的な営巣が観察された (最初のつがいが 1993 年と 1994 年、2つめのつがい
が 1993 年と 1996 年)。その上プラットフォームでの営巣後最初のつがいが再び
塔に営巣した。しかし2つめのつがいは2年 (1994, 1995) にわたって営巣せず、
1997 年はプラットフォームでの営巣に成功しなかった。プラットフォームの
2つがいは営巣しなかったが、5つのうち2つめと3つめをとまり場として
利用した。後者では巣が造られたが活用されなかった。
巣を塔に残したままでイヌワシをプラットフォーム (Perm'州立大学? 動物学教室設置)
に誘致する成功例の報告が Perm' 州 Gajnsk 地域でも存在する
(Shepel', Fisher, 口述, 1991)。
ベラルーシでも人工巣にイヌワシ誘致の試みが成功している (Ivanovskij 1985)。
このように Kamsk-Vychegdsk-Pechrsk と Tavdinsk-Kondinsk イヌワシ個体群
に対する集中的な人工巣設置によって彼らに本質的な支持を与えることができる
かも知れない。この方向での活発な研究がこの個体群の数の増加をもたらす可能性
があるように我々は思える。
[OOPT におけるこの種の所在とその保護のための OOPT ネットワークの進展の展望]
Perm' 州ではイヌワシは 500 のうち 26 の自然保護地域に営巣している。
66 の知られているつがいのうち自然保護地域に 25 が営巣している
(知られているうちの 37.9 %)。
Perm' 州の自然保護地域全体でイヌワシの地域個体群の約 30% が営巣している。
この種の主な OOPT は Verkhnekamsk 自然保護地域集合体にある Verkhnyaya Kama
に存在している: 2つの動物禁猟区 "Alovskij", "Pernaty"、天然記念物とミニ
動物禁猟区の並び、そして Visherskij 自然保護区内である。残りの OOPT には
イヌワシは1つがいしか営巣しておらず、高い密度をなしていない。
イヌワシの保護のためにミニ動物禁猟区を Gajnsk (8), Kosinsk (1),
Kishertsck (1) 地域に、それぞれ面積 1 ヘクタールで組織することが素直で
ある。1つの営巣地区の立法上の保護にもかかわらず、別の様式の2つの OOPT
(伐採が全面禁止されている) に位置するものが Perm' 州自然保護委員会の完全
な黙認のもとに伐採されてしまった。
州の南側半分の開発された地域と Verkhnekamsk 高地においてはイヌワシの
領域的保護は事実上欠落している。ここでは 23 の知られているつがいのうち
1つがいが保護されているだけである - Kishertsk 地域のイヌワシの保護の
ために特別に儲けられた "Chertova Katushka urochishche (= 自然境界、
区画のような意味のよう)" ミニ動物禁猟区において。
中央ウラルの知られている4つがいのうち、1つがいが Basegi 自然保護区内
で完全に保護されているに過ぎない。
Perm' のイヌワシの生息地を信頼できる形で保存するのためにはまず第一に
Kumikushsk と Kamsk 水-沼地群を完全な保護下 (自然保護区か国立公園) に置き、
Verkhnekamsk 高地地域に大型の一連の OOPT を組織し、南半分の Perm' 州と
中央ウラル山地の全てのイヌワシ営巣テリトリーを完全な保護下に置く必要がある。
Sverdlovsk 州では 350 のうち 9 の OOPT に営巣している。
65 の知られているつがいのうち OOPT に 11 が営巣している (知られている
うちの 17%)。
3つがいは Yansaevsk 動物禁猟区に、2つがいはVisimokij 自然保護区
複合体で保護され、1つがいが Koizhakovskij Kamen' 山の保護区群である
Denezhkin Kamen' 自然保護区、5つがいが Tavda 川流域の動物禁猟区に
営巣している。
Sverdlovsk 州の自然保護地域全体でイヌワシの地域個体群の約 10% が営巣
している。そのうえ地域のイヌワシは州の自然地域のうち一つも満足の行く
形で保全されていない。
イヌワシの地域個体群の生息地を信頼できる形で保存するのためには、
以下の地域にさまざまなカテゴリーかつ広い面積の OOPT を設立することが
必要である: Sarana 村から州境に至るまでの Ufa 川渓谷を含む Ufimsk 台地、
Vogulka 川の上流、Konovalovsk 山脈、Sysert' 川上流、Kosolmansk 沼、
近隣の山と Kedrovyj Spoj 山脈を含む Konzhak 山塊、Burmantovo に至る
Loz'va 川渓谷全体と上流を含む中央ウラルの山塊、Pelymiskij Tuman 湖と
隣接する沼地、Vagil'sk 水-沼地群、Chrnoe と Kuminskoe 沼の一塊、
大 Indra と Tunba 湖を含む Tavdinsk 水-沼地群。
Lyavlinskij 禁猟区を完全に静かな詳細に熟慮されたモザイクゾーンで複合型
あるいは動物型の形で再建することはたいへん望ましい。
Bashkortostan 共和国では 180 のうち 9 の OOPT に営巣している。
共和国の OOPT に 23 つがいが営巣している (知られているうちの 18.8%)。
南ウラルのイヌワシのもっとも顕著なグループは 70% が保護された状態に
ある: Shul'gan-Tash 自然保護区、Bashrikiya 国立公園、そして全体として
12 つがいの営巣が知られている Altyn-Solok 禁猟区群である。
Yuzhnoyural'sk (南ウラル) 自然保護区領内には4つがいのイヌワシが営巣
し、2つがいが Bashkirsk 自然保護区、2つがいが Ikskij 動物禁猟区領域
に営巣、1つがいが Shajtan-Tau 動物禁猟区領域、そして1つがいが Birskij
動物禁猟区領域である。
Ufimsk と Zilairsk 台地の中央山岳地帯と外ウラルの OOPT にはイヌワシは
分布していない。
これまで述べたこと全てから Bashkiria 領内の OOPT に Bashkiria の
イヌワシ個体群の 15% が営巣していると結論される。そのうえ地域のイヌワシ
は自然地域のうち一つも満足の行く形で保全されていない。
Bashkiria のイヌワシを保証できる形で保護するためには、共和国のこの種の
主な生息地のある山岳森林地帯に OOPT ネットワークを拡大する必要がある:
Zilim 川と Inzer 川の禁猟区の整備、ここにはさらに2つの ... が集中して
いる。
[ボネリークマタカの分布]
Moleon et al. (2024) Wildlife following people: A multidisciplinary assessment of the ancient colonization of the Mediterranean Basin by a long-lived raptor
ボネリークマタカ (和名はクマタカが付くが、現在は Aquila属でイヌワシの近縁種) は基本的に熱帯の種だが、なぜ地中海地域にも生息しているのか。
イヌワシの方がボネリークマタカより優位で、イヌワシと同じところにはボネリークマタカは住めない。
氷期に地中海地域がレフージアになり、イヌワシには適した環境だったがボネリークマタカには向いていなかった。その後温暖になるとともに人が入って人為活動により敏感なイヌワシの空白地が生まれ、50000 年前ぐらいにボネリークマタカが定着したとの考え。化石記録からもボネリークマタカの方が新しく定着したことがわかっている。初期の個体群はごく少数だったと考えられている。
ボネリークマタカに関連して興味深い話がある。Trainor et al. (2013)
Bonelli's Eagle Aquila fasciata renschi in the Lesser Sundas, Wallacea: distribution, taxonomic status, likely origins and conservation status
ボネリークマタカの主要分布 (地中海地域とインド) から離れてインドネシアの小スンダ列島に孤立個体群があり亜種 renschi とされる。
小型で模様も多少違い、分布が離れているため別種と考えられたこともあったが、遺伝的にはほとんど違いがないとのこと (ただし詳しい結果がこの時点で発表されていない)。気候変動による隔離があったと考えにくいとのこと。この著者は人が入植の際に持ち込んだ可能性を否定できないとしている。同地域に過去に持ち込まれて定着したと考えられる種類は複数あるとのこと。
ボネリークマタカは生態的には比較的弱いようなので、気候変動 + 他種との競争の結果も考えられるのかも。
同様の分布を示すチュウヒワシは亜種相当の違いが明らかにされた: Ng et al. (2017) A new subspecies of Short-toed Snake-eagle from Wallacea determined from morphological and DNA comparison。
チュウヒワシは長距離の渡りをする種類なので遠距離の個体群が存在してもそれほど不自然でないかも。
[サハラ砂漠以南のイヌワシ]
イヌワシは北半球の比較的高い緯度に生息するため北方系の種とみなされ、サハラ砂漠より南のアフリカにも生息していることはあまり知られていない。マリとニジェールに繁殖成績のよい個体群があり、高い繁殖成功率はノウサギが豊富であり競争種もないことによるが、同地域の他の猛禽類が減少していることに比べると異例である:
Clouet (2006) Golden Eagle Aquila chrysaetos in south Sahara。孤立個体群で亜種相当になるかも知れないと記載がある。
一方比較的最近発見され、世界でも南限のエチオピア個体群は世界のイヌワシの中でも巣立ち率 0.28 と最も低く、放浪個体も少なく近隣の繁殖個体群もないのでこちらは非常に危ない状態とのこと。
こちらは同所的に生息するコシジロイヌワシ (下記参照) とも熾烈な競争関係にある。Clouet (1999) The Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in the Bale Mountains, Ethiopia。
Clouet and Barrau (2015)
Decline of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in Ethiopia、
Bautista et al. (2017)
Situation of the Ethiopian Golden Eagle Results of the Golden Eagle Preliminary Survey in Bale Mountains National Park (Ethiopia) Prepared by Jess Bautista (Wilder South) Survey team によれば 2017 年時点で成鳥全体で 15-20 羽ぐらいしかいないだろうとのこと。
非繁殖の若鳥が観察されていない。低地は人の利用で生息できず、4000 m ぐらいの高地に追いやられている。険しい崖に営巣するが、家畜を襲うヒョウの隠れ場所となる崖のふもとにある草地を人が焼いてしまう。繁殖の重要な時期に草焼きが行われると致命的な結果になる。
Wentworth (2018) Golden eagle (Aquila chrysaetos) in the Bale Mountains of Ethiopia: a isolated and critically endangered population に 2018 年の観察結果が出ている。
新しいつがいが見つかってこのシーズンは3つがい。巣立ちは確認できず。全部で7個体。集落の近くの巣はほぼ使われなくなっている。巣の下にあった骨格が巣立ち直前に死んだひなかも知れない。チームとしては新亜種と早く記述してもらって保護の重要性を訴えたいと考えている。遺存亜種または個体群 (#ゴビズキンカモメの項目参照) とも考えられた。
Wentworth のエチオピアのイヌワシのブログ。保護活動は海外研究者が進めざるを得ず苦しい状態にある。放牧の家畜が草を食べ尽くしてノウサギは激減、しかし食料不足が原因というわけでもなさそうで、獲物をハイラックスや齧歯類に変えたとのこと。
ブログの現地報告は 2019 年で止まっており、新型コロナの渡航制限で現地調査ができなくなったためか? ここの記載によれば DNA 解析の結果は地中海系統 (亜種 homeyeri) に相当し、新亜種にはあたらない (Wink) との結果が出ているが、上記のようにイヌワシの従来の亜種記載と分子遺伝学との整合性は必ずしも良くなく、分子遺伝学のみで亜種を決定することが適切とは言い切れないかも知れない。
[ニホンイヌワシと日ソ渡り鳥等保護条約]
渡り鳥条約については山階芳麿 (1979) 渡り鳥条約 (山階鳥類研究所 日本経済新聞 1979年5月23日)。
「日ソ条約も日米条約と同じ内容で、昭和 48 年に締結し、ソ連側はすぐ批准したが、日本では、北方領土問題から、まだ現在まで批准が済んでいない」
との記述がある。
「日ソ渡り鳥等保護条約」調印から 15 年ぶり "日の目" (毎日新聞 1988年12月15日) に
「しかし、ソ連側が国後 (くなしり)、択捉 (えとろふ) など北方四島だけにしかすまない鳥としてニホンイヌワシを同国の特殊鳥類にリストアップしたことから、日本側が難色を示し調整に手間どっていた。今回ニホンイヌワシをソ連がリストから外したことなどで、日本もやっと条約批准となった」
との報道が残っている。
「野鳥」1989年2月号 (No. 510) p. 33 の記事によればこれに加えてエゾシマフクロウが挙げられており、エゾシマフクロウは両島以外のソ連領にも生息していることを認めると連絡してきたので、急に決着したとのこと (朝日新聞 1988年12月19日)。
状況を少し見ておくと亜種認識が複雑であったらしいことがわかる。Dement'ev and Gladkov (1951)
では kamtschatica (ロシア名東のイヌワシ) のシノニムに japonica を挙げており、kamtschatica と日本、千島列島、満州、中国北部のものは同じ型だろうと記している。
Gizenko (1955) の「サハリン州の鳥」には挙げられていない。
[イヌワシ類似の大型イヌワシ類]
イヌワシに似た容貌を持つ大型の Aquila 属の現存のワシが他に2種または3種知られている:
・コシジロイヌワシ Aquila verreauxii アフリカ中南部。
英名 Verreaux's Eagle; 現地名 black eagle も使われるが標準的英名で Black Eagle と呼ばれるカザノワシ Ictinaetus malaiensis が別にあるので注意が必要。
南アフリカの言語 (Afrikaans、アフリカーンス語) での名 witkruisarend はオランダ語由来で wit 白 kruis X-字 (英語 cross) (kruis には牛の腰の意味もある) arend ワシ。現地名は ukhozi (ズールー語) など他にもいくつもある。
現在の標準的オランダ名は zwarte arend (黒いワシ)]。
Brown (1976) p. 181 によればコシジロイヌワシは巣立ちに 90-95 日を要し、イヌワシの 65-80 日より長いが、これは温帯の夏は日照時間が長く狩猟に用いられる時間はどちらも 1260 時間と大差ないとのこと。
同書 p. 182 ではワシの親が巣立ちを促すと広く信じられているが、しっかりした記録のあるものは 孵化後 98 日のコシジロイヌワシの1例に限られるとのこと。
・オナガイヌワシ Aquila audax (英名 Wedge-tailed Eagle) オーストラリア
・モルッカイヌワシ (ガーニイイヌワシの名もあった) Aquila gurneyi (英名 Gurney's Eagle) ニューギニアやパプアの島。よく知られていない。
それぞれの地域の頂点捕食者であり、イヌワシ、コシジロイヌワシ、オナガイヌワシは「Amadon の言うところのタカ科進化の頂点であることを疑うものはほとんどいないだろう」(ワトソン「イヌワシの生態と保全」(2006) p. 32、原著 1997 年) と記されている。イヌワシ、コシジロイヌワシ、オナガイヌワシ、モルッカイヌワシが上種を形成するとの見解もあった (Jollie 1957; Brown et al. 1982)。
この容貌などの類似性から、イヌワシを含めてこれらの3(4)種が分子系統樹上でまとまったグループを形成することが大いに期待されるが、Catanach et al. (2024) (#アカハラダカの備考参照) の最新研究ではそうではなく、オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、モルッカイヌワシがまとまった系統をなしていた
(ただし後2者は全ゲノム解析がまだなされていないので従来の遺伝子解析に基づくもの)。
なおオナガイヌワシは単形属の Uroaetus 属に分類されていたことがあった。oura 尾 (uro- は尾が長い種類によく使われる) aetos ワシ Gk。
この属に分類した Kaup (1844) Classification der Saeugethiere und Voegel も読めるので参考までに (さまざまな猛禽類が記述されている)。uraete の名前は現在でもオナガイヌワシを指すフランス語として使われる。
イヌワシは少し異なる系統で、イヌワシ系統に属するものはモモジロクマタカ Aquila spilogaster (英名 African Hawk-Eagle) とボネリークマタカ Aquila fasciata (英名 Bonelli's Eagle) というイヌワシと外見上類似性が少ない種類である驚くべき結果となった。
この結果は過去にも部分的に知られていて、もとクマタカに近い Hieraaetus 属に分類されていたこの2種が Aquila 属に改名された。和名や一部の英名も過去の分類を引き継いでいる。
ボネリークマタカの種小名 fasciata は帯のある < fascia バンド、帯。イヌワシ属とそれ以外の識別に尾のバンドの有無がしばしば登場するが、ここでは逆になっている。尾のバンドは系統的特徴の現れというよりも、生態的必要性に応じて比較的容易に生じるものなのだろうか。他のタカ類の尾の模様についても検討の価値があるだろう。
fasciata は他の種類にもよく現れる種小名だが日本産の種には出てこないよう。
ボネリークマタカのロシア語名は "タカのようなワシ" または "尾の長いワシ" の意味でクマタカ類とされた容貌に対応している。
モモジロクマタカはアフリカの猛禽類の写真でもよく紹介されるなかなかハンサムな種類で種小名 spilogaster は spilos 斑点 gaster, gastros 腹 (Gk)。それほど腹の斑点が目立つわけではないのに、なぜこのような学名になっているかは今一つわからなかった。
ボネリークマタカとモモジロクマタカはかつて同種とされたこともあった。遺伝的にも確かに近く、ソウゲンワシとアフリカソウゲンワシの関係と同程度。
2種ともどこがイヌワシと似ているのかよく見てもあまり思いつかない。ヨーロッパのボネリークマタカは生態や行動はむしろオオタカに似ているとのこと。
この最新解析はゲノム解析結果を用いており、イヌワシ系統の系統樹の精度は非常に高いと考えられる。
オナガイヌワシ、コシジロイヌワシ、モルッカイヌワシとイヌワシ系統に近縁の種類にアフリカクマタカ Aquila africana (英名 Cassin's Hawk-Eagle または Cassin's Eagle) という比較的小型で目立たない生活をしているワシ (この種はかつては旧クマタカ属 Spizaetus 属に分類されていた) が含まれることも驚きの結果であった。
現代的知見からはこの7種がイヌワシグループの鳥と言える。この結果は Lerner et al. (2016) Phylogeny and new taxonomy of the Booted Eagles (Accipitriformes: Aquilinae) でもすでに指摘されていて、クマタカ類との外見の類似性は収斂進化の結果ではないかと考えている。
イヌワシ類は開けた環境、典型的には例えばステップ、に適応して進化を遂げたとよく考えられるが、イヌワシに最も近縁の仲間の一つに熱帯雨林に適応して進化を遂げた種類もあったことを意味すると考えられる。
細かく見ると イヌワシ属 Aquila の (系統 2) は3つに分けることができる。
コシジロイヌワシの全ゲノムは調べられていないが、アフリカのコシジロイヌワシ、モモジロクマタカとボネリークマタカは Aquila 属のうちでも単一系統にまとまっている。
この系統が主にアフリカからユーラシア (ボネリークマタカ) のグループ。ボネリークマタカは比較的分散能力が高くアジアまで分布を広げたのだろう。
次の系統がイヌワシのみからなるもの。これは北半球中・高緯度中心のステップや山岳地帯に広く分布した。出所はどこだろうか。
アフリカの系統と同様にアフリカが出所とすれば、[サハラ砂漠以南のイヌワシ] はもしかするとより古い系統が高所のみ生き残った可能性が考えられるが、暫定的な遺伝解析は地中海系統らしいのでこの見方には合わない。氷期には地中海盆地とサハラ砂漠以南のレフージアがつながっていたのだろうか、あるいは分散能力が高くて (または渡りで) 個体交流があったのだろうか。
詳しい分子系統解析の結果が待たれるところである。
そして3つめの系統がモルッカイヌワシとオナガイヌワシ。地理的にはまとまっていて、この2種も遺伝的に近い関係にある (モルッカイヌワシの写真が少なく類似性がわかりにくいが)。
モルッカイヌワシの生息数そのものは多いと考えられていて [Raptor Research & Conservation Network (2018) "A Field Guide to the Raptors of Asia" によれば全体で 10000 つがいぐらい生息するのではないかとのこと]、オナガイヌワシとともにイヌワシ属の中では大型の割には普通種的なグループかも。
参考までにモルッカイヌワシの若鳥の飛翔正面顔 Gurney's Eagle あまりイヌワシっぽく見えない気がする。
Gurney's Eagle の顔つきはオナガイヌワシと多少似ている感じもする。
この3系統の出現順序までは系統解析からわからないが、アフリカクマタカが古い分岐にあたっているのでアフリカが起源と考えればここで並べた順序で分布を広げたように見える。
イヌワシ属 Aquila (系統 1。ソウゲンワシ属 Psammoaetus とする分類学者もある) とは系統が異なっており、分布は似ていてもイヌワシとソウゲンワシ、カタシロワシなどとは直接の関係はない (ソウゲンワシのような鳥からイヌワシが進化したわけではなさそう)。
Negro (2008) Two aberrant serpent-eagles may be visual mimics of bird-eating raptorsではオナガヘビワシ Circaetus spectabilis (英名 Congo Serpent-Eagle) がアフリカクマタカに擬態している
(#ハチクマの備考参照) 説を唱えているが、アフリカクマタカがそれほど強力で目立つ種でないことを考えると疑問にも思える。
ハチクマ類のクマタカ類との類似性 (擬態?、あるいはクマタカに似た表現形はタカ類にそもそも出やすい?) やイヌワシ類の進化起源を考える上でも重要な種類と思われる。これら Aquila 属で〜クマタカと呼ばれる種類の英名は将来改名されるかもしれない (和名は変わらないかも知れない)。#クマタカの備考も参照。
Aquila 属で最も古い化石は Gaff and Boles (2010)
A New Eagle (Aves: Accipitridae) from the Mid Miocene Bullock Creek Fauna of Northern Australia で 1200 万年前、オーストラリアで化石種 Aquila bullockensis でイヌワシより少しい小さい大型種だった。オナガイヌワシの祖先かどうかは推測の域を出ない。
オナガイヌワシはオーストラリアとタスマニア島が別亜種とされる。マイクロサテライト解析によって遺伝的交流を調べたもの: Burridge et al. (2013) Did postglacial sea-level changes initiate the evolutionary divergence of a Tasmanian endemic raptor from its mainland relative?
現在は遺伝的交流の証拠がない。これまで定説とされていた気候変動で大陸とつながっていた時期 (1.3 万年前) に分断されたとは考えにくい結果が出ている。自力で海を超えて島に定着した可能性があり、小島の迷行例もその可能性を裏付ける。
本土の個体群よりも大型で生活史にも違いがある。少数個体による創始者効果が現れている可能性がある。
人が持ち込んだ可能性はほとんどなく、1803 年の入植すぐに 1836 年にすでに目撃されているので人為導入としては早すぎる。亜種とする意義があるかこれまで議論されてきたが、迫害や汚染、森林伐採や風力発電など人為的影響を大きく受けている個体群で保全単位として意味があるのではないか。
イヌワシ類似の大型猛禽類の海を超える分散能力を判断する一つの材料にもなりそう。
人為要因によるタスマニア島の絶滅動物としてここに入れておく: フクロオオカミ Thylacinus cynocephalus Thylacine (Tasmanian tiger。1936 年絶滅) の遺伝的特異性 Salve and Vijay (2025) Illuminating the mystery of thylacine extinction: a role for relaxed selection and gene loss (preprint)
標本を用いて遺伝子を調べたところ複数の遺伝子が不活性化の変異を起こしていた。そのうち SAMD9 の喪失は肉食に関係するもので、フクロオオカミが極端に高度な肉食となった時期に失われていた。また嗅覚に頼らない捕食を行っていたため嗅覚関連遺伝子に選択圧がかからず脳の嗅覚機能も失われていったと考えられるとのこと。
直接の絶滅原因は人為的なものだったが、タスマニアの閉じた小さな環境であまり過剰に肉食性なることで進化の袋小路状態となっていたらしい。
このような肉食固有種を絶滅させたことがタスマニア島のオナガイヌワシの絶滅が懸念される理由の一つにもなっているが、オナガイヌワシの方は移動能力があるため大陸との多少の交流があって同じ肉食動物でもフクロオオカミのように極端な進化を遂げなかったことが運命の分かれ道となったのかも知れない。
[オナガイヌワシの共同ハンティング]
オナガイヌワシの現在の主な獲物は外来種のウサギだが、かつては集団でカンガルーを襲って弱らせて捕食していたといくつかの文献に記載されている。
Fuentes and Oslen (2015) Observations of the killing of large macropods by Wedge-tailed Eagles Aquila audax
の最近の報告がある。伝聞としては知っていたが、論文で見るのは初めてで斬新であった。頭部と首を狙って反復急降下して弱らせ、死に至らせたとのこと。著者が知る限りでは詳しい報告は初めてとのこと。
イヌワシでも弱った動物に対する同様の事例が過去に報告されている。大型のイヌワシ属は死体が豊富にあっても生きた獲物が少ない場合は繁殖しないとの報告がある (Brown and Watson 1964)。
オナガイヌワシはカンガルーの死体が豊富に出た場合に巣に運ばれた未報告情報はあるが、著者の観察では通常では死体はひなに与えないとのことで (おそらくひなの免疫がまだ発達していないのであろう: 私見。#インドガン備考の *1 参照)、このような集団での大型動物の捕食が役に立つ可能性がある。理想的条件では 5 kg まで巣に運べるが通常は 3.8 kg までとのこと。
過去のオーストラリアでどの動物が最も重要な捕食者であったかについて科学者の間で意見が分かれている。哺乳類か爬虫類かと考えられていたが鳥類は検討対象にもならなかった。しかし現在そうであるようにオナガイヌワシが最も重要な捕食者の一つであった可能性は十分考えられる [2023 年に化石巨大猛禽類 (#カンムリワシの備考参照) が発表される前の論文]。
イヌワシのことを調べる上でも役立ちそうな論文である。
オーストラリアではオナガイヌワシはトビのような普通種と言われバーダーにはあまり珍重されない印象もあるが (死体を食べているところは映像にもなりやすく、スカベンジャー的印象が必要以上に強められているかも知れない。普通に見られるとはいえ近くで見ることは現地の人でもまれだそうである)、十分に立派な生態系の頂点の猛禽のようである。
かつてオオイヌワシの和名が使われていたことがあり、山階 (1986)「世界鳥類和名辞典」にもこの名前が出ていたらしい。高野 (1973) ではオナガイヌワシ。1986 年よりもっと早い時期に名前を見た覚えがあり、あるいは山階 (1986) が付けたものではないかも知れない。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 115 p. 23 に事例があった。この書物はおそらくフランス語からの翻訳で (それ以前からあった名称からも知れないが) フランス語名の1つである uraete で表記されていたならば直に訳すこともできず、イヌワシよりも全長、翼開張ともに大きいのでオオイヌワシの名称が採用されたのかも知れない。
日本に翻訳紹介された時点の出典言語が英語であるとは限らず、一種の盲点だった感じがする。英語以外の書物からの翻訳の場合は鳥類学者も十分に関わっていなかった事例もありそうに思える。
高野 (1973) は英語から訳したのでオナガイヌワシの名称となった。
読んだ当時オオワシ + イヌワシ ならばもっと強いのではないかとちょっと思ってしまった。
この論文中にいくつかの結末のわかわらないカンガルーに対する (共同) ハンティングの YouTube ビデオが紹介されているのでここでも取り上げておく:
Kangaroo vs 2 eagles 2013、
Eagle attacks kangaroo、
Eagle Attacks Kangaroo.mov。
猛禽類の共同ハンティングの事例については #トビの備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] のモモアカノスリの事項も参照。
なお屋外ショー中に子供を襲ったオナガイヌワシがある: Photo Catches Eagle Trying to Snatch Little Boy During Bird Show at Australia Park (2016)。この個体は以後ショーから外されたとのこと。
飼育員が襲われたケースもあるとのこと Currumbin Wildlife Sanctuary worker attacked in face by wedge-tailed eagle (2016)。
イヌワシではキルギスの屋外ショー中に立ち入り禁止区域にいた子供が襲われた映像がある Golden eagle attacks 8 yo girl at ethnofestival in Kyrgyzstan。
コメントによれば真面目に襲ったわけではないとのことで、しっかり襲うつもりであれば成人であっても抵抗できないだろうとの専門家コメントが付いている。
いずれも飼育個体なので野生個体がヒトを獲物とみなすかどうかはこれら事例から推測するのは危険であろう。
かつて「サッカーをするワシ」として有名になったオナガイヌワシがあったが、Eagle tries out for Mountain United を見るとオナガイヌワシだけの習性ではなさそうである。
オナガイヌワシの種小名 audax は「大胆不敵な」の意味 (Oslen によれば少なくとも現在の習性とは合っていないとのこと)。英語の同系語に audacious がある。
記載時は Vultur 属だった当時の分類概念の影響かも知れない (#クロハゲワシ備考参照)。
ヒツジをさらうとの考えからオーストラリア入植者による大規模虐殺があり、過去最も迫害を受けた猛禽類と言えるとのこと (北米のイヌワシでも同様のことがあったことは Gordon も生々しく記載している)。
Can wedge-tailed eagles survive the slaughter? (Koob 2018, Sydney Morning Herald)
にワシを駆除することがまだ美徳と考えられていた 1963-1966 年の写真も掲載されている。
現在では保護されているが同様の虐殺事件もまだある。またタスマニア島では森林伐採と風力発電タービンと衝突が問題になっている。ロードキルのカンガルーを食べていた個体が二次的なロードキルの被害を受けることもしばしばある。
オーストラリア先住民のアボリジニは天地の創造者を Bunjil と呼んでいたが、しばしばオナガイヌワシを指すものとされる。ある伝説によれば Bunjil は星のアルタイルとなり、2羽の妻のコクチョウがその両側の星になったという。
オナガイヌワシは目先に裸出部があり、腐肉食への適応と考えられたこともあったが寒冷気候に適応したイヌワシとは異なった高温環境への適応が主な理由と考えられている。翼開長は Aquila 属で最も大きく、1931 年にタスマニアで殺されたメスは翼開長 284 cm あったという。最大長はオオワシに匹敵するとのこと。
ただし体重はイヌワシの方が大きい。体格はオオワシやオウギワシよりは小型でそこまで頑丈ではないが、骨格はイヌワシとよく似ているとのこと。
すべてのワシ類中最長の尾を持つ。食性は大型 Aquila 属で唯一のジェネラリスト。死体を食べる時は他の個体や他種を排除しない (wikipedia 英語版より)。
エミューの卵を巡って小競り合いを行った
Wedge tail eagles Will fight for an emu egg (Emu Logic 2024) の映像が出ている。
クロムネトビ (名前から想像するようなトビでも見かけから想像するようなノスリでもないので注意) のように石で卵を割る習性 (知恵?) は持っていないのか。
松村 (2010) Birder 24(5): 74 にロードキル増加に伴ったオナガイヌワシの食性変化についての記事がある。冬季に多く見られるとのことで、子育て期は先述のように生き餌が必要なために依存度が下がるのかも知れない。
Wedge tail eagle, fox stand off (Emu Logic 2024)。オナガイヌワシ対キツネ。キツネの方が腰が引けている感じ。
[大型哺乳類を襲うイヌワシ]
2011 年のロシアのラゾフスキー保護区のカメラにイヌワシが若いニホンジカ (日本と同種で亜種ウスリージカであろうか) を襲う場面が記録されていて話題となったことがあった。
過去にも状況証拠はあったが実際に襲う場面が記録されたのは初めてとのこと。
例えば Golden Eagle Attacks Deer, A Photo Of An Epic Confrontation
に写真と北米の事例も含めて解説がある。
68 分後にハゲワシがやってきたとのことでかつて記録カメラにハゲワシが写ったことはなかったとのこと。シカは長時間苦しむことはなかったと考えられるとのこと。
Kerley and Slaght (2013)
First Documented Predation of Sika Deer (Cervus nippon) by Golden Eagle (Aquila chrysaetos) in Russian Far East
が論文。
ロシア沿海地方でウシ科オナガゴーラル Nemorhaedus caudatus Long-tailed Goral / Amur Goral を襲う映像が撮影された: Myslenkov amd Voloshina (2024)
The first reliable case of an attack by the golden eagle Aquila chrysaetos on the Amur goral Nemorhaedus caudatus and facts of hunting the sika deer Cervus nippon (pp. 983-988)
2024年1月27日のカメラ映像に写っていた。シホテ・アリンで 30 年、ラゾフスキー保護区で 20 年オナガゴーラルの生態を研究してきて、オジロワシ、オオワシ、イヌワシが攻撃することは一度も観察しなかったが初めての確実な事例となった。メスの体重は 35 kg 程度と推定される。
なおオナガゴーラルの自動記録も行われているが、2023 年が初の撮影成功とあり、オナガゴーラルの撮影そのものが難しいよう。
Kerley and Slaght (2013) に関係した続報もあり、2017 年にもニホンジカを食べているところを撮影した。これは 45 kg ぐらいあるのではとのこと。イヌワシによるニホンジカの捕食はゴーラルよりも頻繁にあり、成功率も高いらしいとのこと。
Mason (2000) Golden Eagle Attacks and Kills Adult Male Coyote
イヌワシによるコヨーテ成獣の捕食事例。
コヨーテを襲う事例は過去にも報告されていた: Ford (1964) Observations of Golden Eagle Attacks on Coyotes。
Khabibrakhmanov (2023) The golden eagle Aquila chrysaetos in the Altyn-Emel National Park (pp. 5209-5216)
カザフスタンでコウジョウセンガゼル Gazella subgutturosa の捕食事例の写真が出ている。他にアジアノロバ Equus hemionus やまれにアリガリ Ovis ammon を捕食することもあるとのこと。
[ゴマバラワシによるライオン幼獣の捕食]
Hatfield et al. (2024a) Predator becomes prey: Martial eagle predation of lion cubs in the greater Mara region, Kenya
写真あり。ケニアで観察。初報告とのこと。7個体のライオン幼獣が捕食され、少なくとも一部は食べられた。特定の場所で起きているわけではなくゴマバラワシにとって都合よい獲物であればライオン幼獣も捕食対象になっていると推測される。
1羽のゴマバラワシは2012年12月に1コホート (集団) のライオン幼獣を食べ尽くすまで繰り返し訪れたとのこと。ゴマバラワシの主要な獲物とは言えないが個体の個性によっては例外的な状況もあり得てライオンの個体群動向に影響を与える可能性もある。
"an individual lion pride could be highly affected" (全部の子供を食べられてしまった) ライオンのプライドを大きく傷つけた可能性もある。
最近巣立ったばかりのゴマバラワシがライオン幼獣を捕獲した写真も出ており、ゴマバラワシの個体次第ではライオンの子は意外にたやすく狙える獲物なのかも知れない。
フクロウ類も含めた大型猛禽類が大型肉食動物を捕食する過去の記録についてもまとめられており、ゴマバラワシがヒョウの幼獣を捕食した目撃例などがある
[Balme et al. (2012) Reproductive success of female leopards Panthera pardus: the importance of top-down processes]。
他にもカラカル、チーターの幼獣なども捕食の対象となっている [Hatfield et al. (2024) にサーバル (キャット) やチーターの幼獣を掴んでいる写真あり]。
ちなみに他の肉食哺乳類と比較してライオンやヒョウの巨大さが目につくが、これはメガファウナの数少ない生き残り (メガファウナについては #カンムリワシ備考の [メガファウナの絶滅] も参照) と考えてよい。百獣の王でも生態的には脆弱である:
Nicholson et al. (2023) Socio-political and ecological fragility of threatened, free-ranging African lion populations。
アフリカ西部の個体群は 250 未満で CR 種の基準に相当する。
このような捕食を行うゴマバラワシとはいったい何者か、系統樹を見るとイヌワシ亜科 Aquilinae に含まれるが、ゴマバラワシの含まれる系統にはカザノワシやカラフトワシ属のような必ずしも強力でないグループも含まれる。強力な捕食能力はゴマバラワシの含まれる系統内ではゴマバラワシとソウゲンワシ類でないイヌワシ類がそれぞれ進化させたことになる。
アフリカでは比較的普通種のためか意外にもそれほど詳しい分子系統は調べられていない。
もっともイヌワシ亜科全体ではクマタカ類も含まれるのでこれらの共通祖先が強力な捕食能力を持てる基盤を持っていたのだろう。
イヌワシも登場するのでこの項目に含めたが、この論文によればイヌワシがヒグマやアメリカグマ Ursus americanus American Black Bear の幼獣を捕食した事例は複数知られている [Sorensen et al. (2008) Predation by a Golden Eagle on a Brown Bear Cub]。
オオカミの幼獣の捕食例: Fernandez-Gil et al. (2024) Observations of golden eagles attacking and consuming wolf pups。
クロワシミミズク Bubo lacteus Verreaux's Eagle Owl によるライオン幼獣の捕食例もある: Eagle owl carrying off a lion cub (Mike Taylor 2017.8.3 昼間の一連の写真)。
Hatfield の修士学位論文 (2018) Diet and space use of the martial eagle (Polemaetus bellicosus) in the Maasai Mara Region of Kenya。この中にはまだライオンの記述はない。
Hatfield et al. (2024b) Africa's overlooked top predator: Towards a better understanding of martial eagle feeding ecology in the Maasai Mara, Kenya
アフリカでは大型の肉食哺乳類が多数存在するため鳥類の捕食者が軽視されてきた。ゴマバラワシも最近まで頂点捕食者とは認識されていなかった。この研究で加速度センサー付き GPS 追跡を行うことで何を捕食しているか飛躍的によくわかるようになり、大型肉食哺乳類に近い頂点捕食者と考えてよい結果が得られた
(こちらの論文の方が先述論文より早い出版。肉食獣の幼獣を捕食していることは触れていない。どのような形式で発表するか慎重に検討していたのだろう)。
ゴマバラワシがライオンの幼獣の捕食を試み、攻撃する鳥は視野に入っていないが親が飛び上がって防御する過去の映像がある: Lion cubs play when Martial Eagle attempts snatch 1223 - Kicheche Mara Camp, Mara North Conservancy (Mark Mallone 2016)。
コメントにはゴマバラワシが判断を誤ったのだろうなどの記述があるが、本気で狙ったのかも知れない。
Martial Eagle Lion killer! This young martial eagle was seen just weeks ago killing and flying away with a lion cub. Anyone else have a similar record?! I know goldies can take wolves but... wow! (backshall.steve 2023)
によればこの写真そのものではないが同じ個体がライオンの幼獣を殺して運ぶのを目撃したとある。
状況証拠はそこそこ知られていたらしい。
Cheetah Predators: These 4 Animals Can Kill and Eat Cheetahs (Mike Edmisten 2023) のページでチーターの捕食者にゴマバラワシも挙がっている。"空飛ぶヒョウ" とも呼ばれるとのこと。
カラカルやサーバル (キャット) を殺したことも知られているとある。
おそらく幼獣を親から引き離すためにヒョウやライオンの成獣を襲った記録があるとのこと。
チーターの成獣はさすがに襲わないだろうが (特に親が守っていない) 幼獣は捕食の対象になると書かれている。
wikipedia 日本語版のサーバルのページには幼獣がゴマバラワシに捕食された例もある (Luke Hunter 「サーバル」山上圭子訳『野生ネコの教科書』今泉忠明監修、エクスナレッジ、2018 年、70-76 頁 が出典とのこと。原著は "Cats of Africa: behavior, ecology, and conservation" 2006)。
動画もあった: Martial Eagle with Serval Cat kill (Gian Schachenmann 2011 タンザニア)。これは幼獣でさすがに成獣は襲えないだろうが、皆さんは猛禽類の能力をきっと過小評価しているなどのコメントがある。
ヨーロッパや北米の研究者が多いので北半球ではイヌワシが昼行性鳥類の頂点捕食者の印象が強く (さらに範囲を広げてもハクトウワシやオジロワシなど Haliaeetus 属にとどまる)、イヌワシは讃えるがタカ類発祥の地で百戦錬磨のはずのアフリカの種類でも研究者もあまり重視していなかった可能性がありそう。
日本語に翻訳されたニュースがあった: ライオンを狩るワシ、初の詳しい報告 ケニアの「戦闘ワシ」。
上記から論文が見られるので日本語解説から知られた方も論文をご覧いただきたい。
[兄弟殺し]
多くの鳥類、特に猛禽類でひなの間の兄弟殺し (siblicide, sibling cannibalism, cainism, fratricide)、あるいは兄弟闘争 (sibling aggression) が報告されている。ほぼ必然的に起きる obligate siblicide と条件によって起きる facultative siblicide に分けられる。
イヌワシ類では特に顕著である。イヌワシの日本亜種 japonica では極めて高率 (98% 以上、日本イヌワシ研究会) で兄弟殺しが起きるが、イヌワシ全体としては普通に2羽が巣立つ地域もある。
ゴードンの「イヌワシの生態」には常時3羽を巣立たせているスコットランドのイヌワシの例が紹介されている)、イヌワシは facultative siblicide を行う種に分類されている (この点では日本のイヌワシはやや特殊)。さまざまな段階の同種間闘争は広い分類群で知られていて、鳥類の兄弟殺しが特殊というわけではない (資料)。
しかしながら obligate siblicide は鳥類のものがよく知られている。Redondo et al. (2019) Broodmate aggression and life history variation in accipitrid birds of prey がタカ類の兄弟殺しをまとめているが、疑問のある種類も多い。
例えばツバメトビ Elanoides forficatus を最も強い兄弟闘争を行う種に分類している (そのような記載を行っているページがあるが確実な根拠が見当たらない)。
ヨーロッパハチクマも中程度の兄弟闘争を行う種としているが文献根拠は1つのみで (ヨーロッパハチクマでさえも兄弟殺しが起きるという Brown の記述のみ)、(ヨーロッパ)ハチクマの近年の巣の (ビデオ)観察ではそのようなケースは (ほとんど?全く?) 知られていない (つつく程度の写真はある)。
RSPB のヨーロッパハチクマのページにもヨーロッパハチクマでは他の多くの猛禽類とは異なり、兄弟間の闘争はなく、餌をめぐる争いもほとんどないと記載があり、この点はハチクマの日本の研究者の見解と一致している (ただし#ハチクマの備考の中国の事例で確実な兄弟殺しが映像記録された。ロシアの文献からの情報も参照)。
このように個々の種については疑問な点もあるが、Aquila 属で多く見られる行動である点は確かだろう。なおこの論文ではトビにおける事例が写真で示されている。また兄弟殺しが起きやすい要因も列挙されている。
鳥類の子殺しは「暴力の進化」の文脈でも研究されている (参照)、この中ではミサゴとコシジロイヌワシが紹介されている。
ミサゴは実験も紹介されており、鳥類の兄弟殺しはひなが育たなかった時のための予備として産卵する「保険仮説」がもっともよく当てはまる例と紹介されている。
ワシ類の兄弟殺しのまとめは Simmons (1988) Offspring quality and the evolution of cainism にあり、この時点ではかなり多くの種を obligate と分類している。
現在 obligate に兄弟殺しが起きる種類とみなされて有名なものはアシナガワシ Clanga pomarina (英名 Lesser Spotted Eagle) とコシジロイヌワシである。コシジロイヌワシでは古く Hoffmann (1931) に記述がある。
ほぼ 100% 兄弟殺しが起きるとされるコシジロイヌワシでも2羽の巣立ちの報告例はある (参考)。
コシジロイヌワシにおける人工操作の例として Gargett et al. (1982) Synchronous Hatching and the Cain and Abel Struggle in the Black Eagle
があり、同時孵化するように操作して餌も十分にあるのに2番めのひなは死んだとのこと。大きい方のひなが小さい方のひなが食物をとるのを妨害した。攻撃は相互に見られたが大きい方の攻撃の方が強力だったとのこと。
Gargett et al. (1990) "The Black Eagle" によれば2羽のひなの片方を交互に持ち帰って人工飼育して戻す実験、同時孵化するように操作した実験いずれも2羽を巣立たせることはできなかったとのこと。十分に羽毛が生えた8週齢で2羽を巣に戻すと兄弟闘争は起こっていたが、致命的なことにはならなかったらしい。しかし2羽目の巣立ちまでは確認できなかったそうである (須藤一成氏からの情報 [kbird:05916 2023.4.26])。
須藤明子 (2010) Birder 24(7): 32-33 に「猛禽類の兄弟殺し」の解説がある。上記コシジロイヌワシでは10週齢を過ぎて戻した場合は2羽のとも巣立ったと記載されている (Gargett et al. 1990)。
コシジロイヌワシにおいてはハイラックスが主たる獲物で、ハイラックスの分布などが非常に安定しているのでつがいのテリトリーが非常に固定化されて、しかも長命のため若鳥が入り込める場所を見つけるのは至難であることが obligate な兄弟殺しが起きることに関係しているかも知れないとの考察がある [Rob Davies, in "The Eagle Watchers" (2010)]。
アシナガワシについて、この種や保護の専門家の Meyburg によれば2番目のひなを人工飼育して巣に戻すと、仮親を使っていて、トビ (日本のと同種だが向こうでは渡り鳥) を仮親にしていたとのこと [この部分の出典は Brown (1976) "Birds of Prey"]。「鳶が鷹を生む」ではなくてなんと「鳶が鷲を育てる」であった。仮親を使う方法は刷り込みなど (例えば雑種ができてしまうなど) の問題があってその後は推奨されていないとのこと。
当時は英国でオジロワシが絶滅していて、それまでにもオジロワシの若鳥を数羽放したものの成功しなかったが、仮親を使うアイデアが提唱されている。仮親はなんとイヌワシ。イヌワシは人工的に育てることができるので(!)、代わりにもっと貴重なオジロワシを育ててもらおうとのことだったようである。
アシナガワシに戻ると親鳥は巣立ちまで育てることができて巣立った後も面倒をみていたらしいと同書に記載がある。
[Meyburg は冷戦の最中西ベルリンに住んでいた。小さい時に Wendland のモノグラフを読んでアシナガワシの兄弟殺しに深い関心を持った。アシナガワシは当時西ドイツでは絶滅。
東ドイツでも数を減らしていて、Meyburg は兄弟殺しの習性を利用し、確実に無駄になる2番目のひなを人工飼育することで個体数回復を試みたかったが、自宅からそこそこ近くにアシナガワシの巣があるのに当時はベルリンから出ることは叶わなかった (近年の状況について #カラフトワシの備考も参照)。
しかしチェコスロバキアの現地研究者の招待状を得て訪れることはできて上記実験を行えた。その後ベルリンから日帰りで年 30 日までの範囲ならば外出可能になり、東ドイツの研究者のもとでアシナガワシの研究を行った。頻繁に東ドイツを訪れるのは不審で、持っている用具ももちろん目をつけられて、東ドイツの秘密警察にずっと追跡されていたことが後になってわかったとのこと。西側のスパイだと思われていて、鳥類学者を装って入国しているとの読みだったらしい。
秘密警察による行動の膨大な記録を後に読むことができて、思わず笑ってしまったとのこと。10月になるとぱったり来なくなるのを、秘密警察は警察が警備を強めたためと解釈していた。疑念が晴れるのに 10 年を要して、秘密警察も鳥が渡っていなくなるのが原因との正しい解釈にたどりついていたとのこと]。
イヌワシにおける兄弟殺しは Gordon (1927) "Days With the Golden Eagle" にすでに記述されていたが、後に出る書物には必ずしも引用されていない。Gordon は最初に生まれるひなが体の大きなメスで、後で生まれるひなはオスであると確信していると書いていて、性比が問題にならないのかと自ら問うている。
オナガイヌワシについては Oslen (2005) "Wedge-tailed Eagle" によればオーストラリア本土とタスマニアの個体群があるが、タスマニアの方がクラッチサイズが小さく、2羽育つ率も低いらしい (2% とのこと)。一つの解釈として、これは島では個体群が小さくまとまっていて成鳥の死亡率が低く、個体の入れ替わりが遅いために多くのひなを必要としないためとも考えられると書いてある。
コシジロイヌワシでも同じような解釈が述べられており、個体群による2羽育つ率の違いは成鳥の死亡率を反映した生存戦略の違いによるもので、必ずしも食物の量を反映するものではないとするのがよりもっともらしい解釈なのかも知れない。
"The Eagle Watchers" に、イヌワシ近縁種であるヒメイヌワシ (かつてコイヌワシと呼ばていた) Hieraaetus wahlbergi (英名 Wahlberg's Eagle) についてチュウヒ類の研究で有名な Robert E. Simmons が記事を書いている。
チュウヒ類の研究でアフリカに滞在し、ヒメイヌワシがごく普通に見られることに気づいてここで兄弟殺しの研究を始めた。数が少なく保全上も操作が困難な多くのイヌワシ類に比べ、数の多い種類ならば人為的な実験で確かめることも可能なのではと考えたようである。
ところがヒメイヌワシは1卵しか産まない。そこで考えたのが適切な時期のひな同士を一緒にすると兄弟殺し行動が起こるかどうか。実験してみると実際に起きた (そこで介入した)。1卵しか産まない種類でも兄弟殺し行動が起きることが確かめられた。
次は成長して兄弟殺しが起きなくなった段階で、ひなを巣に補充して2羽のひながいる状態にしたが、8ペアで実験した結果いずれも2羽めを育てることができずひなは餓死した。興味深い結果として、これら2羽育てさせられたペアは1ペアを除いて翌年は繁殖しなかった。結果的に1羽しか育てられなくても、2羽を育てようとしたことが余分な負担となっているようで、毎年2羽を育てようとする戦略は隠れたコストがあり、結果的に子孫の数を減らすことになることが示された。
Starikov and Akentieva (2025) A case of cannibalism in the steppe eagle Aquila nipalensis in the Zaisan Basin (pp. 2194-2197) ソウゲンワシでの事例。著者は 40 年ソウゲンワシを観察しているが初めてとのこと。ハイタカも食物になっていたとのこと。
オオタカ・ハイタカのグループではイヌワシ類に比べて兄弟殺しが起きにくい (#ハチクマの備考も参照)。
チュウヒ類では兄弟殺しがほとんど記録されていない (#ハイイロチュウヒの備考参照)。
近年のハヤブサの巣のビデオモニター調査から多少の争いはあったが深刻な攻撃はなく、過去の文献でもこれまで兄弟殺しが記録されていないとのこと: Marziliano et al. (2022) Using videos from social media to study the begging behaviour of peregrine falcon (Falco peregrinus) nestlings。
猛禽類以外でも兄弟殺しは知られている。Bryant and Tatner (1990) Hatching asynchrony, sibling competition and siblicide in nestling birds: Studies of swiftlets and bee-eaters
の先駆的研究が有名で シロハラアナツバメ Collocalia esculenta や ルリノドハチクイ Merops viridis Blue-throated Bee-eater で観察されている。ルリノドハチクイの攻撃は特異で上嘴に突起が一時的に生じ、闘争は必ず致命的になるという。
ワライカワセミ Dacelo novaeguineae Laughing Kookaburra でも上嘴の突起による兄弟殺しが知られている: Nathan et al. (2001) Nestling aggression in broods of a siblicidal kingfisher, the laughing kookaburra。
この事例は托卵鳥であるミツオシエ類でカッコウ類のように宿主の卵を排除するのではなく、上嘴の突起で宿主のひなを殺す行動や形質の起源として紹介される。ワライカワセミは逆サイズ性的二形 (メスの方が大きい) を示す点は猛禽類に似たところがある。
#カッコウ備考の「カッコウの托卵: 進化論的だましのテクニック」(ニック・デイヴィス) に登場する。
兄弟殺しはサギ類、コウノトリ類、アホウドリ類、ペリカン類などでも知られている。
鳥類全般の総説では Morandini and Ferrer (2015) Sibling aggression and brood reduction: a review がある。
アオアシカツオドリの兄弟殺しの研究は #アオツラカツオドリの備考を参照。
Wegrzyn et al. (2023) Hatching asynchrony as a parental reproductive strategy in birds: a review of causes and consequences
で兄弟殺しに強く関係する非同時孵化の要因のレビューが読める。必ずしも互いに排他的でない 20 の仮説があるとのこと。この著者によればよく検証されていると考えられるのは保険仮説と egg viability hypothesis (長期間抱卵しないと胚の発生率が下がる Arnold et al. 1987) にとどまるとのこと。
Lack (1947, 1968) のオリジナルの brood reduction hypothesis (予測困難な環境変化への適応) は同時孵化では競争が増すため全体として子供の数が減ると考えたが実験的検証では肯定的・否定的なもの両方があるとのこと。現在では Lack の仮説は部分的に支持されるとのこと。
コシジロイヌワシとアオツラカツオドリでは2番めのひなが単独で育つ確率は 22% で少ない投資に見合う保険になっているとされるている。1卵しか産まない場合と2卵の場合でどちらが適応度が高いかを調べる実験が理想的だが絶対的な兄弟殺しを行う種は通常2卵を産むのでこの研究は現実的に困難。
イワトビペンギン Eudyptes chrysocome chrysocome Southern Rockhopper Penguin では2卵めにより多くの投資をして、2卵めが先に孵化して (reversed hatching asynchrony) 食物を独占するとのこと。
生活史戦略としての理論的研究は古くからのテーマで、Hamilton (1964)、親子の対立 (parent-offspring conflict: Trivers 1974) に始まる。
wikipedia 日本語版の "親子の対立" の鳥類の項目では英語版を訳したようで、ニュアンスは英語版を見ていただいた方が安全。英語版ページも鳥類の項目は少なく、鳥類に特化した研究は思ったより少ないのかも (同じことが当てはまるならば対象を鳥類に限る必要もないのでもっと簡単に実験できる方を用いることになるだろうか)。
ごく初期の理論でも理屈の上では説明できる部分があるが実際的検証は難しいのだろう。それゆえ猛禽類の兄弟殺しの一般的説明に理論的背景があまり登場しないのか。
どのような生態で兄弟殺しが起きやすいかなどは比較的調べやすいが、托卵行動の方は理論・実証研究も進んでいて矛盾するように見える行動が適応的かどうか議論も行いやすいが、特に猛禽類の兄弟殺しの実際の行動の解釈はなかなか難しいのかも知れない。
#クマタカの備考 [クマタカ類の隔年繁殖の理由?] に関連話題を紹介し考察を追記した。イヌワシ類で兄弟殺しが起きやすいのは獲物が r 戦略的であることが多いためとの解釈。
イヌワシ類は生態系の頂点で繁殖能力も低いと考えられてきたが実は違うのでは。人為的影響がうまく除かれた地域ではイヌワシは世界どこでも繁栄しているし、オーストラリアのオナガイヌワシでも迫害されなくなれば生態系の頂点かつ普通種となっている。
イヌワシの繁殖能力には十分な余裕があって、制約要因さえ取り除かれれば容易に数の増える種類なのだろう。中央アジアで鷹狩りにかなりの数使われても生息数に影響を与えるほどでもない。
以下の論文でも述べられている通り、むしろコロニー性の鳥に近い分散パターンを示している。孤高の鳥とする伝統的なイヌワシ観とはだいぶ違う。コロニー性の鳥に近い分散パターンを少なくとも生涯のある時期に示すために、個体分布密度が低いと増殖率の低下する効果 (Allee effect アリー効果) も考えられるかも知れない。
[若鳥の分散]
前述のようにヨーロッパアルプスでは保護が奏功して個体密度が飽和している。
その状況で GPS 追跡を行って若鳥の分散過程を調べた研究: Bronnvik et al. (2025) Decoupling of emigration timing and skill acquisition in a saturated population of golden eagles (preprint)
論文表題を見て意味の取れる方は英語論文を相当読み慣れているだろう。よくソアリングができるようになった個体ほど早く分散する予想に反する結果となったとのこと。飛翔能力は比較的早い段階で発達するものと考えられ、飛翔能力が未熟ゆえに分散を遅らせているわけではないと考えられる。両親の保護を受けられなくなる不利益の方がより影響を与えている可能性があるとのこと。
こちらも関連する研究で Chaubet et al. (2025) Prospecting movements during the transit phase of immature eagles are driven by age, sex and season
若鳥の分散過程の性別・年齢による違いを追っている。prospecting behaviours (踏査行動のような訳になるだろうか。鉱山の試掘などに対応する) の表現を用いている。段階的に prospecting を進め (つまり近場に適所がないか順次探す)、コロニー性の鳥のパターンに合うとのこと。
春と秋に prospecting behaviours が活発となり、またメスの方が広範囲を prospecting を行い、メスの方が広く分散する鳥の一般的パターンと一致するとのこと。prospecting の範囲が段階的に広がってゆくのはブラウン運動的に捉えることができそう。
10 年単位で GPS 追跡をしないとこれらの行動はなかなかわからなかっただろう。
[同種間争い]
イヌワシでの同種間の致死的な争いはいくつか記録がある (ゴードン「イヌワシの生態」など)。
近年確実な記録としてアルプスで個体数が環境収容力の限界に達し、若いオスがテリトリーを得られず争いで死亡していると考えられる事例が知られている: Dispersal ecology of Alpine Golden Eagles。
GPS 追跡がなされており、迅速に死体回収が行われて調べられた結果、若鳥に限らずテリトリー争いが主要な死因になっているとのこと。足で攻撃するため腹部に致命傷を負っている [この状況はゴードンが記載している喉を引き裂かれた事例などと少し異なる。
「イヌワシの生態」(原著 1955) に大原総一郎氏訳があるが、"Days with the Golden Eagle" (1927) に初出していたもの、2009 年再版書から引用しておくと A fight to the death between two golden eagles must be
a magnificent sight and one that is very rarely seen.
John MacDonald, a head stalker in Inverness-shire, writes:
"I did not see the fight myself, but my youngest boy did.
I came on the scene immediately afterwards and picked up
the dead eagle, the other fluttering off amongst the trees.
The dead eagle's gullet was torn completely out of
the throat. They were both male birds, and I expect
the fight originated over a hen eagle, as it happened
during the mating season (Chap. 19, p. 143)。
でこれはメスをめぐるオスの争いの模様]。
同種間の争いは繁殖個体の繁殖成功率にも影響を与えるぐらいであるとのこと。迅速に調べれば未経験の若鳥が狩りに失敗して死んだか同種間闘争かは区別できる。前者の例はほとんどない。
他の死因には鉛中毒、意図的なものや害獣駆除のための薬物中毒もあるが同種間闘争の方が上回っている。世界的にはそうではないだろう。アルプスに比べてスコットランド (ゴードンの記述などを紹介した) では食物量は豊富で営巣場所の方が制約になっているのでは。
北米は一部が渡りをする点が異なりそこまで競争は激しくないだろうが、アルプスの個体群は狭い場所に限定された留鳥が年中争っている必要がある。1.5 年ごとに繁殖するとすれば 20 年で1つがいが2羽を残し、28 羽の若鳥が (かなりの割合が同種間闘争で) 死ぬ計算になる。
イヌワシの若鳥の食物は大部分死肉で、活発に狩りを行えるようになるのに 4-5 年かかる。成鳥もしばしば死肉を食べる。若鳥を支える死体が十分なければイヌワシの個体群に加わる若鳥が将来減少する可能性がある。アルプスでもマーモットの個体数が繁殖成功の制約要因となっていて、獲物が不足するため子育てには大型の水鳥などあらゆるものを狩る必要がある (Safi から共有許可を得た情報を含む)。
アルプスの場合には厳重に保護された地域でイヌワシは一見繁栄しているが、人為環境が周囲を取り囲んでいる状況で本来可能であるべき遠隔地への分散ができない。このような人為的な特殊な状況がイヌワシの長期的な個体群動態にどのような影響を与えるのかは世界的にも未知で (若鳥の死亡率が高いために将来的に個体群の衰退があり得る) 研究の価値も高いと考えているらしい。
Zimmermann (2021) の修士学位論文 (同種間闘争は特に触れられていない):
The early life of juvenile golden eagles (Aquila chrysaetos): Sex and activity drive fledging time and pre-dispersal exploratory behaviour
[ボネリークマタカの雌雄の仕事量]
3次元加速度を測定できる最先端技術によって、イヌワシ近縁種であるボネリークマタカの子育てにおける雌雄の活動が調べられている: Lopez-Lopez et al. (2022) Tri-axial accelerometry shows differences in energy expenditure and parental effort throughout the breeding season in long-lived raptors
メスが巣にとどまる時期の子育て中はオスの仕事量が大きく増大するとのこと。ほとんどの期間でオスの方が仕事量が大きいが、後期にメスの関与が高まる。近年の研究では巣のビデオ観察が多く行われるようになっているが、巣だけの観察では巣にいないオスの労働量を過小評価する可能性がある。
特に食物事情のよくないテリトリーでは繁殖時期が進むにつれて行動圏を広げ、エネルギー消費も増え、(この研究例の場合は) 保護区を離れて採食する必要が生じ、死亡率を高めることになる。
同じ研究者が巣のビデオ観察 (特に近くに置く場合) によって繁殖成功率が下がる報告を行っている: Lopez-Lopez (2022) Potential negative effects of the installation of video surveillance cameras in raptors' nests。
アメリカのイヌワシでも動体感知型カメラで同様の事例が報告されている: Harrison et al. (2019)
Using Motion-Activated Trail Cameras to Study Diet and Productivity of Cliff-Nesting Golden Eagles
[猛禽類が代替巣を造る理由]
ボネリークマタカでの研究事例がある: Ontiveros et al. (2008) Possible functions of alternative nests in raptors: the case of Bonelli's Eagle。
これまでに提唱されている (互いに排他的でない) 仮説は [Bildstein (2017) "Raptors" p. 178 の記述順とした]
(1) 産卵前に捕食者に見つけられるか、他のペアが先に使ってしまった場合
(2) 競争者に繁殖中のつがい (active pair) の存在を知らせる。テリトリーの主張とともに無用な競争を避ける
(3) 寄生虫対策
(4) ミサゴなどで "frustration nests" (苛立ちの巣?) と呼ばれるものがあり、繁殖初期に失敗して新たに巣を造る。北米で DDT で数が激減した後回復時に調べられたためミサゴでよく知られている模様だが、ミサゴの営巣は妨害があったりよく落ちるなど結構失敗が多いようで造り直しを簡単に行うらしい (キジバトの巣が粗雑な理由として語られる話に似ている)。
Ontiveros et al. (2008) の結果では崖に営巣する場合他の崖営巣の猛禽を避けるのに役立っているが寄生虫対策の方がより重要な役割を果たしているのではとのこと。
Sumasgutner et al. (2016) Is multiple nest building an adequate strategy to cope with inter-species nest usurpation?
によれば南アフリカ共和国でオオハイタカ [高野 (1973) ではシロクロオオタカ] Astur melanoleucus Black Sparrowhawk がエジプトガン Alopochen aegyptiaca Egyptian Goose にしばしば巣を乗っ取られるとのこと。
学名から判断できるようにハイタカよりもオオタカの系統であると思って見るとよい。そのため高野 (1973) の名称も残した。
遅い時期ほど巣の乗っ取りが多くなりより早い時期に営巣することが有利になる。乗っ取りは繁殖成績に影響を与えるがテリトリーは乗っ取られるわけではないのでテリトリー内に代替巣を持つ戦略は有効である。
相手は大型で攻撃的なので競争は避けたい。なんとオオタカ類の方が自発的に水鳥から逃げている。
生態学で用いられる「タカ対ハトのゲーム理論」においてはエジプトガンがタカでオオハイタカ (シロクロオオタカ) がハト役になるとのこと (!)。熱帯ではクバリーガラス Corvus kubaryi Mariana Crow (ロタとグアム2島のみに生息する IUCN CR 種) も頻繁に複数の巣を造ることが知られている。年2回の繁殖に用いることもあり、オオハイタカ (シロクロオオタカ) でも年2回繁殖を試みることがあり半数は成功したとのこと。
猛禽類 (同種、異種とも) 間で巣の配置によって競争を防ぐ (competition avoidance by nest site) 仮説はこれまでも調べられていて
Carrete et al. (2005) Demography and habitat availability in territorial occupancy of two competing species (イヌワシとボネリークマタカ)、
Krueger (2002) Analysis of nest occupancy and nest reproduction in two sympatric raptors: common buzzard Buteo buteo and goshawk Accipiter gentilis (ヨーロッパノスリおよびオオタカ) などの研究がある。
ただし複数の巣を造るコストが生涯の適応度を落とす可能性も否定できない。
エジプトガンは他の猛禽類の巣を乗っ取ることも知られていてコシジロイヌワシですら事例があるとのこと。
イヌワシで代替巣も使われている巣と同様に土地利用計画の際に配慮すべきとの論文: Millsap et al. (2015) Conservation significance of alternative nests of golden eagles。
アメリカのユタでイヌワシが代替巣の数とどのような頻度で用いているか: Slater et al. (2017)
Interannual Golden Eagle (Aquila chrysaetos) Nest-Use Patterns in Central Utah: Implications for Long-Term Nest Protection
テリトリー内の巣は平均 2.9 個。同じ巣の利用は 3.3 年に1回。テリトリー内の産卵間隔は平均 1.8 年。次の繁殖で巣を変える割合は 43.3% だったとのこと。
#ハチクマ備考の [マレーシアの留鳥ハチクマの繁殖生態] に前回利用した巣に巣立ち後 25 日目の若鳥を誘導し、食物を与えた事例がある。
[カメを落として割って食べるバルカンのイヌワシと道具使用]
イヌワシがマケドニアではカメを落として割って食べる話は「イヌワシの生態と保全」にも記載があるが、バルカン半島のイヌワシは極めてカメに依存していて繁殖期は獲物の7割がカメとのデータがある。
ギリシャのイヌワシの論文: Sidiropoulos et al. (2022) Pronounced Seasonal Diet Diversity Expansion of Golden Eagles (Aquila chrysaetos) in Northern Greece during the Non-Breeding Season: The Role of Tortoises がある。
この文献によればイヌワシは結構茂ったところでも、また降りて歩いて捕食することもあるとのこと。ウサギは食物中数 % しかなかった。バルカン半島でカメを食べるのはエジプトハゲワシ (Neophron percnopterus) と現在この地域では絶滅しているヒゲワシ (Gypaetus barbatus)。
ここのイヌワシは変温動物に依存しているが、他の同様の変温動物食のワシのように渡りをせず、冬はいろいろ食べている (カメも想像以上に活動があって食料にしている)。ヒゲワシのように岩に落として割って食べるとある。
クルミを落として割る行動はいくつかの系統で観察されていて境界領域の道具使用と考えられる。このような多様な採食行動をとるのは通常頭脳の大きなジェネラリストの種類にみられる。「文化」として親子で引き継がれる習性の可能性がある。若鳥が親をまねて落とす必要のないものを落とすのを観察した。若鳥がカメを落とすのに不適切な場所に落とす行為も見られ、学習経験も関係しているかも知れない。
イヌワシにとって、カメを食べるのはコストがかかる(何度も落とす必要があり、落し方によってはなくしてしまうことがある)が、それでもカメを好むのは茂ったところでは敏捷に動けないイヌワシにとってウサギや鳥に比べて捕まえるのは簡単である。生息密度が高く、栄養価も高い。カメは日光浴をするので見つけやすい。カメは 1500 m より高所には生息せず、そういう場所ではウサギやキジ類を食物にしているかも知れないと記されている。
ゴードン「イヌワシの生態」ではペルシャでワシに向かってカメを投げると空中で捕まえて岩に落として割って食べるとの話が出ているが、ゴードンはそれはヒゲワシの習性ではないかとコメントをしている。
Predation impact on threatened spur-thighed tortoises by golden eagles when main prey is scarceにも食べ方に関係した記載と、巣での写真、巣の下に落ちていたカメの甲、ペリット中のカメの映像が出ている。
紀元前 455 年のギリシャでアイスキュロスがカメを岩へ落として食べるワシに、頭を岩と間違えられカメを落とされたという伝説的な死因が伝わっている (wikipedia 日本語版、他言語版にもある)。
[この逸話はワトソン「イヌワシの生態と保全」にも記載があるが、Dementiev (=Dement'ev) がキルギス部族の一員との記載は原書の誤りか翻訳の問題であろう。
Dement'ev はロシア (ソ連) 生まれで主として標本をもとに研究を進めた鳥類学者であった (Gladkovと共に残した「ソ連の鳥」全6巻は非常に有名で、彼は猛禽類に強い関心を持っていた)。世界大戦でドイツが侵攻した時、モスクワ大学の標本をトルクメニスタンに避難させたそうで、その結果この地域の鳥類相はソ連でも一番よく調べられることになったとのこと (wikipedia 英語版)。
ワトソンの本に引用されてる Dement'ev の初期のイヌワシの文献もオンラインで読むことができる L'Oiseau et la Revue francaise d'ornithologie 6:361-368 "Le vol a l'aigle au Turkesta" (1936)]。
これは一般的にヒゲワシの習性と考えられたが、イヌワシも同様の行動をすることはギリシャ時代から知られていた。ワシの種類はわからないがイソップ物語に「ワシとカラス」「カメとワシ」の話がある。紀元前79年の書物では6種のワシがいて、そのうちの morphnos (perenos) と呼ばれる2番目に大きい種類がアイスキュロスの逸話と同じではないかとの 考察 がある。
morphnos の正体はイヌワシではないかとの 考察 がある。尾が際立っているのはヒゲワシの方の特徴にも思えるが、黒い点からはイヌワシに似ている。2番目に大きいというのがハゲワシに次いでの意味ならばイヌワシとも解釈できる。
鳥の道具使用 (境界領域も含む) については Lefebvre et al. (2002) Tools and Brains in Birds に一覧文献があり、食物を落として食べやすくする行為はカモメ類でも知られており、ヒゲワシやイヌワシ (そしてカラス) が必ずしも特殊ではないようである。
動物の道具使用については Colbourne et al. (2021) Extending the Reach of Tooling Theory: A Neurocognitive and Phylogenetic Perspective によりより現代的な定義や道具使用の分類がなされ、分類群ごとの道具使用の統計も出ている。鳥類の道具使用は非霊長類の哺乳類よりも霊長類に近い値となっている。
What do Golden eagles eat?
に他のワシは肉しか食べないがイヌワシは果物や野菜を食べることもあるとある。特に獲物がない時に何でも食べられるとある。嗅覚で探すこともできて、必要があれば食べるとある。本当だろうか? → この話題は #クロハゲワシ備考の [猛禽類の植物食] に移動した。
[イヌワシと他のワシとの種間関係]
イヌワシと他の猛禽類のどちらが強いか話題になることがある。ナショナルジオグラフィックのカムチャツカ越冬地の映像ではより体の大きな海ワシに比べてイヌワシが劣勢である。ブルガリアのハゲワシの給餌ステーション (#クロハゲワシの備考も参照) にイヌワシが現れ、成鳥イヌワシは危険なことがわかってすぐ飛び去ったが、イヌワシの若鳥は危険を知らず、無謀にもシロエリハゲワシ Gyps fulvus を襲って反撃された。
シロエリハゲワシの方が強くて致命傷を負うところだったが逃げることができた。若鳥にとってはよい経験になったとの記事がある (ブルガリア語ではハゲワシ類を leshoyad と呼ぶ。lesh が死体の意味なのでここまでスラブ言語の語義を読まれた方には意味がすぐわかるだろう)。
アルタイ山脈近くでのイヌワシとクロハゲワシの争いの映像がある: Fighting of Golden Eagle and Cinereous Vulture, Fighting on the ground。どちらも足を使って攻撃しているが、やはり体格差が効いているようである。
オジロワシの wikipedia 英語版に英国スコットランドにオジロワシが再導入された後の経緯が記されている。イヌワシは本来の生息地の岩山から進出して本来オジロワシのすみかである海岸近くの低地まで生息するようになっていた。
オジロワシの再導入後にこの2種の間の競争が熾烈になっている。生態的にはオジロワシの方が優位であるとされている (生息密度が高くなり得る。腸が長くて食物が少なくてもより効率よく吸収できる)。両者争って両方死ぬこともある。
北米では越冬期にハクトウワシがイヌワシをよく殺していて、イヌワシはハクトウワシの営巣地付近を意図的に避けていると報告されていると記されている。
ワトソン「イヌワシの生態と保全」にはイヌワシとオジロワシがまだ両方いた古い時代の分布が多少紹介されていて、それが正しいとすればすみわけていたよう (イヌワシはやはり山地)。まだオジロワシがいたころは、イヌワシは生息可能な場所であってもやはりオジロワシを避けていたと考えるのが妥当そうである。
他の解説でイヌワシは (海ワシに比べ) 消化機能が弱いようで、嘴の力に頼っている部分があるとの記載もある。
Ivanovsky and Sobole (2024 初出、2025 再掲) On the issue of trophic plasticity of the white-tailed eagle Haliaeetus albicilla when occupying nesting territories of the golden eagle Aquila chrysaetos that are not typical for it (pp. 1002-1006)
ベラルーシでもオジロワシの方が優勢らしく、イヌワシのテリトリーを奪ったとのこと。かつてはオジロワシは主に魚食だったが、陸上部のテリトリーを占めることでシュバシコウなどを多数捕食するようになり適応力があるとのこと。特にかつてまったく捕食していなかったシュバシコウが主要な食物となっておりシュバシコウの保全上はより脅威となっているかも知れない。
イヌワシ対オジロワシでこの状況であれば、カラフトワシがかつてサハリンに多数生息していたとの目撃談も信憑性が低い印象を受ける (#カラフトワシ備考 [なぜ "樺太" ワシ?] 参照)。
食性に関係した他の猛禽類との関係では、イヌワシが飛翔中の猛禽類を襲うことがある。須藤 (2006) Birder 20(2): 34 によれば成功率は低いがトビ、ノスリ、カラスを頻繁に襲う。時々はハチクマ、ハイイロチュウヒ、キジバトなども攻撃するとある。イヌワシは小回りが得意でないので比較的大きな猛禽類を狙うとのこと。
他の猛禽類ではないが、ノルウエーで一度絶滅した地域に再導入されたホッキョクギツネをイヌワシが主に捕食している。イヌワシにとってはたやすい獲物とのこと。
Jackson et al. (2023) Predation of endangered Arctic foxes by Golden eagles: What do we know?
ホッキョクギツネ用の餌箱はカラス防御はしていたが、餌のありかを知ったカラスやワタリガラスが集まるようになってイヌワシの注意を引く、またいつも周囲に鳥がいることでホッキョクギツネが上空の敵に鈍感になる。カラス類も幼若なホッキョクギツネを殺すこともある。
餌箱を木製のものにすることでカラス類があまり来なくなった。回転式の鳥除けを設置したが効果はなかった。ワシに見える太いロープで逃げ込める鳥除けを設置したところ効果があった。
イヌワシも保護されている種類で知恵が必要とのこと。
[タカを育てたイヌワシ]
アカオノスリを育てたイヌワシの報告がある (Golden Eagles Raise A Hawk)。巣立ちまで育て、イヌワシのひなは約 20 日後に巣立ったとのこと。
ワシ類 (特にハクトウワシ) の巣で他の種類のタカのひなを育てるケースがまれに報告されており、タカがワシの巣に産卵したのか (托卵?)、それとも食物として運んだタカのひなか卵を育ててしまったのか議論となっていたが、近年の巣のライブカメラの発達により餌として運んだタカのひなを育てたと思われる事例が報告されるようになった
[Bay Area birdwatchers mourn the failed rescue of 'Tuffy,' the kidnapped baby hawk (2023)
最初はアカオノスリのひな2羽が運ばれたが、1羽は生き残らなかった (理由は不明); Friends of the Redding Eagles にさまざまな情報や映像あり。2019 年にも同様の出来事があった]。
カザフスタンでもニシオオノスリ Buteo rufinus Long-legged Buzzard を育てたソウゲンワシが報告された: Pulkova et al. (2021) Rearing of Juvenile Long-Legged Buzzards by Steppe Eagle in Western Kazakhstan 同様に食物として運んだ事例の可能性があるとのこと。
リトアニアでオジロワシの巣にヨーロッパノスリのひながいるのが見つかったが、この時は原因まで特定できなかった: Dementavicius (2004) Common Buzzard (Buteo Buteo) and White-Tailed Eagle (Haliaeetus Albicilla): Breeding Parasitism or Atypical Feeding Behaviour?
[タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳]
これまでに測定されている動物の中で視力が一番よいとされるのがオナガイヌワシなのでここに含めておく。
視力一覧は List of Animal Spatial Acuities にある。ヒトの視力 (この表では視力 2.4 に相当) を超えるのは大型の昼行性猛禽類のみで、それでも最大2倍ぐらいである。Acuity (cyc/deg) を 30 で割れば日本で使われる視力に相当する (*1)。
タカ・ハヤブサ類の視力が人間よりよいことがあることは昔から知られていたが、そのような分解能は理論的に不可能であると考えられていたようである。タカ類などの網膜に深い中心窩 (central fovea) があり、望遠レンズのような働きをして分解能を高めているとの説明は現在もよく行われているが、
その出所は Snyder and Miller (1978) Telephoto lens system of falconiform eyes (redwood.berkerley.edu のサイト) にあり、中心窩の深いくぼみが凹レンズのように働いて像を拡大することで分解能を高めているとの説明である。
これは網膜と硝子体で屈折率が異なることでレンズ効果があることを前提としているが、後の研究ではその効果はほとんどないだろうとのこと (*8 に別の視点から追記あり)。
Potier et al. (2020) Visual adaptations of diurnal and nocturnal raptors
のレビュー論文でのその後の研究がまとめられている。
ここでは他の文献も参照にしつつ主にこの論文から要旨を紹介しておく。
像を拡大して分解能を高るよりもむしろ中心窩で回折限界 (diffraction limit; 波動光学による限界 *2) まで光受容細胞を詰め込んでいることの方が重要なようである (デジタルカメラで言えばピクセルサイズを小さくして分解能を上げることに対応する。その分1ピクセルあたりの光の量は減るので感度は犠牲になる。日暮れの明るさでは猛禽類は最大視力を発揮できない)。
回折限界というのは光が波の性質を持つため解像度は瞳孔の大きさ (レンズで言えば口径) で決まる上限があること。これは焦点距離 (眼球の大きさ) にはよらない。
瞳孔の大きさが 1cm で角度の 12" (秒)に対応する (人間の場合は視力 1.0 で 60" なので、12" は視力 5.0 に対応する)。
大型フクロウ類では 1cm を超える瞳孔を持つ種類があるようだが、これは視力のためではなく光を集めるため。それほど大きな瞳孔のタカ類は多分いないのではないだろうか
オープンアクセス論文では Potier et al. (2020) Inter-individual differences in foveal shape in a scavenging raptor, the black kite Milvus migrans
でトビの虹彩サイズを測定している。鷹匠に持ってもらったトビの目に定規を当てて測っている画像が紹介されている。虹彩サイズは 10.5-12 mm ぐらいだったとのこと。
瞳孔サイズは同画像からみると 5mm よりは小さそうに見える。
この記事を書いた後、散瞳剤を使った研究を見つけたので追記しておく: Rhim et al. (2023) Application of topical rocuronium bromide dosing by ocular size in four species of wild birds
チョウゲンボウで通常 4 mm のところが 6 mm まで開いた。アオバズクで通常 6 mm, 最大 11 mm ぐらい、ワシミミズクで通常 11 mm, 最大 16 mm の数字になっている。さすがに自然条件でここまで開くことはないだろうし、レンズの外側を使うと収差が増えるので野外条件に対応する数字ではないだろう。
昼間ならば瞳孔は縮小するので、もし 5 mm とすれば回折限界は 12/0.5=24" となって視力 2.5 に相当する。タカ・ハヤブサ類でも人の目に比べて何倍も視力が視力がよいはずがないことがわかっていただけると思う。ちょっと検索すると人の視力の8倍と書いてあったりするがこれは俗説だと考えていただいてよい
[この俗説が誤りであることは Potier et al. (2020) も指摘している]。
Shlaer (1972) An Eagle's Eye: Quality of the Retinal Image によい研究がすでにあり、人の視力の8倍はそもそもあり得ないことを述べている。
この著者は地元のペットショップ (いかにも当時の状況らしい!) でオナガヘビワシ 現在の学名で Circaetus spectabilis 英名 Congo Serpent Eagle (体重 1.33 kg) を買って専門機材で検査をしている。
瞳孔サイズは 6-6.5 mm だったそうである。無限遠にある点光源 (すなわち平行光) の光が網膜ではどのように広がっているか (この文献の Fig. 1) を調べて視力を測定するものだが、被検者の鳥は実験の2日目は焦点を合わせてくれなくなり、その日の終わりには協力してくれなくなったそうである。
中心波長が 600 nm で 400-760 nm の範囲の光を使っている (つまり単色光ではなく色収差も影響を与える)。
この論文ではこの広がりのことを linespread と呼んでいて、論文を読んでもこのあたりで意味がわからなくなってきた読者があるかも知れない。実際には実験に用いた光源には大きさがあるため、理想的な点光源を見た場合よりも広がって見える。この補正を伝達関数 (transfer function) を用いて行っている (論文2ページ目の式)。
そのようにして理想的な点光源がどのように広がるかの関数形を知ることができる
(一般的な生物学者にはあまり馴染みがないかも知れないが、バーダーにはいろいろな分野の方がおられるだろうから、広い分野で使われる伝達関数の表現の方がわかりやすく感じられる方もきっとあるだろう)。
実際の光源を表す画像 (例えば視力検査のランドルト環でも何でもよいが) を周波数空間で表したものに伝達関数をかければ (だいたい掛け算みたいなもの、少し詳しい説明が下記にある) 網膜でどのような像になるかがわかる。すなわち光学系の特性は伝達関数を知ればほぼ把握できると考えてよい。
なお望遠鏡などでは点光源が光学系でどのように広がるかを示すものとして点広がり関数 (point spread function, PSF = この論文での linespread に相当) がよく使われる (wikipedia 英語版/日本語版によれば最近は眼科学でも使われているとのこと)。実際の光源を表す画像に基づいて点広がり関数を重ね合わせれば網膜でどのような像になるかがわかる点は伝達関数を使う場合と同じ
[(少し難しいので飛ばしていただいてよい) 読者各人の分野によってわかりやすい表現が異なるだろうことを念頭にあえて追加説明しておくと、Shlaer (1972) も書いているように PSF と伝達関数はフーリエ変換の関係にある。
伝達関数の場合は掛け算になるところが PSF を使う場合は畳み込み積分となることに対応する。理想的光学系の PSF は Shlaer (1972) の脚注12で伝達関数の表現で表されている。
これらの表現が理解できれば、実際の光源を表す画像に高い周波数成分 (細かい構造) があってもこの伝達関数を掛け算すると (この光学系を通すことに相当) ある上限周波数以上は0になるので細かい構造が消え去る。この掛け算は周波数ごとに独立に行われるので、他の周波数の伝達関数が別の周波数の結果に影響を与えない。
これが周波数空間で議論する利点で、伝達関数が0になる上限周波数が解像度の原理的な限界になる。
伝達関数が上限周波数付近でどのように0に近づくか、低い周波数での伝達関数の形なども画質に影響を与える。単純に視力あるいは分解能だけを記述するよりも伝達関数 (または等価な PSF) にいかに多くの情報が含まれているかわかっていただけるだろう]。
この光学的実験はワシの目を光学系として評価したものになっている。網膜に視細胞が十分密にあればこの光学系の限界まで分解できるが、光学系の限界なので網膜にたとえ像の拡大機能があってもそれ以上は分解できない。細胞密度が低ければそこまで分解できないことになる。
鋭い人であれば網膜の細胞密度や、さらには上位の脳の中でどう処理されているかわからないと実際の視力がわからないのでは? との疑問を持たれるかも知れない。
この実験では焦点合わせを実験者が行っているのではなく、被検者 (ワシ) が行っている点がある意味ミソで、つまり網膜のみならず脳の中の回路も経てそこまで分解できて (細かいところまで視認できて) いないと焦点をそもそも追い込めない (マニュアルフォーカスで写真を撮る時と同じ)。
つまり細胞密度を測らなくても焦点合わせ能力を用いてワシの視力を事実上測定できる。またこの能力から回折限界近くまで視細胞が詰まっていることが間接的にわかる。
生物学的視点からは細胞密度も測って行動による弁別実験も行わないと納得しにくいかも知れないが...
このオナガヘビワシの視力はヒトの2倍となったとのこと。この文献の Fig. 2 にある一番上にある点線が波動光学 (*2) による限界で理想的な光学系の場合。実際の生物の目は理想的な光学系ではないのでそれよりは下になるが、同じ方法で測定したヒト (一番下の曲線) よりは上である。
この文献の Fig. 1 の曲線は理想的光学系の PSF またはエアリー・ディスク (*2) よりも裾野が広いが中心部のピークは理想的なものにかなり近い。この結果分解能は理想的なものにそこそこ近いものになっているが、全体的なコントラストは理想的光学系ほど良くない結果となっている (細かいところは見えるが全体的には少しぼんやりしている。双眼鏡などのグレードの表現と対比すると意味がわかりやすいだろう)。
ただし実験室条件なので最大分解能を示す瞳孔サイズになっていない可能性はあるとのこと。
ただし瞳孔サイズを絞れば回折限界の効果で分解能が下がるので、この論文の著者は最大視力はこの実験の結果と大きく違わないとみているだろう。
ゴマバラワシ 現在の学名で Polemaetus bellicosus 英名 Martial Eagle は焦点距離 36 mm という報告があり、そのまま外挿すれば人の目の 3.0-3.6 倍に達する可能性があるとしている。
この文献ではイヌワシで人の 2.4-2.9 倍に達する可能性があるとの推定で、オナガイヌワシによる測定以前のものだが結果的によく合っている [先に分解能は瞳孔サイズで決まり焦点距離によらないと書いていたのと矛盾するように感じられるだろうが、瞳孔サイズも眼球の大きさに対応して大きくなる状況を考えているのだろう]。
ただし比例的に大きくすれば性能が比例して上がるだろうと考えるのは安易で、小さい時は目立たなかった収差もその分大きくなる。大きさだけでなく細かいところの構造も大事で、望遠レンズが大型になると急に高価になるのはこの影響もある。
もし眼球の大きさなどが体サイズに比例し、細かい光学的性能も維持できるならば体重 W (kg) の猛禽類の視力はヒトの 2*(W/1.33)^(1/3) 倍と推定できる。5 kg (オジロワシ、フィリピンワシ程度) でようやくヒトの3倍。
しかし大型種ほど頭部が相対的に小さいことを考慮し、眼球の大きさは体重よりも脳サイズとよく相関するとの研究をもとに考えると 1/3 乗は大きすぎる。タカ類の脳重量が体重の 0.54 乗の関係 (#ハチクマの備考参照。1乗より小さいので negative allometry と言われる) を用いると体重の 0.18 乗 (=0.54/3) が適切に思える。
2*(W/1.33)^0.18 として改めて見積もってみると 5 kg でヒトの 2.5 倍となる。このあたりが猛禽類の視力の限界だろう。500 g のタカだとヒトの 1.7 倍、小型種で 100 g でもヒトの 1.3 倍程度。
小さな体の割には確かに驚異的な視力かも知れない。
Shlaer 自身が調べた多くの猛禽は多少遠視気味で、色収差も加味して分解能がより高くなり得る青色光を用いて視力を稼いでいる可能性も考えているなどさすがに専門家だけあってなかなか面白い
(青色光の方が屈折率が高くてより短い距離で焦点を結ぶため、若干遠視気味の目の方が青色光の方が波長が短くて回折限界的には有利だが、この効果があってもせいぜい 1.5 倍ぐらいよくなる程度。実際には青い光の光受容細胞がそれに対応する密度で詰まっているわけではないのでこの効果はほぼ考えなくてよいだろう)。
ワシの網膜では (高い解像度を得るため) 視細胞が小さいので明るさが暗くなるとすぐに視力が下がるはずとすでに述べている。ワシの目は伝説ほどは視力が良くない主な論点はこの 1972 年の論文ですでに出尽くしている印象である (その後に出た鳥の本を見て育った者にとってはそんなに早くからわかっていたのか...とちょっと驚きであり、なぜ誰も教えてくれなかったのかと思ってしまう)。
その割にはあまり言及されていないのは、見てすぐわかるような図がなく論文がやや難しい表現で書かれていて光学などの知識がないと理解しにくいためかも知れない。知識を補充した上でじっくり読まれるとよい論文であろう。
さらに脱線して技術面に注目すれば、この時点で PDP-8 という世界初の商用コンピュータが手元にあってそれを用いて計算したとある。PDP-8 は最初の発売が 1965 年とのことで現在の価格に換算すると 1000 万円以上だったそうである。
wikipedia の解説によれば正面パネルに並ぶスイッチを ON/OFF することでビットを入力する、まさしくマイクロコンピュータである。命令は3ビットで8種類しかなく、プログラマに見えるレジスタは3個だったという。現在の電子機器でどのぐらいのものに相当するかすら言えないぐらいである。
アポロ 11 号の月着陸が 1969 年。当時のコンピュータ技術で達成できたことは信じがたいぐらい。
惑星探査機のボイジャーが打ち上げられたのは 1977 年でさほど違わない時期。木星・土星・天王星・海王星まで撮影や様々な観測に成功し、現在も 200 億 km 離れた地球からの命令を受け取って 1970 年代の電子機器が現役で活躍している。当時の技術を考えると驚くべきとしか言えない。Shlaer の研究もそのころと思っていただければいかに時代の先端を行っていたかわかる。
Reymond (1985) のオナガイヌワシを使った行動実験 (Spatial visual acuity of the eagle Aquila audax: a behavioural, optical and anatomical investigation) が有名 (残念ながらこの系統の論文の多くがオープンアクセスでない) でこれまで測定された中で最大視力を得ているが、もちろん「伝説」のヒト8倍には遠く及ばない。
Martin (1986) Shortcomings of an eagle's eye でアメリカチョウゲンボウの視力はヒトと同程度 [Gaffney and Hodos
(2003) The visual acuity and refractive state of the American kestrel (Falco sparverius)] であることも記されている。
なおオナガイヌワシの目でもコントラスト分解能はヒトの目に劣るとのことで、コントラストの低い対象物はヒトの目より細かいところを見分けられないそうである。
「伝説」を信じている鳥類学者、鷹匠、バードウォッチャーなどにはにわかに受け入れ難いだろうが、ワシの目の視力も物理法則の限界を超えないことを知ってある意味安心するのではないかとも記されている。
例えば琵琶湖のオオワシがとまっているとこから魚の動きが見えて...というのは多分無理だと思う。
また人間の場合でも昼間の瞳孔の 5 mm はかなり大きいので (十分暗いところでは若い人ならば 7-8 mm ぐらいまで広がるらしい)、視力 2.0 より上を測る意味がないこともわかっていただけると思う。
また光の波長によって屈折率が異なるためレンズには色収差があり、通常の光と波長の短い光を同時によく結像させることはできない。昼行性猛禽類では鮮明な像を結ぶためにむしろ硝子体で紫外線をカットしている (#チョウゲンボウの備考参照)。霊長類の中心窩も青の受容体を避けている。波長の短い光を活用して分解能を上げていることは特になさそうである。
生物の目は光学設計されたレンズというわけではなく、瞳孔を大きくすると各種収差の影響も大きくなるので必ずしも視力が上がるわけではない。ヒトの目で視力が最大になるのは瞳孔径 2.4 mm 程度との研究があるそうである [先に紹介の Shlaer (1972) に紹介あり]。
この場合の回折限界は視力 1.3 ぐらいに相当。これを超える視力の方は瞳孔径を広げても目の収差が小さいなど恵まれた眼球を持っておられるのだろう。
Potier et al. (2020) の論文では、中心窩の深いくぼみに結像することで平坦な網膜に比べて像が歪んで動く獲物を見つけやすくなるとの Pumphrey (1948) の仮説が紹介されているが実験的には確かめられていないようである。
深い中心窩では網膜が薄いため光が網膜を通って光受容体に到達するまでの距離が短く、光が吸収や散乱を受けにくくより鮮明な像を結ぶ点については疑いはない (人間の目でも構造は同じで、光は神経層を通ってから光受容体に到達する。
このような構造になっているのは目は脳が外に飛び出たものであるためで、発生学的に構造上裏面から光を受けざるを得ないため。眼底検査で脳の動脈の状態を推測するのも目が脳の一部であることによる。またこのような構造になっていることが網膜剥離のような病気が存在する原因でもある
無脊椎動物の頭足類 Cephalopoda の眼球は独自に進化したもので、発生が異なるために網膜の裏表は脊椎動物とは逆になっている)。
鳥類の眼球の動きについてもしばしば誤解がある。タカ・ハヤブサ類では眼球は眼窩に固定されて動かないというのは誤り。鳥類にも(動)眼筋はあり、我々と同様に動眼神経 (第 III 脳神経)、滑車神経 (第 IV 脳神経)、外転神経 (第 VI 脳神経) の3種類の脳神経によって眼球が動く (*3)。
Cunha et al. (2022) The relative sizes of nuclei in the oculomotor complex vary by order and behaviour in birds
にさまざまな鳥でこれらの眼球を動かす神経の神経核の発達程度を調べた論文がある。フクロウ類は神経核の発達が悪く、眼球をほとんど動かさないことに対応している。
タカ・ハヤブサ類は外転神経が発達しており、獲物を追跡して捕獲する時などに眼球運動で目的物を中心窩から側方窩に移動させて視野を合わせ直しているのに対応していると考えられる。スズメ目にも同様の性質が見られた。アイサの1種でも同様の性質が見られ、水中で獲物を追う時に必要と考えられるとのこと。
Plochocki et al. (2018) Extraocular muscle architecture in hawks and owls
によればタカとフクロウで外眼筋の働きが違い、フクロウの筋肉は眼球を固定する役割が中心で、タカでは筋肉で眼球を固定する必要はそれほどなく眼球を素早く動かすのに役立っている。
鳥でも我々と同じように前方近くを見る時に目を寄せることができる。
ただしどれだけ眼球を動かせるかは種によってかなり大きく違うようである。
猛禽類ではアメリカワシミミズク Bubo virginianus 英名 Great Horned Owl で眼球は最大 1.5° しか動かせないなど、フクロウ類では「眼球を動かせない」常識がだいたい正しいと考えてよさそうである。
タカ類では必ずしもそうではない。例えばアカヒメクマタカ Hieraaetus morphnoides 英名 Little Eagle では水平方向に眼球を 24° 動かせるとのことで正面の近くを見る時に目を寄せることができる。通常 5° 以内だが我々と同じようにサッケード運動 (視覚目標を視力の高い網膜中心窩で捉えるための急速眼球運動) を行うことも知られている
(ヒトの場合の研究の紹介: 神経科学: 急速眼球運動で素早く見る)。
アメリカチョウゲンボウやアカオノスリではこれほど眼球運動は大きくなく、種差が大きいと考えられるがよく調べられていない。しかし猛禽類は一般的にはカラス類 (最大 39°) よりは眼球運動は小さいとされる。
両眼視できる視野の範囲などを調べる場合にも眼球運動も正しく考慮に入れる必要がある。
関連情報や文献へのリンクが#ハイタカ備考の [ハイタカの急降下による捕食行動] にある。
地上の生きた獲物を探す種類では後上方を見る必要がないためこの部分は見えない領域が他の種類よりも広い。このような種類が飛びながら下を向いて獲物を探すと前方が見えにくいため、風力発電ブレードや送電線に衝突する理由になるのではとの考えがある。
(鳥類の脳と睡眠の関係をここに記載していたが、#オオグンカンドリの備考に移動してまとめた)。
#ハチクマの備考にも少し紹介したが、多くのタカ類には中心窩 (central fovea) の他に側方窩 (lateral fovea または temporal fovea 側頭窩) が存在する。中心窩は我々の中心窩と同様に視力が最大になる場所で、斜め前方が最もよく見える種類が多い (我々のように両眼視の正面が中心窩ではない)。
側方窩 (側頭窩) は前方で両眼視できる方向に対応しているが、正面よりは少し外側に視力の中心がある (目を寄せられる種類であれば真正面に向けることも可能かも知れない)。鳥の種類によっては側方窩の視野が左右で重なっていないものもある (#ツバメの備考参照)。
「鳥たちの驚異的な感覚世界」(ティム・バークヘッド著 沼尻由起子訳 河出書房新社 2013) でも鳥類の視覚については多く記述されている。しかし猛禽類で深い中心窩が正面を詳細に見るのに役立っているような記述 (ギル「鳥類学」の訳書でも同じように書いてあるが原書は確かめていない)、また先述のように中心窩で凹レンズで拡大される説明は誤りのように思える。
フクロウ類の目が正面に近い向きなのは立体視のためではなく聴覚を優先したためそちらを向かざるを得ない説明が記載されている (ただしフクロウ類で大脳で立体視処理を行っているとの研究がある。以下の説明も参照 *4)。
この訳書を見ても2つの中心窩の解剖学名称に定訳がないらしいことがわかる。この本では中心窩を「深い中心窩」、側方窩 (側頭窩) を「浅い中心窩」と訳している (原著は見ていないがそのように記述されているのだろう。また注釈には前中心窩、後中心窩の別名が挙げられている)。ヒトの場合は1つしかないので fovea と言えば fovea centralis を指し、これには中心窩の定訳があるので fovea を中心窩と訳しているのだろう。fovea もラテン語で「くぼみ」の意味。
この文書では lateral fovea を文字通り側方窩としている。temporal fovea 側頭窩 の呼び方もあって同じものを指す。
目の焦点調節 (遠近調節。専門用語で accommodation と呼ぶがあまりよい訳語がないようである) は鳥類では角膜と水晶体 (レンズ) の湾曲を変えることで行っている。哺乳類では水晶体による調節のみ。
Potier et al. (2020) によれば (若い) ヒトでこの調節能力は 8.6 D (Diopter ディオプトリー/ディオプトリ/ディオプター) とのこと。
100/8.6 = 12 cm ぐらいまで近くのものにピントを合わせられると読めばよい。加齢によりこの調節能力は大きく低下することはご承知の通り (加齢変化は鳥類でも起きるそうである)。
哺乳類の調節能力が鳥類に比べて相対的に発達していないのは、哺乳類が夜行性生活を長く続けたために調節の必要があまりなかったとの考えもある。
猛禽類で調べられている種類ではアカオノスリで 28 D、他の昼行性の種で 4-16 D の値が得られている。小型種は角膜による調節を行わないが、アカオノスリやイヌワシなどの大型種では角膜で 3-9 D の調節を行うとのこと。
フクロウ類の大半は角膜による調節を行っていないようである。アメリカメンフクロウ Tyto furcata 英名 American Barn Owl では 10 D の調節能力があるが、他の種では 0.6-6 D の値が得られている。
昼行性猛禽類の方が調節能力が大きいのは、フクロウ類は獲物を丸のみするが昼行性猛禽類は獲物を解体するので近くにピントを合わせる必要がある理由が挙げられている。
鳥類の眼球内にあるペクテン (pecten 櫛状体) は血管に富む構造で浸透によって網膜に栄養や酸素を送ったり眼圧を調整する役割があるとされる (鳥類では網膜に血管がほぼない)。昼行性猛禽類はペクテンがよく発達しているとのこと。
また鳥類の目には他の動物に見られないグロビン (Globin) E (GbE) があり、ちょうどヘモグロビンのように網膜に酸素を供給するのに役立っていることも指摘されている [Blank et al. (2011) Oxygen Supply from the Bird's Eye Perspective]。
眼球内にペクテンがあると視覚を邪魔しそうだが、ペクテンの影は網膜周辺部のあまり重要でない場所に落ちるようである。
ペクテンに光受容機能があり、光周性に関係している可能性が最近示唆されている。Kusakabe et al. (2024) Characteristics of pectens in diurnal and nocturnal birds and a new functional proposal relating to non-visual opsins
実験はニワトリの網膜を用いたオプシン (次項参照。網膜の光受容に関連しないタイプのオプシン) の遺伝子発現による。夜行性のアオバズクではペクテンが血管に乏しいとのこと。
よく知られているように網膜細胞には主に暗い時に働く弱い光も感じる桿体細胞 (rod cell; 光を感じる物質はロドプシン rhodopsin) と 明るい時に働いて色を感じ、空間分解能も高い錐体細胞 [cone cell; 光を感じる物質はオプシン opsin (*5) で多くの鳥類で色覚に対応した4種類がある。ヒトは3種類] がある。夜行性の鳥では桿体細胞が中心で錐体細胞が少ない。深い中心窩はほぼ錐体細胞が占めていて視力と色覚を活用していることがわかる。
この点は我々も同じで、網膜周辺部は桿体細胞が多く視野の中心より外側の方が感度が高い (夜間の外敵への対応の名残としてよく理解できる)。
鳥類の多くは錐体細胞に3種類の色の油滴 (oil droplet) を持っていて色フィルターの役割を果たしている。いずれもカロテノイド色素由来で青の油滴はガロキサンチン (galloxanthin) とジヒドロガロキサンチン (dihydrogalloxanthin)、緑はゼアキサンチン (zeaxanthin)、赤がアスタキサンチン (astaxanthin) (#ベニマシコの備考参照)。
鳥類の紫外線を感受する錐体細胞は油滴による吸収を受けない。
フクロウ類などいくつかの系統でアスタキサンチンを作る酵素を失っており (#フクロウの備考参照)、フクロウ類ではそれによって紫外線への感度を高めていると考えられている。
昼行性猛禽類では基本的にこれら4種の油滴色素を持っているが、調べられた範囲でチゴハヤブサ、アメリカチョウゲンボウ、ヨーロッパノスリは赤の油滴を欠いているとのこと。
鳥類では視神経は視交差で全交差するとされ (この点は両眼視をするヒトや肉食哺乳類などで部分交差する点と異なる)、反対方向の脳に送られる。網膜からの信号は中脳の視蓋 (optic tectum または optic lobe 視葉; 哺乳類の上丘 superior colliculus に相当。鳥類でもこの用語も使われる) にまず送られる。
ここでは左右それぞれの目からの情報処理が行われる。解剖学的にも鳥類の視蓋が非常に大きいことはよく知られている。
(なぜ反対側の脳に向かうのかは不思議な点であるが、仮説はいくつかあるそうである: 山拓 (2020) 脳が対側支配をする進化的な利点は何か)。
ここから視床を経て大脳に情報が送られる。同側からの入力も得て哺乳類の視覚野に対応する部位 (*6) に両眼視の視野の情報が入る [論文には supraoptic decussation を通じてとあり、もしそうならば視交差で部分交差になりそうだが、それ以上の情報はわからなかった。
部分交差は哺乳類だけの特権ではなく、魚にも見つかっている: Vigouroux et al. (2021) Bilateral visual projections exist in non-teleost bony fish and predate the emergence of tetrapods。両眼視の進化的起源は古いようである]。
ごく少数の種類 (アメリカチョウゲンボウとアメリカメンフクロウなど) でこの部位で立体視を含めた両眼視の処理が行われていることを示す研究があるが、実際の立体視の機構はよくわかっていない。Tyrrell and Fernandez-Juricic (2017) Avian binocular vision: It's not just about what birds can see, it's also about what they can't
はヒトが行っているような両眼視で奥行きを知るのではなく、嘴をガイドとして使って距離情報を得ている可能性を示唆している。
上丘の役割について近年の理解の進展を示した入門者向けレビュー論文: Hoy and Farrow (2025) The superior colliculus。
鳥についての記述は少なく哺乳類が中心。視線の変化、狩りや逃避などの本能的行動、顔の認知、注視点の移動などが主な役割に挙げられている。マウスやハトでは網膜ニューロンの 80% 以上が上丘に向かうが霊長類では 10% 以下と見積もられている。全体的に齧歯類と鳥類をまとめて扱い、霊長類は少し異なる文脈で書かれている印象を受けるがどうだろうか。
遺伝子発現を調べた次の研究も同様: Liao et al. (2025) Single-nucleus profiling decoding the subcortical visual pathway evolution of vertebrates。鳥類・哺乳類で回路が少し違う。本能的な逃避反応に関係する哺乳類の細胞層が鳥類には見られないとのこと。左右の目の情報をどのように統合するかの神経機構も異なる。しかし発現している遺伝子は共通性が高い。
哺乳類で鳥類とは別系統の回路が優勢になった理由が必要と思えるが、視覚情報が中心でなかった哺乳類がなぜそちらを採用したのか簡単には思いつかない。視覚情報が決定的に重要でなかったために別回路を冗長に使うこともできて結果的に後に優秀な解決方法となった? (ただし霊長類の両眼視能力が最も進んでいるとみなす人類至上主義的な観点かも知れない)。
用いているのがハトとキンカチョウなので両眼視がもっと重要な種類では状況が多少異なるのかも知れない。難しい内容なので論文所在紹介にとどめておく。フクロウ類では霊長類と異なる神経回路で両眼視を実現したが、その方法があまり効率的でなかったために脳の多くの部分を使ってしまい、大きな脳の割には知能を進化させることが難しかったなどの解釈は (これまでの描像に従って) 考えらえるが適切な推論かどうかはわからない。
論文では鳥類は脳の仕組みが異なるので (視覚など) 左右の脳をどのように統合しているのか哺乳類と異なった視点から進化を研究できるモデルになると見なしている。まだまだこれからだろうか。
なお Borges et al. (2019) Avian Binocularity and Adaptation to Nocturnal Environments: Genomic Insights from a Highly Derived Visual Phenotype
によればフクロウ類の目に関係する遺伝子が調べられており、ephb1 遺伝子 (視神経を部分交差させる機能に関係) に対する進化的な束縛が弱まっており、同側の脳にも情報を送って両眼視に役立てている可能性が指摘されている。agtpbp1 (網膜の光受容細胞の変性を防ぐ) は遺伝子機能が失われていて、フクロウ類がいくつかの色彩光受容体を失ったことに関係があるとみられる。
鳥類では視力以外にも時間分解能がよいこともよく知られている。Potier et al. (2020) How fast can raptors see? によるフリッカー融合周波数 (例えば蛍光灯のちらつきをどこまで感じられるかに相当) の実験によれば、
これまで調べられた種類で一番高い (130-140 Hz まで識別できる) のは飛翔性昆虫を捉えるヒタキ類、ハヤブサはそれに次いで 124.5 Hz、ワキスジハヤブサで 102 Hz。モモアカノスリ (ハリスホーク) は少し悪くて 77.7 Hz (ニワトリと同程度)。
動く獲物を空中で追跡するかどうかが重要なようである。フクロウ類は低い部類 (40-68 Hz) に属する。
モモアカノスリは中心窩が深く、中心窩の機能を考えると中心窩が深いほどフリッカー融合周波数が高いだろうとの予測に合う結果は得られなかった。
偶然ではあるがこの文書の執筆中に「野鳥」2023年11・12月号に「徹底解説! 鳥の目」(杉田昭栄) が掲載され、内容的には共通部分も相互補完的な部分もあるので合わせて読んでいただけるとわかりやすいと思う。杉田氏の記事では瞬膜、調節の機構、網膜の構造と網膜内での情報伝達などが詳しい (*7)。
Ruggeri et al. (2010) Retinal Structure of Birds of Prey Revealed by Ultra-High Resolution Spectral-Domain Optical Coherence Tomography
生体の猛禽類の網膜を広帯域波長光源による光干渉断層撮影 (SD-OCT) で調べたもの。仕組みは例えば井上 (2010) 光干渉断層計。
この研究は 2008 年に最初に報告され、この手法で猛禽類の網膜を調べたのは初めてとのこと。網膜の構造や2つの中心窩の構造の違いなどが明らかになっているが猛禽類の網膜の特殊性などはそこまで議論されていない。出てきたデータが何を意味するのかの解釈はまだこれからだろうか。
側方視と前方視で異なった中心窩の使い方をしているらしいことがわかる。死体組織を用いた解剖学的特徴以外にこのような現代的方法で例えば前方の両眼視の能力なども再評価されるかも知れない。
備考:
*1: ただしこの測定方法はヒトの視力検査に使われる方法 (円に切れ目のあるランドルト環など) とは異なるので多少の違いがあるだろう。回折限界の備考に出てくる2つの点を見分ける能力とも異なる。
縞のパターンを見分ける能力が測定されているが、このパターンは縞の間隔 (空間周波数) と縞の濃度 (振幅) の2つのパラメータで記述できるため標準的方法として使われているのだろう。
これはもちろん猛禽類が実際に獲物を探す時のパターンとは異なるので猛禽類の視力を正しく評価できていない可能性は残る。しかしながらこれらの結果は網膜の細胞密度から推定される視力とよく合うようなので実際の視力をほぼ測定できていると考えてよさそうである。
ヒトの結果を見るとランドルト環を用いた数字よりも少し高い値が出る傾向があるかも知れない (2点を見分けるよりもパターンを見分ける方が情報量が多いかも知れない)。この効果を考えるとオナガイヌワシの換算視力を5とするのはやや過剰見積もりかも知れない。ヒトの視力の2倍程度と読むのがよいだろう。
またこの実験は室内で行われたものであり、野外の直射日光を受ける条件では瞳孔のサイズが縮小し、回折限界 (*2) の効果でこれほどの視力は出ないのではないかと思われる。表に示されている値は最大値と捉えてよいと思う。
Martin (1986) によればオナガイヌワシの眼球の焦点距離は 22 mm、ヒトの目では 17 mm で大差ないのでワシの目はヒトの目より焦点距離が長いので拡大して見えるとの説明はそれほど適切でない。
網膜の凹レンズで 1.3 倍に拡大されるとの記述をしばしば見かけるが、もしかするとこの焦点距離の比を表したものだろうか?
飼育されているオナガイヌワシと人が並んで目の大きさを比べている写真を見てもいわゆる「黒目」の大きさはほぼ同じに見えるので瞳孔のサイズもおそらくあまり違わないと思われる。
直射日光下での大型ワシの目の現実的な視力は瞳孔径 5 mm 程度の回折限界に相当する視力 2.5 程度と考えるのが妥当と思える。
(特に若い時期に眼科検査を受けた方ならば薬で一時的に散瞳すると世間がいかにまぶしく見えて動きがとれないことをご存じだろう。明るいところでは瞳孔のサイズは小さくなっているはずである)
[その後以下の写真を知った Brutus and I (Currumbin Wildlife Sanctuary)。これはかなり大きく見える。ヒトの目の2倍の視力を得るためにはこの程度のひとみ径が必要なのだろう]。
日光が直接当たると縮瞳するので、「ひさし」とされるタカ・ハヤブサ類の眼窩上の張り出し supraorbital ridge (骨の突出構造、軟部組織由来のものの両方があるようである) や「ハヤブサ髭」も回折限界の効果で視力が落ちることを防ぐ役割もあるのかも知れない (私見仮説)。
猛禽類と言っても新大陸ハゲワシ類の視力が悪いことがわかる (目が小さいことからも視力をあまり重視していないことは想像が付く。嗅覚が良い)。フクロウ類も視力が悪いがこれは弱い光への適応のため網膜が桿体細胞中心であるためだろう。
トビやモモアカノスリ (ハリスホーク) が視力 1.0 の数字でむしろヒトより低いのは結構意外ではないだろうか。
ワシより眼球の小さい中型猛禽類の視力はおそらくこのあたりが標準的なのであろう。
昼行性猛禽類でハヤブサ目であるがチマンゴカラカラ Milvago chimango 英名 Chimango Caracara の視力が思ったより低いことを示した論文もある: Potier et al. (2016) Visual acuity in an opportunistic raptor, the chimango caracara (Milvago chimango)
猛禽類でない鳥よりはよいが、昼行性猛禽類の中では最も低いとのこと。ハヤブサ目とはいえカラカラ類にはあまり視力のよくない種類が含まれているかも知れない。
Potier et al. (2019) Sight or smell: which senses do scavenging raptors use to find food? によればカラカラ類は視覚に加えて嗅覚も使っている可能性が示唆される。ゴミ袋が不透明でも食べ物が入っている方を開けるとの観察が紹介されている。
*2: Potier et al. (2020) の論文では limitations of waveguide optics と持って回った表現で表されているが、回折限界 (diffraction limit) の用語があるのでそれを使えばよいところ。
Barlow (1965) Visual Resolution and the Diffraction Limit ですでに回折限界の用語を用いて視力を議論している。
waveguide と言えば通常は別の意味を指す。波動光学に対応する通常の英語は wave optics になる (それに対して反射、屈折のように通常思い浮かべるような波動性を考えない光学を幾何光学 geometrical optics と呼ぶ)。回折限界の代わりに波動光学的限界などと呼んでもよいだろう。
回折限界の概念は様々な光学分野で現れるが、特に望遠鏡や顕微鏡の分解能で話題になることが多く天文学ではよく使われる。
望遠鏡の分解能では経験的にドーズの限界 (Dawes' limit) がよく知られていて William Rutter Dawes が接近した2つの星をどこまで分解できるか観測で導いたもの。この結果は前記の理論限界ともよく合っている。望遠鏡の倍率を上げればもっと細かいところが分解できるように期待するかも知れないがこれは誤りで前述の限界を超えることはできない。
古くドーズの限界を超えて分解した観測報告があったが (火星の運河など)、「心眼」とも呼ばれていた。
回折限界はスポッティングスコープでも問題になり得るが、野鳥観察用のスコープはコンパクトにしたり正立像を作る必要があるため光学設計にやや無理があって回折限界よりも光学系の結像性能の方が限界を決めているかも知れない。スポッティングスコープでも木星の模様や土星の輪を見ることができるが、同口径の天体望遠鏡で見ると見え方の違いがわかるだろう。
これは天体望遠鏡の方が分解能を重視して単純な光学設計になっているためで、天体望遠鏡 (例えばボーグ) が野鳥撮影に使われるのもその利点を活かしたものと言える。ほとんどの天体望遠鏡で (すばる望遠鏡のような大きなものでも) 回折限界まで分解できるように設計されている。
回折限界の効果はカメラレンズなどでも同様で、レンズを小さくせざるを得ない超望遠コンパクトデジタルカメラで拡大率を最大にするとこの効果 (それ以上分解できない、あるいは実際に回折によるパターンであるエアリー・ディスク Airy disk の形が見える) を体感できる。
通常のカメラレンズ (一眼レフ) などでも同様であるが、レンズの口径が大きいためにこの効果は通常無視できる (ようなピクセルサイズが使われている)。
逆に換算すれば、視力 1.0 を実現するのに最小限度となるレンズ口径は 2 mm となる。パソコンやスマートフォンなどの小さなレンズのカメラでもそこそこの画像が得られるのはほぼこれに対応している。
1 mm 以下の小さなピンホールなどを使って見ていただければ回折限界やエアリー・ディスクを体感できる。
鳥の視力を考察する場合もこの考慮は必ず必要で、例えば瞳孔が 2 mm の小鳥であれば人間以上の視力にはなり得ない。
*3: 12 対の脳神経がある。生物のどこかで多分習うので爬虫類、鳥類、哺乳類では 12 対と覚えた記憶のある人もあるかも知れない。魚類、両生類の脳神経は 10 対。
日常的によく名前を聞くものは第 V 脳神経の三叉神経、第 VII 脳神経の顔面神経、第 X 脳神経の迷走神経などがある。前方から順番に名前が付いているので第 I 脳神経が嗅神経、第 II 脳神経が視神経などとなっている。
なお鳥類の発声器官である鳴管 syrinx は舌下神経 (第 XII 脳神経) の支配を受ける。
哺乳類の声帯を動かす神経は第 X 脳神経の迷走神経の一部で (迷走神経は腹部内蔵などにも広く分布する)、反回神経 (recurrent laryngeal nerve) と呼ばれる。
この神経は心臓に近い動脈弓の下を通ってから喉頭に向かうもので、一度胸部に入ってから喉に戻るために「反回」(recurrent) の名前が付いている。このような無駄に思える構造の理由は発生学的制約によるもの (本来は下方にあったものが進化・発生に伴って上部に移動したため)。
ヒトだとまだ大した遠回りではないが (それでも経路が長いので途中の損傷などで反回神経麻痺が起きやすくなる)、キリンだと大変な遠回りになる。これは発生学的制約によるものでやむを得ない。
鳥の鳴管の神経支配は哺乳類の声帯とは異なっているためこのような問題は発生しない。
*4: これに関連して、この文書では当初#フクロウの項目で「鳥たちの驚異的な感覚世界」や Potier et al. (2020) などに従い「正面視のために目が前に付いているわけではないようである。現代の書物でフクロウ類の目が立体視のために前を向いていると書いてあれば少し眉に唾をつけて読んだ方がよさそうである」と記述していたが、
フクロウ類で立体視が行われていることを検証した論文があるためこの記述を削除した。
「鳥たちの驚異的な感覚世界」によれば奥行き感覚は飛ぶ時に障害物を避けるために必要であることが述べられているが、獲物を捕る時には必ずしも必要でないようである (#ヒガシメンフクロウの備考参照。完全暗黒でも聴力だけで獲物を捉えられる点はフクロウ類では聴力による獲物の定位が実験的により確立されていると言うことはできる)。
障害物を避ける役割は十分考えられるが、移動中は運動によって (例えば視差) 奥行きの情報を得ることもできるので両眼視による立体視を用いているとは限らない。
ただフクロウ類に立体視能力があることは実験的に確かなようなので、生活に何らかの形で役立っていることは間違いないだろう。
Potier et al. (2023) Binocular field configuration in owls: the role of foraging ecology
がフクロウ類の両眼視についてさらに報告を行っていて、この研究者グループはフクロウ類の立体視の役割には懐疑的なようで、神経科学的に Wulst と立体視に相関があるらしいとの研究と対立仮設をなしている模様。神経科学的アプローチの方では特に Iwaniuk のグループが Wulst が立体視処理を行っているとみなしている。
Iwaniuk のグループは Gutierrez-Ibanez et al. (2018) Parrots have evolved a primate-like telencephalic-midbrain-cerebellar circuit
がオウム類が霊長類に似た神経回路を発達させている (認知機能も説明しようとしている) と報告しているが、個々に見てゆくとあまりすっきりしない。鳥類全体で比較を行うとオウム類の有意性が出てこず、フクロウ類を除けば有意差が出たとのこと。
フクロウ類の大きな大脳は視覚情報処理のためのもので認知にはあまり関与していないので除外するとの説明があり、このグループは視覚情報処理のためと考えていることがわかる (詳細は引用文献参照)。
しかし夜行性の鳥で両眼視をしない鳥 (ヨタカ類の一部) でも同じような傾向が見られるので視覚情報処理仮説は本当なのかとも感じられる (#ヨタカ備考の [ヨタカ類の視覚特性] も参照)。
Iwaniuk and Wylie (2006) The evolution of stereopsis and the Wulst in caprimulgiform birds: A comparative analysis にヨタカ類の脳の比較がある。ズクヨタカ科 (Aegothelidae, Owlet-nightjars)、ガマグチヨタカ科 (Podargidae, Frogmouths) はフクロウ類に似た脳の構造を持っているとのこと。
当時はフクロウ類とヨタカ類が近縁と考えられたことも要因であるが...。
[ヨタカ類の視覚特性] にある Salazar et al. (2020) の見解は明らかに対立しており、口ひげ状の羽毛など触覚に頼っているらしい点など後述のようにフクロウ類にも生態的共通性が感じられる。
Potier et al. (2023) によれば両眼視の範囲は昼行性猛禽類とフクロウ類で実はあまり違いがない (フクロウ類の方が広く両眼視を行っている印象は正しくない) が視野の形は違っている。
両眼視野の形は昼行性か夜行性かの違いが出ているかも知れない。フクロウ類では両眼視の範囲は比較的保存されているが種による生態的違いを反映している可能性がある。混んだ環境や無脊椎動物を食べる種類で両眼視の範囲が広い傾向がある。フクロウ類の場合は羽毛が両眼視の範囲を狭める効果が一部あって聴覚と視覚のどちらを優先するかどうかのトレードオフが働いている可能性があると考えている。
つまり集音機能などのために羽毛を特殊化するとその分視野の広さが犠牲になる。
フクロウ類で両眼視に関係する中枢神経回路が発達しているのは聴覚と視覚を併用して獲物の位置を決めるためとの考えもあって、神経回路の構造から立体視で獲物を見つけているとは言い切れない。
両眼視の視野内での嘴の位置が昼行性猛禽類とは異なり、フクロウ類は嘴が直接あまり見えておらず、むしろ捕食の際に足元が見えている (これは昼行性猛禽類でも重要)。フクロウ類は他の夜行性の鳥同様に嘴周辺の剛毛があって触覚として働いている。獲物を口に運ぶ際には触覚も併用しているのでは。
この著者たちはフクロウ類は複数の手がかりを使っているものの、獲物を位置を知るのには立体視はそれほど役に立っていないのではと考えている。よく実証されている聴覚の役割の方がより重要なのではないか、聴覚のために視覚の側方視野が制約されていると見ている模様。
眼科学的研究と神経科学的研究の整合性が必ずしもよくなく、どちらに重点を置くかによって表現が違ってくるらしい。文献を読む時もどちらの視点で書かれたものが注意が必要だろう。
またフクロウ類でよく研究されているメンフクロウとそれ以外の違いも考えられる。
例えば Gutierrez-Ibanez et al. (2013) Comparative study of visual pathways in owls (Aves: Strigiformes)
によればメンフクロウは strigid (Strix 属など) に比べて視覚に関わる神経が貧弱であるとのこと。この知見からは Strix 属などは相対的に聴覚の役割が小さいことが想像され、耳の左右差の発達が悪い (#ヒガシメンフクロウ備考の [フクロウ類の音源定位] 参照) こととも整合する。
耳の左右差と神経核 (時間差に関係する核と音圧差に関係する核で、耳の左右差は後者に関係する) の発達程度も整合性があるとのこと:
Gutierrez-Ibanez et al. (2011) Relative size of auditory pathways in symmetrically and asymmetrically eared owls。
我々が日本で一般的に見聞するフクロウ類はメンフクロウのような種類よりも視覚を用いて定位を行っている可能性がある。
*5: オプシン opsin 類については1冊の本が書けるぐらいのさまざまな内容があるが、ここでは鳥類に関係する話に絞る。何と言っても「体内時計の分子生理学的仕組み」が 2017 年ノーベル医学・生理学賞のテーマであったぐらい大きな分野で、1冊でも収まらないであろう。
網膜のオプシンは記述したが、網膜以外にもオプシン類が存在する。脳には「松果体」(pineal body/pineal gland) が存在し、「第3の目」とも呼ばれることがある。これは系統発生的には脳から外に飛び出た光受容組織でありほぼすべての脊椎動物に存在する。
ヤツメウナギ、魚類、両生類、トカゲ類などで光受容機能があり (一部は表面近くに突出している) 目に似た構造を持っているものもある。
鳥類の松果体にはピノプシン (pinopsin) と呼ばれる光受容機能のあるオプシンが存在する [Okano et al. (1994) Pinopsin is a chicken pineal photoreceptive molecule]。
真骨魚類と哺乳類以外はこのオプシンを持っているが、真骨魚類以外の魚類、両生類やカエルでは脳以外にも網膜にもこのオプシンが存在し、ロドプシンと独立に暗所視機能を進化させた可能性が指摘されている [Sato et al. (2018) Pinopsin evolved as the ancestral dim-light visual opsin in vertebrates]。
松果体は少なくとも一部の鳥類では1日周期の概日リズム (circadian rhythm < circa およそ diem/dies 日) の中枢 (ペースメーカー) の役割を果たしていると考えられ、ここで光受容を行って、概日リズムを調整するメラトニン (ホルモン) を分泌する
(さらに脱線するとメラトニンはアミノ酸のトリプトファンからセロトニンを経て合成されるためトリプトファンを摂取すると睡眠の質が上がるとの噂もある。この真偽はともかくトリプトファンはタンパク質中で最も含有量の少なく必須アミノ酸なので良質のものを食べないと不足するかも知れない)。
哺乳類の松果体には光受容機能こそないがメラトニンを分泌する内分泌器官となっている。
脊椎動物の視交差の上に視交差上核 (suprachiasmatic nucleus) があり、網膜からの光情報を受けて概日リズムに関与している。哺乳類では視交差上核が概日リズムの中枢とされていて、ここからの信号で松果体がメラトニンを分泌する。
鳥類でも視交差上核の機能を失うとリズムを失う実験があり、松果体と両者が関与しているのだろう [Patton and Hastings (2018) The suprachiasmatic nucleus]。概日リズムの中枢はイエスズメでは松果体だったがウズラでは目の方が重要、ハトでは両方重要など種によって重要性が違うようである。
時計遺伝子 (Per1, Per2 など) も発見されており、鳥類の磁気受容に関係して出てくる (#アマツバメの備考参照) クリプトクロムの Cry1, Cry2 もここで現れる。鳥類の Cry1, Cry2 が極めてよく保存され概日リズムに役立っている一方、磁気受容に関係する Cry4 は種によって違いが比較的大きい (見当たらない種類もある。渡りをしない種類ではおそらく必要性が下がって失われることもあるらしい) ことと比較して考えると面白い。
鳥類の脳内奥深くではさらに他のオプシン類が発現していて日照時間 (日長) を感じ取りこれが視床下部を通じ脳下垂体から甲状腺刺激ホルモン (TSH) → 甲状腺ホルモンなどの分泌を調整して年周リズムを作ると考えられている
[cf. Nakane and Yoshimura (2018) Photoperiodic Regulation of Reproduction in Vertebrates]。
哺乳類が脊椎動物の進化の頂点とする伝統的考え方に従えば、松果体は脊椎動物の進化の初期は実際に目であったが、進化とともに目の機能を失い哺乳類でついに光受容機能も失ったと考えるのは都合よいだろう (実際にそういう説明を聞いたことがある。だから下等な鳥類はまだ光受容機能を持っている...との文脈である)。
しかしながらこの考え方には哺乳類が長期間の夜行性生活の制約を受けて進化したことが抜けている。脳内オプシンの感度は非常に高く、脳や頭蓋骨を通しても光を受けることができる。哺乳類以外の脊椎動物はそこまで夜行性生活の制約を受けたことがなく、昼間の光ならば脳内の光受容体が十分検知できる。
哺乳類では夜行性生活の間にその機能が退化した可能性がある (たとえば3つあるメラトニン受容遺伝子のうち1つが失われている)。カモノハシ類の中には夜行性生活の制約を免れた系統があり、網膜の色受容体も3色型である。これらを調べることで脳の光受容機能の進化をよりよく理解できるかも知れないとの指摘がある
[Wyse and Hazlerigg (2009) Seasonal Biology: Avian Photoreception Goes Deep] (記載の図は哺乳類の脳内は暗黒で鳥類は薄明かりがあることを模式的に示したものになっている)。
光を受けるとオフになる動物のユニークな光センサーを発見
にも「ほ乳類の祖先が夜行性になって生きながらえた恐竜時代に、使わない多くのオプシン遺伝子を捨ててしまったためであると考えられています」とあり、最近はこちらの解釈が主流と考えられているのであろう。
Gerkema et al. (2013) The nocturnal bottleneck and the evolution of activity patterns in mammals
を参考にすれば、哺乳類の祖先が夜行性ボトルネックを体験した考えは Walls (1942) に始まるとのこと。現代の知見をもとにこのアイデアを検証した論文だが、概ね妥当と考えられるとのこと。
哺乳類で色受容体の一部がが失われているが、興味深いことに古いタイプのオプシンである parietopsin, parapinopsin が鳥類・哺乳類で共通に失われているが一部爬虫類には存在する。
ワニも哺乳類同様に夜行性ボトルネックを体験したと考えられるとのこと [Emerling (2017) Archelosaurian Color Vision, Parietal Eye Loss, and the Crocodylian Nocturnal Bottleneck]。
現生動物でワニ類は系統的には鳥類に一番近縁であるが、鳥類とワニ類の類似性はあまり強調しない方がよいかも知れない。夜行性ボトルネックを体験しているらしい点ではワニ類と哺乳類の共通性も考えられる。
カメとトカゲは別のより古い系統で、これらは夜行性ボトルネックを体験していないと考えられる。
parietopsin, parapinopsin は頭頂眼 (parietal eye, 第三の眼) に関係するオプシンで、爬虫類では体温に関係しているとのこと。恒温性を獲得するとともに必要性が薄れた仮説があるとのこと (この場合は鳥類・哺乳類で収斂/並行進化となる)。カメ類では地下生活時間が長いなどの理由で不必要になった可能性も考えられている
[ごくおまけ的に考えてこの系統樹に基づくと、哺乳綱、トカゲ・ヘビ綱、カメ綱、鳥綱、ワニ綱と分ければ単系統性および分岐年代を反映したものになる。さすがにあまり受け入れられないだろうが]。
光周性 (脳科学辞典 吉村 2013) に日本語の解説がある。「鳥類は脊椎動物の中で最も洗練された光周反応を示す」
とあると鳥ファンにとってもちょっと嬉しい。
鳥類の感覚と言った場合は通常思い浮かべる5感と磁気感応ぐらいしか書かれていないことが多いのでこういう解説があると助かる。
最近はマウスにも脳深部光応答分子とニューロンの存在が示されているそうである: 代謝:OPN5を介したマウスの光応答性中枢神経軸 (2020)。
時代的には古いが、脳と光の生理学について和田 (2004) Birder 18(2): 74-76 にこれらの事項が解明され始めたころの解説がある (もっと専門的な雑誌にはもちろん新しい記事があるだろうが Birder ならばお持ちの方も多いだろうと紹介した)。
この記事ではスズメ目の頭蓋に墨汁を入れると生殖腺ホルモンが変化する実験が紹介されているが出典はわからないとのこと。スズメの脳に墨汁を入れると朝起きてこなくなる実験の話をこの記事のだいぶ前に聞いて「ほんまかいな?」(ここだけ関西弁) と思ったことがある。
おそらく出典は同じでどこかに書いてあったものだろうが、和田氏でも見つけられなかったとすると何かの逸話に尾ひれが付いて広まったのかも知れない。この記事から 20 年も経っていないのにその間の分子生物学の進歩は驚くべきものである。
さてさて新しいレビューも出ていて、考察にあたって一種の盲点となることも記されている: Valdez (2025) Role of deep brain photoreceptors in regulation of daily and seasonal responses in birds
これまで脳深部光応答が調べられているのはキジ目、カモ目、ハト目、スズメ目のみで系統的にも遠い。これらの結果だけを見て鳥類全体に当てはまると考えるのはちょっと早計であろう。キジ目、カモ目というのは要するに家禽であって、家禽化によって遺伝子機能や発現状況が変わっている可能性もあり得る。ハト目 (これもドバトが対象) は年中繁殖できるので季節性などホルモンへの反応は他と違うかも知れないなどが取り上げられている。系統関係を考えた考察が必要。
鳥類の体内時計と遺伝子についてこちらも面白いレビューが出ている: Wellard et al. (2025) Avian circadian clock genes: ontogeny and role for adaptive programming in avian embryos
目レベルで違うのは不思議でないとしても、スズメ目の中でも概日リズムの制御が異なるとのこと。早成性か晩成性かで傾向の異なる点もある。
あまり考えたことがなかったが、発育中の卵の中で概日リズムが存在することは1日のうちの孵化時刻や孵化同期などにも役立つ。生態的にも適応的意義があるので概日リズムの分子機構や個体発生における発現時期と組み合わせて考察する必要があるだろうとのこと。
個体発生における概日リズムは哺乳類の方が遅く現れるとのこと (上述のような孵化タイミング調整などのためにリズムが早く発育するのが有利なのだろう)。哺乳類では胎児を母体と切り離して調べることが難しいが、卵生の動物では遺伝子やホルモンの働きを調べるのにむしろ都合がよいとのこと。
Perry et al. (2018) Molecular Adaptations for Sensing and Securing Prey and Insight into Amniote Genome Diversity from the Garter Snake Genome
これも面白い garter snake [#ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] (5) 毒鳥ピトフーイなどの対毒性 (BTX 耐性) 参照] はテロロドトキシン (TTX) 耐性で知られるが、これらヘビ類ではオプシン遺伝子を多数失った (網膜の構造も退化傾向にある)。どちらも 11 個のオプシン遺伝子を失ったとのこと。有胎盤類ではさらに3つのオプシン遺伝子を失っているとのこと。
ヘビ類進化の初期に夜行性生活を体験したと思われ、ヘビ類と哺乳類が収斂進化している。失われた遺伝子も似ているとのこと。夜行性ボトルネック症候群と呼んでもよいかも知れない。
嗅覚遺伝子 (ORs) のレパートリーはヘビ類の初期系統では特に増えていないがヘビ類の進化の過程で固有の ORs のレパートリーの拡大があったとのこと。
TTX 耐性にかかわる変異も共通のものがあり、この著者たちは共通祖先に先立つ段階で獲得した変異の可能性も考えている (独立に獲得した可能性もある)。NaV1.5, Y371C の変異は羊膜類の共通祖先段階に遡る可能性があるが、ニワトリ (鳥類では当時は多分他に調べられていなかった) や Anolis (アノールトカゲ属。イグアナ類) では失われている (TTX に感度がある)。
この範囲の生理学の分子生物学側面のみで見ると爬虫類も哺乳類も実は同じようなものに見えてくる。
羊膜類のうち鳥類などを含む一部の系統 (恐竜の系統と呼んでもちろんよいが遺伝子まではさすがにわからないのでどの系統まで類似していたかは不明) がむしろ飛び抜けた特徴を持ったのではないか。鳥類はずっと勝者の系統であったらしいことはバードウォッチャーとしてはちょっと自慢してもよいだろう。
*6: Potier et al. (2020) では visual Wulst の表現を使っている。これは解剖学用語でドイツ語の Wulst (ヴルスト 隆起。英語読みでウルスト) に由来し、鳥類の大脳の大きな隆起部分を指すが、古くは哺乳類の大脳基底核 (basal ganglia) に相当するもの (線条体 striatum と呼ばれていた) と考えられていた。
哺乳類の大脳基底核は本能的な行動調節などに関わっていることから鳥類の Wulst は巨大な本能装置で、鳥類の行動は本能や反射で成り立っていて哺乳類のような大脳皮質の支配を受けていないと長年考えられていた (このように考えられていた時代に神経生理学の専門家になぜ鳥が知的な行動を行えるのか聞いてみたことがあるが、わからないとの返事だった)。
その後研究が進み Wulst は哺乳類の大脳皮質に相当するものであることが明らかになってきた。
これは比較的最近 (20 世紀末ごろから 2000 年前後) の話で、The Avian Brain Nomenclature Consortium (2005) Avian brains and a new understanding of vertebrate brain evolution
に鳥類の脳の古い理解と新しい理解が示されている [これにかかわる会議は 2002 年に行われたとのこと]。
ここに示されている図は現在鳥の脳の解説をする時によく使われるものである。新しい理解では線条体は中心部の限られた領域で、大脳の外側を覆う多くの領域は哺乳類の大脳皮質に相当する。新しい名称ではこの部分を外套 pallium と呼び、acropallium (哺乳類の扁桃体 amygdala に相当する部位を一部含む)、巣外套 nidopallium、中外套 mesopallium、高外套 hyperpallium に分けられる。
最後の3者が外套連合野とされるもので、哺乳類の大脳皮質の連合野に相当する。
例えば伊澤 (2008) 鳥類における大型脳について が日本語文献として参考になる。
哺乳類の大脳皮質を外套と呼んでも構わず、実際に使われている (失外套症候群のような名称もある。この外套は大脳皮質を指している)。また鳥類の外套の部位を指して cortex (皮質。解剖学的には鳥類にはないが) と呼ぶこともある (例えば鳥類でも感覚野 sensory cortex のような使い方がなされる)。
大脳新皮質における神経新生プログラムの哺乳類と鳥類との進化的な保存性
も参考になる。原論文: Suzuki et al. (2012) The Temporal Sequence of the Mammalian Neocortical Neurogenetic Program Drives Mediolateral Pattern in the Chick Pallium。
Jarvis (2009) Evolution of the Pallium in Birds and Reptiles
も大脳の発達について参考になる。哺乳類の大脳皮質の特徴とされる6層の構造に対応する神経回路も示されている。
鳥類の視覚野 (皮質) (avian visual cortex) という名称すら使われている: 例 Pusch et al. (2022) Visual categories and concepts in the avian brain。現段階で鳥類の脳で視覚情報処理がどのようになされているか次第に明らかになりつつあると言ってよいのだろう。
この論文では鳥類の "前頭前野" (prefrontal area) という用語も使われている。脳科学辞典によれば 前頭前野 「前頭前野はヒトをヒトたらしめ、思考や創造性を担う脳の最高中枢であると考えられている」などと記されている。それに相当する部位が鳥類にもあって意思決定や反応抑制などの行動に関わっているようである。
Pusch et al. (2022) のこの論文は専門用語は使わざるを得ないが難しい表現も少なく鳥の脳についてさらに知りたい方ならば十分読めると思う。既刊本などの説明に物足りない方は読んでみられるとよい。
このような経緯があるため、説明には古い名前である Wulst を使わず、哺乳類の視覚野に対応する部位と説明的に記した。
wikipedia 英語版に大変面白い比較が出ている List of animals by number of neurons。
後半の List of animal species by forebrain (cerebrum or pallium) neuron number が大脳皮質 (外套) に相当する部分のニューロンの数であるが、クジラやゾウのような大型動物でニューロン数が多いのは当然としても、鳥類の大脳皮質に相当するニューロン数の多さに驚かされる。大型のオウム・インコは霊長類なみである。
大型フクロウ類もニューロン数が多いが、これは聴覚処理が大脳に依存する部分が大きいためかも知れない。視覚処理はかなりの部分が中脳で行われて中脳がよく発達しているが、この部分はこの表のニューロン数に含まれない
[pallium で視覚情報処理は nidopallium 中の entopallium が色情報を扱うなどが知られている: cf. Niu et al. (2023) Gamma-band-based dynamic functional connectivity in pigeon entopallium during sample presentation in a delayed color matching task]。
しかしフクロウ類は脳のサイズでみても大きいらしい (#ヒガシメンフクロウの備考 [フクロウ類の脳のサイズ] 参照)。
カケスのニューロン数が小型犬なみというのは賢さを考えると納得できる気がする。キクイタダキでも齧歯類より数が多い。じっくり見て楽しんでいただければと思う。
脳の大きさや重量は目安になるが、大事なのはニューロン数の方であり、鳥類は一見小型の脳に見えても細胞が小さい [飛翔への適応のためにゲノムから余分な部分を除いてゲノムサイズを小さくしているとの考えもある。最新の研究で別の可能性が示唆されている。#ツリスガラ備考の [スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン] を参照]
ため集積度が高いことがわかる (ニューロン数だけでなくニューロンをつなぐシナプスの数も多いそうである)。
同じ体積 (重量) の脳ならば哺乳類より鳥類の方が賢いと言ってよいのではないだろうか。しかも系統的に後で出現したグループほどニューロン数が多く、鳥類の進化に伴って脳機能も強化されてきたことがわかる。
研究者は本格的な陸鳥 (#ミサゴの備考参照) の出現に伴って神経系の進化が一段と進んだ可能性に興味を持っているようである。
同じページの日本語版では (現時点で)「哺乳類のみが大脳皮質を持っているので、このリストには哺乳類しかない」とあって近年 (といっても 20 年も経っているのに) の学問の進展に追いついておらず、世間的にも鳥の脳の認知度はいまだに低いのかも知れない (単に英語の情報が一般にあまり届いていないだけかも知れないが)。
始祖鳥と現代の鳥の中間的な位置のよく保存された化石が見つかり、脳 (と言っても cranial and endocranial morphology) の発達を調べることができた: Chiappe et al. (2024) Cretaceous bird from Brazil informs the evolution of the avian skull and brain (2024.11.13 オープンアクセス)
約 8000 万年前のものとされ場所は現在ではブラジル。
現代の鳥の (胚の) 発生段階で後の時期に成長する脳の構造である、大脳や小脳が発達しておらず現代の鳥の発生の早い段階に相当する (これは脳以外でも知られる現象)。小脳の機能は認知や動作の制御など広範に渡っているので、この段階ではまだ認知や複雑な動作は十分発達しておらず始祖鳥と現代の鳥の中間段階であったのだろう。
Bird brain from the age of dinosaurs reveals roots of avian intelligence (英文一般向け解説)。研究者たちは鳥の知能の起源を考える上で重要な発見とみなしている。
脳に関係するのでここに含めておくが、ヒトの大きな脳にドーパミンニューロンが大きな役割を果たしている可能性がある研究が preprint 段階で公開され、すでに Nature news となっている (How human brains got so big: our cells learned to handle the stress that comes with size (2024.11.15)。
論文は Nolbrant et al. (2024) Interspecies Organoids Reveal Human-Specific Molecular Features of Dopaminergic Neuron Development and Vulnerability (preprint)。
霊長類に比べてヒトの脳のドーパミンニューロンの数は倍程度だが、シナプス数が多くしかも前頭前野でその傾向が顕著とのこと。鳥の場合はどうなのかなど当然比較研究が行われても不思議でない。
調べてみたら案外鳥の方がシナプス数が多かったりして。
関連する話で Herculano-Houzel (2023) Theropod dinosaurs had primate-like numbers of telencephalic neurons 大型恐竜は霊長類に匹敵するニューロン数を持っていたとの推定で従来推定以上に強力な捕食者の可能性があったのでは。
一方で Reiner (2023) Could Theropod Dinosaurs Have Evolved to a Human Level of Intelligence? 大脳皮質構造でない鳥類型の脳では神経連絡の経路が長くなってある程度以上高度な知能を持てないではの議論。それぞれ主張があり、後者はサイズ拡大に伴う制約で上記ヒトの大きな脳を可能にするメカニズムとも関係がある。関連論文やコメントもいくつもあってまだまだ議論中のテーマ。
主に2系統に分かれるようで、恐竜が現在の鳥に似た脳を持っていたか、あるいはトカゲのような脳だったか。
Balanof (2024) Dinosaur palaeoneurology: an evolving science がレビューとなっているので紹介しておく。
Hulke は鳥と恐竜がつながっていると考えた Huxley に Mantellisaurus の頭蓋骨を提供したが他の仕事などが忙しくて十分に扱われなかった。1880 年代になって古生物学者の Marsh が Morosaurus や Stegosaurus の脳が "鳥よりもトカゲ的" と記述したものが1世紀にわたって標準的とされてきたとのこと。
確かに昔の図鑑にはどこにでもそう書いてあったような気がする。最近になって恐竜の脳が話題になるのはある意味復権とも言えるのかも知れない。これは哺乳類至上主義の見直しでもある一方、現生鳥類をテーマとする者にとっては複雑な位置関係とも言える。現生の高度な鳥の出現にはかなりの時間がかかっているのでそれ以前の段階でそれほど簡単に脳機能が進化するものなのだろうか?
この Balanof (2024) の研究は現生鳥類から恐竜脳の機能推定を考えているが、体重に占める脳重量で評価した場合は鳥が進化して小型化した結果脳が相対的に進化したように見える見かけの効果もあるのでこの指標は注意して取り扱う必要があるとのこと。
現生鳥類系統の知性を見ているとやはり何段階かの進化ステップがありそうでさてどうなのでしょう。
Hecker et al. (2024) Enhancer-driven cell type comparison reveals similarities between the mammalian and bird pallium (preprint)
脳の遺伝子発現の enhancer code に注目した解析で哺乳類新皮質と鳥類の外套は細胞の分化が際立っており (深層学習による分析を利用)、哺乳類新皮質の層と相同部位が示された。
羊膜類の祖先に存在していた基本的な遺伝子制御機構があって鳥類、哺乳類がそれぞれ進化させた描像が考えられる。
2025 年の Science に2本の論文が掲載された。Rueda-Alana et al. (2025) Evolutionary convergence of sensory circuits in the pallium of amniotes;
Zaremba et al. (2025) Developmental origins and evolution of pallial cell types and structures in birds
羊膜類で共通機構があるが、鳥類、爬虫類、哺乳類でそれぞれ独立に脳を発達させた。鳥類と哺乳類は異なる遺伝子を用いて同等の脳の機能を達成した。鳥類では大部分の inhibitory neurons は他の脊椎動物同様に存在するが、excitatory neurons は哺乳類と異なる方法で独自のものを進化させていた。
一般向け解説。
Chen et al. (2025) Genomic evolution reshapes cell-type diversification in the amniote brain (preprint 版) 鳥類では終脳の excitatory neurons で SLC17A6 哺乳類では SLC17A7 をもっぱら発現しているが、これらの2遺伝子は羊膜類の初期に遺伝子重複で生まれ、鳥類は SLC17A7 の機能を失いつつあることに起因する可能性がある。
鳥類の方が皮質下や小脳で哺乳類でグルタミン酸濃度が高く、高いグルタミン酸濃度と親和性の高い SLC17A6 が向いていたのではとの議論があるとのこと。爬虫類では両者の遺伝子が発現するとのこと。
小脳のプルキンエ細胞で鳥類特有の SVIL+ タイプの細胞が同定され、lysine-specific demethylase 11 (LSD1)/KDM1A 経路が概日リズムや小脳の果たす運動機能 (飛翔への適応など) の選択圧下で進化したことが考えられるとのこと。
SLC2A ファミリーでの同様の例については #ヤマセミ備考の SLC2A ファミリーの遺伝子と代謝 を参照。遺伝子の番号はどちらが祖先型などの意味があるわけではない。
これまで知能の研究の対象外だった古い系統 (Palaeognathae 古口蓋類/古顎類) のエミューに問題解決能力があることがわかった: Clark et al. (2025) Palaeognath birds innovate to solve a novel foraging problem。
なお Palaeognathae でも同種の視線を追う行動は知られていて、この点は霊長類に似たところがあるとのこと。この系統の鳥類の脳が相対的に小さいことは確かで、問題解決能力に必要な最小限の脳の大きさを検討する研究ともなっているが、これまで想像されていたよりも早く知能が進化していたことも示唆するとのこと。
Yang and Long (2025) Convergent vocal representations in parrot and human forebrain motor networks 音声を真似る鳥とヒトの脳にはやはり共通の基盤があった。
上記の acropallium のうち anterior arcopallium (AAC) が脳幹の音声を制御するニューロンに直接投射しているが、AAC に音声機能に対応するマップがあり、音声の特性を制御している。これまでは音声学習を行うスズメ目の研究が行われてきたがより複雑な模倣を行うセキセイインコを調べたもの。ヒトの脳の言語野との共通性がより明らかになり、オウムとヒトの脳の回路の収斂であると表現している。
Lee et al. (2025) Amino acid patterns in independent lineages of vocal learning and other birds give insights into convergent evolution 音声学習を行う鳥のアミノ酸変異に収斂進化の証拠はあるか。
Peglar and Fryxell (2025) Convergent Evolution of Two Dopamine Receptor Genes: Repeated Evolution of Exon 6 Skipping in Drd2, and Repeated Deletion of Exon 6 in Drd3
それぞれの系統の中で系統的に原始的な魚、両生類、爬虫類 (カメ)、鳥 (ダチョウ)、哺乳類 (単孔類と有袋類) の脳のドーパミン受容体 (Drd2) に共通の欠如部位が見られたとのこと。それぞれの系統の中でより派生的な (世の中一般的な表現では進化段階の高い) 種には見られなかった。
トカゲ・カメはやはり脳の能力が低かった: Santaca et al. (2025) Lizards and tortoises show evidence of low inhibitory control 自動的に起きる反応を状況によって抑制する脳の機能が弱かった。脳が小さいなどの限界を示す従来仮説を支持する結果となった。
*7: この文章は主に猛禽類の視力の説明のために独立して書いていたもので用語など若干の違いがある部分もある。
杉田氏の記事にはカラスとアヒルの網膜の顕微鏡写真が出ているが、Mitkus et al. (2017)
Specialized photoreceptor composition in the raptor fovea (#ハチクマの備考参照) に出ているタカ・ハヤブサ類の中心窩の電子顕微鏡写真 (電子顕微鏡写真ゆえモノクロなので分かりにくいかも知れないが色が付けられれば各色の油滴が見えるはず) と比べてみていただきたい。
杉田氏の記事で多少気になる部分を挙げておくと、鳥類の多くで中心窩を2つ持つ (p. 16) はおそらく言い過ぎで捕食性の鳥類は中心窩を2つ持つものが多いぐらいが適切であろう。
神経節細胞密度から視力を推定する部分 (pp. 19-20) で密度を分解能に換算する場合は平方根をとる必要がある。平方根をとると 10 倍ではなく約3倍になる (記述では回折限界も考慮されていないようである)。また細胞密度だけでなく焦点距離も考える必要があり、焦点距離も考慮すればさらに下がるはずである。
獲物を追うフクロウ類の立体視について (p. 9) はまだ議論がある。
杉田氏の記事はカラスなどをベース、本記事は猛禽類をベースに記述しているので力点などに多少のニュアンスの違いがあるかも知れない。
*8: 深い中心窩 (central fovea) の機能の新 (?) 解釈
[鳥類の眼球と脳サイズのデータ] の項目で眼球の自重変形による結像性能の低下があるのか考察した派生物として、深い中心窩 (central fovea) がタカ・ハヤブサ類でなぜそれほど深いのか理由が見えてくるような気がした (2025.1 追記)。網膜の神経組織と硝子体の間に屈折率の違いがあれば光路差が生じて焦点深度が深い (あるいは多焦点とも言える) のである。屈折による像の拡大効果よりも有効な気がする。
Potier et al. (2020) Inter-individual differences in foveal shape in a scavenging raptor, the black kite Milvus migrans
の網膜断面図の写真 (Fig. 5) によれば深さは 200 μm ぐらいと考えてよさそう。屈折率の違いが 0.1 あれば光路差が 20 μm となり、可視光の波長の数十倍となる。この値で十分意味がありそうに思える。
前述の Snyder and Miller (1978) "Telephoto lens system of falconiform eyes" では硝子体と網膜内の屈折率をそれぞれ 1.336, 1.4-1.55 程度と考えていた。0.1 程度の違いはあってもよさそうである。
この考えが正しければ物体が central fovea に入りさえすればどこかの場所で焦点が合うことになる。
さらによく見たければ焦点を合わせたまま解像度の高いところに視線を移動すればよい。
昼行性猛禽類が回折限界まで焦点を合わせることができることは [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] の Shlaer (1972) の実験で示されている。いわば動体追従 AF のようなものである。
特に見たくないと思えば central fovea から外すだけでよい。この実験で被検者のワシが協力してくれなくなったのは単に視線をそらすようになったためと解釈できる。
平坦な網膜であれば単一焦点なので映像を見てピントの山を探す必要がある。コンパクトデジタルカメラと同様。この場合は光の強度のみを測るので焦点合わせに位相差情報が利用できない。ピントの山を探す方法の場合の反応には中枢神経での画像処理に時間がかかるので、焦点深度を深くする (一種の多焦点光学系にする) ために central fovea の凹みを利用する方向に進化が進んだ。この説明でどうだろうか。過去にこのような説明を見た覚えがないので誰か考えた人はあるだろうか。
[鳥の視力はなぜそれほどよいのか]
上記の一連の部分は主に光学特性からの考察であったが、網膜の光受容体の分布が一様分布でないことが解像度や色の分解能力を高めている可能性の考察がある:
Jiao et al. (2014) Avian photoreceptor patterns represent a disordered hyperuniform solution to a multiscale packing problem。
hyperuniformity (超一様性) の概念は Salvatore Torquato and Frank Stillinger が 2003 年に提唱したもので、観測的宇宙論では独立に super-homogeneity の名称が与えられていた (wikipedia 英語版)。
日本語では訳せば super- も hyper- もいずれも「超」となって区別が付かないが、hyper- のほうがより上位。ある程度流行も反映しているように思え、supernova (超新星) の概念は 1931 年に最初に用いられたものであったが、さらに規模の大きなものが見つかって 1998 年に hypernova (極超新星) と呼ばれるようになった。2003 年ごろはちょうど流行時期にあたる。
hyper- の付く学名が日本の鳥もありそうな気がするが、ジュウイチやチャバラアカゲラの種小名は hyper- でなく hype- で分割され意味が違う。シロカモメの種小名に使われる hyperboreus は北の端の意味となり語義的には同じ。
Torquato によればニワトリ網膜では5種類の cones (錐体) の配置を最適化することで色彩判別などの最適解法を見出しているらしい。
Hyperuniformity found in birds, math and physics (Princeton University 2016) から文言を紹介すると Balancing these constraints, the system "settles for disordered hyperuniformity," Torquato said.
Hyperuniformity gives birds the best of both worlds: Five cone types, arranged in near-uniform mosaics, provide phenomenal color resolution. But it's a "hidden order that you really can't detect with your eye," he said. (人が目で見ても気づかない秩序がある)
格子状にピクセルを配置する以上に解像度を上げることができる可能性がある。
なぜ5種類となったのかなどこれらの最適化プロセスを考慮することで説明できるのかも知れない。また比較生物学でこの構造がどのように進化したのか知ることもできるだろう。
構造の問題なので鳥の群れ構造や構造色の機構 (微細構造のフーリエ変換で決まる) にもきっと関連があるのだろう。
[鳥類の眼球と脳サイズのデータ]
Liu et al. (2023) Evolution of Avian Eye Size Is Associated with Habitat Openness, Food Type and Brain Size
の論文から Supplementary Materials をダウンロードすれば一覧の pdf file として鳥類の眼球と脳サイズのデータが手に入る。
脳サイズについては Sayol et al. (2017) Environmental variation and the evolution of large brains in birds (#ハチクマの備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] 参照) にも情報があり、Bird Tree project を用いたこの形式の系統樹の見かたもこちらに説明がある。
Sayol et al. (2017) と Liu et al. (2023) を比べると、Liu et al. (2023) 図の目レベルの少なくとも最後2つの名前が間違っているように思えるなど変なところがいくつかある。
ただし眼球と脳サイズのデータを利用するには多分差し支えはない。
分類名も少し古い (Bird Tree project に合わせた) 学名が使われている可能性がありその後分離された種などは少し注意を要するかも知れない。
川口 (2024) Birder 38(4): 52-53 で眼球の最大サイズはダチョウで 5.2 cm、ゾウで 5 cm で陸上生物では重力による変形でこれが最大サイズかとの議論を述べているので調べてみた。
Lautenschlager et al. (2024) Orbit size and estimated eye size in dinosaurs and other archosaurs and their implications for the evolution of visual capabilities
で恐竜化石を調べているがあまり頭打ち関係が見えないのでこの程度のサイズは上限になっていないのでは (ただし化石では眼球サイズを直接測ることはできないので眼窩サイズを用いている)? 視力を増すためならばワシの眼球で十分意義があると思えるので、それより大きなものは視力よりはむしろ光を集める能力のためだろう (水中生活をする動物で大きい理由にもなる)。
鳥類では網膜に血管がないため網膜細胞に栄養を届ける、あるいはガス交換には硝子体での浸透が必要で生理的な大きさの制約があるとすればむしろこちらのように思えるがいかがだろうか。
ダチョウの眼の強膜骨 (Scleral Ring and Scleral Ossicles) の構造を調べた最近の論文: Masoudifard et al. (2025) Anatomical Study of the Scleral Ring and Scleral Ossicles of the Ostrich (Struthio camelus) With Gross Anatomical Methods and Diagnostic Imaging Techniques。
鳥の強膜骨の比較や発生由来や機構の論文も紹介されているので参考までに。機能は議論があるが主に2つで、眼球を機械的に支えて変形や外傷を防ぐことと、毛様体筋肉の付着部位となって調節 (visual accommodation) に働いている。爬虫類・鳥類の発生と魚では機構が異なる。系統によって多少違いがあって Type A と B に分けられ、ossicles には番号も付いている。
近年では micro CT が活躍している。最大の眼球を持つダチョウと、ヒトより大きな眼球を持つフクロウ類とはタイプが異なるとのこと。
なおダチョウの眼は大きいが神経細胞の分布から視力が悪いことも知られている。視神経も細い。
Boire et al. (2001)
Quantitative Analysis of the Retinal Ganglion Cell Layer in the Ostrich,
Struthio camelus
視力は我々にも遠く及ばず、ワシの最大視力に比べると1桁近く悪い。
地平線方向の解像度のみ相対的によいようで同種や外敵を見つけるのに役立っているのだろう。上空方向の視力があまりないのは上から襲われる心配がないためかも?
ただし網膜表面での輝度は夜行性動物に近い数字になるとのこと。ダチョウの大きな眼は視力を増すためのものではないことがわかる。
また大きな目で自重変形がたとえあったとしても、ダチョウの目は地平線方向のみ解像度がよいので、重力変形の影響を受けにくい円周方向ともなるだろう。視野全体を鮮明に見る必要はない。
この話題を少し深掘りしてみることにした。眼窩に収まっている眼球が重力でそれほど変形するものか自分にはわからないが (構造計算のできる方ならば評価可能と思う)、眼球が変形しても別に問題ないのではと思えてきた。つまりレンズなどの結像部分が変形しなければさほど問題が発生しないように思える。
水晶体は房水の中にあるので重力による変形はそのまま働かないのでは? 水中生活でなければ角膜は空気と接しているのでこちらは変形があるだろうがひとみ径より少し大きい程度の範囲で形が保たれていれば十分なので全体の形が保たれる必要はない。眼の骨性リング (強膜骨) も形を保つのに役立つだろう。
多少歪んだとしても水晶体や角膜 (鳥の場合) は調節可能なので補償光学を内蔵しているとも言える。
川口氏が望遠鏡のレンズのたとえを出されているので誤解のないよう補足しておくと、現代の大型望遠鏡ではレンズを使う屈折望遠鏡は事実上ない。川口氏もご存じだろうと思うが反射鏡を使う。大きなレンズを使わない理由は屈折による色収差が克服し難い欠点となる上、均一な大型レンズを作ることも難しく、レンズ内の光の吸収も問題になる。理科年表に世界の大型望遠鏡のランクが出ているので建設年を見ていただけば傾向がわかる。
みかけは立派だが大型の屈折望遠鏡は古い時代の遺物と言って差し支えない。屈折望遠鏡はスポッティングスコープ程度の小型のものを除いて少なくとも天体望遠鏡では欠点の方が多いのである。スポッティングスコープクラスでも ED ガラスやフローライトを用いるなど色収差克服に苦労しているのはご存じの通り。
自重変形を補正する機能はかつて世界最大だったパロマ山の 5 m 望遠鏡でも必要ないぐらいだった。最近使われているのは鏡を薄くする、あるいは分割鏡にして制御で単一焦点を作る目的が大きい。
[コンラート・ローレンツのワシ類の記述]
コンラート・ローレンツ Konrad Lorenz の「ソロモンの指環 動物行動学入門」[日高敏隆 (1930-2009) ほか訳 早川書房 1963 が初出で、自分は 単行新版 1970 の版を持っている。原書 "Er redete mit dem Vieh, den Voegeln und den Fischen" (1949、ただしこの年には出版されなかったらしい) とほぼ意味不明の題で、英訳 King Solomon's Ring (1952) の表現が定着している模様]
は世界でもおそらく最も読まれた本の一つではないかと想像するが、この中でワシがボロクソに書かれている。
日高訳 (原著からの訳) で "猛禽類はすべておよそバカな動物である。とくにわれわれの山々にすみ、われわれの詩人にうたわれてきた「ワシのなかのワシ」であるヨーロッパイヌワシときたら、ワシのうちでもまた指折りのバカであり、そこらのニワトリにもはるかにおとるのだ" (1970年版で pp. 169-170)
とまで書かれていると原文はいったい何が書いてあるのか確かめざるを得ない。
alle Raubvoegel sind ... sehr dumme Tiere, und gerade der
Steinadler, >>der Adler<< unserer Berge und unserer
Dichter, ist eines der duemmsten unter ihnen, viel duemmer
als jedes Hendel!
と書かれていた。日高訳はずいぶん自由な訳になっていて意味は概ねこのままでよさそうだが、"ワシのうちでもまた指折りのバカ" はひっかかるところで、unter ihnen (英語ならば among them ぐらいか) は複数形になっているので単数形のワシを受けているのではなく、複数形の猛禽類の方ではないかと思う。"猛禽類のうちでもまた指折りのバカ" となるだろうか。
Steinadler にヨーロッパイヌワシの訳語が与えられているのも多少興味あるところで、イヌワシと書くと誤解を招くとか、あるいは当時の本でヨーロッパイヌワシの名称を見かけることもあったので多少日本のものと区別して使われていたのかも知れない。
実際に性質を調べたのは巡回野獣商から買った (日高訳。実際には頼んで手に入れたのでは?) Kaiseradler カタシロワシでイヌワシではない。当時よく使われていたカタジロワシと訳されている。
"たとえ断食させられていたときでも、実験用のウサギにさえ指一本ふれようとしなかった" は原文 mein Adler, auch wenn ihn hungerte, dem Versuchskaninchen nichts zuleide tat
日高訳はかなり意訳になっていて、"腹が減っていても実験用のウサギに危害を加えることはなかった" ぐらいだろうか。hungern は自動詞なのでわざわざ断食させているわけではないと思う。
"飛ぶのがあまり好きでなかった" は原文 Er zeigte sich auch wenig fluglustig 訳文で意味はよいと思うが、あまり活発に飛ばなかったぐらいか。カタシロワシは大きいし庭からあまり飛ぼうとしなくても不思議ではない。ここで比較に挙げられている中に (空を喜んで飛ぶ) ヨーロッパ? ノスリ (Bussard) が含まれているので、先述の "猛禽類のうちでも" の意味が通じる感じがする。
"そしてこのワシはちがっていた" (訳文) 原文 Anders dieser Adler となる。
適切な上昇気流がある時のみ飛び立つが、"しかもそういうときでさえ、高いところで輪を描くようなことはけっしてなかった" (訳文) 原文 und selbst dann kreiste er niemals wirklich hoch hinauf とのこと。飼育下で飛ぶ訓練がほとんどなされていなかったためでは?
"下りてこようとすると、こんどはいつも帰り路がわからなくなる" (訳文) 原文 Wollte er
wieder herunter, misslang es ihm regelmaessig, seine Heimstaette
wiederzufinden. 意味は訳文通りで良さそう。原文やヨーロッパ語の同様の表現 (ロシア語なら v polyadke が "うまく行っている"。語そのものもほぼ regelmaessig の意味) を参考にすると日本語では "うまくいかない" ぐらいの感じか。
なお迎えに行く時は自転車を恐れるそうで徒歩で行く必要があったとのこと。これも思い当たるふしがあって、琵琶湖で越冬のオオワシが驚くのはだいたいトラックの物音で、動物園のハチクマはベビーカーの音をずいぶん嫌う。音が近づいてくると遠くからでも後ろを向いて逃げられる姿勢をとる。
動物園はもちろん幼児歓迎の場なのだが、そのままベビーカーで近づき、子供が手を出したりすると逃げてしまって「愛想がない」結果になりがちである。見ていると奥に引っ込んでしまうのはこのようなケースがかなり多い。
鷹匠が人混みの音にどのように慣れさせるかなどの話も含め、猛禽類の嫌がる音の種類がありそうなので参考になれば幸いである。生息への配慮なども単に騒音を dB で評価する他に音の種類が重要な気がする。
Lorenz のカタシロワシの話に戻ると、このような大型のワシがつながれた状態で何年も屋内飼育されていただけのものを買っただけならばいかにもありそうな気がする。野生のものの行動と比較してもバカかどうか判断できそうもない。Lorenz にしては考察 (観察) 不足の気がする。
もっとも本の中で Brehm が触れられていて、Alfred Brehm 「ブレーム動物事典」(#ハチクマの備考 [飼育下の行動: ドイツのヨーロッパハチクマ] 参照) を読んでいて無意識のバイアスになっていただろうことは容易に想像が付く。当時のドイツ語圏の飼育者には「ワシはバカ」が常識になっていたのだろう。
これらの記述が (飼育下では)「ワシはバカ」の印象を世界の人に植え付けた可能性がありそうに思えた。
同訳書 p. 115 にイヌのすることは "学習" されたもので "洞察" をふくんでいるが、鳥がなすこと語ることは、すべて生まれながらの遺伝的なものである。
原文 Ausserdem ist das, was der Hund tut, erlernt und einsichtig, was die Voegel tun und sagen, aber ist restlos
angeboren und vererbt. は原文通り。
当面の目的に応じてこのように手段を変えるという柔軟性は、鳥類の表現運動や信号音にはまったくみられないものである (p. 116) 原文 Eine derartige, dem augenblicklich verfolgten Zweck
angepasste Veraenderlichkeit fehlt den Ausdrucksbewegungen und Signallauten der Voegel vollstaendig. "当面の" は多分 augenblicklich 瞬時に、即座に の誤訳だろう。"即座に続く目的に応じて表現運動や信号音を変える" のような意味になりそう。Lorenz はコクマルガラスでもイヌのように柔軟に行動を変えることはできないことを示していた。
訳文 (またはそれをさらに引用した記述) を引用してゆくとやはり何か間違ったニュアンスが入り込みそうで、面倒でも可能な範囲で原文を参照した方がよさそう。最初のワシの記述が気になって原文を見ただけなので、ごく一部気になった記述をチェックしたにとどまることを断っておく。邦訳の新しい版ではあるいは表現が違っているものがあるかも知れない。
翻訳を出された当時の「新鋭」の日高氏は 33 歳ぐらいで、1980 年代の雑誌アニマでは多くの生物関係者が推薦図書として挙げていたし、おそらくどこの図書館にも置いてあると思う。
あえて原書から翻訳された意気込みなどや、当時の世代が英語以外の外国語を学ぶことの意義を当たり前のように語っていた雰囲気も伝わってくる。日高氏は鳥にはそこまで馴染みがなかっだのだろうか (鳥がなすことはすべて遺伝的、などに疑いを持たれなったのだろうか) と上記翻訳部分を見て感じた。
一方、「ハチクイは、旦那が実家に入り浸り」(安西英明・木挽裕美訳 翔泳社 1998; 原著 "The Science times book of birds" Nicholas Wade) はニューヨーク・タイムズの科学記事から抜粋されたものであるが、この中では「モモアカノスリの見事な狩りの連携プレー」(pp. 147-153) と題して当時発見されたばかりの共同ハンティングが紹介されている (#トビの備考参照)。
この中 (原記事は 1993年1月) で David Ellis はイヌワシの能力を高く讃えている。マニトバでイヌワシの幼鳥がキツネに対して大きな声を出して攻撃して注意を向けさせる間に成鳥が音もなく急降下、4回でキツネを仕留めたという。
もっともキツネも同様の方法で仕掛けてイヌワシの餌を横取りすることもあり、どちらが賢いとも一概に言えないらしい。Ellis によればイヌワシは過去の失敗から学んで次に役立てているようで、生まれつきというよりは頭を使っているらしいとのこと。
参考: Ellis et al. (1993)
Social Foraging Classes in Raptorial Birds: Highly developed cooperative hunting may be important for many raptors (雑誌サイト)。
擬態によるものから社会的なハンティングまでいくつかの段階を考察しており、文献記録も集めてある。イヌワシはつがいで共同ハンティングを行うこともあるが、冬場に複数個体が同じ獲物を狙う場合は協調した行動ではないとのこと。開けた場所でウサギを狩る場合は単独での狩りで十分だがよく茂った場所では共同で狩るなど使い分けているように見えるとのこと。
近年の発見も受けたものだが、Lorenz の考えとは正反対となっている。
イヌワシが水平の紐を引いて食物を得る実験については#ハチクマ備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] で他種事例も含めて紹介した (Gifts of an Eagle - Testing Lady's Intelligence)。
[ネアンデルタール人時代から人はイヌワシの外敵だった?]
Gomez-Olivencia et al. (2018) First data of Neandertal bird and carnivore exploitation in the Cantabrian Region (Axlor; Barandiaran excavations; Dima, Biscay, Northern Iberian Peninsula)
遺物に残った骨に生きている時に人が傷つけた痕が見つかった。肉を剥いだと思われる痕もあった。肉食動物を食べることは生態的な競争相手を排除することにもつながったと考えられる。
Finlayson et al. (2019) Neanderthals and the cult of the Sun Bird
この著者の考察では少なくとも 13 万年前ネアンデルタール人時代からワシを捕えて羽毛や爪を利用していた。動物の死体のところで待ち伏せして捕らえていたのではないか。イヌワシは最も多く捕えられていたワシ。
当時の人類とイヌワシは類似した生息環境に住んでいた。最も大型の種を選択的に捕えていたと考えられるとのこと。
[イヌワシに憧れるインディアンの話]
この題で松本正氏が「野鳥」2000年5月号 (No. 631) p. 31 にエッセイを寄稿されている。
アメリカ先住民族の Lakota 族は、イヌワシを「ワンブリ・グレンカ」と呼び、プレーリードッグを襲う際のイヌワシの観察、判断、覚悟を決める行動に「あこがれ」を持って「生き方」の手本としたとのこと。
調べてみると音訳でしか表示できないが、Wangbli そのものがイヌワシを指すようで、Wangbli Gleska がまだらのワシ (Spotted Golden Eagle) の意味となる。
松本氏の紹介されたエピソードによれば elk + eagle の絵をプレゼントされた Lakota の人が、これは違う。アメリカ政府のシンボルで、「白人はなんでも白黒をハッキリさせたがる。それ故に "正義" や "真実" の為にと言って自分たちと違うものを排除したり...殺したりまでもする。我々のシンボルはまだらの鷲だ (中略) だからこそ我々はお互いに違っていても、物事に矛盾 (まだら) があっても関わりあい、折り合いをつけて生きていくのだ」と言葉が引用されている。
綴りは歌詞のサイトをご覧いただきたい (イヌワシの歌)。
該当の「野鳥」誌をお持ちの方はご覧いただきたい。
当時の世界史的時代背景を考えて読んでいただくとわかりやすいだろう。
Lakota Spirit Animals: Eagle のような Lakota の精神を紹介するページにハクトウワシが出ていては「違う!」と言われそう。
[White Eagle とは何者か?]
"White Eagle" of Charleton 1668, and Latham 1781, "Aquila alba cygnea" of Klein 1750, and "Aigle blanc. Aquila alba" of Brissson 1760 のようなさまざまな記述がヨーロッパに残っている (The Key to Scientific Names の albus の項目)。
Whether the list white eagles of Europe and America (Karl Shuker 2014, 2017) の検討があったので紹介しておく。
学名まで与えられていて Aquila alba や Falco cygneus など。白いワシまたは白鳥のようなタカ。
アメリカでも同様の記述があって Louisiana white eagle Aquila candidus 別名 conciliating eagle "調停するワシ"。Antoine-Simon le Page du Pratz の "Histoire de la Louisiane" (1758) の記述によれば 1718-1734 年ルイジアナに住み、先住民 (Natchez) の言葉を習ったとのこと。
この鳥の王はアルプスの鳥の王より小型でより美しく全身はほとんど白いが翼の先端のみ黒いとのこと。羽毛は先住民の間で高値で取り引きされ平和の象徴として用いられたとのこと。原文が
Histoire de la Louisiane: contenant la decouverte de ce vaste pays; sa description geographique; un voyage dans les terres; l'histoire naturelle, les moeurs, coutumes & religion des naturels, avec leurs origines; deux voyages dans le nord du nouveau Mexique, dont un jusqu'a la mer du Sud
(Tome II Chapter IX, p. 109) にあった。英訳を読むと訳に用いられた単語につられがちだが原文を見るとイヌワシとは断定していない。ただし比較対象などからイヌワシらしく見える。ワシ以外にも生物の博物学的記述が記されているので比較してみると面白いかも知れない。
平和の calumet (カルメット。儀式の道具。植民地時代に「聖なるパイプ」を指して呼ばれた名称。wikipedia 日本語版に解説あり) での Aigle blanc (白いワシ) の羽毛の利用については 同上 (Tome I Chapter VII, p. 105) に記述がある。
Le Calumet de Paix とある。paix = 第一語義は平和。他に講和、和解など。
[イヌワシに憧れるインディアンの話] ともつながるように思える。
conciliating eagle に基づいて Falco conciliator の学名も与えられたとのこと。平和をもたらすワシとはなかなかよい。
これらの白いワシはいったい何者だったのか? Karl Shuker のこのページにはコロラドで撮影されたイヌワシの白変型 (leucistic) が紹介されている。白いワシはまれであったとも記述されており、イヌワシの色彩変異だったのか?
この記事へのコメントで主に南米に生息するシロノスリ Pseudastur albicollis White Hawk の亜種 ghiesbreghti はメキシコや中米に分布して記述に一致する候補となるのでは。かつてアメリカ南部に分布していても不思議でないが、ワシと呼ぶにはちょっと小さすぎるかも、などの議論が出ている。
アメリカではあるいは候補になるかも知れないが、ヨーロッパでの記録はより謎が深そう。
2020 年に white eagle を撮影したとのコメントが出ているが写真は紹介されていないので不明。
他のタカ類では white morph を持つものがあるが、もしかするとイヌワシにも white morph があったのだろうか。目立つので狩猟の対象になったりして (おそらく劣性形質の) 白色型の遺伝型が失われたのではとの考察もこのページに出てくる。
conciliate は日本人には比較的馴染みの薄い単語かも知れない (学術的表現によく使われる動詞で reconcile があり、これも訳出も使い方も難しい。対立する結果を納得できるようにする、のような感じだろうか)。
conciliate の辞書の訳語もあまりすっきりしない (おそらく植民地時代の価値観が含まれている) が、異なったものをお互いを尊重しつつ認め合うと理解すればよいだろうか。仮想的な学名であるが Falco conciliator は現代最も必要とされるものかも知れない。
そのような鳥にぜひ世界を飛び回ってもらいたい。
conciliation と consilience (論理学の用語) は別の意味を持つ単語だが、
社会生物学や生物多様性で有名な故 E. O. Wilson の著作に "Consilience: The Unity of Knowledge" (1998) がある。邦訳では「知の挑戦」(山下篤子訳 角川書店 2002) と訳されているが (内容は書物の紹介などを読まれたい)、社会生物学をどこまでヒトの行動に適用できるかの議論 (論争) も背景として書かれたものだろう。
Biedenweg et al. (2023) Seeking consilience: Traditional ecological knowledge and Western social science contributions to orca conservation knowledge の紹介も参考に。
consilience はおそらく conciliation も引っ掛けた表現ではないか、あるいは英語圏の者には意図が自動的に通じるのではないかと感じている。
#ハヤブサ備考の [月に行ったハヤブサ] 項目で紹介の
Review of: Feduccia, A. 2020 - Romancing the Birds and Dinosaurs: Forays in Postmodern Paleontology. BrownWalker Press/ Universal Publishers, Inc.
Boca Raton, FLA and Irvine, CA. を部分再掲しておくことにする。
この評者の最後の部分 (Epilogue) は含蓄がある。科学における "合意" には2種類あって consilience と consensus で、議論のあるテーマに対して前者は異なるアプローチで互いの見解を尊重しつつ到達した合意点で、後者はどちらかと言えば多数派の原理による合意。
consilience と conciliation の両方の意味が含まれていることを前提として Wilson が伝えたかったものは "The Creation: An Appeal to Save Life on Earth" (2006) 邦訳では「創造 - 生物多様性を守るためのアピール」(岸由二訳 紀伊國屋書店 2010) によりよく現れている感じがする。
「社会生物学」が発表された時、科学会のみならず創造論者から激しい反発があったことはよく知られている通り。生物多様性の保全のためには生物進化や社会生物学の理解は不可欠だろうと (少なくとも自分は) 考えるが、たとえそれを否定する人にとっても危機的状況にある地球環境や生物多様性を守るために "consilience" を形成することができるのではないか。
この当時 (2000 年代初頭) は地球温暖化や生物多様性の危機が目に見えて現れてきた時代で、当時の環境問題のメーリングリストで、創造論者のグループも地球温暖化問題や環境問題にも自らが積極的な行動をなすべきとの訴えを出している報道を読んで勇気づけられたのを思い出す。
Wilson もそれらの機運を積極的に捉えたのではないかと感じる (同著 17 章や原注に参考になる情報がある。いずれも訳文で参照した。この本の中にある自然科学者が哲学者や政治家に向かない理由なども含蓄が深くて面白い)。そしてその Wilson も今はいない。
[オナガイヌワシの重金属中毒と不思議な救出事例]
Rescuing a Dying Eagle Uncovers a Land's Toxic Secret (Thrilling Wildlife 2025)
弱ったオナガイヌワシが保護され原因不明だったが、同位体分析を含む最新技術によって鉱山跡の汚染が原因と特定された。重金属の慢性毒性を示す事例となるとともに、同様の事例が気づかれずに起きている可能性が高い。
The Eagle Painted by Spirits (Thrilling Wildlife 2025)
こちらは "彩色された" オナガイヌワシが瀕死の状態で発見され、原因究明をめぐる謎解き物語。例えば "いたずら" による彩色が行われて弱った状態のワシが発見されたわけではなかった。字幕で読めるので謎解きの続きは判読いただきたい。
すでに低体温で体もほとんど機能していない状態からいかにして生還し、野外放鳥にまで至ることができたか、ICU でなされた獣医学的な対応なども驚くべきもの。深部体温が上昇し始めるまでかなりの期間を要したなど、恒温動物の生理が我々にいかに似たものか、瀕死の状態から救うことがいかに難しいか改めて感じられる。
もちろん最初から強制給餌はできない。強制給餌に対して多少なりとも嫌がる初期の兆候を見せるまでに3週間も要したとのこと。その後も容態はなかなか改善せず長期間不安定だったとのこと。
リハビリテーションの段階では救命に携わった2名に恐怖反応をあまり示さなくなっていたとのこと。
謎解き物語にも先住民の口伝文化の聞き取り、最先端の元素分析や地質学調査など驚くほど多様な要素が含まれていた。
[大気重力波を用いるイヌワシのソアリング]
Carrard et al. (2025) Golden eagles regularly use gravity waves to soar: new insights from high-resolution weather data
ソアリングに上昇気流や山岳気流を用いることはこれまでもよく記述されてきたが (#アホウドリ備考 [ソアリングの分類] 参照)、アルプスのイヌワシの高精度記録と高精度気象データを組み合わせてこれまで注目されてこなかった大気重力波を頻繁に用いていることが明らかになった。ソアリング全体の少なくとも 19% で活用されているとのこと。冬季は上昇気流が相対的に弱いので山岳気流や大気重力波の役割が増すとのこと。
Atmospheric wave の wikipedia 英語版の記述を確認しておくと、internal gravity waves がコリオリ力など他の要素を含まない最も単純な大気重力波で、安定した平行平板大気構造 (対流などが発生していない。対流発生条件は Schwarzschild criterion があり、ブラックホールの内部解を導いたシュヴァルツシルトと同一人物。対流安定 = 対流が発生しない の場合は internal gravity waves が成長できる。恒星天文学では g-mode と呼ばれる振動モードに対応する。ちなみに太陽ではこの振動モードは外からはほとんど見られず、5分振動と呼ばれるものは音波) 条件で見られるとのこと。
対流が発生していない静かな条件でもソアリングする必要が生じることもあって、イヌワシはこれを活用しているということになる。意外なところで天文学の概念と接点がある。実際には大気重力波要素を含むが最も単純ではない大気波を用いているのだろう。
ごくおまけで、ここで出てくる重力波 (gravity wave) は一般相対性理論で使われる重力波 (gravitational wave) とはまったく別物。英語では別用語だが翻訳すると同じ日本語になってしまう。重力波望遠鏡など後者の方が一般に馴染みがあるかも知れない。
物理にあまり馴染みのない人向けの注記: 波などの説明をする際に、一般的によりわかりやすいと思われる表現と考えられて「引っ張られて」とか「押されて」など説明されることがある。余計に紛らわしい気がするので、ここでは一つ「復元力」の表現を押えておけばよい。重力 (浮力) が復元力なので gravity wave となる次第。
復元力とは何かぐらいは調べてね、となるわけだが、何と wikipedia 日本語版には項目がない (2025.6 現在)。英語版の Restoring force もあまり大した説明になっていないので、別の説明を見てね、となるが、高校物理ではバネを使うようで弾性の表現が主になって概念が矮小化されてしまう...。
星の振動では圧力 (pressure) が復元力となる場合は p-mode と呼ばれる。こちらの方がずっと簡単ではないか (?!)。
[鷲の漢字の由来]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 87 VII に解釈 (藤堂) が記されていたので紹介しておく。「就」は 京 (小高い丘、丘にできた集落、みやこ) + 尤 (手を曲げてひっぱる) で、人々を集落に引き寄せること。「就」の文字は「水の下 (ひく) さに就くがごとし」(孟子) として使われ、目標目がけて引き寄せられる (例えば就職のような事例がある) ワシの動作を表したのではないかとの解釈。
jiu と発音する。
中国語ではワシを表す別の文字があり (一般にはこちらが多い) 周+鳥 でこちらは diao と発音し、中国西北部から中ソ国境 (当時の表記) にかけてすむ大型の灰色のワシを指す。イヌワシは確かにこの文字がふさわしい。
古くは猛禽を広く シ (執 = とらえる + 鳥 の文字) と呼んだ。この文字にさらに鳥を加えて2文字としても使われる。
-
クマタカ
- 学名:Nisaetus nipalensis (ニーサーエトゥス ニパレーンシス) ネパールのタカのようなワシ
- 属名:nisaetus (合) タカのようなワシ (nisus タカの姿に変えられたメガラの王ニースス、転じてタカの意味で使われる、aetos ワシ Gk) 合わせて英語の hawk-eagle に対応
- 種小名:nipalensis (adj) ネパールの (nipale ネパール -ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Mountain Hawk-Eagle
- 備考:
-aetos は a が長母音。#オジロワシ の事例をみるとこの綴りの場合は ae は分けて発音し、a が長音となると考えられる。
nisus も i が長母音なのでそれが保存されると考えれば上記の発音で "サー" にアクセントがある (ニーサーエトゥス)。
古く使われていた方の spizaetus は "スピザーエトゥス" となりそう。
nipalensis は場所の -ensis の冒頭が長母音でアクセントもある (ニパレーンシス)。
OED によれば英語で使われる Hawk Eagles の用例は新しく 1883 年 Cassell's Natural History に現れるとのこと。Hodgson が属名 (当時 Nisaetus。英語の hawk-eagle に対応) を提唱した後に作られた英名と考えられる。
[名称と分類]
英名は Hodgson's Hawk-Eagle も使われ、英国博物学者 Brian Houghton Hodgson がヒマラヤで記載したことによる。
記載時の学名は Nisactus Nipalensis Hodgson, 1836 であった (原記載) 基産地 ネパール。属名にミスがあり Nisaetus と後に訂正された。
同属に含まれていた Nisactus grandis Hodgson, 1836 (同上) は現在はクマタカのシノニムとされるよう。
ただし Hodgson の記載したこの "2種" と属記載の表現に曖昧なところがあり、インドのワシ類をどのように分類するか Blyth (1846), Gray (1855) が議論していた (The Key to Scientific Names の Tolmaetus の項目)。ただし Nisactus Nipalensis Hodgson, 1836 が現在のクマタカと判定すればタイプ種が指定されているので特に問題は起きない。
AviList v2025 - errors, typos (BirdForum 2025.6) にも Nisaetus の年代について議論が紹介されている。1836 年が有効で後の論文にて裁定されたとのこと。
この問題は再度取り上げられて AviList v2025 - errors, typos Avibase の運用者によるもので、種は 1836 年、属は 1837 年となっているがどちらが正しいのか。
その後最近までアカエリクマタカをタイプ種とする Spizaetus 属に統合されていた。
spizias タカの一種、おそらくハイタカ (Gk) aetos ワシ (Gk) だが、spiza フィンチ (Gk) と混同して解説されている文献もあるので注意 (語源は spiza フィンチ < spizo 高い声で鳴く; piazo 捕まえる Gk。#トビも参照)。
日本のクマタカは該当しないが、Aquila 属に〜クマタカ (英 hawk-eagle) の名前で含まれている種類があり、英 eagle に変更すべきとの提言もある
[Lerner et al. (2016) Phylogeny and new taxonomy of the Booted Eagles (Accipitriformes: Aquilinae)] (#イヌワシの備考も参照)。
海外の種類で〜クマタカとなっている種類は分類を見る時に注意が必要。
かつて〜クマタカと名前のあった種類は現在では多数の属に分離されている。これは Spizaetus 属が多系統であったこと [Haring et al. (2007) Convergent evolution and paraphyly of the hawk-eagles of the genus Spizaetus (Aves, Accipitridae) - phylogenetic analyses based on mitochondrial markers]、
Nisaetus 属と {Spizaetus 属 + Hieraaetus 属} が独立したグループとなっていて、Hieraaetus 属が Aquila 属に近いことによる (これらの属名は現在の分類による)。
それぞれの属の単系統性を保つためにいくつかの種が別属に移動となった。さまざまな系統の種類がクマタカに似た容姿となったのは似た環境 (特に Nisaetus 属と Spizaetus 属では熱帯雨林に適した丸まった翼と長い尾、Jollie 1977) で収斂進化した結果と思われる (Haring et al. 2007)。
Nisaetus 属と Spizaetus 属の関係については [Nisaetus 属と Spizaetus 属は結構違う?] の項目でさらに取り上げる。
クマタカが Nisaetus 属となったのは Hodgson (1836) がクマタカを Nisaetus 属のタイプ種として記載したためで、元の学名に戻ることになった。
Spizaetus 属は3属 (アジア、アフリカ、南アメリカ) に分割されたが、Vieillot (1816) が用いた属名で、Gray (1840) がアカエリクマタカをタイプ種と定めたため、南アメリカのグループが Spizaetus 属を引き継ぐことになった。Spizaetus 属のタイプ種はアカエリクマタカとなる (Haring et al. 2007; The Key to Scientific Names)。
概要は Gamauf et al. (2005a) Molecular phylogeny of the hawk-eagles (genus Spizaetus)でも示されている。
東南アジア島嶼部のクマタカ類については、
Gamauf et al. (2005b)
Species or subspecies? The dilemma of taxonomic ranking of some South-East Asian hawk-eagles (genus Spizaetus) も参照。
島嶼部の多数の種類を種とみなすかカワリクマタカの亜種とみなすかの議論がある。
なお Anita Gamauf については#ハチクマ備考の [フィリピンのハチクマの不思議] の追記部分を参照。
現在ではイヌワシ類から近い順に、
Aquila 属: モモジロクマタカ、ボネリークマタカ、アフリカクマタカ。これらはワシ扱いとなるだろう。
Hieraaetus 属:
アカヒメクマタカ (ヒメアカクマタカ) Hieraaetus morphnoides (英名 Little Eagle)
(ニュージーランドの絶滅巨大種 ハーストイーグル Hieraaetus morphnoides Haast's eagle もこの仲間)
ヒメクマタカ (ケアシクマタカ) Hieraaetus pennatus (英名 Booted Eagle)、
コビトクマタカ Hieraaetus weiskei (英名 New Guinea Hawk-Eagle)、
シロハラクマタカ Hieraaetus ayresii (英名 Ayres's Hawk-Eagle)、
(ヒメイヌワシ Hieraaetus wahlbergi もこの仲間。#イヌワシの備考も参照)
Lophaetus 属:
エボシクマタカ (カンムリクロクマタカ) Lophaetus occipitalis (英名 Long-crested Eagle)
[この間にゴマバラワシ (ゴマハラワシ) Polemaetus bellicosus (英名 Martial Eagle) が入る]
Lophotriorchis 属:
アカハラクマタカ Lophotriorchis kienerii (英名 Rufous-bellied Eagle)
Spizaetus 属:
アカエリクマタカ Spizaetus ornatus (英名 Ornate Hawk-Eagle)、
アカクロクマタカ Spizaetus isidori (英名 Black-and-chestnut Eagle)、
セグロクマタカ (チリーワシ) Spizaetus melanoleucus (英名 Black-and-White Hawk-Eagle)、
クロクマタカ Spizaetus tyrannus (英名 Black Hawk-Eagle)
Nisaetus 属:
カワリクマタカ Nisaetus cirrhatus (英名 Crested Hawk-Eagle/Changeable Hawk-Eagle)、
フローレスクマタカ Nisaetus floris (英名 Flores Hawk-Eagle)、
フィリピンクマタカ Nisaetus philippensis (英名 Philippine Hawk-Eagle)、
ピンスカークマタカ Nisaetus pinskeri (英名 Pinsker's Hawk-Eagle、フィリピンクマタカより分離)、
セレベスクマタカ Nisaetus lanceolatus (英名 Sulawesi Hawk-Eagle/Celebes Hawk-Eagle)、
カオグロクマタカ (ブリスクマタカ) Nisaetus alboniger (英名 Blyth's Hawk-Eagle)、
ジャワクマタカ Nisaetus bartelsi (英名 Javan Hawk-Eagle)、
クマタカ、
レッグクマタカ Nisaetus kelaarti (英名 Legge's Hawk-Eagle、かつてクマタカの亜種とされていた)、
ウォーレスクマタカ Nisaetus nanus (英名 Wallace's Hawk-Eagle)
Stephanoaetus 属:
カンムリクマタカ Stephanoaetus coronatus (英名 Crowned Hawk-Eagle/African Crowned Eagle)。
Glenys and Derek Lloyd "Birds of Prey" (1969) [高野伸二訳「猛禽類」(1973)] (この訳本で過去に和名のなかった多くの猛禽類に名前が付けられた。大部分は現在も使われているがその後変更された名称もある) ではクマタカ類を以下のように分類している。参考のために括弧内に現在の属の冒頭2文字を記してある:
カザノワシおよび森林性のクマタカ類:
カザノワシ Ictinaetus malaiensis [英名 Black Eagle。名称は#カラフトワシの備考にまとめた。現在の分子系統樹ではエボシクマタカと Clanga 属 (カラフトワシ類) の間に入るがこの系統の全ゲノム解析は進んでいないので今後位置づけが変わる可能性もある]、
クマタカ (Ni)、
ジャワクマタカ (Ni)、
セレベスクマタカ (Ni)、
フィリピンクマタカ (Ni)、
カオグロクマタカ(ブリスクマタカ) (Ni)、
ウォーレスクマタカ (Ni)、
カワリクマタカ (Ni)
大型のクマタカ類:
アフリカクマタカ (Aq)、
クロクマタカ (Sp)、
アカエリクマタカ (Sp)、
カンムリクマタカ (St)、
アカクロクマタカ (Sp)、
ゴマバラワシ (Po)
草原または丘陵性のクマタカ類:
エボシクマタカ (カンムリクロクマタカ) (Lo)、
セグロクマタカ (チリーワシ) (Sp)、
ヒメクマタカ (ケアシクマタカ) (Hi)、
アカヒメクマタカ (ヒメアカクマタカ) (Hi)、
[シロハラクマタカ Hieraaetus dubius が含まれているが、これは現在ヒメクマタカ (ケアシクマタカ) のシノニムとされる]、
ボネリークマタカ (Aq)、
アカハラクマタカ (Lo)、
ヒメイヌワシ (コイヌワシ) (Hi)
との分類となっている [括弧内は高野 (1973) で用いられた名前]。当時から「ワシ」の名が付いていてもクマタカ類に分類されていた種類が少なからずあったことも興味深い。アジアのクマタカ類については若尾 (2023)「クマタカ生態図鑑」に個々の種の解説がある
[The Asian Raptor Research & Conservation Network (2018) A Field Guide to the Raptors of Asia が主な出典; 若尾 (2023) に記載の系統樹は概ね最新のものと同様であるが、系統樹の学名は2006年の研究前のものになっているので注意 (本文中に新しい分類が紹介されている)。
Catanach et al. (2024) (#アカハラダカ、#カラフトワシの備考参照) があるのでこちらを参照されたい]。
これらクマタカ類とイヌワシ類を合わせて亜科 Aquilinae とされ、いずれもふしょが羽毛に覆われている (ゆえに英語では booted eagles と呼ばれる)。Aquilinae 亜科以外でふしょが羽毛に覆われているタカはごく少数で、ケアシノスリのように寒冷気候などへの適応など収斂進化とされる。
[ロシアや日本周辺のクマタカ]
ロシアでクマタカが最初に記録されたのは1914年10月19日、当時日本領だったサハリン島の南西に位置するモネロン島 (Munsterhjelm 1922)。Dement'ev and Gladkov (1954) では第6巻末の補遺に記載されている。当時はサハリン南部に (千島列島でも見られたとあるが確かめられていない) 北海道から標行すると考えられていた。日本の亜種はインドや中国の大陸のものに比べてより淡色で、冠羽があまり発達しておらずないものもあると記述されている。
モネロン島では崖で観察されたとのこと。Jahn (1942) によれば日本では山岳地の標高 1600 m にみられ、4月末に2卵 (クラッチサイズ) と記述されていて現代の知見とはやや異なっている。
1980 年代前半までの記録は Gorchakov and Nechaev (1994) より再掲に詳しい。
中部シホテ・アリン、シホテ・アリン保護区、ラゾフスキー保護区北部の森林タイガ地域で複数回採集され、まだ幼羽の残る若鳥を含めわなにかかった事例があり、繁殖の証拠はあった (Elsukov 1977) が、営巣が確認されたのは比較的最近で、沿海地方のボリソフスキー高原で 1985 年に発見された (Gorchakov 1988)。Karyakin (2007) New Record of the Mountain Hawk Eagle Nesting in Primorye, Russia を参照。
ロシアの文献ではこれまでのところ、日本と同じ亜種 orientalis (ロシア名 vostochnyj khokhlatyj orel:「東方クマタカ」に相当) を用いている
[Kurdyukov (2021) Russian Orinithology Journal 30, 3801; Nechaev and Kharchenko (2019, 2012初出) Russian Orinithology Journal 28, 244 など。標行と考えられていた Dement'ev and Gladkov (1954) でももちろん同じ]。
限られた遺伝子と個体の解析であるが前述の Haring et al. (2007) によれば、ロシア沿海地方のクマタカからのサンプル (Snipori8, Snipori12) は nipalensis グループに近い。
Haring et al. (2007) は大陸の個体群はかつて連続分布をしていたが、南東アジアとロシア沿海地方に残存しているのは中間地域で生息地が失われたための可能性を示唆している。(データの量からはやや大胆な感じもするが) ロシアのクマタカの亜種は nipalensis とすべきであろうとしている。
もっとも、この解析は短い遺伝領域のみを用いているため限界もある。核遺伝子も含めたさらなる解析が望まれる。もしこの解釈が正しければ繁殖個体群の orientalis は日本固有亜種となる。ちなみにこの研究では北海道のクマタカも使われているが、ロシア個体との類縁性は高くない。
最近のロシアの文献では Kolomitytsev and Poddubnaya (2024) Breeding of the mountain hawk-eagle Nisaetus nipalensis in the south of Khabarovsk Krai (pp. 5306-5309)。ハバロフスク州南部。
亜種は Glushchenko et al. (2016) の見解に従っている。さまざまな時期に記録されていることから沿海地方に広く分布していると考えられる。
しかし繁殖が確実に知られているのは南部のみ。この種類が隠蔽的 (英語では cryptic に対応) なためかも知れないとのこと。
見つかったのが比較的最近で、沿海地方南部に定着したのはタイガで起きている変化 (気候変動などを指しているのか) に適応したものとの解釈。ただし 20 世紀中頃以降に自然の研究が進んだため見つかった可能性もあることも無視できない。著者たちはかつては生息していなかったところに定着したことを想定し、最も近い繁殖地 (北海道) から分布を広げたと推論しているらしい。
ロシアのクマタカが大陸亜種ならば、より南方 (例えば北朝鮮や中国東北部) に未知の繁殖個体群があったものが分布を広げた、あるいは 20 世紀中頃まで長年見逃されていたことを示唆することになる。ロシアでも少数が生息していたが目立たないため発見されず、近年数が増えて見られるようになったものかも。
歴史を遡るのは難しいとしても今後の分子遺伝研究次第で思わぬ結論になるかも知れない。
またなぜロシア沿海地方に限定なのか考察するのも興味深いだろう。大陸のイヌワシは日本のものより大型でクマタカの分布の制約要因になっているなど種間関係もあるのかも知れない。ロシア沿海地方のイヌワシの繁殖は少なくクマタカにとって比較的住みやすい? 皆様も考察いただきたい。
クマタカは台湾にも生息する。Huang et al. (2021) Vocal behavior of the Mountain Hawk-Eagle Nisaetus nipalensis in Taiwan によれば「日本の亜種」との違いを示す表現があり、日本の亜種とは異なることを意味していると考えられる (この文献は音声の項目で後述)。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" によれば台湾のものは亜種 nipalensis (ネパールの) とされている。韓国では日本から迷行があるようである [wikipedia 英語版; Dement'ev and Gladkov (1954)]。世界で認められている亜種はこの2亜種(IOC)。
ネパールから中国、台湾 (そしておそらくロシア) に至るこの大陸亜種の和名にタイワンクマタカがある (コンサイス鳥名事典)。
日本の亜種の記載時学名は Spizaetos orientalis Temminck & Schlegel, 1844 (原記載) 基産地 日本。
フランス語名で l'aigle-autour oriental ("東洋のオオタカのようなワシ" の意味)。インドのものと比較しているので、"oriental" はインド大陸 (= 現代では基亜種) に対するものとして命名された模様。l'aigle-autour に含まれるものは当時アフリカやスマトラなどすでにいくつも知られていた。
"ネパール" にしても "東洋" にしてもヨーロッパから遠く離れた地域の大雑把な区域を示すもので特徴などに特に注意を払った命名ではなさそう。
Aquila 属などとまとめられることはなかったので問題は起きなかったが orientalis はいろいろな属で用例があってそこそこ危ない名前だった。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば英名は Indian Crested Eagle となっていた。
ここにも驚くべきことに日本からのクマタカの若鳥が Zoological Gardens in London (現代の London Zoo ロンドン動物園 の前身で 1828 年科学研究のため開設、1847 年一般公開開始と wikipedia 英語版から) で飼育され、成鳥の羽衣に換羽したことが述べられていた。
Hartert (1910-1922) p. 1132 によれば、"Fauna Japonica" に描かれた鳥は成鳥ではない。Hartert が調べた時点では少数の標本しかなく、nipalensis と合体させるべきか別種とすべきか判断が難しい。
(大きさは明らかに異なるが) 若鳥は非常に似ているため亜種とするのが妥当だろうとの判断。日本産の標本には冠羽が欠けているものが大部分だが脱落した可能性もある。日本のクマタカはサルの声を真似るのでサルをおびき寄せて食べているのではとの推測があった模様 (Pere David の報告による)。
当時の Spizaetus 属 (現在の Nisaetus 属を含む) のドイツ語名は Schopfadler (冠のあるワシ)。分類上は日本のクマタカは分布の端でもあってあまり冠羽がない点が気になっていた模様。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) ではもう1亜種 kelaarti をリストしているが、IOC では別種レッグクマタカ Nisaetus kelaarti 英名 Legge's Hawk-Eagle と分けている (参考写真ページ 世界の猛禽類 Vol.7 レッグクマタカ)。
分子系統解析ではクマタカの側系統に相当するためこの分離は妥当。前述のように Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) はタカ類の新しい文献情報に追いついていないためだろう。
記述文献は Gjershaug et al. (2008) An overlooked threatened species of eagle: Legge’s Hawk Eagle Nisaetus kelaarti (Aves: Accipitriformes)
スリランカと南インドに分布。クマタカより少し小型で測定値や色彩、音声も異なる。cyt b で4.4% の違いがある。
比較用のクマタカ orientalis の音声出典は「日本野鳥大鑑」と山崎氏の録音によるもので、日本のクマタカは研究者も多くデータも記録されているはずなのに音声記録は海外からアクセス困難な (だった) ことがこれからもわかる。
[Nisaetus 属のクマタカ類の系統分類 (イヌワシ亜科その1)]
Catanach et al. (2024) の分子系統樹に基づく Nisaetus 属系統を示しておく。イヌワシ亜科は大きく2系統に分かれ、Spizaetus 属は Aquila (イヌワシ) 属などの含まれる後者に属する。
ここでは前者の Nisaetus 属系統のみを示す。
種の順序は Catanach et al. (2024) に基づく。
イヌワシ亜科 Aquilinae (の前半) (後半は #カラフトワシ備考)
カンムリクマタカ属* Stephanoaetus
カンムリクマタカ Stephanoaetus coronatus Crowned Eagle
マダガスカルカンムリクマタカ** Stephanoaetus mahery Malagasy Crowned Eagle (絶滅種。分子系統樹にはもちろんないが追加)
クマタカ属 Nisaetus
ウォーレスクマタカ* Nisaetus nanus Wallace's Hawk-Eagle
レッグクマタカ* Nisaetus kelaarti Legge's Hawk-Eagle
クマタカ Nisaetus nipalensis Mountain Hawk-Eagle
ジャワクマタカ* Nisaetus bartelsi Javan Hawk-Eagle
カオグロクマタカ* [高野 (1973) ではブリスクマタカ] Nisaetus alboniger Blyth's Hawk-Eagle
セレベスクマタカ* Nisaetus lanceolatus Sulawesi Hawk-Eagle
ピンスカークマタカ* Nisaetus pinskeri Pinsker's Hawk-Eagle
フィリピンクマタカ* Nisaetus philippensis Philippine Hawk-Eagle
フローレスクマタカ* Nisaetus floris Flores Hawk-Eagle
カワリクマタカ Nisaetus cirrhatus Changeable Hawk-Eagle
カオグロクマタカとセレベスクマタカの間の空白はここで系統が分かれることを示す。
この2系統の分岐は 900-1000 万年前程度と比較的新しい。
Nisaetus 属で核遺伝情報を含めた解析がなされているのはクマタカとカワリクマタカの2種のみであるが、他の種類も遺伝的にそこそこ離れているのでこの系統樹はそれほど曖昧さがないと考えてよいだろう。
前半のクマタカ系列でクマタカ以降は遺伝的距離が比較的近く、ジャワクマタカは島の亜種が隔離進化して種相当の違いが生じたものと考えてよいだろう。ウォーレスクマタカも同様だがクマタカより先に分岐している。クマタカとカオグロクマタカは北方系統と南方系統のそれぞれ基本となる種に相当すると考えられる。
後半の系統ではセレベスクマタカは島の亜種が隔離進化、ピンスカークマタカとフィリピンクマタカはフィリピンの南部・北部に分かれているが分岐時期は約 400 万年前と非常に新しいわけではない。
Gamauf は Spizaetus philippensis pinskeri Preleuthner & Gamauf, 1998 の記載 [A possible new subspecies of the Philippine Hawk-eagle (Spizaetus philippensis) and its future prospects] を行い、
Gamauf et al. (2005b) で2005 年の自身の分子系統研究で独立種の扱い。ピンスカークマタカの記載者の一人となっている。フィリピンでルソン島とミンダナオ島で過去に隔離されたものがそれぞれ進化したと考えられる。猛禽類の近年の新種記載は大変珍しい。IOC 14.2 で調べてみるとタカ類の中では 2010 年のソコトラノスリ Buteo socotraensis に次ぐ新しさだった。
1998 年の論文では North Philippine Hawk-eagle と South Philippine Hawk-eagle の名称が提案されていた。現在の世界のチェックリストではあまり使われている形跡がないが、フィリピンのリストでは別名扱い。
オランダ語ではこの名称に対応している。現在のドイツ語名では Haubenadler (頭巾のあるワシ) をこれらの一般名として地域名を付けている。英語では Hawk-eagle なので世界でも一般的にそのように呼ばれているように感じてしまいがちだがむしろ英語が特殊なよう。
フィリピンの飼育下で巣立ちや子別れまで記録されており、オスのみが造巣と巣材集めを行い、抱卵はメスのみが行う。ピンスカークマタカは毎年産卵するが同種とされていたフィリピンクマタカは2年に一度などの興味深い記述が wikipedia 英語版にある。少なくともこの記述の時点では野外生態はほとんどわかっていなかった。
ピンスカークマタカの容貌 (特に若鳥) はフィリピンハチクマ Pernis steerei Philippine Honey Buzzard とそっくりとのこと。どちらが得をしているのか (?) この話題は#ハチクマ [擬態と種・亜種の関係] の方で。
The PEC as the first in the world to breed Pinskers Hawk Eagle in Captivity (Philippine Eagle Foundation 2020) 世界初のピンスカークマタカの飼育下繁殖の紹介。このつがいはからこれまで6羽のひなが生まれたとのこと。
Nature Talks 2021: The Pinsker's Hawk Eagle こちらも紹介ビデオ。解説している人の映像ばかりだが鳴いている声はずいぶん大きい。これらの解説でも booted eagle とイヌワシに近い扱いとなっている。
North Philippine Hawk Eagle, pabalik-balik sa pangangalaga ng isang residente?! | Born to Be Wild (GMA Public Affairs 2024) こちらは英語ではないが飼育個体の訓練などの映像がある。ところどころに英語の説明が入っている。
若鳥は遠目には本当に Philippine Honey Buzzard (ハチクマの亜種ではない) そっくり (関心のある方は Philippine Honey Buzzard でビデオ検索を)。
ピンスカークマタカ (フィリピンクマタカの亜種の扱い) の初の飼育下繁殖成功の時のニュース: Endangered Philippine hawk-eagle bred in captivity (phys.org 2012)。飼育下繁殖成功まで 11 年かかったとのこと。
救助された個体をもとに 2001 年にプロジェクトが始まり、相性のよいペアが成立してしたのが 2009 年で 2010 年と 2011 年に産卵したが採取前に割れてしまった。2012 年が初成功の模様。
フィリピンクマタカ (ここでは Luzon Hawk Eagle の英名となっている) の写真例: Luzon Hawk-Eagle or North Philippine Hawk-Eagle (Nisaetus philippensis) (Loel Lamela 2022.3 撮影)。つがいと死亡したひな。我が子が死んだため落ち込んでいる写真なのだろうか。
判断はお任せしたい。
Luzon Hawk-Eagle or North Philippine Hawk-Eagle (Loel Lamela 巣にいるつがい。2024.1 撮影とのこと)。研究して2種に分離した故人 Anita Gamauf がこの写真を見ればきっと喜ぶだろうとのコメント。当時は野外の繁殖形態はまだ知られていなかった。
ジャワクマタカもインドネシアで飼育下繁殖が試みられているようだが Withaningsih et al. (2024) Morphometric and DNA sexing accurately in male Javan hawk-eagle (Nisaetus bartelsi) determination at Kamojang Eagle Conservation Center, West Java, Indonesia
では7羽の DNA 性別判定が報告されており飼育下繁殖成功に関わる言及はない。形態的特徴による性別判定は用いる特徴により異なっていて合わない個体もあった。
フローレスクマタカはカワリクマタカの中から Gjershaug et al. (2004) The taxonomic status of Flores Hawk Eagle Spizaetus floris
が別種として提案したもの。遺伝情報が出る前の記事として参考になる。morph の有無など外見の違いが主で、遺伝的にカワリクマタカの範囲内とも言えるが下記参照。
カワリクマタカはカオグロクマタカとは多少分布域の重複があるがすみわけている模様でクマタカに比べると南方系になる。
Nisaetus 属はカワリクマタカとクマタカが南北を分け合い、残りの種類はそれぞれのグループに属して亜種よりは大きな違いがあるので独立種と認められていると理解するとわかりやすそうである。
この分布はハシブトガラスの北方系統と南方系統の関係に似ている (#ハシブトガラスの備考参照)。
ハシブトガラスの北方系統はハシボソガラスに似た開けた環境に適応したものとの解釈があるが、東南アジアのクマタカ類に比べて日本のクマタカにそのような傾向はあるだろうか。
マダガスカルカンムリクマタカ Stephanoaetus mahery は (和名がみつからないので仮に与えた → 使われていたが同じ名称だった: フェドゥーシア「鳥の起源と進化」 で使われていた) カンムリクマタカ属で知られている2種のうちの1種でマダガスカルに生息して生態系の頂点で、キツネザル類を捕食していたと考えられるが人が入植して獲物を捕りすぎたために 16 世紀に絶滅したと考えられる。
伝説のロック鳥 (Roc) のモデルの候補の一つとされている (wikipedia 英語版より)。
マルコ・ポーロの「東方見聞録」のマダガスカルに関する記述の中に、現地人がルク (ruc) と呼ぶ大きな鳥が登場する (wikipedia 日本語版より)。
この絶滅種はマダガスカルの生態系を考える上で非常に重要な存在で、マダガスカルのキツネザル類が現存の小型猛禽類に対して警戒行動をとるのは長らく謎であった。
霊長類研究者の Goodman et al. (1993) A Review of Predation on Lemurs: Implications for the Evolution of Social Behavior in Small, Nocturnal Primates 自身も夜行性猛禽類の可能性も検討していた。
しかしマダガスカルカンムリクマタカの遺物の発見により大型猛禽類がまだ残っていた時の習性の名残とのロマン溢れる仮説が発表された
(#ハチクマの備考 [60 年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)] 参照)。
しかしもちろん反論もあった: Csermely (1996) Antipredator behavior in lemurs: Evidence of an extinct eagle on Madagascar or something else?
現存のより小型の猛禽類でも十分な脅威を与えているのではないか。
これらの研究や議論が霊長類学の専門雑誌で主に行われ、鳥の研究の世界にはあまり顔を出していないのも面白い。大型猛禽好きの人であれば話題に取り上げてもおかしくない種類であるがなぜか知名度があまりない。
現生の小型種がキツネザル類を攻撃したり獲物にするかどうかが判明するまで決着が持ち越されることになった。続きは [60 年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)] をご覧いただきたい。
カンムリクマタカの属名に使われる Stephanoaetus の由来は stephanos 冠 aetos ワシ (Gk)。
ウォーレスクマタカの nanus は「小さい」。レッグクマタカの kelaarti 英国の軍医、動物学者でスリランカで仕事をした Edward Fredric Kelaart にちなむ。
ジャワクマタカの bartelsi はオランダ出身でジャワ島の茶のプランテーション監督者の Max Eduard Gottlieb Bartels にちなむ。カオグロクマタカの alboniger は albus 白 niger 黒。
セレベスクマタカの lanceolatus は小さな槍斑のある (マキノセンニュウ参照)。
ピンスカークマタカの pinskeri はオーストラリア動物学者 Wilhelm Pinsker にちなむ。
カワリクマタカの cirrhatus < cirratus 巻き毛の (冠羽を表す)。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では フィリピンクマタカ Luzon Hawk Eagle、ピンスカークマタカ Visayan Hawk Eagle の英名を与えている。他は IOC と同じ。
フィリピンのリストでは IOC 名を採用しているが、別名として North Philippine Hawk-Eagle, South Philippine Hawk-Eagle も挙げている。
カワリクマタカは5亜種 (IOC)。英名や和名の由来は種内の変異が大きく、morph による色彩の差も大きいことを意味する。
記載時学名 Falco cirrhatus Gmelin, 1788 (原記載) で冠羽のあるタカ類は多いがこれが元祖となっている。見ての通り基産地がインドで、英名で Crested indian Falcon, フランス名で Faucon hupe des Indes (英名と同じ意味) となっている。
英名別名にも Crested Hawk Eagle もあり、これは外見と学名の両方が由来と考えられる。
英名をそのまま訳せば "カンムリクマタカ" なので和名では別の種類に相当することなるが、こちらは属名、種小名ともに "カンムリ" が入っている (現行学名で Stephanoaetus coronatus。Falco coronatus Linnaeus, 1766 が記載時学名なのでこちらの方がより元祖かも)。
eBird ではインドクマタカを種名とし、東南アジアにも分布する limnaeetus を亜種カワリクマタカとしている。基産地で決まる基亜種がインドの比較的狭い範囲に分布するためにこのような名前になっているものと想像できるが少なくとも現状は紛らわしい (例えば種ハチクマを基亜種に基づいてジャワハチクマと呼ぶような名前になっている)。
カワリクマタカは2グループに大別され、cirrhatus, ceylanensis が冠羽のあるグループ、limnaeetus, andamanensis, vanheurni
が冠羽のないグループ。eBird の名称はこれらが将来別種扱いとなる場合に備えたものかも知れない。
limnaeetus を別種とする提案もあり、かつて Spizaetus limnaeetus (当時の属名を使用) が使われていたこともある (IOC 1.7 までなど)。
カワリクマタカの暗色型。このタイプは冠羽がないとのこと: DARK HAWK EAGLE DOWN: LIFER! A CRESTLESS CHANGEABLE (Ferdie Llanes de AvesFlores 2024.11.28 投稿。フィリピンのパラワン島)。
Gamauf et al. (2005b) で limnaeetus は単系統でないことも示唆されているが、冠羽のないグループの遺伝子プールの基礎となっているとされる。
cirrhatus 系統と limnaeetus 系統 を別とした場合は後者にフローレスクマタカが内包されてしまうことが系統分類上は問題となる (これは別系統扱いにしなくてもすでに起きている問題だが)。
カワリクマタカの島の亜種には重要な保全単位となるものもあり、従来の系統分類概念 (例えば単系統性) を厳密に適用せず進化的に意味のある単位 evolutionary significant unit (ESU) あるいは保全的種概念 conservation species concept とすることも提唱されている。
上記 Gamauf et al. (2005b) 参照。フローレスクマタカも位置的には亜種か種か微妙であるが、保全的に重要として一般的には種扱いされているのであろう
(フローレスクマタカは迫害、密猟、生息地破壊などで世界で最も個体数の少ないワシ類の一つとされる。IUCN CR 種 Flores Hawk-eagle Nisaetus floris; 参考情報
Collaerts et al. (2013)
Discovery of the Critically Endangered Flores Hawk Eagle Nisaetus floris on Alor island, Indonesia)。
フローレスクマタカとカワリクマタカの他亜種の間の遺伝的距離が近いとはいえ、ヌマチュウヒ類の種間距離と同程度である。別種にしても特に問題がある数字ではないが、単系統性の問題をどこまで厳密に見るか次第だろう。Gamauf et al. (2005b) はカワリクマタカの複雑な遺伝構造 (地理的隔離と複数回の導入や接触など) や遺伝子浸透によって厳密な単系統性概念を持ち込みにくいことも述べている。
カワリクマタカは分布域も広いため、種内全体の多様性と1島と隣接地域だけの違いを比べるにはそもそも無理もあるだろう。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では同じ文献を参照しつつ別種でない根拠としている (系統樹だけを見て議論のニュアンスまで読んでいないかも知れない)。
Gamauf et al. (2005b) ではフローレスクマタカとカワリクマタカの関係の議論は
フィリピンの2種が分離されたものとは位置づけがまったく違うとある。
分類学者がごちゃごちゃと議論するのはよいが、そう言っている間に肝心の個体群が絶滅しては分類学研究すらできなくなる。物事の優先順位を考えるべきだと述べているように読める。
同様の意味で島の亜種の vanheurni, andamanensis も分離の考慮対象になるかも知れない。
また #イヌワシ備考の [サハラ砂漠以南のイヌワシ] の保全にも同じような考え方を持ち込む方が適切なのかも知れない。
カワリクマタカの Gamauf et al. (2005b) はデータが少し古く、ごく限られた遺伝情報しか使われていないので新たな遺伝情報も追加した研究も欲しいところである。この論文でも言及されている "Altai falcon" ではまったく違う部位に大きな違いが発見されている (#シロハヤブサの備考参照)。(とまあ寸評する側は簡単に言えるわけであるが)。
Gjershaug et al. (2020) Integrative taxonomy of the Changeable Hawk-Eagle Nisaetus cirrhatus complex (Accipitriformes: Accipitridae) in India
によればインドでは cirrhatus と limnaeetus の生殖隔離は弱く、同種と考えるべきとの結論になっている。
これらのカワリクマタカの研究はクマタカ類 (あるいは他系統でも遺伝的に分離の難しいグループ) の進化を考える上でも役立つと思われるので関心のある者の一読をおすすめしたい。
Spizaetus 属のタイプ種に関連した話題があった: Accipitridae (BirdForum 2025.6) 通俗名のみで定義された場合はタイプ種とみなされない。
Spizaetus 属は当初有効な種 (nominal species) を含まない形で定義されたが、1931 年以前に定義された属の場合は後に含まれたものを有効として扱う規則によって有効な属定義 Spizaetus Vieillot, 1816 となり、Grey (1840) が定めたアカエリクマタカがタイプ種となった。このタイプ種指定が有効とみなされたのは Vieillot (1816) に通俗名ながら含まれていたため。
[Nisaetus 属と Spizaetus 属は結構違う?]
#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] から一部再掲:
Carvalho et al. (2021) Comparative chromosome painting in Spizaetus tyrannus and Gallus gallus with the use of macro- and microchromosome probes
クロクマタカ Spizaetus tyrannus は染色体数 2n = 68 とクマタカ 2n = 66 と似ているが染色体再構成のパターンは大きく違うとのこと。かつては同属とされ姿も似ているが実はかなり異なっているらしい。同じクレードの他のデータがあまりなく染色体再構成がどのように起きたかまだ辿れないとのこと。
この結果を見ると染色体再構成に共通点が少なく Nisaetus 属と Spizaetus 属は結構異なった経緯を経て形成されたことが期待される。Catanach et al. (2024) の系統樹でも分岐年代は 1500 万年前程度。
分岐した後にそれぞれが染色体再構成を含む進化速度の速い時期を経験し (おそらく transposable elements など分子進化を加速する要因も働いていたのでは?)、独立して強力な捕食者の地位を確立したのではないだろうか (その意味ではアジアと南米で収斂進化を起こしたとみなせる部分がある)。
この時期には乾燥化が進みつつあって、アジアで進化した Nisaetus 属にとっては中東に地理的バリアが存在し、アフリカへとさらに進出することはできなかったのではないだろうか。
少しだけ遺存的系統のアフリカのカンムリクマタカ Stephanoaetus coronatus が残っていたが、
後の系統にあたるアカハラクマタカ Lophotriorchis kienerii や ゴマバラワシ [高野 (1973) ではゴマハラワシ] Polemaetus bellicosus そして Hieraaetus 属や Aquila 属と Nisaetus 属がアフリカで競争することは起きず、
主にアフリカで {Hieraaetus 属 + Aquila 属} の系統が躍進することを可能としたのかも知れない。
アフリカ起源のこの系統が躍進した結果、アジアの一部の領域で Nisaetus 属との接触が発生したと想像できる。ヒメクマタカ [高野 (1973) ではケアシクマタカ] Hieraaetus pennatus の繁殖地南限あたり (この種は小型でそれほど強力でない) とクマタカ/イヌワシの接触する日本やロシア極東部あたりが該当する。ヒメクマタカの越冬地は Nisaetus 属と重なる。
おそらく Nisaetus 属が (染色体再構成を含む進化速度の速い時期を経験して) 強力な捕食者の地位を確立するのに時間がかかり、系統的にはより遅く分岐したはずの {Hieraaetus 属 + Aquila 属} ですでに多様化が始まっていたが主な分布が地理的に遠いため、Nisaetus 属から強力な捕食者を生み出す時間的余裕も生じさせたのではないだろうか。
日本のクマタカは系統的にはイヌワシより古いが、分岐年代から見るとそれほど古くから生息していたわけではなく、イヌワシと同じような時期に到達していた可能性がある。
[タカ類の鼻汁]
宮崎 (1987)「鷲鷹ひとり旅」ではクマタカがひなに鼻汁を与えることが記載されている。この記述によれば、クマタカの場合、ひなが生まれて2週間ぐらいまでは量が多いが、その後減少して3週間もすればほとんど出なくなる。また、ひなの上に運び、ひながおいしそうに飲んでいた などの記述がある。
イヌワシ、オオタカについての同じ現象も同書に記載されているが、他の観察者によるものである。久野 (2006) Birder 20(10) p.23 でハチクマがひなに唾液を与えることが観察されている記載があるが、鼻汁と同じものかはわからない。
昼行性猛禽類が食事の際に鼻汁を出すことは鷹匠に古くから知られていたが、Cade and Greenwald (1966) Nasal Salt Secretion in Falconiform Birds によれば海鳥などに見られる塩腺らしいとの記述がある。
Sabat (2000) Birds in marine and saline environments: Living in dry habitats
によればサバンナノスリ Buteogallus meridionalis のように乾燥地域に住む種類は、直接塩水に曝されるわけではないがタンパク質が豊富な食物を食べるため、ナトリウムを腎臓以外から排泄することで水分の喪失を防ぐ意味があるとの記載がある。
Chiu et al. (2024) Convergent evolution of kidney sizes and supraorbital salt glands for birds living in saline habitats
が塩腺と腎臓サイズの比較系統研究を行っていて猛禽類も含まれているので紹介しておく。
海鳥などはもちろん含まれている。タカ類・ハヤブサ類は完全な淡水環境でも塩腺を持っているものが多く、やはり肉食と関係があるようだが持たないものも報告されている。この研究では
アカオノスリ Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk、
コシジロハゲワシ Gyps africanus White-backed Vulture、
サンショクウミワシ Icthyophaga vocifer African Fish Eagle、
アメリカチョウゲンボウ Falco sparverius American Kestrel、
ラガーハヤブサ Falco jugger Laggar Falcon
が含まれいる。サンショクウミワシは和名に "ウミワシ" の名前は付くが完全に淡水環境とのこと。すべてのタカ類・ハヤブサ類が塩腺を発達させているわけではなく、鼻汁が何かはまだ調査が必要なのだろう。
鷹狩りに通常使われる広義 Accipiter 属やハヤブサは持っているらしいことから従来考えられていた知見と不整合があるわけではないが、淡水環境のクマタカが同様かどうかは調べないとわからないだろう。
サギ類では持たない傾向が強い、ハト類も持たない (塩分の少ない食物で必要ない) など細かく見てゆくと面白い。腎臓の大きさと塩腺の有無には相関があるがタカ類・ハヤブサ類では腎臓は特に大きくなく、やはり塩分負荷の大きいシギ・チドリ類や海ガモなどで発達している。
塩腺の退化しているスズメ目の中にも腎臓の大きいものがかなりあるが、何と関係しているのか系統樹を見る限りではあまり想像が付かない。海岸に生息するユキホオジロでも塩腺は退化し、大きな腎臓を持たないとのこと。
塩腺も大きな腎臓も複数の系統で独立に進化したと考えられる。この論文の系統樹ではタカ類・ハヤブサ類が並んでいて (系統順的におかしい配置ではない。フクロウ類やブッポウソウ類をどちらに置くか次第)、分離されたはずなのに多少面白い形になっている。
塩腺と呼ぶと一部の系統の動物のみが持つ特別な機能のように思えるが、"nasal glands" の一種で塩分排出機能は収斂進化を遂げているとのこと: Babonis et al. (2012) Perspectives on the Convergent Evolution of Tetrapod Salt Glands。カメ類では眼窩に機能が移動している。
鳥類の複数の系統で進化したり退化するのは不思議なことではない模様。
Laverty and Skadhauge (2008) Adaptive strategies for post-renal handling of urine in birds
が鳥類の電解質排泄について面白いまとめを行っている。複数の戦略を利用していて (用語は著者自身が名付けたもの)、(1) "爬虫類型": 腎臓ではそれほど濃縮を行わず後で再吸収する、(2) "哺乳類型": 膀胱がなく、腸管に尿を排泄することで coprodeum が実質的に哺乳類の膀胱のような調節の働きをする、(3) 腎臓から排泄後にホルモンの働きで電解質輸送を行う (interaction mode)、(4) 塩腺を用いた salt-recycling。
水分の喪失を避けるために腸管の一部を膀胱のように働かせるのは有効な方法とのこと。
乾燥環境のダチョウの coprodeum の上皮は事実上哺乳類の膀胱のように働いている。
猛禽類はこの点で興味深いとのことで、これらの種では糞と尿がよく混ざるので上記 (2) のような尿だけを濃縮するメカニズムがあまり有効に働かない可能性がある
(糞を飛ばさない系統ではあるいは濃縮力と関係があるのかと気になるところ)。
大型猛禽類は飼育下で特に水を飲む必要がないとされており、マウスを丸ごと食べれば全身の 70% の水分を補充できるが、生肉や肝臓を食べるとカリウム量が過剰になるとのこと。
甲殻類や大型の無脊椎動物のみを食べると海水とほぼ同じ濃度になりナトリウム排泄の必要があるはず。猛禽類の腸管や coprodeum に電解質輸送能力があるかどうかこの時点でまだ調べられていないとのこと。
例えばインコの排泄をよく観察しているだけではわからない部分があるかも。もしかすると鷹匠はよく知っているかも。
爬虫類で海に進出したウミヘビでの研究があり、塩腺のあるものもないものもあるらしい。
Babonis et al. (2012) Morphology and putative function of the colon and cloaca of marine and freshwater snakes
が調べたウミヘビでは下部腸管が鳥類同様に期待される機能を果たしているらしいが総排泄孔にはその機能がなかった。代わりの機能を尿管が担っているらしいとのこと。電解質調節にはいろいろなやり方がある模様。
鳥は汗腺を持たないので塩腺が必要との説明も時折みかけるが、おそらく関係ない。ヒトの例では Baker (2019) Physiology of sweat gland function: The roles of sweating and sweat composition in human health
汗の Na+ が腎臓のようにホルモンで調節されているわけでもなく電解質を濃縮して排泄する機能もない (塩腺のようには働かない。再吸収は行われる)。老廃物排泄を積極的に行っている証拠も乏しい。蒸発による体温調節と皮膚の状態を保つ機能が中心のよう。
タカ類の鼻汁は宮崎 (1987) の観察ではひなの日齢に応じた変化がみられており、塩分排泄以外の意義 (例えば細菌叢や免疫を与えるなど) もあるのかも知れない。
Taub and Dunson (1967) The Salt Gland in a Sea Snake (Laticauda)
によればカメやワニで眼窩のハーダー腺からの分泌物が塩腺機能を補強しているとある。鳥類のハーダー腺は免疫物質の分泌に重要な役割を果たしており (#インドガンの備考の *1
参照) 孵化後しばらく自身で抗体を十分作れない時期に抗体を与えている可能性が実際にありそうに思える。さらなる研究が望まれる。
タカ類の鼻汁とは直接の関係はないかも知れないが、鳥類、爬虫類、ヒトの涙の成分を比べた研究が出ている。
Oria et al. (2020) Comparison of Electrolyte Composition and Crystallization Patterns in Bird and Reptile Tears
結果的にはヒトの涙に似ているとのことで、ヒトの眼科学で用いられる方法と同じ方法で結晶化を分析したとのこと。鳥類の対象種はルリコンゴウインコ Ara ararauna、
アオボウシインコ Amazona aestiva、
メンフクロウ Tyto alba、
オオハシノスリ Rupornis magnirostris だが肉食の鳥でナトリウム濃度が高い結果は見られていない。この文献では涙腺からの分泌のみに言及しており、塩腺にかかわる言及はない。タカやフクロウの涙が塩っぽいわけではなさそうである。
'Crocodile tears' are surprisingly similar to our own (National Geographic 2020) の記事に涙の採取方法などの写真が出ている。カイマン亜科のワニのクチビロカイマンは何時間も瞬きをしないとのこと。
[クマタカ類の音声研究]
Huang et al. Preliminary Study on the Vocal Behavior of Mountain Hawk-eagle Nisaetus nipalensis in Taiwan
に台湾のクマタカの音声研究があり、9種類の声を記述している。著者原稿であろう。
Huang et al. (2021) Vocal behavior of the Mountain Hawk-Eagle Nisaetus nipalensis in Taiwan
が本論文であろう (オープンアクセス)。こちらでは8種類としており、音源も付いている。日本でもほぼ同じ音声が聞かれると思われるので比較に役立つだろう。
["Raptor Research and Management Techniques" (Raptor Research Foundation 2007; 邦訳され「猛禽類学」山崎亨監訳 文永堂出版 2010。どちらも現在入手可能だが現在の為替レートでも原著の方がかなり安価)
によれば台湾の猛禽類研究者は国際的な雑誌に論文を出版する傾向があると書かれているが、これもその例であろう。海外研究者にはありがたい]。
日本の文献は森本・飯田 (1992) クマタカの生態と保護について の文章とカタカナ記述と
「日本野鳥大鑑」のソノグラムを引用しており、定量的なデータは発表されていないとある。
若尾 (2023) の「クマタカ生態図鑑」にはソノグラムも示されているので海外研究者の目に触れれば新しい知見も得られるかも知れない。
カワリクマタカの音声研究が Mah et al. (2023)
Vocal Activity Patterns of the Changeable Hawk-Eagle (Nisaetus cirrhatus) in Peninsular Malaysia during Mid-Breeding Season
にあり、Huang et al. (2021) のクマタカ音声とかなりのものを対応させることができたとのこと。最も普通の音声は5日で 2738 回 (1発声を1声と数えているようである) 確認されたとのこと。
役割まではまだわからないが何事も記述しないことには始まらないということだろう。
[クマタカは愚鈍?]
野鳥方言名サシバ、ノスリ、クマタカ、ハチクマ
によれば、"馬糞鷹" の方言名があり「愚鈍で兎より外何も取れぬ」(クマタカ、秋田県) とのことで、ノスリが鷹狩りに使えないのと同様、他の獲物を取れないクマタカのことを蔑視していたとも考えられますとの記載がある。クマタカの性質を実はよく表しているように思います、と言うとクマタカファンの方からお叱りが来そうである (笑)...これはもちろん冗談だが。
[クマタカと鷹狩り]
(クマタカの話が中心になったためハヤブサの項目から移動した)
#ハヤブサ の備考 [亜種と系統] にある Weiss and Krone は鷹狩りの歴史についても詳しく説明しており、歴史や博物館の中のみにあるものでなく現役であって今日でも意味があることを述べている (アメリカでは鷹匠の技術が DDT で激減したハヤブサの個体数回復に役立ち、現在でも猛禽類保護のために技術が使われている)。
希少な文化であり保護や推進に努める必要がある。ユネスコの文化遺産にも登録されている。
各国の状況も述べられている。日本では歴史的な変遷や 19 世紀初めから近年まで行われたクマタカを使った鷹狩りを紹介しているが、Unfortunately, this bore the brunt of opposition by
birdwatcher fanatics and it has almost disappeared
と記されている。ほぼ直訳に近い言葉で書けば残念なことに狂信的なバードウオッチャーの反対の矛先が向けられ、ほぼ絶滅に追い込まれたと記している (#ハチクマの備考 [ハチクマの繁殖行動] に紹介のアニマの記事も参照)。
表向いて意見されたことはなかったかも知れないが、当時の日本の "自然保護" 運動は (断片的な情報からのみであろうが) 海外からはかなり異様に見えていたのかも知れない。
クマタカを使った鷹狩りについては「聞き語り 最後の鷹匠」(朝日新聞社秋田支局編; 伊藤政明文・鈴木洋一写真 無明舎出版, 1987) があり、他にもいくつも書籍などがあるがクマタカを使った伝統的鷹狩りの終焉時期の様子を知ることができる。
「環境庁」(p. 140) では1982年6月 (時期は確か、とある) に伝統を守るため幼鳥の捕獲許可願いを環境庁に陳情に行った様子が述べられている。結果的に「学術研究などの必要性」は認められなかった。
「記録映画」(p. 142) には文化庁から町への要請で猟を永久的に残しておきたいと訓練風景を撮影した様子も述べられている。テレビ局の人が「映画に残すぐらい大切なら、文化庁も...」と文化庁の人に述べていたことも記されている。「鷹匠を育てる会」の要望により、1957 年文化庁は「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選んでいたが、環境庁は学術研究と認めなかった。
同項目では医師が微生物研究のために捕獲許可をもらったことも記されている。
「自然」(p. 152) (スギが植えられ) 雑木がなくなると小動物もタカもみんないなくなった。スギ林はタカもくぐり抜けられない、など (今では周知のことになっているが) 鷹匠に限らずそうだろうが本質にずっと早くから気づかれていた。
この書籍では鷹狩り用のタカは絶食など無理をさせるので野外ほど長生きできない、多くのタカをいろいろな要因で死なせてしまったことも触れられている (事故のない名人もあったらしい)。絶食でタカを死なせてしまった仲間もいた。環境庁への陳情の前にタイから輸入 (1978 年) のクマタカも使っていたとのこと。
1980 年に CITES に加盟して以来、日本にクマタカの輸入が許可された例はないと当時記されている。
特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律 (1972) [日米渡り鳥保護条約 (1972) に基づいて作られた]。
武田宇市郎さんは 1986 年に廃業宣言を行った。タカは、可愛い鳥で利口です、とも述べられていた。
オオタカ、クマタカともに 1984 年特殊鳥類に指定とこの本にもコンサイス鳥名事典にもある、いずれの種も鷹狩り用などの密猟が絶えない、のような表現でコンサイス鳥名事典に記されている。専門の鳥類研究家にとってもおそらくこれが共通認識で、自分もおそらく刷り込まれていただろうと思う。
Birder でも「鷹匠になれますか」の Q&A (2002年7月号 p. 27) に対して読者から厳しい投書もあった [Birder (2002) 16(9): 78。編集部からの回答もあり。この指摘はクマタカを用いる伝統的鷹狩りに触れているものではない。詳しいニュアンスは原文をお読みいただきたい]。
「鷹匠ものがたり」(土田章彦文 野沢博美写真 無明舎出版 2006) は鷹匠文化を知らない世代に伝え残すために「聞き語り 最後の鷹匠」を引き継ぐ形で出版されている。環境庁への陳情時の写真なども掲載されている。
陳情では「許可されれば飼育の記録をすべて環境庁に報告したい、生態記録としても貴重なはずだ」と申し出たが学術研究とは認められなかった。
藤原審爾は「鷹匠を育てる会」顧問の作家。環境庁への陳情では「(前略) 現在の保護行政は捕るなというだけで、全国各地のブナ林の大規模伐採に目をつぶり、伝統習俗を守るための数羽のヒナの捕獲に目くじらをたてる。これでは木を見て森を見ずだ」と抗議したが容れなかったと記述されている。
藤原審爾は新聞雑誌などで環境庁と野鳥の会に対し、クマタカの幼鳥を捕獲することの理解を求める発表し、自身も小説「熊鷹・青空の美しき狩人 (あらすじへのリンク)」(藤原審爾 角川書店 1985。初出は「別冊文藝春秋」154-156 号 1982) を発表したとのこと (「鷹匠ものがたり」 pp. 70-71)。丸山健二「イヌワシ讃歌」(1977) は初出時に読んだのでもしかすると熊鷹の方も読んでいたかも知れない。
この本ではクマタカを特殊鳥類に指定する法改正は1976年となっている。
藤原審爾は 1984 年に急逝。「藤原審爾 "熊鷹" 文学碑」が 1986 年に建立され [野鳥シリーズ 76 クマタカ (水と森の郷あきた) に碑の写真あり]、その除幕式の日に武田宇市郎さんが廃業宣言を行ったとのこと。
1989 年には藤原審爾氏の亡くなった日を記念して「くまたか忌」の会を設けて動物作文を募集・表彰を始めたとのこと。この時点で東北の鷹匠は2名だけとなり1名は 2001 年廃業。
捕ることも輸入することも認められない中で人工繁殖の試みが行われていたが、この書籍の時点では成功例がなかったところで終わっている。人工繁殖を試みていた沓沢朝治氏は産卵したが孵化できなかった。映画製作の人が小屋に入ったため失敗したと語っていた (p. 55)。
飼育下繁殖は釧路市動物園で成功している。高橋 (2005) Birder 19(2): 27 によれば 2002, 2003年に成功とのこと。クマタカ (釧路市動物園) によれば 2008 年には人工ふ化・育すうを行ったとのこと (2011 年死亡とのこと)。
しかしながら「偶発的事例」に近く、安定した保全につなげるにはまだまだであろう。
鷹匠の郷 仙道
でも情報がまとめられている。出典、特に「遊鳳窟」の「最後のタカ匠についての雑記」はすでに読めなくなっているのでここで読めるうちにお読みいただければ。
唯一「アニマ」が鷹狩りをどう考えるかなどのアンケートを行っていたように記憶している。当時の社会情勢の下では野生動物を扱う雑誌が鷹狩りを肯定的に扱うことに厳しい視線があったのだろう。
それ以前の時代、季刊アニマ 2「鷲と鷹」(1975) が現役時代の伝統的鷹狩りを伝えている。こちらではクマタカは可愛がって大切に飼育すると野生のものより長生きするとある (p. 126)。
現在では大陸から隔離されて進化した日本の固有生態系や種を守ることは当たり前のごとく語られているが、厳しい自然の中で生まれた文化の保全までには考えが及ばなかったのだろうか。それとも「残すに値するものがない」考えはそのまま受け入れられて行ったのだろうか。
以上は 1980 年代の話。今では「鷹 (たか) を継ぐもの」(NHK 2023) のようなエピソードが放映され、書籍も刊行されるなどむしろ肯定的に扱われているように見える。かつてはどうだったのかなどは伝えられないのだろうか。
第 41 回日本野鳥の会東北ブロック協議会総会で「最後の鷹匠を訪ねて」との報告もあり、今では認識もまったく違っているということだろうか。
「野鳥」2013年5月号 pp. 7-15 に野沢氏による記事もある。「野鳥」のこの号の導入部には「クマタカが置かれている現状、そして最後の鷹匠の生きざまを垣間見ることで、環境保護の大切さを改めて考えていきたい」と結んでいる。
ここでまとめたクマタカの別項目に [飼育クマタカの栄養不良死事例] の獣医学論文がある。鷹匠の経験や技術と (獣) 医学知識がともにあれば海外のように希少猛禽類の保護や保護された野生個体の救命、また海外の Nisaetus 属への応用にも役立てることができるのではないだろうかとも感じる。
Neoaves などの鳥類進化などの新しい知見を知るほどに猛禽類の卓越した生理能力とその類まれなる進化を感じ取ることができる。猛禽類で得られた知見はニワトリのようなモデル動物とは違った面で生物学の理解や医学にも役立つのではないかと思う。
市田 (2006) Birder 20(8): 76-78 「環境保護 激動の 30 年」シリーズの一つで当事者による記録が読める。これはオオタカの特殊鳥類指定にかかわる記事で、指定してほしいと陳情した際の役人とのやりとりが述べられている (役人というものは...と一般化したくもなる)。この記事では1984年指定となっている。
この記事へのコメントは山岸哲氏によるもので、(当時の) レッドデータブックは「科学」ではない。
作成する際に、かなり乱暴に政治的圧力をかけられた場合があると聞く (明瞭に上記を指す記述となっている) と記し、ある意味両方向の立場からバランスのとれた記事になっていると言えるだろう。
山岸氏は「鳥学者」と「保護に携わる方々」の双方は...という表現も用いており、少なくとも当時は両者の間には見解の乖離があったことをうかがわせる。それほど遠い昔の話ではない。(少なくとも一部の) 鳥学者にとっては猛禽類問題にかかわりたくない雰囲気も感じられた時代のころ。
市田氏も、「日ごろ、私たちがやりとりする自然保護の議論にはどうも科学性が乏しいのでないかと反省もせざるを得ない」とも述べている。
要約でニュアンスを伝えるのは難しいので実際の記事に当たっていただければと思う。
伝統的鷹狩り文化に加えて、当時の自然保護運動がほとんど駆逐したものに飼い鳥文化もあるだろう。これについては #ベニマシコ備考 [おまけで鳥の芸や知能のこと] で触れておきたい。
山岸 (2006)「私たちの自然」2006年3月号 (No. 514) pp. 8-11 に「今後の猛禽類保護の方向性」(シリーズ「猛禽類との共生をめざして」- 自分には猛禽類とは "共生" するものかとひっかかるが、近頃の日本語ではこの用法が普通のようなので気になったことのみ触れておく - の第 11 回)
の記事がある。同時代と思って見ていただくと興味深い記事である
["Birds note: 野生の不思議を追いかけて" (山岸哲 信濃毎日新聞社 2012) pp. 158-165 に再録]。
5つの戯れ (ざれ) 用語として「猛禽テロ」「猛禽特需」「猛禽カリスマ」「猛禽御殿」「猛禽マフィア」を挙げて説明している。これらの語が今でも意味を持つのかどうかは知らないが、意味が想像しにくいものでは3つめは環境コンサルタント会社が高報酬で雇いあげる調査員のことを指すとのこと。
山岸氏はこれらの語の生まれた背景として、猛禽類はこれまで大学や研究機関の専門家によってあまり研究されてこなかったことにあると分析している。保護に活用できる信頼できる論文があまりにも少なすぎるとのこと。山岸氏はアカデミズムの人なので「アカデミズムの怠慢」を要因の一つに挙げている。
猛禽類の研究は科学論文に直結しにくいので敬遠されてきたとのこと。限られたデータで解析をしても大しておもしろい研究にならなかったとのこと。そのため論文作成を第一の目的としない猛禽愛好家がアカデミズムの外で研究を行ってきた部分が多い。理学の研究では研究の完成度のためにデータ収集を優先するので、愛好家からは嫌われる (「あの人は猛禽をいじめている」と記されている) 材料になる、など。
山岸氏は猛禽愛好家が行った研究がアカデミズムの怠慢を埋め合わせてきた点は評価しつつも、研究成果を科学論文にまとめることをあまり行わなかった。愛好家の長年の努力も論文の蓄積になっていないため共通の財産となっていない。猛禽類に関する知識にはある種の「神話」に近いものもあった。
当時は国交省、農水省、環境省、経済産業省などの研究所や関連財団などが環境コンサルタント会社と提携して猛禽調査に大規模に乗り出すようになり、潤沢な調査費から戯れ用語のような事態が発生している。
提言として大学や研究機関に属している専門家が猛禽研究にもっと積極的に参加すること。猛禽研究に携わっているすべての人たちがヘゲモニー (主導権) の奪い合いのようなことを止め、などと書かれている。
ヨーロッパのような長期の個体群研究がないので、特定の個体やつがいの保護問題に矮小化されてしまう。
地域個体群でもソース個体群なのかシンク個体群などかの問題も等閑視されてきた。
レッドリストについての批判もあり、いつまでも古臭い情報でランクを決めていると...とある。
オオタカやクマタカの個体数が以前に比べて桁違いに多いことは誰の目にも明らかだが (保護しなくてもよいという意味ではない)、サシバやハチクマといった里山の猛禽類が激減している、など書かれている。
本稿で紹介している海外の研究の蓄積を見ると山岸氏の指摘も納得できる部分もある。
市田氏の書かれていた 2006 年の Birder 20(8) のこの号はオオタカの特集で、オオタカだけを保護するのではなく生態系を保護するのが本来の姿であることが認識されて行ったころ。
同号他の記事で川上氏がオオタカのみを取り上げて指標とするのが適切でないことを取り上げており、動物園のオオタカの飼育個体数が大幅に増加した研究: Kawakami and Higuchi (2003)
Population Trend Estimation of Three Threatened Bird Species in Japanese Rural Forests: the Japanese Night Heron Gorsachius goisagi, Goshawk Accipiter gentilis and Grey-faced Buzzard Butastur indicus
を紹介している。サシバは減少している (#サシバの項目でも紹介)。
ただし、環境意識の向上による保護数増加、飼育技術の向上による寿命期化などのため、増加傾向が過評価されている可能性もあります ともある: 生態系保全は "バランス" の保全 (川上和 研究の "森" から 2004)。
"環境意識の向上" というのは、昔は保護したらそのまま飼っていたり知り合いのタカを飼う人に譲ったり剥製にしたり...していたこともあるかも知れないなあ、とふと感じた。特殊鳥類に指定されたらさすがに人目につくことは避けるだろうなとか。時期はよく合っているなあ...とか。
ちなみに 1975 年出版の季刊アニマ 2「鷲と鷹」に当時の日本の動物園のワシ・タカ案内が出ていて、いつの時期の数字かはわからないが数えてみるとオオタカ3、サシバ8 (福岡市動物園に4羽もいた)、クマタカ 15、ノスリ 15 となってオオタカが異様に少ない。
クマタカが多いのは動物園が目玉となる種類を欲しがった、イヌワシはさすがに無理だろうが、当時の法律の下ではどこかからこっそり手に入れたなどもありそう。クマタカ密猟者が動物園に提供していた聞き語りが井上他 Birder (2005) 19(2): 37 にある (四国のクマタカ、特に愛媛)。林野庁からクマタカ入手を頼まれたケースもあったらしい。
やはりオオタカは捕まえた人が動物園に持って行かなかったのかなあと思ってしまう。
この時期の目撃記録に基づく増加傾向については論文でも述べられているが、後述のような適応能力の高さから都市近郊に進出しつつある傾向が見え始めた時代だった可能性はあるだろうか。
Birder のオオタカ特集号は愛知万博 (2005) の時代の記事と考えると時代背景がわかりやすい。海上の森はメイン会場の候補地だったがオオタカの営巣が確認されたことなど、自然保護団体からの反対運動が起こり、主会場を移した経緯があったが、オオタカが営巣地を移してしまえば意味がなくなるなどの議論もあった。
山岸哲監修 近畿地区・鳥類レッドデータブック (京都大学学術出版会 2002) で「これでレッドデータは信頼できる <科学> となった」が本の帯の謳い文句となっている。
「科学」なのだからこの根拠は間違っているなど誰もが反証することができる (はず)。成果がいかなるものか、現実のシステムとして反証可能になっているのかなどは皆さんの判定にお任せしたい。
昔を振り返ってみると、トキやコウノトリのようにしてはいけない (あるいはアメリカのリョコウバト、タンチョウなどでもよいだろう) 考え方もあっただろう。猛禽類は食物網の頂点捕食者なので生物の教科書にも出ているように基盤が脆弱であるなどの理由も十分考えられる。しかしこの論理は本当に成り立つのだろうか?
猛禽類がトキやコウノトリのように絶滅しやすいのか、基盤が脆弱なのかは改めて科学的考察に値する対象であろうし、おそらく研究も行われているだろう。
過去の鳥類絶滅事例の多くが古い系統の鳥であることも注目に値する。現代の知見では従来の考えとは違って猛禽類は新しい系統でそれだけ高い能力を持ち、古い系統の鳥に比べて擾乱に対する環境適応性も高いと考える方がむしろ自然に思える (夜行性猛禽類はあまり知らないがどうだろうか)。
腫れ物に触るように猛禽類をとらえてきたのは実はあまり正しい理解ではなかったのではないか?
離島や亜種レベル、地域個体群はともかく、昼行性猛禽類の種レベルの人為的絶滅事例は実は非常に少ない。
モーリシャスチョウゲンボウ (#チョウゲンボウの備考 [離島のチョウゲンボウ類と超希少種の保全] 参照) は非常に際どいケースであったが、Bildstein (2017) "Raptors" によれば種レベルの人為的絶滅事例は過去 330 年 (ドードー絶滅推定時期以降) でグアダルーペカラカラ (#ハヤブサの備考参照) が唯一のものである。
これは害鳥とされ、警戒心もなかったため簡単に駆除や毒殺され、鳥類学者の標本採集が最後のとどめを刺したとのこと。
Bildstein (2017) によれば猛禽類は resilient (日本語でもレジリエントとそのまま使われるように訳が難しい。柔軟性がある、回復力があるなど) で過去これほどの迫害にも耐えることができた。
地域的に見ればイギリスのようにオジロワシを絶滅させた、ヨーロッパでヒゲワシやハゲワシを絶滅させたなどはあるが、猛禽類一般として見れば非常に柔軟で従来考えられていたほど脆弱ではない可能性がある。
Bildstein (2017) の言葉では "far more resilient than many conservationists have thought them to be" (保護論者が想定していたよりもずっとレジリエントである) となっている。
何千と撃たれたアメリカのイヌワシも、最も迫害を受けたと言われるオーストラリアのオナガイヌワシも絶滅することはなかった。それでも絶滅させるならば「よほど」の条件を課しているのだろう。
猛禽類が resilient とである実例として、Bildstein ではアラスカのハクトウワシ、殺虫剤時代のアメリカやヨーロッパのハヤブサが挙げられている。原因がわかっていずれ復旧できるならば、そして影響が大きすぎて全滅させることでもなければ、意図的・非意図的を問わず人間の擾乱に対応する能力を表していると言えるとのこと。
絶滅の不可逆性と現在の脅威を強調してもし過ぎることはないだろうが、猛禽類の resourceful nature を強調してもし過ぎることはないだろうと述べている。resourceful は訳が難しいが辞書によれば智謀のある、戦略縦横のなど困難を乗り切ることのできる性質など。
resource は日本語でも資源の意味が定着しているので「資源の豊富な」と訳しそうだが、resourceful の主要な意味は違うらしい。単語の英露辞書訳を見るとぴたりの適訳があるようで
(なぜそんなものを持っているのかと不思議がられそうだが Oxford の外国語 mini dictionary を買うと付いてきた。多分旅行者用。円高時代でセットで 1000 円程度と破格の値段で買えたもの。スラブ言語は我々の熟語のように語構成がわかりやすいので英語でわかりにくい言葉もスラブ言語で見ると納得できることもしばしばある)、
「見つけることに長けた」のような意味らしい。和訳では機転の利くなど。どちらにしても相当の褒め言葉である。
脳科学的にも裏付けられてきているが、「猛禽類は賢い」と言われていた方はこのような点に気づかれていたのだろうか。古い系統分類に馴染みすぎているとむしろ理解困難かも知れない。
猛禽類が都市環境を積極的に利用するようになっても説明困難な事象ではなく、驚くに値しないということだろう。対人為環境の戦略を変えただけで、それをもって個体数が増えた証拠とする根拠にするのは適切でないかも知れない。
都市適応した猛禽類をどう保全するのか? 生態系を保全する考えに立てば餌となるハトやカラスを減らさない、営巣に適する高層建築物を保全する? 保全の考え方の立脚点が問われそうな気がする。
Bildstein はその上で猛禽類保護の3要素を挙げている。
・過去の教訓に学ぶ
・猛禽類が必要とする生態的な要求を知る
・猛禽類の resilience を理解する
[Bildstein (2017) pp. 258-260]。
最後の項目は (本にはそこまで書いていないが) 個体数が増えた、あるいは新しい環境に適応した個体群が出てきたのは保護の効果が現れたのか、猛禽類自身の resilience の結果と区別することが難しいと読むこともできるだろう。保護の成果が現れたと思っていたら実はほとんど関係なかったこともあり得るだろう。
また数の変化と外部要因との相関を統計的に探す時にも誤った関係を導く原因にもなるだろう。
resilience がどのように働くかを理解しておく必要がある。そしてその傾向は猛禽類では顕著であると言えるのだろう。
Bildstein (2017) p. 238 では個体数と絶滅のおそれの関係について、個体数が少ないほど危険度が高いことをもちろん述べているが、渡りをする種は一般に個体数が多く、絶滅の危険性は低いと考えられるとある。ただし普通種では人の影響による危険のおそれはないことを意味するわけではない。
サシバ (こちらは繁殖地は日本周辺に限定されている)、ハチクマともに IUCN では LC (ほぼ懸念なし) 種となっているのも渡りをする種のリスクの相対的な低さが現れているかも知れない。
渡りをすることによる特有のリスクは考慮する必要はあり、特に繁殖地・越冬地いずれも固有種である場合は保全上の注意が必要である。
猛禽類の場合はこのように言えるようだがスズメ目でも同じかどうかはわからない。「夏鳥たちの歌は、今: 利尻島から西表島まで 102 人の緊急レポート」(遠藤公男編 三省堂 1993) のような本もあった。
この本で気になった事例を少し紹介しておく。pp. 103-104 で日光 (御厨) ではコサメビタキの繁殖は1971年が最後となった。p. 50 仙台市野鳥園ではセンダイムシクイが極端に減って 1992 年には聞かれなかった。これらの種は今や (少なくとも自分の周辺では) 最も目立つ夏鳥になっている (コサメビタキのさえずりが集中的に聞かれる期間は短めなので知らないと気づきにくいかも知れない)。
p. 97 (笹川) 「東京の空から消えたトビとミサゴ」で、ミサゴは特殊鳥類 II 類に登録すべき種類と思うとある。ミサゴの復活は皆さんもご存じの通り。
かつて伝えられたようなコーラスはもう聞けないかも知れないが、分布を広げている夏鳥の小鳥も多いように思う。これも人為的擾乱が一時的に急速に進んだ後の系統依存の resilience (越冬地の天然林の面積が回復したとも思えないので) を反映している可能性を考えると理解が深まるかも知れない。
いや実は主な原因は越冬地ではなくて繁殖地の方にあったのだ、などもあり得るかも知れない。
チゴモズはどうなのかと言われるかも知れないが、世界的なモズ類の退潮傾向 (草原の減少?) に加えて大陸を中心とする種で繁殖分布の限界に近い日本ならではの現象かも知れない。シマアオジも南限であるなど似ている。
ミゾゴイは Telluraves よりは系統が古いので猛禽類より危険性が高い可能性があるなど。
Bildstein (2017) の猛禽類に戻ると p. 239 にスカベンジャーの方が捕食性の高い種より絶滅の危険性は高い。これはハゲワシの事例などを想定したものと推定できる。
もちろん種差もあるだろうが、生息地破壊、組織的な迫害や密猟などが行われない限り猛禽類はそこまで脆弱でない感じもする (それでは開発業者の言い分と同じと言われそうだが)。
ただし人間活動が猛禽類の活動に一定の制約を課していることは確かで、コロナで人の活動が減少すると猛禽類が増えすぎて他の希少種を食べてしまうなどの話は世界で聞かれる。
日本のクマタカやイヌワシの繁殖成功率が低下しているならば、「よほど」の事情があるに違いない。もともと日本はこれらの種にとって生存限界に近く (ほんとう?)、限界の生存条件を奪ってしまっているのか。森林形態については東北のクマタカ鷹匠の指摘の方が正しいのだろうか。自然林に戻す実験は簡単には行えないので因果関係は不明のままに終わるだろうか。
田悟他 (2014) クマタカの繁殖成功率とそれに係わる環境要因 は科学的要因分析を試みているが、
平均的な繁殖成功率 (33.2%) が得られたことが中心で少なくとも 1994-2008 年の経年変化はないらしい。変動要因はあまりはっきりしない。森林の管理形態と関係があるかなども情報不足で、この繁殖成功率が低いのかどうかもよくわからない。前年の繁殖の成功と相関が強いのは生態特性や生理学的要因で理解しやすいが、他の要因とはこれだけの例数をもっても相関がそれほど明瞭でない。
医学研究すなわち疫学でも同じようなもの。因果関係が統計的に実証されるのはよほど明らかな事例である。タバコが健康に有害であることは証明されていないと長年主張されていた古い時代の話と同じ。有害物質が含まれていることは明らかでも因果関係の証明は難しい。
因果関係が予め予想されるものを調べてこの状況なので、何と因果関係があるかわからない場合には実際上調べようがないだろう。このぐらいの自由度ならば因子を増やせば何個かは統計的に有意な関係が見つかっても不思議でない。
上記論文を見る上では AIC (赤池情報量規準) が最小になるモデルがおおむねなるべく少数の因子で結果を説明するものになるが、前年の繁殖成功・失敗は選択された多くのモデルに含まれているので信頼できる因子はこれだけ、と言っても過言でない気がする。
このデータでは繁殖成功率の特に低かった2007年の場合は翌年にはそれを補うように回復しており、猛禽類の resilient な性質も全体的要因を隠す方向に働いているかも知れない (もっとも同種の次の研究ではこの変化は現れていない)。
このデータでは特に高かった 2008 年を除くとあるいは有意な繁殖成功率減少傾向が出るかも知れない。
調査期間の前半には繁殖成功率が 20% を下回ることは一度もなかったのに、後半には2回もあった言えば異常事態が起きているようにも見える。受ける印象は統計の数字の提示方法次第のようにも思える。
いずれも科学的に意味のある数字だが「科学的根拠」と言っても難しいことがわかる。
この論文と出所の同じデータを用いた研究に山崎「日本のタカ学 生態と保全」(2013) 第 15 章があり、用いるデータの選択が微妙に違うようだが 1996-2012 年の結果が出ている。田悟他 (2014) にある 2007 年の顕著な低下や翌年の回復はこのデータは見えず、2005 年に下がっていることは共通している (出所が似ているので独立した検証というわけではない)。
長期的繁殖成功率減少傾向は見られておらず、平均の繁殖成功率は 29% となっている。2年に1回繁殖し、100% 成功するならば繁殖成功率は 50% で、(阻害要因のない) 理想的な場合はその数字に近づくと推定できる。滋賀県鈴鹿山脈では 47% の数字も得られているとのこと。
横山 (2005) Birder 19(2): 30-31 では熊本の川辺川流域では 44% とのこと。近年激しさを増す梅雨時期の大雨と繁殖失敗が重なっているケースが紹介されている。同様の話は Bildstein (2017) "Raptors" にもあって、猛禽類の繁殖成功率を下げる要因として遅すぎる春の雪、雨の多い春を挙げている。ただし晴れすぎると日射からひなを守る問題が出てくる (p. 52)。
田悟他 (2014) の方にしか現れていないが、この研究でクマタカの繁殖成功率が非常に低かった 2007 年は異常気象で有名で (このころから常態化した? 2010 年にも高温記録更新などがあって印象が薄くなってしまっているが)、4月は大暖冬を覆す顕著な低温になったとのこと (wikipedia 日本語版より)。
井上 (「日本のタカ学 生態と保全」第8章、p. 162) は数々の阻害要因のある中で、あれだけ体の大きなクマタカが日本の多様な環境に幅広く生息できるということは、環境がクマタカに適しているというよりもクマタカが環境にうまく適応して生息していると考える方が納得できる、と記している。
上記の resilience の考え方にも合っていると思われ、納得できる見解に思える。自分の (ごく限られたものだが) クマタカとの出会いの印象とも合っている感じがする。しかるべき所ならばクマタカは (出会う頻度は低いが) 普通に生息しているのではないだろうか。
個体数の長期的減少が顕著に記録されているならばともかく、これらの資料を見る限りではあまり心配はいらないような印象を受ける。
比較のために先行研究の飯田他 (2007) クマタカ Spizaetus nipalensis の繁殖成功率の低下と行動圏内の森林構造の変化との関係
も挙げておく。飯田 (2014) Birder 28(1): 20-23 にもクマタカの繁殖成功率の低下の記事がある。
それぞれどうだろうか。
猛禽類研究といえば「保護のため」と常套句のように唱えるだけでなく、猛禽類そのものの魅力を味わったり調べたりする方がずっと楽しいような気がする。
葉山・今井 (2016) Birder 29(12): 22-23 にブナの実がクマタカの命運を握っている? 記事があり、山形県最上郡の 1990-2008 年ののべ 414 事例から傾向を調べたもの。
論文は葉山他 (2014) 変動するブナの結実状況の下でクマタカの繁殖に影響する要因
で読むことができる。Birder の記事からはわかりにくいが、繁殖結果に最も関連していた要因は前年の繁殖結果であったとのこと。ブナの結実状況が悪い場合には繁殖結果に対し天然林面積が負に,人工林面積が正に作用する傾向を示した (これは Birder 記事でも紹介されている)。
この地域は人工林の割合が低いので人工林面積の多い地域とは要因が異なる可能性もある。どこまで物が言えるかは原論文を見て判断いただくのがよいだろう。
この研究でも人工林の割合が低いが繁殖成功率そのものはそれほど高いわけではなく、2005, 2007 年には 10% を割っている。この研究では示されていないが経年変化を数字通り解釈すると有意な長期的減少と判断できるかも知れない。何に注目して結果を述べるか次第なのだろうか。
古い記事で浦本・内田 (1986)「動物の世界」2版 10 (日本メール・オーダー) pp. 1374-1375 に 1936 年の狩猟統計でニワトリを襲う害鳥として、あるいは尾羽を矢羽に使うためにこの年だけで 1467 羽のクマタカが捕獲されたとのこと。桁が大きいのに驚いた。あくまで自分の想像だが、この数字にはクマタカという名前のハチクマもかなり含まれていたのではないだろうか。害鳥として駆除されていたならばとんだとばっちりである。
クマタカも少なくなかったのだろうと思う (環境省のページでは現在は 1800 羽の数字が出ているが、もっと多いと思っている人も多いのでは)。
[クマタカの羽を飾りに使う民族]
台湾のパイワン族。Huang et al. (2021)
A Sacred Bird at the Crossroads of Destiny: Ethno-Ornithology of the Mountain Hawk-Eagle (Qadis) for the Paiwan People in Taiwan
という論文がある。Qadis は現地名のクマタカ。
現地住民のクマタカの習性についての記述 (伝承?) があり、クマタカは羽を巣に差しておいて捕食者からひなを守るとのこと。しかしこの言い伝えの科学的検証はまだ行われていない。
台湾ではかつては森林伐採がこの種に最も影響を与えていたが規制と森林回復が行われ、現在では狩猟圧の方が重要になっている。2000-2005 年の間に 40 羽が狩られたとのこと。
現地住民のクマタカの識別点にふしょの羽毛があるとのことであるが、写真を見せてのインタビューでは(オオ)カンムリワシやハチクマの淡色型をクマタカと見誤っていたとのこと。
西洋の研究者は台湾のクマタカは冠羽の短いもののみであると考えていたが、現地住民の長老は冠羽の長いものがいる、少なくとも 1950 年以前にはいたと証言した。これは後日の研究で確認された (long-crested morph でかなり珍しいとのこと)。
夜行性のモモンガも捉えるとのことだが西洋の研究者の記録にはない。
[クマタカ類の隔年繁殖の理由?]
「動物の世界」2版 9 (日本メール・オーダー 1986) pp. 1180-1181 のカンムリクマタカの項目 (浦本・安部) に興味深い記述があった。サル類やレイヨウを襲うカンムリクマタカやオウギワシが2年に1度しか繁殖しないのはこれらの獲物の基本増殖率が低く、短期間で大量に捕食すると食物不足が起きる恐れがあるが、基本増殖率の大きいノウサギなどを獲物とするイヌワシでは獲物の数は急速に回復するため毎年の繁殖が可能である説明がある。
これは r-K 選択説 (MacArthur and Wilson 1967) で獲物がどちらの傾向があるか次第と言えるのだろう (#カワウ備考の [ウの増加と生態系への影響] 参照)。
原著にあたる "Purnell's Encyclopedia of Animal Life" の出版年は 1968 年なので、概念的には同様のものですでに知られていた、あるいは萌芽期のアイデアはあったが、著者は一般向けにわかりやすく説明するためにこの用語を使っていたなかったかも知れない。r-K 選択説は当時歴史を変えるほどの画期的アイデアであったことは生態学の歴史に書かれている通りで、おそらくこの説明を意識して書かれたのではないかと想像する。
同書フラミンゴの項目 = 「動物の世界」2版 9 (日本メール・オーダー 1986) pp. 2270-2276 (浦本) にも同様のことが述べられており、生息地の要求が特殊なため繁殖しない年もある一方、条件が良ければ2回繁殖することもある。個体が長命であることで補われている趣旨の解説があった。当時画期的な解釈として受け入れられていたらしいことが想像できる。
翻訳紹介されたのは 1973 年だったが、日本の生態学の中ではどのように位置づけられていたのだろうか。
日本のクマタカには必ずしも当てはまらないかも知れないし、またこの考え方が現在でも受け入れられているのかどうかは不明だが、クマタカ類の系統で隔年繁殖種が存在し、イヌワシ類が大型でも比較的毎年繁殖する一つの要因になるのかも知れない。日本のクマタカ・イヌワシを比較する以外の観点にも目を向けていただきたい。
イヌワシ類の方が齧歯類などの突発的な獲物の増加に対応できる、よりノスリ的な生活史戦略を持っているのかも知れない。因果関係はどちらが先かわからないがイヌワシ類の方がより北方型で乾燥環境を得意とし、大型種の割には子供の自立を早く済ませて渡りも行う北方個体群もあることにも整合性があるのだろう。
イヌワシは早い話が大きな (他系統では例えばノスリ類のような) 齧歯類向きの猛禽類のようなものだと思えばよい (?)。
オーストラリアでオナガイヌワシの方がよりクマタカ類に近いアカヒメクマタカ [高野 (1973) ではヒメアカクマタカ] より広く分布しているのも、この大陸特有の予測困難な気象条件変動 (獲物は r 戦略のものが中心となる) に適応しやすいためかも知れない。
海外のイヌワシもオナガイヌワシも、過去に大規模な迫害を受けて膨大な数が殺されたが個体数を回復している点もこれらの生活史戦略の現れかも知れない。アルプスのイヌワシが飽和状態になっているのも保護策が奏効すれば個体数を短期間に増やすことができるためだろう。
このような視点から見るとクマタカの隔年繁殖が特殊なのではなく、むしろイヌワシの方が大型種の割には繁殖頻度が高すぎると言えるのかも知れない。突発的な獲物の増加があっても対応可能にする戦略だろう。
条件次第で個々の繁殖が失敗することはある程度やむを得ないのは織り込み済みだろう。
またこのように考えれば、イヌワシ類のいくつかの種が、ほとんど見込みのない1卵を余分に産む理由もなんと統一的に説明できてしまう。無条件の兄弟殺しの起きるタカ類はいずれもイヌワシ系統である。
さてイヌワシ類とノスリ類の嗜好が似ているならば、より古い系統であるイヌワシ類 (イヌワシ亜科 Aquilinae) の方が先に占拠してしまっていても不思議でない。そのようになっていないのは、どちらも乾燥化で森林が開けた時期に適応放散を開始したためだろう。その時期にはどちらの系統もすでに存在して先に誕生した系統である優位さはすでになくなっていたと考えられる。地域によって順序関係が異なるので少し細かく見ておこう。
Catanach et al. (2024) の分子系統樹ではイヌワシ亜科 Aquilinae は 1600 万年前ごろに誕生、この当時はまだ森林性のものが中心で Nisaetus 属や Spizaetus 属を生み出していた。Aquila や類縁属が広がったのは 1000 万年前ごろ。
イヌワシ亜科の方が先に誕生していながら Nisaetus 属や Spizaetus 属を生み出すのが遅かったのは既存系統に対して優位に立てる一線を超えるのが難しく、いろいろな試行錯誤 (ゲノムレベルの話) に時間がかかったのだろう。これらの大型ワシ類を生み出すことに適切な時期に成功していなければ現代のクマタカやイヌワシはなかったかも知れない。
他にも系統はあったのだろうが一線を超えることができず撤退 (消滅) したものもあるのだろう。
現代の意味のハイタカ亜科 Accipitrinae に対応する系統も結構古く (2700 万年前ごろ) 誕生しているが、既存系統に対して優位に立つのがなかなか難しかったために小鳥食に活路を開いたと考えることもできるだろう。
この時期にイヌワシ亜科 (クマタカ類) の森林への適応放散を妨げるほどの既存系統と言えば現生系統ではハチクマ亜科 Perninae かチュウヒワシ亜科 Circaetinae となるだろう (後者にフィリピンワシが含まれる)。
現在の名前を使って表記すれば、クマタカ類やハイタカ類とハチクマ類、チュウヒワシ類は長らくライバル状態であったのだろう。
ノスリ亜科 Buteoninae まで含めるとトビや海ワシ類も含まれるので、ノスリ族 Buteonini に範囲を限定すればサシバの Butastur 属が最も古くて 1900 万年前ごろ。もっとノスリらしくなる Buteogallus 属だと 1200 万年前ごろ (ただし南米)。Buteo 属の誕生が 500 万年前ごろ。
北アメリカに到達した Aquila や類縁属はイヌワシのみで、そもそも南米に到達していなかったかも知れない。そこではノスリ類が大規模に適応放散して北へ進み、さらにはユーラシアからアフリカに分布したと考えられる。
ユーラシアからアフリカで先に分布していた Aquila や類縁属の方が制覇してしまわなかったのは、これらが系統的に少し古いため生態的あるいは認知能力などに制約があり、新しく到達したノスリ類に対してそれほど有利な立場に立てなかったのかも。おかげでイヌワシ類は大型種のみが残っていると考えるとわかりやすいかも。
このような視点で見ると、イヌワシ類がタカ類の進化の頂点であるとの従来的な見方はおそらくふさわしくないのだろう。「Amadon の言うところのタカ科進化の頂点であることを疑うものはほとんどいないだろう」(ワトソン「イヌワシの生態と保全」(2006) p. 32) をここでは敢えて疑ってみよう。昔はカラス類が鳥類の進化の頂点とされていたが、分子系統解析の結果あまりそれらしくないことが従来にも増して明らかになって、現代の図鑑では最後に並ばないのと同様である。
タカ類でも事情は同じで、最も新しい系統はノスリ類となって世界分布を見ても大変優勢である。イヌワシ類は比較的古い系統で、あまり芸がない (?) ため大型種しか生き残れなかったと考えることも可能であろう。イヌワシをタカ類の進化の頂点、あるいは代表種だと考えて知的能力などを評価するとタカ類全体の多様性の理解を誤る可能性がある。
ここで表した言葉を組み合わせれば「大きくて強いがそれ以上の芸がない」種類と言えないこともない。あまり融通がきかない感じもあり、この点は同亜科のクマタカも同様かも知れない。
イヌワシに対するこのような定型的な評価が生まれたのは、大きく強いものへの憧れ (これは恐竜趣味にもつながるかも) があるだろうが、イヌワシを褒め称えて紹介した Seton Gordon の影響も大きいのではないかと想像する。Seton Gordon の活躍した時代は英国のオジロワシは絶滅していて、大きなワシと言えばイヌワシしかいなかったわけだ。
たまたま英国では国内唯一の大型ワシとして称賛の限りを尽くされ ("英国の誇り") 世界に紹介された結果となるだろう。北米では別種のワシが存在したため入植者にとってはイヌワシはあまり称賛の対象とならず、大規模な迫害を受けることにもなったのだろう (そのハクトウワシが称賛に値するかと言えば別件で堕落したワシ・タカの系統とまで書いているわけだが...)。
英語では Golden Eagle で、学名もそれに対応するものが付けられた点も過剰評価につながっている気がする。イヌワシの英名・学名解説ですでに述べた通り、これは単に他のワシより黄色味が目立つことが由来であって「最上のワシ」と解釈するのは過剰とも言える。最上だと思っていると意外に期待通りでないところを見つけてむしろ落差が大きい。
「鳥の王」(Seton Gordon がまさしくこの表現を使っている) と言われながら全然だめではないかとか、鳥類全般の評価を下げる遠因にもなっている気がする。
上記の繁殖戦略を考慮するとイヌワシ類は体サイズの割にはそれほど長命でないかも知れない (これも Seton Gordon の信じていたことと反する)。イヌワシ類をタカの類代表と考え、海鳥の寿命と比較考察するのは必ずしも適切ではないかも知れない。
生態学的に見ればすべての点で最上などあり得ないことはすぐ理解できるが、植え付けられた先入観の危なさをここでも強調しておきたい。人間は万物の霊長だからすべての点で優れているはず、と論じるのとあまり違わない。
「金のワシ」よりは「イヌワシ」の名前の方がふさわしい感じがする。
複数回登場するので、乾燥化に伴って (齧歯類や有蹄類の繁栄など) 繁栄を遂げたタカ類系統を Catanach et al. (2024) の系統樹を見ながら挙げておくと、カタグロトビ類 (Elanus 属)、ハゲワシ亜科 Aegypiinae 特に Gyps 属、
イヌワシ類 特に Aquila および近縁属、チュウヒ類、ノスリ類 特に Buteo 属および近縁属となる (抜けがあれば失礼)。
[クマタカの顔はなぜ黒い?]
クマタカは顔黒と言われるが、なぜ黒いのか少し考えてみた。これはおそらく目を隠すためではないだろうか。#ハシブトガラの備考参照。
目が橙色なのに顔を黒くすれば目立つのではないかと思えそうだが、これはおそらく我々の視覚で物事を考えがちなためだろう。クマタカの獲物に多い哺乳類は色覚も視力もよくなく、白っぽい下面と黒い顔の組み合わせはよい隠蔽色になっているのではないだろうか。
#ハチクマ備考の [目を隠す模様は何のため?] でさらに広く扱ってみた。
[クマタカもヘビにやられる?]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 76-VII に読者投稿で「ヘビにやられたクマタカ」(林英一) の記事があった。1964.8 に愛媛県西条石鎚山国有林での測量の際にもがき苦しんでいる鳥が見つかり、後にクマタカと同定されたとのこと。70 cm ぐらいのアオダイショウが首に三重巻きぐらいとなって締め付けていたとのこと。鳥は間もなく動かなくなったがヘビを叩いて追い払ったとのこと。死んだクマタカが翼を広げた写真が紹介されていた。
この程度のアオダイショウであれば、ハチクマが同じぐらいのものを運んでいるのを撮影したことがあるので (2つ折りになっていて鳥の全長と同じぐらい、ヘビの全長は 80 cm ぐらいか。頭は食いちぎってあった)、ヘビの捕食能力ではクマタカもハチクマもさほど違いがないのではと感じた。
[フィリピンクマタカの生態研究]
Gan et al. (2022)
First description of the breeding biology of the North Philippine Hawk-Eagle (Nisaetus philippensis)
マニラ市の郊外で営巣したフィリピンクマタカを主に遠隔カメラで観察。巣での行動の初観察報告。
2019 年に発見され 2020 年にも繁殖成功。クラッチサイズは1。両親が子育てにかかわり、オスが主に餌運び、メスが主に巣を守る。オスも少しは抱卵する。食物は地上性の鳥と哺乳類が多かった。コウモリも結構捕えている。
ひなは生後 78 日で巣立ったとのこと。2020 年の事例では 5/18 に巣立ち、親から食物をもらうのが最後の観察されたのが 6/19 だったとのこと。
人為環境に近いところで営巣する理由は食物が豊富である可能性が挙げられる。ジャワクマタカでも同様の事例がある。
[保護され予後不良だったクマタカの事例]
Ushine et al. (2023) Clinical examination and necropsy findings of a mountain hawk-eagle (Nisaetus nipalensis) that died during rehabilitation
2021年4月25日に滋賀県長浜市でわなの網にからまった状態のクマタカが保護された。4日間わなにかかった状態であった。解き放たれる時に翼に開放骨折が認められて獣医に治療された。
救出時の状態は悪く4日間自力で立てなかった。保護期間中に翼を壁に打ち付ける行為があり、風切羽が次第に脱落、85 日目に脚に骨折が見つかりピンで固定された。その後は夜間はハンモックを使っていたが 90 日めにピンが正しくささっていないことが判明して再手術をしたが 92 日目に死亡。
手術後の後遺症は観察されなかったが死の1週間前から食欲がなかった。
剖検の結果肝臓への脂肪蓄積と肥大、細胞変性、骨格筋の変性・壊死が見られた。
肝臓の脂肪変性による肝不全が死因の可能性がある。"capture myopathy" と呼ばれる過度の運動やもがく行動、ストレスなどによる筋肉疾患 (広義の概念であるが和訳はなくミオパチー。"capture myopathy" にはあまり適当な日本語がないようであるが、野生動物を過剰に追跡して捕獲、保定した場合によく起きるためにこのような名前になっているのだろう) を複数回経験していると思われる。
筋肉壊死によるミオグロビン放出に伴う腎不全は起きていなかったようである。
翼の筋肉の萎縮も風切羽の脱落に関係している可能性がある。
日本で保護される野生動物の9割が鳥類であるが希少種のリハビリの情報は少なく、また詳細があまり明らかにされないことも多く、症例報告で知見を増やしてゆくことも重要であるとのこと。
"capture myopathy" 関連では次のような論文もある。Nielsen et al. (2019) Can acute stress be fatal? A systematic cross-disciplinary review
さまざまな病態があるがこのような状態の共通背景を医学、獣医学の枠を越えて探るもの。
この文献の "Capture myopathy" のセクションによると恐怖、交感神経の活性化、副腎ホルモンの分泌、筋肉の活動が病態の背後にあるとされる。(哺乳類の話になるが) 捕食者よりも被食者の方によく起きる病態でこの反応そのものは捕食者がある場合に捕食から逃れるのに有益であるが、捕食者のいない環境ではストレス死の可能性を高めるので進化的に有利な場合も不利な場合もあると議論がある。
Shipley (2018) Capture Myopathy in Avian Species: A Review
によれば哺乳類に比べて腎障害は出にくいとのこと。次の文献も合わせてまとめると筋肉中の酸素不足下の運動で嫌気的代謝が高まって代謝性アシドーシス (乳酸レベルが高まる) を起こす。この結果筋肉が損傷する。exertional rhabdomyolysis (運動誘発性横紋筋融解症) の名称もある。
筋肉の損傷を示すマーカーが上昇する。治療は困難で多くの場合不成功に終わる。これまで試された治療方法が挙げられているが予防の方がより重要である。
Businga et al. (2007) Successful Treatment of Capture Myopathy in Three Wild Greater Sandhill Cranes (Grus canadensis tabida)
にカナダヅルでの治療成功例がある (そこまで重篤ではなかった模様)。この例では輸液、副腎皮質ステロイド、ビタミン E とセレン (抗酸化物質) を与えているが発症後に抗酸化物質が有効であった証拠はあまりない。
Hurtado et al. (2021)
Successful Treatment of Capture Myopathy and Satellite Transmitter Injury in an Atlantic Yellow-nosed Albatross (Thalassarche chlororhynchos)
に捕獲ストレスと装着した発信機に対して起きた ニシキバナアホウドリ の capture myopathy の報告がある。ハーネス接触部位に潰瘍が生じたとのこと。この場合は発信機を外して水分補給と抗酸化物質やビタミンを与えて安静にすることで回復したようである。アホウドリ類にバックパック型の発信機が適さないことも議論されている。
他にも猛禽類の報告もいくつもあって (転帰までは調べなかったが) 捕食者でも起きる反応のようである。鳥類と哺乳類で捕食者での反応に違いがあるならば反応の適応的意義の解釈にも役立つかも知れない。
このような記録を見るとどうしても ハチクマ (zukan.com) の事例との違いが気になってしまう。
別写真、
保護から放鳥まで
保護時の状態はおそらくだいぶ違うとはいえ (骨折はなかったようだが自力では立てなかったそうである)、こちらは放鳥までクマタカと考えられて飼養されたもの。
全く大人しく無抵抗でしたと書かれている。クマタカのつもりで餌を与えていたが食いつきは悪くなかったとのことで上記論文のクマタカのような強制給餌まで必要なかったらしい。
保護中もおそらくあまり暴れなくて順調に回復したのだろう。
このような反応の差は保護時の状態にも関係するかも知れないが、種の特性の違いも表している印象を受ける (ハチクマがあまり抵抗しないことは #ハチクマの備考紹介の [ハチクマのお客さんになって] や [飼育下の行動: ドバイで保護されたハチクマ] にもある)。
何かの参考になれば幸いである。
[飼育クマタカの栄養不良死事例]
Toyoda et al. (2004) Nutritional secondary hyperparathyroidism and osteodystrophia fibrosa in a Hodgson's hawk-eagle (Spizaetus nipalensis)
この時代に鷹狩り用にクマタカが飼育できるのかと驚いたのだが、輸入個体の場合は大丈夫なのだろうか。
秋田で鷹匠が高齢化で伝統的鷹狩りを行うことができなくなり、内蔵を取り除いた肉だけのみを与えていて弱ってしまい、多発骨折にて来院。
本来望ましい Ca:P 比に比べて餌のリンの量が異常に多く、カルシウム不足で副甲状腺が異常に発達して甲状腺よりも肥大していた。副甲状腺機能亢進症の結果骨からカルシウムが失われて線維性骨異栄養症 osteodystrophia fibrosa (fibrous osteodystrophy) を起こして悲惨な転帰となった。
△ フクロウ目 STRIGIFORNES メンフクロウ科 TYTONIDAE ▽
-
ヒガシメンフクロウ (第8版で検討種)
- 学名:Tyto longimembris (テュト ロンギメムブリス) 脚の長いメンフクロウ
- 属名:tyto (外) メンフクロウ (擬声語) Gk
- 種小名:longimembris (adj) 脚の長い (longus (adj) 長い membrum 脚 -is (語尾) 〜の)
- 英名:Eastern Grass Owl
- 備考:
tyto は由来となるギリシャ語 tuto は末尾が長母音文字でアクセントがあるが標準的発音では伸ばさない。ラテン語ではアクセントは冒頭になる "テュト"、"テュトー" のいずれでもよいと考えられる。
ラテン語に tutubo の単語がありフクロウのように鳴く意味の動詞。この場合は動詞語尾で伸ばしている。tutu- 部分は短母音。
longimembris はlongus, membrum ともに短母音のみだが変化形では -bris 部分は伸ばすかも知れない。同等の構成の brevitarsis (brevis + tarsus + is) のような合成語では伸ばしていないので短母音を採用した。
-mem- がアクセント音節と考えられる (ロンギメムブリス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。単形種。中国やインドの一部から東南アジア、オーストラリアの一部に生息する。
[フクロウ類の系統分類]
タカ類のような詳しい分子系統樹はまだないが、山崎他 (2017)「フクロウ目の新しい種和名」が発表されて世界全種のフクロウ類の和名が公表されている状態になっているので、確認も兼ねて Boyd の分類と比較してみる。
山崎他 (2017) の分類は IOC v7.2 (2017) に依っている。和名の後に * のあるものが山崎他 (2017) による新称または改称である (タカ類での記号と異なるので注意)。
学名の後の * は 山崎他 (2017) と属が異なることを示す。
和名の後の ( ) 内の名称は山崎他 (2017) に記載されている別名。
英名は Boyd のものを主に用いているが若干の統一や綴りの変更 (gray → grey) がある。
大文字の名詞の間にハイフンを用いるかどうかは好み次第の問題だが、IOC では使わない方向になっている。Hawk Owl のような場合はハイフンを付けた方が意図がわかりやすいので残してある。
ハイフンの前が形容詞や一般名詞の場合には原則外してある。
複合形容詞となっているもの (Ashy-faced など) のハイフンは外せないので注意。これらはハイフンの後が小文字になっていることで区別できる。
山崎他 (2017) の段階の分類よりは系統関係がわかりやすいと思う。
ただし Boyd の系統順は IOC 14.1 とも違い、分岐の取り扱い方や考え方の違いの程度と考えていただいてよい。
属名や亜科名などの和名がほぼ自動的にわかる、あるいはすでに付けられているものは与えてある。
山崎他 (2017) にないが検索すると和名の存在するものは ( ) を付けて単独で与えてある。
メンフクロウ科 Tytonidae (Barn Owls)
ニセメンフクロウ属 Phodilus
ニセメンフクロウ Phodilus badius Oriental Bay Owl
セイロンニセメンフクロウ* Phodilus assimilis Sri Lanka Bay Owl
メンフクロウ属 Tyto
コンゴニセメンフクロウ Tyto prigoginei * Congo Bay Owl (Phodilus 属から移動)
マダガスカルメンフクロウ Tyto soumagnei Red Owl
メンフクロウ Tyto alba Western Barn Owl
アメリカメンフクロウ* Tyto furcata American Barn Owl
ヒスパニョラメンフクロウ* Tyto glaucops Ashy-faced Owl
アンダマンメンフクロウ* Tyto deroepstorffi Andaman Masked Owl
セレベスメンフクロウ Tyto rosenbergii Sulawesi Masked Owl
オーストラリアメンフクロウ* Tyto javanica Eastern Barn Owl
スラメンフクロウ Tyto nigrobrunnea Taliabu Masked Owl
ミナハサメンフクロウ Tyto inexspectata Minahassa Masked Owl
ミナミメンフクロウ Tyto capensis African Grass Owl
ヒガシメンフクロウ Tyto longimembris Eastern Grass Owl
ススイロメンフクロウ Tyto tenebricosa (Greater) Sooty Owl
ヒメススイロメンフクロウ Tyto multipunctata Lesser Sooty Owl (Boyd では上種の亜種扱い)
ニューブリテンメンフクロウ Tyto aurantia Golden Masked Owl
マヌスメンフクロウ* Tyto manusi Manus Masked Owl
モルッカメンフクロウ* Tyto sororcula Moluccan Masked Owl
オオメンフクロウ Tyto novaehollandiae Australian Masked Owl
フクロウ科 Strigidae
アオバズク亜科 Ninoxinae (Hawk-owls)
パプアオナガフクロウ属 Uroglaux
パプアオナガフクロウ Uroglaux dimorpha Papuan Hawk-Owl
ワライフクロウ属 Sceloglaux
ワライフクロウ Sceloglaux albifacies Laughing Owl
アオバズク属 Ninox
オニアオバズク Ninox strenua Powerful Owl
ヒメアオバズク* Ninox sumbaensis Little Sumba Hawk-Owl
ニュージーランドアオバズク Ninox novaeseelandiae Morepork
オーストラリアアオバズク Ninox connivens Barking Owl
スンバアオバズク Ninox rudolfi Sumba Boobook
ミナミアオバズク Ninox boobook Southern Boobook
アオバズク Ninox japonica Northern Boobook
フーアアオバズク* Ninox scutulata Brown Hawk-Owl
チョコレートアオバズク* Ninox randi Chocolate Boobook
トギアンアオバズク* Ninox burhani Togian Boobook
ムジアオバズク* Ninox obscura Hume's Hawk-Owl
アンダマンアオバズク Ninox affinis Andaman Hawk-Owl
ルソンアオバズク* Ninox philippensis Luzon Hawk-Owl
ミンダナオアオバズク Ninox spilocephala Mindanao Hawk-Owl
ミンドロアオバズク Ninox mindorensis Mindoro Hawk-Owl
ロンブロンアオバズク* Ninox spilonotus Romblon Hawk-Owl
セブアオバズク* Ninox rumseyi Cebu Hawk-Owl
カミギンアオバズク* Ninox leventisi Camiguin Hawk-Owl
スールーアオバズク* Ninox reyi Sulu Hawk-Owl
チャバラアオバズク Ninox ochracea Ochre-bellied Hawk-Owl / Ochre-bellied Boobook
シュイロアオバズク* Ninox ios Cinnabar Hawk-Owl / Cinnabar Boobook
セラムアオバズク* Ninox squamipila Southern Moluccan Hawk-Owl / Hantu Boobook
ハルマヘラアオバズク* Ninox hypogramma North Moluccan Hawk-Owl / Halmahera Boobook
タニンバルアオバズク* Ninox forbesi Tanimbar Hawk-Owl / Tanimbar Boobook
クリスマスアオバズク Ninox natalis Christmas Island Hawk-Owl
セグロアオバズク Ninox theomacha Jungle Hawk-Owl / Papuan Boobook
アドミラルティアオバズク* Ninox meeki Manus Hawk-Owl / Manus Boobook
フイリアオバズク Ninox punctulata Speckled Hawk-Owl / Speckled Boobook
ニューアイルランドアオバズク Ninox variegata Bismarck Hawk-Owl / New Ireland Boobook
ニューブリテンアオバズク Ninox odiosa Russet Hawk-Owl / New Britain Boobook
ソロモンアオバズク Ninox jacquinoti Solomons Hawk-Owl / Solomons Boobook
オナガフクロウ亜科? Surniinae (Owlets and Pygmy-Owls)
カオカザリヒメフクロウ属 Xenoglaux
カオカザリヒメフクロウ Xenoglaux loweryi Long-whiskered Owlet
サボテンフクロウ属 Micrathene
サボテンフクロウ Micrathene whitneyi Elf Owl
キンメフクロウ属 Aegolius
キンメフクロウ Aegolius funereus Boreal Owl / Tengmalm's Owl
アメリカキンメフクロウ (ヒメキンメフクロウ) Aegolius acadicus Northern Saw-whet Owl
(バミューダキンメフクロウ) Aegolius gradyi Bermuda Saw-whet Owl
メキシコキンメフクロウ Aegolius ridgwayi Unspotted Saw-whet Owl
セグロキンメフクロウ Aegolius harrisii Buff-fronted Owl
? 属 Athene
コキンメフクロウ Athene noctua Little Owl
インドコキンメフクロウ Athene brama Spotted Owlet
(モリコキンメフクロウ) Athene blewitti Forest Owlet
(マダガスカルアオバズク) Athene superciliaris White-browed Hawk-Owl
アナホリフクロウ Athene cunicularia Burrowing Owl
ヨコジマスズメフクロウ属? Smithiglaux (Glaucidium 属より分離)
ヨコジマスズメフクロウ Smithiglaux capensis * African Barred Owlet
コンゴスズメフクロウ* Smithiglaux albertina * Albertine Owlet
? 属 Taenioglaux (Glaucidium属より分離)
オオスズメフクロウ Taenioglaux cuculoides * Asian Barred Owlet
ジャワスズメフクロウ Taenioglaux castanoptera * Javan Owlet
モリスズメフクロウ Taenioglaux radiata * Jungle Owlet
クリセスズメフクロウ Taenioglaux castanota * Chestnut-backed Owlet
オナガフクロウ属 Surnia
オナガフクロウ Surnia ulula Northern Hawk-Owl
スズメフクロウ属 Glaucidium
アフリカスズメフクロウ Glaucidium perlatum Pearl-spotted Owlet
スズメフクロウ Glaucidium passerinum Eurasian Pygmy-Owl
ヒメフクロウ Glaucidium brodiei Collared Owlet
ムネアカスズメフクロウ Glaucidium tephronotum Red-chested Owlet
セアカスズメフクロウ Glaucidium sjostedti Sjostedt's Barred Owlet
(? 亜属 Phalaenopsis)
メキシコスズメフクロウ* Glaucidium gnoma Northern Pygmy-Owl
グアテマラスズメフクロウ Glaucidium cobanense Guatemalan Pygmy-Owl
キューバスズメフクロウ Glaucidium siju Cuban Pygmy-Owl
コスタリカスズメフクロウ Glaucidium costaricanum Costa Rican Pygmy-Owl
コロンビアスズメフクロウ* Glaucidium nubicola Cloud-forest Pygmy-Owl
アンデススズメフクロウ Glaucidium jardinii Andean Pygmy-Owl
ユンガススズメフクロウ* Glaucidium bolivianum Yungas Pygmy-Owl
アネッタイスズメフクロウ Glaucidium parkeri Subtropical Pygmy-Owl
アマゾンスズメフクロウ* Glaucidium hardyi Amazonian Pygmy-Owl
ペルナンブコスズメフクロウ* Glaucidium mooreorum Pernambuco Pygmy-Owl
コスズメフクロウ Glaucidium minutissimum Least Pygmy-Owl
ミナミスズメフクロウ Glaucidium nana Austral Pygmy-Owl
チュウベイスズメフクロウ* Glaucidium griseiceps Central American Pygmy-Owl
タマウリパススズメフクロウ* Glaucidium sanchezi Tamaulipas Pygmy-Owl
コリマスズメフクロウ Glaucidium palmarum Colima Pygmy-Owl
ペルースズメフクロウ Glaucidium peruanum Peruvian Pygmy-Owl / Pacific Pygmy-Owl
アカスズメフクロウ Glaucidium brasilianum Ferruginous Pygmy-Owl
フクロウ亜科 Striginae
(? 族 Otini: Scops-Owls)
カキイロコノハズク属 Pyrroglaux
カキイロコノハズク Pyrroglaux podargina Palau Owl
? 属 Mascarenotus (絶滅属。Otus 属より分離)
(レユニオンコノハズク) Mascarenotus grucheti Reunion Owl (絶滅種)
(モーリシャスコノハズク) Mascarenotus sauzieri Mauritius Owl (絶滅種)
(ロドリゲスコノハズク) Mascarenotus murivorus Rodrigues Owl (絶滅種)
コノハズク属 Otus
アカヒメコノハズク Otus icterorhynchus Sandy Scops-Owl
ハイイロコノハズク Otus ireneae Sokoke Scops-Owl
ハナジロコノハズク Otus sagittatus White-fronted Scops-Owl
アカチャコノハズク Otus rufescens Reddish Scops-Owl
セイロンコノハズク* Otus thilohoffmanni Serendib Scops-Owl
アンダマンコノハズク Otus balli Andaman Scops-Owl
フロレスコノハズク Otus alfredi Flores Scops-Owl
タイワンコノハズク Otus spilocephalus Mountain Scops-Owl
ラジャーオオコノハズク Otus brookii Rajah Scops-Owl
ジャワコノハズク Otus angelinae Javan Scops-Owl
ムンタワイオオコノハズク* Otus mentawi Mentawai Scops-Owl
インドオオコノハズク Otus bakkamoena Indian Scops-Owl
チャメオオコノハズク* Otus lettia Collared Scops-Owl
スンダオオコノハズク Otus lempiji Sunda Scops-Owl
パラワンオオコノハズク Otus fuliginosus Palawan Scops-Owl
オオコノハズク Otus semitorques Japanese Scops-Owl
オニコノハズク Otus gurneyi Giant Scops-Owl
ネグロスオオコノハズク* Otus nigrorum Negros Scops-Owl
ルソンオオコノハズク Otus megalotis Philippine Scops-Owl
ミンダナオオオコノハズク* Otus everetti Everett's Scops-Owl
アラビアコノハズク* Otus pamelae Arabian Scops-Owl
フロレスオオコノハズク Otus silvicola Wallace's Scops-Owl
ヨーロッパコノハズク Otus scops Eurasian Scops-Owl
キプロスコノハズク* Otus cyprius Cyprus Scops-Owl
サントメコノハズク Otus hartlaubi Sao Tome Scops-Owl
ペンバコノハズク* Otus pembaensis Pemba Scops-Owl
アフリカコノハズク Otus senegalensis African Scops-Owl
サバクコノハズク* Otus brucei Pallid Scops-Owl
ミンダナオコノハズク Otus mirus Mindanao Scops-Owl
ルソンコノハズク Otus longicornis Luzon Scops-Owl
ミンドロコノハズク Otus mindorensis Mindoro Scops-Owl
リンジャニコノハズク* Otus jolandae Rinjani Scops-Owl
モルッカコノハズク Otus magicus Moluccan Scops-Owl
スラコノハズク* Otus sulaensis Sula Scops-Owl
シアウコノハズク* Otus siaoensis Siau Scops-Owl
マンタナニコノハズク* Otus mantananensis Mantanani Scops-Owl
リュウキュウコノハズク Otus elegans Ryukyu Scops-Owl
セレベスコノハズク Otus manadensis Sulawesi Scops-Owl
サンギヘコノハズク* Otus collari Sangihe Scops-Owl
ビアクコノハズク Otus beccarii Biak Scops-Owl
シムルエコノハズク* Otus umbra Simeulue Scops-Owl
エンガノコノハズク Otus enganensis Enggano Scops-Owl
ニコバルコノハズク* Otus alius Nicobar Scops-Owl
オナガマダガスカルコノハズク* Otus madagascariensis Torotoroka Scops-Owl
マダガスカルコノハズク Otus rutilus Rainforest Scops-Owl
マヨットコノハズク* Otus mayottensis Mayotte Scops-Owl
グランドコモロコノハズク* Otus pauliani Karthala Scops-Owl
モへリコノハズク* Otus moheliensis Moheli Scops-Owl
アンジュアンコノハズク* Otus capnodes Anjouan Scops-Owl
セーシェルコノハズク Otus insularis Seychelles Scops-Owl
ソコトラコノハズク* Otus socotranus Socotra Scops-Owl
コノハズク Otus sunia Oriental Scops-Owl
(トラフズク族? Asionini: Eared Owls)
アフリカオオコノハズク属 Ptilopsis
アフリカオオコノハズク Ptilopsis leucotis Northern White-faced Owl
ミナミアフリカオオコノハズク Ptilopsis granti Southern White-faced Owl
オニコミミズク属 Nesasio
オニコミミズク Nesasio solomonensis Fearful Owl
トラフズク属 Asio
コミミズク Asio flammeus Short-eared Owl
アフリカコミミズク Asio capensis Marsh Owl
タテジマフクロウ (ウサギフクロウ) Asio clamator * Striped Owl (別属 Pseudoscopsとされていた)
ナンベイトラフズク Asio stygius Stygian Owl
ジャマイカズク Asio grammicus * Jamaican Owl (別属 Pseudoscops とされていた)
トラフズク Asio otus Long-eared Owl
アビシニアトラフズク Asio abyssinicus Abyssinian Owl
マダガスカルトラフズク Asio madagascariensis Madagascan Owl
(? 族 Megascopini: Screech-Owls)
アメリカコノハズク属 Psiloscops
アメリカコノハズク Psiloscops flammeolus Flammulated Owl
プエルトリコオオコノハズク属 Gymnasio
プエルトリコオオコノハズク Gymnasio nudipes * Puerto Rican Screech-Owl (Megascops 属から)
ユビナガフクロウ属 Margarobyas
ユビナガフクロウ Margarobyas lawrencii Bare-legged Owl
? 属 Megascops
ヒゲコノハズク Megascops trichopsis Whiskered Screech-Owl
パナマオオコノハズク Megascops clarkii Bare-shanked Screech-Owl
ノドジロオオコノハズク Megascops albogularis White-throated Screech-Owl
スピックスコノハズク Megascops choliba Tropical Screech-Owl
ケプケオオコノハズク* Megascops koepckeae Koepcke's Screech-Owl
ミミナガオオコノハズク Megascops sanctaecatarinae Long-tufted Screech-Owl
ヒゲオオコノハズク Megascops barbarus Bearded Screech-Owl
クーパーオオコノハズク* Megascops cooperi Pacific Screech-Owl
ニシアメリカオオコノハズク Megascops kennicottii Western Screech-Owl
アメリカオオコノハズク Megascops asio Eastern Screech-Owl
バルサスオオコノハズク Megascops seductus Balsas Screech-Owl
アンデスオオコノハズク Megascops ingens Rufescent Screech-Owl
コロンビアオオコノハズク Megascops colombianus Colombian Screech-Owl
ニッケイコノハズク* Megascops petersoni Cinnamon Screech-Owl
アンデスコノハズク Megascops marshalli Cloud-forest Screech-Owl
ユンガスオオコノハズク* Megascops hoyi Montane Forest Screech-Owl / Yungas Screech-Owl
キタホソジマオオコノハズク* Megascops guatemalae Middle American Screech-Owl
ホソジマオオコノハズク Megascops vermiculatus Choco Screech-Owl
ナポオオコノハズク* Megascops napensis Napo Screech-Owl
ロライマオオコノハズク* Megascops roraimae Roraiman Screech-Owl
(サンタマルタオオコノハズク) Megascops gilesi Santa Marta Screech-Owl
シロエリオオコノハズク Megascops roboratus Peruvian Screech-Owl / West Peruvian Screech-Owl Screech-Owl
チャバラオオコノハズク Megascops watsonii (Northern) Tawny-bellied Screech-Owl
(未定) Megascops usta Southern Tawny-bellied Screech-Owl (上種から分離)
ズグロオオコノハズク Megascops atricapilla Black-capped Screech-Owl
(メガネフクロウ族 Pulsatricini)
ミミナガフクロウ属 Lophostrix
ミミナガフクロウ (カンムリズク) Lophostrix cristata
メガネフクロウ属 Pulsatrix
メガネフクロウ Pulsatrix perspicillata Spectacled Owl
キマユメガネフクロウ Pulsatrix koeniswaldiana Tawny-browed Owl
アカオビメガネフクロウ Pulsatrix melanota Band-bellied Owl
(フクロウ族 Strigini: Wood-Owls)
タテガミズク属 Jubula
タテガミズク Jubula lettii Maned Owl
フクロウ属 Strix
カラフトフクロウ Strix nebulosa Great Grey Owl
フクロウ Strix uralensis Ural Owl
シセンフクロウ Strix davidi Pere David's Owl
モリフクロウ Strix aluco Tawny Owl
ミヤマモリフクロウ* Strix nivicolum Himalayan Owl
インドモリフクロウ Strix ocellata Mottled Wood-Owl
マレーモリフクロウ Strix seloputo Spotted Wood-Owl
オオフクロウ Strix leptogrammica Brown Wood-Owl
ウスイロモリフクロウ Strix butleri Omani Owl
アフリカヒナフクロウ Strix woodfordii African Wood-Owl
サバクフクロウ* Strix hadorami Desert Owl
? 属 Ciccaba (Strix 属より分離)
ニシアメリカフクロウ Ciccaba occidentalis * Spotted Owl
アメリカフクロウ Ciccaba varia * Barred Owl
メキシコフクロウ* Ciccaba sartorii * Ciccaba Owl
チュウベイフクロウ* Ciccaba fulvescens * Fulvous Owl
ブラジルモリフクロウ Ciccaba hylophila * Rusty-barred Owl
アカアシモリフクロウ Ciccaba rufipes * Rufous-legged Owl
チャコモリフクロウ* Ciccaba chacoensis * Chaco Owl
ナンベイヒナフクロウ Ciccaba virgata * Mottled Owl
シロクロヒナフクロウ Ciccaba nigrolineata * Black-and-white Owl
クロオビヒナフクロウ Ciccaba huhula * Black-banded Owl
アカオビヒナフクロウ Ciccaba albitarsis * Rufous-banded Owl
(ワシミミズク族 Bubonini: Eagle-Owls)
ワシミミズク属 Bubo
シロフクロウ Bubo scandiacus Snowy Owl
アメリカワシミミズク Bubo virginianus Great Horned Owl
ベンガルワシミミズク* Bubo bengalensis Indian Eagle-Owl
アフリカワシミミズク Bubo africanus Spotted Eagle-Owl
ハイイロワシミミズク* Bubo cinerascens Greyish Eagle-Owl
イワワシミミズク Bubo capensis Cape Eagle-Owl
サバクワシミミズク Bubo ascalaphus Pharaoh Eagle-Owl
ワシミミズク Bubo bubo Eurasian Eagle-Owl
ウスグロワシミミズク Bubo coromandus Dusky Eagle-Owl
アクンワシミミズク Bubo leucostictus Akun Eagle-Owl
クロワシミミズク属? Nyctaetus (Bubo 属より分離)
ヨコジマワシミミズク Nyctaetus shelleyi * Shelley's Eagle-Owl
クロワシミミズク Nyctaetus lacteus * Verreaux's Eagle-Owl
ウオクイフクロウ属 Scotopelia
ウオクイフクロウ Scotopelia peli Pel's Fishing Owl
アカウオクイフクロウ Scotopelia ussheri Rufous Fishing Owl
タテジマウオクイフクロウ Scotopelia bouvieri Vermiculated Fishing-Owl
シマフクロウ属 Ketupa
ネパールワシミミズク Ketupa nipalensis * Spot-bellied Eagle-Owl (Bubo 属より移動)
マレーワシミミズク Ketupa sumatrana * Barred Eagle-Owl (Bubo 属より移動)
ウサンバラワシミミズク* Ketupa vosseleri * Nduk Eagle-Owl / Usambara Eagle-Owl (Bubo 属より移動)
コヨコジマワシミミズク Ketupa poensis * Fraser's Eagle-Owl (Bubo 属より移動)
フィリピンワシミミズク Ketupa philippensis * Philippine Eagle-Owl (Bubo 属より移動)
シマフクロウ Ketupa blakistoni * Blakiston's Fish-Owl (Bubo 属より移動)
ミナミシマフクロウ Ketupa zeylonensis Brown Fish-Owl
ウオミミズク Ketupa flavipes Tawny Fish-Owl
マレーウオミミズク Ketupa ketupu Buffy Fish-Owl
オニコノハズクは単形属の Mimizuku gurneyi (属名は Hachisuka, 1934, Birds Philippine Islands, Pt. III, p. 50 が提唱) とされていたことがあったが Otus 属に統合された。Howard and Moore 4th edition (incl. corrigenda vol.1-2) にはこの学名が残っている。
参考 Miranda et al. (1997) Phylogenetic Placement of Mimizuku Gurneyi (Aves: Strigidae) Inferred from Mitochondrial DNA
及び Miranda et al. (2011) Phylogeny and Taxonomic Review of Philippine Lowland Scops Owls (Strigiformes): Parallel Diversification of Highland and Lowland Clades
によるもので、統合は比較的最近のこと。オニコノハズクはミンダナオ島に一足早く定着したと考えられ、この研究で従来の Otus megalotis がいくつかの種に分離された。
オニコノハズクは Otus 属の中に内包されることが明らかになり独立属とすべきではない。
Otus 属に変更された時期がリストによって異なるのはどちらの文献に基づくかによるのだろう。
Wink and Sauer-Guerth (2021) (#シマフクロウの備考参照) では若干異なっており以下の亜科、族となっている。
このリストは Wink and Sauer-Guerth (2021) の順をそのまま並べただけで、分岐時期を意識して並べ替えていない。メンフクロウ科内の順序は分岐順であれば Boyd のようになる。
フクロウ科内部は時期が接近しているので Boyd と Wink and Sauer-Guerth (2021) の順序が異なることはやむを得ない部分がある。
我々に関係するところでは Surniinae と Ninoxinae の順序が逆転しているところであろうか。
Wink and Sauer-Guerth (2021) の系統樹に従えば Surniinae は フクロウ科 Strigidae の中で最初の分枝で独立した系統をなしているので Boyd のリストは Surniinae と Ninoxinae を入れ替えるのが適切に見える。
Ninox 属のオーストラリアやチモール島周辺の Wallacea (ワラセア) 地域の種分化については Gwee et al. (2016) Bioacoustic and multi-locus DNA data of Ninox owls support high incidence of extinction and recolonisation on small, low-lying islands across Wallacea
(別サイト) も参照。
かつてはある程度ミナミアオバズク Southern Boobook とまとめておくことも可能だったが...。
非常に複雑でどこまでを種に分けるか自明ではなく定着と絶滅の過程も考察して一定の判断を示したもの。
音声がこの程度違えば別種と考える一つの基準ともなった。
Micrathene をどこに入れるかは悩ましいところであり、Surniinae にも Ninoxinae にも入れることができない (Boyd は前者に含めているが Wink and Sauer-Guerth の系統樹では Surniinae が単系統にならない)。
このあたりはタカ類で行われたような全ゲノム解析を行って系統関係を確認する必要があるところだろう。
我々に関係するところではキンメフクロウとアオバズクの図鑑の登場順序がどちらになるかに関係する部分。Wink and Sauer-Guerth (2021) に従えば Boyd とは逆に キンメフクロウ、アオバズクの順になる。これらはフクロウ科の中でも古い方の系統 (とはいえ時期の違いは大きくないが) と考えてよいだろう。
メンフクロウ科 Tytonidae
Tytoninae
Phodilinae
フクロウ科 Strigidae
Surniinae
Surniini
Aegolini
Ninoxinae
Ninoxini
Striginae
Otini
Megascopini
Asionini
Pulsatrigini
Strigini
Bubonini
系統樹はいずれもオープンアクセスなので比べてみていただきたい。
Salter et al. (2020) Extensive paraphyly in the typical owl family (Strigidae)
にも解析があり、一部の種はタカ類の系統解析と同様に核遺伝情報 (UCE) を用いている。こちらはこれまで提案されていた属に包含関係があるため比較的統合する傾向を示している。
しかし Salter et al. (2020), Wink and Sauer-Guerth (2021) をともに参照した上で Salter et al. (2020) の属統合を採用せず、むしろ Ketupa 属はむしろ違いが一層明らかになったとの記述もある
(例えばネパールワシミミズクの wikipedia 英語版; #シマフクロウの備考 [シマフクロウを Ketupa 属に残すことは可能か?] も参照)。
Hains et al. (2025) The Complete Genome Sequences of 22 Species of Owls (Strigiformes, Aves) がフクロウ類 22 種のゲノムを解読し公開している。我々に関係のあるオオコノハズクやリュウキュウコノハズクも含まれている。
Hartert (1910-1922) p. 957 によればフクロウ類とヨタカ、アマツバメ類をまとめたのは Fuerbringer and Gadow とその後継者とのこと (この分類を採用していた時期の書物ではフクロウ類とワシタカ類の類似性は偶然の産物で一種の収斂進化と説明されていた)。Coraciiformes の目名称 (現在ではブッポウソウ目となる) を与えていた。
一方で猛禽類にも分類されるのである程度人為的分類をせざるを得ない。
Hartert 自身はブッポウソウ類との類似性を気にしていたが、ヨタカ類とフクロウ類は夜行性など共通点がある点を見逃してはいけないが、一方で昼行性猛禽類との骨格や筋肉、嘴の類似性などは無視できるようなものではない。
当時は想像もできなかっただろうが、結論は分子系統研究の進展まで待たざるを得なかったことになった。
#ミサゴ備考の [近代的な陸鳥の進化] も参照。
#フクロウ備考の Jarvis et al. (2014) のレトロトランスポゾン研究が決定的だった。
[英国のメンフクロウの減少]
週間アニマルライフ (1973) pp. 3713-3715 のメンフクロウの項目 (内田) ではナヤフクロウ (英名から当時の名称。現在分離されメンフクロウ) Tyto alba は英国では農業様式の変化で営巣場所だったウマ小屋や朽ち木などがなくなり、1940 年代から減少が目立ち始め、その後は農薬の大量散布で 1965 年には多くの地方で絶滅寸前まで追い込まれたとのこと。
[フクロウ類の音源定位]
フクロウ類の音源定位 (sound localization) で最もよく調べられているのはアメリカメンフクロウ Tyto furcata 英名 American Barn Owl、
[メンフクロウ Tyto alba 英名 Western Barn Owl から分離]
なのでここで紹介しておく。
音の方向を知る方法として、哺乳類でも鳥類でも両耳に届く音の時間差 (interaural time difference) と音の強さの差 (interaural level difference) を用いている。
音の時間差がアメリカメンフクロウの脳内でどのような神経経路で処理されるかは Carr and Konishi (1990) A Circuit for Detection of Interaural Time Differences in the Brain Stem of the Barn Owl
ですでに知られている。[この概念の最初の発表は Konishi (1973)。このグループを率いた小西正一氏 (1933-2020) は鳥の脳やさえずり研究のパイオニアであり第一人者である。日本語著書に「小鳥はなぜ歌うのか」(岩波新書 1994) があり、
小鳥のさえずり研究にあたって親の声を聞かずに育てる人工孵化から飼育の実験系を確立する必要があり、人工餌だけではどうしてもうまく行かず親鳥のそのう抽出液を与える育てることができた苦労のエピソードもあり、鳥類の発育条件などの点でも興味深い (#インドガン備考の *1 も参照)。
この本の竹下信雄氏の書評 [1994, Birder 8(9): 86] をめぐり、Birder 誌上で著者からの返事が紹介されたこともあった]。
10-20 マイクロ秒の違いがニューロンの反応の違いに現れ、
音速を 340 m/s とすれば (#ヨタカの備考も参照) 10-20 マイクロ秒は 4-7 mm の違いに相当する。同様の値は Wagner et al. (2005) Microsecond Precision of Phase Delay in the Auditory System of the Barn Owl でも報告されている。
アメリカメンフクロウの両耳間の距離を 44 mm とすればこれは 4-9° 程度に相当する。
行動実験的にも 14° (500 Hz) - 6° (8 kHz) 程度の分解能が得られており [Krumm et al. (2019) The barn owls’ Minimum Audible Angle 最近の研究の一例]、
よく一致している (この実験では時間差と強さの差の効果は区別できない)。ちなみに 8 kHz の音でも波長は 4.3 cm 程度で、両耳の時間差というよりも信号の位相差を検出していると言った方がむしろ近い。
500 Hz の音で 14° の音源定位を行うならば波の位相に直すと 0.016、8 kHz の音で 6° であれば位相差は 0.11 程度となる。低い音の方が波長が長いので音源定位には不利で、位相 0.016 の判別は生理的限界に達しているのだろう。高い音は波長が短いので音源定位には有利であるが鳥の耳の感度が低くなるためこのあたりが限界なのだろう。
フクロウ類が両耳の時間差 (位相差) で音源定位を行う点については曖昧なところはなさそうである。
(ただし哺乳類では機構が少し異なる可能性もある。McAlpine (2005) Creating a sense of auditory space)。
実験室では完全暗黒でも音源定位で獲物を捕まえることができることが示されており (Payne 1971)、視覚は獲物を捉えるのに必ずしも必須でないとのこと。
"位相差" と表現したところで詳しい方ならば察されると考えるが、位相が1違ったものは同じ信号になって位相差では区別できない。
フクロウ類ではそのような場合は強さの差を用いて音源定位の曖昧さを回避しているらしいとのことである [Kettler et al. (2017) Combination of Interaural Level and Time Difference in Azimuthal Sound Localization in Owls]。
ちなみに Krumm et al. (2019) の実験ではヒトの方がより高い分解能が得られている。これは両耳の間隔がヒトの方がずっと大きいことを反映しているが、ヒトでは高い音の方が分解能が悪い。これは音声コミュニケーションに用いる音への適応と考えられるとのこと。
ネコでも高い音の方が分解能が悪いが、ネコでは 4 kHz より高い音の波の位相情報 (論文では phase locking 位相固定 の用語を使っている) をうまく扱えていない解釈があり、フクロウ類 (10 kHzまで位相情報をうまく扱える。通常の鳥類では 3-4 kHz までとの研究がある) の聴覚のすぐれた点を表す可能性がある。
高い音で位相情報がうまく扱えない (phase locking ができない) 場合 (種類) では主に左右の耳での音の強さの差が方向の手がかりとなる。小鳥の出す高い警戒音の方向が (ヒトにとって) わかりにくいのはこの性質によるものだろう。ネコでも同様のようなので哺乳類の捕食者に方向がわかりにくい声と考えてよさそうに思える。
アメリカメンフクロウの音源定位にはさまざまな実験が行われているが、Pena et al. (2010) Auditory Processing, Plasticity, and Learning in the Barn Owl
はプリズムを付けて音声の方向と視覚情報から得られる方向を違える実験を行っているが、60 日齢以内の若い時にプリズムを取り付けると視覚情報と違った角度からの音声を補正できることが示されている。これは脳が可塑性を示す敏感な期間があることを示す。プリズムに適応した個体のプリズムを外すと数か月でもとの状態に慣れるそうである。
聴神経からの信号は視神経の入る視蓋の下に並ぶ中脳の下丘 inferior colliculus に入る (#イヌワシの備考参照)。この点は哺乳類と同じである (後に紹介する小西の解説では別の用語を用いているが、近年の鳥類の聴覚の解説では下丘の用語が使われているのでそのまま用いた)。
両耳に届く音の時間差と音の強さの差は横方向の音源定位に役立つが、上下方向はわからない。
フクロウ類に耳が左右非対称なものがあることから、これが上下方向の音源定位に役立つと考えられている。フクロウ類が音源を探知した場合、(たとえば音の時間差を用いて) 音源の正面方向に頭を向けると左右対称な耳であれば左右の耳には同じ強さの音に聞こえるが、耳に非対称があれば左右で違う強さに聞こえるので原理的には上下方向の情報が得られる。
小西による "Listening with Two Ears" の一般向け解説が Scientific American (1993) に掲載され、日経サイエンス1993年6月号に和訳が掲載された。現在では「鳥のサイエンス」(日経サイエンス社 2018) で一部改訂された形で読むことができる。
Listening with two ears でも図はないが読むことができる。
この記事に従えば左右の耳の時間差と音の強さの信号はそれぞれ別の神経経路で処理され、より上位で左右の統合が行われるそうである。
小西の解説によれば、音の強さの信号は角状核 (angular nucleus) を通り上位で情報処理され脳の外側核 (external nucleus、ただしいずれも当時の用語で紹介しているため現在では別の名称が使われているかも知れない) 中に特定の方向 (水平方向および垂直方向) に反応する細胞が存在することが示されている。
図を見る限りでは垂直方向の分解能はやはりあまりよくなく 20-30° 程度のようである。時間差を利用できる水平方向よりはだいぶ悪そうであるが、それでも情報がないよりは有利なのだろう。
なお実験にはフクロウが受け入れてくれる形状のイアホンを作成し、立体的な方向からの音刺激を作って聞かせたそうである。エピソードをご覧にになりたい方は日本語か英語で原文をお読みいただくとよいと思う。
[今から考えればの話だが小西グループの研究が非常にうまく行ったのは、音は時間的にみると1次元の情報であり、遅延検出・位相差検出の回路は比較的簡単であるため当時の技術や理論でも解明できたのかも知れない。視覚のような (片側の目である瞬間だけでみても) 空間2次元情報の処理は現在でも難しく、別の項目で述べる立体視の研究もそれほど進んでいないのかも知れない]。
意外にもニワトリも他の鳥に比べて音源定位能力が高いとのこと: Maldarelli et al. (2022) Azimuthal sound localization in the chicken。12-16° ぐらいの水平分解能があるとのこと。
Fig. 4 に比較の図があるが、一般的な鳥 (シジュウカラ、セキセイインコ、カナリアなどは悪い) に比べてメンフクロウやネコは何倍もよい。昼行性猛禽類はその中間ぐらいだがニワトリもそれに次ぐぐらい。体も大きいので有利な点もあるらしい。
聴覚を特別の目的に用いているものを auditory specialist と呼ぶそうで、エコーロケーションを行う動物などは典型。フクロウ類、ネコ、ヒトはこちらに分類している。
そうでないものを auditory generalist と呼ぶ。
Krumm et al. (2022) Chickens have excellent sound localization ability も同様の結果を得ており、実験動物として扱いやすいので注目を集めている模様。
フクロウ類などの「顔盤」は英語では facial disk。外周を facial ruff と呼ばれることもあり、これはエリマキシギの Ruff と同じ意味。顔盤の羽毛には特殊化はなくそのまま音を透過するとのこと。外周の羽毛は密で音の方向を変える機能を持つ可能性がある。
顔盤の機能を調べた研究もある:
Hausmann et al. (2009) Improvements of Sound Localization Abilities by the Facial Ruff of the Barn Owl (Tyto alba) as Demonstrated by Virtual Ruff Removal。
フクロウ類の左右非対称な耳については Norberg (2002)
Independent evolution of outer ear asymmetry among five owl lineages; morphology, function and selection (in "Ecology and Conservations of Owls" eds. Newton et al.)
が詳しく、フクロウ類の5系統でほぼ独立に進化しただろうとのこと (Norberg によるほぼ同様の研究はもっと早い時期のものがある)。
Fig. 6 にキンメフクロウの頭骨の極端な非対称を示す図があり、他文献でもよく紹介されている。
「鳥たちの驚異的な感覚世界」では非対称な耳を持つ種類としてキンメフクロウ、アメリカキンメフクロウ (ヒメキンメフクロウ) Aegolius acadicus 英名 Northern Saw-whet Owl、カラフトフクロウ Strix nebulosa 英名 Great Grey Owl、フクロウが挙げられている。
Norberg (2002) では Strix 属は左右差の発達が悪く、左右差があっても単純とのことで、Strix 属はナンベイヒナフクロウ Strix virgata 英名 Mottled Owl とカラフトフクロウ を例に挙げている。Strix 属ではカラフトフクロウが最も複雑な左右差を示すとのこと。
Asio 属は川口 (2023) (#フクロウの備考参照) がトラフズクについて述べた通り、骨格は完全に左右対称だが軟部組織に非対称があるとのこと。
Strix 属では一部の種のみが非対称で、「鳥たちの驚異的な感覚世界」にフクロウが含まれたのはあまり適切な例ではなかったようである (フクロウでどの程度の左右差があるかについてはフクロウの備考参照)。
この文献では耳の左右非対称のある種を持つ属として他に Tyto 属、Phodilus 属、いずれも Tytonidae メンフクロウ科、Bubo 属 (ワシミミズク) が挙げられている。
耳の左右非対称はかつて属の判定に使われたことがあったが現在は使われていない。
左右非対称な耳の利点は、完全に対称な耳の場合は1次元 (例えば左右方向) の場所しかわからず、別次元 (上下方向) の情報を得るには頭を傾けて再度聞く必要がある。獲物の動く音は一般に短く、再度聞くまでの間に移動もするので一度に情報が得られることは利点がある (Norberg 1968, 1978) と解説している。
以下 #フクロウの備考 [フクロウ類などの耳の左右差] に続く。
Beaufrere and Laniesse (2016) Current Therapy in Avian Medicine and Surgery によればフクロウ類の耳について Cranial and caudal to the auditory meatus are the preaural (also known as the operculum) and postaural folds, which can be erected and the shape of the opening (normally closed) altered by the muscles that insert onto the skull の説明がある (ScienceDirect の topics 紹介より章の一部が読める)。
この説明によれば普段は耳を覆う羽毛を閉じていて、聞き耳を立てる時に羽毛を立てるらしい。
この構造そのものは古くから知られていたようで、Norberg (1978) Skull asymmetry, ear structure and function, and auditory localization in Tengmalm's owl, Aegolius funereus (Linne) のキンメフクロウの耳の構造研究で左右差の由来、外耳口の前後の "ひだ" につながる羽毛に外耳口の前 (preaural flap) は音透過機能、後ろ (postaural flap) は反射機能があるとともに紹介されている。
この論文で耳の左右差が上下方向の情報を得るために使われていることが示唆されていた。
#イヌワシの備考の [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] の注釈 *4 に追記がある。
音を出さない飛行については #ウスハイイロチュウヒの備考 [音を出さない羽毛構造] にまとめた。この中で紹介している文献にフクロウ類の音源定位、暗黒下での獲物の捕獲などの多様な話題も扱われているのでご一読をおすすめする。
[鳥の聴力は老化しない?]
鳥の内耳の hair cell に再生能力があるので聴力を失っても回復すると一般に考えられているが、加齢変化があるかどうかは必ずしも自明でない。
メンフクロウを使った研究で年齢差はほとんど認められなかったとのこと: Krumm et al. (2017) Barn owls have ageless ears。
一方コウモリは加齢難聴があるとのこと: Tarnovsky et al. (2023) Bats experience age-related hearing loss (presbycusis)。従来はコウモリは同種の出す騒音に抵抗性があると考えられていた。コウモリでも他の哺乳類同様に加齢で高音が聞こえにくくなるとのことだがメカニズムはよくわかっていない。
反論論文もある Capshaw et al. (2024) Resistance to age-related hearing loss in the echolocating big brown bat (Eptesicus fuscus) (preprint)。
コウモリの聴力の研究はホットなテーマのようで新しい研究もいくつも出ている。
[フクロウ類の脳のサイズ]
タカ目 (#ハチクマの備考)、ハヤブサ目、オウム目 (#ハヤブサの備考) と同様にフクロウ目の脳のサイズを示しておく。
赤がフクロウ目、緑がハヤブサ目、黄色がタカ目である。
 猛禽類3グループの中ではフクロウ目の脳が相対的に大きいことがわかる。特に小型種で相対的に大きくオウム目に匹敵する。
{タカ目 + ハヤブサ目} とオウム目の間ぐらいになり、オウム目とも重なっている。夜行性生活、あるいは特異な聴覚・視覚系と関係があるのだろうか (眼は大きくても視細胞の数は少ないので視覚情報処理はむしろ少なくてもおかしくないが)。
フクロウ目が飼育下で他の猛禽類より特に賢い話も聞かないのでなぜこうなっているのかはよくわからない。
Twit or true: are owls really intelligent?
(Bill Naylor, New Scientist 2020) にも飼育下で平均以上の知能は示さないとある。生活様式から好奇心を示す必要はないのではとのこと。道具使用にあたる行動を行う種類はあったり救助された時に協力的な種類などはあるようだが。
「ブボがいた夏: アメリカワシミミズクと私」(ベルンド・ハインリッチ著 渡辺正隆訳 平河出版社 1993, 原著 "One Man's Owl" Bernd Heinrich 1987, 1994 改訂版) があり、遊びの様子や内輪の親しい間柄にある相手のための抑えた声の記述などがある。この点を見るとタカにも似ている感じがするが、昼行性のタカ・ハヤブサに比べて、夜行性中心のため人の行動との類似点が少なく知能を感じることが少なめなのかも知れない。
この本の書かれた猛禽類の知能についてはそれほど知られておらず、当時は「空を飛ぶトラ」とも呼ばれ人に慣れることすら困難と思われていた時代とのこと。フクロウ類ファンの皆さんのご意見はいかがだろうか。
#イヌワシ備考の [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] の注釈 *4 の Gutierrez-Ibanez et al. (2018) ではフクロウ類の大きな大脳は視覚情報処理のためのもので認知にはあまり関与していないとしている。つまり頭はよくない、となるがどうだろうか。
文献は該当部分を参照。
猛禽類3グループの中ではフクロウ目の脳が相対的に大きいことがわかる。特に小型種で相対的に大きくオウム目に匹敵する。
{タカ目 + ハヤブサ目} とオウム目の間ぐらいになり、オウム目とも重なっている。夜行性生活、あるいは特異な聴覚・視覚系と関係があるのだろうか (眼は大きくても視細胞の数は少ないので視覚情報処理はむしろ少なくてもおかしくないが)。
フクロウ目が飼育下で他の猛禽類より特に賢い話も聞かないのでなぜこうなっているのかはよくわからない。
Twit or true: are owls really intelligent?
(Bill Naylor, New Scientist 2020) にも飼育下で平均以上の知能は示さないとある。生活様式から好奇心を示す必要はないのではとのこと。道具使用にあたる行動を行う種類はあったり救助された時に協力的な種類などはあるようだが。
「ブボがいた夏: アメリカワシミミズクと私」(ベルンド・ハインリッチ著 渡辺正隆訳 平河出版社 1993, 原著 "One Man's Owl" Bernd Heinrich 1987, 1994 改訂版) があり、遊びの様子や内輪の親しい間柄にある相手のための抑えた声の記述などがある。この点を見るとタカにも似ている感じがするが、昼行性のタカ・ハヤブサに比べて、夜行性中心のため人の行動との類似点が少なく知能を感じることが少なめなのかも知れない。
この本の書かれた猛禽類の知能についてはそれほど知られておらず、当時は「空を飛ぶトラ」とも呼ばれ人に慣れることすら困難と思われていた時代とのこと。フクロウ類ファンの皆さんのご意見はいかがだろうか。
#イヌワシ備考の [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] の注釈 *4 の Gutierrez-Ibanez et al. (2018) ではフクロウ類の大きな大脳は視覚情報処理のためのもので認知にはあまり関与していないとしている。つまり頭はよくない、となるがどうだろうか。
文献は該当部分を参照。
ハヤブサ目のデータは基本的に Falco 属で、いわゆる知的とされるカラカラ類がほぼ含まれていないのであるいはカラカラ類のデータを含むと多少違ってくるかも知れないが。
夜行性適応を示すタカ類 (カタグロトビ類) にはこの傾向は見られず、少なくとも脳のサイズの点では収斂進化を示していないようである。
△ フクロウ目 STRIGIFORMES フクロウ科 STRIGIDAE ▽
-
オオコノハズク (分割された)
- 第8版学名:Otus semitorques (オートゥス セーミトルクゥエース) 半分首輪があるミミズク (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Otus lempiji (オートゥス レムピイイ) スンダオオコノハズク
- 第7版亜種学名:Otus lempiji semitorques (オートゥス レムピイイ セーミトルクゥエース) 半分首輪があるスンダオオコノハズク (代表的亜種。他亜種あり)
- 属名:otus (m) ミミズク (otus (m) フクロウの一種、otos 耳 Gk)
- 第8版種小名:semitorques 半分首輪がある semi- 半分の torques/torquis 首輪、首飾り、首に特徴がある
- 第7版種小名:lempiji (外) スンダオオコノハズク ジャワ語
- 第7版亜種小名:semitorques 半分首輪がある semi- 半分の torques/torquis 首輪
- 英名:[Collared Scops Owl 分割前の名称], IOC: Japanese Scops Owl
- 備考:
otus は冒頭が長母音。ギリシャ語 otos でも同様。
semitorques は semi- の冒頭が長母音。torques の末尾が長母音。-tor- がアクセント音節 (セーミトルクゥエース)。semi- はインド・ヨーロッパ祖語の *semi- に由来 (e は長母音)。ギリシャ語由来の hemi- の音にも合わせたとのこと (wiktionary)。
lempiji の発音はわからないが j は i と同じ音と表記した。あえて付ければ "レムピイイ" のアクセント位置と推定される。
lempiji の由来については (Strix lempiji) の原記載参照。現地語で Lempi-ji とのこと。
Horsfield (1821) は種小名を思いつくのに苦労していたようで、"ジャワ島" などの主だった種小名は当時の Strix 属ですでに使われていたため、マレーウオミミズク (#シマフクロウ参考) などとともにフクロウ類複数種に現地名を採用していた。
Lempi-ji はもしかして音声由来かと想像して音声を聞いてみたが判断できなかった (現代のインドネシア語ではこの名称ではない。wikipedia インドネシア語版では wuuup.., whiio, pwok.. の音声表記があり、デュエットもある)。他のフクロウ類の記載当時ジャワ語では音声由来らしいものがいくつかみられる。
分割のため第7版学名は代表的亜種まで記した。
現在ではスンダオオコノハズク Otus lempiji (英名 Sunda Scops Owl) は別種となり、スンダ列島の固有種となっている。
日本のオオコノハズクの現在の学名は Otus semitorques (semi- 半分の torques/torquis 首輪) 英名 Japanese Scops-Owl。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
インドオオコノハズク Otus bakkamoena (英名 Indian Scops-Owl)、チャメオオコノハズク [山崎他 (2017)] (ヒガシオオコノハズク) Otus lettia (英名 Collared Scops-Owl)、スンダオオコノハズクと近縁であり、この4種が同種として扱われることもあると wikipedia 英語版には記載されている。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では Otus bakkamoena の亜種としている。
Wink and Sauer-Guerth (2021) Molecular taxonomy and systematics of owls (Strigiformes) - An update に系統樹が出ているが、オオコノハズクはスンダオオコノハズクよりもルソンオオコノハズク Otus megalotis (英名 Philippine Scops-Owl) の方にむしろ近縁のようである。
日本の書物でも「コンサイス鳥名事典」では Otus bakkamoena の亜種としていた。
日本では古くはアメリカオオコノハズク (現在の学名では Megascops asio、当時は Otus asio) と同種としていたとの記述が Glenys and Derek Lloyd "Birds of Prey" (1969) 高野伸二訳「猛禽類」(1973) にある。「コンサイス鳥名事典」によると鳴き声の類似性が由来のよう。
#コノハズク備考の [コノハズク類の分子系統解析] にあるようにこれら過去に同種とされた種とは系統は近くなかった。
なおタイやマレー半島の個体群は IOC 14.2 では Otus lempiji だったが 15.1 で Otus lettia と変更されるなど地域によっては種境界が不安定な部分がある模様。Otus 属はまだまだ流動的要素があるかも。
記載時学名 Otus semitorques Temminck & Schlegel, 1844 (原記載) 基産地 日本。具体的記述は p. 25 以降にある。変種 (variete) または現在も亜種に相当する意味で使われる race (種族) の概念で Otus scops グループの7 "種" を扱っている。
Le hibou petit-duc a demi-collier du Japon のフランス語名を用いている (フランス語も "半分首輪がある" の意味)。具体的記述は p. 26 から、首輪 (collier) の記述は p. 27 の前の方で sur le dessus de l'oiseaeu entre le cou et le dos, un collier clair assez large, qui se prolonge sur les cotes du cou pour se reunir aux plumes ecailleuses encardrant le disque facial と出てくる。
首と背中の間に首輪模様が目立ち、首の側面から顔盤へとつながっているとのこと (そのため背中側 "半分" の意味らしい)。
Le hibou petit-duc du Japon がコノハズクを指しており、それに半分首輪がある位置づけ。japonicus は双方に使うことはできないためコノハズクの方に付け、オオコノハズクには別の学名と与えた模様。
英名も Collared Scops Owl だったが ("半分" の意味が抜けてしまった)、何を指して首輪と称したかはあまり把握されていなかったかも知れない。
Temminck and Schlegel が semitorques を用いた理由には Strix torquata Daudin, 1800 (参考) や Strix torquata Fischer von Waldheim, 1812 (参考) の用例があって属統合などで無効となる可能性を避けたためかも知れない。
フクロウ類では模様の特徴を採用することが難しく、地名や現地名が多用された事情もわからないでもない。
世界で3亜種が認められている (IOC)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に記載の亜種は3つで、基亜種オオコノハズク semitorques、琉球諸島のリュウキュウオオコノハズク pryeri (英国商人・博物学者で日本で横浜に住んでいた Henry James Stovin Pryer が由来)、まれな冬鳥のサメイロオオコノハズク ussuriensis (ウスリーの) である。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)にはさらに亜種不明が追加されている。
先崎 (2016) Birder 29(9): 9 はサメイロオオコノハズクに触れ、秋から冬に北海道で記録されるオオコノハズクの亜種に注意を促している。
Otus bakkamoena hatchizionis Momiyama, 1923 (参考) 基産地 八丈島 は Kuroda (1932) が pryeri のシノニムとした。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には当時の学名で Scops pryeri Gurney (Okinawashima) を別種プライヤーズクの名称としていた。
原記載 (Gurney 1889)。Seebolm の収蔵品の中にリュウキュウコノハズクとは異なるものを見つけて記載した模様。リュウキュウコノハズクと同所的に生息する別種とされたが、オオコノハズクに近いことはわかっていなかったようで標本と採集場所の情報しかなく生息状況などはわからなかったよう。
Ogawa (1908) で "リュウキュウ" を冠する名称となっていなかったのはおそらくこれらの事情によるもので、オオコノハズクの分布にも Okinawashima が含まれていた。
[音声]
オオコノハズクの「木魚鳴き」は少なくとも最近は有名になっていて、存在確認に有効な声である。
松田 (2021) Birder 35(6): 28-29 にこの音声についての解説がある。2013 年、飼育個体がこの声で鳴いたことで正体が明らかになった。
木魚鳴きにもさまざまなパターンがあるようで、時にミゾゴイと紛らわしいこともあるので注意が必要。
他にもさまざまな音声を出し、「ネコのような声」と称される声もある。この声は動物園個体でもよく聞かれ、餌乞いの声 (begging call) かも知れない。
オオコノハズク (バードリサーチ鳴き声図鑑) に亜種オオコノハズクの声が一通り登録されているようなのでご確認いただきたい。
-
コノハズク
- 学名:Otus sunia (オートゥス スニア) コノハズク
- 属名:otus (m) ミミズク (otus (m) フクロウの一種、otos 耳 Gk)
- 種小名:sunia (外) ネパール語 Sunya kusial (コノハズクを指す)
- 英名:Scops Owl, IOC: Oriental Scops Owl
- 備考:
otus は#オオコノハズク参照。
sunia の発音はわからないが短母音とすれば "スニア"。
東アジアを中心に分布する種で、世界で9亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は japonicus。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で亜種不明が追加されている。
少なくとも一部は渡りをするが越冬地は十分に記述されていない。種全体としては中国南部や東南アジア大陸部、インドネシアの一部、インドの一部が含まれている。
種の記載時学名 Scops sunia Hodgson, 1836 (原記載) 基産地 Nepal。
英名を Sunia または golden Scops としており、ネパール語で Sunya Cusyal とのこと。
もう1種記載する必要があり現在のヒガシオオコノハズク 記載時学名 Scops lettia Hodgson, 1836 (続きページ) で、こちらもネパール語から。Hodgson はネパールの種に nipalensis を与えることが多かったが同地から2種新規記載となったために nipalensis のような簡単な学名にならなかったらしい。コマドリとアカヒゲの学名のようなものと思えばよいだろう。
かつては Otus scops と同種とされその亜種扱いだったが分割された。
日本のコノハズクを含むと考えられるグループで最初に記載されたものが Otus sunia であったため現在はこの亜種となっている。Hodgson の記載経緯もあって学名語義があまりわかりやすいものではない状況になった。
後述のように Otus 属は島ごとに固有種を生む状況で新種が多数記載されている。分類見直し次第でコノハズクがどのグループに含まれるか扱いが変わることがあるかも知れない。
日本近傍の亜種として stictonotus (stiktos 斑点のある -notos 背中に Gk) 南東シベリア、中国北東部、サハリン、北朝鮮に分布し、中国南東部から少なくともタイ南部まで渡るとの記載がある。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではこの地域の亜種を stictonotus としているが、まだ名前の付いていない亜種が分布しているかも知れないとしている。
Hartert (1910-1922) p. 982 では熱帯のコノハズク類 (当時は同種) を Otus scops の亜種と考えるのに疑問を呈していた。翼式が違って十分に分割可能としていた。
japonicus は分離可能で stictonotus はシノニムと考えるとのこと。他の熱帯亜種は Otus scops に含まれるべきではないとしていた。亜種の音声についての記述はないがヨーロッパコノハズクの音声についてはすでに述べられており後述。
IOC の英名は Scops Owl(s) が複数種に分割されたため。
OED によれば scops は 1706 年の辞書に登場するとのこと。1781 年の Latham, General Synopsis of Birds で耳角のあるフクロウ類 (その後の記述では特に小型のものを指す) として記述。ラテン語 scops からの借用とのこと。これはギリシャ語 skops 由来で小型の耳角のあるフクロウを指していた。
Scops がなぜ属名に残っていないのか疑問を感じるが、Scops de Savigny, 1809 (分離前のヨーロッパコノハズクを指していた) の属名があって 19 世紀にはこの属名がかなり使われていた。
Hartert (1910-1922) p. 973 によれば Otus Pennant, 1769 が早いとの判定で同じ系統のものは Otus 属にまとめられた。
ただし Otus 属のタイプ種はインドオオコノハズク、Scops 属はヨーロッパコノハズクと異なるので系統分離次第では復活する可能性もある。
例えば NC_028163.1 (インドオオコノハズクのミトコンドリアゲノム) から BLAST を行うとコノハズクとかなり違う系統であることがわかる (一致率 85% 程度)。解読されている種類がごく一部なのでこれからの課題だろうか。
もう少し広い範囲で見ると分子系統分類にはまだ課題が残っており、Wang et al. (2023) Mitochondrial genome analysis, phylogeny and divergence time evaluation of Strix aluco (Aves, Strigiformes, Strigidae)
のミトコンドリアゲノムの系統解析ではフクロウが単系統にならない。
Otus scops と Otus sunia の関係が非常に近く見えるがこれは過去の学名が用いられていたためで前者のサンプルは韓国で得られたもの。現在の分類では Otus sunia に含まれる。上記の解析でヨーロッパコノハズクの学名に見えるものはすべてコノハズクだった (2025.4 時点)。
古い時代に用いられた Scops の属名から派生する属名は現在もいくつか使われている。
なお Scops Gray, 1841 の属名があって何とアネハヅルを指して使われていた。ギリシャ語 skops (見張り人。この意味は Phylloscopus の属名に現れる) で o は短音でギリシャ語の綴りは異なっている。
今では現れない属名だがこちらを読むならば "スコプス" と伸ばさず読むのが正しそう (The Key to Scientific Names の情報よりまとめ)。
ヨーロッパコノハズクの種小名は現在の日本産の学名には現れないが、これは "スコープス" と伸ばして区別するよい。短く読んでも間違いではないが語源を考えると伸ばして区別した方がよい。Phylloscopus を長音で読むのは同様の意味でふさわしくない。
コノハズク類を指す英語の scops は、OED によればイギリス式発音では o は "ア" と読み二重母音や長音を使わないのが標準的らしい。語末に子音が並ぶためだろうか。複数形も scops とのこと。
一方 scope (望遠鏡なども同様) の o は二重母音で発音する。
[ヨーロッパコノハズクとコノハズク]
japonicus の原記載。
Le hibou petit-duc du Japon Otus scops japonicus Temminck & Schlegel, 1844 でヨーロッパの Otus scops の日本版との位置づけ (当時は現代の亜種概念はまだ確立していなかった)。
duc はミミズクを指し、petit-duc でコミミズクに相当するフランス語名になる。hibou (イブと読む) はフクロウ類全般を指す。Le hibou petit-duc が現代の概念ではヨーロッパコノハズクに対応する。
当時すでに Otus 属と Strix 属が分離されていたため、コノハズクとアオバズクいずれにも japonicus / japonica を用いることができた (#フクロウ, #アオバズクの備考参照) が日本産なので japonicus / japonica とした程度でフランス語名とともにあまり深く考えていなかった印象を受ける。
ヨーロッパやアフリカとは違いがあるので、第3の "変種" (原文 variete。現在の日本語だと "バージョン" の意味が近い) として名付けたとのこと。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Otus japonicus と種扱いで、コノハズクとカキズクの名前が載せられていた。
Otus scops (ヨーロッパ) と Otus sunia (アジア) および Otus flammeolus (北米) のものは同種・別種扱いがさまざまだったが、Delacour (1941)
On the Species of Otus scops は色彩や形態学 (特に翼式) からすべてを Otus scops の亜種とすべきと提案。
Scops japonicus と種にする用例は Bonaparte (1854), Gray が行っていた。Ogawa (1908) の学名はこの時代のものと思われる。
Sharpe (1875) は Scops giu の亜種に japonicus を置いたとのこと。
Dement'ev and Gladkov (1951) は Delacour (1941) への注釈付きで別種扱い。これらが superspecies を形成していると考えていた。
声も違うとあり、Otus sunia は "ke-vyuyu-vyuyu" または "t'ok-klok-klok"、Otus scops は "splyu-yu, splyu-yu" または "k'yuyu-k'yuyu" で音節数が違い、音声も別種とする判断基準としていたことがわかる。なおコノハズク類のロシア名は splyushka (または sovka 小さいフクロウの意味) だがこの音声が由来 (Kolyada et al. 2016)。
ロシア語で splyu は "(私は) 寝る" の意味になり、"寝るよ、寝るよ" と鳴いていることになる。
splyushka は "寝る子" ぐらい雰囲気だろうか。
なお現在の名称でヨーロッパコノハズク Otus scops はヨーロッパでよく知られた鳥で声もよく知られている。高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) にも (当時はヨーロッパと同種とされていた) 「東半球の熱帯から温帯の大部分に分布し、林が十分にあれば、どこにでも見られる。夜のなき声で、彼らのいることがわかる」と記述されていた。
[姿のブッポウソウ]
日本でブッポウソウと鳴くのはコノハズクであることが (近年において) 判明したのは 1935 年のラジオ放送がきっかけであった歴史はよく伝えられている。
黒田 (1935) 仏法僧問題の終結。
「美濃飛騨 鳥と人 鳥の方言と民話」(日本野鳥の会岐阜県支部 1987, 2008 復刻) p. 10 に徳山門入地域の方言に "トキトン" とーきとん、とーきとんと鳴くという、と挙げられている。同県他の方言は仏法僧と聞きなしているものが多く、姿のブッポウソウと混同されていた時代の方言も含まれているかも知れないが、トキトンは純粋に声を聞きなしたもののように見える。
この資料は伝承を聞き取ったもので姿が確認されていたかどうかまでは不明。
「夏の鳥」(小学館 1984) pp. 142-143 に中村司氏の記事があり、概略を紹介しておくと 1933 年 (注記参照) に NHK が愛知県蓬莱山で夜間「ブッポウ」と鳴く声を放送し、ブッポウソウの声と説明したため、昼の声と夜の声は違うのか、ブッポウソウとは別種の鳥かと世間を賑わせたとのこと。早い話、世間では正体を知っている人も多かったが鳥類学者が説明できなかったらしい。
当時朝鮮在住の下郡山誠一氏と山梨の中村幸雄氏 (中村司氏の父) がブッポウと鳴く鳥はコノハズクであることを以前から知っていたことを山階氏が述べていたとのこと。
中村幸雄氏は正体を確かめようと山に通っていたが 1935.6.12 の夕暮れに声を聞いて大木を叩いたところ枯枝にとまって弓矢で射止めたとのこと。黒田長禮氏は飼育者から譲り受けて 1935.6.10 より飼育していたが 1935.6.12 早朝にブッポウと鳴くのを聞いたとのこと。黒田 (1935) も微妙な書き方で、下郡山氏の方が約4ヶ月早く決定の印刷公表と記しているなど、お互いの立場を尊重しつつも水面下で第一発見者争いが行われていたことが想像される。
中村司氏の記事も真相をもう少し世に残しておきたい意図で書かれた部分もあるだろう。「学会への公表」を山階氏が述べたものを有効とするか、印刷公表を有効とするかによって判断が分かれる部分もあるのだろう。現在に至る印刷公表至上主義 (?) にもつながっているのかも知れない。学名の先取権と同様、客観的に判断できるのはそれが最も確かではあろうが。
黒田 (1935) にも "Hartert 氏による" と記述されている部分があるので、後述の Hartert (1910-1922) の記述を読んでいなかったとは弁解できないだろう。
中村司氏の上記記事には若干不正確な部分もあるようで、国松 (2006) Birder 20(6): 34-38 から補っておくと、1933 年はラジオ放送の年ではなく、日本動物学会で川村多実二氏 (当時京都帝国大学教授。日本野鳥の会京都支部初代支部長) が「ブッポウソー」と鳴く鳥は姿のブッポウソウでないと考えると述べたもの。
上野動物園の古賀忠道氏はブッポウソウが夜間餌を食べていないことを明らかにした。
1934 年 NHK が真偽を明らかにするため中継を試みたが天候の問題失敗。
1935 年 NHK が 6/7, 6/8 に音声を全国中継に成功。6/7 21:30 が最初の中継だったとのこと。2日めも成功。黒田氏がレコードへの記録を依頼し、飼育者から譲り受けたコノハズクが再生に明瞭に反応したとのこと (この記事では 6/14 となっている)。この記述から推定すると中村幸雄氏は放送を受けて明確な証拠を残すために射止めたらしい。
黒田 (1935) 論文の表現からも 1935 年の放送はこの時系列らしい。この論文で川村多実二氏のことには触れられていないのは不思議でもある。
川村多実二の wikipedia 日本語版によれば 1908 年、東京帝国大学を成績優秀にて卒業し、大学院に進学した。このころから、形態、分類に偏った日本の昆虫学に対して疑問を抱くようになる との記述がある。1919 年に、京都帝国大学に日本で 2 番目の動物学教室が開設され、川村はその助教授に就任した。同じ年に 2 年間コーネル大学に留学し、そこで行った野外実習に強い影響を受けた。帰国後の 1921 年に同大の教授となり、動物生理生態学講座を開設、動物生態学の講義および実習を日本で初めて実施したとのこと。
形態、分類を中心としたと思われる東京を中心とした日本の鳥学と一線を画していたため生態研究が評価されにくかったのかも知れない。
中西悟堂「定本・野鳥記」8 p. 39 から補足しておくと、1934 年の中継の試みは、1933 年に当時は長野で全国で初めて戸隠から野鳥の音声中継を行った、前橋放送部長の猪川氏が上州迦葉山 (現在群馬県沼田市) で試みたものとのこと。
中西悟堂「野鳥と生きて」(1956, 該当部分は 1954) によれば猪川氏は転任して京都部長となったが辞任してしばらく消息不明だったとのこと。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 164 からさらに補足しておくと、6 月の生放送の時に東京浅草の傘屋さんの家で飼われていた枯れ葉色の小型ミミズクが突然ラジオの声に誘われて鳴いたとのこと。このことで問い合わせを受けた鳥学者が飼育者から譲り受けて確かめた経緯らしい。
中村幸雄氏は「ブッポウソー」と鳴くのはコノハズクであると主張していてこの放送のために捕獲許可を得ていて当夜、河口湖の北方の御坂の山で声の主を撃ち落としたと、中村司氏と若干異なる記述となっている。
おそらく情報に多少の混線が入っていて、1933 年の川村多実二氏の見解を受けて中村幸雄氏が本腰を入れて正体解明に取り組んだものと考えられる。中村司氏の記述には日付や時刻が入っているのでこちらの方がおそらく正しく放送の後に射止めたものだろう。
これらの情報を見ておくと、単独で飼育されている場合は傘屋さんが声を知らなかったぐらいにあまり鳴かないらしい。
「甦れ、ブッポウソウ」(中村浩志 山と渓谷社 2004) の第 10 章 なぜ声をとり違えられたのか (pp. 115-124) に姿/声のブッポウソウの歴史的経緯の考察がある。簡単に振り返っておくと、取り違えの確実な証拠は 1809 年の「紀伊国名所図会」にコノハズクとして矛盾しない記述がある (pp. 119-120)。
1833 年にブッポウソウを指していると考えられる記述がある。
1929 年矢沢米三郎「雷鳥」、1931 年太田成和「ぶっぽうそう鳥の研究」はいずれも間違いに気づいていないとのこと。
同書 pp. 116-117 に 1935 年の出来事が記述されているので少し補足しておくと、コノハズクを飼育していたのは西尾勇氏とのこと。譲り受けた黒田氏が 1935.6.12 早朝 5:10 にブッポウと鳴くのを聞いたとあるが、録音再生に反応したことは書かれていなかった。出典は「山梨の理科ものがたり」(山梨県小中学理科教育研究会 1981) とのこと。語り継がれてすでにかなり長期間を経ているので情報は少し変質していたかも知れない。
後に見つけて挿入する形となるが、「野の鳥の生態」(下村兼史 1931 初出。「日本野鳥記」1 講談社 1985 収録より) pp. 11-12 でも気づかれていなかった。南九州の霧島山麓で地元の人は唐雲雀と言って仏法僧と云う鳥は未だ此山の奥に居て「仏法僧」と鳴くと言っているが、下村氏は唐雲雀こそ仏法僧で人々の言う仏法僧は架空のものと考えていた。
実は地元の人の方が違いをよく知っていたのかも知れない。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 105 (1946 年初出) には年々三河国蓬莱山からその音声を放送しているものとの記述があった。一度始めると同じことを毎年行うのは慣習だったのかも知れない (日本的なのかどうかは知らない)。確かに毎年新しい番組を考えるよりも安上がりだったかも知れない。
姿と声のブッポウソウの判明経緯が毎年同じように学者の言う通りに説明されていたことは想像に難くなく、番組に登場しない詳しい経緯を知っている者にとっては物足りなく感じたことだろう。中西氏は表現は抑えているものの、苦々しく思いながら聞いていたのではないだろうか。
海外では以前から当たり前のように判明していたのでは? と思わせるが簡単に探した範囲で (古い話すぎて?) 古い記述を見つけられなかった。
Eversman (1866) "Estestvennaya istoriya ptits Orenbugskogo kraya" を調べてみるとヨーロッパコノハズク (まだ同種だった時代) はこの時代は sova-malyutka (小さなフクロウぐらいの意味) と呼ばれていて、音声由来の splyushka は比較的新しい名前なのかも知れない。ただしこの書物に声の記述はあって特有の声はすでに知られていた模様。
Hartert (1910-1922) p. 980 にヨーロッパコノハズク (まだ同種だった時代) の音声の詳しい記述があった。単調な物憂げな声でヒキガエル (Unke) にもやや似ている "Klue" (最後は u のウムラウトでクリューのような音になる) を長く続ける。渡りの際にも声が聞かれる。より短い2音節にもなって "Kiwi" とも鳴く。
昼間出会うとどのような反応を示し、危ないので標本採集の際は要注意なども書かれている。
となっていた。ヨーロッパコノハズクは声も姿もやはりよく知られていて Hartert の本ならば当然日本の鳥学者も目を通していたことだろう。
Dement'ev and Gladkov (1951) の音声表現もどこかに記載されているものではないかと思われるが特に音声部分を指す文献の記載はなかった。ヨーロッパと違う声で鳴く "コノハズク" がいることは周知事項だったのではないだろうか。繁殖などに関係する過去の文献は引用されているのでその中に記述があるかも知れない。
なお Delacour (1941) は標本のみの検討で音声への言及はない。音声を検討すれば別種相当になっていたかも。
Dement'ev and Gladkov (1951) のブッポウソウの項目では音声はよくない声で、低くのどにかかった声で鳥類学者 Spangenberg [1898-1968, Dement'ev と同時代で Dement'ev and Gladkov (1951) 編集のヨタカ類を記述した著者の一人] が伝えるように "karr-karr" または "cher-cher" (多分真似したのだろう) と鳴くとある。
この部分の表現や著者内訳を読むとコノハズク類の音声は Dement'ev 自身が実際に聞いて違いを確認しているかも知れない。
多少不思議に感じるのはコノハズクという小型のフクロウの姿は日本でも別名があるぐらいに知られていたはずなので、このフクロウは何と鳴くのか誰も、特にヨーロッパでは何と鳴くのかなど日本の鳥類学者が気にしなかったのだろうか。
「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) では漂鳥 (一部夏鳥か?) となっていた。声のブッポウソウ、姿のブッポウソウの解説は同書 p. 39 で、ブッポウソウはフクロウ類の後に並べられていた。
コノハズクの音声記録は世界の音声データベースでも驚くほど少ない (海外バーダーのよく訪れるリュウキュウコノハズクの方が多い)。音声録音が普及した現代ではコノハズクはもはや身近に声を聞く鳥でなくなっている感じがする。
また大陸のコノハズクの音声は少し違う印象を受ける。
一方で興味深い中国の記事を見つけた: 三宝鳥。
このページの解説によれば、日本の民話で土佐に大変聡明な人がいて、山には三宝鳥というとても声のよい鳥がいると広めた。この噂が領主に届いてそれはぜひとも聞きたい。しかし道がないので行けない。
道路を作って山に行けるようにするようもちかけたとのこと。
実際に山に行ってみるといるのは山鳩ではないか。デデポーポーと鳴いている。問い詰められてこの声が三宝鳥のものだと思っていたと答えた。批判は浴びたが道ができて村人は山に行けるようになって喜んだとのこと。
和訳あり。
これは "とんち" ではあるが、三宝鳥 = ブッポウソウ はキジバトの声とも混同されていた可能性もあるのかも。
中国語の三宝鳥 (ブッポウソウ) は日本語由来とのこと。
神秘的三宝鳥 によれば、806 年弘法大師が中国から日本に帰って高野山でブッポウソウを指す "閑林" (漢字表記は原文参照 Xianlin) の7つの驚きについて記述し有名な詩文を残したとのこと。詩文もそのまま表記できないので原文を参照。
漢詩と翻訳があった 漢詩紹介 (関西詩吟文化協会 2014)。
コノハズクとブッポウソウの関連は弘法大師にまで遡るらしい。
国松 (2006) Birder 20(6): 36-37 にも同じ漢詩が紹介されている。
佛法僧と手紙 (ブッポウソウ総合情報センター・ニュース 2021) に関連した情報や考察もある。
経典がインドまたは中国由来と考えるとブッポウソウはインドの一部と中国南部にも分布する。
コノハズクであればおそらく亜種 sunia で、日本のコノハズクほど等間隔の声ではないのでこれを3音節に聞きなすのは無理がありそうな気がする。経典の佛法僧の名称は (架空のものかも知れないが) やはり色彩などに由来していたのでは? ブッポウソウの色彩を指していたとすれば三宝鳥でもふさわしい感じもする。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 pp. 248-249 (1942 年初出) に面白い逸話が紹介されている。
1935.7.27, 28 の両日 (1935 年に鳥学上で正体が解明されたとされる直後) に東京の市中でコノハズクの声が相次いで聞かれ、東京市内にいるはずがない、アオバズクの聞き間違いではないかと議論になったとのこと。声を報告したのは中西氏の知人の情報で信頼できる情報とのこと。
1935 年当時は種明かしはされていなかったようだが、東京目黒でコノハズクを飼育している人があり、中西氏が訪問して外に出して写真を撮ろうとしているうちに飛び去ってしまったもので、その翌日と翌々日の記録であったとのこと。このことから移動経路が判明した事例として紹介されていた。その時点で明らかにしなかったのは無断で飼育していたならば迷惑がかかる可能性があるためと解説しているが、自分が逃してしまったのでは立場上格好が悪く、公式記録に残る前に後になって真実を伝えたのだろう。
中西氏は情報ネットワークが重要であることを記されているが、状況は今とあまり違わなかったのかも知れない (昔でも今でも情報は全部自分のところに入ってくるとの自慢話と思って見ればよい)。
中西氏が訪問した目的も正体解明が発表されたことに関連があるかも知れない。
コノハズクを飼育している人というのは当時案外あったのかも知れない。黒田氏が譲り受けた事例は東京だったのでたまたま有名となったが、ラジオ放送に反応した飼育コノハズクは全国で他にもあったのではないだろうか。黒田氏が譲り受けて2日後に声を聞かれるぐらい鳴くのであれば、飼育コノハズクの声を知っている人はたくさんいたのではないだろうか。動物園で飼育されていても基本的に勤務時間外となる夜の声は把握されていなかったなど。
中西悟堂「野鳥記コレクション」I 野鳥と共に (もとは「定本・野鳥記」10 巻所収だが持っていない) に興味深い記事がある。記述された年代を見るとかなり新しい記事で、1930 年代の状況がどこまで正確に記憶されているかは必ずしも確かでないが、より詳細をたどることができる。以下私的注釈付きで紹介 (英語ならば annotated などと表現される):
p. 143 に朝鮮京城の動物園園長の下郡山氏が旅順でプッポウソーと鳴いていたものを射ち落としたらコノハズクであったことを発表し、川村氏がこれを披露したとのこと (学会報告は川村氏自身による情報ではなかった。また黒田氏が印刷公表にこだわったのは印刷された形で発表されなかったためと想像できる)。
p. 144 中村幸雄氏は過去ブッポウソウの繁殖地を調査していたがブッポウソウと鳴くのを聞いたことはなく、コノハズクであると主張していた。
p. 145 中村氏はブッポウソウと鳴いているところを何度も目撃していた。中西氏のもとに中村氏から「中央の学者は中村氏のコノハズク説を信用していないようだが、従来の常識にもとづいて仏法僧鳥についてはうかつに講演や執筆をしないように」趣旨の書信があった。当時の中西氏は野鳥運動の大衆化を進めていたころで、誤ったことを述べてしまうと信用を失うとの忠告であったとのこと。
中西氏はこのころは自身でも疑問と持っていて昼と夜で二通りに鳴き分ける鳥はどう考えてもあり得ぬ。と記述していたがあくまで回想録なので「中西氏も真実は把握していなかった」と読むのが正しいだろう。
以下コメント: 文面だけを見れば中村氏の親切な忠告と読めてしまうが、文脈から全体的に判断すると、中村氏は中西氏が真実を把握しているかも知れないので、中西氏の社会的立場を褒めながら利用して、自分が証拠物件を得るまでは先に発表しないように釘を差しておいたものだろう。そして中村氏は先を越されないように勤めを終えて毎晩山に通うことになる。
中西氏の方はこの書簡を紹介することで自身に情報が集まることと、自身が野鳥運動の大衆化の中心であったことを間接的に自慢する形になっている。
このように読むと「定本・野鳥記」がいろいろ内幕を紹介していてどれほど面白い文献かわかっていただけるだろう。
p. 146 ブッポウソウの生息地では夜に鳴かない。中西氏はブッポウソウと鳴くのは何かを突き止めるために鳥獣商からコノハズクを入手しようとしたが手に入らなかった。ひなを捕獲して1年飼育してみればと考えたが手に入らなかった、またそれでもあきらめずに秋のかすみ網にかかることを期待したがこれも手に入らなかった。中西氏も含めて一番乗りを目指していたことはいかにも明白だった模様
(皆が同じことを考えたので奪い合いになって鳥獣商も調達できなかったのだろう)。
pp. 149-150 中村氏は前述のように証拠物件を射止めて 1935.6.14 に学会に報告。6/15 に黒田氏が学会発表をした順序となっている。
以下コメント: 昔も今もそうであろうが、「新発見を学会 (または専門家) に報告」はあまりよくない場面も多い。新発見ならば論文発表をした方がよいし、「学会で報告された」などの形で報道で取り上げるのは好ましくない。学会で発表されても撤回されている事例はいくらでもある。
中村浩志氏の「甦れ、ブッポウソウ」の記事でも黒田氏が中村幸雄氏と同日にコノハズクの声を聞いているのを「奇しくも」と表現されていたが、なぜ同じ日付なのか不自然さも込められていたのだろうか。
p. 152 ブッポウソウと考えていたものコノハズクであったことが判明した霊場鳳来寺では、尊厳を傷つけるとのことで担当した放送局長が「天下の怪鳥」との論文を出し、浅草の傘屋や甲州の山奥のものが鳳来寺のものと同じとは限らない、とケチを付けたとのこと。(言い出したのは誰かわからないが放送局長の責任として対処する必要があったのだろう)
p. 153 正体が判明したため改名の議論があって候補の名前も提案されたが、仏法僧目仏法僧科に使われているので遡って全部書き換えるのは困難なのでそのまま変更なしとなった。
以下コメント: 日本鳥類目録 改訂第8版でアホウドリの改名提案に対する説明と同じだなあ、と思ってしまった。もとは日本に1種しかいないブッポウソウを世界を代表させて科名や目名に用いたことに始まっていたわけだが、ここで由来となった属・科を重視して名称を整理していれば世界に合わせたものになってむしろすっきりしていたかも。
この点はサンショウクイ科でも感じるところ。中国はサンショウクイ属を除いて名前を変えた。ただし仏法僧目は中国でも現在使われており、ブッポウソウ属のみ三宝鳥属と変更となった。
ブッポウソウは戦前の話なので、現在以上に一度付けた名前は変えたくなかったかも知れない。
冒頭 AviList の目一覧を見ていただいても、ブッポウソウ目 Coraciiformes の対応が悪いのが目立ってしまう。ブッポウソウの名称を変えないと一度決断してしまったために後世で変更しづらくなってしまった側面もあるだろう。
中西氏がこういう話題を取り上げられる時は一般的にちょっと違和感を残されていたようである。後は読者の判断に任せるとしても、ここでブッポウソウを改名しなかったことは [大幅に表現を抑えて表現すると (笑)] いかにも人間模様らしい部分を感じられていたのだろう。当時は海外のブッポウソウ目の鳥にはまだあまり和名が付いていなかったかも知れないがこれは調べればわかるだろう。
「Coraciiformes はなぜブッポウソウ目なのですか?」と聞かれれば以上のような回答になる。
p. 154 学会ではコノハズクは渡り鳥ときめていた (中西氏の表現) が、岡董高 (しげたか) 氏が 1956 年青梅市の奥の小曽山村でコノハズクの越年を記録して留鳥ではないかと申し立てたとのこと。もっとも当時の学会の黒田氏の表現も曖昧だったようで余り他地方に渡りをしないとも折りにふれて述べていたとのこと。
コノハズクの所在は繁殖期の音声が決め手となっていたので冬は渡ってしまうのか鳴いていないだけなのか判断が難しかった。現代の図鑑を見てもどちらとも解釈できる表現になっている。
アオバズクの方は昼間もみつけやすく渡りをすることはより容易にわかっていたのだろう。
ヨーロッパコノハズクでは Eurasian Scops Owl (Bird Migration Atlas) を見ると比較的短距離の渡りを行うグループだろうか。小型の種類なので GPS 追跡なども難しさがあるのだろう。コノハズク類全般の渡りについての情報は他の項目も参照。
p. 159 武蔵野名所図会によれば、鳴き声由来のコノハズクの名称を、御岳は神域のため「御祈祷」とされ、高尾山は仏域ゆえ「仏法僧」と呼ぶとのこと。聞きなしにも違いがあると言うこともできるが、中西氏が取り上げたかったことは明白だろう。
[ロシア沿海地方のコノハズク]
Glushchenko et al. (2014) On morphism and subspecies of the oriental scops owl Otus sunia in Primorsky Krai (pp. 443-447)
がロシア沿海地方 (ラゾフスキー地域) で 1983.5.14 に採集された標本に色彩から亜種 japonicus ではないかと考えている個体を紹介している。
Koblik (2003, 2019 再掲) On the question of color variation of the oriental scops owl Otus sunia (pp. 5107-5109)
に亜種 stictonotus のロシアでの色彩多形についての全般的議論がある。2002.5.21 に採集した1例のみが純粋に "褐色型" と言えるとのことで、日本の亜種 japonicus に最も近いとの議論がある。
The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声) part 2 1:44 Slovno khronometr, otschityvayut nochnye chasy ussurijskie sovki (まるでクロノメーターのようにコノハズクが夜の時を刻んでいます)。(聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
[コノハズク類の分子系統解析]
近年コノハズク類の島の固有種の発見が相次いでいる。Melo et al. (2022) A new species of scops-owl (Aves, Strigiformes, Strigidae, Otus) from Prncipe Island (Gulf of Guinea, Africa) and novel insights into the systematic affinities within Otus
分子系統樹も出ていて日本に関係する種ではコノハズク、リュウキュウコノハズク、そしてこの2種と系統の異なるオオコノハズクが含まれている。オオコノハズクとかつてい同種とされた Otus lempiji は近くなかった。インドオオコノハズク Otus bakkamoena、チャメオオコノハズク [山崎他 (2017)] Otus lettia ともあまり近くなかった。
コノハズク (+ リュウキュウコノハズク) とヨーロッパコノハズクも系統的にかなり離れている。コノハズク周辺も結構細かく種に分かれているのでコノハズクも詳しく調べるとさらに分割されるかも。
この研究で調べられているコノハズクは中国とタイのものを同種として遺伝情報を組み合わせて使っている (新種記載のアフリカ地域から遠いためまとめて扱っている可能性もあるが、個々の個体の情報も十分ではないのだろう)。
Flint et al. (2015) Reprising the taxonomy of Cyprus Scops Owl Otus (scops) cyprius, a neglected island endemic こちらはキプロスの島の固有種。上記 Melo et al. (2022) の系統樹ではそれほど分離されていない。
Sangster et al. (2013) A New Owl Species of the Genus Otus (Aves: Strigidae) from Lombok, Indonesia リンジャニコノハズク Otus jolandae Rinjani Scops-Owl の記載。
Rando et al. (2013) A new species of extinct scops owl (Aves: Strigiformes: Strigidae: Otus) from Sao Miguel Island (Azores Archipelago, North Atlantic Ocean) (絶滅種。半化石で人が定住したことで絶滅したと考えられる)。
Otus 属は高次捕食者にもかかわらず飛翔力を失いやすく島で半ば地上性の固有種になりやすいらしい。フクロウ類はあまり飛ばなくても獲物が捕れるのだろうか。
[マダガスカル地域で地上性となった・巨大化したコノハズクの系統]
Duhamel et al. (2020) Cranial evolution in the extinct Rodrigues Island owl Otus murivorus (Strigidae), associated with unexpected ecological adaptations
にも面白い情報があり、ロドリゲス島の絶滅種 Otus murivorus Rodrigues Owl は頭も脳も小型化し、嗅球 (olfactory bulb) は大きかったとのこと。地上性となって嗅覚で食物を探すスカベンジャーになっていた可能性があるとのこと。ただし 18 世紀中頃と推定される絶滅前には小鳥や両生類、爬虫類を食べていたとの歴史的記述があって骨格からの予想とは少し違いがある。
ロドリゲス島にはキツツキがおらず、樹洞は限られていたので地上に営巣していたのではないかとのこと。そのため人為導入されたネズミ類の被害を受けた可能性がある。
島に定着できるぐらいの飛翔能力は持っていたが地上性に移行したフクロウ類の運命だったのだろうか。飛翔能力をディスプレイに用いることの多い昼行性猛禽類とは進化の道筋が異なりそう。
#アマツバメ備考の [渡り鳥における磁気定位] にもあるように夜行性となることで磁気定位能力が弱まった可能性もあり、猛禽類の中でも昼行性系統と夜行性系統で分散様式や種分化メカニズムが違う要因にもなっているかも知れない。
Louchart et al. (2018) Ancient DNA reveals the origins, colonization histories, and evolutionary pathways of two recently extinct species of giant scops owl from Mauritius and Rodrigues Islands (Mascarene Islands, south-western Indian Ocean)
比較的近年絶滅した大型のコノハズク類の半化石を用いた系統研究。この地域の島に何度かにわたって定着した。鮮新世 (Pliocene) にサイクロン活動が現在より活発であったことに助けられた遠方の離島への進出ではないかと考えている。体サイズは通常のコノハズク類の2倍にもなったが複数の系統で翼の縮小、頭骨や眼窩サイズの相対的な縮小が独立して起きた。
例えば日本のコノハズクは渡りを行うが#リュウキュウコノハズクの遠距離の島の間の移動で提案されているような台風やサイクロンの影響を考えている点も面白い。
MF381872.1 から BLAST を行うとだいたいの関係がわかるのでお試しを。コモロコノハズク Otus rutilus Madagascar Scops Owl / Rainforest Scops Owl がこの中でマダガスカルの種。
絶滅した Mascarenotus sauzieri Mauritius Scops Owl は古く分岐した別系統だがコノハズクのグループに入る。全長 60 cm 程度。人の入植前は最大の肉食動物だったとのこと。
1837 年の目撃が最後でサトウキビや茶のプランテーションによる生息地縮小や狩猟のため 1859 年には絶滅したとされる (wikipedia 英語版)。
2021 年以降 IOC は Otus 属に移動。Boyd は他の絶滅種と合わせて別属でもよいと考えている。
[ヨーロッパコノハズクの減少]
ヨーロッパコノハズクはここ数十年減少が著しいとのこと。Treggiari et al. (2013) Habitat selection in a changing environment: the relationship between habitat alteration and Scops Owl (Aves: Strigidae) territory occupancy
のイタリアの研究によれば好む生息地は中程度の斜面の中程度の標高、生息地に河川や放牧地・草地が含まれたがニセアカシア Robinia pseudoacacia を含む森林地帯は避けていたとのこと。土地利用がモザイク環境の場所ではあまり減少していないとのこと。
保全のためには河川改変を避け、放牧地・草地を維持するような農業形態が望まれるとのこと。
Sergio et al. (2008) Conservation of Scops Owl Otus scops in the Alps: relationships with grassland management, predation risk and wider biodiversity
はその前の研究になるが耕作放棄による無秩序な森林の拡大を避ける、草地が大事であるとの指摘がある。
コノハズクとは違いがあるかも知れないが一般論的にあてはまると考えてみると、コノハズク類は純森林性というより草地の存在 (採食場所だろうか) が重要で、森林ばかりの所には住みにくいらしい。生息に森林は必要だが森林と草地の境界が大事で河川改修とともに生息に向かない環境が増えているのかも、フクロウはむしろ森林が得意でフクロウの分布が広がっているのかも (全国鳥類繁殖分布調査 2016-2021 の結果より)。
フクロウのみが身近な繁殖フクロウ類となってきている状況はあまり歓迎すべきものではないのかも知れない。
原 (2019) Birder 33(9): 46-49 によればオオコノハズクとコノハズクはほぼ同所的に生息するがフクロウの多いところでは少ないとのこと。ヨーロッパとは事情が異なるかも知れないが、種間関係よりもこのような環境の好みが現れているのかも知れない。アオバズクの繁殖地では営巣できるような木のまわりに開けた空間のある環境がそもそも限られたところにしかないこと、ヨタカの減少も同様の環境変化が現れているのだろうかとふと考えてしまう。
-
リュウキュウコノハズク
- 学名:Otus elegans (オートゥス エーレガンス) 優雅なミミズク
- 属名:otus (m) ミミズク (otus (m) フクロウの一種、otos 耳 Gk)
- 種小名:elegans (adj) 優雅な、上品な; 日比 (2000) Birder 14(1): 68-70 では上等な、より抜きの
- 英名:Ryukyu Scops Owl
- 備考:
otus は#オオコノハズク参照。
elegans は冒頭が長母音でアクセントもここにある (エーレガンス)。
世界で4亜種が認められている (IOC)。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) でも同じ扱いだが英名は Elegant Scops Owl としている。複数種に分けられる可能性を示唆している。
記載時学名 Ephialtes elegans Cassin, 1852 (原記載) によれば下面は handsomely mottled とあり、解説にも This is one of the handsomest of the small species of owl とあり、記載者の意図は "優雅な、上品な" の意味でよさそう (同じ種小名を持つ #ミヤマホオジロよりは明確)。
採集場所の経緯度が記されてあるが海上にあたり、生息地は Northern Asia, Japan? とちょっと怪しい表記になっている。記載されたものは亜種と対応しているかなどまだ歴史的検証が必要な部分が残っているかも。
記載時の Ephialtes の属名は von Keyserling and Blasius (1840) が Scops ephialtes Savigny, 1809 と当時ヨーロッパコノハズクに用いられた学名 (Linnaeus の Strix Scops の種小名を属に昇格したために提案されたもの) の種小名を属に昇格したもの。ephialtes (Gk) 悪魔や悪夢の意味。
Kaup (1851) も同名の Scops の亜属を用いた。こちらは現在の分類でアフリカオオコノハズク Ptilopsis leucotis Northern White-faced Owl がタイプ種 (The Key to Scientific Names)。
すなわち記載時学名では "優雅な悪魔" だったことになる。Cassin が当時 Ephialtes 属で命名したフクロウ類は人名由来が2つあって色彩を表現したものはなかった。当時は別属だったが Scops 属などには多数の種が記述されており、重複可能性を考えるとすでに記述的種小名が難しい時期だったのかも。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に記載の亜種は亜種リュウキュウコノハズク elegans とダイトウコノハズク interpositus (interpositus 中間の)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
この亜種は黒田 (1923) の記載 (原記載。当時は Otus japonicus interpositus とコノハズクの亜種) したものだが、
黒田 (1928) の記載した台湾の蘭嶼島の亜種 botelensis (英名 Lanyu Scops Owl。記載時学名 Otus sunia botelensis Kuroda, 1928 で Otus japonicus と Otus sunia が別種とされていた時代のもので実にややこしい。現在の分類ではリュウキュウコノハズクが別種でその亜種となっている) と混同されていることがたまにある。
1980 年代後半から 1990 年代にかけてセレベスコノハズク Otus manadensis 当時の英名 Celebes Scops Owl の亜種とされて (山階 1986)、リュウキュウコノハズクの名称が日本産鳥類から一時消えたことがある [田仲 (2021) Birder 35(6): 71]。分類の変遷については安部 (1993) Birder 7(8): 18-21 にも記載がある。
現在のセレベスコノハズクはスラウェシ島のみに分布する種類とされ、IOC 英名は Sulawesi Scops Owl。
#コノハズク備考の [コノハズク類の分子系統解析] にあるようにこれら過去に同種とされた種とは系統は近くなかった。
高木 (2021) Birder 35(6): 32-33 にダイトウコノハズクの研究「南大東島にのみ生息する希少種 世界最先端の生態学研究が行われているダイトウコノハズク」がある。
亜熱帯島嶼のフクロウの個体群動態を最新統計手法で解明 で解説を読むことができる。Sawada et al. (2021) Missing piece of top predator-based conservation: Demographic analysis of an owl population on a remote subtropical island が発表論文。
Sawada et al. (2018) Distinctive features of the skull of the Ryukyu Scops Owl from Minami-daito Island, revealed by computed tomography scanning
は頭骨の解析。
Takagi et al. (2015) A breeding record of the Ryukyu Scops Owl on Okinoshima, in northernmost Fukuoka, Japan 福岡の離島 (沖ノ島) での繁殖。少なくとも 23 個体のオス。DNA でも確認。
Hsu et al. によれば南北でかなりの遺伝的距離があるが島の間の非対称な移動が起きていることが示唆され、台風の動きに一致しているかも知れないとのこと。Phylogeography of Elegant Scops Owl (Otus elegans)
Genbank データを用いて BLAST をしてみると2系統に分かれて通常ならば別種でも構わないように見えるぐらいだが、分岐は浅くて相互に混じっているらしいことは見ることができる。
さらに Sawada et al. (2023) First direct evidence of inter-island dispersal of Ryukyu Scops Owl Otus elegans 標識個体が島から島へ 52.7 km 移動した初めての証拠とのこと。
リュウキュウコノハズク Otus elegans の島間移動の初めての直接的証拠。
-
シロフクロウ
- 学名:Bubo scandiacus (ブーボー スカンディアークス) スカンディナビアのフクロウ
- 属名:bubo (m) フクロウ
- 種小名:scandiacus (adj) スカンディナビアの (-acus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Snowy Owl
- 備考:
bubo は母音2つとも長母音 (ブーボー)。
scandiacus は Scandia は短母音のみ。接尾辞 -acus の冒頭が長母音でアクセントもここにある (スカンディアークス)。
北極圏と周辺に生息し、冬は少し南に渡る。単形種。かつては単形属で Nyctea scandiaca とされていたが分子系統解析で Bubo 属に含まれた。まだ議論があるとのこと (wikipedia 英語版に他のフクロウ類のとの関係も含めて詳しい解説がある)。
Hartert (1910-1922) では p. 958。Nyctea 属は Bubo 属に非常に近いが "耳のような羽" を欠いている。
nyctea は nuktia 夜の (Gk) 由来。
記載時学名 Strix scandiaca Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 'Habitat in Alpibus Lapponiae' ex Fn. Suec, Aves no. 46, there based on a drawing by Rudbeck (Avibase による。図版がタイプとなっている)。
Strix Nyctea Linnaeus, 1758 は次のページに記載されており、こちらは生息地がヨーロッパとアメリカの極北地方となっている。同じものと判定されたが Strix scandiaca の方が先に現れるため後者はシノニムとなる。
しかし Strix Nyctea の種小名が名詞なのでこちらは属名に昇格できた次第。
有効な学名となる以前には Strix candida (Latham) "白いフクロウ" のような学名もあり、Ermine Owl (Latham) の英名があった。Strix Erminea Shaw, 1809 (参考) はそれをもとにした学名とのこと。Erminea は古フランス語の Hermine / Ermine 白い外套由来とのこと。
凝った学名になっているのは Strix alba Scopoli, 1769 (参考) のような自明な学名は当然すでに使われていたため。これは現在の(アメリカ)メンフクロウ Tyto alba (Western) Barn Owl として利用されて属が変わっているが Strix 属にまとまっていた時代には他には使えなかった。
[虹彩の色]
シロフクロウはなぜ黄色い虹彩を持っているのか、との疑問がある。
Passarotto et al. (2018) The evolution of iris colour in relation to nocturnality in owls
はそれにそのまま答えたものではないが、昼間に狩りをするフクロウ類の虹彩は黄色、完全夜行性になると暗色になる傾向があるらしいとのこと。
フクロウ類の虹彩は基本が黄色系で、暗色の虹彩は夜行性への適応との考えである。夜行性の種類は獲物に気づかれないように暗色の虹彩となったなどの解釈が出ている。
#アオバズクの備考の [昼行性フクロウ類の進化] の論文ではシロフクロウを昼行性に適応した種類として取り上げている。
[フクロウ類のゲノム研究]
フクロウ類のゲノム解析から夜行性の捕食者としてどの遺伝子が関係しているか候補を調べた研究: Espindola-Hernandez et al. (2020) Genomic Evidence for Sensorial Adaptations to a Nocturnal Predatory Lifestyle in Owls。
光の伝達に関わる視覚に関連する遺伝子、聴覚に関連する遺伝子、概日リズムや羽毛構造に関連する遺伝子などが選択を受けている証拠がある程度みつかった。新規調査種は8種で日本で記録される種も多くワシミミズク、フクロウ、トラフズク、コミミズクも含まれている。
Baalsrud et al. (2024) Evolutionary new centromeres in the snowy owl genome putatively seeded from a transposable element (preprint)
フクロウ類では染色体数の違いが多く動原体付近の構造も特殊であることが知られていたが、シロフクロウの高精度の染色体レベルのゲノム解析を行ったところ、鳥類の中でも反復配列率 (28.34%) の際立って高い種であることが明らかになった (#ミサゴの備考 [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] のオウギワシの例も参照)。
多くの部分は内在性レトロウイルス ERV1 起源と見られ、動原体付近に際立っている点はオウギワシと異なる。
動原体付近の反復構造はニワトリのものとは異なっていた。生殖隔離による種分化に役立っていると考えられる (#オシドリ参照)。メンフクロウと比べても反復配列率が高かった。カリフォルニアコンドルとは染色体レベルで共通性がかなり似ているが再編成もある。再編成がいくつも起きているオオタカとはかなり違う。
反復配列の多さが過去の系統解析に影響を与えている可能性がある。
フクロウ目とタカ目 (とはいえより似ているのはコンドル目) の染色体の遺伝子構成の類似性からこの両者が姉妹関係をなすことを示唆するとしている。
精度の高いゲノムが得られたのはこれが最初なので今後さらに研究が進む (タカ類とフクロウ類の進化は何が違うのかや transposable elements から見た進化の歴史など) ことが期待される。
AviList (2025.6) でコンドル目とタカ目が分離されたことも受けてさらに少し可能性を考察してみると、フクロウ目とコンドル目がむしろ系統をなして、タカ目は別系統の可能性もあるかも知れない #ミサゴ備考の [近代的な陸鳥の進化] [2025.6 さらに追記] 部分を参照。
-
ワシミミズク
- 学名:Bubo bubo (ブーボー ブーボー) ワシミミズク
- 属名:bubo (m) フクロウ、特にワシミミズク
- 種小名:bubo (トートニム)
- 英名:Eurasian Eagle Owl
- 備考:
bubo は母音2つとも長母音 (ブーボー)。
記載時学名は Strix bubo Linnaeus, 1758 だったが Dumeril (1806) が Bubo 属を導入したもの。フランス語名では ducs を与えている。
#シマフクロウの原記載に登場する Bubo maximus の学名があるが、種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる (#ノスリの備考参照)。
この学名は Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも登場する。
他にも Bubo Ignavus Foster, 1817 [Hartert p. 960] ignavus は "不活発な" の意味 (イグアナの語源とは無関係)、
Bubo europaeus Lesson, 1830 (参考)、
Bubo strix Gistel, 1848 (参考) もあった。
亜種記載を見ると Bubo bubo の現代の学名が使われるようになったのは比較的遅く、1903 年のものが最初のよう。それまでは Bubo maximus の学名が標準的で、Gould (1873) の図版にも Eagle Owl として現れる: 参考 Bubo maximus。
[亜種]
ユーラシアに広く分布し、16 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は borissowi (ロシアの魚類学者で採集家の Pavel Gavrilovich Borisov に由来) 亜種ワシミミズクと kiautschensis [中国にあったドイツの租借地 Kiaochow (英語表記) / Kiautschou (ドイツ語表記) 日本表記で膠州 に由来] タイリクワシミミズクとされる。
borissowi の記載時学名は Bubo bubo borissowi Hesse, 1915 (原記載) 基産地 Sakhalin。
ussuriensis とまとまる可能性があるが、こちらは Bubo bubo ussuriensis Polyakov, 1915 (原記載) 基産地 Nikolsk-Ussuriski, Ussuriland と同じ年に記載。
Hartert (1910-1922) p. 965 は Bubo bubo の亜種としたが学名を与えなかった。
Bubo bubo doerriesi Buturlin の学名が記載されていた (他の亜種記載を見るとおそらく 1908 年) が、この名称は大陸のシマフクロウ Bubo doerriesi Seebohm, 1895 の学名にすでに使われており無効のもの。Polyakov (1915) が改めて学名を提唱した。
この2亜種を別のものとみなすかどうかは見解が分かれており、Dement'ev and Gladkov (1951) では borissowi を ussuriensis のシノニムとしている。現行の世界の主要リストでは分離している。比較的細分派の Nechaev (1991) は特にコメントなく borissowi (サハリンで繁殖) を用いていた。
大陸亜種は多数提唱されていたが整理されて現行ではかなり少なくなった。
Men et al. (2020) Genetic analysis of three wild Eurasian eagle-owl subspecies, B. b. kiautschensis, B. b. ussuriensis, and B. b. tibetanus, in Chinese populations
中国の3亜種の遺伝的解析。表現型はよく分かれているがミトコンドリアゲノムの遺伝的違いはそれほど大きくなく比較的新しく分化したと考えられる。ussuriensis も中国東北部と北京では若干の違いがある。
上記の borissowi は調べられていないが ussuriensis と kiautschensis の遺伝的関係の近さは参考になるかも。
ついでながら Hartert (1910-1922) は旧北区のみ、アジア地域は北部しか考察していないので Bubo 属は2種のみだった。この分類に従えばワシミミズクとシマフクロウをわざわざ別属にする理由はあまりなく、シマフクロウが Bubo 属に含められていた理由にもなるだろう。
ミナミシマフクロウ Ketupa zeylonensis を別属としていたので北方・南方で分ける意識があったのかも知れない。p. 971 に Bubo 属と Ketupa 属を分ける明瞭な違いが示されているので形態的にも分けることができることは認識されていた。
Ketupa 属は Fischeulen (fish owls に相当) で足の裏に魚食への適応、顔盤が目立たないなど記している。シマフクロウの特徴はまだあまり知られていなかったのかも知れない。
-
シマフクロウ
- 学名:Ketupa blakistoni (ケトゥパ ブラキストニ) ブレーキストンのウオミミズク
- 属名:ketupa (合) Blo-ketupu マレーウオミミズク (Ketupa ketupu, 英名 Buffy Fish-Owl) ジャワ語 より属名へ語尾変更
- 種小名:blakistoni (属) blakistonの 英国の博物学者・探検家の Thomas Wright Blakiston
- 英名:Blakiston's Owl, IOC: Blakiston's Fish Owl
- 備考:
ketupa の発音はわからないが (そもそも外来語なので)、u を伸ばすならばここにアクセント。伸ばさないならばラテン語規則では ke にアクセント。
Strix Ketupu Horsfield, 1821 マレーウオミミズクの原記載 (基産地ジャワ島) 参考。現地名 Blo-ketupu。
これも Strix javanica Gmelin, 1788 (参考) や Strix javanensis Forster, 1795 (参考。Gmelin の学名を改名したもの)
の用例がすでにあって "ジャワ島" を冠した種小名を持ちいることができず、"東インド" (会社) を意味する indica は Strix indica Gmelin, 1788, Strix indica Forster, 1795 などと本家のインドの方で使われており (インドオオコノハズク)、やむを得ず (?) 現地名を用いたものと想像できる (#アカハラダカ備考参照)。
Horsfield は現在の名称でスンダオオコノハズク Otus lempij の種小名にも現地名を用いており、これも当時は Strix 属で "ジャワ島" を冠した種小名を持ちいることができなかったものと想像できる (現地名を用いると過去に使われた学名と重複する可能性をあまり心配しなくて済む)。
命名時にあまり深い意味はなかったかも知れないが、音韻はよくて現在は親しまれる属名となっている。
記載時学名 Bubo blakistoni Seebohm, 1884 (原記載) 基産地 Hokkaido, Japan; type from Hakodate, fide Hartert (Avibase による)。
この記載文献は #オオセッカ の記載文献と同じで、どちらの種も種小名が献名になっている。当時は Bubo maximus (現在のワシミミズク。学名は #ワシミミズク参照) が日本に生息していると考えられていたが取り消す必要があると書かれている。シマフクロウがワシミミズクと誤解されていたものと想像できる。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Ketupa 属 (シマフクロウ属) の扱い。
シマフクロウを Bubo 属に含めるか、Ketupa 属とするかは世界のリストでも見解が割れている。
IOCはずっと Bubo 属 だったものが、13.1 以降 Ketupa 属に、Clements は Ketupa 属、HBW/BirdLife は Ketupa 属であったものを 2014 年以降 Bubo 属としている。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では Bubo 属。
最新の分子系統解析では Wink and Sauer-Guerth (2021) Molecular taxonomy and systematics of owls (Strigiformes) - An update では Ketupa は Bubo に吸収されている。
従来の Bubo と Ketupa は混ざっていることが判明して、Ketupa を認める立場ではその問題を解消するために Bubo から Ketupa にかなりの数の種を移動する必要がある。その分類方法では Bubo に 10 種しか残らない。
属をどれだけ細かく分けるかは決まった定義があるわけではないので、1属にまとめられるものはまとめて構わない立場だと全部 Bubo になる。一方で形態や食性などを考慮して分けた方がよい立場だと Ketupa を属として認める、という扱いの違いになる。
Bubo から Ketupa の移動前でシマフクロウは Bubo 扱いの立場 (例えば IOC 12 まで)だと Ketupa は3種しかいなかったが、分子系統をふまえて Ketupa を残す扱いだと大幅に変わってくる。
古い文献 (例えば下記「極東の鳥類」を参照)ではシマフクロウはミナミシマフクロウ Ketupa zeylonensis (「セイロンの」の意味) 英名 Brown Fish Owl の亜種とされていたが、例えば IOC 12 までの扱いだと、もと亜種関係にあった2つが属まで違うという奇妙な現象になる。
ちなみにまだ十分な情報がなかった時代 (2008) の分子系統樹を Ian (2020) Ketupa ketupu - Buffy Fish Owl で見ることができる。この当時の知見であれば Ketupa 属を Bubo 属に完全吸収することも理解できる。
主に魚食のものを Fish Owl として Bubo からまとめたいのが生態志向の分類学者の意向であろうと思われるが (例えば IOC 英語名はそれに対応)、分子系統との整合性をどうするかなど問題点が残っているのだろう。
wikipedia 英語版によれば他に Fish Owl と名前の付く種類の類縁関係は必ずしも高くなく、Bubo 属内部での収斂進化の可能性も指摘されている (しかし情報がやや古い)。これらの見解に従って英名を Blakiston's Eagle-owl とする (BirdLife) こともある。
しかし Spiridonova and Surmach (2018) Whole mitochondrial genome of Blakiston's fish owl Bubo (Ketupa) blakistoni suggests its redescription in the genus Ketupa Russian Journal of Genetics, 54 (3): 369-373 によればワシミミズクとは近縁でなく、"Fish Owl" の中に置くべきとの見解も紹介されている。
wikipedia 英語版では4亜種をリストしている。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 93 p. 20 では Ketupa はウオミミズク属となっていた。Ketupa zeylonensis の当時の和名はインドウオミミズク。
この号には出てこないがウオミミズクの和名を持つ種は Ketupa flavipes で現在も同じ。タイプ種でもないのになぜこの種にウオミミズクの名称が与えられたかは不明だが、台湾にも分布する種類のため戦前に名付けられたのかも知れない。古くはシマフクロウが Bubo 属扱いだったため、例えば "タイワンシマフクロウ" のような名前も適切でなく、それぞれ別の属和名が必要でウオミミズク属の名称が用いられていたと考えると納得しやすい。
Bubo も Ketupa も今後少なくとも当面は両方使われるであろうが、上記のような複雑さがありどちらが正しいとはすぐには言えないだろう。両属を分けた場合も Bubo にまとめた場合も、フクロウ科 Strigidae フクロウ亜科 Striginae の Bubonini 族となる。
また大陸のシマフクロウと島のシマフクロウはこれまで亜種の違いとされていたが、最近では遺伝的な相違、生態などの違い、音声の違いから別種ともされる [藤巻裕蔵 kbird:06253 (2023.6.24); 藤巻氏による音声の違いの確認 kbird:06259 (2023.6.26) から]。
これを支持する研究は Omote (2018)
Phylogeography of Continental and Island Populations Of Blakiston's Fish-Owl (Bubo blakistoni) In Northeastern Asia (ミトコンドリア DNA の研究で種レベルの違いがある)、
Movin et al. (2022) Using bioacoustic tools to clarify species delimitation within the Blakiston's Fish Owl (Bubo blakistoni) complex (音声学的研究で別種を提案している)。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではこれらを亜種として扱い、日本を含む島の個体群 blakistoni を亜種シマフクロウとして扱っている。
大陸の亜種は doerriesi (ドイツの採集家でシベリアを探検した Friedrich Carl Gustav Doerries に由来) とされる。
マンシュウシマフクロウの和名が文献上は出てくるが現在も使われているのかは不明。この2亜種は近い将来別種とされる可能性が高いだろう。
この亜種の記載時学名は Bubo doerriesi Seebohm, 1895 (原記載) 基産地 Sidemi on the lower Ussuri (ウスリー)。それまでは Bubo blakistoni と考えられていた標本を新種と記載し、2例目の標本は Doerries が得たとのこと。
サハリンの亜種 Bubo blakistoni karafutonis Kuroda, 1931 も記載され、Clements 2019 年まで、Howard and Moore 2nd edition などで亜種扱いだった。
Dement'ev and Gladkov (1951) では blakistoni か doerriesi のどちらに属するかはっきりしないがいずれにしてもシノニムとの位置づけ。
大陸では Bubo blakistoni piscivorus Meise, 1933 (原記載) 基産地 Jakschi, west of the Great Khingan, on the East Siberian Railroad, 75 km. northwest of the Khingan siding (Avibase による)
(これは "魚を食べる" とわかりやすい学名) も記載されたが通常は doerriesi のシノニムとされる。
Clements 2019 年まで、Howard and Moore 2nd edition などで亜種扱いだった。
[シマフクロウを Ketupa 属に残すことは可能か?]
#ヒガシメンフクロウの備考で、Boyd がシマフクロウを Ketupa 属に含めていることが判明したため、
Wink and Sauer-Guerth (2021) の最新系統樹を用いて改めてその可能性を検討してみた。
名称は Boyd のものを用いたが、Boyd から属を移動したものに * を付けてある。
種和名の前に ? を付けたものは Wink and Sauer-Guerth (2021) の系統樹にないもので Boyd の分類をそのまま引き継いである。
クロワシミミズク属? Nyctaetus (いずれもアフリカの種)
コヨコジマワシミミズク Nyctaetus poensis * Fraser's Eagle-Owl (Ketupa 属より移動)
ヨコジマワシミミズク Nyctaetus shelleyi Shelley's Eagle-Owl
クロワシミミズク Nyctaetus lacteus Verreaux's Eagle-Owl
ウオクイフクロウ属 Scotopelia (暫定)
ウオクイフクロウ Scotopelia peli Pel's Fishing Owl
アカウオクイフクロウ Scotopelia ussheri Rufous Fishing Owl
タテジマウオクイフクロウ Scotopelia bouvieri Vermiculated Fishing Owl
ネパールワシミミズク Scotopelia nipalensis * Spot-bellied Eagle-Owl (Ketupa 属より移動)
マレーワシミミズク Scotopelia sumatrana * Barred Eagle-Owl (Ketupa属より移動)
シマフクロウ属 Ketupa
? ウサンバラワシミミズク* Ketupa vosseleri Nduk Eagle-Owl / Usambara Eagle-Owl
? コヨコジマワシミミズク Ketupa poensis Fraser's Eagle-Owl
? フィリピンワシミミズク Ketupa philippensis Philippine Eagle-Owl
シマフクロウ Ketupa blakistoni Blakiston's Fish-Owl
ミナミシマフクロウ Ketupa zeylonensis Brown Fish-Owl
ウオミミズク Ketupa flavipes Tawny Fish-Owl
マレーウオミミズク Ketupa ketupu Buffy Fish-Owl
このようにすれば数種の自然な移動で Ketupa 属も Scotopelia 属も維持され、それぞれ単系統にまとまるがいかがだろうか。
{ウオクイフクロウ属 + シマフクロウ属 (いずれも仮称)} で単系統をなし、少し早く分岐した Nyctaetus 属と並ぶ概念になる。
Boyd に従ってかなり離れた Nyctaetus 属をまとめることと、アフリカのコヨコジマワシミミズクをこちらに移動することで Bubo 属の単系統を保つことができることになる。
Bubo 属は分子系統学的には2系統あるので分ける方がむしろ自然であり、過去の属分類がその2系統と必ずしも合ってなかったために全体で Bubo 属とされているだけである。
? の種類は Scotopelia の方に移動になるものがあるかも知れない。
地理的分布はやや問題があり、ウオクイフクロウ属 Scotopelia の元来の分布はアフリカであったためネパールワシミミズク、マレーワシミミズクの系統が入ることは若干不自然である。ネパールワシミミズクはインドと東南アジアの隔離したグループが存在し、祖先系統はもっと広く分布していたのかも知れない。
この2種は Ketupa 属の中核となる種よりも早く分岐した系統で、{ウオクイフクロウ属 + シマフクロウ属} の中でも祖先系統の分布はアフリカ - 南アジア - 東南アジアと連続分布していたが中東地域の乾燥化などで分断されたことを示唆するかも知れない。
系統樹データはないが ? ウサンバラワシミミズク、? コヨコジマワシミミズク の2種はアフリカ分布なので Scotopelia の方に入った方が自然に思える。
? フィリピンワシミミズク は他の Ketupa 属に近い地域なので Ketupa 属に残りそうに思える。
またこのようなウオクイフクロウ属のグループをまとめればマレーワシミミズクの記載が一番早いためタイプ種が変わったり属名を変える必要が生じるかも知れない。ここではその点は触らないでおく。
このリスト以外の Bubo 属 10 種はすべて Bubo のままでよい (内部で分けても構わないが)。シロフクロウを除き、Bubo 属和名にもすべて "ワシミミズク" が付く形にまとまって整合性もよい。
このように見た Ketupa 属は元来は東南アジアから北東アジアに連続する分布を持っていたのだろうが、途中が (例えば森林消失などで) 分断されたとみると理解しやすいように見える。ちょうど#クマタカの大陸亜種が中国で分断されていると想像されるものに似ている。
これを記述した後、
Spiridonova and Surmach (2018) Whole Mitochondrial Genome of Blakiston’s Fish Owl Bubo (Ketupa) blakistoni Suggests Its Redescription in the Genus Ketupa
が遺伝情報のある4種について同じ概念の Ketupa 属を提案していることを知った (使っている遺伝情報は同じものかも知れない)。
Working Group Avian Checklists では version 0.01 まで Bubo 属だったが version 0.02 以降は Ketupa 属となっている。HBW/BirdLife が採用するかどうかだけの問題になっている。
島と大陸のシマフクロウを別種とする立場で、Ketupa 属を認める立場ならばそれぞれの種学名は Ketupa blakistoni と Ketupa doerriesi となる。世界のリストでは2024年7月段階で種としているものはない。
ロシアのシマフクロウの声: The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声) part 2 2:27 シマフクロウと雛 Vlastvuet zhe nad spyashchej tajgoj pesnya-duet rybnykh filinov, i razbojnich'ya pesnya ptentsov (シマフクロウのデュエットと雛の「山賊の歌」が眠るタイガを支配します。「山賊の歌」というカテゴリーの歌があって、陽気で品のない歌のたとえとのこと) (聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
[その他]
極東の鳥類32A: 論文集「シマフクロウ」にロシアと日本のシマフクロウの論文和訳が掲載されている。
Pukinskiy (1975) Po taezhnoj reke Bikin (1975) が翻訳出版されている: 「ビキン川にシマフクロウを追って - アムールの自然誌 −」(ユーリー B. プキンスキー 著、千村 裕子訳 平凡社 1989年、現在は絶版)。
天然記念物。絶滅危惧 IA 類 (CR)。IUCN 3.1 EN 種。
-
フクロウ
- 学名:Strix uralensis (ストゥリークス ウラレーンシス) ウラル地方のミミズク
- 属名:strix (f) ミミズクの一種
- 種小名:uralensis (adj) ウラル地方の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Ural Owl
- 備考:
strix は長母音 (ストゥリークス)。短い読み方もある。
ギリシャ語 strix は短母音。
uralensis は場所を表す -ensis の冒頭が長母音でアクセントもある (ウラレーンシス)。
亜種の読みも考察しておくと hondoensis "ホンドエーンシス", japonica "ヤポニカ" (または ヤポーニカ), momiyamae "モミマヤエ", fuscescens "フスケースケーンス"。
ユーラシアに広く分布し、10 亜種が認められている (IOC)。15 亜種まで認める場合もあるが、8亜種とするものもあるなど見解は統一されていない。ヨーロッパのフクロウの分子系統解析では5系統が認められたが従来の亜種分類とは対応しなかったとのこと (wikipedia 英語版)。
[属名の意味]
Strix 属のタイプ種はモリフクロウ Strix aluco Tawny Owl。
strix (f) ミミズクの一種 と記したが、雑誌 "Birder's World" 1989.10 pp. 10-13 に Don Alan Hall が "Quavering and Tootling Owls" と題してより詳しい語源解説を行っていたので紹介しておく。
strix は英語では screech-owl に対応するもので、screech の辞書訳から想像される "金切り声のような音声" を指すものではなく、恐怖を連想させる声で夜に鳴く不明のものだったとのこと。フクロウ類を表すギリシャ語やラテン語由来の名称はこのように縁起の悪い意味のものが多いが、例外もあって知恵の神 Athena / Athene (アテーナー、アテナ、アテネ) もありコキンメフクロウなどの属名に使われるが日本には生息していない。
従って Strix を知恵の神のような意味で用いるのは語源的に正しくないことになる。日本野鳥の会の野外鳥類学論文誌の名称は Strix だが、これならば Corvus の方が良かったのかも知れない (笑) (Birder を古くからお読みの方には元ネタを理解いただけると思う)。Corvus も音声由来なのでどちらも大差なしか。Athene が使えればよかったのかも知れないが日本に生息しないので原理的に無理だったのだろう。
Don Alan Hall の記事では北米の Western Screech-Owl, Eastern Screech-Owl (当時の分類) は英語の名前がふさわしくないので、自分がもし改名できるならば Quavering Owl と Tootling Owl と呼びたいと解説したもの。
関連話題は#ヨタカの備考 [ヨタカ目の範囲] - Strisores とは何か にも紹介。ヨタカ類が Strisores と呼ばれたのも "恐怖を連想させる声で夜に鳴く不明のもの" に分類されていたと考えると大変納得がゆく。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 168 によれば羽毛が大きく膨らんで見える「脹 (ふく) ろう」が転じた解釈を紹介している。他にも音声由来などの説がある。
膨の文字を使って説明される場合もあるが、脹の方がふっくらした感じがよく表れているかも知れない。
漢字由来は [梟の漢字の意味] の項目に。
[亜種]
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で認められている亜種は
・fuscescens (記載時学名 Strix fuscescens Temminck & Schlegel, 1850。「黒っぽい」の意味; 原記載) キュウシュウフクロウ。
亜種小名が少し素直でないのは Strix fusca Vieillot, 1817 (参考) があるので重複しない名前を選んだのだろう。
・hondoensis (記載時学名 Syrnium uralense hondoense Clark, 1907。原記載 場所は Iwaki) 亜種フクロウ
・japonica (記載時学名 Syrnium uralense japonicum Clark, 1907。原記載 場所は Sapporo) エゾフクロウ
・momiyamae (記載時学名 Strix uralensis momiyamae Taka-Tsukasa, 1931。Tokutaro Momiyama 由来; 原記載) モミヤマフクロウ
Vieillot の指すものは Ninox の1種と考えられるが同定されていない (参考)。
その他の亜種も地名や人名ばかりで、記載時代も遅かったため特徴を記述しかつ過去に用いられていない名称を見つけるのが難しかったのだろう。
当時用いられていた Syrnium が中性の属名であることにも注意。#ミヤマモリフクロウの備考参照。
japonica はもしかするとアオバズクの japonica と重複した可能性があるが、1907 年当時はアオバズクがすでに Ninox 属に分離されていたため問題が起きなかった模様。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代は別属になっていた。
の4亜種及び亜種不明となっている。
エゾフクロウ以外はいずれも「本亜種の分布域は明確ではないため、検討が必要である」となっている。
Fauna Japonica Strix fuscescens の図版。
Temminck and Schlegel (1845) も日本のフクロウの記載を残している (記載。
同時に記載されている他のフクロウ類同様にやはり "du Japon" (フランス語名 la chouette macroure du Japon ヨーロッパのフクロウの日本版の扱い) と記述されているが、当時 Strix 属だったアオバズクにすでに japonica を与えてしまっているので (#アオバズク の備考参照)、当時は同属だったフクロウには使うことができなかった。
japonensis を使えばよいようなものだが同じような名前が並ぶのを避けたのだろう。
そして Strix rufescens の学名を与えたがこれは Strix rufescens Horsfield, 1821 (参考) の用例がすでにあって無効となった。
Strix rufa Scopoli, 1769 (参考) の用例は早々と使われておりおそらく意識して少し変えたのだがそれでも重複してしまった。
本来はこの記載が日本のフクロウの初記載となるべきだったが重複が判明して 1850 年に改めて命名したと思われる。1845 年には「赤っぽい」と付けたのに、1850 年では「黒っぽい」では色彩の意味が違うではないか、と言われそうだが学名の字義はその程度のもので、意味をあまり深く追求する必要がない事例が多いかも知れない。
Temminck and Schlegel (1845) が日本の (キュウシュウ)フクロウに本来付けたかった学名の意味は「赤っぽいフクロウ」だったが、ヨーロッパ産のフクロウに比べて赤っぽいの意味。重なってしまったため改めて作られた学名が「黒っぽいフクロウ」だったことになる。
この事例ではアオバズクに japonica が与えられたが、逆ならばどうなったかと考えると、日本のフクロウの亜種は九州を基産地とするものが japonica となっていたと考えられ現在とは逆になっていただろう。アオバズクには別学名を与えていたはずなので、現時点で Ninox japonica とはならなかったはず。
Ninox 属を分離する前か後かで事情が変わった次第。
本州以南の亜種の境界がよくわからず、個人的には北海道とそれ以外に分けるだけで十分そうな気がするが...。大西 (2008) Birder 22(11): 59-63 でも同様のことが述べられていてエゾフクロウ以外は1つの亜種としてもよいような気がすると記されている。また 50 km ぐらいの移動も知られているとのこと。
阿部 (1993) Birder 7(8): 14-17 に「フクロウの亜種」の記事があり、この中では神戸市六甲山の個体をキュウシュウフクロウとした写真がある。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも淡路島はキュウシュウフクロウの分布に含まれているので、六甲山も同じ亜種? 千葉や静岡の一部もキュウシュウフクロウの分布に含まれていたらしい。
同記事によれば京都はモミヤマフクロウに含まれているらしい。
同記事に編集部の作成した分布地図が出ているが記述内容と微妙に違う。阿部氏も整理した方がよいだろうニュアンスで記載しており、日本鳥類目録第5版でそれまでカラフトスズメ Passer montanus kaibatoi とされていた北海道のスズメを Passer montanus saturatus にまとめた経緯があることも触れられている
(30 年も前の記事だが...)。
フクロウのサハリンの亜種はキタフクロウ S. u. tatibanai の学名があったそうだが現在では通常 S. u. nikolskii のシノニムとされる。日本の情報で S. u. nikolskii をキタフクロウと呼んでいるものは探した範囲で見つけられなかった。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版のパブリックコメント "分類学上疑問がある国内固有(亜)種について" の項目にも言及があり、鳥類目録の分類は、新たな研究が行われるまで現状維持されるという原則に基づくとのこと。
あまり考えたことがなかったのだが、本州以南の亜種をもしまとめるならば fuscescens の記載が一番早いことになる。海外のリスト (Avibaseなど) でも hondoensis と momiyamae をグループ化する傾向がある。
世界を最小の8亜種とする分類では日本産の亜種は hondoensis, japonica, fuscescens になっている。IOC (14.1, 13.2) では 10 亜種でこれらに加えて momiyamae が認められている。
Saitoh et al. (2015) (#カルガモの備考参照) による DNA バーコーディングではエゾフクロウと本州のフクロウで (別種相当の) 最大 2.81% の違いがある。
高木 (2021) Birder 36(4): 48-51 で主にキュウシュウフクロウ S. u. fuscescens を取り上げて羽色変異と齢差を議論している。この記事でも本州以南の亜種境界が明瞭でないため亜種は議論対象の取り上げられていない。
[音声]
フクロウはよく知られた「ホッホ (間が空く) ゴロスケ ホッホ」と聞きなしされるさえずりの他にさまざまな地鳴きを持っている。例えば 『フクロウ―その生態と行動の神秘を解き明かす』文一総合出版(2007)では成鳥に 14 種、若鳥に4種のレパートリーがあるとのこと(大庭 2007)。
バードリサーチ鳴き声図鑑でも一部の声を聞くことができる(フクロウ)。地鳴きの中でもここで 神奈川県丹沢 (2007-05-14) 植田睦之 と述べられているもの (ギャー、繰り返しながら音が弱くなってゆく) は典型的でよく聞かれる (一般の方はフクロウの声と知らず、何物かと怖れて眠れないこともあるようである)。
この図鑑で地鳴き 栃木県渡良瀬 (2010-04-20) 平野敏明 と述べられているもの (低い声ホホホホ...) は特徴的で、巣を防御する時の声 (defensive call)、ペアリング候補個体にオスが巣を見せる時の声 (nest-showing, ドイツ語 Nestzeigen ネストツァイゲン) などとも呼ばれるが、日本語、英語とも定まった用語はないようである。
フクロウはヨーロッパでは主な分布がスカンジナビア半島など北よりの地域で、研究はスウェーデンやドイツでよく行われており、それぞれの言語で鳴き声の種類を表す語が存在する。ただし前述のように北海道と本州で種レベルの違いがあるとのことで、ヨーロッパのフクロウはもしかすると別種になるかもしれないので以下の記述が日本のフクロウにも当てはまるかどうかは調べてみないとわからないかも知れない。
英語の (しっかりした?) 書籍ではスウェーデン語の用語をもとに対応する英語名を記しているものもあるが、他言語からの翻訳でニュアンスを完全に伝えきれるわけでもないようである。
ドイツのフクロウ類大家の研究では Scherzinger (1980)
Zur Ethologie der Fortpflanzung und Jugendentwicklung des Habichtskauz (Strix uralensis) が公開されている。
問題の音声は Nestzeigen または Nestlocken と記述されていて、主にオスが出すが、メスの声も記載されている。最長で5分鳴き続けることがあるとのこと。メスの声は主にオスの声の合間で1-2節の短いものが普通とのこと。飛行時にはあまり出さない。オスの声の方が周波数の広がりが少なくはっきりした音声で、メスの声の方は周波数が広がってより雑音的に聞こえることで区別できるそうである。
英語では "defensive call" に対応して、一般的な音声の分類名称である "alarm call" (警戒音)の用語が用いられることがあるが、Scherzinger (1980) は別の声に Warnlaut (英語 alarm call の意味) を用いており、単に alarm call とするのは誤解を生じさせる可能性がある。wikipedia 英語版ではコミミズクの対応する音声に基づいて "alarm call" としているようである。
スウェーデンの研究は Lindblad (1967) によるもので I ugglemarker (「私はフクロウ」の意味)。
問題の声はスウェーデンでは Defensivlate と呼ばれていて、Lindblad (1967) によれば同種個体が近づき過ぎた時 (性別は問わない) に出す声「これ以上近づくな、近づくと攻撃する」を意味すると定義している。主にオスが出す。
Lindblad (1967) はフクロウ類他種にも同様の音声を記載しており、モリフクロウ Strix aluco 英名 Tawny Owl での対応する声を Xylofonlate と記述している。Lindblad (1967) はまたメスが "rorororororo" の声を出し、オスがより柔らかな同様の低い声で応じると記載している。
この場面では Defensivlate とは記述されていない。Lindblad (1967) で巣を示す目的の声 (nest-showing) を記載している (ただしフクロウの声とは別物) のはワシミミズクのみとのこと。
これらのフクロウ研究家の意見や訳語の検討結果もふまえ、Cramp (1985, chief ed.) "Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa, Volume IV" では "contact-alarm call" と名付けている。この文献によれば3種類の場面で使われるとのこと。
(1) 興奮時に通常のさえずりと交互に使われることも珍しくない。特に人がさえずりの真似をした場合。(2) オス、メス間のコミュニケーションとして使われる。巣を見せる際に使われることもある。メスが別方向に注意を引く飛行 (distraction flight) 時に発することもある。(3) 飼育下では主にオス、メスでは少ないが巣の吟味に際に出す。
Cramp (1985) では成鳥フクロウの音声を以下に分類している。(1) Advertising-call (さえずりのこと) (2) Contact-alarm call (上記音声) (3) Soliciting-call (4) Twittering-call (5) Feeding-call (6) Grumbling-call (7) Anger-calls (8) Alarm-call (9) Distraction-call (10) Hissing-call。さまざまな種類のフクロウ類の音声の呼称を統一する試みであるが、現在あまり使われているわけではないようである。
Collins Bird Guide では上記音声を "alternative song of male (courtship, nest-showing, anxiety) ...; female has harsher version" と記述している。
The Sound Approach Ural Owl にソノグラムと音声付きの解説がある。このページでは記述的に "pulsed hooting" と呼んでいる。
ロシア極東の個体群では音声の特別な呼び方は付いていないようだが、Shibnev (2018) On biology of the Ural owl Strix uralensis in Primorye
の研究があり、単調な反復する"du-du-du..."の声で、通常オスが巣から飛び去る時または巣に近づいて来る時に出すが、繁殖期には通常のさえずりと交互に使うこともある、との記載がある (xeno-canto 記述及び文献から)。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではオスが時々3-6節からなる低い声 khuv-khuv-khuv-khuv を出す (vzlaivanie 吠えるような声) とあり、カラフトフクロウ Strix nebulosa 英名 Great Grey Owl のさえずりを思わせるところがあると記載がある。
[フクロウ類の視覚]
Harmening et al. (2009) Spatial contrast sensitivity and grating acuity
of barn owls によれば (北米のメンフクロウであるが) フクロウ類の視力は良くなく、鳥類中でも一番低い部類でだいたいハト程度。金魚よりは数倍よい程度。
Martin (2017) (#ハヤブサの備考参照) ではフクロウ類が獲物をとらえるのに立体視を用いている証拠はない (暗所での視力も悪く、暗い条件では瞬時に奥行きを得るだけの光の量がそもそもない)。
フクロウ類では耳の位置や大きさが重要で、大きな耳を格納するために目が正面方向に付かざるを得ない制約があり、必ずしも両眼視のために目が前に付いているわけではないようである。
ただしフクロウが両眼視による立体視を行っていると考えられることは実験的に確かめられている [van der Willigen (2011) Owls see in stereo much like humans do]。
この実験は両眼視による立体視がないと起こらないであろう現象を調べたものである。フクロウ類の立体視が獲物をとらえるのに有効かどうかの解釈、そして鳥類がどのように立体視をしているかの解釈は研究者によって異なっているようである。
哺乳類が長く夜行性生活を体験したために本来4種あったはずの網膜の色覚受容体を失い、大半の哺乳類で2原色であることはよく知られている。ヒトなどで3原色なのは遺伝子重複によって二次的に3種目の色覚を獲得したためであるが、4原色型の動物が持つ受容体の中でヒトの3原色に対応する色覚に比べてヒトの場合は色の分離がやや不完全である。
鳥でも夜行性のものは4原色の一つである紫外線の受容体を失う傾向がある (例えばフクロウ類。#カタグロトビの備考も参照)。ただしフクロウ類は紫外線を感じないわけでなく、眼球内の紫外線透過率は高いので紫外線に感度のある赤の視細胞で紫外線も光源として利用している。薄明中は紫外線強度が高いのでこれは有効と考えられる。
Hoglund et al. (2019) Owls lack UV-sensitive cone opsin and red oil droplets, but see UV light at night: Retinal transcriptomes and ocular media transmittance を参照。
チョウゲンボウが紫外線で齧歯類の尿を見ているか (#チョウゲンボウの備考参照) とはまったく逆で、フクロウ類は紫外線を積極的に利用しているらしい (赤の視細胞を使っていることから、フクロウ類にとって紫外線は赤く見えるのだろう。しかし以下に示すように網膜に赤の油滴がないらしいため、色をそれほど鮮明に知覚していないかも知れない)。
なお現在では鳥類が紫外線を見ることができることはよく知られているが、1990 年ぐらいまでの古い本を見ると必ずしもそのように書かれていなかった。「野鳥」1993年8月号 (No. 561) p. 14 でも蝶や蜂は紫外線を見ることができると言われているが、鳥はおそらくそういうことはなくて、と樋口広芳氏が述べられていた。
ミツバチが紫外線を見ていることは古くから知られていたが、鳥類で知られたのは意外に新しく Wright (1972) The influence of ultraviolet radiation on the pigeon's color discrimination によるハトの実験が最初らしい。
当時は鳥にはおそらく人と同じように見えていると信じられていて (これも大変よく理解できる) 思い込みから発見が遅れたのではないだろうか。
Burkhardt (1982)
Birds, berries and UV. A note on some consequences of UV vision in birds、
Chen et al. (1984) The Ultraviolet Receptor if Bird Retinas、
Burkhardt and Maier (1989) The spectral sensitivity of a passerine bird is highest in the UV
のような論文も 1980 年代にいくつも出ているので、この時代には知る人はすでに知っていたと思われる。
1990 年代前半には野鳥のデータはあまりなく、まだ役割が議論されていた: Bennett and Cuthill (1994) Ultraviolet vision in birds: what is its function?。
羽毛の色彩と関係あるのでは: Finger and Burkhardt (1994) Biological aspects of bird colouration and avian colour vision including ultraviolet range。
ホシムクドリで紫外線反射率が性選択に関連している: Bennett et al. (1997) Ultraviolet plumage colors predict mate preferences in starlings
とかなり新しい。
紫外線の受容体を失うことに伴う思わぬ副次的効果については#アマツバメの備考参照。
Castiglione et al. (2023) Convergent evolution of dim light vision in owls and deep-diving whales
によればフクロウ類と深く潜水するクジラ類の網膜色素 (ロドプシン) のシス-トランス異性体に関係する遺伝子に収斂進化が見られたとのこと。暗い光に適応した網膜が明るい光を受けるとダメージを受ける可能性があり、それに対する適応と考えられていた機構。
Emerling (2017) Independent pseudogenization of CYP2J19 in penguins, owls and kiwis implicates gene in red carotenoid synthesis
によれば、フクロウ類、キーウイ、ペンギンで赤いカロチン色素を作る遺伝子 CYP2J19 (赤いカナリアにも関係。#ベニマシコの備考参照) が独立に機能しなくなっているとのこと。
これは網膜の赤い油滴がないことにつながっていて、暗所視が必須の鳥にとって、光を吸収する赤い油滴を失うのが有利であったことを意味する。ペンギンは深く潜る時には暗いところ見る必要があるため。
鳥類の4色知覚について、「鳥が見ている4原色の世界」「野鳥」2007年10月号 (No. 715) p. 9 に模式図が出ているが、この図は光の3原色と色の3原色の間で混乱がある。単に「間違っているだけ」と思って通り過ぎていたのだが、森本 (2013) Birder 27(1): 36-37 でも使われていたので念のため取り上げておく。
この図では鳥の視覚には黄色が現れないように見え、「カラスは黄色が見えない」のような都市伝説の要因になり得そう。特殊なゴミ袋の黄色はさらに別の意味があるようで、コラム2 カラスが嫌いな色はあるのか? 黄色が嫌いは本当? (CrowLab) の開発者自身の解説を紹介しておく。
[フクロウ類などの耳の左右差]
フクロウ類は耳に左右差があり、音源定位に役立っていると一般には書かれているが、川口 (2023) Birder 37(10): 52-53 によればフクロウはほぼ左右対称とのことで、Birkhead "Bird Sense: What It's Like to Be a Bird" (2012)、邦訳されてティム・バークヘッド著; 沼尻由起子訳「鳥たちの驚異的な感覚世界」(2013 河出書房新社) の記述と合わないことが書かれている。
またトラフズクは頭骨は左右対称だが軟部組織が非対称になっているとのこと
(音源定位については#ヒガシメンフクロウの備考参照)。
なおフクロウの頭骨骨格に微妙な左右差があることは川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019) に紹介されている。
バーダー編集部 (1998) Birder 12(2): 11 にもフクロウの耳の左右差 (軟部組織) の写真比較が出ている。
フクロウ類の視覚・聴覚については #イヌワシ備考の [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] の注釈 *4 に追記がある。耳の左右差と音源定位に関わる脳の神経核の大きさに相関があるとのこと。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 95 V にフクロウ類の耳の左右差が取り上げられており、昔から好まれるテーマだったようだ。メンフクロウの耳は左右が不対称 (原文のまま) であるとして比較写真が添えられていたが、実は種名を間違えていて後の号でトラフズクでしたと訂正が出ていた。
しかし写真を見るとキャプションの左右の表記が逆のように見える。鳥類学者にとって事実は有名であってもフクロウ類そのものはあまり身近な種類でなく、種名を間違っていても気づきにくかったのかも知れない。このような情報が訂正されず引き継がれると間違った記述が氾濫することになるわけだ。
50 年を経過しても情報の不正確さが残ったままで、その都度証拠を確認した方がよい状況が今もなお続いているとも言える。
フクロウ類以外でも耳の左右差が聴覚を積極的に用いている証拠とされることがある (#カタグロトビ、#ウスハイイロチュウヒの備考参照)。
オウム類にも夜行性のものがあり、ヒメフクロウインコ Pezoporus occidentalis 英名 Night Parrot では Shute et al. (2022) Cranial adaptations of the Night Parrot (Psittaculidae: Pezoporus occidentalis), a cryptic nocturnal bird
の研究がある。このオウムでは暗所視はよくないと考えられており、頭骨の研究でフクロウ類に似た耳の左右差があって夜の行動に聴覚を使っていることが示唆される。同様の特徴は他のオウム類では見られないとのこと。
解説記事。
このオウムの遺伝的研究が発表されていて Yeap et al. (2025) Museomics and Salvaged Feathers Piece Together the Evolutionary History and Conservation Genomics of the Elusive, Critically Endangered Night Parrot (Pezoporus occidentalis)
90 年ぐらい前までは実効個体数 (Ne) も多くオーストラリアに広く分布していたと考えられるが現在は 2000 km 離れた2個体群しか存在せず (IUCN CR 種) 遺伝的交流の証拠もない。Ne はこの期間に 10000 から 100 に減少して過去数百万年で最も低くなっているとのこと。
この種の生物学や生息確認方法が明らかになってきたのは 1990 年代以降とのこと。博物館標本と現存個体の羽毛や組織サンプルを得ることができて全ゲノム解析を行った結果とのこと。
wikipedia 英語版によれば 2024 年の段階で鉱山予定地が近くにあり、予定者はノネコやアカギツネの個体数管理や鉱山に向かう私有道路を通る車両に警告音の出る装置を設けるなどの保護策も考えているなどの ABC News 報道が紹介されていた。このオウムを特に狙わないディンゴが生息していて、ノネコが拡大するのを防いでいると考えられているがこのオウムが新規建設される道路の影響にどのように反応するかは未知数とのこと。
またレンジャーはディンゴにも影響を与える可能性のある外来捕食者の個体数管理には消極的とのこと。夜間は鉱山関係車両はこの道路を通らない予定で観光客にも開放しないと説明しているとのこと。また導入されたラクダがこの種にどれほど大きな影響を与えているかレンジャーは注視しているとのこと。
[フクロウ類の首の動き]
どの本を見ても判を押したようにフクロウ (類) の首は左右に 270° 回せると書いてある。一番調べられている種類はアメリカメンフクロウだがおそらくフクロウ類のどの種でも当てはまるのでここで触れておく。
この数字のオリジナルの出典はわからなかったが、Walls (1942) The vertebrate eye and its adaptive radiation (p. 309) にすでに出ている。この本にはフクロウ類同様に目が前方について動かせない霊長類のメガネザルも同様に首を 180° 回せると書いてある。
メガネザルはギネスブックにも出ていて Farthest head rotation by a mammal、これによるとフクロウ類は 200° とある。
270° は極端としてもどんな鳥でも首を 180° 回せるのではないだろうか (さもないとたとえば尾脂線に嘴が届かないのでは?) と思ってしまう (*1)。
Crested Honey Buzzard female はマレーシアのハチクマの例であるが、220° ぐらいは余裕で回っているのではないだろうか。
真横近くを向いた時はもしかすると 270° 近く回っているかも知れない。
Oriental Honey Buzzard (Yvonne Blake 2024.12.22) これも 180° 以上回っている (渡りのハチクマとのことで日本と同じ亜種と思われる)。
ヒトの頸椎のように椎骨が縦に重なったものが少しずつずれて回って 180° 回転できるとの印象は誤りである。屈曲運動 (これは容易) と回転運動を組み合わせて結果的に後ろを向ける。
第1頸椎 (C1 環椎 atlas) と第2頸椎 (C2 軸椎 axis) の間の関節は哺乳類でも鳥類でも同様に特殊な構造で可動域が大きく左右の回転はこの関節が大きく役割を果たしている (サイチョウ類は例外。#ヤツガシラの備考参照)。
鳥類の頸椎は哺乳類と違い鞍状の関節面を作っている (saddle-shaped または 異凹型 heterocoelous と呼ばれる)。この関節形状は脊髄を伸展することなく比較的自由な方向に屈曲ができる。これらは鳥類学の本に普通に出ている内容であろう [たとえば松岡他 (2009)「鳥の骨探」(NTS)」。
「関節が柔らかいので」と説明している書物もあるが、(多分関節面の構造を把握した上での説明ではあろうが) この説明は靭帯などの軟部組織が柔らかくて可動域が大きいと誤解される恐れがある。
フクロウ類の首の動きには世間でも関心があるようで研究もいくつもある。
Krings et al. (2017) Barn owls maximize head rotations by a combination of yawing and rolling in functionally diverse regions of the neck。
この論文のユニークな点は実際にアメリカメンフクロウの死体の首を人工的に回してみてどこがどのように動いているかを調べていることである。図を見ていただけばすぐわかるが首を完全に伸ばした状態で回転させると首が曲がって全体として短くなりつつ回転する様子が見られる。
実際にフクロウ類を外見から見るとそのようには見えないので、普段から首を曲げている状態で首を曲げつつ向きをを変えていると捉えるのが正しいであろう。外見から首の動きが見える鳥が後ろ向きに羽繕いする時と大差ないように思える。
人工的に回す実験では 180° でもかなり曲がっている様子がわかり、270° では首の一部が肩に埋もれる形になりあまり現実的ではなさそうである。人工的に回すことは簡単にできるようだが 180° を超える回転が実際の生体で起きているかはわからないと書かれている。筋肉や靭帯を破壊することなく 360° 以上回せたとのこと。
Grytsyshina et al. (2016) Kinematic constituents of the extreme head turn of Strix aluco estimated by means of CT-scanning
(対象種はモリフクロウ Strix aluco Tawny Owl)
では 360° は回せたが頭が肩に埋もれるようになったとのこと。360° 回した時は実際には頸椎は 160° しか回っておらず (しかもそのうち 90° は頭骨と頸椎の間の回転)、残りは頸椎関節の後ろ向きと横向きの曲げで補っているとのこと。個々の頸椎の間の回転は 15° に満たなかったとのことで、外見から想像する印象とはだいぶ違うのではないだろうか。
いずれの研究も椎骨、筋肉や靭帯のみを扱っており、他の構造物 (例えば気管、血管など) による制約はわからない。#タンチョウの備考 [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] にあるオウギアイサの実験を見ると気管はそこまで伸ばせないように思える。
また外部からの力ではなく鳥自身の筋肉の収縮でそれほどの回転を行えるかもわからない。
頸椎の個数が我々の2倍あるので 270° 回せるとの説明は間違いではないが (角度の数字はやや誇張かも知れない)、おそらく誤解を招いてそうに思える。むしろ羽毛に隠れてわからないだけで後ろ向きと横向きの曲げが回転に半分ぐらい効いていて頸椎はそれほど回っているわけではないことを押さえておくべきなのだろう。
ホースを伸ばした状態で回そうとしてもあまり回らないが、曲げればいろいろな方向に向けられるのと同じような状況を考えるとわかりやすいかも知れない。
(しかしフクロウ類が特殊というよりどんな鳥でも同じような結果になりそうな気もする)。
なおこれらの文献ではフクロウ類の頸椎は 14 個としていて (数は水鳥以外の鳥類としては平均的) 頸肋骨を持つ椎骨も数えているようである [Boehmer et al. (2019) (#コブハクチョウの備考を参照) ではメンフクロウ 12 個、ワシミミズク 11 個となっていてこちらでは頸肋骨を持つ椎骨を数えていない]。その部分も実際に動いているようなので機能的に頸椎の一部と考えて差し支えないように思える (*2)。
一般向けだがこのような記事があった: Which animals are capable of rotating their heads 180 degrees? (Chyrle Bonk, ZooNerdy 2023)。
真偽は必ずしも明瞭でないが鳥以外でもかなり回せるものがあるらしい。ワシも 270° 回せるとあり、おそらくフクロウ類だけの特技ではなさそう。
こちらはコウライウグイスが真後ろを向けるとの記事: Wee (2014) Black-naped Oriole turns head 180 degrees。実際にはほとんどの鳥は真後ろを向けるとある。
ヘビ専門のハンターであるワライハヤブサ Herpetotheres cachinnans Laughing Falcon がとまってフクロウ類のように周囲を見渡すとの記述
(例えば Laughing Falcon (Herpetotheres cachinnans) (Planet of Birds 2011)
があって気になって調べたものだが、おそらくフクロウ類のように頭が相対的に大きいため注目されているだけのよう。
フクロウ類が首を回した場合になぜ血管が圧迫されて脳への血流が途絶えないのか、の疑問で (特にイラストが) 一躍有名になった論文がある。
de Kok-Mercado et al. (2013) の Science 論文であるが図はフリーで見られるので紹介しておく Adaptations of the Owl's Cervical & Cephalic Arteries in Relation to Extreme Neck Rotation。
文章による解説は例えば How owls swivel their heads (BBC、映像あり)。
解説ビデオがあり、確かに 180° 以上は回ってそうである:
How Owls Turn Heads
(SciFri 2013)。
解説によればいくつかの適応が見られ、脳に血液を運ぶ2種類の血管のうち椎骨動脈 (vertebral artery) が頸椎に入るのが通常の鳥では 14 番目の頸椎であるがフクロウ類では 12 番目と動きに余裕があること、
椎骨動脈の通る頸椎の穴がヒトに比べて大きく運動に十分余裕があること、頸動脈はヒトに比べてずっと椎骨の近くを走って回転の影響を受けにくいこと、頭蓋骨の底部で頸動脈が広がっていて血流が途絶えた時に血液を一時的に貯める働きがあるとのこと。
また椎骨動脈と頸動脈の間に連絡 (anastomosis) があって片方が圧迫されて途絶えてももう片方から血流を得ることができるとも述べている。
普通のヒトにはないと書いてあるのだが、大脳動脈輪 (ウィリス動脈輪 circle of Willis) というものがある (wikipedia 日本語版、英語版ともあるが英語版の方が詳しい)。
ヒト以外の動物 (ここで書かれているのは爬虫類、鳥類、哺乳類) にもあり、
片方が途絶えてももう片方から血流を得ることができるとの機能が提唱されていたが、動脈硬化が起きるのは通常高年齢なので、その機能よりも動脈の拍動が脳に直接伝わるのを和らげるためではないかと書かれている。ヒトにとってはそれほど大した意義がないものかも知れないが、ウィリス動脈輪に対して提唱されていたアイデアは実はフクロウ類では当てはまるのかも知れない。
de Kok-Mercado et al. (2013) でも次は他の鳥ではどうなっているのか調べる段階だとあるのだが後続研究はどうも見当たらない。実は他の鳥でもそれほど違わないのかも知れない (椎骨動脈と頸椎を穴の大きさの比較や椎骨動脈の入り方などの形態研究はありそうな気はするが)。
脳の動脈については脊椎動物間の系統比較研究もあるので (脳が巨大化するにつれて血流供給が重要になる) [Rahmat and Gilland (2014) Comparative Anatomy of the Carotid-Basilar Arterial Trunk and Hindbrain Penetrating Arteries in Vertebrates] それほど驚きの発見の感じがしないがいかがだろうか。
比較のためにイヌワシのスキャン画像を見てみた。Interspectral Featured in This Exhibition
にデモ映像がある。この映像の解像度は今ひとつであるが (イヌワシに限った話ではないだろうが首の後部を羽毛が派手に覆っていてイヌワシの場合ここは指がすっぽり入る深さだそうである。外から見ると頸椎の曲がりが想像できないこともよくわかる)
別のより高解像度の血管造影画像を持っているのだが出所が不明になってしまって URL を紹介できないのが残念である。こちらによれば頭部 (脳や眼) にどれほど血流を投資しているかは頸動脈の立派さからわかる [de Kok-Mercado et al. (2013) のフクロウ類のイラストと比べてもかなり違う]。ヒトに限らず「脳は大食い」のようである。
翼の血管の映像は Golden-Eagle-wing にあって頸動脈も一部写っているので参考になるかも知れない。
イヌワシは頸動脈が左右にあって我々と同じ感覚で物が言えるが、鳥の種類によっては1本しかないものもあるそうである。
Carotids (The Wonder of Birds) によれば基本4つのパターンがあるとのこと (なおこのページでは頸動脈しか扱っていないが、前述のように椎骨動脈も脳に血流を送るので頸動脈が大幅に退化していても脳に血流が行かないわけではない)。
1: 頸動脈 (深頸動脈) が左右に2本が基本型で多くの鳥に見られる
2: 左右の頸動脈が1本に合体する: サギ類、フラミンゴ類、一部の旧大陸オウム類
3: 左右の頸動脈が1本に合体するが左側が細くなっている: レア、キーウイ、カイツブリ類、ペリカン類の一部、カワセミ類、ノガン類、ミフウズラ類、ツカツクリ類、一部の旧大陸オウム類、ハチクイ類、サイチョウ類、ヤツガシラ、キヌバネドリ類、アマツバメ類、ネズミドリ類、キツツキ類、スズメ目
4: 左の頸動脈は退化し、合体もしない: ノガン類のうち Eupodotis 属 (2種)
他にもパターンがあって 5. 右の頸動脈と浅頸動脈が存在する: アメリカのオウム類と少数の大陸オウム類
6: 深頸動脈が左右とも退化し左右の浅頸動脈がある: ジサイチョウ Bucorvus abyssinicus で見られた
7: 右の浅頸動脈しかなく、他の頸動脈類がない: オーストラリアのハシリチメドリ Orthonyx temminckii 英名 Australian Logrunner のみで知られる (Forbes 1882)。スズメ目の中でも例外的に特殊。当時同属とされた ニュージーランドのキイロモフアムシクイ Mohoua ochrocephala 英名 Yellowhead と別属である根拠ともなった (現在は科も違う)。
オウム類ではさまざまであるが1本の種類でも途中で分かれて頭部に入る前に2本になるとのこと。それら動脈がどのように脳に血流を送るかは種類によっても違うらしい
(Sulphur-Crested Cockatoo; これにも鳥類でもウィリス動脈輪同等のものがあると書いてある)。Max Fuerbringer (ドイツの解剖学者・分類学者) はオウム類のさまざまな頸動脈パターンから進化起源を推定したとのこと。
オオフラミンゴの例: Alan et al. (2016) A Study on Branching of Aortic Arch in the Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus, Pallas 1811)。
猛禽類はこれらのリストに現れないのでおそらく基本型で、頭部への血流の重要性が高いのかと思ってしまうがどうであろうか。フラミンゴやサギ類他で頸動脈が1本になるのは首を細くできる有利な点があるのかも知れない。
もしかしたら最新系統樹で考えると傾向があるかと期待したが系統とあまり関係がなかった。カイツブリ類とフラミンゴ類が似ているのは系統を反映しているかも知れない。
オウム類などの1本になる系統も視力がそれほど発達していないものが多いように思える
(これらの情報がたくさんあるのはイヌワシの血管画像を探して見つからなかった副産物)。
イヌワシの場合はフクロウ類よりも頸動脈が外側を通っているように見え、フクロウ類ほどは回転運動に対して窮屈ではないのかもしれない。
頭蓋骨の下で頸動脈が折れ曲がっている部分があり、あるいはこれはフクロウ類で血液を一時的に貯める働きがあるという部分に相当するのかも知れない。フクロウ類と比べて椎骨動脈は頸動脈よりかなり細いように見える。
一方向からの画像のため椎骨動脈と頸動脈の間に連絡があるかは明瞭にはわからないが、あってもよさそうに見える。
The Virtual Museum of Life で イベリアカタシロワシの骨標本 (クリック2段階ぐらいで個々の骨が見られる) を見ることができるが、椎骨動脈の通る穴はフクロウ類同様に十分余裕があるように見える。椎骨動脈の穴がはっきり見えるのは 12 番目の頸椎からで、ここから頸椎に入っているように見える。
de Kok-Mercado et al. (2013) の研究は世間的話題にはなっただろうが、実はフクロウ類と猛禽類他種 (少なくともタカ類) でそれほど差がないのではと思える。
最近の参考総説論文: フクロウ類の夜行性生活への解剖学・生理学的適応の総説 Sieradzki (2022) Designed for Darkness: The Unique Physiology and Anatomy of Owls (in "Owls")。
当初の論文に対する疑問もやはりあったようで、その後新しい研究が発表されている: Panyutina and Kuznetsov (2023) Are owls technically capable of making a full head turn?
フクロウ類は本当に両方向に 360° 回せるか。360° 回した状態で CT を使って検証した。基本的にはホースのように思えばよさそうで、曲げと回転を組み合わせて 360° 回すことはできるとのこと。
水平方向の回転より頸椎中央部の前方向の曲げと頸椎下部の横方向の曲げが大きく寄与しているとのこと。
曲げることなく単純に水平方向の回転では可動域を足し合わせても 190° にも達しないとのことで、よく想像される (ヒトのような) 首の回転のイメージとはかなり異なる。
生理的に可能な範囲でどの筋肉が収縮すれば実現可能かを示した。原理的には可能であるとのこと。CT から構成した画像には気管も含まれていてこの程度は伸縮できるようだが、当然のことながら気管が首の後ろを通っている。こうなる前に息苦しくて止めそうな気がする。
他の鳥と違うのか、についてはガチョウとダチョウを用いて比べたとのことで、各関節の移動範囲はそこまで顕著な違いはなかったが (頸椎数は違うがフクロウ類と同じ数で打ち切ってもあまり違わない)、フクロウ類がガチョウより少し柔軟かも知れないとの結果になったとのこと。ガチョウのデータ Zarnik (1926) と古いもので、測定条件も違うかも知れないのであまり確実なことは言えないかも。
他の鳥では調べられていないが、360° 回せる能力は羽繕いなど他の鳥でも重要なのでは、と主張がだいぶ後退している。野生あるいは飼育下の鳥で 360° 回した記録はまだないとのこと。
この論文を見る限り、「フクロウは首の関節が柔らかいので...」と説明するのは多分適切でないだろう。
この研究は Grytsyshina が学生時代にこの論文の著者 Panyutina and Kuznetsov の指導下で始めたものとのこと。
備考:
*1: どんな鳥でも (頭部などを除いて) 体全体を羽繕いできる、あるいは尾脂腺に嘴が届く首の長さがあって完全に後ろを向くことがができるはず、とつい言ってしまいそうな場面である。
尾脂腺が発達していない鳥はあるので届かなくても大丈夫かも知れないが、羽繕いができないのは困りそうである (セキセイインコでも背中は届きにくいようで触られるとちょっと嫌がる)。
そういえばハチドリの仲間に長過ぎる嘴の種類があって、これでは絶対羽繕いできないはず、と思って調べてみたところ例えばヤリハシハチドリは Ensifera ensifera 英名 Sword-billed Hummingbird では Sword Billed Hummingbird: fencing champion?
にあるように足で羽繕いをする (思わぬところから足が出てくるもっと驚くべき動画を見たことがあるが行方不明になってしまった)。これも足を器用に使う鳥と言ってよいだろうか。Clayton and Cotgreave (1994) Relationship of bill morphology to grooming behaviour in birds
足を使って羽繕いは可能だが嘴を使う方法に比べて手間暇がかかるとのこと。
*2: Boehmer et al. (2019) の論文では実際にフクロウ類を首が相対的に最も短いグループに分類している (この論文の Fig. 3 参照)。ただしこの図は脚の長さに対する比をとっているので、フクロウ類など足で獲物を捕える猛禽類の脚が長いことを考えると首の長さを過小評価している可能性がある。実際にこの図ではフラミンゴは普通になっていて実感とも合わない。
そのためには体の大きさに対する比をとればよさそうだが、標本の測定値なので精密な測定が難しく使っていないのだろう (論文の図なので一番相関の大きい脚の長さで比べたものを出している理由はわかる)。
データは論文に付いているので、より相関の低いとされる体重の 1/3 乗 (体の大きさにほぼ対応するだろう) を使って作図してみるとグループ間や種間の違いがよりよくわかる。
体重の 1/3 乗をベースとして脚の長さと首の長さの相対値を調べてみると、フクロウ類は脚は平均的な陸鳥より 1.1-1.4 倍ぐらい長め (これはご承知の通り)、首の長さは平均的な陸鳥より2割短い結果となった (正規分布ではないのでいずれも数値的な平均ではなく中央値/最頻値に近い値を使っている)。
「フクロウ類の首は一見短く見えるが羽毛に隠れているためで実際には長い」との説明はしばしばなされるがあまり正確ではない。フクロウ類の首はやはり鳥類全体でも一番短い部類なのである (インコ類で最も短いものとほぼ同程度)。
同じ方法で調べるとヘビクイワシは脚は平均的な陸鳥より 2.2 倍ぐらい長い、首は 1.4 倍ぐらいと納得できる数字に思える。シロエリハゲワシでも脚は平均的な陸鳥より長く 1.2 倍ぐらい (ハゲワシ類も脚はそこそこ長い)、首は 1.7 倍ぐらいとこれも妥当な数字に見える。
猛禽類3系統で比較してみると、ハゲワシ類やヘビクイワシ等特殊な形態のものを除いたタカ類に比べてハヤブサ類の首は1割ぐらい短く、フクロウ類は2割ぐらい短い結果となる。
イヌワシの脚は平均的な陸鳥より 1.1 倍ぐらいと実は想像したほど長くない。首は平均程度となった。獲物を引き裂く力が必要なため首が短くなるような適応は特にないようである。
ミサゴはどちらもほぼ平均ぐらい。
他のグループでは目立ったところでヤマセミ類 (調べられているのはクビワヤマセミ Megaceryle torquata) の脚は (これもよく知られている通り) 非常に短く、標準の 0.5 倍ぐらいだが首は平均程度だった。
フクロウ類の首が特別に短いことにどのような適応的意味があるのかはわからないが、首が短いため回転に対する余裕が少なく、de Kok-Mercado et al. (2013) のような相対的な特殊化が見られるのかも知れない。
フクロウ類、ハヤブサ類で立った状態で獲物を足で嘴に運べる種類が多い [Gutierrez-Ibanez et al. (2023) #ハチクマの備考参照] のも、あるいは首の短さが関係しているのかも知れない (あくまで私的仮説であるが Gutierrez-Ibanez に聞いても特に否定しなかった)。
[高精度ゲノム解析]
Winter et al. (2025) Near-chromosome-level genome assembly and transcriptome of the Ural owl, Strix uralensis PALLAS, 1771
フィンランドの個体の保存されている組織サンプルとオーストリアのサンプルから。反復配列比率は 12.48% と結構高かった。保全のためにゲノムを高精度に読んだ報告で系統研究などそれ以上の議論は特になされていない。
フクロウはヨーロッパ中央部で再導入されたとのこと。
[梟の漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 115 VII (藤堂) によれば、号+鳥 の文字、梟 ともに中国語ではキョウ xiao と発音される。号は音符号で、口から息がまがって出てきたもので、低いだみ音を表す。高い声には対応しないとのこと。類似事例に号令 (低い声) などの用例がある。
フクロウをとらえて串ざしにして木の上の高いところに置くと他の鳥が近づかない。よって梟の文字となる。罪人に対する梟首の意味も同じとのこと。いずれにしてもフクロウは不吉なものと捉えられていた。
-
キンメフクロウ
- 学名:Aegolius funereus (アエゴーリウス フーネレウス) 喪のフクロウ
- 属名:aegolius aigolios 岩場や洞窟に住む不吉な鳥、おそらくフクロウの一種と考えられる (Gk)
- 種小名:funereus (adj) 死をもたらす、喪の (色彩が喪服のように黒っぽいことから? 備考も参照)
- 英名:Tengmalm's Owl (スウェーデンの博物学者 Peter Gustaf Tengmalm に由来), IOC: Boreal Owl
- 備考:
aegolius は起源となるギリシャ語 aigolios は1つめの o が長母音。ギリシャ語では末尾にアクセントだがラテン語化すると "アエゴーリウス" と考えられる。
funereus は冒頭が長母音。fu-ne-re-us と区切り、アクセントは -ne- にある (フーネレウス)。funus (フーヌス。葬式など) 由来。
北半球のやや高緯度に広く分布し、7亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は sibiricus (シベリアの) とされる。Tengmalm's Owl はヨーロッパでの呼称。Boreal Owl は北アメリカでの呼称。
Linnaeus がフクロウ類を整理して記載した時は Strix 属であったが、1829 年 Kaup がキンメフクロウをタイプ種として Aegolius 属を分離した (wikipedia 英語版)。
1986年4月、大雪山系の針葉樹林で抱卵するキンメフクロウが発見された。クマゲラの掘った巣穴を利用し、同じ巣穴をその前にモモンガとオシドリが使用したという。この年の繁殖は失敗に終わったが、1990年に2つがいの営巣 (クマゲラの巣穴を利用)。巣立ちも観察されたのこと: 「動物たちの地球」(週刊朝日百科 鳥類 II 1 フクロウ・トラフズクほか 朝日新聞社 1991) p. (7) 24-25 (川辺百樹) より。
同記事によればキンメフクロウはタイガに分布するが針葉樹林には樹洞がほとんどなくクマゲラの巣穴を利用しているとのこと。ユーラシアでは確かにクマゲラの分布とよく一致しているが、シベリアのフクロウの分布もそれほど違わないのでタイガのフクロウも事情は同じだろうか。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" ではキンメフクロウは北海道に広く分布する留鳥の可能性もあると記載されている。海外バーダーにはむしろ馴染みの種類で音声記録事例などが散発的にあるためだろうか。
先崎 (2015) Birder 20(9): 17 によれば道東地方で夏季に偶然撮影されたり探鳥会で声が聞かれるなど繁殖を示唆する情報が散見されるとのこと。
北米ではハシボソキツツキ Colaptes auratus Northern Flicker、エボシクマゲラ Dryocopus pileatus Pileated Woodpecker の巣穴を用いるとのこと。
ひなの養育をオスに任せてメスが遠くに離れてシーズン2回めの繁殖をすることがある (一妻多夫)。一夫多妻の例も知られているとのこと。つがいのきずなはシーズンを越えず、シーズン中でも途切れることがあるとのこと。逆に何年かの間に再度つがいになることもある (wikipedia ドイツ語版)。
ほとんど渡りを行わないとされるが一部は冬に多少南に移動する (アメリカやヨーロッパの話か)。遠距離の移動例はほとんどないが、これは越冬時に声による確認が難しいことも理由に挙げられる (wikipedia 英語版)。
ヨーロッパでは "ネズミの年" に北方個体群が irruption を起こすことがある (wikipedia ドイツ語版。この種の情報はドイツ語版に詳しい。スウェーデンでもよく研究されてスウェーデン語版も詳しい)。
ドイツ語では Raufusskauz で Fuss は足、Kauz はフクロウ類。rau- は英語の rough (毛皮などを指す。鳥類学では "羽毛の生えた") に相当するが現代ドイツ語ではほとんど生き残っておらず、鳥類学でもっぱら使われる (ケアシノスリ Raufussbussard など)。ロシア語名も同じ意味になっている。
同ページによれば、種小名はフクロウ類が死期が近いことを予告するとの伝説に基づき「死をもたらす」と名付けられたと解釈している。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 95 pp. 8, 13 によればクマゲラの巣穴をよく利用してクマゲラの分布に制約されているとも、そうでないとの考え方の両方が紹介されていた。
巣穴には何も持ち込まず、巣の持ち主の集めたおがくずの上にじかに産卵する。メスは卵が孵化しても巣をきれいにはせず、ひなたちははきだめの中で育てられるとある。
-
アオバズク (分割された)
- 第8版学名:Ninox japonica (ニーノックス ヤポニカ) 日本のタカのようなフクロウ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Ninox scutulata (ニーノックス スクトゥラータ) 市松模様のタカのようなフクロウ
- 第7版亜種学名:Ninox scutulata japonica (ニーノックス スクトゥラータ ヤポニカ) 日本の市松模様のタカのようなフクロウ (代表的亜種。他亜種あり)
- 属名:ninox (合, f) Nisus タカ Noctua フクロウ の既存の2属名から合成 (解説参照)
- 第8版種小名:japonica (adj) 日本の (japonicus -icus (接尾辞) 〜に属する)
- 第7版種小名:scutulata (adj) 菱形の、市松模様の (scutulatus)
- 第7版亜種小名:japonica (adj) 日本の (japonicus -icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:[Brown Hawk Owl 分割前の名称], IOC: Northern Boobook
- 備考:
ninox の読みはわからないが、ni- が nisus 由来とすれば長音と考えられ上記の表記 (ニーノックス) を採用した (2音節なのでアクセントも冒頭にあり、長音も自然な表記になる)。
Noctua の由来の nox, noctis はいずれも短母音のみ。nox が女性名詞で女性の属となる。
scutulata は -la- の a が長母音で無事この位置にアクセントが置かれる。
japonica は -po- がアクセント音節 (ヤポニカ)。アクセント位置を伸ばす読み方もある。
[分類と亜種]
分割のため第7版学名は代表的亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Ninox scutulata から分離されて Ninox japonica (日本の) となった。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
世界で3亜種 (IOC) だが、日本で認められるものは japonica 亜種アオバズクと totogo [台湾南部の Botel Tobago (スペイン語名) 島 (日本語名蘭嶼) に住む Totogo Hawk Owl の現地名] 留鳥のリュウキュウアオバズクである。
記載時学名は Strix hirsuta japonica Temminck & Schlegel, 1845。
これは Temminck (1824) が Strix hirsuta (hirsuta ひげのある、など) として記載した種の日本版 (当時は現在の亜種概念はなかった) として示したもの。
原記載では la chouette hirsute du Japon となっていて2つの型があり、ベンガルやボルネオのものを Strix hirsuta と呼び、日本のものを Strix hirsuta japonica と呼ぶ記載になっている。
この前後の種をみても "du Japon" ばかりでよい種小名を思いつかなかったためすべて japonica / japonicus とした模様。当時はすでに Otus 属が分離されていたためどちらにも japonica / japonicus の名称を与えることが可能だった。以下#フクロウ備考の亜種の項目に続く。
その後整理され、スリランカやインド南西部の亜種として学名 (Ninox scutulata hirsuta IOC 14.1 でも同じ) が残っている。Salgado Some observations on the Brown Hawk Owl (Ninox scutulata hirsuta)。
種和名はフーアアオバズクとなっている。
音声によってアオバズクを種として分離提案をした論文は King (2002) Species Limits in the Brown Boobook Ninox Scutulata Complex。
リュウキュウアオバズクの台湾での繁殖の論文は Lin et al. (2012)
Breeding ecology of the Northern Boobook Ninox japonica totogo in central Taiwanがある。Ninox 属の英名には Hawk-Owl と Boobook の両方が存在する。
英語で Hawk Owl と言えば Surnia ulula オナガフクロウ (ulula は声に由来) を指した (あるいは指す) [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)]。
こちらは尾が長くてタカに似て見えることから付けられたよう。分布域の広い範囲で Hawk Owl に相当する名称が用いられている。
オナガフクロウの分布は日本にも近く (サハリンやロシア沿海地方なども含む北半球のやや高緯度地帯)、もしかすると記録例が出るかも知れない。
アオバズク類の Hawk-Owl とは後述のように語源が異なると考えられる。
OED によれば Hawk Owl の用例は結構古く、1747 年に The Little Hawk Owl. This Bird is rather bigger than a Sparrow-Hawk. の記載がある。そもそもコミミズクを指していたらしい。
オナガフクロウの用例も記述されており、コミミズクもオナガフクロウも他のフクロウ類よりタカに似て頭が小さく昼にも活動するため Hawk Owl の名前となっていたとのこと。1812 年に Wilson, American Ornithology で Hawk Owl..This is another inhabitant of both continents..a connecting link between the Hawk and Owl tribes. の記述があり、当時はタカ類とフクロウ類は連続したもので中間型とみなされていたらしい。
"猛禽類" と称した場合にフクロウ類も含める場合の (少なくとも一時期はフクロウ類はヨタカ類と近縁とされ、タカ類との類似性は見かけ上のものとされていたので必ずしもまとめる必然性はなかった) 歴史的背景と見てもよいだろうか。
ちなみに owl の方も調べておくと 1275 年ごろにすでに用例があって当時の綴りは hule だった。直接の語源はわからないがヨーロッパ語に類似の単語がいくつもある。中世オランダ語の ule, hule など。おそらく音声由来と考えられているとのこと。現代でも owl を英語発音すれば howl (吠えるなど) と似た音になる。
アオバズク類 (Ninox 属) 以外で現行の英名に Hawk-Owl が付くのは マダガスカルアオバズク Athene superciliaris White-browed Hawk-Owl のみで、ヨーロッパや北米には生息しないためオナガフクロウを Hawk Owl と呼んで紛らわしくないがこれらの他系統の Hawk-Owl の名称があるためやむを得ずオナガフクロウを Northern Hawk Owl と呼ぶようになったと推定できる。
Lin et al. (2013) Genetic differentiation between migratory and sedentary populations of the Northern Boobook (Ninox japonica), with the discovery of a novel cryptic sedentary lineage では遺伝情報解析によって亜種アオバズクとリュウキュウアオバズクは種相当の違いがあるとしている。
Sadanandan et al. (2015) DNA reveals long-distance partial migratory behavior in a cryptic owl lineage では差異が小さいとの指摘がある。各グループと Brown Boobook/Hawk-Owl (アオバズク分離後の和名がわからないため英名で記す) の分布図も示されている。
大陸の florensis は独立種に値する可能性があり研究が望まれるとのこと。研究者によってはさらなる研究が出るまで亜種 totogo を無効とする考えもある。
シンガポール、ブルネイの個体の一部が留鳥とされている台湾の個体群に近いことがわかった。
一部長距離の渡りをしているらしい。
アオバズクの (高い精度のものではないが) ゲノムはすでに読まれている。Sequencing for Northern boobook genome ... (Birds of prey genome 2018/2019)。飼育個体から。
Cho et al. (2019) Raptor genomes reveal evolutionary signatures of predatory and nocturnal lifestyles の解析に使われている。
「決定版 日本の野鳥650」(平凡社 2014) では亜種チョウセンアオバズク Ninox scutulata macroptera (学名は当時のもの、「翼の大きな」の意味) が稀に飛来するとあるが、現在では Ninox japonica japonica のシノニムとされている。この亜種を認める世界の主要リストはなく、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)にも含まれていない。
[属名・和名の語源]
Hodgson のもとに標本が持ち込まれた時、これはタカか、それともフクロウかと考えた。もちろんフクロウ類ではあるが、フクロウ類の中で最もタカに似ているとのことで上記属名になった。
記載 (Hodgson 1837)。Suruninae のうちタカ科とハヤブサ科のような違いかどうかを議論している。チョウゲンボウと同じ昆虫食なので Suruninae のうちこれに対応するものかなどの考察がある。
当時 Ninox nipalensis として名付けられたものだが、これは Strix lugubris のシノニムとわかり、これはさらに現在 Brown Boobook の亜種とされる (Ninox scutula lugubris)。アオバズクもこの種の亜種だったのでアオバズクについての話として読んでほぼ差し支えない。
(The Key to Scientific Names, wikipedia 英語版)。旧英名も同じ意味。
Hodgson (1837) の 記載。当時は科名が Noctuinae だったことがわかる。Ninox は Niso (ハイタカの Nisus 王参照。転じてタカの意味) と Noctua (フクロウ類の属名 < 語源は nox, noctis 夜)。
属学名に Ni- が含まれ、これが重要な意味を持つことを認識しておくのがよい (Nis- まで含まれているが同様の例にクマタカの属名 Nisaetus がある)。
Ninox に nox 夜 の意味は含まれているが、命名者によればこれは直接の語源ではなく Noctua のフクロウ類を指していたもの。
古い学名で Noctua はかつての用法は混乱していてさまざまなフクロウ類の属を指していた。
ラテン語 noctua はミネルヴァに捧げられたフクロウ (The Key to Scientific Names)。
ルソンアオバズクに対して付けられた Nisininox の属名まであった (Nisus が二重に現れることになる)。
かつてはひなに餌を与える姿のストロボ画像などがしばしば紹介されていたが、(正面よりむしろ) 横顔を見ると確かにタカの一種のように見える。
大橋 (2023) Birder 37(10): 50-51 の和名語源考察がある。最初に現れるのが 1802 年の飼育書であり、野外よりも飼い鳥文化の中で青葉と関連付けられた可能性が考察されている。
自分も「青葉の時期にやってくる」解釈で違和感を感じていなかったのであまり気にしていなかったが、このように問われて自分なりの別解釈を考えてみた。"アオバズク" は "コノハズク" に対比して付けられた名前ではないだろうか。"コノハズク" の方は "木の葉" の形容で違和感がないように思える。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば「このはづく」の用例は大和本草 (1709-1715) の時代にすでにあった。
同じような時期に渡ってくるもう1種のフクロウに対して対比的な表現が用いられたのではないだろうか。"アオ" は必ずしも現代の "青" でなくてもよく、古い時代の曖昧な色を指していてもよさそう。"アオバ" と "コノハ" は語呂合わせのようなもの (鳥の英名はこのような対比的な語呂合わせ的な用例が多数ある)。もちろん実際に青葉を指していても構わない。
このように考えると大橋氏も疑問を持たれている、羽角がないのに "ズク" が付く理由が説明できるような気がする。
大橋氏はアオバズクを昼間に青葉と一緒に見ることは難しいため飼育環境下で青葉に関連させた可能性を述べられているが、昼間のアオバズク観察はそれほど難しいものではない。よく知っている人であれば肉眼だけでも渡来日まで確定できるぐらいに見つけられるとのこと。
自身も秋の渡り時期に同じ枝に数日連続でとまっていたのを見たことがある。今よりおそらく個体数も多く、自然に接する時間の長い目のよい時代の人にとって、毎年やってくるアオバズクを昼間に見ることは珍しくなかったのではないだろうか。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 203 (1946 年初出) によれば当時アオバズクを詠むことが流行していたらしく、「馬酔木」の当時の野鳥俳句を調べてみると堂々の1位で 18 首、カッコウ (16)、ホトトギス (12) でさすがのホトトギスもさすがに流行が終わっていたらしい。ただし新参者のアオバズクは題材が限定されていて広がりを欠いていたらしい。
[Ninox 属のサイズ性的二型]
猛禽類では一般にメスの方がオスより大きいが、Ninox 属では逆転している例が知られている。
オーストラリア地域の大型の3種とのことで、オスが昼間に餌を提示する "prey holding" 行動を示す点はフクロウ類中でも唯一とのこと (#トビの備考 [猛禽類の逆性的サイズ二型] 参照)。
[昼行性フクロウ類の進化]
Espindola-Hernandez et al. (2022) Genomic signatures of the evolution of a diurnal lifestyle in Strigiformes
に昼行性に適応したフクロウ類のゲノム研究がある。
オナガフクロウ Surnia ulula Northern Hawk-Owl、
アナホリフクロウ Athene cunicularia Burrowing Owl、
シロフクロウがこの研究での該当種。系統樹から祖先形は夜行性と考えられ、独立に複数回の昼行性への適応が起きたらしい。
これらの種ではタンパク質をコードしない領域の進化速度が非常に速く、例えば昼行性への移行に伴った脳ニューロンの発達などを制御している可能性がある。フクロウ類は昼間も目が見えるので昼行性の習性は簡単に獲得できると想像するのはおそらく甘すぎで、ゲノムレベルでかなりの進化を伴う必要があるようである。
上記昼間に餌を提示する Ninox 属ではどうなっているのか興味あるところであるが研究がなされていないようである。
この研究ではフクロウ類の祖先形は夜行性と考えているが、#ハイタカ備考 [日本と北米の広義ハイタカ属比較] で考察のようにオナガフクロウはもともと昼行性でタカ類の進出とともに北方に分布が制限されたものかも知れない。Ninox 属でも聴覚など夜行性適応が弱いので、あるいはと思ってしまう。
逆に言えばメンフクロウ類や Strix 属などに比べて音源定位はあまり得意でないと想像できるのである程度の明るさのあるところで活動するのが妥当な感じがする。アオバズクにとっては夜は暗いほどよいわけではないのでは。[アオバズクの減少] の東京都区内や街道沿いでも繁殖していたように人里を得意とするのは明かりも欲しいためかも。光に誘われて虫がやってくるためもあるのだろう。樹木が生育して夜の森があまりに暗くなりすぎている可能性も減少要因に含まれるかも知れない。
[卵の形の進化]
よく調べられている種類ではアオバズクの卵は最も丸いとのこと。
Stoddard et al. (2017) Avian egg shape: Form, function, and evolution
は卵の形と hand-wing index (HWI) という飛行効率や分散能力に相関の強い指数がよく相関していることに気づいた。飛翔性の強い鳥 (特にシギ・チドリ類) では飛翔に伴って体を流線型に保つために細長い卵が選択されたのではとの仮説。ただし丸くない卵は鳥類の進化以前にすでにあった。
Montgomerie et al. (2021) The Shapes of Birds' Eggs: Evolutionary Constraints and Adaptations
は系統を絞って (比較的古典的な議論の対象であった) 卵管の太さ、骨盤構造、巣の構造、クラッチサイズなどとの関連を調べた。上記 HWI との相関も調べて卵の細長さには相関があったものの、分類群ごとに限った解析では卵の形との相関が出なかったとのこと。分類群ごとに見るとむしろ (樹) 洞営巣性のものが丸くなるのではとの結果を出している。
骨盤構造とはもちろん相関があるが、これはどちらが原因でどちらが結果と言いにくい。オープンな環境に産卵する卵ほど転がり出にくい形が好ましいとの一般的説明はある程度実証している感じ。
この著者 (Birkhead のチーム) は全体をまとめた解析では分類群内の興味深い傾向が埋もれてしまうとの見解。とはいえ分類群ごとの違いがかなり大きく、営巣習性と系統にも相関があるので統計的扱いが単純すぎる気もする。どちらも研究にもそれぞれ言い分がある感じ。
卵型 (梨型) をしている方が表面積が増えて卵の代謝率が高まり発育時間が短縮されるとのモデル解析: Narushin et al. (2024) Pear-Shaped Eggs Evolved to Maximize the Surface Area-to-Volume Ratio, Increase Metabolism, and Shorten Incubation Time in Birds。
[死亡したオスに代わってヘルパーとなった事例]
尾崎・尾崎 (2019) Birder 33(9): 40-43 に兵庫県 (昆陽池公園) で子育て中のオスが死亡して代わりのオスが現れ、つがいを形成してそのまま子育てを続けた事例が紹介されている。夜間のみのヘルパーだったとのこと。
[アオバズクの減少]
植田・小野 (2015) Birder 29(9): 18-19 に考察がある。一方でフクロウは増加しているとされ、いくつかの要因が挙げられていた。簡単にまとめると、アオバズクの食べる昆虫が減少しているが一方でフクロウの食べる哺乳類は減少していない。哺乳類を食べるノスリもむしろ増えている。アオバズクは渡りをするがフクロウは留鳥である要因が主に取り上げられていた。
ノスリが増えている印象は目立ちすぎる種類のため見かけのものかも知れない (#ホトトギス備考の研究紹介参照)。
アオバズクの減少はおそらくコノハズクとも関連して議論した方がよさそうで、#コノハズク備考 [ヨーロッパコノハズクの減少] でも取り上げた。コノハズクの減少は日本の特殊現象ではなく近縁のヨーロッパコノハズクに非常によく似ている。ここでも再度取り上げておくと Treggiari et al. (2013), Sergio et al. (2008) の論文をもとにコノハズク類は純森林性というより草地の存在 (採食場所だろうか) が重要で、森林ばかりの所には住みにくいらしい。
フクロウはむしろ森林が得意でフクロウの分布が広がっているのかもと考察した。この議論ではアオバズクの繁殖地では営巣できるような木のまわりに開けた空間のある環境がそもそも限られたところにしかないこと、ヨタカの減少も同様の環境変化が現れているのだろうかとふと考えてしまう、と述べた。
アオバズクが営巣できるような木のまわりは今ではぎりぎりまで宅地に、あるいは空き地は "土地の有効活用" (これは税金がかかるためと言える) のため、みな駐車場などになってしまっているのではと感じた。アオバズクは潜在的には渡ってきて十分分布できる個体数が存在する感じがするが、生息地がないことが妨げになっているのでは。
昆虫が減少しているならばヒタキ類も減少しそうだがそういうわけではなさそうで、画一的な土地利用によってアオバズクの生息に適した空間スケールのモザイク化が阻まれているためでは。
昆陽池公園の [死亡したオスに代わってヘルパーとなった事例] も他に行き場がなく、狭い地域で生息せざるを得ない状況から生じたのかも知れない。
保全生物学者も欧米のようにもう少し提言を行ってよい気がするが、アオバズクが減少してもあまり問題がないレベルであれば特に何というほどのこともないのかも。
オナガフクロウのことを調べていて周囲の明るさも重要ではないかと感じた ([昼行性フクロウ類の進化] の項目に)。昆陽池公園も周囲は市街地で明るいので案外適切な場所なのかも。
週間アニマルライフ (1973) pp. 4035-4036 のアオバズクの項目 (内田) にも解説があり、人家近くの大木でホッホー、ホッホーと鳴く鳥はフクロウと呼ばれ昔から親しまれてきているが、その大部分はアオバズクだろうとのこと。
村落や低山の林で東京都区内でも繁殖していたが、広葉樹、針葉樹の区別なく寺社林や屋敷林、あるいは街道沿いのスギ並木でもじゅうぶんである。日本のフクロウ類のなかでもっともよく目にされておそらく数ももっとも多いだろう。ここ 10 年ぐらいのあいだに激減してしまって近い将来には東京からまったく姿を消してしまうおそれもある、と記されていた。
なお「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) で紹介されている古い時代のフクロウの名称は冬に現れる、あるいは音声の記述からフクロウを指しているものと思われる。
[その他]
標識調査で日本からフィリピンへ移動した2例がある (コンサイス鳥名事典)。
巣立ちびなはスズムシのような声で鳴くと形容される。wikipedia 英語版には、日本で繁殖する最も一般的なフクロウ類の一種であるにもかかわらずあまり研究されていないとある。
-
トラフズク
- 学名:Asio otus (アシオー オートゥス) ミミズク
- 属名:asio (m) ミミズクの一種
- 種小名:otus (m) ミミズク (otus (m) フクロウの一種。otos 耳 Gk に由来)
- 英名:Long-eared Owl
- 備考:
asio は o が長母音。アクセントは冒頭 (アシオー)。
otus は冒頭が長母音かつアクセントがある (オートゥス)。#オオコノハズク参照。
英名の Long-eared Owl は特に対応する学名があるわけではないようだが、#コミミズクの Short-eared Owl に対比する形で付けられていたものだろう。コミミズクには対応する学名があって長く使われていた。otus には語源から耳の意味が含まれ "eared owl" に相当する。
北半球のやや高緯度に広く分布し、4亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種はユーラシアに広く分布する基亜種 otus とされる。
Northern Long-eared Owl の英名もある。
かつては属名と種小名を入れ替えると別種になる種類として Asio otus と Otus asio (ヒガシアメリカオオコノハズク) Eastern Screech-Owl があったが、属分割によって Megascops asio となったためクイズの題材には使えなくなった。
一時はオオコノハズクと同種とされたインドオオコノハズク Otus bakkamoena Indian Scops Owl が Otus 属のタイプ種のため (原記載)。
トラフズクが Otus 属のタイプ種となってもよさそうなところで、Otus Cuvier, 1816 は実際にそうなっていた。
しかしインドオオコノハズクのみを指した用例 Otus bakkamoena Pennant, 1769 (参考) の方が早くこちらがタイプ種と認定された次第。属そのものの定義は現れないが単形属であったため有効となったものであろう
[一部 The Key to Scientific Names より取りまとめ。Hartert (1910-1922) p. 973 にも属記載時は単形属と説明がある。今では巨大な属になってしまった]。
BirdForum (2025.3) でも話題となって Inverse Latin Pair Names (two species with a shared name but in reversed order)
現行の IOC 学名では存在しないとのこと。
かつては Asio otus と Otus asio 同様の例として Cygnus olor (コブハクチョウ) と Olor cygnus (オオハクチョウ) があったがこちらは同属に統合されたとのこと。この例からもトートニムとタイプ種の関係が単純でないことがわかる。
一番近い組み合わせは Recurvirostra avosetta (ソリハシセイタカシギ) と Avocettula recurvirostris (ヒメソリハシハチドリ Fiery-tailed Awlbill) ではないかとの提案が出ている。
種小名で使われる asio, otus, scops, bubo はいずれも Linnaeus (1758) に Strix 属として現れる (原記載)。
Hartert (1910-1922) p. 984 にはトラフズクの多数のシノニムが現れる。記載時 Strix 属であったため、Otus 属となった際に多数の改名が提唱されたよう (#ノスリの備考参照)。
Otus Europaeus Stephens, 1826 (参考)、
Otus vulgaris Flemming, 1828 (これは改名よりも英国は大陸と別種と提唱したものかも。普通の Otus の意味)、
Otus communis Lesson, 1830 (参考。普通の Otus の意味)、
Otus aurita Rennie, 1831 (参考。明示的に "耳" を表した)。
Hartert で用いられているドイツ語名は Waldohreule (森の耳のあるフクロウ) で、コミミズクを "沼の" としたものと対比的な名称と考えられる。英語よりも生息環境を重視した名称になっている。ドイツと英国ではこの2種の馴染み度が異なることも背景にあるかも。
Asio 属もややこしい経緯となっており現在使われるものは Brisson (1760) によるもの。ここでは二名法は採用されておらず、属記載のみが有効となった。Asio が指していたものが Strix otus Linnaeus, 1758 と判断されたため Asio と Otus の関係が非常にややこしいものになってしまった。
#ワライカモメ の備考にあるように Linnaeus と Brisson はほぼ同時期に相互参照しながらさらに前の古典を原点にそれぞれに独自路線を歩んでいて、後に Linnaeus の分類体系が採用されたため複雑な関係になった。Linnaeus (1758) の誤った解釈によるワライカモメの学名を Brisson (1760) がそれとなく修正するなどそれぞれ競い合っていた部分があったものと想像できる。
Linnaeus の学名システムを認める代わりに Brisson の属記載は有効と判断するなどの判断が行われたのかも知れない (あくまで想像)。
ドイツ語では Eule (オイレと読む) がフクロウ類を指して使われるが、ゲルマン祖語 *uwwalo に遡るとのこと。これはワシミミズクを指す *uwwo の指小語とのことで、音声模倣の *ufo に由来するとのこと。英語の owl も同様。語源は現在のスウェーデン語 uv (ミミズク) に残っているとのこと。
Eulenspiegel (オイレンシュピーゲル。14 世紀の北ドイツに実在したとされる伝説の奇人。様々な事件を引き起こし、定住することがなく放浪し、人間的に成長することのないアンチヒーローである。wikipedia 日本語版から) は文字通りでは "フクロウと鏡" の意味。
ドイツ語では Kauz (カウツ) の単語も使われ、主に Strix 属を指す。遡るとゲルマン祖語 *kuts (猛禽類)、さらにインド・ヨーロッパ祖語 *gu- (鳴く、叫ぶなど) に遡る。音は古英語 cyta (kite の由来) とも関係する。*kuts から派生した単語には英語の coot (オオバン類) も含まれる。
ドイツ語ではさらにワシミミズクを指す Uhu もあり、これは西ゲルマン祖語の *huo (フクロウ類) に遡るとのこと (以上 wiktionary)。
ロシア語では総称的には sova (単数形ではサヴァーとアクセントは後ろ。複数形で sovy ソーヴィ と前アクセントになる)。実際には sova の付くもの (コミミズク、トラフズク、アオバズクなど)、コノハズクを指す splyushka、キンメフクロウ類の sych、耳のように見える羽のない Strix 属の neyasyt'、オオコノハズクは小型で sovka、ワシミミズクやシマフクロウの filin など細かく分かれている。動物を表す語彙に文化的な違いが現れていて面白い。
英国では大陸に比べてフクロウ類の種類が少ないので英語の語彙があまり発達しなかったのかも知れない。
外国語を代表して「フクロウ類は "owl"」は英語にとらわれすぎかも知れない。
sova に近い語はスラブ言語に広く見られるが語源は古くよくわかっていないとのこと。ギリシャ語の Sojia (知恵) に由来する説があるとのこと (Kolyada et al. 2016)。
骨学による Asio 属の系統分類が分子系統学をサポートする結果となった: Posso and Salomao (2025) Osteology-based phylogeny and systematics implications of the genus Asio (Strigiformes, Strigidae)
包含関係は ((Asio otus ((Asio stygius (Asio clamator/Asio grammicus))) ((Asio solomonensis ((Asio capensis/Asio flammeus)))))
とのことで、属編成によって Asio 属が巨大な属となった結果を解剖学的にも支持することとなった。
多くのフクロウ類で飛行時の音の発生を抑制するメカニズムがあるが、トラフズクの風切羽の特性を調べた研究があったので紹介しておく: Gao et al. (2014) Viscoelastic Characterization of Long-Eared Owl Flight Feather Shaft and the Damping Ability Analysis
ハトやイヌワシの風切羽と比較して羽軸素材の弾性が高く、振動が速く減衰するとのこと。
[コウモリを主に食べる北京郊外のトラフズク]
Tian et al. (2015) Bats as the main prey of wintering long-eared owl (Asio otus) in Beijing: Integrating biodiversity protection and urban management
北京郊外の越冬地では齧歯類と同じぐらいコウモリを捕食しているとのこと。高音に敏感そうな哺乳類が特に選ばれている点は面白い。それだけ消音機能に効果があるのだろう。
Kelm et al. (2023) Continuous low-intensity predation by owls (Strix aluco) on bats (Nyctalus lasiopterus) in Spain and the potential effect on bat colony stability
こちらは種は違う (モリフクロウ) がスペインでコウモリの方に発信機を付けて行動を調べたもの。熱帯ではコウモリを主に捕食する猛禽類 (タカ・ハヤブサ類も含む) は何種類かあるが温帯では少ないとのこと。コウモリがねぐらから出てしばらくの期間と入るころが特に狙われやすい。モリフクロウの食物に占める割合は低いがコウモリの死因の大きな割合を占めている。#ハヤブサ備考の [視覚特性・薄明かりや夜間の狩り] にもタカ・ハヤブサ類の関連情報を示した。
Brighton et al. (2021) Aerial attack strategies of hawks hunting bats, and the adaptive benefits of swarming こちらはブラジルでコウモリを捕食するアレチノスリ [高野 (1973) ではスウェイソンノスリ] の研究。群れを作ることで希釈効果はあるが捕食者を惑わせる効果はない。コウモリの群れと鳥の群れでは捕食者に対する反応に違いがあるらしい。
タカの方の捕食戦略は見ていただくことにして、コウモリを捕食する鳥は 2016 年の段階で少なくとも 237 種知られている [Mikula et al. (2016)。ハヤブサの備考に登場]。コウモリが夜行性になった理由としてよく挙げられるが実験的証拠はあまりない。
Fig. 6 にいくつかの種のコウモリ捕食成功率が示されているが、ハヤブサ類よりタカ類のほうが高めでアカオノスリ Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk はコウモリダカ Macheiramphus alcinus Bat Hawk に匹敵するか上回る。アレチノスリは成功率が低い方に属する。
コウモリハヤブサ Falco rufigularis Bat Falcon は名前から想像されるほど成功率が高くない。フクロウ類ではアメリカワシミミズク Bubo virginianus Great Horned Owl が調べられていてなかなか優秀。
アレチノスリでコウモリダカ同様に短い時間を利用するため飛びながら食べる行動も見られた。まれだがハヤブサでもコウモリの集団を襲って空中で食べる報告がある。
コウモリダカの行動の論文も引用されているので興味ある方には参考になるかも。
コウモリ捕食を行う鳥のエコーローケーション対策?
改めて考えるとコウモリはエコーローケーションを行うため、羽音を消すだけでなくコウモリの出す超音波を反射しにくい特性もあるのではないかと想像する。特にフクロウ類の羽毛は柔らかいので超音波の吸音に役立ちそう。
実際にはもっと高音を用いるが、コウモリには聞こえるが鳥には聞こえない周波数として 20 kHz を考えてみると波長は 2 cm ぐらいになって、このぐらいの大きさの物体で超音波を反射する特性があればエコーローケーションで検出されてしまう可能性があり得る。実際に用いている周波数がこの数倍とすれば数 mm ぐらいの物体を検知することが可能で捕食者の接近を避けることもできるだろう。
このように考えると大きな嘴などがあるとコウモリ捕食に不利になりそう。フクロウ類の嘴が小型で羽毛に隠れるように存在するのもこのような意義があるのかも知れない (そのため余計に丸のみする必要が生じる?)。また足も超音波を反射する可能性があるが、羽毛に覆われている部分が多いのは飛翔時の消音機能や寒冷地への適応以外にも超音波の反射抑制にも役立っているかも知れない。フクロウ類自身が出す音を抑制する研究は多くあるが音を吸収する方の研究はあるだろうか。
タカ類ではコウモリダカがコウモリを主食としているが目先 (lore) がハチクマ類同様に羽毛で覆われている (#ハチクマ備考 [ハチクマと他種猛禽類との識別] 参照)。
コウモリの反撃? から守るための理由ぐらいしか思いつかなかったのだが、あるいはこれも狙う時に正面を向く裸出部を減らして超音波の反射抑制に役立っている可能性があるかも。足は長くないがそこまで羽毛で覆われていないようにも見える (熱帯でそこまで覆ってしまうと暑すぎるかも知れない)。羽毛や裸出部の超音波の反射特性は調べられそうなのでどなたか研究してみると面白いかも (意味のある結果が出るかもちろん保証はできないが...)。
コウモリを捕食するとコロナウイルス感染が多少心配されるが、系統の違いでコウモリ型のコロナウイルスは鳥にはほぼ感染しないのかも知れない (#インドガン備考の [野鳥と鳥インフルエンザ] に鳥類のコロナウイルス科ウイルスと感受性の話題がある)。
[トラフズクの羽毛に蛍光色素]
Griffith et al. (2025) Fluorescent pigment concentration correlated with age, sex, and size in Long-eared Owl (Asio otus) plumage
(一般向け解説)。
蛍光を用いる鳥の最近の話題については#オオルリ備考の [蛍光を用いる鳥] を参照。
羽毛着色にポルフィリンを用いる鳥については#カタグロトビ備考 [カタグロトビ若鳥の色彩メカニズム] を参照。フクロウ類、ヨタカ類、ノガン類とカタグロトビで知られている。
[人に慣れるトラフズク]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 95 pp. 18-20 によれば 19 世紀に Walter がトラフズクの飼育下での行動を記していて、トラフズクは人によく慣れるとのこと。ハンカチやナプキンを足で押し込んで隠そうとする、紙を丸めてやると飛びながらつかんだとのこと。
本来の行動が室内でも現れているような印象で、特段に知的行動らしい印象は受けなかった。#ハチクマ備考 [(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] の "ハチクマのお客さんになって" で見られたダンボールの箱の固まりをもぎ取って落とし、後に丸めた紙を与えられて同じ行動を繰り返す方が、本来の習性ともあまり関係がなく遊びの要素が強そうに思えた。
-
コミミズク
- 学名:Asio flammeus (アシオー フラムメウス) 炎の模様の (または赤みがかった) ミミズク
- 属名:asio (m) ミミズクの一種
- 種小名:flammeus (adj) 炎の色/模様の、(赤みがかった)
- 英名:Short-eared Owl
- 備考:
asio は o が長母音。アクセントは冒頭 (アシオー)。
flammeus は冒頭にアクセント (フラムメウス)。
記載は Pontoppidan (1763) による "Danske Atlas" (記載時学名 Strix Flammea) だがどのような点に着目して flammeus と名付けたかはあまりよくわからない。
flammeus の本来の意味は flamma (炎) に由来するもので、#ベニヒワの種小名にも現れるが意味はおそらく少し違う。他言語でも flammeus を語源としていると考えられるコミミズクの名称は簡単に調べた範囲で見当たらなかった。
同様の種小名を持つ現行の学名ではアメリカコノハズク Psiloscops flammeolus Flammulated Owl が英名に採用している。
flammulated の英語は他にあまり用例がないようで学名ラテン語から由来。OED では赤っぽい (ruddy) と紹介している。色彩に合わせて二次的に解釈された意味かも知れない (なおアメリカコノハズクには褐色型がありその場合は色彩でもふさわしいかも知れない)。
本来は炎に似た、の意味で英語 flammule には小さな炎や炎に似た模様の語義が紹介されている。
コミミズクで赤みを指した可能性がある部位は初列風切の上面基部と考えることもできるが、写真を見る限りではトラフズクに比べてそこまで顕著な特徴に見えないように思える。
他に現在使われている flamm- の学名は鮮やかなサンショウクイ類のみでこれらは明らかに色彩を表している (Orange Minivet, Scarlet Minivet)。
炎に似たパターンの羽毛の模様の構造 (例えば#タカブシギ などに類似の用例) を表していたのかも知れない (トラフズクの "トラ" も同様かも)。学名解釈は本来語義にも近いこちらを優先した。
「日本動物大百科 鳥類 II」(日高敏隆監修 樋口広芳・森岡弘之・山岸哲編集 平凡社 1997) には、学名 flammeus は胸の縦縞模様が「炎」を連想させることに由来する (中川宗孝) とあった。
英語の Short-eared Owl に対応し、もしかするとそのまま和名の由来となったかも知れない学名があった。
Asio brachyotos (brakhus 短い ous, otos 耳の Gk)。
The Key to Scientific Names によれば "Short-eared Owl" of Pennant 1761, 1785, and Latham 1781 などに現れるとのことで、英名とともに広く使われていた模様。
OED によれば Macgillivray (1840) "History of British Bird" でもこの学名が用いられ、英語別名に The Streaked Tufted-Owl, Woodcock Owl, Mouse-hawk などが挙げられていた。
最後の英名は食物を指していると考えられるが、前2者は縞模様やヤマシギに似た模様を指したものと想像できる。
この学名から遡れたものは Strix brachyotos Forster, 1772 があった (参考)。Strix brachyotos Gmelin, 1788 の用例もある (参考)。
Asio 属に変わり、1840 年でもまだ使われていたことから、英語でも学名でもずっと "コミミズク" でよかったらしい。和名も英名の通りで小さなミミズクではなく、耳の小さいミミズクが由来と推定できる (wikipedia 日本語版にも同様の記載あり)。
Hartert (1910-1922) p. 987 でもこの学名はシノニム扱いとなっている。
英名の Short-eared Owl は Long-eared Owl (トラフズク) に対するもの。
Hartert にあるドイツ語名は Sumpfohreule (沼の耳のあるフクロウ)。これはシノニムの Strix palustris Bechstein, 1791 に対応している。この学名もかなり人気があったようでかなり後の時代でも使用例がある。この2種のロシア語名もこれらドイツ語名と同じ意味になっている。
Pontoppidan (1763) が見つかったのはおそらくかなり後の時代。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" でも Strix brachyotos Foster を用いて和名コミミズクを記していた。
同じく現在のコミミズクの種小名に対応する Aluco flammea (Linn.) が記されていて和名なし。多数の学名が列挙されており、当時はどの種を指すのか明確でなかったと考えられる。
ちなみに Linnaeus の記載は Strix flammea Linnaeus, 1766。例によって (?) 何を指しているか同定困難だったのだろう。Pontoppidan (1763) が見つかったため Linnaeus の記載が不明瞭でも使えるようになった学名だったのだろう。
Macgillivray (1840) の時代の英語別名から推定すると flammeus はやはり外見の模様を指したものではないだろうか。ヤマシギは嘴の類似性とは考えられないので体の模様が当時の主な着眼点だったのだろう。
さらに別の学名があって Strix accipitrinus Pallas, 1771 (参考) 基産地 Caspian Sea (タカのようなフクロウの意味) で Pontoppidan (1763) が見つかるまではこちらが早いと考えられ、Menzbier (1882) が用いていた。
しかしこの意味のロシア語名はオナガフクロウ Surnia ulula Northern Hawk Owl に使われる。こちらも古い学名由来のようで Strix nisoria Meyer, 1809 (参考) 英名も Hawk Owl で、
Strix funerea をより記述的に改名したとあるが現在の種概念と異なる - と思ったら Linnaeus の方ではなく Temminck が用いた Strix funerea だった。"nisoria は nisus (ハイタカ) のような" の意味になる。
北半球やや高緯度に広く分布し、南米の一部にも分布する。11 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は北半球に広く分布する基亜種 flammeus とされる。
ハワイにも分布し、Asio flammeus sandwichensis とされるが、基亜種と区別できないとの意見もある。現地名 Pueo。Hawaiian Short-eared Owl とも呼ばれる。
自然分布だけでは考えにくく、ポリネシア人とともに入ったものと考えられる (wikipedia 英語版)。
sandwichensis は学名にしばしば現れ、人名、地名いずれの由来もあるが、ここではハワイの旧名サンドウィッチ諸島に由来する (ハワイガンやハワイクイナの種小名に使われる)。
越冬中はあまり鳴かないとされるが、大阪の淀川水無瀬に廃止されたゴルフ場跡に一時的な集団越冬地ができた時には威嚇しあうギャーという声がよく聞かれた。明るい時間帯でもよく活動していたのが印象的だった。
この時の状況は松村 (2016) Birder 29(9): 26-29 にあり、2014 年 12 月から越冬が始まり、最大 14 羽に達したとのこと。
小林 (2023) Birder 37(2) に北海道大黒島で国内初のコミミズクの繁殖例が報告されている。
wikipedia Crepuscular animal によればガラパゴス島の亜種 galapagoensis は昼間も活動するが、ガラパゴスノスリのいる島では crepuscular (薄明薄暮性) の活動をするとのこと。
[コミミズクの繁殖戦略]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 95 pp. 16-18 のコミミズクの項目ではクラッチサイズは通常 4-8 個、多い年は 14 個も産むことがある。地上に営巣してひなの成長が早く、15-17 日で巣から出るとのこと。いかにも食性の似たチュウヒの繁殖戦略にそっくり。#チュウヒ備考 [チュウヒ類の食性と生活様式の関係] 参照。獲物に合わせて r 戦略的と言ってよいのだろう。
コミミズクではこのようにひなの発育が早いために獲物の多い年にはシーズン2回繁殖も可能とのこと。
渡りも食物量依存で豊富な年には定住することもあり、また春の渡りも秋に通った場所には必ずしも戻ってこないとのこと。
特定の地域にとらわれず獲物を求めて移動する生活様式をとっているかも知れない。
またコミミズクはトラフズクに比べてより高緯度にも分布し、北極圏近くでは夜がほとんどないため昼間にも活動する。少し考えてみても高緯度ではそれほど競争種がない。シロフクロウやケアシノスリ程度だろうか。
ユーラシア東部の個体群の方がより高緯度に分布する傾向があるらしく、越冬地の日本でも明るいうちに飛んでいるのが納得できる (だからこそ写真対象に好まれる次第)。同じようにトラフズクを見ようとしても動き出すのはずっと暗くなってから。
越冬地でも習性は似ていて、同じところで越冬すると想定して、場所を決めて保護区とする保護手段はあまり向かないかも知れない。そもそもある年に現れて別の年には現れない、あるいは年によって越冬したりしなかったりするのはコミミズクの本質であって、一喜一憂するほどのことはない。しかしコミミズクに適した生息場所が一定以上の割合で広域に存在しなければ、いくら特定地域で保護を行っても数が減ってゆく可能性があるなど想像できる。
とそのまま写してみた。上記の大阪の淀川水無瀬のゴルフ場跡の事例もはかないもので、草が茂って見通しが悪くなるまでの一時的なものだった。これほどコミミズクがいるものかと驚いたものだが、ブームが去るのも早く話題にならなくなると訪れる写真家も激減。一時は現地近くで写真展も開かれるほどの盛況だったが、まだ渡来していてもあっと言う間に話題にもならなくなった。
上記のような繁殖戦略の融通性を見ると、繁殖地の食料の方が大切で、越冬地が減少しても例えば大陸に別のよい場所があれば実は思ったほど問題ないのかも知れない。
Strix 属と微妙に違うのかも知れず、週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 95 pp. 3-4 のモリフクロウ Strix aluco の記述では、繁殖は年1回で、クラッチサイズは 3-4 個。食物が不足して後に生まれたひなが死んだ場合はそれも食物として食べるとのこと。
ひなが失われても再度の繁殖はほとんどなく、若鳥が巣から完全に離れるのに 2-3 か月かかり、成鳥とも長命との説明になっている。この解説を見ると K 戦略的なタカに似ている印象を受ける (当時出たばかりの考えでそれに合わせて解釈していた可能性も考えられる)。
95 p. 5 のフクロウの解説では、普通 2-4 卵で、食物が多い年は 5-6 個に増えると言われる。ひなが巣から出るのに1か月ほど。5か月ほどで初めて飛べるようになるとのこと。巣立ってからそれほどかかるのかなあ、と感じるがこれは5週間の間違いかも知れない。文章を読むと日本のフクロウに対して新たに書き下されたと考えるよりはヨーロッパのフクロウの生態を表したものと感じる。
93 p. 12 にメンフクロウ (こちらは Tyto 属) が紹介されていて、年2回繁殖で1年あたりの産卵数は通常 8-10 個、多い例は 18 個が知られているとのこと。ただし飛べるようになるのは 9-12 週間後と遅いと記されていた。個数を見ると r 戦略的に見える。
[台湾で越冬するコミミズクの性比や移動特性などの研究]
Tseng et al. (2017) Wintering ecology and nomadic movement patterns of Short-eared Owls Asio flammeus on a subtropical island
台湾で越冬するコミミズクの研究。メスの方が多かった (75%) が、おそらく越冬分布の南限に対応するためではないかとのこと。コミミズクで過去に調べられた範囲では最も性比が偏っていた。オスの方が先に繁殖地に帰る必要があるためとの仮説が紹介されている。
発信機による追跡によって行動圏の大きさや移動範囲などが調べられている。同じ越冬地に戻った事例は1例あったのみで、齧歯類のように多く変動する食物資源に頼る長距離渡りを行う種でよく見られる放浪的な生活様式を示唆するが、ランダムに渡る種類との中間の性質を示すとのこと。ただし台湾のように人為的な改変の進んだ環境への適応も考えられ、この効果は現状不明とのこと。
[コミミズクの羽音]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 95 p. 16 によればコミミズクは繁殖期や秋の渡り時期には高空を飛んでいて突然両方の翼の先端がくっつくように後ろに伸ばし、地面に向かって降下する。この時に遠くで機関銃を撃っているかのような、あるいはキツツキが木を叩くような音をたてるとのことで、翼がぶつかりあう音、風切羽が振動する音の両方の解釈があるとのこと。#ヨタカの [ヨタカ類の "wing-clapping"] によく似ている。
コミミズクでも wing-clapping と呼ばれるそうで、XC614483 (Romuald Mikusek 2020.5.20) のような音声記録があった。これに反応してタシギの声が続き、おそらく逃げたのではとのこと。
Asio flammeus (Short-eared owl) 1. Territorial calls of male (Owl Voices 2015 音声と羽音のみ)。
フクロウ類もヨタカ類もよく似ていて (一部の種だろうが) 音を出しにくい羽毛構造を持っているにもかかわらず羽音をディスプレイに使っている。「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) には対応する記述がない。繁殖地以外で聞くのは難しいかも。
確かにこのような用例がいくつもあるとハチクマのディスプレイ飛翔を "wing-clapping" と呼ぶことに抵抗もあるのだろう。
△ サイチョウ目 BUCEROTIFORMES ヤツガシラ科 UPUPIDAE ▽
-
ヤツガシラ
- 学名:Upupa epops (ウプパ エポプス) ヤツガシラ
- 属名:upupa (合) ヤツガシラ (epops (m) ヤツガシラ 鳴き声由来)
- 種小名:epops (m) ヤツガシラ
- 英名:Hoopoe, IOC: Eurasian Hoopoe, AviList: Common Hoopoe (予定)
- 備考:
upupa は長母音が含まれず、規則通り冒頭がアクセント (ウプパ)。
epops も長母音が含まれず、2音節なので冒頭がアクセント (エポプス)。
音声由来なので長音にはならなかったのだろう。
ユーラシアや北半球のアフリカに広く分布し、北方のものは冬は低緯度に渡る。世界で6亜種が認められる (IOC。15.1 でアフリカヤツガシラが同種とされ追加される見込み)。
この種統合の結果英名は Eurasian Hoopoe から Common Hoopoe となる見込みとのこと: New unified list of birds - Avilist (2025.5 の項目)。
[分類と亜種の問題]
日本で記録される亜種は saturata (色の濃い、豊富な色の) とされるが、この亜種を認めず基亜種のシノニムと考えるリストもある (IOC など)。ロシアの現在のリストでもシノニム扱い。saturata が世界の記録でもしばしば登場するのは Brazil (2009) "Birds of East Asia" の記載によるかも知れない (epops と同一かも知れないとある)。
HBW/BirdLife (2022), Clements (2019年まで) はこの亜種を認めている (いた)。
「一部学名の変更の見込みについて」(2023年11月28日) にて基亜種 epops と変更された。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では IOC と異なり africana (アフリカ), marginata (マダガスカル、いずれも留鳥で分布域は IOC 分類のヤツガシラの越冬域かも離れる) を分離せず8亜種としている。
Wang et al. (2017) Gene flow and genetic drift contribute to high genetic diversity with low phylogeographical structure in European hoopoes (Upupa epops)
によれば種内の遺伝的系統構造はあまりなく (長距離の渡りをすることにも関係している) 亜種分類は見直されるかも知れない。後述の渡り研究も参照。
Upupa 属は一般的分類で3種からなるが、Howard and Moore のようにヤツガシラ以外のアフリカの2種を亜種とする立場もある。
マダガスカルヤツガシラ Upupa marginata 英名 Madagascar Hoopoe は音声が大きく異なる (wikipedia 英語版にもある = HBW Alive の情報から) ので別種相当でよさそうである。
アフリカヤツガシラ Upupa africana 英名 African Hoopoe は音声面でのヤツガシラとの違いはやや微妙だがツツドリのような2声や4声もしばしば記録されている。典型的なヤツガシラと多少違うように思える。外見はメスはヤツガシラと同様で、オスは上面の模様が異なるとされる。
Howard and Moore も セントヘレナヤツガシラ Upupa antaios St. Helena Hoopoe を別種としている。1550 年ごろ以来記録がなく絶滅種とされる。
2024.12.12 IOC 15.1 でアフリカヤツガシラはヤツガシラと同種に。AviList 2025 でも採用の見込みで英名は Common Hoopoe となる。
英名 hoopoe の由来は中世フランス語 huppe で、ラテン語 upupa (現在の属名と同じ) でやはり音声由来に遡る。古代ギリシャ語で epops でこちらは現在の種小名に使われている (Wiktionary)。
3音か2音かはあまり気にしなかった模様。
ヨーロッパ諸言語も音を用いているものが半数ぐらい。オランダ語では hop と1音まで短縮されている。ロシア語では udod、ウクライナ語では odud と子音交替が起きている。ドイツ語では Wiedehopf (広い頭) と形状を重視したものになっている。
[尾脂腺分泌物]
捕食者対策に尾脂腺より悪臭ある物質を出すので有名であるが、捕食者対策に有効かどうかの実験的検証は意外になされていない (#フルマカモメの備考参照)。
Martin-Vivaldi et al. (2009) Antimicrobial chemicals in hoopoe preen secretions are produced by symbiotic bacteria
によれば繁殖期のメスとひなは悪臭のある "dark secretions" と呼ばれる暗色の物質を分泌するがこれは揮発性物質に富む。その化学物質は個々には限られた抗菌作用しかないが、混合物には調べられたすべての種類の細菌 (例えば羽毛を劣化させる細菌) の増殖を抑制する抗菌作用があることがわかった。
抗生剤で尾脂腺の細菌を除去すると組成が大きく変わったとのことで尾脂腺に共生する細菌
[Enterococcus faecalis が分離されているが、ほとんどの健康な人にもみられる消化器官の常在菌。他の細菌の関与も可能性がある]
が分泌に関与すると考えられる。例えば悪臭成分のインドールは細菌による産物とされる。
非繁殖期の尾脂腺分泌物は揮発性物質を含まず通常の鳥と違わないとのこと。
近縁のミドリモリヤツガシラ Phoeniculus purpureus 英名 Green Wood Hoopoe でも同様の物質の分泌があり調べられている。#ブッポウソウ備考 [ブッポウソウ目と関連目の系統分類] のカマハシ科参照。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 88 V (森岡) によればヤツガシラの脂腺には発達した括約筋があり、普通の排泄物と同じぐらいとばすことができるとのこと。
ヤツガシラが翼を広げるとタカ斑模様のようにも見えるが、これも脅しに役立っているのだろうか。そういえばアカゲラなどの模様もそのように見えるかも知れない。いずれも洞営巣性である点は共通している。
#ヤマセミ [学名の lugubris の意味と生態的意義] も同じようなものかも。
[嗅覚]
ヤツガシラは嗅覚を利用して食物を探すそうである。眼窩にあるハーダー腺 (Harderian gland) と涙腺の分泌物が嗅覚にかかわる粘膜を潤して食物を探すのに役立っているとのこと [cf. Al-Nefeiy et al. (2022)
Morphological and functional relationship between the orbital gland and olfaction in Upupa epops (hoopoe) and Bubulcus ibis (cattle egret)]。
[サイチョウ類の頸椎]
Boehmer et al. (2019) Correlated evolution of neck length and leg length in birds (#コブハクチョウの備考参照) ではヤツガシラは相対的に首が長いグループに分類されている。
川上和人・中村利和「鳥の骨格標本図鑑」(文一総合出版 2019) を見ても確かに個々の頸椎が長いように見える。
Threskiornis (Reptile Evolution) の骨格でも外見の印象とはだいぶ異なって妙に余裕があるように見える。
Boehmer et al. (2019) の fig. 5 を見ても同じ頸椎数 (この文献の数え方で 13 個。普通に本に出ているような数え方ではおそらく 15 個になる) の鳥の中でも最も長くなっている。また頸椎数も一般的なスズメ目と比較すると1個多い。
この文献では足の長さに対する比率で扱っているので #フクロウ の備考で紹介した体重の 1/3 乗で調べてみると足は平均的な鳥より1割短く、首は 1.5 倍長いとなった。
この傾向は (日本にはいないので川上・中村では扱われていないが) サイチョウ類系統 (Bucerotiformes サイチョウ目) に共通のようである。Boehmer et al. (2019) にも同様の傾向が見られるがサイチョウ類は足もヤツガシラより長いため足の長さで規格化するとあまり目立たない。
サイチョウ類やヤツガシラは嘴が大きいあるいは長いため、首がある程度長くないと羽繕いなどに支障があるのかも知れない。あるいはまた別の役割 (ヤツガシラではシギに似た採食様式など) があるのかも知れない。
サイチョウ類 (サイチョウ亜目 Bucerotes だろうか?) は鳥類中唯一、第1頸椎 (C1 環椎 atlas) と第2頸椎 (C2 軸椎 axis) が癒合していて、大きな嘴を保持するための安定した足場を作っているとの解説がある (Hornbill の wikipedia 英語版より)。
VanBuren and Evans (2016) Evolution and function of anterior cervical vertebral fusion in tetrapods
に脊椎動物全体での頸椎癒合 (仙椎の癒合; 複合仙骨 synsacrum にならって syncervical。鳥類では胸椎が癒合して fused thoracic vertebrae = notarium を形成するものがある。synthoracic の用語もあるがあまり使われないよう) の研究がある
[Storer (1982) Fused Thoracic Vertebrae in Birds: Their Occurrence and Possible Significance に大まかな分類での胸椎癒合の研究があるので参考までに。
例えばタカ科は癒合していないがハヤブサ科では癒合している。そのためシンジュトビはハヤブサ科からタカ科への移動が提案されたとのこと。
James (2009) Repeated Evolution of Fused Thoracic Vertebrae in Songbirds にスズメ目で胸椎癒合は少なくとも 12 回独立に生じたとの研究がある]。
サイチョウ類の頸椎癒合はカスクをぶつけ合う行動のために進化したのではとのこと。首の可動域が少なくてもよい脊椎動物の他の例と比較すると鳥類の例はかなり特殊に見える。
ちなみにヤツガシラではこの癒合はないとのこと (とわざわざ Dement'ev and Gladkov に書いてあったのでサイチョウ類の頸椎癒合はよく知られているのだろう)。
サイチョウ類では嘴が注目され、ヤツガシラでは冠羽など特徴が多すぎるので気づきにくいかも知れないが、このグループでは頸椎の特殊化は一つの特徴と言えるのだろう。「外見の割に普通の骨格」の説明ではちょっともったいなかったかも知れない。
サイチョウ類は何 km も先から聞こえる大きな声を出し、Alexander et al. (1994) A possible acoustic function for the casque structure in hornbills (Aves: Bucerotidae)
によればカスクが音声の特定周波数の増幅に役立っているのでは、との考えがある。#タンチョウ備考の恐竜の Parasaurolophus の「とさか」に音響効果が期待されているものと同様か。
サイチョウ類系統で首が長めなのは同様の理由で共鳴に役立てているのかも知れない (こちらもタンチョウ備考参照)。ヤツガシラは特徴的な声を出すが、この発声に気管の長さが関連しているかどうかはわからない。
サイチョウの骨格例は松岡他 (2009)「鳥の骨探」にあるが癒着構造はよくわからなかった。
Surapaneni et al. (2025) The helmeted hornbill casque is reinforced by a bundle of exceptionally thick, rod-like trabeculae
オナガサイチョウ Rhinoplax vigil Helmeted Hornbill のカスクの内部の梁構造の解析。意外にも梁構造は雌雄差がなく、メスもぶつけ合う行動 (jousting) を行っているかあるいはカスクが別の役割を果たしている可能性があるとのこと。
Schindler et al. (2025) Helmeted hornbill cranial kinesis: Balancing mobility and stability in a high-impact joint
同じくオナガサイチョウで μCT を用いて頭骨のキネシスの研究。関節面が広く1次元方向のみの自由度に限定されるため安定性が高い。カスクの内部の梁構造もその方向を向いている。そのものが衝撃のエネルギーを逃がすものではないが頭骨構造が衝撃を和らげるとのこと。
[その他]
ヤツガシラ類は食物を空中へ放り上げて食べることがある (tossing)。ビデオの1例 Hoopoe Tossing。この習性はサイチョウ類に似ている。五百沢 (2006) Birder 20(5): 13 にヤツガシラの tossing の写真が紹介されている。
ヤツガシラでは最後に産まれたひなを餌として利用することが報告されている [Soler et al. (2022) Avian sibling cannibalism: Hoopoe mothers regularly use their last hatched nestlings to feed older siblings]。
猛禽類とは異なり、引き裂けるような嘴は持っていないのでひなが小さい時に飲み込む形で餌としている。ひなが育つと日齢によるが違いが小さくなり、飲み込むことが難しくなるため孵化後早い段階で起きる (#イヌワシの兄弟殺しの備考も参照)。
ヤツガシラは非同時孵化が特に顕著とのこと。Ferrer-Pereira et al. (2023) Food supply and provisioning behavior of parents: Are small hoopoe nestlings condemned to die?
では人為的に食物量を増やしたが、最後のひなへの給餌量は増えなかったとのこと。中程度のひなへの給餌量は増えたが、中程度のひなも満足した状態で最後のひなが餌乞いをしても余分の食物は巣にいるメス (オスが食物を運ぶ。この点は多くの猛禽類に似ている) が消費したとのこと。
Baron et al. (2024) Extra Nestlings That Are Condemned to Die Increase Reproductive Success in Hoopoes
もほぼ同じ点に注目した実験を行い、食物量を増やしても巣立ちに至る数は増えなかった。
Ferrer-Pereira et al. (2023) にも新鮮な栄養分を残しておくとあるが、単なる栄養として余分に1卵を産んでおくのは子育てをする脊椎動物で初めての例とのこと。
ヤツガシラではかなり特別のようで、食物量によって巣立つひなの数の変動する他種とは様相が異なっている。
中国名戴勝 (対応する漢字の表記で表す)。"勝" にはかんざしの意味があり優れた命名とのこと [福井・チャン (2003) Birder 17(8): 68-69]。現在の wikipedia 中国語版では属・科の名前には簡字体でない戴勝が使われている (統一していないだけかも知れないが。台湾の表記は種名も戴勝)。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3794-3795 のヤツガシラの項目 (安部) では、戴勝では「勝利者の冠に見立てたもの」との解説があり、キクイタダキ (戴菊) も参照となっていた。漢字ではシの読みに相当する文字で表現されていて、農耕をすすめる鳥といわれていたとのこと。
ヤツガシラの渡り研究: van Wijk et al. (2018) Diverse migration strategies in hoopoes (Upupa epops) lead to weak spatial but strong temporal connectivity (別リンク)。
ヨーロッパの研究で渡り経路は多様で様々な地域の個体群が混じり合うことができる。時期はよく同期している (日本の春の渡りも同じ印象を受ける)。
van Wijk et al. (2017) Repeatability of individual migration routes, wintering sites, and timing in a long-distance migrant bird 同一個体でも越冬地は決まっていない。越冬地の環境に年変動があるためか。
△ ブッポウスウ目 CORACIIFORMES カワセミ科 ALCEDINIDAE ▽
-
アカショウビン
- 学名:Halcyon coromanda (ハルキュオーン コロマンダ) コロマンデルのカワセミ
- 属名:halcyon (f) カワセミ (= alcyon、カワセミになったアルキオーネから)
- 種小名:coromanda (adj) インド東南のコロマンデルの
- 英名:Ruddy Kingfisher
- 備考:
Halcyon の読み方で、薬剤名の日本語読みにつられたものか "ル" にアクセントを置く発音を聞いてしまった。"ル" は本来子音なのでアクセントは置けない。ラテン語の標準的な発音を調べてみると o は長母音でアクセントは冒頭の "ハ" にある (ハルキュオーン)。
ギリシャ語も同様に長音でこちらではアクセントがその位置にある。
英語の halcyon でもアクセントは冒頭で a の発音は hat の a と同じ。
Alcyone でも (日本語では最後にアクセントを置いて読まれるが) ラテン語では -cy- (キュ) にアクセントがあるとのこと。英語ではキュとは読まないが、同じ音節 (サイと読む) にアクセントがある。
いずれも "ル" にはアクセントを置かないように。
coromanda は地名で -man- がアクセント音節になることは問題ない。すべて短母音とすれば "コロマンダ"。#アマサギ参照。
記載時学名 Alcedo coromanda Latham, 1790 (原記載) 基産地 Coromandel, India。
当時は多数のカワセミ類が命名された時期で、Latham も coromanda と bengalensis とインドの地名を2つ使っている。インドだけでも他に cristata, orientalis を用いていた。
coromand.. はよく現れる種小名の印象を受けていたが、IOC 14.2 で調べると8種にとどまっている。日本の種ではアマサギやカンムリカッコウが該当して3種もあるので数が多い印象を受けるよう。
Halcyon 属は Swainson (1821) によるもので 原記載。
Halcyon collaris Collared Crabeater のみを指した属だったが、この種が何に対応するかは多少複雑だった模様。記載時学名で Alcedo senegalensis Linnaeus, 1766 (セネガルショウビン) と同一 (シノニム) と判定されることとなった (The Key to Scientific Names)。
この点から日本のアカショウビンと Halcyon 属のタイプ種は地理的に離れていて、もし分子系統解析などで別属がふさわしいとなればアカショウビンなどの属名が変わる可能性も残されている。
かつては Halcyon 属はヤマショウビン属と呼ばれていた。この理由も今ひとつよくわからない。
世界で 10 亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は major (より大きい) 亜種アカショウビンと bangsi (アメリカ動物学者 Outram Bangs に由来) リュウキュウアカショウビンとされる。亜熱帯に近く分布する亜種は留鳥。
major の記載は Alcedo (Halcyon) coromanda major Temminck & Schlegel, 1848 (原記載)。図版。
Alcedo (Halcyon) coromanda minor Temminck & Schlegel, 1848 (原記載) 基産地 Borneo and Sumatra, restricted to Pontianak, Borneo, by Oberholser, antea, 1915, p. 649 (ボルネオ島に限定) で大小を対比する形で付けられた学名。
いずれも Halcyon 属での用例がなかったために現在も使われている。Alcedo minor McClelland, 1837 の名称は過去に使われていたが major の方はなかった。別属扱いなので現状問題はないが、過去にはこの表記で preoccupied と判定されていた事例 (#ノスリ参照) あった。
同様に大小を対比する形で Temminck & Schlegel が用いて現在片方のみが用いられている例に #クロツラヘラサギ がある。#カワラヒワ も状況は近かったがオオカワラヒワに major は使わず、フランス語名にこの意味を用いたが種小名には現地名を用いた。事情はそれぞれの備考参照。
Temminck & Schlegel が "大小" の学名を用いた場面の背景事情が多少わかる感じがする。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" には複数の和名が紹介されているが、アカショウビンは3番め。先頭はミヤマショウビンだった。もしこれが採用されていればミヤコショウビンと紛らわしい名前になっていたかも。
Ogawa (1908) では当時の亜種 rufa にリュウキュウアカショウビンの名前を与えていた。この亜種学名は現在でも有効で、現在ではスラウェシ島などインドネシアの亜種を指す。
1915 年に bangsi に分離 (原記載) される前のリストだったため。
アカショウビンの秋の渡りは早く、8月下旬から9月上旬を中心に渡り途中の個体の声を聞く。キツツキを思わせるような地鳴き [この点はヤマセミの声がキツツキと誤認されやすい点に似ている。参考: 松田 (2017) Birder 31(5): 32] が中心だが、さえずりも聞かれる。自分が聞いたのはほぼすべて夜明け直前の時間帯で、明るくなってからはあまり期待できないかも知れない。
裏山からアカショウビンの声に関連記事 (2018.8.25) があったのでリンクしておく。
自分の印象では地蔵盆の後ぐらいの時期が多い感じ。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 87 V では秋の渡りは東京では9月下旬から 10 月上旬にかけて通過するとある (内田)。少し遅すぎる感じがするがいかがだろうか。もっとも自分の確認も声が頼りなので鳴かない個体は記録できていない。
Ruddy Kingfisher (Philippe Verbelen 2008.12.19) にインドネシアで録音された音声がある。渡り途中にも聞かれるタイプの音声 (亜種は異なる可能性が高い)。
XC755450 はマレーシアの例。
XC286023 は石垣島の繁殖期の音声。このタイプの音声と亜種アカショウビンで聞き慣れたタイプの声と両方が記録されている。
XC285995, XC156319 のような少し不規則な声もある。パターンの少し崩れた声は亜種アカショウビンでも聞くことがある。
アカショウビンではさまざまな声が記録されており、例えばマレーシアでは XC359768 (東南アジアでは比較的典型的な声のよう)。短くなると XC894407, XC294060。
いずれも似た声を多少聞いた覚えがあるので渡り時期の不明声にはアカショウビンが含まれているかも知れない。
世界的にはアオショウビンの方が分布も広くよく知られており、同様にさまざまな声を出す。特にキツツキを思わせる声はよく似ている。アオショウビンの音声バリエーションを調べておくとアカショウビンのちょっと変わった声の同定にも役立つかも知れない。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 134 (1946 年初出) によれば別名ミヤマショウビン。もう少し旬の歌に詠まれてもよいのではないかとある。声を知っている人もそこそこあり声由来の地方名もいくつかあることも紹介されているが、どうも鳴いている姿を見ることが少ないためか声由来の名称は残りにくいようで、声を聞いて判断できる人も少なく季節感があるのに歌にもなりにくいらしい。我々もアカショウビンを声だけですぐ理解できるのは音源が普及しているゆえかも知れない。
鳥の和名を声由来として考察する際の参考になるだろう。
p. 127 に南蛮鳥の地方名が挙げられており色由来の名前に分類されている。近年ではあまり馴染みのない用法なので調べておくと猩猩緋 (しょうじょうひ) の名称があり南蛮貿易の舶来品で知られる色で、室町時代後期以降に流行するとのこと (wikipedia 日本語版より)。赤唐辛子 (南蛮) も関係があるよう。
[分類]
カワセミ類の分子系統分類は
Andersen et al. (2018) A phylogeny of kingfishers reveals an Indomalayan origin and elevated rates of diversification on oceanic islands
(ResearchGate)
にある。日本産の種では従来分類に比べてあまり分類上の変更点はない。
アカショウビンは Halcyon 属の中で最も早く分岐したものになる。
カワセミ類は 3亜科 カワセミ亜科 Alcedininae: River Kingfishers (川のカワセミ類), ヤマセミ亜科 Cerylinae: Water Kingfishers (水辺のカワセミ類), アカショウビン亜科 Halcyoninae: Tree Kingfishers (木のカワセミ類) (系統分岐順) に分けられ、日本産の種では Halcyon 属と Todiramphus 属が Halcyoninae に含まれる。
Alcedo 属と Ceyx 属が Alcedininae に含まれる。
Halcyon 属は Swainson (1821) がセネガルショウビン 現在の学名で Halcyon senegalensis Woodland Kingfisher 記載時学名 Alcedo senegalensis Linnaeus, 1766) をタイプ種として設けたもの。
今はすっかり定着しているが実は結構微妙だったらしい。アカショウビンをタイプ種とした Entomothera 属 (entoma 昆虫 -theras を狩るもの Gk) を Horsfield (1822) が提唱しており時期的にはわずかの違いだった。
1915 年に Oberholser がアカショウビンの複数の亜種を記載したがこの時点では Entomothera 属が使われていた。
このように見ると Halcyon 属のタイプ種はアカショウビンから地理的に遠いもので、もし Halcyon 属が複数系統に分割されるならばアカショウビンの属の方が変わることになる。
Andersen et al. (2018) の系統解析、McCullough (2018) Systematics and Diversification of the Pantropical Avian Order Coraciiformes (学位論文) の系統樹を見る限りでは Halcyon 属を分割する必要はなさそうだがアカショウビンはこの中で古い系統なので1種だけ分けることも原理的には可能である。
分岐年代や他の特徴の類似性なども判断材料となるだろう。p. 18 の系統樹を見ると世界分布的にはやや微妙な位置だが (だからこそ日本でも繁殖するのか)、分岐は深くないのでこのまま取り扱われそうに見える。
アカショウビンの祖先系統に近そうなものはカザリショウビン Lacedo pulchella Banded Kingfisher。この程度違っていれば別属と判断される目安となるだろうか。
[その他]
アカショウビンの wikipedia 英語版 Ruddy kingfisher
には the ruddy kingfisher is rare in Japan, where it is highly sought after by birders
との記載がある。日本ではまれで、(超意訳すれば) バーダーに追い回されている、とある。あまり自慢できそうな話ではない。
ドイツ語では Feuerliest で「火のショウビン」の意味。Liest は辞書にも通常出てこない (カワセミは Eisvogel の単語がある) が Halcyoninae 亜科を指す名称とのこと (英語では tree kingfisher)。日本語ではショウビン亜科またはヤマショウビン亜科などと呼ばれるらしい。
植村 (2024) Birder 38(9): 70 にリュウキュウアカショウビンのフィリピンへの渡りの GPS 追跡の記事がある。
論文は Uemura et al. (2019) First tracking of post-breeding migration of the Ruddy Kingfisher Halcyon coromanda by GPS data logger。
-
アオショウビン (第8版で検討種)
- 学名:Halcyon smyrnensis (ハルキュオーン スミュルネーンシス) スムュルナのカワセミ
- 属名:halcyon (f) カワセミ (= alcyon、カワセミになったアルキオーネから)
- 種小名:smyrnensis (adj) 地名スムュルナの (-ensis (接尾辞) 〜に属する) Smyrna/Izmir トルコ西部の地名
- 英名:White-throated Kingfisher
- 備考:
halcyon は#アカショウビン参照。
smyrnensis は固有名詞の発音はよくわからないが場所を示す -ensis の冒頭が長母音でアクセントがある (スミュルネーンシス)。古代ギリシア語発音から前半には長母音は入らないと考えられる。
記載時学名 Alcedo smyrnensis Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Africa and Asia = Smyrna, ex Albin と記載は古い。
Smyrna は現在では Izmir (イズミル) と綴られることが多いが古代ギリシア語で Zmirna, Zmirne 現代ギリシア語で Zmirne。古代ギリシャ語では語末を伸ばしていた。スペイン語で Esmirna など過去の語形が残っている。
英名はかつて同種とされたことのあるチャムネショウビン Halcyon gularis ("のどに特徴のあるカワセミ" の意味) Brown-breasted Kingfisher の学名を引き継いでいるかあるいはこの英名に対応する形で分離されたものかも知れない。
ついでながらこの種は記載時学名で Alcedo Gularis Kuhl, 1820 (原記載) 基産地 Madagascar, ex PI. col., no. 232, error = Philippine Islands (マダガスカルとなっているがフィリピンの間違いとのこと)。
現在の分類ではフィリピンの固有種で #ホウロクシギのようにセレベス島の Makassar と間違えたなどの言い訳は通用しそうもなく、博物学者は遠くの地をマダガスカルだと誤解していた可能性がありそう。この Kuhl のリストにもホウロクシギに Courly de Madagascar の名称を用いている。誰かが間違えると (?) そのままコピーされるので間違いが広まっていったらしい。
もっともチャムネショウビンとアオショウビンが同種であれば、アオショウビンはインドネシアに分布するので同じ言い訳が通用しないわけではない。
と以上考察したが、Alcedo albiventris Scopoli, 1786 (参考) 基産地 Luzon で Martin Pecheur de l'Isle de Luzon (ルソン島のカワセミ) が非常にそれらしい名前になっている。
英語別名の White-breasted Kingfisher はこの学名を訳したと考えると納得できる。この学名は現在のチャガシラショウビン Halcyon albiventris Brown-hooded Kingfisher として使われている。
基産地は 'In nova Guiana' based on 'Martin Pecheur de l'Isle de Lucon' of Sonnerat, Voy. Nouv. Guinee, p. 64, pi. 31 = Cape of Good Hope (Avibase による) ともとはニューギニアと解釈されたが、なんと南アフリカの喜望峰に変更された。大丈夫か?? 現在の英名も学名と無関係で Brown-hooded Kingfisher となっている。
アオショウビンのロシア語名は独自路線で "嘴の赤いカワセミ" に相当するが、これもあまり特異的な名称でない。早い話がカワセミ類は種類が多くどこも苦労している次第。ポーランド語名は "そのう (胸) の赤いカワセミ" に相当するが、これは明らかにチャムネショウビンと同種時代の産物に見える。おそらく英名にも混同の歴史が残っているのだろう。
茂田 (2010) Birder 24(11): 24 によれば台湾でかつては "アオショウビン" に相当する名称だったものを英名に沿ったものに変更する改名 ("蒼" から "白胸" へ) が行われたとのこと。さまざまな種の英名由来を見ていると英名に合わせるのがよいことなのか疑問にも思えるが...。あるいは和名由来の通称名をよりふさわしいものに変更したのかも。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動 (文献に同定根拠が示されていない)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。世界で6亜種だが日本で記録されたとされるものは亜種不明とされる。
Andersen et al. (2018) の分子系統解析ではヤマショウビンの類縁種となり、Halcyon 属の中では後に現れたものになる。
-
ヤマショウビン
- 学名:Halcyon pileata (ハルキュオン ピーレアータ) 帽子をかぶったカワセミ
- 属名:halcyon (f) カワセミ (= alcyon、カワセミになったアルキオーネから)
- 種小名:pileata (adj) フェルトの帽子をかぶった (pileatus)
- 英名:Black-capped Kingfisher
- 備考:
halcyon は#アカショウビン参照。
pileata は i と最初の a が長母音 (ピーレアータ)。形容詞語尾に由来。
記載時学名 Alcedo pileata Boddaert, 1783 (原記載) 基産地 China, ex Daubenton, PI. enlum., no. 673 (Avibase による)。
フランス語名 Martin pecheur a Coiffe noire ("黒い帽子のカワセミ" Buffon の名称)。英名の Black kapped Kingfisher (Latham) もすでに挙げられていた。
英名が "ヤマショウビン" を意味する種が別にある。ヤマキバシショウビン Syma megarhyncha Mountain Kingfisher。和名にも "ヤマ" が入っているが、和名は過去の英名 Mountain Yellow-billed Kingfisher を訳したものと考えられる。英名の方が簡略化されたため現在の英名とヤマショウビンの意味が一致してしまった。
この一致は英名だけでなく世界のいくつもの言語で同様で、中国語名でも (おそらく英名由来で) 山翡翠となっている。
Birder 編集部 (1998) Birder 12(7): 27-31 によれば江戸時代にもヤマセミの名称はあったがヤマショウビンやアカショウビンを指して使われていたとのこと (p. 29)。「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) の同定とは多少異なる点があるがヤマセミの名称がヤマショウビンに使われていた点は一致する。
もとは "ヤマセミ" の名称だったものを分類に合わせて整理して "セミ" 系統と "ショウビン" 系統に分けたと考えるとわかりやすい。
アカショウビンとヤマショウビンをアカショウビンと "アオショウビン" の組み合わせで呼んでもおかしくなかった気がするが、ヤマセミと呼ばれていた歴史的経緯によるものらしい。
単形種。
矢根 (2008) Birder 22(1): 58 に 2007 年の福井県越前でのヤマショウビンの繁殖観察記が紹介されている。
-
ナンヨウショウビン
- 学名:Todiramphus chloris (トディラムプス クローリス) 緑色の嘴の小鳥
- 属名:todiramphus Todus 属と ramphos 嘴 (Gk) の合成。todus は Plautus と Festus が言及した小さな鳥で種類は不明。todus は鳥類学で平らで上に反った嘴の鳥のグループに用いられる。
- 種小名:chloris (合) 緑色の (chloros 緑色 Gk)
- 英名:Collared Kingfisher
- 備考:
todiramphus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となる todus, ギリシャ語の rhamphos ともに短母音のみで長母音は現れないと考えられる。-ram- がアクセント音節 (トディラムプス)。
chloris は o が長母音でアクセントもある (クローリス)。
紅海沿岸からポリネシアに至る 14 の亜種がある (IOC)。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に記載の亜種はフィリピンと周辺の collaris (首輪のある) とされている。フィリピンでは広く記録される留鳥。迷鳥として記録された。
英名はこの亜種由来と想像できる。記載時学名 Alcedo collaris Scopoli, 1786 (参考) 基産地 No locality = Philippine Islands, ex Sonnerat, Voy Nouv. Guinee, p. 67, pi. 33; restricted to Manila, Island of Luzon, by Oberholser, antea, p. 361 (Avibase による)。
分類がまとめられた結果 Alcedo Chloris Boddaert, 1783 (原記載) の記載が早いためこの亜種となった模様。
かつての Todiramphus chloris は6種に分離されたが、collaris は Todiramphus chloris に帰属するとされ日本産の種学名は変わらなかった。
[Todiramphus 属の種多様性とカワセミ類の起源]
Todiramphus 属は種多様性が高く、"great speciators" の一つとされる (Diamond et al. 1976)。メジロ類も同様に種多様性が高く遺伝子機構も明らかになりつつある。これらが代表的な "great speciators"。#メジロの備考参照。
ナンヨウショウビン (紅海からサモアまで 16000 km の範囲に 50 亜種が認められていた。現在は6種に分割されている。種分化速度が最も速いグループの一つとされる) が主要な種で、
Andersen et al. (2015) Rapid diversification and secondary sympatry in Australo-Pacific kingfishers (Aves: Alcedinidae: Todiramphus)
に分子系統解析がある。渡りを行うヒジリショウビン Todiramphus sanctus Sacred Kingfisher を内包しており、未調査の亜種もあるなどまだ十分調べられておらず世界のリストには反映されていない模様。
カワセミ類全種掲載とは簡単に行かないのもこのあたりの事情がある。
Andersen et al. (2018) A phylogeny of kingfishers reveals an Indomalayan origin and elevated rates of diversification on oceanic islands
(ResearchGate) は分子系統研究でカワセミ類の起源がインドマレー地域と判定し、Ceyx、Todiramphus、Actenoides の各属は島で急速な種分化を遂げたとしている。
これら研究者にとってもミヤコショウビンの位置づけも気になるところかも知れないが (サンプル採取も難しいのであまり気にしていないかも?)、ミヤコショウビンは種に値するかどうかを気にしている我々があまり知らないところでこのグループは種分化機構研究の絶好の最新テーマとなっているらしい。
Eliason et al. (2022) Genomic novelty within a "great speciator" revealed by a high-quality reference genome of the collared kingfisher (Todiramphus chloris collaris)
に の高精度のゲノム解析があり ErbB 受容体ファミリーが急速な種分化を可能にしている可能性があるとのこと。
Eliason et al. (2023) Complex plumages spur rapid color diversification in kingfishers (Aves: Alcedinidae)
によれば色彩が複雑なほど種分化速度も速い結果が得られている。
McCullough et al. (2024) Phylogenomics of a genus of 'Great Speciators' reveals rampant incomplete lineage sorting, gene flow, and mitochondrial capture in island systems (preprint)
による Todiramphus 属の最新の成果がある。標本の劣化を補うため全ゲノムの高精度の再解析を行うと遺伝子浸透やミトコンドリア獲得 (現在は失われた交雑帯の存在を示唆する) など状況がさらに複雑であることがわかった。incomplete lineage sorting は用いる遺伝情報によって異なる結果が得られる原因となる。
日本の種とは関係が薄いがカワセミ類に関心の深い方には興味深い結果であろう。
現在使われている種境界はそれほど変える必要はないが一部亜種の移動や新亜種の記載なども行われている。今後の種分化研究はこのレベルのものが標準となって行くだろうことを予感させる。
Ceyx 属についての "great speciators" の側面から分子系統研究がある:
DeRead et al. (2024)
Genomic patterns in the dwarf kingfishers of northern Melanesia reveal a mechanistic framework explaining the paradox of the great speciators
個々の島の種の間での遺伝的交流は認められなかった。390-290 万年前にメラネシア北部に到達して個々の種に定着したが、個体数が少ないことによる founder effect (創始者効果) が何度も起きて、島の個々の環境に適応した種分化を遂げたと読んでよいのではと思う。
定着した初期は分散能力が高かったが、後の段階で島の間で渡りをする行動がコストを要する (適応度を下げる) ならば great speciator になるのではないかと考えている。
日本で記録のある#ミツユビカワセミはこの研究には含まれていない。
-
ミヤコショウビン
- 第8版学名:Todiramphus miyakoensis (トディラムプス ミヤコエーンシス) 宮古島のカワセミ
- IOC 学名:なし
- 属名:todiramphus Todus 属と ramphos 嘴 (Gk) の合成。todus は Plautus と Festus が言及した小さな鳥で種類は不明。todus は鳥類学で平らで上に反った嘴の鳥のグループに用いられる。
- 種小名:miyakoensis (adj) 宮古島の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:(Ryukyu Kingfisher、IOC では種・亜種扱いでない)
- 備考:
todiramphus は#ナンヨウショウビン参照。
miyakoensis は場所の -ensis の冒頭が長母音でアクセントもある (ミヤコエーンシス)。
よく知られている通り 1887 年に標本が一体採集されたのみであり、それ以降一度も発見されていない。生態や習性についても、全く不明である。32 年後の 1919 年にその標本を基に新種として記載された (黒田長礼による)。しかしその時も、そしてそれ以降もミヤコショウビンは発見されていない。
最後に確認されてから 50 年間報告されなければ絶滅とみなす慣習に従えば、最初の標本が採集されて半世紀後、1937 年に絶滅が確認されたことになる。
ただし、そもそも独立種として存在していなかったという説もある。模式標本のラベルの採集年は不明、原産地も不確かであり、ズアカショウビンのグアム島に生息する亜種とミヤコショウビンの形態的な違いはごくわずかとされ、その相違については変異個体ではないかとの指摘がある (以上 wikipedia 日本語版より)。
「鳥学の100年」(井田徹治著、日本鳥学会、山階鳥類研究所協力 2012) pp. 111-114 でミヤコショウビンが取り上げられているが、アメリカの研究者との共同研究では脱落した羽毛からは DNA 抽出はできなかったと記述されている。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) は種として記載しているが英名は Miyako Island Kingfisher となっている。
ズアカショウビンのグアム島亜種は現在独立種とされ、Todiramphus cinnamominus (英名 Guam Kingfisher, Howard and Moore では Micronesian Kingfisher) とされる (和名は亜種とされていた時代のものがそのまま使われるならばアカハラショウビンとなるだろう)。
ミヤコショウビンを Todiramphus cinnamominus の亜種として Todiramphus cinnamominus miyakoensis とすることが提案されたことがあったが [Fry et al. (1992) "Kingfishers, Bee-eaters, and Rollers"]、IOCは 2022 年にこの提案を却下したとのことである (Guam kingfisher の wikipedia 英語版より)。
この学名は wikipedia 英語版で絶滅種として使われており、リストによっては Todiramphus cinnamominus の和名を検索するとミヤコショウビンと出てきて驚かされることがある。
IOC では 3.1-11.2 まで独立種となる前の Todiramphus cinnamominus の亜種としていた。Clements や eBird も 2021 年までは同様の扱いとしていた。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 は Todiramphus cinnamominus の亜種として扱われているので、あるいは WGAC リストが公開されるとアカハラショウビン (?) の亜種として復活するのかも知れないが、まだ作業中で検討前かも知れない。
グアム島のこの種は外来ヘビのミナミオオガシラ (brown tree snakes, #オウチュウの備考も参照) による捕食の影響で 1988 年に目撃されたものが最後で、最後の個体群 29 羽が捕獲され、野生では絶滅したと考えられる。現在 140 羽の飼育個体があり、移入種のヘビのいない島に 2023 年に4羽放鳥された。
将来ヘビの問題が解決されればグアムヘ復帰を考えている (Guardian 紙の記事)。
[グアム外来ヘビの駆除とヘビ類の特異な薬物感受性]
さまざまな方法でこのヘビの駆除が進められており、このヘビが特に敏感なアセトアミノフェンを加えたネズミを用いたわななどが用いられている。
他の動物に有害ではないのか気になるところだが、
Johnston et al. (2002) Risk Assessment of an Acetaminophen Baiting Program for Chemical Control of Brown Tree Snakes on Guam: Evaluation of Baits, Snake Residues, and Potential Primary and Secondary Hazards
のような評価がある。この時点でネコやネズミは比較的感受性があることがわかった (これらは外来種で影響があった方がむしろ有効)。ウオガラス Corvus ossifragus Fish Crow は餌に混ぜて薬物を与えようとすると多くは拒否したが強制的に食べさせたりする実験が行われた。希少固有種のクバリーガラスが二次的に食べる可能性は考えられるがリスクは小さいと判断された。
van den Hurk and Kerkkamp (2018) Phylogenetic origins for severe acetaminophen toxicity in snake species compared to other vertebrate taxa
によればヘビは薬物代謝酵素 glucuronosyltransferase isoforms の遺伝子を2つしか持たず、系統特異的な現象とわかった。ネコも点突然変異で phenol-type glucuronosyltransferase isoform が偽遺伝子化してアセトアミノフェンに高い感受性を示すが、ヘビと哺乳類は別の系統特異性によるものとのこと。
鳥類も気になるところだが Kawai et al. (2019) Characterization of function and genetic feature of UDP-glucuronosyltransferase in avian species
でいくつかの種で調べられていて種子食の鳥では薬物代謝活性が高い (有毒物質に出会う頻度が高い) が、肉食のものは偽遺伝子化で遺伝子数が減り薬物に対する活性も下がる傾向がある。
#クロハゲワシ備考の [ハゲワシ類の集団死とジクロフェナク] の項目で紹介の近年同定された Gyps 属特有の変異、#ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] なども合わせてどのような選択圧が働いているか考えると興味深い。
[ニュージーランドの外来ネズミ類駆除]
系統特異的な薬剤による外来種駆除に関連し、ナショナル・ジオグラフィック日本語版 2025年1月号でニュージーランドの外来ネズミ類駆除に特異的薬剤が発売され期待されていることを知った。
Norbormide (ノルボルマイド / ノルボルミド。商品名 Raticate, Shoxin) の薬剤で、wikipedia 英語版の情報によれば 1960 年代にはすでに知られていたが、他の抗凝固薬の殺鼠剤 (これは特異性が低く猛禽類にも影響を与えている) がより有効と考えられてあまり注目されていなかったとのこと。
Rattus 属に特異的に働く血管収縮や Ca チャンネル阻害薬で他の属の齧歯類や他の哺乳類や鳥類にはあまり影響がないとのこと。
World first: revival of the rat-specific toxin (predatorfreenz.org のページ。2024.10.22)。
もともとは抗リウマチ薬の探索中に偶然発見され、効果はなかったが食欲抑制薬への応用が考えられていた。イエネズミやネコには影響はなかったが Rattus 属に特異的に作用することがわかった。しかし当時の方法ではラットはすぐに学習して避けるようになりうまく行かなかった (他の殺鼠剤の方が合成が簡単で安価だったためあまり追求されていなかったのかも)。
毒性のない餌で慣れさせてから毒餌に切り替える方法で有効に使えるようになったとのこと。
Shapiro et al. (2018) Redevelopment of a Rat Specific Rodenticide Norbormide
にニュージーランドでの研究が紹介されており、Rattus 属への特異的作用があまりにも顕著だったため開発当時は最初は間違いと疑われたとのこと。アメリカで最初に商品化されたが味に対する拒否反応などで効果に限界があり、また抗凝固薬の殺鼠剤が普及して忘れ去られた。
ネズミ類に抗凝固薬の殺鼠剤への耐性なども生じるようになり、また野生動物の残留抗凝固薬も問題となって残留性の低い殺鼠剤の研究が進んだ形で再登場したのが Norbormide とのこと。
鳥やコンパニオン動物に毒性がない点は都会環境でのネズミ類のコントロールには非常に適した性質で (無人島以外にも適用可能となった)、また対象動物以外への慢性毒性もないとのこと。
Rattus 属以外の齧歯類にも多少の薬理効果があるようだがそれ以外は調べられた範囲で鳥も大丈夫でなかなか不思議。
哺乳類・鳥類以外は調べなくてもよいのか、と言われそうだが少なくともこの時点ではあまり気にされていないよう。
これまでは味に対する反応を遅らせるためにカプセルに入れたり味を感じさせない化学形などが研究された (分解されてから効果を発揮するプロドラッグなど) が、このニュージーランドのチームは共通点はあるが違うアプローチで効果の高い手法なども明らかにしたとのこと (おそらく特許の関係もあってアイデアは示されていない)、登録されて5年以内に野外で使用可能になるだろうとの時期の報告。
ニュージーランドで在来種保護のための外来ネズミ類駆除にいろいろな手法が調べられ、研究が進んで実用化に至った模様。ナショナル・ジオグラフィック日本語版の記事を見ても並々ならぬ意欲が感じられる。
Fusi et al. (2024) The Enigma of Norbormide, a Rattus-Selective Toxicant
ラットのミトコンドリアの permeability transition pore [膜透過性遷移孔の訳語があるらしいがこのぐらいの専門用語となるとわざわざ訳さず使うだろうか。機構についての日本語情報: 石田 (2004) 細胞死におけるミトコンドリア Permeability Transition Pore (PTP) の役割に関する研究法]
を選択的に開くなど作用メカニズムはある程度までわかっているが、いかにしてラットを死に至らせるかは不明な点が多い。
殺鼠剤には種類が多いので参考までに種類をまとめておく。有名なものを中心に主に wikipedia 英語版を参照し、抗凝固薬の鳥類への影響の論文をいくつか取り上げた。
・抗凝固薬 (anticoagulants): ビタミン K サイクルを阻害。第一世代、第二世代 (second-generation anticoagulant rodenticides, SGARs) がある。第二世代は効果が高く1回の投与で有効で耐性が生じにくいとのこと。
猛禽類への影響は例えば Gomez et al. (2022) Conservation Letter: Raptors and Anticoagulant Rodenticides。
救護個体の死亡前の症状は十分予想できる話で、死なないレベルの用量でも問題となる。ろう膜からの出血もあるそうで、ろう膜も血流が豊富で色彩シグナル以外にも生理的役割を果たしているらしいことも推測できる。
SGARs の北米猛禽類における危険性評価は Elliot et al. (2024) Anticoagulant Rodenticide Toxicity in Terrestrial Raptors: Tools to Estimate the Impact on Populations in North America and Globally。
Nakayama et al. (2019) A review: poisoning by anticoagulant rodenticides in non-target animals globally。
・リン化金属 (metal phosphides) リン化亜鉛など。摂取すると胃の酸性環境で有毒なホスフィン (PH3 / H3P) を発生する。毒餌は加水分解で魚の腐ったような特有の臭気があり、これが齧歯類を誘引するが他の動物を遠ざけるという。しかしシチメンチョウなどの鳥類はこの臭気をあまり感じず毒の犠牲になることがあるとのこと。
本当か? と調べてみると Poppenga et al. (2005) Zinc phosphide intoxication of wild turkeys (Meleagris gallopavo)
によれば鳥類もやはり基本的にリン化亜鉛の入った食物を避けるが冬場に他の食物がない場合にシチメンチョウの事故死が報告されているとの 1986 年の研究が紹介されている。この薬物も齧歯類が嘔吐しないために多少の選択性があるが他の動物にも毒性を示す。今では殺鼠剤用途では抗凝固薬にほぼ置き換わっているがそれでも容易に手に入るとのこと。作用メカニズムはあまりわかっていない。
MacDonald et al. (2016) Mortality and Disease in Wild Turkeys (Meleagris gallopavo silvestris) in Ontario, Canada, from 1992 to 2014: A Retrospective Review カナダの野生のシチメンチョウでの事例研究。
Bildfell et al. (2013) A review of episodes of zinc phosphide toxicosis in wild geese (Branta spp.) in Oregon (2004-2011) カナダのコクガン属ガン類での研究。ガン類は感受性が高い。2009 年に規制が強化されて事故が大幅に減っている。
Sciuto et al. (2016) Phosphine toxicity: a story of disrupted mitochondrial metabolism こちらはヒトの医学で活性酸素を発生し、いくつかのポイントに作用してミトコンドリア毒で細胞死を招くのではとのメカニズム推定。特異的な解毒方法はまだ知られていないとのこと。
・ビタミン D: 高用量で高カルシウム血症 (hypercalcemia) を起こす。抗凝固薬と共働効果があり併用されるとのこと。
・α-Naphthylthiourea (α-ナフチルチオ尿素。ANTC) かなり種特異性が高いとのこと。
・モノフルオロ酢酸類 (fluoroacetate, fluoroacetamide): #ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] (6) オーストラリアのハト類のモノフルオロ酢酸耐性 参照。
・白リン (黄リン): (商品名「猫いらず」)
・タリウム塩 (硫酸タリウム): 特性や毒性はご存じの通り
さらに参考までにムクドリ・カラス駆除薬剤があり、特異性が高くて猛禽類には影響がないと考えられていたが、ミヤマガラスを駆除した結果ニシアカアシチョウゲンボウの繁殖場所が奪われる思わぬ副作用がハンガリーで生じた事例があった。#アカアシチョウゲンボウの備考 [ニシアカアシチョウゲンボウの営巣習性と現在の問題点] 参照。
-
カワセミ
- 学名:Alcedo atthis (アルケードー アッティス) アッティスのカワセミ
- 属名:alcedo (f) カワセミ (= alcyon、カワセミになったアルキオーネから)
- 種小名:atthis (adj) Atthis ギリシャ神話でハンサムで豪華な衣装を着たインドの若者。鳥に変えられた
- 英名:Common Kingfisher
- 備考:
alcedo は e と o が長母音で前者にアクセントがある (アルケードー)。
atthis は規則上アクセントは冒頭。起源となるギリシャ語でも長音はないのでいずれの音も伸ばさないと考えられる (アッティス)。
ユーラシア中・低緯度からパプアニューギニアに広く分布する。7亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は bengalensis (ベンガル地方の) とされる。ベンガル地方よりもむしろ東洋に広く分布する亜種。
かつて亜種 japonica があったが bengalensis のシノニムとなった。Peters' Check-list of the Birds 2nd edition まで、Howard and Moore 2nd edition がこの亜種を採用していた。
[カワセミの種学名の成立]
種の記載時学名 Gracula Atthis Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Egypt (エジプト) と怪しげな記載。Linnaeus はカワセミをあまり知らなかったらしい。
Gracula 属はキュウカンチョウ、現在の学名で Gracula religiosa がタイプ種と認定され、Linnaeus (1758) の時点では7種からなっていた。
いくらなんでもカワセミとキュウカンチョウが同属とは!
Alcedo 属は Linnaeus (1758) が7種を指して用いており、Alcedo ispida が後にタイプ種と指定されたとのこと。
Alcedo Ispida Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe and Asia = Sweden (スウェーデンに限定)。とのことでこちらが我々に馴染みのカワセミとなる。
Linnaeus (1758) はヨーロッパ・アジアとエジプトのカワセミを別種と考え、なんと違う属に置いていた。
しかし Gracula Atthis Linnaeus, 1758 の記載も簡潔で、それほどヒントが多いわけではないのにどのようにしてカワセミと判定されたか少し謎も残る感じがする。Linnaeus (1766) でもそのまま登場していた (参考)。
この時代は Alcedo Ispida が明らかに本家とされてインドのものもこちらにまとめられていた。
ispida は現在は通常はカワセミの亜種とされるが、我々の視点からはむしろこちらが本家だった。同種となる場合には Gracula Atthis の方が先に記述されているために、現代の考え方では ispida はこの亜種となる。さらにややこしいことに Alcedo Alcyon Linnaeus, 1758 はアメリカの種と見慣れた名称が散在している。
hispida はラテン語でカワセミの意味とのこと (The Key to Scientific Names より情報とりまとめ)。
これを見るとカワセミの学名が Alcedo atthis となったのはかなり偶然の要素があって、ispida を用いた学名になっても不思議でなかった状況、というよりむしろこちらが本家で、エジプトのカワセミを別途 (カワセミ類とすら思わず) 記述してあったために Linnaeus にとってはむしろ馴染みのなかった atthis に先取権が生じた模様。カワセミの学名を考える際に atthis の意味を追求する意味はあまりなさそう。おそらく有り難く意味を覚えるほどのことはない。
Ispida 属も Alcedo Ispida Linnaeus, 1758 をもとに Brisson (1760) が設けた。ドイツ語名 Eisvogel (以下参照) も紹介されており、おそらくこちらの方が馴染みがある名称だったのだろう。Alcedo 属は Linnaeus (1758) がすでに用いていて同種であれば Ispida 属は属名シノニムとなる。
wiktionary を調べておくと hispidus はぼさぼさの、毛が逆だったなどの意味とのこと。ここには名詞の hispida のカワセミの意味は出ていない。
Atthis も固有名詞でギリシャ語語源的には Attica (アテネの後背地) で、古代アテネとほぼ同じような意味 (英語 Attic) とのこと。Atthis 属も別に存在してハチドリ類の属 (分子系統解析の結果、現在では Selasphorus 属にまとめられた)。鮮やかな色を反映したものとも想像できるがカワセミ特有の意味ではなさそう。
japonica の記載時学名は Alcedo japonica Bonaparte, 1854。
bengalensis は Alcedo bengalensis Gmelin, 1788 (原記載)。Little Indian Kingfisher, Indian Kingfisher, Martin-pecheur de Bengale (フランス語名) などの名称が現れている。
Brisson の記述名 Ispida bengalensis (minor) は "(小型の) ベンガルのカワセミ" の意味で Brisson は小型版もある認識だった。Gmelin (1788) が学名を整理した結果のよう。1-2 ページ戻るとベンガルには他にもカワセミ類がいて、ミツユビカワセミも Bengal Kingfisher と呼ばれていたとのこと。
[他国語のカワセミの名称]
カワセミのドイツ語名は Eisvogel で文字通り読めば「氷の鳥」となる。語源はおそらく氷そのものではなく、上面の青緑を指したものと考えられるとのこと (Wiktionary)。
チェコ語でも lednacek と明らかに led = 氷 を意味しており、おそらく氷に住むものの意味だろう。
北欧言語の多くでも同様。
面白いことにロシア語名は zimorodok で、冬に生まれるもの (zima 冬、#ケアシノスリの備考参照) の意味。
Kolyada et al. (2016) のロシア極東動物の語源辞典によれば、すでに大プリニウス (Pliny the Elder) (1世紀) の時代にギリシャではカワセミが冬か夏至のころにしか現れないことが記されていた。アドリア海の住民は冬至のころに最初の寒波が訪れて海が静かになる時にカワセミが営巣してひなを育てると考えていたとのこと。
ポーランド語も同様だが、ウクライナ語は魚を採る方に注目した名称 ribalochka となっていてスロバキア語でも同様。フランス語 (martin-pecheur) やスペイン語、イタリア語でも同様で色に注目した名前は意外に少ない (中国語など)。
英語の kingfisher は合成語としての意味は自明だが、由来はそれほどはっきりしない。kingfisher (OED) によれば 1440 年に Kyngys fyschare、1567 年に Kings Fisher の用例がある。Kings Fisher (Kings-Fisher, king's fisher) の形がしばしば現れていた。
1586 年に king fishers、1658 年に King-fisher の用例があり、この時点で Halcyon の意味の解説として現れた。
halcyon (OED) の方が用例が古いが、ここで 1585 年に a winter birde commonly called the kings fisher とあり、halcyon は通常 kings fisher と呼ばれる冬鳥のことと説明がある。
fisher, fisherman の用例は 1520 年ごろとのこと (Online Etymology Dictionary)。
"king" そのものもよくわかっていないとのことで、古英語の cynn (家族、氏族。現代の英語で kin に対応する) 可能性があるとのことで、king はそれを率いるものではないかとの解釈があるが語源については議論があるよう (Online Etymology Dictionary)。
とのことで、kingfisher の king は王の意味かどうかは不明。
古ノルド語の Kungsfiskare (現在のスウェーデン語でも同じ) から入ったとも解釈される。現在のスウェーデン語では king + fisher にあたるがなぜそのような名称になったかは同様によくわからない。
ヘンリー2世 (イングランド王) (1133-1189)、リチャード1世 (イングランド王) (1157-1199) の墓では青色と赤/オレンジ色の衣装をまとっており、カワセミ色の配色となっている。関係がある可能性が指摘されている [Richter The Kingfisher - The Etymology of Kingfisher (Alcedo Atthis)]。
古い英語でのカワセミの名称は不明だが、「王侯色」の方が先だったのかも。
「青の歴史」(ミシェル・パストゥロー著) (#カタグロトビの備考参照) によれば、ローマにおいては青い服は通常信用を落とす突飛な行為か喪のしるしだった。しばしば死と地獄に結び付けられていたとのこと。ケルト人やゲルマン人が敵を怖がらせるために青く染め、ローマ人にとっては無関心あるいは敵意のある色だったとのこと。用心し回避すべき色とプリニウスが結論しているとのこと。
ギリシャ人、ローマ人の記した虹にも青は現れないとのこと。
12 世紀の数十年の間に青の地位が急に向上し聖母マリアの衣服の図としても現れるようになった。上記 12 世紀後半の王の墓で用いられた青もちょうどこの時期に当たっている。古くから知られていたはずのカワセミに青に関連した名前が付かなかったのも当時まで青が嫌われる色だったためかも知れない。
ドイツ語の Eisvogel もラテン語 caeruleus が cera (蝋) から派生したように曖昧な青系の色の表現の一つだったのかも。ゲルマン人も青を肯定的な意味では捉えていなかったと想像できるので直接の "青" の表現は使わなかったのかも。
英語圏でもなぜ "king" "fisher" なのかやはり問題となった: Death to Tyrants (Sic semper tyrannis) - Some Thoughts on Flycatchers (BirdForum 2025.2) やはりカワセミ類の英名と実体の関係が自明でないと感じる人もある模様
(とんでもなくすごいスレッドのタイトルだともある。"暴君に死を" で、ここでは tyrant flycatchers の通称名が適切でないと議論されている中に現れたもの)。
[カワセミの色は保護色か?]
#ヤマセミ備考の [派手な色彩の鳥はまずい?] にまとめた。
[カワセミの構造色]
Stavenga et al. (2011) Kingfisher feathers - colouration by pigments, spongy nanostructures and thin films に解析結果がある。色素顆粒を持つもの (オレンジ色部分) とスポンジ様ケラチン (青色部分) の2種類の羽枝の構造が色を作り出している。羽枝の皮質が薄膜の役割を果たして光沢を与えているとのこと。
[カワセミの視力]
カワセミ類は捕食性の鳥であり視力が良いと考えられるが、猛禽類と比べてどの程度のものか、視覚特性の研究については#ハチクイの備考参照。
ただしこの文献ではカワセミそのものは調べられておらず、Kolmer (1924) Ueber das Auge des Eisvogels (Alcedo attis attis)
によれば空中では強い近視で水中に入ると正視になるという [#ハチクマ備考で紹介の Gutierrez-Ibanez et al. (2012) Functional Implications of Species Differences in the Size and Morphology of the Isthmo Optic Nucleus (ION) in Birds の情報で知った]。
カワセミは空中では思ったより見えていないのかも知れない。以下の飛び込むカワセミ類のゲノム解析の結果もこれを間接的に支持するかも知れない。おそらく飛び込まず地上採食型のカワセミ類の方が視力がよいのだろう。
[飛び込むカワセミ類の収斂進化]
カワセミ類に飛び込んで食物をとるもの (カワセミ、ヤマセミなど)、そうでないもの (アカショウビンなど) があるが、系統関係と進化速度を調べた論文:
Eliason et al. (2023) Genomic signatures of convergent shifts to plunge-diving behavior in birds
カワセミ類で飛び込んで食物をとる系統が4回独立に進化したことがわかっている。Alcedo (カワセミ) 属や Megaceryle 属は系統の早い時期に飛び込む採食方法を獲得したが、アカショウビン亜科 Halcyoninae には生じなかった。
30 種の全ゲノム解析による研究で、飛び込んで食物をとる系統では視力を弱める網膜の遺伝子変異 (BBS10, ATRIP)、脳を小さくする遺伝子変異 (CENPJ)、脳のタウタンパク質をコードする遺伝子 (MAPT) に収斂した選択が働いていることが見られた。MAPT についてはキツツキ類と同様で脳への衝撃の影響を和らげる働きが提唱されている。
Cavitaves の系統で脳が小さい (#ハチクマ備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] で紹介の Griesser et al. (2023) Parental provisioning drives brain size in birds の研究も参照)
ものが多いのは脳に衝撃を受ける採食系統が多いためか、あるいは系統的特徴が前適応のように働いているのかも。カワセミ科とキツツキ科が系統的にまとまっているのは偶然でなかったのかも (ここは注釈コメント)。
また魚食に適応するためと考えられる酵素にも共通の変化があった。これらの遺伝子への選択は小型で島に住む種類で特に強く、これらの種類が染色体が多い (染色体再編成が頻繁に起きた?) こととも関連がありそうで興味深いとのこと。これらの候補遺伝子が想定された働きをしているかどうかは今後の研究が必要とのこと。
やはり飛び込むカワセミ類も脳に衝撃を受けている間接的証拠となるよう。食物を得るためとはいえ頭から飛び込むのはなかなかハードルが高そう。
同じ研究者によるカワセミ類や他の系統での飛び込みへの形態的適応の研究: Eliason et al. (2020) Morphological innovation and biomechanical diversity in plunge-diving birds。
また Crandell et al. (2019) Repeated evolution of drag reduction at the air-water interface in diving kingfishers によればカワセミ類で突入時の抵抗を減らす形態的適応進化が複数回起きた。系統樹の配置が普通に使われるものと多少違うので少し注意。
突入時の流体力学的シミュレーションも行われているので #カツオドリ 備考 [カツオドリ類の飛び込み時にかかる力] の定性的な解析方法と比べても興味あるだろう。
[カワセミの嘴先端の形・鳥の寄生虫対策]
多くの鳥で嘴の先端に小さな曲がり (mandibular overhang) があり、これは羽繕いの際の外部寄生虫辞去に非常に有効であることがビデオ記録などから確かめられている。Bush and Clayton (2018) Anti-parasite behaviour of birds 参考。
ハトでこの曲がりを除去する実験を行っても採食には影響がなかったとのこと。外部寄生虫がこの形質を維持している可能性があるとのこと。カワセミやミヤコドリの嘴先端にはこの構造がなく、採食の機能を阻害するためと考えられているとのこと。嘴先端に mandibular overhang のない鳥を他にも思い浮かべたり行動を調べてみると興味深い考察が可能なのでは。川口 (2021) Birder 35(12): 54-55 で嘴縁突起に関係して取り上げられている (overhang のある鳥としてシロハラが取り上げられていた)。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 70 p. 2 によればフウキンチョウ科 Thraupidae: Tanagers ではしばしば上くちばしにのこぎりの歯のような刻みがみられ、この科の特徴となっているとのこと。こちらは単なる overhang ではなく嘴縁突起 (刻歯) と呼んでよさそう。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 103 p. 1 によれば回数が多いことを「シギの羽掻」(鴫の羽根掻き) と呼ぶとのこと。シギは羽虫をとるため何度も羽をしごくから、とのこと。俳句を詠む人にしか知られていないかも知れない。シギ類の嘴は採食の機能を優先させるため overhang が発達しておらず、外部寄生虫除去の効率が悪いのではと考えてみた。
猛禽類の曲がった嘴の機能は寄生虫辞去とはほとんど関係ないと考えられ、メンフクロウでは突起が長いのにハジラミが多かった解釈に反する報告があるとのこと。
この論文では鳥の外部寄生虫対策のいくつかの方法がレビューされており、項目だけ挙げておくと相互羽繕い (異種も含む)、頭かき、水浴び、砂浴び、日光浴、他種に掃除させる (鳥ではほとんど知られていない)、アリ浴び (蟻浴 ぎよく anting)、煙浴、ヒゲワシなどの化粧の機能、巣の対策 (なわばりを作る、コロニーのサイズ、新鮮な葉を運ぶなど)、寄生された食物を避ける、渡り途中は外部寄生虫とっては厳しい環境でなので減らす効果が期待できる。
文献も多数引かれているが実験的結論があまりすっきりしないものも多いらしい。巣に葉を持ち込む鳥では揮発性物質を多く含む新鮮な葉を選んでいるらしく、これは一定の効果があるらしい。
主にスズメ目で調べられているが、イヌワシに近い系統のボネリークマタカでは繁殖成功率を高める研究が知られている [Ontiveros et al. (2008) Green plant material versus ectoparasites in nests of Bonelli's eagle]。
アリ浴びは大部分はスズメ目で 200 種以上の鳥で観察されているが、ギ酸がどれだけ効果があるか実際にはほとんど確かめられていないらしい。実際のギ酸濃度では抗菌・抗カビ効果がないとの研究もある。
北米のアオカケス Cyanocitta cristata Blue Jay ではアリを食物とするために食べられるようになるまでギ酸を抜くため、との説がある Eisner and Aneshansley (2009) "Anting" in Blue Jays。Eisner のお気に入りのアイデアとのことで関連文献や記述もある。
「野の鳥の四季」(高野伸二 小学館 1974) p. 21 には蟻浴はスズメ目の鳥のみに知られていると記述されていて当時の知見だったのだろうか。
鳥とアリの関係については Aviles (2024) The evolutionary ecology of bird-ant interactions: a pervasive but under-studied connection に系統樹入りの新しい研究があるので参考までに。Eisner の説はあまり受け入れられていないようで登場しない。
この論文の Appendix S2 (rspb20232023_si_002.xlsx) をダウンロードすればこの論文で集められた事例が載っている。例によって気になるところだけ、タカ科でアリと関係があるのは何だろうと見てみるとアリの捕食や群れを追いかけた事例はそこそこある。
アリに捕食された方の事例ではトビのひながあった。ムネアカハイタカ [高野 (1973) ではアカムネハイタカ] Accipiter rufiventris Rufous-breasted Sparrowhawk の胃にアリが見つかっており、なんと Accipiter 属でもアリを食べるらしい。
#ハチクマの [ハチクマ類の道具使用] で Camacho and Potti (2018) Non-foraging tool use in European Honey-buzzards: An experimental test にヨーロッパハチクマでアリ浴びのための道具使用ではないかとの解釈が出ているが、さすがに直接観察ではないので含まれていない模様。タカ科のアリ浴びの報告はこの表を見る限りないらしい。
ヨーロッパハチクマの胃からアリが見つかっていて食べることはあまり不思議でない。
ヒゲワシの化粧では現状では細菌による羽毛劣化を抑制する機能が見つかっていない [Margalida et al. (2019) Cosmetic colouring by Bearded Vultures Gypaetus barbatus: still no evidence for an antibacterial function]。
研究者も悩んでいるようで、社会的序列を高めるためではなど考察されている: Margalida et al. (2023) New Insights into the Cosmetic Behaviour of Bearded Vultures: Ferruginous Springs Are Shared Sequentially。続きは #クロハゲワシ備考の [ヒゲワシの化粧色] へ。
Bush and Clayton (2018) では櫛状の爪 (#ヨシゴイの備考参照) にも触れられているが外部寄生虫対策に効果があるかよくわかっていないらしい。
[カワセミの巣の悪臭]
ネットの報告を調べるとカワセミの巣は腐った魚の臭いがするとのこと。
カワセミで悪臭が捕食者防御に役に立っているのかと探してみると、Cech and Cech (2022) The role of mammals as Common Kingfisher (Alcedo atthis) nest predators のチェコの研究では哺乳類が頻繁に巣の近くを訪れる割には直接の捕食は記録されなかったとのこと。
この事例では吐き出した魚や排泄物からの悪臭は哺乳類にとって見逃しにくいだろうとのことで、カワセミの巣穴は深く捕食者にとって捕食が労力に見合わないので他の獲物を狙う方が簡単であろうと推論している。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 87 V (藤岡) によれば、巣から出ると、まず川に飛び込んで水浴びをしたり、ひなの羽毛が長い間羽鞘に包まれた状態であるのは、不潔なトンネル生活に対する一種の適応といえなくもない、と記述されていた。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 88 p. 12 によればブッポウソウ (日本のものか海外のものか不明) も巣内をあまり清潔にしないので、ひなのふんや食物の残りが腐敗して悪臭を放つとのこと。
-
ミツユビカワセミ
-
ヤマセミ
- 学名:Megaceryle lugubris (メガケーリュレ ルーグブリス) 喪服色の (白黒の、あるいはくすんだ) 色の大きなカワセミ
- 属名:megaceryle (合) 大きなカワセミ (mega- (接頭辞) 大きな Gk、Ceryle Boie, 1828 によるカワセミの属名)
- 種小名:lugubris (adj) 喪服の、くすんだ (色から)。白黒の模様を指すと考えられる。備考参照
- 英名:Crested Pied Kingfisher, IOC: Crested Kingfisher
- 備考:
megaceryle は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語 megas は短母音。ceryle はギリシャ語 kerulos が由来で e が長母音。この位置にアクセントがあると考えられる (メガケーリュレ)。
lugubris は冒頭が長母音。lu-gu-bris と分割され冒頭にアクセントがある (ルーグブリス)。
lugubris の語源は冒頭が lugeo (悲しく、嘆く。ルーゲオー) であることは間違いないが語尾の由来は明確でない。イタリア祖語の *lougosris, *leugosris が起源で末尾が sr から br に変化した説があるが他説もある (wiktionary)。-bris の末尾は (この場合格や数が合わないが) 長音にするラテン語語尾があるが lugubris はこの変化形由来でないため長音にならないものと思われる。
Megaceryle 属はカワセミ類で最も大型の数種を含む。Ceryle は kerulos (Gk) 由来でアリストテレス他が用いた同定はなされていない鳥だが、おそらく神話上で halcyon に関係があり、カワセミ類を指す名前に使われる。
ヤマセミはかつて Ceryle 属で、愛媛の野鳥「はばたき」ではカワセミと訳している。その後属が分割されたもの。4亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は lugubris 亜種ヤマセミと pallida (淡色の) エゾヤマセミとされる。
中国の大部分の亜種は guttulata とされ北朝鮮にも一部分布するとされていたが最近はまれとのこと。中国東北部の亜種は lugubris か guttulata かよくわからないとある [Brazil (2009)]。
lugubris が最初に記載されて種小名の由来ともなっている。
Alcedo lugubris Temminck, 1834 に記載を見ることができる。
これによればシーボルト伝来の和名として Samo-dori (斑点のある鳥)、Kabuto-dori (冠のある鳥)、Kawara-dori (河原の鳥)、中国名で Kon-fu-tsjo (鳥の美女)、Kwa-van-tsjo (花形斑点の鳥) の記載がある。
フランス語名で Martin-pecheur deuil (deuil = 死別の悲しみ、喪服、葬式)。
声ではなく模様や色彩の記載なので、色から lugubris を付けたものと思われる。また Alcedo 属に入っていることもヒントになり、当然よく知られたカワセミなど色彩豊かな鳥に対比した表記とも想像できる。白黒ばかりが目立つことを伝えたかったものだろうか。
現在ではシノニムとされるが、
・Ceryle lugubris jamasemi Momiyama, 1927 (参考) 基産地 Kami-Kaifu-mura, Iwafune-gun, Prov. Echigo, Hondo, Japan
・Ceryle lugubris sikokiana Momiyama, 1927 (参考 基産地 Ichinomiya (Ikku-mura), Prov. Tosa, Shikoku
の記載があり、いずれも Kuroda (1932) は lugubris のシノニムとした。
・Ceryle lugubris pallida Momiyama, 1927 (参考 基産地 Nopporo, Prov. Ishikari, Hokkaido, Japan は亜種エゾヤマセミとなっているもの。
Dement'ev and Gladkov (1951) では lugubris のシノニム扱い。
Birder 編集部 (1998) Birder 12(7): 27-31 によればヤマセミの和名の由来は新しく昭和に入ってからで、江戸時代にもヤマセミの名称はあったがヤマショウビンやアカショウビンを指して使われていたとのこと (p. 29)。
[学名の lugubris の意味と生態的意義]
Temminck が lugubris と名付けている別の鳥にバルカンコガラ Poecile lugubris Sombre Tit がある 記載
こちらも炭のような黒さなどを挙げている (なお Poecile 属の意味は#ハシブトガラ備考参照)。
トカゲの一種に Lepidodactylus lugubris があり、wikipedia 情報によると黒い斑点などで保護色をなしているとのこと。フランス語 lugubre には陰鬱な、不気味ななどの意味もあり、命名者たちにとってはこのような色彩パターンから連想される単語なのかも知れない。
他にも lugubris の種小名を持つ種類があるが、頭や背が黒い (Cisticola lugubris)、黒い縞 (Dendropicos lugubris) などの特徴を表しているものが多い。
フランス語鳥名辞典 (Noms francais normalises des oiseaux du monde - 2024 - version 6.3) を見ても lugubris の種小名を持つ種類で意味が訳されているものはほぼすべてが色由来で、くすんだ、日陰の、などの意味になっている。
音声由来の可能性のあるものはオウチュウカッコウ (音声が不気味?) のみだった。この種も全体が黒っぽい色彩であるが、白い部分や白い縞模様があるとのこと。
鳥の学名での lugubris の意味はほぼこのような色彩パターンを表していると解釈してよさそうである。学名の訳によく使われる「喪服の」と訳すのが適切かどうかは注目された特徴次第だろう。
英訳されると mourning となるが、フランス語 lugubre の持つような意味は欠落するかも知れない。
Dendropicos lugubris の英名は Melancholy Woodpecker で学名を訳したものと思われるが、フランス語では pic a raies noires 黒い縞のキツツキ となっている (生息地はフランス語圏のアフリカが中心)。英語から意味を推測すると原意から離れたものになる可能性がある。
我々が見ても気味悪く見える模様もある lugubris の意味する色彩は例えば全般的に捕食者に対する警告色 (warning coloration または aposematic signal 警告シグナル) の役割があって、色に頼らないモノクロの警告色は色彩感覚に乏しい哺乳類にも有効なシグナルかも知れない (もちろん実験なしではわからないが)。
このように考えると lugubris は全般的には "不気味な", "気味悪い" と訳すのが適切なのかも知れない。
種類によっては明らかに「喪服色の」(黒と白を指すなど) の意味でも用いられており (例えば原記載で用いられた名称から判定できる)、場合の応じて訳し分けるのがよいかも知れない。
#ハクセキレイの亜種 lugens や、#セグロセキレイらしいものに使われた学名 Motacilla lugubris Temminck または Pallas は明らかにこちらの意味で使われていた。
この部分を書いた後に知ったが、カササギは英文学では白黒の持つ二面性から不吉な鳥と考えられていたとのこと (コンサイス鳥名事典)。ヨーロッパ他所でも普遍的な考え方であったかどうかはわからないが、白黒2色の鳥に lugubris, lugens の名称が多く与えられているのは当時ヨーロッパの "不吉" な (そして喪服を連想させる) 直感的印象を表したものかも知れない。セグロセキレイもハクセキレイの亜種も、実は不吉な色彩のセキレイを意図していたのかも。
ちょっと寄り道して考えてみると、タカ斑模様は同様の効果があるのだろうか。獲物に威圧感を与えるとよく言われているがこれもヤマセミの lugubris の指すパターンに似ている気がする。タカに襲われた経験のある鳥が学習によって模様でタカを避けるのか、それとももっと根源的に訴える一般的シグナルになり得るのか。
タカにとっては避けてもらわない方が都合がよいので...むしろ背景に紛れるのに都合のよい色彩なのか? ここではよくわからないとしておこう。クマタカなど最たる例だが威圧感を与えるのに役立っているのだろうか。
猛禽類の巣を訪れた哺乳類捕食者を驚かせる効果があるのではと個人的に感じるがさてどうだろうか。
#ハヤブサの備考 [ハヤブサ類の免疫の特殊性] 免疫と造巣習性の関係? の考察で紹介した文献 Rohwer et al. (2025) The Evolution of Using Shed Snake Skin in Bird Nests
より派生し、#アリスイの [アリスイの首ふり行動] でアリスイのヘビのように見える行動や色彩が哺乳類捕食者を遠ざけている可能性を考えてみた。
同様に考えるとヤマセミの白黒模様は鳥類に対するものというより色覚に劣る哺乳類捕食者に対する信号なのではないかと一層思えてきた。つまり白黒2色で十分。我々はつい昼行性鳥類捕食者に近い色覚で物事を見てしまうが哺乳類捕食者の色覚は別途考える必要があるだろう。
Temminck も標本を見た時 (色彩豊かなカワセミ類にしては)「気持ち悪い!」と感じたのではないだろうか。
推測にしか過ぎないので訳語としては採用しないが "不気味なカワセミ" や "不吉なカワセミ" が原意だったのかも知れない (ヤマセミファンの方には申し訳ない解釈となるが)。
目立った特徴があったので種小名の選択に困らなかっただろうと想像できるが、日本で記載されたのに japonica を用いなかった理由を強いて考えてみると、当時の同属にカワセミがあり、"日本のカワセミ" のような名称を与えるとヨーロッパのカワセミに対する日本版の意味となり、日本にも生息するカワセミを指してしまって都合が悪かったと思われる。
また#タンチョウの学名に対する Temminck の見解のように同地域に複数種のカワセミ類が記録されるため地域名を与えなかったとも考えられる。
[派手な色彩の鳥はまずい?]
「派手な色彩の鳥はまずい」仮説は雑誌記事などでもしばしば紹介される。
Weldon (2000)
Avian chemical defense: Toxic birds not of a feather によれば、鳥が毒を持つかもしれないとの推測は、Cott がエジプトで 1941 年オリエントスズメバチ Vespa orientalis がワライバト Spilopelia senegalensis Laughing Dove の死体に引き寄せられるのに、
ヒメヤマセミ Ceryle rudis Pied Kingfisher は忌避した観察に始まるとのこと (ここにも白黒2色に対する価値観が潜在的に現れていたのかも知れない)。
ここからさまざまな鳥の肉をスズメバチ類や猫が食べるかどうかを調べ、"派手な色彩の鳥はまずい" 仮説に至ったとのこと。Weldon (2000) の論文に Cott (1947) に掲載された写真が紹介されている。
毒鳥ピトフーイが警告色らしい色彩であったためこの仮説が再び脚光を浴びることになったとのこと。
Weldon (2000) は肉食動物が鳥を食べる時は羽毛をむしることが多いので羽毛に毒を集積することは理にかなっていると解説している (捕食者対策よりも排泄経路の役割の方がより重要かも知れないとの考えも近年出されている)。
毒鳥ピトフーイの発見に関連するもので詳細は #ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] (5) 毒鳥ピトフーイなどの対毒性 (BTX 耐性) をご覧いただきたい。
歴史的経緯があるとわかりやすいため、ここで紹介した部分もヤマガラ備考から一部重複する形で抜粋した。
Cott の研究を引き継ぐ形でにおいが感じられる、あるいは毒気を感じる鳥の Weldon の研究については#フルマカモメ備考の [におう鳥のリスト] も参照。
これらの研究は Cott の歴史的発見から始まったものだったが、時代を経るにつれて視点が多少変わってきており、(当初はスズメバチ類の観察から始まったものだが) 近年は猛禽類が目立つ鳥を狙うかの実験報告や捕食者にどのように見えるかの視覚研究が主になっている。
これら研究のみを見ると研究しやすい (視覚研究ならば計算機上でもできるものがあるので一層扱いやすい) 項目に視点が矮小化される可能性があるので時には出発点に立ち戻ってみるのもよいだろう。
スズメバチ類が忌避する鳥が本当にあるならばハチクマを嫌うかどうか気になるところで、ハチクマの疑問の原点に戻ってしまう。Cott のような方法で調べた人はいないのだろうか。
フランス人はヨーロッパハチクマを捕獲して食べすぎて数を減らしたとのことなので不快な味はないのではと想像できるがハチの感じる化学物質とは異なるかも。
鳥類の警告色や擬態については Hedley and Caro (2022) Aposematism and mimicry in birds
のレビューがある。ヤマセミのような色彩は特に扱われていないが、カワセミなどの目立つ色は捕食者をむしろ引きつけるとの実験が紹介されている [Ruiz-Rodriguez et al. (2013)
Does avian conspicuous colouration increase or reduce predation risk?]。
ブッポウソウ目の色彩が警告色になっている実験的証拠は見つけられなかった。
実験および野外研究ではヤツガシラの捕食率は低く、色彩パターンそのものは警告色としてあまり役立っていないようだがヤツガシラの異様な容貌を猛禽類も避けているか、あるいは見つけにくいとのこと。
猛禽類も盛んにさえずるヒバリは避けてあまり鳴かないものを捕まえる。
マングースがまずいと拒絶した種類と目立つ色彩の間はあまり関連がなかった (ただし古い観察に基づく)。
ついでに Caro はシマウマの縞模様が保護色にも警告色にもなっていないと述べた研究者 (#タシギ備考の [分断色])。Cott 時代から視点がだいぶ変わっているのがわかる。
柴田 (2018) Birder 32(1): 32-33 に「派手な色はまずい?」の考え [Unprofitable Prey Hypothesis, UPH 仮説: Baker and Hounsome (1983)] の紹介があり、鷹狩のオオタカはオスのキジやマガモを嫌う。ハイタカもメスの小鳥の剥製を好んで狩る研究があるらしい。
調べてみると Post and Gotmark (2006)
Predation by sparrowhawks Accipiter nisus on male and female pied flycatchers Ficedula hypoleuca in relation to their breeding behaviour and foraging
のような研究があってマダラヒタキでは雌雄差があまりなかった。自分たちが過去に行った Gotmark et al. (1997) Natural Selection and Sexual Dimorphism: Sex-Biased Sparrowhawk Predation Favours Crypsis in Female Chaffinches
チフチャフからの結論とはいまいち合わない、というところ。
Sirkia and Qvarnstrom (2021) Adaptive coloration in pied flycatchers (Ficedula hypoleuca) - The devil is in the detail
のレビューを見ると、どうも「まずい (不適切な獲物)」逆に「見つけやすい方が捕食される」仮説の両方があって、不適切な獲物説で調べているのはこの Gotmark のグループが中心で、それほど実験的支持は得ていないよう。
Cain et al. (2019) Conspicuous Plumage Does Not Increase Predation Risk: A Continent-Wide Test Using Model Songbirds は見つけやすい方が捕食される証拠は得られないとどちらかと言えば UPH 仮説を補強する結果となっている。
マダラヒタキに関しては緯度によって色彩が異なるパターンも捕食確率とはあまり関係なさそうらしい。
柴田 (2018) にはカワセミの色彩もまずいことを伝えている可能性が挙げられているが、上記実験をみるとカワセミは特に避けていないように見える。
Hedley and Caro (2022) のレビューによれば UPH 仮説の是非の議論は単一の仮説で目立つ色の進化を説明しようとする落とし穴にもなり得て、最近はあまり顧みられていない模様。
Bliard et al. (2020) Examining the link between relaxed predation and bird coloration on islands では島では捕食者が減ることで色彩が豊かになる傾向があるらしい。実験的検証は確かに難しそうだが、色彩的に目立つ方が捕食される傾向は多少確かめられている感じがする。
猛禽類がそもそも「まずい」と感じるかどうかも問題点だが、近年の比較ゲノム学の進歩で猛禽類が味を感じているらしい肯定的と思われる結果が出ている。#メジロの備考 [鳥類の味覚] 参照。
lugubris や lugens の使われる (使われた) ハクセキレイやセグロセキレイも派手な色の方に入ると思われるが猛禽類は避けているだろうか。これはフィールド研究でもある程度判断できるかも知れない。
カワセミの色彩が保護色となっている可能性は上田 (2007) Birder 21(1): 38-40 で紹介されており、水面をバックにカワセミの青い背中はあまり目立たない。オウム類の青と緑の派手な色彩は赤い果実のなっている葉陰では天敵に対して隠蔽的な効果を持っているとの説がある紹介がある。
(一般的議論としてまずさや捕食しにくさを鳥に知らせて捕食を逃れる警告色としての) これらの鳥の美しさも捕食者に対する警告の信号として進化してきたと考えることはできないだろうか、と記している
(フィッシャーのランナウェイ過程も取り上げられている)。
ハチドリ類もすばやく、獲物としては不適切であることを美しさで示しているのではないかとの言及もある。2007 年の記事なので UPH 仮説もよく取り上げられていた時代を表しているかも知れない。
(#ツリスガラ備考の [鳥類の営巣習性の進化] から重複抜粋):
オウム類の樹洞営巣性は派手な色彩を隠す必要があるとの説があるとのこと: Carballo et al. (2020) Body size and climate as predictors of plumage colouration and sexual dichromatism in parrots 参照。
この論文はオウム類の色彩を調べたもので、小型で短命の種類ほどオスは性選択を強く受ける。大型種では両性間の選択、社会的選択、大型種は隠蔽色であることへの選択圧が低いことを理由としている。
上田 (2021)「野鳥」2021年11・12月号 (No. 855) p. 12 に「赤や緑のオウム類の派手な色彩は、赤い果実がたくさん実っている緑の葉陰ではかえって隠蔽色になる可能性がありますが (中略) 捕食者に対する警告色として進化してきたと考えることはできないでしょうか」とあるが、隠蔽色については全体的傾向は逆を示唆する結果となっている。
オウム類の緑色が隠蔽色と考える解釈は以前よりあって Mundy (2018) Colouration Genetics: Pretty Polymorphic Parrots の解説では未だに検証が行われていないとあり、色彩の生態的役割は今後の研究の進展が期待できるとある。
オウム類の樹洞営巣性の説明は Martin and Li (1992) Life History Traits of Open- vs. Cavity-Nesting Birds が出典とのこと。
Soler and Moreno (2012) Evolution of sexual dichromatism in relation to nesting habits in European passerines: a test of Wallace's hypothesis
によれば Darwin, Wallace が 100 年以上前に提唱した、樹洞営巣性の種ほどオスが目立つ色彩でメスは隠蔽色になる傾向をスズメ目である程度確認したとのこと。
#アオバトのところで多少思いついたので少し検討を追加してみた。オウム類の各属一覧を見てみると圧倒的に緑色系統が多い。やはり何らかの共通の意義があるのではないだろうか。
森林性のものは緑色を背景にして一定の保護色になっているように思える。
"青と緑の派手な色彩は赤い果実のなっている葉陰では天敵に対して隠蔽的な効果を持っている" はヒトの視覚の印象からの推定ではないかと思う。哺乳類は基本的に2色型色覚で、ヒトを生んだ系統は遺伝子重複によって3色型色覚を獲得している。しかし遺伝子重複から生まれたもので波長分離に無理もあって緑と赤の見分けは若干苦手と言える。
2色型哺乳類捕食者がいるならばこの考え方は多分完全に成り立ち、緑と赤の組み合わせは実際に目立たないだろう。天敵に見えにくい、しかし自分たちの間では見えるシグナルはいかにも進化しそう。
一方鳥類捕食者にとっては事情が異なってかなり「見え見え」になっていないだろうか。鳥類捕食者がどの程度影響を与えているか、あるいは鳥類捕食者と分布の重複がどの程度あるかなどは検討してみると面白そう。アフリカではタカ類発祥の地でもあり猛禽類の種類も多く一定の圧力は加わってそうに思える。
中南米ではタカ類発祥の地から遠く、現在では深刻な相手はオウギワシやアカエリクマタカ類 (Spizaetus 属) 程度だろうか。ノスリ類は後になって分布したがそれほど大きな種類は生んでいない。ハヤブサ類は中南米が発祥の地だがいわゆる我々の思い浮かべるハヤブサ類は主に旧世界で種分化したもので中南米にはあまり至っていない。
オーストラリア大陸でも同様に猛禽類の種類が少ない。
オウム類の天敵を軽く探してみると一般的な記述ばかり目立って具体的にどのような種に捕食されるかあまり書かれていない。アフリカのヨウム (色彩の目立たない数少ない種類だが) を捕食する鳥は少なく、
重要な捕食者の一つはヤシハゲワシ (これまたちょっと意外な種類) とあるページがあった (wikipedia 英語版でも引用されている) が裏付けとなる資料を見つけられなかった。
オウム類の色素
オウム類の色彩の分子遺伝的メカニズムが一部解明された: Arbore et al. (2024) A molecular mechanism for bright color variation in parrots
オウム類の色彩には独自の色素 psittacofulvins が関わっているがコシジロインコ Pseudeos fuscata Dusky Lory で遺伝子発現と赤や黄色の発色の関係を調べたもの。ALDH3A2 (アルデヒドを脂肪酸に酸化する酵素) の下流の非コード域の点変異で色が変わるとのこと。
表皮の角化細胞 (keratinocytes) の分化の最後の段階で多く発現される遺伝子で、ALDH3A2 のレベルが高いほど黄色くなる。酵母で赤色の psittacofulvins に対するこの酵素の働きからもこの機構が裏付けられた
(HKU and BIOPOLIS-CIBIO Biologists Reveal the Genetic 'Switch' Behind Parrot Color Diversity 一般向け英語解説)。ハシボソガラスとズキンガラスの色彩の違いに構造多形が関与していた (#ハシボソガラス備考参照) ように、オウム類に限らず色彩のメカニズムは相当難しいよう。
psittacofulvins については Roy et al. (2025) Multiple mutations in polyketide synthase led to disruption of Psittacofulvin production across diverse parrot species
の introduction が役立ちそう。オウム類はカロテノイドを羽毛着色に用いる代わりにポリエン (polyene) による発色機構 (大学の化学で分子軌道法を学ぶと教科書的に出てくる。カロテノイド発色も同様) を用い、鎖の長さを延長する酵素 type I polyketide synthase (MuPKS) がこの機能を担っているとのこと。同一酵素が二重結合の鎖の長さを延長できるので構造色と組み合わせてさまざまな色を作ることが可能とのこと。
青いセキセイインコはこの遺伝子に変異 (R644W) がある。
Burtt Jr et al. (2010) Colourful parrot feathers resist bacterial degradation によれば抗菌機能にも役立っているとのこと。もともとはこちらの目的で進化したものを色彩に用いるようになったのだろうか。
Mundy (2017) Colouration Genetics: Pretty Polymorphic Parrots のオープンアクセスのレビューもある。long-chain conjugated aldehydes (長鎖共役アルデヒド) polyenals とも呼ばれる。
7-9 個の共役二重結合からなる色素であることは非破壊的にラマン分光によって Veronelli et al. (1995) In situ resonance Raman spectra of carotenoids in bird's feathers が示唆していたとのこと。
Stardi et al. (2001) The chemical structure of the pigments in Ara macao plumage が実際に抽出して構造を初めて明らかにした。
ということでオウム類の発色機構が判明したのは 21 世紀に入ってから。
ペンギン類の色素
ペンギン類の黄色も系統特異的な色素によるものとこと: Thomas et al. (2013) Vibrational spectroscopic analyses of unique yellow feather pigments (spheniscins) in penguins。芳香族とヘテロ芳香族の結合した pterin の1種と考えられるとのこと。この時点ではまだ既知物質と同定されていない。
魚食ではカロテノイドがあまり得られないので代替方法が進化したのか (論文には書かれていない)。
pterin の化学構造や生合成、動物における着色については Andrade and Carneiro (2021) Pterin-based pigmentation in animals のレビューがあるが、この時点でもペンギン類の色素分子はまだ同定されていなかった。pterin はハシグロアビも含む虹彩の赤いいくつかの種の鳥の発色に関係していると考えられているとのこと。
鳥の目の色を見る時にはこのことも考慮するとよさそう。
虹彩色に関係する遺伝子
Andrade et al. (2021) Molecular parallelisms between pigmentation in the avian iris and the integument of ectothermic vertebrates によればハトの虹彩色に pterin 蓄積が関係していることは以前から知られていた。
変温動物では皮膚の着色に用いていた (色素胞 chromatophore) が恒温動物では皮膚が羽毛や毛で覆われるため機能を失い、虹彩がこの機能の進化的なレフージア (evolutionary refugium) になっているとの考えが提唱されているとのこと。参考までにこのアイデアは Oliphant et al. (1992) Pigment cell refugia in homeotherms - the unique evolutionary position of the iris。
ハトで関連する遺伝子は SLC2A11B とのこと。他の種との配列比較は fig. 3; fig. S1。
pterin / pteridine は主に紫外線領域の光をよく吸収するため、紫外線色覚のある動物の色彩に有用であろうことは想像できる。
Maclary et al. (2021) Two Genomic Loci Control Three Eye Colors in the Domestic Pigeon (Columba livia) によればこの遺伝子は哺乳類では存在しないとのこと。哺乳類で最も近い遺伝子は SLC2A11 (GLUT11) で glucose transporter とのこと。
ハトの目の色、羽毛色などの遺伝的背景について Maclary et al. (2021) は他の遺伝子との関係も調べている。
Si et al. (2021) The genetics and evolution of eye color in domestic pigeons (Columba livia) によればウの目が青系統なのは SLC2A11B の機能をフレームシフト変異で失って虹彩に pteridine 色素を持たないためではないかとのこと。ウの系統の早い時期に起きたようでヘビウ類ですでに失われていたがアメリカヘビウ Anhinga anhinga Anhinga では虹彩に黄色の色素があってこの変異だけでは説明できないとのこと。
イエスズメもナンセンス変異で機能を失っており虹彩に黄色色素を持たないことが説明できるとのこと。スズメでは失われていない。
ヨウムの白い虹彩やノバリケン Cairina moschata Muscovy Duck の茶色の虹彩もこの酵素の変異によるものと推定している。
Maclary et al. (2021) によればズキンガラスでも遺伝子の一部が見つからず、黄色色素を持たないために黒い目になっている可能性があるとのこと。あるいはカケスやニシコクマルガラスの白い目も同じメカニズムでカラス系統の目が黒かったり白かったりするのは遺伝的共通基盤があるのだろうか。
これらの研究は遺伝子変異のみを見ており、実際の虹彩色素や蓄積メカニズムを調べたものではないので上記説明も含めて若干過剰解釈があるかも知れない。イエスズメとスズメの虹彩の色が違うかと言われるとあまり違わない感じもする。
鳥類が虹彩に変温動物の色素胞の遺存物を残したと考えるよりも、哺乳類が夜行性を体験して色覚をあまり必要としなくなったためでは、と思ってしまう。哺乳類で残っておらず、鳥類にそれほど古い遺伝子が保存されているのは鳥類の進化の過程で目の色は重要だったのでは。進化初期でも鳥では "目は口ほどに物を言った" のだろうか。
Si et al. (2021) によれば鳥類全体では SLC2A11B には強い選択圧は働いていない (relaxed selection) と表現しているが、SLC2A11B を持っているものは配列が保存されるが、失うことも可能でその場合は白や黒の目の色を逆に利用しているように見える。
皮膚の着色とは異なり失った場合も別の役割が果たせるので relaxed selection の状態なのかも。Andrade et al. (2021) の配列比較ではハトの目の色に関係する領域しか示していないのでフレームシフト変異などの部分は含まれておらず比較には注意が必要。
Si et al. (2021) の S8 Fig に 52 種の比較がある。キンクロハジロは機能を失っていないよう。白い目のカモ類は気になるがこの研究では調べられていない。Falco 属の虹彩が褐色なのはあるいは影響があるかと思ったが関係ないようでヨウムの変異に対応するものはなかった。
鳥類でも何度も独立に失われているので、哺乳類で完全に失ってしまったのは長期間の夜行性時期に他の感覚を用いたコミュニーケーションの方が重要だったのだろう。
今一度鳥の目の色に注目すべきであろうし、鳥の祖先となる系統でも目の色は重要だったらしいことを念頭に置いた復元が必要なのだろう。ただし遺伝子の役割はごく一部調べられているのみで目の色を決める以外にも重要な働きを行っている可能性もあるだろう。
SLC2A ファミリーの遺伝子と代謝
SLC2A ファミリーの遺伝子は膜での糖の輸送など代謝 (恒温性の獲得などにも) とも密接に関係しているとのこと。Xiong and Lei (2021) SLC2A12 of SLC2 Gene Family in Bird Provides Functional Compensation for the Loss of SLC2A4 Gene in Other Vertebrates
鳥類ではインスリンに反応する SLC2A4 を失っていて高血糖を可能にしている解釈がある。系統解析によれば現生鳥類に共通して失われているが、祖先のどの段階で失ったかは不明。ワニは持っている。
SLC2A4 と SLC2A12 が鳥類や哺乳類で強い選択を受けていて、SLC2A12 が鳥類で SLC2A4 の機能を一部代替するとともに鳥類進化に伴う基礎代謝率の変化に影響を与えてきた示唆が得られ、古い遺伝子を多様化させて高度な機能を実現したらしいとのこと。
問題の SLC2A11 を見ると鳥類・哺乳類とも持つもの、持たないものが存在する。当時は SLC2A11B はまだ認識されていなかったのかハトは持たない方に入っていた。
着色機構との関連を考えると、羽毛のように新しく誕生したものには新しい着色機構を用いたが、古くから連続して存在する虹彩のような部位には古くからの機構をそのまま残した形となったのだろうか。
なお番号はヒト遺伝子に対して付けられたものなので、ヒトが持っていない遺伝子が大きい番号になる。遺伝子ファミリーの系統関係を表した数字で番号が若いほど古くからある意味ではないので注意 (fig. 2 右端に遺伝子ファミリーの系統関係が示されている)。
SLC2A14 はここで調べられた範囲ではヒトのみが持っているが、これは SLC2A3 から派生したもの。古い系統の遺伝子ほどよく保存されている傾向があり、系統分岐に伴って派生して生じた新しいものが系統によって異なる傾向が読み取れる。
注意すべき点もあって Huttener et al. (2021) Sequencing refractory regions in bird genomes are hotspots for accelerated protein evolution ゲノム内で読み取りにくい領域にあって検出されなかった遺伝子が詳しく調べると見つかったものがあるとのこと。鳥類の SLC2A4 はそれでも見つからなかったとのこと。
しかし mRNA やタンパク質のレベルでは GLUT4 (SLC2A4) が検出されたとのことで、ゲノム解析で脱落しやすい領域 (例えば微小染色体) から転写されている可能性があり、SLC2A4 を失っていて高血糖を可能にしているポピュラーな解釈は誤っている可能性があるとのこと。いずれにしてもこれらの筋肉がグルコースを取り込む経路に関わる遺伝子群が鳥で強く選択され高いエネルギー代謝率を可能にした興味深い可能性が浮かび上がるとのこと。
この研究に触発されハチドリがグルコースだけでなくショ糖の成分であるフルクトースも取り込むことのできる SLC2A5 を持っていることを示した研究: Gershman et al. (2023) Genomic insights into metabolic flux in hummingbirds。SLC2A4 はやはり見つからなかった。(#アマツバメ備考の [渡り鳥における磁気定位] からハチドリの話題にも紹介)。
以下さらにオウム類の進化にかかわる話題も記述していたが、#ミサゴの備考 [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] に移動した。
Hedley and Caro (2022) のレビューによれば "毒鳥" の狭義の警告色はいくつか考えられていて、これらはオレンジと黒の色彩となっている。
キバシカマハシ Rhinopomastus minor Abyssinian Scimitar-bill や ミナミカマハシ Rhinopomastus cyanomelas Common Scimitar-bill では青緑色の目立つ鳥で白い模様があり、声が大きく不快な臭気があるという。
ミナミジサイチョウ Bucorvus leadbeateri Southern Ground-Hornbill も目立って赤い嘴で人にとってまずいという (ただし非常に大きな鳥である)。
古くからヒトにとって青い食物は食欲をそそらないと言われ、鳥に対して成り立つかどうかはニワトリなどのいくつかの報告はあるものの一般性はよくわからない。上記カマハシ類は不快さを表す警告色となっている可能性はあるかも知れないが、野外で指摘されている例はあまりない模様。
Gall et al. (2018)
The indestructible insect: Velvet ants from across the United States avoid predation by representatives from all major tetrapod clades
によれば北米のマネシツグミを用いた実験で警告色で塗られた虫を食べるのに明らかに躊躇しているとの言及がある。生得的なものか学習によるものかは議論がなされているが、この著者たちはマネシツグミは過去に警告色の昆虫に対する経験があったが、有毒なアリには出会っていなかった可能性があると推定している。
ここで用いられた有毒なアリはアリバチ (velvet ants) で、毒のメカニズムも解説がある: Borjon et al. (2025) Multiple mechanisms of action of an extremely painful venom
そのうちの1つのペプチド Do6a は虫のイオンチャンネルに作用するが、それに相同なチャンネル Acid Sensing Ion Channels を持つマウスではこの物質は反応を示さず、この物質は捕食者の虫に対して特異的に進化したものと考えられる。哺乳類 (上記実験のように他の陸上脊椎動物捕食者もおそらく同様) には別の非特異的でより弱い物質が作用している。
[ヤマセミ亜科 Cerylinae の系統分類]
属の位置づけは Moyle (2006) A molecular phylogeny of kingfishers (Alcedinidae) with insights into early biogeographic history の分子遺伝学による。このグループはかつてアメリカ大陸からベーリング海峡を通ってユーラシアに進出したグループと考えられていたが、旧世界、おそらくアフリカ起源と考えられるとのこと。
Andersen et al. (2018) (#アカショウビンの備考参照) ではヤマセミ属を含むヤマセミ亜科 Cerylinae亜科はアジア、旧北区か Indomalaya に由来し、新世界に2系統が進出したと考えられるとのこと。
現在の Ceryle 属は1種ヒメヤマセミ Ceryle rudis Pied Kingfisher のみでアフリカから東アジア、ほとんど日本に近いところまで分布しており、ヤマセミグループの起源分布に近そうに見える。
分離されたもう1属は Chloroceryle で中南米のグループ。系統的には Ceryle 属より新しい。
ヒメヤマセミと Chloroceryle 属で単系統を作るが、分布が大きく違うためなどの理由でヒメヤマセミを別にする必要があり、
それぞれの単系統性を保つために Ceryle 属が3分割された模様。
系統的にはかなり大きく離れているので少数の種から構成される属であっても属分割は妥当に見える。
従来の研究ではヤマセミの遺伝情報がなく、Boyd も系統樹に ? 付きで載せていたが、
Andersen et al. (2018) で初めて扱われ、Megaceryle 属に素直におさまることが判明した。ヤマセミ亜科は種数も少ないので全種を Boyd のリスト順に従って紹介しておく。IOC との整合性もよく、Andersen et al. (2018) ともよく合っている。全種に何らかの分子遺伝情報がある。
ヤマセミ亜科 Cerylinae
ヤマセミ属 Megaceryle
ヤマセミ Megaceryle lugubris Crested Kingfisher
オオヤマセミ Megaceryle maxima Giant Kingfisher
アメリカヤマセミ Megaceryle alcyon Belted Kingfisher
クビワヤマセミ Megaceryle torquata Ringed Kingfisher
ヒメヤマセミ属 Ceryle
ヒメヤマセミ Ceryle rudis Pied Kingfisher
ミドリヤマセミ属 Chloroceryle
オオミドリヤマセミ Chloroceryle amazona Amazon Kingfisher
コミドリヤマセミ Chloroceryle aenea American Pygmy Kingfisher
ミドリヤマセミ Chloroceryle americana Green Kingfisher
アカハラミドリヤマセミ Chloroceryle inda Green-and-rufous Kingfisher
△ ブッポウソウ目 CORACIIFORMES ハチクイ科 MEROPIDAE ▽
-
ハチクイ
- 学名:Merops ornatus (メロプス オールナートゥス) 華麗なメロプス王
- 属名:merops (m) エチオピアの王
- 種小名:ornatus (adj) 華麗な、見事に飾られた
- 英名:Rainbow Bee-eater
- 備考:
Merops は起源となるギリシャ語では長母音はない。語末の -ops の ps はギリシャ文字 ψ に由来。この語末はギリシャ語以前の典型的なものと考えられるとのこと (wiktionary)。ラテン語では "メロプス" となるが、ギリシャ語でも同じ位置にアクセントがある。
ornatus は o と a が長母音で規則通り -na- にアクセントがある (オールナートゥス)。
オーストラリア中心に分布する種で単形種。一般書などではハチクイというとより有名な Merops apiaster (apis ハチ に由来して古くから使われている単語) 英名 European Bee-eater ヨーロッパハチクイを指して使われることが多いので注意。
英国では Merops apiaster が迷鳥で他のハチクイ類がいないため紛らわしくなく Bee-eater の英名が使われていた。そのまま訳せばこの種が "ハチクイ" となっていた次第。
ヨーロッパハチクイの記載時学名 Merops Apiaster Linnaeus, 1758 (原記載)。Linnaeus 自身の Fn. Svec. では Ispida と呼んでいてカワセミのこと。色彩が鮮やかで配色が似ているためか (実は誤解していたかも。Linnaeus 自身のカワセミの学名由来はやや怪しげ。#カワセミの備考参照)。
ヨーロッパハチクイは Merops europeus Blyth, 1834 (参考) と改名されたことがあった。英名 European Bee-eater と対応している (どちらが先かは不明)。和名はこの英名由来と想像できる。分布はヨーロッパよりさらに広い。
本種ハチクイは日本では、1904 年に沖縄県宮古島で採集された記録があるだけの迷鳥である (wikipedia 日本語版)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" でもこの記載とハチクイの名称を採用している。
ハチクイの学名にルリオハチクイ Merops philippinus が使われている例があり注意が必要 (wikipedia 日本語版)。
[ハチクイ科の系統分類]
#ブッポウソウの備考も参照。
ハチクイ属はやはりアフリカ中心。
Marks et al. (2007)
Molecular phylogenetics of the bee-eaters (Aves: Meropidae) based on nuclear and mitochondrial DNA sequence data に分子系統研究がある。ムネアカハチクイ属2種のみが特殊で古い分岐と考えられる。
セレベスハチクイはアフリカにも分布するハチクイ属に近いが生物地理学的にも異なっており、同系統か否かまでは結論できないとのこと。渡り能力が高いグループのようで、古く分散したものが一部残っているのかも知れない。
Merops 属は2クレードに分かれ、ハチクイ、ルリオハチクイともにヨーロッパハチクイの属するクレード (論文では Clade B) に属する。
このクレードの最初のものはアフリカのノドジロハチクイ Merops albicollis White-throated Bee-eater で、アフリカが発祥の地で遠距離の渡りを行うヨーロッパハチクイの祖先からアジア (および一部のアフリカの) の系統が生じた描像で話が合いそう。
直接の証拠はないが、ヨーロッパハチクイやルリホオハチクイ Merops persicus Blue-cheeked Bee-eater はセーシェルのようなインド洋離島でも記録され、アカアシチョウゲンボウやカッコウのようにインド洋を渡っている可能性がある。
(#アカアシチョウゲンボウ備考の [渡り] で紹介の TED 講演にも出てくる)
ノドジロハチクイはトカゲなども食べる。リスと共生し、リスがアブラヤシの果肉を食べる時に、落ちてくる外皮の小片を嘴で受けて食べる (コンサイス鳥名事典)。
[ハチクイ類のハチ毒耐性]
ハチを捕食する場合は毒針を抜いてから食べる。また、ハチの毒に対する免疫を持っているため、ハチに刺されても死ぬ事はないと wikipedia 日本語版にあるが、具体的メカニズムはよくわかっていないようである。
Gulbahar et al. (2003) Laryngeal edema due to European bee-eater (Merops apiaster) in a patient allergic to honeybee
の論文ではミツバチの毒に対してアレルギー反応のある人がヨーロッパハチクイを食べてアナフィラキシーを起こしたとのこと。鳥のことも述べられていて
European bee-eater (Merops apiaster) is a colorful bird which eminently eats bees, wasps and hornets (250 bees per day).
Stings are frequently swallowed and found in their food remains.
BEs are apparently immune to venom; they show pain when stung but no other effect is evident.
との記載があり、出典は Cramp ed. (1985) "Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol IV. Terns to Woodpeckers"
で刺されても痛みを感じるだけでそれ以上の影響が見られないとの記載があるようである。
これだけ面白い話だと鳥類学者がもっと詳しく調べそうなものだが (少なくともハチクマ類を調べるよりはずっと簡単だろう)、調べた範囲ではこの医学論文が鳥の習性も含めて一番詳しく記載していた。
養蜂場を襲うヨーロッパハチクイも報告されている。
Galeotti and Inglisa (2001) Estimating predation impact on honeybees Apis mellifera L. by European Bee-eaters Merops apiaster L.
ハチクイが養蜂場を襲うとのことで、ヨーロッパの養蜂家の間で問題視されているとのこと。
ハチクイはミツバチの分布とよく一致していて、それに特化した進化を遂げたのではとのこと。イタリアでの養蜂場への影響の研究である。
ヨーロッパハチクイが問題視されてもヨーロッパハチクマが出てこないのは、ヨーロッパハチクマはやはり養蜂場を訪れないのであろうか (#ハチクマの備考参照)。
[視覚特性]
ハチクイ類とカワセミ類は網膜に中心窩と側方窩が存在する (タカ類など素早く動く獲物を正面で捕らえる鳥に多い)。カワセミ類は両眼視はあるがその視力は猛禽ほどではない [Moroney and Pettigrew (1987)
Some observations on the visual optics of kingfishers (Aves, Coraciformes, Alcedinidae)]。ただしカワセミ類と言っても多様で、ここではカワセミは調べられていない。
この文献にカタグロトビに中心窩と側方窩が存在する未発表?データも紹介されている。
[スズメ目が拡大する前にハチクイ類がスズメバチ類の擬態を促した?]
Dankova et al. (2025) Highly accurate Batesian mimicry of wasps dates back to the Early Oligocene and was driven by non-passerine birds
チェコで保存状態のよいスズメバチ類の 3300 万年前の化石がみつかり、現生のスズメバチ類と同様の色彩を持っていた。当時のヨーロッパにはまだスズメ目は少なく、スズメバチ類の擬態を促したのはスズメ目以前の系統、ここでは Coraciimorphae (ハチクイ類を含むブッポウソウ目の上位階層の名称)、Apodiformes (アマツバメ目) を想定しており、これらの系統が現生の飛翔性昆虫を捕食するスズメ目に対応する生態的位置を占めていた可能性を考えている。
(補足: この時代はタカ類適応放散ぐらいの時期で、ヨーロッパにはまだハチクマのような生態の種類もいなかったかも)。
[ヨーロッパハチクイのひなの捕食者対策]
ヨーロッパハチクイのひなのオレンジ色の嘔吐物が捕食者を追い払う可能性があるとのこと。
Parejo et al. (2013) Armed Rollers: Does Nestling's Vomit Function as a Defence against Predators? 主な食物であるバッタなどが植物から得た物質 (hydroxycinnamic and hydroxybenzoic acids などの phenolic acids; 植物の化学防御) を防御物質として用いている可能性がある。脊椎動物の口からの分泌物がモデル捕食者を忌避させる初の事例とのこと。植物由来物質がまずいらしい。
ヘビにも有効性が期待できるだろうとのこと。
ブッポウソウ目全体ではヤツガシラやカマハシ類の分泌物が有名で、#ブッポウソウ備考 [ブッポウソウ目と関連目の系統分類] に特にカマハシ科の情報を取り上げた。
△ ブッポウソウ目 CORACIIFORMES ブッポウソウ科 CORACIIDAE ▽
-
ブッポウソウ (まだ不詳だが種境界変更により学名が変わる可能性あり)
- 学名:Eurystomus orientalis (エウリュストムス オリエンターリス) 東の (東インド時代のジャワ島の) の広い口の鳥
- 属名:eurystomus (合) 幅広い口 (eurys 広い stoma 口 Gk)
- 種小名:orientalis (adj) 東の、東洋の (-alis (接尾辞) 〜に属する) 原義はジャワ島を指していた。備考参照
- 英名:Broad-billed Roller, IOC: Oriental Dollarbird
- 備考:
eurystomus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-ry- がアクセント音節と考えられる (エウリュストムス) 単語は eury-stomus と分かれる。
orientalis は "オリエンターリス"。
東アジアからオーストラリアにかけて分布。10 亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも calonyx (kalos よい、高貴な Gk) とされるが、世界の主要リストでは亜種 cyanicollis (cyaneus 濃い青の -collis 首の、喉の) のシノニムとされ亜種名として認めているものはない。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" にはこの亜種で記載されている。cyanicollis は東アジアからフィリピンの亜種。
「一部学名の変更の見込みについて」(2023年11月28日) にて cyanicollis に変更された。
orientalis の意味は東インド (India orientali)、すなわちジャワ島とのこと (Stresemann)。原記載。IOC 英名などに合わせて "東洋の" と広義に訳すと原義から離れる可能性がある。
calonyx の方の 原記載 (Sharpe 1890。当時は別種扱い)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Eurystomus orientalis をブッポウソウ、Eurystomus calonyx を和名空欄で Buzen, Tsushima, Loochoo Islands と記述していた。当時は Sharpe (1890) に従って別種扱い。
calonyx の名称が最近まで残っていたのは当時のリストの名残りかも知れない。日本動物大百科 鳥類 II (平凡社 1997) でもこの亜種が用いられていた。
[分類と学名の問題]
Johansson et al. (2018)
Phylogenetic relationships of rollers (Coraciidae) based on complete mitochondrial genomes and fifteen nuclear genes
の分子系統研究でモルッカブッポウソウ Eurystomus azureus 英名 Azure Dollarbird / Purple Roller がブッポウソウに内包されることが判明したが、現状全ての主要リストでブッポウソウに含まれていない。
ブッポウソウの亜種でこの研究で調べられたものは3亜種のみで、東洋の亜種は含まれていないので詳しい関係は不明。
Johansson et al. (2023) Patterns of phylogenetic diversification in the Dollarbird (Eurystomus orientalis) and Azure Roller (Eurystomus azureus) complex
でさらに研究が行われ、ブッポウソウとモルッカブッポウソウを2種とする現在の扱いは支持されない。この2種に 5-7 系統が存在し、複数種に分けられる可能性がある。
亜種 cyanicollis はこの中で北クレード (northern clade) に分類される。大変ややこしいことに現在の亜種 orientalis は複数のクレードに含まれることになり、種が分割された場合はどのクレードを orientalis と呼ぶか自明でなくなる。
orientalis の原記載がジャワ島を指す解釈を受け入れ、もしクレードがそのまま種になれば南クレード (southern clade) に Eurystomus orientalis が与えられるように思える。
現在は通常亜種 orientalis のシノニムとされる deignani Ripley, 1942 の 原記載 はインドシナ半島北部で繁殖し南へ渡る亜種との位置づけ。
これはこの研究では北クレードとなっているが、cyanicollis Vieillot 1819 より新しい。日本で使われていた亜種名 calonyx (Sharpe 1890) の原記載でヒマラヤで繁殖する亜種との位置づけだった模様。
これらを亜種でシノニムとみなすと現在のように亜種 cyanicollis が採用されることになっているが、もし北クレードを種とみなせば Eurystomus cyanicollis となりそう。ただし日本のサンプルは調べられていないので大陸と同じ亜種かどうかは確実でない。
亜種 laetior (インド南端とスリランカ) はこの研究では北クレードとなっている。北クレードとそれ以外はかなりよく分かれているので (日本のものが別種でなければ)、種に分離する場合は北クレードが最もふさわしいとなるのだろう。
海外の方から日本のブッポウソウの声が異なると指摘されることがあるが、これは北クレードと (海外の人にはより馴染みの) 南クレードあるいはオーストラリアまで分布する他のクレードとの違いを反映している可能性がある。おそらく声レベルでも別種相当なのだろう。
ブッポウソウ属 Eurystomus は小さな属で上記問題を除いて複雑でない。
アフリカの アフリカブッポウソウ Eurystomus glaucurus Broad-billed Roller と アオノドアフリカブッポウソウ Eurystomus gularis Blue-throated Roller および上述のアジアからオーストラリアの ブッポウソウ (+モルッカブッポウソウ) となる。
後述の Coracias 属との関係からはアフリカ起源でよいだろう。
[ブッポウソウ目と関連目の系統分類]
ブッポウソウ目 Coraciiformes になると状況がやや複雑で、この目を構成する科の分岐はかなり深く、化石情報も乏しいため科の間の関係があまり明確でない。Prum et al. (2015) は2系統に分け、{ハチクイ科 Meropidae + ジブッポウソウ科 Brachypteraciidae + ブッポウソウ科 Coraciidae} を一つのクレード、
{コビトドリ科 Todidae + ハチクイモドキ科 Momotidae + カワセミ科 Alcedinidae} を別クレードとしている。
Stiller et al. (2024) ([#鳥類系統樹2024]参照) でもこの結果が支持されることになった。分岐年代はそれぞれを目にするほどは古くないとの判断でよいのだろう。
古い時代のブッポウソウ目にはオオブッポウソウ、ヤツガシラ、カマハシ、サイチョウ科も含まれていたが、現在ではオオブッポウソウ目、キヌバネドリ目、サイチョウ目に分けられている。
Stiller et al. (2024) に基づいて関連する系統を示しておく。科の順序は Stiller et al. (2024) の順序に合わせてあるが、2つが並列で並ぶところ (例えばサイチョウ目の系統 1, 2 やその系統内の順序) は現状特に意味はない。複数種が解析されると今後検討されるだろう。
目和名は 山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類 に従っている。
科内の分類を示したところは、Boyd Afroaves III: Trogoniformes, Bucerotiformes & Coraciiformes と IOC による。
目間の系統がまだ確定的でなかったため Boyd のページでは分散しているが、現在ではタカ目はネズミドリ系統よりフクロウ目により近いと考えられる。タカ目、フクロウ目が大きいのでどこに入れるかで雰囲気がだいぶ変わる。
オオブッポウソウ目以下の目の順序はこれで確定でよいだろう。
サイチョウ目は有名な種類を多く含み、過去も属名が付けられていたが分類がかなり変わって属名との対応が変わってしまったものがある。例えばコサイチョウは過去 Tockus に含まれコサイチョウ属だった。属名和名が見つけられないもので複数種を含むものはそのままにしてある。属が3種までは全種掲載とした。
(Telluraves の系統 Afroaves。他にフクロウ目とタカ目が Afroaves に含まれるが系統関係はまだ自明でない)
ネズミドリ目 Coliiformes [Afroaves I]
ネズミドリ科 Coliidae
オナガネズミドリ属 (タイプ種アオエリネズミドリ) Urocolius
アオエリネズミドリ Urocolius macrourus Blue-naped Mousebird (アフリカ中部)
アカガオネズミドリ Urocolius indicus Red-faced Mousebird (アフリカ南部)
ネズミドリ属 (タイプ種セジロネズミドリ) Colius (4種、アフリカ中南部)
オオブッポウソウ目 Leptosomiformes
オオブッポウソウ科 Leptosomidae
オオブッポウソウ属 Leptosomus
オオブッポウソウ Leptosomus discolor Cuckoo Roller (マダガスカル)
キヌバネドリ目 Trogoniformes
キヌバネドリ科 Trogonidae
アフリカキヌバネドリ属 Apaloderma (3種、アフリカ) シマオアフリカキヌバネドリ属を分けることもあった
アジアキヌバネドリ属 (タイプ種インドキヌバネドリ) Harpactes (10種、インドから東南アジア)
ミミキヌバネドリ属 Euptilotis
ミミキヌバネドリ Euptilotis neoxenus Eared Quetzal (メキシコ)
ケツァール/カザリキヌバネドリ属 (タイプ種カザリキヌバネドリ) Pharomachrus (5種、中南米)
キューバキヌバネドリ属 Priotelus (2種、キューバとヒスパニオラ島) ヒスパニオラキヌバネドリ属を分けることもあった
キヌバネドリ属 (タイプ種ハグロキヌバネドリ) Trogon (20+種。分類による。北米から南米)
サイチョウ目 Bucerotiformes
(系統 1)
サイチョウ科 Bucerotidae
? 属 Lophoceros (7種、アフリカ中南部)
? 属 Tockus (10種、アフリカ中南部)
シロクロサイチョウ属 Berenicornis
シロクロサイチョウ Berenicornis comatus (マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島)
? 属 Horizocerus (アフリカ赤道中央から西部)
マミジロマメサイチョウ Horizocerus hartlaubi Black Dwarf Hornbill
シラガサイチョウ Horizocerus albocristatus White-crested Hornbill (Boyd では Tropicranus属)
コブサイチョウ属 Ceratogymna
クロコブサイチョウ Ceratogymna atrata Black-casqued Hornbill
キンコブサイチョウ Ceratogymna elata Yellow-casqued Hornbill
ナキサイチョウ属 Bycanistes (6種、アフリカ中南部)
オナガサイチョウ属 Rhinoplax
オナガサイチョウ Rhinoplax vigil Helmeted Hornbill (マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島、フィリピン)
サイチョウ属 Buceros
サイチョウ Buceros rhinoceros Rhinoceros Hornbill (マレー半島、スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島)
オオサイチョウ Buceros bicornis Great Hornbill (インド南西部、東南アジア)
アカサイチョウ Buceros hydrocorax Rufous Hornbill (フィリピン)
? 属 Anorrhinus
ビルマサイチョウ Anorrhinus tickelli Tickell's Brown Hornbill
アッサムサイチョウ Anorrhinus austeni Austen's Brown Hornbill (インドシナ半島大陸部)
ムジサイチョウ Anorrhinus galeritus Bushy-crested Hornbill (マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島)
(コサイチョウ属) Ocyceros (インド亜大陸、スリランカ)
ニシインドコサイチョウ Ocyceros griseus Malabar Grey Hornbill
スリランカコサイチョウ Ocyceros gingalensis Sri Lanka Grey Hornbill
コサイチョウ Ocyceros birostris Indian Grey Hornbill
カササギサイチョウ属 Anthracoceros (5種、インドから東南アジア)
ナナミゾサイチョウ属 Aceros
ナナミゾサイチョウ Aceros nipalensis Rufous-necked Hornbill (ブータンからインドシナ半島高地)
? 属 Rhyticeros (6種、ベンガルから東南アジア島しょ部、ニューギニア、ソロモン諸島まで)
? 属 Rhabdotorrhinus (4種、マレー半島から東南アジア島しょ部赤道近く)
カオグロサイチョウ属 Penelopides (5種、フィリピン)
ジサイチョウ科 Bucorvidae
ジサイチョウ属 Bucorvus
ジサイチョウ Bucorvus abyssinicus Abyssinian Ground Hornbill (アフリカ中央赤道以北)
ミナミジサイチョウ Bucorvus leadbeateri Southern Ground Hornbill (アフリカ東南部)
(系統 2)
カマハシ科 (モリヤツガシラ科とも呼ばれた) Phoeniculidae: Woodhoopoes
カマハシ属 Rhinopomastus (アフリカ中南部)
クロモリヤツガシラ Rhinopomastus aterrimus Black Scimitarbill
ミナミカマハシ Rhinopomastus cyanomelas Common Scimitarbill
キバシカマハシ Rhinopomastus minor Abyssinian Scimitarbill
モリヤツガシラ属 Phoeniculus (Wood Hoopoe を英名に含む, 6種、アフリカ中南部)
ヤツガシラ科 Upupidae
ヤツガシラ属 Upupa
ヤツガシラ Upupa epops Eurasian Hoopoe (ユーラシア、南で越冬)
アフリカヤツガシラ Upupa africana African Hoopoe (アフリカ赤道以南)
マダガスカルヤツガシラ Upupa marginata Madagascar Hoopoe
セントヘレナヤツガシラ Upupa antaios St. Helena Hoopoe (絶滅種)
ブッポウソウ目 Coraciiformes
(系統 1)
ハチクイ科 Meropidae
ムネアカハチクイ属 Nyctyornis
ムネアカハチクイ Nyctyornis amictus Red-bearded Bee-eater (マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島)
アオムネハチクイ Nyctyornis athertoni Blue-bearded Bee-eater (インドからインドシナ半島)
セレベスハチクイ属 Meropogon
セレベスハチクイ Meropogon forsteni Purple-bearded Bee-eater
ハチクイ属 Merops (27 種、ユーラシア、アフリカ、東南アジア、オーストラリア)
ジブッポウソウ科 Brachypteraciidae (マダガスカル)
ジブッポウソウ属 Brachypteracias
ジブッポウソウ Brachypteracias leptosomus Short-legged Ground Roller
ウロコジブッポウソウ属 Geobiastes
ウロコジブッポウソウ Geobiastes squamiger Scaly Ground Roller
ハシリブッポウソウ属 Atelornis
ルリガシラハシリブッポウソウ Atelornis pittoides Pitta-like Ground Roller
チャガシラハシリブッポウソウ Atelornis crossleyi Rufous-headed Ground Roller
オナガジブッポウソウ属 Uratelornis
オナガジブッポウソウ Uratelornis chimaera Long-tailed Ground Roller
ブッポウソウ科 Coraciidae
ブッポウソウ属 Eurystomus
アオノドアフリカブッポウソウ Eurystomus gularis Blue-throated Roller (アフリカ赤道部中部から西部)
アフリカブッポウソウ Eurystomus glaucurus Broad-billed Roller (アフリカ中部、マダガスカル)
ブッポウソウ Eurystomus orientalis Oriental Dollarbird
モルッカブッポウソウ Eurystomus azureus Azure Dollarbird
ニシブッポウソウ属 Coracias (9種、アフリカ、ヨーロッパ、南から東南アジアセレベスまで)
(系統 2)
コビトドリ科 Todidae
ハチクイモドキ科 Momotidae
カワセミ科 Alcedinidae
キツツキ目 Piciformes
(系統 1 Galbuli)
オオガシラ科 Bucconidae
キリハシ科 Galbulidae
(系統 2 Pici)
(系統 2a)
キツツキ科 Picidae
ミツオシエ科 Indicatoridae
(系統 2b)
ゴシキドリ科 Megalaimidae
アフリカゴシキドリ科 Lybiidae
アメリカゴシキドリ科 Capitonidae
オオハシ科 Ramphastidae
オオハシゴシキドリ科 Semnornithidae
ブッポウソウ目までの系統のほとんどは科レベルでもアフリカ由来と考えてよさそう。
この系統でネズミドリ目以外は穴に営巣する特徴があり、ネズミドリ目は他とかなり特徴が異なる。次のオオブッポウソウとともに遺存種的なものと捉えると理解しやすそう。ただしかつては世界に広く分布していた化石証拠がある (#ミサゴの備考 [近代的な陸鳥の進化])。
マダガスカルのオオブッポウソウ Leptosomus discolor Cuckoo Roller も英名に Cuckoo が入っている。
原記載が Cuculus discolor Herman, 1783 で最初はカッコウ類と考えられていたが後にブッポウソウ類に近いことがわかった。似ている種がないので無理にカッコウ類に入れてしまったようであまり似ていないとのこと。
フランス名由来の courol もあり、カッコウ coucou と Roller と同じ意味の rolle をつなげて短縮したものとのこと。vouroudriou のフランス名があり、Buffon が Histoire naturelle des oiseaux (1803) で使ったとのこと。
The roller that isn't: the Madagascan cuckoo-roller or Courol (tetrapodzoology 2010) に分類経緯の詳しい解説がある。Leptosomus < leptos 繊細な somatos 体 (Gk)。この目もかつて広く分布していた化石証拠があるが、マダガスカルのみ現存。生きた化石とも呼ばれる。
昆虫やトカゲを好んで食べ、カメレオンを多食とのこと (コンサイス鳥名事典)。食性はマダガスカルヘビワシ Eutriorchis astur Madagascar Serpent Eagle と結構似ているかも (#ハチクマ備考の [60年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)] 参照)。
#ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] のようにオオブッポウソウは多少の植物毒耐性があるかも知れない。これが確かめられれば食性面でカッコウ類との収斂進化も考えられるかも知れない。
サイチョウ目などの分布拡大の経緯は旧世界亜鳴禽類とよく似ている (#ズグロヤイロチョウの備考参照)。サイチョウ目も同じように分布拡大して東南アジアに達したのだろう。
サイチョウ目は大型種も多く、動物を食べるものもある。コンサイス鳥名事典から拾い上げておく:
・シロクロサイチョウ: トカゲ、小鳥なども食べる。鳴き声はカッコウに似る (ただし音程はかなり低い)
・キンコブサイチョウ: やかましく鳴くので列車鳥 (Train-bird) とも呼ばれる
・サイチョウ: 時に飛んでいる小鳥を捕食
・オオサイチョウ: トカゲ、ヘビ、ネズミや小鳥なども食べる
・クロサイチョウ Anthracoceros malayanus Black Hornbill は雑食で小鳥を食べる時は嘴で何度もかんで骨ごとこなごなに砕く。枝にこすりつけたりするが足は使わない。
・キタカササギサイチョウ Anthracoceros albirostris Oriental Pied-Hornbill トカゲ、ヘビ、小鳥、魚なども食べる
・シワコブサイチョウ Rhyticeros undulatus Wreathed Hornbill トカゲ、ヘビなど小動物も食べる
・ヒメシワコブサイチョウ Rhyticeros narcondami Narcondam Hornbill トカゲなどの小動物も食べる。ナルコンダム島 (アンダマン諸島でインドで最も東の島) のみ生息。断崖に囲まれた島で人が容易に上陸できず絶滅を免れた。
カマハシ科はヤツガシラ科と近縁と考えられ、種和名にもヤツガシラの名称を含んでいる。分子系統解析で近縁性が裏付けられた。
カマハシ類は洞営巣性で、巣はたいへん臭くヤツガシラ類同様に悪臭ある物質を捕食者に放つという。ミドリモリヤツガシラ Phoeniculus purpureus Green Woodhoopoe は悪臭が研究者の手に何時間も残るとのこと。Burger et al. (2004) Avian exocrine secretions. I. Chemical characterization of the volatile fraction of the uropygial secretion of the green woodhoopoe, Phoeniculus purpureus
(別リンク)
が分泌される物質の成分分析を行っている。短鎖脂肪酸、アルデヒド、トリメチルアミン、インドール、ジメチルスルフィドが揮発性悪臭成分となっているとのこと。他にも単なる羽毛の防水機能とは考えにくい成分もいくつか検出されている。ネコ類やトカゲ類の防御に有効との研究結果も記されている、また抽出物全体が羽毛を劣化させる細菌への抗菌作用を示すとの実験結果も得られているとのこと。
このように見ると防御に用いる悪臭物質の種類は思ったほど多くないのかも。
カマハシ科とヤツガシラ科が近縁なので同じような防御手段を発達させるのは自然な感じがするが、カワセミの巣も臭いとの話から、系統的にある程度類縁性のある種類では似た点があるのではと気になった。続きは#カワセミと#ハチクイに。メカニズムが似ているというよりは洞営巣性ゆえの共通性のように見える。
ブッポウソウの巣の記述を知ったので [ブッポウソウの巣は臭かった] の項目とした。
カマハシ科とヤツガシラ科に近いサイチョウ目のオオサイチョウ Buceros bicornis Great Hornbill では黄色の尾脂腺分泌物で羽毛を着色するとのこと Elder (1954) The Oil Gland of Birds に現れるが出典は Hingston (1933) でさらに原典がありそう。どこも孫引きばかりだが、特に悪臭がある記述は見られない。
ジブッポウソウ科は古い分岐の属のみで遺存種的なグループで、ハシリブッポウソウ属は地上性。
ルリガシラハシリブッポウソウ はカエルも食べる (コンサイス鳥名事典)。
ブッポウソウ科 Coraciidae もアフリカ由来と思われ、ブッポウソウ属 Eurystomus はモルッカやオーストラリアまで分布を広げたが中東付近の中間の分布が消失してアフリカとアジア・オセアニアのものが残ったのだろう。
ニシブッポウソウ属 Coracias はブッポウソウ属とは独立に同様に分布を広げてセレベス島まで至ったよう。ニシブッポウソウのみが長距離を渡り、南から東南アジアのものはあまり渡りをしないためにブッポウソウのように日本まで分布を広げることはなかったと見られる。
この属のうちインドブッポウソウ Coracias benghalensis Indian Roller はトカゲ、サソリなど小動物も食べ、時には小鳥も食べることがあるとのこと。ライラックニシブッポウソウ Coracias caudatus Lilac-breasted Roller も時にカエル、トカゲを食べるとのこと (コンサイス鳥名事典)。
Frederiksen et al. (2023) (#アマツバメ備考の [渡り鳥における磁気定位]) の Cry4 遺伝子を見ると系統の古い枝で Cry4 が失われているものはなかったが、サイチョウ目では比較的不完全、ブッポウソウ目は大部分保持しているがカワセミ科で一部不完全な模様。
ハイイロコサイチョウ Lophoceros nasutus African Grey Hornbill は乾季・雨季で短距離の渡りを行うとのこと (コンサイス鳥名事典)。
ブッポウソウ目は基本的には科レベルの系統まで渡り能力を持ったまま進化して分布を広げたが、熱帯の留鳥となった一部で失われたシナリオが考えられる。ハチクイ科は完全な渡りを行う種の他に部分的渡りを行う種類もいくつかある。
ミツオシエ類はハチの蜜蝋を食べる視点から #ハチクマの備考 (ハチ防御や臭気について)、托卵性から #カッコウの備考、兄弟殺しから #イヌワシの備考といろいろな場所に出てくるが、ハチの巣を壊すのにヒトなど他の動物を頼りにする種類があることも面白い。日本の種ではないのでここでは単独で出てくる機会が少ないが、
Lloyd-Jones et al. (2025) To Bees or Not to Bees: Greater Honeyguides Sometimes Guide Humans to Animals Other Than Bees, but Likely Not as Punishment
アフリカの現地の人によればノドグロミツオシエ Indicator indicator Greater Honeyguide は人をハチではなくもっと大型で危険な動物のところに誘導することがあって、過去に人が期待通りの働きをしなかったため鳥が罰として与えるとの伝承があるとのこと。
この研究ではさすがに罰ではなくハチの巣のある場所の記憶違いによるものではないか、しかし人が罰として文化的に解釈してきたことで、ミツオシエにとっては有利に働く行動になっている可能性も考えられるとのこと。もしかすると人の推論能力の高さが乗っ取られている (?)。
なおノドグロミツオシエがラーテルを誘ってハチの巣を壊す話は神話であるとのこと。Ratel/Honey Badger (Mellivora capensis) Fact Sheet: Taxonomy & History (San Diego Zoo Wildlife Alliance Library)。
1785 年に最初の報告 (Sparrman) があって何度も述べられてきているがそれら文献に十分な根拠はないとのこと。夜行性のラーテルを誘うとは考えにくい [Dean et al. (1990) The Fallacy, Fact, and Fate of Guiding Behavior in the Greater Honeyguide]。
wikipedia 日本語版はこのようなことを探るにはほぼ無力と考えた方がよく、好物の蜂蜜を巡ってミツオシエ科の小鳥と共生関係にあると書かれている (2025.6 時点)。
[英名・中国名の由来]
英名は単に Dollarbird とすることも多い [Brazil (2009), Avibase, Clements 2024 など]。Oriental を付けるのはモルッカブッポウソウの Azure Dollarbird (Azure Roller の英名を使えばブッポウソウは Dollarbird で構わないことになる) と区別するためだが、もし同一種と判断されれば統合される可能性もある。
AviList ではこの2種に Oriental Dollarbird と Azure Dollarbird の英名を用いている。
Dollarbird を使わない Eastern Broad-billed Roller の別名もある。
上述の Johansson et al. (2023) の結果から示唆されるように種が複数に分割されれば英名も変わる可能性がある。
英名の由来は翼に硬貨のような模様があるため (wiktionary)。
中国名は三宝鳥で、これは和名に由来する。仏・法・僧をもって三宝となす (wikipedia 日本語版)。福井・チャン (2003) Birder 17(8): 68-69 に解説がある。
[ブッポウソウの巣は臭かった]
「甦れ、ブッポウソウ」(中村浩志 山と渓谷社 2004) pp. 55-57 に「悪臭ただよう巣穴」の項目があり、巣穴から卵の殻なども運び出さず湿度の高い時期に繁殖するのでとても臭いとのこと。ひなの糞も黒いドロドロしたものでつかまれた時に出る糞は強烈にくさいとのこと。中村氏は「捕食者に襲われた時この糞をすることで、捕食を回避する効果があるのではと考えたくなるほどです」と書かれている。
簡単に調べた範囲では Eurystomus 属で記述された論文は見つけられなかったが、カマハシ類やヤツガシラ類との系統的近さを考えると十分考えられる機能と思われる。
洞営巣性ならでは特別な捕食者防御対策が必要で、フクロウ類の盲腸糞もあるいは同じような役割を果たすのではと思えてきた。フクロウ類は一般的には捕食者の位置づけで、論文を探してもそのような視点のものがなかなか見当たらない (飼育者が気にする程度)。すなわち捕食者の糞のにおいに捕食される側がどのように反応するかばかり調べられている。
鳥のにおいについて関心が持たれるようになったのは比較的最近のことなので有名な事例以外は意外に知られていないのかも知れない。
少し関係しそうなところでは、アナホリフクロウ Athene cunicularia Burrowing Owl が巣穴に主に草食獣の糞を敷き詰めるのは、かつてはひなのにおいを隠すための考えがあったが (草食獣の糞ならばどこにでも落ちているので捕食者は無視する理屈となるのだろう)、巣内の環境を整えたり昆虫をおびき寄せるのに役立っているとの研究があるとのこと (wikipedia 英語版より)。
文献は Levey et al. (2004) Use of dung as a tool by burrowing owls とのこと。道具を利用して昆虫をおびき寄せるのに役立つ例として取り上げられたもの。独立に考えられたものかどうかは不明だが、ハチクマが巣にカエルの死体を置いておとりに使うアイデアも同様のものだろう。動物の道具使用がテーマとなって競い合って報告された時代背景も考えられる。Nature に出た割にはあまり大した後続研究がない。
[ブッポウソウの翼下面の発色]
藤井 (2021) Birder 35(3): 36-37 でブッポウソウの羽は下面も青いことが紹介されている。
これはブッポウソウの含まれるブッポウソウ目 Coraciiformes に色鮮やかな鳥が多く、例えばハチクイ属などは下面を見ても鮮やかなことに対応しているように思える。
ディスプレイの時に rolling flight display (以下参照) を行うために両面に色彩があることが有利なのではないだろうか。
Dollarbird ディスプレイ飛翔の際の側面の鮮やかな色彩が見える。とまっている時の方がむしろ色がそれほど目立たない。
飛翔時は翼の "dollar" の白斑も上面・下面ともよく見える。
[ニシブッポウソウ]
小林 (2021) Birder 36(2): 44 に 2021年11月石垣島に渡来したニシブッポウソウの記事がある。これは Coracias garrulus European Roller とブッポウソウとは属レベルで異なる。ブッポウソウ科で和名のあるすべての種で名称にブッポウソウが含まれている。
Coracias は korakias (Gk) おそらく ベニハシガラス類か < corax ワタリガラス でいずれにしてもカラスを連想させることから。ブッポウソウ目 Coraciiformes はこの和名となるが、(英語でも同様だが) 語源との対応はあまりよくない。
英語ではブッポウソウ科は roller が一般名だが、"転がる" の意味はローラーコースターなどと同じでアクロバティックな飛翔の特性に由来する。ハトの品種にも Roller があって、辞書を引くとこちらが出てきたりする。カナリアにも同名の品種がある。
OED によればニシブッポウソウを指す Roller の用例は 1678 年の Ray, translation of F. Willughby, Ornithology に現れるとのことで、1752 年の用例ではヨーロッパで最も色彩豊かな鳥とある。
dollar-bird は 1847 年オーストラリアの鳥に対して Leichhardt, Journal of Overland Expedition in Australia で使われたもの (OED)。Roller の方が歴史はずっと長い。
[ブッポウソウの分布]
「動物の世界」2版 24 (日本メール・オーダー 1986) のブッポウソウの項目 pp. 3247-3248 (浦本・樋口) では原著が英国で出版されたものであるためニシブッポウソウとともに紹介されている。
ニシブッポウソウの空中ディスプレイははでなものだが、日本のブッポウソウのディスプレイはこんなにはでなものではないとある。
日本で繁殖する多くの鳥と同様に、ブッポウソウが山地で見られることが多いのは、低地にはもはやよい自然林がのこっていないからである、と説明されていた。
当地 (京都の低地) ではおそらく繁殖していないが声は時々記録している。2025.5.25 の夕方にゲッ、ゲッ、... と鳴きながら飛んで行ったのは本種と考えられる (近年はイソヒヨドリが増えて紛らわしい声が多くなったが)。翌日も少し期待したが出会いはなく通過中か。
過去の記録を見て早かったのは 5/22 の事例があり、当地では6月の記録が中心となっている。繁殖地でペアを作ることができなかった個体の移動途中だろうかと考えている。
低地でもこれだけ気配があるのは、本来低地に生息していてもおかしくない種類なのだろう。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 67 (1946 年初出) のキツツキの項目で興味深い話が記されている。
戦後に奥羽本線の坂谷峠では鉄道橋の電柱がことごとくキツツキに孔をあけられ、キツツキが目の敵のように扱われていたとのこと。孔をコンクリートで埋めたりしたが弱まった電柱は風雪で折れてしまうので鉄板で覆うようにして解決したとのこと。
原因調査を依頼されて中西氏の友人が調べたところ、一帯の大木はことごとく戦時の犠牲となって伐採されつくしていたとのこと。木製電柱ぐらいしか営巣木に使えなかったらしい。よくこんな山奥の鉄道の難所まで伐採したものだ。
この話は東北地方だがブッポウソウが数を減らしたのも全国的に同じ原因だったのだろうなあと読んで感じた。浦本・樋口氏の指摘する通りだったのだろう。
なお中西氏は別のところで軽井沢などに比べて比叡山 (京都/滋賀) の鳥の少なさを指摘されていた。
第二次大戦の戦時供出により、列島の山林は再び大規模伐採を経験しますが、その後の高度経済成長期には林業活発化のため無計画なスギ林の植林が大規模に展開し (中略) 比叡山は、歴史的環境としては重要ですが、自然環境としては社会的・国家的に認知されなかったので、政策的な回復はなされなかったのでしょう、との説明がある (上智大学の北條勝貴 全学共通日本史 2015 の質問回答ブログから)。
京都の野鳥を知る者には周知のことだが参考までに。比叡山は世界文化遺産で比叡山鳥類繁殖地は天然記念物となっているが、来て見ていただければ碑のあるあたりは挙げられている鳥の種類とともに鳥の視点からはなかなか虚しい。観光目的ならばともかく、この付近で本格的に山の鳥を期待するならば別の場所がよい。本来ならばブッポウソウが繁殖してもまったくおかしくない所であるが。
浦本・樋口氏の指摘された時代と比較すると記述後さらに 50 年経過してもブッポウソウの自然回復は起きなかった模様。もっとも世界的規模では特に懸念のない種類で日本の固有亜種でもないので、人為理由で分布が縮小しただけと考えればそれほど気にすることもないのかも知れない。100 年ぐらい待てば戻ってくるかも。
[ブッポウソウの胃石]
ブッポウソウが貝殻や金属片を胃石として使っていることの発見経緯は「甦れ、ブッポウソウ」に詳しい。第 7 章「奇妙な物」(pp. 77-101)。
中村・田畑 (1990) ブッポウソウの雛の食物。
ツバメの親はヒナに貝殻を運ぶ (神山和夫 バードリサーチニュース 2016) にも関連情報がある。
中村・田畑 (1990) の論文で引用されている (中村氏の本でも紹介されている) ヨタカ目での胃石の論文は Jenkinson and Mengel (1970) Ingestion of stones by goatsuckers (Caprimulgidae) で読める。
同じく紹介されているアリスイについては#アリスイの備考にまとめた。
△ キツツキ目 PICIFORMES キツツキ科 PICIDAE ▽
-
アリスイ
- 学名:Jynx torquilla (ユンクス トルクィルラ) 首をねじるアリスイ
- 属名:jynx (f) アリスイ (備考参照)
- 種小名:torquilla (adj) 首をちよっとねじる (torqueo (tr) ねじる -illa (指小辞) 小さい)
- 英名:Wryneck, IOC: Eurasian Wryneck
- 備考:
jynx の語源は iunx, iungos アリスイ (Gk) < iuzo 叫ぶ < iu 驚きを表す声 (Gk)。ギリシャ神話では Iynx は歌コンテストで Muses に破れて鳥に変えられた (The Key to Scientific Names)。
1音節なのでアクセントの問題はないがわかりやすいように表記のみ "ユンクス" としておく。
jynx は iynx の別綴りで、冒頭は2重母音風にしてもよい (イユンクス)。
torquilla はおそらく -il- にアクセントがあると思われる (トルクィルラ)。語末の意味や発音上の特性は頻繁に使われる -cilla などと同様。
川口 (2020) Birder 34(6): 54-55 で Jynx に首をひねる意味があるように解説されているが、アリスイは指していたものの語源的には関係なさそう。むしろ torquilla の方と誤解されたのではと想像する。
日本語の "ジンクス" に相当する意味はまずラテン語 iynx 由来の jynx が charm or spell, passionate yearning (魅了する、魔法にかける、熱望) の意味で比喩的に使われたもので、さらに意味が派生して jinx (悪い方の魔法にかける、そしてさらに悪運をもたらすもの) となったアメリカ口語から (wiktionary)。
torquilla は中世ラテン語で Gaza (1476) がアリスイに用いた語とのこと。Brisson (1760) はフランス語で Torcol と呼び、Torquilla を Jynx torquilla Linnaeus, 1758 を指すものとして用いた。属名として取り扱われる (The Key to Scientific Names)。
種小名から属名への昇格のため、当時の習慣に従って新しい種小名も用いられた (#ノスリの備考参照)。Torquilla jynx Schaeffer, 1789 (参考), Torquilla vulgaris Blyth, 1836 (参考)。
参考によれば、Zigzag Wryneck の英名もあったとのこと。
[他言語のアリスイの名称]
学名、英名ともに行動に由来する。ドイツ名も同じく Wendehals でドイツ統合時代に旧東ドイツ時代で特に信念なくその時の政治情勢に合わせる人を指す言葉として使われた [wikipedia ドイツ語版 Wendehals (DDR) の項目]。それ以前から日和見主義者を指す用語として存在していたとのこと。
世界の他言語でも学名、英名と同じ意味を用いているものが多い。ポーランド語、ウクライナ語などスラブ言語の一部では「短い頭」。中国語の名称の一つは地啄木でわかりやすい。
日本語と同じ意味を用いているものにカタルーニャ語 (formiguer) があった。
スウェーデン語の goktyta の意味の見当が付かなかったが、声を聞くと春を告げるカッコウ (gok) がまもなくやって来ることに由来すると言われるとのこと (wikipedia スウェーデン語版より。アリスイは夏鳥でヨーロッパでは日本よりカッコウの渡来はずっと早い)。-tyta はおそらく音声 (tjuta) を指すものか。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) によれば英語に Cuckoo's Mate の名称があるそうで、これはスウェーデン語の goktyta 語源にも対応する。さらにある別名の Snake Bird は特に説明を必要としないだろう。
ポーランド語の別名に dudek があり、これは通常ヤツガシラを指すとのこと。あまり区別されていなかったのかも。
マルタ語で furrax is-summien でアラビア語由来でカニのようなウズラとのこと。
[分類と系統]
ユーラシアに広く分布し (日本では北海道と東北地方の一部で繁殖)、北方のものは冬に南方に渡る。世界で6亜種が認められている (IOC)。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では日本で記録されるものは2つで、japonica 亜種アリスイとされるが、亜種として認める世界のリストはごく少数。
記載時学名 Yunx japonica Bonaparte, 1850。
Schlegel による日本産アリスイがわずかに違うと別種として名付けたもの。
同様の例は#ハシブトガラスにあり、こちらは亜種として認められている。Bonaparte は種小名に国名を繁用しているので大した意味があったわけではないだろう。
"Fauna Japonica" では Les torcols. Jynx. でヨーロッパで普通のアリスイと違いがないとしていた。Pallas がカムチャツカ近くまでのシベリアで、Rueppell がエジプトやアラビアで記録したものも同じものが広く分布していると判定していた。Rueppell や Vigors がアビシニアやアフリカ南部で記録したものは同属で2つの別種扱い (現在のムネアカアリスイ)。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire の p. 158 に Bonaparte の記載についてコメントがあり、基亜種より小型で淡色と主張しているが Seebohm は根拠が認められないと判定。
もう1亜種は chinensis シベリアアリスイとなっている。
Iynx torquilla chinensis Hesse, 1911。
世界で一般的な扱いに従えばこの2亜種は同一となる。H&M4 の記述によれば Dickinson (2003) は japonica を外し (omitted)、Winkler and Christie (2002) は亜種記載と認めなかった (not recognized) とのこと。
Bonaparte (1850) の方が Hesse (1911) より早いので両者をシノニムの関係とすれば Bonaparte (1850) の方に先取権があるはずだが世界の主要リストでそうなっていないのは Bonaparte のものはタクソンの適切な記載として認めないとの判断となっているのだろう。
Jynx 属には世界でもう1種アフリカに局地的に分布するムネアカアリスイ Jynx ruficollis Rufous-necked Wryneck で、ディスプレイの際は尾を上げ、喉から胸の赤い部分を誇示するとのこと (wikipedia 英語版より)。
Jynx 属はキツツキ類の中で最も早く分岐したグループ。
我々が通常目にするキツツキ類との間に位置するグループに piculets (Picumninae 亜科、Sasiinae 亜科) があるが新世界が中心、アジア・アフリカに少数のグループ。アリスイと我々が通常目にする新しく分岐したキツツキ類の間の系統が大きく飛んでいるためアリスイの特異性が一層強調される形になっている。
[アリスイの首ふり行動]
種小名 torquilla は Gaza (1476) がアリスイに対して与えた名前で、(捕獲時の) ヘビのような奇妙な頭の動きを表す (The Key to Scientific Names)。巣で外敵に襲われた場合はヘビのようなシューという脅しの声 (hissing sounds) を出すと言われるが、捕獲時に奇妙な頭の動きをする時はこの声は聞かれないという。
キツツキ類の中で自ら巣穴を掘らない数少ない種類。キツツキ類の行うドラミング (drumming) というよりもタッピング (tapping) の音を出し、ドラミングでなわばりを誇示することはない
[Gerard Gorman (2022) "The Wryneck: Biology, Behaviour, Conservation and Symbolism of Jynx torquilla" の書評より抜粋]。
捕獲時以外で捕食者に対する首ふり行動を行うかを確かめた実験が行われているが、少なくとも巣の近くに捕食者がいるだけでは首ふり行動をしないことが分かったと述べられている [生態図鑑(要約版)アリスイ バードリサーチニュース 2015年8月 著者:橋間清香・加藤貴大。加藤・橋間 (2016) Birder 29(12): 70 にも記事がある]。
wikipedia 英語版によれば時には目を閉じてぶらさがり、死んだふりをする (擬傷行動) こともあるとのこと [Witherby, H. F., ed. (1943) Handbook of British Birds, Volume 2]。
#ハヤブサの備考 [ハヤブサ類の免疫の特殊性] 免疫と造巣習性の関係? の考察で紹介した文献の再掲:
Rohwer et al. (2025) The Evolution of Using Shed Snake Skin in Bird Nests
北米の研究で巣にヘビの皮を持ち込むのは圧倒的に洞営巣性の鳥に多かったとのこと。実験結果からヘビの皮があると捕食が避けられるが開けた巣を造る種類ではそうではなかったとのこと。洞営巣性には別の苦労もあるらしい。
Fancy birds decorate nests with a natural pattern: snakeskin (Nature news)。
Some Birds Adorn Their Nests With Snakeskin to Scare Off Predators, New Study Finds (Audubon の記事)。
洞営巣性の鳥の巣を捕食するのは小型の哺乳類が中心で、ヘビに捕食される種類が多いためではないかと推測している。アナホリフクロウはガラガラヘビに似た音を出す。
上記行動と北米の研究から想像するとアリスイの行動は基本的に哺乳類対策だろうか。北米にはアリスイはいないのでこの研究対象になっていない。
派手な模様でなく地味なヘビに似せているのは (もちろん猛禽類にも目立ちにくいだろうが) 巣での捕食を避けるため哺乳類の色覚に対応したものかも知れない。
アリスイが主に北方林に渡りをするのは食物が豊富に発生するのが主要因だろうが、あるいは巣を狙う捕食者が相対的に少ない可能性も気になった。
アフリカで留鳥として繁殖するムネアカアリスイ (Jynx はアリスイと2種のみ) があるので直接の説明にはならない気がするが、ムネアカアリスイの分布はいくつにも分断されているのでアフリカには "住みにくい" 地域もあるのかも知れない。新天地を求めて渡りをするようになったのがアリスイと考えればわかりやすい感じがする。
分布的にはヤツガシラとアフリカヤツガシラ (IOC 15.1 で同種となる見込み) の関係に似ている。こちらも洞営巣性 (どちらも Eucavitaves の系統) で、ヤツガシラは特異な容貌かつ激しい対捕食者反応を示す点も似ている。(アフリカ)ヤツガシラはアフリカでアリの巣の穴に営巣するとのこと (コンサイス鳥名事典)。アリスイの食物は存在しそうに思える。
形態・色彩的な点からヤツガシラを猛禽類が嫌うか議論した研究はあって#ヤマセミ備考の [派手な色彩の鳥はまずい?] の Ruiz-Rodriguez et al. (2013) Does avian conspicuous colouration increase or reduce predation risk?。
むしろ哺乳類捕食者の方を念頭に置く方がよいのかも知れない。この項目がヤマセミ (やはり Eucavitaves) に登場したのは偶然ではなかったかも知れない。
さてさて、#ミサゴ備考の [ミサゴは不器用?] でカワセミ類の採食様式がなぜサギ類のようにならなかったのかを考察する途中で、洞営巣性の Eucavitaves ではそもそも長い首は邪魔だったのではとの解釈を行った。アリスイの首が比較的長く首ふり行動を行うことと、アリスイがキツツキ類の中で古い系統であることは無関係ではないのではないかと考えてみた。
キツツキ類の祖先系統はおそらく洞営巣性で、捕食者に激しい防御反応を示す必要があっただろう。アリスイのヘビのように見える行動はまさしくそのような捕食者対策が考えられる。
キツツキ類の祖先系統はおそらく簡単に手に入るアリなどの昆虫を食べていたのだろうが、洞営巣性ゆえ捕食者対策としてアリスイのような行動を進化させ、そのために首ふり能力を進化させて比較的長い首と強力な首の筋肉が有利になったのではないだろうか。付随的に樹皮を剥がして昆虫を食べるのは容易に予想される採食様式の拡張であるが、その時に比較的長い首と強力な首の筋肉がうまく役立ったのではないだろうか。
アリスイの tapping からドラミングが発達すれば採食とは必ずしも関係なく性・社会選択によって強力な嘴や首の筋肉が進化する可能性も考えられる。そして樹皮の下の虫を食べる行動がさらに有利となった。いかがだろうか。
[アリスイのドラミング]
アリスイがドラミングをするかは長年の課題であり、日本の書籍では「日本野鳥大鑑 鳴き声420」(小学館 2001) では「まれにドラミングも行うようだ。北海道在住の田辺至氏が録音した本種のものと思われるドラミングは、アカゲラやヤマゲラのものよりテンポが遅い」との記述があり、この記載に関わる記事が Birder 2014年6月号 (p. 44) にアリスイはドラミングをするかの記事がある (松田道生)。
「山溪ハンディ図鑑 日本の野鳥」の上田秀雄氏による音声関連の解説で抱卵交代の際にドラミングをする記載がある。
海外でもベラルーシのオンライン図鑑で巣でまれにドラミング (barabannaya drob' 本文はロシア語) をするとある。
先述の Gorman は Turner and Gorman (2021) The instrumental signals of the Eurasian Wryneck (Jynx torquilla) という論文を出して "tapping" と記述しており、この音は樹洞の中やその入口で記録された。
大きな音ではなく、ペアの間のコミュニケーション以外では使われず、ドラミングと呼べるぐらいの速さだが短い2例の tapping があったが、意義は明らかでない。と記載している。真にドラミングと呼べるものではないとの見解を示している。この論文ではソノグラム表示のみで実際の音源は公開されていない。Ruge (1988) "Der Wendehals" も同様の見解を示しているとのこと。
キツツキ類のドラミングの系統進化については Garcia et al. (2020) Evolution of communication signals and information during species radiation
で解析されている。この論文ではアリスイはドラミングをしない方に分類されている。
採食やつつく時に出る音の外適応 (exaptation) と儀式化が進み、ドラミングが進化した経路を考えている。
アリスイ類を含むキツツキ類の系統は 2250 万年前ぐらいに出現したと推定されている [cf. Shakya et al. (2017) Tapping the woodpecker tree for evolutionary insight]。
キツツキ類の多くの系統が現れたのは 1500-1000 万年前ぐらい。
キツツキ類の世界分布については Vergara-Tabares et al. (2018) Gone with the forest: Assessing global woodpecker conservation from land use patterns
の図が参考になる。アリスイ以外のいずれのキツツキ類も成熟森林が必要で、長距離を移動するのはやはり得意でないようで過去に陸続きにならなかったような地理的障壁があるとそこで途切れてしまうよう。
ニューギニアからオーストラリア、ニュージーランドにキツツキ類が生息しないのはこの図からも理由がわかる。
日本も大陸から離れているため種多様性は低い。東南アジアと南米に種多様性のホットスポットがあることがわかるが東南アジアは森林消失速度が早く世界的にも保全上最も懸念される地域。
[キツツキ類の甘味知覚]
鳥類全般での甘味の知覚の進化については#メジロの備考参照。
Cramer et al. (2022) A single residue confers selective loss of sugar sensing in wrynecks
によればハチドリ類やメジロ類と同様、キツツキ類でも旨味受容体が変化して甘みを知覚できるようになった。通常のキツツキ類は果実を含む甘いものも食べるので甘みを知覚できることは意味がある。
アリスイはアリ類のスペシャリストであって甘みを知覚する必要がなくなり、1アミノ酸の変異のみで甘みの知覚を失ったとのこと。
[アリスイの胃石?]
#ブッポウソウの備考 [ブッポウソウの胃石] に登場し、「甦れ、ブッポウソウ」(中村浩志 山と渓谷社 2004) でブッポウソウ同様の胃石と解釈されている。
記述した文献は Terhivuo (1977) Occurrence of strange objects in nests of the Wryneck Jynx torquilla、
Terhivuo (1983) Whydoes the Wryneck Jynx torquilla bring strange items to the nest?。
Terhivuo (1983) 自身は胃石とは考えておらず、ひなに食物として与えるためでもなく、誤って取り込まれたものだろうかと議論している。Terhivuo のこれら以前の論文もいくつかあってオンラインで読めるので気になる方は引用文献から参照いただきたい。アリスイの専門家の Gorman のモノグラフにはきっと書いてあるのだろうが。
近年はあまり話題になっている形跡が見当たらなかったが、The Eurasian Wryneck (Kai Pflug, 10,000 Birds 2023) に体にカタツムリが付着したまま生きたまま運ばれているアリスイの映像が紹介されている。
このページで Terhivuo (1983) の論文と推論にも言及されており、このページの著者は Terhivuo (1983) の解釈には納得せずおそらくこのように運ばれたものであろうと考えている印象を受ける。
同じくこのページで知ったが鳥 (おそらく死んだシキチョウ Copsychus saularis Oriental Magpie Robin) を食べる報告がある:
Madhav and Victor (2011) Wryneck Jynx torquilla feeding on bird in sundarbans, West Bengal, India。
鳥を殺す能力があるか、ひなに与えるかなどは何とも言えないとのこと。
Pflug (2023) のページでは記載順からカタツムリなども食物として利用してもおかしくないとの示唆を与えているものではないかと考えられる。このページの記載から想像すると新しい研究はなされていないかも。
-
チャバラアカゲラ
- 学名:Dendrocopos hyperythrus (デンドゥロコポス ヒュペリュトゥルス) 腹の赤い木を打つ鳥
- 属名:dendrocopos (合) 木を打つ鳥 (dendro 木 kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 種小名:hyperythrus (合) 腹の赤い (hyp- (接頭辞) 下の erythros 赤い Gk)
- 英名:Rufous-billed Woodpecker
- 備考:日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本で記録された亜種は subrufinus (少し金色の sub 下の rufinus 金色の) とされ極東から中国南東部の亜種。
-
コゲラ
- 第8版学名:Yungipicus kizuki (ユンギピークス キズキ) アリスイのようなキツツキ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Dendrocopos kizuki (デンドゥロコポス キズキ) 木を打つキツツキ
- 第8版属名:yungipicus (合) Yunx (アリスイ) 属と Picus (キツツキ) 属の合成
- 第7版属名:dendrocopos (合) 木を打つ鳥 (dendron 木 kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 種小名:kizuki (外) キツツキ
- 英名:Japanese Pygmy Woodpecker
- 備考:
yunx は#アリスイ参照。picus は冒頭が長母音でアクセントがある。
dendrocopos は#アカゲラ参照。
kizuki は原音を考えると u を長母音としにくく、短母音で冒頭アクセント (キズキ) が適切と考えられる。
[英名由来は以下に追記修正あり。保存のため残しておく] 英名の Japanese Pygmy Woodpecker はおそらくチャガシラコゲラ Yungipicus nanus Indian Pygmy Woodpecker に対応して与えられたもの。
こちらは記載時学名 Picus nanus Vigors, 1832 とそのまま "小人のキツツキ" で当時はこの種に Pygmy Woodpecker が与えられていたと思われるが、コゲラが Picus kizuki Temminck, 1835 が記載されたためそれぞれ地名を冠したと想像できる。
現在はコゲラの方を Pygmy Woodpecker と簡略化している (いた) リストもいくつかある (Clements が一時期用い、eBird も 2019 年まで用いていた)。おそらく日本以外にも分布するためであろう。
過去に別種を指していた可能性があったりこの種だけが Pygmy Woodpecker と修飾なしで呼ばれるのは不自然など変更に慎重な理由はあるかも知れない。過去に改名がなされたり現在も Avibase の見出しに使われているので、英名に Japanese が付くケースには多少敏感になった方がよいのかも。
他言語でも日本を冠しているのはフィンランド語などごく少数。
[英名の由来など]
その後さらに情報を見つけ、LeCroy and Dickinson (2001) Systematic notes on Asian birds. 17. Types of birds collected in Yunnan by George Forrest and described by Walter Rothschild を手がかりとして、関連のある以下の学名があったことを知った。
・Picus pygmaeus Wagler, 1827 (参考) 基産地 insulis moluccia。これは重複に気づいて Picus variegatus と変更された。しかしこれまた Picus variegatus Latham, 1790 の用例があって無効。
Eyton (1845) の用いた auritus の種小名があって、現在有効な学名はハイガシラコゲラの亜種となっている Yungipicus canicapillus auritus [Gould (1883) 参考]。
・Picus pygmaeus Vigors, 1831 (参考) 基産地 Himalayas。
・Picus pygmaeus Lichtenstein, 1823 (参考) 基産地 Brazil (現在のシロボシヒメキツツキ Picumnus pygmaeus Spotted Piculet) がすでに使われていたので上記2つは無効。
Picus pygmaeus Vigors, 1831 は重複に気づかずそのまま英名の Pygmy Woodpecker の語源となっていた。参考: Greenway Jr. (1943) Oriental Formes of the Pygmy Woodpecker。
この種は現在では分離されてハイガシラコゲラ 現在の学名で Yungipicus canicapillus Grey-capped (Pygmy) Woodpecker となっているがコゲラと同種とされていた時代があり、当時は有効な学名と考えられていた Picus pygmaeus Vigors, 1831 の記載の方がコゲラよりも早いためにまとめる場合にはコゲラが当時の Picus pygmaeus の亜種となり、種英名が Pygmy Woodpecker となっていた次第。
その後学名が無効とわかって逆にコゲラの方が早い記載でハイガシラコゲラなどはコゲラの亜種扱いとなったが英名はそのまま引き継がれた。その後の分割で Japanese が付けられた次第のよう。
ハイガシラコゲラの最も古い有効な学名が Picus canicapillus Blyth, 1845 でコゲラの記載 (1835) よりも遅くなったため Pygmy Woodpecker は英名はコゲラの方に譲ったのかも。
LeCroy and Dickinson (2001) (p. 190) にも Picoides (kizuki) canicapillus kaleensis (Swinhoe, 1863) の表記 (Short 1982) が現れ、どちらを早いとみるか難しい問題だったらしいことが想像できる。
チャガシラコゲラの記載 (1832) の方が早いので問題が起きそうにも思われるが、Picus pygmaeus Vigors, 1831 が有効と考えられていた期間が長く、それより1年遅いチャガシラコゲラが基亜種として取り扱われることがなく、属が変わった Dryobates pygmaeus の亜種として長らく記載されていたらしい。
Picus pygmaeus Vigors は現代では無効学名なのでシノニムとして表面上現れることもなく起源がわかりにくくなっていた。
Vigors は2種類にほとんど同じ意味の学名を付けていたことになる。このように pygmaeus や nanus を用いた理由はおそらく Picus minor Linnaeus, 1758 (コアカゲラ) の学名がすでに存在したため。
同様の用例では Picus miniaceus Pennant, 1769 や Picus miniatus Forster, 1781, Picus minutus Latham, 1790, Picus minutissimus Pallas, 1782 とすでに多数あって "小さい" を意味する種小名は使い尽くされていた模様で、やむなく別系統の語彙を用いたと想像される。
これらの用例を見ていると学名はやはりヨーロッパの視点で付けられていったことも読み取れる。コアカゲラより小さなキツツキはいなかったのでこれを minor としておけばヨーロッパでは事足りたわけである。さらに小さいものが世界に存在することがわかって名前を付けて行ったが泥沼状態に...。
Picumnus minutissimus Temminck, 1825 (ヤジリヒメキツツキ) の用例もあったそうで、Picus minutissimus Pallas, 1782 の方が早かったために Temminck の学名は属名のみ有効となった (wikipedia 英語版 Picumnus の項目より)。
このような経緯もあって Temminck はキツツキの記載に "小さい" の種小名を使うのを避けるようになって行ったのだろう。キツツキ類の複雑な学名の重複もあって地名や地方名を使うのが安全と悟っていったのではないだろうか。
上述の Gould (1883) ではアジア地域の小型キツツキ類を Pygmy Woodpeckers と種グループとして扱っていたことがわかる。大陸と東南アジア島嶼部の種について述べられているが不思議にコゲラを取り上げていない。1883 年段階では日本の情報は限られていたのだろうか。
Hartert (1910-1922) p. 928 ではコゲラとチャガシラコゲラ当時の学名で Picus canicapillus を別種扱いなので問題は発生していなかった。
Temminck が綴りを Picus kisuki と訂正した記録がある (資料) が認められなかった模様。
Hartert は後に Picus pygmaeus が preoccupied であることに気づいて補遺を出していた (p. 2188)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Yungipicus 属 (コゲラ属) となる。これはアリスイに対して用いられた属名 Yunx Linnaeus, 1766 と Picus Linnaeus, 1758 キツツキ から合成された。yinx は jinx (iynx) の別名。
Yungipicus 属は Bonaparte (1854) が設けた属で、Gray (1855) がチャガシラコゲラをタイプ種に指定した (The Key to Scientific Names)。やはりこちらが本家と考えてよさそう。
海外の主要リストでは Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) のみが Dendrocopos 属を採用している。
キツツキ類の系統解析と属分類については Fuchs and Pons (2015)
A new classification of the Pied Woodpeckers assemblage (Dendropicini, Picidae) based on a comprehensive multi-locus phylogeny (出版社サイト) を参照。
この分子系統樹に従えばコゲラ属は Dendrocopos - Picoides のグループの中で最も古い分枝にあたり、コゲラを Dendrocopos 属とするならば Picoides 属なども Dendrocopos 属にする必要がある。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では Picoides 属なども認めているので コゲラを Dendrocopos 属とする整合性がないことになる。2015 年の研究なのでまだ反映されていないだけかも知れない。我々は新しい属名を使って問題ない。
命名者の Temminck (1835) (原記載) は日本語で kizuki = kitutuki の名称を想定して、フランス語名として Pic Kisuki を与えた (The Key to Scientific Names)。Temminck はオランダ人だが著名な著作はフランス語で書かれており、フランス語に最も親しんでいたようである。
ts の音はフランス語ではもっぱら外来語のみに使われるので、日本の "キツツキ" の発音は聞き取りにくかったのかも知れない。z の音 (表記) もフランス語化される時にはしばしば s に変わる
(フランス語で z で始まる単語は非常に少ない。また tu はテュと読むので日本の "キツツキ" からはかけ離れた音になる) ので Temminck 自身も kizuki と書いて kisuki と読んでいたかも知れない。
原記載では Picus Moluccensis 現在の名称でマレーコゲラ Yungipicus moluccensis Sunda (Pygmy) Woodpecker に似ているとあり、Temminck にとってコゲラのような小さなキツツキをすでに知っていて、コゲラの標本を見ても特に驚かなったよう。
マレーコゲラとの比較が主に述べられれていてコゲラの方が少し大きい。"小型の" などの種小名を付けるのはふさわしくなく、日本からアオゲラも同一文献で記述しているため "日本の" などの意味を冠するのも適切と考えなかったと思われる (#タンチョウの備考参照)。
Temminck (1845) 自身の後の記述 Pic Kusuki ではフランス名で Pic Kisuki 学名は Pikus kisuki と書いていて (2ページ前のアオゲラでは Picus を使っているのに)、文字の扱いは結構あやふやだったらしい。
ラテン系言語では c を k や z と間違えるケースは現在でもよくあって学名でも自身の発音に合わせて記述されていることがある。Temminck もおそらく同様だろう。
かつて Picoides 属 (現在はミユビゲラを含む) に含められていたこともあった。
wikipedia 英語版の記述を見ると現在の Yungipicus 属の英名から "Pygmy" を外した別名があるようで、おそらく差別的な用語を排する動きに対応したものなのだろう。Japanese Pygmy Woodpecker から "Pygmy" を外すと Temminck も悩んだであろう名称になってしまい、学名から命名すると意味の広い日本語由来になってしまうので現状やむなく使われているのかも。
他国語名を見ると kizuki は結構使われているが "Pygmy" に相当する語を用いているのはイタリア語程度で世界的にはかなり排除されて英語での扱いが少し特別なものになっている。中国語では小星頭 (または冠に対応する文字) を付けている。ロシア語では "小型の翼の尖ったキツツキ" の意味。将来英名が検討されるならばこれら名称は候補となるかも。
Hartert (1910-1922) によれば zisuki とも書かれたとのこと。やはり発音がよくわかっていなかったらしい。
Picus Kogera Malherbe, 1861 の用例もあるが原稿に現れるのみとのこと。1861 年には "コゲラ" の名前が知られていたことがわかる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代の学名は Iyngipicus kisuki となっている。属名は Yungipicus の異なる綴りに相当するもの。
[亜種]
環日本海に分布する種で 10 亜種が認められている (IOC)。IOC で認められている亜種では大陸の permutatus 以外のすべての亜種が日本の目録に記載されている。
amamii アマミコゲラ、kizuki キュウシュウコゲラ (基亜種)、kotataki ツシマコゲラ、matsudairai ミヤケコゲラ、nigrescens (nigrescentis 黒っぽい) リュウキュウコゲラ、
nippon 亜種コゲラ、orii オリイコゲラ [八重山諸島 (西表島)]、seebohmi (英国鳥類学者 Henry Seebohm 由来) エゾコゲラ、shikokuensis シコクコゲラ。
亜種コゲラ、シコクコゲラ、ミヤケコゲラは日本鳥類目録改訂第7版で分布域が明確ではないため要検討とされる。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) によれば、かつて亜種 kawikowchiensis Kiyosu, 1954 が提唱されていたが、おそらく日本鳥学会の検討で学名の要件を満たしていないと判断したと思われるとある。
かなり複雑なのでまとめておく。記載時学名、基産地は Avibase より。
・Picus kizuki Temminck, 1835 o (原記載) 基産地 Japan, Kyushu に限定。キュウシュウコゲラ
・Iyngipicus seebohmi Hargitt, 1884 o (原記載) 基産地 Honshu and Hokkaido ("In insulis Niphon et Yezo dietis"); restricted to the latter by Stejneger (Stejneger が基産地を北海道に限定) エゾコゲラ
・Iyngipicus kizuki nigrescens Seebohm, 1887 o (原記載) 基産地 Naha, Okinawa, Loo-choo (= Ryukyu) Islands リュウキュウコゲラ
・Yungipicus kizuki matsudairai Kuroda, 1921 o (原記載) 基産地 Miyakeshima, Seven Islands of Izu, Japan ミヤケコゲラ
・Yungipicus kizuki ijimae Taka-Tsukasa, 1922 基産地 Rantomari, Maoka-gun, Sakhalin (サハリン) = seebohmi (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Yungipicus kizuki nippon Kuroda, 1922 o (原記載) 基産地 Nakahata, Gotemba, Prov. Suruga, Honshu (駿河 御殿場) 亜種コゲラ
・Yungipicus kizuki kotataki Kuroda, 1922 o (原記載) 基産地 Nitamura, Tsushima ツシマコゲラ
・Yungipicus kizuki shikokuensis Kuroda, 1922 o 基産地 Shusogun, Prov. lyo, Shikoku シコクコゲラ
・Yungipicus kizuki amamii Kuroda, 1922 o (原記載) 基産地 Amamishima, Ryukyu Islands アマミコゲラ
・Yungipicus kizuki orii Kuroda, 1923 o (原記載) 基産地 Sonai, Iriomote, Ryukyu Islands オリイコゲラ
・Yungipicus kizuki harterti Kuroda, 1923 * (参考) 基産地 Miyanoura, Yakushima, one of the largest islands south of Kiusiu ヤクシマコゲラ = petersi (Kuroda 1929 が改名) = matsudairai
・Yungipicus kizuki wilderi Kuroda, 1926 基産地 Eastern Tombs, 75 miles northeast of Peiping, Hopeh
・Yungipicus kizuki saisiuensis Momiyama, 1926 * (参考) 基産地 Quealpart Island (韓国の済州島) = nippon (Kuroda 1932 による)
・Yungipicus kizuki siragiensis Momiyama, 1927 * (参考) 基産地 Koryo, C. Korea = nippon (Kuroda 1932 による)
・Yungipicus kizuki toohokuensis Kumagai, 1928 * (参考 1, 2) 基産地 Ooka-mura, Kuribara-gun, Prefect. Miyagi (宮城), n.e. Hondo, Japan = nippon (Kuroda 1932 による)
・Dryobates kizuki petersi Kuroda, 1929 * (参考 1, 2) = ヤクシマコゲラ = matsudairai
・Dryobates kizuki acutirostris Yamashina, 1931 (参考) 基産地 Kongosan, Kogendo, eastern Korea = nippon
・Yungipicus kizuki kurilensis Bergman, 1931 基産地 Chinomizi, Kunashiri, Kurile Islands (国後島) = ijimae = nippon
・Yungipicus kizuki kurodae Bergman, 1931 * (参考) 基産地 Shana, Yetorofu, Kurile Ids. (択捉島) = nagamichi (改名) = ijimae = nippon
・Dryobates kizuki permutatus Meise, 1934 o 基産地 Sidemi
・Dryobates kizuki nagamichi Bergman, 1935 * (参考) 基産地 Schana, Yetorofu (択捉島) = kurilensis (Dement'ev and Gladkov 1951) = nippon
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
海外の主要リストで ijimae を認めているものはない模様。wilderi は Clements 2023, HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v8 (Dec 2023) など少数のリストが認めるが nippon のシノニムとされることが多い。
H&M4 の記述によれば Placement in nippon as in Dickinson (2003) [Dickinson, 2003] may be justified but was not discussed by Dickinson et al. (2001) [Dickinson, 2001]. Pending confirmation of this we restore wilderi recognised by Vaurie (1965) [Vaurie, 1965] and Cheng (1987) [Cheng Tso-hsin, 1987]
とのことで一度は nippon に含めたが異論もあって復活させたとのこと。
seebohmi, ijimae, acutirostris, harterti のシノニム扱いは H&M4 の記述による。
ということで、現在の扱いでは離島以外は大陸と日本は距離があるが同じ緯度帯は朝鮮半島も日本も nippon で日本国内はいくつかの亜種に分かれていることになる。
本州 (北の方?)、四国 (と本州の南の方?)、九州は別亜種になる。九州と本州のコゲラは違うのでしょうか (?)、となるわけだが、同一亜種とすればすべて亜種 kizuki にまとまってしまうので統一しにくい、ということだろう。#フクロウでも同じ感想だがそこまで伝統に従うこともなく、まとめて (離島はどの程度違うのかわからないが) 1亜種でよいのではと感じる。
なぜさまざまな種類の亜種の基産地が九州かといえば海外との交易が限定されていたため。他の分類群では出島を基産地と定義しているものもある。
ミヤケコゲラの分布域が明確ではないため要検討とされる理由の一つはもとヤクシマコゲラがこの亜種に含まれているためだろう (同じような状況はコマドリの亜種タネコマドリ Larvivora akahige tanensis とヤクコマドリ L. a. kobayashii の間で生じていた)。
海外の方も日本でコゲラに普通に出会うが自分の出会ったのはどの亜種なのかさっぱりわからないとのこと。日本人でもわかりませんので...。固有亜種数には貢献している種だが、単に整理されていないだけのようにも見える。むしろ大陸とは差がないのだろうか。
Hartert (1910-1922) p. 928 では seebohmi の範囲を Hondo, Jesso und Ussriland, auch Hargitt auch Korea (本土、蝦夷、ウスリー、Hargitt によれば朝鮮半島も) とのこと。他亜種を本土で記載するために基産地が北海道に限定されたようにも読める。
時代的には中間にあたる Dement'ev and Gladkov (1951) では亜種分布図の作成に苦労しているようで基亜種 kizuki を載せていない。代わりに本州・四国・九州をまとめて nippon と shikokuensis を並列で載せている。南西諸島に3亜種が並ぶ。大陸も3亜種で分布境界不明で全体をまとめて3つの亜種を配置してあるだけ。
「ここで載せる亜種の大部分は分布域は非常に狭く、そのうちいくつかは特徴の記述が非常に不明瞭 (対応する英語にすれば very poorly characterized)」と述べられている。原語だと ochen' plokho で、成績に使うならば "落第" になるような表現。
ロシアに近い部分は一部統合したが、さすがの Dement'ev and Gladkov も日本国内は扱いきれないと判断した模様。日本国内は細かく分けるが大陸と日本を同じ亜種にまとめる Hargitt 由来の考えに賛同していないこともわかる。
ロシアのコゲラについてはまとめた上で3亜種 permutatus, seebohmi, kurilensis を挙げているが、最初のもの以外は書けることは計測値程度でほとんどない状況。seebohmi はウスリーのものより小さい (Buturlin 1936 による) とされるが、羽衣には違いがないと書かれている。
このあたりのニュアンスは Dement'ev and Gladkov の記述の行間を読み取って欲しい。
同書にやはりロシア大陸部にも分布するチャガシラコゲラの分布図が出ていて、東南アジア大陸部分はコゲラ同様によくわからない状況となっているが、大陸東北部 (ロシア、朝鮮半島、中国東北部) は1亜種となっている。
命名者の意図まではわからないが、nippon の意味は必ずしも現在想像する日本の国名ではなく、北海道以外の主要島を指していたこともあった (#トキの備考参照。本州のみを指す用例もあった)。エゾコゲラに対する nippon の意味で使われていたかも知れない。
Birder 編集部 (1993) Birder 7(4): 20-25 に「日本全国のコゲラを比べる」の記事がありほぼすべての亜種の写真 (地域から判定) と記述を載せている。この記事によれば Vaurie (1965) は seebohmi の基産地を横浜と判定し、分布を本州、済州島、朝鮮半島とし、nippon をシノニムとした。
つまり2つ記載されている基産地 (Honshu and Hokkaido) の特定次第で亜種名が変わる
(同一亜種の記載に Honshu and Hokkaido が出てくるぐらいならばそもそも差がないのではと思ってしまうが...)。
また ijimae を認めるかどうか、Peters (1948) と Vaurie (1965) で見解が分かれているとのこと。
表題にあるように亜種を違いを記述する記事というより色彩の地域差と亜種学名の由来などを中心としたもの。
中西悟堂「定本・野鳥記 3」(p. 76) にも一種の「ぼやき」的文章があり、「たかがキツツキ類が 45 通り (戦前の領土を含む) にも分かれているとは、分類学とは厄介千万のものだと思われるだろうが (中略) 学者とは一々にこのようなめんどうな呼び方をしているのである。が、ちかごろはしだいにこのような細分はせずに、どこ産のコゲラとかアカゲラとか言う傾向になっており...」と記されていた。この文章は 1946 年初出。80 年近く前でも面倒なものだと感じられていたことがわかる。
さて自分は地元のコゲラの亜種をどのように扱っているかと言えば「亜種は書かない」で済ましている [いろいろな意味に解釈できると思われるので行間を読み取って欲しい (笑)]。
[北方と大陸のコゲラの亜種の再検討]
北方のコゲラについては Red'kin and Zhigir (2020) Northern subspecies of the Japanese Pygmy Woodpecker Yungipicus kizuki (Temminck, 1836) (pp. 3699-3718。英文でそれぞれの亜種の記述あり)
が亜種の整理と改訂分布図を出していた。計測値が主成分分析でほぼ分離でき、羽衣の特徴も記述できる4亜種にまとめた。
・permutatus は朝鮮半島、中国東北部、ロシア大陸部、(孤立して記載された wilderi は分離できると考えているが基産地周辺のみを表してある)
・seebohmi が北海道から国後島まで
・ijimae がサハリンと隣接する大陸沿岸部 (?)
・kurodae が択捉島からさらに千島 (?)
となっている。本州以南は他の分布をそのまま採用 (kizuki は図の範囲外として判断を避けている)。
翼長の計測値に重なりがないかと言えば大いに重なっている。
この文献によれば kurodae の亜種名の復活は以下の理由。
Yungipicus kizuki kurodae Bergman, 1931 と Dryobates leucotos kurodae Goetz, 1926 (オオアカゲラの亜種) は記載時は別属だったが、一時的に Dryobates 属にまとめられた時に衝突した。
そのため Bergman (1935) は Dryobates kizuki nagamichi Bergman, 1935 と前者に新しい名前を与えた。しかしこれも Yungipicus scintilliceps nagamichii La Touche, 1932 = Yu. canicapillus nagamichii (チャガシラコゲラの亜種)
と衝突していることが判明し、Dryobates 属が分割され Yungipicus 属に戻った現在では kurodae を再度認めてもよいのではが著者の考え。
本州以南は扱われていないので十分ではないが、北方亜種については形態学的のみではあるが定量的な新しい研究によるものなので (やや細分主義的な傾向はあるが) この亜種扱いをある程度考慮してもよいのでは。
標本のしっかりした写真も載せられていて、大陸と島で模様がどの程度違うかなどを見ることができる。
コゲラの亜種を判別されていて、北からの渡り個体の記録に興味のある方には必読の論文だろう。
[音声]
コゲラの声と言えば「ギー」と聞こえるのが有名である。繁殖期を中心に「キッキッキッ...」と鳴くこともあり、これを song とすることもある。
実はこの2種類の音は同じで、音の間隔が違うだけである。おかしいと思われる方があれば録音してソノグラムを描いてみればすぐわかる。
-
コアカゲラ
- 第8版学名:Dryobates minor (ドゥリューオバテース ミノル) 小さな木を歩く者 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Dendrocopos minor (デンドゥロコポス ミノル) 小さなキツツキ
- 第8版属名:dryobates (合) 木を歩く者 (drus, druos 木 bates 歩くもの Gk)
- 第7版属名:dendrocopos (合) 木を打つ者 (dendron 木 kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 種小名:minor (adj) より小さい
- 英名:Lesser Spotted Woodpecker
- 備考:
dryobates の読み方は明確でない。起源となるギリシャ語 drus は u が長母音 (ドゥリュース)。-bates は e が長母音。アクセントは -ba- の前になると考えられる。
dry-o-ba-tes と区切られると思われるのでこれらの長母音を残し、o にアクセントを置いた (ドゥリューオバテース)。音を伸ばさない場合でもアクセント位置は変わらない。
dendrocopos は#アカゲラ参照。
minor は "ミノル"。
アカゲラ (オオアカゲラではない) の major に対するものでいずれも Linnaeus (1758) が与えた種小名がそのまま使われており、英名とも対応している。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Dryobates 属 (drus, druos 木 bates 歩くもの Gk) に移動、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。Dryobates 属はコアカゲラ属となる。
系統関係は Fuchs and Pons (2015) を参照。かつての Dendrocopos 属、Picoides 属は互いに単系統の関係になく分離されることになった。この結果 Picoides 属はタイプ種ミユビゲラを含む系統である必要があるため、小さなグループとなった。
Dryobates 属も同様で、タイプ種セジロコゲラ Dryobates pubescens Downy Woodpecker (北米の種) を含むクレードが分離されたもの。
セジロコゲラはかつてケワタゲラ (英名に対応) の名称もあった [週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 86 p. 3]。
Dryobates 属はユーラシア北方部 (より南方に分布するヒムネアカゲラ Dryobates cathpharius もある) に広く分布していたものが北米にも進出してセジロコゲラなどを生み出したと考えると系統的にも整合性がよい。
日本の亜種は amurensis (アムールの。アムール川下流から朝鮮半島、日本に分布) となっている。日本国内で観察の難しい種であるが、世界的にはヨーロッパからカムチャツカにかけて広く分布し、13 亜種 (IOC) がある。
コアカゲラがより大きなオオアカゲラに擬態している考えがある。Prum (2014) Interspecific social dominance mimicry in birds (#ハチクマの備考 [擬態と種・亜種の関係] 参照)。
また#アカゲラにもキツツキ類での擬態に関連する文献情報などがある。
-
オオアカゲラ
- 学名:Dendrocopos leucotos (デンドゥロコポス レウコトス) 背の白いキツツキ
- 属名:dendrocopos (合) 木を打つ者 (dendron 木 kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 種小名:leucotos (合) 白い背の (leuko- 白い (接頭辞) notos -背の Gk)
- 英名:White-backed Woodpecker
- 備考:
dendrocopos は#アカゲラ参照。
leucotos は後述のようにおそらく誤記でこの意味を採用すれば長母音の要素はなく u がアクセント音節となる (レウコトス)。
種小名は otos 耳 (Gk) とも解釈でき、愛媛の野鳥「はばたき」でも「白い耳の」となっているが上記の方がもっともらしく、英名とも整合する。
Bechstein の 1802 年の図版では leucotus と綴られていたが、Bechstein (1805, 1812) では leuconotos と綴られた (The Key to Scientific Names) おそらく後者が意図するものであり、誤って綴られたものが学名となったものらしい。
学名意義は本来の意図と考えられる解釈を採用した。オオアカゲラの背から腰に白斑があり、飛翔時にはっきりする。
leuconotos ならば -no- を長母音でアクセントを置いてもよかった。
-cotus の音を -notos から借用する解釈ができれば長母音で読むこともあるいは可能かも知れない。
英名と比べられた方であれば一度は疑問視されたことがあるだろうが、White-backed Woodpecker はあまりふさわしい英名でないように思える。本州であればアカゲラの方が白い部分が目立つ。
英名が学名由来とすれば納得できるわけが、上記 "本州であれば" という点がミソで、亜種エゾオオアカゲラでは背が結構白い。ということは...とさらに大陸を見てゆくと本当に背が白いのである。
つまり基亜種であるヨーロッパの白い背の leucotus が種小名となるためこのような状況になっている。種オオアカゲラ全体で見ると必ずしも適切な英名でないことも理解できる。
最も早く記載されたものが基亜種となる規則であるため、おそらく綴りを間違えて意図した意味がわかりにくくなったものも採用せざるを得ない状況にもなっているなど学名の規則もわかる事例となっている。
ヨーロッパから日本まで広く分布し、12 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は subcirris (sub 下が kirrhos 黄色っぽい、バフ色の Gk) エゾオオアカゲラ、
stejnegeri (ノルウエー生まれのアメリカの動物学者 Leonhard Hess Stejneger の) オオアカゲラ (本州北部・中部)、
namiyei ナミエオオアカゲラ (本州中部・南西部、四国、九州)、owstoni (英国博物学者、採集家の Alan Owston の) オーストンオオアカゲラ (奄美大島。天然記念物)。
オーストンオオアカゲラは独立種 Dendrocopos owstoni (英名 Amami Woodpecker) 英名 Amami Woodpecker とするリストもある (HBW/BirdLife Amami Woodpecker)。
オーストンオオアカゲラは絶滅危惧 II 類 (VU) 種。IUCN NT 種 (2016)。
分子系統研究は例えば Pons et al. (2020) Phylogeography of a widespread Palaearctic forest bird species: The White-backed Woodpecker (Aves, Picidae) (出版社サイト)
を参照。この研究ではオーストンオオアカゲラは独立種とは言えないとのこと。
それほど詳しく調べられてはいないが、日本の個体群の間にも大きな違いはなさそうである。
ノグチゲラがオオアカゲラの系統で最初に分岐した枝に相当することもこの図から読み取れる。
個別の遺伝子で BLAST で簡易系統樹を作っても同じような結果になる。ノグチゲラを独立属とすることも原理的には可能で、その場合は単系統性の要請からオオアカゲラとアカゲラを別属にする必要があり、他にも Dendrocopos から別属に分離する必要のあるグループが生じるなど細かくなりすぎて従来概念に反するので採用されなかったのだろう。
[ドラミングの分類]
Garcia et al. (2020) Evolution of communication signals and information during species radiation (#アリスイの備考参照) オオアカゲラなどの Dendrocopos 属 や Dryocopus 属のドラミングは
によれば "acceleration" のグループに属し、次第に早くなってゆくのが特徴とのこと。アオゲラの "steady fast" (速い等間隔) とは異なっている。
ドラミングでアオゲラとオオアカゲラを区別する一応の根拠になる (「一応の」と書いたのはすべての個体が同様かわからないため)。
日本で出会うキツツキはこれらの特徴に分類されるが、世界のキツツキ類は他に "steady slow", "double knock", "irregular sequence", "regular sequence" に分類されるとのこと (どの系統が属するかは論文をご覧いただきたい)。
もっとも系統間でそれほど一貫した分布になっているわけではなく、同じクレードの中でも Dryocopus 属がやや特殊になっている。Dendrocopos 属とはクレードが異なるの一種の収斂進化のようなものだろうか。
-
アカゲラ
- 学名:Dendrocopos major (デンドゥロコポス マヨル) 大きなアカゲラ
- 属名:dendrocopos (合) 木を打つ者 (dendron 木 kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 種小名:major (adj) より大きな
- 英名:Great Spotted Woodpecker
- 備考:
dendrocopos の読み方は明確でないが、起源となるギリシャ語の dendron, kopos が短音のため、ラテン語でも長音は含まれないと思われる。ギリシャ語 kopos は ko-pos と区切られるので同様に -co-pos と区切るならばその前にアクセントがある (デンドゥ(ロコポス)。
major は "マヨル"。
ユーラシア中緯度部に広く分布し、世界で 24 亜種が認められている (IOC)。
Dendrocopos 属のタイプ種。
日本で記録される亜種は brevirostris (brevis 短い -rostris くちばしの) ハシブトアカゲラ (迷鳥)、japonicus エゾアカゲラ、hondoensis アカゲラ とされるが、
hondoensis を亜種と認める主要リストはなく、通常は japonicus のシノニムとされる。
この立場の場合、エゾアカゲラをアカゲラと改名する必要が出てくるであろう。
kitsutsuki の種小名はかつてアカゲラの亜種の学名として Hachisuka (1952) が与えたが、現在はコーカサスからアジア南西部亜種 tenuirostris (細い嘴) のシノニムとされる。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) によれば、もしこの種が Picoides 属になれば (現状その心配はなさそうだが)、ありふれた種小名である tenuirostris の名称はすでに Picoides 属で使われているためにこの亜種の学名は kitsutsuki となるだろうとの備考がある。
Perktas and Quintero (2012) A wide geographical survey of mitochondrial DNA variation in the great spotted woodpecker complex, Dendrocopos major (Aves: Picidae)
にアカゲラのミトコンドリア DNA 1遺伝子を用いた分子系統研究がある。これによればアカゲラは4系統に分かれ、それぞれ別種に値するレベルである。中国のクレードと日本のクレードはユーラシアから北アフリカのものと異なるが、日本のサンプルは北海道のみに限られている。著者は少なくとも4種への分割が妥当としている。
分岐順は中国、日本、ユーラシアから北アフリカとなっている。ユーラシアから北アフリカの個体群はイベリア半島、クルスク、北アフリカのレフージアから急激な分布拡大を遂げたものと考えている。
日本、中国、および大陸北部・西部のアカゲラは将来別種となる可能性がありそうだがこの研究では本州と北海道の違いなどが調べられておらず (海外の分類では北海道も本州も同亜種なので特に調べなかったのかも知れない)、別種扱いには情報不十分なのだろう。
現在のところこれらのクレードを種として分離して扱っている海外の主要リストはないが、日本のアカゲラは将来 Dendrocopos japonicus のような学名になるかも知れない。
この点は#オオアカゲラ備考の Pons et al. (2020) の系統樹でも同様で、カオジロアカゲラ Dendrocopos syriacus Syrian Woodpecker や キバラアカゲラ Dendrocopos darjellensis Darjeeling Woodpecker がアカゲラに内包される形になっている。
これをこのまま受け入れると単系統性の要請から japonicus を分離するのが望ましいとなりそうだが、ND2 遺伝子を用いて BLAST を試してみると (極東個体のデータはないが) 少し異なった系統樹形になる。
カオジロアカゲラやキバラアカゲラ、そして日本のアカゲラが先んじて適応放散して、その後アカゲラの主系統が再度適応放散することで古い分岐の系統が周辺部にのみ残存しているように見える (#セグロセキレイ や #ルリカケス の考察参照)。データがまだ不十分なのでさらなる研究に期待したい。BLAST は簡単に試せ、系統関係を議論した論文出版以降に発表された配列も利用可能になっていることもあるので理解進展に役立てていただきたい。
#オオアカゲラの方に記したが、オオアカゲラの種小名の意味と日本の特に南部のオオアカゲラの対応は必ずしもよくない。アカゲラの翼の方が白いところが目立つ、と感じるが、アカゲラの若鳥が頭の色彩などオオアカゲラに類似していることを思い出した。
系統的に類似しているためとも考えられるが、コキアシシギがオオキアシシギに擬態していると指摘されるぐらいであれば (#コキアシシギ参照)、より小型のアカゲラの方がオオアカゲラに擬態した結果の可能性もあるように感じる。
このあたりは大いに憶測のレベルだが、アカゲラとオオアカゲラが同所的に分布する場合は互いに似せることが有利に働くのではないかとも考えてみた。その結果アカゲラが分布しなかった地域ではノグチゲラや (遺伝的にはオオアカゲラとあまり違わない) オーストンオオアカゲラのような表現型を保つことが可能だったなど。
このようなことを考えた理由はハチクマ類とクマタカ類の対応関係にあまりによい部分があるため (#ハチクマ備考の [擬態と種・亜種の関係] 参照。どちらがどちらに似せているのかもよくわからない)。
我々が理解していないだけでお互いに似せることで有利に働く機構が何かあるのかも知れない。そういえばハシブトガラとコガラはなぜそこまで似ているのだろう、など。
[キツツキ類の擬態]
Prum (2014) Interspecific social dominance mimicry in birds (#ハチクマの備考 [擬態と種・亜種の関係] 参照) では
北米の セジロアカゲラ Leuconotopicus villosus Hairy Woodpecker とセジロコゲラ Dryobates pubescens Downy Woodpecker は属が異なるにも関わらず見かけがほとんど同じあるとのこと。後者が前者に擬態していると考えている。
同文献に載っているリストではコアカゲラがオオアカゲラに擬態のアイデアはあるそうで、これも属が違うことが判断根拠になっている模様。
文献は Weibel and Moore (2005) Plumage Convergence in Picoides Woodpeckers Based on a Molecular Phylogeny, With Emphasis on Convergence in Downy and Hairy Woodpeckers とのこと。
系統が異なるにもかかわらず目で見て似ているかどうかを特徴を選んで議論した論文で、画像類縁性などを判定できる現代であればさらに進んだアプローチが可能と思える。
アカゲラも分析対象に含まれているが、ヨーロッパの亜種同士を比較対象にしているのでそれほど似ていないと判断されている可能性もありそう。系統的にはオオアカゲラの方が古く、アカゲラが後から適応放散した形となっているので系統進化的にも興味あるところである。
前述のようにアカゲラとオオアカゲラを別属にしても構わない程度なので、北米の2系統の比較に匹敵するぐらいの対応関係を考えてもよいかも知れない。興味ある方の検討に期待したい。
南米種でも擬態の可能性が指摘されている: Benz et al. (2015) Phylogenetic relationships of the Helmeted Woodpecker (Dryocopus galeatus): A case of interspecific mimicry?
どのぐらい似ているか、分子系統がどの程度違うかは図版参照。この論文で紹介されている互いに似せるメリットとしてセジロアカゲラとセジロコゲラで提案されている ISDM 仮説の他に、Moynihan (1968) は混群を作る際に互いの認識を容易にする、
逆に Cody (1969) Convergent characteristics in sympatric species: A possible relation to interspecific competition and aggression は競争する種の間の認識を容易にし、種間のテリトリーの形成を容易にするアイデアもあったがいずれもあまり有望な仮説とは考えられていないよう。
そして ISDM 仮説提唱の理論的背景も触れられている。キツツキ類では互いに似せているらしい組み合わせが多いらしい。
[アカゲラの一妻二夫]
小高 (1997) Birder 11(6): 37-40 に 1994 年に記録された北海道大学キャンパスでのアカゲラの一妻二夫が紹介されている。
論文は Kotaka (2008) Classical polyandry in the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major。
Birder 記事にも記載されているがこのような事例は非常に珍しく、当時他のキツツキも含めて知られていたものは1例のみだったとのこと。これは Willimont et al. (1991) Classical Polyandry in the West Indian Woodpecker on Abaco, Bahamas で見ることができる。
その後の文献では、Wiebe (2002) First Reported Case of Classical Polyandry in a North American Woodpecker, the Northern Flicker,
ミユビゲラの例 Pechacek et al. (2006) Classical polyandry found in the three-toed woodpecker Picoides tridactylus。
一妻二夫の進化的考察は例えば Safari and Goymann (2020) The evolution of reversed sex roles and classical polyandry: Insights from coucals and other animals
キツツキ類やバンケン類ではオスが抱卵する (夜も) 傾向があるため、このような性質は進化しやすいなどの説明がある。報告のあるキツツキ類ではメスよりもオスの方が子供の面倒を見る能力が高いとのこと。
[キツツキ類の尾羽の強度]
Dickinson et al. (2023) Tail feather strength in tail-assisted climbing birds is achieved through geometric, not material change
にキツツキ類を含む、尾を支えに木を登る鳥の尾羽の構造や強度の研究がある。キツツキの共通種ではアカゲラとクマゲラが調べられている。
尾を支えに木を登る鳥は尾羽が長く、羽枝の幅が広いなど曲げに強い構造を持つ傾向があったが、ケラチンそのものの特性は他のものと違わず、素材よりも形態の少しの違いで体を支えている。
なおこの論文のグループはオウム類は嘴を支えに使う新しい移動方法として beakiation の用語を発案している: Dickinson et al. (2024) Beakiation: how a novel parrot gait expands the locomotor repertoire of living birds。
映像も紹介されてちょっと話題となったがインコの飼育経験のある人ならばよく知っている行動。どのぐらいの力が必要かなど見積もっている点が新しい。オウムの嘴は体重の 37 倍の力を出せる測定値があるとのこと。これまであまり調べられていなかったがオウムの首の筋肉は例外的によく発達していて屈筋は体重の 28 倍の力を出せるとのこと。ヒトでは体重の 19% とのこと。
プエルトリコシトドフウキンチョウ Spindalis portoricensis Puerto Rican Spindalis は翼や足を使わずに嘴だけに頼って深い茂みを移動するとのこと。
[キツツキ類の分布と森林の関係]
中部ヨーロッパ (ポーランド南部) で8種のキツツキ類と森林環境との相関を調べたもの: Belcik et al. (2025) Forest fragmentation and heterogeneity shape the occurrence of woodpecker species in Central Europe
アカゲラとクマゲラでは森林パッチのサイズと遭遇頻度が正の相関を示したがアリスイは逆だったとのこと。針葉樹の多い森林パッチではキツツキ類の種多様性が低かった。
[キツツキの力の釣り合い]
上記のようにキツツキの中央尾羽が硬いのはご存じの通り (アリスイは硬くない)。体を支えるためと説明されるが何となく不十分な印象を受けておられる方も多いのではないだろうか。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 86 V-VII (浦本) に力の釣り合いの図 (図は V にある) が描かれていて、重力が働くのはよい。これを2成分に分割して尾はその1成分を支える説明となっている。
もう1成分 (この方向に分割すれば体が幹から離れる方向の力) に対抗するためにキツツキは足が短くて曲げているのだという。また対趾足でない鳥も木に同じようにとまる (ミユビゲラのような例もある) ので対趾足が役立っているわけではないと説明されている。
部分的には正しい気がするが、なぜ力の分解のみにこだわるのか不思議に思った。もしかするとギル「鳥類学」の訳書に力の釣り合いの図が出ているかと期待したがなかった。
大きさのある物体を静止させる場合は力の釣り合いだけで理解するのは不十分で、「力の釣り合い」と「力のモーメントの釣り合い」の両方を満たす必要がある。これは高校物理の力学で習うことで、大学入試の物理の力学の問題ではこの2つの式を立てて解くものも多い。
想像すると力の分解 (ベクトルの概念) は中学までで習うが、生物好きの者は高校で物理を履修しないことが多く (昔のことで今は多少違っているかも知れない)、力のモーメントの概念に馴染みがないためかも知れない。
木にとまるキツツキであれば、重力と足で支える力、尾羽で支える力の3つ (後者2つは方向は面に垂直方向とは限らない) を「力の釣り合い」と「力のモーメントの釣り合い」の両方を満たすように解くことに相当する。後者2つの力は4成分 (面に垂直な方向とそれに直角な方向) あり、満たすべき式は3つ (力の釣り合いがベクトル量なので2成分) なので自由度が残る。つまり尾羽で支える力は重力に抗する方向とは限らない。足の力も2成分を考えるべきとなる。
この自由度がなければ力は一通りに決まり、キツツキは動くことにも不自由するかも知れない (この推論は正しくないかも知れない)。
そのような解説をあまり見たことがないのは、力の釣り合いのみで満足されている方が多いのだろうか。
スポーツクライミングではもう少し解説があって例えば Fuss and Niegl (2009) Instrumented climbing holds and performance analysis in sport climbing。
キツツキの場合も支えるために必要な筋肉の力を最小化する、あるいは移動の際のエネルギー消費を最小化するなど研究がありそうに思えるが、誰もが木を叩く時の動作やそのための適応の方に注目するためかあまり研究が見当たらない。従ってミユビゲラの趾が3本なのは何のための適応なのかもあまり言及されない。
Plenary03: Functional and evolutionary morphology of woodpeckers [Bock, W.J. 1999. Functional and evolutionary morphology of woodpeckers. In: Adams, N.J. & Slotow, R.H. (eds) Proc. 22 Int. Ornithol. Congr., Durban. Ostrich 70 (1): 23-31]
があってある程度 浦本 (1972) 時代の考えを伝えてくれているように思える。Stolpe (1932); Bock and Miller (1959) の研究があって Fig. 3 Stolpe (1932) が 浦本 (1972) で使われている図と基本的に同じである。この仮定は間違いであるとのこと。Fig. 4 に正しい式が示されており、3つめの式が力のモーメントの釣り合いを表している (解説では rotational displacement effect となっていて力のモーメントと言えば済むのに...世界的にもこの状態だったので、物理の概念によほど馴染みがなかったものと想像できる)。
Winkler and Bock (1976) が正しい式を与えたとのことで、浦本 (1972) の時代にはまだ知られておらず、40 年以上も誤った説明が通用していたことになる。おそらく今でも通用しているのでは?
現代の鳥類学の教科書に出てこないのはなぜ? キツツキの尾や足の適応はまだまだ検討するべきことがあろうと想像する。
#ゴジュウカラ [木の幹を登る鳥の下肢の適応] の方が尾を使わず力学的には単純なのでまだ調べられているのかも。
しかし、ゴジュウカラのように尾を接触させない方法だと接触点で働く足の力 (2成分のみ) しか自由度がなく、Bock (1999) で正しいとされる Fig. 4 の表式では「力の釣り合い」と「力のモーメントの釣り合い」を同時に満たすことができないことになる。この Fig. 4 は尾が支えていることでようやく成り立っているわけだ。
ゴジュウカラが幹にとまることができることを説明するためには力を最低限もう一つ追加する必要がある。接点は足しかないので、最も単純な考え方では足の前部 (前向きの趾) と後部 (後ろ向きの趾) に分けるのがよいことになる。この場合は離れた2点から異なった力が働き (合わせて4成分となる)、「力の釣り合い」と「力のモーメントの釣り合い」を満たすことができる。
ゴジュウカラの足の力を分割する必要があるならば、同じことはキツツキでも成り立つはず。ということで原理的には尾羽が支えなくても釣り合いを保つことができるはず。キツツキの尾羽が硬いことは力の釣り合いによる必然の帰結というわけではない (1932 年の誤った力分解の解釈に沿っていることになる)。
また Winkler and Bock (1976) の扱いも正しいとは言えなかった。「より正確には複雑な取り扱いが必要で、コンピュータシミュレーションが必要である」のような表現はよく理解できていないことを表す時の常套句で、それでは「現実を表現するためにどこまで単純化が可能か」を考えるのが正しい方向である。
キツツキの方が体重が大きいので、と言えるかも知れないがそれでは尾羽を使う必要性の境界は何が決めているのか、と問われても答えられない (よく調べれば論文があるのかも知れないが)。
ゴジュウカラが尾を接触させないのは、上向きの場合は役立っても下向きでは役立たない理由もあるのだろう。ゴジュウカラではその代わり前向きの趾と後ろ向きの趾がそれぞれ十分に力を発揮する必要がある。この握力と離れた2点の距離 (足の広がり) が大きいほどモーメントも大きくなって「力のモーメントの釣り合い」を満足するのに適することになる。
常時上向きしか使わないキツツキやキバシリでは、そこまで前向きの趾と後ろ向きの趾が十分に力を発揮する必要がなく、代わりに尾羽を使うことで尾羽から生じる力のモーメントを大きくして「力のモーメントの釣り合い」を満足させた。もっともこれは相対的なもので尾羽を積極的に使わなくても実現できる。その場合は足の広がりを大きくしたり爪で掴む力を増すなどの必要が生じるだろう。ミユビゲラが趾3本でも "構わない" 理由は一応説明できそうに見えるが適応的であるかどうかまではこの議論では判断できない。
趾3本でも "構わない" ならば、ミユビシギでもあるように後ろ趾を省略した方が素早い動きが可能かも知れない。ミチバシリのように対趾足の方が後趾1本の場合より地上を歩くのに有利かも知れない (#カッコウ備考 [カッコウ類の足と近縁系統] 参照)。キツツキでも対趾足か3本趾が選択されたのかも知れない。
大型になるほど「力のモーメントの釣り合い」(尾羽が支える力も限界があるので、後ろ向きの趾にも力を出して「落ちない」必要がある。「落ちない」ためになぜ後ろ向きの趾の力が必要かはここまでの議論を読まれれば理解できるであろう) のために後ろ向きの趾を失いにくくなり、対趾足の方が一般的となったのかも知れないがあくまで参考レベルの推測。「力のモーメントの釣り合い」を積極的に取り上げていないことが過去の議論の決定的弱点ではないかと思う。
これは木の幹にとまる鳥に限った話ではなく、飛んでいる鳥に働く力、足で立つ (特に1本足で) などを議論する場合も同じである。「力の釣り合い」のみで考えると往々にして間違いが発生しがちで、重心の位置が云々も「力のモーメントの釣り合い」を考えた方が自然に理解できる。
ギル「鳥類学」の訳書の飛翔時の力のバランスにもベクトルの分解の図しかないので、力学を扱っている部分は全体的にちょっと怪しいかも知れない。
なおここではキツツキがとまっている時は両足を揃えていることを仮定している。両足を前後に配置すれば力の自由度は増すが、そのような姿勢でなくてもとまることができるので特に考察しなかった。
またキツツキの重心と木 (垂直と仮定する) を通る面内での「力の釣り合い」「力のモーメントの釣り合い」のみを考慮した。空間には3次元の自由度があるのでもう1方向も考慮することが可能であるが、ここでは "キツツキの尾羽はなぜ硬い" を主に扱うため上記面内の考察でほぼ間に合うだろう。
浦本氏の考察 (1972) では趾の方向なども議論されており、横方向の力も考慮することが必要であろうが、そもそももっとも単純な状況での力の扱いが正しくなかったため、その上に派生的に議論を重ねるのはちょっと怪しいかも知れない。
またキツツキが木を叩く時は嘴が接点となって力がもう一つ増えるが、定常的な力ではないのでここでは扱わないこととしておく。足と尾羽が支える力のバランスは上述のように力学的に一意に決まるわけではないので、木を叩く時の効率などが尾羽に必要な力を決める選択圧の要因となっているかも知れない。
浦本氏の考察 (1972) で、キツツキ類の対趾足の後趾が木を掴むのに役立っていない考察の補強材料としてケラインコ類 (Micropsitta 属 Pygmy parrot) が取り上げられており、趾が4本とも前を向く皆前趾足であると述べられていた。
調べてみると pamprodactyl とのことで、アマツバメ類の一部、ネズミドリ類の一部が wikipedia 英語版に取り上げられていた。
ケラインコ類について現在そのような記述があまり見当たらないので調べてみると Botelho et al. (2015) Altriciality and the Evolution of Toe Orientation in Birds
によれば、かつてはそのように考えた学者もいたが Collins (1983) A Reinterpretation of Pamprodactyly in Swifts: a Convergent Grasping Mechanism in Vertebrates
が正しくないことを指摘したとのこと。
ケラインコ類についてそのように記述したのは Bock and Miller (1959) とのこと。浦本氏の 1972 年段階では世界の主流派の解説を紹介したもので、まだ誤解もやむを得ない状況だった模様。
ケラインコ類の画像は属名で検索すれば見ることができるのでご覧いただきたい。普通に後趾を使ってとまっており、ゴジュウカラのように下向きになることもできる。食性が面白く地衣類 (lichen) やコケとのこと。通常のインコ類ように果実食と思われていた時代があり飼育できなかったとのこと。特に絶滅が危惧される種類はなく、飼育下繁殖も試みられていないらしい (wikipedia 英語版より)。
飼育できなかったので乱獲を免れ、飼育下繁殖も積極的に試みられていないというところだろうか。
木の幹を登り降りする鳥の考察がまったくないわけではなく Norberg (1981) Why foraging birds in trees should climb and hop upwards rather than downwards があるが、当時話題の歩くかホッピングするかの選択に関連する研究で、ここで疑問としている話に答えてくれるものではなさそう。
時代的にもおそらくまだちょっと無理。ゴジュウカラ類の足が相対的に長い理由は行動への適応として説明できる、というところ。
翼や嘴のことは力学的に高度な考察 (特に飛翔の航空力学は高度である) が行われているのにこの違いはなぜ (?)。研究というものも基本的には流行を追うものであることが理解できる次第。
バードウォッチャーにも当然工学関連出身の方が含まれていて、「その議論はおかしい」など 1976 年を待つまでもなくすでに指摘されているのではないかと想像するが単に見たことがない。偉い先生の講演や著書なのでケチを付けにくいのは世界どこでも共通なのかも知れない。
-
ミユビゲラ
- 学名:Picoides tridactylus (ピーコイーデース トゥリダクテュルス) 三本指のキツツキに似た鳥
- 属名:picoides (adj) キツツキに似た (picus (m) キツツキ -oides (接尾辞) 〜に似た)
- 種小名:tridactylus (合) 三本指の (tri- (接頭辞) 三つの daktulos 指 Gk)
- 英名:Eurasian Three-toed Woodpecker
- 備考:
picoides は picus の冒頭が長母音。ギリシャ語 -oides の語尾は i, e が長母音となり前者にアクセントがある (ピーコイーデース)。
tridactylus は tri- は短母音。daktulos も短母音のみ。ギリシャ語音節に合わせて dac-ty-lus と区切れば -dac- がアクセント音節 (トゥリダクテュルス)。
ユーラシアの主に北部に広く分布する。8亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は inouyei (Motonori Inouye 由来) とされる。
wikipedia 日本語版にはアラスカ、カナダから北アメリカ北部も生息地に含まれているが、これはアメリカミユビゲラ Picoides dorsalis が同種とされていた時代の名残り。
北アメリカの北部にはさらにセグロミユビゲラ Picoides arcticus Black-backed Woodpecker が分布し、これらが Picoides 属の全種になる。
分布的には Dryobates属 (#コアカゲラの備考参照) と似ているが、Picoides 属はより古い時代に北半球北部に分布を広げたもの。
日本では 1988 年以降観察記録が途絶えていたが、2006-2011 年に観察記録が報告された [稗田他 (2013) 北海道におけるミユビゲラ Picoides tridactylus の観察記録]。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 77 (1946 年初出) ではミユビゲラの名称は樺太産のものに使われており、北海道にもいることがわかってエゾミユビゲラの名称が与えられた。他にチシマミユビゲラ、チョウセンミユビゲラの名称が示されていた。樺太産が本家の名称だった事例を初めて知った。形態的特徴が明瞭だったので、カラフトなんとかゲラのような名称にならなかったのだろう。
絶滅危惧 IA 類 (CR)。国内希少野生動植物種。種全体としては IUCN で懸念なしに分類されている。
ミユビゲラでは和名、英名、種小名ともに指が3本の意味 (tridactyla はミツユビカモメにも出てくるが、ミユビシギは学名・英名にはこの意味は現れない)。
スズメ目でも例があってミユビダルマエナガ Cholornis paradoxus Three-toed Parrotbill。
かつては Paradoxornis 属で、かつての属名、種小名ともに paradoxos (Gk) 変わった、特別な の意味を含んでいる。さまざまな点が異常との記述で digitus externus が非常に短い点は当時の Cholornis 属の特徴に含まれているが、特に趾が3本を指したものではなかった。
Paradoxornis 属もミユビダルマエナガがタイプ種ではなく、属が分割された際に Cholornis 属に戻ることになった。
スズメ目で特例の趾が3本にふさわしい学名になっているとの解説を見ることもあるがこれは正確ではない。
-
キタタキ
- 学名:Dryocopus javensis (ドゥリューオコプス ヤウエンシス) ジャワのカシノキを打つ鳥
- 属名:dryocopus (合) カシノキを打つ鳥 (drus カシノキ kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 種小名:javensis (adj) ジャワの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:White-bellied Woodpecker
- 備考:
dryocopus は#クマゲラ参照。
javensis は場所の -ensis の冒頭が長母音になりそうだが、おそらくその前の v を u の音で読むために主に短母音で読まれるよう。アクセントは -ven- = -uen- の位置にあるが2重母音的な扱いのため "ヤウエンシス" とした。-ensis の冒頭にアクセントを置くつもりで読んで問題ないだろう。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では亜種 richardsi (英国海軍 George Henry Richards とその息子にちなむ) が挙げられている。英名 Tristram's woodpecker (記述した英国鳥類学者 Henry Baker Tristram にちなむ)。
Boyd によれば Dryocopus 属は単系統でない可能性があり、新世界のものは別属になる可能性があるとのこと。
歴史的には日本の対馬と朝鮮半島に生息していたが、狩猟と西洋博物館の標本にするための採集によって対馬の個体群はほぼ消滅し、黒田 (1920) が採集した標本が最後のものになった。韓国でも森林伐採により減少し、1952 年から法的保護を受けることになったが 1989 年に消滅し、1993 年に非武装地帯で目撃されたが 2017 年に公式に絶滅が宣言された。
現在では北朝鮮のみに生息すると考えられるが個体数は 50 羽より少ないと考えられる (wikipedia 英語版)。Birder (2019) 33(1): 32-33 に北朝鮮のキタタキの記事があり (分布図も掲載)、最後に巣立ちが目撃されたのは 2003 年とのこと。
島の亜種が多く、絶滅が懸念されているものも多い。種全体としては IUCN で懸念なしに分類されている。
「全集日本野鳥記」(講談社 1985) 1 に収録されている「キタタキ 生きていた幻の鳥」(鴨川誠 1975 初出) に詳しい。
1972.8 の韓国での聞き取り調査でキタタキのスライドを見せていると、老人が「鳥は、戦争で、いなくなった」と日本語で答えて立ち去ったとのこと (p. 263)。
p. 321 にはキタタキの存在が学会に発表されていらい海外からも (対馬のキタタキの) 標本の注文が頻繁にあり乱獲して輸出されたと伝えられている。島内の学校にも標本がかつては保存されていたが今はないとのこと。
種としての基産地はジャワ島だったが、亜種 Dryocopus javensis richardsi Tristram, 1879、記載時学名 Dryocopus richardsi (原記載) 基産地 Tsushima が発表され、当時は別種扱いであったため世界の注目を浴びて標本が求められた状況が想像できる。
原記載では当時の Tzus Sima は日本と朝鮮半島の間にあって seldom visited ([動物学的には] ほとんど調べられていない) 状況だった。採集した多くの種は日本と同じ型と考えられたが、このような大きなキツツキは日本で知られておらず別種と考えられ、あえてここに発表する、との表現になっている。
当時の学名で Thriponax hodgsoni 現在はキタタキの亜種 hodgsoni や Thriponax crawfurdi (現在では基亜種に相当するものの旧名) と似ているが、この属 (当時 Thriponax) は広域に隔離分布しており、中間地域で見つかっていないとのこと。また北京のクマゲラは違う、と書かれている。
つまり、これまで知られている類縁種 (当時は種扱い) の分布と大きく違うため、分類学上興味を持たれて海外から発注が相次ぐことになったのだろう。なぜ注目されるのか国内ではまだ理解されていなかったかも知れない。
ほぼ同じような時代に乱獲されたルリカケスも同様であったが、当時は日本にとってよい輸出品になっていたのかも知れない。
Thriponax richardsi の学名は YIO-15654 (山階鳥類研究所) の古い標本などにも見られ、当時は種扱いであったことがわかる。別名「あまのじゃく」が記されている。学校にも標本があるぐらいだったはずだが日本産のものは少数しか残っていない。
[ハシジロキツツキは生き残っているか]
アメリカ国内においてハシジロキツツキは絶滅したと一般に考えられているが、探索はまだ行われている模様。
Williams, Mission Ivorybill (2024) Spectrograms of Ivory-billed Woodpecker (Campephilus principalis) kent sounds from seven expeditions show 587 Hertz as a pattern (preprint)
は形態から予測される発声に合致すると考えられる音声が記録されている証拠について議論しており、まだ生き残っている可能性を考えている。
比較できる確実な過去の音源も少ないために難航している様子。cf. XC770846 (2022 年の録音)。
キツツキの声やドラミングが聞こえても姿が見えないのはごく普通にあり、難航しているのはよく理解できる。他にも "double knock" が特徴的らしいが肝心の時に録音をしていなかった、とか。
ハシジロキツツキに特有とされる "double knock" の発音メカニズムを考察した論文: Collins (2017) Periodic and transient motions of large woodpeckers
体を調和振動子と考えて周期的な外力を加えると通常のドラミングが再現できるが、同じ条件で瞬間的外力を作用させると2回の振動 (余波みたいなもの) が再現できるとの考察。木を打ったところで 0.8 倍の速度で反発する仮定になっているがそれほど反発力があるのか (?) この値次第のような気がする。
もしハシジロキツツキが絶滅していれば、最大のキツツキはボウシゲラ Mulleripicus pulverulentus Great Slaty Woodpecker (東南アジアなど) で、こんな形態でドラミングができるのかと思ってしまうが、記述にも録音にもドラミングが出てこないので、我々が想像するようなドラミングはおそらくあまり行わないのではと想像する。
飛んでいる姿はサイチョウ目 Bucerotiformes を思わせるところがあり、分子系統からも近縁とされる類似性が見える感じがする (なおボウシゲラの系統がキツツキ類で原始的というわけではない)。
採食方法は "gleaning" (採集) が最も一般的で、木の割れ目などなどから食物を集めるとのこと。生態的にはサイチョウ類やカラス類に似ているとのこと (wikipedia 英語版より)。
-
クマゲラ
- 学名:Dryocopus martius (ドゥリューオコプス マールティウス) マルスのキツツキ
- 属名:dryocopus (合) カシノキを打つ鳥 (drus カシノキ kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 種小名:martius (adj) 軍神マルスの
- 英名:Black Woodpecker
- 備考:
dryocopus は -copus 部分は#アカゲラ参照。ラテン語化の際に -us の語尾に変わったものと思われる。dryo- 部分は#コアカゲラ参照。
これらを合わせると dry-o-co-pus で y が長母音、o がアクセント音節となると考えられる (ドゥリューオコプス)。-pus が付くが足の意味ではないので長音にならない。
martius は冒頭が長母音でアクセントもある (マールティウス)。
火星の Mars もラテン語では長母音で読む。
ユーラシアの主に北部に広く分布。日本の亜種は広く分布する基亜種 martius だが、中国中部の山岳地帯にもう一つの亜種 khamensis が孤立して分布する。
本来森林性の鳥だったが、世界、特にヨーロッパでは一時は森林伐採で減少したものの森林性草原にも分布を拡大中とのこと。ユーラシア一般では普通種だがアジアの分布はより断片的で比較的まれとのこと (wikipedia 英語版)。Dryocopus 属のタイプ種。
種小名の語源について。Linnaeus 原記載 は 過去に使われた名称 Picus niger maximus (最大の黒いキツツキ). Gesn. av. 708. Aldr. orn. l. 12. c. 31. Will. ornith. 22. t. 21. Raj. av. 42. を紹介している。
Linnaeus はアメリカのハシジロキツツキ Picus principalis (当時学名) を最大のキツツキとして紹介 (Picus maximus) している。
これらから想像すると大きいことを表したものと考えられるが、wikipedia オランダ語版では 'gewijd aan Mars' (Mars に捧げられた) すなわち 'oorlogszuchtig' 好戦的な、喧嘩早いなどの意味と解説がある。
オランダ語名は zwarte specht (黒いキツツキ)。ドイツ語名 Schwarzspecht も同じ意味。
wikipedia ドイツ語版でも "Mars に捧げられた" と訳しており、おそらく軍神マルスと関係があって防衛行動を示している可能性があるが、Mars は本来肥沃と森の神であり、春の目立つドラミングと (つがい形成の際の) 鳴き声が Mars と結びついたかも知れないとのこと。古代ギリシャでは神託の鳥で動きで未来を占ったとのこと。
Mars に結びつく点はおそらく疑いないが、結びつきの理由はいくつかの解釈がある模様。
[キツツキの脳は反復衝撃による外傷が起きないのか?]
キツツキ類が脳挫傷を起こさないのかは長年の問題になっている。脳にダメージが加わらないいくつかの仮説が提唱されているがどれも確かなものではない。
キツツキ類の脳に異常タンパク質が蓄積していることを指摘した論文がある。
Farah et al. (2018) Tau accumulations in the brains of woodpeckers
この論文で調べられたキツツキ類と共通の属のものがクマゲラのため、ここに注記した。
タウタンパク質 (tau protein) というのはアルツハイマー病やパーキンソン病にも関係するもので、過剰なリン酸化がなされたタウの神経細胞への蓄積が毒性を示す (wikipedia 日本語版より)。
キツツキの脳はヒトの反復脳外傷などの病変などのモデルになるかと期待されていたが、
Smoliga (2018) Reconsidering the woodpecker model of traumatic brain injury
がキツツキは高度に適応したもので、鳥類学には興味があるだろうが医学にはあまり適用できないのではと医学のトップジャーナルに出した見解もあって研究が少し下火になっているのかも。
Hollin (2022) Consider the woodpecker: The contested more-than-human ethics of biomimetic technology and traumatic brain injury
も興味深い歴史レビューを出していて、初期にキツツキ類が脳挫傷を起こさない理由として提唱されたものはポピュラーな題材となって商業利用もされているが、肝心のキツツキ類で働いているかもよく確認されておらず 2016 年以降はキツツキ類で研究された論文もほとんどないとのこと。
メディアで有名になったことで話題が先走ってしまって科学的裏付けに乏しい模様。舌骨が役立っているとの研究も確認されていない。キツツキ類の解説でもよく取り上げられる有名になった古い研究をあまり強調しない方がよさそう。
より広範にさまざまな動物での脳の外傷性損傷の論文として Ackermans et al. (2021) Unconventional animal models for traumatic brain injury and chronic traumatic encephalopathy
があり、キツツキ類と大きなカスクをぶつけ合うオナガサイチョウ Rhinoplax vigil 英名 Helmeted Hornbill (学名は現在のものに合わせた) の例が扱われている。
キツツキ類におけるリン酸化タウタンパク質の蓄積は反復衝撃による外傷以外にも老化などの因子がどの程度関わっているかわからない。また哺乳類におけるリン酸化タウタンパク質の病原発現部位は皮質の「しわ」であり、これは鳥類にはない (哺乳類には大脳皮質があるが、鳥類ではそれに相当する構造が神経核の形で存在する違いがある) ので機構が違う可能性も考えられるとのこと。
異常タンパク質が蓄積が反復衝撃による外傷と結論づけるのはまだ早いようである。
Van Wassenbergh et al. (2022) Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks
キツツキの頭骨には従来言われていたような衝撃を和らげる機能はなく、むしろ固くてハンマーの役割を高めている。脳への衝撃は霊長類の脳にダメージを与える以下にとどまっているとの新しい研究がある。
Physiology: Woodpecker skulls are not shock absorbers (英文解説)。
嘴を覆うケラチン層の rhamphotheca の微細構造にキツツキに特有のものが見つかっている:
Lee et al. (2014) Hierarchical multiscale structure-property relationships of the red-bellied woodpecker (Melanerpes carolinus) beak
によれば rhamphotheca を構成するナノスケールのうろこ構造が他の鳥と異なっていて細長く、互いに重なりあう配置でずり応力 (shear) を分散させるのに役立つとともに剛性を高めているとのこと。嘴は黒いほど硬いらしい。ミクロン単位の構造がひび割れの進行を防いでいる。
これも細長い構造を作りやすい β ケラチンの性質の副産物のようなものだろうか。
Beatty et al. (2024) Comparative analysis of meningeal transcriptomes in birds: Potential pathways of resilience to repeated impacts
硬膜における遺伝子発現を調べた結果、セジロコゲラ Dryobates pubescens Downy Woodpecker ではエボシガラ Baeolophus bicolor Tufted Titmouse に比べて免疫にかかわる遺伝子の発現を調節しているようで炎症を抑えている可能性がある。細胞ストレスに反応に関係する遺伝子などの発現が強く修復に関わっている可能性がある。
キツツキでもやはり脳損傷が発生しているが修復機構など通じて影響を和らげているよう。
-
アオゲラ
- 学名:Picus awokera (ピークス アオケラ) アオゲラのピークス
- 属名:picus (m) ピークス (キツツキに変えられた伝説の人)
- 種小名:awokera (外) アオケラ (日本の特産種 kera 鳴き声から)
- 英名:(Japanese Woodpecker), IOC: Japanese Green Woodpecker
- 備考:
picus は#ヤマゲラ参照。
awokera はラテン語風に発音すれば "オ" にアクセントがある。"アウォケラ" または "アオケラ"。
アオゲラの名称は古くからあるものと想像したが意外に用例が少ないよう。「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710) きげら/あおげら、「百千鳥」(1799) の青列鳥 (あおげら) が同定されている。アオゲラの呼称はもう少し歴史を見た方がよさそう。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の和名も Awokera となっていて濁音になっていない。他の和名はすべて -gera "ゲラ" と濁音となっている。アオゲラだけはアオケラと呼ばれていたのかのかも知れない。
また属も Gecinus となっていた。これは Boie (1831) が名付けた属で ge 地面 kineo 動く (Gk) から。ヨーロッパアオゲラ、ヤマゲラなどが含まれていたがアオゲラは記載前。Gray (1840) がタイプ種をヨーロッパアオゲラと指定した (The Key to Scientific Names)。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 86 p. 8 ではアオケラやヨーロッパアオケラの表記となっていた。
日本固有種。3亜種あり awokera アオゲラ (本州と一部の離島)、
horii (由来は後述) カゴシマアオゲラ (四国、九州)、
takatsukasae (鷹司信輔公爵が由来) タネアオゲラ (種子島、屋久島)。
太田 (2006) アオゲラの亜種分類基準の再検討と新たな分類基準の設定が日本鳥学会ポスター発表された。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)に「亜種不明」がリストされている。
亜種一覧を示しておくと (記載時学名、基産地は Avibase から)、
・Picus awokera Temminck, 1836 (原記載; Fauna Japonica の記載。原記載ではない; 図版) 基産地 Japan, i.e. Honshu 亜種アオゲラ
・Picus awokera horii Taka-Tsukasa, 1918 (原記載) 基産地 Kagoshima カゴシマアオゲラ
・Picus awokera takatsukasae Kuroda, 1921 (原記載) 基産地 Anno, Tanegashima タネアオゲラ
・Picus awokera etigo Momiyama, 1927 * (資料) 基産地 Shionomachi-mura, Iwafune-gun, Prov. Echigo, Hondo, Japan = awokera?
・Picus awokera tosa Momiyama, 1927 * (資料) 基産地 Sakawa-machi, Takaoka-gun, Prov. Tosa, Shikoku = horii?
* は Avibase に登場しない。
= の後は分布から現在先行シノニムとなっている亜種を推定したもの。
カゴシマアオゲラの horii の由来を調べておくと、人名ではなく掘る音「ホリホリ」の模写とのこと The Key to Scientific Names 出典不明) などと書いてある。
horii の原記載 のページからは由来はわからないが論文冒頭の p. 438 に堀井榮吉の名前があり、由来ではないだろうか。
堀井榮吉氏は「鹿兒島地方ノ鳥類ニ就テ」Japanese Journal of Ornithology 1 (5), 77-88, 1917 や「新領土南洋諸島動物調査報告書」(1916) などの著作もあり献名されたものだろう。これを読解するのは確かに日本語がわからないと難しいだろう。
この稿をまとめるにあたって本州と九州のアオゲラが別亜種であるらしいことを初めて知ったが、各種図鑑でも亜種の違いは積極的に述べられていない。そもそも亜種に値するのだろうかとの根源的疑問もあるが、コゲラの方は同じ Temminck の記載でも基産地が九州に限定されている。
アオゲラも同じであってもよさそうに感じるがそうなっていないのは、おそらくコゲラの基産地を日本から九州に限定したのが海外研究者で、アオゲラの方は同時期に亜種の記載がなかったために基産地が日本のままとなっていたものだろう。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire にも Siebold の標本産地の推定は特に出ていないが、Pryer collection は横浜から、Ringer は長崎近く (Blakiston のリストにある) とのこと。
Taka-Tsukasa (1918) にも基産地の明確な記述はなく、本州産の「あをげら」に比べたものになっている。暗黙で Temminck のものを本州と考えたものだろうか、しかし horii の基産地は鹿児島なので、Temminck の基産地を九州北部 (例えば長崎付近) としてもこの時点では整合性があったことになる。
horii の分布を九州・四国としたのはこの後の時代で、Kuroda (1921) にこの形で現れていた。
Kuroda (1921) によれば小川 (1905) が種子島の標本と本土のものを比較し、同じであると述べていたが、黒田氏の見解では九州の方が色が濃く、種子島のものが一番濃いので小川の見解は間違いであると述べていた。献名となった Prince N. Takatsukasa は日本鳥学会の会長だったとのこと。
アオゲラの英名はまったく不自然なところを感じさせないが、これはヨーロッパアオゲラ Picus viridis Eurasian Green Woodpecker の従来の英名 Green Woodpecker との対比ではないかと想像した。viridis = 緑色の なのでヨーロッパアオゲラの英名は学名と同一。
探してみるとやはりアオゲラに別名が使われていてフランス語名 pic vert japonais (日本のヨーロッパアオゲラ。Temminck のフランス語名とは別物) があった。ヨーロッパから見ればヨーロッパアオゲラの方が本家で、それに "日本の" を付けた状況になっている。アオゲラがヨーロッパアオゲラの亜種となった状況は見つけられなかったが状況はそれに近い。
ノスリのようにヨーロッパアオゲラに別の属名が与えられていればあるいは japonicus が付いていたかも知れないが、Picus のように広義だとさすがに使えなかっただろう。
Nouv. Recueil Pl. Color. Ois. の Picus awokera Temminck, 1836 (原記載) ではフランス語名 pic Awokera。この時点ではヨーロッパアオゲラとは種が違う (il forme toutfois une espece distincte) と記している。
種が違う以上、当時の表記で Picus viridis の後に装飾的に補うわけには行かなかったのだろう。
和名では son nom japonais designe Kera-vert (緑の "ケラ" と名付けている) と記している。
記述には学名が和名由来と明瞭に述べているわけではなく、Kera がキツツキを意味することも示していない。この記載だけを読んだ者には何のことかわからなかったかも知れない。
文章を深読みすればヨーロッパアオゲラを指して Pic-vert と述べているので、それに対比した表現とみなせば "日本語で (フランス語と同じように) Pic-vert に対応する意味で呼ばれている"、と解釈することができ、Kera = Pic と理解できる次第となるが、これは和名を知っているからこそ判断できる内容に思える。
この点はコゲラの記載でも同じで和名由来とは明瞭に述べていない。Pic Kizuki ou (または) Kizuzuki の表現となっているのみ。
また vert とあるのも興味深いところで、緑色を指して "awo" を用いていたらしいこともわかる。
アオゲラの漢字表記では "緑" が用いられるがこれはアオバトも共通。
しかし、Temminck は何と 図版 ではアオゲラの図版に Pic kuzuki とコゲラのフランス語の名称を与えている (!)。また大文字の用法も一定しておらず、こちらは kizuki と小文字になっている。
図版に学名が記載されていなかったためどちらに先取権があるか問題は発生しなかったようだが、後の研究者が "アオゲラの図版がない" とコメントを残す原因となっていたよう。
つまり後の研究者も文章を読んで Kera-vert = Awokera と気づかなかったと思われる。
我々が見ればコゲラとアオゲラを間違える心配はないが、現物をまったく知らない者にとってはこのアオゲラの図版こそがコゲラだと考えたのだろう (このスキャンの訂正書き込みに現れている。本文記載の図版番号は正しい)。
Temminck にとってもこの時点では "kuzuki" が何を指すかあやふやで、図版の名称が間違っていても気づかないぐらいだったらしい。同書の他の図版と比較すると kuzuki は外来語由来の名詞ではなく形容詞扱いとなっていた模様。
学名を付記しておらず後世を困らせることにならなかった点はまだよかったが、またまたありがたみが薄れそうな事例だった。
"Fauna Japonica" の記述では le pic-vert Awokera とあり、この時期には上述 Boie (1831) が Gecinus と名付けた pic-vert のグループ名を用いたとある。当時の学名でネパールの P[icus] squamatus 現在はヒマラヤアオゲラ Picus squamatus Scaly-bellied Woodpecker (Vigors 1831 が記載)
と P[icus] occipitalis (参考) の類縁種が知られていたため、ヨーロッパアオゲラを基本種とする種グループをなすと考えた結果のよう。
後者は Picus occipitalis Vigors, 1831 (図版参考) とヒマラヤで記載されたものだが、Picus occipitalis Valenciennes, 1826 (参考) 基産地ギアナ の用例がすでにあって無効な学名だった。従って現在亜種やシノニムを探しても現れない。
Temminck 自身はこの属名を用いていないが、もし用いて Gecinus ... としていれば ... の部分には awokera よりも日本を指す形容詞が入っていたかも知れない。
Temminck (1836) ではこの種グループを認識していなかった段階で Picus awokera の学名や対応するフランス語名を先に付けたため、そのまま awokera を用い続けた可能性も考えられる。
"Fauna Japonica" の段階で少し理解が進んで、改めて種グループを検討し直したと考えられる。
もっとも Temminck (1836) は日本から2種 (アオゲラとコゲラ) を記載しており、複数種が存在する場合には日本を意味する学名を原則的に用いなかったようで (#タンチョウの備考参照)、いずれにも現地名を用いるのが既存学名との重複の心配もなく簡単だったのだろう。
もし "日本の" を付けるならばアオゲラの方がヨーロッパアオゲラと対応関係がよいのでこちらに付けるの方がふさわしいが、Temminck (1836) では別種だと述べて亜種的 (race) とみなしていなかったため、"日本版" に相当する学名を与えなかったと想像できる。本文冒頭には大文字固有名詞扱いで "Pic du Japon" (ただし表題には用いていない) とあるのでこの点はある程度は意識していたと思われる。おそらくどちらにするかは多少悩んで、コゲラもあるので Pic Awokera を選択したものだろうか。
参考までにこれら類縁種の亜種数を見ておくと IOC 14.2 でヨーロッパアオゲラは3亜種、ヨーロッパアオゲラから遺伝情報をもとに分離されたイベリアアオゲラ Picus sharpei Iberian Woodpecker は単型種。ヒマラヤアオゲラが2亜種。
ヨーロッパアオゲラは過去に多くの亜種が認められていたが3亜種に整理された模様。
日本固有種なので現在の英名も適切となったものだろう。ノルウエー語の Samuraispett はちょっとお笑い感がある。ヒマラヤアオゲラの Scaly-bellied Woodpecker に対応する Wavy-bellied Woodpecker の英名もあったらしい (Avibase による)。英名は Japanese Woodpecker では Temminck も指摘する通り日本に1種しかいないようにも読めてしまうので Japanese Green Woodpecker の方が適切なのだろう。
アオゲラに近縁のヨーロッパアオゲラのゲノム解析と系統樹: Forest et al. (2024) Chromosome-level genome assembly of the European green woodpecker Picus viridis。現在の属分類ともよく整合するとのこと。
試しに簡単にできる範囲で MF766703.1 を出発点に ND2 遺伝子の BLAST をやってみるとアオゲラとヨーロッパアオゲラ、ヤマゲラがグループを作るというよりはアオゲラの方が古く分岐した系統となった。
ヨーロッパアオゲラとヤマゲラの関係ではヨーロッパアオゲラがまとまった系統をなし、ヤマゲラはコシアカアオゲラ Picus erythropygius Black-headed Woodpecker (東南アジア大陸部) とモロッコアオゲラ Picus vaillantii Levaillant's Woodpecker とまとまった系統をなす結果となった。
アオゲラより古く分岐したものにはタケアオゲラ Picus vittatus Laced Woodpecker (東南アジア)、ヒマラヤアオゲラ Picus squamatus Scaly-bellied Woodpecker、ムナフタケアオゲラ Picus xanthopygaeus Streak-throated Woodpecker (インド、中国、東南アジア) が系統を作り、確かにアオゲラに似た印象がある。
これらの種の分布を考えると、アオゲラの祖先系統は南アジアから東アジアにかけて種分化し、海を越える分散能力が高くないため日本にはアオゲラを残したと見ることができそう。そのためアオゲラは南方系で、おそらく後に北方系のヤマゲラ系統が分布したため北方や大陸はヤマゲラが支配的となったものと想像できる。
アオゲラの祖先は先発の系統だったため、大陸にヤマゲラが進出するとあまり得意でない朝鮮半島などの生息環境では競争排除されたのかも知れない。
ヤマゲラ近縁種の系統は陸続きの範囲で南方にも進出したが限定的で、南方ではアオゲラおよびその祖先系統の方が有利だったらしいように読める。ヤマゲラ系統はユーラシア大陸西部ではヨーロッパアオゲラとの競争もあっただろう。部分的には同所的に分布するが、大陸西部ではヨーロッパアオゲラの方が少し優勢に見える。
この系統樹で見られる範囲では Picus 属で最も古く分岐したものはヒメアオゲラ Picus chlorolophus Lesser Yellownape でアオゲラとは相当異なって見えるがやはり東南アジアに分布でこのあたりがアオゲラ類の発祥の地らしい様子がわかる。
この程度のことならば日本語の解説記事があるのではと想像したが簡単に探した範囲で見当たらなかった。
系統解析の論文では Dufort (2016) An augmented supermatrix phylogeny of the avian family Picidae reveals uncertainty deep in the family tree
が広くキツツキ類の系統関係を探ろうとしている。オープンアクセスでないので今ひとつの情報量だが系統樹は見られる (Semantic Scholar。Picus 属に限ってみるとここで議論したものと同じような結果が得られている。簡易系統樹でもかなりのことはわかると想像できる。
Benz et al. (2008) Evolutionary history of woodpeckers and allies (Aves: Picidae): placing key taxa on the phylogenetic tree ではサンプルがまだ限られていた。キツツキ類の適応放散は新世界で主に関心が持たれているようで我々が気にする地域や種の研究は意外に少ない。
-
ヤマゲラ
- 学名:Picus canus (ピークス カーヌス) 灰白色のピークス
- 属名:picus (m) ピークス (キツツキに変えられた伝説の人)
- 種小名:canus (adj) 灰白色の
- 英名:Grey-headed Woodpecker
- 備考:
picus は冒頭が長母音 (ピークス)。
canus は冒頭が長母音 (カーヌス)。
ヨーロッパから東南アジアに広く分布する種類で 10 亜種が認められている (IOC)。日本(北海道)の亜種は jessoensis (蝦夷の) とされ、シベリア東部、中国東部・東北部、朝鮮半島、ロシア極東部、サハリン、北海道に広く分布する。
朝鮮半島の亜種は griseoviridis と扱われることもあるが、通常は jessoensis に含まれる。ユーラシアの北方亜種はこの亜種と、シベリア西部から西に生息する基亜種 canus。他の亜種は中国から東南アジアに分布する。
英語別名 Grey-faced Woodpecker で HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v9 (Oct 2024) などではこちらを用いている。
jessoensis の記載時学名は Picus canus jessoensis Stejneger, 1886 (原記載) 基産地 Sapporo, Hokkaido。Yesso Green Woodpecker と名付けている。
perpallidus は同じ Stejneger (1886) の次ページで、ウスリーのものを指したもの。脚注に現れる。Dement'ev and Gladkov (1951) では jessoensis のシノニムとしている。
griseoviridis の記載時学名は Gecinus canus griseoviridis Clark, 1907 (原記載) 基産地 Seoul, Korea。
この当時は perpallidus も亜種と認識されていたため、同程度の違いがあれば別亜種として記載されていた模様。
Dement'ev and Gladkov (1951) の注記では多くの文献で極東とヨーロッパのヤマゲラには全く違いがないと述べられているが、そんなことはなく色が違うと述べている。この当時は 15 亜種だったが Picus dedemi Sumatran Woodpecker が 2021 年に分離された。色彩は全く違っている。
Picus 属のタイプ種はヨーロッパアオゲラ Picus viridis European Green Woodpecker。
特にイギリス英語ではこの種を指して Green Woodpecker と呼ぶことが普通だった/なので、それに対応する色彩の違いを表現して Grey-headed を英名に用いたのではないだろうか (種小名も同様)。ヤマゲラは英国には分布しないので単に Green Woodpecker と呼んでも紛らわしくない。
アオゲラのメスも "Grey-headed" と言えるのではないかと言いたくなるかも知れないが、あくまで英国事情で付けられた英名と考えれば納得が行く。
-
ノグチゲラ
- 第8版学名:Dendrocopos noguchii (デンドゥロコポス ノグキイ) 野口のキツツキ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sapheopipo noguchii (サペーオピポー ノグキイ) 野口の独特なキツツキ
- 第8版属名:dendrocopos (合) 木を打つ者 (dendron 木 kopos -を打つ < kopto 打つ Gk)
- 第7版属名:sapheopipo (合) 独特なキツツキ saphes, sapheos 独特な pipo キツツキ (Gk) (The Key to Scientific Names)
- 種小名:noguchii (属) 野口の (採取者)
- 英名:Pryer's Woodpecker (英国商人・博物学者で日本で横浜に住んでいた Henry James Stovin Pryer が由来)。IOC: Okinawa Woodpecker が使われることが多い
- 備考:
dendrocopos は#アカゲラ参照。
sapheopipo は The Key to Scientific Names の語構成に従えば saphes は e が長母音、pipo も末尾が長母音。そのまま取り入れれば中央の o がアクセント音節で "サペーオピポー" となる。今後使われる必要性はないだろうが参考までに。
記載時学名 Picus noguchii Seebohm, 1887 (原記載)。Pryer の助言により命名したとある。
旧属名は saphis 明確な Gk、picchio キツツキ 伊 と ノグチゲラ (環境省 2007, 2010, 2018) の解説で説明されている。
この属名は Hargitt (1890) Cat. Bds. Brit. Mus., 18, 1890, p. 6 (目次), p. 378 がノグチゲラに与えたもの (The Key to Scientific Names)。
かつては単形属とされたが、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Dendrocopos 属に移動、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
Sapheopipo 属は消滅 (Dendrocopos のシノニムとなる)。
ノグチゲラがオオアカゲラに近縁であることは Winkler et al. (2005) On the phylogenetic position of the Okinawa woodpecker (Sapheopipo noguchii) で明らかにされ、国内の報道記事にもなった。
この結果は Fuchs and Pons (2015) でも確認された (#コゲラの備考を参照)。
特別天然記念物。絶滅危惧 IA 類 (CR)。IUCN でも CR 種。
△ ハヤブサ目 FALCONIFORMES ハヤブサ科 FALCONIDAE ▽
-
ヒメチョウゲンボウ
-
チョウゲンボウ
- 学名:Falco tinnunculus (ファルコー ティンヌンクルス) チョウゲンボウ
- 属名:falco (m) ハヤブサ
- 種小名:tinnunculus (m) チョウゲンボウ (tinnio (intr) 甲高い声をあげる)
- 英名:Kestrel, IOC: Common Kestrel
- 備考:
falco は#チゴハヤブサ参照。
tinnunculus は tin-nun-cu-lus と区切り、-nun- にアクセントがある (ティンヌンクルス)。
種小名は文字表記から上記解釈が受け入れられているが、titiunculus などの別綴りもあり、Lindsay (1918) は titus (モリバト) 由来の可能性を指摘したとのこと。この語源をもとにした類縁単語はロマンス系ヨーロッパ言語にいくつもあるとのこと (wiktionary)。音声由来ではない可能性も残り、よく説明されるチョウゲンボウの学名ですら語義が確立しているわけではないらしい。
英語 kestrel は中世英語の castrel (猛禽類)、これは中世フランス語の cresserelle, crecerelle (猛禽類) で通常は crecelle (現代ではがらがらと音を立てる玩具に対応) 由来とされるがこの語源はよくわかっていない。
中世ラテン語 clisterella (チョウゲンボウと推定されている) とも関係するかも知れないとのこと。より似て見える crepitaculum の指小形の俗ラテン語 *crepicella, *crepitacillum < crepitare (割る) を語源とする考えは語形の点で説明困難とのこと。
鳴き声由来で中世オランダ語 craken などからの可能性もあり、この単語は英語の creak などにも関係がある。
英語別名に windhover もあり、こちらは習性から大変わかりやすい。別名 staniel もあって中世英語の staniel (猛禽類) から。由来は stan (石、岩) + gella (叫ぶ、鳴く) とのこと。現在の英語 stone にも関係がある (英語語源は wiktionary より)。猛禽類の鳴き声は昔から相当目立っていた模様。
ロシア名の pustel'ga は他の語との類縁関係をあまり思いつかず覚えにくい単語と感じていたが、Kolyada et al. (2016) の語源辞典でもそれほどよくわかっていないよう。pustoj (空っぽの) に関係していることは着目されているが、関連が今ひとつすっきりしない。
一つの解釈は pustynya (砂漠、荒れ地) に生息していることだが、砂漠はだいぶ印象が違うので誰もが納得する解釈とはなっていないよう。もう一つが鷹狩りに役立たないため "空っぽの" となったとするもの。納得できるようなできないような。
日本語の "馬糞鷹" と微妙に似ている感じもするが指している意味は多少違うかも知れない [南米に英語で Roadside Hawk 属名で Rupornis < rhupos 汚物 ornis 鳥 Gk があって "馬糞鷹" はこちらの方が近い感じがする (#トビ備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] 参照]。
しかし pust- の語幹は "空っぽの" 関連しか思いつかないのも事実。
[亜種と記載経緯]
ユーラシアからアフリカに広く分布する。11 亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で interstinctus (まだら模様の) 亜種チョウゲンボウであったが、
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で基亜種 tinnunculus チョウセンチョウゲンボウ (和名からは朝鮮半島を想像するが、ヨーロッパから中央シベリア東部にかけて、中央アジアなどに広く分布する。Clements checklist では朝鮮半島は分布域とされていない)
が追加され、さらに亜種不明が追記された。
かつてチョウゲンボウの亜種とされたミナミアフリカチョウゲンボウ Falco rupicolus Rock Kestrel が分子系統解析 (Fuchs et al. 2015) の結果種に昇格となった。IOC 14.2 では同種扱い。
この学名由来のメジロチョウゲンボウ Falco rupicoloides Greater Kestrel は別種扱い。Tinnunculus rupicolinus Heine & Reichenow, 1890 (参考) と新名を与えられた経緯があるが現在はもとの種小名が使われている。
なお日本のチョウゲンボウの記載経緯は複雑で (#ノスリの備考も参照)、
(Bulletin of the British Ornithologist's Club) Ticehurst, CB 1929, Bull. Brit. Orn. Club 50 p. 10 によれば Falco japonicus が先にあることが見逃されているとのことで、チョウゲンボウの亜種名 Falco tinnunculus japonicus Temminck and Schlegel, 1844
(図版 1, 2。"Fauna Japonica" の代表的図版であった) は無効。
Falco tinnunculus japonensis の新名が提唱される複雑な状態だったらしい。
Temminck (and Schlegel) が japonensis でなく japonicus を用いたのはおそらく使い分けていた (#タンチョウの備考参照)。
しかし (参考) によれば Falco japonensis Gmelin, 1788 の名称 (Falco japonensis 参考) が訂正されて Falco japonicus Latham, 1790 と新名が与えられたものだった。
japonensis は後にハヤブサの亜種となってこの名前で生き残っている。
つまりこの時点の japonicus はハヤブサのことでチョウゲンボウの亜種にはならなかった (ハヤブサ亜種の japonensis のシノニムとなる)。
ここで japonicus, japonensis のいずれも使われてしまっていたため、後に Falco tinnunculus japonicus Temminck & Schlegel, 1844 と付けられたものも、それを改名された Falco tinnunculus japonensis Ticehurst, 1929 のいずれも有効な学名として残らなかったと考えられる。
Temminck & Schlegel は時代背景的には亜種としての記載ではなく、ヨーロッパのチョウゲンボウの日本版の位置づけだろう。
Latham が Gmelin の学名の訂正を行っていなければおそらく有効な亜種となっていたのだろう。
Falco japensis Bechstein, 1793 (参考) なる名前まで出てくる。これも Bechstein が Falco japonensis の問題点に気づいて Latham と独立に新名を与えたもの。
Latham も Bechstein も Gmelin の Falco japonensis は問題があると判断して新名を与えたようだが、あるいは先に用例があったのだろうか。現在はこの学名が使われていることを見ると先にあった用例は学名と判定されなかったなどの経緯も想像できるが詳細は不明。
このことは多分忘れ去られていて Gmelin の Falco japonensis すら Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも出てこないので、Temminck & Schlegel が気づかなかったこともやむを得ない時代だったのだろう。
このことを知っていれば Temminck & Schlegel が別の学名を与えていたのだろうが、おそらく気づいていなかったのだろう。
さらに Falco Buteo Japonicus Temminck & Schlegel, 1844 があり (#ノスリの備考 ["Himalayan Buzzard"] 参照)、これは現在 Buteo 属になっているため衝突しているわけではないが、Falco 属のままであればこれも問題となっていたことになる。
ノスリでは実際に問題となった時期があって Dement'ev and Gladkov (1951) は japonicus を採用していなかった。
同じものかどうかよくわからないが、Falco japonicus はかつては学名として使われていたらしく、
Black Chinned Gosshawk [Schwarzkehliger Habicht; Falco japonicus]. Kolorierter Stahlstich von Lizars nach Swainson
のように 1840 年ごろの "The Birds of Western Africa, part of The Naturalist's Library" (Swainson) のようにアフリカでもこの名前が出てくる。
もしチョウゲンボウのことを指しているならば Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 の方がもちろん早いので別種とされていた時代の産物かも知れない
(ただチョウゲンボウの名前なのかタカ類の一種を指しているのかは表記上はよくわからない。Schwarzkehliger Habicht も Black Chinned Gosshawk も現在使われていない名称。英語・ドイツ語名からはオオタカ類を意味するように見える)。
このように見るとチョウゲンボウの Falco tinnunculus japonensis は別のものにシノニム化された (Avibase の表示ではそのように見える) というより、ハヤブサの亜種で先に使われているのでそもそも無効だったよう。
世界の主要チェックリストでは Peters' Check-list of the Birds に現れたのみだった。
1930 年代の話で、Ticehurst (1929) の指摘を受けて取り入れたが、preoccupied であることがすぐに判明したものと想像される。
無効でリストにも現れなくなった学名はおそらく早々に忘れられ、地理的亜種として意義があるかどうかもあまり検討されなかったかも知れない。有効な学名として残っていれば現在でも島の亜種として取り扱われている可能性もあったのでは?
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代にはまだ判明しておらず Falco tinnunculus japonensis の学名が使われていた。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では亜種に値するかも知れないとの表現でこの学名を用いていた。
初野 (2012) Birder 26(9): 22-23 にチョウゲンボウの亜種の検討があり、シベリア東部、中国東北部と朝鮮半島で繁殖し、中国東部や東南アジアで越冬する (分布は Clements checklist による) perpallidus (per- 全体が、非常に pallidus 淡色の) の可能性のある個体を検討している。
Young Guns (2016) Birder 30(9): 44-47 で tinnunculus にヨーロッパチョウゲンボウ、perpallidus にチョウセンチョウゲンボウの名称が提唱されている。
この2亜種はかつてはシノニムとされ、tinnunculus が東西に分割された結果 perpallidus が認められるようになった経緯があるため、旧称の tinnunculus に先に大陸型としてチョウセンチョウゲンボウの名前が与えられていたのかも知れない
[未確認。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト等でのこれらの亜種が分離されて扱われているかは記載されている範囲で明確でなかっった]。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)にて基亜種 tinnunculus チョウセンチョウゲンボウ は亜種分類の変更に伴って削除とのこと。
チベット以東の中緯度帯のチョウゲンボウを interstinctus とする扱いとなった模様。後述の Seong et al. (2025) でも北京地域で2亜種越冬は否定的とのこと。
以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種記載もわかる範囲で含めた。
・Falco Tinnunculus Linnaeus, 1758 o (原記載) 基産地 Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761 (Linnaeus によりスウェーデンに限定)
・Falco alaudarius Gmelin, 1788 * (参考) 年は前後するが引用より下記のものの属を変えたもののよう (特に亜種や変種の意味ではなさそう) = tinnunculus
・Accipiter alaudarius Schaeffer, 1789 * (参考) 年は前後するが上記と同じ
・Falco rupicolus Daudin, 1800 o (原記載) 基産地 Cape of Good Hope (南アフリカ喜望峰) (ミナミアフリカチョウゲンボウ)
・Falco rufuscens Swainson, 1837 o (原記載) 基産地 no locality. Type presumably from Sierra Leone (シエラレオネと推定)
・Falco interstinctus McClelland, 1840 o (原記載) 基産地 Assam (インド)
・Falco tinnunculus japonicus Temminck & Schlegel, 1844 * = preoccupied で japonensis Ticehurst, 1929 と改名
・Cerchneis rupicolaeformis Brehm, 1855 o (原記載) 基産地 Egypt (エジプト)
・Falco saturatus Blyth, 1859 (原記載) 基産地 Ye, Tenasserim, Burma (ビルマ) = interstinctus
・Tinnunculus atratus Gray, 1869 * (参考 1, 2 saturatus の誤記と判定) = saturatus = interstinctus
・Falco neglectus Schlegel, 1873 o (原記載) 基産地 St. Vincent, Cape Verde Islands (カーポベルデ諸島セントビンセント)
・Falco tinnunculo similis Bruhin, 1875 * (参考 無効とのこと)
・Tinnunculus fuscatus Anderson, 1879 * (参考) = saturatus = interstinctus
・Tinnunculus minutus Millet-Horsin, 1912 * (参考) = tinnunculus (Hartert 1913 がシノニム化)
・Cerchneis tinnunculus canariensis Koenig, 1890 o (原記載) 基産地 Tenerife, Canary Islands (カナリア諸島テネリフェ島)
・Cherchneis perpallida Clark, 1907 o (原記載) 基産地 Fusan, Korea (韓国釜山島)
・Cerchneis tinnunculus carlo Hartert & Neumann, 1907 * (参考) 基産地 Bussidimo bei Harar となっているがこれは雑誌名のよう。Dement'ev and Gladkov (1951) ではアフリカ東部の湖水地方 = ?
・Falco tinnunculus dacotiae Hartert, 1913 o (原記載) 基産地 Lanzarote, Canary Islands (カナリア諸島ランザローテ)
・Cerchneis tinnunculus doerriesi Swann, 1920 * (参考) 基産地 Sidemi, E. Siberia = perpallidus (Dement'ev and Gladkov 1951), = interstinctus?
・Tinnunculus rupicolus rhodesi Finsh-Davis, 1920 * (アフリカ南西部 Dement'ev and Gladkov 1951) = ?
・Cerchneis tinnunculus objurgatus Baker, 1927 o (原記載) 基産地 Ootacamund, Nilgiris, southern India (インド南部)
・Falco tinnunculus japonensis Ticehurst, 1929 (原記載) 基産地 日本 (Temminck and Schlegel の鳥 Falco tinnunculus japonicus を改名。しかしおそらく preoccupied) = interstinctus
・Falco tinnunculus ultratinnunculus Kleinschmidt, 1929 * (参考) 基産地 Wladikaukaus (コーカサス) = tinnunculus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Cerchneis tinnunculus stegmanni Portenko, 1931 * (参考) 基産地 Oase Kelpen in Nord-Kaschgarien zwischen Tauschkandarja amd Kalpin (カシュガル北部) = tinnunculus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Falco tinnunculus archeri Hartert & Neumann, 1932 o (原記載) 基産地 Waghar Mountains, Somalia (ソマリア)
・Cerchneis tinnunculus ngamiensis Roberts, 1932 * (参考) 基産地 Shorobe, Maun District, Ngamiland, South Africa (南アフリカ) = ?
・Falco tinnunculus buryi Grant & Mackworth-Praed, 1933 * (参考) 基産地 Dthala, Amiri District, South Arabia; Menacha, Yemen, South Arabia (アラビア南部、イエメン) = ?
・Falco tinnunculus rubinoi Trischitta, 1939 * (参考) 基産地 Saredgna (サルデーニャ島。イタリア) 無効名?
・Falco tinnunculus tanganyikae Grant & Mackworth-Praed, 1933 * (参考) 基産地 Kigoma, Tanganyika Territory (タンガニーカ地方) = ?
・Falco tinnunculus alexandri Bourne, 1955 o (原記載) 基産地 Sao Tiago, Cape Verde Islands (カーポベルデ諸島サンチアゴ)
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
このようにみると日本のチョウゲンボウの記載はかなり古く、もしそのまま有効であればユーラシア東部を代表する亜種 (または日本列島の亜種) となっていたと思われる。しかし学名の重複が判明して新名が与えられたのが 1929 年と遅く、その間に他の亜種が記載されて先取権を奪われた上、改名された名称にも重複があって世界のリストに現れなくなった。
Gmelin の用例があり訂正された学名まで存在することが長く忘れられていて日本の立場からは一種の不幸な状況だったとも言える。
さらに考えてみると、アメリカチョウゲンボウに対して与えられた Tinnunculus 属 (Vieillot 1807) やチョウゲンボウに対して与えられた Cerchneis 属 (Boie 1826) もある程度使われており、亜種記載の用例を見ると属命名の 1807 / 1826 年から少なくとも 1932 年までは利用されていたことがわかる。
Tinnunculus 属は記載当初は (Falco tinnunculus の名称があるのに) チョウゲンボウを含んでいなかったとのこと (The Key to Scientific Names の情報から。Linnaeus の与えた種小名から直接属に昇格されたものではなかった)。
Tinnunculus 属は主にアメリカチョウゲンボウの亜種の記述、Cerchneis 属は主にチョウゲンボウの亜種の記述に用いられていた。
これらの属を用いる立場であれば Falco 属内の衝突は起きないので Cerchneis tinnunculus japonicus (Temminck & Schlegel, 1844) の学名は有効で問題なかったと考えられる。
Tinnunculus 属 や Cerchneis 属が Falco 属に世界的レベルで統合されたのが比較的後の時代だったため、新名が与えられたのが 1929 年と遅くなった可能性がある。
山階鳥類研究所の標本データベースでも 1920 年代の標本ラベルに Cerchneis tinnunculus japonicus の名称はかなり使われており、当時は標準の学名だったと想像できる。朝鮮半島の標本にも同じ亜種が使われていた。1900 年以前の標本には亜種記載がなく、和名の欄に学名が記されているなどチョウゲンボウの和名はかなり新しいと想像できる。
Falco 属を用いる場合には japonensis は有効な亜種名でなくなるため interstinctus に含められている模様で、Dement'ev and Gladkov (1951) でもユーラシア東部の亜種は緯度で区切っているようで日本も朝鮮半島も同じ亜種扱い。
perpallidus はユーラシア北東部の亜種として認めている (基産地は越冬地記載のよう) が、Dement'ev and Gladkov (1951) では通常は亜種ごとにある項目が interstinctus には設けられていない。
perpallidus の方が tinnunculus よりずっと淡色で赤みが少ないとのこと [Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では世界で 12 亜種でシベリアは perpallidus も含めて2亜種としている]。
Shokhrin et al. (2020) Nesting birds of Primorsky Krai: falcons Falconidae (pp. 4479-4513)
(極東の鳥類42:沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める) では沿海地方の亜種は interstinctus としている。
もし日本列島と大陸のチョウゲンボウで例えば遺伝的に亜種相当の違いがあるならば日本のチョウゲンボウの亜種は未記載となるのではないだろうか。もっとも Dement'ev and Gladkov (1951) が亜種の扱いに悩むぐらいなので少なくとも大陸では亜種の違いはあまりないらしい。
この亜種リストに現れる見慣れない属名の Tinnunculus はチョウゲンボウの種小名と同じ意味だが、チョウゲンボウをタイプ種として昇格したものではなく、アメリカチョウゲンボウ を指して与えられた (Vieillot 1807)。タイプ種は後にチョウゲンボウと指定された (Sharpe 1874)。
Cerchneis は kerkhneis, kerkhneidos (Gk) でチョウゲンボウの意味。Boie (1826) が当時の Falco rupicolus のみに与えた属名だった (これは IOC 14.2 ではチョウゲンボウの亜種) (The Key to Scientific Names)。
当時は別種だったがチョウゲンボウもこの属に含められた模様。タカ類も含めてあまりにも何でも Falco に含まれていたため分ける機運が高まっていた時代と想像できる。
以下は単なる仮想的な話だが、大型ハヤブサ類に対して使われる亜属 Hierofalco があり、属として用いられることもあった。もしこれを属とみなすならばハヤブサとチョウゲンボウは別属になるので、チョウゲンボウの亜種 japonicus (japonensis の方ではない) が有効になる可能性がある。
現在の亜種分布の通りであれば interstinctus の記載の方が早いので japonicus は interstinctus のシノニムとなると想像されるが、インドと日本のチョウゲンボウはどのぐらい違うのかの問題になりそう。
Falco 属はよくまとまっていて単系統をなし、保全分野でも Falco 属の概念は広く受け入れられているので属分割の機運はあまりないだろうが、カラカラ類ではもっと新しい分岐年代で属が与えられているので少し分けようとも考えられないことではないように見える (#ハヤブサ備考の分子系統樹を参照)。
Falco 属内部の最初の分岐でチョウゲンボウとハヤブサは別クレードに属するので Falco 属をもし最低限の2つに分けるだけでも japonicus は有効になると考えられる。
この場合は Falco 属のタイプ種のチゴハヤブサ (タイプ種をハヤブサとする扱いもある。#チゴハヤブサの備考参照) はハヤブサと同じクレードに含まれるため、チョウゲンボウを含むクレードの方の属名が変わることになる。これはこれでよくまとまったクレードで日本産種では他にヒメチョウゲンボウが含まれる。
他にもっと早い属名があるかどうかは調べていないがチョウゲンボウの旧属名 Tinnunculus または Cerchneis が復活する可能性もあり得るかも。Tinnunculus 属の過去の提案や包含範囲については#ハヤブサ備考の [ハヤブサ目の系統分類] に紹介されている。
Tinnunculus の方が古いが記載時のようにアメリカチョウゲンボウを含むと別クレードにまたがることになり分子系統上では適切な属でないかも知れない (詳しい規則は知らない)。
なおクレードをもう少し細かく分けた場合は Falco 属のタイプ種がチゴハヤブサのためハヤブサは Falco 属に含まれないことになる。
これもあまり分けたくない理由の一つかも (#オオタカ備考で紹介のように Linnaeus はオオタカの現在の種小名 gentilis をハヤブサのつもりで用いていたと想像でき、これがその通りに認められていればややこしい話は発生しなかった)。
そして japonicus が再度有効となれば大陸と日本のチョウゲンボウはどのぐらい違うか再検討されるのではないだろうか。もし interstinctus を大陸のものとするならばこれがチョウセンチョウゲンボウの概念によりふさわしくなりそうだが現在の名称と混乱を招くかも。
perpallidus は Dement'ev and Gladkov (1951) は "東のチョウゲンボウ" に相当する名称を与えている (ヨーロッパ側から見た概念)。この名称は日本では適切でないがシベリアは tinnunculus が広い範囲を占めているので、シベリアなんとか、のような名前も適切でなさそう。
あくまで空想上のシミュレーションと思って見ていただきたい。
Seong et al. (2025) Revisiting subspecies identification of Common Kestrels (Falco tinnunculus): A critical look at Zhang et al. (2008)
によれば Zhang et al. (2008) Genetic variation between subspecies of Common Kestrels (Falco tinnunculus) in Beijing は DNA 解析から北京地域で越冬するチョウゲンボウは2亜種と報告していたが、DNA barcoding のための primer 選択が適切でなく、新しく作成した primer を用いて調べると遺伝的には1亜種 interstinctus に属する結論となったとのこと。
ロシア沿海地方での繁殖: Shokhrin et al. (2020) Nesting birds of Primorsky Krai: falcons Falconidae (pp. 4479-4513)
(極東の鳥類42:沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める)。亜種は interstinctus としている。
[アメリアチョウゲンボウの亜種境界の検討]
Ruegg et al. (2021) The American Kestrel (Falco sparverius) genoscape: implications for monitoring, management, and subspecies boundaries
ゲノム解析でアメリアチョウゲンボウの亜種と亜種間の遺伝子流入を検討したもの。
アメリアチョウゲンボウには最大 17 亜種が認められている。
通常の扱いでは基亜種がアメリカ、カナダ、メキシコの大部分に分布、paulus がアメリカ南部ルイジアナ州からフロリダ州までとなっていた。この研究はこの2亜種をターゲットにしたもの。
地域的なサンプルはもちろん十分ではないが、アメリカとカナダのいくつかの地点で得たサンプルからそこそこの違いが見つかり、北アメリカの東西で分けられ、アラスカ、アメリカ西部、テキサス、アメリカ東部の北側、フロリダの5系統を認めてよいのではないか。つまり伝統的な亜種扱いとあまり合っていない部分がある。
遺伝的違いは渡りの表現型に対応しており、渡り個体の越冬地での遺伝子流入は eBird の目撃記録も参考にしてこれまで考えられていたよりずっと少ないと考えられる。
もしチョウゲンボウにもこの考察が当てはまるとすれば (1) 大陸の東西はおそらく別亜種扱いが適切 (ユーラシアは広いのでヨーロッパからシベリアまでを1つにまとめてよいかの問題もありそう)。
(2) 留鳥繁殖個体群と北方で繁殖する渡りの個体群は別亜種扱いがおそらく妥当。
となりそうな感じがする。ただしアメリアチョウゲンボウは名前から想像されるほどチョウゲンボウと近縁ではないので違うかも知れない。
チョウゲンボウで言えば (1) は tinnunculus と perpallidus の関係に対応。
(2) は perpallidus と interstinctus の関係に対応することになるだろうが、テキサスが遺伝的に別集団となるならば大陸中央部 (例えばチベット) と東端ではそれなりに違いがあるかも知れない。interstinctus は部分的渡りをするようなので実際は調べてみないとわからないだろう。
チョウゲンボウでもヨーロッパ大陸部と離島亜種の関係は調べられており、Kangas et al. (2018) Bottlenecks, remoteness and admixture shape genetic variation in island populations of Atlantic and Mediterranean common kestrels Falco tinnunculus
によればカナリア諸島など離島亜種は遺伝的にも結構違いが認められている。諸島内でも東西で違いがある。
アジアは台湾と日本のそれぞれ1個体のサンプルが解析に含まれているがサンプル数が少なすぎて結論は出せないとのこと。
[チョウゲンボウの和名検討]
チョウゲンボウの和名由来はよくわかっていないらしい。
Ogawa (1908) には Magusodaka とともにすでに現れるのでこの時代には存在した名前のはず。前述のように山階鳥類研究所標本データベースを見ても、古い時代には和名がほとんど現れず、属名も Cerchneis がよく使われていた。しかも Ca- や語末が異なるなど綴りもしばしば間違えられていた。Cerchneis は何のことかよくわからずに使われていた可能性が高い。
Boie (1826) の属名定義は F. rupicola Lichst. 1種を指すものとして使われており (The Key to Scientific Names。参考。Boie の記載はドイツ語)、
Cerchneis の語源となるギリシャ語では kerkhneis, kerkhneidos (複数形) でギリシャ文字の綴りを見ていると複数形の語末は "ヘ(ゲ)ードウ" と読めないこともない (h と g の子音交代はよくある。文字の形から δ を b にこじつけて読めばより似た音になる)。
ラテン語の Cerchneis (ドイツ語読みでは冒頭がツェルとなる) と組み合わせれば "チョウゲンボウ" に近い音になるかも知れない。当時の鳥学者も語源を調べようとギリシャ語辞書に当たったりしていたのではないだろうか。
YIO-09858 の籾山氏名による八丈島の 1922 年標本では地方名ヒヨドリダカが記されていた。
YIO-09842 (東京 1884) の標本ではマグソダカ。この時代の標本はマグソダカとなっていた。
コチョウゲンボウの古い標本ラベルも学名はあっても和名欄が空白になっているなど、そもそも名前がなかったのだろう。
チョウゲンボウはそもそも鳥学者にあまり知られていなかった種類で、あまりありふれた和名由来ではなさそう。"マグソダカ" ではあまりに品がないので、当時はまだ細かく属に分割されていた類縁種 (Tinnunculus 属にまとめられたこともあった) にまとめて名称を付けるにあたって、意味もあまりよくわからない属名をドイツ語読みでカタカナ表記にしようとしたところ思いついた表記ではないだろうか。
あくまで思いつきなので参考までに。
鳥学者にとっても意味も把握しにくく覚えにくい属名を記憶するのは大変で、記憶の手がかりとして "チョウゲンボウ" の名前を与えたのかも知れない。標本ラベルに多くの間違いがあるのは、当時の鳥のリストなどからその都度写した綴りではなく、音声記憶に頼って覚えた属名を綴りを確認せず用いたものだったためかも知れない。現在でも一度カタカナを通してしまうと人名や英語の綴りをしばしば間違えるのはよく経験する通り。
国松・長島 (2011) Birder 25(9): 65-67 がチョウゲンボウの名称由来を考察されていて、魚の名前にキョウゲンバカマ (カゴカキダイの別名) があって「狂言袴」に衣装の模様に似ているため付けられた説明がある (これは #ダイゼン [和名について] の和名由来解釈に似ている)。
チョウゲンボウも狂言の音が変わったものではないかと推測されていたが、古くから登場する名称ではないので、(当時のチメドリやフウキンチョウなど他の例にも見られる) 学名や外国語の音訳由来は一考の価値があろうと思う。
[日本のチョウゲンボウの繁殖確認]
中西悟堂「定本・野鳥記」4 pp. 212-213 (1954 年初出) に含まれていた。
長野県の十三崖のコロニーが知られるまでは日本のチョウゲンボウの繁殖はほとんど知られていなかった。横浜で Pryer が入手した4卵が大英博物館に収められて繁殖記録があることは確実であったが、その後の記録では 1934.6 に初めて山形で巣とひなが見つかったもので、すでにひなだったために卵の情報が全然わからず、鳥学の専門書もヨーロッパ産の卵の測定値を示していたとのこと。
1942.4 に下村兼史氏が長野で巣と卵を発見。1950.4 に十三崖の集団繁殖地が発見され、地元ではハイタカなどの名前で呼ばれていたとのこと。そして「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」として天然記念物に指定 (1953)。中西氏のこの記事は発見後のものものしい (?) 調査で、メンバーであった時の崖の調査が大変であった時の一種の自慢話。はしごをかけて巣の近くに機材を運びこめば逃げるのは当たり前か。
p. 219 (その後の追記部) では 1961 年松本の加賀崎武氏による報告で、樹上にも巣をつくりネズミの毛や小鳥の羽・骨などを巣材にすると記されていた。崖に営巣して巣材を使わないのは珍しいとの認識だった。
現在ならばハヤブサ類が巣材を用いて樹上にも営巣するのか不思議な感じもするが、中西氏の時代ではそもそもハヤブサ類の繁殖はほとんど知られておらず、他の (当時は同じグループとされた) タカ類と同じだろうと想像されていたものかも知れない。
今の時代ならばチョウゲンボウの繁殖は格別珍しいわけでもないので、なぜ天然記念物に指定されたのか不思議に思っていたがこのような経緯だった。
十三崖 (十三崖のチョウゲンボウ繁殖地) とは (長野市 2016/2023) によれば「チョウゲンボウの集団繁殖は、スペイン、ドイツ、日本、ノルウェー、ロシアなどで記録されていますが、最も多くの記録があるのは日本です」
とのこと。
ヨーロッパではコロニー性の高いヒメチョウゲンボウと混成コロニーを作るなど記事がいくつか見つかるがチョウゲンボウ単独では世界的にも比較的珍しいのかも知れない。
鉄橋やビルなどの人工建造物が現れる前は営巣適地が少なくて限られた場所に集結して繁殖していたものだろう。チョウゲンボウにとって地上性の捕食者が重要な外敵らしいこともわかる。
チョウゲンボウが現在都市鳥になりつつある背景も同時に見てとれる。台湾ではカタグロトビに座を奪われかねないぐらいの状況で、生態的にもそれほど強い鳥ではなかった。
過去を推察してみると、チョウゲンボウも "タカ類" として扱われていたわけで、タカが崖に集団営巣するのは (本当に "ハイタカ" であれば一層) 常識を覆していたのだろう。世界的にも珍しい、学会としてもそれはぜひとも天然記念物に指定すべきとなったと想像できる。ハヤブサも同様の理由でタカの仲間に含まれていて、鳥学者は樹上に営巣することを期待したがそれらしい確実な報告が見つからず、日本では繁殖しないと長年考えられていたと想像すれば納得できる。
ハヤブサで有効と認められている亜種 japonensis も繁殖地記載ではないし、硫黄島で繁殖するとされていた亜種シマハヤブサ furuitii も Momiyama (1927) の記載で、古くは (学会では) 日本のハヤブサの繁殖地は硫黄島しか知られていなかった
(#ハヤブサの備考 [亜種と系統]、[亜種 japonensis は何者?] 参照。千島列島のハヤブサは記述されていたが当時はまだ japonensis と考えられていなかった)。
1961 年のチョウゲンボウの樹上営巣の報告も、タカの仲間なのできっと樹上の巣もみつかるはず、と考えて探された結果かも知れない。
十三崖のチョウゲンボウが地元ではハイタカなどの名前で呼ばれていたことも考慮すると、古文献由来のハヤブサ類の繁殖地は種同定が確実と言えないかも知れない。
十三崖のチョウゲンボウについては本村健 (2012) Birder 26(9): 43 の記事があった。指定時は 20 つがい以上が営巣していたが、外来種が茂るなど 2001 年には2つがいまで減少、2005-2006 年に外来種の刈り取りや巣穴の増築を行い、2010 年には5つがいに増えた。その後は巣穴にミツバチ類が営巣するなど再び数が減少とのこと (記事当時の時点)。
[離島のチョウゲンボウ類と超希少種の保全]
チョウゲンボウ類でインド洋離島に複数の種が存在する。Groombridge et al. (2002)
A molecular phylogeny of African kestrels with reference to divergence across the Indian Ocean によれば鮮新世の寒冷化で海面レベルが 100 m ぐらい下がっていて途中の島が出現し、チョウゲンボウ類が離島に分散する手助けとなったとの仮説がある。その前に火山島の形成時期があって、火山活動が弱まったところで定着したのではとのこと。
離島のチョウゲンボウ類の一種として モーリシャスチョウゲンボウ Falco punctatus 英名 Mauritius Kestrel は特筆に値するだろう。絶滅を免れたモーリシャスチョウゲンボウ で日本語記事が読める。
環境破壊、DDT の大量使用、外来哺乳類による影響があまりにも大きく、最小4個体まで減少して当時世界で最も稀な鳥になっていた。保護経緯は wikipedia 英語版 に非常に詳しい。
近縁種のレユニオンチョウゲンボウ Falco duboisi は 1670 年代に絶滅したという。
Mauritius kestrel: A conservation success story (Scientific American の寄稿記事) によれば、当時の主なアプローチは生息地保全を含む総合的アプローチだったが、このプロジェクトではまずは個体数回復を最重要課題とした。
そのためには飼育下での増殖は必須であり、様々なテクニックが用いられた。仮親、人工飼育、飼育個体の放鳥技術 (ハッキング hacking) の改善 (鷹匠技術)、野生個体の卵採取やその他の手法など様々なテクニックが駆使された。生息地を保全すべきとの助言もあったが、それは簡単には手に負えるものではなかった。しかし絶滅が回避されたためにモーリシャスの英雄であり国鳥となり、結果的に生息地保全にもつながった。
Le Cri de la Crecerelle モーリシャスの公共放送の「モーリシャスチョウゲンボウ この 40 年の保護の軌跡(奇跡)」 人工飼育は 11:08 あたりから。
個体数がここまで減少すると近親交配による悪影響が十分に懸念されるが、これまでのところ大きな問題は発生していないようである。これはモーリシャスは火山島なので火山爆発によって個体数が極端に減少することを何度も経験しているはずで、近親交配による悪影響が及ぶような対立遺伝子は除かれていったはず。
そのため実効個体群サイズが最小4-5になっても近親交配の悪影響があまり現れないのだろう。同様の現象は個体数が極端に減少することを何度も経験している小さな島の個体群で知られていると wikipedia に記載されている。
高精度ゲノム解析による結果が示されている (#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] にも紹介あり): Wang et al. (2025) Genomic erosion through the lens of comparative genomics (preprint)。過去も個体数が少なく希少種だった模様。
定着はしたものの、もともとチョウゲンボウ類にはあまり向かない環境だったのかも知れない。
おそらく世界で最も厳しい条件での絶滅の回避劇として、ニュジーランド離島の チャタムヒタキ Petroica traversi 英名 Black Robin が有名で、繁殖力のあるメス (足環の色から "Old Blue" と呼ばれた) は1羽のみとなってしまった。
現在生き残っているチャタムヒタキは全てこのメスの子孫である。帰ってきたチャタムヒタキ: 次の自然保護活動の成功に向けて で保護歴史の一部 (南半球のこの緯度は荒れる海で有名で、実際には断崖を登り繁殖に適する島への卵の輸送を行うなど極めて大変な物語であった) などが日本語で読める。
チャタムヒタキの場合もモーリシャスチョウゲンボウ同様に近親交配による悪影響が及びにくい状況になっていたのであろう。
オールド・ブルー 世界に1羽の母鳥 (メアリ・テイラー作、百々佑利子訳 1999) が絵本で出版されていたが残念ながら品切れ重版未定。当時の「野鳥」誌に読者によるこの本の感想が述べられており、現代から見ても一読の価値があると思う。お持ちの方は探してみていただきたい。
[チョウゲンボウは齧歯類の尿の跡が見えるか]
チョウゲンボウは紫外線を見ることができて齧歯類の尿の跡が見えるとの説が有名であり、いろいろなところに紹介されている。この説を提唱したのは Viitala et al. (1995) の Nature 論文 Attraction of kestrels to vole scent marks visible in ultraviolet light で、一躍有名になったものである。
しかし後続研究を出したのはこのグループだけのようで、Lind et al. (2013)
Ultraviolet sensitivity and colour vision in raptor foraging の研究で、齧歯類の尿の跡のスペクトルと猛禽類の視覚特性を組み合わせると (ここで計測されたものはヨーロッパノスリであるが、視覚はチョウゲンボウとほぼ同様とのこと)、齧歯類の尿の跡は有効な信号になりそうもない結論が得られた。
これは昼行性の猛禽類の眼球は紫外線を通しにくいこと (強烈な日光から網膜を守る。また高解像度の視力が必要なので、色収差の原因になる紫外線をかなりカットしている。知られている範囲ではヨーロッパチュウヒは例外とのこと) が主な要因だが、尿の跡は簡単に消え去りあまり役に立たないことも要因である。
猛禽類の視覚のレビュー Potier et al. (2020) (#イヌワシの備考参照) ではこの説はもはや紹介すらされておらず、Mitkus et al. (2018)
Raptor Vision, Oxford Research Encyclopedia of Neuroscience でも否定的扱いであった。未検証の説 (または俗説) と考えておいてよさそうである。少なくとも分かっているかのように紹介するのは間違いと言ってよいだろう。
当時は鳥類が紫外線を見ることができることが判明して一躍脚光を浴びていた時代で、流行や話題には乗ったが実証性が今ひとつ乏しかったよう。
オーストラリアの齧歯類で研究があった。Kellie et al. (2004) Ultraviolet properties of Australian mammal urine
オーストラリアの齧歯類の尿の跡はそもそも紫外線で光っていない。ヨーロッパの齧歯類のみが特別なのでは? 他の要因も考えると猛禽類が紫外線で獲物の尿の跡を見るのに頼っているとは考えにくい。
こちらはフィンランドの研究で "齧歯類の尿の跡が見える" 説の支持派: Huitu et al. (2008) Consumption of grass endophytes alters the ultraviolet spectrum of vole urine
食べ物によって尿の紫外線反射率が変わって猛禽類に見えやすくなる。この説の支持者はどうもフィンランドの研究者のみで主張も後退してきているよう。
[チョウゲンボウとコキンメフクロウの目の比較]
Shalaby et al. (2024) Comparison of anatomical visual features of the eyeball, lens, and retina the diurnal common kestrel (Falco tinnunculus rupicilaeformis) and the nocturnal little owl (Athene noctua glaux)
エジプトとサウジアラビアの研究。電子顕微鏡を主として用いた形態研究。気になったところだけ見ておくと網膜構造がだいぶ異なるようで、チョウゲンボウではメラニン顆粒を多く含む色素上皮が顕著で、光の散乱による解像度の低下を防ぐあるいは紫外線反射による網膜の損傷を防ぐ昼行性適応があるがコキンメフクロウではあまりない。
フクロウ類の方が色素上皮が光をよく反射するので光を当てると目が反射して光って見え、また網膜の感度を上げる効果もある。昼行性種がむしろ積極的に反射を防いでいる。tapetum lucidum については #ヨタカ備考の [ヨタカ類の視覚特性] を参照。
コキンメフクロウでは暗所視に関与する視細胞が中心であるなど従来知見を確認できた。
[近赤外線で輝くチョウゲンボウ類]
多くの鳥は紫外線が見えるので、紫外線で見るとどのように見えるかは比較的調べられてきた。
近赤外線で見るとまた興味深い結果が出ている: Medina et al. (2018) Reflection of near-infrared light confers thermal protection in birds
オーストラリアの鳥を調べたものだが、オーストラリアチョウゲンボウ Falco cenchroides Nankeen Kestrel は特によく近赤外線を反射するとのこと。ルリミツユビカワセミ Ceyx azureus Azure Kingfisher の方がさらに反射率が高いが、オーストラリアチョウゲンボウの方が可視光との違いがより顕著なのでこの項目に入れた。
オーストラリアでも Falco 属の他種も同様というわけではなかった。
カワウでも可視光や紫外線ではほとんど真っ黒だが、近赤外線はそこそこ反射していた (上記2種に比べるとそこまで反射率は高くないが可視光を吸収する色素による制約もあるのだろう)。
高温で乾燥した環境の種ほど反射率が高い傾向が認められた。紫外線・可視光の反射率には同様の傾向は認められなかった。
日光のエネルギーがある程度 (ただしピークは可視光にある) 含まれる近赤外線をカットすることで高温環境に適応していると考えられる。モデル計算ではこの効果がなければ1時間に 2% の割合で水分を蒸発で失う必要があるとのこと。
紫外線で相関がない理由は、黒い色は紫外線による羽毛の劣化を妨げる効果もあるためと考えられる。
系統関係も図もあるので見ていただくと面白いだろう。
日本の暑さは湿度がまったく違うので別途調べてみると面白い結果になるかも。
[アメリカチョウゲンボウの消音飛行]
アメリカチョウゲンボウの羽毛がフクロウ類に匹敵する程度の消音性能を持つことが示された。
#ウスハイイロチュウヒ備考 [音を出さない羽毛構造] Liu and Clark (2024) を参照。
[チョウゲンボウのホバリングと捕食]
週間アニマルライフ (1972) pp. 2348-2350 のチョウゲンボウの項目 (浦本・斎藤) によればホバリングを行って降下しても哺乳類がまったく捕れず、チョウやガ、あるいはミミズだけしか捕食されないことが観察されているとのこと (この項目は英国のチョウゲンボウのことを指すのか日本のチョウゲンボウのことを指すのか曖昧)。
#ミサゴの備考で [ミサゴは不器用?] でミサゴのホバリングの高さを考察した際にチョウゲンボウのホバリングも気になったため。獲物の上でホバリングすればむしろ逃げるのではないかと思ったわけだが、やはり逃げられることが多い記述があった。齧歯類食では昼行性種ではタカ類の方がおそらく上で、台湾のようにカタグロトビと直接競合するとチョウゲンボウの方が劣勢になるのではと感じた (#カタグロトビ備考 [分布拡大] 参照)。
週間アニマルライフの同記事によれば、ヨーロッパとアメリカのチョウゲンボウ (アメリカチョウゲンボウ) で小鳥の餌台に置かれた肉片やパンさえも食べることが知られているとのこと。
[飼育下のチョウゲンボウ類の行動]
Blagosklonov (1960) による野鳥飼育の本 "飼育下の鳥" (#ハチクマの備考参照。当時の背景についてもそこに記載) からチョウゲンボウ類の項目を紹介しておく:
チョウゲンボウは最も有益な鳥の1つです。
チョウゲンボウは非常に広く分布する猛禽類です。
彼の響き渡る叫び「クリクリクリクリ」が春の森のはずれで聞かれます。
目に見えない糸にぶら下がっているように、地面の上で一箇所で羽ばたく
のを頻繁に見るのはチョウゲンボウです。鳩ほどの大きさの鳥です。
赤の色調で美しく彩られていて、オスは特に良いです。巣から連れてきた
ひなは完全に飼育下に慣れてすぐに完全に飼れます。
スターリングラード地方から持ってきたチョウゲンボウのひなたちは
面白くて楽しい鳥として長い間記憶に残っていました。
私たちは主に肉を彼らに与えました。
彼らは明らかにニシアカアシチョウゲンボウよりも喜んでそれを食べました。
ひなが成長したとき、彼らは独立したケージの中で一緒に住んでいました。
若い鳥は遊ぶのが大好きでした。ケージの中には木の幹がありました。
それを使用して、チョウゲンボウはかくれんぼを開始しました。
一羽はその後ろに隠れ、樹皮にしがみついて、外を見ました。
もう一羽は相棒を探しているふりをしました。
それから突然相棒に飛びかかりました:追跡と乱闘が始まりました。
時々、一羽がゲームに飽きて、その場を去り、もう一羽は楽しみ続けました。
ケージの床のトウヒの円錐または棒をつかみ、それを空中に放り投げ、
くちばしで捕まえようとした。これはすべて、鳥としては珍しい、
気取った身振りとジャンプで行われました。この手本に夢中になって
落ち着いていた鳥も同じゲームに加わりました。
彼らは再び大騒ぎを始めました。そして、実際、その瞬間、チョウゲンボウ
は鳥というより子猫を演じているように見えました。
チョウゲンボウを世話する時は、これが私たちの有用な鳥の1つであることを
忘れないでください - 野原の齧歯類の害虫駆除業者です。
ヒメチョウゲンボウ - 色やサイズがチョウゲンボウとは少し異なります。
ヒメチョウゲンボウは雄のニシアカアシチョウゲンボウよりも大きくはありません。
ヒメチョウゲンボウは動物学者 M. N. キシュキンが飼っていました。
鳥は近所の茂みから小さな羽毛として家にやってきたものです。
鳥は肉(ほとんどの場合子羊)や大きな昆虫 (主に直翅目と甲虫) を与えられ
ました。鳥の最も好きな食べ物は、冬に与えられたトウダイグサの蛹でした。
上記に加えて、ヒメチョウゲンボウは他の多くのものを食べました。
この鳥の視力は飼い主の話で判断できます。ある日、部屋の天井のそばに鳥が
とまっていると、テーブルを横切って這うミバエに気づきました。
この昆虫はノミほど大きくはありません。ヒメチョウゲンボウは飛んで、足で、
またはむしろ指を拳に折りたたんでハエを押しつぶしました。
ヒメチョウゲンボウは水を入れたボウルで泳ぐのが大好きでした。
これに関連してスキャンダラスな事件が起きました。
完全に禿げた教授が飼い主のところへ訪ねてきました。
光沢のある表面を見て、鳥は即座にゲストの頭に飛び、しゃがみ始め、
彼女が入浴中にしたように、翼を振りました。
ヒメチョウゲンボウにはさまざまな習慣がありました。
最もうれしくないものの一つは鳥が手から鉛筆、ペン、ブラシをひった
くったり、部屋に置いてあるものを探したりしたこと。
鳥は盗んだものすべてを天井の下のカーテンレールに置いた。
キシュキンは、ヒメチョウゲンボウを優れた「気圧計」だと考えました。
天候が変わる3-4時間前に、鳥は眠くなりました。目を閉じて、居眠りし、
「くちばしでついばんだ」のです。
このヒメチョウゲンボウは飼育下で4年以上、部屋の中を自由に飛び
回りました。鳥は完全に慣れており、もちろん、みんなのお気に入りです。
鳥は完全に珍しい理由で亡くなりました - 鳥がとても愛していた
サワークリームを食べました。剖検の結果、サワークリームが固いコルクを
形成して腸閉塞を起こしたために死んだことがわかりました。
ニシアカアシチョウゲンボウは、ロシアのハヤブサの中で最も小さく、
最も美しく、そしておそらく最も有用です。
オスはスレートグレイで、真っ赤な足と光沢のあるくちばしを持っています。
女性は胸に縞模様があり、上は濃い灰色です。若いものはほとんど同じ色
ですが、明るいです。
ニシアカアシチョウゲンボウは、ネズミがたくさんいると、熱心にネズミを
捕まえます。しかし、主な一般的な食べ物は大きな昆虫です。
これらのハヤブサは、軽くて速い飛行ができて、それら (イナゴ、カブトムシ)
を空中で捕まえるか、飛びながら野原の穂からついばみます。
ニシアカアシチョウゲンボウは我が国に広く分布していますが、南の草原に
のみ多数存在します。ここでは彼らは巣を作らず、古巣、ほとんどの場合
カササギのものを利用します。
ただし、南部のカササギの巣は、他の樹洞性の鳥、森のフクロウや
コノハズク、チョウゲンボウなどの樹洞でとって代わります。
私はかつてスターリングラード地域のイロブリ (ドン川の支流) の岸から
モスクワに約 20 羽のニシアカアシチョウゲンボウを連れて行く必要がありました。
飛行の研究のために必要でした。また、モスクワ郊外でリリースしたい
気がしました。あるいは彼らはここに定住してくれないかと。
たくさんあるカササギの巣ではたくさんのニシアカアシチョウゲンボウが
住んでいました。しかし、ひなだけが選び出されました - 綿毛のようなものか、
羽が生え始めたものです (後で、前者は後者よりも比類のないほど慣れることが
わかりました)。
ひなは片側に金属メッシュが付いた特別な長い箱に3-4羽ずつ入れました。
家族ごとに分けるのではなく、年齢によって分けました。
ニシアカアシチョウゲンボウの主食は生肉ですが、あまり積極的に食べません
でした。網でつかまえて昆虫を与えなければなりませんでした: 彼らはイナゴを
貪欲に食べました。スズメは私たちを助けてくれました - 私たちは彼らの
農業価値について観察を行い、たくさんのひなをさばきました - 日によっては数十。
もちろん、この時、ニシアカアシチョウゲンボウは飢えていませんでした。
時折、砕いた卵殻が肉に与えられました。そのような単調な食事にもかかわらず、
私たちの鳥は正常に成長し、成長しました。
私たちはそれらに1日3回給餌しました。成長したひなは、彼らが住んで歩いて
いた箱から解放されました。走る機会、その後飛ぶ機会を与えました。
鳥が人々にもっと慣れるように、鳥を手に持っていました。
ニシアカアシチョウゲンボウはボルシェフスク生物ステーションに連れて
行きました。輸送の難しさは、空腹になると、20 羽のひなが叫んだことでした。
声は私たちが運んでいた他の鳥に響き渡りました。給餌が始まるとすぐに、
叫び声が上がりました。それは数分間続いたので、私たちはひなを馬車の暖房室に
置いておかなければなりませんでした。そこからは聞こえませんでした。
ボルシェフスカヤ生物ステーションでは、ニシアカアシチョウゲンボウが最も
珍しい方法で現れました。記念日のお祝いの日と時間に遠征から到着しました。
鳥はとても飼いならされていたので、私はそれらをちょっとしたいたずらに
使うことにしました。所長がスピーチを終えると、私は厳粛なテーブルの前に
現れました。黒いカーテンに包まれて、肩、頭、腕 - ニシアカアシチョウゲンボウ
はいたるところにとまっていました。
2羽のニシアカアシチョウゲンボウと3羽のユリカモメが大きなケージに
入れられました。
私たちの鳥は間違いなく、食べ物を持ってきた女性を他の人々から区別しました。
そして彼女らと長い時間を過ごしました。
すでに冬に、彼女のアパートに住んでいたニシアカアシチョウゲンボウの一羽は、
人々の手からから食べ物をもらっているのに、部屋に入ったすべての人々に無関心でした。
しかし、女性が仕事から帰ってくるとすぐに、鳥は変わり、彼女のところに飛んで、
彼女の肩にとまりました。そして、鳥はすべての行動で喜びを表しました。
鳥は叫び、頬を押しました。
ニシアカアシチョウゲンボウは何時間も女性の肩に座り、部屋から部屋へと
彼女と一緒に移動しました。
生物ステーションに住むニシアカアシチョウゲンボウはしばしば散歩に出されました。
彼らは素晴らしく飛んで、家の近くで稲妻のようにきらめきましたが、
しかし、彼らは臆病で、生物ステーションから離れることはありませんでした。
ある日、おびえたニシアカアシチョウゲンボウが村の方から急いでやって来ました。
鳥はケージの上の樹冠に飛び込み、そこに隠れました。ツバメが追いかけていました。
攻撃を受けて夕食のために家に帰ったときのニシアカアシチョウゲンボウの
行動は非常に奇妙でした。鳥はケージの近くの木にとまって、食べ物を求めて
叫び始めました - 食べさせてくれ。
地面から最もおいしいおやつを見せられたとしても、どうしても飛び降りたく
ありませんでした。私ははしごを木の上に置き、それぞれのニシアカアシチョウゲンボウ
の後ろに登らなければなりませんでした。
てっぺんに行くと、彼はすぐに小枝から人の肩または頭にジャンプし、
一緒に降りました。地面に着くと、貪欲に食べ物に襲いかかりました。
飼育下でのニシアカアシチョウゲンボウの好きな食べ物はたとえばブロンズ色の
大きなカブトムシであり、これは他の鳥は食べていないようです。
ニシアカアシチョウゲンボウはカブトムシを「こぶしで」曲げずに取り、
くちばしに持ってきて、最初に頭を引きちぎり、次に鞘翅と羽を引き裂きます。
その後、鳥は昆虫を内側から滑らかにし始め、1分後に空の殻にして丁寧に
食べ終えたキチンを投げます。
ニシアカアシチョウゲンボウはどんな餌でもこぶしで運びます、
そしてこれは給餌プロセスをとても面白くします。
秋が来ました。何羽かのニシアカアシチョウゲンボウが研究を続けるために
モスクワの研究所に連れて行かれました。他の鳥は解放されました。
実際、彼らはすでに自由の身になっていて、ただ餌をやめただけです。
その後長い間、ニシアカアシチョウゲンボウは家に飛んでいきました。
彼らは叫び、人を呼び、窓際にとまってくちばしでガラスをたたき、
部屋に入ろうとしました。窓が大きく開いていた夏には、とても簡単に
できたのですが。訪ねてくるニシアカアシチョウゲンボウはどんどん
少なくなり、それから完全に姿を消しました。
そのうちの1羽だけの運命がわかっています - 彼は (タカだと考えられて!)
ある「ハンター」に撃たれました。
[チョウゲンボウの共食い]
Haddad and Yosef (2022) Cannibalism in common kestrel (Falco tinnunculus)
に報告がある。チョウゲンボウで観察されたのはこれが初めてだそうである。
[アメリカチョウゲンボウの交尾]
猛禽類は交尾回数が多いことで有名だが、記録保持者はおそらくアメリカチョウゲンボウ Falco sparverius American Kestrel だろうか。
Villarroel and Kuhnlein (1998) Copulatory behaviour and paternity in the American kestrel: the adaptive significance of frequent copulations
ではつがい外交尾などの競争 (paternity assurance 父権の確保) などの理由で交尾回数が多い仮説などを検証している。
Bildstein (2017) "Raptors" p. 114 でこの著者の研究が紹介されているが、Villarroel は当時大学院生で David Bird の指導のもとアメリカチョウゲンボウの 1992-1993 年の繁殖期行動を観察した。
Birder 2012年4月号が特集で扱い、記事でも数字が紹介されたこともあってご存じの方もあると思うが、何と平均でシーズン (クラッチあたり) 推定 454±78 回交尾。1か月半の期間でピーク時は1日14回、ほぼ1時間に2回の交尾をしたという。推定数は実測値ではなく、1日1-2時間時間帯を変えてサンプルしたものから推定したもの。
観察された 80% 以上の交尾は成功したと判断され、失敗は 13% と判定された。
交尾はオスもメスも誘い、失敗例の 2/3 はオスが誘った事例とのこと。
DNA 判定でつがい外交尾は少なくこの対策とする仮説は当てはまらないとのこと。また交尾とともに餌を受け取る利益の仮説もあるがこれも当てはまらなかった。オスと他のメスとのつがい外交尾を防ぐためにメスが頻回の交尾を要請する仮説もあるが、メスが交尾の大半を誘うわけではないので棄却。
実際の繁殖前にオスにとって体力的なコストの大きい (energetically costly) 交尾によってオスがしっかり餌を運べるか資質を判定している仮説はあって哺乳類では比較的述べられている。両性が子育てにかかわる鳥類では当てはまると考えられるが、メスが産卵するのをオスが確認できれば頻度がすぐに減少すると考えられる。
検討した仮説の中では最後のものが最も当てはまるが、初期は主にオスの資質を表し、受精に適した時期には確実な受精のためなど時期によって交尾の役割が異なる可能性も考えられるとのこと。
ただしこの文献はかなり古いので Bildstein (2017) での引用が適切かどうかはわからない。
他の猛禽類でもいくつか研究があるので文献を紹介しておく。ボネリークマタカ Aquila fasciata Bonelli's Eagle: Martinez et al. (2019) Copulatory behaviour in the Bonelli's Eagle: Assessing the paternity assurance hypothesis
交尾期間が長く1日平均で 0.86 回だがシーズン全体では 99.8 回で 96% は成功しているとのこと。猛禽類ではつがい外交尾は少ないようで、前述の解釈以外に別仮説としてテリトリーの誇示や繁殖状況を他の同種個体に知らせて潜在的に危険な闘争を避けている解釈も紹介されている。
この仮説は Negro and Grande (2001) Territorial signalling: a new hypothesis to explain frequent copulation in raptorial birds
で一覧表も出ている。
Balgooyen (1976) Behavior and ecology of the American kestrel Falco sparverius によればアメリカチョウゲンボウで最大 690 回の記録があるらしい
[柴田 (2012) Birder 26(4): 43 に紹介されている。この記事では猛禽類は繁殖期は雄が狩りに出かけていて留守になり、雌の防衛ができないため、たくさん交尾をすることで自分の子供が生まれる可能性を高めていると考えられているとの記載になっている]。
Negro and Grande (2001) のまとめではオオタカで 518 回、ヒメチョウゲンボウで 362 回の数字も出ている。
週間アニマルライフ (1973) p. 3897 にライオンが5時間で 157 回交尾したとの例があるとのことで、当時の "百獣の王" の関心事だったのかも知れないが、おそらく作り話だろうと少し文献を調べてみると Tefera (2003) Phenotypic and reproductive characteristics of lions (Panthera leo) at Addis Ababa Zoo
の動物園での記録があり、交尾は1日 16.5±7.5 回、交尾時間は 12.2±9 s、次の交尾までの間隔 (refractory period) は 50±25 min とのこと。早い話起きている間は交尾しているような数字になるが上記の回数はとても実現できそうにない。
猛禽類では交尾中に騒々しい種類も多くてこれは他の同種個体へのテリトリーの誇示の仮説の裏付けとなる。チュウヒ類は地面で交尾するがこれも騒々しいという。
[同様の事例はツメバケイで知られている。#ミサゴの備考の [近代的な陸鳥の進化] で紹介。この場合は ritual copulations (儀礼的な交尾) とも呼ばれる。
ワシミミズクでも同様の用語が使われている: Harms (2021)
Pre-incubation period behaviour of a pair of Eurasian Eagle-owls (Bubo bubo) based on IR-video recordings at a nest site in Baden-Wrttemberg, Germany, in 2014-2015]。
Negro and Grande (2001) は猛禽類で交尾頻度が高い理由はこの仮説がもっともらしいと考えている。他のグループに比べて武器があるので闘争が致死的になる可能性があるため闘争を避けるコミュニケーション手段を理由に挙げている。
テリトリー性だが防衛手段を持たない種類は交尾頻度が低く静かである予測が得られるが、小型シギ類のムラサキハマシギ Calidris maritima Purple Sandpiper は当てはまるとのこと。この予測に基づいて猛禽類の一覧表を見る限りではあまり傾向がわからない。
中村 (2012) Birder 26(4): 12-13 でイワヒバリが取り扱われ、厳しい自然環境のもとで多夫多妻の繁殖様式を進化させたことが述べられていてオスの交尾回数は 100 回以上になると考えられるとある。
カヤクグリのオスでは繁殖期に輸精管の末端の肥大によるこぶ状の総排泄腔突起 (cloacal protuberance) を形成することが知られている [cf. 中村・松崎 (1995) 総排泄腔突起によるカヤクグリの性判定]。
「赤いカナリアの探求」(#ベニマシコの備考) に出てくるバークヘッドはこの分野の先駆者でヨーロッパカヤクグリ Prunella modularis Dunnock をよく調べている: Birkhead et al. (1991) Sperm competition and the reproductive organs of the male and female Dunnock Prunella modularis。
Birkhead et al. (1993) Male sperm reserves and copulation frequency in birds など。
この精子競争がイワヒバリの種分化要因にも関わっているらしいとのこと (#イワヒバリの備考参照)。
さらに交尾回数の多い猛禽類ではいったいどうなっているのだろう?
さらに見ると Avian Male Reproductive Tract - Anatomy & Physiology
によれば輸精管の末端が肥大して精子を蓄える構造は (seminal) receptacle と呼ばれる
(メスが蓄える方の用語でも使われることがあるらしいので文脈要注意かも。メスの方は sperm host gland, sperm storage tubule 蓄精腺などの用語がある) とのことで、スズメ目とセキセイインコに見られるとのこと。
そう言われればセキセイインコも交尾回数が多いと思った。野生では集団生活なのでつがい外交尾が起きやすいためとすれば納得できる気もするが、本来の生息環境では乾季・雨季が予測されない形で現れるのでいつでも繁殖に備えておくため、との説明も読んだ。
獣医学ページなので鳥類全般のデータではないかも知れないが、別項目で猛禽類の言及があるのでこの構造はおそらく猛禽類にはない?。
(seminal) receptacle を持たない鳥 (オスのこと) は精子貯蔵能力はほとんどないとのこと。また精巣上体 (epididymis) は鳥類では痕跡的なもものと考えられており、精子の成熟は輸精管 (vas deferens) で起きるとのこと。
その後鳥類の精巣サイズのデータを見つけたので作図してみた。データは Calhim and Birkhead (2007) Testes size in birds: quality versus quantity-assumptions, errors, and estimates
(フリーアクセスなので他のグループに興味ある方は試してみていただきたい)。
たくさんのサンプルがあるわけではないので複数種の含まれているグループを試してみた。大きくばらついているが精巣が縮小している時期 (あるいは非成熟) のデータもあると思われるので、上限の点を見ていただくとよさそう。
比較のために体重はまったく違うが有名なカヤクグリ属を入れてみると、予想通り同じ体重ではトップグループとなる。大きめの鳥ではカモ類を入れてみた。
広義 Accipiter 属の上限は同じような体重の鳥の中でもトップグループに位置する。特に大きな2種はオオタカとアカハラオオタカ (新分類では Tachyspiza)。他の広義 Accipiter 属は小さい値なのでおそらく精巣の縮小時期 (または非成熟) の測定だろう。
このようにみると (やはり調べてみないとわからないもの) 広義 Accipiter 属は交尾回数に見合う大きな精巣を持っていることがわかった。ノスリ類はどうもそれほどではなさそう (サンプルを得た季節にもよっている可能性は残る)。
ハヤブサ類はばらつきが大きいが、一番大きなものは体重比でやはりトップグループに入る。ここで挙がっている2種はソウゲンハヤブサとアメリカチョウゲンボウ。交尾回数の観察データとも合致する。
ハヤブサやチョウゲンボウも測定されているがいずれも値が小さいので精巣の縮小時期のものだろう。
ここには示さなかったがヨーロッパチュウヒやトビも精巣の大きいハヤブサ類2種と同等ぐらい。
イヌワシ (7.36 g) は中程度。
何とミサゴが飛翔性鳥類全体でも最大クラスの精巣 (17.65 g) を持っていた。体重の 1.2% が精巣となって脳 (9.2 g) の2倍もある! プロットの右上の緑の点。
もしやと思ってみるとやや小型のアカハラオオタカ (精巣 7.66 g) では脳 (4.65 g) よりだいぶ重い。ハヤブサ類は小型種が多く脳の比率が相対的に高めなのでそれほど目立たない。
ミサゴはコロニー性がそれほどあるわけではなさそうで、そんなに頻繁に交尾しているだろうか?
出典は Moller (1991) Sperm Competition, Sperm Depletion, Paternal Care, and Relative Testis Size in Birds のようだが、外れ値や測定上の問題もあるかも知れないのでミサゴの精巣が大きいかどうかは別の標本で測定した方がよさそう。
少なくともミサゴとオオタカの系統の繁殖期の精巣に大きな投資をしていることがわかる。
タカ類で測定されているグループはこの程度に限られているが、フクロウ類 (Asio 属、Strix 属) も大きく、猛禽類は昼行性・夜行性ともに精巣サイズが大きい結論となった。精巣の大きな猛禽類はなんと乱婚のカヤクグリ属並みと言っても構わないぐらいとなった。
高頻度の交尾を可能にする生理的メカニズム (精巣の大きさ) は納得できる感じもする。
北半球の多くの地域で生態系の最上位に近く、捕食性の強いオオタカの系統で大きいのは能力や社会的地位の高さを示す指標になっている可能性を示唆するのかも知れない...と思ったが、この系統はクラッチサイズが比較的大きい (オオタカ類は採食に技術が要求されるので若鳥の生存率が低い、チュウヒ類は地上営巣なので、など) のでそれを反映しているかも知れない。
さらに、相対的に精巣が大きいのはミサゴを除けば逆性的サイズ二型の著しい種類であることにも気づいた。オスの体重に対する比率でみると大きいが、メスの体重に対する比率ならばそれほど極端に大きくないかも (受け取るのはメスなのでメスの体重の方と相関が強くてもおかしくない)。
そのような視点で見ると、オオタカの系統は生殖的機能まで犠牲にしない範囲で体重の軽いオスが選択されているのかも知れない。逆性的サイズ二型を説明する仮説は多数あるが、オオタカの系統ではよく言われるように子育てに際して小型で敏捷なオスが有利なのかも。猛禽類の中でも系統によって主な理由が異なるかも知れない。
Baker et al. (2020) Rapid decreases in relative testes mass among monogamous birds but not in other vertebrates
は全体の傾向を見た比較研究だが、一夫一妻の脊椎動物で精巣サイズがそうでない場合に比べて相対的に一番縮小するのは鳥類とのこと。まぜこぜのデータを使っているのでどこまで信用してよいかわからないが、鳥類内の系統別の傾向が出ていないので何とも言えない感じ。

付随的な情報として Simmons (2000) "Harriers of the World" ではチュウヒ類では一夫多妻の場合の方が孵化率が低く精子枯渇が起きている可能性があるとのこと (Copulation patterns and sperm depletion)。この知見は受精を確実にするために交尾頻度が高い仮説を一応支持する。
比較的古い方の研究だがアカトビで近隣個体の密度が増えると交尾頻度が上がり、主に paternity assurance 父権の確保仮説を補強する解釈がなされている:
Mougeot (2000) Territorial intrusions and copulation patterns in red kites, Milvus milvus, in relation to breeding density。
Bildstein (2017) では近傍個体が多いと mate guarding により多くの時間を費やすとしてこの研究が紹介されている (p. 115 つがい外交尾関連)。
関連して述べられている話ではシュバシコウではコロニー繁殖をするがつがい外交尾は非常に少ない。Tortosa and Redondo (1992) requent copulations despite
low sperm competition in white storks (Ciconia ciconia) これは頻繁な交尾はオスの資質を示しているのではとの文脈。
極端な猛禽類ほどではないが交尾頻度はかなり高いよう (ピーク時は2時間に1回ぐらい)。
猛禽類に対して近年提唱された他個体へのシグナル仮説はコウノトリ類ではどうだろうか。
なお「頻繁な交尾はオスの資質を示す」仮説は交尾にはコストがかかることが前提となっている。当たり前のような気もするが、哺乳類など他の分類群に比べて鳥での状況は実はあまりよくわかっていないとのこと。
鳥 (ヘラサギ) において証拠となると考えられる研究を紹介しておく: Aguilera (1989)
Sperm Competition and Copulation Intervals of the White Spoonbill (Platalea leucorodia, Aves, Threskiornithidae) (論文サイト)。
こちらはつがい外交尾が多いようで間につがい外交尾をはさんだオスでは交尾間隔は長くなって回復に時間を要することを示すとのこと (単に満足しただけかも知れないが?? 行動の解釈は難しい)。
上位のオスの頻繁な交尾で精子枯渇が起きる野生動物での証拠は哺乳類にはあるようで Preston et al. (2001)
Dominant rams lose out by sperm depletion
ヒツジ Ovis aries では交尾回数は1日最大 13 回、体サイズに対して大きな精巣を持つが、飼育下実験で電気刺激で人工的射精を1日8回を 18 日続けると精子数は 85% 減少したという (ただしこれを調べるのが目的の研究ではない模様)。野外でも交尾期後半では精子枯渇が起きていると考えられ実際にも精子数が少なく形態異常も多いとのこと。
野生脊椎動物で精子生成の限界を実証した初めての研究とのこと。鳥類と哺乳類で異なる点もあるだろうし婚姻形態も異なるが参考データになるだろう。
古典的なフィールド研究はこのようなものがあるが、生理学的見地などもう少し現代的なものはないかと当たってみると獣医学で研究があるようで
Partyka and Nizanski (2021) Supplementation of Avian Semen Extenders with Antioxidants to Improve Semen Quality - Is It an Effective Strategy?
のようなものがあり、生殖細胞は鳥の場合も不飽和脂肪酸を大量に含んで酸化ストレスに弱いとのこと。そのためビタミン A, C, E やカロテノイドなどの抗酸化物質が消費される。抗酸化物質量が多いと受精成功率も高まるとのこと。
このような話だとヒトの医学でもありそうなものだが、現代の医学は圧倒的にエビデンス主義 (evidence-based medicine, EBM) なのでエビデンスが弱い話は特に専門家からはうかつにはできないらしい。
形式に則った研究はいろいろあるようだが [cf. Dimitriadis et al. (2023) Antioxidant Supplementation on Male Fertility - A Systematic Review。臨床医学研究でエビデンスを得るのは大変なのである]、
新型コロナ流行初期に「感染予防にマスクが有効であるエビデンスはない」(新型コロナウイルスに対するエビデンスがあるはずがない) などと言われたのと同じような話かと思う。エビデンスがない = 意味がない とは異なる。根拠もなく想像で予防方法などを述べていた過去への反省もあるのだろうが、徹底的にエビデンスを求めているように感じる。
以下のような推測に基づく議論は現在の医学では多分敬遠されるだろう。医学の世界はあまり気にせずに進もう。
ご存じの方もあるだろうがビタミン E の化学名はトコフェロールで tocopherol tokos (子供をもうけること) pherein (性質を持つ) (Gk) なのでそもそも関係がないとは考えにくい。
実験的検証はともかく、この話はカロテノイドを色彩に使うか抗酸化物質として使うかのトレードオフと同様なので同じように考えられるのではないかと思う。つまり原理的には「頻繁な交尾のためには十分な抗酸化物質が必要で、体内の抗酸化物質量やオスの資質を示す正直なシグナル」になり得ると考えてよさそうに思える。
シロハヤブサの若鳥の褐色の色彩には抗酸化物質量が関係している Galvan and Jorge (2015)
The Rusty Plumage Coloration of Juvenile Gyrfalcons is Produced by Pheomelanin and its Expression is Affected by an Intracellular Antioxidant
のような研究はあるので、抗酸化物質をどこに投資するか性選択にかかわるトレードオフの研究がありそうなものだが探した範囲であまり見当たらない。誰もが古くからのアイデアである精子競争に影響されすぎているのかも知れない。
卵にも抗酸化物質として ビタミン A, E やカロテノイドが多量に必要とのこと: Barton et al. (2002)
Vitamins E and A, Carotenoids, and Fatty Acids of the Raptor Egg Yolk。
猛禽類がビタミン E をどこから得ているのか生態的にも興味ある事項なので #クロハゲワシの備考 [猛禽類の植物食] にまとめ直した。
猛禽類で全般的に交尾頻度が高い理由について戻ると、(根拠があるわけではないが) 「オスの資質を示す正直なシグナル」、つまりトレードオフのある資質は性選択材料とおそらく有用だろう。多くの小鳥が目に見える色彩や行動とさえずりを併用するなど複数の性質を用いるなど複数のシグナルを用いるのは有用と思える。
ディスプレイ飛行などはアピールには有効だろうがトレードオフとはあまり関係ないかも知れない。小鳥の場合にはカロテノイドを必要とする色彩などトレードオフの理由のある形質は使えるだろうが、捕食性の強い猛禽類では色彩であまり目立ってしまっては捕食者としては不利になる。
目立たない色の隠蔽色の猛禽類が多い理由だろう。また捕食性の行動のために羽毛強度を高める必要があり、メラニン着色が使われるのも納得できる。
普段は目立たない翼下面などに模様を施すことはできるだろうが、色彩をあまり派手に使うことのできない猛禽類にとってトレードオフが存在するだろう資質として交尾頻度が選択された可能性があるかも知れない (「猛禽類ならでは」の理由として考えてみた)。
その後追記: 猛禽類ではカロテノイドを嘴、足、裸出部に用いているとのこと (#鳥類系統樹2024 紹介の Davis and Clarke (2022) Estimating the distribution of carotenoid coloration in skin and integumentary structures of birds and extinct dinosaurs)。
実証的研究はあまりないようだが解釈はいくつかあって栄養状態のシグナルになるアイデアも存在する。
同じく [鳥類系統樹2024] 紹介の Neoaves 関連論文では Neoaves では酸化ストレス対応が一段と高度なものになっているとのこと。定常的に獲物が穫れるとは限らない猛禽類では他のグループに比べて予備力がさらにあるのではないか? 栄養状態のシグナルとして交尾頻度が使われるならば猛禽類では (ならでは?) 上限値が高くなる要因になり得るのではと考えた次第。
こういう研究、あるいは反論があれば教えてほしい。交尾頻度と抗酸化物質の関係などは直接調べることもできそうだがツバメの研究でも難しいので猛禽類では容易ではないかも。
つがい外交尾頻度の高いイエスズメで社会的順位を人工的に操作した実験はある。Mora et al. (2017) Antioxidant allocation modulates sperm quality across changing social environments
社会的順位の高いオスは交尾頻度が高いのでより酸化ストレスを受けるはずとの予測なども述べられているが実験結果はあまりすっきりしない。一夫一妻の種でオスの繁殖戦略に酸化ストレスが至近要因として関係する可能性を実証した初めての研究とある。
ヨーロッパシジュウカラでは色彩の濃い (色彩に資源を投資できる) オスほど酸化ストレスに対して精子の質が保たれたとのこと: Helfenstein et al. (2010) Sperm of colourful males are better protected against oxidative stress。
この分野の研究はまだ始まったばかりのようで今後の進展が期待できるかも知れない。
抗酸化物質は免疫など生存や生活の質を高めるのに極めて重要なので、性選択においてこれをトレードオフ対象とする一般的性質が存在するなら面白い。
獲物をプレゼントすることで餌をとる能力 (子供を育てる能力を近似) を示すことはできるだろうが、交尾頻度でも間接的に能力を表すことができるのでは。栄養の劣ったオスにはできない、と想像する次第。
小鳥などでは頻繁な交尾は捕食リスクも増えるのでこちらは選択できなかった (これも「猛禽類ならでは」と言えるかも)。
猛禽類と酸化ストレスに関係する研究では渡りとの関係などは調べられているようだが、生殖に関するものは簡単に探した範囲では見当たらなかった。
チョウゲンボウ類など弱いコロニー性の営巣をする種で交尾頻度が特に高いのはこれまでの提案のように精子競争 (父権確保) も役割を果たしているのだろう。
Negro and Grande (2001) は猛禽類特有の性質を考えることで不要な競争防止のためのシグナル仮説に至ったわけだが、抗酸化物質のトレードオフ対象としての交尾頻度とそれぞれ二次的な役割になっているかも知れない。
植田 (2012) Birder 26(4): 46-47 に「交尾の回数の謎」の記事があり1日最大回数の表がある。この記事ではコロニー性や巣と採食地の距離、食物などが示されていて「浮気される可能性で決まっている」仮説を多少なりとも裏付けようとする意図でまとめられたものであろう。
植田・平野 (2003) ツミの交尾行動 - 多数回交尾の適応的意義の検討 -の結果は父権の確保は主要な理由とは考えにくいとのこと。Negro and Grande (2001) の仮説は検討されていなかった。
Negro and Grande (2001) の交尾回数があまりに大きいので同じように抜粋してみた。種名の後に * があるのは追加資料から。
つがい外交尾率 (EPC) の項目で EPF 以降の数字 (%) はつがい外の受精成功率。EPC は交尾回数比率。(LC) は一部ゆるいコロニー性 (loose colony)。C はコロニー性。他は単独つがいで繁殖 (solitary)。
種の順序は現代の分子系統樹で系統順に並べ替えてある (元資料ではかなり異なる)。和名と系統関係が対応しない場合があるので属名で確認いただきたい。
| 種 | 交尾回数 | つがい外交尾率 (%) |
| ミサゴ Pandion haliaetus | 160 | 1 (LC) |
| カタグロトビ Elanus caeruleus | high | ? |
| エジプトハゲワシ Neophron percnopterus | 55 | 2.6 |
| ヒゲワシ Gypaetus barbatus | high | 0.52 |
| ヨーロッパハチクマ Pernis apivorus | high | ? |
| チュウヒワシ Circaetus gallicus | high | ? |
| ベンガルハゲワシ Gyps bengalensis | high | ? C |
| マダラハゲワシ Gyps rueppelli | high | ? C |
| シロエリハゲワシ Gyps fulvus | high? | ? C |
| ケープシロエリハゲワシ Gyps coprotheres | 100/female | 0.5 C |
| オウギワシ Harpia harpyja | 9 | ? |
| ヒメクマタカ Hieraaetus pennatus | low? | ? |
| イヌワシ Aquila chrysaetos | high? | ? |
| ボネリークマタカ Aquila fasciata | 99.8 * | ? |
| コシジロイヌワシ Aquila verreauxii | high? | ? |
| アフリカツミ Tachyspiza minulla | high | ? |
| タカサゴダカ Tachyspiza badia | high | ? |
| ハイタカ Accipiter nisus | high | EPF 5.4 |
| クーパーハイタカ Astur cooperii | 372 | 0 (しかし解説参照) |
| オオタカ Astur gentilis | 518 | EPF 1.3 |
| オオハイタカ Astur melanoleucus | low? | ? |
| ヒメハイイロチュウヒ Circus pygargus | 105 | 3.5-3.4 (LC) |
| アフリカチュウヒ Circus ranivorus | 135 | 2.1 (LC) |
| アカトビ Milvus milvus | 234 | 3.5 |
| トビ Milvus migrans | 196 | 3.2 (LC) |
| オジロワシ Haliaeetus albicilla | high? | ? |
| サンショクウミワシ Icthyophaga vocifer | high | ? |
| ヒスパニオラノスリ Buteo ridgwayi | high? | ? |
| ヨーロッパノスリ Buteo buteo | high? | ? |
| ヒメチョウゲンボウ Falco naumanni | 362 | 6.7 EPF 3.4 C |
| チョウゲンボウ Falco tinnunculus | 218 | 1 EPF 5.3-1.9 |
| アメリカチョウゲンボウ Falco sparverius | 690 | 0.3 EPF 10 |
| コチョウゲンボウ Falco columbarius | 60 | 7 EPF 0 |
| エレオノラハヤブサ Falco eleonorae | high | <1 EPF 0 C |
| ソウゲンハヤブサ Falco mexicanus | 194 | 0 |
| タイタハヤブサ Falco fasciinucha | high | ? |
| ハヤブサ Falco peregrinus | high | ? |
| シロハヤブサ Falco rusticolus | 47 | ? |
| ワキスジハヤブサ Falco cherrug | high | ? |
いずれも欧米の種や研究が大半なので同種でも日本の個体に当てはまるかどうかはわからない。
定性的な記述しかないものは Cramp and Simmons (1980) "Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa, Volume II: Hawks to Bustards"
の出典が多いので新しいデータはそれほどないのだろうか。
数字を見るとつがい外交尾率の高い種やコロニー性の種が交尾回数が多い傾向は見える。アメリカチョウゲンボウは Villarroel and Kuhnlein (1998) の結果と EPF はかなり違う印象を受けるが個体群や研究によって違うのだろう。
ハイタカやオオタカで EPF が結構高い値になっていてこの系統は想像以上に EPC が多いのだろうか。とはいえしっかりした値が出ていないものも多いので猛禽類全体に交尾回数が多いことは確かなのだろう。
交尾回数の総数だけで見るとつがい外交尾などによる精子競争のようにも見えるが、前述のように交尾頻度のパターンを見るとあまりよい説明になっておらず代替仮説が必要だろうとのこと。
再度まとめておくと (0) 古典的な精子競争。これでうまく説明できないパターンを示すので (1) オスの資質を選ぶため (抗酸化物質云々の提案もこれに含まれる)、
(2) つがいの絆を深める、言い換えれば途中でパートナーを失うのを避けるため [Petrie and Hunter (1993)
Intraspecic Variation In Courtship And Copulation Frequency - An Effect Of
Mismatch In Partner Attractiveness 仮説の予測や検証方法も出ている]、
(3) (猛禽類特有) 闘争などを避けるための他個体へのシグナル、の仮説が現在までに出ていることになる。
鳥類全体のつがい外交尾の割合について Brouwer and Griffith (2019) Extra‐pair paternity in birds
の総説がある。
系統的にはかなり違いがあり、フクロウ類は特に少なく、タカ類、ハヤブサ類は少ない種類が多い (例外的な種類も少しある)。
オウム類ではほとんど見られていない。他の系統ではさまざまだがスズメ目に高い種類が多い。ツバメ類は高い方に入る。非スズメ目でもミズナギドリ目などやや目立つ系統がある。
もっと多そうな感じのするカモ類はそれほど高くない。全体的には猛禽類のつがい外交尾は少ないと言えそう。
いろいろな説明変数との相関を調べているがあまりすっきりした結果は得られていない模様。
その後クーパーハイタカでつがい外交尾が非常に多い結果を知った。Rosenfield et al. (2015) High frequency of extra-pair paternity in an urban population of Cooper's Hawks
13.9% のひながつがい外交尾で生まれ、34% の巣につがい外交尾のひながいた。観察からつがい外交尾はつがいを作っていない floater のオスによるものが大部分 (8割以上) と推定されるとのこと。
これまで猛禽類で測定された最高値とのこと。この論文では交尾の前に食物を受け取る仮説 [Negro and Grande (2001) では否定的書き方のため特に挙げなかった] を考えているが、これほどつがい外交尾率が高いと (0) 古典的な精子競争 で結構説明できてしまうのかも知れない。猛禽類全体で特に多いのは闘争などを避けるための他個体へのシグナルなどの別の説明が必要になるのだろうが。
Brouwer and Griffith (2019) にはこの研究は引用されていなかった。
都市環境に適応した猛禽類で食物が豊富、数も近年増えたばかり、などの特殊な状況では個体数も多くて精子競争が熾烈に起きているのかも。
その後このクーパーハイタカの個体群ではなんと種内托卵がに頻繁にあることが判明した #オオタカ備考の [クーパーハイタカの種内托卵] 参照。チュウヒ類に一夫多妻がしばしば見られるように {オオタカ属 Astur 属 + チュウヒ類} の系統の婚姻形態は他のタカ類に比べて複雑かも知れない印象を受けた。
あるいは兄弟殺しの少ない系統とも相関があるかも (誰か調べてみられませんか?)。
他のタカ類でも調べられていないだけで交尾回数の多い種類では実はもっと起きているのかも。
鳥類全体を対象とした (ただしスズメ目が中心) 子育ての手間とつがい外交尾率の相関の研究: Soraker et al. (2023) The evolution of extra-pair paternity and paternal care in birds
オスの餌運びとつがい外交尾率に逆相関がある。子育てとつがい外交尾率が逆相関にあることを最も確実に示した研究とのこと。
この結果に従えば圧倒的にオスが餌運びを行う広義 Accipiter 属でつがい外交尾率が低くなりそうだがそうなっていない。
抗酸化物質に関連して、肉食の鳥はやはり抗酸化物質のグルタチオンが少ないとの結果があり、関係があるかも知れないので紹介しておく: Pap et al. (2025) Phylogenetic Relationships of Immune Function and Oxidative Physiology With Sexual Selection and Parental Effort in Male and Female Birds 論文の主眼点ではないが...。
なお、交尾によって病原体感染のリスクも増えるのではと考えられるが、#カワラバト 備考 [トリコモナスはハト由来?] のような面白い研究があり、(この系統の) 寄生生物が交尾によるルートを選択していないことから病原体感染については案外安全なのかも知れない。ヒトでの感染ルートと比較しての話であるが。ヒトで例外的に多いだけかも知れない。頻回の交尾やつがい外交尾を可能にする一要因として考慮に入れるべきなのだろう。
[都会のチョウゲンボウのストレス]
Damiani et al. (2024) Blood transcriptome analysis of common kestrel nestlings living in urban and non-urban environments
によれば、都会とそうでないチョウゲンボウのひなで遺伝子発現が異なる点があった。都会のチョウゲンボウでは炎症、DNA 損傷の回復、アポトーシスに関係する遺伝子発現が高く、郊外のチョウゲンボウは発育、免疫機能などに関係する遺伝子発現が高かった。この違いが適応的なものかどうかまではわからないが、汚染物質などによる影響が考えられる。
都会生活には一定の慢性ストレスがあると言ってよさそうな結果と言えるだろうか。
都会では病原体や寄生虫の種類が少なく、それに関わる免疫機能を発現しなくてもよい可能性もこれまで指摘されているとのこと。
Sumasgutner et al. (2023) Integument colouration and circulating carotenoids in relation to urbanisation in Eurasian kestrels (Falco tinnunculus)
オーストリアのウィーンのチョウゲンボウの個体密度は世界の都市の中でも最も高いところの一つとのこと。都会にはネズミが少ないので鳥類に獲物を切り替えている。
ここで調べられたチョウゲンボウのひなは色合いが薄く、血中抗酸化物質のカロテノイド量も少なかったとのこと。都市にはそもそもカロテノイド源が少ないことが考えられるが、都会に住むことに伴うストレスでカロテノイドを着色に回せない可能性も考えられるとのこと。
都会の猛禽類のメタ解析が Kettel et al. (2018) The breeding performance of raptors in urban landscapes: a review and meta-analysis
にある。都会に多いハトを狙うハヤブサは世界的傾向で餌が豊富でクラッチサイズも大きいとのこと、しかし都市が必ずしも優良な環境とは言えない。チョウゲンボウでは主な食物が違うため都市で繁殖成功率が低いなど他の種も調べられているので参考までに。日本の事例は含まれていない。
[チョウゲンボウはなぜ頭を上下左右に動かすか]
チョウゲンボウのこの行動は遠近感を得るためと解釈されるが、O'Rourke et al. (2010) Hawk Eyes II: Diurnal Raptors Differ in Head Movement Strategies When Scanning from Perches
の研究がある。クーパーハイタカは両眼視の視野 (39°) が広く、側面視野が 132° 眼球もよく動く (8°)。アカオノスリは中間で側面視野が 122° 眼球の動きは 5°、アメリカチョウゲンボウは側面視野が 130° だが眼球は 1° しか動かなく (だが議論もあるとのこと)、前2者はそれぞれの餌探し・追跡方法に適応しているという。
motion parallax (頭の移動などに伴う視差) も重要であるとされてきたが、眼球の動きの方が奥行き情報が得られるとの研究もある。クーパーハイタカがこの中で最も頻繁に頭の向きを変えて対象をスキャンしていた。
アメリカチョウゲンボウは眼球が動かない分、頭を動かして奥行き情報を得ていると考えているが間接的証拠が中心で状況も少し複雑なので引用文献も含め、詳細はお読みいただきたい。
[チョウゲンボウの貯食行動]
伊関 (2011) Birder 25(2): 48-49 にチョウゲンボウの貯食の可能性のある行動が紹介されている。自ら食べるところまでは未確認。
マーリン通信の チョウゲンボウが足環のついたオオジュリンを捕り、貯食した! (1996) などの事例も日本のチョウゲンボウで時々記録されているよう。
アメリカチョウゲンボウの例では Toland (1984, 2024 再掲)
Unusual Predatory and Caching Behavior of American Kestrels in Central Missouri のような報告がある。古典的実験では秋から越冬期は 58% は蓄えたものを部分的にも食べたが、繁殖期は 7% に過ぎなかったとのこと。食欲が誘引 ("hunger drive") の古典的解釈は否定的とのこと。
またつがい形成時にメスへのプレゼントのためなども否定的とのこと。食物が多量にある場合に捕りすぎてしまうなどの解釈 [Nunn et al. (1976) Surplus killing and caching by American kestrels (Falco sparverius)] もある。
Collopy (1977) Food Caching by American Kestrels in Winter
の記録も読める。
Kerr (1999) Caching behaviour in captive American kestrels (Falco sparverius) (修士学位論文)。モズ類の「はやにえ」との比較もある。貯食した場所も覚えているらしい。
フクロウ類の貯食行動はよく知られているが、タカでも観察されていて Berry (2007)
Nesting and Food-Caching by Sharp-Shinned Hawks in Ipswich アシボソハイタカの事例。
Jorge et al. (2011) Handling time and the evolution of caching behavior に一般論として貯食行動がなぜ進化するかなど。
食物を貯蔵するために必要な時間が消費するのに必要な時間より短ければ行動が進化し得る。一般的に言われる食物が豊富な時に多めにとっておき、少ない時に用いる解説とほぼ同義 ("search time reallocation"。貴重な食物探しの時間を再割り当てする) になるが、食物が時間とともに劣化する場合でもこの行動は成り立つとのこと。
#ハヤブサの備考 [ハヤブサ目の系統分類] で紹介の、
エレオノラハヤブサの渡り途中の食性: Samraoui et al. (2022) Diet of breeding Eleonora's falcon Falco eleonorae in Algeria: Insights for the autumn trans-Mediterranean avian migration
2010-2012 年の調査では食物と渡る鳥の種類が極めてよく一致していた。
後に食べるために貯めてある事例もあり写真が紹介されている。渡りが集中する時期に集中的に捕獲しているらしい。渡りのピークは断続的に起きるので鳥類食のハヤブサ類が貯食行動を行ってもまったく不思議でなかった。
この事例は渡りの小鳥を主な食料とする種であったが、系統的にも近いのでチョウゲンボウに貯食行動の能力は十分あるだろう。渡りの小鳥ほど資源が断続的でない場合は、一度は貯食してもすぐに新しい食物が得られて結果的に貯食したものを食べる必要がない場合もあるだろう。上記 Jorge et al. (2011) と同様の議論となるが、新しい食物がすぐ得られる場合ほど貯食行動は進化しないのだろう。
貯食行動は海馬などの脳の記憶部位や回路の発達を促すだろうが、貯食行動を行うので賢い鳥であると短絡的に結び付けない方がよさそう。それらの部位や回路の維持にはコストがかかるので、行動に必要がなくなれば relaxed selection によって失われてゆくだけかも知れない。
-
アカアシチョウゲンボウ
- 学名:Falco amurensis (ファルコー アムレーンシス) アムールのハヤブサ
- 属名:falco (m) ハヤブサ)
- 種小名:amurensis (adj) アムールの (amur アムール -ensis (接尾辞) 〜に属するの)
- 英名:Amur Falcon
- 備考:
falco は#チゴハヤブサ参照。
amurensis は場所の -ensis で冒頭が長母音でアクセントがある。-ren- にアクセント (アムレーンシス)。wiktionary には短母音のみの発音が主に紹介されているがここでは統一しておく (wiktionary でも長母音発音も載せられている)。直前の音の影響を受けて短母音になりやすいのか。長音記号に忠実に読むかどうかの違いで実際上はどちらでもよい。
アカアシチョウゲンボウとニシアカアシチョウゲンボウが同種時代の英名 Red-footed Falcon に対応する学名があった Falco rufipes Beseke, 1792 (赤い足のハヤブサ) (参考) (Kessler 1851, 参考文献参照)。
英名とこの学名は対応していると考えるのが自然だろう。
The Birds of Europe (1837) にもこの学名と英名を用いた用例がある。
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 は後の調査で同定されて有効な学名になったものと想像できる。
和名は直接の起源は英名かも知れないがこれらに由来するものだろう。
[アカアシチョウゲンボウとニシアカアシチョウゲンボウ]
単形種。和名の英語に対応する Red-footed Falcon は別に存在し、ニシアカアシチョウゲンボウ Falco vespertinus (夕方の、薄明の < vesper 夕方)。アカアシチョウゲンボウとニシアカアシチョウゲンボウはユーラシア東西の姉妹種とされるぐらいに類似しているが (かつて同種とされた) 生態に大きな違いがある部分がある。
記載時学名 Falco vespertinus var. amurensis Radde, 1863 (原記載) 基産地 Zeya River, Amurland とニシアカアシチョウゲンボウの変種扱い。
変種であったため新たに Falco Raddei Finsch & Hartlaub, 1870 (資料) の学名も付けられたが変種が有効な亜種名と採用された [Dement'ev and Gladkov (1951) も参照]。
ニシアカアシチョウゲンボウの方には Falco vespertinus obscurus Tschusi, 1904 (参考) 基産地 Tomsk (シベリア西部) などの複数の亜種が提唱されていたがシノニムとなった。
Falco pyrrhogaster Reichenow, 1915 (赤い腹のハヤブサまたはタカの意味。参考) がカメルーンで記載されたが Dement'ev and Gladkov (1951) ではニシアカアシチョウゲンボウのシノニムとなっている。
和名が付けられた時点では両種が同種とされ、Amur Falcon は Falco vespertinus の東部の亜種とされていた。英語別名 Eastern Red-footed Falcon
[高野 (1973) でもアカアシチョウゲンボウの名前が使われている]。その後両種が別種扱いになったため、和名と英名が対応しなくなったものである (和名が長いので "アムール" を冠した名前の方が有り難いが... 自身では Amur Falcon と言い直した上で「アムール」としばしば呼んでいる)。
[ニシアカアシチョウゲンボウの営巣習性と現在の問題点]
ハヤブサ属は原則自分で巣を作らない。ニシアカアシチョウゲンボウはミヤマガラスのコロニーに依存し、自身もコロニー性に営巣パターンをとる。ルーマニアの事例ではミヤマガラスが巣立つころにちょうどニシアカアシチョウゲンボウが渡ってくるそうである。
ハンガリーではミヤマガラスが郊外でなく都市にコロニーを作るようになってニシアカアシチョウゲンボウの生息環境が減った (資料)。ハンガリーではムクドリ駆除薬剤 (DRC 1339 別名 Starlicide、種特異性が高くカラス類には有効だが猛禽類には影響がない。離島で固有種に対して安全な場合に外来種駆除に利用される例がある) がミヤマガラスの駆除のために使われたが、ミヤマガラスが急減したためにそれに依存するニシアカアシチョウゲンボウの個体数が激減し、薬剤は使用禁止となった。
Soltesz et al. (2018) Dipteran Assemblages in Red-footed Falcon (Falco vespertinus) nest boxes
によればハンガリーのニシアカアシチョウゲンボウは現状 (2006) では 2/3 のつがいが人工の巣箱に頼っているそうである。ミヤマガラスの巣は毎年作られるので寄生虫などが少ないが巣箱だとそうも行かないとのこと。この研究では巣箱は毎年更新する必要があるとのこと。
ハンガリーではこの状況も受けてモノグラフも出版され、最初はハンガリー語で書かれ、英訳が出版された Palatitz et all. (2019) The Blue Vesper - Ecology and Conservation of the Red-footed Falcon で冒頭の部分を見ることができる。
この本は 2019 年 British Birds/British Trust for Ornithology Best Bird Book of the Year を受賞。Dwyer and Dwyer (2020)
The Blue Vesper: Ecology and Conservation of the Red-footed Falcon
などに書評がある。なかなかアクセスの難しい英語圏から遠く離れた言語での文献も広く紹介するなど、英語圏以外の鳥を紹介するよいアプローチになっているとのこと。
"The Blue Vesper" では vesper を「夜」と訳しており、夕暮れ時に狩りをする習性や渡りの時のねぐら入り前に大きな集団を作ることに由来するそうである。ルーマニア語 (falcun vespertin)、セルビア語 (siva vetruska) では「夜のハヤブサ」を意味する名前になっているとのこと (おそらくロシア語 veter 夕方 と同様の語源か。
ただしニシアカアシチョウゲンボウのロシア名はまったく異なり kobchik で中世ドイツ語の habuch タカに由来とのこと。オオタカのドイツ語名も参照)。現代では kob (ハヤブサ類) の小型 -chik との解釈もあるとのこと (Kolyada et al. 2016)。
意外なところでこの名称に関連するものがあり、ハチクマ類は古く (19 世紀ぐらい) kobets と呼ばれていたことを知った。色彩の似た "タカ" 類をまとめた語だったのかも。現代では食性を反映した名前になっている。
英語 Vesper には宵の明星の意味もある。
Fehervari et al. (2012)
Allocating active conservation measures using species distribution models: A case study of red-footed falcon breeding site management in the Carpathian Basin ではハンガリー、ルーマニアと隣接分布になるセルビアでも人工巣箱によるコロニー確立が必要との研究がある。
アカアシチョウゲンボウの分布に近いロシア東部でニシアカアシチョウゲンボウがどのように繁殖しているのかも気になるところであるが、Bajkalskij Zoologicheskij Zhurnal (バイカル動物学雑誌) の 2022年の第1号 が(ニシ)アカアシチョウゲンボウの特集号となっている。
ロシア中央部のオムスク州でもニシアカアシチョウゲンボウはミヤマガラスの巣を使ってコロニーで繁殖している。イルクーツク州では (アカアシチョウゲンボウの分布に近いところ)、数が少なくて繁殖までは確かめられていないらしい。バシキリスタン共和国 (ウラル付近) では 1890 年からずっと減少を続けているとのこと。
[アカアシチョウゲンボウの営巣習性]
アカアシチョウゲンボウはニシアカアシチョウゲンボウと異なり主にカササギの古巣を使う。これはミヤマガラスのコロニー (ミヤマガラスの東の亜種 Corvus frugilegus pastinator もコロニーを作って繁殖する) のある地域であっても同様である (ミヤマガラスの古巣を使うこともないわけではないらしい)。カササギはコロニー性でないので、営巣習性や巣の間の空間分布はニシアカアシチョウゲンボウと異なる。
Burner et al. (2019) Nesting ecology of solitary-nesting Amur Falcons (Falco amurensis) in central Mongolia (モンゴルの事例)、
Dorzhiev et al. (2008 初出, 2019 再掲) Ecology of the Amur falcon Falco amurensis in the Western Transbaikalia (ロシアの事例)、
Shokhrin et al. (2020) Nesting birds of Primorsky Krai: falcons Falconidae (ロシア沿海地方で繁殖するハヤブサ類) [極東の鳥類42「沿海地方の繁殖する鳥類 2」 で訳文が読める]。
ロシア極東部では Frommhold et al. (2019) Breeding habitat and nest‐site selection by an obligatory "nest‐cleptoparasite", the Amur Falcon Falco amurensis の最近の論文もあり、遠方より長距離を渡ってくるので到着が遅く、他種の巣を間借りする行動が進化したとの考えもあることが紹介されている。
上記バイカル動物学雑誌 (2022) 第1号では、アカアシチョウゲンボウはザバイカルとモンゴルでまだらに分布していて、カササギの古巣を使っている。巣の間隔は 3-200 m 以上ぐらい。近接した巣が並んでいて使われていることもある。巣が古いと壊してその巣材を使って少しは巣造りもする。モンゴルとは巣の間隔など少し違いがあるようである。ハシボソガラスの巣の例が1つあるらしい。
中国でもアカアシチョウゲンボウはカササギの古巣を使っている(参考)。「詩経」(全 305 篇からなる中国最古の詩篇、紀元前前 11-7 世紀)にも記載があり、カササギの巣にハトが住むとの言い伝えがある。
「詩経」のこの部分は故事成語にもなっていて「鵲巣鳩占」(じゃくそうきゅうせん、逆順に書くこともある)になるそうである。「他人の地位や成功を横取りすること。または、嫁いできた女性が夫の家をわが家とすることのたとえ。巣作りが得意な鵲の巣に鳩が住み着くという意味から」(出典)。
本来の意味は、結婚して夫の家に住んでいる女性を指すとのこと (カササギが新郎、ハトが新婦)。この「ハト」とされるものが実はアカアシチョウゲンボウを指しているとのこと。
なお中国でカササギの古巣を使う種類に関して Zhou et al. (2009) Patterns of magpie nest utilization by a nesting raptor community in a secondary forest の調査論文がある。アカアシチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、トラフズクの事例が多いが他の猛禽類も利用している。猛禽類以外ではブッポウソウの利用が目につく。
ロシア沿海地方での繁殖: Shokhrin et al. (2020) Nesting birds of Primorsky Krai: falcons Falconidae (pp. 4479-4513)
(極東の鳥類42:沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める)。個体数は変動が大きいとのこと。
アカアシチョウゲンボウやニシアカアシチョウゲンボウの適応放散の年代とカラス類とどちらが古いのか確認してみた。Fuchs et al. (2015) (#ハヤブサ備考参照) の分子系統樹によれば、{アカアシチョウゲンボウ + ニシアカアシチョウゲンボウ} が他の系統から分離したのは 500-600 万年前程度。この2種が分岐したのはさらに最近で 100 万年より少し前程度。
後者がユーラシアに広く適応放散した年代と考えればカラス類は先に住んでいてこれらの種類は営巣場所に困らなかったと想像できる。
Pica 属では適応放散は比較的新しく、属全体では 230 万年前程度、個々の種では 150-100 万年前と結構新しく個体数は最近急に増えたものと考えられる [Song et al. (2018) Complete taxon sampling of the avian genus Pica (magpies) reveals ancient relictual populations and synchronous Late-Pleistocene demographic expansion across the Northern Hemisphere]。
Pica 属もアカアシチョウゲンボウ類も乾燥地域の拡大に合わせて同じような時期に分布拡大したらしい。カラス類の分散に合わせて生息地を拡大した (?)。
コクマルガラス類やミヤマガラスの分岐の方が 350 万年以上前と古く (#ミヤマガラス備考の Weissensteiner et al. (2020) を参照)、アカアシチョウゲンボウ類にとってはこちらの方が適した間借り相手だったかも (ニシアカアシチョウゲンボウでは今でも続いている)。カラス類の方がハヤブサ類よりも一般的には古い (ユーラシアで Falco 属を考察する場合) ことは一種の盲点かも知れない。
[渡り]
アカアシチョウゲンボウは猛禽類中最長の海上の渡りをする種類として有名である。かつては繁殖地が極東周辺、越冬地がアフリカ南部しか知られておらず、どこをどのように渡っているのかは推測の域を出なかった。
秋の渡りの際にインドに集結して大きな群れを作ること (このころは重要性がわからず大量に食用にされていた) や、その後地上を渡る姿が観察されないことからインド洋を渡っているだろうと推測されていた。成書にもそのようなルートが記載されているが
[例えば Bildstein (2006) "Migrating raptors of the world: their ecology and conservation"。Lloyd and Lloyd (1969) を高野 (1973) が訳したものにもこのルートはすでに示されていた]、確かにインド洋を渡ることが示されたのは近年になってからである。
Tracking the Incredible Journey of the Amur Falcon の衛星追跡の結果が目覚ましい (引用されている文献も役立つ)。
周年の渡りは例えば
Year-round satellite tracking of Amur Falcon (Falco amurensis) reveals the longest migration of any raptor species across the open sea を参照。春の渡りではより大陸沿いに北上する。
From Prey to Protected Species: How the Tide Turned for the Amur Falcon も食用から保護にいかに転じたかも興味深い。この資料にはインドから渡る直前の大群の写真が出ている。大規模ねぐらの写真と記事。
中国内を北上する衛星追跡事例もある: Wanglei et al. (2018) Spring Migration and Home Range of Amur Falcon (Falco amurensis) Documented by Satellite Tracking。
この研究では副産物として繁殖地の情報も得られ、衛星追跡で明らかになった繁殖地にはカササギの巣がたくさんあって優良な繁殖場所を提供しているとのこと。
インド洋を通るこの渡り経路はモンスーンの風 (貿易風) を助けにしている。この風はインド洋交易ルートと呼ばれる少なくとも紀元前3世紀には始まった人間の交易も助けているものである。
この風を利用して移動する生物も多く、自分がアカアシチョウゲンボウと貿易風の関係に興味を持ったのは2010年の Charles Anderson discovers dragonflies that cross oceans の TED 講演を見たのがきっかけであった (字幕も出て翻訳で見ることもできるので見ていただきたい)。
この当時はアカアシチョウゲンボウの渡りの衛星追跡の証拠がまだ得られる前であったがすでに渡りが紹介され、他にも同時期に渡る鳥をいくつも紹介している。そして、その渡り時期はトンボが渡る時期と完璧に一致するとのことである。後はこの講演も聞いていただいて生物学者が何を考えるか皆様の想像にお任せしたい。プレゼンテーションとしても大変優れた内容と思う。
先にニシアカアシチョウゲンボウとアカアシチョウゲンボウの関係を長々と述べたのもこの渡り経路の進化にも関係していると考えるためである。この2種はともにアフリカで越冬する。
アカアシチョウゲンボウがアフリカへ長い旅をするのは祖先種の性質を引き継いだもので、これらの祖先種がユーラシアに広く分布していてアフリカで越冬していたのが分断が起きて東西で種分化したものと考えると理解できるように思える。
なおニシアカアシチョウゲンボウの渡りについては例えば Katzner et al. (2016) Unusual clockwise loop migration lengthens travel distances and increases potential risks for a central Asian, long distance, trans-equatorial migrant, the Red-footed Falcon Falco vespertinus を参照。春と秋で経路の異なるループ状の渡りを行う。
アカアシチョウゲンボウの祖先が多分東に分布を広げたころは律儀に大陸を通る渡りだったのだろうが、どこかでショートカットする戦略が「発見」され、秋の渡りは貿易風を利用してインド洋を横断する壮大な渡りになったのではと考える (しかしこんなことは誰でも思いつきそうなのでどこかに書いてあるのではないかと考えるが...)。
追い風の助けは得られるとしてもインド洋を横断する間の食料事情はどうするのか。これまで提示した要素を組み合わせれば推定できそうである。
これに関係して ecosystems in the sky にさらに解説がある。アカアシチョウゲンボウの渡りと同じ時期に globe skimmer dragonflies (Pantala flavescens) というバッタがインド洋の島に現れるとのこと。一緒に渡って餌にしているのではとのこと。
今のところこのフライウエイを使っていることが確実に確認されているのはアカアシチョウゲンボウとカッコウのみである。バッタ類の大発生の時にアカアシチョウゲンボウが実際にコントロールに役立っているとの説明がある。
(この記事とは関係ないが) ちなみに日本のハチクマの秋の渡りも猛禽類としては長距離の海上の渡りだそうである。
-
コチョウゲンボウ
- 学名:Falco columbarius (ファルコー コルムバーリウス) ハトぐらいのハヤブサ
- 属名:falco (m) ハヤブサ
- 種小名:columbarius (adj) ハトぐらいの/ハトを狩る? (columba (f) ハト -arius (接尾辞) 〜に関連する)
- 英名:Merlin
- 備考:
falco は#チゴハヤブサ参照。
columbarius は接尾辞 -arius の冒頭が長母音でアクセントもある (コルムバーリウス)。
オオタカの旧学名 (Astur palumbarius で palumbarius はモリバトの種小名) ではおそらくハトを狩る意味と考えられるが、コチョウゲンボウの場合は食性やサイズから大きさを用いる方が適切と思えるためこちらを採用した。
コチョウゲンボウの記載が北米で先行したことを考慮すると、アメリカの英語俗名の pigeon hawk をそのまま学名に訳して命名したものかも知れない。その場合はあまり深く解釈せず "ハトに関連するハヤブサ" ぐらいの学名解釈がよいかも知れない。
かつては北米で pigeon hawk とも呼ばれていた (wikipedia 英語版より)。
OED (pigeon hawk の項目) によれば北米で pigeon hawk と呼ばれたものは現在のアメリカオオタカ、アシボソハイタカ、クーパーハイタカ で、絶滅したリョコウバト (!) を食物としていたためそのように呼ばれていたとのこと。コチョウゲンボウに対する用例解説は OED には出ていないが hawk の項目には hobby-hawk の用例があるので小型のハヤブサ類にも使われていたのだろう。
英名 Merlin はしばしば言われるような 12 世紀の偽史「ブリタニア列王史」に登場する魔術師 アンブローズ・マーリン Ambrose Merlin に由来するものではないとの説明が wikipedia 英語版にある。
この意味の Merlin は英語では当時 Myrddin であり鳥の名前と関係がない。Bird of The Week: Merlin (Audubon)。
wiktionary でも別項目扱いで merlin の語源は古フランス語のハヤブサを意味する esmerillon 由来とのこと。古フランク語 (Frankish) で *smiril (ハヤブサまたはタカ)、さらにゲルマン祖語の *smirilaz (ハヤブサ、特にコチョウゲンボウ) に由来するとのこと。この語源は不明とのこと。
同系語で古高地ドイツ語に smirl (ハヤブサ)、古ノルド語 smyrill (ハヤブサ) があったとのこと。
現在のアイスランド語 smyrill などに残っている。
[亜種と分類]
北半球高緯度帯に分布し、冬は南に渡る。9亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは insignis (驚くべき、特筆に値する) 亜種コチョウゲンボウ (繁殖地はシベリアのエニセイ川とコリマ川の間) と pacificus (太平洋の) ヒガシコチョウゲンボウ (繁殖地は北東アジアとサハリン)。
Falco columbarius Linnaeus, 1758 (原記載) が採用されているが基産地はアメリカ。この記載を見ると Linnaeus 以前に Accipiter palumbarius の名称があったことがわかる (もちろん有効な学名ではない)。
現在オオタカのシノニムとされる Falco palumbarius Linnaeus, 1758 はどちらもハトが種小名なので意味の上では大変紛らわしい。
ユーラシアと北米のコチョウゲンボウは独立種とする考えがある [Wilcox et al. (2019) Falcon genomics in the context of conservation, speciation, and human culture]。
この場合 Falco columbarius (英名 American Merlin) は北米の種を指し、ユーラシアの種には Falco aesalon (英名 Eurasian Merlin) の名称が提唱されている。将来後者に改名される可能性がある。Fuchs et al. (2015) の分子系統樹では Falco aesalon を種として扱っている。
Falco Aesalon Tunstall, 1771 の 原記載。英名 Merlin としてリストに現れる。
aesalon はアリストテレスがタカの1種に用いたもので aisalon, aisalonos (Gk) タカでコチョウゲンボウ、ヨーロッパチュウヒ、ボネリークマタカなど様々に同定されている (The Key to Scientific Names, wiktionary)。
wiktionary によれば r と l の交代現象からギリシャ語以前の語源が考えられる説がある。ギリシャ語の読みでは古典式で "アイサローン" で 時代を経て "エサロン"。ラテン式でもギリシャ語古典式同様 (アエサローン) に発音してよさそう。
日本で記録されているとされる2亜種は2種に分割された場合にどちらに属するかはさらに研究が必要であろうが、wikipedia 英語版では日本の亜種は aesalon グループとしている。
将来この学名になる可能性があるため読み方も少し知っておくとよさそう。
以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種など記載もわかる範囲で含めた。
・Falco columbarius Linnaeus, 1758 o (原記載) 基産地 America = South Carolina ex Catesby (アメリカ。Catesby がサウスカロライナに限定)
・Falco Aesalon Tunstall, 1771 o (原記載) 基産地 No type locality = France, from Brissonian reference (Brisson の文献からフランスに限定)
・Falco regulus Pallas, 1773 (参考) 基産地 Siberia (シベリア) = aesalon
・Falco lithofalco Gmelin, 1788 * (参考) = Falco columbarius
・Falco subaesalon Brehm, 1827 o 基産地 Iceland (アイスランド)
・Falco Hypotriorchis richardsonii Ridgway, 1871 o (原記載) 基産地 mouth of Vermillion River, South Dakota (サウスダコタ州)
・Fako columbarius var. suckleyi Ridgway, 1874 o (原記載) 基産地 Shoalwater Bay and Fort Steilacoom, Washington (ワシントン州)
・Lithofalco aesalon pallidus Sushkin, 1900 o (原記載) 基産地 Western part of the Kirghiz Steppes (キルギス西部)
・Falco christiani-ludovici Kleinschmidt, 1900 = pallidus に新名が与えられたもの (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Aesalon regulus insignis Clark, 1907 o (原記載) 基産地 Fusan, Korea (釜山、韓国) 亜種コチョウゲンボウ
・Falco aesalon lymani Bangs, 1913 o (原記載) 基産地 Tchegan-Burgazi Pass, Altai Mountains (アルタイ山地)
・Falco alfred-edmundi Kleinschmidt, 1917 * (新名が与えられたもの。以下の Kleinschmidt 1917 参照。参考) 基産地 アイスランド = Falco subaesalon
・Falco columbarius bendirei Swann, 1922 (原記載) 基産地 Fort Walla Walla, Washington (ワシントン州) = suckleyi
・Aesalon columbarius pacificus Stegmann, 1929 o (参考) 基産地 Rasboinik Rock, Sea of Okhotsk (オホーツク海) ヒガシコチョウゲンボウ
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
北米の記載が先行しているのは興味深い点。
Falco lithofalco Gmelin, 1788 はおそらく Linnaeus (1758) の記載がまだ同定されていない時代だろうか。Falco lithofalco の学名を用いた亜種 (当時は変種) suckleyi が 1874 年に記載されているので、Falco lithofalco の学名は結構長期間使われていた可能性がある。
Hypotriorchis (英語の hobbies に相当) は亜族の概念で種小名ではない。
Lithofalco aesalon pallidus に別名が与えられたのは Falco 属にまとめられた際に Falco pallidus Schlegel & Sysemihl (参考)
と Falco tinnunculus pallidus Brehm, 1866 の名称がすでにあるため Kleinschmidt が preoccupied (すでに使用されている) と判定して新しい名前を付けた (Nomenklatorisclies und Systematisches Kleinschmidt 1917)。
orientalis と付けてもよかったこれは無効名だったとのこと。Falco orientalis Gmelin, 1788 がすでにあった (参考 基産地日本で "Oriental Hawk"。記載。これはハヤブサの亜種 japonensis のシノニムとされる)。
ハチクマの亜種 orientalis は記載時に属が違う (Pernis) ので可能だった名前となる理屈になる。Falco apivorus だった時代に記載されていればこの亜種名にはならなかったと想像される。
Type specimens in the bird collections of the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn Van den Elzen (2010)
によれば Brehm の pallidus 名称は無効 (Vaurie 1965) で、Falco pallidus Schlegel & Sysemihl は実際には Circus pallidus = 現在の学名でウスハイイロチュウヒ Circus macrourus (Dickinson 2003) と同定されたため、Falco 属内の衝突がなくなって使えるようになったと解説されている。
Falco regulus Pallas, 1773 の扱いが問題で、シベリアと西ヨーロッパ (越冬地記載) が別亜種と考えた場合は古い記載のこの亜種が生きてくる可能性がある。
名称面では regulus が "小さな王" の意味 (#キクイタダキ参照) なのでコチョウゲンボウにふさわしいのだが、越冬地の西ヨーロッパと同一亜種と扱われて表面上現れなくなった。
現在使われる亜種名の insignis はこの "種" の亜種として命名されたもので、"驚くべき、特筆に値する [小さな王]" と "小さな王" が隠れていると考えると一層面白い。
もっとも insignis も越冬地記載なので繁殖分布がどうなっているのかそれほどすっきりしたものではない。
我々に近いところでは pacificus のみが比較的特定された場所で Dement'ev and Gladkov (1951) も基産地周辺のオホーツク海沿岸を分布域にしているだけのように見える。aesalon と似ているがより暗色でサイズが違う。
羽衣はアメリカのものに似ていて、ユーラシアとアメリカの関係ではケアシノスリと相同性があると書かれている。pacificus の個体変異は大きく、insignis と違わないような明るい色で白っぽい斑点を持つ個体も含まれるとのこと。
他亜種の特徴を持つ個体が含まれている程度ならば、基産地の関係でそれぞれ亜種として認められているものの実はあまり違いがないのでは?
見慣れない属名をチェックしておくと、Aesalon の意味は(亜)種小名に使われるものと同じで Kaup (1829) がコチョウゲンボウに提唱した属。Steinfalke (石または岩のハヤブサ) となっていて岩場に住むことを意味したものだろう (イヌワシのドイツ語名 Steinadler と同様)。
同じ属名を Morris (1837) が用いてこちらはハイタカ類を指したものだった。
Lithofalco は Falco lithofalco が使われていた時代にコチョウゲンボウのみを含む属として種小名から昇格したもの。Hahn (1835) によるもので Blau-Falke (青いハヤブサ。これはよくわかる) とのこと。Lithofalco 自身の意味は litho- (Gk) が石で Steinfalke に対応するギリシャ語を用いたもの (The Key to Scientific Names)。
ハヤブサ類の分子系統樹については Wink (2018) Phylogeny of Falconidae and phylogeography of Peregrine Falcons も参照。
[音声研究]
ハヤブサ類とオウム類の系統が近いことがわかり、ハヤブサ類でも音声の (あるいは音声学習の) 進化の可能性を調べる研究が始まっている。
Griffiths and Aaronson (2023) Analysis of vocal communication in the genus Falco。
特に結論が出ているわけではなくて、まだ基礎データを集めている段階の感じではあるが、調べられた7種のうち4種で音声の内部構造に有意な違いが見つかった。北米の研究で、日本と共通種はコチョウゲンボウのみなのでここに含めておく。ハヤブサ類でも音声は普通地鳴きと呼ばれるが、地鳴きとさえずりの区別は厳格なものではなく、音声学習の可能性も含めて song (さえずり) と記述しておくとのこと。
意外な感じもするがコチョウゲンボウ (ただし別種となる可能性もある) の研究はアメリカが進んでいる。
音声学習にもさまざまなものがあり、スズメ目と同じ神経経路を使わない学習も考えられる。
(音声学習に関与するとされる神経核がなくても音声学習をしないとは言い切れない)。
通常は音声学習をしないと考えられる種類での音声学習的な記述については#ハクトウワシの備考も参照。
[採食にハイイロチュウヒを利用するコチョウゲンボウ]
McConnell (2011) Merlin chases passerines flushed by Northern Harrier
ハイイロチュウヒが低く飛ぶと小鳥類が飛び出し、ハイイロチュウヒは特にそれらを追わなかったがコチョウゲンボウが狙って採食する。
現象としては古くから知られていて 1950 年代にも記録がある。英国で列車で飛び出した小鳥類を獲物にした報告 (Kenyon 1942) もある。英国ではいずれも日本よりは数の多い種類なのでその後も観察報告はいくつもある。
Merlin (Hawk and Owl Trust) によればコチョウゲンボウの飛翔形は特有で (clipped flight style) 獲物にとってハヤブサ的に見えず、遠くからはむしろヤドリギツグミのように見えるという。
この解釈が本当であればこれも aggressive mimicry と呼べるのだろう。
コチョウゲンボウはまれだが定義次第で共同ハンティングを行っていると呼べる可能性が示唆されている: Buchanan (2010)
Is Simultaneous Hunting in Winter by Merlins Cooperative?。
これまでにハヤブサ類で共同ハンティングと考えられる行動はしばしば報告されている。
-
チゴハヤブサ
- 学名:Falco subbuteo (ファルコー スブブーテオー) ノスリのようなハヤブサ
- 属名:falco (m) ハヤブサ
- 種小名:subbuteo (adj) ノスリのような (sub- (接頭辞) 多少 buteo (m) ノスリ 補足参照)
- 英名:Hobby, IOC: Eurasian Hobby
- 補足:
falco はラテン語では語末が長母音。アクセントは冒頭 (ファルコー)。短く読んでも構わないが知っておいて損はなさそう。
語源は諸説あるが、西ドイツ祖語では *falko で語末は長音。他にも由来は考えられるが *-(u)k- はいろいろな鳥に使われていた。オオハシウミガラス の alca の由来となる *alko など (これも語末は長音)。*kranuk (ツル) など。
falx (鎌) から曲がった嘴の説はあるが通常は俗説とされるとのこと (wiktionary)。
subbuteo は buteo 由来なので -bu- を長母音で読むのが適切と思われる。この解釈ならばアクセントもここに生じる (スブブーテオー)。
ユーラシアのやや高緯度に広く分布し、冬はアフリカへも含め南に渡る。日本では北海道などで繁殖。2亜種あり、日本で記録されるものは基亜種 subbuteo とされる。
種小名の subbuteo はアリストテレスの述べたタカの一種 hupotriorkhes (Gk) に対応するとのこと (triorkhes Gk はノスリに似たタカ全般に用いられる)。hupo (Gk) が「似ている」で、種小名はギリシャ語からラテン語に訳されたものと考えるのが妥当そう。hupotriorkhes は同定されていないが、伝統的にチゴハヤブサだと考えられてきたとのこと (The Key to Scientific Names)。
意味は「ノスリのような」で構わないが、どの点でノスリに似ているのか問うことは大した意味がなく、伝統的にチゴハヤブサを指すものとされてきただけのよう。多分褐色のタカみたいな鳥は幅広く triorkhes と呼ばれていたのだろう (#ハチクマ備考の [60 年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)] 参照)。
hobby の英名の由来は中世英語 hoby, hobeye < 古フランス語 hobe, hobei, hobet < 中世ラテン語 hopetus < harpe (< harpe 猛禽、ハヤブサ、三日月型の刀 Gk) の指小形。「趣味」の意味の hobby とは別語源 (wiktionary)。
ロシア語名では cheglok (チェグローク。アクセントは後) でチュルク語の chauli (チャウリ) に由来するとのこと (Dement'ev and Gladkov 1951)。微妙に気になるのが確立した和名語源解釈のないチョウゲンボウと音が似ている点。
#チゴモズ では中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 114 (1940 年初出) によればモズとは比較にならぬぐらい美しいので、チゴ (稚児) という美称がついたとのこと。
現在の日本産の鳥で "チゴ" が付くのはチゴモズとチゴハヤブサのみなので、チゴハヤブサにも同じ説明が適用可能だろうか。確かにチゴハヤブサの方は赤い色彩があって特に成鳥は艶やかである。
"チゴ" は小さい意味と思っていて、チョウゲンボウより小さいわけではないのに (ハヤブサよりは小さいが)、と感じていたが色彩の意味も含められていると考えるとより納得できる。
[Falco 属のタイプ種]
チゴハヤブサは Falco 属のタイプ種 (The Key to Scientific Names の表示による)。これは AOU Committee (1886) が後に定めたもので、Gray (1840) によるタイプ種指定はハヤブサ。
Peters (1931) や BOU (1915) は AOU Committee (1886) のものを採用。
Hellmay and Conover (1949) は AOU Committee (1886) の扱いを批判していたとのこと (The Key to Scientific Names)。
他のページでもハヤブサをタイプ種としているものもある [cf. FALCONIFORMES Falcons (Checklist of the Birds of New Zealand, Ornithological Society of New Zealand 2019)]。
Accipitridae (BirdForum 2025.3) によれば記載者がタイプ種を指定しなかった場合、リストの中で最初に現れる種類をタイプ種と認定する考え方は過去にあり AOU が用いていたとのこと。しかしこの方法ではグループの中で特異な種類がタイプ種に選ばれる可能性があるため、現行のタイプ種を後に指定する方法に変更されたとのこと。20 世紀初頭の話。
参考: Allen (1906) The 'Elimination' and 'First Species' Mothods of Fixing the Types of Genera。タイプ種の指定に関する規則は 1842 年、1905 年に改定され、それを受けた議論の模様。
Allen (1907) A list of the genera and subgenera of North American birds, with their types, according to Article 30 of the International code of zoological nomenclature は考え方を変えたとのこと。
この BirdForum スレッドで言及されているものは Vultur 属のタイプ種で、Allen (1907) は自身が 1906 年に提案したタイプ種を最初に定義されたタイプ種と認定した。この 1907 年論文が Vultur 属のタイプ種を定義した文献として一般的に引用されるとのこと。
Falco 属も状況はおそらく同じで AOU Committee (1886) の時代には最初に現れる種類をタイプ種と認定する考えを用いたものと想像できる。Gray (1840) のタイプ種指定の方が早いのでこちらの方が優先されそうにも見える。
しかし問題があるとすれば Falco Linnaeus, 1758 には現在の定義ではハヤブサが含まれない。Gray (1840) は Linnaeus の Falco 属に "Falco peregrinus L." を含めていた [現在の解釈ではハヤブサは Tunstall (1771) が命名したことになっている]。
Falco Linnaeus, 1758 にハヤブサが含まれないのでタイプ種になり得ないと解釈すれば AOU Committee (1886) の指定が有効になってチゴハヤブサがタイプ種となる理屈になる。AviList (2025.6) ではこのタイプ種を採用。
これも元をたどれば Falco gentilis Linnaeus, 1758 の問題で (#オオタカと#ハヤブサの備考参照)、これが何者か長年定義されないままで、結果的に 20 世紀初頭にオオタカの若鳥を指すと認定されオオタカの学名が変わったことに由来している。
Falco gentilis Linnaeus, 1758 が Linnaeus がおそらく意図したようにハヤブサであったならば何の問題も起きなかったことになる (Falco 属タイプ種指定の経緯を調べていないので推定を含む)。
今のところ分子系統研究で Falco 属の分割を積極的に進める証拠はないが、もし行われることがあればこのタイプ種問題の議論が再燃する可能性がある。もっとももし分離されてもハヤブサは Hierofalco 属となって Falco 属が昇格したように読めるので文句を言う人は少ないだろうが。
Falco 属は現代の学名概念が確立されてから Vultur 属に次いで2番めに早く diagnose された属とのこと (The Key to Scientific Names)。
[系統と分類・渡り]
#ハヤブサの備考にあるようにチゴハヤブサは分子系統的にマダガスカルで越冬する特殊なハヤブサ類のエレオノラハヤブサ、ウスズミチゴハヤブサそしてアフリカチゴハヤブサと混ざってしまうぐらい近い。
#コチョウゲンボウの備考にあるようにチゴハヤブサでも東西で種相当の違いがあることを示唆しているものかもしれない。
これらの種を含んだより詳細な分子系統解析によって単系統のグループに分けると現在の種概念と異なるものになる可能性がある。
チゴハヤブサによるコウモリの群れの捕食と薄明かりでの狩りへの適応についてはハヤブサの補足参照。
hobby と kestrel の違いはかつて Accipiter と Astur に分割されていた広義ハイタカ属内の関係に対応する [Brown (1976)。#オオタカの備考 [系統と分類] 参照]。
チゴハヤブサとチョウゲンボウの関係はツミ・ハイタカとオオタカの関係に相当となる。
チゴハヤブサグループは亜属 Hypotriorchis と呼ばれることがあり (かつてチゴハヤブサの属名として使われていた)、
Hobbies によれば
オーストラリアチゴハヤブサ、ミナミチゴハヤブサ、エレオノラハヤブサ、ウスズミハヤブサ、チゴハヤブサ、アフリカチゴハヤブサの6種からなるとのこと。#ハヤブサの備考で示したチゴハヤブサグループからコウモリハヤブサ、アカハラハヤブサを除いた形になっており、少し細かめに分けるとこの6種で単系統を作ることも確かである。
この記事でその後に暫定的にリストされている3種ニュージーランドハヤブサ、チャイロハヤブサ、タイタハヤブサまで含めると単系統にならない。
チゴハヤブサを考える時には近縁の特殊なハヤブサ類エレオノラハヤブサ、ウスズミチゴハヤブサとの生態の類縁性の有無なども考察するべきであろう。
検索などの便宜のために#ハヤブサの備考から関連種の分類部分を抜粋しておく。今ではネットで画像や世界分布を簡単に見ることができるので各種と比較してみていただきたい。
(通称チゴハヤブサ亜属 Hypotriorchis 候補)
オーストラリアチゴハヤブサ [高野 (1973) ではヒメチゴハヤブサ] Falco longipennis Australian Hobby
ミナミチゴハヤブサ Falco severus Oriental Hobby
エレオノラハヤブサ [高野 (1973) ではオオチゴハヤブサ] Falco eleonorae Eleonora's Falcon
ウスズミハヤブサ [高野 (1973) ではウスズミチゴハヤブサ] Falco concolor Sooty Falcon
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby
アフリカチゴハヤブサ Falco cuvierii African Hobby
なおこの "亜属" は属全体を複数亜属に分類する通常概念とは違って、類似していて遺伝系統が確認できているグループの意味で使われているので厳密な分類概念として使用するのはふさわしくないかも知れない。
名称の由来は hupo 少し triorkhes ノスリ、タカ (Gk)。これまで読んで来られた方には triorchis はまたかと思われるだろうが、原意の「3つの精巣」は失われていて単に (特にノスリに似た) タカの意味になっている。hupotriorkhes (Gk) がそもそもタカの一種の意味で、後にチゴハヤブサと同定されたとのこと (The Key to Scientific Names)。
越冬地までの渡り経路について日本語で記した記事は見つけられなかったが、伊藤 (2002) 茅ヶ崎市で保護されたチゴハヤブサの記録 によればチゴハヤブサの観察例は沿岸部で多く、北日本で繁殖した個体の秋の渡りのルートは、内陸ではなく沿岸に近いところなのであろうとある。
この状況はエレオノラハヤブサの特に東の個体群とよく似ている。
2023年の白樺峠のタカの渡り・2023年度速報 速報・白樺峠のタカの渡り を見るとチゴハヤブサは9月後半から10月かなり遅くまで渡るようであるが数はかなり少ない。
沖縄でも10月に (迷鳥ではなく) 記録されているのでハチクマとは違って秋はこのルートも通っているらしい。台湾は少数が渡りで記録される程度とのこと (Brazil 2009)。
宮崎 (1987)「鷲鷹ひとり旅」でも南西諸島をサシバのように南下してゆく観察結果や描像が記載されており、台湾やフィリピンに渡ると想像されていた。
フィリピンのチェックリスト (2023) では過去7回で迷鳥の扱い。メインルートではなさそうである。
京都府や滋賀県でも秋の渡りに少数記録されるが、春の渡りはどうなっているのだろう。
いずれももし沿岸部を通っているならば通常のタカの渡り観察地はあまり通っていないかも知れない。
韓国では Birds Korea's Bird News October 2009 のように10月に繁殖個体と渡り個体が見られるとのことで、ここでも沿岸部や島での記録がある。
渡りルートの考察とともにもう少し調べてみたい。
ヨーロッパのチゴハヤブサのアフリカへの渡り経路は衛星追跡で調べられている。
ヨーロッパの人にとっては他のチゴハヤブサ類と同じようにアフリカからやってくる夏鳥と認識されているだろう:
Strandber et al. (2008) Converging migration routes of Eurasian hobbies Falco subbuteo crossing the African equatorial rain forest、
Strandberg et al. (2009)
Daily travel schedules of adult Eurasian Hobbies Falco subbuteo - variability in flight hours and migration speed along the route、
Fiuczynski et al. Intercontinental migration of an Eurasian Hobby (Falco subbuteo) tracked by means of a 5g satellite transmitter
などがある。
Bildstein (2006) "Migrating raptors of the world: their ecology and conservation" ではヨーロッパのチゴハヤブサは渡りの際に super-flocking (100 羽以上の大きな群れを作る) 種類に分類されている。
日本のチゴハヤブサは単独や少数での渡りが基本で、同様の性状が示されていないのは、単に分布の東端で個体数が少ないためか、ヨーロッパのように個体が集まる経路が存在しないのか、それとも単にそのような地点が発見されていないだけなのだろうか。
チゴハヤブサの東北アジア個体群については越冬地がよくわからない。亜種 subbuteo 全体としての越冬地はアフリカから南アジア、中国南部と表現されている。
チゴハヤブサにはもう1亜種 streichi ミャンマー、中国南部、北インドシナの留鳥がある。
これらの関係はカッコウの繁殖地、越冬地、亜種の関係に似ているように見える。カッコウ同様に東北アジア個体群もアフリカで越冬している可能性はないだろうか。カッコウの場合には亜種 bakeri (長い渡りをしない) の分布と渡り習性がチゴハヤブサの亜種 streichi に似ている。
[亜種]
以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種記載もわかる範囲で含めた。
・Falco Subbuteo Linnaeus, 1758 o (原記載) 基産地 Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761 (Linnaeus がスウェーデンに限定)
・Falco subbuteo major Bechstein, 1793 * (参考) 基産地 in tiefen Tannenwaeldern (当時は亜種ではなく "大きな Falco subbuteo" の意味。subbuteo の意味づけも不明瞭で深い大森林ではどこかわからず学名と判断されなかったと想像される)
・Falco subbuteo streichi Hartert & Neumann, 1907 o (原記載) 基産地 Swatow, Kwangtung (中国南部)
・Falco subbuteo jugurtha Hartert & Neumann, 1907 (原記載) 基産地 Tangier, Morocco (モロッコ) = subbuteo
・Falco saturatus Buturlin * 基産地 Abyj, Indigirka (インディギルカ。ロシアのヤクーチア) preoccupied で無効 = jakutensis に改名 [Dement'ev and Gladkov (1951) の情報による] = subbuteo
・Falco subbuteo cyanescens Lonnberg, 1905 * (参考 1, 2) 基産地 Baimgol, Tianshan (天山山脈) = centralasiae = subbuteo
・Hypotriorchis subbuteo centralasiae Buturlin, 1911基産地 Baimgol, Tien Shan Range (天山山脈) = subbuteo
・Falco subbuteo jakutensis Buturlin, 1911 * Falco saturatus の新名 [Dement'ev and Gladkov (1951) の情報による] = subbuteo
・Falco subbuteo ussuriensis Domaniewski, 1917 * (参考 1, 2, 3)
基産地 Sidemi, Amuria (中国東北部・アムール地方) = subbuteo? [Falco peregrinus ussuriensis Buturlin, 1915 年以前の同じ亜種小名の用例 (参考) があるため無効となったと考えられる]
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
Dement'ev and Gladkov (1951) では亜種 jugurtha, jakutensis を有効としていた。基本的には色彩の違いから。
jakutensis は ? 付きでカムチャツカ南部、千島列島、サハリンも分布域に含めていて基本的に北方型の扱い。亜種 subbuteo を中緯度帯としていた。
現代のリストではいずれも 亜種 subbuteo にまとめられている。
ヨーロッパ地域に比べてユーラシア東部のチゴハヤブサの到来が遅い点もカッコウに似ている (ヨーロッパ地域のチゴハヤブサは3月にも現れることがあるとのこと)
(#カッコウの備考参照)。
南から東南アジアの越冬地に含まれると思われるインドやタイの情報を見ても亜種判別についてははっきりしない。インドの越冬地とされる地域でもそれほど豊富な種類ではないようである。
Greatwich (2019) Eurasian Hobby Falco subbuteo at South Lake, Perth, February 2016: The first Australian mainland record でオーストラリアの記録があるが亜種は記述されていない
[ちなみに記載の分布図は Orta et al. (2018) Eurasian Hobby (Falco subbuteo). In: "Handbook of the Birds of the World Alive" and eBird (2019) によるものだが何と日本は分布域に含まれていない]。
極東の個体の衛星追跡で渡り経路を明らかにしないとわからないかも知れない。安定同位体解析もある程度役立ちそうに思える。
もしユーラシア東側のグループもアフリカに渡っているならばアフリカの類縁種との系統の近さも理解しやすいし、もしそうでなければ最初に示唆したように東西で別種相当の可能性もあるかも知れない。
久野 (2004) Birder 18(10): 42 にチゴハヤブサが渡り途中に楽々とトンボなどを捕まえておやつにしている話が紹介されている。越冬にどこまで飛んで行っているのかはわからないが、これならばアカアシチョウゲンボウのように食事をしながらインド洋を横断しても大丈夫かも知れない。
ただしそのような証拠は知らない。セーシェルでは迷鳥なので Eurasian Hobby and Northern Wheatear at Alphonse (2017 年段階で過去 29 例の記録あり)、もしアフリカに渡っていてもアカアシチョウゲンボウのような定常的ルートではなさそうである。
なお Dement'ev and Gladkov (1951) では亜種 jakutensis を認め、シベリアからカムチャッカ? サハリン? 千島? で繁殖する北方型と考えている。他にアフリカの亜種 jugurtha を認めているが、この分布図にも日本の繁殖分布は示されていない。
同文献で subbuteo のシノニムとされた亜種は cyanescens (天山地域中央部)、centralasiae、
irkutensis、distinguendus、pianicola、ussuriensis
が載っていて地域的には最後のものが日本に近い。
ロシア沿海地方での繁殖: Shokhrin et al. (2020) Nesting birds of Primorsky Krai: falcons Falconidae (pp. 4479-4513)
(極東の鳥類42:沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める)。亜種は subbuteo としている。
[後頭部の目のように見える白斑]
#ハチクマ備考 [目を隠す模様は何のため?] にて紹介した。
「野の鳥の四季」(高野伸二 小学館 1974) p. 48 でチゴハヤブサの後頭部の目のように見える白斑が取り上げられていた。
コンサイス鳥名事典にも後頸には並んだ二つの白斑があると記述があるが、目のように見えるとまでは書かれていなかった。
例によって目の見えていない写真は写真図鑑に載らないので後側の模様がどうなっているのかほとんどわからない。これほど特徴があるならば後ろから見た時の識別点を述べた図鑑があってもよさそうなのに...。
世界的にも図鑑写真はかくあるべしのような固定観念がやはりあるのだろう。
「鳥630図鑑」(1988) に後ろ向きの絵が載っていた。それ以上のことは書かれていなかった。
その後の文献があって Negro (2004) Do Eurasian Hobbies (Falco subbuteo) Have "False Eyes" on the Nape。独立に気づかれたものか。標本を調べざるを得なかったのは後ろから撮った写真がほとんどなかったためだろう。
論文ではチゴハヤブサの羽衣については猛禽類の本やフィールドガイドで非常に詳しく取り扱われているにもかかわらず、この点を指摘したものは知る限りでないとのこと。
高野氏の本の絵を見ていた、あるいはさらには高野氏が別の書物を出典としていた可能性も完全に否定できないかも。
[世界最小の猛禽類]
系統的に近いわけではないが、ヒメハヤブサ (falconet) というグループがあり、世界最小の種類は
モモグロヒメハヤブサ Microhierax fringillarius 英名 Black-thighed Falconet で全長 14-16 cm とのこと。
We need to talk about tiny falconets (Bee Crew 2018) の記事を紹介しておく。葉をプレゼントする行為が求愛の儀式とのこと。
-
ワキスジハヤブサ (第8版で検討種)
- 学名:Falco cherrug (ファルコー ケルルグ) カルグハヤブサ
- 属名:falco (m) ハヤブサ
- 種小名:cherrug (合) charg (メスの Saker falcon の名称) ヒンディー語
- 英名:Saker Falcon
- 備考:
falco は#チゴハヤブサ参照。
cherrug の発音はわからないがアクセントは冒頭のはず (ケルルグ)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動 (文献に同定理由の記載なし)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。世界的には4亜種 (IOC) ある。
英語名からセーカーハヤブサ [高野 (1973) ではセイカーハヤブサ] とも呼ばれる。
英語名の由来はアラビア語 saqr (saqur) でベドウィンによるハヤブサを意味する名称とのこと [wikipedia 英語版、Macdonald (2006) "Falcon"]。
wikipedia ロシア語版によればイランの鷹匠は渡りのワキスジハヤブサを balaban と呼び、繁殖するものを sharg と呼んでいた。前者がロシア語名の baloban、後者が学名に使われる cherrug (ヒンディー語) に似ているとある。baloban の単語は 18 世紀まで知られていなかったとある。
別説もあってチュルク語で balaban が大きい、balban が力持ちまたは戦士の意味があるとのこと。
wikipedia ドイツ語版では Wuergfalke ("絞め殺すハヤブサ" の意味) の一般名で挙げられており、
同様にアラビア語の caqr (saqr) が Saker の語源としているが、caqr (saqr) はハイタカを指すとの注釈も出ている (ドイツでは鷹狩りもよく行われていて書籍情報も豊富なよう)。
"絞め殺すハヤブサ" の意味はなんと Falco Lanarius Linnaeus, 1758 (参考) に遡るとのこと (ラテン語動詞 laniare に由来)。ドイツ語ではモズの Lanius = Wuerger と呼ばれるので "絞め殺す" となったとのこと。
Linnaeus (1758) の記載している種が明らかでなく後の記載に先取権を譲ったよう。
本家のモズ類はもう少し後に出てくる (参考)。
なおこの名前はおかしいとの批判もある。ワキスジハヤブサも他のハヤブサ類同様嘴で獲物を殺し、掴んで殺すわけではない、特に攻撃的な種類ではない、とのこと。Sakerfalke の名称も普通に用いられている。
古くは Blaufuss (青い足) の名称が一般的だったが、これはハヤブサ若鳥の足が黄色なのに対する名称とのこと。
ドイツ語では嘴で殺す種類を Bistoeter、足で掴んで殺す種類を Grifftoeter と呼び分けているとのこと。
系統樹の説明もあり、もし Hierofalco を属扱いにするならば Falco 属が4系統に分割される概念図が出ている。
フランス語では Faucon sacre で sacr\'e (ここだけ TeX 表記) ではない。"聖なるハヤブサ" ではなくアラビア語でこの種のメスを指す語由来であると説明がある (wikipedia フランス語版)。
Zhan et al. (2013) Peregrine and saker falcon genome sequences provide insights into evolution of a predatory lifestyle によれば、ハヤブサで 99% 以上、ワキスジハヤブサで 97% 以上の常染色体ゲノムを解読した。
砂漠地帯で生活するワキスジハヤブサではホメオスタシス (恒常性維持) に関係する遺伝子が特徴的で、ナトリウム吸収を抑制する遺伝子を3コピーも持っている。trpv1 という熱調節遺伝子が働く遺伝子になっているなどの特徴がある。この遺伝子は (例えばヒトでは) 発汗に関係するもので、鳥でも体温調節は同じ遺伝子が関係しているらしい。
関連した情報で Selescu et al. (2024) TRPM8-dependent shaking in mammals and birds (prepeint) によれば、TRPM8 は哺乳類でも鳥類でも水をかけると体を捻って振って払う行動 (wet dog shake) に関係していることがわかった。
先述の trpv1 とともにいずれも TRP (Transient receptor potential) channel (一過性受容体電位型チャネル。特に、温度受容体としての機能が知られるほか、さまざまな化学的・物理的刺激を感受するセンサーとして多様な生体機能に関与している: wikipedia 日本語版より) のサブファミリーに属する。
進化を考えると共通祖先段階では脊柱を捻る能力はなく、そもそも水を払う必要はなかっただろう。冷たさに反応している直接の証拠はまだ知られていないが、冷たさと濡れた状態が組み合わさることで冷感センサーに関係のある TRPM8 に対する類似の反応を (恒温性の獲得とともに) 収斂進化させたのではとのこと。
哺乳類と鳥類が同じような行動を示すと当たり前のように解釈してしまいがちだが、必ずしもいつも自明なわけではなさそう。この論文ではニワトリにシャワーをかける実験を行っている。
なお遺伝子の表記が大文字だったり小文字だったりするのは、対象とする種によって規則が違うためだそうで (ヒトとマウス/ラットでさえ規則が違う)、遺伝子はイタリック表記だがそうでなくてもよい場合もあるとのこと。タンパク質はイタリック表記をしないが大文字/小文字の規則がある。ここでは細かいことは問わないので論文の表記を (イタリックがある場合は外して) 使っている。
Joseph et al. (2018) Chromosome Level Genome Assembly and Comparative Genomics between Three Falcon Species Reveals an Unusual Pattern of Genome Organisation によればシロハヤブサとワキスジハヤブサの間では明らかな染色体再構成 (chromosome rearrangement) がなく、本当に別種なのかとの疑問も出てくる。ミトコンドリア DNA のハプロタイプは両種でほとんど差がないとの研究もある。
シロハヤブサと同種? については #シロハヤブサ の備考も参照。
西カザフスタンでワキスジハヤブサ対オオノスリのビデオ。どちらも大きい。
ノガンを狩るワキスジハヤブサ。
ロシア沿海地方での繁殖: Shokhrin et al. (2020) Nesting birds of Primorsky Krai: falcons Falconidae (pp. 4479-4513)
(極東の鳥類42:沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める)。
亜種は progressus としている。
[ワキスジハヤブサによるペルシャのワシの狩り]
ワキスジハヤブサによるペルシャのワシの狩りの記述がある:
原著 Husam al-Dawlah Timur Mirza (1868; 1285 の数字を挙げているページがあるがこちらはイスラム暦)、Phillott (英訳 1908) The Baz Nama Yi Nasiri: A Persian treatise on Falconry. London: Bernard Quaritch (p. 110 から、特に pp. 113-114)
この本については A Persian treatise on Falconry に雑誌 Nature の紹介 (1909) がある。地域方言の技術用語なども多くペルシャ語が理解できてかつこのような分野を訳せる人はほとんどなかった模様。
現在でも意義ある内容が含まれていると思われるので、関心のある方は中身を見ていただければよいと思う。
風切羽が根元から傷つくと生えてこないので抜いてはいけない。尾は抜いても生えるが欠陥が残る。大きな獲物で風切羽が抜けてしまった場合はその場所に再植する (ヒトで事故で歯が抜けた場合の措置と同様のよう) (p. 176-177)。
寒風の中で鷹狩りをして食物がなくそのままでは死にそうな場合に鷹匠が自身の血を与える。瀉血の具体的方法 (p. 184)、ガゼルのように血の大量に出る獲物ではハヤブサ型の円形の鼻孔が詰まってしまう (p. 189) ための対策など。
ハヤブサとタカの鼻孔が違うのはなぜかと問われることがあるが、このような性状も案外関係しているのかも。
ワシを捕まえるワキスジハヤブサ (charkh。ワキスジハヤブサのうち巣から捕獲したものを指す用語) は、まず若いワシに似た色のエジプトハゲワシの若鳥を用いた訓練をするという。
エジプトハゲワシが手に入らない場合は "black buzzard" それが手に入らない場合は "yellow buzzard" を用いるが、これらを使う場合は後趾をふしょに縛っておく。この "練習用" の鳥に朝2回、夕方2回飛ばしてその上で食物を与える。
"練習用" の鳥の2羽めが入手できるならば、3日めには1羽めを殺して背中に肉を結んで食べさせる。背中でのみ食べることを学習するため獲物の頭部は見せないようにする。そして獲物の背中を切って背中の肉のみ見せて少し味見をする程度に食べさせる。
"練習用" の鳥の背中につけた肉を次第に減らして次第に遠くから飛ばし、肉がなくても獲物の背中に向かうようになる。これらの鳥の風切2枚は大きいのでこれらの羽を肉に付けて目立つようにする。
"練習用" の鳥での訓練を終えると野生のエジプトハゲワシの若鳥を獲る訓練をする。注釈によればエジプトハゲワシは臭気以外に防御手段がないとある。報酬には他の鳥の肉を与える。
次は bug khura でワシの中で最も ignoble (高貴でない) であるという。注釈によれば p. 31 にこの名称のワシは常に沼地か河川敷に多くいてカエル、死んだ魚、弱ったカモなどを食べるとある。
spotted eagle (現在の Clanga 属) を主に指しているのではと想像できる (pp. 31-32 に原書名で "Frog-eagle" や "Frog-eater" に対応する名前で出てくる)。
近づいてワシが地上から立ち上がったところで飛ばすとワシの背を攻撃する。駆け寄ってこのワシを確保し、黒いニワトリを殺して bug khura の翼の下から肉を少し与える。
bug khura をワキスジハヤブサの爪から離して (注釈によるとニワトリの肉を代わりに与えている間、あるいはフードを付けた後) 生け捕りにするという。
このワシの脚を束ねて飛ばせワキスジハヤブサに捕えさせる。さらに野生のこのワシで 4-5 回の訓練を行い、次に斑点のない "black eagle" に向けて飛ばす (p. 31 によれば模様のない黒いワシで強くないとのこと。この解釈の通りカザノワシでよいだろうか)。そして斑点のある a,ina-li (p. 31 の解釈ではカタシロワシらしいとのこと) を狙わせる。ここまで到達すればどんな種類にも飛ばすことができるとのこと。
もっと大型の (後述のように) ワシでも追っ手の大声の叫び声でワシの判断力を失わせ、防御能力を失わせることで狙おうと思えばできることもある。最大の3種類が挙げられていて、karlak (大きさは "moon-tailed eagle" に匹敵する。嘴と爪は黒く非常に強力で全体に褐色で模様がない p. 31。イヌワシ成鳥のことか?)、
kujikan/kuchigan (p. 31 の注釈ではオジロワシかとのこと)、uqub-i muh-dum "moon-tailed eagle" (p. 30 尾は白くて先端が黒い。渡りはせずキジ類、ノウサギ、"barra" 子羊または子鹿 を捕食するとのこと。イヌワシ若鳥のことか? アラブで月と言えば満月より三日月型を指しそうなので、尾の模様を月に見立てることは考えやすい)
(p. 30 Phillott によれば原著のワシ類の記述は曖昧で種類を同定できないものも多いとあるが、解釈を少し追加してみた。Phillott 自身による解釈は後述)。
地上のワシはワキスジハヤブサが自分を襲うとは想像せず気楽に構えているとのこと。
メスのワシは強力なので襲われてもそのまま乗せて遠くまで運んでしまうが、オスのワシは半分ぐらいの距離しか飛べないとのこと。疲れて地上に降りるまで馬で急いで駆け寄る必要がある。常に大声で叫びながら追いかけること。地上ではワシは羽ばたきながら追われて疲れたニワトリのように翼をひきずりながら走るとのこと。
ワシがニワトリのように走り出すと一名が降りて行く手を阻み、ワシ ["son of a dog" と形容。直訳で "犬の息子"。注釈にしばしば abuse の対象の意味で使われるとあり、日本語の「かませ犬」のような表現かも知れない。あるいは鳴き声が犬のように聞こえるためかも知れない]
は飛べないことや叫び声に囲まれていることを知って、ワキスジハヤブサがワシの背中を押さえていることも忘れて怒りと狼狽から爪を地面に向けてしまうとのこと。
ここまで行けば "犬の息子" を他の獲物と同じように処理せよとある。
ただし鷹匠自身が早まって飛びかかってやられないように注意せよとのこと。
ワシが痙攣したように地面をつかみ始めるとすぐに馬から飛び降り、後ろからブーツで肩の間を踏んで無抵抗とし、後ろからワシの足を上手につかみ、のどを切ってとどめを刺すとのこと。
ワシの心臓を取り出してワキスジハヤブサに与え、ワシの肉はハトとは違って脂ぎって消化できず与えすぎると具合が悪くなるので注意とある。
ワキスジハヤブサがワシを狙うことはできるものの、人が叫び声などを上げて追いかけてワシを怖がらせる効果による。人工的条件で成立するもので、オオタカをキジ類に飛ばすようなやり方だとワシが逆に捕まえてしまうだろうとのこと。
(神が人間に与えた能力による。この本で類似の記述が非常に多い) 鷹匠の技術のおかげでより弱いワキスジハヤブサがより強力なワシを仕留めることができるとの説明になっている。
歴史的文献として紹介し、現代の視点ではふさわしく感じない表現もあるがそのまま残した。アラブの鷹匠にとってワキスジハヤブサがおそらく最上のもので、どこまで能力があるか技術的な挑戦の意味もあったのだろう。
また当時はワシ類は獲物を横取りするなどどちらかと言えば迫害される対象だったかも知れない。
ワシを尊重する表現も同時に見られるので単なる迫害の対象ではなかったと想像できる。
もっとも 20 世紀前半まで、時にはそれ以降もワシ類は広く迫害されており、現代の我々の考え方も猛禽類の有用性が理解され始めた以降の認識に基づく、歴史的にはごく新しいものと言えるかも知れない。
ひなから育てたワキスジハヤブサで、目の黒い一部のものしかワシの狩りはできないとのこと。
p. 28 には非常に良質のワキスジハヤブサで "ワシ" (qara-qush = 黒い猛禽類の意味で、特にイヌワシを指すを言葉として使われた単語が使われているとのこと) を獲ったことがあると述べている。
"moon-tailed eagle" は p. 30 の注釈によればキガシラウミワシ Haliaeetus leucoryphus Pallas's Fish Eagle のことかとある。確かに成鳥は尾の内側が白くて外が黒いがそこまで強力ではないかも。また部分的に渡りをする。
原著翻訳ではワシ類のうちで "moon-tailed eagle" のみは渡りの必要がないとあり、雪の積もる中でも見たことがあるとのこと。平野にはめったに降りてこないとある。最も強力なワシとされる。
原著翻訳はキガシラウミワシのように水辺に生息すると書いていないので訳者の Phillott も解釈に自信がない模様。やはりイヌワシ若鳥のことでは? 月の形の模様の方が全身褐色の鳥より文化的により尊重されたかも。
この方法で他の猛禽類を生け捕りして飼育したり鷹狩りに用いるなどの記載もある (ハヤブサ類は脚力がそれほどでないのであまり傷つけることなく生け捕りにすることが可能なのだろう)。
p. 29 にこの方法でミサゴを生け捕りしてしばらく飼育したとある。
p. 33 に同様に dubarar (hawk eagle?, ヒメクマタカかも?) を捕獲して鷹狩りに用いることに成功したなど書かれている。
p. 34 にハヤブサでチュウヒ類を捕獲した記載がある。チュウヒ類は飛翔力も弱く鷹狩りに用いるには訓練が難しくて割に合わないとのこと (p. 26)。
ワキスジハヤブサによるガゼルの狩りの項目もある。p. 47 にはハヤブサもガゼルを狩ることができるが角で傷つくことも多くあまり向かないとあり、ワキスジハヤブサが最も優秀とされていた。
p. 47 脚注では英国でハヤブサでガゼルの狩りに挑んだ者が1人のみいるとされているが、実際はワキスジハヤブサを用いたとのこと。この訳本は英国で書かれているので英国以外、例えばヨーロッパ他国のことは念頭になかった可能性がある。
#オオタカ備考の [オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑] に Linnaeus (1758) の Falco gentilis にガゼルを獲物にできるとあるのはやはりオオタカではなくハヤブサを意図したものに思える。
鷹狩りによるガゼルの狩りについては 高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) p. 170 に中央アジアではチュウヒワシを用いるとあるが習性から考えにくい気がするので何かの誤りか。アラビアでのセーカーハヤブサによるガゼルの狩りにも多少の具体的言及がある。
同書 p. 121 には「この種は、大きな鳥を殺すことができ、カタジロワシを殺したのが観察されている」との記述がある。
-
シロハヤブサ
- 学名:Falco rusticolus (ファルコー ルースティコルス) 田舎に住むハヤブサ
- 属名:falco (m) ハヤブサ
- 種小名:rusticolus (adj) 田舎に住む (rusticus (adj) 田舎の colo (tr) に住む)
- 英名:Gyrfalcon
- 備考:
falco は#チゴハヤブサ参照。
rusticus は冒頭が長母音。-colus は短音のみなので "ルースティコルス" の読み方でよいと思われる。
単形種。
英名の語源はフランス語 gerfaucon、中世ラテン語の gyrofalco。gyr- はハヤブサと比べた時の大きさからハゲワシ (ドイツ語で Geier) に由来するか、ラテン語 gyrus 円 で旋回する様子に由来する説がある (wikipedia 英語版)。
OED では語源は1つに特定していないが高地ドイツ語で gir がハゲワシ、中世ラテン語 gyrofalco で上記説明と同じ。イタリア語の ger- はしばしばラテン語の hier- を意味するとのこと。フランス語 gerfaucon はラテン語 *hierofalco 由来の解釈もあるとのこと、
「鷹狩りの書」(フリードリッヒ二世著 吉越英之訳 文一総合出版 2016) p. 168 によればラテン名は iero (神聖な Gk) または gyri (王者の Gk) を語源としている。
亜属または上種 Hierofalco (ヒエロ王またはタカのようなハヤブサ、もとシロハヤブサなどの属名に使われていた) に分類され、他のメンバーはワキスジハヤブサ、ラナーハヤブサ Falco biarmicus 英名 Lanner Falcon、ラガーハヤブサ Falco jugger 英名 Laggar Falcon で遺伝的にも近く雑種形成も多いグループ。
特にシロハヤブサとワキスジハヤブサはかつて同種とされたように関連が深く、相互に遺伝子浸透があるとされている (#ワキスジハヤブサの備考も参照)。
和名の "シロハヤブサ" に相当する学名があるのでは、と想像したらやはりあった。Falco albus Gmelin, 1788 (資料)。アイスランドのシロハヤブサと考えられる (Falco islandicus Gmelin, 1788 の学名もあった)。
Falco rusticolus Linnaeus, 1758 は最初からあった学名だが、白いものは別種と考えられていてもおそらく不思議でない。この学名は White Falcon に由来するかも知れないが、いずれにしても有名な英名でアイスランドの国鳥の英名はかつてはこちらが使われていた。
Iceland's National Bird: The Gyrfalcon
によると特に投票が行われたわけではないが、アイスランドの人にとってはアイスランドの独立運動にも関係して自然に受け入れられていたとのこと
[Icelandic Coat of Arms それまでの cod タラ に代わる独立運動のシンボルとなった。(アイスランド語。自国ではアイスランドハヤブサと呼ばれるよう)]。
現在アイスランド語で種シロハヤブサの名称は単に Falki で、アイスランドではハヤブサと言えばこの種なので問題ないのだろう。アイスランド語ではハヤブサは Forufalki で foru の部分は古ノルド語で旅などを意味するとのことで他言語名称と同様。
アイスランドの国鳥の名前は古い図鑑にも載っており、国鳥の名前を和名表記する必要性などから訳されて早い段階でシロハヤブサになった可能性もあるだろうか。国際的には国鳥を決める決議は 1960 年の ICBP 大会でなされ、1962 年に一部の国の国鳥が発表された。アイスランドのシロハヤブサも含まれていた。
なお#オオタカ備考の [オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑] Gesneri (1555) に Linnaeus 以前の学名として Falco albus (意味は白いハヤブサ) が登場する。現在のシロハヤブサを指すものかどうかは不明。
"Falco albus" がシロハヤブサと同種であるならば Linnaeus (1758) の学名に先取権があるのは現在では自明 [ただし以下の Dement'ev (1951) の見解もあり Linnaeus (1758) の同定に疑問もあった] としても、
Falco albus の学名には別の問題があって、同じ学名の別解釈がある Falco albus Gmelin, 1788 (資料)。
さらに 資料。
要するに学名はあって "White Falcon" (または "White Eagle") の名称はあったものの何を指しているのか後世になって判断できなかったものと思われる。
2番めのものが#イヌワシ備考の [White Eagle とは何者か?] に対応するもので、このラテン名の記述自身は学名の記載以前に古くから残っている。
このため Falco albus の学名は使われたものの同定不明として亜種名に残らなかったものと想像できる。有効な名前にならなかったのでシノニムとしても残っていないが、もしかすると英名に名前を残したの (あるいはその逆) かも。
Falco islandicus の方は残ってもよさそうだったが、Falco islandus Bruennich, 1764 の用例がさらに早くあって残らなかった。1年違いなので先取権争いは熾烈であった。亜種 islandus が認められていた時期もあったが、現在は亜種を認めない単形種となっている。
シロハヤブサに亜種を認める立場もあり、HBW では主に色の現れる頻度から地理的分布に合わせて rusticolus, obsoletus (北米極北でほとんど黒いとのこと), islandus, candicans
と分けることがあることが紹介されている。
Dement'ev (1951) "Sokola - Krechety" では学名を Falco gyrfalco Linnnaeus, 1758 としており、Falco rusticolus
は多くの著者が不適切に使っている (auctorum plurimorum) シノニムとしている (シロハヤブサと同定された根拠が不明瞭とのこと)。
亜種 gyrfalco (ラプランドのシロハヤブサ)、
intermedius (シベリアのシロハヤブサ、樹上の巣の写真あり)、
grebnitzkii (東シベリアまたはカムチャツカのシロハヤブサ、樹上の巣の写真あり。日本のもこの亜種としている)、
altaicus (アルタイのシロハヤブサ)
をソ連時代の亜種として認めており、HBW の亜種分類とは相当違っている。各亜種の詳しい計測値や生態その他の情報も記載されている。Dement'ev and Gladkov (1951) でも同じ分類を用いている。
Johnson et al. (2012) Genetics of Plumage Color in the Gyrfalcon (Falco rusticolus): Analysis of the Melanocortin-1 Receptor Gene
によれば MC1R 遺伝子 (メラニン生成やメラノサイトへの蓄積に関わる) がシロハヤブサの色彩に関連していることを述べている。調べられているのは北米の北極圏とアイスランド。
色彩による孵化時期の違いなどが知られているが、色彩によるつがい形成の好みはグリーンランドの個体群で観察されなかった。
[シロハヤブサとワキスジハヤブサの関係、"Altai falcon" とは何か]
"Altai falcon" と呼ばれる中央アジアのハヤブサがあり、鷹匠の間で評判が高い。モンゴルで turul として知られる [Macdonald (2006) "Falcon"]。
シロハヤブサとワキスジハヤブサの雑種であるかについてはまだ確実な証拠はなく、暫定的にワキスジハヤブサの亜種 altaicus? ともされるが通常のチェックリストには記載されない。亜種 milvipes のシノニムともされる。
Al-Ajli et al. (2023) Genomic, genetic and phylogenetic evidence for a new falcon species using chromosome-level genome assembly of the gyrfalcon and population genomics
の分子系統研究では "Altai falcon" は約 42 万年前にシロハヤブサとワキスジハヤブサの共通祖先から分かれた、特に W 染色体に違いがあるとの結果を示して独立種 Falco altaicus とするのが適当との結果を出しているがまだ査読されたものにはなっていないようである。
この研究よりは前であるが、Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではかっこ付きだが種扱いにしている。雑種の可能性も述べている。
Hu et al. (2022) Arctic introgression and chromatin regulation facilitated rapid Qinghai-Tibet Plateau colonization by an avian predator
によれば氷河期のレフージアでシロハヤブサとの交配が起きてワキスジハヤブサの東部個体群のチベット高原への高地・低温環境に適応する性質を得たとの解釈。この研究ではワキスジハヤブサよりシロハヤブサの方が古い系統になっている。
低温環境の適応のため血中コレステロール値が高いとのこと。対応する遺伝子変異がある。非コード領域の変異でヘモグロビン濃度が高く高地適応をしていると推定。メラニン発色遺伝子を通じて紫外線量増加に適応している。
Zinevich et al. (2023) Phylogenomic insights into the polyphyletic nature of Altai falcons within eastern sakers (Falco cherrug) and the origins of gyrfalcons (Falco rusticolus)
の論文があり、Al-Ajli et al. (2023) も preprint として触れられているが他の遺伝子解析の結果は Zinevich et al. (2023) のものと類似しており、飼育個体由来のワキスジハヤブサの地理的起源も不明なので結論は導けないと批判的に評価している (東西の遺伝的違いを明らかにした後なのでこの指摘は批判的に行いやすい)。
ワキスジハヤブサの東部個体群の由来については Hu et al. (2022) の考え方とは少し異なるものになり、ワキスジハヤブサの東部個体群が高地・低温環境に適応していてシロハヤブサがそこから北極圏に定着可能であったことになる。
Zinevich et al. (2023) はワキスジハヤブサの東部グループ ("Altai falcon" を含む) は単系統でなくさまざまな出所由来と考え "Altai falcon" は種に値しないとの考えを示している。
"Altai falcon" の色彩は地域的な突然変異的なものや他の遺伝的メカニズムで高所への適応の結果固定したなどの要因も考えられるとしている。
もっとも Al-Ajli et al. (2023) は染色体レベルのゲノムアセンブリを得ており、Zinevich et al. (2023) はそこまで行っていないので W 染色体に関係した部分はあまり踏み込んだ批判になっていない。
なおワキスジハヤブサの東部グループと西部グループの間の現代の遺伝的交流の直接的証拠は得られていない (5000 個体の標識、200 個体の衛星追跡による)。
遺伝的な浸透よりは、祖先段階での系統分離が不完全 (incomplete lineage sorting) な可能性を考えているが区別は難しい。
この研究ではシロハヤブサが遺伝的にはワキスジハヤブサの東系統中に含まれてしまう。シロハヤブサをワキスジハヤブサの亜種とするなど
(F. cherrug rusticolus と書いているが記載年を考えると F. rusticolus cherrug となりそうに思える。シロハヤブサに統合されて亜種が5種となる?)
の可能性も考えられるが、生態的には種レベルの違いがあるなど厳密な遺伝系統のみにとらわれない種の扱いも議論の対象と考えられるとのこと。
解析方法で若干の違いがあり、外群の加え方次第でシロハヤブサを種として保持し、ワキスジハヤブサの東系統と西系統を別種とする考えも可能と思える系統樹になっているものもある (現在の遺伝的交流の証拠がないようなので保全単位なども考えると調べられた範囲で全体で3種にしてもよいような気もするが...。ワキスジハヤブサはもしかしたら2種相当かも知れないことを頭の片隅に置いてみておいて欲しい)。
もちろんサンプルが不完全であることも述べられている。東系統と西系統の代表的な地域を選んで調べたものなので、地理的に間に位置する個体が中間的な性質を持っているのか、それともどこかで区分があるのかなどわからない。ワキスジハヤブサで記載された他の亜種についてもわからない。種や亜種の見直しはお茶を濁したような書き方になっているのだろう。
現在の世界のリストで同種としているものはない。
亜属 Hierofalco はアフリカ起源と考えられるので次第に東方へ分布を広げつつ氷河期のレフージアにワキスジハヤブサの西グループが生じ、さらに東に分布を広げてユーラシア中央部に進出。
氷河の後退に伴ってタイガが広がり、ワキスジハヤブサの東グループの中に北に分布を広げたシロハヤブサのグループがあった進化史が考えられる。いずれも歴史的には新しい時代の出来事であり種分化も不完全なのだろう。シロハヤブサは広い意味でアフリカ起源の種類と言えるかも知れない。
様々な地域でワキスジハヤブサの個体数の減少があったが、保全活動が功を奏してきている。
遺伝的にはそれぞれの地域を独立した個体群とみなした方がよく、起源のわからない個体の安易な再導入は避けるべきなどの提言がある。幸いにして近親交配の程度を表す指数は低いとのこと。
Wilcox et al. (2022) Linked-Read Sequencing of Eight Falcons Reveals a Unique Genomic Architecture in Flux
に高精度ゲノム解析によるハヤブサ類を含むグループのさらなる検討がある。亜属 Hierofalco とハヤブサには明らかな違いがあってそれぞれのクレードをなす。
この2クレードの分岐年代は約 588 万年前。ラナーハヤブサとワキスジハヤブサの分岐は約 304 万年前。ワキスジハヤブサとシロハヤブサの分岐、ハヤブサの亜種 (ここで調べられた個体は peregrinus, pelegrinoides, peregrinator) 間の分岐は約 150 万年前より新しいと推定された。
この結果からはワキスジハヤブサの方が早く、シロハヤブサが極北に定着したシナリオを裏付ける。
ハヤブサ目で nuclear mitochondrial DNA segments (NUMTs) が特に多く、約 5600 万年前にハヤブサ類の系統が生じてからカラカラ亜科とワライハヤブサ/モリハヤブサ亜科が分岐まで間に挿入されたものが多いが、ワライハヤブサ/モリハヤブサ亜科のカラカラ亜科の分岐後にもかなりの挿入があった。
チョウゲンボウでは独自のものが多いとのこと。
過去の実効個体数の推定ではシロハヤブサのみが分岐後を減らしてきており、氷河の後退と新石器時代の人為活動の始まりに対応しているものと思われる。他は近年の一時的減少を除いて数が増えており、現在もユーラシアのハヤブサの数は増えているが理由は不明とのこと。
染色体レベルの高精度ゲノム研究
Al-Ajli et al. (2025) Chromosome-level reference genome assembly of the gyrfalcon (Falco rusticolus) and population genomics offer insights into the falcon population in Mongolia
これらの種の扱いは生物学者に異なり、別種とするもの、"Altai falcons" はアルタイ地域で自然の交雑の結果生まれたもの、鷹狩り用の鳥が逃げたものなどの説があった。
W 染色体に関連した遺伝子が生殖隔離を通じてハヤブサを独立種にした可能性がある (卵巣に関連する SPINW 遺伝子がハヤブサで停止コドンになっているなど)。モンゴルはラナーハヤブサも含めたハヤブサ類の交雑のホットスポットと考えられる。常染色体では十分交雑が起きているが W 染色体には違いがあるとのこと。
シロハヤブサとワキスジハヤブサを別種とみなして保全単位とするならば Altai W-haplotype は独立種に値する可能性がある (W 染色体の遺伝子が生殖隔離機構に関与している可能性を考えている)。
保全単位とみなすことは中央アジアからのワキスジハヤブサの人為的導入を防ぐなど明らかに有益である。
高精度ゲノムが明らかにするそれぞれの系統や交雑個体の実効個体数の変化など。意外にもハヤブサが数を増したのは比較的最近の現象 (200 万年前ぐらいに実効個体数最小で、主な増加は数十万年前ぐらいから起きた) のよう。
逆性的サイズ二型に関係する遺伝子候補が挙げられていて NTRK2 (ヒトやマウスで体重に関係する) が シロハヤブサではメスが持つ W 染色体に2コピーある。
[シロハヤブサのグリーンランドへの定着]
Burnham et al. (2011) Gyrfalcon Falco rusticolus post-glacial colonization and extreme long-term use of nest sites in Greenland
によれば氷河期が終わってまもなくグリーンランドに定着したと思われ、年代測定で 2740-2360 年前から受け継がれている営巣地があるとのこと。このように長期間使われた猛禽類の営巣地は他に例がないとのこと。
[シロハヤブサのモノグラフ、生態など]
本稿のさまざまなところに現れるロシアの Dement'ev が前述のシロハヤブサのモノグラフを書いている。Shergalin (2011)
Brief Review of Russian-language Literature on the Gyrfalcon (Falco rusticolus) の紹介記事を読むことができる。
本種に興味のある方ならば重宝されるであろう文献。原著は 1951 年 Sokola - Krechety で、ドイツ語と英語に訳されているとのこと (原著はネットで読める)。Eugene and Sale (2005) "The Gyrfalcon" の英文の後継モノグラフが出ており、こちらは現在でも入手可能。
研究されているものは繁殖生態が主で、繁殖後の分散や越冬地での研究は不十分である。
グリーンランドでの生態研究、
アラスカでの衛星追跡 などの論文はある。
カムチャツカから中東に密輸のシロハヤブサが摘発されるなどしばしばニュースに現れる。
岩田 (1995) Birder 9(1): 30-33 に 1992 年末に多数の飛来があった (irruption であろう)。捕食習性などの記載や、つがいを思わせる2羽が見られたこと、渡りの時にハヤブサより群れる傾向があることなどが議論されている。
岩田 (1993) 北海道砂崎岬におけるシロハヤブサの越冬生態 の論文があり、ここではつがいと記述されている。
Lobkov et al. (2011) Status of the Kamchatka Gyrfalcon Falco rusticolus population and factors affecting it
のカムチャツカのシロハヤブサの現状が紹介されている。
ヌマライチョウ (旧名カラフトライチョウ) Lagopus lagopus 英名 Willow Ptarmigan のピークが約 10 年おきに起きるとのこと。問題の 1992 年は観察地域での 16 の巣は空でヘリコプターを使った密猟があったとの住民証言がある。1980 年代から密猟が深刻な問題になっている。
Ryabitsev (2014) によればメスの方が大きく通常オスより暗色であるとのこと。ほとんど白色の淡色型があるがまれである。分布域の東端ほど白い個体の比率が大きくなる。
日本の図鑑では極地近くに生息する分布になっているが、この図鑑ではワキスジハヤブサの分布域でも越冬する分布図となっている。この図鑑はシロハヤブサに5亜種を認める立場で、シベリアの亜種は intermedius としている。
[シロハヤブサの急降下速度]
Tucker et al. (1998) Diving speeds and angles of a gyrfalcon (Falco rusticolus)
がシロハヤブサの急降下速度を測定している。体重 1020 g とのこと。最大 500 m 上空から角度 17-62° で急降下し、速度の上限は 52-58 m/s (187-209 km/h) に達したとのこと。この加速は理論値に近い。定速度の時間は短時間 (数秒以内) しか続かない。減速の加速度は 0.95 G (ここでは G を重力加速度とした) であったとのこと。
より高くから急降下した場合は理論的には 70 m/s (250 km/h) に達し得るとのこと。
Gowree et al. (2018) Vortices enable the complex aerobatics of peregrine falcons (#アホウドリの備考 [海鳥の翼先端にはなぜスロットがない?] で紹介)
に引用されている値ではハヤブサで 51 m/s の数字があるとのこと: Peter and Kestenholz (1998) Sturzfluege von Wanderfalke Falco peregrinus und Wuestenfalke, Der Ornithol. Beob. 95, 107-112。
Tucker (1998) Gliding Flight: Speed and Acceleration of Ideal Falcons During Diving and Pull Out
が理論的推定を行っており、完全に理想的形状のハヤブサ類 (体重 1 kg) で 1200 m を降下すれば終端速度は 89-112 m/s (316-403 km/h)。体重が大きいほど終端速度は大きくなる (雨粒と同様の現象)。
高速飛行で抵抗値が小さくなるとすれば 138-174 m/s (497-626 km/h) まで達することもあり得るとのことだがそこまでの加速には 2900 m を要し、その距離では目標が見えないだろうからそもそも現実的ではなさそう。
減速は体重の 25% が筋肉として肩関節が耐えられるトルクの限界を考えると 1.5 G までだろうとのこと。
いずれも実測値と 1.5 倍程度の範囲で納得できる値に見える。大きな減速に耐えられるかのような表現がしばしばなされるが、そもそも生体力学的にはあり得ない話のよう。1 G が現実的な数字のよう。
27 G の値が紹介されていて、「羽: 進化が生みだした自然の奇跡」(ソーア・ハンソン著 黒沢令子訳 白揚社 2013) p. 161 にある。英文記事では例えば Falling with the Falcon (Harpole 2005)。
John Szabo が数学的にモデル化したものとある。この研究者で調べても関連研究が見当たらないので出版されていないものと思われる。数字的には "神話" の印象を受ける。ソーア・ハンソンも疑問を持たなかったのだろうか。なお上記 Harpole (2005) に野生のハヤブサを指して haggard が使われている。
意味や語義の変遷は #ハヤブサ の備考参照。
ハヤブサよりシロハヤブサの方が体重が大きいのでこれらの測定値や推定値は上限のよい目安になるだろう。
ハヤブサについてレーダーによる測定値 Alerstam (1987) Radar observations of the stoop of the Peregrine Falcon Falco peregrinus and the Goshawk Accipiter gentilis
があり、31-39 m/s、オオタカで 30 m/s 程度であったとのこと。古くから言われている数字はかなり神話気味らしい。他の測定値でハヤブサ 51 m/s がある (Peter and Kestenholz 1998)、上記シロハヤブサの測定値が上回っているのでそれほど特別な数字ではない。
速度の上限値については Baumgart Im "Distanz-Verfolgungsflug" sind 400-500 km/h fuer viele Wanderfalken Falco peregrinus Normalitaet
(英文要約は最後に)。研究者が通常用いる 160 km/h は遅すぎて、実際にはもっと速い速度が出せるとの主張。高速で数 km 飛ぶ時には観察者にはほとんど見えておらず、低速で獲物を捉える時を観察しているとの解釈。他にも実験で使われた個体の亜種の問題や雑種が使われたりしている点も問題としている。
スカイダイビングの測定値 (320 km/h) は出ているが、野生での狩りとは条件が違うのでそれだけの速度を実際に使う必要があるかどうかは疑問があるかも知れない。
Franklin (2000) "Greifvoegel und Falknerei" (1999) の本に紹介されているそうだが中身までは不明。
Schmitz et al. (2018) The peregrine falcon's rapid dive: on the adaptedness of the arm skeleton and shoulder girdle
(オープンアクセス版) は急降下をしない鳥に比べて肩の骨密度が高いことを示している。80 m/s の数字が出ているがこれは実測値ではなく、翼に働く力を考えるとここまで行けるのではないかとの推定。
Schmitz et al. (2015) Morphological properties of the last primaries, the tail feathers, and the alulae of Accipiter nisus, Columba livia, Falco peregrinus, and Falco tinnunculus
ではハヤブサの風切羽は羽軸断面積も大きく曲げに強いとのこと。
Schwab and Maaggs (2004) The falcon’s stoop
によれば、急降下の際は目の表面の水分がすぐ蒸発してしまい、また空中の汚れが付着する問題があるが、瞬膜に "feather epithelium" と呼ばれる特別な上皮があり、表面の汚れを掃き取ることができる (この文献に写真あり)。
涙腺は退化的だがハーダー腺 (Harderian gland) があり、成分は不明だがおそらくヒアルロン酸などが眼球をコートしていると考えられる。正面視では高い解像度が得られない。急降下の際は頭を正面に保持しないと抵抗が増してしまうので網膜の解像度の高い場所に対象を固定し、らせんを描くように降下する。獲物を捉える直前に両眼視に切り替えると説明している。
Maina (2025) Structure and function of the avian respiratory system に鳥類呼吸器のレビュー論文があり、何とハヤブサの飛行速度は 565 km/h に達するとある。
引いている文献は Orton (1975) The speed of a peregrine's dive. Field 9, 588-590 で 300 km/h を超えるとのこと。及び前述の Tucker (1998) の理論計算。上述のようにこれは現実的な範囲の理論的限界値を示したもので測定値ではない。科学文献に記載されることで半世紀前の怪しげな情報が再生産されているよう。
しかしハヤブサ類の急降下速度とは言ってもほぼ自由落下の速度を見ているに過ぎない。その先どうなるかを考えなければ、人でも同様の自由落下速度を出すことができる。「人の最高飛行速度」のような表現は通常使わず、人の場合ならば「人の最高落下速度」と呼ぶのが適切であろう。同じ現象なのになぜ用語を使い分けるのか...となる次第。ハヤブサ類でも最高落下速度と呼んだ方が用語の統一性が高まる。めでたしめでたし。
stoop (本来は "かがむ" などの意味から、高いところから下るの意味となり、この語義は現在廃れてしまったが上記のように学術的には生きている。猛禽の急襲の語義が残っている。OED より) と swoop (本来の語義も語源も違っていた) は音も意味も似ているので、急襲と統一して訳され、その速度で獲物にぶつかっていると誤解されがちな部分もあるだろう。
水平飛行の最高速度としてしばしばハリオアマツバメが取り上げられるが、これも位置エネルギーを運動エネルギーに変換しているようなもので、適切な飛行速度の評価になっているか怪しい。「最も速く飛べる鳥は?」の疑問はこのようにして曖昧な結論となってしまう。近年あまり話題にならないのはこのような理由もあるのかも知れない。
[シロハヤブサの獲物追跡]
頭を傾けた場合の抵抗の増加は Tucker (2000) Gliding flight: drag and torque of a hawk and a falcon with straight and turned heads, and a lower value for the parasite drag coefficient
で見積もられていて風洞実験では 11.7 m/s でも抵抗が 50% も増して体がその方向に傾いてしまう。
らせんを描くような軌跡は最短距離よりも経路は長くなるが速度が速くなる効果の方が有効に働く。
Lorimer (2006) Curved paths in raptor flight: Deterministic models によればモデル計算で得られる経路は現実の飛行経路と一致するとのこと。
Kane and Zamani (2014) Falcons pursue prey using visual motion cues: new perspectives from animal-borne cameras のシロハヤブサなどにカメラを装着した新しい研究があった。
動く獲物を追跡する場合にいくつかの戦略があり、この論文の Fig. 1 をもとに分類すると、
(A) classical pursuit 獲物の方向に向かって飛ぶ。速度差があるのでいずれ追いつくが時間がかかる。
(B) constant bearing decreasing range (CBDR)。classical pursuit では常に獲物の方向に向かって飛ぶ想定になっているが、獲物から少し外れた角度 (φ。φ = 0 の場合が classical pursuit に対応する) を目指して飛ぶ。獲物と追跡者の速度を用いて最適の角度を表すことができて、この最適値を保って飛べば獲物への到達時間が最短になる。よく受け入れられている解釈。
(C) motion camouflage with the baseline held at a constant absolute angle。獲物の側から見て同じ方向に見えるので動いていないと錯覚させる (motion camouflage) 戦略。
追跡者の体から見て向く方向が一定角度になるため constant absolute target direction (CATD) とも呼ばれる。獲物が定常的に動いている場合の最適値は CBDR と同じになる。
獲物が直線運動以外の逃避行動を行う場合は CBDR の拡張版と言える。獲物が時々ランダムに動く場合は classical pursuit より短時間で到達するとのこと。
一定時間・労力で最大量を食物を得る最適採餌理論 (optimal foraging theory) では最短時間・最小労力の経路になることが期待されることが背景にある。
とまっている猛禽類は新しいものや遠くのものは deep (=central) fovea で詳細を見ようとすることが多いが、この向きは体軸の方向から 30° 以上離れているので、獲物を追跡運動中に遠くのものを正面で詳しく見ることはできない (このような視覚特性は猛禽類が何を見ているのか、関心を持って見ようとしているのか、例えば観察者に警戒感を示しているのか安心してのんびり見ているのかなど行動の解釈にも役立つ)。
そのため Tucker et al. (2000) は頭を傾けず体の向きを獲物方向から外すことでらせん運動の飛行をして deep fovea に獲物を捉え続けるアイデアを考えた次第。
眼球がほとんど動かないとすれば CBDR モデルでは φ = 30° 程度で deep fovea、φ = 9-16° ぐらいで shallow fovea で捉え続けることができると考えられる。classical pursuit 以外の戦略の φ の最適値は獲物と追跡者の速度比に依存するのでそれぞれの速度と φ を実測すれば区別できるとの考えに立っている。
なお論文中に出てくる φ の最適値 (Eq. 1) の式は v_p sin φo = v_e sin β と書き直すとわかりやすい。v_p, v_e が追跡者と獲物の速度の大きさ。φ, β がそれぞれの進行方向の角度。
この図は少し概念がわかりにくいので、追跡者の正面に逃げる獲物がいる状況を想定するとよい。獲物が追跡者の進行方向と同じ向きに逃げている場合はその方向を追跡するのが最も早く φo = β = 0 の場合に対応する。
獲物が直角方向に逃げている場合が sin β = 1 で最大となり、v_p > v_e ならば sin φo = v_e/v_p の角度で斜め向きに追うことで最短時間で追いつくことができる。実際にはこの両者の間のどこかの値になる。獲物が一定速度で一定方向に逃げる場合が CBDR に対応。獲物が向きを変える場合はその都度方向を変えるのが CATD に対応する。
頭につけたカメラの向きを測定することで獲物を探す際に実際に頭の方向を変えて (head saccades)、deep fovea に目標を入れて詳しく見る行動が確認された。左右の目の使用頻度には差がなかった。
空中で獲物 (ハシボソガラス) を捕える瞬間のデータもあり最後の瞬間には獲物の方を向いて飛行し、230 ms 前以内に翼と尾を広げ、足を完全に伸ばすのに 67 ms 以内の時間だった。これらの値はアカオノスリやハヤブサで報告されたものとほぼ同じだった。
測定された角度分布は正面を中心に向く classical pursuit を否定する結果となった。獲物を shallow fovea 方向で捉える傾向があるが正面も結構向いている [Tucker (2000); Tucker et al. (2000) の想定した deep fovea ではなかった。Tucker の説明は人気があったらしく、時代的にはやむを得ないがギルの「鳥類学」の訳本 (2007) でもこの説が取り上げられている]。
平均的には shallow fovea で捉えるより小さめの角度になっていた。8 m 以内の距離まで接近すると正面視の傾向が強くなった。
全体的には CATD に矛盾しない戦略となっている結果が得られたとのこと。最適角度は獲物と追跡者の速度比で決まるので、追跡者の方が圧倒的に速い条件では φ の最適値が小さくなって shallow fovea に近いところで像を捉えることができる結果になり生理的にも都合がよい。
#オオタカ 備考の [オオタカの獲物探索の視線の動き] でも同一グループによる似た結果が得られているが、従来考えられてきたような deep fovea や shallow fovea に固定して獲物を追跡するわけではなくより正面を向いている。
#ハイタカ備考の [ハイタカの急降下による捕食行動] にも若干の考察を追加した。
ハイタカ備考の [障害物がある場合の獲物追跡アルゴリズム] の扱いと何が違うのだろうと思われるだろうが、上記の CBDR や CATD は感覚生理学 (視覚) をベースとして行動最適化を考えるもので、そのような行動やその行動を最適とする感覚生理学が進化の過程で選抜されてきたと考える生態学的観点が背景にある。motion camouflage を仮定する場合はさらにその色合い (生態学 + 心理学) が強い。
捕食性鳥類における shallow fovea の役割の考察
上記のような状況は捕食者と獲物の心理学的な認識を含めて、最適採餌理論から期待されるように視覚系が最適化されたと考えると話がわかりやすい。つまり捕食者から見て "最も見えやすい方向" に獲物を固定して飛べば自動的に最適の追跡方向になるように進化したと考えることもできるだろう。
shallow fovea も正面立体視のためよりもそのような追跡のために進化したと考えれば、空中で獲物を追跡する必要があまりないヨーロッパハチクマで shallow fovea が認められない (#ハチクマ備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ]) ことも説明できそうに思える。#ツバメ [視覚特性] で飛翔性昆虫食の鳥の左右の shallow fovea の視野が重なっていないことも飛びながら獲物を追跡するのに特化した構造なのかも知れない。
タカ・ハヤブサ類と飛翔性昆虫食の鳥の収斂進化と言えるかも知れない。
中国のハチクマの巣の映像では巣に戻ってくる際に明らかに正面を向いていて障害物なども巧みに避けているので shallow fovea を使わなくても両眼視による距離感は十分つかめているように見える。
動物園のハチクマでもケージに飛びついてくる映像をいくつも撮影したが、目の荒いケージにもかかわらず翼と尾を広げて減速とともに上手に足で掴んでいて、足元が狂って掴みそこねる事例は観察しなかった。目標に向かって足を差し出す行動はタカ類全般と同様に行えているように見えた。
またネズミが大量に発生した場合にハチクマが主な食物とすることも報告があるので地上の獲物を追うには shallow fovea は必須ではないのかも知れない。他にも海外でハチクマを "鷹狩り" 方式で訓練する映像もあったが地上の動くおとりを追跡するとのこと。地上で動く獲物は比較的簡単に捕れるのかも知れない。
正面を向いていない shallow fovea は立体視よりむしろ CBDR や CATD のような戦略が要求するような運動する獲物、特に空中飛行するもの、を追跡する戦略を実現するために進化した構造なのではと思える。どこかで議論されてそうな気がするがツバメの視覚特性の Tyrrell et al. (2017) では触れられておらず、むしろ眼球を動かして正面視できる可能性を考えていた。
ヨーロッパハチクマやハゲワシ類 [Mitkus et al. (2017) 参照] のように必要がなければ shallow fovea が発達していないのは shallow fovea の維持にコストがかかることも示唆するのだろう。
一方で獲物追跡アルゴリズムの方は制御工学が由来で、視覚などのセンサーと脳回路がどのように制御しているかモデルを立てることを目的としている。こちらもそのような回路が進化の過程で洗練されてきたはずで、互いに排他的ではないが立脚点が少し異なる。
極端に言えば後者の扱いは物体の運動を記述するもので、進化生物学の観点はあまり取り入れなくても構わない。
上述の CBDR や CATD のような戦略もそれを可能にするセンサー機能が問題になる。我々は動かない地上の座標系で物事を考えがちだが、動いている物体から見ると座標系が異なり獲物の絶対的な位置などはわからない。その際に視覚情報だけで CBDR や CATD を実現できるのか、動いている自身の加速度感覚も用いているのかなどを考える上で制御工学的な視点も重要になる。
ハヤブサ類の飛行はミサイルの制御工学と共通点が多く論文もいくつもある: Brighton et al. (2017) Terminal attack trajectories of peregrine falcons are described by the proportional navigation guidance law of missiles 実際の経路をモデル化することで制御定数を求めるなど。
Brighton et al. (2021) Attack behaviour in naive gyrfalcons is modelled by the same guidance law as in peregrine falcons, but at a lower guidance gain。ハヤブサとシロハヤブサで制御定数の比較など。
Kempton et al. (2023) Visual versus visual-inertial guidance in hawks pursuing terrestrial targets モモアカノスリ (ハリスホーク) への適用。視覚情報のみで制御可能な結果になっているか、加速度など他の情報を必要とするか。
ハイタカ備考の [障害物がある場合の獲物追跡アルゴリズム] で紹介した研究も同じグループによるもので同じ定式化を用いている。何がわかれば行動を理解できたと言えるのか両者の手法ともある程度の壁になりそう。ドローンなどへの実用応用を論文結論に含めているのは研究が最適採餌理論のような生物学の理論体系に役立つか評価しにくいこともあるのだろう。
視覚だけによる同様の飛行制御はミツバチなど昆虫でも示されており、鳥ではもう少し高度な情報や判断を用いているだろうと考えられるため工学的な制御因子が他にないか調べる動機にもなっているのだろう。
[アイスランドでシロハヤブサが激減]
Gyr Falcon shows worrying decline in Iceland (BirdGuides 2024.9.5) 2019 年から 2023 年までに 53% 減少、eBird では 2020 年から 2024 年で 78% 減少。
2021 年以降は鳥インフルエンザの影響の可能性もあると考えられるが原因究明中。
Steady decline in the gyr falcon population
アイスランドのページ (2024)。ここ 3-4 年続いている傾向だが調べた範囲はアイスランドの個体群のわずかな部分で全貌はわからないよう。ライチョウ類の不足
[cf. Concern Over Plummeting Ptarmigan Population (Jelena Ciric, Iceland Review 2024) こちらは 2024年6月始めの降雪のため巣を放棄したとのこと]
ではなく海鳥からの鳥インフルエンザの感染の可能性がある。シロハヤブサが普段食べる種類ではないがシロカツオドリを食べるのが記録されているとのこと。
関連して#ハヤブサ備考 [鳥インフルエンザのオランダのハヤブサへの影響] も参照。
-
ハヤブサ
- 学名:Falco peregrinus (ファルコー ペレグリーヌス) よそ者の (移住する) ハヤブサ
- 属名:falco (m) ハヤブサ
- 種小名:peregrinus (adj) よそ者の、移動する。原義推定は備考参照。
- 英名:Peregrine Falcon
- 備考:
falco は#チゴハヤブサ参照。
peregrinus は pe-re-gri-nus と分割され、i が長母音でアクセントもここにある (ペレグリーヌス)。-inus の形容詞語尾由来。
オオタカとハヤブサの原記載には混乱があった可能性がある。#オオタカ 備考の [オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑] 参照。
渡りのことなどそこまでわかっていなかった時代と想像されるので、巣があって繁殖の確認されている「地元のハヤブサ」の意味で gentilis、営巣地のわからない「よそ者のハヤブサ」の意味で peregrinus が使われていたとすると理解しやすい。
当初から「移住する」または「渡りをする」の意味が種ハヤブサに与えられていたわけではなく、ハヤブサは複数に分けられており、peregrinus に相当するものはそのうち一部だった。
ハヤブサの学名に与えられるべき gentilis (とはいえおそらく「高貴な」の意味ではなかった) がシノニムと判定されてオオタカの方に持って行かれてしまったらしい。
オオタカ備考の [オオタカとハヤブサの学名の関係は複雑] で紹介の Gesneri (1555) Conradi Gesneri Historiae animalium liber III qui est de Avium natura - 1555 からハヤブサらしいものをリストアップしておくと (二名法以前の学名のため学名に使われる単語数はさまざま):
・Falco montanus (山のハヤブサ), Ray (1678) p. 78 によればオオタカ並に大きいという。記述があるので何を指しているか調べてみていただきたい。目は漆黒とあり、他の記述からも Peregrine と比較しており、種ハヤブサでよさそう。
Linnaeus は Falco Gentilis と同種と扱っている (この学名が後にオオタカに使われることになった)。
・Falco peregrinus (移住する/よそ者のハヤブサ), Ray (1678) p. 76 によれば国から国へと移動しているか、巣がまだ見つかっていないことが名称の由来とある。
・Mediani (英語 middle に相当。中程のサイズを指す?),
・Gentiles (地元のハヤブサ), Ray (1678) p. 79 によれば Peregrine と区別できるか疑問を持っていると述べている。Frederick II の記述にも言及があるが訳書の通りなので割愛する。Belisarius は Peregrine と区別できる点は飛び方だけだという。Gentile の方が翼をよく動かし、飛ぶのは遅いとのこと。
Carcanus が Dutch Falcon または German Falcon と呼んだものはほとんど違いがなくこれと同一と考える。
これら記述からはやはり Gentile と Peregrine は同一種とみなすのがふさわしそう。Ray は後の部分にオオタカとの明確な違いを述べている。
・Falco gibbosus (こぶのあるあるいは猫背のハヤブサ), Ray (1678) p. 76 によれば 英語で Haggard Falcon (Peregrine の項目では首が長いと書かれている) 首が短いのでそのように呼ばれた。頭が肩の上に少ししか出ない。あるいは翼が背で縮まっていてこぶのように飛び出て見える。ドイツ語では Hagerfalck または Hogerfalck で後者の方が普通。ドイツ語で Hoger はこぶを意味するとあるが現代では使われていないよう。
ラテン語で Gibbosus。渡りをするハヤブサに比べて寸詰まりの体型なのか?
Ray によれば英国の鷹匠は Peregrine Falcon をこの名前で呼び、区別していないと考えている。
現代の鷹狩り用語では haggard は1歳以上で野生捕獲されたものを指しているようだが、歴史的用法とは異なるよう。英語の haggard は 1560 年代から使われており、古フランス語の faulcon hagard (野生のハヤブサ) に由来すると考えられる。英語の hag の意味の影響を受けたのではとのこと。
伝来途中で本来の「こぶ」の意味が失われて別の意味になったように思える。
・Falco niger (黒いハヤブサ),
・Falco albus (白いハヤブサ。シロハヤブサとは別物), Ray (1678) p. 80 には全体に白くて目が黒と黄色とある。これは種ハヤブサではないかも知れないが、黄色は虹彩の色を指すものではない可能性もある。
・Falco rubeus (赤っぽいハヤブサ),
・Falco cui pedes coerulei (足の青いハヤブサ)
ここでの Ray (1678) は The ornithology of Francis Willughby of Middleton in the County of Warwick, Esq., fellow of the Royal Society: in three books: wherein all the birds hitherto known being reduced into a method sutable [sic]
to their natures, are accurately described: the descriptions illustrated by most elegant figures, nearly resembling the live birds, engraven in LXXVIII copper plates
すべてが種ハヤブサを指すかどうかはわからないが以上が挙げられるだろうか。
Ray (1678) にオオタカもあり、short-winged hawk の項目に含めて Accipiter Palumbarius を用いている (p. 85)。翼をたたむと尾の先端よりずっと短く、この点だけで他のタカ・ハヤブサ類と区別するのに十分であるとのこと。
英国の鷹匠は goshawk はフランス語の Autour または Astur と同じと考えているとある。
オオタカの解説と重複するが、Linnaeus の Falco gentilis の記載の生息地 (基産地) について。
Linnaeus の「アルプスに住み」が気になったので調べておくと、Falco gentilis をオオタカとする解釈ではスウェーデンのダーラナ地方 (Dalarna) にも Alps と呼ばれるところがあり (Dalecarlian Alps) 一般的にはここが基産地と解釈されるとのこと。
現在はスウェーデンの名称になっているがかつてはもっと広い地域を指されていたよう (後述)。
Falco palumbarius がオオタカを指していたことは疑いないが、こちらの生息地 (基産地) はヨーロッパとなっている。同所に記されているヨーロッパチュウヒ、ハイタカも同じ生息地の記載になっている。
他の種と見比べると Falco gentilis の生息地はヨーロッパと記さず局地的で特殊な記載になっている。
Lindberg (2008) The fall and the rise of the Swedish Peregrine Falcon population では歴史的分布も再現されているが、かつてはスウェーデンに広く分布していた。
迫害、有機塩素化合物、水銀汚染で一度はほぼ絶滅して再導入され、現在では南西部の山岳地の崖と北部ではタイガにある崖で沼地が近いところを好むとのこと。崖好みの習性からは Dalecarlian Alps の表現は整合性がよいと思える (つまり Falco gentilis はハヤブサを指していたと考えて矛盾はない)。
British zoology (Pennant, Thomas 1768-70) によれば FALCON GENTIL は鷹匠が高く評価した種で、ドイツの鷹匠は Dalecarlian Alps (Denmark in Jutland and Norway) に求め、英国の鷹匠はスコットランドに求めたとある。
Dalecarlian Alps 特にドイツの鷹匠には上質の Falco gentilis の産地として有名だった模様。
なお Rizzoli et al. (2010) Density, productivity, diet and population status of the Peregrine Falcon Falco peregrinus in the Italian Alps
のようにハヤブサはイタリアアルプスにも生息している。ただし食べ物はツグミ類、ハト類、カラス類が中心とのこと。
Linnaeus が他のタカ類のように生息地をヨーロッパとしなかったのは、ハヤブサの繁殖地があまり知られていなかったのだろうか。鷹狩りに使われるものは渡り中に捕獲されることも多かったようなので繁殖地があまり知られていなかったのかも知れない。
また巣から捕えたハヤブサは「正真正銘の地元産」と言えるので、Frederick II が Falco gentilis absolute (ほぼ字義通りだと正真正銘同一民族のハヤブサ) と呼ばれたとしても不思議でない感じがする。「最初の羽が生え変わると、風切り羽はハヤブサの風切り羽に非常に似ている」 (「鷹狩りの書」訳書 p. 187) との表現も若い鳥を示唆しているように見える。
Don Juan Manuel (1282-1347) より Baist (1880) El libro dela caza [von] Don Juan Manuel; zum erstenmale hrsg. von G. Baist (Baist による鷹狩り用語集の補遺部分)
Bahari: Falco gentilis, peregrinus, Edelfalk, Wanderfalk で南ヨーロッパで繁殖するなどの記述がある。この記載では明らかに Falco gentilis, peregrinus ともにハヤブサを指している。
Edelfalk はドイツ語で「高貴なハヤブサ」の意味になる。Wanderfalk (peregrinus) が「渡りハヤブサ」に対応する。鷹狩り用語集は Baist (1880) によるものなので意味は比較的新しいものかも知れない
(想像だが Frederick II の著書のドイツ語訳書にもこの用語が使われているかも)。
[英名の由来]
OED によれば faukon peregryn の用例が 1395 年ごろにすでにあるとのことで、その後も綴りを変えながら使われて続けていた。そのため Peregrine Falcon の英名は (現代用いられる) 学名から名付けたものとの解釈は適切でなく、Falco peregrinus Tunstall, 1771 は英名に対応する形で用いられた学名と考えるのが適切と思える。
ただし上述のように peregrinus などの名称は英語以外ではすでに使われていたため、"古い時代の現代有効とされないラテン名" 由来と呼ぶことはできるかも知れない。OED では falco peregrinus のラテン名が 1200 年ごろに見られることが紹介されている。
英国ではハヤブサは繁殖せず (少なくとも当時は繁殖は知られていなかったよう)、渡り鳥としてのみ知られていたため英語ではこの用語は適切であった。OED によれば The peregrine falcon is a migratory bird and is so called because the young were not, like the eyas, taken from the nest (which is usually built on an inaccessible crag or precipice), but caught on their migration or 'pilgrimage'
とある。"peregrine" が適切であったのは英国事情 (ドイツでも同様) で、Tunstall によって英語から学名に逆輸入されてしまったために現在の学名語義となったものと考えてよさそう。Linnaeus が名付けたスウェーデンでは状況が異なることはあまり考慮されなかったのかも知れない。Linnaeus がこの種小名を用いなかったのはスウェーデンでは繁殖する理由によるかも知れない。
他の種でもしばしば見られるように、英国が大陸とは別物、あるいは (フランスでもそうであったように) スウェーデン方式の学名システムを嫌って英語由来で独自のラテン名を付けたものかも知れない。
OED によれば鷹狩り用語では Peregrine Falcon と Peregrine の用法には使い分けがあって、前者はメスのみを指すのが正しいとされている。
[ハヤブサ目の系統分類]
ハヤブサ類の分子系統樹については Wink (2018) Phylogeny of Falconidae and phylogeography of Peregrine Falcons も参照。
タカ類の Catanach et al. (2024) のような詳細な分子系統の解析はハヤブサ目についてはまだないので、Catanach et al. (2024) の言うところの「伝統的な遺伝子を用いた分類」がベースとなっている。
Fuchs et al. (2015) Rapid diversification of falcons (Aves: Falconidae) due to expansion of open habitats in the Late Miocene
だがオープンアクセスの版がなさそうなので、これをもとにして作成したとなっている Boyd に基づいている [以下 Costantini and Dell'Omo (2020) で系統樹を見ることができる]。綴りは IOC の方に合わせてあるので分布地域によらず gray でなく grey と綴っている。
順序などは今後の全ゲノムを用いた研究で変わるかも知れない。
この順序は IOC 13.2 に基づいた日本鳥類目録 改訂第8版 第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開 とほぼ同じになっている。ハヤブサとシロハヤブサの順序が違っている程度であるが、これは分子系統樹でもほとんど差がないのでどちらでも同じと思ってよい。
以下に示すようにハヤブサ目は南米起源で、ノスリ類と同様に世界的に見ると日本に馴染みのない系統や種類が多い。ハヤブサ目やハヤブサ科を語る時には日本の種の印象のみを情報源としない方がよいだろう。
Costantini and Dell'Omo (2020) "The Kestrel" から Systematics and Evolution of Kestrels の冒頭部分サンプルを見ることができ、Fuchs et al. (2015), Cenzio et al. (2016) の系統樹も含まれている。
ノガンモドキ目 Cariamiformes ノガンモドキ科 Cariamidae
(現生種では1科のみだが化石科は他にいくつか提唱されている)
ノガンモドキ属 Cariama
ノガンモドキ Cariama cristata Red-legged Seriema
クロアシノガンモドキ属 Chunga
クロアシノガンモドキ (ハイイロノガンモドキ) Chunga burmeisteri Black-legged Seriema
ハヤブサ目 Falconiformes ハヤブサ科 Falconidae
(現生種では1科のみだが化石科は他にあって Masillaraptoridae が確実なメンバーと思われている)
ワライハヤブサ亜科またはモリハヤブサ亜科 Herpetotherinae
ワライハヤブサ属 Herpetotheres
ワライハヤブサ Herpetotheres cachinnans Laughing Falcon
モリハヤブサ属 Micrastur
シロエリモリハヤブサ [高野 (1973) ではヒメシロエリモリハヤブサ] Micrastur buckleyi Buckley's Forest-Falcon
クビワモリハヤブサ [高野 (1973) ではシロエリモリハヤブサ] Micrastur semitorquatus Collared Forest-Falcon
アオモリハヤブサ Micrastur mirandollei Slaty-backed Forest-Falcon
ヨコジマモリハヤブサ Micrastur ruficollis Barred Forest-Falcon
インベイモリハヤブサ? Micrastur mintoni Cryptic Forest-Falcon
ハイイロモリハヤブサ [高野 (1973) ではアオグロモリハヤブサ] Micrastur plumbeus Plumbeous Forest-Falcon
ヒメモリハヤブサ Micrastur gilvicollis Lined Forest-Falcon
カラカラ亜科 Caracarinae (または Polyborinae)
シラボシハヤブサ属 Spiziapteryx
シラボシハヤブサ [高野 (1973) ではシラホシハヤブサ] Spiziapteryx circumcincta Spot-winged Falconet
カラカラ属 Caracara
ミナミカラカラ (カンムリカラカラ) [高野 (1973) ではオージュボンカラカラまたはカラカラ] Caracara plancus Southern Crested Caracara
(オーデュボンカラカラまたはカラカラ) Caracara cheriway Northern Crested Caracara (上記と同一種とされることが多い)
グアダルーペカラカラ Caracara lutosa Guadalupe Caracara (絶滅種)
アカノドカラカラ属 Ibycter
アカノドカラカラ Ibycter americanus Red-throated Caracara
キノドカラカラ属 Daptrius
キノドカラカラ Daptrius ater Black Caracara
キバラカラカラ属 Milvago
キバラカラカラ Milvago chimachima Yellow-headed Caracara
チマンゴカラカラ Milvago chimango Chimango Caracara (Phalcoboenus 属に移動の可能性がある)
アンデスカラカラ属 Phalcoboenus
フォークランドカラカラ [高野 (1973) ではアカスネカラカラ] Phalcoboenus australis Striated Caracara
マダラコシジロカラカラ Phalcoboenus carunculatus Carunculated Caracara
アンデスカラカラ [高野 (1973) ではコシジロカラカラ] Phalcoboenus megalopterus Mountain Caracara
シロハラカラカラ Phalcoboenus albogularis White-throated Caracara
ハヤブサ亜科 Falconini
ヒメハヤブサ族またはコビトハヤブサ族 Polihieracini
コビトハヤブサ属 Polihierax
コビトハヤブサ [高野 (1973) ではアフリカヒメハヤブサ] Polihierax semitorquatus Pygmy Falcon
ヒメハヤブサ属 Microhierax
フィリピンヒメハヤブサ [高野 (1973) ではシロクロヒメハヤブサ] Microhierax erythrogenys Philippine Falconet
モモアカヒメハヤブサ Microhierax caerulescens Collared Falconet
シロハラヒメハヤブサ [高野 (1973) ではマダラヒメハヤブサ] Microhierax melanoleucos Pied Falconet
モモグロヒメハヤブサ [高野 (1973) ではクロアシヒメハヤブサ] Microhierax fringillarius Black-thighed Falconet
ボルネオヒメハヤブサ [高野 (1973) ではシロガシラヒメハヤブサ] Microhierax latifrons White-fronted Falconet
ハヤブサ族 Falconini
アジアコビトハヤブサ属 Neohierax
アジアコビトハヤブサ [高野 (1973) ではハイイロヒメハヤブサ] Neohierax insignis White-rumped Falcon
ハヤブサ属 Falco
[チョウゲンボウグループ Costantini and Dell'Omo (2020) による]
ヨコジマチョウゲンボウ Falco zoniventris Banded Kestrel
ヒメチョウゲンボウ Falco naumanni Lesser Kestrel
キツネチョウゲンボウ Falco alopex Fox Kestrel
メジロチョウゲンボウ Falco rupicoloides Greater Kestrel
セーシェルチョウゲンボウ [高野 (1973) ではセイシェルズチョウゲンボウ] Falco araeus Seychelles Kestrel
マダガスカルチョウゲンボウ Falco newtoni Malagasy Kestrel,
レユニオンチョウゲンボウ Falco duboisi Reunion Kestrel (絶滅種)
モーリシャスチョウゲンボウ Falco punctatus Mauritius Kestrel
ミナミアフリカチョウゲンボウ Falco rupicolus Rock Kestrel
モルッカチョウゲンボウ Falco moluccensis Spotted Kestrel
チョウゲンボウ Falco tinnunculus Common Kestrel
オーストラリアチョウゲンボウ Falco cenchroides Nankeen Kestrel
アメリカチョウゲンボウ Falco sparverius American Kestrel
ニシアカアシチョウゲンボウ Falco vespertinus Red-footed Falcon
アカアシチョウゲンボウ Falco amurensis Amur Falcon
[Costantini and Dell'Omo (2020) のチョウゲンボウグループはここまで。最後の2種は Brown and Amadon (1968-1969) と Fuchs et al. (2015) の提案による]
コチョウゲンボウ Falco columbarius Merlin
ハイイロチョウゲンボウ Falco ardosiaceus Grey Kestrel
ハイガシラチョウゲンボウ [高野 (1973) ではディッケンソンチョウゲンボウ] Falco dickinsoni Dickinson's Kestrel
チャイロハヤブサ Falco berigora Brown Falcon
コウモリハヤブサ [高野 (1973) ではコウモリチゴハヤブサ] Falco rufigularis Bat Falcon
アカハラハヤブサ [高野 (1973) ではアカムネハヤブサ] Falco deiroleucus Orange-breasted Falcon
オーストラリアチゴハヤブサ [高野 (1973) ではヒメチゴハヤブサ] Falco longipennis Australian Hobby
ミナミチゴハヤブサ Falco severus Oriental Hobby
エレオノラハヤブサ [高野 (1973) ではオオチゴハヤブサ] Falco eleonorae Eleonora's Falcon
ウスズミハヤブサ [高野 (1973) ではウスズミチゴハヤブサ] Falco concolor Sooty Falcon
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby
アフリカチゴハヤブサ Falco cuvierii African Hobby
ニュージーランドハヤブサ Falco novaeseelandiae New Zealand Falcon
オナガハヤブサ Falco femoralis Aplomado Falcon
アカガシラチョウゲンボウ [高野 (1973) ではアカガシラコチョウゲンボウ] Falco chicquera Red-necked Falcon
ソウゲンハヤブサ Falco mexicanus Prairie Falcon
ハイイロハヤブサ Falco hypoleucos Grey Falcon
タイタハヤブサ Falco fasciinucha Taita Falcon
ハヤブサ Falco peregrinus Peregrine Falcon
バーバリーハヤブサ Falco pelegrinoides Barbary Falcon (通常はハヤブサの亜種とされる)
[以下5種は小さなグループをなし、亜属 Hierofalco とされることもある (#シロハヤブサの備考参照) が、ハヤブサグループ内ですら残りが単系統にならないのであまり意味がない。上種ぐらいの扱いが適当か?]
ラナーハヤブサ Falco biarmicus Lanner Falcon
ラガーハヤブサ Falco jugger Laggar Falcon
クロハヤブサ Falco subniger Black Falcon
シロハヤブサ Falco rusticolus Gyrfalcon
ワキスジハヤブサ [高野 (1973) ではセイカーハヤブサ] Falco cherrug Saker Falcon
ノガンモドキ目とハヤブサ目で単系統をなすわけではないが、ハヤブサ目に最も近縁の祖先型のグループとして含めておく。The Peregine Fund ではノガンモドキ目も猛禽類に含めている。
{ノガンモドキ目 + {ハヤブサ目 + {オウム目 + スズメ目}}} が単系統をなす系統関係で、これらが通常 Australaves と呼ばれる (wikipedia 日本語版のハヤブサ目の項目ではオーストラリア鳥類の訳語が与えてあるが、地名のオーストラリアと「南」の意味が混同されるおそれがあり、この訳語は避けた方がよいと思う)。
この系統は比較的広く受け入れられているが、解析方法で形が異なることもあるのでまだ異論の余地も残っているよう。
{ハヤブサ目 + {オウム目 + スズメ目}} には Eufalconimorphae の系統名称があり、真ハヤブサ形類 (wikipedia 日本語版) の訳語はこれでよさそうに思える。
山崎・亀谷 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類 ではノガンモドキ目、ノガンモドキ科の名称は記載されているが系統分類における位置は古いものである。
またノガンモドキ目は高野 (1973) には含まれていないため高野氏による種名はわからない。
ノガンモドキの詳しい資料があったので紹介しておく: Red-legged Seriema Cariama cristata care manual
(ツル目の研究グループが扱っている)。まつ毛のような羽毛を持つ数少ない種類。
地上 1-5 m の樹上で営巣。親鳥は飛び跳ねて巣に入るとのこと。ひなの自立が非常に早く通常は 3-4 週間で巣立つが (まだ飛べないとのこと)、生後 10 日で立てるようになり、14 日で巣を出ることさえあるとのこと (p. 39)。
ハヤブサ類と似ていないところが多く感じるが共通の系統と考えながら見ると面白いかも。求愛行動はヘビクイワシに似たところがあるらしいが系統的には近くない。
ノガンモドキはヘビが好みとのことで、ヘビクイワシとは違ってヘビを地面に打ち付けて殺すとのこと。参考映像 (デモンストレーション): Red-legged Seriema - snake attack (David Hodson 2024)。
#カンムリワシ備考の [猛禽類のヘビ毒耐性] や #ミサゴ備考の [猛禽類の分類など] (ヘビクイワシの考察) も参照。異なる系統で独立にヘビを捕食する方法を編み出したと見える。ノガンモドキの方法を使う場合は言うまでもなく体高が高いことが有利で、首も脚も長い直立姿勢が役立つ。
改めて解釈するほどのことではないが出発点が高いほど位置エネルギーも有効利用でき、同じ力でも加速に用いる時間が長いので衝突時の速度も大きくなる。
#オオモズ備考の [アメリカオオモズの獲物の殺し方] にあるように、地面に打ち付けて殺すだけではなく加速度を与えることで脊髄に損傷を与えやすくなっている効果もあるだろう。この効果は回転半径や角速度が大きいほど有利に働く。モズ類の体型やサイズではノガンモドキの方法は使えないので別方法をさらに進化させた関係になるだろうか。
外見はかなり長く見えるが他の猛禽類系統に比べて特に頸椎数が多いわけではなさそう (#ハチクマ備考 [フィリピンのハチクマの不思議]。資料がはっきりしないが 14-15 個か。以下の骨格も参照。頸椎の上部の骨は確かに少し長く見える)。古い系統なので首が長いというわけではなくヘビ食のための形態的適応と考えると理解しやすい気がする。基本的にはハヤブサ類を含む祖先系統から派生する形なのだろうか。
ハチクマの項目を記述してから気づいた文献だが解剖学については Martin (1836) Notes on the visceral and osteological anatomy of the Cariama (Dicholophus cristatus, Ill.)
の古い情報があり、頸椎数は 13(2) (2 は不完全な肋骨) となる。これであればハヤブサ目と同じ基本形となる。
骨格は (分類から想定されるような) ツル類よりキジ目に似ているとのこと。他の部分は猛禽類にほとんど似ていないが眼の骨性リング (強膜骨) はキジ目とまったく似ておらず猛禽類に似ているとのこと。
骨格は Cariama (Reptile Evolution) のページで見られるがこのページではノガンモドキの系統がフラミンゴ類につながっているような解釈となっており現代の知見とは大きく異なる。骨格を見るために (のみ) 参考にしていただければ。他の種でも化石骨格を見て足が長いのは獲物の反撃から逃げるためと解釈してしまうのはちょっと怪しそうで、もっと機能的意義がありそう。
しかし化石証拠が可能性を指摘しているようなノガンモドキ類がヘビクイワシも含めたタカ系統に先立つ可能性 (#ミサゴ備考 [タカ類の初期の適応放散] 参照) はあるのだろうか。このような獲物の捕獲技術からヘビクイワシの行動は生まれない気がするので、もし同じ系統に乗るなら個別に捕食方法を編み出したことになる。もっともノガンモドキの系統は2種しか現存していないので、グループ全体ではもっと多様な捕食形態を持っていたのかも知れない。
ノガンモドキ類が足でヘビを殺すわけではない点は、ある意味ハヤブサ類が嘴でとどめを刺す点と類似性があるかも知れない (さらに言えばモズ類の系統ともつながっているので...というのは足が捕食に適していないスズメ目ではさすがに飛躍しすぎかも知れないが)。
ノガンモドキ類の考察で寄り道をしたが、以降の部分は Fuchs et al. (2015) の分子系統樹に従って系統が少し離れるところに空行を入れてある。
Fuchs et al. (2015) の分子系統樹によれば Micrastur 属は2系統に分かれる。空行を入れてある。ヨコジマモリハヤブサ以降の系統は系統樹上でばらつきが大きく、隠蔽種の存在が示唆される。
Micrastur mintoni はヒメモリハヤブサに分類されていたが、2002 年の研究で新種とされた。和名は英名を訳したものと想像できるが、インベイ- は インペイ- の誤りではないだろうか。
ヒメモリハヤブサは 1972 年までヨコジマモリハヤブサの亜種と考えられていたとのことで、高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) の時代にはまだ種としてリストされていなかった。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) ではカラカラ類のうち現在の Daptrius 属と Ibycter 属をワライハヤブサ亜科またはモリハヤブサ亜科 Herpetotherinae に相当する森林性ハヤブサ類に含めていた。
モリハヤブサ類 Micrastur は深い森の下生えに生息し、自ら空中に姿を見せないため研究が非常に難しい (Brown 1976)。
Brown の時代にはモリハヤブサ類の巣はまったく知られていなかったが、クビワモリハヤブサの巣が 1978 年に発見された: Mader (1979) First Nest Description for the Genus Micrastur (Forest Falcons)。
これによると樹洞にあったとのこと。
ワライハヤブサも樹洞に営巣するとのことで、ハヤブサ科の早い段階で枝などを使って巣を造る習性が失われた系統があったことになる。
Piacentini et al. (2024)
On the identity of Micrastur guerilla jugularis Gurney, 1884, with lectotype designation
Micrastur guerilla jugularis は Micrastur ruficollis ruficollis のシノニムと判定。
標本の写真があるので広義ハイタカ属に似たハヤブサ科の鳥とはどんなものか見ていただけるだろう。
Herpetotherinae の訳名はタイプ属を優先すればワライハヤブサ亜科となるだろうが、1種を除いてモリハヤブサ属であり Herpetotherinae の英名 Forest-Falcons [高野 (1973) でも森林性のハヤブサ類とおそらくそのまま訳している] を考慮するとモリハヤブサ亜科でもよさそうである。
ワライハヤブサ属に使われる Herpetotheres の意味は herpeton ヘビ、爬虫類 -theras 狩るもの (Gk)。cachinnans は 大声で笑うの意味。おそらく学名が英名の由来で、和名にもつながっている。
南米ではヘビワシのグループがいないのでハヤブサの仲間のワライハヤブサがヘビ食となっている。
モリハヤブサ属に使われる Micrastur の意味は容易に想像できるだろうが mikros (超) 小型の (Gk) Astur オオタカの属名。名前の通り姿は (広義) ハイタカ属によく似た印象を受ける。
ハヤブサ類だが翼を広げた飛翔中はタカ類のように翼指が開いて見える (Brown 1976, p. 88)。
参考写真: Collared Forest-Falcon (Rodrigo Ferraz 2023.7.19)、
Collared Forest-Falcon (Charles Davies 2023.4.3)。このように見るとタカ類とハヤブサ類の違いは系統による絶対的なものではなく、環境に応じた適応の産物も含まれていることがわかる。ハヤブサ類でも対応するタカ類がいないところではタカ類のような形や模様になり得るのかも (?)。
wikipedia 英語版によればしばしばオオタカ型の採食を行うとのこと。
Thorstrom, Russell K. (2012). "Collared Forest Falcon". In Whitacre, David F. (ed.). "Neotropical Birds of Prey" が収斂進化と述べているとのこと。
逆に言えばタカ類の方が生態的に相対的に優勢で、森林のようにタカ類が占めているニッチにはハヤブサ類は簡単に入り込めないのだろう。
それほどタカ類に似ているわけではないがマダガスカルの ヨコジマチョウゲンボウ Falco zoniventris Banded Kestrel もタカ類とハヤブサ類の中間型があると言えないこともない。この場合も模様は収斂進化なのだろうか。あまりハヤブサ類が出しやすい模様のパターンの感じに見えない。
マダガスカルの シロハラハイタカ Tachyspiza francesiae Frances's Sparrowhawk や マダガスカルハイタカ Accipiter madagascariensis Madagascar Sparrowhawk に似ていると言えば若干似ている。比べてみると面白い。
マダガスカルには マダガスカルオオタカ [高野 (1973) ではヘンストオオタカ] Astur henstii Henst's Goshawk も生息するが、こちらはさすがに Astur 属の感じ。
Micrastur 属は実際にはこのように飛翔する姿を見るのは難しく、翼指がソアリングのために進化したものではないらしいこともわかる (#アホウドリ備考 [海鳥の翼先端にはなぜスロットがない?] 参照)。
Micrastur 属は実験室条件では飛んで抜けられないような茂った下生えを走ってウサギを捕らえることができる。長い尾は走る時に操縦性を高めている可能性がある。
採食様式はカッコウ科のミチバシリに似ているとのこと (以上 Brown 1976, p. 101)。#カッコウ備考の [Otidimorphae とはいったい何者?] で少し検討してみた点にも関係があるかも知れない (カッコウ科が南北アメリカにほとんど残らなかったのはなぜか)。
Brown (1976) p. 79 によれば Micrastur 属は外耳道の開口部が大きく、薄暗い条件でも音声を流すと簡単に近くまでやってくるとのこと。
Collared Forest Falcon (Micrastur semitorquatus (Planet of Birds) の記述では耳で獲物を探すとある。
wikipedia 英語版にも聴覚が非常によいとある。
(広義) ハイタカ属のようでもあり、フクロウ類 (またはチュウヒ類やカタグロトビ類) のようでもあるグループ (?)。
Fuchs et al. (2011) Pliocene diversification within the South American Forest falcons (Falconidae: Micrastur)
によればこの属の分岐は 700 万年前、属内の分岐は 250-360 万年前と推定され、更新世の寒冷化の際のレフージア仮説よりも古い時期に分岐していたことになる。中新世の海面低下の時期よりも遅く、南米の種多様性を説明する他の仮説の年代とも特に合わないとのこと。
ワライハヤブサ亜科またはモリハヤブサ亜科 Herpetotherinae がハヤブサ目の中の1系統で、残りの系統が単系統をなす。モリハヤブサ属の容貌を見るとこれがそのままハヤブサに進化してもよさそうに見えるがそうなっていないところがまた面白いところ。ここまですべて南米の種である。
Caracara plancus と Caracara cheriway は Boyd では別種としている (過去にも別種だった)。IOC 14.1 = 13.2 や他のリストでも cheriway を Caracara plancus の亜種とするものが大半である。
同種とする場合は英名・和名ともに問題があり、英名では IOC が Crested Caracara を採用している。かつてはよく知られたオーデュボンカラカラの和名があり、この当時の学名は
Polyborus cheriway または Polyborus plancus (当時の属名は異なっていて、Polyborus は現在使われない。以下参照)
であったため、オーデュボンカラカラを用いた場合にこの分類群を指すのかわかりにくい。同種であるこを前提にカンムリカラカラとすべきか難しいところである。ミナミカラカラの名称を認めるならばキタカラカラでもよさそうだが通常は種扱いでないためか用例は見当たらなかった。
オーデュボンカラカラは単にカラカラとも呼ばれた。
現在の動きから見てアメリカでオーデュボンを冠した名前が復活するとは考えにくいので、カンムリカラカラと呼ぶ方が世界的動向からもふさわしいだろう。亜種を指す場合、あるいは種として扱う場合も経緯や現在の英名を考えるとキタカンムリカラカラ、ミナミカンムリカラカラとするのが整合性がよさそうに思える。
英名とは対応しなくなるがカラカラとミナミカラカラでも構わないかも知れないが、亜種名とするには後者が基亜種であるため落ち着きが悪い感じがする。
カラカラの属名は最近まで Polyborus だったものがどのように Caracara に変わったのかは
Northern Crested Caracara (IFAS Extension, University of Florida) に解説がある。
初期記載は Polyborus vulgaris John James Audubon, 1834 で 1865 年に学名が Polyborus audubonii と変わった。
1876 年に3種に分割されて audubonii の種小名を持つ種はなくなった。1949 年に2種が同種とされ現在の (広義) カラカラに対応する Polyborus plancus に改名された。おそらくこの時代が一番長くてこの学名が広く使われてきたものと想像できる。
オージュボンカラカラの名前も Polyborus audubonii の時代に付けられたものかも知れないが、知名度が非常に高いので学名が変わっても英名や和名は歴史を引き継いでいたかも知れない。
1992 年に属名が Caracara Merrem, 1826 に改められた。
現在はヒメコンドル属を指す Cathartes の属名は (現在別属とされる) さまざまな種類に使われていて、カラカラ plancus もその一部に含まれていたため、Merrem (1826) は Caracara 属を分離したことが経緯だった模様。
protonym は Falco Plancus Miller, 1777 で、
Audubon による Polyborus vulgaris の記載の方が実は遅かった。Merrem (1826) の記述は Amadon (1979) が Peters "Check-List of Birds of the World" すでに紹介しており (The Key to Scientific Names の Caracara の項目)、1992 年の変更まで時間がかかったのは慣れ親しんだ学名を変えるのに抵抗があったのかも知れない。
Audubon を記載者とする上記解説もアメリカ的歴史観かも知れない。audubonii の名前は亜種名として残っている。
Polyborus 属は早かった (Vieillot 1816) のだが、Schneider (1938) が原著図版を検討したところハネナガチュウヒ Circus buffoni を指していることが判明した。
Vieillot の文章の記述は (恐らく Northern) Crested Caracara [(北米の) (カンムリ) カラカラ] を基にしていることは明らかであるが、著者がこの属は1種と記載しているために自動的に Polyborus は Circus のシノニムとなる (Hellmayr and Conover 1949) (The Key to Scientific Names の Polyborus の項目より)。
このような事情もあって Polyborus は現在は完全に封印状態になっていると想像される (つい最近までは普通に見かけた属名だったのに...)。図版の取り違いは致命的だったのだろう。従って Circus か Caracara のシノニムかもすっきりしない。
タカ類のチュウヒダカ類 Polyboroides (#ハチクマの備考 [ハチクマ類の系統分類] 参照) に痕跡を残すのみとなっている。Polyborus で検索してもおそらくこちらが出てくると思う。
wikipedia 英語版の Falconidae を見ると現在でも Polyborinae の名称が痕跡として残っており、論文などでもまだ統一されていないようである。
属名が無効または改名となった場合にそれに基づく亜科の名称も自動的に変わるのか規則を知らないことと、文献では (Caracara属で記述しても) Polyborinae の名前を使っているものもあるので上記リストではかっこを付けて付記しておいた。
Gregory (2024) The correct family-group name for a clade of the Falconidae Leach, 1819, the Caracaras and Spot-winged Falconet
がその後この問題を再検討。Polyborus Vieillot, 1816 と Polyborinae Bonaparte, 1838 の名称は先取権の原則には則るが同名の原則には合わないので ICZN によって採用される決定が出されなければ利用を控えるのがよいだろうとのこと。
グアダルーペカラカラは子ヤギを襲う害鳥とされて (警戒心がなかったため) 簡単に駆除され、鳥類学者の標本採集が最後のとどめを刺して 1911 年絶滅とされる (wikipedia 日本語版より)。
英語版では 1900 年の採集が最後で、経緯は Abbott (1933) Closing history of the Guadalupe Caracara
1876 年には当たり前の種類だった。最後の採集者の Rollo Beck は 11 羽の群れを見かけてそのうち9羽を射止めたとのこと。それが最後の個体であったとは気づいていなかったが、その後の採集者は見かけることもなく、絶滅させてしまったことがわかった。
さすがにこの場合はあまりにも自明で他の要因すら探すこともできなかったのだろう。鳥類学者はあまり語りたがらないが、鳥類学者が標本を求めて絶滅させた種類は世界中いたるところにあったわけだ。
このような負の歴史も記述し、公開で読める形にしてあるのはさすがと感じる。
この Abbott (1933) の記述は#カンムリツクシガモの Nowak (1983) の記述に大変似ている。Nowak (1983) も採集者が鳥類学者の求めの結果絶滅させた可能性があることを暗に示唆したかったのではないだろうか。
アカノドカラカラはハチクマに興味のある方ならば新世界の対応種としてご存じかも知れない。ひいき目ではあるがハヤブサ類が進化してハチクマの役割を果たすのはやや無理がある感じで、機能的にはハチクマの方がずっとハチの子食に適応しているように見える。
あくまで冗談でハチクマカラカラと呼んでもよさそうだが (笑) 3種の生物名が並ぶといよいよ何かさっぱりわからないかも (新和名の提案ではない)。
そのため防御物質を出している説も長年提唱されてきたが現代的な研究で否定された (#ハチクマの備考 [ハチの幼虫を主食とする猛禽類・ハチの巣の蜜蝋を食べる鳥] 参照)。
属名に使われる Ibycter は ibukter 戦歌を歌うもの (Gk) 大声で叫ぶことから。
キノドカラカラと同属 (Daptrius) だったが分子系統解析で分離されてそれぞれ単形属となった。キノドカラカラの和名は別名 Yellow-throated Caracara に由来する。
シロハラカラカラの英語別名に Darwin's Caracara がある。シロハラカラカラはかつてはアンデスカラカラの亜種とされていた [高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) の時代にはすでに別種]。
ダーウィンフィンチの名前は有名だが、Charles Darwin にちなんだ動物名のリストがある: Milicic et al. (2011)
How Many Darwins? - List of Animal Taxa Named After Charles Darwin。
Darwin を含む鳥類の学名は意外に少ない。英名にはいくつか現れて、シロハラカラカラは Gould (1837) が記載したものだが Darwin が南米で観察したカラカラ。
昆虫には Darwin にちなむ種類が多数あるとのこと。
チマンゴカラカラをどの属に入れるかは見解が別れている。本稿のハヤブサ目のリストは Boyd を基本にしているが、この種は IOC に合わせた。Boyd は Phalcoboenus 属に含めている。
キノドカラカラ以降のカラカラ類は分類によって多少の違いがあり、例えば Gaudin は全部 Daptrius 属 にまとめている。この提案は Mindall et al. (2018) でなされたもの。別属にすると他の属の分岐年代より相対的に若くなりすぎるとの指摘したもの。
このあたりはそれぞれの属が生態などもどの程度違っているかなど総合的判断も求められ、南米の種で研究されていない部分が多いので分類再編には多くのリストが慎重で現状維持となっているのだろう。
Fuchs et al. (2015) の分子系統樹では Daptrius 属とキバラカラカラ Milvago chimachima の統合は可能だが Ibycter 属は系統が離れていて Phalcoboenus 属を認めた場合は単系統を作らないので統合できない結果となっている。
Ibycter が分離された経緯を確認できる結果となった。
少し分岐年代が古くなってしまうが、カラカラ属とそれ以外のすべてにまとめることは可能で Mindall et al. (2018) の提案に相当する。
Fuchs et al. (2015) の分子系統樹に忠実に従えばチマンゴカラカラ Milvago chimango は Phalcoboenus 属に帰属させないと Milvago 属が単系統にならない。
IOC と Boyd で違うのはこのチマンゴカラカラ1種のみなので、他のリストの傾向も見て属分類は IOC に合わせることにした。このあたりの結論にはタカ類同等の詳しい分子遺伝解析が必要になるのだろう。暫定的扱いとして見ておいて欲しい。
なお Phalcoboenus 属の各種の間の系統はかなり近い。南北のカラカラを1種とするならばこのグループも同程度の近さである。
Merge Milvago and Phalcoboenus into Daptrius (SACC 2024.12) によれば分布の "本家" の南米でも議論中。
分子系統的にも外観からも妥当だが、Milvago 属のタイプ種がキバラカラカラ Milvago chimachima Yellow-headed Caracara なのでチマンゴカラカラ Chimango Caracara を独立させて Milvago 属とすることはできない。
Phalcoboenus 属にまとめるか新しい属名を与えるかいずれかだが、後者の名前が存在しない状況では Phalcoboenus 属にまとめるか、さらにもっと大きく Daptrius 属とするかのいずれかが適切との議論。
チマンゴカラカラをタイプ種とする属があれば属名称の付け方も変わっていたかも知れない状況で、分子系統解析で属の割り振りが一意に決まるわけではなく属のタイプ種との兼ね合いもある事例。分子系統解析で得られた系統に対応するタイプ種を持つ属名がない場合には (提案者次第の部分もあるが)、新たに属名を提唱するよりも大きめの属にまとめられる傾向がある。
関連する系統の分岐年代との整合性の調整 (ある系統だけ細かく分けるのは不自然) も関係するので議論の分かれる可能性のある部分。例えばカラカラ類を細かく分けるならば Falco 属内の分岐年代と整合するかどうか問題となり得る。
Boyd もこれを受けて 2024.12.25 に Daptrius 属に統合とした (Daudin の判断と同様となった)。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) の時代にはフォークランドカラカラの知能的な行動やいたずらは知られていなかったらしくそれらしい記載はない。色の特徴だけで和名を付けているが現在フォークランドカラカラの名前が広く用いられているのでこちらでよいだろう。むしろ英名が素っ気ない。
アンデスカラカラは飼育個体のショーをご覧になられた方もあるだろう。この属はカラカラ類でも特に知的なグループと考えてよいかも知れない。
属名の由来は Daptrius は daptes 血を吸うもの (Gk)。黒い容姿からそのように思われたのだろうか。
Milvago は想像の通り milvus トビ -ago 似ている。
Phalcoboenus は phalkon, phalkonos ハヤブサ baino 歩く (Gk)。Brown and Amadon (1968-1969) は姿はハヤブサなのにニワトリのように地面を歩いて餌を探す。そんな猛禽を想像することは難しいと記している (The Key to Scientific Names)。
シロハラカラカラは学名も英名も「喉が白い」なのになぜかここだけシロハラになっている。腹も白いことも確かだが。
古い名前で オージュボンカラカラ (カラカラ) は北アメリカにも生息するのでこの絵や写真を目にすることも多いだろう。これがカラカラの代表ということではなく、今ではネットで簡単に世界のカラカラ類を見ることができるのでもっと多様なカラカラ類が存在することを見ていただきたい。
見る人が見ればハチクマとアカノドカラカラのような対応種が見つかるかも知れない (気のせいかも知れないが、とまっているアカノドカラカラの逆光のシルエットがハチクマのように見えることがある)。
カラカラ類もごく一部を除いて南米のみに生息する。Brown (1976) によればアンデスカラカラ属 Phalcoboenus はアンデスの沼地でズキンガラス (ハシボソガラス) や ワタリガラスに相当する役割を担っているとのこと。
アジアコビトハヤブサはかつては Polihierax 属に含まれていたが分離されハヤブサ族の方に帰属することになった。IOC など新しい分類を取り入れているリストでは分離されている。分子系統研究、形態研究からも支持されるとのこと (The Peregrine Fund のページに記載されているが、これに用いられている情報は必ずしも新しいものではない)。
Mindall et al. (2018) は分子系統研究によるものでそれぞれの単系統性を維持するためとあり、この表現で意図することは十分理解できる。
カラカラ類系統まではほぼ南米にとどまっていたハヤブサ目であるが、ハヤブサ亜科 Falconini で2系統に分かれ、ヒメハヤブサ族またはコビトハヤブサ族 Polihieracini と Neohierax 属から始まるハヤブサ族 Falconini で南米を離れてアジア・アフリカで分化したことがわかる。
ヒメハヤブサ族またはコビトハヤブサ族 Polihieracini は Falco属につながるグループとは異なる。このうち大部分を占める Microhierax 属はアジアで小規模な進展、Polihierax 属のコビトハヤブサ1種がアフリカに分布でいずれも小型種でこの系統が大きな広がりを見せることはなかった。
Falco 属とは遺伝的にはかなり離れている。
コビトハヤブサはシャカイハタオリドリ類の大きな集団巣の中で繁殖するとのこと (Brown 1976)。
ヒメハヤブサ類 (falconets) は枯れ枝などにとまって樹冠近くを飛ぶ昆虫を捉えるヒタキのような採食を行う。行動もモズ類に似ているとのこと。
barbets [キツツキ目、山崎・亀谷 (2019) では主に新称ゴシキドリ科 (Megalaimidae, Asian barbets) と思われるが (Brown 1976) の時代から分類概念が変化しているので参考までに挙げるにとどめる。barbets と呼ばれるものは世界他地域にも存在する] やキツツキの穴を利用し、自身で巣は造らない。
このため大木のある環境に依存している。他のハヤブサ類とは違って卵は白色で穴に産卵するため隠蔽色にする必要がないのだろう (Brown 1976)。
ハヤブサ類は自身で巣を造らず、ヒメハヤブサ類はキツツキ類の巣穴を使わざるを得ないため生息できる分布が限られ、それ以上の放散ができなかったのかも知れない。
Falco 属は全世界に分布することとなったが、その以前の系統で旧世界にも広がっていたことがわかる。世界の乾燥化で草地が広がり、生息に適した空間が広がったことが急速な種分化の要因と考えられている [Costantini and Dell'Omo (2020) にも記載されている]。
どのような経緯で旧世界に分布を広げたかはこの系統樹と現在の地理分布だけからはわからないが、Cenizo et al. (2016) によれば祖先系統と考えられる北米の化石種 Pediohierax ramenta があるそうで、北米を通じて旧世界に広がったのかも知れない。
参考: Becker (1987) Revision of "Falco" ramenta Wetmore and the Neogene Evolution of the Falconidae 属名由来は pedion 平原 hierax タカ (Gk)。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) では小型ハヤブサ類として シラボシハヤブサ [高野 (1973) ではシラホシハヤブサ] Spiziapteryx、Microhierax 属、コビトハヤブサ [高野 (1973) ではアフリカヒメハヤブサ] Polihierax、アジアコビトハヤブサ [高野 (1973) ではハイイロヒメハヤブサ] Neohierax、
チャイロハヤブサ Falco berigora をまとめていたが、現代の分子系統分類では複数の亜科、族のものが混ざっていたことになる。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969) ではこれに続くグループをチョウゲンボウ類としている。このグループに属する種は高野 (1973) ですべてチョウゲンボウの付く和名で記載しているのでどの種が対応するかは名前を見ていただければわかる。この次がチゴハヤブサ類で当時和名にすべてチゴハヤブサがついている点は同様。
その次が大型ハヤブサ類で、クロハヤブサ、ニュージーランドハヤブサ、オナガハヤブサ、ハイイロハヤブサ、ラガーハヤブサ、ラナーハヤブサ、ソウゲンハヤブサ、ワキスジハヤブサ [高野 (1973) ではセイカーハヤブサ] が含まれていて現代の分類に非常に近い。
最後にシロハヤブサおよびハヤブサの分類があり、最も進化の進んだ形と捉えていたのだろう。シロハヤブサ、タイタハヤブサ、アカハラハヤブサ [高野 (1973) ではアカムネハヤブサ]、クラインシュミットハヤブサ (現在はハヤブサの亜種の morph とされる。後述)、ハヤブサでまとめている。
同種とも考えられるほど遺伝的に近いシロハヤブサとワキスジハヤブサが別グループに分けられているのは分布の違いも考慮されていると思われるが、最後のグループは地理的にはかなり多様なので本来の意図はわからない。現代の分類と一番違っているのは主に南米のアカハラハヤブサであるが、容貌は確かにハヤブサ似ている。
現代の分類ではコウモリハヤブサ [高野 (1973) ではコウモリチゴハヤブサ] と色彩や音声も似ていて姉妹種の関係にあるとされる。これら2種はオナガハヤブサに近い (wikipedia 英語版) とあるが Boyd のまとめた分類ではそうなっていない。以下の SACC のリストを見て南米種だけで判断した記述かも知れない。
このリストを見ると Falco 属で南米種は少なく、ハヤブサ目発祥の地に戻ったものはあまり多くない。wikipedia 英語版の記述はこれら南米の定住性の種が単系統をなしている (渡ってくる種を除いて南米への1回だけの導入) ことを前提としているかも知れない。
wikipedia 英語版の参考文献に Griffiths (1999)
Phylogeny of the Falconidae inferred from molecular and morphological data
があり、一時代前の系統関係が出ていてハヤブサ科内はそれなりに現在に近いものになっている。
当時はタカ・ハヤブサの分子系統関係はまだわかっていなかったので外群にタカが用いられモリハヤブサ属 Micrastur がタカとハヤブサの中間に位置すると捉えられていたことも興味深い (属の学名の由来からも同様のことがうかがえる)。
#ミサゴ備考の [オウム類とハヤブサ類の近縁性はどのように解明されたか] によれば Sushkin (1905) の考えのようで、Jollie (1976, 1977) は否定していた。
Griffiths は当時の Falconiformes の単系統性を主張する立場だったのでモリハヤブサ属を意識的に中間に配置したと考えると納得が行く。分子系統から決定的証拠が出されるまで影響力の大きかった Griffiths の考えが業界では支配的だったのかも知れない。
この論文でも形態学に関する Becker (1987), Kemp and Crowe (1990) は引きつつも、より広範な研究を行っていた Jollie (1976, 1977) を無視している。(発表された雑誌も創刊まもなくだったこともあり) そもそも全然知らなかったのか、あるいは確執でもあったのだろうか。
関連して、南米の種のリストは A Classification of the Bird Species of South America (South American Classification Committee, SACC) で最新状態に維持されている。
SACC は 2002 年にアメリカ鳥学会 (AOS) と協力を始めたが 2023年11月に AOS がエポニム (eponymous name。この場合は人名にちなむ名前のこと) を排除することを決め、SACC が英名に係ることができなくなったため関係を打ち切り、現在は IOC の地域メンバーとして世界の鳥の分類に携わることになった。
ここで示したチョウゲンボウグループ (kestrel group) に含まれる種は Costantini and Dell'Omo (2020) による。
Brown and Amadon (1968-1969) は亜属 Tinnunculus を提案。
アフリカのチョウゲンボウグループには亜属 Dissodectes (Snow 1978) が提案され、電気泳動や羽毛のタンパク質の解析からも支持されるとのことだが資料が古いためここでは特に分離しないでおく。
Brown (1976) でもこれら亜属は触れられていない。
Fuchs et al. (2015) の分子系統樹ではこれらをすべて含めると単系統にならない。特にアメリカチョウゲンボウの位置は Tinnunculus に相当するグループとは別系統になる。もしアメリカチョウゲンボウを旧世界のチョウゲンボウグループに近縁として含めるとチョウゲンボウグループは実はもっと大きいかも知れないとのこと。
アカアシチョウゲンボウ、ニシアカアシチョウゲンボウについても同じことが言え、分子系統的にはアメリカチョウゲンボウの方に近いグループになる。
亜属 Tinnunculus の概念を取り入れるならばこのリストでヨコジマチョウゲンボウからオーストラリアチョウゲンボウまでを含めば単系統となる。ヒメチョウゲンボウもこの系統に入るが、この中では少し離れている。ヨコジマチョウゲンボウも同様に少し離れている
[もっともタカ類ほど精度の高い系統樹ではないので、全ゲノム解析などが進めば包含関係が少し変わってくるかも知れない点は少し注意して見ておいて欲しい。タカ類で言えば Mindall et al. (2018) に相当する精度の系統樹と言える]。
メジロチョウゲンボウの和名は英語別名の White-eyed Kestrel に由来。
モーリシャスチョウゲンボウ、インド洋離島のチョウゲンボウ類固有種の起源については #チョウゲンボウの備考 [離島のチョウゲンボウ類と超希少種の保全] を参照。
セーシェルでは 1940-1950 年代ネズミの駆除のためにメンフクロウが放たれたが、在来種も食べてしまうため現在では駆除に報奨金が支払われているとのこと (Introduced Land Birds)。
ネズミの個体数が多いので目に見えるほどの効果はなく、むしろ飛翔力が強いのでネズミがおらず、海鳥の営巣する離島にも飛んで食べてしまうとのこと。
セーシェルチョウゲンボウにとっても脅威となっているとのこと (人為導入された猛禽類が別の猛禽類を脅かしている事例)。
オーストラリアチョウゲンボウの英名が Nankeen Kestrel は奇妙な気もするが、これは南京産の黄色っぽい織物の色に由来するとのこと。Australian Kestrel の別名もある。
Brown (1976) ではエレオノラハヤブサ [高野 (1973) ではオオチゴハヤブサ] と ウスズミハヤブサ [高野 (1973) ではウスズミチゴハヤブサ] は渡りも特殊であり、ある意味で「水辺のハヤブサ」とも呼べるとしている。ミサゴ以上に水辺に依存していると述べている。
前者は地中海から北アフリカで繁殖するが沿岸での繁殖はごく一部で、ほとんどは地中海の島で繁殖する。
東の個体群は紅海に沿って見られ内陸も通るがマダガスカルに渡る。西の個体群は内陸を通る。
秋の小鳥の渡り時期に合わせて夏の終わりから繁殖を始める。ひなの巣立ちがハチクマ以上に遅い珍しい渡りの猛禽類で、近年のトラッキング調査で渡りルートなどもよく調べられている。イタリアのサルジニア島の 14-15 世紀の女王 Eleonora d'Arborea にちなむ。
9月に入ってタカの渡り観察途中に餌を運んでいるハチクマが観察され、こんな遅い時期に子育てしていて大丈夫なのでしょうかとか問われることがあるが上には上がいるものである。
後者は中東やアフリカ東部沿岸部など (他にも局所的に内陸に分布) で繁殖してやはりマダガスカルに渡る。海沿いで待ち構えて渡りの鳥を狙うという。
Brown (1976) の時代にはエレオノラハヤブサは紅海に沿って渡ると考えられており、そのような渡りルートが載せられていた。
両者ともになぜマダガスカルで越冬するのかなど謎が多い。繁殖地では小鳥を食べるが越冬地では昆虫類を中心に食べるという。昆虫食のみでは卵やひなの発育に必要な栄養分 (特にカルシウムや必須アミノ酸など) の比率が脊椎動物と異なるため、繁殖地では子育てのため小鳥を主に食べる必要があるのだろう。
主に昆虫食の猛禽類の食生活も同じように見ると面白い。例えばハチクマもひなにとってあまり好物ではないかも知れないが脊椎動物を与える必要がある - 実はおそらく極めて重要 -のは同様の理由からだろう。
エレオノラハヤブサの渡り途中の食性: Samraoui et al. (2022) Diet of breeding Eleonora's falcon Falco eleonorae in Algeria: Insights for the autumn trans-Mediterranean avian migration
2010-2012 年の調査では食物と渡る鳥の種類が極めてよく一致していた。
後に食べるために貯めてある事例もあり写真が紹介されている。渡りが集中する時期に集中的に捕獲しているらしい。渡りのピークは断続的に起きるので鳥類食のハヤブサ類が貯食行動を行ってもまったく不思議でなかった。
このリストでコウモリハヤブサからアフリカチゴハヤブサまでは単系統をなし、このグループをチゴハヤブサグループと考えてよさそうである。ニュージーランドハヤブサとオナガハヤブサは他と少し離れてハヤブサおよびシロハヤブサ類の最初の分枝に入れることができる。
オナガハヤブサの共同狩猟については #ハヤブサの備考 [オナガハヤブサの共同狩猟] も参照。
同じくこのリストでアカガシラチョウゲンボウ [高野 (1973) ではアカガシラコチョウゲンボウ] から ワキスジハヤブサ [高野 (1973) ではセイカーハヤブサ] は単系統をなしており、これらをハヤブサおよびシロハヤブサ類と考えてよさそうである。シロハヤブサ類はこの中に含まれ、特に分かれた系統はなしていない。
アカガシラチョウゲンボウ [高野 (1973) ではアカガシラコチョウゲンボウ] の英名の Red-necked Falcon は学名 Falco ruficollis Swainson, 1837 由来。この種小名は現在は亜種に使われている。Falco chicquera Daudin, 1800 と同種とされこちらの記載の方が早いため種学名は後者だが英名に由来を残すことになった。
途中のコチョウゲンボウ、{ハイガシラチョウゲンボウ + ハイイロチョウゲンボウ}、チャイロハヤブサはそれぞれ少し独特で、それぞれ {チゴハヤブサグループ + ハヤブサおよびシロハヤブサ類} の前の分枝にあたる。
これらでまとまった系統は作らず、もし {チゴハヤブサグループ + ハヤブサおよびシロハヤブサ類} とまとめて単系統を作るならばアカアシチョウゲンボウ、ニシアカアシチョウゲンボウはこちらのグループに含めることになる。アメリカチョウゲンボウを含めても単系統になるが、かなり離れているのでアメリカチョウゲンボウのみを個別系統とすることも可能である。
名前から想像されるようにアメリカチョウゲンボウがチョウゲンボウがほぼ同種でユーラシアとアメリカで分けられたものに相当するわけではない。
バーバリーハヤブサ Falco pelegrinoides は IOC 14.1 = 13.2 等の世界の主要リストではハヤブサの亜種とされる。Boyd は別種としており、ここでは暫定的に含めておいた。
wikipedia 英語版によれば系統学的種概念は満たしていないが、生態・形態などは種に相当する違いがあり、生殖隔離も見られることから生物学的種概念を満たすかどうかの議論の対象となり得る。
種分化の機構はシロハヤブサとワキスジハヤブサの関係 (#シロハヤブサの備考参照) と同様と考えられる (ここではバーバリーハヤブサがワキスジハヤブサに相当する)。
単系統をなさないのは古い時代の不完全な系統分離の影響とも考えられる。
後述の Johnson et al. (2023) の最新解析では全体として単系統ではないが単独で Indomalayan 型となっている。中国とインド・スリランカの個体群は異なる系統を作るとある。
高野 (1973) = Lloyd and Lloyd (1969)、Brown (1976) には アカハラハヤブサ [高野 (1973) ではアカムネハヤブサ] とハヤブサの間 (シロハヤブサおよびハヤブサのグループ) にもう1種の記述があり、
アルゼンチン南部とチリのクラインシュミットハヤブサ Falco kreyenborgi Keinschmidt's Falcon (Pallid Falcon) の名称が出ているが、これはその後ハヤブサの南米亜種 cassini の "morph" と判定された:
Ellis and Great (1983) The Pallid Falcon Falco kreyenborgi Is a Color Phase of the Austral Peregrine Falcon (Falco peregrinus cassini)。
Peters "Checklist od Birds of the World" (1931-1986) では別種扱い。
ハヤブサ亜科 Falconini 以降の属名の由来は、
Polihierax は polios 灰色 hierax タカまたはハヤブサ (Gk)、
Microhierax は mikros (ごく) 小さな hierax タカまたはハヤブサ (Gk)、
Neohierax は neos 新しい hierax タカまたはハヤブサ (Gk)
とあまり面白いものはない。
種小名ではモモグロヒメハヤブサ [高野 (1973) ではクロアシヒメハヤブサ] の fringillarius はアトリ類の学名のわかる方には理解しやすい。fringilla フィンチ 由来で、フィンチに似た小型の意味。
ボルネオヒメハヤブサ [高野 (1973) ではシロガシラヒメハヤブサ] の latifrons は latus 広い frontis 額。
アジアコビトハヤブサの insignis は驚くべき、特別ななど (#コチョウゲンボウの日本で記録される通常の亜種と同名)。記載時学名は Polihierax insignis Walden, 1872 でコチョウゲンボウの亜種学名と衝突しなかった。
キツネチョウゲンボウの alopex はキツネ (Gk, 色を示す)。ホッキョクギツネのかつての属名が Alopex であったが Vulpes属に統合された。英語の alopecia (脱毛症) も同系語だが、毛の抜けたキツネやキツネに関係した毛の抜ける病気などの語源があるとされる (Online Etymology Dictionary)。
ミナミアフリカチョウゲンボウの rupicolus は岩に住む (英名と同じ)。メジロチョウゲンボウの rupicoloides はそれに似たもの。
オーストラリアチョウゲンボウの cenchroides は kenkhris チョウゲンボウ に似た (Gk)。
アメリカチョウゲンボウの sparverius は #オオジュウイチを参照。
ハイイロチョウゲンボウの ardosiaceus はフランス語 ardoise (スレート灰色の) から。
チャイロハヤブサの berigora はアボリジニの呼称 Berigora (おそらく鳴き声由来) から。
アカハラハヤブサ [高野 (1973) ではアカムネハヤブサ] の deiroleucus は deire 喉 が白い (Gk)。
ミナミチゴハヤブサの severus は 厳しい、容赦ないなど (英語 severity, おそらく severe も同系: Online Etymology Dictionary)。
ウスズミハヤブサ [高野 (1973) ではウスズミチゴハヤブサ] の concolor は同じ色の。
アカガシラチョウゲンボウ [高野 (1973) ではアカガシラコチョウゲンボウ] の chicquera はヒンディー語の chicquera (ハンターの意味で、タカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] の英名 Shikra と同じ意味)。
タイタハヤブサの fasciinucha は fascia 帯 nuchus 後頸 (英 nape)。
ラナーハヤブサの biarmicus はおそらく「ひげのある」意味で用いられた (#ヒゲガラの備考参照)。
ラガーハヤブサの jugger はヒンディー語の jaggar でラガーハヤブサのオスを指す。
(以上の学名解説は The Key to Scientific Names より。全種ではなく気になったもののみを調べた)。
コウモリハヤブサ [高野 (1973) ではコウモリチゴハヤブサ] と類似の アカハラハヤブサ [高野 (1973) ではアカムネハヤブサ] の全ゲノム解析による遺伝的多様性が調べられている: Martin et al. (2024) Contrasting genomic diversity and inbreeding levels among two closely related falcon species with overlapping geographic distributions
コウモリハヤブサは個体群サイズも大きく遺伝的多様性も高いがアカハラハヤブサは多様性が小さく、大陸と島の種の関係に似ている。アカハラハヤブサが個体数ボトルネックを経験した影響も現れていると考えられる。
Catanach et al. (2024) The Complete Genome Sequences of 30 Species of Falcons (Falconiformes, Aves) がハヤブサ目 30 種のゲノム解読結果を報告している。いずれも野生個体から。
腕力のある方は系統解析など試みていただきたい。
ハヤブサと近縁種シロハヤブサの遺伝的関係などは#シロハヤブサの備考参照。ハヤブサ類の交雑地域のモンゴルでの研究で常染色体では交雑が見られるものの、ハヤブサに特有の Z 染色体遺伝的変異が多数あり別種となる要因となっている可能性が指摘されている。
[日本のハヤブサ類の由来]
分子系統分類が非常に長くなったので別項目とした。現生種の分子系統分類および化石種の証拠から、現生種のハヤブサ目は南米が起源であることは疑いない。
それ以前の化石は世界の他の場所でも見つかっているのでハヤブサ目を生んだ系統はかつて世界に分布しており最初の起源はわからないが、現生種として生き残ったのは南米という意味である。
その後南米に長らくとどまっており北米への進出はわずかだった。
そしてハヤブサ亜科 Falconini を生み出す系統がおそらく北米経由でユーラシアに分布し、ユーラシアとアフリカで発展を遂げた形になっている。北米には当時の系統は現存していない。
日本で繁殖するハヤブサ類は主に3回にわたってやってきたと考えることができる。
小型のチョウゲンボウグループ (チョウゲンボウ)、チゴハヤブサグループ (チゴハヤブサ)、そして大型のハヤブサグループ (ハヤブサ) である。
チョウゲンボウはグループの起源はおそらくアフリカで大陸から東に分布を広げた模様。チゴハヤブサグループは南米に広く分布しアフリカ、オーストラリアにも分布するが日本にやってくるチゴハヤブサはアフリカ由来でやはり大陸から分布を広げたものだろう。
これらを考慮するとこの2系統はアフリカで主に種分化したものがヨーロッパや中東から東に分布を広げたものがやってきているらしい。
ハヤブサは後述のように世界分布を遂げたが日本のグループは北米型に縁があり、ユーラシアからよりもベーリング海峡やアリューシャン諸島を経てやってきたのだろう。
世界分布は違いがあるが、ハイタカグループの (新しい名前で表現して) ツミ属またはアカハラダカ属 Tachyspiza、ハイタカ属 Accipiter 、オオタカ属 Astur が3回にわたって世界に拡大した経緯とよく似ている。
ハイタカグループのこれらの属は形態・習性が少しずつ違って少しずつ違った獲物を捕るわけだが、ハヤブサ属 Falco でも全体で単系統でまとめられているものの、形態・習性が少しずつ違う系統が同じように複数回にわたって種分化と世界進展を遂げたと考えるとわかりやすいように思える。
日本で繁殖しない種類は渡り途中にかすめるものか越冬地であるが、ニシアカアシチョウゲンボウ、アカアシチョウゲンボウは基本はアフリカ型で長距離渡りをして北から東に分布を広げてごく少数が日本をかすめるようになったもの。ヒメチョウゲンボウは系統分類ではチョウゲンボウグループの冒頭付近だが、アフリカで越冬しユーラシアに繁殖分布を広げた典型的なチョウゲンボウ類の進出パターンである。
コチョウゲンボウも類似種 (ハイイロチョウゲンボウ、ハイガシラチョウゲンボウ。ニシアカアシチョウゲンボウ、アカアシチョウゲンボウも少し遠いが類似系統にあたる) の起源はアフリカが考えられ、北に分布を広げたものがユーラシアに広がり、ヨーロッパから北米にも広がったと考えられそうに見える。
シロハヤブサ、ワキスジハヤブサはハヤブサグループに属し、中央アジアの乾燥地帯に適応し、東の個体群からシロハヤブサが極地に進出したものがやってきていると思われる。
チョウゲンボウグループ、チゴハヤブサグループはアフリカが中心で、ハヤブサグループも最初の由来はアフリカのようだが早期に世界に分布し、ハヤブサそのものの起源はややわからないものの日本のハヤブサは北米に近い。北米に分布したソウゲンハヤブサと (現在のハヤブサの亜種間に相当する関係ではないが) ハヤブサの起源に関係があるかも知れない。
ハヤブサ目にしてもハヤブサ属 Falco にしても南米やアフリカなど日本から地域で分化を遂げてきたもので、日本で馴染みの種類の大半はユーラシアか世界に分布を遂げた分布の広いものに限られているようである。これらは分散能力の高いものばかりなので、日本のハヤブサ類だけを見て「ハヤブサ観」を熟成してしまうと全体像を見誤る可能性がある。
この点はアジアで分布を広げた種類も含まれるタカ類とは少し違う部分がある。
特に南米ではタカに類似したハヤブサ類 (Micrastur 属)、ハヤブサ類に似た特徴を持つタカ類 (#トビの備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] の Harpagus 属) がいずれも存在し、分類学者がタカ類・ハヤブサ類は連続的なものと考えても不思議でない状況だった。
極東で馴染みのハヤブサ類の種類は西からやってきた場合も東からやってきた場合も分布の終端にあたり、世界のハヤブサ類に多くの種類があるのに日本では図鑑の図版1-2ページに収まる種類数しかいないのはこのような分布事情を反映しているのだろう。
ハヤブサ類に近縁とされるオウム類はハヤブサ類より以前に世界に分布していたことが化石証拠から知られているが、北半球の多くの地域で消え去ってしまったらしい。初期の放散の後に海洋による隔離が進んだ後に分布を広げることは難しかったのだろう。
Fuchs et al. (2015) の分岐年代を見るとハヤブサ類が日本に分布を広げたのは 100 万年前ぐらいの時期と最近である。ハヤブサ類自身の大規模な種分化 (主にアフリカ) は 400-700 万年前ぐらい。
ハヤブサ類より後発のスズメ目の方が先に到着していたことになる。
またこれまでの進化系統を振り返ってみると、もしカラカラ類などの系統が絶滅していれば我々はハヤブサ類はアフリカで進化したとみなすであろう (タカ類はそのように考えられている)。現生種を見て物事を考える限界とも言える。
[亜種と系統]
ハヤブサは汎世界的に分布し、18 亜種が認められている (IOC)。
wikipedia 英語版では 19 亜種とあり分布地図がある。
違いはオーストラリア南西部に submelanogenys を認めるかどうかで、HBW/BirdLife (2023), Clements (2023) は亜種として認めているが、多くは macropus のシノニムとしている。
Peregrine Falcon Subspecies (Lauren Weiss) に19 亜種の解説がある。
Lauren Weiss and Margaret Krone の
The UMass Amherst Libraries Falcon Curriculum: An Open, Common Core PreK-12 Curriculum on Peregrine Falcons
のマサチューセッツ大学の公開講義本の一部で、本全体もダウンロードできる。2003 年に大学の図書館屋上で繁殖を始めて 2012 年にライブカメラ中継を始めたことがきっかけで始まった講義科目とのこと。
日本に生息する主な亜種は japonensis (北東シベリアからカムチャツカ、日本に分布)。
北硫黄島、硫黄島で繁殖するとされていた亜種シマハヤブサ furuitii (日本の採集家 Inukiti Furuiti 古市犬吉 に由来) は 1937 年以降記録がない。
記載時学名は Falco peregrinus fruitii だったが訂正された模様。
献名が明示されているため誤植と解釈されたとのことらしい (Mayr and Cottrell 1979)。
Checklist of Japanese Birds (7th ed.)
に議論や解説があり、ICZN Article 32.5.1: supported by internal information の同一文献内の情報に基づく修正に該当するとのこと。
ハヤブサの亜種の中でウスハヤブサ calidus はユーラシアのラップランドから北東シベリアのツンドラ地帯で繁殖し、長い渡りをする (亜種名は「暖かい」の意味だがこれは越冬地で記録されたため)。この亜種は南半球オーストラリア近くを含む広範囲で越冬し、日本も通過していると思われる。
可能性のある写真も撮影されて図鑑や書籍、Web にも掲載されているが、同定根拠が示されていないため日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では検討亜種扱いとなっている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)に他に掲載されている亜種はオオハヤブサ pealei (アメリカの博物学者 Titian Ramsay Peale に由来; 英名 Peale's Falcon アリューシャンからワシントンにかけて分布)、
アメリカハヤブサ anatum (「カモの」の意味 (< anas); アメリカ北部のツンドラ以南からメキシコに分布) および亜種不明のものである。
検討亜種に tundrius (ツンドラの) ツンドラハヤブサ が含まれている。
オオハヤブサは越冬地オレゴン州で記載されたもの。
参考までにフィリピンのハヤブサ亜種 ernesti の写真 Peregrine falcon ssp. ernesti (Richard C. Ruiz 2024.9.24)。
かなり暗色のハヤブサが見られるようで、Peregrine Falcon (Ronet Santos 2019.10.10), Peregrine Falcon (Ronet Santos 2019.10.10)。亜種は判定していない。
Peregrine Falcon with a prey (Bo Apostol 2024.12.8) 同亜種の狩りの画像。
フィリピンのリストでは比較的まれな種類で、留鳥と越冬種で亜種 ernesti と calidus を認めている。
ハヤブサ亜種は渡りをするものとして我々から見て北方のもののみが紹介されがちだが南方にも目を向けると面白い発見があるかも。
Peregrine Falcon (Falco peregrinus) (Kevin Manila 2025.1.17) 冬季の写真だが亜種は?
初野 (2012) Birder 26(9): 22-23 にハヤブサの亜種の検討が述べられている。ツンドラハヤブサ、アメリカハヤブサ、ウスハヤブサも取り扱われている。
渡辺 (2005) Birder 19(10): 59 にアメリカハヤブサが 1993 年に観察され、標識から 1991 年アリゾナで捕獲・標識されたものであることが明らかになった事例が出ている。船に乗って移動した標識者の解釈が紹介されている。
参考までにロシアの記録を見ておくと、Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" ではシベリアで4亜種:
・calidus: ツンドラで最も明るい色で褐色味や黄土色味はないか極めて弱い
・harterti: ヤナ川盆地東部のツンドラ。より暗色で下面に黄土色味があり脇腹は灰色
・亜種 peregrinus: より南部の森林地帯。北方の亜種より暗色で下面に黄土色味か褐色味がある
・japonensis: 基亜種よりさらの東方でさらに暗色。下面の黄土色味や褐色味が強い
Glushchenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraya: Kratkij Faunisticheskij Obzor" では沿海地方では japonensis が繁殖。harterti は渡り中に見られる。
pealei (オオハヤブサ) は標本記録にあるものが確実なもので、冬季はいずれの亜種も可能性があるが証拠が必要 (野外観察で確実かどうかは検証が必要の意味だろう) とある。
前述の Weiss and Krone の解説 (+ wikipedia 英語版) ではオオハヤブサは基本的に留鳥で、島内部よりも外洋に飛び出てウミスズメ科を飛行中に捕食することに特化している。
翼開長より低い水面すれすれを飛ぶことで揚力を得て空気抵抗を減弱している (ground effect)。
特に好みの種類はエトロフウミスズメやウミスズメとのこと。陸から遠く離れて捕食して飛びながら食べるか遠くの陸へ持ち帰るとのこと。おそらくこの食性と寒冷気候に対応してハヤブサ他亜種より中央の趾が短い。
この記述によれば内陸はあまり好みでないかも知れない。
オオハヤブサは2系統に分かれ、アリューシャン列島からアラスカ半島外部の島に生息し、胸の上部やそのう部位、喉に丸いかしずく状の斑点があり、下面は汚れた白色で灰色っぽい。背中は濃いスレート色。足は他の亜種より明るい黄色。
もう1系統 (Haida Gwaii) はアラスカ南西部沿岸で斑点や縞模様はそこまで明瞭でない。
Dement'ev and Gladkov (1951) によればロシア名はアリューシャンハヤブサまたは黒ハヤブサ。
コマンドル島では "黒いタカ" (chernyj yastreb) と呼ばれているとのこと。日本は函館への漂行が紹介されている。繁殖地ではほぼ完全に海鳥を食べて生活している。
島の海岸から 50 km 離れたところでアメリカヒバリシギを飛行中に捕らえて食した観察例がある。
他にもヌマライチョウ、カイツブリ類、カモメ類、特にオナガガモやクロガモなどのカモ類、各種シギ類、特にウミスズメ科でエトピリカ、ウミスズメ、アメリカマダラウミスズメを捕食する (記述からここまでがロシアに近い分布のオオハヤブサを指していると思われる)。
場所によりウミスズメ類のコロニーのみで捕食。沿海地方で採集された個体の胃にはエトロフウミスズメ類が入っていた。カワガラスを襲った例もある。コマンドル諸島からカムチャツカ沿岸で秋に特にウミスズメ類、時にカモやフルマカモメを食べる。
Dement'ev and Gladkov (1951) は日本のハヤブサを知らなかったのか分布に出てこない。
Artukhin (2002, 2024 再掲) Materials on the peregrine falcon Falco peregrinus distribution on the Kurile Islands (pp. 2787-2794) に千島列島のハヤブサの情報がある。
それほど高緯度ではないが、シジュウカラガンの放鳥で有名になったエカルマ島では 10 つがい以下が繁殖しているとのこと。ある程度詳しい情報は南部の島に限られるが千島全体で繁殖していると考えられる。
Nechaev (1998) によれば海鳥のコロニーのそばにのみ生息して、コロニーのない島では繁殖しない。
エカルマ島のように内陸で営巣するものもあって個体数を見積もるのは難しいが 50 つがいぐらいが繁殖しているのではないか。
以下記載時学名、基産地は Avibase。その他の亜種記載もわかる範囲で含めた。リストによっては Barbary Falcon (バーバリーハヤブサ) が別種にされたことがあったが分子系統研究で一致度が高く同種となった。Barbary Falcon に対応する亜種も含んでいる。
・Falco Peregrinus Tunstall, 1771 o (原記載) 基産地 Northamptonshire, England (英国)
・Falco japonensis Gmelin, 1788 o (原記載) 基産地 Japan (実際は海上) 亜種ハヤブサ
・Falco orientalis Gmelin, 1788 * (原記載) 基産地 Japan (実際は海上) = japonensis
・Falco calidus Latham, 1790 o (原記載) 基産地 India. Migrant (インド。渡り鳥) ウスハヤブサ
・Falco pelegrinoides Temminck, 1829 o (原記載) 基産地 Nubia (ヌビア。エジプト南部アスワンあたりからスーダンにかけての地方) Barbary Falcon, バーバリーハヤブサ
・Falco peregrinator Sundevall, 1837 o (原記載) 基産地 At sea in lat. 6° 20' N. between Ceylon and Sumatra, 70 Swedish miles off the Nicobars (スリランカとスマトラ島の間の海上)
・Falco macropus Swainson, 1838 o (原記載) 基産地 Tasmania (タスマニア島。オーストラリア)
・Falco Anatum Bonaparte, 1838 o (原記載) 基産地 Great Egg Harbor, New Jersey (ニュージャージー州) アメリカハヤブサ
・Falco minor Bonaparte, 1850 o (原記載) 基産地 South Africa (南アフリカ) 一時期名称変更され perconfusus
・Falco punicus Levaillant, 1850 基産地 アルジェリア? = brookei
・Falco leucogenys Brehm, 1854 (原記載) 基産地 Hummelshain, valley of the Saale; Germany. Migrant (ドイツ。渡り鳥) = calidus
・Falco radama Hartlaub, 1861 o (原記載) 基産地 Madagascar (マダガスカル)
・Falco babylonicus Sclater, 1861 o (原記載) 基産地 Oudh, in India, Babylonia and Abyssinia. Type from Oudh (インド北部。英国東インド時代) (Barbary Falcon 時代はその亜種)
・Falco Cassini Sharpe, 1873 o (原記載) 基産地 Straits of Magellan and Chile (マゼラン海峡とチリ)
・Falco Brookei Sharpe, 1873 o (原記載) 基産地 Sardinia (サルディーニャ島。イタリア)
・Falco tscherniaievi Severtzov, 1875 * (参考) 基産地 Aul'e-Ata = babylonicus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Falco communis var. pealei Ridgway, 1874 o (原記載) 基産地 Sitka, Alaska and Oregon [アラスカとオレゴン州。Dement'ev and Gladkov (1951) では越冬地オレゴン州と記述] オオハヤブサ
・Falco peregrinus cornicum Menzbier, 1882 * = brevirostris の黒色型 (Dement'ev and Gladkov 1951) = peregrinus
・Falco peregrinus brevirostris Menzbier, 1882 [Dement'ev and Gladkov (1951) では 1888] = peregrinus
・Falco ernesti Sharpe, 1894 o (原記載) 基産地 Mt. Dulit, Sarawak (ボルネオ島北部。マレーシア)
・Falco peregrinus germanicus Erlanger, 1903 基産地 ドイツ東部 = peregrinus
・Falco barbarus arabicus Erlanger, 1903 (原記載) 基産地 Lahadsch = Lahej, near Aden (現在イエメン) = pelegrinoides Barbary Falcon 時代は基亜種のシノニム
・Falco peregrinus riphaeus Buturlin, 1907 基産地 Urals (ウラル山脈) = brevirostris (Dement'ev and Gladkov 1951) = peregrinus
・Falco peregrinus harterti Buturlin, 1907 基産地 Lower Lena to Anadyr, common on the Kolyma (レナ川下流からアナディリ、コリマ地方) = japonensis または calidus
・Falco peregrinus ussuriensus Buturlin, 1907 * 基産地 ロシアのウスリー地方 = leucogenys (Dement'ev and Gladkov 1951) = japonensis?
・Falco caucasicus Kleinschmidt, 1907 (原記載) 基産地 Northeastern Caucasus (北コーカサス) = brookei
・Falco rudolfi Kleinschmidt, 1909 (原記載) 基産地 Hakodadi, northern Japan (函館) = pealei
・Falco peregrinus rhenanus Kleinschmidt, 1912 基産地 = peregrinus
・Falco peregrinus submelanogenys Mathews, 1912 (原記載) 基産地 Southwest Australia. Type from Bokerup according to Mathews (オーストラリア南西部) = macropus
・Falco peregrinator atriceps Hume & Menzbir, 1916 * = caucasicus (Dement'ev and Gladkov 1951) = peregrinus
・Falco peregrinus fruitii Momiyama, 1927 o 基産地 Isino-mura, San Alessandro Islands = Kita Iwo Jima (北硫黄島) シマハヤブサ
・Falco peregrinus perconfusus Collin & Hartert, 1927 * (参考) minor の新名
・Falco kreyenborgi Kleinschmidt, 1929 基産地 Based on a cage bird in the Zoo at Miinster, Germany, which was said to have come from Punta Arenas, Chile (動物園の鳥でチリのプンタアレナス由来とのこと) = cassini
・Falco peregrinus pleskei Dementiev, 1933 基産地 Great Shantar Island, Sea of Okhotsk (オホーツク海) = japonensis
・Falco peregrinus kleinschmidti Dementiev, 1934 (原記載) 基産地 Olekminsk, southern Yakutia (ヤクーチア南部) = japonensis
・Falco peregrinus caeruleiceps Stegmann, 1934 基産地 Gyda River, northwestern Siberia (シベリア北西部) = calidus
・Falco peregrinus gobicus Stegmann, 1934 * 基産地 Turkestan = babylonicus (Dement'ev and Gladkov 1951)
・Falco peregrinus nesiotes Mayr, 1941 o (原記載) 基産地 Tanna Island, New Hebrides (ニューヘブリディーズ。現在バヌアツ)
・Falco peregrinus madens Ripley & Watson, 1963 o (原記載) 基産地 Provoca O, Brava, Cape Verde Islands (カーボベルデ。アフリカの西)
・Falco peregrinus tundrius White, 1968 o (原記載) 基産地 Adelaide Peninsula, Northwest Territories, Canada (カナダ北西部) ツンドラハヤブサ
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。
* は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
和名は日本で話題となる亜種のみボールドで付けてある。
perconfusus は minor が Falco nisus minor Behher, Borkhausen & Lichthammer, 1800-1811 (ハイタカが Falco 属時代に付けられた "小さなハイタカ" の意味) の用例があるとして改名されたもの。
ハイタカが Falco 属から分離されてまた使えるようになったものらしい。minor は現在有効なハヤブサ亜種名になっている。
Dement'ev and Gladkov (1951) では leucogenys (1854) を有効とし、harterti (1907), ussuriensus (1907), caeruleiceps (1934) をシノニムとしていた。この包含関係であれば leucogenys に先取権がある。
多くの著者が calidus (1790) のシノニムとしている記述がある。
kleinschmidti は "ヤクーチアハヤブサ" に相当する名前で記載。現地語で moksokol とのこと。羽衣は anatum に非常によく似ているとのことで、同一かどうかはさらに調べる必要があると記していた ("ヤクーチアハヤブサ" は繁殖地記載なので渡り途中などの問題は少ない)。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば pleskei をサハリンの、または小型のハヤブサ に相当する名前で記載していた。現在では minor (当時 perconfusus) は同様に小さいが南アフリカで地域も違うので別亜種とした。タカブシギとマガモを襲った例が挙げられているとのこと。
研究者によっては pleskei の存在を認めていないが、pealei とは分布域が異なるので動物地理学的には同一とは認めがたいとの見解。
そして brevirostris を "ロシアハヤブサ" に相当する名称で亜種と認めていた。確かに (japonensis は知られていなかったとして) calidus 以外のこの地域の亜種は記載されていないのでヨーロッパとシベリアが別亜種と考えればこの亜種が早い記載となる (cornicum の扱いはよくわからないが有効な学名ではなかったのかも)。
Dement'ev and Gladkov (1951) は calidus は知っていた。Yamashina (1931) を引用し、シベリア型が "calidus" と考えられていたことは把握していた模様。
函館の Falco rudolfi については pealei (現在の概念ではオオハヤブサ) が日本や、ロシア沿海地方、カムチャツカ、? 付きで満州にも漂行していると考えていた。
同一か判定しかねる状況で上記のような区分になったものと考えられる。japonensis については知らなかったか、あるいは有効と認めていなかったのかも。
Dement'ev and Gladkov (1951) は亜種を比較的細かく分けていたが、その後北極圏を除くユーラシアの大部分が peregrinus にまとめられ、北極圏は別、ユーラシア東端部も別と認識されたものと考えられる。
記載順の通り japonensis, calidus のように判定の難しいものが早い時期に記載され、しかも多くが渡りをするため困難な状況となっていた模様。
peregrinus と japonensis が大陸の東西端で記録されているためユーラシア中緯度に亜種を認めるならばこれらは外せないことになる。後述の Vaurie (1961) も最小限の分割の立場からこの2亜種を用いたと考えられる。
この分割の場合は japonensis の範囲をどこまでと認めるかの問題となるのだろう。
harterti を認めるかどうかは確かに自明ではない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では世界で 16 亜種、シベリアに4亜種で harterti も認めている。japonensis と peregrinus はバイカル湖付近で接している考え方になっている。
これは大陸東部の中緯度帯の亜種を japonensis のシノニムとする考え方に近い。中緯度で東西2亜種ならば (境界をどこにするかの問題はあるが) このような考えにならざるを得ないところか。
ussuriensus を japonensis のシノニムとして brevirostris [Dement'ev and Gladkov (1951) で採用されていた亜種] の境界で区切るならばこのぐらいの位置になるのかも。
[ハヤブサ亜種の分子系統解析]
Johnson et al. (2023) Whole-genome survey reveals extensive variation in genetic diversity and inbreeding levels among peregrine falcon subspecies
に全亜種をカバーした全ゲノム解析の結果がある [後述の Gu et al. (2021) のデータも活用されている]。
島の亜種の一部を除いてこれまで記述されてきた亜種関係をおおむね確認できたとのこと。
前述のオーストラリア南西部の submelanogenys も亜種扱いで、オーストラリア東部の macropus とは一定の違いがあった。
japonensis は地理的には旧北区に属するが系統的にはさらにアメリカ北方型、南アメリカを含む新世界熱帯を含むクレードに属する結果となっている。
カムチャツカからロシア北東部に亜種 harterti (シベリアハヤブサ) を認める場合もあるが通常は japonensis のシノニムとされる。
これは分子遺伝的にもある程度支持される結果となった、と一見思ったがロシア東部のサンプルは harterti に対応する地域しか調べられていないので japonensis の範囲がどこまでなのか何とも言えない感じ。
また calidus はヤマル半島のもののみなので他の北極地域とはどの程度違うかはわからない。
日本のものは2個体で研究に使われた他の個体に比べてゲノムの読みが比較的浅め。
なお地域から harterti と判定したサンプルは記録者次第で japonensis または calidus とラベルされていたものとのこと。
極北地域のハヤブサとシロハヤブサの研究: Feanke et al. (2019) Status and trends of circumpolar peregrine falcon and gyrfalcon populations
このような北極中心の分布図を見ると北方ではあまり亜種分化していないだろうことも納得できる。
[亜種 japonensis は何者?]
肝心の japonensis の記載を見ると Gmelin (1788) 原記載
Latham が Japonese Eagle と述べたものと同一と判定している。全体記述では cera obscura ろう膜は黒っぽい pedibus luteis 足は黄色 corpore fusco 体は暗色 (後にもう少し詳しい記述があり、嘴の基部は青いっぽい、のどは白くて黒い縦縞があるなど)。
ハヤブサ幼鳥と判定されても不思議でない感じがするが Dement'ev and Gladkov (1951) の時代にはまだ判定されていなかったのか、先取権に関連する記述がないので多少不思議である。
Dement'ev and Gladkov (1951) によれば山階 (1931) は千島列島のハヤブサは pealei と calidus の雑種かも知れないと判断していた模様。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも japonensis の名前は出ていないので、Gmelin (1788) の記載が同定されたのはもう少し後の時代だったのだろう。
Dixon et al. (2012) The subspecies and migration of breeding Peregrines in northern Eurasia
にヒントがあり、Vaurie (1961) Systematic notes on Palearctic birds. No. 44, Falconidae, the genus Falco. (Part 1, Falco peregrinus and Falco pelegrinoides) が東西に分けて
harterti を Gmelin の japonensis のシノニムと考えたとのこと。japonensis の基産地は a migrant which "flew on board off Japan" during Capt. James Cook's last voyage in the North Pacific
とのことで、ジェームズ・クックが北太平洋を航海中に日本から離れた場所に飛んできた渡り個体とのこと。なんと japonensis は船上で採集されたものだった。
#ツバメチドリの原記載と似た状況だった。
(この部分を記述した後に気づいた Latham, Gmelin 時代の記述を後に追記した。この個体だけでなくハヤブサの可能性のある2個体が採集されてそれぞれ別の名称が付けられていた。japonensis でない方の個体の図版がある。この時代は図版がタイプ標本の代わりとなることもあった)。
亜種の分離もロシア語圏とそれ以外で異なっていたとのこと。Dement'ev and Gladkov (1951) もあるいは気づいていたのかも知れないが、あまりにも不定性が大きく、生息が確実に知られているロシアの亜種を優先して記述したものかも知れない。
Vaurie (1961) も Gmelin の japonensis が何者かは深く検討しているわけではなく、harterti 同様渡り個体と考えられることからこのグループのシノニムとみなし、最も古い記載なのでこの名称を採用したとのことのよう。
つまり日本のハヤブサの繁殖個体群が当時は世界には (おそらく) あまり知られていなかったため、日本での記録 = 渡り個体 = harterti と同一とみなされたと考えられる。これもまた少し不思議で日本のハヤブサの繁殖個体についての情報がいつごろ海外に知られるようになったのか気になっているところ。
若杉氏にも調べていただいたが、鷹狩り関連のハヤブサの産地は民間で知られていたものの、ハヤブサの繁殖について日本の鳥学者もあまり注目していなかった印象を受ける。
山階鳥類研究所の標本データベースでも日本列島本土の古い標本がほぼなく、ほとんど千島か北硫黄島のものだった。
1884 年埼玉県の標本は後に付けられたラベルで亜種 leucogenys となっており、1925 年北海道の標本は亜種 calidus、1927 年富山県は亜種 pealei でいずれも北からの渡り鳥が想定されていたと思える。
日本列島本土の繁殖個体の標本がないので Dement'ev and Gladkov (1951) も分布地域に挙げようがなかったのだろう。
高橋 (1939) 樺太産鳥類未記録種に就いて (II) に記述があった。「III. 1938 中知床半島調査 の際も多數蕃殖育雛せるを確かめ, 1羽捕獲するを得た」と記述されており、1938 年に知床半島での繁殖は知られていて 少なくとも 1939 年には公表されていた。ただしこの部分に対応する英文記述がないため Dement'ev and Gladkov (1951) も気づき得なかったかも知れない。
当時の学名は Falco peregrinus calidus としており japonensis はまだ認識されていなかったよう。Falco peregrinus の命名者は Tunstall でなく M. Ogawa とある。
この文献では Falco communis Temminck & Schlegel (参考) の "Fauna Japonica" を採用しており、Gmelin ではないとしている ("Fauna Japonica" には図版はない)。
Gmelin の該当するものは Falco communis Gmelin, 1788 (参考) (普通のハヤブサまたはタカの意味) で、対応種が複数種あり得る (#トビの備考 [トビの学名の変遷]) ため無効として Temminck & Schlegel の用例を採用したものか。Falco peregrinus の方が早いのでこの場合は実質的な問題にはならなかった。
Vaurie (1961) の分布は Dementiev (1955) に従って、IOC 総会の集録由来とのこと。
japonensis は先取権の原則から採用されたもので実は案外曖昧なものだった。
追記: Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire に記述があった。日本のハヤブサは Pallas が千島列島で記載、Snow (1882) は同地で夏に普通に見られると記述。Seebohm は日本のもっと南の島にも住んでいる (resident。留鳥の意味もある) と記述している。函館、横浜、そしておそらく長崎近くからの Siebold の標本がある ("Fauna Japonica" に現れる)。
もっとも標本が複数あることのみが根拠で繁殖の証拠は述べられていない。
Vaurie (1961) では Falco peregrinus orientalis がアメリカ型 (anatum) とヨーロッパ型の中間になるかも知れないが Stejneger and Ridgway はこの見方に否定的で、Gurney は日本のハヤブサ (当時の繁殖状況は少なくとも海外研究者には明らかでなかった) とヨーロッパのものに違いがないとしたとのこと。
この亜種名は Falco orientalis Gmelin, 1788 (記載) Latham の Oriental Hawk が由来。
亜種を細かく分けることも可能だが、実際の違いはさほど大きくなく研究者の見解次第で変わる程度のものとみなしてよさそう。
またこの文献の記述を見ると Gmelin (1788) の文献も早い時代に知られていたが、Falco japonensis Gmelin, 1788 は Falco orientalis と別分類で、前者は Aquilae (実際にイヌワシなどもこちらに入っている)、後者は Falcones に入っていたため日本のハヤブサは後者に相当すると考えられていたらしい。
なお 1780 年代には国名を付けた当時の Falco 属が多数記載されており、当時の流行だったものと想像される。#サシバの学名に登場する indicus も同じ Gmelin (1788) によるもの。当時の Falco 属の新種をたくさん記載する必要があり、地名や国名を付けるのが最も簡単だったようで実はあまり面白味がなかった。
Gmelin (1788) はサシバの可能性のある種類に Falco javanicus の別の名称も付けており、地名由来の学名を乱発していた印象がある。
Gmelin の例が非常に多数あり、海外の鳥で素性もよくわからないが ("Oriental Hawk" と "Japonese Eagle" が同じかどうかも検討していなかった) その他大勢のうちの一つとして命名されたように見える。
さらに調べたところ Hartert (1910-1922) p. 1046 に ?? 付きで Falco orientalis Gmelin, 1788 の記述があり、Latham (1781) をもとに "Habitat in Japonica" と記述されているとのこと。この記載をもとに遡ってみた。
Latham の 本文記述 (p. 34*)。学名はなし。
This is also in the possession of Mr. Banks. Both of them flew on board a ship, near the coast of Japan. 足は pale lead-colour とのこと。
この部分だけちょっと見ると船に飛び込んできたのは実は Falco orientalis の方だったのかと一瞬思ってしまうが、"Both" とあるので実は2羽だった。
この前のページ p. 33* に b. Japonese H[awk] が出てきて上述の個体と同様に船に飛び込んできたとのこと。こちらは足が黄色でこの個体が Falco japonensis Gmelin, 1788 とされるもの (記載の Latham の p. 33 とも合う)。Gmelin は Japonese Eagle の名称としている。前述のように Aquilae に分類していた。
Gmelin (1788) は p. 33* の個体 (Oriental H[awk]) は別に Falco orientalis と記述しているので、もしこの両者を同種とみなすならば Falco japonensis の方が先に現れるので先行シノニムとなり orientalis の名称は表面上現れなくなる (実にややこしい)。
この Latham (1781) では Japonese H[awk], Oriental H[awk], Javan H[awk] がこの順で連続して現れ、いずれも船に飛来で海上で採集されたもの。最後のものがサシバとなった。
Hartert はもしかすると Falco orientalis は Falco japonensis とは別物で orientalis は calidus の初記載の可能性があるとも考えていたが確証が得られず ?? のまま扱っていたと思われる。
Hartert には Falco japonensis は現れないので何と判断していたのだろうか。
なお図版 Chinese Eagle が途中にあって実に紛らわしいがこれは別物。inhabitant of India とあるが何者か。Gmelin (1788) でも学名が付けられた形跡を見つけられなかった。
先崎他 (2017) Birder 31(1): 10-19 にも Johnson et al. (2023) の分子系統解析前だが japonensis とされるタイプ標本についておよびこれらの亜種関係の可能性について少し解説がある。逆に言えば分子系統解析が行われるまでは japonensis とされる日本の個体群と harterti を同一とみなしてよい根拠それほどなかったことになる。
[ハヤブサ亜種の分子系統解析] に戻る。
このクレードはさらにおおまかに2つに分かれ、japonensis と新世界のグループ (オオハヤブサ pealei、チリなど南米からフォークランド諸島までの cassini、アメリカハヤブサ anatum、ツンドラハヤブサ tundrius)
からなる。後者のグループも北米のものは日本でもほとんど記録または検討中の記録があるので分子系統解析との整合性はよい。
旧北区のグループは亜種 peregrinus (スウェーデンとロシア南西部)、ウスハヤブサ calidus、シマハヤブサ furuitii が含まれる。
シマハヤブサと亜種ハヤブサが別クレードになることは興味深い。あるいはウスハヤブサが渡り途中で島に定着したのだろうか。#ハチクマ備考の [台湾で留鳥化したハチクマと渡りの謎] も参照。なおシマハヤブサはアメリカの博物館標本を用いて日本のハヤブサのサンプルよりむしろ深くゲノムが読まれている
(このような海外標本があるのを見るとシマハヤブサの絶滅要因は採集者が一番よく知っているのではないかと思ってしまう...)。
他のクレードの Indomalayan (前述のバーバリーハヤブサに相当)、
オーストラリア、ヨーロッパ南部や中東からアフリカの3系統は日本からの距離も遠く、いずれも関係が薄いようである (全体的にはこれら3系統が前述の2系統と別グループをなす)。
peregrinator の中国サンプルの位置づけは不確定な部分がある。
少なくとも日本で記録されたあるいは検討中の亜種については分子遺伝的に亜種分類をすぐに見直す必要はなさそうである。harterti (シベリアハヤブサ) を別亜種とする根拠も現状特にない結果となった。
ただし fig. 3 の NeighborNet network では peregrinus, calidus, harterti の関係は入り組んでいるのでおおまかにはこれらは分子遺伝学的には1亜種にまとめてもよいぐらいなのかも知れない。
japonensis 2個体は北米系統に近いが harterti とされる1個体もこちらの系統に近い位置にある。
比較的近くにも分布するはず (とはいえ分布もよくわからないが) の peregrinus の明らかな飛来報告もないようで、ロシア北東部およびウスハヤブサを除いた大陸と日本の交流は少なく、大きく分けた場合は日本のハヤブサはむしろ北米型に近いと言ってもよさそうである。
ロシア沿海地方での繁殖: Shokhrin et al. (2020) Nesting birds of Primorsky Krai: falcons Falconidae (pp. 4479-4513)
(極東の鳥類42:沿海地方の繁殖する鳥類2 タカ科とハヤブサ科 で和訳が読める)。亜種は japonensis としているが繁殖個体数は少ないとのこと。
もっとも亜種間の違いが小さいことは、より精度が低く亜種サンプルも少ない過去研究にも現れていて、Bell et al. (2014)
Genetic Evidence for Global Dispersal in the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) and Affinity with the Taita Falcon (Falco fasciinucha)
ハヤブサのように広域移動をする種類では種分化は起きにくくハプロタイプと地理的亜種の対応がよくない結果となっていた。ただしアジアの亜種は含まれていない。
北米では DDT のために激減したハヤブサの再導入プロジェクトが行われ、その影響や島の亜種の遺伝的多様性と保全の問題も大きなテーマとして議論されているがここでは系統解析の紹介にとどめておく。
参考までに北米高緯度のハヤブサの少し前の研究もある: Talbot et al. (2017)
Intraspecific evolutionary relationships among peregrine falcons in western North American high latitudes。
[渡り]
(世界の) ハヤブサの中には留鳥のものと長距離の渡りをするものがある。
「On the Wing - ハヤブサに託した地図のない旅」(アラン・テナント著; 鳥見真生訳 星雲社 2005) というアメリカの長距離の渡りをするハヤブサ (ツンドラハヤブサ) を発信機を取りつけてアラスカから飛行機で追跡した物語がある。この亜種は南米まで渡るそうである。
その後の研究の先駆けとなる、どの遺伝子が渡りの特性を決めているのか全ゲノム解析を行って調べた途方もない研究が Nature に発表された。
Gu et al. (2021) Climate-driven flyway changes and memory-based long-distance migration。
遺伝情報も調べることによって過去の個体群サイズを見積もることができて、10 万年前から増加し、最終氷期のころにピークに達した。最終氷期のころがツンドラの面積が広くて個体数が多かったことと話が合う。氷河サイクルが越冬地分布や渡り経路を決めたと考えている。ADCY8 遺伝子と渡りの長さに関連がある。
ADCY8 という遺伝子はネズミを使った迷路実験で記憶や認知能力に関係していることがわかっている (A peregrine falcon’s power to migrate may lie in its DNA)。
渡り様式の違いがこの遺伝子に関係していることがわかったのは初めてのこと。北極圏のハヤブサの渡り経路の調査はロシア北極圏で標識放鳥されたもの。ハヤブサ 35 個体について全ゲノム解析を行った。短距離と長距離渡りをするハプロタイプ2種を人工合成して遺伝子調節部位に導入し、ニワトリの海馬 (記憶に関係する部位) での働きを調べた。
ハヤブサの海馬での遺伝子発現の解析には北京猛禽類センターで安楽死させられた個体のサンプルを使ったという、様々な分野の最先端技術を注ぎ込んだ遺伝子レベルの渡りの研究である。
生態学:ハヤブサの渡りを解読するで日本語要約が読める。
A bird’s migration decoded によれば渡り経路を学習するツルや、若鳥が自分で渡るシギチドリ、スズメ目などとも比較研究する必要があるだろう。など書かれている。
Delmore et al. (2020) The evolutionary history and genomics of European blackcap migration にズグロムシクイの渡りと遺伝の関係の論文が出た直後であったとのこと。
ハヤブサのゲノム解読がこれほど進んだのは背景があって、Zhan et al. (2013) によるハヤブサとワキスジハヤブサの大部分のゲノムが解読されたことに始まった (#ワキスジハヤブサの備考参照)。
渡りの研究がこのレベルに入ってきたことを象徴するような論文であったが、莫大な費用を要しているはずである。
[関連した名称について]
tiercel (アメリカ英語)、tercel (イギリス英語) は鷹狩り用語でオスのハヤブサまたはタカを指す。中世英語 tercel、古フランス語 tercuel < ラテン語 tertius (3番めまたは3分の1) の指小形。よく解説に現れるのはオスの方がメスより 1/3 ぐらい小さい説だが意味まで確定しているわけではない (wiktionary)。
イランでは留鳥ハヤブサ (亜種 babylonicus) を Shaheen-e kuhi (丘の Shaheen)、渡ってきて海岸に住むハヤブサ (亜種 calidus) を Shaheen-e bahri (海の Shaheen) と呼ぶとのこと。Shaheen は皇帝を意味するとのこと [Macdonald (2006) "Falcon"]。
ハヤブサの営巣場所や巣は英語では eyrie (= aerie、ワシの巣も同様に呼ばれる)、scrape と呼ばれ、通常岩棚などの高所に作られることに由来する (Weiss and Krone)。英語の辞書にはこの意味は載っていないこともある。
[巣を造るハヤブサ類]
タカ類と違ってハヤブサ目は一般に自分で巣を造らない (タカ類の巣の構造もかつてコウノトリ類と近縁と考えられた理由の一つ)。
少なくとも Falco 属には造る種類はいない。ハヤブサ族 Falconini まで広げても (新分類で) アジアコビトハヤブサ [高野 (1973) ではハイイロヒメハヤブサ] も樹洞に営巣するとのこと (wikipedia 英語版より)。
オナガハヤブサ Falco femoralis Aplomado Falcon が木にプラットフォーム状の巣を造るともある (wikipedia 英語版)。この話はどうも正しくないようで、他の鳥の古巣または乗っ取ったものと書いてある情報が多い (この情報も使い回しの可能性が高い)。
Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" では驚くほど情報が少ないとあり、多くは他の鳥 (猛禽類やカラス類など。アルゼンチンでは特にチマンゴカラカラ) の巣を利用する。樹木が茂った場所も時に利用する (occasional 'ledge' formed by epiphytic growth, in tree, shrub or cactus at 2-15+ m) が巣材は足さないとある。天然の巣に似た構造は利用することもあるが "巣を造る" とは言えないよう。
ハヤブサ目全体を見渡すと例外的なものがあり、カラカラ類は巣を造る。
キバラカラカラ Milvago chimachima Yellow-headed Caracara は枝を使って粗雑な巣を作るほか、樹洞を使うこともある。木がないところでは地上や岩の上にも作るなど変化がある。
自分で巣を作らなくなる途中の段階ではないかとの考察もある [Brown (1976) の p. 155]。
Brown (1976) によればハヤブサ類 (Falco) が小枝で巣を造ることがある伝説があるが誤りとのこと。
同じく例に挙がっていた (が当時は巣が見つかっていなかった) 森林性のハヤブサ類 forest falcons (Micrastur 属) も前述のように樹洞に営巣することがわかった。
木がないところで繁殖できるのはある意味一つの利点と言える部分もあり。それゆえハヤブサ類は乾燥地帯や極地にまで進出できたとも言えるだろうか。
必ずしも乾燥地帯に適応していないハヤブサ目の系統でも自分で巣を造らないものが早い段階で現れており、何のために進化した習性か興味あるところである。全ゲノム解析も進んでいるので造巣にかかわる遺伝子も近い将来明らかになるのではないだろうか。
[視覚特性・薄明かりや夜間の狩り]
Martin (2017) What Drives Bird Vision? Bill Control and Predator Detection Overshadow Flight によれば、ハヤブサが遠くの獲物を見つける時は視力のよい側方視 (どちらかの目。斜め前が一番視力がよい) を用いる。
側方視で獲物を追うために、直接向かうのでなく曲がった経路で追跡することが多い。両眼 (正面) 視をするのは獲物を捕まえる直前になってから。ただ別の種類のハヤブサ類では早い段階から正面視もすることが報告されている。正面視と側方視は頭の方向を変えるだけで切り替えられるので両方を併用するのは大して面倒でない [現状の理解はもう少し複雑なよう。#シロハヤブサ備考参照]。
タカ類に比べてハヤブサ類は夜行性の種類が多く知られており、暗所視に適していると考えられる。ハヤブサ目の 1/3、タカ目の 5% が薄明かりや夜間に活動すると報告されている。ハヤブサ類でよく知られている種類ではコビトハヤブサ類 Pygmy-falcons (Polihierax 属)、モリハヤブサ類 (Micrastur 属)、チャイロハヤブサ Falco berigoraなど。
タカ類ではカタグロトビ、クロオビトビ (ほぼ完全な夜行性、#カタグロトビの備考参照) が挙げられている
[Mitkus et al. (2018) Raptor Vision (in Oxford Research Encyclopedia of Neuroscience)]。
上記は日本では馴染みの薄い種類が中心であるためハヤブサ類は昼行性の印象が強いが、日本に生息するハヤブサ類でも薄明中の捕食活動が知られている。
Stanton (2016) Predation of Dawn-swarming Bats by Eurasian Hobby (Falco subbuteo) が報告しているようにチゴハヤブサがコウモリの群れを襲って複数個体を捕食したとのこと
このチゴハヤブサのコウモリ捕食は成功率 100% で他の猛禽類より高かったとのことである。
同様の行動で有名な種類に コウモリダカ Macheiramphus alcinus (英名 Bat Hawk。狩りの映像 1, 2)、コウモリハヤブサ Falco rufigularis 英名 Bat Falcon がある。
昼行性と考えられている猛禽類でコウモリを捕食するものとして他にハヤブサ、アカオノスリ、ミナミツミ、ヒメイヌワシ、アフリカオオタカなども知られている。また中川・竹田 (1991) Birder 5(6): 12-17 にチュウヒによるアブラコウモリの捕食が紹介されている。
Mikula et al. (2016) Bats as prey of diurnal birds: A global perspective (出版社サイト)
に昼行性猛禽類によるコウモリの捕食にレビュー論文がある。多くの系統の猛禽類がコウモリの捕食を行うか試みたことが報告されている。
ミサゴでも例があり (ヘビクイワシでは例がない) ハゲワシでもコシジロハゲワシ Gyps africanus で例があるが他の Gyps 属では記録がない。よく知られている分類群ではほとんど例があるらしい。捕食例がないまとまったグループとして地上性のハヤブサ目がある。
スペシャリストのハチクマ類は事例がないとの説明だが、単にそもそも捕食場面の画像が不足しているためかも知れない (この部分は補足コメント。他のハチクマ亜科には捕食例は普通にある上、ハチクマも哺乳類を食べる)。著者はオウギワシ類などいくつかのグループで事例がないのはデータ不足のためだろうとしている。
猛禽類が初めてコウモリを襲う時は最初は恐れることがあるがすぐに慣れて優秀なハンターになるとのこと (Mikula et al. 2013)。
コウモリ類が夜行性になった理由に鳥類による捕食圧があるとされるがそれを裏付ける結果となったとのこと。
コウモリダカは猛禽類中最も口を大きく開けられるなどヨタカ類やアマツバメ類に似た特殊な進化が見られ [Jones et al. (2012)
Evidence for Convergent Evolution in Gape Morphology of the Bat Hawk (Macheiramphus alcinus) with Swifts, Swallows, and Goatsuckers]、
おそらく昼行性の脊椎動物中唯一のコウモリを主食とする種類だろうとのこと (コウモリダカは完全な昼行性というより薄明に適した crepuscular 薄明薄暮性 の種類であるが)。捕食可能な時間帯が限られるため空中で捕食・処理をして飲み込む形態に適している。このような形態への進化で新たなニッチを獲得したと考えられるとのこと。
瞳孔も大きく (昼間は半分寝たような顔も多いが)、暗さへの適応がわかる。正面顔はアオバズクにも似て見え、飛ぶシルエットは翼先は比較的分離せずタカよりもハヤブサに似ている。
一方でコウモリハヤブサはコウモリ食が主ではなく昆虫や鳥をよく食べる。形態的に特別な適応はないとのこと。
Goodman et al. (2015) Macheiramphus alcinus diet in the Melaky Region of lowland western Madagascar によればコウモリダカはコウモリ類がねぐらを立つわずかな時間帯に特殊化しているため、栄養面の要求を満たすために鳥もある程度食べているとのこと。
コウモリハヤブサは Seijas (1996) Feeding of the bat falcon (Falco rufigularis) in an urban environment の研究があって鳥をコウモリよりむしろ多く食べている。
ニュージーランドハヤブサ Falco novaeseelandiae 英名 New Zealand Falcon では夜中にミズナギドリ類の巣穴を歩いて襲って成鳥を捕食していることが確認されたとのこと
[Miskelly et al. (2022) New Zealand falcons (Falco novaeseelandiae) hunting petrels at night and underground during the day]。
北海道でハヤブサがまだ暗い薄明中にマガモを捕食した報告 [Hirata et al. (2013) Hunting in the dark by a peregrine falcon (Falco peregrinus)]も報告がある。
吉岡 (2017) Birder 31(1): 28-29 のハヤブサの夜間ハンティングの記事がある。
Wu et al. (2016) Retinal transcriptome sequencing sheds light on the adaptation to nocturnal and diurnal lifestyles in raptors が網膜における遺伝子発現を調べていて、ハヤブサ類では高速で動くものに応答する機能 (応答時間が短い) が高まることに関係のある遺伝子がよく発現していると同時に、フクロウ類同様に暗所視に関係する遺伝子も SLC24A1 発現している。
光受容体の LWS (赤のオプシン) の感度が短波長に、SWS2 (青のオプシン) が長波長にシフトするアミノ酸変異を持っていることもフクロウ類と共通しているとのこと [Correction: Corrigendum: Retinal transcriptome sequencing sheds light on the adaptation to nocturnal and diurnal lifestyles in raptors]
これはハヤブサ類が薄明かりの中で狩りをする生態情報とも整合しているとのことで、薄明かりの中でのハヤブサ類の行動にもっと注目すべきなのだろう。この研究では猛禽類に近いが猛禽類でない系統とも比較しているが、視覚にかかわる遺伝子に特に変わったところはなく、やはり猛禽類が視覚を特化させているようである。
タカ類でも少なくとも2種クロハゲワシ、カタグロトビでも紫外線用の視細胞を持たないことも示している論文。
注記: Haagen et al. (2023) The evolutionary history and spectral tuning of vertebrate visual opsins
によればより紫外線領域の SWS1 はハヤブサとタカ類は同じ。ハヤブサ系統のオウム類、スズメ目の一部はより短波長に寄っている。ヨタカ類もハヤブサやタカ類と同様で薄明かりの中での視覚との関係はそれほど明確でないかも知れない。カモメ類もオウム類、スズメ目のようにより短波長を感じている。
短波長側の視覚波長の変化は視覚的コミュニケーションの役割の方が大きいかも。
Wu et al. (2016) でもあくまで可能性を述べている程度で、ハヤブサ類が暗所視に適応している証拠はそこまで高くないかも知れない。
[高度 3000 m を飛行中のダイゼンを日没後に捕食したと考えられる事例]
(#ダイゼンの備考にも掲載)
Boom et al. (2024) Migrating shorebird killed by raptor at 3000 m above ground as revealed by high-resolution tracking
シギ・チドリ類が高い高度をノンストップで渡るのは捕食を避けるためとの考えがあるが、GPS と加速度ロガーを付けたダイゼンが捕食されたと考えられる事例。日没後 25 分とのこと。
捕食されたと考えられる時点の 15 分前に加速が増し、ここで捕食者に気づいて逃げ始めたと考えられるとのこと。ハヤブサの巣から 200 m 以内にタグと標識が発見されハヤブサに捕食されたと考えられるとのこと。これだけの状況証拠があれば日没後にハヤブサが高高度の狩りを行う証拠にもなるのだろう。
日没後 25 分とは言え、この数字はあくまで地上の日没時刻と思われるので、3000 m 近い上空であればまだ十分明るく、ダイゼンを含むであろうシギ・チドリ類の群れは夕日または散乱光を受けて輝いて見えた可能性がある。ハヤブサはこのような格好の獲物を逃さないように、日暮れとともに巡航高度を上げて狙っていたのではないだろうか。3000 m 近い上空の獲物を低いところから見つけてわざわざ飛び上がるとは考えにくいので。
たかだか地上から数百 m 程度までの行動を目視で追跡していてもこのような行動は把握できていない可能性が高そうに思える。
[ハヤブサ髭の役割]
日光の反射を和らげるためとの解釈は昔からあったが、Vrettos et al. (2021)
Malar stripe size and prominence in peregrine falcons vary positively with solar radiation: support for the solar glare hypothesis
による世界のハヤブサの公開写真と日照の相関を調べてこの仮説を裏付ける結果を出している。
[タカとハヤブサの排泄様式の違い]
糞を飛ばすかどうかはタカとハヤブサの違いとしてよく取り上げられる。
鷹匠は英語でタカのものを slice、ハヤブサのものを mutes と使い分けている (Brown 1976)。
参考記事 Mutes or A Primer in Poop-ology (The Modern Apprentice)。
英語表題は対応する日本語をすぐ思いつかれる方もあるだろうがここではあえて記さないことにする (笑)。apprentice は (昔の) 徒弟、初心者 のような意味だが鷹匠用語では非常によく出てくる。
ここでは何も付けなくてもサイト名から鷹匠の話題であることがわかる。
初心者 (apprentice) が上級者に仕えて仕込まれてゆくことを想像していただくと多分合っているだろう。転じて他の分野 (バードウォッチングを習うなど) などでも使われるので知っておいて損のない英語。英語を味わって読む時にもこのような背景知識があるとより楽しめる。
逆に言えばバードウォッチングなど技能を習うには習い事と同じく独学よりも上級者から習う方がよいことも示されているのだろう (少しは探鳥会への誘いになっているだろうか?)。
糞は3つの部分からなる (いわゆる糞 fecals 尿酸 urates 尿 urine) が、タカが勢い良く飛ばすとこれらがよく分離することから slice (行動は slicing) と名付けられたと思わせる解説になっている。
この記事によるとハヤブサの方が糞が臭く、タカはすぐには臭わないとのこと。
Red-tailed Hawk With A "Slice" To Be Proud Of (Ron Dudley 2017)。
タカ目の中にも糞をほとんど飛ばさない種類があるがご存じだろうか。
[肉食の鳥には胃石はない?]
川口 (2021) Birder 35(11): 54-55 によれば肉食の鳥には胃石 (gastrolith) はなく、魚食の鳥 (シロエリオオハム、ペリカン) には持つものがあるとのことで調べてみた。
鷹匠の間では rangle という小石を与えることが行われていて、起源はよくわからないが飼育下の鳥が自分から小石を食べることが知られていたのではないかと考えられ、吐き出したものを洗ってハヤブサに与えると自分で飲み込む観察例も報告されている。
Fox (1976) Rangle より。何のためかはよく調べられていないが、前胃 (proventriculus) で消化を助けていると鷹匠は考えていた。今ではあまり行われていない (必須のものではないらしい)。そのまま排泄されることもある。
砂漠に住むハヤブサ類は砂を食べていて小石を飲み込む必要は特にないとのこと。
野外での観察は難しいがこの Fox (1976) はニュージーランドハヤブサ Falco novaeseelandiae New Zealand Falcon でそれらしい事例を観察して報告したもの。
小石を食べるアメリカチョウゲンボウ Falco sparverius American Kestrel の写真: American Kestrel Eating "Grit" (Ron Dudley 2012)。
Bildstein (2017) "Raptors" (pp. 159-160) では種子食の鳥 (フィンチからダチョウに至るまで) は一般に小石を食べ、動物食でも脂肪分が多い、肉が多い、魚食の食事に関係がある可能性を述べている (例としてウ、ミズナギドリ、フルマカモメを挙げている)。猛禽類でも飼育下、野生でもしばしば事例がある。関連のある鉛中毒については #オオワシの備考に。
カリフォルニアコンドルではボトルのキャップ、薬きょう、色付きガラスの破片などを食べて問題となっている。繁殖期の特にメスの猛禽類はカルシウムを必要とするため、ハゲワシ類は骨片を好んで食べるようだが不消化物を食べる役割はよくわかっていないとのこと。
肉食の鳥でも胃石を用いる例が全然ないわけではないらしい。ブッポウソウは種子食の鳥とは言えないだろうが、胃石を用いていることが知られている (#ブッポウソウの備考に)。
[タカ目、ハヤブサ目、オウム目の脳の比較]
データの出所など解説は #ハチクマの備考[嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] 参照。Sayol et al. (2017) と Liu et al. (2023) を用いた。
黄色の丸がタカ目全般、緑の四角がハヤブサ目全般で、系統が違うのに脳のサイズはほとんど違いがなかった。参考までにオウム目全般を赤丸で示してある。
ハヤブサ目はオウム目と近縁なのでオウム目に少し寄っているかも知れない期待があったが、オウム目の脳は共通系統から分かれた以降に独自に進化したのだろうか。
ハヤブサ目はオウム目に近いので飼育してもタカより賢いと言われる方もあるが、脳のサイズだけではものが言えないのかも知れない。
比較的小型のハヤブサ目は少し上位にくる傾向がある。
ハヤブサ目の点のうち、体重の大きい方から3点はフォークランドカラカラ、(カンムリ) カラカラ、シロハヤブサであるが、カラカラ類と Falco 属の間には特に差がなかった。
世界で一番賢い猛禽類と呼ばれるフォークランドカラカラの脳のサイズは実はタカ類と違わない。脳を大きく進化させたというより使い方 (好奇心の向け方) を変えたのだろう。
Harrington et al. (2023) Innovative problem solving by wild falcons
によればフォークランドカラカラを用いた実験で道具を使うオウム類に匹敵する能力を示したとのこと。
ジェネラリストの種で新しいものを怖がらない種類は問題解決能力が高いとの予測を裏付けるものとなった。この研究は
These falcons excel at problem-solving - and outdo some of the world’s smartest birds (Nature 2023)
オウム類でも最も賢いと言われる言われるシロビタイムジオウム Cacatua goffiniana Tanimbar Cockatoo/Goffin's Cockatoo でも苦労する問題をフォークランドカラカラが解くことができたニュースとして紹介されている。
1年前の実験を覚えていた: Harrington et al. (2024) Long-term memory in wild falcons。
最近の文献を見ると (例えば獣医学上のケアの観点などで) 猛禽類は知能が高いと書いてあるものが多くなっており、頭脳面ではこれまでオウム類やカラスだけが着目されてきただけで、系統分類の見直しもあって世界の認識も変わってきているのかも知れない。
いやカラカラに限らず他のハヤブサ類やタカ類も意外に賢いかも。
ハヤブサ目のデータ点の中で非常に体重の小さいもの (100 g 未満) があるがこれは ヒメハヤブサ属 Microhierax で、生活様式は猛禽的な行動を行うスズメ目に近いもの。

[ハヤブサの鼻孔の構造]
ハヤブサの鼻孔には骨の突起があり、高速で急降下する時でも呼吸ができるのに役立つとよく言われるが実際にはよくわかっていない。
Kesel et al. (2018) Flow Phenomena in the Falcon Nose - an Interpretation Approach
は実測と流体数値計算でどのぐらい効果があるかを確かめたもので、流れを緩やかにする効果は確かめられたがわずかとのこと。ちなみにイヌワシも急降下で 300 km/h ぐらい出すとの報告があるがイヌワシでも鼻孔入口は螺旋状の構造があるとのこと。
必ずしも高速で飛ばないハヤブサ類にも存在する。
また Jollie (1976, 1977)
A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes (part III) p. 229, 234 (nasal turbinal), fig. 118 に解説がある。
[ハヤブサ類の免疫の特殊性]
MHC (主要組織適合遺伝子複合体) 遺伝子は免疫などに重要な役割を果たし、保全生物学でも MHC 多様性と個体群や種の存続可能性の関係がよく議論される。
この常識を打ち破り、Falco 属の中でハヤブサ類で MHC 遺伝子のコピー数や多様性が著しく低いにも関わらず世界で繁栄していることが明らかにされた:
Gangoso et al. (2012) Colonizing the world in spite of reduced MHC variation
チョウゲンボウ類とハヤブサ類でもパターンが異なり、ハヤブサ類の MHC 多様性が非常に低い。他のゲノム領域では同様の多様性の低さは見られず、MHC 多様性を下げる選択圧の存在を示唆する。
この結果からはハヤブサ類は特化した免疫機能のみを持っていると想像されるが、進化する病原体に対抗する他のメカニズムを考えないといけないことになる。
これを受ける形で Minias et al. (2019) Evolution of Copy Number at the MHC Varies across the Avian Tree of Life
が広い範囲の系統で調べた。一般的傾向ではスズメ目のみが特別で MHC 遺伝子のコピー数が多い傾向があるが、特に多いのは一部の系統のみ (Sylvioidea が多く、ツバメやヨーロッパシジュウカラが含まれる, Muscicapoidea ヒタキ上科) で理由が今ひとつわからない。Falco 属のコピー数は特に低いが他にも低い系統はいくつもあってスズメ目にも存在する。
他の相関が期待される生態的パラメータと比較しても今ひとつよくわからない。例えば渡りをする種類は病原体の種類も多い、長寿の種類は長期間病原体に晒されるはずだが相関は顕著に強いわけではない。
Minias et al. (2023) Evolutionary trade-off between innate and acquired immune defences in birds
が興味深い結果を出している。複雑な獲得免疫機能を維持するのにはコストがかかるので、もっと単純な自然免疫系 (非特異的免疫) で十分ならばそちらを利用するのも戦略の一つとの解釈。
MHC 遺伝子のコピー数と自然免疫の指標に逆相関が見られ、全体の傾向もこの解釈を裏付けるようにも見える。しかしハヤブサ類 (ここではチョウゲンボウ) で自然免疫の指標が特に高いわけではなく謎が多い。
スカベンジャー種では多様な病原体に晒されるので特異免疫に頼るよりは自然免疫でまず広く対応した方が有利との考えもできる。ハヤブサ類の特異性やスズメ目のある系統で多い理由などは判然としない
(もちろん MHC 多様性と晒される病原体を関連付ける研究は多数ある。これらは想定される結論なので論文になりやすいバイアスがかかっている可能性もあるかも)。
猛禽類の方がさまざまな病原体に接する頻度が高そうに感じるが、どうもそうではないらしい。Qui et al. (2024) The global distribution and diversity of wild-bird-associated pathogens: An integrated data analysis and modeling study
1959-2022 年に報告された研究からとりまとめ。論文の主眼は動物由来感染症の分布 (特に人にも感染するもの) を調べるものだが他の情報も十分含まれている。
病原体の種類は水鳥、次いでスズメ目が多かったとのこと。水鳥は鳥インフルエンザの自然宿主なので高率なのは理解できるが他の病原体も多い。群れを作る習性や生活環境のためだろうか。
サンプルのバイアスは相当入っているはずで注意は必要だがハヤブサ目 (ただしおそらくほとんど Falco 属) は低く見える。ハヤブサ類は病原体に出会う頻度が想像以上に低くて高い免疫機能を持つ必要が少ないのかも。個体間の接触も限られているし、生きたものを食べる場合は獲物も病原体をあまり持っていないのかも?
免疫と造巣習性の関係?
ふと思いついたのだがハヤブサ類が巣を造らなくなったために病原体に接する頻度が下がった可能性はあるだろうか。枝などで造った複雑な構造の巣は病原体が繁殖しやすい欠点もあるかも知れない。
これを感じたのは森林性タカ類が新鮮な枝をわざわざ折っている点から。マレーシアのハチクマの例では嵐で大量に落ちた枝は拾わず、新たに枝を折るのでなかなか苦労しているとのこと。それだけ衛生上の理由が重要なのだろうと想像する。若葉の付いた枝をしばしば運ぶのも病原体や寄生虫対策と言われる。
そう思って考えるとタカ類がどの枝を折るか匂いも参考にして決めているかも。テルペノイド臭が強いほどおそらく効果があってこの匂いは森林性タカ類も好んでいるかも知れない。あくまで想像。そのように感じるのは自分もこの匂いが好きだから - 本当ならばもしかすると同じ理由で収斂進化?? (なんでもかんでもタカ類が我々と同じように感じていると考え過ぎと批判されそう?)。
話が明後日の方向に行きそうだが、この視点で少し考えてみると我々はタカ類に似ている。
ヒト 家をつくるサル (榎本知郎 京都大学学術出版会 2006) という本もある。
樹上性の鳥類 (Telluraves) で、現在樹上に巣を造る主な系統は圧倒的にタカ類とスズメ目である。タカ類も(半)晩成性だし、スズメ目とは違ってずいぶん成長してから巣立つ。これは捕食者と被食者の違いが大きいだろうが、樹上から出発した霊長類で家をつくるようになった我々とタカ類は衛生に気を配る必要など生理学的要求から生じる共通点が多いかも知れない。
猛禽類、特にタカ類の巣のライブカメラ映像に人気があるのは、単にかっこいいからだけではなく、我々と共通した点を見い出せ、少数の子を丁寧に子育てするなど (その割にはよく踏んでいるが) 行動の意味がわかりやすいからではないだろうか。
ヒトを指して哺乳類の中の鳥類 (昼行性で視覚動物、視力も特によい、子育て様式など) と言われたこともあったが、さらに我々は哺乳類の中のタカ類と言えるかも知れない。かっこいい比喩はどんどん使おう (笑)。
タカ類の子育てを見てきめ細やかな点を感じる部分も多い。これらはもちろんその方がより多くの子供を残せて適応度が高いからと生態学的に説明できるわけだが、このように表現すると擬人的に聞こえるだろうか。
しかし我々も言語による文化の伝達が行われるまでは同様の淘汰圧にさらされて進化させた習性のはずで、タカ類が我々にように気遣いをしていると言ってもそう間違いではないのではないだろうか。習性は収斂進化の産物ではないか、と考えるとヒトの進化を考える上ではサルを見るよりタカを見るのがよろしいとなる (笑)。
さらに考察すると "新鮮な枝を集める" 行動にはかなりの認知が必要ではないだろうか。うまく見つからない場合に体を使って折るなど代替手段への切り替えも必要である。これら場合に応じた行動を個々に進化させることは可能だろうが、全部を遺伝的に制御するには複雑すぎるように思える。我々で言えばこの場合はこのようにせよと記述された膨大なマニュアルを覚えるようなものであまり効率のよいやり方とは思えない。
適度に大きな単位に抽象化され、たとえば "新鮮な枝を集める" 程度にまとめられていて必要な記憶容量を節約し、後は応用力で対応した方が賢明であろう。このためには認知や推論能力が必要で、やはり頭脳を進化させる必要があったのでは。
ハヤブサ類は巣造りのための労働から開放されているとも言えるがしかし生息空間も限定される。
あるいはハヤブサ類の嘴が枝を折るのに適していない構造の可能性もあるかも知れない。タカ類でも嘴以外に体を使って足でも折るが、ハヤブサ類はこのような行動はあまり得意ではないかも知れない。
ハヤブサ類でも樹洞営巣性のものがあるので開放空間で産卵するものと免疫の違いを調べると何かわかるかも。
陸鳥の中でハヤブサ類 (わかっているのは Falco 属) では免疫以外にも他にもまだ説明されていない奇妙な現象があり、例えば Wang et al. (2024) A comprehensive study of Z-DNA density and its evolutionary implications in birds
Z-DNA と呼ばれるジグザグな構造を持つ DNA の比率の鳥類で調べたもの。この構造は DNA の不安定化をもたらし、まとまった欠損を生じやすいなど進化速度を早める効果があるとのこと。古い方の系統の鳥やスズメ目の一部で系統特異的に高くなっているが、Falco 属もそのような系統の一つ。調べると結果は出たが現状解釈が難しい。
"Colonizing the world in spite of reduced MHC variation" の論文の表題が示すように、免疫多様性が低いにもかかわらず世界の広い環境に適応している。何か他の要因があると想像できるが、DNA 構造もあるいは環境適応に関係があるのか気になるところ。
Minias et al. (2019) のデータを参考に Telluraves の中で MHC 遺伝子のコピー数が Falco 属同等に低い種類を見ておくとオーストラリアのキンカチョウ Taeniopygia guttata Zebra Finch が含まれていた。と思ったがこの図は多分間違いで Minias et al. (2023) ではむしろ多い方になっていた。
この研究で調べられた範囲ではスズメ目の中では Falco 属ほど MHC 遺伝子のコピー数が少ないものは他になかった。
Minias et al. (2023) を見るとヨーロッパノビタキ Saxicola rubicola European Stonechat が含まれていた。巣は地上で草をまばらに編んで造るとのこと。
コガラパゴスフィンチ Geospiza fuliginosa Small Ground Finch も MHC 遺伝子のコピー数が少ないが (いずれも Falco 属よりは多い) それほど特殊な巣ではないよう。
造巣習性を失ったため免疫機能が弱まった解釈に基づけばハヤブサ類の都会繁殖要因の一つも理解できる気がする。単に獲物が豊富、あるいはコンクリートが自然の崖のようにみなされるなだけでなく、コンクリートの人造物は相対的に清潔で抗病原体の面で有利な環境なのかも知れない。
造巣習性と免疫の関係は今のところ証拠不十分で可能性の考察にとどまるが、造巣習性と Telluraves 内の進化を考えると面白い解釈の可能性が考えられる気がする。枝を使って造巣する習性は手間もかかり森林が必要で、もしかすると免疫のために余分なコストもかかるかも知れない。
しかし樹洞営巣のような他力本願 (?) ではないので、素材さえあれば巣を造って分布を広げることもできる。造巣習性にはさまざまな行動や認知が必要で、一度必要性を失って関連する遺伝子にも変化が生じてしまうと再度造巣習性を獲得することは難しいかも知れない。必要になっても(ニシ)アカアシチョウゲンボウのように他種の巣に頼らざるを得ない。
ハヤブサ目ではこの能力喪失が進化の早い段階で起きたものと想像できるが、そのためか一部の系統が世界に分布した形跡があるが (コビトハヤブサ類 Polihierax やヒメハヤブサ類 Microhierax)、相対的にマイナーな存在にとどまっている。やはり自身で巣を造る能力がある方が生態的に優位だったのだろう。
ハヤブサ目では Falco 属が生じるまでは生態系でそれほど (タカ類が多い地域では) 上位に食い込めず、限られたニッチを占めていたにとどまっていたらしい。
Falco 属が何かの革新に成功しタカ類に次ぐ第二の昼行性猛禽類となったが、南米から始まったハヤブサ目の適応放散の過程で現在の北米の系統が過去の北米の系統をそのまま引き継いでいないなど、生態的には弱い部分があったのではないかと想像できる。
この革新 (試行錯誤) 過程が Z-DNA のようなゲノム不安定性 (進化速度を速める) に残されていると理解すると面白そうである。Falco 属は苦労して (?) 生み出された産物だったのかも知れない (#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] も同様の意義が考えられる)。
Falco 属が生じていなければハヤブサ目はマイナーなグループのままで、各地に散在する系統は遺存的なグループとされていたかも知れない。
同じように造巣習性を失った Telluraves 系統はいくつもあったかも知れない。しかしそれらは相対的に不利だったため Falco 属のような革新的進化を果たせなかったグループは競争で失われてしまったのかも知れない。
簡素化 (?) や認知や推論能力の節約のため造巣習性を失う方向への進化は何度も試みられたがほとんどは失敗に終わったのかも。
造巣習性を (ほぼ) 失った Telluraves 系統としてフクロウ類やオウム類が思い当たるが、これらは夜間への特殊化、競争相手のあまりなかったオーストラリアを中心とした進化 (オウム類ではさらに社会性や知的能力の高さ、系統によっては大型化) で生き残ったのかも知れない。
オウム類でも競争で破れていたらしいことはかつては世界分布していた化石証拠からわかる。
それ以外の系統が消滅したと考えれば、おそらく K-Pg 境界大絶滅以降に生まれ、大規模な絶滅を経験していない ([#鳥類系統樹2024]と年代に関する 2024 年の議論も参照)、つまりたまたま K-Pg 境界を生き延びた系統が残ったものではない Telluraves の中でタカ類、フクロウ類、オウム類、ハヤブサ類、スズメ目のような未だに系統関係がすっきりしないぐらいに縁の遠いグループが残っている説明となるかも知れない。
これらの中で主に樹上造巣習性を持つのはタカ類とスズメ目の2大グループのみで、他は特殊化によって生き残っていると考えることもできる (系統は飛ぶが托卵性のカッコウ類も特殊化で生き延びたグループと言えるかも知れない)。
オウム類、ハヤブサ類、スズメ目は Australaves としてまとめられることが多いが、造巣習性を考えると {ハヤブサ類 + オウム類} とスズメ目は早い段階で分かれたように見える。スズメ目は祖先からずっと巣を造るグループのまま。ハヤブサ類とオウム類が独立に習性を失ったのか、共通祖先段階で生じたものかわからないが、習性を失う遺伝的な共通基盤はあったのかも知れない。
樹上造巣習性を失ったより小規模な例として、チュウヒ類が樹上営巣性から地上営巣性に移行したものも挙げられるだろう。かつては地上営巣性から樹上営巣性に再度戻ったウスユキチュウヒ Circus assimilis Spotted Harrier があると考えられたことがあったが分子系統解析の結果否定された (#チュウヒの備考 [樹上営巣するチュウヒ類])。
後戻りが難しいであろうことを想像させる事例である。
チュウヒ類はオオタカ類 (Astur 属) と姉妹群の関係にあるが、チュウヒ類にはオオタカ類のような生態的強さが感じられず、やはり限定された環境に適応しているグループのように見える。地上営巣性に移行することによって一種の進化の袋小路状態に入っているのかも知れない。
ただしチュウヒ類は海上を超える分散能力の高さでこの欠点を補っているかも知れない (チュウヒの備考 [チュウヒ類の離島への定着、ニュージーランドの鳥の定着と衰退])。
ハヤブサなどの渡り能力の高さもあるいはなんらの不利を補う同様の生態的意義があるのかも知れない。
#ツリスガラ備考の [鳥類の営巣習性の進化] で紹介の Mainwaring et al. (2023) The evolution of nest site use and nest architecture in modern birds and their ancestors (出版社サイト)
も振り返ってみると、樹上営巣性から他の形態に移った系統から樹上営巣性に進化するのはやはり難しそうに見える。この解析では基本的に現生鳥類を扱っているので、たとえば樹上営巣性から他の形態に移った結果消滅した系統があっても見かけ上現れないことになる。ハヤブサ類の独立性の高い位置を考えるともっと多くの系統が消滅していた可能性も考えられるのでは。
タカ類でも乾燥環境で岩場に粗雑な巣を設けるだけのものも存在する。それらも一緒に考えてみるとさらに興味深そうで、大雑把に見るとハゲワシ類のようにやはり特殊な適応を行った系統のように見える。
タカ類中最も夜行性に適応していると言われるクロオビトビ [高野 (1973) ではクロオビハイイロトビ] Elanus scriptus Letter-winged Kite (トビとは縁の遠いカタグロトビ属) でもフクロウ類とは違って樹上に営巣する。放浪性の強い種でも少なくともオーストラリアの環境ではやはり樹上がより安全なよう。
上記 Telluraves に今でも系統のよくわからない面白いグループがある。ネズミドリ類 (Mousebird, Coliiformes) で系統的にはフクロウ類と同じく洞営巣性の Eucavitaves の祖先系統に含まれることが多いがネズミドリ類だけは樹上営巣性である。
#マガモの備考にある [カモノハシ] で紹介の Salve et al. (2024) の CXCR6 遺伝子の解析結果を見るとネズミドリ類と Eucavitaves は比較的縁が遠いように見える。
Telluraves の中で樹上造巣習性を持つのはタカ類とスズメ目の2大グループのみと書いたが、小さな系統だがネズミドリ類を加えて3系統になるかも知れない。もしネズミドリ類と Eucavitaves と系統がまとまるのであればこの系統でネズミドリ類を分岐した後に樹上営巣性を失ったと考えると都合がよさそうである。
あるいはネズミドリ類とスズメ目の祖先に共通性があるのか...いずれもまだはっきりしていない。ネズミドリ類は遺存グループで、かつてはもっと広く分布していた化石証拠があるが化石種は多系統かも知れないとのこと。ハヤブサ目も Falco 属を生み出さなければ同様に遺存グループのように捉えられていたかも知れない。
樹上営巣性から他の形態に移った系統から逆戻りが難しそうなことはスズメ目ではセキレイ類の例を挙げることもできる (#ツリスガラ備考の [スズメ小目 Passerida の系統分類] 参考)。ただし一部系統のようで全体としては樹上営巣性の能力を保ちつつ新世界まで適応放散したと言えるのだろう。
日本で見られるホオジロ類が草地に適応した繁殖形態をとっているとはいえ、これらは新世界から旧世界に分布を広げたものである。旧世界のホオジロ類のような系統がそのまま新世界に適応放散して再度樹上営巣性に戻ったわけではない。スズメ目の場合はタカ類と樹上営巣の意義は異なるかも知れないが、捕食者対策はどちらも共通性があるだろう。
樹上営巣性は優れた性質なのでスズメ目の多くの系統で保持され、草原の広がりなどで一部地上性に進化を遂げたと考えられるように思える (本当か? このあたりは多分に憶測を含む)。
Rohwer et al. (2025) The Evolution of Using Shed Snake Skin in Bird Nests
北米の研究で巣にヘビの皮を持ち込むのは圧倒的に洞営巣性の鳥に多かったとのこと。実験結果からヘビの皮があると捕食が避けられるが開けた巣を造る種類ではそうではなかったとのこと。洞営巣性には別の苦労もあるらしい。
Fancy birds decorate nests with a natural pattern: snakeskin (Nature news)。
Some Birds Adorn Their Nests With Snakeskin to Scare Off Predators, New Study Finds (Audubon の記事)。
洞営巣性の鳥の巣を捕食するのは小型の哺乳類が中心で、ヘビに捕食される種類が多いためではないかと推測している。アナホリフクロウはガラガラヘビに似た音を出す。
スズメ目のみを対象としたものだが、洞営巣性と遺伝子発現の関係を調べたもの: Lipschutz et al. (2025) Repeated behavioural evolution is associated with convergence of gene expression in cavity-nesting songbirds (オープンアクセスでない)
行動の収斂進化 (洞営巣性では特にメスでほどテリトリー争いが激しいなど) が見られる。脳に関係する遺伝子発現のネットワークは遺伝的浮動よりも早く進化しているとのこと。生活様式に進化に共通の部分があったため系統的に離れたグループの間で少数の遺伝子の収斂進化でも洞営巣性が収斂進化しているかも知れないとのこと。
少数の遺伝子の変化で洞営巣性が進化できることを述べていて、タカ類とフクロウ類、ハヤブサ類の間では機構が違うかも知れないが気にしておこう。
[鳥インフルエンザのオランダのハヤブサへの影響]
Caliendo et al. (2024) Highly Pathogenic Avian Influenza Contributes to the Population Decline of the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) in The Netherlands
では鳥インフルエンザがオランダのハヤブサ個体群減少に関係があるとの論文。検査された検体の多くが陽性だった。分子系統解析でも個々の地域のカモメ類のウイルスとの近縁性がわかり、ハヤブサ個体間でなくカモメ類のコロニー近くで繁殖してカモメ類から感染したと考えられる。
#シロハヤブサ備考の [アイスランドでシロハヤブサが激減] も参照。ハヤブサ類が影響を受けているのは免疫の特異性とも関係があるのだろうか。
シロエリハゲワシでは感染した成鳥が高い確率で回復したことも報告されている (#クロハゲワシ備考の [高病原性鳥インフルエンザ感染を生き延びたシロエリハゲワシ])。
[月に行ったハヤブサ]
以下 Macdonald (2006) "Falcon" (Reaktion Books。このシリーズの本がすべてそうではないだろうが、この本は歴史や文化などの内容が中心で、生物学的情報はそれほど多くない) から抜粋しつつ紹介する。
5章 Military Falcons で軍事とハヤブサに深い縁があることが紹介されている。ここでは洋の東西を問わず鷹狩りと戦いの関連が古くから存在するとあり、日本の武家と鷹狩りの関係も含まれている。
ロシアの Dement'ev はシロハヤブサのモノグラフの中で東洋の言い伝えとして "falconry is the sister of war" と記していると書いているが、これはおそらく英訳本 (1960年とある) を参考にしていると思われる。Dement'ev 原書 "Sokola - Krechety" (1951。ネットで読める) に当たってみると p.143 に、
チュルクやモンゴル族の戦闘部隊においては鷹狩りは娯楽/スポーツや商売のためだけでなく、戦闘の訓練にもあたるとみなされていた。東洋の言い伝えにも「鷹狩りは戦争の姉妹 (のようなものである)」という部分がこれに相当する。
このようなこともあって鷹狩りに用いられる中で最上で希少なシロハヤブサは特別に高く評価され、「勇敢な戦士」の象徴とみなされた、と続く。
この話は D. Yrsaliev (1966) (#イヌワシの備考 [亜種・中央アジアの鷹狩り歴史] 参照) にも引用されており、言い回しが少し違うが Obychenie lovchej ptitsy の後半 03-01, 22:17 のところでテキストに起こされたものを読むことができる (この引用では Dement'ev にあるシロハヤブサの名前が省略されている)。
D. Yrsaliev (1966) ではこの後に Dement'ev の記述とよく似た文脈でキルギス人の残した詩なども紹介されており、おそらく原典が他にあってそれをロシア語に訳したものが伝わっているのではないかと思う。さらに英訳され抜粋されて意味が変質して行っている可能性もあるので注意であろう。
"Falcon" に戻ると (多分にアメリカ、イギリスの歴史に偏っているだろうとは思うが)、古典時代の話を除いて軍隊と鷹狩りに直接の関係が生まれたのは、アメリカが 1940 年代にミッドウェー島のアホウドリ類のコロニーのまっただ中に基地を設けたことに始まるとのこと。
この時から軍事科学の一分野に鳥類学部門が置かれ、この時はアメリカ軍は島の多くを舗装してアホウドリ類が営巣できないようにしたとのこと。
しかし空港の草地はどこにでもあり、1970 年代にスコットランドで鷹匠 Philip Glasier が軍の空港でデモンストレーションを行い、観衆が疑う中で鳥を追い払う任務を完璧に果たしたという。
現在でも世界各地で同様の任務が果たされている。軍隊も空軍力の自然の象徴として鷹匠部隊を好み、軍事と鷹狩りが自然に一体化して見られるようになった。
タカ・ハヤブサがなわばりで獲物を捉えることと人間が領土 (territory) を守ることは同じように見えるので、鳥類学者が意味が異なっていることを述べてもこの関連性は一般の者にとってはまったく不自然でなかった。
なお鳥類学と軍事との関連についてはそれ以前にもさまざまな側面があり、伝書鳩時代に鷹匠ネットワークを用いて無効化するなどのアイデアもあったそうである。ハヤブサに敵と味方のハトを区別することをどのように教えるかなども調べられていたらしい。そんなものはもちろん軍事機密だ、ハハハッとある。
猛禽類の本 Brown (1976) にも鳥 (特に猛禽類) の翼の計測値などもっとあるはずなのだがあまり発表されていない。データはあるが軍事機密だからと教えてくれた、という記載もあった。
本題に戻ると、月に行ったハヤブサというのはアポロ 15 号 (1971 年) のことである。アポロ計画における4度目の月面着陸飛行。着陸船は「ファルコン」であり、アメリカ空軍のハヤブサが必然的に任務を務めることとなった。空軍のマスコットの "Hungry" の名前のソウゲンハヤブサ (種ハヤブサと思っていたのだが違っていた) の羽根を宇宙に持って行ったのである。
これには重大な任務があった。真空の宇宙空間では物体によらず同じ時間で落ちるというガリレオの発見を確かめるためであった (地上で真空で実験すればよいだけの話なので超高価な、しかし宣伝には抜群のデモンストレーションである。法則が正しくなければそもそも月着陸ができるはずがないので)。
当時は写真は撮られておらず、月からのノイズだらけの中継ビデオが残されているだけである。船長の Scott はノイズに埋もれながら片手にハンマーを、もう片手に羽根を持って興奮した口調で以下のように語った (途中部分は省略されている):
One of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo
a long time ago, who made a rather significant discovery about falling
objects in gravity fields...
The feather happens to be appropriately a falcon feather, for our Falcon,
and I'll drop the two here, and hopefully they'll hit the ground
at the same time...
[我々が今日ここに来ている理由の一つはガリレオという名前の紳士がずっと昔に重力の中で物体は同時に落ちるという発見をしたためである。この羽根は「ファルコン」号にふさわしいハヤブサの羽根で
これから2つ (羽根とハンマー) を同時に落としてみよう。たぶん同時に地面に落ちるだろう]
そして沈黙の後、"This proves that Mr. Galileo was correct in his findings"
(ガリレオは正しかったことが証明された) と Scott は宣言した。
Apollo 15 Hammer-Feather Drop で映像を見ることができる。上記スクリプトでも見ながら聞いてみていただきたい。
本の著者 Macdonald は「驚愕の象徴的表現」と述べている。月の砂のオーロラのようなダストの中で強烈な日光を浴びたのは、(アメリカと宇宙開発競争をしていた旧ソ連の象徴である) ハンマーと鎌ではなく、ハンマーとアメリカのハヤブサの羽根だったのだ。宇宙から中継された映像は宇宙競争での勝利を意味し、自然の法則を実証する権利はアメリカにあることを示すことになった (*1)。
Macdonald の本では引き続きタカ (ハヤブサ) を訓練することは愛国心を証明することにもなったと述べているが、アメリカ空軍の鷹匠の Cadet Peterson は、とどのつまりアメリカ空軍のハヤブサたちが感動的だったとは必ずしも言えず、ハヤブサたちにとって我々が信頼できることを示しただけに過ぎない、と回顧していたとのこと。
ちなみにこの羽根を持ち帰る任務は含まれていなかったのか、現在でも羽根は月に残されているはずである。
同じ話題は「羽: 進化が生みだした自然の奇跡」(ソーア・ハンソン著 黒沢令子訳 白揚社 2013) にも取り上げられているが Macdonald (2006) ほど詳細ではない。別の情報は多少含まれている。
「月に残されているはず」はこちらで読んだ方を記憶していたかも知れない。こちらの方を読むとソウゲンハヤブサとは書いていないのでハヤブサと思うだろう [Macdonald (2006) の方を先に読んだが途中で記憶が混線していたかも知れない]。
ソーア・ハンソンの方には Macdonald (2006) のような羽根とハンマーの象徴的意味については触れられおらず、ハヤブサの翼は羽の付いたハンマーのようなものであるとの生物学に重点を置いた的記述になっている。
同書の別のところで (テーマとしてもちろん触れざるを得ないだろうが) Prum が Alan Feduccia "The Origin and Evolution of Birds" (1996, 1999)「鳥の起源と進化」 (少し横道。アラン・フェドゥーシア著 黒澤令子訳 平凡社 2004) の鳥と飛翔の起源を痛烈に批判していたことが取り上げられている。
Prum (2002) Why Ornithologists Should Care About The Theropod Origin of Birds
(表題の意味は違うが) 鳥類学者はなぜ鳥の起源に関わる問題に無関心なのか。今でこそ鳥=恐竜が定説になっているが関心のある方は読まれると面白いだろう。あくまで欧米の話が中心なので鳥類学コースでは鳥の特殊性を教えていれば事が足りるかのように記述されているが、鳥類学コースに相当するものが日本では (たぶん) 確立されていないので、そもそも背景が違いすぎるかも知れない。
Feduccia の反論も見てみよう Feduccia (2002) Birds are Dinosaurs: Simple Answer to a Complex Problem
Phylogenetic systematics stands alone in the sciences in demanding that
critics of a particular phylogenetic hypothesis not criticize the hypothesis
without proposing an "explicit alternative hypothesis"
この表現は「羽: 進化が生みだした自然の奇跡」にもそのまま紹介されているのだが、代替仮説を提示することなくある仮説を批判してはいけないと要求する学問は系統分類学ぐらいのものである、とのこと。
こんな記事もある The "Birds Are Not Dinosaurs" Movement (Darren Naish, Scientific American 2017)。
「鳥は恐竜ではない」学説というより「運動」(Birds Are Not Dinosaurs = BAND) との呼び方になっている。
当時の「鳥の起源と進化」の日本での書評でも、このような視点から取り上げたものは見た覚えがないと思う。
一般的な鳥類学者の関心事はそんなところになかった、というのが正解だろうか。もっとも自分も恐竜とそれ以外の系統がどう違うのかそれほど関心もなかったので (当時の日本語の恐竜紹介本でも違う系統も混ざっていたし)、あまり話題について行っていなかった (現在もいない) のも事実である。
当時は (かつては、あるいは実は重大ではなかったかも知れないが) 重大な対立仮設であった認識も乏しかったかも知れない。
今の鳥類の分類学でも系統に関心がなければ系統分類上の面白い話があってもそのまま素通りしてしまうかも知れない。
「鳥の起源と進化」には中国の化石についての Feduccia も私見も述べられていて比較して読まれると面白いだろう。
「鳥の起源と進化」を買った当時は大絶滅後の鳥類の「ビッグバン」を斬新な思いで見たのを思い出す。当時はこのように広範に鳥類の進化を議論した書籍などがあまりなかったこともあるだろう。今ならば Boyd の分類解説なども含めてネットで簡単に文献の一次情報なども得られ、wikipedia (英語版) にもよく反映されているのであまり有り難みがなくなってしまった。
改めて系統分類に関係しそうなところを見てみていたのだが、本稿に追加すべき記述があまり見当たらなかった。
少し関係しそうなところで、Dodson (2025) China shares fossil treasures with the world がオープンアクセスで読めるので紹介しておく。Feduccia 「鳥の起源と進化」を読むと中国の化石について懐疑的な態度を持つかも知れないが、この論文で古生物の世界で中国がどのように世界に門戸を開いたか歴史が述べられている。
Sinosauropteryx の発見を期に 1996 年に中国の古生物の黄金時代が始まったとのことで、現在では鳥類や恐竜に限らず多くの興味深い化石を世界に提供しているとのこと。Feduccia "The Origin and Evolution of Birds" (1996, 1999) の時代は中国の古生物学の進展を予測・評価するのにまだ早すぎたのだろう。
新しいところで、
Review of: Feduccia, A. 2020 - Romancing the Birds and Dinosaurs: Forays in Postmodern Paleontology. BrownWalker Press/ Universal Publishers, Inc.
Boca Raton, FLA and Irvine, CA.
という Feduccia (2020) の新著の詳しい内容紹介も含めた主に批評的書評もある。
この評者の最後の部分 (Epilogue) は含蓄がある。科学における "合意" には2種類あって concilience と consensus で、議論のあるテーマに対して前者は異なるアプローチで互いの見解を尊重しつつ到達した合意点で、後者はどちらかと言えば多数派の原理による合意。しばしばメディア露出度などの影響も受ける。
この評者によれば「鳥は恐竜である」は後者の方に近い。多くの反論が残っている段階で対立議論を無視することは科学にとってよいことではないだろう。鳥類学を教えるにあたって cladistic phylogenetic method (分岐学的系統学手法) のみを "唯一" の仮説として示すのは他の仮説を学んだり検討する機会を奪いかねない。Feduccia の本もおすすめするとの内容。
日本語で読める論文では川上・江田 (2018) 鳥類の起源としての恐竜と,恐竜の子孫としての鳥類
が例えば歴史を手早く知るためなどに役に立ちそうである。この系統樹1つを見ても上位分類概念の難しさがわかる。
この文献の図 1 では鳥綱 Aves を始祖鳥までを含む系統名としているが、これは引用文献の中では Chiappe and Dyke (2006) The early evolutionary history of birds
によるもので、後2つの引用文献
Brusatte et al. (2014)
Gradual Assembly of Avian Body Plan Culminated in Rapid Rates of Evolution
across the Dinosaur-Bird Transition
と Xu et al. (2014)
An integrative approach to understanding bird origins
ではこの系統を Aves と呼ぶことを慎重に避けているように見える。
McLachlan et al. (2017) Maaqwi cascadensis: A large, marine diving bird (Avialae: Ornithurae) from the Upper Cretaceous of British Columbia, Canada
でも同様。この文献では現生の鳥類を Aves と称している。
古い系統の名称に Aves を用いるのは多分に著者の価値判断が含まれるだろう。用例をみると 鳥群 Avialae、現生鳥類を含む最も新しい系統の 真鳥類 Ornithurae [-urae は尾の意味で、鳥の尾 (尾骨) を持つグループの意味] は広く受け入れられているように見える。
そんなものは過去に定義されているのでは? と思われるだろうし、日本語で「始祖鳥とイエスズメを含む最小限のクレード」のような記述も本にある。川上・江田 (2018) もそのように定義した上で (ただし問題点も記述されている) 用いている。
真鍋 (2011) Birder 25(2): 18-19 の段階でも Aves が始祖鳥を含む位置づけは変わっていないとあるが、異なる考え方も紹介されている。
wikipedia 英語版によれば 1990 年代に標準的だった定義で、現在では Gauthier (1986)
Saurischian monophyly and the origin of birds が現代の鳥を含むクレードとして定義し直して多くの研究者に使われているとのこと
(これを執筆時の wikipedia 日本語版はどこかで間違えたようで途中から Avis の名称となっている)。
現生グループを含むクレードは現生グループに基づき、現生種とその近縁の絶滅種に限るとの原則に基づく。
Avialae は代わりに定義された用語とのこと。恐竜との関係云々にかかわらず、始祖鳥などを含まない現在の鳥類を Aves とこれまで通り呼んで問題ないのが世界の主流らしく安心してよさそう。
従来 non-avian dinosaurs (非鳥類型恐竜) に代わる用語として non-avialan dinosaurs も使われている (非鳥群型恐竜?)。Yu et al. (2024) Avialan-like brain morphology in Sinovenator (Troodontidae, Theropoda) のような用例も参考になる。
Xu et al. (2014) の系統樹は見やすく特徴も付記されていておすすめ。
この系統樹によれば鳥類、恐竜とワニ類も含む系統名は 主竜形類 Archosauromorpha となる。
通常恐竜と呼ばれる Dinosauria はもう少し限定された系統になるので翼竜を恐竜に含めるのは間違いとなる。翼竜と恐竜を含む系統の名前は鳥中足骨類 Avemetatarsalia となる。
このように見てゆくと Dinosauria は大きなクレードではあるが、クレード分岐は多段階あるのでこの段階だけ取り出して恐竜かどうかを議論するのも多少の違和感を感じないでもない。一般的に知られている恐竜と呼ばれるものがこのグループに含まれるので Dinosauria と名付けているだけで、恐竜に見えるかどうかの人の主観も入ってそうである。
このクレードを区別する主たる特徴は2足歩行だけなので他のクレード名同様、形態や機能を反映した別のクレード名であっても構わなかったように思える (あくまで個人的感想だが)。2足歩行はそれほど大事な要素なのだろうか (ここにも人の価値観が入っているかも知れない?)。
系統樹を眺めていると、「鳥は恐竜である」と言うのは現生の鳥類で例えば「チュウヒはオオタカである」と言うのにほぼ等価な関係になることがわかる。「チュウヒはタカである」とはだいぶ印象が違う。
チュウヒ類とハイタカ・オオタカ類の系統名称関係がどれほど込み入った状況になっているかを見てもそう簡単な話ではないだろう。
また基礎代謝率 (BMR) が何段階かにわたって徐々に増大していることも記されている。現生鳥類に匹敵する BMR を獲得したのは 真鳥類 Ornithurae の段階で、この段階で他にもいくつもの現代的な形質が追加されている。骨学的な類縁性は古い系統にも遡れるが本当に現代の鳥らしくなったのはここから、と見てよさそうである。
恐竜は温血 (内温性) だったかもしばしば話題になるが、徐々に BMR を高めて内温性を獲得してきたと考えればよいんだろう。
Chiarenza et al. (2024) Early Jurassic origin of avian endothermy and thermophysiological diversity in dinosaurs は古気候などのデータも用いて内温性がいくつもの系統で進化したと主張している。内温性は寒冷気候条件で生まれたとの考え。
ここまで遡ると鳥綱・爬虫綱が単系統の関係にならないが、このあたりの扱いはさすがに取り扱い範囲を超えるので後世にお任せしたい。「鳥は恐竜である」は鳥以外に現生系統がないだけであって、"ここまで遡ると" とあまり違わないレベルの表現をしていることになる。
川口 (2023) Birder 37(3): 52-53 にトロオドン科アンキオルニスという記事がある。
Anchiornis を「ほとんど鳥」の意味と紹介している。
記載論文では Anchiornis is from the Greek 'Anchi' (meaining 'nearby') and 'ornis' (meaning bird), referring to the animal's being very closely related to birds とあり、訳はこれで構わないだろう。
Xu et al. (2009) A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a morphological gap in avian origin (記載論文。出版社サイト)。
この論文では Aves を始祖鳥と現代の鳥を含む最小クレードとする従来定義を用いている。
Li et al. (2010) Plumage Color Patterns of an Extinct Dinosaur
では Aves を現代の鳥に用い、Avialae を始祖鳥を含むクレード名としている。Anchiornis を含むクレードは Paraaves との位置づけ。この論文に色の推定復元図などがある。
Anchiornis がトロオドン科 Troodontidae に属する見解は Hu et al. (2009) A pre-Archaeopteryx troodontid theropod from China with long feathers on the metatarsus。
川口氏の用いたトロオドン科 Troodontidae が現生鳥類につながるクレードの可能性があるとの位置づけは Tsuihiji et al. (2014)
An exquisitely preserved troodontid theropod with new information on the palatal structure from the Upper Cretaceous of Mongolia
の研究がベースと考えてよいだろう。
Xu et al. (2014) は Tsuihiji et al. (2014) を見る前の論文だが、Anchiornis の系統樹では現生鳥類とは別系統として、Anchiornis と現生鳥類 (+ 始祖鳥) を含むクレード名は Deinonychosaria としている。
もう少し後の研究では Foth and Rauhut (2017) Re-evaluation of the Haarlem Archaeopteryx and the radiation of maniraptoran theropod dinosaurs が
Anchiornis は Troodontidae と別系統と考え、
Anchiornithidae 科を与えている。この考えに立てば川口氏の名称や議論は成り立たないことになる。
Lefevre et al. (2017) A new Jurassic theropod from China documents a transitional step in the macrostructure of feathers
の系統樹 (wikipedia 英語版 Anchiornis で見られる) では現生鳥類を含む Avialae、トロオドン科 Troodontidae と Dromaeosauridae を含むクレードを Eumaniraptora としている。
Anchiornithidae 科はその側系統にあたるもので、トロオドン科、Anchiornithidae 科いずれも現生鳥類につながるものではない。wikipedia 英語版を見る範囲ではこれが現在の標準的理解で、Xu et al. (2014) の系統樹とも矛盾するわけでない。
Foth and Rauhut (2017) の主張するようにこの時代に現生鳥類と共通した特徴のある多数の系統が生まれ、そのうち1系統のみが現在まで残ったのだろう。
Pei et al. (2020) Potential for Powered Flight Neared by Most Close
Avialan Relatives, but Few Crossed Its Thresholds
自力飛行は少なくとも3系統で独立に進化して非鳥群でも近づいたグループも他にあったが、一線を超えることは難しかったとの研究。この論文の改訂系統樹では Avialae に始祖鳥よりもう少し広い系統 (Anchiornithinae) を含んでいて始祖鳥を含む最小クレードを採用していない。ただし Avialae に対応する英語は birds (意図的に使っているかも知れない) となっているのでややこしさは残っている。
この著者たちが系統樹を改訂したためこちらに帰属させる必要が生じたものらしく、Anchiornithinae をどこに置くかは学問的にもまだ議論があると見るのがよいのだろう。
現生の鳥に類比して考えると (系統が生まれる時間スケールはおそらくまったく違うだろうが) Elementaves のようなさまざまに多様化した時期で、Elementaves でも現生種を見ると類縁関係がわからないのと同様、発見された化石のみからどのように多様化したのかはごく一部しかわからないのだろう。
始祖鳥と Anchiornis のどちらが最古の鳥か、の議論はそもそもあまり意味をなさないのだろうし、もちろん現生鳥類が1つの科にまとまるようなことはない。
始祖鳥を含む系統名として Aves を用いなくなったのもこのような事情が反映されていると考えれば納得でき、この意味で Aves を使うことは逆に誤解を招くおそれがある。
川口氏の記事は 2023 年なので最新情報を反映しているようにも見えてしまうが、広く受け入れられている模様ではない。2014 年の論文時点での一つの解釈だったと読んでおくのがよいだろう。そうならば定説を覆して面白かったのだろうけど、ぐらいだろうか。
新しい化石が発見されると理解が大きく進展することがあるのはまったくその通りだが、バックボーンはそれほどゆるいでいない模様。
備考:
*1: 解釈は少なくも 1971 年当時はまったくその通りだと思うが、宇宙開発 = 国家間競争 の図式が今でも信じられ、そのように報道されることには戸惑いもある。現代では宇宙開発は国際協力が当たり前で、宇宙での国際協力が冷戦終結に少なからず果たした役割を知っている者としては、1970 年代のステレオタイプ的な思考が未だ引き継がれていることを残念に思う。
1986 年、76 年に一度しか帰還しないハレー (ハリー) 彗星の観測に東西の垣根を超えた国際協力が行われ、大成功を収めた Nature の特集号 "Voyages to Comet Halley" (Vol. 321, No. 6067) を今でも記念に残している。
このような話の背景を知っているのは、ただ一度の機会の実現のために各国が惜しむことなく技術や情報を提供しあった素晴らしい解説記事か図書を読んだためだが、今となっては当時の興奮を wikipedia でも YouTube でも見ることができないのは残念である。
ネットでもこの話はほとんど読むことができず、よほど歴史に関心のある方が当時の書籍や雑誌を調べたりしない限り出会えないと思えるので、リアルタイムで知っていた者として紹介することにする。何分古い話なので記憶が多少間違っているかも知れないがお許し願いたい (過去の情報は wikipedia のものをかなり利用している)。
ハレー彗星の名前はご存じであろう (ちなみに個人名の読み方は原語の発音になるべく忠実にとの考えからハリー彗星と呼ぶことを推奨する動きがかなり以前からあるが、原語の発音にも複数のものがあるらしいのと、ハレー彗星の名称があまりに長く定着しているためにこちらで記す)。
彗星は古くから知られていたが、惑星のように太陽の周囲を公転しているとは考えられていなかった
(ちなみに惑星の公転についてのケプラーの法則が発表されのは 1609-1619 年で、ニュートンがこれが重力の法則で説明できることを発表したのが 1687 年)。
英国天文学者の Edmond Halley (1656-1742) が自身が 1682 年に彗星を観測し、イタリアの天文学者
カッシーニによる彗星も太陽の周囲を公転しているアイデアを聞き、よく似た軌道を持つ 1531 年、1607 年の彗星が同一のものが約 76 年周期で公転していると判定し、この彗星が 1758 年に戻って来るだろうと1696年に予言した。Halley 自身は生きてその予言を確かめることはもちろんできなかったが、
「もし確認されればこれはニュートンの重力の法則の最も劇的な検証になるだろう」とのこと (1986 年ハレー彗星接近前の BBC のドキュメンタリー番組から。非常によい内容だったのだが YouTube でももはや見られなくなっているのが教育的にも残念である)。
1531, 1607, 1682 年の間隔が少し違うことは当時から議論の対象となっていたが、ニュートンが "できたてほやほや" の重力の法則を用いて木星と土星の引力で説明できることを示した。
そして多くの人が (一部は半信半疑で) 待ち受けるなか、ドイツの天文学者 Johann Georg Palitzsch (ヨハン・ゲオルク・パリッチュ) が 1758 年のクリスマスの晩に彗星が帰ってきたことを望遠鏡で発見し、Halley の予言を確認した。予言者に基づきハレー彗星と呼ばれるようになった。
現在ではこのような周期彗星は多数知られているが、記念すべき第1号であり、しかも確実に肉眼で見える周期彗星はこのハレー彗星が唯一のものである。
ついでに名称のことを紹介しておこう。生物の世界と同じく「学名」に相当するものがあろうことは容易に想像できるであろう。"Halley's Comet" などの名称は通称である。命名規則は何度か変わっているが、短周期彗星 (周期 200 年以下か、複数の回帰の記録があるもの) では確定番号順に番号を振り、ハレー彗星の場合は 1P である。
おそらくこれだけでも「学名」に相当するものだが、これだけでは何かわからないかも知れないので通常は生物の学名と同様に発見者 (と認定された名称。独立発見の場合は最初3名まで、最近では2名までとのこと) が付記され、1P/Halley が「学名」相当のフルネーム (systematic name) に相当する (P = periodic)。
生物の学名では命名者が学名を提案するが、彗星の場合は発見者の名前が付く。同じ発見者が複数の彗星を発見することがあるので、通称ではシューメーカー・レヴィ第6彗星のような名前が付くが、このようになると 181P のような短い学名の方がむしろわかりやすいぐらいである。分裂して崩壊してしまったなどと考えられる周期彗星では 3D/Biela のような名称が付く (D = disappeared など)。
2I/Borisov (2019 年クリミアのアマチュア天文家による発見) のように I は最近設けられたカテゴリーで太陽系外からやってきた (I = interstellar) 彗星を表す。後で出てくるが太陽系と太陽系外で組成がどのように違うのかを知ることのできる貴重な資料となる。
小惑星にも学名に相当するものがあって、これも登録順に番号を ( ) でくくったものと (発見者ではなく) 公認名称がフルネームに相当する。公認名称は発見者が一定の提案権を持ち (確か政治家の名前などは制約があったはず)、どこかの地名やだれそれが星に名前が付いたなどの報道はだいたいこれを意味するものである (自身もイタリア人が名付けてくれた小惑星を持っている)。恒星に非公式の名前をつける商売はあるがそれとは別物である。
公認名称を持たない小惑星も多く (科学とあまり関係ない業務があまりに煩雑になるのを避けるため1人が提案できる数に制限が設けられており、また提案権を行使しない発見者も多い)、公認名称が付いているのは比較的古いものか、軌道が特殊であるなど特別に名前を与えたいものに限られている。そのため「学名」に相当するものは (番号) となる。
かつて惑星だった冥王星は現在は小惑星の番号が与えられ (134340) である。フルネームだと (134340) Pluto。記念すべき (100000) にしようとの動きがあったのだが、冥王星は惑星かそうでないかの議論が生まれ、最終的に国際天文学連合総会の投票 (2006) で惑星でないとの判断を待つことになったため記念番号にはならなかった。
どの分野でもそうであろうが分類は結局は人が判断するものなので、あまり科学的に見えないかも知れないが多数決になるのはやむを得ないところだったのだろう。
元に戻るとハレー彗星の 1758 年は当時の予測よりも戻ってくるのは1か月遅れだったとのこと。同じ彗星をフランスの天文学者 Charles Messier (シャルル・メシエ) が1か月遅れで独立発見し (当時の情報伝達はもちろん極めて遅かった)、パリッチュに遅れをとったことから彗星探索に一層の熱意を傾け、現在でも有名な星雲・星団の「メシエカタログ」を作った (アンドロメダ銀河は M 31 など)。
その次の回帰 (return。彗星の場合はこの訳語が一般に使われる。見えなくなったものが戻ってくる感覚。彗星の回帰の検出は英語では recovery と言う。標識調査などの鳥類学の用法とも比べてみていただきたい。完全に見失ったものが偶然再発見された場合は rediscovery となる) は 1835 年で、
当時写真技術はすでに発明されていたがハレー彗星の回帰には間に合わなかった。つまり人が目で見て描いたスケッチしか残っていない。この時には回帰日時の正確な予想が競われたが最も近い予想でも4日以上外れていた。
この年の観測で、1456 年と 1378 年に観測されていた彗星もハレー彗星と同定された。
次の回帰はもう近代の 1910 年である。第二次世界大戦前の当時はドイツが天文学の中心地で初めて写真により回帰が確認された。太陽に最も近づく (近日点通過) の7か月前に発見されるなど写真観測の威力がわかる。
この時でも回帰日時予測には3日の誤差があった。
この回帰は特別で、ハレー彗星の尾の中を地球が通過することになり、当時利用可能になっていたスペクトル観測でシアンが検出されており、大衆の間でパニックが起きたり便乗商売が流行る由来ともなった。
当時は都市明かりなどもなく雄大なハレー彗星が観察できたとのこと。
そして次は 1986 年に帰ってくることは昔の図鑑には必ず書いてあったが、正確にいつ帰ってくるかが一般に知らされたのは回帰がかなり近づいてからであった。
当時は大型計算機も使えるようになり、ハレー彗星の回帰を過去にも遡ることができるようになっていた。
西洋文明では星空は神の住む天上のようなものと長くみなされ、彗星や新星、超新星の記録もほとんど残っていなかったが星空の古記録は東洋や中東に残されていた。
Yeomans and Kiang (1981) The long-term motion of comet Halley は近代的な数値計算で軌道を遡り、古記録を地道に調べて過去の記録を同定していったのである。
現在確実に認められている記録は紀元前 240 年の中国の歴史書「史記」にあるもの、その次が紀元前 164 年でバビロニア粘土板や中国の「漢書」の記録があるとされる。
世界の人々は紀元前 240 年の回帰以来、ハレー彗星を一度も見逃すことなく忠実に記録にとどめてきたのだった (このあたりの話も前述 BBC 番組で詳しく触れられていた)。昔の人が一度も逃すこと記録にとどめ、考古学者が解読し、天文学者が精緻な軌道計算を行って同定して行ったプロセスには振り返るたびに感慨を覚える。
日本最古の記録は 684 年「日本書紀」にあるとのこと。
従来のように前回の回帰に周期を足し算して微修正を加える方法には精度の限界がある。
重力の法則を利用すればいくらでも精度の高い計算をすることができそうに思えるがこれは正しくなく、彗星のようにガスを放出する天体に重力以外の力も働く (非重力効果と呼ばれる)。この効果を見積もるには実際に観測や過去の記録に遡って計算して確かめるしかない。
また写真を使った精度の高い測定は 1910 年の回帰が最初であって、それ以前の観測データの精度は限られている。古く遡ることができればたとえ限られた記録であっても軌道の精度を格段に上げることができる。
その時にわかったのは 1986 年の回帰は非常に条件が悪く、近日点通過を太陽の反対側で迎えること、一番明るくなる近日点通過後に北半球からの観測が困難であることであった。
このように最新の予想の発表が 1981 年と遅くなった背景には探査計画があり、できる限り正確な軌道を知る必要があったためだろう。
1910 年に比べて飛躍的に大型の望遠鏡が稼働しており、1970 年代にはすでに世界の大望遠鏡がハレー彗星の回帰検出の一番乗りを目指していたという。
実際に検出されたのは1982年10月で、近日点通過の3年半近く前のことであった。Yeomans の予測に対してわずかに角度の 8" の違いであったとのこと。
この時に多くの人々にとって「黒船」となったのは CCD が使われたことだった (CMOS が一般的になる前は民生用の撮像素子として用いられるようになったのもよくご存じであろう。CCD の発明に関連して 2009 年のノーベル物理学賞が与えられた)。
この回帰を日本で初めて観測 (1984) したのはアマチュア天文家で、発表された写真に不自然な部分があるとの指摘もあるが公式記録として残されているはずである (現代の技術で解析すれば判断できると思うが...)。日本のプロの天文学者が観測に成功したのは翌年になってからであった。
当時はすばる望遠鏡はもちろんなく、日本の天文学者が使える大型望遠鏡は事実上なかったのである。
さてハレー彗星探査計画に戻ろう。唯一の大型彗星を直接訪れる 76 年に一度のチャンスをみすみす見過ごすことは考えられず、宇宙時代の始まりの時期でもあり早い時期からさまざまな計画が考案されていた
(さらに遠くからやってくる彗星にはヘール・ボップ彗星のようにさらに大型のものがあるが、これは予測不可能なので現代の技術でも探査機を計画的に飛ばすことはできない)。
一番の問題は惑星のように軌道が正確に定まっていないこと、彗星は大きく広がって見える (コマと呼ぶ) ので中心核がどこにあるのか地上観測からでは十分な精度で求めることができないこと。
そして探査上問題となるのはハレー彗星は地球などと逆方向に公転していることである。これは高速道路で対向車線の車を詳細に撮影するようなもので、相対速度が極めて大きくごく短時間しか観測できない。
この欠点を補うために探査機を木星に飛ばし、その重力を利用してハレー彗星と同じ方向に公転させるアイデアもあったが当時の技術や時間的余裕では不可能であった。結果的に探査機は正面衝突方向で観測することとなった。
近日点通過の3年半近く前に検出され、かなり正確な到達時刻がわかったために探査機の計画や打ち上げには時間的余裕があったが、実際に接近した時に彗星の中心核の位置をどこまでの精度まで追い込めるかが成功の鍵となる。
1982年の検出以来アメリカ NASA のジェット推進研究所 (JPL) が中心となって "International Halley Watch" というプログラムを開始した。これはプロもアマチュアも問わずハレー彗星回帰の全観測記録を残そうというプロジェクトで、もちろん観測によって軌道をさらに正確に求めて探査成功に活かす目的がある。
自分も当時アマチュア天文家だったのでこのプロジェクトに参加し、報告に残されているはずである。暫定的な終了後個々の観測者に報告集が送られてきたのはさすがにアメリカと思った。
当時宇宙探査の "本家" であったはずのアメリカはこの国の特徴で議会勢力次第で科学政策も変わり、当時は有人探査 (スペースシャトル) を中心にせざるを得ない状況で、独自でハレー彗星への探査機を送り出すことはできなかった。つまりアメリカは後方支援に徹することになった。
代わって主役となっていたのがヨーロッパで、「ジオット」(Giotto) 探査機で、1301 年に出現したハレー彗星をパドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂の壁画のモチーフに描いたイタリアの画家ジョット・ディ・ボンドーネにちなむとのこと (wikipedia 日本語版)。世界の研究者がハレー彗星探査を成功させようと誓いあったパドヴァの契りというのがあったはずだが現在調べても見つけられなかった。
この探査機は人類がまだ見たことのない彗星核に近づき映像や観測データをとるものであったが、何しろ高速の正面衝突 (68 km/s、毎時でなく毎秒である。時速 24.5 万 km に相当) で彗星のちり (ダスト) と衝突して破壊されるおそれも多分にあり、幾重もの防御機構が用意されていた。
さて問題となる軌道の精度である。1986 年のハレー彗星は太陽の向こう側で近日点を迎え、世界のどこからも観測できない期間がしばらく続いた。探査機はもちろんすでに打ち上げられていたが、彗星が見えない期間中に分裂などの現象で軌道が変わってしまうこともあり得る。探査機の接近まで1か月の猶予もなかったが確認することは至上命題であった。
近日点通過後は彗星は南半球の空に移り、世界で初めて近日点通過後の姿を捉えたのは大望遠鏡を持つ南米のヨーロッパ南天文台であった。明け方の地平線近く、通常は天体観測を行わないような条件で撮影された画像はヨーロッパの意地も感じられるものであった。
この観測によって軌道の精度も確認されることとなった。
ジオット探査機の到着の一足前にハレー彗星に向かったのがソ連のベガ2機である。これは大変欲張ったミッションでまず金星に向かって着陸探査機と探査プローブを分離し、金星の重力を利用してハレー彗星に向かうものであり、ベガの名称はロシア語の金星とハレー彗星の頭文字の合成。いずれの探査にも成功して当時のソ連の技術力を見せることになった。
ジオット探査機よりは 10 倍程度遠くからで、解像度も低いものであったが、ハレー彗星の核の映像を人類は初めて目にすることになった。
しかしこの直接撮像は大変大きな意味を持っていた。地上からは広がった彗星に隠されて中心核の位置はわからないが、近づいて撮影すれば位置がわかる。ベガ探査機の映像と探査機の向きの情報などから方向はわかる。しかし探査機の正確な位置はわからない。ハレー彗星やベガ探査機は南半球にあってソ連など北半球からの測定には向いていない。
そこで協力したのがアメリカの南半球の電波望遠鏡ネットワークで、複数の電波望遠鏡での測定を組み合わせることで精密な位置を測ることを可能にしたのである (大まかに言えば三角測量のようなものである)。これはパス・ファインダー計画と呼ばれていた。
これも言うは簡単だが当時はインターネットなどはないに等しく、データのやりとりは磁気テープを飛行機で輸送するなどして行っていたはずである。
探査機の画像や飛行データなどを迅速に解析し、NASA に送って探査機の位置の計算やハレー彗星の核の軌道計算などが行われ、限られた時間 (ベガ1号の接近とジオット到着は 10 日しか違わない) の中でジオット探査機の最後の軌道修正に間に合わせたはずである。
考えられないほどの軍事機密データに相当するものが交換されていたのだろう。
計画ももちろん長い時間をかけて事前準備されていたのだろう。
結果的にジオットミッションは大成功を収め、ハレー彗星の核から 596 km まで近づいて画像撮影や科学データの取得が行われた。探査機がいつ破壊されるかわからないため映像もデータも同時中継である。
ハレー彗星の核への最接近は日本時間の午前で、ニュースの時間を含めハレー彗星からの生中継がお茶の間 TV に映されることとなった。自分もその早朝にハレー彗星を観測して朝から TV 中継を見ていたのだが、
月からの中継はともかく、惑星間空間からの生中継はこの後に行われた例を知らず、あるいは唯一かも知れない。
当時生中継の解説を担当した "専門家" も、もちろん見たことのない映像であまり正しい解説をしていなかったように記憶している。
探査機のカメラも一番明るい方向を向くようにプログラムされており、彗星の核はほとんど真っ黒であることがわかったのはデータを解析してからになった。そのため最接近の時は核そのものを捉えたものではなかった。
生中継では突然画像が乱れ、これが噂されていた衝突による破壊かと思われたが、大きな粒子と衝突して向きが変わってしまったことが後に判明した。探査機はその後自律的に方向修正を行い地球との通信を回復したがカメラの機能は失われ、通信途絶の間のデータは得られなかった。
このように書くと彗星の核の映像を撮影することが最も重要な目的にようにも読めてしまう。wikipedia の解説などにもそれ以上のことはなかなか書かれていない。
それはもちろん最大の任務の一つではあったが、科学者が特に興味を持っていたのは彗星の組成である。
生命を育んだ地球の海はどこから来たのか。原始地球に彗星などが多数ぶつかって海を形成した考え方があるが、彗星からやってきたか実証するためには実際に調べるしかない。
彗星から放出された物質はすぐに太陽光にさらされて分解し、彗星特有のコマや尾を形成する。分解後の物質の観測から彗星に炭素、水素、酸素、窒素を持つ有機物が存在することは確実であるが、これは地上の生命の素になったのだろうか。
直接に調べるには近くに到達して化学組成を分析するのが一番確実である。多数の周期彗星があるがハレー彗星が特に選ばれたのは大型かつ活動が活発で比較的若い彗星と考えられるため、長年太陽の周囲を公転して表面が蒸発し "ひからびた" 彗星を観測するより始原状態をより的確に知ることと考えられるためである。
化学分析に用いられるのは生物研究にも用いられる質量分析器でこれが大活躍することとなった。
結果的には重水素の比率が異なり、ハレー型彗星が地球の海の起源とならないことがわかった。
この目的のためにはなるべく接近して "生の" 物質を調べたいわけだがあまりに接近すると探査機が破壊される可能性が高くなる。この妥協点ととしてとられたのが 596 km という数字だったわけである。68 km/s の相対速度を考えるとこれがいかに近い距離で、実質的に探査できる時間の短さを理解いただけるだろう。
NASAのスターダスト (2004 年に別の彗星のサンプルを得て 2006 年に帰還)、
日本の「はやぶさ」「はやぶさ2」探査機も小惑星のサンプルを持ち帰ったわけだが、これらの目的はハレー彗星探査とまさしく同一線上にある。原始時代の地球にもたされた水や有機物を知りたいのである。
その先にはもちろん生物がどのように誕生・進化したのか知りたい大命題があり、宇宙への興味は生物学に戻ってくる。生物に興味があるからこそ宇宙を調べているのである。すでに十分長いのでこの先は別項目としよう。
さらに少し脱線して触れておくと太陽系の歴史の中で地球のような惑星がどのように生まれたのかはかつてはそれほどよくわかっていなかった。月探査以前は月のクレーターがどのように生まれたのかまだ異論もある時代で、隕石の衝突とする説 (外因説)、火山活動によるとする主に日本の説 (内因説) があった。
日本の説は京都大学の天文学を率いる研究者が唱えていたものだが、当時の日本の書籍ではクレーターと呼ばず火口と呼んでいた。この 主に西洋の外因説 / 東洋の内因説 の関係はこれだけにとどまらず、天文学の他の分野でも、また生物の進化や大絶滅の解釈としてもたびたび現れることになる。
結果的にはどちらが正しいかは研究を通じて明らかになるものであるが、比較的最近まで例えば恐竜大絶滅は日本の大手メディアでも内因説に基づいた解説がなされていたなど
(しっかりしたカラー印刷の本まで手に入る。付記: 調べてみてこの話はもう少し複雑であることがわかった。[#鳥類系統樹2024]」参照)、学問や西洋/東洋の自然観の違いが現れているようで意識して読まれると面白いだろう。
月のクレーターについてはアポロによる直接観測が得られ、衝突によるものであるものであることを疑う研究者は現在はおそらくほぼないだろう。
太陽系の古い時期は多分 "ぐちゃぐちゃ" だっただろうから隕石が多数飛び交っていたのだろうな、とか考えて納得するのは素人的考え。学問の世界ではなぜそれほどの隕石が降り注いだのか理由を考える必要がある。
ヒントはアポロ計画で集められた月の石の年代測定の結果にあった。41-38 億年前の時期に衝突がまとまって起きていたことが明らかになってきたのである。この時期の存在は多くの研究者が認めており「後期重爆撃期」(late heavy bombardment, LHB) と呼ばれる。この時期には地球にも多くの彗星や小惑星が衝突していたと考えられ、生命の起源や進化にも影響を及ぼしただろうと考えられる。
現在盛んに研究されている分野である。最古の生命の痕跡とされるのはこの数字よりは少し前とされ、全生物の共通祖先の LUCA はもっと古いと考えられている。皆さんはこれらの数字をどう考えられるだろうか。
後期重爆撃期の概念が特に注目視されるようになったのは有力な機構が近年提唱されたことに由来する。従来は惑星は形成された場所付近を公転するだけと考えられていたのだが、(太陽) 系外惑星 (exoplanet) の偶然の発見
(1995 年。当時は太陽以外の恒星の惑星は検出不可能と考えられおり組織的探索は行われていなかった。この発見は 2019 年ノーベル物理学賞を受賞することになる)
に伴い、「惑星は生まれた場所から移動する」(planetary migration。惑星が公転で移動することとは別で、惑星と太陽や恒星の間隔が長期間で大きく変わること) ことが次第に明らかになって太陽系の描像も大きく変わっていったのである。
この可能性に気づいて木星 (現在の公転周期 12 年) と土星 (現在の公転周期 29 年) が移動して周期の比がちょうど 1:2 になった時に両者が強力な共鳴作用を起こして太陽系の姿を大きく変え、天王星と海王星の順序が入れ替わり後期重爆撃期をもたらしたのだろうとの奇抜で革新的なアイデアが 2005 年に Nature に発表された
(Gomes et al. Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets)。
提唱地の地名に基づき「ニースモデル」(Nice model) とも呼ばれる。
このモデルは従来説明困難であった太陽系のさまざまな特徴を一気に説明できる可能性があり、一種のコペルニクス的転回とも言える。地球の生命誕生の必然性、あるいは逆に困難性を論理的に説明できるかも知れない時代がやってきたのだ。
アイデアはそのままに、もっと早い時期に起きていたとの考察もある: Mojzsis et al. (2019) Onset of Giant Planet Migration before 4480 Million Years Ago。
生命初期進化にもまさしく関わる話であり、この分野にも注意を払っておいてよいだろう。またこの程度の知識があると宇宙や生命に関係する科学記事も一層楽しめるだろう。
ジオットミッションに戻ると、1971 年のハヤブサとハンマーほどには一般的に象徴的な意味はなかったかも知れないが、背景を知る者にとってはわずか 15 年で国際協力、特に東西協力こそが世界の主役となることを象徴させるできごととなった。ゴルバチョフのソ連書記長時代と関係があるかも知れないが就任は 1985 年であり、さらに以前から西側との協力関係が進められていたことになる。
この成功と東西協力は (政治家にはあまり関係なかったか、あるいは迷惑だったかも知れないが) 科学者のおそらく多くは両手を挙げて歓迎したであろう。当時の Nature 特集号の誇らしげな扱いが物語っている。
そしてベルリンの壁崩壊 (1989) を次の歴史的大事件として知ることになった。
イヌワシの子殺し (#イヌワシの備考参照) に出てくるドイツの Meyburg もまさしくこの時代に生き、しかも今も活躍中の人である。
しかしこの間には少し異なった出来事もあった。ハレー彗星最接近前の1986年1月のスペースシャトルチャレンジャー号爆発事故、そして1986年4月のチェルノブイリ原子力発電所事故である。
これらだけを見て科学技術への不信感を持たれた方も多いだろう。アメリカは同年1月にボイジャー探査機による天王星探査を成功させていたが (これは 1970 年代の遺産とも言える)、これもジオットミッションやベガ探査機の成功も吹き飛んでしまうような出来事だった。自分も双方を知る時代に生きて位置づけが悩ましかったことを覚えている。
チェルノブイリ原子力発電所事故について、後日アメリカの Discovery Channel のドキュメンタリーで事実を知ることになってしまった (もちろん福島事故の前)。最初に見たものとは違うバージョンだが英語字幕も付けられているので紹介しておく: The Battle of Chernobyl - Full Documentary (2006)。
初めて見た時は6部作だったように覚えているが、思わず最後近くまで連続して見てしまうほどの驚くべき内容であった。これほどの大事故を世界が経験したことがなかったために放射線による障害の恐ろしさなどを知らずに対応に当たったらしいことなどは世界から批判を浴びても不思議ではないが、
ゴルバチョフ書記長の演説やインタビューを見ると我々が報道などから持っていただろう印象とはまったく違う責任感を持って対処していたことがよくわかる。未曾有の大事故である。制御不能になった核燃料が何を起こすかは誰にもわからない。もし地下に及んで放射性物質が流れ込めばドニエプル川が汚染され、下流のキエフ (キーウ) や黒海まで人が住めなくなるかも知れない。
さらに核燃料が大規模な臨界と爆発事故を起こせばヨーロッパ中に人が住めなくなるかも知れない。
それらを阻止するための壮絶なプロジェクトの記録である。政治的な解釈はともかく、これだけ大規模の事故を起こし対応に総力を注げばソ連崩壊も必然と思えた。原子力大事故の後は処理が極めて困難であることは 40 年近く経た今でも根本的に変わっていない。
もう一つ非常に印象的だったのが、1986 年当時にニュースなどで盛んに伝えられていたことと真実があまりに違うことであった。当時は偵察衛星による情報として、アメリカによれば...と情報が日々垂れ流しされていたが、結果的にはソ連発の情報が正しかったところがいくらでもあった。
かつては 1986 年の日本のテレビニュースの映像などが YouTobe に掲載されていたこともあり、上記記憶を裏付けてくれたが福島事故の後消されてしまった。都合の悪いことでもあったのだろうか。
これほどのプロパガンダを見てしまうと昨今のニュースもにわかには信じがたい部分もある。少なくともニュースソースには気を配った方がよいだろう。
ロシア・ウクライナ問題も見ていて気になるところとして、ジオットミッションのような東西の歩み寄りをあまりも軽視しているのではないかと思えることがある。
今でも宇宙開発 = 国家間競争 の図式が当たり前のように語られている 1960-1970 年代の価値観が健在である中、他分野でもロシアからのメッセージを徹底的に無視するか国威発揚と解釈してきたことも遠因にあるとする論考 (どなたかであったかは忘れてしまったが京都新聞で読んだ) もある程度成り立つのではないかと感じる。
「月に行ったハヤブサ」「ジオットミッション」「チェルノブイリ」と見てきた素直な感想である。
新型コロナウイルスでも世界初のワクチンはロシアが開発し、医学のトップジャーナルに治験結果も掲載されたにもかかわらず西側は有効なワクチンと認めなかった。
ロシアやソ連で開発されたゆえに品質が悪いと言えるわけではなく、日本でもポリオ (急性灰白髄炎) の大流行に際して 1961 年にソ連からワクチンの緊急輸入が行われている。中国のコロナワクチンは当初有効なワクチンと認めなかったが渡航者を求めるようになると有効なワクチンに含められたらしい。科学は置き去りである。
新型コロナウイルスの時もロシアのメッセージを適切に受け止めていればあるいは現在の事態は起きていなかったかも知れない。
政治は知らないが宇宙などの科学に詳しい者の感想として見ていただければと思う。
[オナガハヤブサの共同狩猟]
オナガハヤブサ Falco femoralis 英名 Aplomado Falcon は少し離れているがハヤブサの系統ともみなせる南米に生息する種類。aplomado はスペイン語由来で鉛色を意味する (動詞 aplomar の過去分詞 = 英語動詞 plumb に対応。これも鉛の重りに由来する)。
Borges and Coulson (2023)
Trio of Aplomado Falcons Captures a Swallow-Tailed Kite に3羽でツバメトビ Elanoides forficatus 英名 Swallow-tailed Kite (#カタグロトビの備考参照。ハチクマに近い系統の種類) を襲っておそらく捕食したと考えられる報告がなされている。
猛禽類でペアでの狩猟は知られているが、3羽以上で共同狩猟はほとんど知られていない [モモアカノスリ (ハリスホーク) が有名で、この共同狩猟が見つかった時には哺乳類以外で初と大きな話題になった。#トビの備考 [ノスリ亜科 Buteoninae の系統分類] 参照]。
Observation remarquable de trois Faucons aplomados poursuivant et capturant un Naucler a queue fourchue au Bresil に映像が紹介されている。
[グレリン遺伝子を失ったハヤブサ類]
Seim et al. (2014) Comparative analysis reveals loss of the appetite-regulating peptide hormone ghrelin in falcons
によれば、胃から産生されるペプチドホルモンで下垂体に働き成長ホルモン (GH) 分泌を促進し、また視床下部に働いて食欲を増進させる働きを持つグレリン (ghrelin) (wikipedia 日本語版より) がハヤブサとワキスジハヤブサで失われていることがわかった。
共通祖先段階でおそらくウイルス由来のレトロトランスポゾン (ERVK) が挿入されて機能が失われたとのこと。
ヒトやマウスでは食欲増進機能があるが、ニワトリやウズラでは逆に抑制するとのこと。論文の著者はおそらく他の鳥類でも同様であろうと考えているが、グレリンには食欲以外にも様々な働きがあり、鳥類では脂肪蓄積にも関係しているとのこと。
ほとんど肉食の猛禽類の代謝についてはわかっていないことが多いが、胃腸運動を抑制することで時間をかけた完全な消化を助けているのかも知れないとのこと。よく似た働きのモチリン (motilin) が機能を代替している可能性もある。
この研究で調べられている他の猛禽類はメンフクロウとヒメコンドルでこれらはいずれもグレリン遺伝子を保持していて、ハヤブサ系統に独特のものかも知れない (類縁関係のあるオウム類やスズメ目は調査されていない)。
その後の研究で何とスズメ目の Eupasseres で失われたことがわかった: Prost et al. (2025) The unexpected loss of the 'hunger hormone' ghrelin in true passerines: a game changer in migration physiology
Eupasseres が Acanthisitti から分岐した 5000 万年前以降に起きた。しかし受容体は健在でよく保存されており、別の (おそらく) ホルモンがグレリンを代替するようになったと考えられる。
例えばグレリンであればフィードバック反応が働いて脂肪の蓄積を妨げる可能性があるが、その反応を起こさない方法で渡りの際に大量の脂肪を蓄積可能にしたなどが考えれるとのこと。
公開ゲノムを用いているがゲノム読み取りの精度の問題もあり、特定の遺伝子を持たないことを確認することはなかなか難しいよう。
この研究を受け入れると我々が通常見聞するスズメ目のすべての系統で失っていると考えられる。スズメ目で特異的に起きている理由は、小型で渡りに際して相対的に大量の脂肪蓄積が必要になるなど考えられ、このメカニズムを獲得することでこの系統が繁栄している可能性があるとのこと。
スズメ目と Falco 属は独立に失っており、後者ではレトロトランスポゾン挿入によるものだがスズメ目では同様の証拠はなかったとのこと。スズメ目とハヤブサ目の系統的関係を反映するものではなさそう。
[ハイイロハヤブサの行動様式と食性]
Schoenjahn et al. (2022a) Low activity levels are an adaptation to desert-living in the Grey Falcon, an endotherm that specializes in pursuing highly mobile prey
によればオーストラリアのハイイロハヤブサはハヤブサのほどに活発な空中の狩りを行わず、高温環境下でオーバーヒートを避けているのではとのこと。比較的湿度の低い地域に生息するのも蒸発によって熱を逃しやすいためか。
Schoenjahn et al. (2022b)
Has the Australian Endemic Grey Falcon the Most Extreme Dietary Specialization among all Falco Species?
によればほとんど鳥しか食べないとのこと。ホバリング飛行から襲う様式を持たないことや脚の短さも地上の獲物を狙うには適していない。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ヤイロチョウ科 PITTIDAE ▽
-
ズグロヤイロチョウ
- 学名:Pitta sordida (ピッタ ソルディダ) 汚れた小鳥
- 属名:pitta (合) 小鳥 (pitt 小鳥 テルグ語)
- 種小名:sordida (adj) 汚れた (sordidus)
- 英名:Hooded Pitta
- 備考:
sordida のアクセントは冒頭 (ソルディダ)。
インド北部、ネパールから東南アジアに分布。世界に 12 亜種が認められている (IOC)。日本で記録された亜種は cucullata (「帽子をかぶった」の意味) とされる。
[旧世界亜鳴禽類の進化と生物地理学]
Selvatti et al. (2016)
An African Origin of the Eurylaimides (Passeriformes)
and the Successful Diversification of the Ground-Foraging
Pittas (Pittidae)
に Pitta 属を含む分子系統解析があり、アフリカと南アメリカが地続きであった時代に共通祖先を持ち (2800 万年前)、その後の進化はアフリカを中心として進んだ。
地上採食タイプのこれらのグループ Eurylaimides (Old World suboscines = Eurylaimidea 上科 旧世界亜鳴禽類 ヒロハシ下目またはヒロハシ上科) はまだスズメ目スズメ亜目 (Passeri, oscines) が到達していなかった地域で分布を広げたが、オーストラリアにはすでにスズメ亜目が分布していたために定着できなかったとの仮説を述べている。
ただし系統樹サポートは低めで地理的分布も考慮したシナリオを作っている。他の Eurylaimides がアフリカと東南アジアに存在しない中で、ズグロヤイロチョウから分化したグループのみが唯一が定着しているのは、あるいは渡り能力で比較的近年到達した可能性もあると考えている。
Ericson et al. (2019) Genomic differentiation tracks earth-historic isolation in an Indo-Australasian archipelagic pitta (Pittidae; Aves) complex
にインド-オーストラリアのズグロヤイロチョウの亜種の分化が調べられている。
近縁のヤイロチョウを含むグループとしてはアジアの西から東へ (最終的にフィリピンまで) 分布を広げたと考えられ、氷河期の海面低下と上昇に伴う種/亜種の分化が起きたシナリオが考えられる。
ズグロヤイロチョウのグループは渡りを行うものはまれで、渡りの能力は独立に失われたのか祖先が失った可能性があるが区別は難しい (ズグロヤイロチョウは磁気定位にかかわる最有力候補とされる Cry4 遺伝子を失っている。#アマツバメの備考参照。Tyranni 亜鳴禽類 とヨタカ系統はこの遺伝子が失われている種類が多い)。
松村 (2022) Birder 36(11): 4-5 で述べられている地理分布の解釈もこれら研究とほぼ同じシナリオとなっている。ソロモン諸島のカオグロヤイロチョウ Pitta anerythra Black-faced Pitta が東端。
オーストラリア北東・東沿岸と最も南に到達したものがノドグロヤイロチョウ Pitta versicolor Noisy Pitta。さえずりは日本のヤイロチョウと共通点が多く系統上の近さにあまり違和感を感じない。
Harvey et al. (2020) The evolution of a tropical biodiversity hotspot
で核遺伝情報を含めた詳細な分子系統解析が行われ、この系統の系統樹はほぼ定まったと考えてよいらしい。
Harveyetal2020_Fig1_tree_HiRes.pdf
にこの論文の系統樹の高解像度版があるが相当拡大しないと文字が見えない。
Boyd はこの系統樹 (と他の情報) を用いた分類を提供しているのでここではそれを紹介する。
ヒロハシ下目 Eurylaimides: Old World Suboscines (そのままの名称では旧世界亜鳴禽類であるが新世界に分布するものも含まれる)
マミヤイロチョウ科? Philepittidae Sharpe, 1870: Asities (マダガスカル)
マミヤイロチョウ属 Philepitta (2種)
ニセタイヨウチョウ属 Neodrepanis (2種)
ヒロハシ科 Eurylaimidae Lesson, 1831: Eurylaimid Broadbills
アフリカミドリヒロハシ亜科 Pseudocalyptomeninae
アフリカミドリヒロハシ属 Pseudocalyptomena (コンゴ東部のルワンダ境界近くのみ)
ヒロハシ亜科 Eurylaiminae
オナガヒロハシ属 Psarisomus (インド北部から東南アジア大陸部)
ガマヒロハシ属 Corydon (マレー半島からスマトラ、ボルネオ)
モンツキヒロハシ属 Sarcophanops (2種。フィリピン)
ギンムネヒロハシ属 Serilophus (東南アジア)
クロアカヒロハシ属 Cymbirhynchus (マレー半島からスマトラ、ボルネオ)
アズキヒロハシ属 Eurylaimus (2種。属名はタイプ種より)
アフリカヒロハシ科 Smithornithidae Bonaparte, 1853: African Broadbills
アフリカヒロハシ属 Smithornis (3種。アフリカ中部から南部森林地帯に広く分布)
ミドリヒロハシ科 Calyptomenidae Bonaparte, 1850: Asian Green Broadbills
ミドリヒロハシ属 Calyptomena (3種。マレー半島からスマトラ、ボルネオ)
ヒロハシマイコドリ科 Sapayoidae Irestedt et al., 2006: Sapayoa
ヒロハシマイコドリ属 Sapayoa (パナマからエクアドル)
ヤイロチョウ科 Pittidae Swainson, 1831: Pittas
(パプアヤイロチョウ?)属 Erythropitta (15 種。マレーシア、インドネシアからニューギニア、一部オーストラリア北部)
ツノヤイロチョウ属 Anthocincla (1種、Hydrornis属より分離。ミャンマーからカンボジア)
アオエリヤイロチョウ属 Hydrornis (11 種。東南アジア大陸部からスマトラ、ボルネオ。属名はタイプ種より)
ヤイロチョウ属 Pitta (16 種。アフリカからオーストラリア、中米から南米北部に一部分布)
このうち山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類
に名称があるものはヒロハシ科、ヤイロチョウ科のみだが、上記で使われている科は記載の通り過去に提唱されたことがあるものである。
ヒロハシ科はコンサイス鳥名事典によるとスズメ目の中では最も原始的とされ、頸椎は 15 個 (他のスズメ目は 14 個。Olson によると脊椎の数が違うわけではなく完全な肋骨が一つ少ないとのこと)、後趾屈筋の腱が他の3趾と細い糸状の腱で連結されている、腸の回転型も特異など解剖学的特徴で違う点が多いとのこと。
cf. Olson (1971) Taxonomic Comments on the Eurylaimidae。
属分類は Anthocincla のみを除き IOC と一致する。この1種はかなり離れているので属相当としてもよいのだろう。
名称がほぼ自動的に決まるものは与えてある。種数は Boyd の分類に基づく。
Erythropitta はタイプ種が Erythropitta macklotii でパプアヤイロチョウの和名が出てきて英名と整合するが Erythropitta属は和名がない種類も多いため仮に与えてある。
このグループの種数が非常に多いのは、great speciator であることを反映している (#メジロの備考参照)。
スールーヤイロチョウ (ノドグロムネアカヤイロの和名あり。コンサイス鳥名事典) Erythropitta yairocho Sulu Pitta は アカハラヤイロチョウ Erythropitta erythrogaster Philippine Pitta の亜種ともされるがここでは別種扱いになっている。
yairocho と付いているが日本語由来の亜種または種小名でヤイロチョウの学名ではない。
[亜鳴禽類の睡眠中の発声]
鳴禽類の睡眠中に音声発声の脳の回路が働くことは知られているが、亜鳴禽類についての報告が最近なされた。Doppler et al. (2021) Replay of innate vocal patterns during night sleep in suboscines
によれば南米のキバラオオタイランチョウ Pitangus sulphuratus Great Kiskadee で夜に昼の音声の一部を発声し、鳴管筋の働き、体もディスプレイのように一部動くとのことで、赤外線カメラ、呼吸モニターから睡眠中と考えられるが、REM 睡眠か NREM 睡眠のいずれかまでは判定できなかったとのこと。音声は昼間のものとは違いがあるとのこと。
これまでは鳴禽類が睡眠中に発声回路を働かせることで学習を深めていると考えられてきたが、学習を必要としない音声を睡眠中に発声する機能はそれに先立って生じたものと考えられるとのこと。
あるいはヤブサメの夜鳴きも同様に寝ながら鳴いているのかも知れない。
-
ヤイロチョウ
△ スズメ目 PASSERIFORMES モリツバメ科 ARTAMIDAE ▽
-
モリツバメ
- 学名:Artamus leucorynchus (アルタムス レウコリュンクス) 白い嘴の屠殺者
- 属名:artamus artamos 屠殺者 (Gk) モリツバメは以前 swallow-shrikes ツバメとモズの両方の特徴を持つ鳥との名前があった
- 種小名:leucorynchus (合) 白い嘴の (leuko- (接頭辞) 白い rynchos 鼻口部 Gk) (種小名の確定について備考参照)
- 英名:White-breasted Woodswallow
- 備考:
artamus は起源となるギリシャ語は短母音のみでアクセントは冒頭。ラテン語読みでもし長音にしない場合は発音規則から先頭にアクセントが置かれるのでこの読みを採用した (アルタムス)。ラテン語で別の意味の artamus の単語があって中央の a が長母音だがこちらは動詞の変化形のため除外した。
leucorynchus は起源となるギリシャ語は短母音のみで -ryn- がアクセント音節と考えられる (レウコリュンクス)。
フィリピンからオーストラリアに分布。9亜種が認められている (IOC)。日本で記録されたものは基亜種 leucorynchus (フィリピンに広く分布する普通種留鳥) とされる。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では
leucorhynchus (Mayr 1962) や leucorynchus (Dickinson 2003) の綴りは正当化されないとのことで、種小名・亜種名を leucoryn としている。HBW/BirdLife はこの学名を用いている。
記載時の学名は Lanius leucoryn. Linnaeus, 1771 であった:
Regni Animalis Appendix. Aves (p. 524)。
"leucoryn." の最後のピリオドが短縮形かどうかが問題となっているようで、ICZN (2017) Case 3715
によれば短縮形と判定された。記載時学名は Lanius leucoryn. と書くのが正しい。非省略の表記では leucorynchus 以外は除外されると裁定した。
ICZN (2017)
Case 3715 - Punctuated avian species-group names as abbreviations in the zoological appendix of Linnaeus' Mantissa Plantarum Altera, 1771: proposed conservation of leucorynchus and mascarinus as justified emendations of their respectively punctuated original spellings as Lanius leucoryn. and Psittacus mascarin.
によれば David and Dickinson (2013, 2014) Howard and Moore 4th edition が leucoryn が正当であると使い出した張本人のようで、リストでもそのまま残しているのであろう。
この ICZN (2017) 論文では In 2013 and 2014, David and Dickinson resurrected usage of ... という表現になっており resurrect は古いものを復活させるの意味。
表現は抑えているが、David and Dickinson が見逃していることへの論調を見ても「(終わった話を) 蒸し返してきた」ぐらいの語感も込めて使っているのでないかと想像する。
和名のモリツバメは英名の Woodswallow (かつては Wood Swallow と分けていた) を訳したと考えると納得できる。
OED によれば Wood Swallow の用例は新しく、1854 年に Adams et al., Manual of Natural History が Artamidae にこの英名を付けたのが最初。Swallow-Shrikes の用例も特に古いわけでなく 1887 年の百科事典に登場。海外の鳥なので用例が遅くなった模様。
英名と学名の対応がよくないが、英名は現在は亜種となっている記載時学名 Ocypterus albiventer Lesson, 1830 (下面の白い) 由来ではないだろうか。記載年代も古く、Linnaeus (1771) の用いた学名が有効と判断されるまではこちらが使われていたのではと想像する。
Linnaeus (1771) の学名の意味と外見があまり合わないので現在もこの英名が使われ続けているのだろう。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3743-3744 のモリツバメの項目 (内田) によれば、いろいろ特殊な点がある。列挙すると、粉綿羽 (powder downs) がありスズメ目の他の鳥では見られない。
高く舞い上がることができてカラス類を除くスズメ目では唯一帆翔ができる。
ホオグロモリツバメ (当時の名称でシロエリモリツバメ) Artamus personatus Masked Woodswallow はミツバチを食べるので養蜂家に嫌われる。
びっしり並んで集団ねぐらを作る。
パプアモリツバメ Artamus maximus Great Woodswallow で1羽のひなを 4-5 羽の成鳥が養っていた記録があるとのこと。
[オオハシモズ科]
モリツバメの含まれる系統の ヤブモズ/モリツバメ上科? Malaconotoidea にオオハシモズ科 Vangidae: Vangas が含まれる。マダガスカルに生息するものだが、日本の研究者と縁が深いのでとりあげておく。
Yamagishi et al. (2001) Extreme endemic radiation of the Malagasy vangas (Aves: Passeriformes)
が基礎となった論文。
Jonsson et al. (2012) Ecological and evolutionary determinants for the adaptive radiation of the Madagascan vangas と
Reddy et al. (2012) Diversification and the adaptive radiation of the vangas of Madagascar
がオープンアクセスで読みやすいのでモリツバメ科との関係も含めて見やすいだろう。
オオハシモズ科が単系統である、すなわち Yamagishi et al. (2001) が示す通り1回の導入によるもので、様々なニッチに適応放散したことを裏付ける。
Newtonia 以降の属がこの系統になる。Newtonia 属はかつてはウグイス科またはヒタキ科とされていたがまったく関係がないことがわかった。
Philentoma 属 (2種) は東南アジアの種で、Newtonia 以降と同じクレードに属するため扱いが難しい。現在は通常オオハシモズ科に含められているが、生物地理があまりに異なるので Boyd のように別科を与えているものもある。
チャバネアカメヒタキ (チャイロジュウイチの宿主として登場) の名前の通り従来はヒタキ科とされていた。
1属の間でここまで大きな違いを生み出せることは驚きである (山岸氏もダーウィンフィンチに匹敵すると述べられている)。
マダガスカルの鳥 (マダガスカル研究懇談会) に解説がある。
日本語の書籍は「アカオオハシモズの社会」(山岸哲 京都大学学術出版会 2002)。「これからの鳥類学」第 14 章で系統解析や適応放散を読むことができる。
山岸氏はオオハシモズ科の姉妹群はメガネモズ類 (helmetshrikes、Prionops属で現在は通常オオハシモズ科に含められる) やヤブモズ科 Malaconotidae ではなくオーストラリアのフエガラス類 (亜科) Cracticinae ではないかと推定されているが、現代の分子系統解析ではむしろ否定的となった (分類表記は新しいものを用いた)。
メガネモズの和名はドイツ語の旧名 Brillenwuerger (そのままの意味) 由来とのこと (コンサイス鳥名事典)。
オオハシモズ科 Vangidae の名称の歴史的経緯についての考察もあり (pp. 358-359)、Swainson (1831) は古すぎて確認できないとのことだった。
Swainson and Richardson "Fauna Boreali-americana: The Birds" London: J. Murray, 1831 p. 171 で Vangae の名称が使われたのが最初とのこと (wikipedia チェコ語版に出てきてこの文献へのリンクあり。英語などのメジャーな言語版では見当たらず。タイトルには 1831 年と題されているが実際の出版は 1832 年でこちらを用いているものもある)。
wikipedia チェコ語版の解説によれば、これは単なる属の複数形の意味でさらに上位の分類の名称を示したものではないだろうとのこと [Olson (1995) Review of History and Nomenclature of Avian Family-Group Names の解説に従う。
Bock (1994) History and nomenclature of avian family-group names. Bulletin of the AMNH; no. 222 が Vangidae Swainson, 1831 を認めたことへの批判]。
Fauna boreali-americana, or, The zoology of the northern parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the late northern land expeditions under command of Captain Sir John Franklin, R.N
と似た文献があるが別物のよう。
Delacour (1932) L'Oiseau et la Revue francaise d'ornithologie が Vangides のフランス名を与えたがラテン語でないため
Rand (1936) The distribution and habits of Madagascar birds: summary of the field notes of the Mission Zoologique Franco-Anglo-Americaine a Madagascar が正しいラテン名を与えた。
山岸氏は Delacour (1932) 以降を示し、Rand (1936) を Vangidae の初出としている。
1936年以前にも Vangidae は使われている [例えば Wetmore (1930) A systematic classification for the birds of the world] ので、おそらく Rand (1936) 以前のどこかの段階で Vangidae の名称はすでに認められていたということだろうか。
いずれの文献も現在はオンラインで読めるので興味ある方はご検討いただきたい。
vanga はマダガスカル語でカギハシオオハシモズ Vanga curvirostris Hook-billed Vanga を指す名称。
Auerbach et al. (2025) Tempo and mode of evolution across multiple traits in an adaptive radiation of birds (Vangidae) (prepint)
島への導入後初期に急激な適応放散を遂げた証拠は見つからなかった。より遅い時期になって複数系統で key innovations が起きて放散が起きたと言える。
["Laniarius liberatus"]
幻の学名となった面白い事例がある。1988 年ソマリアで新種のヤブモズ類 "Bulo Burti boubou" が発見され、貴重な個体を標本にすることは絶滅を招くおそれがあると血液と羽毛サンプルのみを採取して放された。血液と羽毛サンプルは DNA 配列決定のために破壊された。
現代の鳥類学で標本によらない初めての記載となった。
Smith et al. (1991) A new species of shrike (Laniidae: Laniarius) from Somalia, verified by DNA sequence data from the only known individual
DNA 解析の結果、生体を捕獲して標本とすることなく記載可能になったと注目を浴びたが、1個体のみの記載であることが当初から問題視されていた。
新種 Laniarius liberatus の学名 (種小名は「解放された」の意味) が与えられたが、その後の研究でソマリーヤブモズ Laniarius nigerrimus Somali Boubou の色変わり個体であると認識されるようになり、
IOC は 2008 年 Laniarius liberatus を Laniarius nigerrimus のシノニムとし、幻の新種・学名となった (Black boubou の wikipedia 英語版より)。
記載当初のエピソードも現代的で面白いものだったが、1個体で記載することの危険性を明らかにする有名事例ともなった
[Peterson (2014) Type specimens in modern ornithology are necessary and irreplaceable。2000-2013 年に記載された新種の鳥で羽毛のみサンプルが3例、1標本のみが9例とのこと]。
[歌を教育する鳥?]
厳密な意味で鳥に "教える" 行為があるかどうかを定義することは難しい。オーストラリアのノドグロモズガラス Cracticus nigrogularis Pied Butcherbird (モリツバメ科) で、歌の学習に際して積極的に介入を行って "教える" 行為をとっている可能性が報告された:
Taylor (2021) Evidence for Teaching in an Australian Songbird
現代的な定義に従って "教える" 行動の証拠となるのではとの事例を紹介。ヒト以外で "教える" 行動を定義するのは難しいが、ヒトが音楽を "教える" ことに類比することができる事例になり得るとソノグラムや楽譜まで出して紹介している。
若鳥が "騒々しい" 叫び声を出すと親がクリック音を出した記録が出ている。
そういえば思い出したのだが、日本の飼鳥文化でほぼ同様の手法で飼育者が好ましくない鳴き声を矯正することを読んだことがある。この "罰則" メカニズムは実際に働き、鳥の間でも用いられているのかも知れない。
△ スズメ目 PASSERIFORMES サンショウクイ科 CAMPEPHAGIDAE ▽
-
アサクラサンショウクイ
- 第8版学名:Lalage melaschistos (ララゲ メラスキストス) 黒っぽい鳴く鳥の一種 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Coracina melaschistos (コラキナ メラスキストス) 黒っぽいワタリガラスのように黒い鳥
- 第8版属名:lalage lalax, lalagos, lalages は Hesychius の用いた不明の鳥 < lalazo 鳴く (Gk)
- 第7版属名:coracina (adj) ワタリガラスのように黒い korakinos ワタリガラスのように黒い < korax ワタリガラス -inos 形容詞語尾 (Gk)
- 種小名:melaschistos (合) 黒っぽい色の [melas 黒い schistus スレート (#オオセグロカモメの項目参照)]
- 英名:Black-winged Cuckooshrike
- 備考:
lalage は由来となるギリシャ語に長音が含まれないので lalage も長母音を含まないと考えられる。この場合はアクセントは冒頭になる (ララゲ)。
coracina はギリシャ語 korakinos 由来で長母音を含まない。-ra- がアクセント音節と考えられる (コラキナ)。ラテン語の corax も通常は短母音。ラテン語の形容詞を作る -ina の語尾は冒頭が長母音になるがギリシャ語から直接構成されたために長母音にならないものと思われる。
The Key to Scientific Names と wiktionary の意義解説に少し相違がある。前者はギリシャ語でワタリガラスの指小語としている。
類似の属名に Coracias (ニシブッポウソウ) 属がある (#ブッポウソウ参照)。こちらも corax ワタリガラスに由来する実在の鳥を指す。
melaschistos は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-chis- がアクセント音節と考えられる (メラスキストス)。
Coracina 属は Vieillot (1816 年 4 月) の提唱によるものと判定されており、タイプ種は後にパプアオオサンショウクイ Coracina papuensis White-bellied Cuckooshrike と定められた。
ただし Vieillot (1816) には現在の分類では複数のグループが含まれていた。
Swainson (1837) は南米種に限定すべきとアカフサカザリドリ 現在の学名で Pyroderus scutatus Red-ruffed Fruitcrow をタイプ種とするものを提唱したが Cabanis (1853) が現在のタイプ種を提唱した模様。
Lalage 属は Boie (1826) がマダラナキサンショウクイ Lalage nigra Pied Triller のみに対して与えた属。Boie (1828) は同じ属名を別のグループにも与えており、こちらはタイプ種にシキチョウ 現在の学名で Copsychus saularis Oriental Magpie-Robin が指定された。先に用いた方が優先された形になっているがいずれもあまり単純でなかった。
Lalage 属はアサクラサンショウクイ属。lalax, lalagos, lalages は Hesychius の用いた不明の鳥 < lalazo 鳴く (chirp) (Gk)。(The Key to Scientific Names の情報よりまとめ)。
Coracina 属と Lalage 属の関係は複雑で、1属にまとめる場合は先に用いられた Coracina 属となる (第7版学名)。分子系統研究で十分な違いがあることが判明して一部の種を移動して単系統性を保って分離された。
記載時学名 Volvocivora melaschistos Hodgson, 1836 (原記載) 基産地 Nepal。分類がはっきりしておらず他の類縁種に Nipalensis を付けたためここでは使えなかった模様。
Volvocivora 属は Hodgson (1836) が上記記載とともに用いた属名で、volvox (< volvo 回転する) から毛虫のこと。(Volvox 緑藻ボルボックスと同語源だがボルボックスを食べる意味ではない) を食べるの意味。
Hodgson (1836) は複数種を記載するにあたって少し違うものを別属としていた。記載では The principal food is caterpillars and other soft wingless insects ... とある。
4亜種が認められている (IOC)。日本で記録されたものは intermedia (中間の) とされる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Lalage 属に移動。鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。種小名は変化なし。
"アサクラ" の名称は剥製師・採集人の朝倉喜代松由来とのこと [cf. 松田 (2003) Birder 17(8): 31-35]。
Jonsson et al. (2010) Biogeographical history of cuckoo-shrikes (Aves: Passeriformes): transoceanic colonization of Africa from Australo-Papua
の分子系統解析で Coracina 属が単系統でないことがわかり、かなりいろいろなものが混ざっていた。アサクラサンショウクイは Lalage 系統に属することが判明して属名が変更された。
サンショウクイ科では Coracina グループ (Clade A) と Lalage グループ (Clade B) に主に分けられ、これらを core Campephagidae と呼ぶ (大半の種がこれららに属する)。分布もインド太平洋からアフリカで、日本のサンショウクイは地理的にも系統的にも例外的。
Lalage 属の英名は半数弱が Cuckooshrike で残りが Triller と声にちなむ命名になっている。
Coracina 属の英名はすべて Cuckooshrike が付いている。
cuckooshrikes は幼虫を好んで食べることから英語別名 caterpillar birds とも呼ばれる。ドイツ語の Raupenfaenger も同様の意味。サンショウクイ科の和名の印象とはかなり異なる。
オーストラリアのジサンショウクイ Coracina maxima Ground Cuckooshrike はサンショウクイ科唯一の地上性の種。カッコウ類に似た飛び方をする。和名もカッコウサンショウクイの別称がある (コンサイス鳥名事典)。
カッコウ類に似たサンショウクイ科については #カッコウ備考の [カッコウのタカへの擬態] でも取り上げている。
日本のサンショウクイは core Campephagidae の外群のような位置を占め、早い時期に分岐してアジアに分散したと考えられる。
そしてサンショウクイ科の名前から日本のサンショウクイに似たグループを想像するのはおそらく誤解の原因になり得る。
サンショウクイ科に近縁の科もやはりアフリカ、オーストラリアに分布するものが多く、日本にわずかに関係してくるグループはコウライウグイスのグループ程度。
cuckooshrikes と呼ばれるが、カッコウ類にもモズ類にも近縁でない。科としては多くの種類がカッコウ類に似た色彩を持つこと (上記のように Pericrocotus 属は例外的)、カッコウ類に似た飛び方をすることが由来とのこと (wikipedia 英語版より)。
Boyd の分類に従ってカラス小目 Corvida の系統を紹介しておく。新しい研究により科の追加があって後述。
科名があるものは山崎剛史・亀谷辰朗 (2020) 鳥類の目と科の新しい和名 (2) 鳴禽類 を使用。推測できる名称は ( ) に入れてある。
上科の名称は科名から推測。科の順序は鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)とおおまかに同じだが少し入れ替わって部分がある。
このグループはスズメ目の中でも日本鳥類目録 改訂第7版 で大きく変わった部分で従来分類から関連が推察しにくいものが多い。
日本の種類は限られているが、広い意味でカラス類とスズメ類に大別される中でカラス類に属するグループになる。スズメ類よりも系統的に古いのでカラス類は系統分類の最後にならない。
カラス類のグループは Kuhl et al. (2021) による oscine higher-level clades (OHCs) ではすべて [OHC5] になる。スズメ類は [OHC6-10]。
カラス上科 Corvoidea に馴染みのグループがかなり含まれている。モズ科はこちらで、"何とかモズ科" のものは別系統になる。亜科はサンショウクイ科のみ記載。
日本産種の含まれる分類を緑で示してある。
カラス小目 Corvida
(ウズラチメドリ上科?) Cinclosomatoidea
(ウズラチメドリ科?) Cinclosomatidae: Quail-thrushes and Jewel-babblers (Eupetidae より移動)
サンショウクイ上科 Campephagoidea
サンショウクイ科 Campephagidae: Cuckooshrikes
サンショウクイ亜科 Pericrocotinae: Minivets
アサクラサンショウクイ亜科? Campephaginae: Cuckooshrikes
オーストラリアゴジュウカラ上科 Neosittoidea
オーストラリアゴジュウカラ科 Neosittidae: Sittellas
モフアムシクイ上科 Mohouoidea
モフアムシクイ科 Mohouidae: Whitehead & allies
コウライウグイス上科 Orioloidea
ホオダレモズガラ科 Eulacestomatidae: Ploughbill
シラヒゲドリ科 Psophodidae: Whipbirds and Wedgebills
カンムリモズヒタキ科 Oreoicidae: Australo-Papuan Bellbirds
(ハシブトモズヒタキ科) Falcunculidae: Shriketits (科扱いでない場合もある)
カンムリハナドリ科 Paramythiidae: Painted Berrypeckers
(モズチメドリ科?) Pteruthiidae: Shrike-babblers (Boyd 独自)
モズモドキ科 Vireonidae: Vireos
モズヒタキ科 Pachycephalidae: Whistlers
コウライウグイス科 Oriolidae: Orioles, Figbirds
ヤブモズ/モリツバメ上科? Malaconotoidea
ハシビロヒタキ科 Machaerirhynchidae: Boatbills
モリツバメ科 Artamidae: Woodswallows, Butcherbirds
モリツバメ亜科: Artaminae: Woodswallows
フエガラス亜科: Cracticinae: Butcherbirds & allies
フイリモズヒタキ科 Rhagologidae: Mottled Berryhunter
ヒメコノハドリ科 Aegithinidae: Ioras
ブタゲモズ科 Pityriaseidae: Bristlehead
ヤブモズ科 Malaconotidae: Bush-shrikes, Puffbacks
メガネヒタキ科 Platysteiridae: Wattle-eyes, Batises
オオハシモズ科 Vangidae: Vangas
カラス上科 Corvoidea
(ビロードムシクイ科?) Lamproliidae: Silktail, Drongo Fantail (科扱いでない場合もある)
オウギヒタキ科 Rhipiduridae: Fantails
オウチュウ科 Dicruridae: Drongos
ズアオチメドリ科 Ifritidae: Ifrit
フウチョウ科 Paradisaeidae: Birds-of-paradise
カササギヒタキ科 Monarchidae: Monarchs
オオツチスドリ科 Corcoracidae: Australian Mudnesters
クロチメドリ科 Melampittidae: Melampitta
カンムリカケス科* Platylophidae: Crested Jayshrike (東南アジア)
モズ科 Laniidae: Shrikes
シロズキンヤブモズ科* Eurocephalidae: White-crowned Shrikes (アフリカ)
カラス科 Corvidae: Crows, Jays
[#鳥類系統樹2024]の結果は順序に違いがあるので上記をそのまま残して別に記すことにした。以下は Stiller et al. (2024) の配列に従う。
# はサンプリングされていないもの。カラス上科 Corvoidea の方の分岐が早い系統樹となっているが、これが決定版と言えるほどでもないだろうから情報の一つとして見ていただきたい。
Corvides
(ウズラチメドリ上科?) Cinclosomatoidea
(ウズラチメドリ科?) Cinclosomatidae: Quail-thrushes and Jewel-babblers (Eupetidae より移動)
サンショウクイ上科 Campephagoidea
サンショウクイ科 Campephagidae: Cuckooshrikes
サンショウクイ亜科 Pericrocotinae: Minivets
アサクラサンショウクイ亜科? Campephaginae: Cuckooshrikes
(ここまでは変わりなし)
カラス上科 Corvoidea
# (ビロードムシクイ科?) Lamproliidae: Silktail, Drongo Fantail (科扱いでない場合もある)
オウギヒタキ科 Rhipiduridae: Fantails
オウチュウ科 Dicruridae: Drongos
カササギヒタキ科 Monarchidae: Monarchs
オオツチスドリ科 Corcoracidae: Australian Mudnesters
ズアオチメドリ科 Ifritidae: Ifrit
フウチョウ科 Paradisaeidae: Birds-of-paradise
# クロチメドリ科 Melampittidae: Melampitta
# カンムリカケス科* Platylophidae: Crested Jayshrike (東南アジア)
モズ科 Laniidae: Shrikes
# シロズキンヤブモズ科* Eurocephalidae: White-crowned Shrikes (アフリカ)
カラス科 Corvidae: Crows, Jays
ヤブモズ/モリツバメ上科? Malaconotoidea
モフアムシクイ科 Mohouidae: Whitehead & allies
ハシビロヒタキ科 Machaerirhynchidae: Boatbills
モリツバメ科 Artamidae: Woodswallows, Butcherbirds
モリツバメ亜科: Artaminae: Woodswallows
フエガラス亜科: Cracticinae: Butcherbirds & allies
フイリモズヒタキ科 Rhagologidae: Mottled Berryhunter
# ヒメコノハドリ科 Aegithinidae: Ioras
# ブタゲモズ科 Pityriaseidae: Bristlehead
ヤブモズ科 Malaconotidae: Bush-shrikes, Puffbacks
メガネヒタキ科 Platysteiridae: Wattle-eyes, Batises
オオハシモズ科 Vangidae: Vangas
コウライウグイス上科 Orioloidea
オーストラリアゴジュウカラ科 Neosittidae: Sittellas
ホオダレモズガラ科 Eulacestomatidae: Ploughbill
# シラヒゲドリ科 Psophodidae: Whipbirds and Wedgebills
カンムリモズヒタキ科 Oreoicidae: Australo-Papuan Bellbirds
(ハシブトモズヒタキ科) Falcunculidae: Shriketits (科扱いでない場合もある)
モズヒタキ科 Pachycephalidae: Whistlers
コウライウグイス科 Oriolidae: Orioles, Figbirds
カンムリハナドリ科 Paramythiidae: Painted Berrypeckers
# (モズチメドリ科?) Pteruthiidae: Shrike-babblers (Boyd 独自)
モズモドキ科 Vireonidae: Vireos
あまりに何がなんだかわからない分類が少しわかりやすくなっただろうか。
ごく大雑把に言えば古く分岐した系統を除いてスズメ亜目 (鳴禽類、一般に小鳥と呼ばれるほとんど) はカラスの系統とスズメの系統に大別される。
そしてどの種類がカラスの系統に属するか知っておけば理解しやすいと説明するとよいかも知れない。
日頃出会う種類ではカラスの系統は多くなくて、サンショウクイ、サンコウチョウ、モズ (ちょっとレアなものを含めると +コウライウグイス) がこのグループと覚えておけばほぼ間に合いそうである。他の "小鳥" はスズメの系統 (これが巨大であるが) でよい。
モズ科とカラス科の近さは納得しにくいが徐々に見てゆきたい。他の科は前後との類似点が多少はわかりやすい。
モリツバメ亜科、フエガラス亜科は科扱いとすることもある。
カンムリカケス科 Platylophidae (1種)、シロズキンヤブモズ科 Eurocephalidae (後者はタイプ種の和名より) の位置付けは McCullough et al. (2023)
Ultraconserved elements support the elevation of a new avian family, Eurocephalidae, the white-crowned shrikes
による。カンムリカケス科 Platylophidae の名称を提案したのはこの研究の前で Gaudin et al. (2021)
A family name for the Crested Shrikejay Platylophus galericulatus
シロズキンヤブモズ科の大学のプレスリリース: UNM Department of Biology Ph. D. candidate discovers new bird family
従来はカンムリカケスはカラス科、シロズキンヤブモズ科はモズ科に含められていたものだが、シロズキンヤブモズ科 Eurocephalidae がモズ類とカラス類をつなぐことになった。画像や精度の高い分子系統樹を見ていただいていかがだろうか。
この分子系統樹を見ていただけばオウチュウ類やサンコウチョウ類から最終的にカラス類につながる系統を理解いただけるだろう。熱帯中心に分布して日本では縁が薄い系統が途中に多いので日本の鳥だけを見ていると関連性に気づきにくいことになる。
一方のカラス類ではベニハシガラス属 Pyrrhocorax が最初に分岐したグループになる (ベニハシガラスとキバシガラスが含まれる)。
このグループはかなりカラスのように見えるが、その次のシロハラオナガ属 Dendrocitta Treepies はいかがだろうか。モズのようでもあり、尾の長さはサンコウチョウにも似て見える。
我々が普段見かけるカラス類は後の段階で出現したものが中心なので、モズ類とあまりにも違って見えるということだろう。
中間的な形態のものを見ればカササギやオナガの尾の長さはモズやサンコウチョウの性質を受け継いでいると解釈することもできるのではないだろうか。そして系統の先頭に来るのが小鳥も捕食することのあるオウチュウ類である。サンコウチョウ類はヒタキ類に収斂進化したものかも知れないが、オウチュウ類の捕食能力はモズ類に引き継がれていると言えるのかも知れない。
カンムリカケスはモズ類の前に分岐した系統だが、Crested Jay や和名にもあるように冠羽がある点以外はカケスらしく見える部分がある。色もカラスのように全体的に黒っぽい。
つまり {モズ類 + カラス類} の祖先系統は状況によって (外見的には) モズ類のような、あるいはカラス類のような鳥を生み出せたことになる。
フエガラス亜科にはモズガラス属 Cracticus という両者の特徴を持つそのものずばりの名前もある。フエガラス亜科はオーストラリア・ニュージーランドに固有で、カラス科と同様の生態的地位を占める (コンサイス鳥名辞典)。比較的小型の猛禽類にとっても脅威となる種類 (#ハチクマの備考の [カンムリカッコウハヤブサの生態] 参照)。
Stiller et al. (2024) では Corvides (Boyd の カラス小目 Corvida に相当) の最後はカラス類ではなくモズモドキ科 Vireonidae となる。
大まかに言えば Corvides は2つに分けられ、カラス類で終わる系統とモズモドキ科で終わる系統になる。日本の種類ではモリツバメとコウライウグイスが後者に属する。この分子系統樹に従えば日本の鳥類図鑑はカラス類の後にモリツバメ、コウライウグイスが並ぶことになる。
週間アニマルライフ (1973) p. 3730 モズヒタキの項目 (斎藤) に面白い情報があった。
カンムリモズヒタキ Oreoica gutturalis Crested Bellbird (オーストラリアの種類) が生きた獲物を繁殖期に蓄える習性があるとのこと。巣にチョウやガの幼虫を、巣のへりの上や、巣に卵のあるときは巣のなかにおいておく。くちばしで幼虫を殺さないていどに強くはさみ幼虫の神経を麻痺させる。幼虫は生きてはいるが正常にはいでて巣から逃げるほどでもない。
つまり彼らはえさを腐敗させず新鮮なまま蓄えていることになるとの記述。
Crested Bellbird (Australian Museum) にも解説があり、食物として蓄えるか巣の防御のためとの解釈があるとのこと。こちらは毛虫らしく巣の防御機能の方が重要なのかも。
毛虫の幼虫は孵化したひなの食物ではないらしい (コンサイス鳥名事典) と紹介されていた。
#ハチクマの備考の [死体をおとりに使うか?] にて紹介。ハチクマの事例の方がよりあてはまるかも知れない。
-
サンショウクイ (リュウキュウサンショウクイが分離された)
- 第8版学名:Pericrocotus divaricatus (ペリクロコートゥス ディーウァーリカートゥス) 二股に分かれた尾の濃い黄色の鳥
- 第7版種学名:第8版と同じ
- 第7版亜種学名:Pericrocotus divaricatus divaricatus (ペリクロコートゥス ディーウァーリカートゥス ディーウァーリカートゥス) 二股に分かれた尾の濃い黄色の鳥
- 属名:pericrocotus (合) およそサフラン色の (peri- (接頭辞) およそ、非常に、全体が krokotus 濃い黄色の < krokos サフラン Gk; 濃い黄色の (コンサイス鳥名事典)。Pericrocotus 属の多くは全身鮮やかな色の種類が多く、サンショウクイのような灰色の種は例外的
- 種小名:divaricatus (adj) (尾羽が) 二股に分かれた (divarico (tr) 間があいている の過去分詞形)
- 英名:Ashy Minivet および分離された Ryukyu Minivet (いずれも IOC 名)
- 備考:
pericrocotus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語では peri- は短母音。krokotos は中央の o が長母音。これらを採用すれば -co- が長母音でアクセント音節となる (ペリクロコートゥス)。
divaricatus は i と2つの a がいずれも長母音でアクセントも規則通り "ディーウァーリカートゥス"。
英語の minivet は 1862 年に用例があるが語源不明とのこと (wiktionary)。OED によればラテン語の miniatus (鮮紅色の) 由来の可能性を挙げている。この由来であれば minimum の mini- ではなく minium (色素の名前) となる。日本のサンショウクイのみを知っていると誤解しそうだが、小さいから mini- が付くとは考えられていないよう。以下のスンダベニサンショウクイの学名も参照。
[似合わない属名と英名の由来]
Pericrocotus 属は Boie (1826) がスンダベニサンショウクイ 現在の学名で Pericrocotus miniatus Sunda Minivet のみに対して設けたもの (記載) で、この種だけが際立ってサフラン色を呈していたためと考えられるが属記載には命名理由は記されていない。
この種の記載時学名は Muscicapa miniata Temminck, 1822。系統の中にたまたまよく目立つ種があって属名が付けられたが系統全体の特徴を代表しているわけではない。
miniatus < miniaceus 鮮紅色 < minius。
英語/ラテン語 minium = vermilion 色素 (鉱物) の名前。初めて見つかったスペイン北西部の Minius 川が由来とのこと。化学式 Pb3O4 四酸化三鉛 Lead (II,IV) oxide 和名 鉛丹 がある。化学構造 [Pb^{2+}]_2[PbO_4^{4-}] (TeX/LaTeX 表記) = lead (II) orthoplumbate (IV) を見れば奇妙に見える酸化数の由来がわかる。
鉛でこのような酸化数が安定になりやすい化学的理由や毒性との関係については#オオワシ備考の [鳥類、特に猛禽類の鉛中毒] 参照。
古代や中世では現在の蛍光色素のように目立つ色素として用いられた。中世の絵画の様式 miniature (フランス語由来でミニアチュール、彩画、細密画) はこの色素が用いられたことに由来する。小さい意味の minute とは別語源だが、誤解されてミニアチュールの翻訳語として細密画が採用される由来ともなったとのこと。我々がサンショウクイの "minivet" の英名を見て "小さい" と解釈するのももっともな理由がある。
特に電車の屋根の塗料として多用されたとのこと。wikipedia 日本語・英語版などより。写真を見ればなるほどとわかる色彩。
Temminck はスンダベニサンショウクイをフランス語名 Gobe-mouche vermillon と名付けていた。
Pericrocotus 属は Hartert (1910-1922) では p. 466。
このように見てゆくと、異国の珍しい色彩の鳥を名付けたもので英名も同様。サンショウクイ類を代表するのにふさわしい名前と考えられず caterpillar birds の総称も用いられたが幼虫 (ケムシ、イモムシ) を食べる鳥は他にもあってむしろカッコウ類にふさわしい名称のためそれほど使われていないのだろう。
このグループには他の属名では Ceblepyris Cuvier, 1816 があったがマダガスカルオオサンショウクイ 現在の学名で Ceblepyris cinereus Ashy Cuckooshrike がタイプ種で東洋のサンショウクイ類は含まれなかった。
この種の学名・英名を見ると "ウスサンショウクイ" の和名を復活させない方がよいらしいことがわかる。
東洋のサンショウクイ類縁種に提唱された他属名では同じくスンダベニサンショウクイがタイプ種となった
Acis Lesson, 1830 があったがこちらの方が遅いのでシノニムとなる。Pericrocotus Boie, 1826 の記載に気づかず独立に提唱したのかも知れない。
Acis Lesson, 1830 はヒイロサンショウクイ 現在の学名で Pericrocotus flammeus Flame Minivet を同属に含んでいた。目立った色彩のものをまとめた属だった。
Phoenicornis Selby, 1840 はヒイロサンショウクイのみに対して与えられた属でこちらも色彩が目立つ鳥を独立させたもの。同じ属名を Boie (1827) がすでに使っていたため無効。Boie (1827) の用例もスンダベニサンショウクイとヒイロサンショウクイを含む属として再定義したもので、後にスンダベニサンショウクイがタイプ種と指定され、Pericrocotus のシノニムとなった。
これらがシノニムや無効名だったため現在の分類に現れることはないが、目立った種に独立属を与えることは当時よく行われていた。
一つだけ例外的なものがあって、Pericrocotus motacilloides Swinhoe, 1860 (参考) 基産地 Amoy, China と命名した (セキレイのようなサンショウクイ) ものがあり、これを属名に昇格させた Motacilloides Buturlin, 1910 があった。
これはサンショウクイ (当時は Pericrocotus cinereus) のシノニムで、サンショウクイをタイプ種とする属名が存在することになる。もし分子系統研究の結果 Pericrocotus 属を分割する必要が生じればあるいは使われる可能性があるかも知れない。ただし提唱された情報のみで有効かどうかは知らない (The Key to Scientific Names 情報よりまとめ)。
英名やかつて使われた "ウスサンショウクイ" の名称は後述のように過去の学名 Pericrocotus cinereus に由来 ("灰色の"。同様の意味でよく使われた色彩を示す和名については#サメビタキ備考も参照) と思われる。
この学名は記載時 Perierocotus cinerus Lafresnaye, 1845 (参考) 基産地 Luzon (フィリピンのルソン島) だった。Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではこの学名が使われていた。
Pericrocotus japonicus Stejneger, 1887 (参考) 基産地 Amagi, Idzu, Japan もあったが cinerus のシノニムとされた。
同様に Perierocotus cantonensis Swinhoe, 1861 (参考) 基産地 Canton (広東) もあったがやはり cinerus のシノニムとされた。
この頃は場所ごとに少しの違いをもとに別種記載していた (亜種概念はまだはっきりしていなかった)。
リュウキュウサンショウクイはその中でも違いが大きく生き残る形となった。
同備考で系統の紹介をしているが、その中で core Campephagidae の系統とはかなり違っていてることがわかっており、Corvida I (Boyd) にあるようにサンショウクイグループはサンショウクイ亜科 Pericrocotinae Sundevall, 1872 とするのが適切であろうとのこと。
もう1亜科である Campephaginae Vigors, 1825: Cuckooshrikes と何と呼ぶかは悩ましいかも知れない。日本で記録のある種を優先すればアサクラサンショウクイが代表になるが迷鳥に近い上にサンショウクイと名前が近いので悩ましいだろう。
このグループの種和名はサンショウクイが付くものばかりであまり選択肢がないのでアサクラサンショウクイ亜科になるのだろうか。
[サンショウクイの和名・中国名について]
浦本 (1986)「動物の世界」2版 13 (日本メール・オーダー) pp. 1797-1798 によれば地方名レイフリ (鈴振り) があるとのことで浦本氏はこれは優雅なよい名前であると評価している。「山椒は小粒でピリリと辛い」はこれはまたなんとひどいこじつけであるかと記していた。
コンサイス鳥名事典でも「こじつけされる」と表現され、「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) では「ヒリヒリと鳴く声がサンショウを連想させることから、この名があるという」の記述。
言い伝えが複製されてゆく過程で表現が短縮され、いつの間にか定説とされるようになってしまったのでは。
「言葉の手帳」(https://tutitatu.com/) を見ておくと、「山椒は小粒でもぴりりと辛い」の由来は残念ながら不明です。文献としては、江戸時代初期の俳人・松江重頼の俳諧論書「毛吹草」(1638 年)などに文言が記されています、とのこと。https://www.zukan.earth によれば「さんせうは小粒なれどもからし」とのこと。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 119 (1940 年初出) では和名の出所は明らかでない。昔はヤマセキレイと言ったらしいが飼鳥家が飼うようになってからサンショウクイの名が出たのであるまいかという人もあるとのこと。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 119 (1946 年初出) にはサンショウクイの過去の名称にヤナギスズメもあったとのこと。これほど身近な鳥でありながら歌人が詠んでいないのは不思議である旨述べられているが、鳥にはあまり関心が向いてなかったのだろうこともうかがわせる説明になっている。
鳥を見ず、あるいは聞かずに詠んだ歌も多いと思われるので、ホトトギスのように流行に乗らなかったのだろうなあと想像してしまう。
現在でも探鳥会や見聞鳥の本命とはなっていない感じがする。自分がリュウキュウサンショウクイに初めて気づいたのは平地の探鳥会中で音声によるものだったが、ベテランを含めて他に誰も気づかず、たまたまうまく記録できていた音声をその場で聞いてもらって (当時はサンショウクイがこの時期に? という時代) 納得してもらった次第。
ムジセッカでも同じような体験があって、鳥合わせには録音分析が間に合わなかったので (可能性があることは鳥合わせで取り上げておいた) 後日探鳥会中の個人記録種の扱いとなった。その後は同地で毎年のように記録されている。
野鳥の会メンバーにとってさえも意外にサンショウクイの知名度が低い。またサンショウクイは山の探鳥地で出会うものとの先入観もあったかも知れない。たまたま出席した他県の探鳥会で出会ったぐらいなので、実際にはもっと早い時期から進出していたのだろうが聞き逃されてきたのではと考える理由にもなる。
「山椒喰」の名称が初めて俳句で使われたのは、中西氏の知る範囲では 1940 年水原秋桜子が京都の光悦寺で詠んだものが最初とのこと。場所も状況も想像できるので自分にとっては大変わかりやすい。
中国名は灰山椒(鳥)で和名に由来するが、中国にはサンショウは自生せず別種があるが味は違うとのこと [福井・チャン (2003) Birder 17(8): 68-69]。
中国の解説を見ると Campephagidae によればおそらく日本語からの借用で、中国では 1927 年の出版物に最初に現れるとのこと。
サンショウ (pricklyash peppers) を食べることとは直接の関係はないとある。日本語と違って山椒鳥は現在 Perierocotus 属のみを指して使われており、Campephaginae の現在の中国語名は英語の cuckoo-shrike を訳したものとのこと。
サンショウクイ和名由来の別説
上記部分を記述してからオオサンショウウオの名称由来が気になった。松井 (1986)「動物の世界」2版 5 (日本メール・オーダー) pp. 694-695 で語源説が取り扱われており、おおまかには サンショウウオの呼び名 で「天然記念物のオオサンショウウオをいじめると、肌のぶつぶつから乳白色の液体を出し、これが山椒の香りがするのだそうです」に該当し、出典は和漢三才図会 (1712) などで「山椒の気ある故に山椒魚」。
および日本山海名産物図会 (1754) で「又山椒の木に上り樹の皮を取り会う」とあるが松井氏はさすがに疑問とされていた。
上記 "サンショウウオの呼び名" のページでは「山椒のにおいそっくりであることからオオサンショウウオと名付けられたと書かれています。しかし、これは全くのでたらめです」との友田規隆氏の見解が紹介されている。さらに中国語を調べてみると山椒魚 (日本語が先か中国語が先か不明)、中国語では「山椒」は「山花」と書くことが記されている。日本語の「山椒」には "きつい匂い" という意味もあるとのこと。
中国語のページも見ておくと Hynobius には現在は別の属名 (小鯢) が与えられており、中国語の山椒魚は日本統治時代の主に台湾の種を指した名称 (台湾山椒魚など) 由来のように思える: 参考 台湾山椒魚。1920 年に日本の学者南川仁博 (1892-1984) が見つけたとのこと。学名は Hynobius formosanus Maki, 1922。
魚類ではないので属名通称名の変更は妥当なとことだろう。
さてさてここから例によって推論であるが、(オオ)サンショウウオの名称が匂い由来であり得るならばサンショウクイも匂いや味由来の可能性はないだろうか。というのは [サンショウクイの色彩と系統] にあるようにサンショウクイ科は毒耐性を持っている可能性があり [Jonsson et al. (2008) 幼虫が好みの Campephagidae (サンショウクイ科) が多少の毒耐性を持っているのでは、そして尾脂腺に分泌している可能性があるのでは、とのこと]、
かつて食用なり飼育のために捕えられたサンショウクイがたまたま毒虫を食べていて有毒物質を尾脂腺に分泌した、あるいは食用にしようとするとピリリと感じた可能性があり、オオサンショウウオが山椒の木にのぼり、その樹皮を食べると解釈されるぐらいであれば、木にとまるサンショウクイならばより現実的にそのように考えられた可能性があるのでは。
むしろ「山椒は小粒でもぴりりと辛い」の表現が使われるようになってから音声を記憶するための表現として結びつけられたのではないだろうか。
系統的には近い#サンコウチョウの [サンコウチョウのフンは毒?] も参照。毒耐性は毒鳥ピトフーイなども含むカラス小目 Corvida (corvoid birds) の祖先的な形質と考えられる。
ここまで書いてしまうとサンショウクイの和名の解釈に別説は知られていない、とはもはや言えなくなるわけだ (笑)。
[サンショウクイの学名]
現在使われる学名は記載時 Lanius divaricatus Raffles, 1822 (原記載) 基産地 Singapore (シンガポール、だがスマトラ島でも知られると記載がある)。
Campephaga cinerea Swinhoe, 1860 (参考) (kampe 毛虫 -phagos 食べる Gk) の学名もおそらく広く使われていた。
Perierocotus cinerus intermedius Clark, 1907 (参考) 基産地 Seoul, Korea (韓国ソウル) の記載もあり、Perierocotus cinerus の学名が一般的に使われていたらしい。
英名 (または過去に使われた和名) に過去の学名の痕跡が残る形となった。
Dickinson et al. (2002) Systematic notes on Asian birds. 23. Types of the Campephagidae
に過去に使われた学名の一覧がある。Lanius divaricatus Raffles, 1822 が早かったためこちらに先取権があった。
Lanius (モズ) となっているのは #アサクラサンショウクイの備考にあるように cuckooshrikes と呼ばれることもあってモズのグループと考えられていたためだろう。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版ではリュウキュウサンショウクイは別種 Pericrocotus tegimae 英名 Ryukyu Minivet となる (世界の主要リストでも別種扱い)。
種小名は日本の教育学者 Seiichi Tegima (手島精一) が由来。サンショウクイ、リュウキュウサンショウクイはともに単形種となるため亜種名はなくなる。
Pericrocotus tegimae の提唱時 (#リュウキュウサンショウクイ参照) はサンショウクイは一般的に Pericrocotus cinereus Lafresnaye, 1845 (Grey Pericrocotus) と呼ばれていた。
この名前の種はフィリピン由来 Pericrocotus cinereus (Gould 1875)。
日本の個体を指して Pericrocotus japonicus と命名した Stejneger (1887) はフィリピン由来のものは日本から来たものか、中国 (現在のチャイロサンショウクイ Pericrocotus cantonensis Brown-rumped Minivet) から来たものかわからないとしていた。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でも Pericrocotus cinereus の学名を用い、英名は Siberian Minivet としている。ウスリーや満州でも繁殖することからこの英名となっていたものと想像できる。北海道の標本がないのが驚くべきと記している。
この点は現在の全国鳥類繁殖分布調査 (2016-2021) でも同様で確かに不思議である。#リュウキュウサンショウクイの項目で少し検討してみる。
和名はサンショウクイからウスサンショウクイへの改名も検討されていた (日本鳥学会鳥学通信) が、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではそのままの扱いとなり決定された。
Ogawa (1908) の時代はまだ別種扱いの時期。現在と同じ和名が使われている (サンショウクイの学名は Pericrocotus cinereus が使われていた)。
その後リュウキュウサンショウクイは同種扱いとなったがサンショウクイの方が基亜種のために複雑な状況にはならなかった。
[サンショウクイの色彩と系統]
Jonsson et al. (2010a) (#アサクラサンショウクイの備考参照) ではサンショウクイを含む Pericrocotus 属はサンショウクイ科の中でも特に古く分岐した系統で、"core Campephagidae" の主系統に含まれないことが示されている。core Campephagidae をなす属は Corcoracina と Lalage 属で、これに含まれるのは日本ではアサクラサンショウクイのみ。
Jonsson et al. (2010b) A molecular phylogeny of minivets (Passeriformes: Campephagidae: Pericrocotus): implications for biogeography and convergent plumage evolution (sci-hub)。
が Pericrocotus 属を扱っているがオープンアクセスでない (現時点 sci-hub から読める)。
リュウキュウサンショウクイの分子遺伝学的位置づけは改めて#リュウキュウサンショウクイの項目に含めることにした。この分子系統樹を調べてから上記文献の読めるサイトを知ったがおおむね同じような結論となっていた。
サンショウクイ類は Corvides とカラス類に近い系統なので起源は熱帯。熱帯では派手な色彩が有利に使えたが北方に進出すると不利になり地味な色彩となったと考えられる。Jonsson et al. (2010b) では渡りコストおよび捕食されやすさを要因に挙げている。カロテノイド色彩かどうかはここでは述べていないが、サンショウクイ類がカロテノイド発色であれば渡りの際の酸化ストレスとトレードオフの関係が生じる可能性がある。
Jonsson et al. (2010b) によれば短期間の進化で色彩が変化することは驚くべきとのこと。スズメ目で渡りをする鳥ほど地味な色彩になる傾向を収斂進化としている。
北方に生息する種でもマシコ類のように赤い鳥は存在するので捕食されやすさを主因に説明するのは難しいかも知れない。
色彩的な面で類似性が気になるのがコウライウグイス類のヒゴロモなど (#コウライウグイス備考の [コウライウグイス類に毒耐性があるか?] 参照)。毒鳥ピトフーイ (Pitohui) などカラス小目 Corvida に対イオンチャネル毒性が散発的にあるので、毒鳥ピトフーイに系統が近い熱帯の色鮮やかなサンショウクイ類でも類似点があるかも知れない。ピトフーイの系統にサンショウクイ類が含まれる。
Jonsson et al. (2008) Polyphyletic origin of toxic Pitohui birds suggests widespread occurrence of toxicity in corvoid birds 参照。この研究の時点で使われた遺伝子はかなり限られているので系統間の精度はそれほど高くないと思われるが類縁系統であることはわかる。著者は幼虫が好みの Campephagidae (サンショウクイ科) が多少の毒耐性を持っているのでは、そして尾脂腺に分泌している可能性があるのではと推定している。
日本にやってくる淡色のサンショウクイはこの地域を離れ、あるいはそのような (仮想的) メカニズムを失っているかも知れない。そして地上性より飛翔性昆虫をよく食べるようになった (??)。ゲノム解析が進めばもう少しわかるようになるだろう。
Jonsson et al. (2010b) の研究ではサンショウクイを含む淡色の系統が Pericrocotus 属内で別系統を作ることは否定的。系統樹では連続した進化の延長上と考えられる。スンダベニサンショウクイとヒイロサンショウクイはむしろ系統をなさず、色彩の類似性は生息地域依存と言える。
熱帯と温帯では食物中のカロテノイド量が違うのではないかとも考えてみた。幼虫の持つカロテノイドは植物由来で、Robinson et al. (2023) Macroevolution of protective coloration across caterpillars reflects relationships with host plants のようなレビューがあった。
この論文では幼虫の色彩の役割は捕食されにくさを増すためとして、緑の草に対して背景とのコントラストを下げる、あるいは縞模様が分断色 (#タシギの備考参照) となる、さらに化学防御を行う有毒な植物を食べる場合は警告色となり得る可能性を系統解析も用いて検討している。
熱帯の方が毒々しい印象を受ける幼虫が多い印象を受けるが、捕食者への防御の生態的必要性から熱帯の幼虫の方がより多くのカロテノイドを着色に用いているのではないだろうか (研究があるかも知れないが知らない)。
カロテノイドは抗酸化物質として重要であるが、脂溶性のビタミン A のように過剰になれば有害にもなるだろう。大量のカロテノイドを摂取する熱帯の鳥は羽毛を排泄先に選択した可能性はないだろうか。皮膚を着色する場合と異なり、羽毛が死んだ組織なので過剰分をそのまま捨てられるので都合がよい。副産物の色彩を同時に信号に用いることも有効だったためこの着色経路が進化したのではないだろうか。
羽毛の着色経路にある程度制約があって、地域が違い、別系統の種類でも同じような赤と黒の色彩の組み合わせが進化した可能性を考えてみた。温帯では背景が比較的単調で幼虫もカロテノイド着色をそれほど派手に用いる必要がなく、鳥のカロテノイド摂取量も少ないため (虫を食べる鳥では) 派手な色彩は失われやすい、また抗酸化物質のトレードオフ対象になりやすいのかも知れないと思った。
もしかしたら毒耐性があるかも知れないサンショウクイ類、毒耐性があると考えられる毒鳥ピトフーイやカッコウ目のバンケン類などがこれらの色彩で武装した (?) 幼虫を好んで食べ、他の系統の鳥は好まずあまり食べないために特にこれらの種類で共通の派手な色彩が発達したと考えるのも面白そう。
ビタミン A の排泄機能は突飛なアイデアかと思ったが先例があった。「動物の世界」2版 24 (日本メール・オーダー 1986) pp. 3289-3290 のフルマカモメの項目 (内田) によれば、フルマカモメが吐き出す悪臭物質の成分はマッコウクジラの脳油に似ていて ビタミン D, A が多いとのこと。
食物の甲殻類はビタミン A を多量に含んでいて、過剰になると有害作用があるので体外に排泄するとの説もあると紹介されていた。
マッコウクジラ Physeter macrocephalus の英名 sperm whale はこの脳油が精液と勘違いされていたためとのこと (wikipedia 英語版など)。
マッコウクジラのこの部位は spermaceti organ と呼ばれ、脂質や wax ester からなっていてイルカ類のメロン (melon) 以上に音の屈折による集音能力があり、浮力調節にも役立っていると考えられているとのこと。
そう言えば肝油ドロップなる栄養補助剤があってビタミン A, D の補給源だった。浮き袋を持たない軟骨魚類は海水より比重の軽い油を肝臓に蓄え、浮力を得ているとのこと (wikipedia 日本語版より)。
鯨油は捕鯨時代の産物とも言えるだろうが、クジラ類や魚類も脂肪を過剰なビタミン A の排泄先として利用しているのだろうか (未確認)。そして人はそれをうまく商品化したのかと考えてしまう。
学名の観点から考えると若干ややこしいのはヒイロサンショウクイとサンショウクイは系統的に近いが、スンダベニサンショウクイはそれほど近くない。現在使われている属名はスンダベニサンショウクイをタイプ種とするものなので、将来の研究によって系統樹形態や属を分割する基準が変化すればサンショウクイが別属になる可能性は皆無と言えない (おそらくないが)。亜属程度の概念は現れるかも知れない。
サンショウクイ類が関係あるかどうかわらかないが、McCoy et al. (2023) The carotenoid redshift: Physical basis and implications for visual signaling
に面白い話があり、中南米の Ramphocelus 属 (ベニフウキンチョウ類) ではオスの赤の彩度が特に高く、羽毛の微細構造で赤色の濃さを増しているとのこと。
カロテノイド着色を性選択の信号に使い、赤色が濃いほど遺伝子が優良であることを示すならば構造色を混ぜるこの方法はちょっとインチキである (笑)。大事なカロテノイドをあまり使わなくても濃い色が出せるならばその方向に進化するのだろう。濃い赤色が好まれる系統ほどこのような形質が進化して世界のどこでも同じような色のパターンが出現するのかも知れない。我々は進化の産物である一端を見て毒々しいなどと感じてしまうのかも知れない。
この文献でヒメレンジャクの尾の先端の黄色についても触れられていて、見える部分のみを着色するのが最も効率的とのこと。これも資源の最適な利用で性選択を欺いていると述べている。
なおここで使われている redshift は天文学の用語の赤方偏移で一種の言葉遊びとなっている。
"Bird Coloration" の一般書が刊行されるぐらい、鳥の色彩は進歩が著しくさまざまな分野が関係していてホットで面白い分野となっていることがわかる。
参考までに音声を確認しておくと淡色のサンショウクイグループは互いに似ていて、それ以外の Pericrocotus 属とはだいぶ違う。これも生息環境による影響も考えられ、必ずしも系統の違いを表したものではないかも。
カラス小目 Corvida ではそれほど音楽的なさえずりを進化させなかった傾向があり、単純な、あるいは機械的な音声が多い感じがする。系統的にはそこそこ近いサンコウチョウも繰り返し音が特徴的でこれもカラス小目の特徴が現れているかも知れない。
[カラス小目の夏鳥]
このような視点で種類をまとめた例は過去になかったと思えるので、現代の分子系統解析に基づく新しい夏鳥のグループを考えてみる。広く言えば "夏鳥のカラス系統" と呼んでも構わないかも。
日本で普通種では
サンショウクイ、サンコウチョウ、アカモズ
が該当だろうか。もう少し珍しい種を含めれば
コウライウグイス、チゴモズ
まで含めてよさそう (チゴモズは繁殖種だが普通種とは呼びにくい)。他に迷鳥が少数ある。
分子系統的にも カラス小目 Corvida と スズメ小目 Passerida は大きく違うのでおそらくここで分けるのが適切だろう。夏鳥が多数含まれるツグミ・ヒタキ類は後者に含まれる。
#ツリスガラ備考の [スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン] も参照。カラス小目はスズメ目の中では祖先的な系統と称することもできる。
サンショウクイとサンコウチョウをまとめるのはおそらく新しい視点ではないかと思う。
このように並べてみると、日本の夏鳥の中では生態的にどことなく弱さを感じられる種類も含まれていて一定の系統的理由があるのかも。それはまたカラス小目の夏鳥の種類数が少ない理由にもなっているかも知れない。
[その他]
サンショウクイとリュウキュウサンショウクイの音声による判別方法は三上、植田 (2016) 日本のサンショウクイ2亜種の音声の違いと簡便な判別法 参照。
Mikami (2016) Morphometric Variation in the Pericrocotus Minivets of Northeast Asia
は形態学。
「鳥のおもしろ私生活」(ピッキオ 1997) によればサンショウクイはヒヨドリと同様に昼に渡りをする種類で、渡りの時期は都会地でも声を聞くことができる。
本稿の執筆途中の 2024.8.27 にも声を聞いた。動き出しの季節だろう。
サンショウクイはさえずりと地鳴きの区別が明瞭でなく、日本の図鑑ではさえずりとされることが多い音声を海外では地鳴きと呼ぶのが普通のようである (どちらがより適切かはわからないが)。他の Pericrocotus 属でも扱いはさまざまとなっている。
東洋の種なのでヨーロッパ他言語では名称にあまりこだわっていないと想像できるが、ロシアでは繁殖するのでもう少し詳しく見ておこう。ロシア語名は seryj lichinkoed で seryj は英語 ashy と同じでおそらく古い学名から。lichinka が幼虫で "幼虫を食べるもの" の意味。Kolyada et al. (2016) では昆虫や幼虫を主に食べるためとある。
Campephaga cinerea Swinhoe, 1860 の過去の学名由来と考えられる。
科名の Campephagidae は属名 Campephaga に由来。由緒ある属だが分子系統解析の結果4種のみとなった。属が細かく分かれる傾向があるのはスズメ目カラス小目の中でも古く分岐した系統で系統内部の分岐年代も古いため。スズメ目の中でも比較的古い系統の生き残りとも言える。
[サンショウクイの色彩と系統] に示したようにカッコウ類と同様毒のある幼虫を食べられることによる特殊な適応の可能性が提唱される理由にもなる (まだ確認されていない)。
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the ashy minivet Pericrocotus divaricatus (pp. 4671-4689)
ロシア沿海地方のサンショウクイの繁殖。
数の変動については特に触れられていない。日本では一時期数が減ったとされていたが日本 (あるいは特に関東平野) 特有の現象だったのかも。日本では宅地化が急激に進んだ時代でもあった。
秋の渡りは早く 7/18 にはすでに移動がみられたとの記述がある (Panov 1973)。
本格的な渡りは9月中旬から 10 月初めまで。渡る大群の写真もある。
△ スズメ目 PASSERIFORMES コウライウグイス科 ORIOLIDAE ▽
-
コウライウグイス
- 学名:Oriolus chinensis (オリオルス キネンシス) 中国の笛のような声の鳥 (金色の鳥)
- 属名:oriolus (合) 金色の鳥 (aureolus (adj) 金色の) としばしば解釈されるが、12 世紀フランスですでにニシコウライウグイスを指して使われていた oriol, orioel, orieul で笛のような声が由来 (The Key to Scientific Names)
- 種小名:chinensis (adj) 中国の (-ensis (接尾辞) 〜に属する) (備考参照)
- 英名:Black-naped Oriole
- 備考:
oriolus そのものの発音は見つけられなかったが、同意義の aureolus であれば長母音は含まれない。この単語は -re- にアクセントがあり、同様と考えれば "オリオルス" が推定される。
chinensis は場所の -ensis 由来で短音も長音のどちらの読み方もあるが前者が普通とのこと (キネンシス または キネーンシス)。どちらでもよい。
同じ意味の学名 Oriolus sinensis Gmelin, 1788 が存在したが、これはカラムクドリを指していた (#カラムクドリ参照)。
世界で 20 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は東アジアで繁殖する diffusus (「広がった」の意味) Sharpe, 1877 とされる。
Oriolus diffusus によれば中国のものとインドのものは区別できないが、chinensis は明らかにフィリピンのものを指すとある。
Oriolus chinensis で Oriolus cochinensis (Briss が分布は中国とした) に由来。
そのためにインドのものに Oriolus diffusus を提唱したもの。コウライウグイス類の中で黒いバンドが最も広がっているためこの名称が与えられた。
現在では亜種 diffusus が中国に夏鳥として渡来すると考えられ、基亜種 chinensis はフィリピンの北部、西部が生息地となっている。
和名を英訳して Korean Warbler の名称も使われたこともあった。
Oriolus 属のタイプ種はニシコウライウグイス Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では当時の学名で Oriolus indicus Japan でコウライウグイスとともにヲーチョウ (Wocho、黄鳥) の別名が出ている。
この学名は Jerdon (1845) に由来するものであったが、Dickinson (2000) Systematic notes on Asian birds. 7.
Black-naped oriole Oriolus chinensis Linnaeus, 1766: some old nomenclatural issues explained
によれば Daudin (1802) がすでに用いた学名で無効であり、中国からインドものの名称は diffusus が引き続き使われることになったとのこと (Baker 1930)。
坂田 (1989) 漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 pp. 57-60 (大修館書店) に「詩経」にも登場する中国の「黄鳥」と呼ばれる鳥が何を指すかの解明経緯が述べられている。
江戸時代には中国の諸書に現れる別名の文字からヒバリまたはウグイスとも解釈された。ウグイス類だが日本にはいない種類でウグイスより大型であることが明らかになり、異国のウグイスの意味でカラウグヒス、カウライウグヒス、テウセンウグヒスの名称も使われたとのこと。
志村 (1995) Birder 9(3): 72-75 によれば「梅に鶯」はこの鶯はコウライウグイスとのこと。梅も中国から伝わった文化だったとのこと。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 75 VII (藤堂) では黄鳥は古代中国の呼び名。麗 + 鳥 の文字もこの鳥を表すが、麗は高麗の麗よりはきれいで調和が取れていることから生まれた愛称だろうとのこと。当時は中国でよく飼育されていたとのこと。
[コウライウグイス類はさらに分割か?]
Jonsson et al. (2010) Phylogeny and biogeography of Oriolidae (Aves: Passeriformes)
の分子系統研究によりこれまでの Oriolus chinensis chinensis と Oriolus chinensis diffusus は別系統をなすことが明らかになり、Oriolus chinensis は少なくとも3系統は種の検討に値することを述べているが、まだ十分な亜種を調べたわけではないため分類変更の提案までは至っていない。
Jonsson et al. (2019) Complete subspecies-level phylogeny of the Oriolidae (Aves: Passeriformes): Out of Australasia and return
はさらに詳細な研究を行い、コウライウグイスを含む Oriolus 属のいくつかの種は別種に分割に値することを示した。かつては分割されていたので元に戻る形になるのか。
Oriolus 属の分類に関して、我々に関係するものでは Boyd は Oriolus diffusus Asian Golden-Oriole, Oriolus chinensis Black-naped Oriole の英名を与えている。
英名はこのようになるかどうかわからないが近い将来種に昇格されて学名が変わるだろう。
現在の広義コウライウグイスも細かく分かれる見込み (島に分布する現在の固有亜種) なので海外で探鳥される方は Oriolus 属の他種も含めて要チェックかもしれない。
[国内繁殖や渡り時期]
埼玉県で 繁殖例のビデオがある。佐藤 (1997) Birder 11(2): 96 に埼玉県秋ヶ瀬公園に3年連続飛来し、1996年に繁殖に成功した記録が紹介されている。
さまざまな声を出すことが特徴的で、その中でも「オレオ」(サッカー応援)「ミャー」(ネコの声) などと聞きなしされる (繁殖例動画参照)。写真を撮ったり雑談に夢中で、聞いたはずの声を全く覚えていないのはもったいない。
春の渡り時期については波多野邦彦 (2019) 独断と偏見の識別講座 第74回 Black-naped Oriole <コウライウグイス> に完全に同意する。
京都での自身の記録では5月下旬から6月中旬で思ったよりよく声を聞く。この時期は主な夏鳥の渡りが終わって観察が不十分になり見過ごされているのかも知れない。
「通?」好みの珍しい鳥はこのころよく記録されるので注意。聞いたことのないよくわからない声を聞いた場合はそのままにせず音声記録を残して他人に聞いてもらったり、他の音源と比べるなど同定を試みるのがよい。その場合、いくら熟練者であっても単発の声を判定するのは難しいので長めの録音を記録しておくのがよい。
Black-naped Oriole (Birding in Taiwan) によれば台湾では 19 世紀には普通種だったが生息地減少と飼い鳥人気で少なくなっており、確実に出会えるところは限られているとのこと。現在では保護されている。
シンガポールやマレーシアではごく普通の種類 (しばしばマレーシアのハチクマの食物となっているぐらい)。ただし主な亜種 (maculatus) は異なる。
Wee (2006) Nesting of Black-naped Oriole マレーシアの巣の例。
Wee (2018) Black-naped Oriole feeding on nectar 主に昆虫食の種類だが蜜を食べている様子。果実も食べ、小型の鳥のひなも襲うことがあるとのこと。
Gluschenko et al. (2025) Breeding birds of Primorsky Krai: the black-naped oriole Oriolus chinensis (pp. 3-28)
ロシア沿海地方のコウライウグイスの繁殖生態。亜種は diffusus。
[コウライウグイス類に毒耐性があるか?]
遺伝子解析の結果、コウライウグイス類にある程度の毒耐性があるかも知れないとのこと #ヤマガラの備考 [ヤマガラの植物毒耐性] 参照。
Crested Honey Buzzard mummy returns (Yvonne Blake 2024.5.9) マレーシアのハチクマがひなにコウライウグイスの若鳥を与えている。
ひなはある程度自分で羽をむしって食べることができたが、その後親がちぎって与えたとのこと。
コウライウグイスの若鳥には毒性はないのか (派手な色合いでもそれほど警告色にもなっていない?)、あるいはハチクマにある程度の耐性があるのか。
コウライウグイス類の中で大陸の ギンイロヒゴロモ Oriolus mellianus Silver Oriole が ヒゴロモ Oriolus traillii Maroon Oriole (4亜種) に内包されることがわかった:
Ernst et al. (2022) Utilizing museomics to trace the complex history and species boundaries in an avian-study system of conservation concern。
近年の遺伝子浸透の証拠がなく、ヒゴロモの色彩で区別されてきた亜種を独立種とするのがおそらく適当であろうとのこと。
いずれも派手な色の鳥で、色の違いが生殖隔離に関わっていると考えられ、発色に関連するらしい遺伝子候補もある程度見つけられている。
Boyd はこの2種 (とさらに1種) を Analcipus属と分けているが、ヒゴロモの種分割まではまだ取り入れていない。
ヒゴロモの中には毒鳥に似た色彩を示すものがあり、上田氏は「野鳥」2021年11-12月号 (No. 855) pp. 12-13 (警告色) で赤と黒のデザインが警告色として機能している可能性を挙げている。ルリカケスの色彩も同様ではと提案している。
Ernst et al. (2022) ではこの可能性には触れられておらず性選択と考えているが、色彩の進化は非常に速いとのこと。
コウライウグイス類にある程度の毒耐性がある可能性、カラス小目 Corvida に対毒性が散発的に存在するらしいことから、このグループにある程度有毒な鳥が含まれているかも知れない。
熱帯のコウライウグイス類の攻撃的なハゲミツスイ属への擬態については #ハチクマの備考 [擬態と種・亜種の関係] 参照。
[ニュージーランドに分布していたコウライウグイス類]
Johansson et al. (2011) The New Zealand Thrush: An Extinct Oriole によれば分子系統解析の結果これまでツグミ類と考えられていた絶滅種 Piopio はコウライウグイスの仲間の古い分岐に当たることが明らかになった。分岐年代は 2000 万年前と推定され海を越えて定着したはずとのこと。
詳しい生態は知られていないが wikipedia 英語版の記述によれば地上で見られることが多く、地上から 2-3 m の樹上に巣を造ったと記録が残されている。コウライウグイス類でも地上性捕食者のいない島では地上性に移行していたことがわかる。
2種が生息していて北島では 1902 年に撃たれたのが最後、南島では 1905 年が最後の確かな目撃だったとのこと。北島では 1970 年代でも不確かな目撃報告があり捕食者のいない島への移転も考えられたが実行に移されることはなく絶滅したとのこと。
△ スズメ目 PASSERIFORMES オウチュウ科 DICRURIDAE ▽
-
オウチュウ
-
ハイイロオウチュウ
- 学名:Dicrurus leucophaeus (ディクルールス レウコパエウス) 灰白色の先の分かれた尾羽の鳥
- 属名:dicrurus (合) 先の分かれた尾羽の鳥 (dikros 先の別れた oura 尾 Gk。The Key to Scientific Names)
- 種小名:leucophaeus (合) 灰白色の (leuko- (接頭辞) 白い phaios 灰色の Gk)
- 英名:(Pale) Ashy Drongo, IOC: Ashy Drongo
- 備考:
dicrurus は#オウチュウ参照。
leucophaeus はギリシャ語 phaios は短母音で、長母音が生じないと考えれば "レウコパエウス" のアクセント位置と考えられる。
英名・和名ともに意味は学名に対応している。
記載時学名 Dicrurus leucophaeus Vieillot, 1817 (原記載) 基産地 'Ceylon' (error for Java). Based on 'le Drongri,' Levaillant, 1805 (Avibase)。セイロン (スリランカ) とあるがジャワ島の間違いと解釈されているらしい。
この記載のフランス語名が le drongo gris でこれをそのまま訳せばハイイロオウチュウになる。英名も同様かも。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。東南アジアからインド南部を中心に分布。世界に 15 亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は基亜種 leucophaeus とされる。
-
カンムリオウチュウ
- 学名:Dicrurus hottentottus (ディクルールス ホッテントットゥス) ホッテントットの先の分かれた尾羽の鳥(誤命名)
- 属名:dicrurus (合) 先の分かれた尾羽の鳥 (dikros 先の別れた oura 尾 Gk。The Key to Scientific Names)
- 種小名:hottentottus (adj) ホッテントットの (南アフリカの民族 -tus (接尾辞) 〜に関連する) 南アフリカの Cape of Good Hope (喜望峰) で採集されたと誤解して名付けられた。実際はベンガルの Chandannagar であったが判明したのは学名が付いた後だった (wikipedia 英語版)
- 英名:Hair-crested Drongo
- 備考:
dicrurus は#オウチュウ参照。
hottentottus は -tot- がアクセント音節と考えられる (ホッテントットゥス)。
記載時学名 Corvus hottentottus Linnaeus, 1766 (原記載) Avibase によれば基産地は Cape of Good Hope. Based on 'le Choucas du Cap de Bonne Esperance,' Brisson, 1760, Ornithologia, 2, p. 33, pi. 2, fig. 2. Type locality Chandernagor, southern Bengal とあり上記 wikipedia 英語版 の説明と同じ。
英語別名に Spangled Drongo があるが、これは テリオウチュウ Dicrurus bracteatus と同種時代の名前とのこと。現在は Spangled Drongo は テリオウチュウ の方に使われている (wikipedia 英語版)。
テリオウチュウの方が記載が新しい Dicrurus bracteatus Gould, 1843 ので、あるいは Linnaeus (1766) の hottentottus の同定がまだ行われていない時代はこちらにまとめられていたのかも知れない (未確認)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本で記録された亜種は brevirostris (嘴の短い < brevis 短い -rostris 嘴の) とされる。足を器用に使う鳥 (#オウチュウの備考参照)。
和名カンムリオウチュウに相当する英名の種類が存在する。マダガスカルオウチュウ Dicrurus forficatus Crested Drongo。
こちらも同時に記載されたもので Lanius forficatus Linnaeus, 1766 (原記載) で、基産地が間違って解釈されていた hottentottus よりもこちらの方が Crested Drongo の本家だったのかも。
△ スズメ目 PASSERIFORMES カササギヒタキ科 MONARCHIDAE ▽
-
クロエリヒタキ
- 学名:Hypothymis azurea (ヒュポテュミス アズレア) 瑠璃色の鳥
- 属名:hypothymis hupothumis Aristophanes が用いた未同定の鳥
- 種小名:azurea azureus < azura 瑠璃(鉱物)
- 英名:Black-naped Monarch
- 備考:
hypothymis 外来語由来のため発音は明確でないが、ギリシャ語は短母音のみで長母音は現れないと考えられる。規則によれば -po- がアクセント音節と考えられる (ヒュポテュミス)。
azurea はいずれも短母音で -zu- にアクセントがある (アズレア)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。オオルリもかつて Hypothymis 属に含められていたことがあり、青いヒタキ類を指して用いていたようである。東南アジアからインドにかけて分布。世界に 23 亜種が認められている (IOC)。日本で記録された亜種は不明。
-
サンコウチョウ
- 学名:Terpsiphone atrocaudata (テルプスィポネ アートゥロカウダータ) 黒い尾の楽しむ殺し屋/黒い尾の殺されるまで楽しんでいる鳥
- 属名:terpsiphone (合, f) 楽しむ殺し屋/殺されるまで楽しんでいる鳥 (terpo 楽しむ phonos 殺すこと。phone "声" ではない Gk) 属記載にラテン語語義が添えられており備考参照。ヒタキ類似の鳥を一般的に表したもので特にサンコウチョウ類を指したものではなかった可能性あり。
- 種小名:atrocaudata (adj) 黒い尾の (ater (adj) 黒い cauda (f) 尾 -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名: Black Paradise Flycatcher (IOC も 13.2 より), (Japanese Paradise Flycatcher IOC 13.1 まで)
- 備考:
外来語由来の合成語のため発音は明確でないが、後述のように属の原記載で -phone は音声の意味ではなく、phonos 由来で短母音であることが明示されている (テルプスィポーネではない)。発音規則からはアクセントは "テルプスィポネ" が適切と考えられる。
-phone を含むウグイスの種小名やイカルの属名は長音で読むのが適切で、サンコウチョウの方は短く読む、もともとの語源が違うので、などと説明するとあるいは尊敬され...ないかも (笑)。
-caudata は -da- に長母音が含まれるのでこの位置にアクセントでよい (アートゥロカウダータ)。atro- は ater 由来で冒頭が長母音。
種サンコウチョウの学名には "天国の" の意味はまったく含まれず、英語の Paradise Flycatcher は旧 (広義) カワリサンコウチョウの種小名に使われる paradisi に由来すると思われる。何と言っても Linnaeus (1758) ですでに記載されている学名でこちらが本家。我々から見れば "カワリ" だが、世界的に見ると逆になる。
日本の東北以南と韓国、台湾の限られた地域で繁殖する。台湾では留鳥。3亜種が認められている (IOC)。九州以北の atrocaudata 亜種サンコウチョウと南西諸島の illex (「魅惑的な」の意味) リュウキュウサンコウチョウ、及び亜種不明がリストされている。
現在のフィリピンのチェックリスト (2023) では亜種 periophthalmica を独立種とする扱いも紹介されており、Lanyu Paradise-flycatcher の英名が載せられている。この分類を採用している世界的なリストは今のところないようである。
リュウキュウサンコウチョウは石垣島で Terpsiphone illex Bangs, 1901 と記載されたもの (原記載。illex の語義も alluring, enticing と説明されている)。
Spaeth et al. (2018)
Distribution, habitat, and conservation status of the near-threatened
Japanese Paradise-Flycatcher (Terpsiphone atrocaudata periophthalmica) on Lanyu, Taiwan
によればサンコウチョウの3亜種は十分に違いがあって種相当の可能性があり、遺伝的研究が望まれるとのこと。フィリピンのリストでは先行してこの考えを取り入れているのかも知れない。
[属名 Terpsiphone の意味]
Terpsiphone 属の 原記載 (Gloger 1827):
Terpsiphone の o の文字が音声を表す単語と異なり (ギリシャ文字では別文字で、属の原記載でもラテン語の o の上に長音・短音の記号をわざわざ付けて区別している)、
necando gaudens の意味で necando < neco (殺す) gaudens 楽しい、であって voce laeta (voce 声 laetus 楽しい) ではない (nicht) とある。解説は von ihrem schnellen, muntern Jagen nach Insekten und ihrem froehlichen Wesen 楽しそうに昆虫を狩る速く活発な動きから (The Key to Scientific Names を見て気づいた)。
"Jagen" と "狩り" を意味する語を使っている。英語 flycatcher の catch に相当する単語は別にあるので、この鳥がより積極的に "狩り" を行っていることを表現したいためと推定できる。
一般に言われている "楽しい声" は誤りと判明した。
当時の Muscipeta 属の改名 (後述のようにこの属は複雑な経緯をたどっていた)。
標本のみで分類した人は動作まではわからなかったためこの属を用いるのに躊躇したかも。
wikipedia 英語版によれば The Key to Scientific Names の Jobling (2019) を出典として "声" と誤っていた。Jobling (2010) "The Helm dictionary of scientific bird names" では間違った方の記述になっているため、比較的最近訂正されたのかも知れない。
この誤解は世界的なものだったようで、例えばリトアニア語では名称に "音楽的な" を付けている。
ヨーロッパには生息しないため wikipedia 各国語版で語源を扱っているものは少ないが、アムールサンコウチョウの生息するロシアでは英語版同様の説明になっている。
(その1) 該当ラテン語から他言語への機械翻訳も参照し (ecstasy とも訳された。死ぬほどの絶頂状態)、死ぬほど楽しそうな動作の鳥と訳してみた。
"死ぬほど" と訳してみたが、鳥の名前に "殺/死" が現れるのは不自然な感じもあり、過去にも原記載はおそらく多くの人に読まれているはずなのに、鳥学では見慣れない "殺/殺" の単語に気づかず (誤りと原著者が明確に書いているにもかかわらず) "楽しい声" の解釈に疑いが持たれなかったのかも知れない。
-phone の学名語尾は "声" と暗黙で解釈されることが多いかも知れないが実は他にも例外があるかも。
当時のヨーロッパでは "死" が意味するものは現代とかなり異なったものだった可能性もある。このように考えたのはリストの作品に「死の舞踏」(Totentanz, 1849, 1853, 1859) という曲があるため。サン=サーンスにも同名に訳される曲 (Danse macabre, 1874) があり、他の作曲家もこのテーマでいくつも作品を残している。
我々が "死" から連想するものとはだいぶ違う気がする。
Totentanz も (冒頭だけでなく) 音源を楽しんでいただきたい。サンコウチョウの活動的な動きにむしろ合っているかも。クラシック音楽を聞き慣れた方ならば他でも出てくる有名な主題 (Dies Irae 怒りの日) が使われるなど二重に楽しめるだろう。
wikipedia 英語版によれば Richard Pohl はこの曲を評して "Every variation discloses some new character - the earnest man, the flighty youth, the scornful doubter, the prayerful monk, the daring soldier, the tender maiden, the playful child"
と表しているとのこと ("気ままな若者"、"遊び好きの子供" などサンコウチョウの動きにぴったりではないか)。
例によって「おまけ」であるが、リストがなぜ "死" をテーマにしたか、人生における年代をテーマにした同時代ロマン派ピアニスト・作曲家のシャルル=ヴァランタン・アルカン (Charles Valentin Alkan) による「グランドソナタ 四つの時代」(Grande sonate Les quatre Ages, 1847) を連想してしまった。当時は 50 代が人生の終焉であった。
マルカンドレ・アムラン (Marc-Andre Hamelin) による素晴らしい演奏があるのでこれも動画鑑賞をお勧めしておく。
(その2) 上記を記述してから思いついたが、(その1) は機械翻訳につられすぎた可能性がある (AI の限界とも言える)。
原語の対応英語をみると necandus = which is to be killed, which is to be murdered (殺される予定の), gaudens = rejoicing, taking pleasure in, delighting, enjoying (楽しんでいる)
ギリシャ語の phonos は殺すこと、殺人。他の用例を見ると androphonos で "殺人"、tisiphone で "復讐の殺人" の意味。
"殺すことを楽しんでいる" または "楽しみながら殺している" と解釈可能で、わざわざ Jagen を用いたのもその意味かも知れない。この場合は (虫に対する) "楽しむ殺し屋" と訳すことができると思われる。この訳を採用することとした。
#セアカモズの古いドイツ語名・英語名にも通じる感じがする。
かつて使われた属名で Phoneus および派生する名前の属 (モズ類の一部。派生する属名は一部現在も使われる)、Phoneutria (Cliff or Swallow Flycatcher)、Rhodophoneus (バラフヤブモズ Rosy-patched Bushshrike) など、
現在も使われる学名で Mycophonus (オオルリチョウ Blue Whistling Thrush) は文字通りだと "ネズミ殺し"、
Adophoneus はカンムリオウチュウに使われたことのある属名で、"歌う殺し屋" の意味。ドイツ語では Wuergensaenger (絞め殺す歌い手) で phoneus は Moeder (殺人) と Kaup (1829) と説明している (The Key to Scientific Names)。
サンコウチョウの属名だけを追いかけるとむしろ気づかないかも知れない。オオルリチョウの学名を調べるともしかしたら気づく可能性もありそう。
近縁なオウチュウ類とサンコウチョウが含まれるのは偶然ではなかったのかも知れない。命名者はサンコウチョウの捕食方法がヒタキ類よりオウチュウ的であることを見抜いていたのかも知れない (Linnaeus 1758 時代のカワリサンコウチョウの分類に遡る可能性も否定できない)。
この時代に "殺す" 動作が積極的に命名に用いられた背景には (その1) もあるかも知れないので参考までにそのまま残しておく。
(その3) さらに気になったのは necando の形で、未来・受動・単数で与格または奪格でなぜこの格になっているのか今ひとつわからない。奪格であれば「〜から」「〜によって」が基本の意味で "殺されるだろうものによって楽しんでいる" (ロシア語ならば造格や ot + 生格、英語ならば by や from に対応)、のような意味になるだろうか。
与格ならば「〜に」で "殺されるだろうものに楽しんでいる"、で少し意味が通じない感じがする。
利害関係のある対象を与格の形式で加える構文 (wikipedia 日本語版から) があるとのことで結果的に「〜によって」の意味になるのかも。
なぜこれが気になっているのかと言えば英語に "to death" の表現があるため。この "to" は与格を表している。"to death" の言い換えでは "until you die" (死ぬまで)、意味がさらに派生して "to a great degree" (極度に) などがある。英語では古くからある用法で 1610 年代にすでにあったとのこと (Online Etymology Dictionary)。
ラテン語にこのような用法があったのかどうかわからないが、"殺されるまで"、"殺されるほどに" と訳すことも可能に思える。殺されるまで楽しんでいるならば (その1) の解釈にある程度戻ることになる。
自動詞的な "死ぬ" 方ではなく、採集者によって "殺される" 方を用いたのかも。
ドイツ語でも toedlich は "死ぬほどに" の意味で使われるので考えることは万国共通なのかも知れない。
日本語でも "死ぬまで愛す" の表現があるので (外国語からの翻訳由来かも知れないが)、この用法を拝借して "殺されるまで楽しんでいる" を実験的に代替訳として採用してみることにした。未来・受動・単数・与格に一番正確に対応するかも知れない。
一見同一に解釈できるモズ類やオウチュウ類の学名解釈と同じでないかも知れない。
学名の謎解きを楽しめる部分でもある。
いずれにしても、種サンコウチョウの学名には "天国の"、"(楽しい) 声の" のような意味はまったく現れない。
[学名と基産地について]
Temminck & Schlegel の "Fauna japonica" ではまったく違う学名 Muscipeta princeps だった。図版、本文。
Le moucherolle principal のフランス名が与えられ、この名称は現在ではアメリカの Onychorhynchus 属または Oxyruncinae (英名 Royal flycatcher) に用いられる。mouche は「はえ」で mouche- で広義にヒタキ類を指している。rolle は現代の辞書には出てこないが中世の用法のようで英語の roll/role に類似のよう。ハエを追いかけ回す感じだろうか。
属名 Muscipeta は musca はえ petere 攻撃する、Cuvier が導入したもの。あまりにも多数の分類群を含む名称として使われており後に再定義されたよう。
princeps は王子、主、リーダーなどの意味。現代の学名では日本産種ではないがオオハイガシラオオタカ、ヨコジマノスリなどに使われている。類似の学名は絶滅した可能性のある北米のハシジロキツツキ Campephilus principalis にも現れる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではこの学名に Gloger の提唱した属名を与えた Terpsiphone princeps を用いていた。学名一覧には atrocaudata は現れず同じものとはまだ認識されていなかった模様。
Blyth (1846) Notices and Descriptions of various New or Little Known Species of Birds は日本の princeps と atrocaudata は別種と考えていたことがわかる。
当時は Tchitrea, Philentoma の属名も使われていた。あまりに特異な形態なので誰もが分類に悩んだ結果だろう。
Tchitrea は現在もフランス名 (Tchitrec) で健在で、マレー語の名称 Tchitrec に由来するとのこと (The Key to Scientific Names)。
atrocaudata は 原記載 Muscipeta atrocaudata Eaton, 1839 で基産地は日本ではなく Malaya マレー (日本鳥類目録第5版 1974 で基産地が日本と誤って記述されていると Avibase にある)。
属名・種小名ともに Temminck (1836) によるものは生き残らなかった。
Dickinson et al. (2002) Systematic notes on Asian birds. 23. Types of the Campephagidae
によれば Muscipeta princeps Vigors, 1831 がヒイロサンショウクイの亜種 Pericrocotus flammeus speciosus (参考)
(現在の分類では Pericrocotus flammeus Flame Minivet。この亜種は種扱いとなって シュイロサンショウクイ Pericrocotus speciosus Scarlet Minivet)
にすでに用いていたため無効学名となったらしい。シュイロサンショウクイも先に記載があってこの学名は付かなかった。
Hartert (1910-1922) p. 471 ではこのことまで気づいておらず Tchitrea princeps の学名を与えていた。この学名ならば基産地は日本と朝鮮半島となり、この基産地が長く誤解して使われていたらしい。
サンコウチョウでは Temminck の命名はシノニムや亜種名としても残らなかった。
ありふれた学名 (日本語人名だと例えば鈴木太郎ぐらいの感覚) を用いると過去の用例と衝突し、先に日本で記録されながら基産地が日本にならなかったケース。Muscipeta princeps で探すとサンコウチョウとはまったく違った絵が出てきてよくわからなかった (もしかしてメスを間違えたのかと思ったが違っていた) がこのような理由だった。
Gloger (1827) が属名を提唱した後なのにそれに該当すると考えず Muscipeta の属名を用いてしまったために起きた衝突とも言える。最初から Terpsiphone 属としていれば Temminck (& Schlegel) の学名が採用されたのだろうが、しかし別記のように Gloger の属名にも難点があった...。
Muscipeta が不適切と判断されたのは後の時代で Temminck は Gloger (1827) の属名を使う必要は特になかったのだろう。
Temminck (& Schlegel) の他の学名の命名傾向からみて、ヨーロッパに対応する種類のあるものはその日本版として japonica/japonicus などを与えているが、サンコウチョウは対応種がないので "日本の" を付けるのが難しかったと思われる。フランス語名も与える必要があるので一般名の意味がわかりにくい表記にもできない。
誰にでもわかるすっきりした図版を残しながら原記載にならなかったのは惜しいところ。
#ムギマキの例にもあるように Temminck (& Schlegel) の日本に関係する学名は結構危なかったものがある。
[属名成立経緯はさらに複雑だった!]
Hartert (1910-1922) p. 478 では多くの著者の使っている Terpsiphone の属名はアジアの鳥に適用できないとして Tchitrea の属名を用いていた。Tchitrea Lesson, ? 1830 (The Key to Scientific Names。Hartert は 1831 としていた) の方が新しいが適用されるとのこと。
この議論の出典は Oberholser (1900) Catalogue of a Collection of Birds from Madagascar とのこと。Terpsiphone の属名は Gloger が Muscipeta Cuvier, 1816 の新名として用いたもので、Muscipeta 属のタイプ種を南米の種としてアジアの種類には適用できないと考えたため。
The Key to Scientific Names の情報によれば Muscipeta Cuvier, 1816 が2つのグループを含んでいて南米の種とカワリサンコウチョウのグループ (サンコウチョウはまだ未記載時代) を含んでおり Vigors and Horsfield は 1827 年に後者をタイプ種と認定した。
Vigors and Horsfield (1827) A Description of the Australian Birds in the Collection of the Linnean Society; with an Attempt at arranging them according to their natural Affinities が Muscipeta Cuvier のタイプ種にカワリサンコウチョウを与えたもの。
Cuvier の記載が多様なグループを含んでいることはわかっていて、範囲を狭める必要があったため生じた選択だった。Cuvier の属記載の特徴に最も近い性質を持つものとしてカワリサンコウチョウを選んでもよいのではないか (we may perhaps select) とのこと。
南米の種 (記載時学名で Todus regius Gmelin) を Muscipeta Cuvier のタイプ種としたのは別の著者によるもので、The Key to Scientific Names の情報では誰が行ったか不明とのこと。この扱いは Cory and Hellmayr (1927) に現れるとのこと。Oberholser (1900) は同じ考えに従っていたと思われる (例えば最初に出現するものをタイプ種と考えるなど)。
つまりカワリサンコウチョウを含む複数種に Muscipeta 属が与えられていたが、どの種をタイプ種とするか命名者が示していなかったため後世の解釈が2通り生じ、(カワリ)サンコウチョウの属名はどちらを採用するか次第だった。カワリサンコウチョウをタイプ種としたのは記載順でもなくやや変則的だったようだが、もう一方の解釈の出典が明示的に存在しないためカワリサンコウチョウがタイプ種となった模様。
Gloger (1827) はカワリサンコウチョウをタイプ種とする方の Muscipeta Cuvier を改名したものと判断されて現在は Terpsiphone の属名が用いられているよう。
Gloger の改名理由も Muscipeta の名称が zu aehnlich und ganz gleich bedeutend mit Muscicapa (Muscicapa の名称とあまりに似ていて意味もほとんど同じなので) Terpsiphone と改めて名付けたもの。
Gloger はふさわしくない属名をつけ直した文献 "Etwas ueber einige ornithologische Gattungsbenennungen" (いくつかの鳥類属名についての緒言、ぐらいの意味) で Terpsiphone はその1つに過ぎなかった (Gloger は当時大学院生)。
属名を変更したのみの論文のため、Terpsiphone が何を指すかも明示されておらず、本当にカワリサンコウチョウの行動を意図していたのかも怪しくなってきた。
Gloger (1827) がカワリサンコウチョウの特性を知った上で提唱した属名なのか、ヨーロッパのヒタキ類と少し違う種類を指しただけなのか資料からは今ひとつわからない。"楽しそうに昆虫を狩る速く活発な動きから" は (当時の) ヒタキ類全般を意図していても別に不思議ではない。Gloger は法則で有名なドイツの動物学者・鳥類学者 Constantin Wilhelm Lambert Gloger (1803-1863)。
日本語ではグロージャーの読みが定着しているがドイツ語読みではグローゲルとなりそう。
著作からはヨーロッパの鳥に親しんでいたと思われ、ヨーロッパのヒタキ類の行動が念頭にあったかも知れない。
"楽しむ殺し屋" の解釈の方がより当たっているかも知れない。この場合は necando を "死ぬほどに" と解釈可能に思える。
Muscipeta の属名が使われなくなった理由まではすっきりしなかったが、複数の著者が別のグループを指して用いており、Muscipeta Illiger, 1811 の用例があるとのこと (The Key to Scientific Names によれば無効とのこと)。
Caroli Illigeri ... Prodromus systematis mammalium et avium additis terminis zoographicis utriusque classis, eorumque versione germanica の該当部分。
この中では Muscipeta Cuvier が引用されており、1816 年以前に Cuvier の属名はすでに知られていてここで初めて言及された模様。
ただしヒタキ類全般を指す属名だった。Linnaeus の記載した種から6種が含まれていて冒頭は現代のムナフヒタキ。カワリサンコウチョウも含まれていた。
古くはこの用例がまだ無効と判定されないか、あるいは混乱を防ぐためにより遅い用例の Muscipeta Cuvier, 1816 は使われなくなったのかも知れない。
語義も経緯も大変ややこしいグループだった。従来からの "楽しい声" の解釈は何重にも問題がある模様。
[サンコウチョウ近縁種の分子系統分類]
Bristol et al. (2013) Molecular phylogeny of the Indian Ocean Terpsiphone paradise flycatchers: Undetected evolutionary diversity revealed amongst island populations:
インド洋のサンコウチョウ類の分子系統分類。この研究で調べられたサンコウチョウは中国北部もの (日本と同亜種とされる)。
旧カワリサンコウチョウが3種に分割されたようにリュウキュウサンコウチョウが別種となる可能性もありそうである。
現在のカワリサンコウチョウ Terpsiphone paradisi Indian Paradise Flycatcher は記載時 Corvus paradisi Linnaeus, 1758 であり、何と最初からカラス類 ("楽園のカラス") に分類されていた。
Linnaeus 恐るべしであるが、「サンコウチョウはカラスである」を唱えて激震を走らせた Sibley and Monroe は気づいていただろうか。
なおサンコウチョウの記載は Muscipeta atrocaudata Eyton, 1839、アムールサンコウチョウは Muscipeta incei Gould, 1852 (原記載) 基産地 Shanghai。
アムールサンコウチョウの incei は採集家 John Matthew Robert Ince に由来。当時はインドのカワリサンコウチョウ (当時の学名で Muscipeta paradisi) と日本のサンコウチョウ (Temminck の学名が使われていた) の中間型と考えていた。当時は英名に人名を付けることが多く、Incei's Paradise Flycatcher の名称で紹介されていた。
旧カワリサンコウチョウが複数系統からなる分子系統研究: Fabre et al. (2012)
Dynamic colonization exchanges between continents and islands drive diversification in paradise-flycatchers (Terpsiphone, Monarchidae)
旧カワリサンコウチョウの祖先となる系統は東アジアから東南アジア、インド洋、アフリカに複数回にわたって定着したシナリオを裏付ける。
サンコウチョウおよび旧カワリサンコウチョウのタイでの識別の記事: 'White' Paradise-flycatchers (Ayuwat 2011)。サンコウチョウには白色型は知られていないが、旧カワリサンコウチョウにはあり、白色型の識別は難しい。
サンコウチョウ類の一部でなぜ色彩多形が存在するのかは年齢の違いで色が変化するとの解釈もあったがマダガスカルサンコウチョウ Terpsiphone mutata Madagascar Paradise-Flycatcher では遺伝的に決まったものであることが明らかにされている:
Mulder et al. (2002) Ontogeny of male plumage dichromatism in Madagascar paradise flycatchers Terpsiphone mutata。
このような遺伝に基づく色彩多形は交雑によって失われてゆく可能性が考えられるが存続している理由があるはず。旧カワリサンコウチョウでは地域によってそれぞれの色彩多形が分布している報告があり、それぞれ何らの利点があって固定されたものになっている可能性があるが遺伝機構も含めてよくわからない。
マダガスカルサンコウチョウでは両者が同所的に存在するとのこと。
サンコウチョウのミトコンドリアゲノムが韓国で読まれているので NC_032725.1 から BLAST を試みてみると旧カワリサンコウチョウと思ったほど差がない (一致率 97.6%) ことがわかる。系統樹にカラス類も含まれるのでサンコウチョウ類とカラス類の類縁関係 (一致率は 86% 程度とかなり下がる) も見ることができる。
Andersen et al. (2014) Phylogeny of the monarch flycatchers reveals extensive paraphyly and novel relationships within a major Australo-Pacific radiation
にも Monarchidae の系統研究がある。この研究で得られたサンコウチョウの cyt b KP036808.1 を用いて BLAST を行うと旧カワリサンコウチョウとの関係を見ることができる。サンコウチョウが旧カワリサンコウチョウに内包されるので、サンコウチョウをカワリサンコウチョウの亜種とするか、旧カワリサンコウチョウを分割する必要があり、Fabre et al. (2012) に基づいて後者が採用されたものと思われる。
旧カワリサンコウチョウを2つに分割してサンコウチョウを一方に含める方法も可能であることがわかる。
{旧カワリサンコウチョウ + サンコウチョウ} は種グループとして扱うことができて2系統の分岐はかなり深く、そのうち1系統から比較的新しい分岐でサンコウチョウが分化したことがわかる。
[サンコウチョウ類の進化]
Terpsiphone 属は一般に長い尾を持っていて性選択の結果と考えられているが、アオサンコウチョウ Terpsiphone cyanescens Blue Paradise-Flycatcher (フィリピンのパラワン島)、ミヤマサンコウチョウ Terpsiphone bedfordi Bedford's Paradise-Flycatcher (コンゴ東部)
は長い尾を持たないとのこと (wikipedia 英語版より。ただし以下参照)。
前者は真っ青なので尾よりも色彩が性選択の材料となったものか。後者は分布も狭く写真も少ないがまったくサンコウチョウらしく見えない。
Fabre et al. (2012) Dynamic colonization exchanges between continents and islands drive diversification in paradise-flycatchers (Terpsiphone, Monarchidae)
(ResearchGate)
によればサンコウチョウ類は東アジア (マレー半島やフィリピンなど東南アジアの方が的確か) から発祥して南西アジア、インド洋、アフリカに複数回の導入があったとのこと。
アフリカの種類が多いのでアフリカ発祥かと思ったがそうではなく [Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire にも同じことが述べられていた]
分子系統樹からはフィリピン、北東・東南アジア、マスカリン諸島 (マダガスカルの東)、南アジア、マダガスカル、アフリカの順になっている。
上記の変わったミヤマサンコウチョウもそれほど特別な位置ではなくアカハラサンコウチョウ Terpsiphone rufiventer Red-bellied Paradise Flycatcher / Black-headed Paradise-Flycatcher と同種と言えるほどに近い。ベイツサンコウチョウ Terpsiphone batesi Bate's Paradise-Flycatcher を含めた3種が極めて近縁で、ごく最近種分化した species complex をなすと述べられている。
この論文ではこれらのアフリカ原生林の種類の大部分 (アカハラサンコウチョウの亜種の大部分も含まれるとのこと)。Terpsiphone 属のうち5種が長い尾を持たないとのこと。祖先型は尾が長いので二次的に失った模様。これらの種は冠羽も失っているものが多い。
論文では主に島の種で性的二形が失われる傾向についての議論があり、性選択は生存を犠牲にする部分があるので絶滅確率を上げる可能性があるなど述べられている。少数個体から始まる創始者効果や遺伝的浮動の影響も受けやすい。
論文には書いてないがコンゴ盆地も発祥の地より最も遠く、創始者個体群が小さくてたまたま尾が長い形質が弱まったのか、あるいは密な熱帯林では長い尾は生存に不利なのか。
またこのように見るとパラワン島の種のみが真っ青で、パラワン島の生物地理的特異性もわかる。
なぜ日本にサンコウチョウがいて、変わった形態を持っているのか考える上でも論文を見ていただくのが面白いと思う。
この論文を受け、IOC 15.1 では Annobon Paradise Flycatcher Terpsiphone smithii を Red-bellied Paradise Flycatcher Terpsiphone rufiventer に含められることになった。
分子系統がますます重視されるようになってきた (Latest IOC Diary Updates)。
サンコウチョウ類は皆ホイホイホイと鳴くのか、ちょっとチェックしてみた。アジアの種で見かけも似ているブライスサンコウチョウ Terpsiphone affinis Blyth's Paradise Flycatcher (旧カワリサンコウチョウより分離) の音声サンプル: XC922112 (David Boyle 2024)。
前半は大変似ているが、ホイホイホイもここまで繰り返されるとやはりヒタキ類らしい声には聞こえない。
アフリカの種ではさらに違ってアフリカサンコウチョウ Terpsiphone viridis African Paradise Flycatcher では XC616030 (Nature sounds by Simply Birding 2004)。
多少近縁の属を見ておくとカンムリヒタキ Trochocercus cyanomelas Blue-mantled Crested Flycatcher / African Crested Flycatcher は XC547954 (Dries Van de Loock 2020) など。結構サンコウチョウに似ている。
クロエリヒタキでは XC963678 (Hans Matheve 2024) とサンコウチョウはこれら系統の声と共通性が高そう。
#モズ備考の [モズ類の繁殖と移動] で "系統的に近いサンコウチョウのさえずりも音声起源的には地鳴き要素の方が強いかも" と触れたようにサンコウチョウのさえずりは系統的には "さえずり" 的なのか少し気になって調べてみた。
アムールサンコウチョウ Terpsiphone incei Amur Paradise Flycatcher によい例があって、地鳴きとされる XC344922 (Albert Lastukhin & Yuri Glushchenko 2016.6.24) と さえずりとされる XC658132 (Bo Shunqi 2021.6.19) からサンコウチョウのさえずりが構成されたと思えばよいと考えられる。
この音声に関する情報は Amur Paradise Flycatcher Terpsiphone incei (The Avifauna of Hong Kong 2025.6.4) が参考になった。
上記例にもあるように熱帯のサンコウチョウ類は繰り返し音が多く、例えばブライスサンコウチョウの亜種 XC501396 (Frank Lambert 2019.9.2) など、虫の声の繰り返しのように聞こえるものさえある。これらの反復音は カササギヒタキ科 Monarchidae (ヒタキ類ではないので和名に違和感が残る) に一般的なので単音を反復する (どの程度音声学習が必要なのだろう?) のはこの系統の祖先形質に近いと想像される。
そもそもあまり凝ったさえずりの得意なグループではなく、サンコウチョウの場合は地鳴き要素とさえずり要素を組み合わせることでさえずりを形成したと考えられる。機能的にはさえずりと呼べるものだろうが、構成要素を考えると複雑なフレーズを複数学習するヒタキ類と異なっていて系統的違いが現れている。
単音の反復は温帯地方の鳥のさえずりに似ていないので日本では目立ち、サンコウチョウの声が一層特徴的に感じられるのだろう。
[サンコウチョウはヒタキ御三家の一員?]
ヒタキ御三家と称してオオルリ、キビタキ、サンコウチョウと挙げられることがしばしばあるが、そろそろこの取り上げ方は止めた方がよいと思う。サンコウチョウがヒタキ類に入れられたのは「何でもかんでもヒタキ科」の古い時代の話だし、カササギビタキ科の名前が付いているとは言っても、それはツバメとアマツバメを一緒にするようなもの。鳥と恐竜が同じ系統であることを強調しつつ、一方でサンコウチョウの扱いが異なるのは整合性がよくない。
系統関係を重視する現代の見方では、サンコウチョウがヒタキの仲間の仲間のように思われる表現はむしろ長く続いた誤解を長引かせる原因となるだろう。サンコウチョウが積極的な防衛を行うこと (カラスに対する威嚇の声を聞かれた方も多いだろう)、地鳴きの違いなどはむしろカラス類との近縁性を強調した方がよい。
新ヒタキ御三家はぜひコサメビタキに入って欲しい。日本で繁殖しないムギマキとは違って (「フィールドガイド日本の野鳥」の表紙を想像している) 身近な種でもあり、この機会にさえずりなども取り上げられれてよく知られるようになればファンも増えるのでは。
[サンコウチョウの尾羽の換羽]
サンコウチョウの尾羽の換羽は誰もが気になるところだが、Mayr and Mayr (1954) The Tail Molt of Small Owls
によれば Ticehurst (1938) が中央尾羽2枚を最後に換羽すると記載しているとのこと。
Ticehurst (1938) On the Birds of Northern Burma. Part III (オープンアクセスではない)。
The Paradise Flycatcher, a regular visitor to Sri Lanka (Munidasa 2012) によればカワリサンコウチョウのオスでは2回め (2年目のことと思われる) の換羽で伸びるとある。
マダガスカルサンコウチョウ [前述 Mulder et al. (2002)] では2月の post-breeing molt で入れ替わるとある。
越冬時期の写真がそもそも少なく判定が難しいが、マレーシアで Black Paradise Flycatcher (Andy Lee 2022.3.19)、Black Paradise Flycatcher (Ang TH 2019.3.17) など3月にはすでに伸びた写真が撮影されている。
1月の写真はやや微妙 Black Paradise Flycatcher (Bruce Robinson 2009.1.26)。
12月 Black Paradise Flycatcher (Ang TH 2018.12.22)。
地域を限らず探しても 11, 12 月に尾を伸ばした個体の写真は見つからず。1月の写真は非常に少ない。
2月になると亜種 (種?) は違うがフィリピンで尾の長い写真が多数ある。
11-12 月のオスの写真をよく検討すれば中央尾羽が揃っているかなど判定できるかも知れないがそこまでの根気がなかった。中央尾羽のみは越冬地で伸ばすのか? 1-2 月の写真の少なさを考えると、あるいはこの時期に尾を伸ばしつつひっそり暮らしているのかも?
アムールサンコウチョウでも1月の写真は非常に少ない。12 月末に伸長中らしい写真があった: Amur Paradise-Flycatcher (Ang TH 2021.12.31)。こちらも 11 月に尾を伸ばした個体の写真は見つからず。
2月にはかなり伸びた写真がある: Amur Paradise-Flycatcher (Adolfo Castro 2024.2.24)。
渡り習性はサンコウチョウと似ていると考えれば、上記のサンコウチョウの中央尾羽の伸長時期の推測はおおむね正しいかも?
[サンコウチョウの分布変遷]
浦本 (1986)「動物の世界」2版 13 (日本メール・オーダー) pp. 1787-1789 がサンコウチョウの項目で面白い考えを述べていた。
日本には標高 1000 m 以下の地域で木の植生が広く残っているところはもはや存在していない。そんな状態でもまだ生き残っているサンコウチョウはかなり適応力があるほうなのだろう。
日本の鳥学者の一部には、低地の鳥種の少ないのはこの状態を自然状態と錯覚して、鳥の生活は涼しいほうがいいのだということをいう人まである。(中略) 日本の鳥の少なさ、とくに西日本のばあいはけっして温度のせいではない。それは人間による植生破壊のためである。
と大部分を引用した。植生破壊以前の分布状況を知ることはもはやできないので本来の状況はわからないとの趣旨。
この記事の初出は 1972-1973 年で、そういえば思い当たるふしがあった。Herbert Andrewartha などが牽引役となって気候学派なるものがあったとのこと (「生態学入門」日本生態学会 p. 241 で使われている名称)。wikipedia 英語版では best known for attributing density-independent forces, such as weather, to be even more important than density-dependent factors in influencing population regulation と解説されている。「鳥の生活は涼しいほうがいい」は時代的にはこの流れかも知れない。
「日本の鳥の少なさ」はオースチン Oliver L. Austin が日本を訪問して驚嘆して述べた印象由来だろう。
この件が関連する話題は#ホトトギスの備考で紹介した、ちょうど日本の鳥の過去 40 年の数の変化を統計解析した論文が出された: Yamaura et al. (2025) Range size and abundance dynamics of Japanese breeding birds over 40 years suggest a potential crisis in warm areas
の論文。
サンコウチョウは繁殖分布の平均気温が下がった特殊な事例で、温暖化に伴う森林の成熟に伴って分布を広げた (These forest species likely expanded into mature forests under warming temperatures) 種類に含められている。
考察はホトトギスの備考を参照。結果だけを見れば近年では低地から少し標高の高い地域にも分布を広げたように見える。
しかし全国鳥類繁殖分布調査も「繁殖期に声を聞いた」記録が大部分で、繁殖の確認されている A ランクのメッシュは過去の調査とあまり差がなくやはり低地に集まっている。標高の高い地域に分布を広げた結果は果たして正しいのだろうか。というのはサンコウチョウはずいぶん遅い時期でも移動するので、全国鳥類繁殖分布調査の行われた季節の「繁殖期に声を聞いた」は実は渡り途中の個体の可能性はないのだろうか。
自分もアンケート調査で何点か貢献したが、渡り途中でなく繁殖しているだろう確証まで持てていない。
同様に数が増えたとされるアカショウビンも遅い時期にも移動するので、渡り個体を「繁殖期に声を聞いた」に含めれば同じ潜在的問題があるかも知れない。過去の調査と同じ時期なのか、あるいは調査した時期と記録された割合の相関もとってみるべきかも知れない。調査時期が遅くなればサンコウチョウやアカショウビンの記録割合が高くなる効果は十分考えられる気がする。
そう言えば、「鳥の生活は涼しいほうがいい」説は過去に一般にも認知されていたようで鳥に必ずしも詳しくない人から聞いたことがある。浦本氏が安易に因果関係としてとらえることを批判している気温との相関をまず考えるのは、昔も今もあまり変わっていないのかも知れない。
[ロシア沿海地方のアムールサンコウチョウ]
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Amur paradise flycatcher Terpsiphone paradisi incei (pp. 5015-5039)。
貴重な写真も多数あり。この文献のロシア語では "中国のサンコウチョウ" の名称になっている (ロシア語でもアムールを付けた名称もある)。白色型のオスも 9.2% 存在するとのことで写真も紹介されている。確かにアムールサンコウチョウの名称も分布をうまく反映していないとも言える。
[サンコウチョウのフンは毒?]
「キビタキのなかまたち」(谷口高司絵; 日本野鳥の会編 あすなろ書房 1992, pp. 48-50) によれば熊本でサンコウチョウのフンに毒があるとの言い伝えがあり、また鹿児島では 10 日ほど人の与えたすり餌を食べると毒がなくなると言われていたとのこと。
この本の著者はサンコウチョウの飼育が難しいことを表現していると解釈しているが、毒耐性はカラス小目 Corvida (corvoid birds) の祖先的な形質と考えられ (#ミサゴの備考 [ミサゴはフグ毒に耐性があるか]、#ヤマガラの備考 [ヤマガラの植物毒耐性] (5) 毒鳥ピトフーイなどの対毒性、#コウライウグイス備考の [コウライウグイス類に毒耐性があるか?] などの項目参照)、
もしかするとサンコウチョウにも毒耐性があって有毒な虫を食べた個体があったのかも知れない。ぜひゲノム解析でも調べて欲しいところ。そういえばサンコウチョウ類の越冬域では有毒そうな派手な色の種類の鳥が多いので、もしかすると越冬地では有毒昆虫を食べているかも。
サンコウチョウのオスの長い尾羽は「まずい」ことを示しているとまでは考えないが (笑)。
そういえばオウチュウなどはまずいのだろうか。サンコウチョウのひなを捕食したハチクマの話を聞くので多少有毒としても大したことはないだろうと想像するが。
サンコウチョウはいわゆるヒタキ系統ではないことをここでも確認しておきたい。
[カササギビタキ科]
サンコウチョウは現在カササギビタキ科に分類される (現在ではヒタキ科とは縁が遠いことがわかっている) が、このカササギビタキというのは何か、と見てみると中西悟堂「定本・野鳥記 3」p. 143 にヤップ島 (現在はミクロネシア) 産とあった。
該当する鳥を探してみるとカササギビタキ Monarcha godeffroyi Yap Monarch だった。ヤップ島の固有種でオスはカササギ風の配色になっている。ヤップ島の州の鳥とのこと (wikipedia 英語版より)。戦前の南洋の統治地域の島で記録された種類の和名由来だった。
海外言語でカササギビタキに相当する名称を用いているものは一見なさそう...と思えたがなんとロシア語が "カササギ" に相当する修飾語を採用していた。現代の名称に見当たらないだけで過去どこかの言語で用いられていたのかも知れない。
現在の Monarcha 属の和名はチャバラビタキ Monarcha takatsukasae Tinian Monarch を除いてカササギビタキを装飾する名前となっている。この種は尾が短いので別属と考えられ、記載時学名 Monarcharses takatsukasae Yamashina, 1931 だった。日本で記載された割には地味な和名が与えられているのも不思議なところ。
「定本・野鳥記」の同ページにはオオギビタキ (現在の表記ではオウギビタキ) も同様に紹介されている。こちらもオウギビタキ科の名称由来となるがかつては戦前の統治地域の鳥の和名だった。
現在の学名で Rhipidura rufifrons に対応するが種分割が行われたため対応関係は複雑。記載時学名が Muscicapa rufifrons Latham, 1801 でこの属名からは「ヒタキ」でよかった。Rhipidura Vigors & Horsfield, 1827 の属名が後に与えられ、rhipis, rhipidos (扇) + oura (尾) Gk で英名の fantail や和名に残っている "オウギ" に対応する。
"オウギ" と英名の対応はよいが "ビタキ" の方はカササギビタキ同様に古い時代の分類を反映していることになる。
[目先の剛毛の意義]
ヒタキ類のように空中で虫を捕食する種類で目先の剛毛 (rictal bristles) が発達していることはよく知られている。カササギビタキ科はそもそもヒタキ科でなく別系統だが、ヒタキ科のどれか1種を選ぶのは難しいので便宜上こちらにまとめておくことにする。以下で紹介の研究でも研究対象は旧世界のヒタキ類ではない。
#オオモズ備考の [目先の剛毛 rictal bristles の役割と進化] で紹介の研究によればこの剛毛はそもそも捕食には役立っておらず、目を保護する機能も特に期待できないとのこと。飛翔性昆虫食の鳥の捕虫網と考える過去のアイデアはほぼ否定されている。
それでは何の役に立っているのか見解はまだ定まっていない。感覚器官であろうことはかなり確からしいが何を感じているのかはよくわからない。単純な反射に役に立っているものとも考えにくい。
△ スズメ目 PASSERIFORMES モズ科 LANIIDAE ▽
-
チゴモズ
- 学名:Lanius tigrinus (ラニウス ティグリーヌス) トラの模様のあるモズ
- 属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 種小名:tigrinus (adj) トラのような模様がある
- 英名:Tiger Shrike
- 備考:
lanius は短母音のみで冒頭にアクセント (ラニウス)。
wiktionary によれば lanio 由来説は Ernout and Meillet (1985) とのこと。De Vaan (2008) はイタリア祖語 *lanios でインド・ヨーロッパ祖語の *lem(H)- (引き裂く) に遡ると提案しているとのこと。モズのラテン名の方が先にあって lanio が派生した考えもあったようだが、Ernout and Meillet (1985) は lanio から派生した可能性の方が高いと考えた。
tigrinus は i が長母音でアクセントもここにある (ティグリーヌス)。tigris (トラ) と形容詞接尾語の -inus 由来。成鳥オスの背中、腰、肩の模様を指すとのこと (wikipedia 英語版より)。
Drapiez (1828) による記載で基産地はジャワ島。
英名別名に Thick-billed Shrike がある。対応するロシア語名 tolstoklyuvyj sorokoput がある。スロバキア語で Thick-billed に対応する名称があるが大部分の言語で Tiger に由来する名称が使われている。
この英名やロシア語名は Lanius magnirostris Lesson, 1832 (参考) が由来で産地は l'Inde (論文表題は Voyage aux Indes-Orientales) 東インドといえばインドネシアのこと?
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でもこの学名と英名が使われていた。Drapiez (1828) の記載が見つかるまではこの学名が長く使われていたよう。
さらに Enneoctonus crassirostris Bonaparte (参考) そのものは無効だったが、Enneoctonus crassirostris Cabanis, 1850 (参考) もあった。
これは Lanius crassirostris Kuhl の属を変えたもので、この Kuhl の学名は英語別名の Thick-billed Shrike とよく対応する。英名別名はこの学名が使われていた時代に付けられたと想像できる。
Lanius tigrinus Drapiez, 1828 に先取権があると判明して英名の方も Tiger Shrike と変更されたのだろう。例によってヨーロッパや北米から遠い地域なので学名をそのまま訳したものが使われていたと想像できる。
今西他 (2007) 雄アカモズと雌チゴモズの種間つがいとその雑種 ではこの英名が用いられている。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 114 (1940 年初出) によればモズとは比較にならぬぐらい美しいので、チゴ (稚児) という美称がついたとのこと。またモズよりは少し小型。
山階鳥類研究所の標本データベースから YIO-26093 (神奈川県 年不明) では "大モス" の古いラベルが訂正されていた。
モズとは違うことまでは認識されていたが、オオモズとチゴモズの区別は曖昧だったのではないかと想像できる。区別されるようになってから付けられた比較的新しい和名ではないだろうか。
学名由来の可能性も考えてしまう。tigrinus であれば音も近い。ドイツ語の方が身近な言語であった時代を考えると、ドイツ語では "チ" の音は基本的に外来語にしか現れず、英語のように "ティ" と "チ" の音のカタカナで表記を使い分ける必要がない。
つまり ti- を "チ" と表記しても構わない。例えばこの種に対応する意味の Tiger (トラ) は英語と同じ綴りでも "チーゲル" と普通に読んでいた (カタカナで書いたものを読んでも多分通じないだろう点は英語と同じ)。tigrinus をドイツ語のカタカナ読みをして似た日本語を探すと "チゴ" になっても構わない気がする。
学名を覚えるために付けられた和名の可能性も感じられる (#チョウゲンボウの備考 [チョウゲンボウの和名検討] にて考察)。
学名やドイツ語に関連した可能性の高い和名が多かった過去の背景を検討して考えてみた。
Shrike の語源は鳴き声からだが、本来はヤドリギツグミの呼称だったとのこと [Newton (1896) "A Dictionary of Birds"; 茂田 (1993) Birder 7(10): 36 に記載がある。古英語で scric はモズまたはツグミとのこと (Online Etymology Dictionary)]。国内では絶滅危惧 IA 類 (CR) であるが、世界的には大陸にも分布して懸念なしとされる (IUCN)。単形種。
フィリピンのリスト (2023) では迷鳥とあり、主に大陸経由で越冬地に渡るのだろうか。After 124 years, the 'Tiger' returns to Philippines... では 2011 年にフィリピンで 124 年ぶりのチゴモズの記録が紹介されている。
2015 年にもミンダナオ島で記録された Photo of the Month: Tiger Shrike。
分布図によってはフィリピンを越冬域にしているものがあるがこれはほぼ間違いと言える。
Gluschenko et al. (2023) Breeding birds of Primorsky Krai: the tiger shrike
Lanius tigrinus (pp. 3781-3803)
ロシア沿海地方での繁殖情報。沿海地方レッドデータブックのランクが3から2に上がった。
他種と同所的に繁殖する事例もあってイワミセキレイ、コイカル、コウライウグイスの名前が出ている。
生息環境や巣などの生態写真は出ているがそれほどよく調べられているわけではなさそう。
ここではより多く生息する他のセアカモズ類との交雑も起きている。
-
モズ
- 学名:Lanius bucephalus (ラニウス ブーケパルス) 大きな頭のモズ
- 属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 種小名:bucephalus (合) 牛の頭 (bous 雄牛 kephali 頭 Gk)
- 英名:Bull-headed Shrike
- 備考:
lanius は#チゴモズ参照。
-cephalus は短母音のみで、-ce- にアクセントがある。bu- の方が問題で由来となるギリシャ語 bous は "ブース" の発音だったため、bu- は長音となる可能性がある。これを採用して "ブーケパルス" と解釈した。bu- を長音とした方が牛らしさが現れる気がする。
記載時学名 Lanius bucephalus Temminck & Schlegel, 1845 (原記載) (図版) と "Fauna Japonica" 由来で新しい学名。フランス語名 la pie grieche bucephale とほぼ学名のまま。
pie-grieche は pie がカササギ由来で、grieche は "ギリシャの" の意味と考えられている。pie-grieche でモズ類を指す (wiktionary)。
grieche を含むフランス語はほとんどないらしい (語源がすっきりしない理由にもなる)。
Temminck and Schlegel (1845) によれば自分たちが日本で見つけたモズ類はこの1種で、Boie の言うところの pie-grieches ecorcheurs (Enneoctonus。#セアカモズ備考参照) に属すると考えるとのこと。
当時は "普通の pie-grieche" の名称でジャワ島のものが知られていて、ヨーロッパのセアカモズとも比較している。日本のものは La tete est assez grande (頭が十分大きい) が種小名の由来と考えられる。嘴が大きいことも同様に述べられている。
英名に対応するフランス語名ではないので英名は学名から訳されたものと想像できる。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Bull-headed Shrike の英名となっていた。
世界で2亜種が認められている (IOC)。日本のものは基亜種 bucephalus。もう1亜種 sicarius は中国中部に局地的に分布。sicarius は1標本のみで亜種を認めない立場もあった [茂田 (1993) Birder 7(10): 36-41]。
[モズ類の系統解析と托卵排除]
Peer et al. (2011) Complex Biogeographic History of Lanius Shrikes and its Implications for the Evolution of Defenses Against Avian Brood Parasitism
論文そのものはモズ類の托卵排除能力の進化を議論したものだが cyt b を用いた分子系統樹も見られる。
"Gray Shrike" Clade と "Non-Gray Shrike" Clade の2系統に大別され、オオモズとオオカラモズは前者、日本産のその他のモズ類は後者。後者のクレードの最初にあたる種類がシロクロモズ Lanius nubicus Masked Shrike でヨーロッパ南東部、地中海東部からイランで短距離の渡り鳥で主にアフリカ東北部で越冬。
オオモズとオオカラモズを除き、日本のモズ類系統はこのあたりから出発したと考えてよい。全体的傾向として東に行くほど新しい系統になる。論文ではこの2系統内部の一部で托卵排除能力が存在する結果となった。
2系統が分岐したのは 350 万年前ぐらいとの見積もりになっている。その先の細かい進化や托卵排除の進化はよく調べられている北米の種類が中心 (北米ではカッコウ類ではなくコウウチョウが主な托卵種)。
Lanius 属の共通祖先段階でユーラシアでカッコウに対する托卵排除が進化した可能性が提案されていたが、ユーラシアの Lanius 属はあまり托卵排除を進化させていない。北米の2種の分岐年代から 110-180 万年前ぐらいに托卵排除を進化させた可能性があり、托卵種がいなくても長期間能力が維持される可能性を考えている。
#キレンジャク備考の [キレンジャクの托卵排除行動] でも同じことを主張しているグループ。
その後のデータは多少増えているので EF621583.1 (cyt b) から BLAST を試してみると中国と日本のモズが別系統になってしまう (?)。アカモズの方がむしろよく調べられている。アカモズの NC_028333.1 (ミトコンドリアゲノム) から出発することもできるがモズは調べられていないため含まれない。
これらを見ると {アカモズ + モズ} が最近になってユーラシア東端に定着したがアカモズが渡りをするグループ、モズが比較的定住性が高いグループとして分化したように見える。両種の関係は結構近い。
我々が見ればモズが基本のような印象を受けるが逆の関係となる。中国古典に登場する "モズ" や伝来文化で扱われるものも、我々は現在モズと呼んでいる種とは別のものを指していたかも知れない。
上記ミトコンドリアゲノムから出発した場合は Peer et al. (2011) のようにタカサゴモズが {アカモズ + モズ} に含まれてしまう問題は避けられるよう (単純にサンプルが少ないためかも知れない)。タカサゴモズとチベットモズは非常に近い。
ユーラシア東端への定着年代をタカサゴモズとアカモズの分岐で代用してみると 208 万年前 (median time) - 332 万年前 (adjusted time) (timetree.org) 程度となって、モズの定着はもう少し新しい数字が想定できる。チュウヒ類がやってきたのもこのころ、ノスリがやってきたのはさらに新しいぐらいでだいたいの年代感覚がわかる。モズ類もこれらの猛禽類同様に草原の広がりに合わせて東に分布を広げたものだろう。
アカモズに限らず、現在はこのグループの数十年スケール (あるいはもっと続く?) の衰退過程を見ているのかも知れない。[ロシア沿海地方のモズ] 参照。
[ロシア沿海地方のモズ]
ロシア沿海地方で 1910 年代に比べて大幅に数が減り、1990 年代には絶滅したと考えられたこともあったが、2014 年に確実な繁殖が記録された: Kurdyukov (2014) The bull-headed shrike Lanius bucephalus has not disappeared as breeding bird in the Ussuri region: first nest record of the species in the Ussuri Reserve, observation in 2014 (pp. 3569-3580)。
Panov (2011) はモズ類のモノグラフでロシア極東地域では見られないと書いていたとのことだが、この著者の Kurdyukov は Panov や Nazarenko の意見はまったく意外とのことで繁殖の証拠を探した成果。
過去 40 年沿海地方のモズは減り続けており、1970-1980 年代に急に減少して過去の 1/15 未満となったとのこと。
日本の状況との比較は Tamada et al. (2014)
Population Trends of Grassland Birds in Hokkaido, Focussing on the Drastic Decline of the Yellow-breasted Bunting
が引用されており 1970 年代から 1990 年代に減少したとされているが、この論文の Abstract からは読み取れない (オープンアクセス化処理忘れ?)。
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the bull-headed shrike Lanius bucephalus (pp. 5127-5151)。
現在でも珍しい鳥には違いないが定常的に見られている。North Eurasia Birds Watch の市民データベースではチゴモズよりも多くの写真が投稿されている。
[モズの遊び]
中西悟堂「定本・野鳥記」1 pp. 121-125 (1933 年初出) に飼育下のモズの遊びが詳しく述べられている。物をひっぱり合う、物を空中で捕える、独り遊び、ぶら下がる行動など。
表現を見るとハチクマの室内遊び (#ハチクマの備考 [(ヨーロッパ)ハチクマの飼育下の行動: ロシアなど] で翻訳を紹介した [ハチクマのお客さんになって] 参照) に大変よく似ている。モズ類は小鳥の中の猛禽類ともされるぐらい猛禽性が高く、中西氏もそのために必要な能力だろうと推定されている。
推定された通りこのような行動には猛禽性が深く関わっているのではないだろうか。そしてモズ類・カラス類は非常に近い関係にあって、この系統は猛禽性が強いものが含まれる (オウチュウ類など) ので、猛禽性は知能の発達に重要な役割を果たしたのではないだろうか。昆虫食でも猛禽的なところがあるし、動かない植物を食べるよりは相手の動きを読むなど知能の進化の必要性が高いのではないかと思う。
なお、中西氏もモズの「はやにえ」には関心を持たれていて貯食を考えられていたよう (一番自然な発想で昔からあったことがわかる)。ウグイスの鳴き声をまねる、カシラダカのこまかい声でもたくみにまねる
記述があるが、現代の書籍に見られるように多様な種類は挙げられておらず理解できる範囲に思えた。中西氏は joking のようなものではないかと表現されていた。中西氏が別の意味で使われていた可能性はあるが、英語で joke がかつて現代とは別の意味で使われていたようではなかった (OED)。
モズの声を "多数の種の鳴き真似" とする解釈は案外新しいのかも知れない。季語でもよく目立つ秋か冬に用いられることが圧倒的に多く、春の "ぐぜり" はあまり意識されていなかったのかも知れない。
「カシラダカのこまかい声」というのも単に複雑なだけなので、聞く人によってはヒバリを模倣しているように聞こえるかも知れない。単にモズが不規則にぐぜっているだけかも知れず、録音して分析しないとわからないだろう。
[モズの鳴き真似]
「モズは鳴き真似上手」は常識とされているが、常識を多少は疑ってみよう。
#コサメビタキの [音声] の項目に「ものまねは特にその印象が強い。過去に誰かが書いたものまねのリストをまとめたものなど、音源などの客観的データがないと信頼度がまったくわからないので、そのまま上書きしてさらに伝聞で伝えられてゆくことに危惧を感じるぐらいである」と書いたが、モズはその印象が強い。
成書にも多数の種類のものまねが挙げられているが聞き取りすぎの部分があるのではないだろうか。「モズの鳴き真似」の種類のリストが一度どこかに載ると次はそれを用いて付け加える形で種類が追加されて行ってどんどん膨らんでいるのではないだろうか。
このように感じたのは松田 (2019) Birder 33(12): 22-23 に冬の東京板橋区の荒川河川敷でセンダイムシクイをまねるのを聞いて、夏にはセンダイムシクイのいるような山地にいたことになると書かれていたことによる。センダイムシクイをまねることは同じく松田氏による情報 (1968.2.13 場所からこの事例を指していると思われる。2019 年の記事から見ると実に 51 年前の話である) として「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) にも紹介されている。
おそらく「高原モズ」(繁殖を終えたモズが夏は高原に行くと噂される) をふまえた解釈と思われるが、センダイムシクイがさえずっている期間はそれほど長いものではなく、一部の独身個体と思われるものは長期間さえずることもあるが、モズがもし夏に高原に行くことがあったとしても、そのような時期にはセンダイムシクイはそもそも活発にさえずっていないのではと考えるためである。
センダイムシクイがそれほど長期間さえずらないため、声を知っている人でも (関東以西の) 低山では旅鳥と考えたのではないだろうか (#センダイムシクイ備考の [センダイムシクイの和名の検討] 参照)。
松田 (2019) ではその場所にいない鳥のものまねからモズがどこで過ごしていたかわかることが述べられていた。「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」にも同じようなことが書いてあり、北海道のモズが北海道に生息しないコジュケイを真似た記録があり、本州に漂行したのではないかという (小川厳 1985)。
これを疑わしいと感じるならばキビタキがコジュケイを真似る解釈も同じように疑うべきとなるわけだ。
多くの人がよくわかる種類の声は限られていて、モズの複雑なぐぜりの中に知っているフレーズを聞き取ってしまうのではないだろうか。
そのつもりで「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」に掲載されている模倣される種のリスト (出典は 1985 年の「野鳥」編集部によるもの) を見ると圧倒的にさえずりで同定されたものと想像できる。カラ類などは大抵入っているが地鳴きかさえずりかよくわからない。カラ類の実物の音声識別でも難しいぐらいなので人によって何に聞こえるか違う可能性も大いにあるだろう。
セグロセキレイはおそらく地鳴きの方ではないかと想像する (セグロセキレイのさえずり自身が十分複雑なのでこれを模倣していると言われても少し納得し難い)。ミソサザイが含まれているがこれはさえずり? 地鳴き? 複雑なミソサザイのさえずりを模倣すると考えにくい (部分的なフレーズの一致はあるかも知れない)。もし地鳴きを模倣したとされるならばモズの地声と区別が付かない気がする。セキレイ類の地鳴き模倣とされるものがあっても、モズの地声と区別が難しいかも知れない。
複雑な声なのでヒバリの模倣と解釈されたものもありそうな気がする。ベテランでもクロツグミの声とコサメビタキを間違えるぐらいなので。
中西悟堂「定本・野鳥記」1 で取り上げられているカシラダカが含まれていないのも面白い。そもそもカシラダカの春先のさえずりはあまり有名でないためかも知れない。ある人はヒバリと解釈し、別の人はカシラダカと解釈した可能性も十分にありそうに思える。
確実な模倣はオオヨシキリ (「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」に音声が収録されているがそれほど上手くない) など生息環境の近い数種に限られるのではないだろうか。音声から夏に高原に行っていた客観的証拠はほとんどないのではないだろうか。
カラ類の模倣はヒヨドリでも行うのでモズの能力が特に高いというほどでない感じがする。
もちろん音声模倣をしていること自身を否定するわけでもないし、誤学習も含めて音の拾いこみはある程度行うだろうが (これは音声学習を行う他の種でも多数ある)、ぐぜりが複雑なのでたくさんの種類の鳥を聞き取ることができる (ように感じられる) だけではないだろうか。しかしヒタキ類や他のものまね鳥に比べると類似度がだいぶ違う気がする。
モズとカケスは系統が近いので音声模倣能力は共通で持っていても不思議ではない (#カケス備考の [音声模倣をするスズメ目] も参照)。
しかし過去の文献を引き継ぐだけでなくもう少し客観的に評価すべきなのではと感じる。
世界と比較すると日本に住むモズはなぜか多数の種類を模倣する結果になっているかも知れない。xeno-canto では韓国で1例の紹介がある: XC571412 (Wonseok Jang 2020.5.18)。ダルマエナガとエナガとのこと。ダルマエナガの音声を聞いてみると確かに特徴は似ている。エナガも含めて読者に判断をお任せする。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば百舌鳥の漢字表記を百鳥の音を真似ることからとしたのは国語辞典の「大言海」が出典のようで、当て字も含めた他説もあって解釈の一つのよう。この解釈に無意識に影響を受けて、モズの声を聞くとものまねと解釈しがちなのではないだろうか。
そのような字義解釈のない (知名度も低い) コサメビタキでは音声模倣があっても近年まであまり話題に登らなかったのだろうとも言える。"モズのものまね" だからこそ話題性が高く、「野鳥」に紹介されたように競って種類を挙げあった側面も否定できないだろう。相当古い記録を用いて紹介されているのも、近年はそのような競争習慣があまりなくて話題になっていないだけかも知れない。近年のモズはあまりものまねをしなくなった (?)。
「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」では清棲 (1965) に (コサメビタキは) ジュウイチ、ホトトギス、ヒガラの声を真似したのを聞いていると書いてあって、著者の蒲谷氏も「ほかの鳥の鳴き声を真似することがあり」と書いている程度で自身の記録した種類を残していない。モズのものまねをたくさん記述した共著者の松田氏による言及もない。
自分にはコサメビタキの方がモズよりずっと音声模倣能力が高いように感じられる。この点はメジロでも同様で、いずれも完全な歌と模倣の多い歌の2種類がある。後者をぐぜり (subsong) と慣習的に呼んでいるが、これは飼い鳥用語やヒトの音声の発達段階にも類比した考え方で、適切な名称なのかどうか実はよくわからない。模倣歌のような名称でもよいのかも知れない。
他のモズ類ではオオモズ (アメリカオオモズ) が他の鳥の声を真似ておびきよせて食物にしている話が有名で Atkinson (1997) Singing for Your Supper: Acoustical Luring of Avian Prey by Northern Shrikes (#オオモズの備考でも紹介)。
有名な学者の Atkinson の説なので信頼されているかも知れないが、実験手法も今から考えると相当原始的であまり額面通りには受け取らない方がよさそう。
他の鳥を引きつけて捕食する生態的意義があるならば、小鳥が興味を示す声であれば何でもよいとも言える (おびき寄せに使われる pish / pishing など音の正確さはそれほど問わないらしい)。自分で多数の複雑な音を発する際に他種の声を取り込んでしまうのはそれなりに有利な戦略なのかも知れない。コサメビタキでは同様の解釈は成立しそうもないのであくまでモズ類限定の解釈となるだろうが。
2025 年段階でもカラス科の音声模倣の意義の定説はないらしいので、まだまだ発展途上の分野だろうか。
#オウチュウの備考 [捕食者の声を真似る鳥] にもあるように、モズ類やオウチュウ類のように捕食性の強い種類は捕食に役立つと都合よく解釈されがちで、同じ系統でも捕食性が強くない種類は考察から省かれているだけかも知れない。
カラス小目 Corvida に比較的広く存在する形質で、サンコウチョウではさすがにあまり思い浮かばないが、コウライウグイスの多彩な声を考えると模倣または音声拾いこみが含まれていてもよさそうに思える。コウライウグイスは鳥をおびき寄せて食べるとは考えにくいので考察されていないだけの可能性があり、これらの系統は多くの種類が行うがそれほど統一的な役割はないのかも知れない。
国松・長島 (2009) Birder 23(6): 66-68 によれば「万葉集」に現れるモズの歌は2首のみであまり魅力がなかったらしいとのこと。用例としてモズの草潜 (くさぐき) があって、春になると人里で姿が見えなくなるのは山地に移って草に潜って隠れるものと解釈されていたものとのこと。
[モズ類の繁殖と移動]
モズ類で altitudinal migration が記載されている種類があるのか少し調べてみたところ、Barcante et al. (2017) Altitudinal migration by birds: a review of the literature and a comprehensive list of species
の文献調査の段階ではモズは Probable altitudinal migrant に分類されているが文献情報はなし。
Lanius 属でこの文献 Supporting Information Appendix S3 (この部分はアクセス自由) にあるものは3種で、論文が載っているものはチベットモズ Lanius tephronotus Grey-backed Shrike と高地で繁殖するもの。
[モズ類の系統解析と托卵排除] で紹介のようにタカサゴモズに近縁の種類。
Lu et al. (2010) Nesting Ecology of the Grey-backed Shrike (Lanius tephronotus) in South Tibet (オープンアクセスでない)。
オープンアクセスでより新しい繁殖関連の論文で Fan et al. (2021) The Grey-backed Shrike parents adopt brood survival strategy in both the egg and nestling phases を紹介しておく。Lu et al. (2010) の研究では標高の高い分布限界ではクラッチサイズが減少するとのこと。
変化の大きい条件下で繁殖するモズ類の研究モデルに適しており、その後の研究もある。
Zeng et al. (2024) Variation in parental investment preferences for nestlings of the Gray‐backed Shrike (Lanius tephronotus) in alpine environments。
どちらの論文も渡りについては特に言及はないがこれだけ高地で繁殖するならば冬は低地に下るのだろう。
もともと調べたかったのはモズ類の標行だったがあまり情報がない模様。
換羽戦略の視点から越冬地で繁殖する珍しい例については#キタヤナギムシクイ備考の [渡りと換羽戦略] ムナジロカワガラス Cinclus cinclus White-throated Dipper のスカンジナビア個体群で知られているとのこと。
この話題が気になっているのはいわゆる「高原モズ」の解釈は本当なのだろうかと疑問があるため。音声模倣が証拠になっているかどうかは疑わしい気がすることは既述した。
今西 (2005) Birder 19(10): 30-31 に標識調査によって同一個体が低地と高原で捕獲された2例があり、1例では神戸で標識されたものが長野へ、もう1例は長野で標識されたものが徳島で再捕獲され、同一個体はそれぞれ1か所で繁殖を行ったと考えられるが場所を変えて2回繁殖した証拠までは得られなかったらしい。
今西氏は海外の研究事例も紹介して low site fidelity (繁殖地または越冬地への執着性が弱い) 生活様式をとり、適所で繁殖している可能性を指摘していた。
アメリカオオモズ Lanius ludovicianus Loggerhead Shrike では Haas and Solane (1989) Low return rates of migratory Loggerhead Shrikes: winter mortality or low site fidelity? の論文が引用されていた。
比較的長距離の渡りを行う北米のオオモズ (分離されて別種となる) では再捕獲の例数が多いため越冬地または中継地の site fidelity は高いのではないかとの逆の研究結果もある: Rimmer and Darmstadt (1996) Non-breeding Site Fidelity in Northern Shrikes。
アメリカで北米のオオモズ (分離されて別種となる) の越冬地装着のジオロケーターによる研究が試みられたがこの時は回収できなかった: Origins of Northern Shrikes (Lanius borealis) Wintering in the Western Great Lakes Region (Minnesota Ornithologists' Union Savaloja Grant Report 2021, 2023)。
なかなか難しいらしい。
類縁性があるかも知れない繁殖様式では itinerant breeding があり、#ヤマシギ備考の [渡りながら繁殖するアメリカヤマシギ] に論文があり、スズメ目にも指摘されている事例がある。モズはそこまで極端でないものの中間的な繁殖様式の形態があるのかも。
冬場に「はやにえ」を作る習性も食物不足に備える役割がしばしば指摘されるように食物量や繁殖適地の変動が大きいのかも知れない。スズメ目でありながら猛禽類に似た生きた動物食に特化している点が冬場の食物不足につながりやすいのかも知れない。
草地や湿地に適応した生活様式をとって site fidelity の高くない猛禽類は #チュウヒ や #コミミズク を思いつく。対象とする主な食物は違うとはいえ、モズも生活様式にある程度の類似性が生じても不思議でないかも知れない。
モズ類は草地が出所で大陸から比較的近年日本に定着したがまだ森林被覆が大きく、繁殖に適した場所は高原の草地か河川敷の特に氾濫原などぐらいしかなく、パッチ状に存在する限られた適地の間を移動 (分散) しつつ適切な場所を見つけて繁殖していて (チュウヒ類からの連想)、その痕跡が個体によっては低地と高原を移動する生活様式に残っているのかも知れない。
アカモズ系統から進化したと思えば、定着後日本列島が大陸から分離されてしばらくは海を越えた渡りもあったかも知れないが、渡り行動の適応度が低くなって失われ、その後は国内短距離の移動を行っていたが、農地が開かれたことで生活可能範囲が広まって定住生活が可能になったのが現在の状況で、渡り距離が次第に短くなって部分的渡りをしているのではと解釈してみた。
明確にはわかっていないがアカモズとモズの分岐年代が日本列島が分離された時期に近いので、地理的に移動可能で交流のある間はアカモズとモズの祖先はまだ十分に分化していなかったのかも知れない。
農耕文化が広まらなければ大陸のモズの個体群ももっと広範に渡りを行っていたかも知れない、また日本はそれほど住みやすいところではなかったのではないかと考えてしまう。
草原性で生きた動物食でありながら長距離の渡りに適していないことが現在の生活様式を生み出したのでは。そしてもう少し広い範囲のモズ類の持つ「はやにえ」は、最初は貯食として進化したものかも知れないが別の役割も現れて同種へのアピールなど (毒の無害化の可能性なども含む) 複数の面で適応的となっているのではと考えてみた。
ほぼ渡り途中の小鳥を捕食しているエレオノラハヤブサの貯食行動を含めたハヤブサ目の事例は #チョウゲンボウ備考の [チョウゲンボウの貯食行動] の項目参照。
モズ類の肉食性の強さは カラス上科 Corvoidea (#アサクラサンショウクイの備考参照) がある程度共通に持つ性質を引き継いでいるものかも知れない。例えばオウチュウ科は肉食性が強く猛禽類に近い性質がある。
カラス上科の多くは熱帯系統であまり移動する必要がなかったが、モズ科は乾燥化に伴って草原に分布を広げ、季節や年変動の大きな草地に依存するためにある程度の移動生活が必要となり、種によっては長距離移動も行うようになった。熱帯からより冷涼な気候に進出したことで食物量の季節変動が大きく貯食行動が進化した。モズはユーラシアの分布の東の端となって長距離移動能力をまた失ったが、短距離移動は行い、「はやにえ」行動は一部は貯食の意義で他の目的にも役立つためそのまま維持されたと考えてはどうだろうか。
明瞭なさえずりを持たないのも生活や繁殖様式に関係があるかも知れないが、もともとさえずりをあまり進化させなかった系統で、自身のさえずりの多様性を進化させるよりも音を取り込む方を得意として、さえずりがあまり進化しなかったために中途半端な模倣で代用しているのかも知れない。同種への音声シグナルはさえずりにこだわる必要はなく、魅力を伝えられるならば別のものでも構わないだろう。
系統的に近いサンコウチョウのさえずりも音声起源的には地鳴き要素の方が強いかも (#サンコウチョウの備考 [サンコウチョウ類の進化] に取り上げた)。
松井・高木 (2005) Birder 19(10): 27-29 に大東諸島と小笠原に定着したモズの紹介がある。いつから定着しているのもかはわからないが、最も近い陸上分布から飛来したのであれば 500-1000 km の海上移動能力を持つことになるかも知れないとのこと。
多少気になっているのは船舶で運ばれた可能性で、過去にタカサゴモズが港近くの野鳥公園で記録された時にしばしば気にされたため。ライフリストに入れるべきかどうか迷った人もあったらしい。
大東諸島と小笠原のモズについては遺伝情報が調べられれば定着年代や経路が推定できるかも知れない。
高木 (2019) Birder 33(12): 26 によれば父島のモズ個体群は絶滅したとのこと。
-
アカモズ
- 学名:Lanius cristatus (ラニウス クリスタートゥス) 冠羽のあるモズ
- 属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 種小名:cristatus (adj) とさかのある
- 英名:Brown Shrike
- 備考:
lanius は#チゴモズ参照。
cristatus は a が長母音でアクセントもここにある (クリスタートゥス)。
種記載時学名 Lanius cristatus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Bengal ですでに存在した Lanius fulvus cristatus の名称をもとに整理した学名。
世界で4亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは superciliosus (眉のある、横柄な) アカモズと lucionensis (フィリピンの Luzon 島から) シマアカモズ (主にまれな旅鳥。九州で繁殖事例が知られ、南西諸島で越冬する個体もある)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で亜種不明がリストされている。
亜種 cristatus カラアカモズと confusus (混同された、混ざった) ウスアカモズは検討亜種。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には Lanius lucionensis と種扱いで、分布は Loochoo Islands リュウキュウモズまたはシマモズの名称が与えられていた。この "シマ" は島の意味でよさそう。
Linnaeus (1766) の付けた学名で由緒あるもの (原記載)。基産地ルソン島。
superciliosus の方がむしろ新しく 原記載 (Latham 1801) で基産地ジャワ島。Ogawa (1908) ではこちらがアカモズの学名となっていた。
#セアカモズの備考にあるようにこのグループの学名 (関連して英名) 変遷は複雑だった。Ogawa (1908) は別学名を与えておらず、この時代には Linnaeus (1758) の学名が有効なものとみなされていなかったか別種扱いだったと想像できる。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Lanius superciliosus Japanse Red-tailed Shrike の学名と英名を与えていた。
Red-tailed の由来はシベリアの Lanius phoenicurus Pallas, 1776 (参考。"赤い尾のモズ") 由来と想像され、Seebohm (1890) は日本のものはシベリア・インドのものと異なると記している。
Pallas のこの学名は現在使われておらず、複数種に対応するとされたものか (未確認)。ただしアカオモズ Lanius phoenicuroides Turkestan Shrike / Red-tailed Shrike に "Lanius phoenicurus に似た"、の意味で残っている。
Hartert (1910-1922) では p. 443。Lanius phoenicurus の変種として記載されたものもあって一定期間は有効な学名と考えられていたらしい。
さらに調べると Lanius phoenicurus Mueller, 1853 (参考) があり、これらの Lanius phoenicurus を用いた記載は Mueller (1853) の方を用いていた可能性がある。Pallas がすでに用いていたので無効学名として消え去ったものだろう。
Seebohm (1890) が Japanse Red-tailed Shrike としたのはシベリア・インドのものに対応する日本の種の位置づけであろう。
同じく Lanius lucionensis を Chinese Red-tailed Shrike と別項目にしているが、The Chinese race のように亜種扱いも念頭に置いていた。
アカモズの別名にモズタカ、シロモズ (現在とまったく違う)、タカモズがあったとのこと (コンサイス鳥名事典)。
Ogawa (1908) には別属名 Otomela が現れ、Bonaparte (1853) が命名した属名。ous, otos 耳 melas 黒い (Gk) から。
Gray (1855) が (当時の分類で) Lanius cristatus Linnaeus, 1758 をタイプ種に指定したもの (ただし現在の学名と含有関係の異なる概念だった可能性がある)。
(The Key to Scientific Names の情報からまとめた)。
加藤 (2023) Birder 37(9): 46-49 にアカモズ成鳥の亜種識別の記事がある。
フィリピンのリスト (2023) では lucionensis が留鳥および冬鳥で普通種。cristatus と confusus はまれな冬鳥か旅鳥となっている。superciliosus が含まれないのはやはり大陸経由でスンダ列島に渡っているのだろう [下記 Aoki et al. (2021) なども参照]。
Lanius cristatus Northern Brown Shrike と Lanius lucionensis Philippine Brown Shrike を独立種とする扱いの可能性も記されている。シマアカモズを独立種とする扱いは納得できる気もする。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" では superciliosus を時に Japanese Shrike と独立種とする扱いがあると記載されている。
アカモズと類縁種の分類については#セアカモズの備考参照。
Imanishi (2002) The Drastic Decline of Breeding Population on Brown Shrike Lanius cristatus superciliosus at Nobeyama Plateau in Central Japan
が野辺山で 1997 年と 1998 年の間に繁殖個体群の急激な減少があり、同時期に起きたインドネシアの大規模森林火災の影響の可能性を取り上げている。
[熱帯と温帯間の渡りの進化]
Aoki et al. (2021) Migration-tracking integrated phylogeography supports long-distance dispersal-driven divergence for a migratory bird species in the Japanese archipelago
に遺伝的解析を組み合わせて探る日本周辺のアカモズの渡り経路の進化 (この経路になった歴史的経緯) の論文がある。
渡りの進化に関係した論文で、Winger et al. (2019) A long winter for the Red Queen: rethinking the evolution of seasonal migration
の論文があり、上記 Aoki et al. (2021) にも引用されている。
渡る種類にとって、本拠地は熱帯か繁殖地か、という議論がなされて
きていた。熱帯が本拠地とする考え方では熱帯で留鳥であったものが
競争によって異なる緯度に分散した。温帯の方が繁殖期には資源が豊富
で競争も少ない、というのはよく聞く説明だが、これはこの
「熱帯が本拠地」仮説に基づくもの。多くの文献でこの仮説が広く信じられていると記述されている
(よく聞く説明を説明する時はあくまで仮説であると断った方がよさそう)。
しかしながら競争による分散は渡りと同じものではないし、競争によって
定常的な渡りがもたらされる根拠に乏しい、などの点で代わりとなる
仮説が提唱されているとのこと。季節変化の少ない地域からより季節変化の大きい地域への移動は
渡り行動を進化させる方向に働き、自然選択はこの表現型をより選択する方向に働く。
-
セアカモズ
- 学名:Lanius collurio (ラニウス コルルリオ) モズ
- 属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 種小名:collurio (合) kollurion アリストテレスの用いた同定されていないツグミ大の鳥 Gk。モズ (Belon 1555) または ノハラツグミ (Turner 1544) と推定された (The Key to Scientific Names)
- 英名:Red-backed Shrike
- 備考:
lanius は#チゴモズ参照。
collurio の読み方はよくわからないが、由来となるギリシャ語は kollurion の語末の -on が長音なので語末を伸ばす可能性がある。col-lu-ri-o と分割すれば -lu- にアクセントでよいと思われるので "コルルリオ" を採用した。
英名と学名の対応が悪いが、これは Lanius rufus Forster, 1817 (赤っぽいモズ) がかつて用いられていた時代の英名ではないかと想像する。
Foster (1817) 資料 は Lanius collurio に新しい学名を与えたもの (おそらく同定不十分など適切でない学名と考えたものと想像できる)。
この学名自身はセアカモズ (ただし当時の分類概念で) を指していることは疑いないが、同じ学名に使用例がいくつもあって Lanius rufus Latham, 1787 (ここに出てくる woodchat は現在はズアカモズ Lanius senator Woodchat Shrike) と同一か判定できないために無効学名となったものらしい。
Lanius rufus Linnaeus, 1766 もあって (こちらは基産地マダガスカル) すでに別概念で使用された学名であることは明瞭だった。
なお -backed が付いているのはアカオモズ Lanius phoenicuroides Red-tailed Shrike, Turkestan Shrike があるため対比のためと想像できる。
Lanius phoenicurus Pallas, 1776 (種小名の意味はジョウビタキの属名と同じ) の学名は古くからあり、これを訳して Red-tailed Shrike としたものと考えられるが、ややこしいことにこの学名が指すものは現在では単一種でないため使われなくなったものと想像できる (タカサゴモズの亜種が含まれていた)。
古い記載にはこの学名が現れることがあるが英名はおそらくこの学名由来。
phoenicuroides は phoenicurus に似た、の意味だが本家がなくなってしまった結果こちらが残り、英名もある程度引き継いだが種概念の変更によって地名に基づく Turkestan Shrike の方が適切となったものらしい。
和名は英名を訳したものと想像できるが、Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) ではこの英名に対する学名は Lanius cristatus が示されていた。こちらは現在アカモズを指す学名として用いられている。
現在のアカモズの分布に英国は含まれていないので、これはセアカモズとアカモズが同種とされた時代にどちらに先取権があるかの問題で解釈できそう。どちらも Linnaeus (1758) 参考 に出てくるが、Lanius cristatus の方が先に現れるため同種とされればこちらに先取権がある。
その後の分割で英名は Lanius rufus (Lanius collurio を意図していた) と改名されていた時代の学名由来のものをヨーロッパでより普通種のセアカモズに引き継ぎ、和名では逆となった可能性が考えられる。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) でアカモズは島もずと呼ばれていたと同定され、「百千鳥」(1799) で赤鵙/藪鵙の名称が登場していた。
一方「百千鳥」(1799) ではチゴモズに朝鮮鵙/島鵙の名称が与えられていたと同定されている。
これらの時代の用例も含めて英名や学名も参照して後に整理されたものだろう。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。食べ始める前に9回獲物を殺すとの伝説があり、"Neunmoder" (Neunmoeder? ドイツ語、セアカモズを指していた)、派生して英語で "nine-killer" (wiktionary、こちらはオオモズを指すよう) とも呼ばれる (コンサイス鳥名事典)。
参考: Colloquial bird names (BirdForum)。
セアカモズ1種を含む属名 Enneoctonus ennea 数字の9 ktonos 殺すもの (Gk) が提唱されたことがあった (Boie 1826)。意外に人気があり他種もこの属で記述されたものもあった (The Key to Scientific Names の情報よりまとめた)。
Dement'ev and Gladkov (1954) では Lanius cristatus はユーラシアからアフリカまで広範に分布する種としており、現代のセアカモズも含まれていた。
[セアカモズ類の分類と交雑]
これらの大陸のモズ類には雑種がしばしば見られる。日本に渡来するモズ類にも基本はセアカモズだがモウコアカモズの特徴を備えているなどの個体が見られる。
これらの大陸のセアカモズ類の関係については高木 (2013)「モズ類の新しい見どころ教えます」Birder 27(12): 26-27 に詳しく、頻繁な交雑の対象となる種類はセアカモズ、モウコアカモズ、アカオモズ Lanius phoenicuroides 英名 Turkestan Shrike または Red-tailed Shrike (IOC はこちらを採用) の3種で、これらは「半種」とされている。アカモズとの交雑頻度はこれらより低い。
高木 (2013) には Panov (1995) の示したこれらの種の関係と動作の絵も出ている。
Birder のこの号はモズ類の特集号で、マニアックな識別情報や交雑個体の識別などの記事も出ている。
アカオモズはかつてモウコアカモズと同種と考えられたが分離されたもの (日本語名を引くとどちらも同じ表記が出てきたりするのでややこしい)。
梅垣 (2019) Birder 33(12): 46-49 にセアカモズの第一回冬羽の形態と識別がある。これにもモズ類各種の分布図がある。
最近の研究でセアカモズは広範囲に分布するのに遺伝的特徴が重なり合っていて個体群レベルの構造 (例えば亜種) を見出せないことがわかってきた。
Parau et al. (2022) Red-Backed Shrike Lanius collurio Whole-Genome Sequencing Reveals Population Genetic Admixture
このような現象を panmixia という (参照)。
他によく知られた例ではヨーロッパのコキジバトなどがある。
大陸のモズ類は英語圏では迷鳥なので英語の情報が少ない。上記以外に Panov (2008) が写真も多数入った世界のモズ類の大著 "Sorokoputy (semejstvo Laniidae) mirovoj fauny. Ekologiya, povedenie, evolyutsiya" (世界の動物相のモズ類。生態、行動、進化) を出している。
分類変遷の表 (p. 393) もあり、Dement'ev (1937) で現在の4種を Lanius collurio、Dement'ev (1954), Portenko (1960) で Lanius cristatus (現在のアカモズの学名) に統一していた一方、Hartert (1910), Stepanyan (1969) は現在のセアカモズのみを Lanius collurio で他は Lanius cristatus。
Stegman (1930) では現在のアカモズのみを Lanius cristatus として残り全てを Lanius collurio に分類。
Oliver (1944), Johansen (1944), Stepanyan (1978), Voous (1979) は現在の Lanius isabellinus と Lanius phoenicuroides を Lanius isabellinus と分類し、他2種は現在通り。
Korelov (1970), Panov (1972) で Lanius isabellinus と Lanius phoenicuroides を独立種とした。Nejfel'dt (1978) も4種としたがどの亜種をどちらに入れるかは上記と微妙に異なる。
このように分類は非常に複雑である。
なお英語では "Shrikes of the World" [Norbert Lefranc (Author), Tim Worfolk (Illustrator) (2022) Helm] が出版されており、1997 年の初版の改訂版。中身を見たわけではないが、上記ロシアの研究などがどの程度扱われているのか興味あるところである。
上記「半種」は英語 semispecies ロシア語 poluvid であるがあまり使われる用語ではなく、通常の分類学では種として扱う [Mallet (2021) Subspecies, Semispecies, Superspecies]。
(モズ類を深く調べようとするとロシア語文献を読むことが不可欠なように思えてくる...)。
[モズ類のロシア語名]
興味深いことにロシア語ではモズ類を sorokoput と zhulan と2つに呼び分けている。セアカモズ類を呼び分けるのは分類にも対応していて面白い。sorokoput はもとウクライナ語で「カササギを追うもの」らしい (ロシア語が母語でウクライナ語のわかる人に意味を聞いてみたことがあるが、後半の意味はよくわからないと言われた。put は「惑わす」の意味かな?と言われていた)。
日本で主に見られるモズ類はこちらに入る。
zhulan はセアカモズ類。アカモズもこちらに入る (#カササギの備考参照)。
zhulan は語源不明とされるが、lexicography では zhulik 由来かも?との説がある。zhulik にはいくつかの意味があるが (こそ泥が主な意味)、小さな鋭いナイフ、引き裂くなどの意味はモズと整合性があるように思える。
[セアカモズは嘴の曲がっていない鳥を恐れない?]
話半分と思って見ておいた方がよいかも知れないが、Nemec et al. (2021) A kestrel without hooked beak and talons is not a kestrel for the red-backed shrike (Lanius collurio)
の実験では、嘴の先端の曲がりをなくしたチョウゲンボウの剥製を恐れなかったとのこと。
この前に当たる論文があって (話を聞いた覚えがあるのでどこかで紹介されていたかも)、Novakova et al. (2020) Object categorization by wild-ranging birds in nest defence ではチョウゲンボウの体を分割して順序を入れ替えたものを見せるとほとんどのセアカモズは外敵と認識できなかったとのこと。ただし完全に無害とは見なさなかったとのこと。
同じ研究者グループの実験で Krausova et al. (2022) Red‐backed shrike (Lanius collurio) versus common cuckoo (Cuculus canorus): An example of ineffective cuckoohawk mimicry
カッコウがハイタカに似ていても激しく攻撃されたのでタカへの擬態に意味がないのでは、との報告も出している。#カッコウ備考の [カッコウのタカへの擬態] の他研究の結論とはかなり違うのだがどれが正しいのだろう。
同じ研究者グループの実験で Antonova et al. (2021) Untrained birds' ability to recognise predators with changed body size and colouration in a field experiment
で、餌台を訪れる鳥 (ヨーロッパシジュウカラなど) がタカの模型を小型にするとより恐れないとのこと。
Abstract を見ると、このグループは "正統派" Lorenz and Tinbergen の流れをつぐ動物行動学者のよう。何をもとにタカを見分けているかなどを調べている (#ハイイロガンの備考 [首の短い鳥は危険?] 参照)。このグループは 2010 年ぐらいから古典的実験の再現などを試みているようで、いろいろなバリエーションの報告を行っている。
ハイイロガンの備考にあるように、危険な鳥を見分ける着眼点 (Lorenz の言葉では "解発因" Ausloeser) は最初は "短い首" と考えられたが違っていた。その後は曲がった嘴、鉤爪、腹の縞模様などが候補に挙がっていた模様。
この著者たちの研究でも selective habituation hypothesis も多少考慮しているが、野外で何度も見せているし違った鳥が餌台を訪れるので "慣れ" の要素は無視できるとして考察している (ほんとうか? 以下ハイイロガンの備考を参照)。
-
モウコアカモズ (第8版で検討種)
- 学名:Lanius isabellinus (ラニウス イサベルリヌス) 灰色っぽい黄色のモズ
- 属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 種小名:isabellinus (adj) イザベルのような (isabell イザベル (女性の名) -inus 〜に関連する) 英語にもなっている isabelline は灰色っぽい黄色の意味だが語源はよくわかっていない
- 英名:Isabelline Shrike
- 備考:
lanius は#チゴモズ参照。
isabellinus のラテン語発音が不明だが、すべて短母音とすれば isa-bel-li-nus で -bel- にアクセントがありそうに思える (イサベルリヌス)。参考までにラテン語 bellus は短母音のみ。
旧和名オリイモズ。日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。世界で3亜種 (IOC)。
かつてはセアカモズと同種と扱われることもあった (#セアカモズの備考参照)。
-
タカサゴモズ
- 学名:Lanius schach (ラニウス スカク) スカクの声の(?)のモズ
- 属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 種小名:schach (外) A-Scack (Pehr Osbeck 1757) による (音声起源の) 造語で、この種の中国名に由来すると言われている (The Key to Scientific Names)
- 英名:Long-tailed Shrike
- 備考:
lanius は#チゴモズ参照。
schach は1音節なのでアクセントは問題になり得ないが、sch- を例えばドイツ語式に読むのは適切でない。Osbeck の由来に基づけば s, c は別の子音として発音すべき (ラテン語発音規則にも合う)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では基亜種 schach とされる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
世界には9亜種があり (IOC)、台湾の亜種は formosae とされていたが現在は通常基亜種に含まれる。和名の「タカサゴ」は台湾の意味。
Lanius schach (英名 Rufous-backed Shrike; いわゆるタカサゴモズ東部亜種) と分離されることがあるとのこと [Brazil (2009) "Birds of East Asia"] だが IOC では採用されていない。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも IOC 同様の扱いと思える。
タカサゴモズの現代の中国語での俗名は「海南 (島の名前) モズ」に相当する。
森岡 (2003) Birder 17(9): 47 に日本産タカサゴモズと他の亜種との比較検討がある。日本に来ているものはおそらく基亜種としている。台湾個体の写真との比較もあるが白斑の有無の異なるものがあるとのこと。
現在ではシノニム扱いだが Lanius schach lingulacus Hachisuka, 1939 (参考) 産地 Shanghai, China があり、タイプ標本を YIO-00149 (山階鳥類研究所) で見ることができる。
lingulacus は lingua 舌 から派生でおしゃべりな人などの意味 (The Key to Scientific Names)。
採集者は Rosenberg, W. F. H. (1884.3.3)。ラベルにはタカサゴモズの名称はなかった。
台湾の標本は 19 世紀よりあり、台湾では普通種であることがわかる。
かつてタカサゴモズの亜種扱いだったこともあるチベットモズ (別名セアオモズ) Lanius tephronotus Grey-backed Shrike は現在は分離されている。Peters' Check-list of the Birds (2nd edition も)、Howard and Moore 2nd edition では同種扱いだった。
コンサイス鳥名事典によるとタカサゴモズの英名が Black-headed Shrike となっていた。
かつて使われていた Lanius nigriceps の学名由来と考えられる。
Lanius nigriceps yunnanensis Yamashina, 1944 (参考) 当時はこの学名が使われていた。
この英名は東部またはヒマラヤの亜種 tricolor を指すとのこと。
-
オオモズ (分割された)
- 第8版学名:Lanius borealis (ラニウス ボレアーリス) 北のモズ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Lanius excubitor (ラニウス エクスクビトル) 番人のモズ
- 第7版亜種学名:Lanius excubitor bianchii (ラニウス エクスクビトル ビアンキイ) ビアンキの番人のモズ (主要亜種。他亜種あり)
- 第7版属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 第8版種小名:borealis (adj) 北の
- 第7版種小名:excubitor (m) 番人 (excubo (intr) 見張りをする -tor (接尾辞) 行為者を表す)
- 英名:[Great Grey Shrike 分離前の名称], IOC: Northern Shrike
- 備考:
lanius は#チゴモズ参照。
borealis は a が長母音でアクセントもここにある (ボレアーリス)。
excubitor は変化形では長母音が現れるが、この形では短母音のみ。ex-cu-bi-tor で -cu- にアクセントがあると考えられる (エクスクビトル)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版以降 Lanius excubitor の分割に伴い、日本のオオモズは Lanius borealis (北方の) となる (英名 Northern Shrike)。
この種は世界に5亜種が認められており (IOC)、日本で認められている亜種は bianchii (ロシアの鳥類学者 Valentin Lvovich Bianchi に由来) オオモズ (サハリンから南千島に分布) と mollis [柔らかいの意味。羽毛の特徴を述べたものと思われる (The Key to Scientific Names)] シベリアオオモズ (アルタイ山脈からモンゴル北西部に分布) である。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では亜種 funereus を mollis に含めて4亜種としている。Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) でも同じ扱い。
ユーラシア東部から北アメリカの中・高緯度帯で繁殖。基亜種 borealis は北米の亜種。亜種 sibiricus は東シベリア、モンゴル北部からカムチャツカ分布と日本に近い。
第7版の亜種に第8版の種小名が現れないのは分割に際して Lanius borealis に移動となり、borealis の記載の方が早いため。
分離後の Lanius excubitor (Great Grey Shrike) と呼ばれるものは (和名はまだないよう?) ユーラシア中・西部からアフリカ北部に広く分布し、12 亜種が認められている (IOC)。これまでの学名や英名を使う時は注意が必要である。この種が Lanius 属のタイプ種。
分離前の Great Grey Shrike の Great は Lanius major Pallas, 1811 (参考) 由来と考えられ、Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire ではこの学名と対応する Pallas's Grey Shrike が与えられていた。
この学名をそのまま訳せばオオモズになるが和名との関係は? 当時知られていた日本のモズはモズ、アカモズ (+ シマアカモズ)、チゴモズ、オオモズの4または5種のみであったため名称整理はあまり複雑でなかったものと思われる。大きいモズと学名由来のいずれも考えられそう。
しかしこのような単純な学名は早々に使われていて、Lanius major Gmelin, 1788 (参考) Pallas のものはおそらく無効となったものと想像される。
Gmelin (1788) の記載は当時同種だったオオモズ (Lanius excubitor) の変種 (var.) として記述されたものだったが(亜)種小名と扱われたものと考えられ、対応する minor がヒメオオモズ Lanius minor Lesser Grey Shrike となっている。
ヒメオオモズの 原記載 (Gmelin 1788) 基産地は Italy, Spain, Russia; restricted to Italy (Hartert 1910) (Avibase による)。フランス語名の Pie-grielche d'italie が記述されているため基産地はイタリアに限定された模様。
Lanius major の学名は奪い合いだったようで、Wilkes (1812)、Brehm や Bogdanov も用いていた。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「百千鳥」(1799) に大鵙が現れているが、モズ類の名称は当時も複雑で学術的な整理もおそらく必要になったと想像できる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではオオモズの名称は Lanius major Pallas, 1811? に対して与えられており、上述のように学名と英名の対応がよいが、
Shalow (1884) Notes on 'Lanius cristatus' and 'L. borealis,' of Nelson's 'Birds of Bering Sea and the Arctic Ocean'
にあるように当時から同定は混乱していた模様。
学術的な名称整理の際に用いられた可能性があるとすれば Pallas の学名は和名に残っているのかも知れない。
"Great Grey Shrike" の英名に関連して、さらに チベットオオカラモズ Lanius giganteus Giant Grey Shrike があり、"Great" はすでに使われているのでやむを得ず "Giant" を使った (学名との整合性はよいが、学名も同じような経緯で付けられたものかも) ものもある。新しく分離されたオオモズの英名が Northern Shrike とされたのも "Great" を避ける意味があるかも。
何語でも同じだが "Great" とか "Greater" を付けた名称にするともっと大きいものが見つかった場合に困る例。
Ryabitsev (2014) では広義オオモズを2種を分離しない扱いだが、分離する扱いも紹介されていて、その場合ほとんどすべてのシベリアの亜種は北米を中心とした Lanius borealis に属するが、leucopterus のみが Lanius excubitor に残るとある。
しかしこの亜種は Lanius excubitor homeyeri のシノニムとするリストも多い。西シベリアに分布。
複数種に分離する分子系統研究は Olsson et al. (2010) The Lanius excubitor (Aves, Passeriformes) conundrum - Taxonomic dilemma when molecular and non-molecular data tell different stories。
Lanius excubitor は単系統でなく、ミトコンドリア ODC 遺伝子では少なくとも6種に分離できる可能性が示されたが他の取り扱いも可能で、ここでは系統分類の変更提案はなかった。しかし clade D とそれ以外の違いが十分大きいので現在の分類に至っている模様である。
mollis と sibiricus の違いも小さく mollis に吸収されるかも知れない。
さらに北米の borealis ともある程度近い。
1例しかデータがないがサハリンの bianchii のみが少し離れた系統を作る点はむしろやや意外かも知れない。
ただし今から見るとやや古い限定的な解析なのでより広い領域の遺伝情報を用いた新しい研究が出れば結果が変わるかも知れない。
・bianchii の記載時学名は Lanius excubitor bianchii Hartert, 1907 (原記載) 基産地 Sakhalin Island (サハリン島)。
・mollis は Lanius mollis Eversmann, 1854 (原記載) 基産地 Chuya River (Chujskaya steppe), Russian Altai (ロシアのアルタイ地方)。羽毛はキレンジャクほぼ同様に特に柔らかいとある。
・sibiricus は Lanius excubitor var. sibiricus Bogdanov, 1881。基産地 Chukotski Peninsula, Okhotsk, Khanka, etc. . . . restricted to Chukotski Peninsula by Dementiev, 1935, Oiseau Rev. Franc. Orn., 5, p. 92 (Avibase による)。
Dement'ev and Gladkov (1954) によれば Lanius major Pallas, 1811 もこれを指したものとされるが preoccupied? とのこと。
・Lanius seebohmi Gadow, 1883 (参考) 基産地 Amur は Dement'ev and Gladkov (1954) では sibiricus のシノニム扱い。
[アメリカオオモズ]
アメリカオオモズ Lanius ludovicianus Loggerhead Shrike は 1960 年代以来減少を続け、カナダでは亜種 migrans が絶滅寸前状態。
アメリカのいくつかの州では見られなくなった。減少原因は不明とのこと。
San Clemente Island Shrike (亜種 mearnsi) も1983-1988に 5-10 個体まで減少 (wikipedia 英語版などより)。
San Clemente Loggerhead Shrike (San Diego Zoo) の記事によればこちらはヤギが増えすぎ、1994 年にようやく駆除されたとのこと。飼育下個体群が確立され野外放鳥も行われている。
カナダの亜種は Eastern Loggerhead Shrike Captive Breeding (Tronto Zoo) の記事によれば限られた孤立した草原のみで繁殖しているが、個体数減少は生息地減少の速度を上回っているとのこと。アメリカ南部の越冬地の環境悪化の可能性もある。こちらも飼育下個体群が確立され繁殖地の環境改善や野外放鳥も行われている。
カナダでは Loggerhead Shrike - Wildlife Preservation Canada
というパンフレットもあり、おそらくそれほど詳しく知らない土地所有者に向けたもの。こちらでは入植前にあった草原 (prairies) が農地に変わるに伴って牧草地にすみかを移したが、現在ではそれも放棄されたり農作物を植えるようになって生息地が減少したとなっている。
日本だと見つけてもバードウォッチャーに知らせないようにと注意がありそうだがこちらはそうでもない模様。表現からはバードウォッチャーも生物学者と同列に記されており社会的信用も高そうな印象を受ける (日本のカメラマン問題は海外でも多少は知られていて、ここでは今のところそこまで心配はしていないがもし問題になってくるようならば対応を変える、などの表現を聞く)。
特に誰かに知らせる必要はないが、正確な数の把握は重要なので知らせてもらえるとありがたいような書き方。専門家によって繁殖が確認されれば Conservation Land Tax Incentive Program に従って税の割戻しが受けられる可能性があり、このモズの繁殖に必要な環境の維持に役立てて保護に協力してもらえる可能性があるとのこと。
[アメリカオオモズの毒バッタ対策]
情報出典は「野鳥」2021年1・2月号 p. 10。
アメリカの Eastern Lubber Grasshopper Romalea microptera は有毒で警告色を持ち、試した鳥は皆吐き出したという: Schowalter (2018) Biology and Management of the Eastern Lubber Grasshopper (Orthoptera: Acrididae)
食物からカテコールやヒドロキノンなど、また神経ペプチドを合成するとのこと。
Yosef and Whitman (1992) Predator exaptations and defensive adaptations in evolutionary balance: No defence is perfect
アメリカオオモズのみは "はやにえ" にすることで、1-2 日で毒性が失われ特別な代謝機構を発達させることなく食べることができるとのこと。大型で数も多いバッタなので食べられるならばよい獲物とのこと。
Yosef and Eisner (1996) Contrasting reactions of loggerhead shrikes to two types of chemically defended insect prey によれば万能でもなく、
pyrrolizidine alkaloids (ピロリジジンアルカロイド。肝毒性があり、アサギマダラなどが蓄えるとのこと wikipedia 日本語版より) を有するガ Utetheisa ornatrix (これも警告色を示す。こちらはこちらで毒性の強いものが性選択されるとのこと) は食べたが、cantharidin (テルペン類) を有する甲虫の Lytta polita は拒否したとのこと。
ピロリジジンアルカロイドは鳥にも有毒のようで、飼料が汚染されていてニワトリが中毒死した例がある: Pyrrolizidine Alkaloid Toxicity (Adrian Gallagher)。
肝臓で dihydroalkaloids など寿命は短いが非常に有毒な代謝産物になって急性毒性を示す。一部はより毒性が低いが長寿命で細胞分裂に影響を与える dehydroamino alcohols となる。
ピロリジジンアルカロイドは一部の植物 (対草食動物) やそれを摂取した虫などに含まれるとのこと: Moreira et al. (2018) Pyrrolizidine Alkaloids: Chemistry, Pharmacology, Toxicology and Food Safety。
[アメリカオオモズの獲物の殺し方]
Sustaita et al. (2018) Come on baby, let's do the twist: the kinematics of killing in loggerhead shrikes
はアメリカオオモズ (体重約 50 g) が嘴でどのように獲物を殺すか高速度ビデオ撮影で記録した。6-17 Hz の周波数、角速度 49-71 rad/s で頭を振って獲物に強力な加速度を与えるとのこと。
ネズミの首周辺には重力の6倍の加速度が働くと推定。ラットでの実測値では 2.45 N (0.25 kg 重) の力で頸椎の靭帯の損傷が始まるとのこと。アメリカオオモズの実測に使われたネズミではこの 1/20 ぐらいとのこと。
獲物を高速に振ることで獲物の体 (の遠心力と読めばよいだろう) からかかる力がこの4倍ぐらいとなって頸椎に損傷を与えることができるとの見積もり。実際にも獲物の頸椎の中央部付近が損傷していることが多く、ちょうど交通事故におけるむち打ちのような効果を与えていると考えられる。
他の種類でも獲物をくり返し振って殺すものがあるが、獲物を物体に打ち付けているわけではない点が異なる。
論文著者もこれだけが要因とは考えていないようで嘴で噛む力も加わっているだろうとしているが、噛む力だけでなく加速度による力が効いているらしい点が新しい。獲物の体に構造的な弱点があり、つながった重い体に加速度を与えることで大きな力となり比較的簡単に弱点にダメージを与えることができる
(我々が同じような構造のものを振り回すと簡単に壊してしまう状況に似ている。振り回す側のモーメントは小さいので大した力が必要ないのは体験する通り)。
同じ著者が同様の実験で嘴に働く力 (噛んだりひねる力) も測定している: Sustaita and Laurin (2024) Biomechanics of biting in loggerhead shrikes: jaw-closing force, velocity and an argument for power。
[目先の剛毛 rictal bristles の役割と進化]
モズ類などの目先 (lore) の剛毛 rictal bristles には抵抗する獲物から目を守る役割があるとも言われる。ここではミナミオオモズ Lanius meridionalis Iberian Grey Shrike/Southern Grey Shrike を扱っているが機能はヒタキ類などにもおそらく当てはまるのだろう。
主に羽毛の種類と分布の記述の論文:
Labouyrie (2022) Feather characteristics of loral zone in an insectivorous passerine: The Iberian gray shrike Lanius meridionalis, in southern France。
生える部位や羽毛の形状にも種類がある。
夜行性のフクロウ類やヨタカ類などで触覚センサーともなっていることはよく知られている通り。
rictal bristles の進化の系統研究もあって興味深いので紹介しておく: Delaunay et al. (2022) The evolutionary origin of avian facial bristles and the likely role of rictal bristles in feeding ecology。
87% の種類が持っていると推定。圧倒的に陸鳥。またわかりにくい系統樹なのでじっくりどこが何に相当するか見て欲しい。
意外にも食物や環境、採食様式などとの相関は弱く、夜行性との相関が強かったが他にも役割がある。目をほこりなどから守る役割も挙げられているが、この著者は羽毛進化の最初は bristles で感覚の役割を果たしていたアイデアを気に入っているよう。夜行性の鳥でよくみられるのは祖先的形質ではないかと想像している。
以下追記。ヒタキ類にも当てはまると思っていたら違うらしい。
Lederer (1972) The Role of Avian Rictal Bristles。
高速度撮影 (当時はアナログ時代で撮影してフィルムを手作業で処理したとのこと) してみると虫は rictal bristles にまったく当たっておらず、捕虫網の役割は果たしていない。上嘴の鈎の部分で捕えているとのこと。
著者によるページ Rictal Bristles (Lederer 2018)。
コメントも多様で面白い。新しいコメントもある。著者は感覚器の役割が大部分 (三叉神経につながっている点が重視されている) で目を保護する機能はほぼないと考えている。
三叉神経を介した反射で目を動かす / 閉じるなどのアイデアも出ているが著者はあまり有力と考えていない。
多様な種類の鳥に存在し、ヨタカ類やキーウィが含まれるが夜行性以外の共通点は少ない。ヨタカ類もキーウィ同様に嗅覚に頼っているのではとのアイデアも出されている。
2018 年にヨタカ類の組織学的研究を行ったが Auk が論文を reject した (つまりおそらくまだ出版されていない)。感覚器であろうことは多分確かだろうが、との書き方になっている。
レンジャク類にもあるが主たる食性は飛翔性昆虫食ではない。ただし虫を食べないとまでは言っていない。
空中で虫を捕食しないイヌワシにもある。共通点がよくわからないとのこと。
(ここからは自身の考え) この部分の羽毛がハチクマではうろこ状になって覆いを作っているのはもしかするとヒントになるかも。ハチクマでも単なるハチが刺すことへの保護のためだけではなく、もっと積極的に感覚器の役割を果たしている可能性もありそうに思える (この点はコウモリダカも同様)。虫からの振動を感じて顔をそむけるぐらいのことはできるかも知れない。
ハチクマといえどもこの部位の羽毛は比較的薄いため刺されるのを避けるための虫センサーの役割は有効かも知れない。1か所だけ接触があればよけるなり頭を振るなりすればよさそう。複数の接触が同時にあって対処できないレベルになれば一度離れればよいなどの危険密度センサーの役割が考えられる気がする。それ以外の場所はほとんど刺さる危険性はないと想像すればこの点だけ注意すればよい。目の直前なので視覚的にも判断しやすい。
さらなる考察は #ハチクマ [目先の羽毛の役割] に重複掲載と追加検討を加えた。
イヌワシでは特に役割を果たしていないかも知れないが、視線を遮らない最も原始的な発達段階の羽毛になっている。鳥類の皮膚では完全に羽毛なしとすることは難しい。それでもイヌワシのこの部位の羽毛の長さが最短まで短縮しているわけではないのは何か積極的な役割があるのだろうか。
#イヌワシ備考の [中央アジアの鷹狩り歴史] muz-murut の種類のイヌワシでは鼻孔から嘴の先端に達する硬い剛毛のような毛が突き出ている との記述がある。この種類は寒冷地に住むらしい。あまりアイデアを思いつかない。
ヒゲワシの剛毛は装飾のように見えるが、感覚器の役割もあるのだろうか。
#ハチクマ備考 [タカ類の嘴縁突起] で紹介した「アニマルライフ」(日本メール・オーダー 1974) p. 248 の嘴縁突起のはっきり見えるオオタカの写真を見ていて、これも rictal bristles が長く鼻孔に及んでいることに気づいた。羽毛の生え方までわかる鮮明な写真だった。
日本のオオタカよりだいぶ淡色なのであるいは北方型なのかも。
写真を見ながら役割を考えていたが、鼻孔にまで及んでいるのはあるいは鼻孔に獲物の肉、血、羽毛などの異物が入るのを防ぐ可能性もあるように思えた。ハヤブサ類の鼻孔内の突起は高速飛行時の呼吸を助けるためとの説があるが、あるいは同じような役割なのかも。
タカ類ではハヤブサ類と鼻孔の形が異なるので rictal bristles を発達させることができる場合はそちらを伸ばすことで対応しており、ハチクマで鼻孔がスリット状になっているのはハチが入ることを防ぐとともに、防御やセンサーのための羽毛として用いたため rictal bristles を伸ばすことができない制約を鼻孔の形で補っているなどの考えも思い浮かぶ。
このオオタカのような場合は rictal bristles が異物に対する感覚器となっているかも知れない。
[モズの鳴き真似は捕食効率を上げる?]
出典となる論文は Atkinson (1997) Singing for Your Supper: Acoustical Luring of Avian Prey by Northern Shrikes。
北米のオオモズ (分割で別種となる予定) の鳴き真似を流すことでコマツグミのさえずり以上に他の鳥が集まってきたという。
十分な実証が行われているわけではない。情報出典は Carouso-Peck et al. (2021) The many functions of vocal learning のレビュー論文から。音声学習についてはキンカチョウは山のような論文があるが、他はほとんど調べられていないとのこと。
-
オオカラモズ
- 学名:Lanius sphenocercus (ラニウス スペーノケルクス) 楔形の尾羽のモズ
- 属名:lanius (m) 引き裂くもの (lanio (tr) 引き裂く)
- 種小名:sphenocercus (合) 楔形の尾の (sphina 楔 Gk、cercus (m) 尾葉)
- 英名:Chinese Grey Shrike
- 備考:
lanius は#チゴモズ参照。
-cercus の由来となるギリシャ語は短母音のみでラテン語にも長母音は現れないと思われる。
sphen- の方はギリシャ語 sphen, sphenos の e は長母音でラテン語でも伸ばす可能性がある。発音規則からは -no- にアクセントがあり "スペーノケルクス" となりそうだがいかにも読みにくい。
単形種。
かつてはチベットオオカラモズ Lanius giganteus Giant Grey Shrike と同種とされたが分離された。
この分割経緯による可能性があるが、英語別名に Chinese Great Grey Shrike があり、これはほとんどそのままオオカラモズの和名につながっているように見える。もしそうであればオオカラモズの "オオ" は同種時代の Lanius giganteus に由来することになる。
ミナミオオモズ Lanius meridionalis Southern Grey Shrike の近縁種もあり、他の大陸モズ類同様に分類学者によって意見が分かれている。
さらにこれら英名はオオモズの別名 "Great Grey Shrike" とも同様で、さらに古くはこれらがすべて同一種で地域名などをつけて区別していたのかも知れない。
Gluschenko et al. (2023) Breeding birds of Primorsky Krai: the Chinese grey shrike Lanius sphenocercus (pp. 3285-3305)
の沿海地方で繁殖する鳥に紹介されている。少数が地域的に繁殖する種だが繁殖生態の写真も多数掲載されているのでご覧いただきたい。繁殖地の光景も越冬地とよく似ている感じ。
△ スズメ目 PASSERIFORMES カラス科 CORVIDAE ▽
-
カケス
- 学名:Garrulus glandarius (ガッルルス グランダーリウス) ドングリを好む騒がしい鳥
- 属名:garrulus (adj) 騒々しい
- 種小名:glandarius (adj) ドングリを好む (glans glandis (f) ドングリ -arius (接尾辞) 〜に関連する)
- 英名:Jay (鳴き声から), IOC: Eurasian Jay (分割候補種で、学名英名ともに変わる可能性がある)
- 備考:
garrulus は長母音を含まず冒頭にアクセント (ガッルルス)。
"ガルルルス" の表記でもよいだろう。不自然に感じるのは日本語で R と L の区別がないことと母音があってもなくても同じ表記になってしまうため。
R と L の区別を行わないとセキショクヤケイなどの属名 Gallus とカタカナ表記 (ガルルス、または詰まる音を用いる表記では ガッルス) がよく似てしまうのでその点からも区別を意識しておくのがよいかも。
glandarius は -da- の a が長母音でアクセントもここにある (グランダーリウス)。glans は a に長音記号があるが短音で読まれることが多い。-arius の冒頭の長母音とアクセントに由来。
ユーラシアに広く分布し、世界で 34 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は japonicus 亜種カケス、
brandtii (プロイセンの動物学者でシベリアを探検した Johann Friedrich Brandt に由来) ミヤマカケス (北海道)、tokugawae (徳川家康に由来) サドカケス、orii (Hyojiro Orii 由来) ヤクシマカケス とされる。
亜種カケスの記載時学名 Garrulus glandarius japonicus Temminck & Schlegel, 1847 (記載)。図版。フランス語名 Le geai ordinaire du Japon。
当時は亜種概念は明確でなかったが6つの races (種族、亜種相当の意味で使われる) の一つ、学名は (ヨーロッパの) 普通のカケスの日本版の位置づけ。他の races では必ずしもそうなっておらず他命名者が別種扱いとしているものもあった。
カケス周辺の他の種の記載を見ても "du Japon" になっているのでヨーロッパに身近な対応種が存在して違いが小さいものにはその日本版と名付けたよう。
brandtii は Garrulus brandtii Eversmann, 1842 (参考) 基産地 Altai。
tokugawae は Garrulus glandarius tokugawae Taka-Tsukasa, 1931 (参考) 基産地 Sado Island。
orii は Garrulus glandarius orii Kuroda, 1923 (原記載) 基産地 Yakushima。
現在はミヤマカケスのシノニムとなっている pallidifrons Kuroda, 1927 の 記載。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire ではミヤマカケスを Garrulus brandtii Brandt's Jay、亜種カケス (当時は日本の他の亜種はまだ記載されていなかった) を Garrulus japonicus Japanese Jay としていた。
さらに Garrulus sinensis Chinese Jay が載せられており、Cptain St. John によって長崎で収集された1例があるのみとのこと。
OED によれば英語 jay は 1350 年ごろにすでに用例があるとのこと。広義に使われるようになったのは 1694 年の用例が最初とのこと。
カケス類以外を指す用例もあってニシコクマルガラスを指す用例などが 1484 年より記録されている。
[カケスは何種?]
Saitoh et al. (2015) (#カルガモの備考参照) による DNA バーコーディングではミヤマカケスと亜種カケスは (別種相当の) 最大 4.43% の違いがある。
Aoki et al. (2021)
Formation of Macro- and Microrefugia Explains Morphological Divergence of the Eurasian Jay Garrulus glandarius in the Japanese Archipelago
に大陸のカケス (亜種 krynicki のみ)、ミヤマカケス、日本本土のカケス、サドカケスの分子系統研究がある。{日本本土 + サドカケス} と {ミヤマカケス + krynicki} は大きく分かれ、240 万年前に分かれたと考えられる。
本土のカケスとミヤマカケスはそれぞれの分布の南限にあたり、氷河期のそれぞれの系統のレフージアであったと考えられる
[Aoki et al. (2018) Quaternary-related genetic differentiation and parallel population dynamics of the Eurasian Jay (Garrulus glandarius) in the circum-Japan Sea region]。
この研究では日本周辺のみが調べられているが、日本本土のカケスとサドカケスは分岐年代 22 万年前ぐらいで、佐渡が小型のレフージア (microrefugia) の役割を果たしていた可能性がある。
大陸と近い日本列島で固有種が進化するプロセス -カケスから見えてきたこと- (バードリサーチニュース2018年11月: 2)。
鳥博セミナー「日本列島の鳥の起源と進化 - DNAの研究でわかった鳥たちの歴史ー」 (我孫子市鳥の博物館 2020)。
青木 (2021) Birder 35(12): 73 にも解説がある。
カケス全体を網羅した研究はまだのようだが、ロシアとヨーロッパを中心とした亜種の研究は Akimova et al. (2007) First insights into a DNA sequence based phylogeny of the Eurasian Jay Garrulus glandarius (出版元サイト)
にある。ユーラシア北部の亜種より日本の亜種の方が古い系統にあたり、カケスは東南アジア由来ではないかと考えている。ルリカケスはさらに古い分岐にあたることになる (#ルリカケスも参照)。
Garrulus 属にはもう1種あり、インドカケス Garrulus lanceolatus Black-headed Jay。ルリカケスと類縁の可能性があるとされた (Goodwin 1976 "Crows of the world")。
Goodwin (1952) A Comparative Study of the Voice and Some Aspects of Behaviour in Two Old-world Jays。
その後はあまり調べられていないよう。
カケスは世界では色彩をもとに8グループ (分子系統がわかっていないので8系統とは書けない) に分けられるとされる (例えば wikipedia 英語版)。Kleiner and Stresemann (1940) が出典とのこと。
HBW/BirdLife はカケスは3種に分割している。
東南アジアのもの (leucotis グループ) HBW/BirdLife では Garrulus leucotis White-faced Jay としている。
ヒマラヤなどのものを Garrulus bispecularis Plain-crowned Jay として中国の亜種 sinensis や台湾の亜種 taivanus などをこちらに含めている。カケスが東南アジアが由来であれば、東南アジアやヒマラヤなどの系統がより古い可能性があるが分子系統関係はまだ明らかにされていない。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" は北海道を除く日本周辺のグループを Japanese Jay Garrulus japonicus としている。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) によればシベリアの亜種は1つでミヤマカケスとなっている。
ヨーロッパの基亜種とミヤマカケスが別種となれば、ミヤマカケスが Garrulus brandtii Eversmann, 1842 となるかと言えばそれほど自明でもない。
Akimova et al. (2007) の結果を見ると亜種 brandtii は分けられそうだが、亜種 krynicki と基亜種を分けるかどうかが問題となりそう。分ける場合には krynicki Kaleniczenko, 1839 の記載が早いので、この周辺の亜種は Garrulus krynicki とまとめられそうだが他の亜種との関係がまだ十分わかっていない。
Akimova et al. (2007) では krynicki と基亜種の雑種も挙げられているので生殖隔離はあっても弱いのだろう。Garrulus krynicki は独立させずに現状通り Garrulus glandarius にまとめることにことになるのだろうか。
もしヨーロッパの基亜種と brandtii が分離されないのであれば、ミヤマカケスの種名称がヨーロッパの基亜種についても使われることになる可能性がある。いかにもややこしそう。
他にも記載の早い亜種では atricapillus Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832 (シリア、ヨルダン、イスラエル)、bispecularis Vigors, 1831 (ヒマラヤ) があり、いずれも japonicus Temminck and Schlegel, 1847 より早いので、もしカケスとミヤマカケスが分離された場合に種カケスあるいは種ミヤマカケスの学名はどの亜種を含むか次第となる。
シリア、ヨルダン、イスラエルは遠いので日本のカケスとは遺伝的にも多分遠いだろうと想像はできるが、基亜種の方に近いのか、それとも分布の広い brandtii の方に近いのか、独自性が高くて種相当かはまだわかわない。
atricapillus と隣接する地域には hyrcanus (アゼルバイジャンからイラン) があって分布的には brandtii に遺伝的に近くても不思議でなさそう。しかし前述の krynicki (コーカサス) がその北側に分布しているのでどこで線を引くか微妙である。
atricapillus と brandtii が同種に含まれ、基亜種と別の種になる場合は atricapillus の方が種学名となるはず。
顔のパターンが全然違うので別種が適当にも見えるが遺伝情報を調べないと結論は難しそう。
bispecularis も同様で、中国・台湾の亜種と分布がつながっている。独立したグループなのか、それとも日本のどれかの亜種と関係があるかどうか次第で学名がややこしくない可能性がある。
中国にも sinensis と pekingensis があって、後者は brandtii グループに含まれるらしいが分布が途切れているわけでもないのでどこで区切るのか難しそう。
さらに中国中部には kansuensis もある (これらはいずれも記載が新しいので種学名に影響を与えるわけではないが、カケスを複数種に分離するならば境界がどこになるかの問題にシジュウカラ同様に関係してくる)。
Dickinson and Martens (2004) Systematic notes on Asian birds. 44. A preliminary review of the Corvidae に検討がある。
アジアの亜種のシノニムなどの情報が Dickinson et al. (2004) Systematic notes on Asian birds. 45. Types of the Corvidae にある。
ミヤマカケスにはかつて pallidifrons Kuroda, 1927 の亜種学名があった (タイプ標本は消失) が brandtii のシノニムとなった。
本州以南のカケスとミヤマカケスが独立種に相当するほど違うことが明らかでも、カケス全体を何種に分けるか次第の部分があり、簡単に種学名を与えることができない理由となる。HBW/BirdLife は東南アジアのグループは日本とは違うだろうとの判断から、記載は遅いが leucotis Hume, 1874 を採用している模様。
なおミヤマカケスは世界分布的には「シベリアのカケス」と呼んでふさわしそうなのだが、アカオカケス Perisoreus infaustus の英名が Siberian Jay なので英名で「シベリアのカケス」とは呼べない。英名では Brandt's Jay が使われている。
[音声模倣をするスズメ目]
Goller and Shizuka (2018) Evolutionary origins of vocal mimicry in songbirds
が音声模倣をするスズメ目の系統解析を行っている。音声模倣の定義そのものも難しいが、スズメ目内で何度も進化し、また失われたことがわかる。
結論よりも系統樹を見て考えていただく方が面白い。カケスとモズの系統は比較的近いので模倣が多いのかと多少納得できる気がする。そういえば#オウチュウ類もこのグループ。
系統的には近いのに reed warblers (ヨシキリ類など) では模倣が多いが他のムシクイ類 (特に leaf warblers) ではないのはなぜか。
ムクドリ類やヒタキ類で比較的多いのはよく知られているがこれらは確かに系統的にまとまっている。
新世界のフィンチを含めたホオジロ類系統では非常に少ない。新大陸の研究者は音声模倣の研究対象種が限られ、うらやましく思っているかも。
[信号に外敵の種類を信号に盛り込む鳥]
カケスとは属が違うがアカオカケス Perisoreus infaustus Siberian Jay はモビングの際にタカとフクロウで異なる声を出すという: Griesser (2009) Mobbing calls signal predator category in a kin group-living bird species。
外敵の種類を情報に盛り込むことは血縁選択で進化したのではとの解釈をしている。
#シジュウカラ、#オウチュウの備考も参照。
Gill and Bierema (2013) On the Meaning of Alarm Calls: A Review of Functional Reference in Avian Alarm Calling
に比較的新しいレビュー論文があり、外敵の種類を情報に盛り込む (ここでは外界の情報を示す信号として functional reference と呼ぶ) ことが確認されている報告の一覧もある。
ニワトリでの Evans et al. (1993) On the meaning of alarm calls: functional reference in an avian vocal system が先駆的研究とのこと。
ミツスイ上科 トゲハシムシクイ科の マミジロヤブムシクイ Sericornis frontalis White-browed Scrubwren で地上と空中の捕食者で信号を使い分けることが知られ、シジュウカラの場合と同様ひなの声への反応も調べられている (Higgins and Peter 2002 など)。
他に北米でよく知られているコマツグミ Turdus migratorius American Robin、キイロアメリカムシクイ Setophaga aestiva American Yellow Warbler で調べられている。
この時点では鳥で知られているものは6種で、過去の他の報告は証拠が十分でないとしている。霊長類での研究が先行して当初は高度な認知能力を持つ動物に特有と考えられていたがそうとは言えない証拠が集まりつつある。
Carlson et al. (2019) Wild fledgling tits do not mob in response to conspecific or heterospecific mobbing calls
のアオガラを用いた実験では若鳥は同種または異種のモビング音声に対して成鳥のようにモビングを行わず、モビングとモビング音声の関連は学習されるものの可能性が示唆されるとのこと。
Davies et al. (2024) Eurasian jays (Garrulus glandarius) show episodic-like memory through the incidental encoding of information
カケスにもエピソード記憶と呼べるものがある研究。過去の実験は必ずしもエピソード記憶に頼っていない能力を測っていた可能性がある。
[フロリダカケスの保全と問題]
フロリダカケス Aphelocoma coerulescens Florida Scrub Jay はフロリダ州の固有種で、アメリカ合衆国大陸部の固有種 15 種のうちの一つ。
IUCN では VU 種、生息地の減少や人間活動で過去 100 年で 90% の個体数減少があったとのこと。現在は 10 未満の個体群からなっており、それぞれの個体数が 1000 を超えず消失の危険があるとのこと (wikipedia 英語版より)。
2000 年代前半により良好な生息域への個体群移転が行われた。個体数は増加したが遺伝的劣化を免れなかったとのこと: Linderoth et al. (2025) Translocations spur population growth but fail to prevent genetic erosion in imperiled Florida Scrub-Jays。
[カラス科の音声模倣]
Wascher et al. (2025) Vocal mimicry in corvids (preprint)。
ここで調べられた種類ではワタリガラスのスコアが高かった。カケス、ハシボソガラスも多くの事例がある (調査には xeno-canto を用いている)。非繁殖期にも模倣を行うため性選択によるものではないのではなどの考察。
-
ルリカケス
- 学名:Garrulus lidthi (ガッルルス リドティ) リッズの騒がしい鳥
- 属名:garrulus (adj) 騒々しい
- 種小名:lidthi (属) lidth の (オランダの動物学者 Theodorus Gerrit van Lidth de Jeude 献名およびタイプ標本の所在地博物館名)
- 英名:Lidth's Jay
- 備考:
garrulus は#カケス参照。
lidthi はラテン語式読みではこうならざるを得ないと思われる (リドティ)。
記載時学名 Garrulus lidthi Bonaparte, 1850 (原記載) 基産地 Asia orientali [= Amami Oshima] (Avibase より) で、特に問題となることがなさそうに見えるが記載時の Asia orientali がどこを指すか長くわからなかったらしい。
標本はあるが 参考 1 (アジアのどこか、としかわからない)。
1905 年に奄美大島で再発見されたとのこと: 参考 2。Hartland (1905) Ibis の報告 (1905.1.25 の報告日付。この号は 1905 年4月出版)。
Ibis の報告では Owston の採集人数名が台湾と九州の間の主な島を 1904 年に調べ、ルリカケスがこの島にのみ見つかったと記述している。世界の鳥学に再発見として認識されたものはこれが早かったよう。
国松・長島 (2011) Birder 25(11): 65-67 (ルリカケスのことは p. 66) によれば、明治 30 年代には再発見されておらず産地などが不明だった。奄美大島に多く生息することを小川三紀氏が見出したとのこと。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にはルリカケスの名前で Amami-Oshima (Terra typica) と記述されていた。
「日本動物大百科 鳥類 II」(日高敏隆監修 樋口広芳・森岡弘之・山岸哲編集 平凡社 1997) の「日本の鳥類目録と鳥類分類学」 p. 175 では小川氏が奄美大島のルリカケスを再発見となっている。
Ogawa (1905) Garrulus lidthi が出典のようで Owston の採集人によるものである点は Hartland (1905) の報告と同じ。この文献ではカケスを Kashidori と呼び、ルリカケスを Ruri-Kashidori と呼んでいた。
この論文の冒頭は Notes on Mr. Alan Owston's Collection of Birds from the Islands lying between Kiushu and Fermosa (オオトラツグミの記載論文と同じ。この号は 1905 年7月出版)。
奄美大島の調査は 1904.8.22 - 1904.9.10 の期間だったとのこと。Owston と採集人についてはこの文献に詳しい。
小川の調べた標本の一部は地元猟師が得た期間外のものや採集隊が離島した後に 1905 年1月の標本が含まれていたそうだが、ルリカケスの標本はすべて上記採集期間に含まれている。この記述部分を見ると 1905 年1月以降に標本を調べる機会を得たものかも知れない。
コンサイス鳥名事典では 1900 年ごろから帽子の装飾用に多数が捕獲されたが 1921 年に天然記念物に指定されて保護されるようになったとのこと。なんと再発見されるとすぐに乱獲が始まっていた。
再発見に伴って世界の博物館が標本を欲しがったのも後押しになっていたのかと思ったが、「原色日本野鳥生態図鑑」(中村登流・中村雅彦 保育社 1995) p. 66 によれば 1915 年ごろには標本として輸出され年に 3000 羽が殺されたと書かれていた。
単形種。
[ルリカケスとカケス類の関係]
おそらく一般向けの表現と思われるが、ルリカケスからカケス類が進化したような説明をしばしば見るのでそのように言ってよいのか少し検証してみた (#カケスの備考参照)。
ルリカケスとカケスのみで系統樹を作るとそのような関係になるが、インドカケス Garrulus lanceolatus Black-headed Jay を加えて解析してみると少し様相が異なる結果が得られた。
ただしあくまで Genbank の BLAST で cyt b 遺伝子を簡易解析したものでそれ以上深い解析は自分の力量を超える。この結果例では {インドカケス + ルリカケス} がまとまってカケスと並列の関係になった。
あくまで解析の1例でこの系統樹が正しいかどうかわからないが、インドカケスがカケスから進化したものではなく、{インドカケス + ルリカケス} の系統がそもそも存在していたのではとも読める。
そのように考えると {インドカケス + ルリカケス} の系統 (2系統あっても構わないが) がインドから奄美大島にかけてかつては分布しており、その中間部分で消滅したため隔離された形になっている可能性が考えられる。オナガのユーラシア両端の分布だけが残っているなど、これらの比較的古い分岐のカラス系統は大陸のように競争の激しいところで消滅しやすかったのではないだろうか。
ルリカケスはたまたまカケスやカササギなど競争相手になりそうな種類の分布しない島嶼部でぬくぬくと (?) 独自の進化を遂げて生き残ったものではないだろうか。ルリカケスの祖先となる集団は大陸で進化したが競争種 (特にカケスなど) の出現で消滅しただけではないだろうか。
Garrulus 属は Pica 属から系統的にも少し離れているので、Garrulus 属の祖先系統は何度も定着を試みたが生態的に優位に立つことが難しく消え去ってしまったのではないだろうか。カケスの出現である段階を突破し、ようやくグローバルな競争力を獲得して広範囲に安定した生態的地位を築くことができた。いかがだろうか。
日本列島は大陸と距離があって競争による絶滅頻度が低く古い系統のものが残存し得たので、系統解析すると他地域で同系統が消滅している場合に一見日本列島が種の供給源になっているように見えることもあるのかも。
上記の場合も系統樹の正当性まではわからないが、もしインドカケスが絶滅していればルリカケスの祖先が大陸にかつて分布していた証拠が見つけられないかも知れない。
この部分を記述してから気づいた「日本の鳥の世界」(樋口広芳 平凡社 2014) pp. 35-37 にもインドカケスとの関係を取り上げて同様の趣旨の説明がなされていた。
西海 (2014) Birder 28(8): 4-5 でもルリカケスは遺残固有との説明があった。
スズメ目最初の系統とされる イワサザイ科 Acanthisittidae (#ミソサザイの備考参照) も同じようなことを考えている。地上性の捕食者のいなかったニュージーランドでこそこの系統の末裔が何とか生き残ったもので、ニュージーランドでスズメ目が生まれて進化したとは言えないのではないだろうか (比較参照「野鳥」2024 年 9・10 月号 (No. 872) p. 11 西海功氏の解釈)。
Claramunt and Cracraft (2015) A new time tree reveals Earth history's imprint on the evolution of modern birds によればイワサザイ科は Passeri とは独立した系統として現れたもので、鳴禽類 (oscines) は 4730 万年前のオーストラリア (Australian landmass) 由来と推定できるとのこと。
亜鳴禽類 (suboscines) では現生で最も祖先に当たる系統の Eurylaimides は新大陸に分布し、こちらは 3700 万年ぐらい前でオーストラリアに至る旧世界におそらく複数回の導入があったと考えられるとのこと。
系統的には 亜鳴禽類 → 鳴禽類 の順序となるが現生系統の確立や適応放散の年代は逆順になるかも知れない。鳴禽類はオーストラリア由来の従来解釈には変更はないが亜鳴禽類は別だろうとのこと (#ズグロヤイロチョウの [旧世界亜鳴禽類の進化と生物地理学] に関連情報がある)。
かつてタカ類が古いと考えられていた時期にアフリカと南アメリカが地続きであった時代の名残りの系統関係が提唱されていたが現在では否定されており、タカ類の主要系統の適応放散時期の新しさがここでもわかる。
もっとも、島が種生成に果たす役割が近年評価されてきていることも確かで、#メジロ備考の [Great Speciator] にいくつかの研究がある。メジロ属はあるいはスリランカで誕生? など。
#コウライウグイス備考の [コウライウグイス類に毒耐性があるか?] で紹介した中で、上田恵介氏は「野鳥」2021年11-12月号 (No. 855) pp. 12-13 (警告色) で赤と黒のデザインが警告色として機能している可能性を挙げてルリカケスの色彩も同様ではと提案している。
色にうるさい鳥類捕食者には意味があるかも知れないが、奄美大島の猛禽類は越冬時期のサシバとリュウキュウコノハズク、繁殖期のアオバズクで、リュウキュウコノハズクはいかにも小さいしアオバズクも関連が薄そう (色覚の面でも夜行性捕食者はあまり関係がないかも知れない)、サシバも繁殖期にはいない。
有力な猛禽類不在だったため自由に生息環境や性・社会選択に任せて進化することができた色彩ではないだろうか。他のカケス類もこのような色を発達させたかった (?) が、大陸のように有力な猛禽類の生息する環境では色彩に対する選択圧が強く、一点飾り程度にとどまっているのかも知れない (このような視点でカケスの飾りを考えるのも面白いかも)。
佐渡のカケスもある程度本土のものと異なっているようだが、佐渡にはノスリやオオタカも生息するので有力な猛禽類不在とはならないと想像できる。中津 (2013) Birder 27(7): 21 によれば佐渡はオオタカやサシバが少なくノスリが多いとのこと。#オオタカ備考の [オオタカの生息確認は難しい?] のようにノスリはよく姿を表す効果も考慮する必要があるかも知れない。
このような観点から見れば、奄美大島の固有種の存在は猛禽類不在がもたらしたものとも言えるのかも知れない。猛禽類がなぜそれほど生息しないのか考えてみると、日本に生息する北方系、南方系のタカ類いずれにとっても分布域より遠く、多くの種が海を越える能力をあまり持たないため定着困難だったのだろう。海外ではミナミチュウヒのように分散力の高いものはあるが地域があまりに違っていた。
Tachyspiza 属は分布可能と思われるがちょっと小型すぎて定着しても大した捕食圧にならなかったかも。
ノスリ類は定着可能だったかも知れないが訪れる確率が低くたまたま定着しなかったのか。いずれも現在の分布状況に基づくもので、過去に一時的に定着してルリカケスの進化に影響を与えた可能性は否定できない。
捕食者に対する適応を失ってしまうとそう簡単に取り戻すことはできず、捕食者の少ない島で進化したものが大陸に進出するのはそもそも難しったのではないだろうか。
-
オナガ
- 学名:Cyanopica cyanus (キューアノピカ キューアヌス) 青いカササギ
- 属名:cyanopica (合, f) 青いカササギ (kyanos 紺青色の Gk、pica (f) カササギ)
- 種小名:cyanus (m) ラピスラズリまたは瑠璃 (ギリシャ語 kuanos 由来)
- 英名:Azure-winged Magpie
- 備考:
cyan- は長母音。アクセント規則によれば "キューアノピカ" となる。
cyanus は冒頭が長母音でアクセントがある (キューアヌス)。
Cyanopica 属は Bonaparte (1850) によるものとされ、Avibase によれば記載が該当記載と思われる。この時点の Cyanopica cyana の学名も 1990 年代からさらに一部は 2000 年代初頭まで長く使われていた。
Cyanopica 属は同年の Conspectus Generum Avium (Bonaparte 1850) にも登場し、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) のコメントによればこちらの文献が初出とのこと。
AviList v2025 - errors, typos (BirdForum 2025.6) にも Cyanopica の年代について議論が紹介されている。事情はかなり複雑で最初の有効な記載と判定されるものは 1850.11.11 と考えられるとのこと。
AviList v2025 - errors, typos (BirdForum 2025.7) でも Avibase 運用者による直々の解説がある。
AviList の学名は検討委員会が一通り目を通しているが、まだ暫定的で記載年や元文献などまだ詰めてゆく部分があるとのこと。Cyanopica の年代は 1850 年で確定と考えられるが、文献は2つあるどちらを採用するか決まっていない。H&M4 の時代のように少数の分類学専門家が決めていた時代からコミュニティで議論してゆく形式に変わりつつある背景が現れているよう。
AviList が世界共通の分類体系となっても誰もが意見を述べられる状況になるので、多くの人の目による文献検証によってこれまでの専門家の判定を覆す事例も出てくると想像できる。
オナガは最初 Corvus cyanus Pallas, 1776 基産地 Dauria と記載されたもので、Bonaparte (1850) は性を属に合わせて cyanus を cyana と変更したものだが、cyanus は形容詞ではなく男性名詞 (鉱石のラピスラズリまたは瑠璃) であってそもそも女性形もなく名詞の性は変化させない新しい規則に基づいて cyanus に固定されたものと考えられる。
Cyanopica は女性であるため、亜種が japonica の形となっているのは性の一致のため。種小名の性と一見一致しないように見えるがこのような事情と想像される。
かつてはイベリア半島のイベリアオナガ Cyanopica cooki (英国生物学者 Samuel Edward Cook に由来、英名は Iberian Magpie) と同種とされた。
「本種の特異な隔離分布は長らく謎とされており、15 世紀の南蛮交易船が日本からイベリア半島へ持ち帰ったという珍説まであった」(wikipedia 日本語版)。
別種とされるに至った研究は Fok et al. (2002) Inferring the phylogeny of disjunct populations of the azure-winged magpie Cyanopica cyanus from mitochondrial control region sequences;
Kryukov et al. (2004) Synchronic eastwest divergence in azure-winged magpies (Cyanopica cyanus) and magpies (Pica pica) と比較的最近である。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では学名 Cyanopolius cyanus (Pallas, 1776) 英名 Eastern Blue Magpie だった。
この当時は当時の名称で Spanish Blue Magpie (cooki) と亜種以上のレベルで異なるかは疑問としていた。
Temminck (1820) の時代にはまだ cooki は知られていなかったが 1835 年の書物には含まれている。"Fauna Japonica" の 記述 と 図版 で別種としていないが、同じ図版を使って Seebohm (1890) は別扱いとした。
"日本からイベリア半島へ持ち帰った" に相当する説は Seebohm (1890) に紹介されており、もと連続分布だったものが途中で途絶えたとは非常に考えにくく、中国からスペインに持ち込まれた説を考え、タイリクキジが中国から英国に持ち込まれたのと同様であるとした。東西の特徴の違いはスペインの方が雨が多くて自然選択で適応したとこの部分は現代的な進化的考え方を示している (進化のタイムスケールは当時はまったくわかっていなかったかも)。
当時用いられた Cyanopolius の属名は Gray (1855) が提唱したもの。Cyanopica Bonaparte, 1850 の方が早いので使われなくなった。
原田 (2016) Birder 30(9): 34-35 によればオナガは 1950 年代まで西日本でも点々と記録があったとのこと。
[オナガの亜種と和名]
中西悟堂「定本・野鳥記」1 p. 61 (1934 年初出) によれば亜種 japonica が与えられており、別名に大和鵲、オナガドリ、関東尾長が与えられていた。朝鮮にはコマオナガがいるとのこと。
この "コマ" は古い国名の高麗の読み (こま) 由来で、現在ではコマホオジロ Emberiza jankowskii Jankowski's Bunting の和名に残っている。この種は現代の図鑑でも朝鮮半島に少数繁殖または迷鳥の表記となっている [Brazil (2009) "Birds of East Asia"]。
コマオオルリはかつてオオルリの亜種和名だったが亜種チョウセンオオルリと改名された (亜種小名も変わった)。
日本の亜種記載は記載時学名 Cyanopica cyanus japonica Parrot, 1905 (参考 基産地 "Nippon")、原記載。
Hartert (1910-1922) p. 23 では基亜種 cyanus が朝鮮半島から日本南部の島まで生息するが蝦夷にはいないと表現されている。Cyanopica 属はおそらく朝鮮半島経由で日本に到着したため蝦夷には生息しないとの推論が述べられている。
日本のものはおそらく小さいとあるので Parrot の記載を参考にした可能性があるがシノニムとして載せられていない。
Parrot (1905) では日本のオナガが小さい点については Hartert も注目していて別の場所に述べる、とあり、Hartert の記述はおそらくこれに該当する。朝鮮半島から日本への分布を検討した結果亜種にに値しないとして一度は基亜種に含めたものと考えられる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には Onagadori, Onaga の両名が併記で、Parrot の記載が新しかったためまだ別亜種と認識されていなかった可能性がある。
亜種 swinhoei Hartert, 1903 (原記載; 基産地 Kiukiang, northern Kiangs) は Hartert 自身の記載。
さらに亜種 interposita Hartert, 1917 (原記載) を Hartert 自身が記載することになり、japonica のグループに含めてしまうと japonica に先取権があるため Parrot のものを日本の亜種として認め、自身の記載を有効にしたと考えることができる。
ここで Hartert も認める亜種 japonica となったものと推定できる。
Hartert (1910-1922) p. 2026 では補遺の形で japonica と interposita を認めた。
かつては Cyanopica cyanus koreensis Yamashina, 1939 (原記載 Note on the Specimens od Manchurian Birds Chiefly Made by Mr. Hyojiro Orii in 1935) と朝鮮半島のものをさらに亜種とする扱いもあった。
この文献ではさらに pallescens Stegmann, 1931 アムールヲナガ、stegmanni Meise, 1932 マンシウヲナガ の名称がすでにあり、jeholica Yamashina, 1939 ネツカヲナガ もさらに名付けていた (旧満洲国の地名熱河)。この時点で山階氏が調べたものは7亜種あった。
山階鳥類研究所の標本データベースによれば YIO-00146 (1930 年 Moppo, S, Korea) が亜種 interposita コマオナガ が koreensis テウセンヲナガ と訂正されており、かつては朝鮮半島のものは Hartert (1917) の記載した亜種 interposita コマオナガ と認識されていたらしい。
YIO-00141 (1935 年 Pref. Heisen, Jehol, China) は 亜種 stegmanni マンシウヲナガ が jeholica ネツカヲナガ と訂正されていた。
亜種が多数記載され、当時の日本統治下の亜種それぞれに和名を与えるために表記を "オナガ" に統一して短縮された経緯ではないだろうか。
ちなみにニワトリの品種のオナガドリの方は 1923 年「土佐ノ長尾鶏」(チョウビケイ) の名称で天然記念物に指定、高知ではナガオドリ、オナガドリと読ませていたとのこと (土佐のオナガドリ)。特別天然記念物「土佐のオナガドリ」は 1952 年指定。
土佐のオナガドリの名前が先に決まっていたため "オナガ" に短縮されたわけではなかったものと想像できる。
現在の日本国外の亜種はすべて基亜種にまとめられた。
おそらく Kryukov et al. (2004) で形質が連続的に変わり、形態的には japonica のみが区別できる結果を受けたものだろう。ただし分子遺伝学的には分離されなかったとのことで、japonica を認めるのは形態学が根拠と思われる。
イヌワシの日本亜種と似た状況かも知れない。
AviList では日本のオナガの亜種は現在 japonica とされ、他に基亜種 cyanus を認めている。
現在認められている亜種と分子遺伝学の整合性が悪い例は他にもいくつもあるので今後概念の再検討が行われるかも知れない。カンムリワシでは国内でも島ごとに遺伝的違いが認められているので別亜種に値するのか、のような問題になる。
-
カササギ (分割された)
- 第8版学名:Pica serica (ピカ セーリカ) 絹のように光沢があるカササギ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Pica pica (ピカ ピカ) カササギ
- 属名:pica (f) カササギ 備考参照
- 第8版種小名:serica 絹のように光沢がある
- 第7版種小名:pica (トートニム)
- 英名:[Magpie 分割前の名称], IOC: Oriental Magpie
- 備考:
pica の語源は witionary によればイタリア祖語 *peika で、遡るとインド・ヨーロッパ祖語の *(s)peyk- キツツキまたはカササギとある。同じ語からキツツキを表すラテン語 picus が派生したとある。
サンスクリット語で pika がカッコウとのこと。
serica は冒頭が長母音でアクセントがある (セーリカ)。
#ヤマセミ備考の [学名の lugubris の意味と生態的意義] にあるように英文学では白黒の持つ二面性から不吉な鳥と考えられていたとのこと (コンサイス鳥名事典)。magpie や pied の名称は必ずしもよい意味で使われていない可能性もあるので注意。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で種が分割されて Pica serica (「絹のように光沢がある」の意味)となり、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。対応する英名は Oriental Magpie。
ユーラシア東西のカササギは同種でなくなる見通し (#オナガの備考も参照)。
IOC は2亜種 serica, anderssoni (スウェーデンの考古学者で中国を探検した Johan Gunnar Andersson に由来) を認めているが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)には亜種の言及はない。
[カササギの japonica はどうなった?]
かつての亜種 japonica (伝統的な九州の個体群) は Avibase では anderssoni のシノニム表示になる。この経緯を以下で少し考察してみる。
分離前の種記載は Corvus pica Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europa, restricted to Sweden by Hartert, 1903, Vog. pal. Fauna, 1, p. 19; and further restricted to Uppsala by Meinertzhagen, 1954, Birds Arabia, p. 79 (Avibase による)。
Pica 属は Brisson (1760) が定義したものが有効とされた。このまま属名にして種小名もそのまま使うとトートニムとなるため種小名変更も行われた (#ノスリの備考参照)。
Pica caudata Eyton, 1836 (参考) (尾に特徴のあるカササギ)、
Pica communis Selby, 1831 (参考) (普通のカササギ)、
Pica varia Salis, 1863 (参考) (染め分けられた? カササギ の意味か)
など。年は Richmond Index に出ているもので初出年かどうかまではわからない。いずれももっと早い用例があったものと想像できる。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では学名 Pica caudata Common Magpie となっていた。学名は改名されたもので、由来は Gerini (1760) となっている。1890 年段階でもトートニムが避けられていたことがわかる。
japonica の記載は Pica japonica Bonaparte, 1850 (原記載) この記載によれば Pica varia japonica Schlegel 由来とある。
"Fauna Japonica" で 記載 フランス語名 la pie ordinare du Japon (普通のカササギの日本版の位置づけ)。図版なし。こちらも改名された学名を用いている。
こちらが記載とされていないのは Bonaparte (1850) の出版の方が少し早かったのだろうか、あるいは Bonaparte は別種にするなど明瞭に分離する意図を示していたためだろうか。
anderssoni は Pica pica anderssoni Lonnberg, 1923 (原記載) とこちらの方が遅い。
Pica 属が他の属とまとめられた時に japonica が preoccupied となったのかも知れない。Bonaparte (1850) は Pica japonica と Corvus japonensis の同一文献で記述しており、例えば Corvus 属に統合されると問題が発生したのかも知れない。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) のオンライン情報を見ていると Introduced (serica) to Japan (Kyushu) とあり、移入種扱いなので独立したタクソンとは認めらなかったのかも。後者の方がそれらしいがいずれも可能性がありそう。
分割前は Pica pica serica と書けたので japonica を表面に出す必要がなかったが、Pica pica と Pica serica が別種となって、日本の個体群が後者に含まれることになり、亜種を認める場合は扱いがややこしくなっている模様。
記載時期は serica, japonica, anderssoni の順なので、serica と anderssoni を別亜種とするならば anderssoni より japonica の方に先取権が発生する可能性がある。
上述のような何らかの理由で japonica の使用が避けられているようなので表立った問題とはなっていないようだが、移入種扱いは解釈の一種なので自然分布だったならば覆る可能性が残るかも知れない。過去に preoccupied であったとしても現在は preoccupied の状態になっていないので少し不明瞭なところが残る感じがする。
日本鳥類目録第8版のように Pica serica を単形種とすれば問題は起きないが、これは亜種概念次第であり命名上の都合から単形種とする扱いはできないだろう。
H&M4 では種を分割するにはサンプル数が十分でないとの判断のようであるが、今となってはかなり古く後述 Kryukov et al. (2017) への言及はまだない段階だった。
世界の主要リストも Kryukov et al. (2017)
Deep Phylogeographic Breaks in Magpie Pica pica Across the Holarctic: Concordance with Bioacoustics and Phenotypes
を受けて分割した模様。Clements も 2018 年、IOC 8.2 より採用。
そして Song et al. (2018) Complete taxon sampling of the avian genus Pica (magpies) reveals ancient relictual populations and synchronous Late-Pleistocene demographic expansion across the Northern Hemisphere の研究が後続する。
北海道には 1980 年代より目撃があり、近年急速に数が増えている (北海道カササギプロジェクト)。原田 (2016) Birder 30(9): 34-35 にも解説がある。
この個体群はロシアのものと遺伝的に近いとされる (Kryukov et al. 2017)。北海道カササギプロジェクト掲載の他学術文献も参照]。
この論文によれば少なくとも亜種 serica と jankowskii を認めることが妥当との結論になっているが、この段階で確定的なことは言えないとの記述から目録への亜種記載が見送られているのかも知れない。
坂田 (1989) 漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 pp. 57-60 (大修館書店 1989) によれば異国のカラスの意味でトウガラス、コウライガラスの名称が江戸時代に使われていたとのこと。
[カササギのロシア語名]
ロシア語でカササギは soroka (サローカと読む) であるが、数字の 40 は sorok (ソーラックと読む。変化形で soroka とカササギと同じ綴りになることがあるが、こちらはサラカーと読むので音で聞く時には混乱の恐れはない。複数形 soroki も同じ綴りになるが同様に区別できる)
で文字で書く時にはしばしば混乱の元になり、「カササギ」を含むロシア語文を機械翻訳するとややこしいことになることもある。「カササギ」が「40 代の人」と訳されていても気づかないかも知れない。
ロシア沿海地方のカササギの繁殖: Gluschenko et al. (2023) Breeding birds of Primorsky Krai: the Eurasian magpie Pica pica (pp. 3521-3541)。
[カササギの分子系統解析・大陸と日本の関係]
カササギの分布と遺伝子型の関係の研究: Kryukov (2025) Genetic variation and phylogeography of the magpie's genus Pica in the Holarctic (中身は英語)。
分離される前のカササギの分布の東端に位置する東洋のカササギは西から分布を広げたものではなくむしろ祖先系統と言える。
カムチャツカは別系統 (これら以降現在の通常の扱いで別種。カムチャツカは地理的には分離する場合は種カササギの方に含まれるように見えるが北回りで分布を広げたよう) でユーラシアを西に進んで基亜種は最後の系統に属する。Pica 属は東南アジア由来と考えられるとのこと。2種に分ける場合の分岐年代は 110 万年前ぐらい。
亜種 serica と jankowskii は分離されておらずむしろ混ざった形で2系統に分離され、従来の亜種分布概念と分子系統が整合していない。
Pica 属内のカササギは grazing animals (和訳に困る。グレイジングとそのまま書いてあったりする) の進展に伴って分布を広げたと考えられるとのこと。
Fig. 5 に日本周辺のカササギの遺伝子タイプが図示されているが大陸とは遺伝子タイプの頻度が異なるとのこと。九州の個体群は特に均一性が高く少数の個体から始まった創始者効果が考えられる。
北海道の個体群は大陸との類縁性が高く 1980-1990 年代に船舶経由で定着した可能性が考えられるとのこと。この論文では 400 年前に朝鮮半島から導入された古い記録を由来としているが、古い記録の信憑性の検証やより広範囲なゲノム解析によって、本当に創始者効果由来かまだ検討の余地がある気がする。
大陸個体群と隔離されていることは確かだろうが隔離年代はそれほど新しいものか、など。
それほど少数個体から始まっていれば近親交配の影響や遺伝的多様性の低さがゲノムに現れているのでは。
-
ホシガラス
- 学名:Nucifraga caryocatactes (ヌキフラガ カリュオカタクテース) 木の実を砕きクルミを食べる鳥
- 属名:nucifraga (合) 木の実を砕く [独 Nussbrecher からの Turner (1544) 訳] (The Key to Scientific Names)
- 種小名:caryocatactes (合) クルミを食べるもの (caryon (n) クルミ、katakto 捕える -tes 〜するもの Gk)
- 英名:Nutcracker [nut はヘイゼルナッツ hazelnut のこと (コンサイス鳥名事典)], IOC: [Spotted Nutcracker 分離前の名称], 14.2 で Northern Nutcracker
- 備考:
nucifraga の読みはわからないが、nux, nucis および frangere のいずれにも長母音が現れないので合成語も短母音のみと考えられる。この場合は規則により "ヌキフラガ" のアクセントになると考えられる。
caryocatactes は由来となるギリシャ語で末尾が -tes が行為者の長母音。-tac- が音節を形成すると考えれば "カリュオカタクテース" のアクセントになると推定される。
ユーラシアに広く分布し、世界で8亜種が認められている (IOC 14.1 まで)。IOC 14.2 で分離されて4亜種。
日本で一般的な亜種は japonica 亜種ホシガラス。
記載時学名 Nucifraga caryocatactes japonicus Hartert, 1897 (原記載)。ヨーロッパ型とは別にすべきと Japanese form に与えたもの。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によればそれ以前に Nucifraga caryocatactes leptorhynchus Blasius, 1886 (参考) の名称があり、Seebohm (1888) はシベリアと日本のものをこの学名で表していた。
Hartert (1897) によれば、Seebohm も Stejneger もヨーロッパまたはシベリアのものと日本のものを一緒に扱っている点で間違っているとしている。leptorhynchus の名称はここには現れず (現在も使われていない) 複数の概念を含むため無効となったものだろうか。
Nucifraga caryocatactes pachyrhynchus Blasius, 1886 (参考) とセットで名付けられた学名のようで、単に旧北区を東西に分けて嘴が細い・広いと名付けた学名のため概念的に無効となったものだろうか。
IOC では旧ホシガラスから Nucifraga multipunctata Kashmir Nutcracker を分離している。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) にもこの言及があるが同種のままのため9亜種となっている。
南アジアの亜種 hemispila Southern Nutcracker を独立種とすることもある。
分類概念が少し異なるが、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) でのホシガラスの英名は Eurasian Nutcracker となっている。
Nucifraga 属はカラス類の中でコクマルガラス類 (IOC では Coloeus 属) の分岐する前に分岐した系統。
macrorhynchos (「大きなくちばしの」の意味) ハシナガホシガラス [北から北東アジアに分布し、イラン、朝鮮半島、中国に侵入的渡り (irruption) をすることがあるそうである。サハリンにも分布する。南千島の亜種は日本と同じとされる]
は過去に福岡県で1例の記録があるがその後長期間認められていないとのこと。朝鮮半島への irruption の際に飛来の可能性が考えられるが、海を渡るのは難しいかも知れない。
Clements 2024, IOC 14.2 ともに Southern Nutcracker Nucifraga hemispila を分離 (4亜種)。日本産のものの学名は変わらない。分離後の日本産の英名は Northern Nutcracker となる。
ロシア名 kedrovka。kedr がヒマラヤスギ属 Cedrus を指してわかりやすい名前。タイガ林に多くロシアではごく馴染みの種類らしい。カラス類の中で種子植に特に適応したもの。
両親ともに抱卵する。これはオス・メスそれぞれが相棒がどこに蓄食しているかを知らないためと説明されている。両親ともそのうで柔らかくした種子で給餌を行う。蓄食の蓄えがなくなると小型の鳥類や哺乳類も含む小動物を与える (wikipedia ロシア語版より)。
OED によれば Nut-cracker の名称はそれほど古くからあったわけではなく、1693 年 Staphorst の翻訳物に現れるのが最初とのこと。ここではドイツ語の Nusshoeher が併記されており、別名 Sucuruck, Alsecrach が挙げられていた。英語の鳥を指す Nut-cracker はドイツ語名を訳されたものだったのかも。他の鳥を指す用例もあったが廃れたらしい。
英名の Nutcracker とチャイコフスキーの3大バレエの一つ「くるみ割り人形」The Nutcracker の英名が同じためにまったく同じように解釈されることがある。ロシア語ではバレエの名称は Shchelkunchik で shchelkat' ぽんと音を立てて割る (さらに1回動詞 shchelknut' の形となって Shchelkunchik はここから派生)。調べた範囲では鳥を指す用例は見当たらなかった。ロシア語では元来は音が由来。
フランス語原題では Casse-Noisette で casse が割る、noisette がハシバミの実。
チャイコフスキーの3大バレエの中では「白鳥の湖」に次いで有名な個々の曲があるが、チャイコフスキー自身は「眠れる森の美女」の方が自信作で、成功を買われて作曲し、珍しい楽器の用例はあるが音楽的にはそれほど統一感がない。
ホシガラスの生態について河辺 (1999) Birder 13(7): 34-39 の記事がある。両親ともに抱卵するなどの生態も記されている。
-
ニシコクマルガラス
- 第8版学名:Corvus monedula (コルウス モネードゥラ) コクマルガラス
- IOC 学名:Coloeus monedula (コロエウス モネードゥラ) コクマルガラス
- 第8版属名:corvus (m) カラス
- IOC 属名:coloeus (m) コクマルガラス (Gk)
- 種小名:monedula (f) (ニシ)コクマルガラス < moneta コイン edulis 食べ物 < edere 食べる。トラキア (Thracia, Thrace) の Arne が金のために祖国を裏切りニシコクマルガラスに変えられた神話に基づく
- 英名:Western Jackdaw
- 備考:
corvus は#ワタリガラス参照。
coloeus はギリシャ語 koloios (ニシ)コクマルガラス 由来でギリシャ語ではすべて短母音で最後にアクセントがある。ラテン語読みでは -lo- がアクセント位置と考えられる ("コロエウス")。
ギリシャ語語源はよくわかっておらず、古典ギリシャ以前の起源が考えられる (wiktionary)。
monedula は e が長母音でアクセントもここにある (モネードゥラ)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。IOC では早い時期から2種のコクマルガラス類を Coloeus 属 (コクマルガラス Gk) に分割している。IOC 分類では Coloeus monedula の学名になる。
他のリストでは Corvus にまとめており、IOC も戻すかも知れない。IOC 14.2 では現行のまま。
Swinhoe (1871) の時代は Lycos 属で、Boie (1828) が用いた属名。由来となる lukos (Gk) は (ニシ)コクマルガラス。無効名とのこと (The Key to Scientific Names)。
ちょっと調べてみると 1804 年命名のクモ目の Lycosa 属 (コモリグモ科) があるためか。wiktionary によれば lukos (Gk) はオオカミまたはクモの一種とのこと。(ニシ)コクマルガラスを指す語義もあるとのことで多義語だった模様。このクモの属の英名は Wolf spider なので整合性はある。オオカミ / クモ と コクマルガラス の共通性は (?)。
なお IOC が使ってきた Coloeus 属 (Kaup 1829) の方が後になるが Lycos 属が有効でなかったために用いられるよう。
系統的 Corvus 属にまとめることも可能なので属を分けるほどの必然性があるわけではなく、2種のみなので世界のリストも積極的に取り入れていない様子。
その後 AOU Proposals 2024-B p. 42 (2024-B-7) にて議論が行われていることを知った。
全体を Corvus 属とするか、Coloeus を亜属とするか、Coloeus 属を認めるかのいずれか。NACC では Coloeus 属を認める提案がなされている。分子系統樹以外にも Corvus 属との音声の違いも判断要素の一つ。
Clements 2024/eBird で Coloeus 属を採用。
世界に4亜種が認められている (IOC)。日本の記録は亜種不明とされる。
分布が一番近いのは soemmerringii (#ヤマドリの備考参照) だがどうなるだろうか。
jackdaw の語源は jack (Jack 16 世紀ぐらいの英国で普通の人を指す名前で召使いなどをこの名で呼んだ。オスの動物を指す名前となった) + daw おそらく古英語 dawe からでおそらく鳴き声から (Online Etymology Dictionary)。
ドイツ語では Dohle (daw と音は似ている) でこちらもおそらく擬音語とされる。
デンマーク語で allike で、fuld som en allike (コクマルガラスのように酔っ払った) という成句があり、ほぼ同じ形でスウェーデン語でも使われる。この説明によれば allike (alike) の語源はカラスを意味する kaja にさまざまな寓話に鳥として出てくる Adelheid 女性名を指小辞とした ale- を付けて中世ドイツで al(l)eke と呼ばれていたことに由来するとのこと。
コクマルガラスはアルコールが好きで酒粕を捨てると集まってくる、またブランデーに浸したパンを与えて楽しんでいたとの逸話に基づくとのこと (wiktionary)。
Hahn et al. (2025) Pair-bond strength is consistent and related to partner responsiveness in a wild corvid
ニシコクマルガラスのつがい間のきずなの強さが何と相関するか。しかしきずなの強い方が適応度が高い積極的な結果は得られなかった。きずなの強さをどのように定量化するかなど。いろいろな指標が使われているが、相互羽繕いの圧倒的多くはオスが始めるとのこと。
Social Intelligence (or Social Brain) Hypothesis 社会性が脳の発達を促す仮説は魅力があるが議論も多いとのこと。脳や認知機能の発達は霊長類とは違って鳥類では長期のつがいの維持に相関がある。つがいを維持する行動に必要な能力の要求から脳が進化した考え方もある (引用文献参照)。
[ニシコクマルガラスの虹彩はなぜ白い]
#ヤマセミ備考の [派手な色彩の鳥はまずい?] から派生した項目の 虹彩色に関係する遺伝子 より再掲:
Maclary et al. (2021) によればズキンガラスでも SLC2A11B 遺伝子が見つからず、虹彩に黄色色素を持たないために黒い目になっている可能性があるとのこと。カケスやニシコクマルガラスの白い目もきっと同じメカニズムだろうと納得してしまう。カラス系統の目が黒かったり白かったりするのは遺伝的共通基盤がありそう。
この2種の遺伝子はこの論文では調べられていないが、カラス類の比較的早い段階で失われたのでは。
そういえば青い目をしたカラスの話題がしばしばあった。週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 82 p. 16 に非常に青い目のハシボソガラスの巣内ひなの写真が出ていて、(おそらくフランス) 西洋ではカラスまで目が青いのかと (もちろん冗談で) 思ってしまった。
日本のネットの写真を見てもそこまで極端なものを見つけられなかったが、ほぼ白っぽい虹彩の写真もあった。つまりカラス類、特にズキンガラスに近い種類では SLC2A11B 遺伝子を持たないため虹彩に黄色色素が現れず、褐色・黒色色素が少ない場合は通常の鳥では褐色になりそうな目が青くなると思われる。
生物学的に意外に深い理由があった。カラス博士でも真っ青かも。
そのように意識してみると、初野 (2007) Birder 21(8): 30 (写真は中野) に青い虹彩のハシブトガラス幼鳥の写真があった。成鳥・幼鳥の比較記事であったが、当時はあまり意識されていなかったのか虹彩の色に関する言及はなかった。
童謡「七つの子」では七つの方ばかりが話題となるが、「まーるいめをした」をついつい「あーおいめをした」と間違えてしまっても実は間違いでなかったのだ (この間違いは別の童謡と混線するために発生したわけだが...。wikipedia 日本語版によれば 1995 年に著作権が消滅しているので歌詞を書いても文句は出ないだろう)。この際替え歌で覚えてしまうのもよいかも知れない。
理屈っぽく解釈するならこちらを検討してみてはいかがだろうか。
童謡「七つの子」は自分も大好きな音楽で、鳥の童謡では「かなりや」とともに傑作だと思う。
日本の童謡は西洋音楽に馴染んでいると伴奏パートを覚えにくいものが多いが、「七つの子」は別格。七つの子 (UTABON.JP) の例のように「かわい かわいと なくんだよ」のコード進行を追ってみていただきたい。「なくんだよ」の最後は Am/D で解決してしまわずに D7 のままでもよいかも知れない。
-
コクマルガラス
- 第8版学名:Corvus dauuricus (コルウス ダウウーリクス) ダウリア地方のカラス
- IOC 学名:Coloeus dauuricus (コロエウス ダウウーリクス) ダウリア地方のコクマルガラス
- 第8版属名:corvus (m) カラス
- IOC 属名:coloeus (m) コクマルガラス (Gk)
- 種小名:dauuricus (adj) バイカル湖東のダウリア地方の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:(Jackdaw ニシコクマルガラスが分離される前の名前)、IOC: Daurian Jackdaw
- 備考:
corvus は#ワタリガラス参照。
coloeus は#ニシコクマルガラス参照。
dauuricus は2つめの u が長母音でアクセントもここにある (ダウウーリクス)。ラテン語本来は固有名詞のため大文字で記述する (Dauuricus)。
IOC では早い時期から2種のコクマルガラス類を Coloeus 属 (コクマルガラス Gk) に分割している。IOC 分類では Coloeus dauuricus の学名になる。
単形種。
ダウリア (ロシア語 Dauriya) 地方はロシア語のザバイカル (Zabajkal'e) に相当し、首都からみて「バイカルの向こう側」の意味。ダウール族の居住地が語源。トランスバイカル (Transbaikal) とも言う。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では現在と同様の学名 (Corvus dauricus と u が1文字少ない) でコクマルガラスの名称がすでにあった。
Pallas (1776) では dauuricus で現在はこちらが採用されている。dauricus を用いたのは Gmelin (1788) でこちらの方がよく使われていた:
Temminck and Schegel の "Fauna Japonica" 本文 フランス語名 le choucas oriental。
図版 1, 2 (daauricus となっている)。
長音が入ることはわかっていてもどの文字を伸ばすかよくわかっていなかったよう。
他に Corvus capitalis Wagler, 1827 ("頭に特徴のあるカラス" の意味) が載せられていた。参考 によれば Pallas の Corvus dauuricus がシノニムとされており、おそらく Pallas を元にした学名かとある。
Ogawa (1908) にはさらに Corvus neglectus Schlegel, 1859 を和名空欄で載せている。場所は長崎、大阪としている。neglectus は無視された、見過ごされたなどの意味。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では別種扱いで Pallas's Jackdaw (Corvus dauricus) と Swinhoe's Jackdaw (Corvus neglectus) となっており、これを引き継いだものだろうか。学名綴りが少しずつ違っているので注意。
Salvadori (1909) Note on the Corvus neglectus of Schlegel
が正体を検討し、最初に Pallas がコクマルガラスの変種 (β?) として気づいたらしい。"Fauna Japonica" に記述した Schlegel ["Fauna Japonica" の時点の図版 1, 2 を参照] は最初は成鳥と若鳥だと考えていたが、いずれも成鳥で別種であると認識して Corvus neglectus (1859) の名称を使ったとのこと。
Hartert "Die Voegel der palaearktischen Fauna" は Corvus neglectus は種に値しないことは極めて確からしいと記していて著者の Salvadori はやや驚いている。
Swinhoe (1871) は若鳥説は受け入れられない、なぜならば自分が巣から採集して成鳥と同じ色彩だったと反論を残した (参考)。
淡色型、暗色型が成鳥・幼鳥の関係にあるのか現在でも議論がなされているぐらいだが、この当時から混乱があったことがうかがえる。もし別種であれば中間型は雑種とも考えられるなどの議論が載せられている。
Salvadori (1909) で別種説があるぐらいなので Ogawa (1908) 段階では同種か別種かわかっていなかったよう。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではニシコクマルガラス (こちらの記載の方がもちろん早い) の亜種扱いで Corvus monedula davuricus の学名、Corvus neglectus と Corvus fuscicollis Vieillot, 1823 (褐色の/ぼんやりした色の首のカラス) をシノニムとしている。
ロシア語名はダウリアを用いた名称も挙げられているが、pegaya galka (白黒まだらのコクマルガラス) の名称も出ている。ニシコクマルガラスとは違って白っぽい変種と黒っぽい変種がある。個体によっては中間型がある。Vorob'ev による沿海地方南部で白っぽいものが多いがイマン川下流や Spangenberg 周辺では黒っぽい個体が多いとの記述が紹介されている。
近年の日本での年齢識別は Leader (2003) Identification of Daurian Jackdaw の記述が用いられている印象を受けるがヨーロッパの迷鳥としての識別情報なので必ずしも正しくないかも知れない。
渡辺・三河 (2007) Birder 21(8): 59-65 の記事では Svensson の記述が紹介されていて「バイブル」とされるこの文献かの情報が広く使われていたのかも知れない。
Young Guns (2014) Birder 28(11): 48-50 の記事では要点を要約すると体色の違いは実は齢差、若いシロマルがいる? となる。1911 年中国北部の繁殖地採集された巣内雛の一部がシロマルだった論文があるとのことだが引用文献が示されていないので具体的には不明。"巣内雛の一部がシロマル" は後述の Gluschenko et al. (2024) の記述とは合わない感じがする。
各種文献を見ると白黒まだらのは生まれてすぐからやはり白黒まだらだが成鳥より色は弱いとのこと。Swinhoe (1871) の記述と合っている感じがする。Vorob'ev の記述は地域によってこれら型の割合が異なることを示唆しているように感じられる。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) をチェックしておくと白黒まだら型 (morph と呼んでいる) は生涯色が変わらず容易にニシコクマルガラスと区別できる。
暗色型は生まれた時は白黒まだら ("巣の" 羽衣) だが次第に成鳥に似た暗色に変わってゆく。首のまわりの "ネクタイ" のみが例外で明るい灰色からほとんど真っ黒に変化することもある。この羽衣ではニシコクマルガラスに非常に似ていて虹彩の色と後頭部から後頸部の明るい色の部分の大きさのみが異なる。
1歳の次の換羽で白黒まだらになる。言い換えれば黒色の個体はその年生まれの暗色型の個体で2暦年で白黒まだら型になる ("型" で表記するならば生涯で "型" が変わる) と表現することもできる、とのこと。
これまで読んだ範囲ではこの記述が最も具体的で詳しい感じがする。
その後さらに Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Daurian jackdaw Corvus dauuricus (pp. 3907-3934)
が出ていることに気づいた。この論文によれば過去意見が対立していた。この議論に終止符を打った (ロシア語でもこのままの表現) のが Nechaev (1975) だとこの著者は述べている。
Nechaev (1975) によれば羽衣は3つで (1) "巣の" 羽衣 (gnezdovoj naryad または最初の若い羽衣 pervyj yunosheskij naryad)、(2) 当年生まれの羽衣 (pervyj godovoj naryad または二番目の若い羽衣 vtoroj yunosheskij naryad)、(3) 成鳥羽衣 とのこと。この概念では morph は存在しないので生まれた時から暗色型はないことになる。
"gnezdovoj" は "巣" の形容詞だが、巣外の写真も出されているので上記のように形容した。yunosheskij は英語では youth に相当するがこれも訳出すると日本の鳥類学で一般的な用語と合わない可能性があるので原語も示しておいた。
具体的にどんな色かは説明するより写真を見ていただく方が早いだろう。巣での写真も掲載されている。
なおこの論文は沿海地方の話で、20 世紀後半の初頭は沿海地方では渡り鳥とされていて冬は少数が残るのみだった。21 世紀初頭以降は沿海地方の南西部では留鳥化の傾向が顕著とのこと。
2001/2002 年の冬には初めて大群が越冬した。
同じ巣にオシドリとコクマルガラスの両者の卵がある例が知られており写真も出ている。この著者の観察では巣穴を最初オシドリが使っていたものをコクマルガラスが追い出して自分たちが使ったのではないかとのこと。
色彩について Nechaev (1975) がかなり昔に決着を付けたはずなのになぜ今でも決定的見解が定着していないのか不思議ではあるが、Ryabitsev (2014) はシベリアの鳥を記述していて、例えばシベリアでは色彩に関してニシコクマルガラス系統の遺伝子型も存在するなど、あるいは地域によって色彩に違いがあるのかも知れない。
ハシボソガラスとズキンガラスの分子遺伝学研究をみてもそのような可能性が十分ありそうな気がする。単にまだ調べられていないだけかも。
Weissensteiner et al. (2020) (#ハシボソガラス備考参照) でもレトロトランスポゾンの比較に3個体が用いられている (主に調べられているのはヨーロッパの種類) が、いずれも Russia, Muraviovka Park のものでコクマルガラス全体を代表しているかどうかは何とも言えない感じ。
ニシコクマルガラスもスウェーデンのもので、シベリアのニシコクマルガラスの個体はコクマルガラスとどの程度違うのかなどは何とも言えない。
Gluschenko et al. (2024) に越冬時期の群れの写真も出ているがほとんど白黒まだらの群れから黒っぽい個体が中心となる群れまであるようで、1年めの若鳥と成鳥は行動パターンが違うのかも知れない。
しかし全体的に白黒まだらの個体比率は日本より高いように見え、成鳥はあまり遠くまで渡らないのかも知れない。
簡単に調べられた範囲では Nechaev (1975) の論文のオンライン版は見当たらないよう。この本の一部日本語訳が出ている情報がみつかるが、本の全訳は「極東の鳥類」一覧を見る限りではなさそう。
これらをふまえると、Ogawa (1908) にある2種のうちコクマルガラスの付けられている方は白黒まだらのタイプを指したもので、コクマル = "黒丸" と解釈されることは正しいように思える。ニシコクマルガラスに対比した特徴を表したものと考えられる。
黒っぽいものはその時点では別種扱いでリストされているが和名は付いていなかったよう。
この和名解釈に基づけばニシコクマルガラスに "コクマル" を含めるのは本来の命名意図に矛盾するかも知れない。
そう考えているうちに思い出したのが現在のニシコクマルガラスに相当する鳥が過去に日本の書物でも紹介されていたはずで、例えば Konrad Lorenz の「ソロモンの指環 動物行動学入門」[日高敏隆訳 早川書房 1963 が初出] などを思いつく。
この訳本の中ではコクマルガラスの訳名が使われており、あとがきによれば鳥の名前は黒田長礼、黒田長久、浦本昌紀氏にうかがったとある。当時ニシコクマルガラスが別種扱いであったかどうかは知らないが、日本の対応種のコクマルガラスの名前を便宜的に用いていたかも知れない。あるいは同種であれば日本と同じ和名で構わないことになる。
(ニシ)コクマルガラスの過去の他の学名についての追記情報が#ハシボソガラス備考の [クビワガラスの学名] にある。
コクマルガラスの鳴き声はキョンキョンという犬の声に似た高い声がよく注目されるが、他のカラスのような濁った声で鳴くこともある。
-
ミヤマガラス
- 学名:Corvus frugilegus (コルウス フルーギレグス) 穀物を集めるカラス
- 属名:corvus (m) カラス
- 種小名:frugilegus (合) 穀物を集める (frux -ugis (f) 穀物 lego (tr) 集める)
- 英名:Rook
- 備考:
corvus は#ワタリガラス参照。
frugilegus の発音はわからないが、frux, frugis ともに長母音を含む (英語 fruit 同様)。
-legus の語尾は短母音とあるのでこれを採用する (#ミヤコドリ参照)。
この解釈によれば "フルーギレグス" の発音となる。
世界ではユーラシア東西に2亜種 (IOC)。日本で記録される亜種は pastinator (「塹壕を掘る者」の意味 < pastinare 掘る) とされる。
それぞれの記載時学名は、
・Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europa; restricted to Sweden by Hartert (1903, Vog. pal. Fauna, 1, p. 13) (Avibase による)
・Corvus pastinator Gould, 1845 (原記載) 基産地 Chusan, China
#ハシボソガラスの備考の Jonsson et al. (2012) や Haring et al. (2012) の分子系統研究によればこの2亜種は種相当の違いがあり、将来別種とされる可能性がある。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では形態差が小さいためまだ慎重に扱っているようである。
別種となる場合は日本の種の学名が変わり、Corvus pastinator ミヤマガラス、Corvus frugilegus 例えばニシミヤマガラス のような名前が考えられる。
将来別種を想定して亜種 frugilegus との識別の研究も必要かも知れない。もっともミヤマガラスの大群の中に1羽わずかに違うのがいても見つけられないかも知れないが...。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" では独立種の提案はないが、東西の亜種を Eastern Rook, Western Rook と呼び東の亜種には顔 (嘴の基部) の白い部分がない、嘴がより尖っている識別点も示されている。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では学名 Corvus pastinator 英名 Eastern Rook で、Temminck and Schegel が "Fauna Japonica" で Corvus frugilegus とした (参考。図版なし) のは間違いとの記述となっている。
"Fauna Japonica" には Corvus pastinator への言及はなく、Gould (1845) の記載が直近であったため記述時点では検討されていなかったのかも知れない。
カラス類の集団を表す英語 rookery はこの種が由来。
英語 rookie (新人、ルーキー) は語源がよくわかっていないものの、この種の名前の影響を受けたかも知れないとのこと(Online Etymology Dictionary)。
OED によれば古英語では hrooc, hrocas の綴りで、1175 年ごろに Roc の用例が見られラテン語の教科書に Graculus に対応する英語として現れるとのこと。rookery は 1662 年に用例がある。
rookie は直接の語源は recruit + -y ではないかとしているが、rook の影響や rookery の短縮も考えられ、rook + -y の可能性もあるとしている。
「全集日本野鳥記」(講談社 1985) 1 に収録されている「キタタキ 生きていた幻の鳥」(鴨川誠 1975 初出) に 1972.8 調査時の韓国のミヤマガラスの貴重な情報がある。p. 244 で朴学長によればミヤマガラスは 2-3 年前まではこのあたりにたくさん棲んでいたが、あるとき野ネズミが大繁殖してモノフルオロ酢酸塩をまいたらほとんどのカラスが死んでしまったとのこと。
高木 (2010) 日本におけるミヤマガラスの越冬分布の拡大 にあるような 1970 年代以降の越冬数増加のある部分は朝鮮半島の環境改善によるものかも知れない。またカラス類では有機塩素系化合物より殺鼠剤の方が効いていたのかも知れない。
Volkovskaya-Kudryukova (2012 初出, 2023 再掲)
Modern population dynamics of the rook Corvus frugilegus pastinator in the Ussuri region against the backdrop of a decline in agricultural production (pp. 1463-1466)
によれば農業生産の減少伴ってウスリー地区のミヤマガラスが減少しているとのこと (ただし 2012 年段階のデータ)。
ミヤマガラスのコロニーの近くで繁殖しているチゴハヤブサ、アカアシチョウゲンボウ、チョウゲンボウへの影響も気になるところだが、これらはより数の多いカササギを利用しているとのこと。
[烏の漢字について]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 82 VII (藤堂) によれば鳥も烏も象形文字で、烏は発音が a → o → u と変化したとのこと。音声由来だった。
鴉の漢字は nga → ia(ya) と変化し、こちらも音声由来だった。
Birder 編集部 (2023) Birder 37(12): 27 によれば鴉の牙はかみ合う説を紹介していた。
wiktionary を確認しておくと牙の文字は古代中国語で *nga の発音で形声文字の解釈を採用している。中世中国語の音も初期の母音が保存されているとのこと。
[ハワイガラス]
Jonsson et al. (2012) によれば ハワイガラス Corvus hawaiiensis 英名 Hawaiian Crow は北米由来でなく、ミヤマガラスの系統とのこと。
過去にはワタリガラスが定着したものとの考え方もあった: 参考 Pyle and Pyle (2017) HAWAIIAN CROW (The Birds of the Hawaiian Islands: Occurrence, History,
Distribution, and Status. B.P. Bishop Museum, Honolulu, HI, U.S.A. Version 2)。
この記事によれば、Corvus tropicus Gmelin, 1789 (参考) が初記載と考えられて近年まで使われていた学名だったが標本も残っておらず、ずっと小型の種類でまったく違うオウチュウ類を指していたのではとの解釈もあり現在は使われていない。
Corvus 属の範囲はかつては非常に広く、Linnaeus (1758) がカワリサンコウチョウを Corvus 属で記載したことも思い出そう。
Weissensteiner et al. (2020) Discovery and population genomics of structural variation in a songbird genus でゲノムデータを用いた新しい系統樹が見られる。
Coloeus 属 (コクマルガラスとニシコクマルガラス) を分離する場合はミヤマガラスとともに Corvus 属で最も古い分岐となる。
どのようにして海を越えたのだろう?
ハワイガラスは野生個体の目撃は 2002 年が最後で IUCN 3.1 では EW (野生絶滅)。
ハワイ入植に伴った土地改変や放牧などで生息地を失い、1980 年代は違法にもかかわらずまだ撃たれていた。
人が持ち運んだ齧歯類やネコがひなや卵を食べる。また 20 世紀初頭に持ち込まれ、数々の固有種を絶滅させた鳥マラリア (Avian malaria) が 1826 年に持ち込まれた外来種の蚊や温暖化の影響で標高の高いところにも拡大して個体数が激減した (鳥マラリアはスズメ目への感受性が高く、ハワイでは外来種の方が抵抗性があるとのこと)。
飼育下増殖の試みは 1970 年に感染症 (鳥ポックス Avian Pox Avipoxvirus 天然痘に近いウイルス) で保護されたひなから始まったが 1979-1991 年は人工飼育で人為的に育てても非常に成功率が低かった。その後技術が確立され 1999 年に 24 羽から 2012 年に 100 羽を超える状況になった。2011 年に親自身にひなを育てさせる実験が始まったが 2023 年段階で 17% しか成功していないとのこと。世界で最も絶滅に近いカラス科の種とのこと。
サンディエゴ動物園で飼育されて再導入も行われているがハワイノスリ Buteo solitarius Hawaiian Hawk に捕食されるなどうまく行っていない。感染症や寄生虫など脅威も続いている。
2019 年に1つがいが営巣したが無精卵だったと考えられる。野外で生き延びることができない事例が続発して 2020 年に生存個体の再捕獲が行われた。
2024 年ハワイノスリのいないマウイ島への再導入が検討され、12 月に2羽のメスと3羽のオスが放された (wikipedia 英語版から。以下記事参照)。Weissensteiner et al. (2020) の論文でも遺伝的多様性の低さが際立っている。
ハワイガラスとミヤマガラスの推定分岐年代は 520 (510-740) 万年前 (timetree.org による)。かなり古く定着したらしいことは Weissensteiner et al. (2020) の系統樹とも整合する。
主たる捕食者であるハワイノスリはアメリカ大陸の Buteo 属のノスリ類 (有名な種では アレチノスリ [高野 (1973) ではスウェイソンノスリ] や ガラパゴスノスリ) が含まれ、ハワイノスリの分岐年代は 200-300 万年前と推定できる。ノスリ類の中でも最も新しく分岐したグループである。
つまりハワイガラスが定着したころは安住の地だったが、その後ハワイノスリが定着したことによって生存が脅かされることになった。人為的影響の少ない時期にはまだ共存可能だったが、激変した現在の環境や感染症・寄生虫の影響が多大な条件では共存がなかなか難しくなっているのではないだろうか。ノスリ類はある意味万能型なので恐るべし。
ハワイへのハワイノスリの定着時期がニュージーランドへの猛禽類などの鳥の定着時期のピーク (#ミサゴ備考 [オウム類・ハヤブサ類の年代推定] 参照) に近いのも偶然ではないだろう。このころは乾燥化が進んで開けた地域を好むチュウヒ類やノスリ類が進展して種分化を遂げたころ。
Buteo 属のノスリ類がユーラシアから北米にも進出できるようになった時期に渡り能力を活かしてハワイにも定着することができたのだろう。
ここでもまた後に進展を遂げた猛禽類がより早い時期に分岐したカラス類の運命を左右したらしい事例を見ることができる (#ルリカケスが固有種として生き残った経緯に思いを馳せてみた)。常識的にはタカ類の方が先にいてカラス類が後から進化したように思えるがここでは逆である。
カラス類はもともとそれほど生態的に強い種類ではなく、早い時期に分岐したカラス類の多くが失われてしまって Coloeus 属 (コクマルガラスとニシコクマルガラス) とミヤマガラスしか残っていないのかも知れない。
現在のハワイガラスは飼育下で長年維持されてきた個体群なので捕食者への対応などの文化も失われているかも知れない。
The Hawaiian Crow Is Once Again Extinct in the Wild (Kim Steutermann Rogers 2020, Audubon の記事)。
'Alala, the Hawaiian crow that went extinct in the wild decades ago, released on Maui
(Hawai'i Public Radio/AP 2024.12.6)。
ハワイガラスの道具使用: Rutz et al. (2016) Discovery of species-wide tool use in the Hawaiian crow。
鳥マラリアのハワイミツスイへの影響に関連して Kyriazis et al. (2025) Population genomics of recovery and extinction in Hawaiian honeycreepers の話題がある。
アケキ Loxops caeruleirostris Akekee の 20 世紀末の急速な個体数減少は鳥マラリアの拡大が主要因だった。現在野生では 100 個体を割っており、個体数モデルでは近々絶滅の可能性がある。遺伝的多様性は残っているため、もし蚊がうまく制御できれば個体数回復の望みがある。
-
ハシボソガラス
- 学名:Corvus corone (コルウス コローネ) カラス
- 属名:corvus (m) カラス
- 種小名:corone (合) カラス (korone カラス < krozo かあかあ鳴く Gk)
- 英名:Carrion Crow
- 備考:
corvus は#ワタリガラス参照。
corone はギリシャ語由来で、ギリシャ語では後半の2つの母音が長音。少なくとも -ro- の o は長母音としてここにアクセントを置くとよいと考えられる (コローネ)。ギリシャ語に忠実であれば語末も伸ばす可能性もある (コローネー)。
ラテン語に冠などを意味する corona の単語があり、これは -ro- の o が長母音 (コローナ)。変化形には corone は現れないが語末を伸ばす変化形もあり、corone の語末も伸ばして発音するのがあるいは自然かも知れない。
なおこの corona も語源は同じギリシャ語 korone 由来で、wiktionary によればミズナギドリかカラスとある。インド・ヨーロッパ祖語で *(s)ker- (曲げる) から曲がっているものを広範に指し、鳥の嘴や冠など複数の概念に派生したとのこと。
上記の korone カラス < krozo かあかあ鳴く の語源関係はあるいは逆かも知れず、corone は鳴き声由来ではないかも知れない。
英名の Carrion Crow の由来を OED で調べると、1528 年にすでに用例が知られていて、英国にはハシブトガラスがいないためワタリガラスとともに "肉を食べる" 種類として知られていたことが由来のよう。1774 年の記述ではワタリガラスと似ているがワタリガラスより人に好まれていない点が異なるとのこと。
1803 年には Carrion Vulture を Carrion Crow の同義語として用いた記述がある。
英国事情での比較対象となるのはミヤマガラス (rook) で、こちらの用例はさらに古くからある。ミヤマガラスが穀物食中心 (学名語義に示される通り) で、限られた比較対象の間ではハシボソガラスが肉を食べる特徴が目立っていたのだろう。英語の意味はハシボソガラスとハシブトガラスの違いを意識したものではない。
ハシボソガラスがなぜ Carrion Crow なのか質問されることもあるかも知れないが多少の参考になるのではないだろうか。また Seebohm (1890) は日本のハシボソガラスとヨーロッパのものに別の英名 (後者に Common Crow) を用いていた (ハシブトガラスの備考参照)。ハシブトガラスを知った上では日本のハシボソガラスの方がヨーロッパより "Carrion-Crow" にふさわしいとの判断による。
carrion は "死体"、"死肉" の意味だが、フランス語を経て遡るとラテン語 caro (肉) とのこと。-ia は名詞を作る語尾とのこと。
ハシボソガラスの日本の亜種 orientalis を独立種 Corvus orientalis (Oriental Crow) とする議論があったが、現在では亜種として Corvus corone orientalis と扱われている (基亜種 corone はヨーロッパに分布)。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" でも orientalis を独立種とする考えが紹介されている。
[ハシボソガラスとズキンガラスは別種?]
一般にズキンガラスと呼ばれる Corvus cornix は長くハシボソガラスの亜種とされた。2010 年の沖縄県与那国島での記録が報告されている [佐野他(2018) 沖縄県与那国島におけるズキンガラスの観察記録] が日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版には掲載されていない。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でハシボソガラスの亜種 ズキンガラス Corvus corone sharpii (英国鳥類学者 Richard Bowdler Sharpe に由来) として記載されている。この扱いはズキンガラスをハシボソガラスの亜種とする Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) によったものと思われる。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) の脚注によれば Parkin et al. (2003) The taxonomic status of Carrion and Hooded Crows
がこれらを2種に分ける (大陸東西の基亜種 corone と orientalis は同種に扱う) 提案を行い、IOC 分類はこれに従っている。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では3種とする扱いは検討に値するとしているがどの亜種がそれぞれのグループに属するかの判定は示されていない。
少なくともヨーロッパのハシボソガラスとズキンガラスにおいて、Parkin et al. (2003) ではつがい形成時の生殖隔離 (同じ色彩の個体を好む assortive mating) が見られることを別種の根拠としている (wikipedia 英語版にも説明あり)。
近年のいくつかの研究では全般的には相互の遺伝子発現にはほとんど差がない [Poelstra et al. (2014) The genomic landscape underlying phenotypic integrity in the face of gene flow in crows]。
Vijay et al. (2016) Evolution of heterogeneous genome differentiation across multiple contact zones in a crow species complex
では氷河期に東西のグループに分かれたものが再度接触した歴史を分子解析から描いている
(この論文では亜種または種の扱いとしている)。
orientalis の中でもシベリア型とロシア沿海地方の型には差があって (少数サンプルだが) 後者は中国のクビワガラス Corvus pectoralis 英名 Collared Crow にむしろ近い
東アジア地域については後述の Haring et al. (2012) により広範な分類群の分子系統解析があるのでそちらを参照されたい。
分子系統と色彩が対応する部分も必ずしもそうでない部分もあるようでさらに研究が必要だろう。
少なくともヨーロッパのハシボソガラスとズキンガラスでは2つの色彩遺伝子の関わる組み換えが抑制され色彩の表現型が混じることを防ぐメカニズムがある [Knief et al. (2019) Epistatic mutations under divergent selection govern phenotypic variation in the crow hybrid zone]。
つがい形成時の生殖隔離が特に否定されているわけではなく、全体を1種とするか (その場合のクビワガラスの扱いはどうなるのか)、あるいは複数の種に分けるかは限られた生殖隔離を別種の証拠と認めるかどうかの程度問題のようである。いずれにしてもサンプル数があまりに少ない上、日本の個体は取り扱われておらず大陸とどの程度違うかはよくわからない。
Weissensteiner et al. (2020) Discovery and population genomics of structural variation in a songbird genus
によれば (スペインの) ズキンガラスの色彩を決める NDP 遺伝子の上流に約 53 万年前に内因性レトロウイルス (ERVK) 起源のレトロトランスポゾンが挿入され、これが NDP の調節部位に相当している可能性が非常に高く、接合前生殖隔離 (prezygotic reproductive isolation) に働いていると考えられるとのこと。
カラス類の表現形の違いや種分化に染色体の structural variations (構造多型) が関係しているとのこと (#ツリスガラ備考の [スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン] を参照。#マガモ備考の [白い大きなアヒルの起源] も類似事例。トランスポゾンの挿入だけで大きな表現型の変化が生じる)。
ハシボソガラスとズキンガラスは別種かの問題は鳥の色彩を決める遺伝子、そしてトランスポゾン、カラス類の種分化機構全体まで話がどんどん難しくなってきているような気がする...
Working Group Avian Checklists, version 0.02 ではまだ別種扱いだが、British list set for major taxonomic shake-up (birdguide.com 2024.10.18)
の情報によれば WGAC は同種扱いとする見通しとのこと。
Latest IOC Diary Updates では同種とする根拠が理解しにくいともある。一定の生殖隔離の存在するものをどこまで種の判定基準と認めるか学術的にも難しい問題があるのだろう。
生殖隔離機構以上に遺伝情報の類似性や単系統性を以前より一層重視する (DNA 情報のみで判断できるので客観的にわかりやすいなどの利点もある) 判断になりつつあるように思える。ハシボソガラスとズキンガラスはゲノムレベルではほとんど同じだが色彩に関係する部分のみが違って一定の生殖隔離が働いている。
種概念に関わる問題で、従来わからなかった生殖隔離機構も分子遺伝学レベルで次第に解明されつつあり、このような基準も今後さらに議論されてゆくのだろう。
構造多型はズグロムシクイの渡りの特性にも関係しているとのこと: Delmore et al. (2023) Structural genomic variation and migratory behavior in a wild songbird。
これら構造多型は重要な遺伝子の調節部位に関わっている。渡り遺伝子の研究として数年前までは標準的だったタンパク質をコードする遺伝子だけを見るだけではわからないことがたくさんある模様。
カラス類は上記のように最近レトロトランスポゾンの放散を起こしたグループだが、メス由来の W 染色体にトランスポゾンが蓄積して (トランスポゾンの排除機能が十分働いていない)、過剰に発現することでメスの適応度を下げている可能性があるとのこと: Warmuth et al. (2022) Accumulation and ineffective silencing of transposable elements on an avian W Chromosome。
同様の状況はショウジョウバエの Y 染色体で起きていてオスに変異負荷を与える "toxic" Y 染色体と呼ばれるとのこと。ヒトのようにオスが Y 染色体を持つ場合、Y 染色体の "毒性" によりオスの方が短命である説があるがまさに議論の最中。カラス類では W 染色体を通じて同じような説明があり得るかも知れない。
鳥類で逆パターンが調べられればこれら研究にも新しい展開があるかも知れない。またカラス類以外の状況はよくわかっていない。
[クビワガラスの学名]
最近同種扱いとなったハシボソガラスとズキンガラスと似た関係なので、クビワガラスの学名も少し考察しておく。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) によれば IOC 13.2 などの学名の種小名 torquatus はすでに以前に亜種名に使用されており無効とのこと。
torquatus の記載時学名は Corvus torquatus Lesson, 1830 (原記載) 基産地 'Nouvelle Hollande,' error for China according to Schlegel (Avibase による。オーストラリアなどを含む地域となっていたが中国と訂正された)。この記載のフランス語でも Le Corbeau a collier で "首輪のあるカラス" となっていた。
IOC 14.2, Clements/eBird 2024, はこの学名を用いており、H&M と (現状で) HBW and BirdLife が Corvus pectoralis 派となる。IOC も一時後者を使っていた。
Corvus pectoralis Gould, 1836 (記載) 基産地 China。
Corvus torquatus Lesson, 1830 の基産地が間違っていたため当時は同種と気づかず中国のカラスに新しくを名前を付けたらしい。pectoralis は "胸に特徴がある" の意味。
重複となった過去の用例は Corvus monedula torquata Suckow, 1800 (参考。Bechstein, 1791 の用例がさらに早い) のようでニシコクマルガラスの色彩変異か、のコメントが入っている。もしかしてコクマルガラスの淡色型のヨーロッパへの迷行例だったりして。ただしコクマルガラスの記載の方が Pallas (1776) と早いのでもしそうであってもひっくり返る心配はない。
Corvus torquatus Spalowsky (参考) の用例がアフリカのものにあってシロエリオオハシガラス 現在の学名で Corvus albicollis のことか、とある。ただし (全般の) 記載が二名法に基づいていない? との指摘があって有効な学名とならなかったと見られる。
どの記載も誤りやいわく付きばかりのものだったよう。H&M4 が問題としているのはおそらく前者の方で、これでも使用例とみなすかレベルの解釈となりそう。torquata は学名の一部でなく単にラテン名に修飾をつけたものとの解釈も考えられる (以下の BirdForum 2011 の RaMa の指摘に一致する)。この場合はクビワガラスに Corvus torquatus の学名が有効になると考えられる。大変微妙なところ。
いずれにしてもありふれた(亜)種小名を与えると重複の危険性が増す様子がわかる。地名や人名が好まれるようになって行った経緯も理解できる気がする。
Collared Crow (BirdForum 2011) に議論がある。Corvus monedula torquata は亜種より下の階層にあたるとの解釈。Bechstein (1791) は色彩に基づきニシコクマルガラスを5型 (Abaenderungen 変わり者) に分けたもの (これは大いに理解できる!) で亜種を意図したものではない。
[Corvus 属の系統解析]
Corvus 属全体の分子系統解析は Jonsson et al. (2012) Brains, tools, innovation and biogeography in crows and ravens
にあり、Corvus 属を8クレードに分けている (なお Clades には分岐時期の近いものもあり、将来の研究で順序は変わる可能性がある)。
我々に関係の深いところでは、
Clade I: コクマルガラス、ニシコクマルガラス。このグループは Corvus 属中最初の分枝にあたり、この2種を別属 (IOC のように Coloeus) に分ける意義はある (他の Corvus 属の単系統性に影響を与えない)。実際に同程度離れた Nucifraga ホシガラス属は別属になっている。
Clade IV: ミヤマガラス。2亜種の frugilegus と pastinator には十分違いがあり、別種扱いが適当な可能性があると論文にも記されている。
Clade V: ワタリガラス
Clade VI: これが問題のハシボソガラス/ズキンガラス/クビワガラスおよびアメリカの1種 (アメリカガラス Corvus brachyrhynchos) またはその亜種の caurinus を独立種としたものが含まれる。
Clade VIII: ハシブトガラス。亜種内には philippinus のように独立種程度違うものがある。これをハシブトガラスに含めるとクバリーガラス Corvus kubaryi 英名 Mariana Crow が内包されてしまって単系統にならない。
クバリーガラスは保全上の意義が大きいために広範囲の種を同種にまとめる選択は採用されなかった (Clements 2024; IOC 14.2 など) ものだろう。
この文献では一部の分類群しか調べられていないので分類の見直しは提唱されていないが、今後ハシブトガラスや類縁種は複数種に分離・再編されるかも知れない (#ハシブトガラスの備考も参照)。
さらにもう一つ Haring et al. (2012) Genetic divergences and intraspecic variation in corvids of the genus Corvus (Aves: Passeriformes: Corvidae) - a rst survey based on museum specimens
の研究がある。まず Clades では
Clade 1: コクマルガラス、ニシコクマルガラス
Clade 4: ワタリガラス
Clade 5: ミヤマガラス。2亜種の frugilegus と pastinator には十分 (4.8%。コクマルガラス、ニシコクマルガラスは 5.8%) 違いがある。
Clade 6: ハシボソガラス/ズキンガラス/クビワガラスおよびアメリカの2種 [Jonsson et al. (2012) と同じ]
Clade 7: ハシブトガラスとその他複数種。ニューカレドニアガラスもここに含んでいるが、Clade 7 は2系統に分割も可能。ここではハシブトガラスを含む方の系統のみを紹介する。
ハシボソガラス/ズキンガラス/クビワガラスなどのグループではハシボソガラスの西グループ (ズキンガラスを含む) と東グループ (クビワガラスを含む) に大きく分けられることがわかった。アメリカのものは大きく離れている (2種に分けられるかは疑問)。
ハシボソガラスの東グループは orientalis よりももっと狭い範囲でロシア極東、サハリン、カムチャツカ南端、日本、中国 (クビワガラス) を含んでいる。
カムチャツカ南端やオホーツク海沿岸は西グループで、カムチャツカ南端では両グループのサンプルがある。もしこの東グループ/西グループを種と考えるならばハシボソガラスは日本周辺のものとクビワガラスが含まれる可能性があり、orientalis は意味のある亜種概念ではなくなることになる。ただしそれぞれ1サンプル程度なので分布域のもっと広範なデータが必要である。
クビワガラスをハシボソガラスに含める議論は Meinertzhagen (1926) がすでに出していた。
従来は色の異なるハシボソガラス/ズキンガラスの接触する地域での研究が盛んになされていたが、その場所を調べることが遺伝的に異なるグループの生殖隔離の研究に妥当かどうかも問題になる可能性がある。
Haring et al. (2012) は分類変更までは提唱していないが、白い特徴のあるカラスはカラス類の中で何度も現れており、目に付きやすい特徴なので分類に取り入れられやすいが必ずしも系統を反映するものではないので分類上の注意が必要とのことである
(ハクセキレイの亜種をどう数えるかの問題にも似ていて扱いが難しいかも知れない)。
ハシボソガラスを東西2種と考えると日本のハシボソガラスとズキンガラスは別種となる (ただしそれぞれの種の範囲は現在のものと大きく異なる) 可能性の高い組み合わせになりそうである。
IOC 13.2 の扱いではハシボソガラスは世界で2亜種、ズキンガラスが4亜種。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) ではこれらを別種とせずハシボソガラスが6亜種となる。もし将来これらグループが3種に分離された場合は現在基亜種から昇格し、ヨーロッパで一般的なズキンガラスに別の種和名を与える必要が出てくることになる。
分子遺伝的研究はまだ一部しか行われておらず、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) も IOC 13.2 もまだ整合性のある体系になっていないように見える。
Khan et al. (2025) Genetic characterization and phylogenetic analysis of common house crows (Corvus splendens)
主にパキスタン地域のイエガラス Corvus splendens の分子系統解析を扱ったものだが他の Corvus 属の系統樹も見られる。Cox1 遺伝子のみだがクバリーガラス Corvus kubaryi Mariana Crow と北方型のハシブトガラスの遺伝的違いは大きく内包するのに適さないことがわかる。
この解析ではハシボソガラスとズキンガラスが分かれてしまうがサンプルの地域が限られているため、および1遺伝子しか使っていないことによるのだろう。
パキスタンのイエガラスは複数クレードに分けることができるが他の地域のものと地理的によく分離されるわけではない。
この程度の系統樹ならば自分でも作成可能と AB092480.1 (ハシブトガラス。cyt b) を出発点に BLAST を行ってみるとやはりクバリーガラスは大きく分かれる結果となった。日本とスリランカのハシブトガラスも結構異なっていておそらく別種相当が適切なのだろう (#ハシブトガラスの備考も参照)。
[カラス類の適応放散]
Garcia-Porta et al. (2022) Niche expansion and adaptive divergence in the global radiation of crows and ravens
によれば、カラス上科 Corvoidea (#アサクラサンショウクイの備考参照) の中で Corvus 属 (カラス類とワタリガラス) は特異な適応放散パターンを示すとのこと。
それまでのカラス上科 Corvoidea がすでに占めてきたニッチ (*1) を改めて占める形で適応放散 (1000 万年前ぐらいから) し、表現型 (嘴の形など) の進化速度もランダムな過程から予測されるより早く、島にも多くの種類が定着したとのこと。
分散能力が高く、新しい環境への適応性が高いなど、カラス類の頭脳の大きさと関係があるだろうなどいかにも受け入れやすそうな結論を導いているが、予想に合う形質を探しているような印象もなきにしもあらずなのでカラスだからと先入観なく見ていただたいた方がよいかも知れない。
似たような種類でありながら、カササギ類は南米に分布を広げたがオーストラリアには分布せず、Corvus 属は南米に分布せず、一方でオーストラリアにも分布を広げ、アフリカもカササギ類より広く分布している。
Corvus 属の方がより乾燥気候にも適応できているようだが、Corvus 属が南米に分布を広げなかった理由は特に議論されていない。
備考:
*1: どこの項目でもよいのだがここで読み方の問題だけを扱っておく。"ニッチ" はもはや日常語になっているので日本語でもこの用語が標準でよいと考えているが、wikipedia 日本語版を見ると「フランス語読み: ニーシュ」とあり語末の e を発音しないのが正しい。
"ニッチェ" の読み方はどこからだろうか。ドイツ語かと思ったが Nische で発音は "ニッシェ" の方が近い。医学のレントゲン用語では普通ニッシェ (へこみ) と呼んでいるので、こちらはドイツ医学由来で理解できそう。
"ニッチェ" はもしかすると "日本語読み" なのかも知れない。OED によれば 1991 年の発音辞典でイギリス式ではニーシュ、アメリカ式でニッチとのこと。
wikipedia 日本語版のこのページを見ると今西錦司の棲み分け (habitat segregation: 今西氏による訳語) が紹介されている (ただし説明をみると必ずしも自然科学との折り合いが良いわけではないとある)。
habitat segregation も英語としては素直で実際に使われている。対応する概念では niche partitioning (よく見かける), niche differentiation, niche segregation などが使われている。
"segregation" は分離、"partitioning" は分割のような意味で、資源を指して resource partitioning や niche partitioning に修飾を付けて behavioral niche partitioning, spatial niche partitioning, trophic niche partitioning などの使い方がある。この用語が現代的でもあり活用範囲が広いかも。
niche/Nische の語源はラテン語の nidus (巣) 由来なので実は鳥と縁が深い。ロシア語で巣を gnezdo と呼ぶなど関連が見える (インド・ヨーロッパ祖語で *nisdos でいずれも同根)。スラブ系ではこれに近い綴りのものが多く、"巣" の単語が見つけられれば知らない言語でも把握しやすくなるので知っておいて損はない。
gnezdo を無声化すれば nest の音になるので関連がわかりやすい。
ドイツ語や関連する言語ならばもっとわかりそうなものなのだが、猛禽類の巣は通常 Horst と呼ばれるのでちょっと単語の雰囲気が違う。
[鳥の知能行動]
カラスは賢いというのはあまりに常識になっているので他書に譲るが、高校? の生物参考書などで動物の迂回実験の記述を読まれた方もあるのではないかと思う。
障害物の向こうに食べ物がある時、障害物を迂回して食べにいくことができるかで、イヌならば迂回できるのにニワトリは直接食べ物の方向に向かい障害物にぶつかってしまう。知能の違いが現れているという話である。もっと賢い鳥がいるはずと習った時から思った気がしていた。
この出典が何だろうかと思っていたのだが、寒河江・金田 (2022) 幼児前期の発達における迂回概念の検討 を参考にすればケーラーの「類人猿の知恵試験」とのこと (この文献にケーラーの行った犬と鶏の実験結果も紹介されている)。
おそらくケーラーの実験がよく知られて、系統進化と知能の進化の関係として語られるようになったのだろう。
ケーラーは Wolfgang Koehler で、The Mentality of Apes (1925)、
Gestalt psychology: an introduction to new concepts in modern psychology (1947)、The task of gestalt psychology (1969) などの本を出しているとのこと。
天井からバナナをひもで吊るした「チンパンジーの洞察学習」の実験を行ったとのこと。
Epstein のグループがハトを使って同様の実験に成功。Epstein et al. (1984) 'Insight' in the pigeon: antecedents and determinants of an intelligent performance (Nature サイト)。pdf リンク。
Epstein (1987)
The spontaneous interconnection of four repertoires of behavior in a pigeon (Columba livia)
の論文があり、過去に個々の行動を訓練されたハトが行動を組み合わせてまるでヒトのように問題解決できるとのこと。届かないバナナに最初は戸惑うが一連の動作を示したとのこと。
この事例は「鳥脳力: 小さな頭に秘められた驚異の能力」(渡辺茂 化学同人 2010) p. 82 にも紹介されている (2022 年加筆・修正版があるがこちらは見ていない)。
このような研究もあるので Koehler の実験も知能行動の証拠となっているか徐々に怪しくなってくる (霊長類研究者には "不都合な真実"?) が今でもそのように教えられているように見える。
以下の論文を見てゆくとそもそもこのように教えてはいけないのではと思える。
Kabadayi et al. (2018) The detour paradigm in animal cognition のレビュー論文があり、この回避行動実験 (detour paradigm) に至った背景も触れられている。
イヌの話は窓越しに飼い主を見て迂回してドアから入ってきたという Hobhouse (1901) の話がもとになっているらしい (このぐらいならば鳥でもありそうな気がするが)。
ニワトリが金網を迂回できないとの報告は Thorndike (1911) "Animal intelligence" とのこと。
Koehler (1925) は金網ごしに目標を見た場合の行動は "洞察力" を反映しているとのパラダイムに基づいて実験を行ったらしい。
この論文にこれまでの実験の一覧があり、気になる鳥のところを見ると前述のニワトリやハトの成績は悪いが、ハトで成功している例もある。
Kabadayi et al. (2018) によれば、Koehler も後の実験で個体差が大きく、孵化後数日以内のニワトリでさえ驚くべき迂回行動を示すことも見つけている (本人の発表ではなく他の著者が述べている)。
しかしロボットを使った実験で、予めプログラムされていなくてもニワトリと同程度の成功率でニワトリが問題解決に心象を用いている証拠にはならないとの指摘もある。
成績の悪い方にカナリア、おそらくニシセグロカモメ、ウズラが含まれているがカラス類を含めてかなり多くの種類は成功している。キバタンが不思議に成功していない (これは Lorenz 1932 によるもので、「ソロモンの指輪」を見ていると先に結論ありきだったかも?)。
最近の実験はおそらく標準的な手法であろう透明シリンダーが主に使われている。後述で気になった猛禽類は報告には含まれていない。
哺乳類の方を見ておくとネコ、ヤギ、ウマ、ヒツジも成功せず、イヌも同様の条件で意外に成功していない (それぞれの文献の実験目的が違うので同列に比べにくいが)。Koehler (1925) が引用されているが、窓ごしに投げたものを取りに行ったというもの。オオカミでも典型的な鳥の反応と思ったほど違わない。Koehler (1925) ではチンパンジーは動きは示したが窓ごしに投げたものは取らなかったらしい。
この表を見ると霊長類は特別だが他は哺乳類も鳥類 (カラス類の成績は一般によい) もそう違うわけではない。教科書に書いてあることをそのまま信じてはいけない模様。
その後もさまざまな研究がなされていて、地上性の動物と空中を移動する動物にとっては障害物の捉え方が違うなどの研究もある。肉食哺乳類にとっては障害物を避けるのは必須の行動であり、生態と知能のどちらを反映しているかわからない。
たまたま霊長類にとって自然界で必要な技能を調べたことになっている可能性がありそう。カラス類も地上移動で餌に到達することも多いので当たり前なのかも知れない。この表にあるものでは爬虫類、両生類、魚類では成功例の報告はない模様。
この系統進化と知能の進化の関係には別系統の研究もかかわっていて、「おもしろい動物行動学」(ザヤンチコフスキー著 田中百平訳 時事通信社 1973) に載っていた。この本も図書館に広く置かれていてかなり読まれたのではないかと想像する。
こちらは archive のサイト で原書 (Zayanchkovskij 1971) が読めて、関連の記述が p. 306 にある。
Krushinskij の実験を記述したサイト があり (ロシア語)、Koehler とはまた違った "洞察学習" を見ている。嗅覚を頼りにできないように工夫をこらしている。
Zayanchkovskij (1971) および訳書 (1973) に書かれているほぼその通りだが、実験をうまくこなしたのは肉食哺乳類、イルカ、カラス科の鳥、カメ、クマネズミ類、ネズミ類の一部とのこと。うまくこなせなかったのは魚、両生類、ニワトリ、ハト、大部分のげっ歯類とのこと。
Zayanchkovskij (1971) ではカモや猛禽類が後者に含まれているが、オリジナルの Krushinskij の実験には現れていないよう。系統進化的にはカメや大部分の齧歯類の位置が変に見えるが (何とカメとイヌの成績には大差ない)、だいたいの傾向として知能の進化は系統進化を反映している結論になったのだろう。Epstein et al. (1984) が実験に成功したハトの成績が悪いのが興味深い。
実験を重ねるとニワトリの成績は向上するものの、キツネはむしろ悪くなる傾向があった。
このページを機械翻訳して気づいたのだが、専門用語であるカラス類 vranovye が一般の辞書には出ておらず、機械翻訳でも猛禽類と訳された。後に "一部のカラス類" の表現も出てきてあるいはどこかで猛禽類と誤解された可能性もありそうに思えた。この実験ではカラス類以外の鳥類の成績が妙に悪くトカゲやカメを含む爬虫類を下回っている。地上を這うものにとって得意で、鳥にとっては得意でない実験なのかも知れない。
文化圏が異っていて Koehler ほどは議論の対象になっていないようだが訳書を通して日本に影響を与えているのではないかと思う。
このサイトの 次の章 で Epstein のハトの実験も触れられていて、外部刺激によるもので霊長類のものとは違うとの反論もなされたとのこと。
Epstein らの初期の実験は個々の過程をトレーニングして、それを組み合わせることができることを示したものだが (ヤマガラの芸の話とも似ている)、対照群として用いたハトにはスタンドの上でついばむ行動かスタンドを動かす行動のいずれかを学ばせたものだったが2回めの試行で餌をとることに成功してしまったという。
スタンドを動かす行動を学習することが大事で、動かせば上に登って餌をとることは特に訓練を必要としなかったとのこと。また Krushinskij の研究は独自の発想で行われたものだったとのこと。
Liao et al. (2024) Crows "count" the number of self-generated vocalizations
ハシボソガラスを用いて数字を見せるなどの刺激に応じて 1-4 回の声を出し分ける訓練ができたという。また次の数を予測している証拠もあったとのこと。英文解説記事。
鳥を中心とした特に社会的「遊び」のレビュー論文があるので紹介しておく。Kaplan (2024) The evolution of social play in songbirds, parrots and cockatoos - emotional or highly complex cognitive behaviour or both?
タイトルでは鳴禽類・オウム類が中心だが、他の種類の遊びも触れられている。カラス上科でも社会的遊びがよく知られている系統は限られている、というよりごく一部の種類についてしか情報がない。内容は多岐に渡っているので必要そうなところをお読みいただきたい。
鳥の認知能力に関連して、回転して同じになる図形を見分ける (ヒトでも知能テストに使われる) 課題をハトがヒトより速く解ける。ヒトが得意な分野だけ見ると他の動物の知能が劣って見えるが、他の動物のほうが優れている事項もある。3次元の空中生活者にとっては回転図形の課題は易しいと読まれた方もあるだろう。
Hollard and Delius (1982) Rotational Invariance in Visual Pattern Recognition by Pigeons and Humans が出典で、
Delius (1985) Cognitive Processes in Pigeons でも読むことができる。裏返し図形はヒトと同様に苦労するとのこと。
反論もすぐに出て例えば Cerella (1990) Pigeon pattern perception: limits on perspective invariance。
ヒトが樹上から地上生活に変わったことでこの能力を失ったのではとの解釈もあったが、アカゲザルを用いた実験ではあまりはっきりしない結果に。Koehler et al. (2005) Mental rotation and rotational invariance in the Rhesus monkey (Macaca mulatta)。
Giri and Garcia-Pelegrin (2025) Opportunistic Tool Use by Two Unexpected Corvid Species
が飼育個体でスンダガラス Corvus enca (系統的にはハシブトガラスに近い) とイエガラス Corvus splendens がカレドニアガラスのように鈎を作って食物を得る行動を偶然行ったとのこと。
同様の行動がさまざまな Corvus 属で記録されていることから、この行動は Corvus 属の分化以前に獲得された Corvus 属特有の形質では、あるいはより一般的に貯食行動や枝などの物を触ってみる傾向が道具使用の起源として考えられるなどの議論がなされている。
[ハシボソガラスによる鳥やコウモリの捕食事例]
田仲 (2023) Birder 37(11): 31 にハシボソガラスによる生きたズグロカモメの捕食の事例が紹介されている。水没させて捕食したとのこと。
前田・船越 (2022) 熊本県天草市におけるハシボソガラス Corvus corone によるヒナコウモリ Vespertilio sinensis の捕食事例
の報告がある。
[その他]
Wascher and Hillemann (2024) Observation of female-male mounting in the carrion crow (preprint)
飼育下ハシボソガラスでメスがオスにマウントした事例。これまで提唱された仮説とともに鳥類約 30 種での報告のリストが載せられている。必ずしも社会性の種というわけではなさそう。ヒメウミスズメの交尾では 5% がメスがオスにマウントとの報告があるが、そのうち1つがいは半数の交尾で逆転があったとのこと。
青い (白い) 目のカラスの話題は#ニシコクマルガラスの備考 [ニシコクマルガラスの虹彩はなぜ白い] を参照。
-
ハシブトガラス
- 学名:Corvus macrorhynchos (コルウス マクロリュンコス) 大きな嘴のカラス
- 属名:corvus (m) カラス
- 種小名:macrorhynchos (合) 大きな嘴の (macro- (接頭辞) 大きな rynchos 鼻口部 Gk)
- 英名:(Jungle Crow 広い意味での旧称), IOC: Large-billed Crow (ただし分類概念はリストにより異なる)
- 備考:
corvus は#ワタリガラス参照。
macrorhynchos は外来語からの合成語で発音は明確でないが、起源となるギリシャ語がいずれも短母音のみのためすべて短母音と考えられる。-rhyn- にアクセントがあると考えられる (マクロリュンコス)。
英名は学名によく対応している。学名を訳したものとも考えられるが種学名の変遷はやや複雑。
Jungle Crow は OED には出てこない (そもそもイギリス・アメリカとも分布しない) が、jungle-fowl (ヤケイ) については項目があり、1824 年の用例があるとのこと。インドを英国が支配した時代に付けられた名称のよう。
wikipedia 英語版によればイエガラス Corvus splendens House Crow との対比が挙げられているので House に対する Jungle の名称が付けられたものかも知れない。現在は分割されているが、インドの Jungle Crow は Corvus culminatus Indian Jungle Crow および Corvus levaillantii Eastern Jungle Crow。
Corvus culminatus の原記載は英語で、Sykes (1832) 原記載 だったが当時はまだ Jungle Crow の英名は与えられていなかった。英国から見た House とインドの Jungle の対比であったならば "Jungle" の英名の意味にあまり重点を置いて考える必要はないかも知れない。
世界に9亜種 (IOC)。日本で記録される亜種は japonensis 亜種ハシブトガラス、connectens (「くっついた、つながった」の意味) リュウキュウハシブトガラス、
osai (Masamichi Osa が由来? 以下参照) オサハシブトガラス、mandshuricus (満州の) チョウセンハシブトガラス、及び亜種不明となっている。
osai の由来は オーストン貿易会社 (1882-1910) の日本のチーフ (head clerk) Masamichi Osa だったとのこと。
Bjorn Bergenholtz (私信) によれば Nobuhiko Osawa (ここまで The Key to Scientific Names)。
Ogawa (1905) Notes on Mr. Alan Owston's Collection of Birds from the Islands lying between Kiushu and Fermosa には The collecting party consisted of Messrs. M. Osa and T. Osada とある。
山崎 (2016) Birder 30(9): 30 では 20 世紀初頭に琉球列島の鳥の標本を採集した長聖道 (おさまさみち) とある。The Key to Scientific Names はこの同定を採用していると考えられる。
松田 (2003) Birder 17(8): 31-35 はオーストンコレクター長の "長" をオサと誤読した説を取り上げている。
標準的な読み方を考察しておくと、japonensis "ヤポネーンシス"、connectens "コンネクテーンス" (現在分詞形語尾による)、
osai は オサイ でよいだろうか。採用する人名次第だが長聖道を想定して長音としなかった。
mandshuricus は wiktionary によると mand-shu-ri-cus と文節されるそうで、ラテン式読みでは "マンドゥスリクス" となる。d と s をくっつけた発音にはならない (ラテン語にこの音はない)。後の時代でもこの発音規則は変わっていないようで d が無声音となる傾向もあまりない。
参考までにロシア語の地名の綴りを確認しておくと Man'chzhuriya、中国語では Manzhou。
ドイツ語式発音であれば、辞書によれば mandshu- の部分はマンチュー (d が無声化) またはマンジュー (dz の音) となる。"マンチューリクス" または "マンジューリクス" の読み方でよいと思われるが、ドイツ語式であると認識しておくとよさそう。
現在の種学名の記載時学名 Corvus Macrorhynchos Wagler, 1827 (原記載) 基産地 'Nova Hollandia, Nova Guinea et in insulis Sumatra et Java' [= Java] (Avibase による)。
これによれば Corvus Macrorhynchos の名称はジャワ島の標本について Temminck がすでに用いていたが、Wagler がしっかり記載したとのことらしい (参考 1, 2)。
Temminck の記載が表面に出なかったのは、Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux... にあるようにフランス語名 corbeau a long bec で Latham の Corvus australis で大陸からインド列島 (インドネシア) に分布し、ジャワ島で極めて普通と記したものと考えられる。
Corvus australis Gmelin, 1788 (参考。South-sea Raven) と Corvus australis Gmelin, 1788 (参考。Cayenne red-billed Crow)
のように Gmelin がオーストラリアと南アメリカのものを同種と考えて (あるいは誤って) "南のカラス" を意味する名称としたしたためにおそらく有効な学名にならなかった。
Temminck は深く検討することなく同一と考えてこの学名を用い、このタイミングで記載を行わなかったために Wagler の方が記載することとなったよう。
Wagler も Corvus australis は用いていたが別物と考えていた。
後述の "Fauna Japonica" にも現れていて Corvus macrorhynchos, Temm. と自身が命名者と記しているものの Wagler が記載したと記している (Temminck の記述は複数の文献を横断してよく見ないと真意がわかりにくいこともある)。
Temminck が South-sea Raven と同種とみなしたことは、あるいは後日ハシブトガラスとミナミワタリガラス Australian Raven が一時同種とみなされたことにも関係があるかも知れない。
この Wagler の "Systema avium" は BHL の情報によれば Forster の記述、Captain Cook の 1772-1775 年の2回めの航海で得られた標本も含めて著されたものだったが完結することはなかったとのこと。あまりにも膨大で完全な百科事典的著作を目指しすぎたらしい。
[ハシブトガラスの分類]
#ハシボソガラスの備考の Jonsson et al. (2012) の分子系統研究によれば現在ハシブトガラスとされる種は将来再編される可能性が高い。日本の亜種の検討はまだなされていないため、複数種に分離された場合にどれに属するかなどはまだ何とも言えない。
Dement'ev and Gladkov (1954) では Corvus levaillantii Lesson, 1831 の学名になっており、japonensis などはその亜種となっていた。IOC では Corvus levaillantii を独立種 Eastern Jungle Crow としている。
これは Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) ではハシブトガラスの亜種とされているが、Rasmussen and Anderton (2005) "Birds of South Asia: the Ripley guide" は andamanensis をその亜種に含めて独立種と扱っているとの注釈がある。IOC は独立種としているが、亜種を認めない単形種の扱いとなっている。
Dement'ev and Gladkov (1954) の Corvus levaillantii はマレー半島やスンダ列島のカラスを含めない分類であったため levaillantii に先取権があったが、これらのカラスを含めると macrorhynchos Wagler, 1827 の方が早いために Corvus macrorhynchos となっている次第である。
かつての Corvus macrorhynchos にはフィリピンの亜種 philippinus も含められていたが (IOC 13.2 でも同様)、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では別種 Corvus philippinus Philippine Crow としている。
この扱いは Jonsson et al. (2012) の分子系統樹と整合している [しかし H&M の種分割基準と整合しているかは不明。#サカツラガンの備考参照]。
フィリピンには他にも複数のカラス類が生息するので、この英名はあまり適切でないかも知れない。
フィリピンのチェックリスト (2023) ではハシブトガラスの亜種としているが、学名別名で独立種としても扱っている。英名別名に Philippine Jungle Crow を与えている。ごく普通種とのこと。
フィリピンではむしろスンダガラス Corvus enca 広い意味の英名 Slender-billed Crow (この英名こそ和訳するとハシボソガラスになる) の複数の亜種を独立種として扱う問題の方が大きそうである。
IOC ではもと Slender-billed Crow から Corvus pusillus Palawan Crow と Corvus samarensis Small Crow (さらに分ける立場だと Samar Crow) を認めているが Corvus samarensis Sierra Madre Crow を認める立場もあるようである。
Philippine Crow の姿や声がどの程度違うかは Ask the experts (eBON 2012) が参考になるだろう。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) の脚注によれば、ハシブトガラスを複数種に分割する提案がなされているが、系統解析サンプルが不十分で Corvus philippinus のみが根拠をもって分離可能であったとある。
これは後述のようにおそらくハシブトガラスの単系統性を保つための措置。
東南アジアの他の Corvus macrorhynchos については同様に調べられているわけではないが、亜種 macrorhynchos と例えば japonensis を別種とすることが適切 (Dement'ev and Gladkov 時代と同様) となれば学名が変わることになる。
その時には Corvus levaillantii は別種扱いとなっているだろうし、Rasmussen and Anderton (2005, 2012) はインドの culiminatus、japonensis を別種と考えているとのことで、ハシブトガラスの学名は Corvus japonensis になるかも知れない
(macrorhynchos と levaillantii 以外での記載順序は culiminatus Sykes, 1832、japonensis Bonaparte, 1850 の順であり、Corvus japonensis になるかどうかは culiminatus が独立種になるかどうか次第)。
Vocal variation and future splits of the Large-billed Crow complex (Nelson 2013) による音声比較もあり、Martens et al. (2000) によれば3-7種に分けるのが自然で、ヒマラヤ、中国、日本のものを Corvus japonensis とまとめるのが適切であろうとのこと。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" では Corvus japonensis (connectens、osai を亜種として含む) Japanese Crow と
Corvus macrorhynchos (mandshuricus、中国東部や台湾の colonorum を亜種として含む) Large-billed Crow の分離が提案されているとの記述がある。
上記 Nelson (2013) の区分とも微妙に異なっている。
系統サンプルがなされれば近い将来日本のハシブトガラスの学名は Corvus japonensis になりそうに思える (島の亜種も一緒に含まれるかどうかは想像できないが)。
Haring et al. (2012) (#ハシボソガラスの備考参照) では
ハシブトガラス内の違いはそれなりにあるがデータはまだあまり十分でない。この文献によれば、
亜種 macrorhynchos は問題なく東南アジア熱帯雨林が起源と考えてよいだろうが、levaillantii と japonensis はハシボソガラスに似た開けた環境に適応して進化したものと考えられ、音声の違いもありそれぞれ独立種の扱いに値する可能性がある。
現状のデータと過去に提唱された種の分離を考察して地理的には大まかに4グループに分けることが考えられる:
(1) インド亜大陸 levaillantii、(2) マレー半島の小スンダ列島 macrorhynchos、(3) フィリピン philippinus、(4) 北方型 japonensis, mandshuricus, colonorum, culiminatus
論文では種分類の変更の提案までしていないのですべて亜種としての記載となっているが、ここではあえて三名法はとらなかった。グループの間の違いは見て取っていただけると思う。これまでの経緯を考えるとデータが揃った場合この4グループをそれぞれ種と認められるかも知れない。
この通りであれば日本のハシブトガラスの学名は Corvus culiminatus となるがさてどうだろうか。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) でもこの文献は参考にしているが、philippinus を例外として、種を分割するにはサンプル数が十分でないとの判断のようである。
Clements 2024, IOC 14.2 ともに Philippine Jungle Crow Corvus philippinus のみを分離。系統樹的には最低限の分離で大きなところにはまだ手を付けることができない。
亜種 macrorhynchos は熱帯雨林起源でよいとしても北方型は生態的にはだいぶ異なっているようである。広い意味での英名 Jungle Crow や東南アジアの亜種 (現行分類で) を想定して「ハシブトガラスは南方系で森林性で」と説明するのは、起源まで判明していない現状では実はあまり適切でないかも知れない。
Alamshah and Marshall (2025) Distribution-wide morphometric data of Jungle Crows (Corvus macrorhynchos) にハシブトガラスの分布の広範な地域の形態データベースが発表されている。論文そのものには亜種による違いの図などはないのでデータから自分で調べよ、となるだろう。
[日本の亜種の記載時学名]
・Corvus japonensis Bonaparte, 1850 (原記載) 基産地 Japan; restricted to Hokkaido by Stresemann (1916, Verh. Orn. Ges. Bayern, 12, p. 279) (北海道に限定)。
Temminck and Schlegel の "Fauna Japonica" 本文、図版 ではジャワ島のものと大きな違いが認められないとしている。
前述のように自身が付けたはずの学名を Wagler に先取りされてしまったショック (?) もあり、この学名は本来自分が付けたものだとここで主張したくてこの学名を用い、別種に値する可能性まで気が回らなかったのかも知れない。Bonaparte は冷静に見るとちょっと違うと判断して別種としたもの。
つまり Temminck and Schlegel が提唱した学名ではない。Temminck and Schlegel の他の用例を見ても、もし自身が付けていれば japonensis とはしなかっただろう。他の特徴で記述すれば学名に困ったかも知れない。亜種ハシブトガラス
・Corvus macrorhynchus osai Ogawa, 1905 (原記載) 基産地 Kobamashima, southern Ryu Kyus. オサハシブトガラス
・Corvus macrorhynchus mandshuricus Buturlin, 1913 (原記載) 基産地 Samarga River, Ussuriland チョウセンハシブトガラス
・Corvus coronoides connectens Stresemann, 1916 (原記載) 基産地 Miyakoshima, southern Ryu Kyus. リュウキュウハシブトガラス
種小名は一度 macrorhynchus に修正された経緯がわかるが、原記載に基づいて戻された模様。
リュウキュウハシブトガラスの記載時代には Corvus coronoides の種学名が使われていた。これは現在ミナミワタリガラス Australian Raven を指す。Stresemann (1916) はオサハシブトガラスもこの亜種と考えていた。大型の黒いカラス類をどこで区切るか当時も悩ましかったらしい。
シノニムとされた記載はいくつもあって、
・Corvus coronoides borealis Momiyama, 1927 (参考 1, 2) 基産地 Naikawa, S. Sahkalin = japonensis
・Corvus coronoides hondoensis Momiyama, 1927 (参考 1, 2) 基産地 near Tottori, Hondo, Japan
・Corvus coronoides ijimai Momiyama, 1927 (参考) 基産地 Tsushima = mandshuricus
・Corvus coronoides quelpartis Momiyama, 1927 (参考 1, 2) 基産地 Quelpart Island (済州島) = mandshuricus (現在は日本ではないが含めておいた)
・Corvus coronoides tikzenensis Momiyama, 1927 (参考 1, 2) 基産地 Sawara-gun, Prov. Thikuzen, N. Kiusiu, Japan = hondoensis
いずれも Kuroda (1932) がシノニムとしたものだが、hondoensis は亜種として認めていた。Temminck and Schlegel の "Fauna Japonica" の基産地が北海道に限定されたため本州・九州を別亜種とすることができた。津島は大陸型と考えていたことがわかる。
亜種が最初に記載されたころは Corvus macrorhynchus (綴りは現在のものと異なる) の学名が使われていた (1905 年など)。この当時であれば学名と和名の対応が非常によかった。
種学名は 1927 年当時は Corvus coronoides で、coronoides は "corone に似た" の意味なので、この当時の学名は "ハシボソガラスに似たカラス" の意味となっていたことがわかる。ヨーロッパからオーストラリアへと入植するにあたって馴染みのハシボソガラスはおらず、故郷のワタリガラスに似た大型のカラスを Raven と名付けていたのだろう。しかし学名は "ハシボソガラスに似た" 方が採用された。
macrorhynchos の種小名も記載が早いため同種とする場合は基亜種となるだけの話で、日本のハシブトガラスそのものに対して名付けられた学名ではない (ただし Temminck and Schlegel は同種と考えていた)。
現在の学名と和名の対応は非常によく見えるが、これは分類依存のもので、種分割の方法次第で必ずしも一致しなくなる。ただし和名が整理された時代はおそらく Temminck and Schlegel が用いていた現在の種学名と同じで整合性がよい理由にもなっていたかも知れない。
ミナミワタリガラスは Corvus coronoides Vigors & Horsfield, 1827 の記載で、ヨーロッパからオーストラリア入植や探検順に学名が付いていった経緯が読み取れる。#ツツドリの現在の学名も同様で当時の歴史が現れている。
macrorhynchus はジャワ島、そしてインドの亜種などヨーロッパから到達しやすい地域から先に命名された次第となる。記載が古いほど基亜種になる可能性が高いので日本の亜種がどのグループに入るか次第で種学名が変化した次第。今後も変わるかも知れない。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Corvus macrorhynchus の学名と英名 Oriental Raven を用いていた。ヨーロッパから見るとハシブトガラスは巨大で "Raven" にふさわしかったのだろう。
サイズはワタリガラスとヨーロッパのハシボソガラス (Common Crow) の中間だが嘴はワタリガラスと同じぐらい厚いとのこと。途中で Japanese Raven, Crow of Japan の表記も出てくるがこれはおそらく言い換え表現と思われる。Indian Jungle-Crow が基本形 (基亜種に相当) で、日本のものは Corvus macrorhynchus japonensis と呼ぶこともできるだろう (may be called) との表記。
琉球のものは嘴が細く、Swinhoe (1863) の台湾の colonorum と同一ならば Corvus macrorhynchus levaillantii の方に先取権があるとの解釈。
Seebohm (1890) による日本のハシボソガラスの記述では学名はヨーロッパのものと同じものを用いているが、より大型でハシブトガラスに近い。英名は Carrion-Crow としていた。
分類学者によっては分離する考えもあるので特にヨーロッパのものを指す上記表現には Common Crow が使われていた。
[サハリンとロシア沿海地方のハシブトガラス]
中村 (2021) Birder 35(2): 40-41 に「小さなハシブトガラス 誕生の秘密」の記事がある。サハリンで小さなハシブトガラスが記録され、Nechaev は大陸型 (mandshuricus) と日本型 (japonensis) の交雑帯がサハリン北部にあるのではと考えたとのこと。
中村氏による DNA 研究でサハリンの個体はそれまで考えられていたように japonensis ではなく mandshuricus のみで、氷河サイクルとともに大陸から小型の mandshuricus がサハリンに繰り返し定着したシナリオを考えている。
「謎のカラスを追う - 頭骨と DNA が語るカラス 10 万年史」(中村純夫 築地書館 2018) の著書がある。
Nakamura and Kryukov (2015) Phenetic analysis of skull reveals difference between Hokkaido and Sakhalin populations of the Jungle Crow Corvus macrorhynchos (pp. 1845-1858) の英語論文がある。
この論文は主に頭骨形態を扱い、分子系統研究と合わせて進化史を考察したもの。
ハシブトガラス内で遺伝的違い (mtDNA) は大きなものではなく、大きく分けて大陸と島に弱く分離される程度だった。サハリン内、サハリンと北海道の間にも大きな遺伝的違いはなかった。記述からは済州島のものは別の可能性があるそうで、あるいは quelpartis の亜種記載が生きてくるのかも知れない。
引用されている分子系統研究は Kryukov et al. (2012)
Comparative Phylogeography of Two Crow Species: Jungle Crow Corvus macrorhynchos and Carrion Crow Corvus corone (ResearchGate)。
発端の一つとなった Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" (Birds of Sakhalin Island。表題と要約のみ英語あり) では pp. 364-365 に記述があり、標本を調べて主に南部が japonensis、北部に mandshuricus と考えた (嘴の大きさなどの計測値から)。サハリン北部で両亜種が同所的に分布する地域がある。
しかし雑種と思われる中間型は同定の難しさもあって確実に見つけられていないとのこと。未知の隔離機構がある可能性も考えていた。Nechaev は冬季の漂行がそれぞれ日本と大陸に向かうと考えていた。
極東の鳥類 12-14 「サハリンの鳥類 1-3」では該当部分はシリーズの 2 に含まれていた。
サハリンのカラス類の現状情報 Vorony i mesta ikh obitaniya (Pasyukov 2021)。かつてはハシブトガラスはユジノサハリンスクで繁殖していなかったが現在では市内に 6000-7000 羽いるとのこと。ごみが冬季生存を支え、繁殖成功率を高めているとのこと。どこも同じか...。
関連してロシア沿海地方のハシブトガラスの繁殖生態: Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the large-billed crow Corvus macrorhynchos (pp. 2291-2319)。
ロシア沿海地方のものは亜種 mandshuricus としている。japonensis の可能性のある記録があるが十分確認されていない。20 世紀末までは人が住む場所を避けて繁殖していたが、1990 年代終わりから 2000 年代初めから自動車の増加やツーリズムの発展などの影響で人に慣れるようなったとのこと。
ソ連崩壊でたとえば旅行者への開放が進み "人の近くは危ない" 意識が変わって行ったのだろうか。
他の文献の情報も参照すると繁殖地はさらに内陸地域にも広がってハシボソガラスとの雑種も記録されているとのこと。人の出すごみで個体数が増えて分布も広がったのか、温暖化の影響もあるのか?
[色丹島のハシブトガラス]
色丹島のハシブトガラスを扱った番組 Strana ptits. Shikontanskie vorony (Telekanal Kul'tura)
"鳥の国" というロシアの TV 番組の1つで製作者直々のアップロード。自動字幕も表示できるので翻訳を選択すればある程度内容がわかるだろう。住民の方の証言では犬のように賢いと笑いながら驚かれている (何だか楽しそうにカラスの仕草を真似られている)。1994 年北海道東方沖地震 (ロシア語では色丹島地震の名称となっている) までの状況。
エトピリカ? の巣穴のそばで繁殖する。後の映像にもあるように電柱にも営巣する。カラスからニワトリや作物を守る防鳥網も用いられる。
しかし住民も食物を与えるなど厳しい島の暮らしにお互い様と妥協点を見出している (当時のロシア経済も最悪の時期だったと思われる)。家ごとそれぞれにカラスの家族があるとのこと。地震の後は餌を与えるようになった人もある。お互いに対等の関係になっている (ここまで第1章)。19:54 ぐらいから夜間にカラスの巣を調査して標識する科学者。
18 日齢から親はひなを暖めなくなる。夜は寒くひなは体を寄せ合っているとのこと。その後ひなの巣立ち、見守る親、巣立ち後のひなの行動や集団形成など。最後は大学院生による親から子に文化の伝達があるかの実験。
[オオハシガラス]
英名や学名が "ハシブトガラス" を意味する種類がある。オオハシガラス Corvus crassirostris Thick-billed Raven (アフリカの角地域の高地)。カラス類中 (スズメ目でも) 最大の嘴とのこと。wikipedia 英語版によればスズメ目中最も体重の大きな鳥でメスで 1.15 kg、オスで 1.5 kg とのこと。
ここまで嘴が大きいと単純に採食の機能のみとは考えにくく、社会的地位を示すためや放熱器官としても役立っているかも知れない。飛行時の写真などを見るとサイチョウの形態に似た印象も受ける。腐肉食への適応ともされるがハゲワシ類はそれほど大きな嘴を持たない。オオワシの嘴の進化を想像すると同じような考えができるかも。
高緯度地域のカラス類ではこれほど大きな嘴は熱喪失が大きく持てないのでは。
[その他]
青い (白い) 目のカラスの話題は#ニシコクマルガラスの備考 [ニシコクマルガラスの虹彩はなぜ白い] を参照。ハシブトガラスでも当てはまる。
-
ワタリガラス
- 学名:Corvus corax (コルウス コラクス) カラス
- 属名:corvus (m) カラス
- 種小名:corax (合) カラス (koraki カラス < krozo かあかあ鳴く Gk)
- 英名:Common Raven, IOC: Northern Raven
- 備考:
corvus はラテン語では v を u の音で読むため uus と u の音が2つ並ぶ。音節区切りも cor-vus。r を子音で読んで u を重ねて読む発音が古典式ラテン語発音に最も近そうだが発音が難しそうなので "コルウス" を採用した。古典式を離れれば英語読みのように u を v の音で読んでも構わない。
corax は短母音のみ (コラクス)。
Corvus peregrinus Brehm, 1828 ("よそ者の/渡りのカラス" の意味) の学名があり和名の由来となった可能性がある。
Brehm (1828) の記載は無効名とされるが、Corvus peregrinus の 1831 年の記述もある (Handbuch der Naturgeschichte der Voegel Deutschlands ドイツの鳥の自然史ハンドブック)。1818 年のタイプ標本もある。
Corvus Corax Linnaeus, 1758 (原記載) があるためシノニム、または無効学名となったものと思われるが著名な書物に用いられた学名のため一定使用されており、
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも別学名として登場する。当時の記録は千島列島。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 82 p. 13 ではワタリガラスの和名の由来はよくわからない、渡ってくるカラスのことか、となっていた ("ワタリ" をこのような意味の接頭語として用いた用法が当時他にあったのかなどが議論のポイントになるのだろう)。コンサイス鳥名事典では北海道に渡ってくるからとなっている。過去の学名由来はある程度有力なのでは?
世界に 12 亜種 (IOC)。日本で記録されるものは kamtschaticus (カムチャツカの) とされる。日本で出会うことが難しい種であるが、ヨーロッパやアメリカでは普通の種類。北方の種と考えがちだが中央アジア、アフリカ、アメリカではかなり低緯度まで生息している。
日本近辺での個体はあまり問題にならないようだが、Haring et al. (2012) (#ハシブトガラスの備考参照) によれば北米のワタリガラスの遺伝系統関係は単純でなく、隠蔽種が存在する可能性があるとのこと (候補地域の個体はまだサンプルが得られていない)。
Corvus 属のタイプ種。
週間アニマルライフ (1973) pp. 3982-3983 のワタリガラスの項目 (浦本) によれば、ひなが孵化してしばらくすると巣を離れて別のところで眠るようになることが古くから知られていて、ドイツでは子供の面倒を見ない母親のことを Rabenmutter と呼ぶとのこと。
辞書を確認しておくとドイツ語 Rabe (単数形) はカラス一般を指すが英語の raven に対応するとのことで、無慈悲なものの代名詞のように扱われていた。Rabenart に無慈悲な両親の仕打、Rabeneltern に無慈悲な親 (カラスが自分のひなを巣から捨てることから)、父親の方は Rabenvater と呼ぶなど、これら訳語と解説があった。
wikipedia ドイツ語版によれば Rabenmutter の用例は 1350 年、Rabeneltern は 1433 年にすでにあったとのこと。意味の転用も行われ、ドイツの詩人で有名なハインリヒ・ハイネ (Heinrich Heine 1797-1856) は我が祖国を指して Wir, ich meine Deutschland, die alte Rabenmutter と述べたとのこと (ハイネの経歴参照)。
[カラスのロシア語名]
ハシボソガラスのようなカラスは vorona (ヴァローナと読む)、ワタリガラスは voron (ヴォーランと読む) で、複数形にすると同じ綴り vorony になる。これは文脈では区別できないので (ロシア語はアクセント記号は通常使わないが) アクセント記号を付けるかアクセント母音を大文字にしてどちらか区別されていることもしばしばである。
カラス同士なので機械翻訳でややこしいことにはならないが、ワタリガラスのつもりで書かれているものを普通のカラスと思ってしまう可能性がある。
カラス類全般を指す時は複数形の後アクセント (ハシボソガラス類) を用いる。
△ スズメ目 PASSERIFORMES キクイタダキ科 REGULIDAE ▽
-
キクイタダキ
- 学名:Regulus regulus (レーグルス レーグルス) 小国の王
- 属名:regulus (m) 小国の王、首長、王子
- 種小名:regulus (トートニム)
- 英名:Goldcrest
- 備考:
regulus は冒頭が長母音でアクセントもここにある (レーグルス)。
ラテン語 regulus にはミソサザイの意味もある (#ミソサザイ参照)。
王 rex の単語も e は長母音。"レックス" は英語読み。
ユーラシアに広く分布。14 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は japonensis とされ、この亜種が大陸東部まで分布する。
Regulus (レグルス) はしし座の1等星の名前でも有名。天文では「小さな王」と解されることが多く、1等星の中では最も暗い星であることからふさわしい名前になっている。日本の亜種は japonensis とされ、日本以外に朝鮮半島、中国東部、ロシア極東からサハリンに分布する。世界的には多数の亜種がある。
japonensis の記載時学名は Regulus japonensis Blakiston, 1862 (原記載) 基産地 Hakodadi, Yesso (= Hakodate, Hokkaido, Japan) (Avibase による)。
ヨーロッパのもの (当時の学名で Regulus auricapillus。下記参照) とはわずかに違う (ほとんど違わないが目と顔がやや白っぽく覆われているとのこと) ので新種となっているが、Blakiston (1862) は Bonaparte の学名としている。Bonaparte のものが文献に現れないため (?) Blakiston のものが原記載となっているのだろうか。どちらにしてもそれほど意味のある記載ではなさそう。
ヒマラヤで Reg[ulus]. himalayensis Bonaparte, 1856 (原記載) があり、もしアジア東部地域が統合された亜種概念となるならばこちらの記載の方が早く、この亜種名が使われる可能性がある。
ルクセンブルクの国鳥でヨーロッパ最小の鳥がふさわしいと選ばれたとのこと。また "小国の王" の意味は大変ふさわしいとのこと (10 fun facts about Luxembourg you (maybe) didn't know の情報より。1960 年に東京で行われた ICBP 総会で各国が国鳥を決めるべきとされたのが経緯とのこと)。
原記載 ここでは Motacilla Regulus Linnaeus, 1758 が記載時学名 (セキレイに分類していたことがわかる)。
属名の Regulus は種小名から昇格と思ったのだが、(Fauna Svecica) を見ると古くから使われていた属名で、古くは Regulus cristatus (冠のある Regulus) などの学名があったこともわかる。
これらは規約により有効な学名ではないので、Regulus 属は Cuvier (1800) が導入した属名となる。
当時はトートニムが積極的に避けられており、属名変更に伴って Regulus vulgaris Stephens, 1817 (参考) (普通のキクイタダキの意味)、
Regulus auricapillus Selby, 1831 [=1825] (参考 (耳と頭部に特徴があるキクイタダキの意味) や Regulus cristatus Vieillot (冠のあるキクイタダキの意味) が使われていた (#ノスリの備考参照)。
学名に対応する kinglet の英名はキクイタダキ科 Regulidae を指して使われるが、通常使われる英名に kinglet の含まれる鳥は2種のみ。
OED によれば Goldcrest の用例は意外に新しく 1819 年。以前は gold-crested wren (1754 年初出) や Golden Crested Wren (1761 年初出) と呼ばれていたとのことで近年でも別名として使われていた。
北海道や本州のやや高地以外は冬鳥として観察されることが普通だが、さえずりを知っておくとそれほど高地でなくても繁殖個体がいることに気づきやすい。ヨーロッパではごく普通の鳥で、声もよく知られている。
ヨーロッパには同属のマミジロキクイタダキ Regulus ignicapilla (英名 Firecrest) がほぼ同じように分布している。台湾の高地には類似のニイタカキクイタダキ Regulus goodfellowi (英名 Flamecrest または Taiwan Firecrest) が分布している。英名の印象が類似しているので混同に注意。
...と書いたが混同するのは自分ぐらいかと思っていた。なんと Birder 2021年5月号 p. 23 のキクイタダキのキャプション英名が Madeira Firecrest となっていた (!)。
ニイタカキクイタダキはいかにも日本式名称だが、中国語では台湾戴菊または火冠戴菊(鳥)。
中国名戴菊だが中国名と和名のどちらが先かは不明とのこと [福井・チャン (2003) Birder 17(8): 68-69]。
「動物の世界」2版 9 (日本メール・オーダー 1986) pp. 1189-1190 (浦本・樋口) にキクイタダキが渡り中のコミミズクの背中に乗ってヒッチハイクしたのが発見されたとあるが出典は不明。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ツリスガラ科 REMIZIDAE ▽
-
ツリスガラ (分割された)
- 第8版学名:Remiz consobrinus (レミズ コンソブリーヌス) (ニシツリスガラの) いとこのツリスガラ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Remiz pendulinus (レミズ ペンドゥリーヌス) ぶらさがるツリスガラ(チューの鳴き声由来か?)
- 第7版亜種学名:Remiz pendulinus consobrinus (レミズ ペンドゥリーヌス コンソブリーヌス) (ニシツリスガラの) いとこのぶらさがるツリスガラ(チューの鳴き声由来か?)
- 属名:remiz (外) ポーランド語でツリスガラ
- 第8版種小名:consobrinus いとこ < cum 一緒に sobrinus 母方のいとこ。ニシツリスガラのいとこの意味。
- 第7版種小名:pendulinus (adj) ぶらさがっているような (pendulus (adj) ぶらさがった -inus (接尾辞) 〜に関連する)
- 第7版亜種小名:consobrinus いとこ < cum 一緒に sobrinus 母方のいとこ。ニシツリスガラのいとこの意味。
- 英名:[Penduline Tit 分割前の名称], IOC: Chinese Penduline Tit
- 備考:
外来語だが、ポーランド語であれば remiz には長母音は含まれず冒頭にアクセント。アクセント位置はラテン語規則とも合うので "レミズ" と読めばよいだろう (なおポーランド語の場合は語末が無声音となる)。
consobrinus は i が長母音でアクセントもここにある。(sobrinus の長母音由来とのこと)。
pendulinus は pendulus は短母音のみの単語だが、-inus の接尾辞由来で長音でアクセントもある (ペンドゥリーヌス)。
ロシア語でも remez で、語源は「職人」「技のある者」(remeslo, remeslennik) で、特有の芸術的巣造り行動を意味するものだろうと記載がある (ロシア極東動物の語源辞典 Kolyada et al. 2016)。
ポーランド語 語源資料 によればポーランド語からロシア語に入ったと説明されている。
ドイツ語 Riethmeise からの借用も考えられるが他の鳥の名がドイツ語からほとんど入っていないので考えにくく、スラブ独自の名前の可能性の方が高い。スラブ語 remzati = 英語 chirp あるいは rzemiesniczk- (ロシア語の職人に対応) が考えられるが、rze- が re- に変化するのは考えくいにとのこと。
The Key to Scientific Names ではポーランド語の職人 rzemieslnik を語源に採用しており、ポーランド語語源資料と見解が多少異なる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で亜種から独立種 Remiz consobrinus [consobrinus いとこ < cum 一緒に sobrinus 母方のいとこ; ヨーロッパのニシツリスガラ Remiz pendulinus (英名 Eurasian Penduline-Tit) の東洋のいとこと考えられた] に昇格。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。海外のリストでも同様。
かっこ内の英名はヨーロッパと同種とされた時代のもので学名に対応している。
東洋の方の種の英名は Chinese Penduline Tit で中国から朝鮮半島、日本では西日本を中心に分布する。単形種。Remiz 属のタイプ種はニシツリスガラ。
属の記載は Jarocki (1819) によるもので当時は現在の Remiz 属が記載される前の Remiz pendulinus のみを含むもの。現代の分類概念ではニシツリスガラのみに対応する。
ツリスガラの記載時学名 Aegithalus consobrinus Swinhoe, 1870 (原記載)。
シラガツリスガラ、記載時学名 Aegithalus coronatus Severtsov, 1873 に近縁とされ Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2), 4th edition (incl. corrigenda vol.1-2) では同種扱い。coronatus の方の記載が遅かったため日本のリストにこの学名は現れなかった。
第8版の亜種の扱いも H&M4 とは異なって coronatus を別種扱いとしていることがわかる。
[属名の変遷]
ニシツリスガラの属名変遷も複雑で、記載時は Motacilla pendulinus Linnaeus, 1758 とセキレイの仲間 (尾が多少似ている?)。
その後 Parus pendulinus も用いられたが Cuvier が Remiz 属を導入したことが Jarocki (1819) でポーランド語で記載され、これが属の記載となっている (The Key to Scientific Names)。この記載によれば Cuvier は他種も含んでいたらしいが Jarocki は1種しか知らないのでそれのみを含めたとのこと。
あくまで Jarocki (1819) による伝聞調の記述で Cuvier が実際に何と書いていたのかは現在ではわからないが、ポーランド語とフランス語を用いて記述したとある。由来をポーランド語とするのはこの記述に基づくものであろう。
Remiz 属の現代の他種はまだ記載されていない時代なので Cuvier は現在はニシツリスガラの亜種レベルでシノニムとされるものを含めていたのだろう。
ツリスガラやシラガツリスガラの記載に用いられた属 Aegithalus は Boie (1822) がニシツリスガラに用いたものだが、同じ属名がヒゲガラ (Billberg 1828) やキバラアフリカツリスガラ 現代の学名では Anthoscopus minutus にも用いられる (Swainson 1837) など複数の分類群に付けられていた。
ツリスガラ類については先取権のある Remiz が用いられるようになった (The Key to Scientific Names の Aegithalus の項目から)。アフリカツリスガラ類も 1844 年に付けられた別の属名に変更となった。
Aegithalus は見たことのある属名と感じる人が多いだろうが、1文字違いの Aegithalos Hermann, 1804 は有効でエナガ属である。
古い時代には Aegithalos と Aegithalus は同じものとされてより早く使われたエナガ属が有効になったものかも知れない。Remiz Jarocki, 1819 の方が Aegithalus Boie, 1822 より早いのでこの問題は表面には現れず、Remiz をツリスガラ属とすれば問題なくなった。
ツリスガラ類もエナガ属に似た特徴を捉えて、しかしエナガ属には含まれない形で命名されていた時代があった。
ツリスガラの属名確定経緯はもう一段複雑な部分があり、外来語の文法性にかかわる問題だった。
AOU-NACC Proposals 2019 によればポーランド語の remiz は男性名詞で Remiz は男性の属名になる。
同じ語源で Remiza Stejneger, 1886 と女性形にした属名が独立に提唱されていた (Remiza consobrina と女性形で用いていた。資料) とのこと。
しかし性を変更するラテン語化は適切でないとして Prazak が Remizus Prazak, 1897 に変更したとのこと (資料)。
現在の Remiz Jarocki, 1819 の命名は 1910 年代後半に Mathews によって "再発見" された (資料) もので、Stejneger の時代には忘れ去られていたとのこと。
そのためしばらくの期間は Remiza や訂正された Remizus の属名が使われれていた。
The Key to Scientific Name の Remizus の項目などにはこの情報を受けた経緯がすでに反映されている。
Stejneger (1886) ではポーランド語由来としているが、フランス語など他言語でも用いられるとの記述がある。フランス語では Mesange remiz のように使われる (上記 BirdForum 情報より) ので文法性は女性に見えるとのこと。Stejneger の記載では由来となる言語が明示されているので問題はない (さらにややこしいことにポーランド語に remiza の名詞があるが、これは主格ではツリスガラを指さないので問題となる点はない)。
Jarocki の記載は伝聞調のもので、Cuvier がポーランド語とフランス語で記述したとあるので若干不明確。Jarocki がポーランド語で記述しているのでポーランド語由来と判定された模様。
Jarocki (1819) が記載した時代は。1795 年第三次ポーランド分割に引き続くころ (独立国家としてのポーランドは 123 年にわたり地上から姿を消すこととなった。wikipedia 日本語版より)。
ポーランド語の使用は認められていたが、Jarocki の記載が長く忘れられていたのはこのような背景もあったのかも。
1831 年のワルシャワの戦い (1830 年 11 月蜂起) に先立つ時代で、ショパンの有名な「革命のエチュード」 (1831 年ごろ) はこの蜂起失敗に影響を受けたとも言われる。ショパンの練習曲集 作品 10 を締めくくる曲で中間部の和声変化が実にすばらしい曲である。
この曲を取り上げたら練習曲集 作品 25 の終曲も挙げておきたいし、24の前奏曲作品 28 の終曲も取り上げたい。「革命のエチュード」にも似た性格の曲である。いずれも時期的にも近くバラード第1番の終わり方も、ショパンの内面に共通のものを感じてしまう (いずれも名曲として受け継がれている所以だろう)。
ポーランド語由来の珍しい属名から当時の情勢や芸術にも思いを馳せてみたい。
Prazak が提唱した際の属のドイツ語名は Beutelmeise で Beutel は小袋、たばこ入れ、財布など。Meise はカラ類のこと。以下の茂田 (1995) も参照。
亜種が記載されたこともあり、Remiza consobrinus japonicus Clark, 1907 (参考) 属は Remiza だったかあるいは Remiz だったかこの記述からははっきりしない。
タイプ標本もなかったらしく、基産地も学名から想像するほどはっきりしない。長崎からの標本とされるが朝鮮半島産の標本しか持っていなかったとも書かれている。
Remiza consobrinus suffusus Clark, 1907 (参考) は基産地釜山。
いずれも現在は基亜種のシノニムとされる。
[足を手のように使うツリスガラ類]
ツリスガラ科の特徴として、片足で物をつかみ、たぐり寄せたり嘴に運ぶことのできる行動がスズメ目で最初に記載された [Loehrl (1981) Verhaltensmerkmale der Familie Remizidae (Beutelmeisen)]。情報は茂田 (1995) Birder 9(1): 46-52 による。この行動はその後他の種類にも見つかっている (#オウチュウと#ハチクマの備考参照)。
足を器用に使う鳥の論文(2023)を著した Gutierrez-Ibanez に確認したところ、ツリスガラやカラ類の行動は真の意味の「足で嘴に餌を運ぶ行動」と言えないのではないかとの見解であった。
Taylor (1971) A Breeding Biology Study of the Verdin, Auriparus flaviceps (Sundevall) in Arizona アメリカツリスガラ Auriparus flaviceps 英名 Verdin で観察されるものと同等のものではないかとのこと。(あるいは巣付近でしか見られないのかも知れないが) ツリスガラを観察する際は注意していただきたい。
Loehrl (1981) の該当部分の記述は次のようなものである「スズメ目で記述されていない行動を見つけた。それは葉の新芽を嘴でつまみ、片足でとまりながらもう片方の足でそれをつかみ、嘴で葉を取り除くというもの。
飼育下でも同じ行動が見られ、さらに過去にアメリカツリスガラで知られているように巻き上がった葉の周りを回って葉と枝をしっかり掴みながら葉を編む行動が見られた。
E. Schuez (1979) によるアフリカツリスガラ Anthoscopus caroli Grey Penduline Tit の写真を偶然見つけた。片足で巣につかまりながらもう片方の足で巣の入口を開けた。嘴は餌をくわえているのでこの目的には使えない。足で物を掴む能力がなければ巣を閉じる方法は進化し得なかったであろう」。
「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 177 にキバラアフリカツリスガラ Anthoscopus minutus Cape Penduline Tit が巣の「ふた」を足で開ける写真が出ていた。
茂田 (1995) によればアフリカツリスガラ属 Anthoscopus の古巣が財布や物入れに使われるそうである。茂田 (1995) によればツリスガラのドイツ名 Beutelmeise がこれに対応するとのことだが、Beutel には小袋などの意味の他に動物学で育児嚢の意味もあり、財布や物入れに使うこととの直接の関係はないかも知れない (Meise はカラのこと)。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 79 p. 8 によればアフリカツリスガラ Anthoscopus caroli African Penduline Tit では巣の入り口が扉のようになっていて内から引くか外から押せば開く。ひなは生後数日で内から引けば開くことを覚える。ヘビは開けることができないとのこと。
[ツリスガラ類の分布拡大]
ヨーロッパ (新分類では別種となる) で分布拡大が指摘されている: Valera et al. (1990) The situation of penduline tit (Remiz pendulins) in southern Europe: A new stage of its expansion、
Amezian et al. (2011) On regular wintering of Eurasian Penduline Tits Remiz pendulinus in northern Morocco。
日本でも少なくとも最近まで分布拡大があったが類似の現象なのかも知れない。
[スズメ小目 Passerida の系統分類]
Boyd の分類に従ってスズメ小目 Passerida の系統を紹介しておく。
対応するカラス小目 Corvida は #アサクラサンショウクイの備考を参照。
科名があるものは山崎剛史・亀谷辰朗 (2020) 鳥類の目と科の新しい和名 (2) 鳴禽類 を使用。推測できる名称は ( ) に入れてある。 上科の名称は科名から推測。科の順序は日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)とおおまかに同じだが多少入れ替わって部分がある。
系統番号は独自に振ったもの。
上科の後の [OHC] 番号は Kuhl et al. (2021) による oscine higher-level clades (OHCs) で相当する番号。この番号が同じで上科に分かれているものは clade 内部でさらに分岐していることを示す。我々に関係するところでは [OHC9] と [OHC10] (キクイタダキ上科から) の系統が別になると考えるとよいだろう。
あまりにも巨大なグループで Boyd の該当ページも見つけにくいので対応する場所にリンクを張っておく。
日本産種と関連の薄いグループの亜科・族分類は省略した。緑字は日本で記録のある種を含むこの表示での最下位階層である。
スズメ小目 Passerida (Basal Passerida)
パプアハナドリ上科 Melanocharitoidea [OHC7]
パプアハナドリ科 Melanocharitidae: Berrypeckers & Longbills
フウチョウモドキ上科? Cnemophiloidea [OHC6]
フウチョウモドキ科? Cnemophilidae: Satinbirds (科扱いでない場合もある)
ホオダレムクドリ上科? Callaeoidea [OHC8]
シロツノミツスイ科 Notiomystidae: Stitchbird
ホオダレムクドリ科 Callaeidae: New Zealand Wattlebirds
サンショクヒタキ科 Petroicidae: Australasian Robins
ハゲチメドリ上科? Picathartoidea [OHC8]
ハゲチメドリ科 Picathartidae: Rockfowl
アカイワトビヒタキ科 Chaetopidae: Rockjumpers
クイナチメドリ科 Eupetidae: Rail-babbler
シジュウカラ上科 Paroidea (Paroidea and Sylvioidea I) [OHC9]
センニョヒタキ科 Stenostiridae: Fairy Flycatchers
ミドリモズヒタキ科 Hyliotidae: Hyliotas
ツリスガラ科 Remizidae: Penduline-Tits
シジュウカラ科 Paridae: Tits, Chickadees, Titmice
ウグイス上科? Sylvioidea (Paroidea and Sylvioidea I) [OHC9]
(系統 1)
ムシクイヒヨドリ科 Nicatoridae: Nicators
ヒゲガラ科 Panuridae: Bearded Reedling
ヒバリ科 Alaudidae: Larks
(系統 2)
ハシナガムシクイ科 Macrosphenidae: Crombecs, African Warblers
(系統 3a)
ヒメサザイチメドリ科 Pnoepygidae: Cupwings
ヨシキリ科 Acrocephalidae: Reed-Warblers (#オオヨシキリの備考)
ミズベマネシツグミ科 Donacobiidae: Donacobius
マダガスカルムシクイ科 Bernieridae: Malagasy Warblers
センニュウ科 Locustellidae: Grassbirds
セッカ科 Cisticolidae: Cisticolas
ニセムシクイチメドリ亜科? Neomixinae
ヒメムシクイ亜科? Eremomelinae
ウチワドリ亜科? Priniinae
セッカ亜科 Cisticolinae
(系統 3b-1) (Sylvioidea II)
(ツバメ科 Hirundinidae: Martins, Swallows)
カワツバメ亜科? Pseudochelidoninae: River Martins (通常はツバメ科だが系統が分離し、科相当の可能性あり)
(系統 3b-2)
ツバメ科 Hirundinidae: Martins, Swallows
ツバメ亜科 Hirundininae: Martins, Swallows
ショウドウツバメ族 Prognini
クロツバメ族? Psalidoprocnini
ツバメ族 Hirundinini
(系統 3b-3)
ヒヨドリ科 Pycnonotidae: Bulbuls
ヒゲヒヨドリ亜科? Crinigerinae: Greenbuls
ヒヨドリ亜科 Pycnonotinae: Bulbuls
(系統 3b-4)
コバシミドリムシクイ科? Hyliidae: Hylias (科扱いでない場合もある)
エナガ科 Aegithalidae: Long-tailed Tits
ウグイス科 Cettiidae: Cettiid Warblers
ヒメヒタキ亜科? Erythrocercinae: Bristle-flycatchers
スナチムシクイ亜科 Scotocercinae: Streaked Scrub Warbler
ウグイス亜科 Cettiinae: Cettiid Warblers
ムシクイ科 Phylloscopidae: Leaf-Warblers
ズグロムシクイ科 Sylviidae: Sylviid Warblers (ここから Paroidea and Sylvioidea III)
ダルマエナガ科? Paradoxornithidae: Parrotbills, Fulvettas
メジロ科 Zosteropidae: White-eyes
マルハシ科 Timaliidae: Babblers, Scimitar-Babblers
(ジチメドリ科) Pellorneidae: Ground Babblers
(チメドリ科) Alcippeidae: Alcippe Fulvettas (科扱いでない場合もある)
ソウシチョウ科 Leiothrichidae: Laughingthrushes
(ここで系統が分かれる)
キクイタダキ上科 Reguloidea (Reguloidea and Bombycilloidea) [OHC10A]
キクイタダキ科 Regulidae: Kinglets
レンジャク上科 Bombycilloidea (Reguloidea and Bombycilloidea) [OHC10A]
シロボシサザイ科 Elachuridae: Elachura
フサミツスイ科 Mohoidae: Hawaiian Honeyeaters
レンジャクモドキ科 Ptiliogonatidae: Silky-flycatchers
ヤシドリ科 Dulidae: Palmchat
ミミグロレンジャクモドキ科 Hypocoliidae: Hypocolius and Hylocitrea
レンジャク科 Bombycillidae: Waxwings
キバシリ上科? Certhioidea (Certhioidea) [OHC10A]
ゴジュウカラ科 Sittidae: Nuthatches
カベバシリ科 Tichodromidae: Wallcreeper
ホシキバシリ科 Salpornithidae: Spotted Creepers (IOC 14.2 で科に昇格 2024.8.6)
キバシリ科 Certhiidae: Treecreepers
(キバシリ亜科 Certhiinae: Treecreepers ホシキバシリ科 の分離により亜科は消滅と思われる)
ブユムシクイ科 Polioptilidae: Gnatcatchers, Gnatwrens
ミソサザイ科 Troglodytidae: Wrens
イワミソサザイ亜科? Salpinctinae: Geophilous Wrens (Boyd 独自)
オナガミソサザイ亜科? Odontorchilinae: Tooth-billed Wrens (Boyd 独自)
ミソサザイ亜科 Troglodytinae: Typical Wrens
ヒタキ上科? Muscicapoidea [OHC10A]
(系統 1: ムクドリ類) (Muscicapoidea I)
ウシツツキ科 Buphagidae: Oxpeckers
マネシツグミ科 Mimidae: Mockingbirds, Thrashers
ムクドリ科 Sturnidae: Starlings, Mynas
キュウカンチョウ亜科? Graculinae: South Asian/Pacific Starlings
キバシリモドキ族? Rhabdornithini: Philippine Creeper
キュウカンチョウ族? Graculini: South Asian & Pacific Starlings and Mynas
ムクドリ亜科 Sturninae: African/Eurasian Starlings
(系統 2: ツグミ・ヒタキ類) (Muscicapoidea II)
カワガラス科 Cinclidae: Dippers
ツグミ科 Turdidae: Thrushes
ヒタキ科 Muscicapidae: Old World Flycatchers, Chats
サメビタキ亜科? Muscicapinae
ムジヒタキ族? Alethini: True Alethes (Boyd 独自)
シキチョウ族? Copsychini: Scrub-Robins, Magpie-Robins, Shama
サメビタキ族? Muscicapini: Old World Flycatchers
オオルリ (アオヒタキ) 亜科? Niltavinae: Blue Flycatchers
ヨーロッパコマドリ/ツグミヒタキ亜科? Cossyphinae: African Robins
ノビタキ亜科? Saxicolinae: Robins, Chats, Wheatears
(ここで系統が分かれる)
スズメ上科 Passeroidea [OHC10B]
(以下 Basal Passeroidea スズメ上科のうち古い分岐)
オナガミツスイ科 Promeropidae: Sugarbirds
ノドボシツグミヒタキ科 Modulatricidae: Spot-throat & allies
ハナドリ科 Dicaeidae: Flowerpeckers
タイヨウチョウ科 Nectariniidae: Sunbirds
ルリコノハドリ科 Irenidae: Fairy Bluebirds
コノハドリ科 Chloropseidae: Leafbirds
(ここから Core Passeroidea スズメ上科の中心部分。冒頭2科の後いくつかの clade に分かれる)
オリーブアメリカムシクイ科 Peucedramidae: Olive Warbler
イワヒバリ科 Prunellidae: Accentors
(系統 1 Estrildid カエデチョウ clade)
バライロマシコ科 Urocynchramidae: Przevalski's Finch
ハタオリドリ科 Ploceidae: Weavers
テンニンチョウ科 Viduidae: Indigobirds, Whydahs
カエデチョウ科 Estrildidae: Estrildid Finches
キンパラ亜科? Lonchurinae
カエデチョウ亜科 Estrildinae
(系統 2 Passerid スズメ clade) (Core Passeroidea II)
スズメ科 Passeridae: Old World Sparrows, Snowfinches
ニッケイメジロ亜科 Hypocryptadiinae: Cinnamon Ibon
ウスイロイワスズメ亜科 Carpospizinae: Pale Rockfinch (Boyd 独自)
スズメ亜科 Passerinae: Old World Sparrows, Snowfinches
(以降を系統 3 "Nine-primaried Oscines" その1 注参照)
セキレイ科 Motacillidae: Wagtails, Longclaws & Pipits
(以降を "Nine-primaried Oscines" その2 注参照)
アトリ科 Fringillidae: Finches, Euphonias
アトリ亜科 Fringillinae: Chaffinches
フウキンチョウ亜科? Euphoniinae: Euphonias, Chlorophonias
マヒワ亜科 Carduelinae
シメ族 Coccothraustini: Grosbeak Finches (イカルもこのグループ)
ウソ族 Pyrrhulini: Bullfinches and Arid-zone Finches
オオマシコ族? Carpodacini: Rosefinches
ハワイミツスイ族? Drepanidini
マヒワ族 Carduelini: Canaries, Siskins and allies
(系統 4) epifamily? (外科: 上科と科の間) ホオジロ外科? Icteroidae (Emberizoidae とも呼ばれるが先取権は前者とのこと) (Core Passeroidea III)
ツメナガホオジロ科 Calcariidae: Longspurs, Snow Buntings
バラムネフウキンチョウ科 Rhodinocichlidae: Rosy Thrush-Tanager (Boyd 分類による)
(系統 4a-1: 以下のグループが1系統 Buntings and Sparrows)
ホオジロ科 Emberizidae: Buntings
キンムネホオジロ亜科? "Fringillariinae" (Boyd 独自)
ホオジロ亜科 Emberizinae
チャキンチョウ/レンジャクノジコ亜科 "Melophinae" (Boyd 独自)
オオジュリン亜科? "Schoeniclinae" (Boyd 独自)
ヤブシトド/アメリカホオジロ科? Arremonidae: American Sparrows (Boyd による再編成)
(系統 4a-2: 以下 Blackbird / Warbler Group Core Passeroidea IV)
ヤシフウキンチョウ科? Phaenicophilidae: Palm-Tanager and allies
ムクドリモドキ科 Icteridae: New World Blackbirds
アメリカムシクイ科 Parulidae: Wood-Warblers
(系統 4a-3: 以下 Thraupid Group Core Passeroidea V)
ヨゴレフウキンチョウ科? Mitrospingidae: Mitrospingus and allies (科扱いでない場合もある)
ショウジョウコウカンチョウ科 Cardinalidae: Cardinals, Grosbeaks
フウキンチョウ科 Thraupidae: Tanagers
膨大な種を抱えたグループであり、Boyd も分類に苦労している。属分類はだいたい決まるとしても分子系統分類による中間の階層は必ずしも分類学で想定された階層の数に合わないため、"階層が足りない" とも記されている。特にスズメ上科 Passeroidea のここで示す系統 4 以下はさらに系統があって科をまとめる中間的な階層名に適切なものがないため Group としか呼べない状況になっている。分類学者によっても階層の扱いは異なる。
仮に与えてある和名 (? 付き) は基本的にタイプ属に基づく。属で決着しない場合はタイプ種も用いている。タイプ属内の種が共通和名部分を持っている場合は共通部分も用いている。
ヤブシトド科?、ヤシフウキンチョウ科? のように種和名が長く、タイプ属内の種の和名と英名総称が整合する場合も採用した場合がある。
ウグイス上科? Sylvioidea には非常に多くの馴染みのグループが含まれるため名称は悩ましい。由来となるズグロムシクイ科 Sylviidae は日本でも記録があるためこの名前でも構わないと思われるが、Sylviidae に似た外見、ウグイス科の命名経緯や圧倒的知名度からウグイス上科としてみた。ヨーロッパと日本の普通種の異なりが現れる部分である。
(ジチメドリ科) Pellorneidae、(チメドリ科) Alcippeidae は山崎剛史・亀谷辰朗 (2020) と分類概念が異なり、種チメドリがどちらに含まれるかで名称の扱いが異なる。
山崎剛史・亀谷辰朗 (2020) では両者を含んだ Pellorneidae をチメドリ科としている。分割する場合はタイプ属 Pellorneum の和名に従い、山崎剛史・亀谷辰朗 (2020) の選択肢にも含まれているジチメドリ属とするのが適切であろう。
ヒタキ上科? Muscicapoidea の名称は由来となる科およびかつて現在のツグミ科を含めた時代のヒタキ科の名称に従った。(新) ヒタキ科の分類は Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考) も参照。Boyd の概念と多少違う部分もあるが我々に通常関係する部分はほぼ同じとみてよいだろう。
ヨーロッパコマドリ/ツグミヒタキ亜科? Cossyphinae は日本産種を用いれば前者、タイプ属に共通の和名を用いれば後者になる。英語概念とは後者の方が整合性がよい。
ソウシチョウ科はタイプ属を優先すればソウシチョウ科。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではガビチョウ科で和名検討中あったが最終的にソウシチョウ科となった。
キュウカンチョウ族? Graculini には検討種が存在し、Aplonis カラスモドキ属の和名はそこそこ知られている。亜科・族のタイプ属に含まれ、知名度も高いキュウカンチョウ Gracula religiosa を採用しておく。外来種の Gracupica クビワムクドリ属は名称が似ているが属は異なる。
フウキンチョウ亜科? Euphoniinae はタイプ属 Euphonia からのものだが、イカルの属名 Eophona と非常に似ているので注記しておく。
オオマシコ族? Carpodacini も全体を代表する簡単な名前の方が良いかも知れないがタイプ属の和名からはこの名前になる。
ホオジロ類は Boyd の細分類 (#アオジの備考参照) に基づくので IOC や現在の日本の分類とは属の扱いが異なる。外科はあまり使われない階層だが "がいか" と読むのではないかと想像している。
スズメ上科の名称があってホオジロ上科とは呼べないが、何か名前は欲しくてやむを得ない使い方になっているのだろう。つまりこのグループが新世界のものを含めて大きすぎるため。
チャキンチョウ/レンジャクノジコ亜科 "Melophinae" はタイプ属 Melophus はレンジャクノジコの方だが検討種となる見込み。
Granativora属は2種 (チャキンチョウ、ズグロチャキンチョウ) とも記録があり、この亜科は3種とも日本で記録ないし検討種となる。記録種を優先すればチャキンチョウまたはズグロチャキンチョウだが短い方を採用した。
ヤブシトド科? Arremonidae は Boyd によって再編成された名称で、日本で使われている科名ではゴマフスズメ科 (和名検討中だったが確定した) Passerellidae はその中の族 Passerellini となっている。
Arremonidae の和名は悩ましいが族 Arremonini: Scrub Sparrows の英名および一部の種に共通で使われる和名をもとにしてみた。
概念的にはアメリカホオジロ科のような名前でもよさそうに見える。分類そのものもまだ流動的要素があるようなのでここでは両者を仮に与えておいた。
少しでもわかりやすく理解するためには、日本産全科を網羅するのではなく (ここでは簡単化のため ? は外しておく)、
シジュウカラ上科、ウグイス上科、ヒタキ上科、スズメ上科にこの順に大別されると理解するとよさそうである。ウグイス上科、ヒタキ上科には多くのグループが含まれるので何が含まれているかはそれぞれ把握が必要だがそこそこ雰囲気が似ている部分もあるのでわかる部分もあると思える。
過去の分類が染み付いていると誤解の原因になりそうなのが、エナガ科はシジュウカラ上科でなくウグイス上科。
ツバメやヒヨドリもスズメ目の分類の最初の方ではなくウグイス上科に入る。ヒヨドリとサンショウクイを並べて覚えておくと誤りのもとになる。カワガラスとミソサザイも同様。
わかりやすく言えば、身近な鳥でよく一緒に扱われるスズメ、ヒヨドリ、ムクドリは全部別系統になる。日本鳥類目録第7版以降の新しい分類を採用した図鑑ではすでに大きく離れている。昔の探鳥会の鳥合わせだとだいたいスズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラスで終わったわけだが...。
これらに含まれなかった単独系統のグループではキクイタダキはシジュウカラ上科からは遠い。
レンジャクは形はムクドリに似ているが系統はそれほど近くない。
ゴジュウカラ・キバシリ・ミソサザイがまとまるのは形態や行動から理解しやすい。ゴジュウカラの名前だがシジュウカラ上科からは遠いことは意識しておけば比較的わかりやすい。
ウグイス上科にはヒバリ、ヨシキリ、ツバメ、ヒヨドリ、{エナガ + ウグイス + ムシクイ + メジロ} が含まれ、スズメ上科はスズメ、セキレイ、アトリ、ホオジロ の3つに分けて理解する。
ヒタキ科内部の系統は過去の分類とかなり概念になっている。#ヨーロッパコマドリの備考参照。例えばキビタキ類などはサメビタキ亜科? Muscicapinae ではなくノビタキ亜科? Saxicolinae の方に入る。ノビタキ亜科? Saxicolinae にはずいぶんいろいろなものが含まれるので上記備考を参照いただきたい。
そのため上位分類の名称を ヒタキ亜科 Muscicapinae としなかった。Muscicap- で始まる名称の上位分類で階層によって和名が違うものが生じている。
ヒタキ科があるのにヒタキ亜科はない奇妙な状況になるが、従来「ヒタキ」とされていたものが複数の系統に分離され、別亜科になったものが多いのでこの方がよさそうに思える。Muscicapini: Old World Flycatchers の英語概念についても同様。我々の想像する "旧世界ヒタキ" でもこの分類に入らないものが多い。
現代の分子系統樹でのツグミ科とヒタキ科の関係は [#鳥類系統樹2024] の extended data fig. 3 を見ていただくとわかりやすいだろう。
ツグミ科をヒタキ科に内包してヒタキ科ツグミ亜科でも構わない (ただし従来のいわゆる "小型ツグミ類" はここには含まれない) が、分岐年代が 1500 万年ぐらいとそれなりに深い分岐なので科相当が適切となったものだろう。
カワガラス科とツグミ科をまとめてしまうと単系統をなさないのでこれらは分離する必要がある。分岐年代のさほど違わないツグミ科も別科とするのが適切となる。
もしツグミ科をヒタキ科に内包してしまうと、この分岐年代より若い分岐の例えばムクドリ科とマネシツグミ科、ウシツツキ科が生じるので、科の基準の統一性を保つためにはツグミ科を分けるべきとなる。
主に新世界のアトリ科以降との関係はさらに深刻で、フウキンチョウ科とショウジョウコウカンチョウ科の分離などはさらに若い。これらの名称は広く定着していて改めて変えるまでのこともないので、スズメ目では分岐年代が 1000 万年ぐらいを超えるものはだいたい科に分けてよいのではないか、のような合意が得られてきたのだろう。
参考までにタカ科の分岐年代は 3000 万年以上前と見積もられており、すべてのグループを一律に分岐年代で分けるのはふさわしくない。1000 万年ぐらいで合意が得られているのはスズメ目の方が世代が短く進化速度が速いことも表れている。
この問題はやはりまた議論されていて AOU-NACC Proposals 2025 (BirdForum 2025.5) 参照。
主に新世界のアトリ科以降をどのように扱うか再検討されている模様。やはり科としては分岐年代が若すぎることが問題となっている。分岐年代以外に判断基準はないのか、などの疑問も出ている。
実際にも「実用的な大きさになる程度に区分する」程度しかないのではないだろうか。現代ならば類似系統の間で分岐年代基準があまり違わない、というところだろうか。さすがにツグミ科がまたヒタキ科に含まれることはないかも知れないが...
Boyd の解説 (Cinclidae, Turdidae, and Muscicapidae) を参照すると、何でもかんでもヒタキ科に入れてしまったのは 6th edition AOU checklist (1983) などが由来のよう。Sylviinae, Muscicapinae, Monarchinae, Turdinae, Timaliinae がすべて亜科として扱われていた
(現代の分子系統樹でのツグミ科をヒタキ科に内包可能の意味とは異なる)。
かつて使われたヒタキ科ウグイス亜科のような名称はこの分類に対応する。山階芳麿 (1986) 世界鳥類和名辞典が採用していたとのことで影響力が大きかったのだろう。山崎剛史・亀谷辰朗 (2020) 鳥類の目と科の新しい和名 (2) 鳴禽類 に解説がある。
さらに遡って Hartert (1910) (#メグロの備考参照) 時代にすでに当時の "広義ヒタキ科" にまとめられていた。6th edition AOU checklist (1983) の Timaliinae のニュアンスも Hartert (1910) の記述参照。分類学の "ゴミ箱" 状態が長く続いていた。
その後徐々に分子系統解析が取り入れられ (大きなグループなので部分的な証拠にとどまっていて、少数種から構成された初期の研究では系統樹の形が現代と異なるものになっていた)、分割や移動の必要性が徐々にわかってきた経緯のよう。
日本鳥類目録改訂第7版では当時系統が遠いことがすでに判明していたウグイス科やムシクイ科は早い段階で分離されたが、ツグミ科とヒタキ科の関係は複雑で、過去の Turdinae (ツグミ亜科) に現在のツグミ科以外にいろいろなもの (Boyd の表現を用いれば old world robins, chats and wheatears) を含めるのが一般的で、これらの扱いが明らかになるまでに時間がかかったので取り残されていたのだろう。
Sibley and Monroe (1990) も DNA-DNA hybridization で分離を試みていて Muscicapinae (当時のヒタキ亜科) をヒタキ族 (Muscicapini) と robin-chat-wheatear group (Saxicolini) に分離して多少の傾向はすでに現れていたが、この中で chats (たとえばノビタキ類) とキビタキ属が近縁であることはなかなかわからなかった。
上記のスズメ小目 Passerida の系統を見ても ヒタキ上科? Muscicapoidea の中で最後に分岐した系統なので解剖学などの形態的特徴の系統的要因と環境への適応 (脚の長さなど) の分離が困難で最後まで混乱のあったグループとなったのだろう。
平岡 (2024) Birder 38(11): 31 にも簡単な解説がある。日本の鳥類目録の更新は最近では約 10 年に一度なので、ツグミ科とヒタキ科の分離が世界的な動きからかなり遅れた感じがするのはやむを得ないだろう。
"小型ツグミ類" の概念はもはや系統的には成り立たないのできっぱりと忘れてしまうか、地上生活に適応した脚の長いヒタキ、乾燥生活に適応したヒタキのように適度に区分して説明的に使わざるを得ない感じがする。
また "小型ツグミ類" の表現は日本独自のものだった可能性も考えられる気がしてきた。"A Field Guide to the Birds of Japan" (WBSJ 1982) に Small Thrushes とあって、英文補足説明があるためである。現在英文で検索しても分類概念としての用例が見当たらず、small thrushes は文字通り小さなツグミ類の一般的表現で (ハクセキレイの White Wagtail と白いセキレイ white wagtail の違いと同様)、"Small Thrushes" は英語表現と一対一対応をせず、日本語から訳出した英語でそのままでは意味が通じなかったため補足する必要があったのではないだろうか。
規模は違うが他のグループの例では従来 "イヌワシ類" と考えられていたものと "クマタカ類" と考えられていたものが混ざっていることが判明した。この場合は英名で従来の Hawk Eagle (クマタカ類相当) を Eagle と改名されたものもある (ボネリークマタカ Bonelli's Eagle)。和名には "クマタカ" があってもイヌワシ類である。
黒っぽいワシ類に比べて模様の目立つ従来の "森林性クマタカ類" の概念は系統として意味をなさなくなった (#カラフトワシ備考参照)。
それではヒタキでは何なのですが、と改めて問われると日本語の由来はやはり地鳴きと考えられるので同じような声を出す鳥をヒタキと思ってしまって別に構わないか。むしろ学術用語の Muscicapidae (はえを捕らえる) の字句よりは日本語の名称の方が一般性があるかも。
Nine-primaried Oscines について。Wallace (1874) がスズメ目の分類のために提唱したもので、スズメ目原型の初列風切 10 枚のうち最も外側の P10 が外見からほとんど見えず、9枚に見えるため名付けたもの。定義はいろいろあって9枚の "機能している" 初列風切と言われることもある。
Wallace (1874) の最初の分類では広い分類群が含まれていた (ツバメ類なども含まれた)。系統的概念として提唱されたものではないが、主に新世界のスズメ亜科を扱うには有用な概念であるため、この特徴を持つもので系統的にまとまるものが "nine-primaried oscines" としばしば呼ばれる。
Wallace (1874) の分類に従えばセキレイ科もこのグループに含まれる。
Ericson et al. (2000) Major Divisions in Oscines Revealed by Insertions in the Nuclear Gene c-myc: A Novel Gene in Avian Phylogenetics
により、c-myc 遺伝子への3アミノ酸挿入をマーカーとしてカラス小目、スズメ小目、セキレイ科以降のスズメ小目の系統関係がはっきりわかり、カラス小目とスズメ小目にこの順に分けることが適切であることがまずわかる。そしてスズメ小目の中では (このマーカーによれば) セキレイ科以降を別系統に分けるのが適切であることがわかる。
この分子遺伝学的知見と、古く分岐したもので例外的なものを除いた "nine-primaried oscines" の概念がほぼ整合することから系統的に意義のある概念として使われている。ただしどこまでを含めるかは多少の任意性があり、セキレイ科は3番めのアミノ酸にスレオニンが挿入される一方他の多くはセリンなので (例外もそこそこある) セキレイ科だけは別扱いにする理由は一応存在する。
そのようにして3アミノ酸挿入のあるグループのうち (新世界にはほとんどいない) セキレイ科を除いたものを "New World nine-primaried oscines" として分ければまとまりがよいグループとなるのでは (若干新世界からの物の見方にも思えるが) との考えになる。上記の分類表はセキレイ科を含むか除くかの2つのパターンを示してある。
狭義のグループでも含まれるグループは必ずしも新世界のものだけではないので New World は外して、nine-primaried oscines と呼ぶことも多い。
Hall (2005) Do nine-primaried passerines have nine or ten primary feathers? The evolution of a concept のように系統的にあまり有益な概念ではないとの提言もある。
積極的に使うほどの概念ではないが、古くから使われていることと (分類階層が不足して) 表現しにくい系統を表すには程々に意味があると思っておいてよいのだろう。
wikipedia の系統樹を見ると Nine-primaried Oscines で大きく分かれるように見えてしまうが、文字を入れるため生じたもので実際にそれほど大きな分岐があるわけではない [Kuhl et al. (2021) の分子系統樹も参照]。
セキレイとアトリがなぜ類縁グループなのかはわかりにくいが、スズメ類を含む系統からまずセキレイ類が樹木に依存しない環境に進化して独自の進展を遂げ [前例を参照すればオオタカ系統から草原に進出したチュウヒ類のような関係。セキレイ類では #イワミセキレイ、チュウヒ類ではウスユキチュウヒ (#チュウヒの備考に解説あり) が中間的な性質を持っている]、
アトリ類以降が種子食に特化して進展を遂げたということだろう。新世界にはまだ広大なニッチが存在して、これらのグループから旧世界のムシクイ類、ムクドリ類、ツグミ・ヒタキ類などに相当するグループを生み出したのだろう。
新世界グループを考えると、旧世界ならば生態的には上科に分けてもよいようなグループがホオジロ外科? Icteroidae (Emberizoidae) にの下に並ぶことになる。分類学者がどのような分類階層で考えるか悩む次第である。
少し古い本であるがお持ちの方も多いのではと思われる「これからの鳥類学」(裳華房 2002) の 13 章に鳥類と系統学 (由利たまき) があり、Yamagishi et al. (2001)
Extreme Endemic Radiation of the Malagasy Vangas (Aves: Passeriformes)
の分子系統樹をもとにスズメ目の系統の解説があある (pp. 360-361)。サンプルされた種類が少ないのと遺伝子も限られているが、現在の系統も再現できている部分も多く、比較すると参考になると思われる。
Ericson et al. (2000) の分子マーカーについては触れられていなかった。
茂田 (1995) Birder 9(12): 47-53 によれば、Mayr and Amadon (1951) がセキレイ科をツグミ科かウグイス科に近縁とした (それまでは通常ヒバリ科の近くに置かれていた)。
Sibley (1970) の卵白タンパク質電気泳動でウグイス科またはヒタキ科に近縁としたが、Sibley and Ahlquist (1990) DNA-DNA 分子交雑法ではスズメ科に近いと判定され、これは現代の分子マーカーによる理解と整合性がある結果となった。#オオヨシキリ備考で取り上げた分類学的視点の変遷についても参照。
[スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン]
B10K の成果の一つが発表された。
Chen et al. (2024) Adaptive expansion of ERVK solo-LTRs is associated with Passeriformes speciation events
は 362 種の鳥類ゲノムを解読し、endogenous retroviruses (ERVs 内在性レトロウイルス; 過去にレトロウイルスに感染した生物のゲノムにレトロウイルスのゲノムが取り込まれ、それが子孫に受け継がれたものと考えられている: wikipedia 日本語版から)
由来の solitary long terminal repeats (solo-LTRs: LTR = 長い末端反復) がある。
この solo-LTRs は過去に ERVs を排除した (レトロウイルスに感染したが排除した) 痕跡と考えられる。排除によって失う DNA と新しく取り込まれる DNA が動的平衡状態にあると考えられるが、鳥類では哺乳類や爬虫類に比べて solo-LTRs の比率が高く、より効率的なレトロウイルス由来 DNA の除去を行っていることを示唆する。
solo-LTRs はスズメ目、特にスズメ目内の後の系統ほど蓄積し、2240 万年間の種分化に大きく働いてきたと考えられるとのこと。
キンカチョウに固有の solo-LTRs がありその一つは脳で発現しており、遺伝子の調節領域としても働いていることがわかった。ERVK provirus は生殖器官で特によく発現しているとのこと。
キンカチョウに ERVK solo-LTRs の多形がみつかり、現在も進化 (種分化) の途上であることが示される。
鳥類ゲノムサイズが小さい理由として飛翔の制約のためとの考えもあったが、飛翔進化以前にゲノムサイズの縮小が起きたことを示す研究もあり (両生類で知られている例がある)、他の理由も考えられていた。
Kapusta and Suh (2017) Evolution of bird genomes - a transposon's-eye view。トランスポゾン (または transposable elements TEs) により小型のゲノムでも機能を果たせる仮説があったがその解釈にもある程度沿う結果となった。
生命活動に必須な t-RNA の遺伝子は鳥類では種類が少ないが、必要な多様性維持にトランスポゾンが関与している可能性: Ottenburghs et al. (2021) Genome Size Reduction and Transposon Activity Impact tRNA Gene Diversity While Ensuring Translational Stability in Birds
(これらの一連の論文の図を見ると多少痛快である。系統樹は 両生類 → 哺乳類 → 爬虫類 → 鳥類 の順に並んでいる。教科書にはこう書きたくないだろうなあ)。
スズメ目における solo-LTRs の蓄積は強い選択圧の結果と考えられる。論文の著者たちは新しく挿入される ERVK への防御機構として働いている可能性、あるいは LTRs 間の高い組み換え率を通じて ERVK の拡大による有害な結果を防いでいるのではと提案している。
哺乳類では ERVK は蓄積されて行っているが、鳥類では組み換えによって積極的に排除しているとのこと。
ヒト類に特徴的な ERVK が役割を果たしていることが指摘されているが、スズメ目の認知や複雑な音声学習のために solo-LTRs を遺伝子の調節領域として用いることが考えられる。
この研究は TE が種分化を加速したとの仮説を補強するとのこと。
スズメ目以外にも solo-LTRs 率の高いキツツキ目とブッポウソウ目があり、キツツキ目でも同様に速い種分化を可能にしたとの解釈がある [Manthey et al. (2018) Multiple and Independent Phases of Transposable Element Amplification in the Genomes of Piciformes (Woodpeckers and Allies)]。
しかし判断基準の選び方で結果も変わり、大きな変化は Passeri 以降の系統となることもわかる (Supplementary Fig. 13)。TSDs (target site duplication, solo-LTRs の終端) の蓄積を見ると確かに Corvides, Passerides の順で、その中でも Passerida が系統の最後になることがわかる。
トランスポゾンにより同様の機構は飛ぶ鳥と飛ばない鳥のゲノム進化の違いにも現れている (Kapusta and Suh 2017)。
哺乳類の胎盤の起源に内在性レトロウイルス遺伝子が関与していることはよく知られている (哺乳類の胎盤形成にはウイルスが関与しており、その遺伝子は順次置き換わることができる 参照) が、鳥類進化にさらに鮮明に関与していることが明らかになってきた。哺乳類の胎盤の話を聞く時は鳥類進化への関与も念頭に置くとよさそう。
これらの研究を発端として鳥類におけるトランスポゾンの役割はさらに調べられていくだろう。
オウギワシの高精度ゲノム、タカ類の進化における最新の知見は#ミサゴの備考 [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] も参照。
この研究とほぼ同じ時期、新世界スズメ目の数種を対象として、TEs が非常に多いことが報告されていた: Benham et al. (2024) Remarkably High Repeat Content in the Genomes of Sparrows: The Importance of Genome Assembly Completeness for Transposable Element Discovery
W 染色体に非常に多いこと (一種のゴミ箱状態になる) も報告していた。このような反復配列を読むことは難しく、100 塩基程度を読んでつなげるゲノム解析では抜け落ちる部分だった。
新世界スズメ目はスズメ目の最後の系統にあたり、この特徴が際立って見えたのだろう。
スズメ目の中でも比較的大型の鳥の多く系統も古いカラス類の Corvides では TSDs の蓄積はそれほど高くなく、この数字がそのまま認知能力として表れるわけでないことがわかる。
飛翔の制約説にも関係するが、やはり小型化のための制約 (どちらがニワトリか卵かわからないが) も関係しているのではないかと感じる。
#ミサゴ備考の [染色体再構成と transposable elements から見るタカ類の進化] の話題にも近いのでこちらも参照。
アカマシコを含むアトリ類の高精度ゲノムが読まれ、オウギワシのゲノム同様にスズメ目の進化プロセスが見えてきた。
Fang and Edwards (2025) Avian germline-restricted chromosomes are reservoirs for active long-terminal-repeat retroviruses (preprint)
germline-restricted chromosomes (GRCs) (生殖細胞のみに存在し体細胞に存在しない染色体。これまで調べられたすべての鳴禽類に存在する) に endogenous retroviruses (ERVs 内在性レトロウイルス) の長い反復を多く含む配列が集まっており、体細胞では排除されているとのこと。
また転写解析ではこれらの ERVs が体細胞に比べて活性を持っていることがわかった。
GRCs にスズメ目の広い範囲でよく保存されている遺伝子セット (特に CPEB1) があり亜鳴禽類の分岐 (5000 万年前程度) 以前に生じたスズメ目に必須のものと考えられる。過去 5000 万年間 ERV が増殖して GRCs に蓄積し、ERVs と LTR の活動が過去 1000 万年前以降特に活発となって現在も続いている。
ピークは 1000 万年前ぐらいで Passerida (スズメ小目) が出現して多くの系統を生み出した時期に対応する。
大部分の GRC に関連した遺伝子は種特異的で、近年になって鳴禽類内で生じたものと考えられる。GRCs は種分化を起こす ERVs の貯蔵庫となっているのではとのこと。
アトリ類3種の高精度ゲノムが読まれたことでこのグループの近年の爆発的な種分化と ERVs の関係が見えてきた。アカマシコを読んだのは新世界アトリ類との比較のためと思われる。
Ruiz-Ruano et al. (2025) Programmed DNA elimination drives rapid genomic innovation in two thirds of all bird species (preprint)。
これまで調べられたいたものはスズメ目のごく一部だったが、さらに新しいドラフトゲノムを得て範囲を広げて調べると亜鳴禽類にも認められ、おそらくスズメ目全体に存在すると考えられる。
プログラム化された DNA 除去機構はこれまで見過ごされていた種分化機構に関係がある可能性があるとのこと。Fig. 2 にどの種がどの GRC 遺伝子を持っているか示されているが比較的近い属の間でも大きく違う。Fig. 3 で系統のどの段階で常染色体にあったものが GRC に移行し、遺伝子重複を起こした後失われたのかなど示されている。スズメ目の系統順序が大筋正しいだろうこともこの図からある程度読み取れる。
ここ数年で急速に進んだ分野で、参考までに Borodin et al. (2022) Mendelian nightmares: the germline-restricted chromosome of songbirds の一世代前のレビューも参考。1998 年に生殖細胞に余分な染色体が偶然発見されたものが最初のものだったとのこと。鳥類ではスズメ目以外では見つかっていない。
こちらもまた難しい論文で中身のごく一部しか読めていないが、He et al. (2025) Phylogenomics unveils the complex evolution of retroviruses in birds
ERVs を評価できるレベルのゲノム情報が増えてきていろいろなことがわかってきた。鳴禽類に ERVs が特に多く近年活動してきたことは前記の通りだがタカ目でも多い。鳴禽類とタカ目が共通で持つグループ ERV-L1 はハヤブサ目に見られない (ハヤブサ目は少なめで他に ERV-E も検出されていない)。
フクロウ目、ノガンモドキでは主要系統の ERVs を持っている。気になるヘビクイワシやミサゴはまだ読まれていない。
ハヤブサ目の Falco 属内でも細かく見ると ERVs の配列が異なり系統を追うこともできる。ハヤブサとシロハヤブサは似ていて近縁度がわかるが、ワキスジハヤブサとはかなり異なっていてシロハヤブサと同種とされるほど似ていないかも知れない。ラナーハヤブサも大きく異なる (fig. 6)。近縁種間でもずいぶん異なる。この精度で多くの種が読まれるようになれば系統関係の理解も一気に深まるかも。
また ERVs はレトロウイルス感染でもたらさものと考えられるので、どのような動物がどのような動物にウイルスを提供したかある程度推測できる。鳥類が鳥類以外から受け取ったと思われる系統のウイルス、また逆のウイルスもある。鳥からカメや肉食哺乳類に感染したと思われるものも存在する。しかしまだデータ不足でどの経路で感染したかを議論するのは難しい。
現代の鳥の共通祖先段階で少なくとも 10 系統の ERV グループが流行していて鳥類と共進化を遂げた可能性があるとのこと。
ゲノム中の ERVs 同士の組み換え現象も検出され、現在の学名で書くと クロアカオオタカ Tachyspiza melanochlamys Black-mantled Goshawk とオオタカ (アメリカかどうか未確認) の共通祖先段階 (なのでかなり古い) と Buteo 属4種 (ケアシノスリ、ノスリなど) それぞれ独立に起きたことがわかっている (fig. S9)。
ということでこの2系統が異なることがわかり、その後の変異などをたどればどの段階で起きた事象であったか年代推定もできることになる (そこまではなされていない)。
以下論文にも書いていあるかも知れないが想像で: 肉食哺乳類が鳥からレトロウイルスを受け取ったものがあると考えられるなので、現在でも転写活動の見られる鳴禽類の ERVs を猛禽類が受け取ることがあるのはごく自然で、タカ目 (特に小鳥食系統) で ERVs が多いのも関係があるかも知れない。鳴禽類の ERVs の活動ピーク時期、猛禽類に小鳥食の系統が進化した時期と ERVs 配列の関係を調べると生態の進化なども追跡できるかも知れない。
さきほどのクロアカオオタカとオオタカの共通祖先は約 2000 万年前でまだアフリカにとどまっていた時期と思われる。この時点でこの2つの ERVs を持っていたことは確実なので、何から獲得したものだろうか。アフリカやアフリカを起源とする鳥の高精度ゲノムが多数読まれれば判断できるかも知れない。
この ERVs が鳴禽類由来でも構わない気がするので、もしそうであれば小鳥食をこの時点ですでに進化させていた証拠になるかも知れない (現代の分子系統樹から予想できる共通性質とも合う感じがする)。
ERVs の転写活動の低い系統 (古い系統は一般にあまり ERVs が多くない) を食べる系統では新たに獲得する ERVs が少ないことも推定できるが、宿主側の ERVs の排除 (あるいは積極的利用) 機構とバランスの上の数字と思われるのでなかなか難しいかも知れない。
個々の ERV の導入は一点突破と考えられる (例えば SARS-CoV-2 がヒトに感染を起こした、渡り鳥で運ばれ得る HPAI H5N1 がインドガンのような宿主への感染で始まったと考えられるのと同様)、この個々の事例を追うのは感染当時の詳細なウイルスゲノムでもない限り難しいだろう。しかし現在残っている痕跡の系統解析や複数の ERVs があれば統計的な議論が可能になってくる。
この精度で読まれている種類はモデル生物か、保全のために特に詳しく調べられたものが中心なので、系統的にはかなり偏っている。これからの研究の出発点となる段階の論文とみてよいだろう。
この時点ではまだコンドル目とタカ目を分離していないが、コンドル目のカリフォルニアコンドルはタカ目に比べてかなり少ない。ヒゲワシはタカ目らしくイヌワシやオジロワシとほぼ同じ。系統関係とともに過去の食性などを探る手がかりになるかも知れない。
オウギワシはオオタカとほぼ同じで食性のみを考えると不思議な気もする。これらの ERVs の系統関係までは追っていないので、タカ目誕生に関わった ERVs が残っているのか、肉食になって新たに獲得したものかなど判別してみると面白いかも。
この論文はどちらかと言えばまずは ERVs の系統解析、そして数の多い鳴禽類の ERVs の統計的研究が中心で、生態学や進化関係までは手が回っていないかも知れない。
霊長類の ERV で日本の関係した論文が発表されたので紹介しておく: Chen et al. (2025) A phylogenetic approach uncovers cryptic endogenous retrovirus subfamilies in the primate lineage。現在進展中の話題の分野と考えてよさそう。
[鳥類の営巣習性の進化]
凝った巣を造る種類としてここで紹介しておく。Mainwaring et al. (2023) The evolution of nest site use and nest architecture in modern birds and their ancestors (出版社サイト)
が鳥類の祖先も含めた営巣習性の進化をまとめている。
この著者は祖先も含めた進化段階を提唱している: 地下 → 一部が露出した巣 → 半分開いた巣 → 開いた巣 (ここから現生鳥類): 地上営巣でプラットフォーム構造、粗雑な構造 (scrapes ハヤブサ類の巣もこのように呼ばれる)、カップ状の構造 → 一部樹洞営巣性に → ドーム状の巣/開いたカップ状の巣 (スズメ目、相互の間の進化あり)。
樹洞営巣性になった系統としてオウム類、キツツキ類、カワセミ類を例示している。
全体の系統樹をみると系統的に決まっている部分もあるが (特にフクロウ類からブッポウソウ目の樹洞営巣性)、より古い系統でも樹洞営巣性のもあるのでそこまで進化段階を反映している感じに思えない (カモ類は多彩)。ハヤブサ類の古い系統は樹洞営巣性なのでオウム類の特性はそこに遡る? しかし分岐したスズメ目は別の進化を遂げたよう (このテーマは#ハヤブサ備考の [ハヤブサ類の免疫の特殊性] から派生して少し考察してみた)。
類似のデータを用いた解析は Chia et al. (2023) A global database of bird nest traits にもある。
こちらは系統解析の紹介とともに巣のタイプの世界の地理的分布を紹介している。
オウム類の樹洞営巣性は派手な色彩を隠す必要があるとの説があるとのこと: Carballo et al. (2020) Body size and climate as predictors of plumage colouration and sexual dichromatism in parrots 参照。
この論文はオウム類の色彩を調べたもので、小型で短命の種類ほどオスは性選択を強く受ける。大型種では両性間の選択、社会的選択、大型種は隠蔽色であることへの選択圧が低いことを理由としている。
上田 (2021)「野鳥」2021年11・12月号 (No. 855) p. 12 に「赤や緑のオウム類の派手な色彩は、赤い果実がたくさん実っている緑の葉陰ではかえって隠蔽色になる可能性がありますが (中略) 捕食者に対する警告色として進化してきたと考えることはできないでしょうか」とあるが、隠蔽色については全体的傾向は逆を示唆する結果となっている。
オウム類の緑色が隠蔽色と考える解釈は以前よりあって Mundy (2018) Colouration Genetics: Pretty Polymorphic Parrots の解説では未だに検証が行われていないとあり、色彩の生態的役割は今後の研究の進展が期待できるとある
(この項目について、#ヤマセミの備考 [学名の lugubris の意味と生態的意義] で追加検討を行った)。
オウム類の樹洞営巣性の説明は Martin and Li (1992) Life History Traits of Open- vs. Cavity-Nesting Birds が出典とのこと。
Soler and Moreno (2012) Evolution of sexual dichromatism in relation to nesting habits in European passerines: a test of Wallace's hypothesis
によれば Darwin, Wallace が 100 年以上前に提唱した、樹洞営巣性の種ほどオスが目立つ色彩でメスは隠蔽色になる傾向をスズメ目である程度確認したとのこと。
ヨタカ系統 (Strisores) は営巣習性であまりまとまりがない感じ。
比較的大型の水鳥 (系統的に近いハト類も) でプラットフォーム型はそこそこ系統的にまとまっているよう。Telluraves でタカ類のプラットフォーム型は例外的だが、系統より体サイズの方が関連が深いかも知れない。大型の鳥で凝った巣を造ると時間がかかりすぎるので最小限の機能の簡素なものになっている?
(開放型にしないとそもそも入れないかも知れないような気もするが、フクロウ類はそうでもない? 翼長はだいぶ違う感じはするが)。図を見ていろいろ考えていただくと面白そう。
この解説では鳥類の多くが片側の卵巣しか持たないのは重量を減らすためか (ワニには2つある) の仮説を紹介している。鳥類の祖先段階では両方の卵巣が機能していて交互に卵を作っていたのでは。抱卵が進化した段階では全部を産んでから抱卵を開始したと考えられる。
タンパク質の豊富な卵白が増えることで転卵の必要が生じた (地中で孵化させて転卵を行わない現生種は卵白が少ない)。完全托卵性ズグロガモを例外として親は多少なりとも子の世話をする。
子の世話によって兄弟競争が生じ、子が親にねだる行動や子供の世話を行う性質を相互に強め合う形で進化した (親子の一種の共進化みたいなもの?)。参照文献も紹介されているので特に現代の鳥類への進化の部分は論文をご覧いただきたい。
複雑な巣を造るのは認知能力を必要とするのかも議論されている。
Perez et al. (2023) Variation in nest-building behaviour in birds: a multi-species approach スズメ目での検討。知能の指標とされる創造的行動とあまり関係がない?
Healy et al. (2023) Bird nest building: visions for the future 知能の高いと言われるカラス類が複雑な巣を造らない。
巣材に何を用いるか: Sheard et al. (2023) Beak shape and nest material use in birds
嘴の形状と相関がある? こちらにも系統樹が出ているが、それほど系統で決まっているわけではない?
関連してこんな研究もある: Sugasawa et al. (2021) Object manipulation without hands
霊長類の手よりはるかに単純な構造の嘴でなぜ複雑な行動ができるのか。ただし昆虫も行っているが。特にロボット工学の視点から (ロボットに同じことをさせるならば暗黙に人の手のような構造を考えるだろうが、鳥の嘴からも学べることは多いということだろう)。
[フウキンチョウの和名の由来]
フウキンチョウ科 Thraupidae は英語では一般に Tanagers とまとめられ、どのような関連があるのか、何かの当て字かと想像していたが、フウキンチョウ は漢字では "風琴鳥" と書くことを知って由来を知りたくなった。
ネット検索をしてみると Euphonias 属名で Euphonia でよい音を指すとあった (ネット出典を示してもよいが出典が別にあろうと思われるので特に示さないでおく)。
この属名自身はギリシャ語 euphonia = eu- よい phone 音 (o は長音。#サンコウチョウ備考参照) 由来で曖昧なところは何もないが、"風琴鳥" との間には若干のギャップがある。当時の鳥類学用語でしばしばドイツ語からの翻訳があったのでドイツ語名をみてみると大当たり (!)。
ドイツ語属名 Organisten = オルガン奏者 だった。かつてはオルガンが風琴、ピアノが洋琴。
OED を調べてみると organist tanager Euphonia musica (さらに属が分割されて現在では Chlorophonia musica)
現在の英名で Hispaniolan Euphonia 和名サンショクフウキンチョウがあって、英語では現在は死語となっている。1793 年に英語の最初の用例 (The Organist) があり、少なくとも 1894 年までは用例があった。
1793 年の J. Leslie, "translation of Comte de Buffon, Natural History of Birds" は Buffon のフランス語からの翻訳で、フランス語では Organiste と表記、St. Domingo (地理的には複雑なのでそのまま表記しておく) での名称とのこと。つまり現地でオルガン奏者 (に対応する意味) で呼ばれていて、Buffon がフランス語で紹介、英語やドイツ語に用いられることになったが英語の用例は廃れたので現在わかりにくくなっている次第。
"風琴鳥" の由来は廃れる前の英語、またはフランス語やドイツ語由来が考えられる。フランス語では現在でも Organiste が用いられており、他の言語ではオランダ語やスロバキア語、ポーランド語に残っている。飼い鳥由来ならばオランダと交易していた時代の名称かも知れない。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 85 表 4) 江戸時代に日本で飼われていた可能性のある輸入鳥には含まれていないので、もう少し後の時代の方が考えやすい。
名前の由来となったサンショクフウキンチョウがどのぐらいよい声で鳴くのかと録音を聞いてみたが、予想通り大したことがない。
Jilguerillo - Antillean Euphonia (Euphonia musica) 鳴いている動画。
名称に含まれる jilguero はゴシキヒワのスペイン語名。こちらもむしろ色彩の類似性から名付けられたのでは? (色彩の類似性からゴシキヒワと同じようによい声で鳴くと想像された ?? などの道筋も考えられそう)。
原記載。Buffon の Organiste、Latham の Tuneful Manakin、記載には cantu harmonico (調和的な歌) などが出てきて "音楽的" (musica) の種小名を与えたものと思われるが、博物学者の早合点の印象が強い。
属名の Euphonia の 原記載。Cette particularite a fait donner a cet oiseau le nom qu'il porte, et meme, dans quelques cantons de Saint-Domingue, celui de Musicien. サントドミンゴ (当時フランス植民地) のある地域で音楽家と呼ばれることから採用した属名とのことで、伝聞に推量を重ねて誕生した Organiste と属名 Euphonia となったらしい。
もとは音楽家程度ならば許容範囲なのだろうがさらに musica やオルガン奏者、そして和名へと拡大解釈されていったらしい。
Ad99999 04 013a/eng - Interlinking_Pictura によれば The tuneful Manakin. (Pipra musica.), This Manakin is called tuneful for its sweet and pleasant singing, which many travellers prefer to that of our Nightingals. It lives in the woods of St. Domingo... (Birds XLIX. Vol. IV. No. 11., MANAKINS OF DIFFERENT KINDS)
でサントドミンゴの旅行者にとって我々のナイチンゲールよりもよい声だとのこと。Manakin (マイコドリ類。フウキンチョウ類とは関係がない) はそもそも短い声しか出さないが、この種のみは特別で...ということらしい。さえずりらしい声を持たない Manakin 類 (分類を誤っていたため) の中ではまだ評価できる方だったのか、あるいは現地名はさらに別のことを指していたのか (?)。
関連して意味のわかりにくい センニョヒタキ科 Stenostiridae の由来を考えておくと、おそらく英名の Fairy Flycatcher(s) から仙女鶲だろう。センニョムシクイの名称もあり、こちらが種英名の Fairy Warbler により対応する。warbler を系統をあまり考えず "ムシクイ" と訳していた時代の名残りとも言える。もっとも現代の系統樹ではシジュウカラ上科 Paroidea の系統なのでどちらも適切な英名ではなかった。
中国語 (台湾) の旧名に霊仙鶲があった。"仙女" そのものは古代中国からある概念で古くは神話の人物、現代では美人、妖精、小仙女は現在もよく使われるとのこと。
△ スズメ目 PASSERIFORMES シジュウカラ科 PARIDAE ▽
-
ハシブトガラ
- 学名:Poecile palustris (ポエキレ パルーストゥリス) 沼地にいる黒い帽子のカラ
- 属名:poecile (合) 黒い帽子の (カラ) (poikilos 多彩の、まだらのなどの Gk; 属訳名は属定義から)
- 種小名:palustris (adj) 沼地の (paluster)
- 英名:Marsh Tit
- 備考:
poecile は外国語由来で発音はわからないが、起源のギリシャ語は長母音を含まないためラテン語も短母音のみと考えられる。po-e-ci-le と分割すれば e にアクセントがあると思われる (ポエキレ)。
palustris は u が長母音でアクセントもここにある (パルーストゥリス)。
ラテン語 paluster も u が長母音で "沼地の" の意味。palus (パルース) が沼。
記載時学名 Parus palustris Linnaeus, 1758 (原記載)。
Linnaeus 以前から Gessner など palustris の名前は使われていた。
英名のように特に湿地を好むわけではないとコンサイス鳥名事典にあるが、この英名は学名に対応するものと考えられる。ドイツ語名なども同様で wikipedia ドイツ語版やスウェーデン語版でも一般名と生息環境の関係はあまり対応していないことが記されている。
palustris は#コミミズクのシノニムやドイツ語名などの由来、ヌマヨシキリの種小名となっているように当時よく使われたもの。
OED によれば Ray (1673) に The Marsh Titmouse: Parus palustris の用例が現れるとのこと (まだ有効な学名ではない)。つまり英名があって対応するラテン名を与えていた可能性がある。marsh や palustris が用いられたのは英国事情の模様。英国の基本的なカラ類は5種類で(ヨーロッパ)シジュウカラ、ヒガラ、アオガラ、ハシブトガラ (Marsh Tit)、コガラ (Willow Tit)。
ハシブトガラとコガラは英国でのわずかな生息地好みの違いを使い分けたものらしいが willow tit/titmouse の用例は比較的新しいようで 1907 年に現れる。
属名の Poecile は Kaup (1829) で、ギリシャ語 poikilos の意味はドイツ語で bunt (多彩の、まだらのなどの意味) と説明している。与えられたドイツ語属名は Dohlenmeise で黒い帽子のカラの意味でよいと思われる。当時はヒガラもこの属に含まれていた (The Key to Scientific Names)。属定義にも黒い頭が現れる。
そのため poecile の訳語を属定義に基づき「色彩に富む、変化のある鳥」から「黒い帽子の (カラ)」に変更することにした。このように見るとヤマガラが Poecile 属であった理由がわかる。
雑誌 "Birder's World" 1989.8 pp. 10-13 に Robert W. Storer (#カワウ備考の [ガラパゴスコバネウの進化] 参照) による "Now You See Them..." の隠蔽色の記事があった。この中でアメリカコガラ (現在の学名 Poecile atricapillus Black-capped Chickadee) の頭が黒いのは目の存在をわかりにくくするためとあり、類似に事例はクロハサミアジサシ Rynchops niger Black Skimmer のように多数あると記述されている。日本の種でもいくらでも事例を挙げることができるだろう。
捕食者としても捕食される側としても目が隠蔽色になるのは好都合なことが多いのだろう。頭頂の黒い鳥が多いことを説明する一つの理由となる。顔の黒いオオルリ成鳥オスも、目を通る黒い縞のあるキビタキも成鳥オスも目が判別しにくいのは同じ理由でよいのだろう。どちらも写真家泣かせかも知れない。
ここまでならば隠蔽色の解説に載っているだろうが、Poecile 属のドイツ語名は Dohlenmeise で黒い帽子のカラで見事に一致する (アメリカコガラがタイプ種)。
その昔 Parus 属が分割され Poecile 属が用いられるようになり、その包含範囲が変わって身近な鳥の学名が変わったために学名はあてにならないと感じられた、あるいは「今の細分主義の "流行" はけしからん」と分類学そのものに拒否感を持たれた方もあるのではないかと想像する。
このように見ると "黒い帽子の" は機能的なものであって必ずしも系統を反映するとは限らないことがわかる。つまりかつての Poecile 属は機能的収斂によってみかけが似たものの寄せ集めであって、系統分類の指標としてはふさわしくなかったわけだ。かつての Poecile 属に一度まとめられたものが整理された背景には、このような奥深い生態学的理由があった。
日本では北海道限定だが、ユーラシア東西に広く分布し、朝鮮半島でも生息。世界で 10 亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は hensoni (日本を訪れた英国の Harry Vernon Henson に由来) とされる。
朝鮮半島の亜種は異なっていて hellmayri (オーストリアの鳥類学者 Carl "Charles" Eduard Hellmayr に由来)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では当時の学名で Parus palustris hensoni Hokkaido, Iturup ヘンソンガラの名前を与えていた。
一方 Parus palustris japonicus Kurile Is., Hokkaido, Hondo にコガラの名称が与えられ、分布を見る限りではコガラとハシブトガラが十分区別されておらず、コガラをハシブトガラの亜種としていたことがわかる。
Seebohm (1879) の用いた学名のようで Parus japonicus Stephens, 1817 の用例があるため無効な学名となった模様。Dickinson et al. (2006) Systematic notes on Asian birds. 50 Types of the Aegithalidae, Remizidae and Paridae に解説 (p. 85) があった。
Stephens の用例が何を指していたか確定できない (#コガラの備考参照) が無効とする効力はあるとの考え。この用例があるために従来は広義だった Parus 属には亜種も含めてそもそも japonicus を新たに与えることはできなかった模様。
Parus atricapillalus baicalensis Hokkaido エゾコガラ もリストされている。Parus atricapillalus は現在の学名ではアメリカコガラ。
Poecile baicalensis Swinhoe, 1871 が記載時学名 (原記載)。現在はコガラの亜種 Poecile montanus baicalensis とされる。Ogawa (1908) の時点では北海道に3(亜)種のコガラ/ハシブトガラが生息すると考えられていた模様。
「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) の索引にはヘンソンハシブトガラの名称が現れるが本文ではハシブトガラとなっていた。
ヘンソンハシブトガラの名称はハシブトガラの亜種扱い時代のものと考えられる。
山階鳥類研究所の標本データベースでも 1928 年などの標本に "からふとこがら" の名称があり、ラベル学名は Parus palustris hensoni が使われていた。
1926 年の樺太の標本で "をりゐこがら" P. p. orii の表示 (ラベルそのものは後に付けられたものらしい) もあり、YIO-00168 がこの学名に対応するタイプ標本だったが、後に亜種 ernsti のシノニムと判定されてラベルも書き換えられていた。
当時は Parus palustris の種和名がコガラだったが、後に分離されたことでコガラとハシブトガラに分けられ、コガラの種学名が変わることとなった。
Bossoh (2023) Classification, Observational Practice, and Henry Seebohm's The Birds of the Japanese Empire in Late-Victorian Britain
に Seebohm の残した日本の他の鳥の記録も含めて解説がある。
Seebohm のこの亜種を用いる三名法の用例は最初のものだったとのこと (#カンムリツクシガモ備考にも、進化思想の興隆に伴う当時の分類学の動向がある)。
Seebohm 自身は日本を訪れずに日本の鳥目録を出版した。Seebohm の日本の鳥についての業績についてはこれまであまり調べられていなかったとのこと。
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the marsh tit Parus palustris (pp. 2657-2682)
ロシア沿海地方のハシブトガラの繁殖生態 (亜種 crassirostris)。
-
コガラ
- 学名:Poecile montanus (ポエキレ モンターヌス) 山の黒い帽子のカラ
- 属名:poecile (合) 黒い帽子の (カラ) (poikilos 多彩の、まだらのなどの Gk; 属訳名は属定義から)
- 種小名:montanus (adj) 山の
- 英名:Willow Tit [英名のように特にヤナギの木を好むわけではない (コンサイス鳥名事典)]
- 備考:
poecile は#ハシブトガラ参照。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 151 (1946 年初出) によればコガラに「ナベカブリ」の名称もあるとのことで、属定義の特徴も非常によく捉えた名称だった。
montanus は a が長母音でアクセントもここにある (モンターヌス)。
ユーラシアの主に北方に広く分布。世界では 14 亜種が認められている (IOC)。
記載時は Parus cinereus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 とシジュウカラ (現在の分類での概念。当時は Parus cinereus は Parus major と別種だったので南方系のシジュウカラの亜種と認識されたらしい)。
原記載。基産地はスイスの Graubiinden。
アメリカコガラの方が先に記載されており、Linnaeus (1766) Parus atricapillus 原記載。
現在のコガラのドイツ名は Monchsmeise (Moenchsmeise) 僧侶のカラ または Weidenmeise 牧場に草を食べに出ること (英語 pasture) またはヤナギのカラ。Conrad von Baldenstein (1827) には Moenchs-Meise は当時の学名で Parus cinereus communis を指しており、それとは異なる山岳性の亜種として Berg-Moenchs-Meise を与えていた。
種小名 montanus とはよく整合している。
英名は Weidenmeise が由来と思われるがドイツ語 Weide でどの語義が使われた名称かすっきりしなかった。ヤナギにもぐるカラぐらいの意味だろうか、それとも放牧場に現れたのだろうか。
OED によれば語源は記されていないが英国では珍しい鳥で 1907 年の用例が最初とのこと。1979 年の記述では当時英国で記録された最後のカラ類だったとのこと。珍しい鳥でそもそも生息環境を適切に反映した英名ではなさそう。
日本の亜種は restrictus (限定された、閉じ込められた) 亜種コガラと、sachalinensis (サハリンの) 亜種カラフトコガラとされる。カラフトコガラの通常の分布域はサハリンとされる。カムチャツカから千島は別亜種 kamtschatkensis とされる。
「第二回パブリックコメントに向けた暫定リスト」では亜種カラフトコガラは最近 50 年間以上、確実な国内記録がない、とある。
restrictus の原記載 (Hellmayr 1900)。Parus borealis restrictus が記載時学名だった。
Parus japonicus Steph. が不明確なので代わる名前を与えたい、とある。おそらく日本南部 (本土の表現あり) に限定された、の意味で使っているのだろう。
Parus atricapillus abei Mishima, 1961 が提唱されたことがあった [Japan Wildlife Bulletin 18(1): 160] が、現在採用しているリストはない (アメリカコガラの亜種扱いだった理由は以下参照)。
sachalinensis の原記載 (Lonnberg 1908)。
kamtschatkensis の原記載 (Bonaparte 1850)。
baicalensis の原記載 (Swinhoe 1871)。
一時は現在のアメリカコガラと同種とされ、Parus atricapillus の学名が使われていたことがあった。アメリカコガラの方が先に記載されていたため同種扱いの場合はこの種の亜種となる。
Peterson Field Guide for the Birds of Britain and Europe の古い版にはこの分類が用いられていたとのこと (wikipedia 英語版より)。
アメリカコガラは現在は Poecile atricapillus 英名 Black-capped Chickadee である。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではサハリンの個体群は亜種 baicalensis とし、sachalinensis はシノニムとなっている。カムチャツカは別亜種としている。これら東部の亜種は記載時属名 Poecile が用いられていた。
Lobkov (1997) は baicalensis とカムチャツカの亜種 kamtschatkensis は大きく違うとして別種扱いも提案している。
地鳴きはヤマガラとパターンが似ているが音質が特徴的でわかりやすい。「ニーニーニー」または「ジャージャージャー」の前に「ツツ」を付けるのがコガラという説明を聞いたことがあるが、ヤマガラも付けるので識別点にはならない。
「ヒーツーヒーツー...」と2つの音を繰り返すのは東洋のコガラに特徴的なさえずりと言われ、ヨーロッパの亜種はこのようにはさえずらない。「ヒーヒヒーヒ...」とほぼ同じ音で続くさえずりはヨーロッパの亜種と共通にある。
Eck and Martens (2006) Systematic notes on Asian birds. 49 A preliminary review of the Aegithalidae, Remizidae and Paridae
ではさえずりを4つに分類し、Alpine type (大陸高地型)、Lowland type (大陸低地型)、Siberian type (シベリア型)、Sino-Japanese (中国日本型) としている。最後のものが東洋のコガラに特徴的なさえずりとされるものである。
[北海道のコガラの分類]
先崎 (2018) Birder 32(11): 23 によれば北海道のコガラは本州のものと音声が異なるとのこと。バードリサーチ鳴き声図鑑 コガラ には1例のさえずり記録がある。[先崎 (2018) の記事の北海道のさえずりのソノグラムは地鳴きのように思える]。
大橋 (2018) Birder 32(11): 25 では北海道のものは亜種カラフトコガラではないかとの推測がある。
Eck and Martens (2006) (#シジュウカラの備考参照) にも北海道のコガラの分類についての記載があり、Hartert (1905) は北海道のものは亜種コガラ restrictus とは異なると述べたが、後に統合した (Hartert and Steinbacher 1934) とのこと。
日本鳥学会も1922年には北海道のものを sachalinensis としたが、1974年に restrictus とした。
Eck and Martens (2006) によると北海道個体のさえずりは Alpine type に属し、カラフトコガラ sachalinensis に所属すべきと提案している。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol. 1-2) もこの提案に従っている。先行研究もリストされているのでこの文献が手がかりになるだろう。
第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開では北海道個体は restrictus と扱っている。
IOC 14.1 では sachalinensis と restrictus は第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開と同じ扱いで特に注釈はない。
sachalinensis, baicalensis, kamtschatkensis がそれぞれ亜種に値するのかなど未解明の部分があって分類に手がつけにくいかも知れない。(記載年代では sachalinensis が最も新しいので統合があれば学名が変わる)。
[マミジロコガラの記憶と遺伝子]
コガラの近縁種の北米のマミジロコガラ Poecile gambeli Mountain Chickadee は貯食行動を行うが、この行動に必要な遺伝子が最近調べられた。
Cognition: 'Caching' in to nd the genetic basis of spatial cognitive ability。
論文は Branch et al. (2022) The genetic basis of spatial cognitive variation in a food-caching bird。
フィーダーを訪れるマミジロコガラを用いて空間記憶能力を調べ、ゲノム解析によって空間記憶能力と遺伝子や調節部位との関係を調べた。空間記憶能力の低い遺伝型をホモ接合で持つものは見当たらず、空間記憶能力の低い個体が厳しい条件で生存できないことを示唆する。空間記憶能力は遺伝で中程度決まるとのこと。
空間記憶能力の高い個体が性選択で好まれる実験的証拠もある。類似種であるアメリカコガラ Poecile atricapillus Black-capped Chickade とカロライナコガラ Poecile carolinensis Carolina Chickadee の雑種は空間記憶能力が低い研究結果もあり、温帯で厳しい冬を越す留鳥にとって空間記憶能力が生殖隔離機構となる可能性がある。
Semenov et al. (2024) Genes and gene networks underlying spatial cognition in food-caching chickadees
はさらに全ゲノム解析を行って 100 近い遺伝部位が空間記憶能力に関係している (ポリジーン)。多くの遺伝部位がシナプスの可塑性に関わっているとのこと。最長で9年記憶を保つことができるが、あまりに長期の記憶を持つと新しい環境 (環境変化) に適応するのに時間がかかるのでトレードオフが存在する。
Mountain chickadees have remarkable memories. A new study explains why (解説記事)。
Chettih et al. (2024) Barcoding of episodic memories in the hippocampus of a food-caching bird (preprint 版) によれば、貯食場所は海馬の少数 (スパース) のニューロンがバーコードのような発火パターンと結びつけられていることを示した。
同じ考え方はヒトの脳科学でも知られていて、例えば Wixted et al. (2014) Sparse and distributed coding of episodic memory in neurons of the human hippocampus と関連文献参照。
スパースがキーワードの一つで 脳の画像・音声処理戦略を解き明かすスパースモデリング (寺島裕貴 2014) 参照。情報を全て持たなくてもスパースなデータから適切な基底を用いれば真実に非常に近いものを再現できる。
想像だが、おそらくコガラ類の海馬における空間記憶にもおそらく同じようなスパース性があり、それぞれのニューロンの発火に従った適切な基底 (あるはカーネル) を足し合わせれば真実に近い空間記憶が再現されるのだろう。少々記憶が劣化してニューロンの発火パターンが違っていても、適切な基底が使われていればほどほどに認識できる像を再現できることになる。
どのような基底を用いるか、貯食場所をどのような形でスパースな情報に分解するか、などの点に自然選択が働き、最小限の情報で貯食場所を記憶する能力が厳選されてきたと考えれば納得できる気がする。
実際の生物ではもっと複雑な仕組みがあるだろうが、ここでは線形代数の用語を用い、重ね合わせの原理を用いて解説してみた。
スパースモデリングについては#タンチョウの備考の [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] でクロハチドリの音声解析に実例を示してみた。通常のソノグラムは2次元画像になるが、スパースモデリングを用いると疎行列 (情報量ははるかに少ない) で表すことができる。
少数の情報しか含まれないスパースなソノグラムが音声が表現できることを見ていただけるのではないかと思う。
-
ヤマガラ (新分類で独立種オリイヤマガラが分離。オーストンヤマガラも海外では通常分離される)
- 第8版学名:Sittiparus varius (シッティパルス ウァリウス) 色変わりのゴジュウカラのようなシジュウカラ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Poecile varius (ポエキレ ウァリウス) 色変わりの黒い帽子のカラ
- 第8版属名:sittiparus (合) Sittiparus 属 [Sitta (ゴジュウカラ) 属と Parus (シジュウカラ) 属から合成
- 第7版属名:poecile (合) 黒い帽子の (カラ) (poikilos 多彩の、まだらのなどの Gk; 属訳名は属定義から)
- 種小名:varius (adj) 変化のある、多色の、さまざまな色の ここではヨーロッパシジュウカラの色変わりと解釈した。備考参照
- 英名:Varied Tit
- 備考:
sittiparus は合成語のため発音はよくわからないが、parus は長母音を持たないため規則からは -ti- にアクセントがある。sitta の由来であるギリシャ語の sitte は語末が長母音で -ti- も伸ばされるかも知れない (シッティパルス または シッティーパルス)。
varius はすべて短母音で冒頭にアクセントがある (ウァリウス)。
#ハシブトガラ参照。
記載時学名 Parus varius Temminck & Schlegel, 1845。原記載。図版。
基産地 Japan; restricted to Honshu by Hartert, 1905 (日本となっていたが Hartert が本州に限定した) (Avibase 情報より)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Sittiparus 属 [Sitta (ゴジュウカラ) 属と Parus (シジュウカラ) 属から合成] に移行。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。種小名は変化なし。
Temminck and Schlegel (1845) の記載時は la mesange variee のフランス名が使われている。varie は英語の of variety, various とほぼ同じ意味。"盛り合わせ" のような "取り混ぜ" にも使われる。
学名提示部分に我々のヨーロッパシジュウカラと色が明瞭に違っているなどの記述がある:
se reconnait tout de suite a la distribution des taintes de son plumage et notament au beau brun-roux の記述は "ヨーロッパシジュウカラとは色の分布、特に美しい赤茶の色彩で容易に区別できる" の意味。この部分を見ると色彩面でヨーロッパシジュウカラの変わり者の意味で用いられたように見える。
記述に les dimensions de cette espece presentent des differences assez considerables suivant les individus, mais nous ignorons s'il faut attribuer ces diffrences a des varits accidentelles ou au sexe.
この種は個体間の大きさの差がかなりあるが、これらの違いが偶然の個体変異なのか性によるものかはわからない、とある。個体間の差を示した命名の可能性もある。
"多色の"、"変種の"、"個体間の差" はいずれも可能性があるが、ヨーロッパシジュウカラの色変わりと解釈するのがもっともらしいように思える。色彩豊かな点も考慮に入っていると思われる。
Temminck and Schlegel (1845) では日本からのカラ類3種めの記載で、前2者のシジュウカラ、エナガの亜種はヨーロッパのものと類縁性が高いので記述の論理的順序から先に紹介したと考えられる。日本からの3種めであり、ヨーロッパのものと類縁性が高くないので地域名を付けた学名やフランス語名は避けられたと考えられる。
また#ハシブトガラの備考にあるように Parus 属に japonicus を新たに使うことはできなかったため "日本版" の使い方もできなかったと想像できる。
英名も学名やフランス語名を訳したものと想像できる。
中国名は雑色山雀、染色山雀となっているので "多色の" となるがどうも種を分割する時に付けた名前のよう。ロシア名は tisovaya (tissovaya) sinitsa で植物の紅豆杉 (タキサス) を指すらしくこの実を好むとのこと (Kolyada et al. 2016)。色彩とは関係なさそう。
Parus sieboldi Seebohm, 1890 (参考) の改名もあった。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば Parus varius は Bartram (1791) が現在の分類でアサギアメリカムシクイ Setophaga americana Northern Parula を指してすでに用いた学名であったとのこと。
この学名は有効なものと認識されないと考えられるが、念のために与えた新名とのこと。すでに広く使われている Parus varius の学名を破棄する意図はないとのこと。
もし Bartram (1791) が全く別の種に用いた用例が有効とされていればヤマガラの学名は "シーボルトのカラ" となっていたことになる。
Seebohm (1890) のこの文献では英名に Japanese Tit を採用していた。シジュウカラの方は Manchurian race of the Indian Great Tit (当時の種学名で Parus atriceps) との表現で、大陸にも分布するので "日本のカラ" とは呼ばなかったらしい。文中には Japanse Great Tits の表現が現れるが、これは種類の英名というよりは日本の Great Tits は朝鮮半島から来ているかも知れないとの文脈で使われている。
Sittiparus 属はヤマガラ属。もとは Parus 属であったものが一時期 Poecile 属となったため非常にややこしい。Poecile 属の名称がコガラ属である点には影響がない。
カラ類の分子系統研究は例えば Johansson et al. (2013) A complete multilocus species phylogeny of the tits and chickadees (Aves: Paridae)
この研究で従来の Poecile 属が単系統でないことがわかり、Sittiparus 属に分類された。形態学的にもこの属への分類は以前にも行われていた (Harrap and Quinn 1996) が、分子系統的にも支持される結果となった。
なお Sittiparus の属名はオリイヤマガラの記載時に使われたもの (Kuroda, Nagamichi, 1923)。
ヤマガラは日本と朝鮮半島周辺にのみ分布する。Sittiparus 属もヤマガラおよびその亜種であったものと、台湾 (タイワンヤマガラ Sittiparus castaneoventris 英名 Chestnut-bellied Tit) と、フィリピンに局所的に分布するシロビタイガラ Sittiparus semilarvatus (英名 White-fronted Tit) からなる分布の狭い属である。
タイワンヤマガラはヤマガラに似ているが、シロビタイガラは全体的にはあまり似ていない。額が白い点がヤマガラとの共通点である。
亜種 olivaceus (オリーブ緑色の) は日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では亜種扱いだが名称をオリイガラに変更、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では和名を元に戻して独立種 #オリイヤマガラとし、学名は Sittiparus olivaceus となる。
この変更は世界のリストでも行われていて、対応する英名は Iriomote Tit となっている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも亜種扱いであるが、海外のリスト (HBW/BirdLife, Clements, eBird, IOC いずれも) では owstoni (英国博物学者、採集家の Alan Owston の) も独立種 Sittiparus owstoni オーストンヤマガラ、対応する英名 Owston's Tit とされる。
ヤマガラの分子系統と色彩を含めた解析は McKay et al. (2014) Incorporating Color into Integrative Taxonomy: Analysis of the Varied Tit (Sittiparus varius) Complex in East Asia
を参照。これに従ってオリイヤマガラが分離された。同文献でオーストンヤマガラも独立種とされているが分子系統的にはあまり違いがなく、色彩によって分離できるとのこと。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で採用されていないのは分子系統的な分離が不完全なためかも知れない。
これらを除いた亜種で varius 亜種ヤマガラ、amamii アマミヤマガラ、namiyei ナミエヤマガラ、orii ダイトウヤマガラ (絶滅亜種)、sunsunpi (ヤマガラの地方名から) タネヤマガラ、及び IOC リストにはない yakushimensis ヤクシマヤマガラと亜種不明が含まれている。
亜種 yakushimensis は世界の主要リストでは Clements のみが認めている。他のリストでは sunsunpi のシノニムとして扱われている。
上記 McKay et al. (2014) によれば5亜種 amamii, namiyei, orii, sunsunpi, yakushimensis は varius と区別できず、シノニムの関係にあると一旦は結論している。
しかしヤマガラは外見の変異の多い種であり、亜種の中でも同様に変異があると考えられる。現状の限られた情報から亜種分類について結論を出すのはまだ時期尚早とも考えられるとのことのようである。
オーストンヤマガラに似た色彩のヤマガラ (?) が本来の生息地 (八丈島、御蔵島、三宅島) 以外でも記録されており、オーストンヤマガラなのか、色変異のヤマガラか議論がある。"ベンケイヤマガラ" と呼ばれている。
鈴木・樋口 (2004) Birder 18(11): 26 に三浦半島二子山での暗色ヤマガラの記録が紹介されている。この個体はオーストンヤマガラほど大きくなかったとのこと。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) によればオーストンヤマガラまたはこの色変異の可能性のあるヤマガラを指して "あいぜんがら" と呼ばれていたとのこと。
英名で Japanese Tit とも呼ばれることがあるそうである (コンサイス鳥名事典)。分布からはふさわしい名前であるが、この英名は通常はこれまでの分類で Parus minor のシジュウカラを指す。シジュウカラのこの英名が適切かどうかは用いる分類次第でもある (#シジュウカラの備考参照)。
[ヤマガラの変わり鳴き?]
学術的用語があるのかどうか知らないが、ヤマガラのさえずりに通常のものと異なったタイプのものがあり、variant song と呼ばれることがある。サンプル: XC626397 (Jerome Chie-Jen Ko)。場合によってはシジュウカラよりテンポが速いので例えばヒガラなどと混同される可能性があるかも。
さらにややこしいのは別の種類の "変わり鳴き" があって、さえずり要素のように聞こえる反復があって、しばしば知らない種類の鳥のさえずりかと思ってしまうことがある。
知ってしまえば疑問になるほどでもないが、先日この声を出しているヤマガラを観察してヤマガラの声と判断しにくい理由がある程度わかった。嘴を開けずに声を出しているので目の前の鳥がいるのに鳴いていると判断しにくいのだった。繁殖期でなくても聞かれること、発声時の行動から自分は地鳴きの性格の方が強いと考えている。
[ヤマガラの植物毒耐性]
上田 (2023) Birder 37(1): 29 によればヤマガラは他の鳥が食べない有毒な種子を食べるとのこと。
イチイ Taxus cuspidata の種子にはアルカロイドのタキシン (taxines 複数の物質がある) が含まれ、有毒物質の含まれない果肉を食べる鳥はあるが、ヤマガラは種子も食べるという。
シキミ Illicium anisatum にはアニサチンが含まれるがこれもヤマガラが食べる。
エゴノキ Styrax japonicus もアルカロイドのエゴノール (egonol) を含む。他の鳥も食べるがヤマガラは種子を割って食べるとのこと。
「野鳥」2021年7・8月号 (No. 803) pp. 14-15 (上田氏の会長挨拶) でもヤマガラが有毒な種子を食べることが触れられている。
日本のイチイ (Japanese Yew) の毒性は海外でも有名で、Japanese Yew (United States Department of Agriculture) のような記事があり、ペットや家畜、野生動物が食べて死亡する例がしばしば報告されている。
Shropshire et al. (1992) Evaluation of selected plants for acute toxicosis in budgerigars
pdf で読める。
ではセキセイインコでの実験が行われ、いずれも食べて2時間後には激しい反応を示して嘔吐を試みたり実際に嘔吐した。1羽は症状が出て15分以内に死亡したという。生きた鳥も2-4時間以上運動失調状態が続き、その後次第に回復した。Arai et al. (1992) のカナリアの実験でも毒性が強かった。
タキシン類の毒性は種差が大きく、ニワトリでは LD(min) 82.5 mg/kg とヒトの 3.0 mg/kg よりかなり高い [wikipedia 英語版: Clarke and Clarke (1988) "Poisonous plants, Taxaceae" in Veterinary Toxicology]。
Niznansky et al. (2022) Natural Taxanes: From Plant Composition to Human Pharmacology and Toxicity
のレビューによると Taxus 由来のの生理活性物質は必ずしもアルカロイドであることによらず、窒素を含まない化合物もあるため taxanes と総称されるらしい。
毒性が一番問題となるタキシン B (アルカロイドのもの) を摂取した場合の急性作用は胃液が酸性のためすぐに吸収され (アルカロイドは塩基性)、心臓の Na/Ca チャンネルと結合して伝導を阻害するとのこと。高血圧の治療に用いられるカルシウム拮抗薬は末梢の Ca チャンネルと結合して作用するが タキシン B は心臓に特異的に作用する点が異なる。ヒトの場合の死因の多くは心不全か不整脈とのこと。
アニサチン (anisatin) はアルカロイドではなくテルペノイドの1種 (sesquiterpenoid) で γ-アミノ酪酸 (GABA) 受容体をブロックする。
上田氏が研究チームに含まれる Yoshikawa et al. (2018) Highly toxic seeds of the Japanese star anise Illicium anisatum are dispersed by a seed-caching bird and a rodent
のシキミの種子分散の研究がある。ヤマガラ以外にヒメネズミ Apodemus argenteus も食べて両種とも種子分散に役立っている。
植物由来毒について消化管での解毒、尿に排泄、肝臓で解毒の毒物排除のメカニズムの研究があることが紹介されているが、ヤマガラやヒメネズミはまだ未解明。共生関係をなしている可能性もあるとのこと。
吸収経路を考えると、#ライチョウの備考にあるような、完全に植物食の鳥でみられるような腸内細菌による解毒はアルカロイドではあまり有効でなさそうに思える。
調べてゆくと有望そうな情報があったので少しまとめておく。
(1) 強心配糖体への耐性 (Na/K ポンプの α-サブユニット): 広範な動物における共通の耐性メカニズムと動物による植物由来毒の利用
「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 80 によればエボシドリがブッシュマンの毒とよ呼ばれる赤イチゴを食べても死なないとのこと。アデニウム属 (Adenium) のようで、Adenium boehmianum や Adenium obesum には強心配糖体が含まれ、矢毒に使われるとのこと。
強心配糖体は Na/K ポンプの α-サブユニットに結合するとある (wikipedia 日本語版)。
エボシドリではないが、Groen and Whiteman (2021) Convergent evolution of cardiac-glycoside resistance in predators and parasites of milkweed herbivores
によれば全ゲノム解析された鳥類データからチャバライカル Pheucticus melanocephalus Black-headed Grosbeak (イカルとは近縁ではなくホオジロ科に近い系統のショウジョウコウカンチョウ科。#ツリスガラの備考参照。チャバライカルのオスはオレンジと黒の鳥)
で Na/K ポンプの α-サブユニットの変異を見つけ、これが植物毒への耐性に関係している可能性が高いとのこと。wikipedia 英語版でも触れられている。
これは昆虫の毒耐性が1つのアミノ酸変異で起きる収斂進化から予言されていたとのこと [Whiteman and Mooney (2012) Insects converge on resistance]。
Ujvari et al. (2015) Widespread convergence in toxin resistance by predictable molecular evolution 毒耐性は収斂進化で分子レベルでよく予測できる (この論文には鳥は出てこないが結果的に鳥でも同様であることが確かめられることになった)。
毒のある食物を食べない種類には耐性がなく、耐性を持つのはコストがかかるので必要としなければ失われるらしい。
チャバライカルの耐毒性は古くから知られていて、「世界の鳥 行動の秘密」p. 87 心毒性のあるトウワタ類 Asclepiadaceae (milkweed foodplants) を食べるオオカバマダラ Danaus plexippus の幼虫を食べられる鳥が2種あって、ズグロムクドリモドキ Icterus graduacauda Audubon's Oriole は大量に食べると毒性を示すがチャバライカルは大丈夫とのこと
[Fink and Brower (1981) Birds can overcome the cardenolide defence of monarch butterflies in Mexico オオカバマダラは幼虫、さなぎ、成虫いずれも警告色を示すとされる]。
この分子機構が同定されたことになる。生態学のキーストーン種に相当するキーストーン遺伝子 "keystone genes" があるとのこと。
同じグループによるオオカバマダラの同じメカニズムの毒耐性は Karageorgi et al. (2019) Genome editing retraces the evolution of toxin resistance in the monarch butterfly にある。
Groen and Whiteman (2021) の研究によればチャバライカルの変異がおそらく最も強力だが、ジサイチョウ Bucorvus abyssinicus Abyssinian Ground-Hornbill にも似た変異がある。この種類は有毒なカエルを食べる。
#オニカッコウの項目で有毒な Cascabela thevetia の実を食べても大丈夫な種類に wikipedia 英語版からインドコサイチョウ Ocyceros birostris Indian Grey-Hornbill を取り上げていた。
後日気づいて追加: 「動物の世界」2版 13 (日本メール・オーダー 1986) pp. 1686-1690 のサイチョウの項目 (浦本・斎藤) に東南アジアのサイチョウにストリキニーネを含む有毒なマチンの実を食べるものがいるが、猛毒の成分を含む種子を割らずに飲み込むので安全との説明があった。この系統も Na/K ポンプの α-サブユニット由来の強心配糖体への耐性がありそう。
週間アニマルライフ (1974) にキバシコサイチョウ (現在は分離され、記述の学名通りであればヒガシキバシコサイチョウ) Tockus flavirostris Eastern Yellow-billed Hornbill がとげのある青虫を食べている写真が出ていた。
ニシコウライウグイス Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole に同様の変異の可能性があり、コウライウグイス類が有毒なガも食べるとの報告、食べるとまずい、警告色に分類されていることとも整合する可能性があるとのこと。コウライウグイス類が毒を利用しているか興味がある。
毒虫への実際の反応も含めて調べられた種類はアメリカのものに偏っているので旧世界の情報は少なめ。
絶滅したカロライナインコ Conuropsis carolinensis Carolina Parakeet もミトコンドリアの ATP ransporter に変異があり、この種の主な食物に含まれている有毒な carboxyatractyloside に耐性があるとのこと
[Gelabert et al. (2020) Evolutionary History, Genomic Adaptation to Toxic Diet, and Extinction of the Carolina Parakeet]。
いろいろな系統で食物に対応する形で起きていて、アミノ酸置換は散発的に比較的簡単に出現しそう。調べればもっと見つかるだろう。
Mohammadi et al. (2022a) Constraints on the evolution of toxin-resistant Na, K-ATPases have limited dependence on sequence divergence
でかなりの種類が調べられている (Supporting information S2 Dataset 参照)。毒耐性と変異の相関がよいことはわかっているが、個々の変異と毒耐性の関係はまだ明らかではない。以下は「可能性」を含めた検討として見ていただきたい。この中で毒耐性に関係のありそうな変異 Q111E に注目してみると、
シマオアフリカキヌバネドリ Apaloderma vittatum Bar-tailed Trogon、
ノドジロシギダチョウ Tinamus guttatus White-throated Tinamou、
コシギダチョウ Crypturellus soui Little Tinamou、
シロハラシギダチョウ Crypturellus undulatus Undulated Tinamou、
ヤシオウム Probosciger aterrimus Palm Cockatoo
および次の論文で述べるカッコウは候補になるかも知れない。ズグロムクドリモドキは調べられていない。
ヤツガシラも調べられているがあまり他種と差がない。有毒なヤツガシラを食べた経験からタカが嫌うようになったわけではなさそう。
ニシコウライウグイスで指摘されている Q111R を持つものは、
フタオビチドリ Charadrius vociferus Killdeer、
オオブッポウソウ Leptosomus discolor Cuckoo Roller、
キノドサケイ Pterocles gutturalis Yellow-throated Sandgrouse、
カカポ Strigops habroptilus Kakapo (植物食で発酵するのでいかにも?) がある。
キタベニハチクイ Merops nubicus Northern Carmine Bee-eater はどちらにもひっかかっていないので、ハチ毒耐性はこのメカニズムとは関係なさそう (ヨコジマハチクマ Pernis celebensis はゲノムアセンブリが発表されているがこの研究には間に合っていない)。
ヨーロッパシジュウカラも他種と似ているので有毒種子への耐性はおそらくなさそう。キレンジャクも同様で有毒種子を食べると中毒になりそう。ただしアカガシラエボシドリ Tauraco erythrolophus Red-crested Turaco と似ている (ヘビクイワシ、ミサゴとも似ているのであまり関係がないかも知れない)。
ここで検討したのは2つの変異だけなので、他のより効果の弱い変異まで含めるともう少し候補が増えそう。
ここで調べられた範囲では昼行性・夜行性とも猛禽類には植物毒への耐性傾向はなさそうで、毒鳥を食べるとやはり毒に当たるだろう。毒のある獲物を専門に食べていないためだろう。猛禽類が植物毒への耐性を持たないことは外敵防御に毒を使う鳥、および擬態が有効な理由になるだろうか。
Mohammadi et al. (2022b) Epistatic Effects Between Amino Acid Insertions and Substitutions Mediate Toxin resistance of Vertebrate Na+,K+-ATPases
の結果をみると Q111E がカッコウ科 (托卵性、非托卵性とも) で出現しており、この系統は耐性がありそう。有毒そうな毛虫を食べても大丈夫な理由がある程度理解できる。むしろ毒虫に特に適応した系統かも知れない (#カッコウの備考 [カッコウの植物毒耐性?] も参照)。#オニカッコウは実際にそのよう。
カンムリエボシドリ Corythaeola cristata Great Blue Turaco でも同じ変異が見られるが、エボシドリ類すべてではない。「世界の鳥 行動の秘密」のエボシドリがどの種かわからないがこの種か近縁種かも知れない (巻末の種類一覧では Tauraco corythaix Knysna Turaco となっているが一般名を指していた可能性もあり原著を見ないとわからない)。
Turaco Nutrition: A Complete Guide to a Healthy and Balanced Diet (Team Pro-Meal 2023) によればアボカドは有毒なのでエボシドリ類に与えてはいけないとある
[ペルシン (persin) が毒成分で通常ヒトに対しては無害だが鳥類には特に危険とのこと。毒性機構は明らかでないがアルカロイド系とは異なる模様でエボシドリ類でも対応できないのだろう。このページには (多分わざわざ与えないので) 強心配糖体を含む食物への注意はない。また色素に必要な銅をどのように与えるかも特に記載がない]。
Mohammadi et al. (2022b) では Otidimorphae の近縁性が現れていて エボシドリ目、ノガン目、カッコウ目に部分的に共通の基礎的変異があり、植物食、毒虫を食べる一部系統で系統固有のある程度の耐性を得ている模様。
Otidimorphae を含む Columbaves を調べた論文だが、ハト目は他の系統と特に違いがなく耐性は持っていないように見える。
サケイ目は独自の挿入を伴ってかなり変わっているが、どの程度耐性があるかは若干の実験的根拠がありそう。
#オニカッコウ備考にある有毒な実を食べることのできる種類ではコウラウン Pycnonotus jocosus Red-whiskered Bulbul が Mohammadi et al. (2022a) に含まれていて上記2種類の変異は持っていない。他の部位の変異も影響を与えている可能性がある。
Q111E を持つシマオアフリカキヌバネドリ Apaloderma vittatum Bar-tailed Trogon の変異と他の部位で共通点が見られ、耐性機序に関与している可能性が高そうに見える。
カンムリワシがこの変異を持っていることが明らかになった: #カンムリワシ備考の [カンムリワシの強心配糖体への耐性変異] Tobe et al. (2025) 参照。
ヤマガラは分子系統分類のための少数遺伝子は調べられているが、全ゲノム解析は調べた時点ではなさそうなのでまだこれからわかるのだろう。植物毒への耐性遺伝子だけに絞った解析はあり得るだろうが、全ゲノム解析はどこが最初に行うだろうか。仕組みはほぼわかってきたようなので後は解析を行うだけの模様。
Sittiparus属は他の種類もあるがいずれもゲノムアセンブリはまだ出ていない模様。この属ではヤマガラが一番有名種で、オリイヤマガラ、タイワンヤマガラ Sittiparus castaneoventris Chestnut-bellied Tit がそれに次ぐ。
ヤマガラは野外行動の証拠からはいかにも植物毒への耐性を持ってそうだが、植物種子を食べる時期にはヤマガラも多少の毒性を持っているかも知れない。派手な模様で結構目立ちそうに思えるが、あるいはヤマガラを食べて過去に気分が悪くなった猛禽類が避けているのかも。猛禽類がヤマガラをどの程度食べているかなど調べる価値がありそう。
ヤマガラの配色はもしかすると毒鳥で言われるような警告色になっている可能性もあるのかも? Sittiparus 属の他種ではどうだろうか。
同じグループがさらに後続研究を出している: Mohammadi et al. (2025) Historical Contingency Shapes Toxin Resistance in a Specialist Avian Predator (preprint)。
スズメ目で生じた V113L は毒耐性を弱める傾向があった。ちなみにアメリカオオモズのこの周辺の配列は耐性を特に持たないスズメ目 (例えば ビスマルクメジロ Zosterops hypoxanthus) と同じで Na+,K+-ATPase の分子レベルの毒耐性はなく行動で有毒な虫の摂取を防いでいるらしい。他の変異との相互作用など他の部分は複雑そうなので出版を待って後回しとしておく。
(2) テルペノイド耐性 (GABA 受容体)
Guo et al. (2023) Convergent resistance to GABA receptor neurotoxins through plant-insect coevolution
は植物食昆虫における GABA 受容体 (Rdl 遺伝子。さすがに鳥や哺乳類と共通ではない) の植物毒耐性と共進化が広範囲の系統において収斂進化したことを示している。殺虫剤耐性もあって昆虫でむしろよく調べられているかも。
受容体まわりの話なので、テルペノイド耐性と共進化のメカニズムは鳥や哺乳類でも同様かも知れない。
(3) カプサイシンへの反応と鳥・植物の共進化
化学構造も作用も異なるが、アルカロイドの一種であるカプサイシン (capsaicin) が鳥類の受容体に反応しないことはよく知られている。wikipedia 日本語版では鳥類はトウガラシを辛いとは感じず食べることができる。鳥類は食べ物を丸のみにするため、種が潰されない鳥類に食べられるほうが種の生存率が上がると考えられているとある。
出典となる研究はおそらく Tewksbury and Nabhan (2001) Directed deterrence by capsaicin in chillies。
カプサイシン は TRPV1 (transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 TrpV1、カプサイシン受容体) に作用するが、鳥類 (ニワトリ) の受容体アミノ酸を1つ変えるだけで (ニワトリで直接実験できないのでモデル動物を用いている) カプサイシンに反応するようになったとのこと:
Chu et al. (2020) A single TRPV1 amino acid controls species sensitivity to capsaicin。
この変異はカモ、ダチョウ、ハチドリと鳥類でよく保存されているがカエルやヘビではそうではなく鳥類系統で生じたものと考えられる。哺乳類に食べさせず、種を潰さない鳥類に食べられる戦略とよく合う結果になった。大絶滅を生き延びた鳥類が種子食だったらしいと考える仮説があって整合性があると書いていたがこれは読みすぎかも知れなかった。
小林 (2020) Birder 34(8): 30-32 (#鳥類系統樹2024で紹介) にも大絶滅を生き延びた鳥類が種子食だったらしいことが紹介されている。もっとも同所 Torres et al. (2025) も参照。現生鳥類と別系統ではない Galloanserae の古い系統で現生鳥類の直系の祖先と考えられる最も古い化石証拠 (大絶滅前) は、カイツブリ類やオオハム類のような深い潜水採食生態が考えられ種子食ではなかったらしい。#ミサゴの備考 [鳥類系統樹2024] Torres et al. (2025) も参照。大絶滅を生き延びた鳥類が種子食だったアイデアはどこから生じたのかなど紹介している。
なお TRPV1 は鳥によっては働かないものもあるらしい (#ワキスジハヤブサの備考参照)。おそらく面白い分野なのだろう。
カプサイシンに関係した鳥の話題では、薬理効果を利用した「鷹の爪」がある。はるか昔、この名前の商品に本当に鷹の爪が入っているのかとちょっと期待したことを白状しておこう (笑)。鷹ならば爪の垢を煎じて飲んでもよい気がすると思った (どれほど好きなのかと言われそう...笑)。
Shields (2022) Avian cardiomyocyte architecture and what it reveals about the evolution of the vertebrate heart
によれば鳥類の心筋細胞は形態的には変温動物の爬虫類に似ているが、哺乳類よりも高い心筋の能力を持っている。このパラドックスはまだ十分解決されていない。微細構造 [哺乳類では t-tubules、鳥類では calcium (Ca 2+) release units CRUs) の違いなどによる Ca 2+ の動態が異なる]、
心筋細胞の発生過程細胞分裂時の倍数化 (polyploidy。これは哺乳類と共通) などが関係していると考えられるがあまりわかっていない [これが心筋細胞が再生しないと言われる理由かと見てみるとやはりそのような考察があった。
Derks and Bergmann (2020) Polyploidy in Cardiomyocytes: Roadblock to Heart Regeneration?]。
分子機序などはまだこれから、というところだろうが恒温性を獲得した経緯における心臓の進化など興味を持たれている。鳥の心臓を知ることは再生医学にも役立つかも?
(4) 微小管のダイナミクスに関わる作用
taxanes に含まれる物質には抗腫瘍活性のあるものがあり、Taxol (タキソール) の商標のがん化学療法剤として使われる。微小管のダイナミクスを抑制して有糸分裂阻害作用がある。樹皮中の内生菌が合成していることが発見された (wikipedia 日本語版より)。タキシン B の心臓への作用以外にも、taxanes が微小管のダイナミクスに影響を与える可能性も考えられるかも知れない。
taxanes の中で薬物動態が一番よく調べられているのはこの系統の化合物だろう。こちらは肝臓で代謝を受ける酵素も同定されている。
世界の他の地域でも類似の化学物質を含む植物が見つかっており固有種であることも多い。名古屋議定書「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」(2010) は生物多様性条約 (1993) の COP 10 で採択されたものだが、生物由来有用物質や遺伝資源を用いて先進国の大企業が莫大な利益を得ていることも背景にある。
(5) 毒鳥ピトフーイなどの対毒性 (BTX 耐性) (Nav1.4 Na チャンネルの SCN4A)
毒鳥ピトフーイ (Pitohui) 類の複数種 (Pitohui, Ifrita kowaldi が有名) が羽毛に batrachotoxin (BTX) を含有し、有毒であることが知られている。
Bodawatta et al. (2024) Multiple mutations in the Nav1.4 sodium channel of New Guinean toxic birds provide autoresistance to deadly batrachotoxin (ePub 2023)
がゲノム解析によって ニューギニアの毒を持つ鳥の一部の種類に Nav1.4 Na チャンネルに関係する SCN4A 遺伝子に複数の変異があることを見出した。有毒なカエル Phyllobates 属も変異場所は違うが同じセグメントに複数の変異があり、収斂進化と考えられる。
毒を持つとされる鳥と完全に整合しているわけではないが、この研究で毒が確認された種類には共通の変異があった。また有毒とされてこなかった種類にも同じ置換を持つものもあり、知られていなかった有毒系統があると考えられる。
複数部位のアミノ酸置換がいろいろな程度の耐性に効いているらしい点は (1) 強心配糖体への耐性 (Na/K ポンプの α-サブユニット) と非常によく似ている。
この研究で カラス小目 Corvida はある程度調べられており、我々に馴染みのものではコウライウグイス (Oriolus 属)、カラス (Corvus 属) では見つかっていないよう。
これ以前の研究を少し紹介しておくと、ピトフーイのような仕組みで毒を持つ鳥は多系統にあり、カラス小目 Corvida に他にもあるかも知れないとのこと: Jonsson et al. (2008) Polyphyletic origin of toxic Pitohui birds suggests widespread occurrence of toxicity in corvoid birds。
この著者は幼虫が好みの Campephagidae (サンショウクイ科) が多少の毒耐性を持っているのでは、そして尾脂腺に分泌している可能性があるのではと推定している。
Bodawatta et al. (2024) は Corvida (この研究では Corvoidea カラス上科 と呼んでいて Boyd の用いている分類とは違う) に絞った研究を行っており、この予想をある程度裏付けることになった。
鳥が毒を持つかもしれないとの推測は Cott がエジプトで 1941 年オリエントスズメバチ Vespa orientalis がワライバト Spilopelia senegalensis Laughing Dove の死体に引き寄せられるのに ヒメヤマセミ Ceryle rudis Pied Kingfisher は忌避した観察に始まるとのこと。
ここからさまざまな鳥の肉をスズメバチ類や猫が食べるかどうかを調べ、"派手な色彩の鳥はまずい" 仮説に至ったとのこと。Weldon (2000) Avian chemical defense: Toxic birds not of a feather Cott (1947) に掲載された写真が紹介されている。
ピトフーイが警告色らしい色彩であったためこの仮説が再び脚光を浴びることになったとのこと。
Weldon (2000) は肉食動物が鳥を食べる時は羽毛をむしることが多いので、羽毛に毒を集積することは理にかなっていると解説している (後述のように捕食者対策よりも排泄経路の役割の方がより重要かも知れない)。
Abderemane-Ali et al. (2021) Evidence that toxin resistance in poison birds and frogs is not rooted in sodium channel mutations and may rely on "toxin sponge" proteins
[Marquez (2021) 解説]
の研究によると、調べた範囲で Na チャンネルには対毒性の変異はない。鳥では実験できていないが、同様に Na チャンネルには対毒性の変異がない有毒のカエルでは毒性を示した。チャンネルの変異はチャンネル機能の変化などコストが大きいので進化しなかったのでは。
フグなどの魚がテロロドトキシン (TTX) などに結合するタンパク質を持つように、カエルでは毒に結合するタンパク質 (Sxph が候補に挙げられている) が役割を果たしている可能性が考えられるがまだ確認されていないとのこと。この研究はしばらく有力候補として取り上げられていたが、Bodawatta et al. (2024) の解析では新しいタンパク質は発見されず可能性が低いとのこと。
TTX に対する耐性は鳥ではまだ報告されていない。#カンムリワシ備考 [猛禽類のヘビ毒耐性] の van Thiel et al. (2022) 参照。BTX と TTX の機構は似ており、ヘビ毒にも同様の機構のものがある。
Bodawatta et al. (2024) の研究が出たため今後新たな展開になるかも知れない。
どこが変異すればタンパク質の構造が変わってチャンネル特性を変えることができるか、分子構造計算から推定できそうだがあまりすっきりした結果が出ていない: Geffeney (2022) In Silico Analysis of Tetrodotoxin Binding in Voltage-Gated Sodium Ion Channels from Toxin-Resistant Animal Lineages。
耐毒性チャンネルのアミノ酸変異にはある程度共通性があるが、計算機上で得られた分子極性の指数などはあまり一貫性がない。耐毒性のタコやヘビ、イモリなどを扱っているが系統的にはかなり離れていて、哺乳類以外のチャンネルの機能や構造があまり知られていないこともあって単純な指数で表すのは限界もあるよう。
類縁種の範囲ではアミノ酸配列から予測できる部分もあるだろうが、現状ではアミノ酸配列のみからさまざまな分類群の動物の耐毒性を一般的に予測するのは難しそう。
少し前の有毒なカエルの対毒性のレビュー: Santos et al. (2016)
A Review of Chemical Defense in Poison Frogs (Dendrobatidae): Ecology, Pharmacokinetics, and Autoresistance。
さらに最近のレビュー: Gonzalez and Carazzone (2023) Eco-Metabolomics Applied to the Chemical Ecology of Poison Frogs (Dendrobatoidea)
毒矢に使われていた毒ガエルの正体は何かなども面白い。モウドクフキヤガエル Phyllobates terribilis Golden poison frog は脊椎動物中最も有毒とのこと。
有毒なカエルの "警告色" は本当に生態的意味があるのか、警告色を持つ種類は研究されているが同じ系統でも隠蔽色のものはあまり調べられていない、など鳥の視点でも面白そうな話が出ている。
アルカロイド毒は調べる方法が確立しているが他の化学防御物質は抽出方法なども含めてあまり研究されていない。
アルカロイド毒のうち脂溶性アルカロイドは生合成、食物からの濃縮や代謝産物などいくつかのルートがある。これら毒ガエル類に含まれる親水性アルカロイド (TTX を含む) がどのように作られるかはよくわかっていない。カリフォルニアイモリ属 (以下に) では皮膚細菌が TTX を合成することが報告されているが、毒ガエル類の細菌叢ではこれまでの研究で TTX を検出できなかったとのこと。
Gonzalez et al. (2021) First characterization of toxic alkaloids and volatile organic compounds (VOCs) in the cryptic dendrobatid Silverstoneia punctiventris
によればこの系統の隠蔽色のカエルにもアルカロイドを含む化学防御物質が見つかったとのこと。
隠蔽色のカエルでも TTX を持っている可能性や、Aromobates nocturnus は不快臭 (メルカプタン臭) を出すとのこと。警告色と毒性が関連している系統もあればそうでない系統もある。
毒ガエルに対する行動学的研究は一部の霊長類で行われている程度で鳥などの他の捕食者については事実上わかっていない。
メルカプタン臭をもたらしている化学物質は同定できていない。これまでの研究は薬理学的価値があると考えられるアルカロイドに対するものが中心で他の物質はあまり調べられていない。今のところ確実にわかっている防御物質は不快味をもらたすアルカロイドのみとのこと。
Silverstoneia punctiventris においては複数段階の化学防御が考えられていて (i) 揮発性化学物質が捕食者に有毒アルカロイドの存在を知らせる防御フェロモン的役割を果たす (olfactory aposematism)、(ii) 有毒アルカロイドも揮発して離れた捕食者に忌避反応を起こす、(iii) 揮発性化学物質 + 有毒アルカロイド の複合作用。
有毒アルカロイドが忌避反応を起こすならば鳥が最も数の豊富なこのカエルを忌避する理由が説明できるとのこと (必ずしも嗅覚によらなくても末梢のイオンチャンネルに作用することで毒物の存在を感知できる。この意味では末梢のイオンチャンネルの感度が高い方が鳥が毒物を摂取する可能性が減ることになる)。捕食者防御化学物質が他の役割 (節足動物を防ぐ、フェロモン、化学コミュニケーションなど) も果たしている可能性がある。
Silverstoneia punctiventris から分離された化合物の中にはヒトも含めた他の生物と共通のものがある。カエルの種によっては一部の物質は細菌が合成していることが知られているとのこと。
毒を有するカリフォルニアイモリ属 Taricha を食べる garter snakes の TTX 耐性の進化: Predator-Prey Arms Race (解説ページ)。ヘビ類でまず末梢神経の NaV1.7 の耐性から始まり、約 5000 万年前に NaV1.6 の耐性が進化した。末梢神経のチャンネルですでに耐性を持った一部の系統で骨格筋の NaV1.4 の強力な耐性が進化したとのこと。
以下の Perry et al. (2018) も参照。
garter snakes などの一部の種類はフグの捕食者となっているらしい。参考: Feldman et al. (2010) Genetic architecture of a feeding adaptation: garter snake (Thamnophis) resistance to tetrodotoxin bearing prey。
まず末梢神経からは妥当な順序で、運動など機能に制約をもたらす骨格筋での適応は後から進化したのだろう。
McGlothlin et al. (2014) Parallel Evolution of Tetrodotoxin Resistance in Three Voltage-Gated Sodium Channel Genes in the Garter Snake (Thamnophis sirtalis
garter snake では TTX 耐性の平行進化が起きている。哺乳類の grasshopper mice (Onychomys spp.) では有毒なサソリ (Centuroides) を捕食して NaV1.8 に変異があるとのこと [Rowe et al. (2013) Voltage-Gated Sodium Channel in Grasshopper Mice Defends Against Bark Scorpion Toxin]。
garter snake では哺乳類で耐性に関連している NaV1.5, 1.8, 1.9 の配列は読めなかったが、この時点でのゲノム解析の範囲では真骨類 (真骨魚類)、両生類、鳥類、爬虫類ではこの変異は見つかっていないとのこと [Vornanen et al. (2011) Tetrodotoxin Sensitivity of the Vertebrate Cardiac Na+ Current 。NaV1.5 は特に心臓に関連がある]。
garter snake では中枢神経に関係する Nav1.1-1.3 の変異は認められず、これは TTX が血液脳関門を通らないことを反映しているとのこと。
Zakon (2012) Adaptive evolution of voltage-gated sodium channels: The first 800 million years
少し前のものになるが主に脊椎動物での NaV チャンネルの進化について。
羊膜類の共通祖先段階で NaV1 は9個の遺伝子を持っていたが哺乳類の進化初期に遺伝子重複が起きて 10 個になったとのこと。
電気魚、有毒なヘビやフグなどの魚類、哺乳類では naked mole rat (Heterocephalus glaber ハダカデバネズミ。ほぼ完全に外温性とのことでさまざまな過酷環境に対応できるあまり哺乳類らしくない種) の特殊な環境への適応でそれぞれ進化したことが知られているとのこと。
ハダカデバネズミでは人では痛みを感じる (H+ に神経末端が反応している) ほどの高い CO2 濃度でも電気的反応がない。NaV1.7 の変異で低い pH でも痛みの感覚が発生しないらしい。
Hague et al. (2018) Large-effect mutations generate trade-off between predatory and locomotor ability during arms race coevolution with deadly prey。garter snake では TTX 耐性で運動能力が下がる結果が得られているとのこと。捕食者にとっては TTX 耐性と運動能力はトレードオフの関係にある。
複数の地域で独立に進化が起きていて、運動能力を犠牲にしても TTX 耐性を進化させるに見合う地域のみで進化が起きていると考えると説明しやすい。
del Carlo et al. (2023) Coevolution with toxic prey produces functional trade-offs in sodium channels of predatory snakes (preprint) にも同様の研究がある。TTX 耐性を持つ筋肉は収縮力や速度に劣るとのこと。
複数の地域で独立して進化が起きている点は世界規模で Feldman et al. (2012) Constraint shapes convergence in tetrodotoxin-resistant sodium channels of snakes の図もわかりやすい。
TTX 耐性進化はランダムな変異による適応度地図上の探索 (adaptive walk along a mutational landscape) でうまく表現できるが目的に至る経路と解には制約があって独立に進化してもある程度同じような結果に落ち着いている。
より短い探索パスで TTX 耐性を得たものもあるとのこと: Reimche et al. (2022) The road not taken: Evolution of tetrodotoxin resistance in the Sierra garter snake (Thamnophis couchii) by a path less travelled。
これまでは NaV チャンネルの α サブユニットに注目して研究が行われてきたが、あまり注目されていなかった β チャンネルも TTX 耐性と関連している可能性もあるとのこと。Seneci and Mikheyev (2024) Sodium Channel β Subunits-An Additional Element in Animal Tetrodotoxin Resistance?
まだアミノ酸配列や塩基置換から正の選択を受けている場所を推定している段階だが、TTX 耐性に特異的と言える部位は同定できず。ただし α サブユニットと結合するので役割を果たしている可能性はある。
この中でヘビクイワシにも言及があり behavioral resistance と表現されている。毒耐性は持たないが行動で毒を防いでいる。
有毒な外来のカエルの毒の部分を物理的に除去する行動は Australian rakalis (Hydromys chrysogaster オオミズネズミ) で知られているとのこと。cf. Parrott et al. (2019) Eat your heart out: choice and handling of novel toxic prey by predatory water rats。学習によるものか在来種の捕食行動から発達させた行動か。
行動学は Seneci and Mikheyev (2024) の論文の主眼ではないので探せばもっと事例があるかも。
これらを見ていると鳥は圧倒的に上位消費者が多いので、鳥にとって特に重要そうな運動能力に影響を与えそうな骨格筋でイオンチャンネルを変異させてまで毒耐性を持つ必要性があまり生じないかも。(TTX とは異なるが) 有毒物質を持つ鳥がわずかな系統に限られているので、ヘビ類のように段階的に耐性を進化させた兆候もなさそう。
ヘビ類は魚などの捕食者であるとともに、特に鳥類捕食者にも狙われるため毒を持つことが見合う部分もあるのだろう。
捕食者の鳥自身は警告色が通じる程度に頭もよいので一般的には行動以外の方法で防御に頼る必要はあまりないかも。
Robinson et al. (2024) Where Does All the Poison Go? Investigating Toxicokinetics of Newt (Taricha) Tetrodotoxin (TTX) in Garter Snakes (Thamnophis)
によればイオンチャンネルの変異だけがすべてではなく、毒の代謝や排泄速度も早いとのこと。代謝や排泄の方が先に進化した可能性もある。ヘビに毒は数日から数週間残るが自身にも有害で排泄を早めている点は毒鳥ピトフーイで提唱されている考えとも似ている。garter snake の毒も従来想像されたほどには鳥類捕食者対策向けでもないのかも。
Perry et al. (2018) Molecular Adaptations for Sensing and Securing Prey and Insight into Amniote Genome Diversity from the Garter Snake Genome も面白い。オプシン遺伝子に関連して#イヌワシの備考 [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] *5: オプシン の備考に紹介している。
この論文に TTX 耐性の進化も考察されており、耐性に関係するある変異は羊膜類の共通祖先段階に獲得したが鳥類系統では失われた可能性も示されている。鳥類を生む系統 (現生のものは鳥類だけなのでどの段階で失われたかは不明。化石種で外見は鳥らしくても TTX 耐性を持っていたかも知れない) ではパフォーマンス向上 (?) のためにむしろ積極的に TTX 耐性を捨てたのかも知れない。
鳥類が陸上に上がるごとに化学受容の遺伝子が減ったり (#マガモ備考の [カモノハシ] など)、毒物代謝機能の必要性が低下する (#ミヤコショウビン備考の [グアム外来ヘビの駆除とヘビ類の特異な薬物感受性] など) など地上に束縛されない生活への適応が遺伝子にも現れている模様。そして最も樹上性で進化した Telluraves を生んだ順序となる。
(6) オーストラリアのハト類のモノフルオロ酢酸耐性
Leong et al. (2017) Fluoroacetate in plants - a review of its distribution, toxicity to livestock and microbial detoxification
オーストラリア、ブラジル、南アメリカの植物 (Acacia spp., Gastrolobium spp., Oxylobium spp. など) がおそらく草食動物への防御としてモノフルオロ酢酸を合成する。
また Compound 1080 の名前で殺鼠剤などの目的で用いられたが、非特異的にさまざまな動物に害を与えるため現在では規制されている。酢酸と化学構造が非常に似ていて、フルオロクエン酸に代謝されるがそれ以上の代謝が進まないためにアコニット酸ヒドラターゼ (アコニターゼ) 酵素を阻害して TCA サイクルを阻害し、ATP 合成が止まり、クエン酸が蓄積することでアシドーシスや代謝に異常を起こす。
オーストラリアのハト類にこの毒耐性を持つものがある。ニジハバト Phaps chalcoptera Common Bronzewing、チャノドニジハバト Phaps elegans Brush Bronzewing。box-poison pigeon の別名もある。
毒は筋肉には蓄積しないが内蔵や骨にはあるそうで、骨を食べたペットが中毒したケースがあるとのこと。
[情報は 茂田 (1996) Birder 10(9): 40;「動物の世界」37 p. 824; Yeung et al. (2022) Avian Toxins and Poisoning Mechanisms よりまとめた]。
オーストラリアでは移入種も含めて肉食哺乳類への毒性が強く、直接毒に接することの多い種子食の鳥で耐性を持つものが多い (#ミヤコショウビン備考 [グアム外来ヘビの駆除とヘビ類の特異な薬物感受性] も参照)。エミューではこの毒のある地域に生息するものはそれ以外の地域に比べて 150 倍の耐性が報告されている。
殺鼠剤として使われた経緯もあり猛禽類の二次的中毒の影響も調べられているが比較的毒性が弱いとのこと: Martin and Twigg (2002) Sensitivity to sodium fluoroacetate (1080) of native animals from north-western Australia
肉に蓄積しないので影響が比較的少ない。また植物毒のある環境に住むチャイロハヤブサやフクロウ類 (オーストラリアメンフクロウ?) はおそらく多少の耐性を持っているだろう。
種子食の鳥の耐性メカニズムは相対的な酵素の働きや分解能力の違い程度でよくわかっていないが、反芻動物では分解する共生細菌を持つものもある。
(7) grayanotoxin グラヤノトキシン (ジテルペン)
これも (5) 毒鳥ピトフーイの毒と同様に Na チャンネル (voltage-gated sodium channel group II receptor) に結合する。
北米のエリマキライチョウ Bonasa umbellus Ruffed Grouse が mountain laurel Kalmia latifolia からこの毒を摂取し、エリマキライチョウを食べた人が中毒した事例があるとのこと。
この毒は Rhododendron spp. の蜜由来でハチミツに含まれ、黒海沿岸アナトリアで "mad honey disease" としてむしろよく知られている。cf. Jansen et al. (2012) Grayanotoxin Poisoning: 'Mad Honey Disease' and Beyond。
エリマキライチョウの情報は Yeung et al. (2022) より。ハチミツに含まれるならばハチ幼虫にも含まれるのか気になってくる。
エリマキライチョウの Na/K ポンプの α-サブユニット配列はまだ調べられていないが、毒鳥ピトフーイ同様に別機構かも知れない。
-
ヒガラ
- 学名:Periparus ater (ペリパルス アーテル) 黒いシジュウカラに似た鳥
- 属名:periparus (合) シジュウカラに似た鳥 (peri- (接頭辞) およそ Gk、シジュウカラ Parus 属)
- 種小名:ater (adj) 黒い
- 英名:Coal Tit
- 備考:
periparus は合成語で peri の由来のギリシャ語は短母音のみでおそらく短母音のみと考えられる。
parus は短母音のみで、規則からは "ペリパルス" のアクセントと考えられる。
ater は冒頭が長母音でアクセントもここにある。
Poecile 属の定義時はヒガラも含まれていた (#ハシブトガラ参照)。
英名の Coal Tit はドイツ語名とも関連するかと期待したが、"Coal Tit" に対応するドイツ語名は(ヨーロッパ)シジュウカラの方に使われてた。ヒガラは Tannenmeise でもみの木のカラ。"黒いカラ" の名称はフランス語などいくつかの言語で用いられている。
OED によれば Coal Tit は coal titmouse を短縮したもので、Pennant (1766) に Cole Titmouse として現れる。Pennant (1812) で The head of the cole titmouse is black で頭の色を指したことは明確。
ユーラシアに広く分布し、世界で 21 亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は insularis (島の) とされる。
亜種記載時学名 Parus ater insularis Hellmayr, 1902 (参考) 基産地 Suruga, island of Hondo. From Alan Owston で、本州が基産地だったが Parus 属に japonicus がすでに用いられていたため (#ハシブトガラ備考参照) 用いることができなかったと考えられる。
台湾には insularis と ptilosus (「羽衣、羽」の意味) の両亜種が分布しており、外見とさえずりで区別可能とのこと。屋久島を訪れた台湾の観察者 Ko Chie-Jen が両亜種のさえずりを記録している (xeno-canto 2015)。
こちらは Parus ater ptilosus Ogilvie-Grant, 1912 (参考)。
1930 年代まで西日本で和名がコガラと混同されていて、古い文献を読む時に注意が必要 (コンサイス鳥名事典)。
-
キバラガラ
- 第8版学名:Pardaliparus venustulus (パルダリーパルス ウェヌストゥルス) 小さな魅力のあるホウセキドリのようなカラ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Periparus venustulus (ペリパルス ウェヌストゥルス)
- 第8版属名:pardaliparus (合) Pardalotus (ホウセキドリ) 属と Parus 属の名前から合成
- 第7版属名:periparus (合) シジュウカラに似た鳥 (peri- (接頭辞) およそ Gk、シジュウカラ Parus 属)
- 種小名:venustulus (adj) 小さな魅力のある (venustus 魅力のある -ulus 指小辞)
- 英名:Yellow-bellied Tit
- 備考:
pardaliparus は合成語で pardalote (由来はフランス語。英語でも同じ語が使われる) の語源となるギリシャ語 pardalotos は最初の o が長母音。
parus は短母音のみで規則からは pardaliparus のアクセントは -li- にあると考えられる。長音由来でアクセントがあることから "パルダリーパルス" と読むとよいと思われる。pardalos はヒョウのことでホウセキドリは斑点がヒョウに似ているとのこと (The Key to Scientific Names)。
英語の leopard も leo + pard である。ラテン語にも leopardus の名詞があり、leopardi の変化形になると語末の i が長母音となり上記解釈とも整合する。
leopard の pard に関連すると考えれば属名も少し覚えやすくなるかも知れない。
venustulus はすべて短母音で ve-nus-tu-lus と分割され "ウェヌストゥルス" のアクセントになる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。 日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Pardaliparus 属
[Pardalotus 属 (オーストラリアに分布するホウセキドリ類の属名で英語で pardalote、と Parus 属の名前から合成] に変更。
Johansson et al. (2013) の研究 (#ヤマガラの備考参照) で
Periparus 属から Pardaliparus 属が分離された。元来の Periparus 属7種は単系統であったが2系統に分割でき、分布域も違っているために2属に分けられた。
種小名は変化なし。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。Pardaliparus 属はキバラガラ属。単形種。
かつては中国の固有種とされたが、梅垣 (2019) Birder 33(1): 48-51 によれば近年は朝鮮半島でも繁殖し、分布拡大中かとある。
Breeding Yellow-bellied Tit (2023) の Yellow-bellied Tit の項目では、韓国の初記録は 2005 年。全国的に急速に数を増やしており 2017 年に繁殖を初確認。その後も繁殖記録が増えているとのこと。
eBird でも韓国で多数の記録が報告されている。
Gluschenko and Belyaev (2023) New observations of the yellow-bellied tit Pardaliparus venustulus in the south of Primorsky Krai (pp. 2875-2879) にロシア沿海地方の記録が紹介されている。
21 世紀に入って急激に分布を広げている種の一つとある。2023年6月の観察でこの種のものと考えられる巣の跡が見つかっており、詳細はわからないはひなが見えた。さえずるオスの密度はシジュウカラにも次ぐ程度になっているとのこと。他のカラ類の方が少ないぐらい。
日本でも出現記録の増えている種類はやはり進出の最中と納得させられる研究だった。そのうち珍しくもなんともなくなるかも?
Gluschenko et al. (2024) Materials for the study of the yellow-bellied tit Pardaliparus venustulus on the Borisovskoye plateau (Southern Primorye) (pp. 3623-3635) にも後続情報がある。
-
シジュウカラ (合体で日本産学名も変わった)
- 第8版種学名:Parus cinereus (パルス キネレウス) 灰色のカラ (IOC も同じ)
- 第8版亜種学名:Parus cinereus minor (パルス キネレウス ミノル) 小さい灰色のカラ (代表的亜種。他亜種あり)
- 第7版学名:Parus minor (パルス ミノル) 小さいシジュウカラ (新提案の学名では灰色のカラ)
- 属名:parus シジュウカラ類
- 第8版種小名:cinereus (adj) 灰白色の
- 第7版種小名:minor (adj) より小さい
- 英名:[Japanese Tit 統合前の旧名]。新分類では Cinereous Tit となる。Asian Tit の名称も使われる
- 備考:
cinereus は短母音のみで -ne- にアクセントがある (キネレウス)。
minor は "ミノル"。
major は "マヨル"。
[一般名の語源]
英語の tit は複数の語義があるが、カラ類を指すものは北ゲルマン / スカンジナビア語起源と推定されており、最も早い用例は titling, titmouse とされるとのこと。フェロー語の titlingur はいろいろな小型の鳥、主にタヒバリ類を指す。
アイスランド語で titlingr ("tit sparrow")、古ノルド語に titlingr (スズメ)、tittr (シジュウカラ類) の類似例があり、言語的には北方起源らしい (wiktionary)。
ドイツ語では Meise で遡るとゲルマン祖語の maiso だがそれ以前は不明とのこと。複数の説があるとのこと。ラテン語でクロウタドリを指す merula との共通語源説、ノルウェー語の meis (弱い) に関係、あるいはゲルマン祖語の *meisa- (小さい) に関係あるなど (wiktionary)。
フランス語 mesange は直接には中世ラテン語 misinga から、またゲルマン祖語 maiso とも関係、英語の古名 mase (小さい鳥) とも関連する (wiktionary)。
ロシア語 sinitsa は青い (sinij) に直接関係すると思っていたら半分俗説らしく、zinitsa, zin' から音が変わったものと解釈されているらしい。こちらは音声由来とされているが sinij の影響を受けた可能性がある (Kolyada et al. 2016)。音声由来ならばいかにも地鳴きのよう (英語の chickadee 同様)。しかし多くのロシア人は俗説の方で納得しているのでは?
ウクライナ語でもほとんど同じで sinitya。ポーランド語がやや面白く bogatka で bogaty (豊かな、金持ちのなど) に由来。数がたくさんいるので? (未確認)。
和名のシジュウカラの語源はいくつも提案されているようで、群れること (40 羽は比喩) や音声由来説などがある (「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990)。音声由来であればカラ類は地鳴き由来の名称が世界的に共通性が高いことになる。確かに音程変化が中心のさえずりより音質が現れやすい地鳴きの方が人語で表現しやすいかも知れない。
群れること由来であればあるいはポーランド語の発想に近い可能性があるかも。
[旧シジュウカラの分割と合体]
合体のため第8版学名は代表的亜種の例を記した。
もと現在のヨーロッパシジュウカラ Parus major と同種であったものが分離されて独立種となった。Parus major 時代の亜種小名が minor であったため Parus minor となった。この時には「シジュウカラが格下げ」と話題になった。
ヨーロッパシジュウカラはユーラシアに広く分布し、ロシア極東部でシジュウカラと分布が重なるが交雑程度が低いため別種と判断された
[Nazarenko et al. (1999)
Secondary contact and overlap of Parus major and Parus minor populations in the middle Amur River basin。
Nazarenko et al. (1999) にも論文があり、極東の鳥類 31 で和訳が読める]。
以下の Paeckert et al. (2005) も参照。
旧 Parus major からはさらにもう1種 Parus cinereus (「灰色の」の意味) 英名 Cinereous Tit [クロシジュウカラ] (とも呼ばれるが、後述の問題があるため括弧付きで記述する) が分離され、現在までの分類 (例えば IOC 14.1 まで) ではインド、ビルマ、タイからインドネシアを中心に分布するとされる。
この3種への分類は分子遺伝学と音声の研究 Paeckert et al. (2005) The great tit (Parus major) - a misclassified ring species による。この文献に分布、分子系統樹が出ている。
東南アジアからネパール、アフガニスタンにかけてもう1種 キバラシジュウカラ Parus monticolus (「山に住む」の意味)が分布し、シジュウカラと [クロシジュウカラ] の間の中間に位置する分布 (および台湾) となっている。Paeckert et al. (2005) の研究では分子系統的には上記3種のシジュウカラとはかなり離れている
(2024年6月以前の記述は情報が古くなったので以下まとめ直した。2024年7月に世界の複数リストが Parus minor と Parus cinereus を1種にまとめる分類を採用した。その経緯を検討する)。
Clements 2024 の草稿に続き、IOC 14.2 の編纂段階で 2024.7.10 に合体して2種とする案が採用された。日本のシジュウカラも世界のリストで Parus cinereus となる予定。
Zhao et al. (2012)
Pleistocene climate changes shaped the divergence and demography of Asian populations of the great tit Parus major: evidence from phylogeographic analysis and ecological niche models 主に中国のシジュウカラを調べたもので5クレードを認めた。
Song et al. (2020) Great journey of Great Tits (Parus major group): Origin, diversification and historical demographics of a broadly distributed bird lineage
(出版社サイト)
が最新の分類の根拠となる最新論文。
Zhao et al. (2012) と Song et al. (2020) は用いている遺伝情報が異なるため結果が少し異なっている。
後者によればシジュウカラはおそらく東南アジアが由来で地理的隔離や気候変動によって分化が生じた。この研究では5クレードが認められ、推定分岐年代は 157-50 万年前と推定され、最も古い分岐に対応する形で2種の扱いとした模様。
次に古い分岐が {東アジア + 南アジア} と 東ヒマラヤ の間で、推定分岐年代は 111 (73-153) 万年前 となかなか微妙。これらは tibetanus, subtibetanus を含むとのこと。
この研究によって日本と中国や韓国の個体群を別種とする遺伝的根拠がない結果となった。これまでの Parus cinereus と Parus minor の地理的境界は支持されなかった。
この論文ではマレー半島とジャワ島をそれぞれ1例含んでいて日本を含む東アジアクレードと同じと分類しているが、サンプル数が少し少ないかも知れない。
cinereus の基産地が Batavia (ジャカルタのオランダ植民地時代の名称) とある (記載時学名 Parus cinereus Vieillot, 1818; 原記載 フランス語名 La Mesange grise) ので、ジャワ島の個体群を同種とするかどうかで種小名が変わる。
東アジアとマレー半島 + インドネシア の間に顕著な地理的障壁がなく種分化は起きていないだろうとの判断も含まれていると思われるので、確定のためにはもう少しデータが欲しい印象を受ける。
Latest IOC Diary Updates で英名の議論もあり、Cinereous Tit 以外に以前の学名に基づく Lesser Tit でもよいのではとの意見も出ている。
Cinereous Tit の包含範囲が大きく変わるので (英名の由来となる基亜種の分布も狭く) 新しい名前を与える方が適切との認識による議論だろう。確かに Cinereous Tit の英名を用いるとこれまでの概念と区別が付かない可能性がある。IOC は暫定的に Cinereous Tit を与えている。
世界も含めた分類が変更された現状ではシジュウカラの種英名に Japanese Tit を使い続けるのはふさわしくない (分類概念が異なる)。亜種シジュウカラの英名として使う範囲であれば問題ないように思えるが、過去の Japanese Tit の概念とは異なることに注意が必要であろう。シジュウカラの種英名は日本鳥類目録第8版にも従い現状では Cinereous Tit がふさわしい。
AviList でこの分類が採用され英名は Cinereous Tit。Clements v2024 で Asian Tit と英名は統一されていない。
AviList の解説では 20734 1100 The Parus major complex is treated as comprising two species, western and central Palaearctic Parus major and southern and eastern Asian Parus cinereus (including subspecies in the minor complex), based on the level of mitochondrial DNA divergence between them (Zhao et al. 2012; Song et al. 2020), presence of a narrow hybrid zone (Kvist & Rytkonen 2006), and vocalizations (Paeckert et al. 2005).
なおこの英名も紛らわしいものがあって、ハイイロガラ Melaniparus afer Grey Tit。"Cinereous Tit" をそのまま訳すと同じような意味になってしまう。
日本で記録されるものは minor 亜種シジュウカラ、amamiensis アマミシジュウカラ、okinawae オキナワシジュウカラ、nigriloris (「黒い目先」の意味) イシガキシジュウカラ、及び亜種不明である。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" では当時の分類で nigriloris を Parus cinereus に含めていた。Brazil (2009) の概念に従えば日本にシジュウカラが2種生息することになる (最新の分類では統合されたのでこの問題は発生しなくなったが、イシガキシジュウカラを観察して1種と数えていた人にとってはライフリストが減ることになる)。
日本鳥類目録第7版では minor の亜種扱いと少し異なっていた。
亜種 minor の記載時学名は Parus minor Temminck & Schlegel, 1848 (原記載) で、ヨーロッパのものより小さいことが述べられている。
フランス語名 la mesange charbonniere du Japon。Temminck (& Schlegel) の他の用例も参考にするとヨーロッパのシジュウカラの日本版の意味で用いたと考えられる。英名などはこのフランス語名に由来したかも知れない。
race du Japon とあり、現在では亜種に相当する位置づけと考えられるが当時は亜種の学名記述方法は確立したものでなく、種名の形で表したと想像できる。Parus major の小型版なのであまり考える必要もなく Parus minor となったものだろう。
同じ文献で Temminck and Schlegel は同属でヤマガラ (および広い意味の同属でエナガの亜種) も記載しているのでいずれにも日本を意味する学名は付けにくかったと考えられる (#タンチョウ備考の Temminck の学名に対する見解参照)。
Parus major は Linnaeus (1758) が用いたので問題ないが、minor のようないかにもありがちな名前が Parus 属の過去の学名と重複しなかったのが不思議な感じもする。Temminck & Schlegel (1848) より早い時代の Parus 属の命名ではすでに凝った種小名が用いられていたので、何らかの理由で minor は避けられていたのかも。
Temminck & Schlegel (1848) より早く Parus minimus Townsend, 1837 や Parus minutus Jerdon, 1840 など別の語で "小さい" を示す用例がすでにあった。Temminck & Schlegel (1848) が初記載となったが、あるいは Parus minor の学名は文書には残っていないがすでに使われていたのかも。
Japanese Tit Systematics に過去に記載された (多くはシノニムとなった) 多数の亜種がリストされている。
しばしば話題となるところでシジュウカラの和名に基づく Parus major sidsiukara Momiyama, 1927 があり、九州と本土で亜種が違うと考えたようだが、タイプ標本も挙げられておらず記述も十分なものではなく無効学名となった。
[ここから古い記述を保存のために残しておく]
この部分は、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でシジュウカラの学名が Parus cinereus と変更されたことに際し、当時の世界のリストで Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) のみがこの分類を用いていたため、このリストの記載文献をもとに分類変更の理由を検討してみたものであった。
実は Song et al. (2020) の分子系統研究がすでに出版されていたのでそちらも参照すべきであった。
(ここから) 参考までに Kvist et al. (2003) Evolution and genetic structure of the great tit (Parus major) complex にも先行研究があるが、Parus cinereus についてどのサンプルを用いたかなどの状況は同じである。
ただし調べられたサンプルの間で major, bokharensis, cinereus, minor はよく分離した系統をなしており、それぞれを種とみなしても構わないだろうが、その場合は種間の交雑を前提としたものになるとしている。
日本鳥類目録 改訂第7版や、IOC (14.1 まで), Clements (2023 まで) などの分類変更は主にこれらの研究をもとにしたものと考えられる。
ただし Paeckert et al. (2005) 自身も述べているように Parus cinereus で対象としたものはネパールの個体群で、Parus minor とはこの解析では遺伝的に離れているとは言え、中国の Parus cinereus 個体も同じであるかはわからない。
Paeckert et al. (2005) は旧 Parus major を3分割するこの分類は暫定的なものとして、東南アジアでの cinereus グループと minor グループの遺伝子や音声の研究がさらに必要であると述べている。
この2グループは伝統的には背中のリポクロームの色彩で判別されてきたもの (cinereus にはこの色彩がない) であるが、音声は似ていると述べている。
Paeckert et al. (2005) は bokharensis グループ [Paeckert et al. (2005) の地図参照] は形態的には異なるが遺伝的には major との違いが小さく、Parus major に含めるべきとしている。
この論文が出された後、Eck and Martens (2006) Systematic notes on Asian birds. 49 A preliminary review of the Aegithalidae, Remizidae and Paridae
では遺伝的に異なっていてもそれが必ずしも外見に反映されるものではなく、違いが遺伝子レベルでないと「見えない」ことを一つの問題としている。音声研究はこの状況を一歩進めるのに役立つと述べ、自身が他文献で発表した結果なども用いて Parus 属、Aegithalos 属などの分類をレビューしている。
焦点となる cinereus グループと minor グループの扱いについては、いくつかの交雑場所が存在し、歴史的にはそのうち commixtus (「混ざった」の意味) のみがこの2グループが交雑した亜種として記述されてきた。中国南東部からおそらくタイにかけての交雑場所での個体群構造や交雑の度合いや音声についてはほとんどわかっていない。
分子遺伝学研究もほとんどわかっていない。
ミャンマーからベトナムにかけてはこの2グループがモザイク状に分布している。
minor グループと狭義の major
(ヨーロッパの個体群) との違いは音声でも明瞭であるが、cinereus グループと minor グループの間には共通点もあるとのこと。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol. 1-2) ではこの研究をもとに Parus cinereus (このリストでの英名 Cinereous Tit) に
minor (サハリン南部、千島南部、日本の九州まで)、
amamiensis (奄美黄島、徳之島)、
okinawae (沖縄島)、
nigriloris (西表島、石垣島)、
そして海外では
wladiwostokensis (ロシア極東部; IOC では minor のシノニムとされる)、
artatus (中国北部の中央から東部、東部中央)、
dageletensis [韓国の鬱陵島 (うつりょうとう、Ullung-do)]、
tibetanus (中国チベット自治区、ヒマラヤ、ミャンマー北部)、
subtibetanus (中国雲南省北部)、
commixtus (中国南部から東部、台湾、ベトナム北東部)、
nubicolus (東南アジア大陸部でミャンマー東部からベトナム北西部) までをグループ 1、
hainanus (海南島)、
decolorans (アフガニスタン北東部、パキスタン北西部)、
ziaratensis (アフガニスタン中央から南部、パキスタン西部)、
caschmirensis (ヒマラヤのパキスタン北部からインド北部の Uttarakhand)、
planorum (ヒマラヤの Uttarakhand から Sikkim、インド北東部、バングラデシュ、ミャンマー西部から中央部)、
stupae (インド西部、中央部、南東部)、
mahrattarum (インド南西部、スリランカ)、
vauriei (インド北東部)、
templorum (東南アジア南部でタイより西側)、
ambiguus (タイ-マレー半島海岸の中部から南部、スマトラ)、
sarawacensis (ボルネオ西海岸)、
cinereus (ジャワ島、バリ島、小スンダ列島)
をグループ 2 として含めている。
IOC 14.1 ではこのグループ 1 を Parus cinereus、グループ 2 を Parus minor
としていた。
このリストでは上記問題となっていた bokharensis グループを独立種 Parus bokharensis (英名 Turkestan Tit) とし、
bokharensis,
turkestanicus,
ferghanensis
を亜種に含んでいる [Eck and Martens (2006) の扱いとは異なる]。これらは IOC では Paeckert et al. (2005) に基づいて Parus minor に含まれている。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではシジュウカラはおそらく Eck and Martens (2006) および Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol. 1-2) に従って Parus cinereus に含まれる変更が提案されている [追記: この部分は異なっていた]。
2種を統合した場合の種小名は、
minor Temminck and Schelegel, 1848、cinereus Vieillot, 1818 と後者の方が早いので後者の学名になる。
そして Parus cinereus にシジュウカラの名称が与えられることになるが、日本のシジュウカラを Parus cinereus に含める海外主要リストは現状 Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) のみで、現在 (2023 年の記事時点) の世界の多くのリストの扱いと異なるものになる。
なお minor の記述時は Parus cinereus minor Temminck & Schlegel, 1848 であった (採集地は中国北部) のである意味記載時の学名に戻ることになる。
3種ではなく2種とする説明については西海 (2023) Birder 37(12): 31 に述べられているが、変更の根拠については述べられていなかった [追記: Song et al. (2020) に西海氏が共著者に入っているのでこの論文を見ていただくのがよさそう]。
上記文献の記載を参考にすると、一度は3種に分けられたがそのうち2種の分離は不十分な根拠に基づくものであった判断だろう。
英名については、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol. 1-2) に従っていると思われるが、
日本鳥学会の出版物で日本のシジュウカラを Cinereous Tit と呼んでいる論文はすでにある: Fujita et al. (2023)
Ecological Determinants of Inter-Island Distributions through Occasional Dispersal of Two Closely Related Species, Varied Tit and Cinereous Tit, in the Volcanic Izu Archipelago, Japan
(目録第8版発行前であるが)。
海外の論文では3種に分離する考えに従い一般的 (2024 年まで) には Japanese Tit であるが、Parus minor を Oriental Tit と呼んでいるものもある。例えば Ha et al. (2020)
Experimental study of alarm calls of the oriental tit (Parus minor) toward different predators and reactions they induce in nestlings、Eastern Great Tit も使われている。
例えば Lee and Park (2019) An increase in song pitch of eastern great tits (Parus minor) in response to urban noise at Seoul, Korea (韓国の研究例)。
韓国の論文でも Japanese Tit を用いているものもある。
中国の論文では Japanese Tit を用いているものが多い: Zhang et al. (2022) Geographic Variation in Note Types of Alarm Calls in Japanese Tits (Parus minor)、
Yin et al. (2023) A case report of an Eurasian jay (Garrulus glandarius) attacking an incubating adult and depredating the eggs of the Japanese tit (Parus minor)。
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Oriental tit Parus minor
とロシアの最近の論文では Oriental tit。この論文では亜種は wladiwostokensis となっている。
Parus minor の海外分布域の名称を少し見ておくと、中国本土では遠東山雀 (対応する日本の漢字で示した。遠東=極東の意味; 名大山雀、日本山雀などの別名も挙げられている)、台湾では 日本山雀 (東方大山雀、白頬山雀)、韓国には minor しか分布しないため日本同様に従来の名称が使われているようである。ロシア語では vostochnaya sinitsa (東方のカラ)。
分布地でない地域の言語では「日本の」を使っているものが多めで、「中国の」としている言語もそれなりにある。「東方の」としている言語も多少ある。
Parus major は中国本土と台湾で特に違いはなく大山雀またはその他の名前。韓国ではシジュウカラに相当する名称の前に「黄色」を補っている。ロシア語では bol'shaya sinitsa で英名・学名と同じ意味。
旧 Parus major を分割する際に、日本以外にも分布域が広いことがあまり考慮されず、IOC 名を "Japanese Tit" としてしまったため、逆にこの名称を世界共通名として使いにくくしているのかも知れない
[過去にもタンチョウ Japanese Crane → Red-crowned Crane (ロシアでは「日本の」にしている); トキ Japanese Crested Ibis → Crested Ibis; ノジコ Japanese Yellow Bunting → Yellow Bunting などの変更があった。
Parus cinereus と Parus minor を分離しなければ発生しない問題でもある]。
AOU-NACC Proposals 2021 でも、広く分布する鳥の英名に Japanese を使うことの不適切さについての議論がある。ここで問題となっているのはノビタキの英名だが、もし人名を使わない場合は地域名として何が適切か。Amur がよいのではないかとの提案もある。
ツミの英名 Japanese Sparrowhawk にも同じ問題がある。どの地域でも固有種でないものに国名を付けるのはよくないのではなどの議論が続いている。シジュウカラの英名の Japanese Tit は中国南部の留鳥を指す際にすでに混乱が生じているとのこと。
日本で Cinereous Tit の英名を使い始めたために、同じものを呼ぶ英名が Japanese Tit, Oriental Tit, Cinereous Tit と3種類になる状態が発生する。Japanese Tit, Oriental Tit については何を指すかが明瞭であるが、Cinereous Tit は他のリストの名称が指すものとの混乱を招くかも知れない [追記: 2024.7.10 の情報によればこれはおそらく解消される模様]。
Parus minor (IOC 14.1 による) には8亜種が認められている。(もし Parus cinereus と合体すれば 20 亜種になる。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では上記の通り少し扱いが違う)。
3種にするか2種にするかは考え方の違い程度で、現在の情報ではどちらが正しいとも言えないだろう (根拠とした研究も今となってはやや古い)。Parus major と Parus minor との分離に比べると3種にする根拠が (少なくとも学術研究として発表された中では) 薄いと読んでよいと思う。
一方で Brazil (2009) "Birds of East Asia" のように日本周辺のシジュウカラと中国南東部以南は非常に異なっており、音声も異なることからこの個体群を Parus cinereus として英名 Southern Great Tit (別名 Cinereous Tit)、日本や朝鮮半島、中国東北部からロシア沿海地方のものを Parus minor Eastern Great Tit (別名 Japanese Tit) としたものがある。
中国のこの個体群は亜種 commixtus に相当する。これは東アジアのシジュウカラ類をどこで区切るかの見解の違いによるものであろう。
Brazil (2009) の音声が異なる記述は Paeckert et al. (2005) や Eck and Martens (2006) が述べたものと多少異なっている。音声に関してもう少し検討の余地がある印象を受ける。
Brazil (2009) 以降の海外音声データも増えてきているので、commixtus の声を聞いてみたが、特に地鳴きはシジュウカラと違うものが多い感じがする。もし野外で聞いたらシジュウカラみたいだが何か違うと感じそうである。
さえずりはシジュウカラのバリエーションも大きいので日本の個体の鳴き声の範囲外となるかは確実ではないが、かなりテンポが早い印象を受ける。皆様も聞いてみていただきたい。
中国でも最近統合されたとのこと。Paridae (Birds of China) では Parus major Great Tit 大山雀、Parus cinereus Cinereous Tit 蒼背山雀、Parus bokharensis Turkestan tit 西域山雀 の3種となっている。
参考までに Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Parus commixtus Amami-Oshimam, Tokunoshima, Yagachishima, Okinawashima, Ishigakishima, Iriomoteshima をリュウキュウシジュウカラの名称で独立させている。
他は Parus major minor シジュウカラ と Parus major okinawae オキナワガラ としていた。
Parus commixtus Swinhoe, 1868 の原記載 (基産地 Tingchow Mountains, Fohkien, China)。
さらに参考までに、かつてのシジュウカラの種境界の扱いには Hartert (1910-1922) の影響も大きい印象を受けた。p. 341 が Parus major の部分。ドイツ語名 Kohlmeise Kohl はキャベツ、Kohle は石炭でおそらく後者の "石炭色のカラ"。英語の "大きなカラ" には対応しない。
この文献では Parus major に 13 亜種を認めており、日本の Parus minor や大陸の Parus bokharensis, commixtus も含めていた。
旧北区とアジア北部の鳥に限定した書物ゆえに低緯度のカラ類の検討は不十分で、cinereus は文中に現れるのみで独立した項目になっていない。
caschmirensis の項目 (p. 345) でアッサムやビルマのものはスンダ列島 (cinereus。ここでも Hodgson は nipalensis のシノニムを命名しており、nipalensis をいかに多用していたかわかる)
とあまり区別できない、インド南部にも他の亜種があるが取り扱い範囲外なので述べられていない形になっている。
この文献では cinereus を Parus major の亜種としていた。
このように分布北部の亜種だけが比較対象であれば major と minor の生殖隔離が問題となり、ロシアの交雑帯を調べれば major と minor を別種とすることが一時は妥当な結論に至ったものと想像できる。
Hartert の扱いのように cinereus を Parus major の亜種としておけば記載年代順の問題も発生せず、ユーラシア北東部の亜種グループを Parus minor として独立させることができる。
大陸の亜種をどこまで Parus minor グループに含めるかも Hartert の取り扱い範囲に影響されていた可能性があるかも知れない。例えば commixtus に対応する地域を含むなど比較的広義に取り扱っていた日本鳥類目録第7版時代の分布図などを参照。
Hartert は commixtus は minor に似ているが小さいとしていた。okinawae オキナワシジュウカラをcommixtus より分離して記載した。okinawae は commixtus の延長上にあると考えていた。
nigriloris イシガキシジュウカラは色彩に大きな違いはあるが major グループの石垣島亜種と考えていた。つまりこの地域には major と minor グループの両者が存在していると考えていた (関連部分 p. 346)。
Hartert が扱ったのはここまでで、これより南の亜種は記述範囲外だった。ヨーロッパから近い方から検討して行ってここまでの扱いとした順序になっている。
Brazil (2009) がこの nigriloris を日本のシジュウカラと別種としたのもこのような考え方が背景があったかも知れない。
["小鳥との語らい"]
古い本になるが、ヨーロッパシジュウカラを主に扱った "Living with Birds & Birds as Individuals" Len Howard (1952) archive.org、和訳され「小鳥との語らい」: レン・ハワード 斎藤隆史・安部直哉訳 (思索社 1980)。
Instant Views [o.] Living with Birds & Birds as Individuals | Photos by Len Howard, 1950-56 に本に登場する写真がいくつも見られる。
欲しいものを食べてよい時とそうでない時の人間の反応を理解して正しくふるまうとか、朝は窓をたたいて起こしにくるとか面白い話がたくさんある。個体によって性格が大きく違うとのこと。
代々の家系図が出ている (標識せずに個体識別可能であった)。
家の中に巣を作ったヒタキの話も出ていて、著者を信用していたとのこと。
日本語に翻訳されていないがこの本には第2部があって、音楽の
専門用語 (著者はプロの音楽家) なども使って鳥の音楽について記述されているそうである。
あとがきでは日本で馴染みの薄い鳥なので省いたとありますが、音楽家
の文章を素人向けに訳すのは難しかったかも知れない。
音楽をやっていると鳥の声 (やその識別) に敏感になることは多少あるかも知れない。
[Wytham Woods のヨーロッパシジュウカラ]
英国オックスフォード大学の「生きた実験室」Wytham Woods の 75 周年を記念するニュース 75 years of the influential Great Tit study at Wytham Woods (2022)
この地でヨーロッパシジュウカラの研究が長年に渡って行われ学位論文 70 本、350 本以上の科学論文を生み出したとのこと。YouTube へのリンクもある。
Recalde et al. (2025) The demographic drivers of cultural evolution in bird song 歌の進化 (文化) の研究。
長年個体追跡をして歌の変化を記録しないとできない研究とのこと。よそから来た個体は地域の歌をむしろ用いる傾向があるとのこと。
[シジュウカラの言語能力]
「野外鳥類学を楽しむ」(上田恵介編 海游舎 2016) の第9章に鈴木俊貴氏がシジュウカラの言語能力を見いだす観察に至るまでの経緯が述べられている。鈴木俊貴氏によるシジュウカラの言語能力の研究は報道でもよく知られ、日本語記事も多いので個人的にはそちらよりも研究室の雰囲気が面白かった。
この記事では最初はコガラが音声を使い分けることを見いだし、その後シジュウカラのひなが親鳥の警戒音にどのように反応するかを見いだした経験などが述べられている。
一般記事では最初からシジュウカラと書いてあることもあるが、図示されているコガラの声のソノグラムと対比すると聞き慣れたコガラの声との関係がよくわかるだろう。
いつまでも読めるのかわからないが、東大の助教を辞め、5年任期の教員に...シジュウカラにすべてを捧げる「小鳥博士」の壮大すぎる野望
の記事がある。
ここで紹介されている論文を引いておくと
Suzuki (2011) Parental alarm calls warn nestlings about different predatory threats 異なる種類の外敵に対して異なる警告音を用いる (#カケスの備考も参照);
Suzuki et al. (2016) Experimental evidence for compositional syntax in bird calls ヒト以外での初めて音声に文法の存在;
Suzuki (2017) Alarm calls evoke a visual search image of a predator in birds
警告音に応じた探索像を示す;
Suzuki et al. (2017) Wild Birds Use an Ordering Rule to Decode Novel Call Sequences 初めて聞く声の順序から意味を理解する。
とまとめることができるだろうか。
自分は大変に疑い深いので (笑)、そもそもシジュウカラがヘビをどのように外敵とみなしているのかあたりからすでに気になっている。疑い深くない人にとってはそれはヘビを恐れる本能として素直に理解されるだろうが、
#カンムリワシ備考の [霊長類はなぜヘビを恐れるか] の本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」(マーク・S・ブランバーグ著; 塩原通緒訳 早川書房 2006) を見ているとそこまで単純でなさそうな感じがする。ヘビを外敵として恐れるのが遺伝的に備わったものならば鳥類全体ではなさそうなので、どの段階で備わったものなのか。
ヒトでは無意識に反射的にヘビに反応しているわけではなく対象物を意識して始めてヘビから逃げる証拠があるとのこと。
ヘビ認識が生得的にそれほど完全なものでなかったならば、異なる種類の外敵に対するシグナルの確実性はどれほどのものかなど気になってくる (もちろん研究を批判しているわけでなく単なる疑問である)。
回帰文法に関して Gentner et al. (2006) Recursive syntactic pattern learning by songbirds; Nature サイト
がホシムクドリでヒト言語に固有と考えられていた文脈自由文法を学習する能力を持つ発表は当時衝撃を持って迎えられたが、そもそも文脈自由文法を学習したと言えるのか、あるいは同等のヒトでの実験そのものも完全だったのか意義が問い直されることとなった [藤田耕司 (2007) 生物科学 59(2): 85-94 を参照した]。学習に用いた反復回数があまりにも膨大だったので、そのぐらい学習させれば他の動物でも可能なのでは、など話題となった。
Corballis (2010) Recursion, Language, and Starlings では回帰文法した証拠にはなっていない。
Beckers et al. (2012) Birdsong neurolinguistics: songbird context-free grammar claim is premature ももっと簡単な類似度の判別だけで説明できるのでは (岡ノ谷氏も著者に含まれている)。
Suzuki et al. (2015) 論文の中では引用されていないので "文法" の位置づけが異なる (自身の発する声、回帰文法でないため?) のだろうと思うが本質はよく理解していない。
言語文法についてはどの文献も Chomsky (1957) "Syntactic Structures" (Mouton) あるいは Chomsky (1965) "Aspects of the Theory of Syntax" (MIT Press) を引用している。チョムスキーの生成文法 (generative grammar) はあまりにも有名な言語学理論なので当然だが、
チョムスキーが普遍文法 (universal grammar) の生得性を訴えた部分は議論を呼んでいる。藤田 (2007) の解説を見ると「母語獲得を各個体の生後の経験だけに基づいて説明しようとした行動主義への批判であるが、」とあり、当時の時代背景とも結びついていたことがわかる。Lorenz が生得的 (本能的) なものに焦点を当てていたのと同じ時期である (#マガモの備考 [カモのひなはなぜ親鳥を追う?] 参照)。
なお藤田氏の記事では、チョムスキーは発達と進化の深い関係性を指摘し、普遍的な自然法則の関与をも重視している点では、近年の進化発生生物学 (Evo-Devo) の展開と、その生成文法への波及を早くから見越していた、と評価している。
「本能はどこまで本能か: ヒトと動物の行動の起源」(マーク・S・ブランバーグ著 2006) ではいくつかの疑問点が提示されていて、普遍文法に言語の根本的な構造が反映されるのは、すべての人間の言語が唯一の共通の祖先を持っていて、関係がまだ断ち切られたことがないことを挙げている。つまり N=1 の観察例とも言え、言語の持つ普遍的文法規則とは言い切れない。
Deacon (2003) Multilevel Selection in a Complex Adaptive System: The Problem of Language Origins 及び
Deacon (1997) "The Symbolic Species" (邦訳「ヒトはいかにして人となったか - 言語と脳の共進化」金子隆芳訳 新曜社 1999) をベースとして、
もし言語に子供の頭の働かせ方が組み込まれているなら、子供の頭に生まれつき言語の構造が組み込まれている必要はない。また、子供が容易に学習できる言語の側面が選択されてきた (それが普遍文法として見える) など。
もちろんいずれも作業仮説の段階で実験もできるわけではないだろうが、言語としてあり得る多くの可能性の中でヒトが進化した環境で選択された言語構造があってもおかしくなく、それを同じように他の動物に求めるのは何となく人間至上主義が見えるようでいつもちょっと違和感を覚える部分である (鈴木氏の論点に直接関わるものではないが)。
なおチョムスキーの考えは当時進歩した計算機科学と非常に相性がよかった点も広く受け入れやすかった理由に挙げられるだろう (コンピュータ言語の記述にも広く用いられている)。
チョムスキー自身への批判や評論ではまったくないが、鳥の音声コミュニケーションの話題を聞く時に、つい直感的に簡単に受け入れてしまいそうな話題も少し疑ってみた方が科学はより面白くなるだろうと取り上げてみた。
ヒトと共通する特徴が見つかった。鳥はすごいと見るか、ヒトにあるなら鳥にあってもおかしくないと見るか、そもそも大した問題でないと見るか (ホシムクドリの実験は大したものなのか、など)? なかなか難しそうでもあり、考えると面白そうである。
(さえずりと言語の起源については #オウチュウ備考に続けておく)。
[カラ類は音声の組み合わせを 1100 万年以上前から使っていた]
Salis et al. (2025) Birds combined calls more than 11 million years ago
鈴木俊貴氏が記述した警戒音声の組み合わせ (ここでは2つの音の順序 FD で表されている。これはカロライナコガラで使われる用語に対応するらしい)。
最も近縁のツリスガラ科 Remizidae やセンニョヒタキ科 Stenostiridae では見られない。系統解析からこの音声の組み合わせは 1100-2600 万年前にヒマラヤ東部で生じたと考えられるとのこと。
他の研究でサル類の "boom" 音声が 500 万年前以上、セグロカモメ類の "gagaga calls" が 550 万年前に生まれたなどの年代推定が紹介されている。
カラ類について日本では "FD" に相当する呼び方が使われているが、北米のカロライナコガラ Poecile carolinensis Carolina Chickadee でも似たタイプの音声が知られていて、日本のシジュウカラで "F" に対応するとされる音声がこちらでは A, B, C の3種に区別されている (D の概念はどちらも同じ)。カロライナコガラにも同じような "音声文法" と意義が存在するかどうかは今後の検証課題。
シジュウカラ科全体で "FD" のパターンはかなり広く存在し、特に Poecile 属や Melaniparus 属で目立つ。逆順の "DF" も種類次第で多少存在し、アカエリシジュウカラ Periparus rufonuchalis Dark-grey Tit のように逆順の方が多く記録される種もある。
シジュウカラ科の最も古い分岐にあたるキマユガラ Sylviparus modestus Yellow-browed Tit では記録がないことからこの音声の出現年代の上限を推定した。
祖先形質再構成によって "FD" が 1100 万年前の共通祖先段階で使われていた可能性は 99.8% と推定。
これらの結果から "FD" が文法的意味を持つのかなどいくつかの仮説が議論されている。北米のカロライナコガラでは日本のシジュウカラと意味が少し違うらしい。個々の音声の出現とそれを組み合わせて意味を作ることが別プロセスで起きたものだったならば、日本のシジュウカラの祖先段階でいつから意味を持つようになったのか、そのような進化をもたらした理由はなぜかなどの問いかけを残して次のステップの研究に引き継いでいる。
機能なく音声のみが進化するとは考えにくいので、個々の音声あるいは組み合わせが何かの機能を持って進化し、組み合わせて文脈的意味を持たせることが別途進化する過程を考えるのは確かに難しい気がする。"FD" がこれほど古くから存在しているのに日本のシジュウカラ (およびおそらくヨーロッパシジュウカラ) が特別な意味で用いる理由も確かになぜか、ということになる。
この研究には xeno-canto のデータベースが使われており、これも大変称賛されている (まったく同感で、これだけの種類の音声データを音声種別で分けて調べられるサービスはおそらく他にない)。一方録音の際に人が近くにいることによる発声バイアスや、目立つ大きな声のみが報告されている可能性 (これは写真データベースなどで目立つ画像や珍しい画像が投稿されやすいのと同様) なども指摘されている。観察・記録の科学的意義を意識する場合は常に念頭に置いておくのがよいだろう。
さて、シジュウカラ科で 1100-2600 万年前に新種の警戒音が作られたとすれば多少思い当たるところがあある。それ以前は「捕食者」全体を指す信号で十分だったものが、空中からの捕食者が現れると区別するのが有利となり、ヘビ用の信号と猛禽類用の信号を使い分けるのが適応的となったと考えられる。
ヘビの聴覚は弱く鳥の声の範囲とあまり一致しないので、どのような音声信号を使うことも可能であったが、猛禽類は聴覚も優れているので探知しにくい音声が有効となり使い分ける意義が生まれた。
シジュウカラ科にとって特に重要な昼行性猛禽類捕食者と考えられるのは Tachyspiza 属と狭義 Accipiter 属である。前者の方が出現年代が少し早く、ヒマラヤ地域 (シジュウカラ科の種分化中心地) ならば南方系の Tachyspiza 属の影響が強いと考えられる。
Tachyspiza 属がアジアで適応放散したのは 1300 万年前ぐらい (Catanach et al. 2024 の系統樹から) で、見事に一致する。あるいはむしろシジュウカラ科が適応放散するのに合わせてこれらのタカ類も分布を広げたのかも。
狭義 Accipiter 属のハイタカがやってきたのはもう少し遅く (例えば 400 万年前ぐらい)、捕食者に対する音声信号を分化させたとすれば主に Tachyspiza 属が対象と考えられる。年代推定のもっと早い方 (2600 万年前に近いもの) を考えればハチクマ亜科の一部の種が小鳥も食べていたかも知れない。現在でも鳥の巣を襲うのでこの時期から捕食していても不思議でない。
"FD" の組み合わせが "DF" より好まれたのは、後者の組み合わせがたとえば背景音にあまりない不自然な音として昼行性猛禽類が気づきやすいのかも知れない。これも実験的検証が可能であろう。
音を発する物理的過程を考えても内部エネルギーの低下とともに音程が下がるのが自然で、自然の外界音でも同様の過程が起きやすいので捕食者にも聞き慣れた自然音に感じるかも知れない。
それに反して "DF" を信号に使うためには一層のエネルギー (メッセージを伝えるための労力) が必要であるとともに、自然界の音としては捕食者に目立つ可能性がある。
さえずりであればハンディキャップ原理から目立つ、あるいは余分なエネルギーを要する音声が逆に質を表す正直なシグナルとなり得るだろうが、警戒音にはそのような選択は働かないかも知れない。
我々が地鳴きに注意を払いにくいのも同じ理由かも知れない。そもそも仲間内以外に気が付きにくい声が選択されてきたわけだ (そのため地鳴きを聞き取れる人は耳が良いと言われることになる)。
"DF" の多いアカエリシジュウカラの分布を調べておくとヒマラヤ西部からウズベキスタン、キルギスなど高地または比較的乾燥気候を好むよう。捕食者になりそうなタカを見ておくとタカサゴダカ [高野 (1973) ではミナミハイタカ] Tachyspiza badia Shikra が有力候補で Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" を見ると主に標高 1500 m 以下とあるのであまり重なりがない。
ハイタカのヒマラヤ亜種も候補となるが、ウズベキスタン、キルギスなどの地域は繁殖分布でなく渡りで通過するのみで接点が少ない。アカエリシジュウカラにとってはタカ類捕食者が少ないため "DF" と "FD" を分化させる必要性が少なかったのかも知れない。アカエリシジュウカラの捕食者を調べてもあまり情報がなく、そもそもあまり研究がないのかも。
タカ類分布と関連した警戒音の系統解析を行えば新たにわかる点があるかも知れない。
またツリスガラ科で音声分化が進化していないのは、アシ原の小鳥食の昼行性猛禽類の出現が少なくともユーラシアでは比較的遅かったためとも理解できる。チュウヒ類が現れるのはオオタカの Astur 属以降のことで、シジュウカラ科とツリスガラ科が分化した時代にはまだ主要な昼行性猛禽類捕食者がいなかった。
#セッカの備考 [セッカの和名検討] でこの系統のさらなる考察を行い、ツリスガラ科の分化した時代・地域にはまだ Accipitrinae 亜科があまり現れておらず、飛翔性の小鳥食の猛禽類が少なかったと想像されるが、巧妙に巣を狙える別の系統は存在した。地上性捕食者と同列に扱って共通の警戒信号で十分だったのかも知れない。
セッカの場合はさえずりなのでカラ類の警戒音とは機能が異なると思われるが、純音に近い高音から雑音に近い音に遷移する順番はカラ類の "FD" と共通性があるように見える。逆順の音声はタカに目立つため "FD" に近い順序が選択されたのではないだろうか。
このあたりの考察の正当性を検証するには、カラ類の昼行性猛禽類用の警戒音の進化を同様に系統解析すればよいことになる。誰か試してみられないだろうか。
[オクターブ認識能力]
音声認識関係なのでこちらにまとめておく。
アメリカコガラ Poecile atricapillus Black-capped Chickadee はオクターブ違う音を似ている (octave equivalence) と認識しない: Hoeschele et al. (2013) Chickadees fail standardized operant tests for octave equivalence。音楽の訓練を受けていないヒトでもこの能力があるとのこと。
Hoeschele et al. (2023) Lessons learned in animal acoustic cognition through comparisons with humans この能力はヒトの系統のみで (例えば自身の音声構造や言語の獲得に並行して) 進化した性質の可能性も考えている。
振動数が簡単な整数比 (オクターブでは 1:2) となることは協和音・不協和音に関係する。生物由来でない音は不協和であることが多いので、協和音を聞き分けることは有利であった可能性も考えられるが実際には雑音的な信号も使われるので推論は難しい。音声学習を行う際に発声音程の高い小児がオクターブ違う音は原音との重なりが小さく octave equivalence の認知能力は有利であろうなどの解釈がある。
かつてホシムクドリで調べられた時には octave equivalence は見つからなかった。(ヒトの小児と多少共通性のある) 自身の通常の声と異なる音域を学習する種類として、著者がセキセイインコを使った実験でも見つからず、音声学習がこの認知機構を生じさせるのには十分でないことがわかる。
この論文で Suzuki et al. (2016) も引用されていて階層構造のある音声の証拠を見つけた可能性がある、の中で取り上げているが、それほど著者の焦点ではなさそうなので軽く触れる程度になっている。主に音楽の視点からヒトの認知をベースとした種間比較の盲点を取り上げている。
同じ著者による Hoeschele (2017) Animal Pitch Perception: Melodies and Harmonies
のレビューもある。鳥の「音感」については 1990 年代に盛んに研究されたが、鳥は相対音感を使っていない? 2つの鳴管を同時に制御する鳥にとっては、ヒトと同じように和音を認識していない? など興味深い話題も取り上げられている。
ひよこのインプリンティング実験で協和音を聞かせる方が不協和音より成績がよかったとの結果があったがいま一つすっきりしないよう。
過去の実験で主張された結果も後に再現できないこともあるようで、古い話題は注意して読む必要がありそう。
Maldarelli et al. (2024) Chicks produce consonant, sometimes jazzy, sounds
ニワトリのひよこで音声周波数分析を行うとヒトの音楽の協和音に相当する音程が高頻度で使われる。一方で不快な時には不協和音程を用いる傾向があり、系統的には遠く離れていてもヒトの音楽に共通する側面がある。
さてさて、これまた余談的な話だが、野鳥の声に敏感だと「クラシック音楽をやっている人は特別」としばしば言われることがある。
自身ではあまり関係がないのではと考えていたが、最近になって日本の音楽教育の意義についての考察を読み (最近読んだのに読んだ時点で思いつかずどこで読んだかメモするのを忘れてしまった。著者の方すみません)、なるほどと考え始めた。
近代的な日本の西洋音楽の教育は歌詞と音楽を切り離したのが重要であるとのこと。つまり歌詞のない音楽 (器楽) を重要な教育項目とした。この教育を受けていれば歌詞にとらわれず音楽だけを鑑賞することができる (はず)。自分が習った小・中学の音楽の先生が比較的器楽好き (多分ピアノが得意な人が教師になりやすかった) で、歌うことより器楽重点の教育を受けることとなった。ピアノ音楽好きになったのもおそらくその影響で (幼少時から習っていたわけではない)、小学校の早い段階から主要三和音の識別なども習った覚えがあるので、ここで音感が鍛えられたのではないかと想像する。
このような話に思い至ったのは、歌詞のない音楽を情報として認識する能力が人によってずいぶん違うことを経験していたためだった。人によっては旋律や和声をあまり判別できず単なる音として認識されるようで、それならば隣家のピアノの音など騒音以外の何者でも場合があることも理解できる。
中学の音楽授業で体験したが、同じ音楽を楽器を変えて演奏したもの (例えばピアノとオーケストラ) を聞いて同じ音楽と認識できる人がほとんどいなかった。座って聞くだけのクラシック音楽鑑賞の授業など苦痛以外の何者でもないかもしれない。
つまり歌詞のない音楽を情報として認識する能力は生まれつき備わったものではなく、教育によって身につくものだと理解した。
小学校の音楽など、楽しく歌っていれば十分で特に勉強する必要もない、好きなことをやればよいと考えるのと、楽譜も読めるようになってさらに勉強しようと考えるのとでは雲泥の差が生じる可能性がある。
ここで鳥の声に対する認識の違いが生じるのではないだろうか。音楽を歌詞とともに理解する方法でのみ音楽に親しんでいれば、音楽部分だけでは違いを聞き分けることができないかも知れない (だからこそイントロクイズが成立するのだろう)。
音楽部分だけでは記憶困難なので歌詞に相当する「聞きなし」を添える必要がある。近代的な西洋音楽の教育以前の文化を引き継いでいるため鳥の音声が得意な人も少ないのだろう。ちなみに「聞きなし」にぴたり相当するような包括的な英語表現をあまり知らない。
かつて "catchy phrase" だと聞いたことがあったが、これは単に覚えやすい表現として使われたもので、「聞きなし」全般に対応するものではないと思う。海外の鳥関係の情報源を見ていても出会ったことがない。
小学・中学の音楽いずれも義務教育なのだから、軽視せずに取り組んでいれば相当する音感を万人が身につけていて本来不思議でない。
いまさら遅いと言われる方も多いかも知れないが、「聞きなし」やカタカナ表現を排除して記憶するよう努めてはどうだろうか。音楽の習得はどの年齢でも可能と思われるので、鳥の声でも同じではないだろうか。
もっともカタカナ英語に慣れ親しんだ人がいきなり排除せよと言われても困難なのと同様、鳥の声に直接馴染むのはそれ相応の努力は必要と思われる。
外国語を学ぶ場合にしばしば強調されるが、早い段階から音も中心にして習得するのがよいのだろう。
音楽教育では音感を学ぶ方法は古くから研究されていて、なるべく少ない手間で学べるようにさまざまなものが開発されているが (何とかメソッドなど)、鳥の声を学ぶ需要は少なく (たとえ教えても月謝も期待できないだろうし...)、「鳥の声学習コース」は開発されないままとなっているのだろう。
細川 (2019) Birder 33(7): 66-67 では江戸時代に飼い鳥が輸入されていたが、西洋音楽と鳥にまつわるヨーロッパの書物は輸入されていた記録が見つけられなかったとのこと。西洋音楽と鳥はあまりにかけ離れていて、書物の表題を見ても輸入しようとは考えなかっただろうか。この時代に両者が結びついていれば日本人の鳥の声に対する音感も変わっていたかも知れない。
「小鳥との語らい」(["小鳥との語らい"] 参照) でも著者の本来専門とする音楽の話題を中心とした第2部は和訳でも省略されていた。
同様に教育が基礎となっている野鳥観察行為に「カウントする」が挙げられるかも知れない。「鳥の数を数えなさい」と言えば誰でもできるように思われるだろうが、これは言語によって数を数える教育を受けているこそ成り立つのだろう。「数を数える」概念は日常生活にあまりにも重要なので、この部分で手を抜こうとする人はあまりいないだろうが、算数に相当する概念をまったく習っていなければできない気がする。
数が多い場合は「たくさん」、もっと多い場合は「もっとたくさん」で済んでしまうかも知れない。
野鳥観察における意義はこのようなものなものを想定するが、この問題は実は根が深いのではないかと思う。音楽を聞き分けるハトの実験を行われている研究者も、上記オクターブ認識能力などを調べられている方も圧倒的に器楽に慣れている人に偏っているのではないだろうか。
その能力が生まれつき備わったものではなく学習によるものとすれば、ハトの能力を評価するにあたって研究者の音楽経験によるバイアスが入ってしまい、ハト本来の認知能力を評価できていないのではないだろうか。
ハトにとっては音楽刺激は音楽経験のない人の聞く隣家のピアノ騒音と同様に認知されていて、騒音の種類の違いを聞き分けているに過ぎないのではないだろうか。
同じジャンルの音楽でも楽器を変えた場合にハトが同じジャンルと認識するか疑わしい気がする。
また動物の数認知なども「数の概念を知っている」研究者ならでは成り立つ話で、数の概念を用いた教育を受けていなければ (ありそうもない話だが)、むしろ別の認知プロセスを考えるかも知れない。
[ヒメサバクガラス]
「野鳥」2024 年 9・10 月号 (No. 872) p. 10 に分子系統解析の結果ヒメサバクガラスがシジュウカラに近縁であることが示されたことが驚きであったと上田恵介氏が述べられているので、どのような鳥か調べてみた。
ヒメサバクガラス Pseudopodoces humilis Ground Tit が現在の学名・通常の英名で、英名はかつて Hume's Groundpecker, Hume's Ground Jay または Tibetan Ground Jay だった。
記載時学名 Podoces humilis Hume, 1871 (原記載)。
Hume による英名は Dingy Clough-Thrush でカラス類とツグミ類の中間の位置づけ。地上生活のためにそのように位置づけられたらしい。
Hume が同属に分類して記載した種にハシナガサバクガラス Podoces hendersoni Mongolian Ground Jay があり、こちらは現在もカラス科だが見かけはそれほど似ていない。
日本では名称の安定性 (?) のためかつての分類に基づく名称が使われているが、海外では分類改訂を受けた名称が取り入れられていて、中国名では地山雀と適切な感じがする。新しいロシア名も同様、ドイツ語も Tibetmeise とカラ類の名称になっている。
Pseudopodoces 属を導入したのは Zarudny and Loudon (1902) で 記載。色による分類でカラス類の Podoces のグループであることは疑っていなかった。
ヨーロッパからは遠く離れた地域であるため記載以来ほとんど調べられておらず、Borecky (1978) "Evidence for the removal of Pseudopodoces humilis from the Corvidae" Bulletin of the British Ornithologists' Club 982: 36-37 が解剖学的証拠からカラス類でない示唆を与えたものが最初とのこと。
Hope (1989) "Phylogeny of the avian family Corvidae" の学位論文も同様とのこと。
分子遺伝学的結果が出るまでわからなかった表現も wikipedia ロシア語版に見られるが必ずしも正確でない模様。
分子遺伝学による結論は James et al. (2003) Pseudopodoces humilis, a misclassified terrestrial tit (Paridae) of the Tibetan Plateau: evolutionary consequences of shifting adaptive zones
で得られた。当時の分類の Parus major (シジュウカラまたはヨーロッパシジュウカラ) に最も近く、樹木のない環境に適応したため淡色の隠蔽色となり、地上生活のために足が長くなった。しかし骨学的特徴や遺伝的特徴に本来の系統が現れており、洞に営巣する点も同様であるとのこと
(以上の情報は wikipedia 英語版をもとにまとめた)。
分子系統的にはこの種が Parus 属に近いことが判明したことで従来の Parus 属が単系統でなくなったと言うこともできるが、この種を Parus 属に編入、あるいはアオガラとルリガラに別属 Cyanistes を与える扱いも可能だった。
結果的には従来の Parus 属の subgenus を属に昇格するのが適切と判断され、Gill et al. (2005) Phylogeny of Titmice (Paridae): II. Species Relationships Based on Sequences of the Mitochondrial Cytochrome-B Gene の提案となった。
この判断にはヒメサバクガラスの特異性も一役買っていた、というところだろうか。
ヒメサバクガラスに対する Ground Tit の英名はこの論文で提唱された。
[鳥の社会的学習]
鳥の社会的学習はほとんどスズメ目とオウム目の研究に限られる傾向があり、例えば捕食者の危険性を社会的に学習する証拠が得られているものは限られている。捕食者に対する信号の使い分けはシジュウカラでよく調べられているのでここに含めておく。
もし社会的に学習できなければ自身が捕食の危険に実際遭遇するまで捕食される危険を学べないことになるが本当だろうか。
Aplin et al. (2025) Social learning and culture in birds: emerging patterns and relevance to conservation
に系統ごとに何が調べられているかレビューがあるので紹介しておく。
学習項目として音声、採食、渡り、対捕食者を挙げて主な系統ごとに存在が示されている。スズメ目では渡りは社会的学習の証拠は得られていないらしい。渡りの社会的学習証拠のあるグループにタカ目とブッポウソウ目が挙げられているがハヤブサ目では証拠がないとのこと。
ツル類やガン類ではもちろん証拠があるが、C (culture 文化)、SL (social learning 社会学習)、SIU (social information use 社会的情報の利用) に分けてあり、ツル類やガン類では C、シギ・チドリ類では SL、タカ目とブッポウソウ目は SIU となっている。
捕食者の危険性を社会的に学習する証拠が得られているものはスズメ目とオウム目のみで、例えば群れで行動するカモメ類やシギ・チドリ類にはそのような能力は必要ないのか、あるいは系統的制約があるのかなど問題提起にもなっている。
音声、採食の学習などはここでは触れなかったが、個々の行動の論文が多数引用されているので参照されるとよいだろう。保全を考える場合もこれら "文化" の要素を念頭に置く必要がある (ツルに渡りを教えるなどは典型的な例) とのこと。
伝統的な研究方法に加えて文化を調べる数学的モデルや AI の活用も進んでいる Whiten and Rutz (2025) The growing methodological toolkit for identifying and studying social learning and culture in non-human animals (動物全般を取り扱っている)。
鳥はやはり手軽に調べられるためかさえずりの研究が多い。文化的行動の伝達では Fisher and Hinde (1949) の英国のヨーロッパシジュウカラやアオガラの牛乳瓶の蓋を開ける記録が今でも代表的なものとして扱われている (その後の事例はないのだろうか?)。キバタンがゴミ箱を開ける行動を近傍個体に伝達した事例 (Klump et al. 2021) が取り上げられている。
ヨーロッパシジュウカラやアオガラで cross-fostering によって仮親と似た行動をする例が報告されている (Slagsvold and Wiebe 2011)。Table S1 に一覧と文献がある。
-
ルリガラ
- 学名:Cyanistes cyanus (キューアニステス キューアヌス) 紺青色の鳥
- 属名:cyanistes (合) 紺青色の鳥 (kyanos 紺青色の -tes (接尾辞) 〜するもの Gk)
- 種小名:cyanus (m) ラピスラズリまたは瑠璃 (ギリシャ語 kuanos 由来)
- 英名:Azure Tit
- 備考:
cyanistes はギリシャ語由来だがラテン語の cyanos などは冒頭が長母音でこれも同様と考えられる。
規則からは "キューアニステス" のアクセントと考えられる。
cyanus は冒頭が長母音でアクセントがある (キューアヌス)。
東欧から極東に広く分布し、世界で8亜種が認められている (IOC)。日本で記録された亜種は tianschanicus [「天山(山脈の)」の意味] とされる。この亜種の分布はカザフスタンから中国北西、満州、パキスタンとされる。分布的にはシベリアから日本海、アムール川下流の亜種 yenisseensis (エニセイ川の) が近い。
ヨーロッパに広く分布するアオガラ Cyanistes caeruleus Eurasian Blue Tit のユーラシア東部の対応種で両者は交雑も知られている。交雑個体は Pleske's tit の名称もありかつて別種とされていた時代の名前の名残り (種小名 pleskei だった)。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ヒゲガラ科 PANURIDAE ▽
-
ヒゲガラ
- 学名:Panurus biarmicus (パヌールス ビアルミクス) ビアルミア地方の尾の際立った鳥(誤命名)
- 属名:panurus panu 際立った -ouros 尾の (Gk)
- 種小名:biarmicus Biarmia (ロシアの白海沿岸の地域の古名、Bjarmaland)から誤って付けられた (Newton and Gadow 1896; BOU 1915) (The Key to Scientific Names)
- 英名:Bearded Reedling
- 備考:
panurus はギリシャ語からの合成語で発音は明確でないが、-urus の語源の oura から -urus の冒頭は長音と考えられる。その場合アクセントもこの位置でわかりやすい (パヌールス)。
biarmicus は外来語で何とも言えないがいずれも短音とすれば規則からは "ビアルミクス" のアクセントになる。
biarmicus はラナーハヤブサ Falco biarmicus においては明らかに「ひげのある」(ハヤブサ髭) の意味で使われた (原意は「二つの武器のある」) (Temminck 1825) が、ヒゲガラでの用法は異なっていると考えられている (The Key to Scientific Names)。
日本で記録されたものは東方の亜種 russicus (「ロシアの」の意味)とされる。この亜種の越冬地は渤海沿岸近くまで。基亜種 biarmicus はヨーロッパに分布する。もう1亜種 kosswigi がトルコ南部で記載されていたが、おそらく絶滅したとされる。
分子系統学的には系統の近い鳥がなく、一科一属一種。
名前から想像されるカラ類よりヒバリ類に近いと考えられている。
湿地のスペシャリストで大きなアシ原にコロニーを作って繁殖する。
OED によれば英名由来は若干ややこしいようで、1835 年の Analyst には The sedge reedling (Salicaria phragmitis, Selby), he calls sedge warbler, and the marsh reedling, (S. arundinacea, Selby) he calls reed wren, thus giving different generic names..to the same genus
とオオヨシキリ類を指して使われており、この用例は 19 世紀中見られていた。
1837 年に Blyth, Magazine of Natural History で bearded reedling を紹介し、この用例が次第に受け入れられるようになって行った模様。19 世紀中はオオヨシキリ類でも使われ混乱原因となっていたらしい。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ヒバリ科 ALAUDIDAE ▽
-
クビワコウテンシ
- 学名:Melanocorypha bimaculata (メラノコリュパ ビマクラータ) 二つの斑紋のある黒いヒバリ?
- 属名:melankoruphos 黒いヒバリ? (melas Gk) koruphos アリストテレスの記述した未同定の鳥 (Gk) が原意だが、Boie (1828) により korudos (ヒバリ Gk) と混同されたらしい (The Key to Scientific Names)
- 種小名:bimaculata (adj) 二つの斑点や模様をつけた (bi (接頭辞) 二つの maculatus (adj) 斑点をつけた)
- 英名:Bimaculated Lark
- 備考:
melanocorypha はギリシャ語由来の合成語のため発音は不明だが、いずれも短母音とすれば -co- にアクセントがある (メラノコリュパ)。
bimaculata は -maculata が -maculatus の女性形主格で -la- の a が長母音でアクセントがある。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。トルコから中央アジアが本来分布。記録された亜種は分布域南東部の torquata (「首輪のある」などの意味) とされているが、亜種を認めない立場もある (現 IOC など)。
「一部学名の変更の見込みについて」(2023年11月28日) にて単形種に変更された。
和名は Melanocorypha torquata Blyth, 1847 (原記載) 基産地アフガニスタン 時代の名称由来と考えられる。
亜種を認める場合の基亜種の方は記載 Alauda bimaculata Menetries, 1832 (原記載)。
後者の方に juguli latetibus utrique macula nigra extorsum deflexa と首の両側の斑紋を示している。
Blyth (1847) の方も同じ特徴を指しており、"二つの模様" も torquata も同じものを指していたらしい。これらを考慮すると torquata は "首に模様がある" 意味で、collared と英訳されていたとすると少し誤訳っぽい。
Alauda collaris Muller, 1776 の用例は古くからあって、一番普通の "首に特徴がある" ヒバリの学名はすでに使えなかったものと想像できる。bimaculata は少し工夫した感じ。
属名の意味を「黒い頭の」と解釈される場合もある (コンサイス鳥名事典) が、The Key to Scientific Names にあるように「頭」は出てこないようである。属の原記載 (Boie 1828) で7種を含んでいた。
アリストテレスの用いた不明の鳥 melankoruphos 由来と脚注にある。アリストテレスは黒い頭の鳥を指していたらしいが、The Key to Scientific Names の解釈では Boie はおそらくギリシャ語の korudos 冠羽のあるヒバリ と混同したのだろうと述べられている。
属に含まれるものに当時の学名で M. melanococephala = Alauda melanocephala Lichtenstein, 1823 と頭の黒いものを指す用例もあるが、M. deserti = 現在のスナヒバリ Ammomanes deserti Desert Lark のように頭の黒くないものも含まれるので "黒い頭の" を属の意味としたわけではなさそう。
7種が現代の何に対応するか調べる楽しみもあろうと思われるのでヒバリ類好きの方は調べていただければ。
アリストテレスの用いた不明の鳥でおそらくヒバリに似た鳥 (アリストテレスが指したものは頭は黒かったと推定される) を指すものと解釈しておいてよい感じがする。不明の "小鳥の一種" ぐらいでもよいのかも。
クビワコウテンシは地中海沿岸から中東に分布するクロエリコウテンシ Melanocorypha calandra 英名 Calandra Lark (現在の分類での英名) の東方の対応種に相当する。Eastern Calandra Lark の英名は別名になっているが、クロエリコウテンシの東方 (中東) 亜種 psammochroa にすでに使われているもので、Calandra Lark の名称とともに避けた方がよいとのこと (wikipedia 英語版)。
英名の関係は複雑であるが、最近まで同種扱いされていたわけではない。Dement'ev and Gladkov (1954) ではそれぞれ別種扱いで現代の扱いと大きな違いはない。属名 Melanocorypha も当時から同じで、Dement'ev and Gladkov はこの属を「ステップヒバリ」と総称しており、適切な表現であろう。
ドイツ語にも対応する Steppenlerche の名称があるが総称ではなく、クロコウテンシ Melanocorypha yeltoniensis (ロシアのアストラハンにある Yelton/El'ton湖から) 英名 Black Lark に使われるのみである。
この種がこの属のタイプ種で、かつては Melanocorypha tatarica とも呼ばれたが Melanocorypha yeltoniensis のシノニムとして扱われる。
ヒバリ類の最新分子系統研究は Alstrom et al. (2023) Systematics of the avian family Alaudidae using multilocus and genomic data
にある。この研究で新しい亜科が提唱されている:
Alaudinae Vigors, 1825 亜科 (日本で記録されたヒバリ科の種類はすべてこの亜科に含まれる)、
Certhilaudinae Le Maout, 1852 亜科 および Mirafrinae Bianchi, 1905 亜科。
またこの研究によりかつて Mirafra 属に分類されていた5種が新属 Plocealauda に移行となった。
同様に3種が Amirafra 属、6種が Corypha 属に移動。
Plocealauda 属はアジアの属であるいは日本にも関係してくるかも (以上3属は IOC 14.2 の資料による)。
-
コウテンシ
- 学名:Melanocorypha mongolica (メラノコリュパ モンゴリカ) モンゴルの黒いヒバリ?
- 属名:melankoruphos 黒いヒバリ? (melas Gk) koruphos アリストテレスの記述した未同定の鳥 (Gk) が原意だが、Boie (1828) により korudos (ヒバリ Gk) と混同されたらしい (The Key to Scientific Names)
- 種小名:mongolica (adj) モンゴルの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Mongolian Lark
- 備考:
melanocorypha は #クビワコウテンシ参照。
mongolica はすべて短母音で -go- にアクセントがある (モンゴリカ)。
単形種。「告天子」(こうてんし) はヒバリの別名 (この漢字で「ひばり」とも読む) であった。中国語でもヒバリを告天子、告天鳥と書く。
-
ヒメコウテンシ
- 学名:Calandrella brachydactyla (カランドゥレルラ ブラキュダクテュラ) 短い指の小さなヒバリ
- 属名:calandrella (合) 小さなヒバリ (korydallos ヒバリ Gk、-ella (指小辞) 小さい)
- 種小名:brachydactyla (合) 短い指の (brachy- (接頭辞) 短い dachtylo 指 Gk)
- 英名:Greater Short-toed Lark
- 備考:
calandrella は合成語で発音が不明だが、-ella は短母音とのこと。語全体がすべて短母音であれば -(r)el- は子音で終わるのでここにアクセントがあると考えられる (カランドゥレルラ)。
brachydactyla もすべて短母音であれば "ブラキュダクテュラ" のアクセントになると考えられる。
中央アジアから南ヨーロッパ、中東、北部アフリカに分布。世界で8亜種 (IOC)。日本で記録された亜種はカザフスタンなどの亜種 longipennis (longus 長い -pennis 翼の) とされる。
かつての学名は Calandrella cinerea とされていて当時の英名は Short-toed Lark 和名旧名 カラフトコヒバリ、英語別名 Red-capped Lark だった (コンサイス鳥名事典)。
これは現在の Calandrella dukhunensis 英名 Mongolian Short-toed Lark (または Mongolian lark。IOC 英名ではコウテンシがこちらの名称になる)、
ヒメコウテンシ Calandrella brachydactyla、ソマリーヒメコウテンシ Calandrella eremica 英名 Rufous-capped Lark、Calandrella blanfordi 英名 Blanford's Lark、
Calandrella cinerea 分離された現在の英名 Red-capped Lark、和名 アフリカヒメコウテンシ を含む大きな種だったが後に細分化された。
これはヒバリ類の系統分類の難しさを表している (#コヒバリの備考参照)。和名がまだない種類もある。
現在の Calandrella cinerea はアフリカ南部に分布する種で、古い学名で報告すると全然違う種類になってしまうので注意。
Calandrella 属の分子系統研究: Stervander et al. (2020) Molecular Species Delimitation of Larks (Aves: Alaudidae), and Integrative Taxonomy of the Genus Calandrella, with the Description of a Range-Restricted African Relic Taxon。
この論文にミトコンドリアの cyt b 遺伝子のみの研究だがヒバリ類他属の分子系統樹もある。
かつて日本のヒバリは独立種相当との考えもあったが、この論文で示された種境界では Alauda arvensis + Alauda gulgula は3種とするのが適切で、"eastern birds" 日本と中国の安徽省のヒバリはカザフスタンと分岐年代 226 (143-302) 万年前と推定。Alauda japonica を採用する根拠は出ている。
Alstom et al. (2023) Systematics of the avian family Alaudidae using multilocus and genomic data により核遺伝情報も含めた新しい解析がある。
亜科の定義 (diagnosis) は形態学ではなく分子遺伝学的に行われた。
新属 Plocealauda の定義は形態学と分子遺伝学の両者を併用。
ほとんどはアフリカなど日本と関係の薄い種だが多くの種で属変更の提案がなされた。
副産物としてスウェーデンとカザフスタンのヒバリの遺伝的距離は非常に近かった。
さらに Garcia-Navas et al. (2024) Diversification history and morphological evolution of larks
によればヒバリ類の種分化は時期的には一様に近く、過去にも爆発的な種分化は示さなかった。生態的な多様性の限界に近づいている可能性がある。嘴以外の形態はほとんど環境や生態に関係がなく系統的によく保存され形態的な収斂進化があまりみられない。また複数の系統 (亜科) でそれぞれ乾燥環境に適応したと考えられる。
乾燥環境では熱帯雨林に比べて種分化の平衡状態に早く到達する考え方を支持する結果となった。
-
コヒバリ
- 第8版学名:Alaudala cheleensis (アラウダラ ケレエーンシス) ヂーリー(直隷省)の小さなヒバリ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Calandrella cheleensis (カランドゥレッラ ケレエーンシス) ヂーリー(直隷省)の小さなヒバリ
- 第8版属名:alaudala Alauda (ヒバリ) 属の指小語
- 第7版属名:calandrella (合) 小さなヒバリ (korydallos ヒバリ Gk、-ella (指小辞) 小さい)
- 種小名:cheleensis (adj) Chelee Province/Zhili/Chihli/ヂーリー(中国直隷省) の (-ensis (接尾辞) 〜に属する) (1928年河北省に改編され直隷省は消滅)
- 英名:Asian Short-toed Lark
- 備考:
alaudala の発音はよくわからないが、alauda は主格では短母音で終わるため、長母音は発生しないと推定する。その場合は "アラウダラ" のアクセント位置と考えられる。
cheleensis は場所を示す -ensis の e が短母音または長母音でアクセントがあり、"ケレエンシス" または "ケレエーンシス" と推定される。長音の方がアクセント位置がわかりやすそうなのでこちらを採用した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Alaudala 属 [Alauda (ヒバリ) 属の指小語] に分離。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。Alaudala 属はコヒバリ属。Calandrella 属はコウテンシ属のまま。
従来は Calandrella rufescens (分類と最近の名称については以下参照) と同種とされ、コヒバリの学名にはこれが使われ、英名も Lesser Short-toed Lark とされていた。これは Short-toed Lark (ヒメコウテンシの旧分類での英名。#ヒメコウテンシの備考参照) に対するものであった。
以降近年に至るまで分類の変更 (属も分けられた) と細分化が続いている。
コヒバリと類縁種の分子系統研究は Ghorbani et al. (2020) Densely sampled phylogenetic analyses of the Lesser Short-toed Lark (Alaudala rufescens) - Sand Lark (A. raytal) species complex (Aves, Passeriformes) reveal cryptic diversity
にある。この研究ではコヒバリと Alaudala rufescens IOC: Mediterranean Short-toed Lark (この論文では Lesser Short-toed Lark) の関係は非常に複雑で、従来から記述されている種、亜種のほとんどが単系統でなく、隠蔽種が多数あることを示唆する。
外見的には非常に類似しているが遺伝的には4-5種に分離されると思われる。分類変更にはさらなる音声や行動などの研究が必要で、この時点での提案は見送られた。
Alstrom et al. (2020) Multiple species delimitation approaches applied to the avian lark genus Alaudala
の研究 (上記研究と研究者はかなり共通する) では、Alaudala rufescens-Alaudala raytal (インドコヒバリ 英名 Sand Lark/Indian Short-toed Lark) のグループの分子系統研究と音声研究を行い、Alaudala heinei (英名 Turkestan Short-toed Lark/論文では Heine's Short-toed Lark) を分離できることを示し、これらのグループから4種とそれぞれの亜種を挙げた。
この結果は現在の IOC 分類に反映されている。
コヒバリ Alaudala cheleensis Asian Short-toed Lark には2系統 cheleensis と tuvinica 及び leucophaea と kukunoorensis がある証拠があり、別種となる可能性があるがまだ結論できないとしている。
これほど分類が複雑なのは種分化の初期段階にあるためと考えられる。
あまりにも分類が新しいので一部の種には和名が与えられていない段階である。
コヒバリの話に戻ると、IOC 分類上では中央アジア、特にモンゴルから朝鮮半島に分布。世界で4亜種が認められている。日本で記録された亜種は基亜種 cheleensis とされる。
ただし上記論文にあるように外見だけでは正しい種/亜種を区別できないかもしれない。
Jiang et al. (2024) Selected Lark Mitochondrial Genomes Provide Insights into the Evolution of Second Control Region with Tandem Repeats in Alaudidae (Aves, Passeriformes)
にもミトコンドリアゲノムを用いた関連種の系統樹が出ている。
ミトコンドリアの second control region (CR2) が Alauda 属を含むこの系統で特別な進化を起こしている (詳しくは論文参照)。細かいメカニズムはともかく系統関係の確認には十分役立つ。
Sigeman et al. (2024) The rate of W chromosome degeneration across multiple avian neo-sex chromosomes
では性染色体と常染色体間の系統固有の染色体転座 (translocation) を用いた研究があり、同様の系統を得ているのでここに一緒に紹介しておく。Alaudala は含まれていないが近縁系統が含まれている。
-
ヒバリ
- 学名:Alauda arvensis (アラウダ アルウェンシス) 畑のヒバリ
- 属名:alauda (f) ヒバリ
- 種小名:arvensis (adj) 畑の (alvum -i (n) 耕地 -ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:[Skylark], IOC: Eurasian Skylark
- 備考:
alauda は -au- が2重母音なのでここにアクセントがある (アラウダ)。
arvensis は -ven- にアクセントがある (アルウェンシス)。-ensis の語尾の e 発音は長母音に統一しているが、ここでは直前の u の母音が入るため wiktionary の発音表記を採用した。伸ばしても構わない (アルウェーンシス)。
ユーラシアに広く分布。北アメリカやオセアニアの入植地にも持ち込まれている。世界で 11 亜種が認められている (IOC)。
日本の亜種は japonica 亜種ヒバリ、迷鳥として pekinensis (北京の) オオヒバリと lonnbergi (スウェーデンの動物学者 Axel Johan Einar Lonnberg に由来) カラフトチュウヒバリ、及び亜種不明である。
Skylark はヒバリ類全体を指すこともあり、ヒバリの種英名は Eurasian Skylark がよい。
OED によれば lark (および類似綴り) の用例は 1325 年ごろにあったとのこと。より古くは lauerce の名称 (参考ドイツ語では Lerche) や 1700 年前後には laverock の名称もあった。前者はラテン語との関係がわかりやすい。skylark の方が相対的に新しく 1672-1680 年ごろの用例があるとのこと。
対応する tree-lark もあって日本と同じように(ヨーロッパ)ビンズイのこと。
亜種ヒバリの記載時学名は Alauda japonica Temminck & Schlegel, 1848 (原記載)。図版。フランス語名 l'alouette commune du Japon で (ヨーロッパの) 普通のヒバリの日本版の位置づけ (フランス語名から判断できる)。
Temminck & Schlegel の他の類似の記載のように亜種のような表記になっていない (ただし当時ははっきりした亜種概念はなかった) のは、Alauda が単独で (ヨーロッパの普通の) ヒバリを意味するため種小名に相当する部分を置く必要がなく "日本の Alauda" で十分だったためだろう。
日本周辺の亜種は独立種 Alauda japonica 英名 Japanese Skylark とされることもある。例えば Clements 4th, Birdlife 2015 までなど。Avibase では現在も独立種として扱っている。Paul F. Donald "The Skylark" (T. & A.D. Poyser 2004) のモノグラフでも同じ扱い。
この扱いの場合はヒバリは2種となり、Alauda arvensis と Alauda japonica となる。上記日本で記録のある亜種は Alauda japonica の亜種となっている。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" にも言及はあるが、どこまでをこの「種」に含めるかの境界ははっきりせず、しっかりした分離の根拠となる研究は発表されていないとのこと。
その後 Stervander et al. (2020) Molecular Species Delimitation of Larks (Aves: Alaudidae), and Integrative Taxonomy of the Genus Calandrella, with the Description of a Range-Restricted African Relic Taxon
(#ヒメコウテンシの備考参照) では種ヒバリを目的とした研究ではないが分子遺伝学的に分離するある程度の根拠が示されている。
同じ備考に紹介の Alstom et al. (2023) の研究ではスウェーデンとカザフスタンのヒバリの遺伝的距離は非常に近い結果が得られている。種ヒバリ全体を対象とした分子系統研究は十分でなく (サンプルも非常に少ない) まだ分類に反映されていない段階だろうか。
ヒバリが音声を途切れさせずにさえずるように聞こえることから、息を吐く時も吸う時も声を出していると説明されることがあるが、これはおそらく誤り。
発声全般については #タンチョウの備考 [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] 参照。ヒバリぐらいに十分分離した音ならば個別に息を吐いて発声することは簡単にできるだろう。息継ぎは非常に短くてよく、わずかな合間があれば十分息を吸うことができる。
#ウグイスの備考 [ウグイスは息を吸う時に声を出すか] でハト類を中心に取り上げている。
[月夜に渡るヒバリ?]
Prinz et al. (2025) Lunar cycle and moonlight intensity influence nocturnal migration patterns in a small songbird
昔から想像されていたことで、話題性もあってわかりやすそうなのできっと取り上げられるだろうと想像して論文出典を紹介しておく。月夜に渡る傾向が出たのは、明るい夜は捕食を受けやすい、あるいは渡りに用いる星が見えにくいので避けられるとの従来の考えに反するとのこと。
このような書き出しの紹介の仕方をする場合は何か疑っていると考えていただいてよい (笑)。moonlight intensity (月光の強さ) と最も相関が高かったそうだが、そもそも moonlight intensity をどうやって見積もったのか今ひとつ詳細に書かれていない。完璧に晴れていれば天体暦からある程度予測できるが、局地の雲の光透過率はどのように見積もったのだろうか。
また月光の強さは衝効果があるので満月の前後だけ異様に高い。月の光っている面積に比例するわけではない。つまり残りの時期のデータは一見たくさんあるように見えるが、特に線形関係を仮定した場合は統計に役立っているのは満月の前後だけの可能性がある。月の位相 (moon fraction) との相関は少し弱い。
月が見えている時間などは月の位相でほとんど決まるので独立な要因とはならない。月が見えている時間との相関があまりないのは、実は月光との因果関係があまり強くないことを示唆しているのかも知れない。
統計に用いられたのは 2018-2020 年の3年だけで、秋の渡り時期の満月の前後だけの日数はたかだか知れているような気がする。風の強い日や雨が強い時、かすみ網が凍る時は避けたとあるので調査期間中ずっと晴れていたわけではなさそうで、調査可能日が限定されるとなおさら満月の前後にちょうどあたる晴れた晩の観測点の影響を受けやすくなるだろう。
軽く見た範囲では非線形効果は交絡因子のみ間接的に取り入れているようで、月光の強さと渡り強度の関係に適切に盛り込まれているのか判然としなかった。
また標識調査をされている方の視点から、月光が強いほどかすみ網にかかりやすい要因など考えられるだろうか (渡り密度を正直に反映した数字かあまりはっきりしない)。
-
ハマヒバリ (将来種分割される可能性があるが日本産亜種はこの学名にとどまる?)
- 学名:Eremophila alpestris (エレーモピラ アルペストゥリス) 高山の砂漠を好むヒバリ
- 属名:eremophila (合) 砂漠を好む鳥 (erimo 砂漠 philos 友人 Gk)
- 種小名:alpestris (adj) 高山の (alpes (f) アルプス山脈)
- 英名:Horned Lark
- 備考:
eremophila の発音はよくわからないが、由来となるギリシャ語では2つめの e が長母音のため同様に長母音となる可能性がある。他は短母音とすれば "エレーモピラ" のアクセント位置が推定される。
alpestris はすべて短母音で -pes- がアクセント (アルペストゥリス)。(Alpes は e が長音だがこの形容詞は短母音)。
東アジア地域を除く北半球中・高緯度に広く分布。世界では 42 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は flava (黄金色の) とされる。
Horned Lark はアメリカ英語で、ヨーロッパ (ユーラシア) では Shore Lark とも呼ばれる。和名は後者に対応する。
Eremophila 属も最近分離された属ではなく古くから使われていた。
Dement'ev and Gladkov (1954) では「角のあるヒバリ」(英名と同じ) としている。Dement'ev and Gladkov (1954) の時代以降に大所帯の Eremophila alpestris から分離された種は ウスイロハマヒバリ Eremophila bilopha (bi- 2つの lophos 冠、冠羽 Gk) 英名 Temminck's Lark のみである。
最近の分子系統解析では
Drovetski et al. (2014) Limited Phylogeographic Signal in Sex-Linked and Autosomal Loci Despite Geographically, Ecologically, and Phenotypically Concordant Structure of mtDNA Variation in the Holarctic Avian Genus Eremophila
が6つのクレードを見出し、将来的に種として認識される可能性があることを示した。
Ghorbani et al. (2019) Mitochondrial phylogeography of the genus Eremophila confirms underestimated species diversity in the Palearctic
では4つのクレードを同定し、
(1) Himalayan Horned Lark Eremophila longirostris
(2) Temminck’s Lark Eremophila bilopha (これまで通り)
(3) Mountain Horned Lark Eremophila penicillata
(4) Common Horned Lark Eremophila alpestris
が種相当であるとしている。
日本で記録される亜種が flava であれば、この (4) に含まれるため学名は変化しないことになる (英名が少し変わる)。
Drovetski et al. (2014) では flava をクレードの1つとして扱っており、もしこれが種として扱われれば学名が変化することになる。この2者の分類の違いは極北に分布する亜種をアメリカとユーラシアで別種にするかしないかに相当する。
Drovetski et al. (2014) では brandti (プロイセンの動物学者でシベリアを探検した Johann Friedrich Brandt に由来) 英名 Steppe horned lark または
Brandt's horned lark もクレードの1つとなっている。Ghorbani et al. (2019) ではこれも (4) のクレードに属する (系統内の関係はいずれの研究でも同じで、どのぐらいの違いを別種と認めるかの問題となっている)。生物地理学を優先すれば別種となる可能性もあるかも知れない。
brandti は地理的位置関係からは日本に飛来する可能性もありそうなので (将来別種になるかも知れない) 亜種識別も重要になるのだろう。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" にはユーラシア北部・東部の亜種の図版が出ている (ちなみにこの本での見出しは Shore Lark となっている)。
ちなみに flava, brandti はともに最初は独立種として記載された (ただし当時はそう記述せざるを得なかった) ものである。
Alstom et al. (2023) Systematics of the avian family Alaudidae using multilocus and genomic data (#ヒメコウテンシの備考参照)
によれば Eremophila longirostris, 狭義 Eremophila alpestris, Eremophila bilopha (これまで通り), Eremophila penicillata
を認めており、出典は Ghorbani et al. (2020) Mitochondrial phylogeography of the genus Eremophila confirms underestimated species diversity in the Palearctic (Alstom も共著に含まれる)
としている。IOC 14.2 では Eremophila bilopha のみが分離されて他はまだ Eremophila alpestris の亜種扱い。
引用文献はまだ Drovetski et al. (2014) のままで Ghorbani et al. (2020), Alstom et al. (2023) は参照していない。Calandrella 属の種分割の分岐年代とほぼ同程度で将来分割される可能性は高そう。これらを取り入れれば種が比較的早い時期に分割される可能性があると思われる。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ツバメ科 HIRUNDINIDAE ▽
-
タイワンショウドウツバメ (AviList で分割)
- 第8版学名:Riparia paludicola (リーパーリア パルーディコラ) 沼地に住み土手に巣を作る鳥
- AviList 学名:Riparia chinensis (リーパーリア キネンシス) 中国の土手に巣を作る鳥
- 属名:riparia (adj) 土手に巣を作る (riparius、ripa (f) 土手); 河岸に多い (コンサイス鳥名事典)
- 第8版種小名:paludicola (adj) 沼地に住む (palus -udis (f) 沼地 colo (tr) 住む)
- AviList 種小名:chinensis 中国の (暫定)
- 英名:[Plain Martin], Brown-throated_Martin, IOC, AviList: Grey-throated Martin (Riparia chinensis)
- 備考:
riparia は#ショウドウツバメ参照。
paludicola は u が長母音で -di- にアクセントがある (パルーディコラ)。発音しにくそうだが辞書の記述もこの通り。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに Riparia paludicola の亜種扱いであるが、現在の世界のほぼすべての主要リストでこの種を2種に分割。
Riparia paludicola (アフリカショウドウツバメの名はある) が Plain Martin の英名を引き継ぐか、Brown-throated Martin (IOC 14.2) とされる。
日本鳥類目録改訂第8版の学名を用いる場合は IOC 14.2 に対応する種があるが概念が異なるので注意。
2種に分割する場合は日本で迷鳥記録された方の種は Riparia chinensis (「中国の」の意味。台湾、フィリピン北部、東南アジア北部からインド北部に分布) とされる。英名 Grey-throated Martin (IOC)、別名 Asian Plain Martin (BirdLife) 。
この場合は2亜種 (IOC) で日本で記録されたものは基亜種 chinensis となる。
見出しの IOC, AviList 学名はこれを用いているが、新しい分類に相当する種レベルで検討が行われているか不明なので暫定的に与えたもの。
AviList では亜種 chinensis の分布を Afghanistan and Pakistan to northern India, Myanmar, and southeastern Asia、tantilla を northern Philippines (Luzon and [?] Negros) としている。
Riparia paludicola を2種に分離しない場合は世界で9亜種 (IOC)。AviList では分離されて Riparia chinensis は2亜種。
AviList では Riparia chinensis の分離はすでに行われていたためかあまり問題になっておらず、22635 993 Taxon cowani is treated as a monotypic species separate from Riparia paludicola based on a relatively deep genomic DNA divergence (Brown 2019), supported by plumage and vocalizations. However, a comprehensive review of morphological, vocal, and genetic variation across the R. paludicola complex would be informative.
全体としては Riparia paludicola complex のさらなる解析が望まれるとのこと。
-
ショウドウツバメ
- 学名:Riparia riparia (リーパーリア リーパーリア) 土手に巣を作る鳥
- 属名:riparia (f) 土手、川辺、海辺 (解説参照)
- 種小名:riparia (adj) 土手に巣を作る (riparius、ripa (f) 土手); 河岸に多い (コンサイス鳥名事典) (トートニム)
- 英名:Sand Martin
- 備考:
riparia は 最初の i と次の a が長母音。後者にアクセントがある (リーパーリア)。
英語別名に学名と同じ意味の Bank Martin もある。
OED によれば martoune の用例が 1525 (1448) 年ごろにあり、1589 年にはすでに Martins と呼ばれていたとのこと。語源は人名の Martin (St. Martin 聖マルタン。#ハイイロチュウヒのフランス名参照) から作られた martinet 由来と推定されている。鳥を指す martinet 及び類似綴りの用例は 1440 年ごろにすでにあった。
martin はフランス語でしばしば鳥の名前に使われ、カワセミは martin-pecheur、より古くは martinet-pecheur などがあり英語と同様の語源と推定できるとのこと。
記載時学名 Hirundo riparia Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 Europe = Sweden (Avibase による)。riparia は形容詞扱い。
Riparia 属は Forster (1817) が当時のショウドウツバメのみを含む属として昇格したもので、トートニムを避けるために (#ノスリの備考参照) Riparia europaea? の新名を与えた (記載 p. 17, 参考)。
よく調べていないが形容詞を属名に昇格するのは珍しいかも知れない、と思ったが riparia には名詞 (f) があって川辺、海辺などを指す。形は同じだがこの名詞を用いたらしい。さすがの The Key to Scientific Names にもそこまで書かれていない。
北半球に広く分布し、赤道近くから世界的にはアフリカ北部、南アメリカにも渡る。世界で4亜種 (IOC)。日本の亜種は ijimae (動物学者 飯島魁 Isao Ijima に由来) とされる。
この亜種は記載時学名 Clivicola riparia ijimae Lonnberg, 1908 (原記載) 基産地 Tretiya Padj, Sakhalin とサハリンで飯島魁氏のサハリン探検で得られた標本から記載のため献名となった。Lonnberg がかなり頑張って (venture とある) 亜種に分けたもの。
Clivicola は Riparia と同じく Forster (1817, 記載 p. 55 同じものを指していたがこちらの方が後に現れる)、clivus 斜面 -cola 住む者 が由来。同一文献内なので訂正したものとも解釈可能で、どちらが有効か見解が分かれていたのかも知れない。
多少類似の事例として#クロヅルの備考のジャイアントモアの記載時属名を参照。この場合は経緯がわかっていて片方を直し忘れた結果同一文献に2つの属名が現れることになった。
Forster (1817) のショウドウツバメの記載の2つめにも綴りは違うが同じ種小名が用いられており、種小名の riparia を保存して属を変えてトートニムを避けたわけではなかった。Linnaeus (1758) の riparia が形容詞扱いだったので問題があると考えて訂正したのかも知れない (単なる想像。あるいはジャイアントモアの場合のようにどちらかを直し忘れたものかも)。
他の属名も 1876 年までに5つも提唱されており、Forster (1817) の属名はまだ知られていなかった時期のものか、あるいは Forster の扱いに問題があると判断されていたのかも知れない。
Hartert (1910-1922) p. 810 では Riparia が採用されていた。
シベリア南部からインド北部、中国南東部で繁殖しパキスタン、インド南部やスリランカに渡る個体群は近年 Riparia diluta 英名 Pale Martin と分けられた。
Young Guns (2013) Birder 27(10) は仮称ウスショウドウツバメを与え、この種も観察される可能性があるため識別などを紹介している。
この2種の分子遺伝学研究は Pavlova et al. (2008) Pleistocene evolution of closely related sand martins Riparia riparia and R. diluta にある。
梅垣 (2023) Birder 36(1): 48-51 にショウドウツバメとウスショウドウツバメ再考の記事がある。手にとってもわからないぐらい識別が難しい。
この記事で Tang et al. (2021) Seasonal migration patterns and the maintenance of evolutionary diversity in a cryptic bird radiation の論文も紹介されている。
ウスショウドウツバメの亜種 fohkienensis (中国南東部低地) と tibetana (チベット) の間の遺伝的交流がなく、渡りも異なっている。
Schweizer et al. (2018)
Contrasting patterns of diversification in two sister species of martins (Aves: Hirundinidae): The Sand Martin Riparia riparia and the Pale Martin R. diluta
でも取り上げられているが、外見差があまりに小さいので遺伝情報から別種とする提案は控えておくとある。
Schield et al. (2024) Phylogeny and historical biogeography of the swallow family
(Hirundinidae) inferred from comparisons of thousands of UCE loci [出版社サイト] にツバメ科の最新分子系統樹が発表された。営巣習性の進化なども議論されている。
Riparia diluta と Riparia riparia には十分な遺伝的距離があることが確認された。
この論文では Riparia diluta 内の構造までは調べられていない。
ツバメ科の分子系統研究については de Silva et al. (2018) Recognition of a new generic-level swallow taxon from central Africa も参照。
イワツバメ、ニシイワツバメに最も近く早く分岐した系統のアフリカのモリサンショクツバメ これまでの学名で Petrochelidon fuliginosa Forest Swallow に新しい属名を与えて Atronanus fuliginosus とした。従来の Petrochelidon 属が多系統と判明したため。
モリサンショクツバメはかつて Lecythoplastes 属に置かれていたが、この属のタイプ種は別種なのでモリサンショクツバメのみを含む新しい属に用いることができない。そのため新しく提案されたもの。
電子出版にもかかわらず ZooBank に事前登録を行っていない命名上問題があり、まだ未出版と取り扱う人が多いとのこと (BirdForum の Taxonomy in-flux updates, The Key to Scientific Names)。GBIF では Taxonomic status unknown の扱いとなっているが、IOC などでは新しい学名を用いている。
指摘が行われているのでおそらく ZooBank への登録申請と訂正論文が出されるのではないだろうか。Catanach et al. (2024) のタカ類の新しい系統名称提案の時と状況は同じ。論文出版前に事前申請が行われていなかったため3か月後に訂正論文が出された。
その後 BirdForum で著者にコンタクトを取ったとの報告があり、著者が取り下げなければ近々訂正論文が出される見通し。
ショウドウツバメの和名は小洞燕で特に違和感はなかったが、コシアカツバメの別名にトウツバメがあることを知った (コンサイス鳥名事典)。この名称に対して与えられたショウドウツバメであったならば一層理解しやすい感じがする。
[翼前縁に serration のあるツバメ類]
Hasegawa (2023) Sexually dimorphic leading-edge serrations evolved in silent swallows (preprint)
フクロウ類で消音機能として提唱されているもの。キタオビナシショウドウツバメ Stelgidopteryx serripennis Northern Rough-winged Swallow など。顕微鏡的特徴なのでそのまま野外同定の特徴とはならない。日本のショウドウツバメと外見は同じように見える。
#ウスハイイロチュウヒ備考 [音を出さない羽毛構造] に含めておいた。
[ショウドウツバメによる死体(雄)への同性間交尾]
岩見 (2018) Birder 32(1): 70 にショウドウツバメのオスがオスの死体に対して交尾した事例が紹介されている。
Homosexual necrophilia in the Sand Martin 雄のショウドウツバメによる死体(雄)への同性間交尾、で動画が見られる。日本語版ページには少し解説がある。
Tomita and Iwami (2016)
What Raises the Male Sex Drive? Homosexual Necrophilia in the Sand Martin Riparia riparia が論文。
#ツバメの備考も参照。
北米のムラサキツバメ Progne subis Purple Martin でゲノム解析によって渡り時期に関連のある遺伝部位が明らかになった: de Greef et al. (2023) Genomic architecture of migration timing in a long-distance migratory songbird
第1染色体に関連する部位があり、遺伝的特性のみで春の渡り時期を相当よく再現できる。この部位にある遺伝子に Ppfia2, nts があり、睡眠や覚醒に関係しているとのこと。夜間の渡りに関係ある可能性が指摘されている。mettl25, acss3 のようなエピジェネティクな修飾を行う遺伝子も含まれており、これも行動に関係している可能性がある。
複数の遺伝子の関与するメカニズムが考えられるが詳しいところまではまだ解明できていない。
-
ミドリツバメ (第8版で検討種)
- 学名:Tachycineta bicolor (タキュキネータ ビコロル) 二色の速く飛ぶ鳥
- 属名:tachycineta (合) 速く飛ぶ鳥 (tachy- (接頭辞) 速く kino 動かせる Gk、-tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 種小名:bicolor (adj) 二色の (bi- (接頭辞) 二つの color (m) 色)
- 英名:Tree Swallow
- 備考:
tachycineta の発音はよくわからないが起源となるギリシャ語の takhukinetos の e が長音のため同様に長母音となる可能性がある。その場合はアクセントもその位置 (タキュキネータ)。
bicolor はすべて短母音で冒頭にアクセント (ビコロル)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
-
ツバメ
- 学名:Hirundo rustica (ヒルンドー ルースティカ) 田舎のツバメ
- 属名:hirundo (f) ツバメ
- 種小名:rustica (adj) 田舎の (rusticus)
- 英名:[House Swallow], IOC: Barn Swallow
- 備考:
hirundo が末尾が長母音。アクセントは -run- にある (ヒルンドー)。
rustica は冒頭が長母音でアクセントもここにある (ルースティカ)。
rus (日本語では "田舎" の意味が近い) も長母音で "ルース"。複数形 rura (ルーラ) など、英語の rural を想像でき、英語を "ルーラル" と読むならば "ルースティカ" と読むのも自然に感じる。
英名の House Swallow はショウドウツバメ (Sand Swallow の別名があった) に対する名称。この名称関係は英国の一部地域と北米 [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)]。
北半球に広く分布。南半球にも渡る。世界で8亜種 (IOC)。日本で記録される亜種は gutturalis (「のどに特徴がある」意味 < guttur, gutturis のど) 亜種ツバメ、saturata (「色の濃い」の意味) アカハラツバメ、及び亜種不明とされる。
亜種 saturata の扱いは分類学者によって見解が別れている [Dickinson and Milensky (2002) Systematic notes on Asian birds. 31. Eastern races of the barn swallow Hirundo rustica Linnaeus, 1758] が、IOC はこの亜種を認めている。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではカムチャツカやオホーツク海沿岸で繁殖するツバメは北米の亜種と同じ erythrogaster (腹の赤い) 亜種として扱い、この地域で過去に提案された亜種 saturata, camtschatica はシノニムとして扱っている。
このグループをロシア名で「アムールのツバメ」、亜種 tytleri (英国軍人で博物学者の Robert Christopher Tytler に由来) を同じく「シベリアの、あるいは腹の赤いツバメ」と称している。
現代の分布では南シベリア (バイカル湖周辺) からモンゴル、中国の内モンゴル自治区とされている。必ずしも日本鳥学会のアカハラツバメと同一ではないが、いわゆる「赤腹ツバメ」の正体 (というよりも東アジア大陸部のツバメ全般に) はよくわかっていないと言った方がよさそうである。
東シベリアの個体群は北アメリカから分布を広げた (通常の分布拡大のパターンとは逆) ことがわかっている [Zink et al. (2006) Barn swallows before barns: population histories and intercontinental colonization]。
特にツバメの亜種間の関係については Dor et al. (2010) Phylogeny of the genus Hirundo and the Barn Swallow subspecies complex の研究がある。亜種間の分岐年代は新しいため (10 万年程度) 適応放散に伴う分化の早い段階を見ているだろうとのこと。
#ショウドウツバメ備考の Schield et al. (2024) も現代的な分子系統解析を行っているが、亜種 rustica が一番古い系統で、
tytleri, erythrogaster, gutturalis の3亜種が近い関係にある。この順序で分岐した可能性があるが、系統樹サポートはまだ十分でなく確定的ではない。
Lombardo et al. (2022) The Mitogenome Relationships and Phylogeography of Barn Swallows (Hirundo rustica)
がミトコンドリアゲノムを用いた生物地理系統学の結果を紹介している。ヨーロッパのツバメが主だが他の亜種も調べている。約 28 万年前にアフリカ (かその近く) から出発しまずユーラシアに分布を広げた。この推定はツバメの近縁種の分布からもっともらしいと考えられる。
その子孫が少なくとも 5.1 万年前にアメリカに分布を広げ、最近 (2万年前以内) にアメリカからアジア北部にも分布を広げた。
この研究では日本の個体は調べられていないが、同じ gutturalis の分布する中国の個体が扱われている。これらはユーラシア内部で分布を広げたと考えられる。
saturata は分析されていないが、アメリカからやってきたのだろうか。ユーラシア北東部はツバメに適した民家などの建造が遅く、到着が遅れたためアメリカからの渡り個体群の方が先に到着したのだろうか。
これらのヨーロッパの研究の多くは亜種 transitiva の位置づけなどを気にしているものと想像できる。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the barn swallow Hirundo rustica (pp. 221-238)
ロシア沿海地方の繁殖。gutturalis の特徴を示すものが多いが、tytleri の特徴のものが少数、中間型も生息しているとのこと。
両亜種の交雑帯に近く遺伝子浸透が起きていると考えられる。
[ツバメ亜種間の生殖隔離と性選択]
ツバメ亜種間の生殖隔離機構に性選択が関わっているとの報告: Schield et al. (2024) Sexual selection promotes reproductive isolation in barn swallows
336 個体のゲノム解析。rustica, tytleri, gutturalis の腹の色彩は第1染色体と Z 染色体が中心的に決めているが、色彩の他の表現型はメラニンに関係するものも含めた 10 座位の遺伝子が関連している。尾の外側の streamer の長さは第2染色体が決めているとのこと。
亜種の交雑域で性選択の対象となる形質に関わる遺伝子の交流は抑制されているが、ゲノムの他の領域はそれほどではなく、性選択の対象となる形質に関わる遺伝子の交雑域での地理的クラインも複数の座位の特定の組み合わせが選択されている。亜種間の雑種の形質は選択されにくいことを示す。
いずれも性選択が生殖隔離に関与する証拠となる。
特にユーラシア大陸部の中東から東部での交雑域での研究でヨーロッパでなく我々に関係深い地域で行われたことも興味深い。
現実に起きている性選択による(亜)種分化の証拠として取り上げられている。
A front-row seat to evolution: What common barn swallows can teach us about how new species form (一般向け英文解説)。
日本の研究者によるツバメ類の進化速度と形質の関係の研究: Hasegawa (2024) Swallows with sexually dimorphic tails have higher speciation rates (preprint)。
尾 (streamer) の長さに性的二形が発達している種ほど統計的に有意に進化速度が速い (詳しくは論文参照)。
Schield et al. (2024) の論文と手法や対象範囲は異なるが種分化機構を議論している観点は同じ。
こちらは性的二形がさまざまに発達した広い範囲の種を対象として導いたもの (#カッコウ備考の [カッコウのタカへの擬態] の Medina and Langmore (2015) の研究なども参照。タカへの擬態らしいカッコウ類の模様の進化が速い)。
日付から Schield et al. (2024) の論文公表後に preprint 投稿が行われたもの。ツバメのゲノム解析の結果を見ると尾の長さ以外にも (おそらくツバメ以外の種でも) 性選択の対象となる形質があってもおかしくなさそう。
Lombardo et al. (2025) The end of the American dream: a hard to Swallow reality - How the Barn Swallow (Hirundo rustica) returned from America, a complete mtDNA phylogeny
mtDNA の研究から新しいハプログループが見つかり、tytleri と同定され、従来は erythrogaster の枝と考えられていた。
ツバメ属はアフリカ南部に生まれアラビア周辺に集団がありそれぞれ各地に分散した。アフリカからオセアニアの系統がアフリカ由来 (リュウキュウツバメはこちら)。
北方へはアラビア (種ツバメはこちら) からで、ヨーロッパに亜種 rustica、東アジアに gutturalis。北米にアジア東部から erythrogaster これがユーラシアに戻って tytleri。東アジアには2系統が別ルートで入って遺伝子浸透があるので中間地域のものに亜種名が付いていた状況のよう。
この論文では日本は gutturalis に含まれているがサンプルは少ない。
[人工物以外への営巣]
本によってはツバメの人工物以外への営巣は世界的にも知られていないと書かれているものもあるがこれは正しくない。
日本の書物では「ツバメのくらし百科」(大田眞也 弦書房 2005) に自然の石灰洞窟への営巣のことが述べられているとのこと。
ML Kbird に提供された話題によれば、杉本 [kbird:03860, kbird:03862 (2021.5.19)] によれば、20 世紀初頭のアメリカで湖畔の崖などに営巣しているケースが報告されているとのこと (写真はない)。
Bent (1942) Life histories of North American flycatchers, larks, swallows, and their allies. Order Passeriformes (Families Cotingidae, Tyrannidae, Alaudidae, and Hirundinidae)" の p. 442 から。
動いている列車や船に営巣した例も紹介されているとのこと。
ロシアでは結構多くの事例が報告されている。
Mal'chevskij and Pukinskij (1983) レニングラード州と隣接地域の鳥 (ツバメ) に 1967 年にロシアで崖に営巣した写真が出ている。
Atemasov and Atemasova (2015) An interesting nest of the barn swallow Hirundo rustica on the banks of the Seversky Donets (pp. 1202-1203)
に1994年7月29日から31日、ハリコフ地域のバラクリー地区にある Chervony Shlyakh (Seversky Donets の下流) の村の近くで、川面から 2 m の高さ、水面から 45° 傾斜した木の隙間でツバメの営巣を見つけた。ツバメはひなに餌をやっていたとのこと。村は約 0.5 km のところにあったとのこと。
同文献によれば Koshelev and Korzyukov (1986) と Kostyushin (1994) が岩の下部にツバメの営巣を報告しているとのこと。Krivitsky (1994) はポプラの枝にツバメが巣を作ったことを報告している (文献は論文中にあり)。
Bardin (2006) The barn swallow Hirundo rustica nests on bluffs of Pimzha River (pp. 286-287) 張り出した崖の下の垂直壁の水から 3 m の高さにひなが巣立ったばかりのツバメの巣を見つけた。集落から遠く離れた場所では、ツバメが巣を橋の下に造ることが多い。同文献中で Koloyartsev (1989) はツバメが人間から遠く離れ、洞窟、岩、崖、木の幹に営巣する例を紹介している。
Bardin (2018) Barn swallows Hirundo rustica builds a nest in hut of branches on a raised bog (pp. 4445-4448) に人里離れた (人の住む場所から 4-5 km) 放棄された人工物 (狩猟用のハイド) への営巣の写真付きの紹介がある。
Kostyushin (2017) New data on the nesting of the barn swallow Hirundo rustica on the rocks in Ukraine (p. 4281) ウクライナで渓谷の岩場のツバメのコロニー。
Koloyartsev (1989) "Lastochki" ツバメのモノグラフがあり、p. 141 に崖の営巣写真がある。
このモノグラフにはヨーロッパやロシア都市でのツバメ盛衰も記されている。さらに先史時代、つまり人間がまだ建物を建ててなかった時、人間も洞窟に住んでいたためツバメも一緒に住んでいたのではないかとの推論がなされている (同書 p. 139)。
19 世紀半ばから 20 世紀初めまではヨーロッパの家の多くにはまきなどを使った暖房設備があり、ツバメはその煙突に好んで営巣していたが、その後石炭やコークスなどが使われるようになって煙突が狭くなり営巣場所を変えたとのこと。
このためドイツ語でツバメは Rauchschwalbe (煙のツバメ) と呼ばれている (家のツバメ Hausschwalbe の別名もある)。エストニア語でも同様で suitsupaasuke (suits 煙 paasuke ツバメ) とのこと (同書 p. 142)。
Dement'ev and Gladkov (1954) (Vol. 6, p. 695) にも天然物への営巣の記載があり、大きな猛禽類の巣の下に造ることもあるそうである。
Dement'ev and Gladkov (1954) の有名な書物にも記載されているため、ロシアではツバメの人工物以外への営巣は比較的よく知られ、注意して調べている研究者もいるようである。日本でもそのつもりで探すと見つかるかも知れない。
ロシアでもクルーズ船に営巣したツバメの事例がある: Urusova (2022) Nesting case of the barn swallow Hirundo rustica on a cruising riverboat (pp. 1194-1196) 2021 年の事例で無事巣立ったとのこと。過去の事例も言及があり写真もある。
#ヒメチョウゲンボウもスペインや地中海では現在はほとんど都市のみで繁殖するとのこと。こちらは古い建物好みだそうで比較してみると面白いだろう。
[ツバメの夫婦愛? 死体を好む行動?]
ツバメ類では necrophilia (死体を好む) 行動が比較的よく知られていて、例えば事故死した相棒を生き返らせようとケアしているように見える場面は necrophilia なのではないかとしばしば議論になる。
Unusual swallow necrophilia
では台湾のツバメの事例 (2004) が紹介されている。これはネットで紹介されて一時はツバメの夫婦愛として多くの人の涙を誘ったが necrophilia の可能性が生態学者から指摘された。
論文中でも引用されているマガモの事例は Moeliker (2001) The first case of homosexual necrophilia in the mallard Anas platyrhynchos (Aves: Anatidae)
でこの研究はイグ・ノーベル賞も受賞したとのこと
[ショウドウツバメによる死体(雄)への同性間交尾については #ショウドウツバメの備考参照]。
同年の2004年5月、京都の「花背山の家」で死んだように見えるオスをメスが介抱し、5分後にオスが目を醒まして一緒に飛んでいった事例が京都新聞に報道された。報道ではビデオにも記録され、映像は来訪者にも紹介されていたとのこと。
海外に紹介したところ動物行動学者の Jonathan Balcombe が興味を持ち、新聞記事以上の情報は得られなかったのだが "Pleasurable Kingdom: Animals and the Nature of Feeling Good" (Macmillan, 2006) に紹介された。
「動物たちの喜びの王国」(ジョナサン・バルコム著 土屋昌子訳 インターシフト 2007) で邦訳あり。
同書 p. 219 に載っている。この行動は "夫婦愛" のような人間的解釈でなくても、繁殖行動に投資したコストを無駄にしないための行動の生態学的解釈も可能だしそれを否定するわけでもない。
しかしそれならば人間の親が溺れそうになっている子供を助けるのも同じように説明できるのではと指摘している。「がちがちの進化論的解釈」の限界も述べている。正統派の生態学者はこういう本はあまり読まないかも知れないが。
ちなみに著者は熱心なバードウォッチャーでもあり、鳥たちが遊んでいる / 楽しんでいる / いたずら心 などと思われる行動もいくつも記載されている。
「野鳥」2024年7・8月号 (No. 571) p. 57 会員フォーラムに相手を亡くしたキジバトの類似の行動が報告されている (有川氏)。
[視覚特性]
Tyrrell et al. (2017) The Hawk-Eyed Songbird: Retinal Morphology, Eye Shape, and Visual Fields of an Aerial Insectivore (別サイト) によれば、空中で虫を捕えるスズメ目の鳥の視力は猛禽類によくたとえられる。
ツバメは多くの昼行性猛禽類同様に網膜に2つの視力のよい場所 (中心窩と側方窩) があって、側方と前方の視力がよい。しかしツバメでは左右の前方視 (側方窩) の視野に重なりがなく、左右の目で4か所の視力のよい点がある。捕食性の鳥は視力のよい両眼視を使っているとの一般的な考えとは合わない。
[ブルグミュラーの "つばめ"]
ピアノを習われた方はブルグミュラー (Burgmueller) の 25 の練習曲 Op. 100 を使われた方も多いのではないかと思う (少なくともピアノを習う人の大半が子供だったかつてはそうだったが、今では異なっているかも知れない)。
この曲集には鳥が登場する曲が2つあり、1つが「せきれい」(La bergeronnette) もう1つが「つばめ」(L'hirondelle) (このようにクラシック音楽では題名にフランス語が登場することも多く、経験があれば子供のうちから何となく知ってしまう。ツバメの学名もすんなりわかってしまう)。
初歩の練習曲 (のはず) なので子供時代に習うと普通は小学生ぐらいでこの曲集に接することになることが多いだろう。
秋末直志「ブルグミュラーの再発見」(ショパン 1996) という面白い本があり、ピアノ教師側からどのように指導するかを説明している。「せきれい」は知らない子供も多いので図鑑や百科事典なで調べてどんな鳥か調べることを宿題とするとよいとのこと (インターネットはまだ普及していない時代)。
教師自身が子供を連れて実物を見に行くよう提案すればよいわけではあるが、忙しい教師にはさすがにそこまでは望まないというところだろうか。この「せきれい」は鳥たちの1日の日常を描いているとの解釈になっている。例えば冒頭の部分は集まって来た鳥たちが周囲に警戒を行いつつも最後に決断した様子が和音の動きから読み取れるとのこと。
ブルグミュラーの 25 の練習曲は全体的に易しい曲が中心で「せきれい」も易しい方に入るだろう。
中には少し難しい曲があって「狩り」(19世紀の話で、馬に乗って出かける貴族のスポーツとしての狩り) では、技術不足のまま弾かせると馬ではなく豚に乗って狩りに出かけるような音楽になると手厳しい。難しい曲は後回しにしてもよい例としている。
さて問題の「つばめ」であるが、これは 25 曲の中で飛び抜けて難しいと思う。自分も他の曲は簡単に弾けるが「つばめ」だけは難しい。昔習った時の教則本ではここに「つばめ」の絵が出ていて早く弾きたいと (当時から鳥好きだったので) 先回りして練習していたのだがそれでも納得できるものにはならなかった。
秋末氏の解説によれば中間部で一時的に短調になるが、これは「つばめ」が渡り鳥のため悲しいこともあるだろうと解釈している。最後は秋の日暮れのつるべ落としである。ツバメのねぐら入りの「木の葉落とし」を想像してもよいかも知れない。
自分が習った時の教則本では全曲でペダルを使う指示があり秋末氏もペダルが必要ですと書いている。
過去の経験も考えると子供の力量ではこの曲をペダルなしで弾くのは困難で、他の曲ではペダルの使い方を細かく指示している秋末氏も妥協せざるを得なかったのかも知れない。
この曲は基本的に両手の交差の練習曲だが、同じ技術を扱ったツェルニー 30 番 (平均的技術的にはブルグミュラーの 25 の練習曲を終えるぐらいから学ぶ練習曲だろう) の曲の方がずっと易しい。
「つばめ」の難しさを多少分析してみると、ある程度以上のテンポで弾かないとそもそも颯爽としたツバメにならない。ペダルなしで弾く時は、楽譜上ではスラーの表示でレガートを意図しているのだろうがノンレガートで弾くと軽やかなツバメらしくなる。この程度の演奏者の裁量による解釈変更はロマン派音楽では普通にある。
この学習段階ではノンレガートをおそらくまだ習わない (ツェルニーでは 40 番で初めて現れるぐらいだが、自分の先生もそういう弾き方は教えてくれなかったと思う) ので初学者ではこのような表現は難しいかも知れない。
中間部の短調部分はノンレガートを抑えてベース音が変わらないことを意識し、少しぼんやりした弾き方にする。最後はまた軽やかなツバメに戻り、全体をペダルなしで弾くのがよいと思う。
ちなみにツェルニーの練習曲は基本的にベートーヴェンを弾くため、ブルグミュラーはロマン派音楽を弾く入門のようなもので少し目的が異なる。ロマン派音楽をもっと体験してから弾いた方がよい曲かも知れない。
過去にクラシックのピアノを習われた経験のある方も「つばめ」は改めて表現に工夫を凝らされるとよい曲ではないかと思う。
物事ついでにこの 25 の練習曲に「タランテラ」があり、これは本来毒グモのタランチュラにかまれて踊り狂う音楽なので最後までイン・テンポで弾かない方がよいのではと思う。音型は難しくないので最後は速度を上げて最速まで達すればよいと思うが、そういう演奏を習っている最中の人が聞いてしまうと変な先入観を持たれてしまうかも知れない。
この曲を反田恭平さんも弾いているのだ (YouTubeにあり) とちょっと驚き (上記の自身の解釈とは少し違っているが)。
音楽好きの方だとここで終わるのはちょっと物足りないと感じられるだろう。速めのテンポの「つばめ」を快適に感じるのは似た音型のリストのパガニーニによる大練習曲第4番の影響が大きいと感じる。パガニーニのバイオリンのための原曲ほとんどそのままでピアノ音楽なのに珍しく一段譜になっている。
この練習曲の第6番もまたパガニーニによる変奏曲に非常に近いものだが、この旋律は当時の作曲家に大変好まれ、ラフマニノフが素晴らしい変奏曲 (パガニーニの主題による狂詩曲。一種のピアノ協奏曲) を残している。第 18 変奏が際立って有名で、このアイデアがあまりに素晴らしかったためラフマニノフはこの全曲を仕上げたのだろうとも言われる。よく知られた曲なので聞いてみていただきたい。
[ツバメは人に助けを求めるか?]
巣が外敵に襲われた場合に人に助けを求めたかも知れないツバメの例があったのを覚えていたが出典を思い出せなかった。「はじめての野鳥」(長谷川博著 岩波書店 1993) だった。夜間に窓に当たる音やひっかく音が聞こえたので見にゆくとアオダイショウがツバメのひなを食べたところだったという。
#シジュウカラ備考の ["小鳥との語らい"] のように朝は窓をたたいて起こしにくるヨーロッパシジュウカラの話もあり、ツバメも人に助けを求めても不思議でないかも知れない。
もっとも現代の家屋ではツバメが営巣するとしても人との距離が遠く、窓の防音性も上がっていてそのような行動があっても単に気がつかれていないだけかも知れない。
[燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや]
ツバメでもスズメでもどちらの項目に入れてもよいがツバメの方に入れておく。
これは非常に有名なので説明を要しないだろうが、河田聡美 漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 大修館書店 1989 pp. 122-123 に紹介があり、史記 陳渉世家 が出典。
安んぞ (いずくんぞ 疑問・反語) はこの使用例が有名で、「燕雀安んぞの "いずくんぞ"」と言うのがわかりやすい。外国語を勉強する時に対応する現代語あるいは英語が思いつきにくいが、古典の "いずくんぞ" と解釈すれば理解しやすい場合がある。ロシア語の ved' に同じような意味があると思っているが、辞書から例文を見てみると Ved' on ne rebenok. まさか彼も子供でもあるまいし。
ved' の辞書英語訳では isn't it などが挙げられているが、日本語訳の方が含蓄が深い気がする。
ドイツ語も doch にも同じような使い方がある。こちらも対応する英語は though と記されていたりする。こちらも辞書の例文を紹介しておくと er ist doch nicht etwa krank? 彼はまさか病気ではあるまいね 「いや違う」の返答を期待しているので nicht の否定が入っている。
-
リュウキュウツバメ (リスト次第で学名が変わる)
- 第8版学名:Hirundo tahitica (ヒルンドー タヒティカ) タヒチのツバメ
- IOC 14.2 学名:Hirundo javanica (ヒルンドー ヤワニカ) ジャワのツバメ
- 属名:hirundo (f) ツバメ
- 第8版種小名:tahitica (adj) タヒチの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- IOC 14.2 種小名:javanica (adj) ジャワの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Pacific Swallow, (IOC 14.2: Tahiti Swallow が分離されたが日本産亜種は前者)
- 備考:
hirundo は#ツバメ参照。
tahitica は接尾辞 -icus は短母音。アクセントは "タヒティカ" となると考えられる。Tahiti の成り立ち (#キジカッコウ) を考慮すれば実質長母音で読んでも構わないと思える (タヒーティカ)。
javanica は "ヤワニカ" でよいと思われる。
南西諸島からフィリピン、インドシナ南部、インドネシアからオセアニア島しょ部に分布。世界で7亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は namiyei (動物学者 波江元吉 Motoyoshi Namiye にちなむ) とされる。
Clements 2024, IOC 14.2 ともにタヒチの亜種を単形の独立種 Tahiti Swallow Hirundo tahitica として分離、残りを Pacific Swallow Hirundo javanica と変更する見通し。
日本産は後者に含まれ、学名が変わる。
AviList (2025.6) では Pacific Swallow を Fork-tailed Swift と改名。
Arazmi et al. (2025) DNA Metabarcoding Unveils Habitat-Linked Dietary Variation in Aerial Insectivorous Birds マレー半島で DNA バーコーディングを用いてリュウキュウツバメや Aerodramus sp. (ジャワアナツバメ Edible-nest Swiftlet) の食性を調べたもの。
人が住む郊外環境、水田、アブラヤシのプランテーションの順に多様性が低くなった。細かい内訳は論文を参照。
-
コシアカツバメ
- 第8版学名:Cecropis daurica (ケクロピス ダウーリカ) ドーリア地方のツバメ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Hirundo daurica (ヒルンドー ダウーリカ) ドーリア地方のツバメ
- 第8版属名:cecropis Kekropis アテネの女性名 (Gk)
- 第7版属名:hirundo (f) ツバメ
- 種小名:daurica (adj) バイカル湖の東ドーリア地方の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Red-rumped Swallow, IOC, AviList: Eastern Red-rumped Swallow
- 備考:
cecropis は外来語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は長母音を持たないため同様に読まれると考えられる (ケクロピス)。
daurica はラテン語では地名由来で Daurica で u が長母音でアクセントもここにある (ダウーリカ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Cecropis 属 (Kekropis アテネの女性名 Gk) に分離。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。Cecropis 属はコシアカツバメ属。
ヨーロッパ南部から日本に広く分布し、アフリカ東部やインドネシアなどにも繁殖地がある。世界で8亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は japonica (日本の) とされる。
Clements 2024, IOC 14.2 ともに ヨーロッパのものを Cecropis rufula European Red-rumped Swallow、アフリカのものを Cecropis melanocrissus African Red-Rumped Swallow と分離。
(オオコシアカツバメ) Cecropis striolata Striated Swallow が分離されたことがあったが、Cecropis daurica とほぼ差がないとの研究から統合されることになる見通し。
AviList では統合して亜種の扱いで、種コシアカツバメに対応する英名は Eastern Red-rumped Swallow (Clements 2024 も同じ。BirdLife v9 では未対応)。
#ショウドウツバメ備考の Schield et al. (2024) でも、系統がアフリカ、中東から東欧、アジアの順に分岐しており、Cecropis striolata Striated Swallow は Cecropis daurica に内包される結果となった。
AviList の判断は以下の通り:
22805 1043 Five species are recognized in the Cecropis daurica complex based on a combination of plumage, vocalizations, and evidence from mitochondrial (Sheldon et al. 2005) and genomic DNA data (Brown 2019; Schield et al. 2024): monotypic C. hyperythra based on plumage and vocalizations; monotypic C. badia based on plumage, size, and parapatry with populations of daurica;
polytypic C. daurica involving a merger of most populations of temperate-migratory daurica and tropical Asian striolata based on clinality in plumage and genetic paraphyly; monotypic C. rufula based on plumage, genetics, and a zone of parapatry with populations of C. daurica; and polytypic C. melanocrissus based on plumage and genetics.
A comprehensive review of this complex integrating formal bioacoustic analyses, broad genomic sampling, and phenotypic variation, is desirable.
まだゲノムが読まれているものも少なく他の点も研究が不十分との判断。単系統性を大変重視していることがわかる。読まれている遺伝情報もサンプリングも限られているので、今後の研究でまた分離される可能性も残っている。
和名は見たままの通りのような気がするが、Hirundo erythropygia Sykes, 1832 の学名 (原記載) があり (腰の赤いツバメ)、英名は同種時代のこの学名由来と想像できる。もしかすると和名も英名を訳したもの (?)。
"Fauna Japonica" では 図版 (学名 Hirundo alpestris japonica としている)。
本文には 記載 に現れ、フランス語名 l'hirondelle alpestre du Japon (日本の高山のツバメ = 日本のニシコシアカツバメ)。
コシアカツバメはヨーロッパ南部にも生息するので、世界の他のツバメ類とも比較して日本の対応種と名付けたもの。cette espece とあるので種族 (race、亜種) よりは違いが大きく種扱いだったと思われる。
ツバメの方は Hirundo rustica orientalis Schlegel, 1844 (参考) と名付けていたがヨーロッパのものと同じとして "Fauna Japonica" では Hirundo rustica としていた (参考)。
そのため複数の Hirundo 属の種で japonica を検討する必要はなかった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Hirundo alpestris nipalensis で、
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire の学名を用いたよう。
Seebohm (1890) では種英名は Mosque-Swallow としていた。日本のものは亜種 nipalensis と呼べるとのことでこちらが採用されていた。別亜種とみなすか同亜種とするかの問題となる。
nipalensis の方は記載時学名 Hirundo Nipalensis Hodgson, 1837 (原記載) の記載の方が早いので同一とみなせるならばこの亜種名となる。Hodgson がネパールの鳥に片っ端から Nipalensis と名付けていた時代の話。現在はいずれも亜種名に残っている。
Hodgson は Cypselus Nipalensis Hodgson, 1836 と Cypselus 属にも Nipalensis を残していて上記と同じページにいずれも新種として記載している (#ソウゲンワシ備考も参照)。後者は現在ヒメアマツバメの種小名に残っている。系統が違う種なのでどちらも大丈夫だったが近い種類ならば衝突していた可能性もあった。
Ogawa (1908) のリストではコシアカツバメとともにトックリツバメの名称が記されていた。他にもアカツバメやトウツバメとも呼ばれたとのこと (コンサイス鳥名事典)、何となくコシアカツバメは学術語で出発したようにも見える。
また Ogawa (1908) のリストには和名なしで Hirundo striolata Temm. & Schl. が別記され、別学名に Cypselus striolata Boie と Lilla striolata Hume を挙げていた。
"Fauna Japonica" では p. 33 で、Temminck がこの学名で博物館に収めたとある。参考。しかし Schlegel が 1844 年の Java の標本にこの名前を付けていたため、この学名は有効とならなかったと考えられる (参考)。
そのため "Fauna Japonica" では日本の標本に対して別学名を提案することになったが、新しい学名を与えた背景を示さなかったため (Temminck は自分の方が遅かったとは書きにくい性格だったらしい)、後世に混乱を引き起こすこととなった。
Seebohm (1890) では "Fauna Japonica" の記述から学名の改名意図を読み取っていて新しい分類概念を用いたが、Hartert (1910-1922) は当初気づいていなかったようで p. 806 の記述を p. 2173 と後に訂正されている。striolata の記載者は結局 Temminck and Schlegel ("Fauna Japonica") ではなかった。
Ogawa (1908) は初期の Hartert 同様に "Fauna Japonica" の記述の真意を読み取れていなかったようで、この時点では別種とみなされて、該当するものがわからず和名なしでリストされていたものと思われる。おそらく状況がよく飲み込めなかったのか、Temminck and Schlegel の意図を読み取っていたと思われる Seebohm (1890) の提案したコシアカツバメの分類と両者が登場する。矛盾点が解決できないために Seebohm (1890) の解説する分布概念や雑種の可能性の考えなども考慮に入れて2種としたのだろう。
"Fauna Japonica" を深読みせず、Seebohm (1890) だけを日本の鳥の記載初期の文献として見ると、Hartert でも誤解してしまったぐらい理屈がわからなくなる次第。
また Ogawa (1908) に載っていたため、日本で striolata の標本があったのかと誤解してしまう原因となり得る。
もし striolata を独立種 (オオコシアカツバメ) とする場合には亜種を認めるかなども問題になる。現在は striolata に含められているが、台湾では Hirundo striolata formosae Mayr, 1941 (参考) の記載がある。採集者は Owston。
山階鳥類研究所標本データベースには 1907 年の台湾の標本などがあり、当時の学名は Hirundo striolata Boie と過去の目録を継承し、後に付けられたラベルで和名がオホコシアカツバメとなっていた。
古い標本では YIO-25312 (東京 1887) ではラベルにアマツバメと読める部分があり、その前の部分が判読困難だがなんとか (とっくり?) アマツバメと呼ばれていたらしい。
YIO-25315 (東京 1886) では後から整理された山階旧標本番号のあるラベルにトックリツバメ, コシカ の名称があるので、コシアカツバメに統一されたのはだいぶ後の時代のよう。
学名については Dickinson et al. (2001) Systematic notes on Asian birds. 14. Types of the Hirundinidae に解説があり、
Hirundo alpestris Pallas, 1776 が最初の名称と考えられて使われていたが、Hirundo daurica Laxmann, 1769 の記載が十分詳細でこれが最初の記載と判定できるがタイプ標本は失われた可能性があるとのこと。
それ以前は Hirundo daurica Linnaeus, 1771 に先取権があると考えて使われていた。
alpestris は "高山の" (< Alpes)。我々のコシアカツバメの感覚とは合わないが、人工物の少ない中央アジアや南アジアでは山地の崖などに営巣するようで通常のツバメと比べれば山のツバメなのだろう。
そういえばその昔は比叡山のケーブル駅にコロニーがあって比叡山探鳥会の一つの見どころだったのだが、その後営巣できないようになったと聞いたことがある。比叡山のような山の探鳥でもコシアカツバメの声はしばしば聞かれてちょっと驚かされることがあるが "山のツバメ" なのでおかしくないのだろう。
あまり生息を考えないような場所の録音にも入っていることがあるので録音調査をされる方は要注意。山の "不明の声" はしばしばコシアカツバメだったりする。コシアカツバメの声のバリエーションはたくさん知っておく必要がある。
Laxmann による基産地は Siberia; Mt. Schlangen near Zmeinogorsk, Russia と判定されている [Avibase 情報より。出典は Dickinson and Ericson (2002)]。
シベリア、と言ってもバイカル湖よりずっと西方でカザフスタン国境に近いシベリア南端 (アルタイ地方) ぐらいで我々が "バイカル湖の東ドーリア地方" から想像する場所とはだいぶ違う。
Zmeinogorsk も "ヘビの街" のような意味で、Mt. Schlangen はドイツ語のヘビの意味でドイツ語で Schlangenberg (ヘビの山) ドイツ人探検家が名付けた。その周辺の街とのこと (wikipedia ドイツ語版より)。確かにこの基産地であれば "山のツバメ" でよさそう。
日本に生息するのでどこか近くで命名された種類と考えるとまったく違っていた。少なくともジョウビタキの Daurian とは全然違う。
Laxmann の時点ではすでに使われていた学名で、使われ始めた最初のころはドーリア地方を意味していたのだろうが、分布が広く同種であるために遠い地域でも記述され、規則によって有効な学名は 1758 年以降と (たまたま) 定義されたためそれ以降に遠い地域で初めて記述されたものが原記載として取り扱われることになった経緯が考えられる。
ヨーロッパからみると探検に訪れるような場所で頻繁に記録されることがなかったために日本では普通種なのにこのような状況となったものだろう。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 253 (1946 年初出) によればコシアカツバメは明治末葉以後東京から跡を絶ったとのこと。かつては平地で普通に繁殖する種類であったらしい。バラックや洋館が多くなって深い軒庇がなくなったり、道が舗装されたことなどがツバメの減少との共通要因として挙げられていた。
関東大震災 (1923) の後の建築の影響も大きかったらしい。
-
ニシイワツバメ (リスト次第で学名が変わる可能性あり。第8版で検討種)
- 学名:Delichon urbicum (デリコン ウルビクム) 都会のイワツバメ
- 属名:delichon 現在は使われない Chelidon 属 < ツバメ (Gk) のアナグラム (neut.)
- 種小名:urbicum (adj) 都会の (urbicus)
- 英名:[House Martin], IOC: Common House Martin (備考参照)
- 備考:
delichon は #イワツバメ参照。
urbicum は短母音のみで "ウルビクム" のアクセントになる。英語 urban とは異なる。Delichon の性に合わせて中性形になっている。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。ユーラシアに広く分布し、アフリカ南部でも越冬する。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
リストされている亜種は lagopodum (lagos ウサギ pous, podos 足) だが、世界の多くのリストでは独立種 Delichon lagopodum 英名 Siberian House Martin とされる。この扱いの場合は単形種になる。また Delichon urbicum に対する英名 Western House Martin もこの分類を反映したもの。
旧分類での Delichon urbicum urbicum はこれまでのところ日本で記録はないとのこと。
#ショウドウツバメ備考の Schield et al. (2024) によれば Delichon urbicum, Delichon nipalense, Delichon dasypus, Delichon lagopodum
をそれぞれ分離しないと単系統の関係にならないので、イワツバメとニシイワツバメを別種とするならばこれらの分割が必要になる。あるいは全体をイワツバメとしてニシイワツバメは亜種とするかのいずれかだが、遺伝的距離は結構あるのでそれぞれを独立種とする形に落ち着くのだろう。
ロシア極東地方のニシイワツバメ: Shokhrin et al. (2025) Breeding birds of Primorsky Krai: the Siberian house martin Delichon lagopodum (pp. 2821-2847)。
-
イワツバメ
- 学名:Delichon dasypus (デリコン ダシュプース) 毛深い足のイワツバメ
- 属名:delichon 現在は使われない Chelidon 属 < ツバメ (Gk) のアナグラム (neut.)
- 種小名:dasypus (合) 毛深い足の (dasy 毛深い pous 足 Gk)
- 英名:Asian House Martin
- 備考:
delichon はアナグラムなので発音はわからないが短母音のみと考えて規則に従えば "デリコン" のアクセントとなる。
イワツバメの種小名では判断できないが、日本産でない亜種の語尾から中性属名と判断できる。また#ニシイワツバメの種小名や亜種小名からも判断できる。
Delichon は Moore (1854) が用いた時はタイプ種の種小名 Delichon Nipalensis だったが後に検討されて中性語尾 Delichon nipalense と変更された。
この変更は Dickinson et al. (2001) によるもので比較的新しく、1990 年代のリストまでは Delichon 属に女性語尾が用いられていた。
Chelidon 属は複数の著者が現在では異なる属に用いたため使われなくなった属名。chelidon はラテン語で女性名詞。
由来となるギリシャ語の khelidon (ツバメ) は女性名詞。
Chelidon は現在では使われない属名であるが、#ハシブトアジサシの属名などに同様の由来を持つものがいくつもある。
(The Key to Scientific Names, wiktionary の情報からまとめた)。
dasypus は -pus が長母音 (#ナンキンオシ参照)。冒頭にアクセントがある (ダシュプース)。日本語では区別して表記することは難しいが、-sy- は日本語の -shu- に相当する音ではなく、s の音に "ユ" を付ける (英語ならば shi と si の区別と同様)。
東アジアにやや局地的に分布。世界に3亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は基亜種 dasypus とされる。
かつては Delichon urbicum (現在はニシイワツバメだが亜種の扱い次第で別名になるかも知れない。#ニシイワツバメ の備考参照) の亜種とされていた。
当時の扱いでは亜種 lagopoda をシベリアイワツバメと称していた。
かつて日本で記載され、現在は dasypus のシノニムとされるものがある: Kato (2014) Notes on a re-examination of type specimen of the Japanese House Martin (Chelidon blakistoni)。
ロシア極東地方のイワツバメ: Shokhrin et al. (2025) The Asian house martin Delichon dasypus in the Russian Far East (pp. 767-787)。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ヒヨドリ科 PYCNONOTIDAE ▽
-
シロガシラ
- 学名:Pycnonotus sinensis (ピュクノノートゥス シネンシス) 中国の厚い背中の鳥
- 属名:pycnonotus (合) 背中の厚い (pyknos 密集した、厚い nota 背面 Gk、-tus (接尾辞) 〜が備わっている。背中の羽毛が厚いことを指す)
- 種小名:sinensis (adj) 中国の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:[Chinese Bulbul], IOC: Light-vented Bulbul
- 備考:
pycnonotus は外来語の合成語なので発音はわからないが、起源となるギリシャ語 -notus の o が長音なのでこれを長母音としてアクセントを置くのが自然と考えられる (ピュクノノートゥス)。
sinensis は規則通り "シネンシス" のアクセント。長音でもよい。
英語の Bulbul はペルシャ語またはアラビア語で音声由来とされる (コンサイス鳥名事典)。中国を中心に分布して4亜種が認められている。日本の亜種は基亜種 sinensis と亜種不明とされる。
[亜種の問題]
亜種ヤエヤマシロガシラ Pycnonotus sinensis orii と呼ばれ特殊鳥類となっていたが 亜種 orii の記載 (Kuroda 1923)、
山崎 (2003) により基亜種のシノニムとされた。
世界のリストでの orii の扱いは多少違いがあり、IOC は現在 (14.1) でも亜種扱いで Pycnonotus sinensis orii。Clements, version 2019, HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v8 (Dec 2023) でも同様で、いずれも亜種として認めている。IOC の4亜種は orii も数えたもの。
Howard and Moore 4th edition (incl. corrigenda vol.1-2) は独自で Pycnonotus taivanus orii と台湾を別種 (Styan's Bulbul) としてこちらに帰属させている。このリストではこの種に亜種 taivanus, formosae (つまり湾に2亜種)、orii を認めている。
Pycnonotus sinensis からの分離の根拠は McCay (2013) としている。
Shakya and Sheldon (2017) The phylogeny of the world's bulbuls (Pycnonotidae) inferred using a supermatrix approach
でも距離は小さいが系統分離されている。種とするか亜種とするかは微妙なところであろうか。
Styan's Bulbul の wikipedia 英語版では生息地破壊、中国からの狭義 Pycnonotus sinensis (種を分離した場合の名称) が放生のため移入され、交雑もあって Styan's Bulbul は台湾の宜蘭県ではすでに絶滅とのこと。
台湾の種を Pycnonotus formosae (Taiwan Bulbul) と Pycnonotus taivanus と分けることもあり、orii が前者の亜種とされるリストもあった。
IOC 14.1 では Pycnonotus taivanus を種と認めるが、formosae と orii は Pycnonotus sinensis の亜種としている。
taivanus (のグループ) は世界の主要リストでは別種扱い。日本鳥類目録 改訂第7版の扱いとは異なっている。第二回パブリックコメントに向けた暫定リスト (2023年10月31日) でも一見同じように見えるが種の扱いは異なっているのだろうか。
どちらの種に帰属させるかは異なるものの、orii を亜種として認めない世界の主要リストでは現時点でない模様。
金城 (1998) 沖縄本島におけるシロガシラの生態と被害防 止対策 にも過去の経緯や亜種和名の紹介がある。
外間・村上 (2009) シロガシラによる露地野菜の被害と防止対策 7.台湾西地方におけるシロガシラの分布と被害。
八重山諸島は在来のシロガシラ、沖縄本島のシロガシラは移入種とも考えられるが、日本鳥類目録 改訂第7版では亜種不明の扱い。
Vylakov et al. (2023) New sightings of the Chinese bulbul Pycnonotus sinensis in Primorsky Krai (pp. 4095-4097)
ロシア沿海地方の最近の記録。かつては非常にまれな種類だった。2023年9月に若鳥が見られ繁殖の可能性がある。北朝鮮でも2013年8月に巣立ちびなが観察されている。
[果実を模して種子散布を行う植物]
Jin et al. (2025) Seed dispersal by deception: A game between mimetic seeds and their bird dispersers (レビュー論文)。
レビューされている範囲では日本の分布は少なく鳥の該当種がわからないがアジアでは Pycnontus 属がいくつか挙げられているのでここに含めておいた。ヨーロッパでは繁殖地のウタツグミなども含まれている。レビューに含まれる報告がないだけで近縁のヒヨドリでも見られるのではないだろうか。果実を模すにあたって鳥類が紫外線を見る能力との関係も議論がある。
-
ヒヨドリ
- 学名:Hypsipetes amaurotis (ヒュプシペテース アマウローティス) 暗色の耳の高く飛ぶ鳥
- 属名:hypsipetes (合) 高く飛ぶ鳥 (hypsi 高さ peto 飛ぶ -tes (接尾辞) 〜するもの Gk)
- 種小名:amaurotis (合) ぼやけた色の耳の (amauros ぼやけた otos 耳 Gk)
- 英名:Brown-eared Bulbul
- 備考:
hypsipetes の発音は外来語由来の合成語でわからないが、起源となるギリシャ語では -petes の語末が長母音で同様に伸ばす可能性がある (#ミソサザイの事例参照)。
他は短母音とすれば規則上は "ヒュプシペテース" のようなアクセントとなると思われる。
amaurotis も外来語由来の合成語でわからないが、起源となるギリシャ語では -otis の o が長母音なので伸ばすのが自然と思われ、アクセントもこの位置に来て都合がよい (アマウローティス)。
記載時学名 Turdus amaurotis Temminck, 1830 と最初はツグミ類としていた。英名の "Brown-eared" は種小名とほぼ整合する。
Temminck and Schlegel (1848) はヒヨドリのみを含む属 Orpheus (神話のオルフェウス由来) を提唱した。図版 で用いられていた。
現在は他属と統合されている。Orpheus 属の用例は他にもあり、Swainson (1827) がマネシツグミ 現在の学名で Mimus polyglottos Northern Mockingbird に用いた用例の方が早かったなどさらに他用例もあり混乱していた模様 (The Key to Scientific Names)。
以下 [属名の問題とヒヨドリ属の特徴] に続く。
[亜種]
日本とその周辺の限られた地域に分布する。世界で 12 亜種が認められている (IOC)。
日本で記録される亜種は亜種ヒヨドリ amaurotis、squamiceps (鱗の頭 < squama 鱗 -ceps 頭の) オガサワラヒヨドリ、
magnirostris (嘴が大きい < magnus 大きい -rostris 嘴の) ハシブトヒヨドリ、borodinonis (Borodino 島 大東諸島のこと) ダイトウヒヨドリ、
ogawae (鳥類学者 Minori Ogawa 由来) アマミヒヨドリ、pryeri (英国商人・博物学者で日本で横浜に住んでいた Henry James Stovin Pryer が由来) リュウキュウヒヨドリ、
stejnegeri (ノルウェー生まれのアメリカの鳥類学者 Leonhard Stejneger にちなむ) イシガキヒヨドリ、nagamichii (鳥類学者 Nagamichi Marquis Kuroda に由来) タイワンヒヨドリ。
Saitoh et al. (2015) (#カルガモの備考参照) による DNA バーコーディングではヒヨドリの間、特に本州と琉球の間で (別種相当の) 最大 3.57% の違いがある。
別種になる可能性のあるリュウキュウヒヨドリ (アマミヒヨドリの方が記載は遅い) は Hypsipetes pryeri Stejneger, 1887 と記載されたもの。原記載。
この学名が復活するかも知れない。
海外分布では台湾の nagamichii (Taiwan brown-eared Bulbul) に加え、batanensis, fugensis, camiguinensis がフィリピンのルソン島北の離島に分布する。中国東部は越冬地分布となっている。
フィリピンのリストでは島の3亜種に加えて amaurotis も含まれており、この亜種は冬鳥の扱いと思われる。分布地図で日本付近しか描かれていないものがしばしばあるが誤解を招く可能性があり要注意かも知れない。
近傍の種ではシロガシラクロヒヨドリ Hypsipetes leucocephalus Black Bulbul が台湾 (亜種 nigerrimus) や中国東部 (亜種 leucocephalus) に分布し、これらの地域では夏鳥。日本を訪れても不思議でない分布になっている。
ヒヨドリの亜種も非常に多いので整理しておく。記載時学名、基産地は Avibase より。
・Turdus amaurotis Temminck, 1830 o 基産地 Japan 亜種ヒヨドリ
・Oriolus squamiceps Kittlitz, 1830 o 基産地 Bonin Islands (小笠原) オガサワラヒヨドリ
・Hypsipetes pryeri Stejneger, 1887 o (原記載) 基産地 Naha, Okinawa, Middle Ryukyu Islands (那覇) リュウキュウヒヨドリ
・Hypsipetes amaurotis hensoni Stejneger, 1892 (資料) 基産地 Hakodate, Hokkaido = Turdus amaurotis
・Hypsipetes fugensis Ogilvie-Grant, 1895 o (原記載) 基産地 Fuga Island, Babuyan Islands (フガ島。フィリピンのバブヤン諸島)
・Hypsipetes amaurotis magnirostris Hartert, 1905 o (原記載) 基産地 'San Dionisio' = Minami-iwo-jima, Volcano Islands (南硫黄島) ハシブトヒヨドリ
・Hypsipetes amaurotis stejnegeri Hartert, 1907 o (原記載) 基産地 Ishigaki, Southern Ryukyu Islands (石垣島) イシガキヒヨドリ
・Hypsipetes amaurotis ogawae Hartert, 1907 o (原記載) 基産地 Amami-Oshima, Northern Ryukyu Islands (奄美黄島) アマミヒヨドリ
・Hypsipetes batanensis Mearns, 1907 o (原記載) 基産地 Batan Island, Luzon Strait (バタン島。ルソン島の北。フィリピン)
・Hypsipetes camiguinensis McGregor, 1907 o (原記載) 基産地 Camiguin Island, Babuyan Islands (Camiguin de Babuyanes / Camiguin Norte ルソン島の北。ミンダナオ島のカミギン州とは別物。フィリピン)
・Microscelis amaurotis harterti Kuroda, 1922 基産地 Botel Tobago = nagamichii が新名
・Microscelis amaurotis matchie Momiyama, 1923 o (原記載) 基産地 Hachijo, Izu Islands (八丈島) matchiae と修正。H&M4 によれば前者が本来のもの
・Microscelis amaurotis borodinonis Kuroda, 1923 o (原記載) 基産地 Minami-Daitojima, Borodino Islands (南大東島) ダイトウヒヨドリ
・Microscelis amaurotis insignis Kuroda, 1923 (原記載) 基産地 Nishisato, Miyakojima, Southern Ryukyu Islands (宮古島) = pryeri
・Microscelis amaurotis kanrasani Momiyama, 1927 * (参考 1, 2) 基産地 Sin-sa-men, Quealpart Island (韓国の済州島) Kuroda (1932) が色変わり (hood form) とした
・Microscelis amaurotis coreensis Momiyama, 1932 * 無効名 (参考) 基産地 Korea
・Hypsipetes amaurotis septentrionalis Dementiev & Gizenko, 1950 * 基産地 サハリン = hensoni? = amaurotis?
・Hypsipetes amaurotis nagamichii Deignan, 1960 o (原記載, 参考) 基産地 Botel Tobago (= Orchid Island, 蘭嶼。台湾) タイワンヒヨドリ
・Hypsipetes amaurotis kurodae Mishima, 1960 = nagamichii
学名の後に o のある亜種が IOC 14.2 に載っているもの。 * は Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
harterti は現在の学名で Hypsipetes harterti Sula Golden-Bulbul (harterti) (かつては キンイロヒヨドリHypsipetes affinis Seram Golden Bulbul の亜種) が Hypsipetes 属となった時に衝突して新しい名前 (nagamichii) が与えられた。
IOC リストによると古い名前は permanently invalid (H&M4) とある。1961 年以前に改名されたものは復活させない規則によるとのこと。
他種ほど悩ましい状況になっていないのは hensoni が基亜種がシノニムとされたため。もしそうでなければ "エゾヒヨドリ" に相当するものと亜種ヒヨドリの分布境界あるいは北海道に2亜種あるのかなどが問題となり得た。
北海道から九州までを同一亜種とし、さらにサハリン、韓国、中国東部も同亜種としたため。島の亜種はそのままの扱いとなっている。DNA バーコーディングでは本土と琉球の個体とかなりの違いが認められており、おそらく分けるのが適切なのだろうが他の離島亜種はどのぐらい違うのか、どこで種を区切るかの問題になっているのだろう。
フィリピンのチャムネヒヨドリ Hypsipetes philippinus Philippine Bulbul との関係も気になるところだが、ルソン島の北の島はヒヨドリの亜種とされる点はメジロとフィリピンメジロの関係に似ている (#メジロの備考参照。
Shakya and Sheldon (2017) の分子系統樹によればヒヨドリとはかなり離れている。
フィリピンのチャムネヒヨドリもかつてはより広い範囲を含む種だったが、2010 年にミンドロヒヨドリ Hypsipetes mindorensis Mindoro Bulbul、ヴィサヤヒヨドリ Hypsipetes guimarasensis Visayan Bulbul、 ミンダナオチャムネヒヨドリ Hypsipetes rufigularis Zamboanga Bulbul
が分離されたとのこと (wikipedia 英語版より)。
ヒヨドリの離島亜種も分子遺伝学研究が進めばあるいは分離されるものがあるかも。
現在では日本の DNA バーコーディングの塩基配列を GenBank で見ることができるので AB765889.1 から BLAST を試してみると確かに結構広がりがある。しかし沖縄のサンプルが多くの枝に現れ DNA バーコーディングは配列が短い (700 bp 程度) ので系統分割は難しいかも知れない。
注目すべきは中国で読まれたミトコンドリアゲノム (NC_084285.1) の該当部分と 99% 一致すること。このデータを見る限りでは中国と沖縄のヒヨドリを別に分離する必要性が薄いことがわかる。
この配列の文献は Li et al. (2024) The complete mitochondrial genome of Hypsipetes amaurotis (Passeriformes: Pycnonotidae) で、Xianrendong National Nature Reserve, Liaoning Province (遼寧省 荘河市 遼東半島) で 2023.4.17 に捕獲されたもの。越冬個体ではなさそう。
シロガシラクロヒヨドリ Hypsipetes leucocephalus Himalayan Black Bulbul の方が祖先系統にあたり、中国南東部で夏鳥 (基亜種 leucocephalus。ヒヨドリの大陸越冬域と分布が一致する)、台湾が別亜種で留鳥。この系統が夏鳥として北に分布を広げたものが隔離されてヒヨドリとなったのだろうか。
Hypsipetes 属に現生種ですでに 26 種が含まれている (IOC 14.2)。かつて Sibley-Ahlquist の DNA-DNA hybridization によって誤って Hypsipetes 属に含まれた種もかなりの数があったと wikipedia 英語版の Hypsipetes の項目 にあるが、上記 Gregory (2000) も参照。
サハリンのヒヨドリについては Matyushkov (2016) The brown-eared bulbul Microscelis amaurotis in Sakhalin (pp. 3832-3834) 参照。
亜種 septentrionalis Dementiev & Gizenko, 1950 と記載されたが、Nechaev (1969, 1991) は北海道の亜種 hensoni のシノニムとしたとのこと。
septentrionalis の語義は#アビ参照。
比較的新しい文献で、これによればロシアでは北海道は日本の他地域と別亜種と考えている模様。
Dement'ev and Gladkov (1954) では自身の命名なのでこの亜種を有効としているが、hensoni は北海道で繁殖、非繁殖期は本州から琉球 (沖縄、座間味島、久米島)、済州島や朝鮮半島にも渡ると述べられている。
amaurotis は本州、佐渡、伊豆七島 (大島から宮古島)、壱岐、四国、九州、対馬、済州島で繁殖し、非繁殖期は奄美大島や琉球 (沖縄島、石垣島) に渡るとの記載になっている。
ヒヨドリの亜種は羽衣 (南ほど黒い)、計測値、渡り習性 (他の詳細はよくわかっていないとある) で分けられていると解説がある。
[北方への分布拡大]
ロシア極東の写真サイトに掲載された 2023 年の鳥のまとめ
に 2023 年で印象深い、あるいはなかなか撮れない写真などが掲載されている。見ていただければどのように珍しいかなどすぐわかっていただけるだろうが、なんとヒヨドリがランク入り。
ヒヨドリから写真一覧を見ることができるがほとんどが冬季の記録である。北限のヒヨドリの写真として見ていただくと面白いだろう。
Belyaev et al. (2022) An increase in the number of records of the brown-eared bulbul Microscelis amaurotis in the Russian Far East in recent year
によればロシア極東でヒヨドリが増えてきているが、観察は冬の時期に限られ、繁殖はまだ確認されていないそうである。ヒヨドリが雑誌の表紙の写真を飾っている。
論文によるとヒヨドリは日本や韓国で繁殖するが冬季には広範囲に標行し、サハリン、千島南部、中国東北部でも記録されるとのこと。ロシアの記録では1960年9月31日に若鳥が沿海地方で記録されたのが最初とのこと。
北朝鮮の研究者によれば 20 世紀はヒヨドリが分布を北へ広げ、1940 年代は北朝鮮北部では記録されなかったが 1960 年代には北朝鮮中央部で繁殖を始め、20 世紀末では繁殖しないのは北朝鮮北東部のみになったとのこと
[Tomek (2002) The birds of North Korea. Passeriformes Acta zoologica cracovensia, vol. 45, no.1, pp. 1-235 の pp. 31-32 にある]。ヒヨドリがロシアで繁殖するのも時間の問題とみられていた。
Kharchenko (2018 初出, 2023 再掲) The brown-eared bulbul Microscelis amaurotis in the Ussuriysky Reserve (Primorsky Krai) (pp. 2900-2904)
にウスリーの保護区での記録がある。2017年12月13日には冬季の最初の記録となった。Microscelis は Hypsipetes に統合される前の属名。
おそらく良質の写真が撮れなかったのか "A Field Guide to the Birds of Japan" (1982) のイラストが紹介されているが、Koichiro, Jane はいったい誰かと思ったら Sonobe, Koichiro と Robinson, Jane Washburn (eds.) となっていた。
なおイソヒヨドリも "2023 年の鳥のまとめ" に入っているが、こちらは逆に例えばウラジオストクでは最近あまり見られなくなっているとのこと。
(The first appearance of chestnut-eared bulbul in Baihuashan Nature Reserve, Mentougou District)
(2023) の記事によれば北京近郊の門頭溝区で冬季初観察されたとのこと。
さらに北で繁殖し、環境改善によってこの場所で越冬できる環境が整ってきたのだろうと推測されている。
大陸の個体群が日本から分布を広げたのか、大陸の越冬地から分散して定着するようになったのか判断が難しい気がする。大陸でも少数が夏鳥として訪れていたが越冬するようになって目立つようになった可能性もありそう。
シロガシラクロヒヨドリとの関係を考えるとかつてはヒヨドリも大陸に渡って夏鳥となっていたが、個体群の衰退で一時的に日本の準固有種となっていたプロセスが考えられる気がする。もう少し広範囲、多くの遺伝部位の解析結果が出てからになるだろうか。
[属名の問題とヒヨドリ属の特徴]
上記ロシアのページでは Microscelis amaurotis となっているがこの属名は旧名とのこと。ヒヨドリに対して与えられた Micropus Swainson, 1832 (小さな足。いかにもどこにでもありそうな属名) が他分野ですでに使われていたため新名を与えたものとのこと。
Microscelis 属は Gray (1840) による命名でタイプ種は ズグロヒヨドリ 現在の学名で Brachypodius melanocephalos Black-headed Bulbul だった。この属が Microtarsus Eyton, 1839 と Hypsipetes Vigors, 1831 に分割され、ズグロヒヨドリは前者のタイプ種となったためヒヨドリの属名の方が変わったらしい。
Microtarsus はかつて Pycnonotus 属 (シロガシラに使われている) にまとめられていたが Shakya and Sheldon (2017) の分子系統研究で分岐が深いことが判明して別属となったもの。
Brachypodius Blyth, 1845 があってズグロヒヨドリの学名には Clements 2022 までこの属名が使われるなど最近まで扱いが統一されていなかった模様。Working Group Avian Checklists, version 0.03 以降は Microtarsus となっている。
属の解説 Kurzschenkel (短いふしょ) や過去の属名を見てもヒヨドリ類の脚の短さがよほど目立っていたらしい。ここではヒヨドリとズグロヒヨドリの学名変遷だけを見ているが、現在の属名の成立経緯はヒヨドリ類全体を見て分類が過去どのように変わったかを知るべきなのだろう (ヒヨドリはヒヨドリ類の分布北限にあたるため日本以外に多数の種がある。日本は分布範囲外なので詳細は調べていない)。
(The Key to Scientific Names などよりまとめた)。
Hypsipetes 属はもともと Hypsipetes psaroides Vigors, 1831 として記載されたが、これはシロガシラクロヒヨドリ Microscelis leucocephalus Black Bulbul の亜種として扱われるようになった。
Hypsipetes 属は Mr. Vigors がモズ類の中で尾が分かれて翼が尖り、足が弱くてオウチュウ類に似たものとして Hypsipetes で名付けられたもの Hypsipetes Vigors, 1831。
翼が尖っていて足が弱いので空を飛んで生活していると考えられたものだろうか。
ヒヨドリの Temminck, 1830 記載時は Turdus amaurotis とツグミの仲間とされていた。Vigors (1831) の時点ではまだ Hypsipetes 属に含まれていなかった。
属名 Microsceli も使われていたことがある [Dickinson et al. (2002)
Systematic notes on Asian birds. 26. Types of the Pycnonotidae]。
Boyd によれば Hypsipetes 属が Microscelis 属を吸収した記述になっている。
Microscelis amaurotis の学名も他にも使われているところがあるようなので注意しておいてよいだろう [Howard and Moore 3rd edition (incl. corrigenda 8) まで、IOC でも 2.5 まで。Brazil (2009) もこちらの属名になっている]。
Ixos amaurotis も過去に使われていて Birdlife 2015 年まで、Clements 2010 年までこちらの属名だった。
日本の研究でも Honda et al. (2015) Seeing Is Feeding for the Frugivorous Bird Brown-Eared Bulbul Microscelis amaurotis
のように使われている。
Hypsipetes 属は特に Ixos 属との関係など複雑だった模様で、Gregory (2000) Nomenclature of the 'Hypsipetes' Bulbuls (Pycnonotidae)
に解説がある。歴史的には1種のみを含んだ Ixos Temminck, 1825 の属名が早かった。Hypsipetes Vigors, 1832 も1種のみを含んだ属として定義された。
Sibley and Monroe (1990) は特に説明もなくこれらの種類を Hypsipetes にまとめてしまったが Ixos 属の名称を消す明確な理由がない。
Gregory (2000) Ixos と Hypsipetes の両属を残してそれぞれグループ化する解決策を提案したが、この分類ではヒヨドリは Ixos 属になってしまう。
Temminck and Schlegel (1848) の提案した Orpheus 属より、ヒヨドリのみを含む Microscelis Gray, 1840 の方が早かったとのこと。この属名がしばらく使われていた理由。
一段とややこしいことに Hypsipetes に先立つ類似の属名 Ypsipetes Stephens, 1829 があるが、これは別物と判断されたとのこと。The Key to Scientific Names の情報によれば Deignan in Peters (1960) の判断とのことで、分類学者によっては Hypsipetes を無効と考えて対処した人もあったかも。
Gregory (2000) の時代にはまだ形態による分類が主な理由だったが Oliveros (2009), Oliveros and Moyle (2010) Origin and diversification of Philippine bulbuls の分子系統解析によれば Ixos と Hypsipetes の両属を残すことも可能となって、ヒヨドリも後者に含められるようになった模様 (Boyd の解説による)。
アジアのヒヨドリ類については Moyle and Marks (2006) Phylogenetic relationships of the bulbuls (Aves: Pycnonotidae) based on mitochondrial and nuclear DNA sequence data
とのこと。いずれの論文もオープンアクセスでないが新しい系統樹は以下参考。
この系統樹形態をとれば Microscelis 属を残す必要はなくなるとのこと。つまり 2000 年段階でもヒヨドリの属学名は不定だったことがわかる。
Shakya and Sheldon (2017) The phylogeny of the world's bulbuls (Pycnonotidae) inferred using a supermatrix approach
によれば Ixos と Hypsipetes の2系統は分かれているので、ヒヨドリの属学名が Ixos に戻ることはまずは心配しなくてもよさそう。
この2クレードを合体させるべきとの見解になれば Ixos 属にまとまることになるが複数のタイプ種の存在と包含関係で混乱した結果落ち着いた歴史的経緯もあるので分離したままとされるのではないだろうか。
Hypsipetes をさらに2系統に分けようとの機運 (2系統はアジア・アフリカが混ざっているので生物地理的にも分ける必然性は低そう) でもない限りヒヨドリの現行の属が継続されると思われる。
この論文の fig. 3 に Hypsipetes 属の世界分布の図がある。
従来の Cerasophila 属と Thapsinillas 属は分子系統的には Hypsipetes 属に含まれ、これらもまとめた Hypsipetes 属は島を好むヒヨドリ類の位置づけになっている。
この研究で Hypsipetes 属は分子系統的にも地理的にもまとまりのよいグループとなった感じがする。
IOC では Shakya and Sheldon (2017) の系統がすでに採用されているが Boyd はまだ未処理のようである。
系統関係が複雑で、最近まで信頼性の高い分子系統解析がなかったためにいろいろな分類が生じていた模様である。
ヒヨドリ科 Pycnonotidae はアジアからアフリカに分布する大きなグループで、日本で観察されるのは実質2種のため国内で分類が問題になることはあまりないが海外探鳥をされる方ならば多数出会っておられるだろう。
属名変遷がかなりあり、古いあるいは海外の図鑑と現在の学名が違っているものもあると思われるので観察された方は現行の IOC 分類か上記 Shakya and Sheldon (2017) を参照されるとよいだろう。
[紫外線で見たヒヨドリの雌雄差]
ヒヨドリは一般に雌雄同色とされるが、多くの鳥が見ることのできる紫外線で見ると雌雄差があるとも言われる。ヒヨドリそのものの論文は見つけられなかった。
シロガシラクロヒヨドリ Microscelis leucocephalus の亜種 niggerimus (台湾) では確認されている:
Hung et al. (2017) Himalayan black bulbuls (Hypsipetes leucocephalus niggerimus) exhibit sexual dichromatism under ultraviolet light that is invisible to the human eye。
ペットショップで購入したものと標本を使った研究とある。
[波状飛行と尾の役割]
ヒヨドリは波状飛行が目立つが、断続的な羽ばたきは多くの鳥で見られる。これを利用して尾の航空力学効果が見積もられているとのこと。
Tobalske (2022) Aerodynamics of avian flight 入門者向けのレビュー。翼の役割も前半に解説されている。
尾は翼を閉じる場合に体重の 10-15% の揚力を生み出しているとのこと。尾の揚力で頭が下がるはずで飛行機と比較すると鳥の飛行は力学的に不安定なはず。中枢神経による制御を行っている。
この数字は例えば Tobalske et al. (1999) Kinematics of flap-bounding flight in the zebra finch over a wide range of speeds が出典。飛行速度が小さい時は羽ばたき時間が増える (遅く飛ぶためにはエネルギーが余分に必要)。
ツバメ類では翼のアスペクト比が大きいので滑空が効率的で、断続的羽ばたきと滑空を組み合わせている。
フリーで読める総説論文では Tobalske (2007) Biomechanics of bird flight
にもまとめられていて 300 g 以上の鳥では断続的な羽ばたきは見られない。断続的な羽ばたきが遅い飛行ではエネルギーの節約になるとの一般的な説明はそれなりに正しそうだが、多くの鳥がなぜ羽ばたかない時に翼を閉じるのかはあまり明確な説明がないらしい。エネルギーだけの問題でなく神経コントロールの特性も関係しているかも知れないとのこと。
関係あるがどうかわからないが、我々が歩く時になぜ腕を振るのかもよくわかっていないらしい。cf. Canton and MacLellan (2018) Active and passive contributions to arm swing: Implications of the restriction of pelvis motion during human locomotion
腕を振るよりも鳥の飛行の方がもう少しエネルギー効率と関係がありそうな感じがするが、それだけで説明できるものでもないかも知れない。
関連して二股の尾が航空力学的に有利なのか調べてみたが、どうもあまりすっきりした結論が得られていないよう。外側尾羽が長過ぎると航空力学的に不利になって最適値があることは確かのようだが、積極的に二股の尾を用いる理由はあまり見当たらなかった。
航空力学的に有利との解説もあるが根拠があまりはっきりしない。古典的研究では Balmford et al. (1993) Aerodynamics and the evolution of long tails in birds、
Thomas and Balmford (1995) How natural selection shapes birds' tails。これらは航空力学の文献を適用したもの。しかし、
Evans et al. (2002) How do birds' tails work? Delta-wing theory fails to predict tail shape during flight (ツバメの風洞実験ではうまく再現されない)。
Thomas (1993) On the aerodynamics of birds' tails の論文は8年 (この時点) で 60 回以上引用されているが実証を欠いている。
Thomas (1993) は性選択のハンディキャップ原理に対抗する仮説として航空力学的解釈のアイデアを提唱したようだが実証不足のままの結論が広く使われ過ぎている模様。
Evans (2003) Birds' tails do act like delta wings but delta-wing theory does not always predict the forces they generate (二股の尾は実験に用いていない) が航空機の理論の適用限界も示している。
ツバメなどの多くの種類では性選択などの効果の方がむしろ強いのかも?
Clark (2010) The Evolution of Tail Shape in Hummingbirds
ではハチドリでは近い系統でも複数回二股の尾が進化して性選択が働いている傾向が示唆されるが、航空力学的にはハチドリの尾の働きは他の鳥とは違うのではないかとあまりすっきりしない。
ツバメ類の尾の航空力学的役割は過去の研究でも検討されておりこの論文の引用文献にリストされている。これらの研究も古めのものが多く結果も条件次第のようで、他種の近年の (後述) 数値計算の結果の解釈の困難さを見ると古典的な定性的な議論はあまり参考にできない感じがする。
Herdenstrom (2002) Aerodynamics, evolution and ecology of avian flight
には Even a casual observer, however, will notice the continuous spreading and twisting of, for example, the tail of a red kite Milvus milvus during flight, suggesting that there is some aerodynamic benefit from the tail. But what that function is remains largely an open question.
とあり、アカトビが尾を広げて制御しているのに役に立っているように見えるが航空力学的機能はほとんどわかっていないとある。
ソウゲンワシのソアリングについては Gilles et al. (2011) Soaring and manoeuvring flight of a steppe eagle Aquila nipalensis
に尾を使っていることは論じられているが効果を分離して測定できるわけではないので一般的な観察の記述とそれほど違わないかも知れない。
新しい研究でも Ducci et al. (2022) On the role of tail in stability and energetic cost of bird flapping flight では中程度の重量の鳥で尾を開くほど安定領域に入るとの解析があるが、モデル計算では長距離飛行には尾をたたむ必要があり、別の安定化メカニズムが必要と歯切れがよくない。
Song et al. (2020) Virtual manipulation of tail postures of a gliding barn owl (Tyto alba) demonstrates drag minimization when gliding
翼、体、尾の効果は関連しているので、尾だけ取り出して効果を議論することは難しく、数値計算や実測を含めた過去のアプローチで尾の効果を定量的に示せたものはなかったとのこと。尾を取り除く実験を行ってもバランスが変わるので解釈が難しい。
この研究では数値計算でメンフクロウの滑空中の尾の姿勢が抵抗を最小にするモデルと合っていたとのこと。
これらを見ると二股の尾が航空力学的に有利かなどはまださらに先の話のよう。何を評価すれば航空力学的に有利と言えるのかなどもまだ確立されていない印象を受ける。
Mohamed et al. (2022) Opportunistic soaring by birds suggests new opportunities for atmospheric energy harvesting by flying robots
にソアリングのレビューがあり、ソアリングのメカニズム、上昇気流をどのように見つけるかなどが議論されている。二股の尾についても少し言及があり、翼の dihedral flight による安定化 (#チュウヒの備考 [チュウヒ類の飛翔形]) とは逆に働き操縦性を高めるとある。
ツバメの尾については Warrick et al. (2016) Foraging at the edge of the world: low-altitude, high-speed manoeuvering in barn swallows に研究があるとのこと。
文献を見ると Norberg (1994) Swallow tail streamer is a mechanical device for self-deflection of tail leading edge, enhancing aerodynamic efficiency and flight manoeuvrability
(ResearchGate) となっていて定性的議論による提案を引用せざるを得ないよう。
鳥を模した羽毛を付けたドローンを用いることで近年もう少し研究が進んでいる模様: Phan and Floreano (2023) Raptor-informed feathered drone reveals tail-twist functions in avian turning manoeuvres (preprint)。
A twist of the tail in turning maneuvers of bird-inspired drones (2024 出版論文)
この時点ですら猛禽類が翼を動かさず尾をひねるだけで方向転換 (banked turn) をしているのかよくわかっていなかったと書かれている。実験によって翼に後続する気流の中で尾が roll や yaw のモーメント (論文の概念図参照) を生み出せることがわかった。
尾をひねることで翼も少し上向きの角度となって方向転換に伴う揚力の減少を補う結果となった。
低速飛行だけでなく高速飛行時も翼の形状を非対称に保つことで急速旋回が可能になる。これらは風洞実験のみで確かめることが難しいとのこと。この実験を行うまでは尾をひねるだけで方向転換ができるかは自明でなかった。
ドローンの形態は実際の猛禽類の翼の形状に合わせ関節の運動も可能にしたもの。羽毛は人工のもので実際の羽毛を模した素材を用い風切羽も再現している。尾も 11 枚の人工羽毛を用いて 3D プリンターで腱で結びつけ現実に近いものを再現するなど凝っている。詳しい図もあって面白い。
ちなみにモデルの体重 460 g、翼開長 1.1 m。トビが尾を動かしている理屈はだいたいわかったと言ってよいだろうか。
Tay et al. (2025) Numerical Simulation of a Bird-Inspired UAV Which Turns Without a Tail Through Proverse Yaw 多くの鳥が尾羽を特に動かさずに方向転換できることに着目した尾翼なし飛行機の操縦性能のシミュレーション研究。
Askari et al. (2024) Crash-perching on vertical poles with a hugging-wing robot は同じチームによる "木に着地する" 運動機構 (どちらかと言えば飛翔性哺乳類を模している) の研究。
[短足の鳥に共通する遺伝的背景]
Shakya et al. (2025) Convergent evolution of noncoding elements associated with short tarsus length in birds
スズメ目ではヒヨドリ科とツバメ科が足の短い代表グループとして調べた。鳥類全体ではカワセミ類やペンギン類など多系統で短い足が進化している。
この研究ではアマツバメ類など代表的な短い足のグループを調べていないなど限界はあるが、足の短い系統の鳥に共通する conserved non-exonic elements (CNEEs。タンパク質をコードしないがよく保存されている配列でおそらく遺伝子発現の制御に関わっている) への選択圧が認められた。
これらの系統の間で共通の遺伝的メカニズムで短足化が起きたと考えている。他にも系統固有で短足化に関係すると考えられる遺伝子も挙げられている。
形態的な収斂進化のメカニズムに迫る研究。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ウグイス科 CETTIIDAE ▽
-
ウグイス (チョウセンウグイス が別種となる)
- 第8版学名:Horornis diphone (ホロルニース ディポーネ) 2種類の声を持つ丘の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Cettia diphone (ケッティア ディポーネ) 2種類の声を持つチェッティの鳥
- 第8版属名:horornis oreos 丘 ornis 鳥 (Gk)
- 第7版属名:cettia (合) フランチェスコ・チェティーの (-ia (接尾辞) 人名を属名にする) イタリアの数学者で動物学者の Francesco Cetti)
- 種小名:diphone (合) 2種類の声の diphonos (di- (接頭辞) 二つの phone 音声 Gk) 亜種ハシナガウグイスのさえずりと谷渡りのこと (備考参照)
- 英名:[Bush Warbler 分離前の名称], IOC: Japanese Bush Warbler
- 備考:
horornis の読みは外来語由来で不明だが、起源となるギリシャ語 oros, ornis が長母音を含まないためすべて短母音で発音されると思われる。Hodgson (1845) による属名で、ギリシャ語 oreos はそのまま合成すると読みにくいので英語の hill に合わせて h を補ったと考えるとわかりやすい (Inhabits the northern hills とある)。
ギリシャ語 ornis (オルニース。鳥) は or-nis と分割され i が長母音。"ホロルニース" のアクセントでよいと考えられる。
diphone も外来語由来だがギリシャ語の diphonos は2つの母音が長母音なので -pho- を長母音で発音するのが自然と思われる。"ディポーネ" を採用した (伸ばさない場合は別意味になる可能性がある。#サンコウチョウ備考参照)。
語末も "ディポーネー" と伸ばすかも知れない。
参考までに diphone は英語圏では通常 "ダイフォン" と読まれている。発音を聞くとまるで日本語の "台本" のような抑揚に聞こえて驚かされる。
旧属名に使われる cettia は "ケッティア" のアクセントでよいと考えられる。Cetti のイタリア語読みは英語風には chet-tee と表記されるようで e は特に詰まる音というわけでなく語末は長音。発音を聞いて近いカタカナ表記を与えた。
分割のため第7版学名は亜種まで記してもよいが、その場合は第7版学名で亜種ウグイスは Cettia diphone cantans となる。第8版と第7版で主な亜種の扱いが変わらないため特に別記しなかった。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Horornis 属 (oreos 丘 ornis 鳥 Gk) に変更、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。Horornis 属はウグイス属となる。
Cettiidae (ウグイス科) には変わりがない。この新しい学名は英語の図鑑や海外サイトなどを見たり投稿する時に最初に問題となる種の一つであることは多くの方が気づかれていたことだろう。
「世界標準」(?) の学名が採用されることになる。
種の記載時学名 Sylvia diphone Kittlitz, 1830 (原記載) 基産地 Bonin Islands (= Ogasawara-gunto) (小笠原)。
小笠原のウグイスなので種ウグイス全体を代表する種小名にふさわしいかどうかわからないが、最初に記載された亜種のためウグイスの種小名となる。#メグロでも述べたように Kittlitz の小笠原の記載が相対的に早すぎたのである。
2種類の歌 (zwei sehr auffalend verchiedene Singstimmen 2種類の全く違った歌) が由来で、記載を見る限り der andere Gesang (別の歌) は ka, ki!, ka, ki! の非常にはっきりした音節が含まれるとあり、谷渡りを指しているらしい。この歌は警戒音らしい (Es scheint dieser Gesang unruhige Empfindungen auszudruecken) と記述している。
diphonos の意味は The Key to Scientific Names では many-tongued (多くの声/舌を持つ) と訳されているが、ここでは伝統的な "二つの声の" を採用しておく。
意味的にはウタイムシクイの polyglotta に近いかも知れない (#ヒメウタイムシクイの備考参照) とも考えたが原記載を見て2種類の歌と判明した。
"ホー ホケキョ" を指して "2つの音で鳴く" 意味ではない。
現行の学名ではウグイス以外の用例は見当たらない。The Key to Scientific Names の記述はおそらく原記載を調べていないと思われる。
多くの鳥の名称に現れる Warbler の語源を調べておくと、warble はフランス語 werbler からの借用とのこと。遡ると古ゲルマン語 *hwerb- (回転する revolve) で、英語の whirl (渦を巻く) にも関係するとのこと。
回転するように音を繰り返す (trills)、震わせる (quavers) などを意味していたと想像される。1530 年以来の用例がある。鳥のように柔らかく甘く歌う声と説明があるが、鳥に使われた用例の方が遅い。ヨーデルを意味するのはアメリカの語義で新しく 1880 年とのこと。
若い鳥のように歌う試み (ぐぜる?) を指す用例は 1605 年に知られているとのこと。鳥がはっきり甘い声でさえずる表現は 1606 年に知られている (以上 OED より)。
本来は複雑な声で反復的な部分の多いさえずりを指していたと思われ (この語義は#メジロの現在の英名に使われている)、ウグイスのさえずりはあまり当てはまらないかも知れない。
"bush warblers" の概念はもともと分類上の「ゴミ箱」状態 (Bush-warbler の wikipedia 英語版より) で、既存の分類に当てはまりにくかったウグイスも一緒に混ぜられていた経緯が関係しているかもしれない。旧 Cettia 属が単系統でなかったのも同様の理由からだろう。
旧 Cettia 属が単系統でないこと、および新属名の提案は Alstrom et al. (2011)
Non-monophyly and intricate morphological evolution within the avian family Cettiidae revealed by multilocus analysis of a taxonomically densely sampled dataset。
Horornis 属の名前もここで提唱されたが、この属名そのものは古くから (1844) 使われていたもの。
Cettia 属のタイプ種がヨーロッパウグイス Cettia cetti Cetti's Warbler であるため、属の分割が行われるとそれ以外の系統の属名が変わることになる。
旧北区に広く部分する鳥ではヨーロッパの種類が最初に記載されることが多く (ホオジロ類のキアオジなど) 属分割されると極東などの種類の属名は変わりがちである。これは記載が早いものが優先される規則によるものでやむを得ない。
IOC では Cettia 属を4種にしているが、Boyd はさらに系統分割を提案していて、この場合では Cettia 属は1種のみになる (かつてはあれほど多数の種が含まれていたのに!)。この分類は分子系統樹に基づくものだがヨーロッパ1種と残り3種 (ユーラシア中央部) の分布を考えるとうなずけないこともない。
Boyd によれば、上記 Alstrom et al. (2011) の fig. 3 を見れば現在のように Cettia 属を4種にするのは無理があり (Tesia 属の属名を Cettia に変えない限り単系統にならない)、
ヨーロッパウグイス1種のみを分ける方が妥当であるとのこと。系統樹上では確かにそうなる。
いずれも日本とは関係の薄い種類なので我々にとっては実用的にはそれほど問題になることはないだろう。
系統図上ではウグイスはヨーロッパウグイスから大きく離れていて、ウグイス科を全部 Cettia 属にしない限り単系統の Cettia 属を作ることはできない。その場合は従来の他の属 (ヤブサメなど) も Cettia 属に変える必要があってこれはさすがに容易に受け入れられない
(もっともヤブサメもかつては Cettia 属とされていた)。
従ってウグイスはヨーロッパウグイスとは別属になることはやむを得ない。
この結果かつて Cettia 属だった東アジアの多くの種が Horornis 属となった (日本で影響を受けた種類は比較的少なかったが)。
Horornis 属のタイプ種は Horornis fortipes (fortis 頑強な pes 足; 英名 Brownish-flanked Bush-Warbler) タイワンコウグイスなどの和名がある。
ヒマラヤから台湾にかけて分布し、台湾には固有亜種 H. f. robustipes (「頑強な脚の」が生息。英名でしばしば Strong-footed Bush Warbler とも呼ばれる。この種も分類学的には複雑である
[Wei et al. (2019) From the Himalayas to a continental Island: Integrative species delimitation in the Brownish-flanked Bush Warbler Horornis fortipes complex]。
この種は近年分布の北上が顕著であるとのこと: Zhang et al. (2023) Recent Northward Expansion of a Passerine Bird Species, Brownish-Flanked Bush Warbler (Horornis fortipes)。
分類の捉え方次第でウグイスの学名に Cettia diphone を使い続けること自身は無理ではないが、その場合いはヤブサメの学名も Cettia squameiceps としないと現代の分子系統分類と整合性がとれなくなる。
Boyd による Horornis属一覧を紹介しておく。
ウグイス属 Horornis
タイワンコウグイス Horornis fortipes Brown-flanked Bush-Warbler
キバラウグイス Horornis flavolivaceus Aberrant Bush-Warbler
スンダウグイス Horornis vulcanius Sunda Bush-Warbler
インドウグイス Horornis brunnescens Hume's Bush-Warbler
ミヤマウグイス Horornis acanthizoides Yellow-bellied Bush-Warbler
チョウセンウグイス Horornis borealis Manchurian Bush-Warbler (新研究によりこの学名は適切でない。解説参照)
フィリピンウグイス Horornis seebohmi Philippine Bush-Warbler
ウグイス Horornis diphone Japanese Bush-Warbler
ナンヨウウグイス Horornis annae Palau Bush-Warbler
タニンバルウグイス Horornis carolinae Tanimbar Bush-Warbler
サンクリストバルウグイス Horornis parens Shade Bush-Warbler
ブーゲンビルウグイス Horornis haddeni Odedi / Bougainville Bush-Warbler
フィジームシクイ Horornis ruficapilla Fiji Bush-Warbler
基本的に IOC 分類とあまり違いがないが、インドウグイス、ブーゲンビルウグイス の和名は eBird から採用した。
IOC と違いがある部分は日本周辺の分類である。Boyd は Alstrom et al. (2011) に基づき、Horornis canturians (ニシウグイスの名前もあった) のうち亜種 borealis が種相当の違いがあるとして分離している。
日本で記録されている亜種のため、もし種名を与えるならばチョウセンウグイスとなるだろうが、Boyd は分子系統樹に基づいて canturians を borealis と同種と考えず、canturians はむしろ cantans と遺伝学的に非常に近いためにウグイスの亜種としている。
wikipedia 日本語版ではこの通りの説明があり、チョウセンウグイス H. borealis と マンシュウウグイス H. diphone canturians を別種としているが、IOC や日本鳥類目録 改訂第8版の第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開 (2023年10月) とは異なっている。
canturians の記載の方が早いため、これを含むかどうかで種小名が異なることになる。
チョウセンウグイスを検索しても2種類の学名が現れるのはこの概念の違いによる。
Boyd はこの上で、日本のウグイスは Alstrom et al. (2011) で十分調べられていないので暫定的取り扱いとしている。音声的には日本と大陸と違いがあることは指摘されておりそれぞれ種に値するかも知れないとしている。
その後 Wei (2021) Rapid morphological evolution on remote islands
Resolving the taxonomic status of an island dwarfism warbler population のレポート (BOU) に遺伝情報と歌の解析結果が出ており、日本と大陸で分離できることが明らかになっている。
bootstrap 値も低めなのでどうだろうかと思っていたが、Alstrom et al. (2011) のデータは細かな亜種の帰属を議論するにはやはり不十分であった。
この研究を受けて日本鳥類目録 改訂第8版の第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの扱いになっているのだろう。Boyd はこの結果をまだ参照していないものと思われる。
結果的に canturians と borealis を同種としてチョウセンウグイス Horornis canturians とする扱いが適切で、カラフトウグイスは不明であるが日本の他の亜種もウグイスに含めてよいことが判明した。
ただし基亜種ハシナガウグイス diphone は evolutionary significant unit (進化的に意義のある単位: ESU) とみなすことができて保全上注意を払うべきとしている
(分子系統的には必ずしも完全に支持されるわけではなくても保全上有益な地理的グループを種とみなす傾向のある最近の論調に基づけば独立種に値するかも知れない。
もし分離されればこれが基亜種のため、我々が通常出会うウグイスの学名が Horornis cantans となるわけだが、離島の基亜種名を種小名に使うよりこちらの方がふさわしいかも知れない。昔からの学名の変遷を見てきた人は頭を抱えそうだがハシナガウグイスの保全の重要性を表すには案外よいかも知れない)。
[本論文はまだ未発表? 大陸と台湾のタイワンウグイスの関係は前記 Wei et al. (2019) に発表されている]。
wikipedia 日本語版も内容更新が必要であろう。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Cettia cantans ウグイス、Cettia ussuriana (Suruga, Yakushima) シオサザイ (#ヤブサメの項目へ)、Cettia diphone (Bonin Islands) オガサワラウグイス となっていた。
フィジームシクイ Horornis ruficapilla について詳しい遺伝研究があった: Gyllenhaal et al. (2020) A test of island biogeographic theory applied to estimates of gene flow in a Fijian bird is largely consistent with neutral expectations
大きな島から小さな島に遺伝子流動が起きる島嶼生物学の予想通りの結果だったとのこと。Horornis属の中で遺伝学が一番よく調べられた種類になっているかも知れない。
[チョウセンウグイス]
かつて亜種扱いであったチョウセンウグイス Horornis canturians (canturians < canere 歌う; cantula 不明の小型の鳥) (英名 Manchurian Bush Warbler または Korean Bush Warbler) が別種となった (かつてはニシウグイスの和名もあった)。
チョウセンウグイスのうち日本で記録のあるものは亜種 borealis (北方の) と記載されている。基亜種は検討亜種扱い。
チョウセンウグイスのバンディング記録や計測値について
Itoh et al. (2009) Banding Records of a Subspecies of Japanese Bush Warbler Cettia diphone borealis along the Sea of Japan Sea Coast of Central Honshu, Japan 伊藤他 新潟市関屋海岸における亜種チョウセンウグイス Cettia diphone borealis の標識記録 (和文)。
[ウグイスの亜種]
ウグイス Horornis diphone で日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに以下の亜種を記載している:
・亜種ウグイス H. d. cantans (< cantare < canere 歌う) 記載時学名 Salicaria cantans Temminck & Schlegel, 1847 (原記載) 基産地日本 (図版)
フランス語名 le riverain chanteur。riverain は沿岸地帯の住人 (辞書訳)、chanteur は歌手。riverain は形容詞の意味もあるがここでは名詞で用いている。
Les riverans にオオヨシキリ (Salicaria turdina orientalis Temminck & Schlegel, 1847) の原記載があり、ヨシキリ類を指していた名詞とわかる。
"歌手のヨシキリ" の意味となる。
・亜種カラフトウグイス H. d. sakhalinensis (サハリンの; 南千島で繁殖し少数が冬鳥) 記載時学名 Horornis cantans sakhalinensis Yamashina, 1927 基産地 Nayoro (= Gastello), Sakhalin
・亜種ハシナガウグイス H. d. diphone (小笠原諸島、琉球諸島) 記載時学名 Sylvia diphone Kittlitz, 1830
・亜種ダイトウウグイス H. d. restricta (「限定された」の意味; 奄美諸島、沖縄諸島、大東諸島) 記載時学名 Horornis cantans restrictus Kuroda, 1923 (原記載 基産地 Minami-daito-jima, Borodino Islands
・亜種リュウキュウウグイス H. d. riukiuensis (琉球の; 琉球諸島) 記載時学名 Horornis cantans riukiuensis Kuroda, 1925 基産地 Sonai, Iriomote-jima, southern Ryukyu Islands
および亜種不明のもの。
記載時学名は現在認められている亜種のみ示した。Temminck and Schlegel (1847) は Salicaria cantillans Temminck & Schlegel, 1847 (原記載) (図版)
フランス語名 le riverain petit-chanteur "小歌手のヨシキリ" も記載しており、前種 Salicaria cantans Temminck & Schlegel, 1847 の小型版とのこと。
cantillans はやはり cantillo 歌うの変化形で、英語では warbling に対応とのこと。
この種小名を持つ有名な種にシラヒゲムシクイ Curruca cantillans 過去の学名で Sylvia cantillans があってコノドジロムシクイの近縁種 - と言っても日本ではあまりピンと来ない方が普通。
"小型版" の方がメスとの話題は Cettiidae (BirdForum 2011.12.5 のところ) にもあってチョウセンウグイスでも同様の事例があり、Cettia minuta の学名があったとのこと。
記載時学名 Arundinax minutus Swinhoe, 1860 (参考 1 訂正名, 2)。
Campbell (1892) XVIL-A List of Birds collected in Corea に解説がある (pp. 234-235)。Cettia cantans minuta Seebohm が使われていた。ここでは渡りの個体群の種学名とすることを提案したもの。
Blakiston and Pryer (1878) A Catalogue of the Birds of Japan では Herbivox cantillans? の学名で "Ko-yoshi" としている。同定は Fauna Japonica の図版と比べたとあり、Fujisan, Yamato, Yezo が出ている。
ここではオオヨシキリとウグイスの間に置かれており、コヨシキリとの混同があった可能性もある。
見慣れない属の Herbivox (herba 草 vox 声) は Swinhoe (1871) が提唱したもので、Salicaria cantans T. & S., Arundinax canturiens, Swinh., Arundinax minutus Swinh. の3種に加えて Salicaria cantillans T. & S. を含むとのこと (The Key to Scientific Names)。
この時点では "小さいウグイス" は別種扱いで、今では見慣れない学名が並ぶが、現代の分類に従えば Swinhoe (1871) はウグイスとチョウセンウグイスそれぞれのオス・メス (現代の解釈) を別種として4種と数えたことになる。新属を提案したのはウグイスとチョウセンウグイスがそれぞれ別属で記載されていたことも理由の一つだろうか。もちろん新属の提案者の名前を残すこともできる。
Sharpe, 1881, Cat. Birds Brit. Mus., V, p. 133 が Herbivox 属のタイプ種を定めているので、このあたりで同種のオス・メス説が提唱され始めていたのかも。
Owston (1899) Price List of Birdskins and Eggs. Collected in the Yayeyania Group of the Loochoo Islands (Lai. 24° 80' N., Long 124° E.)
に価格表があり、
(当時の学名で) Cettia cantans (T. & S.) を Large Japanese Bush Warbler, 和名 Uguisu、Cettia cantillans (T. & S.) を Small Japanese Bush Warbler 和名 Ko-uguisu と呼び、石垣島で採集された後者の標本はすべてメスだった。前者には両方が混ざっていた。
この時点で cantillans は cantans のメス説があったようで、この結果はこの説を支持する方向であると記述されている。
石垣島で採集のもので Temminck and Schlegel (1847) の記載したものと同一のものを指していると限らないため不定性も残ると考えられる。Cettia cantans (T. & S.) とされた商品にはオス・メスとも含まれていたため、"支持する方向" のような曖昧な表現にとどめているのだろう。当時は南西諸島のものを現代の概念で別亜種とする認識はまだなかった。
Temminck and Schlegel (1847) の記載した2種のタイプ標本はいずれもライデン博物館所蔵 (参考) とのことで調査されて現在のように同定されたものだろう。同一種でシノニムであれば先に登場した cantans に先取権がある。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では2種として紹介 (Large Japanese Bush-warbler と Small Japanese Bush-warbler)。同じ分布で似た2種が存在するのは説明が難しいが、中国の北方型と南方型がそれぞれ分布するようになったと解釈を試みている。同種のオス・メス説は示されていなかった。
この文献では Cettia diphone は別種扱いとされていたため日本にウグイスが3種存在していたように見え、現代の学名を見慣れているととても変な感じがする。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には整理されていたようでいずれもウグイスの学名となっている。
Horornis fortipes の和名がタイワンコウグイスになっている。確かにウグイスより小さいがタイワンウグイスでもよかったはずで、あるいは "コウグイス" の和名が生きている時期に命名されたのだろうか。台湾だけに分布するわけではなく和名は分布域を適切に表していない。
Temminck and Schlegel (1847) が種小名に日本に由来する語句を使わなかったのは、日本から3種のヨシキリ類 (オオヨシキリとウグイス2種) を記載する必要があったためではないだろうか。3種存在すれば "日本の" とは形容しにくい (#タンチョウ学名に関する Temminck の見解や)。複数種存在する場合は色彩などの他の特徴を表したものと考えられる。
#ヒレンジャクに Temminck の与えた学名も参照。
またフランス語名で他の日本産種を記述する時にしばしば使っていた "du Japon" の名称もいずれにも用いていない。
3種の中ではオオヨシキリの方がヨーロッパのものによく似ていて、日本以外にもボルネオ、Macassar (スラウェシ島)、スマトラからの標本もあり、こちらにヨーロッパの対応種に相当する意味で地域を指して orientalis を優先して用いたためと想像できる。当時は亜種概念は明確でなかったので亜種記載というより "東洋のオオヨシキリの意味" で使われている。ただし race と現在の亜種に対応する概念も用いて表現している。
ヨーロッパのオオヨシキリですでに複数の races が報告されていたので東洋の race が見つかってもまったく不思議でなかっただろう。
orientalis をすでに用いた以上、同属でさらに "日本の" を重ねるのは無理がある。あるいはそもそもそのつもりはなかった。
日本を代表する鳥と言えそうなウグイスに japonica / japonicus が登場しなかったのは当時同属とされたオオヨシキリの方にヨーロッパの対応種があり、地域名を奪われた結果、さらに (オス・メスを別に) 2種記載するための案外簡単な理由だったのかも。
南西諸島のウグイスと渡りについては梶田他 (2002) 沖縄島に生息するウグイス Cettia diphone の二型について。この文献では「リュウキュウウグイス」は本州以北に繁殖分布域を持つ可能性が高く、独立亜種としての妥当性に検討の必要があるとのこと。
絶滅鳥ダイトウウグイスが復活? 〜ワークショップ「ダイトウウグイスとは何者か?」〜 (山階鳥類研究所 2004)、ダイトウウグイスの巣と卵の発見・撮影に成功/『絶滅』から『再発見』へ - ダイトウウグイス『消失』の謎 (国立科学博物館 2008) などの日本語情報がある。
南西諸島の亜種についての見解はまだ国際的な一致を見ていないようで、Brazil (2009) "Birds of East Asia" でも上記と異なった見解が示されている。IOCでは H. d. sakhalinensis を認めていない [なお Brazil (2009) は南西諸島で越冬するウグイスと同一である可能性を示唆している]。研究者によるさらなる解明を待ちたい。
小笠原個体群の遺伝的研究 Emura et al. (2013) Genetic and Morphological Differences among Populations of the Japanese Bush-Warbler (Aves: Sylviidae) on the Ogasawara Islands, Northern Pacific。
Brazil (2009) ではウグイスを複数種に分割する意義もあるかも知れないと述べている。Horornis属全体では多数の種が存在し、遠くはフィジーのような離島の固有種も多い。日本のウグイスはハワイに持ち込まれて外来種となっている。
濱尾 (1992) 番い関係の希薄なウグイスの一夫多妻について。
[ウグイスは息を吸う時に声を出すか]
発声全般については #タンチョウの備考 [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] 参照。ウグイスは非常によく話題になるのでここで取り上げておく。
Beckers et al. (2003)
Mechanisms of frequency and amplitude modulation in ring dove song
には結構驚くべき結果が出ていて、バライロシラコバト Streptopelia roseogrisea African Collared-Dove から家禽化された ring dove (ジュズカケバト?) では、ハト類のクックウーの音声の最初の1音は1回吐く音声で、その後息を吸った後クウーは細かく息継ぎをして空気を貯めながら最初の少し震えるような音を出し (息を吐く時にのみ声が出るので少し震えるような音声になる)、最後に 0.5 s ぐらいまとめて吐いて連続音を作っている。
息継ぎの時間が非常に短いので我々には個々の音を発声しているように聞こえず、少し震えるような (こもったような) 声として聞こえるのだろう。
ring dove ではまだ間隔が長いので震えるような感じに聞こえるが、通常のソノグラム (見栄えを重視するために時間分解能を犠牲にしている: #ヒクイナの備考参照) では震える連続音のように見える。ソノグラムで震えるように見える音声があれば分解能を上げて不連続な音を出していないか調べるのがよさそう。
ヨーロッパのコキジバトでは明らかに震える感じの声を出しているがこれはその震えごとに息を吐いているのだろう。ハト類の似た声は同様と考えれば、キジバトの少しこもったような感じのする音も細かく息を吐きながら作っているのだろう。おそらく高解像度のソノグラムでないと個々の音と判別できていないのだろう。
ring dove → コキジバト と見てゆくとハトの声は吐く時に出していると考えてよさそう。
アオバトはどうなのだろうかと考えるが、あの程度の長さならば連続で出せるのだろうか。アオバトに近縁のオナガアオバト Treron sphenurus Wedge-tailed Green Pigeon では ring dove 同様に震わせる音声も記録されているので、息継ぎの面から音声の系統進化を調べてみるのも面白そう。
ウグイスもホーホホホ、ホケキョと分かれて聞こえることがあるが途中で息が続かなくなって息継ぎをしていると思われ、やはり吐く時に音を出していると考えるの妥当そう。
吸う時にも声を出す通説の根拠の一つと考えられるものに、中西悟堂「野鳥記コレクション」I 野鳥と共に p. 187 があった。キジバトの声でポッポーは吐く息、ゼゼッの方は吸う息、またニワトリのコケコッコーのコーは吸う息とあった。
出典は述べられていないので中西氏自身の観察結果かも知れないが、あるいは当時の常識だったのかも知れない。上記 ring dove の研究結果を見ると、息継ぎが早すぎて人の目には息を吸いながら発声しているように見えたものと想像できる。
-
ヤブサメ
- 学名:Urosphena squameiceps (ウーロスペーナ スクアーメイケプス) 鱗状斑の頭で楔形の尾の鳥
- 属名:urosphena (合) 楔形の尾羽の (oura 尾羽 sphina 楔 Gk)
- 種小名:squameiceps (合) 鱗状斑の頭の (squameus (adj) 鱗状の、-ceps 〜の頭の)
- 英名:(Short-tailed Bush Warbler), IOC: Asian Stubtail
- 備考:
urosphena は外来語由来の合成語で発音はわからないが、ラテン語 urus は冒頭が長母音 (ギリシャ語の ouros はこれらら派生とされる) であること、ギリシャ語の -sphen は e が長母音であることから、それぞれ長音にして "ウーロスペーナ" のアクセントが適切と思われる。
squameiceps はラテン語 squama は最初の a が長母音であること、caput は短母音のみであることから、"スクアーメイケプス" ("スクアーメイケプス" かも知れない) のような発音が考えられる。
上記かっこ内の英名はウグイス類とまとめられていた時の名残りで、現在では Asian Stubtail が普通で、形態もよく表している。中国名も「短尾鶯」、ロシア名も korotkokhvostka (短い尾) でどれも尾の短さを表している。
しかし初記載の時点では以下のようにそうではなかった。
ほとんどのリストで単形種。Howard and Moore 3rd edition (incl. corrigenda 8) までは亜種 ussuriana を認めていた。
英語の Stubtail は新しい名称のようで、OED では stub-tail にこの用例は現れない。むしろキジ類の発育段階を指して使われていた。
[ヤブサメは2種だった? - 概念と学名の変遷]
#ウグイスの備考にあるようにウグイスの同属の Cettia 属とされていることもあった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Cettia squameiceps でヤブサメの和名とともに別名にカワリウグイスが載せられていた。
さらに Cettia ussuriana シオサザイ の名称が登場する。
ヤブサメの原記載 (Swinhoe 1863) はややこしく、当時の学名は Tribura squameiceps だった。基産地は Canton とある。なんとこの標本には尾がなかったとのこと (尾はあったが短すぎて尾が脱落していたと判断されたのか?)。
この時用いられた属名は現在チャイロオウギセッカ Locustella luteoventris Brown Bush Warbler をタイプ種として命名されたもので、尾があれば長いだろうと想像されていた模様。
チャイロオウギセッカは後に Bradypterus 属に含められて Tribura はそのシノニムとなった (The Key to Scientific Names)。その後再度分類再編があって Locustella となった。
Bradypterus は "ゆっくりした翼の" の意味でヒタキ類にも使われた。現在はアフリカオウギセッカ Bradypterus baboecala Little Rush Warbler をタイプ種とする属に用いられている (The Key to Scientific Names)。
このグループは分類学者も頭を悩ませていたことがわかる。
Swinhoe は中国の広東の最初の標本の他、第2標本となる台湾の個体を入手し、当時の Tribura 属のような長い尾ではないことがわかった。
Blakiston による函館の第3標本、Taczanowski によるウスリーの第4標本の情報を得て、Swinhoe はヤブサメをタイプ種として 1877 年 Urosphena の属名を新たに与えた (解説。図版)。
この属名と1文字のみ異なる Urosphen Agassiz, 1835 (化石魚類) がすでに使われていることを指摘し、Stejneger (1892) は Urophlexis に変更した
(oura 尾 phlexis Aristophanes が言及した不明の鳥。Phlexis Hartlaub, 1866 が bush warbler を指した用例がある Gk)。その後これら2つは別の属名と判断されて Urosphena が有効とされ戻された模様。
Stejneger (1892) Urophlexis ussuriana Seebohm の記述 (以上 The Key to Scientific Names)。
Seebohm (1881) がウスリーのヤブサメを主に色の違いから Cettia ussurianus と分離した (記述)。Taczanowsky's Bush-Warbler と名付けている。
しかし手元に標本があるわけではない。Taczanowsky によればウスリーの谷に生息するとのこと。
Stejneger (1892) は函館の4標本を用い、Seebohm (1881) の分類に従っているが、この同定は確実ではない。韓国と日本の標本は Swinhoe が台湾 (第2標本) で記載した squameiceps と尾の形が異なる。
明らかになるまでは squameiceps よりも少し丸い形の尾のものを ussurianus と呼んでおくこととしたとのこと。
[和名の由来考察]
Ogawa (1908) はこの種小名を用い、Cettia 属とまとめられていた時代のもの。当時は squameiceps (Yabusame, Kawari-uguisu) と ussurianus/ussuriana (Shiwosazai) が別種と考えられていた。
シオサザイの名称は別名というより Seebohm (1881) が2種に分離したため生じたもののようだが、後述の標本ラベルを見るとこの名称の方が普及していたものと考えられる。
Ogawa (1908) はそれぞれ Hokkaido, Fuji-yama と Suruga, Yakushima の分布を与えていた。
"シオ" は "塩" か "潮" かの考察もあったらしい。この名称はミソサザイに似て海の近くに分布すると考えられたためだろうか。記載されている分布とは表面上では一応整合するように見えるが、おそらく別の意味があって後に考察する。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) の "島さざい" をヤブサメと同定している。
大橋 (2021) Birder 35(5): 52-53 がシオサザイの語源を推定している。この記事では Ogawa (1908) にはシオサザイの名称のみ出てくるとあるが何かの間違いか。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 119 (1940 年初出) によればさえずりをもとに 藪 + 雨 (藪に降る雨のような声) からヤブサメと解釈したのは籾山徳太郎の説とのこと。
"藪鮫" の表記もある (コンサイス鳥名辞典) ので、音声ではなく色由来とも感じられる (コサメビタキを小雨鶲と解釈してしまうのと同じ問題)。コサメビタキの方はサメビタキがあって、こちらは色彩由来と考えられてわかりやすい感じがする (サメビタキはさらに和名が整理される際に英名や学名が参考にされたかも知れない: #サメビタキ備考 [サメビタキの分類と名称])。
ヤブサメを色彩由来と考えてみたい背景には、ヤブサメの生息地はウグイスのような藪というよりむしろ山地の崖地であまり合わない感じがするため。ヤブサメの "ヤブ" は古い時代の英名の Short-tailed Bush Warbler などに含まれる Bush Warbler に関係していないだろうか。英名で "Bush" の付く種類が "ヤブ" と訳されている事例が非常に多い。
ドイツ語名でも Buschstutzschwanz と Busch が入っており、デンマーク語ではより直接的に Brun Busksanger (英語では Brown Bush Warbler に相当) で、かつて色彩と "藪" を示すこの名称があった (あるいは逆に他言語に訳した) と考えるのが妥当そうに思える。現在の Brown Bush Warbler はチャイロオウギセッカの名称で、ヤブサメの原記載時でチャイロオウギセッカをタイプ種とする属 (Tribura 属) に含まれるとされていたことと非常によく整合する。
つまり現在呼ぶところのチャイロオウギセッカ属の1種として記載されたため Brown Bush Warbler に相当する外国語名で紹介されていたが、まったく無関係と後に判明してこの名称は大部分の言語で消滅した (#カラフトワシ の備考 [なぜ "樺太" ワシ?] で紹介の "アシナガワシ" に相当する学名の経緯に似ている)。デンマーク語では検討不十分でそのまま残ってしまったのだろう。
種小名の squameiceps も「鱗状斑の頭の」で、色彩とともにサメ (例えば鮫肌) を連想しても不思議でないかも知れない。英語別名にも種小名をそのまま訳した Scaly-headed Bush Warbler があった。
ヤブサメ - シオサザイ - ミソサザイ の関連を見ると、ミソサザイが "味噌" ならば "鮫色" でもよいかも。
音声に当てはめるのはサンショウクイ同様音声を聞き分ける (覚える) ための表現として用いられたものかも知れない。
ヤブサザイのような名称がもし途中であれば関連が見えるかもと思ってみたが、ヤブサザイは Xenicus longipes Bush Wren (ニュージーランドのイワサザイ類) の和名に使われていて、Bush = "ヤブ", Wren = "サザイ" の形になっている。どことなくよく似ている。
なおイワサザイの名前はイワヒバリの古名としてあって、同様にオホサザイはカヤクグリの古名だったとのこと [Birder 編集部 (2003) Birder 17(8): 42-43]。
山階鳥類研究所の標本データベースでは日付の表示されている最も古い標本 (1906 屋久島) のラベルには和名がなかった。
YIO-25640 (採集年不明。福岡県) にはシホサザイ、YIO-25643 (済州島 1927) でもシホサザイとあるので、古くはシホサザイの方が一般的な名前であったか、長く別種扱いで南部のものをシホサザイと呼んでいたのかも知れない。
squameiceps と ussurianus/ussuriana が別種と考えられていた時代は、どちらも比較用標本が手元にないため判定に困り、片方に広く使われていたシホサザイの名称を保存するともに、もう片方に新称ヤブサメまたはカワリウグイス (後者は過去からあった名前らしい) を与えたと考えると納得しやすい。ヤブサメは外国語 (あるいは種小名からの連想) 由来で命名されたとすればいろいろな問題が解決する感じがする。
この解釈だとヤブサメ = 藪鮫 = 英語ならば Bush Brown に相当、は外国語名に対応するものとなって面白くも何ともないかも。外国語由来で命名する際の語の組み合わせの選択時に流鏑馬に掛けたものかも知れない。
#ウグイスの備考 [ウグイスの亜種] にあるように、通常のウグイスと "小さいウグイス" (コウグイス = メスのウグイス) が別種扱いで、Owston (1899) の価格表にも別学名で表示されていた。
時期的にはほぼ同じころで、ウグイス、コウグイス、カワリウグイス のような種概念で認識されていたのかも知れない。現在のヤブサメが2種に分かれていると考えられても全く不思議でない時代背景だった。
またこの解釈が正しいと考えるとヤブサメのさえずりは鳥類学者にとってもそれほど馴染みでなく、標本の特徴や文献の名称からのみ名前を付けていた可能性がある。シホサザイも形態、行動と生息環境由来と思われる。あの特徴的なさえずりをヤブサメのものと最初に判定したのは誰だったのだろう。実は多くの人は虫の声だと思っていたとか...?
「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) にもあまり古い文献が現れず、過去それほど注目されていなかったのかも。中西悟堂 (1940 年の引用) や 籾山徳太郎 (1885-1962) 両氏が把握していたことは確実だが意識されるようになったのは案外新しいのかも知れない。
このように考えてみるとこの時代の標本を基礎とした日本の鳥学者の多くは鳥の声はあまり知らず、一般市民の知識と同程度で声にはあまり関心が払われなかったのも知れない。録音を簡単に残せる時代でもなくやむを得なかった部分もあるが、西洋音楽に親しんでいる人もおそらく少ない中で、音声を文字表記せざるを得なかった点では一般市民も鳥学者も大差なかったかも知れない (#シジュウカラ備考の [オクターブ認識能力] にて考察)。
そのように考えれば #サンショウクイ [サンショウクイの和名・中国名について] の名称由来を鳥学者が書き残さず、歌人も詠んでいなかったこと、
#コノハズク [姿のブッポウソウ] の音声を鳥学者が把握していなかったらしいこと (海外文献にあっても音声の記述に関心が持たれなかった、鳥学者が確実には知らなかったとは書きにくいのでいろいろ説明を加える必要があったなど)、野鳥の声の聞き分けのできる中西悟堂氏の探鳥会に鳥学者も多く参加して盛況で、鳥学者も現場で声を学ぶ必要があったのだろうなどの事項が説明できるように思える。
中西悟堂氏が活躍するようになる以前は鳥を意識して聞くことはあまり行われておらず、声に注意が払われていない時代に和名が整理されたと考えれば、古くからよく知られた鳥、漢語由来のもの、飼育家由来のもの以外に鳥の和名に音声があまり使われていないことも納得できる感じがする。ビンズイも "ジュリン" も1説しか知られていないので鳴き声由来と解釈されているが、#センダイムシクイも含めて再検討の余地があるかも知れない。
ヤブサメのこの部分を書いてからセンダイムシクイの項目の [センダイムシクイの和名の検討] を書いたが、ヤブサメの "サメ" はサメビタキの "サメ" に対応と考える方が当時のムシクイ類・ヒタキ類の垂直分布やブラキストン線の概念とも整合性がよい感じがする。同様にシホサザイは南部の種類、ヤブサメは北部の種類で、ブラキストン線より南では富士山のような高地に分布するはずと考えれば Ogawa (1908) で表記されている分布が大変よく理解できる。ムシクイ類・ヒタキ類の分布の理解とも整合性がとれてめでたしめでたしとなる。
[センダイムシクイの和名の検討] でムシクイ類の声が知られていなかったらしい考察から想像すると、当時の鳥学者はヤブサメの鳴き声を知らなかったのではないだろうか。
さらに #カヤクグリ備考にて、かつては "サザイ" 系統の和名が用いられていたが、分類学の進歩や海外の鳥にも名前を付ける必要に合わせて "サザイ" は英語の "wren" 系統の訳名に用いるように統一されたと考えるとうまく説明できることを紹介した。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 116 (1947 年初出) によればヤブサメが以前に詠まれた例を知らず、中西氏の同時代の歌人が詠み始めたとのこと。また中西氏の他の記事によく記されている地方名などの記述もなく、そもそも知られていない鳥だったことが想像できる。ヤブサメの名称は新しく与えられたものと考えると整合性が高く思える。
大橋 (2023) Birder 37(12): 68-70 の対談記事で、ヤブサメは一番気に入っていて、昔の人のセンスには脱帽と述べられているが、昔の人といってもそれほど古くない可能性があり、また元祖出典は外国語なのかも知れない。また大橋 (2019) Birder 33(12): 32-33 では古語の美しさの例として取り上げられていた。
[音声]
さえずりはよく知られるような尻上がりに音が高く強くなる虫のような声 (8-10 kHz) が典型的であるが、渡来当初はもっと平板な声も聞かれる。なわばり形成のころには声を震わせて競うような特殊なさえずりが聞かれるが、短期間しか聞かれないためあまり知られていない。夜中にも連続してさえずるとされる。
地鳴き (単発のもの) は特徴的で他の「チャッ」系の地鳴きの中でも特異な音声で、聞き慣れると一声でも存在がわかる
[波多野邦彦 (2016) 第39回 Asian Stubtail <ヤブサメ>と同意見。ちなみにさえずりよりも地鳴きの方が音が低いので聞き取りやすいはず]。
秋の渡りなどでもこの声を聞き慣れているとよい手がかりになる。ヤブサメは地面近くを動いていることが多く、繁殖地でも都市公園の渡りでも近くを人が通った時に出す声のようである。警戒音と呼んでもよいだろうか。
同じ特徴を持つ地鳴きを出す種類にムジセッカがあり (ヤブサメより音が低い)、これも一声聞けばわかるタイプの種類で、海外のバーダーもムジセッカを簡単に識別している人も多い (ヨーロッパでもごくありふれた "迷鳥" であり、声で識別可能なので記録も多い)。ヤブサメの地鳴きを知っておくことは他の種類の判別にも役立つ。
ヤブサメの巣立ちびなの声も特徴的で、チチ、チチチのようにホオジロの地鳴きに似た声である (この声もさえずりより音程が低いので聞き取りやすいはず)。この声を知っていると繁殖確認にも役立つ。
ヤブサメの "夜鳴き" はあるいは寝ながら鳴いているのかも知れない。#ズグロヤイロチョウの備考 [亜鳴禽類の睡眠中の発声] 参照。
ヤブサメの "夜鳴き" について上沖 (2018)「ヤブサメの夜鳴きの真相」Birder 32(8): 36-37 の記事がある。「野鳥」1998年7月号 p. 43 に遠藤公男氏 (宮古支部) の記述がり、当時は広く知られておらず地域特異的なものと考えられていたと思われる。
[配偶様式]
ヤブサメはヘルパー行動を行うことが知られている [大原・山岸 (1984) ヤブサメのヘルパーの観察他]。
同時的一夫多妻 (偶発的か?) も知られており [Kawaji et al. (1995) An Example of Polygyny in the Short-tailed Bush Warbler Cettia squameiceps]、
ヤブサメの配偶/繁殖システムは複雑である [Kawaji et al. (1996) Breeding Ecology of the Short-tailed Bush Warbler Cettia squameiceps in Western Hokkaido]。
[その他]
ウグイス科の中ではチョウセンウグイスの北部個体群とともに数少ない長距離の渡りをする種類 (Zhang et al. 2023)。
△ スズメ目 PASSERIFORMES エナガ科 AEGITHALIDAE ▽
-
エナガ
- 学名:Aegithalos caudatus (アエギタロス カウダートゥス) 長い尾のカラ
- 属名:aegithalos (合) カラ類の総称 (aigithalos アリストテレスの記述した3種の鳥の総称で、エナガ、ヨーロッパシジュウカラ、アオガラを指すとされる Gk, The Key to Scientific Names)
- 種小名:caudatus (adj) 長い尾の (cauda (f) 尾 -atus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Long-tailed Tit
- 備考:
aigithalos は外来語由来で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみで "アエギタロス" のアクセントになると推定される。
caudatus は -da- の a が長母音でアクセントがある (カウダートゥス)。所有の -atus 由来。
日本の亜種の読み方を考察しておくと trivirgatus は "トゥリウィルガートゥス"。japonicus は "ヤポニクス" または "ヤポーニクス"。magnus は "マグヌス"。
[分類と亜種]
エナガ科 Aegithalidae は従来カラ類に近いと考えられていたが、例えば Oliveros et al. (2019) Earth history and the passerine superradiation
などによりカラ類と異なった系統のグループであることが示されている。ウグイス科 Cettidae、ムシクイ科 Phylloscopidae を含む系統に含まれ、日本鳥類目録第8版 第二回パブリックコメントに向けた暫定リスト でもその位置に置かれている。
エナガ科を指す英語名は long-tailed tits も使われるが bushtits も英名が bushtit の種類が多いためよく使われる。
OED によれば long tailed tit の用例は 1668 年にあり、long-tail'd Titmouse は 1678 年の Ray による Willughby, Ornithology のラテン語からの英訳に現れるとのこと。bushtit は主にアメリカ英語で 1878 年の用例があるとのこと。Bush-Titmouse は 1874 年の用例がある。
エナガはユーラシア中緯度帯に広く分布する。
かつては中国の主に中央部に分布するギンノドエナガ Aegithalos glaucogularis 英名 Silver-throated Bushtit も同種とされた。例えば Brazil (2009) "Birds of East Asia" では同種の扱いで、Silver-throated Bushtit を分離し、残りに Northern Long-tailed Tit の名称を提案していた。現在は通常別種として扱われる。
ギンノドエナガには2亜種が認められていて、北京近郊など北方の vinaceus と上海近郊など南方の glaucogularis に分けられる。これらの亜種名はエナガとギンノドエナガを同種とする立場ではエナガの亜種としてしばしば登場するためここでも記しておく。
狭義 (現在通常に使われる意味の) エナガには 17 亜種が認められている(IOC)。
ヨーロッパ北部から東シベリアまで広く分布する北方型 caudatus 亜種がある。北海道のシマエナガと同亜種かどうかについては後に。
ヨーロッパから西アジアにかけては、
ヨーロッパ大陸中央部に広く分布する亜種が europaeus で日本の亜種エナガに近い色彩だが虹彩の色は異なる。
ヨーロッパ中央部の人にとっては caudatus と europaeus がちょうど日本のシマエナガと亜種エナガの関係になり、それぞれ色の配置もよく似ている。
例えばドイツでは Die Voegel der Erde 3. Aufl. (2022) によれば caudatus を Weisskopf-Schwanzmeise (頭の白いエナガ)、europaeus を Streifenkopf-Schwanzmeise (頭に縞のあるエナガ) と呼び分けている (実際には中間型もあってもう少し複雑のようである)。
以下は島の亜種や地理的障壁によって分かれながら中央アジア近くまで分布する:
・rosaceus がブリテン島などの亜種。
・aremoricus がフランスの西のユー島 (フランス) とチャンネル諸島 (英国)。
・taiti がフランス南部からイベリア半島。
・irbii がイベリア半島南部とコルシカ島。
・italiae がイタリアとスロベニア南西部。
・siculus がシシリー島。
・macedonicus がアルバニアからギリシャ、バルカン半島からトルコ北西部。
・tephronotus がギリシャ東部からトルコ中央部、イラク北部からシリア。
・tauricus がクリミア半島。
・major がトルコ北東部からコーカサス。
・alpinus がアゼルバイジャン南西部、イラン北部、トルクメニスタン南西部。
・passekii がトルコ南東部とイラン南西部。
北方型を除いてここまでがユーラシアの西側グループである。
このような分布は似た環境に生息するかつての広義シジュウカラ (旧 Parus major) の分布を考えていただけるとわかりやすいだろう。
広義シジュウカラの場合はユーラシア中央部の砂漠や山脈の地理的障壁部分を囲むように北部も南部も分布がほぼ連続しているため後の分類がややこしいことになっている。
エナガ系統の場合は南部 (アフガニスタン付近) で少し連続していない部分があり、ヤマガラモドキ Aegithalos iouschistos Rufous-fronted Bushtit (ネパールなど)、
マユグロヤマガラモドキ Aegithalos bonvaloti Black-browed Bushtit (ミャンマーやベトナム北部から中国四川省)、ギンガオエナガ Aegithalos fuliginosus Sooty Bushtit (中国甘粛省など) などが間に分布する。
これらは互いに近縁で種の扱いは IOC によるが分類学者によって多少の相違があるが、エナガとは遺伝的にも明白な違いがあり、その点は広義シジュウカラの場合と異なる。
広義シジュウカラについては Paeckert et al. (2005) The great tit (Parus major) - a misclassified ring species の論文がある。
さらにズアカエナガ Aegithalos concinnus が同所的にネパールから中国東部、台湾まで分布している関係になる。
ユーラシア東側では上記北方型 caudatus に加えて日本の中央部 (北海道や九州などを除く) trivirgatus (3本の縞のある < tri 3 virgatus 縞のある) 亜種エナガ、virgatus はラテン語 virga (小枝など。現代の英語では尾流雲を指す) に由来。
南部日本の kiusiuensis キュウシュウエナガ、
朝鮮半島と対馬の magnus (偉大な、大きい) チョウセンエナガで、
IOC などの世界のリストに含まれる亜種はここまでである。
[日本の亜種]
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開に含まれている亜種は、亜種エナガ、キュウシュウエナガ、チョウセンエナガに加えて japonicus シマエナガ、及び亜種不明とされる。
世界の主要リストで japonicus を亜種として認めているものはなく、通常は基亜種 caudatus のシノニムとされる。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" でも同じ扱い。また三上 (2016) Birder 30(4): 66-67 に青森におけるシマエナガの分布が示されているが、この記事でも大陸と同亜種の可能性の言及がある。
caudatus にはコウライシマエナガの和名が存在するが、高麗は本来朝鮮半島を指すものなので適切な和名でない感じがする。世界分布を考えると (シマエナガと別亜種とするならば) キタエナガのような名前がふさわしいように思える。シマエナガと同亜種と扱うならば大陸のものも指してシマエナガでも構わないだろう。
wikipedia 日本語版ではシマエナガを基亜種 A. c. caudatus のシノニムとする学説が提唱される以前には、基亜種をコウライシマエナガと呼称する場合もあったと注釈があるが、コウライシマエナガの名称は現在も使われているようである。
wikipedia 日本語版の同上の学説の文献には浅井他 (2016) スズメ目 15 科を対象とした日本鳥類目録改訂第7版の学名と分類の検証 - 第6版および IOC リストとの相違 - が挙げられているが、もちろん海外ではもっと古くからシノニムと扱われてきた。
亜種エナガの記載時学名は Parus (Megisturus) trivirgatus Temminck & Schlegel, 1848 (原記載)。図版。
フランス語名 le mesange a longue queue du Japon (日本の尾の長いカラ)。エナガはヨーロッパでも知られているため une race (現代の亜種に相当) の表現となっているが、当時は亜種の概念や記述方法が確立されていなかったので別種扱いの学名となっている。
Megisturus は mekistos 最も長い < makros 長い + oura 尾 (Gk)。Leach (1816) がエナガ1種を指して Mecistura vagans Leach, 1816 と名付けたが無効名とのこと (The Key to Scientific Names)。GBIF によれば Megisturus Temminck & Schlegel, 1847 と登録されている。
Temminck and Schlegel はおそらく Leach (1816) の属名に対応するものを参考まで記して綴りを訂正した形になっているのだろう。図版学名を見てもノスリの時とは違いおそらく新属に分類する意図までなかったと想像される。
Mecistura の属名用例は結構多くあって、Mecistura vulgaris Blyth, 1840 (参考) など。#ノスリの備考のように当時新属を用いるとともに Linnaeus の学名 (Parus caudatus) を改名したものの一つ。亜種記載などで一定期間用いられた属名だった模様。
その後 Mecistura の属名が無効と判明したものと思われる。Temminck and Schlegel が綴り訂正を試みたが別物と認定されたものかも知れない。
エナガを指す属名は Aegithalos Hermann, 1804 が早かったためにこれらの属名は使われないこととなった。Megisturus の属名は時期も遅く、その後亜種などの記載に使われた形跡は見られない。
Temminck & Schlegel が何を指して "3つの縞" と表現したのか、
il existe toujours, sur le dessus de la tete, de chaque cote, une raie
noire qui commence sur la region des freins pour s'etendre en arriere sur la nuque
頭頂部両側に縞があって後ろでつながっている、を指しているものと考えられる。"3つ" と表現する理屈は今ひとつすっきりしない。ミナミツミに virgatus (Temminck 1822)、カンムリオオタカに trivirgatus (Temminck 1824) を用いるなど、Temminck のお気に入りの表現だったのかも知れない (#アカハラダカの備考 [ハイタカグループの分類] 参照)。タカのように尾の模様を指すとは考えにくい。
Hartert (1910-1922) の時代 p. 385 では trivirgatus の基産地を Japan、p. 383 では Aegithalos caudatus japonica Prozak, 1897 (基産地は北部日本) を基亜種のシノニムと判定していたため日本を基産地とする2亜種が存在する問題が生じなかった。
そのため Hartert も trivirgatus の基産地を Japan とのみ記して、例えば他の種にあるように九州に限定などの指定を行わなかったと考えられる。
状況が複雑になったのは Aegithalos caudatus kiusiuensis Kuroda, 1923 (キュウシュウエナガ、原記載) 基産地 Imazu, Chikuzen Province, northern Kyushu, Japan の亜種が記載されたため。
状況は四国・九州を別亜種とした#アオゲラに似ている。
ここで四国と九州全体を kiusiuensis の分布域とした。trivirgatus は本土 (Hondo) との記述。
もう1亜種 Aegithalos caudatus shimokoriyamae Kuroda, 1923 の記載 (Koryo, Keiki district in Central Korea) があるが、現代の世界のリストには現れない。どちらも trivirgatus とよく似ているとある。
Dement'ev and Gladkov (1954) では日本や朝鮮半島の亜種まで深入りせずそのまま採用している。
この問題を別の形で解決しようとした痕跡があり、Aegithalos caudatus enaga Momiyama, 1927 (参考 1, 2) があり、trivirgatus に代わる亜種名を提唱していたが 参考 1 によればタイプ標本がない? らしく、Kuroda (1932) が trivirgatus のシノニムとして整理したらしい。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では2種で当時の学名で Acredula caudata シマエナガ、Acredula trivirgata エナガ で分布は現在のものに対応している。別種扱いだったため前者が基亜種になるなどの状況は起きなかったよう。
この当時の概念ではシマエナガは大陸のものと同一と判定していたようにも一見思えるが、学名一覧に Aegithalos caudatus japonica Prozak, 1897 が含まれているので、エナガと別種扱いだったため単純に大陸と亜種の違いまで表立って議論する必要がなかったよう。
Prozak の原記載。この記述を見ても独立した概念と捉えていたかかなり微妙な感じ。亜種学名はこの記載で与えられたが Stejneger (1886) が日本のものが色が少し違うと述べている部分は1つ前のページにある。
北海道以外の者にとってはシマエナガが違っていることは目立つが、むしろヨーロッパの研究者にとっては同じようなものに見えていて本質的には同じと考えていたよう。わずかな違いから亜種に値するかを議論していた模様。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire ではそれぞれを英名 Continental Long-tailed Tit (Acredula caudata) と Japanese Long-tailed Tit (Acredula trivirgata) で当時は北海道は大陸のものと考えられ、津軽海峡を超えることは知られていないと記述されている。
ヨーロッパで見られているような両者の中間型があるかも知れないと考えていた。
Linnaeus (1758) は Parus caudatus の学名で記述しており、当時の Parus 属を分割する時に Acredula 属が導入されたよう (中世ラテン語 agredula カラを意味する)。Acredula Koch, 1816 だったが Aegithalos J. Hermann, 1804 が用いた方が早かった (The Key to Scientific Names)。
しかしこの文献では Pipra? europaea の学名が使われており (参考)、Aegithalos は文中に新しい属名を付けるならばとして現れる。
Aegithalos の属記載もこのように若干怪しいものだったが Pipra? europaea Hermann, 1804 を指すものと解釈され、属のタイプ種は現在の Aegithalos caudatus europaeus (エナガの亜種だが、もしエナガが種分割される場合などはこの亜種を含む方がタイプ種となる)。
この文献に気づかれたのが遅れたか、有効な属名な記述かどうかおそらく議論があって Acredula がその後も使われていたものと想像できる。よく知られた学名でも十分複雑な歴史があったことがわかる。Ripra はアリストテレスなどが用いた鳥の名前だが同定されていない。
現在ではアカクロマイコドリ Pipra aureola Crimson-hooded Manakin をタイプ種とする属となっており、こちらはブラジルのポルトガル語 (おそらく現地名由来か) に由来する説もありややこしい。Linnaeus (1758) にも Parus Pipra の記述があり生息地インド (正体不明?)。その2つ先にアカクロマイコドリの記載時学名 Parus aureola がある。
[北海道以外のシマエナガ(?)・大陸個体群との関係]
宮城県内でシマエナガのような個体が観察され、深瀬氏が [kbird:06976 (2024.1.15)] で取り上げられたので、その情報 シマエナガとコウライシマエナガ に基づいて調べてみた。
深瀬氏によると東北で以下の報告があるとのこと。
三上他 (2014) 津軽海峡を越えるシマエナガ Strix 30, 77-86。
鳥潟 (2020) 秋田県における亜種シマエナガ Aegithalos caudatus japonicus の観察記録 Strix 36, 75-80。
前記の 三上 (2016) 青森におけるシマエナガの分布 Birder 30(4): 66-67 も資料として加えられるであろう。
新鞍 (2004) エナガ Aegithalos caudatus の本州・北海道産2亜種における形態的比較
の研究発表があり、長野県産の標本の中には眉斑をもたない個体が1個体含まれていること、北海道産の標本の中には眉斑をもつ個体が含まれていることが明らかになったとのこと。
これらの起源の可能性を調べるための研究で、亜種エナガの白化個体、個体変異、迷鳥のシマエナガ、A. c. caudatus などの別亜種の侵入の可能性を計測値をもとに考察している。
さらに新鞍 (2005) 東アジア産エナガ亜種の形態比較
の研究発表で形態を用いた亜種分類の可能性を調べている。キュウシュウエナガ A. c. kiusiuensis とチョウセンエナガ A. c. magnus は形態的 (主に最長尾羽長) に分離できるとのこと。
眉斑をもつ個体グループでは主に蹠長、自然翼長をもとに韓国産と済州島産のチョウセンエナガが分離できることが示されたが、亜種エナガでは地域差が認められなかったとのこと。
眉斑のない個体ではサハリン以西 (A. c. caudatus に相当) と北海道以東 (A. c. japonicus に相当) がほぼ分けられたとのこと。
これらは形態学的研究であるが、分子系統研究では Paeckert et al.(2010) は Phylogeny of long-tailed tits and allies inferred from mitochondrial and nuclear markers (Aves: Passeriformes, Aegithalidae)
が主に Aegithalidae 属の種の分離とエナガの亜種の一部を調べている。上記のエナガ系統の南部 (中国からヒマラヤ) の系統が非常に近いことが示されており、どの範囲を種と考えるか難しくなっている。この点は細分した場合の Parus minor と Parus cinereus の関係に似ている。
我々に関係の深いアジア北東部ではギンノドエナガが分離できることは示されたが、エナガの亜種の色彩の違いによる明確な遺伝的違いはみられなかった。南北の違いはあまり現れなかった。
ただしサンプリングされたエナガの地域分布は限られていて、ヨーロッパ中央部の南北、東アジアでは大陸4サンプル (ロシア東部が3つで最北がマガダン。韓国1つ)、日本が2つで北海道やサハリンは含まれていない。
これだけのサンプルではあるが、極東ロシアの caudatus と trivirgatus に大きな遺伝的違いがないことを示しているようである。
Paeckert et al.(2010) も色彩による違いが系統の違いに現れない、しかしなぜこの色彩の系統が地理的に分離されているのかを不思議に考えているが、ハシボソガラスとズキンガラスの関係にも似ている可能性を示唆している (#ハシボソガラスの備考参照)。
あくまでヨーロッパの話であるがハシボソガラスとズキンガラスは全ゲノムが解読されるレベルで調べられているものの、色彩を決める遺伝部位以外の差は事実上ない。この程度の違いを種の違いとして認める根拠とできるのか問題となっているが、色彩以外の通常の遺伝部位を使うとまったく違う分類結果が得られることがわかっている。
同じレベルでエナガが調べられるのがいつになるかわからないが、同様の状況は想像できる。その場合ハシボソガラスとズキンガラス同様に通常の遺伝部位を用いてエナガ全体 (もちろんさらにサンプルが必要だが) を現在と異なる少数の分類群にまとめるか、色彩を決める遺伝部位を決定してそれを分子系統分類の根拠にできるか議論をするかとなるだろう。
浅井他 (2016) では「少なくとも Paeckert et al. (2010) ではサンプルに北海道産のエナガが含まれていないため、japonicus を caudatus のシノニムとすることはできない」と述べられているが、
Paeckert et al. (2010)は北海道産の問題というよりも、大陸と日本のエナガを同一分類群ととらえてよいのかのレベルの問題を提起していると読める。調べられた遺伝子もごく少なく結論を急ぐ必要はないだろうが。
Johansson et al. (2016) The phylogenetic position of the world’s smallest
passerine, the Pygmy Bushtit Psaltria exilis
でも解析が行われていて、分子系統樹を見る限りは Paeckert et al. (2010) 同様 caudatus と trivirgatus の系統は混ざっていて分離できていない。
この研究でジャワ島の世界一小さなスズメ目ジャワエナガ、現在の学名で Aegithalos exilis Pygmy Bushtit がエナガ属に属することが判明して移動となった。
以前は Psaltria 属であったが当時は単形属であった。
和名も当時からジャワエナガであった。コンサイス鳥名事典によると全長 8.5 cm でそのうち半分が尾とのこと。
その後 Lukyanchuk et al. (2017)
Geographical Variability of Morphological and Acoustic Signs of the North Populations of the Long Tailed Tit Aegithalos Caudatus (Passeriformes, Aegithalidae) の計測値及び音声研究があり、
比較的高緯度に広く分布する基亜種 caudatus (および北海道のもの) グループの中で japonicus は分けられる可能性があるが他のものは区別できない連続分布を示す結果が得られている。
北海道以外は地理的隔離が不十分なのだろうと説明されている。これには分子遺伝学研究は含まれていないので最終結論はまだ先になりそうである。声の違いは見つけられず、現時点ではあくまで計測値のみで japonicus を亜種と認める部分的証拠がある、と考えておいてよさそうである。
ただし Paeckert et al. (2010) の結果を見る限りではあまり大きな違いは期待できないかも知れない。
カラス類に対して言われるように白黒は何度でも簡単に現れるので色彩は系統の証拠には向かない (つまり遺伝子を調べても色彩に伴う亜種の違いが判定できない可能性が多分にある) 結果になるかも知れない。
分類群によって色彩出現機構、生殖隔離に果たす役割や分類上の扱いが違う可能性があり、エナガのような分類群で分類をどこまで遺伝情報に依存するかなど世の中の趨勢がはっきりするまで現在の亜種名を使っておいてよさそうに思える。
面白いことに Dement'ev and Gladkov (1954) はカムチャツカは別亜種 (kamtschaticus。現在は caudatus に吸収) としているが、北海道とサハリン、千島列島南部は caudatus と trivirgatus の中間型的な扱いにしている。(少なくともロシア領内では) よく調べられていないとしている。
Aegithalos caudatus japonicus Prazak, 1897 はすでに知られていた (基産地は千島) が caudatus のシノニムとして扱われている。
海外の方にとってはシマエナガと大陸のものが同じかどうかに関心があるようで、例えばエナガの声を海外データベース等に登録される場合は亜種まで記載することが望ましい (我々は北海道以外ではシマエナガはほとんど出会えないことを知っていても、海外の方には自明でないようである)。
ただしシマエナガ以外の日本の亜種を野外同定できると思えないので、「外見上シマエナガでない」ことが伝わればよいものと思う。
KJ483368.1 を出発点として (適当に選んだだけ) cyt b を使った GenBank の BLAST を試してみるとエナガとギンノドエナガは分離できないぐらい近い関係で同種としてもよいぐらいなのがわかる。これから予想されるようにエナガ内も非常に近く、ヨーロッパもユーラシア大陸東部も大差なかった。
Johansson et al. (2016) の結果と同様日本の trivirgatus も含まれてしまい特に系統を作らない。
韓国の magnus とフランスの irbii のそれぞれ1検体は多少離れていた程度。
Nishiumi and Kim (2004) "Little Genetic Differences between Korean and Japanese Populations in Songbirds" の論文があるそうで (オンライン版なし)、日本と韓国の遺伝的違いはほとんどないことがすでに示されていたらしい。
[ロシア沿海地方のエナガ]
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the long-tailed tit Aegithalos caudatus (pp. 5495-5521)。
2亜種 caudatus と magnus の写真が紹介されている。後者は少ないとのこと。ほとんどの生態記録は亜種を区別せずに行われている。生態の違いはあってもわずかと考えられ、沿海地方では両亜種の表現型での雑種が普通に見られるためとのこと。
["チバエナガ"]
千葉県北西部に顔の白いエナガが観察されており、"チバエナガ" と呼ばれている。柴田 (2018) Birder 32(11): 32-35 に情報や写真がある。
シマエナガならぬ「チバエナガ」? 眉の薄いエナガの正体 (BuNa 2020) に目撃情報の分布調査結果が示されている。
通称 チバエナガ 動画ではないが写真が複数掲載されている。
wikipedia 日本語版によれば、日本鳥類目録 改訂第7版によれば、シマエナガは千葉県でも記録されているが「偶然飛来したもの」とされているため、日本野鳥の会千葉県支部はこのような個体はシマエナガとは別物という見解を示しているとのこと。
参考までにドイツでは中間型が観察されており、4タイプ (EE, EC, CE, CC) に分類されている。それぞれ2つずつを亜種 caudatus と europaeus に帰属させている (エナガの wikipedia ドイツ語版)。
前述のように本州以南のエナガと大陸のものは遺伝的にほとんど違いがないので、本州以南でシマエナガのような表現型が現れても別に不思議ではないかも。色彩を決める遺伝子頻度の違い程度?
[エナガにさえずりがあるか]
エナガにさえずりがあるか、について松田 (2022) Birder 36(2): 24-25 に考察がある。清棲幸保 (きよすゆきやす) (1965)「日本鳥類大図鑑」にはチリチリチリと可憐な声でさえずると記載。中村登流(1959) エナガの言語的発音表現 野鳥 24(4): 19-25 ではさえずりは持たないが、シジュウカラの小囀りに似たもので頻繁にチルルルルルのような顫音 (trill) が入って長々と歌うような小囀りと記載されているとのこと。
松田氏は xeno-canto も検討されたようだが、確かに song とされている録音の大部分は我々が普通に地鳴きとしているものである。しかし非常に長い「さえずり」のような音声もノルウエーで記録されている (XC362743, XC362773)。キクイタダキのさえずりを思わせる。
シジュウカラのように典型的なさえずりと呼べる声は持たないものの、この長い声はさえずりと分類してもよさそうに思える。
[エナガの "めじろ押し"]
上田 (2022) Birder 36(3): 42-43 で "エナガ団子" ができる理由にチメドリ類との系統的近さの可能性が示唆されている。
現代の分子系統樹 [#鳥類系統樹2024] を参考にしてみると、エナガ科の類縁科はウグイス科とムシクイ科でチメドリ類とはむしろあまり近くない。
系統的なものよりエナガ科で独立に進化した方が考えやすい。
もっともチメドリ類とメジロ科の類縁関係は近いので (メジロは "めじろ押し" をしないそうだが) こちらの方に系統的類似性が現れてもおかしくない。
なおエナガ科とシジュウカラ科はウグイス上科? Sylvioidea には収まるが相当離れており、間にヒバリ科やツバメ科などのあまり似ていない科が存在する。
小型の鳥ではネズミドリ科 (Coliiformes) の方が "めじろ押し" のような行動 (clustering) が知られているが、こちらは乾燥環境での外気温の変動に対する適応と考えられている。cf. McKechnie and Lovegrove (2001) Thermoregulation and the energetic significance of clustering behavior in the white-backed mousebird (Colius colius)。
もっともこの研究も調べやすいところを調べたもので他の役割も果たしているかも知れない。
小型の鳥だがスズメ目とすら縁が遠いので独立に進化できる習性なのだろう。
「動物の世界」2版 24 (日本メール・オーダー 1986) p. 3312 (浦本・樋口) のベニスズメの項目でも「めじろ押し」が紹介されていて個体間距離をとらないとのこと。
[エナガの共同繁殖]
Halliwell et al. (2024) Coordination of care reduces conflict and predation risk in a cooperatively breeding bird
(なかなか難しいので新しい研究の存在のみ紹介。推定されている機能が実際に適応度を増すかどうかを実証研究したもの)
こちらも難しいので所在の紹介のみ: Morinay et al. (2025) Ecological and demographic drivers of kin‐directed cooperation in a social bird: Insights from a long‐term study
(Family first: scientists reveal long-tailed tits' remarkable family bonds (一般向け解説)。
△ スズメ目 PASSERFORMES ムシクイ科 PHYLLOSCOPIDAE ▽
-
キタヤナギムシクイ
- 学名:Phylloscopus trochilus (ピュルロスコプス トゥロキルス) 小さな小鳥の (迅速に動く) 葉の観察者
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:trochilus trokhilos アリストテレスの言及した小型の森林の鳥 (Gk)
- 英名:Willow Warbler
- 備考:
phylloscopus のラテン語 scopus は長母音を含まない。その前の -lo- にアクセントを置く (ピュルロスコプス) と原音に近い。
英語読みでは -sco- にアクセントを置いている。この o を2重母音とするか (scope) 単音とするか (scopula) は英語でも用例によるようで、学術語としてラテン語を重視する場合は単音としている模様。実用上はどちらでもよく英語読みで問題ないだろう。コノハズクの旧種小名、現在のヨーロッパコノハズクの種小名の方は本来は伸ばす発音 (#コノハズク の備考参照)。
trochilus は短母音のみで冒頭にアクセント (トゥロキルス)。
コンサイス鳥名事典では種小名はキクイタダキを表す名称に由来するとあるが確認できず。
The Key to Scientific Names によれば後の著者はミソサザイと同定して用いた (過去の英名 willow-wren にも対応する)。
Wilkinson (1841) は ナイルチドリ Pluvianus aegyptius Egyptian Plover / Crocodile-bird に同定したとのこと。
trochilus の語源は trekho (走る、迅速に動く) + -ilos (鳥の一種を指す)。ナイルチドリとミソサザイの2つの語義が wiktionary に挙げられている (一般向けの解説で森林または水辺の鳥を指すとあるのは知名度が低く具体的な種名を挙げにくいためかも)。
ラテン語 trochilus は小鳥の一種の語義となっている。またハチドリ類の Trochilus 属の由来にもなっている (wiktionary)。
ラテン語になった段階で原意は失われていたかも知れないが、trekho (走る、迅速に動く) の語源を考えるとムシクイ類の敏捷な動きを表したかったものか。地上を走ると解釈するとナイルチドリやミソサザイの同定になるのかも知れない。
インド・ヨーロッパ祖語の *dhregh- (英語の drag に対応する)、アオリスト (Aorist) 相の *drem を通じ、学名に "走る" の意味でしばしば現れる dromos (Gk) も語源に関係があるとのこと。
ヨーロッパからシベリア東部まで広く分布し、越冬地はサハラ以南のアフリカとされている。ヨーロッパではごく当たり前の種類で、次第に下がってゆく複雑なさえずりはヨーロッパの音景によく入っている。
ロシア語名は vesnichika で春の愛小形で春を告げる代表的な種類なのだろう。
英語の Willow Warbler ("ヤナギムシクイ" の意味) は古くからありそうな名前と感じるが、OED によれば意外に新しく 1846 年初出とのこと。英語では willow-wren の方が古くから使われていて 1766 年の Pennant, British Zoology に The willow-wren frequents large moist woods. 用例がある。湿った森には普通に生息するとのこと。
ドイツ語名では総称では Laubsaenger で Laub (葉の集まり) で、leaf warbler の意味に近い。
キタヤナギムシクイを指すドイツ語名は Fitis, Fitislaubsaenger でドイツ語の語源は出ていなかったがオランダ語の fitis は音声を模したものとのこと (wiktionary)。おそらく同じ。
ドイツ語でも Fitis や Zilpzalp (チフチャフ) のように過去は個別に呼ばれていたが分類が進歩して総称を用いる必要が生じラテン名を起源として導入されたものだろう。
英語の leaf warbler も OED によれば 1857 年 Natural History Review で以下に登場する Phillopneuste を指して使われたもので、leaf の部分は属名由来と考えられる。
現在は Phylloscopus 属で、この属はキタヤナギムシクイのみを指して Boie (1826) が設けたもの。同様によく使われた属名に Phillopneuste があり、こちらは Boie (1828) がヨーロッパの複数種 (現在ムシクイ類でないものも含まれていた) に拡張したもの。タイプ種は同じくキタヤナギムシクイであるため属名シノニムとなる。pneustiao は呼吸する < pneo 生きる (Gk) (The Key to Scientific Names)。
Hartert (1910-1922) p. 499 によれば Phillopneuste は 1822 年 Meyer が用いたものとして先取権があると考えられ使われてきたが、これは属記載に該当しないとのこと。Phillopneuste の最初の属記載に該当するものは 1826 年となってシノニムとなった。
Phylloscopus 属を広く扱ったのはこの Hartert で、他に提唱されていた属もまとめた (オオトラツグミを Turdus 属に編入など大規模な編成を行ったのも同じ Hartert)。現在のように Phylloscopus 属を広義に扱う起源とも言える。
ただし Hartert が別属として扱った Cryptolopha, Abrornis は現在は Phylloscopus 属に含まれてさらに広義となっている。
Hartert の次ページ (p. 500) の表にはこの扱いが現れるが C. trochiloides のみ表では別属扱い。本文では Phylloscopus trochiloides の学名となっている。
Hartert の扱いと現在で Phylloscopus 属の範囲が異なることで問題となったであろう種類が Abrornis affinis Moore, 1854 で、Phylloscopus 属に統合されるとキバラムシクイ Phylloscopus affinis と衝突してしまう。
この種には別の記載 Cryptolopha intermedia La Touche, 1898 があったため、Phylloscopus 属に統合された時点で Phylloscopus intermedius の学名となった (wikipedia 英語版から)。和名ではメジロモリムシクイ。
日本産の種ではないためあまり目立たなかったが、分子系統樹が発表されたのが 2018 年で、アジアに広く分布するため系統解析の取り扱い次第で種学名が根本的に変わってしまって混乱もあったかも知れない。
もとをたどれば affinis のようにあまりにありふれた種小名を使ったことに問題があったとも言えるだろう (オオトラツグミの major も同様だが...)。
Phylloscopus 属を分割する議論がもし再燃すればまた問題となるかも知れない。
このように圧倒的知名度のある種類で Willow Warblers の代表種だが、なぜ和名ではヤナギムシクイが別種に使わたのか想像してみると、現在のヤナギムシクイが含まれていた種には多数の英語別名があり、Green willow warbler, Greenish willow warbler のように知名度の高い "キタヤナギムシクイ" の名称をベースとして修飾する形の英名も使われていた (Avibase より)。
これらの一連の種の中で日本で最初に記録されたものに最も単純なヤナギムシクイの訳名を与え、後に記録されたキタヤナギムシクイは英語別名の Northern Willow-Warbler を訳したものを与えたのではないかと想像するが、キタヤナギムシクイの方が第7版以前の記録種でヤナギムシクイ (現在はさらに分離されて学名・英名が変化しているので注意) は第7版で追加と順序が逆になっているようにも見える。
これはヤナギムシクイの方が先に和名が付けられたのだろうか。かつて日本が統治していた地域で先に命名されたのかも知れない。山階鳥類研究所の標本データベースには 1920-1930 年代の大陸の標本が多数あり、すでにヤナギムシクイのラベルがあった。
キタヤナギムシクイは海外標本で 1920 年代中心に標本があるが、キタヤナギムシクイの名称は後から追記されたように見える。当時の日本が統治していた地域でのキタヤナギムシクイの標本はこのコレクションの範囲にはなかった模様。
コンサイス鳥名事典によればキタヤナギムシクイの国内初記録は 1981.9 にカムチャツカで標識されたものが 1981.10 に福岡で死体で発見されたものとのこと。茂田・尾崎 (1999) 標識調査で確認された日本新記録の烏種 (1)。
詳しい前後関係は確認していないが、現在のような名前になっている背景はキタヤナギムシクイがヨーロッパでは最も普通種で英語では Willow Warbler の基本名となり、東洋の種はそれを修飾する名称あるいはグループ名で Willow Warbler を用いてそれぞれの種に修飾語が使われていた名残りかも知れない。
ヤナギムシクイも名称が整理されて Greenish Warbler と短縮され、さらに分割された日本産の種は Two-barred Warbler とかつての英名からは想像できない形となって対応関係がわかりにくくなっている。
Phylloscopus 属のかつての和名はメボソムシクイ属だった。コムシクイ属 Camaroptera の名称が別に存在していた。現在の属和名は知らない。タイプ種はミドリコムシクイ Camaroptera brachyura (過去の種小名 olivacea 由来)。もしかすると今でもコムシクイ属?
和名のムシクイの起源は「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710) に "せんだい蟲くひ" または "鶯むしくひ" が現れ、他に "こむしくひ" の名称もあった。後者が現在のコムシクイと同定可能かどうかは不明。"ムシクイ" の名称は古くからあったもののツツドリがオオムシクイと呼ばれたように必ずしも特定のグループを指して使われたものではなかったと考えられる。
メボソやイイジマメボソのように "ムシクイ" を付けない名称が長く使われていたことから、分類概念に基づいて現在のムシクイ類を指して使われるようになったものと想像できる。おそらくその時点で海外の鳥については英語の warbler を "ムシクイ" と置き換えた形で使われたのだろう。
Phylloscopus 属は分割されていた時期もあり、Phylloscopus 属そのものを指して "ムシクイ" と置き換えたものではなさそうに感じる。
キタヤナギムシクイも過去のヤナギムシクイの種学名も種小名が記述的なものではなかったため英名を訳したと想像できる。
ムジセッカなどの名称も和名の付いた当時は現在とは異なる分類認識であったらしいことを示唆させてくれる。
その後週間アニマルライフ (1973) pp. 3666-3672 のムシクイ (浦本) の記述を見つけた。
ムシクイの名称は山階芳麿博士の提案によるもので、当時は本州産のものがメボソ、北海道から北のものがコムシクイ、さらに北方で繁殖するものがオオムシクイと呼ばれていて (北ほど体が大きい Bergmann-Allen の法則を踏まえた解釈と名称だったのかも。この定義によればかつて使われたコメボソムシクイの名称は間違いではなかったわけだ)、この種全体をよぶ名がなかったためであった。
当時は亜種が重要と考えられていたが、種こそ重要であると種に和名を提案した。当時は理解されず無視されていたとのこと。
この説明も何となくあまり正確でない感じがして、亜種の概念がまだ明確でなかった時代でコムシクイ、オオムシクイ、メボソムシクイともに記載時学名は種扱いだったのでそれぞれに名前があったのでは?
後の時代になって亜種と読み替えられたが、メボソムシクイはコムシクイの亜種扱いの期間が長く、種としての名称が付くのが遅くなったのでは。
(亜種にもすべて和名を付ける習慣は種扱い時代を引き継いでいるのか、それとも亜種にも付けるべきと考えられたのかどうかは知らない。地域によって別の名前を付けることは、おそらく現代の分類概念の考え方とは必ずしも対応していなかったのでは。我々がこのように考察するのも世界の分類を見るようになって以降の話だろう。亜種か否かにかかわらず種としての記載以前からニホンカワウソの名称があったなど)。
それはともかく、浦本氏のこの記事によれば英語で warbler と付くものも「ムシクイ」と訳すようになり、warbler が付かなくても対応するものを「ムシクイ」と訳してしまって複雑になっている旨の記述があった。例えばアメリカムシクイ科 (Parulidae) は旧世界のムシクイ類とは系統的関係がない。
ヨーロッパから入植するに当たって馴染みのムシクイ類がいないため、似たものに warbler と名付けたのがそのまま引き継がれている。
3亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは東シベリアの yakutensis (ヤクーチアの) とされる。
アフリカで越冬するヨーロッパの亜種 acredula と yakutensis の遺伝的違いはあまりなく、渡りの表現型が異なる程度: Lundberg et al. (2018) Genetic differences between willow warbler migratory phenotypes are few and cluster in large haplotype blocks。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では違いの少ない3亜種でシベリアで2亜種 acredula と yakutensis としている。
森岡 (1998) Birder 12(2): 62-65 に1987年10月4日に舳倉島で記録されたキタヤナギムシクイの識別点についての記事がある。
[Phylloscopus 属の分類]
Phylloscopus 属は大きな属であるため少し細分化した系統情報が欲しいところである。
Martens (2010) Systematic notes on Asian birds: 72. A preliminary review of the leaf warbler genera Phylloscopus and Seicercus
による主にアジアのムシクイの分類が参考になるだろう。日本に関係する種類は以下のグループに分けられている (名称は日本で使われている名称がないものは代表となっている種類の和名をそのまま使った)。
この文献を見ていただければ日本のどのムシクイと世界の他の種が近縁であるか関係がつかみやすい。それぞれのグループ、個々の種や亜種についても音声比較も含めて記述されている。
P. [collybita] チフチャフ上種: チフチャフ
P. [fuscatus] ムジセッカ上種: ムジセッカ
P. [affinis] キバラムシクイ上種: キバラムシクイ
P. schwarzi カラフトムジセッカ (特にグループなし)
P. [proregulus] カラフトムシクイ上種: カラフトムシクイ
P. [inornatus] キマユムシクイ species complex: キマユムシクイ
P. [borealis] メボソムシクイ上種: コムシクイ、オオムシクイ、メボソムシクイ (世界的にはコムシクイが標準であるが日本でよく使われている表記に合わせた)
P. [trochilus] キタヤナギムシクイ species complex: キタヤナギムシクイ、ヤナギムシクイ
P. [tenellipes] エゾムシクイ species complex: エゾムシクイ、アムールムシクイ
P. coronatus センダイムシクイ (特にグループなし)
P. ijimae イイジマムシクイ (特にグループなし)
一方 Alstrom et al. (2018) (#ムジセッカの備考参照) ではムシクイ類を9グループに分けている。
日本に関係するものをグループの分岐の古いものから並べると
* モリムシクイ
* キマユムシクイ、カラフトムシクイ
* カラフトムジセッカ、ムジセッカ、キタヤナギムシクイ、キバラムシクイ、チフチャフ
* センダイムシクイ、イイジマムシクイ
* ヤナギムシクイ、エゾムシクイ、アムールムシクイ、メボソムシクイ、オオムシクイ、コムシクイ
となり Martens (2010) とやや異なった結果となっている。それぞれ分子系統樹が出ているので比較してみていただきたい。
Boyd SYLVIOIDEA II では細分化した属名を提案しており納得できる部分もある。
この解説でムシクイ類を Phylloscopus 属と Seicercus 属に大別する概念が紹介されていて Johansson et al. (2007) and Olsson et al. (2005) などで使われていたとのこと (#センダイムシクイの備考も参照)。
Boyd はかつてこの分類を用いていたが、現在では系統を考えて細分化した属の方が適切と考えている。
タカ類、特に広義ハイタカ属の分割で取り上げているように、近年の単系統性を重視した分子系統解析では適応放散を遂げたグループごとに属にまとまるのが適切となる傾向がある。
広義ハイタカ属ではチュウヒ属を残すかハイタカ属に含めるかの至上命題があり、結果的に単系統で適応放散を遂げたグループに自然に分かれる形となったが、現在の Phylloscopus 属には単系統性の問題はないと思われるので属に分けることは必然ではなく好みの問題とも言える。
適応放散を遂げたグループごとにまとめる傾向に従えばムシクイ類の上種に相当する概念が属に相当する可能性がある。
日本に関係するものを Boyd の分類によってまとめると以下のようになる:
Abrornis 属: キマユムシクイ、カラフトムシクイ
Rhadina 属: モリムシクイ
Phylloscopus 属: キタヤナギムシクイ、ムジセッカ、キバラムシクイ、カラフトムジセッカ、チフチャフ
"Pycnosphrys" 属: センダイムシクイ、イイジマムシクイ
Acanthopneuste 属: コムシクイ、オオムシクイ、メボソムシクイ、ヤナギムシクイ、エゾムシクイ、アムールムシクイ
Alstrom et al. (2018) の順序とは最初の2属が異なるが、日本産種については同じ分類となった。
#センダイムシクイの備考にある Seicercus 属がセンダイムシクイなどを含まない理由は旧 Seicercus 系統が2系統に分離されたため、センダイムシクイなどが Seicercus 属から外れる結果となった。
Alstrom et al. (2018) も Boyd の分類について言及しており、いくつかの問題を指摘している。
もしこの分類を採用する場合は "Pycnosphrys" に新しい属名を与える必要があること、あるクレードはまだよく確立されていない (例えば Acanthopneuste 属がどこまでを含むか)。多数の種の属名を変えることはコミュニケーションの障壁にもなる。単系統性の問題がなければ大きな属でも構わないと考える、とのことである。
ここではこの分類が提唱されていることを紹介のみ行っておく。
[ムシクイ類の進化の考察]
Yang et al. (2023) Mitochondrial genome characteristics of six Phylloscopus species and their phylogenetic implication
がいくつかの種のミトコンドリアゲノムを解読し、Phylloscopus 属が大きく2系統に分かれ、その分岐年代を 1106 (95% 信頼区間 753-1477) 万年前と考えている。
我々に関係の深い種類がどちらに入るかを見ておくと、
(系統 I) センダイムシクイ、ヤナギムシクイ、エゾムシクイ、アムールムシクイ、コムシクイ、オオムシクイ
(系統 II) キマユムシクイ、カラフトムシクイ、モリムシクイ、カラフトムジセッカ、ムジセッカ、キタヤナギムシクイ、チフチャフ
となる。それぞれのグループ内でほぼ系統分岐順に並べてある。系統 I, II にもし別属を与えるならばタイプ種のキタヤナギムシクイを含む系統 II が Phylloscopus 属となり、系統 I の属名が変わる可能性がある。つまり日本で繁殖するムシクイ類はすべて Phylloscopus 属から外れる可能性がある。
系統 I の中ではセンダイムシクイが最も古く分岐した系統の一つであることは注目に値する。同じ系統に属する種としてマユグロモリムシクイ Phylloscopus burkii Golden-spectacled Warbler がある (ヒマラヤで繁殖してインドで越冬)。
近い種類にヒマラヤムシクイ Phylloscopus reguloides Blyth's Leaf Warbler がある。旧ヤナギムシクイ (Phylloscopus trochiloides)、エゾムシクイ、コムシクイ上種 (この研究には含まれていないがメボソムシクイはおそらくこの位置) がこの系統から分岐したらしい点も注目される。最後の2つは極東のムシクイ類不在だった地域に進出したものと考えるとよいだろうか。
センダイムシクイとヒマラヤムシクイの分岐年代は 591 万年前程度とのこと。
系統 I はムシクイに対してよく言われる通りヒマラヤや中国などで種分化を遂げたように見え、渡りをするものは越冬地は東南アジアから南アジアとなっている。
この論文でもコムシクイとオオムシクイ、エゾムシクイとアムールムシクイの系統の近さが指摘されている。
日本で繁殖するムシクイ類はすべて系統 I となり、系統 II は比較的まれな冬鳥・旅鳥か迷鳥レベル。
系統 II は少し様相が異なり、カラフトムシクイとキマユムシクイが祖先系統に近いと考えられる。キマユムシクイの越冬地は系統 I と同様だがヨーロッパで多数記録されるように西に分布を広げている。カラフトムシクイの越冬地も同様。次の系統に相当するモリムシクイはヨーロッパの種類となり、アフリカで越冬する。モリムシクイはユーラシア西部に進出して東南アジアと縁が切れたものと想像できる。
次の系統はまた祖先系統に近い分布を持つキバラムシクイと類縁種 + カラフトムジセッカ。
さらに次がユーラシア西部への進展の足がかりとなったと考えられるムジセッカ。越冬地は東南アジアから南アジアでかなり西部に広がっている。ヨーロッパでもよく記録される種類。このムジセッカを含む系統からヨーロッパに分布域を広げたムシクイ類の系統が比較的近年派生したものと考えられるが、チフチャフは亜種間の系統解析からヨーロッパから分布を広げた可能性もある (ムシクイ類全体の系統樹では亜種を分離して調べられたものではないのでヨーロッパの亜種に結果が引きずられ、実際は多系統かも知れない)。
キタヤナギムシクイは越冬地がアフリカとなって、ユーラシア東西の隔離が解消されて東方に分布を広げても忠実に越冬地に戻っていると考えると解釈しやすい。
系統 I, II のどちらが祖先系統になるかは自明ではないが、Martens (2010) や Alstrom et al. (2018) では系統 I, II を逆順と捉えているらしいことがわかる。ヨーロッパから見た観点が入っていると思われ、アジアには最後に到達したと考えているものと想像できるが、上記のような越冬地の関係を考えると系統 I から始まったと考えるのが自然な感じがする。
このように考えるとセンダイムシクイ (おそらくイイジマムシクイも) の祖先系統が最初に分布し、後続のムシクイ類系統がアジアに広がって分布を上書きしたように感じられる。特に系統 I では大陸ではヤナギムシクイおよび類縁種が優勢で、センダイムシクイやエゾムシクイ、アムールムシクイの分布をユーラシア東端に限定させる要因となったものかも知れない。本州以南の平地近くの山で繁殖するムシクイが事実上センダイムシクイ1種のみなのはこのような種分化過程の背景を考えると説明できるかも知れない
ヒタキ類が複数種繁殖するのにムシクイ類が1種のみは少し少なすぎる感じがするが、ヒタキ類の主要繁殖種はすべて別属なのでヒタキ類の方が生態的違いが大きいのが原因かも。
イイジマムシクイのミトコンドリアゲノムがある LC541468.1 ので BLAST を試みてみると、センダイムシクイが系統樹に含まれないので若干不詳な点があるが、イイジマムシクイはマユグロモリムシクイの枝に含まれる。Yang et al. (2023) の結果と合わせると {センダイムシクイ + イイジマムシクイ + マユグロモリムシクイ} がムシクイ類の中で比較的古く分岐した系統と言えるかも知れない。
これはマユグロモリムシクイの音声を聞いてみなければ、と試してみると少なくともチヨチヨの部分はセンダイムシクイに似ている感じがする。見かけはあまり似ていないが系統的には近いのかも。
このように見るとセンダイムシクイは白黒セキレイ類の中のセグロセキレイのような進化的位置づけになるのかも知れない。
簡単にまとめてみると、日本で繁殖するムシクイ類は センダイムシクイ + イイジマムシクイ は多少遺存的なところがあり、他は隔離固有的と考えることができそう。ただしエゾムシクイ、おそらくメボソムシクイもいずれも大陸との分岐は浅い。
不十分な系統樹をもとにした考察なので、将来さらに解析が行われれば描像が変わるかも知れない。
多数の種を含むグループで系統解析がまだ十分に行えていないのでおそらく Phylloscopus 属を分割する議論がまだあまり本格的に出てこないのだろう。分岐年代 1000 万年はスズメ目他系統では属分割に匹敵するレベル。ムシクイ類はそもそも外見が酷似しているので分割の機運が少ないのかも知れない。
ツグミ科とヒタキ科では分岐年代が 1500 万年ぐらいで科に分けている。Boyd の属分割も適切かどうか現時点では不明。
[キタヤナギムシクイの渡りと経路進化]
Sokolovskis et al. (2018) Ten grams and 13,000 km on the wing - route choice in willow warblers Phylloscopus trochilus yakutensis migrating from Far East Russia to East Africa
ヤクーチアからアフリカ東部へジオロケータによるキタヤナギムシクイの渡りの研究。近年有力となっている磁場の傾きと太陽を組み合わせたナビゲーションで現実的な経路を再現できるとのこと。
アフリカで越冬する現在のヨーロッパの亜種 acredula とともに氷河期の東南アジアの refugia から出発して温暖期 (6000-8000 年前) 北東へと分布を広げたが、渡り経路選択にかかわる遺伝メカニズムを大きく変更することなく (亜種間の差があまりなくても) 現在の渡り経路が実現可能の可能性がある。アラスカからアフリカに渡るハシグロヒタキでも同様の機構を考えている。
キタヤナギムシクイは年2回の完全換羽を行うとのこと。「ヨーロッパ産スズメ目の識別ガイド」(Lars Svensson 著、村田健訳 文一総合出版 2011) によれば珍しい換羽様式で、旧北亜区のスズメ目ではチゴモズ、一部のアカモズ、おそらく一部のシベリアセンニュウに限られるとのこと。
Underhill et al. (1992) The biannual primary moult of Willow Warblers Phylloscopus trochilus in Europe and Africa。
アフリカのムナグロハウチワドリ Prinia flavicans Black-chested Prinia (セッカ科) でも知られている [Herremans (2008) Biannual complete moult in the Black-chested Prinia Prinia flavicans]。
[渡りと換羽戦略]
渡り鳥 (主にスズメ目) の換羽戦略の多様性、地理的な違いなどについて: Barta et al. (2008) Optimal moult strategies in migratory birds。繁殖地で換羽するか、越冬地で行うかは何が決めているのか。
関連の深いところのみ取り上げると、北区と新北区では越冬地が乾燥地域 (アフリカの場合) か熱帯雨林か地理的な違いがある。
旧北区では長い渡りをする Phylloscopus 属の一部の種が秋の渡りの前にも換羽を行う理由となり得る。
年2回の完全換羽はしばしば摩耗が速いためとされるが、このモデル計算では秋の渡り前の換羽コストが低い (食物が豊富、エネルギーをあまり消費しない) ことが原因とも言え、年2回の完全換羽は摩耗が速い結果というより原因とも解釈できる (耐久性のある羽よりも換羽コストの低い羽が選択されるなど)。
もっとも個体追跡ができているわけではないので個々の個体が繁殖地・越冬地で毎年換羽を行っているとは限らず、計算上は条件を少し変えるだけでも最適戦略が変わるとのこと。これは主に究極要因を調べる研究。
モデル計算では越冬地で繁殖を行ってもよい結果となるがそのような例は極めてまれでムナジロカワガラス Cinclus cinclus White-throated Dipper のスカンジナビア個体群で知られているのみとのこと。
論理的には個体群の一部が越冬地のみで繁殖しても現実に見られない理由として、越冬地は個体密度が高く競争が激しいためとの古典的解釈がある (Cox 1968)。
一部の渡り鳥は molt-migration と呼ばれる戦略を進化させ、食物資源のピークに合わせて先に南に移動して中継地で換羽を行いその後越冬地へ向かう。push-pull 仮説が提唱されており "push" は夏の終わりの乾燥機構で繁殖地から「押し出され」、"pull" は豊富な食物資源に引き寄せられるの意味。
Contina et al. (2023) Genetic and ecological drivers of molt in a migratory bird
個体群により異なる渡り・換羽パターンを示す北米のゴシキノジコ Passerina ciris Painted Bunting で換羽をコントロールする遺伝領域を全ゲノム解析から判定して遺伝子レベルの機構を探る。換羽地は安定同位体解析で判定。個体群間で遺伝子浸透が妨げられている証拠は見られなかった。
羽毛の形成にかかわる GLI2, CSPG4 遺伝子の変異が関係する可能性があるが実際の遺伝子発現を調べるまでは理論的予測段階とのこと。
-
チフチャフ
- 学名:Phylloscopus collybita (ピュルロスコプス コルリュビタ) 両替のムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:collybita (adj) 両替の (collybus -i (m) 両替 -tus (接尾辞) 〜が備わっている、声がコインを数える音に似ている)
- 英名:Chiffchaff, IOC: Common Chiffchaff
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
collybita はラテン語 collybus は長母音を含まないが語末の -i の変化形は長音となる。i が長母音であれば "コッリュビータ" そうでなければ "コルリュビタ" が自然と思われる。ラテン語の発音の聞けるベージでは長音としていないので後者を採用することにした。
よく現れる亜種の tristis は冒頭が長母音で "トゥリースティス"。
実用的には英語読み (同じ意味の triste のまれな用例の英語があり短音) で問題ないと思われる。
種記載時学名 Sylvia collybita Vieillot, 1817 (原記載) 基産地 'regions septentrionales' of France; restricted to Normandy by Mayaud, 1941, Oiseau, 11, no. spec, p. 87 と判定 (Avibase による)。
ここではフランス語名 Le Pouillot collybite (pouillot 小鳥、現在はムシクイ < poule ニワトリの指小語。小型の意味の語尾はラテン語の pullus, pusilus にならっているとのこと)、Sylvia rufa Bechstein & Meyer と同じものとしていた。
スウェーデンにも分布するのに Linnaeus がなぜ学名を付けていないのか不思議だが、1758 年当時はムシクイは Motacilla 属に含めていてキタヤナギムシクイのみ命名していた。キタヤナギムシクイも基産地が後に英国と指定されたようにムシクイ類の情報が乏しかったのかも知れない。
ユーラシア (中国付近と東南アジアを除く) と越冬地の北部アフリカに広く分布する。世界で6亜種が認められている (IOC)。
Young Guns (2015) Birder 29(2): 46-47 に亜種の解説あり。西ヨーロッパで越冬する "grey chiffchaff" は従来亜種 abietinus (モミの木の意味)と考えられていたが、2012年の DNA 解析によって東シベリア (分布の東端) の亜種 tristis (物憂げななどの意味) と判定される驚きの結果となった
[以前よりそのような見解はあった。de Knijff et al. (2012) Genetic identity of grey chiffchaffs trapped in the Netherlands in autumns of 2009-11]。
地鳴きを指して「物憂げな」と思っていたのだが、tristis の原記載 (後述) では「物憂げな」は緑や黄色味を欠く色彩を指したもののよう。devoid of any greenish or yellowish tinge on the plumage や legs and claws black, or rather dull black (much darker than in Ph. rufus) とあって「怠い色」らしい。
ここで Ph. rufus は基亜種の学名で当時有効と考えられていたもの。
インドハッカの種小名も tristis でやはり色彩を指すものか。
ラテン語 tristis は悲しい、陰鬱ななど全体的にあまりよくない意味があるが語源は不詳とのこと (wiktionary)。派生したフランス語 triste はもっぱら「悲しい」の意味。
亜種 abietinus、fulvescens (現状 IOC 等多くのリストでは認めておらず、tristis に含めている)、tristis が西から東に並び、この3亜種のソノグラムが上記記事に掲載されている。
亜種 fulvescens (黄色く燃えるの意味) と考えられる写真が Birder 2011年3月号に掲載されているとのこと。亜種 tristis の地鳴きは抑揚のない「ヒー」で、他亜種とは異なるため発声があれば識別に有効。tristis は実際には中央アジア、南アジア、中東からヨーロッパで幅広く旅鳥または冬鳥として記録されており、日本に渡来すること自身は驚きではない。
基亜種 collybita と tristis が互いの歌を認識しないとの実験結果があり [Martens (1989) Der sibirische Zilpzalp (Phylloscopus collybita tristis): Gesang und Reaktion einer mitteleuropaeischen Population im Freilandversuch; Schubert (1982)]、これらを別種として扱う考えがある [例えば Brazil (2009) はこの扱い]。
この場合 (現状の亜種の名前も同じだが) は英名 Siberian Chiffchaff となる。fulvescens のとの関係がまだ解決されていないため [この2(亜)種の雑種ともそうでないとも考えられている]、まだ標準的な取り扱いは決まっていない (wikipedia 英語版より)。
この2亜種の記載時学名は
・Ph[ylloscopus] tristis Blyth, 1843 (原記載) 基産地 Calcutta と越冬地記載。
・Ficedula fulvescens Severtsov, 1873 基産地 Turkistan。
中央アジアの調査困難な地域で tristis との分布境界などは今でもおそらくよくわかっていないと想像できる。
Hartert はこれらが同一のタクソンでトルキスタンを通過してカルカッタで越冬すると考えていた。
tristis を別種扱いにしていたリストはいくつかあって、HBW and BirdLife 2016-2024、Sibley and Monroe, Birds of the World Version 2.0 など。
fulvescens の扱いはリスト次第で、tristis を別種にしない場合は Phylloscopus collybita の亜種、する場合は Avibase のように hylloscopus tristis の亜種またはシノニムとなる。
分離してもらっても自分はまったく違和感はないが、和名はおそらく難しいだろう。日本で記録のあるものに従来からの種和名を用いる規則ならば tristis の方がチフチャフで、ヨーロッパのものは例えばヨーロッパチフチャフのような名前が考えられる。
クロウタドリやシジュウカラの場合は海外の種類で長年使われた慣用名を変える程度で済むが、チフチャフの場合は後世の人が「チフチャフなのに "チフチャフ" と鳴かない」と悩む原因になりそうな気がする。オーストラリアでツツドリを「待望のカッコウ」と名付けたのにカッコウと鳴いてくれないのと同じような問題である。
今や世界のリストも統一されつつあり、世界の視点で物事を考える時代なので従来通り日本産かどうかに強くこだわる必要はないように思える。
tristis の音声については The Sound Approach 16: Drab も参照。さえずり、地鳴きのバリエーションとともにソノグラム表示を含めた音源がある。Arnoud and Alan’s Thoughts on Siberian Chiffchaffs も参照。これらはいずれもヨーロッパの音源であるため、日本で聞かれる声のバリエーションと同じかどうかは調べる必要があるだろう。
かつて「チフチャフ」に亜種として含まれていたものから独立種が3種類生じた: イベリアチフチャフ Phylloscopus ibericus (英名 Iberian Chiffchaff)、
カナリーチフチャフ Phylloscopus canariensis (英名 Canary Islands Chiffchaff)、
Phylloscopus sindianus (英名 Eastern Chiffchaff) で、最後のものは Phylloscopus lorenzii (英名 Caucasian Chiffchaff) をさらに分離する考えがある (和名はいずれもまだない)。
Siberian Chiffchaff は暫定現在の位置に置かれているものの、将来別種として扱われる可能性が高いだろう。基亜種 collybita は現地の鳥の声をまったく知らなくてもそれとわかるほどに名前の通りにさえずるが、tristis はそのようにはさえずらない。基亜種はヨーロッパではあまりに普通種だが、おそらく将来は2種に分割されるつもりで両方記録しておくとよい。
日本におけるチフチャフ (tristis) の記録については、
森岡 (1998) Birder 12(4): 66-69 で 1997 年の舳倉島で観察された個体についての考察がある。亜種 tristis と判定し、類似種、亜種の検討が述べられている。
梅垣・大西 (2012) 沖縄県与那国島におけるチフチャフ Phylloscopus collybita tristis の南西諸島初記録と国内における冬期の記録を参照。その後も国内どこかで毎年のように記録があるが、気づきにくさもあって実際にはずっと多くの個体が飛来していると考えられる。
試しに Z73482.1 (cyt b) から BLAST を試してみると類縁配列と認識されないぐらいの違いがある。tristis 以外との類似率は 97% 程度と急に下がるのでやはりいずれは別種扱いになるだろうか。
ミトコンドリアゲノムで見ると上記分離されたイベリアチフチャフ、カナリーチフチャフ、Phylloscopus sindianus は明らかに分離されそれぞれ種扱いが適切であることがわかる。ミトコンドリアゲノムではこれらの3種の方が祖先系統となるが生物地理学を考えると tristis の方が祖先系統の可能性もある
(#キタヤナギムシクイ備考 [ムシクイ類の進化の考察] 参照。モリムシクイが先にヨーロッパに到達しているのでチフチャフもヨーロッパから分布を広げた可能性もある)。
ヨーロッパのチフチャフのデータは多数あるが肝心の tristis のミトコンドリアゲノムがまだ発表されていないので同じ基準で判断することができないのも種分割がまだ行われていない理由の一つだろう。
Doniol-Valcroze (2024) On the taxonomic status of the Siberian Chiffchaff Phylloscopus [collybita] tristis (Phylloscopidae) (別リンク)
tristis を独立種とすることが妥当とする提案。tristis と abietinus は同所的に生息する場所がある。
fulvescens と riphaeus は意味のある亜種ではなくおそらく雑種であろう [Shipilina et al. (2017) Patterns of genetic, phenotypic, and acoustic variation across a chiffchaff (Phylloscopus collybita abietinus/tristis) hybrid zone]。
参考までに Hartert (1910-1922) を見ておくと基亜種が p. 501。ドイツ語名 Zilpzalp または Weiden-Laubvogel。前者の名称は英語同様音声由来らしい。
p. 503 に tristis があり、fulvescens はシノニムとされている。基亜種とさえずりが異なって単調であることも述べられている。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では世界で9亜種 (おそらく3種を分離していない)、シベリアのものは tristis としている。abietinus はザウラル (ウラル山脈の東) の南部に漂行し、tristis の色彩の違いは少ない (翼式で区別できる)。亜種間の雑種は中間的な形質を持つ。
亜種はさえずりで容易に区別できるとある。チフチャフのロシア名は penochka-ten'kovka (前半はムシクイの意味) で、やはり (ヨーロッパの方の) さえずり由来で "ten'-tin'-tyan'-tyun'" などと聞きなしされる。名称の読み方は "チンコフカ" のように聞こえる。
Recuerda et al. (2024) Repeated evolution on oceanic islands: comparative genomics reveals species-specific processes in birds
チフチャフなど4種のヨーロッパ大陸と大西洋の島の個体群の全ゲノム解析による比較。同じように島に定着した種類でも種それぞれ別個のパターンを示している。島環境で適応度を高める性質はポリジーンが関わっており、また種特異的な選択圧が存在すると考えられる。定着した個体数が小さい創始者効果は結論に含まれておらず、大陸との違いは適応の産物と考えている模様。
-
モリムシクイ
- 学名:Phylloscopus sibilatrix (ピュルロスコプス シービラートゥリクス) 虫のように鳴くムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:sibilatrix (合) ピーピーと鳴く鳥 [sibilo (intr) シューシューいう (英訳では whistle, chirp; 備考参照) -trix (接尾辞) 女性の行為者を表す]
- 英名:Wood Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
sibilatrix は語源の sibilo は最初と最後が長母音で、それに従えば "シービラートゥリクス" となる。a を長母音にすればアクセント位置も自然に感じる。
単形種。
種小名の意味の解説は#シマゴマの備考参照。モリムシクイも音程を下げながら震えるようにさえずるので、この特徴を捉えたものと思われる (センニュウ類の属名に Sibilatrix が使われたこともあり、確かにセンニュウ類の声にも似ている)。シマゴマも参照にして学名の和訳を与えた。
なお震えるようなものとは異なるタイプのさえずりもあり、これは地鳴きに似ているとのこと (wikipedia 英語版)。海外音源を聞いてみると、震えるようなさえずりのうち短いものは確かにコマドリに似た印象を受ける。単純な方のさえずりはカラ類に似た印象を受ける。
森岡 (1997) 11(11): 62-65 にモリムシクイの識別の記事がある。
-
ムジセッカ
- 学名:Phylloscopus fuscatus (ピュルロスコプス フスカートゥス) 黒ずんだ色のムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:fuscatus (adj) 黒ずんだ色の (fuscus (adj) 黒ずんだ -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Dusky Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
fuscatus は a が長母音でアクセントもここにある (フスカートゥス)。ちなみに fuscus は長母音でない。
世界で一般的には2亜種、日本で記録されるものは基亜種 fuscatus とされる。
Red'kin and Malykh (2011) Review of northern group of subspecies of the dusky warbler Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842) with description of new taxon from Sakhalin Island
がサハリンの新亜種 sachalinensis (「サハリンの」の意味)を記述した [極東の鳥類38: ロシア極東のムシクイ類 (2020) で和訳が読める]。この文献は亜種の分布図も示されていて参考になるだろう。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に対してパブリックコメントによるこの新亜種が日本を通過している可能性の指摘が行われ、それに対する回答では日本に渡来する亜種は従来通り基亜種 fuscatus とみなすとの結論であった。
計測値が他の亜種と重複し、世界の3つのチェックリストで基亜種のシノニムとしており、音声や DNA 研究がないのでこの亜種を認めるかどうかはまだ検討が必要であるとの見解であった。
シベリア東部からカムチャツカ北部に亜種 homeyeri (ペルシャの鳥類学者 Eugen Ferdinand Edler von Homeyer に由来) Dybowski, 1883 を認める立場もあり [Red'kin and Malykh (2011) も同じ]、この分布は日本の北側に当たっているため同様に日本に渡来している可能性がある。この亜種も sachalinensis 同様に世界の一般的なチェックリストに従えば基亜種のシノニムとされている。
Glushchenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraya: Kratkij Faunisticheskij Obzor" によれば沿海地方で sachalinensis の疑いない標本が記録され、homeyeri は渡り時期に定期的に通っている見解になっている
[極東の鳥類38: ロシア極東のムシクイ類 (2020) に和訳がある]。
日本のチェックリストでは迷鳥の扱いなので sachalinensis は大陸のみを通っているのだろうのとの解釈はちょっと飛躍がありそうである。
Martens et al. (2008)
Intraspecic differentiation of Sino-Himalayan bush-dwelling
Phylloscopus leaf warblers, with description of
two new taxa
(P. fuscatus, P. fuligiventer,
P. afnis, P. armandii,
P. subafnis)
に分子遺伝学と音声研究があり、かつてムジセッカの亜種とされた weigoldi は マユナガムシクイ Phylloscopus fuligiventer Smoky Warbler に属することが明らかになった。Red'kin and Malykh (2011) もこの扱いを受け入れた上でムジセッカを5亜種としている。
Martens et al. (2008) は沿海地方やオホーツク海沿岸のサンプルも用いているがサハリンのものは含まれていない。xeno-canto にはサハリンの音声データがあるので興味ある方は調べてみていただきたい。
Alstrom et al. (2018) Complete species-level phylogeny of the leaf warbler (Aves: Phylloscopidae) radiation にムシクイ類の分子系統樹が示されている。ムジセッカは日本のムシクイ類の中で他とは離れた系統で、カラフトムジセッカとも近縁でないことがわかる。
より単純であるが、DQ174603.1 (cyt b。ロシアのサンプル) から出発して BLAST を試してみると意外にもコムシクイに近縁で、オオムシクイも混ざってくる一方、かつてムジセッカの亜種とされた weigoldi やマユナガムシクイ Phylloscopus fuligiventer は確かに大きく離れている。
ムジセッカのミトコンドリアゲノムも読まれているので試してみるとオオムシクイのサンプルに非常に近いものがある (オオムシクイ OR243068.1 で Collier and Winker が読んだもの) 一方、遠いものもある。そのまま読めば imcomplete lineage sorting が起きているようにも見えるが、系統関係は Alstrom et al. (2018) の結論ほど簡単でないかも知れない。地鳴きは全然違うが...。
データを見るほどオオムシクイとコムシクイの違いが従来言われているより小さく見えてくる [Collier の修士学位論文 (2023) Avian Divergence and Speciation across Beringia Examined using Comparative Mitogenomics を見てもオオムシクイとコムシクイの分離が弱い]。
#ヤブサメの備考に示したように、ムジセッカの地鳴きはヤブサメの地鳴きに似た特異な声に聞こえる (ヤブサメの方が音程は高い)。この声を知っているとムジセッカが案外身近に越冬している (あるいは渡り途中) ことがわかる。やはり葦原や川べりで聞くことが多い (ご存じのように姿を見るのは難しい)。
表現が難しいのだが「突き抜けるような感じ」を受ける。英語で適切な比喩を見たことがあるのだが忘れてしまった。
録音をしておけば客観的証拠にもなるのでおすすめしておきたい。ヤブサメの地鳴きもそうであるが、野外で聞くと録音を聞く場合と少し違う印象を受けることもある (周波数範囲が広いため、機材や再生時の周波数特性にもよると思う)。機会があればぜひ野外で体験してみていただきたい。
「野鳥だより・筑豊」では録音で声による確認も報告されているので釈迦に説法の感じがしないでもないが、音声をご存じでない方もおられると思われるので (自分の身近にはほとんどいない) 注意して聞いていただくのがよい種類として紹介しておく。
複雑な声でさえずり、聞き慣れないさえずりから姿が確認されたケースもある。ムジセッカ (バードリサーチ) にさえずりが収録されている (滋賀県琵琶湖 2014-04-23 村尾嘉彦)。
宇山 (1992) Birder 6(8): 62-23 にムジセッカとカラフトムジセッカの越冬地についての記事がある。与那国島、西表島などを調査した結果で、ムジセッカは春秋の渡りの時期には決して珍しい鳥ではないと記されている (この点は南西諸島でなくても同感する。越冬時期でも同様)。
[営巣習性]
ムシクイ類の中でも地上または近くに営巣するメボソムシクイ上種と近縁の可能性があるので、ムジセッカはどのような場所に営巣するのか少し調べてみた。
Dement'ev and Gladkov (1954) によればサハリンでは地上低い小枝を用い、地上近くであったり 70 cm 以下の低いところとのこと。
地上営巣に一歩近づいている感じがする。日本のメボソムシクイでは地上の窪みを用いると成書にある。Dement'ev and Gladkov (1954) では (現在の分類で) オオムシクイも地上近くの低いところに草に紛れて目立たないように造るとのこと。
ムジセッカ系統の中で樹木の少ない、あるいは一層低い環境に適応したのがメボソムシクイ上種かとふと感じてしまったのだが、エゾムシクイやセンダイムシクイも崖の窪みなどに造るので上記の系統的推測は怪しいかも知れない。
ただオオムシクイの渡りがなぜそれほど遅いのかはある程度説明できそうな感じがする。地上近くに十分に草が茂って巣の場所が目立なくなるまでに渡来してもあまり意味がないのだろう。カムチャツカの春の到来の遅さを反映しているのだろうか。カムチャツカで繁殖するスズメ目はそれほど多くなくそれだけ条件が厳しいのだろう。
もっと高いところに造巣してもよさそうな感じがするが、余計に危険であったり厳しい気象条件ではすぐ落ちてしまうのかも知れない。
ハクセキレイの営巣環境はもっと条件が緩そうでカムチャツカで繁殖することは難しくなさそうだが、エゾビタキの場合はどうなのだろうと思って見てみると Dement'ev and Gladkov (1954) では繁殖生態不明とある。Peklo (1987) "Mukholovki Fauny SSSR" (ソ連の動物相のヒタキ) では Nazarenko (1971) の観察が紹介されていて、地上 1.8-15 m とのこと。ただしカムチャツカの事例は調べられていない。この程度の数字であればサメビタキに似ている。
森林性であっても地上低く営巣するのはムシクイ類全体の性質なのだろうか。
-
キバラムシクイ (第8版で検討種)
- 学名:Phylloscopus affinis (ピュルロスコプス アフフィーニス) (キタヤナギムシクイに?)類似したムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:affinis (adj) 隣の、姻戚関係の
- 英名:Tickell's Leaf Warbler (英国鳥類学者 Samuel Tickell 由来)
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
affinis は -fi- の i が長母音でアクセントもここにある (アフフィーニス)。ad + finis が語源。-ff- を単音で、i を短母音にする英語読みでも実用上問題ないだろう。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。
命名時の学名は Motacilla offinis (Tickell 1833) であった。offinis は affinis の誤りであったとのこと。
Olive Willow Wren に "似ている" (affinis の由来) とのことだが、これは現キタヤナギムシクイ Phylloscopus trochilus (Willow Wren の別名があった) のことかと推定されている (The Key to Scientific Names)。
Hartert (1910-1922) p. 525 によれば Abrornis xanthogaster Hodgson, 1844 (参考。The zoological miscellany 大英博物館に収めた標本のリスト) 産地ネパールの記載があったが、記述がないため Hartert は無効名と判定。
Round et al. (2021) Non-breeding season records of the Alpine Leaf Warbler Phylloscopus occisinensis。Hodgson (1844) の記載したものと現代の Phylloscopus affinis は同一かなども調べる必要があると記している。
和名は Abrornis xanthogaster の学名と一致していて、一時はこの学名に相当する英名も存在したのかも。Yelllow-bellied Warbler の英名を持つ種は別にある (マミジロムシクイ Abroscopus superciliaris。この和名は学名由来らしい) ので使われなくなったなど (?) も考えられる。
キバラムシクイに相当する名称は和名由来かも知れないが中国語にもある。Avibase ではミヤマムジセッカの別名も登場する。
[分類上の問題点]
梅垣 (2023) Birder 37(6): 29 によれば、この種と Alpine Leaf Warbler Phylloscopus occisinensis (中国のチベット-青海高原から四川、甘粛で繁殖) はかつて別種とされたが、過去の絶滅個体群との交雑の結果と考えられ、現在では occisinensis を Phylloscopus affinis の亜種とすることが多いとのこと。
Liu et al. (2019) Phylogenetic relationship and characterization of the complete chloroplast genome of the alpine leaf-warbler in Qinghai-Tibet Plateau で (P.) occisinensis のミトコンドリア DNA を解読。
Zhang et al. (2019) "Ghost Introgression" As a Cause of Deep Mitochondrial Divergence in a Bird Species Complex
が上記に記載のある過去の絶滅個体群との交雑帯の変遷などを議論した論文。遺伝的には (一見) 距離があるが、形態や音声面では違いがないとのこと。絶滅個体群にあった遺伝情報がミトコンドリアにのみ残り、ミトコンドリア DNA だけを見るとにはあたかも別種のように考えられてきたが (この現象は deep mitochondrial divergence DMD と呼ばれており、想像以上によくあるが見逃されているだけではと指摘されている)、核 DNA を見ると種レベルの差はないとの解釈である。
この論文の Fig. 2 で左にミトコンドリア遺伝子、右に核遺伝子を用いた系統樹がある。左では別種に見えるものが右では同種に見える。
現在 IOC 等の世界のリストでもその扱いだが、多くのリストで比較的最近 (2021年ごろ) まで別種として扱われていた。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種扱いに移行。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。上記 occisinensis を含め3亜種あるが(IOC)、亜種不明の扱い。
森岡 (1997) Birder 11(10): 62-65 に舳倉島で1996年5月19-20日に記録された個体の検討がある。この記事ではオリーブムシクイ Phylloscopus griseolus 英名 Sulphur-bellied Warbler、バフイロムシクイ Phylloscopus subaffinis 英名 Buff-throated Warbler との識別について、またキバラムシクイの分類の変遷について述べられている。
-
カラフトムジセッカ
- 学名:Phylloscopus schwarzi (ピュルロスコプス スクワルズィ) シュヴァルツのムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:schwarzi (属) 帝政ロシア時代のドイツ天文学者でアムール川に至るまでの探検・天文測量を行った Peter Carl Ludwig Schwarz の。この地図は後のシベリア横断鉄道計画に生かされることとなった。
- 英名:Radde's Warbler (Schwarz 門下の博物学者・探検家の Gustav Radde が由来)
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
schwarzi は原音を優先することも可能でその場合は "シュヴァルツィ" となる。schwarz = ドイツ語で "黒"。
wikipedia ロシア語版を参考にすると活躍したロシアでもドイツ語と同じ読みとなっていたので原音に曖昧さはない。
記載時学名 Sylvia (Phyllopneuste) Schwarzi Radde, 1863 (原記載) 基産地 Tarei Nor and Bureya Mountains, Transbaikalia and Amurland (Avibase による)。
この時代には Sylvia 属 (当時は非常に広義だった) はすでに多数記載されていたため、師に授ける人名を用いて既存の種小名と重複する可能性を避けたものと想像できる。英名は記載者から。
Peter Carl Ludwig Schwarz (1822-1894) で、Radde の記載では天文学者となっているが、分野的には測地学者の方がふさわしそう。the Imperial Russian Geographical Society やメダルをもらっており、測地学の業績について Demidov Prize を授けられている (wikipedia 英語版より)。
天文学でも (古い学年の) 位置天文学または実用天文学の分野と考えてよさそう。
NASA ADS を検索すると古い人物にも関わらず意外に見ることができて 1871-1893 年の著作4件がヒットする。
単形種。さえずりについて#コルリの備考参照。地鳴きはムジセッカに似ておらず、もっと低く太い声。
コンサイス鳥名事典によれば日本初記録は 1985.10 飛島とのこと。山階鳥類研究所の標本データベースによれば古い時代の樺太や朝鮮半島や満州での標本は多くある。
宇山 (1992) Birder 6(8): 62-23 にムジセッカとカラフトムジセッカの越冬地についての記事がある。与那国島、西表島などを調査した結果で、カラフトムジセッカはオリーブ色から褐色と体色に著しい変化があるとのこと。典型的な地鳴きの他にも、チュルル...などの声をよく聞いたとのこと。
海外データベースでは典型的な地鳴き以外の地鳴きは示されておらず、この声はさえずりまたはぐぜりの一種かも知れない。
大西 (2009) Birder 24(3): 60 によれば八重山諸島のカラフトムジセッカの越冬記録の多くはチョウセンウグイス Horornis canturians borealis (新しい学名で記載する) の誤認の可能性が高いとのこと。さえずりがコルリに似た点があることはこの文献でも指摘されている。
The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声)
03:48 No bol'she vsego ptits - v pojmennykh debryakh (そしていちばんたくさん鳥がいるのは水辺の草地の木です)。Zdes' mozhno ushlyshat' gortannye karkan'ya bol'sheklyuvykh voron, nezhnyj peresvist taezhnoj ovsyanki, trel' tolstoklyuvoj penochki (ここではハシブトガラスの喉音でかあかあ鳴く声、シロハラホオジロのやさしい鳴き交わし、カラフトムジセッカのトリルが聞かれるでしょう)。
(聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
-
カラフトムシクイ
- 学名:Phylloscopus proregulus (ピュルロスコプス プローレーグルス) キクイタダキのようなムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:proregulus (合) キクイタダキに似た (pro- (接頭辞) 〜のまえの regulus キクイタダキ)。頭に中央線がありキクイタダキとも似ている (コンサイス鳥名事典)
- 英名:Pallas's Warbler (プロイセンの生物学者 Peter Simon Pallas に由来)
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
proregulus は regulus 部分は#キクイタダキ参照。pro- は単音、長音のいずれもあるが子音の前では長音となる模様。これらを採用して "プローレーグルス" とした。アクセントはこのままで長音としない英語読みでも実用上問題ないだろう。
単形種。Andy Stoddart によるモノグラフ Siberia's Sprite - A History of Fascination and Desire (2016) が出版されている。
繁殖域からは遠いが、ヨーロッパでは比較的頻度の高い迷鳥で人気も高い。音声もヨーロッパのバーダーの間でよく知られている。かつて使われた属名については#キマユムシクイの備考参照。
コンサイス鳥名事典によれば日本初記録は 1967.4 山口県角島とのこと。山階鳥類研究所の標本データベスでは古い時代の樺太や朝鮮半島などの標本は多数ある。
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Pallas’s leaf warbler Phylloscopus proregulus (pp. 4513-4533)
ロシア沿海地方での繁殖の論文。
-
キマユムシクイ
-
コムシクイ
- 学名:Phylloscopus borealis (ピュルロスコプス ボレアーリス) 北のムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:borealis (adj) 北の
- 英名:Arctic Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
borealis は a が長母音ででアクセントもここにある (ボレアーリス)。
種記載時学名 Phyllopneuste borealis Blasius, 1858 (原記載) 基産地 Sea of Okhotsk, lat. 59° 38' N., long. 147° 30' E (Avibase による)。
意外にもヨーロッパでなく我々の近くで記載されていた。
Hartert (1910-1922) では p. 517。
Blasius (1858) 当時比較対象とされた種に Phyllopneuste javanica (Horsf.) がありこれはジャワ島。原記載は Sylvia javanica Horsfield, 1821 ではないかと想像されるが (参考) これは現在はジャワハイノドメジロ Heleia javanica Javan Grey-throated White-eye を指す。
Phyllopneuste javanica (Horsf.) がどうなったのかよくわからないが、borealis が用いられた背景はジャワ島に対して北方の意味ではないかと想像する。少なくともヨーロッパ北部の意味ではなかった。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。よく知られているように (日本の分類では) メボソムシクイから分離された。
北米で従来記述された亜種 kennicotti (アメリカコムシクイ) は現在はコムシクイのシノニムとされる。記載時学名 Phyllopneuste kennicotti Baird, 1869 基産地アラスカ。
Hartert (1910-1922) がこのシノニム扱いを行っているが ?? を付けていた。
Ridgway (1904) は亜種 Ph. borealis kennicotti 扱いとしたことも述べられている。
[メボソムシクイ (コムシクイ) 上種の分類]
春の遅い時期に渡るメボソムシクイと違った声のムシクイが長らくこの種 (当時は亜種) と誤解されていて、亜種コメボソムシクイと呼ばれていた。旧称コメボソムシクイの大部分は現在はオオムシクイに相当すると考えられる (少なくとも自身は現在のオオムシクイをコメボソムシクイと呼んでいた)。日本で観察される数はオオムシクイよりコムシクイの方がはるかに少ない。
ユーラシア北部に広く分布し、分布域はアラスカまで広がっているが、知られている越冬地は東南アジアのみで、越冬時は [メボソムシクイ上種 (英語ではコムシクイ上種となっていずれの名称も使われる) の故郷らしい] ここに戻ってくると考えられている。
現在の狭義コムシクイは通常単形種とされるが、Martens (2010) (#キタヤナギムシクイの備考参照) によれば地域によるデータ不足やさまざまな問題があってまだ見解の一致に至っていない (またコムシクイ類は標本での変色が早く、色彩による解析を難しくしているらしい)。
Martens (2010) は Saitoh et al. (2006、ポスター発表) の結果を支持し、コムシクイ、オオムシクイ、メボソムシクイへの分類が適切であると考えている。Saitoh et al. (2006) にはそれ以上言及されていないが、チトクローム b 遺伝子で 2.3% の異なりのある第4のクレードがある。
広義 (従来の) コムシクイの亜種 hylebata (hule 森林地 -bates 〜を歩むもの) の扱いの問題もある。Martens (2010) はこの亜種に相当すると考えられる個体のさえずりはフィンランドのコムシクイのものと区別が付かないとしている (ただし判定は場所のみによるもので個体数も1例のみ)。
ロシア研究者の見解は異なっており、#オオムシクイの備考参照。
関連する一連の研究は
Reeves et al. (2008)
Mitochondrial DNA data imply a stepping-stone colonization of Beringia by arctic warbler Phylloscopus borealis
ロシアとアラスカの個体のミトコンドリア DNA 解析で、現在の狭義コムシクイとカムチャツカ、サハリンの個体群が分離できること、狭義コムシクイが旧北区東端からアラスカに分布を広げたことが示唆された。日本のサンプルは扱われていない。
カムチャツカ、サハリンの個体群はこれまでの分類に従って Ph. b. xanthodryas (当時は日本と同じ亜種と考えられていた) とされており、これらは種相当の違いがことが示された。過去に現在の狭義コムシクイに対して提唱されていた亜種は支持されない結果となった。
ベーリング海峡 (ユーラシアとアラスカの間) よりもむしろベーリンギア西方 (レナ川-コリマ山脈障壁) が遺伝子交流を妨げている結果になった。
Saitoh et al. (2008)
Morphological differences among populations of the Arctic Warbler with some intraspecific taxonomic notes に分子系統に基づき判定されたグループの形態学による研究、
Saitoh et al. (2010) Old divergences in a boreal bird supports long-term survival through the Ice Ages に分子系統樹が出ている。
Alstrom et al. (2011) The Arctic Warbler Phylloscopus borealis - three anciently separated cryptic species revealed に音声比較もあり、この文献はよく使われている。
日本語で齋藤他 (2012) メボソムシクイ Phylloscopus borealis (Blasius) の分類の再検討:3つの独立種を含むメボソムシクイ上種について の総説がありさまざまな情報が詳しく述べられている。
専門家による解説で過去の経緯も詳しいのでぜひお読みいただきたい。
齋藤他 (2014) メボソムシクイ上種 種の外部形質を用いた識別方法。
齋藤他 (2012) によれば日本鳥類目録では 1922 年の初版から一貫してメボソムシクイ (かつてはメボソの名称も用いられた) の学名に Phylloscopus borealis xanthodryas が用いられてきた。改訂第7版以前の種学名は Phylloscopus borealis であった。
オオムシクイとの地鳴きの区別は#オオムシクイの備考参照。
[ドイツ語・ロシア語の名称]
ドイツ語名では各種ムシクイ類のうちコムシクイを Wanderlaubsenger と渡りムシクイのような名前にしている。典型的な渡りのムシクイなのだろうか。
ロシア語ではムシクイ類を総称して penochka (アクセントは最初でピェナチカのような発音になる) と呼ぶ。
ロシア語で歌が pesnya なので関係してそうな感じがするが無関係らしい。ムシクイ類の方の語源ははっきりしないらしいが、penka 古北ドイツ語でフィンチの意味からきていると考えられる (Kolyada et al. 2016)。
コムシクイ類を総称して talovka と呼ぶが、典型的な生息場所であるヤナギ tal'nik の木立から来ていると考えられる。単純に talovka と呼ぶことが多く、カムチャツカの talovka ならばオオムシクイと場所を考えて解釈する必要がある。
[ベイズ状態空間モデルを用いた近年の渡り経路推定について]
Adams et al. (2022) The first documentation of the Nearctic-Paleotropical migratory route of the Arctic Warbler
にジオロケータを用いたアラスカのコムシクイの渡りルートの研究がある。春と秋で渡りルートが異なる可能性が示唆されるが、越冬地がほとんど海 (陸地はパラウ島) で海上移動ルートが長い例があるなど、信頼できる結論を得るためにはもう少し事例が必要そうに見える。
この論文では Bayesian state-space model (ベイズ状態空間モデル) を用いていて、(測定値がしっかり得られていれば何の問題もないが) 測定値がなくても間の挙動をそれとなく推定できてしまう。
例えば「物理のためのデータサイエンス入門」(植村誠 2023 講談社) 第7章にデータがない部分がどのように推定されるかなどの実例がある。
このようにモデルの仮定がそのまま表れている部分がある可能性があるので経路を読むには注意が必要かも知れない。
越冬場所の経度とだいたいの緯度を明らかにした、50-60° 以北の渡り経路をおよび渡り途中の経度 (その経度に陸地があるのは日本なので多分日本を通ったのでは、ぐらいの議論になる) を明らかにしたことがこの論文の主要成果と言えると解釈している。
同様の手法を用いている論文に#ノビタキの備考にある Yamaura et al. (2016) があり、解説はこちらの方が詳しい (上記論文の計算もこの論文と同じように行われていると推測した)。例えば海岸線から離れた解を得る確率を下げるなどの事前分布 (prior distribution) が置かれている。
このように「ベイズ」を用いたものは原理的には恣意的な仮定も導入できる。それが生物学・生態学的に適切かどうかは実際にデータを扱っていて種の生態を把握している専門家でないと判断できないかも知れない (このような恣意性ゆえに「ベイズ」というだけで拒否される時代もあったが、最近はほぼ受け入れられている印象を受ける。また現代の生物学は系統推定などベイズなしには成り立たない。
事前分布や状態空間モデルが適切かどうかは査読者が必ずしも把握しているとは限らないので、査読論文なので信頼度が高いとは必ずしも言い切れない)。
結果はノビタキの方が信頼性が高そうに思えるが、最近の研究では「生の結果」をそのまま見せるのではなく高度な技法で解析されたものもあるので、結果を見る時にはこのような仮定にも注意を払う必要があるだろう。解析コードも公開されていて論文に記述されているが分野専門家でないともはやついて行けないのかも知れないが。
-
オオムシクイ
- 学名:Phylloscopus examinandus (ピュルロスコプス エクサーミナンドゥス) 調査されたムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:examinandus (adj) 検討された、調べられた
- 英名:Kamchatka Leaf Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
examinandus は最初の a が長母音で、アクセントは -nan- にある (エクサーミナンドゥス)。長音にしない英語式でも実用上問題ないだろう。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
原記載 (Stresemann, 1913)。
Hartert がインドネシアのスンダ列島で越冬する (広義) コムシクイに2つの型があることを示唆していた (参考) ので調査した (untersuchten) 結果見つかったのが種小名の語源のよう。untersuchen の辞書訳は調べる、調査する、研究する、分析するなど。
いずれも当時の学名で記すが、バリ島を含むスンダ列島のこの地域で典型的なコムシクイ (Ph. b. borealis) よりも大きく色調も異なるものを認め、メボソムシクイ (Ph. b. xanthodryas) とも色調や風切りの長さなどで区別できるとのことで新亜種として記載したもの。越冬地 (バリ島) が基産地であるため繁殖地の亜種の同定を難しいものにする結果となった。
Hartert (1910-1922) p. 2139 にこの新記載の記述あり。繁殖地は不明とある。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではメボソムシクイとオオムシクイの繁殖地分布が現在とは逆になっている。以下 Dement'ev and Gladkov (1954) の説明から抜粋要約する。
Phylloscopus borealis var. xanthodryas Swinhoe, 1863 と記載されているムシクイ (#メボソムシクイの備考参照) はカムチャツカでは早くから知られていて Pleske (1899) がこの名称で記録しているためそのように呼ばざるを得ない。
しかしカムチャツカの亜種は最大のものではなく最大亜種は日本のメボソムシクイ。バリ島とスンバ島で Stresemann が採集した大きな亜種は日本のものかも知れない。そのため日本のメボソムシクイに Ph. b. examinandus Stresemann を与えざるを得ないとの推論であった。
Alstrom et al. (2011)
The Arctic Warbler Phylloscopus borealis - three
anciently separated cryptic species revealed
に基づき、名称に関するいくつかの問題点を紹介しておく。
この論文では xanthodryas Swinhoe, 1863 の syntype (総模式標本: 正基準標本および従基準標本全て) の標本の3つのうち2つの DNA 配列は調査している。残り1つについても計測値を得ている。
xanthodryas と想定された syntype 標本の模式標本としてのふさわしさは検証の必要があることが指摘されているが、これらの計測値と本州他の個体の計測値は対応しており、Swinhoe (1863) の記述ともっともよく対応するのが本州の個体である。その点で日本の本州などで繁殖する個体群を xanthodryas と呼ぶのは適切であろうとのこと。
広義メボソムシクイ Phylloscopus borealis には他の亜種も提唱されていて、hylebata Swinhoe, 1861 ← 1860となっている文献も多い (原記載) が
xanthodryas と同じ場所で (渡り途中) 2年前に記載されている。タイプ標本の可能性のあるものが存在するが博物館にそのようには登録されていない。
hylebata のタイプ標本は調べていない。
sylvicultrix Swinhoe, 1860 も同じ場所で記載されているが標本が見当たらない
[Glushchenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraya: Kratkij Faunisticheskij Obzor" (沿海地方の鳥: 簡潔な動物相の一覧) によればこの亜種は基亜種 Ph. b. borealis のシノニムとしている。この位置づけであれば sylvicultrix については先取権の問題は発生しない]。
Swinhoe は個人所蔵の標本を多数持っていたが、それらは博物館に残っておらず、初記載以降の出版物での記述もない。
そのため命名上の不定性が残るが本州・四国・九州の個体群に xanthodryas を、カムチャツカ・サハリン・北海道の個体群に examinandus を与えることにした。
Ticehurst (1938) と異なるのは北海道と千島列島の個体群を examinandus とした点で、四国・九州で繁殖することは Ticehurst (1938) の時代には知られていなかった。
Dement'ev and Gladkov (1954) は hylebata をロシア名で南のコムシクイの名前で呼んでおり (基亜種を北方型としている)、transbaicalicus Portenko, 1939 はシノニムとしている。Dement'ev and Gladkov (1954) はサハリンはこの亜種としているが前述のようにカムチャツカは別亜種となっている。
talovka Portenko, 1939 (基産地はシベリア西部の北ウラルの Sertyn'ya) を borealis のシノニムとしている。
hylebata の調査や未発見情報次第ではこれが現在のメボソムシクイやオオムシクイのどちらかと同一と判明して hylebata に先取権が発生する可能性が皆無ではない、というところだろうか。Alstrom et al. (2011) では3種が分離できることを示すことが主目的なので歴史的なところは追求できる範囲にとどめ、手に入る情報の範囲で最も考えられる名称を与えたということだろう。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" ではシベリアのコムシクイは2亜種の扱いで transbaicalica を認めている (語尾はなぜか -a がしばしば使われるが hylebata でも同様。
ロシア名由来の talovka の語尾に合わせているのかも知れない。この場合はロシア名がそのまま用いられているので語形変化しない?)。
シベリア南東部でバイカル湖以東で上面がより緑っぽく下面はより黄色いとある。
かつての亜種名も現役で使われているのだろう (研究が不十分な地域で、将来見直しの結果復活の可能性のある地域で記載された亜種として記録に用いておく意義はあるだろう)。
Alstrom et al. (2011) の時期には地域的な網羅性や音声データは十分でなく将来の研究を待つ形になっていた。
例えば採集された越冬地での地鳴きが本当に想定されている分類と対応するかなど。
その後の情報によって変わることもあるかも知れない。
[hylebata の位置づけの議論]
Glushchenko et al. (2016) では Alstrom et al. (2011) や Saitoh et al. もふまえた上でロシア東部の同定を検討している。狭義基亜種 borealis (西の talovka、transbaicalica と区別して扱った場合) は沿海地方では渡りの時期のみ見られる。
この亜種はオホーツク海沿岸の山地、コリマ山脈とコリャースク山脈、アナディリ盆地で繁殖する。
最も北の個体群 (アナディリ盆地) は上面がより暗色で下面に黄色みがある。Portenko (1973) はこの個体群を hylebata と考えたが、
Swinhoe は sylvicultrix (= borealis?) よりもずっと大きいと記載しているのでこれは明らかな誤りである (アナディリ盆地の標本は borealis の最も南部の標本と大きさで区別できない)。
標本を調査するとこの型 (亜種 borealis) のものは沿海地方では渡り時期に数で優勢で5月下旬から6月上旬の標本が得られている。
狭義基亜種 borealis に比べてゆっくりした歌のグループ (近年 examinandus とされるもの) はシホテ・アリニで繁殖し、渡りの時期は沿海地方全域で見られるとしている。
この地域、ニージニー・プリアムール、サハリン、千島列島南部のものは borealis より大きいがカムチャツカや千島列島北部のものはより大きく嘴が長い。
ゆっくりした歌のグループは地域的に2型があることになる。
カムチャツカ型はこれまでほぼすべての文献で xanthodryas とされてきたが (Portenko 1938, 1939, 1954, 1973; Ptushenko 1954; Vaurie 1959; Kishchenskiij 1980; Howard and Moore 1984; Stepanyan 2003; Dikinson 2003; Koblik et al. 2006; Nechaev and Gamova 2009 他)、これは誤りであるとわかった。
これは xanthodryas と examinandus がいずれも大型で明るい色である点がよく似ており、タイプ標本が越冬地で採集されて異なる博物館にあることによる。多くの分類ではシノニムとされ、先に命名された Phyllopneuste xanthodryas Swinhoe, 1863 が優先されることになったため。
タイプ標本の DNA 分析ができるようになってようやく決着が付いた (Alstrom et al. 2011)。
ゆっくりした歌の南部グループ (より小型で千島列島南部、北海道、サハリン、プリアムール、沿海地方のものは大部分の文献で Ph. b. hylebata Swinhoe, 1860 としている (Portenko 1938, 1939, 1954, 1973; Ptushenko 1954; Vaurie 1959; Howard and Moore 1984; Koblik et al. 2006; Nechaev and Gamova 2009 他; 日本の過去のチェックリストは検討していない?)。
(記載時の) diagnosis と各地の標本を分析した結果、この解釈は適切であると考える。このグループは先に命名された hylebata を用いるのが適切で、
その場合は極東と北海道を Ph. hylebata hylebata、カムチャツカ南部から千島列島北部を Ph. hylebata examinandus となる可能性を挙げている。
これはあくまで Ph. hylebata と記載されたタイプ標本の所在が明らかになって DNA も調べられた後のことである。この段階では Ph. hylebata が種に値するかを述べることはできないと書いている。
特にこのグループと borealis とを分離できる有望な形態学的特徴を得ることができていないため両者の分布の関係を調査することができない点を挙げている。
速い歌のタイプとゆっくりした歌のタイプの分布は明らかに混在している。速い歌のタイプの中にゆっくりした歌のタイプが存在する最も西の地域はザバイカルの Khentei-Daur Highlands (Khenten-Chikojckoe nagor'e モンゴルとバイカル湖間のやや東側 Nazarenko 1978)、南ヤクーチアの Olyokma オリョークマ川) にあたる。
Nazarenko (1978) によればザバイカルでは同一個体のオス (複数) が両方の歌を歌うと記述している。我々のデータでもサハリンで同一個体の鳥 (複数) が速いタイプの歌あるいは両方の要素を持つ歌を歌うことがある。
サハリンやプリアムールでは特徴の混じった標本も見られ、千島で採集された個体にはそのような特徴はほとんど見られない。Lobkov (1986) によればカムチャツカ北部で基亜種 borealis の分布域に接するところのみで特徴の混じった個体が見られる。これらの地域が交雑帯を形成していると考えられる。
この特徴はチフチャフの Ph. collybita abietinus と Ph. c. tristis の関係に似ている (チフチャフも tristis を種と考えるか議論が続いている)。
日本の xanthodryas が迷行している可能性があるが、現在までのところでは標本にはみつかっていないとのこと。
Glushchenko et al. (2016) はコムシクイとオオムシクイを別種にせず多形種とする考えも示している (ロシアでの近年まで主流の考え)。本州など日本のものまで亜種にするかどうかはかっこ付きで示している。
オオムシクイを Ph. borealis の亜種扱いならば hylebata との先取権の問題は一応回避できて (シノニムにする場合は別だが)、これまでのロシア流の亜種 hylebata、examinandus を並列に扱えばよい話になるわけだが...。
[Glushchenko et al. (2016) の記述を要約してから、2021 極東の鳥類 38:ロシア極東のムシクイ類 にこの部分が翻訳されていることに気づいた。要約や訳し方によってニュアンスの違いが感じられるかも知れない]。
Hartert (1910-1922) p. 517 では hylebata は亜種 borealis のシノニム扱い。この時点でまとめられてしまったために世界のリストに現れなくなくなり、日本のリストでもあまり検討される機会がなかったのかも知れない。
亜種 borealis のシノニムであれば表面に現れないが、別亜種と考えれば先取権の問題が発生する次第。
上記サハリンでの交雑に関係して、
Spiridonova and Valchuk (2022) Mitochodrial Genome of Phylloscopus examinandus and Hypothesis of Its Origin
にサハリンのオオムシクイのミトコンドリアゲノム解析結果があり、1個体はミトコンドリアはオオムシクイ型で核遺伝情報はコムシクイ型のものがみつかったとのこと。
試しに OR890423.1 から出発して BLAST を試みてみるとオオムシクイは遺伝的にはかなり広がりがあり意外に多様性に富んでいるよう。コムシクイと完全に分かれた系統でなく混ざってしまう結果が出てくる。この場合はサンプル数が少ないためかメボソムシクイも内包されてしまう。
一方 AB362456.1 のように伝統的な cyt b を使うと Saitoh et al. (2010) と同様の結果になって3種が分かれることになる。この場合はアラスカの kennicotti は特に系統を作る傾向はない。用いる遺伝子によって分子系統樹が異なる可能性がある。
もう一つだけ試みておくと MH079202.1 から出発するとサンプル数が少ないものの3種が分かれる傾向はあるがあまりすっきりしない (この部分配列は短いのでそれほど精度が高くない可能性もある。エゾムシクイとアムールムシクイも混ざってしまう)。
従来の cyt b ではっきり分かれたのでそれぞれ別種扱いとなったが、他の遺伝子を考慮するとそこまですっきりしないのかも知れない。少し試しただけで全体像をつかめているわけではなく皆様もお試しを。
Glushchenko et al. (2016) の記述を読むと、hylebata は基亜種 borealis よりも明らかに大型で基亜種 (現在は種コムシクイ) のシノニムと考えるのは難しそうである。基亜種と比べて上面のオリーブ緑色は同様だが、過眼線や下面はずっと黄色いと Swinhoe は述べている。
メボソムシクイ (コムシクイ) 上種が3種のみとすれば hylebata は大型の種のオオムシクイかメボソムシクイのいずれかに属するのが自然に見える。いずれの場合も hylebata の方が記載年が早いので学名変更を伴う可能性がある
(標本が見当たらない場合などの扱いなどは規約があるかも知れないが知らない)。
主に形態面と分布を重視して "オオムシクイ" を北方型、南方型の亜種に分ける Glushchenko et al. (2016) の考えは妥当な点もあるように思える。
学名が最終的にどうなるかはわからないが、主にカムチャツカの個体群を亜種とし、和名では北海道や周辺のものをオオムシクイ亜種オオムシクイ、カムチャツカのものをオオムシクイ亜種カムチャツカムシクイのように呼べば英名・ロシア名とも整合性が非常によくなる。
またカムチャツカではこの分類群のムシクイは極めて普通の種類で、カムチャツカの音景を形作っているらしいことからもカムチャツカの名前は何らかの形で残るとよいのではと思う。実際にカムチャツカの自然番組のビデオなどを見ると "オオムシクイ" のさえずりを頻繁に聞くことができる。
この話題 (カムチャツカムシクイ?) は和名オオムシクイが決まる前にメーリングリストで行ったことがあるが、日本の繁殖個体群があるので当時の英語新称だった Kamchatka Leaf Warbler からカムチャツカの名を訳すよりは日本で使われた名称を用いる方が適切との判断になったと記憶している。南北で亜種が提案されているならば検討することは面白いと思う。
なお地理的にはカムチャツカは大陸の半島であるが、大陸とは高緯度でのみつながっているので北部まで分布しない種類にとってはカムチャツカは生物地理学的には島と同様にみなすこともできる。他の種類の分布を考える時も参考になるだろう。
参考ビデオ: カムチャツカでさえずるオオムシクイ。ペトロパブロフスク郊外でよく聞く。飛ぶ時に翼で鋭い音を出すが、なぜなのか知っている人があれば教えてほしいとのこと。
カムチャツカの鳥の声。オオムシクイのさえずり これもペトロパブロフスク近郊とのこと。
北海道のオオムシクイの繁殖期分布について: 藤巻 (2021) 北海道におけるオオムシクイの繁殖期の分布。北海道でも極めて限られた地域でのみ繁殖可能性がある模様。
[フィリピンは主要越冬地でない?]
Hoefferle et al. の解析によればフィリピンの 19 個体の cyt b 解析では 18 個体がコムシクイだったとのことでオオムシクイは含まれていなかった。筆頭研究者はアラスカ在住で、アラスカの亜種がどこで越冬しているを特に気にしているのだろう (#コムシクイの備考の Adams et al. (2022) も参照)。1個体のみメボソムシクイ。
オオムシクイが記載された越冬地 (スンダ列島) と整合する結果となっている。オオムシクイは大陸沿いに渡って、より低緯度で越冬するのだろうか。
[音声による識別]
日本では北海道東部を中心に繁殖している。本州中部では春の渡りが最も遅い (5月下旬-6月上旬) 種類の一つ。
3拍のさえずりで区別できるとよく言われるが、メボソムシクイにも3拍に聞こえる個体があり拍数だけには頼らない方がよい。
参考ビデオ メボソムシクイ囀り (鳴声メイン) 3拍子 ver. 2020年8月31日 長野県長谷村。
3拍のうち1回が少し低く持続した音になるのが特徴 (ジジロ、ジジロとよく表現されるがロの音が低いことを表している)。さえずりのフレーズの前に地鳴きも発するので、これを聞けばオオムシクイかメボソムシクイをより判断しやすい (メボソムシクイの地鳴きが最も低い)。
梅垣 (2016) Birder 30(10): 16-17 にソノグラムも含めたメボソムシクイ上種3種の識別がある。
コムシクイのさえずりは連続して聞こえるのでさえずりを聞けば迷うことはないだろうが、秋の渡りなどで地鳴きだけでの区別は少し難しい。中心周波数はオオムシクイ (6-7 kHz) の方がコムシクイ (5-5.5 kHz) よりが高いが重なりもある。
音域の広がりの方がよい識別点で、オオムシクイ (強度分布を正規分布で当てはめた時の 1σ = 1.0 kHz 以上) の方がコムシクイ (1σ = 0.5-0.8 kHz) より広く、オオムシクイの方がより雑音っぽく (力強く) 聞こえるのに対してコムシクイはより純音に近い (濁りの少ない) 音に聞こえる。1音 (ジ) か2音 (ジジ) かは判断材料にならない。
5 kHz 以下にほとんど信号のないメボソムシクイ上種はコムシクイを疑ってよいのではと考えている。
オオムシクイとメボソムシクイは野外で外見で見分けることは困難とされるが、
齋藤他 (2014) メボソムシクイ上種3種の外部形質を用いた識別方法。
[秋の渡り]
秋の都市公園の渡りではオオムシクイの地鳴きのみを聞くような印象がある (さえずりを聞くこともたまにある)。標識調査ではメボソムシクイの方が若干早いが時期には重なりがある。繁殖地で遅くまでさえずりを聞くことがあるとのこと。渡部 (2023) Birder 37(9): 30-31 ではメボソムシクイは10月上旬でも繁殖地に残るものがあってさえずることもあると書かれている。また、1シーズンに2回繁殖することが知られているそうである。
メボソムシクイの方が標高の高いところを渡るらしく、それが都市公園の秋の渡りでオオムシクイが主になる理由とも考えられる。メボソムシクイは9月中下旬に渡る時にさえずって行くものもあるらしい [大西敏一氏および知人の知見から kbird:05441 (2022.9.25)]。梅垣 (2019) の考察では通過時期がやや違うので (#メボソムシクイ の備考参照) 比べて考えるのも面白そうである。
[台湾のメボソムシクイ類の DNA バーコーディングによる判別]
Cheng and Hsu (2024) Use of DNA Barcode Sequences for Distinguishing the Three Species in the Arctic Warbler (Phylloscopus borealis) Species Complex
台湾にコムシクイ (現在の分類での名称) が訪れていることはわかっていたが、他2種については示唆する観察記録があったものの確実ではなかった。
COI 遺伝子による DNA バーコーディング法で3種とも通過していることが確認された。
ハプロタイプは3グループに分けることができてサンプルはコムシクイが一番多かった。
地鳴きは多く記録されているはずなのに、非繁殖期はさえずりでは区別できないと書いてあるだけで音声についての記述が特にないのも不思議。音声解析や音声データベースにあまり詳しくない著者なのだろうか。
[オオムシクイの和名]
オオムシクイの和名由来は日本産鳥類の新和名及学名訂正 (Kuroda 1915)。当時は北大東島の渡りの際の記録を指して使われた。
「鳥類の図鑑」(学習図鑑シリーズ 4 高島春雄 共著; 黒田長久 共著; 小林重三ほか絵 小学館 改訂版 1962。初版は 1956) p. 122 に旅鳥としてオオムシクイの名前がムギマキと並んで登場している。図版や本文解説には出てこない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にツツドリの別名としてオオムシクイが挙げられていた。
-
メボソムシクイ
- 学名:Phylloscopus xanthodryas (ピュルロスコプス クサントドゥリュアス) 黄色の木と森の精のムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:xanthodryas (合) 金髪の木と森の精 (xanthos 黄色の dryas 木と森の精 Gk)
- 英名:Japanese Leaf Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
xanthodryas は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。規則に従えば "クサントドゥリュアス" のアクセントになる。
単形種。
原記載 中国の福建省南部沿岸アモイで採集され、記載者によればこれまで自身が中国で出会った最大の Phyllopneuste (ムシクイ類に使われた属名の一つで Phyllopneuste "Meyer" Boie, 1828 で、Phylloscopus Boie, 1826 のシノニムとされる)
で、嘴の大きさは (広義?) センダイムシクイにも匹敵するが頭中線はない。新種 Phyllopneuste xanthodryas として記載する。おそらく中国中央部に夏にやってくるものでアモイは渡り途中であろうとしている。
現在の分類では (おそらく) 日本の繁殖固有種となるが記載と学名は日本に縁がなかった。
コムシクイと同種とされていた時代もあり、その時の学名は Phylloscopus borealis xanthodryas となる。古い図鑑などに Phylloscopus borealis と記載されていることもあり学名の指す種や学名字義は現在意味するものとは異なるので注意。
またコムシクイと同種時代の英名は Arctic Warbler で、Brazil (2009) "Birds of East Asia" でも同様。また当時の日本の亜種にも特に英名を与えていない。Japanese Leaf Warbler の英名は3種の分離に伴うものでかなり新しい名前と言える。
越冬地などを含めれば日本固有種ではないので、近年の国名を避ける傾向から Avibase では Pacific Leaf Warbler を見出しに用いている。Kamchatka Leaf Warbler (オオムシクイ) はそのまま使われているのでこれは地理名との判断かも。
Hartert (1910-1922) の時代は亜種扱いで p. 518。Phylloscopus borealis xanthodryas アモイで記載されたため繁殖地は明瞭でなかったが、当時は千島列島や北海道の型に相当すると考えられ、Seebohm によれば日本の北海道より南側の山でも繁殖とのこと。
カムチャツカでも捕獲されているがこの時点では繁殖は確認されていなかった。
xanthodryas は当初は千島列島や北海道が中心と考えられていた模様で、#オオムシクイの備考のように Dement'ev and Gladkov (1954) ではメボソムシクイとオオムシクイの繁殖地分布を現代とは逆に解釈していた由来の一つにもなっていたのだろう。Hartert の「カムチャツカでも捕獲されている」は Pleske (1899) の記述を指すと思われる。
Pleske (1899) がカムチャツカのものを xanthodryas と記録したため Dement'ev and Gladkov (1954) はカムチャツカの個体群をこの亜種名 (当時) で呼ばざるを得ないとの論理だった。
Hartert はこれらムシクイの研究に深く関係しており、スンダ列島で越冬する Phylloscopus borealis には2型あると提唱し、実際に2型が確認された (現代のコムシクイとオオムシクイ。大きさの差が目立つので2型あることは気づきやすく確認しやすかったのだろう。現代のメボソムシクイも混ざっていれば判定困難だったかも知れない)。
しかしスンダ列島の大きい方の型 (現代のオオムシクイ) と xanthodryas の2亜種の繁殖地の同定は困難で Dement'ev and Gladkov (1954) の時代でもまだわかっていなかった。歴史的背景はオオムシクイの備考も参照。
#コムシクイ、#オオムシクイの備考参照。「鳥のおもしろ私生活」(ピッキオ 1997) によれば、一夫多妻のうわさがあり、秋遅くまでさえずるとある (同書エゾムシクイの項目)。#オオムシクイの備考も参照。
かつては秋の都市公園の渡りで見られるメボソムシクイ類はすべてメボソムシクイとして記録されていたわけだが、音声判定では実際は多数がオオムシクイのようである。オオムシクイの和名が決まる前から秋の渡りでも観察者によっては区別されることもあり、現在オオムシクイとされるものはコメボソムシクイと呼ばれていた。
梅垣 (2019) Birder 33(4): 46-49 で渡り時期のメボソムシクイ上種の記事があり、大阪平野での事例を調べている。メボソムシクイは地鳴きをあまり発しないので確認が難しいとあるが、色彩などの微妙な違いから推定したメボソムシクイの秋の渡り時期は9月5日過ぎから 10 日台にピークがあるとしている。コムシクイは大阪平野ではレギュラーではないが9月上-中旬と考えている。
この記事にはソノグラムも表示されている。
ロシア極東部でメボソムシクイらしい声が記録されることがあり、メボソムシクイがロシアにも渡ることがあるのか、あるいはコムシクイの中に (例えばまだ調べられていない個体群の中に) メボソムシクイに似たさえずりを持つものがあるのか話題にはなっているがよくわかっていない。
Round et al. (2015)
A record of Japanese Leaf Warbler Phylloscopus xanthodryas in Thailand
タイでのメボソムシクイの確実な初記録。標識による。オオムシクイはこれまで遺伝子も調べられた記録 [Round et al. (2016)
Addition of Kamchatka Leaf Warbler Phylloscopus examinandus and Sakhalin Leaf Warbler P. borealoides to Thailand's Avifauna]
があるが、これまで翼が長いか緑っぽくメボソムシクイと暫定的に記録されてきた個体はオオムシクイの可能性があり再調査が必要であろう。
[ニューギニア地域の島のムシクイ類の進化]
日本のムシクイ類とは近縁ではないが、メボソムシクイ/コムシクイ類と共通祖先を持ち、赤道地域を中心に適応放散したクレードがある。かつてセンダイムシクイと同種とされたニシセンダイムシクイがこのクレードに含まれる。Boyd は Cryptigata 属を与えている。
ムシクイ類の中では最も新しく分岐したクレードにあたる。
このクレードのムシクイ類でニューギニアからビスマルク諸島などの離島の種分化の研究がある: DeCicco et al. (2024)
Phylogeography of the Island Leaf Warbler (Aves: Phylloscopus poliocephalus) in Northern Melanesia Reveals Rapid Secondary Sympatry or Ecological Speciation on Kolombangara Island, Solomon Islands。
Phylloscopidae で種を分割するに値するとの議論もなされている。
-
ヤナギムシクイ
- 学名:Phylloscopus plumbeitarsus (ピュルロスコプス プルムベイタルスス) 鉛色の脚のムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:plumbeitarsus (adj) 鉛色の脚の (plumbum 鉛 tarsus (m) ふしょ骨、脚)
- 英名:Two-barred Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
plumbeitarsus は合成語で発音はわからないが、tarsus は短母音のみ。plumbeus, plumbum, plumbea のいずれにも長母音が現れないので "プルムベイタルスス" ("プルムベイタルスス" かも知れない) のアクセントが自然と考えられる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。系統的には Martens (2010) ではキタヤナギムシクイに近いとされたが、 Alstrom et al. (2018) ではエゾムシクイやメボソムシクイに近いグループになっている (#キタヤナギムシクイの備考参照)。
かつては Phylloscopus trochiloides (キタヤナギムシクイに似たもの) 現在の英名 Greenish Warbler の亜種とされていたが分離されたもの。種学名に変化があるので注意。
和名は以前は Phylloscopus trochiloides をヤナギムシクイと呼んでおり、亜種時代は Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus にフタオビヤナギムシクイの名前があった。
現在の英名との対応がよくないが歴史的経緯の考察を#キタヤナギムシクイの備考で行ってみた。
英名は Two-barred Warbler は IOC 15.1 と一致するが、Avibase では Grey-legged Leaf-Warbler を用いている。
Hartert (1910-1922) 時代は p. 511 のように Phylloscopus nitidus plumbeitarsus とミドリムシクイ Green Leaf Warbler の亜種扱いだった。ミドリムシクイのドイツ語名は Wacholderlaubsaenger とネズ (Wacholder) のムシクイ。和名との関係は特になさそう。
森本 (2002) Birder 16(9): 50-53 に2019年5月に舳倉島で観察された個体の同定と識別がある。この時代はまだ亜種の名前で呼ばれていた。
現在は分離された Phylloscopus plumbeitarsus をヤナギムシクイと呼ぶため、Phylloscopus trochiloides にはニシヤナギムシクイの和名が与えられ日本鳥学会でも検討種になっている。
後者は大陸 (特にインドからヨーロッパ) ではごく当たり前の種類で、過去にも旧和名はそれなりに使われていると思われるので新旧の名称に注意が必要である。
英名 Green Warbler Phylloscopus nitidus ミドリムシクイと Greenish Warbler は似た地域に生息して地鳴きも似ているためしばしば混同される。
英名は類似しているので識別対象種になることがわかりやすいが、和名はまったく異なる。
種小名に出てくる「鉛色」は鉛の元素記号 Pb を思い出せば覚えやすいだろう (語源は同じ)。
-
エゾムシクイ
- 学名:Phylloscopus borealoides (ピュルロスコプス ボレアーロイーデース) コムシクイのようなムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:borealoides (合) コムシクイに似た (Phylloscopus borealisコムシクイ -oides (接) 〜に似た)
- 英名:[Pale-legged Warbler 分離前の名称], IOC: Sakhalin Leaf Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
-oides の語尾は i, e が長母音で前者にアクセントがあるとのこと。#コムシクイの音を参考にすれば、"ボレアーロイーデース" となると考えられる。
エゾムシクイ と アムールムシクイ Phylloscopus tenellipes (英名: Pale-legged Leaf Warbler、日本鳥類目録改訂第8版に登場) はかつては同一種とされたがさえずりは全く異なり、2種に分離された
[Veprintsev et al. (1990) On species status of the Sakhalin warbler - Phylloscopus borealoides Portenko。極東の鳥類(2008) 25: 53-60に和訳あり]。Phylloscopus tenellipes は第7版掲載種ではなかったがすでに分離されており第7版からエゾムシクイの学名に変化はない。
分離後はいずれも単形種。
Phylloscopus tenellipes Swinhoe, 1860 の方が記載が早く (基産地アモイ)、
Phylloscopus tenellipes borealoides Portenko, 1950 の記載 (基産地国後島) の方が後であったため、同種とする場合には Phylloscopus tenellipes の種学名だった。
少し前の図鑑ではエゾムシクイがこの学名で登場する。Ogawa (1908) 時代でも同じ。
第7版のエゾムシクイの学名が Phylloscopus borealoides となっていたことからも分離されていたことが判定できる。日本から見るとエゾムシクイからアムールムシクイが分離されたように見えるが世界的に見ると逆になる (#ニシオジロビタキと同様の事例)。
英名も旧名の Pale-legged Leaf Warbler は旧エゾムシクイで現在のアムールムシクイの種小名に対応するものなので注意。現在のエゾムシクイはサハリンのムシクイの意味となっている。
エゾムシクイの他国語名は "日本の" を用いているもの (フランス語など)、"サハリンの" を用いているもの (ドイツ語など) いずれもある。ロシア語ではもちろん "サハリンのムシクイ"。
ノルウェー語では Ainosanger だがこれはおそらくアイヌを指している。
エゾムシクイとアムールムシクイの地鳴きの判別については#アムールムシクイの備考参照。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によれば Hokkaido とあり当時は本州などの繁殖は (それほど?) 知られていなかったよう。主な生息地から "エゾ" の名前が付いたのだろう。
エゾムシクイは秋の渡りが非常に早く始まり、平地でも7月の早いうちから地鳴き (時にさえずり) を聞く。2023 年伊吹山のイヌワシ子育て生中継でもエゾムシクイの声がこの時期から頻繁に聞かれた。
今西他 (2009) ムシクイ類3種の秋の渡り時期の違い [深瀬徹氏 kbird:05161 (2022.7.18) 紹介の論文] では少数ながらも7月中旬の記録があり、当地の観察とよく合っている。
文献でなぜそれほど早いかの考察は十分にはなされていないが、
「一部が南方起源であるために早く渡去するのではないかという指摘がある」と述べられている。
Bozo et al. (2021) Factors controlling the migration phenology of Siberian Phylloscopus species
にロシア極東のムシクイ類の渡り時期を決める要因を考察している。対象種はアムールムシクイ、コムシクイ、キマユムシクイ、カラフトムシクイ、カラフトムジセッカ、ムジセッカ、ヤナギムシクイであり、
エゾムシクイは含まれていないが近縁のアムールムシクイの秋の渡りが相対的に早いことがわかる。
春の渡りは換羽スケジュールに相関があり、秋の渡りは越冬地の南限緯度と相関があるとのこと。
-
センダイムシクイ
- 学名:Phylloscopus coronatus (ピュルロスコプス コローナートゥス) 冠を戴いたムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:coronatus (adj) 冠を戴いた (corona (f) 冠 -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Eastern Crowned Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
coronatus は2つ目の o と a が長母音で a にアクセントがある (コローナートゥス)。
かつてはネパールやタジキスタン、インドなどの一部で繁殖するニシセンダイムシクイ Phylloscopus occipitalis 英名 Western Crowned-Warbler と同種とされていた (現在の分子系統学の見解とはかなり異なる)。
当時はセンダイムシクイは Phylloscopus occipitalis の亜種扱いであったため、センダイムシクイにこの学名が使われていた。亜種まで書くと Phylloscopus occipitalis coronatus。
現在は分離されてそれぞれ単形種。
記載時学名 Ficedula coronata Temminck & Schlegel, 1847 (原記載) 基産地日本 (図版)。
フランス語名 Le bec-fin courronne (冠のある bec-fin) とムシクイ類とヒタキ類の区別が十分でなかった。p. 50 に au millieu de la tete, ... と頭央線の模様が特徴的と記している。
種小名の語義はいわゆる冠羽とは異なるのでフランス語の courronne の訳語を採用した。王位についたなどの訳語もある。
このように解説していたが、頭央線についてはあまり鮮明でないことや消えている個体もあることが述べられている ([センダイムシクイの和名の検討] でもう少し詳しくみてみた) ことから、頭央線を指す語義を削除した。むしろ帽子のような頭の模様全体を指したものかも知れない。"冠を戴いた" で十分と思われる。当時 Temminck and Schlegel は日本の (現代の分類で) ムシクイ属はセンダイムシクイのみを知っていたので日本産他のムシクイと区別できる特徴を与えた学名を考案する必要はなかったと想像できる。
かつて使われていた学名時代の occipitalis の語義 "後頭部に特徴のある" が説明に用いられていたためにその解釈を引き継ぎ過ぎたかも知れない。
"冠羽を持つ" の意味の種小名には cristatus / cristata が使われることが多いが、coronatus / coronata が用いられることも多少あり、有名なところではカンムリクマタカ Stephanoaetus coronatus Crowned Eagle がある。
この種の記載時学名は Falco coronatus Linnaeus, 1766 で Falco coronatus Linnaeus, 1766 (TreatmentBank) によれば Brisson (1759) が AQUILA AFRICANA CRISTATA と記述していた (ラテン語で示しただけで有効な学名と判断されなかった) ため避けたものと考えられる。
coronatus / coronata の用例はこのように訳し分ける必要があり、英名では crowned, crested がそれぞれの意味で使われている。学名由来を考察する時も先行する学名との重複を避けた名称か検討が必要になる。
センダイムシクイではもちろん冠羽ではなく crowned の方に対応する。
ニシセンダイムシクイ (原記載。Jerdon が付けた名前らしいが原記載にならず Blyth, 1845 の記載) の occipitalis は "後頭部に特徴のある" でセンダイムシクイと同様の特徴を記したもの。
センダイムシクイとニシセンダイムシクイが同種扱いであった時期にはニシセンダイムシクイの方の記載が古いために種学名に occipitalis が現れる。古い時代のセンダイムシクイの学名語義にはこちらの方が登場するのでご注意を。ただし意味に似たところもある。occipitalis がすでに使われていたため Temminck and Schlegel が別の種小名を選択したものだろう。頭央線をどのように記述したかは [センダイムシクイの和名の検討] を参照。
センダイムシクイの系統的位置づけについては#キタヤナギムシクイ備考 [ムシクイ類の進化の考察] 参照。
[Seicercus 属]
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2), Avibase 2015-2020 では Seicercus (< seio 振る kerkos 尾 Gk) 属が使われている/いた。Seicercus Swainson, 1837 による属名。
分子系統研究の結果、2000 年代に使われていた Seicercus 属は単系統でないことがわかり [Olsson et al. (2004) Non-monophyly of the avian genus Seicercus (Aves: Sylviidae) revealed by mitochondrial DNA]、
現在は一般的には Phylloscopus のシノニムとされる。Alstrom et al. (2018) (#ムジセッカの備考) も参照。
タイプ種は Cryptolopha auricapilla Swainson, 1837 = Sylvia burkii Burton, 1836 (現在の通常の学名では Phylloscopus burkii Golden-spectacled Warbler マユグロモリムシクイ) で、Phylloscopus 属を分割する扱いの場合、この種と同一属に含まれるかどうかの判断で属名の扱いが異なる。
かつてセンダイムシクイがこの属とされたことがあるのは同一属と考えられたため。
なお、どのムシクイを Seicercus 属に含めるかは分類学者によって異なっていたようで、Martens (2010) (#キタヤナギムシクイの備考参照) では狭義に扱っている。
Alstrom et al. (2018) の 図 に採用されている分類では日本の一般的なムシクイ類は含まれていない。wikipedia 英語版の Seicercus の解説でも同様。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では日本の主なムシクイ (エゾムシクイ、メボソムシクイ上種、イイジマムシクイ、ヤナギムシクイ) もこの属に含めていたが、分子系統がはっきりしてきた現在ではセンダイムシクイなどの属名としては忘れてしまってよい模様である。
...と書いていたが、#キタヤナギムシクイ備考 [ムシクイ類の進化の考察] の知見によれば、もし Phylloscopus 属を2分割とすれば復活する可能性があるかも知れない。つまりセンダイムシクイとマユグロモリムシクイが意外にも近縁の可能性が出てきた。
Boyd のリストに現れる属名の年代のみチェックしておくと Abrornis J. E. and G. R. Gray, 1846 (他の用例もあって微妙にややこしいらしい)、Rhadina Billberg, 1828 (モリムシクイ)、Pindalus Gurney, 1862、Pycnosphrys Strickland, 1849、
Acanthopneuste Blasius, 1858 (コムシクイ)、Cryptigata Mathews, 1925 (The Key to Scientific Names より)
なのでモリムシクイが Phylloscopus の方のクレードに入るとすればもう1系統は Seicercus Swainson, 1837 と呼ぶことになりそう (2分割でなくさらに分割が必要となれば違う結果になる)。2分割が採用されれば日本の繁殖種に Seicercus の属名が復活するかも知れない。この場合の Seicercus 属の概念は従来とかなり異なるものになる。
Alstrom が分割したい意向ではあまりなさそうなのと、ミトコンドリアゲノムを用いた分子系統樹と Alstrom et al. (2018) の系統樹に多少の違いがあるのでしばらくは様子見状態が続くだろうか。
[センダイムシクイの和名の検討]
通説はよく知られているのでここでは特に紹介しない。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 pp. 95-99 (1946 年初出) によれば中西氏は仙台の地名か仙台藩のいずれかにちなんだものと考えていた (p. 98)。仙台地方の人が鶴千代君と関連させた説は某君由来とあって当時の中西氏と同世代の人物による説なのだろう。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 pp. 109-110 (1940 年初出) の方に出典が記されていて、宮城県の鳥の研究家である熊谷三郎氏とのこと。同氏はニュウナイスズメの新嘗祭由来説も提唱していた (p. 109)。
中西悟堂「野鳥記コレクション」I 野鳥と共に p. 196 によれば仙台の人は (鶴千代君由来説を) 主張するんです、とのことでお国自慢的な要素も含まれているらしいことを示唆している。
中西氏の 1946 年記事では当時 (戦前領土を含む) のムシクイ類の名前一覧が挙げられていて、コシジロムシクイ (台湾)、ヤナギムシクイ (朝鮮)、エゾムシクイ、オオムシクイ (千島)、コムシクイ (樺太、北海道)、メボソムシクイ、イイジマムシクイ、カラフトムシクイ、キマユムシクイ (満州) で、いずれも場所や身体的特徴、人名、学名または外国語名由来などでセンダイムシクイも地名由来と考えるのは自然な感じがする。
なおコシジロムシクイは現在のムシクイ属ではない。これも現在の学名や英名と一致度が低いのでいずれ調べていたい。
それでは学術界ではセンダイムシクイはどのように認識されきたかを見てみると、Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Sendai-mushikui の和名は与えてあるが、分布は Hokkaido, Fuji-yama となっていて現在どこにでもいるムシクイとしては奇妙である。これは Seebohm (1890) "The birds of the Japanese Empire" p. 69 に頼ったものと考えられる (そして後述のように小川氏自身が富士山で記録している)。
ここでは英名 Temminck's Crowned Willow-Warbler が与えられていて、"Fauna Japonica" 由来 (図版 当時用いられた学名は Ficedula coronata)、となっているが頭央線が図版に現れないのでこの図版が何を表していたのか今ひとつ明瞭でない。
本文記載は 本文 フランス語名 Le bec-fin courronne で On remarque au milieu de la tete, une raie assez large et un peu plus claire que la teinte du fond; elle se prolonge depuis le front jusqu'a la nuque, mais elle est toujours tres peu apparente, et parait souvent s'effacer completement. とあって本文には頭央線の記述があり、種小名の由来であることは納得できる。
しかしこの記述にも、常時不鮮明で (toujours tres peu apparente) でしばしば完全に消えてしまう (parait souvent s'effacer completement) とされている通り、図版はこの特徴を表したものと推定できる。頭央線のないセンダイムシクイがあるのかどうか知らないが、記述を読んで図版と現物を比べた者が大いに悩まされたであることは容易に想像が付く。もともとは Ficedula 属だったので、"ヨーロッパのキビタキ属に比べて頭に特徴が目立つ" ("Fauna Japonica" ではキビタキは Ficedula 属ではない) 程度だったのかも。
Temminck and Schlegel はホウロクシギでも図版と本文の記述を混乱しており (#ホウロクシギ の備考参照)、和名を与える際の問題となっていた可能性がある。
Ogawa (1908) のセンダイムシクイの項目は確かな標本記録のある Hakodai (Henderson) と Fuji-yama (Jouy, Ogawa) のみを取り上げ、日本であることは明らかだが詳しい採集地不明の "Fauna Japonica" は取り上げなかったものと思われる。つまりそこら中に生息するセンダイムシクイと Ficedula coronata Temminck & Schlegel, 1847 が同一であるかは確実に判定できていなかった。
この点は山階鳥類研究所の標本データベースでもある程度裏付けられて、1906 年の YIO-28456 (山形) および同時代 (1891 年の標本もある) のオリジナルの標本ラベルにも和名が記されていない。
YIO-28475 (静岡 1885) などはセンダイムシクイの名称が示されているが山階旧標本番号とともに記されているので後につけられたものだろう。
各地にみられる種がセンダイムシクイであることが自明であれば Ogawa (1908) にも Hokkaido, Fuji-yama 以外の分布に当然含まれていただろう。
小川氏が富士山で 1906 年採集の YIO-28457 がある。富士山は既知の分布域に含まれていたいるので特に問題はない。模範標本とあるのでこれが命名されて以来確実な国内最初の標本だったのだろうか。海外の研究者によって命名時に使われた標本は国内にはないので、この標本を国内の模式標本のように扱う意味だろう。
Weiss! (白い) とドイツ語で記述されており、医学を修めた小川氏にとってはドイツ語は身近な言語だっただろうことがわかるとともに、感嘆符を付けるぐらいなのでこのような淡色のムシクイにそれまで出会ったことがなかったのだろう。野外では写真も撮ることさえできず、野外識別も発達していない時代では採集して標本を見るしかなく、見たことすらない白いムシクイの意味だろう。これが噂の Ficedula coronata Temminck & Schlegel, 1847 なのか! というわけである。
ちなみに山階鳥類研究所の標本データベースでもこれだけ普通種なのにセンダイムシクイの古い標本は予想以上に少なかった。小型で動きの早い小鳥を標本に残せる程度に遠方から傷付けずに撃つことは難しかったのだろう。#オガサワラマシコ の記述も参照。
なお標本ラベルを見る場合は学名や和名表記にも注意。採集当時付けられたものでないことが判断できる場合もある。
つまりムシクイ類が古くから十分に区別されていたわけではなく、#ホウロクシギ の備考 [日本での記載と和名について] 同様に海外から知識が入るようになって、日本にこれほどの種類の鳥がいるのかと驚くとともに、学名に対する和名を与える必要が生じた結果、Ficedula coronata Temminck & Schlegel, 1847 にセンダイムシクイの名称を割り振ったものだろう。
ホウロクシギで Ogawa (1908) の段階で国内産の情報が取り入れられていないにもかかわらず、Seebohm (1890) の情報をもとに産地を記述し、和名がすでに付いていたのと同じ状況である。
ある程度根拠があって割り振ったものもあるだろうが、声のことは当時の海外文献からは判断できないので単に地名の仙台から振られた可能性が見えてくる。
さらに考察を進めると、Ogawa (1908) に出てくるエゾムシクイは産地 Hokkaido、エゾムシクイの産地も Seebohm (1890) 由来 (Hakodai で Whitely と Fauire が採集) で、つまり Ogawa (1908) 時点のムシクイ類の産地はすべて海外情報から輸入されたものとなる。
エゾムシクイの小川による富士山の標本 (1906) が同様に存在するが、YIO-28408 にあるように当時は Phylloscopus b. borealis の学名が用いられてエゾコムシクヒとなっていた。後に学名訂正とともにエゾコムシクヒから "コ" の文字が消された。こちらも模範標本となっている。
現在の分布のみから考えるとなぜ borealis と判断したのか不思議に思えるが、borealis の基産地はオホーツク海沿岸で (#コムシクイ備考参照)、日本に近い地域に分布するムシクイと考えられたものだろう。Arctic Warbler の英名をもとに考えると誤解のもとになり得る。
Ogawa (1908) はこの標本を "エゾコムシクヒ" と考えていたため、エゾムシクイの分布に本州を含めることができなかった理由となるだろう。海外文献で北海道で2種記録されているので、日本の命名慣例に従って地名を付けてエゾムシクイとエゾコムシクイとなったものだろうが、実物がどちらに対応するかまでは特定できていなかった。
1906 年の標本を一時は borealis を国内の標準標本とみなしたが、後に異なることが判明し、ラベルの修正とともに (当時の学名で) Phylloscopus tenellipes をエゾムシクイと呼ぶことに統一されたのだろう。
山階鳥類研究所の標本データベースでメボソムシクイを検索しても当時の判別は容易ではなかったことがわかる。ムシクイ類は形態的にはあまりにも難しく、当時の日本の鳥学者は鳥の声にあまり馴染みがなかったらしいことは他の種の状況からも想像できるので、音声をあまり重視していなかった時代には場所をもとに整理・命名せざるを得ない部分があったと想像できる。"メボソ" の名称もそれほど普及していたわけではなく、"キタムシクヒ" (学名または外国語名から訳したものと考えられる) の名称もよく使われていた。
イイジマムシクイも日本人による記載ではなかった。
これらの例を見ると標準和名の必要性も理解できるが、ムシクイ類は分類も名称も混乱極まっていて "メボソ" 派 (外見的特徴を重視) と "キタムシクヒ" 派 (学名または外国語名との整合性を重視) の両者があったようなので裁定が必要で特殊な事例かも知れない。
声にこそ特徴のあるムシクイ類で、声に基づく分類が用いられていなかったのでオオムシクイの認識も遅れたのか知れない。誰が最初に指摘したのかはわからないが、声の異なる "メボソムシクイ" が遅い季節に通ることが明らかになってようやく鳥学者も存在を認識するようになったのだろう。時期が遅いのでこれこそが北で繁殖する "コメボソムシクイ" なのではないか、というわけである。
メボソムシクイとオオムシクイの音声の違いが長年区別されていなかったらしいことは、中西悟堂「定本・野鳥記」8 p. 146 の兵庫県武庫川の記載 (1939.5.27) を見てもわかる。珍しや渡りの途中らしいメボソの声とあるが、現代の知識からはおそらくオオムシクイだろう。中西氏も他のところで繁殖地で5拍で鳴くメボソムシクイのことを書かれているなど、おそらく拍数で判断されていて音のリズムや音程にはあまり関心を持たれていなかったものと想像できる。
音声があまり着目されていなかったためメボソムシクイも "ゼニトリ" (地方名由来の別名にはあるらしい) などに由来した和名にならなかった。
そしてセンダイムシクイの声の解釈は声を覚えるための後付けのものかも知れない。現代のように声による区別の情報が普及した状況で音声由来の解釈を考えるのは危険かも知れない。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) にせんだい蟲くひ / 鶯むしくひ の名前が現れるが (ムシクイは全部ウグイスのようなものだし)、現代のものと同じものを指すかどうかはわからない。
なお中西 (1946) によれば風騒 (詩文を作る意味) の士のあいだにも、最近までは無縁同様の鳥であった。鳥にくわしい若山牧水の歌にもさすがにこの鳥は現れない (p. 95) とのこと。
そもそも世間ではほとんど認知されていなかったらしい。中西氏は各地の聞きなしをいくつか紹介して、この声で鳴くのは何の鳥かと聞かれてたちどころにわかる聞きなしもあったとのこと。
当時は東京地方でも低山帯どこにでも繁殖していると記述されていた。少し行間を補って読めば、こんなに普通に繁殖しているのに鳥学者はなぜ気にせずに遠方に採集に出かけるのかとも言いたかったのだろう。
現在の京都では中西氏の述べていたその状態に近づいており、かつて森林植生が大きく破壊されたために少し標高の高い山の鳥となっていてわざわざ山に行って声を聞く鳥だった。京都の低地では渡り途中の鳥だったものが本来の分布に戻りつつあるのだろう。古い時代の記述が長年使われてきていて、京都の低地では渡り途中に出会える鳥の認識だった。
「野の鳥の生態」(下村兼史 1931 初出。「日本野鳥記」1 講談社 1985 収録より) 夏鳥の声を順次紹介する部分にはツグミ類・ヒタキ類などは多数紹介されているものの (下村氏はクロツグミを気に入っておられた。中西氏がアカハラを推されたのもこの理由があったのかも知れない)、センダイムシクイもヤブサメも登場せず、特徴的な声と認識されていたのか文面からは不明である。
知っておられればいかにも取り上げておかしくない場面なので、少なくともこの時代にはまだセンダイムシクイやヤブサメの名称由来の通説が誕生していなかったのではないだろうか。
下村氏はその後の部分でセンダイムシクイが托卵したツツドリの子を育てる場面の撮影を述べられているがここにも声のことは記されていない。産卵・子育て時期にはもうさえずっていなかったのかも知れない。
参考: 日本の鳥類生態写真のフロンティアを駆け抜けた 下村兼史 - 「ツツドリのヒナを育てるセンダイムシクイ」ガラス乾板 - [塚本洋三 山階鳥研 NEWS 2007 年 11 月 1 日号 (No. 214) より]。
当時の下村氏の記述を読むと、西洋音楽のことは取り上げられてカッコウの音程なども音楽用語で示されているが、鳥の声にはそれほど詳しい印象は受けず、取り上げられている種類は誰もが気づきやすい種類に限られている。
また訪れられている場所をみると季節ごとに最適の場所を選ばれていたようで (現代ならばモデルコースのように何月はどこに行く、秋はタカの渡りと決めているなど。ハチクマは秋の渡りで見ればよいと決まっていてそれ以外の時期にあまり探さないので...というのは別話題としておく。いずれにしても遠方に外出できる生活・金銭的余裕がないとむしろできないかも知れない)、おそらく最大収穫を期待してそれぞれの場所のピーク時期に訪れておられたのではないかと思える。目視・写真重視ならば自然にそうなるかも知れない。
まだ杜鵑 (カッコウ) 類も含めた夏鳥の揃っていない時期はまだ早すぎると別の所を訪れておられたならば、例えば低山のセンダイムシクイのさえずりのピーク時期にあまり遭遇されなかったかも知れない。
今でも探鳥会は種類の揃ったピーク時期を狙って行われることも多く、早い時期によく鳴く種類が "あまりいないですね" となっている可能性がある。こちらも参加者向けになるべく多くの種類を見てもらえるように配慮したものと言えるがいつの時代でも選択効果に注意が必要であろう。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 225 によれば、京都では4月下旬に数日から1週間ほど立ち寄り、繁殖地に向う旅鳥です。とあり、その後に、4月下旬に鞍馬寺等で... と音声の記述が続くので素直に読めば鞍馬寺等では旅鳥と読める。ただし渡り途中とは明確には書かれていない。同書では京都府の山間部のことも取り上げられているので "京都" は市街地周辺のみを指すものではない。
なお同書では聞きなし由来の語源説も紹介されていたが、名称には "先代" の表記を用いていた。"旅鳥" なのであまり深く意識されなかった可能性もあるが、1980 年代でも聞きなし由来説はまだそこまで一般に認められていなかったのではないだろうか。
鞍馬寺等の話も、間を開けて5月に行ったら鳴いていなかったので (繁殖に入っていただけかも知れない) 旅鳥だろうと判断されていたのかも知れない。京都の野鳥の第一人者にさえあまり関心を持たれていなかったのだろう。野鳥の第一人者ゆえにあらゆる種類や場所を押える必要があって、下村氏のところで述べたようにピーク時期以外の特定の場所を連続して調べておられなかったかも知れない。
かつては東京でも同様に旅鳥と考えられていて (京都の記述も、東京で書かれたものが参考にされていたかも知れない)、蝦夷地の南側で中間にあたる仙台藩の地名を付けた、そして旅鳥の認識なので高いところに生息すると考えて富士山に採集に行ったなどの認識もあったのかも知れない。廃藩置県で 1871 年に仙台県となったが、仙台藩 / 仙台県 の概念はその後も長く馴染みのものであっただろう。
ブラキストン線の概念 (1883 年発表) も注目を集めた時代で、蝦夷地と仙台藩の境界に合致するのでこの区分けは生物地理学的にもおそらく都合が良かった。
今でもよく分布の説明に使われるが、当時は斬新だった垂直分布の発想が用いられて 19 世紀終わりぐらいから 1900 年代初頭ぐらいには富士山では低い順にセンダイムシクイとエゾムシクイ (ラベル当時はメボソムシクイ、現在のコムシクイに対応する亜種名が用いられて後に訂正された)、北にゆくと分布の標高が下がるのでセンダイムシクイは仙台、エゾムシクイは北海道の認識で整理されたものかも知れない。
北海道に採集に行くのは大変だが、東京から近い富士山に "キタムシクヒ" (= コムシクイまたはメボソムシクイに対応) のような同じ種類が生息しているならばずっと手頃で高いところへ行けばよい理屈となる。
このように考えればエゾビタキが富士山で繁殖していると考えられていた理由も説明ができる。
ムシクイ類とヒタキ類の分布を統一して説明できる。これは素晴らしいアイデアだ、となった可能性がある。
もう一つ "センダイ" の付く種名があったならばこの解釈の妥当性が実証されそうな気もするが、ヒタキ類では#サメビタキの和名は外国語名や学名をもとに整理することが可能だったので (このように考えると、海外文献由来で2種に分割された#ヤブサメの "サメ" の語源も同様に解釈できる理屈にもなる) エゾビタキのみが地名を冠するものとなった、エゾビタキは学名や外国語名が複雑でそのまま訳しにくかったので分布を考えて地名を優先した、センダイムシクイも学名や外国語名が複雑で直訳しにくいので地名を用いた、と考えることができる。
鳥学者が和名の理由を書き残していない背景には、このような分布に関する未検証 (未発表) の仮説が含まれていたため公開するわけには行かなかったと考えることもできる。
当時は種分化などの機構もあまりわかっていなかった時代で、地理的に遠くても同緯度帯を同じ亜種とする事例は#コゲラ [亜種] にも見られる通り。かつては主流の考え方だっだのだろう。
一言で言えば分布が江戸と蝦夷の間と考えられたので仙台説となる。
この説の成否はセンダイムシクイが東京の低山では旅鳥と考えられていたどうか次第ではあるが、ここまで解釈すれば、中西氏は「そんなものは富士山まで行かなくても東京地方低山帯に普通にいる」と述べたかったのだろう。
中西氏が地名説を重視したのは上記のような沿革があったためかも知れない。
やはり中央の鳥学者はセンダイムシクイの声を認識していなかったのではないだろうか。
当時の「野鳥」の読者も、当時ならではわかる背景知識とともに、表現から行間を読んで中西氏の文章を堪能していたのかも知れない。反骨精神に富んで深読みのできる者にとっては面白くてたまらなかったかも知れない。
かつてかなり古い野鳥の会会員の方 (現在おそらく故人) が仕事場に古い「野鳥」誌をすべて保管されているのを見せていただいたことがあったが、近年 (当時 1990 年代) の「野鳥」は面白くなくなったと言われていた。
このように話を遡りながら当時の中西氏の文章を読むと痛快極まりない。隅々に中西氏がなぜその表現を用いたか読み取れるのである。
文芸と野鳥・科学を単に融合させたものではなかった。単に文芸と科学を融合させれば当時の「野鳥」の雰囲気を再現できるわけでもなく、今となっては状況を再現できない現在においては、「野鳥」誌も形だけ縦書きの古い形式を引き継ぐことにこだわることはないのでは。
さて、全国鳥類繁殖分布調査の報告書を見ても 1974-1978, 1997-2002 では低地に空白地帯がある程度認められる。2016-2021 の京都付近のランク A の点は自分がアンケート調査で打ったものなので、繁殖確認は案外なされていものと想像できる (探鳥会でも簡単にわかる種類しか聞いていないので巣立ち雛の声を気に留める人はほとんどない)。
ランク A のメッシュ数はこの3回の調査でほとんど変化がないので、繁殖確認は特に増えていない。
かつては声を聞いても後に聞かなくなれば当時の常識に従って旅鳥と判断されていたものが、現在では繁殖の可能性ありと判断されるようになっただけかも知れない。
声を知っているかどうか次第の部分が大きく、過去には繁殖していないと思われていたので旅鳥扱いで低地で記録点がなかったのか、本当に繁殖していなかったのか判断が難しい印象も受ける。つまり巣立ち雛の声や親鳥の警戒の声を知っている人は 50 年近く経っても増えていないのだ。
中西悟堂「定本・野鳥記」2 p. 70 (1936 年の記録) にもカタカナ表記で十分理解できるセンダイムシクイの幼鳥と親鳥の声が記述されていた。センダイムシクイの親鳥の警戒の声は、鳥の声を少し知っている人はキビタキの地鳴きと判断しているかも知れない。
以前は低地にも豊富にいた鳥かどうかは、カッコウやホトトギス程度の声のみが認識できた程度の時代には記録も残っていないのだろう。声を知った上で意識して聞かないと記憶に残らない。鳥の声に馴染みのない方にセンダイムシクイの声を指して指摘してもわかってもらえないことがあった。音声のパターンを知っていないと認識困難であろう。我々が馴染みのない言語を聞いても音すら把握できないのと同様。例えばロシア語の y の音 (キリル文字表記では ы) を発音するだけで今何と言ったのかと聞き直される。センダイムシクイの声も知っているならこそごく当たり前に聞き取れる。
センダイムシクイの名前は過去にも存在したものだったが、現在のセンダイムシクイの概念は比較的新しい時代に与えられたものと考えられる。
「京都の野鳥図鑑」p. 223 ではメボソムシクイも4月下旬になると1週間ぐらいで通過してゆく旅鳥、となっていてセンダイムシクイと同じ時期なのは自分の感覚とはやや異なる。センダイムシクイは昔はかなり少なかったのだろうか。
エゾムシクイの方が少し早い時期が示されていてこちらは合っている感じがする。
[音声]
さえずりのフレーズ途中で「超音波」とも呼ばれる (実際には聞こえるので超音波ではないが) 音声を混ぜることがある。センダイムシクイ (バードリサーチ) にある「高い声」(さえずりのフレーズ合間のヤブサメのような高い声)。繁殖地で懸命にさえずっている時に出すことがあるが近くでないと聞こえない。渡り途中にこの声だけで鳴いていて何かわからなかったが、その後姿も見られ普通のさえずりもあってセンダイムシクイと判明したことがある。
キビタキの地鳴きのようなヒッ、ヒッ...の声を出すこともあるが、これは多くの場合警戒の声で近くに巣があるか巣立ちびながいる可能性が高い (以後#オオルリの備考参照)。
この声は渡来初期にも聞かれ、牽制行為や相互の争いでも用いていると思われる。
その他単独の「ビッ」という声も出す (さえずりのフレーズ前に出すことも多い。サンコウチョウの地鳴きに多少似ている)。
他にさえずりの断片やさまざまなバリエーションの声があり、聞き慣れない声を聞いた時は正体をよく確認する必要がある。巣立ちびなの声はヤマガラの地鳴きまたは餌乞いの声 (begging call) に特によく似ていて紛らわしく、ソノグラムでも類似して見えるぐらい。類似した特徴の声はコサメビタキの地鳴きにもあって繁殖時期が重なるので要注意。
ヤマガラの地鳴きとみなして聞き逃している場合もあるかも。低山の夏鳥の巣立ちびなの時期の音声聞き分けは難易度が高い。
[ロシア沿海地方のセンダイムシクイ]
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the eastern crowned warbler Phylloscopus coronatus (pp. 5407-5428)。
ロシアのセンダイムシクイのさえずりがだいぶ異なることに気づいた。ウスリーのタイガの声 5:31 から。このビデオは初めて見た。解説に種一覧が出ているので参考までに。
-
イイジマムシクイ
- 学名:Phylloscopus ijimae (ピュルロスコプス イイマエ) 飯島のムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:ijimae (属) 動物学者 飯島魁 Isao Ijima の (ijima -ae (f) 飯島)
- 英名:Ijima's Leaf Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
ijimae はラテン語読みを示した (-ji- を "ジ" と読めない言語も多い)。後半の "イ" はヤ行の "イ"。日本人が読む場合は "イジマエ" でも構わないと思う。
単形種。
記載時は Acanthopneuste ijimae Stejneger, 1892 (原記載)。
黒田長礼 (1926) の研究でセンダイムシクイの亜種とされ、この分類が後続の研究者にも認められていたが、Austin and Kuroda (1953) がさえずりと営巣習性の違いから独立種とした (文献)。
Williamson (1976) は当時のエゾムシクイ (現在のアムールムシクイが基亜種だった時代) の亜種 Phylloscopus tenellipes ijimae として扱った。音声および DNA の違いから現在は独立種とされている (wikipedia 英語版より)。
Martens (2010) (#キタヤナギムシクイの備考参照) によるとセンダイムシクイとはかなり差がある見解が示されていたが、Alstrom et al. (2018) ではセンダイムシクイと近縁となっている。
天然記念物。絶滅危惧 II 類 (VU)。生息地の台湾、中国、フィリピンのいずれでもレッドデータブックあるいは相当するリストに入っている。かつてはイイジマメボソの名前があった。
渡部 (2011) Birder 25(3): 41 イイジマムシクイの渡りの謎に迫る。伊豆諸島で繁殖した個体は8月中旬から9月にかけて紀伊半島から四国の山岳部を通過し、大隅半島経由で沖縄以南の島に渡っていると思われるとのこと。
加藤 (2024) Birder 38(8): 46-49 に渡り時期 (特に九州南部) のイイジマムシクイ発見・識別方法についての記事がある。
地鳴きを xeno-canto でチェックしてみるとムシクイ類ではチフチャフの亜種 tristis に似ている印象を受けるが皆さんはいかがだろうか。センダイムシクイ、キビタキの地鳴きは音がもっと低い。エゾムシクイは音程は似ているが音が一般にもっと短い。
そういえばと思い出したがモリムシクイは音程はずっと低いが地鳴きのパターンは似ている。
日本産の他のムシクイ類では似たものを思いつかない。チフチャフとは系統が違いそうなのに似た点があるのはなぜかと考えてしまう (あるいは音声にも収斂進化のような現象があるのだろうか)。
そのつもりで日本産ムシクイ類の地鳴きをしていただくと面白いと思う。
引用されている Crystal (2005) に関して、Iijima's Leaf Warbler で解説が読める。
論文の記載されている雑誌は Ijima's Leaf Warbler。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ズグロムシクイ科 SYLVIIDAE ▽
-
コノドジロムシクイ
- 第8版学名:Curruca curruca (クルルーカ クルルーカ) コノドジロムシクイ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Sylvia curruca (シュルビア クルルーカ) ムシクイの森の妖精
- 第8版属名:curruca (外) Kruka コノドジロムシクイを指す古スウェーデン語 (The Key to Scientific Names)
- 第7版属名:sylvia (f) 森の妖精
- 種小名:curruca (外) Kruka コノドジロムシクイを指す古スウェーデン語 (The Key to Scientific Names)
- 英名:Lesser Whitethroat
- 備考:
curruca はラテン語では2つ目の u が長母音になっている。アクセントもここにある (クルルーカ)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Curruca 属に変更。種小名は変化なし。Curruca 属はノドジロムシクイ属。このため Sylvia 属は日本産鳥類から消える見通し。
分類の見直しは Voelker and Light (2011) Palaeoclimatic events, dispersal and migratory losses along the Afro-European axis as drivers of biogeographic distribution in Sylvia warblers の分子系統研究による。
新 Sylvia 属に属する有名な種類にズグロムシクイ Sylvia atricapilla (英名 Blackcap) がある。科名 Sylviiidae はズグロムシクイ科のまま。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種不明。世界に3亜種 (IOC)。ヨーロッパでは一般的な鳥だがユーラシアのかなり東方にも分布する。モンゴルなどで記録される東方の亜種は blythi (英国鳥類学者 Edward Blyth 由来) とされる。
地鳴きはウグイスに似るもののウグイスを聞き慣れていると微妙な違いが感じられるとも言われる。聞き分けは難しい。違うタイプの地鳴きもある。
△ スズメ目 PASSERIFORMES メジロ科 ZOSTEROPIDAE ▽
-
メグロ
- 学名:Apalopteron familiare (アパロプテロン ファミリアーレ) よく知られた繊細な羽の鳥
- 属名:apalopteron (合) 繊細な羽の (hapalos 繊細な phtero 羽 Gk)
- 種小名:familiare (adj-f) よく知られた (familiaris)
- 英名:Bonin Honeyeater (小笠原諸島の) この英名はミツスイ類に近縁と考えられた時のもので、現在では (IOC でも同じ) Bonin White-eye が使われる
- 備考:
apalopteron は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語はいずれも短母音のみで長母音は現れないと考えられる。この場合は "アパロプテロン" のアクセント位置と考えられる。
familiare は2つめの a が長母音でアクセントもここにある (ファミリアーレ)。
記載時学名 Ixos familiaris Kittlitz, 1830 (原記載)。基産地 'Boninsima'; restricted to Muko Shima, northern Bonin Islands, by Yamashina, 1930, Tori, 6, p. 330 (Avibase による)。
原記載では dem Besucher von Boninsima zumeist und gewoehnlich auch zuerst ins Auge faellt (Boninsima の採集人にとってまず最初に見かける見慣れた鳥) で、haeufiger Vogel des Landes scheint Ixos familiaris die Berge ueberall, wo nur Gebuesch ist, zu bewohnen と茂みのあるところならば山の至るところごく普通に生息する鳥としてこの命名となった。
属はよくわからない部分があって Ixos 属に入れたよう。
Ixos 属については#ヒヨドリの備考 [属名の問題とヒヨドリ属の特徴] 参照。Temminck (1825) の用いた属で Trudoiden (ツグミ類似) と表現されていた。
現在はこの属はムナフヒヨドリ Ixos virescens Javan Bulbul をタイプ種とするヒヨドリ類に使われている。Temminck 自身はクロサンショウクイ Campephaga phoenicea Red-shouldered Cuckooshrike を Trudoide のタイプ種として定義したものの、この箇所で Ixos 属が示されていなかったためにムナフヒヨドリをタイプ種とする属となったとのこと (The Key to Scientific Names)。
いずれにしても全然似ていない。Kittlitz 自身は Muscicapa との比較も行っているが全般的にはツグミ類似と考えていたよう。
#メジロの備考のように Zosterops 属が設けられたのは Vigors and Horsfield (1826) とメジロ類との類縁性を議論する以前の段階だった。種メジロの記載は 1845 年でメグロの方が早い。早く記載されすぎて類縁系統が見つけられなかったよう。
Apalopteron 属は Bonaparte (1854) が導入したもの。この時は Bonaparte は Schiff. のペンネームで記載しており、Gray が Jora familiaris とすでに属を変えていた (The Key to Scientific Names)。
Jora はヒメコノハドリ 現在の学名で Aegithina tiphia Common Iora を指していた。外見はこちらの方がまだ似ている。
なお "コノハドリ" と Iora に何の関係があるのだろうと思われるだろうが、当時は分類がよくわからず "leafbirds" に含められていたため。メグロがどこに含まれていてもおかしくなかった。
現在はヒメコノハドリ科 は カラス小目 Corvida、コノハドリ科 Chloropseidae と ルリコノハドリ科 Irenidae は スズメ小目 Passerida とそもそも全然異なるものであることが明らかになって英名は付け直されたが、和名は過去に (おそらく) 英名から訳したものをそのまま残しているため対応関係がわかりにくくなっている。
コンサイス鳥名事典ではヒメコノハドリの属名 Aegithina はアオガラに似た (鳥) の意味であるが似ていないとある。#エナガの属名解説にあるように、アリストテレスの記述した3種の鳥の総称 aegithalos があり、この中にアオガラが含まれているとされているのでおそらくこちらと同意と判断されていたものであろう。Aegithina は同じくアリストテレスの記述した aigithos または aiginthos 由来と解釈されている (The Key to Scientific Names)。
2亜種あり。familiare 日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で亜種ムコジマメグロと改名され、亜種メグロの名前はなくなる見込み (絶滅亜種)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。hahasima ハハジマメグロ。
Apalopteron 属は現状単形属。
メグロの系統は長らく議論があり、ヒヨドリ類 (Ixos 属)、(Jora 属は現在はヒメコノハドリ科)、チメドリ類 (後述 Delacour 1946)、ミツスイ類 (後述 Deignan 1958) それぞれに近縁と分類されることがあった。しかし記載当時はメジロ類があまり知られておらず、Temminck (1825) の Ixos 属もヒヨドリ類とサンショウクイ類が混ざっていたのでこの当時何に分類されたかはあまり重要でないかも知れない。
分子系統研究によりメジロ類に近いことが判明した。Springer et al. (1995) Molecular Evidence That the Bonin Islands "Honeyeater" Is a White-eye。
樋口 (1996) Birder 10(4): 74-75 に「メグロはメジロの1種」の記事がある。
マリアナ諸島のオウゴンミツスイ (過去の分類が残った名前である) Cleptornis marchei (英名 Golden White-eye) が最も近縁とわかった。
オウゴンミツスイはかつてミツスイ科に分類されていたが、行動や分子遺伝学研究によりメジロ科に移された (wikipedia 英語版)。この情報は少し古かったので以下に追記。
山崎 (2019) Birder 33(6): 20-21 にもメグロの位置づけについての記事がある。ここに記載の "樹上にいることが多いものの、茂みの中や地面にも降り、時には木の幹に止まったり、そこをよじ登ったりもする" に相当する部分は原記載では
(Es ist ein flinker, lebhafier, aeusserst artiger Vogel),
den man gleich haeufig auf den Wipfeln der Baeume, als im niedrigsten Gestraeuch und selbst auf den Boden suchend antrifft. (この部分は要約にほぼ同じ。木のてっぺんと同じぐらい頻繁に最も低い枝にも降りる。探しながら地上にも降りる)
Zuweilen sah ich ihn sogar die Stellung eines Spechts annehmen und ganze Strecken an den Staemmen emporlaufen, was mich im Anfange mehrmals veranlasst hat, ihn fuer irgend einen mir unbekannten Klettervogel zu halten.
に相当する。キツツキのような姿勢で木にとまり、最初のうちは知らない (広い意味で) ゴジュウカラ類かと思った、などの記述になっている。
ここで紹介されている研究は:
Deignan (1958) The Systematic Position of the Bird Genus Apalopteron (ミツスイ科と考えた論文)、
この Deignan (1958) で引用されている Delacour (1946) Les timaliines (チメドリ科に入れた。p. 21 本文, p. 29 分類表)。
Apalopteron 属を設けた Bonaparte (1854) は当時の "Timaliindae" に含めたが、かつての "Timaliindae" は現在の分類とは大きく異なったものでその後アカヒゲもこの分類に含まれることになり、これを現在チメドリ科と呼ぶのはふさわしくなさそう (チメドリ類については別項目に分離した)。
Sharpe (1882) は Pycnonotus とメグロをヒヨドリ類に戻した (ヒヨドリ類の分類は現在でも混乱しているのでややこしかったことはやむを得ない)。
ということで現代的な意味に対応するチメドリ科に入れたのは Delacour (1946) が最初になる。
Delacour (1946) が近縁と考えた属は Actinodura (和名ではシマドリやチメドリの名前が多く付いている) や Minla (現在 Actinodura に統合)。
大事な情報源であるはずの Morioka and Sakane (1978) Observations on the Ecology and Behavior of Apalopteron familiare (Aves, Meliphagidae). Memoirs of the National Science Museum, Tokyo. 11: 169-190 は国立科学博物館でオンライン公開されている範囲には含まれておらず、オンラインで読めるところがあるのかよくわからない。
古いリンクが wikipedia 英語版にあるのでかつては pdf が読めたものと想像できる。
分子系統解析の方は Cai et al. (2019) Near-complete phylogeny and taxonomic revision of the world’s babblers (Aves: Passeriformes) (出版社サイト)。
Cai et al. (2020) The role of evolutionary time, diversification rates and dispersal in determining the global diversity of a large radiation of passerine birds で同一データによる系統樹と種分化速度の研究が見られる。
この 2020 年系統樹ではセラムメジロ Tephrozosterops stalkeri Bicolored White-eye (単形属。絶滅種) が近縁種となっているが、2019 年論文とは少し異なる。
まだ限られた遺伝情報に基づく系統樹で系統樹サポート率も低いため、単系統性に基づく属の再編の必要性などの検討は本格的に行われていない模様。IOC 14.2 では Apalopteron may be embedded within Heleia, but STET pending a more comprehensive analysis (Cai et al. 2019) と記述されている。
Apalopteron Bonaparte, 1854 の方が Heleia Hartlaub, 1865 より古いので、もし統合すると多くの種の属名が変わってしまうため系統樹の信頼性が上がるまで少し待とうとの判断と思われる。Apalopteron は本来特殊な性質の1種を指す属名だったので広範囲の種を指すのは紛らわしい。
状況はチドリ類の Anarhynchus 属 (ハシマガリチドリ1種を指す属名だった) に似ている (#タゲリの備考参照)。
チドリ類では属を細分することでこの問題が避けられるが、メグロは現在の系統樹では Heleia 属に内包されているので分割できずその回避方法もない。
Heleia 属自身もチモールハシブトメジロ Heleia muelleri Spot-breasted White-eye 1種に与えられた属名で、現在の Heleia 属の他種の属名は系統解析の結果最近変わったばかり。
それ以前は例えば Lophozosterops 属の種類が多かった (2020 年の系統樹でもこの属名が使われていた) が、統合とともにまとめられた次第。多数派の原則ではなく記載年代順になるため起きる現象。
IOC では 10.2, Clements/eBird では 2021 年に変わったばかりなので頻繁に属名が変わると困る...ということになるだろう。
全体を Zosterops 属にまとめるのも一つの解ではあるが、こちらも多くの種の属名が変わり、属統合には名前の衝突など問題も多くどちらにしても多分悩ましい状況と想像できる。
もとをたどれば#ウグイスの基亜種同様、Kittlitz の記載が例外的に早かったことも要因の一つとなるのだろう。
広義? Heleia 属は Zosterops 属の種分化の早い時期の、少し古い系統の東南アジア島嶼部の系統にあたる。
IOC 15.1 (2025.2) では Heleia 属で英名 White-eye が付いていたものを Clements などにならって Heleia に変更とのこと。もしメグロが現在の Heleia 属に内包されることが確実になれば将来 Bonin Heleia になるのだろうか (??)。
[チメドリ類について]
Old World babbler の wikipedia 英語版によれば "Timalien" (ドイツ語名) は Hartert によれば 19 世紀から 20 世紀の多くの期間はゴミ箱状態で、かつては分類できないものは何でもここに含めていたとのこと。
Hartert (1910) Die Voegel der palaearktischen Fauna systematische Uebersicht der in Europa, Nord-Asien und der Mittelmeerregion vorkommenden Voegel。
この記述当時の名称は Timeliindae だったようで、タイランチョウ同様そのまま読めばチメドリ類の和名になったのか?
由来となる当時の属名 Timelia の由来は timao 崇める helios 太陽 (Gk)。それ以前に Timalia の名称があったものの綴りが修正されたものだった。その後元に戻された (The Key to Scientific Names)。英名に sunbirds の名称の別系統の鳥があるが語源的には関係あるのか?
当時はヨーロッパから見た分類が中心で、Sylviidae (現在ズグロムシクイ科。古くはムシクイ類やウグイス類を含んでもっと広義だった)、Turdidae (古い概念のツグミ科)、Muscicapidae (古い概念のヒタキ科) とヨーロッパ産の鳥に似たものをそれぞれ分類して行った残りがしばしば Timeliindae に行ったよう。つまりヨーロッパから見て馴染みのないアジアの小鳥は "ゴミ箱状態" の "Timeliindae" に行きがちだったよう。
Hartert (1910-1922) 自身は 目次 にあるように過去の "Sylviidae", "Timeliindae", "Muscicapidae" を統合した Muscicapidae を採用していた。ムシクイ類なども全部まとめて "ヒタキ科" となっていたのはこの時期に遡るよう。
科の名称の記載は Sylviidae Leach, 1819、Timeliindae Vigors & Horsfield, 1827、Muscicapidae Fleming, 1822 となっていて必ずしも先取権の原則に合わせて統合したものではなさそう。
ソウシチョウ類 (Leiothrix 属) が何に近いかはよくわかっていなかったようで、Turdus 属に近い位置になっている。
この分類ではメジロ類はメジロ科でキバシリ科の近くに置かれている。全世界の鳥を扱ったものではないのでメグロは含まれていない。
Complete Checklist of the Birds of the World で現在の分類が過去どの科に属していたか経緯を見ることができるが、Sylviidae, Timeliindae, Muscicapidae は著者次第で相互に行き来していたようで、どの科に分類されていたかは決定的に重要なわけではなかったかも知れない。
現在のメジロ科も Muscicapidae, Meliphagidae, Illadopseidae, Timaliidae, Sylviidae に分類されていたことがあって要するに何でもありだった模様。
現代の分子系統研究による系統の包含関係は (Pycnonotidae ((Sylviidae + Paradoxornithidae) (Zosteropidae (Timaliidae (Pellorneidae (Alcippeidae + Leiotrichidae)))))) となっており、何でもありに近い状況はある程度裏付けられる。
さすがに Muscicapidae や Meliphagidae とは縁が遠いことがわかったが、メジロ科やソウシチョウ類は広い意味ではヒヨドリ類の仲間と言うこともできる。Kittlitz (1830) がメグロを Ixos 属に含めたのはそれほど大きな間違いだったわけではなかった。
-
チョウセンメジロ
- 学名:Zosterops erythropleurus (ゾーステーロープス エリュトゥロプレウルス) 赤い脇腹をした目に帯のある鳥
- 属名:zosterops (合) 目に帯のある (zoster, zosteros 帯 ops, opos 目 Gk)
- 種小名:erythropleurus (合) 赤い脇腹の (erythro- (接頭辞) 赤い pleuro 脇腹 Gk)
- 英名:Chestnut-flanked White-eye
- 備考:
zosterops は#メジロ参照。
erythropleurus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。語末から2つめの二重母音がアクセント位置で "エリュトゥロプレウルス"。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。ウスリーから中国東北部では夏鳥で東南アジアに渡る。メジロ科で長距離の渡りをする種類は珍しいとのこと。
茂田 (1999) Birder 13(2): 79 によれば日本鳥学会 (1922) の和名はコメジロ。朝鮮半島では通過鳥なので安倍他 (1976) の提唱したワキアカメジロまたはワキアカシロハラメジロの名称の方がふさわしいと述べている。
-
メジロ
- 学名:Zosterops japonicus (ゾーステーロープス ヤポニクス) 日本の目に帯のある鳥
- 属名:zosterops (合) 目に帯のある (zoster, zosteros 帯 ops, opos 目 Gk)
- 種小名:japonicus (adj) 日本の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Japanese White-eye, IOC: Warbling White-eye メジロ類の全般的な分類見直しによりこの名称が主に使われるようになった
- 備考:
zosterops は外来語由来の合成語なので発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語の長音を引き継げばすべての母音が長母音となる。この解釈で規則に従えば "ゾーステーロープス" のアクセントとなる (なおどのような解釈でも末尾の -ops にはアクセントはない)。
japonicus は綴り上は a と o が長母音だが古典ラテン語で使われる単語ではないため長音で読む事例はない模様。長音でなくともアクセント位置は "ヤポニクス"。
古典式ラテン語読み方に統一されたいならば "ヤーポーニクス" となるだろうか。
世界では 15 亜種が認められている (IOC)。日本のリストに記載があるのは6亜種で、japonicus 基亜種メジロ、stejnegeri (ノルウェー生まれの鳥類学者 Leonhard Stejneger に由来) シチトウメジロ、
alani (英国博物学者、採集家の Alan Owston 由来) イオウトウメジロ、daitoensis ダイトウメジロ、insularis (島の) シマメジロ、loochooensis (琉球が由来) リュウキュウメジロ、及び亜種不明である。
かつて (当時の分類で) ハイバラメジロ Zosterops palpebrosus 英名 Indian White-eye の亜種とされたこともあった。これも分割によってこの学名を持つ種は現在インドメジロとなっている。
現在はメジロのシノニムとされる Zosterops palpebrosus yesoensis Kuroda, 1951 も当時この種の亜種として記載されていた。
他にも Zosterops japonicus dageleticus Momiyama, 1930 (韓国鬱陵島。現在は基亜種 japonicus のシノニムとされる)、
Zosterops japonicus ohsimensis Momiyama, 1930 (伊豆大島。現在は 亜種 stejnegeri のシノニムとされる) も記載されていた。
Zosterops 属は Vigors and Horsfield (1826) が設けたもので、Lesson (1828) がタイプ種をマダガスカルメジロ Zosterops maderaspatanus Madagascar White-eye と定めた。この種は Motacilla maderaspatana Linnaeus, 1766 と記載された由緒あるもの。
メジロ属の "本家" はマダガスカルだった。
多くの Zosterops 属の種が目の周囲に白い羽毛の輪を持つ (The Key to Scientific Names)。
日本の現在の種メジロの記載は 1845 年 Temminck & Schlegel (原記載) でフランス語名は特になく学名をそのまま用いている。類縁の身近な種類がヨーロッパにないため適切なフランス語がなかったのだろう。
日本の Zosterops 属は1種のみとの記述があり、複数種の存在する地域ではないので "日本の" と付けてよい判断があったものと想像できる (他の地域では複数種が見られて地名ではなく特徴による記載もみられる)。
基産地は Japan; restricted to Decima, Nagasaki by Mees, 1957, Zool. Verh. Rijksmus. Nat. Hist. Leiden, no. 35, p. 99 (後に出島に限定。Avibase による)。
かつての英名はおそらく学名をそのまま訳したものと想像できる。
かつて同種とされたハイバラメジロ/インドメジロの方が記載が早い Sylvia palpebrosa Temminck, 1824。この時期にはまだ Zosterops 属は提唱されていなかった。ハイバラメジロの記載が早いため同種扱いの時はメジロはこの種の亜種となる。ハイバラメジロが種に分割される前は Oriental white-eye と呼ばれていたとのこと (wikipedia 英語版から)。
Zosterops 属全体で見ると 18 世紀の記載はマダガスカルからレユニオン島、モーリシャス島、バヌアツと離島のものが相次いであり、次に古いものはオーストラリアのハイムネメジロ Silvereye で Latham (1801) による。
Silvereye の対比的な名称から想像するとこの時代にはすでに white-eyes の名称はあったのだろう。
次に古いのがジャワメジロ (Horsfield 1821) と植民地化とともに博物学者も入って記載が進んだ経緯が推定できる。ハイバラメジロ/インドメジロ がこの次となったのも自然な順序だったのだろう。
このころには目の周りの白いよく似た小鳥が複数種存在することが明らかになって、属を新たに設ける機運が高まったものと想像できる。
かつての種メジロにはフィリピンからインドネシアの広範な亜種が含まれていたが、過去に同一種とみなされたこともあった中国のヒメメジロ Zosterops simplex (英名 Swinhoe's white-eye) は別種となった (この種にも複数の亜種がありメジロと近縁種の分類は非常に複雑である)。
分類見直しと分布地域の変更に伴い、英名も Warbling White-eye (IOC 9.1 から) が一般的となった (語義は#ウグイスの備考参照)。かつて Mountain White-eye と呼ばれたものも含む形となり、大陸にも分布するため Japanese の英名は適切でないと判断されたものと想像できる。
ハワイやアメリカ本土の一部に持ち込まれて移入種となっている。
Zosterops 属の学名にしばしば女性種小名が付けられているのを見ることがある。例えば Zosterops japonica。これはギリシャ語 -ops の語尾は男性名詞にも女性名詞にもなり得るものだったため。1985 年の国際動物命名規約で属名の -ops は男性名詞と定められたため現在の種小名の性に統一されている [茂田 (1999) Birder 13(2): 36]。
フクロウオウム (カカポ) の属名の Strigops も同様の例とされたが、旧種小名 habroptila はかつて形容詞と考えられたため。2023 年の検討で合成名詞と判定され habroptilus となった (IOC 14.2)。
メジロ識別マニュアル (環境省 2016) も参照。このマニュアルはメジロ類の全般的な分類見直し以前のもので、フィリピン、インドネシアの亜種は含まれていない。
このマニュアルに記載されている別種フィリピンメジロは現在も Zosterops meyeni (英名 Lowland White-eye) であり、フィリピンに分布する現代の分類のメジロの亜種 (pectoralis, vulcani) とは異なる。
上記マニュアルの著者である茂田 (1999) Birder 13(2): 72-79 の「メジロ (1)」に (当時の分類での) メジロの亜種と、日本周辺のメジロに近縁の種類の解説がある。この中で亜種キクチメジロ batanis (フィリピン北部の Batan 島由来) への言及があり (これは現在でもフィリピンメジロの亜種とされるが検討の余地があるとのことである)、茂田氏によればフィリピンメジロはメジロの音声に反応せず、別種と考えられると記されていた。
上記マニュアルでは亜種キクチメジロはフィリピンメジロの亜種となり、フィリピンメジロの亜種キクチフィリピンメジロと改名され、台湾南東沖の紅頭嶼 (蘭嶼) と火焼島 (緑島)、およびフィリピンのバタン諸島に分布すると記載されている。
Japanese White-eye が従来の英名で、フィリピンのものが ヤマメジロ Zosterops montanus とされていたが、下記の 2018 年の分類見直しにより統合され標準的な英名も Warbling White-eye と変更された。
かつて Zosterops japonicus に含まれていたいくつかの亜種はヒメメジロ Zosterops simplex (英名 Swinhoe's white-eye) に分離されたが日本産亜種は含まれていなかった (wikipedia 英語版より)。
このように外見が非常に似ているにもかかわらず複数の種に分けられることになった根本的要因が最近明らかにされた。みかけから想像される以上に生殖隔離が生じている模様。[Great Speciator] を参照。
見かけと地理分布だけでは種または亜種境界を見極めることが難しいようで、日本の島の亜種も研究が進めば種として分離されるものが出てくるかも知れない。
2018 年の変更も限られた遺伝子による分子系統しか見ていないので Great Speciator の特異な性質は十分に反映されていない可能性がある。音声応答実験などで再度細分される可能性もある。Zosterops 属はすでに 100 種以上となり、種分割好みの Boyd もほとんどあきらめ気味の様子。
世界のメジロ図譜 増補改訂版 (全国野鳥密猟対策連絡会 2016) では H&M 4.2 に基づき Zosterops 84 種の図版を掲載している。
輸入メジロ (チョウセンメジロ) が多数放鳥されたはずだが目立った雑種形成などの事例がないのも Great Speciator の特性による生殖隔離機構が関係しているのかも知れない (要検証)。
日本近傍のメジロ類の亜種が複雑になったため整理しておく。
・Zosterops erythropleurus チョウセンメジロ Chestnut-flanked White-eye (単形種。長い渡りをする)
・Zosterops japonicus メジロ。このうちフィリピン北部の亜種 (及びヒメメジロの各亜種) は最近までメジロの亜種とされていたもの。亜種学名の後に * があるものが ヤマメジロ に一時分類された後 2018 年の分類改訂で編入されたもの。
| 亜種 | 和名 | 分布 |
| japonicus | 亜種メジロ | 日本、朝鮮半島沿岸部、サハリン南部 |
| stejnegeri | シチトウメジロ | 伊豆諸島鳥島まで |
| alani | イオウトウメジロ | 硫黄島 |
| insularis | シマメジロ | 琉球列島北部 |
| loochooensis | リュウキュウメジロ | 琉球列島南部 |
| daitoensis | ダイトウメジロ | 大東諸島 |
| obstinatus * | | Ternate, Tidore, Bacan Islands (インドネシア ハルマヘラ島の西) and Seram Island |
| montanus * | ヤマメジロ | スマトラ島山地、ジャワ島、バリ島、小スンダ列島、セレベス島、モルッカ南部 |
| difficilis * | | スマトラ島南部 Mount Dempo |
| parkesi * | | パラワン島 (フィリピン) |
| whiteheadi * | | ルソン島北部 (フィリピン) |
| diuatae * | | ミンダナオ島北部 (フィリピン) |
| vulcani * | | ミンダナオ島中央部 (フィリピン) |
| pectoralis * | | ネグロス島 (フィリピン) |
| halconensis * | | ミンドロ島 (フィリピン) |
・Zosterops simplex ヒメメジロ Swinhoe's white-eye (かつてメジロと同種。短い渡りをする)
| 亜種 | 和名 | 分布 |
| simplex | 亜種ヒメメジロ | 中国東部、台湾、ベトナム最北部 |
| hainanus | ハイナンメジロ | 海南島 |
| erwini | | タイ-マレー半島沿岸部、スマトラ島低地、Riau Islands, Bangka Island, Natuna Islands、ボルネオ島西部低地 |
| williamsoni | | タイランド湾沿岸、カンボジア西部 |
| salvadorii | | スマトラ島西部 Enggano Island |
・Zosterops meyeni フィリピンメジロ Lowland White-eye
| 亜種 | 和名 | 分布 |
| batanis | キクチフィリピンメジロ | 台湾南東部蘭嶼などの島、フィリピン北部の離島 |
| meyeni | 亜種フィリピンメジロ | カラヤン島、ルソン島、ミンドロ島など |
杉田 (2016) 86年ぶりに小笠原諸島のメジロの起源を調べた (日本鳥学会) のオンライン記事も面白いで紹介しておく。
論文は Sugita et al. (2016) Origin of Japanese White-Eyes and Brown-Eared Bulbuls on the Volcano Islands。
メグロとメジロの間で競争排除があった可能性も議論されているが、現在の個体群の間では目立った種間競争は見られない報告がある。メグロの方が系統的には古いので (#メグロの備考参照)、メグロが定着した時代はもっとメジロに似た種類だったのかも知れない。後に到達したメジロとの間で競争排除が現代より顕著にあったのかもと感じた。
[鳥類の味覚]
古い本を読むと鳥類には味を感じる 味蕾 (みらい taste bud) が少なく、しかも舌の前の方ではなくのどの入口近くに分布するため、飲み込む時にようやく味がわかる程度の「味音痴」とよく書かれていた。
一昔前になるが、ハチドリが甘味受容体なしで甘味を感知できるとの研究が出された ハチドリ、甘味受容体なしで甘味を感知 (ナショナルジオグラフィックの日本語記事)。Baldwin et al. (2014) Evolution of sweet taste perception in hummingbirds by transformation of the ancestral umami receptor
もともとは甘味受容体を持っていなかったが、「旨味」の受容体のアミノ酸配列が少し変わることで甘味も感じることができるように進化したとのこと。
この研究が出た時、鳥のことを少しでも知っている人ならばたちどころに「メジロが甘いものを好きなのは承知の事実」と考えたことだろう。
Baldwin のグループもやはり同じことを考えたようで、ハチドリの他、オウム類、スズメ目でそれぞれ独立に甘味を感知できるように進化したとの研究を発表した。スズメ目でメジロ類以外にもいくつかの系統で進化したとのこと。
Toda et al. (2021) Early origin of sweet perception in the songbird radiation。
筆頭著者他に日本の研究者が含まれているため日本語資料も豊富にある。これも Baldwin グループの一連の研究の一つ。
鳥が花蜜を味わう新たな仕組みを解明「スズメ亜目を鳥類最大の種数へ繋栄させた糖の受容機構」が明らかに、
(同上)
をご覧いただきたい。
鳥類の味覚は Niknafs et al. (2023) The avian taste system の総説が詳しい。この分野は日本の研究者の論文もいくつもあるので引用文献を参照していただくとよいだろう。
3種類の味蕾があり、type I が舌などに存在するもの。type II が舌で食物を探る鳥のもので、マガモでは嘴の先端でも味を感じる。type III が長い嘴と舌を持つもので、キツツキ類、ハチドリ類、オウム類など。
形態的には哺乳類のもの (4種類) と同じようなものがあるが種類による。
T1R1-T1R3 ヘテロダイマー (heterodimer 異なるタンパク質分子からなる二量体) の受容体は調べられたすべての食性の鳥に存在し、食べ物中の栄養分のアミノ酸を感知していると考えられる。T1R1-T1R3 の変異によってアミノ酸と糖に対する感度が変化し、糖分の多い食物を食べる鳥はこれを利用している。
アマツバメに比べてニワトリの受容体は L-アラニン とよく結合し、これは食性も反映している。しかし T1R1-T1R3 はニワトリの味蕾ではあまり発現していないので今後の研究が必要とのこと。
これら以外にも mGluR1 など複数の味覚受容体が鳥類の口腔に発現している。
鳥類の祖先系統は甘み受容体である T1R2 を持っていたが失われた。一部の系統で T1R1-T1R3 の変異次第で炭水化物への結合能力を増して甘み感覚を再度獲得した。アミノ酸と糖分は一般的には混ざって存在することが多く、その割合に応じて対応する感度変化が起きているとのこと。
昆虫食、雑食、肉食の鳥 (ハヤブサ類やフクロウ類も) も一般的に甘い液体を受け入れるが感度は種により異なる。ニワトリの甘い物への感度が非常に悪かったため鳥は味をあまり感じないと考えられてきた部分があるよう。
T1R1-T1R3 の変異以外にも甘みを感じる機構がある。哺乳類と同様の SGLT1 が口腔にあって T1R2 を失っても糖分を検出している可能性がある。SGLT1 は小腸でも発現してマウスは小腸で砂糖に反応しているという。
Cockburn et al. (2022) Synergism, Bifunctionality, and the Evolution of a Gradual Sensory Trade-off in Hummingbird Taste Receptors
によれば系統の近いアマツバメ類とハチドリ類の比較でアマツバメ類はアミノ酸 (旨味) のみ反応して糖には反応せず、混ぜても効果に変わりはないがハチドリ類ではアミノ酸と糖のそれぞれの効果を足し合わせた以上の反応を示すとのこと。ただし同じ受容体でアミノ酸と糖の両方を感じるためハチドリ類ではアミノ酸への感度は多少犠牲になっているとのこと。飲み込んでいるだけのように思えるアマツバメ類もアミノ酸の味を感じているらしい。
苦味受容体は T2R で哺乳類と共通している。有害物質を排除するのに役立っていると考えられるが、食性や種によってかなり異なる。T2Rs は肉食、魚食などの鳥には少なくスズメ目で一般に多い。防御物質を含む食物を食べる種類に多いが、蜜を食べる鳥にも多く受粉にかかわる花粉の味への特異性の現れか。
羽毛に毒を持つ鳥や警告色の鳥が存在する点に関連して猛禽類に味がわかるのか話題になることもあるが、苦味を感じる機能も持っていることがわかる。解剖学的な舌の構造は Abumandour and El-Bakary (2016)
Morphological features of the tongue and laryngeal entrance in two predatory birds with similar feeding preferences: common kestrel (Falco tinnunculus) and Hume's tawny owl (Strix butleri)
を少し見ていただくとよさそう。チョウゲンボウもウスイロモリフクロウ Strix butleri Omani Owl のどちらも舌に味蕾があるが分布が多少違う程度。チョウゲンボウでは舌根部には舌腺の開口部がないが味蕾は多数あるとのこと。
昆虫食は広い意味で肉食と同じではないかと言われることもあるが、昆虫食の方が苦味感覚を要求されるようで味覚に関してはかなり違うようで、昆虫の化学防御を反映しているのだろう (この点は#ゴビズキンカモメの最新のゲノム解析でも指摘されている)。
鳥類の味蕾の分布の理解が遅れた理由は例えば Niknafs and Roura (2018) Nutrient sensing, taste and feed intake in avian species ニワトリでは上口蓋の唾液腺開口部の隠れた場所にあった。
Madkour et al. (2024) Scanning Electron Microscopy of the Oropharyngeal Floor of Northern Bobwhite (Colinus virginianus, Linnaeus, 1758) Focusing on the Numerical and Regional Distribution of the Taste Buds コリンウズラの電子顕微鏡による解剖学的研究など。味蕾は舌表面よりは口腔の他の部分に多い。
飲み込む時にようやく味がわかるとの従来の解釈は相当古い。
海鳥以外では好みの塩分濃度があるようで塩味の感覚は哺乳類と似ている可能性がある。他の味は味蕾が感知しているが塩味は複数の感覚細胞が働いている。カルシウムは鳥に非常に重要であり、哺乳類同様に CaSR が働いている可能性があるとのこと。カルシウム摂取に関係する野外行動は記載があるが、実験的に調べられているのは家禽に限られるよう。
ハト類が塩やカルシウムの含まれた水を好むのはおそらくこれらが働いてそうだが特に記述はない。
酸味は哺乳類同様に OTOP1 が働いていると考えられるがあまり調べられていない。
脂肪酸の味は FFARs が検出していると考えられニワトリの口腔に発現しているとのこと。実験的には脂肪酸の種類によって好みがあるようで、哺乳類と似ているのではないかとのこと。
アミノ酸、塩分、脂肪酸を感じ、{旨味から甘み} を種差があるものの感じていて味に好みがあるとすれば一般に想像されるほど我々の感じている味と違わないのかも知れない。舌や口腔のどの部分に感度があるか、甘み感覚をあまり持たない種類がある点が主な違いだろうか。
猛禽類でも多少は甘みを好むことや、他の味覚も他の鳥と同様に持っていることは #クロハゲワシの備考 [猛禽類の植物食] の解釈に都合がよいかも知れない。
脂肪分への好みはいかにも味覚が関係ありそう。
ゲノム [および脳科学: #ハチクマ備考で紹介の PrV 核] 時代になって解明が急に進んだ印象を受ける。逆に言えばゲノム時代以前に書かれた書物の記述はあまり信頼しない方がよさそう...(x)。日本語解説も出ているのだろうと想像するが、分子系統学同様分野の進展が非常に早いので英語総説論文 (があるのが助かる) を読むのが手っ取り早そう。
タカ類の苦味受容体の研究: Xiang et al. (2025) Functional decline of a bitter receptor gene in New World vultures (別リンク。著者原稿)。
この研究で調べられたタカ類全般 (ハゲワシ類 6 種と他 22 種) で苦味受容体 Tas2r1, Tas2r2 の遺伝子を保持していたがミサゴは例外とのこと。Tas2r3 はすべてのタカ目で偽遺伝子化したか失われていたとのこと。フクロウ目では保たれており、タカ目特有の現象と考えられるとのこと。
サンプルにはヘビクイワシも含まれており他のタカ類とあまり違わない。
ミサゴでは3つの遺伝子がすべて偽遺伝子化していた。
3つの遺伝子の機能を同様に失っている他の例ではペンギン目やアビで知られているとのこと。
何とミサゴは苦味を感じないのかも? ミサゴ科とタカ科の分岐は非常に古いので苦味機能をどの時点で失ったのか、魚食への適応のためなのか別に理由があるのか興味あるところ。
比較的早めの時期に失っていたならばミサゴ系統が現代のタカ科に相当する位置を占めて適応放散できなかった理由の一つになるかも知れない。著者はペンギン目やアビ同様に完全魚食の食性が理由と考えている。
Policarpo et al. (2024) の解析にはミサゴは含まれていなかった。
T2Rs は肉食、魚食などの鳥には少ないとの Niknafs et al. (2023) との結果と合わせると、肉食と魚食で二重の意味で苦味の味覚の必要が薄れミサゴでは失われたのかも。味覚がペンギン目やアビに似ているとすれば姿・形はタカだがここでも海鳥に機能的に収斂進化していることになる。
Tas2r2 の配列から予測されるタンパク質と苦味物質の結合性を計算機で評価すると、新世界ハゲワシ類 (コンドル類) では旧世界ハゲワシ類に比べて結合が弱いことが示唆され、この点は用いた物質種類はより少数だが細胞を用いた実験でも確認された。
遺伝子維持のための選択圧が弱まっている理由を考えつくのは難しく、著者は死体食への適応のために苦味物質を感じない進化が起きたと推定している (従来見解的)。
しかし旧世界ハゲワシ類 (Gyps 属やヒゲワシ) には存在して他のタカ類と感度があまり違わないことから、死体食の適応のための必然的結果とは考えにくい感じがする。系統特異的に失う例は他にも知られているとのこと。生態的には収斂進化と言えても似ていない部分もある。
もっともヒゲワシ亜科は1種しか調べられていないのでこの亜科の旧世界ハゲワシ類を調べる必要があると記されている。
新世界ハゲワシ類が苦味に鈍感なことは人工的な毒物などを排除する機構が弱く、現代の環境では保全上考慮すべき点になり得るとのこと。
逆に言えばほとんどのタカ類は苦味受容体を役立てていることがわかる。ハチクマはこの研究に含まれていないが近い系統 (とは言え多少遠い) のオナガハチクマ Henicopernis longicauda が含まれていて他のタカ類と違わないように見える。ハチクマはおそらく苦味感覚を持っていると想像できる (動物園でも古い肉は拾っても捨てた)。
魚を食べることの多いオジロワシやオオワシの Haliaeetus 属では他のタカ類同様でミサゴのようには失っていない。
反応する物質ではカフェインやニコチンなどのアルカロイドに反応する種類は比較的多いが種による違いもある。Benzopyrones は比較的反応率が高い。
先行研究の Wang and Zhao (2015) Birds Generally Carry a Small Repertoire of Bitter Taste Receptor Genes を見ておくとアメリカガラス Corvus brachyrhynchos は遺伝子コピー数も多く、カラス類は苦味を感じていると想像できる。上記旧世界ハゲワシ類の話と矛盾するようだが怪しいものを食べるので余計に苦味感覚が必要なのかも。
スズメ目では一般にコピー数が多く種子食の種類で特に多い。系統的に関連のあるオウム類やハヤブサ類・何とノガンモドキ類も調べられておりいずれも少ない。意外にもツメバケイでは多くない。毒虫を食べそうなカッコウ類でも多くない。
鳥類は味覚が乏しいので悪食になれるとはもはや言ってはいけない。現代では遺伝子を見るべきとなる。
Zhang et al. (2025) Molecular evolution of sour tolerance in birds によればスズメ目で甘み感覚の進化とともに果実に含まれる酸味への感度を下げた可能性が示されている。OTOP1 が酸味受容体で鳴禽類ではさらに変異があるとのこと。
オープンアクセスではないがいずれもう少し詳しい後続研究が出されるだろう。
Study Reveal Molecular Evolution of Sour Tolerance in Birds (一般向け英文解説)。低い pH (つまり酸味) で鳥類の OTOP1 は反応を抑制し、カナリアの OTOP1 をマウスに導入すると酸味への反応が顕著に低下したとのこと。逆にハトやカナリアで OTOP1 を活性化させると酸味耐性が弱まったとのこと。
少なくとも鳴禽類は我々ほどは酸味を拒否しないものと想像できる。
一般向けではあるが、まるで哺乳類から鳥類が味覚を順次進化させたかのような図になっている。系統順の視点からは哺乳類の方が先に分岐したと考えられているので確かにこの順が妥当であろうし、化学知覚の点では哺乳類の方が祖先的とも言える。我々の方が鳥類より味覚が優れていると考えるよりも、哺乳類の方が化学知覚に頼る必要性が大きく祖先的な形質を残していると見るのが適切だろう。
[Great Speciator]
Ernst Mayr (1904-2005) が Whitney とともに 1929-1930 年ソロモン諸島を訪れた際、島ごとに異なる種類のメジロ類が生息していることに驚いたとのこと [年代は後述の Diamond and Mayr (1976) を参照した]
その成果が Mayr (1945) "Birds of the Southwest Pacific: a field guide to the birds of the area between Samoa, New Caledonia, and Micronesia"。
Jared Diamond は 1969, 1974 年に同地を訪れ、
Diamond (1970) Ecological Consequences of Island Colonization by Southwest Pacific Birds, I. Types of Niche Shifts;
Diamond (1972) Biogeographic Kinetics: Estimation of Relaxation Times for Avifaunas of Southwest Pacific Islands が初期の報告。このあたりまでは伝統的概念で解釈しようとしていたことが読み取れる。
Diamond が中心となってそれだけで説明できない現象を明らかにし、従来の島しょ生物学では説明しきれない種分化として "great speciators" の概念を提唱した。当時はその機構まではわからなかった。
論文は Diamond et al. (1976) Species-distance relation for birds of the Solomon Archipelago, and the paradox of the great speciators。
ちなみに Diamond and Mayr (1976) Species-area relation for birds of the Solomon Archipelago にはまだこの概念は出ておらず、"great speciators" の元文献としてこちらを引用するのは誤り。
代表的な great speciators をこの文献からリストしておくと、
・メジロ類
・アオヒラハシ Myiagra ferrocyanea Steel-blue Flycatcher (カササギヒタキ科、ソロモン島など。"サンコウチョウ" としばしば書かれるのはあまり正確でない)
・キバラモズヒタキ Pachycephala pectoralis Golden Whistler (モズヒタキ科。オーストラリアなど。キバラモズヒタキだけで現在の分類で59亜種とのこと)
・オウギビタキ Rhipidura rufifrons Australian Rufous Fantail (オウギヒタキ科。オーストラリアなど。現在は複数種に分割され Rhipidura属は 61 種)
・#ナンヨウショウビン
代表的な "great speciators" であるメジロ類の特異性を明らかにするための分子系統研究やゲノム解析は多数行われている:
Moyle et al. (2009) Explosive Pleistocene diversification and hemispheric expansion of a "great speciator" は脊椎動物で知られる最大の種分化速度を明らかにした。環境要因だけでは説明できない (Diamond も共著)。
メジロ科は 446-557 万年前に出現、メジロ属 Zosterops は 200 万年で 80 種を生んだ結果となった。
Ernst Mayr は死去していたが、Diamond はもし Ernst Mayr が生きていればこの結果を歓迎するだろうと述べている。
Cornetti et al. (2015) The Genome of the "Great Speciator" Provides Insights into Bird Diversification
はハイムネメジロ Zosterops lateralis Silvereye (南西太平洋地域。この種だけで 17 亜種) の高精度ゲノムを解読し、メジロ類他種や亜種間の比較を行うことでこの属特有の色彩多形や急速な種分化につながる遺伝部位を特定した。
DNA の置換が早いことが予想されるが、実際に多くの遺伝子重複があり、変異に対して柔軟な遺伝構造を持っていることを示したとのこと。
Cowles and Uy (2019) Rapid, complete reproductive isolation in two closely related Zosterops White-eye bird species despite broadly overlapping ranges
小さな Kolombangara (コロンバンガラ) 島 (ソロモン諸島の火山島) に ソロモンメジロ Zosterops kulambangrae Solomon Islands White-eye と クランバングラメジロ Zosterops murphyi Kulambangra White-eye (種分割の結果学名と一般名の整合性がよくない)
が同所的に生息しているが、遺伝的解析により交雑の証拠が認められなかった。200 万年前に種分化して再度接触するようになったものと考えられるが生殖隔離が確実に認められた。鳥類で完全な生殖隔離が起きている分岐年代の最も若い事例の一つとなった。
Ottenburghs (鳥類雑種の専門家。2019) Digest: White-eye birds provide possible answer to the paradox of the great speciator
さえずりの違いなどでつがい形成前に生殖隔離が起きている可能性があるが、メジロ類でゲノムレベルの進化の速さから雑種不稔になっている可能性も考えられるがまだ確かめられていない。
詳しい生殖隔離の機構は不明だが、メジロ類で他の系統よりも速く完全な生殖隔離を生じることが "great speciators" の機構を解明する手がかりになるのでは。
Estandia et al. (2023a) Candidate gene polymorphisms are linked to dispersive and migratory behaviour: Searching for a mechanism behind the "paradox of the great speciators"
"great speciators" はあまり分散したくない特性を持つと言われ (Diamond 1981)、事実上飛べない鳥と同じような傾向がある ("behavioural flightlessness" 行動学的に飛べない鳥) と考えられる。渡り習性や分散傾向などの行動 ("個性") に関係あるとされる遺伝子をハイムネメジロで調べたもの。
渡り習性に関係があるとされる CREB1 遺伝子に島しょ部に定着後大きな変化があり、また概日リズムに関係する CLOCK もタスマニアの同一個体群でも動かないグループと小距離移動を行うグループで違いがあることがわかった。集団間の遺伝子比較研究はまだ始まったばかりだがすでに興味深い結果が得られている。
Estandia et al. (2023b) Standing genetic variation and de novo mutations underlie parallel evolution of island bird phenotypes (prepeint)
ではハイムネメジロが島に定着すると体サイズが大きくなるが (最も新しいものは 200 年前)、それぞれの島で新たな変異も起きているが、基盤となる共通の遺伝的多形も関与している結果となった。
上記とも関連するがメジロ類の分類に関しては Lim et al. (2018) Molecular evidence suggests radical revision of species limits in the great speciator white-eye genus Zosterops (この文献が種分類を見直したもの)、
Martins et al. (2020) A comprehensive molecular phylogeny of Afrotropical white-eyes (Aves: Zosteropidae) highlights prior underestimation of mainland diversity and complex colonisation history (アフリカのメジロ類の多様性は従来考えられていたよりずっと高い)、
Oliveros et al. (2021) A phylogeny of white-eyes based on ultraconserved elements (ゲノムデータを用いた最新の解析)。
Gwee et al. (2020) Phylogenomics of white-eyes, a 'great speciator', reveals Indonesian archipelago as the center of lineage diversity インドネシアがメジロ類の種分化の中心地か。
Engler et al. (2021) Niche evolution reveals disparate signatures of speciation in the 'great speciator' (white-eyes, Aves: Zosterops)
は生態学的な種分化機構の研究。
Vinciguerr et al. (2023) Island life accelerates geographic radiation in the white-eyes (Zosteropidae) ワラセア (Wallacea) やメラネシアの島で種分化速度が早く、島から大陸に移入するものの方が逆より多い。
Estandia et al. (2025) Islands Promote Diversification of the Silvereye Species Complex: A Phylogenomic Analysis of a Great Speciator (preprint) オーストラリアのハイムネメジロでも同様の結果が得られている。ハイムネメジロの系統は 150 万年前に生じたばかり。
Radu et al. (2024) Genetic patterns reveal geographic drivers of divergence in silvereyes (Zosterops lateralis)
オーストラリアのハイムネメジロの SNPs の研究では島の間の距離よりも海が障壁となっている。
かつては Zosterops 属は東南アジア起源と考えられていたが、セイロンメジロ Zosterops ceylonensis Ceylon White-eye が最も古い系統とわかり
[Wickramasinghe et al. (2017) Non-sister Sri Lankan white-eyes (genus Zosterops) are a result of independent colonizations]、起源も見直しが必要とされている (wikipedia 英語版)。
この結果もスリランカで系統が誕生して大陸に進出している描像に合致する。
世界のメジロ類でこれほど最先端が研究がなされているのは驚きであった。
キバラモズヒタキについては Andersen et al. (2014) Molecular systematics of the world's most polytypic bird: the Pachycephala pectoralis/melanura (Aves: Pachycephalidae) species complex
当時この2種だけで 70 以上の亜種があったとのこと。
現在はかなり分割され Pachycephala 属で 53 種 (IOC 14.2) とのこと。この地域でライフリストを数えている人には相当大変そう。
オウギビタキ類については Klicka et al. (2022) Genomic and geographic diversification of a "great-speciator" (Rhipidura rufifrons)
の研究があり分岐年代 135-231 万年で表現形の急速な進化があり species complex に複数の系統が認められる。オウギビタキが great speciator の特性を持っていると考えられる。
アカハラヤイロチョウ Erythropitta erythrogaster Red-bellied Pitta グループについては Irestedt et al. (2013)
The spatio-temporal colonization and diversification across the Indo-Pacific by a 'great speciator' (Aves, Erythropitta erythrogaster)
でやはり great speciator と呼んでよいとのこと。
Jared Diamond ジャレド・ダイアモンド とはいったい何者か、は Dunavan (2017) Jared Diamond Confidential Reflections on Writing, Science, and Life によれば ornithologist-physiologist-turned-evolutionary biologist and biogeographer
ということで、鳥類学 - 生理学 - 進化生物学 - 生物地理学者が人類史を語った、という扱いになっている。
日本では「鳥類学者でもある」捉え方で表現されることが一般的かも知れないが (鳥類学者の社会的認知が低いのか?)、上記を見ても堂々の鳥類学者である。
・「銃・病原菌・鉄」(倉骨彰訳 草思社 2000、原著 "Guns, Germs and Steel: A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years" 初版 1997)、
・「文明崩壊」(楡井浩一訳 草思社 2005、原著 "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed" 2005)。
有名な著書は多数あり高く評価されているが、上記2つは特に有名で読まれた方も多いだろう。この著作を読むと (読者によるだろうが) "納得させられる" 感が強いが、彼の鳥類学者としてのキャリアを知るとこれら著作の理解も一層深まるだろう。鳥類学者ならではの本なのかも知れない。
生物地理学や進化生物学の発想が根底をなしていて、従来はアイデアに過ぎなかったかも知れない "Great Speciator" が現在実証されてくる経緯を見ると彼のアイデアの信憑性が一層高まるような印象を受ける。
よく知られている「文明崩壊」からイースター島などトピックス的に取り上げて議論するのは少し誤解を招く可能性がありそう。
彼のバックグラウンドをもう少し知っておいた方がよいだろう。
イースター島の話は Diamond が初出ではなく、上田 (1995) Birder 9(5): 104 の書評にある「緑の世界史 上・下」(C・ポンティング 著、石 弘之・京都大学環境史研究会訳 朝日新聞出版 1994。原著 "A green history of the world: the environment and the collapse of great civilizations" Clive Ponting 1992) で紹介されいる。
続報があり、ゲノム解析によれば Diamond の紹介で有名になった原初の説は否定されるとの論文が出た: Moreno-Mayar et al. (2024) Ancient Rapanui genomes reveal resilience and pre-European contact with the Americas。
非常に興味深い結果でおそらく日本語解説も出ると思われる。論文もオープンアクセスなのでご覧いただきたい。欧米からの渡来人と何度も接触があった。持ち込まれたネズミで植生が破壊された説もあった。
航海術もあって当時は大洋を越えて別の島に移住することができただろうが、現代に当てはめると含蓄が深い気がする。
彼は一般的に polymath (博学者と訳される) として知られている。
彼がこれほど多様な分野で活躍しているのは、7歳から鳥類に目覚め生涯熱意の対象であったこと、生化学者、生理学者のトレーニングを受けたところが大きいのかと感じる。幼少時よりピアノを習っていたとのこと (それぞれの情報は wikipedia 英語版より) で他の "博学者" とも似ている。
生化学や生理学の学習には論理が非常に重視される (暗記では対応しきれない) ので、後の進化生物学を極めるのにもおそらく相当役立っているはず。鳥類学者を目指す人もこれらを基礎学問として習得しておくとよさそう。
polymath の math は数学だが、Diamond et al. (1976) はいきなり微分から始まっているように、数学も得意だったことは間違いないだろう。
great speciator そのものに対応するものではないが、インドネシア - オーストラリア列島地域がスズメ目の固有種多様性に大きく貢献している。分子系統研究が進んで一層明らかになった: Prasetya et al. (2025) Supermatrix Phylogenetic Tree of Passerine Birds From the Indo-Australian Archipelago Highlights Contrasting Histories of Regional Endemism
新しい系統の固有種 (neoendemism) と古い系統の固有種 (paleoendemism) のタイプがあり、オーストラリア地域は後者、世界の多様性の中心地であるニューギニア島は両者の存在する superendemism の地とのこと。
我々の地域とはウォレス線 (Wallace Line) で隔離されているので関連性は低いが系統樹を見ても面白い (なぜかオオルリがヒタキ類代表種になっている)。スンダ列島はこれまで考えられていたほどスズメ目の固有種多様性のホットスポットではない。この地域は非スズメ目の方が目立っている。
[メジロの地鳴きの雌雄差]
メジロの地鳴きの雌雄差について、茂田 (1999) Birder 13(5): 46 に記事がある。川村多実二「鳥の歌の科学」(1947) にすでに記述されており、茂田氏自身も雌雄識別に有効であるとしている。
この記事はカタカナで表現されているが、中村 (2019) Birder 33(6): 26-27 がソノグラムを示している。
△ スズメ目 PASSERIFORMES センニュウ科 LOCUSTELLIDAE ▽
-
マキノセンニュウ
- 学名:Locustella lanceolata (ロークステルラ ランケオラータ) 小さな槍斑のある小さなバッタ
- 属名:locustella (f) 小さなバッタ (locusta (f) イナゴ -ella (指小辞) 小さい) 鳴き声から
- 種小名:lanceolata (adj) 小さな槍斑のある (lanceola (f) 小さな槍 -tus (接尾辞) 〜が備わっている) 胸にある縦斑を指す (英名も同様。コンサイス鳥名事典)
- 英名:Lanceolated Warbler
- 備考:
locustella は冒頭が長母音。lo-cus-tel-la と分割されるとすれば -tel- にアクセントがある (ロークステルラ)。英語の locust も冒頭は2重母音なのでこの発音で違和感がない。
lanceolata は -la- の a が長母音でアクセントもここにある (ランケオラータ)。
Alstrom et al. (2018)
Comprehensive molecular phylogeny of the grassbirds and allies (Locustellidae) reveals extensive non-monophyly of traditional genera, and a proposal for a new classication (出版社サイト)
の分子系統および音声の研究によってセンニュウ科 (Locustellidae) の従来の多くの属が単系統でないことが示され、11 属に再分類された。
この結果日本の「センニュウ」の多くが新属 Helopsaltes (helos 沼 psaltes ハープ奏者、音楽家 Gk の意味) に移されることになり、IOC 等で採用されている。
Locustella 属 (この論文で Clade J) と Helopsaltes 属 (この論文で Clade K) はさえずりに違いがあり、日本の種ではマキノセンニュウのみ虫を思わせる連続音でさえずることからも他のセンニュウ類との違いを感じられている方もあるのではないかと思う。
この分類では日本のセンニュウ類のうちマキノセンニュウのみが Locustella 属に残るが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では新分類はまだ採用されていない (がいずれ導入されるものと期待している)。
2亜種ある(IOC)が、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種の記載はない。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)にて亜種は hendersonii (アメリカ軍医、博物学者、収集家の Andrew Augustus Henderson にちなむ) となった。IOC 3.1-, Howard and Moore 3rd edition 以降、HBW and BirdLife 2020- がこの亜種を採用している。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Hokkaido と記述し、学名 Locustella lanceolata のみで和名は空欄になっていた。
原記載 Sylvia lanceolata Temminck, 1840 の学名で記載された。フランス名 bec-fin lanceole。bec-fin は細い嘴の意味でムシクイ類などに使用。
lanceole は槍の穂先形の。植物学で葉が被針形の意味とのこと。
queue assez longue, fortement contique;
toutes les parties inferieures, la partie mediane du ventre seule exceptee, couvertes de longues meches lanceolees と記述されており、下面の中央部だけ例外的に槍の穂先形の羽毛に覆われているとの記述になる。
基産地は Mayence とされるが誤りで、ロシアであるとのこと (Hartert, 1909, Vogel Pal. Fauna, p. 553, Avibase より。ロシアでそれ以上細かい場所は指定なし)。
和名はまだなかったが Ogawa (1908) の段階で北海道に生息することは知られていた模様 - Hartert の記述によると Lusciniopsis Hendersonii Cassin, 1858 基産地 Jesso, Japan があった。
Avibase では記載時学名 Ephialtes Hendersonii Cassin, 1858 だが (原記載) とあるので Lusciniopsis Hendersonii が正しそう。Hakodadi, Island of Jesso, Japan. Discovered by A. A. Henderson, M. D., U. 8S. Navy. となっており、発見者 Henderson にちなむもの。
現在は亜種扱いで基亜種がロシアならば北海道で記載されたものが日本の亜種となるのは極めてわかりやすい、と思ったがこの前のページに Lusciniopsis japonica Cassin, 1858 があり、こちらはシマセンニュウのシノニム扱い (#シマセンニュウの備考参照)。この記載とマキノセンニュウは明らかに別物とのことで両者の関係に悩む必要はなさそう。
ロシア名は pyatinstyj sverchok。pyatinstyj は "斑点のある" でぶち猫などを指して用いられる単語とのこと。sverchok は sverchat' に由来する音由来のコオロギ類を指す名前でラテン名の由来同様。基本的に大陸中央部の種類でサハリンでは少ないとのこと。西シベリア平原南部にあたる Salair 周辺 (ノボシビルスク、ケメロボなどに近い) で特に多いとのこと (Dement'ev and Gladkov 1954)。
日本は分布の周辺に当たりあまり馴染みの種類でないのも納得できる。
The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声) part 2 4:26 マキノセンニュウ Zavodit svoe beskonechnoe strekotanie pyatnistyj sverchok (マキノセンニュウが果てることのない鋭い連続音を立てています) (聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
大橋 (2022) Birder 36(10): 52-53 によれば和名の "牧野" は人名ではないとのこと。"ぼくや" と読み主として家畜の放牧またはその飼料もしくは敷料 (家畜小屋に敷く草類) の採取の目的に供される土地 (コトバンクの解説)。"牧野" の地名は各地にあっておそらくこの意味で付けられたものだろうが、多くの地名は "まきの" または "まぎの" と読まれているよう。
奈良県の牧野古墳は "ばくやこふん"。
近畿地方で有名なのは滋賀県高島市マキノ町牧野で、明らかにマキノと読んでいる (JR マキノ駅 があり、JR では ニセコ駅とともに多分2駅のみのカタカナ表記の駅名)。
京阪電気鉄道京阪本線の牧野 (まきの) 駅があり、枚方 (ひらかた) 市駅と牧野駅の間の淀川河川敷は探鳥地としても有名。地名の由来は大変納得できる。牧野駅は 1910 年に開業しており、さらに以前よりあった牧野 (まきの) 村に由来。
マキノセンニュウの命名当時からこの読み方は普通にあったのではないだろうか。
マキバタヒバリの "マキバ" もおそらくほとんど同じような意味でこちらは学名や英名とよく整合する。
アメリカのマキバシギ Bartramia longicauda Upland Sandpiper の名称もあり、学名には対応していないがシギにもかかわらず草地や農地が生息地である (wikipedia 英語版より) ことから名付けられたのだろうか。家畜の放牧地と生息地が重なるとのこと。
英名別名に Field Plover があり、他言語でも prairie (プレーリー、北米大陸中央部でカナダ南部からアメリカ南部まで広がり、草原・サバナ・低灌木からなる生態系である: wikipedia 日本語版より) を冠したものがいくつもある。prairie はフランス語由来で牧草地のこと。
このように見ると#オオノスリが学名などから連想できない Upland Buzzard と呼ばれる理由が理解できる気がする。この種では英語特有の呼び名になっているが、おそらくモンゴルの草原を北米のプレーリーのようなものと捉えたのではないだろうか。
大橋 (2022) によれば 1879 年のマキノセンニュウの図版にシマセンニュウの名前が記されており、当時はマキノセンニュウは種として認識されていなかったのだろうと推察している。
以降新たに追記 (2025.5):
マキノセンニュウのマキノは人名との解釈もある (例えば 中西悟堂「定本・野鳥記 5」p. 126。1940 年初出) ので山階鳥類研究所の標本ラベルを見ておくと YIO-27634 (東京都 1892.9.28 とあるがラベルは 1872 のようにも読める) に M. Makino, netted by (... 以下不鮮明) と読めるように思えるので M. Makino の人名ではないだろうか? 新しく付けられれたラベルには Coll. (採集人) 牧野 とある。
別のラベルには Caught while netting sparrows (スズメをかすみ網で捕獲中に捕獲。以下読みきれないが色彩などの記載あり) とある (追記終わり)。
狭義 (IOC では普通に使われているので "狭義" と付けるまでもないかも知れないが) Locustella 属について、タイで見られる6種類の解説: Locustella Warblers (Ayuwat 2022)。
-
シマセンニュウ (将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Locustella ochotensis (ロークステルラ オホテーンシス) オホーツクのセンニュウ
- AviList 学名:Helopsaltes ochotensis (ヘロプサルテス オホテーンシス) オホーツクの沼の音楽家
- 第8版属名:locustella (f) 小さなバッタ (locusta (f) イナゴ -ella (指小辞) 小さい) 鳴き声から
- AviList 属名:helopsaltes 沼の音楽家 helos 沼 psaltes ハープ奏者、音楽家 (Gk)
- 種小名:ochotensis (adj) オホーツクの (ochotsk オホーツク、-ensis (接尾辞) 〜に属する Gk)
- 英名:Middendorff's Warbler (ドイツ-ロシアの博物学者でシベリアを調査した Alexander Theodor von Middendorff), IOC, AviList: Middendorff's Grasshopper Warbler
- 備考:
locustella は#マキノセンニュウ参照。
helopsaltes は外来語由来の合成単なので発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語では -tes 部分が長母音なので伸ばす可能性がある。推定されるアクセント位置には影響はなく "ヘロプサルテス" でよいと思われる。
ochotensis は由来となるロシア語には特に長・短母音の概念はなく "オホーツク" と伸ばしているのはアクセントを示しアクセント母音が長く読まれる傾向があるため。-ten- にアクセントがあることに影響はないので2つめの o はそのままでも伸ばしてもどちらでもよい。場所の -ensis は一般的には冒頭が長母音でアクセントがある (オコテーンシス)。
本稿では一般的にはラテン語での ch の読みは h を発音せず c の音 (k の音) で表記しているが、本来は h の音を入れてよいもの。ただしカタカナではうまく表記できない。この例でもう少し考察を進めると命名者は c の音ではなく h (に似た音) の入った音を想定していると想像される。
音に合わせて kh と書けばロシア語のラテン文字転記と同じものになる上、ドイツ人によるものなので ch はドイツ式に発音することを意図したことが想定できる。ドイツ語読みにすればこの部分はロシア語と同じ音になる。ロシア語の ch に相当する音はドイツ語読みを想定した学名では tsch の表記が一般的に使われるので、ここは ch ではなく kh の音を想定していると想像できる。
ドイツ語の doch やロシア語の kh の音を知っている人ならばその音で読んでもよいだろう。ラテン語式で h を添えて発音する場合もかなり似た音になる。k と h の中間のような音を考えるとわかりやすい。
ドイツ語辞書をぱらぱらと見て発音記号を確認してみると (普通は綴りだけで読みがわかるので発音記号まで載っていないが ch の入る単語は結構示されていた)、ドイツ語で ch の発音は案外多彩であることがわかった (おそらく語源次第)。語頭の場合は k の発音で英語類似になるものが多い。ochotensis の場合は o に挟まれているので doch と同様に発音されるのではないかと想像する。
ドイツ語でのオホーツクの表記を調べてみると Ochotsk なので学名は多分ドイツ式綴りで、ドイツ語式発音は以上の解釈でよいのではと考える。
このように考えると種小名のカタカナ表記は "オホテーンシス" または "オホーテーンシス" の方が命名者の意図、地名の原音に近いかも知れない。この表記は日本語でも意味がわかりやすいので少し例外的にドイツ語読みを採用してみた。
日本語の "ホ" よりは硬い音 (舌の後ろの方を上げて摩擦音に近い発音になる) を想定していただくとよい。k ほどには破裂音にはならない程度に、というところ。
間違っても オチョ... とは読まないように。
Alstrom et al. (2018, #マキノセンニュウの備考参照) に従えば Helopsaltes 属 (「沼の音楽家」の意味) になる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では新分類はまだ採用されていない。単形種。
Clements/eBird 2021 より、HBW/BirdLife 2021 より、IOC 8.2 よりこの属を採用。Working Group Avian Checklists でも最初から採用されているので世界のリストはこの分類に統一されてゆくと思われる。
AviList でこの学名を採用。英名も AviList, Clements 2024 で Middendorff's Grasshopper Warbler, BirdLife v9 で Middendorff's Grasshopper-warbler とわずかに違う程度。BirdLife の更新は古いので AviList 英名に統一されるかも知れない。
記載時学名 Sylvia (Locustella) Ochotensis Middendorff, 1853 (原記載) 基産地 Udskoj Ostrog (= Udskoye), lower Uda River, Sea of Okhotsk (Avibase による)。図版。
Hartert (1910-1922) p. 545 によればシノニムに Lusciniopsis japonica Cassin, 1858/1859 Hakodadi (記載) の名前が挙がっている
(ここではウチヤマセンニュウと区別されていないが、ウチヤマセンニュウの記載に採用されていないことからどちらか不明であったがシマセンニュウと判定されてシノニムとなったものと想像できる)。
数年の違いだが、japonica の付く種が増えていたかも知れなかった。
さらに Locustella hondoensis Stejneger, 1893 (参考) Province of Shimosa, Japan があったが記載者がシノニムと修正。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Kurile Is., Hokkaido, Suruga とある。"シマ" は主に北海道や千島列島を指したものか。当時ウチヤマセンニュウは別種扱いで、場所は Suruga と記述されていたが和名は空欄となっていた。
つまりウチヤマセンニュウは後に整理されて付けられた名前と思われる。
海外の研究者が名付け合戦を行っていた時代で、特にセンニュウ類では記載文献を見てもどれに対応するのか判断困難だっただろう。
山階鳥類研究所の標本データベースの YIO-27544 小川氏の 1906 年の標本ラベルに Locustella hondoensis の学名が使われていた。この標本は模範標本のスタンプがあり記載に用いられた標本は国内にないが国内で基準となる標本の意味と思われる。
Ogawa (1908) では Locustella ochotensis に Suruga が含まれているため、小川氏自身は Locustella ochotensis と考えて記録したもの (おそらく国内にある初標本とみなした) だったが、後に Locustella hondoensis Stejneger, 1893 [この学名は Ogawa (1908) に現れない] の記録が先に近くにあることに気づいて新たに同定して付けたラベルではないだろうか。
Locustella hondoensis のタイプ標本は別にある (#ウチヤマセンニュウ 備考)。
Ogawa (1908) はそもそも Locustella hondoensis を知らなかったか、Stejneger (1894) (ウチヤマセンニュウ備考参照) が訂正して hondoensis はなくなったものと考えたかのいずれかだろう。目録では和名のない Locustella pleskei の方も Suruga となっているので 1906 年の標本がどちらを意図したものか不可解なところがある。もし Stejneger (1894) を知っていれば下総を産地に含めていたのではないだろうか。
1906 年の時点では Locustella hondoensis の標本を知っていてこの名前を用いていたが、1908 年の時点で訂正に気づいて Locustella pleskei のみを載せたなどの経緯も考えられるが、Locustella hondoensis の標本がすでに国内にあるならば「模範標本」が印字された理由がよくわからない。
北方の Locustella ochotensis と同じと見たが、学名の入ったラベルは後に付けられて整理される段階で本土と北海道など北部に分ける考えが採用されたのではないだろうか (この問題は複雑そうなので未解決)。
#ナキイスカの名称でも考察したが、本土から見てより遠いものに "シマ" を与える傾向があったと考えると解釈しやすい部分があり、産地を本土と北部に分ける考えからオホーツクなどの遠いものに "シマ" を付けたのではないだろうか。本土のものを "センニュウ" (学術的に存在したかも知れない仮想的名称)、北海道などのものを "エゾセンニュウ"、分布がオホーツクと思われるより北方のものを "シマセンニュウ" とすればエナガ同様にうまく落ち着く。"センニュウ" が本土に生息しているかどうかは当時まだ情報がなかった。
早い話がムシクイ類 (特にメボソムシクイ類似種) 同様に見ても区別困難なので、分布地域をもとにした名称を付けるのが都合がよかったことになる。
その後 Hartert が Locustella hondoensis = Locustella pleskei を ochotensis のシノニムとしたためにややこしいことになった。
シマセンニュウは命名がより古く、統合されて ochotensis が基亜種となった段階でそのまま残されたのだろう。シマセンニュウ類の和名変遷過程にはおそらく Locustella hondoensis が途中で意識されその後シノニム化されたことが関わったいたのだろう。これらの変化が比較的短期間に起きたため途中経緯があまり残っていないものと想像できる。
#セッカの備考で紹介したが、当時は世界的にもセッカ類とセンニュウ類の区別は難しかった。おかげでセンニュウ類なのにオオセッカの名前がある。現代の分子系統解析でも近縁の科であることが判明しているので混乱があってもやむを得ない。海外文献の記載で日本に {セッカ類とセンニュウ類} が多数種記録されていることが判明し、対応する既存和名があまりなかったためセッカ類とセンニュウ類に分けてそれぞれに名称を与えたのだろう。
ロシア語ではオホーツクのセンニュウの意味、中国語では北のセンニュウとなっている。オランダ語では日本のセンニュウだがおそらくウチヤマセンニュウを含んだ名前。
-
ウチヤマセンニュウ (将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Locustella pleskei (ロークステルラ プレスケイ) プレスケのセンニュウ
- AviList 学名:Helopsaltes pleskei (ヘロプサルテス プレスケイ) プレスケの沼の音楽家
- 第8版属名:locustella (f) 小さなバッタ (locusta (f) イナゴ -ella (指小辞) 小さい) 鳴き声から
- AviList 属名:helopsaltes 沼の音楽家 helos 沼 psaltes ハープ奏者、音楽家 (Gk)
- 種小名:pleskei (属) pleske の (ロシアの動物学者 Fedor Dmitrievich Pleske)
- 英名:Styan's Grasshopper Warbler (英国商売人・採集家で中国で長く過ごした Frederick William Styan)
- 備考:
locustella は#マキノセンニュウ参照。
helopsaltes は#シマセンニュウ参照。
かつてはシマセンニュウの亜種とされていた (ウチヤマシマセンニュウ)。Alstrom et al. (2018, #マキノセンニュウの備考参照) に従えば Helopsaltes 属 (「沼の音楽家」の意味) になるが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では新分類はまだ採用されていない。
Clements/eBird 2021 より、HBW/BirdLife 2021 より、IOC 8.2 よりこの属を採用。Working Group Avian Checklists でも最初から採用されているので世界のリストはこの分類に統一されてゆくと思われる。
AviList でこの学名が採用された。英名は AviList は IOC に合わせて Styan's Grasshopper Warbler、Clements 2024 で Pleske's Grasshopper Warbler、BirdLife v9 では Pleske's Grasshopper-warbler と多少違いが残っている。狭い地域に生息する種類なのであまり英名統一の話題になっていないかも。
単形種。越冬地はよくわかっていない。
原記載。Locustella de la Coree で、朝鮮のセンニュウとして紹介されている。採集地は Techimulpo (Techimulpa, = Inchon) となっていて、地名が和名の由来かも知れない。現在この地名は日本語では仁川と表記されている。
原記載ではペテルブルグ博物館の友人の M. Theodore Pleske に捧げるとある (Theodor Eduard Pleske の名前で、ロシア表記だと Fedor Dmitrievich (Eduardovich) Pleske となる。
Locustella hondoensis Stejneger, 1893 (参考。記載は Notes on a Third Installment of Japanese Birds in the Science College Museum, Tokyo, Japan with Descriptions of New Species pp. 633-635) のシノニム (Stejneger による後の判定) があり日本で採集されたもの。
Stejneger の最初の記載 (1893) では当時の学名で Locustella fasciolata (後に pleskei と訂正されたもの) とシマセンニュウ (当時の学名で Locustella ochotensis) との比較は行っていたが、pleskei と訂正されていたことを知らなかった。
Stejneger (1894) が後に Notes on a Japanese Species of Reed Warbler で Taczanowski から論文コピーを直々に得て pleskei のシノニムとしたもの。
1887 年に得た Techimulpo の標本を Taczanowski は最初 Locustella fasciolata と記録 (1888 記述) したが、Locustella pleskei と訂正 (1889) して前述の新種記載としたもの。出版年が微妙に違うと見てみると 1889 年は原稿受け取りと印刷物に示されている日付で、実際に出版されたのは 1890 年だったのだろうか。
Locustella fasciolata はすでにエゾセンニュウ (現在では分離) に使われていた学名なので無効で新しく付けたものではなく、最初はエゾセンニュウと考えて報告したものだった。
Hartert (1910-1922) p. 545 ではまだ pleskei を確実な亜種と分離しておらず、Locustella ochotensis のシノニムとして扱っていた。
山階鳥類研究所の標本データベースでは YIO-00025 で 千葉県 Prov. Shimosa, Japan Shimosa (下総。しもうさ/しもふさ) とのこと。Locustella hondoensis のタイプ標本。
下総の内山はあるいは地名または人名? 下総中山駅の駅名があるが 1895 年開業時点で "なかやまえき" の読みだったので関係ないかも。
この Locustella hondoensis のタイプ標本に触発されて「内山」の地名を調べると千葉市花見川区内山町があった。現行の町名では千葉県内唯一の「内山」だった。下総国の範囲に含まれるので実はよい候補かも知れない。標本採集が行われた時代には環境的には低湿地帯と思われ渡り時期にはセンニュウ類が通っていてもよさそうに感じるが、特に島を好むウチヤマセンニュウが果たして通っていたかは?
海外の名称では人名 (Pleske, Taczanowski または Styan) を用いているものが多い。
ロシア語では "島の" を冠している (大陸から見れば納得できる名称)。"日本の" をつけているのはチェコ語、ウクライナ語の他は見当たらないが、"朝鮮の" を付けている言語はいくつかある。
"日本の" は Locustella hondoensis、あるいは#シマセンニュウの Lusciniopsis japonica が採用されていた時代のものかも知れない。
中国語 (特に台湾) では "史氏" (shi-shi) が付くがこれは何を指すのだろう (Styan のこと?)。
-
シベリアセンニュウ (将来の属学名変更に注意)
-
オオセッカ (将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Locustella pryeri (ロークステルラ プリュエリ) プライヤーのセンニュウ
- AviList 学名:Helopsaltes pryeri (ヘロプサルテス プリュエリ) プライヤーの沼の音楽家
- 第8版属名:locustella (f) 小さなバッタ (locusta (f) イナゴ -ella (指小辞) 小さい) 鳴き声から
- AviList 属名:helopsaltes 沼の音楽家 helos 沼 psaltes ハープ奏者、音楽家 (Gk)
- 種小名:pryeri (属) Pryerの (英国商人・博物学者で日本で横浜に住んでいた Henry James Stovin Pryer が由来)
- 英名:Japanese Swamp Warbler, IOC, AviList: Marsh Grassbird
- 備考:
locustella は#マキノセンニュウ参照。
helopsaltes は#シマセンニュウ参照。
Alstrom et al. (2018, #マキノセンニュウの備考参照) に従えば Helopsaltes 属 (「沼の音楽家」の意味) になるが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では新分類はまだ採用されていない。
Clements/eBird 2021 より、HBW/BirdLife 2021 より、IOC 8.2 よりこの属を採用。Working Group Avian Checklists でも最初から採用されているので世界のリストはこの分類に統一されてゆくと思われる。
英名は Japanese Marsh Warbler が使われていたこともあったが日本だけに生息する種ではないので現在は Marsh Grassbird が主に使われている。
学名・英名ともに AviList で採用。英名の Marsh Grassbird は AviList, Clements 2024, BirdLife v9 ともに同じ。
このグループでオオセッカは「センニュウ」の名前を持たず、さえずりのパターンもとやや異なる。
しかしオオセッカはさえずり飛翔を行い、これはエゾセンニュウ (とシベリアエゾセンニュウ) 以外の Helopsaltes 属に共通している (Alstrom et al. 2018) と記載されているが、オオセッカのものが特に特徴的で、他種はそれほど記述されていない。
2亜種 (IOC) あり、日本のものは基亜種 pryeri とされる。大陸のものは sinensis (中国の、オナガオオセッカの名称もある) とされる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では基亜種の他に亜種不明がリストされている。
記載時学名 Megalurus pryeri Seebohm, 1884 (原記載) 基産地 Tokio, not very far from Yokohama。標本 No. P5 とあるので Pryer から得た標本の意味か。
同じ文献でシマフクロウを Bubo blakistoni と記載。標本を届けた2名にそれぞれ献名の形となっている。
sinensis の記載は Lusciniola pryeri sinensis Witherby, 1912 (原記載) 基産地 Hankow。
オオセッカは翼角に爪があり、茂田 (1991) 日本の生物 5(3): 48-51 に写真付きで解説がある。基産地は横浜とされることが多いが原記載によればおそらく東京が正しい。翼角の爪は日本産スズメ目では初めてのものとのこと。籾山 (1949) オホセッカに就いて の論文が読める。
日本鳥類目録第4版までは Bradypterus (bradus 遅い -pteros 翼の Gk) オオセッカ属とされていた。
Bradypterus 属は Swainson (1837) が提唱した属でアフリカオウギセッカ 現代の学名で Bradypterus baboecala Little Rush Warbler のみからなる属だったがオオセッカも一時含められたよう。アフリカオウギセッカが自動的にタイプ種なので、分離される場合はアフリカオウギセッカを含む系統が Bradypterus 属となった。
Megalurus (megas, megale 大きい、長い oura 尾 Gk) が一昔前の属名で Brazil (2009) "Birds of East Asia" ではこれが使われている。Horsfield (1821) による属名でオニセッカ 現在の学名で Megalurus palustris Striated Grassbird のみを含む属だった
(The Key to Scientific Names の情報より一部まとめた)。
Megalurus 属にはその後他種が含まれるようになりオオセッカも含められたことがあったが単系統でなかったためオニセッカを含む系統のみが Megalurus 属となった。意味はオオセッカの属名にふさわしい感じがするが系統が違っていた。
これらを見ていると属名は何回変わるのかと思ってしまうが舞台裏は以上のような状況。
-
エゾセンニュウ (分割で学名が変わる。さらに将来の属学名変更に注意)
- 第8版学名:Locustella amnicola (ロークステルラ アムニコラ) 川辺に住むセンニュウ
- AviList 学名:Helopsaltes amnicola (ヘロプサルテス アムニコラ) 川辺に住む沼の音楽家
- 第7版学名:Locustella fasciolata (ローステッラ ファスキオラータ) 小さな帯のあるセンニュウ
- 属名:locustella (f) 小さなバッタ (locusta (f) イナゴ -ella (指小辞) 小さい) 鳴き声から
- AviList 属名:helopsaltes 沼の音楽家 helos 沼 psaltes ハープ奏者、音楽家 (Gk)
- 第8版種小名:amnicola 川辺に住むもの amnis 川 -cola 住人 (Gk)
- 第7版種小名:fasciolata (adj) 小さな帯のある (fasciola (f) 小さな帯 -atus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:(Gray's Grasshopper Warbler 分離前), IOC: Sakhalin Grasshopper Warbler
- 備考:
locustella は#マキノセンニュウ参照。
helopsaltes は#シマセンニュウ参照。
amnicola は短母音のみで "アムニコラ" のアクセント。
fasciolata は fasciola は短母音のみだが、-atus の冒頭が長母音のためここにアクセントがあると考えられる (ファスキオラータ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版でもと亜種扱いだったものが2種に分離され、fasciolata は大陸のものを指すことになった (シベリアエゾセンニュウ)。
いずれも単形種となる。北海道で繁殖するものは amnicola (「川辺に住む」の意味。amnis 川 -cola 住人 Gk) となった。後者の英名は Sakhalin Grasshopper Warbler (IOC) または Stepanyan's Warbler となる (サハリン、南千島から北海道で繁殖し、フィリピンで越冬とされる。Leo Surenovich Stepanyan はロシアの鳥類学者で 1972 年にサハリンで新種と記載した)。
fasciolata も渡り途中に日本で記録されている可能性があるが、センニュウ類で一般的であるように外見は非常によく似ており、野外識別が可能かどうかはよくわからない。また2種の音声による識別点も明らかになっていない [例えば Alstrom et al. (2018) のソノグラム参照]。
Alstrom et al. (2018, #マキノセンニュウの備考参照) に従えば Helopsaltes 属 (「沼の音楽家」の意味) になるが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では新分類はまだ採用されていない。もし反映されれば Helopsaltes amnicola と、これまで親しんでいた学名とは全く異なったものになる。
Clements/eBird 2021 より、HBW/BirdLife 2021 より、IOC 8.2 よりこの属を採用。Working Group Avian Checklists でも最初から採用されているので世界のリストはこの分類に統一されてゆくと思われる。
英名も人名を避けて Sakhalin Grasshopper Warbler に統一されているよう。
AviList でこの学名・英名が採用された。BirdLife v9 のみ Sakhalin Grasshopper-warbler と表記がわずかに違う程度。
Alstrom et al. (2018) では Helopsaltes 属の中でエゾセンニュウとシベリアエゾセンニュウが最初に分岐し、オオセッカが次に分岐、残りのセンニュウ類がまとまったグループを作っており、さえずり飛翔の有無、さえずりの違いが分子系統樹にもよく現れているように思える。
Alstrom et al. (2018) によれば amnicola は無変化のため属 (Helopsaltes は男性) が変わっても末尾は変化しない。このグループでは fasciolata のみが形容詞で、Helopsaltes fasciolatus と変わる。Avibase ではシベリアエゾセンニュウの和名が現れる。
"シベリア" と "エゾ" と地名が2つ並ぶのは奇妙な気もするがシベリアセンニュウの和名はすでに存在するので付けようがないだろうか。エゾセンニュウの亜種のように聞こえてしまうので悩ましいところ。
地名で名付けるのは同地域の類似種の存在を確かめた上で行った方がよいらしいことがわかる。
参考までに原記載をチェックしておくと、Acrocephalus fasciolatus Gray, 1861 (原記載) 基産地 Batchian (= Batjan), Moluccas と越冬地のもの。
Acrocephalus insularis Wallace, 1862 (参照) の記載もあって Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にはこの学名も紹介されている。
分離されたエゾセンニュウは Locustella amnicola Stepanyan, 1972 と記載が新しい。基産地 lower part of the valley of the Igriva River, where it flows into Aniva Bay, Tonino-Anivsky Peninsula, southern Sakhalin (サハリン南部)。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではもちろんまだ分離される前の記述だが、Johansen (1935) がすでにサハリンとウスリーのものにわずかな色の違いがあると述べていることが紹介されている。
これはわずかな標本に基づくものでもっと多くの例を調べる必要があるが、もし分離する際に該当する可能性のある記載としてザバイカル地方で Calamoherpe subflavescens Elliot, 1870 (資料 Dahouria, in Central Asia) があることを述べていた。
現在ではこれは Helopsaltes fasciolatus のシノニムと考えられている。Dement'ev and Gladkov (1954) の時代にはサハリン型とウスリー型の分布境界がどこになるかが念頭にあったようで、fasciolatus は越冬地記載なので繁殖分布境界がどこになるかを直接教えてくれるわけでなく、
分布境界の定義次第で subflavescens の学名が現れる可能性があり得る。
Alstrom et al. (2018, #マキノセンニュウの備考参照) を見るとこの2種の分離に使われた標本はサハリン、日本、中国河北省のものでシベリアや沿海地方のものは調べられていないのでよく調べると実はもっと細かく分かれて subflavescens が復活するかも知れない。
Alstrom et al. (2018) の解析ではサハリンと日本の個体の間も一定の距離 (シマセンニュウとウチヤマセンニュウの違い程度) があって、実は亜種レベルで違うのかも知れない。それぞれ1個体しか調べられていないのでさらに調べる必要があるだろう。もし亜種レベルで違うならば日本産は未記載亜種の可能性がある。
センニュウなんて外見ではほとんど区別付かないので...と単に記載されていなかっただけかも知れない。
後述のように音声は重要ポイントとなる可能性があるので渡り途中に音声を聞いたらぜひとも録音しておくべきとなる。"シベリアエゾセンニュウ" が記録されるかも知れないし、サハリンの個体も通っていて亜種は違うかも知れない、など (もっともサハリンへは大陸経路で渡りそうだが)。
xeno-canto にバイカル湖付近での録音もそれなりの数含まれており、聞いてみるとやはり違う。中国東北部の録音は日本で聞くものとバイカル湖周辺のものの中間の性質があるように感じる。
サハリンと日本の音声に違いがあるかどうかはサハリンのサンプルが少なくあまりはっきりしないが、違っていると言えば違っているようにも聞こえる。もう少しデータを集めて特徴抽出と統計処理などをすべきであろう。
大陸には "隠蔽亜種" が隠れている可能性がありそう。
The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声) part 2 3:43 エゾセンニュウ (シベリアエゾセンニュウに対応) V temnote kusta zadorno poet taezhnyj sverchok (茂みの暗闇の中でエゾセンニュウが熱っぽく歌っています) (聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。北海道のものと違いがわかるだろうか? 国内で聞くものほど鮮明でない印象を受ける。
Ogawa (1908) では分布は Hokkaido, Ishigakishima となっている。カラフトホトトギスの別名が記載されており納得してしまう。
よく知られている (?) 通り、ホトトギスのさえずりを詰まらせたようなフレーズでさえずる。北海道ではお馴染みの種類だが、渡り途中は北海道以外でも記録される。石沢・中村 (1964) エゾセンニュウの渡りに関する研究 (1. 本州及びその周辺の分布と渡り) に灯台衝突事例の研究がある。
中村司 (2012) 「渡り鳥の世界 - 渡りの科学入門」(山日ライブラリー) にも渡り時期などの情報がまとまっている。
香川の野鳥ファイル No.5 エゾセンニュウ、香川の野鳥ファイル No. 37 エゾセンニュウ(2) も参照。後者には「観察では困難だが、誰が出会っても不思議はない」と記載されている。
この資料でも、他の標識記録でも秋のものが多く、春は日本海側を通っているとも考えられている。しかし京都市においても春の渡りでしばしば出会える種類であり、渡り時期が遅い (5月中旬から下旬が中心) ことが記録されにくい原因ではないかと考えている (遅いグループのトケン類の渡ってくるころ)。
この時期は中村 (2012) の記述とも合致している。姿を見ることは難しいが、特徴的な声なので (オスの) 春の渡りに遭遇すれば容易にわかる種類である。湿ったところで出会うことが多い気がするが (山地では小さな沢や大阪城公園の空堀のようなところ) 山際の市街地で崖っぽいところでも記録している。地表面近くを大胆に駆けるように飛んでゆくのを見たことがある。
5/15 ごろはエゾセンニュウが来ていてもおかしくないと思って観察した方がよい。シマセンニュウはもう少し遅い時期 (6月上旬) の渡り途中の記録を持っている。
"センニュウ" の由来はあまりよくわからなかったが、漢字表記では仙入、潜入がある。後者は行動を指したもののように見えるが、前者は単なる当て字?
ドイツ語で旧 Sylvia 属を広く指した Grasmuecke (草むらにかがむ) をもとに意味が近い和名が選ばれた可能性も考えられる。#セッカ備考 [セッカの和名検討] 参照。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ヨシキリ科 ACROCEPHALIDAE ▽
-
オオヨシキリ
- 学名:Acrocephalus orientalis (アクロケパルス オリエンターリス) 東洋の尖った頭の鳥
- 属名:acrocephalus (合) 尖った頭 (acro- (接頭辞) 先端 (akron) kephali 頭 Gk 備考参照)
- 種小名:orientalis (adj) 東洋の (-alis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:[Great Reed Warbler 分割前の名称で現在はニシオオヨシキリ Acrocephalus arundinaceus が受け継いでいる], IOC: Oriental Reed Warbler
- 備考:
acrocephalus は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語はいずれも短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。"アクロケパルス" のアクセントで問題ないだろう。
orientalis は a が長母音でアクセントもここにある (オリエンターリス)。
分離される前の学名の種小名 arundinaceus は arundo (茎などの意味) + -aceus (〜に関係する) でこの a が長母音でアクセントがある (アルンディナーケウス)。
記載時学名は Turdus arundinaceus Linnaeus, 1758 で何と Turdus 属だった。
さらに Salicaria turdina の学名 (ツグミに似た) が使われたことがあった (現在の分類でのオオヨシキリの記載時学名参照) が、これはおそらく種小名から属名に昇格しつつもとの属名を活かして種小名としたもの。
Salicaria 属は salix ヤナギ 由来で Selby (1831) が設けたもの。Latham がスゲヨシキリに用いた学名 Sylvia salicaria 由来とのこと (The Key to Scientific Names)。この属名は亜種ウグイスやセッカの記載で Temminck and Schlegel が用いた。
古い時代の学名の影響はロシア語名に残っていて "ツグミのような" を冠している。類縁言語でもあまり同様の例がない。
Acrocephalus の属名提唱の方が早く、この属名は現在使われていない。
英名に使われる Great はヨーロッパヨシキリ Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed Warbler、あるいは単純に Reed Warbler とも呼ばれるヨーロッパで普通種に対する概念と考えられる。この種は記載時学名 Turdus scirpaceus Hermann, 1804 と同様に Turdus 属。
scirpaceus もアシに関係したの意味 (scirpus アシや名付けるほどでない草など)。
Acrocephalus 属は Naumann (1811) が設けたもので、Gray (1840) がタイプ種を Acrocephalus arundinaceus (当時は分離前) と定義した。
属名は一般的には上記のように解釈されるが、Naumann がギリシャ語 akros (最も典型的な意味は英語の edge が派生したもので、ラテン語では対応する acer の単語がある) の意味を間違えてラテン語 acutus と考えたのではないかとの推論がある。他にも同様の間違い例が知られている (BOU 1915)。
(The Key to Scientific Names)。wikitionary を見ると第2語義には鋭いなどの意味があるのでそれほど大きく間違っているわけではなさそう。
ただし他の鳥の属名で Acro- を用いているものは最も典型的な意味 (edge, point) から派生して極端な、最上のなどの意味で用いているものが多く、他の学名を把握している者にとっては Acrocephalus の字解が不自然に見えるのだろう。
現在の分類でのオオヨシキリの記載時学名は Salicaria turdina orientalis Temminck & Schlegel, 1847 (原記載) 基産地 Restricted to Japan by Dekker et al. 2001 (Avibase による)。フランス語名 le riverain rousserolle oriental (東洋のニシオオヨシキリ)。
原記載では日本の他にボルネオ、Macassar (スラウェシ島)、スマトラも含まれていて、亜種を示す際に Temminck & Schlegel の基産地を絞る必要があり "Fauna Japonica" 由来で日本に限定された模様。
記載時学名はもっと広い範囲に対応するものだった。
オオヨシキリの記載時学名はウグイスの学名に影響を与えた可能性があり、#ウグイスの備考 [ウグイスの亜種] にて紹介している。
和名のオオヨシキリが英名に関連するかどうかは不明だが、日本の場合はコヨシキリとの比較が念頭にあったようで、「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「百千鳥」(1799) におほよしきり、こよしきりの名前が登場している。
ヨシキリ類の名称を学術的に整理する際に英名とも対応がよいのでそのまま採用されたものかも。
単形種 [後述 Malykli and Red'kin (2011) の提案も参照]。
かつては Acrocephalus arundinaceus の亜種としても扱われ、ヨシキリ類が北方型で渡りをする和名ではオオヨシキリと熱帯からオーストラリアのチュウヨシキリ (Acrocephalus stentoreus) に分けられていたことがあった。
このあたりの事情は「これからの鳥類学」(裳華房 2002) 12 章の鳥類学における分子手法の適用 (西海 功) に説明がある。
Leisler et al. (1997)
Taxonomy and phylogeny of Reed Warblers (genus Acrocephalus) based on mtDNA sequences and morphology
のミトコンドリア DNA 研究 [(1) 大型の旧世界からアフリカの単系統のクレード arundinaceus,
stentoreus brunnescens, orientalis, australis, andvaughani、
(2) 小型で縞のあるクレード (おそらく単系統) bistrigiceps, melanopogon, paludicola, schoenobaenus、
(3) 小型でのっぺり模様のクレード dumetorum, palustris, scirpaceus, fuscus, baeticatus, avicenniae と
agricola-complex agricola, tangorum, andconcinens
を認めるがこれらの関係は解明されていない] と
Helbig and Seibold (1999)
Molecular Phylogeny of PalearcticAfrican Acrocephalus and Hippolais Warblers (Aves: Sylviidae) (単系統に分離する種分割の提案を行っている。現在一般に用いられる分類はこの提案に基づくものになっている。理屈は西海氏の見解と比較しつつこの論文を読んでいただくのが手っ取り早いだろう) をもとに、
当時分類でオオヨシキリとチュウヨシキリは単系統をなさないこと、チュウヨシキリからオオヨシキリが進化したならばオオヨシキリの当時の4亜種の形態的特徴は渡り行動に関連した収斂進化の可能性があるとも述べられている。
また逆にオオヨシキリからチュウヨシキリが進化した可能性があり、古気候はこちらの解釈の方とよく合うことも述べられている。
互いに単系統でない当時のオオヨシキリとチュウヨシキリの亜種を分子系統に忠実に従って種に分ける考えには賛成できないと述べられていた (「分けすぎ」の表現も使われている)。西海氏は進化分類に対する概念としての分岐分類には賛成できないことを表明している。
分類学の「哲学」レベルの問題なのでどちらが正解とは言えないが、シブリー・アールキスト Sibley and Ahlquist (1990) の DNA-DNA 分子交雑法による分類が混乱をもたらしたとの批判も同じこの記事の中にある (正確な表現は書物をお読みいただきたい)。
#シジュウカラ備考にある Birder 誌の西海氏による (3種に分けるのは)「分けすぎ」との表現もある程度この価値観 (哲学) が含まれているかも知れない。
「日本動物大百科 鳥類 II」(日高敏隆監修 樋口広芳・森岡弘之・山岸哲編集 平凡社 1997) の「日本の鳥類目録と鳥類分類学」の項目を森岡弘之 (1931-2014) 氏が著されている。日本鳥類目録改訂第6版の準備中の時期で、第5版までの歴史や欠点なども説明されている。
一時期亜種を細分化しすぎた問題も記されている。その後も戦争もあり生殖隔離に基づく分類など国外情報がわからずやむを得ない部分もあった。
新しい動きとして「Sibley-Ahlquist の DNA-DNA 分子交雑法について、一般の鳥学者は好意的だが、分類学者や古生物学者の多くは、その結果に疑問を呈している (中略)」などが記されている。批判文献は示されているので主張が適切であったかは今でも検証可能である。
日本動物大百科 本文中では DNA-DNA 分子交雑法の結果を紹介しているものもいくつもあるので、全幅の信頼を置くことはできないが新しい方法の結果として一部紹介、というところだろうか。
しかしながらこの時代には Sibley-Ahlquist の当時 "先進的" 結果については知る人は普通に知っていたのでこの鳥類分類学の解説はちょっと古っぽい感じもする。
森岡氏はさらに、「DNA 分子の塩基配列を直接読みとり比較する研究も増えるであろう、しかし系統分類学的研究の場合 (中略) 重要なのは、どの研究方法をとるにせよ、はっきりした分類学的視点をもって研究することである。
(中略) なんらかの生化学的あるいは分子遺伝学的解析を行えば (中略) 論文も書けるだろう。そうした論文を最近しばしば見かけるが、分類学的視点を欠いた論文は、こうしたらこうなったというだけのもので、ほとんどなんの価値もない」と述べている (詳しいニュアンスは原文をお読みいただきたい)。
ある意味正しいことは述べられているのだろうが、専門外の不特定読者にとってはどう受け取られただろう。また図書館などでも置かれている比較的新しい時代の鳥類図鑑なので今でも普通に読まれているだろう。この記述は分子生物学が劇的な進展を遂げたその後の 10-20 年の歴史を超えて普遍的なものだっただろうか
[「図鑑日本のワシタカ類」(1995, 1998) などの著者森岡照明氏とは別人。時期が近くて混同した記述を述べたことがあったのでおわびして訂正しておく]。
#ミサゴ備考で紹介の Tim Low "Where Song Began" (2014) に書かれているように、「Ernst Mayr は (塩基配列などによる) 新しい研究を高く評価しつつも自説を生涯曲げなかった」に類似した状況が日本でも長く続いていたのかも知れない。
#ツリスガラの備考 [スズメ小目 Passerida の系統分類] にあるように、Mayr and Amadon (1951) はセキレイ類を分類学的視点からツグミ科かウグイス科に近縁としたが、Sibley and Ahlquist (1990) は結果的に正しい系統を導いていた。
Ernst Mayr (1904-2005) は存命中に Ericson et al. (2000) の分子マーカーの仕事を見ているはずだが彼の目にはどう映っていただろうか。
このシリーズの分類と学名は森岡弘之氏が主に担当されたと書かれている。
日本のハチクマの学名として Pernis ptilorhynchus japonicus が相当遅くまで使われていた理由がわかった (この亜種名の歴史については #ハチクマの備考 [ヨーロッパハチクマとの関係・亜種] 参照)。1997 年の本にそのように記載されていたのだった。
ここでも気になっていたカッコウの亜種も telephonus となっていた。
現代の分類では圧倒的に分子系統学による分岐分類が主流で、当時のオオヨシキリとチュウヨシキリも複数種として扱うことが普通になっている。オオヨシキリについて日本鳥類目録改訂第7版の学名でもすでにそうなっている。
日本鳥類目録改訂第8版第一回パブリックコメント本文 日本鳥類目録改訂に向けた第一回パブリックコメント (日本鳥類目録編集委員会 2021) にも基本的考え方が紹介されているので参考になるだろう。
以下 Boyd の分類に従ったヨシキリ科 Acrocephalidae を紹介しておく。
ヨシキリ科 Acrocephalidae: Reed-Warblers
マダガスカルシマヨシキリ属? Nesillas (マダガスカルと近くの島)
マダガスカルシマヨシキリ Nesillas typica Malagasy Brush Warbler
ハンサバクシマヨシキリ Nesillas lantzii Subdesert Brush Warbler
アンジュアンシマヨシキリ Nesillas longicaudata Anjouan Brush Warbler
オオコモロシマヨシキリ Nesillas brevicaudata Grand Comoro Brush Warbler
コモロシマヨシキリ Nesillas mariae Moheli Brush Warbler
アルダブラシマヨシキリ Nesillas aldabrana Aldabra Brush Warbler (絶滅種)
ハシブトオオヨシキリ属 Arundinax
ハシブトオオヨシキリ Arundinax aedon Thick-billed Warbler
ハシボソキイロムシクイ属 Calamonastides
ハシボソキイロムシクイ Calamonastides gracilirostris Papyrus Yellow Warbler (アフリカ東部に限局的に分布)
ヒメウタイムシクイ属 Iduna (アフリカからユーラシア中西部、南部に分布)
ヒメウタイムシクイ Iduna caligata Booted Warbler
アラビアウタイムシクイ Iduna rama Sykes's Warbler
ハイイロウタイムシクイ Iduna pallida Eastern Olivaceous Warbler
ニシハイイロウタムシクイ Iduna opaca Western Olivaceous Warbler
キイロムシクイ Iduna natalensis African Yellow Warbler
ヤマキイロムシクイ Iduna similis Mountain Yellow Warbler
ウタイムシクイ属 Hippolais (ユーラシア西部、アフリカ)
アレチウタイムシクイ Hippolais languida Upcher's Warbler
オリーブウタイムシクイ Hippolais olivetorum Olive-tree Warbler
ウタイムシクイ Hippolais polyglotta Melodious Warbler
キイロウタイムシクイ Hippolais icterina Icterine Warbler
コヨシキリ属 Titiza (Acrocephalus 属より分離)
スゲヨシキリ Titiza schoenobaenus Sedge Warbler
ハシボソヨシキリ Titiza paludicola Aquatic Warbler
マミジロヨシキリ Titiza melanopogon Moustached Warbler
セスジコヨシキリ Titiza sorghophila Speckled Reed Warbler
コヨシキリ Titiza bistrigiceps Black-browed Reed Warbler
ヤブヨシキリ属 Notiocichla (Acrocephalus 属より分離)
イナダヨシキリ Notiocichla agricola Paddyfield Warbler
マンシュウイナダヨシキリ Notiocichla tangorum Manchurian Reed Warbler
コバネヨシキリ Notiocichla concinens Blunt-winged Warbler
ヤブヨシキリ Notiocichla dumetorum Blyth's Reed Warbler
オオハシヨシキリ Notiocichla orina Large-billed Reed Warbler
ヌマヨシキリ Notiocichla palustris Marsh Warbler
アフリカヨシキリ Notiocichla baeticata African Reed Warbler
* Notiocichla avicenniae Mangrove Reed Warbler (ヨーロッパヨシキリより分離)
ヨーロッパヨシキリ Notiocichla scirpacea Eurasian Reed Warbler
* Notiocichla fusca Caspian Reed Warbler (ヨーロッパヨシキリより分離)
オオヨシキリ属 Acrocephalus
バスラオオヨシキリ Acrocephalus griseldis Basra Reed Warbler
アシナガヨシキリ Acrocephalus gracilirostris Lesser Swamp Warbler
オオアシナガヨシキリ Acrocephalus rufescens Greater Swamp Warbler
ケープベルデアシナガヨシキリ Acrocephalus brevipennis Cape Verde Warbler
セーシェルヤブセンニュウ Acrocephalus sechellensis Seychelles Warbler
マダガスカルアシナガヨシキリ Acrocephalus newtoni Madagascar Swamp Warbler
ロドリゲスヤブセンニュウ Acrocephalus rodericanus Rodrigues Warbler
ニシオオヨシキリ Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler
オオヨシキリ Acrocephalus orientalis Oriental Reed Warbler
チュウヨシキリ Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed Warbler
ナンヨウヨシキリ Acrocephalus luscinius Nightingale Reed Warbler (絶滅種)
サイパンヨシキリ Acrocephalus hiwae Saipan Reed Warbler
オーストラリアヨシキリ Acrocephalus australis Australian Reed Warbler
(ニジョウナンヨウヨシキリ) Acrocephalus nijoi Aguiguan Reed Warbler (絶滅種)
カロリンヨシキリ* Acrocephalus syrinx Carolinian Reed Warbler
クリスマスヨシキリ Acrocephalus aequinoctialis Bokikokiko
マルケサスヨシキリ* Acrocephalus mendanae Southern Marquesan Reed Warbler
(ヤマシナナンヨウヨシキリ) Acrocephalus yamashinae Pagan Reed Warbler (絶滅種)
ギルバートヨシキリ Acrocephalus rehsei Nauru Reed Warbler
レイサンヨシキリ Acrocephalus familiaris Millerbird
ピトケアンヨシキリ Acrocephalus vaughani Pitcairn Reed Warbler
タヒチヨシキリ Acrocephalus taiti Henderson Reed Warbler
クックヨシキリ Acrocephalus kerearako Cook Reed Warbler
ツバイヨシキリ Acrocephalus rimitarae Rimatara Reed Warbler
ソシエテヨシキリ* Acrocephalus musae Garrett's Reed Warbler (絶滅種)
ハシナガヨシキリ Acrocephalus caffer Tahiti Reed Warbler
モーレアヨシキリ* Acrocephalus longirostris Moorea Reed Warbler (絶滅種)
キタマルケサスヨシキリ* Acrocephalus percernis Northern Marquesan Reed Warbler
ツアモツヨシキ Acrocephalus atyphus Tuamotu Reed Warbler
マンガレヴァスヨシキリ* Acrocephalus astrolabii Mangareva Reed Warbler (絶滅種)
IOC 14.1 (13.2) との違いは Acrocephalus 属を3分割している点、ヨーロッパヨシキリを3種に分けている点で全体的にはそれほど違いはない。
後者は Olsson et al. (2016)
Mitochondrial phylogeny of the Eurasian/African reed warbler complex
(Acrocephalus, Aves). Disagreement between morphological and molecular evidence and cryptic divergence: A case for resurrecting
Calamoherpe ambigua Brehm 1857
も参考。アフリカのアフリカヨシキリも含めて種としても亜種としてもよいレベルだが生殖隔離の証拠まではよくわからない。アフリカヨシキリのうち亜種 ambiguus はここで改めて亜種と認識され使用されることになった。
このグループの分類が複雑な状況は Fregin et al. (2009) Multi-locus phylogeny of the family Acrocephalidae (Aves: Passeriformes) - The traditional taxonomy overthrown
にもある。Boyd の狭義 Acrocephalus 属が独立した系統をなしていて他を別属にする意味もあるだろう。イナダヨシキリなど似たものが分けられている点、オオヨシキリとコヨシキリの違いも大きいので分類的にも納得できる印象を受ける。
日本産種類に出てこないのでわかりにくいが、この系統分類を見るとヨシキリ科はアフリカ、特にマダガスカルから出生してユーラシア西部、そして東に分布を広げて離島にも及んだことがわかる。
ハシブトオオヨシキリのみが早い系統の中では特殊な分布となっている。
オオヨシキリグループからチュウヨシキリグループが進化した可能性も系統的に不思議でない。
Acrocephalus の属和名は日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではヨシキリ属だが、Boyd の分類を使う場合はオオヨシキリとコヨシキリが別属になるためここで示した名称が適切と思われる。
マダガスカルシマヨシキリ属は共通名称 "シマヨシキリ" でもよさそうだがすべての種がマダガスカルと周辺に分布するためマダガスカルを付けておいた。タイプ種もマダガスカルシマヨシキリ。
ナンヨウヨシキリ類に関する記事は マリアナ諸島に棲息する「ナンヨウヨシキリ類」の進化を探る (山階鳥類研究所 齋藤武馬 2018) で読むことができ、この時点では和名は未確定であった。
論文は Saitoh et al. (2012) The complex systematics of the Acrocephalus of the Mariana Islands, western Pacific。
サイパンヨシキリ Acrocephalus hiwae、カロリンヨシキリ Acrocephalus syrinx の和名は eBird などで使われているためこちらを表示しておく。これら5種のうち和名の未定のものは旧亜種名をかっこ付きで挙げておく。
他の種で eBird から和名を用いたものは * を付けてある。
Saitoh et al. (2012) も引き継ぎ、Kearns et al. (2024) Untangling the colonization history of the Australo-Pacific reed warblers, one of the world's great island radiations
がナンヨウヨシキリ類の種分化の新しい研究を発表している。斎藤氏も共著に入られている。
このグループにはマリアナ諸島で日本の研究者が記載した3種が含まれている (そのうち2種は絶滅)。
ミトコンドリアゲノムでは絶滅種の (ニジョウナンヨウヨシキリ) Acrocephalus nijoi Aguiguan Reed Warbler と (ヤマシナナンヨウヨシキリ) Acrocephalus yamashinae Pagan Reed Warbler (絶滅種) は互いに近い関係にありクレードを形成するが、
現在も絶滅の危機にあるサイパンヨシキリ Acrocephalus hiwae Saipan Reed Warbler とは少し距離がある結果となった。
常染色体の SNPs から作られた系統樹とは違いがありこれらを含むグループをまとめることができるが他のグループと単系統の関係にはならない。
オーストラリアヨシキリ Acrocephalus australis Australian Reed Warbler と (ヤマシナナンヨウヨシキリ) Acrocephalus yamashinae の祖先段階の間で遺伝子移入があった可能性を考えている。
系統的には遠いが長距離を渡るセスジコヨシキリや、系統的にも地理的にも比較的近い渡り鳥のオオヨシキリにも過去に関係があった可能性も否定できないようだが議論がやや複雑なので詳しくは論文を参照いただきたい。
属名の由来は Titiza titizo ひなのような声で鳴く (Gk) タイプ種はスゲヨシキリ。
Notiocichla notios 南の kikhle ツグミ (Gk) タイプ種はヨーロッパヨシキリ。
属和名はイナダヨシキリの方が知名度が高いかも知れないが検討種となる見込みのためヤブヨシキリを採用した。記録はないがヌマヨシキリは簡潔でグループ名として適切かも知れない。
[オオヨシキリの越冬地、渡り、亜種?]
オオヨシキリの越冬地はあまりよくわかっていないらしい。永田 (2003) Birder 17(11): 79-81 によれば DNA 解析の結果一般に越冬地とされるタイやインドネシアのものと日本のものは異なるとのこと。
オオヨシキリ (Bird Research News 2007 西海功) によれば足環の回収例から日本で繁殖する個体は主にフィリピンで越冬していると思われるとのこと。ロシア沿海州 (沿海地方) や朝鮮半島など大陸で繁殖する個体は、遺伝学的、形態学的研究から、インドシナ半島からジャワ島にかけて越冬していることが示唆されているとある。
インドシナ半島での越冬地行動をもとに渡り特性を考察した過去の研究 Dyrcz (1995) ヨーロッパとアジアの異なる個体群におけるオオヨシキリの繁殖生態 は現代では注意して読んだ方がよいことになる。
フィリピンのチェックリストでは普通の越冬種で特別なことは書かれていない。
Gluschenko et al. (2023) Breeding birds of Primorsky Krai: the Oriental reed warbler Acrocephalus orientalis (pp. 1517-1538) ロシア沿海地方の繁殖。
この文献では沿海地方の個体群は別亜種 magnirostris としている。"基亜種" orientalis より少し小型で上面がオリーブ色などの違いがあるとしている。"基亜種" はサハリンでおそらく定常的に繁殖している。
1960 年代はまだ少なかったようだが、ハンカ湖では現在数の多い普通の鳥のこと。中国では同亜種がカッコウの宿主となっているがロシアではまれなよう。
別亜種と考える根拠については Malykli and Red'kin (2011) New data on geographic variability and systematics of Black-browed Reed-warbler (Acrocephalus bistrigiceps) and Oriental Reed-warbler (A. orientalis) (pp. 195-203)。
Swinhoe (1860) がアモイで採集して記載した magnirostris の標本とも特徴が合致する
(Swinhoe 自身は Fauna Japonica の orientalis と考えたが Blyth の指摘で別種として記載) とのこと。
Malykli and Red'kin は2亜種に分けるのが適切としている。サハリンでは "基亜種" が記録されているが繁殖はまだ確認されていない。
上記西海 (2007) では「集団が分化しつつある日本と大陸のオオヨシキリ」の項目で 2〜3 割の個体に重複があるため亜種としては分けることはできない。ミトコンドリア DNA の違いはごくわずかで 10 万年程度の分岐を示すにすぎないと記している。DNA 解析が互いに単系統の関係をなすかどうかはこの記述からは不明。
現状日本とロシアで見解が異なっている。
ニシオオヨシキリのジオロケータによる渡り経路追跡: Horns et al. (2016) Geolocator tracking of Great Reed-Warblers (Acrocephalus arundinaceus) identifies key regions for migratory wetland specialists in the Middle East and sub-Saharan East Africa。
[オオハシヨシキリ]
オオハシヨシキリ Acrocephalus orinus (通常使われる分類で) はかつて最も珍しい種とされ、1867 年にインドで採集された標本しか知られていなかった。
2006 年タイで野生個体が再発見され DNA 解析で同種と確認され、2例めの標本となった。
繁殖地はタジキスタン、キルギスタン、ウズベキスタン東部、カザフスタン南部で 2011 年にタジキスタンで巣が発見されたとのこと。IUCN では LC 種。
Svensson et al. (2008) Discovery of ten new specimens of large-billed reed warbler Acrocephalus orinus, and new insights into its distributional range。
Kvartal'nov et al. (2011) From museum collections to live birds (pp. 56-58。巣の発見と観察記録。ロシア語。写真あり) (以上 wikipedia 英語版より)。
2009 年に同地で若鳥が目撃され 2011 年に捜索した結果巣が発見されたとのこと。調査地域に 15 巣を発見した。
[ヨーロッパヨシキリの分布拡大と遺伝的多様性]
Bergman et al. (2025) Combined evidence reveals the origin of a rapid range expansion despite retained genetic diversity and a weak founder effect (preprint)
近年北方のフィンランドへの分布拡大の見られる種で site fidelity (営巣場所に固執する傾向) は他のスズメ目と同様だが、分布拡大に伴う創始者効果など遺伝的多様性の低下はあまり見られなかった。同様の現象は移動能力の大きい種の分布拡大過程でしばしば報告されている (クロヅル、シロガシラが挙げられている)。
遺伝的見地からもこの種はヨーロッパでは南西地域から分布を拡大したと考えられる。
適した環境が点在してつながっており、元来の渡りの方向と合致していたため分布拡大を手助けしたのではなど議論がある。
-
コヨシキリ
-
セスジコヨシキリ (第8版で検討種)
- 学名:Acrocephalus sorghophilus (アクロケパルス ソルゴピルス) 草を好むヨシキリ
- 属名:acrocephalus (合) 尖った頭 (acro- (接頭辞) 先端 (akron) kephali 頭 Gk)
- 種小名:sorghophilus (合) 草を好む (Sorghum 属の植物 < sorgo 伊 philos 友人 Gk。The Key to Scientific Names)
- 英名:Speckled Reed Warbler
- 備考:
acrocephalus は#オオヨシキリ参照。
sorghophilus は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、長母音は現れないと考えられる。
起源のイタリア語 sorgo も短母音のみ。その場合は "ソルゴピルス" のアクセントが想定される。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。単形種。
-
イナダヨシキリ (第8版で検討種)
- 学名:Acrocephalus agricola (アクロケパルス アグリコラ) 耕地にいるヨシキリ
- 属名:acrocephalus (合) 尖った頭 (acro- (接頭辞) 先端 (akron) kephali 頭 Gk)
- 種小名:agricola (m) 農夫 (ager (m) 耕地 colo (tr) 耕す 住む)
- 英名:Paddyfield Warbler
- 備考:
acrocephalus は#オオヨシキリ参照。
agricola は短母音のみで "アグリコラ" のアクセント。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動 (山階鳥類研究所 鳥類標識調査報告書 2006, 2009, 2012 をもとにしたもので、可能性のある他種を明示的に否定できていないため)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。
2亜種あるが (IOC) 日本の目録では亜種不明としている。
森岡 (1997) Birder 11(6): 74-77 に1992年5月の舳倉島での記録の検討がある。
識別対象に (現在の名前で) #マンシュウイナダヨシキリ Acrocephalus tangorum 英名 Manchurian Reed Warbler が挙げられていた。当時は Acrocephalus agricola の亜種扱いで、亜種間の識別となっていた。
tangorum を完全に否定できない識別点は残るが、agricola が支持されるとの結論となった。
-
ヤブヨシキリ
- 学名:Acrocephalus dumetorum (アクロケパルス ドゥーメートールム) イバラのやぶにいるヨシキリ
- 属名:acrocephalus (合) 尖った頭 (acro- (接頭辞) 先端 (akron) kephali 頭 Gk)
- 種小名:dumetorum (属) イバラのやぶにいる (dumetum -orum (複数-属) (n) イバラのやぶ)
- 英名:Blyth's Reed Warbler (英国鳥類学者 Edward Blyth 由来)
- 備考:
acrocephalus は#オオヨシキリ参照。
dumetorum は冒頭の3母音がすべて長母音。"ドゥーメートールム" のアクセントになる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
-
ハシブトオオヨシキリ
- 第8版学名:Arundinax aedon (アルンディナクス アエードン) ナイチンゲールのアシの主人 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Acrocephalus aedon (アクロケパルス アエードン) ナイチンゲールのヨシキリ
- 第8版属名:arundinax (合) arundo, arundinis アシ (L) anax, anaktos 主人、支配者 (Gk) "オオヨシキリに似た" かも (備考参照)
- 第7版属名:acrocephalus (合) 尖った頭 (acro- (接頭辞) 先端 (akron) kephali 頭 Gk)
- 種小名:aedon ナイチンゲール (合) aidon ナイチンゲールにされた女性 (ギリシャ神話)
- 英名:Thick-billed Warbler
- 備考:
arundinax は外来語を含む合成語のため発音は必ずしも明確でないが、arundo は末尾が長音。変化形で語末が -i- になる場合は短音になるため長母音は現れないと考えられる。ギリシャ語 anax にも長音がない。短母音のみと考えれば "アルンディナクス" のアクセントが想定される。
The Key to Scientific Names ではこの語義で解釈されているが、属記載の比較対象に Calamoherpe arundinacea (?) が現れ、ギリシャ語 anax と結合させたものか必ずしも明確でない気がする。多くの場合動詞に結合して形容詞を作る -ax の語尾ならば長音。対応するラテン語動詞がないのでギリシャ語と結合させたものと解釈されているのかも知れない。
-ax の語尾ならば "に似た" の意味となり得る。#ガビチョウの属名のように単に "に似た" の意味で使われている場合もあるので、"オオヨシキリに似た" の意味とも解釈できると思う。この場合は "アルンディナークス" と読むのが適切となる。
aedon は e が長母音でアクセントもここにある (アエードン)。
ナイチンゲールの意味だが、ナイチンゲール (サヨナキドリ) の種小名が megarhynchos であることと関係があるのだろうか。
記載時学名 Muscicapa Aedon Pallas, 1776 で基産地 Dauria (= southeastern Transbaikalia, eastern Siberia) (Avibase による)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Arundinax 属 [arundo, arundinis アシ (L), anax, anaktos 主人、支配者 (Gk)] に変更。種小名は変化なし。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では和名もハシブトヨシキリとする案になっていたが日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で元の名前に戻された。
Arundinax 属はハシブトオオヨシキリ属となる。単形属。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では日本で記録される亜種は rufescens (「赤っぽい」の)とされる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では亜種 stegmanni (ロシアの鳥類学者 Boris Karlovich Shtegman に由来) とされていた。この亜種は現在では rufescens のシノニムとされる。世界には他に基亜種のみ (IOC)。
Hartert (1910-1922) p. 554 では Phragamaticola Jerdon, 1845 を有効とし、こちらに先取権があると判定していた。
Phragamaticola は phragmites 草の一種 -cola 住む で、ハシブトオオヨシキリのみを含む属として定義されたもので、属創設に伴って Phragamaticola olivacea の新名 (#ノスリの備考参照) が与えられた。属名は Blyth (1849) が Phragmaticola と訂正した (The Key to Scientific Names)。
Hartert は Gekennzeichnet durch sehr dicken, kurzen, gewoelbten Schnabel, starke
Schnabelborsten ... と厚く膨らんだ嘴で Acrocephalus 属 (オオヨシキリなどを含む) から区別できると記述していた。
これは Blyth (1845) の Arundinax 属定義ではなく、ハシブトオオヨシキリの記述をほぼ踏襲していて、オリジナルは at once distinguished by its shorter and thicker bill ... (参考)。
属名は異なるが単形属のためこの記述で十分で Hartert が属記述に拡張したらしい。英名も Thick-billed (Reed) Warbler となったのだろう。もともとは Reed が付いていたが最近は一般に省略されている。
分子系統研究によりさまざまな属が提案されてきた: Fregin et al. (2009) Multi-locus phylogeny of the family Acrocephalidae (Aves: Passeriformes) - The traditional taxonomy overthrown でヒメウタイムシクイ Iduna 属に置くことが提案されたが、
Arbabi et al. (2014) A re-evaluation of phylogenetic relationships within reed warblers (Aves: Acrocephalidae) based on eight molecular loci and ISSR profiles で否定、Arundinax が先取権の原理から採用された (wikipedia 英語版より)。
Arundinax 属は Blyth (1845) が提唱したもので、こちらもハシブトオオヨシキリのみを含む属として定義され、Arundinax olivaceus の新名を Jerdon (1845) と同様に与えた。
どちらが早かったかの議論は Hartert p. 554 にあって Hartert は Phragamaticola が有効かつ早いと考えていたが、Pittie and Dickinson (2013)
The dating of the Second Supplement to Jerdon's Catalogue of the birds of the peninsula of India in the Madras Journal of Literature and Science が年代の再判定を行った。
Rosenberg et al. (2018) Notes Thick-billed Warbler (Iduna Aedon at Gambell, Alaska: First Record for North America
に北米初記録の事例がある。
-
ヒメウタイムシクイ
- 学名:Iduna caligata (イドゥナ カリガータ) 長靴をはいている春の女神
- 属名:iduna (合) 北欧神話で春の女神 Iduna。スズメに変えられた
- 種小名:caligata (adj) 長靴を履いている (caliga (f) 長靴 -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Booted Warbler
- 備考:
Iduna の発音は明瞭でないが、英語の発音を聞けるページでも I- は2重母音にせず -du- を短音でアクセントを置いている。
caligata は -ga- の a が長母音でアクセントがある (カリガータ)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。ヒメウタイムシクイ属は主にアフリカ、ヨーロッパから南アジアに分布する。
梅垣他 (2011) Birder 25(12): 46-47 に2007年4月に粟島で記録されたヒメウタイムシクイ属の考察がある。当時は Hippolais属とされていた [hupolais アリストテレスの言及した不明の小鳥。hupo 下 laas 石 (Gk) の語源も考えられるとのこと]。
識別対象となった種はアラビアウタイムシクイ 現在の学名で Iduna rama 英名 Sykes's Warbler。この種の和名にミナミヒメウタイムシクイが与えられていたが分布から新称アラビアウタイムシクイが提唱されたもの。
かつてはヒメウタイムシクイとアラビアウタイムシクイは同種とされていた。
渡部他 (2005) 日本におけるヒメウタイムシクイ Hippolais caligata の初記録、
高木 (2011) 鹿児島県トカラ列島平島におけるヒメウタイムシクイ Hippolais caligata の観察記録
ヒメウタイムシクイがあるならばウタイムシクイがあろうと考えるのは当然であるが、この種は Hippolais polyglotta と現在では属が異なる。ヨーロッパで繁殖してアフリカに渡る。英名 Melodious Warbler。
種小名 polyglotta はおそらく大変覚えやすく、英語にも polyglot (数カ国語に通じた人、多言語使用者) の単語がある < poly 多くの glottos 舌 (Gk)。
北米のマネシツグミ (英名 Northern Mockingbird) も Mimus polyglottos の学名を持つ。
△ スズメ目 PASSERIFORMES セッカ科 CISTICOLIDAE ▽
-
セッカ
- 学名:Cisticola juncidis (キスティコラ ユンキディス) イグサで作ったような小さなバスケットに住む鳥
- 属名:cisticola (合) kistis 小さなバスケット (Gk) -cola 住人。巣の形状から (The Key to Scientific Names)。しかし [セッカの和名検討] を参照
- 種小名:juncidis (adj) イグサで作ったような (juncus -i (m) イグサ -idus (接尾辞) 状態を表す)
- 英名:(Fan-tailed Warbler), IOC: Zitting Cisticola
- 備考:
cisticola は外来語由来の合成語で発音は明らかでないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのためおそらく長母音は現れないと考えられる。"キスティコラ" のアクセントになると推定される。英語 (冒頭は si- の音になる) でも同じアクセント位置なので問題なし。
juncidis は juncus も -idus も短母音なので長母音は現れないと考えられる。"ユンキディス" のアクセント位置が想定される。
ヨーロッパ、アフリカ、中東、アジア南部から東部、インドネシアからオーストラリア北部まで広く分布する種類。17 亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は brunniceps (「茶色い頭の」の意味)とされる。
この亜種の記載時学名は Salicaria (Cisticola) brunniceps Temminck & Schlegel, 1850 (原記載) で、"Fauna Japonica" の補遺に現れる。図版。
図版で使われた学名は Salicaria brunniceps で Cisticola はこちらには現れない。
比較的近くでは中国東部や台湾、東南アジアに生息する亜種 tinnabulans (「チリンチリンと音を立てる」の意味) がある。
旧英名の Fan-tailed Warbler はアメリカに同名の種オウギアメリカムシクイ Basileuterus lachrymosus があるなどの理由により推奨されない (wikipedia 英語版)。Avibase では streaked fantail warbler の名称を挙げている。
音声なども異なるなど、複数種に分割する考えもあるが Cisticola (セッカ) 属がすでに非常に多くの種を含んでおり、亜種の扱いなどはまだあまり検討されていない模様。
属名に使われる cisticola はハンニチバナ科ゴジアオイ (Cistus) 属の草に住む (コンサイス鳥名事典) の解釈がある。Cistus 属は Linnaeus, 1753, cistus, rock-rose として記載したもの。
属を記載した Kaup (1829) に Sie leben wie die uebrigen Rohrsaenger, bauen aber ein trichterfoermiges Nest ins hohe Gras (高い草の中の漏斗状の巣) に記載があり、The Key to Scientific Names の解説をもとに巣の形の解釈を採用した。
Temminck and Schlegel (1850) の時代の属名に使われた Salicaria は salix ヤナギ由来で、Sylvia salicaria Latham から Selby により属名に昇格されたもの。この種は現在の学名では Acrocephalus schoenobaenus スゲヨシキリ で、Acrocephalus の属名の方が早くて有効と判定されたため残らなかったが、Salicaria 属の名称はかなりの期間使われた模様 (The Key to Scientific Names の情報よりまとめ)。
Cisticolidae によれば Merion の属名に先取権が存在する可能性があることを否定できないとのこと。Cisticola が慣用的に使われてきているが、ICZN の裁定がなされているわけではなく完全に保護されている状態とも言えないよう。
[セッカの和名検討]
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) に "せつか" の名称がすでに登場して学名などとは関係はないと思われるが、鳴き声由来説もあるらしい。この鳥の場合は音声があまりに特徴的なので他の生態などを反映した説よりあり得そうな気がするが飼育下でさえずりを聞くのは難しいかも知れない。
分布が広いので他言語で1つぐらい音声由来のものがないかと探してみると、中国語別名の錦 句+鳥の漢字 が候補となるかも知れない。日本語の音とはだいぶ違うのであまり関係ないかも知れない。
これほど広範な分布にも関わらず鳴き声由来の名称がほとんど見当たらないのは、世界的にも知名度の高い種類ではなかったためではないだろうか。一般的な飼い鳥ではなかったため「喚呼鳥」の "せつか" も現代のセッカと同じかどうか判定が難しいし。外国語由来で鳥学者が整理した可能性も含めて振り出しに戻しておこう。Salicaria を短縮すればセッカにならないこともないかも知れない程度。
参考までにオオセッカに現れるセンニュウ類はドイツ語で Schwirl。こちらは動詞 schwirren に由来で鳴き声を表す (wiktionary)。潜る意味は含まれていない。どれも音があまり似ておらず決め手を欠く感じ。
関連種を調べていて、ドイツ語由来の気がしてきた。Segge (= 英語の sedge に対応) = Riedgras スゲ で、ドイツ語読みだと "ゼガ" だが濁りすぎなので綴りを英語風に読んで清音として "セッカ" とした。
スゲは菅 (スゲ/スガ) 由来でよいのだろうがたまたまなのか音がよく一致している。人名にもよく現れる通り大変身近な植物だった。そして連想が働いた。"なんとかスゲ" では植物の名前になってしまうので少し変えたなど。
Segge を wiktionary で見ておくと、地方名 Saher とも関連があるとのことで、これはアシとのこと。つまり sedge warbler も reed warbler も概念的には大差なかった。
このように考えた理由は "なんとかセッカ" と呼ばれる海外の種類が結構多く、最初は日本語の "セッカ" が先にあってそれを修飾して作られた和名と考えていたが、旧分類概念でヒタキ科ウグイス亜科に散在しているため、旧ヒタキ科ウグイス亜科で対応する和名のないものに "なんとかセッカまたはセンニュウ" と名付けたのではないかと感じたため。
海外の "なんとかセッカまたはセンニュウ" の代表種がヤチセンニュウ 現在の学名で Locustella naevia Common Grasshopper Warbler と英名が付く通り最も一般的な "なんとかセッカまたはセンニュウ" に対応する。かつての Sylvia 属の代表的な種類の一つだが、このドイツ語名に Segge-Rohesaenger がある: Hartert (1910-1922) p. 568。Hartert はこの種を Acrocephalus 属に含めたように現在の分類概念とは科レベルで違っていた。
Grasshopper Warbler は和名に訳しにくいので (過去にも使われていたかも知れない) センニュウやセッカの名前を割り当てたのではないか。「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) p. 134 表 5 によれば「喚呼鳥」(1710)「センニウ」の挿絵があるとのこと。この一覧を見るとウグイス以外の "なんとかセッカまたはセンニュウ" はおそらくはっきり区別されておらず (少なくとも注目されておらず) pp. 164-167 表 7 に名前は登場するもののひとまとめにされていたものかも知れない。
Hartert は何でもヒタキ科に割り当ててしまって亜科すら作らなかった (真正ヒタキ類、"チメドリ類"、"Sylviidae"、ツグミ類 を概念的には区別していた: p. 469)。
チメドリ類はドイツ語名をそのまま音にしたものと考えられるが (#メグロの備考 [チメドリ類について] を参照)、"Sylviidae" (Hartert 以前からある名称) に対応する概念がなく対応するチメドリのように日本語に転写することも困難であった。
後には日本の代表種を用いたウグイス亜科と名付けられたが、それ以前はタイプ属をもとにした名称としたかったために旧 Sylvia 属の代表的な種類を用いたのではないか。ナイチンゲールなどは訳名が定着していたため対象外で、残りにセンニュウやセッカ、ヨシキリ、ウグイスを割り振ったのではないだろうか。ただし時期を考えると Hartert の分類以前に和名整理が行われていたと想像される。
チメドリの訳名も Hartert の著作以前で、当時はドイツ語に合わせようとしていたと考えればいろいろ納得できる部分がある。"バイト" もアルバイト (Arbeit)、"ゼミ" もゼミナール (Seminar) 由来だし。"ゼミやバイトが忙しい" というといかにも大学生の日常で日本語で通じてしまうが、どちらもドイツ語なのだ。
スポーツなどに使われるゼッケンの由来は何かと見てみるとドイツ語由来が濃厚で、decken (覆う。動詞。鳥の羽の雨覆にも使われる単語) や Zeichen (目印) のローマ字読みがなまったものなどの説があるとのこと (wikipedia 日本語版)。この時代でいかにも外来語由来でも由来が確定していないのか...。
ドイツ語の綴りを原語でなくローマ字読みしてもあまり不思議でない。
英語が主流言語となった時代でも warbler の概念が大まかすぎて、あまりにも何でも含まれていたため、warbler を全部そのまま訳すわけには行かず (例えばすべて "なんとかウグイス" のような名前ばかりになってしまう。中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 112 によれば実際に Grasshopper Warbler をバッタウグイスと訳した例があったとのこと)、英語の warbler の分類を参考にしつつ、例えば Leaf Warbler には "ムシクイ" などの名称を与えていった。しかし Sylvia は困るので代表種由来で日本名らしく通じる名称を選んだなどのプロセスを考えることができるような気がする。
いずれも鳥学者にも馴染みの薄い種類ばかりで、"センニュウ" もこのころに Locustella 属の名称 (エゾセンニュウを指すカラフトホトトギスではさすがに総称に使えそうもないので) として採択されたものではないだろうか。
"なんとかセッカ" には例えばハシナガオウギセッカ 現在の学名で Locustella major Long-billed Bush Warbler があって、"セッカ" と "センニュウ" があまり区別されず用いられていた経緯も示唆される。標本を見ても同じように見えてしまうわけだ。
現代の分類ではムシクイに含まれるムジセッカも同様。Dusky Warbler では warbler に修飾語が付いていないのでどの分類かわからず色から名付けたのだろう。
"オウギセッカ" に対応する英名の fantail warbler はかつて分離される前のセッカの英名。warbler に修飾語が付いていない場合の warbler の訳出に苦労していたことが推察される。
セッカ類の別名に tailorbird が使われていたこともあって、こちらは訳出されてサイホウドリ。現在ではセッカ科の Orthotomus 属の英名に用いられている。有名な種ではオナガサイホウチョウ Orthotomus sutorius Common Tailorbird (南から東南アジアの極めて普通種)。
この訳出は weaverbird (Ploceidae 科) をハタオリドリと訳したのと同列で身近な生活に関係する名称が英名・和名ともに使われていた。
なお英語の Grasshopper Warbler も属名の Locustella 由来。
Latham, Index Ornithology (1790) で紹介されたもの (OED)。この属のタイプ種が前述のヤチセンニュウ。英語もバッタに例えたというより学名から訳したもの。それをさらにバッタウグイスと訳してゆくとどんどんおかしな方向に向かってゆく。
実際にどのような声で鳴くかは音源を聞いてみていただきたい。日本の種で現在 (AviList 分類で) 同属なのはマキノセンニュウのみで、この声を知っていればほぼ想像していただけるだろう。
エゾセンニュウと系統が遠いことも音を聞いていただけば納得されるだろう。
スゲヨシキリ Sedge Warbler の英名は 1776 年 Pennant, British Zoology であまり違わない (OED)。英語で warbler が英語の warble にまったく対応しそうにないさえずりのヤチセンニュウなども指して使われるようになったのは分類概念がある程度進んでからのことで比較的新しかった。
#キタヤナギムシクイ備考の「ムシクイの名称は山階芳麿博士の提案」部分も参照。英語で warbler と付くものをあまり系統関係を考えず「ムシクイ」と訳すようになった経緯が述べられている。英語の warbler の概念があまりに広範であったため (ドイツ語でも Saenger で同じく区分に役立たない)、もう少し小分けする必要があって複数の起源をもとに英名などを手がかりに名称が作られたのだろう。そして当時は分類も混乱していたころで、その後属分類もよく変わりいろいろなところで混ざってしまった - いかがだろうか。
"センニュウ" はドイツ語に対応させたもの?
上記ドイツ語名は Hartert などを参考にしたが、Sylvia 属を指して Grasmuecken と呼ばれることを知った。これは古いドイツ語 grasmugga 由来で gras (草) + schmiegen (かがむ、従うなど) の意味があるとのこと (wikipedia ドイツ語版より。辞書にもうぐいすの一種として載っている。かつての日本ではすべてうぐいすの仲間に含められていたこともわかる)。
"センニュウ" の名称選択にはこの影響が現れているかも知れない、と考えたのは キンメセンニュウチメドリ 現在の学名で Chrysomma sinense (なお種小名語尾を見て中性であることに気づかれる方もあるだろう) Yellow-eyed Babbler の現在のドイツ語名が Goldaugen-Grasmuecke であるため。
この訳名は "キンメ" の部分はドイツ語の通り。Grasmuecke にセンニュウを与えたと見るのが適当に見える。ドイツ語別名で Goldaugen-Timalie でチメドリ部分はこちら由来と推定できる。"キンメチメドリ" でも十分だったのにわざわざ "センニュウ" を加えているのは Goldaugen-Grasmuecke と Goldaugen-Timalie の名称過渡期だったのではないだろうか
(当時はアジアの鳥の分類が明確でなく、チメドリ類はゴミ箱状態だった: メグロの備考 [チメドリ類について]。つまり我々が海外の鳥を "なんとかウグイス" と呼ぶのと同じ感覚で Goldaugen-Grasmuecke の名前があったが分類を分けた方がよいことが明らかになってきて、"センニュウ風チメドリ" のような名称が過渡的に用いられたと考えられる)。
現在のドイツ語では現在の Sylvia 属に大部分にこの Grasmuecke の名称を与え、一部の種に Saenger (英語 warbler に相当) を付けている。Sylviidae 科がドイツ語名 Grasmueckenartige、現代の亜科でも同様に用いられるのでこの名前が一般的によく知られていた (いる) と考えられる。
過去の名前を見るとキンメセンニュウチメドリのように、旧 Sylvia 属に相当するものを広く Grasmuecken と呼んでいたようで "草むらにかがむ" から "センニュウ" が割り振られ、セッカやヨシキリは別の特徴があるので別系統の名前を与えたと考えることができるかも知れない。
別の言い方をすれば英語の Bush Warbler 類にウグイス、ドイツ語の Grasmuecke にセンニュウを割り振ったと考えればうまく説明できる感じがする。この時代の命名はドイツ語の影響を濃厚に感じる。
#カヤクグリの備考にあるように、ドイツ語では早い段階で世界の鳥に名称が与えられて他国語にも影響を与えていたものと思われ、和名を与えるに当たって英語よりも役に立ったかも知れない。
ドイツ語の意味に対応する鳥の名前で過去の国内の用例のあるものを (同じかどうかはわからないが用例重視で) 割り当てたものかも知れない。"バッタウグイス" よりは格調があって意味もよく再現していたのだろう。
あまり言及されていない他の可能性を考えてみると、「石火」は火打ち石から出る火花のこととのこと (wiktionary)。転じて短時間を指すこととなったが、セッカの声にヒタキ類が石を打つのにたとえられるような音があるのでこの可能性もあるかも。
セッカのさえずりを表記するとイソヒヨドリの地鳴きと同じようになるので、西洋の人が聞いたらノビタキのように石を打ち合わせるような音と聞いても不思議でないと感じた。そう思ってみると妙な共通点があることに気づいた。これらの種類の属名はみな -cola で終わるのである。
Saxicola は chat の意味?
-cola は通常動詞 colere から由来して "住む" の意味と解説されることが多いが、#ノビタキの備考の属名 (Saxicola) 解説にあるように、ドイツ語定義では -cola に "住む" の意味を与えておらず、Steinschmaetzer (岩場の舌鼓を打つ者) としている。ここでは説明的に訳していたが、これはまさしく "石火" ではないか。
ノビタキの属名解説では「-cola に "住む" 意味を含めたというより単に "者" を指して、造語の際に種小名と韻を踏んだものかも知れない」と記述した。属名としては不自然なところが残っているのである。
そのような視点から調べてみると、現在使われる属名で -cola の語尾を持つものは、いわゆる英語の "chats" が非常に多く、別の系統で "住む" の用例はむしろ少数であることがわかった。
現在使われる属名の一部は種小名からの昇格なので、"住む" の意味で属名に -cola を用いることはむしろ珍しかったのではないか。確かに標本から命名する場合はどこに住んでいるか必ずしも自明でないので、よく知った種類以外は生息環境をもとに属名を与えるのは危険もあり (推定が間違っていても訂正できない)、より安全な身体的特徴をもとにした属名が主に使われたと想像できる。
その中で、"chats" に -cola が多用されているのは類似性 (ここでは音声に共通点がある) を示す一種の語呂合わせだったのかも知れない。Saxicola, Monticola (イソヒヨドリ属)、Cisticola (セッカ属) の系列となる。他にも Schoenicola (センニュウ類の属) がある。
-cola を語呂合わせで "chats" を指したものと思えば、Saxicola は岩場の chats、Monticola は山の chats (この場合は音声のみの類似性)、Cisticola は Cistus (ゴジアオイ属 = rock-rose) または kistis 小さなバスケット の chats、Schoenicola はアシの chats などとなる。
-cola を "住人" と訳してもそのまま意味が通じるが、"chats" に共通の性質として選択されたと考えれば納得できる部分も多々ある。-cilla のように原意を離れて "尾" の意味で使われるようになったものもあり、-cola を "住人" と訳して意味が通じるのでそのまま解釈に採用されているものの、"chats" に特に限定して使われる理由があったのではないだろうか。当時の博物学者は由来まで記していないが、博物学者の間では通じる合言葉のようなものだったのかも知れない。
さらに考えてみると Saxicola Bechstein, 1802,
Monticola Boie, 1822,
Cisticola Kaup, 1829,
Schoenicola Blyth, 1844 の順序となっている。
Bechstein (1802) は Saxicola に "住む" 意味は特にない定義を与えているので、Saxicola そのものを (いわゆるヒタキ音のように) 舌鼓を打つ者 と理解することも可能である。
つまり、Montisaxicola のような名称で山の舌鼓を打つ者を表すことも可能であったが (これはアトリの種小名に使われた montifringilla からの類推)、長くなっていかにも嫌われそうなので省略して Monticola とした、他も同様とすればすべて納得できる気がする。
Bechstein (1802) が特に住人を意味するわけではない語義を定義しているので、それを踏襲すれば "そこから派生したことは自明" で博物学者もわざわざ語義を書き残すまでもなかったと考えることができる。この場合 (Saxi)cola = chat ということになる。
Saxicola が複合的に用いられている属名に Muscisaxicola がある。例えば南米のイワタイランチョウ Muscisaxicola rufivertex Rufous-naped Ground Tyrant がタイプ種。こちらは音声はそれほどでもなく (標本ではおそらくわからない)、Saxicola との習性や生息環境の類似性から。複合属名に用いるぐらいなので博物学者にとって Saxicola がそれほど身近な種類であったとも言えるだろう。
ヨーロッパにも生息するセッカのさえずりは類似性を示すよい特徴根拠になったかも知れない。
学名には現れにくいが、ヨーロッパの博物学者もセッカのさえずりに気づいていて、暗黙で属名に利用していたのかも知れない。
このように考えると和名と「石火」を関連させるのはなかなかよいかも知れない。和名採択の理由も一つではなく、当時考えられた複数要因のいずれも満たす解として収束したものかも知れない。
参考までに chat の利用例を OED で調べておくと、いわゆるおしゃべりのチャットとは別語義とされており、1678 年の Ray, translation of F. Willughby, Ornithology が初出で、Whin-chat とともに現れる。すなわちラテン語からの翻訳。同じ文献ですでに語義が Saxicola 属または類縁種以外に拡張されて海外の鳥も指していた。
つまり英国でも海外の文献を紹介する必要があって chat や Whin-chat の名称は訳名として現れたもの。OED はおそらく音声由来の語源としている。分布を調べてみると Whinchat は英国で夏鳥で、この段階で名前が定義される程度なので一般にはそこまで知られた種類ではなかったのかも。日本でも目立つ有名な鳥以外はそんなものかも知れない。
さらに興味深いのはドイツではヨーロッパノビタキに英語の "stonechat" (英名は学名からの翻訳なので同等に扱う必要はない) に相当する語を与えているが (= 属定義)、スウェーデン語では同じ意味 (Stenskvatta) をハシグロヒタキに与えている。つまり相互に翻訳された結果ではなく "stonechat" に相当する概念はそれぞれの地域で目立つ種に別途与えられたものと想像される。
これだけ見れば慣用名は統一されていなくて紛らわしいですね、の豆知識に終わってしまいそうだが、それだけ "stonechat" に相当する音声は目立つ特徴となる普遍性があったとも言える。
Linnaeus は Motacilla Oenanthe Linnaeus, 1758 と学名を与えたが、音声は知らなかったためアリストテレスの古典から名称を採用せざるを得なかったのだろう。
日本で "ヒタキ" あるいは石を打つ音に相当する音声が注目を浴びたのも、ある意味世界的に普遍的な現象だったのかも知れない。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 140 (1946 年初出) によれば、虚子の「改訂新歳時記」では鶲の項目の記述はジョウビタキの特徴とノビタキ (色彩表記) の特徴が入り混じっているとのこと。共通性を考えればやはり音声だろうか。過去の知識を想像するとノビタキが冬にはジョウビタキになると考えても別に不思議でなかったかもしれない。音声が注目され東西共通で似た名前が付いたグループだろう。
不思議なことに野鳥を始めるまで自分はジョウビタキに気づいていなかった。わかってしまえばあれほど季節感があってわかりやすい声も少ないのに。もっとも誰もが気づくわけではないらしく、近隣の学生は誰も気づいていた者はおらず、「今鳴いている」と示してもどの音声かわかってもらえないこともあった。
以下にも議論するように確かに猛禽類にも目立ちにくい声なのかも知れない。
セッカはなぜ人目を引かなかったのか
中西悟堂「定本・野鳥記」8 p. 97 (東京の 1937 年の観察メモに基づく) があって、こどもは鳴く虫は追いかけてもセッカの声には気づいていない。いや大人も誰一人関心を持っていないのではないか (要約。原文通りではない) 感想が述べられている。我々がセッカの声がわかるのもセッカの声と教えられているゆえで、鳥に関心のない者にとってはそもそも注意を引かない音声かも知れない。そのように考えると一般には馴染みの鳥ではなく古くから名前が付いていない理由も説明できる気がする。
和名語源説の一つである巣材の色から「昔の人はよく観察していた」と解釈を広げるのはおそらく過剰解釈なのだろう。
注意を引かない音声は生態的理由を考えるのがよいだろう。要するに捕食者対策だと思えばよい。さえずり前半のヒッ、ヒッ... の部分は音声から定位しにくい声で、チャ、チャは降りる時に出す声。この声は定位しやすいが目立たない環境に降りることになる。
しかしさえずりの役割を考えると同種には目立つ必要があるので、定位しにくい声を出しながらもさえずり飛翔をして同種には目立たせているのだろう (この点はオオセッカもよく似ている)。冬場は非常に目立たなくなって、越冬しているのかどうかすら判断困難になることからみても、本来は目立たない方を好む種類なのだろう。
セッカは ウグイス上科? Sylvioidea で鳴禽類の中でも比較的古い系統。この系統の出現年代を見ておくと 1800 万年前程度 (Stiller et al. 2024) でそれ以降に適応放散したと考えられる。出生は分布から見てもアフリカだろう。
乾燥化が進んでパッチ状の草原や湿地が現れるようになって適応放散したグループだろうか。
アフリカならばタカ類の主要系統はすでに揃っていたので (こちらも適応放散要因の一つに草原の広がりがある)、昼行性猛禽類対策で目立たない声や潜行性を進化させる理由が十分ある。これらの草原や湿地に生息する小鳥の増加に合わせて猛禽類も増えたのかも、そして北半球への拡大や渡りの進化も同様に進んだのかも。
#ツリスガラ備考の [スズメ目の進化とレトロウイルス/トランスポゾン] で紹介の He et al. (2025) の結果と合わせてみても面白い。主に小鳥食の Accipitrinae 亜科がまだアフリカにとどまっていた時期に、これらのタカ類で ERVs (内在性レトロウイルス) の遺伝子組み換えが起きていたと考えられる。このころウグイス上科? Sylvioidea の鳴禽類に適応放散に伴って Accipitrinae 亜科の中で特に小鳥食の特性が生み出された経緯が ERVs に痕跡をとどめているのはないだろうか。
さらに系統を遡って Accipitrinae 亜科でウタオオタカ類などまだ小鳥食を本格化させていない系統の高精度ゲノムが読まれれば Accipitrinae 亜科と Sylvioidea 上科の共進化が読み取れるかも知れない。
センニュウ科も近縁なので生態的には同様に考えることができる。センニュウ類の声もタカ類にとって我々と同じようにやはり虫のように聞こえて目立たないのかも知れない。
セッカもセンニュウも目立たないので古くからよく知られた和名がなかった。その理由を遡ると出生の地の昼行性猛禽類による捕食圧由来、そして昼行性猛禽類が我々に近い音声感覚特性を持っているためとも言えることになるのかも知れない。そして世の中になぜハイタカ類がいるのか、などにもゲノム生物学が合わせて答えを提供してくれるかも知れない。
セッカやセンニュウと似た環境に生息し、巧妙な巣を造ることで有名なツリスガラ科はセッカやセンニュウとは別系統で シジュウカラ上科 Paroidea。この分岐は 2100 万年前程度 (Stiller et al. 2024) と少しだけ古い。この習性の違いは小鳥食猛禽類の進化の時期との前後関係を反映しているのではないだろうか。
空からの捕食者があまりなければ地上からの捕食者のために最適化して吊り巣を造ることに特化した、あるいは枝の上に造るより捕食者の入り込みにくい (かも知れない) 洞を主に用いるようになった (ユーラシアでは例えばカラ類) などの可能性を思いつく。造巣行動には高い認知能力が必要で、そのために神経ネットワークを構築してしまうと大幅な構造の変更は難しく、既存のやり方を少しずつ改良する形の造巣行動の進化が一般的となったのだろう。
巣ではないが造形行動が系統的に固定されて大幅な変更が起きにくい例としてニワシドリ類を思いつく。参考 Ericson et al. (2020) Parallel Evolution of Bower-Building Behavior in Two Groups of Bowerbirds Suggested by Phylogenomics。
セッカ類がマダガスカル (マダガスカルセッカ Cisticola cherina Madagascar Cisticola) にも生息することを知って、もしかするとマダガスカルが出生の地だったのではと気になって調べてみた。
系統研究の論文がオープンアクセスではないので、ここでは AF094625.1 から BLAST を行ってみると Cisticola 属の中でセッカやこのマダガスカルセッカを含むクレードが祖先的となった。
このクレードの中でもマダガスカルセッカが比較的祖先的。ただし使っている遺伝子が限定的でセッカと単系統の関係をなしていないので暫定的に見ていただきたい。ND2 (DQ871377) を使うと異なる系統樹となり、セッカを含むクレードが Cisticola 属内でも祖先系統らしいことはおそらく確かだが、セッカやマダガスカルセッカは "上種" の関係と思ってよさそう。
xeno-canto の録音の範囲ではマダガスカルセッカの音声にはセッカのヒッ、ヒッ... の部分がない。
このようなことを考えた理由は、大陸に比べてマダガスカルの方が猛禽類の種類が少ないため新しい系統が生まれやすかったのではないかと思った次第。
Accipitrinae 亜科には我々に身近な Tachyspiza 属の一つ前に分岐した系統である アフリカオオタカ Aerospiza tachiro African Goshawk があるが Aerospiza 属はマダガスカルに分布していない (亜科や属の和名を添えてくれると親切なのに、と思われるかも知れないが、2025.7 時点でまだなく横文字ばかりになる)。
シロハラハイタカ Tachyspiza francesiae Frances's Sparrowhawk とマダガスカルハイタカ Accipiter madagascariensis Madagascar Sparrowhawk は後にマダガスカルに定着した系統でマダガスカルセッカが誕生したころにはまだ生息していなかった。
つまりアフリカ大陸部には Aerospiza 属や Tachyspiza 属が生息しているがマダガスカルには生息していない若干の時間的空白があったのではないだろうか。
Accipitrinae 亜科のさらに古い分岐にあたる Melierax 属 (ウタオオタカ類。小鳥食をまだあまり発達させていない) や別属の カワリウタオオタカ [高野 (1973) ではモリウタオオタカ] Micronisus gabar Gabar Goshawk もアフリカ大陸部のみ。
主に小鳥食の猛禽類がまだ入っていなかったため大陸部に比べると捕食圧が低かったのではないかと想像できる。
それ以前から存在していたタカ類では、目立つところではマダガスカルチュウヒダカ Polyboroides radiatus Madagascar Harrier-Hawk とマダガスカルヘビワシ [高野 (1973) ではマダガスカルオナガヘビワシ] Eutriorchis astur Madagascar Serpent Eagle があり、名前からはどんな種類かわかりにくいが、ハチクマ亜科あるいはそれに近い系統と思えばよい。この系統の種類は他にも生息していたが、後の種類の定着などの理由で失われたものもあるかも知れない。
マダガスカルヘビワシは生息環境破壊が進んでほとんど絶滅手前の状況で情報も少なく、もはや本来の生態を表しているかどうかわからないが (#ハチクマ備考の [60 年ぶりに再発見されたマダガスカルヘビワシ (ハチクマ亜科)] 参照)、
マダガスカルチュウヒダカならば対応種 (チュウヒダカ [高野 (1973) ではアフリカチュウヒダカ]) が大陸にも生息していてある程度わかる。これは器用で樹洞の獲物を捕えるのが得意なのである (#クロハゲワシ備考 [変わった採食方法を用いる猛禽類] 参照)。
マダガスカルでは主に小鳥食の猛禽類が不在だったが、セッカやこのマダガスカルセッカが生まれたころはこの種類が捕食者となっていたため、セッカやこのマダガスカルセッカは営巣に洞を選択しなかったと考えると整合性がよい感じがする。吊り巣でもこのような種類に狙われればあまり逃れられない。
ツリスガラ科は Anthoscopus 属 (アフリカツリスガラ類) と Remiz 属のいずれが祖先系統かよくわからなかったがアフリカの南の方で発祥したならばチュウヒダカにも対策する必要があって巧妙な巣を作る必要があったのかも知れない。アフリカツリスガラ類の方がより巧妙な巣を造るのも捕食者が多いためだろう。
一方近縁だが後に誕生したシジュウカラ類はユーラシア中央部で種分化して、このような捕食者がいなかったため洞を選択することができたと言えるのかも。
Polyboroides 属の分岐年代は 3300 万年前ぐらい (Catanach et al. 2024)。大陸のチュウヒダカの方しか調べられておらずマダガスカルチュウヒダカの分岐年代は不明。マダガスカルヘビワシの方が若干新しい可能性があり 3100 万年前ぐらい。
両種ともこの時代から生息していた可能性もあるが、マダガスカルチュウヒダカが後に定着したならばマダガスカルヘビワシやもしかすると消滅した類縁種がマダガスカルの頂点捕食者だった可能性もある。
より強力な捕食者であったはずの マダガスカルカンムリクマタカ Stephanoaetus mahery Malagasy Crowned Eagle (絶滅種) は 1600 万年前以降ともっと後の時代。マダガスカルカンムリクマタカの遺伝情報はもちろんわからないので、大陸の現生のカンムリクマタカの年代を上限値とした。クマタカ類系統は誕生に苦労したようで比較的近年まで現れなかった。
もしそうであればマダガスカルヘビワシはそこまで器用に見えない (あくまで外見から) ので、マダガスカルがセッカやこのマダガスカルセッカの系統が育まれた環境に一層ふさわしい感じがする。
セッカのさえずりの特徴や、シジュウカラ科内でツリスガラ科と異なる警戒の音声を分化させた理由も、猛禽類の進化と関係があるかも知れない。#シジュウカラ備考の [カラ類は音声の組み合わせを 1100 万年以上前から使っていた] にて近年の研究と独自考察を紹介した。セッカのさえずりとシジュウカラ類のヘビを示す警戒音声の間で音の時間的配列に共通点があるのはタカに目立たないための共通の性質ではないかと考えた次第。
セッカの生態を考える時、なぜアフリカの特殊な猛禽類を考えることになるのか不思議な気もするが、進化史を振り返って想像を巡らせてみた。
[セッカのひなの威嚇音]
Barlow et al. (2023)
Snake-like hissing calls made by nestlings of the open nesting zitting cisticola Cisticola juncidis
によればセッカのひながヘビの音 (hissing) を真似て威嚇するとのこと。同様の声を出す他の種類もあり、音声の特徴を用いたクラスター解析が行われている。分類的にはさまざまな系統で記録されており、カラ類、フクロウ類にも同様の声を出すものもある。
△ スズメ目 PASSERIFORMES レンジャク科 BOMBYCILLIDAE ▽
-
キレンジャク
- 学名:Bombycilla garrulus (ボンビューキルラ ガッルルス) おしゃべりな絹の尾の鳥
- 属名:bombycilla (合) 絹の尾 (bombyx -ycis (m,f) 絹 cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さなもの)
- 種小名:garrulus (adj) 騒がしい、おしゃべりな
- 英名:Bohemian Waxwing
- 備考:
bombycilla は合成語で発音が明確でないが、bombyx は y が長母音で変化形でも長母音のため合成語でも保存される可能性がある。-cil- は子音で終わるのでここにアクセントがある。"ボンビューキルラ" が想定される。
garrulus は冒頭にアクセント (#カケス参照)。
動詞 garrio 由来で英語では chatter に相当する。garrulus は talkative, garrulous と訳される (wiktionary) の "おしゃべりな" とした。garrulous はくだらないことをよくしゃべる、などの意味が辞書に紹介されている。フランス語名も chatter に近い意味で、"騒がしい" の訳語はあまり適切でない感じがする。
IOC 分類では世界的には2亜種 garrulus (ユーラシア)、pallidiceps (「淡色の頭」の意味。北米) が認められている。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに使われている亜種 centralasiae (中央アジアの) は HBW/BirdLife、Clements が採用している。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)では亜種 garrulus となった。
[属名の由来]
属名の bombycilla はドイツ語 Seidenschwanz (Seide 絹 Schwanz 尾 < schwanken 揺れる、で、ラテン語の -cilla には本来は尾の意味はないこととよく対応する) をラテン語に直訳したもの (wikipedia 英語版より)。現在のドイツ語名も同じ。デンマーク語やノルウエー語では同様であるが、日本語は習性を表すように言語により着目点は様々である。
例えばオランダ語では pestvogel で疫病 (ペスト) 鳥で、語源は中世に遡り、この鳥が疫病を運んでくると信じられていたことによる (wikipedia オランダ語版より。年によって大量に現れたり来ない時もあるなどの irruption は疫病の流行に似ているかも知れない)。
フランス語では jaseur でぺちゃくちゃしゃべるもの。ロシア語でも音声由来で sviristel'。
[レンジャクの属名決定経緯は複雑]
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代の学名は Ampelis garrulus だった。
Linnaeus (1758) では Lanius Garrulus (原記載)。当時は β. Garrulus carolinensis を別型にしてヨーロッパとアメリカ北部に生息するとしていた。
ちなみに Linnaeus (1758) の分類では Lanius 属は Aves Acciptres とタカの仲間だった。さすがにレンジャクは違うだろう...
Lanius 属から分離する際に用いられた属名のようで、Linnaeus の Fauna Suecica には Ampelis 属と記載されたものに Ampelis garrulus が含まれていたためキレンジャクを意図したことは疑いないが、
Ampelis 属の本来の用法は南米の全く異なるものを指していたとのこと。Ampelis の意味は Aristophanes が用いた不明の鳥 ampelidos に由来するが、Linnaeus はキレンジャクがしばしば食べる ampelos ブドウ (Gk) の意味で用いたとのこと。
Linnaeus の用いた Ampelis は同定できる範囲で6種からなっており、南米の Cotinga 属などの複数の属にまたがっている。
Ampelis は複数の属のシノニムとして扱い、キレンジャクは Bombycilla Vieillot, 1807 と同定できるので 1910 年にこちらが採用された模様 [Hartert (1910-1922) p. 455]。
しかし Bombycilla Vieillot, 1808 や Bombycivora Temminck, 1813 (#ヒレンジャクの備考参照) は不適切で混乱を招くとして Linnaeus (1758) の種小名を昇格した Garrulus Dumont, 1822 も提唱されたが、この名称はカケス類を指してすでに使われていた (Brisson 1760)。(The Key to Scientific Names よりまとめ)。
これらの属変更に伴って新名も与えられていた (#ノスリの備考参照): Parus Bombycilla Pallas, 1811 (参考。何とカラ類)、
Corvus lientericus Temminck, 1807 (参考。こちらはカラス類) lientericus は leienteria (Gk) 未消化のものを排泄する、の意味。
Ampelis lientericus Meyer, 1809 (参考)。と lientericus は習性を表現していて納得して使われていたよう。
Bombiciphora poliocoelia Meyer, 1819 (参考)、
Bombycilla bohemica Leach, 1816 [参考 Bohemian Waxwing とあり英名から対応する学名としたもの。この時点では無効名だったが Foster (1817) の同名の用例があった]。
レンジャク類の属名の成り立ちはそれほど単純ではなかった。
属が変化したため種小名を新たにつけ直したものもある (#ノスリの備考参照)。Bombycilla Bohemica Forster, 1817 (参考) = Bohemian Waxwing (英名と同じ意味の学名を用いた)。この学名は広く受け入れられていたようで長期間の用例がある。英名も現在に至るまで長く残っている。
Dumont (1822) はキレンジャクの学名を Garrulus europaeus Dumont, 1822 または Garrulus major Dumont, 1822 (参考)。
Bombycilla europaea Blyth, 1834 (参考 ただし無効)。これらは "ヨーロッパのレンジャク"。そして Bombycilla vulgaris (参考) "普通のレンジャク"。
Bombysilla vagans Blyth, 1836 (参考) "放浪するレンジャク"。
これだけ多数の名前が付けられたのは逆に言えば Linnaeus (1758) のカケスを思わせるような種小名はあまり人気がなかったのだろう。
ただし当時は "疫病鳥" だったことも考えると、今日我々が楽しみにするほどよい意味で付けられたものばかりではなかったかも知れない。
[冬のレンジャク類はどこに?]
英名・学名の関係を調べていてキレンジャクは英国では秋の結構早い時期に訪れることを知った。日本で春先によく訪れ冬場はどこにいるのか話題となることがあるが、英国の eBird データを見ると 11 月から 2 月まではほぼ均等に訪れており、冬場がピークとなっていて日本のように春先に多いわけではない。日本よりは高緯度であることも関係しているのかも知れないが、日本にやってくるレンジャク類は冬はどこにいるのか疑問が深まってしまった。
英国でも海を越える必要があるためか東海岸が多いが、日本の場合は大陸からの距離が一層大きく海を越える障壁も大きいのかも知れない。冬型の気圧配置が安定している時期はむしろ渡りにくく、低気圧の通過する時期になってようやく渡る条件が整って大陸からやってくるのだろうか (あくまで想像。もしそうであれば冬の日本の気象条件の厳しさが現れているようにも見える)。
参考までに韓国の記録を同様に調べてみるとキレンジャク、ヒレンジャクともに1月がピークで3月には非常に少なくなる。ヒレンジャクの方が少し早く渡来するようで 10 月にも一定の記録がある。あくまで限られたデータだがこれらから推定すると 10 月以前にはまだ繁殖地からそれほど遠くない地域に食物が十分あり気温もまだそれほど下がっていないが、冬には不足して朝鮮半島に南下している印象を受ける。日本のレンジャク類は真冬にはまだ大部分が朝鮮半島に滞在中だろうか。
[キレンジャクの托卵排除行動]
Peer et al. (2011) Persistence of host defence behaviour in the absence of avian brood parasitism によれば新世界のキレンジャクは現在同所的に生息していないカッコウとコウウチョウの托卵を排除する能力があるとのこと。過去に托卵を受けて排除した性質が引き継がれているのでは。
ヒメレンジャクとキレンジャクが分岐したのは 280-300 万年前でその期間排除能力が引き継がれた可能性もあるが、もっと近年に絶滅した鳥に托卵を受けていた可能性もある。コウウチョウの分布はかつてはもっと広かった可能性があるが、それでも 8000-10000 年は托卵排除能力を維持してきたと考えられるとのこと。
[砂糖を分解できる鳥]
レンジャク類はスクラーゼ (砂糖分解酵素) を持っていて効率的に糖分を吸収できるとのこと。
McWhorter et al. (2021) Sucrose digestion capacity in birds shows convergent coevolution with nectar composition across continents
ハチドリなど花の蜜を食べる鳥が砂糖分解酵素を持っていてレンジャク類にも共通点がある。
[キレンジャクはにおいでヒレンジャクを認識する?]
Zhang et al. (2013) Uropygial gland volatiles facilitate species recognition between two sympatric sibling bird species の研究から。成分は違うとのことだが種固有の化合物はなかった。
[ヤドリギを最初に樹冠に運んだのは誰?]
Watson (2020) Did Mammals Bring the First Mistletoes into the Treetops?
現代では主な種子散布者は果実食の鳥だが、それらが適応放散する以前からヤドリギが進化しており霊長類や有袋類が運んでいたのではないかとの考え。果実食のスズメ目の鳥が新参者であることが改めてわかる。
[他個体に食物を与える行為]
週間アニマルライフ (1973) pp. 3963-3964 のレンジャクの項目 (浦本) で北米のヒメレンジャクでは食物をボール送りのように他個体に渡す行動が観察されたとのこと。端にいたイエスズメが送られてきた木の実を食べてしまった事例があるとのこと (出典や真偽のほどは不明)。
またキレンジャクの巣の写真も紹介されている。レンジャクはなわばり防衛を行わず、さえずりらしいものもほとんど発達していないとのこと (レンジャクの声が単純なのはそのような理由があるのか。これはエナガにあまりさえずりらしい音声がない理由にも関連があるかもと思った。もしかしてサンショウクイではどうだろう)。レンジャク類が繁殖する地域ならこそ可能な研究と言える。
この記事でレンジャク類と類縁関係のあるヤシドリ Dulus dominicus Palmchat が取り上げられており、現在では1種で1科を形成する。この鳥はアパートのような巣で共同繁殖をするとのこと。アブラヤシに強く依存した生活形態とのこと (wikipedia 英語版より) で、現代の分子系統解析ではレンジャク類の祖先系統に位置し、レンジャク類の行動の起源を考える上でも興味深い。
[英名と関連おまけ]
waxwing の由来を調べておくと用例は意外に新しく、1817 年 The Wax-wings, which have been detached from the Chatterers by Monsieur Vieillot, have a most remarkable and peculiar appendage on the tips of some of the quills, which has very much the appearance of red sealing-wax (J. F. Stephens, Shaw's General Zoology) に現れたとのこと。
羽毛の先端の着色部分をロウ (sealing-wax = 封ロウ) に例えたもの、は間違いないが、赤色となっているので尾の先端のことではなく翼の次列風切の先端の "ろう状" と呼ばれる方。この書物にはキレンジャクと Carolina Waxwing (Linnaeus の指す β と思われる) が記述されており翼に小さく赤い部分がある。
ノースカロライナ州のレンジャク類の記録をみるとヒメレンジャクに対応すると考えられる。Stephens の記述する wax-wings はキレンジャクとヒメレンジャクの両方を指していたと考えられる。ヒメレンジャクの記載は 1808 年と時代的にも整合する。
Vieillot からの英訳で Chatterers (フランス語名に対応) と名前が紹介されていたことがわかる。1876 年の書物 S. Smiles, Life of Scotch Naturalist では Bohemian Waxwing or Chatterer と Waxwing と Chatterer とは別名の関係になっていた (以上 OED より)。
Leach (1816) Bohemian Waxwing の用例があるのでもう少し遡れそうだが、ほぼこの時期に使われ始めたらしい。
英名に使われる Bohemian の意味は現在では Bohemia (ボヘミア。現在ではチェコ) の住人の意味が中心だが、かつてはジプシーやロマも指していた (語源は同じ。現在ではほとんど用いられない)。
命名当時は放浪的な渡り習性がよくわかっていたとは想像しにくいので、神出鬼没的なところや irruption 的な大群で突如現れることを指していたのかも ("疫病鳥" と扱われたことも参考になる)。古くから使われていた英名を指して "放浪的な" と解釈するのは渡りの習性がわかってから後付けになっているかも知れない。
ジプシーやロマの音楽がクラシック音楽に与えた影響は計り知れないほど大きいが、鳥に関係するところで動画を紹介しておこう。Prezhde my byli ptitsami。ソ連時代の音楽アニメーション (1982) で、冒頭に若干ロシア語導入部分が入るが "我々はかつては鳥だった"。ジプシーやロマの移動を渡り鳥にたとえた物語 (表題をキリル文字で検索すれば youtube 以外にも他の版もいくつも見つけられるのでお好みのものをどうぞ)。
当時のアニメーションで鳥をどのように描写していたかもわかり面白い。最後は有名な曲で終わっているがおわかりだろうか。
wikipedia ロシア語版 に作品のあらすじや制作背景がある。
主題も音楽もすべてジプシーに関連するもので作曲者や演奏の背景も記されている。主役はハヤブサがモデルとのこと。
富への執着がかつては渡り鳥だったジプシーを地上生活の現在の姿に変えた物語。アニメーションで意図のわかりにくい部分があれば上記ページを機械翻訳で読めばほぼ理解可能。
この解説ではジプシーの意味で tsygan (ツィガン) の単語を用いている。言うまでもなくツィゴイネルワイゼンなどの曲名に使われるのと同じ意味。
ひと押しの曲としてラヴェルのツィガーヌ (Tzigane 1924 年初演) を紹介しておこう。クラシック音楽が馴染みでなくても間違いなく楽しんでいただける。
航空機事故で若くして他界したフランスのヴァイオリニスト ジネット・ヌヴー (Ginette Neveu) と兄ジャン・ヌヴ― (Jean Neveu ピアノ) との共演も伝説的名演で一緒に紹介しておこう。
-
ヒレンジャク
- 学名:Bombycilla japonica (ボンビューキルラ ヤポニカ) 日本の絹の尾の鳥
- 属名:bombycilla (合) 絹の尾 (bombyx -ycis (m,f) 絹 cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さなもの)
- 種小名:japonica (adj) 日本の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Japanese Waxwing
- 英名:
bombycilla は#キレンジャク参照。
japonica は#メジロ参照。
単形種。
Siebold (1824) が Hist. Nat. Japonia Statu に Bombycivora japonica の学名で記載。基産地 'Fyco ac Tsikuzen' = Kumamoto and Fukuoka prefectures, Kyushu, Japan (Avibase による)。
この属名は Temminck (1815) がキレンジャクに対して用いたもの Bombycivora garrula (The Key to Scientific Names)。Bombyci- は絹、-vorus は食べるもので意味が一貫していないように見えるが、羽毛は絹のようだがよほどの大食漢を表現したかったのだろう。
参考カイコの属名 Bombyx。
Bombycilla Vieillot, 1807 の方が早かったためにこちらに先取権が与えられたのだろう (実はそれほど単純でなく一度別の属名が与えられた。#キレンジャクの備考参照)。
[学名の経緯]
ヒレンジャクの種小名は japonica に決まっているではないか、英名もその通りなので別の学名があったと思えない...と想像しそうだが、なんと Temminck は別の名前を付けていた Bombycilla phoenicoptera Temminck, 1828。
紹介 フランス語名 Jaseur phoenicoptere。
記載。産地は長崎周辺 (おそらく出島を意図したもので正確な産地は不明) となっている。
図版の 450 がこの書物のどこかにあるはず [図版そのものは後述 van Oijen and Roselaar (2007) で見ることができる]。参考。"翼に紅の部分のあるレンジャク" ぐらいの意味。
Siebold (1824) の記載の方が早かったので現代は Siebold の付けた種小名が使われているが、文献もそれほど知られているものでもなく、Siebold の方が先に命名していたことはあまり知られていなかったようで、Temminck の学名が用いられていたこともあった: 参考 Pelzeln and Lorenz (1886)
Ueber eine an das k. k. naturhistorische Hofmuseum gelangte Sendung von Vogelbaelgen aus Japan。
現在は "日本のレンジャク" の学名になっているが、わずかの違いで Bombycilla phoenicoptera になっていた可能性がある。
さらなる経緯は van Oijen and Roselaar (2007) Notes on types and early specimens of Bombycivora japonica von Siebold, 1824, and of Bombycilla phoenicoptera Temminck, 1828。
16 ページのパンフレットで、Siebold のヒレンジャクの記載は脚注に登場するのみだったとのこと。
"Fauna Japonica" の図版には Temminck の学名で登場する (図版)。
Siebold はそもそも刷り上がり原稿に目を通す機会がなく誤植だらけで自身の名前さえ間違っていたとのこと。おそらく Siebold 自身のリクエストで再版された 1826 年版では多くの誤りは正されていたが内容はほぼ同じで B. Japonioa と学名の綴りすら間違っていた
(このあたりはクラシック音楽の同時代の誤植だらけの楽譜や何度も改訂された経緯を知っていると雰囲気がよくわかる。手書き原稿から活字にする場合、ラテン語も楽譜も出版社泣かせだったのだろう)。
基産地 provincis Fyco ac Tsikuzen (1824 年版) で後世を悩ませる結果となっている。後半はなんとなく筑前に読めるが...。provinciis Tyko ac Tsikuzen (1826 年版)。手書き文字が T か F か区別できなかったらしく、Siebold 自身にとっても地名は多分あやふやだったのだろう。
Temminck より早いので原記載となるがあまり気合が入っていない感じ。ヨーロッパにはキレンジャク (Bombycilla 属になって改名された Bombycilla vulgaris "普通のレンジャク" の学名もあった) がいるのでその日本版の位置づけだろうか。
この文献では、Dickinson からの私信によれば Temminck が新しい学名を付けた理由は標本が違って別種と考えた、あるいは地名を付けるのを好まなかったための推測があるが不明のままとのこと。しかし後者については Temminck は他の種に japonicus などを付けているので別の理由がありそうな気がする。
Siebold と Temminck の種小名の付け方の違いはアメリカのヒメレンジャクがすでに知られていたためではないだろうか。Temminck の記載ではヒレンジャクは3種めのレンジャク類で、キレンジャクやヒメレンジャクとも比較しており、すでにアメリカのレンジャクに別系統の学名が付いている中で "普通のレンジャク" の日本版とは付けにくかった可能性があるのがその1。
Siebold は "普通のレンジャク" とのみ比較したので単純に "日本の" とすることができた。Siebold の記載にはこの2種が出てくる。日本滞在中に成果を急いで (?) 執筆した (原稿はおそらく Blomhoff に託して運んだらしいとのこと) ためおそらくヒメレンジャクの情報がなかったかあるいは比較する機会がなかった。11 種の新種記載を含んでいたとのことだが、現在この文献が原記載となっている種はヒレンジャク1種のみ。残りはどうなったのか??
Temminck が Siebold の出版物や学名を知っていたのかは自分は知らないが、知っていた上であればヒメレンジャクも加えた既知のレンジャク類とも比較したより完全な記述として差別化を図るためにあえて地名を使わない記述的学名を付けたのかも知れない。Siebold の記述では既知の種であるヒメレンジャクとの相違が示されていないので不十分な記載と主張できる可能性がある。
またどちらの記述が有効とされるかはまだ自明でなかったので改めて命名する意義があったのかも知れない。
Temminck (& Schlegel) も自身の学名が最初と考えていた可能性があり、あるいは自身の学名の有効性を世に知らせるために "Fauna Japonica" の図版で念押しをしたのかも。
ドイツ語名でも Blutseidenschwanz, Blut-Seidenschwanz (血の色のレンジャク) の名称があり、素直に "赤" の意味ではないのでかつてはドイツで使われていた Temminck の学名を反映していたかも知れない。Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にも両方の学名が現れていた。
Hartert (1910-1922) p. 457 ではドイツ語名は与えられていないがもう1つシノニムがあるそうで Ampelis Maesi Oustalet, 1892。この Maesi はフランスの鳥類飼育・収集家 Jules Albert Maes 由来とのこと (The Key to Scientific Names)。
David and Oustalet (1892) の Ois. Chine (中国の鳥) の図版に現れるとのこと。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
)、「百千鳥」(1799) でひれんじゃく / 緋連雀、きれんじゃく / 黄連雀の名前はすでに登場して現在の和名に相当するものは早くから存在したことは疑いないが、和名の標準化の際に Temminck の学名も参考にされた可能性もあるかも知れない。
この点が気になるのはヒメレンジャクの和名由来で、北米では cedar Bird の名前はすでに使われていて記載時学名 Bombycilla cedrorum Vieillot, 1808 (原記載) やフランス語名は英名をそのまま保存したと記されている。
当時はヒメレンジャクはレンジャク類の2種目だったが、このころには "小さなレンジャク" を意味する用語は目立たなかった。
一方で Temminck のヒレンジャクの記述ではヒレンジャクを指す Le petit Jaseur de cet article (この文書の小さなレンジャク) が "普通のレンジャク" (キレンジャク) よりも小さいことを示している。また全長ではヒレンジャクが北米のヒメレンジャクに似ているとある。
ちなみにヒメレンジャクの和名別名にスギレンジャクがあるそうで (コンサイス鳥名事典) これは cedar Bird やその後付けられた Cedar Waxwing をそのまま訳したものと思われる。
アメリカレンジャクの別名もあったそうで、これは自明の気もするが Bombycilla americana (参考) を訳したと考えた方がすっきりする。
この名称は Bombycilla carolinensis Stephens, 1817 (参考) を改名したものとのこと。この時代はヨーロッパのものが Bombycilla europaea とも呼ばれて対比する形となっていた (#キレンジャクの備考参照)。ヨーロッパレンジャクに対するアメリカレンジャクとなる。
ヨーロッパのものを "大きなレンジャク"、北米のものを "小さなレンジャク" の用例は Dumont がレンジャク類に Garrulus 属を導入し (#キレンジャクの備考参照。"大きなレンジャク" の方はタイプ種に相当)、Garrulus minor Dumont, 1822 (参考) としたものがあった。
Garrulus 属の名称はカケス類に用いられたものの方が優先されることになったが、レンジャク類を指していた用例も一定見つけることができる。Temminck もこの名称に気づいていたかも知れない。
Vieillot (1808) のヒメレンジャクの記載の方が早かったためこれら北米で記載された学名は結果的には残らなかった。
ヒメレンジャクの和名が大きさに注目したものとなった経緯は自明なものではなく、当時の英名や学名を訳したと想像できる別名が存在し、そのまま使われていてもおかしくなかった。どこかの段階で別の要素を取り入れて大きさに基づく名称に整理されたように見える。現在の和名の意味の "小さなレンジャク" は Temminck の記述または当時の学名にヒントを得たかも知れない。
日本産のものも含めたレンジャク類の和名確定と同時期だった可能性も考えられる気がする。
現在北米やヨーロッパの一部の国で鳥の一般名から人名を排する動きが始まっており、固有種でない種の名称から国名が次第に外されつつある傾向がある。ヒレンジャクは日本で繁殖するわけでも固有種でもないので今後再検討対象とされるかも知れない。その場合は Temminck の学名や和名はよい検討候補となるかも知れない。
[ロシアのヒレンジャク]
日本近郊 (ロシア極東や中国東北部の北より、例えばハバロフスク付近で繁殖、中国東北から東部の一部、朝鮮半島、日本、台湾に渡る) のみに生息する東洋特産種。繁殖地域が限られているため繁殖生態もあまり知られていないが、例えば
Gluschenko et al. (2020) New information on the distribution and breeding biology of the Japanese waxwing Bombycilla japonica に繁殖生態の説明や巣と卵、若鳥の写真が出ている。
営巣地の発見にはかなりの困難を伴ったそうである。この記録での繁殖期は5月中旬から8月終わりまで。ヒメレンジャクではシーズン2回の繁殖が知られていて (7-8月から遅い時は 10 月初めまで)、ヒレンジャクでも2回繁殖の可能性がある。
レンジャク属は世界で3種が知られ、北米ではよく知られた鳥であるヒメレンジャク Bombycilla cedrorum (英名 Cedar Waxwing) のみ日本で記録がない。
[レンジャク類の色素]
ヒメレンジャクでは羽の色素成分が分析されており、アスタキサンチン Astaxanthin というカロテノイド色素 (#ベニマシコの備考にある赤い色素カンタキサンチン canthaxanthin と類似物質) Brush and Allen (1963) Astaxanthin in the Cedar Waxwing。
Surmacki (2016) How to reduce the costs of ornaments without reducing their effectiveness? An example of a mechanism from carotenoid-based plumage キレンジャクで同様のカロテノイド色素による着色が見える部分に限定することで着色コストを最小にして最大の効果を上げている
[オオルリの羽毛で見えない部分は青くないのと同様だろう。藤井 (2021) Birder 35(3): 36-37 によるとブッポウソウの表面の青い部分も同様だが、ブッポウソウは裏面も青い点が特殊であるとのこと]。
[レンジャクの集団死]
最近はあまり話題にならないが、かつてレンジャクの集団死が話題となったことがあった。
1997年1月から3月にかけて長野県内各地で発生し、合わせて 13 件、死亡数 187 羽に達した事件である。
当時は採食中に驚いて窒息死した [中村浩志 (1997) 科学 67, 484] などの解釈も述べられていたが、
上田 (2006) Birder 20(1): 38-41 によると野外で自然選択による選抜を受けていないピラカンサなどの栽培種で、果実が赤くなってもシアン配糖体が残ったままになっているとの興味深い仮説が提唱されていた。
宮川 (2007) 長野県におけるレンジャク類の大量死の原因究明とその経過 に分析結果がまとめられ、シアンは検出されたが原因として特定するにはいたらなかったとのこと。
小諸市の事例については殺虫剤の EPN (エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト) が原因と推定されたが、各事例において病理解剖の所見や検査データがそれぞれ異なっており、同じ原因で突然死したのではないことが予測されたとのこと。
一部の事例にシアンが関わっている可能性はあるが、農薬の不適切使用例も多かったようである。
海外でもレンジャクの集団死の事例は昔からあるようで、原因はさまざまのようだが解明されないことも多いようである。
Fossler (1936) The Death of Hundreds of Cedar-Waxwings シアン化水素中毒の可能性を示唆している。
Fitzgerald et al. (1990) Suspected ethanol toxicosis in two wild cedar waxwings アルコール中毒の疑い。
Woldemeskel and Styer (2010) Feeding Behavior-Related Toxicity due to Nandina domestica in Cedar Waxwings (Bombycilla cedrorum)
このアメリカ ジョージア州での 2009 年の事例では病理検査によってナンテン Nandina domestica によるシアン (HCN; 化学でシアンと言うと C2N2 のことを指すが、ここではシアン化合物から発生するシアン化水素のこと) 中毒とのこと。
シアン濃度は短時間で消失するため数時間以内に測定する必要があり調べなかったとのこと。食道内容物と病理検査の所見からこの結論を下して大丈夫との判断のようである。
レンジャク類は食べられるだけ食べる習性があり、食べたものがそのうに入る前の食道に詰め込むそうである。
Kinde et al. (2012) Strong circumstantial evidence for ethanol toxicosis in Cedar Waxwings (Bombycilla cedrorum) 北米の事例。アルコール中毒となって衝突死の可能性。
2014 年のアメリカ ネブラスカ州では上田 (2006) の推測と同じように栽培種からシアンを摂取した可能性が述べられている。
上記北米の事例はいずれもヒメレンジャク。
Powers et al. (2025) Mass Mortality in Migrating American Robins (Turdus migratorius) in Virginia, USA: Data Beyond a Diagnosis
では 2022 年のアメリカのコマツグミの集団死事例を研究、発酵した American holly (Ilex opaca アメリカ在来種) の実を食べたためではないかとのこと。実そのものの直接の検査は行えなかった。レンジャク類以外でも生じるようで、現代でも原因特定は必ずしも容易でないらしいことがわかる。
[レンジャク類の系統解析]
FJ177357.1 (RAG 1) から出発して BLAST を行ってみると東洋の種でよく見られるようにヒレンジャクが古く分岐したものではなく、キレンジャクの方が祖先系統でヒレンジャクとヒメレンジャクが分岐した形態となった。
ヒレンジャクとヒメレンジャクはサイズ的にも近く、まずユーラシア中央部で分断されて東西でそれぞれ種分化したらしいことを想像させる。キレンジャクはヒレンジャクと再度接触するようになったが、より北方に適応していて、全体的にはキレンジャクの方が優勢でヒレンジャクは比較的南の方に限定して残ったと考えることもできそうである。
この配列は Spellman et al. (2008) Clarifying the systematics of an enigmatic avian lineage: What is a Bombycillid? で調べられたもので、この当時はレンジャク類が他の何の系統に近いのか調べられていた。あまり近縁の系統がなく近い系統でも単形属のものも多く地理的由来ははっきりしない。
Phainoptila 属はコスタリカ、Ptilogonys 属は中米でこれらはこの研究ではレンジャク類から派生する形となる。
レンジャク類の古い分岐にあたる Hylocitrea 属はインドネシアのスラウェシ島。同じく Dulus 属はカリブ海。
レンジャク類がユーラシア由来か北米由来かは簡単に決着できない結果と言える。論文の系統樹ではヒメレンジャクが祖先型を示唆していてこの場合は北米由来の可能性がある。
FJ177349.1 (RAG 2) を用いて BLAST を行っても RAG 1 と同じ系統樹形が得られる。一方 cyt b を用いると論文の系統樹と同様になる。ミトコンドリアと核遺伝子で多少相違があるのかも知れない (例えば incomplete lineage sorting など)。現状のデータからはここまで。
キレンジャクとヒレンジャクは色しか違わない印象でかなり近縁に思えるが、分子系統解析の結果は比較的異なった種類であることを示唆する。
Zhao et al. (2025) The phylogenetic position of the extinct Hawaiian honeyeaters: Overcoming the limitations of antique DNA (preprint) にさらに UCEs を用いた系統研究がある。絶滅したハワイミツスイ類の Moho 属などがレンジャク類の系統に近い。古い標本からでもこのレベルの系統研究が行えるようになってきた。
[ヒレンジャクは過去に減少?]
「冬の鳥」(小学館 1984) p. 139 によれば大正から昭和初期に日本で見られたのは主にヒレンジャクだったが、最近キレンジャクが多い。ヒレンジャクの急激な減少が目立つのでは、とあった。関東地方の話かも知れない。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ゴジュウカラ科 SITTIDAE ▽
-
ゴジュウカラ
- 学名:Sitta europaea (スィッタ エウローパエア) ヨーロッパのキツツキに似た鳥
- 属名:sitta (外) sitte アリストテレス等が記述したキツツキに似た鳥 (Gk)
- 種小名:europaea (adj) ヨーロッパの (Europa ヨーロッパ -eus 形容詞に -a 女性形に)
- 英名:Nuthatch, IOC: Eurasian Nuthatch
- 備考:
sitta はギリシャ語 sitte (スィッテー) では語末が長母音。ラテン語化される際に短音化されたと考え "スィッタ"。
ギリシャ語 sitte の語源は不明だが Beekes は音声を真似たもの、Furnee はオウムを意味する psittakos 由来を考えたとのこと (wiktionary)。
europaea は o が長母音で -ae- が2重母音のためここにアクセントがある (エウローパエア)。
記載時学名 Sitta europaea Linnaeus, 1758 (原記載) と由緒ある学名。
Linnaeus の Sitta 属は1種のみだったのでタイプ種も自動的に決まり、一見何の問題もなかったかのようだが、Habitat in Europe, America と記載されていてアメリカのものは違う! と後に restricted to Sweden by Hartert, 1905 (Avibase による) とスウェーデンに限定された。
北米のゴジュウカラ類は Linnaeus が Sitta canadensis Linnaeus, 1766 (原記載) 基産地 Canada (ムネアカゴジュウカラ) を改めて記載しているが、この時点のゴジュウカラの記述はまだ Habitat in Europe, America となっていて実は怪しかった。
さらに Linnaeus (1766) は Sitta 属にもう1種 Sitta jamaicensis Linnaeus, 1766 (記載) とジャマイカの謎の鳥を記載している。
何者かわからないので現在使われる学名に登場しないが、The Key to Scientific Names の Baristus の項目によれば "Baristus 1" と同定できるとのこと。"Baristus 1" は現在の分類ではオジロハイイロタイランチョウ Tyrannus caudifasciatus Loggerhead Kingbird に対応すると考えられるとのこと。
古い学名なので何かと同定されれば先取権があるがまったく検討された気配がない。Sitta 属でジャマイカに分布するものはないので Linnaeus の勘違いなのか。
ゴジュウカラの学名も属名も由緒あるが、どうも Linnaeus の勘違いも含まれていたよう。
Sitta の名称は他の属名にもよく使われるので把握しておいてよいだろう。ヤマガラ属の Sittiparus など。オーストラリアゴジュウカラ科 Neosittidae もあるがこれまた系統が全然違う。
後に話題となる Buturlin (1916) が提唱した属に Cyanositta があり、ビロードゴジュウカラ 現在の学名で Sitta frontalis Velvet-fronted Nuthatch の亜種 corallipes に付けられた属名。
どこかで見たことのある属名と感じたらステラーカケスの属名が Cyanocitta だった。こちらの citta は sitta と無関係で、kitta カケス Gk とのこと。
ゴジュウカラ類の英語名 nuthatch は "nuthack" のなまったものとのことで、クルミ (nut) に割れ目を入れて切り刻む (hack) 習性からとのこと (wikipedia 英語版)。OED でも英単語の合成によるとみなしている。1350 年ごろ notehache、1450 年ごろの nutthache、1500 年ごろの notthache の用例がある。1668 年には Nuthatch の用例があった。現在でも t と h は th と結合せず別に発音される。
英語では属名の sitta と英語 sit の間の関係があるのか気になってしまうが、英語の sit は遡るとインド・ヨーロッパ祖語の *sed- (座る) に由来とのことで特に語源的関係はなさそう。鳥の方の sitte / sitta 由来と思われる sit はカタルーニャ語にあってホオジロ類を指す。
座る意味の英語 sit は各国語に似た単語があるが、鳥類学的に興味あるところではラテン語 sedere と同根 (sedentary 移動しない; 留鳥の)。リトアニア語で座る sedeti (ロシア語でも sidet')、アルメニア語では nstim で英語の nest とも関係があるとのこと (ni- はサンスクリット語、インド・ヨーロッパ語で同様の意味の接頭語とのこと。ni- + sit で nest になる次第。英語の nest には "座る" 意味が隠れていた。
サンスクリット語で ni-sad が営巣する意味) (以上 OED から)。
nest に関係した nidus (ラテン語)、gnezdo (ロシア語) については#ハシボソガラス備考 [カラス類の適応放散] で niche の読み方のところで触れた。
おまけの豆知識としてロシア語の動詞を見ておくと、sidet' は鳥の場合は "とまっている"。"とまる" に相当する意味には別の動詞 sadit'sya, sest' が使われるが文法的なことはここでは詳しく触れないことにする。いずれも sid や sad などの形が現れて語幹をよく反映している。
このことを知っておくと鳥の用語が大変理解しやすい。nasizhivanie は抱卵。-vanie は行為を表す名詞を作る接尾語なので意味は前半にある。sizh は sid が形を変えたものであることがわかる。
また主に猛禽類などの見張り場は prisada。sad にとまっている意味が現れている。pri- は接頭語で "やってくる" 感じ。とまりにやってくる場所などと理解すればよい。
スラブ言語ではこのように語幹がよく保存されていることが多く、仕組みがわかっていると単語を理解するのに大変役に立つ。単語が長いので覚えられないとよく言われるが、個々の構成部分は日本語における漢字のようなものと思えばよい。知らない単語でも語幹がわかれば意味がだいたいわかり、英語のように語源の異なる短い単語が混在している (brood, perch など) よりむしろ統一して覚えやすい。
本稿ではしばしば英語以外の他言語で鳥名がどのように呼ばれているかも取り扱っているが、スラブ言語ではこのように共通性が高いので1言語でも知っていれば他の言語に応用できる場面が多い。聞いてもわからないが文字を見て語形がつかめれば何を意味しているかわかる次第。個々の言語の辞書をいちいち引いて調べているわけではない。
おまけついでに "使う" は英語では use で至極簡単だが、ロシア語ではスラブ言語の語構成に従うため ispol'zovat' ととても長くなる。日本語で言えば "利用する" に近い。日本語では当たり前と思ってしまうが、改めて "利" とは何か、"用" とは何かと問われると個々の意味を説明するのが難しいのと同様。pol'za が利益、効用の意味に対応していてそこから作られた動詞であるため。
より短い動詞がないためロシア語でも主に若者スラングとして英語の use をそのままロシア語化した uzat' も使われている。日本語のカタカナ動詞みたいなものではあるが、これほどの基本語に現れるのは面白い。辞書を見ても載っていないことも多いので注意。
ドイツ語の nutzen (Nutzen 有用、利益など) の使い方に大変近い。英語はフランス語の影響を受けてある程度独特のものになっている。フランス語の user も "使う" の意味があるが、"擦り切れさせる" がむしろ原意。"古書" が英語で used book となるのと同様。フランス語の形容詞 use は "擦り切れた" が基本語義。"使う" を擦り切れさせると見るか、利用すると見るか文化圏の違いが現れているようで面白い。
ゴジュウカラはドイツ語では Spechtmeise (キツツキのようなカラ) または Kleiber (kleiben 粘土をつける。Kleiber に左官の意味がある)。フランス語では sittelle torchepot と属名が生きている。torcher (拭く) と pot (多義語。俗語の尻かも) の合成語。
ロシア語では popolzen' で polzat' (這い回る) 由来。どれも語源的にわかりやすい。他の言語を見てもキツツキの単語を使っていたり何に分類するか悩ましかったらしいことがわかる。今でも何の系統なのかわかりにくい。
カラ類とは関係なく、系統を重視する立場であればカラ類と一緒に紹介する際は注意した方がよい。
昔の分類だと エナガ科 - ツリスガラ科 - シジュウカラ科 - ゴジュウカラ科 と並んでいたが現在はまったく異なっている。
"ゴジュウカラ - キバシリ - ミソサザイ" と覚えればよいことになる。この組み合わせならば納得できる。
シジュウカラ科、エナガ科 (この2科も系統がだいぶ違う) よりもむしろレンジャクやキクイタダキに近い。#ツリスガラ備考の [スズメ小目 Passerida の系統分類] 参照。
ユーラシアに広範に分布する種類で、21 亜種が認められている (IOC)。
日本で記載されているものは amurensis (アムールの) 亜種ゴジュウカラ、asiatica (アジアの) シロハラゴジュウカラ (北海道)、roseilia (roseus バラ色の ile 脇腹) キュウシュウゴジュウカラ (九州南部)、及び亜種不明である。後述のように日本鳥学会と世界の主要リストの間で亜種認識の異なるものがある。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire に面白い考察がある。Sitta caesia Wolf, 1810 (参考) の記載 (現在は Sitta europaea のシノニム) があった。
1890 年当時は日本のものは Sitta uralensis Gloger, 1834 (参考) の可能性が考えられていた。
現代的な亜種学名が使われるようになって整理されていた段階のようで、どの種を基亜種とするか問題となっていた。先取権の原則によれば Sitta europaea uralensis のような学名となるが、これはばかげている (日本の鳥を例えばウラルのヨーロッパのゴジュウカラと呼ぶことになる)。
そのため発表年代は新しいが Sitta caesia の種学名を用いてヨーロッパのものは Sitta caesia europaea と呼ぶことにするとある。今では遠い地域を表す基亜種地名でもあまり違和感がない場合が多いが、歴史的にはこのような議論もあった。
このような議論もふまえておかないと "この学名は間違っている" と即断してしまうことがあるかも知れない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" でもこの種小名が用いられていた。
[ゴジュウカラ類の分子系統解析]
Paeckert et al. (2020)
A revised phylogeny of nuthatches (Aves, Passeriformes, Sitta) reveals insight
in intra- and interspecic diversication patterns in the Palearctic
に最新のゴジュウカラ類の分子系統研究がある。ゴジュウカラ類は 10 クレードに分かれ、アジアのゴジュウカラ類は clade X に含まれる。中国からヒマラヤのものは clade IX に含まれ、この2系統はともに RAG-1 遺伝子に共通の1アミノ酸の重複が見られて同じ系統であることは疑いない。
台湾の formosana、中国東北部の sinensis は clade X の中でも大きな分岐を示し、独立種とされるかも知れない。もし分離するならば Sitta sinensis となるだろうが、Oriental Nuthatch の名称をすでに与えているリスト (HBW) もある
(formosana の方の記載がもし早かったならば Sitta formosana となって既存の Sitta formosa との関係は大丈夫かと問題になるかも知れないところだったがその心配はない)。
日本のリストでの扱いはわからないが、すでに世界の多くのリストが分割している Sitta arctica Siberian Nuthatch の分離は妥当との結果となった。和名はまだないようである。ロシア名ではヤクーツクゴジュウカラに相当する名称が与えられている。
系統的には古く分岐したもので (clade VII)、遺存種的なものと考えられる。分布はシベリア北東部で他の亜種より北に生息する。
Avibase では種ゴジュウカラに Wood Nuthatch の英名を与えている。この英名はまだ分離前の GenBank でも用いられている。IOC は分離したが Eurasian Nuthatch の英名を残した。
日本で記録されている亜種はすべて調べられているわけではないが亜種の間で特に離れた系統を示唆する結果は出ていない。
clade IX は生息域をもとにいくつかの種に分割されているが、その間の遺伝的距離はゴジュウカラとされる clade X より小さいものがあり、clade によって種分割の整合性がよくない。clade IX の種の妥当性 (生態の違いなど) の検証の必要があるだろうとのこと。
Oriental Nuthatch 以外の clade X を分割する提案は出ていないが、一番大きな分岐はユーラシアの東西なので、東西で別種にするかどうかの議論は生まれるかも知れない。もし分離されれば Sitta asiatica のような名称が想像される (他の分岐年代を見ると微妙なところだがおそらく分離されない?)。
Imfeld et al. (2024)
Diversification and dispersal in the Americas revealed by new phylogenies of the wrens and allies (Passeriformes: Certhioidea)
に (亜種レベルは扱っていないが) 解析があり、Sitta arctica Siberian Nuthatch の分離は問題なし。遺伝的距離はかなりあってゴジュウカラと Sitta arctica Siberian Nuthatch がまとまった系統を作るわけではない。
ゴジュウカラはミナミゴジュウカラ Sitta nagaensis Chestnut-vented Nuthatch、カシミールゴジュウカラ Sitta cashmirensis Kashmir Nuthatch、チャバラゴジュウカラ Sitta castanea Indian Nuthatch、
ビルマゴジュウカラ Sitta neglecta Burmese Nuthatch、クリハラゴジュウカラ Sitta cinnamoventris Chestnut-bellied Nuthatch と系統を作る。
かつては色彩で系統が区別されていたようだがみかけはむしろ北方・南方の違いを反映していたようで分子系統解析は少し違う解釈を与えている。
[亜種の問題]
日本鳥類目録改訂第8版による日本関係の亜種の記載時学名を見ておくと、
・Sitta amurensis Swinhoe, 1871 (原記載) 基産地 Amoorland and, in winter, south to Peking (Avibase による)
・Sitta asiatica Gould, 1835 (原記載) 基産地 Russia
・Sitta roseilia Bonaparte, 1850 (原記載) 基産地 Japan, restricted to Hiuga, Kyushu, by Orn. Soc. Japan, Handlist Japanese Birds, p. 34 (日本鳥学会が日向に限定)
amurensis のシノニムともされる亜種に Sitta europaea hondoensis Buturlin, 1916 があり、IOC 15.1 では Honshu to n Kyushu (Japan) Red'kin & Konovaleva 2006; Harrap 2008c を出典として認めている。
IOC 15.1 では amurensis は Russian Far East, ne China and Korea、
roseilia は s Kyushu (extreme s Japan) となっている。
IOC の扱いであれば日本のゴジュウカラの一般的亜種は hondoensis となり、日本鳥類目録改訂第8版の扱いと異なる。Clements 2024, HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v9 (Oct 2024) でもこの亜種を認めている。
H&M4 でも亜種として認めており、but included in subspecies amurensis by Orn. Soc. Japan (2000) と日本鳥学会の扱いと異なることが示されていた。
興味深いことに wikipedia 日本語版では hondoensis が採用されている。
hondoensis の亜種名はいかにも日本人が命名したような印象を受けるが異なっていた。自分が調べた範囲ではこの名称の用例は海外の研究者によるものの方が早く Locustella hondoensis Stejneger, 1893 (現在のウチヤマセンニュウのシノニム) があった。
この分類を用いる場合の参考文献は Red'kin and Konovaleva (2006) Systematic notes on Asian birds. 63. The eastern Asiatic races of Sitta europaea Linnaeus, 1758
で、北海道や国後・色丹島は亜種 clara となる。IOC でも認めており、s Kuril Is. and Hokkaido (n Japan) となっている。こちらの記載時学名は Sitta amurensis clara Stejneger, 1887 (原記載) 基産地 Sapporo, Hokkaido。
Sitta asiatica と同じとする立場であれば asiatica の方が記載年代が古いのでシノニムとなる。しかし基産地が北海道なので大陸と分離する立場であれば必ず現れる亜種となる。
さらにややこしいことにカムチャツカから北海道までをまとめる考え方もあって、albifrons Taczanowski, 1882 (基産地カムチャツカ) の方が少し早いので、この場合は大陸と別亜種でありながら albifrons の亜種名になる。wikipedia 英語版の Siberian nuthatch の図版にこの概念が現れる (参考)。
Dickinson (2006) Systematic Notes on Asian Birds. 62. A preliminary review of the Sittidae が Red'kin and Konovaleva (2006) に先行あるいは補完するもので、Harrap (1996) は本州の標高の高い所は asiatica と考えていたが、Morioka (1994)、Red’kin and Konovalova (2006) ともに同じ本州の単一個体群の範囲と考えた (しかし採用する亜種名称は両者で異なる) ことが述べられている。
Dickinson も Red'kin and Konovaleva (2006) の考え方と日本鳥学会の扱いに違いがあることを認めた上で両論併記の形となっている。
問題となる Sitta europaea hondoensis Buturlin, 1916 は "A Short Review of Nuthatches (Fam. Sittidae)", Travaux Soc. Imp. Nat. Petrograd 44 p. 145-173 にて発表されたもので、今のところオンラインで読めるところを知らない。
論文については S. W. (1916) Buturlin's Review of the Nuthatches の紹介記事があり、当時のゴジュウカラに少なくとも 22 亜種を認めたとのこと。当時は世界的に細分主義時代かつ日本でも多くの亜種が記述されていた時代で、日本では独立した亜種とは認めなかったなどの経緯が考えられる。
Buturlin の記載した亜種は他種にも多数あり、現在も認められているものも多い。
Buturlin (1916) の記載したゴジュウカラの亜種はこの hondoensis に加えて sakhalinensis がある。サハリンの亜種を同定する過程で副産物的に本州も別亜種と記述する方がよい結論となったものだろうか。
Hartert (1910-1922) 時代では p. 330 のように北海道は当時の亜種 uralensis 記載時学名は Sitta uralensis Gloger, 1834 と考えていて、asiatica はそのシノニムの扱いだった。
この場合は北海道の亜種名は uralensis となるが、この亜種は現代では何と Sitta arctica の方にシノニムで含まれる。この当時の分類にそのまま従うと現在では北海道とそれ以南でゴジュウカラが種レベルで異なることになる。
Hartert (1910-1922) では p. 331 のように amurensis は Sitta roseilia Bonaparte, 1850 と同一かも知れないと考えており、もし roseilia が有効と認められればこちらの方が早い記載となる問題があった。
Hartert 自身は朝鮮半島、北海道より南の日本は amurensis と考えていた。
このようにあまりにも複雑な状況だったものを Buturlin (1916) が整理し、シノニム関係も含めて世界がある程度納得できるものとなって主要リストで採用されているものと考えられる。しかし日本の本州に新亜種 hondoensis を記載したため日本国内の扱いがややこしくなった模様。
Hartert がこの部分を著した時期に Buturlin (1916) が発表されたため執筆当時はまだ詳細が知られていなかった。後の巻で補遺の形で特にコメントなく紹介されている: p. 2106。
Dement'ev and Gladkov (1954) でも hondoensis を認め全体で 16 亜種としていた。日本北部は amurensis の扱いで、九州と四国は herterti Momiyama, 1925 とこれまた現代と異なる。
この亜種は Buturlin (1916) 以降に記載されたもので新たに追加された形になっていた模様。
Hartert (1910-1922) も ? を付けていたように、Sitta roseilia Bonaparte, 1850 (記述があまりに短く、ex Japonica となっていてタイプも明示されていない) の有効性に問題がある議論があったのだろうと想像できる。
世界的には東アジアのゴジュウカラをさらに整理した Red'kin and Konovaleva (2006) が現状ほぼ受け入れられているように見える。
千島列島ではまだ問題があって Sitta europaea takatsukasae Momiyama, 1931 が基産地 Urup and Etorup, southern Kurile Islands として記載されている。IOC や H&M4 ではこの亜種 takatsukasai (綴りが修正されている) を認めている。
千島列島で単独の亜種でなく、島によっては違った亜種がある可能性があるのでよく調べられていない現状保存せざるを得ないのだろう。Red'kin and Konovaleva (2006) でもそのまま認めている。
日本近くではもう一つ bedfordi Ogilvie-Grant, 1909 が済州島の亜種とされる。
日本鳥学会はこれまでの目録での取り扱いや Morioka (1994) の見解に従い、clara や hondoensis を分離しない立場と考えられる。
また asiatica の範囲を千島列島南部までとしているので亜種 takatsukasai を含んでいると考えられる。
本稿の他種では細かな亜種分離に比較的批判的なニュアンスを感じられていると思うが、ゴジュウカラでは地域による遺伝的な違いもかなり大きく外見以上に亜種分化が起きているかも知れないこと、世界的に整合性のとれた亜種分類体系が確立していないらしいことや、名称の先取権関連の複雑さから亜種を比較的広く認めた記述とした。
英名・分類・日本の亜種の名称ともにたいへんややこしい種のよう。ゴジュウカラの亜種識別の話題があまり取り上げられることがないのも理由があるのだろう。Red'kin and Konovaleva (2006) の地図を色彩タイプにも分けながらゆっくり見てどのように分化してきたのだろうか、そしてどの分類が妥当そうか考えてみるのも面白そう。
音声も参考になると思えるがそれほど情報がなく、限られた xeno-canto のさえずりの記録では大陸・北海道・本州がそれぞれ違うように聞こえる。個体差や同一個体でも違うさえずりを用いる可能性もあってすぐに結論が出せそうにない。試してみていただきたい。
参考までに Red'kin and Kurkamp (2007 初出, 2016) Invasion of the Siberian nuthatch Sitta europaea asiatica in autumn 2006 (pp. 775-780) は 2006 年にウラル地方に asiatica の irruption があったことを報告している。
ユーラシア東西ではゴジュウカラの亜種の違いは目立つのでどこかで線引きが必要なことは確かなのだろう。また定住性というわけでもなくかなり移動するものもあるらしいことも示唆する。
各リストの亜種比較を示しておく。wikipedia 英語版 Siberian nuthatch の項目は Red'kin and Konovaleva (2006) を引用しているものの独自分布図で、ユーラシア極東部で最も亜種数の少ない場合の事例として参考に挙げた。
| 地域 | 改訂第8版 | IOC 15.1 | Red'kin and Konovaleva (2006) | wikipedia 英語版 Siberian nuthatch の項目 |
| サハリン | asiatica | sakhalinensis | sakhalinensis | albifrons |
| カムチャッカ | | albifrons | albifrons | albifrons |
| 千島列島北部 | | albifrons | albifrons | albifrons |
| 千島列島南部 | asiatica | takatsukasai (sc Kuril Is.) | takatsukasai | albifrons |
| 同上 | | clara | clara (一部) | |
| 北海道 | asiatica | clara | clara | albifrons |
| 本州・四国・九州北部 | amurensis (分布域は検討が必要) | hondoensis | hondoensis (境界不明確) | hondoensis (地図は北部日本まで) |
| 九州南部 | roseilia (分布域は検討が必要) | roseilia | roseilia (本州南部も含む) | (範囲外) |
なお Ogawa (1908) の時代には amurensis (Kurile Is., Hokkaido, Nikko, Fujiyama, Yokohama) に Gojukara, Kimawari の和名、uralensis (Hokkaido) に Shirohara-kimawari、albifrons (Hokkaido) に Shirobitai-kimawari の名称が使われていた。
この時代までは "キマワリ" の方がよく使われていたのかも知れない。
roseilia は別名にも現れていなかった。asiatica は amurensis の方に含めてあるがおそらく Hartert 同様の時期で asiatica が何を指すかまだはっきりしておらず、どこに帰属させるか結論が出されていなかったのだろう。
[ゴジュウカラはカラ類か?]
Birder 2024 年 12 月号 38(12) の特集は「見たい!知りたい!カラ類」であったが表紙はゴジュウカラで、記事も見れば見るほど「ゴジュウカラはカラ類」として扱われている印象を受ける。
「お食事中のカラ類」(pp. 24-28) でも特に断りなくゴジュウカラが扱われている (p. 25)。もっとも同記事でエナガも扱われている。
よほど系統に関心のある読者でなければゴジュウカラはカラ類に近縁と解釈してしまうのではないだろうか? これはちょうどタカ類の記事にハヤブサが含まれているようなものである。さすがに今ではハヤブサをタカ類に含めず、通常はタカ・ハヤブサ類と書くだろう。
タカの渡りや、遠くで見つけた鳥がタカ類かハヤブサ類か判断できない場合に広義にタカと呼ぶことは構わないだろう。これはかつてタカ目がありタカ科、ハヤブサ科があって総称が可能だったものを継承しているとも言える。
しかしシジュウカラとゴジュウカラの名前は日本語の語呂合わせと考えられていて、系統的にも近くない。シジュウカラ科とゴジュウカラ科をまとめてカラ類と呼んでよいならば、これらを包含するすべての系統を論理的にカラ類と呼べることになる。ツバメでもヒヨドリでも全部含まれてしまう (#ツリスガラ備考の [スズメ小目 Passerida の系統分類] 参照)。
鳥の系統進化と言えば目レベルのもので、スズメ目は全部一緒に扱われて内部構造まで議論されることがあまりないためかも知れない。
古くからの読者の方であれば「最近は属を細かく分けるのが流行しているので、もとは一括してカラ類だったものを細かくシジュウカラ科、ゴジュウカラ科、エナガ科と分けるようになった」と読まれてしまうかも知れない。系統関係が明らかになりますます重視されている現在、ゴジュウカラやエナガはカラ類とは系統が異なるが便宜上一緒に扱うなどのコメントが欲しい気がする。
森林性で同じような行動をするものを一括して扱うのであればキバシリが入っていてもおかしくないし (当地京都では珍しくなく、ゴジュウカラよりはるかに出会いやすい。北海道の都市公園でゴジュウカラにあまりに簡単に出会えるのに驚いてしまった)、名前にカラの付くツリスガラはカラ類に含めてよいのかなど疑問も生じる。カラ類はシジュウカラ科に限定して用いる方がよい気がする。
面倒な気もするが、タカ・ハヤブサ類と書くように、カラ類・ゴジュウカラ・エナガのような書き方がよいのだろう。
一方でエナガ・メジロをまとめるのは系統的には悪くない (ただしムシクイ科も同じ系統に含まれる)。
[ゴジュウカラ類の道具使用]
ゴジュウカラの仲間には道具使用を行うものがある (コンサイス鳥名事典)。
枝を用いて幼虫を引き出す。
チャガシラヒメゴジュウカラ Sitta pusilla 英名 Brown-headed Nuthatch: Morse (1968) The use of tools by Brown-headed Nuthatcher、
幼鳥も実験室で同様の行動を行うことが最近明らかになった: Gray et al. (2016) Tool Usage by Juvenile Sitta pusilla (Brown-headed Nuthatch)。
この行動は本能と学習が組み合わさったものと考えられるとのこと。
ムネアカゴジュウカラ Sitta canadensis 英名 Red-breasted Nuthatch、ヒメゴジュウカラ Sitta pygmaea 英名 Pygmy Nuthatch でも真の道具使用が見られ、Sitta 属には道具使用の前段階の行動を行う種類が他にも複数ある。
Pasquet et al. (2014) Evolution within the nuthatches (Sittidae: Aves, Passeriformes): molecular phylogeny, biogeography, and ecological perspectives
によるゴジュウカラ類の分子系統研究に基づけば道具利用を行う種類は8種を含む1つの系統におさまっているとのこと。日本のゴジュウカラはこの系統には含まれていないが、地理的には比較的近いチョウセンゴジュウカラ Sitta villosa 英名 Chinese Nuthatch、
ウンナンゴジュウカラ Sitta yunnanensis 英名 Yunnan Nuthatch
はこのグループに含まれる種であり、道具使用を行うか興味が持たれているところだそうである。
[木の幹を登る鳥の下肢の適応]
ゴジュウカラ類そのものを調べたものではないが、同様に木の幹を登ったり下ったりすることのできる南米の亜鳴禽類の Furnariida 小目 (ovenbirds カマドムシクイ類、woodcreepers オニキバシリ類) の形態的適応を調べた研究がある:
Leblanc et al. (2023) Foot adaptation to climbing in ovenbirds and woodcreepers (Furnariida)。
Furnariidae においては第 II 趾と第 III 趾が皮膚でつながっていて (dermal syndactyly) 足と物体の摩擦を増すことに役立つ仮説 [Hoefling and Abourachid (2021) The skin of birds' feet: Morphological adaptations of the plantar surface] を裏付けるとのこと。
キツツキ類のように尾を支えに使うわけではなく純粋に足の力のみで移動している。
ゴジュウカラ類のように頭を下にして下ることはできないとのこと。
同様の syndactyly を示すカワセミ類で巣穴での機能も同様に考えてよい感じがする (論文に書いてあるかも知れない)。
ゴジュウカラ類で趾が長いことで掴む力を増している指摘はすでにあった (Cartmill 1985) が、ゴジュウカラ類の移動メカニズムについて調べられている目立った研究はなさそう。
Smyth et al. (2024) Hand and foot morphology maps invasion of terrestrial environments by pterosaurs in the mid-Mesozoic
論文そのものは翼竜の上肢・下肢の骨の形態的特徴から生態を推定し、現代の鳥類のように一部は地上生活を行っていたらしいが地上性の爬虫類が存在するため限定的であったなどの結果を得た内容だが、現生鳥類の比較もあるので紹介しておく。
物を掴む鳥は相対的に第 III 趾が長く、キツツキ類のように木を登る鳥ではさらに顕著である。アマツバメ類で比率的により顕著なのは第 I 趾が特に短いためだろう。
#アカゲラ備考の [キツツキの力の釣り合い] でもゴジュウカラの力の釣り合いを議論している。ゴジュウカラ類のように頭を下にして下ることができる種類にケラインコ類 (Micropsitta 属 Pygmy parrot) があるらしい。
△ スズメ目 PASSERIFORMES キバシリ科 CERTHIIDAE ▽
-
キバシリ
- 学名:Certhia familiaris (ケルティア ファミリアーリス) 見なれた木に住む昆虫を食べる小さな鳥
- 属名:certhia kerthios アリストテレスの述べた木に住む昆虫を食べる小さな鳥 (Gk)。キバシリかも知れないが同定されているわけではない (The Key to Scientific Names)
- 種小名:familiaris (adj) 家族の、親しい
- 英名:Tree Creeper, IOC: Eurasian Treecreeper
- 備考:
certhia は短母音のみで冒頭にアクセント (ケルティア)。
familiaris は#メグロ参照。
記載時学名は Certhia familiaris Linnaeus, 1758 (原記載) で最初から "馴染みのキバシリ" として命名されていた。
当時の慣習により (#ノスリの備考参照)、属を変えて種小名を変えた学名も提唱されていた: Motacilla scolopacina Strom, 1788 (参考)。
ユーラシアの主に中緯度帯に分布でヨーロッパではありふれた種類。世界で 10 亜種が認められている (IOC)。日本の亜種は japonica 亜種キバシリ、daurica (ダウールの) キタキバシリ (北海道、南千島) とされる。
daurica はユーラシア東部の大陸にも分布する。かつて shikokiana (四国) も提唱されたが、japonica のシノニムとされる。
Treecreeper / Tree Creeper はいかにも古くからある英名のように思えるが、OED を見るとそれほどでもなく、tree-creeper の用例が 1814 年に現れるとのこと。
単に creeper の名前は古くからあって、1661 年にすでに用例が知られているが古い時代はあまり区別されておらず複数の種を指していたとのこと。
英語圏のこのような状況を見ると和名のキバシリもどのように付けられたのか興味あるところである。さすがに飼い鳥向きではなかったようで飼育書にも名前が現れず、中国の分布も限られているので文化的に伝来する機会もなかったかも知れない。
Hartert (1910-1922) p. 317 によれば基亜種は Nordlischer Baumlaeufer とキタキバシリの意味になっている。
キバシリの和名が英語またはドイツ語由来の可能性はあるのだろうか、と思ってみるとミズバシリ類 streamcreepers (Lochmias 属) があって一緒に整理または命名された可能性がありそう。なおミチバシリ類 roadrunners (Geococcyx 属) があってこちらは英語からそのままの訳。creeper ならば "這う" の意味なのに "キバシリ" の名称となったのはこの影響があるかも知れない。
japonica は記載時学名 Certhia familiaris japonica Hartert, 1897 (原記載) 基産地 Iwaki, northern Hondo。
当時の記述では日本には2型があって北海道は Certhia Scandulaca Pallas, 1811 (参考) 由来の亜種 scandulaca と考えられていて少し小さく色彩が少し異なると本土のものに別亜種名を与えた。
Certhia Scandulaca Pallas, 1811 には Certhia familiaris Linnaeus, 1758 がシノニムと記載されているとのこと。
Hartert (1910-1922) p. 317 は Linnaeus の名称を改名したものと判断してシノニムとしたため現在では亜種名にも現れなくなった模様。
Certhia familiaris daurica Domaniewski, 1922 (参考 1, 2) 基産地 Darasun, Transbaicalia の方がむしろ遅い記載になっている。
Dement'ev and Gladkov (1954) でもユーラシアの東端を daurica としている程度であまりはっきりしたものではない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では亜種 japonica (Kibashiri, Hondo) と亜種 familiaris (和名なし。Kurile Is., Hokkaido) となっていた。
キバシリ上科? Certhioidea の分子系統解析: Imfeld et al. (2024)
Diversification and dispersal in the Americas revealed by new phylogenies of the wrens and allies (Passeriformes: Certhioidea)
により、これまでのキバシリ科から ホシキバシリ科 Salpornithidae (2種) の分割が採用された (WGAC, IOC 14.2)。
この分子系統解析には ゴジュウカラ科 Sittidae、ミソサザイ科 Troglodytidae も含まれているので参考になりそう。キバシリ上科? Certhioidea はユーラシア由来でキバシリ科までは大部分がユーラシア、一部の種がアフリカやアメリカに進出。
その次の系統である {ブユムシクイ科 Polioptilidae + ミソサザイ科 Troglodytidae} からなる系統が南北アメリカで適応放散し、そのうちミソサザイ1種のみがユーラシアにやってきたと見るとわかりやすい。
かつてはホジソンキバシリ Certhia hodgsoni Hodgson's Tree-Creeper (ヒマラヤ) が同種扱いでその後分離されたものだが、この系統樹を見ると別種にふさわしいことがわかる。ヒマラヤ系統のキバシリ類が別に存在するが、この種は別途ヒマラヤで分布した北方系統。
Certhia 属は現在9種からなり、大まかには2系統でキバシリを含む4種の系統 (Holarctic lineage) にアメリカキバシリ Certhia americana Brown Creeper が含まれる。アメリカキバシリは Certhia 属のうち唯一アメリカに進出したもの。
分布からはアメリカキバシリとキバシリがもっとも近縁な感じがするが、アメリカキバシリに最も近縁なものはタンシキバシリ Certhia brachydactyla Short-toed Tree-Creeper (ヨーロッパ) とのこと。ただしアメリカキバシリとキバシリも遺伝的にはそれほど遠いわけではない。
もう一つの系統がヒマラヤ系統となる。
[音声]
繊細なさえずりとされるが、ミソサザイのような出だしでセンダイムシクイのように終わると言えば理解されやすいだろうか (本州の話で、北海道個体では成り立たない説明かも)。繁殖時期が早いために早春の山に聞きに行く方もあるが、繁殖期を通じてさえずるのでキバシリを聞くのが目的であれば早春にこだわる必要はない。
「原色日本野鳥生態図鑑」(中村登流・中村雅彦 保育社 1995) p. 124 にはさえずりは早春と秋によく聞かれるとあり、そのように信じられていたのかも知れない。
地鳴きは何種類かあり、ヒガラに似た要素があるものがある。慣れればすぐわかるようになるタイプの音声である (このタイプの地鳴きはさえずりの要素を含むことが多いのでさえずりに慣れていれば判別しやすい)。
上記2系統 (北方とヒマラヤ) でさえずりが違うとのこと。キバシリでも中国の個体は違うとのことで (wikipedia 英語版 Certhia)、japonica の位置づけも気になるところである。分布の関係で録音が難しいのか xeno-canto にはキバシリの中国のさえずり記録はなかった。
Eurasian Treecreeper (Tao Liu 2020) に1つ記録があるが本州のものとそれほど違わない感じがする。
北海道のキタキバシリの声は本州と違って聞こえるので、コガラ同様キタキバシリと亜種キバシリは案外違うのかも知れない。大陸との関係も含めて今後の検討課題か。
また平板で高いタイプの地鳴きはキビタキの巣立ちびなと区別しにくいが (#キビタキの備考参照)、キバシリの音は震えるように聞こえる。そのまま待っていればさえずってくれることも多い。声を聞き慣れれば広範に木から木へど移動して採食していることがわかりやすい。
キバシリの家族群でもよく聞かれる声でキビタキの繁殖時期とも多少重なる。
キバシリの平板で高い地鳴きは次第にテンポを速めることが多く、この点はキビタキの巣立ちびなと異なる。テンポを速めるのが移動の合図のことが多いのでこれも判断材料になるだろう。
長く震える感じの地鳴きが多いが、短い地鳴き (警戒? 飛ぶ時など) もあって場所や季節的にはクロジの地鳴きを思わせることもある。頭上から聞こえてきたり近づいてきた音声でその後長く震える感じの地鳴きに移行することが多くあまり迷うことはないが。
印象ぴたりではないが XC346344 (Piotr Szczypinski 2016) は近い感じがする。
京都では低山まで分布を広げていて今では結構身近な鳥になっている。筑豊では未記録とのことで少し驚いたが、おそらくすでに分布しているか記録されるのも時間の問題ではと想像する。なかなか見えにくいので音声で気づくのが役立つが、カラ類などの地鳴きと誤認されている場合もあるかも。地鳴きでも録音してソノグラムを見ればわかりやすい。
[分布変化・英国との比較]
「動物の世界」2版 9 (日本メール・オーダー 1986) pp. 1253-1254 (浦本・安部) にキバシリの項目があるが英国の出版物由来のため内容的には英国のキバシリと世界分布の話が大半。項目名だけを見て日本のキバシリのことを書いてあると考えると誤解の原因ともなるだろう。
ヨーロッパには2種のキバシリ類が生息し、タンシキバシリ (当時の名称はニワキバシリでドイツ語名 Gartenbaumlaeufer を訳したものと思われる) Certhia brachydactyla Short-toed Treecreeper は大陸に広く分布。氷河期以降に広葉樹林の拡大に伴って北に分布を広げたが、その時代にはドーバー海峡がすでに形成されていて英国には到達しなかった。
一方キバシリは針葉樹林に依存して分布を先に広げていたため英国にはこの種のみが分布し、低地の広葉樹林にも分布できたと思われるとのこと。
この辺や世界分布の話だけ見ていると日本のキバシリの話が出てこないので面白くないかも知れない。タンシキバシリは英国に (もちろん米国にも) 分布しないため、英名は機械的に (英国から見れば大陸のものだと冷淡に) 学名から付けたものと思われ面白くない名前となっている。新しい方の和名も分布地でない英名を由来としているためこちらも今ひとつ面白みがない。もとのニワキバシリの名称の方が生息環境も反映されていてよかったかも知れない。
この状況は日本のキバシリの分布拡大もある程度説明してくれるかも知れない。日本ではキバシリは1種のみなので英国の状況に近い。競争相手のない状況で低山まで分布を広げるのはあまり障壁がなかったのでは。また北海道とそれ以南で遺伝的交流が少ないらしいのも理解できる。
それではこれまでなぜ高いところにしか分布していなかったのだろうか。一時期森林破壊が進み過ぎて標高の高いところにしか住める場所がなくなっていたのかも知れない。移動能力に乏しいので森林伐採で分布が寸断されるだけで簡単に消滅したのかも知れない。
針葉樹林を得意とするものの広葉樹林にも住めるため全国的な森林の成熟に伴って分布を拡大したのかも。あるいは我々が気づいていない競争相手があったのかも知れない。
いずれにしても気候の温暖化に伴って標高のむしろ低いところに分布を広げているので、気候変動で野鳥の分布域が北上したり標高を上げている、"あるいは鳥の生活は涼しいほうがいい" 論には都合の悪い種となる (#サンコウチョウの備考 [サンコウチョウの分布変遷] や #ホトトギスの備考参照)。
キバシリには別要因がありそうなので、と言えるならば他の種にも別要因があってもおかしくないので、個別要因を考慮しない気候変動由来の議論はほどほどにしておいた方がよい感じがする。
考察をしつつ、この点に注目して改めてキバシリの行動と声を観察したところ、広葉樹にも普通に飛び移って採食を行っていた。昔から知っていたが意識して観察すると明瞭だった。採食中の声はエナガの短い地鳴き (よく聞くジュリリの声ではなく短い contact call) に似ていた。ただし声を追跡できれば移動しながら採食している様子を観察するのはそれほど難しくない。夏鳥のさえずりの一段落した程度の時期が気になる声が減って調べやすい。
見ているとコゲラの好みにも似ている感じがした。地鳴きも遠くから聞くコゲラの声の性状に近い部分がある印象を受けた (音源探知のしやすさ / しにくさや森林内のコミュニケーションの面で適しているのだろうか)。
コゲラの方が早くから低地の森林に分布しており (ただしキバシリが分布していなかったのは低地の森林への人為的影響が大きかったためかも知れない)、より質の低い森林でも生息可能なので現代では都市に適応するようになったが、少し遅れてキバシリが似た経過をたどっているのかも知れない。
キバシリの分布拡大はまさしく進行中の現象で、自身の観察ではここ 10-15 年程度の期間に顕著のように思える。あるいは 20 年ぐらい前まで遡れるかも知れない。こちらの連続した森林ではもう分布し尽くしたかも知れないが、まだ身近でない地域では分布拡大の経緯を調べるには格好の題材ではないだろうか。
森林が不連続区間がどの程度あれば簡単に分布を広げられないなど、密に調べれば一目瞭然の結果が得られるような気がする。
以上、観察しやすい時期なども含めてあくまでこちらの状況で、地域によって状況はまったく違うかも知れない。
かつて東京でカワセミの経年分布がアンケート調査で調べられたことがあったが、目立たず知名度も低いキバシリではさすがに無理だろうか。経験のあるバーダーの出番と思う。本稿をお読みの方もご自身の記録や支部への報告記録など調べていただくと面白いだろう。
その後再度間近で見る機会があった (2025.6 上旬) ので観察してみた。短い地鳴きは盛んに出しており、これをカラ類やエナガの地鳴きと思って見過ごさないことが大事と思えた。採食中の個体をじっくり見ていると、他個体の長い地鳴きを聞くと動作を止めた。しばしば alarm call と表現されるがこの行動を見ると納得できる部分がある。おそらく他個体の注意を引くための声なのだろう。
逆に言えばこの声が移動の合図になっている場合もあって、姿をじっくり見るには短い地鳴きを出しているうちに気づいて見つけるのが多分向いているのだろう。
ロシア沿海地方のキバシリの繁殖: Shokhrin et al. (2025) Breeding birds of Primorsky Krai: the common treecreeper Certhia familiaris (pp. 337-355)
亜種は orientalis としている。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ミソサザイ科 TROGLODYTIDAE ▽
-
ミソサザイ (新分類で学名が変わる可能性あり)
- 学名:Troglodytes troglodytes (トゥローグロデュテース トゥローグロデュテース) 穴へもぐる鳥
- 属名:troglodytes (外) 穴へもぐるもの Gk (穴居人) < trogle 洞窟 -dutes 潜るもの (Gk)
- 種小名:troglodytes (トートニム)
- 英名:[Wren, Winter Wren], IOC: Eurasian Wren
- 備考:
troglodytes は起源となるギリシャ語の長音がよく保存されている。tro-, -tes が長母音。
-glo- にアクセントがある (トゥローグロデュテース)。
新属名となる可能性のある nannus は起源となるギリシャ語は短母音のみで、"ナンヌス" の読みでよいだろう。
亜種の fumigatus は "フーミガートゥス"。fumigo (煙を立たせる) の長音と分詞形語尾に由来。
mosukei はラテン語読みだと -su- にアクセントがある。
troglodytes の意味が日本のミソサザイとあまり合わない印象を受けるかも知れないが、後述のように属名はアメリカのイエミソサザイに対して与えられた名称で、この種類は樹洞や巣箱で営巣する。
ヨーロッパのミソサザイに対する troglodytes の名称は Linnaeus (1758) (原記載) 以前からあった。
分子系統解析の結果から属が分割される可能性があり、もし種も分割されれば troglodytes の意味と生態の若干の乖離に悩むこともなくなるのだろう。
ユーラシアの主に中緯度に広く分布する種類で、世界では 28 亜種が認められている (IOC)。
日本で記録されるものは fumigatus (煙の色の) 亜種ミソサザイ、mosukei (Mosuke Saito 由来。伊豆諸島中部以南) モスケミソサザイ、
ogawae (鳥類学者 Minori Ogawa 小川三紀 由来。屋久島、種子島) オガワミソサザイ、及び IOC リストにはない orii (Hyojiro Orii 由来。大東諸島。絶滅したと考えられる) ダイトウミソサザイ がある。
dauricus (ダウール地方の) チョウセンミソサザイは日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討亜種リストへ。本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
亜種 orii は世界の主要リストでは mosukei のシノニムとされる。wikipedia 英語版でも 1940 年ごろ絶滅したとされる "disputed" (議論のある) 亜種とされている。
亜種ダイトウミソサザイは 1938 年の冬季に1羽のみ模式標本の採集例しか記録がないことから、単に冬季に南大東島に飛来した個体の可能性もある (wikipedia 日本語版)。
Yamashina (1938)
A New Subspecies of Troglodytes troglodytes from the Borodino Islands は長距離を迷行することは考えにくいため他標本と比較して亜種と記載したものだが、近年与那国島や沖縄諸島で迷行例が観察されていることから、南大東島の個体も本土か他の島の亜種が迷行した可能性が議論されている (wikipedia 英語版)。
Vaurie (1955) Systematic notes on Palearctic birds. No. 16, Troglodytinae, Cinclidae, and Prunellidae (p. 12) にも検証が必要とある。
ダイトウミソサザイは特殊鳥類に指定されていた。
fumigatus はアスペルギルス症をもたらす最も一般的な真菌 Aspergillus fumigatus にも使われていてあまり嬉しくない学名かも。
種の記載時学名 Motacilla Troglodytes Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地スウェーデン。
Troglodytes fumigatus Temminck, 1835 (原記載 は日本を基産地として記述、ヨーロッパの普通のミソサザイ (le Troglodyte ordinaire) より少し大きいなど異なるものとしていた (和名 Misosasasi が紹介されている。やはりフランス語で z は表記しにくいよう)。
もし別種であればヨーロッパの普通のミソサザイの少なくとも3つめの親戚 (voisine) になると記述している。
しかし Temminck & Schlegel (1845) は基亜種 (当時の表記で Troglodytes vulgaris) との違いが認められないとして普通のヨーロッパのミソサザイと同じとして戻した (参考)。
現在使われている亜種 fumigatus も結構あやふやだったことがわかる。
[分類の問題]
これまでの Troglodytes 属が単系統でない証拠が強まってきた。
Barker (2017)
Molecular Phylogenetics of the Wrens and Allies (Passeriformes: Certhioidea), with Comments on the Relationships of Ferminia
によれば、これまでの Troglodytes 属が
キューバのセジマミソサザイ Fermini cerverai Zapata Wren [これもキューバクイナ Cyanolimnas cerverai Zapata Rail (#クイナの備考参照) 同様 Zapata ザパタ半島の沼地のごく限られた場所にのみ生息し絶滅の恐れがある。
キューバカギハシトビ Chondrohierax wilsonii Cuban Kite (#ハチクマ備考 [ハチクマ類の系統分類] に紹介) も参照]
および南北アメリカに分布するマヌマミソサザイ類 (Cistothorus 属5種)、中米のヤブミソサザイ Thryorchilus Timberline Wren の3属を内包している根拠が強まってきた。
系統樹サポートがまだ高くない部分もあり全面的に採用されているわけではないが、この分子系統樹に基づけば Troglodytes 属は新世界の種を指すものとなり、旧世界のミソサザイはいずれ別属となることは避けられそうもない。その場合 Nannus 属となる (nannos 小人 Gk)。
この場合のミソサザイの学名は Nannus troglodytes となる。
種小名が troglodytes で属名と種小名が同一の学名トートニムなのでミソサザイの方が Troglodytes 属になりそうな気がするが、
Troglodytes aedon (新世界のごく普通種イエミソサザイ House Wren。現在はさらに分離され Northern House Wren。aedon は#ハシブトオオヨシキリ参照。ナイチンゲールのこと) の名称が早く、こちらがタイプ種。
[なお Winter Wren potential split (BirdForum 2014 とこの次のページ) に議論がありもう少し自明ではないよう]。
ミソサザイの方は Motacilla troglodytes Linnaeus, 1758 と当初はセキレイ類とした名前がついていた。新世界の troglodytes に類似として Le Troglodyte d'Europe (ヨーロッパのイエミソサザイ) の使い方がなされた。
ミソサザイが Troglodites (綴りがわずかに違う) 属となったのは 1816 年 (Cuvier 1816)。イエミソサザイに Troglodytes 属が与えられたのが 1808? 年 (Vieillot 1809) なのでこちらの方が早い (The Key to Scientific Names)。
Vieillot の用いた Troglodites 属の方は種小名から属名への昇格でミソサザイには Troglodites vulgaris Fleming (普通のミソサザイ) の代わりの学名も与えられていた (参考)。(属名への昇格に伴う種小名については #ノスリの備考参照)。
属名への昇格に伴う新名は独立に与えられるケースもあったようで Troglodytes europaeus Stephens, 1817 (参照) も与えている。この学名もよく使われた模様。
属を記載した Vieillot 自身も Troglodytes europaea Vieillot, 1819 (参考) と与えたが、こちらは Linnaeus 由来の名前ではなく Sylvia troglodytes Lath. をシノニムとしていた。
American Ornithology; or the Natural History of the Birds of the Unites States (Wilson 1808) によればミソサザイのようで、アメリカで迷鳥記録の際にこの学名が用いられていた。アメリカでは "Wren" と呼ばれるものが別にあって呼ばれる属も違うので混乱要因となっていたらしい。
Troglodites と Troglodytes が同一綴りと判断されまとめられたのは多分後の時代の規則によるものだろうか。
ということで、属分割の際にトートニム (この場合は疑似トートニムと呼ばれる) なのに属学名が引き継がれないという奇妙な現象が起きる。
Imfeld et al. (2024)
Diversification and dispersal in the Americas revealed by new phylogenies of the wrens and allies (Passeriformes: Certhioidea)
の最新分子系統研究でもこれまでの Troglodites 属を分割する提案で、我々のミソサザイは Nannus 属になる。
文献などではすでに使われているので、我々も Nannus troglodytes に慣れておいた方がよいことになるのだろうが、困ったことにミソサザイは何種からなるかの問題がある。
Albrecht et al. (2020) Phylogeny of the Eurasian Wren Nannus troglodytes (Aves: Passeriformes: Troglodytidae) reveals deep and complex diversification patterns of Ibero-Maghrebian and Cyrenaican populations
の研究のように (旧) ミソサザイのいくつかのクレードを別種とすべき提案がある。この研究では2種 Nannus pacificus (北米西海岸からアラスカまで Pacific Wren タイヘイミソサザイ)、Nannus hiemalis (北米 Winter Wren フユミソサザイ) を別種として扱っている。この学名を見てかつてはミソサザイだったことを連想できる人はほとんどないのではないだろうか。
IOC ではすでに別種となっている。上記和名はネットで用いられているものだが、タイヘイミソサザイはあまり日本語らしくない感じもする。ミソサザイの英名は北米では Winter Wren と言われるのは昔の話で、今は別種扱い。
日本の主な亜種の fumigatus はユーラシア東部のクレードに属し、
基亜種 troglodytes を含むユーラシア西部のクレードとは異なる。この論文では同種として扱っているので Nannus troglodytes fumigatus の学名になるが、研究が進んで東西を分けるべし、となれば変わってくるかも知れない (全亜種を調査できていないのでそこまでの提案を行っていないのだろう)。
幸いにして (?) ミソサザイの亜種の中でも fumigatus Temminck, 1835 は早いので、もし分割された場合も Nannus fumigatus となって大陸亜種が種小名に採用される心配はなさそう (それでもこの学名からミソサザイを想像するのは難しい)。
ミソサザイ科は上記 Nannus 属 (新称) の一部を除いてすべて南北アメリカの種類で、特に中米が発祥の地と考えられている。南米には独立した6系統の適応放散があったと考えられる。生物地理学の視点からも広義 Troglodytes を分割することは意味がある。従来分類ではミソサザイ1種のみとなる。
このような分布からみると北米西海岸からアラスカまで Pacific Wren がベーリング海峡を通って北米からユーラシアにやってきたと考えるのがわかりやすそうである。(昔から言われていたことではあるが) 馴染みのミソサザイがアメリカ大陸からやってきたとはちょっと不思議な感じがする。
東アジアに定着したのは比較的古い系統で、ヨーロッパの主な系統は比較的新しい系統と考えておおむねよさそう。
ただヨーロッパにも飛び地的に古い系統があり、気候変動などで隔絶されたものかなど検討されているがヨーロッパの種分化の特殊事情は詳しくないのであまり把握していない。ヨーロッパのサンプルが密にあったため判明したものかも知れないので、同様のことが東アジアで起きていないと言えない気がする。
ミソサザイを何種に分けるか、従来の亜種との整合性などこれからも議論されるだろう。この研究では遺伝子しか扱っていないが、音声面の系統関係を調べるのもおそらく面白いだろう。
ミソサザイ科は新大陸では複数種が馴染みで、英名でも Wren の付く名前はいろいろある。イワミソサザイ Salpinctes obsoletus Rock Wren は別属だが北米・中米の有名種。
ニュージーランドに入植した人が故郷の Wren を懐かしんで付けた Rock Wren もあり、イワサザイ Xenicus gilviventris 混同を防ぐために South Island Wren または New Zealand Rockwren と呼ばれるが、みかけも系統も異なる。
スズメ目の中でも {Tyranni (亜鳴禽類) + Passeri (鳴禽類)} 合わせて Eupasseres とされるよりさらに前の系統で、New Zealand Wrens: Acanthisitti の2系統2種のみが現存しているもの。和名では イワサザイ科 Acanthisittidae で、スズメ目の冒頭になる。鳴禽類の分類一覧を探しても出てこないので注意。
[#鳥類系統樹2024] の Stiller et al. (2024) でもスズメ目の冒頭が妥当な系統樹が得られているが、他のスズメ目との推定分岐年代は 5000 万年前程度と非常に古い系統となる。この系統樹では亜鳴禽類にも含まれないスズメ目の中でも独自系統になる。
近縁系統の化石記録はあるので、より後に出現した Eupasseres との競争でごく限られた系統のみが残ったものか。
音声も xeno-canto などから聞いてもらうとよいが、亜鳴禽類 (ヤイロチョウなどを想像するとよい) よりも一層単純でさえずりらしく聞こえるものもない。10 kHz 付近 (ヤブサメさえずりの高音部分ぐらい) あるいはそれ以上の声で、鳴いていることの認識も難しいかも知れない。音声的にはミソサザイとはあまりに違って観察者泣かせだろう。
スズメ目の進化の歴史を考えながら音声を聞いてみるのも面白いだろう。
このような非常に古いスズメ目の系統であるイワサザイ科に音声学習能力があるのか興味あるところだが、その可能性をある程度示唆する結果が得られた:
Moran et al. (2024) Vocal convergence and social proximity shape the calls of the most basal Passeriformes, New Zealand Wrens
個体ごとの発声の違いがあり、他個体の声に合わせた発声をする vocal convergence を示すとのこと (コウモリの call convergence については#タンチョウ備考の [ツル類やハクチョウ類の気管・鳥の発声メカニズム] を参照)。音声の違いは遺伝的違いで説明できず、原始的な音声学習能力の存在を示唆するとのこと。
この論文に音声学習レベルの系統樹があるので参考になる。vocal convergence はオウム目以降の系統 (スズメ目を含む) に共通して見られ、他にもヤツガシラ類、ハチドリ類 (これは音声学習が確かめられている)、ペンギンでも報告されており、音声学習をしないとされた種類でも発声にさまざまな段階があることを示唆するとのこと。現代的手法でしっかり調べれば他にも見つかりそうな感じ。
托卵鳥の音声学習 (#カッコウの備考参照)、ハクトウワシの音声学習? (#ハクトウワシの備考参照) の話題もあり、鳴禽類以外の音声学習について、鳴禽類の音声学習の起源解明にもつながる可能性のある面白いテーマになりそう。
哺乳類でもマウスの超音波コミュニケーションに学習が関与しているか、音声学習はある・なしではなく、もっと連続的なものと考察されている: Arriaga and Jarvis (2013)
Mouse vocal communication system: are ultrasounds learned or innate?。脳の構造的にも音声学習をする鳥との類似性があるとのこと。こちらでも pitch convergence があるとのこと。
[チンパンジーはミソサザイ?]
なお troglodytes の種小名は他のグループでも使われており、ミソサザイの特権というわけではない。名前がよく知られているところでは飼い鳥でも有名なカエデチョウ Estrilda troglodytes Black-rumped Waxbill がある。
鳥に限定しなければチンパンジーの学名 Pan troglodytes。
洞窟に住むものとしてふさわしい Troglodytes の属学名がすでに鳥で使われていた (1809) ため属には使えなかったとのこと。Pan は Lorenz Oken が 1816 年に提唱。
知名度の高い鳥でなければもしかするとチンパンジーの方が優先されていたかも [なんてことはないだろうが...ウズムシとウオクイワシの学名関係 (#オジロワシの備考参照) を見るとあり得ない話でもないかも知れない]。
Pan の由来は明示されていないが、おそらくギリシア神話のパーン神だろうとのこと。他の学名も提案されていたが、ICZN が 1985 年に決定したとのこと Opinion 1368 The generic names Pan and Panthera (Mammalia, Carnivora): available as from Oken, 1816 (wikipedia 英語版)。
この文献によれば Homo troglodytes Lianneus, 1758 が原学名 (洞窟に住む人の意味) で、Homo (ヒト) 属が分割される際の属名が問題となった。
Skott (2014) Linnaeus and the troglodyte によれば Lianneus はマレー半島のヒトをヒト属の別種とみなしたらしい。
また Troglodytae はアフリカの紅海沿岸に住んでいた古い人のグループを指す名前だった (wikipedia 英語版)。
Lianneus 自身の指していたものも明確でなく、改めて学名が与えられる理由ともなったらしい。
Troglodytes niger Geoffroy, 1812 の提案もあったとのことで文献にも現れていた学名であった。
2000 年以降でも Homo niger の使用例があり、2000 年の ICZN の規約で古い先行シノニムであっても1899 年以降使われていなければ排除される規則が盛り込まれて使えなくなったとのこと (Pan troglodytes)。
2003 年にはチンパンジーを Homo 属に戻す議論が再燃し、ゲノム解析で別属相当が適切であると判明した。
イエミソサザイの属名に先に使われていなければ、我々が普通にみかける現在のミソサザイの学名 Troglodytes troglodytes はもしかするとチンパンジーの学名になっていたのかも知れない。現在の学名が変わる前に今一度ミソサザイの学名を見ておこう。
[音声]
地鳴きはウグイスに似ていて区別が難しいとよく言われるが、近くで聞くことができれば音質が全く異なる (ウグイスの方が雑音っぽく聞こえる)。慣れればすぐに存在のわかる声である。
ソノグラム解析をすればミソサザイでは特徴的なパターンを見ることができる [Kato (2021) A code for two-dimensional frequency analysis using the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (Lasso) for multidisciplinary use に日本のものを含め、いくつかの亜種を紹介している]。
ウグイスは音を一つずつチャ、チャと鳴くが、ミソサザイは数個の音をまとめて出す傾向があることも判別に役立つ。警戒時の音声はニシオジロビタキにやや似ている。
[ミソサザイは鳥の王]
他言語での名称はオランダ語 Winterkoning (冬の王)、ドイツ語 Zaunkoenig (生け垣の王) と王を用いているものがある。
アイルランドでは聖ステファノの日 (St. Stephen's Day, Wren Day) にミソサザイの飾り (かつては実際のミソサザイの死骸) を持って家々を回り、踊り歌い、音楽を奏でる (wikipedia 日本語版より)。
Celtic myth had it that the robin that was suppose to represent the New Year killed the wren which represented the Old Year during this time ... Originally, groups of small boys would hunt for a wren, and then chase the bird until they either have caught it or it has died from exhaustion.
The dead bird was tied to the top of a pole or holly bush, which was decorated with ribbons or colored paper.
(Winter/Religious Festivals Saint Stephen's Day)。
英文学に詳しい方ならば他にもいろいろご存じだろう。
How the wren became the king of all birds
によれば鳥が王様を決める時に、ワシが自身が王であると確信して降りて来た時に「自分こそが王だ」との声が上から聞こえてきた。ミソサザイがワシに隠れて乗っていたのだった。アイルランド語でミソサザイは dreoilin (= trickster 詐欺師)。
悪い意味で使われ、上記の聖ステファノの日の行事につながる。
ミソサザイは鳥の王様で検索すると日本でも多数出てくるが、日本の民話なのか海外から伝承されたのものが変形されたものかよくわからない。
ドイツ語名称の語源はイソップの寓話に遡るとあり (wikipedia ドイツ語版)、上記と内容は同じようなのでたどれる範囲ではイソップに由来のよう。
ドイツの NABU (ドイツ自然保護団体 Naturschutzbund Deutschland, 1899 年創設で日本野鳥の会より歴史がある。2022 年で会員数 73 万とある) のサイトでは Wie der Zaunkoenig zu seinem Namen kam
に名称の由来の解説がある。アリストテレス時代にすでに Basileus (王) または Basiliskos (小さな王) と呼ばれていたとのこと。日本でも鳥の王と呼ばれると紹介されているがこれは独立して呼ばれたものなのだろうか。古高地ドイツ語で wrendo と呼ばれ英語の語源につなかっているとのこと。
[ミソサザイはかつて高山の鳥の扱いだった]
中西悟堂「定本・野鳥記」8 pp. 111-112 (1944 年初出) によれば、以前は学会でも高山の鳥と思われていて、中西氏などが山地の鳥を調べる以前は学会では山歩きをする人がまれだったとのこと。確かに山が観光地化される以前は、アクセスもそれなりに大変で山の鳥はあまり調べられていなかったかも知れない。
富士山のような特別なところは調べられたが一般の山地は鳥学者もおそらくあまり知らなかった、と考えればセンダイムシクイが低標高で繁殖していることが知られていなかったことも納得できることになる。
中西氏のこの記事で当時の狭義武蔵野 (東京西部) の鳥類相がわかるが、なんとトビは冬鳥だった。
一方サンコウチョウ、サンショウクイやアカモズなどは低地でも繁殖。ウグイスはいくつかの事例を除いて東京近郊での繁殖は皆無とあった。
「定本・野鳥記」1 pp. 218-219 (おそらく 1937 年ごろの観察記録) では富士山では一般の野鳥より高いところに住んでいる。北・中央・南アルプスでも同様の渓谷の歌の王者だが、存外にも高尾山などでも繁殖している (要約)。高山の鳥と考えられたのは登山道のあるような限られた高山では高いところで記録されたためだったらしい。その後数年で中西氏も経験を積んでもっと低いところでも生息していることを把握されるようになったのだろう。
もとから標高のある山間地域に住んでいる方ならば何の話をしているのかと思われたのではないだろうか。1944 年の記述も他人の情報を合わせたものになっているので、中西氏の 1937 年ごろの記述を読んでそんなことはなくもっと低いところに生息していると伝えられた方があったのかも知れない。学会は知らない、情報網のある自分は知っている、とまあそう言いたかったのだろう。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ムクドリ科 STRUNIDAE ▽
-
ギンムクドリ
- 学名:Spodiopsar sericeus (スポディオプサル セーリケウス) 絹もののような灰色ムクドリ
- 属名:spodiopsar (m) 灰色のムクドリ (spodios 灰色の psar, psaros ムクドリ Gk)
- 種小名:sericeus (adj) 絹物のような (sericum (n) 絹物 ceu (adv) 〜のように -s (語尾) な)
- 英名:Red-billed Starling
- 備考:
spodiopsar は#ムクドリ参照。
sericeus は冒頭が長母音で -ri- にアクセントがある (セーリケウス)。
記載時学名 Sturnus sericeus Gmelin, 1789 (原記載) 基産地 China。学名のもとになった Silk Starling (Brown)、Silk Stare (Latham) が挙げられている。言うまでもなく絹はヨーロッパにとっては貴重なもので中国のムクドリを指して silk を付けるのは実に適切だったのだろう。
この名称に相当するものは現在でも多くの言語で使われている。
Spodiopsar 属は Sharpe (1888) が東洋のムクドリ類 (Oriental Starlings) を指して与えた属名。後にギンムクドリがタイプ種と指定された。
この属名はそれ以前に Cassin (1867) が新世界の鳥に用いていたが Icterus 属のシノニムとなったようでより遅い Sharpe (1888) の用例が使えるようになったらしい (The Key to Scientific Names)。
分子系統解析などで Cassin (1867) の概念を復活させる必要がもし生じた場合はどうなるのか素人にはわからない。
単形種。
分子系統解析によって旧 Sturnus 属が単系統でないことがわかり、ムクドリ類が細分された [Zucoon et al. (2007)
Phylogenetic relationships among PalearcticOriental starlings and mynas (genera Sturnus and Acridotheres: Sturnidae)]。
日本産の種では Spodiopsar (ムクドリ属)、Agropsar (コムクドリ属)、Sturnia (カラムクドリ属)、Pastor (バライロムクドリ属) の各属はこの文献で過去の属名を復活する形で導入された。
Sturnus 属 (現在の名前でホシムクドリ属) に残るのはホシムクドリとごく近縁の1種のみになった。
[ムクドリ科の系統分類]
Boyd のものを利用。IOC などもほぼ同じ分類でリストにより順序が変わる程度。日本産種に関係する部分のみ少し詳しく分けた。Graculinae の代表名としてキュウカンチョウがふさわしいかどうかわからないが、非常によく知られている種なので参考までに挙げた。
アフリカの種類は "テリムク" が付く和名が多いが、"ムクドリ" のものも多く族にふさわしい和名は難しいものもある。Onychognathus はチャバネテリムク属 (タイプ種と合っている) の名称があるようでそれに合わせた。
ムクドリ科の属分類はやや細かく、かつては Sturnus 属にまとめられていた日本産種の間でそれほど大きな違いがあるわけではない。ハッカチョウ属 Acridotheres がよくまとまったグループで属として独立するのは妥当で、その場合は単系統性の要請から他を細かく分離する必要があり現行の分類につながっている。
ムクドリ科 Sturnidae: Starlings, Mynas
キュウカンチョウ?亜科 Graculinae: South Asian/Pacific Starlings
キバシリモドキ族 Rhabdornithini: Philippine Creeper (フィリピン、3種)
キュウカンチョウ?族 Graculini: South Asian & Pacific Starlings and Mynas (キュウカンチョウ Gracula religiosa などを含む複数属)
ムクドリ亜科 Sturninae: African/Eurasian Starlings
ムクドリ族 Sturnini: Eurasian Starlings
ホシムクドリ属 Sturnus (自然分布はヨーロッパ中心の2種)
トサカムクドリ属 Creatophora (アフリカ東部の1種)
バライロムクドリ属 Pastor (1種)
クビワムクドリ/ホオジロムクドリ属 Gracupica (中国から東南アジアの 2-4 種)
コムクドリ属 Agropsar (東から東南アジアの2種)
シロガオムクドリ属 Sturnornis (スリランカ、1種)
カンムリシロムク属 Leucopsar (バリ島、1種)
カラムクドリ属 Sturnia (東・東南から南アジア、5種)
ムクドリ属 Spodiopsar (2種)
ハッカチョウ属 Acridotheres (自然分布は東南アジアから南アジアが中心。10 種)
シロハラムクドリ?族 Cinnyricinclini: Madagascan and Violet-backed Starling (アフリカ、2属2種)
チャバネテリムク?族 Onychognathini: Red-winged Starling (アフリカからアラビア半島、1属)
(テリムクドリ)?族 Lamprotornini: African Starlings (複数属、アフリカ)
このようにムクドリ科は自然分布はアフリカからユーラシアの種類で、渡り能力が低いものが多いためにアメリカやオセアニアに分布しなかったのだろう。
しかし生息できるニッチは十分にあったため外来種として持ち込まれたホシムクドリが簡単に分布を広げることができた。東アジアには Gracupica 以降の属が分布しており、ホシムクドリは東アジアにあまり分布を広げられなかったと考えるとわかりやすい。体格的にもムクドリの方が有利だろう。東・東南アジアの気候などへの適応の問題も関係しているかも知れない。
さらに新しいムクドリ類の分子系統解析は Lovette et al. (2008) A complete species-level molecular phylogeny for the "Eurasian" starlings (Sturnidae: Sturnus, Acridotheres, and allies):
Recent diversication in a highly social and dispersive avian group も参照。
属名は当初 Poliopsar (polios 灰色 psar, psaros ムクドリ Gk) を使いたかったが、他にすでに使われていたためこの属名になったとのこと (The Key to Scientific Names)。
ムクドリ類の学名でよく現れる psar のような綴りは英語ではほとんど見かけないが (英語ではこの綴りで始まる場合は p は発音しない) ps はギリシャ文字の ψ (プサイまたはプシー) に対応する。
さらに新しい分子系統研究がある: Han et al. (2024) Sturnidae sensu lato Mitogenomics: Novel Insights into Codon Aversion, Selection, and Phylogeny。
ここでは広義ムクドリ科の概念を用い、マネシツグミ科 Mimidae、ウシツツキ科 Buphagidae までを広義ムクドリ科として解析している。
この解析でも過去に発表されたミトコンドリア配列がキメラとわかっている種類を除外している。
中国の個体からムクドリとギンムクドリの核ゲノム配列も新たに得られて使われている。
ムクドリ科で過去の研究で導入された属の単系統性も確認され、現在使われる学名を変える必要は生じないと思われる。
日本に関係するムクドリ類以外では オオサマムクドリ 普通に使われる学名で Basilornis galeatus Helmeted Myna は カササギムクドリ Streptocitta albicollis White-necked Myna など Streptocitta 属と単系統をなすなど他の系統では過去の分類の単系統性が確認できなかったものがあり、今後属の修正が行われるだろう。
Zucoon et al. (2007) の結果とは異なる部分があるとのこと。
ムクドリ科は subclades を認めることができて (1) Phillipine Rhabdornis, (2) South Asian/Pacific Starlings, (3) Eurasian Starlings, (4) Red-winged Starlings, (5) African Starlings, and (6) Amethyst and Madagascar Starlings
に分けられるとのこと。(6) を除いて単系統性が強く支持される結果となったとのこと。これら英名以外にもクレード学名 (Boyd はすでに族に分けている) が使われることになるかも知れない。ムクドリ類で細かく分けられた属名の系統関係を見る時はこの系統樹を参考にするとよさそう。
日本鳥類目録改訂第8版の順序 (= IOC 13.2 順) とはかなり異なるものになりそうで、おおよそ Sturnus, Pastor, Agropsar, Sturnia, Spodiopsar
の系統順となりそう。現行のものとほぼ逆順に近くなる。Boyd の順序にも一致している。
これらはすべて (3) Eurasian Starlings のクレードに含まれる。検討種にも (2) South Asian/Pacific Starlings は含まれておらず熱帯のムクドリ類は相当留鳥性が高いよう。
[ムクドリ類の繁殖形態]
佐藤他 (2010) 高知県宿毛市におけるムクドリとギンムクドリの異種間つがいによる繁殖事例
[木村 (2009) Birder 24(3): 48-49 にも記事があり]、
續 (2019) 山梨県北杜市におけるムクドリとギンムクドリの異種間つがいによる繁殖例
が報告されている。
Nichols and Arbuckle (2022) A case of cooperative breeding in the European Starling, Sturnus vulgaris
に系統樹とともにホシムクドリの共同繁殖事例が報告されている。多くのムクドリ科が行うがホシムクドリではまれとのこと。
共同繁殖を行うかどうかは系統にかなりよく現れているとのことで、ヨーロッパや日本周辺のムクドリ類の系統は基本的に共同繁殖を行わない方の系統に属する。系統樹は古い学名が用いられているので旧 Sturnus 属を分割する必要性がわかりやすい。
共同繁殖を行う系統はアフリカの色鮮やかな Lamprotornis 属などに多い。
[ツキノワテリムクの社会性の研究]
日本の系統からは遠くどこに入れるか悩ましいが前項目に合わせてここに含めておく。東アフリカのツキノワテリムク Lamprotornis superbus Superb Starling の 20 年にわたるヘルパー行動の研究:
Earl et al. (2025) A cryptic role for reciprocal helping in a cooperatively breeding bird (オープンアクセス)。導入部分によれば鳥類・哺乳類の共同繁殖種の半数近くは血縁関係のあるもの・ないものが混ざった社会を作るとのこと。血縁個体を助けることで間接的に適応度 (包括適応度) を増す理論はよく知られているが、血縁関係にない個体を助けることもよくあり、共同繁殖社会の安定性に役立っているとの議論がある。
ツキノワテリムクにおいては長期の関係を結んだヘルパーのペアが役割を交代する (ヘルパー行動を行ったものが逆に助けられる方になる) ことが判明したとのこと。この行動の血縁性との関係を調べると血縁個体を助けることでヘルパー行動は間接的に適応度を増す効果が大きいと考えらえるとのこと (この点は従来の予測通り)。
ヘルパーのペアが役割を交代する行動はこれまであまり注目されてこなかった社会の安定要因となっているかも知れないとのこと。New Study Shows That Birds Form Bonds That Look a Lot Like Friendship (一般向け解説。よくありがちだが一般向け表題からは何を伝えたいのかさっぱりわからない)。
-
ムクドリ
- 学名:Spodiopsar cineraceus (スポディオプサル キネラーケウス) 灰色ムクドリ
- 属名:spodiopsar (m) 灰色のムクドリ (spodios 灰色の psar, psaros ムクドリ Gk)
- 種小名:cineraceus (adj) 灰色の
- 英名:(Grey Starling 旧名), IOC: White-cheeked Starling
- 備考:
spodiopsar は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-io- が2重母音でアクセントがあると考えれば "スポディオプサル" が自然な発音と思われる。
cineraceus は a が長母音でアクセントがある (キネラーケウス)。
Grey Starling の英名は長く使われていて学名に対応している。英名の改名の理由はよくわからなかったが、より "灰色のムクドリ" にふさわしい種があるなどの理由だろうか。
似た地域に生息するコムクドリの英名 (Red-cheeked Starling など。こちらは学名由来。現在の標準的英名は少し異なる) に対応する英名に統一された時代のものかも。
対応する英名を持つ種には シロガオムクドリ Sturnornis albofrontatus White-faced Starling がありムクドリ類の英名を整理する際に合わせたのかも。
またカラムクドリの別名に Grey-backed Starling (Myna) があり紛らわしいためだったのかも。
"灰色ムクドリ" に対応する名称を用いている他言語は多数ある。Avibase にはムクドリの別名にハクトウオウ (白頭翁) が登場する。「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によれば白頭翁の異名はヒヨドリにも使われたとのこと。
単形種。中国東部からロシア沿海地方、日本に分布。中国南東部に渡る個体もある。
ロシア沿海地方の繁殖の論文: Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the grey starling Sturnus cineraceus (pp. 317-341)。
-
シベリアムクドリ
- 学名:Agropsar sturninus (アグロプサル ストゥルニーヌス) ムクドリのような畑のムクドリ
- 属名:agropsar (m) 畑のムクドリ (agros 畑 psar, psaros ムクドリ Gk)
- 種小名:sturninus (adj) ムクドリのような (sturnus -i (m) ムクドリ -inus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Daurian Starling
- 備考:
agropsar は#コムクドリ参照。
sturninus は -inus の冒頭が長母音でここにアクセントがあると考えられる (ストゥルニーヌス)。
記載時学名 Gracula sturnina Pallas, 1776。基産地 Southern Dauria, between the Onon and Argun (Avibase による)。
同じ基産地で Sturnus dauuricus Pallas, 1778 (参考) の学名があり、こちらの方がムクドリらしい学名なのでこの学名が使われていたことがあったのかも知れない。そのように考えると英名の由来がよく理解できる。Dement'ev and Gladkov (1954) でもシノニムとして紹介されている。
Gracula 属もムクドリ類で現在ではキュウカンチョウがタイプ種 (#カワセミの備考参照)。
1776 年の記載も同じものと同定されて種小名が変わったと推定できる。
Gracula sturnina Pallas, 1776 は種小名に "ムクドリのような" を付けて "ムクドリのようなキュウカンチョウ" の学名だったが、Sturnus 属に一時統合されて先取権を考慮した結果 Sturnus sturninus と "ムクドリのようなムクドリ" と何を言っているのだと思えるような学名となっていた。
単形種。Daurian についてはコクマルガラスの項目参照。Agropsar 属のムクドリ類は長距離の渡りをするのが特徴。1羽のシベリアムクドリが朝鮮動乱で生き別れになった父子をつないだ実話に基づく物語として「アリランの青い鳥」(遠藤公男 1984 講談社。垂井日之出印刷所から 2013 年に復刊されている) が有名。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Daurian starling Sturnia sturnina (pp. 141-158)
ロシア沿海地方での繁殖。繁殖地の風景や巣箱利用など。
-
コムクドリ
- 学名:Agropsar philippensis (アグロプサル ピリッペーンシス) フィリピンの畑のムクドリ
- 属名:agropsar (m) 畑のムクドリ (agros 畑 psar, psaros ムクドリ Gk)
- 種小名:philippensis (adj) フィリピンの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Red-cheeked Myna, IOC: Chestnut-cheeked Starling
- 備考:
agropsar 外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。a-gro-psar と分解されるならば冒頭にアクセントがあると考えられる (アグロプサル)。
philippensis は場所を表す形容詞であれば -ensis の e が長母音でアクセントもここにある (ピリッペーンシス)。短音でも構わない。
"Fauna Japonica" では Lamprotornis pyrrhogenys Temminck & Schlegel, 1847 (記載) で登場。フランス語名 le lamprotorne a joues rouses。
pyrrhogenys は purrhos 炎の色の genus 頬 (Gk) でフランス語名にも対応する。
日本やボルネオで記録されると記載されている (従って Temminck の考えでは国名を学名に用いることができなかったと想像できる)。
英名に使われる Red-cheeked はこの学名由来と考えられる。
図版 の学名は本文と異なっていて Lamprotornis pyrrhopogon pogon はひげの意味 (Gk) (The Key to Scientific Names)。実は学名にはそれほどこだわっていなかった?
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Sturnia pyrrhogenys の学名で英名は Red-cheeked Starling だった。
この文献に過去の学名変遷経緯が詳しく、非常に多数の名前があったとのこと。philippensis が最初に現れたのは Brisson (1760) だったが二名法を用いておらず有効な学名でない (この時はノビタキの仲間と考えられていた)。
d'Aubenton は成鳥と幼鳥を描いているが前者をノビタキの仲間、後者をクロウタドリの仲間と考えたとのこと。
それぞれに別属の学名が与えられ Motacilla violacea Boddaert, 1783 (参考 フランス語名 le grand traquet des Phillippines、
Turdus dominicanus Boddaert, 1783 (参考) 参考にされたフランス語名 Merle Dominiquain des Philippines (Buffon) 英名 Dominican Thrush (Latham) とのこと。この dominicanus は国名の意味ではなく色彩を表すものと考えられる (#クロシロカンムリカッコウ参照)。
現在の学名の基礎となる Motacilla philippensis Gmelin, 1789 (参考) も付けられた。
Seebohm (1890) の記述を見ると年代的には Boddaert (1783) の学名に先取権があるように見えるが、Motacilla philippensis Forster, 1781 (参考) が存在して [この学名は Brisson (1760) の表記を短縮したもの] があり、
さらに古い用例が見つかったようで Motacilla Philippensis Pennant, 1781 (原記載。一覧表に現れる)
が最初のものとされて現在の学名となっている。
他にも属を変えて Pastor ruficollis Wagler, 1827 (参考) と命名されたものもあった。
Boddaert (1783) の violacea が残っていた可能性も高かったが、Temminck and Schlegel (1847) はかなり遅い時期でどちらにしても残らなかったと考えられる。
Seebohm (1890) の時期は先取権の扱いが現代と少し違っていたのか Temminck and Schlegel (1847) の学名を用いていた。英名に痕跡が残る形となった。面白いことに Temminck and Schlegel (1847) は過去の記載との比較を行っておらず、日本とボルネオからの新種記載となっている。
violacea は英語の過去の別名の Violet-backed Starling (現在は別のアフリカの種類を指して使われている) や中国語やデンマーク語名などに痕跡が残っている。このぐらい混沌とすれば国名を含めて何を用いるか悩みそうだが Temminck and Schlegel (1847) の記述的学名が優れていたので英名にはそのまま採用され続けているよう。
Temminck and Schlegel (1847) で用いられた Lamprotornis 属は Temminck (1820) が設けたもので、lamprotes 驚嘆すべき ornis 鳥 (Gk)。当時の学名を見ても属構成種が何かほとんどわからないが、後に判定されたタイプ種は オナガテリムク 現在の学名で Lamprotornis caudatus Long-tailed Glossy Starling で現在はこの種を含むクレードの属名となっている。
写真を見てもコムクドリとどのような点が似ているのか想像しにくい。
単形種。かつてはシベリアムクドリと同種とされた。
[コムクドリはなぜ日本の繁殖準固有種となったか]
EU403600.1 (シベリアムクドリの ND2) をベースに BLAST をやってみるとコムクドリとシベリアムクドリがまとまるがそれほど類似性が高くないことがわかる。
#ギンムクドリ備考の Lovette et al. (2008) の系統樹を見ると Agropsar 属 (2種のみ) と最も類縁度が高いのは Gracupica 属で中国から東南アジアに分布し、コムクドリとシベリアムクドリがこの2つの系統のうち渡りを利用して分布を広げたものと想像できる。
上記 BLAST の結果を見ると Gracupica 属より Agropsar 属に近い系統があってカンムリムクドリ Fregilupus varius Hoopoe Starling でマダガスカル東方のレユニオン島のみに生息していた絶滅種。
見かけはコムクドリやシベリアムクドリと大きく違うが 19 世紀中頃絶滅。
wikipedia 英語版の記述によれば害虫駆除のために持ち込まれたインドハッカ (これは世界初の生物導入による害虫駆除の試みの一つだったとのこと。当時の発想がわかる) との競争、持ち込まれたネズミ類があったが、外来ヘビによって食物を奪われたために最終的に絶滅したと考えられているとのこと。
コムクドリやシベリアムクドリの祖先の系統が分散能力を利用して島伝いに離島に定着し、独自の進化を遂げて特異な形態となったが人が持ち込んだ外来種によって絶滅させられたと言える。
類縁する絶滅属が知られている: Hume et al. (2014) Systematics, morphology, and ecological history of the Mascarene starlings (Aves: Sturnidae) with the description of a new genus and species from Mauritius。水深の低い時期に何度も定着したらしい。
ここで興味深いのはインドハッカとの競争が挙げられていることで、インドハッカが優勢な南アジアには Agropsar 属が進出することができず、ハッカ類の生息しない東アジアで細々と生き延びている印象を受ける。
Gracupica 属はもう少し分布を広げてインドにも生息するが、ホオジロムクドリ Gracupica contra Indian Pied Myna はインドハッカほど攻撃的でないとある (wikipedia 英語版)。
Agropsar 属、Gracupica 属ともにムクドリ類の中では比較的古く分岐した系統で、後に種分化を遂げて熱帯で競争力を強めたインドハッカを含む Acridotheres 属に対抗できなかったのではないかと想像できる。
ムクドリを含む Spodiopsar 属は Acridotheres 属以前に分岐した系統で、そこまで攻撃的ではなかったためコムクドリとも共存可能であった。
コムクドリが日本の繁殖準固有種となった経緯を考察してみたがいかがだろうか。
ホシムクドリがムクドリを駆逐してしまわないのも同様の系統順序を考えると理解できる気がする。
-
カラムクドリ
- 学名:Sturnia sinensis (ストゥルニア スィネーンシス) 中国のムクドリのような鳥
- 属名:sturnia (adj) ムクドリのような (sturnus -i (m) ムクドリ -ius (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:sinensis (adj) 中国の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:White-shouldered Starling
- 備考:
sturnia は sturnus, -ius が短母音のみのため (-inus とは異なる) 長母音は現れないと考えられる。"ストゥルニア" の発音でよいと考えられる。
sinensis は規則通り "スィネーンシス" のアクセント。短音でもよい。
記載時学名 Oriolus sinensis Gmelin, 1788 (原記載)。記載時学名ではコウライウグイスの Oriolus chinensis Linnaeus, 1766 と紛らわしかった (意味はどちらも同じ)。
単形種。
カラムクドリのジオロケータと安定同位体解析による渡り経路の研究: Dingle et al. (2025) Geolocator Tracking and Stable Isotope Analysis Suggest Mixed Migration Strategies in White-Shouldered Starlings (Sturnia sinensis)
香港のカラムクドリの個体群はベトナムやカンボジアに渡りを行い渡りパターンが2種類あるとのこと。
過去の標識記録からも冬に標識された個体が夏に見られない、夏に標識された個体は翌年以降も戻ってくることが知られていたとのこと。
-
バライロムクドリ
- 学名:Pastor roseus (パーストル ロセウス) バラ色の羊追い
- 属名:pastor (m) 羊追い バライロムクドリが集団でやってきた時、ヒツジの後を追って餌を探す行動から (The Key to Scientific Names)
- 種小名:roseus (adj) バラ色の
- 英名:Rosy Starling
- 備考:
pastor は冒頭が長母音でアクセントがある (パーストル)。
roseus は短母音のみで冒頭にアクセント (ロセウス)。
長く使われていた学名は Sturnus roseus でこの学名の時代には Rose-coloured Starling の英名がよく使われていたが短縮されて Rosy Starling となった。
英名は学名そのまま。和名も現在の英名以上に類似性が高く、おそらく当時の英名をそのまま訳したものと想像する。
記載時学名 Turdus roseus Linnaeus, 1758 (原記載)。
興味深いことに生息地はラプランドと現在はスイスに相当する地名。現在の通常分布から大きく離れているが大丈夫か (?)。
単形属。単形種。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。Lovette et al. (2008) (#シベリアムクドリの備考参照) ではこの種(属)は非常に放浪的な生活様式を示し、食物量の変化に応じて西から中央アジアを広く移動し、そのため侵入的渡り (irruption) が起きる。インド半島で越冬するとある。
トルキスタン地方では害虫駆除に役立って「神の鳥」とも言われるが、果樹園などで作物を食害することもある (コンサイス鳥名事典)。
中国新疆 (西部) で人工的に「アパート」風の巣塔を用意して害虫駆除に役立てているとのこと: (バライロムクドリ) (2018)
新疆の農牧民族は害虫を駆除する能力からさまざまな名前で呼んできたとのこと。「トルキスタン地方」にはここも含まれているので「神の鳥」に相当する名称もあるかも。
(解説動画) アパート風の巣塔なども見られる。
-
ホシムクドリ
- 学名:Sturnus vulgaris (ストゥルヌス ウルガーリス) 平凡なムクドリ
- 属名:sturnus (m) ムクドリ (stella (f) 星) 小さな星斑から)
- 種小名:vulgaris (adj) 平凡な、ありふれた
- 英名:Common Starling
- 備考:
sturnus は "ストゥルヌス"。
vulgaris は a が長母音 (-aris に由来) でアクセントもここにある (ウルガーリス)。
Sturnus vulgaris は Linnaeus (1758) の与えた学名そのままで、種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指したものではない (#ノスリの備考参照)。
世界に 13 亜種が認められている (IOC)。日本で記録される亜種は poltaratskyi (ロシアの Vladimir Alexandrovich Poltaratsky 由来。シベリアなどを探検した) とされる。
ホシムクドリと直接の関係はないが、世界的に有名な侵略的外来種となっているインドハッカ Acridotheres tristis Common Myna のゲノム研究: Atsawawaranunt et al. (2024) Parallel Signatures of Diet Adaptation in the Invasive Common Myna Genome
複数回の導入に伴い AMY2A 遺伝子まわりで独立の変異が見られた。人や犬の食べ物に多く含まれるデンプンへの適応に伴うと考えられるとのこと。同様の変異はイエスズメにも見られるとのこと。
食物となる人の食べ物への (遺伝レベルの) 適応も侵略的外来種となる基盤となっているのかも。
△ スズメ目 PASSERIFORMES カワガラス科 CINCLIDAE ▽
-
カワガラス
- 学名:Cinclus pallasii (キンクルス パルラスィイ) パッラスの尻を動かす鳥
- 属名:cinclus (合) 尻を動かす鳥 (kino 動かす Gk、culus (m) 尻); kinklos (Gk) アリストテレス他の記述した尾を振る鳥。セキレイやシギなどが提案されているが未同定
- 種小名:pallasii (属) pallas の (ラテン語化 -ius を属格化) プロイセンの生物学者 Peter Simon Pallas
- 英名:Brown Dipper
- 備考:
cinclus の発音はよくわからないが起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる (キンクルス)。
pallasii は pal-la-si-i と分割すれば -la- にアクセント (パルラスィイ)。
記載時学名 Cinclus Pallasii Temminck, 1820 (原記載) 基産地はなんと Crimea = Eastern Siberia fide Hartert, 1910 (Avibase による)。
Pallas のクリミア滞在中に送られてきた標本から Temminck が速報的に新種のカワガラス類として報告したもののよう。クリミアに生息すると "推定できる" と結構怪しい推測。
生息地が誤って記述されていたためか、Cinclus maculatus Hodgson, 1844 (参考。Cinclus Pallasii の若鳥か、の解釈が出ていた。当時は "クリミア" の東側ではどこまで分布しているかわからなかった) がネパールで得た標本を用いた学名もあった。こちらは "斑点のある" の意味。
亜種は pallasii。他に2亜種あり、中央アジアからヒマラヤ、東南アジアに分布。複数亜種が認められるので Pallas がどこで見つけたものか基産地を特定しないといけないが、Avibase の記述を参考にすると Hartert が東シベリアと決めたよう (同じ時期の Pallas の標本などから地域を推定したのだろうか)。
ヒマラヤの亜種は tenuirostris Bonaparte, 1850 (記載) とされ Hodgson (1844) の記載の方が早いので先取権があってもよさそうだが無効として処理されたものと思われる。
この記載を見ると Pallas 自身はカワガラスを Sturnus cinclus (ヨーロッパのムナジロカワガラスの当時の学名) の var. (変種。現在では Pallas の var. は亜種記載と認められる) として記述していたらしいことがわかる。Pallas 自身が名称を付けていて現代の記載年代の解釈ならばこちらにカワガラスの学名の先取権があったと思われる。
この文献によれば Cinclus Pallasii の名称 (有効な学名とはされていない) は Vieillot も用いていて、こちらは現在の tenuirostris に対応して中央アジアとのこと。このような複雑さもあって Hartert が東シベリアと決めたものと考えられる。
Gould の図版があって成鳥と若鳥が出ているが、記述されているようにヨーロッパ産ではなくシベリアと日本に生息するとこの時点で判定されていたよう。
Cinclus Asiaticus Swainson, 1831 (参考) 基産地インド の名称もあった (ただし無効とのこと) ようで旧英名の Asian Dipper, Asiatic Dipper はこの名称に対応と考えられる。
メキシコカワガラス (現在の学名で Cinclus mexicanus American Dipper) の別名 Cinclus Americanus Swainson, 1831 (参考) American Dipper に対応させたものと想像できる。アメリカカワガラスの別名もあって分布からはこの名称の方がふさわしい。
Swainson はメキシコで記載されたものと違うと考えていたようだが却下されたと記述がある。
アジアにはムナジロカワガラスも生息するため Asian Dipper, Asiatic Dipper は適切な英名でないと変更されたものが現在の英名由来だろう。北米から見ていた時代はインドで記載されたものは Asian / Asiatic が適切に見えたということだろう。
Hydrobata 属 (hudro- 水 bates 歩く Gk) は Vieillot (1816) が導入したもので属変更とともにムナジロカワガラスの学名を Hydrobata albicollis と変更していた (The Key to Scientific Names) (#ノスリの備考参照)。
これに対応する英名もあり (どちらが先からはわからないが) White-breasted Dipper (-collis は本来は首の意味だがのどや胸を指すこともあって英語では -breasted も多く使われる)。
日本のカワガラスに比べて色彩からムナジロカワガラスとなったのかと思っていたが、このようにみると英名由来の可能性が高く見える。
属名は Bechstein (1802) の Cinclus の方が早かったためこちらが使われるようになった。Bechstein も Cinclus aquaticus Bechstein, 1800 (参考) の新名を与えていた (属の記載の方が後になった)。
しかし Accentor aquaticus Bechstein, 1797 と一度はイワヒバリ類と考えていたことがわかる。この用例を見ると種小名を属に昇格するに際して直接与えられたものではなかった。
ムナジロカワガラスの種小名は Linnaeus が最初に付けた cinclus に戻された経緯となる。1902 年以降にこの種小名を用いた亜種記載が複数あり、この時代に戻されたものと推定できる。
日本国内でも複数亜種が記載されていた:
・Cinclus pallasii hondoensis Momiyama, 1927 (参考 1, 2) 基産地 near Imachi, Prov. Schimotsuke, Hondo
・Cinclus pallasii hiugaensis Momiyama, 1927 (参考 1, 2) 基産地 Koyu-gun, Prov. Hiuga, Kiusiu
・Cinclus pallasii itooi Momiyama, 1927 (参考 1, 2) 基産地 Kawaguchi, kagami-mura, Prov. Tosa, Shikoku
Kuroda (1932) が hondoensis に統一したがその後さらに基亜種のシノニムとされたことになる。
Dement'ev and Gladkov (1954) では hondoensis を認めており北海道までこの亜種、サハリンや南千島は基亜種としていた。
カワガラスの和名は素直な名称に感じるが、さすがにカワガラスを飼い鳥とする者はあまりいなかったのか古い飼育書にも名前が出てこない。意外に新しい名前なのかも。
[カワガラス類の潜水適応]
カワガラス類はスズメ目で唯一潜水するグループだが、翼を推力をしている。潜水する水鳥ほどに体の他の部分の大きな変化はないがいくつかの点で収斂進化が見られる: Smith et al. (2022) Convergent evolution in dippers (Aves, Cinclidae): The only wing‐propelled diving songbirds。
他の潜水する水鳥同様に尾が短く水の抵抗を減らすためと考えられる。
皮膚も厚く皮下脂肪も多い。断熱のためと考えられる。
カワガラス類全般に鼻孔は narial flap または羽毛に覆われていて水が入るのを防いでいる。narial flap は角化した rhamphotheca (嘴を覆うケラチン層) からできている。嘴を覆う構造から発達した鼻の「ふた」があると言ってよさそう。
他の潜水鳥についても言及があり、ウミスズメ類の多くは鼻孔が短い密生した羽毛で覆われ、ツノメドリ類ではスリット状の鼻孔になっている。ペンギン類の大部分では rhamphotheca が成長途中で鼻孔を覆ってしまい、鼻孔が開いているのは少数の系統に限られる。
潜水するミズナギドリ類では管状の鼻の開口部が小さく前よりむしろ横を向いている。
全体的に潜水する水鳥ほどの大きな特殊化がないのは比較的最近生じた系統のためではないかとのこと。
[越冬地でも繁殖するムナジロカワガラス]
カワガラスは渡りをする印象を受けないが、ヨーロッパのムナジロカワガラス Cinclus cinclus White-throated Dipper のスカンジナビア個体群は冬に越冬地繁殖も行うという (#キタヤナギムシクイの [渡りと換羽戦略] 参照)。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ヒタキ科 MUSCICAPIDAE ▽
-
マミジロ
- 第8版学名:Geokichla sibirica (ゲオーキクラー シビリカ) シベリアの地ツグミ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Zoothera sibirica (ゾオテラ シビリカ) シベリアの虫を狩る鳥
- 第8版属名:geokichla (合) geo- 地面 kikhle ツグミ (Gk)
- 第7版属名:zoothera (合) 虫(動物)を狩る鳥の (zoo- (接頭辞) 動物 thira 狩り Gk)
- 種小名:sibirica (adj) シベリアの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Siberian Thrush
- 備考:
geokichla は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は ge- と kikhle の末尾が長母音のため、これらが長母音となるのが自然と思われる。-i- を含む音節が子音で終わると解釈できるならば "ゲオーキクラー" のアクセントとなると考えられる。
sibirica は短母音のみで -bi- にアクセントがある (シビリカ)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Geokichla 属 (geo- 地面 kikhle ツグミ Gk) となる見通し。世界のチェックリストでも同様。
Geokichla 属や Catharus 属は他の多くのツグミ類の属する Turdus 属より古く分岐したと考えられている。
亜種 davisoni (英国鳥類学者 William Ruxton Davison 由来。Hume のために収集を行ったなど) と基亜種 sibirica が認められており、日本鳥類目録改訂第8版では前者を亜種マミジロとしている。また亜種不明が含まれている。
かつて朝鮮半島で記録されたシベリアマミジロの名称があった。
種記載時学名 Turdus sibiricus Pallas, 1776 基産地 Siberia [= Konda River, Transbaicalia, vide Pallas, ibid., p. 186] (Avibase による)。
亜種 davisoni の記載時学名は Turdulus Davisoni Hume, 1877 (原記載) 基産地 Mooleyit, Tenasserim (Mount Mulayit 現在のタイ)。
Hartert (1910-1922) では p. 644。次ページに davisoni がある。Hartert は後者の亜種が日本で繁殖し、冬にはビルマや Tenasserim (ビルマ・タイの国境からインドシナ半島の高地) に渡ると記述している。
シベリアマミジロは現在の目録に現れないので正式な標準和名ではないだろうが、かつてはおそらく基亜種 sibirica を意図していたと考えられる。山階鳥類研究所の標本データベースでも済州島の標本にシベリアマミジロの名前が現れる。
Dement'ev and Gladkov (1954) では基亜種 sibirica が日本とサハリンを除くほとんどの分布域に分布し、インドや中国西部、インド-中国、スマトラで越冬するとある。ロシアから見ると "島の亜種" (ロシア語名ではサハリンのマミジロに対応) と捉えられていた模様。色彩が多少違うとのこと。ロシアでは大陸の対する島の亜種または種の扱いが他の種でも多くみられる。
Dement'ev and Gladkov (1954) では日本では春の到着は遅く 5/8-14、秋は9月にすでに渡去すると記述されていた。今では春の到着はわずかに早くなっている程度 (?) で今でもあまり違わないかも。
マミジロの亜種があまり話題にならないのは (離島では話題になっているかも)、日本で渡り時期に出会える地域では時期がサンコウチョウと重なって本命になりにくいためかも知れない。またそれほど違いのある亜種とみなされていないかも。
大陸とどの程度違いがあるのか AB843845.1 (COI) から BLAST を行ってみると韓国のサンプルのミトコンドリアゲノムとは若干の違いがある (一致率 99.1%)。大陸や越冬地で広くサンプルされている段階ではないが亜種扱いが妥当程度の違いはあるかも知れない。さすがに別種相当にはなりそうにない。
マミジロの高い地鳴きは日本の他の (一般的な) ツグミ類と異なり、まるでアオジの地鳴きのように聞こえる。これも系統の違いを反映したものと思えるが、季節外れのアオジのような地鳴きを聞いた時はマミジロも考察の対象となるだろう。なお春の渡りでこのような季節外れのアオジはノジコの渡り時期にもあたり、マミジロの渡りとも重なる。"季節外れのアオジ" はいずれの時期も要注意。
参考例では XC752867 (Ray Tsu 2022.9.30) の中国の音声記録。姿は観察されていないが多分大丈夫だろう。もう少し長いツグミ類的な地鳴きもあるが、このようなホオジロ類を想像してしまう地鳴きもある。音声面では聞いた範囲ではあまり違いを感じないが、大陸とは亜種レベルで違っている可能性がある。
-
トラツグミ (日本のリストでは亜種の一部がミナミトラツグミに分離。海外ではオオトラツグミは独立種)
- 第8版学名:Zoothera aurea (ゾーオテーラ アウレア) 金色の虫を狩る鳥 (IOC と部分的に同じ)
- 第7版種学名:Zoothera dauma (ゾーオテーラ ダウマ) 虫を狩るツグミの一種
- 第7版亜種学名:Zoothera dauma aurea (ゾーオテーラ ダウマ アウレア) 金色の虫を狩るツグミの一種 (代表的亜種。他亜種あり)
- 属名:zoothera (合) 虫(動物)を狩る鳥の (zoo- (接頭辞) 動物 theras 狩るもの < therao 狩る Gk)
- 第8版種小名:aurea 金色の
- 第7版種小名:dauma (合) Dama(ベンガル地方でオレンジジツグミ Geokichla citrina); ヒンディー語で Dauma チャイロイワビタキ Oenanthe fusca。トラツグミに関係する現地名は特にないらしい (The Key to Scientific Names)
- 第7版亜種小名:aurea 金色の (代表的亜種。他亜種あり)
- 英名:White's Thrush
- 備考:
zoothera は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は zoo- の冒頭の o が長母音、-theras の e も長母音のため対応する母音を長母音とするのが自然と考えられる。その場合アクセントもこの位置になる (ゾーオテーラ)。
aurea は短母音のみで冒頭にアクセントがある (アウレア)。
dauma は外来語で発音は不明だが短母音のみであれば "ダウマ" となる。
英名の White は英国博物学者 Gilbert White (ギルバート・ホワイト。「セルボーンの博物誌」が有名) に由来とのこと。
この White を冠した学名があり Turdus whitei Eyton, 1836 (参考 英国 Hampshire で記録とのこと)、Temminck and Schegel の "Fauna Japonica" ではこの学名で紹介されている。
分割のため第7版学名は代表的亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で単形種 Zoothera aurea (種小名は「金色の」の意味) となる。
[トラツグミの新学名は Zoothera aurea か Zoothera varia か?]
かつての Zoothera dauma が分割される以前、
Dement'ev and Gladkov (1954) ではシベリアから日本 (九州まで) の亜種に Turdus dauma varius (Pallas, 1811) を与えられていた。現在の亜種名 (そして新学名で種小名となる) aureus Holandre, 1825 は varius のシノニムとして扱われていたようである。
日本の旧トラツグミに相当するものはロシアのチェックリストではしばらく前までは Zoothera dauma (日本鳥類目録改訂第7版の概念と同じ) とされていたが、Zoothera dauma が南アジアの種として分離される際に Turdus varius を有効な学名と認め、Zoothera varia としている。
Pallas の記載は
Turdus varius
に載せられている (この出版物は 1831 年)。
この経緯は非常に複雑なようで、Links to digitized versions of original sources of bird names
(2016) laurent raty による説明がある。Zoographia rosso-asiatica の出版年が問題とされ、図版を除いて全3巻のうち最初の2巻は 1811 年に出版された (鳥はこの部分に含まれる)。Pallas は生前に図版も含めたいと考えていて版画師に依頼していた。そのためこの年にはごく小部数が印刷されたにとどまった。
図版が欠落しているものも多かったが多数部が印刷されたのは 1811-1831 年の期間で、動物学者の一部はその期間に Pallas の仕事をすでに知っており、その学名を一部使っていたが Zoographia rosso-asiatica の正確な出版年の問題が残り、Opinion 212 of the ICZN (国際動物命名規約) で 1954 年に Zoographia rosso-asiatica の最初の2巻の出版年が 1811 年と決められた。
この結果 Turdus varius Pallas, 1811 が Turdus aureus Holandre, 1825 よりも先取権があると決まった。Dement'ev and Gladkov (1954) の学名はこれに基づいていると思われる。
しかしながらこの学名は Vieillot, 1803 がオーストラリア頭の黒いツグミ類に似た種にすでに用いており、無効な学名と判定された。
Zoothera aurea
にも無効の記載あり。
Zoothera aurea とするのが正しく、現在のロシアのチェックリストの学名は正しくないようである。
一部の記載で Turdus varius Pallas, 1831 の方が記載が遅いためとの理由をうかがわせるものがあるが、少なくとも 1954 年以降はこの説明は正しくない
(Vieillot, 1803 がすでに使用していたことが知られるようになったのはいつの段階かはわからないが)。
Turdus varius White's Thrush の名称は古い文献に出てくるので注意しておく価値はありそうである。またロシアの文献を学名検索する場合は Zoothera varia も使う必要があるので経緯を知っておいて損はない。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) によれば英語別名に Golden Mountain Thrush が挙げられており、この Golden は aurea 由来と考えると納得できる感じがする (使われていた学名は分離前のものだった)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" に別名 Nuyejinai が挙げられており、これは鵺 (ぬえ) が由来か?
[亜種と分類]
問題を複雑にするのは日本のトラツグミに亜種があることで、特に奄美大島のオオトラツグミは、尾羽の枚数が 12 枚でトラツグミの 14 枚と異なり、さえずりも異なることから独立種とする考えが以前よりあった。
「山溪ハンディ図鑑 日本の野鳥」(初版 1998) では亜種トラツグミとオオトラツグミとの野外識別は鳴き声以外ではできないとの記載があった。この図鑑では亜種名に amami を与えていた。また西表島にはコトラツグミ Zoothera dauma horsfieldi が生息するといわれているが、近年では未確認、と記している (しかし後の解説参照)。
オオトラツグミに対する亜種名 amami は日本のレッドデータブック英語版 (いつのものか書かれていない) でも使われ、Turdus dauma amami White's ground thrush (Amami-oshima subspecies) と記載されている (ちなみに日本語版 2020 では Zoothera dauma major となっている)。
一時期は Hertert (1921/1922) が尾羽 12 枚を記載して与えた亜種名 amami が使われていたようである。
Turdus dauma amani Hartert, 1922 参考
この資料によれば Turdus major は Brehm (1831) がすでに使っているので使えない学名とのことで与えたものらしい。
さらに早い用例があり Turdus major Forster, 1817 (参考) ヤドリギツグミの新名として与えられたもの。Turdus major Brehm, 1828 (参考) はドイツの鳥のリストに出てくるだけで無効としている。
Turdus major Brehm, 1831 (参考) によればドイツの鳥で Brisson の名称由来。
Hartert (1910-1922) p. 643 ではまだ指摘されておらず、Turdus dauma major (Ogawa) の学名を用いていた。
すなわちトラツグミが Turdus 属に含められていた時代には major の学名は有効でなく amami が用いられていたと考えられる。
記載時は Geocichla major Ogawa, 1905 (原記載) 基産地 Amami-O-Shima (奄美大島) で衝突していなったが、属の統合が行われてツグミ類をまとめて Turdus 属とした時代に衝突した次第。ツグミ類の分類は意外に奥が深い。
コンサイス鳥名事典の段階では Turdus 属で amani が用いられていた。当時一般的に用いられていた学名と考えられる。英名の Amami Thrush もこの学名に関連があるのかも。
その後分類変更で Zoothera 属となった時もしばらくは過去の経緯が盛り込まれておらず amani が用いられていたと想像できる (東洋のツグミ類で欧米研究者もおそらくあまり気にしていなかったかも)。
属が変わって衝突が回避された場合に一度 preoccupied となった学名を戻すかどうかは事例によって違うようで、このあたりもオオトラツグミの扱いの難しさに関係しているのかも知れない。
つまりオオトラツグミの学名はある程度分子系統解析次第で、Zoothera 属と Turdus 属が分離されていれば major は活かせて Ogawa (1905) の学名が有効とできるが、そうでなければ Hertert (1921/1922) の方が有効になる可能性もあり得るのか (詳しい規則は知らない)。
#ヒヨドリ に登場する "1961 年以前に改名されたものは復活させない規則" との関係はよくわからない。
そのような視点で分子系統研究を探してみると思ったほど新しいものがない。Voelker and Klicka (2008) Systematics of Zoothera thrushes, and a synthesis of true thrush molecular systematic relationships。
従来使われていた Zoothera は単系統でないので一部の種のサンプルでどの程度多系統なのかを明らかにする。
Geokichla 属の方がむしろ調べられていて Voelker and Outlaw (2008) Establishing a perimeter position: speciation around the Indian Ocean Basin。
このためか Boyd も Zoothera 属の系統樹を示していない。
形態が大きく違うことなど Zoothera 属が Turdus 属に再併合 (ツグミ属の逆襲!? - ご存じでない方もおられると思われるので参考までに Birder 2023 年 11 月号タイトルが "ツグミ科の逆襲" だったため) されることは多分なさそうに見える。
なお Zoothera 属のタイプ種は オオハシツグミ Zoothera monticola Long-billed Thrush で、将来の研究で Zoothera 属がもし分割されればトラツグミの属名が変わる可能性もあり得る (分離されても major の衝突の心配はない)。
Li et al. (2020) The complete mitogenome of scaly thrush Zoothera aurea (Passeriformes, Turdidae)
にトラツグミのミトコンドリアゲノム解読の論文があり、Turdus 属への統合は心配しなくてもよさそうに見える。Weir (2018) が複数種に分かれることを示唆しているものの、トラツグミそのものの遺伝情報はほとんどわかっていないとある。
近年は属の細分化しすぎ (多くの場合は単系統性の要請から行われている)、との声もしばしば聞かれるが、過去の Turdus 属に関しては分割してもらった方が問題点が少なくなり、統合されていた時期は日本の鳥学者にとっては冷や汗ものだったのかも知れない。
詳しい規則を知らないことを前提に見ていただきたいが、仮想的に考えると (分類は日本鳥類目録改訂第8版に従ったものにした。独立種とする場合は種小名部分を削除して亜種小名を種小名に)、(オオ)トラツグミを Turdus 属とする場合は 、
Turdus aureus amami Hartert, 1922
Zoothera 属とする場合は、
Zoothera aurea major (Ogawa, 1905)
となると推定される。前者の場合は発見者である価値は失せないだろうが学名記載に現れなくなるなど何かと不都合そう。"1961 年以前に改名されたものは復活させない規則" がもし適用されるならば違った結果になるかも知れないが、このような点には最も詳しいはずの H&M が後者 (ただし独立種) を採用しているのでおそらく大丈夫なのでは?
当時は別属扱いだったのだから Ogawa (1905) の用いた major が保護される意味があるのでは、と考えることもできるが、先取権の規則を悪用して意図的に別属に入れることも可能なので公平を期すために上記のような規則が採用されたのだろう。
同じような事例でズアカアオバトの亜種名の重複を見抜いて自身が亜種名を付けた Hachisuka (1952) の事例 (#ズアカアオバト備考の [和名の由来] 参照) があるので公平性を重視するならばやむを得ないのだろう。
現代の海外のリストの多くでは奄美大島のオオトラツグミを Zoothera major (種小名は「大きい」の意味) (英名 Amami Thrush) として扱っている。少数のリストが Zoothera dauma の亜種としていた (Clements 2018 年まで、しかし 2019 年に独立種。eBird 2018 年まで、しかし 2019 年以降独立種。HBW 2015 年まで、2017 年以降独立種)。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では独立種としているが "Treatment as a species apart from Z. aurea and Z. major remains tentative" とある。
ここでは暫定的に独立種として扱うがまだ決定的な結論が出ていないと読めばよいだろう。
Working Group Avian Checklists は当初より Zoothera major を用いており、世界のリストはおそらくすべて別種扱いに統一されると思われる。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Zoothera dauma の亜種とし、トラツグミが独立種との扱いになって (しかし以下参照) この種の亜種ではなくなったため、Zoothera dauma にミナミトラツグミの新称を与えている。この扱いによれば和名はミナミトラツグミの亜種オオトラツグミという名称になる。この名称をすでに取り入れている図鑑も存在する。
しかしながらこれは世界の趨勢とは異なった扱いである。eBird のミナミトラツグミには奄美の個体群は含まれていない。eBird のオオトラツグミのように独立種として扱う方が問題が少ないであろうし、国内で受け入れられやすいと思われる。日本鳥類目録第8版ではオオトラツグミを独立種として扱っていない。
この見解は後述 Nishiumi and Morioka (2016) によっていると考えられる。この後に後述 Weir (2018) の見解が発表され、西海 (2021) Birder 35(10): 36-37 の記事はここまでを踏まえたものになっていると思われる (この項目の記載経歴の関係で一部後の部分と重複があるがご了承いただきたい)。
Zoothera aurea に亜種を認める立場もある。Clements によれば日本と「満洲」(Manchuria、地理的には中国東北部だが極東ロシアも含んだ意味で使われているかも知れない) で繁殖し、
台湾や蘭嶼島で越冬するものを亜種 toratugumi (Moriyama 1940) としており、亜種 aurea をシベリアから満洲、朝鮮半島で繁殖して中国からインドシナで越冬するものに与えている (この場合は日本はシベリアと別亜種の扱いになる)。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) でも亜種を認めており、亜種 toratugumi の繁殖域をロシア極東、サハリン、千島列島、日本、朝鮮半島としている。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023) では日本はシベリアの亜種の違いを認めていない扱いになる。他に亜種 hancii も提唱されたが (Swinhow 1863)、これは現在ではほとんどの場合 aurea のシノニムとされる (越冬期のインドシナで記録がある)。
もし Zoothera aurea に亜種を認める立場であれば、トラツグミは亜種まで含めた記載で Zoothera aurea toratugumi となる。日本鳥学会のリストには現れないかも知れないが、文献など (特に越冬地などで) では使われる可能性があるので念頭に置いておいてよさそうである。
Vaurie (1955) Systematic notes on Palearctic birds. No. 15, Turdinae, the genera Turdus, Grandala, and Enicurus
に考察があり (いずれも当時の学名)、Portenko が亜種 exorientis をウスリーの Sputinika 川を基産地として記載した。基亜種 aureus よりも小型であるとしたが、Momiyama が亜種 toratugumi をすでに記載 (基産地四国) しており、exorientis はそのシノニムとの判断を示した。
toratugumi を亜種と認める可能性はあるが Vaurie と Johansen が測定し比較したがウスリーの個体の計測値は toratugumi に近いもので、一方 Yamashina (1939) が満州で採集記述した個体は 基亜種 aureus に近いとのことで結論は持ち越している。
過去の文献ではかつてこれらがすべて広義のトラツグミの亜種だった時代、「亜種 horsfieldi が台湾やタイ、ベトナムに属するが西表島からの記録もある」(コンサイス鳥名事典) と記載されていた (Kuroda 1925)。「山溪ハンディ図鑑 日本の野鳥」にもあるように、一時は西表島の生息状況は明らかでないと記載されていた。
Nishiumi and Morioka (2016)
A New Subspecies of Zoothera dauma (Aves, Turdidae) from Iriomotejima, Southern Ryukyus, with Comments on Z. d. toratugumi が示しているように、西表島で1936年7月にまだ幼羽に残るに似た成鳥の標本が採集されたことから、繁殖していることは疑いないとしている。
この論文で記載された亜種 iriomotensis では尾羽が 14 枚 (ホロタイプでは1枚欠損で 13 枚) で、オオトラツグミ (分類概念は必ずしも明確でなく後の音声研究も参照) の亜種ではないと考えてよさそうである。
日本本土のトラツグミに比べて小型であり、この点は本土のトラツグミよりも台湾の繁殖個体に似ている (この文献では Z. d. horsfieldi としているが、Z. d. dauma とする立場も述べられている。次項の台湾での解釈も参照)。
この論文では Kuroda (1925) ではなされていなかった台湾個体との色調などの比較も含めて、新亜種 Zoothera dauma iriomotensis (名称は西表が由来) 和名コトラツグミとして記載した。この論文では Zoothera aurea の亜種についても考察を行っており、亜種 Z. a. toratugumi は形態学的には大陸のものと区別する必要はないと考えている。
亜種コトラツグミが属するとこの研究から考えられる種 Zoothera dauma の和名を与える必要があり、ミナミトラツグミの和名を導入することは避けられないと思われる。ただし台湾の繁殖個体群は大陸の分布からかなり離れているため、別の分類群になる可能性もありそうである。
この論文では音声のことは触れられていないが、Zoothera dauma dauma のインド個体は一般的なツグミ類のようなさえずり記録がある。台湾の個体では日本のトラツグミのようなヒーのさえずりが記録されている (繁殖期のもので越冬個体のさえずりではないと考えられる)。
いずれも例数が非常に少ないが、台湾の個体はむしろ Zoothera aurea に近い可能性もあるかも知れない。この記述は以下の Weir (2018) を知る前に書いたものだが、ほぼ同じような結果となっている。
西表島でのさえずり録音や台湾個体との音声比較なども望まれる。
コトラツグミの和名由来は日本産鳥類の新和名及学名訂正 (Kuroda 1915)。当時は亜種 horsfieldi を指し、迷鳥? とある。
齋藤・田仲 (2019) Birder 33(4): 72-73 にインタビュー記事があり、オオトラツグミについても言及がある。齋藤氏も海外分類と同様にオオトラツグミを独立種とするのが適切との考えであるが、一般的に広まらないのは論文が出ていないためではないかと推察している。トラツグミ類は分布が広く亜種も多いので網羅的研究が難しいとのことである。
台湾の研究によれば [Chen et al. (2017) Breeding behavior and nestling diet of Zoothera dauma dauma in Taiwan]、
台湾では、Clements に従って留鳥の Zoothera dauma dauma と日本から冬鳥の Zoothera aurea toratugumi および ロシアから冬鳥の Zoothera aurea aurea と使い分けている [出典は Lin (2014, 2016) とのこと]。
亜種 horsfieldi (この文献では Zoothera dauma の亜種としている) はスマトラ、ジャワ、小スンダ列島の亜種としており、「コンサイス鳥名事典」の時期の記載とは異なっている。
過去に台湾の「小虎鶫」(中国語名) は horsfieldi あるいは hancii とされたことがあった
[Lin et al. (2016) First measurement of the nest of Zoothera dauma dauma in Taiwan; 台湾の「小虎鶫」について詳しい]が、(冬鳥の) Zoothera aurea toratugumi と Zoothera aurea aurea と混同されてきたとのこと。
この論文では「小虎鶫」は Zoothera dauma dauma としている。これらの記述を総括すると、日本で過去に亜種 horsfieldi とされたものは、当時台湾で「小虎鶫」と十分に区別されていなかったトラツグミ類を指していたのではないかと思われる。
比較的新しい資料では This is White's Thrush の記述が役立つのではないかと思われる。Jerome Chie-Jen Ko の 2023.3.13 の説明では当時台湾のチェックリスト作成に当たって台湾のトラツグミは Zoothera dauma dauma のまま据え置く判断となったとのこと。
しかし個人的には明らかな繁殖個体であるこの音声は Zoothera aurea の方に非常によく似ている。
投稿の際は Zoothera dauma dauma が用いられたが、音声記録のラベルは Zoothera aurea に変更されたままとされている。
世界の鳥の音声についての専門家である Shaun Peters のコメントによれば台湾の状況は複雑で繁殖個体群に対して記載された学名 (available name) がまだ存在しないとのこと。分類不詳のため台湾の記録には Zoothera dauma と Zoothera aurea の両者が混在することになっている。
IOC は越冬個体群に Zoothera aurea を与えているのみとのこと。
台湾で実際に録音を行っている Ko の見解を参照しても台湾でトラツグミに出会ったとしても "ミナミトラツグミ" (特に亜種 iriomotensis) に出会ったとは言い切れないと考えられる。ミナミトラツグミとする見解であっても台湾のリストと亜種の扱いが異なる。
台湾の繁殖個体群は現在までの情報からは次の Weir (2018) のように未記載亜種と考えるのがやはり適切でないだろうか。
音声を主に扱う分野では明らかに音声の異なる個体群を便宜的に ssp. nov.? (新亜種?) のように表現することもよく行われていてこの場合それに該当するかも知れない。どちらの亜種にするかの問題も残りこの表記が積極的に用いられていないのかも。
[広義トラツグミは何種に分かれる?]
ここまで挙げた分類の検討は従来の広義トラツグミが2種に分割されることが前提になっている。
日本の繁殖個体を含む北方型 Zoothera aurea と南方型 Zoothera dauma に分かれると考え、後者にミナミトラツグミの新和名を与える。そして奄美黄島付近が南方型の北限と考える分類である。
しかしながら音声研究の結果はそれほど単純なものでなさそうである。
Weir (2018) Description of the song of the Nilgiri
Thrush (Zoothera [aurea] neilgherriensis) and song differentiation across the Zoothera dauma species complex
がインドの亜種 neilgherriensis の音声初記載を含め、既存の広義トラツグミの音声分析を行っている:
(1) 単純な口笛のような音声のグループで北方の aurea, toratugumi (日本本土のものはここに含めている)、および未記載の台湾の繁殖個体群
(2) 中国から東南アジア大陸部の dauma グループで北方のものと同様にさえずるが音域が広い (この文献で初記載)
(3) 音程が下がる口笛のような音声で熱帯の留鳥 imbricata (スリランカ)、horsfieldi (インドネシア)
(4) 複雑な声で歌うヒマラヤの dauma、インドの neilgherriensis、日本のオオトラツグミ major
に分けている。インドの neilgherriensis はヒマラヤの dauma の亜種にするか独立種とするべきと考えられるが、データが不十分で別種とすることが難しい現状では暫定的に dauma の亜種扱いを提唱している。
iriomotensis は現在情報がない。
複雑な歌を持つ dauma の範囲をヒマラヤに限定すればオオトラツグミ major とその周辺に分布する分類群との違いは一層際立つ。
ツグミ類は複雑な声でさえずる方が普通で、単に「複雑な」では同種の根拠にならないだろう。ヒマラヤと遠く離れた奄美は連続的につながった分布と考えるより音声面から独立種が妥当に思える。
明らかに違ったさえずりを持つ個体群は分子系統解析でも別種となるのが通例で (例えばエゾムシクイとアムールムシクイなど)、さえずりの違いが生殖隔離に果たす役割を考えても音声による分類は適切に思える。
音声と地理的分布を考慮すると、Weir (2018) が示すように:
(1) が北方型 Zoothera aurea に属すると考えるのが妥当であろう。台湾の繁殖個体群は北方型でかつて未記載の亜種となる。
(2) は東南型で分類群としてはかつて未記載。音声の特徴は比較的近いので北方型の亜種とするか、あるいは分布も考えて別種とするかの議論になるだろう。
(3) は分布は南方だが他の分類群と音声が異なるためおそらく Zoothera dauma から分離して別種と捉えるのが望ましそうに思える。別種とするならば Zoothera imbricata となる。別種扱いの検討は Rasmussen and Anderton (2005), Collar (2005) にもあるが、含まれる亜種はこの音声研究とは少しずつ異なっている。
neilgherriensis を含む場合 (Collar 2005) は記載年代からこれが基亜種となって Zoothera neilgherriensis となるが、この包含関係は音声研究からは支持されない。
(4) は地理的に大きく離れているために複数種に分離される可能性がある。
Zoothera dauma をヒマラヤの個体群とするのはおそらく適切で、neilgherriensis を同種とするか独立種とするかはこの論文の結論のようにまだ明確ではない。
遠く離れた major を別種とするのは世界の多くのリストがそのように扱っている通り妥当であろう。
このように考えると少なくとも4種への分割は妥当となる。neilgherriensis を独立種とすれば5種。(2) の東方型も別種 (学名未定) とするならば最大6種となりそうである。
世界の分類動向に従い、上記音声情報も加味すると、日本で記録のあるトラツグミ類は トラツグミ Zoothera aurea (英名 White's Thrush)、オオトラツグミ Zoothera major (英名 Amami Thrush)、
亜種 コトラツグミ iriomotensis 帰属未定だが台湾の繁殖個体群が北方型と考えられることから暫定 Zoothera aurea の亜種でよいかもしれない (音声などの情報次第)。あるいはオオトラツグミの亜種の可能性もある。
台湾の個体群は Zoothera aurea の未記載の亜種とするのが妥当そうである。
このように考えると日本の分類にミナミトラツグミが現れる必要もないかも知れない。
Weir (2018) のように台湾固有の繁殖個体群の亜種名は hancii も考えられるかも知れない。
ただし確定のためにはサンプルが十分でない (音声面でもトラツグミ類のさえずり記録は我々が思っている以上に難しいようである)、プレイバック実験もあった方がよい。形態や色彩などの詳細な比較も望まれるなど流動的な要素も多そうである。
西海 (2023) Birder 37(12): 31 の記事を見て 西海 (2021) Birder 35(10): 36-37 の記事があることを知った。現物を見るまでに時間がかかってしまったが、音声はやはり重要な要素であるとのこと。台湾個体の音声にも言及があり、Weir (2018) は参照して書かれた記事だろう。
これまでのトラツグミを2種に分割するに当たって、オオトラツグミを含む種 (この分類では Zoothera dauma) にオオトラツグミの名称を与えると、コトラツグミの名称が混乱を招く恐れがあるので新称ミナミトラツグミを提案したとのこと。
なおコトラツグミは標本のみで音声は知られていないとのことで、形態的には horsfieldi (インドネシア) に似ているとのこと。
なお Avibase によれば、Zoothera dauma の過去の和名にはカッショクトラツグミ、コトラツグミ、タニンバルトラツグミ、トラツグミ が含まれている (同種時代の名称や、亜種名なども現れていると考えられる)。
タニンバルトラツグミの名称は eBird によれば Zoothera machiki Fawn-breasted Thrush (インドネシアタニンバル島) に与えられている。
Zoothera 属をそれほど細かく分ける必要があるかについては、IOC 14.2 では 21 種で分布範囲の狭い種が多数認められている。近年分離されたものあり Island Thrush のように研究が進めばさらに分離が行われても不思議でない印象を受ける。
音声をもとに DNA 解析の結果近年新種と認められた Zoothera 属にヒマラヤトラツグミ Zoothera salimalii Himalayan Forest Thrush がある。
Alstrom et al. (2016) Integrative taxonomy of the Plain-backed Thrush (Zoothera mollissima) complex (Aves, Turdidae) reveals cryptic species, including a new species。2016 年の新種記載でインドでは 1947 年以来の発見とのこと。
シセントラツグミ Zoothera griseiceps Sichuan Forest Thrush もこの研究で種として分離。
'Adele' like song leads scientists to identify bird as new species (Guardian の記事)。
やはりトラツグミ類の歌の違いは種分化に役立ちそうに思える。これら類縁種の音声は xeno-canto で聞くことができるが、トラツグミとオオトラツグミの関係よりずっと似ているように感じる。いずれも結構ツグミ的な歌声。
この研究にはトラツグミとアミメジツグミ Zoothera andromedae (ジャワ、スマトラ) も外群として含まれており cty b でトラツグミと 6.9% 異なるとのこと。上記の種間の遺伝的距離はこの値より大きく種に値する根拠の一つとなっている。
IOC 15.1 から Zoothera atrigena Bougainville Thrush と Zoothera talaseae New Britain Thrush を分離。
Zoothera 属でも分子系統研究が進めば種分離が進みそうな印象を受ける。
AviList の扱い AviList (2025.6) ではこれまでの広義 Zoothera dauma を5種に分離。
26611 104 The Zoothera dauma sensu lato complex is treated as five species based on a combination of morphology, vocalizations (Weir 2018), and biogeography: Z. dauma (polytypic, including iriomotensis and horsfieldi); Z. aurea (polytypic, including toratugumi); Z. neilgherriensis; Z. imbricata; and Z. major. Analyses of fragmentary genetic data (Klicka et al. 2005; Sangster et al. 2010; Price et al. 2014; Robin et al. 2015) indicate the presence of multiple species within this complex but a more comprehensive review including all taxa is required.
根拠は形態、音声、生物地理学と部分的な遺伝情報によるもの。
日本鳥学会は独立種と認めていない見解や根拠は特に紹介されていない。この種の相違点を幅広く扱っている H&M4 のオンラインサイトにも日本の分類についての言及はなく、日本鳥学会のリストを参照したり大部分は日本語でのみ書かれた文献を参照しない限り、世界の読者にとってオオトラツグミを独立種としない概念は知られないことになる。
日本のリストに現れる (た) ものでは Zoothera dauma に属するものは iriomotensis と horsfieldi。major はこれまでの海外リスト通り独立種。toratugumi は Zoothera aurea に含められた。
Zoothera dauma はさらに複数種が含まれる可能性があるがさらなる研究が必要。
おそらく種境界の問題と、先取権の原則から現在の亜種をどの種に帰属するかに伴う判断による学名の不安定性をなるべく避ける暫定的扱いで、世界的にはこれまでの広義トラツグミをさらに分割する考え方が支持されているものと思われる。Zoothera aurea と Zoothera dauma の範囲では先取権の原則の問題が発生しないため先行して分離されたものと考えられる。
[ロシア沿海地方のトラツグミ]
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the White’s thrush Zoothera varia (pp. 5073-5094)。
この論文では沿海地方のトラツグミを亜種 exorientis としている。
日本のものと比較して違いは見つかるだろうか。記述から判断する範囲では音声 (さえずり) は日本のものと似ているよう。
[トラツグミのダンス]
トラツグミが体をゆすって採食しているのを見られた方は多いだろう。
飯島 (2017) Birder 31(5): 44-46 に詳しい解説がある。
この行動は Simmons (1961) Foot-movements in plovers and other birds がシギ・チドリ類について獲物を追い出す行動として記述したものである。
英語では foot-trembling, foot-tapping, foot-pattering, foot-quivering などと呼ばれる。
飯島 (2017) によると日本の他のツグミ類では観察していないが、チャイロツグミ Turdus kessleri 英名 White-backed Thrush、ハイイロチャツグミ (これは日本で記録されている種類)、ビリーチリツグミ Catharus fuscescens 英名 Veery、
アカオトラツグミ Zoothera heinei 英名 Russet-tailed Thrush、キタニュージーランドコマヒタキ Petroica longipes 英名 North Island Robin で記載があるとのこと。
キタニュージーランドコマヒタキでは左右の好みも報告されている [Berggren (2006) Topography affects foot trembling side preference in the North Island robin (Petroica longipes)]。
これらの種類をみると Turdus 属よりも、ジツグミ類 (ground thrushes) がよく行う行動のようである。
foot quivering in thrushes (Birding-Aus 2019) のような記事もある。この記事でも Catharus 属 (ハイイロチャツグミが含まれる) のツグミ類で観察されると書かれている。
Cantlay et al. (2019) Visual fields and foraging ecology of Blacksmith Lapwings Vanellus armatus の研究によればツグミ類ではないが、シロクロゲリ Vanellus armatus では獲物を視野が入ってくるのを助け、実質的に視野を広げているとの説明がある。
-
オガサワラガビチョウ
- 第8版学名:Cichlopasser terrestris (キクロパッセル テッレストゥリス) 地面にいるツグミスズメ
- IOC 学名:Zoothera terrestris (ゾーオテーラ テルレストゥリス) 地面にいる虫を狩る鳥
- 第8版属名:cichlopasser (m) ツグミスズメ (kikhle ツグミ Gk passer (m) スズメ) (The Key to Scientific Names)
- IOC 属名:zoothera (合) 虫(動物)を狩る鳥の (zoo- (接頭辞) 動物 thira 狩り Gk)
- 種小名:terrestris (adj) 地面の
- 英名:Bonin Thrush (bonin 無人 小笠原)
- 備考:
cichlopasser は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は kikhle の語末が長母音のため伸ばす可能性がある。アクセントは問題なく "キクロパッセル" (または忠実に2重子音で発音すれば キクロパスセル") でよい。
zoothera は#トラツグミ参照。
terrestris はすべて短母音で -res- にアクセントがある (テルレストゥリス)。英語にも terrestrial の対応する単語があり、territory (ラテン語 territorium 由来) も同語源。若干紛らわしいのはラテン語 tellus にも土の意味があり元素のテルル (Te) はこちらが由来。日本語で書くと同じような文字になってしまう。
terra と tellus は似ているが別語源とのこと。terra は "乾いた" 意味が語源。tellus はそれほどよくわかっていない (wiktionary)。
絶滅種。現在のすべての主要リストで Zoothera 属となっている。種小名は変わりなし。
原記載は Turdus terrestris Kittlitz, 1830。1850 年に Bonaparte が Geocichla 属とし、同じく Bonaparte によって1854 年 Cichlopasser 属としたもの。この属では単形属。
標本は日本国内に存在せず、ライデン・ウィーン・フランクフルト・サンクトペテルブルクの博物館に所蔵されているとのこと (wikipedia 日本語版より)。
和名からは何の仲間かわかりにくいが、世界の分類動向を見るとトラツグミに近いと考えている模様。
地上性で木の枝にとまらなかったという (コンサイス鳥名辞典)。#ハヤブサ備考 [ハヤブサ類の免疫の特殊性] 免疫と造巣習性の関係? で考察したように樹上造巣習性を失うことはいくつもの系統で独立に起きていたよう。
Zoothera 属の古い系統にあたるならば地上捕食者のいなかった島で完全地上性に移行した地ツグミ類だったのかも。スズメ目であっても樹上造巣習性の維持にはコストがかかり、必要なければ失われる性質であることを意味するのかも知れない。完全に失った後に再度獲得することはおそらく容易でなく一方通行の進化だったのかも。
Zoothera 属系統では高地環境への適応など比較的起きやすいように見える。
Kittlitz が訪れた時にはすでにブタがいたそうで、William Stimpson が 1854 年に島を訪れた時には人が持ち込んだネズミ類、ヤギ、犬や猫がいたとのこと (wikipedia 英語版より)。
-
ハイイロチャツグミ
- 学名:Catharus minimus (カタルス ミニムス) 最も小さい斑点のないツグミ
- 属名:catharus (合) 純粋な (katharos 純粋な Gk)
- 種小名:minimus (adj) 最も小さい
- 英名:Grey-cheeked Thrush
- 備考:
catharus は起源となるギリシャ語は短母音のみなので "カタルス" の読みになると思われる。
minimus も短母音のみで冒頭にアクセントがある (ミニムス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。属名はアカハシチャツグミ Catharus aurantiirostris (英名 Orange-billed Nightingale-Thrush) の (多くのツグミ類にあるような) 斑点のない褐色と白色の模様を指している (The Key to Scientific Names)。
亜種は日本鳥類目録改訂第7版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに aliciae (アメリカの博物学者 Robert Kennicott の妹 Alice Mary Kennicott に由来) で北東シベリアからカナダまで分布。越冬地は南アメリカ。
もとは北米から進出した種類でユーラシアではチュコト半島からコリマ川河口まで分布するとのこと。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) でも同様の記述がある。
クレチマル・千村 (訳) (1991) Birder 5(7): 20 に巣と子育て中のハイイロチャツグミの写真がある。
森岡 (2005) Birder 19(4): 52-53 に 2004 年 10 月に舳倉島で観察されたハイイロチャツグミと考えられる個体の検討がある。識別対象種の一つにヒスパニョラチャツグミ (当時は和名がなかったらしい) Catharus bicknelli 英名 Bicknell's Thrush が含まれている。
同属のオリーブチャツグミ Catharus ustulatus Swainson's Thrush のアメリカ大陸亜種間で渡り特性が大きく異なるが、染色体レベルのゲノム研究で亜種分化機構を議論したもの: Blain et al. (2025) Repeatable selection on large ancestry blocks in an avian hybrid zone。
難しいので論文所在の紹介まで。実際に読んでいただきたい。
Turdidae (BirdForum) でもこの研究への言及があり、別種に値する根拠となるのかなど議論も出ている。過去の研究文献も紹介されている。亜種間の雑種は渡り特性の違いから生存率が低いが、この生殖隔離機構 (postzygotic) に比べて音声の違いなどによるつがい形成や稔性などの (prezygotic) 点では生殖隔離機構が特に高いわけではない。
音声研究で活躍している Peter Boesman によればさえずり・地鳴きの違いを独立に記述していたとのこと: Notes on the vocalizations of Swainson's Thrush (Catharus ustulatus) (2016)。
[Catharus 属の渡り特性の進化]
Winker and Delmore (2025) Seasonally migratory songbirds have different historic population size characteristics than resident relatives
ハイイロチャツグミと北米の類縁系統について渡り特性と実効個体数 (Ne) を調べたもの。渡りを行う種は熱帯地方の留鳥種に比べて Ne が大きく渡り行動が遺伝的多様性を高めるのに役立っているらしいことが想像できる。渡りを行う種ほど Ne の初期変化の速度も速い。
Ne 変化のタイムスケールは種の誕生・消滅のタイムスケールに近い。難しい内容を含むので詳しくは論文を参照。
Halley et al. (2025) Phylogenetic comparative analysis of functional morphology sheds light on the evolution of seasonal migration in nightingale-thrushes (Turdidae: Catharus)
系統解析の結果、祖先形質は短距離または elevational migration (標高の上下方向の渡り)、短距離の渡りが長距離の渡りの先駆けとなったと考えられる。ハイイロチャツグミは長距離の渡りを行う分岐に含まれる。
比較的長距離の渡りを行う系統に含まれるチャイロコツグミ Catharus guttatus Hermit Thrush が短距離の渡りしか行わない経緯の検討も行われている。祖先形と考えるのは難しいらしく、新しく生まれた系統でありながら短距離の渡りの形質が生じた理由の解釈を試みている。地理的に縁の薄いところで議論内容も難しいのでこちらも詳しくは読んでみていただきたい。
また亜種の間で分子遺伝学的にはどの程度違うのか参考になる情報が含まれている。
-
カラアカハラ
- 学名:Turdus hortulorum (トゥルドゥス ホルトゥロールム) 公園にいるツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:hortulorum (属) 公園の (hortulus -orum (複数-属) (m) 公園) 基産地がマカオの公園だった。備考参照
- 英名:Grey-backed Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
hortulorum は複数・属格で -orum の o が長母音。冒頭にアクセントがある (ホルトゥロールム)
記載時学名 Turdus hortulorum Sclater, 1863 (原記載) 基産地 Camoens Garden, Macao (マカオ)。
"公園の" は Camoens Garden を指すらしい。Luis de Camoes Garden で中国語では (White) Pigeon/Dove Nest Park の意味とのこと (wikipedia 英語版)。
種小名が複数形になっているのは例えば京都府立植物園を Kyoto Botanical Gardens と呼ぶようなものだろうか。
かつてはムナグロアカハラ Turdus dissimilis (英名 Black-breasted Thrush) の亜種とされた。同種としていたものは例えば Peters' Check-list of the Birds (2nd edition) まで、Howard and Moore 2nd edition など。
上野 (2024) Birder 36(11): 35 に広島県でのカラアカハラの繁殖についての記事がある。かつてはシロハラが繁殖していたが現在は確認できていない。アカハラの不在が要因となっている可能性が述べられている。
上野他 (2021) 広島県臥竜山麓におけるカラアカハラの繁殖確認。シラガホオジロが定期的に越冬するなど面白い地域である。
山本・上野 (2023) 広島県におけるカラアカハラの営巣初確認。この論文の引用文献参照。
-
クロツグミ
- 学名:Turdus cardis (トゥルドゥス カルディス) アザミ模様の(?)ツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:cardis (合) carde カード 仏 < Merle carde (Temminck の与えたフランス名) (備考も参照)
- 英名:Grey Thrush, IOC: Japanese Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
種小名 cardis は (合) 心臓の (kardis 心臓 Gk) (菊池氏のオリジナル解釈) もある。愛媛の野鳥「はばたき」ではフランス名のラテン語化、とある。
参考。
該当部分は sur les cotes du ventre, de petites taches triangulaires noirs
腹に三角形の小さな斑点がある。
The Key to Scientific Names では カード 仏 < Temminck がフランス名 Merle carde を与えたが (merle ヨーロッパのクロウタドリまたは広義のクロウタドリ類似の鳥。すべての Turdus属が merle とは呼ばれるわけではなく、「ツグミ類」を表すフランス語総称はないらしい)、腹部模様がカードゲームのように見えたためではないかと思われるとある。
これは carde のフランス語の意味を取り違えている可能性がある (英語 card にすきぐしを意味する別語義があるが、これを通常語義のカードと解釈している可能性がある)。「コンサイス鳥名事典」にはアザミとある。
アザミ類に Carduus 属 (ラテン語でアザミの一種) があり、この語は英語 card (すきぐし) とも関係があるとのこと (wikipedia 英語版より)。
辞書訳でがフランス語 carde アザミなどの 葉肋 (ようろく、食用になる)、梳刷毛、梳綿、けば立て機 の意味がある。派生した英語は chard とのこと。
carde metalique はワイヤーブラシの意味で、上記すきぐしにも近い。
フランス語 carder は織物を梳 (す) く。(織物を) けば立てる時にもこの単語が用いられる。
辞書にはカードの意味は現れないので、アザミや織物に現れる模様や形態を表すと考える方が自然に思える。
フランス語原記載を考慮し、「アザミ模様の」と訳すことにした。
なおイタリア語では cardo がチョウセンアザミ、(食用) カルドン、クリのいが、他の意味はフランス語と同じ。
Merle carde or Turdus cardis Temminck, 1831 (BirdForum 2021) でも議論が行われいるが特に有力なアイデアは出ていない。
その後 Merle carde or Turdus cardis Temminck, 1831 に 2024年8月段階で新たな議論が追加されている。
他の動物群では "mottled" (まだらの) または心臓型の、の意味で使われている用例があるとのこと。
トビケラ目の Parapsyche cardis は心臓型と記載されている。
cardisoma の用例もあってこれは文字通り "心臓型の" の意味になる。しかしクロツグミの斑点が心臓型かと言われるとあまりそのようには見えない。
ツグミ類の系統樹 [#クロウタドリ (第8版追加) の項目参照] では、クロツグミとカラアカハラが近い関係にある。分離前のクロウタドリと近い系統ではない。かつて中国で繁殖する個体群に亜種名 lateus Thayer & Bangs, 1909 (参考)
が与えられたことがあったが、現在では単形種とされる (wikipedia 英語版)。
亜種 yessoensis とでもいいたい大型の個体 [伏原 (1959)
クロツグミの蟻浴] は Avibase に亜種として載っており、シノニムの扱いになっている。
Stresemann (1929) は中国で亜種 merulinus を記載したがこれも現在亜種と認められていない (参考)。
英名は AviList では IOC に合わせて Japanese Thrush を採用。eBird/Clements, BirdLife v9 とも同じ名称を採用したため現在の標準的英名となっている。古くは原記載の地名をもとにした英名が一般的に用いられていてそれ以上の特別な意味はなさそう。クロツグミの場合は分類変遷などが発生しなかったので過去の英名がそのまま使われているものと思われる。
茂田 (1998) Birder 12(6): 46-55 によればクロツグミの第一回冬羽で成鳥のような色彩を持つ個体があるとのこと (例えばオスならば黒い)。ヨーロッパのクロウタドリでこの現象が知られていてドイツ語で Stockamsel と呼ばれるとのこと (Amsel はクロウタドリだが、Stock をどの意味で用いているかはわからず。切り株などの意味がある)。
Blackbird variety and 'variety'?
によればメスのように見える若いオスの意味で、Johann Andreas Naumann が考案したらしいとのこと。1960 年代によく使われたが最近は使われないらしい。Stockamsel: a name to conjure with
では大陸でクロウタドリと同義語のようなもので、若いオスでうろこ模様が特に目立ってメスのように見える個体を指しているだけで大した意味はないのではとの議論をしている。
矢根 (2012) Birder 26(7): 49 に福井県で積雪期に越冬したクロツグミが紹介されている。
GenBank のミトコンドリアゲノムを使って BLAST を試してみるとカラアカハラとかなり近いことがわかる。さすがにツグミとハチジョウツグミの関係よりは遠いが、ツグミと {ノドアカツグミ + ノドグロツグミ} の関係よりは近い。かつて同種扱いだったシロハラとマミチャジナイの関係よりも近い。
{ツグミ + ハチジョウツグミ} のグループにチベットウタツグミ Turdus mupinensis Chinese Thrush が含まれる結果となった。
[クロツグミが日本三鳴鳥に選ばれなかった理由関連]
大橋 (2025) Birder 39(7): 71 にクロツグミが日本三鳴鳥に選ばれなかった理由が考察されていて、この話題は過去にも取り上げられているのでここでは別の角度から取り上げてみよう。"三鳴鳥" は飼い鳥を指す用語であることは当然のように知られているものとする。つまり飼育困難なものは含まれない。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 45 (1946 年初出) によれば俳諧歳時記にはこれまた取り上げられていない。春はたいていの歌い手がさえずりと一括され、クロツグミも秋のツグミ類に入れられていた。季語にないため作例もないとのことであった。
今で言えば音景を指して「鳥のさえずり」(世間的には地鳴きでも何でも含まれる) と表記するのとほとんど違わないだろう。ハイキングや登山をするほとんどの人も、ウグイスなど有名なものを除いてすべて「鳥の声を聞きながら」と感じているのではないか。野鳥の会に入ったきっかけも山でよく聞いている鳥の名前を知りたい方も多かったのでは。
つまりクロツグミが特別な声とはほとんどみなされていなかったと想像できる。だからこそ鳥の声の聞き分けにアカハラをまず覚え、それに対比する形でマミジロやクロツグミを覚える方法がよく紹介されているのだろう。西日本の人にとってはおそらく違和感のあるところだろうが、関東ではアカハラが身近なのでアカハラが基準とされた次第。アカハラとシロハラの聞き分けが難しいのはまた次元の違う話だがここで深入りする必要もないので別記。
これはオオルリでもおそらく同様で、三鳴鳥はいずれも「よい声」であることは必要条件であっただろうが、選定要因は音声よりも色彩だったのだろう。つまり音声は十分条件とはならなかった。
古くはコルリなども含めて「るり」と総称されていたのも音声の違いにはあまり関心が向けられなかったことの現れでもあるのだろう。当時の技術ではコルリの冬場の飼育は困難で、オオルリのみが残ったのだろう。
ただしクロツグミが単独で飼育されている場合にもさえずるのかどうかは知らない。
褒め称えられるウグイスを別格として、宮中を飾る飼い鳥として天然のものと思えないような青と赤が珍重されたであろうことはおそらく疑いないだろう。黒は同様の理由からおそらく好まれなかったのでは。
コマドリの駒は馬のいななきを指す解釈もあるが、他の事例と比較すると色彩と形からの連想で、声由来は後付けと見る方がもっともらしい気がする (「本朝食鑑・和漢三才図会」にすでに登場するが、#サンショウクイの サンショウクイ和名由来の別説 のような解釈も可能なので後付けであっても不自然ではない)。
「和鳥四品」にはウグイスを除いて、キビタキ、ミヤマホオジロが含まれていたらしい (間接的出典しか見ていないのでこれが唯一の定義であったかどうかは知らない)。これを見ると黄を補いたかったらしいことが読み取れる (ミヤマホオジロのさえずりが特別によい声であるかどうか判断し難い)。
すなわちクロツグミを特別と認識する文化はそもそもほとんどなく、鳥の声に注目して聞き分けようと努力がなされる時代になって認識が進んで現代に至っているものと想像できる。
日本人と西洋人では鳥の声の聞こえ方が違っていたというよりは、#シジュウカラ備考の [オクターブ認識能力] で考察するように鳥の声を人語に焼き直して聞くか、音声そのものを聞く文化あるいは教育による違いだろう。自分の考えるところでは音声そのものを聞くことは積極的な教育あるいは訓練がないと身につかない。
色彩認知は人によってあまり違わないと考えれば、より多くの人の賛同を得られる (今の時代ならば「いいね!」が付く) 色彩が自然と判定基準の中心となって行ったであろうことも理解できる。
たとえ「この音色はすばらしい」と褒める人があったとしても、通じる人にしかわからなければ市民権を得にくいわけである。そのような世界と無関係なところにむしろ独自の聞きなしが残っている。
このようにして鳥の色や形が重視され、声を重視しない文化が進展し、日本の近代的な鳥学の創始時期の研究者にも影響を与えていたものと考えられる。鳥の研究者ならばキジ目を扱うのは当然となった理由にもつながるだろう。
鳥の声を識別に用いるようになったのは比較的最近の話である。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) には何とクロツグミの項目がない (!)。p. 212 のアカハラの項目でシロハラとクロツグミの近縁種として登場する程度。
アカハラとシロハラ (+ マミチャジナイ, アカコッコ) の近縁度は現在でも正しいが、クロツグミは現在では異なる系統と考えられている。
それはともかく、1980 年代にはクロツグミの知名度が低かったらしいことがわかる。もとは新聞連載だったのでたまたまクロツグミを取り上げなかっただけかも知れないが、三鳴鳥に値する種と考えられていれば新聞連載でもおそらく見逃されていなかっただろうし、書籍にまとめる際に補われていても不思議でない。
あまり馴染みの鳥ではなかったのかも知れない。かつてアカハラ、マミジロ、クロツグミの音声識別が話題となっていた程度なのでクロツグミの声を聞いてクロツグミとわかる人は案外少なかったのかも知れない。
同書で #センダイムシクイ が旅鳥とされていたようにクロツグミも渡り途中にそれほど出会う種類ではないため省略されていたのかも知れない (単純に書く題材がなかっただけかも知れないが - 本稿でも大した解説がないのは学名の意味がよくわからない以外にあまり題材がないためである。大橋氏も日本を代表する鳥としてクロツグミを取り上げたものの、あまり目立った話題がなくて困られたのではないだろうか)。
他の古名を見ても音声由来のものが見当たらず、ツグミ類は秋の渡りで捕獲して食べるものと認識されていたらしいことがわかる。
クロツグミの声を「美声」と評価されるようになったのは、主に蒲谷氏などの音源が普及するようになって以降ではないだろうか。それ以前は音声を聞いてもカタカナ記録も難しく、一括して「鳥のさえずり」と扱われていたが、蒲谷氏などが美声と宣伝した結果「クロツグミは美声で有名」とこれまたステレオタイプに受け継がれるようになったものではないだろうか。
「美声」と思って渡り途中にクロツグミだと解釈されて聞かれているものが実はアカハラだったりするのは体験される通り。ツグミ類のさえずりの聞き分けは案外難しく、習えばすぐわかるようになるほど簡単ではない。どちらかと言えば上級編だろう。地域次第では今ではソウシチョウやガビチョウもよく間違われる。
かつて相当古い時代に参加した探鳥会でクロツグミの声をリーダーにコサメビタキと判定された経験もあるので (なぜそのような判断になったのか理解困難であったが、「複雑な声でさえずる」と言葉で記述すれば同じになってしまうわけだ)、さえずりを区別できていない人の方が多いのではと思う。声で区別できないならば声の「三鳴鳥」と呼びにくいかも。
さらに面白い記述を見つけてしまった。中西悟堂「定本・野鳥記」2 p. 109 (1940 年と思われるが再販時に編集が入っている可能性もある) によればクロツグミの声はただ弾くようだがアカハラのほうは幾分の艶がある。したがって響きもあります。とのことでアカハラの声の方をより評価されていた。
この部分は少人数の個人探鳥会で鳥の声を教えている場面で、...と言ったが馴れぬ耳には、こういう些細な区別はとてもむずかしいらしいと続けられていた。メンバーの耳にはウグイスやカッコウ以外はとても難しい様子が述べられていた。
さらに同書 p. 138 (1938 年の記録) ではクロツグミはあまり余韻もない張り切った声で (中略) 景気よく鳴くのが祭りの囃子のようである、と述べられていた。つまり賑やかであっても品がない、ということだろう。音声面でも三鳴鳥候補から落選しても不思議でなかった。
中西悟堂「定本・野鳥記」4 p. 158 (1946 年初出) ではアカハラの声を「明かるく奥行きのある、大きい声だがうるさくない」と記していた。
これだけ見ていると人による感じ方の違いとも解釈できるが、我々がクロツグミの声がよいと感じる (人にもよるだろう) のは蒲谷氏などの先人がそのように記述したためで、解説などもそのままに伝え、探鳥会担当者も同じように伝えたため教え込まれた結果かも知れない。中西氏のようにアカハラの声の方がよい、と主張する人があっても不思議でないが、クロツグミの声がよいと言っておく方が波風が立たず、教え込まれたことに従う習性から異なる意見が述べにくいのだろう。
ちなみに自分もウグイスがよい声とは特に思っていない。
さて中西氏が評価したアカハラの声の良さとは何だろうか、と考えるうちに、(少なくとも現時点では) 野鳥の声の第一人者と言えば基本的に高齢者であることに気づいた。つまり野鳥を始めるころはまず姿の識別が中心で、声に関心の及ぶ人は少ないため必然的に声を議論するのは経験者中心になる。高齢者が多くなり、また "第一人者" は通常経験を積んだ人を指すことが多いので若者が選ばれることは少ない。
ちなみに海外では必ずしもこの通りではなく若い世代の音声の第一人者も存在する。齢を重ねた人の言うことほど正しいとは必ずしも限らない。
つまり中西氏は高齢者に聞き取りにくい成分を捉えて「艶がある」と評価されていたのではないかと想像して音源をチェックしてみると、クロツグミの音声にはあっても2倍音 (second harmonic または first overtone。呼び方によって数字が異なるので注意) までで倍音成分が乏しい。
そしてアカハラの声は3倍音が含まれる: 参考 XC156357 (Frank Lambert 2013.6.25)。この例では2倍音が欠如している。
この特徴はオオルリのさえずりと同じで「アカハラの声の方が艶がある」ことになる。興味ある方はネットにもたくさん記事があるのでフルートと倍音などで検索して調べてみていただきたい。
「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) のヤブサメの項目でも「それほど高い、小さな声で鳴く鳥である」と書かれていて蒲谷氏が録音されていた時代にはすでに高音の聴力を損なっておられたのではないだろうか。引き継がれた松田氏も高音が聞き取りにくいことをしばしば述べられていた。
ヤブサメの声を間近に聞かれた方ならば音圧に驚かれた方もあるのではないだろうか。録音時でも振り切れないよう設定する必要があるぐらいで「小さな声」はまったく当たらない気がする。
#ヒガシメンフクロウの備考 [鳥の聴力は老化しない?] にあるように一般的には鳥の hair cell に再生能力があって聴力はほとんど老化しないが、哺乳類ではそういうわけには行かない。
再生医療でもあまり有効な結果は認められておらず、高音を補強する補聴器に頼るか、高音聴力をなるべく低下させない生活がよい。鳥の声を長く楽しみたいならば、聴覚は消耗品であることを認識した上で、大音量の音を聞かない、四六時中音楽を聞かないなど注意するのがよいだろう。微小循環障害など (例えばメタボリックシンドローム) もおそらくよくないだろう。
つまり「クロツグミの声がよい」は高音成分を聞き取りにくい人が判断し、受け継がれた「神話」のようなものかも知れない。
さらに3つをまとめたがるのは日本人的と言われることもあるが、必ずしもそうでもない。「三位一体」のような使い方もあるし、西洋では triad のような表現もよく使われる。
4つではなく3つが好まれたのは日本語では4は「死」の読みにつながるためとも解釈できるが、数学的構造に由来する可能性も思いつく。3つであれば平面に等価に並べる (正三角形) ことが可能で順序を付ける必要がない。4つであれば正方形に配置すると、辺の関係になるか対角線の関係になるかの違いが発生する。つまり順位付けの必要性がある程度発生する。3次元にして正四面体とすれば対称になるように配置できるが人の認知上このような関係を考えるのは難しいわけだ。順序付けを好まなければ4つよりも3つの方がよいことになる。
"A Field Guide to the Birds of Japan" (WBSJ 1982) ではクロツグミは英文表現で Song rich in quality, long and warbling; given from tops of high trees、同書コマドリは Characteristic trill、オオルリは Melodious warble with distinctive jit-jit ending notes、キビタキは Melodious warble with three-syllable whistling notes でそもそも音声識別に役立ちそうもない (!) ...というのは置いておいて、1980 年ごろでも文字で表現する限界はあったとは言え音声よりもやはり外見重視であったのだろうことは想像できる。
そういえば過去にクラシック音楽が趣味だった時代に相前後されて放送されていた「朝の小鳥」(だと思うが現在の記事を見てもわからなくなっている) も合間に聞いていた時期があったが、一発で覚えられたのはセンダイムシクイだけだった。他の種類は何があったか覚えていないぐらいでクラシック音楽を聞いている者にとってさえそれほど印象に残りにくいものである。
鳥の声はしっかり意識して覚えないとどれも同じように聞こえてしまう。野鳥観察を始めるに際して改めて音源を聞くようになったが、最初に覚えられたのはクロツグミだった。録音時間も短く1種1音源に限られていた時代で、最上のさえずりで最上の録音が選ばれると個体差の大きい種では必ずしも現実に即していないことがあるのはご存じの通り。最も覚えやすい音声のクロツグミが採用されていたものと想像できる。
ただしクラシック音楽をやっていたためか進歩は早く、始めたその年のうちに「鳥の声は得意」と言える程度になってしまった。
録音はまだ行っていなかったので地鳴きなどはその後現場で逐次覚えることになった。これから始められる方のためにヒントを紹介しておくと、コーラスの中からわかる声をピックアップするのは効率的な覚え方ではない。一通りの声がその場で判別できるようになった段階で「聞き慣れない声」に気づいて正体を確かめる・調べるようになれば格段に上達が早まる。
秋の渡りでもよく聞かれるクロツグミの特徴的な地鳴きも案外知られていない。今の声は何ですかと聞かれても誰も答えられないこともしばしばあるタイプの音声。
さて、クロツグミ、オオルリ、キビタキともに大陸の類縁種に比べて日本の種の方がよい歌い手のように思う。なぜなのか理由はよく知らないが、多少気になる研究があったので紹介しておく: Coria et al. (2025) Elements of male song performance and complexity are associated with reduced risk of paternity loss in a South American passerine。
系統的にはかなり違うのでそのまま当てはまるかどうかは不明だが、父権 (paternity) を失いにくい種ほど歌が複雑である傾向があるとのこと。日本の種に当てはめれば長距離の渡りをする種ほどメスの間の競争が弱まり (メスが忙しいので同性間の競争が起きにくい) 色彩の性的二形が進化しやすい理屈 (#イソヒヨドリの備考 [メスもさえずる鳥] 参考) と一応整合する感じもする。
大陸の種に比べて海を超えた長距離移動が必要なのでメス同士の競争が強くなく、オスによい声を進化させる余裕を与えた。アカコッコは留鳥でアカハラと系統的に非常に近いにもかかわらずオスがさえずりをあまり進化させる必要がなかった?
リュウキュウキビタキにも同様のことが言えるかも知れない。
さらに音源を聞くとコマドリの亜種タネコマドリ (AviList では独立種 Larvivora tanensis) の方がさえずりが若干派手でない感じがする。「日本野鳥大鑑 鳴き声 420」(蒲谷鶴彦・松田道生 小学館 2001) にも同じように書かれている - さてどうだろうか。
-
クロウタドリ (分割で日本産学名も変わった)
- 第8版学名:Turdus mandarinus (トゥルドゥス マンダリヌス) 中国のツグミ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Turdus merula (トゥルドゥス メルラ) クロウタドリ
- 第7版亜種学名:Turdus merula mandarinus (トゥルドゥス メルラ マンダリヌス) 中国のクロウタドリ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 第8版種小名:mandarinus 中国の (ポルトガル語で中華帝国時代の官吏 mandarim から < マレー語 menteri 相談役) (The Key to Scientific Names)
- 第7版種小名:merula (合) クロウタドリ (merle 仏、merlo 伊)
- 第7版亜種小名:mandarinus 中国の (ポルトガル語で中華帝国時代の官吏 mandarim から < マレー語 menteri 相談役) (The Key to Scientific Names)
- 英名:[Blackbird 分離前の名称], Chinese Blackbird
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
mandarinus は外来語由来で発音はよくわからないが、短母音のみで規則通りとすれば "マンダリヌス"。
merula は短母音のみで冒頭にアクセントがある (メルラ)。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Turdus merula の亜種とされていた mandarinus (mandarinus 中国の) が種に昇格、Turdus mandarinus (英名 Chinese Blackbird) となる (原記載)。
ヒガシクロウタドリと改名が提案されていた。最終的にクロウタドリが採用された。
この種には他に亜種 sowerbyi もあるため単形種にはならない。
Turdus-Project に系統樹が示されている。
これによれば Turdus mandarinus と Turdus merula とは特に近縁でなく、そのため別の和名が与えられたのかも知れない。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではクロウタドリに戻り、最終的にこの名称となった。ヨーロッパで馴染みのクロウタドリに別名 (Avibase はニシクロウタドリを用いている。IOC 英名 Common Blackbird) を与える必要が生じることになる。
日本で記録されたものは基亜種 mandarinus とされる。
かつては Turdus merula 英名 Common Blackbird だったものが分離された。
記録論文は Brazil and Suzuki (1988) 石川県舳倉島で観察されたクロウタドリ、
繁殖行動: 石塚他 (1998) 金沢市でみられたクロウタドリの造巣行動
などの論文がある。1982 年の与那国島のペアの記録が初の公認記録とのこと。
同様に Turdus merula より分離された種に
Turdus simillimus 英名 Indian Blackbird (インドクロウタドリ)、
Turdus maximus 英名 Tibetan Blackbird (チベットクロウタドリ) がある。
Nylander et al. (2008) Accounting for Phylogenetic Uncertainty in Biogeography: A Bayesian Approach to Dispersal-Vicariance Analysis of the Thrushes (Aves: Turdus)
による分子系統研究があり、Turdus merula (clade IIc に近い) と Turdus mandarinus (clade IIIb に近い) は特に近縁でない結果が得られている。
Turdus simillimus と Turdus maximus は clade I と大きく異なっていた (生物地理学にもほぼ従っている)。この研究に従えばこれらの種類は色が似ていただけのようである。
Linek et al. (2024) Migratory lifestyle carries no added overall energy cost in a partial migratory songbird
部分的渡りを行うヨーロッパの Turdus merula に体温、心拍センサーを取り付け経路も追跡。渡る個体は渡りの 28 日前から体温や心拍を下げておそらく渡りのエネルギー消費を減らしたと思われるが、体温調節に多くのエネルギーを消費しないと考えられる越冬地でエネルギー消費は想像以上に減らなかった。
越冬地ではエネルギー消費を増やす何かのコストが存在する (例えば新しい環境で警戒する、免疫など) と考えられる。総エネルギーコストが有利なため渡りを行うとの単純な解釈は見直しを迫られる。
-
マミチャジナイ
- 学名:Turdus obscurus (トゥルドゥス オプスクールス) くすんだ色のツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:obscurus (adj) 解り難い、不明瞭な; くすんだ色の (コンサイス鳥名事典)
- 英名:Eyebrowed Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
obscurus は u が長母音でここにアクセントがある (オプスクールス)。英語の obscure も同様の発音でわかりやすい。
種小名の意味は「黒ずんだ」(愛媛の野鳥「はばたき」) ともあり、「コンサイス鳥名事典」の表現を採用した。ツグミ類の系統樹 (クロウタドリ/ヒガシクロウタドリの項目参照) では、マミチャジナイ、シロハラ、アカハラ、アカコッコは従来考えられていた通り近い関係にある。マミチャジナイは古くはシロハラの亜種とされていた。単形種。
原記載 では英名 Dark Thrush でやはり全体の色調を表す学名のよう。「暗色のツグミ」でもよさそう。
英名に Grey-headed Thrush の別名がある。これは現在は多種に分けられた従来の Turdus poliocephalus Island Thrush によく対応している。
分離前のこの種にはハイガシラツグミの和名もあってそのまま訳したもののよう。
この種の別名に Grey-headed Thrush があったのでは? この英名がマミチャジナイの英語別名なので同種とされていた時期があっても不思議でない。
Turdus poliocephalus Latham, 1801 の記載が非常に早いので、Gmelin (1789) の Turdus pallidus obscurus の記載がまだ見つかっていなければマミチャジナイ Turdus pallens Pallas, 1811 (Pallas のこの文献は非常に有名。現在はシノニム。別学名の可能性もあって後述参考) の学名が使われていた可能性があり、
もし亜種にする場合は Turdus poliocephalus の亜種となっていてもおかしくない。アカハラの記載はさらに遅い。全部 "ハイガシラツグミ" の亜種となっていても不思議でない。
他に対応候補となる学名では Turdus griseiceps Delessert, 1840 があるがこれはブータンで採集なのでおそらく関係なさそう。用例があまり見当たらず現在何を指しているかは不明。同じ種小名を持つ シセントラツグミ Zoothera griseiceps Sichuan Forest Thrush とは記載者が違うのでおそらく別物。
このようにみると#アカハラでも取り上げたように、これらのツグミ類は同種と見られていた (何と同種と考えるかによって学名が変わる)、あるいは十分に区別されていない時期があって、マミチャジナイの英語別名、アカハラの英語別名やあるいは和名にも影響を与えていた可能性があるかも知れない。
マミチャジナイの "ジナイ" は古来からの日本語由来で問題ないだろうが、"マミ", "チャ" の部分は英語と似ているのでどちらが先か少し気になってくる。英語別名に White-browed Thrush があるので、"マミチャ" で切るのではなく "チャジナイ" = (広い意味で) 茶色のツグミ Brown Thrush を指していたのではないだろうか (実際に "チャ" は体色との説明があった)。
そうすれば "マミ" は英語と同じ意味になり整合性が大変よくなる。眉は茶色ではなく白いのでこの解釈がもっともらしい気がする。White-browed Thrush の名称はかなり広く使われていたようで各国語の名称もこれを翻訳したと思われるものが多い。
ロシア語では "オリーブ色のツグミ" で由来が明らかでない。もしかすると現在使われるオリーブツグミ Turdus olivaceus Linnaeus, 1766 (原記載) 由来かも。
現在はアフリカの種類を指しているが分布も広く、写真を見ても腹の赤いツグミ類と結構似ている。
もしかすると全部同種で扱われていた時代があったのかも知れない (ノビタキ、オオヨシキリ、セッカなどの事例を見てもアフリカとユーラシア、東洋の種類が同種とされることはしばしばあったので不思議ではない)。
もしこの種と同種扱いであれば何と言っても Linnaeus (1766) が早いので同種とされたすべてのツグミ類が Turdus olivaceus でオリーブツグミになってしまうことになる。ロシア名からそのような時期があった可能性が想像できる。
Turdus olivaceus の用例は他にも多数あり、Forster (1781) (参考) はインドの個体をこの名称で呼んでおり、Linnaeus (1766) の Turdus olivaceus と同じか、としている。
Boddaert (1783) (参考) はインドで自分が与えた学名としているがもちろん Linnaeus (1766) が先に用いているので有効でない。
Giraud (1844) の 用例 に至っては英名 Olive-backed Thrush でニューヨークのもの。もちろん無効な学名だがオリーブチャツグミ Catharus ustulatus Swainson's Thrush の英語別名や和名に生きている。
このようにみると分類学者次第で Turdus olivaceus はアジアのツグミ類も指していたと思われる。特に Forster (1781) はそのように考えていたと見られる。
ロシアの分類学者もこの概念を受け入れて通俗名を付けたものが残っているのではないだろうか。
Kolyada et al. (2016) もさすがにそこまで考察していない。
さてそれでは英名の White-browed Thrush は何に由来するのかと探してみると Turdus leucocillus Pallas, 1811 (参考) の可能性がありそう。leucos 白 cilium まぶた (Gk)。この参考データにも Dauria で自身が名付けたとあるので場所の整合性もよい。
Pallas 自身は自身が以前に付けた Turdus sibiricus Pallas, 1776 のシノニムと注釈しているとのこと。これは現在のマミジロとされるもの。
何と言っても Pallas の有名な文献である。英語ではこの学名が知られていて White-browed Thrush が付けられたかも知れない。
その後 Turdus obscurus Gmelin, 1789 が見つかって学名が変わったものの、obscurus はあまりにも曖昧な意味なので英名はそのまま残された経緯が考えられる。
もっとも Pallas (1811) にはマミチャジナイの学名シノニムと考えられている前述の Turdus pallens も出現するのでどちらに優先権があるかなどの問題も関係していた可能性もある。シノニムとした現在はマミジロとされる学名との同定の問題なども関係していたかも知れない。
古い時代の文献で何を指しているか後になって同定された可能性がある (1811 年の Pallas の文献からの同定事情は #ムギマキ も参照)。
これを見るともしかするとマミジロの和名も Pallas の学名に関係あるのかも (??)。マミチャジナイは英名経由で、マミジロは学名からで元をたどれば実は同じものだった (??)。大胆仮説なのでどなたか調べていただきたい。
ロシアでは異なる分類を採用していた時期があってより早く命名されていた "オリーブツグミ" の方になったと考えるとわかりやすい。あるいは上述のような同定の不確実さがあってより確実な記載が優先されたのかも。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" によればシロハラの和名別名にヤブチョウマの名前があり、シロハラの方が学術語由来のように感じる。これら一連のツグミ類の和名は実は学名や英名に関連して新たに整理されたものだったのでは (?)。いかにも日本風らしい語に見えるマミチャジナイが学名または英名由来の可能性があるとは。
これらを記述した後に日本で過去に使われていた名称の載っている本を持っていることを思い出した (#タヒバリの備考に)。
「大江戸飼い鳥草紙」(pp. 164-167 表 7) の「喚呼鳥」(1710) でアカハラは あかつばら、ほし鶫、マミジロは まへつむぎ、こんなへ の名前があったらしい。「百千鳥」(1799) ではアカハラのみ記載で 茶鶫、シナエ の名前が紹介されている。「喚呼鳥」の挿絵にはいずれも出てこないようなので記述から細川氏の同定によるものと解釈すればよいだろうか。
あかつばらはアカハラに短縮されてもよいかも知れない。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」では本朝食鑑 (1697) に中国の漢字の解釈として "釈名赤腹" が現れる。
同書に「梅園禽部」(1839) の図版が紹介されていて、シロハラの図版 (pp. 152-153) では 白ツグ、マミ白、白ツハラ と複数の名前が挙がっていて "赤ハラ" のメスとは判別が難しいが別物であると添えられている。
別所にツグミ類について述べた部分があり、赤シナイこれは俗に赤ツハラと言う、とある。
ツグミの図版 (pp. 158-159) にはツグミ類一覧があり、ここに関係するもののにあげておくと 眉白、赤ハラ、白ツクミ、解説は現代でも理解可能な内容が多く、眉白ツクミの解釈はマミジロで問題なさそう。
(ツグミ類のうち) 腹が照るように赤いのは赤腹という。白ツクミはシロハラで問題なさそうだが、茶ジナイとも言うとのこと。
この時代になれば海外情報との交流もあるはずなので日本独自に付けられた名称かどうかはわからないが参考までに。
マミチャジナイの名称はこれ以降に付けられたように見える。
Latest IOC Diary Updates (BirdForum 2025.2) にかつて "Eye-browed" の表記だったが英語では「眉の上に目がある」ようにも読めるので "Eyebrowed" と訂正されたとのこと。
[音声]
ツグミ類 (特に Turdus 属) は共通して高い地鳴き (flight call) を出すが、判別不可能とあきらめられがちである。マミチャジナイのみはその中でも音程が少し低く、ソノグラムでも判別しやすい。
シロハラは一般にもっと高い声であるがマミチャジナイ程度の低い声を出すこともあり、音程だけで判断するのは (だいたいは正しそうだが) 少し危険そうである。マミチャジナイには他のツグミ類にない地鳴き (10 kHz 程度の高いところから急に 8 kHz 付近に下がって少し続き、少し震える) があり、これが記録できれば種判別は大丈夫そうである。
夜間の渡り途中の地鳴き nocturnal flight call (NFC) は渡り研究のために世界でも広く使われている。The Sound Approach guide to nocturnal flight calls (ヨーロッパ、"nocmig" という用語もある)、
Nocturnal Flight Calls of North America (アメリカ) などがあるが、日本ではあまり調べられていない印象を受ける。最近では日本と同種の判別を中国のバーダーなどが行っていて (都会地で記録するのでも十分だそうである)、ツグミ類まどをほぼ種レベルまで同定できるようになりつつあるらしい。
ツグミ類のさえずりは繁殖地以外で聞く時は完全なものではないようである。そのため判別が難しく、シロハラ、アカハラ、マミチャジナイが同時に見られる春の渡りでは聞き分けに苦労する。シロハラは越冬時は4声のフレーズの後にツィーのパターンと考えているが、完全なさえずりを聞くとあまりに違うので声による識別は悩ましい。
マミチャジナイのみは比較的区別しやすい (2つや1つの短めのフレーズで少し軽い感じがする) とされるがこれも渡り途中のものが中心なので繁殖地でも同等かどうかはわからない (繁殖地でのさえずり記録も少ない)。このタイプのさえずりがあって、その場合はマミチャジナイと判定できる程度に捉えておくのがよさそうである。
-
シロハラ
- 学名:Turdus pallidus (トゥルドゥス パルリドゥス) 青白いツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:pallidus (adj) 青白い
- 英名:Pale Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
pallidus は pal-li-dus と分割され冒頭にアクセントがある (パルリドゥス)。
Turdus daulias Temminck, 1831 の記載がある (参考) 日本に生息して雌雄ほぼ同色とある。Fauna Japonica の図版。
Turdus pallidus Gmelin, 1789 (原記載) 基産地 Sibiria, ultima lacum Baikal (シベリア) の方が早く、Temminck の日本での記載は学名に残らなかった。
現在シノニムとしても現れないので、あるいはこの記載ではシロハラと特定できなかったのかも。
Hartert (1910-1922) p. 655 には他のシノニムもあって Turdus advena Swinhoe, 1860。advena はよそ者、外国人などの意味だが、Hartert によれば daulias を書き間違えたものだろうとのこと。
Turdus obsoletus Brehm, 1862 (参考) があり、基産地は日本としている。obsoletus は退色した、忘れられたなどの意味。
残念なことに Turdus obsoletus Lawrence, 1862 (参考。パナマ) の用例があってこちらの方が若干早かったらしく、Hartert (1920) はこちらの学名を用いて南米の亜種の記載を行った。上記 p. 655 には preoccupied となっていないので後に気づいたものだろうか。
いずれにしても遅い記載なので日本は基産地とならなかった。もっとも主な繁殖地を考えると Turdus pallidus Gmelin, 1789 が妥当だったとも言える。
Kolyada et al. (2016) によれば何を指して青白いと呼ばれるかはカラアカハラに対する比較とある。この文献では上面の色がより白っぽいことを根拠としている。
日本の限られた地域で繁殖する (広島県、対馬)。上野 (2015) 広島県のブナ林で繁殖するシロハラ Birder 29(2): 22-23。臥龍山とのこと。単形種。
Shokhrin et al. (2023) Breeding birds of Primorsky Krai: the pale thrush Turdus pallidus (pp. 4753-4744)
ロシア沿海地方の繁殖生態。
-
アカハラ
- 学名:Turdus chrysolaus (トゥルドゥス クリュソラウス) 金色のツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:chrysolaus (合) 金色のツグミ (chrysos 金色の laios ツグミ Gk)
- 英名:(Brown Thrush), IOC: Brown-headed Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
chrysolaus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる (クリュソラウス)。-laus は2音節と取り扱った。
-laus 部分のギリシャ語 laios の元来の意味はイソヒヨドリとのこと (wiktionary)。
現行の学名で -laus をこの意味で用いているものはこの1件のみ。Turdus 属には多数の記載があり、ありふれた種小名を用いると過去の用例と重複する可能性があるため珍しい用例となったのだろうか。
chryso- まで用いた Turdus 属の種小名はこの時点ですでに複数あった。
Temminck 自身も Turdus chrysorhoeus Temminck, 1822 (こちらは "金色の腰" の意味) をすでに用いていたがこの学名は現在使われていない。
The Key to Scientific Names の解説によればおそらくコシジロヒヨドリ Pycnonotus aurigaster Sooty-headed Bulbul と同一のようだがシノニムリストに現れず有効な学名ではなかったのかも知れない (現在有効な亜種名 chrysorrhoides に痕跡がある)。当時はたくさんの種を記載する必要があって数あるツグミ類の1つで個々にはあまり考えていなかったかも。
Hartert (1910-1922) p. 656 では Turdus jouyi Stejneger, 1887 (参考) のシノニムがある。富士山で Jouy が採集したもの。
一時期はシロハラの亜種とされていた。シロハラの記載の方が早いため同種扱いの場合はシロハラの亜種になる。
Dement'ev and Gladkov (1954) はこの扱いで、シロハラ、アカハラ、マミチャジナイが同種となっていた。
英語別名の Brown Thrush はこの同種時代に使われたものか不明だが、チャイロツグミモドキ Toxostoma rufum Brown Thrasher にも使われていた名称で混乱を防ぐため現在はそれぞれ別の英名で呼ばれている。
アカハラの由来は、と改めて聞く必要はなく何をいまさらと言われそうだが、不思議なことに英語別名にそのままずばりの Red-bellied Thrush が存在する (コンサイス鳥名事典より)。アカハラの和名から訳したもの、とも感じられるがもしかするとアカハラの由来と英名に関係があるかも知れない。
ほとんど同じような名前のナンベイコマツグミ Turdus rufiventris Rufous-bellied Thrush があり、この種の現在の英名は学名の意味そのままであるが、Red-bellied Thrush とも呼ばれていたとのこと (ブラジルの国鳥)。この英名も学名を訳したものと推定できる。これは地理的にも遠くアカハラと混同されることはないだろう。
ナンベイコマツグミの方は東洋の "Red-bellied Thrush" と紛らわしいために英名が変更されたのかも知れない。
さらにほとんど同じ意味の Turdus erythrogaster Boddaert, 1783 (文字通り "アカハラ" の意味) があってこれはセネガルとあるので関係ないが現在のどの種に対応するかは確認できず。
Turdus erythrogaster Vigors, 1832 (これも "アカハラ" に相当) の用例もあり、これは Boddaert がすでに使っているので無効学名だが、カオグロイソヒヨドリ 現在の学名で Monticola rufiventris Chestnut-bellied Rock-Thrush に対応するとのこと
[参考: McAllan and Bruce (2002) Systematic notes on Asian birds. 27.
On the dates of publication of John Gould's "A Century of Birds from the Himalaya Mountains"]。
一方気になる学名があって Turdus hypopyrrhus Hartlaub, 1844 でこれは "下面が赤い" の意味。記載されたのはジャワ島 (参考) で、"広義シロハラ" の越冬地にも近く、もしかすると混同されていた可能性もあり得るかも (アカハラも繁殖地でなく越冬地で記載されることもあり得るので)。
Temminck によるアカハラの記載は 1831 年とそれほど違わない。
この hypopyrrhus は Island Thrush から分離されたばかりの Sundaic Island Thrush Turdus javanicus の亜種 fumidus のシノニムとされているが英名に影響を与えた可能性は不明。
世界中に腹の赤いツグミのような鳥はたくさんあって (ここに示されていないものもまだあるかも知れない) どれを指して "Red-bellied Thrush" とされたのかはよくわからなかった。和名から訳された可能性も否定できない感じがする。
なお Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではアカハラの和名には別名がなく、由来になりそうなアカジナイの和名はツグミの別名となっていた。
日本周辺にのみ分布。2亜種がある: chrysolaus アカハラ (北部、中部日本で繁殖して渡る) と orii オオアカハラ (サハリン、千島で繁殖して冬鳥として渡来する。基産地パラムシル島)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)には亜種不明がリストされている。
サハリンの亜種については数も少ないらしくあまりはっきりしない [上記分布の記載は H&M より。Brazil (2009) ではサハリンの亜種について言及がない。Dement'ev and Gladkov (1954) ではサハリンは日本と同亜種となっている]。
記載時学名だけを見ておくと、
・Turdus chrysolaus Temminck, 1832 (原記載) 基産地 日本 参考
・Turdus chrysolaus orii Yamashina, 1929 (原記載) 基産地 Paramushir Island, northern Kurile Islands (パラムシル島、千島列島北部)
参考 によると
Temminck (1831) では Turdus chrycolaus と綴られていたとのこと。chrysolaus は修正した学名とのこと (参考)。
上記図版には Merle chrysolaus となっているが、学名・フランス語名ともに chrycolaus を使っているのでこの当時は誤解していたのだろう。脇腹の赤が特に鮮明であるとの記載になっている。
[Turdus 属の分類]
アカハラグループを含むツグミ類の現代的な分子系統解析が Reeve et al. (2021)
The Sulawesi Thrush (Cataponera turdoides; Aves: Passeriformes) belongs to the genus Turdus
にある。この研究ではアカハラ、マミチャジナイ、カラアカハラの3類似種について核遺伝情報 (UCE) も解析しており調べられた種類に対しては精度が高い。これらがヨーロッパのクロウタドリと別クレードになることは間違いなさそうである。
伝統的な遺伝子によるツグミ類の分子系統も出ている。
遺伝情報はこの研究によるものではないが、ツグミとハチジョウツグミ、ノドアカツグミとノドグロツグミはそれぞれ系統がかなり近く、亜種レベルの違いにかなり近い。
一方非常に多くの島の亜種を含むハイガシラツグミ (タイワンツグミが分離された。下記参照。ハイガシラツグミの和名もあまり適切でないので見直した方がよさそう。英名の方がふさわしいので以下 Island Thrush とする) Turdus poliocephalus Island Thrush は亜種ごとの違いが大きく、例えばアカハラとアカコッコぐらいの違いがある。
ツグミとハチジョウツグミを別種とする基準であればは Island Thrush 多数の種に分離される可能性がありそうである (調べられているのは5亜種のみだが IOC 14.1 によれば絶滅亜種も含めて 45 亜種以上ある)。
近い将来にツグミ属の種数が膨大に増える可能性がある。
一方でこの論文の主題であるセレベスツグミ Cataponera turdoides Sulawesi Thrush は現在の Turdus 属に内包されることがわかった。
Reeve et al. (2023) Population genomics of the island thrush elucidates one of earth’s great archipelagic radiations にさらに新しい研究が出ていて予想通りすごいことになっている。
Island Thrush は系統 A-L まであってどこまで種に分けるのか。祖先系統のフィリピンのミンドロ島のはおそらく別種相当、ルソン島もおそらく同様。また未記載の亜種相当がいくつも見つかっている。
#メジロ備考の [Great Speciator] に匹敵する状況になっている。
これらはフィリピンを発祥の地として島ごとに (亜) 種分化したと考えられる。
Clements 2024, IOC 14.2 とも草稿段階でこれらを 17 種に分離 (世界のリストの統合化に向けて分離数を合わせたのだろう)。This is a fairly conservative treatment and more splits may eventually be expected. とあり、種数は将来さらに増えると考えられる。
Island Thrush と日本の他のツグミ類は同じ系統で、日本産の他のツグミ類も同様に調べられれば分離されるものが出てくるかも知れない。
東アジアのツグミ類も一部調べられていて {アカハラ + アカコッコ}、{シロハラ + カキイロツグミ Turdus feae Grey-sided Thrush + マミチャジナイ} がそれぞれ系統をなして、これら5種が近縁系統のグループになる。
タイワンツグミ Turdus niveiceps Taiwan Thrush は Island Thrush に含まれていたが、この論文では別種。分子系統樹でも遠く離れている。
Island Thrush もアカハラやシロハラに近い系統で分岐年代 240 万年程度。Island Thrush 内の (亜) 種分化は 110-150 万年前程度。Island Thrush が比較的冷涼な気候の場所に山地に生息するのは祖先の性質を引き継いだものか。渡り個体群から島に定着した可能性、現在は絶滅した大スンダ列島 (インドネシア) の個体群からフィリピンに定着した可能性の両方が考えられる。
同じようなパターンを示している種としてムネアカヒタキ Ficedula hyperythra Snowy-browed Flycatcher グループがあり、これらも多数の亜種を持っている: Pujolar et al. (2022) The formation of avian montane diversity across barriers and along elevational gradients。
Ficedula 属の種分化はヨーロッパでよく調べられて有名であるが、むしろこちらの方が Ficedula 属の種分化中心地のよう。
Boyd はまだこれら論文を取り入れていないのか伝統的な分類に近いものになっている。
現在の Turdus 属はすでに非常に大きなものなので、セレベスツグミの系統上の位置や生物地理学の特殊性も含めて大きなクレードを別属に分離する考えも出てくるかも知れない。そのような目で (伝統的な遺伝子による結果であるが) 系統を分けてみると、
[Reeve et al. (2021) の系統樹による]
系統 1:
ウタツグミモドキ Turdus litsitsirupa Groundscraper Thrush
チベットウタツグミ Turdus mupinensis Chinese Thrush
系統 2:
ウタツグミ Turdus philomelos Song Thrush
ヤドリギツグミ Turdus viscivorus Mistle Thrush
系統 3:
(ヒガシクロウタドリ) 第8版でクロウタドリ Turdus mandarinus Chinese Blackbird
(クロウタドリ) 新和名不詳 Turdus merula Common Blackbird
ワキアカツグミ Turdus iliacus Redwing
などそれなりに大きな系統
系統 4:
セレベスツグミ Cataponera turdoides Sulawesi Thrush
系統 5:
日本産の他のツグミ類、Island Thrush など
のような分離が考えられる。系統は分子系統樹から自分が与えたもので論文に記されているものではない。
系統 1-3 に異なる属名を与えればセレベスツグミの特異な位置と属名を保持できることになる。
1種を移動して大きな属を保持するか系統分割するかの違いになる。IOC では前者の扱いで Turdus turdoides にすでに変更しているが多くのリストで Cataponera のままになっている。
このような場合は分類群によって両方の扱いがあり、大きな属を残しても構わない扱い (Phylloscopus 属など) や細分化する扱いなどさまざまである。ウタツグミやヤドリギツグミを見られた方ならば日本産ツグミ類との雰囲気の違いからこの分類に納得していただける方もあるのではと感じる。
もし分割するならば Turdus 属のタイプ種がヤドリギツグミなので、系統2の2種のみが Turdus 属となるが、これは確かに西欧人には受け入れにくいかも知れない。
生物地理的に 系統 5 を独立させるなど Turdus 属を分子系統研究に基づいてもし分割すれば日本産の種の大部分は Turdus 属でなくなる。
Batista and Olsson (2020)
Phylogenomics and biogeography of the world's thrushes (Aves, Turdus): new evidence for a more parsimonious evolutionary history
は主なクレードを5つに分けているが、Reeve et al. (2021) では系統樹の形が異なる (例えば南米のものは単系統かどうか結果が一致していない) のであまり強い結論にしていないかも知れない。
しかしウタツグミやヤドリギツグミ (Turdus 属のタイプ種) が古い系統に属することはどちらも同じ結果となっている。
Boyd がどのように反映するかを見てみたい。
-
アカコッコ
- 学名:Turdus celaenops (トゥルドゥス ケラエノープス) 黒ずんだ顔つきのツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:celaenops (合) 黒ずんだ顔つきの (kelainopos 黒ずんだ < kelainos 黒 Gk ops, opos 顔つき Gk)
- 英名:Izu Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
celaenops は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は -ops の o が長音のため該当部分を伸ばすと考えられる。-ae- が2重母音でここにアクセントがあると考えられる (ケラエノープス)。
単形種。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" には Seven Islands (Terra typica), Suruga!! と記述され、駿河で記録されることが驚きとされていた模様。
この時代はヤクシマアカコッコを別亜種 yakushimensis として基産地 Yakushima (Terra typica) と記述されていた。
この記載時学名 Turdus celaenops yakushimensis Ogawa, 1905 (原記載)。
「原色日本野鳥生態図鑑」(中村登流・中村雅彦 保育社 1995) p. 74 ではアカコッコがアカハラよりムナグロアカハラ Turdus dissimilis Black-breasted Thrush (中国南部から東南アジア) に類似していることから、この系統がかつては広く分布していたものが離散分布となった遺存的なものとみなしていたが、現代的な分子系統解析では支持されていない。
#クロウタドリ備考で参照の Turdus-Project を参考にすると、アカコッコとアカハラは近く、ムナグロアカハラはカラアカハラに近く地理的に系統がまとまっている。特に遺存的要素は見られず、色彩で系統を議論するのは危険であることがわかる。
-
ノドグロツグミ (分割され学名も変わった)
- 第8版学名:Turdus atrogularis (トゥルドゥス アートログラーリス) のどの黒いツグミ
- 第7版種学名:Turdus ruficollis (トゥルドゥス ルーフィコルリス) 赤い首のツグミ
- 第7版亜種学名:Turdus ruficollis atrogularis (トゥルドゥス ルーフィコルリス アートログラーリス) のどの黒い赤い首のツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 第8版種小名:atrogularis のどの黒い (ater 黒 gularis のどの < gula のど)
- 第7版種小名:ruficollis (adj) 赤い首の (rufus (adj 赤い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 第7版亜種小名:atrogularis のどの黒い (ater 黒 gularis のどの < gula のど)
- 英名:[Dark-throated Thrush 分割前], IOC: Black-throated Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
atrogularis は -la- の a が長母音でアクセントもここにある (アートログラーリス)。atro も ater 由来で冒頭が長母音。
ruficollis は ru-fi-col-lis と分割され冒頭は長母音。アクセントは -col- にある (ルーフィコルリス)。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
もとノドグロツグミは2亜種 (ノドグロツグミ、ノドアカツグミ) あり、後者を採用していた。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で別種となり、ノドグロツグミ Turdus atrogularis の学名を採用。
ノドアカツグミ Turdus ruficollis は同定根拠が十分でないため検討種となった。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。
それぞれの記載時学名は、
・Turdus ruficollis Pallas, 1776 基産地 Dauria [= Transbaicalia] (Avibase による)
・Turdus atrogularis Jarocki, 1819 基産地 Poland (Avibase による)
で、Turdus ruficollis の方の記載が早いので亜種扱いの場合は Turdus ruficollis atrogularis のような学名となっていた。
記載当時は亜種概念は確立されておらず、このような学名とせざるを得ない部分もあったので、記載時は別種扱いと読むのはあまり正確でない。
当初はおそらく現在の英名と同様に学名に従って Black-throated Thrush, Red-throated Thrush の名称が使われていたと想像できる。和名も学名か英名から訳されたと想像できる。
同種扱いとなり名称を前者にまとめることは不自然なので、同種時代の名称として Dark-throated Thrush が導入されたと推定できる。
同種時代の種和名を決める際に、国内では atrogularis の方のみ認めれられた記録があったために種和名は基亜種名ではなくノドグロツグミとなったと推定できる。第8版目録でもノドアカツグミはまだ検討種。#オジロビタキと#ニシオジロビタキと似た事例だが、オジロビタキとニシオジロビタキは現在では両種とも第8版目録に含まれている点が異なる。
ノドアカツグミは目録記載種ではないのでまだ亜種とみなして記録を付けてしまう可能性があるが、これは第7版時点のオジロビタキとニシオジロビタキと同様。第7版時点でニシオジロビタキはすでに別種で記録がまだ公認されていなかっただけで、種名を記述する場合はニシオジロビタキと呼ぶのが正しかった。種小名の変化をきちんと追えばこのような間違いを避けることができる。
またノドアカツグミのみを観察し、第7版時点の分類に従ってノドグロツグミと記録している場合、第8版の日本産種目録に従った場合は検討種に移動となって記録種が1種減るので注意。単に日本産と認められる論文が発表されているかだけの問題であるが。
-
ツグミ (分割され学名も変わった)
- 第8版学名:Turdus eunomus (トゥルドゥス エウノムス) よく整ったツグミ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Turdus naumanni (トゥルドゥス ナウマンニ) ナウマンのツグミ
- 第7版亜種学名:Turdus naumanni eunomus (トゥルドゥス ナウマンニ エウノムス) よく整ったナウマンのツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 第8版種小名:eunomus (adj) よく整った (eu よい nomos 使い方、習慣 Gk) はっきりしたまだら模様を指したと考えられる (The Key to Scientific Names)
- 第7版種小名:naumanni (属) ナウマンの (ドイツの鳥類学者 Johann Andreas Naumann。学名に名前を残した Naumann の名の鳥類学者は複数いるので注意)
- 第7版亜種小名:eunomus (adj) よく整った (eu よい nomos 使い方、習慣 Gk) はっきりしたまだら模様を指したと考えられる (The Key to Scientific Names)
- 英名:Dusky Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
eunomus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音なので短母音で読まれると考えられる。ギリシャ語では no-mos と区切り、その場合アクセントは "エウノムス" と想定される。[種小名の解釈] の項目も参照。
なおギリシャ語では -nomos の語尾の合成語でも -no- にアクセントがある。ここではラテン式アクセント規則を採用した。
種が分離されて種小名を使う機会も増えると考えられるのでこの機会に注意していただくとよいだろう。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
亜種ツグミ と 亜種ハチジョウツグミ は日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版ではいずれも種 (ともに単形種) となる。これまでツグミ (種) の学名として使われてきた Turdus naumanni はハチジョウツグミを指すことになるので注意。
Turdus naumanni Temminck, 1820 (原記載) 基産地 Silesia and Austria, Hungary (Avibase から。生息地の記載はさらに広く原記載を参照)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では学名 Turdus fuscatus となっていた。当時はツグミとハチジョウツグミは別種扱いだったため別の和名があってもまったく問題なかったのだろう。
その後ツグミとハチジョウツグミが亜種の関係となり、ハチジョウツグミが基亜種となる状況が生じて一時的に和名との関係がわかりにくい状況になったものと思える。新分類で分離されて元の状態に戻ることになる。
ハチジョウツグミが基亜種となる時代でも英名は一般的に Dusky Thrush の方が使われていた。
[ツグミとハチジョウツグミの学名の成り立ち]
学名の扱いは単純でなく、ロシアやアジアの鳥で非常に頻繁にあったことだが、ツグミも含めてシノニム関係が複雑だった。
Gould Turdus fuscataus, Pall. および
Species Myiagra (Seisura) inquieta (Latham, 1801)
によれば、
Turdus dubius (疑わしいツグミ) は2名が付けており、Naumann と Bechstein (1795) による。Temminck は後者がノドグロツグミの羽衣の一つと判定した。
Turdus dubius Bechstein, 1795 (参考)、
Turdus dubius Latham, 1801 (参考)、
Turdus dubius Bechstein, 1802 (参考) が該当するもの。
ノドグロツグミは (亜種名だった時代) Turdus ruficollis Pallas, 1776 の学名が先に与えられていたため、ノドグロツグミに対する Turdus dubius はシノニム相当 (シノニムと呼べるかどうかは規則を詳しく知らないのでわからない) となる。
Temminck は混乱を避けるために改めて Turdus Naumanni と命名したとのこと。
Bechstein が同じ名称を別のものに使っていたため生じた問題で、最初に正しく記載した Naumann を正当に残すために種小名に採用したことが推定される (同様の事例に #オオジシギ がある)。
Turdus dubius Naumann の方が記載が早い (1804) のに採用されなかったのはこの理由のよう。
これらを除いて当時最も早い記載と考えられたものは Turdus fuscatus Pallas とのこと (fuscatus 黒っぽい)。
Gould のこの記述では Turdus fuscatus が用いられているが、Pallas の記載年を記していない。Dusky Thrush (Historical Rare Birds)
の記述によれば Pallas の記載の方が遅かったとのこと。
[Bull B.O.C. 1981 101(4)] の記述によれば Pallas の命名は Zoogr. Rosso-Asiat., 1, Taf. 12 (1811) とのことで、この学名は Turdus fuscatus Vieilot, 1808 の用例 (原記載) ですでに使われており無効となった。
これは現在オオウロコツグミモドキ Margarops fuscatus Pearly-eyed Thrasher を指す。
結果的に Turdus fuscatus はツグミまたはハチジョウツグミの学名として残らず、Turdus dubius は異なる著者が別のものに使ったためあるいはノドグロツグミのシノニムに相当するとして混乱を避けるため除外され、記載は遅いが Turdus naumanni Temminck, 1820 が残った経緯となる。
種ツグミはさらに遅く (1831) 同じく Naumann によって記載されたため亜種時代はハチジョウツグミが基亜種だった。Turdus eunomus Temminck, 1831 (記載) 基産地日本。
Ogawa (1908) にあるように Turdus fuscatus の学名はかなり長く使われていたようで英語の Dusky Thrush の由来はこの種小名由来と想像できる (Gould は Clouded Thrush を用いていた)。
アメリカでも英国でも馴染みの鳥ではないので学名をそのまま訳したものが使われていたのだろう。
Pallas による古い学名は英名にのみ痕跡を残したことになる。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire が Merula fuscata の学名と英名 Dusky Ouzel を用いていた。
Hartert (1910-1922) p. 658 でも Turdus fuscatus を用いていたが、後に preoccupied であることを知って p. 2159 Turdus eunomus を使うべきとした。
Dement'ev and Gladkov (1954) では Turdus fuscatus Pallas、1811 をシノニムとしているがすでに使われていて無効となっている (nomen praeoccupatum)。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではツグミはハチジョウツグミの亜種扱い。
ハチジョウツグミはシノニム Turdus abrekianus Taczanowski, 1876 (オホーツク海沿岸の Abrek 湾由来) が挙げられているが記載時期も遅くあまり問題にならなかった模様。
[種小名の解釈]
種小名の意味は「野鳥の学名入門」(菊池秀樹) のオリジナルの解釈では eunomus (adj) よい旋律の [eu (int) よい nomus (m) 旋律] で、これもツグミ類の声の表現としてもっともらしいが、ツグミのよい旋律を聞くことは後述のように容易ではなく、原記載にも現れないため The Key to Scientific Names の解釈を採用した。
Merle Eunome Temminck の記載では模様について細かく述べられているが声への言及はない。
日本産とあるが和名についての言及はない。Temminck はハチジョウツグミを先に記載しており、それに比べても模様の特徴が目立って見えたと考えられる。
現行の学名を調べるとギリシャ語由来の「よい」の意味の) eu- は (ほぼ?) すべてギリシャ語と結合し、nomus はギリシャ語由来と考えられる (逆に ラテン語接頭語 + ギリシャ語 の学名は多数ある)。
ギリシャ語にも nomus の綴りの語彙は存在するが "名前" の方の変化形になる。
ギリシャ語の nomos にも音楽用語では旋律の語義は存在するが日本語ではむしろ "律法" に相当する概念でやはり秩序に由来している。また eunomos の語彙があり以下の Eunomia と同語義とのこと。
古ギリシャ語 Eunomia 法の秩序、よく整った の意味。Temminck が用いたフランス語 eunome そのものは通常使われる語ではないが同じような意味で用いたと推定できる (英語に同系の eunomy の単語がある。法の秩序の整った状態を指すらしい)。ツグミの wikipedia 英語版では "orderly" を紹介している。
どちらでもよいような細かい話に思えるが、ラテン語かギリシャ語かを追求する必要性は -nomus の o を伸ばすか、アクセント位置をどこに置くかに関連する。ラテン語であれば nomus の o は長母音だが意味も合わず、eu- + ラテン語の学名の確実な用例が見当たらないためここでは却下した。ギリシャ語由来であれば伸ばさずアクセントも冒頭になる。
"エウノームス" と伸ばしてアクセントを置くのは言語由来的には正しくないことになる。
[他言語名]
原 (2024) Birder 38(4): 43 で夜に渡るツグミの翼の下面が赤く見えることから、この姿を見れば英語の Dusky Thrush とは名付けなかったのではないかとも紹介しているが、現代のフランス語では Grive a ailes rousses で翼の赤褐色のツグミ (roux 赤褐色、赤毛のなど) のような意味になってしっかり反映されている。
ドイツ語でも錆色の翼のツグミになっていて他の多くの言語も褐色やシベリアのなどを使っている。
ヨーロッパのほとんどの国にとって東洋の縁の遠いツグミのよう。
しかしハチジョウツグミは錆色の尾のツグミになっていたり、スウェーデン語のように赤と褐色を使い分けるなど色による呼び名はそう単純ではない模様。
英語でも Brown Thrush の名称はあったようだが前述のようにおそらく古い学名由来で、褐色のツグミは多数あって紛らわしいので Dusky Thrush に統一したのかも知れない。
[亜種ニツグミ]
かつて亜種ニツグミが記載されたことがあった。Turdus eunomus ni Momiyama, subsp. nov., 1927。"ni" は (ツグミに) 似ているの意味 ("Ni" is a Japanese and means resemblance or likeness in English と記載論文に脚注)。暗色の個体を指していた。現在は Turdus eunomus のシノニムとされる。
もし亜種として認められていれば ma (#ミヤマモリフクロウ の亜種) とともに最短の亜種小名となっていたと思われる。
茂田 (1992) Birder 6(12): 36-41 「ニツグミとは何か」の記事がある。
日本人の手によって記録された鳥類 (Marquess Hachisuka 蜂須賀 1942) の一覧があり、当時の多数の亜種などを読み解く参考になりそう。
Johansen (1954) が現在の種ツグミのうち西部個体群 (基産地 Dudinka, on the lower Yenisei) がやや大型であることから Turdus naumanni turuchanensis (当時の亜種名) と分離したが、
Vaurie (1955) Systematic notes on Palearctic birds. No. 15, Turdinae, the genera Turdus, Grandala, and Enicurus
によれば計測値が重なり、東の個体群が小さいわけではないと否定的見解を示した。
[ツグミと近縁種の分布]
ツグミ類の系統樹 (クロウタドリの項目参照) では、ツグミ、ハチジョウツグミ、ノドグロツグミ、ノドアカツグミは従来考えられていた通り近い関係にある。分布も重なっている。4種の分布関係については森岡 (1999)「ノドアカツグミとハチジョウツグミ」 Birder 13(1): 62-65 参照。
Young Guns (2013) Birder 27(5): 42-44 にも分布図とともに中間型と思われる個体の写真が掲載されている。
ハチジョウツグミはシベリアでも比較的南方で繁殖するが、我々が普通にみかけるツグミはシベリアでも北方 (森林限界近くまで) で繁殖し、ロシアでもツグミは人里離れたところで繁殖する。そのため巣の観察も容易でなく、巣の発見が論文報告されるぐらいである。ただし巣そのものや繁殖生態は他のツグミ類に似ている。
福田 (2022) Birder 16(5): 6 にツンドラのツグミの巣の写真が紹介されている。
本格的なさえずりの記録も難しく、繁殖地でのさえずり音源もあまりない。日本での数の多さから、シベリアに行けば普通にいる印象を受けがちだが、実情は大きく異なっている。日本で渡去前に聞かれる「ぐぜり」と本格的なさえずり (サンプル数は少ないが) は少し異なっているようである。
ハチジョウツグミの方がまだ人里近くであるが、人口密度の低い地域であり、繁殖地でのさえずり音源もやはりあまりない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではさえずりの記載はあるが抽象的なので省略する。暁と白夜に最もよくさえずるとのこと。分布域の範囲はよく調べられておらずよくわかっていない。より南で繁殖するハチジョウツグミの方がよくわかっている。
2016 年に英国に現れた珍鳥ツグミにウオッチャーが集まる状況が報道されている:
Amateur's ultra-rare sighting of Siberian dusky thrush brings hundreds of birdwatchers to Derbyshire village (Tom Ough, The Telegraph 2016)。
有料駐車場の写真もある: Birdwatchers in Beeley to see 'very rare' dusky thrush (BBC 2016)。
観察者の言葉では「アジアに 20 回行っているが見たことのない珍鳥だ」が紹介されているが、多くのバーダーは繁殖期などを狙って訪れるためか冬場に記録されるアジアの鳥をあまり見ていないこともある。
ツグミは結構遅い時期まで残っているので、これだけの回数訪問して出会っていないのも不思議な気がするが。
[ツグミとカスミ網]
市田 (2005) Birder 19(2): 76-78 がカスミ網密猟の根源を断て、と題して販売禁止に至った経緯を振り返られているので紹介しておく。1947 年に使用が禁止されたが販売は禁止されていなかった。
販売禁止に至る前は当時の通産省の見解によれば「使ってはいけないものが売れるはずはない。したがって販売禁止にする必要はない」とのものだった。市田氏も後になって考えると法律の論理としては理解できると述べられている。
1970 年に5万人の署名を添えて国会に請願した「カスミ網の一般販売禁止」も国会で採択されたものの何も変わらなかったとのことで、当時の環境庁も販売禁止は無理だと考えていたとのこと。
日本野鳥の会は一般販売禁止に向けて 39 万人の署名を集めたが環境庁の担当管は法律的には意味がないし、捨てるのがたいへんとつぶやいたとのこと。
国際鳥類保護連盟 (ICBP、BirdLife の前身) の 1990 年世界大会でカスミ網の販売に対する法規制を日本政府に勧告する決議を提案し、決議採択となった。環境問題に関する国際的な批判に敏感な日本政府の対応は早かったとのこと (抜粋でニュアンスを伝えるのは難しいので詳しくは記事をお読みいただきたい)。
日本野鳥の会推薦図書として「ツグミたちの荒野」(遠藤公男 講談社 1983) を読まれた方も多いのではないかと想像する。
この本の pp. 121-124 に岐阜大学学長の I 氏は、のちに文化勲章をもらった動物学者だが、1967年11月、朝日新聞の「東海随想」に
「近ごろ新聞に、ツグミを捕って検挙されたという記事がときどき出る。なんと腹の立つことか。(中略) こんな愚かな法律を設けて、いつまでも国民をしばっていることに腹が立つのだ。(中略) こんなにたくさんいるツグミを、なにも禁鳥にしなくても...。(中略) 現在の押し付けられた屈辱的な法律を変えずにいることのほうが、むしろ、われわれの文化の低さをあらわしていることになりかねないのである」
なんとも、あきれ果てた説である。これが動物学者として権威ある人の発言なのだ、と遠藤氏は記している。
この I 氏というのはもちろん今西錦司氏のことだが、今西錦司氏の追悼として日本の動物学者の間での反応がアニマ 1992年10月号の対談 (pp. 13-19) でふり返られている。それで「今西さん大変やったでしょう」と言ったら、「そやねん。いっぱいアホみたいな手紙が来て。あいつらみんなアホや」と答えたと述べられている (河合雅雄氏発言より)。
同席した日本の動物学者が自然保護運動をどのように見ていたかが読み取れる貴重な資料であるが、抜粋でニュアンスを伝えるのは難しいので資料の所在を示すにとどめておく。興味ある方はお読みいただければと思う。
カスミ網 (mist net) の wikipedia 英語版によれば、300 年近く日本で使われていたもので、Oliver L. Austin が 1947 年にアメリカの鳥類学に導入したとある。カスミ網がバンディングに非常に優れていることは Low (1957) Banding With Mist Nets で述べられている。
Cleminson (2012) Bird Banding
1950 年代日本発のカスミ網が使われるようになって捕獲効率が飛躍的に高まり、鳥類学、コウモリの研究に革命が起きたとのこと。日本の技術 (?) の鳥類学への最も大きな貢献だったのかも知れない。
日本のカスミ網猟について海外の視点では Anderson (1985) War on war on migrating birds
も読める。雑誌が Nature なのでもちろん自然保護推進路線で、当時の日本野鳥の会の活動を評価している (海外から見ると自然保護面で日本もようやく先進国的になってきた、という視点だろうか)。
環境庁は販売禁止の権限を持たず、これまでのところ通産省は販売者側に立っているとの解説になっている。理由は憶測レベルだがヘアネット業者への影響も含まれている可能性も紹介されていた。日本からの情報発信も当時は非常に少なかったのだろう。「ツグミたちの荒野」は 1983 年出版だが海外研究者の目にはとまりにくかったかも知れない。
時期も古いため、あるいは海外ではあまり関心が持たれていなかったのか、ネット上に海外の日本のカスミ網問題の情報はほとんど見当たらなかった。
ドイツ語では Japannetz、フランス語では filet japonais と呼ばれているとのこと。wikipedia では日本語のみが特殊で学術研究について触れられていない。チェコ語では ornitologicka sit で鳥類学の網 と呼ばれる。
特定の種類に関する話題ではないが、バンディングにかかわる話題なのでここに紹介しておく。2023年10月14日のアメリカの金環日食の際に過去にないほど多くの鳥がカスミ網にかかったという。
DeNiro et al. (2023) Solar Bird Banding: Notes on Changes in Avian Behavior While Mist-netting During an Eclipse (preprint)
過去にも急に夜になったと反応する生物の事例は報告されているが、これほど明瞭な反応はこれまで記述がないとのこと。夕暮れが近づいてあわててねぐらに入ろうとしたものが捕獲されたのだろうとのこと。
-
ハチジョウツグミ (分離された)
- 第8版学名:Turdus naumanni (トゥルドゥス ナウマンニ) ナウマンのツグミ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Turdus naumanni (トゥルドゥス ナウマンニ) ナウマンのツグミ
- 第7版亜種学名:Turdus naumanni naumanni (トゥルドゥス ナウマンニ ナウマンニ) ナウマンのツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 第8版種小名:naumanni (属) ナウマンの (ドイツの農家、博物学者の Johann Andreas Naumann に由来。有名な Johann Friedrich Naumann とは別人なので注意)
- 第7版亜種小名:naumanni (属) ナウマンの (ドイツの農家、博物学者の Johann Andreas Naumann に由来。有名な Johann Friedrich Naumann とは別人なので注意)
- 英名:Naumann's thrush (由来は種小名を参照)
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
naumanni は -man- にアクセントと考えられる (ナウマンニ)。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で種ハチジョウツグミTurdus naumanni。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。
和名の由来は八丈島ではない。【ハチジョウツグミ】の名前の由来は【八丈紬】の赤褐色から (あうるの森 2022) で堀田正敦編纂の「観文禽譜」を調べられた結果が紹介されている (日本語の由来を探る方が学名や英名の由来を探るよりずっと難しそう...)。
日本での初記録も八丈島ではなかった [茂田 (1992) Birder 6(12): 36-41 で紹介されている]。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" には別名のアカジナイが載せられており、色彩に注目された名称が付いていたことがわかる。
-
ノハラツグミ
- 学名:Turdus pilaris (トゥルドゥス ピラーリス) ツグミの一種
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:pilaris ツグミ pilus 髪 からの造語の際に trikhas ツグミの一種 (Gk) と trikhos 髪 (Gk) を混同して作られた (The Key to Scientific Names)
- 英名:Fieldfare
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
pilaris はラテン語で "髪の" だが発音も従うと考えれば a が長母音でアクセントを持つ (ピラーリス)。複雑なことを考えるよりはこれが単純で発音もわかりやすい。
単形種。
原記載。Linnaeus (1758) 以前から使われていた学名。
北海道で観察例が増えている。先崎・先崎 (2019) Birder 33(1): 42-43 による。2018 年には 20 羽を観察したとのこと。
繁殖地も東方に拡大傾向があるようでヤクーチアでも観察されている。
英名の語源は古英語 feldefare で < feld (野原) gefara (旅するもの) (wiktinary)。
この名称はいかにもドイツ語的なので参考までに現在のドイツ語名を見ると Wacholderdrossel となっていてほとんど関係がない。Drossel はドイツ語のツグミ類一般 (ちなみにロシア語では drozd で共通語源を持つことがわかる。ポーランド語でもこの通りに drozd と書く)。
Wacholder は植物の名前でビャクシン属 (セイヨウネズ) を指すそうである。
ノハラツグミのロシア名は ryabinnik で ryabina がナナカマド。ロシアの鳥の一般向け案内などにも非常によく出てくるお馴染みの種類のようである。
-
ワキアカツグミ
- 学名:Turdus iliacus (トゥルドゥス イーリアクス) 脇腹に特徴のあるツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:iliacus < ile 脇腹
- 英名:Redwing
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
iliacus は冒頭が長母音でアクセントは2重母音のある -lia- にある (イーリアクス)。脇腹の ile も冒頭は長母音。
腸骨の ilium も "イーリウム" (英語読みでは冒頭は短母音)、
回腸の ileum も "イーレウム" (英語読みでは冒頭は短母音)
など学術用語に派生語が多数ある。原語を知っているとアクセント位置を覚えやすい。
2亜種あり (IOC)。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では亜種 iliacus とされる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。他の亜種はアイスランドなどで繁殖する coburni。
原記載。Linnaeus (1758) 以前からこの学名があった。
ワキアカツグミの学名として同じ文献から Turdus musicus が過去に広く使われ、現在の学名が確定した複雑な経緯については#ウタツグミを参照。
Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition) も Turdus musicus の学名が用いられており、BOU が採用していた模様。相当近年までこの学名が使われていたと想像できる。
-
ヤドリギツグミ
- 学名:Turdus viscivorus (トゥルドゥス ウィスキウォルス) ヤドリギを食べるツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:viscivorus (合) ヤドリギを食べる (viscus (m) ヤドリギ voro (tr) 貪り食う)
- 英名:Mistle Thrush
- 備考:
turdus は短母音のみで "トゥルドゥス"。語源はインド・ヨーロッパ祖語の *trosdos に遡るとのこと。この語からロシア語の drozd も派生した。ウエルシュ語でホシムクドリを意味する drudwy にも残っている。リトアニア語では両者が混ざったような strazdas がツグミ類を指す (wiktionary)。
viscivorus はすべて短母音で -ci- にアクセントがある (ウィスキウォルス)。-vorus を長母音でアクセントを置きたくなるが異なる。voro は (ウォロー) で冒頭は長音でない。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。亜種不明。世界では3亜種 (IOC)。Turdus 属のタイプ種。
英語 mistletoe はヤドリギ。古英語 mistel。
Turdus 属の最近の分子系統樹は Nagy et al. (2019) Phylogeny, migration and life history: filling the gaps in the origin and biogeography of the Turdus thrushes
を参照。ヤドリギツグミはウタツグミ (日本鳥類目録第7版には含まれず、第8版に登場の見込み) ではとともに最初に分岐した種類の一つで、ツグミ類の中では最初に東南アジアからヨーロッパやアフリカに分布を広めた種類の一つと考えられる。
同じく Nagy (2020) Biologia Futura: rapid diversification and behavioural adaptation of birds in response to Oligocene-Miocene climatic conditions
のレビュー論文で世界のタカ目とスズメ目の分布と地理分布の進化を考察したものがある。それほど目新しいことを述べている印象は受けないが、これぞれの系統ごとの多様性地図が一覧できるのが興味深い。ツグミ類・ヒタキ類・ムシクイ類・チメドリ類は圧倒的にヒマラヤ地域の種多様性が高く、ここから種分化したと考えられる。
タカ類はアフリカ (と南アメリカ。ここはスズメ目のホオジロ類系統と同じく二次的に分布して適応放散したもの)。どの分布図を見ても北半球の中緯度以北は陸鳥の多様性が低く、日本は大陸から距離もあってさらに低い傾向がある。世界の多くの地域に比べて識別に悩むほど種類数が多くなく、細かい分類が注目される要因にもなるのだろう。
多くのグループが南半球で誕生または種分化を遂げていることについて小惑星衝突地点から遠かったことも理由の一つに挙げているがどうだろうか。Nagy はタカ類と Turdus 属の渡りに興味を持っていて寒冷化で渡り行動が進化したことなども取り上げているがそれほど深い議論には発展していない。
日本鳥類目録第7版では Turdus 属の最後に並ぶが、日本鳥類目録第8版 (IOC 13.2 の分類順と同じだが) ではこの系統を反映して最初に並ぶ順序になっている。
ヤドリギツグミやウタツグミを見て、日本でお馴染みのツグミ類とちょっと違う点を感じられたとすれば、この系統の違いのためかも知れない。
ヤドリギツグミの地鳴きはジジジ...という我々が馴染みのツグミ類とはかけ離れたもので、警戒音と思っていたがどうもこれが普通の地鳴きのようである。
-
ヨーロッパコマドリ
- 学名:Erithacus rubecula (エリタクス ルベークーラ) 赤い尾の小鳥
- 属名:erithacus (m) 不明の小型の冬鳥を指していて、おそらくヨーロッパコマドリのこと。夏には別の鳥 (例えばジョウビタキ類) になると考えられていた < erithakos (Gk) 不明の小鳥でおそらくヨーロッパコマドリやジョウビタキ類のような赤い鳥を指していた。
フランス語で "Rouge-gorges" (「赤い喉」の意味) = Erithacus (Cuvier 1800) とのこと (The Key to Scientific Names)。
「孤独な鳥」とコンサイス鳥名事典にあるが対応する語源は見つけられず。
- 種小名:rubecula (f) 赤い尾 cf. rubeo 赤くする culus 後ろ? 別説あり
- 英名:Robin, IOC: European Robin
- 備考:
erithacus は短母音のみで規則通り -ri- にアクセントがある (エリタクス)。
rubecula は e と u が長母音で古典式に発音すれば "ルベークーラ" のアクセントと考えられる。
erithacus の単語の由来は完全には明確でなく、Theodorus Gaza がアリストテレスの Historia animalium (1476) を翻訳する際に導入したものと考えられている。
Gaza は属名に対応するギリシャ語の別綴り eruthakos を eruthros (赤) + thakos (座る、とまる) と解釈した可能性があり、culus (クールス。後ろから尾) を構成した解釈があるが、不規則に作られた指小辞由来で -culus の解釈もあるとのこと (wiktionary)。長音文字が使われることから前者の方がよりもっともらしい。
指小辞由来の -ulus は長音で読まないが rubecula は指小辞由来ではない (可能性がある) ためこの綴りでも長音で読む。
この解釈によれば種小名は属名を分解して作られたものでどちらも "赤" を基調とした意味になる。
rubecula は形容詞でなく女性名詞。文法上の性は avis (鳥) の性に合わせた可能性があると wiktionary にある。
なおこの属名は思わぬ種の種小名となっている: ヨウム Psittacus erithacus Grey Parrot なんとこの種小名は Linnaeus (1758) が用いており、ヨーロッパコマドリの属名の用例より早いのでこちらの方が本家かも (?)。
同じギリシャ語名は人の声を真似ると言われた鳥にも用いられていたとのことで、使われた当時はクロジョウビタキ (またはシロビタイジョウビタキ) を指していたとの解釈がある (これらジョウビタキ類は人懐こいことはヨーロッパでも有名。鳴きあって楽しんだ人はあるのではないだろうか)。
これを由来としてヨウムにつけられたと解釈されているとのこと (The Key to Scientific Names)。
ヨウムにも赤い部分があるので関係があるのかと想像したが別語源のよう。
記載時学名 Motacilla Rubecula Linnaeus, 1758 (原記載) と種小名は名詞扱いで大文字で始まっている。
erithacus は男性名詞なので形容詞と考えると性が一致していないように見えるが、名詞の種小名のため変化させない。Erithacus rubeculus と変化させていたこともあった (例えば Johann Friedrich Naumann の図版に現れる)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。亜種不明。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。世界では9亜種 (IOC)。
世界のリストにはまだ反映されていないようだが、亜種から独立種への昇格が提唱されているものがある。
Erithacus superbus (テネリフェ島)、
Erithacus marionae (カナリア島)。
参考: Sangster et al. (2022) Integrative taxonomy documents two additional cryptic Erithacus species on the Canary Islands (Aves)。
これらが種となれば Erithacus 属は3種でヨーロッパコマドリは7亜種となる。
Zhao et al. (2023) A near-complete and time-calibrated phylogeny of the Old World flycatchers, robins and chats (Aves, Muscicapidae) に旧世界ヒタキ類のほぼ完全な分子系統樹が出ている。
Ornithologists Unveil Family Tree of Old World Flycatchers, Robins and Chats
の一般向け記事も参考。
これによると (新) ヒタキ科は4つのクレード (亜科) に分類される。この論文の記載順に並べると以下のようになる。この新分類で用いている属の和名は日本鳥類目録改訂第7版および日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で改訂されたものによっており、第7版でそれぞれの属が含んでいた範囲とは同じではない。それぞれの亜科の日本名は同じ名称の属名より推定したものを挙げておく:
Clade A: Muscicapinae (サメビタキ亜科?): Muscicapa 属 (サメビタキ属)
Clade B: Niltavinae (オオルリ/アオヒタキ亜科?、迷鳥を除いて日本で馴染みの深い種類を優先する立場であればオオルリ亜科の名前が適切かも知れない): Niltava 属 (アオヒタキ属)、Eumyias 属 (アイイロヒタキ属)、Cyanoptila 属 (オオルリ属)。
Clade C: Cossyphinae: Erithacus 属 (ヨーロッパコマドリ属、日本で記録のある種では新分類ではヨーロッパコマドリ一種のみ。過去に使われた Erithacus 属の範囲と大きく異なっているので注意が必要) [Cossypha 属は英語で robin-chat と呼ばれるアフリカの種類で一般に〜ツグミヒタキのような名前が与えられている]
Clade D: Saxicolinae (ノビタキ亜科?): Luscina 属 (オガワコマドリ属)、Calliope 属 (ノゴマ属)、Larvivora 属 (コルリ属)、Ficedula 属 (キビタキ属)、
Tarsiger 属 (ルリビタキ属)、Phoenicurus 属 (ジョウビタキ属)、Monticola 属 (イソヒヨドリ属)、Saxicola 属 (ノビタキ属)、Oenanthe 属 (サバクヒタキ属)
亜科 Niltavinae の名称は Sangster et al. (2010) Multi-locus phylogenetic analysis of Old World chats and flycatchers reveals extensive paraphyly at family, subfamily and genus level (Aves: Muscicapidae)
が従来記載のなかった分類群の新しい亜科名として提唱したものだが、Zuccon (2011) Taxonomic notes on some Muscicapidae
によればこれは 1999 年以降新たに提唱する場合の ICZN の要件を満たしておらず、無効な名称であるとのこと (wikipedia 英語版 Old World flycatcher より)。
Sangster et al. (2016) Niltavinae, a new taxon of Old World flycatchers (Aves: Muscicapidae)
でこの問題は解決しており、現在は亜科 Niltavinae の名称を使うことができる。wikipedia 英語版は Sangster et al. の出典を間違えているか情報が古いままの模様である (2016 年までは無効だった)。
Zhao et al. (2023) のこの研究はほとんどの部分が公開遺伝情報を用いて行われた解析であり、解析ソフトなどが駆使できれば誰にでも可能となっていると言える。ルリビタキやキビタキなどの系統樹での位置づけは専門機関の研究者の解析を待たなくても行える時代になってきている。
この著者たちはアメリカムシクイ科 Parulidae について同様の研究を発表している: Zhao et al. (2024)
A phylogenomic tree of wood-warblers (Aves: Parulidae): Dealing with good, bad, and ugly samples。
高価な機器やフィールドサンプルが必ずしもなくても行える研究なのでもっと多方面から参入があってもよい感じがする。計算機に強い方チャレンジしてみられませんか。
参考までに茂田 (1996) Birder 10(6): 27 が小型ツグミ類を取り上げているが、当時は Saxicolini ノビタキ族、Turduini ツグミ族 の名前も使われていたそうである。
Saxicolini ノビタキ族などの名前は Voelker and Spellman (2004) Nuclear and mitochondrial DNA evidence of polyphyly in the avian superfamily Muscicapoidea のヒタキ上科の遺伝系統解析にも現れる。この論文ですでに多くの種類が亜科、族レベルで違っていたことが明らかになっている。
Zhao et al. (2023) の結果でキビタキ属がこれまでの位置からかなり離れてしまってかつて「小型ツグミ類」と呼ばれていたものの仲間になった。Clade D: Saxicolinae (ノビタキ亜科?) に我々の馴染みの種類が多く含まれる。灰色系のヒタキは Clade A: Muscicapinae (サメビタキ亜科?) とまとめられ、離れたグループになった。
この論文では Muscicapa 属 (サメビタキ属) が単系統でないことが述べられているが、1種のみの問題でこの種を Muscicapa 属に変更するのみの修正で済む。イヌワシ類・クマタカ類で発生したような大きな変更の必要はない。
我々の馴染みの Muscicapa 属が分割されたり別属名に変更される心配はおそらくなさそうである (#エゾビタキの備考も参照)。
Clade D: Saxicolinae (ノビタキ亜科?) の分子系統研究については以下の文献も参照:
Aliabadian et al. (2012) Convergent evolution of morphological and ecological traits in the open-habitat chat complex (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae)
(リンク切れ?)。
砂漠や岩場のような開けた環境に生息するグループの多くが単系統でなく、異なる系統が生息環境に応じた収斂進化して外見上似た種が生じたとのことである。日本ではサバクヒタキ類は迷鳥なので実用上はあまり問題にならないかも知れないが、サバクヒタキ類に関心の深い方には興味深い論文であろう。
[スズメバチと擬態種を見分けるヨーロッパコマドリ]
Volponi et al. (2025) How effective are insect aposematism and Batesian mimicry in deterring a wild avian predator?。スズメバチの Vespa crabro と擬態種の Sesia apiformis では明瞭に反応が違った。
Taylor et al. (2025) Mapping the adaptive landscape of Batesian mimicry using 3D-printed stimuli (容易に思いつきそうな発想ではあるが) 3D プリンターを利用して Batesian mimics (ベイツ型擬態) を見分ける能力を調べたもの。ここではニワトリのひよこを利用している。
生得的に有毒なハチ類を忌避するというより、有毒なハチ類と無毒なもので擬態していないものを食物による条件付けを行ったもので、3D プリンターで作成した擬態した虫を見せて反応を見る実験を行っている。
有害な刺激を受けて学習する場合とは多少条件が異なるかも知れない。3D プリンターを用いた利点は現実に存在しない模様や形を再現することで、どの特徴がベイツ型擬態に役立っているかを調べることができる。
またニワトリと無脊椎動物捕食者の反応の違いも調べていて、無脊椎動物でもニワトリほど効率はよくないもののある程度の見分けが可能である。ただし系統があまりにも違うものの反応を比較することにも制約があるとのこと。脊椎動物が昆虫を捕食するようになる以前からベイツ型擬態の進化が考えられることになる。
この研究はアイデアの速さ勝負で、ある意味誰でも思いつくことが可能なため、他のグループが先行することを避けるため、迅速に実験できるニワトリのひよこを用いたものと想像できる。
-
コマドリ (AviList で2種に分離)
- 第8版学名:Larvivora akahige (ラルウィウォラ アカヒゲ) アカヒゲという幼虫を食べる鳥)
- AviList 学名:Larvivora akahige (ラルウィウォラ アカヒゲ) アカヒゲという幼虫を食べる鳥) と Larvivora tanensis (ラルウィウォラ タネーンシス) 種子島の幼虫を食べる鳥)
- 第7版学名:Luscinia akahige (ルスキニア アカヒゲ) ナイチンゲールのアカヒゲ
- 第8版属名:larvivora 幼虫を食べる larva 芋虫、幼虫 -vorus を食べる
- 第7版属名:luscinia (f) ナイチンゲール (サヨナキドリ)
- 種小名:akahige (外) アカヒゲ
- AviList 種小名:akahige (外) アカヒゲ と tanensis 種子島の
- 英名:Japanese Robin, AviList: Japanese Robin と Izu Robin
- 備考:
larvivora は#コルリ参照。
規則通りであれば "アカヒゲ" のアクセントとなる。フランス語のように h を読まない言語もあるので "アカヒゲ" の読みが万国共通とはならないものの、我々は "アカヒゲ" と読んでおいて構わないだろう。
記載時学名 Sylvia akahige Temminck, 1835 (原記載) 基産地 Riu Kius, south of Japan; corrected to Hondo by (Avibase はここで終わっている)。
フランス語名 Bec-fin akahige。M. von Siebold によるもので dans les iles Lioukiou, au sud du Japon (上記基産地の前半の原語表記)。
"Fauna Japonica" では 本文 フランス語名 l'humicole akahige 学名 Lusciola akahige となっている。図版。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Larvivora 属となる。種小名は変化なし。
亜種 tanensis は独立種 Larvivora tanensis (種子島から) タネコマドリ Izu Robin とされるリストが多い (HBW/BirdLife、Clements 2022 以降、eBird 2022 以降、IOC 13.1 以降) ので採用されるかも知れない。本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種扱い。
tanensis は -ensis の語尾から "タネーンシス" のアクセント位置と長音となる。
記載時学名 Erithacus akahige tanensis Kuroda, 1923 (原記載) 基産地 Nishino-omote, Tanegashima, south of Kiu Siu。
Seki (2023) Genetic structure of the Japanese Robin (Larvivora akahige) endemic to East Asian islands (author manuscript)。
Working Group Avian Checklists も version 0.02 から独立種。
AviList では分離。Larvivora tanensis 英名 Izu Robin。分布域記述は Izu, Tanegashima, and Yakushima islands (southern Japan)。
判定理由は 27763 197 Taxon tanensis is treated as a monotypic species separate from Larvivora akahige (monotypic) based on plumage, vocalizations (Zhao et al. 2016), and genetics. While mitochondrial DNA data show evidence of extensive introgression (Seki et al. 2012; Seki 2023), nuclear microsatellites mostly assort along taxonomic lines (Seki 2023), supporting the split.
参考までに LC666796.1 (cyt b) から BLAST を行ってみると haplotype T1, Tn1, Tn2 が他と別系統を作り別種相当と思える。LC541457.1 (Larvivora akahige akahige) のミトコンドリアゲノムもこちらに含まれる。
梶田 (2010) Birder 25(7): 30-32 によれば屋久島と種子島は繁殖分布から外される可能性が高いとのことをすでに示唆されていた。
屋久島を訪れる海外バーダーの間でもどちらかしばしば話題となっている (図鑑によって記述が異なる)。
関氏の BOU サイトへの寄稿記事 (分布境界の地図あり) Robins on East Asian islands (Seki 2023)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では基亜種 akahige コマドリの他に屋久島の亜種 kobayashii (Moriyama, 1940) ヤクコマドリを認めており、
Seki et al. (2012)
Distribution of Two Distinctive Mitochondrial DNA Lineages of the Japanese Robin Luscinia akahige Across Its Breeding Range Around the Japanese Islands
によれば亜種の妥当性までは断定できないが他の個体群との有意な遺伝的違いがあり、保全単位としても意義があるとの考えである。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)には含まれていない。
亜種リシリコマドリ rishirensis (Kuroda, 1965) が提唱されていたが多くのリストで用いられていない。日本鳥類目録改訂第8版第二回パブリックコメントに向けた暫定リストでも分布地の記載から基亜種のシノニム扱いとみられる。
旧属名でもコマドリとヨーロッパコマドリと近縁でないことがわかるが、ヨーロッパコマドリとは関係が薄く、色合いの類似は他人の空似で、色彩面での収斂進化と考えられている (プレスリリース参照) (#ヨーロッパコマドリの備考参照)。
関 (2009) Birder 23(6): 37 にもコマドリとヨーロッパコマドリが近縁でないことを示す記事がある。
ロシア名は yaponskaya zaryanka で前半は自明だろうが、後半の zaryanka はヨーロッパコマドリのこと。zarya が "暁" の意味なのですぐ理解できる名前。
コマドリモズなる和名の鳥がある。Lanioturdus torquatus Chatshrike / White-tailed Shrike。どこがコマドリなのかと思えるが Chat Shrike を訳すとそうなるのかも。ヨーロッパの鳥にウグイスを付けて呼んでいたとか、逆にヨーロッパからは日本のウグイスを Japanese Nightingale と呼んでいた時代の産物か?
そういえば Amrican Robin はコマツグミだった。robin をコマドリと訳してツグミと結合させたものか。
[コマドリと少年、手塚治虫さんとかつての日本野鳥の会のこと]
手塚治虫氏の代表作「ブラック・ジャック」に「コマドリと少年」というエピソードがある。
コマドリのことを知っている者が見れば「全然違う」あるいは現実ではあり得ない話がいっぱいあるが、そこは漫画に許された話だと思って見ていただくとよい。手塚治虫氏が動物を取り上げた漫画の中でも秀作ではないかと思う。
短編の中で探偵的な謎解き部分もあり、「幸福な王子」(アイルランド出身の文人オスカー・ワイルドによる子供向けの短編小説) の要素もあり、「ごんぎつね」のように終わると言えばネタをばらしすぎであろうか。改めてアニメーション化されたものを見て感心してしまった。
手塚治虫氏の鳥に関わる漫画として桐原 (2003) Birder 17(11): 55 にも紹介されたことのある「鳥人大系」(1971-1975 年に連載) が有名である。バーダーとしてはこれは見ておかないといけないかも知れない (なお他の著者によるバードウォッチングや鳥に関係する漫画があることは知っているが、オールドファンとして古典を紹介させていただく)。
「鳥人大系」ではしばしば「疑似学名」が登場する。この記事をお読みの方であれば何を示しているかはそれなりに簡単に想像いただけると思う。
例えばトウルドス・メルラ・サピエンスとは何のことだろうか。手塚氏は学名の成り立ちをご存じであったようで、時に亜種として、時に種として対象の鳥を扱っている。謎解きはぜひ現物を見て行っていただきたい (著名な作品なので前述のブラック・ジャックも含めて簡単に手に入る)。
もちろんこちらも「あり得ない」話ばかりであろうが、これもあくまで「お話の世界」として楽しんでいただけると思う。野鳥飼育問題から始まっているあたりは当時の時代背景をよく把握されていたものであろう。手塚氏の時代には鳥の脳の構造はあまりわかっておらず、知性を得た鳥は前頭葉 (解剖学的には鳥にはこのような部位はなく、相当する部分が違う場所に神経核として存在する。#イヌワシの備考参照) が膨大しているなどの描写はある意味間違っていて面白い。
要所要所に大変写実的な鳥の絵が出てくるが、これも手塚氏が描いたのだろうか、それともアシスタントの作品だろうか? というのも面白い。
手塚氏は雑誌「アニマ」の連載の中で、鳥の擬人化は哺乳類に比べて難しい (苦手) のようなことを書かれていた。それにしては珍しく鳥を中心に選んだ題材である。「火の鳥」の脚が擬人化されると鳥とは逆に曲がるなどは鳥を知り尽くし過ぎていると逆に描きづらいかも知れない。
さて、これもいずれ忘れ去られるか読めなくなりそうなので読めるうちに読んでおいていただきたいのだが
「知られざる日本野鳥の会」 - 手塚治虫さんも、サンクチュアリに協力したけれど 99.2.20 というキューソクさんのコラムがある。
"ナカニシ・ゴドー" というと日本野鳥の会の創始者であり神様のように扱われることもあるぐらいだが、案外と了見の狭い方だったようである。
一方の中西氏の方からは「野の鳥は野に」(小林照幸 新潮選書 2007) pp. 182-183 に述べられており、サンクチュアリ運動に協力した漫画家との関係は中西氏の会長辞任の一要因ともなっていたらしい。
手塚治虫氏がもし日本野鳥の会と積極的な関わりを持っていたら日本の自然保護はどう変わっていただろうかと想像することもあるが、手塚氏も作品で自然保護や環境問題を自身の切り口で深く扱われていたので今となってみれば「それでよかった」のかも知れない。
このコラムにはおそらく「野鳥」誌などには決して書かれないであろうエピソードや当時の日本野鳥の会の中で何が起きていたのかが残されており、100 周年も近い日本野鳥の会の歴史を振り返るに当たっていずれか誰かがこのような歴史を隠すことなく語っていただければと思う。
ちなみに若き日の市田則孝氏の「革命」の時代の記事は (今となっては入手困難であろうが) 雑誌「アニマ」1984年5月号の特集「創立 50 周年を迎えた<日本野鳥の会>」に当事者の言葉として残されており、キューソクさんのコラムとともにぜひお読みいただきたい内容である。
この部分を記述してから気づいた (思い出した) のだが、「野鳥」1982年11月号 (No. 484) p. 26 に「わが家の鳥達」と題して手塚治虫氏がエッセイを書かれている。奥様が鳥好きで、ご自身が医学博士らしからぬ (笑) エピソードとともに、東京郊外の新興住宅地にもかかわらず裏山に入ると夏にはカッコウの声が聞かれるとも記されている。
少し漫画の話に戻るが、鳥関連の話題を取り上げている以上、手塚治虫氏の代表作と言われる「火の鳥」も取り上げておくべきであろう。個人的には「未来編」で鳥類・哺乳類が再度現れ、そして火の鳥が世界中を飛ぶ部分の描写が素晴らしいと思っている。「鳥人大系」にも鳥が群れで飛ぶ描写はたびたびあるが、火の鳥「未来編」のこの描写は特筆していると思う。
ちなみに英訳された版も持っているのだが、手塚氏が生き物へ向けた温かい視線を他言語に写しきることほとんど不可能なのだろうと思う。アニメーション化もされているが、手塚氏がおそらくチャイコフスキーのピアノ協奏曲1番の3楽章 (*1) でも聞きながら乗りに乗って描いたであろうこの部分が大幅にカットされているのが惜しいところである。
備考:
*1: もちろん何かの根拠があるわけでもない。手塚治虫氏は「チャイコフスキー党」であることを自身で明かしており、その後「ブラームス党」になったとのこと。
チャイコフスキーのピアノ協奏曲1番の3楽章はベスニャンカ (ベスニヤンカ) というウクライナ発祥の歌・踊りをテーマに作られている。
ベスニャンカ vesnyanka (wikipedia ではロシア語版、ウクライナ語版とも複数形で -i の語尾が見出しになっている) というのは vesna (ウクライナ語、ロシア語とも「春」の意味) の到来を讃える歌でもあり、これから農作業が始まる労働歌でもある。
ベスニャンカの wikipedia ロシア語版ページには、歌詞の一例として以下のようなものが紹介されている。
「ヒバリよ、ヒバリよ / 夏をおくれ / 冬はあげるから / 食べ物が何もないんだ!
ヒバリよ / 飛んできて (後略)」
このページにも紹介されているように、春の農作業が間もなく始まること、そして渡り鳥がやってきて春をもたらすことを表し、春を呼び入れる歌である。
チャイコフスキーはこのピアノ協奏曲1番の3楽章に終始ベスニャンカのモチーフ (動機) を用い、poco meno (少し控えめに) で始まる第2モチーフ (これもベスニャンカの変形とされる) を発展させ春の訪れを讃える壮大な音楽に仕上げている。
この曲は題1楽章冒頭の序奏部分が非常に有名であるがこの旋律は再度現れることはない。しかしながら3楽章の第2モチーフを発展させることで実質的に冒頭の序奏を再現させて見せる心憎い演出を行っている。チャイコフスキーがモチーフの再現や調性にいかにこだわって意味を持たせたかは「白鳥の湖」などを聞いてもわかり、上記の解釈もそう外れていないのではないかと思う。
手塚氏の「火の鳥」の該当部分はあるいはチャイコフスキーのこの作品の手法から影響を受けた点もあるかも知れない。「体温をもった生き物たちが/あらわれはじめたのだった/はじめはえんりょぶかげに/...やがてわがもの顔に...」(「火の鳥」より引用) の表現は3楽章の第2モチーフにまさしくふさわしい表現である。
そして (年のスケールはまったく違うが) 待ちに待った鳥たちが戻ってくるシーンが続く。この部分は「火の鳥」全シリーズ (未完のまま手塚氏死去) の最終編にもあたり、チャイコフスキーの協奏曲のフィナーレとの相似性は一層高いように感じる。チャイコフスキー流に書けば新しい生命の訪れへの讃歌である。
バードウォッチャーであれば毎年戻ってくる鳥たちに同様の感銘を大なり小なり受けているだろうが、バードウォッチングという世界を知ったことに幾ばくかの感謝を感じる時でもある。
-
アカヒゲ (ホントウアカヒゲが独立種となった)
- 第8版学名:Larvivora komadori (ラルウィウォラ コマドリ) 幼虫を食べるコマドリ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Luscinia komadori (ルスキニア コマドリ) ナイチンゲールのコマドリ
- 第7版亜種学名:Luscinia komadori komadori (ルスキニア コマドリ コマドリ) ナイチンゲールのコマドリ
- 第8版属名:larvivora 幼虫を食べる larva 芋虫、幼虫 -vorus を食べる
- 第7版属名:luscinia (f) ナイチンゲール (サヨナキドリ)
- 種小名:komadori (外) コマドリ
- 英名:Amami Robin, IOC: Ryukyu Robin
- 備考:
larvivora は#コルリ参照。
komadori は規則通りであれば "コマドリ" で日本語と同じ発音になるがご承知のように紛らわしいことこの上ない。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Larvivora 属となる。種小名は変化なし。
亜種 namiyei は独立種 Larvivora namiyei (動物学者 波江元吉 Motoyoshi Namiye にちなむ) ホントウアカヒゲ (英名 Okinawa Robin) となる。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
記載時学名 Sylvia komadori Temminck, 1835 (記載)。
フランス語名 Bec-fin komadori。
次ページのコマドリ (記載) では Siebold によれば琉球に生息とあるので単純な取り違えのよう。
"Fauna Japonica" では 本文 フランス語名 l'humicole komadori 学名 Lusciola komadori となっている。図版。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では基亜種 komadori アカヒゲの他に亜種 subrufus (少し赤っぽいの意味) ウスアカヒゲ (Kuroda, 1923; 絶滅亜種) を認めている。たった1羽の亜種も参照。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではこの亜種は外され、新参異名 (junior synonym) とすると記述されている。このまま採用されればアカヒゲは単形種となる。
川路 (1996) Birder 10(6): 32-34 によればこれらの経緯は複雑で、シーボルトが持ち帰った標本の記載論文では採集地が朝鮮半島近くとなっている。黒田 (1925) によればこれは間違いとのことで、標本ラベルに誤りがあったのではないかと考えられている。
関 (2017) Birder 31(2): 66-67 によればシーボルトが持ち帰った標本の原産地は奄美諸島で、大島赤髭と呼ばれていたが、亜種に分割される際にこちらが基亜種となるためオオシマアカヒゲではなく基亜種 komadori がアカヒゲとなり、沖縄本島のもの namiyei が亜種ホントウアカヒゲと改名された経緯がある (さらに別種扱いとなる見込み)。
川路 (1996) によれば、ウスアカヒゲのタイプ標本が戦災で消失したと考えられていて日本鳥学会 (1974) も検証不能としていたが、実際には他所に移されていたことがわかりその後検証された。
Kawaji and Higuchi (1989) Distribution and Status of the Ryukyu Robin Erithacus komadoriの検討で亜種 komadori の変異範囲に収まり、シノニムでよいとの判断になった。
より北方の個体が与那国島で越冬していたものかと述べられている。
関 (2017) によれば、アカヒゲの「ヒゲ」の由来も不明で、現地の言葉の意味の取り違えがあった可能性を考えている。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば Temminck's Robin と呼ばれており Siebold の探検に基づく標本で産地が日本になっていたが、後に飼い鳥らしいと判明したことのこと。
当時は朝鮮半島から飼い鳥が輸入されており、朝鮮半島産と考えられたが見つけられず謎となっていたとのこと。Stejneger (1887) が八重山諸島からの標本を得てようやく判明したとのこと。
ホントウアカヒゲをタイプ種とした Icoturus (eikos 適切な、など oura 尾 Gk) 属が提唱されていた (Stejneger, 1886)。Icoturus namiyei が提唱当時のタイプ種の学名。尾の色彩が際立っているとのことで、当時は Timaliidae となんとチメドリ科に分類されていた (The Key to Scientific Names)。
Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" (Birds of Sakhalin Island) でもコマドリにこの属名が用いられていた。
-
オガワコマドリ
- 学名:Luscinia svecica (ルスキニア スウェキカ) スウェーデンのナイチンゲール
- 属名:luscinia (f) ナイチンゲール (サヨナキドリ)
- 種小名:svecica (adj) スウェーデンの (-icus (接尾辞) 〜に属する)。基産地 Europae alpinis でラプランド地方の高地に対応。#ハマシギ参照。
- 英名:Bluethroat
- 備考:
luscinia は短母音のみで "ルスキニア" のアクセント。
luscus (片目の) + cano (歌う) の語源の可能性が挙げられている (wiktionary)。
svecica は短母音のみで "スウェキカ" のアクセント。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版での変更に伴い、Luscinia 属に残るのはオガワコマドリのみとなり、属名もオガワコマドリ属となる見通し。
和名は日本で初めて採集した小川三紀 (Minori Ogawa) にちなむ。
動物学雑誌と珍鳥 オガワコマドリ (スズメ目ツグミ科) [山階鳥研 NEWS 2001年7月1日号 (No. 148) より] に当時の経緯や和名の由来の紹介がある。標本のページ。
Erithacus cyaneculus caeruleculus (Pallas) の学名は Kuroda が判定したもの。
Sylvia Cyanecula Meisner, 1804 の学名は現在は亜種のシノニム扱い。
標本ラベルを見るとさらに Ogawa の同定した別の学名 Luscinia svecica weigoldi が付いている。
ヨーロッパでは普通種なのでもちろん Linnaeus (1758) が記載している (原記載)。"スウェーデンの" と付けたのはそれだけ多く見られる鳥なのだろう。
OED によれば Linnaeus (1758) 以前の英名は Blue-throat Redstart (1743 年用例) があった。Pennant, Arctic Zoology (1785) が学名紹介とともに Blue-throat と呼んだ。
[Luscinia 属の由来は複雑]
Luscinia 属のタイプ種はサヨナキドリ Luscinia megarhynchos Common Nightingale で、種小名がトートニムになっているヤブサヨナキドリ (別名ヨナキツグミ) Luscinia luscinia Thrush Nightingale ではない。
こちらは Motacilla Luscinia Linnaeus, 1758 が原記載 (参考) となっている。
Luscinia 属の提唱時 (Foster 1817) は当時の通称学名で "Sylvia luscinia" のみを含む属として定義され、属変更に伴って Luscinia aedon Forster, 1817 (参考; the Nightingale)
と改名された (#ノスリの備考参照)。
aedon は#ハシブトオオヨシキリ参照。ナイチンゲールのこと。タイプ種はその後 Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 と判定された (The Key to Scientific Names などから)。
Yarrell (1839) The Nightingale (A history of British birds) にあるようにサヨナキドリは古くからよく知られた鳥で、疑いもなく "Sylvia luscinia" の学名が使い続けられていたようだが、これは Linnaeus (1758) 由来のもので後日別種のヤブサヨナキドリに同定され、サヨナキドリが学名を失って Brehm (1831) のものが採用された経緯らしい。
Luscinia aedon Forster, 1817 の方は "Sylvia luscinia" を改名したものでサヨナキドリの有効な学名にはならなかったらしい。
このようになった経緯はどこかに書いてありそうだが、記載から想像してみると Motacilla Luscinia Linnaeus, 1758 は生息地 Europae で frondosis が続いている。frons は葉の意味。wikipedia 英語版では leafy Europe と訳しているが、形が frondosus の複数与格または奪格なので、from leaves (葉の多いところから、あるいは葉の多いところに) ぐらいの意味ではないだろうか。
生息地 Europae であればヨーロッパ全体を指していても構わないが、Hartert (1910-1922) p. 736 が基産地をスウェーデンに限定した。
Hartert によるとこの記載は Fauna Sueeica No. 221 (第1版の番号で p. 83 に現れる) に対応するとのこと。
この点を重視すればスウェーデンに生息していないと困る。2種の "ナイチンゲール" のうち Linnaeus がスウェーデンでは小さい方のナイチンゲール (Hartert の記述では die kleine Nachtigall) は見られないと述べていることから、サヨナキドリではない方のヤブサヨナキドリ (別名ヨナキツグミ) と判定されたとか考えられる。
Linnaeus (1746) によれば p. 84 OBS. LUSCINIA MINOR ... quam non dum observavi の記述 (なおこの当時の学名はまだ無効) に対応する ("まだ観察していない" と記述)。Hartert はしかしこのコメントは正確でないとしていた。
この結果 Motacilla Luscinia Linnaeus, 1758 はヤブサヨナキドリと判定されたと考えられる。ヤブサヨナキドリはヨーロッパ東部からシベリア西部・中央部で繁殖しアフリカ南部に渡る。Linnaeus にとってはサヨナキドリの方はスウェーデンに生息せず身近な種ではなかったため "自然の体系" に盛り込み損ねたらしい。
しかし Linnaeus の記載したものがスウェーデン語で Nacktergahl と呼ばれていた (1746 年の記述参照) ことから、英国で Nightingale と呼ばれるものと同じと考えられて、サヨナキドリをこの学名で呼び続けていた。サヨナキドリの方はヨーロッパ中南部を中心に繁殖する種で、英国ではこちらの種が繁殖。
例えば Forster はこの誤解に気づかず、"Sylvia luscinia" (当時の属名) = Nightingale と信じていたため、それを指して設けた属 Luscinia は必然的にサヨナキドリをタイプ種となることとなったと想像できる。
[オガワコマドリは結局どの属?]
この周辺の関連種 (コマドリ、アカヒゲ、コルリなども) かなり最近まで Erithacus 属に分類されていた。しかし遺伝的にコマドリとヨーロッパコマドリが近縁でないことが判明するなど、旧 Erithacus 属が多系統であることが明らかになってきた (#ヨーロッパコマドリの備考参照)。
そのため属分割が必要となった。個々の種の系統関係は詳細な解析が行われた近年まで明らかでないものあり、2010 年代後半はまだ不確定な時期に当たって属名も様々に扱われてきた。
オガワコマドリのみを含む属 Cyanosylvia Brehm, 1828 も提唱され (青い Sylvia 属)、使われていたこともあった。
Zhao et al. (2023) の分子系統樹 (#ヨーロッパコマドリの備考参照) ではこのあたりの系統樹形態は確定している。
AOU Proposals 2024-B によれば、NACC は 2018 年にオガワコマドリのみを含む Cyanecula 属 (cyaneus 暗青色 の指小語) に移していたとのこと。
この属名も Brehm (1828 年 12 月) が提案。The Key to Scientific Names によればこの2属は別文献に現れるようで、Brehm はオガワコマドリのみを指して2つの属名を与えたことになる。おそらく年代判定の問題もあり、Brehm が訂正したものとみなすかなどどちらが有効か議論もあって両者が使われていたのだろう。
その当時の各種リストの属変遷も記されている。この提案は 2023 年の分子系統研究に基づき Luscinia 属に含めるとのもの。
分子系統研究の結果ようやく十分な根拠のある属名を与えることが可能となってきた。2023 年なのでごく最近の出来事である。
日本鳥類目録改訂第7版と第8版で学名は同じで一見何の変化もなく問題もなかったように見えるが、途中の 10 年強の間により精度の低い Sangster et al. (2010) の系統樹をもとに属が整理された経緯もあり、世界で見解が分かれている時期があった。
Luscinia 属のタイプ種サヨナキドリとオガワコマドリはいずれもヨーロッパで普通種なので、同属かどうかすぐ結論が出てもおかしくなさそうなものだが、オガワコマドリのみが独立系統を作るかどうか判定するには近縁種も調べる必要があり、確実に判断を下すには時間がかかったものと想像できる。
AOU-NACC Proposals 2025 (BirdForum) に議論があり、Dutch Birding で 2014 年に議論が行われて AOU Proposals 2024-B を受けた 2025 年の George Sangster の見解も紹介されている。
Sangster 自身はオガワコマドリを別属にする提案は行っていなかったとのこと。
オガワコマドリを Cyanecula 属とすることも原理的には可能で、その場合はサヨナキドリとヤブサヨナキドリのみが Luscinia 属となり、オリイヒタキ Hodgsonius phaenicuroides (Boyd の分類による学名の場合。一般的には Luscinia 属) White-bellied Redstart は単形属をなすことになる。
Boyd はこの分割を採用。Luscinia 属を4種にまとめることには万人が納得しているわけではない模様。
参考までにこの4種の Boyd の分類を紹介しておく。系統順序は Zhao et al. (2023) の分子系統樹に従って入れ替えてある。一般的に用いられている分類ではないので要注意だがこのような考え方もあり得る:
ヒタキ科 Muscicapidae: Old World Flycatchers, Chats
ノビタキ亜科? Saxicolinae: Robins, Chats, Wheatears
サヨナキドリ属 Luscinia
ヤブサヨナキドリ (ヨナキツグミ) Luscinia uscinia Thrush Nightingale
サヨナキドリ (ナイチンゲール) Luscinia megarhynchos Common Nightingale
オガワコマドリ属 Cyanecula
オガワコマドリ Cyanecula svecica Bluethroat
オリイヒタキ属 Hodgsonius
オリイヒタキ Hodgsonius phaenicuroides White-bellied Redstart
この部分の英名だけを見ると自然な属分割に見える。
オガワコマドリに非常に近縁な種は存在せず、最も系統の近いものがオリイヒタキ。これを {サヨナキドリ + ヤブサヨナキドリ} と一緒にまとめるかどうかの問題となる。系統はかなり遠いのでオリイヒタキの系統からオガワコマドリが進化したかどうかは何とも言えない。同様に {サヨナキドリ + ヤブサヨナキドリ} の系統からオガワコマドリが進化したかどうかも不明。
さらに古い分岐にノドジロコマドリ Irania gutturalis White-throated Robin があってアジア西部の乾燥地帯で繁殖とのこと。進化を考える上ではこの種も考慮する必要と考えられるが生息環境がずいぶん違う。オガワコマドリの好む環境は少し近いかも知れない。
なおオリイヒタキの名称は山階鳥類研究所標本データベースによれば 1935 年の5標本があり (MT, Mulei, S, Manchuria) 採集者折居彪二郎なので納得できる名前だろう。亜種は ichangensis (地名 Ichang に由来)。この標本データベースではオリイヒタキ属 Hodgsonius の扱いになっている (2025.3 現在)。
オガワコマドリとオリイヒタキの色彩はそれぞれまったく違うが、ヒタキ類の青い鳥の色彩の違いがあまり系統を反映していない事例はコルリとコマドリの関係、#カワビタキがジョウビタキに近縁のように他の系統でも多く認められるので思ったほど参考にならない。スズメ目以外でもアカショウビンとヤマショウビンなども色が全然違う。分子系統による分岐年代をどの程度反映するかの程度問題となる。
IOC や NACC では4種を3属に分けるのはさすがに細かすぎる判断もあるのだろう。ヨーロッパでよく知られた鳥で色彩が明らかに違うので分けるというわけにはいかない。同じ理屈が通るならばコルリは {コマドリ + アカヒゲ} と別属にすべきとなるし、それほど派手でないシマゴマはどうするのかなどの問題が発生する。
オガワコマドリを何属とするかは、分子系統樹の読み方や、青い鳥はなぜ青い (#オオルリの備考参照) などにも関連する問題で大変奥が深い。#ムギマキ備考の [Ficedula 属の話題]、BirdForum の議論なども読んで楽しんでいただきたい。
Luscinia 属は4種しかいないので違いが目立つが、種数の多い Ficedula 属を見れば属内で色彩の違いが大きいことも納得できるだろう。
[その他]
亜種は svecica とされる。この亜種は北方のもので、スカンジナビアからベーリング海峡を超えてアラスカまで分布しており、渡りまたは越冬に日本を訪れることも理解できる。
英名で Red-spotted Bluethroat または Arctic Bluethroat とも呼ばれ、後者は分布域をよく表している。リストによっては日本は渡り中継域 (旅鳥) として表示しているものもある。他にもより低緯度に分布する多くの亜種がある。この種は越冬中でもしばしばさえずり (あるいはぐぜり)、よい声を聞いた報告もしばしばある。
-
ノゴマ
- 第8版学名:Calliope calliope (カルリオペー カルリオペー) 叙事詩を司る女神 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Luscinia calliope (ルスキニア カルリオペー) ナイチンゲールのカッリオペ
- 第8版属名:calliope (神) 叙事詩を司る女神 (ギリシャ神話)
- 第7版属名:luscinia (f) ナイチンゲール (サヨナキドリ)
- 種小名:calliope (神) 叙事詩を司る女神 (ギリシャ神話)
- 英名:Siberian Rubythroat
- 備考:
Calliope はラテン語では語末が長母音。アクセントは -li- にある (カルリオペー)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Calliope 属 (ノゴマ属) となる。種小名は変化なし。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。
記載時学名 Motacilla Calliope Pallas, 1776 基産地 between the Yenisei and the Lena Rivers (Avibase による)。
Calliope 属は Gould (1837) が設けたもの (参考。図版)。
当時の英名で Gorget Warbler。フランス語名 La Calliope。
当時の Gould は Pallas (1776) の学名には気づいていなかったようで属創設とともに Calliope Lathamii と Latham の鳥類学への貢献に対して献名したもの。
なお後の 参考 では Calliope camtschatkensis の学名となっていた。
図版。本文。
Turdus camtschatkensis Gmelin, 1789 (参考) を本種と同定し、自身の命名より早いために種小名を変えたものらしい。この文献でタイプ種と記載している。現在亜種名として残っている。
Motacilla Calliope Pallas, 1776 が同定されたのはおそらくその後のことらしい。Hartert (1910-1922) では p. 738。形式的には種小名から属名への昇格に見えるがそうではなかった。
例えば Hartert の時代には系統がわかっておらず、Luscinia 属に分類されていた (このころは "小型ツグミ類" の時代)。分子系統研究で Luscinia 属とは別系統と判明して分離された。
関連部分を Boyd の分類から抜粋しておくと:
ヒタキ科 Muscicapidae: Old World Flycatchers, Chats
ノビタキ亜科? Saxicolinae: Robins, Chats, Wheatears
コンヒタキ属 Myiomela
コンヒタキ Myiomela leucura White-tailed Robin
シロビタイコンヒタキ Myiomela diana Javan Blue Robin
ノゴマ属 Calliope
ムネアカノゴマ Calliope pectardens Firethroat
ノドグロコマドリ Calliope obscura Blackthroat / Black-throated Blue Robin
ノゴマ Calliope calliope Siberian Rubythroat
ムナグロノゴマ Calliope pectoralis White-tailed Rubythroat / Himalayan Rubythroat
オジロノゴマ Calliope tschebaiewi Chinese Rubythroat
で IOC と一致する。ムネアカノゴマとノドグロコマドリが系統を作り、ノゴマ以降のグループと分岐した形となる [Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考) の分子系統樹を参照]。
コンヒタキ属がより古く分岐した系統であることを考えるとこのグループの発祥の地はインド亜大陸から東南アジアと考えられる。熱帯では青系統の色彩が有利で進化したものがコンヒタキ属、北に分布を広げたものがノゴマ属となる。北に分布を広げるにあたって森林環境から離れて青色が必要でなくなったらしい一方、のどの色は性選択に重要だったようでノゴマ属のオスはいずれものどに特徴がある。
分子系統樹を見る限りこれらの系統と Luscinia 属を統合しようと再度考えられることはないと思われ、Calliope 属のタイプ種がノゴマなのでノゴマの学名はこれ以上変わる心配はないと考えられる。
Myiomela 属と統合された場合でも Myiomela Gray, 1846 の方が新しいので Calliope の方に統合される。見かけも大きく違い、分子系統的にもある程度離れているので多分統合されることはないだろう。ただしこの分岐年代を受け入れるならば Luscinia 属を分割しても構わないぐらいである (#オガワコマドリの備考参照)。
Calliope 属が優先される背景はノゴマが北半球の比較的北部で繁殖する種で、早めに記載されてヨーロッパの Luscinia とは違いが大きいので早い時点で属記載が行われた点が大きい。ヨーロッパのものとあまり違いのない種類であれば Myiomela 属の方が先に命名されていたかも知れない。
亜種を認める分類も多い (例えば IOC では3亜種)。
この場合北海道で繁殖する亜種は camtschatkensis (カムチャツカの) となる。基亜種 calliope もウラル山脈以東のシベリアなど日本北方から北西に分布しており、日本に渡って来ている可能性がありそうである。世界には中国に1亜種がある (IOC 15.1)。
ただし狭義ノゴマのこの亜種認識は多分に基産地を反映したものとなっており、Hartert は亜種を認めていなかった。
Dement'ev and Gladkov (1954) では3亜種を認め、カムチャツカのものはシベリアの基亜種より大型でのどの色はより赤く、全体に淡色であるとのこと。この文献ではサハリンと北海道は基亜種 calliope、千島列島は camtschatkensis と考えていた。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では世界で5亜種、シベリアは calliope としていた。2016 年の研究によりムナグロノゴマ、オジロノゴマが分離される前の分類と思われる [Dement'ev and Gladkov (1954) は分離していた]。
Zhao et al. (2023) の分子系統解析では十分に別種と認識される程度離れている。
ノゴマは「ヒューイ」のような柔らかい声で鳴くことがある。繁殖行動に際しても同じ発声があるそうだが、越冬地でよく聞かれてしばしば不明声とされる (南西諸島では一部越冬するため、現地録音をされている方にはお馴染みの声だそうである)。この声は渡り途中の早朝でも聞かれることがある。録音ができれば同定は難しくないためお試しいただきたい。他に「タッ」と短い地鳴きもある。
Zhao et al. (2024) Seasonal migration patterns of Siberian Rubythroat (Calliope calliope) facing the Qinghai-Tibet Plateau
中国のノゴマの渡りの研究。チベット高原を避けている。GPS と気圧による標高推定を用いている。
低地の渡りの多くは 1000-1400 m の高さ。3500 m を超えることもあったが 3000 m 以上の高地を中継地とすることはなかった。GPS データは Movebank で公開されている:
Siberian rubythroat tracking from Qinghai, China (何と public domain になっている)。
Heim et al. (2018) Full annual cycle tracking of a small songbird, the Siberian Rubythroat Calliope calliope, along the East Asian flyway のロシアのアムール州から追跡した研究もあるがデータは公開されていない。
-
コルリ
- 第8版学名:Larvivora cyane (ラルウィウォラ キューアネ) 幼虫を食べる濃青の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Luscinia cyane (ルスキニア キュアネ) 濃青のナイチンゲール
- 第8版属名:larvivora 幼虫を食べる larva 芋虫、幼虫 -vorus を食べる
- 第7版属名:luscinia (f) ナイチンゲール (サヨナキドリ)
- 種小名:cyane (f) 濃青 cyanos の泉に変えられた nymph (ギリシャ神話の妖精)
- 英名:Siberian Blue Robin
- 備考:
larvivora は短母音のみで -vi- にアクセントがある (ラルウィウォラ)。
cyane の発音は cyaneus などより推定。
種の記載時学名は Motacilla Cyane Pallas, 1776 で基産地 Dauria, between the Onon and Argu Rivers [southeast Transbaicalia] (Avibase による)。
Cyane は名詞で性変化がないこともわかる。同様の事例については#オナガ参考。
なお Pallas は Motacilla Cyanurus Pallas, 1773 とルリビタキも同じ属で記載している。コルリの方が尾の青さが目立たないかと言えばそういうわけではないのだが、先にルリビタキで使ってしまったので別の青由来の名前を与えた状況のよう。
Pallas (1776) 以降に cyaneus の女性形で Motacilla cyanea が複数あるが Ellis (1782) のものは ルリオーストラリアムシクイ Malurus cyaneus Superb Fairywren として生き残っている。-a が付くかどうかの違いだがどちらも有効な種小名となった。
[Larvivora (コルリ) 属の系統分類]
Larvivora 属 (larva 芋虫、幼虫 -vorus を食べる) は Hodgson (1837) が提唱したもので、Gray (1841) がコルリをタイプ種に指定した (The Key to Scientific Names)。ベンガル地方の鳥の記述で新属を提案したもの 記載。
色彩をもとにした属ではなく、blue Larvivora (コルリのこと) と brown Larvivora (Larvivora Brunnea) の2種を含めていた。後者はネパール産で雌雄同色 (参考)。現在はアカハラコルリ Larvivora brunnea Indian Blue Robin を指す。
よくこれほど色彩の違う種を同属にまとめたものと感心するが、もしかしてコルリのメスとアカハラコルリのメスが似ていることからの着想だろうか。雌雄同色としているのでアカハラコルリのオスを見ていなかったのかも知れない。
属名の由来は胃に大量の昆虫の幼虫が見つかったためとのこと。Crateropodinae に分類していて古い時代の概念でチメドリ類に近いと考えていた模様 (当時の考え方については #メグロの備考 [チメドリ類について] を参照)。同じコルリでも熱帯で見ればチメドリ類に思え、繁殖地で見ればサヨナキドリ (ナイチンゲール) のような種類に見えていたことになる。それぞれの土地での先入観の恐ろしいところ。
分子系統解析 [Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考) の分子系統樹を参照] により現在では安心して語ることができる (...と思っていたがしかし、の話を後に行う) が、Luscinia 属とはかなり縁が遠かった (別の言い方をすれば旧 Luscinia 属は多系統だったので分割する必要があった)。
コルリやコマドリの属名が複数回変わって、慣れた学名が変わるのはこりごりと感じられた方も多いと思うが、これは古く記載された属ほどヨーロッパのものが中心で、Luscinia Forster, 1817 はサヨナキドリ (ナイチンゲール) がタイプ種、Erithacus Cuvier, 1800 はヨーロッパコマドリ、Sylvia Scopoli, 1769 はズグロムシクイ。
属を分けるのを嫌ってまとようとすると必然的にヨーロッパの種がタイプ種となる属になってしまい、大きな属を採用するほど縁の遠いタイプ種になるため。これらの古典的な属が単系統をなさないことがわかって分割されるようになると、タイプ種から遠い地域の種類が特に何度も影響を受けることになった。
Larvivora 属の一覧を作っておくと:
ヒタキ科 Muscicapidae: Old World Flycatchers, Chats
ノビタキ亜科? Saxicolinae: Robins, Chats, Wheatears
コルリ属 Larvivora
(系統 1)
コルリ Larvivora cyane Siberian Blue Robin
アカハラコルリ Larvivora brunnea Indian Blue Robin
(系統 2)
コマドリ Larvivora akahige Japanese Robin
タネコマドリ Larvivora tanensis Izu Robin
ホントウアカヒゲ Larvivora namiyei Okinawa Robin
アカヒゲ Larvivora komadori Ryukyu Robin
ズアカコマドリ Larvivora ruficeps Rufous-headed Robin
シマゴマ Larvivora sibilans Rufous-tailed Robin
アカヒゲとホントウアカヒゲ、コマドリとタネコマドリは Zhao et al. (2023) では区別されていない。タネコマドリの分離は世界のリストに揃えた。
コルリ系統の2種とコマドリ系統の5(6)種の間には若干の系統的開きがあって別属にする扱いも可能なぐらい。
ただしこれを分割すると分岐年代整合性を保つためには Ficedula 属も分割した方がよいことになるため、分割されずに Larvivora 属にまとめられたものと考えられる。
この系統に最も近いのは Brachypteryx 属で、我々に近い場所のものではタイワンコバネヒタキ Brachypteryx goodfellowi Taiwan Shortwing がある。青いものではヒマラヤコバネヒタキ Brachypteryx cruralis Himalayan Shortwing などがある。見比べれば Larvivora 属との系統的近さが多少納得できる。
それぞれの属の順序などは難しいが、属内の配列はほぼ確定している。ヒタキ類の系統関係は系統樹全体を見て呆然とするよりもこの程度細かく個別に見てゆくと理解しやすい感じがする。
これらの結果は適当な配列から BLAST をやってみるだけでも十分理解できる。例えば AB236376.1, LC666796.1 (cyt b) などから。
アカヒゲとホントウアカヒゲが別種に値するほど違うこと、コマドリとタネコマドリが次の分離の候補になることがわかる。ルリビタキは分布範囲が広く地理的障壁が弱いので、種内の違いが大きめだが大きな系統には分かれていない (マガモなどと同様)。つまり分布域全体で比べると種内の違いは結構あるのに亜種に分けられない。
コマドリやアカヒゲは分布が狭く、地理的障壁に左右されやすい性質の種の場合は種分化が起きやすかったことも想像できる。
コルリと {コマドリ + アカヒゲ} 系統はそれなりに違うらしく、それぞれを出発点にすると一緒に現れないこともある。BLAST はコルリとコマドリが類似とあまりみなさないようなので、本当に同属にするほど近いのか少し確認しておくことにした。
アカハラコルリのさえずりを聞いてみると XC916279 (Peter Boesman), XC547680 (Andrew Spencer) のように "前奏" が存在する点がコルリに大変似ている。系統が近いことがわかり、分子系統樹ともよく対応している。
地鳴きは別にあって "前奏" が地鳴きの延長上にあるわけではなさそう。地鳴き (XC547697: Andrew Spencer) はルリビタキに似ていて系統関係がますますわからなくなる (BLAST でも系統樹にルリビタキがよく現れ、実際にある程度近いよう)。
一方でコマドリのような地鳴きもあるらしい (XC812014: Sandip das)。
JX256060.1 (ND2) を出発点に BLAST をしてみるとコルリと {コマドリ + アカヒゲ} は相当違う系統となる。
一方核遺伝子から HM633599.1 (myo intron) では Zhao et al. (2023) のような樹形が得られる。しかし HM633736.1 (ODC) ではまた樹形が異なってコルリとコマドリが分離される。
これらの系統はヒマラヤ周辺で早い時期に複数系統に分岐したため系統関係が不明瞭で、incomplete lineage sorting が存在する印象を持った。
Zhao et al. (2023) の時点では Larvivora 属全体で共通して調べられた遺伝子は上記4つしかなく、論文の系統樹形から想像すると核遺伝子の myo intron を重視した結果と思われる。ただしこの断片は短めであまり精度が高くないかも知れない。コルリの方が保全上あまり問題にならない種のためか思ったほど遺伝子が調べられておらず、直接比較しにくい要因となっている。
BLAST が "コルリと {コマドリ + アカヒゲ} は違う" 結果をこれほど返してくるのは何か理由があって無視できない気がする。
Zhao et al. (2023) が示すほどはコルリと {コマドリ + アカヒゲ} の関係は自明でなく、UCEs などを使ったさらに精度の高い解析が行われればもう一度再編される可能性もあるのではと思えてきた。
コマドリの系統が比較的離れていて単系統をなすことは確かなので分離して扱っておいてもよさそうに見える。ホントウアカヒゲをタイプ種とした Icoturus Stejneger, 1886 属 (#アカヒゲの備考参照) も候補に上がるかも。ぱっと調べた範囲ではコマドリ類の他種に独自の属名が与えられたことはなかったように見える。
論文の分子系統樹を頭から信頼するのではなく、疑問のある場合は確かめてみるべきと感じた。コルリはタイプ種なので属名が変わることを心配しなくてもよいが、コマドリやアカヒゲはそうではない。最も影響を受けるのは日本なので日本で関心のある人が調べないと海外では調べられないかも。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Larvivora 属となる。種小名は変化なし。
[亜種]
パブリックコメントで Red'kin (2006) の文献 (「極東の鳥類」31 (2014) p. 84 に和訳あり) に基づきサハリン、日本列島、千島列島の亜種を大陸とは別亜種 nechaevi (ロシアの鳥類学者 Vitaliy Andreevich Nechaev 由来) が提案され、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも採用されている (他に亜種不明が含まれている)。
海外のリストでも採用されている。なお沿海地方などのコルリは亜種 bochaiensis (Bokhai、極東ロシアにあった中世王国 渤海 698-926 の名前から。ロシア語表記は Bokhaj。Shulpin, 1928) とされ、日本の亜種名は従来はこちらだった。
基亜種 cyane は中央シベリア、北モンゴルなどで繁殖し、中国南部、インドシナ、タイ-マレー半島、スマトラなどで越冬するとされるが、越冬域は亜種ごとによく分離されているわけではないようである。亜種によるさえずりの違いなどはほぼ研究されていない。
亜種 bochaiensis の記載は Larvivora cyane bochaiensis Shulpin, 1928 で基産地 Fansa Station, Suchan railroad, southern Ussuria (Avibase)。
[音声など]
大阪城公園で2021年5月12-13日に記録されたカラフトムジセッカのさえずりが部分的にコルリによく似ていると表現された (出典)。
「前奏」とも呼ばれる匕、匕、匕...の繰り返しはコルリに特徴的であり、カラフトムジセッカではコルリよりも短く低い前奏が少数存在する程度である。このコルリの「前奏」を地鳴きと表現しているものもある (コンサイス鳥名事典) が、さえずりの一部と考えるのが妥当であろう。「前奏」のないコルリのさえずりも記録されているそうで、この場合コマドリとの識別が問題になる。
越冬地では太い声で短い低い単発の地鳴きが記録されているが、自身が観察した範囲で渡り時期に聞いたことはない (と思う) が、「鳥のおもしろ私生活」(ピッキオ 1997) には記載があり、繁殖地では聞ける声なのかも知れない。
コルリのメスのさえずりの記録がある。Tamara and Ueda (2000)
Female Song in the Siberian Blue Robin Luscinia cyane> この論文では外敵に対する警戒の意味があるように見えるとの記述がある。コマドリ、アカヒゲ、ルリビタキのメスのさえずりについても私信も含めた言及がある。海外記述ではノゴマ、オガワコマドリの事例が挙げられている。
田村・植田 (2001) コルリの繁殖生態 にも少し記述がある。
[渡り時期]
よく知られている通り、コルリの秋の渡りは早い時期 (もっともムシクイ類にもっと早く渡る種類があるが) で、8月後半から9月初めぐらいが中心である。猛暑の都市公園で蚊の襲撃を受けながらコルリを待つのは苦行以外の何物でもないと称されることもある。
過去の飼育書などではコルリは気温低下に敏感で、少し秋風があるぐらいで体調を崩すことが多いなどの記述がある。飼育には暖房設備が必須であるとのこと。コルリの低温耐性の弱さが早い時期の渡りに関係しているのではないかと思える。
ロシア沿海地方のコルリの繁殖: Shokhrin et al. (2025) Breeding birds of Primorsky Krai: the Siberian blue robin Luscinia cyane (pp. 385-406)。
亜種は bochaensis としている。秋の渡りは大部分8月と9月のこと。ここでもジュウイチの宿主となっている。
-
シマゴマ
- 第8版学名:Larvivora sibilans (ラルウィウォラ シービラーンス) シューシュー (虫のように) 鳴く幼虫を食べる鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Luscinia sibilans (ルスキニア シービラーンス) シューシュー (虫のように) 鳴くナイチンゲール
- 第8版属名:larvivora 幼虫を食べる larva 芋虫、幼虫 -vorus を食べる
- 第7版属名:luscinia (f) ナイチンゲール (サヨナキドリ)
- 種小名:sibilans (分詞) シューシュー鳴くこと (sibilo (intr) シューシューいう 英訳では whistle, chirp);「ピーピーという声」 (コンサイス鳥名事典) 備考参照
- 英名:Rufous-tailed Robin
- 備考:
larvivora は#コルリ参照。
sibilans は冒頭が長母音でアクセントもある (シービラーンス)。動詞 sibilo の現在分詞形 (英語では ...ing に相当) で変化形由来の長音。
記載時学名 Larvivora sibilans Swinhoe, 1863 (原記載) 基産地 Macao, southeastern China (Avibase による)。
質のよくない標本1体をもとに記述したもので、1861 年に自身が Larvivora ? として発表したもの (Notes on the Ornithology of Hongkong, Macao, and Canton, made during the latter end of February, March, April, and the beginning of May, 1860) に学名を与えた。
1861 年の記述では When I first heard the note, I could scarcely believe it to be
that of a bird, so like was it to the single chirp of the grasshopper; ...
When two of them came together, the sibilant note was repeated more
hurriedly and loudly, and then much resembled the chirrup of a
shrew mouse.
と音声の記述があり、最初聞いた時はバッタ類かと思ったとのこと。2羽で追い合う場合は "sibilant note" を出すとのことでトガリネズミの声に似ているとのこと。
英語の sibilant は摩擦音の入る子音 (sh など) を指し、高い周波数成分まで伸びた音声を形容しているものと思われる。「シューシュー (虫のように) 鳴く」の訳を採用した。
コマドリの地鳴きに近い雑音的なものを指しているのかと少し感じたが、やはり長く続く場合にセンニュウを思わせるさえずりが命名由来と推定した。
参考 XC448397 (Vadim Ivushkin)。
少し前奏が入るタイプもあり、コルリとの関連性が多少わかる感じがする: XC319946 (Tom Wulf)。
英語別名 Swinhoe's Red-tailed Robin。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Larvivora 属となる。種小名は変化なし。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。単形種。
亜種を認める考えもあり、記載時学名で Pseudaedon sibilans swistun Portenko, 1954 基産地 Lake Mazharskoye, east of Minusinsk (Avibase による) もあった。swistun はスイス? とか思ってしまうが、ロシア語名の svistun をそのまま亜種名にしたもの。svistet' は口笛を吹くなどの意味で種小名の意味と大差ない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Japan とあり、当時からシマゴマの名前があった。北海道あるいは島を指していたものかこの記述からは明確でない。
種小名について、Sibilatrix はかつてセンニュウ類の属名に使われていた。
その説明では peculiar sibilous cry とある。英和辞典ではこれも「シューシューいう」という訳語が出ているが、属の記載説明を読む限りでは虫のようなセンニュウ類の鳴き声を比喩した表現のようである (The Key to Scientific Names)。
おそらくシマゴマのさえずりのコマドリに対応する特徴的な震える声の部分を表現したものと思われる。
Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考参照) の分子系統樹ではコマドリの方が祖先系統にあたり、後に大陸にシマゴマが分布を拡大したように見える。北方に進出するにあたってあまり派手な色は不利だったのだろうか。
シマゴマは全ゲノムが読まれているのでいずれ系統関係がよりはっきりしてくるだろう。
PQ120420.1 のミトコンドリアゲノムから BLAST を行ってみるとコマドリ、ホントウアカヒゲの間で結構距離があることがわかる。思ったほど似ていない (コルリのデータはない。系統の問題は#コルリの備考参照)。この解析ではシマゴマの方が祖先系統にあたる。まだ順序ははっきり言えない段階だろうか。
-
ルリビタキ
- 学名:Tarsiger cyanurus (タルシゲル キューアヌルース) ふしょを持った青い尾の鳥
- 属名:tarsiger (合) ふしょを持った (tarsus (m) 足首(鳥の)ふしょ骨 gero (tr) 持つ) 直立してとまる姿から
- 種小名:cyanurus (合) 青い尾の (kyanos 紺青の oura 尾 Gk)
- 英名:Red-flanked Bluetail
- 備考:
tarsiger は tarsus, -ger ともに短母音のみのため長母音は生じないと考えられる。アクセントは "タルシゲル" と考えられる。
cyanurus はギリシャ語由来の合成語だが、cyano-, -urus ともに長母音が使われるので長音で発音されると思われる。アクセントは "キューアヌルス" と推定される。
OED によれば英語の bluetail はもとは別のものを指していて 1836 年にノハラツグミの用例がある。この用法はその後も使われていた。
1878 年に Dresser, Hist. Birds of Europe がアジアの鳥を紹介する時点で Red-flanked Bluetail の名称が導入され現在に至っている。こちらの方が bluetail にふさわしいとつけ直した可能性があるが、"脇腹の赤いノハラツグミ" の意味だった可能性も残るかも知れない。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では亜種 cyanurus となっているが、IOC 13.2 では単形種の扱い。
Clements 2022 以降、eBird 2022 以降は中国中央部の北部の亜種 albocoeruleus を認めているためかも知れないが、以前に同種とされていたヒマラヤルリビタキ Tarsiger rufilatus と亜種扱いにしているためかも知れない。
これらが別種であることが提案されたのは比較的新しく Luo et al. (2014) Deep phylogeographic divergence of a migratory passerine in Sino-Himalayan and Siberian forests: the Red-flanked Bluetail (Tarsiger cyanurus) complex。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では単形種となった。
茂田 (1996) Birder 10(11): 46-52 にルリビタキの記事がある。これによれば Sharpe (1879) 時代は当時ヒタキ科だった Tarsiger 属を Sharpe (1901, 1903) が キンイロヒタキ 現在の学名で Tarsiger chrysaeus Golden Bush Robin のみを含む Tarsiger 属 (当時ヒタキ科) と
Ianthia 属 (当時ツグミ科) に分割した経緯があるとのこと。ルリビタキは後者に含まれた。当時からヒタキかツグミかの問題があって同じ属がヒタキとツグミに分割されたこともあった。
Tarsiger 属 はもともと Hodgson (1845) による命名でキンイロヒタキのみを含んでいた (すなわちタイプ種)。その後概念が広げられたようでルリビタキも含まれたが一時は Ianthia 属と分離されていたよう。
Ianthia は ianthos 紫色の (Gk) から (#カラスバトの種小名参考) で、現在の分類ではヒマラヤルリビタキ Tarsiger rufilatus Himalayan Bluetail をタイプ種として Blyth (1847) で命名されたもの。
実は Nemura Hodgson, 1844 の属名がすでにあったが、Nemoura Latreille, 1796 の用例 (カワゲラ目) があり、Nemura に変更され、すでに使用されている属名として無効となったもの。Blyth (1847) が新たに名前を与えた (The Key to Scientific Names の情報から)。
ルリビタキとヒマラヤルリビタキは同種とされていたぐらいなのでふさわしい属名だったのだろうが分子系統研究の結果で属に分けるほどではなく復活しなかった模様。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Tarsiger cyanurus の学名とともに、これら2属の学名がいずれも示されている。
なおルリビタキの記載は古く Motacilla Cyanurus Pallas, 1773。基産地 Yenisei (エニセイ)。
その後属名が何回も変わったのはご存じの通り。Erithacus 属だったことも Luscinia 属だったこともある。分子系統研究を待たざるを得なかった。
Zhao et al. (2023) の分子系統樹 (#ヨーロッパコマドリの備考参照) によれば現在の Tarsiger 属は他の系統 (例えばジョウビタキ類) と分離したクレードとなっており、今後再編されるおそれはなさそう。
Tarsiger 属内部はすべての分岐が系統樹サポート率 100% なのでこの部分の系統樹は確定と考えてよい。
よほど変なことを考えない限りルリビタキの属名は Tarsiger でようやく確定したと言ってよいだろう。
ルリビタキ類、ジョウビタキ類が特にサバクヒタキ類などに比べて早く分岐したことは確かだが分岐順の系統樹サポート率はそれほど高くなくルリビタキ類、ジョウビタキ類の順序程度は今後入れ替わりが発生するかも知れない。ジョウビタキ類以降のクレード (イソヒヨドリ類、ノビタキ類など) は順序が変わる心配はほぼない。
そのように見ると旧 Ianthia 属は分離できないこともない。
同程度の分岐年代で属が分けられているグループも存在するが、Ficedula 属など大きな属も認められているので小さな Tarsiger 属がわざわざ分割されることはなさそうに思える。
過去の分類学者が提唱した属も分割の細かさだけの問題で方向性は正しかったことが確認できる。
それに比べれば Erithacus 属や Luscinia 属にまとめた分類は相当大雑把 (誰だ?) であったこともわかる。時間のある時にでも分子系統樹を見て楽しんでみてほしい。
Lan et al. (2024) Complete Mitochondrial Genome and Phylogenetic Analysis of Tarsiger indicus (Aves: Passeriformes: Muscicapidae)
にもより小規模ながらキクチヒタキを含めた解析がある。系統樹に表示されている種数が少ないのでヒタキ科とツグミ科の分離はむしろわかりやすいかも。
Wei et al. (2022) Cryptic species in a colorful genus: Integrative taxonomy of the bush robins (Aves, Muscicapidae, Tarsiger) suggests two overlooked species
によれば Tarsiger albocoeruleus Qilian Bluetail は別種。
台湾の Tarsiger indicus formosanus も別種 Tarsiger formosanus Taiwan Bush Robin が適切であるとのこと。
Working Group Avian Checklists, version 0.04 はこれらを別種としている。IOC 14.2 でも反映される予定。
非常に分布の広い種で、ヨーロッパから東アジアにかけて生息する。過去の #シマアオジ に似た分布拡大を行ってきたよう (#ツツドリの備考も参照)。
wikipedia 英語版によれば分布拡大は現在も続いているようで、フィンランドでは 500 つがいが繁殖とあり、ヨーロッパ地域で数が増えつつある迷鳥となっている。北アメリカでも記録があり、主にアラスカ西部が多いとのこと (ベーリング海を超えて分布拡大中?)。
Rare red-flanked bluetail bird spotted for the first time in the eastern US: See photos (USA Today) 2023年12月アメリカ東部で初記録。それ以前の最も新しい記録は2019年11月ワイオミング州 (アメリカ西部) とのこと。
越冬域は東南アジアで比較的狭いので遠くまで渡っていることになる。この関係はメボソムシクイ上種に似ている。ヒマラヤルリビタキも含め、メボソムシクイ上種のような拡大と種分化過程を見ているのかも知れない。
[Tarsiger (ルリビタキ) 属の系統分類]
Zhao et al. (2023) の分子系統樹に基づく。配列も分子系統樹順。ヒマラヤルリビタキはルリビタキと区別できないぐらい似ているが、他がどの程度似ているかは画像など見ていただきたい。
ルリビタキ属 Tarsiger
キクチヒタキ Tarsiger indicus White-browed Bush Robin
アリサンヒタキ Tarsiger johnstoniae Collared Bush Robin
キンイロヒタキ Tarsiger chrysaeus Golden Bush Robin
チャムネヒタキ Tarsiger hyperythrus Rufous-breasted Bush Robin
ヒマラヤルリビタキ Tarsiger rufilatus Himalayan Bluetail
ルリビタキ Tarsiger cyanurus Red-flanked Bluetail
[大陸とは亜種が違う?]
地域によってさえずりはかなり異なり、日本での声を知っていると別種に聞こえるほどである。またヒッヒッ...という地鳴きのジョウビタキとの識別がよく話題になるが (ただし#イソヒヨドリの備考も参照)、日本の個体では 5 kHz 以上であればジョウビタキ、もっと低ければルリビタキの識別が一般的に可能である (ジョウビタキでは興奮時もっと高い声も出すこともある)。
しかしながらこの識別方法は大陸の個体には通用せず、ルリビタキでも 5 kHz を超える地鳴きを出す。大陸では音声識別には音の高さでなく音質も考慮する必要がある (大陸ではジョウビタキよりルリビタキの方がより「まろやか」でソノグラムでは音声の立ち上がりとともに周波数が上がる構造が見られる)。
前記 Luo et al. (2014) では日本の個体は扱われていないが、サハリンと千島列島の個体はデータがある。中国のものとはそれなりの距離があるように見え、(この論文では単形種とあるが) 多少異なったグループかも知れない。
論文そのものの趣旨がもと亜種関係だったルリビタキとヒマラヤルリビタキを独立種とする提案なのでルリビタキの内部構造にはあまり立ち入っていない。また地理的に中央に位置する日本やシベリアなどのデータがないためあえて議論しなかったのかも知れない。
歴史的には Portenko (1954) "Ptitsy Sovietskogo Soyuza" 3, p. 191 (参考文献参照 ptitsy_sssr_3_1954.djvu) は6亜種と記述し、当時のソ連には3亜種としている。基亜種に加えて ussuriensis Stegman (ウスリー地方の。シベリア南部帯でアルタイ、サヤンから沿海地方まで) と
pacificus Portenko, 1954 (国後島 Yuzhno-Kurilsk ユジノ・クリリスク / 古釜布 1948 年がタイプ標本) でカムチャツカ、サハリン、千島列島、日本をこの亜種の分布域としている。東のこの型が最も青いとのこと。
わずかな色彩の違いから記載され、違いが小さく亜種としてまとまりを欠くためその後シノニムとされた。
参考: Vaurie (1955) Systematic notes on Palearctic birds. No. 15, Turdinae, the genera Turdus, Grandala, and Enicurus。
Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" pp. 511-518 (No. 304) では pacificus を島の亜種 (ここではサハリン) として取り上げ色彩が異なる特徴を挙げている。
音声面も考慮するとあるいはこの亜種が復活するかも知れない。地鳴きに違いがあるので遺伝的な違いも想定され、遺伝情報も調べてみると興味深いかも。
Wei et al. (2022) では一部取り扱われていて日本のルリビタキと大陸のものは遺伝的違いがないとしている。
[ルリビタキ類の altitudinal migration]
高所で繁殖して冬は低所で越冬する altitudinal migration (高低差渡り? 定訳があるのか知らない。ギル「鳥類学」訳本ではハチドリについて山を上下に移動する渡りの表現がある) があるが、大陸のルリビタキ類について低酸素適応に関係する遺伝子などの発現を比較したもの。
比較対象種はキクチヒタキとキンイロヒタキ。表現型の可塑性と渡り様式に関連があることを示唆する。
週間アニマルライフ (1973) p. 3954 (浦本) が日本のルリビタキを紹介しており、伊豆半島天城山脈の万三郎岳の頂上で毎夏にルリビタキのさえずりが聞かれる。天然の針葉樹林のある高度ではない。氷河期以来2万年の間しだいに温暖化してきたことを裏付けとともに、鳥が毎年生まれた故郷に戻る性質がいかに強いものを示していると見るべきであろう、と記している。
確認しておくと万三郎岳は標高 1405.6 m でこの地域は多雨地帯とのこと。全国鳥類繁殖分布調査の報告書には 1974-1978, 1997-2002, 2016-2021 いずれにもこの地点は表示されていない。標高 1000-1500 m 程度で繁殖期に声を聞くなどの記録は確かに少ない。
同じ記事で当時の長野県の志賀高原での緑川忠一氏が調査した 40 巣のうち 1/3 がジュウイチとツツドリの托卵を受けて全滅し、天敵となっているとのこと。ルリビタキ (Bird Research News 2007) にも短く触れられている。
-
セアカジョウビタキ
- 学名:Phoenicurus erythronotus (ポエニクールス エリュトゥロノートゥス) 赤い背中のジョウビタキ
- 属名:phoenicurus (合) ジョウビタキ (床屋の看板の赤色から赤いの意、phoinikiko koureas フェニキアの床屋 -ouros 尾の Gk)
- 種小名:erythronotus (合) 赤い背中の (erythro- (接頭辞) 赤い nota 後 Gk、-tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:IOC: Eversmann's Redstart
- 備考:
phoenicurus は#ジョウビタキ参照。
erythronotus は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は nota の冒頭が長母音なのでこれに合わせればアクセントもこの位置にあり "エリュトゥロノートゥス" となる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。英名の由来はドイツの生物学者 Eduard Friedrich Eversmann が由来。単形種。
英語別名 Rufous-backed Redstart。
-
クロジョウビタキ
- 学名:Phoenicurus ochruros (ポエニクールス オークルロース) 黄土色の尾のジョウビタキ
- 属名:phoenicurus (合) ジョウビタキ (床屋の看板の赤色から赤いの意、phoinikiko koureas フェニキアの床屋 -ouros 尾の Gk)
- 種小名:ochruros (合) 黄土色の尾の (ochra (f) 黄土、oura 尾 Gk)
- 英名:Black Redstart
- 備考:
phoenicurus は#ジョウビタキ参照。
ochruros は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は ochra の冒頭が長母音、oura 由来と考えればこちらも長母音となると推定される。アクセントはおそらく冒頭で "オークルロース" となると推定される。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では記録された亜種は中国南西部からチベットに分布する rufiventris (rufus 赤っぽい venter, ventris 腹) とされる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
その北部のモンゴルには亜種 phoenicuroides が分布し、ヨーロッパではごく普通の種類。世界で6亜種 (IOC)。
ヨーロッパではごく普通の種類となった経緯は #イソヒヨドリ備考 [山から人里に分布を広げた鳥] 参照。
中西悟堂「定本・野鳥記 3」p. 142 によれば戦前の朝鮮咸鏡北道 (現在の北朝鮮) でただ1回の記録ありとのこと。
-
シロビタイジョウビタキ
- 学名:Phoenicurus phoenicurus (ポエニクールス ポエニクールス) ジョウビタキ
- 属名:phoenicurus (合) ジョウビタキ (床屋の看板の赤色から赤いの意、phoinikiko koureas フェニキアの床屋 -ouros 尾の Gk)
- 種小名:phoenicurus (トートニム)
- 英名:Common Redstart
- 備考:
phoenicurus は#ジョウビタキ参照。
記載時学名 Motacilla Phoenicurus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 'in Europa'; restricted to Sweden by Hartert, 1910, Vog. pal. Fauna, 1, p. 718 (Hartert がスウェーデンに限定)。
和名はおそらく過去の学名に由来。#ジョウビタキの属の説明参照。
OED によれば redstart の用例は古く 1553 年にすでに使われ、ラテン語で ruticilla と説明されていた (別名 redtail に相当)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では記録された亜種は東はモンゴルまで分布する基亜種 phoenicurus とされる。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。他亜種は中東や南ロシアの samamisicus がありこれが世界の2亜種。基亜種はヨーロッパではごく普通の種類。
-
ジョウビタキ
- 学名:Phoenicurus auroreus (ポエニクールス アウローレウス) オーロラのようなジョウビタキ(赤い尾の鳥)
- 属名:phoenicurus (合) ジョウビタキ (床屋の看板の赤色から赤いの意、phoinikiko koureasフェニキアの床屋 -ouros 尾の Gk)
- 種小名:auroreus (adj) 暁の女神オーロラのような (神話)
- 英名:Daurian Redstart
- 備考:
phoenicurus はギリシャ語 -ouros の冒頭が2重母音のため -urus の冒頭は長母音となると考えられる。意味は違うがラテン語 urus も冒頭は長母音。長母音であれば "ポエニクールス" のアクセントになり語調も自然で覚えやすい。
auroreus は o が長母音でアクセントもある (アウローレウス)。
Phoenicurus 属は Forster (1817) が#シロビタイジョウビタキの記載時学名 Motacilla Phoenicurus Linnaeus, 1758 の種小名から属名に昇格したもの (シロビタイジョウビタキがタイプ種)。
同じ意味で Phoenicura 属の属名も使われたことがあった。
この事例ではこの2つの属名は同じものとして扱われている。
種小名から属名への昇格の際の当時の習慣で別名が導入され (#ノスリの備考参照)、シロビタイジョウビタキには Phoenicura albifrons Wood, 1836 の名称があった
(参考 1, 2。この名称を使ったのは Blyth で無効の可能性があったがこの記載は有効とのこと)。
シロビタイジョウビタキはこの学名が使われていた時代の和名と想像できる。
他にも Phoenicurus familiaris の学名も使われこちらは Common Redstart に対応する。
同じ属名は Bonaparte (1855) がアカオネッタイチョウを指して導入したものがある (The Key to Scientific Names)。
なお Phoenicurus 属と r と l が違うだけの特に日本人にとって非常に紛らわしい属名 Phoeniculus がカマハシ科 (モリヤツガシラ科とも呼ばれた) に存在する。
この属のタイプ種はミドリモリヤツガシラまたはミドリカマハシ Phoeniculus purpureus Green Woodhoopoe で学名を見てジョウビタキ類と早合点しないように。
こちらの -ulus は指小辞で長母音にならない。Phoenicurus を長母音で発音すれば Phoeniculus の "ポエニクルス" と r と l の区別に頼らなくても (あくまで理論的には) 区別できることになる。長音やアクセントを意識する利点が多少感じられる。
ジョウビタキをポエニクルスと発音するとミドリモリヤツガシラ類と誤解される可能性が (理論的は) 存在する (超マニアックな話なので受け流していただいてよい)。
ジョウビタキの記載時学名 Motacilla aurorea Pallas, 1776 基産地 Selenga River (Avibase による。バイカル湖に注ぐ川)。参考 によれば aurorae と綴っていたものが直されたよう。
英名の Daurian については#コクマルガラスの項目参照。
英語の redstart は中世英語の *redstert 由来で red + start に相当。start は現代の英語では失われているが尾の意味。オランダ語では staart が尾の意味で同様に roodstaart と呼ぶ。デンマーク語 rodstjert にも残っている (wiktionary)。
ロシア語でジョウビタキ類は gorikhvostka で gori が goret' (燃える) から、khvostka < khvost 尾 の指小語と着眼点が同じで基本語を覚えるのに役立つ。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では基亜種 auroreus。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
他の亜種には中国西部からチベット、タイの一部で繁殖し北東インドから東南アジアに渡るとされる西方型の leucopterus があるとされる。
こちらの記載は Phoenicura leucoptera Blyth, 1843 (原記載) 基産地 Malay Peninsula (マレー半島)。記載では Indian Redstart の英名を用いている。
Dement'ev and Gladkov (1954) によれば中国北部で Erithacus auroreus filschneri Parrot, 1907 (参考 1, 2) の記載がありこちらの方が古いので亜種の分離方法次第でこちらに先取権がある可能性を指摘していた。
また Phoenicurus aurorea orientalis Domaniewski, 1933 (参考) 基産地 Sidemi (ウラジオストク近郊) もあり、Dement'ev and Gladkov (1954) は亜種扱いを決めかねている。現在は基亜種のシノニムとされるが、もし亜種をさらに追加認識するならば日本のジョウビタキはこの亜種相当になるかも知れない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では亜種は 2? との表記で決めかねているよう。
Fauna Japonica での学名は Lusciola aurorea となっていた 。図版。
当時の Lusciola 属は Forster (1817) によるもので Motacilla luscinia Linnaeus, 1758 = ナイチンゲール から。Luscina 属も同じく Forster (1817) による (The Key to Scientific Names)。
日本語では海外の鳥を "なんとかウグイス" と呼ぶ感覚でヨーロッパでは "なんとかナイチンゲール" とみなしていたことがわかる。
日本で繁殖分布が高原地帯などで広がっていることはよく知られている。例えば山路他 (2021) 八ヶ岳周辺と高山市におけるジョウビタキ Phoenicurus auroreus の繁殖環境の選好性。
ジョウビタキが日本海を越えるか実はまだよくわかっていない。Valchuk and Irinyakov (2023) Does Daurian redstarts Phoenicurus auroreus cross the Sea of Japan during seasonal migrations? Ringing data analysis
身近な鳥でもまだ直接渡り経路を調べる研究がなされていないということだろう。
[大陸繁殖地のジョウビタキ]
中国ではジョウビタキがカッコウの宿主となっている。
Yang et al. (2016) Egg polymorphism and egg discrimination in the Daurian
Redstart Phoenicurus auroreus, a host of the Common Cuckoo Cuculus canorus、
Zhang et al. (2021) Host personality predicts cuckoo egg rejection in Daurian redstarts Phoenicurus auroreus。村には巣箱も多数あるそうである。
人工物やツバメの古巣などでも営巣し、人に頼る生活様式はカッコウ托卵を防ぐためとの解釈もある
[Zhang et al. (2023) Brood parasitism risk drives birds to breed near humans;
Passerine bird takes advantage of human settlements (Max Planck Society の解説記事 (2023)]。
ジョウビタキの繁殖解説記事。
中国越冬地でも繁殖を始めている報告がある。Rui et al. (2016) Breeding Ecology of Phoenicurus auroreus in Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve。
韓国でも建物や人工物で繁殖する映像が多数ある。1, 2, 3。
地上にも巣を作る。
ロシア沿海地方: Glishenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Daurian redstart Phoenicurus auroreus (pp. 849-875)。
[ジョウビタキのさえずり]
平地でも渡去前に完全なさえずりを聞くことがある。まとまった節のないぐぜりはよく聞かれるが、完全なさえずりとは特に似ていない。
Lee et al. (2019) The song structure and repertoire size of Daurian Redstarts (Phoenicurus auroreus) in South Korea
英文で読みやすいと思われるのでまずこちらを紹介しておく。ジョウビタキの完全なさえずりは「ヒー」で始まり、その後に複雑な節が続く。この研究では「ヒー」の部分は whistle part と呼んでいる。
Lee et al. (2019) Distinct patterns of geographic variation for different song components in Daurian Redstarts Phoenicurus auroreus では地理的変異などを調べている。
これらの研究のベースとなっているのが Huang et al. (2012) Two distinct parts within the song of Phoenicurus auroreus, and individual identification on the basis of the song で、
歌の2つの部分を stereotyped part (「ヒー」の部分 安定部分 中国語表記は下記を参照) variable part 可変部分 と呼んでいる。
論文全文は こちら から。この論文にも営巣環境の記述がある (1.1)。
-
マミジロノビタキ
- 学名:Saxicola rubetra (サクスィコラ ルベートゥラ) キイチゴの茂みの(地虫を食べる)石を打つ音を出す者 (または岩間の住人)
- 属名:saxicola (合) 岩間の住人 (saxum -i (n) 石 -cola 住人 < colere 住む) 命名時原意は石を打つ音を出す者 (#ノビタキ備考参照)
- 種小名:rubetra (合) キイチゴの茂みにいる (rubetum -orum (複数-属) (n) キイチゴの茂み)
- 英名:Whinchat
- 備考:
saxicola は#ノビタキ参照。
rubetra は rubetum 由来とすれば e が長母音でアクセントもある (ルベートゥラ)。語源説は他にもある (The Key to Scientific Names)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。
Linnaeus を始め、多くの初期の学者はマミジロノビタキ (Whinchat) と ヨーロッパノビタキ Saxicola rubicola (英名 European Stonechat) を混同していて、これらのノビタキ類の住む環境 (batos キイチゴ Gk) からアリストテレスの記載した地虫を食べる鳥 batis (Gk) を rubetra と翻訳したもの (The Key to Scientific Names)。
種小名の意味はトートニムに近い。亜種を認めることもある。
近年ではヨーロッパで越冬するマミジロノビタキが顕著に増えているとのこと。
-
ノビタキ (分割された。しかし AviList では第7版と別の形で統合され学名も英名も変わる)
- 第8版学名:Saxicola stejnegeri (サクスィコラ ステイネゲリ) シュタイネゲルの石を打つ音を出す者 (または岩間の住人) (IOC 14.2 も同じ)
- AviList 種学名:Saxicola maurus (サクスィコラ マウルス) 黒っぽい石を打つ音を出す者 (または岩間の住人)
- AviList 亜種学名:Saxicola maurus stejnegeri (サクスィコラ マウルス ステイネゲリ) シュタイネゲルの黒っぽい石を打つ音を出す者 (または岩間の住人) (IOC 15.1 では未採用)
- 第7版種学名:Saxicola torquatus (サクスィコラ トルクヮートゥス) 首飾りをつけた石を打つ音を出す者 (または岩間の住人)
- 第7版亜種学名:Saxicola torquatus stejnegeri (サクスィコラ トルクヮートゥス ステイネゲリ) シュタイネゲルの首飾りをつけた石を打つ音を出す者 (または岩間の住人)
- 属名:saxicola (合) 岩間の住人 (saxum -i (n) 石 -cola 住人 < colere 住む) 命名時原意は石を打つ音を出す者 (備考参照)
- 第8版種小名:stejnegeri ノルウエー生まれアメリカの動物学者 Leonhard Hess Stejneger の
- AviList 種小名:maurus 黒っぽい
- 第7版種小名:torquatus (adj) 首飾りをつけた
- 第7版亜種小名:stejnegeri ノルウエー生まれアメリカの動物学者 Leonhard Hess Stejneger の
- AviList 亜種小名:stejnegeri ノルウエー生まれアメリカの動物学者 Leonhard Hess Stejneger の (IOC 15.1 では未採用)
- 英名:[Stonechat 分割前の名称], IOC 14.2: Stejneger's Stonechat, IOC 15.1: Amur Stonechat (Siberian Stonechat への統合は未採用), AviList: Siberian Stonechat
- 備考:
saxicola は短母音のみで sak-si-co-la と分離され、-si- にアクセントがある (サクスィコラ)。慣れるまでは -cola を伸ばさないように意識的に長音にして "サクスィーコラ" と読んでおいてもよいと思う。
stejnegeri は規則通りであれば "ステイネゲリ" のアクセントになる。別の読み方については#ビロードキンクロ参照。
maurus は短母音のみで "マウルス"。
torquatus は a が長母音でアクセントがある -kwa- の発音で (トルクヮートゥス または トルクアートゥス)。Aquila で "w" の音を添える感覚と同じ。
torquatus (現代の分類では African Stonechat) の記載時学名は [Motacilla] torquata Linnaeus, 1766 (原記載) で、
Collum a tergo album で "首が白く拭かれている" ぐらいの意味でよいだろうか。写真を見ても全周が白いわけでもないので首飾りと言っても首輪のようなものを想定しているわけではなさそう。
Linnaeus の発明した種小名というわけではなく Muscicapa torquata (Brisson) の用例を参考にして整理した模様。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Saxicola stejnegeri (種小名はノルウエーの動物学者 Leonhard Hess Stejneger 由来。英名 Stejneger's stonechat または Amur Stonechat)。Stejneger の綴りと読み方については#ビロードキンクロの備考参照。
Saxicola torquatus はかつては南アフリカから日本まで広範な分布を持つ種であったが、現在はサハラ以南のアフリカから中東南部の種類を指し、英名 African Stonechat となる。
ノビタキはこの種からシベリアノビタキ Saxicola maurus (英名 Siberian Stonechat) などとともに分離された。
参考 Opaev et al. (2018) Species limits in Northern Eurasian taxa of the common stonechats, Saxicola torquatus complex (Aves: Passeriformes, Muscicapidae)。
シベリアノビタキと同種に扱われることもあった。新分類では単形種。
旧英名の Stonechat は分離以前の名前。
Working Group Avian Checklists, version 0.02 以降でシベリアノビタキとノビタキが統合され、シベリアノビタキの記載の方が早いので、日本のノビタキの学名は Saxicola maurus (亜種まで記して Saxicola maurus stejnegeri) に変わることになる。
第8版に合わせて Saxicola stejnegeri の学名を使い始めた方の中にはもし翌年 WGAC (IOC 15.1 では未採用) 学名を取り入れればノビタキの学名が数ヶ月の間に2回変わる体験をされる方もあるかも知れない。しかも (おそらく。しかし実証は DNA を見ないとわからない) 日本産でない亜種が基亜種となるので#オオモズの学名変更と同様にややこしい。
覚えたばかりなのに、と思われる方もあるだろうが、"学名は世界共通" であることを重視するならば世界共通化のためこのような状況はやむを得ない。
統合後の英名には Stejneger's Stonechat は種名には残らないだろうが、亜種名として残ると思われる。IOC 15.1 では未採用だが英名は Amur Stonechat となった。
Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では統合したものとなっており、英名は Eastern Stonechat / Siberian Stonechat としている。
後述の 茂田 (1992) の記述も参考。この時点では形態学によるものであったが、Saxicola maurus の亜種となっている variegatus が現在の学名で Saxicola stejnegeri と mtDNA で確実に分離できない (Zink et al. 2009) ことが根拠の模様
(Latest IOC Diary Updates および
Stejneger's Stonechat から始まるスレッドを参照)。
少し古い研究なので、今後核 DNA の調査が進めば事情が変化する可能性もあるかも。この統合は現在の遺伝的情報に基づく暫定的なもので将来再度分離される可能性もあるかも知れない。分子遺伝学によって単系統性の弱い亜種を統合し、一方で単系統をなすグループが見つかればこれまでと違う種境界で種を分離することもあり得るかも。
AviList (2025.6) では Saxicola maurus stejnegeri となった。
27988 171, 172, 171)) Taxon stejnegeri is treated as conspecific with Saxicola maurus pending further research. Although mitochondrial DNA data (Zink et al. 2009; Illera et al. 2008) indicate the presence of deep divergences within the Asian stonechats, not all taxa have been sampled. Furthermore, unsampled taxa have senior scientific names and may be closely related to stejnegeri; consequently, the split of stejnegeri is considered premature; genomic data required.
172)) Saxicola torquatus is treated as three species based on available evidence: S. maurus (Asian stonechats, polytypic); S. torquatus (African stonechats, polytypic); and S. rubicola (European stonechats, polytypic). Genomic (Van Doren et al. 2017) and mitochondrial DNA data (Zink et al. 2009; Illera et al. 2008) do not recover S. torquatus sensu lato as monophyletic, with S. dacotiae embedded within it. A more comprehensive taxonomic review of this complex is required given the ecological and phenotypic similarities among these species.
非常に複雑で2回に分けて議論が行われた。stejnegeri を Saxicola maurus の亜種とすることは 171 ですでに決まり、172 では Saxicola torquatus の範囲の扱いが問題となった。
171 ではアジアのノビタキの間の遺伝的違いの深さ (種相当) が問題となったがすべての亜種が調べられたわけではない。遺伝的情報の得られていない亜種の中に stejnegeri より早い時期に記載されたものがあるため、先取権の原則から stejnegeri の種小名とならない可能性があるので分離してこの種小名を与えるのは時期尚早と判断された
(逆に言えば文献が少し古いため、最新の分子遺伝学情報によってまた分離されて学名が戻る可能性がある)。
IOC 15.1 ではまだこの統合がなされていなかったため IOC 名はなく (Clements, BirdLife も同様)、AviList で採用された英名 Siberian Stonechat が採用されるものと思われる。
属名の性については #ヤマザキヒタキの備考参照。
分離前の種は Saxicola torquata と女性扱いのこともあったが、これは誤りとのこと。cf. David and Gosselin (2002) The grammatical gender of avian genera。
rubetra (マミジロノビタキ) は女性形容詞のように見えるがラテン語名詞とのこと。rubicola (ヨーロッパノビタキ) は合成名詞。種小名の語尾の性が統一されていないように見えるが、Saxicola は男性とのこと。-cola で終わる名詞は男性か両性で、使用例をもとに性が決まるとのこと。
Petricola は当初女性で扱われたため女性の扱いとなっている。
-cola で終わる属名の性は一般則があるわけではなく個々に確認する必要がある模様。
属名の由来は文字通り解釈すれば石の住人であるが、茂田 (1992) Birder 6(10): 36-41 によれば岩間に住む種類ではなく、(石を打ち合わせる音に似た) 地鳴きが由来ではないかとの説があるそうである (Gulch 1981)。英名も同じ解釈ができる。
Bechstein (1802) が名付けた属名で 記載。属記載のドイツ名 Steinschmaetzer で Stein 石 schmatzen が舌鼓を打つなどの意味なので 茂田 (1992) = Gulch (1981) の解釈を裏付ける。
また当時提案された同属の種にハシグロヒタキ (大きい Steinschmaetzer と表記) も含まれていた。
現在のドイツ語の属総称は Wiesenschmaetzer で Wiesen- (草場の) で岩場などの意味は含まれていない。むしろ日本の "ノビタキ" の語感と同じになっている。
タイプ種がヨーロッパノビタキ (現在の Saxicola rubicola) なので -cola に "住む" 意味を含めたというより単に "者" を指して、造語の際に種小名と韻を踏ませたものかも知れない。
そう思ってみると Perdicula 属は Perdicula rubicola [Hodgson, 1837] = 現在のヤブウズラ Perdicula asiatica として定義されたもので、Perdix の指小形を意図するとともに韻を踏ませたように見える。ヨーロッパ言語では韻を大変重要視するので、特に当時はこのような使い方が多かったのかも知れない。
OED によれば stonechat の用例は Latham, General Synopsis of Birds (1783) によるもの (当時は Stone-Chat) で、当時の学名で Motacilla rubicola となっていた。すでに使われていた一般名かも知れないが証拠はなく Bechstein (1802) の記載由来かも知れない。
茂田 (1992) によれば亜種時代に、stejnegeri と maurus は区別できないので前者は後者のシノニムとすべきとの見解はあった (Svensson 1984)。Svensson (1992) [翻訳され「ヨーロッパ産スズメ目の識別ガイド」 (2011 文一総合出版)] では両亜種の違いを認めている。
現在では多くのリストで別種とされ、シベリアノビタキ Saxicola maurus Siberian Stonechat。こちらは Pallas (1773) が記載で基産地 Karassum (西シベリア)。maurus は黒い、暗色の意味。
Zink et al. (2009) Taxonomic status and evolutionary history of the Saxicola torquata complex の研究でユーラシア東西で大きな遺伝的違いがあり、3種への分離が妥当としたもの。
ツバメチドリ類の種小名や英名に現れる pratincola (prati 牧草地 incola 住人 の意味) はノビタキ類の属名に使われていたことがあった。Pratincola Koch, 1816 で現在は Saxicola のシノニムとされる。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではノビタキの学名は Pratincola maura となっていた。上述の分類変遷経緯を見ていただけばこの学名も理解可能だろう。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では Pratincola maura で英名は Siberian Stonechat。
Parrot (1908) により亜種記載時学名 Pr.(atincola) rubicola stejnegeri 原記載。基産地は択捉島と北海道。北海道以南もこの亜種に含めたのは後世の判断となる。
この文献でも亜種 maura の地理的変異である可能性はさらに調べる必要があるとしている。
ノビタキ類のロシア名は chekan で日本語の "チカン" と同じ発音になる。由来はやはり音声で、chik-chek-chek と石を打つような声から (Kolyada et al. 2016)。音声がなぜそれほど目立つのかは後記参照。
ウクライナ語では trav'yanka + 種ごとの形容詞 で「草に住む者」。
フランス語は上記語源とはあまり関係がなく、tarier patre で tarier は tarin (マヒワ) 由来とのこと (wiktionary)。patre は羊飼い。おそらくマヒワにそれほど深い意味はなく羊飼いに馴染みの小鳥を指したのだろう。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では stejnegeri は亜種扱いで Saxicola torquata に含めていた。別種にする見解があることも述べられている。この時点では Saxicola torquata に 20 以上の亜種があった。
Ryabitsev (2014) の見解ではシベリアの亜種は maura と stejnegeri の2つで色彩の違いは小さい。メスはほとんど同じと記述していた。
[ノビタキ類似種の識別の問題・ヨーロッパへの迷行]
東ユーラシアで2種に分けられたことで繁殖地以外での区別が困難となり、Stejneger's Stonechat in Korea: A Quick Introduction with Images (Nial Moores, Birds Korea 2012) のような記事もある。
亜種 przewalskii (中国西部で繁殖するとされる) の位置づけはほとんどわかっていない (現在の通常の分類では暫定的に Saxicola maurus に含まれている)。
英国で 2012 年に記録されたノビタキは DNA 判定で確認されたとのこと。Cade and Collinson (2015) 'Stejneger's Stonechat' in Dorset: new to Britain。標識捕獲しても識別が難しい。
ミトコンドリアの ND2 遺伝子を Zink et al. (2009) と比較した結果だが、ミトコンドリアしか調べていないので核遺伝子の結果も同じになるかどうかは 100% 確実ではないとのこと (雑種の場合は異なる可能性がある)。Genbak entry にこの個体の塩基配列がある。
この論文によれば 2008 年のスウェーデン個体が予備的な DNA 解析で、そしてこの後の 2013 年のフィンランド個体が遺伝的解析で stejnegeri と同定されているとのこと。
ヨーロッパ以外では UAE でも ND2 遺伝子解析による同定がある: Campbell et al. (2023) A record of Amur Stonechat Saxicola stejnegeri from the United Arab Emirates confirmed by genetic analysis。
現状 DNA を調べないと確実に区別できないらしい。
Cade and Collinson (2015) にも書かれているが、ユーラシアを横切るように渡ってヨーロッパで越冬するする種類がいくつも存在する。種全体ではノビタキは案外西でも越冬しているのかも知れない。
Zink et al. (2009) 以降のノビタキ近縁種の系統研究の情報がないが、Saxicola 属も西アジアが起源 (例えばマミジロノビタキのように) で草地の広がりとともに分布を東西に広げた可能性がある [後述 Illera et al. (2008) の議論も参照]。渡りルートやヨーロッパへの迷行 (または越冬) 傾向にもその由来が含まれているかも?
アフリカの Saxicola 属は系統が新しく後に分散したもののようで、アフリカ起源ではなさそう。
Oenanthe 属は比較的よく調べられているが、Saxicola 属はあまり注目されていない様子。
これらを含むグループの全体的な系統樹は Aliabadian et al. (2012) Convergent evolution of morphological and ecological traits in the open-habitat chat complex (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae)
参照だが種サンプルは少ない上、現状オープンアクセスでない。
オープンアクセス論文では Woog et al. (2008) Distinct taxonomic position of the Madagascar stonechat (Saxicola torquatus sibilla) revealed by nucleotide sequences of mitochondrial DNA (シベリアノビタキが含まれている) や
Illera et al. (2008)
Phylogenetic relationships, biogeography and speciation in the avian genus Saxicola の系統樹が参考になる。これらの時点では東アジアの情報は不明だった。
東アジア抜きに考えれば Saxicola 属は同様にアジア由来で他の広域に拡大したグループ (タヒバリ類やセキレイ類) と異なって "その場" での種分化の傾向が見られるとのこと。この研究の時代にはノビタキ近縁種が別種に分離されていなかったので全種サンプルされたことになっており、東アジアのノビタキをサンプルする必要性があまり感じられなかったのかも。
この論文でもマダガスカル起源でアフリカに広がった可能性は除外してよいのではと考えている。
ノビタキ類の分散に際してサハラ砂漠は障壁になっていない。
Saxicola 属はイソヒヨドリを含む Monticola 属の次に分岐した系統と考えられており、Oenanthe 属はその後の出現順序になる。
日本鳥類目録改訂第8版の配列 (= IOC 13.2) はこの分岐順序を反映したものになっている。
アフリカや中東の種分化は興味を持ってよく調べられているが Saxicola 属は解析から外れてしまう印象を受ける (ユーラシアのサンプルは得にくいのかも)。
[#鳥類系統樹2024] の Stiller et al. (2024) ではハシグロヒタキとシベリアノビタキのみが解析対象で、Ficedula 属よりも新しく分化した系統であることがわかる。
Saxicola と Oenanthe の分岐は 500 万年前ぐらいといずれも新しく (この数字を Saxicola の出現年代とおおよそ考えてよい)、相互に識別困難な種が多く含まれている理由も理解できる。
[北海道のノビタキの渡り]
北海道のノビタキはジオロケータ調査で本州を通らず、大陸を経由して越冬地に渡ることが明らかにされた
: Yamaura et al. (2016) Tracking the Stejneger's stonechat Saxicola stejnegeri along the East Asian-Australian Flyway from Japan via China to southeast Asia;
日本語資料。
本州のノビタキと亜種レベルで異なるのか興味あるところ。
藤巻 (2009) Birder 23(6): 35 によれば標識のカラーリングが翌年に退色し、よほど日射しの強い日光下で越冬しているのではとの考察がある。
Stonechat reaches south-east Texas (Birdguides 2025.3.25) の記事によればアメリカテキサスでもおそらく (シベリア)ノビタキ と考えられる個体が 2024.12.19 記録された。アラスカを除く大陸部でアメリカで未同定の 1995 年の記録以来過去2例目とのこと。アラスカでは比較的定期的に記録されている。
[行動と繁殖]
「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) pp. 179-180 によるとノビタキ (当時は日本のものも同種) の地鳴きの音源定位が容易なのは地上性捕食者に対して自身に注意を向けさせるため (はぐらかしディスプレイ。ホワイトノイズ的な音声は音源定位が容易なことは理論的にも予想され、後の実験でも確かめられている) で、白斑も見せて目立たせるとのこと。チドリ類の擬傷行動と同様との説明になっている。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Amur stonechat Saxicola stejnegeri (pp. 1169-1187)
にロシア沿海地方のノビタキの繁殖生態がある。北海道のノビタキ個体群との関係も予想されるので比較して参考になる情報と思われる。
ホオアカによる托卵の写真があるが、これは 30 m 離れたところにホオアカが営巣しており、産卵場所を間違えたのではと解釈している。
-
クロノビタキ
- 学名:Saxicola caprata (サクスィコラ カプラータ) 石を打つ音を出す者 (または岩間の住人) のクロノビタキ
- 属名:saxicola (合) 岩間の住人 (saxum -i (n) 石 -cola 住人 < colere 住む) 命名時原意は石を打つ音を出す者 (#ノビタキ備考参照)
- 種小名: Maria-capra 由来 Brisson (1760) によればルソン島の住人による現地名とされる
- 英名:Pied Bush Chat
- 備考:
saxicola は#ノビタキ参照。
caprata は外来語由来で発音はよくわからないが -atus を用いて造語したのであれば -ata の冒頭は長母音となる。これを前提に "カプラータ" とするのがアクセントも語調もわかりやすい感じがする。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。世界に 16 の亜種があるが (IOC) 日本の亜種は不明。Brisson (1760) がラテン名を付けたが二名法に則らない書物であったため、Linnaeus が Brisson (1760) の仕事を参照して新たに付けた学名 (wikipedia 英語版)。Brisson はフランス語名では Traquet de l’isle de Lucon として紹介した。
-
ヤマザキヒタキ
- 学名:Saxicola ferreus (サクスィコラ フェルレウス) 鉄のような石を打つ音を出す者 (または岩間の住人)
- 属名:saxicola (合) 岩間の住人 (saxum -i (n) 石 -cola 住人 < colere 住む) 命名時原意は石を打つ音を出す者 (#ノビタキ備考参照)
- 種小名:ferreus (adj) 鉄の
- 英名:Grey Bushchat, IOC: Grey Bush Chat
- 備考:
saxicola は#ノビタキ参照。
ferreus は短母音のみでアクセントは冒頭 (フェルレウス)。
2亜種 (ferreus, haringtoni) あるが (IOC 13.2 など)、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では特に言及はない。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種不明と記載されている。
かつてはクロシロノビタキ Saxicola jerdoni (英名 Jerdon's Bushchat) の亜種とされたこともあった。
松田 (2003) Birder 17(8): 31-35 によれば "ヤマザキ" は人名山崎への献名だがそれ以上の情報がないとのこと。
原記載 記載時学名は Saxicola ferrea Gray, 1847 で、Saxicola は女性名詞として扱われていたことがわかる。
David and Gosselin (2002) The grammatical gender of avian genera に属名の性について解説があり、Saxicola は男性とのこと。同じ -cola でも Pinicola は女性になるとのこと。両性名詞で最初に確立された用例で性を決める規則に当てはまる事例とのこと。
Hartert (1910-1922) では p. 711。Hartert は Oreicola Bonaparte, 1854 (タイプ種 チモールノビタキ 現在の学名で Saxicola gutturalis White-bellied Bush Chat) に分類していた (p. 710)。
Rhodophila Jerdon, 1863 (クロシロノビタキ 現在の学名で Saxicola jerdoni Jerdon's Bush Chat のみに与えられた属) は属名シノニムとのこと。
英語でなぜ Grey Bush Chat なのかわからなかったのだが、原記載にもこの色の記述はなく、もしかすると発見者の名前から Gray Bushchat となり、アメリカ英語から変換する時に Gray を色と解釈して Grey とされたのかも (?) 印象を受けた (後によりもっともらしい別解釈を紹介する)。
原記載でも黒・白が目立つ記載になっていて、なぜ学名に「鉄の」が付くのかもすっきりしない。
同種とされることもあったクロシロノビタキの方の 原記載 (Blyth 1867)。こちらは多くの言語で Jerdon の名前を付けて呼ばれている。"クロシロ" に相当するものが散発的にあり中国語 (和名から由来?)、ポーランド語、スロバキア語など。ロシア語では "2色のノビタキ" で、これはクロノビタキの英名に対応する。
確かにクロシロノビタキの方が "クロシロ" がより明瞭なのでこの和名はこちらに当てるのがふさわしかったのだろう。
英名ではクロノビタキが Pied Bush Chat の名前を持っているため、"クロシロ" に相当する英名を付けられなかった可能性がある。
なお英名末尾は Bush Chat (IOC)、Bushchat (Avibase) など流儀が多少分かれている。
さらに調べるとややこしいものがあった Pratincola ferrea Blyth, 1847 (参考 Hodgson n.s.) 基産地 eastern Himalayas。記載。
当時は Pratincola 属はノビタキ類に用いられていたが (Koch 1816)、ツバメチドリを指した Forster (1795) の用例があったため後にこちらに先取権があることが判明した模様 (#ツバメチドリの備考や英名を参照)。Hartert の時代にはまだ知られていなかったようで Pratincola 属をノビタキ類に用いていた。
ツバメチドリの Pratincola 属は Brisson (1760) の Glareola が有効となってシノニムとなり、Pratincola 属の名称は現在は表面上現れなくなっているが Bush Chat との意味的対応はよく見える。(Stonechat は意味の上では Saxicola に対応する)。
Bush Chat と付く英名は Pratincola 属が有効だった時代に付けられたものではないだろうか。
この Blyth (1847) のものは有効とされず、Gray (1847) が有効となった模様。この Blyth (1847) にも英名の由来は現れないが、ferrea と名付けたのは Hodgson らしい。
Hodgson Volume IV に多少のヒントがあり、Hodgson が Dark Grey bush chat と呼んでいたらしく、Pied bush chat に対する用語、Hodgson は後者を leucomelura と呼んでいた。
少し形が違うが Black-and-White Stone-Chat Saxicola leucomela を指していたのではないだろうか。Gould の図版と解説。セグロサバクヒタキと思われる [Hartert (1910-1922) p. 688 のシノニムでもこれでよさそう]。
この読み方が正しければ Hodgson はセグロサバクヒタキと対比させて "Dark Grey" と名付けたものと考えられる。白黒まだらではなく一様で濃い灰色と考えたとすれば英名の由来も納得できる気がする。
長いので Dark を外して Grey Bush Chat となったと想像できる。
なお Catalogue of the specimens and drawings of mammalia and birds of Nepal and Thibet (1846) では p. 71 に The Stout Stonechat. Saxicola ferrea. Rubecola ferrea. Hodgs. Gray. Zool. Misc. p. 83 (該当ページ Rubecola ferrea で英名はない) として現れる。
stout は頑強な、太ったなどの意味。語源的には威張った (英語 proud に相当。現在はこの語義では使われない) などの意味が目立つ。ferrea はもしかすると威張ったような行動、たとえて鉄のような頑強さを表現したかったのかも。また stout はビールにも (dark and strong malt brew。イギリス産の濃厚でアルコール分の高い黒色のビール, wiktionary から) 使われるのでこの色彩を表現したものかも知れない。
種小名の解釈はこれらを加味して「鉄色」とはせず「鉄のような」とした。英名・学名・和名いずれも一筋縄で行かない種類のよう。
-
イナバヒタキ
- 学名:Oenanthe isabellina (オエナンテー イサベールリーナ) 灰色っぽい黄色の渡り鳥
- 属名:oenanthe (f) oinanthe (Gk) アリストテレスの記載した、ブドウの花の咲く頃に渡ってくる鳥
- 種小名:isabellina (adj) イザベルのような (Isabella イザベラ (女性の名) -inus 〜に関連する) 英語にもなっている isabelline は灰色っぽい黄色の意味
- 英名:Isabelline Wheatear
- 備考:
oenanthe は#ハシグロヒタキ参照。
isabellina は isabella は e が長母音、-ina の i も長母音となる。"イサベールリーナ" のアクセントと考えられる。英語 isabelline は e にアクセント。英語読みの場合はこちらに合わせそう。
OED によれば Isabel は色の名前で Isabel yellow などの名称も使われた。Isabella がもとの語形で 1600 年にすでに用例があった。女性の名前 Isabella 由来とのこと。
記載時学名 Saxicola isabellina Temminck, 1829 基産地 Nubia。記載 フランス語名 Traquet isabellin。記載から色彩に由来。Rueppel のアフリカ北東部探検で採集された。
図版 (上)。
翌年に Saxicola isabellina Cretzschmar, 1830 (参考) に同じ学名で記述されている。こちらには Rueppel の Atlas zu der Reise im noerdlichen Afrika と出典が示されている。
単形種。
英名の wheatear は現代の英語で簡単に理解してしまいそうな wheat (小麦) ear (耳) の意味ではなく、16 世紀の英語で white arse (腰の白い部分を指す) がなまったものとのこと (wikipedia 英語版より)。
もっとも英語 wheat も種が白いことが語源なので、語源が全く無関係というわけではない。
OED によれば同様であるが、1653 年に Because they come when wheat is yearly reap'd と小麦の実る季節にやってくるとの解釈がすでに出ており、俗解釈だったかも知れないが早い段階で綴りは wheat の影響を受けたことがわかる。1591 年の初出時の綴りは whekeres だったとのこと。1661 年ごろの用例で *whiteeres があるので white arse 説が有力視される。オランダ語では witstaart、ドイツ語では weiss-schwanz などいずれも白い尾または腰の意味となっている。
ロシア語名が少し面白く kamenka-plyasun'ya。kamenka はサバクヒタキ類で、plyasun'ya は踊り手。plyasat' 踊る。よくしゃがむ行動に由来する名前とのこと (Dement'ev and Gladkov 1954。尾の模様の特徴を示しつつその姿勢の図版も載せられている)。
Kolyada et al. (2016) によれば飛び上がる、しゃがむ、お辞儀する、翼を羽ばたく行動を指すとのこと。
他の学名シノニムに Saxicola saltator Menetries, 1832 (参考) があり、saltator は踊り手で、フランス語 sautiller は飛び跳ねる (The Key to Scientific Names)。
Saxicola squalida Eversmann, 1835 (参考) squalida は粗雑な、硬いなどの意味。
森岡 (1998) Birder 12(6): 70-73 にイナバヒタキとハシグロヒタキの識別がある。
波多野邦彦氏の第20回 Oenanthe <サバクヒタキ類> (独断と偏見の識別講座 II 2014)。
Kakhki et al. (2023) A phylogenomic assessment of processes underpinning convergent evolution in open-habitat chats (bioRxiv preprint)
にサバクヒタキ類のゲノム解析による分子系統研究がある。なぜ互いにそれほど似ているのか。開けた環境での収斂進化、incomplete lineage sorting (ILS) が関わっている。ILS は実効個体数が大きく、急速な種分化を遂げた系統でよく見られる。そして遺伝子浸透の影響が考えられる。
核遺伝情報とミトコンドリア遺伝情報で異なる系統樹になる部分もある。
日本に関係する種ではセグロサバクヒタキと Oenanthe melanoleuca Eastern Black-eared Wheatear の間で発生している。後者はカオグロサバクヒタキ Oenanthe hispanica Western Black-eared Wheatear の亜種とされることもあるが、分子系統解析からはセグロサバクヒタキを種とみなすならば分離するのが妥当。
日本で記録されている種類では {イナバヒタキ + ハシグロヒタキ} と {セグロサバクヒタキ + サバクヒタキ} が別の系統になる。推定分岐年代は 300 万年前以上とサバクヒタキ類としては結構古く、ノビタキ類などと分岐してからそれほど経たない時期に複数の系統に分かれたことになる。
後者の系統はこの論文では hispanica-complex の名前になっている (カオグロサバクヒタキ Oenanthe hispanica Western Black-eared Wheatear を代表としている)。
イナバヒタキとハシグロヒタキが別種であることは分子系統解析からも明らかだが、ハシグロヒタキとサハライナバヒタキ Oenanthe heuglini Heuglin's Wheatear およびチャムネサバクヒタキ Oenanthe bottae Botta's Wheatear の間は関係が近く核遺伝情報とミトコンドリア遺伝情報で異なる結果が出ている。
Oenanthe 属は色彩と生息地に基づいて種が分離された経緯もあり、100 万年前以降のかなり新しい分岐がかなり多数ある。種分化年代が若い上にさまざまなメカニズムが関係して互いに非常に似ているらしい。
-
ハシグロヒタキ
-
セグロサバクヒタキ
- 学名:Oenanthe pleschanka (オエナンテー プレシャンカ) 頭にはげがあるヒタキ
- 属名:oenanthe (f) oinanthe (Gk) アリストテレスの記載した、ブドウの花の咲く頃に渡ってくる鳥
- 種小名:pleschanka (合) 頭にはげがある pleshanka [plesh' はげ、はげたところ (頭の模様を指す) -nka 愛称/指小的な造語語尾 露]
- 英名:Pied Wheatear
- 備考:
oenanthe は#ハシグロヒタキ参照。
"プレスカンカ" はラテン語読みでアクセントは "プレスカンカ" でよいと思われる。原語では "プリェシャンカ" の音に近い。ラテン語化のため音が変わるのはやむを得ない。
しかしロシアの鳥学はドイツから大きな影響を受けていたので、学名もドイツ語読みを意識して綴っていたかも知れない。その場合は "プレシャンカ" と読むことが可能。原語読みに非常に近いのでこちらを採用した。
#アカハラダカの属名など、ドイツ語読みの方が意図された読み方に近いと推定される場合に本稿では例外的に採用することとした。やロシアの地名・人名を用いた学名に登場する tsch などの読み (#ツメナガセキレイ備考など) も同様。
古典的なラテン語読みを利用してももちろん構わない。
記載時学名 Motacilla pleschanka Lepekhin, 1770 (原記載)。
この原記載で紹介されているロシア語の pleshanna は種小名と1文字違っていて誤植のようにも見えるが、学名の意味を示すために付記されたもので現在では使われない動詞の被動形から派生する形容詞の女性短語尾形とも考えられる。いずれにしても頭部が白髪のように白っぽい特徴を意味したものだろう。
なお pleshanka はロシア語辞書にもシベリアヒタキの訳名で登場する。次のページに (No. 6) slepyshok のロシア語表記現れるがこちらは学名が記載されていない。
例によってサバクヒタキ類の分類は困難で Motacilla leucomela Pallas の学名が使われていたことがあった。これは "白と黒" の意味で英名の Pied Wheatear はおそらくこの学名に由来。
Ash and Rooke Female Pied Wheatear: the Problem of Identification にあるように 1950 年代でもこの学名は使われていた。
Lepekhin (1770) の用例が見つかりこちらに先取権があると認められた経緯だろう。長く使われた leucomela の方は英名に残っていると考えればよい。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではすでに Oenanthe hispanica pleschanka と亜種扱いではあるがすでに pleshanka の用例が採用されていた。
同文献によれば Saxicola melanogenis Severtsov, 1872 (1873) や Saxicola melanotis Severtsov, 1872 (1873) の学名もあったとのこと。melanogenis は melanos 黒い genus, genuos 頬など (Gk)、
melanotis は melanos 黒い -otis 耳の (Gk) と別の特徴に注目している。
古い文献には Saxicola morio Hemprich & Ehrenberg や Saxicola vittata Hemprich & Ehrenberg の学名も現れるとのこと。morio はラテン語で暗色の褐色の石の意味。vittata はラテン語で帯のある・まだら模様の意味。
Oenanthe hispanica の方も気になるところだが、この学名は現代ではカオグロサバクヒタキ Western Black-eared Wheatear を指すもので、同種とされた時期には最も記載の早い (Linnaeus 1758) hispanica が基亜種となっていたいため。
これらをまとめてロシア名では "黒い白黒まだらのサバクヒタキ" のような名称になっていたが (当時の亜種) セグロサバクヒタキだけは pleshanka と短く呼ばれていた。
極めてややこしいことに Oenanthe melanoleuca と使われなくなった Pallas の leucomela とほとんど同じ意味の学名が存在し、かつては Oenanthe hispanica の亜種とされたこともあった。これは現在はまだ和名がないようだが Eastern Black-eared Wheatear を指す。
この2種は最近まで同種の扱いで IOC でも 9.2 まで、Clements, version 2019 まで使われていた。HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v8 (Dec 2023) では同種扱い。Howard and Moore 4th edition (incl. corrigenda vol.1-2) も古いので同種扱い。
英名の Black-eared Wheatear はおそらく上記の melanotis または melanogenis が訳されたものではないかと想像できる。識別のみならず分類、学名と英名の関係いずれも複雑である。#イナバヒタキで紹介の論文にもあるように Kakhki et al. (2023) の分子系統解析でもこれらの種の関係は交雑の証拠があるなど込み入っている。
単形種。
森田 (1998) Birder 12(7): 66-69 にセグロサバクヒタキの識別の記事がある。
-
サバクヒタキ
- 学名:Oenanthe deserti (オエナンテー デーセルティー) 砂漠のヒタキ
- 属名:oenanthe (f) oinanthe (Gk) アリストテレスの記載した、ブドウの花の咲く頃に渡ってくる鳥
- 種小名:deserti (属) 砂漠の (desertus -i (m) 砂漠)
- 英名:Desert Wheatear
- 備考:
oenanthe は#ハシグロヒタキ参照。
deserti は冒頭と最後が長母音で中央にアクセントがある (デーセルティー)。英語の desert とはだいぶ違う。
この種類は学名、英名、和名が大変よく一致している。記載時学名 Saxicola deserti Temminck, 1825。基産地エジプト。
日本で記録される亜種とされる oreophila は起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。二重母音で両方にアクセントを置く表記とすれば "オレオピラ"。
記載時学名は Saxicola oreophila Oberholser, 1900 (基産地チベット) だったが亜種扱いとなった。
原記載 によれば Saxicola montana Gould, 1865 に対して与えた新名とのこと。Gould の名称は Saxicola montana Koch, 1816 などが用いており (参考) 無効だったとのこと。
Koch (1816) の用いた学名はコシジロイソヒヨドリ 現在の学名で Monticola saxatilis、記載時学名で [Turdus] saxatilis Linnaeus (1766) を指していた。Linnaeus の学名から Saxicola に移す際に種小名を新しく付けたらしい。
この学名は誰もが思いついたらしく、Saxicola montana Stephens, 1826 (参考) もあった。無効名だったためか何を指していたかあまり資料がないが基産地南アフリカ。
記載のフランス語名を頼りにするとカタジロサバクヒタキ Myrmecocichla monticola Mountain Wheatear のよう。
こちらの記載時学名は Oenanthe monticola Vieillot, 1818。
"山に住む" の意味では多数の種が該当してしまうのだろうが、英名はこの学名をそのまま訳したものに近い。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では亜種 oreophila (oreos 山 philos 愛する Gk) とされている。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。この亜種は中国西部からカシミール、チベットで繁殖しパキスタンから北東アフリカに渡るとされる。他にもアフリカから中国まで全部で3亜種があり (IOC)、留鳥も含まれる。
山階鳥類研究所の標本データベースでは YIO-42055 が千島列島新知島中泊で採集され、トウヨウサバクヒタキを訂正しシベリアサバクヒタキの名称が与えられていた。当時は本邦にて始めての標本とあった。
本邦初記録時点で deterti が付いていたので "サバク" を和名に付けたのだろう。
ラベルには Saxicola deterti albifrons (Brandt) の学名が記されており、この亜種名は Saxicola albifrons Brandt, 1843 (参考) 基産地 Siberie occidentale が由来と考えられる。トウヨウサバクヒタキもシベリアサバクヒタキもいかにも亜種であることを意識した名前となっている。
Hartert (1910-1922) にもこの学名は登場しないが、参考 によれば Rueppell が先に用いていた学名で無効だった。こちらはシロビタイアリヒタキ Oenanthe albifrons White-fronted Black Chat の学名に用いられている。
Oenanthe 属となっても preoccupied の状態となっていたので Brandt (1843) の方は現在では誰も取り上げないらしい。
ところが Dement'ev and Gladkov (1954) では preoccupied に気づいていなかったようで、亜種 atrogularis のシノニムとしている。
現在の日本国内にはあたらないのでこの和名はあまり取り上げられないらしいが、中西悟堂「定本・野鳥記 3」p. 141 で言及されていた。記載が無効名であったため deterti に含められる形となったが、Dement'ev and Gladkov (1954) の判定に従えば別亜種に含めるべき可能性も残っているかも知れない。
-
イソヒヨドリ
- 学名:Monticola solitarius (モンティーコラ ソーリターリウス) 孤独な山の住人
- 属名:monticola (m) 山地の住人 (mons montis (m) 山 colo (tr) 住む)。しかし #セッカの [セッカの和名検討] も参照
- 種小名:solitarius (adj) 孤独な
- 英名:Blue Rock Thrush
- 備考:
monticola は -ti- にアクセント。-cola に長音を置きがちで注意を促すため -ti- を長音の表記としたが、慣れれば "モンティコラ" と短音で読んでいただくとよい。伸ばして読んでも間違いとは言えない。
#セッカの [セッカの和名検討] にあるように、ノビタキの属名に使われる Saxicola 由来で、"山で舌鼓を打つ者" の意味も考えられる。
solitarius は o と a が長母音で後者にアクセントがある (ソーリターリウス)。
かつてはツグミ類・ヒタキ類の区別があり、ツグミ類は小型ツグミ類、大型ツグミ類のように記述されている図鑑も多かった。日本鳥類目録改訂第7版でヒタキ科に統一され、このような扱いがあまり行われなくなった。
世界的にはツグミ科とヒタキ科に分割するのが主流であり、日本でも採用されるであろう (wikipedia 参照)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱い。
かつて大型ツグミ類とされていたがヒタキ科に移動されたグループで有名なものがイソヒヨドリ属 Monticola で、ツグミ科とヒタキ科を分割する分類ではイソヒヨドリもヒタキの1種と呼ぶのが妥当。
Monticola 属のタイプ種はコシジロイソヒヨドリ Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock Thrush と言われてもあまり実感が湧きにくいが日本産種類に含まれている。
ヨーロッパから中国にかけて繁殖し冬はアフリカに渡る。wikipedia 英語版の記述によれば通常 1500 m 以上の開けた岩場に住み、岩の割れ目に営巣する。
Monticola 属に言及する場合にはおそらくこの種が典型的と考えればよいだろう。属名が "山地の住人" であってもイソヒヨドリもそれを意図して命名されたと考えるのは必ずしも正しくない。あくまで古くは類似性から、現在は分子系統上で属にまとまるため。ただし岩の割れ目に営巣するなど習性に似た点は感じられる。
コシジロイソヒヨドリのかつての英国での名称は Rock Thrush [Fitter and Richmond (1966, 1968) Collins pocket guide to British birds (Revised Edition)] で "Rock Thrush" と言えば十分でこの種を指していた。英国からみて海外の Monticola 属から区別するために Rufous-tailed を補ったらしい。
イソヒヨドリの英名はこれを引き継いでいるだけで、青いから Blue を付けたに過ぎないと考えられる。
現在の英名から習性まで解釈するのはおそらく過剰。
OED によれば rock thrush の用例は Latham, General Synopsis of Birds (1781) に登場で当時の学名 Merula saxatilis で学名 (1766) の方が早く、英訳されたものと考えられる。
モリカワリツグミ (最近分離されたので和名は適切でない可能性がある) Monticola sharpei Forest Rock Thrush は英名の通り森林性の種類。Monticola 属は山地や岩場に住むだけでなく森林にも分布を広げた。
系統関係がわかったのはやはり分子系統研究が出てから。IOC でも 1.7 まで Pseudocossyphus 属だった。写真を見てもイソヒヨドリとどこが似ているのか判断困難と思われる。
ただしイソヒヨドリはコシジロイソヒヨドリとの類似性が比較的高く、早い段階から Monticola 属に含まれていた。Forest Rock Thrush のように分類変遷はあまり経ていない。
記載時学名 [Turdus] solitarius Linnaeus, 1758 (原記載)。
基産地 Oriente; Hartert (1910) がイタリアと判定した (Avibase 情報による)。
Linnaeus の命名はもう一つあって Turdus Cyanus Linnaeus, 1766 (基産地イタリア) はシノニムとなっている。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の段階ですでに Monticola 属となっていた。
Turdus manillensis Forster, 1781、
Turdus manilla Boddaert, 1783 (Merle solitaire de Manille)
Turdus solitarius manillensis Gmelin, 1789 などの記載はあるがいずれも Linnaeus (1758) の記載から大きく離れるものではない。亜種の概念が明確でなかった時代にそれぞれを種として記述したものの Linnaeus (1758) のものと類似であることを押さえて記述している (フランス語名に表れる)。これらの学名は Ogawa (1908) にも登場する。
現在ではこれらは亜種として、Turdus philippensis Muller, 1776 が早い記載として採用されたよう。
Ogawa (1908) には Turdus philippensis が出てこないのはフィリピンの(亜)種と認識されて日本産でないと判定されたためか。場所や実体は同じであっても manillensis, manilla は種で記載されていたので Turdus solitarius のシノニムの扱いとして載せられていたものと想像できる。
いずれもツグミ類に分類しており現代の我々の直感とも一致する。分子系統解析までは近縁関係はわからなかった。そのまま Monticola 属にまとめられたよう。
solitarius は文字通り "孤独な" の意味だが、用例を見てみるとかなり広義に使われているよう。地理的に隔離されて "孤独な" 意味の学名利用もある。
イソヒヨドリの場合は イワムシクイ Origma solitaria Origma やアオシギなどとの類似性が感じられる。いずれも岩場環境で孤独に生活していると考えられたものかも。
さらに記載時 Turdus 属であった (現代的に見れば正しくなかった) ためにツグミ類にしては群れない、などの意味が入っていたかも ("群れないツグミ" と訳せるかも)。この場合は分類概念の違いによる一種の誤解とも言える (ヒタキ類であれば群れない方が普通)。
さらに Linnaeus から見て縁の遠いイタリア (?) に住むらしいことも地理的な "孤独な" の意味もあるいはあったかも知れない。記載順序の関係で Turdus solitarius の方が採用されたが、Turdus Cyanus の方が先に記述されていれば、英名はおそらく Blue Thrush となってはるかにわかりやすかったのかも知れない。
大きさはツグミ類のような印象を受け、「ツグミ類らしいよい声で鳴く」などの説明も行いやすかったが、系統分類を反映した説明では「ヒタキ類らしいよい声」(ちなみによい声で鳴くオオルリ、キビタキなどは日本の「〜ヒタキ」では少数派で、Muscicapa 属はこのような声では鳴かない) と変更せざるを得ない。
英名も Blue Rock Thrush となっているように、生態の説明に英名の訳語を使うのが便利であったが、これもツグミ類と誤解を避けるために注意が必要になるのだろう。
種小名は Linnaeus が整理したものだが、それ以前からこの種小名が存在した。Merula caerula (青いツグミ) または Passer solitarius (孤独なスズメ/小鳥) の学名があり、Merula caerula, Passer solitarius dictus の図版で見ることができる。
世界的に5亜種があるが、日本のものは亜種イソヒヨドリ philippensis (フィリピンの。南東シベリアから中国、日本を経て分布し、渡りをするものはインドネシアで越冬するとされる) とアオハライソヒヨドリ pandoo (マラーティー語でオスのイソヒヨドリの名前。メスは maal と呼ばれる) が迷鳥として記録がある。
日本産の種でありながら学名にフィリピンの名前が現れるものとして他にコムクドリが有名。
[日本やフィリピンのイソヒヨドリはユーラシア西部と別種?]
Zuccon and Ericson (2010) The Monticola rock-thrushes: Phylogeny and biogeography revisited
に Monticola属の分子系統の再検討があり、The polytypic
Monticola solitarius includes two reciprocally monophyletic clades that should be recognized as full species,
M. solitarius s.s. and M. philippensis.
との記載があり、この著者は現イソヒヨドリは単系統でなく、Monticola solitarius (ユーラシア西部を中心とした狭義の大陸個体群) と Monticola philippensis (日本などの個体群) の別種にすべきとの見解を述べている。ただし亜種 philippensis のサンプルはフィリピンと中国だけである。
現時点でこの分類を取り入れている世界的なリストはない模様であるが Brazil (2009) "Birds of East Asia" では (色の違いを主な理由に) 別種にする意義があるとして Monticola philippensis を Red-bellied Rock Thrush とも呼んでいる。
Cinclidae, Turdidae, and Muscicapidae (John Boyd の鳥類分類サイト) では 亜種 pandoo (中国の中部から東部に主に生息する亜種で腹は赤くない) と亜種 philippensis
は交雑もするので、Brazil (2009) の名称よりも "Variable Rock-Thrush" のような概念の名前が適当でないかと提案している。
この分類がまだ広く受け入れられていないのは種境界がまだ曖昧であること、どの亜種をどちらの種に含めるかがはっきりしていないためかも知れない。
問題の2グループは遺伝的にはイソヒヨドリとコシジロイソヒヨドリ Monticola saxatilis 英名 Common Rock Thrush 程度に異なっているので将来分割が検討される可能性は十分ありそうである。
[海岸志向と内陸志向]
ヨーロッパまで分布する大陸ではなぜ山に主に住み、日本では内陸進出もしているが海外を好むのかは、あるいはそもそも種レベルの違いが関係しているのかも知れないので要注意かも知れない。
もっとも、橋本啓史氏の情報 [kbird:04369 (2021.10.19)] によれば
清棲図鑑増補改訂版 pp. 233-235 に
まれには山地 (たとえば長野県長野市郷路山麓。標高500m: 1917 高松良氏採集) に飛来することもある。タイワンイソヒヨドリ M. s. philippensis は生息環境:海岸地方に多いが、山地の渓流にも生息し、次高山 (1926-1931 調査) ではシカヤウ社 (標高 1576 m) 付近の渓流にも生息する。との記載があるそうである。
フィリピンでは (birdwatch.ph の情報による) 渡り鳥で一部繁殖する。岩場で川の岩場にも生息するとのこと。都市には渡りの時に立ち寄るとの記載があり、特に沿岸部に固執していないようである。
鳥の方の生態よりもあるいは海岸地形の違いも関係しているのかも知れない。
イソヒヨドリ (ロシア) によればロシア極東ウラジオストクではイソヒヨドリが減少し、見るのが難しい鳥になってしまったとのこと。日本とは逆の現象でこれも興味深い。
Biserov (2025) The blue rock thrush Monticola solitarius philippensis sighting on the border of the Middle Amur Lowland and the Bureya Highlands (pp. 2442-2443) のハバロフスク州の記録 (写真あり) も出ていてロシア極東部でも地域次第かも。こちらでももともとは沿岸部の鳥と認識されていた。
なおマルタではイソヒヨドリを国鳥としている (マルタ語で il-Merill。BirdLife Malta の機関誌名にもなっている。この名前を冠したレストランなどが多数ある)。
Galea and Caruana (1998)
The Breeding Population of the Blue Rock Thrush Monticola solitarius on Comino Island in 1988
のようにマルタで 1988 年に生息記録が報告されるぐらいに生息地が狭まり、1971 年から保護鳥となっていた。イソヒヨドリはマルタの飼い鳥文化に深く浸透していたらしい (他の記事も参照した)。
Fenech (2022)
Substantial increase in urban breeding Blue Rock Thrush Monticola solitarius in Malta
によれば 1990 年代でもまだ飼い鳥として捕獲されていて、一時は海岸の崖まで追いつめられていたが近年急激に数を増やして都市鳥となっているとのこと。
アフリカのアルジェリア北部でも都市域に進出: Rouibi et al. (2020)
Nesting of blue rock thrush (Monticola solitarius) in an Urban area in North Africa。
Wee (2008) Blue Rock Thrush でマレーシアの都市部のビルで営巣するようになった。
Amar-Singh HSS (2018) Blue Rock-thrush - juveniles。
やはり世界的にビルが増えて生息地に適した場所が増えたのか。海岸に比べて都市部は天敵も少ないかも知れない。
シンガポールでは基本的に冬鳥でそれほど記録が多くない: Blue Rock Thrush (Bird of Singapore 2024)。
2024年4月にアメリカ初記録: Bowman (2024) Hobbyist photographer snaps photo of extremely rare bird in 1st U.S. sighting と進出傾向は世界的なもののよう。
[山から人里に分布を広げた鳥]
イソヒヨドリはヨーロッパでは南部限定の種でマルタのように過剰捕獲があった地域以外ではそこまで分布拡大は注目されていないが、イソヒヨドリに似た分布拡大経緯を示した種にクロジョウビタキ Phoenicurus ochruros Black Redstart (日本でも記録のある種類) がある。
wikipedia 英語版によればクロジョウビタキは元来は山地の崖場などに生息していたが、1900 年ごろ以降は都市環境に急激に分布を広げた。特に第二次世界大戦後は各地に崖地に似た建物からなる工場が建てられて、英国ではそのような環境に好んで生息するようになったとのこと。
イソヒヨドリやハヤブサなどの都市営巣開始についてコンクリートの建物を岩場に見立てて、と表現されることがあるが、あるいはこのクロジョウビタキで英国進出の解釈に用いられた表現がそのまま引き継がれているのかも知れない。
Black Redstart (BTO 1977) にイソヒヨドリとよく似ている。The habitats used ranged from the original sea-cliff sites in Sussex to a rural farmyard in Hertfordshire, but the majority were in areas 'built-up' to varying degrees with the typical site being an industrial complex in a large urban area
もともとの生息環境は海岸の岩場だったが次第に都市の工業地域に進出 (1977 年の情報なので最近の傾向までは含まれていない)。
旧ソ連圏では Dement'ev and Gladkov (1954) では工業地帯やコンクリートの建物の表現は用いておらず建屋の屋根や石造りの建築物の隙間を営巣場所として利用するようになったと記述している。ジョウビタキやシロビタイジョウビタキでは環境嗜好性がクロジョウビタキより広く、より古い時代の建屋にも適応して早くから人里に住むようになり、我々が元来の習性をあまり知らないのかも知れない (ジョウビタキで人の近くに住むメリットはカッコウの托卵を避けるとの研究がある)。
ジョウビタキによく似たセアカジョウビタキ Phoenicurus erythronotus Rufous-backed Redstart (こちらも日本で記録のある種類) も繁殖地はアルタイ地方などの山岳地の乾燥した石の多い土壌の樹木が多いとのこと。ジョウビタキ類の繁殖地は元来このような場所が好みだったらしい。
分子系統解析ではジョウビタキ属 Phoenicurus とイソヒヨドリ属 Monticola はヒタキ科の中の Saxicolinae (ノビタキ亜科?) の中で隣り合うぐらいに似た系統 [Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考) を参照] で、クロジョウビタキとイソヒヨドリは類似例と言えるのではないだろうか。
Phoenicurus と Monticola はまとめると単系統をなさないためクレードを作ることはできないが、Saxicola (ノビタキ類), Oenanthe (サバクヒタキ類) を合わせればクレードを作ることができる。これらの属名を眺めると共通の環境を想像することもできる。
Yuan et al. (2024) Complete Mitochondrial Genome and Phylogenetic Analysis of the Blue Whistling Thrush (Myophonus caeruleus) のミトコンドリアゲノムによる分子系統樹も参照。
Zhao et al. (2023) では Ficedula 属なども合わせて Saxicolinae としているが、このような生息環境の類縁性を考えると Saxicolinae は上述の系統と森林性の Ficedula を含む系統に大別した方が良さそうに見える。
ここで考察する範囲ではジョウビタキ属とイソヒヨドリ属の生息地の好みは似ている、地鳴きも似ている、などと解釈して構わないように思える。日本ではジョウビタキだけが身近な種類なのでジョウビタキ属全体の好みはジョウビタキに似ていると考えると誤解のもとになるかも (ここでも身近な種を広い系統の名称に用いる欠点が感じられる)。
ジョウビタキが国内のやや高い標高地の建物や別荘地などで繁殖するようになってきているのは逆過程を見ていると言えるかも知れない。例えば本来はそのような地形が好みだった。人為環境に適応することで捕食や托卵を逃れるなど生存率を上げる戦略となったが、そのような地形にも人が住むようになると生存率を下げる要因が少なくなって本来の地形嗜好が現れてきているなど。
ジョウビタキは結構標高が高く意外に感じるような所でも越冬しており (例えば天文台のあるようなところ)、高い標高地も本来好きなのではないだろうか。これほど寒いところで越冬できるならば冬に渡らなくてもよさそうに感じるぐらいだが、極東大陸部の冬の自然条件は一層厳しいのだろう。
[地鳴き]
イソヒヨドリは特に繁殖期にヒッ、ヒッ、カカッとジョウビタキの地鳴きに似た声で鳴く。特にヒッ、ヒッの部分は定量的な音声分析をしてもジョウビタキと区別できないほどに似ており、人が聞き分けるのは不可能と言ってよいぐらいと思われる。秋でもこの声で鳴くこともしばしばあり、イソヒヨドリの分布地域ではジョウビタキを音声で初認する場合に注意が必要である。上述のように分子系統的にも近い。カカッの部分の声は違うのでここまで聞けば判定できる。
[メスもさえずる鳥]
イソヒヨドリはメスもよくさえずるが、イソヒヨドリ属の他の種でもメスのさえずりが記録されているものがある。この属に一般的な性質かどうかはまだ確かめられていない。
一部の鳥でメスがオスのようにさえずる理由について、日本の鳥ではおそらくまだ研究がないのではないかと思われるが、アメリカでよく調べられている Icterus (ムクドリモドキ) 属 (New World oriole, 系統はホオジロ科に近い。位置づけは #ツリスガラの備考参照)
では留鳥の種類ではメスの間の競争も強く年中繁殖可能でメスがテリトリーを持ってさえずり、羽衣も派手になる傾向がある (メスにも選択圧が働く) 一方で、渡りを行う種類ではこれらの性質を容易に失う傾向がある (メスにおける選択圧が弱まる) ことが示されている:
cf. Friedman et al. (2009) Correlated Evolution of Migration and Sexual Dichromatism in the New World Orioles (Icterus)。
メスのさえずりはメスの間の競争が顕著な表れかも知れない。またオスによるメスの選り好みも関係しているかも知れないとも書かれている。この論文は雌雄それぞれにかかる選択圧の重要性を強調するものとなっている。
Logue and Hall (2014) Migration and the evolution of duetting in songbirds
ではより広い範囲の分類群を調査し、渡りを行う種ではオス・メスによるデュエットは明瞭に少なく、この著者たちは渡りを行うために共同行動に費やす時間が限られることなどを要因と考えているが雌雄それぞれの選択圧については特に議論を深めているわけではない。
Najar and Benedict (2015) Female Song in New World Wood-Warblers (Parulidae)
はやはり新世界のアメリカムシクイ科を用いて同様の研究を行い、メスのさえずりはこれらアメリカムシクイ科では祖先的な性質ではなく何度も独立に進化したらしいこと、メスのさえずりと渡りとの関係は明瞭でないが色彩の性的二形は渡りとの関連は見られた。メスがさえずることが生態的に有利な場合にこの性質が獲得されることもあるだろうが比較的不安定で簡単に失われることを示しているとのこと。
ムクドリモドキ類とアメリカムシクイ類では事情が異なっている可能性があるかも知れない。例えばムクドリモドキ類は祖先的な性質としてメスのさえずりを獲得していてその後の進化に影響を与えたのかも知れない。
Price (2015) Rethinking our assumptions about the evolution of bird song and other sexually dimorphic signals
ではこれらの研究結果ばかり見ていると鳥のさえずりの進化が性選択の産物であるとの従来の一般的解釈を覆しているようにも見える [例えば Odom et al. (2014) Female song is widespread and ancestral in songbirds]
が、新しい知見は必ずしも矛盾しているとは言えない。従来の研究で見逃されてきた側面などもレビューした論文。この著者は他にも性的二形を性選択の産物のみと考えるのは誤りであるなどの論文を出している。
Webb et al. (2016) Female Song Occurs in Songbirds with More Elaborate Female Coloration and Reduced Sexual Dichromatism
ではメスのさえずりとメスの羽衣の派手さには明確な相関がある。この両者はトレードオフの関係にはなく、メスのさえずりとメスの派手さは同じ選択圧のもとに進化した示唆を与える。メスがさえずるコストはそれほど高くないと考えられる。
Krieg and Getty (2017)
Not just for males: females use song against male and female rivals in
a temperate zone songbird (出版社サイト)
対象種はイエミソサザイ Troglodytes aedon House Wren (現在はさらに分離され Northern House Wren)。
これまでこの現象が見逃されてきたのは雌雄同色でさえずるのはオスとの思い込みがあったためだろう。
またオスとメスのさえずりは異なっており、メスのさえずりを知らないとおそらく別種の不明の声と考えてしまうだろう。オスはメスのためにさえずっていると考えるのも先入観につながる。
温帯の鳥でもメスがさえずり、同種のメスのさえずりに最もよく反応するとのこと。まだ抱卵を始めていない産卵初期に最もよくさえずる。限られた営巣場所 (この場合は巣箱) をめぐるメス間の競争、あるいはメス・オスの競争も関係している可能性がある。近隣のメスによる卵殺しもあり、よくさえずったメスほど卵を失いにくい傾向があった。
ツバメでも少なくとも一部似た傾向が見られる。Wilkins et al. (2020) Analysis of female song provides insight into the evolution of sex differences in a widely studied songbird
こちらも営巣初期にさえずる。これほどよく知られている種類なのに、何とこれがツバメのメスのさえずりを記載した最初の論文。これを書いている時期は3月で、これからまさしくツバメのこの行動が記録できるかも知れない。皆さんも注意していただきたい。
まだ結論の出ていないテーマで盛んに研究が行われている。色彩での性的二形に比べて少なかった音声データが比較的容易に入手できるようになって進みつつあり、またこれまではっきりしていなかったスズメ目内の分子系統研究が進んで研究に適した分野となってきたとも言えるだろう。
例えば音声サイトの xeno-canto ではこれらプロジェクトのために "Female Song" をキーワードとして用いる (female & song のクロス検索以外に "Female Song" のキーワードが予め存在している) ことが推奨されている (ただしオオルリの警戒音のようなケースについて注意は必要だろう)。
2017 年に始まった Female Bird Song プロジェクトのサイト。
Which species to record? に文献に記述はあるがまだメスのさえずりの音声が録音されていない種などの一覧が見られる。
このリストでは Odom et al. (2014), Webb et al. (2016) が取り上げた種も一覧となっているが、"メスもさえずる" 文字だけの情報はあっても、ほとんどの種で録音がなく、オスのさえずり違うか知られていないことがわかる。
日本の鳥についての情報はおそらく少ないと思われるので、メスのさえずりを記録された場合はこれらの国際的なデータベースに登録したり報告論文を書くのがよいだろう。
Odom et al. (2025) Global incidence of female birdsong is predicted by territoriality and biparental care in songbirds に後続論文がある。
ツグミ科にはほとんど事例がない。一方ヒタキ科はメスもよくさえずる。ミソサザイ科 (ほとんどが新世界) はメスが同等にさえずるものが多い。ヒバリ科はほとんど例がない。ホオジロ科も同様。センニュウ類ではメスがよくさえずっている。
ツグミ科でもマミジロがそうであるように古い方の系統でメスもさえずるが、新しい方の系統ではメスはほとんどさえずらないよう。コルリなどのメスがさえずるのは "小型ツグミ類" とされていた時代には特別な事例のように感じられたが (新しい意味の) ヒタキ科に分類され直したことによってむしろ系統との整合性が高まったように見える。新分類ではコルリやコマドリのメスがさえずるのはイソヒヨドリやオオルリのメスがさえずるのと同様に考えることができるようになった。
カラス科はよくさえずっていることになっている (どれをさえずりと判定しているのか?)、一方でモズ科はむしろ少ない。カササギヒタキ科はよくさえずっていてサンコウチョウの印象にも合致する。
この図を見ると地域にかなり偏りがあるように見えて新世界ではよく記録されていている。ツグミ科で少ないのはユーラシア東部およびさらに分布を広げた種類の記載があまりに少ないためかも知れない。
またイエミソサザイの例のように雌雄同色の種類はどのようにメスのさえずりを判定するか難しさもありそう。
Source Data をダウンロードできるが、案の定クロツグミは含まれていない。コマドリ、コルリ、キビタキは含まれているがオオルリもウグイスも含まれていない。日本三名鳥と褒めながら世界ではほとんど認識されていないことがわかる。
センダイムシクイもサンコウチョウも含まれていないし (上記カササギヒタキ科はすべて海外の種類だった)、イカルもコイカルもない。日本の鳥は音声の世界ではほとんど存在感がないのではないだろうか。なぜこれほどまで英語圏と情報が隔離されているのだろうか。
プロジェクトは 2017 年から始まっているので、日本語書籍や記事もあるので誰かが日本の鳥の情報をまとめて提供すれば済む話で、プロジェクトそのものが日本ではまったく知られていなかっただけなのだろうか。
以下の雑誌記事を書かれている皆様に期待したい。
Young Guns (2014) Birder 28(7): 48-50 に「ヒタキ科の幼鳥とさえずる雌」の記事がある。この記事にはメス同士の争いは直接には出てこないが、イソヒヨドリが非繁殖期に単独でテリトリーを持つ、
雌雄・年齢に関係なくさえずりで越冬期のテリトリーを確保する記述がある。巣穴をめぐる闘争中の可能性のあるイソヒヨドリのメスの写真が掲載されている。
他にサンコウチョウはつがいのテリトリーに他個体が入った時、メスがオス同様にさえずるとある。
これらを書いていて改めて気づいたのだがハチクマ特有のディスプレイ飛行をメスが行うのも同様の意味があるかも知れない。限られたオス、あるいは好みの営巣場所をめぐるメス同士の技の比べ合いなどもあるかも知れないし、オスもメスの資質を見極めているかも知れない。つがい形成以外の時期にも見られるのでそれだけの意味ではないと考えるのだが。
-
ヒメイソヒヨ
- 学名:Monticola gularis (モンティーコラ グラーリス) のどに特徴のある山の住人
- 属名:monticola (m) 山地の住人 (mons montis (m) 山 colo (tr) 住む)
- 種小名:gularis (adj) のどに特徴のある (gula (f) のど -aris (接尾辞) 〜に関連する)
- 英名:White-throated Rock-thrush
- 備考:
monticola は#イソヒヨドリ参照。
gularis は a が長母音でアクセントがある (グラーリス)。
記載時学名 Oroecetes gularis Swinhoe, 1863 (原記載) 基産地 Peking (Avibase)。参考 では near Tientsin, Hopeh Province, China (越冬地らしい) とある。
記載によれば gularis はこの種に特徴的なのどの白い線を指すとのこと。英名と整合している。
英名には別名 White-breasted Rock Thrush, Swinhoe's Rock-Thrush もあった。
またモンツキイソヒヨドリよりも少し小さいとの記述があり、和名成立にも関係していたかも知れない。
当時の Oroecetes 属は Gray (1840) がモンツキイソヒヨドリ 現在の学名で Monticola cinclorhyncha Blue-capped Rock-Thrush をタイプ種として設けたもの。oros, oreos 山 (ここではヒマラヤ) oiketes 住むもの (Gk)。
すでに Swainson (1837) が Petrophila 属 petra 岩 philos 好む (Gk) を設けていたが植物で使われた属と重複とされて改名されたもの。実際には植物ではなくチョウ目の属 (Guilding 1830) だったとのこと (The Key to Scientific Names)。
Petrophila 属の用例はいくつもあってイソヒヨドリの亜種記載 (1920) にも使われていた。
植物の属名との重複が許されるようになった時代になってからは Petrophila 属が有効となって戻っていたが (それでも重複を嫌って使わなかったケースもあるだろう)、別途動物の属名との重複が判明して無効になった歴史があるかも知れない (未調査)。
モンツキイソヒヨドリとヒメイソヒヨは同種とされたこともある (Peters' Check-list of the Birds 2nd edition まで)。この場合は cinclorhyncha の方が基亜種となる。
Dement'ev and Gladkov (1954) では別種扱い。ロシア語名で lesnoj kammenyj drozd とイソヒヨドリ類の中では森林環境に住むことが由来とのこと。英名では同じ意味の種に Monticola sharpei Forest Rock Thrush がある (#イソヒヨドリの備考参照)。
いずれも森林性の岩場に住むツグミと矛盾した名前になっているが、これは Rock Thrush の表現の方がむしろ限定的すぎるのだろう。
単形種。
Hou et al. (2025) Characterization of the complete mitochondrial genome of Monticola rufiventris and phylogenetic implications
によればこの時点で Monticola 属でミトコンドリアゲノムが GenBank で公開されているものはヒメイソヒヨのみだったとのことで、カオグロイソヒヨドリ Monticola rufiventris Chestnut-bellied Rock-Thrush のミトコンドリアゲノムを解読した。ヒタキ科 Muscicapidae 内およびスズメ目内の系統関係については論文をどうぞ。
Golosa pits v prirode の 5-2 では 0:08 Lesnoj kamennyj drozd - odin iz luchshikh pevtsov Ussurijskoj tajgi (ヒメイソヒヨはウスリーのタイガの一番よい歌い手のひとつです) とのこと。(聞き取りはネイティブ・スピーカーによるもの)。
ロシアでの野外録音の歴史は 解説 があり、1950 年代の蒲谷鶴彦氏とほぼ同じ時代に始められていたとのこと。
-
ムナフヒタキ
- 学名:Muscicapa striata (ムスキカパ ストゥリアータ) 線条斑のあるハエトリ
- 属名:muscicapa (合) ハエを捕まえる鳥 (musca -ae (f) ハエ capio (tr) 捕まえる)
- 種小名:striata (adj) 線条の (striatus)
- 英名:Spotted Flycatcher
- 備考:
muscicapa は#サメビタキ参照。
striata は最初の a が長母音でアクセントがある (ストゥリアータ)。
#コサメビタキの備考にあるように、Muscicapa grisola (grisola 灰色の) の学名が使われていたことがあった (Linnaeus が用いた種小名。後の分類では複数種にわたるため無効となったものと推定される)。20 世紀初頭でもこの学名が用いられていた。
和名の "ムナフ" は "胸斑" だが、他の用例を見ると学名の striata やおそらく学名由来の旧英名の Striated Flycatcher を表現したものと想像できる。
他の用例ムナフイカル Saltator striatipectus Streaked Saltator (この場合は和名は種小名をそのまま訳したものとなっている)。ムナフムシクイチメドリ Mixornis gularis Striped Tit-Babbler。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。
5亜種あり (IOC)。日本の亜種は南西アルタイからモンゴル、バイカル東方に分布する mongola (モンゴルの) とされている。種の主な分布域はヨーロッパから中央アジアでアフリカに渡る。
-
エゾビタキ
- 学名:Muscicapa griseisticta (ムスキカパ グリーセイースティクタ) 灰色の斑点のあるハエトリ
- 属名:muscicapa (合) ハエを捕まえる鳥 (musca -ae (f) ハエ capio (tr) 捕まえる)
- 種小名:griseisticta (合) 灰色の斑点の (griseus (adj) 灰色の、stikos 斑点 Gk、-tus 〜が備わった)
- 英名:Grey-spotted Flycatcher, IOC: Grey-streaked Flycatcher
- 備考:
muscicapa は#サメビタキ参照。
griseisticta は合成語で griseus は i が長母音、変化形で語末の i も長母音となる可能性がある。
ギリシャ語の stiktos は短母音のみのためこの部分には長母音は現れないと考えられる。
stictus のラテン語は存在しないようだが、ギリシャ語の -tos は語尾を作り、ラテン語で類似の strictus は stric-tus と分解されるので griseisticta も -stic- がアクセント音節と推定される (グリーセイースティクタ)。
エゾビタキの英語別名の Grey-spotted Flycatcher は学名を訳したものと推定できる。
かつて日本でも九州や富士山で繁殖するとされたことがあった (Jan 1942) がおそらく誤認。中国東北部、ヤクーチア、ロシア極東部、カムチャツカ南部、千島列島北部などで繁殖するとされている。サハリンでも繁殖するが非常にまれとのこと。
中西悟堂「野鳥記コレクション」II pp. 91-92 によれば尾瀬近くの鳥について、1949.7.28-31 の調査期間に中村幸雄氏 (#コノハズクの備考参照) が亜高山の三平峠 (峠標高 1760 m 程度) 北腹で記録したとのこと。尾瀬近くの鳥について中西氏を含む他の3名が調査を行ったがエゾビタキを記録したのは中村幸雄氏のみだったとのこと。サメビタキは他の調査者も記録していた。
中西悟堂「定本・野鳥記」4 pp. 131-132 に含まれていた。
本州などの亜高山に "蝦夷" の鳥が生息することは当時の垂直分布の知識から予見されていたのではないだろうか (#センダイムシクイ備考の [センダイムシクイの和名の検討] の考察参照)。
現在の標準的リストでは亜種は認められていないが、Peklo (1987) "Mukholovki Fauny SSSR" (ソ連の動物相のヒタキ) では大陸の亜種 griseisticta とカムチャツカの亜種 pallens (「色の淡い」の意味) を認めている。後述のようにほとんど研究されていない東洋固有種なので、将来の遺伝子研究などで亜種が復活する可能性もあるかもしれない。
日本では旅鳥であるエゾビタキは秋の渡りでは多数観察されるが、春の渡りでは (北海道を除き) 観察例が非常に少ない。秋と春で異なった渡りルート (例えば春は大陸まわりで北海道を通過するなど) をとっていると考えられる (例えば春の渡りでは北海道のノビタキの渡りコースに類似するなど: #ノビタキの備考参照)が、詳細は明らかでない。
[Hemichelidon 属]
エゾビタキは最初 Hemichelidon 属の1種として記載された (原記載)。この属名の意味は hemi- 半分 khelidon ツバメ であり、「外見上ツバメに似たヒタキ」で、概形はツバメであり翼と口の付近のみがヒタキに似ている。
嘴もツバメのようであるがそれほど広くなく、周囲に口角のひげ状羽毛がある。他のヒタキ (おそらくヨーロッパのヒタキ類のことだろうか) よりも力強く連続して飛ぶ (Hodgson 1845) とある (The Key to Scientific Names)。
Hodgson (1845) はこの属名を用いる際に H. fuliginosa [= 現在のサメビタキの亜種 Muscicapa sibirica cacabata (ヒマラヤからチベットで繁殖する亜種) とされる] とミヤマヒタキをタイプ種とした。
ミヤマヒタキが Muscicapa に移され、この学名が古くから使われていたことがわかり先取権を検討した結果ややこしいことになった模様 [ Vaurie (1952) 提案
Opinion 416 Validation under the Plenary Powers of the specific name ferruginea Hodgson, 1845, as published in the combination Hemichelidon ferruginea (class Aves)]。
そういえばサメビタキのロシア名の別名に mukholovka-kasatka (ツバメのヒタキ) があり、この時代の学名を反映したものかも知れない。Kolyada et al. (2016) の語源辞典では解釈困難とあり、一枚上手を行ってしまったかも?
比較的早い時期に Hemichelidon 属が Muscicapa 属に編入されたのかも知れない。
詳しい経緯はわからなかったが、エゾビタキはあまりに研究されていなかったために編入見送りになっていたのかも。
オンラインで公開されている山階鳥類研究所の 20 世紀前半の古い時代の標本ラベルにも Hemichelidon の属名が使われており、かなりの期間この属名が用いられていたものと考えられる (サメビタキとの同定誤りはやはりあった模様)。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではすでに Muscicapa 属となっていた。
現在では Muscicapa 属に吸収されてシノニムとなっている。
この時代のコサメビタキの英名は Broad-billed Flycatcher となっていて現在の英名よりも特徴をよく表している気がする (現在のロシア名はこの英名が由来かも)。
一時期は多くのヒタキ類を Muscicapa 属として扱っていたことがあるが、分類学者も多種の灰色系統の似たヒタキの分類に頭を悩ませていたのであろう。
Zhao et al. (2023) の系統樹 (#ヨーロッパコマドリの備考参照) ではエゾビタキは Muscicapa 属で最初の分枝にあたる。
飛び方の違いなどは観察していても気づく点で、系統の特性は他のヒタキとの識別の上でも参考になる点が含まれているだろう。
例えば将来の分子系統研究でエゾビタキが Hemichelidon 属になっても個人的には面白いと思う。
後述の Harris et al. (2014) のスラウェシサメビタキの記載では模様はエゾビタキと類似性が高いと考えていたが、KM924385.1 (スラウェシサメビタキの COI) から BLAST を行ってみると類縁性はあまり高くなくスラウェシサメビタキがこの系統では最も遺存的性格が強い種類かも知れない。
COI しか調べられていないのでより詳しい系統研究が行われることを期待したい。このような視点で見るとエゾビタキの下面の模様は必ずしも系統的傾向を示したものではなく、何度でも進化可能な形質かも知れない。
#アネハヅルで [日本産ツル類の系統的位置づけ] を考察したが、Grus 属内のタンチョウ、ユーラシア東部の Muscicapa 属内のエゾビタキの位置が非常に似ているように見える [Zhao et al. (2023) の系統樹を用いた場合]。
エゾビタキのミトコンドリアの配列は読まれているので NC_045181.1 から BLAST を行ってみると Zhao et al. (2023) と異なる系統樹形になった - ? - と不思議に感じたところ、この配列は同定誤りが指摘されていることを思い出した: [その他] 参照。
他の遺伝子を用いるとやはり cyt b などが中心となってしまうが、HM633336.1 から気を取り直して (笑) やってみることにした。結果は系統を議論できるほど確実なものではなく、エゾビタキが遺存的かどうかまだ何とも言えない感じがする。
ND2 KU192869.1 を用いるとエゾビタキがユーラシア東部の Muscicapa 属内で最も早く分岐した系統になる (ただしよく調べられていないスラウェシサメビタキの方が古い分岐かも知れない)。
なおユーラシア東部・西部の Muscicapa 属は別属にしてもよい程度分かれている。タイプ種はムナフヒタキなのでもし分割されれば日本産の大部分の Muscicapa 属の属名が変わる。
日本で記録される Muscicapa 属のほぼすべてはユーラシア東部の系統に属し、ムナフヒタキのみがユーラシア西部から東部にも若干分布を広げている。
ヨーロッパからの迷鳥記録のある他グループとは少し様相が違い、ユーラシアの東部・西部の系統分離がより完全なように見える。ユーラシア東部の Muscicapa 属がどこで種分化したか、なぜ現在の渡りルートとなったかなどの推定材料ともなるだろう。またニシオジロビタキと違い、Muscicapa 属はヨーロッパからなぜ越冬に来ないのかなどの仮説を立てることができるかも知れない。
Phylloscopus 属の東西系統とも多少似た点がある (#キタヤナギムシクイ備考 [ムシクイ類の進化の考察] 参照)。
分子系統樹は大いに活用すべし。
cty b の結果ではコサメビタキから種分化した可能性もあるがサメビタキからはやや遠いように見える。ND2 の結果は少し印象が違う。
もしエゾビタキが Muscicapa 属内で早く分岐した系統であれば生物地理学的には興味深い。アネハヅルの項目でタンチョウの位置づけを考察したように、エゾビタキ類縁の系統は一度はユーラシア大陸東部にも広く分布したがユーラシア東部の Muscicapa 属の後の系統の進展で競争排除され限定的な分布となった可能性が考えられるためである。
この解釈を自身が少し支持したいのは、後述のようにさえずりの特性が他のユーラシア東部の Muscicapa 属に比べて独特で、コサメビタキやサメビタキから離れた単一の系統をなす可能性が示唆されるためである。いずれも複雑で小声のさえずりと一括してしまうのはよくない。もしさえずっていればぜひとも録音を優先すべし。
エゾビタキ類縁の系統のうちエゾビタキは大型で、より北方の疎林に適応して競争を免れたと考えればエゾビタキのみが大きいことも納得できる気がする (この環境の好みの違いは渡り時期にもよくわかる。都市公園で通路を隔てるだけで分布が違うのである。エゾビタキの方が空中遠くまで飛び出すため広い空間が必要であまり茂った場所には向いていない。またタカ渡りの観察ポイントは開けた場所が多いので、タカ渡り本命の観察者はエゾビタキばかりお馴染みになりがち)。
もっとも大きさは寒冷地仕様かも知れないので解釈には多少注意を要する。
このように解釈すると極東の北部の島 (カムチャツカを含む) ではエゾビタキが優勢となったが、大陸では後発の Muscicapa 属の方が優勢で限られた地域に細々と暮している程度、のように解釈することもできる。エゾビタキの春の渡りが若干遅めなのは繁殖地がより北方である要因もあるだろうが似た採食様式の種との競争とも関係しているかも知れない。
大陸のより中央部から分布を広げたものが遺存分布となったと考えれば、春は本来の拡大ルートを渡り (例えばハチクマも似たようなものかも)、秋はショートカットして日本も通過する経路が優勢になったのでは、などの解釈も統一的に考えられる気がする。今後のゲノム解読に期待したい。サメビタキの遺伝子が大陸と島で異なる可能性も指摘されているので、これらもともに解読して考察する必要があるだろう。
現在は北海道で繁殖していないのになぜ "エゾ" が付いているのか疑問もあったが、Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" (p. 388)
には Hakodate, Kurile Is. (Yezobitaki) とあるので当時の認識では北海道にも産すると考えられていたためと考えてよいのだろう。このリストではエゾビタキのみ Hemichelidon 属となっている。
[エゾビタキのさえずり]
ロシアでの標本採集地は Peklo (1987) p. 145 にあるが、ロシアの他のヒタキ類に比べて圧倒的に数が少ない。繁殖地も人口密度の低い地域で、研究もごく限られている。たとえば繁殖地でのさえずりの確実な音声録音記録はない。
ロシア極東部での繁殖状況については Nazarenko (2017) Review of the book by Yu. N. Glushchenko, V. А. Nechaev and Ya. A. Red'kin "The Birds of Primorsky Krai: a brief faunistic review" (2016)に過去の文献も含めて詳しい (エゾビタキの記述は p. 2193)。これによると Glushchenko et al. (2016) の本の内容はかなり誤りが多いらしい。
Nazarenko (1971) の On the distribution and biology of the Gray-spotted Flycatcher - Muscicapa griseisticta (Swinh.) in Southern Primorye territory は「極東の鳥類」25, pp. 69-74 で日本語訳を見ることができるが、繁殖地は (当時は) 十分に明らかでなく、サメビタキとの混同もあるとのことである。
On the distribution and biology of the Gray-spotted Flycatcher - Muscicapa griseisticta (Swinh.) in Southern Primorye territory (pp. 2892-2900) に再掲されている。
Nazarenko からの私信によればこの種の音声はほとんど調べられておらず、Nazarenko の研究していた時代は録音機もなかったため記憶に頼るしかなかったとのこと。エゾビタキとサメビタキの声は似ているが、前者の方が声が低めであるとのこと。Peklo (1987) ではサメビタキとコサメビタキのさえずりは非常に似ているとしか書いていない。
Nazarenko によればウスリーではシホテ・アリンの中央部の "蛭島" のような森林のみの地域にのみ生息する。南部では Zob Tigra (The Call of The Tiger) 国立公園の "Muta" での生息を知っているとのことであった。
しかし Chuguevka 集落からは 100 km も北に位置するとのこと。エゾビタキとサメビタキのさえずりは似ているが同じではない程度のコメントがあった (ラゾフスキー保護区の協力を得て訪れて録音してみないかとの提案はあったが、とても無理...)。
ロシアの録音家 Veprintsev が過去にこの地域を訪れ、エゾビタキのさえずりとされるものを1件残しているが、その音声には「コサメビタキの可能性もある。両者はよく似ているので」とのコメントが音声で残されており、同定は確実でない。
日本で聞き慣れたコサメビタキのさえずりとは違って似た節を繰り返すところがあり、ヨシキリ類の声に近い印象を受けたがコサメビタキのさえずりも地域差が予想されるのでこの種でないとは言い切れない。また飛びながらさえずっているとのことだが、Nazarenko (1971) では枝にとまってさえずると記述されており(ヒタキ類ではこちらの方が普通に思える)、その点も異なっている。
Veprintsev の音源は The B. N. Veprintsev Phonotheka of Animal Voices catalog numbers are: 86-12-15_17, 100139, Russia, Primorskyy kray, Chuguyevskyy rayon, settlement Chuguyevka. Sikhote-Alin, mts. が請求番号および情報で、一般公開はされておらず必要であれば研究目的を示してこの研究所 (Veprintseva が管轄) に請求する必要がある。
Muscicapa 属新種 (スラウェシサメビタキ Muscicapa sodhii 英名 Sulawesi Brown Flycatcher) の音声比較でかつて論文で使われていた [Harris et al. (2014) A New Species of Muscicapa Flycatcher from Sulawesi, Indonesia]
にはこの音源 (エゾビタキのソノグラムも一部出ている)。Krechmar も音源を持っているのではと示唆はあったが Krechmar からは得られなかった (以上 2017 年当時の話)。
2018-2019 年に京都御苑でエゾビタキが越冬し、2018 年末より短いさえずりを交えるようになった。最初は非常に小声だったが渡去までこの音声が続き、後の方ではそれなりの声量も出すようになった。最後のころに樹冠部で採食をしながら飛びながら鳴いていたことがあったが、あるいはこれが Veprintsev の記述に対応するのかもしれない。
この音声が繁殖地でのさえずりと同じものか、あるいはぐぜりかは繁殖地での決定的資料がないためよくわからないが、コサメビタキで聞かれるような他種のさえずりを交えたぐぜりとは違うもので、節回しもあってさえずりではないかと考えている。
音声は倍音関係にない2つの周波数を同時に示し (ポリフォニー polyphony。ここでは2つなので biphonation)、左右の鳴管から別々の音声を出していると考えられる (*1)。この特徴はコサメビタキやサメビタキとは決定的に違っていた。エゾビタキのさえずり (またはぐぜり) に特有のものと言えそうである。
2015.5.16 に Bo Shunqi により上海で渡り途中と思われる個体の「ぐぜり」とされる記録があり (XC762192)、これは上記のポリフォニーを一部示している。後述のように春の渡り時期が非常に遅い種類である傍証にもなる記録であろう。
上記のように既知の繁殖地は訪れることも困難な場所であり、ジオロケータで渡り経路を調べることも容易ではないだろう。秋と春で異なった渡りルートをとっているかどうかを確認することもいつ可能になるかわからない。
カムチャツカの方にあるいは到達難易度は低いところがあるかも知れないが (カムチャツカの方が数が多そうな印象がある)、大陸とカムチャツカは別亜種とされたこともあって大陸の個体も調べる必要があるのだろう。Peklo (1987) によればカムチャツカで繁殖場所で採集されたものは1つもなく、カムチャツカでも繁殖地を探すことから始める必要があるかもしれない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では、さえずりはほとんど明瞭でなく、サメビタキやコサメビタキに非常によく似ているとある。音声は spit-sit, siit-tit-tit, ttsit'-tsi-tsi などと記述されている。エゾビタキはさえずりに警戒音を混ぜることが他種との識別点としている。
同様の音声はサメビタキではまれで、巣の近くでしか聞かれないとのこと。これら3種の警戒音は非常によく似ていて柔らかくもの悲しい tsr'...tsr' であるが、エゾビタキは少し深い声で音程が低いとある。
文字だけの記述では何を指しているのかあまりよくわからず何とも言えない感じだが...。
この記述は Nazarenko (1971) が出典のよう。
少なくとも近畿地方では春の渡りのエゾビタキは珍鳥であり、大阪城公園でも確実な記録はなかったと記憶している。エゾビタキの春の渡り時期は遅く5月半ばぐらいであることも観察を難しくしている要因である。過去の記録にあるものでは、同時期に通過するサメビタキとの誤認も多いのではないかと考えている (下尾筒に軸斑がなく真っ白であることを確認できる写真がぜひとも必要である)。
舳倉島などの離島はそれなりの数が観察されているが、いわゆる珍鳥ではないためおそらくあまり注意を払われておらず、わざわざ音声を調べる人もいないだろう。春の渡り途中の「小囀り」について、中村登流・行田哲夫 (1984) ブルーバックス B-566「野鳥検索小図鑑 山野の鳥」(講談社) に言及があるが、自分が知っている範囲ではこれが唯一の記載である。
地鳴きは秋の渡りでも比較的簡単に聞くことができてコサメビタキやサメビタキとほとんど区別できない。これをさえずりとして収録しているものもあるので注意 (海外音源でも同様)。春の渡りでエゾビタキに出会われたらこれら情報を背景としてできる限りの記録を試みていただきたい。
独断と偏見の識別講座 II 第55回 Flycatchers III <エゾビタキ、サメビタキ、コサメビタキ> (波多野邦彦 2017) に「渡ってくるタイミングは春秋ともにエゾビタキ、コサメビタキの2種が先行し」とあるが、春のエゾビタキについては誤解のように思える (九州北部では事情が異なるのかも知れないが)。
コサメビタキは個体数も多いので春のヒタキ類の渡りでも最も早く渡来し始める種の一つ。しかし渡り期間も長いため5月中旬近くまで渡り個体をみかけることがある。
フィリピンでは我々にとってのジョウビタキのようにありふれた冬鳥だそうである。写真撮影者に音声を聞いたことがあるか聞いてみたことがあるが、聞いたことはないとの返事だった。音声が重要であることを意識して観察しないと気づきにくいのかも知れない (普通種でもあり、色鮮やかな種類の多いフィリピンでは特に注目されることもないかも知れない)。
備考:
*1: 発声と非線形現象 鳴禽類では音程の違う2つの音を出す場合は通常左右の鳴管から別々の音声を出していると解釈されるが、ペンギンやクジラなど哺乳類でも biphonation が知られていて振動子が示す非線形現象で説明できるとの考えが提唱されている:
del Olmo et al. (2025) Exploring nonlinear phenomena in animal vocalizations through oscillator theory (レビュー論文。オープンアクセス)。ここでは2つの振動数を two-frequency torus (3次元位相空間上の構造を示す用語) で説明しようとしている。
音 (振動) の始まりからパラメータを変えてゆくと純音、振動数の不連続なジャンプ、subharmonics (倍音成分の間に見られる成分)、カオス (雑音的音声に相当)、biphonation が非線形現象の理論から連続的に説明できるとのこと。「音程が飛ぶ」現象 (人で言えば声が裏返る?) は確かにタカの声などソノグラムでしばしばみかけるのであるいは振動子の非線形物理が関連しているのかも知れない。
例えば Kato (2021) A code for two-dimensional frequency analysis using the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (Lasso) for multidisciplinary use にハチクマの whistling call のサンプルのソノグラムがあって2つの倍音成分の中間にジャンプしている。
わずかなパラメータの違いで2つの状態の間を遷移すると考えれば納得しやすい気がする。
(この解釈が正しければ) もちろん声のニュアンスにそれらの自然現象を巧みに利用しているのだろう。
振動子と共鳴物などの間、2つの鳴管の振動子の間など非線形相互作用の場が考えらえるとのこと。2つの音の振動数が倍音関係でない整数倍になる現象なども説明可能とのこと。あくまで振動の非線形理論による解釈ではあるがなかなか面白い。著者は鳥の音声にそこまで詳しくないようだがナイチンゲール (サヨナキドリ) の2種類の音声 loud and soft calls の間の遷移は説明可能なのではなど提案している。
ペンギンのひなの biphonation は個体識別に役立つ信号となっているとのこと。
さらに深読みすると鳥が左右2つの鳴管を進化させたのはこれらの非線形相互作用を活用できるためかも知れない。単一の振動子と共鳴物では音のバラエティーに制約があるが2つになると自由度が上がってより複雑な発声が可能になるなど。
Amador et al. (2025) Transitions and tricks: nonlinear phenomena in the avian voice は Abstract のみだが上記論文同様に非線形効果を考えたもので、この論文では主に鳥の声を扱っている。
Lefevre et al. (2025) Biphonation in animal vocalizations: insights into communicative functions and production mechanisms は主に哺乳類の biphonation を扱っているが機能や流体力学効果を含む発声メカニズムの提案などのレビュー。biphonation と他の類似現象の判定方法など。
Terrade et al. (2025) Nonlinear phenomena make animal calls alarming for human listeners
少なくともヒトを被験者とした場合はカオス状態は常に警戒音として認識されるが、他の非線形効果 (周波数跳躍、倍音以外の subharmonics、振幅変化) はそうではないとのこと。あくまでヒトの認識なので哺乳類の音声に敏感である可能性がありそうだが、どのような性質の音が警戒音 (あるいはそうではない音声) として進化したのか、あるいはその発声メカニズムの進化を考える題材になりそう。
オウギワシが霊長類の獲物の追い出しに音声を用いているが、カオス状態ではなさそうなので警戒音として本能的に認識させているわけではなく、やはり獲物の学習によって捕食者の音声を認識をさせているのだろうことも想像できる。
[その他]
エゾビタキのミトコンドリアゲノムが発表されている [Liu et al. (2019) The complete mitochondrial genome of Grey-streaked Flycatcher Muscicapa griseisticta (Passeriformes: Muscicapidae)]
中国江蘇省塩城市で採集された標本によるとのことだが、Sangster and Luksenburg (2021) Sharp Increase of Problematic Mitogenomes of Birds: Causes, Consequences, and Remedies
によればこれは同定間違いとのこと。Muscicapa 属の他の種と間違っているわけでもなさそうなので不思議である。
-
サメビタキ
- 学名:Muscicapa sibirica (ムスキカパ シビリカ) シベリアのハエトリ
- 属名:muscicapa (合) ハエを捕まえる鳥 (musca -ae (f) ハエ capio (tr) 捕まえる)
- 種小名:sibirica (adj) シベリアの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:(Sooty Flycatcher 旧名), IOC: Dark-sided Flycatcher
- 備考:
muscicapa は合成語で musca, capere いずれも長母音を持たないため短母音のみと思われる。規則によればアクセントは "ムスキカパ" となる。
sibirica は短母音のみで -bi- にアクセントがある (シビリカ)。
日本の亜種は基亜種 sibirica。世界では4亜種があるとされる (IOC など)。Shulpin (1927) はロシア沿海地方に亜種 opaca (暗色の) を記載したが、Peklo (1987) によればほとんど差が認められないため、基亜種のシノニムとされる。
[Muscicapa 属の成立経緯]
Muscicapa 属のタイプ種は#ムナフヒタキ Muscicapa striata Spotted Flycatcher で日本記録種だが馴染みが薄いため Muscicapa 属の由来はこちらにまとめる。和名でもサメビタキ属の名称になっている。
定まった経緯は知らないが、日本産種でサメビタキとコサメビタキの2種に共通する属で、エゾビタキは別属だった時代もあるので共通する名称部分が選ばれたのだろうか。
この属について歴史的な情報が Taxonomy in-flux updates (BirdForum 2025.3) に示されている。最初に用いたのは Brisson (1760) でまず 分類一覧 に現れ、本文 がある。
参考 Genus Muscicapae。Genus Muscicapae で末尾は合字。
Linnaeus (1766) は Brisson をもとに Muscicapa 属を用い、それぞれ包含範囲が違っていた。過去はタイプ種を定めた著者が重要であったが、現代の規則では nominal species を含む有効な属名を含めた最初の出版物とされるとのこと。
少なくとも過去には誰が用いた属名を優先するか議論があって厳密な規則が定められたらしい。
Brisson (1760) が最初に提唱した段階 (Supplement d'ornithologie 1, 2 巻) では Linnaeus (1758) の Systema naturae 10th ed. をまだ見ていなかったらしく、第 5, 6 巻でようやく Systema naturae 10th ed. を引用した記述が登場するとのこと。Systema naturae 10th ed. を引用したことによって species-group names が有効となって上記要件を満たすようになったと解釈されるらしい。ただし個々の種の記述は第 5 巻以前に現れるとのこと。
現在 Muscicapa 属のタイプ種は通常トートニムによるとされるが、これは 第 2 巻の p. 357 の Le Gobe-mouche, Muscicapa を指すとされる (ここでは属名でなく種名のラテン名として Muscicapa が登場する)。
しかし Brisson は Linnaeus (1758) の Systema naturae 10th ed. のどの種に対応するか同定できていなかったようで、第 6 巻の Muscicapa 属の nominal species の一覧にはこれは含まれないとのこと。
つまり定義に by tautonymy と記述されていても (例えば The Key to Scientific Names)、muscicapa の種小名を持つ種は現在も過去シノニムにも Muscicapa 属に存在しない。種小名から属名への昇格とは別の概念となる。
当たり前のように用いている現在の Muscicapa 属の厳密な歴史的定義は実は非常に複雑だったらしい。
Brisson (1760) あるいは Linnaeus (1766) のどちらの属名を最初の有効な記載とみなすか次第でタイプ種 (いずれも後に定められたもの) が異なり、現代では Brisson の属名が有効と判定されて採用され (Brisson の指した種 "Muscicapa" を判定して) ムナフヒタキとなっている。ただし Brisson (1760) の書物は二名法を採用していないため、個々の種の学名はこの書物にたとえ二名法に則ったように見える形で現れても有効な学名と判断されない。
Gray (1840, 1841) は Linnaeus (1766) を採用していた。
Linnaeus (1766) を用いた場合にはマダラヒタキ Muscicapa striata Spotted flycatcher がタイプ種となるが、Linnaeus (1766) に先取権がある考えは現在採用されていない。
現状はどちらも Muscicapa 属なので事実上問題ないが、分子系統解析などによる属境界の見直しがあった場合にタイプ種でない種は属名が変わることも原理的にあり得る。
[サメビタキの分類と名称]
サメビタキはエゾビタキよりはずっと広く分布し、アフガニスタンからシベリア、チベット、中国からインドシナ半島に分布し、北のものは渡りをする。
英語の標準的な名称は Dark-sided Flycatcher であり、Sooty Flycatcher はアフリカのススチャヒタキ (IOC 13.1 まで Muscicapa infuscata または Bradornis fuliginosus HBW/BirdLife の2022 年 v6b までの学名、Clements、Artomyias fuliginosus HBW/BirdLife の 2022 年 v7 での学名。IOC 13.2 でこれに変更された) の標準的な英名となっているので混同される恐れがある。
ただし Sooty Flycatcher の名称は現在の和名が整理される際に影響を与えたかも知れない。
同様の和名に "サメメジロ"、現在はウスイロメジロの方がよく使われるらしい Zosterops pallidus Pale White-eye や "サメイロ" を冠した和名もある
("サメイロイヌワシ"、こちらも現在はアフリカソウゲンワシ Aquila rapax Tawny Eagle、"サメイロタヒバリ" Avibase では ヒガシヨーロッパタヒバリ Anthus spinoletta 現在は Water Pipit など。他にも サメイロツグミ Turdus leucomelas Pale-breasted Thrush など多くある)。
英語で tawny, pale, sooty などの色彩用語に対応した適切な色彩名称があまりなく、海外の鳥の和名が整理された当時は "サメイロ" が好まれたのかも知れない。"サメメジロ" や "サメイロイヌワシ" の事例では分類の整理があり、改めて和名を検討する際に現代の和名が用いられるようになったが、サメビタキではそのような変遷がなく、コサメビタキの名前も普及しているので名称がそのまま残っているのかも (未確認)。
同様の意味でよく使われているのは "ウス" や "ウス" に色名を付けたもの。
現在の新しい和名では "サメイロ" は避けられている印象を受ける。"サメイロ" と言っても現代ではあまり馴染みがなく、鳥の名前に集中していて他の動物分類群ではあまり用いられている形跡がないためかも知れない。
Muscicapa fuscedula Pallas, 1811 (参考) があるいはこの英名の由来かも知れない。Dauurica で普通でバイカルの森林やカムチャツカ南部に住むなどの記述がある。
少しややこしい種小名になっていたのは Muscicapa fusca Mueller, 1776 の学名がすでに用いられていて (おそらく違うものを指す同じ学名の用例がすでに複数あった) 重複を避けるためだろう。
fuscedula は fuscus + -ula (指小辞) になりそうだが d が余分にも見える。ficedula の場合は edo (食べる) が入っていると解釈できるが The Key to Scientific Names の解説では fuscus の指小形の意味でよいそう。
もう一つ候補に Muscicapa grisola Linnaeus, 1766 (ヨーロッパ) があり、Pallas (1811) によるコサメビタキはこの変種 (var. dauurica) の記載だった。#コサメビタキの備考にあるように Muscicapa striata (ムナフヒタキ) に吸収されシノニムとなった。
Muscicapa fuscedula は記述からサメビタキ類の判別ができず有効にならなかったかシノニムとなったが、あるいは英名に痕跡を残した可能性があるかも (未確認)。現在の文献には Muscicapa fuscedula は現れない。極東の種なので英語圏の文献に姿を見せないのはやむを得ないかも。
サメビタキの 原記載 (Gmelin 1789)。Dun-Fly-catcher (Latham 1783) とある
Dement'ev and Gladkov (1954) でサメビタキのシノニムとされる Muscicapa ficedula Pallas, 1811 の記載もあり、ficedula の名称はこんなところにも使われていた、と思ったがもしかするとこの ficedula は fuscedula の間違いではないだろうか。Dement'ev and Gladkov が語形を修正したのかも知れない。
#マダラヒタキの備考も参照。
[大陸のサメビタキと別種?]
DNA バーコーディングにより、大陸のサメビタキと日本・サハリンのものが種レベル (2.3%) で異なる可能性が指摘されている。
Barcoding Japanese birds (2014)。この程度の差異のあるものはこれまで別種扱いとなっているものが大半であり、他の遺伝情報を用いた解析が待たれるところ。もし別種になれば学名も変わる。
参考までに GQ482226.1 (COI) から出発して BLAST をやって見るとサメビタキは2系統に分けてよいことがわかる。一致率 97% 程度になる。他の遺伝子がほとんど調べられていないので今後の判断か。
[サメビタキとエゾビタキの識別]
サメビタキとエゾビタキはしばしば識別上問題となり、コサメビタキも汚れたように見える個体はサメビタキと混同されることがある。サメビタキとエゾビタキの決定的な識別点は下尾筒の軸斑の有無であり、胸の模様は図鑑で記載されているほど当てにならない。
また翼を閉じた状態で風切先端が尾の半分以上あるか (エゾビタキ) も識別点として役に立つ。コサメビタキは嘴基部の広さが特徴的で、サメビタキの嘴は最も小さく狭い (顔がよい角度で写っていれば嘴を見るだけで違いがわかる)。
それぞれ適切な角度からの写真が残っていればおそらく混同することはない。参考: コサメビタキ・エゾビタキ・サメビタキの識別 (大阪南港野鳥園)
[一般的には複数の特徴を確認するのがよいが、(もちろんこの3種に絞り込めた上で) 全体の特徴を把握していれば先に述べたピンポイントの識別点を使えばこの3種の識別には十分である]。おかしな時期の記録も散見され、しかも客観的な記録が残っていないものが多いので (この文書では識別についてはあまり述べないが) 注意を喚起しておく。
英名の Dark-sided Flycatcher の意味も識別の際に役立つ印象がある。サメビタキは胸の斑点が両脇によって分布する傾向がある (英名の由来) が、エゾビタキでは中央部にも均等に分布している感じがする。
もちろん個体による差も考えられるので決定的な識別点ではないと思われるが、観察の際は英名を思い出してみるのもよいだろう。
さえずりはこの3種の中でサメビタキが一番高い声だが、地鳴きではおそらく区別できない。サメビタキの春の渡り時期は#エゾビタキの備考で述べたようにコサメビタキよりだいぶ遅い。
秋は (低地では) いずれも同じような時期に通過する [独断と偏見の識別講座 II 第55回 Flycatchers III <エゾビタキ、サメビタキ、コサメビタキ> (波多野邦彦 2017) に少し異なる見解が出ている]。
エゾビタキはフィリピンで普通の冬鳥だがサメビタキはまれとのこと (2023 年版チェックリストによる)。日本では繁殖個体もあってよくエゾビタキと似たところを渡っている印象を受けるが、サメビタキは大陸系の渡りルートをとると考えるのがよいかも知れない。
[その他]
風 (2008) Birder 22(5): 26-31 によればサメビタキの別名に「たかむしくい」があるとのこと。
日本語で "フライングキャッチ" と呼ばれるヒタキ類の行動は英語の誤用 (ハエを意味する fly を飛ぶと勘違いしたため) で、英語では hawking などと呼ばれるが、まさしくそれに相当する和名が実際にあった。
東郷 (2017) 31(5): 47 によれば flycatching は正しい英語であるとのこと。
「世界の鳥 行動の秘密」(バートン 1985) p. 62 に「飛んでとらえる (フライ キャッチャー)」と説明があり、少なくともこの時点で日本語での誤解が存在していて文字にもなっていたことがわかる。
「原色日本野鳥生態図鑑」(中村登流、中村雅彦 保育社 1995) でも全文が "フライングキャッチ" の用法で統一されているが、この時代の書物を読んだ人はこの用法が身についてしまっているかも知れない。
flycatcher などカタカナを使わずそのまま英語で記していた方がむしろよかった。この表記ならば fly の後に -ing の挿入しようと思わないだろう。古い時代の図鑑に使われた「ヒタキ型採餌」の用語の方が正確だった。
本稿の執筆にあたって 1930-1940 年代に最初に出版された書物を見ることがあるが、当時は縦書きでしかも一般向け書籍でも、英語を横文字のまま記述することも多かった (ふりがなもしばしば付いていた)。そのままの伝統が受け継がれていたならば、学術用語は横文字で記述することが普通になっていたかも知れない。戦時中の英語使用禁止に伴ってこの伝統が途切れ、訳語を用いたり英語を使う場合も改めてカタカナで記述する習慣が広まったことが日本人の英語力低下に貢献したのかも知れない。
横文字が入っていると「わからない人もいるので」と拒否することはやめよう。かつては入っていても当たり前だったのだから。
鳥関係の他の和製英語らしいものでは "マイ フィールド" が気になるところ。"my field" で検索してもほとんど用例がないのでおそらく使われない英語なのだろうと想像する。my field of interests (興味分野) などの使い方、my field experience (野外経験)、
The bird flew into my field of vision の組み合わせなどはそもそも "my field" の結合ではない。in my field や this is my field は正しい英語とのことで、自身の専門分野を指す。
"マイ何とか" の表現を見るとおそらくそもそも英語かどうかを疑った方がよい。
鳥関係では同じような意味で local patch の用語が使われるがこれも鳥関係に特化した用語らしく OED など辞書にも出てこない。What exactly is a "local patch" (BirdForum 2005)、What is your "local patch"? (BirdForum 2014) なども参考にどうぞ。
この用語は英語圏では通じ、個々人が定期的に訪れて観察している場所を指している。
patch の表現もバーダーの間で広く使われ、find a patch (観察場所を見つける) のように一般的に用いられる。"my patch" の表現はバーダーの間で使われる。
英語では "in the field" の表現があり、これも鳥見用語とのこと。以下雑誌 "Bird Watch" 1995.6 p. 52 より部分紹介。この記事は鳥見特有の用語が何を意味するか (冗談も含めて) 取り上げたもので著者名は R. G. Tickworthy となっていてこれも本名ではないだろう。
英語では field は通常野原を指すので、森林や海を指して "field" と呼ばれると混乱してくるだろうが、"in the field" の表現は ticking 業界では鳥の見られる野外環境を指すもので、この用法は英語圏の者にとっても不思議に聞こえるらしい。
当時の用語で "telly-ticks" があり、これは TV で鳥を探すことを指すとのこと。TV に現れた鳥を同定して (TV の) ライフリストに数える趣味もあり、この場合はライフリストに含めるためには放送で鳥の名前が挙げられていないなどのルールがあるらしい。"in the field" のライフリスト同様もちろん識別力は要求されるので優れたバーダーの指標になる。
この記事では残念なことに多くのバーダーが "telly-ticks" ばかりやっていて、"in the field" のバーダーから電話で情報が入って来るのを待っているだけであると用法の説明とともに皮肉っている。
この "in the field" を拡大解釈して "マイ フィールド" の和製英語が作られたのかも。
この記事に "local patch" (普通の人が聞けばいったい何かと思うだろう) の解説もあって同程度の ticking 業界の用語らしい。
当時は "telly-ticks" が流行していたようで、雑誌 "Bird Watching" 1995.12 p. 12 (Weyman) に窓の外から熱心に覗き込んでいる Herring Gull (ニシセグロカモメに相当) の報告があった。鳥の出てくる TV 番組を熱心に見ていたのではないかとのこと。
東郷 (2021) Birder 35(6): 45 によれば、my birding patch の表現が紹介されていた。この場合に適した単語は site, patch, spots で、spot は単数形では指す範囲が狭すぎるとのこと。
"マイ フィールド" がいつごろから使われるようになったのかは知らないが、中村忠昌氏の Birder 24(5): 34 (2010) の「マイフィールドをもとう!」の記事があり、当時は意味が括弧内に示されていた。使用されるようになって比較的早い段階の記事だろうか。
和製英語ではないが用法に関連して紹介しておくと lifer (ライファー) の由来解説が Birder 編集部 (2002) 16(6): 61 にあった。この当時紹介される通り相当新しい用語で、戦後のアメリカで life bird と表現され、その口語と思われる lifer となったとの雑誌記事の紹介があった。
もとは twitcher (トゥイッチャー) の間で使われる用語との紹介があり「一般的なバードウォッチャーが使えることばではないようです」と 2002 年には日本国内でもまだ市民権を得ていなかったことがわかる。この Birder 記事では日本ではもう少し広く捉えてもよい見解も示しており現在のように普及したのかも知れない。
自分も古い人間なので (?) ライファーの用語は日本語・英語とも使ったことがない。
-
コサメビタキ
- 学名:Muscicapa dauurica (ムスキカパ ダウウーリカ) ダウリア地方のハエトリ
- 属名:muscicapa (合) ハエを捕まえる鳥 (musca -ae (f) ハエ capio (tr) 捕まえる)
- 種小名:dauurica (adj) バイカル湖東岸のダウリア地方の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:(Brown Flycatcher), IOC: Asian Brown Flycatcher
- 備考:
muscicapa は#サメビタキ参照。
dauurica は2つめの u が長母音でアクセントもここにある (ダウウーリカ)。ラテン語本来は固有名詞のため大文字で記述する (Dauurica)。
一時期使われた種小名の latirostris の方が特徴を覚えるのに適した名称だったが、こちらは a, o が長母音で後者にアクセントがある (ラーティローストゥリス)。latus (ラートゥス。広い) と rostrum の長母音由来。
学名が過去変遷した。IOC でも 3.2 で Muscicapa dauurica だったものが 3.3-4.4 で M. latirostris (latus 広い rostrum 嘴)、5.1 以降は M. dauurica に戻り、海外図鑑でも両者が混在して学名の書き換えを複数回経験した人もあるだろう。
ちなみに Muscicapa grisola var. davurica (または dauurica) Pallas, 1811 が最初の記載であった。
Muscicapa grisola はその後アフリカからユーラシアまで広範に分布する Muscicapa striata (ムナフヒタキ) に吸収されシノニムとなった。学名については#サメビタキの備考も参照。
学名や英名が和名整理の際に影響を与えた可能性も考えられる。
dauurica は種小名や亜種ではなく変種として提唱されたもので (そのためムナフヒタキの以前の分布図などにも現れない)、どの名称が優先されるか議論があったために学名が変遷したのであろう (以下に詳細がある)。
M. latirostris はスマトラの標本に基づき Raffles (1822) による。
現在はこの種に使われなくなった種小名だが latirostris (latus 広い rostrum 嘴) はこの種の特徴をよく表している。
ロシア語名の shirokoklyuvaya mukholovka (広い嘴のヒタキ) も同じ意味である (#サメビタキの備考参照)。
学名の変遷については Mlikovsky (2012) Correct name for the Asian Brown Flycatcher (Aves: Muscicapidae, Muscicapa)、
Dikinson (2014) Correcting the "correct" name for the Asian Brown Flycatcher (Aves: Passeriformes, Muscicapidae, Muscicapa) にそれぞれ提言があり、
Pallas の記載した var. dauurica を亜種として認めるか (その場合種小名は dauurica)、亜種以下の分類階層なので認めないか (その場合種小名は latirostris) が争点になっていた。
Mlikovsky (2012) は字面通りに var. を「変種」と解釈したが、Dikinson (2014) は Pallas がラテン語の書物として記載した var. が他の種において亜種として認識されていることも示し、命名規則に基づいて dauurica は亜種として認められるとした。
この見解が現在採用されているが、Boyd は Mlikovsky (2012) のみを参照の上で逆の見解をとっている。Dikinson (2014) を見ていないだけかも知れない。
日本やシベリアに広く分布するものは基亜種 dauurica で、他の2亜種、例えばインド亜大陸やアンダマン諸島のものは poonensis とされるが、違いはわずかで単形種としても扱われるとのこと (wikipedia 英語版)。IOC では3亜種の扱い。
かつてコサメビタキに含まれていて分離された種にミナミコサメビタキ Muscicapa williamsoni Williamson's Flycatcher とスラウェシサメビタキ Muscicapa sodhii Sulawesi Brown Flycatcher がある。
これらを独立種とするか分類により異なるのでコサメビタキの亜種数はリストにより異なる。
スラウェシサメビタキは外見は似ているが DNA や音声に大きな違いがあることが示され、通常は独立種として扱われる (#エゾビタキ備考参照。スラウェシサメビタキは遺存種の可能性がある)。
ロシア沿海地方のコサメビタキ: Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Asian brown flycatcher Muscicapa dauurica (pp. 4957-4982)。
交尾とその後の給餌など珍しい写真も紹介されている。
この論文ではロシア沿海地方で繁殖する亜種を dauurica とし、島の亜種 cinereo-alba が渡り時期に通過している可能性を紹介している。
この亜種は Muscicapa cinereo-alba Temminck & Schlegel, 1847 (参考) 基産地日本で1標本のみで記載されたもの (図版。幅広い嘴を表す図が付いている)。
"Fauna Japonica" の原記載。フランス語名 le gobe-mouche gris-blanc と学名と同様に色をそのまま表したもの。性も年齢も不明。
大陸と島の亜種が別との考えならばこの記載が生きてくるのかも知れない。Dement'ev and Gladkov (1954) ではシノニムにも出てこないが Avibase にはシノニムとして登場する。サハリンの標本でこの学名を用いているものがあったので大陸とサハリンは別亜種との考え方もある模様。
英名で Asian Brown Flycatcher で「それほど褐色に見えない」と言われることがしばしばあるがこれは同意する。"Brown Flycatcher" と総称される種類がいくつかあるため (一部は同種とされた) グループとしては少なくともヨーロッパの白と黒の目立つヒタキよりは褐色と言えるだろう (#イヌワシに金色のワシのラテン名が与えられた感覚に近いかも知れない)。
記載時学名の Muscicapa grisola var. davurica (または dauurica) の grisola は Aldrovandus 1603 の用いた鳥の名前で灰色とのこと (griseum 灰色) (The Key to Scientific Names)。
コサメビタキはムナフヒタキと変種として記載されたが、ムナフヒタキは多くの言語で「灰色の」の名前が付き、今度はどこが灰色かと言われそうなので、地味なヒタキの色彩表現は結構曖昧なものなのだろう。
[音声]
春の渡りで都市公園などを通過する時はよくぐぜっている。この声はメジロのぐぜりに似ていて他種の声を交えるなど区別が難しい。コサメビタキは他種の声の取り込みの名手であり、シジュウカラ、ヤマガラ、キビタキ、オオルリ、ウグイス、センダイムシクイ、エゾムシクイ、カワラヒワ、コゲラ、サシバなどいずれもそっくりに真似をする。いずれの対応種も録音記録を持っている。特にサシバの声は思わず探してしまうほどによく似ていた。
しばらく待っていると本格的なさえずりに移行することがあり、ここでは他種は真似しなくなる (いつもとは言い切れないが)。このぐぜりは相当のベテランにとっても非常に聞き逃しやすい声のようで、有名な渡り中継地でも気づく人がほとんどいない [多くのベテランも、あるいはベテランほど (?) 複雑な声は全部メジロとみなしているのかも知れない。不思議なことに過去に参加した探鳥会で声でコサメビタキを指摘したリーダーは1人も出会わなかった]。
コサメビタキのものまねについては先崎 (2017) Birder 31(10): 40 にも記事があるが、ものまねの判断は主観が入りやすいので周波数の一致など客観的に判断できる音源をぜひ残して欲しい。
リストにマミジロが含まれているがマミジロを思わせる音声は非常に多い (マミジロは当地では春の渡りでは珍しく声が聞けないか毎年気にしている)。特に紛らわしいのがキビタキの短いさえずりで、何度マミジロまたはマミジロキビタキを期待したことか...。
ツミの「キィキィキィ」も似た声を出す種類があるのでこれも録音とソノグラム比較結果などを紹介していただきたいところ。
本稿の他の項目を見ていただいても他人の判定をあまり信頼していないと感じられるのではないかと思うが、ものまねは特にその印象が強い。過去に誰かが書いたものまねのリストをまとめたものなど、音源などの客観的データがないと信頼度がまったくわからないので、そのまま上書きしてさらに伝聞で伝えられてゆくことに危惧を感じるぐらいである。
この種に限らず、ものまねを調べられる方は (新たに記録する分には録音や録画すればよいのでおそらく問題ないが)、過去の記録を引用する際は客観的データの有無など信頼できる参照文献を追記することなどを検討していただければと思う。
このぐぜりの段階で声を頼りに場所を探せば大抵コサメビタキが鳴いているのを見つけることができる。このように見つけている人をほとんどみかけないので、春のコサメビタキの見逃し率は非常に高いと考えている。
コサメビタキは春の渡りではあまり出会わないと言っている人はおそらく単に見つけられていないのだろうと想像する。
またぐぜりやさえずりの合間に特有の地鳴き (サメビタキ類共通の「ジリリ」のような声、オジロビタキ類の地鳴き同様の声を想像していただけばよい。サメビタキ類の間では区別できないが、早い季節であればまずコサメビタキと考えてよい。alarm call とされる場合もある) も交えることもあり、これも見つける手がかりになる。あるいはこの音声をエナガと勘違いされている場合もあるかも知れない。
また最近は十分に茂った場所があればキビタキ同様都市部の公園でも繁殖していることがある。繁殖期にシメを思わせる「ツィ」の声を聞けば要注意。ホオジロ類の地鳴きとも多少似て聞こえるかも知れない。待っているとコサメビタキが現れるかも知れない。
少し古い本に「かつては都市部の公園のようなところでも繁殖していた」のような表現を見ることがあるが、コサメビタキの認知度の低さを考慮するとこれは単に気づく人がいなくなってしまっただけだったのかも知れない。ヤブサメが減ったのか観察者の高齢化のためか判断が難しいのと似ているかも知れない。
コサメビタキも数が増えて平地でも再度繁殖するようになったのか、途中でも繁殖していたが気づかれていなかっただけなのか区別が難しい。市民科学データから増減傾向を判定しにくい種だと思う (さらに言えばオオルリやキビタキの初認記録は詳しく記録されているものの、話題になる種しか扱われていない傾向も感じる)。
またよく言われるようにコサメビタキのさえずりの期間は短く、特定のつがいに注目すればつがい形成後造巣時期にはほとんどさえずらなくなる (コサメビタキはオスも造巣を分担する)。この点はオオルリやキビタキとかなり違う。コサメビタキのさえずりを聞きたい場合は早い季節を狙うとよい。到着してすぐの時期は単独で採食中でもよくさえずる。ただし渡り期間は長いので遅い時期でもさえずっていることもある。さえずる個体密度は4月後半の方が高いかも知れない。
オオルリやキビタキのように繁殖していれば遠くから声ですぐわかる種類ではないが、「こつ」(および時期の選択) がわかれば存在確認は容易でよく出会える種類なのでもっと注意すべき種類だろう。
抱卵中はあまり声を出さなくなるが、相棒を誘う時などのコミュニケーションに「ツィ」の声を出す。この声を知っていれば相棒が帰ってきた、あるいは他個体と争っているなど状況がよく判断できる。
「ツィ」の声は秋の渡り時期にも聞くが、「ジリリ」のような声は抱卵中には聞いた記憶がない。秋の渡り時期にこの声を出すのは非繁殖期のなわばり確保のような意味があるのかも知れない。秋の渡り時期しか見ていないとコサメビタキの音声レパートリーをあまり把握しないままに終わる可能性が高いので注意。
[コサメビタキの初認時期]
野鳥だより・筑豊 2025 年 3 月号 の初認日を予報する\夏鳥/有働孝士 web 記事 になぜコサメビタキが現れないのかと不思議に感じたが「観察サイト」の記録そのものが少ないらしいと知った。
2025 年の春は寒くて夏鳥の到着が遅れたが、当地 (京都) ではコサメビタキの造巣行動を 4/20 に初観察している (ちなみに 4/26 現在もまだ作業している)。初認は 4/15 だった。
過去の記録を少し見てみると 2017 年は 4/17 に求愛行動が見られ、4/18 に造巣を開始していた。参考ビデオ。筑豊ではおそらくさらに早い時期に到着していると思う。
ちなみに標準偏差が大きいとされるコシアカツバメは当地では例年ツバメに次いで早い時期 (オオルリなどとほぼ同じぐらい) に到来する種類で 2025 年の初認は 4/10 だった。筑豊の 2014-2023 年の最速記録が 5/6 とはちょっと信じがたい。飛んでいて気づくことも多く、京都大学キャンパスでもかなりの頻度で出会う。もしかすると声があまり知られていないのかも知れない。
[オーストラリアで見つかった超珍鳥ミナミコサメビタキ]
サメビタキの項目で「地鳴きではおそらく区別できない」と書いたが、興味深い事例が報告されている。
Unusual song and collected poo confirms obscure Asian bird species brown-streaked flycatcher found in Australia。
オーストラリアで2020年10月、聞きなれない声 (見出しに song とあるが地鳴きのよう) で珍鳥に違いないと判断。コサメビタキ (これもオーストラリア本土では記録されていない) かどうか判断に迷った。声を判断した者は音声データベースと比べてミナミコサメビタキ Muscicapa williamsoni Williamson's Flycatcher ではないかと考えた。この種の音声記録は過去に1例しかなかった。
DNA 分析が必須となって、鳥がフンをするのを待って、幸運にも汚染なく採取された。オーストラリア博物館もフンの DNA 分析など経験がなかった (でもきっとしぶしぶ引き受けてくれた: ここは想像)。費用も結構高額だった (600 豪ドル)。ヒタキの仲間まではわかった。
しかしあまりに珍しい種類のため公開されている塩基配列がなく迷宮入り...しそうなところでシンガポールで東南アジアのヒタキを研究している研究者がいることを教えられ、その研究者が2検体を持っていて同定が確認されたとのこと。生息地でも姿を見た人はほとんどいない種類だそうである。
音声をもとに超珍鳥が判定され、しかも DNA 判定までできたとの驚きの物語である。聞く人が聞けばサメビタキ類の地鳴きも識別できるのかも知れない。世界のレベルの高さがわかる。
この事例を見ると音声に違いがあり、コサメビタキと別種とするのは妥当と思える。
-
ミヤマヒタキ
- 学名:Muscicapa ferruginea (ムスキカパ フェルルーギネア) 鉄錆色のハエトリ
- 属名:muscicapa (合) ハエを捕まえる鳥 (musca -ae (f) ハエ capio (tr) 捕まえる)
- 種小名:ferruginea (adj) 鉄錆色の (ferrugineus)
- 英名:Ferruginous Flycatcher
- 備考:
muscicapa は#サメビタキ参照。
ferruginea は u が長母音で -gi- アクセントがある (フェルルーギネア)。英語ではこの長母音の位置にアクセントがあって異なっているが英語読みされることが多いかも知れない。
記載時学名 H[emichelidon] ferruginea Hodgson, 1845 (原記載) 基産地 Nepal。Hemichelidon の属名も Hodgson がこの記載で提唱したもの。#エゾビタキ参照。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。繁殖地では高地に生息するそうである (原記載参照)。この場合は "ミヤマ" は深い山でもよさそうに思える。
山階鳥類研究所の標本データベースには結構多数の標本があり、戦前の台湾のものが多い。当時からミヤマヒタキの名称が使われていた。
Zhao et al. (2023) の分子系統解析 (#ヨーロッパコマドリの備考参照) によればミヤマヒタキに最も近縁なのはサメビタキである。単形種。
所崎 (2000) Birder 14(11): 66 に鹿児島県平島での観察報告がある。他のヒタキ類と違って枯れ木先端などにはあまり止まらず、地上1mぐらいの切り株によく止まったとのこと。過去にも同時期に平島での記録があり、春には少数が飛来しているらしいとのこと。
-
マダラヒタキ
-
マミジロキビタキ
- 学名:Ficedula zanthopygia (フィーケドゥラ ザントピュギア) 黄色い腰のイチジクをついばむ鳥
- 属名:ficedula (f) < ficus イチジク edo ついばむ
- 種小名:zanthopygia (合) xanthos 黄色 -pugios < puge 腰 (Gk)
- 英名:Yellow-rumped Flycatcher
- 備考:
ficedula は#キビタキ参照。
zanthopygia は外来語由来の合成語で発音はよくわからないが、起源となるギリシャ語は短母音のみなので長母音は現れないと考えられる。その場合規則によれば "ザントピュギア" のアクセントとなり語調的もわかりやすい。
キサントフィル (xanthophyll) の名前を知っていればこの学名はわかりやすい。
英名は種小名と対応している。
Muscicapa zanthopygia Hay, 1845 (原記載) として記載されたもの。
Xanthopygia leucophrys Blyth, 1847 は新属名を提案するとともに Xanthopygia leucophrys Blyth, 1847 (参考) 基産地 Malacca (マラッカ) を新種として記載した次第。この種小名は "マミジロ" の意味 (The Key to Scientific Names の Zanthopygia から一部まとめた)。
Xanthopygia = Zanthopygia 属が採用されていた時代には leucophrys も別種扱いで使われていたのではないだろうか。
両者はシノニムとされ zanthopygia の種小名が有効となった模様。
Muscicapa leucophrys Orbigny & Lafresnaye, 1837 の記載 (参考) 基産地 Bolivia (ボリビア) が先にあって Muscicapa 属に統合された際にこの Blyth の与えた学名は preoccupied と判定された表に現れなくなったと思われる
マミジロキビタキの和名は眉の黄色いキビタキよりもこの "マミジロ" を意味する leucophrys (または他言語を通じて) から影響を受けた可能性も考えられる。なお Blyth は同時に Xanthopygia chrysophrys Blyth, 1847 (参考) の学名をキビタキに与えているので、学名が "マミジロキビタキ" と "キマユキビタキ" となって和名との整合性もよい。
マミジロキビタキの学名または他言語由来は検討に値するかも知れない。
"Fauna Japonica" では Muscicapa hylocharis の学名で登場したと言われる (日本動物誌 Fauna Japonica 鳥類 の表から)。
記載 フランス語名 le gobe-mouche hylochare で、1標本のみで性別不明。日本の他のヒタキ類からはだいぶ離れていて、Hylocharis や Vireo との類似性があるのでこの種小名を与えたとのこと。
通常のヒタキ類よりずっと強力で背も高いとのこと。嘴も太いなど記されている。
Hylocharis はここでは何を指しているのか今ひとつ不明 (現在の属名では通常ハチドリ類のシノニムとなっている)。モズヒタキ類を指す用例はある (現在の属名で Pachycephala) でこれかも知れない。
図版。
Letters, Extracts from Correspondence, Notices, etc. によれば、Schlegel がオスのよい標本をアモイで採集し Muscicapa hylocharis Schlegel, 1861 とこの学名を用いたとのこと。(ニシ)オジロビタキ (parva の方) に似ているが尾に白い部分がないとのこと。
Fauna Japonica の図版もマミジロキビタキらしく見えず何者か不明。(ニシ)オジロビタキと対比されるぐらいなので Fauna Japonica で意図されたものと異なるのかも。
Swinhoe (1874) On some birds from Hakodadi, in northern Japan では "Fauna Japonica" の図版はキビタキのメスとしている。図版はそのように見えるが本文の記述や分類との整合性は (?)。
Schlegel (1861) と Swinhoe (1874) で解釈が異なるようなのであまり精緻に同定されていなかったかも知れない。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire でもキビタキのメスとしている。マミジロキビタキと判定したのは Sharpe だったよう。
Hartert (1910-1922) p. 490 ではマミジロキビタキと判定 (当時はキビタキの亜種扱い)。
1984 年、富士山麓でマミジロキビタキのオスとキビタキのメスが自然交雑 (営巣) したが巣立ちには至らなかった例はよく知られている
[キビタキ類の識別点も含め、独断と偏見の識別講座 II 第6回 Flycatchers I <ヒタキ類:キビタキ、リュウキュウキビタキ、キムネビタキ、マミジロキビタキ、ムギマキ> 波多野邦彦 (2013) を参照]。単形種。
マミジロキビタキには Korean Flycatcher の別名もあった。
[マミジロキビタキとカオグロヒタキの学名の関係]
Muscicapa tricolor Vieillot, 1818 (参考 1, 2。産地は Timor とされる) が由来と思われる Tricolor Flycatcher の英語別名があった (学名とともに "3色のヒタキ" の意味)。
この学名はおそらく有効でなかったようで、Hartert (1910-1922) p. 406 では Muscicapa [Muscicapula] tricolor Hartlaub, 1845 (1846) (参考) の方が示されている。
Seebohm (1890) でも Xanthopygia tricolor の学名と Tricoloured Flycatcher の名称で登場する。
現在 Ficedula tricolor の学名を持つ別種 (カオグロヒタキ、Slaty-blue Flycatcher) があるのでこの名前は紛らわしい。
こちらは記載時学名 D[igenea] tricolor Hodgson, 1845 (原記載) で当時は Hodgson (1845) 自身が与えた属があって Muscicapa tricolor Vieillot, 1818 とは別属だったために大丈夫だったのだろう。
現代の概念ではどちらも Ficedula 属になるので衝突しそうだが、Muscicapa [Muscicapula] tricolor Hartlaub, 1845 (1846) よりも Hay (1845) の学名が少し早くてマミジロキビタキの tricolor に先取権が生じず、カオグロヒタキの学名の方も有効なままだったのだろう。
このケースはかなり複雑そう、と思ったらやはり複雑で Dickinson and Walters (2006) Systematic notes on Asian birds. 54. Comments on the names proposed by Hodgson (1845) and their priority
に解説があった。やはり カオグロヒタキの tricolor は preoccupied と考えられて カオグロヒタキに Muscicapa leucomelanura の学名を用いていた時代があった (Hartert 1907)。
Hartert (1910-1922) p. 489。Hodgson はカオグロヒタキの雌雄に別の学名を付けていたためもう一方が生きることになった。これは属統合によって Muscicapa の大きな属としたため。
Hartert は当時の権威だったが、ここで Muscicapa 属を大きな属としたため衝突が発生した (マミジロキビタキとキビタキはいずれ同属になる運命だったので結果的にやむを得なかったが) が、同時にヒタキ科の概念も広げてしまった (#メグロの備考参照)。
ごく最近までヒタキ科やヒタキ類の分類が安定しなかった要因の一つとも言えるだろう。サンコウチョウがヒタキの仲間に入れられていたのもこの時代の分類が根底にあり、Hartert (1910-1922) を見てもサンコウチョウとヒタキ類が見事に並べられている。
おそらく旧北区の鳥のみを扱ったため、熱帯地方の鳥との近縁関係が見えず、サンコウチョウに生態的に一番近いのは (他はよく知らないので) ヨーロッパのヒタキ類と考えられたのだろう。
Baker (1930) がさすがに大まか過ぎると Muscicapula 属を分離して tricolor に戻した。一方 Vaurie (1953) Systematic Notes on Palearctic Birds. No. 2. Geographical variation in Ficedula tricolor は preoccupied でないとの議論を行った。
カオグロヒタキの記載は 1845年8月、マミジロキビタキに与えられた方 (Muscicapa [Muscicapula] tricolor Hartlaub) が 1845年10月以降、Hay のマミジロキビタキの学名は 1845 年初めで最も早かったと判定。
マミジロキビタキに Hay の zanthopygia の種小名を与えることで解決したとのこと。カオグロヒタキの記載の方が早かったので、Ficedula 属に統合されるとマミジロキビタキの tricolor はシノニムでなく無効となる。
旧広義の Muscicapa 属を分割するか再編するかの問題にも関連して近年まで扱いが一定でなかった。
非常に複雑なので改めて整理しておくと、1845 (1846) 年に Muscicapa [Muscicapula] tricolor Hartlaub のマミジロキビタキの記載があった。
カオグロヒタキが 1845 年に記載され同じ tricolor の種小名が付けられた。記載時は別属だったので双方に tricolor の種小名が付いても問題なかったが Hartert が広範囲に Muscicapa に属統合を行ったため衝突してしまった。カオグロヒタキは雌雄別々の学名があったためもう一方の学名を用いることで一度は解決された。
この時代は tricolor はマミジロキビタキの種小名として使われた [しかし Hartert (1910-1922) 自身はマミジロキビタキをキビタキの亜種とした上で zanthopygia を用いていた]。
カオグロヒタキの tricolor はそのまま無効となるかと思われたが、文献年代の判定によりマミジロキビタキに 1845 年同年のより早い時期に付けられた学名 (Muscicapa zanthopygia Hay) があり、マミジロキビタキに zanthopygia の種小名を用いることで、カオグロヒタキの tricolor が有効とされて復活した次第。
マミジロキビタキの過去の英名に痕跡が残っている。比較的最近の資料まで現れるので過去の資料を見て英名を記述する際には注意が必要。
文献によってどちらの学名も登場するので古い記述を見る時にはかなり注意が必要そう。一時的には Hartert のやや強引な属統合の結果とも言えるが、現代の分子系統研究ではいずれも Ficedula 属となるため再度別属となることはおそらくないと思われる。
念のため GenBank の NC_015802.1 (ミトコンドリアゲノム) を出発点に BLAST を行ってみると、マミジロキビタキとキビタキはそれほど近いわけではなかった。シロエリヒタキのグループには含まれるのでこの枝全体を Ficedula とする扱いとなっているが、マミジロキビタキとキビタキをそれぞれ別属に分離できないほど近いわけでもない。
#キビタキ備考の Zhao et al. (2023) の分子系統樹による系統では (その 1) をさらに分けるかどうかの問題に対応する。この中でマミジロキビタキが古い系統なのでキビタキとの違いがやや目立っている模様。音声の類似性や交雑なども考慮すると同属扱いが適切なのだろう。
文献の系統樹を探す以外にも GenBank を使うといろいろな楽しみがありそう。
[マミジロキビタキとキビタキの日本初記録と交雑]
茂田 (1991)「マミジロキビタキとキビタキ」Birder 5(7): 42-45 によれば日本での初記録は1911年6月28日に長野で標本として採集されたものである。上記 1984 年の交雑例は1984年6月23-24日に山中湖畔で標識放鳥されたもので、キビタキのメスとつがいでひなを育てていたことは6月24日に確認されたとのこと (浅見・堀田 1985)。
[マミジロキビタキとキビタキの識別など]
繁殖地では川沿いの広葉樹林に住むとされており (コンサイス鳥名事典)、キビタキほどは成熟した森林内部を好まず、より開けたところに生息するようである。渡りの時期、特に春の渡りで森林内のキビタキの中に混ざっていることを期待するよりも、より開けたところを探す方がよいかも知れない。
春の渡り時期は比較的遅めでゴールデンウィークのころから6月にかけて見られるが、6月の個体は春の渡りというよりも放浪中のものかも知れない。遅い時期になるとキビタキは渡来当初ほどはさえずらなくなり、「ちょっと短いフレーズの変なキビタキのさえずり」としてマミジロキビタキの声に気づきやすくなるかも知れない。
秋の渡りでキビタキのメス型 (メスまたはその年生まれの若鳥) の中に翼に白斑のある個体があり、マミジロキビタキのメスではないかとしばしば話題になる。「白斑キビタキ」とも呼ばれる (元山裕康氏の大阪城公園の野鳥から: 1, 2)。
マミジロキビタキとは白斑部の形が異なり、マミジロキビタキは白斑部が大きく、三列風切羽縁にも白斑が広がり T 字型のように見える点が識別点の一つ。
キビタキでは秋に換羽を中断して渡りをするものがあることが知られており、岡久 (2017) Birder 31(5): 70 に詳しい情報がある。昔から「半ナリ」の名で知られており、岡久の調査によれば換羽と渡りにトレードオフがあり、遠方に渡りをする個体ほど茶色っぽく、近距離の渡り個体ほど黒っぽいことが予想されるとのことであるが、特に九州ではいかがだろうか。
これらの不完全換羽も紛らわしい個体の原因になっているかも知れない。
Bakewell et al. (2021) Identification of the Narcissus Flycatcher - Yellow-rumped Flycatcher complex in subadult and female plumages
キビタキ類の分布、渡りや識別点が出ている。これによればマミジロキビタキの秋の渡りは他種より早く、タイで8月1日の記録がある。韓国では渡りのピークは8月中旬から9月中旬とある。
(大陸経由が主なルートであることも主要要因だろうが) 秋の一般的な小鳥の渡りピーク時期より早い (渡り観察者も少ない) ことも秋に観察例が少ない一つの要因かも知れない。春の渡りでは日本での観察よりも早い時期が示されており、遅い時期に記録される個体は日本滞在中でパートナーを探して放浪しているものかも知れない。
さてマミジロキビタキが6月に入ってから記録されることが結構あるのが多少気になっている。同じような分布を示すムギマキではあまり聞かないためである。ムギマキの声を知っている人が少なく、あるいは都市公園に現れることが少ないためあまり気づかれていない可能性も考えられるが、ムギマキは最短距離でサハリンに分布してパートナーを探して放浪すると言ってもわざわざ海を越えないのかも知れない。
ではマミジロキビタキではなぜ、となるわけだが、マミジロキビタキは人知れず日本国内でも少数繁殖していてパートナーを探して放浪する個体があるのではないだろうか。数の多いキビタキに紛れてしまえば声も似ていてほとんど気づかれないかも知れない。キビタキのメスとつがいでひなを育てていた事例が過去に報告されているので、偶然発見される例が少ないだけで実はもっと事例があるのかも知れない。
キビタキ類の分子系統や音声解析は Dong et al. (2015)
Taxonomy of the Narcissus Flycatcher Ficedula narcissina complex: an integrative approach using morphological, bioacoustic and multilocus DNA data にある。
この論文ではキビタキ類の4つのグループ (マミジロキビタキ、キビタキ、リュウキュウキビタキ、キムネビタキ) がすべて異なったさえずりを示すこと、分子遺伝学的にもそれぞれを独立種とすべきことが述べられている (#キビタキの備考も参照)。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で同等の扱い。キムネビタキのみ検討種になっている。現在の扱い (世界の主要リストも同様) ではこれらはいずれも亜種を持たない単形種となる。
Dong et al. (2015) で示されているソノグラムでも、たとえ繁殖地でもマミジロキビタキは2-3節の短いさえずりのみで (そのためしばしばツグミ類のさえずりと混同される)、キビタキのように長い節でさえずることがないことがわかる。我々が日本で聞くマミジロキビタキのさえずりもおそらく繁殖地のものとあまり差がないと考えられる。
マミジロキビタキのメスは顔の色合いも第一印象でキビタキと全然違った印象を受け、「悩ましいキビタキ」はやはりキビタキなのだろうと感じる。開けたところで遭遇することもあるためか電柱にとまったオス成鳥を見たことがある。
下面の黄色い部分が下腹部まで広がっていて、下から見るとキセキレイのような色合いの印象を受けた。この個体は「キビタキにしては中途半端に短い」さえずりを聞かせてくれたがキビタキのような派手さはなく、声だけ聞くと聞き逃してしまうかも知れない (皆マミジロキビタキに出会いたがるものだが、キビタキ類の中で音声面はキビタキが最も優れた歌い手のようである)。地鳴きも複数個体を録音したがキビタキと区別できる点を見出すことはできなかった。
[繁殖生態]
Mingju E. et al. (2021) Mate choice for major histocompatibility complex (MHC) complementarity in the Yellow-rumped Flycatcher (Ficedula zanthopygia)
中国のマミジロキビタキでの近親交配回避の研究。ただしどのように近親個体を見分けているのかは不明。つがい外交尾の結果も認められたとのこと。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the yellow-rumped flycatcher Ficedula zanthopygia (pp. 1057-1077)
ロシア沿海地方での繁殖生態。春の渡りはそれほど遅くなく5月上旬から中旬。4月の例もある。
6月終わりには大部分が巣立っている。秋の渡りの始まりは早く8月後半。ただし秋の渡りは非常に目立たないとのこと。最も遅い渡りで9月下旬。10月1日の例もある。
-
キビタキ (リュウキュウキビタキ が分離された)
- 第8版学名:Ficedula narcissina (フィーケドゥラ ナルキススィーナ) 美少年ナルキッソスの (または水仙のような) イチジクをついばむ鳥
- 第7版種学名:第8版と同じ
- 第7版亜種学名:Ficedula narcissina narcissina (フィーケドゥラ ナルキススィーナ ナルキススィーナ) 美少年ナルキッソスの (または水仙のような) イチジクをついばむ鳥
- 属名:ficedula (f) < ficus イチジク edo ついばむ
- 種小名:narcissina (adj) ギリシア神話に登場する美少年ナルキッソスの、または水仙のような (Narkissos Gk; narcissus -i (m) 水仙 -inus (接尾辞) 〜に属する) (備考参照)
- 英名:Narcissus Flycatcher
- 備考:
ficedula は冒頭が長母音 (ficus フィークス イチジク) でアクセントは -ce- にある (フィーケドゥラ)。-dula にアクセントを置いたり長音にしないように。
narcissina は narcissus は短母音のみ。-ina の i は長母音でここにアクセントがある (ナルキススィーナ)。
キビタキ属の学名は日本鳥類目録第1,2版では Zanthopygia で、その後 Muscicapa とされ、第5版から現在の Ficedula となったとのこと [茂田 (1991)。#マミジロキビタキの備考参照]。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版ではリュウキュウキビタキは亜種扱い owstoni (英国博物学者、採集家の Alan Owston 由来。英名 Ryukyu Flycatcher)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で独立種リュウキュウキビタキ Ficedula owstoni となった。
キムネビタキ Ficedula elisae (ドイツの博物学者 Elise Johanna Marie Weigold nee Anders が由来。中国を旅行し、妻は採集家 Hugo Weigold。英名 Green-backed Flycatcher) は日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種で、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
西村 (2014) Birder 28(11): 31 に 2014年5月18日に舳倉島でのキムネビタキと考えられる個体の紹介があり、この記事では国内の野外初記録とある。
リュウキュウキビタキに亜種を認める立場ものある。owstoni (宮古島-西表島)、jakuschima (ヤクシマキビタキ: 屋久島-トカラ列島)、shonis (日本の鳥類学者 Kei Sho 由来。アマミキビタキ: 奄美大島-沖縄)となるが、60年前ほどに統合されたが HBW では亜種の扱い
[高木他 (2017) Birder 31(7): 12]。HBW/BirdLife 2022でも同様の扱い。IOC 等は亜種を認めていない。
Zhao et al. (2023) の分子系統樹 (#ヨーロッパコマドリの備考参照) を検討しておくと、Ficedula 属は主に3系統に分けて考えるとよさそう。日本産か関連の深い種のみ取り上げた:
・(その 1): キビタキ、マミジロキビタキ、リュウキュウキビタキ、キムネビタキ
・(その 2): ムギマキ
・(その 3): オジロビタキ、ニシオジロビタキ
だいたい系統分岐順のグループとしてある。東南アジアを出発して次第にヨーロッパに分布を広げた様子がわかる。
(その 1) の中での分岐順序はマミジロキビタキ、キムネビタキ、キビタキ、リュウキュウキビタキ となっており、大陸でキビタキ類似種がまず生まれて日本列島にも分布を広げて種分化したことがわかる。
このグループではマミジロキビタキが一番早く分岐した種にあたる。Ficedula 属の中でもこの部分は系統樹サポート率 100% で系統樹確定と考えてよい。
キビタキとムギマキは似ているのに別系統というのも面白い。(その 2) にはそれなりの数の種が含まれている。
(その 3) は2系統に分かれ、オジロビタキ、ニシオジロビタキ は古い方の枝に属する。この2種の間ではニシオジロビタキが祖先型でオジロビタキが東に分布を広げてシベリア全体に定着したもの。
(その 3) の新しい方の系統が面白く、東南アジアの特に島嶼部に戻って再度適応放散したものと考えられる。キビタキ属の名称から想像する姿と相当異なる。
(その 2) のグループの中にもずいぶん印象の異なるものがある。日本で観察をしていると (その 1) が中心となるが、Ficedula 属全体では相当多様なものが含まれていて、ムギマキがその一端を多少見せてくれている感じ。ただしムギマキは北方で繁殖するために熱帯種ほど色鮮やかでない。近縁のグループの中でオオルリだけが長距離を渡って我々のところにやってくるようになった状況と似ている。
オオルリ (Cyanoptila cyanomelana) キビタキ (Ficedula narcissina) 識別マニュアル (環境省 2009) にキビタキの主に性と齢の識別、リュウキュウキビタキ、キムネビタキについての情報がある (当時はキムネビタキが別種、リュウキュウキビタキが亜種と扱われていた)。
精度の高い分子系統樹が得られているのでキビタキとリュウキュウキビタキはどの程度違うのか確認しておくと、Ficedula 属の中では相当近い関係にある。
ただしマユヒタキ Ficedula superciliaris Ultramarine Flycatcher (青いキビタキ!) とハジロマユヒタキ Ficedula westermanni Little Pied Flycatcher の関係はもっと近く、遺伝的な違いをもとにすればキビタキとリュウキュウキビタキを分けるのは妥当となる。この系統では色彩は系統を判定する上で必ずしも役に立たないよう。
キビタキとリュウキュウキビタキの関係はよく話題になるオジロビタキとニシオジロビタキの関係よりはずっと近い。キムネビタキは {キビタキ + リュウキュウキビタキ} からは少し離れていて、マミジロキビタキはさらに少し離れることになる。マミジロキビタキとキムネビタキの分岐年代は接近していて、マミジロキビタキを別種とするならばキムネビタキも別種とすることが妥当となる。
(その 1): キビタキ、マミジロキビタキ、リュウキュウキビタキ、キムネビタキ は Ficedula 属から別属にしても構わない程度である。
属分割が好きな Boyd が分割していないのは不思議に思える程度だが、用いている系統樹がまだ古いものだったためだった (キビタキの次にムギマキが現れる)。新しい系統樹を見れば考え直すかも知れない。
もし分割するならば日本鳥類目録第1,2版のように Zanthopygia 属が復活する可能性もある。
西村 (2014) Birder 28(11): 31 に 2014 年5月に石川県舳倉島で記録されたキムネビタキの紹介記事がある。オジロビタキのように頻繁に尾を上げていた点でキビタキと異なる印象を受けたとのこと。
いずれも Ficedula 属なので習性の違いは何を反映しているものなのだろうか。系統的にはキムネビタキとオジロビタキは特に近いわけではない。
キビタキの秋の渡りは大変遅くまで続く。ロシアでも Nazarenko が1959年11月21日に最終記録を残している。繁殖地であっても秋のある時期 (かなり遅くまで) にキビタキの声が急に活発になることがあるが、この現象は都市公園での渡り記録とよく相関しており、繁殖地を渡りのキビタキが通過することで争いが生じているものと想像できる。
この点は春の渡りも同じで、争い行動などに出会いたければ春の渡りの予想される日に繁殖地を訪れればよい。
オオルリがキビタキのさえずりを非常に頻繁に取り込むことはよく知られているが、逆の例は少なくとも自分は経験がない。キビタキが他種の声を取り込まないわけではなく、大阪城公園でヒヨドリの声を真似るキビタキがビデオ記録されている (2022)。
上田 (2008) Birder 22(6): 11 にクマゲラの声を取り入れたと思われるキビタキが紹介されている。
キビタキのさえずりはしばしばツクツクボウシの模倣とも言われるが真偽の程は知らない。
キビタキがウグイスの谷渡りを模倣した可能性のある録音 (XC820953) が報告されている。
キビタキの地鳴き (ヒッヒッ...) はルリビタキやジョウビタキとの区別が話題になるが、キビタキ類全般にルリビタキやジョウビタキよりずっと周波数が低く、聞き慣れると間違える声ではない。むしろ混同されやすいのはセンダイムシクイの警戒時の地鳴きであろう (キビタキでなくセンダイムシクイと聞き分けるにはそれなりの経験が必要である)。クリリ...の声はキビタキ類全般に聞かれるが、この声での種類判別は難しいと考えている。
Muscicapa 属での対応する声はより高い。オジロビタキ類でも類似の声が聞かれるが、こちらはむしろ類似種の間の識別点になる。キビタキで他に高い連続音が聞かれ、この声を聞く時は争っていることが多い。
キビタキの巣立ちびなの声はキバシリの地鳴きによく似ているので注意を要する (いずれも高い声である)。キバシリの地鳴きの方が「震える」ような音声であり、キビタキの巣立ちびなはもっと単調な声である。録音してソノグラムで見ても違いがわかりやすい。
[キビタキ船長]
今ではあまり知られなくなっているかも知れない「キビタキ船長」の逸話がある。
例えば キビタキ船長 (日本野鳥の会京都支部の解説 2012) をご参照いただきたい。
この中で触れられている岩本久則「寄鳥見鳥(よりどりみどり)」(小学館ライブラリー 1994) を見ていて思い出した。
この本は著者の自然保護への思い、日本野鳥の会が果たしたこと・果たせなかったことなども読み取れ、(「野鳥」誌の何周年特集号など以上に) 当時の雰囲気が残る貴重な資料と思う。
[narcissina の語源について]
大橋 (2024) Birder 38(5): 50-51 にキビタキの種小名に使われる narcissina の考察があるので調べてみた。Gobe-mouche Narcisse に原記載がある (Gobe-mouche の意味については #ムギマキの備考参照)。
学名由来については特に記載はないが、フランス名と同じなのでフランス語から意味を取ればよいということだろう。
辞書によると Narcisse (1) ギリシャ神話のナルシス、(2) narcisse 水仙、(3) Narcisse 自分の姿に見とれる男、美男子。とある。冒頭にオスを指して Un beau ... (美しい) とあるので、この記載を素直に読めば「美男子」と連想されることだろう。
日本語で Kibitaki であることも触れられている。現在の鳥の学名で narcissina の種小名を持つものはキビタキのみ。wikipedia 英語版で英名は黄色のスイセンに由来すると説明がある。英語ではフランス語の (3) に相当する意味が辞書にあまり現れないのでスイセンを第一義に解釈された可能性がある。
フランス語の (3) は Narcisse の語義2に対応する。
1363 年 narciz ynde の用例はおそらく黄色を意味する
(ラテン語 Narcissus Yndus からの翻訳。1335 年の用例で Narcissus Albus のラテン語が登場する。これは白いスイセンを指し、narciz ynde は黄色い変種の意味か)。1538 年に植物学の用例がある。
1648 年に美男子が登場、1668 年に自分を愛するもの (自己陶酔者)、と現代に近い意味が出てきている。美男子の方が先に現れて、それを拡張して自己陶酔者の意味が生まれたのだろうか。
語義1のスイセンを指す方がむしろ新しく (語源は語義2と同じ)、Temminck (1836) 時代ではむしろまだあまり使われていなかった可能性がある。語義2の解釈の方が適切な気がする。
スイセンを意味する Narcissus の wikipedia フランス語版を見ると属名が見出しとなっている。名称の由来はこの属の麻薬 (narcotic) 的特性からと思われるとある。
薬用効果があり、1763-1757 年ごろの医学記載がある。フランスの植物学者 Dufresnoy が 1799 年てんかんなどの治療への応用を紹介していた。Narcisse des pres (学名 Narcissus pseudonarcissus) の名称で使われていた (Narcisse des pres: origine, bienfaits, posologie。
この一般名は Narcisse jaune (黄色いスイセン)、jonquille des bois (jonquille は黄色スイセンの一般名。森の黄色スイセンの意味)、fleur de coucou (カッコウの花!) などがある。
おそらくフランスではスイセンはいろいろに呼ばれていて、Narcissus は学名由来の学術語の扱いらしい。カッコウの花はいかにも一般名らしいが、同じ名前の花は他にもあるようで (Coucou (plante) 春を告げる象徴のカッコウのやってくる時期の花の扱いらしい感じがする。単に coucou でもこれらの花を指すらしい。
Narcisse jaune の名称が存在することから、Narcisse だけでは「スイセンのような黄色」の意味にはならなかったのではと想像する。
他言語でのキビタキの名称をチェックしておくと、Narcissus の意味の通じる言語圏ではその意味で持ちているものが多く、スラブ言語の一部や中国では色 (背または眉が黄色) をもとにした名称となっている。ヨーロッパには分布しないので学名や英名からの翻訳だろう。
[キビタキは地上に降りない?]
キビタキは日本の土を踏まずに帰ってしまう、などの解説を見たことがあり、少し観察すればそんなことはないことはすぐわかる。
出典がわかってしまった: 週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 73 V 「繁殖期のキビタキ」(江崎良彦) に「キビタキは...数か月間も長期滞在するにもかかわらず、かれらがはたして日本の土を踏んでいるのかどうかは、はなはだ疑問である。それほどかれらは地上に降りることが少ない」と記述されていた。
この記述をもとに表現が短縮されて伝えられていった結果 (突然変異による変化にたとえればストップコドンのようなもの)、後半が失われてしまってキビタキは地上に降りない説が少なくとも一時期浸透したのだろう。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) p. 229 では「決して地上では採餌しません。水浴びの時以外は日本の土を踏まない鳥です」とあった。
「原色日本野鳥生態図鑑」(中村登流・中村雅彦 保育社 1995) p. 72 に地上でつつき合う激しい行動をする (江崎 1970) とあった。まったくその通りで、この著者ならば文献を引くまでもなく記述できたのではないだろうか。
-
ムギマキ
- 学名:Ficedula mugimaki (フィーケドゥラ ムギマキ) ムギマキという名前のイチジクをついばむ鳥
- 属名:ficedula (f) < ficus イチジク edo ついばむ
- 種小名:mugimaki (外) ムギマキ
- 英名:Mugimaki Flycatcher
- 備考:
ficedula は#キビタキ参照。
mugimaki は規則通りであれば "ムギマキ" のアクセントとなり、日本語と対応がよい。英語圏の話者は違う発音をするかも。
シベリアで広範囲に、沿海地方など極東ロシア、中国東北部、サハリンに分布する。ロシア語名 taezhnaya mukholovka (「タイガのヒタキ」の意味 < mukha はえ lovka 捕まえるもの。英語で同名に対応する鳥はオジロビタキ) はこの種の分布をよく表している。ロシア語名でも「ムギマキ」とも呼ばれる。
原記載は Muscicapa Mugimaki Temminck, 1836 で Gobe-mouche Mugimaki に見ることができる。Mugimaki は和名として紹介されている。
Fauna Japonica には和名が紹介されていない記述がある [大橋 (2019) Birder 33(12): 32-33]。原記載では On le trouve, comme le precedent, au Japon, ou il porte le nom indique en tete de cet article と記述されていて前の種 (キビタキ) と同様に日本で見つかり、そこでこの文章の冒頭に記した名前 (Gobe-mouche Mugimaki) が冠されている、と名称は和名由来であることが紹介されている。
この前のページでキビタキが記載されており、和名の Kibitaki も紹介されている。
フランス語 gobe-mouche(s) はヒタキのこと (gober うのみにする mouche ハエ) 現代では Commission internationale des noms francais des oiseaux (国際鳥類フランス語名委員会? CINFO) が Gobemouche の表記を採用している。フランス語でこの名前の付く鳥は世界で 123 種ある (wikipedia フランス語版)。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire によれば Siebold の標本は1個体のみだったとのことでよく和名を用いることができたのものと関心する。Seebohm は他の標本もあるが少ないため日本では迷鳥と考えていた。1890 年時点では大陸の繁殖地の方がむしろ知られていた。
雌雄ともの外側尾羽基部に白斑があるのは日本のヒタキ類ではこの種が唯一とのこと。
Fauna Japonica の 図版。
和名の由来は秋の麦まきの時期に日本に渡ってくるためとよく言われているが、そもそもこの鳥にそのような和名があったのだろうか若干気になってきた。
柚木 (1989) 漢字百話 鳥の部 鳥・とり事典 (大修館書店) p. 51 によれば福岡県でミヤマガラスが "麦蒔き烏" と呼ばれる (秋の麦まきの季節に渡ってくる)、茨城県ではキセキレイを "麦蒔き鳥" と呼ぶ事例が紹介されている。
ムギマキに対応する和名は「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710) で小つばめ/島むしくひ (?) 「百千鳥」(1799) で小燕の名称に同定されており、小つばめはその後も Ogawa (1908) でも名称に含まれていた。少なくとも 18 世紀には麦蒔の名称は普通に使われていなかったらしい。
ここからは想像に過ぎないが、コマドリとアカヒゲの和名取り違えなど他にも間違いがいくつもある Temminck に正しい名前が伝えられていたのたか多少の疑問も生じてくる。別の鳥に使われていた名前が Siebold や Temminck に誤って伝えられた、あるいは珍しい鳥なので名前を聞かれた人に馴染みがなかったなどの状況があってもよさそうに思える。
Fauna Japonica には和名が紹介されていないが、キビタキの方も紹介されていないので Siebold がこの時点でムギマキの名称由来を述べなかった理由までは想像できない。#ヒレンジャク の事例にあるように Siebold のメモが不鮮明で和名がこの鳥を指す表記を見送った可能性や、学名は発表された後で変えることができないのでもし間違っていたとしても言及しなかった可能性もあるかも。
このような考察を行ったのは小さな目立たない鳥でいつも見られるわけではないので、例えば農作業の目安にならないのではと思えるためである。地方名であったのかも知れないが当時の日本でムギマキの名前が使われていた独立した証拠はあるのだろうか。もしないならば和名は記載 (学名) から逆輸入と解釈できる可能性も考えられるかも。
[ムギマキの学名成立経緯は複雑]
ムギマキの学名成立経緯そのものも単純ではなかった。
ムギマキの学名は現在このようになっているが、Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Muscicapa luteola でこれは Pallas の付けた学名で、Motacilla luteola として 1811 年に記載したもの。
Pallas の方が早いので (旧 Siphia 属や Muscicapa 属に移動後) Muscicapa luteola の学名が使われていた模様。
しかし Pallas は Chryso-bronchites albicilla montanus Tungusicus, vel Chryso-phaeo-bronchites albicilla との記載で後にオジロビタキ (ニシでない方) と同定され、学名から mugimaki の名が消える事態は回避されることとなった (The Key to Scientific Names の luteola の項目から)。同定を間違った経験のある者には実に納得できる (笑)。
Hartert (1910-1922) では p. 487, p. 492 で、Pallas の luteola は mugimaki より先取権があることはないと記している。
Pallas の記載したツングースカでオジロビタキとニシオジロビタキ (当時は亜種の関係) のいずれが繁殖するかは確証がないが、ムギマキでないことは確かとの意味合い。Pallas の luteola がオジロビタキとニシオジロビタキのいずれであってもそれぞれの初記載より遅いのでシノニムとなって表面に現れずいずれに同定されても問題が発生しない。ムギマキと判定された場合のみ先取権が発生する。
なお面白いことに Ogawa (1908) にはオジロビタキは含まれていない。マミジロキビタキも含まれておらず当時はヒタキ類はやや手薄だったのかも。Ogawa (1908) にはムギマキの別名コツバメも載せられている。
一方で中国のチェックリスト (2022) にはニシオジロビタキのシノニムとして現れる (Motacilla luteola Pallas, 1811) とのこと (オジロビタキとニシオジロビタキを同種としているだけかも知れない)。
オジロビタキの学名 Muscicapa Albicilla Pallas, 1811 (原記載) も Pallas が与えている (luteola よりも前のページに現れるためこちらに先取権がある) ので Pallas はオジロビタキのオス・メスを別の種と考えたのだろうか。後世の研究者も Pallas がオジロビタキをすでに記載しているので一時はムギマキと同定したのかも。
ムギマキのメス (または若鳥) は確かに紛らわしく、Muscicapa rufigula (赤みを帯びたのどの意味) の学名が与えられていたことがあった。参考: Muscicapa rufigula。参考。
Hartert (1910-1922) によればこの学名は記述がないので無効となっているが、1835 年のものなので Muscicapa Mugimaki Temminck, 1836 と先取権を争う可能性があった。
さらに Mueller (1835) では学名の記載者を "Kuhl, M. S." としており、当時すでに命名された学名を用いたために自身は記述を行わなかった可能性がある。"Kuhl, M. S." に相当する文献が後年見当たらなかったので Muscicapa Mugimaki Temminck, 1836 がもっとも早い名前と認定されたものと想像できる。
Mueller (1835) の学名は一定用いられた形跡があり、参考 (Sharpe 1879)。Muscicapa Mugimaki の先取権が認定されるまではあるはこちらの学名がポピュラーだったのかも。
[音声]
一度覚えれば大変印象的な次第に早くなって終わるさえずりは、タイガ林の背景音としてもふさわしく感じる (現地で聞いたわけではないのであくまで想像上だが)。春の渡りの時期はゴールデンウイーク半ばぐらいからその後ぐらいででやや遅い。
さえずりを知っていると春にもそこそこ通っていることがわかるが、すでに葉の茂った時期でありキビタキに比べて樹冠内に入ってしまう傾向が強く、鳴いているのに姿が見つけられないことが多い (大阪城公園の超ベテランでも春のムギマキは声はよく聞こえるのに見つけられないと言われていた)。
どの木で鳴いているかはわかるので、葉の隙間を通して執念でオレンジ色を見つけられた方もあったが、しっかり見た気がしないとのことだった。姿がよく見られるのはさえずっている時ではなく、むしろ地鳴きを頼りに探すとよい。キビタキとほぼ同じ地鳴きなのでキビタキの地鳴きに慣れていれば見つけやすい。
都市公園ではムギマキの通過するころはキビタキの渡りも一段落していることも多く、ある区画で鳴いているのがムギマキ1羽のみの状況もある。このような場合は「キビタキの地鳴き」を聞けばそこを探すと突出した枝にとまって鳴いているムギマキが比較的簡単に見つけられる。
その後さえずる時に葉っぱの中に埋もれてしまうのが常で、さえずりを始めてから探しに来た人がいつまで経っても見つけられない原因にもなる。春に探す時の参考になれば幸いである。
春の渡りで上記よりずっと早い時期に記録することがある。2012年4月15日にキビタキがまだ少数渡ってきたばかりの時期に成鳥オスのムギマキを記録したことがある。この個体は約 10 日にわたって滞在し、キビタキとの争いも認められた。
あるいはここに滞在してキビタキとの繁殖も考えられるかと期待したが、4月24日に一度場所を移動した後に翌日は出会わなかった。ムギマキは越冬例も知られているため、あるいは近傍で越冬していたものかも知れない。
The song of birds (ウスリー地方のタイガの鳥の声) にも登場するので紹介しておく。5:33 V vetvyakh poyut mukholovki mugimaki (小枝ではムギマキがさえずっています。ここでは複数形) Vnizu sredi valezhnika predel'no vysokim golosom zayavlyaet o sebe korotkokhvostka (下では落ちた枝の中で極限の高い声でヤブサメが自らを主張しています)。
ロシア語でも "ムギマキ" と呼ばれているのを聞き取っていただけるだろう。
他の珍しい種類のことも知りたいリクエスト (ないかも?) に応えて 3:48 ハシブトガラス、シロハラホオジロ、カラフトムジセッカ。ハシブトガラスがこれほど小さな声でしか入っていないのは森林で聞かれるとしても遠いのだろうか。カラフトムジセッカはこのセクションの最後の方に登場 (4:25)。コルリに似た部分が少し聞かれる。
4:32 V Ussurijskoj tajge net ptitsy bolee shchedroj na golos, chem krokhotnaya korol'kovaya penochka (ウスリーのタイガでカラフトムシクイよりも声が豪勢な鳥はいません)。Ee pesenka zvuchit ves' den'-den'skoj (歌は一日中ずっと響いています)。
7:33 Zdes' v lesnoj pojme obitaet neskol'ko vidov solov'ev (ここ森林の水辺の草地には何種類かのノゴマ類が住んでいます)。Vot rassypal svoyu pesnyu solovej-svistun (ほらシマゴマが自分の歌を振りまきました)。
08:02 コルリとカラアカハラ。今ならば自動字幕でかなり判読できるが、スクリプトはかつて YouTube 以前時代の音声からネイテイブ・スピーカーの方にお願いして起こしたもの。
ムギマキは春の渡りではウグイスの谷渡りのような音声を延々繰り返すことがある。ほとんどの場合「謎の声」として片付けられているかも知れない。さえずりの一種と思われ、キビタキの「ツクツクボウシのような繰り返し」に相当する声ではないかと考えているが証拠があるわけではない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) にも記載があり、もう一種類の面白い声の記録がある (著者自身は聞いていない模様)。警戒時に出し (とあるが自分の観察では多分そうではない)、
電話で数字を並べる時のような音楽的な音で ti-ri-li-ti-li と表現している。
自身が観察・記録したムギマキのかなりの割合がキビタキの節を取り込んでいた。これは春に日本を通過する個体にキビタキと同所的に繁殖しているものが多く含まれているためと考えられる (渡り途中で覚えた声の可能性もあるが)。両種の共通分布からサハリンが考えられ、これは地理的に自然な渡りルートと思える。逆に言えば大陸で繁殖するムギマキは春は日本内陸部をそれほど通っていないのかも知れない。
地鳴きではこれもまたキビタキと区別できなかった。ただし越冬地でキビタキ(ヒッヒッ...) より低く太い声で鳴いているのが記録されており、地鳴きだけでムギマキと判定できる声(または個体)があるのかも知れない。
秋の渡りはご存じの通りキビタキよりだいぶ遅く、秋風も深まったころが中心。マミジロキビタキも同じような時期を想定しているとすでに渡りが終わった時期になっているかも知れない。
魅力的なムギマキなのだが春の渡りであまり話題にならず、もっぱら秋の鳥と思われている理由に多少思い当たるところがあった。春のムギマキの渡りはサンコウチョウの初認時期に近いので写真を撮りたい人はみなそちらを目的にしてしまう (サンコウチョウは後の季節の方が増えるので春にムギマキに遭遇する方が限られたチャンスと思うが...ムギマキの写真を撮るのは難しいからかも)。
秋のムギマキは比較的孤立した時期なので話題になりやすい、など。
サンコウチョウとムギマキがいるならムギマキを優先するのは通好みでよいのでは? 春のムギマキ観察の参考にしていただければと思う。
[Ficedula 属の話題]
ムギマキに近いグループの Ficedula 属に学名がやや悩ましい種類がある。
セアオビタキ Ficedula erithacus Slaty-backed Flycatcher だが、リストによって学名が違う: Ficedula hodgsonii (これはやや古い)、Ficedula sordida
がある。Boyd の解説によれば Siphia erythaca Blyth, 1847 と記載され現在はムギマキのシノニムとなっているものと衝突しているとのこと。
Ficedula sordida にはそのような問題はないとの見解である。
Zuccon (2011) The valid name of Slaty-backed Flycatcher
の議論を受けたものであろう (どの綴りを同一とみなすかなど詳しい規則があるらしい)。
分布的にはまったく無縁の種類ではないかも知れない。
日本で普通に見られる Ficedula 属だけを見ていると黄色系か灰色のものを想像してしまうが、熱帯には青い Ficedula 属がいくつも存在する。
コビトアオヒタキ Ficedula hodgsoni Pygmy Blue-Flycatcher / Pymgy Flycatcher: 参考 Pygmy Flycatcher (Ayuwat 2023)。
カオグロヒタキ Ficedula tricolor Slaty-blue Flycatcher など。
#ヨーロッパコマドリ備考のヒタキ科の新分類で、
Clade D: Saxicolinae (ノビタキ亜科?): Luscina 属 (オガワコマドリ属)、Calliope 属 (ノゴマ属)、Larvivora 属 (コルリ属)、Ficedula 属 (キビタキ属)、Tarsiger 属 (ルリビタキ属)、...
のようにコルリ、キビタキ、ルリビタキが同じグループに入って並ぶ理由が直感的にわかりにくいがこれらの種を見ていただくと類縁関係がはっきりする。骨格などの形態学を重視した従来の分類ではスズメ目は似すぎていて分類が困難で、ツグミ亜科とヒタキ亜科に分かれて類縁関連が見えなかったが分子系統解析が使えるようになってようやく判明した次第。
熱帯の留鳥に青い種類が多いことについては #オオルリ備考の [オオルリはなぜ青い] 参照。他にはコルリ以外が日本に渡ってこないために類縁性が直感的に感じにくいのだろう。
-
オジロビタキ
- 学名:Ficedula albicilla (フィーケドゥラ アルビキルラ) 白い尾のイチジクをついばむ鳥
- 属名:ficedula (f) < ficus イチジク edo ついばむ
- 種小名:albicilla (合) 白い尾の (alba (adj) 白い cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい)
- 英名:IOC: Taiga Flycatcher。Red-throated Flycatcher の別名はあるがあまり使われない。詳細は第8版で掲載の#ニシオジロビタキの備考参照。
- 備考:
ficedula は#キビタキ参照。
albicilla はすべて短母音で -cil- にアクセントがある (アルビキルラ)。
和名はおそらく種小名由来か。ニシオジロビタキと同種時代は種小名が parva となるため関係がわかりにくかったが、記載時は別種とされており別種時代に和名が付けられたと考えると理解しやすい。
記載時学名 Muscicapa Albicilla Pallas, 1811 (原記載)。
ほぼ同様の形である Ficedula albicollis ヨーロッパでごく普通種の Collared Flycatcher の和名はシロエリヒタキとなっており、同様に学名が訳されたものではないだろうか (英名以上に学名に忠実になっている)。
主な繁殖地であるロシアではやはりヨーロッパで普通種のニシオジロビタキの方が優先されて命名されており (同種時代はこちらが基亜種)、学名由来の "オジロビタキ" に相当する名前にはなっていない。"東のニシオジロビタキ" のような名前になっている。英語や中国語名にも学名に由来する名称は現れないよう。
学名も "白い尾の" というより "尾に白い部分がある" ぐらいに解釈するのが適切だろう。尾に白い部分があるヒタキは他にもあるので英名などでは採用されなかったのだろう。
Red-throated Flycatcher の別名は納得できる英名に思えるが、Muscicapa rufigula (赤みを帯びたのどの意味)
参考: Muscicapa rufigula (#ムギマキの備考参照) を訳したものの可能性もあり、当時はオジロビタキとムギマキのメス (または若鳥) が混同されていた背景もあって紛らわしいので使われなくなったものかも知れない。
現在では同じ意味の学名が セレベスヒタキ Ficedula rufigula Rufous-throated Flycatcher に与えられている。こちらは記載時学名が Cyornis rufigula Wallace, 1865 と別属で、
Muscicapa rufigula が Ficedula 属に変更される前に Muscicapa Albicilla Pallas, 1811 と同一で後者に先取権があることが早々に判明した (1878) ために Ficedula 属で衝突してすでに使用された学名 (preoccupied) となることを免れたのだろう。
英名は Red-throated でなく Rufous-throated と訳すことで同一となることを避けた模様。このような紛らわしい種類や学名が存在するために Red-throated Flycatcher の英名はあまり積極的に使われなくなったものではないかと想像する。
Hung and Zink (2014) Distinguishing the effects of selection from demographic history in the genetic variation of two sister passerines based on mitochondrial-nuclear comparison
に両種の核遺伝子とミトコンドリア DNA の研究があり、オジロビタキはシベリアに非常に広範な分布を示すにもかかわらずミトコンドリア DNA の多様性が非常に低い。オジロビタキがニシオジロビタキから分化する際に個体数が非常に少ない状態を体験したのだろうとのこと。
遺伝的にどのぐらい違うのかは公開配列から試してみればよいので、よく使われる cyt b では KJ930547.1 から BLAST を試してみると確かにオジロビタキとニシオジロビタキは別の系統を作る。この解析ではオジロビタキとカシミールオジロビタキ Ficedula subrubra Kashmir Flycatcher と系統を作る結果になる。
カシミールオジロビタキのオスは上面はルリビタキのような色彩で、系統樹精度は高くないのでどの系統が祖先型かまではわからないが、オジロビタキのグループでも低緯度には近縁の青い種類が存在することがわかる。記載時は Muscicapa parva subrubra Hartert & Steinbacher, 1934 とニシオジロビタキの亜種となっていた (色彩がこれほど異なるのに Hartert は本質を見抜いていた!)。
もしオジロビタキとニシオジロビタキを同種とするならばこの種も同種とする必要がある上、オジロビタキとニシオジロビタキの分岐が Ficedula 属の中でも深いので早々に別種扱いとなったのだろう。
なおオジロビタキは B10K で全ゲノムが解読され 2024 年末に公開されている。
カシミールオジロビタキのデータはまだ限られているので ND2 遺伝子を使って試してみると同様にオジロビタキとカシミールオジロビタキが系統を作る結果となった。Hung and Zink (2014) ではオジロビタキがニシオジロビタキから分化とあるが実はもう少し複雑なのかも知れない。
もしカシミールオジロビタキの方が祖先型に近い (近縁のさらに祖先系統があったが現在では消滅して系統樹に現れないなど) ならば、ニシオジロビタキがヨーロッパからわざわざインドなど南・東アジアに越冬に来る理由が納得できるような気がする。たとえば越冬地を考慮するとニシオジロビタキ・オジロビタキの発祥の地はインドやインドシナ半島などなど。
そして北方に分布を広げる際に熱帯地方で持っていた色彩を失ってのどの赤みを特徴としたならば、コンヒタキとノゴマの関係に対応するかも知れない (#ノゴマの備考参照)。
オジロビタキはサハリンでも繁殖する: Taiga Flycatcher (Shokhrin 2021)。
-
オオルリ
- 学名:Cyanoptila cyanomelana (キューアノプティラ キューアノメラナ) 青と黒色で暗青色の羽の鳥
- 属名:cyanoptila (合) 暗青色の羽 (kyanos 暗青色の ptilo 羽毛 Gk)
- 種小名:cyanomelana (合) 暗青色と黒の (kyanos 暗青色の melas 黒い Gk)
- 英名:Blue-and-white Flycatcher
- 備考:
cyanoptila はギリシャ語からの合成語で発音は明確でないが、ラテン語に現れる cyan- の単語は冒頭が長母音で、ptilo は短母音のみのため冒頭のみ長母音と考えられる (キューアノプティラ)。
cyanomelana も同様で冒頭のみ長母音と考えられる (キューアノメラナ)。
和名は遥かに単純明快だが、学名・英名は色彩のみで面白みが欠ける感じがする。
記載時学名 Muscicapa cyanomelana Temminck, 1829 基産地日本 (記載)。フランス語名 gobe-mouche bleu-noiret。
この学名が無効になりかねない酷似した学名がすでに用いられていた: Muscicapa cyanomelas Vieillot, 1818 (参考)。
Temminck (& Schlegel) が日本の鳥を記載する際に現地名をかなり用いているのは、潜在的にすでに使われている学名と衝突を避けるためだったのかも知れない (とするとわざわざ和名を用いた理由として面白みに欠けるかも知れない。トキの Ibis nippon も同じような予防的理由だったならばロマンに欠ける?)。
#サンコウチョウでは学名に適切な現地名がなかったのか独自名を付けた結果すでに用いられており見事に無効になった。
オオルリの現地名を使いにくかったのは、当時は "るり"、"るりちょう" がオオルリ、コルリを指して共通に用いられており [cf. 「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990); 「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 134 表 5) の「喚呼鳥」の挿絵など] 特定の種を指すのに向かなかった、あるいは発音が学名向きでなかったためかも知れない。
#ムギマキは学名としても読みやすいなどの理由で選ばれたのかも (こちらの学名も実は危なかった)。
Fauna Japonica にはまた違った学名が使われていた。図版 1 解説
Muscicapa gularis Temminck, 1822 ("のどに特徴のある" の意味。参考 と思われるがこちらは Brazil になっている。間違えて再度使ったものか) = オオルリのメス。
Muscicapa gularis Stephens, 1817 (参考) の用例はすでにあったのでいずれにしても無効。
図版 2 = オオルリのオス ("青と黒" の意味)。しかし 解説 では自身の 1829 年の学名を用いている。
Muscicapa melanoleuca Guldenstaedt, 1775 (参考) や Muscicapa melanoleuca Forster, 1817 (参考) の用例が先にあってこれも無効。
1829 年に自身が学名を付けたのになぜ? とも思えるが、名前を付けたものの正体がよくわかっていなかった?
Temminck (& Schlegel) はオオルリはオス・メスが別の種類と考え、図も含めると3つの異なる学名を使ったことになる。現在使われている1つを除いていずれも過去に使用された名称のためシノニムとしても残らなかった。オスの学名は用例が先にあることを知って付け直したものだろうが、間違いらしいものが多くて今ひとつありがたみが薄い感じがしてきた...。
"Fauna Japonica" の ヒタキ類 の部分を見ると事情が多少わかる気もする。日本には複数の種類のヒタキ類が記録されているので地名を冠する学名はつけにくかったよう (#タンチョウ備考の Temminck の学名についての提案参照)。
いずれもヨーロッパの種類と似ていないので、馴染みのヨーロッパの種の日本版の表現も使えなかった模様で、色彩か現地名を使う選択となったらしい。
Muscicapa bella Hay, 1845 (参考) があり、香港で記載されたものだった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" にもこの学名が載せられている。Temminck (1829) の学名が有効となって Hay の学名はシノニムとなったが "美しいヒタキ" の意味。
cyanoptila とほとんど同じような意味の種小名を持つアカシマアジ Spatula cyanoptera Cinnamon Teal が存在する。ptilo も pteron (翼) も似たもので学名からはオオルリのような青い鳥を想像できるが色彩はまったく違っている。
-ptera/-pterus の語尾の場合には全体の色彩より翼のパッチなど小さな領域を表すことが多いよう。#ナキイスカの学名参照。
ウスズミモリツバメ Artamus cyanopterus Dusky Woodswallow に至っては青さがあまり感じられず、青灰色のぼんやりした色を指している感じがする。cyano- の指す色の範囲は相当広いよう。
[分類の問題]
従来は単形属の非常にわかりやすい鳥であったが (オオルリのメスと他のヒタキとの識別はともかく)、分類学の進展により複雑になってしまった。
まず大陸のカラオオルリ Cyanoptila cumatilis [cumatilis 海の色の、青い (L) < kuma, kumatos 波 (Gk)] 英名 Zappey's flycatcher (中国で標本を収集した W. R. Zappey に由来) が分離されたことで、これまで亜種レベルであった識別が種レベルになったしまったことが挙げられる。
Leader and Carey (2012) Cyanoptila cumatilis, a forgotten Chinese breeding endemic を参照。
この文献中ではオオルリはこのグループ中で「島で繁殖」のグループと称されている。音声の比較も述べられているがサンプル数も少なく、オオルリのさえずりが地域や個体で極めて多様であることを知っている我々にとってはこの判別は不十分に思える (音声面ではもっと確実な識別方法を見出す必要がありそうである)。
種の識別は大陸でも難しい問題になっていようで、例えば Blue-and-white or Zappey's Flycatcher? - Beijing, China (BirdForum 2021) にあるように野外での確実な識別点は十分わかっていないようである。DNA 解析も行っておらず、別種とする十分な根拠があるのかとの疑問の声も出ている。
Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考参照) の系統樹では分かれていて同種と言えるほどではないが系統樹サポートは弱めである。発表されている遺伝子も限られており、さらに情報が必要であろう。
問題をさらに複雑にしているのがオオルリ Cyanoptila cyanomelana の中国東北部から朝鮮半島の個体群を亜種チョウセンオオルリ intermedia としていることで、これはかつて (亜種であった時代の) cumatilis の分布域を引き継いでいる。
上記でも議論が行われている通り、各種フィールドガイドでは現在 intermedia とされる分布域の個体の特徴を Cyanoptila cumatilis として記載している可能性が十分に考えられる。
日本鳥類目録改訂第7版と日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版の間でも相違が見られ、第7版で Cyanoptila cyanomelana cumatilis チョウセンオオルリであったものを第8版の第一回パブリックコメント版で Cyanoptila cyanomelana intermedia と改名している。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ扱い。
分布域の取り扱いが変わったものを機械的に当てはめたように見えるが、これは後述のように "Zappey's flycatcher" を別種として分離するとともに、亜種包含関係が見直されたことが反映されたものだろう。
確実な初記録は茂田 (2003) 日本からの亜種チョウセンオオルリ Cyanoptila cyanomelana cumatilis の確実な初記録 に記載されているが、この文献でも「朝鮮半島に分布するのは亜種チョウセンオオルリではなく、基亜種オオルリである」と記載され、
ウラジオストク付近で記載された intermedia [当時の名前はコマオオルリ。"コマ" は古い国名の高麗の読み (こま) 由来] は基亜種オオルリ Cyanoptila cyanomelana cyanomelana のシノニムで、亜種チョウセンオオルリは中国大陸で繁殖する亜種とされていた。
この intermedia の記載時学名は Muscicapa cyanomelana intermedia Weigold, 1922。新しい記載であるため原記載の文献は BHL にはちょうど入っていない。
cumatilis の方の記載は Cyanoptila cumatilis Thayer & Bangs, 1909 (原記載 基産地 Ma-fu-ling, Hupeh, China)。
オオルリ (Cyanoptila cyanomelana) キビタキ (Ficedula narcissina) 識別マニュアル (環境省 2009) があるが、
現在の Zappey's flycatcher Cyanoptila cumatilis に相当する分布域は地図に含まれておらず、参考文献を見てもこの "Zappey's flycatcher" を検討したと思える論文は含まれていない。
当時 "Zappey's flycatcher" を別種と認める一般的なリストは存在しなかったと思え、地図と本文の間に不整合がある可能性がある [分類の参考文献の1つとなっている Dement’ev and Gladkov (1954) には現在の "Zappey's flycatcher" の分布域は当時の亜種 cumatilis として含まれている]。
なお日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版に対するコメント(分布地域の記載について)があった。深井宣男 (2021)「1字違いで大違い? 〜オオルリの亜種を深読みする〜」アルラ (62): 20-23 が文献として挙げられていた。
環境省 (2009) の識別マニュアルでは Cyanoptila cumatilis Thayer & Bangs, 1909 の基産地 Ma-fu-ling, Hupeh, China は渡り途中の記録と解釈し (1907.5.14 採集)、繁殖分布域に含めなかったものと考えられる。密猟個体と輸入個体の鑑別のためのマニュアルとして整備されたもので、分類面では現代では古い資料となってしまっているので利用する際は注意が必要であろう。
Leader and Carey (2012) の地理的サンプリングは限られており、これらの疑問には十分に答えてくれない。intermedia をどちらの種の亜種にするかも Leader and Carey (2012) も十分な根拠があるわけではなさそうである (過去の Cyanoptila cyanomelana の分布に従っているのみ)。
山階鳥類研究所の標本データベースでも YIO-38086 (朝鮮 Corea ソンパ) Cyanoptila cyanomelana cumatilis テウセンオホルリ などかつてはこの学名と和名の扱いが標準であったものと考えられる。
YIO-38089 (済州島 1926) では亜種 cyanomelana となっていた。古い時代はオオルリは1種であまり問題がなかったが、Weigold (1922) がウラジオストク付近 intermedia を記載したため複雑となった模様。
つまり3つの taxa が存在して intermedia を亜種 cyanomelana のシノニムと考えれば朝鮮半島の亜種は cyanomelana、cumatilis の方の記載が古いので、intermedia と同一 (つまり大陸と島を分離する考え) とすれば cumatilis に統合されることになる。この場合は朝鮮半島の亜種は cumatilis と呼ばれることになる。
Cyanoptila cumatilis を別種として認める場合に、従来の統合された cumatilis の分布を考えるとこの種が大陸に広がっていることになる。Cyanoptila cyanomelana に大陸 (intermedia) と島で2亜種を認めれば種オオルリが大陸にも分布していることになる。
現行ではこの分類が採用されているが Leader and Carey (2012) が分子系統まで含めた地理的境界の解析を行わなかったため多くのバーダーが困惑している次第。今後より詳しい解析が行われて互いに単系統の関係にないと判断されることになれば境界や名称なども見直されるかも知れない。
過去は cumatilis にチョウセンオオルリの名称を与えていたことがあったがこれは cumatilis と intermedia が同一とされた時代のものと思われる。
intermedia を分割して別 taxon と認めた場合の名称がかつてコマオオルリで、その後チョウセンオオルリと改名され、cumatilis に改めてカラオオルリ (日本未記録。標準的な和名と呼ぶべきかどうかまだわからない) が与えられたものと思われる。和名の変遷は、どの taxa をシノニム関係と考えるか、かつての日本統治地域で記録されたものに優先して地名を付けたなど複雑な経緯をたどったものと想像できる。
日本の識別記事を見ても cumatilis をチョウセンオオルリ として Zappey's flycatcher との比較を述べているものあったので (少なくとも現行の分類では) 注意。
高木他 (2017) Birder 31(7): p. 9 にオオルリの亜種の記事があり、近年の一般向け解説はこの記事がまず思い当たる。Leader and Carey (2012) を反映した海外分類が紹介されているが、使われている亜種和名は日本鳥類目録改訂第8版と異なるので注意。
参考までに xeno-canto の音声を聞いてみると Zappey's flycatcher Cyanoptila cumatilis のさえずりは大きく異なり、これを聞いてもオオルリと感じないかも知れない (もっとも当の鳥がどのように聞き分けているかわからないが。オオルリの音声は個体変異の幅が非常が広く、オオルリが Zappey's flycatcher の音声を認識するかも知れない)。
intermedia も確かに日本のオオルリと多少違うが、サンプルが限られていること、過去にロシアのビデオでよい音声を聞いたことがあるのでサンプルの偏りのためかも知れない。中国のハチクマ子育ての映像で聞かれたオオルリの声はもっと日本のものに似ていたように思えた。
もっとも日本でも XC103905 (Paul Leader 2011.6.10) のような記録があって、あまり典型的でないさえずりもあるらしい。この録音の冒頭のフレーズの終わりは遠方のカワラヒワか何かが重なっていないだろうか (同じような間隔で鳴いているのでたまたま重なっているのでは?)。もしそうであればオオルリのフレーズと考えて解析するとよくないかも。Leader and Carey (2012) の論文でも使われているが大丈夫だろうか。
中国の XC884483 (PT xiao 2023.6.8) も Background の種に何も挙げられていないが別の種 (コルリに似て聞こえるがあまり自信がない) と重なっているのでは?
いずれにしてもチョウセンオオルリや cumatilis の意味は以前と今後で異なるため、過去の記述を参照する場合には注意が必要である。
分類変遷は茂田 (2003) に述べられているがかなりよく読まないとわかりにくい。当時は intermedia は cumatilis のシノニムとされていたので表面上現れなかったが第8版で復活したことになる (このように見ると特に歴史的変遷を経ている場合は、亜種名を和名で表記すると大変わかりにくいことがわかる。同一文献内では整合性がとれていても、引用して再利用されると新しい文脈では間違いになることも発生する)。
なお極東ロシアでもオオルリ (現在の分類に従えば Cyanoptila cyanomelana intermedia) は極東で一番声のよい種類の鳥とされ、場所は違えども「三鳴鳥」のような位置づけは違っていないようである。
ロシア沿海地方の繁殖論文: Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the blue-and-white flycatcher Cyanoptila cyanomelana (pp. 3-37)
写真を見て日本の亜種との違いはわかる?? 生息環境は非常に似ている。3-6卵で5卵が最も多い。ジュウイチに托卵された巣の写真もあり、ジュウイチ2卵の入っている写真もある。
この論文ではハシボソガラスの亜種を独立種 Corvus orientalis として扱っている。
越冬地も両種地図には分けて示されているがよくわかっているとは言い難い。Dewi et al. (2016)
Field records of Zappey’s Flycatcher Cyanoptila cumatilis on Java and Sumatra, with notes on the distribution and status of Blue-and-white Flycatcher C. cyanomelana in Indonesia
でインドネシアでの越冬状況が示されており、識別の参考になると思われる写真も掲載されているのでご覧いただくとよいだろう (このぐらいの写真があると2種が違って見える印象も持てる。メスに関しては見慣れているオオルリのメスと印象の違いがわかるが、オスはオオルリと判定してしまいそうである...)。
なお 2011-2012 年にオス成鳥のオオルリが近畿地方で越冬した記録がある。
我々には見慣れた種類だが、フィリピンでの画像例: "Blue and White Flycatcher", immature male. (Cyanoptila cyanomelana) (Henrick Tan 2023.11) パラワン島とのこと。
カラオオルリ (ここではこの和名を用いておく) Cyanoptila cumatilis Zappey's flycatcher の遺伝子4つが 2018 年に投稿されていて多少調べることができた。Zhao et al. (2023) でも使われているが個々の遺伝子を見た方がよい。cyt b や ND2 を見るとオオルリとは相当離れているので別種扱いで問題なさそう。例えば ND2 での類似性は 93% 程度。
Hooper and Price (2017) Chromosomal inversion differences correlate with range overlap in passerine birds の副産物。
Zhang et al. (2016) Unexpected divergence and lack of divergence revealed in continental Asian Cyornis flycatchers (Aves: Muscicapidae) の外群にカラオオルリ Cyanoptila cumatilis に対応するものが使われていた (当時はまだオオルリと同種時代)。
大陸のオオルリのミトコンドリアゲノム HQ896033.1 は読まれているが島 (日本) のものは情報が少なくどの程度違うのかわかりにくい。日本のオオルリの COI (DNA バーコーディング) は読まれていてカラオオルリとの一致率は 95% 程度だった。韓国のオオルリの例があって一致率 99.84%。日本国内の個体でも同じ一致率もあって大陸と日本で大して違わないのでは?
大陸は種数が多いので種分化研究が行われやすいが日本の種多様性が高くないので研究対象とする動機 (= 研究者にとって面白い結果が期待できるかどうか) が少ないのかも知れない。
上記ミトコンドリアゲノムを用いたオオルリおよび関連種の系統解析と音声についての考察は #ロクショウヒタキの備考にて取り上げた。オオルリの属名は比較的長期間同じものが使われているが、今後の系統解析次第で変化する可能性も残っている。また音声の違いが必ずしも系統的距離を反映していない可能性も考えられる。
[原記載と属名]
オオルリの原記載は Muscicapa cyanomelana Temminck, 1829
(基産地日本)。図版は1ページ前にある。和名の言及はない。
フランス名で gobe-mouche blue-noiret とあり青黒のヒタキとまったくそのまま。日本で称賛される種類との認識はなかったようで、1ページ前におそらく現在のマレーシアヒメアオヒタキ Cyornis turcosus Malaysian Blue-Flycatcher を優雅なヒタキ gobe-mouche elegant Muscicapa elegans と記載している。
こちらの方がより優雅に見えたということだろう。
属名 Cyanoptila は Blyth (1847) がオオルリをタイプ種として与えたもの。
I found this group on a Javanese [sic そのまま。Japanese の単純な綴り間違いかも知れないが越冬地を指しているのかも。この本の所有者は Japanese と訂正しているが、同時に記載されている他の種はジャワ島のものもある] Flycatcher, which is just intermediate (both in form and colouring) to the preceding [Niltava] and
following [Stoporala] divisions, in neither of which it can be placed; and it thus illustrates the affinities of Niltava.
などの記載があり、Niltava 属とは違いがあるとして新しい属を作ったもの。ここに出てくる Stoporala はロクショウヒタキをタイプ種とした属で、現在は Eumyias のシノニムとされるもの。
この後にアオヒタキ類などに比べて翼が長い (渡り鳥なので) などの特徴の記述が出ている。
上記は The Key to Scientific Names による情報だが、ここには C. cyanomelanura (Tem.) の学名が出てくる。Blyth (上記の本の p. 125) の誤解かも知れないが、-ura (尾 Gk) の意味が加えられていた可能性がある。
英語別名に Japanese Flycatcher があるとのこと。
現在の英名は日本産種で唯一 "-and-" を含むものである。英語は単語連結を行いにくいのでこのような名称となってしまうが、複数形にすると Blue-and-white Flycatchers となるが、文字はともかく話し言葉では "青いヒタキと白いヒタキ" と区別が付かない (音は少し違うだろうと言われればおそらくその通りだが)。英語の造語機能の限界とも言えるだろう。
[オオルリの渡り経路]
Heim et al. (2022)
Light-Level Geolocation Reveals Unexpected Migration Route from Russia to the Philippines of a Blue-And-White-Flycatcher Cyanoptila cyanomelana
にロシアでジオロケータ標識をされたオオルリがフィリピンで越冬し、春の渡りでは台湾を経由して中国大陸に入り、黄海を横切って朝鮮半島を経由してロシアに戻る経路が明らかにされた。
日本のオオルリでは南西諸島でほとんど記録がないため九州から海を越えて中国大陸に渡っていると想像されているが実証された研究は知らない。
[争いの時の音声]
オオルリの音声についてあまり知られていない点も紹介しておく。オオルリ (オスの成鳥) は同じフレーズを連続で繰り返さず、一つ前とは違うフレーズでさえずる (ただし何回か後に同じフレーズがまた現れる)。ただし連続して同じフレーズを繰り返し、しかも次第に音声を弱めてゆくことがある。これは怒っている時のさえずりで大抵近くに侵入オスが来ている。
この状態でさらに待つとしばしば侵入オスの方に飛び立って争いになる。争いは簡単に済むこともあるが、2羽で追いかけ合いをすることも多い。この時に非常に複雑な声を出す。この音声を録音すればよくわかるが、10 kHz より高い声成分を不連続に出していて、高い周波数から始まって次第に音を下げてゆく特徴がある。
この音声はオオルリの争い時に特徴的で、知っているとなわばり争いを行っていることがよくわかる。鳥の可聴域は人より狭く、10 kHz 以上の音には感度が悪いと言われるが、違う個体でもこれだけ再現性よく 10 kHz より高い声成分を使っていることはおそらくその音域にも感度があることを示すものであろう。
渡来初期に複数のオスが争いあう状態が知られていて、中村登流 (1977)「野鳥ガイド: 村里へ高原へ山頂へ水辺へ」(カッパ・ホームス) ではオオルリ、コルリ、ルリビタキのるり色の背の鳥はどれもこのような集会を行うとの記載がある。季節の展開する瞬間をぜひ捉えてみていただきたい。
なわばり争いは渡来時だけでなく遅い時期にも観察され、オスが他のオスのなわばりを訪れていることがわかる (つがい外交尾のため? あぶれオス?)。さえずりでの個体識別ができればどの個体が訪れているかを判断することもできることがあるので試みていただきたい。
赤 (2006) Birder 20(7): 52-53 に飼育保護されたオオルリのダンスのポーズのスケッチがあるが、この姿勢はさえずっている途中にメスが近づいて来た時、あるいは対立するオスが現れた時にしばしば見られる (目立った姿勢変化を行わないオスもある)。興奮している状態ではないかと思う。
野鳥飼育が行われていたころはコマドリの手振り駒という飼育者に対する興奮姿勢を取らせる方法があったと聞くが同じようなものかも知れない。「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) pp. 114-115 に解説があり「百千鳥」(1799) に現れるとのこと。細川氏は手乗り鳥の起源とも関連して考察されている。
[メスが抱卵中のオスのさえずりなど繁殖行動]
徐敬善 (2016) "オオルリの繁殖生態と美しい構造色の羽" ではメスが抱卵中はオスはほとんどさえずらず非常に見つけにくくなるとの記述がある。徐 (2020) Birder 34(5): 22-23 にも同様の記述がある。
これだけを読むとオスのさえずりの役割はつがい形成のためのように感じるが、京都での観察ではまったく違っていてメスが抱卵中もオスは十分よくさえずっている。みなさんの所ではいかがだろうか。
朝一番にコーラスの時間帯にさえずってその後食事のために少し穏やかになるがまた高いところに戻ってさえずるのが一般的である。
朝一番の後にオスのさえずりが止むのが孵化のサインで両親による餌運びが始まるのにちょうど対応している。
軽井沢と京都では習性が違うのだろうか。メスが抱卵中もオスが引き続きさえずっているのはつがい形成時のオス間の競争以外の意味もあるように思える。
個体同定はさえずりだけでもかなり正確と考えている。餌運びに対応してさえずりが止むので、自身で観察した事例ではよく言われるようにつがい相手を持てないオスが必死でさえずっている状況ではない。
徐 (2018) Bird Research News オオルリ の記載と同様、繁殖成功率は高いと考えている。
小鳥の繁殖成功率は半分ぐらいとよく言われるがオオルリではその数字よりずっと高いと思う。
2回め繁殖もごく普通に見られ、1回めと2回めの時間差は 45 日で (順調に進んでいる場合) 2回めの繁殖タイミングはほぼ正確に予測できる。2回め繁殖時期に梅雨に入るためこの時期の活動が目立たない可能性がある。
2回めの繁殖を行わないのは主に経験の少ない若い個体で一般に (1回めの) 繁殖開始も遅く、空いている場所があった時に繁殖している印象を受ける。1回め繁殖後に場所を離れるように見える。
2回め繁殖を行う場合はひなが巣立ってまもなくオスは次第にさえずりを再開しつつひなに給餌も行う。
2回めの巣立ちの後はセミの声も大きくなって、特にヒグラシの声が大きくなるとオスは早々にさえずりを止め換羽に入る模様である。2回めのひなは巣内ひなの時点で音声を学習しているのだろうか。
換羽中のオスは大変静かになるが、気に入った休憩場所が繁殖時の行動圏の狭い範囲にあって羽繕いをしている様子や換羽の進みなどが観察できることもある。個体差も大きいようで、嫌われると姿を隠すかも知れないが安全な相手と認識すると常時自然な行動を見せてくれることもある。
他の種類でもそうだが、メスは警戒心が強くあまり慣れない印象を受ける。オスはいつも上でさえずったり見慣れているためか友好的関係? あるいは好奇心? のような行動を示してくれる個体もある。人はよく見分けていて翌年もよく覚えているように感じる。
若鳥は好奇心旺盛でわざわざ見に来たりすることもある。現実はどう感じているのかはわからないが、野鳥でも自身に対して敵対的でない興味を示す人 (もっとわかりやすく言えば好きになってくれている人) を理解しているように感じることがある。人の方が知らずに何か上手なサインを示しているのか、鳥自身の行動に対する何らかの人の態度を読み取っているのだろうか。当然ながら給餌や音声プレイバックは行っていない。
もしかすると鳥の声や微妙な動きから感情を読み取れていて相手の望む反応をしている (お互いに自然にフィードバックできている?) ことがわかるのかも知れない。あくまで推測だが...。だんだん童話の世界になってゆく?
動物園個体だがハチクマがどうしてすぐに親近感を示してくれたのか? 種類によるだろうが何か鳥と接するコツはあるのだろうと思う。具体的にどの反応かはわからないが、自分の場合はインコと接していたのでインコが好む反応 (お互いの自然なフィードバック) はできていると思う。しかし果たしてハチクマやオオルリにも通用するのか...?...
と漠然と思っていたら共通点を見つけてしまった。要するにどれも暇なのである (そんなことやっている人の方がもっと暇であると言われそうだが)。インコや動物園個体はもちろんそうだろうが、メスが抱卵中のオスのオオルリは自身のなわばりを保持する以上の大した仕事はなく、何か興味を引く相手があれば気に留めるぐらいのことはあるだろう。
もちろん種差も個体差も大きいだろうし、それ相応の知能も必要だろうが相手の反応を見て遊んでみるぐらいのことはやっているかも知れない (別のところで述べているようにハチクマは大きなインコみたいなところがある。ヒタキがそんなことをするはずがないと考えるのは一種の先入観だろう)。
かつては写真も録音もしておらず客観的証拠は残っていないが、知り合いのオオルリに出会えるのが楽しくて会いに行っていた。単純な動機である。
そのため観察条件を揃えて規則的にデータをとるなどまったくやっていないのだが、相手の行動に合わせて純粋に交流を楽しんでいた。いわゆるバードウォッチングともちょっと違うし何と呼んだらよいのだろう? 日本野鳥の会から「野鳥をペットにしてはいけません」と言われそうである (笑)。
研究対象や撮影対象として接する場合とは相手の態度も違ってもおかしくない。特に追い詰めるほどに撮影対象としている人からは殺気が溢れているのではないだろうか。
このように親しんだオスであっても巣への餌運びの時はさすがに本能的に警戒して巣へはなかなか飛び込まないが、本能的反応と学習で得た情報との間で葛藤らしい行動を示すことがある (ただし個体差は大きい)。
初めて餌運びを行う時は本能的警戒が上回るらしくなかなか決心がつかなかった。このようなオスは近づいても逃げるわけでもなく、安全と思っている相手に警戒を示すわけでもなく (警戒のサインを示したら信頼関係ができていないと思えばよい) 遠ざかるのを本能的に待っているらしい。相手はドキドキかも知れないがきれいな青い鳥をごく間近に見ることができた。
そしていずれ巣に餌を運ぶところを見られてしまい巣でひなを保温しているメスに怒られる次第である。
面白いのはこのように一度餌運びをして巣の場所を悟られたとわかってしまうと心理的抵抗がなくなるようで、オスは自然な餌運びを見せてくれてひなの糞をくわえてこちらに向かって飛んできたこともあった。
見られてしまったと理解できるのは相手の視線がわかっているのではないだろうか (これはかなり高度な認知のはず)。
メスはそこまで警戒を解かないようでメスの餌運びの時は遠くに離れるようにしていた
(なお子育て時の観察は短時間にとどめている。離れている間に別のペアを見に行くことができ、必要な距離は心得ているので影響は最小限にとどめられているだろうと思っている。繁殖成功率の高さや在巣期間が安定していることもこれを裏付けていると考えている)。
繁殖行動は本能的な部分が大きいが状況判断や知識によって本能的な反応を抑制する場合もあるらしい。
これはヒトで言えば前頭前野の機能に相当すると思われる。相当する機能はカラス類やカラ類を中心に調べられている [cf. Nieder (2017) Inside the corvid brain - probing the physiology of cognition in crows]。
ひなは標準的な在巣日数通り巣にとどまって巣立って行った。地上の巣は危険なのでもっと安全なところに親が誘導するとよく言われるがそれほど遠くには離れない。やはり食物資源が豊富なところにとどまっているようである。
スズメ目の小鳥は一度巣立つと巣に戻ることはないと思っていたのだが、必ずしもそうではないこともわかった。巣立ったひながまるで巣内ひなのように元に戻っているのを観察したこともある。
一刻も早く巣から離れて、というわけではないようである。
ひなが巣立つとそれなりに移動するので隣のなわばりとの関係はかなり怪しくなることもあり、同時に巣立ったような場合には多少入り乱れることもある。巣立ちひなへの給餌は数分に1回程度行っていた。
メス親でも大変よく慣れる個体もあって、巣立ちひながそばにいるのに警戒行動もなくこちらへ向かって給餌に飛んでくることもあった。個体差とどれだけ顔なじみかにもよるのだろうか。オスとの交流の様子を見ていたのかも知れない (*1)。
オスのオオルリとのコミュニケーションは驚いたことに人の声 (日本語) で大丈夫だった。ペットに話しかけている人とあまり違わないだろうか。鳥は自分の歌声で歌い、人の方は人語で応対している状態が続けられるのが不思議である。(普段あまり人も通らない秘密の場所? だが) 途中でハイカーの接近に気づいてさすがに止めていたのだがハイカーと少し話している間も待っていてくれて、通り過ぎた後もそのまま再開してくれた。驚きである。
鳥は絶対音感に敏感で云々と言われるが、音程の違いなどはあまり気にしておらず相手をしているかどうかを判断しているように思えた。
むしろ本当の鳥の声だとなわばり争いに発展してしまうのかも知れない。
知らない人が見たら狂人に見えたかも知れない (笑)。伝説や神話の中だけではなく、本当に普通の言葉で野鳥と話ができる (意味がわかるとは思わないが...) のかも知れない。
子育てに限らず、本能的反応と学習で得た情報との間の葛藤は水浴びで見たこともある。これも個体差が大きく、ある個体は目の前に飛び降りて堂々と水浴びをして驚かせてくれた。双眼鏡のピントも合わない距離でまったく警戒していないようだった。
普段はもっと馴染みの個体は水場に飛び降りたまではよいが水浴びは躊躇したらしく、何かを地面からついばんでこれは葛藤から生じた転位行動だろう。
生態や鳥の感情、能力や本能と学習の対立などを示す事例として紹介したが、おそらくどれも特殊な事例で普通に適用可能とは思っていただかない方がよいだろう。相互にサインを読み取れて信頼関係が成立している場合のみ可能になるのだろうと思う (#シジュウカラの備考レン・ハワードの "小鳥との語らい" も参照。こちらも誰にでもできる話ではなかった模様)。
こんな話もある程度に捉えていただき、安易に模倣して繁殖妨害にならないようにしていただきたい。
このような逸話的要素は科学的記述には馴染まないが、鳥は研究対象として選んだもので「N 個体を観察し、平均と標準偏差は...」のような扱いでは捉えがたい側面はきっとあるのだろうと思う。
捕獲してストレスを与えたりしない、また相手の鳥が好きだからこそわかる点も絶対あるだろうと思う。
特に飼い鳥の感情などをご存じの方はうなずいていただける方もあるのではないだろうか。
ただしいずれも「今は昔」の話。こちらではナラ枯れや台風、シカ食害、頻繁な豪雨も経験して荒れ果ててしまった。昔のような観察適地もなくなってしまった。
オオルリの繁殖事例に戻るが、子育て途中で失敗したと思われる時にオスがいつもとまる枝にメスが並んでとまり、しばらく互いにじっとしていて落胆の感情を示しているかのように見えたことがあった。擬人化しすぎかも知れないが、その後気を取り直すかのように一緒に飛び立って行くのを見た。
鳥にも子育てに関係する感情はあるのではないだろうか。
同一個体が同一なわばりに戻る時期は年による差はほとんどなく、経験を積むと早くなる効果はあまり感じられない。同一個体ならばほとんど同じ日に戻ってくる。知り合いの個体との再会は何物にも代え難い喜びだった。4シーズン連続の経験は何度かある。
別個体が先に到着してなわばり宣言をしていることもあったが、経験を積んだ個体は圧倒的に優位で、到着その日には声で到着したことを教えてくれる程度であっても翌日朝はまだなわばり争い、その翌日にはすっかり入れ替わっていることもあった。
多分知っている人はほとんどいないだろうと想像するが、人がつい「あっ」と言ってしまうのに相当するだろう音声がオオルリにある。相手が期待していない意外なところで偶然出会うとこの声が聞こえることがある。
この声が一番役立つのはやってきたばかりの時で、こちらは昨年来ていた鳥と同じかどうか音声でまだ判別できない (姿ではさすがにわからない) 段階で、低い枝で採食している時に鳥の方が先にみつけて音声が聞かれることがある。前年の状況を思い出すのだろう。個体識別をする前に鳥の方が記憶していることを教えてくれる。
人の識別は驚くほど完璧で、このように呼びかけてきた個体の観察をそのまま続けていると前年と同じような行動を行い、音声でも同一個体と確認でき、相手の判断の正確さを確認できるのである。こちらは一言も声を出していないのに前の年と同じようにふるまってくれる。
おそらく「あっ」と言ってしまったサインに反応したことで人物の同一性を認識したのではないかと想像するが、ここまで音声がわかっていると野鳥とのつきあいも格段に面白くなる。
ジョウビタキやルリビタキも同じような声を出すことがあり、あるいは気づかれている方があるかも知れない。
備考:
*1: オスのようにメスと交流を楽しんだことはない。メスは忙しいのでおそらく構っている暇もないし、そもそも警戒心も強いのだろう。
他個体の動きを観察して態度の変わる鳥は飼い鳥で経験されている方もあるかも知れない。
オスが手乗り、メスがそうでないインコのペアを飼っていたことがあるが、オスだけ出してもらって楽しそうに遊んでいるのを見ているうちにメスも多少ぎこちないが手に乗るし外で遊ぶようになってしまった。
オオルリでも抱卵中のメスは餌を食べに外出するのでその時に相棒の様子を見ているかも知れない。もともと警戒心の弱いメスだった可能性もある。
[メスの"さえずり"?]
オオルリのメスがさえずりに似た声を出すことはよく知られていて、しばしば「メスのさえずり」と誤解されているが、これはほとんどの場合観察者に対する警戒の音声 (警戒音 alarm call と呼んで差し支えない) である。1種類の「ピーリーリーリー」(ほとんどの場合少しずつ下がる) を繰り替えし、しばしば前後に舌打ちのような音を交える。この音声は個体によってほとんど差がなく、オスも同じ声を出す。
同様の見解は石塚 (2020) Birder 34(5): 38 に、本能的に備わった声の可能性があり、さえずりの特徴から少しはみ出ると述べられているがオスも同じ声を出す言及はない。
餌運びをしていることが明らかな場合や同じ場所にとまって鳴いているのは明らかな警戒の声で (あるいは怒っている)、近くに巣があるか巣立ちびながいるはずである。写真撮影のチャンスとばかりに粘って撮影したりすると営巣妨害になるので立ち去るべきである。この声を出す時に尾を上げることも多く、これも警戒のサインである。
ネットに出されていたり、あるいはしばしば出版物にも掲載されている尾を上げている写真があるが、少なくとも繁殖地のオオルリに関しては繁殖に影響を与える撮影が (意識的に、あるいは行動を知らずに) 行われている可能性が高い。
知っている者が見ればすぐにわかるのでご留意いただきたい (もちろん警戒時の行動や音声を記録することは学術的も意義があるので、このような記録を残すことを排除する必要はないが、単により見栄えのする写真を撮りたい目的で妨害するのは避けていただきたい)。この声でオス・メスともに鳴いているものを2羽でさえずりあっているところと誤って解釈しないように。2羽で必死で侵入者を追い払おうとしているところである。
#シジュウカラ [シジュウカラの言語能力] で紹介のように、シジュウカラは外敵の種類によって警戒の音声を変えることが鈴木俊貴氏によって示されている。
オオルリの警戒音もひなに同様の反応を起こさせる可能性があるか興味あるところであるが、無人ビデオでの記録ではひなが伏せる場合もそうでない場合もあり、一概には言えない結果となった (親鳥による生の声なので親鳥の動きも参考にしているかも知れない)。
この警戒音が人など大型の動物に対するものだけなのかはあまり判然としない。カラスが集団で偶然近くにやってきた時に聞いたこともある (カラスによる捕食はなかった模様) ので、人以外に対しても出しているかも知れない。逆に言えば人以外に対する警戒音にバリエーションがあるかは未調査。
さえずりに似た声をオス・メスともに警戒に用い、個体差があまりないとすれば警戒の声からさえずりが進化した可能性もあるような気がする。自身に注意を向けさせるには非常にわかりやすいシグナルなので別目的に進化させるのに都合がよい? さえずりの起源がどのように議論されているかはよく調べていないが、オオルリの発声はヒントになるかも。
[地鳴きと音声学習、季節による変化など]
オオルリの地鳴きはなかなか聞けないと言われるが、警戒時に出す舌打ちのような音は地鳴きである。それ以外の場面で聞くことは少ない。この音声はさえずりの最後に付ける「濁った音」と同じもののこともあり、さえずりを記録していれば自然に地鳴きを記録することができる。
典型的な地鳴きは雨の後の水滴が枯れ葉に落ちるような音と表現するのがよいだろうか。この音は結構遠くからも聞こえて知っていると行動を理解しやすい。
さえずりの最後にはこのような「濁った音」だけではなくいろいろなものを付けることがあり、しばしば他種の音声の真似を交える。例えばエゾムシクイやイカルのさえずりやサンコウチョウのホイホイホイを最後に付けることがある。
さえずり本体の方でも他種の声を歌いこむことはよく知られているが (たとえば多くの個体がキビタキの声を混ぜるので、キビタキが鳴いていると誤解しないよう注意が必要である)、種類はコサメビタキのところに述べたものに似ている。前奏まで交えたコルリの声で歌う個体を聞いたことがある (当時録音はまだ行っていなかった)。
後に聞いた事例では感情が高まった際にオオルリが短い前奏を 1-2 音入れることがあった。さえずりの最後に付ける「濁った音」と同じような位置づけかも知れない。本来の音声でも前奏を入れることがあるためコルリの声も模倣できたのかも知れない。
ジュウイチの声で鳴くオオルリも時々あってこれは托卵への防御の可能性も指摘されているが、多分単に覚えやすい特徴ある声を学習しているだけではないかと思う。
ちなみにメスも音声学習を行っているようで、前シーズンのオスのさえずりを発したりすることがあるが、メスのさえずりは大変まれで、おそらく多くは警戒に関係したものと思われる。
岡村 (2025) Birder 39(4): 28-29 にアカショウビンの声の模倣が紹介されているが音程 (1オクターブ近く違う) も速度もまったく違うので模倣と言えないと思う。オオルリのさえずりの基本形に音程を徐々に下げるものがあるがこれを長く続けたもので基本形と判断してよいと思う。
ソノグラムで異なる場合は別物と思ってよい。人が聞いてメロディーが似ているかよりも特に音程の違いに注意。前述のジュウイチの模倣はソノグラムまでほとんど同じだった。
多少注意すべき点があるとすれば最初に模倣した個体はそっくりに模倣できているが、別個体がその声を取り入れて受け継がれて行くうちに次第に変質してゆくことがある。この場合は最初の模倣を知らないと何の模倣かわかりにくくなるかも知れない。似ているものの少し違うイカルのさえずりの模倣などでこの事例が多い感じがする。次第に変質してオオルリの音声に同化してゆく感じ。
舌打ちのような音以外にも多種の地鳴きがあり、どのオスも同じように鳴く「ピロ、ピウイ」で始まる何種類かの音声は他のオスを見つけた時になわばりの主が出す (その後しばしば争いに発展する)。これらの声を知っていれば何が起きているかわかりやすい (行動が大変わかりやすい種類である) が、声でわかるようになるにはそれなりの経験が必要であろう。
「ニイ」のような声で鳴くこともあって観察者への警戒の声かと思ったこともあるが、巣の近くでの自動録音にも入っていたので、別の目的もありそうである。
さえずりの「ピーリーリーリー」の「リー」を長く繰り返すことは感情の高まりを示していると考えている。さえずっているオスの上にメスが訪れて交尾に成功した後に「ピーリーリーリー」を長く伸ばして続けていたことがあり、勝ち誇った声のように感じた。アカショウビンの声に似たケースもこれに該当するかも知れない。
オオルリの巣立ちびなは特徴的な声を出し、「ニイー」、「ビイー」のように聞こえる頼りなさそうな餌乞いの声である。他にこの声を出す鳥は知らないので、オオルリの繁殖地らしいところでこの声を聞けばひなが出ていることは確実である。巣立ち近いひなも同じような声を出す。
親の換羽期にはほとんどさえずらなくなるが (まったくさえずらないわけではない)、この時期は若オスが親のソングポストでさえずることがある。親のようにはっきりしたさえずりではなく、まだ形成途上の歌であろう。
オスは自身のソングポストに他のオスが侵入することを強く拒むが、子供がさえずることには寛容なようである。親は換羽を終えるとまた同じなわばりを守るようになり、隣のなわばりの個体がさえずると春と同じようにさえずりを競うことがある。
ただし春ほどさえずるわけでなく、この期間は短いためなかなか聞くことができない。この秋のさえずりで春には使わなかったフレーズを使うことがあり、成鳥になっても新しいフレーズを学習していることがわかる。秋のさえずりは渡り直前まで聞くこともあり、連続して観察できていれば旅立った夜がわかるぐらいである。
石田 (2021) Birder 35(8): 41 にも秋の渡り時期でもオオルリがさえずることが記載されている。
[食性]
オオルリは高所から飛んでいる虫を捕まえることが主な採食様式のように考えられているが、実は果実が結構好きで、繁殖期でも果実をよく食べている。樹冠部を飛び回ってもぎとり採食をよく行う。さえずっていてもしばしば中断してペリットを吐き出すのが見られる。
ひなへの餌は虫が多いが、果実を与えている写真も撮影されている [諸角 (1993) Birder 7(5): p. 13 にジュウイチのひなへの給餌写真あり]。
カルシウム補充のために小型のカタツムリを与えることもある。
[幸せの青い鳥]
オオルリの古い和名などにも関係して、大橋 (2022) Birder 36(6): 52-53 に「幸せの青い鳥」は日本の文化とも呼べるかも知れない記述がある。
世界的には「幸せの青い鳥」の起源はもっと古く、ヨーロッパの民話に登場するとのことであり、例えばロシアでは希望の象徴であった。メーテルリンクの同名の劇が創作される前に、Madame d'Aulnoy (1650-1705) (ドルノワ夫人) が L'Oiseau Bleu (青い鳥) の民話を童話作品集に紹介している (ちなみにチャイコフスキーの「眠れる森の美女」に出てくるのはこの民話の方。当時のロシアで観衆も青い鳥といえば象徴性を理解できたのであろう)。
「幸せの青い鳥」そのものはフランスのロレーヌ地方の古い民話に現れるそうである。
これをもとにした作品が作られ、メーテルリンクはそれに刺激を受けて創作を行ったとのことである (wikipedia 英語版より)。
日本に入ってきたのは主にメーテルリンク (この作品でノーベル文学賞を受賞) を通じてであろうが、日本固有というわけではなく世界的にもよく知られ「幸せの青い鳥」の表現は英語でもそれ以外でもよく通じる。「幸せの」は付かないようだが古くは青い鳥が使いとして現れるのは紀元前の中国やネイテイブ・アメリカンの伝承にもあるそうである (wikipedia 英語版より)。
なお、メーテルリンクによる続編「チルチルの青春」(邦訳 あすなろ書房 1990。原題:Les Fiancailles いいなづけ。英訳題 "The Betrothal - A Sequel to the Blue Bird" の方がわかりやすいかも知れない) がある。メーテルリンクの孫が「青い鳥」の続編の未発表原稿を発見 (2021) という報道もある。
「青の歴史」(ミシェル・パストゥロー著) (#カタグロトビの備考参照) によれば中世ヨーロッパで青は好まれる色ではなかった (#カワセミの備考参照)。青は (ドイツ) ロマン主義の象徴的存在となり、愛とメランコリーと夢の色となったとのこと。
メランコリー melancolie という単語そのものも、青い花 ancolie (オダマキ) に合わせて中世に用いられ、ロマン主義以前から空想、おとぎ話は「青い物語」(contes bleus)、まれで到達しえない理想的存在を「青い鳥」(oiseau blue) の成句で呼んでいた (p. 154)。ドルノワ夫人やメーテルリンクはまさしくこのような時代にあたる。メーテルリンクの「青い鳥」はこの成句と現実の青みを帯びた鳥との掛詞なのだろう。
夢の色の意味はその後変質を遂げ、ドイツでは「酔った」の意味、英語では blue hour が午後のオフィスを出る時間帯を指し、バーで酒を飲んで悩みを忘れたとのこと。英語の音楽 blues もロマン主義の語義に由来するとのこと。
[オオルリはなぜ青い]
鳥の青い羽色は色素によるものでなく、羽毛内部のメラニン色素顆粒層の配置が散乱された光を干渉させる (光の波としての性質 (#アマツバメの備考 [渡り鳥における磁気定位]の *2) と波の干渉 (#ヨタカの備考 [反響定位を行うアブラヨタカ] が関係する) ことによって生じる。
メラニン層の配置に規則性がある場合はカモの頭のように角度によって色が変化する構造色にもなる (iridescent structural color; iridescent 虹のような)。羽枝 (barb) の生み出す青色は角度によって色があまり違わない non-iridescent な構造色を生み出し、小羽枝 (barbule) は iridescent な色を生み出す傾向がとのこと
[これら情報は Bagnara et al. (2007) On the blue coloration of vertebrates のレビュー論文より。オープンアクセス論文なのでこのレビューを紹介したが、先行研究も充実しているので関心ある方はそちらも見て欲しい]。
構造色が光を吸収する方に働けば McCoy et al. (2018) Structural absorption by barbule microstructures of super black bird of paradise feathers
のように可視光のあらゆる波長の光を吸い込んでしまって真っ黒に見える例 (ディスプレイ中はとても鳥の姿に見えないことで有名なカタカケフウチョウ Lophorina superba Greater Superb Bird-of-paradise など) が知られている。
ナノテクノロジーで人工的に作り出した漆黒物質にも近いぐらいの黒さとのこと。
カラス類の黒さはこのメカニズムよりも色素が効いているようだが、カラスの全系統で構造色は失われていないとの研究がある: Lee et al. (2015)
Evolution of plumage coloration in the crow family (Corvidae) with a focus on the color-producing microstructures in the feathers: a comparison of eight species (ご承知のように黒いカラスも近くで見ると iridescent な色が見え、カラスの濡れ羽色の所以ともなる)。
ステラーカケス Cyanocitta stelleri のアルビノ個体ではメラニン色素顆粒を欠くため青色も失われるとのこと:
Shawkey and Hill (2006)
Significance of a basal melanin layer to production of non-iridescent structural plumage color: evidence from an amelanotic Steller's jay (Cyanocitta stelleri)
にアルビノ個体と通常個体の反射スペクトルの違いも示されている。
実は紫外線や青の反射率そのものはアルビノ個体の方が高いのだが、反射率がピークとなる波長の反射率で規格化する (これは色を表現することに対応する) と、通常の青い個体は 350-450 nm 付近の紫外線から紫の領域が強いピークになっていることがわかる。
我々が "色" として感知するのは波長による反射率の比なので、このステラーカケスの場合には赤色 (600-700 nm 付近) に比べた 350 nm 付近の反射率は通常個体の方が2倍ぐらい高い (図から読み取った大雑把な数値)。このぐらいの違いを我々は
(我々の色感受細胞の感度分布をかけ算した上で) 青色と判断していることになる (例えば天文学ではこの数値の比率を表す色指数 color index のような便利な概念がある。天文学では等級の概念が用いられ、感覚におけるヴェーバー-フェヒナーの法則 Weber-Fechner law に基づくものとなっている。色指数も同様なので色覚における感覚閾値のような概念は自然に反映されている)。
我々の目は鳥とは異なり紫外線の感受細胞を持たないので、紫外線の見える鳥にとっては一層派手な色に見えていると想像できる。
オオルリの色彩も同様の構造色であることは確かめられている オオルリ [徐 2018 Bird Research News; 徐敬善 (2016) "オオルリの繁殖生態と美しい構造色の羽" in 上田恵介(編) 野外鳥類学を楽しむ (海游舎)]。羽枝が青い色となっているのは non-iridescent な構造色を生み出す傾向とも合致する。
オオルリの方がステラーカケスよりもより濃い青色に見えるのはオオルリでは小羽枝などのメラニン色素によって長波長成分の反射率が低いことを表しているのだろう。
オオルリでもおそらく紫外線から紫の領域が強いピークになっていると想像できるが、紫外線が見える鳥にとってはオオルリは光り輝く青い鳥に見えているのではないだろうか。そんなに目立っていても襲われないのか... ここまではかつてどこかに書いた記憶があるのだがどこに書いたか思い出せない。
最近になって昼行性猛禽類の視覚のレビューから猛禽類の視覚特性を知り、改めて検討してみた。
#チョウゲンボウの備考 [チョウゲンボウは齧歯類の尿の跡が見えるか] にあるように、昼行性猛禽類も基本は4原色である点は変わらないが紫外線をむしろ積極的にカットしている (その光学的理由もある。該当部分を参考にしていただきたい)。
そのため一般に言われるような齧歯類の尿の跡は多分役立つ信号になっていないのではと考えられるわけだが、光り輝く青い鳥はどう見えるだろうか。
チョウゲンボウのところで紹介している Mitkus et al. (2018) では数種の眼球の透過率の波長依存性を示している。網膜で検知されるものは (波長ごとの) 光の強さ × 眼球などの透過率 × 色感受細胞の感度 となるわけだが、紫外線感受細胞の感度のピークより短い波長の光は (他の通常の鳥に比べて) 昼行性猛禽類の網膜にはほとんど届いていないことになる。
さらに Odeen and Hastad (2013) The phylogenetic distribution of ultraviolet sensitivity in birds の紫外線知覚の系統研究によれば、鳥類の色覚は VS 型 (紫外線感受細胞のピークが 430 nm ぐらい) と UVS 型 (同 370 nm ぐらい) に大別され、前者が鳥類祖先型で後者は紫外線感受細胞の感度のピークがより短い波長に移動した紫外線強化型と言える。
昼行性猛禽類は VS 型だが、ヒタキ科で調べられた4種はいずれも UVS 型で短い波長の紫外線がよりよく見えると考えられる [ちなみに少し気になったところで見ておくとヨーロッパヨタカ、バライロユミハチドリ Phaethornis pretrei Planalto Hermit、
コガネオサファイアハチドリ Hylocharis chrysura Gilded Hummingbird はいずれも VS 型で夜行性系統を経験しても紫外線知覚は失っていなかった。
ただしいずれも UVS 型ではなく紫外線強化型ではない]。
つまり紫外線領域で輝く鳥は昼行性猛禽類にとっては判別しにくい対象となっている一方、通常の鳥には見えるので同種の間の信号として役立つ絶妙な波長を選択していると言えそうに思える。
"そんなに目立っていても襲われないのか" は性選択に際して、資質の「正直なシグナル」とも読み替えることもできる一方で、襲う方の猛禽類には実は見えてなくて同種には有効な信号で捕食者には保護色として働いている可能性がある。どちらにも有利な形質として、いったん青い形質を身につけると反射率のピーク波長はより短い方に進化して濃青色の鳥ができる。いかがだろうか。
青い動物は鳥が多いという (魚もそうだが)。これは同種と捕食者の間の視覚特性の違いが反映されていると考えると納得できる部分もあるように思える。
これぐらいの話ならば誰かがすでに思いついて実験もあるかも知れないが...と書いていたが、やはりアイデアを述べている研究があった。
Hastad et al. (2005) Differences in color vision make passerines less conspicuous in the eyes of their predators
はこの可能性を議論しているが、昼行性猛禽類の眼球の紫外線透過率はこの時点ではわかっていなかったので紫外線感受細胞のタイプのみを考慮している。
Lind et al. (2013) Ultraviolet sensitivity and colour vision in raptor foraging
で猛禽類の眼球の紫外線透過率が低いことが示された (#チョウゲンボウの備考 [チョウゲンボウは齧歯類の尿の跡が見えるか])。ここでは主に猛禽類が獲物を探すのにあまり紫外線を用いていないのではとの文脈で使われている。アオガラの色彩が捕食者対策になっているかに関しては猛禽類の色覚との違いが微妙なのでまだよくわからないとの議論で少し後退している。
Lind et al. (2014) Ultraviolet vision in birds: the importance of transparent eye media
でも同様に眼球の紫外線透過率が議論されているが、むしろスズメ目の色覚の方の議論が中心。
Olsson et al. (2021) Lens and cornea limit UV vision of birds - a phylogenetic perspective
に眼球の紫外線透過率の系統進化が調べられているが青い小鳥のシグナルについては従来とあまり記述は違わず、透過率進化の方が中心になっている。この仮説に基づいた議論を行っているのはこのグループだけかも知れない。
猛禽類研究者にはこれら研究はあまり知られていないのかも知れず、年代的には扱っていてもよさそうな Bildstein (2017) "Raptors" にも現れず、むしろワシミミズクが紫外線反射率の高い模様を信号にしていることが紹介されている [Bettega et al. (2013)
Brightness features of visual signaling traits in young and adult eurasian eagle-owls]
フクロウ類が紫外線感受細胞を欠いていることはあまり認識されていなかったようである。
Brown (1976) ぐらいの時代だと研究者が関連文献を全部把握することも可能だったかも知れないが、情報量の多い現在では「耳学問」に頼らざるを得ない部分もあって最新の知識が反映されていない部分もありそうだ。
Hastad et al. (2005) の Fig. 1 に樹木の葉の反射スペクトルが出ている。
緑以外の波長はかなり吸収されて (赤い光はもちろん光合成に重要。紫外線は光合成を阻害したり有害作用があるので吸収するらしい) 400 nm より短いところは葉は暗く見えるはず。この部分は UVS型のヒタキ類などには見えて有益な信号になるが、捕食者のタカ類には見えないので保護色となるという次第。
もちろん哺乳類捕食者にも見えない。哺乳類については Hausmann et al. (2003) Ultraviolet signals in birds are special にも記述あり。
猛禽類の眼球などの透過率の知見をベースにこれらの研究を知らずにこの部分を書き始めたものだが、調べてみると基本的に自分が考えたアイデアと同じ視点で研究が進められていてある意味安心である。
これらの研究は猛禽類を全般として取り扱っているものの、猛禽類の進化のタイミングなどは意識していないようなのでこの点について後に触れる。
色の形成には性選択がおそらくかかわっているが (実験的検証は難しいだろうが)、捕食者対策の方がより有意義かも知れない。
研究の歴史を追いかけたわけではないが、おそらく鳥と哺乳類で色覚が異なることがわかって、鳥の間だけで通用する哺乳類には秘密の信号として紫外線を用いる意義が最初に注目されたのではないかと想像する。
しかし捕食者は哺乳類だけではないのでこの考えには限界があった。その後鳥の紫外線感受細胞に2タイプあって、猛禽類と多くの小鳥でタイプが違うことがわかって研究も俄然活気づいたのだろう。
小鳥でこのタイプの紫外線感受細胞 (というよりオプシンのアミノ酸配列) が選択されたのは捕食者と異なる知覚を得るのが有利であるということだろう。小鳥は猛禽類に比べて眼球が小さくて吸収も少なく生理的にもそのような進化が可能であった。
猛禽類も同様の知覚を進化させて追随できる可能性は原理的にはあるだろうが、これはおそらく猛禽類の生活史で制約を受けるのだろう。紫外線を取り入れすぎると水晶体や網膜の劣化が早まり、長寿命の猛禽類では進化する方向に働かなかったなど。あるいは小鳥に比べて眼球が大きいことによる物理的制約もあるだろう。
後半の部分にかかわるのは光の粒子性の方で、構造色を作る方は光の波動性である。物理学的にも両者が絶妙に用いられている。
そもそも高い木の頂上でさえずるオオルリのオスがよい獲物になるだろうか? 観察体験から考察してみる。頂上で歌うオオルリは見晴らしもよく、さえずる最中も周囲をよく見渡している。高い木の頂上は他の鳥も利用したいので競争もあるが、自分よりも大きな鳥 (ヒヨドリ、カラスなど) が飛んで来る時だけ飛び立っている。フクロウが下界を飛び回っている時は上にいたまま様子見をしてやり過ごしていた。
観察された方はご存じだろうがオオルリは大変敏捷で争う時などは猛スピードを出すことができる。エゾビタキが他の灰色のヒタキと別属にしてもよいぐらい違っている (#エゾビタキの備考参照) のと同じような印象を受ける。たとえ小鳥専門の猛禽類でもよい獲物にはならないのではないだろうか。
捕食されるとすればむしろさえずっておらず、つがい外交尾の機会をうかがっているような周囲に注意が向いていない個体ではないかと思う。高い木の頂上でさえずっているオオルリが攻撃を受けたのは見たことがない。
ただし猛禽類が避けているわけではなく、ロシアでトビによる成鳥オスのオオルリの捕食事例もある (#トビの備考参照)。何らかの理由で弱った個体だったのだろうか。
鳥の青色が性選択要素となることは容易に想像できるが、実験的に確かめることは案外難しいようである。
北米のルリツグミ Sialia sialis Eastern Bluebird において紫外線の色調が強いほど多くのひなを育てた研究がある: Siefferman and Hill (2003)
Structural and melanin coloration indicate parental effort and reproductive success in male eastern bluebirds。
しかしルリツグミで色の濃さが性選択の対象になる野外実験の結果は得られていない: Liu et al. (2009) A field test of female mate preference for male plumage coloration in eastern bluebirds。
Hunt et al. (1999) Preferences for ultraviolet partners in the blue tit
ではヨーロッパのアオガラ Cyanistes caeruleus Eurasian Blue Tit で色彩を人工操作した実験で、紫外線をよく反射するメスをオスが選ぶ結果が得られたがメスがオスを選ぶ選択では有意でなかった。
Parker (2013)
What do we really know about the signalling role of plumage colour in blue tits? A case study of impediments to progress in evolutionary biology
は各種研究をまとめたメタ解析を行っているが、好みについてはしっかりした結論は得られず、オスがメスより紫外線や黄色を強く反射する以上の確実な実験的検証は得られなかった。研究者の思い込みで結論を出しているものも多いのでは?
Fargevieille et al. (2017) Assortative mating by colored ornaments in blue tits: space and time matter
でもそれほど強く支持されているわけではない。よく調べられているアオガラでこの状況なので性選択の実験的検証はかなり難しいのであろう。
アオアズマヤドリ Ptilonorhynchus violaceus Satin Bowerbird でも Doucet and Montgomerie (2003) Multiple sexual ornaments in satin bowerbirds: ultraviolet plumage and bowers signal different aspects of male quality
で紫外線の色合いとあずまやの出来栄えや健康状態には有意な相関があったが性選択までは調べられていない。
Savard et al. (2011) Blue, not UV, plumage color is important in satin bowerbird Ptilonorhynchus violaceus display
では期待されるように紫外線ではなくて青色の方がつがい形成において好まれる結果などが出ている。
Sexual Selection in Bowerbirds (Borgia Lab Web Site) にアオアズマヤドリの研究プロジェクトのページがある。
青色は性選択の結果増強されたと考えがちであるが、実験的証拠はそれほどすっきりしたものではないようだ。徐敬善 (2016) "オオルリの繁殖生態と美しい構造色の羽" の記述では他の鳥では判明しているかのように読めるが必ずしもそうではなさそうである。色彩と健康状態との関係などはまだ調べやすいので研究が進んでいるが、直接的な性選択の研究は難しいのであまり試みられないのかも知れない。
実験も難しそうなオオルリでは結論を出すのはさらに難しいかも知れない。
尾の長さの役割については#オウチュウカッコウの備考参照。古典的実験報告以来成功例がないかも知れない。
オオルリ (アオヒタキ) 亜科 Niltavinae は古い系統も青色で、このクレードの初期段階で青色を獲得したのだろう。発祥の地の熱帯林では青色はむしろ保護色として進化したのかも知れない。種によって性的二形がはっきりしているものもそうでないものもあるが、オオルリはこの中でもはっきりしているように見える。
これはオオルリが長距離の渡りをするため渡り行動に由来する選択圧が関連しているかも知れない (#イソヒヨドリの備考 [メスもさえずる鳥] も参考)。
He et al. (2022)
Deep learning image segmentation reveals patterns of UV reflectance evolution in passerine birds
にスズメ目を対象とした大規模な紫外線反射率の解析結果が出ている。4500 種以上 24000 以上の標本を測定。画像の解析 (鳥の体の輪郭抽出) には深層学習 (deep learning) を利用。これだけ数が多いと人力で画像に輪郭を描き入れて切り出したりするのは不可能に近いということだろう。
紫外線反射の強い種類はスズメ目の多系統で見られるが、色彩は系統的によく保存されているとのこと。
環境色との相関 [Endler (1993) The Color of Light in Forests and Its Implications] は明確に認められた。
オオルリも測定されていて期待通りの値を示しているが、この系統はヒタキ上科? Muscicapoidea の最後の方にあたり、スズメ目全体でも最も青色の目立つグループとなっている。
このように系統樹を眺めてみると [#ツリスガラの備考 [スズメ小目 Passerida の系統分類] を見ながら系統樹を見るとわかりやすい。He et al. (2022) の系統樹での系統内順序は Zhao et al. (2023) のような一般的な系統樹の配列と少し違うかも知れないが青い鳥の位置に注目すればわかりやすい]。
He et al. (2022) では スズメ目のスズメ小目 Passerida の3大グループ {シジュウカラ上科 Paroidea + ウグイス上科? Sylvioidea}、ヒタキ上科? Muscicapoidea、スズメ上科 Passeroidea のそれぞれの中で
オオルリ (アオヒタキ) 亜科? Niltavinae とコルリ、ルリビタキ、イソヒヨドリを含む ノビタキ亜科? Saxicolinae はヒタキ上科? の一番新しい系統になる。
我々が普通みかける小鳥の中でも最も新しいグループと言えるぐらいだった。
スズメ上科の最後に新世界の青い広義ホオジロ類 (フウキンチョウ科 Thraupidae) が集まっているが、旧世界の青いヒタキグループは世界でも代表的な "青い小鳥" グループと言えるだろう。どことなく斬新
さを感じていたのだが、世界にももっと自慢 (?) してもよいかも知れない [オオルリへの思い入れもある (笑)]。
なぜ新しい系統で青色が目立つようになったのだろう?
ここでまた一つ仮説を提供するが、これら青い鳥の比較的新しい出現年代は主に小鳥食の森林性猛禽類 (哺乳類と違って色はずっとよく見える) が適応放散した時期と一致しているのではないだろうか。新しい系統の猛禽類によって駆逐された結果かも知れないが、現存の古い猛禽類系統には主に小鳥食のものがあまりない。
小鳥食には敏捷性なども必要なので特殊能力を持つ系統を生み出すのに時間がかかった可能性もある (もちろん逆の考えも可能でスズメ目が躍進した結果対応する捕食者を生み出した可能性もある)。
主に小鳥食の森林性猛禽類系統と言えばやはり広義 Accipiter 属あるいはハイタカグループであろう。特に Tachyspiza 属と狭義 Accipiter 属であろう。
これらのタカ類の系統の共通祖先が現れたのが 2000 万年前ぐらい、Tachyspiza 属や狭義 Accipiter 属が適応放散したのは主に 1500-1000 万年前ぐらい。クマタカ類はもっと新しく 1000 万年前ぐらい以降 [いずれも Catanach et al. (2024) の値]。
タカ類が誕生してから適応放散を遂げるまでにかなりの時間がかかっており、タカ類・ハヤブサ類ともに案外新参者である (#ミサゴの備考、#ハヤブサの備考参照)。我々が普通にみかけるタカの系統の多くはずっと昔からいたわけではない。
ハヤブサ類は南米で進化を遂げ、旧世界に到達したのは限られた系統のみでかなり遅くなった。森林性のハヤブサ類 Microhierax 属は小型のものが中心で旧世界のものは最小モズサイズ。スズメ目の森林性小鳥にはそれほど大きな脅威にならなかっただろう。
オオルリ (アオヒタキ) 亜科? Niltavinae が現れたのは 1500 万年ぐらい前 [Zhao et al. (2023)] でこれらの値とよく合致する。
新世界のハヤブサ類で広義 Accipiter 属に相当するものは Micrastur 属になるが分岐年代は新しく 700 万年前ぐらい以降
[Fuchs et al. (2011) Pliocene diversication within the South American Forest falcons (Falconidae: Micrastur)]。
フウキンチョウ科 Thraupidae の分岐年代も 1200 万年以降 [Burns et al. (2014) Phylogenetics and diversication of tanagers (Passeriformes:
Thraupidae), the largest radiation of Neotropical songbirds 系統について;
Vinciguerra and Burns (2021) Species diversification and ecomorphological evolution in the radiation of tanagers (Passeriformes: Thraupidae)]。
新世界のタカ類ではヒメハイタカ属 (Microspizias。ヒメハイタカがアマゾンなどに分布) は系統は古いがむしろノスリ類に近くハイタカ属への見かけ上の類縁性は小鳥食は収斂進化だろう。近代的な種類がいつ分岐したかはややわからない。新世界で目立つ小鳥食のタカは Astur 属が中心でいずれも 500 万年前以降と新しい。
狭義 Accipiter 属でアシボソハイタカでこれも同様に新しい。セグロオオタカは古い系統だが主要な種類ではない。タカ・ハヤブサ類を含めて時期的に合っているよう。
ヒタキ上科?、スズメ上科 のいずれでも新しい系統で青い鳥が目立つようになっているのは、ちょうどそのころ小鳥食の猛禽類が現れたため、それまで哺乳類に対して有効だった地味な保護色に加えて紫外線反射を用いる猛禽類に対する保護色 (+ 同種内の秘密の信号) への選択圧が新たに加わったと考えると都合がよさそうに見える。
確認のためにイソヒヨドリ属の分岐年代と生物地理学を見てみると Outlaw et al. (2007) Molecular Systematics and Historical Biogeography of the Rock-Thrushes (Muscicapidae: Monticola)
によればこの系統はアフリカから中東起源で、最も祖先型に近いと思われるアフリカのコイソヒヨ Monticola rufocinereus Little Rock-Thrush はそれほど青くない。この系統は開けた場所を好み熱帯雨林は避けているとのこと。
森林の役割はオオルリ (アオヒタキ) 亜科? とは異なるようだが分岐時期は 550 万年前ぐらいと推定されており、小鳥食の猛禽類はすでに存在していて捕食圧となっていただろう。
He et al. (2022) の作図に使われたデータは公開されているのでさらに分析したい人はそのまま使えそうである。範囲を絞った系統解析やオス・メス両方のデータがあるものは性的二形の進化と渡りの関係なども調べられるだろう。
ハチドリ類は地理的に馴染みがないのであまり詳しく見ていないが、系統的にはスズメ目より古いものの McGuire et al. (2014)
Molecular Phylogenetics and the Diversification of Hummingbirds
によれば青い系統は 1000 万年前後ぐらい以降と比較的新しめの印象を受け、スズメ目と同様の議論が成り立つかも知れない。この図に現れない青い系統や新世界に進出した当時の猛禽類の生息環境と重複するかなど確認する必要があるだろう。ここではスズメ目、特に旧世界のヒタキを中心に検討するため後回しとしておく。
以上の研究結果と自前の解釈も含めると、オオルリが青い鳥になった理由は:
(1) 色覚の優れた小鳥食の猛禽類の出現に伴い、アジア熱帯地方に生息していた祖先系統が熱帯林を背景とする保護色として青色を獲得した。その系統の色が受け継がれている。
(2) 紫外線での輝きは猛禽類には見えにくくむしろ保護色として働く一方、同種内では例えば性選択に際して有効な信号となる。ヒタキ科の視覚特性もおそらく関係している。
(3) この系統のうち長距離の渡りをするようになったのはオオルリのみで、色彩は引き継がれているが渡り行動によってメスの色彩に対する選択圧が弱まり雌雄の色が大きく違うようになった
[#イソヒヨドリの備考 [メスもさえずる鳥]; #ロクショウヒタキ備考の Garg et al. (2024) によればオオルリに近い系統では性的二形は系統によって定まっているわけではない]。
(4) 渡りの進化と一緒にジュウイチを連れてきた? (#ジュウイチの備考。このあたりは妄想レベル)
(5) この系統の中では結果的にオオルリはサイズも大きくなって世界的にも誇れる青い鳥となった。さすが日本三名鳥の一つと言える。HBW の書籍版のヒタキを含む巻でも表紙を飾っている (こういうのを蛇足と言う)。
(6) サメビタキ亜科? Muscicapinae は祖先系統 (起源はアフリカか?) が青色を獲得しなかったために温帯で繁殖する種類はほとんど地味なまま。ヨーロッパコマドリ/ツグミヒタキ亜科? Cossyphinae、ノビタキ亜科? Saxicolinae は系統としてはそれほど熱帯森林性ではなく開けた場所も好むので青くなったのは一部の系統に限られた。
[構造色について]
Bagnara et al. (2007) のレビュー論文から鳥の他の青色の機構も紹介しておく。Prum et al. (1994) Structural color production by conservative reflection from ordered collagen arrays in a bird (Philepitta castanea: eurylaimidae)
によれば皮膚の緑や青の色もコラーゲン繊維の配列による構造色とのこと。アオアシカツオドリ Sula nebouxii Blue-footed Booby などが有名。
青以外の色は色素由来と考えられがちだが、カロテノイドなしで構造色だけでも出せる可能性があるとのこと。嘴の青色もコラーゲン繊維の配列による構造色とのこと。
虹彩の青い鳥は少ないが黄色や赤の虹彩は色素によるとのこと。虹彩の青い鳥についてはこの時点でまだ調べられていない。哺乳類の青色でも構造色が関与している可能性が示唆されている。
構造色は鳥の羽についてよく取り上げられるが、哺乳類でも作り出せるのではないだろうか? あまり見られないのは単に哺乳類の色覚が劣っているため色をあまりシグナルとして使わなかったと解釈した方が適切なのかも知れない
(恐竜時代の夜行性生活のため。同様の事情は概日リズムの機構にも見られる。#イヌワシの備考 [タカ・ハヤブサ類の視力、鳥類の視覚と脳] の *5 オプシン opsin 類参照。我々が普通だと思ってみると鳥類が特殊に見えるが、実は哺乳類の方が特殊なだけ?)。
我々がもし夜行性哺乳類の色覚そのままに進化したものであれば、次元の異なる色彩を持つ鳥を見るバードウォッチングもあまり魅力のないものになっていたいたかも知れない。
これほど豊かな色彩を出せる鳥の羽はすばらしいとよく述べられるが、逆に言えばこれはたまたま鳥類の視力や色覚が哺乳類に比べて非常にすぐれている産物であって、羽ならではと言える説明にはなっていないかも知れない。
カロテノイドの色彩もおそらく鳥類の酸化ストレス対応が一段と進歩したため使いやすくなったもので (#鳥類系統樹2024の解説参照)、酸化ストレス対応能力の相対的に乏しい哺乳類には積極的に使いにくい可能性がある。
(主に夜行性の) 小型哺乳類では捕食者の鳥 (それ以前は恐竜?) が気づきにくいシグナル (private communication channel)、つまり嗅覚シグナルを利用するようになったと考えれば何となく話のつじつまが合うように思える。
構造色の理屈についてより知りたい方のために参考文献としてこの分野の先駆者でもある Prum et al. (1999)
Two-dimensional Fourier analysis of the spongy medullary keratin of structurally coloured feather barbs
を挙げておく (1998 年の Nature 論文 Prum et al. Coherent light scattering by blue feather barbs も有名で、色彩を作る羽毛の微細構造が光の波長より短い規則的な構造を持っていることを示した。光の波長レベルの構造を議論する必要があるため光学顕微鏡で観察しても原理はわからない。より分解能の高い電子顕微鏡が必要であった。内容的には 1999 年論文と大差ない)。
光の散乱は物理学モデルを作ることができて、観察される反射スペクトルをよく再現できるとのこと。よく例えられる空が青い理由 (Rayleigh レイリー散乱) のような位相の揃っていない (incoherent) 散乱は現象を説明できない (実に1世紀に渡ってこの説明がなされていたとのことで日本語の成書にも同様の記述は多数見られる)。散乱体が波長と同程度以上の場合の Mie ミー散乱についても同様。
すなわち青い鳥が青い仕組みを空が青い理由と同じと説明するのは正確でない。単純な (広く離れた) 個別粒子によるランダムな散乱ではなく干渉を伴っていると述べておくとよいのだろう (波の干渉は高校で物理を学ばないと馴染みの用語ではないかも知れないが...波を表すには三角関数を使うのがよいので高校数学を学ぶまでは扱いにくいかも)。
コラーゲン繊維の配置によって逆に光を積極的に透過させることができて角膜の構造はそのようになっているとのこと。Meek (2009) Corneal collagen - its role in maintaining corneal shape and transparency
によればこの考えは 1957 年にすでに提唱されていたらしい。
Benedek (1971) Theory of Transparency of the Eye
は角膜が透明で白内障で水晶体が濁る理由を光学的に説明するためにフーリエ変換を用いた定式化を行った。Prum and Torres (1994)
Structural colouration of mammalian skin: convergent evolution of coherently scattering dermal collagen arrays
によれば Benedek (1971) とは独立にフーリエ変換を用いた構造色の記述を行ったとのこと。古典的に使われるフーリエ光学とは別物としている。
角膜が透明な理由は現在でも完全に解明されているわけではないらしい。
coherent light scattering コヒーレント光散乱。散乱された光の位相が揃っているの意味。Gill の「鳥類学」の日本語訳では干渉性光散乱と訳している。
X 線を結晶に当てるなど高エネルギーが関連する分野では波長の変わる散乱があり、波長の変わらない古典的散乱を干渉性散乱と呼ぶ。波長が変わるかどうかの分類ではレイリー散乱は干渉性散乱に含まれることになって Prum の言っていることと違うではないか、となりかねない。
散乱された光が互いに干渉する点は同じだが似た用語を (扱う波長や散乱体の間隔が全然違う) 分野によって若干違う意味に用いることになる。意味を調べる時には注意が必要 (互いに独立して進歩した分野では用語の概念が異なることもある。例えばガンマ線も放射線用語と天文学では定義が異なる)。
Prum は別用語として constructive interference (波を強め合う干渉) も用いている。どれも現実の鳥の色彩現象を的確に示すには五十歩百歩のようで、coherent scattering と言えば意味のわかる人には文脈を見れば何を言いたいかわかる用語となるだろうか。
物理や工学の人から意味が違うと指摘されれば説明しなければいけない場面が生じるかも知れない。
「鳥類学」の和訳だけで意味を追いかけるのは難しそうなので、空が青い理由と異なることを意識しつつ読むとよいのではないかと思う。
[余談になるが Prum のこのような多方面の活躍を見ていると考え方は物理学者に近いように思える。少数の原理をさまざまな事象に適用するアイデアを出せるのだろう。
難しい数式はむしろいらない。しかし多少の数学的発想は必要で...生物を主に研究される方も参考にしていただければと思う]。
レイリー散乱と他にも名前を聞く Thomson トムソン散乱は何が違うのか、については、後者は束縛を受けていない荷電粒子 (一般的には電子。内部に極性構造を持たない) によるもので散乱は光の波長によらない。自由電子の存在する宇宙ではこちらが普通。レイリー散乱は極性構造を持つ粒子 (典型的には分子レベルで、波長よりもずっと小さい物体) による散乱で波長の4乗に反比例して散乱が弱まる。地球大気による散乱はレイリー散乱になる。
レイリー散乱では波長の短い光ほど散乱されやすいので空が青く、散乱の結果夕日などは赤っぽく見えることになる。またこの性質は鳥類学でも重要で夕暮れ直後、日の出直前の空は短波長の散乱光が強いため紫外線量が相対的に多い。この時間帯の採食行動は紫外線を積極的に利用している可能性がある。
また散乱を受けた光は偏光するため、この時間帯の空を特に紫外線で見れば太陽の方角がわかり、渡り鳥の定位においてコンパスの修正 (re-calibration) に役立つ。
関連するチンダル現象はレイリー散乱よりももっと大きな物体 (主にコロイド粒子) によるもので、散乱体の大きさが波長程度のミー散乱に近い。大きな粒子の場合には散乱は波長によらず、散乱光は白色になる (Tyndall effect にこの3種類の比較表がある)。
ここにも誤用があることが記されており、一般的な解説などでレイリー散乱、トムソン散乱、回折などの現象が同じように説明されていることもよくあるので注意を要する。
鳥の色彩に関して手に入れやすい本では Geoffrey Edward Hill "Bird Coloration" (National Geographic 2010) がおすすめ。構造色も1章使われており、色彩の進化などの章もある。
この本は上述 Prum が Anatomy, physics and evolution of avian structural colors の章を書いている同名の "Bird Coloration" (Harvard University Press 2006。全2巻) を一般読者やバーダー向けに平易にまとめ直したもの。
特に英語圏のバーダーならば読んだ人も結構あるのではないだろうか。
Price-Waldman and Stoddard (2021) Avian Coloration Genetics: Recent Advances and Emerging Questions
の総説もあり、色彩の生じる制御メカニズム、網膜油滴と感受細胞の波長感度特性などの研究が紹介されている。構造色を作る遺伝機構があることは間違いないが微細構造そのものを制御する遺伝子があるわけではなく、メラニン細胞などの自己組織化が働いていると推測される。
Sin et al. (2024) Genetic Basis and Evolution of Structural Color Polymorphism in an Australian Songbird
によればオーストラリアのハジロオーストラリアムシクイ Malurus leucopterus White-winged Fairywren は亜種によって青いものとそうでないものがあり、遺伝的関係を全ゲノム解析で調べた。
青い系統から2つの島で黒い系統が独立に生じたが、黒い系統から再度青い系統が出現したと考えられていたが [Driskell et al. (2010) The evolution of black plumage from blue in Australian fairy-wrens (Maluridae): genetic and structural evidence]、
この研究によって2回の色変化 (青と黒の転換) を経験していて、大陸で分布拡大の際に青い系統が出現したと考えられる結果となった。
島の個体群はヘルパーが少なく一夫一妻が多いとのことで、つがい外交尾も少ないように見えるとのこと (#オウチュウ備考の [警戒音の本質は何か] で類縁のルリオーストラリアムシクイのケースを紹介しているが、厳しい環境が共同行動を発達させる要因と考えられるそうで、島は捕食者も少なくより厳しくないのだろう)。
島では性選択の圧力が違っていて黒い色が有利なのではと考えているが、類縁他種で大陸で白黒の色彩のものもあり、島特有ではない黒色型への進化を促す要因も提案されているとのこと。黒い色になってもメスの青い色への好みは継続していて (共通起源を持つルリオーストラリアムシクイなど青色の他系統がある) 青い系統の進化が起きたと解釈している。
これらの論文でも構造色の色彩変化はアミノ酸1変異によるものではなく、複数の遺伝部位が関与していることが示されている。他研究とも共通するいくつかの候補遺伝子が示されている。
[蛍光を用いる鳥]
Martin et al. (2025) Does biofluorescence enhance visual signals in birds-of-paradise?
一部の属を例外としたフウチョウ科の多くの種類で羽毛やディスプレイに用いる部分の皮膚に蛍光 (例えば紫外線を吸収して可視光で再放射する) が認められた。系統解析も行われている。
熱帯地方の日陰では紫外線量が相対的に多くディスプレイに役立っているのではなどの考察。
生体写真では口内がネオン色の色彩のものが多く黒い嘴や顔に対するコントラストが役立っていて、こちらも蛍光による色彩の可能性がある (多くの標本は綿が入っているなど直接測定できない)。
フウチョウでは構造色による色彩に加えて蛍光も併用しているらしい。Study Finds That Birds-of-Paradise Are Biofluorescent (一般向け解説)。
蛍光による色彩はセキセイインコで調べられていて、Pearn et al. (2001) Ultraviolet vision, fluorescence and mate choice in a parrot, the budgerigar Melopsittacus undulatus;
Pearn et al. (2003) The role of ultraviolet-A reflectance and ultraviolet-A induced fluorescence in the appearance of budgerigar plumage: insights from spectrofluorometry and reflectance spectrophotometry
の研究がある。直射日光下では蛍光の影響は無視できる程度で、フウチョウでは背景色彩に対するコントラスト効果や日陰などの条件を加味して考察しているよう。
Camacho et al. (2019) Correlates of individual variation in the porphyrin-based fluorescence of red-necked nightjars (Caprimulgus ruficollis)
アカエリヨタカ Caprimulgus ruficollis Red-necked Nightjar ではポルフィリン類の蛍光が役に立っているとの研究がある。
夜行性の鳥で蛍光がどのように知覚されるかはよくわからないが、活発に行動する薄明時は相対的に紫外線が強いので質を示す信号になっているのではと考察。捕食者にわかりにくい信号となっている可能性も考えらえるとのこと。
フウチョウの事例を見ると一般的な構造色に比べて分子のエネルギー準位由来の蛍光は狭い波長域の色を出すことができて、干渉性散乱による構造色より天然らしくない際立った色彩を作ることができる利点があるのかも。
こちらはヒトの例だが単一波長に反応する視細胞の実験的条件を作り出せたとのこと: Fonge et al. (2025) Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale 古典的な視細胞の波長感度曲線に制約されない "色彩" が存在するとのこと。
Brand-new colour created by tricking human eyes with laser (Nature news 2025.4.18)。蛍光を用いている鳥がもしかするとこのメカニズムを用いているかも。
フウチョウではどのような分子を使っているかはまだ調べられていないようだが、ポルフィリン類であれば羽毛や皮膚にポルフィリン類を移行させる生理機構が必要になるだろう。これにはおそらくコストがかかるので (だからこそハンディキャップ原理が成り立つのか?) あまり多くの鳥が蛍光色を用いていない理由にもなるのだろう。
もっとも構造色も見えない部分は着色しないようなのでこちらも色を出すのにコストがかかるのだろう。
(フウチョウ類で使われているかは不明だが) ポルフィリン類を着色に用いるようになった進化経緯を考えてみると、もとは不要物または毒物の排泄経路だったのではないだろうか。
エボシドリ類は銅ポルフィリン色素を着色に用いている (#カッコウ備考の [カッコウ類の足と近縁系統]) が、これらの鳥は有毒な銅の濃度の高い地域に生息する。毒物の排泄経路として用いられたものがたまたまうまく着色にも役立ち、独自の色素を進化させたのではないだろうか。
毒鳥ピトフーイも従来感がられていたほどは捕食者対策でなく食物中の毒を排泄する役割も考えられている [#ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] (5) 毒鳥ピトフーイなどの対毒性 (BTX 耐性) 参照]。羽毛への排泄から始まる二次的な役割の進化は一般論として成立し得るかも知れない。
[どの感覚をシグナルに用いるか]
嗅覚は視覚や聴覚とは違って対応物質についてそれぞれ遺伝子が存在して結構な数になる。それぞれの遺伝子が不要になれば機能しない偽遺伝子となっていずれは失われる。失った嗅覚レパートリーを取り戻すことは難しく (遺伝子重複などが起きる必要がある)、一般的には進化とともに数が減ってゆく傾向がある。
すなわち嗅覚を進化させると言ってもたかだか感度を上げるぐらいのことしかできない。
鳥類では飛行への適応のために負担となる遺伝子を捨てる傾向にあるので嗅覚遺伝子も捨てるよい候補になるように思える。逆に言えば嗅覚遺伝子が残っていればそれは生存にそれ相当の意義があるのだろう。
哺乳類が嗅覚遺伝子をしっかり保存すれば嗅覚は哺乳類の世界のものとなって、鳥類とは差が開く一方となろう。これぞ哺乳類の独壇場か?
鳥類の嗅覚遺伝子数はあまり調べられているわけではないが (それなりの高精度の解析が必要でゲノムの精度が上がると数も結構変わってくる)、
Yang et al. (2015) (#ハチクマの備考の [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ]) の表によれば、偽遺伝子の割合は異なるがニワトリとキンカチョウで嗅覚遺伝子数はあまり違いがなく、上記の予想に反して現在の鳥類の祖先系統から Telluraves 系統さらにスズメ目に至るまで嗅覚遺伝子はそれほど失われていない結果となっている
(嗅覚で食物を探すことで有名なキーウィは最も古い系統でこれは素直に納得できる)。
嗅覚はそれだけ生存に有益な情報をもたらしてきたのだろう。
嗅覚が特に鋭敏と言われるフクロウオウム (カカポ) でも数はあまり違わず、嗅覚遺伝子数を増やして対応できるわけではない模様。フクロウオウムは Telluraves 系統中でもスズメ目と並ぶオウム目なのでこの2系統の祖先も同様の嗅覚遺伝子を持っていたのだろう。Australaves まで遡っても同様で、初期のハヤブサ目も同様の嗅覚遺伝子を持っていたと想像できる。
このように考えて後のタカ・ハヤブサと比較すると Telluraves の祖先系統は現在のタカ・ハヤブサのような機能的な空の捕食者ではなかったのではないかと思える。嗅覚も鋭敏で Telluraves の祖先系統が (機能的な空の捕食者ではなかったとしても) すでに捕食者であったとすれば哺乳類も嗅覚シグナルを積極的に使いにくかったかも知れない。
しかしそれぞれの系統の中では不要な嗅覚遺伝子を失ったものは多数ある模様で、やはりタカ、ハヤブサ類は少ない。スズメ目でもカナリアは少ない。ユキドリ (snow petrel) では嗅覚の発達しているはずの海鳥なのに数は少なく、祖先系統で一度失ってしまったのだろうか。系統上ではネッタイチョウやアビなどと比較できるばわかるのかも知れない。
遺伝子数では哺乳類の能力には及ばないだろう (ただし数についてはゲノム精度依存なので今度の解析で解釈が変わるかも知れない。キンカチョウとカナリアがあまりに違うには不自然に見える)。残った遺伝子をどのぐらいフル活用しているかは偽遺伝子化率を見ればわかる。あまり使っていなければキンカチョウのように偽遺伝子化率が高くなる。
猛禽類の中でも嗅覚遺伝子が多いと言われるハチクマですらも祖先型で予想される数字の半分以下なので、新世界ハゲワシから分岐後のタカ類の早い段階で嗅覚遺伝子をかなり失ったのだろう。
そう思ってタカ類系統樹を見直すと旧世界ハゲワシの Gyps 属は祖先が活発なハンターだったため (チュウヒワシ亜科 Circaetinae と並んで系統をなす) 嗅覚もおそらくだいぶ失われており、新世界ハゲワシとは異なって嗅覚で食物を探していないだろうことも理解しやすい。
ただし研究されている種類はいずれも有名種ばかりで (ハヤブサ、ワキスジハヤブサ、イヌワシなど) 系統的に後の方で現れたものが中心なのでどの段階で嗅覚遺伝子が失われたかなどの全貌を知るにはもっと多種のデータが必要だろう。系統樹を参照の上、同系統の他の種も調べればハチクマの嗅覚が特に目立たない結果になる可能性も十分ありそう。
オウム目と並ぶハヤブサ目の新しい系統でタカ類同様嗅覚遺伝子が大きく失われているのは興味深い。これも収斂進化と言えるのだろうか。哺乳類の主要捕食者であるこれら猛禽類の嗅覚があまり鋭くないため、哺乳類では嗅覚による仲間うちのみで通じるシグナルが一層有効なのだろう。
順序関係はわからないが、猛禽類が (嗅覚遺伝子進化の避けがたい宿命として、進化のどこかの段階で) 鋭い嗅覚を失っていたため、哺乳類が温存していた嗅覚シグナルをさらに活用するようになった、ということかも知れない。もっとも嗅覚遺伝子も複雑ネットワークをなすだろうから数が減ると嗅覚が目に見えて劣るとは簡単には言えないかも知れない。少々失っても別の遺伝子が補ってくれる部分もあるだろう。
複雑系でよく見られるべき乗則 (#鳥類系統樹2024の解説参照) から想像すれば遺伝子の実数よりも対数で見ると良いかも知れない。感覚におけるヴェーバー-フェヒナーの法則 (Weber-Fechner law) みたいなもの? 1桁減ったらそれ相応の能力低下があるだろう、という感じだろうか。
聴覚のメカニズムは嗅覚の進化メカニズムとは異なるので聴覚の鋭い猛禽類からはやはり逃れにくい。そのため猛禽類に聞こえにくい、あるいは定位しにくい高音を用いたりすることになる。リスの声も聞き慣れない何かの鳥の声かと思ってしまうが、高い音は野鳥用に設定した録音だと音域がカバーしきれないので鳥の聴覚の世界を超えた音を使っているよう。
バードリスニングも我々と鳥の聴覚特性が (たまたま? それとも何か必然的に?) 似ていることで楽しめる趣味になっているのだろう。
感覚の世界もそうだろうが情報処理能力 (知能) も同様に被食者と捕食者の関係で進化したと考えると納得が行く気がする (これも誰かが議論してそうだが)。被食者がシグナルを工夫するなど見つかりにくい戦略を進化させるとともに捕食者も情報処理能力を高める必要があるだろう。
感覚の進化は生理的限界で制約されるだろうが、ソフトウェアである知能はまだまだ進化の自由度がありそうである。被食 - 捕食の関係は普遍的なものなので、ある程度以上のレベルの頭脳を獲得すれば知能の進化は自動的に起きてもおかしくない気がする。
自己組織化と自然選択により自然界の法則に従って生命が誕生するのならば、知的生命の誕生もまた同じ法則の延長上にあるのかも知れない。ただしそれには膨大な時間を要するだろうというのが地球を観察した N=1 例からの想像である。
[オオルリ用巣箱]
キビタキのために巣箱が利用された事例はご存じであろう。オオルリ用の巣箱もある。オオルリは人工物もよく使うので適当な構造物があれば簡単に用いるようである。
小林他 (2001) 人工巣台に営巣したオオルリ、
大原・片倉 (2007) オオルリ Cyanoptila cyanomelana の巣箱における営巣。
実はもっと簡単な造りでもよいらしく、オオルリの巣箱と営巣記録 (音羽の野鳥ウェブサイト)
こんなに開放的でよいのだろうかと一見思えるのだが、空からの攻撃よりヘビやイタチなどの地上性の捕食者の方がより脅威なのだろう。
[鳥とヒルの関係]
地域によって山の探鳥でヒル対策が必須のところがあるだろう。ヤイロチョウの観察に行った滋賀県の朽木も非常にヒルが多かった。ヒルの多い地域では鳥は宿主になっていないのか不思議な気がするが、
Ji et al. (2022) Measuring protected-area effectiveness using vertebrate distributions from leech iDNA に中国雲南地方でヒルの体内の DNA から宿主を調べた研究があった。
これを見ると哺乳類だけでなく両生類が多く、鳥もかなりの種類が検出されてヒルの宿主となっていることがわかった。ヒルの体内の DNA から地域の生物多様性を調べるのに役立つとのこと。
種類はそれなりに検出されているものの頻度はやはり哺乳類と両生類が高かった。鳥では地上性のキジ科が目立ったとのことだが日本と共通種がないので、検出されたリストに入っているカラオオルリに関連する項目に含めておいた。
どうも地上性がポイントのようで哺乳類が多いのは必然的に地上性が多いため、両生類が多いのはやはり地上性で裸出部が多い (個体数も多い) ことが関係しているのだろう。
爬虫類は少なく、鳥も裸出部が少ないのでヒルにとってはあまり都合がよいわけではないがとりつかないわけではない。カラオオルリは地上営巣性なのでスズメ目の中ではヒルにやられやすいのだろうか。
iDNA とは何のことかと見ると invertebrate の i を用いているようで、無脊椎動物がサンプルした DNA の意味とのこと。脊椎動物がサンプルした DNA を vDNA とは特に書かないようなので、単に流行に乗った命名のような気もするが。
鳥が好みのヒルの系統もあるようで、水鳥が主な宿主となるとのこと。Ceylan et al. (2021) Function of the waterfowl nests as reproduction and living areas for leeches (Annelida: Hirudinea)
のような研究もあり、カンムリカイツブリやオオバンなどが出てくる。水辺で営巣するとリスクも大きいのかも。
鼻腔にとりつかれて死んだカモの子の報告もある: Rollinson et al. (1950) Deaths in young ducklings associated with infestations of the nasal cavity with leeches。
日本でヒルが増えたのはシカの増加に適応したものとのの研究 (新聞記事で知って調べた): Morishima et al. (2020) Sika deer presence affects the host-parasite interface of a Japanese land leech。
この iDNA 研究では鳥は見つかっておらず哺乳類と両生類。シカが増えてカエルからシカに好みを移したらしい。カエルの血液は資源に乏しいらしい。
新聞記事ではシカの場合は免疫が作られず、ヒルに吸われたシカの血を吸っても大丈夫の趣旨の説明があったがこの論文の範囲では不明。
ニホンヤマビルの吸血による抗ヤマビル抗体産生と抗体によるヤマビル生息密度の免疫学的制御 (吉葉・石井 1992)、
何房総に大発生したヤマビル11年間の生態と国内各地の山蛭バイオハザートの実態 (吉葉 1995) に関連すると思われる記述があった (日本語の研究は探すのも読むのも難しい...)。30 年も前の知見だが今でも通用するのだろうか。
[その他]
Kan and Li (2011) Cyanoptila cyanomelana mitochondrion, complete genome
にミトコンドリアゲノムが発表されているが、Sangster and Luksenburg (2021) Sharp Increase of Problematic Mitogenomes of Birds: Causes, Consequences, and Remedies
によればこれは同定間違いとのこと。
-
ロクショウヒタキ
- 学名:Eumyias thalassinus (エウミュイアス タラスシヌス) 海の色の美しい青緑色の鳥
- 属名:eumyias (合) 美しいヒタキ [eu (int) とても美しい、myias ヒタキ < muia, muias ハエ piazo 捕まえる (Gk)]
- 種小名:thalassinus (adj) 海の色の < thalassinos (Gk) < thalassa, thalasses 海 (Gk)
- 英名:Verditer Flycatcher (青緑のヒタキの意味)
- 備考:
eumyias は外来語からの合成語で発音は明確でないが、起源となるギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。推定アクセント "エウミュイアス"。
thalassinus も同様に短母音のみと考えられ、-las- がアクセント音節と考えられる (タラスシヌス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。第7版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)とも亜種不明。世界的には2亜種で基亜種 thalassinus は中国南部からヒマラヤにかけて分布、地理的にはこの亜種が近い。もう1亜種 thalassoides はマレー半島からボルネオ島に分布。
Zhao et al. (2023) の分子系統樹 (#ヨーロッパコマドリの備考参照) ではオオルリに一番近い系統は Eumyias 属となるが、音声的にはむしろ Niltava 属の方が似ているように思える (#チャバラオオルリの備考参照)。
Most beautiful trilling caller in Himalaya: Verditer Flycatcher warbles its call loudly in spring
を見てもあまりオオルリに似ていない印象を受ける。
もっとも Cyanoptila 属と Niltava 属にもそれなりの距離があり、音声が違っていても不思議ではないかも知れない。また表現型としての音声と遺伝的系統に乖離があるのかも知れない。
オオルリはこれら主に亜熱帯 (Niltava) や熱帯〜亜熱帯 (Eumyias) 属の留鳥から長距離の渡りを行うように進化したものと考えられるので、これらの種類とオオルリを比較することはオオルリの進化を考える上でも興味深いであろう。
なお多数の種を持つ青いヒタキ類である Cyornis 属も同系統だが、上記3属とは少し異なる系統になる。音声面でもやや違う感じがするが系統的に調べたことはない。
しかし大陸のオオルリのミトコンドリアゲノム HQ896033.1 から BLAST をやってみるとやや印象が違う。統合されたはずの Rhinomyias + Cyornis 属と Cyanoptila 属が互いに単系統の関係にならない。
ミトコンドリアゲノムを用いた解析のみで、かつ読まれているものは少数種、どれかのゲノムに誤りがあってもわからない状況なので簡単には判断できないが、Cyornis 属と Cyanoptila 属の関係は以下ほど簡単でなく、(系統2) が分離されるかどうか自明でない気がしてきた。Niltava 属とは十分距離があるのでこの系統と分けられることは問題ないだろう。
ノドジロミツリンヒタキ Cyornis umbratilis (現在の学名で) のミトコンドリアゲノムが発表されたのは 2022 年で各種解析にまだ反映されていなかも知れない。
ノドジロミツリンヒタキに属名 Rhinomyias が復活する可能性もある (Rhinomyias のタイプ種なので復活する場合はこの属となる) だろうし、Cyanoptila 属が Cyornis 属に内包されるとなると Cyornis Blyth, 1843 の方が Cyanoptila Blyth, 1847 より古いのでオオルリの属が変わる可能性も考えられる。
系統樹形態次第で、Cyanoptila 属は現在2種のみなので、多数の種の学名変更を伴う他属の分割をしてまで独自性を認めるかどうか判断が分かれるかも知れない。
オオルリの学名を Cyornis cyanomelana とする扱いは過去にあったようで、Laptev (1990) で用いられ、2018 年に Some materials on the biology of the blue-and-white flycatcher Cyanoptila cyanomelana (pp. 3365-3367) で再掲された際には当時の学名に改められていた。
Niltava 属に含まれていた時代もあって、分子系統解析からはこの属に再度戻ることはなさそうに見える。
我々としては現在の Cyornis 属が単系統でない場合は再度分割してもらった方が多分ありがたいことになるが、より分岐の深い Tarsiger 属は分けられていないので、分子系統解析次第で Cyanoptila 属を Cyornis 属に吸収の可能性があるかも知れない。
もう少し高精度のゲノム解析 (例えば UCEs) でもっと多くの種が読まれるまでお預けになるだろうが、オオルリの系統解析はもう一波乱あるかも知れない。逆に言えば Cyornis 属にそれほど近い可能性がある。数年のうちにだいぶわかるようになるかも知れない。
オオルリの属がもし変わってもオオルリを含む属がオオルリ属と呼ばれることはおそらく変わらないだろう。この例を見ても属名を和名で記述する場合は必ず学名を添えておいた方がよい。属名に和名を与える習慣も現代ではあまりふさわしくなくラテン表記のままの方がよいのかも知れない。英語では集合名があるものもあるが、属に必ずしも特別な英名を与えていないことも多い。我々も属名のラテン語表記に慣れておいた方がよいかも知れない。
和名は変わりにくいと言いつつも概念は変化し得る。
単形属 (Cyanoptila 属もかつてはそうだった) は現代的な分子系統樹では祖先系統の古い分岐が残存している傾向が大きいが、Cyanoptila 属ではそれほど古く分岐した系統ではなく、むしろ Cyornis 属から新しく派生した系統の可能性もある。属境界の判定には系統樹と類似性のみでなく生物地理学的知見も用いられるだろうから、詳しい情報が得られればなおさら統合される可能性があるかも知れない。
コマドリやコルリの属が変わったことと同じことがオオルリでも起きる可能性がある。
オオルリのさえずりが熱帯の近縁種や大陸の同属のカラオオルリ (ここではこの和名を用いておく) Cyanoptila cumatilis Zappey's flycatcher と異なるのは長距離渡りによる選択圧の違いの効果も考えられるかも (#クロツグミの備考 [クロツグミが日本三鳴鳥に選ばれなかった理由関連] 参照)。キビタキとキムネビタキ Ficedula elisae の関係にも似ている。
また熱帯や大陸に比べて島では昼行性猛禽類の多様性が低いため、目立つところで目立つ音声でさえずっても捕食リスクが相対的に低いのかも知れない。
[オオルリ (アオヒタキ) 亜科 Niltavinae の系統分類]
Garg et al. (2024)
When colors mislead: Genomics and bioacoustics prompt re-classification of Asian flycatcher radiation (Aves: Niltavinae)
が出版され、Boyd の分類にあった学名未定の属が解消されたため一覧を提供する。
系統順序は Garg et al. (2024) に合わせておく。系統番号は系統が分かれる部分でこちらで振ったもの。(系統0) は Garg et al. (2024) に含まれていないもので Boyd から。
オジロアオヒタキについては Sangster et al. (2021) A new genus for the White-tailed Flycatcher Cyornis concretus (Aves: Muscicapidae) が新属を提案。
オオルリ (アオヒタキ) 亜科 Niltavinae: Blue Flycatchers
(系統0)
ハイイロコバネヒタキ属 Sholicola (インド南部)
ハイイロコバネヒタキ Sholicola major Nilgiri Blue Robin
シロハラコンヒタキ Sholicola albiventris White-bellied Sholakili
* Sholicola ashambuensis White-bellied Blue Robin (シロハラコンヒタキより分離)
(系統1)
オジロアオヒタキ属 Leucoptilon (Cyornis 属より分離)
オジロアオヒタキ Leucoptilon concretus White-tailed Flycatcher (東南アジア)
(系統2)
オオルリ属 Cyanoptila
オオルリ Cyanoptila cyanomelana Blue-and-white Flycatcher
カラオオルリ? Cyanoptila cumatilis Zappey's Flycatcher
アイイロヒタキ属 Eumyias
アイイロヒタキ Eumyias indigo Indigo Flycatcher
チモールヒメヒタキ Eumyias hyacinthinus Timor Blue Flycatcher (Cyornis 属より移動)
アオムネヒタキ Eumyias panayensis Turquoise Flycatcher
ロクショウヒタキ Eumyias thalassinus Verditer Flycatcher
[以下この属と思われるが Garg et al. (2024) の系統樹に含まれていない]
インドアイイロヒタキ Eumyias albicaudatus Nilgiri Flycatcher
セイロンヒタキ Eumyias sordidus Dull-blue Flycatcher
ブルミツリンヒタキ Eumyias additus Buru Jungle Flycatcher
(系統3)
アオヒタキ属 Niltava
チビアオヒタキ Niltava macgrigoriae Small Niltava
オオアオヒタキ Niltava grandis Large Niltava
コチャバラオオルリ Niltava sundara Rufous-bellied Niltava
フッケンアオヒタキ Niltava davidi Fujian Niltava
[以下この属と思われるが Garg et al. (2024) の系統樹に含まれていない]
チャバラオオルリ Niltava vivida Taiwan Vivid Niltava
* Niltava oatesi Chinese Vivid Niltava (チャバラオオルリより分離)
(系統4)
ノドジロヒタキ属 Anthipes (ネパールからスマトラ島)
ノドジロヒタキ Anthipes monileger White-gorgeted Flycatcher
[以下この属と思われるが Garg et al. (2024) の系統樹に含まれていない]
アカメヒタキ Anthipes solitaris Rufous-browed Flycatcher
(系統4a)
ヒメアオヒタキ属? Cyornis
ウスヒメアオヒタキ Cyornis unicolor Pale Blue Flycatcher
ノドジロミツリンヒタキ Cyornis umbratilis Grey-chested Jungle Flycatcher (かつて Rhinomyias 属)
クロアゴヒメアオヒタキ Cyornis caerulatus Sunda Blue Flycatcher
ムナオビミツリンヒタキ Cyornis brunneatus Brown-chested Jungle Flycatcher (かつて Rhinomyias 属)
ボルネオヒメアオヒタキ Cyornis superbus Bornean Blue Flycatcher
マレーシアヒメアオヒタキ Cyornis turcosus Malaysian Blue Flycatcher
シナヒメアオヒタキ Cyornis glaucicomans Chinese Blue Flycatcher
インドシナヒメアオヒタキ Cyornis sumatrensis Indochinese Blue Flycatcher (ノドアカヒメアオヒタキより分離)
マングローブヒメアオヒタキ Cyornis rufigastra Mangrove Blue Flycatcher
スラウェシヒメアオヒタキ Cyornis omissus Sulawesi Blue Flycatcher
(ミヤマヒメアオヒタキ) Cyornis whitei Hill Blue Flycatcher (Cyornis banyumas より分離。いずれもミヤマヒメアオヒタキと呼ばれることがある)
ムネアカヒメアオヒタキ Cyornis rubeculoides Blue-throated Blue Flycatcher
ハイナンヒメアオヒタキ Cyornis hainanus Hainan Blue Flycatcher
オリーブミツリンヒタキ Cyornis olivaceus Fulvous-chested Jungle Flycatcher (かつて Rhinomyias 属)
ダヤクヒメアオヒタキ Cyornis montanus Dayak Blue Flycatcher (Cyornis banyumas より分離)
バンガイミツリンヒタキ Cyornis pelingensis Banggai Jungle Flycatcher (かつて Rhinomyias 属)
スーラミツリンヒタキ Cyornis colonus Sula Jungle Flycatcher
[以下この属と思われるが Garg et al. (2024) の系統樹に含まれていない]
ミミグロヒメアオヒタキ Cyornis ruckii Rueck's Blue Flycatcher
ルソンヒメアオヒタキ Cyornis herioti Blue-breasted Blue Flycatcher
シロハラヒメアオヒタキ Cyornis pallidipes White-bellied Blue Flycatcher
メスガタヒメアオヒタキ Cyornis poliogenys Pale-chinned Blue Flycatcher
(ミヤマヒメアオヒタキ) Cyornis banyumas Javan Blue Flycatcher
オオヒメアオヒタキ Cyornis magnirostris Large Blue Flycatcher
ラムゼイヒメアオヒタキ Cyornis lemprieri Palawan Blue Flycatcher
ノドアカヒメアオヒタキ Cyornis tickelliae Tickell's Blue Flycatcher
フロレスヒメアオヒタキ Cyornis djampeanus Tanahjampea Blue Flycatcher
セレベスヒメアオヒタキ Cyornis hoevelli Blue-fronted Blue Flycatcher
サンフォードヒメアオヒタキ Cyornis sanfordi Matinan Blue Flycatcher
フロレスミツリンヒタキ Cyornis oscillans Flores Jungle Flycatcher
スンバヒタキ* Cyornis stresemanni Sumba Jungle Flycatcher
ニコバルミツリンヒタキ Cyornis nicobaricus Nicobar Jungle Flycatcher
アカオミツリンヒタキ Cyornis ruficauda Philippine Jungle Flycatcher / Rufous-tailed Jungle Flycatcher
和名の後に * のあるものは eBird から。
この論文で解析された種類の系統は相当正確と思われる (ほぼ 100% に近いサポートになっている)。
扱われていない種類は東南アジアの島のものが大半を占める。
(系統2) そのものの分岐は古いが、その中でオオルリ属 Cyanoptila とアイイロヒタキ属 Eumyias の分岐は比較的新しい。
アイイロヒタキ属の中から長距離渡りをするものを含むオオルリ属が分かれたと考えるとわかりやすい。
アイイロヒタキ属 Eumyias のタイプ種はアイイロヒタキ。
アオヒタキ属 Niltava は日本産種には含まれない見通しだが検討種には複数が含まれる。
(系統4) のうちでノドジロヒタキ属 Anthipes のみが古い分岐になっている。
(かつて Rhinomyias 属) とあるのは分子系統解析の結果内包される結果となって統合されたもの。IOC ではすでに反映されている。
ヒメアオヒタキ属? Cyornis のタイプ種はムネアカヒメアオヒタキだが名前も長く、多くの種の和名に含まれるヒメアオヒタキを採用した。検討種 (ムナオビミツリンヒタキ) が1種ある。
この属に関する種分割の研究は Zhang et al. (2016) Unexpected divergence and lack of divergence revealed in continental Asian Cyornis flycatchers (Aves: Muscicapidae) 参照。
スラウェシヒメアオヒタキ Cyornis omissus と セレベスヒメアオヒタキ Cyornis hoevelli はどちらもセレベス/スラウェシ島に分布するがほぼ同名なので例えば後者を変更するのがよさそうに見える。
(ミヤマヒメアオヒタキ) Cyornis whitei と (ミヤマヒメアオヒタキ) Cyornis banyumas は同種の時代は後者の学名であったが、前者 Hill Blue Flycatcher が圧倒的によく知られていて観察数も多いため、ミヤマヒメアオヒタキの名称は前者として後者を新たに命名する方がよさそうに見える。
属名由来は Sholicola タミール語 sholai 森林渓谷 -cola 住む。
Leucoptilon leukos 白い ptilon 羽 (Gk)。
Anthipes Anthus (タヒバリ) 属 + pes 足 (Gk)。
-
チャバラオオルリ (第8版で検討種)
- 学名:Niltava vivida (ニルタウァ ウィーウィダ) 鮮やかなチャバラオオルリ
- 属名:niltava (合) Niltau はネパール語でコチャバラオオルリ Niltava sundara 英名: Rufous-bellied Niltava を指す
- 種小名:vivida (adj) 元気な、鮮明な
- 英名:Vivid Niltava, (IOC分類では Taiwan Vivid Niltava)
- 備考:
niltava は外来語由来で発音は不明だが、すべて短母音とすれば冒頭にアクセントがあると考えられる (
ニルタウァ)。
vivida は冒頭が長母音でアクセントもここにある (ウィーウィダ)。
英語にも vivid の単語があるので英語流の発音はかなり異なっていると想像できる。フランス語の vivre (生きる) は冒頭が長母音でラテン語の影響が残っているのかも知れない。読み方は言語圏次第と想像できる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに検討種扱いに移動。いずれも亜種は当時の基亜種 vivida としており、主に台湾に分布している。
第7版検討の経緯は 本鳥類目録改訂第7版で新たに掲載された種および亜種の記録等について (2014)に記載がある。
当時亜種扱いであった oatesi (英国勅使の Eugene William Oates に由来) は現在 (IOCなど) 別種扱いで、Niltava vivida (英名 Taiwan Vivid Niltava) と Niltava oatesi (英名 Chinese Vivid Niltava、和名はまだなし) となる。記録検討時はこの2種の判別が必要になる。
チャバラオオルリは系統的にオオルリに近い属 Niltava 属で、台湾のビデオ Vivid Niltava を見ていただければ色こそ違うものの、まるでオオルリのようにさえずっているのがわかる。声も生息環境も似ている。
インドのビデオ Vivid niltava (現在の分類では台湾の種とは同一でないが種名はよくわからない。Niltava oatesi Chinese Vivid Niltava かも知れない) に記録されている行動もオオルリに非常に似ている。
ビデオにはコメントはないがオオルリの場合にはこの姿勢はメスが近くに現れて交尾寸前の場合によく見られる (他オスが近づいて興奮している時にも見られる)。
台湾の観察者によるとメスもさえずると言われている。オスのようにさえずるのか、あるいはオオルリのように警戒の声としてさえずるのかはよくわからない。
△ スズメ目 PASSERIFORMES イワヒバリ科 PRUNELLIDAE ▽
-
イワヒバリ
- 学名:Prunella collaris (プルネルラ コルラーリス) 首に特徴のある褐色の小鳥
- 属名:prunella < Braunelle ヨーロッパカヤクグリ (独) < 中世ラテン語の prunus = brunus = 独 braun -elle 指小辞女性形 (Helm Dictionary 他) ヨーロッパカヤクグリ (英名 dunnock) は日本とは異なり、ヨーロッパではごく身近な鳥の一つ。愛媛の野鳥「はばたき」では「褐色の(小鳥)」
- 種小名:collaris (adj) 首に特徴のある (collum (n) 首 -aris に関係した)
- 英名:Alpine Accentor
- 備考:
prunella の発音はあまり明確でないが、prunus (プラムの木で意味は違う) は最初が長母音。
Braunelle から別由来で作られたために発音が異なると想像される。
-nel- の音節にアクセントがあることは明瞭で、音声の聞けるページからは "プルネルラ" でよいと考えられる。
collaris は中央が長母音でアクセントがある (コルラーリス)。
日本鳥類目録改訂第7版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに亜種は erythropygia (eruthros 赤 -pugios 腰の Gk「赤い腰の」の意味)。アルタイ山脈、オホーツク海沿岸、朝鮮半島にも分布する亜種。
Hartert (1910-1922) では p. 765。
この亜種の記載時学名 Accentor erythropygius Swinhoe, 1870 (原記載。次ページに図版) 基産地 Kemeih, Prefecture of Seuenhwafoo (中国北部)。
Hartert (1910-1922) が日本 (Nippon と表記して北海道を除くことを意図していた) も分布に含めたこともあったためか日本からの亜種記載はなかった模様。
世界的には多数の亜種が知られ、ヨーロッパから日本かけて分布する。台湾の亜種は fennelli で主に高山に分布する。
Prunella 属は和名カヤクグリ属。Prunellidae 科はイワヒバリ科と異なっているので注意。
「夏の鳥」(小学館 1984) p. 134 によれば岩地にいるヒバリのような美声の持ち主が名称由来とのこと。
種の記載時学名は Sturnus collaris Scopoli, 1769 (原記載) 基産地 Carinthia (ケルンテン。現在のオーストリア南部)。
collaris は "首輪のある" で使われることが多いが、"首に関係した" の語義もある。ここでは後者。wiktionary によれば collum (首) + -aris で collaris の形容詞、そこから派生して collare (首輪)、その属格が collaris と同じ形になる。
イワヒバリでは gula alba fusco maculata とあってのどが白くて褐色の斑点があることを意味している。
原記載を眺めていると1つ前のページにワキアカツグミ Turdus iliacus [これは Linnaeus (1758) の学名] があり、iliacus < ile (脇腹) に対応させて大まかな部位の名称で collaris < collum (首) としたものかも知れない。
"のど" を意識した学名が実際にあって Fringilla gularis Andreae, 1776 (参考)、これは Scopoli の学名の属を変える (ムクドリ類からアトリ類に) とともに種小名を変更したものと思われる。
英語別名に Collared Accentor があったがこれは誤訳に近い。
一時期は Accentor 属となって現在の亜種 erythropygia は記載時学名 Accentor erythropygius Swinhoe, 1870 (原記載 基産地 Kemeih, Prefecture of Seuenhwafoo (中国北部の山の名前と記載にある)。
この記載をみると Accentor 属が Sturnus 属から分離された時または後に Accentor alpinus の学名が与えられたようで (#ノスリの備考参照)、Alpine Accentor の英名に対応している。当時この英名が存在したため英語から付けられた学名と考えられる。
この Accentor 属は Bechstein (1802) だったが、Bechstein (1797) はヨーロッパのムナジロカワガラス (Dipper) についてこの属名をすでに用いていた。
先取権の原則からはムナジロカワガラスの用例の方が早いが、今からムナジロカワガラスを Accentor とするのは混乱を招く。イワヒバリ類について次に古い属名は Prunella Vieillot でこの属名は Hartert などが用いている
[Hartert (1910-1922) p. 762 参考]。
Accentor の属名はヨーロッパカヤクグリ類 (現在は Prunella 属) のために残しておく (nomen conservandum) ことにして現在の属名の用法が決まったとのこと (BOU 1915) (The Key to Scientific Names)。
イワヒバリ類が Prunella 属に移された結果、新属のために作られた Accentor alpinus の学名はおそらく意味がなくなって (規則も変わって) イワヒバリの中で最も記載の早い Prunella collaris が採用されたものと考えられる。
現在では alpinus/alpina は用いられなくなっているが亜種名の subalpina に痕跡が残っている (記載当時は Accentor alpinus の一つの型とされていた)。
英語の Accentor はラテン語 accentor 由来とのことで ad (一緒に) + cantor (歌い手) が語源とのこと。"アクセントを付ける" の意味の英語の意味は特にない模様。音楽では古い用法で "先のパートを歌う者" の意味があった (wiktionary)。
英語別名に Alpine Dunnock もありこちらは高山のヨーロッパカヤクグリの意味。
[Prunella 属の種分化]
Prunella 属の種分化については Alstrom et al. (2017) Explosive radiation and spatial expansion across the cold environments of the Old World in an avian family がある。
イワヒバリは祖先系統 (clade B)、カヤクグリとヤマヒバリは急速な種分化を遂げたグループ (clade C) のメンバー。
Drovetski et al. (2013) Geographic mode of speciation in a mountain specialist Avian family endemic to the Palearctic の先行研究があり、イワヒバリが大きく離れていることが示唆されていたが核遺伝子なども追加で調べてより確実な系統樹を描いた。
上記 clade C は氷河期に新しい地域に進出し間氷期に分断が進んだ描像となっている。カヤクグリが特に古い系統ではなく、大陸から Prunella 属の2回目の導入で、アジア北東部のヤマヒバリと日本のカヤクグリに種分化した模様。
この clade にはヨーロッパのヨーロッパカヤクグリとヒマラヤや中国高地に分布するアカチャイワヒバリ Prunella strophiata Rufous-breasted Accentor が含まれる。ヨーロッパとヒマラヤの間の低地が日本と大陸の間のように地理的障壁となったものらしい。
他にもユーラシアやイエメンの高地で局地的に分布する他の近縁種のグループも含まれる。隔離固有と言ってよさそう。
ヤマヒバリは南北で隔離分布となっているので南部亜種を認める解釈要因となり得そうだが、長距離の渡りをするため地理的隔離が弱いかも知れない。
この論文の分布図を見るとイワヒバリはかなり多くの亜種に分化していても不思議でない (clade C の種分化も参照)。日本と台湾のイワヒバリは別亜種が与えられているが、日本と大陸は現在同じ亜種になっている。ヤマヒバリとカヤクグリの種分化をみると、イワヒバリでも大陸と日本ではある程度の遺伝的違いがあるのではないだろうか。
ごく簡易的ではあるが KC759302.1 (ND2) をベースに BLAST を試してみるとイワヒバリ内部でかなり違いがあり、亜種の存在はもちろんのこと別種に分離されるものが生じるかも知れない。
精子競争が種分化を促進する? Lifjeld et al. (2023) Rapid sperm length divergence in a polygynandrous passerine: a mechanism of cryptic speciation?
に論文があり、モロッコとスペインでは精子長の分布が重ならないとのこと。強力な精子競争の選択圧の結果、同じ個体群の中ではオスの間で精子長の違いが小さいとのこと。他の表現型に比べて進化速度が何倍も速く、地理的隔離から種分化に寄与すると考えられる。精子長の違いは接合前生殖隔離 (prezygotic reproductive isolation) をもたらす (受精確率が低いなど遺伝子浸透の障壁となる) 可能性があるとのこと。
Alstrom et al. (2017) には精子競争のことは出てこないのでまさしく研究進展中の段階であろう。
分子系統解析の結果ではモロッコとスペインの分離はまだ弱く、ミトコンドリアゲノムを用いた解析 (fig. 5) によるヒマラヤイワヒバリ Prunella himalayana Rufous-streaked Accentor とイワヒバリ (分岐年代 400 万年前程度) の分離よりははるかに新しい。ここで研究されたイワヒバリの2個体群の間の分岐年代は 84 万年程度。しかし精子長の進化速度が非常に早いので推定年代以上に種分化を起こしつつある可能性がある。
ユーラシア東部は調べられていないだけで実は相当違うのかも知れない。もし大陸と日本が別亜種ならば学名が存在しない可能性がある。
先の ND2 を用いた簡易系統樹でも亜種 montana (コーカサスからイラン) と erythropygia (アルタイから日本) は別系統に分かれるので別種が妥当となるかも知れない [Drovetski et al. (2013) の系統樹でも "黄色いセキレイ" の一連の種と同程度の系統分離となっている]。
Drovetski et al. (2013) のサンプルの erythropygia もロシアとなっていておそらく極東個体は未調査と思われる。
この論文では Prunella 属の分割も念頭にあり、大型で山岳性のイワヒバリ (large accentors) を Laiscopus グループ (亜属) として扱っている。残りの Prunella 属が茂みに適応したもの。
分岐年代的にはタヒバリ類とセキレイ類の分岐に近く、別属にしても構わないぐらい。
属分離の好きな Boyd も別属扱いや種分割は行っていながイワヒバリが複数種に分割される可能性には言及がある (2025.3 段階)。
この視点から見れば日本には大型系統 (Laiscopus?) のイワヒバリと、その後小型の Prunella 属のカヤクグリが2系統定着したこととなってわかりやすい感じがする。系統進化的にはタヒバリ類の後にセキレイ類が定着した関係と似ている。この論文ではイワヒバリ類の祖先はヒマラヤ地域出身と考えている。
これらの研究をふまえ、Prunella 属の一覧を作成してみた。配列は Alstrom et al. (2017) による。
スズメ小目 Passerida
スズメ上科 Passeroidea のうち Core Passeroidea
イワヒバリ科 Prunellidae: Accentors
(系統 1: clade B Laiscopus?)
ヒマラヤイワヒバリ Prunella himalayana Altai Accentor
イワヒバリ Prunella collaris Alpine Accentor
(系統 2: clade A)
クリイロイワヒバリ Prunella immaculata Maroon-backed Accentor
ムネアカイワヒバリ Prunella rubeculoides Robin Accentor
(以下最後まで系統 2 のうちの clade C)
(以下の3種を clade E)
ノドグロイワヒバリ Prunella atrogularis Black-throated Accentor
コーカサスイワヒバリ Prunella ocularis Radde's Accentor
アラビアイワヒバリ Prunella fagani Arabian Accentor
(以下の2種を clade D)
シロハライワヒバリ Prunella koslowi Kozlov's Accentor
ウスヤマヒバリ Prunella fulvescens Brown Accentor
(以下の4種は clade 名はないが D, E とは別系統の clade C)
カヤクグリ Prunella rubida Japanese Accentor
ヤマヒバリ Prunella montanella Siberian Accentor
アカチャイワヒバリ Prunella strophiata Rufous-breasted Accentor
ヨーロッパカヤクグリ Prunella modularis Dunnock / Hedge Accentor
{カヤクグリ + ヤマヒバリ}、{アカチャイワヒバリ + ヨーロッパカヤクグリ} がそれぞれ系統をなす。
clade C の中の分岐は E, D が若干早いと推定されているが残り4種のグループと大差はなく、いずれも急速な種分化を遂げた系統となる。
この表では (おそらく著者も意識していると思われる) この系統がヒマラヤ起源と想定し、分岐年代に従って起源から近い順に並ぶ配列を採用している。そのためヒマラヤから遠いヨーロッパカヤクグリが最後になる。しかしヨーロッパから見て最も身近な種であるヨーロッパカヤクグリが Prunella 属のタイプ種となっている。
属名として採用される可能性のある Laiscopus は Gloger (1843) がイワヒバリのみを指して用いたもの。laes 石 (複数形) skopos (調べるなど) (Gk) (The Key to Scientific Names)。岩場に住む習性を反映したものと考えられる。
イワヒバリを種分割する場合は現状境界未定。亜種数も隔離個体群数も多いのでかなり調べる必要がありそう。erythropygia より記載の早い亜種もあるため、どの亜種とグループを作るか次第で学名が変わる可能性がある (ツメナガセキレイ同様)。東西で2種に分けるならば記載年の古い亜種 montana はヨーロッパの方に含まれるように見える。
その場合はユーラシア大陸東部は亜種 nipalensis が代表する可能性がある。3種以上であればこの限りでなく、分子系統研究がなければ種学名も決められないため別種提案があまり出てこないのだろう。
上述 clade C では急速な種分化に伴って introgression や incomplete linage sorting もあり (用いる遺伝部位によって系統樹が異なる)、分類境界は複雑なものとなっている: Jiang et al. (2024) Gene flow and an anomaly zone complicate phylogenomic inference in a rapidly radiated avian family (Prunellidae)。状況はサバクヒタキ類などと似ている。
この文献でも亜属 Laiscopus を用いている。系統樹形は解析方法によって異なるが {カヤクグリ + ヤマヒバリ}、{アカチャイワヒバリ + ヨーロッパカヤクグリ} がグループを作ることはすべての解析で支持されている。イワヒバリの方がカヤクグリより古い系統である点はまったく疑いがない。チベットのアカチャイワヒバリの全ゲノムを解読したとのこと。
-
ヤマヒバリ
- 学名:Prunella montanella (プルネルラ モンターネルラ) 山にいる褐色の小鳥
- 属名:prunella < Braunelle ヨーロッパカヤクグリ (独) < 中世ラテン語の prunus = brunus = 独 braun -elle 指小辞女性形 (Helm Dictionary 他)
- 種小名:montanella (f) 山にいる小鳥 (montanus -i (m) 山の住人 -ella (指小辞) 小さい)
- 英名:Siberian Accentor
- 備考:
prunella は#イワヒバリ参照。
montanella は montanus の a が長母音で、-nel- にアクセントがあると考えられる (モンターネルラ)。
記載時学名 Motacilla montanella Pallas, 1776 基産地 Dauria。記載時は Motacilla (セキレイ) 属で、少し控えめな種小名になっているのは "山のセキレイ" ではすでに用例がある可能性があることを意識したものかも。
Richmond Index には Pallas (1776) より早い用例は見当たらなかったが、Motacilla monatana の用例はその後いくつもあった。何か問題があったらしくこの種小名はそのまま残らず、カタジロサバクヒタキ 現在の学名で Myrmecocichla monticola Mountain Wheatear と改名されている。
日本鳥類目録改訂第7版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに亜種不明。ロシア北方ウラル山脈付近からシベリアに分布し、冬は朝鮮半島や中国に渡るとされる。2亜種あるが日本へはどちらが渡来してもおかしくない地理的関係になっている。音声によるカヤクグリとの識別は困難とされる。
#イワヒバリ備考の [Prunella 属の種分化] にあるように両種は近年の急速な種分化の結果生まれたものと考えられ、系統の近さが音声にも現れているらしい。
ただしさえずりはかなり異なっている。海外録音だがヤマヒバリのさえずりは自分にはアオジのように聞こえてしまう。分布が広いので地域によってさえずりが異なる可能性も考えられる。
英語別名 Mountain Accentor, Siberian Dunnock。小鳥商の間ではミヤママツムシの名称もあったとのこと (コンサイス鳥名事典)。音声を考えるとわかりやすい名前。それならばマツムシはカヤクグリかと考えてしまうが調べた範囲では見当たらなかった。
中西悟堂「定本・野鳥記」3 p. 205 (1939 年初出) によればマツムシはキクイタダキ、シジュウカラ、ゴジュウカラ、コガラ、ヒガラ、コムシクイ (当時の名前)、エナガの方言にあるとのこと。同様のマツ... の方言名は圧倒的にカラ類が多く、生息場所とマツに関連する動作が名称由来であったことが想像できる。やはり見かけ由来の名称が多く、カヤクグリやその声を知っている人は少なかったのではないだろうか。朝鮮半島からカヤクグリは輸入できないのでヤマヒバリの方が主な飼い鳥となっていたのかも。
Mlikovsky and Redkin (2023) Taxonomic revision of the Siberian Accentor Prunella montanella (Pallas, 1776) (Aves: Prunellidae) (pp. 5769-5790 後半に英語版あり)
が2亜種を新たに記載 (世界的に認められるかどうかはわからないが)。
この分類を採用した場合は日本に最も近い分布の亜種は loskoti (ロシアの鳥類学者 Vladimir Mikhajlovich Loskot 由来。大陸東部の南部亜種)、その北方に位置するのが badia (こちらは Portenko, 1929 がすでに記載。badius くり色から茶色) となる。
計測では北部・南部の分離は結構よい。推定分布図も参照。この記述に従えば南部亜種が未記載だったことになる。
-
カヤクグリ
- 学名:Prunella rubida (プルネルラ ルービダ) 赤みをおびた褐色の小鳥
- 属名:prunella < Braunelle ヨーロッパカヤクグリ (独) < 中世ラテン語の prunus = brunus = 独 braun -elle 指小辞女性形 (Helm Dictionary 他)
- 種小名:rubida (adj) 赤みをおびた (rubidus)
- 英名:Japanese Accentor
- 備考:
prunella は#イワヒバリ参照。
rubida は冒頭が長母音でここにアクセントがある (ルービダ)。
日本鳥類目録改訂第7版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに亜種は記載なし。通常は単形種とされるが、亜種を認める見解もある (例えば Clements)。
その場合は2亜種 rubida (本州から南部) と fervida (fervidus 燃えるような; 南千島から北海道。エゾカヤクグリとも呼ばれた) になる。
従来は(準)日本固有種とされていたが、サハリン南部にも分布するためこの呼び方は適切ではなくなった。Nechaev (1991) の著書にすでに繁殖分布として現れており、近年分布を拡大したというより従来十分に調査されていなかったためと考えられる。日露渡り鳥条約の指定種に含まれている。
[カヤクグリは1種? 2種?]
種記載時学名 Accentor modularis rubidus Temminck & Schlegel, 1845 (原記載) 基産地日本。図版。
与えられたフランス語名は l'accenteur ordinaure rougeatre でヨーロッパカヤクグリの別の型で、race の表現は用いているので現在の亜種に相当するものを意識していた模様。
色彩面で記述可能なためにフランス語名では "赤っぽい黒" としたもののよう。
これらの理由から日本を示す学名やフランス語名を用いず単なる日本版の表記にはしなかったのかも。
この記載では日本からカヤクグリ類を1種 (Le Japon produit un Accenteur, ...) と記述しているので、直接的には複数種が存在するので日本を示す学名を避けたわけではないと思われる。
ただし Temminck はカヤクグリの記載以前にヤマヒバリを Accentor montanellus Temminck, 1820 (参考) と記載しており、これは Pallas の学名の属を変えただけのものになっている (#ヤマヒバリ参照)。基産地の表記も曖昧で、同属でアジアの種類にこの学名を先に用いた都合上地域を用いた名称を避けた可能性も考えられる。
fervida の記載時学名は Accentor fervidus Sharpe, 1883 (原記載, 参考) 基産地 Hakodate, Hokkaido, Japan (Avibase による)。
fervida の原記載によれば Accentor rubidus Whitely, 1867 が存在して Gould が Japanese Hedge-Sparrow と図版を描いたが Temminck and Schlegel のものとは色彩が違い、日本に2種存在するとして改めて別の学名を与えた経緯となっている。表記では Subsp. α と亜種扱いだが当時はまだ亜種の表記は現在のものとは異なっていた。
日本のカヤクグリが1種か2種か議論されていたことになる。
[分布について]
H&M4 の情報によれば Stepanyan (1990) が北海道から千島の亜種として認めたが日本鳥学会 (2000) は認めなかったとの記述がある。Dement'ev and Gladkov (1954) では2亜種を認め、色彩の違いの他に生態が違う (rubida は高地にのみ生息し低地に降りるのは冬のみ) としていた。
AviList の扱いでは亜種は認めず、繁殖分布はサハリン南部、千島列島、北海道から四国。九州で越冬となっていて越冬分布は越冬時は九州にも現れる意味だろう。
Ragimov et al. (2024) Winter records of the Japanese accentor Prunella rubida and the common snipe Gallinago gallinago on Kunashir Island (pp. 3084-3087) に国後島での越冬記録が紹介されている。
ロシアで千島列島南部のみの分布であれば北方領土問題から扱いが微妙になり得るところだろうが、この文献によればサハリン中部から南部、千島列島でもウルップ島などでも繁殖するとのことでロシアでも繁殖種としてもお互いあまり気にする必要がない。ロシア語名でも "日本の" を付けていてオオジシギ同様分布にはあまりこだわっていないよう。
大陸のロシア沿海地方でも迷行が知られているとのこと。
参考までに wikipedia ロシア語版を確認しておくと、サハリンは北緯 51° まで、千島列島ではケトイ島までとのこと。出典は xeno-canto だったがこれらの島での録音があるわけではなく、IUCN (2017) の分布 Japanese Accentor と同じ。この図を見ると日本固有種とは呼びにくい。
サハリンを分布に含めていない少し前までの日本の代表的図鑑の分布表記は相当古いもののよう。おそらく極東特有の種類のため、英語圏の著者があまり気にして改訂しなかったものをそのまま使っていたためだろう。Nechaev (1991) のサハリンの鳥に記述されていて巣と卵の写真も掲載されているので過去の欧米の研究者の文献調査不足だったのだろう。サハリンでの記録は特に最近判明したわけではない。藤巻裕蔵氏による Nechaev (1991) の翻訳 (極東の鳥類 12-14) は 1995-1997 年に刊行されていた。
「日本動物大百科」(1997) 4 p. 95 の分布図にはサハリンはまだ含まれていなかった。Brazil (2009) "Birds of East Asia" では含まれている。
他言語名では "日本の" を冠しているものも多いが、学名由来と思われる色彩表記 (ドイツ語、ハンガリー語、アイスランド語など) もあり、ポーランド語では英語 tawny に相当する色彩表記。中国語も色彩 (紅) で示している。ドイツ語では2種に分けられていた時代の表記も残っていて -rubida を付ける名称もあった。
英語には別名がいくつかある割には色彩に注目したものが見当たらず少し多様性が乏しい。おそらく英語圏からは遠い種で当時分離された2種に別名を付ける必要があまりなかったため (および当時の英語では産地を付けるのが普通だったこと) だろう。色彩表記になっている言語は地名を冠する名称を避けたというよりは、2種に別名を付けるために学名由来となったものと想像できる。逆に言えばその時代 (19 世紀末から 20 世紀初めぐらい) に世界の全種に自国語名を付けていた可能性がある。
英名別名に Japanese Hedgesparrow (Hedge-Sparrow)。これはヨーロッパで普通種のヨーロッパカヤクグリの別名 Hedge Sparrow (和名でイシガキスズメとも訳される) に由来。和名別名にタケサザイ、オオサザイ、カキスズメ がある (コンサイス鳥名事典)。最後のものは英名と関係があるかも知れない。
[古名について]
大橋 (2025) Birder 39(8): 70-71 で「かやくき」の名前が紹介されている。「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) に「かやくき」を用いた歌が紹介されており、「色々の花にまぎるるかやくきをかるとて野べりに暮しつる哉」(藤原俊成 1135 頃) とある。
平安時代後期なので用例はあてはまるように見えるが、色々の花にまぎるるで夏の季語とされるかやくきで、しかも環境が野べりで暮らすとはカヤクグリを表したものとは思えない気がする。
「鳥の手帖」では漢字表記に 日+安+鳥 の文字が使われており、日本国語大辞典 (オンライン) でも同じで、この漢字は本来はウズラの意味。ウズラならば上記用例は納得できる気がする。何を指していたかよくわからないままに詠まれていたのではないだろうか。
萱潜は「鳥の手帖」によれば文明本節用集 (15 世紀後) に登場するとのことだが、萱を潜る鳥などいくらでもいるので本種を指していたものかどうか怪しい気がする。それでなくても目立たない、知名度の低い種類なのでそもそもほとんど認識されていなかったのでは? "カヤ" が付けられた鳥は過去に複数種あったのでは。
大阪の地方名で "カヤ"、"カヤススメ" が挙げられているが大阪の平野部ではあまり越冬する種類ではなく (事例は少数ある)、基本的にそれなりの標高のある山の種類の感じがする。大阪のどこで付けられた地方名か次第だろうが、もし山間部でなく下流部の河川敷近くなどであればもっとよい候補が他にもありそうな気がする。
「愛媛の野鳥 はばたき」によれば地方名ちゃちゃどり、ちゃちゃ、おおさざい、かやきり、かやすずめ、しばくぐり、しょうと、のひばり、やぶすずめが挙がっていたがいろいろ混ざっているかも知れない。
京都ぐらいだと比叡山などが典型的な越冬地で山裾近い標高までは下る感じだが、平野部からは多少上がる必要がある。ミソサザイほど低地までは下らない。近畿地方では感覚的にはアオシギの越冬環境に近い感じがするが皆さんの印象はいかがだろうか ... と書きつつ昔の記録を見ていると山科疎水 (平地に近い山裾) で観察されていた方がおられた。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では1種扱いで Kayakuguri, O-sazai の名前を与えているが、分布は Hokkaido, Suruga とあって Seebohm (1890) "The birds of the Japanese Empire" の Fuji-yama および "Fauna Japonica" で横浜近郊で採集された9標本、Whitely が Hakodadi を与えていた。
山階鳥類研究所標本データベースでは YIO-27114 (Suruga 1898) の小川氏の標本があり、Ogawa (1908) は自身の採集記録も含めて産地を採用したものと思われる。
YIO-27132 (宮城 1885) の標本がより早くあって カヤクグリとオホサザイの名称が示されているが山階旧標本番号が振られていることや、Ogawa (1908) の分布に登場しないことから後に同定・整理されて付けられたラベルと想像できる。
カヤクグリはさすがに 1900 年以前に国内標本のない状況ではなかったが、Temminck and Schlegel の記述した種類の名前として他の種同様にそれらしい可能性のある過去の名前から割り振られたものではないだろうか。古い文献にカヤクグリまたは異名が出ていても同じものを指しているとは限らない気がする。
標本ラベルに用いられるぐらいなのでオホサザイは有力候補だっただろうと想像できる。ミソサザイやシオサザイ (ヤブサメが2種と考えられた時代の南部の種類名) と同列に並べることができて名称系列としては都合がよさそうだが、ヤブサメもカヤクグリもミソサザイとは系統がまったく異なるため同じ語尾を与えるのは好ましくないとの判断となり、"サザイ" は "wren" 系統の訳名に用い、ヤブサメを1種に統合する際にヤブサメの名称を採用し、他はそれぞれ別系統の名前が当てられたのではないだろうか。
その際に Seebohm (1890) が用いていた英名 Japanese Hedge-sparrow に合わせてカヤクグリ、Alpine Accentor (イワヒバリ) と整合させると都合がよく、Accentor に "ヒバリ" 系の名称 (ヤマヒバリも同様) を与えると統一性が出る。
カヤクグリがあるならば他にも "カヤ" の付く種類があるだろうと見てみると カヤノボリ Spizixos semitorques Collared Finchbill (ヒヨドリ類に近い種類) があるが類似性がよくわからない。wikipedia 英語版では日本にも分布する記述となっていて (2025.7 時点)、別名の一つに Japanese finch-bill が挙げられている。
亜種 cinereicapillus が Found in Taiwan and Miyako and Yaeyama Islands of Japan とあるので世界のリスト (日本のリスト由来?) で日本が分布地域とされていた時期があるのではないだろうか。AviList では日本の分布は記されていない。いずれにしても台湾産のものに和名を付けた時代のものと考えられる。
哺乳類では言うまでもなく有名なカヤネズミがあるので名前を決める際に影響があった可能性もあるかも知れない。いずれも植物の名前そのものよりは "カヤ場" と縁が深い意味だろう (台湾のカヤノボリも同様かも)。そのように考えると越冬期の棚田周辺のカヤクグリの習性と合っている気がする。
他に "カヤ" に関連が深いと思われる名前は #サンカノゴイ がある。
また現在の分類で Sclerurus 属の種類は "ヤブクグリ" の和名が付く。カヤクグリと何が違うのかと思ってしまうような名前だが、かつての英名 Leafscraper も "ヤブクグリ" からは少し遠い。現在の標準的な英名は Leaftosser)。現在では分離されている古い属名 Thamnophilus (藪の好きな) 由来らしい。
カヤクグリから派生した和名だったのかも知れないが、藪の好きな小鳥を英語風に表現すると Bush なんとかで、みなウグイスのような名前になってしまうので別系統が使われたのだろうか。当時の分類学者にとって "クグリ" は比較的連想しやすい表現だったのかも知れない。
[その他]
西海 (2014) Birder 28(8): 4-5 ではカヤクグリはヤマヒバリとイワヒバリに追われた遺存固有的な可能性が考察されていたが少し違っていた。#イワヒバリ備考の [Prunella 属の種分化] を参照。
鳥をあまり知らない人が見たら「ちょっと変わったスズメ」ぐらいにしか見えない。一方ある程度知っている人は越冬時現れると普段見かけないこの鳥はいったい何? となるちょっと面白い種類。地鳴きを知っていると存在がわかるが当然聞こえているはずなのにまったくわかってもらえないこともある。
つまりあまり鳥らしく聞こえない。探鳥会でのみなさんの反応はいかがだろうか。それほど高い声ではない (6 kHz 程度) のでおそらく多くの人に聞こえているはず。カヤクグリの地鳴きを聞き逃したことを指摘された場合は鳥の声への注意力不足が原因とみなした方がよいだろう。
さて、自分がいつカヤクグリを知ったのかよく覚えていない。高い山の経験はないので、確実に把握しているものでは 1994 年の日本野鳥の会バードソン (1994.11.13) で兵庫県支部 (当時) との合同チームで氷ノ山坂の谷の 6:00 の記録があった。
当日は1種めの記録がトラツグミ (5:35) (トラツグミは冬場はさえずらないわけではなく、少なくともこの季節はさえずる)、2種めがウソ (6:00)、そしてカヤクグリが3種めだった。すべて声による記録。当時「渋い!」と感想が出たのを覚えている。声 (さえずりに近い音声) はこの時に初めて認識した記憶があり、思い出の鳥の一つ。地鳴きはいつ知ったのか思い出せない。
シーズンオフの秋も深まる比叡山にケーブルで登って少し進んだらすぐにカヤクグリが迎えてくれたことがあった。あまりにも近く遊ぶ鳥に自分も草地に一緒に寝そべっていた。当時は観光の人もあまりなく、今から考えてもとても静かな至福の出会いだった。再度、と後日期待したが同じような出会いはなく、もっと低いところでも案外出会えることを知った。
△ スズメ目 PASSERIFORMES スズメ科 PASSERIDAE ▽
-
イエスズメ
- 学名:Passer domesticus (パッセル ドメスティクス) 家のスズメ
- 属名:passer (m) スズメ
- 種小名:domesticus (adj) 家の、家庭の
- 英名:House Sparrow
- 備考:
domesticus は短母音のみで規則通りのアクセント (ドメスティクス)。英語と同じでわかりやすい。
世界に 12 亜種がある (IOC)。日本で記録される亜種は基亜種の domesticus とされる。
イエスズメはロシア東端まで分布を広げているが、極東南部 (ウラジオストクなど) や朝鮮半島では定常分布と言えるほどは進出していない。
1929 年までにシベリア横断鉄道に伴って極東に達した (コンサイス鳥名事典) とある。
人の住むところを追って分布を広げ、本来の生息域ではない森林ツンドラやツンドラにさえ生息する。例えばムルマンスク州、ペチョラ川河口やヤクーチア北部まで。北部の集落では寒い冬には完全にいなくなるがまた現れるという (wikipedia ロシア語版)。Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではツンドラを除いてほぼ全域に生息するとある。
シベリアの亜種は domesticus。おそらく次の Uspensky (1959) の時代よりも分布を広げている模様。
ロシア (極北部) での分布拡大経緯と生態については Uspensky (1959, 2020 再掲。pp. 1709-1720) Special features of avifauna of cultural landscape in Arctic and Subarctic にある。
ロシア式の丸太の住居を好むとのことで、ロシア式の集落の出現とともに定着したとのこと。農業が行われているところ (食物の得られるところ) のみに生息する。
Middendorf (1869) はシベリアでは農業用の木製のすきを追うと記述した。Larionov によればハンティ人 (西シベリアにあるオビ川流域とイルティシ川東岸側に住むウラル系民族) の住民の言葉で「ロシアの農家の隅にいる鳥」の名前があるとのこと。先住民の住居ではなく、"西洋式" 木造住宅に馴染む種類の模様。
こんな極限の地でも生息する例があったので紹介しておく: Mlikovsky (2024) New data on the birds of Pevek township, western Chukotka (pp. 2618-2621)
チュコト半島の北極海沿岸 (日本よりずっと東側) の Pevek (ペベク) ロシア最北端の街。1970 年代に人が持ち込んだと考えられる。周囲には事実上何もなくむき出しの地面あるのみとのこと。
記録される鳥のほとんどは海鳥だがユキホオジロは繁殖する。
北部、あるいは中緯度でも極寒の際に集団死が知られている。南に渡るものもあってそのまま越冬地で留鳥となることもある。越冬地北部の性比は圧倒的にオスに偏っており、オスの方が寒さに強いとのこと。
また北極圏への漂行例もあるとのことで、牛と餌について船でやってくるが、牛が屠殺されるといなくなるとのこと。Ust-Kara (カラ海沿岸) でひなを育て冬を越したが春にはいなくなった例がある。
種は違うが低温環境でとても過ごせないような北米西海岸地域のアンナハチドリ Calypte anna Anna's Hummingbird も人為活動に伴って夜は氷点下になる地域でも越冬するようになったという。
例えば How the World's Smallest Birds Survive the Winter (Liz Langley 2017 National Geographics)。フィーダーを設ける人が増えて分布を広げたとのこと。暖房設備の熱で夜を過ごすなどの話題も他所にあった。
[イエスズメの遊び]
イエスズメがロープを使って遊ぶ行動が報告された: Huertas-Gomez et al. (2025) Playing with the rope: a house sparrow behaviour related to its breeding activity
ケージ内の行動。繁殖期のみに記録されオス成鳥に多く見られたとのこと。
#ハシボソガラス備考の [鳥の知能行動] Kaplan (2024) のレビューも触れられている。
-
ニュウナイスズメ
- 第8版学名:Passer cinnamomeus (パッセル キンナモーメウス) シナモン色のスズメ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Passer rutilans (パッセル ルティラーンス) 輝くような赤みをおびたスズメ (新学名でシナモン色のスズメ)
- 属名:passer (m) スズメ
- 第8版種小名:cinnamomeus (adj) シナモン色の
- 第7版種小名:rutilans (adj) 輝くような赤みをおびた
- 英名:Russet Sparrow
- 備考:
cinnamomeus は o が長母音でアクセントがある (キンナモーメウス)。
rutilans は a 長母音でアクセントがある (ルティラーンス)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに種小名は cinnamomeus (シナモン色の) に変更。3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは亜種 rutilans (基産地日本) とされる。
ニュウナイスズメは日本の標本をもとに Fringilla rutilans Temminck, 1836 と記載された (つまりアトリ類に分類されていた)。
記載 フランス語名 gros bec roussard でアトリ類 ("赤褐色のシメ/イカル類") になっている。日本語では Hezusume とある (この表記を見ると Temminck はスズメの読みを全般的に zusume と勘違いしていたか、日本でもスズメではなくズスメと呼ばれていたのか?)。
正確な出版年が不明であった。当初は 1835 年とされてこれが最初の記載と考えられ、この種小名が用いられていたが、後に 1836 年のいつかであったことがわかった。
規約によりこれは1836年12月31日と解釈され、1836年4月8日に出版された Pyrgita cinnamomea Gould, 1836 (原記載) 基産地 'apud montes Himalayenses' [restricted to NW. Himalayas by Ticehurst, 1927, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc, 32, p. 347] (Avibase による)
の方が先取権があると解釈されるようになり、ほとんどの分類学者がこれに従っている (wikipedia 英語版より他)。種学名変更はこの事情による。
rutilans は亜種学名にそのまま用いられており、日本産の場合は種小名のみが変わったことになる。この変更に伴ってわずかの記載時期の違いでニュウナイスズメの基産地は日本ではなくなった。
Milkovsky (2011) Correct name for the Asian Russet Sparrow に情報がある。
Temminck and Schlegel の "Fauna Japonica" では Passer russatus の学名が利用されていた (図版)。
Fringilla rutilans Temminck, 1836 の学名を用いたにもかかわらず変更は不自然な感じもするが、参考 によれば Fringilla russata Temminck と改名されたものだった。
"Fauna Japonica" 本文でもフランス語名 le friquet roux ("赤褐色のスズメ" の意味) で図版と同じ学名を用いているが 1836 年に記載された時から形容詞も変化させている。種小名変更に対応させたものと想像できる。
Fringilla russata Temminck の学名ですでに紹介していたがスズメ類により近いと判定して名前を変えたと説明されているが、「すでに紹介していた」と思われる文献にこの学名が見当たらない。Richmond Index でも年が記されていないのは文献が見当たらないためと想像できる。
Temminck and Schlegel (1850) は過去にすでに学名を変えたものを出版したつもりだったが実はその学名は提示されていなかったのかも知れない。#ノジコでも "Fauna Japonica" の本文と図版で異なる学名が使われているように、似た意味の種小名の間で勘違いがあったのかも知れない。
現在ではシノニムで問題はないが、もし Fringilla 属で russata を使った命名があれば年代関係など問題になっていたかも知れない。
Milkovsky (2011) は cinnamomeus と rutilans のいずれに先取権があるかを議論したもので、Temminck が改名した理由は触れられていない。
Hartert (1910-1922) p. 161 には特に記述もなく、Fringilla russata がどの時点で導入されたものか判然としない。Passer russatus の方を 1850 年として採用している。
ただし英名はこの学名によく整合するので英名の由来となったかも知れない。英語圏の主な国に分布する種類ではないので英名も学名やフランス語名をもとに深く考えずに付けられたものかも知れない。このような分布の種は英名で何と呼ばれているかあまり重要視する必要はなさそうに思える。
Hartert もドイツに関係ない種類なのでそこまで深く調べなかったかも知れない。
Dement'ev and Gladkov (1954) では5亜種を認めており、台湾の kikuchii Kuroda, 1924 も認めていたが現代のリストには現れず、通常 rutilans に含まれる。ロシアからも比較的縁の遠い種類なので亜種まで詳しく検討しなかった可能性もありそう。
「京都の野鳥図鑑」(河合敏男 京都新聞社 1989) pp. 260-261 によればニュウナイスズメの和名由来には5説あるとのこと。冒頭に登場する新嘗祭 (にいなめさい 11/23 現在では勤労感謝の日に対応) のころに北の地方から大挙飛来する漂鳥でニイナメスズメが転化した解釈を紹介しておく。
中西悟堂「定本・野鳥記」1 p. 105 (1935 年) によれば稲の乳熟期に田畑を荒らすのは、実は普通の雀よりも入内雀のほうであったことが仁部富之助氏の観察により確かめられたと書かれていた。
この時代にはスズメ類はそれほど区別されず一括して害鳥と考えられていたらしいことがわかる。
新嘗祭のころに北の地方から飛来する名称説は「定本・野鳥記」5 p. 109 (1940 年初出) によれば宮城県の鳥の研究家である熊谷三郎氏の説とのこと。同書によればニュウを黒子 (ほくろ) と解釈し、黒子のないスズメとするとのは柳田国男氏の説とのこと。
同書 p. 129 では鹿児島県大島郡岩瀬町の方言としてカゼヒキドリがあるが、中西氏の解釈ではかぜをひくころに渡ってくる意味かとのこと。
[繁殖地のこと]
北海道や、中部より北の本州の高いところにお住まいの方にとってはごく普通のスズメの一種であるだろうが、西日本方面では繁殖に出会うのは難しい。
越冬する場所や春の花見の時期にしかるべき場所に行けば簡単に見ることができるので出会いが難しい種類ではなく、それ以上の興味は持たれないかも知れない。
しかし自身の居住する京都から見て一番簡単に訪れることのできる繁殖地はどこだろうと考えてみると結構難しいことがわかった。
しかし意外なことからそういう場所に気づいてしまった。鉄道で「青春 18 きっぷ」を使われる方もあるだろうが、近畿圏にいると気になるローカル路線があって青春 18 きっぷの利用者はおそらく一度は訪れているのではないかと思う。
福井県の九頭竜線 (正式名は越美北線。北線とあるのはもちろん南線があるわけで、現在の長良川鉄道がその後継。古くからこれを結んで岐阜から福井へつなげる計画があったが実現しなかった。この2本の鉄道とバス、間は徒歩でつないでかつての計画ルートを行ってみた報告レポートもネットに出ている。現在のバス事情で果たして同じことが可能なのかはわからない)
で、福井駅から九頭竜湖駅 (終着から先は路線などはないので戻ってくるだけだが) を結んでいる。
もちろん列車の本数は限界近くまで少なく、多くの青春 18 きっぷ利用者は終点まで行って記念撮影程度をしてスタンプを押した程度で同じ列車で帰ってゆくだろう。しかしバーダーの端くれとしてはせっかく奥地(?)まで来たので何かいないか調べてみたい気になるもので、4時間近く先の次の列車で帰ることにしていた。
とはいえ青春 18 きっぷは年中使えるわけではなく、使えるのは一番探鳥に適さないと思える7-8月、冬鳥は来ているかも知れないが雪もあるかも知れない 12 月、春休みの3月 (それぞれ1か月よりは少し長い期間が設定されている) で、それほど大した鳥は期待できそうにない。
実は時期を変えて複数回行ったことがあるのだが、そのうちの1回は3月の利用期間の最後に当たる4月上旬に行ってみたものである。雪はすでにほぼ解けており探鳥は十分可能であった。駅を出てしばらく先の橋の付近で耳慣れぬ声。主を探してみるとニュウナイスズメだった。ちょうど求愛ディスプレイ時期だったようでオスが盛んに交尾に誘っていた。
おかげでオス・メスとも求愛時の声や行動を記録することができた。「花見の時期のしかるべき場所」はもう少し後の時期なので、繁殖地ではこれほど早い時期から繁殖行動を始めているとは想像していなかった。
オス・メスの色合いが全然違うので見慣れたスズメとは全然違って不思議な感じだった (同じ印象はヨーロッパの公園でくるくる追い合っているイエスズメでも受けた)。
皆様も越冬地や中継地で会うだけで満足することなく、ぜひ繁殖地でも観察していただきたい。
先に書いた京都から一番近い繁殖地は? という疑問もこの偶然の観察の後に調べたもの。実は福井県での繁殖もそれほど調べられているわけではないことがわかった (同地域での過去の情報はあるのでずっと繁殖しているのだろうと考えられる)。
普通のバーダーが訪れない場所なのであまり話題にならないのだろうと思う。福井県動物目録 「本県では、繁殖の記録はなく」とある (1998)。
日本野鳥の会京都支部の支部報の観察報告にも送ったのだが (福井県は報告受け付け県に含まれている)、報告のタイミングが少し遅いかったこともあり、他府県のためか支部報には掲載されなかった。
ニュウナイスズメは普通種なので担当者に報告の意義が伝わらなかったのだろうと妙に納得してしまった (笑)。
今となっては北陸新幹線が敦賀まで開通すると同じように青春 18 きっぷで訪れることは不可能である。特急料金を払ってまで行こうとはもう思わないかも知れない。(追記: 特例に含まれ、福井駅からは乗れないが青春 18 きっぷで九頭竜線に乗れることがわかった)
[ニュウナイスズメの巣箱研究]
Peng et al. (2025) Hanging Position of Artificial Nest Boxes Affects Reproductive Success of Russet Sparrow Passer cinnamomeus 中国東北地方での研究 (オープンアクセス)。
-
スズメ
- 学名:Passer montanus (パッセル モンターヌス) 山のスズメ
- 属名:passer (m) スズメ
- 種小名:montanus (adj) 山の
- 英名:Tree Sparrow, IOC: Eurasian Tree Sparrow
- 備考:
montanus は a が長母音でアクセントもここにある (モンターヌス)。
スズメの英名がなぜ Tree Sparrow なのだろうと疑問を持たれる方は多いだろう。これは Passer arboreus Forster, 1817 (意味は "木のスズメ" = Tree Sparrow) に対応する。これは Fringilla montana Linnaeus, 1758 (スズメの原記載とされるもの。意味は "山のアトリ類")
を改名したもの。
何でも Fringilla 属としていた時代があり、属を分離するべきと考えられて改名されたもの (#ノスリの備考参照)。[ハタオリドリ科とは何だったのか] の項目も参照。当時の考え方がわかる。
Passer の属名は Brisson (1760) によるが、この属を意味する "Moineau" に 20 以上の種を挙げていたとのこと。後にイエスズメがタイプ種と認定された (The Key to Scientific Names)。
OED によれば英名の Tree Sparrow. Mountain Sparrow の用例は 1770 年の Pennant, British Zoology (new edition) にあるとのこと。Forster (1817) が用いた学名はハヤブサの学名同様英名を逆に訳したものの可能性がある。一方 Mountain Sparrow の名称の方は学名の方が古いので学名由来と考えられる。
一方でアメリカでも Tree Sparrow と呼ばれた種があって当時の学名で Fringilla Arborea で英名は Wilson, American Ornithology に 1831 年に登場とのこと。
現在ではムナフヒメドリ Spizelloides arborea American Tree Sparrow で新世界ホオジロ類だが模様が似ていると言われれば確かに多少似ている。"アメリカスズメ" と訳してもよさそうなところだが、ホオジロ類なので "スズメ" を使うのを避けたのだろうか。
ドイツ語名では Baumammer で "木のホオジロ" の意味。
和名に使われる "ヒメドリ" は旧属名 Passerella (スズメの指小形) 由来だろうか。英国と北米でいずれも Tree Sparrow と呼ばれる種類が存在したが、英国で用いられたものの方が早かった。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では現在と同じ学名が使われているが、学名リストに Passer arboreus も含まれていた。
9亜種あり (IOC)。日本の亜種は saturatus (豊富な色の、濃い色の、色の強いの意味) とされる。
この亜種は Ogawa (1908) は別項目扱いでリュウキュウスズメとなっていた。Passer saturatus Stejneger, 1885 (原記載) で、基産地 Riu Kius (リュウキュウ = 沖縄 と判定されている)。
スズメには日本や周辺で非常に多くの亜種が記載されていたがすべて saturatus のシノニムと判定されたため沖縄を基産地とするスズメが日本を代表している。
亜種 dybowskii (ポーランドの動物学者でシベリアに流刑となったが強制労働から開放されて自然研究を行った Benedykt Tadeusz Dybowski に由来) が検討亜種 (和名はまだなし)。
Passer 属の分子系統分類や位置づけについて: Paeckert et al. (2021) A revised multilocus phylogeny of Old World sparrows (Aves: Passeridae)
Passer 属は2クレードに分かれ (600 万年前ぐらい)、ニュウナイスズメおよびスズメは最も古く分岐 (550-500 万年前ごろ) したもの。イエスズメの系統ははるかに新しい (100 万年前より少し古いぐらい以降)。
ユーラシアにはニュウナイスズメおよびスズメが先に分布していて、イエスズメが後から分布を広げた形になっているのでスズメが優勢な地域にはなかなか侵入できないように見える。
イエスズメは人の活動で分布を広げた部分があるだろうが、亜種分化も進んでおり、スズメはもっと早い時期に分布していたと考えるのが妥当そう。北緯 70° まで分布し、スカンジナビア半島は北端近くまで分布する。まばらな森林、森林ステップ、ステップが典型的な生息環境とのこと。
ステップ地域では2種類のまったくことなる生息環境があり、人為環境以外にも崖の穴や河川流域の孤立林の樹洞などにも生息するとのこと (Dement'ev and Gladkov 1954)。
人為環境以外にも十分適応可能で、その後人類の活動に伴って依存関係が生まれたのだろう。
[スズメは稲作文化の到来とともに大陸から日本列島に渡ってきた?]
スズメは「稲作文化の到来とともに大陸から日本列島に渡ってきた」説は何か裏付けがあるのだろうか。
ハタオリドリ (かつてはスズメはハタオリドリ科だった) の故郷はアフリカで旧石器時代に人類の移動ととも分布を広げた説も分岐年代と合わないので考えなくてよいだろう。古くアフリカで誕生した系統であることは大丈夫そうだが、少なくともニュウナイスズメは早い時期に東アジアに到達して氷期におそらく長江下流のレフージアで過ごして現在の分布となった (wikipedia 英語版紹介の解釈)。
あまり違わない時期に分岐したスズメはもう少し環境順応性が高くてユーラシア全体に分布したのだろうか。Paeckert et al. (2021) の研究もまだ全体の系統を明らかにした最初の段階で、スズメの分子遺伝学的生物地理学の研究はこれからに期待か。
イエスズメの定着過程の解説で House Sparrow と最初に記述して英語の習慣から2回め以降は sparrows と表現されたのを「スズメ」と訳したものが誤解され、スズメは人と一緒に分布を広げた解釈が定着した可能性を思いついた。どなたか文献検証を試みていただければ。
「原色日本野鳥生態図鑑」(中村登流・中村雅彦 保育社 1995) p. 10 に解説があり、スズメ属は多分、人の移動とともに地中海地域へ進出し、農耕文化の伝播にともなってユーラシア大陸へとあまねく広がり、氷河期を経て種分化したものであろう、とあった。
中村両氏のオリジナルのアイデアなのか何かの文献出典があるのかこれもまたわからないが (上記のような House Sparrow からの拡大解釈か誤読かも知れない)、このように書物に記載されていれば (変形されつつ) 後世に伝えられても不思議でなかったわけだろう。
Neolithic Revolution (First Agricultural Revolution) の wikipedia 英語版によれば the Fertile Crescent (肥沃な三日月地帯) が 11000 年ぐらい前、推定によって多少異なる説があるとはいえ、いずれにしても Passer 属の分岐年代 (2クレードに分かれたのが 600 万年前ぐらい、ニュウナイスズメおよびスズメは 550-500 万年前ごろ) とは桁が違いすぎる。
氷河期以前から農耕文化が伝播していた証拠が 1995 年当時あったのだろうか。
イエスズメの進出のような個々の種の定着の説明には使えるかも知れないが、Passer 属の種分化とは関係なさそう。英語で探しても出てこないので日本独自の説かも。
[ハタオリドリ科とは何だったのか]
比較的最近までスズメがハタオリドリ科 Ploceidae であったことは記憶されている方も多いだろう。ハタオリドリとはいったい何のこと? とよく話題になったものである。
ハタオリドリ科 Ploceidae の概念は現在も健在で、スズメ科の系統が離れているために分離され、ハタオリドリ科の名称は本家の方を指すものとなった次第。#ツリスガラ備考 [スズメ小目 Passerida の系統分類] を参照。スズメ小目 Passerida や スズメ上科 Passeroidea の概念を用いる場合には馴染みのスズメが登場するのでわかりやすい。スズメ類はヨーロッパに生息するため先に命名された名称が多く、先取権が発生しやすいため。
Passeridae Rafinesque, 1815 と Ploceidae Sundevall, 1836 では前者の方が先に命名されたのでもしまとめるならば Ploceidae でなく Passeridae が優先されそうな気がするが、
Hartert (1910-1922) を当たってみると、Ploceidae は現れるものの Passeridae は現れていなかった。また Passer 属 は Fringillidae (現在ならばアトリ科) に含まれていた (p. 146)。
Passeridae の概念がこの時点で認識されていたのかどうかは判断できなかったが、Passer 属は Fringillidae Leach, 1819 に含まれていたため Passeridae とする扱いが現れず、後の分類改訂の際に Ploceidae の方に含まれたのではいかと想像できる。
Rafinesque (1815) の時代には語尾の扱いが現在と異なっており、Passernia の名称だった。
Fringillidae は古い名称だったので Hartert (1910-1922) 時代にはこれで問題がなかった。
Rafinesque (1815) Analyse de la nature: or, Tableau de l'univers et des corps organises では
p. 68 で亜科の扱いで、Passer 以外にも Pyrrhula (ウソ類)、Fringilla (アトリ類) やホオジロ類も皆含まれていたので後の扱いもややこしかったのだろう。
Fringilla が Passernia に含まれているのになぜ Fringillidae の方が優先されたのか理屈は不明だが、亜科を科と読み替えてよいか、どのような記述をもって有効な科名とみなすかなどの規則がまだ整備されていなかったのかも知れない。
この文献を見るとさらに面白いことがわかって、これらは Conoramphia (円錐形の嘴) の科に含まれていた。その次の科が Leptoramphia (繊細な嘴) で、いわゆるスズメ目の飼い鳥用語のソフトビル (softbills) の概念はこの時代の分類由来ではないかと想像できる。OED を見ると飼い鳥の Soft-Bills の用例は 1830 年から知られており時代的にも一致する。
OED では英語の Hard bill (1792 年の用例があり、フランス語の Dur-bec に対応) に対応したものとなっている。Rafinesque (1815) がまとめたものとほぼ同じ時期となる。
食性や嘴の形をもとにした分類で一応自然な分類になっているように見える。
なお中西悟堂「定本・野鳥記」8 (1944 年著作部分) のでは「きんぱら科」となっていた。キンパラは現在科名に残っておらずカエデチョウ科 Estrildidae となっている。Estrildidae が Estrilda 属由来で、こちらにカエデチョウの和名の付く種が含まれているため和名が変更されたものだろう。現在は Passer 属は Estrildidae に含まれない。
よく知られたスズメの分類でさえこれほど複雑なものだった。
[カムチャツカのスズメ、イエスズメ、ハクセキレイ]
カムチャツカではイエスズメ、スズメともに完全に人に頼って分布を広げたとのこと。
Lobkov (2002, 2024 再掲) Formation and dynamics of populations of the tree Passer montanus and house P. domesticus sparrows introduced to Kamchatka (pp. 2877-2888)。
スズメは 1979 年にナホトカから穀物船に乗ってやってきて最初は 8-10 羽だったとのこと。
カムチャツカでずっと都市鳥となっているスズメ目の鳥は他にハクセキレイ (日本でお馴染みの亜種 lugens) のみとのこと。
イエスズメは 1981 年住民が 24 羽をモスクワから持ち込んだことに始まるとのこと。翌年の春に 15-16 羽のなってこれが創始個体群。Elizovo の都市では当初はスズメが優勢だったがイエスズメが次第に数を増してスズメは 1990 年ごろがピーク。1994 年ごろから数が逆転し今 (2002 年) ではイエスズメの方が多いがスズメも残っている。
スズメ類の増加に合わせるかのようにハクセキレイは減少したとのこと。Petropavlovsk-Kamchatsk では地域によってスズメとハクセキレイの数に反相関があって、人が住む地域はスズメが多ハクセキレイは非常に少ないが中心部ではハクセキレイも多少残っている (それでもスズメより少ない)。
[ロシア沿海地方のスズメ]
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the Eurasian tree sparrow Passer montanus (pp. 4569-4596)
かつては夏鳥だったが現在では沿岸部、特に南部では最も数の多い留鳥になっている。
写真も多数あり、すすで真っ黒になった個体、スズメを捕食したハイタカの写真、白変個体などいろいろ紹介されている。
[スズメの漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 73 VII (藤堂) によれば漢字の由来は単純で 小 + 隹 (小さな鳥)。現在の中国語名は麻雀 (majue) または 雀 x (漢字が出せないので空白としておく。jiaor) で、麻雀はおそらく胡麻のような斑点を示したものだろうとのこと。
"小" の文字は棒の削りかすが両側に落ちるさまを示す。肖、消、削も同系語とのこと。小や肖は siog から sieu と音が変わったが、雀は冒頭の音が ts' となって ts'iok から ts'iak (シャク) に変わったとのこと。この読み方は燕雀 (えんじゃく) に現れる。昔はスズメ目を燕雀目と呼んでいた。
スズメの形にまねた酒器を爵 (シャク) と呼び、部下の功績に対して与えたことから功績の序列を表すこととなった (爵位)。
マージャンの麻雀は当て字で、馬弔 = 馬鳥 から 麻雀や麻将の当て字に変化したとのこと。
△ スズメ目 PASSERIFORMES セキレイ科 MOTACILLIDAE ▽
-
イワミセキレイ
- 学名:Dendronanthus indicus (デンドゥロナントゥス インディクス) インドの林のセキレイ
- 属名:dendronanthus (合) 林のセキレイ (dendron 木 Gk と Anthus (タヒバリ) 属から。The Key to Scientific Names)
- 種小名:indicus (adj) インドの (-icus (接尾辞) 〜に属する) (タイプ標本の採集地)
- 英名:Forest Wagtail
- 備考:
dendronanthus は外来語を含む合成語で発音は不明だが、起源となる dendron は短母音のみで長母音は現れないと考えられる。anthus も短母音のみ。-nan- がアクセント音節と考えられる (デンドゥロナントゥス)。
indicus はアクセント冒頭で "インディクス"。
単形属で亜種もない。
フランスの博物学者 Pierre Sonnerat が 1782 年に記述したものを Gmelin が "La Bergeronnette gris des Indes" (インドのハクセキレイ) と正式に記述したものによる (1789)。
木に営巣する唯一のセキレイ類でインドは越冬地 (wikipedia 英語版)。
海外の分布図では日本の西部が繁殖地に含まれていることがあるが、日本での繁殖記録は非常にまれ (福岡県、島根県)。一般的にはまれな旅鳥か冬鳥とされる。和名の由来は鳥取県岩美町で最初に観察されたことによる (wikipedia 日本語版より) とあるが、島根県石見地方との記述もある。石見鶺鴒と書く (cf. 石見銀山 いわみぎんざん と読む)。
佐藤 (1993)「夏鳥たちの歌は、今: 利尻島から西表島まで 102 人の緊急レポート」pp. 196-198 によれば大社海岸 (島根県出雲) に 1965 年以来渡来して繁殖し、多い年には6羽みられたという。
この記録が世界的にも使われている日本で繁殖個体群の根拠の一つになったのだろう。
1977 年に松くい虫防除のための空中散布以来渡来しなくなったと記されている。中国地方 自然環境 - 生物対象群 (環境省) にも改訂 しまね レッドデータブック -島根県の絶滅のおそれのある野生動植物- を出典として同様の記載がある。
「野の鳥の四季」(高野伸二 小学館 1974) p. 32 によれば他のセキレイ類で見られない求愛給餌を行うとあった。調べてみるとタヒバリ類では知られていてマキバタヒバリでは日常的にあるとのこと: Lack et al. (1941) Courtship Feeding in Birds。もしかすると祖先的な性質が現れているのかと期待したがそうでもなかった。
Harris et al. (2018)
Discordance between genomic divergence and phenotypic variation in a
rapidly evolving avian genus (Motacilla)
の系統樹でもセキレイ類の最も古い分枝にあたり、他のセキレイ類と系統が非常に遠い (この研究でも外群として使っている)。
イワミセキレイはセキレイ類の進化を考える上でも興味深い種類 (#ツリスガラの備考 [スズメ小目 Passerida の系統分類] 参照)。
尾を左右に振る特徴がよく知られている。さえずりがシジュウカラによく似ていて、(海外の分布図を参照して) 日本を訪れた海外バーダーがシジュウカラの声を本種と誤認することがある。
Tiunov et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the forest wagtail Dendronanthus indicus (pp. 2245-2260) ロシア沿海地方のイワミセキレイの繁殖。写真も多数あり。
古い資料では Neufeldt (1961) The breeding biology of the Forest Wagtail, Motacilla indica Gmelin 英文の主にアムール州での繁殖生態の論文もある。
-
ツメナガセキレイ (ニシツメナガセキレイが分離された。ツメナガセキレイの学名も変わった)
- 第8版学名:Motacilla tschutschensis (モタキルラ ツクツケンシス) チュコト半島の尾を動かす鳥 (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Motacilla flava (モタキルラ フラーウァ) 黄色の尾を動かす鳥
- 第7版亜種学名:Motacilla flava taivana (モタキルラ フラーウァ タイウァーナ) 台湾の黄色の尾を動かす鳥 (日本で繁殖する亜種。他亜種あり)
- 属名:motacilla (合) 尾を動かす鳥 (moto (tr) 動かす cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい) 本来は尾の意味はなかったが、誤解により -cilla は尾の意味で使われるようになった。
Varro が名付けた motacilla ("quod semper movet caudam") が中世に誤解されたものと The Key to Scientific Names にある。
もっとも #キレンジャクではドイツ語から直訳で学名が作られており、ドイツ語で尾を表す単語 Schwanz (中世ドイツ語で swanz) も語源は同様 (中世ドイツ語で swanzen 振る)。誤解というより意味の収斂や他言語の影響もあるかも知れない。
- 第8版種小名:tschutschensis Chukotski, Chukchi or Chukotka 東シベリアのチュコト半島の
- 第7版種小名:flava (adj) 黄色の (flavus)
- 第7亜種小名:taivana 台湾の (日本で繁殖する亜種。他亜種あり)
- 英名:Yellow Wagtail, 分離後は IOC 英名では Eastern Yellow Wagtail (ツメナガセキレイ) と Western Yellow Wagtail (ニシツメナガセキレイ) になる
- 備考:
motacilla は mo-ta-cil-la と音節に分解され、-cil- にアクセントがある。モタキルラ。
flava は最初が長母音 (フラーウァ)。
taivana は形容詞化語尾 -ana の長母音とアクセントを採用した (タイウァーナ)。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
2種に分離され、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で種小名を tschutschensis (Chukotski, Chukchi or Chukotka 東シベリアのチュコト半島に由来) に変更され、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同様。
IOC では 3.1 から、HBW/Birdlife も 2017 Dec. より、Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2) より、Clements は 2013 年より、時期は違うがいずれもツメナガセキレイとニシツメナガセキレイの分離が行われた。
亜種 tschutschensis は第7版時代には含まれておらず、マミジロツメナガセキレイの名称は亜種 simillima に与えられていた。
simillima が tschutschensis のシノニムとされ種分割されたことに伴う変更。
従来のこの亜種は第8版の名称では Motacilla tschutschensis tschutschensis となる。
分類学全体にわたる Per Alstrom の講演 (2023) per alstrom BirdLife Finland Dec 2023 ツメナガセキレイの分類については 48:40 から。50:58 よりゲノムを用いた系統解析。
対応する英名は Eastern Yellow Wagtail。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で掲載されている亜種は macronyx (makros 長い onux, onukhos 爪) キタツメナガセキレイ、tschutschensis マミジロツメナガセキレイ、taivana (「台湾の」の意味) 亜種ツメナガセキレイとなっている。
亜種ツメナガセキレイはかつては亜種キマユツメナガセキレイとの名称もあった。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で亜種 plexa (plexus 「絡み合った、編んだ、曖昧な」の意味) シベリアツメナガセキレイを検討亜種に移動。
シベリアツメナガセキレイは亜種 taivana に含まれ亜種名が表面に現れない時代もあった。
種小名の tschutschensis を何と読むかは難関で何と tsch が2回も出てくる。ラテン語の発音規則では sc を sk と読むとして、なるべく原語に近い子音の音を採用してみた。ロシア語では Chukotka チュコートカ や Chukotskij チュコーツキー のような読み方でコにアクセントになるが学名にはこの音は現れない。
ロシア語の ch (日本語にはチャやチョの音があり、その子音部分) に対応する音が他のヨーロッパ言語に必ずしも存在しない、またラテン語の読み方だとクの子音になってしまうので誤読を避けるために tsch の表記を用いたものかも知れない。kamtschatschensis などの他の用例を見るとこの解釈がもっともらしいように見える。
ちなみに ch はフランス語だとシュ、ドイツ語だとヒの子音、イタリア語だとクの子音など言語によって読み方が違う。ドイツの国名 Deutschland ドイチュラント の綴りにも影響を受けているかも知れない (ドイツ語では sch がシュ)。
チャイコフスキーのラテン文字表記に Tchaikovsky が用いられるのもおそらく同様の理由。この考えに基づけば tsch はローマ字の ch と読んで構わないことになり、チューチェンシス (他の事例を見ると命名者の考えはおそらくこちら) と読んでも構わないことになる。ただしこの発音には k の音が現れなくなるので "チュコト" やロシア語表記の読み方とはやや離れてしまう。
kamtschatschensis を同じように読むとカムチャチェンシスとなる。チェよりも k の音を入れたい気がする。
tschutschensis も両方を混ぜたチューツケンシスなどでも構わないかも知れない。読者の好みにお任せしよう。
以前は亜種 simillima (「非常に似た」の意味。カムチャツカで基亜種に非常に似た亜種を記載したもの)、angarensis (シベリアのトランスバイカル地方の Angara 川に由来)、zaissanensis (カザフスタン東部の Zaissan Kul/Zayzan 湖に由来) があったが、tschutschensis
にまとめられた。経緯は高木 (2018) Birder 32(9): 30-31 のツメナガセキレイの亜種に関する記事も参照。
分子系統研究では Pavlova et al. (2003) Phylogeographic Patterns in Motacilla flava and Motacilla citreola: Species Limits and Population History
があり、かつての Motacilla flava は少なくとも東西に分割できるとの見解が出ており、上記分類変更と学名変更につながったものと思われる。
この文献では taivana も別種と扱える可能性を示している。日本の亜種ツメナガセキレイはこれなので、日本で記録されるマミジロツメナガセキレイは将来別種扱いになる可能性がありそうである。その場合ツメナガセキレイの学名はまた変わることになる。
2024 年現在世界の主要チェックリストは taivana を Motacilla tschutschensis の亜種扱い。
記載時学名 Budytes taivanus Swinhoe, 1863 (原記載 表に現れる)。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では Motacilla (tschutschensis) taivana と種扱いに準じて項目も別にしている。英名 Green-headed Wagtail。
同書では Motacilla (tschutschensis) macronix (英名 Chinese Yellow Wagtail) も種扱いに準じて項目も別にしている。
Dement'ev and Gladkov (1954) では Motacilla flava と Motacilla lutea を別種としており、taivana は後者の亜種となっていた。ヤクーチアからサハリンで繁殖し、中国南部・台湾、東南アジアで越冬する扱い。
flava と lutea を別種にする扱いであれば lutea の記載は Gmelin (1774) と古いのでこれが種学名になる (記載時は Parus luteus とカラ類)。
Ferlini and Artemyeva (2020) The Gmelin's wagtail Motacilla lutea: breeding range, migratory movements and wintering range のように独立種としてこの学名を用いた記述もある。
ロシアでは独立種扱いは比較的普通のようで、Yellow-backed Wagtail など参照。このロシアのサイト (North Eurasia Birds Watch の地域サイト) ではニシツメナガセキレイも含めた広義ツメナガセキレイは6種の扱い。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire では英名 Blue-headed Wagtail となっていた。千島列島の標本が Pryer collection にあるとのこと。
Hartert (1910-1922) p. 287 の時代もこの英名が挙げられており、現在でも亜種英名に使われている。なぜ blue なのか由来がよくわからないが、キガシラセキレイまたは亜種 lutea が Yellow-headed Wagtail と呼ばれるのでそれに対応して少し青みを帯びている名称だろうか。
[ニシツメナガセキレイ]
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では別種となった Motacilla flava の亜種が追加される見込みで、種の和名はニシツメナガセキレイ (対応する英名は Western Yellow Wagtail) となる見通し。
後者の種から亜種 beema (インドの Beema/Bhima 川が由来) が記録されているとされている (亜種和名はニシツメナガセキレイで検討中だったが最終的にロシアニシツメナガセキレイとなった)。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版の段階では分離後の "ニシツメナガセキレイ" に分類される亜種 leucocephala (「頭の白い」の意味) カオジロツメナガセキレイからカオジロニシツメナガセキレイに名称変更の上、検討亜種へ移動となった。
そのため日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版には種 "ニシツメナガセキレイ" は現れないものの、すでに別種として扱われていた。
この亜種と考えられる個体の観察について所崎 (2011) Birder 25(9): 48-50 に 2011 年5月鹿児島県平島での記事が出ている。
他にも亜種不明のものが記録されているとされている。両種とも第8版における扱いはこれらの通りとなった。Motacilla flava の学名および英名 Yellow Wagtail (不明確) は新旧で意味が違うため注意する必要がある。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では Motacilla (flava) feldegg Black-headed Wagtail、Motacilla (flava) lutea Yellow-fronted Wagtail を種扱いに準じて項目も別にしている。
[ツメナガセキレイの爪はなぜ長い]
Green et al. (2009) How the longspur won its spurs: a study of claw and toe length in ground-dwelling passerine birds
によれば地上性のスズメ目のセキレイ類、ツメナガホオジロ類、ヒバリ類の一部で後趾や爪が長いのは、草地で生活し凹凸のある環境でより大きな足が必要な適応の結果と考えている。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 5 p. 6 によればツメナガセキレイはつばさをたたんで地面にまっすぐ急降下する着地法をとるとのこと。あるいは爪が長いことに関係があるのかと思ったが、関係する記述が見つけられず、着地の瞬間らしい画像を見ても翼を広げて減速しているように見える。
-
キガシラセキレイ
- 学名:Motacilla citreola (モタキルラ キトゥレオラ) 少しシトロン黄色のセキレイ
- 属名:motacilla (合) 尾を動かす鳥 (moto (tr) 動かす cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい) 本来は尾の意味はなかったが、誤解により -cilla は尾の意味で使われるようになった
- 種小名:citreola (adj) 少しシトロン黄色の (citreus (adj) シトロンの -ola (指小辞) 小さい)
- 英名:Citrine Wagtail
- 備考:
motacilla は#ツメナガセキレイ参照。
citreola は短母音のみで -re- がアクセント音節と考えられる (キトゥレオラ)。-ola の o は長母音にならない。
英語別名 (旧名) が Yellow-headed Wagtail, Yellow-hooded Wagtail で和名はこれを訳したものと想像される。
かつては Motacilla citrinella Pallas, 1811 の学名が長く用いられていたが Motacilla citreola Pallas, 1776 が早かったためこちらに変更になった (Dement'ev and Gladkov 1954)。
基産地 In Siberia orientaliore (シベリア東部) とのこと。
citrinella は citrinus シトロン の指小語と解釈できるが、イタリア語の Citrinella 黄色の小さい鳥 に由来するとのこと。(ニシ)ツメナガセキレイやキアオジなどいくつかのものを指した (The Key to Scientific Names)。
英名 Yellow-headed Wagtail もロシア名も同じ意味になっているので、あるいは Pallas 時代の通称由来かも知れない (いずれも原文を読めないため確認できず)。外観と違和感があるわけではないが和名は英語別名 (旧名) を訳したものと想像できる。
日本で記録されるものは基亜種 citreola とされる。ユーラシアに広く分布し、世界にはもう1亜種ある。
森岡 (1997) Birder 11(9): 62-65 に1996年9月和歌山で記録されたキガシラセキレイの検討がある。識別対象となった主な種はツメナガセキレイ。
かつてはツメナガセキレイの亜種扱いでキガシラツメナガセキレイとも呼ばれていた [茂田 (1996) Birder 10(11): p. 31]。1974 年の目録で現在の名称となった。
現在の系統分類もある意味暫定的。Voelker (2002) Systematics and Historical Biogeography of Wagtails: Dispersal Versus Vicariance Revisited の系統樹参照。
#ツメナガセキレイの備考の Pavlova et al. (2003) で読まれた配列 AH012532.2 をもとに BLAST を行ってみることもできるが、{ツメナガセキレイ + ニシツメナガセキレイ} とキガシラセキレイをまとめて1種で構わないのでは、と思える結果が得られる。
この部分の配列がツメナガセキレイ (taivana) やニシツメナガセキレイの配列と 100% 一致するものもある。ただしミトコンドリアのみなので少し割り引いて見る必要がある。ツメナガセキレイの基亜種でも 99% 一致。
-
キセキレイ
- 学名:Motacilla cinerea (モタキルラ キネレア) 灰色のセキレイ
- 属名:motacilla (合) 尾を動かす鳥 (moto (tr) 動かすcillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい) 本来は尾の意味はなかったが、誤解により -cilla は尾の意味で使われるようになった
- 種小名:cinerea (adj) 灰白色の (cinereus)
- 英名:Grey Wagtail
- 備考:
motacilla は#ツメナガセキレイ参照。
cinerea は短母音のみで -ne- にアクセント (キネレア)。
[キセキレイの学名成立経緯は複雑]
キセキレイの 原記載 (Tunstall 1771) では Grey Water Wagtail の英名を与えている。
Tunstall (1771) の用例も実は危ないところだったようでハクセキレイを指して使われた Motacilla cinerea Gmelin, 1789 (参考) もあった。
Hartert (1910-1922) p. 302 によるとこの用例は 1788 年とのこと。Buffon, Latham がすでに用いていた (有効な学名でない) ものを用いたものとのこと。
驚くべきことに Hartert (1910-1922) の時代には Tunstall (1771) の用例はまだ知られていなかったようで、Motacilla boarula Linnaeus, 1771 が用いられていた。これは有名な「自然の体系」ではなく 記載。
boarula はイタリア語でセキレイを指していて、Linnaeus (1771) 以前の用例もあるとのこと。Motacilla boarula Scopoli, 1769 (参考 1, 2)。The Key to Scientific Names によれば Scopoli (1769) の3つの違ったページに現れるので誤って使われたものではないかとのこと。
Hartert (1910-1922) はキセキレイに対する Motacilla cinerea の方の学名は Leach (1816) を挙げており無効としている。Gmelin (1789) の用例がすでにあるため無効と判断したものだろうか。Linnaeus (1771) の学名は Scopoli (1769) がすでに使っていておそらく無効となり、Scopoli (1769) の方も単一種に限定できないため消去法的に Tunstall (1771) が生き残ったのだろう。
Dement'ev and Gladkov (1954) では Scopoli (1769) の方ではないとの記述があり、無効と考えられていたよう。
この整理が行われていなければキセキレイの学名は Motacilla boarula となっていたか、あるいは後の他のより馴染みのない学名が選択されていたかも知れない。学名の成立経緯はなかなか難しい部分がある。
また Linnaeus (1758) はハクセキレイは名付けながらキセキレイは認識していなかったことがわかる。そう思って分布を見るとスウェーデンにはほとんど分布せず、スカンジナビア半島南端で夏鳥。Linnaeus にとっては馴染みの種類ではなかった理由がわかる。日本でも、もしツメナガセキレイの方が普通種だったならばこちらをキセキレイと呼んでいても不思議でない。
Hartert (1910-1922) のドイツ語名は Schwefelgelbe または Gebirgs-Bachstelze。Schwefel が硫黄で "硫黄のような黄色"。Gebirgs-Bachstelze は "山のセキレイ"。
[ヨーロッパ言語のキセキレイ]
あれほど黄色がはっきりしているのに英語ではなぜ grey wagtail (灰色のセキレイ) なのか気になるところである。
Tunstall (1771) では Grey Water Wagtail の英名が与えられていたが、これは当時の学名で Motacilla flava 広義ツメナガセキレイ (実際に指していたものはおそらくニシツメナガセキレイ) に相当するものが先に命名されていて Yellow Water Wagtail と名付けられていたため。広義ツメナガセキレイの方がより黄色く、キセキレイの方が相対的に灰色が目立つ意味で名付けられたのだろう。
OED を見ていて気づいたのだが、英国のイングランドでは広義ツメナガセキレイは繁殖するもののキセキレイは繁殖しない渡り鳥 (スコットランドでは繁殖する。イングランドの繁殖種が当然優先されただろう) で広義ツメナガセキレイの方がより馴染みがあったのだろう。Willughby and Ray, Ornithologiae (1676) にキセキレイを指して The grey Wagtai と呼ばれたのが最初の用例で、後の世代に Yellow と呼ばれたこともあったが Willughby の用例があるため正しいと考えられなかったらしい。
フランス名も併記されていて、広義ツメナガセキレイの方が le Bergeronette de printems (printemps) 春のセキレイ (春に渡ってくるためだろう)、キセキレイが la Hoche-queue (尾振りの意味) / Bergeronette jaune 黄色のセキレイとなっていて、後者は我々の感覚と同じである。英語表現で気になるものがあった場合は語源や英語以外の言語もチェックするのがよさそう。
ただし現代のフランス名ではそれぞれ Bergeronnette printaniere 春のようなセキレイ、Bergeronnette des ruisseaux 小川のセキレイ となっている。ヨーロッパでは普通に見られる黄色いセキレイが複数存在するので「黄色のセキレイ」は特定の種を表すのにあまり適切な名称ではなかったのだろう。
ドイツ語では Gebirgsstelze と山のセキレイ。スラブ言語でも同じ意味がよく使われている。
日本では基本となるセキレイがセグロセキレイ、キセキレイ、ハクセキレイなので「黄色のセキレイ」で十分だったのだろう。
[亜種]
日本で記録されるものは基亜種 cinerea とされる。ユーラシアから東南アジアやアフリカの一部に広く分布し、世界に他に2亜種ある。Hartert (1910-1922) 以前には他にも複数の亜種があったが違いが小さくまとめられていったよう。
カムチャツカから中国東北部、朝鮮半島、日本の亜種を robusta (「力強い」の意味) とする考えもあり (HBW/BirdLife など。Clements は最近は認めていない)、もしこの亜種を認めれば日本の亜種は robusta となるだろう。
IOC では認めていないのでおそらく現行の扱いが続くと思われる。
記載は Pallenura robusta Brehm, 1857 (原記載) 基産地 Japan。ヨーロッパのものより大型で嘴が力強いとのこと。
Pallenura は Bonaparte (1850) が Pallas の記述をもとに導入した属名。pallo 振る oura 尾 (Gk)。Pallas の名称は学名ではなく通称しか示されていないので属記載とはならないとのこと。タイプ種は Pallenura javensis Bonaparte, 1850 (参考) でジャワ島のキセキレイをもとに記載 (The Key to Scientific Names)。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではアフリカを別の2亜種としているが (離島を含めて全体で5亜種)、ユーラシア大陸部は2亜種で日本やカムチャツカを含む東部は melanope Pallas, 1776 基産地 'Dauria' = Transbaicalia (Avibase による) と図示している。
本文では Parus caspicus Gmelin, 1774 (参考 1, 2) 由来の亜種名 caspica を用いてmelanope はシノニムとしており、分布図と整合していない。
Motacilla melanope Pallas, 1776 (参考) があるがこれより早いと判断した模様。
もっとも亜種間の違いは少ないとあり個々の分布もよくわからないとなっている。ほとんどの研究者に違いがわからないぐらいでユーラシア大陸部は1亜種にまとめられたのだろう。
Hartert (1910-1922) では東部亜種を melanope としていたが地域はカムチャツカから千島列島までで台湾やスンダ列島で越冬するとあるものの日本の記述はなかった。
"Fauna Japonica" は本文に Motacilla boarula で現れる (参考。ヨーロッパと同じでジャワやスマトラ、日本でも記録されると言及されているのみ) のであまり気にしていなかったのかも。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire は現代の知見とそれほど異ならない。学名は Motacilla boarula を用いていた。英名は現在と同じ。アジアのものは尾が短めで melanope としてもよいとの記述になっていた。
[2種類のさえずり]
キセキレイのさえずりに単純な音を繰り返すものと複雑なものがあることはお気づきであろう。
石塚 (2018) Birder 32(9): 29 に「キセキレイの単純歌と複雑歌」という考察がある。この命名はわかりやすく英訳も簡単だが、海外の情報を見ても complex song のような用例が見当たらない。
我々が積極的に広めて行ってよい感じである。「とっておき」の時に複雑歌を使う感じがするが、石塚 (2018) によれば交尾を迫る際にこの歌で鳴くが求愛歌と言えるかどうかはわからないとのこと。
ツグミ類でも緊張状態で複雑な音声を出すことがあるとのこと。
タカがすぐ近くを飛んだ時にキセキレイが「逆説的に」複雑歌で鳴いたことがあった。録音を比較すると通常の複雑歌と同じもので無茶苦茶に鳴いたわけではないようである。この場合は気が動転して逃げる余裕もなく、代わりに転位行動のようにさえずったものかも知れない。
-
ハクセキレイ
- 学名:Motacilla alba (モタキルラ アルバ) 白いセキレイ
- 属名:motacilla (合) 尾を動かす鳥 (moto (tr) 動かす cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい) 本来は尾の意味はなかったが、誤解により -cilla は尾の意味で使われるようになった
- 種小名:alba (adj) 白い (albus)
- 英名:White Wagtail
- 備考:
motacilla は#ツメナガセキレイ参照。
alba は普通に読めば問題なし。
日本で最も身近な亜種名称の lugens は様々に読まれているが lugeo (ルーゲオー 嘆く、悲しむ) 由来で u, e ともに長母音 (ルーゲーンス)。2つめも長母音にするのが煩雑であれば最初だけ長母音 (ルーゲンス) の読みが過去の用例にもある。"ゲ" にはアクセントは置かないように。
カナ書きせずに学名そのままを使っておけば間違う心配はないが...。
現在は一般的には使われなくなった亜種だが dukhunensis の読み方は読みに悩まされる学名の一つだろう。コウテンシの種小名にも出てくるので考察しておく価値はあるだろう。
最後の部分は場所を表す -ensis なので問題ないが、前半をどう読むか。現代の言語の多くでは Dukhun (インド南部デカン高原 < dakshina 南 サンスクリット語) は Deccan (英語) などで綴られるので k の音を表に出して読めばよいのだろう "ドゥクネーンシス" (h の音を入れてもよい)。
kh はキリル文字のラテン文字転記のように "フ" の音として読める可能性があるが、そのような表記が可能なドイツ語 (Dekkan または Dekhan の綴り) やロシア語でも Deccan は k の音の表記になっているので考えなくてよさそうに思える。
語源となるサンスクリット語では右側、または南を意味する daksina (ダクシニャ) の読み (wikipedia ドイツ語版や wiktionary の発音記号表示から)。
ocularis は単純で "オクラーリス" (oculus 目 + -aris 形容詞に)。
leucopsis は "レウコプシス" [leucops 白い顔 "レウコープス" < leucos + ops (Gk) の属格。変化形で長音が消える例。学名用のラテン語。wiktionary から]。
alboides は "アルボイーデース"。
personata は "ペルソーナータ"。
baicalensis は "バイカレーンシス"。
ユーラシアとアフリカ北部に広く分布する。9亜種が認められている (IOC)。日本で最も普通に見られる亜種は lugens (喪服の色の) 亜種ハクセキレイ。
他に日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で掲載さてているものは alba (白い) ヨーロッパハクセキレイ、
この亜種はもと dukhunensis ニシシベリアハクセキレイとされていたが、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で alba に変更とともに和名も変わった。
このようなことが起きるのは Motacilla alba Linnaeus, 1758 (原記載) の記載では産地ヨーロッパとなっているが、後の規則によって Linnaeus 居住地スウェーデンが基産地に限定されたため。
ヨーロッパには複数の亜種の記載があるので、基産地を限定しないと亜種 alba が何を指すか特定できないことになる。
例えば英国では Pied Wagtail と呼ばれ、亜種 yarrellii とされる。
この経緯で北方型亜種は基亜種 alba と定義される。dukhunensis と alba が区別できない見解を採用すれば合体後は古く記載された方の基亜種 alba にまとまることになる。
OED (wagtail) によれば英名の Pied Wagtail は M. lugubris を指すとのことだが、この学名はシベリアのものを指すのでは? (#セグロセキレイ参照)、と思って Hartert (1910-1922) p. 301 を見ると、
何と Motaecilla lugubris Temminck, 1820 と Motaeilla Yarrellii Gould, 1837 をシノニムとしていた。Hartert は lugubris を有効としたためこのようなシノニム関係となったらしい。OED の記述もこの同定の範囲で正しいことになる。
現在亜種 yarrellii の名称が使われるのは Motaecilla lugubris Temminck が後に無効 (preoccupied) と判定された結果による。
基亜種 alba と。dukhunensis が別亜種とされていた時代にそれぞれの亜種和名が付けられていたが、合体によって後者の学名が現れなくなってニシシベリアハクセキレイの和名も変わることになった。
dukhunensis を認める世界のリストはいくつかあるが、IOC では認めていない。参考: Motacilla Dukhunensis Sykes, 1832 (原記載 ここで最も普通の種類とのこと。ハクセキレイでは越冬分布)。
この記載にも alba とほとんど同じと書いてある。わずかな色の違いのみで、場所が違うので別種が生息しているのではと考え、(亜種概念がまとまっていなかった当時) 種学名を与えただけのように見える。記載が古いので一見重要な亜種のように見えがちだが必ずしもそうではない。
ocularis (目の): タイワンハクセキレイ 記載時学名 Motacilla ocularis Swinhoe, 1860 (記載 基産地 Amoy, China)。
leucopsis (leukos 白い opsis 顔 Gk。頬の白いと説明してあるものがあるが、頬の意味は含まれていない): ホオジロハクセキレイ (英名 Amur Wagtail) 記載時学名 Motacilla leucopsis Gould, 1838 (記載 基産地 India)。
繁殖分布と基産地が異なっている点に注意。
alboides (Motacilla alba に似ている): ネパールハクセキレイ 記載時学名 [Motacilla] Alboides Hodgson, 1836 (記載 基産地記載なく Nepal と判定)。
この記載では Motacilla alba の東洋型とのこと。
日本鳥類目録第7版にあった personata (仮面をかぶった) メンガタハクセキレイ (英名 Masked Wagtail)、baicalensis (バイカル湖の) シベリアハクセキレイは日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討亜種に移動、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
検討亜種にはさらに 'persica' (ペルシャの) と引用付きでが挙がっている。この亜種は IOC では認められておらず、personata のシノニムとされる。
カムチャツカから日本に分布する lugens は Black-backed Wagtail または Kamchatka/Japanese Pied Wagtail として別種扱いにされたこともあったが、現在の世界のリストにはその兆候はない。後に紹介の Lee et al. (2018) にもカムチャツカで交雑がまれであるとの報告 (Nazarenko 1968) があったとのこと。
亜種識別は詳しい図鑑にも記載されているが、Young Guns (2016) Birder 30(4): 44-47 にもある。
新しい記事では加藤 (2023) Birder 37(10): 38-39 があり、各亜種の分布図は Semenov et al. (2018) が出典とのこと。Semenov et al. の論文は他にもある (後述) ので参照されたい。
茂田 (1995) Birder 9(12): 47-51 で lugens にセグロハクセキレイの名称が提唱されたことがある。
分子系統解析では、Voelker and Notes (2002) Systematics and Historical Biogeography of Wagtails: Dispersal Versus Vicariance Revisited は亜種 alba と lugens はそれぞれ単系統になっていない (この論文の時点では Motacilla lugens と別種扱いにしていた) ことがわかった。
使われたデータは今となっては限定的であるが、おそらくこの論文をもって lugens を独立種扱いにする議論は一応終わったのであろう。
なお GenBank は独立種扱い (Motacilla lugens) としている (2025.4 段階)。
Shirazinejad et al. (2019) The evolutionary history of the white wagtail species complex, (Passeriformes: Motacillidae: Motacilla alba)
に新しい研究と先行研究が示されているが、N, SE, SW, M の4クレードに大きく分けられるとのこと。生物地理学的な分類とは部分的にしか整合せず、互いに混ざっているとの結論になっている。外見の特徴などをもとに何亜種を認めるか今後の議論になって行くのだろう。
セキレイ類のように進化速度の早いグループでは遺伝型と表現型が必ずしも対応しなくなることは Harris et al. (2018)
Discordance between genomic divergence and phenotypic variation in a rapidly evolving avian genus (Motacilla)
にも示されている。
モロッコ型のみを別系統 (亜種 subpersonata に対応) として他は1系統にまとめるのも一つの解であろうが、あまりに大雑把すぎるとされそうである。
ハクセキレイの分類は外見でも分子遺伝学でも難しいようであり、また亜種 alba と personata の間では頭の模様の一致するつがい相手を好む assortive mating の傾向も示されている
[Semenov et al. (2017) Effects of assortative mate choice on the genomic and morphological structure of a hybrid zone between two bird subspecies] ため分子遺伝学のみに頼るのは適切でないだろう。当面は現在の分類が使われるのであろうか。
Semenov et al. (2021) Asymmetric introgression reveals the genetic architecture of a plumage trait によれば、ハクセキレイの顔の模様を決める遺伝領域 (この論文では亜種 alba と personata) が特定されたとのこと。
メンデルの法則で言うところの優性の法則とエピスタシス [epistasis: 遺伝学において、異なる遺伝子座間の相互作用が一つの形質に影響すること (wikipedia 日本語版より)] が部分的に働いているらしい。personata のようなほぼ真っ黒な模様は劣勢の形質とのこと。
このように顔の模様を決める遺伝領域が例えばミトコンドリアとあまり関係なく進化すれば (これまで調べられた範囲の) 分子系統樹と従来の亜種分類の対応が悪いことも説明できるのであろう。
韓国でのホオジロハクセキレイと亜種ハクセキレイ (lugens) の交雑の研究がある。Lee et al. (2018)
Breeding biology of two wagtail subspecies on Ulleung Island, Korea: Amur Wagtails, Motacilla alba leucopsis and Black-backed Wagtails, M. a. lugens
2亜種の交雑は普通に起きて子孫も繁殖能力があるが、つがい形成の際は同じ亜種を選択する傾向があるとのこと。
茂田 (1996) Birder 10(1): 46-52 にハクセキレイとセグロセキレイの解説があり、lugens は当時は世界的にも分布を拡大中。日本での繁殖初記録時代の情報がある。
フィリピンでも記録されたとの記載があったのでフィリピンの現在のチェックリストを見たところ、lugens はまれな冬鳥の扱いになっており迷鳥扱いではない。
試しに NC_029703.1 (亜種ハクセキレイのミトコンドリアゲノム) から BLAST を行ってみると亜種 alba とはかなり違い、一致度も 93% 程度。亜種ハクセキレイとツメナガセキレイの関係と同程度かやや近いぐらい。
この数字を見ればユーラシアの東と西で別種にする値打ちはあるが (もっともミトコンドリアと核ゲノムで異なる可能性もある)、広域分布で連続的なものとみなすべきか、分ける場合は何種に分割するのが適切かなどの問題があって特に中間地域ではいずれも決着しておらず、他の亜種もあまり読まれていないのでまだ様子を見ている段階だろうか。
Alba / Lugens Wagtails (Birds Korea のコメント 2003)。
[ロシア沿海地方のハクセキレイ]
Shokhrin et al. (2024b) Breeding birds of Primorsky Krai: the white wagtail Motacilla alba (pp. 3797-3819)
ロシア沿海地方のハクセキレイの繁殖について。3亜種の記録があるが繁殖亜種は leucopsis ホオジロハクセキレイ (ロシア名では中国のハクセキレイ) で、これについて述べられている。
この亜種は内陸型で、沿岸沿いの集落では亜種ハクセキレイ lugens が圧倒的に優勢とのこと。ホオジロハクセキレイと亜種ハクセキレイの雑種報告は多くある。
亜種ハクセキレイは Shokhrin et al. (2024a) Breeding birds of Primorsky Krai: the Kamchatka wagtail Motacilla (alba) lugens (pp. 1005-1023)
で取り扱われている。(準) 別種扱いなので別論文となっていて Shokhrin et al. (2024b) の3亜種の記録の中には含まれていない。亜種ハクセキレイはロシアでは沿岸部や島好きの亜種のよう。
分類に関して Nazarenko and Pavlenko (2018) Populations of <> wagtails lugens, leucopsis, alboides and personata (Motacilla alba sensu lato) in a changing world: anthropogenically conditionedniches, counter expansions, sluggish introgression, taxonomic ranks and time parameters of these events (pp. 3985-4001)
の考察がある。この文献では Motacilla leucopsis ホオジロハクセキレイを種扱い、
alboides と personata を種 Motacilla alboides の亜種とする考えを示している。
極東の鳥類48 沿海地方の繁殖する鳥類 5 でこれら論文の和訳が読める。
[ハクセキレイによる異種間ヘルパー]
Zheng et al. (2025) First Discovery on Interspecific Parental Care of Siberian Stonechat (Saxicola maurus) Nestlings Provided by a Male White Wagtail (Motacilla alba)
ハクセキレイがシベリアノビタキ (今度ノビタキと同種とされる可能性あり) の子育てを大幅に手伝ったとのこと。巣が近かったので誘発された可能性が考えられるとのこと。
[セキレイの漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 79 VII (藤堂) によれば中国語ではもともと脊令と記していたが、鳥のことであることがわかるようにそれぞれ鳥を補ったのが現在の文字。
脊は背とは異なり、脊椎動物の脊と同様に背骨や背筋などの意味。令は酋長が人をあつめてひざまずかせ、神のお託言や命令を申し受ける姿を表す文字。冷たいことを指し、組み合わせて冷や玲などの漢字となっている。
セキレイは頭には白い部分があるが、背筋は青黒く冷たい色 (清冷なる鳥) であることを指しているとのこと。
脊令の表記は "詩経" にすでに登場する。英語でも cool はよい意味で使われるので "冷たい" と言っても物理的な意味通りに読む必要はないだろう。
この当時はもちろん使われていなかったが、「令和」が発表された時に "令" の意味が問題となったことがあった。日本の新元号「令和」に関する考察 (ライアン・シャルジアン・モリソン 2019) を参照しておくと、
(1) 古代には「お告げ」、すなわち啓示もしくは神道の神からの命令を意味し、神聖で縁起のよい意味合いを持っていた。
(2)「立派な」もしくは「素晴らしい」ものの前につける伝統的な接頭辞。
(3)「命令」「条令」のように、法律で義務付けられるもの、強制されるものを意味する。
とあった。モリソン氏と藤堂氏の解釈のいずれがより深いのかは知らないが、藤堂氏のセキレイの解釈はいずれも少しずつ加味したものとなっていると思われる。
(2) の "令" の使い方も中国語由来のようで、よく用いられる形では他人の親族などを指す場合に敬辞として用いられるとのこと。例えば令郎であれば 令郎 で "西遊記" にも登場する。
中国のセキレイで最も普通の種類を調べてみるとハクセキレイとのことで、おそらくハクセキレイの色彩を指したのだろうか。
令和に込められた意味はともかく、"令" をセキレイだと思えば、セグロセキレイになるのではないだろうか (?)。
-
セグロセキレイ
- 学名:Motacilla grandis (モタキルラ グランディス) 大きなセキレイ
- 属名:motacilla (合) 尾を動かす鳥 (moto (tr) 動かす cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい) 本来は尾の意味はなかったが、誤解により -cilla は尾の意味で使われるようになった
- 種小名:grandis (adj) 大きな
- 英名:Japanese Wagtail
- 備考:
motacilla は#ツメナガセキレイ参照。
grandis は短母音のみ (グランディス) で英語と同様に読んでよい。
単形種。
現在の学名は 原記載 (Sharpe 1885)。
同書 p. 492 によれば、Temminck は 1835 年に Motacilla lugubris、Temminck and Schegel は 1850 年に "Fauna Japonica" で Motacilla lugens と命名した。
記載 フランス語名 la Bergeronette grise orientale。
(図版)。
Temminck and Schegel は Bergeronette grise (灰色のセキレイ = ハクセキレイのこと) の3つめの race (現在では亜種に相当する用語。当時は亜種の学名記述方法は確定していなかった) としていた。基本型がヨーロッパのハクセキレイ。
Temminck and Schegel が記述したものはカムチャツカ、千島列島、日本、フィリピンで記録されるとあり、"日本の" を示す種小名やフランス語名を付けることはできなかった。代わりにフランス語名で "東洋の" を付けているが学名は色彩由来。この記載からもハクセキレイと混同していたことがわかり、結果的に有効な記載とはならなかった。
カムチャツカと千島列島で記録されていることを示したのは Billings。
Temminck 自身の用例 (1835) では 表 に Motacilla lugubris Pall. とあり、Pallas の用例を引用している。
フランス語名では Bergeronette lugubre plumage d'hiver と冬羽に付けた名称として、夏羽は Motacilla abla et cinerea とみなしていたらしいことが読み取れる。本文にも記述があるらしい記述があるが探すのが難しく見つかっていない。
Motacilla lugubris Temminck, 1820 (記載; 参考) と 1835 年以前の Temminck の用例もあった。この用例では (Pallas) を付けており、これらセキレイはロシア産のものと考えていた。
#クロジの例でもあるように同じ学名を使いつつ、あまり明示しない形で解釈を少しずつ変えて行ったらしいが、もともとはロシア産の考えにとらわれてしまい、日本のものは日本固有と考えにくかったらしい。
Seebohm (1890) The birds of the Japanese Empire に事情説明があり、Swinhoe (1863) がいずれの学名も preoccupied (使用済み) であることに気づいて Motacilla japonica Japanese Wagtail と名付けたとのこと。
しかし "Fauna Japonica" と同様にハクセキレイ (亜種 lugens) を本種の冬羽と勘違いしていたとのこと (参考。冬は中国沿岸で迷鳥とある)。
先に使用された学名の方を見ておくと Motacilla lugens Gloger, 1829 (参考) で Motacilla lugubris Temminck (これを見ると 1820 年のものを指すよう) を改名したもので Motacilla lugubris Pallas の方ではないとある。
この記載が現在のハクセキレイの亜種名に使われている (Temminck の記載はセグロセキレイでなくハクセキレイを指すと解釈されたことになる?)。
さらに Motacilla lugens Kittlitz, 1833 (参考) があり、これは Pallas がカムチャッカで記録した Motacilla lugubris を改名したもの。こちらの方がハクセキレイの亜種の記載としてふさわしいように見えるがなぜか Gloger (1829) が記載者とされている。
改名理由となった学名重複は Motacilla lugubris Lichtenstein, 1818 (参考) でアジアとアフリカとあって1種にはまとめられずこれも有効とならなかったようだが使用例があるため後続の学名に影響を与える形となった。
ハクセキレイの系統は白黒なので、世界どこであっても "白黒セキレイ" に相当する学名が付けられて簡単に重複が発生していた模様。
lugubris や lugens のような凝った学名ではなく素直に "白黒セキレイ" と呼べばよいではないかと思われるだろうが、そんな名前ははるか昔にすでに使われてしまっていた: Motacilla leucomela Pallas, 1770 (参考)。
逆順もあった Motacilla melanoleuca Palmer & Shirley, 1836 (参考)。
時代を見れば Temminck (1820, 1835) ぐらいの時期ならば使えないことのない学名ではなかったようだが、単に "白黒" を "黒白" と入れ替えるだけではあまり芸がないと感じられたのだろう。他にも似た学名はいくつもある。
正しく diagnose されたのは Seebohm (1884) が最初とのこと (これは Seebohm 自身の解釈による説明)。
ただしこの勘違いはセグロセキレイをハクセキレイと同種とみなすか次第で解釈が変わる。ハクセキレイと同種とみなすならば (当時は亜種概念はまだそれほど明確でなかった)、ハクセキレイの亜種 lugens とセグロセキレイを1種にまとめた Motacilla japonica の学名も可能で Swinhoe はこの扱いとしたと Seebohm (1890) は述べている (先取権のことは知らないが...)。
Seebohm は自身は splitter (種を分ける主義) だと述べた上で別種と考え、日本のものにのみ Motacilla japonica を適用し、Kamtschatkan Wagtail を Motacilla amurensis と Motacilla blakistoni の2種に分離した。
Seebohm (1890) は Motacilla grandis Sharpe, 1885 の学名がさらに与えられたことで一層混乱をもたらしたと嘆いている。
Seebohm (1890) 自身は Motacilla japonica Swinhoe, 1863 Japanese Wagtail の名称を使っていた。この学名は使われなくなったが英名に残ることになった。
Temminck (1835), Temminck and Schegel (1850) の学名が有効であったならば Pied Wagtail の入った英名になっていたと想像できる。
(以降は過去に調べた結果が含まれて上記説明と重複する部分があるが、各文献での記述などが含まれるため残しておく)
Tristram (1866) 他は Motacilla japonica、また Swinhoe (1860) は Motacilla lugens var. lugubris とするなどハクセキレイの亜種か、ハクセキレイの (現在は) 亜種 lugens を独立種とするかなど混乱があったことがわかる。
いろいろ議論はあったがハクセキレイとの混同なども解消され、Sharpe (1885) が初めて正しく記載したためこれが採用されたのだろうか (Motacilla japonica Swinhoe, 1863 の時点ではまだ勘違いがあり、正しく diagnose したはずの Seebohm は Swinhoe の学名を使い続けたため有効とならなかったのだろう)。
Sharpe (1885) の文献では Motacilla lugens を別種としている。また Motacilla japonica の学名は Tristram の方を採用しており、Swinhoe ではないとある (Motacilla japonica Swinhoe, 1863 は Motacilla lugens と同じ扱いとなっている。この結果 Swinhoe の誤りが引き継がれなくなったものか)。
生息地には日本の他に東シベリア沿岸も含めていてちょっと怪しい記述だった可能性があるが標本はすべて日本からのもので確実にセグロセキレイと判定できたのであろう。
Sharpe (1885) が別種としたハクセキレイ (Motacilla lugens) や他の多くのセキレイ類に比べてセグロセキレイの方が少し大きいため grandis と名付けたと考えられるが理由は述べられていない。
大きいならば major などでも良さそうだが、これはあまりによく使われており、過去の Motacilla 属は巨大であったためどこかに重複例があって (あるいはそれを恐れて) 違う種小名を与えたと考えられる。
同じく大きいを意味する Motacilla magna Gmelin, 1789 (参考) はすでに用例があった。小さいの方は Motacilla minuta Linnaeus, 1758 があって、大小をありふれた種小名で記述する時代は終わっていたと想像できる。
ところが major は実際には有効だった (記載がそもそもなかった、あるいは過去の用例が学名と認められなかった、さらにあるいは属分離などで有効となったなど) ようで Motacilla major Milne-Edwards, 1871 (化石種) の記載があるらしい。
もっとも grandis はもう少し広い意味があって wiktionary を見ると成長した、成熟した、偉大な、英語版では力強いなどの訳語も与えられている。語源の方を見るとゲルマン祖語の *grautaz ("big in size, coarse, coarse grained") とも関係があるとのこと (英語の great の由来。large とは少し違う)。古ギリシャ語の brenthos (傲慢さ) とも関係があるとのこと。
単なる大きさ比較だけよりも力強さ [または態度がでかい (笑)] を感じ取った命名かも知れない。配色のきめの粗さ (coarse grained。色彩が繊細でない) も反映しているかもしれない。語義解釈を通じて命名者の意図や学名の世界を楽しんでいただける題材になりそうである。
英語でも grand (雄大な、上級のなど) に使われる通り。音楽の発想記号でも grandioso があって雄大に演奏せよ、ということになる。該当するような曲をご存じの方ならば納得いただける表現と思う。
grandis はかなり好まれた(亜)種小名だったようで IOC 14.2 でも多数の用例が残っている。音楽の発想記号で使われたのと同時期なので当時の好みの表現がわかる感じもする。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Motacilla japonica Swinhoe を採用していたが、同じ学名はハクセキレイの現在の亜種 lugens の項目にも含まれているので混ざって記載された認識だったのだろうか。
Swinhoe (1874) Japanese Pied Wagtail。Blakiston から送られた3標本を取り上げていて、後の2つはセグロセキレイの記述に見えるが、最初のメスとされる1個体は一見すると M. ocularis に見えるが、とあるのでハクセキレイかも?
Swinhoe の最初の japonica の用例と言われるもの (1863) が Motacilla ocularis
の項目で脚注に背の黒いタイプのハクセキレイについて議論しており、M. ocilaris Swinhoe, 1860 と M. lugubris Pallas はシノニムかも知れないと述べ、そうであれば日本のものを japonica と呼びたいとある。
"呼びたい" を学名の有効な記載として認めるかどうかはおそらく問題があり、Seebohm (1890) は 1863 年を記載年としているが一般的には 1874 年のものが認められているらしい。
Swinhoe (1863) の中で ocularis のみがタイワンハクセキレイとして現在使われるいることからおそらくどれも記述が曖昧あるいは現在の分類で単一のものと認められないなど確実なセグロセキレイの記述と認められなかった経緯が考えられる。あくまで推測だが Seebohm (1890) の記述を読む限りではハクセキレイ亜種との混乱があったと解釈されている模様。
Ogawa (1908) では Motacilla grandis Sharpe, Motacilla lugubris Temminck の両者を取り上げている。
年の記載はないが前者は 1885 で問題なし。後者は現代の資料からみると 1835 (または 1820) 初出となりそうだが別の資料を参照していたかも知れない。
ハクセキレイの亜種は2つしか含めていないので、タイワンハクセキレイに対応するものはこちらに入っていたのか、あるいは採用しない理由があったのかも。
当時は Swinhoe (1863, 1874) に先取権があると判定されていたのだろう。
Motacilla lugubris の学名はしばらく使われていたようで、これは黒白の喪服色の意味だろうか (#ヤマセミの備考参照)。
オオハクセキレイ Motacilla maderaspatensis White-browed Wagtail がかつては亜種 Motacilla lugubris maderaspatensis として扱われていた。
Motacilla lugubris は現在はハクセキレイの学名のシノニムとされている模様。
Gould (1837) によれば Motacilla lugubris Pallas (この文献では Pallas となっているが Temminck も同じ学名を用いた) とした種はクリミア、ハンガリーの多く、イタリアの一部、エジプト、小アジア、シベリア南部に生息し、日本では非常に多いとある:
White-winged Wagtail 夏・冬羽の図版もあるが、少なくともセグロセキレイとは全然違うことがわかる。
A descriptive catalogue of Japanese wild birds, useful and injurious exhibited (The Agricultural Bureau of the Department of Agriculture and Commerce, Japan 1898)
ではキセキレイを Motacilla boarula L.、セグロセキレイを
Motacilla japonica SW. とするなど学名の扱いは相当混乱していたことがわかる。当時はハクセキレイは一般的でなかったためか含まれていない。
これらを見ると Motacilla japonica が指していたものはセグロセキレイで、現在の学名で Motacilla alba lugens ではないだろう。Temminck も同じものを指していたと考えられるが、ヨーロッパにまで分布するものと同種と考えていた模様。
Motacilla lugens の学名も混乱していたようで Kittlitz, 1833 とあるものも、Motacilla alba lugens Gloger, 1829 としているものもある。
Motacilla lugubris Lichtenstein, 1818 (参考) があるが、アジアとアフリカからとあってちょっと怪しい (ドイツ語名 Trauersanger とあるのでやはり葬送や喪服を意識していた模様)。
Motacilla iugubris Lichtenstein, 1819 (参考) は綴り間違いとのこと。
Motacilla lugubris Temminck, 1820 (参考) によれば Temminck の用例は preoccupied と判定されるとのこと (Hartert)。
Motacilla lugubris Vieillot (参考) もあるが特定の図版は指しているものの他の著者の用例には言及がないとのこと。
lugens は M. lugens (Gloger 1829) が初出でこれが原記載として使われるが、この文献では = M. lugens Temm. とあるのでどれを取っても (現在の知見からは) 明瞭な種・亜種の記載ではなかったと思える。
これは現在ハクセキレイの亜種 lugens は別種か、とはまた違うレベルの問題。
種セグロセキレイ、ハクセキレイの亜種の学名起源は一般に言われているほど単純なものではなく、分類の変遷に伴って折り合いをつけて整理されたものと考えた方がよさそう。Gloger (1829) 以前の用例はいずれも同定できないか複数の種類を含んでいてすべて無効とされたものと考えられる。lugens は意味はおそらく同じもののちょっと語形を変えることによって preoccupied となることを避けたものと想像できる。
lugubris は当時非常に人気のあった種小名で IOC 14.2 でも 11 種の種小名となっている (実際に付けられたものはもちろんもっと多い)。lugens は2種のみ。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではセグロセキレイはハクセキレイの亜種としていた。
セグロセキレイの学名の経緯がどこにも詳しく述べられていないのは、文献も古く複雑すぎて調べきれないためだろう。日本産鳥類を紹介した Temminck の分類は適切でなかったようで、現在とは違う学名を用いたことは知っておいてよいかも知れない。
各種文献で用いられてきた分類と学名一覧がないと変遷がわからない感じがする。
[学名はなぜ結局 Motacilla japonica とならなかったのか]
非常に複雑なのでまとめると Temminck and Schegel は 1850 年に "Fauna Japonica" で日本から記載しているが、ハクセキレイとの混同があって東洋に広く分布する種と考えた。
そのための japonica のような種小名を使うことはできず (Temminck and Schegel もヨーロッパの対応種がある場合に使っていたのでそもそも対象外だったかも知れない)、色彩の特徴から Pallas の用いた種小名を用いたが、すでに使用されていた学名と判明して無効となった。フランス語でも "日本のセキレイ" とは呼ばなかった。
これに気づいた Swinhoe (1863) が改めて Motacilla japonica と名付けてこの学名が有効になる可能性があったが、Temminck and Schegel 同様にハクセキレイとの混同が残っていたためおそらく有効とならなかった。
Sharpe (1885) が Motacilla grandis と付けたものが有効となった。
Swinhoe (1884) は問題を解明していたが自身の 1863 年の学名をそのまま使っていたために正しい学名の記載とはならなかった。1890 年に自身の解釈を述べる形で振り返っているが釈明に近い内容となっている。
Hartert (1910-1922) p. 308 にも記述あり。Swinhoe がここで japonica を使ったためにセキレイ類で他に亜種名でも japonica を使うことはできなくなった。
[近縁種との関係]
日本と韓国に分布するが他所からの報告例もある。かつてはハクセキレイと亜種関係にあり、大陸のハクセキレイが日本に進出して独自の進化を遂げた説もあったが、セグロセキレイにもっと近縁な種が別にあるためにこの考えは少なくとも一旦は葬り去られた。
先述の Harris et al. (2018) の分子系統樹によれば、セグロセキレイに最も近縁な種はメコンセキレイ Motacilla samveasnae 英名 Mekong Wagtail という 2001 年に初めて記述された種。
もう1種は ハジロハクセキレイ Motacilla aguimp 英名 African Pied Wagtail というアフリカの種類。この分析では扱われていないが、インドに分布するオオハクセキレイ Motacilla maderaspatensis 英名 White-browed Wagtail があり、セグロセキレイにもっと近縁な種と言われた (一時期は同種とされた) のはこの種であろう。
「日本の鳥の世界」(樋口広芳 平凡社 2014) pp. 34-35 にセグロセキレイとオオハクセキレイの関係が扱われていた。
茂田 (1996) Birder 10(3): 38-47 にオオハクセキレイとセグロセキレイの courtship display に類縁性があることが述べられている。また亜種ハクセキレイ Motacilla alba lugens にセグロセキレイに似た羽色の個体もあることも述べられている。
中村 (2013) 日本列島におけるセキレイ属近縁2種の分布変遷と種分化 は分子系統の得られる前であるが、過去の見解などもまとめられており、アジア大陸東北部から日本の北部に侵入した個体群と、インドからカシミール (インド北西、パキスタン北東の地方) に侵入した個体群は、侵入先にもとからいた個体群と交雑せずに共存することになった。
つまり、日本とインドの個体群は、地理的に隔離されていた間に大きな違いを発達させ、それらの共通祖先から別種に分化していたのである、という考えが紹介されている (Mayr 1965; 樋口 1984)。
Harris et al. (2018) には過去の分子遺伝学研究でハクセキレイとセグロセキレイが十分分離できなかったことも示されており、頻度は少ないものの雑種形成もみられるために相互の遺伝子浸透が考えられていたが、この研究でその証拠は見つからずセグロセキレイを遺伝的にも独立種として認めてよい結論となった。
Harris et al. (2018) もセグロセキレイやオオハクセキレイのグループが離れて分布していることは気にしており、さらなる研究が必要とされる。
Rancilhac et al. (2024) Introgression Underlies Phylogenetic Uncertainty But Not Parallel Plumage Evolution in a Recent Songbird Radiation
がゲノム解析による系統関係を発表。incomplete lineage sorting や遺伝子浸透もあり関係が複雑。重みのかけかた次第で系統樹が変わる。
メコンセキレイ Motacilla samveasnae Mekong Wagtail の近縁性は支持される結果となったがオオハクセキレイ Motacilla maderaspatensis White-browed Wagtail はむしろ遠くなった感じ。
オオハクセキレイはむしろハクセキレイに近い? がすっきりしていない。セグロセキレイとハクセキレイの間では遺伝子浸透があったと考えられる。
これらのセキレイ類で白と黒の表現型は遺伝子浸透でもたらされた以外に、黒い色彩に関係した部位の少しの変異で短期間で並行して進化した結果の可能性もある。完全に分離していないとはいえ種として扱い、また進化的関係を議論するには十分有用である。このような難しいケースではゲノム系統解析 (phylogenomic analysis) が標準になるのだろう。
解析に用いられたハクセキレイはヨーロッパのものだが lugens がどの程度違うのかも知りたいところ。齋藤氏がセグロセキレイのサンプルを提供し共著に入られているので詳しい説明を聞けるかも知れない。
カラス類も同様だが白と黒の鳥の系統関係は難しいよう。
セグロサバクヒタキを含むサバクヒタキ類の一部でも同様の状況が報告されている: Schweizer et al. (2019) Parallel plumage colour evolution and introgressive hybridization in wheatears。
近縁とされる種の音声をチェックしてみた (xeno-canto)。ハジロハクセキレイは flight call が記録されているがセグロセキレイとあまり似ていない。
メコンセキレイはデータが少なくはっきりした flight call は記録されていない模様。オオハクセキレイはもう少しデータがあるが、call となっているものの大部分は song の要素を含む call のようで純粋な flight call は少ない。おそらく flight call と思われる XC110817 はセグロセキレイにそれほど似ていない。
song よりもむしろ flight call が系統解析にも有効そうだが、データ数が少ないので積極的に取り上げられていないのかも知れない。音声を聞く限りではそこまで近縁でない感じがする。音声は Rancilhac et al. (2024) の前に調べたものだが傾向は合っている気がする。
セグロセキレイのロシアの分布が気になるところだが、文献的には The Japanese wagtail Motacilla grandis - a new bird form for Soviet Union (pp. 1141-1142)
Panov (1963) の再掲で、1960 年、1961 年秋に観察されたもので、1960 年は3羽のハクセキレイと一緒にいたとのことで、ハクセキレイの1羽はヤクーチアの亜種 ocularis、他の2羽は若鳥で亜種不明とのこと。
翌日に 12-15 羽のセキレイ集団がいて、2-3 羽はハクセキレイの亜種 lugens だったとのこと。
セグロセキレイは色彩だけでなく声も明らかに違っていたとのことで種の判定は問題なさそう。
色彩はハクセキレイの亜種 personata (メンガタハクセキレイ) にたいへん似て見えたとのこと。採食様式もセグロセキレイとハクセキレイとは違っている。標本として採集した結果非繁殖のメスと判明したとのこと。1961 年の観察例も特有の採食様式が見られたとのこと。
近年は eBird に中国国境近くで少数の記録があるが写真はない。North Eurasia Birds Watch にも写真記録がない。もともと人口密度の低い地域であろうが少なくとも普通に見られる種類ではなさそう。
ハクセキレイとセグロセキレイの交雑個体については中村・岩本 (1985) ハクセキレイとセグロセキレイの交雑個体について があるが頻繁に観察される種類であるもののあまり例がないようである。
ある探鳥会で聞いた話であるが、セグロセキレイの白化個体はよく聞くがハクセキレイはあまり聞かないと話題になった。
調べるとハクセキレイの例がないわけではないらしいが (国内の写真もいくつか出ているがハクセキレイかどうか判断できないのでこのような記述としておく)、セグロセキレイの方が頻度が高い感じがする。興味ある方は調べていただければと思う。両者の区別に最も有効なのは (野外では) もちろん地鳴きの違いである。
The Leucistic White Wagtail at Arrecife カナリー島で記録されたハクセキレイの白変個体とのこと。真っ白ではない。
系統解析の論文がすでに出ているが試しに GenBank で BLAST をやってみようとセグロセキレイの遺伝情報を探したが驚くほど少なかった (2025.2 時点)。JF499146.1 を起点に行ってみるとハクセキレイと少し異なる系統になるが多少混ざっている。限られた配列情報に頼っているためと、ハクセキレイの世界分布が広すぎる要因もあると思われるがハクセキレイとセグロセキレイは想像以上に遺伝的に近いかも知れない。
ただしツメナガセキレイとニシツメナガセキレイの関係よりは遠い。
ハジロハクセキレイやオオハクセキレイと共通する遺伝子が GenBank にないようで直接の関係は調べられなかったがハジロハクセキレイ、オオハクセキレイともにハクセキレイグループで古く分岐した系統にあたり、ハクセキレイとの系統関係はセグロセキレイと似ている。セグロセキレイも含めて古いグループで、新参者のハクセキレイに次第に圧倒されるようになってそれぞれ局地的にしか残っていないのではないだろうか (#ルリカケスの備考参照)。
この部分を記述してから知ったが、「日本の鳥の世界」にも基本的に同じようなことが書いてあった。
例えば古く分岐した系統のうち体サイズの大きい種のみが残っている、あるいは交雑によって祖先型の種が失われたなどが考えられる。参考までに wikipedia に載っている全長はセグロセキレイ 20 cm、オオハクセキレイ 21 cm、ハジロハクセキレイ 20 cm、メコンセキレイ 17.0-17.5 cm。ハクセキレイは 16.5-19 cm だが東アジアの亜種は大きく 21 cm に達することがあるとのこと。
日本では長い間ハクセキレイは冬鳥で繁殖期の競争はあまり生じなかったが、同所的に繁殖分布するようになるとあるいは将来セグロセキレイが競争的に不利な状況も生じる可能性もあるのかも。
ハクセキレイもここでは主に lugens を想定しているが leucopsis も繁殖が知られるようになり、大陸からの進出が目立ってきている感じがする。ハクセキレイにとって好適な環境が広がったなどの人為要因もあるだろうか。もしセグロセキレイに遺伝的レベルで影響を与えるならば、人為が間接的に準固有種を脅かしていると読むことができるのかも知れない。
同じような広範な分布を示すのにキセキレイには亜種はほとんどなく、ハクセキレイに多数の亜種があるのはハクセキレイの系統では先行して適応放散した仮想的なグループ (セグロセキレイなど) があって後発のハクセキレイがそれらの先行系統を排除あるいは吸収した痕跡の可能性はないだろうか。先行して適応放散したグループに地理的な違いによる遺伝子頻度の違いなどがあれば交雑の結果に残っているのかも。
先行して適応放散したグループは現在の分布では南に偏っており、北方にはあまり進出しなかったのかも知れない。ハクセキレイの亜種がユーラシア中央部から東部で多いのは先行して適応放散したグループの種分化結果を反映しているのかも知れない。
ここまで行くとさらに妄想レベルになるが、セグロセキレイで白変個体が多いのはあるいはセグロセキレイの発色機構の方が安定度が低く、(メラニン合成を行えないアルビノ以外にも) わずかな遺伝的変異で色彩を失いやすいのかも知れない。ハクセキレイの方の発色機構が安定しているならば交雑した場合にセグロセキレイ由来の色彩制御機構が次第に失われてゆく、つまり色彩表現型として吸収されてしまいやすい可能性はないだろうか。
本格的に調べようと思えばハシボソガラスとズキンガラス、あるいはマガモとカルガモの関係のように雑種個体を含めた高精度のゲノム解析を行う必要があるだろう。supergene や構造多型も関係している可能性もあるかも知れない。誰かやるだろうか?
なお上記 JF499146.1 の配列は Chugoku, Iwakuni, Marine Corps Air Station Iwakuni, dump 由来とのことでアメリカの研究。あるいは軍用航空機へのバードストライクの研究のために日本の鳥について DNA バーコードを調べたものだろうか (未確認)。
[尾を振るのはなぜ?]
系統的にはまったく関係がないが、ヨコフリオウギビタキ Rhipidura leucophrys Willie Wagtail が川口 (2019) Birder 31(9): 52-53 に紹介されていたので調べてみた。
セキレイのように尾を振ることから (ただし横に振る) 名付けられた模様。オーストラリアへの入植者が故郷の鳥に似た名前を付けたのだろう。
wikipedia 英語版によればほとんどいつも動いていて、とまって獲物を探している時も尾を左右に動かしたりねじったりしているとのこと。捕食者がそれほど目立ってもよいのだろうかと思ったりしたが、これは虫などをおびき出しているのだろうか。
そう思って調べてみると Jackson and Elgar (1993) The Foraging Behaviour of the Willie Wagtail Rhipidura leucophrys: Why Does it Wag its Tail?
という研究があった。結果はあまりすっきりしないが、地上で尾を振ることで食物となる虫が出てくる効果を期待する解釈とは合うとのこと。日光の強い日はあまり尾を振らないとのことで、これは影に驚いて隠れてしまうためでは、ただし他の解釈も可能とのこと。
関連した新しいレビューでは Randler (2016) Tail movements in birds―current evidence and new concepts (日本鳥学会の Ornithological Science でも一番よく読まれている論文の一つ。オープンアクセスになっているのでまずはおすすめ)
があって prey-flushing (上記に相当), perception advertisement (捕食者に気づいていることを知らせる), quality advertisement (同種間の選択時に質を主張する), alarm signal (同種間の警戒信号) の役割を挙げている。
この論文では尾を横に振るのは prey flushing の可能性があるが、通常のセキレイ類のように上下に振るのは predator-prey context, social function の可能性を考えた分類になっている。上下に振るセキレイ類は採食が主たる要因ではない? イワミセキレイだけ別用途というのも変な気がするが、森林性で比較的暗い環境のためだろうか。
ベニイタダキアメリカムシクイ Myioborus miniatus Slate-throated Redstart では採食に役に立っているよい証拠があるとのこと: Mumme (2002)
Scare Tactics in a Neotropical Warbler: White Tail Feathers Enhance FlushPursuit Foraging Performance in the Slate-Throated Redstart (Myioborus Miniatus)
白黒の尾を持つが人工的に塗りつぶすと採食効率が目立って低下したとのこと。
Mumme et al. (2006) utionary significance of geographic variation in a plumage-based foraging adaptation: An experimental test in the slate-throated redstart (Myioborus Miniatus)。
クロズキンアメリカムシクイ Setophaga citrina Hooded Warbler でも同様とのこと: Mumme (2014)
White tail spots and tail-flicking behavior enhance foraging performance in the Hooded Warbler。
Mumme (2023) Stabilizing selection on a plumage-based foraging adaptation: hooded warblers with average-sized white tail spots live longer ではクロズキンアメリカムシクイの尾の白い部分の大きさが生存期間と相関があるとのこと。この著者は採食効率に関連していると主に考えており、性や社会的信号以外の目的でもこのような形質が選択される証拠としている。
このような捕食者を一般的に flush-pursuit insectivores と呼ぶとのこと。これらの事例を見るとジョウビタキの翼の白斑も同様の目的か。
Jablonski et al. (2006) Habitat-specific sensory-exploitative signals in birds: propensity of dipteran prey to cause evolution of plumage variation in flush-pursuit insectivores (実験に使われた具体的事例は Abstract 参照) によれば背景の色調によって効果が異なるとのことで、ジョウビタキには白斑があるのにシロビタイジョウビタキにはない理由ももしかすると説明できるのかも (勝手に考えただけでどこかに書いてあるわけではない)。
セキレイ類については現状でもあまりはっきりしていないようであまり研究する人もないのかも知れない。
Randler et al. (2020) The functions of tail flicking in birds: A meta-analysis が他種も含めたメタ解析を発表している。
複数の役割を果たしてそうだが、警戒している時、捕食リスクの大きい時に尾を振る一般的傾向があったとのこと。
この Randler は昔から「正直なシグナル」を唱えている: Randler (2006) Is tail wagging in white wagtails, Motacilla alba, an honest signal of vigilance?。
これも羽繕い中でも振っているので採食のためとは考えにくいなどの消去法で正直なシグナル説になっている。
Randler (2007) Observational and Experimental Evidence for the Function of Tail Flicking in Eurasian Moorhen Gallinula chloropus はバンについて同様の提案。
2020 年の論文も自身の仮説を補強する結果として発表したもので、多少割り引いて見た方がよいかも知れない。現在の研究者は実質この人だけのよう。バードウォッチャーの興味と学問的興味の方向/流行が多少離れている。代わりの説があまり提唱されていないので解釈としてよく紹介されるがこのような事情による。
トラツグミのダンス同様採食に役に立っている可能性はもう少し取り上げてもよいのではと感じる。
ハクセキレイもセグロセキレイも尾羽外側が白く、prey flushing の考え方に合致するように思える。
モズやジョウビタキが目立った場所で尾を振るのは prey flushing ではなさそうでなわばり主張の一種なのだろうか。
カトリタイランチョウ Serpophaga cinerea Torrent Tyrannulet という面白い種類があることを知った。南米の流れに住んで尾をセキレイのように上下に振るとのこと (コンサイス鳥名事典、wikipedia 英語版)。セキレイ科はほぼ旧世界限定なので、南米でセキレイ類に対応する進化を遂げた種類と言えるだろうか。
同属のススイロカトリタイランチョウ Serpophaga nigricans Sooty Tyrannulet も同じような行動が紹介されている (wikipedia 英語版)。
Serpophaga の属名由来は serphos (gnat 蚊) -phagos (食べる) (Gk) で、タイランチョウ科なので和名は意味通りとなるがいかにも長過ぎると文句も言われるわけだ。tyrant をタイランチョウとそのまま音訳した (英語 6 文字なのに日本語で 7 文字となった) 時点ですでに長くなる運命となった次第。
旧世界のよく知られたセキレイ類でも尾を振る機能がよくわかっていない状況では南米の研究困難な種類では一層わかっていないのだろう。属名を付けた人はおそらく機能的意味も込めていたのでは?
ヨコフリオウギビタキの方に戻ると、川口 (2019) はセグロセキレイに似ているのは収斂進化ではないかと推定している。オーストラリアの強烈な日差しのもとで採食するならば上面は黒くせざるを得ない気がする。下面は手抜きができるので白いままでも大丈夫 (着色コストを減らせる) とすればセグロセキレイと同じような配色になるのも不思議でない気がする。
同じ説明がセグロセキレイにも当てはまるかどうかはわからないが、ハクセキレイに比べて南方型なので黒っぽくなっている、で傾向の説明はよいだろうか。
鳥ではないがアナウサギでの研究: Huang et al. (2025) The Adaptive Significance of Tail-Flagging: A Test in European Rabbits (Oryctolagus cuniculus)
Caro の研究グループなので懐疑的な方はそのつもりで見ていただくとよいだろう。なかなか複雑のようで逃げる前は同種への警告信号、逃げる途中は捕食者を避けさせる誇示効果が多少あるかも知れないとのこと。警戒していることを知らせる解釈は否定的とのこと。これまでの各種の説がまとめられているので鳥の場合でも参考になると思われる。
-
マミジロタヒバリ
- 学名:Anthus richardi (アントゥス リカルディ) リチャードのセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:richardi (属) リチャードの (フランス郵便局長で採集家 Charles Richard)
- 英名:Richard's Pipit
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
richardi は規則通りであれば -char- にアクセントと考えられる (リカルディ)。
記載時学名 Anthus Richardi Vieillot, 1818 (原記載) 基産地 France。
Hartert (1910-1922) p. 269 の時代には現在のアフリカのチャイロタヒバリ Anthus leucophrys Plain-backed Pipit に現在の Anthus similis Long-billed Pipit の亜種2つが Anthus leucophrys に含まれていた。
こちらの記載時学名 Anthus leucophrys Vieillot, 1818 (原記載) 基産地 Cape of Good Hope で、Anthus Richardi の記載と同一文献。
一度は同一種にまとめられた可能性があるが、その場合は Anthus Richardi の方が先に現れるために Anthus leucophrys のシノニムまたは亜種とはならないはず。
しかしマミジロタヒバリはこの学名由来とすれば納得できる部分があるのでさらに要検討材料。
Anthus richardi は Hartert (1910-1922) では p. 265 に現れ別種扱い。ドイツ語名 Spornpieper (棘のあるタヒバリ)。
後趾の特徴を示したもので、人名を用いるのを嫌って (?) Anthus macronyx Gloger, 1834 (参考) のように特徴を取り入れた改名もなされた。
日本に近いところでは Corydalla sinensis Bonaparte, 1850 (参考) 基産地 China mer[idionalis] の記載もあった。Corydalla 属は korudallos ヒバリ (Gk) 由来で Vigors (1825) が導入したもの (The Key to Scientific Names)。
和名は別種の学名由来でなければ後趾の特徴は取り入れず外観を中心にしたものだったのだろうか。
かつては ヒメマミジロタヒバリ Anthus rufulus 英名 Paddyfield Pipit、アフリカマミジロタヒバリ Anthus cinnamomeus 英名 African Pipit、
ヤママミジロタヒバリ Anthus hoeschi 英名 Mountain Pipit、オーストラリアマミジロタヒバリ Anthus australis 英名 Australian Pipit、(和名不詳) Anthus novaeseelandiae 英名 New Zealand Pipit (これら学名、英名は IOC による) を含む巨大な種だった。
その当時は マミジロタヒバリ/Richard's Pipit と言えば Anthus novaeseelandiae を指していたので、マミジロタヒバリの学名解釈は驚くべきことに「ニュージーランドの」となっていた (コンサイス鳥名事典)。
その後分割されて現在に至っているが、Anthus novaeseelandiae はオーストラリアマミジロタヒバリから比較的最近分離された種で、もとはこの種を指していたにもかかわらず皮肉なことに和名がまだ提唱されていないようである (ニュージーランドマミジロタヒバリ?)。
主に東アジアの大陸部で繁殖するが、冬は南に渡る。中東やアフリカ北部でも渡り時期に通過し、比較的最近まで広義のマミジロタヒバリに現在多くの種類に分けられたものが含められていたため、それぞれの分布域には不詳な部分がある。
分布図も出典によって異なっている場合がある。ヨーロッパでも多くの記録があるが、過去の広義のマミジロタヒバリの他種が混ざっている可能性がありそうである (eBird 分布図も同様)。
IOC では単形種となっているが、亜種を認めるリストが多い。IOC は Alstrom and Wild (2003) "Pipits and Wagtails of Europe, Asia and North America" によって単形種と扱っているとのこと。Howard and Moore は 4th edition で亜種を外し、Clements 2023, HBW and BirdLife Taxonomic Checklist v8 (Dec 2023) は残している。
認める場合には5亜種。日本で記録された亜種は日本鳥類目録第7版では richardi であったが、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ともに ussuriensis (ウスリーの) に変更されている。
かつて Anthus novaeseelandiae の亜種だった時代は richardi でよかったのかも知れないが、種が分離された後もしばらく残ってしまったもののよう。
「一部学名の変更の見込みについて」(2023年11月28日) にて単形種に変更された。日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)でも同様。
亜種 ussuriensis の記載は Johansen (1952/1944) Journal fuer Ornithologie 92, 146 とのこと。
Richard's Pipit account from Alstrom & Mild 2003 Pipits and Wagtails of Europe, Asia and North America...
で Alstrom の記述が読める。Stepanyan (1990) は ussuriensis を sinensis のシノニムとし、さらに dauricus を sinensis に含めたとのこと。
著者によっては別の扱いもあり Glutz von Blotzheim and Bauer (1985) は基亜種のシノニム扱い。
さらにややこしいことに richardi はフランスの迷鳥の標本に付けられた学名で Alstrom and Wild (2003) もその標本は見ていない。どの地域からのものかの同定は間違っていないだろうと考えているが自分たちは単形種として扱うとのこと。
Stepanyan (1990) "Konspekt Ornitologichskoj Fauny SSSR" (pp. 354-355) は3亜種の扱いで特に詳しい解説もなくシノニムとして扱っているのみ。
日本鳥類目録第7版時代はおそらく基亜種のシノニム扱いが一般的だったのだろうが解釈が変わったらしい。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) を見ると世界で6亜種、シベリアで3亜種
richardi (シベリア南部で東はツングース盆地まで)、dauricus (ヤクーチアとザバイカル)、centralasiae をトゥバからアルタイ山脈南部としている。繁殖地生態もよくわかっていないとのこと。
wikipedia 英語版ではこの3亜種と sinensis となっている。
特に新たな研究があったわけではないが識者によって見解が分かれているものらしく、大した違いはないので単形種とした方が合理的との判断もうなずけるところ。
[タヒバリ類の分類]
タヒバリ類の分子系統樹は例えば Pietersen et al. (2019) Multi-locus phylogeny of African pipits and longclaws (Aves: Motacillidae) highlights taxonomic inconsistencies
を参照。この研究はアフリカの種類を重点に調べたものだが、上記マミジロタヒバリのグループも検討されており、最近の上記分割を支持する結果となっている。
この論文では Anthus が単系統でないことが示されており、従来分類の見直しの必要があるとのこと。旧北区の Anthus (Clade 2) はまとまっていて (全種調べられたわけではないが、日本鳥類目録 改訂第7版 のリスト記載種はすべて含まれている)、この属がこのまま残されれば我々への影響は小さいと思われる。
見直しが必要になった場合でも、Anthus 属 (Clade 2) のタイプ種がマキバタヒバリなのでこのグループはそのまま Anthus 属として残りそうに思える。
マミジロタヒバリとコマミジロタヒバリのみは Clade 4 なので、Clade に従って属名が付け直されるならば、この2種のみ属名が変わるかも知れない。Clade 4 は large-bodied taxa とあり大型種のグループで、主にアフリカの種類。
アフリカのツメナガタヒバリ類 (longclaws) について Macronyx 属を廃止して全部 Anthus 属とすれば問題は解消するが、系統関係が明らかになってきたので属に分けようとの機運も出てくるかも知れない。
ツメナガタヒバリ類とされた中でクロスジツメナガタヒバリ Macronyx grimwoodi 英名 Grimwood's Longclaw だけは他とまったく系統が異なる (むしろ他のセキレイ類に近い) ことがわかったので、少なくともこの種の学名は変えることになると思われる。
-
コマミジロタヒバリ
- 学名:Anthus godlewskii (アントゥス ゴドレウスキイ) ゴドレフスキーのセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:godlewskii (属) ゴドレフスキーの (ラテン語化 -ius を属格化、ポーランドの農家、博物学者でシベリアに流刑され、刑期を終えて自然を調査した Wiktor Witold Godlewski)
- 英名:Blyth's Pipit (英国動物学者 Edward Blyth 由来)
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
種小名解説に現れる Godlewski の読み方はポーランド語では w ([v] と発音) は無声音の前で [f] と無声化される。活躍したロシアでの読み方 (Godlevskij の綴りになる) も同じ。学名訳では原語またはロシア語読みを採用している。ラテン語では w の読み方に特別な規則はないので "ウ" としてある。
あえてアクセントを付ければ "ゴドレウスキイ" が考えられる。
記載時学名 Agrodoma godlewskii Taczanowski, 1876 (原記載) 基産地 steppes of the Argun River valley, southern Dauria [= Transbaicalia] (Avibase による)。
命名の由来は特に書かれていない。
単形種。
森岡 (1997) Birder 11(8): 66-68 にマミジロタヒバリとコマミジロタヒバリという記事がある。
-
マキバタヒバリ
- 学名:Anthus pratensis (アントゥス プラーテンシス) 草地にいるセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:pratensis (adj) 草地にいる (pratum -i (n) 草原 -ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Meadow Pipit
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
pratensis は a が長母音で -ten- がアクセント音節 (プラーテンシス)。
Hartert (1910-1922) p. 275 ではドイツ語名 Wiesenpieper で Wiese は草地、干し草刈り場など。辞書にも牧場の訳があり、和名は学名よりもドイツ語名由来かも知れない。ヨーロッパでは普通種で多数のシノニムが挙げられている。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。主にユーラシア西部に分布し、ヨーロッパでは普通種。IOC では単形種。亜種を認める場合は通常2亜種で、pratensis と whistleri (インド警察官で採集家の Hugh Whistler に由来)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。
森岡 (1999) Birder 13(2): 62-65 に 今津で 1997 年に記録されたマキバタヒバリと考えられる個体についての考察がある。外見上の特徴はマキバタヒバリに合致するようだが、ヨーロッパの文献では地鳴きにヒバリの地鳴きに似たピュルリの音声が入ることが記述されているが、本個体では入らなかったことを音声面の不安材料としている。
海外の音声データベースを簡単に調べた範囲ではこの音声は必ずしも入らないようで、ヒバリの地鳴きに似た声はセキレイ類でよく聞かれるさえずりの特徴を持つ地鳴きのことを指しているものかも知れない。
五百沢 (1997) Birder 11(9): 69 にタヒバリとマキバタヒバリの地鳴きはそっくりと書かれている。
-
ヨーロッパビンズイ
- 学名:Anthus trivialis (アントゥス トゥリウィアーリス) 普通のセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:trivialis (adj) 普通の
- 英名:Tree Pipit
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
trivialis は a が長母音でアクセントもある (トゥリウィアーリス)。
英名は広く使われていた学名 Anthus arboreus Bechstein とよく一致している (参考図版)。arboreus 木の < arbor, arboris 木 英語の arboreal (樹上性のなど) の起源となっている。
この時代は Alauda trivialis Linnaeus, 1758 (原記載) が何を指しているか確実でなかったためかこの学名が用いられていた模様。
2亜種あるとされる (IOC)。日本で記録されたものは基亜種 trivialis とされる。
森岡 (1997) Birder 11(7): 72-75 に 1996.5.3 に舳倉島で記録されたヨーロッパビンズイの検討がある。
-
ビンズイ
- 学名:Anthus hodgsoni (アントゥス ホヂソ二) ホヂソンのセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:hodgsoni (属) ホヂソンの (英国外交官で採集家の Brian Houghton Hodgson)
- 英名:Olive-backed Pipit
- 備考:
anthus は短母音のみで悩ましいことはない (アントゥス)。
hodgsoni はラテン語読みだと子音の発音がやや悩ましいが、発音規則に従えばアクセントは冒頭と考えられる。原語の読みでも実用上差し支えないと思われる。
2亜種が認められている (IOC)。
日本で記録されるものは hodgsoni 亜種ビンズイと yunnanensis (Yunnan Province 中国雲南省の) カラフトビンズイ、及び亜種不明とされる。
かつて Anthus maculatus Hodgson, 1844 の学名も使われていた (maculatus 斑点のある、まだらの)。亜種 yunnanensis はこの時代の亜種として記載された Anthus maculatus yunnanensis Ushida & Kuroda, 1916。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" でも Hodgson (1844) のこの種学名が用いられており、Ushida and Kuroda (1916) [記載。この文献では種記載者を Jerdon としていた] でも用いられていたので時期的には当然とも言える。
この種学名は Motacilla maculatus Gmelin, 1788 が Anthus 属となった時に衝突し、preoccupied (すでに使用された学名) で無効となった。
Motacilla maculata Gmelin, 1788 の方は現在は ムジタヒバリ Anthus campestris Tawny Pipit でこの種小名は Linnaeus (1758) が Alauda campestris (当時はヒバリ類) で用いていたもので先取権の原則より Gmelin の学名もまた使われなくなった。
Gmelin (1788), Linnaeus (1758), Hodgson (1844) がそれぞれ別の属で命名したもので記載時点では問題なかったが分類変更で属が整理されたために起きた現象。
一方で種小名の方は Anthus hodgsoni Richmond, 1907 (原記載) で基産地 Bengal' [heavily streaked birds in winter, fide Jerdon] (Avibase から)。基産地から英語名 Indian Tree Pipit もこの論文に記されている ("Tree Pipit" については以下の Bechstein の提案の種小名も参照)。
Richmond (1907) は Anthus maculatus Hodgson, 1844 が preoccupied であることを認識した上で付けたとみられる (Gmelin 1788 の同名の学名への参照がある)。
新たに有効な学名を提案するに当たって、特に記されてはいないが、消えてしまう学名 Anthus maculatus の命名者であった Hodgson を尊重して種小名に採用したのではないかと想像できる。ただし英語名にまでは人名を採用せず自身の記録したインドを採用した (あるいはすでに英名があった可能性もあるかも?) と考えると理解できる印象を受ける。
1907 年に記載されたもののため、Ogawa (1908) はまだ知らずに古い学名を用いていた可能性がある。
Ogawa (1908) には別学名 Anthus agilis Sykes, 1832 (参考。基産地 Dukhun インド高原地帯) が載せられていた。
Hartert (1910-1922) でも p. 273 で Anthus trivialis maculatus とヨーロッパビンズイの亜種扱いだがこの名称を使っていた。
Anthus agilis を用いている著者は多いが、これは Sykes, 1832 のもの (こちらはヨーロッパビンズイと判定している) とは異なるとのこと。おそらくかなり微妙なところなのだろう。
日本でも南部で冬鳥とあるが海外ではほとんど知られていなかったよう。
ヨーロッパビンズイと同種となった時代の学名 (ヨーロッパビンズイの亜種となる) Anthus trivialis hodgsoni もある。いずれにしても基産地は日本からずいぶん離れている。インドは想像される通り越冬地で、分布の表記としてはふさわしくないため英名から Indian を外して別名が付けられたのだろう。
ヨーロッパビンズイと同種時代であれば基産地はスウェーデン。
ビンズイを2亜種に分ける立場であれば、Bengal で採集された標本に相当するものが基亜種、Mengtz, southern Yunnan のものが yunnanensis となる。
現在基亜種のシノニムとされるもので Anthus maculatus berezowskii Zarudny, 1909 が記載されたことがあった (記載)。
これも中国 southwestern Kansu で記載されたもので、ビンズイとヨーロッパビンズイとは色彩で区別できるとしたもの。
Anthus hodgsoni inopinatus Hartert & Steinbacher, 1933 で基産地 Boatassin, Sakhalin Island (Avibase による)。inopinatus は "予想外の" などの意味。
これがむしろ極東のビンズイにふさわしいように見える。
Dement'ev and Gladkov (1954) では実際にこの亜種を採用してシベリアからカムチャツカ、サハリン、北海道や千島をこの亜種としていた (ロシア名でこの亜種が "シベリアビンズイ" に対応)。
もう1亜種 (基亜種) を中央アジア型 (ヒマラヤ西部から台湾まで) としていた。背の色彩が大きく違うとのこと。yunnanensis については記述がなく知られていなかったよう。
面白いことに現代の分類では yunnanensis のシノニムとされているようで、inopinatus の基産地がサハリンなのでそれを引き継いで "カラフトビンズイ" とされているよう。もし同亜種ならば Ushida and Kuroda (1916) の記載の方が早いのでこちらの亜種小名が採用される。"カラフト" と中国雲南省がどう関係するのかと思ったがこのような複雑な事情があった。国外なので "カラフト" のような単純な理由ではなさそう。
この考え方に従うならば Dement'ev and Gladkov (1954) の見解とは違い、サハリンと日本のビンズイは別亜種で、サハリンで繁殖する個体群は大陸に渡って越冬することが示唆されるが本当だろうか。
この問題はやはり微妙なようで Brazil (2009) "Birds of East Asia" は北海道のサハリンの繁殖個体群を同亜種としている。記述する人によって亜種境界が違っているよう。
「決定版 日本の野鳥 650」(真木広造写真; 大西敏一, 五百澤日丸解説 平凡社 2014) でも北海道や本州で繁殖するビンズイの中に中間的な縦斑を持つものがいるなど亜種境界が明確でないことを示唆する記述も見られる。
ほとんどの記載が越冬地でなされたもののため問題が複雑になっている。確実なのは繁殖地で記載された inopinatus であるが、現在は他の広域亜種のシノニムとなっているのであまり明快でない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では全体で2または3亜種で、シベリアの亜種は yunnanensis と記述して世界の分類に従っている模様。シベリア以外のことまで記述がないので、追加の1亜種はサハリンのものを指す意図があるのかも知れない。
シベリア内では1亜種なので亜種識別などの記述はない。
種のロシア名は Dement'ev and Gladkov (1954) では "まだらのビンズイ/タヒバリ" に相当するもので、これは古い学名の Anthus maculatus 由来と考えられる。"オリーブ色のビンズイ/タヒバリ" の別名紹介もありたまに使われるとのこと。これは外見または英名由来?
地鳴きはよく聞かれる声で渡り時期や水辺などで音声記録すると飛翔時の声がよく入っている。多少ホオジロ類の地鳴きに似た高い声だがソノグラムにすると特徴がはっきりする。(地域によるかも知れないが) 冬場の生息していておかしくない探鳥会などでこの種が記録されていない場合は地鳴きを聞き逃している可能性が高そうである。
さえずりは複雑な声でよく知られ、木にとまって複雑に鳴くため木ヒバリとも呼ばれる。越冬地でも渡去前にさえずりが聞かれる。名称の由来はこのように聞いていたが、この "木ヒバリ" の "木" はヨーロッパビンズイと同種時代の英名にある Tree Pipit 由来のような気もしてきた。#ヨーロッパビンズイの備考参照。
Bechstein の提案による学名変更だったが改名前の属が Alauda とヒバリだった。Bechstein の提案の種小名 arboreus (木の) と合わせれば "木ヒバリ" となる。Tree Pipit の英名以外にもこの名称 (または学名) も使われていたのでは?
#タヒバリの備考考察も参照。
標準和名の由来は鳴き声とされ、他に有力な説はないとのこと。音声由来のこちらの方がよく使われて "木ヒバリ" の方はほぼ忘れられたのかも。
Shokhrin et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the olive-backed pipit Anthus hodgsoni (pp. 3997-4017)
ロシア沿海地方のビンズイの繁殖。亜種は yunnanensis を用いており分類学上の議論は特にない。
-
セジロタヒバリ
- 学名:Anthus gustavi (アントゥス グスタウィ) グスタアフのセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:gustavi オランダの鳥類学者 Gustaaf Schlegel の
- 英名:Pechora Pipit (ロシア北西部から北極海に注ぐペチョラ川の)
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
gustavi はあるいは原語に従って a を伸ばすかも知れない。その場合は "グスターウィ"。伸ばさなければ "グスタウィ"。
別学名に Anthus seebohmi Dresser, 1875 があり記載地は Pechora だった。参考。Dement'ev and Gladkov (1954) にもシノニムとして記載あり。英名はこの時代の学名由来と考えられ、他の多くの言語にも波及している。
Anthus gustavi Swinhoe, 1863 が記載 (記載地中国の Amoy) されていたが繁殖地記載ではないために同定が後になったかも知れない。
種小名は Amoy で鳥を最初に手に入れた Gustavus Schlegel (ライデン博物館の有名な Schlegel の息子) への献名とある。The Key to Scientific Names によれば Gustaaf Schlegel (1840-1903)。現行学名ではこの種のにみ使われている。
2亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 gustavi とされる。
亜種 menzbieri (ロシアの鳥類学者 Mikhail Aleksandrovich Menzbir に由来) コセジロタヒバリが検討亜種となっている。
英名は分布をよく反映して覚えやすいのだが和名と並べるとあまりしっくりこない (この点は Amur Falcon アカアシチョウゲンボウ でも同じように感じ、どちらも英名の方が有名なので和名への変換に心理的に一瞬手間がかかる)。もっとも学名も人名由来なのでもっとピンとこない。
他言語でもペチョラ、シベリア、ツンドラを使っているものが多く和名はかなり独自路線。体の白っぽさを用いている言語 (スロバキア、セルビア) も少数ある。中国語では "北" または "白背" をつけているが後者はあるいは和名由来か?
ロシア名は sibiriskij konek (シベリアのタヒバリ) とこちらも分布地を反映したわかりやすい名前。
konek (カニョーク) は通常は馬の指小形だがタヒバリの方の語源は不明とのこと。複数形は kon'ki (カニキー) となるなど一見不規則だがよくあるタイプの変化 (#オオワシ備考のように orel ワシが orly となるのと同様)。発音しやすくするための音韻変化なのでそれほど難しいわけではない。
[セジロタヒバリとコセジロタヒバリ]
松村 (2023) Birder 38(6): 42-43 に2023年9月20日に対馬で記録されたコセジロタヒバリらしい個体の記事がある。参考文献をチェックしておく。
茂田・小倉 (2015) セジロタヒバリ Anthus gustavi とコセジロタヒバリ A. menzbieri の識別および 日本からのコセジロタヒバリの記録 [2015 年度 (第 30 回) 日本鳥類標識協会大会報告]。
ネットに関連記事があったので紹介しておく:
コセジロタヒバリは種へ151031JBF (追記151129、190608) (鴎舞時 / OhmyTime)。
Drovetski and Fadeev (2010)
Mitochondrial DNA suggests independent evolutionary history and population decline of the Menzbir’s pipit (Anthus [gustavi] menzbieri) (出版社サイト)
Menzbir’s pipit (コセジロタヒバリ) と Pechora pipit (基亜種セジロタヒバリ) の mtDNA ND2 遺伝子を調べたもので、相互に単系統の関係にあり、相違は 0.6% (6置換) とのこと。
上記日本の記事では 2.8% の数字を見て別種相当と説明されている (おそらく茂田氏の解説に由来?) が、この数字は基亜種セジロタヒバリのサンプルを得た2か所の間の遺伝的違いを場所の違いがどれだけ説明できるか (他の要因に比べて値が小さいので最近分布を拡大した証拠となる) の数字で亜種間の遺伝的距離の数字ではない。
基亜種セジロタヒバリの方が近年分布を拡大したか安定しているが、コセジロタヒバリは減少している可能性があるとの結論で、個体群として保全ランクを上げるべきとの論文 (もし種とする場合も保全的種概念 conservation species concept の位置づけでよいだろう)。
この論文でも過去に "別種" とされた理由の定量的評価が不足していることも取り上げており、この論文でも別種かどうかまでは判定していない。Lenovich et al. (1997) がさえずりが異なると述べた点もコセジロタヒバリは1例のみで、基亜種セジロタヒバリの3例を示しているに過ぎないとのこと。
世界の状況をみておくと、IOC 14.1 でも別種扱いではなく他のリストでも独立種としているものは見当たらなかった。
wikipedia ロシア語版では別種としている (Menzbir’s pipit)。DNA によると書かれているが、上述のように今ひとつ根拠がはっきりしない。今のところロシアのみ (?) 別種として扱っているよう。
鴎舞時 / OhmyTime で引用されているヴォロビョフ著 (1954/1978 高橋清約)「ウスリーの鳥」も翻訳の問題が考えられるので原文にあたってみると、"しかし、シュルピンが、
< この鳥の中間的な型が存在しない場合には、このセジロタヒバリの亜種は、おそらく1つの種として認めてもよいほど、ひじょうに明瞭な差がある >
と断言しているのは、容認しがたい。著者の見るところでは、この差異はあまりに誇張されているようである。ここに記載されている型は、かなり明瞭に区別される亜種である"
と引用されている部分はおおむね正しいがニュアンスが微妙に違う。< もし中間的な標本がないならば、このセジロタヒバリの亜種は独立種とみなしてよいと言える程度の違いがある > と訳しておく。この部分は仮定法的な書き方で、中間的な標本がないかどうかは記述時点ではわからない。もしなければ別種にしてよい程度違いがある。という意味でよいだろう。
"ここに記載されている型は、かなり明瞭に区別される亜種である" は誤訳に近く "ここに記載されている型は、単に違いがはっきりした亜種に過ぎないことは明らかである" ぐらいの意味になる ("単に...過ぎない" が抜けている)。ヴォロビョフはシュルピンが言うほどの違いはないと考えた模様。
これはシュルピンが "亜種" と記載した (1928) ことに遡る話で、シュルピンもおそらく種とするか亜種とするか迷ったのだろうが、亜種として記載したが種かも知れない可能性も残しておいた記述だろう。
また「ウスリーの鳥」の翻訳も当時はほとんど知られていない地域の情報を紹介するのが主目的で貴重な資料として翻訳されたものと想像され、翻訳は他の部分でもそれほど緻密でない感じがする。精密な参照を行う場合は (ハードルは高そうだが...) 原文をチェックするのがよさそう。
gustavi の 原記載 (Swinhoe 1863) アモイで春の渡り (5月中旬) で採集されたもの。これが基亜種とされるもの。北方に渡るものは時期が遅いことと整合するか。
亜種 stejnegeri (Ridgway 1883) はコマンドル島で別種として記載されたが現在は多くのリストで基亜種のシノニムとされる。Howard and Moore 4th edition (incl. corrigenda vol. 1-2) はセジロタヒバリの亜種としている。
コセジロタヒバリは Shul'pin (1928) がハンカ湖で5個体を採集したものとのこと。Vorov'ev (1948) は4月終わりから5月初めに春の通過個体をみかけると記載しているが、Dement'ev and Gladkov (1954) はこの亜種かどうか明らかでない書き方になっている。
繁殖生態などを記録した Nazarov (1981, 2020再掲) が Biology of the Menzbier’s pipit Anthus gustavi menzbieri in Primorye (pp. 4775-4782) で読める。
[極東の鳥類 40: スズメ目特集 (2023) で邦訳が読める。冒頭行は原文ではこの亜種ではなくセジロタヒバリ全般 Anthus gustavi 全般を指している]。
湿地化してアシなどの生えた河岸や小島のみ営巣する。コロニー性の営巣を示すように見える。春の渡りは文献では4月終わりから5月20日ごろまで (韓国の事例) とあるが、沿海地方では6月初めまで渡るとのこと。基亜種も同時にみられ、こちらの方がずっと数が多いとのこと。
秋の渡りの記述で邦訳のニュアンスが少し異なるので補足しておくと、秋の渡りでも春と同様にコセジロタヒバリはまれである。(最後の個体が9月25日に記録されているが) 9月中旬に現れる渡りの基亜種がこの時期には十分多くなっていて、コセジロタヒバリはさらに一層目立たなくなってゆく、とのこと。
秋の渡りはコセジロタヒバリの方が早く、基亜種セジロタヒバリが後になるが重なりもあると考えている (日本の秋の渡りのメボソムシクイとオオムシクイの関係に近いかも知れない)。
機械翻訳でも意味は十分わかると思うのでお試しいただきたい。
ただし後述 Nial Moores はそもそもどのように区別したのか疑問も呈している。
Pechora Pipit (Manzbier's) 2020年5月5日の写真記録 (沿海地方ではこの時期の写真が多い模様) があり、こちらも同定に疑問が出されていた。文献などで同定したが今となっては思い出せないとある。
さえずりが違うともされているが、xeno-canto の例数も少なく、亜種が特定されていない記録なども含めると個体差がかなりありそうで決定的な違いと言えるかどうかわからない感じがする。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" ではコマンドル島のものも声が違うと記述しているので、音声を判定材料とする場合はコマンドル島の個体群を基亜種に含める現在の扱いは適切でないかも知れない。この個体群も渡り時期に通過していておかしくなさそう。
地鳴きについては 第5回 Pipits <タヒバリ類> 独断と偏見の識別講座 II 波多野邦彦 (2013) にも特徴的な音声が述べられている。2(亜)種間で地鳴きが異なる可能性も考えられるが、繁殖地での確実なデータが足りないために結論を出すのは難しそう。
Veprintsev Phonotheka of Animal Voices にチュコト半島南部で収録された音声が含まれており、さえずりはかなり多様でコムシクイのような連続した反復音もある。
警戒音としての地鳴きも記録されていてこれはある程度チュンチュンと聞こえるが、xeno-canto の渡り途中あるいは迷鳥で記録される声よりは低く (大陸で渡り途中に記録されている声はチュンチュンにはあまり聞こえない) 地鳴きにも複数のパターンがあるものと思われる。
音源のソース (xeno-canto はかなり含まれてそうだが出典を書かないのはよくない) や信頼度などはわからないが Konek. 2 chast' Aziya. Golosa ptits でもかなりの音声を聞くことができる。2:53 からコセジロタヒバリを別種として取り扱っているが地鳴きは含まれていない。
Pechora Pipit Anthus gustavi in South Korea:
some pieces in the menzbieri / gustavi puzzle? (Nial Moores, Birds Korea 2004)
でも2(亜)種を識別できるか韓国の事例を考察している。サイズでの野外識別は危険。渡り時期に違いがあるのでは。季節によって声の違いがあってあるいは2(亜)種の違いが現れているのではとのこと。
渡り時期に違いがあることを前提とした識別点をまとめている。
早く渡るもの (menzbieri?) は セッカの大陸東部亜種 Cisticola juncidis tinnabulans? の地鳴きに非常に似ているが、遅いもの (gustavi?) はハクセキレイを思わせるとある。
これもまた悩ましい話で、日本のセッカではこのタイプの地鳴きの経験があまりない (当地京都では基本的に夏鳥で、越冬地ではあるいは普通の声なのかも知れない)。蒲谷鶴彦・松田道生「日本野鳥大鑑 鳴き声420」に収録されている地鳴きもこのタイプとは異なる。
バードリサーチの 鳴き声図鑑 にはこのタイプのものがあった (地鳴き 栃木県渡良瀬 2010-11-25 平野敏明)。
あまりに普通種過ぎて記録されていないかも知れないが、タヒバリ類地鳴きとの識別も問題になり、地域差も考えられるのでより多数の記録があることが望ましいだろう。
韓国には日本と同じ (C. j. brunniceps) セッカの亜種も分布するとされるが、C. j. tinnabulans と地鳴きは違っているだろうか。セッカの分類も含めて検討課題になりそう。
Veprintsev のチュコト半島の音声は、この記述の範囲では早く渡るものにむしろ近い印象を受ける。地鳴きの種類や個体差の方がむしろ効いているのかも。
多数の個体の通過する韓国で観察をしている Nial Moores の記述を見る限りでは野外識別はやはり難しいと言えるのだろう。
Drovetski and Fadeev (2010) の DNA 解析でもそれぞれの個体群の中での広がりも大きく、基亜種セジロタヒバリはカムチャツカとチュコト半島しかサンプルされていないので、セジロタヒバリの他の地域個体群も含めると相互に単系統にならないかも知れない。
分布域が広大な場合にしばしば起きる問題で、フローレスクマタカとカワリクマタカの関係にも似ている (#クマタカの備考 [Nisaetus属のクマタカ類の系統分類 (イヌワシ亜科その1)] 参照)。
生息環境の悪化した現状、保全を考える上ではコセジロタヒバリを独立種とみなすのが妥当であり、系統解析による証拠は十分でないかも知れないが、主な生息地であるロシアがそのように判断するならば従ってよいようにも思える。
Drovetski and Fadeev (2010) にはカムチャツカとチュコト半島の情報しかないが、Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) の記述では繁殖の確認された場所を点で表しているもので、領域として描けるほど繁殖地の全体像はよくわかっていない。ウラル山脈より西ではまだ繁殖は発見されていないとのこと。
似た地域に分布するムネアカタヒバリの方がまだよくわかっているようで、こちらは領域として図示されている。Ryabitsev (2014) の分布から判断するとコセジロタヒバリの方がやや内陸に位置するように見える。
基亜種のヤマル半島の文献がある: Sokolov (2008) Anthus gustavi in Yamal (pp. 486-491)
分布図も出ているのでどのような場所で繁殖するか参考になるだろう。2000 年代に繁殖地が西進 (侵入 invasion) した可能性があるとのこと。
主要越冬地の一つとされるフィリピンのチェックリストを参照しておくと、gustavi は uncommon winter visitor (あまり多くない冬鳥)、menzbieri は presumed winter visitor (冬鳥として来ていると思われる) となっていた。
越冬地では相当見つけにくいのだろうか。
Pietersen et al. (2019) (#マミジロタヒバリの備考参照) の分子系統樹によれば、ユーラシアのタヒバリ類の中では古い系統にあたる。
この系統 (Clade 2) は新大陸とアフリカの系統 (Clade 1) につながるものとなり、南米のセジマタヒバリ Anthus correndera Correndera Pipit が中間的な位置を占めている。この種以降を Clade 2 とすればセジロタヒバリと南インドの高地のみに生息する希少種ニルギリタヒバリ Anthus nilghiriensis Nilgiri Pipit (留鳥) が最も古い分枝になる。
セジマタヒバリやニルギリタヒバリの位置づけは過去研究の系統樹によって違っている (かなり難しいらしい) が、セジロタヒバリを最も古い分枝とする点はほぼ共通している。
この系統樹をもとに想像すると、ユーラシアに最初に入ったものが適応放散したが、この系統は高緯度などの寒冷気候に適応し (森林地帯はそもそも避けた分布になっている)、現在では高緯度のセジロタヒバリ、そして遺存種のような形で南インドの高地にニルギリタヒバリが残り、極東の気温の低い地域にコセジロタヒバリが遺存的に残ったと考えることができそうである。
ニルギリタヒバリはさえずりの音声はわからないが、地鳴きはセジロタヒバリとはかなり異なっていて種分化以降十分な時間が経過しているのだろう。
Grassland in Okhotsk にオホーツク岸のカムチャツカでツメナガホオジロ、セジロタヒバリ、ムネアカタヒバリが繁殖する草原の映像がある (鳥も声も出てこないが)。ツンドラでは夏には虫が大量発生するのでこれらの鳥にとって都合がよいとのこと。
-
ウスベニタヒバリ
- 学名:Anthus roseatus (アントゥス ロセアートゥス) バラ色のような色のセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:roseatus (adj) バラ色のような (roseus (adj) バラ色の -atus (接尾辞) 〜の衣装の)
- 英名:Rosy Pipit
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
roseatus は -atus の a は長母音なので "ロセアートゥス" と思われる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
-
ムネアカタヒバリ
- 学名:Anthus cervinus (アントゥス ケルウィーヌス) 鹿のような色のセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:cervinus (adj) 鹿のような色の (cervus (m) 牡鹿 -inus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Red-throated Pipit
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
cervinus は i が長母音でアクセントがある (ケルウィーヌス)。
Cervus nippon がニホンジカの学名で Cervus は覚えやすいだろう。
英名および和名と同等の意味の Anthus rufogularis Brehm, 1824 (赤いのどのタヒバリ) の記載があり、主に南方 (Nubien。ナイル川上流) と記されているが、ドイツでも時々やってくるためにこの学名が広く使われていたためと想像できる。
おそらく後に Motacilla Cervina Pallas, 1811 の方に先取権があると認定され (Pallas の文献の出版年の扱いは複雑だった。#トラツグミ参照)、この種学名が採用されているため現在は関係がわかりにくくなっている。rufogularis の名称は亜種を認める分類でなければ出てこない。
Hartert (1910-1922) では p. 277 で Pallas に先取権を認めていた。この時点では 1827 年の扱いで、Brehm は 1831 年の扱いだった。
Pallas の記載を何年とするかはやはり議論があったようで脚注になっている。
この文献でのドイツ語名 Rutkehliger Pieper で Kehle は "のど" なので Brehm の学名と同じになっている。和名もドイツ語由来かも知れない。
当時はエジプトなどで記録されてヨーロッパからも身近な種類であったためか多数のシノニムがあった。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではすでに現在の学名となっていた。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" ではすでに同じ学名でムネアカタヒバリの名称となっており、これ以前に和名が付いていた。
単形種。
ユーラシア西部と東部で別亜種としていた時期もあり、その場合はヨーロッパの個体群は rufogularis となり、基亜種は東の個体群となる。東の個体群の方が翼長がわずかに長く色調が少し異なるという。
現在の多くのリストで単形種とされるが、 Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では2亜種として取り扱っているものの図版は描き分けてはいない。
-
タヒバリ (世界的には日本の亜種が独立種となり学名も変わる見込み)
- 第8版学名:Anthus rubescens (アントゥス ルベースケーンス) 赤みがかったセキレイ
- IOC 学名:Anthus japonicus (アントゥス ヤポニクス) 日本のセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 第8版種小名:rubescens (現在分詞) 赤みがかった (rubesco (intr) 赤くする)
- IOC 種小名:japonicus (adj) 日本の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名: (Buff-bellied Pipit), IOC: Siberian Pipit (14.2 から)
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
rubescens は2つの e が長母音で1つめにアクセントがある (ルベースケーンス)。
語形解説は#ワシカモメの備考参照。この形の語尾の読みは長音に統一することにした。
japonicus は#メジロ参照。
タヒバリの和名は多少違和感がないわけではなかったが、#ビンズイの別名 "木ヒバリ" の由来を検討するにあたって、ビンズイはかつてヒバリ属に分類されていたことを知った。
おそらく同様でないかと調べてみると別種分離前のヨーロッパタヒバリ [記載が早いの同種時代はこちらの学名になる。現在はさらに分離され、この学名はサメイロタヒバリ (ヒガシヨーロッパタヒバリ) と呼ばれる]
は Alauda Spinoletta Linnaeus, 1758 が原記載であった。
やはりヒバリ属だった。
最も考えられそうなのはこれまた Alauda pratensis Linnaeus , 1758 の学名 (現在はマキバタヒバリを指す) が存在し [この種小名は Temminck & Schlegel (1842, 1847) で使われていた。タヒバリとの同種扱いについては後の解説参照]、そのまま訳せば "牧草地のヒバリ" となるところを日本の状況に当てはめて "田のヒバリ" としたものではないだろうか
("木ヒバリ" の対比を意図したとも考えられる)。
つまり
・Alauda arboreus = 木ヒバリ (現在のビンズイ)
・Alauda pratensis = 田ヒバリ
と訳されたものに過ぎず、ビンズイの "木ヒバリ" にも "ヒバリのようにさえずる" の意味は必ずしもなく、単にヒバリ属だったためだけかも知れない。
このように考えると「どこがヒバリに似ている?」の疑問も解消するように思える。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Anthus spinoletta japonicus の学名を使用し (Anthus pratensis japonicus も別学名として記載)、和名別名に "イヌヒ" が載せられていた。タヒバリの方が学術用語由来らしく見える。
マキバタヒバリが (日本から見ると) さらに分離されて訳名に同じような意味を重ねるようになった、など考えられる。
ビンズイやタヒバリがセキレイの仲間であること、どこに共通点があるを説明したり、またなぜそのような名前になっているのか聞かれるなど探鳥会の頻出話題であろう。その際の説明に少し役立つかも知れない。
この解釈を記述してから日本で過去に使われていた名称の載っている本を持っていることを思い出した。
参考にしたものは「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) と「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990)
である (絵の入った豪華本が手が届かない)。和名については過去にも語源調査が行われていて本も出ているが限られた資料しか持っていない。ここでは学名と関連性を考える上の題材として取り上げるもので、限られた資料に伴う考察である点はご了承いただきたい。
「大江戸飼い鳥草紙」を見ると「喚呼鳥」(1710) に「たひばり」「木ヒバリ/びんずい」の名称が現れていた (pp. 164-167 表 7)。ただし「喚呼鳥」の挿絵には含まれていなかったよう (p. 134 表 5)。
「百千鳥」(1799) ではビンズイのみ記載。これらは飼育書なのであまり飼育されない種類は出てこないなど限界はある。
この同定が正しいとすれば 1710 年には「たひばり」「木ヒバリ」の名称はすでにあったため、「ヨーロッパのものと同種とされていた時代の学名由来」説は成り立たないことになる。
もしヨーロッパでの名称と完全に独立に付けられたのであれば「洋の東西を問わず着眼点が同じ」でこれは文化史的にも興味深いだおう。
多少注意すべき点は Linnaeus (1758) の学名とは言え、Linnaeus が独自に付けたものとは限らず、過去に使われた名称を整理して発表したのが Linnaeus (1758) なので学名やそれに相当する通俗名はそれ以前からあっても不思議ではない。
「大江戸飼い鳥草紙」 pp. 27-28 によれば日本にカナリアが渡来した確実な記録は 1709 年とのこと、「大和本草」(1709) にも舶来の鳥が含まれているなど海外の知識は一定程度入っていたかも知れない。
「鳥の手帖」p. 154 によれば本朝食鑑 (1697) に田雲雀の記述があり、「大和本草」にも「ぎうひばりは大也。ひばりに似たり。冬は田にあり。余時は不居。又天にあがらず。又田ひばりと云」との記述があるとのこと。
木ヒバリ、田ヒバリと過去の学名との整合性があまりによいため気になっているものだが、これらの名称がそれ以降ずっと使い続けられたいたものかどうかもわからず、歴史に詳しい方がさらに究明していただけることを期待したい。
3亜種が認められている (IOC 14.1 まで)。日本で記録されるものは japonicus 亜種タヒバリ (英名 Japanese Pipit) と亜種不明とされる。
IOC 14.2 では分離され Anthus japonicus は単形種。
[タヒバリの2種への分割について]
亜種 japonicus を独立種とする考えは以前よりあったが (Zink et al. 1995; Garner et al. 2015)、
Doniol-Valcroze (2023)
Molecular and acoustic evidence support the species status of Anthus rubescens rubescens and Anthus [rubescens] japonicus (Passeriformes: Motacillidae)
の分子遺伝学と音声研究から2種に分けることが妥当との結論となり、結構大きな違いが判明したためおそらく受け入れられるであろう。200 万年前ぐらいに種分化したと見積もられている。
この場合、分離された後の Anthus rubescens は英名 American Pipit、Anthus japonicus は英名 Siberian Pipit が提唱されている (英名 Japanese Pipit も使われている)。
Alauda Rubescens Tunstall, 1771 の原記載 (とはいえ表に現れるのみ)。
japonicus を分離しない場合、Anthus spinoletta の亜種にするか、Anthus rubescens の亜種にするかの問題があり、知る限り後者の亜種となっており Buff-bellied Pipit の英名が普通に使われてきた。
"Fauna Japonica" では Anthus pratensis japonicus Temminck & Schlegel, 1847 (本文の 原記載)。
図版 とさらに広い範囲が同種とされていたことがわかる。この学名では現在の学名からみるとマキバタヒバリの亜種のように見えてしまうが、同種と考えた時代に何が基亜種だったかだけの問題。
日本から見ると同種扱いだとマキバタヒバリがタヒバリの亜種のように感じるが、ヨーロッパから見ると記載順も逆になる。
この当時の亜種小名がついに種扱いとなる方向になってきた。
雑誌 Birder はかつてはキャプションには学名表記だったが最近は英名表記になり、タヒバリの英名に Water Pipit が使われる例が出てきた。これは Anthus spinoletta と Anthus rubescens を同種と考える分類 (古い概念) に基づくものか、あるいは Anthus spinoletta の亜種と考えているのか区別が付かない。
分類を少し遡ってみると Anthus spinoletta と Anthus rubescens が分離された以降は世界のリストで Anthus spinoletta の亜種とはされていないので古い分類に基づく可能性がある。
日本鳥類目録改訂第7版時代にはすでに分離されていたが第6版では同種とされていたとのこと。
wikipedia 日本語版 (タヒバリ) を2024年9月現在見ると学名と分布が一致していない。そのまま英語版へのリンクを見れば英名が Water Pipit となるのか...。
Birder 誌は海外に通じやすいように学名表記から英名表記に変えたのだろうがこれでは余計に通じない (むしろ誤解される)。タヒバリの2種への分割とは別の問題。
亜種 japonicus を独立種とする分類が採用された場合、現在の日本のタヒバリは種和名は変わらないが学名や英名が変わることになる。また単形種となる。American Pipit の方が複数の亜種を持つことになる。
繁殖羽は両種は類似しているが、冬羽はかなり異なる。また種の区別に音声 (ここでは地鳴き) が重要であることも明らかになった (人が聞いて区別できるかはわからないが)。さえずりも重要なのであろうが japonicus の方のさえずりデータがほとんどないので分析できる程度に使えなかったのだろう。わずかにある音声を比較するとさえずりもだいぶ違うことがわかる。
Brazil (2009) "Birds of East Asia" もこの分類に賛成で (まだ別種とはしていないが)、
冬羽の図版をシベリア/日本型とアメリカ型で別に描いてある。これをみると確かにかなり違う。
Research shows Buff-bellied Pipit is two species (BirdGuides) など海外でも話題となっていることがわかる。
この論文ではかつてタヒバリと同種とされたサメイロタヒバリ (ヒガシヨーロッパタヒバリ) Anthus spinoletta 英名 Water Pipit も2種に分かれる可能性を示唆しているが、まだデータが十分でなく新分類の提案までは行っていない。
この和名から予想されるようにかつてタヒバリと同種とされたものは他にもう1種あり、ニシヨーロッパタヒバリ Anthus petrosus 英名 (European) Rock Pipit である。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で Anthus rubescens rubescens は検討亜種扱いでアメリカタヒバリ。上記分類が受け入れられれば独立種となって検討種になる。
Anthus spinoletta blakistoni の亜種がサメイロタヒバリとして検討種となっている。
参考までに Hartert (1910-1922) p. 282。この2亜種が出ている。
spinoletta はフローレンス地方のセキレイの名前 Spipoletta 由来で、Linnaeus (1758) 原記載 以前から Spinoletta florentinis と誤記されていた (誤記の解釈はコンサイス鳥名辞典から)。
Motacilla spipoletta の学名も実際に使われていたことがあった: 参考 Mlikovsky (2011)
Nomenclatural and taxonomic status of birds (Aves) collected during the Gmelin Expedition to the Caspian Sea in 1768-1774。
誤記が正されてしばらく使われ、亜種記載にも用いられたことがあったが原記載の綴りが有効と判断されたものらしい。
Johann Friedrich Naumann の図版
Anthus Pratensis, Cervinus, Spipoletta, Obscurus にも Anthus spipoletta の学名が用いられていた。
検討種からリストに記載されるころには種の分割が行われて学名も変わっているかも知れない。
japonicus の別種扱いは IOC 14.2 で採用された。英名は Siberian Pipit (2024.7.19)。Working Group Avian Checklists, version 0.04 より同じ。Doniol-Valcroze (2023) の提案に従う名称となり、しばしば使われていた "Japanese Pipit" の名称は分布地域の面からも避けられたのだろう。世界共通名となると思われる。
物事の進展が早くどこも大変らしい。
Buff-bellied Pipit は分離前の英名となるが、北米では分離後の American Pipit の名称は以前から使われていたとのこと。
[極東ロシア山地の種類数の少なさ]
Biserov (2008 初出、2025 再掲) Geomorphological features are one of the factors determining the depletion of fauna and bird populations in the highlands of the southern Far East (pp. 755-763)。
この地域 (Ezop, Dusse-Alin') の山地はシベリア東部に比べて種数が大変少ないことが知られていて、標高の高めのところではほとんど数種が繁殖するのみ。高いところではタヒバリが半分を占める地域もあるなど種多様性が大変偏っている。少し低いところではムジセッカなど。
生物地理学的にはこの地域は島の性格を持ち鳥類相の形成が遅かったが気候的特徴の影響がさらに大きいと考えられる。極東周辺部にあたるこの地域から日本に至る高地の鳥類相の乏しさには共通要因があると考えている。
△ スズメ目 PASSERIFORMES アトリ科 FRINGILLIDAE ▽
-
ズアオアトリ
- 学名:Fringilla coelebs (フリンギルラ コエレブス) 未婚のズアオアトリ
- 属名:fringilla (f) ズアオアトリ
- 種小名:coelebs (合) 未婚の (caelebs (adj) 未婚の)
- 英名:Common Chaffinch, IOC: Eurasian Chaffinch
- 備考:
fringilla は#アトリ参照。
coelebs は短母音のみでアクセントは冒頭 (コエレブス)。
種小名 coelebs 未婚の の由来は、Linnaeus (1757) がオスを残してメスがオランダ南部で越冬すると考えたため (The Key to Scientific Names)。現代のスウェーデンでは主に夏鳥で一部は冬も残っていたのかも。
記載時学名 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (原記載)
珍しく習性が記されていて Femina sola migrat per Belgium in Italiam. Mas capite pileata, vere mutata sono aestatem annunciat.
とのこと。前半は上記説明の通りで目的地がイタリアである点は少し異なる。後半は "すっかり声を変えていた頭に帽子のあるオスは夏の訪れを告げる" ぐらいの意味だろうか (ラテン語の機械翻訳をする時はロシア語を翻訳先に選ぶと語形や変化形の意味が近いのでわかりやすいことがある。どちらもわからない点は同じようなものかも知れないが...)。
ロシア語名では zyablik でこの名詞は圧倒的にズアオアトリを意味する代表種の一つ。zyabnut' (凍える、かじかむ) が語源で春は早くに訪れるが最初の雪が積もると越冬地に旅立つことからとのこと (Kolyada et al. 2016)。ロシア (西部に分布) ではほぼ夏鳥。
イタリア語では Fringuello。ほとんどフィンチの代表種のような存在で中部ヨーロッパでは真っ先に聞こえてくる声の一つ。
16 亜種あり (IOC)。日本で記録された亜種は基亜種 coelebs とされる。
-
アトリ
- 学名:Fringilla montifringilla (フリンギルラ モンティフリンギルラ) 山のズアオアトリ
- 属名:fringilla (f) ズアオアトリ
- 種小名:montifringilla (f) 山のズアオアトリ (mons montis (m) 山)
- 英名:Brambling
- 備考:
fringilla は frin-gil-la と分割され、-gil- にアクセントがある。フリンギルラ。
インド・ヨーロッパ祖語の *bhereg- (音をたてる、うめく、吠えるなど) 由来で指小辞の -illa を付けたものとのこと。*bher- の語幹は英語の bark に残っている。ラテン語の frigutio (小鳥などが鳴く) などに関連するとのこと (wiktionary)。
montifringilla も同様 (モンティフリンギルラ)。ラテン語の "山" の mons は主格で o に長音記号が付くが (伸ばして読んでよい)、属格 montis では短音となるので montifringilla の冒頭も短母音。
英名の Brambling は中世英語 bramline に由来で bramble キイチゴ + ling (植物の common heather Calluna vulgaris) とのこと (wiktionary)。
ただしキイチゴとアトリは特に関係がない。
一方 wikipedia 英語版では "bramlyng" (Bram "loud" + lyng "lung") の意味で William Turner が 1544 年に用いたと説明されているが語源は明らかでないとも記されている。
wikipedia 英語版にある資料では Turner on birds: a short and succinct history of the principal birds noticed by Pliny and Aristotle first published by Doctor William Turner, 1544 を見ることができる。原書と Evans (1903) による英文注釈付き。
この時代から montifringilla の名称 (学名として有効になる以前のラテン名) で呼ばれていたことがわかる。ズアオアトリ (fringilla) に対する "山の" 種類との認識。Linnaeus (1758) では Fringilla を属名として用い、アトリの種小名に従来からの montifringilla をそのまま採用した次第。
属名となったズアオアトリの方は種小名に対応するものがなくなってしまうので coelebs を新たに与えたことになる。
では Linnaeus (1758) はなぜもっと簡単な Fringilla montana にしなかったのかと言えばこの学名を別に使う必要があったため。こちらはスズメの記載時学名となっている (こちらも Passer montanus の用例が過去にあってそれを引き継ぐ形となっている)。
いずれもそれまでのラテン名を踏まえる形で命名された。
ただし montifringilla は長くて fringilla の部分の意味が重複する (おそらく) ので改名も提案されていて、Fringilla montana Forster, 1817 (参考)、Fringilla montana Wood, 1836 (参考) などがあった。
これらは無効名のようにも見えるがスズメが別属になった時点で有効だった期間があったのかも知れない。
Linnaeus (1758) のアトリの学名は今ひとつ評判が高くなかったことを推察されてくれる。
Turner (1544) - Evans (1903) の書籍で対応するギリシャ語名称も示されていて、ズアオアトリが spiza (学名の世界では広く小鳥を指す)、アトリが orospizes (山の spiza) となりラテン語にも対応していてわかりやすい。Turner は fringilla の語源を a frigore (寒さから) と誤解していたことがわかるとのこと (#ズアオアトリのロシア語名とも似ていてあるいは似た発想があるのかも)。
ユーラシアの北部から中緯度に広く分布する単形種。
アトリぐらいの広域分布になると亜種記載はなかったのだろうかと考えてしまうが、ないわけではなかった。Fringilla montifringilla subcuneolata Kleinschmidt, 1909 (参考) (sub 少し cuneolatus 楔形の) とあって Ostasien (Terra Typica Japan) とあるので日本を含む東アジアのアトリが別亜種とされた時代もあったのか。
Dement'ev and Gladkov (1954) では基産地シベリアとあって少し合っていないがいずれにしてもシノニム扱い。
-
カワラヒワ (オガサワラカワラヒワが分離された)
- 学名:Chloris sinica (クローリス シニカ) 中国の緑色の鳥
- 属名:chloris (合) 緑色の (chloros 緑色の Gk)
- 種小名:sinica (adj) 中国の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Oriental Greenfinch, IOC: Grey-capped Greenfinch, 14.2 より世界の他リストに合わせて Oriental Greenfinch
- 備考:
chloris の o は長母音でアクセントもここにある (クローリス)。ラテン語 chlorum は元素の塩素 (英語 chlorine)。sinica は冒頭にアクセントがある (シニカ)。
先取りする形になるが使われる可能性のある亜種名の読みも検討しておく。kawarahiba は "カウァラヒバ"、minor は "ミノル"、
ussuriensis は "ウスリエーンシス" でよいと思われる (ussuri- は二重子音としない現地名の読みに合わせた)。
clarki は "クラルキ" (長音でもよい) で多分よいだろう。
sitchitoensis をどう読むかはちょっと問題があるが、ロシアの地名や人名を学名にする際にドイツ式読みが使われ、それと類似と考えれば "シチトエーンシス" と読むことができる。
英名の Greenfinch はヨーロッパのアオカワラヒワの種小名 (その後属名にも使われるようになった) にも対応するものだろう。
本家 Greenfinch に対する英名として東洋版の Oriental Greenfinch が与えられたものと思われるが、Chloris 属に Greenfinch の名前の入る東洋の種は他にもあり、種小名から "中国の" と名付けると分布にふさわしくないため、色彩を表す名称が使われるようになったのだろう。
この名称は非常に新しいため学名由来の部分は特になさそう。
なお最近まで Carduelis 属 (日本鳥類目録改訂第6版など) だった。英名変更もこの分割に伴ったものだったかも知れない。
IOC 14.2 で世界の他リストに合わせて Oriental Greenfinch に変更となり色彩由来ではなくなった。
4亜種あり (IOC。オガサワラカワラヒワが分離されて1つ減った)。日本で記録される亜種は minor (より小さい) 亜種カワラヒワ、kawarahiba (和名カワラヒワから) オオカワラヒワ (カムチャツカから千島で繁殖する。日本では冬鳥。ロシア名はカムチャツカのカワラヒワ)、及び亜種不明とされる。
ussuriensis (以下参照) は日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で検討亜種となっている。
種カワラヒワの記載は非常に古く Fringilla sinica Linnaeus, 1766 (原記載)。記載地は中国だが後に Jacobi (1923) がマカオと限定した (Avibase 情報による)。
アオカワラヒワはさらに古く Loxia chloris Linnaeus, 1758 と当初はイスカ属 (原記載)。
Chloris 属は Cuvier (1800) がおそらくアオカワラヒワの種小名を属名に昇格して分離したもの (記載 の表の中に現れる。フランス語名で Verdiers)。アオカワラヒワがタイプ種と判定された。Cuvier (1800) は Loxia 属を5属に分割。
しかし Chloris 属はアサギアメリカムシクイ 現在の学名で Setophaga americana Northern Parula をタイプ種とした Boie (1826) の用例もあった (The Key to Scientific Names)。
Cuvier (1800) の設けた属が用いられることになった模様。一度は別属に統合されることもあったが Dement'ev and Gladkov (1954) では Chloris を用いていた。アオカワラヒワをタイプ種とする属名は他にもあって知名度の高さがわかるが、Cuvier (1800) のものが早いために採用された模様。
[亜種]
確認も兼ねて亜種 (オガサワラカワラヒワを含む) をリストしておく。記載時学名と基産地 type locality (わかるものは Avibase より) を表記。各亜種の分布については Saitoh et al. (2020)
Cryptic Speciation of the Oriental Greenfinch Chloris sinica on Oceanic Islands を参照。
・Fringilla sinica Linnaeus, 1766 (記載) 基産地 China; restricted to Macao (マカオに限定) ペキンカワラヒワ
・Fringilla kawarahiba Temminck, 1836。基産地 Japan (図版) オオカワラヒワ
・Fringilla kawarahiba minor Temminck & Schlegel, 1848 (記載) 基産地 Japan (図版) 亜種カワラヒワ
・Fringilla kittlitzi Seebohm, 1890 (記載) 基産地 Bonin Islands (小笠原) 現在は別種オガサワラカワラヒワ。Kittlitz (1828) が小笠原で見つけたがヨーロッパのものと同一の種名としていた
(参考。カムチャツカのものに近いが違いも述べられていた)。Kittlitz が先に見つけていたため功績を学名に残したのだろう
・Chloris sinica ussuriensis Hartert, 1903 (記載) 基産地 mouth of Sidemi River, Ussuriland (ウスリー) チョウセンカワラヒワ
・Chloris sinica clarki Kuroda & Mori, 1920 * Ulleung-do Island in South Korea (参考) マツシマカワラヒワ = kawarahiba。基産地 韓国の鬱陵島 (うつりょうとう、ウルルンド、Ulleungdo) マツシマは当時の日本名
・Chloris sinica tschiliensis Jacobi, 1923 * (参考) 基産地 Sichuan = sinica
・Chloris sinica sichitoensis Momiyama, 1923 * 基産地 Hachijojima I. = kawarahiba
・Chloris sinica affinis Momiyama, 1927 * 基産地 Saisiu-men, Quealpart Island (韓国の済州島)。(参考) = minor
・Chloris sinica lonnbergi Momiyama, 1928 * (参考) 基産地 Ohtani, Hirono-mura, Toyohara-gun, Toyohara Prefect.-Distr., S. Sakhalin = sitchitoensis = kawarahiba?
・Chloris sinica chabarovi Stegmann, 1929 (記載) 基産地 Kumara, upper Amur River (アムール川上流) ホクマンカワラヒワ = ussuriensis
Chloris sinica seebohmi Momiyama, 1930 * (参考) 基産地 Isino-mura, Kita-Iwo-to = San Alessandro Island (北硫黄島) = オガサワラカワラヒワ (Chloris kittlitzi)
・Chloris sinica tokumii Mishima, 1961 = minor
* が付くものは Avibase に現れないもので近年の世界のリストに登場したことがない模様。
= 以降は通常のリストでシノニムとされる亜種。
現行の IOC 14.2 ではオガサワラカワラヒワを除いた最初から4つが採用されている。
sitchitoensis は H&M4 (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) によれば kawarahiba tentatively includes sitchitoensis as in Howell et al. (1968) and Orn. Soc. Japan (2000) とのこと。
chabarovi は同上 ussuriensis includes chabarovi; see Stepanyan (1990). But see Clement (2010) とのこと。
tokumii は同上 minor includes tokumii Mishima, 1961; see Orn. Soc. Japan (1974)。
日本鳥学会の目録で sichitoensis [暫定的に。Howell et al. (1968) が先に行った模様]、tokumii ともに他亜種のシノニムとして整理されたとのこと。clarki は日本の過去のリストにのみ現れ海外リストで言及がない。
ロシアでは亜種を広く認める傾向があるようで、Gluschenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraja" (沿海地方の鳥) では chabarovi も多少の違いがある、sichitoensis は島の亜種 (八丈島で記載) で沿海地方の海岸で繁殖する (Narazenko 1990; Koblik et al. 1997)。
ussuriensis とは色彩にだいぶ違いがある。この亜種 sichitoensis は北海道、千島列島、サハリン、アムール州の一部でも繁殖するとのこと (Red'kin and Babenko 1998)。
Chloris sinica lonnbergi Momiyama, 1928 は亜種に値するとしてサハリンの個体群に与えられたとのこと。これからから判断してこれらの地域は亜種 sichitoensis と呼べるだろうとの考え。
ussuriensis が内陸亜種、sichitoensis は島や沿岸の亜種と見ているよう (ロシアではよく採用される考え方。#ハクセキレイ参照)。
根拠となる引用文献もだいぶ古い。沿海地方で繁殖する鳥のシリーズでいずれまた取り上げられるであろう。
lonnbergi は 資料 によれば Kuroda (1932) が sichitoensis のシノニムとした、とのこと (当時この地域の亜種は sichitoensis であると理解されていたらしいことがわかる)。
affinis は 資料 によれば Kuroda (1932) は minor のシノニムとした。
seebohmi は 資料 によれば Kuroda (1932) が現在のオガサワラカワラヒワのシノニムとした。
たくさんの亜種が記載されたがそのうち sichitoensis は比較的シノニムにならずに残ったもののように見える。それ以外はおそらく早期にシノニムとされて日本の目録に現れなかったため海外でも使われなかったのだろう。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では全体で6亜種。オガサワラカワラヒワが含まれているはずなので IOC 14.2 より1亜種多いのみで、シベリアの亜種は ussuriensis としている。chabarovi をシノニム扱いしているらしい。Gluschenko et al. (2016) はかなり細分主義のように思える。
Saitoh et al. (2020) でサンプルされた個体の分子系統解析を見ると沿海地方のものは別系統に分けられる可能性が高い (ussuriensis 相当?)。鬱陵島のものも別系統に分けられる可能性が次に高い (clarki 相当)。
他は系統樹で混在しているのでまとめてよろしい、という感じになるだろうか。kawarahiba と minor の違いは思ったほどなかった。
clarki は亜種として認識した方がよろしい、ぐらいに読んでいる。
この研究が出ているにもかかわらず日本鳥類目録第8版で clarki に言及がないのは韓国の固有亜種で日本産ではないので表面上現れない、ということか。海外ではこの文献はオガサワラカワラヒワ以外は気にしていないかも知れないが、世界のリストにも反映されないのは不思議なところがある (wikipedia 韓国語版にも言及がなく、ごくわずかのページに現れる程度)。
Saitoh et al. (2020) はオガサワラカワラヒワ以外を別種に分ける根拠は十分にないので現状の亜種の亜種の扱いでよいとしている。
参考までに Brazil (2009) "Birds of East Asia" を見ておくと当時のロシアの分類に対応する形で、大陸とは別亜種、北海道を含めその北側の夏鳥を kawarahiba として扱っている。
Gluschenko et al. (2016) で使われる sichitoensis を kawarahiba のシノニムとし、分布域はロシアでの見解を採用したと考えると理解しやすい。Brazil (2009) では minor は北海道で多くは留鳥、それ以南の日本本土で留鳥の扱い。
Saitoh et al. (2020) の分子系統研究の結果を見ると、従来は亜種として扱われていたものの kawarahiba と minor をそれほど意識して区別するほどのことはないかも知れない。
むしろ日本 (小笠原を除く) やカムチャツカまでを含む個体群と大陸亜種との区別の方が重要で、Brazil (2009) にも minor と kawarahiba を区別する図は出ていない。
なお Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では2亜種で Fringilla kawarahiba major T. & S. (オオカワラヒワ) と Fringilla kawarahiba minor T. & S. (コカワラヒワ) となっている。
オガサワラカワラヒワは別種扱い。
このオオカワラヒワの major について、Temminck (1836) が Fringilla kawarahiba を命名した時には亜種相当の扱いはなくそのままの学名となっている。
Temminck and Schlegel (1848) が Fringilla kawarahiba minor を記載した時に、当時は "亜種" というよりは Fringilla kawarahiba の小型版で le petit verdier du Japon (日本の小型のアオカワラヒワ) のフランス語名で紹介している。つまり Linnaeus の二名法以前からの学名の使い方で修飾語を後に追記する形になっている。
この文献では "本家" の方は亜種学名は付けず (当時はそのような習慣はまだできていなかったのだろう) le grand verdier du Japon (日本の大型のアオカワラヒワ) として比較紹介している。
Hartert (1910-1922) p. 63 によれば major を付けた用例は Temminck and Schlegel (1850)
Fauna Japonica とのこと。
2亜種の原記載には現れないが、"Fauna Japonica" で取り扱う際に le grand verdier du Japon Fringilla kawarahiba major と改めて付けたことになる。
時代的には亜種記載というより別種で大きい・小さいをラテン名で表したものと考えられる。
このように見ると和名のオオカワラヒワとコカワラヒワの "オオ" と "コ" は Fauna Japonica 由来のよう。
Fringilla major Brehm, 1855 (参考) は Fauna Japonica より後の時代で上記表記を無効にすることはなかった。
ただし Loxia major Forster, 1817 (参考 = シメのこと) の用例はすでにあったので Temminck and Schlegel (1848) は最初の記載時は意識的に major を避けたのかも知れない (ここも現地名を使っておけば過去の用例を調べなくても名称の衝突が避けられる理由が感じられる)。
Loxia minor Brehm, 1845 (参考) もほぼ同じような時期に付けられているので属の扱い次第では Temminck and Schlegel (1848) の名称も危なかったかも知れない。現在は別属扱いなので問題ない。
Temminck and Schlegel が種小名に japonica を用いなかった理由は日本から2 "種類" を記載したためかも知れない (#タンチョウの学名についての Temminck の見解参照)。どちらかに japonica を付けるのは Temminck の価値観に反していたのかも。
2つの記載年が違っているのはオオカワラヒワの図版のみが先に出版されたため生じたもの。
現在では亜種扱いだが、Temminck and Schlegel の記述では deuxieme espece と "種" の方を用いている。considerer comme ne formant qu'une race un peu plus petite ... とオオカワラヒワの単なる小型 race (種族または現在の亜種) とは考えにくいとしている。
Hartert (1910-1922) p. 65 ではオガサワラカワラヒワは別種 Chloris kittlitzi 扱い。カワラヒワから派生しているようだが違いが大きく同種と考えるのは適切でないと考えていた。Hartert のこの記載がオガサワラカワラヒワの初の十分詳しい記述とのこと。
Ogawa (1908) にはもう一つ見慣れない属名 Ligurinus が出ているが、これは Brisson (1760) がアオカワラヒワを含んで設けた属で、後にムネアカヒワ 現在の学名で Linaria cannabina Eurasian Linnet が追加された。アオカワラヒワがタイプ種と指定された (The Key to Scientific Names の情報より)。
Chloris Cuvier, 1800 の方が遅いが、Ligurinus にはその後の分類で異なる属のものが含まれていたなどの理由で採用されなかったのだろうか。
以下は誰かが論理的に主張した考え方に基づくものでないと思って見ていただくのがよいが (すでに唱えた人もありそうな気がするので私見とも言い切れない)、分子遺伝学からその程度の違いであれば (必ず識別できるとは限らない) minor と kawarahiba を1亜種にまとめてしまってもよい感じがする。
古く記載されたものなのでずっと亜種があるものとして扱ってきた経緯があるので抵抗があるかも知れないが、そう考えれば日本の大部分は1亜種となって大陸亜種の分類の細かさと整合性がとれる気がする。
もし1亜種にまとめるならば、kawarahiba の方の記載が早いのでこちらにまとまることになる。Brazil (2009) の図版が kawarahiba と ussuriensis の比較になっているのはこのような背景も多少意識したものかも知れない。
もし minor を kawarahiba のシノニムとするならば kawarahiba の和名が亜種カワラヒワとなるだろう (#ハマシギの状況に似ている)。学名と和名の整合性はむしろよくなる (少し歓迎)。
「亜種カワラヒワとオオカワラヒワの識別は自分にはできません、なぜならば分子遺伝学的には事実上同じようなものだから」と識別しない理由に使うにはちょうどよいかも (笑)。
これまで使われた亜種名をシノニムにするのは抵抗があり、名称関係もこれまで慣れたものから変わってしまうので Saitoh et al. (2020) も積極的に触れなかったのかも知れない。
しかし分子系統学を主にやっている人が見れば亜種扱いに疑問が持たれる可能性はあるかも知れない。
しかし clarki が世界の目録に出てこないぐらいなので (なんと言っても極東の限られた地域の話でもあり) あまり細かく吟味した人がいないのかも知れない。
音声 (地鳴き) に以下で紹介するようにはっきりした違いがあるので、大陸と主に東アジア島嶼部ではあるいは別種扱いの方が適切と考えられるようになるかも知れない。
そうなれば主な分布域で表現して日本からカムチャツカは Chloris kawarahiba (minor をシノニム扱いすれば単形種)、大陸は Chloris sinica の学名になるかも知れない。ussuriensis は後者の亜種となって音声との対応もずいぶんすっきりする。
ただし Saitoh et al. (2020) の分子系統樹では sinica と ussuriensis がグループをなしていないので、音声面の対応も含めてまだ検討課題として残るだろう。
clarki をどちらに入れるか、種とみなすかなどの問題は存在する。
大陸のもう少し西端に分布する個体群 (現在はシノニム扱い) は別途検討が必要だろうが別種になってしまえばあまり関係ないで済ませることも可能だろう。
このような形になれば和名は別途つけ直す必要が出てきそう。
さて英名 Grey-capped Greenfinch の起源を考えていて、図版を見るとこれは ussuriensis を指したものではと思えてきた。kawarahiba よりも色彩が一層はっきりしている。
前亜種の記載の Hertert (1903) は上面全般の色彩を記述しているが、kawarahiba の方には Oberkopf und Hinterhals dunkel graubraun bis aschgrau とあって頭頂から後頸まで深い灰褐色から灰色との記述がある。
亜種 kawarahiba はここでも Temminck が音を少し変えている。
オランダ語では w の音は標準的には u に近い音になるので日本語の wa は対応する適切な音がなくむしろ破裂音に聞こえたかも知れない。フランス語でも w は基本外来語のみで [v] の発音。w で始まる単語は非常に少ない。
ヨーロッパ言語でも b と v が完璧に区別されているわけではないようで、ラテン語の hibernus (冬) から「冬眠する」は英語で hibernate だが hivernate の綴りも使われたことがあり (wiktionary)、フランス語では hiver になっている。wa が ba に変わってもそれほど不思議ではない。
小田谷、梅垣 (2021) Birder 35(6): 48-51 に「カワラヒワの亜種識別」がある。
北海道で繁殖する亜種カラフトカワラヒワ sitchitoensis (伊豆七島に由来。八丈島で Momiyama 1923 が記載。繁殖域はサハリン、北海道、南千島、ハバロフスクと沿海地方沿岸と記載されていた) の概念があるが、通常は minor または kawarahiba のシノニムとされる。扱いは定まっていない。
与那国島で 2017 年に記録された個体は亜種チョウセンカワラヒワ C. s. ussuriensis (ウスリーの。ロシア名ではウスリーのカワラヒワ) の可能性があるとのこと。地鳴き (flight call) も独特で日本で通常記録されるカワラヒワとは異なるとのこと。
海外の音源を聞くとキリリ...の音声がだいぶ異なるので区別可能と思える。なお亜種 sinica (中国の。ペキンカワラヒワ) も同様の地鳴きを出す。
韓国の鬱陵島 (うつりょうとう、ウルルンド、Ulleungdo) の亜種マツシマカワラヒワ clerki の概念もあるそうだが現在の海外の主要リストには現れない。
この個体群については Kim et al. (2018) Intraspecific variation and phylogeographic patterns of the grey-capped greenfinch Chloris sinica ssp. (Passeriformes: Fringillidae)
も取り扱っていて、通常は亜種 kawarahiba に含まれているが unidentified subspecies for Ulleung population(s) の表記となっている。
大陸の亜種で他に内モンゴルから満州北部の chabarowi (ホクマンカワラヒワ。ロシア名ではアムールのカワラヒワ) がある。
Birder 編集部 (1995) Birder 9(2): 42-43 にカワラヒワの亜種の識別の記事があり、標識調査をする人にとってはある意味お気に入りのテーマかも。この記事では亜種カラフトカワラヒワ sitchitoensis は北海道にも分布。sitchitoensis と minor の大きさを比較した写真なども示されていた。
[音声]
松田 (2018) Birder 32(2): 36 によればオオカワラヒワとマヒワのさえずりが似ているとのこと。
参考までに繁殖地での音声 XC67315 (Rick Bowers カムチャツカ)、XC401718 (Albert Lastukhin & Dmitriy Korobov サハリン)。
バードリサーチ鳴き声図鑑にある オオカワラヒワ (山口県見島 2014-04-27 岡本恭治) は亜種カワラヒワとそれほど違いを感じない。
xeno-canto にはマヒワのさえずりは多数あるがそれほど似ていない感じがする。
[オガサワラカワラヒワ] は #オガサワラカワラヒワ に移動。
[秋のカワラヒワ]
京都盆地のカワラヒワは秋につがい形成を行うとのこと。
「アニマ」1981年10月号「秋、鳥に何が起きているか」から抜粋すると、
「10 日間の不思議なできごと カワラヒワのつがい形成のしくみ」(中村浩志)
秋のある日、カワラヒワが杉の枯木に集まってきた (桃山御陵での観察。8-9月は繁殖地を去り、換羽地に終結する。10 月から換羽が終わった個体が繁殖地に戻ってくる。11/10 ごろには
ほとんどの個体が戻っている。集団誇示行動は 10 月中旬から下旬)
激しい闘争が行われたあと、つがいができていくカワラヒワにとって、秋は一年の始まりであった」
「鳥たちの一年は秋に始まる」(中村登流/川部部浩哉) より:
繁殖期は秋に始まる!? (エナガの中には秋に巣をつくるものもいる)
個体群再編成としての秋 (秋にはその年生まれの多数の個体が入る)
再編成はどの程度に起るのか? (一夫一妻型の場合翌年もつがいになる可能性が高い)
渡り鳥の場合 (コジュリンでそれらしい観察記録がある)
予測はいつがしやすいか? (鳥にとって将来を見通すには秋はよいシーズン)
高密度の場所は条件が非常によい場所と単純に考えるのは間違いらしい。なわばり争いの結果追い
出されて結果的に高密度な場所が生じているらしいとある、
などの記事がある。
中村 (1979)
カワラヒワ Carduelis sinica の夏季の集合と換羽
の研究論文も読むことができる。
-
マヒワ
- 第8版学名:Spinus spinus (スピヌス スピヌス) フィンチ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Carduelis spinus (カルドゥエーリス スピヌス) フィンチのヒワ
- 第8版属名:spinus (合) フィンチ、チフチャフ (spinos フィンチ、チフチャフ Gk)
- 第7版属名:carduelis (f) ゴシキヒワ (< carduus アザミ -elis に関連した)
- 種小名:spinus (合) フィンチ、チフチャフ (spinos フィンチ、チフチャフ Gk)
- 英名:Siskin, IOC: Eurasian Siskin
- 備考:
ラテン語に spinus の単語があり (スピーヌス。棘などの意味)、こちらは spina (スピーナ) に由来するが意味が違う。こちらもしばしば登場するので語義と発音には注意が必要。
属名の方はギリシャ語 spinos に由来でギリシャ語ではチフチャフを表す。ギリシャ語 spiza とシノニムとされる。ギリシャ語では長母音を含まないため学名を読む時も伸ばさないのが適切と考えられる。
carduelis も e が長母音でアクセントがある (カルドゥエーリス)。
carduelis はラテン語でゴシキヒワを指すが語源は carduus アザミ (英語 thistle) または チョウセンアザミ (英語 artichoke)。ゴシキヒワはアザミの実を食べ、綿を巣材に用いるため。英語にも thistlefinch の名称がある (wiktionary)。接尾辞 -elis は冒頭が長母音でアクセントがある。
同じ意味の語尾では -alis の用例が多い。形容詞を作る語尾で、特に "食べる" の意味はない模様。
記載時学名 Fringilla Spinus Linnaeus, 1758 (原記載)。Spinus の名称はこれ以前からあった。
Spinus 属は Koch (1816) が4種を対象として導入したもの。
マヒワはこの時に Spinus viridis Koch, 1816 (参考) の新名が与えられた
(当時の習慣について #ノスリの備考参照)。
かつては亜種記載も少しあって Chrysomitris dybowskii Taczanowski, 1876 (参考)、Chrysomitris spinus buturlini Loudon, 1912 (参考)。
いずれも中央アジアの記載で Dement'ev and Gladkov (1954) でもシノニム扱い。
Chrysomitris 属は Boie (1828) によるもので khrusomitres ゴシキヒワ (Gk) 由来。こちらも Fringilla Spinus Linnaeus, 1758 を含む属を分離したかったがそのままではトートニムとなって当時は避けられたためギリシャ語由来の別の属名を与えた形となっている。
この属名を用いれば Chrysomitris spinus とトートニムを避けることができて後の時代にも (20 世紀初めまで) 使われていたよう。
トートニムも許容され、より早い時期の Koch (1816) の属名が使われるようになったと考えられる。
OED によれば英語 siskin は 1544 年にすでに登場する古い単語。語源はよくわかっていないがオランダ語 sijsken などに類似するものがある。おそらく西スラブ語由来でポーランド語では czyz などとのこと。究極的には声由来ではとのこと。なおロシア語でも同様で chizh (チシュと読む)。
参考までに Kolyada et al. (2016) の語源辞典を見ておくとおそらく音声由来とあり、ウクライナ語では鳴き声を Chij vy! Chij vy! (あなたは誰のもの?) と聞きなすとのこと。
単形種ではあっても "morph" 相当のものは知られているそうで、渡辺・三河 (2006) Birder 20(2): 65 に飼い鳥用語でホンテルとチュウテルが紹介されている。
現在の扱いは同じく単形種だがアトリよりユーラシア東西に分かれて分布している。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Spinus 属となる。種小名は変化なし。
Spinus 属はマヒワ属。Carduelis 属は日本産鳥類リストからは消える見込みだが、検討種にゴシキヒワ Carduelis carduelis が含まれる。
面白いことに spinus でなく pinus の種小名もある Fringilla pinus Wilson, 1810 (参考)。北米での記載。pinus は松の木のこと (当時の英名 Pine Finch) で語源が異なるが、あるいは spinus に語呂を合わせて短縮したい意図もあったのかも知れない。
現在はマツノキヒワ Spinus pinus Pine Siskin の別種で有効な学名となっている。
関連したものに オウゴンヒワ Spinus tristis American Goldfinch があり、これも Linnaeus (1758) が記載。tristis は物憂げななどの意味があるが、ここでは
ゴシキヒワに比べて色彩が派手でないことを表現したものなのだろう。
-
ベニヒワ (種統合あり)
- 第8版種学名:Acanthis flammea (アカンティス フラムメア) 炎色のヒワ (IOC も同じ)
- 第8版亜種学名:Acanthis flammea flammea (アカンティス フラムメア フラムメア) 炎色のヒワ
- 第7版種学名:Carduelis flammea (カルドゥエーリス フラムメア) 炎色のヒワ
- 第8版属名:acanthis akanthis (Gk) アリストテレスなどの用いた未同定の小型の鳥でおそらくムネアカヒワ
- 第7版属名:carduelis (f) ゴシキヒワ
- 種小名:flammea (adj) 炎色の (flammeus)
- 英名:(Common Redpoll 統合前の名称), IOC 14.2 で Redpoll
- 備考:
acanthis は由来となるギリシャ語は短母音のみで長母音は現れないと考えられる。-can- がアクセント音節と考えられる (アカンティス)。
flammea は短母音のみで冒頭にアクセント (フラムメア)。
英語の Redpoll は OED によれば古くからある名称で 1728 年に Red Pole、1772 年に redpoll が登場するとのこと。poll は現在の英語では通常使われないが頭を指すとのこと。
統合のため第8版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では Acanthis 属となる
[< akanthis (Gk) アリストテレスなどの用いた未同定の小型の鳥でおそらくムネアカヒワ Linaria cannabina 英名 Common Linnet を指していたものと考えられる。鳥類学ではヒワを指して使われる。Acanthis がヒワに変えられた神話もある (The Key to Scient
ific Names)]。
Acanthis 属の原記載 (Borkhausen, 1797) 当時はずっと広い概念で使われていた。
Acanthis flammea もこの属に含まれており、ベニヒワ類 (当時) を Carduelis 属から分離する時にこの記載が使われることになった。
Acanthis flammea が女性形で含まれていたため Acanthis は女性の扱い。
現在この属に残るのは種統合された結果ベニヒワ1種となった。
Acanthis 属はベニヒワ属となる。
ベニヒワとコベニヒワは別種とも同種とも扱われるが、日本鳥類目録改訂第7版では別種扱いであった。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では同種扱いとなり、Acanthis flammea flammea 亜種ベニヒワ と Acanthis flammea exilipes 亜種コベニヒワ の扱いになる (exilis 細い、小さい + pes 足)。
この exilipes は日本鳥類目録改訂第7版でコベニヒワを独立種としていた時の亜種名。
IOC では別種扱いで、ベニヒワには基亜種の他に rostrata (嘴の長い。アイスランドの亜種) を認めている。
[Acanthis (ベニヒワ) 属の分類]
参考までに IOC 14.1 分類を挙げておく。
アトリ科 Fringillidae
(他属は省略)
ベニヒワ属 Acanthis
ベニヒワ Acanthis flammea Common Redpoll
亜種 flammea 北ヨーロッパ、シベリア、アラスカから南ヨーロッパ、中央・東アジア、本州、アメリカまで移動 (irruption)
亜種 rostrata カナダ北東部、グリーンランドからアメリカ北東部、英国に移動 (irruption)
ヒメベニヒワ Acanthis cabaret Lesser Redpoll
コベニヒワ Acanthis hornemanni Arctic Redpoll
亜種 exilipes 北ユーラシア、アラスカなどからヨーロッパ中央部、中国北部、アメリカ北部に移動 (irruption)
亜種 hornemanni カナダ北東部、グリーンランドからアメリカ北東部に移動 (irruption)
IOC 14.1, 13.2 ともに同じ分類になっている。IOC 14.2 では1種にまとめられた。
注釈によればベニヒワ類はもとの Acanthis 属に戻された。
Lesser Redpoll (ヒメベニヒワ) はベニヒワから分離されたがコベニヒワとの関係は将来の研究が必要 [ここで後述の Mason and Taylor (2015) も文献に含まれるが、Funk et al. (2021) は含まれていない]。
Arctic/Hoary Redpoll (コベニヒワ) はベニヒワの variant かも知れないが "種" 間のつがい形成の好み (assortive mating) の報告もあるので同一種とするにはまだ納得できない部分が残る [Mason and Taylor (2015) も含まれている]。
これらを同種と扱っているのは HBW/BirdLife v8 (2023), Boyd, Gaudin で他の主要チェックリストでは分けている (ヒメベニヒワを種とするかはリストにより異なる)。
(2024.7 の情報)
IOC 14.2 でヒメベニヒワも含めて同種となる見通し。Chesser et al. (2024), Mason and Taylor (2015), Funk et al. (2021) が文献に挙げられている。英名も統合され Redpoll となる。
Chesser et al. (2024) は新しい研究ではなく AOS の判断 (#アマサギの備考参照)。世界のリスト統一化に向けた動きのよう。ベニヒワは世界で1種となる。
[ベニヒワとコベニヒワの遺伝的関係]
自分には (地域的にも) あまり馴染みがない種であったこと、従来からベニヒワとコベニヒワを別種にするか同種にするか両方の見解があったため、日本鳥類目録第8版で同種となる見込みについてあまり気にしていなかったのだが、
先崎 (2024) Birder 38(2): 36 に記事があり、事情が複雑そうなので確認してみた。
この記事でも参考文献となっている最新論文は Funk et al. (2021) A supergene underlies linked variation in color and morphology in a Holarctic songbird
である。73 個体の全ゲノム解析を用い、第1染色体にある主として 55 Mb の染色体逆位 (chromosomal inversion) 部位に含まれる複数の候補遺伝子がメラニン色素の発現、カロテノイド色彩や嘴の形を決めているらしいことを明らかにした。このような複数の形質を制御し、連鎖して遺伝する遺伝子グループを超遺伝子 (supergene) と呼ぶ。
先崎 (2024) の脚注の超遺伝子の解説 (複数の形質が1つの遺伝子上にまとまっている) はやや不正確に思える (本文の方はむしろ違和感を感じないが)。
超遺伝子は複数の (染色体上近傍にある) 遺伝子が通常期待されるような (相同) 乗換え (chromosomal crossover) を起こさずに一体となって遺伝する状況を指すもの [若干ややこしいのは Funk et al. (2021) は相当する現象をすべて recombination の用語で記述している。
遺伝子レベルで見た時の表現が recombination、染色体では crossover となるが recombination はさらに広い概念でも使われるために染色体で起きる事象であることを重視した表現を選んだ]。
主にヒトを扱ったものだが日本語解説として 染色体の構造の異常 (京都大学 OCW 2021)
が参考になると思われる。これによれば
「逆位内の遺伝子の配列は逆転するが、重複、欠失はないので、逆位は遺伝的に悪影響を及ぼさない」
(しかし、以降も参照) (中略) 「結果的に (相同) 乗換えが抑制され、逆位領域の遺伝子が保存される」
「逆位のある集団と無い集団間の雑種は半不稔になるので、種の分化の出発になる」
とある。つまり逆位内では乗換えが起こっても次世代に残らないために (相同) 乗換えが抑制され、一体となって遺伝する超遺伝子のようにふるまうことがあり得る
(#エリマキシギ備考の nature ダイジェスト日本語記事も参照)。
Funk et al. (2021) では染色体逆位の起きた部位は特定しているが、逆位の起きていない祖先型と逆位の起きた型を区別して扱わず3種の遺伝型として扱っている。祖先型と逆位の起きた型を合わせてその領域を "inversion region" と呼んでいる (各サンプルで逆位が起きていることを必ずしも意味しない) ので注意が必要である。
この領域を除外して系統解析をすると遺伝的多様性が大きく低下し、ベニヒワ類の遺伝的多様性にこの部位が大きく寄与していることは確かである。
"inversion region" が コベニヒワ Arctic Redpoll (または Hoary Redpoll) Acanthis hornemanni と他の2種 (ベニヒワとヒメベニヒワ Acanthis cabaret) を主に分け、他の遺伝部位も関わって ヒメベニヒワ Lesser Redpoll Acanthis cabaret と他の2種を分けている結果になった。
解析結果からは "inversion region" とそれに関連して遺伝する他の部位がこれら3"種"を決定していると考えられる。超遺伝子を中心とする多型 (3つ) があることはこの研究でも認められている。
進化的圧力が何もなければ、超遺伝子は遺伝子浮動などで次第に形が崩れてゆくと期待されるが、現在のような "種" を決定するような機能を果たすためには何らかの維持機構が必要である。
著者はこのような超遺伝子のふるまいは "種" の間の生殖隔離によって崩壊と維持のバランスが取れた状態になっていると考えている。ベニヒワ類は同種を好んでつがい形成を行う (assortive mating) ことが知られているが、地域によってそうでない事例もある。地域依存の生殖隔離や、豊富な年の渡りの irruption によっても遺伝構造が影響を受けている可能性もある。
これだけの機構だけでは表現型の緯度依存性などを説明しきれないため別の要因も考えられるが、この部分が先崎 (2024) にある「環境が異なれば異なる形態が発現する」に対応するだろう。
Funk et al. (2021) では緯度依存の表現型の違いを重視すれば "inversion region" が生殖隔離に果たす役割は限られていると考えられ、この視点で見れば3種と考えるよりは1種が環境に応じた多型を示すように振る舞うように見える、とのことである。後半は詳細な機構はわからないがなぜ多型に見えるかの解釈として挙げたもののように見える。
これをもって同種か別種かを判定するのはおそらく難しいであろう。"inversion region" のみに主な違いがあって (それ以外の部分は十分な遺伝子浸透がある)、しかし多少なりとも生殖隔離で維持されている状況を種とみなすかの問題になる。
上記説明に従って考えれば assortive mating による生殖隔離がもしなければ超遺伝子の構造や機能も変わって多型がなくなり、よく混ざった1種になっていたかも知れない。
現在の多型がこのように生殖隔離で維持されているならばどこまでを種と考えるかの概念の問題にも戻ることになるのだろう。
ハシボソガラスとズキンガラスの関係にも似ているが、こちらは地域を広げると色彩とは別に遺伝的に異なるグループが見出されてこちらも複雑になっている (#ハシボソガラスの備考参照)。
ベニヒワ類の間では逆位のあるものとないものの雑種は不稔になっていないようであるが、逆位は種分化の機構の一つにもなるので飼育下の実験なども含めて機能を確かめてゆく必要があるのだろう。
放浪的な生活様式も遠距離集団間の遺伝子が混ざりやすい原因となり (#イスカの備考も参照)、ベニヒワ類の問題を複雑にしているかも知れない。
参考までに発端となった 2015 年の論文は
Mason and Taylor (2015) Differentially expressed genes match bill morphology and plumage despite largely undifferentiated genomes
in a Holarctic songbird
で、
Lifjeld (2015) When taxonomy meets genomics: lessons from a common songbird
に解説がある。
この解説の口調は分類学の細分化傾向の問題点を指摘しているように読めるが、"old conventional markers" (伝統的な遺伝子マーカー) が事実上同種であることを示せたと述べたもので、Funk et al. (2021) のような逆位の果たす複雑な役割はまだ見えていなかった。
Boyd などでは取り入れているが、Mason and Taylor (2015) の結論だけを見て1種と即断したものがあれば少し早計だったかも知れない。先崎 (2024) もまだ結論が出たわけではないニュアンスで書かれていると読める
(最初にも記した通り、遺伝情報がよくわかっていない過去はどちらの扱いもあったので個人的には事実上どちらでもよいと感じている。科学的に判断を追求するとこのような場合の合意がどの程度得られているかよくわからない。
またこれは極北で種子食の特殊環境下でもあり、細分化傾向や色彩による分類の問題点の一般論として捉えるのはおそらく行き過ぎであろう)。
Young Guns (2016) Birder 30(3): 44-47 におそらく 2015 年の研究を紹介しつつ、ベニヒワとコベニヒワの識別を記載した記事がある。
北米で irruption を起こす種が何の影響を受けているか調べた論文: Widick et al. (2025) Continent-Wide Patterns of Climate and Mast Seeding Entrain Boreal Bird Irruptions
気温に影響される、食物量に影響されるの2大仮説があるが結果の解釈はなかなか難しいよう。データの揃っている北米で相関を探してもこの程度なので、東アジアの局地的なデータから irruption の原因を議論することはそもそも困難かも知れない。
-
(旧名種コベニヒワ) ベニヒワ亜種コベニヒワ
- 第8版亜種学名:Acanthis flammea exilipes (カルドゥエーリス フラムメア エクスィーリペース) 細い足の炎色のヒワ (IOC も同じ)
- 第7版学名:Carduelis hornemanni (カルドゥエーリス ホルネマンニ) ホルネマンのヒワ
- 属名:carduelis (f) ゴシキヒワ
- 第8版種小名:flammea (adj) 炎色の (flammeus)
- 第7版種小名:hornemanni (属) ホルネマンの (デンマークの植物学者 Jens Wilken Hornemann)
- 第8版亜種小名:exilipes 細い足の exilis 細い pes 足
- 英名:Arctic Redpoll
- 備考:
exilipes は exilis は ec-si-lis と分割され -si- の i は長母音。-pes は足の意味のギリシャ語由来で長音。-li- がアクセント音節と考えられる (エクスィーリペース)。上記は古典式発音だがアクセントを変えず短音でも構わない。
hornemanni は -man- がアクセント音節と考えられる (ホルネマンニ)。
統合のため第8版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではベニヒワの亜種となっている (#ベニヒワの備考参照)。このままであれば Acanthis hornemanni (属名は変更してある。英名 Arctic Redpoll に対応) の学名は亜種名も含めて日本のリストから消える。
なお英名で小さいベニヒワに相当する Acanthis cabaret (フランス語でヒワの一種) が存在するが、この和名はヒメベニヒワとなっているようである。
-
ハギマシコ
- 学名:Leucosticte arctoa (レウコスティクテー アルクトーア) 北の白い斑点のある鳥
- 属名:leucosticte (合) 白い斑点のある (leuko- (接頭辞) 白い stiktos 斑点の Gk)
- 種小名:arctoa (adj) 北の (arctois, arktoos Gk)
- 英名:Rosy Finch, IOC: Asian Rosy Finch
- 備考:
leucosticte は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は stiktos の女性の変化形と考えれば末尾が長母音になる。-stic- と分割されるならばアクセント音節と考えられる (レウコスティクテー)。
arctoa はギリシャ語 arktois 由来で o は長母音になる。ラテン語の arctus, arctous などの変化形ではないと考えられるが、arctous の o はギリシャ語由来の長母音である。
ギリシャ語でも arktos (北、クマ) の意味では長母音ではなく、形容詞語尾を追加されて長母音になったもの。arktois (wiktionary) では o は長母音。植物の Arctous 属はこのギリシャ語が由来と説明されている。arktoos (The Key to Scientific Names) の考えもあり、この単語も1つめの o は長音。いずれも普通にギリシャ語に現れる単語ではない模様。
"アルクトーア" のアクセントと考えられる。
恒星名の Arcturus (アークトゥルス、うしかい座 α) も同じ起源で、この場合はクマの意味。-urus は鳥の学名でおなじみの "尾" の意味 (ギリシャ語 -ouros) で、おおぐま座を追う位置にあることから "クマの守り人" と解釈される。鳥類学名風の解釈では "クマの尾" でも十分な気がする。実際におおぐま座の尻尾の先端にある。
日本語では wikipedia 日本語版見出しで "アークトゥルス" (英語読み) と表記されているが語源を考えると "アルクトゥールス" とも読める。この読みも実際に使われており語源をよく反映した読みになっている。
主要亜種の読み方は brunneonucha は brunneus は短母音のみ。nucha は名詞で短母音のみ (The Key to Scientific Names の説明と少し異なる)。-nu-cha と区切るためアクセントはその前にある (ブルンネオヌカ)。ここでは eo を2重母音として全体をアクセントとする表記とした。
記載時学名 Passer arctous Pallas, 1811。
Leucosticte 属は Swainson (1832) が導入 (記載)。
女性の属名となった経緯は規則をよく知らないが、当時の属名 Linaria を引き継ぎ亜属の扱いなので性を合わせたものかも知れない。
ラテン語化してから女性形を作るのではなくギリシャ語段階で女性形を採用したとすれば見慣れない語尾も理解できる感じがする。
-sticte の語尾を持つ属名は現在使われているものでは他に Urosticte があるのみでこちらも女性の扱い。
-sticta とラテン語化してから女性形を作った例もあってコケワタガモの属名など。
5亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は brunneonucha (brunneus 褐色の nucha 後頸 < アラビア語 nukha 骨髄) とされる。英語で nuchal の単語があり、nuchal ligament 項靭帯 (草食哺乳類などでよく発達している)。
この亜種の原記載 Cervix fusco-castanes vix cinerascens (首は黒ずんだくり色でわずかに灰色) とある。
英名の Asian は、かつてのハギマシコが北米に分布するものも含んでいたため。北米のものも複数種に分離された。
Funk et al. (2021) Phylogenomic Data Reveal Widespread Introgression Across the Range of an Alpine and Arctic Specialist
の分子系統解析があり、アジアのもの (ハギマシコ) は単系統で祖先型にあたる。北米のものは色彩をもとにして通常扱われる分類とだいたい整合しているが相互の遺伝子浸透もある。極地域で繁殖する他種と似たパターンを示す。何種に分けるのが適当かは判断基準次第というところ。
アジアと北米の違いは大きくアジアのものを別種とする十分な証拠が得られている。
アジアのハギマシコ5亜種も含めた解析になっているがこの解析では分離されなかった (亜種があるとしても大きな違いではなさそう)。ハギマシコの亜種位置づけについてはさらなるサンプルが必要だろうとのこと。Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) はシベリアで4亜種としており識別点なども記している。
-
ベニマシコ
- 第8版学名:Carpodacus sibiricus (カルポダクス シビリクス) シベリアの果実をついばむ鳥
- 第7版学名:Uragus sibiricus (ウーラーグス シビリクス) シベリアの長い尾を持つ鳥 (IOC も同じ)
- 第8版属名:carpodacus (合) karpos 果実 dakos ついばむ (Gk)
- 第7版属名:uragus (合) 長い尾を持つ (oura 尾 Gk -ago 持つ L)
- 種小名:sibiricus (adj) シベリアの (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Long-tailed Rosefinch
- 備考:
carpodacus 外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-po- がアクセント音節と考えられる (カルポダクス)。
uragus は語源 oura と -ago の長母音よりいずれも長母音と考えられる (ウーラーグス)。
sibiricus は -bi- にアクセントがある。シビリクス。
Carpodacus 属のタイプ種はオオマシコと認定されているが、旧 Uragus 属の行方を見るためにこちらにまとめておく。
Carpodacus 属は Kaup (1829) が提唱したものでドイツ語名 Karminfink。Karmin は辞書訳では洋紅となっている。
wiktionary によれば Karmin はフランス語 carmin 由来でそれ以上の語源は推定程度。アラビア語 qirmiz (真紅, 英語 crimson) 由来の可能性があるとのこと。真紅のフィンチの意味で何語でもそれほど違いはなかった。
["マシコ" 類の分類と属について]
ベニマシコの Uragus 属は単形属だった。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Carpodacus 属 (true rosefinches "真性マシコ類") に合併された (karpos 果実 dakos ついばむ Gk)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
Zuccon et al. (2012) The phylogenetic relationships and generic limits of finches (Fringillidae) の分子遺伝学研究により、Carpodacus 属を単系統にするためにこれまで提唱されていたいくつかの属が合併されることになった。
Boyd がまとめた分子系統樹によれば広義 Carpodacus 属は2系統に分かれており、1系統を Propasser 属、残りの系統について
サバクマシコ Carpodacus synoicus Sinai Rosefinch と ウスマシコ Carpodacus stoliczkae Pale Rosefinch に
新属を与えれば従来与えられた属名を残すことが可能であることが示されている。
このグループ全体の名称として Carpodacini 族: Rosefinches の考えがある。
Boyd の分割はやや細かすぎる感じもするが、アカマシコやオオマシコとベニマシコが別属になるのは習性や分布も違うのでわかりやすい印象も受ける。この分類によるリストを挙げておく。アカマシコは少し系統が離れることがわかった。オガサワラマシコは属早く分岐したもので相当に異なっていることもわかる。
従来の属名がほとんどそのまま残るのはメリットかも知れない:
オオマシコ族? Carpodacini: Rosefinches
アカマシコ属 Erythrina
アカマシコ Erythrina erythrina Common Rosefinch
シュイロマシコ属 Haematospiza
シュイロマシコ Haematospiza sipahi Scarlet Finch
オガサワラマシコ属 Chaunoproctus
オガサワラマシコ Chaunoproctus ferreorostris (絶滅種)
サバクマシコ/ウスマシコ属 (新属学名が必要)
サバクマシコ "Carpodacus" synoicus Sinai Rosefinch
ウスマシコ "Carpodacus" stoliczkae Pale Rosefinch
(チベットマシコ)属 Kozlowia
(チベットマシコ) Kozlowia sillemi Sillem's Mountain-Finch
(ハネナガマシコ) Kozlowia roborowskii Tibetan Rosefinch
ベニマユマシコ属 Propyrrhula
ムネアカマシコ Propyrrhula punicea Red-fronted Rosefinch
ベニマユマシコ Propyrrhula subhimachala Crimson-browed Finch
ベニマシコ属 Uragus
ベニマシコ Uragus sibiricus (Siberian) Long-tailed Rosefinch
(チュウゴクベニマシコ?) Uragus lepidus Chinese Long-tailed Rosefinch (ベニマシコより分離)
オオマシコ属 Carpodacus
オオマシコ Carpodacus roseus Pallas's Rosefinch
ミスジマシコ Carpodacus trifasciatus Three-banded Rosefinch
ヒマラヤマミジロマシコ* Carpodacus thura Himalayan White-browed Rosefinch
チュウゴクマミジロマシコ* Carpodacus dubius Chinese White-browed Rosefinch
シロボシマシコ属 Rubicilla
セスジシロボシマシコ Rubicilla rubicilloides Streaked Rosefinch
シロボシマシコ Rubicilla rubicilla Great Rosefinch
バラマユマシコ属 Propasser
ヒマラヤマシコ* Propasser grandis Blyth's Rosefinch
ヒゴロモマシコ Propasser rhodochlamys Red-mantled Rosefinch
バラゴシマシコ Propasser waltoni Pink-rumped Rosefinch
ヒマラヤコウザンマシコ* Propasser pulcherrimus Himalayan Beautiful Rosefinch
チュウゴクコウザンマシコ* Propasser davidianus Chinese Beautiful Rosefinch
チャゴシマシコ Propasser edwardsii Dark-rumped Rosefinch
バラマユマシコ Propasser rodochroa Pink-browed Rosefinch
シャープマシコ* Propasser verreauxii Sharpe's Rosefinch
フタスジマシコ Propasser rodopeplus Spot-winged Rosefinch
(タカサゴマシコ) Propasser vinaceus Vinaceous Rosefinch
タイワンマシコ* Propasser formosanus Taiwan Rosefinch
このグループは近年種が分割されたものが多く和名が安定していないものも多い。* が付けてあるものは eBird などに用例のある和名。
(チベットマシコ) Kozlowia sillemi と (ハネナガマシコ) Kozlowia roborowskii は後者がタイプ種で英名との整合性およびタイプ種であることを考えると後者をチベットマシコとするのがよさそう。
ヒマラヤマミジロマシコ* Carpodacus thura と チュウゴクマミジロマシコ* Carpodacus dubius も分離されたもので分離前はマミジロマシコだった。ヒマラヤマミジロマシコの用例があり、次の同様の事例で "チュウゴク" が補われているので同様にした。
ヒマラヤコウザンマシコ* Propasser pulcherrimus と チュウゴクコウザンマシコ* Propasser davidianus も分離されたもの。分離前はコウザンマシコの和名。
(タカサゴマシコ) Propasser vinaceus と タイワンマシコ* Propasser formosanus も分離されたもので分離前はタカサゴマシコだった。タイワンマシコ* と英名の対応は良いが、前者をタカサゴマシコの名前にするのが妥当かはよくわからない。
属学名の由来は Erythrina erythrinus 赤い、暗赤色の。
Haematospiza haimatos 血 (の色の) spiza フィンチ (Gk)。
Kozlowia ロシア軍人で探検家の Gen. Pyotr Kuzmich Kozlov に由来。
Propyrrhula pro 近い Pyrrhula (ウソ) 属。
Rubicilla rubicilla ウソを指していた。
Propasser pro 近い Passer (スズメ) 属。
なおギンザンマシコ、ハギマシコは別系統でむしろウソのグループに属する。いずれも属名変更の必要はない。
[ベニマシコの亜種と類縁種]
3亜種あり (IOC 12.1 以降。Carpodacus lepidus を含める場合は5亜種)。北海道で繁殖するものは sanguinolentus (血の色のような < sanguis, sanguinis 血; cf. 英語 sanguinary 血なまぐさい) 亜種ベニマシコ、日本の記録で他に亜種不明とされる。
この亜種の記載時学名は Pyrrhula sanguinolenta Temminck & Schlegel, 1848 (原記載; 図版 1, 2) で、
記載時は Pyrrhula 属でウソ類に赤系統の種小名がすでにいくつも使われているため、preoccupied と判定されないように赤の同義語を選んだものと想像できる。
また orientalis は自身がウソに用いているのでこれも使えない (これはウソの亜種 griseiventris のシノニムとなったと思われる)。
japonicus を使いにくかった理由はおそらく自身がシメに用いたため (分類次第で重複の可能性がある)。これもシメが単形種となったため表面に現れなくなった。今から考えるとベニマシコに使っておけばよかった感じ。
IOC 12.1 以前は Carpodacus lepidus Chinese Long-tailed Rosefinch (留鳥) は亜種の扱いだったが IOC 12.1, HBW/BirdLife 2022 で北部、南部のグループに分離された。世界のリストではまだどちらの分類も使われている。
根拠となった分子系統研究は以下: Liu et al. (2020) Taxonomic revision of the Long-tailed Rosefinch Carpodacus sibiricus complex
ただし2種の間のさえずりの違いは認められなかったとのこと。
2種に分ける場合の北グループの英名は Siberian Long-tailed Rosefinch が提案されている。
この研究では2種への分離と、ベニマシコの亜種 ussuriensis は sanguinolentus のシノニムとするのが適当としている。
亜種のシノニム化の提案は IOC では採用されていない。Liu et al. (2020) の提案に従えば北グループのベニマシコの亜種は sibiricus (大陸型) と sanguinolentus (北海道やサハリンで繁殖) となる。
3亜種の場合の扱いは ussuriensis が大陸型のうち満州から朝鮮半島北部で繁殖し、中国東北部や朝鮮半島南部で越冬する扱いになる。
原記載では Le bouvreuil a longue queue du Japon (日本の尾長ウソ) との表記で、Pallas がアルタイ地方からカムチャツカ近くまで分布するとした Pyrrhula longicauda (ベニマシコの Temminck による当時の学名) Temminck, 1820 の日本型としたもの。
Loxia sibirica Pallas, 1773 と同種とみなされ、Pallas の命名の方が早かったためこちらの種小名となった。
ちなみに Pyrrhula caudata Pallas, 1811 もアルタイで記載されたがその後シノニムとされた。ussuriensis は Buturlin, 1915 によるハンカ湖での記載。大陸のベニマシコについては他の亜種シノニムもある。
Glushchenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraya: Kratkij Faunisticheskij Obzor" によれば島の亜種 sanguinolentus はサハリンからアムール川下流、タタール海峡沿岸の大陸にも分布を広げ ussuriensis と接触しているとしている。
sanguinolentus の方が少し小型で色調が明るい。ロシア名のベニマシコは uragus で属名をそのまま利用。
[音声・羽音]
ベニマシコは最も身近な「赤い鳥」の一つで、声はよくご存じであろう。秋にベニマシコが集団で渡ってきた時、何の声かわらかないような集団の賑やかな音声が聞かれることがある。単独個体の声だけでなくこのような声にも注目していただきたい。
羽音が大きいことが知られていて、例えば愛媛の野鳥「はばたき」には「飛んだとき、羽音がポロッポロッと聞こえる」とある。気づかれた方はあるだろうか。
[赤い鳥はなぜ赤い]
もっと赤い鳥もあるが、身近な赤い鳥ということでベニマシコの項目に紹介する。赤い鳥の「赤」(あるいは鳥の赤い部位) はカロテノイド carotenoid (カロチノイドとも呼ぶ) 色素で、食物由来であることはよくご存じであろう。
鳥やヒトなど脊椎動物はカロテノイドを合成することができず、カロテノイドが前駆体となるビタミンAは必須栄養素となっている。生体内ではいろいろな働きをするが、ビタミンAから作られるレチナール (retinal) がタンパク質オプシンと結合して網膜の光受容体にあるロドプシン (rhodopsin) を形成する。
ビタミンA欠乏症の一つとして夜盲症が知られているのはこれに由来する。
その他にもさまざまな作用があり、免疫にかかわる働きなどがあるが、よく知られているものに抗酸化作用がある。生物が酸素を用いてエネルギーを作る際に有害物質 (ラジカルなど) が発生する (酸化ストレスとも呼ばれる) が、その除去に役立つのが抗酸化物質でありカロテノイドは代表的なものである。
鳥類が哺乳類に比べて長命なのはそもそも有害物質が出にくいエネルギー生成機構を持っている (優れた運動選手に鳥型ミトコンドリアを持っている人があるなど話題になったことがある)、抗酸化物質である尿酸濃度が高いなどいろいろな要因が考えられている。
飛翔の際に大量のエネルギーを作る必要があるため、酸化ストレスをを減らす性質は生存に有利であると考えられ、その結果寿命も伸びたと考えると納得がいく (もちろん寿命を決める因子はこれだけではないし、生態学的に寿命を決める要因もあるのでこれだけで説明するのは危険であるが、大まかな傾向としては多分間違っていないだろう)。
このように生物にとって抗酸化物質は欠かせないものであり、カロテノイドを羽毛などの着色に用いることは体内の抗酸化物質を減らすことになり、羽毛の赤い色と抗酸化物質量はトレードオフの関係にある (両立することが難しい)。そのような制約下で赤い色を強く発色できる個体はそれだけよい栄養状態にあることを示す信号となる。たとえばツバメののどの色などはそのような働きがあると考えられている。
酸化ストレスを発生させるもの、例えば生理的には長距離の渡りなどはこのトレードオフの重要な要因になる。放射線も酸化ストレスと同様にラジカルを生じさせるため、チェルノブイリ原子力発電所の事故の後にツバメののどの赤みが変化したなどの研究があった
[例えば Camplani et al. (1999) Carotenoids, sexual signals and immune function in barn swallows from Chernobyl]。
[赤いカナリア]
赤い鳥の話に戻ろう。赤い鳥は赤い色素を自分で合成することはできず食物から摂る必要があることはよく知られている (ここは正しい)。動物園で飼育しているフラミンゴでも赤い色の材料となる食物を十分に与えないと色が抜けてしまうことはよく知られている。
カナリアにニンジンや赤ピーマンなどをすりおろして与えると赤色が濃くなる、のような説明がされることがあるが [例: 上田 (2007) Birder 21(2): 38-40]、これは半分正しくない。カナリアの原種や、赤くないカナリアの品種にいくらニンジンを与えても赤い色にはならない。せいぜいオレンジ色になる程度であるとのことである。
赤いカナリアを品種改良で作るためには莫大な労力と歳月 (そして犠牲) が必要であった。カナリアの原種の中に現れる変異を品種改良で選んでも赤いカナリアを作ることはできなかった。飼育家が考えたのは他の赤い鳥と雑種を作ることで、カナリアに「赤い」性質を持ち込もうとした。これは大変な難事業で、そもそもどんな種類とでも雑種を作ることができるわけではない。
飼育家が目をつけたのはこれ以上赤い鳥はないだろうと言える南米のショウジョウヒワ Spinus cucullatus (現在の学名。過去の学名は Carduelis cucullata) 英名 Red Siskin (ショウジョウの意味は#アマサギの備考参照) で、
カナリアとかけあわせて赤いカナリアを作ろうと大量に輸入された (カナリアのコンテストに勝つために莫大な数の鳥が犠牲になった。人間の競争心の行くつく先が見えるような話である。生物に負担をかけることがわかりながらも競争心をくすぐられる状況ではこの事例を少し思い出して欲しい)。
しかし物事はそう単純ではなかった。ヨーロッパのアオカワラヒワ Chloris chloris 英名 European Greenfinch に時折見られるルチノー (lutino) と呼ばれる黄色い変異は1遺伝子によるもので、交配により比較的簡単に選抜することができ、20 年で完全に黄色いアオカワラヒワの品種を作ることができたとのことである。
羽毛に赤い色を与えるのは1遺伝子によるものでなく、複数の遺伝部位が関連したポリジーン (polygene) が関与していて交配でその性質を選抜することは容易でなく膨大な年月を要した。
また当時は赤い色は遺伝で決まると考えられ、遺伝的な選抜だけで赤い品種を作ることができると考えられていた。餌に何かを加える必要が明らかになったのは後の時代になってからであった。
この努力の犠牲となったのがショウジョウヒワである。原産地のベネズエラでは 1940 年代に法的に保護されるようになったが、法的に保護されたことで逆に希少性が高まり高値で取引されるようになった。
その後も密猟・密輸は続き、1975年7月には CITES (ワシントン条約: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約) 附属書 I に記載されるまでに個体数が減少した。
しかし輸入国であるオランダが条約に調印しなかったために輸入は続き、オランダが調印した 1987 年には野生のショウジョウヒワは数百羽まで減少したとのことである。法律があっても野鳥の保護に必ずしも結びつかない事例となっている。ショウジョウヒワは現在でも IUCN 3.1 EN種で、人為導入されたトリニダードでは絶滅。
これまでに知られていた生息地から 1000 km 離れたガイアナに数千羽の個体群が 2003 年に発見され、野生絶滅回避への希望がようやくつながった。スミソニアンの保全生物学研究所が "Red Siskin Initiative" を立ち上げ、野生絶滅回避に取り組んでいるとともに飼育下保全が進められている (最後の部分の現在の保全状況は wikipedia 英語版より)。
現代の知見では黄色や緑色の鳥は食物中のルテイン (lutein) を黄色の材料としていることがわかっている [McGraw et al. (2003) Lutein-based plumage coloration in songbirds is a consequence of selective pigment incorporation into feathers]。少数の種はゼアキサンチン (zeaxanthin) も用いている (ヒトの網膜黄斑部もこの色素)。
色素を与えても容易に羽毛に移行するわけではないことがわかる。
カナリアが赤くなる生化学的機構が判明したのは最近のことである。Lopes et al. (2016) Genetic Basis for Red Coloration in Birds
によれば、黄色の色素を赤に変換するそれまで知られていなかったケトラーゼ (ketolase) 酵素が必要であることがすでに 2000 年以前の過去研究で示されていたが、ショウジョウヒワとカナリアの全ゲノム解析を行い、2つの遺伝部位が導入されたことがわかった。その一つが CYP2J19 遺伝子でこれがケトラーゼである可能性が高い。この酵素は β-カロテンを赤い色素のカンタキサンチン (canthaxanthin) に変換することができる。
2つめの遺伝部位が表皮の分化に必要な因子で、これが羽毛に色素を与えているようである。
ケトラーゼは網膜でも発現し、網膜の赤の色素を作る証拠が得られたとのことである (#フクロウの備考も参照)。
なおカンタキサンチンの役割は鳥類でも調べられており、例えばフラミンゴがひなに与える血のように赤いフラミンゴミルクにも含まれて、敏感な生後早い時期に酸化ストレスを防ぐ効果があると考えられている (wikipedia 英語版より)。フラミンゴミルクの画像や解説は北條 (2023) Birder 37(5): 44-45 にある。
最後の部分を除き、上記の話は「赤いカナリアの探求 - 史上初の遺伝子操作秘話」(ティム バークヘッド Tim Birkhead 原著 The Red Canary: The Story of the First Genetically Engineered Animal 2004; 小山幸子訳 新思索社 2006) からの抜粋である。バークヘッドの著書については#エトロフウミスズメと#ハチクマの備考も参照。
本の表題だけを見ると野鳥関係者とは縁の遠い飼い鳥の話で、しかも遺伝子のような難しい話は読む気が起きないかも知れないが、抜粋した通り多岐の内容を含む物語でバークヘッドの著書としては事項羅列的でなくさまざまなストーリーが盛り込まれている
(ここでは紹介しなかったが、遺伝は優生学にかかわる話につながる。まさにナチス・ドイツの時代背景のもとでどのような物語に展開したかは読んでみてのお楽しみとしておこう。カナリアなので音声や音声学習の話題もある。鳥のことに関心があり、生物学の背景知識があるほどに読み応えのある本である)。
羽毛のカロテノイド着色に関わっている遺伝子が CYP2J19 だけでないことが明らかになった: Koch et al. (2025) Multiple Pathways to Red Carotenoid Coloration: House Finches (Haemorhous mexicanus) Do Not Use CYP2J19 to Produce Red Plumage (オープンアクセス)
メキシコマシコ Haemorhous mexicanus ではこれまでに同定されていた CYP2J19 (広く分布してよく知られている) BDH1L (網膜の赤い油滴が CYP2J19 なしでも形成されることが判明して同定された) をのいずれでもなかった。別の着色ルートがあるはずとのこと。
さらにもう1種の酵素 TTC39B が知られているとのこと。
それぞれの酵素がどのように作用して色彩が変わるかの図がある (fig. 1)。
オオアメリカムシクイ Icteria virens Yellow-breasted Chat では酵素を用いず食物中のカロテノイドをそのまま羽毛着色に用いているとのこと。色彩はキビタキやムギマキに似ているのでこれらの鳥も同様かも知れない。
酵素による色素変換は肝臓のミトコンドリア膜で盛んに行われる換羽時期に活発な発現が示されている。
fig. 2 に主なフィンチ類を中心とした系統樹と、どの鳥がどのカロテノイドを用いているか示されている。日本と共通種で目立つものではウソ (カロテノイド2種類)、イスカ (5種類)、ナキイスカ (3種類)、ベニヒワ (2種類)、アトリ (1種類)、東洋の種でも調べられているものがあってオオマシコ、ベニマシコともに4種類。使われるカロテノイドの構成は種や系統によってかなり違う。
ハト類は1種類 rhodoxanthin のみでこの色素は系統が進むとほぼ使われなくなっている。
McGraw (2006) "Mechanics of Carotenoid-Based Coloration." In Bird Coloration: Mechanisms and Measurements と
Toomey et al. (2022) "Methods for Extracting and Analyzing Carotenoids From Bird Feathers." (Abstract) In Methods in Enzymology のまとめを利用したとのこと。いずれもオープンアクセス版はなさそうなのでフィンチ類を中心に Koch et al. (2025) の fig. 2 を見るのがよさそう。
メキシコマシコではおそらく未発見の酵素が使われていて、異なる系統で異なる分子を用いて何度も着色が進化しているので異なった代謝経路が進化していても不思議でないとのこと。黄色のカロテノイド色素を赤く変色される酵素は何種類もあって、複数の代謝経路があることは冗長性にも役立ち、鳥類の多様性の理解にも役立つ可能性があるとのこと。
オオマシコやベニマシコを調べたのは誰か探してみると Stradi et al. (2001) Carotenoids in bird plumage: the complement of red pigments in the plumage of wild and captive bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) だった。博物館標本があるので東洋の鳥でも比較で調べられた次第。
Thomas et al. (2014) Non-destructive descriptions of carotenoids in feathers using Raman spectroscopy でもラマン分光で化学組成が非破壊的に調べられベニマシコも含まれている。色彩と系統樹の関係も示されている。これを見るとカラスが黒いのは「系統が古いため羽毛の色素着色のための酵素が比較的発達していない」と答えることもできそうに見える。
Johnson and Hill (2013) Is carotenoid ornamentation linked to the inner mitochondria membrane potential? A hypothesis for the maintenance of signal honesty
がミトコンドリア膜であることを予測した研究。ユビキノン (コエンザイム Q10) と着色のためのカロテノイドの立体化学がよく保存されていてもとは同じ経路から進化したものと予測できる。両者が酸化還元反応に関与してエネルギー需要が特に大きい時に膜を安定化させる。カロテノイド着色が "優良遺伝子" の指標となる生化学的基礎となるとのこと。
高音難聴のあるカナリアの品種の話題は#ヨタカ備考の [反響定位を行うアブラヨタカ] に収録。
オウム類・ペンギン類の色素や赤い目の鳥などカロテノイド着色以外の話題は #ヤマセミ備考 [派手な色彩の鳥はまずい?] を参照。
[おまけで鳥の芸や知能のこと]
なおこの訳者は「ヤマガラの芸 - 文化史と行動学の視点から」(法政大学出版局 1999) を著している。この本はどちらかと言えば「文化鳥類学」的なものと感じていたが、「赤いカナリアの探求」の内容、あとがきにあるバークヘッドとのつながりなどを読むと現代的な生物学のさまざまな分野にも造詣の深い方であることがわかる。
この「ヤマガラの芸」の中では (過去の事例も含めて) 中国における飼育野鳥の芸も詳しく触れられていて、(想像もしないような)さまざまな鳥に芸を教えることができる、あるいはできないことを教えてくれる (野鳥飼育の話なので野鳥の会など保護団体の方には好まれない話題かも知れないが、種による能力の違いなどはこのような事例を通じて明らかになるものもある)。
例えば「タカが車を引く芸」が過去にあったそうである (同書 p.148)。Birderで連載されている静岡県の掛川花鳥園のスタッフ北條 (2023) Birder 37(6): 44-45 によると猛禽類の中で芸ができるのはカラカラ類だけで、他のハヤブサ類、タカ、フクロウでは教えることができないとある。中国にはカラカラ類はいないし、いったいどんなタカが車を引く芸を行っていたのか、どうやって教えたのか想像もつかず興味あるところである。
なおカラカラは「世界一賢い猛禽類」として知られている。
Jonathan Meiburg による "A Most Remarkable Creature: The Hidden Life of the World's Smartest Birds of Prey" (2021) という本がある。
A Most Remarkable Creature - Extract によると例えばオオタカと鷹匠との関係との比較が述べられている。
フォークランドカラカラ Phalcoboenus australis 英名 Striated Caracara について、飼育下の個体で、仕事の関係で数年出会えなかった。数ヶ月以上会わない鳥は再度慣れさせる必要があるものだが、すぐに人を見分けて肩に乗ってきて鳴いたとのこと。まるで犬のようだった (他の鳥との比較の部分は多少誇張の感じの印象を受ける。渡り鳥が1シーズン後に渡ってきて前年のことをよく覚えているらしい行動を示すことを体感された方もあるのではと思う)。
北條 (2023) Birder 37(4): 46-47 によればケープペンギンが人の顔を覚えているのは1年ぐらいが限度とのこと。
フォークランドカラカラは遊び好きで人に構って欲しがるとのこと。色を見分けたり言葉と色を結びつけることもできて、形を区別することができるとのこと。
古いナショナル・ジオグラフィックの映像だが Flying Devils をご覧になられた方もあるだろう。
掛川花鳥園ではフォークランドカラカラが飼育されていてデモンストレーションを見ることができる。
フォークランドカラカラについては最近飼育下実験で大きな発見があった (続きは #ハヤブサ備考の [タカ目、ハヤブサ目、オウム目の脳の比較] 参照)。
上記のように行き過ぎた "飼い鳥文化" によって絶滅寸前まで追い込まれた種類があり、ご存じのようにオウム類密猟・密輸など深刻な問題が今も続いている。
一方で飼い鳥文化の極端な抑制によって失われたものもあるだろう。#クマタカ備考の [クマタカと鷹狩り] と合わせて見ていただきたい。
「赤いカナリアの探求」の訳者の小山氏も訳者あとがきで、日本の和鳥飼育文化にとって鳴き合わせなどもあった。(科学者に) さえずり学習が知られる 300 年も前からさえずりを学習する必要が知られていた。
「押し付けがましい」の「押し付け」は教師役の鳥がこのように呼ばれていたことが由来。
(以下原文通り)「昭和にはいり、野鳥の捕獲と飼育が許可なしには行えなくなってしまって以来、野鳥の飼育は一般には (表面的には) 行われなくなってしまった。長い歴史がありながらすたれてしまったことはとても残念なことだ。
野鳥の保護という問題を考えるといたし方のないこことは言え、すたれたことによって一つの文化もすたれてしまったからだ。
本書が飼育文化の歴史だけではなく小鳥類の飼育文化が持っている面白さ、その熱気、そしてその影響を伝える役割を果たしてくれることを期待している」と結んでいる。
細川 (2019) Birder 33(12): 66-67 が日本の飼い鳥文化の歴史の連載の最後に小見出し "鳥を飼うことは本当に「悪」か?" で論述されている。鳥類学に携わる者が鳥を飼うことをしつように「悪」と決めつける風潮が今も強い、とある。
前文で (こどもの) とりわけ鳥への関心の低下が著しいという。鳥類学を志す者も減少を続け (中略。日本の鳥類学者は絶滅危惧種?) 鳥を巡るこの 100 年の環境が招いた弊害でもある、と記されている。
もう昭和ではないのだから (中略) 日本における鳥研究の現場においても、鳥の飼育を全面否定しない方向にあらためて舵を切る必要があるのではないか、とある。
抜粋でニュアンスを伝えるのは限界もあり、意図を正しく伝えられていない可能性もあるのでいずれも原文をお読みいただきたいが、自分にも思い当たるところはたくさんある。
もともと生き物好き、アウトドア志向の方は鳥にも関心をお持ちの方も多いだろうが一般の人の関心は低い。鳥を飼わなくても野鳥を観察すればよい、というのが野鳥の会関係者の間ではよく言われる話だったが、結局飼育可能な鳥を飼う人も減って鳥との距離を遠ざけることにつながったかも知れない
(遠くなった分、光学機器や高価なカメラなどの市場には貢献し、何らかの経済効果があったかも知れないが、野鳥はカメラマンのものになってしまった...など考えたりもするが、もちろん飼育文化との因果関係まではわからない)。
もっともこれは鳥の世界だけに限らないかも知れない。
動物園のハチクマを観察している (いた) と言うと多分眉をひそめて聞く人も多いのではないかと思う (ケージに閉じ込めてかわいそうに、などはしばしば聞く)。乏しい経験ではあるが学術界でもあからさまに別世界をほのめかすコメントも受けた。
そのようなところで観察していると時には尋ねられることもあり [まるで専属の解説担当者のようなものである。飼育員以上に何でも答えられますから (笑)]、その機会に聞いてみるとハチクマの映像が TV で放映されてかつて人気だったことを誰一人知らないのである。動物番組はよく見られていると考えるのは我々の思い込みで、ハチクマの採食シーンはもはや記憶にすら残っていない過去の出来事のようである (とはいえ自分も TV で直接見たわけではないが)。
ハチクマの秘密とか渡り経路解明とか言ってもおそらくほとんどの人には意味が通じないだろうし (研究者にとってもマイナスだろう)、ここで述べている文章も一般の人にとっては何が書いてあるかさっぱりわからないだろう。
そのぐらい鳥の世界と人の世界の縁が遠くなってしまったらしい。飼い鳥云々というよりも都市に住む人が増えた結果かも知れないが、一昔前は街角でカナリアの声を聞いたり近所でハトを趣味とする人もあったような気がする。今では忌み嫌われるようになっている可能性がある。鳥インフルエンザで学校でも飼育が敬遠され、ますます縁が遠いものになってしまったのだろう。
カラスの本が売れるのは世間ではカラスぐらいしか知られていないことの反映かもしれない。
若い世代の動向も気になるので、広い分野の学生に鳥への関心度もアンケートさせてもらったりしたこともあるが、鳥のことに関心のありそうな人はほとんどない。様子見だけで結果も残していないがサンプルは4桁ある、多少なりとも鳥の名前を知っていそうな人はおそらく 1% よりずっと少なそうだった。
サンコウチョウの語源など詳しく述べていただいた学生の方があったが事情は知っているので統計的には例外とみなす (笑)。
近年の大学院生にもっと直接聞いても (それなりのサンプルはある) 鳥は全然知らない。昔はこんなことはなかったような気がする。東京大学の探鳥会 (鳥が専門のグループではない) にも参加させてもらったことがある。古くは鳥のことを知っているのはそこそこ常識で鳥を話題に普通に話ができたような気がする。
これほど世間で鳥のことが知られていないと、鳥類と哺乳類の進化云々など取り上げてもわかってくれる人はあまりいないのではないだろうかと想像する。カラス、スズメなど一部を除いて鳥との距離感は絶滅した恐竜とさほど違わないのではないかと思う。鳥類学者が無謀にも恐竜を語っても仲間内しか受けないかも知れない。
あるハイカーの方が書かれた記事に無愛想な野鳥カメラマン集団が不気味であるとの記述もあった。これまでは野鳥観察とか撮影は理解できる活動と好意的に受け入れられていた面もあったかも知れないが、鳥のことがあまりに知られなくなると単に邪魔で不気味な集団となってしまうかも知れない。
このような視線は時に感じることがある。
大阪の野鳥ドーム計画反対などは小さな自然保護や意識改革にはつながったかも知れないが、結果的に人と鳥の距離を徹底的に遠ざけて歪んだ構図を作り出した可能性もあるのではないか。野鳥ドームに限らず、"自然保護" にそぐわない意見を示した鳥学者が非難される場面もあったと記憶している。
映画 WATARIDORI (2003 年公開) でも飼育鳥を使っていることによる反発もあった。もう 21 世紀なのにこれほど反発があるとは予想もしなかった [自分は気にせず楽しませてもらったが。人の声による解説はない映画で、"やらせ" 感のある部分や過剰メッセージと感じた部分は多少あったが自然保護メッセージも多数含まれている。黙殺するのは実にもったいない。
海外バーダーの間では大変好評であることを知っていたがなぜか日本では反対があった。今から振り返るとこの時代の日本野鳥の会 (のすべてではないだろうが) は進化の袋小路に入りかけていたかも知れない]。
自然保護行政 (もっとも野鳥飼育は禁止だが海外から輸入したものは可能である理由は自分には未だにわからない。問題があまりなくなったように見えるのはこの 15-20 年ぐらいは鳥インフルエンザのためとも言える)
や自然保護団体の活動と鳥を知らない人が増えたように感じることとの因果関係まではもちろんわからないが、鳥に関心のある我々にとって、細川氏の指摘されるこの 100 年の環境を振り返りつつ考えなければいけない課題だろう。
日本野鳥の会の現会長 (2024 時点) の上田恵介氏も、中西悟堂も最初から「野の鳥は野に」(しばしば中心原理のように扱われる) ではなかったのだろうなど定着した既成概念を解きほぐすことも進められているように思えるが (例えば「野鳥」2024年1・2月号 pp. 22-23)、なかなか難しい舵取り役かも知れない。
日本野鳥の会だけが関わったものではないが、他団体の事情は知らないし、何と言っても鳥の話でありメンバーの一人として自省すべき点も込めて挙げさせていただいた。
-
オガサワラマシコ
- 第8版学名:Carpodacus ferreorostris (カルポダクス フェッレオローストリス) 鉄の嘴の果実をついばむ鳥 (IOC も同じ)
- 第7版学名:Chaunoproctus ferreorostris (カウノプロークトゥス フェッレオローストリス) 鉄の嘴の広い腰の鳥
- 第8版属名:carpodacus (合) karpos 果実 dakos ついばむ (Gk)
- 第7版属名:chaunoproctus (合) khaunoproktos 裾の広い(半ズボンなど) < khaunos 緩い proktos 尻、臀部 Gk オガサワラマシコの柔らかくふさふさした羽毛に覆われた腰から (The Key to Scientific Names)
- 種小名:ferreorostris (adj) 鉄の嘴の (ferreus (adj) 鉄の rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Bonin Grosbeak
- 備考:
carpodacus は#ベニマシコ参照。
chaunoproctus 外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は o が長母音となっているので同様の扱いが考えられる (カウノプロークトゥス)。
ferreorostris は -ros- は長母音 (cf. rostrum ローストルム) でアクセントがあると考えられる (フェッレオローストリス)。
長音でなくてもアクセントはこの音節にある。
絶滅種。
記載時学名 Coccothraustes ferreo-rostris Vigors, 1829 (原記載) 基産地 no locality [= Bonin Islands] (Avibase による)。こちらはごく単純な記載。
一足遅かった Fringilla Papa Kittlitz, 1830 (記載)。
行動はこちらに詳しく述べられている。
papa は父島を指す可能性があることを Birder 編集部 (1995) Birder 9(7): 28 の記事が示唆しているが The Key to Scientific Names は別の解釈で、Er haelt sich gern versteckt, ist aeusserst phlegmatischer Natur の原記載から phlegmatic (英語では "物ぐさな" の他に "冷静な" の意味もある) と色彩を組み合わせて神父のように見えると解釈している。phlegm は中世に物ぐさな原因と考えられた粘液とのこと。
人が近づいても他の鳥のようにあまり逃げようとしなかったのだろう。
ドイツ語の語義を見ると Phlegma が対応する名詞で、phlegmatisch は粘液質の、冷淡な、無情ななどの訳語が出ている。
Jobling がこの解釈に至ったのは "Pape" of d'Aubenton の用例のある ゴシキノジコ Passerina ciris Painted Bunting の鮮やかな色、"Vultur papa" of Edwards 1737 現在は トキイロコンドル Sarcoramphus papa King Vulture (和名の通り) を意識したものと考えられる。いずれも色彩がポイントになっている。
Kittlitz の種小名をもとにした Papa 属も Reichenbach (1850) が設けたとのこと。Reichenbach がトキに Nipponia 属を提唱する3年前の話。オガサワラマシコには種小名をつけず1単語で呼んだらしい。Gray (1855) が図版をオガサワラマシコと同定したらしい (The Key to Scientific Names)。
Birder 9(7): 28 には最大の島で父島を指すと一般に考えられている示唆が記されているが、原文は p. 232
Die drei groesseren Inseln, welche das eigentliche Boninsima bilden (eine aehnliche Gruppe von drei kleineren liegt in geringer Entfernung davon, ward aber von uns nicht betreten) licgen zwischen dem 27. und 28. Grade nuerdl. ..
との記述があり3つの大きめの島が元来の Boninsima を構成し、似た小島のグループが少し離れたところにあるが我々は訪れていないとのこと。後者は北緯 27-28° とのことなのでこちらが聟島列島のことではないだろうか。Kittlitz は父島も母島も訪れていたように読める。
さらにこの Birder 記事は森岡 (1993) を引用して「...人から隠れているようであった。しかし人擦れはしていなかった」と紹介されている。誤訳感があり原文を参照すると so wenig scheu, dass man, um einen zu schiessen, gewoehnlich eine grosse Strecke weit zurueckgehen muss, wenn man ihn nicht ganz zerschmettern will, gewoehnlich fliegt er in solchen Faellen vom Boden auf einen niedrigen Zweig oder umgefallenen Baumstamm,
von dem man ihn vergebens durch leises Winken zu verscheuchen sucht, er bewest Kopf und Schwanz regelmaessig nach beiden Seiten, bleibt aber ruhig sitzen, wird er indess endlich doch gescheucht, so entfernt er sich gewoehnlich sehr weit.
の部分に該当するだろうか。
試みに訳してみると (この文章は関係代名詞などが複数使われて構造がわかりにくく、日本語で言えば悪文と言える気がする。もっとも理系の観点から見れば悪文としか思えないものが国語の入試問題に出るのと同じようなものか。一読して誰にでも意味がわかるような文章はそもそも学力判定に使えないわけだ。何か矛盾している気がする):
「人をあまりに恐れないので、人が撃とうとして、あまりに粉々にしないように十分な距離を引き下がるような場合でも、地面から近くの低い枝や倒れた木の幹に移動する程度で、軽く (手を振るなど驚かせる) 合図をしてみても頭と尾を両側に振る程度でその場に穏やかにとどまったままで無駄だった。それでも最終的には脅かすことができて相当遠くへ飛んで行くのが常だった」
このような行動が種小名に用いられた papa の由来と考える方がもっともらしい気がする。
あまりにも簡単に採集できるので拍子抜けしているように読める。実は目につくものを全部採集したが粉々にしてしまったものなどもあって状態のよいもののみを標本に残したのかも知れない。
Kittlitz のこの報告は小笠原の鳥の基本文献と言えるだろうが全訳はなされていないのだろうか。
Tietze et al. (2013) Complete phylogeny and historical biogeography of true rosefinches (Aves: Carpodacus) の分子系統研究によって他の Carpodacus 属の中でも早く分岐していたことがわかった。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で Carpodacus 属に含められた。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ (#ベニマシコの備考参照)。
地上を走り、樹上の高所に行くことはほとんどない (コンサイス鳥名辞典)。この部分は Kittlitz (1830) では Nur selten sah ich ihn hoch auf den Baeumen, am meisten auf der Erde laufend に相当する。ich が主語なので Kittlitz 自身が観察した記述になる。
沿岸からの動きなど他の行動記述を見てもハギマシコの行動に似た印象を受ける。同じく絶滅した#オガサワラガビチョウで考察のように地上捕食者のいなかった島でほぼ完全に地上性に移行したのかも知れない (絶滅要因も同様?) と感じて調べてみた。
ハギマシコの繁殖生態を見ても樹上造巣性ではなく岩の隙間に木の枝、苔、枯れ草などを組み合わせた皿状の巣を作り (wikipedia 日本語版より。ハイガシラハギマシコと同種時代の記述かも知れない) とあるので地上性と呼べそう。
ハイガシラハギマシコ Leucosticte tephrocotis Gray-crowned Rosy-Finch は北米の種で習性はこちらの方がよく知られているが、wikipedia 英語版によればやはり地上造巣性 (on the ground or on a cliff) とある。
{Leucosticte + 古く分岐した Carpodacus} のグループ (これらが系統をなすわけではないがマシコ類の中で古く分岐したもの) は地上造巣性に移行しやすいのかも知れない。
Tietze et al. (2013) のクレードに含まれる種はアカマシコ (巣は低木で地上 2-2.5m とのこと。wikipedia ロシア語版)、シュイロマシコ Carpodacus sipahi Scarlet Finch (ヒマラヤでは留鳥。インド北部から東南アジアにも分布。繁殖習性はあまり知られていないとのこと)。
オガサワラマシコはもとは渡り鳥だったはずで同じクレードから小笠原以外にも定着していてもおかしくないが、ほぼ完全に地上性に移行し他所では記載される前に絶滅してしまったのかも。
-
アカマシコ
-
オオマシコ
- 学名:Carpodacus roseus (カルポダクス ロセウス) バラ色の果実をついばむ鳥
- 属名:carpodacus (合) karpos 果実 dakos ついばむ (Gk)
- 種小名:roseus (adj) バラ色の (rosa (f) バラ)
- 英名:Rosefinch, IOC: Pallas's Rosefinch (プロイセンの生物学者 Peter Simon Pallas に由来)
- 備考:
carpodacus は#ベニマシコ参照。
roseus は短母音のみで冒頭にアクセント (ロセウス)。
Carpodacus 属のタイプ種。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは portenkoi (ロシアの鳥類学者 Leonid Aleksandrovich Portenko に由来) とされる。
オオマシコの地鳴きは特徴があり (少し調子の合っていない声とも言われる)、特にソノグラムで見ると特徴的なパターンを示す。しかしオオマシコがどのような声でさえずるのか、Brazil (2009) "Birds of East Asia" には repeated whistled call notes と記載があるが、未だに公開音源がない。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) ではさえずりは地鳴きと同じような高い whistles を素早く繰り返し、木のてっぺんなど高いところにとまってさえずるとあるが実際の音声はよくわからない。
エゾビタキ同様 (#エゾビタキの備考参照)、東シベリアで繁殖する鳥特有の難しさがあるのだろう。
分類上の位置づけについては #ベニマシコの備考参照。
日向野 (2008) Birder 23(6): 87 にトリカブトの種子を食べるオオマシコ (長野県南佐久郡) が紹介されている。東洋特産種なのであまり調べられていないだろうが、チャバライカル (#ヤマガラ備考の [ヤマガラの植物毒耐性] 参照) のような毒耐性があるのかも知れない。
Nechaev (1977, 2024 再掲) The Pallas's rosefinch Carpodacus roseus on Sakhalin (pp. 4499-4509) にサハリンで繁殖するオオマシコの記述がある。
図鑑ではサハリンが越冬地表記になっているものがあるがこれは正確ではなさそう。Gizenko (1955) はサハリンで普通に繁殖する鳥としたがこれは間違いでベニマシコをオオマシコと間違ったらしい。
サハリン北部で繁殖する可能性を示唆する情報はある程度あったが Nechaev のグループが調査して散発的に少数が繁殖していることを確認したもの。
さえずりの文字表記もあって "chi-chi-chiii, chi-chi-chii", "chi-chi, chi-chi, chii, chii, chii, chii" の2つの替え歌があって、前者を 10 回まで繰り返すと後者が現れるが 4 回を超えないとのこと。
-
ギンザンマシコ
- 学名:Pinicola enucleator (ピニコラ エーヌクレアートル) 松の木に住み種子を取り出す鳥
- 属名:pinicola (合) 松の木に住む鳥 (pinus (f) 松の木 colo (tr) 住む)
- 種小名:enucleator (合) 種子を取り出すもの (enucleo (tr) 種子を取り除く -tor (接尾辞) 行為者)
- 英名:Pine Grosbeak
- 備考:
pinicola は -ni- にアクセントでピニコラ。
enucleator は直接見つけられなかったが、nucleatus は a が長母音。接頭語 e- も長母音なので "
エーヌクレアートル" の発音と思われる。
英語に近い単語があるので英語読みの方が使われているかも知れない (英語でも a にアクセントだが2重母音になる)。
ギンザンマシコの別名に松雀がある (コンサイス鳥名事典)。中国語でもこの名称。これは習性を示したものか、あるいは学名や英名などとも対応している。
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 67 p. 66 によればヨーロッパでは白夜が続く夏の夜によく鳴くので "夜まわり" のあだ名があるとのこと。
北半球高緯度に広く分布し、8亜種が認められている (IOC)。日本で記録されるものは sakhalinensis (サハリンの) 亜種ギンザンマシコ と kamtschatkensis (カムチャツカの) コバシギンザンマシコ とされる。
分子系統分類ではウソのグループで、一番最初に分岐した種にあたり単形属となる。
かつては Pinicola 属に他種が含まれていて、ベニマユマシコ 現在の学名で Carpodacus subhimachalus Crimson-browed Finch があった。
当時の学名では Pinicola subhimachalus でドイツ語名 Rhododendrongimpel (Rhododendron = シャクナゲ属、Gimpel = ウソ) 対するギンザンマシコは Hakengimpel (Haken = 鈎) で分布地域はまったく違うが、同属であったためしばしば対比して取り上げられていた。"ギンザン" の "ギン" にあるいは例えば古い時代のドイツ語が関係していないかと気になった次第。証拠は見つけられていない。
ドイツ語名に -gimpel に形容語が付くものが結構あって、ハギマシコ属は Schneegimpel (雪のウソ)。Rhodospiza 属は Weissfluegelgimpel (翼の白いウソ) など。英語では何でも finch にまとめてしまったが、ドイツ語ではだいぶ違って "ウソ" の前を色彩などでしばしば形容している。
ギンザンマシコのリトアニア語名に "雪の" が残っているのでかつては別名があったのでは。
ギンザンマシコの和名由来説に関連して少し調べてみたものだが、山階鳥類研究所の標本データベースを見ると、サハリンの標本にはカラフトギンザンマシコのラベルがあって、ギンザンマシコの名称は現在の日本国内のものを指していたと考えられる。
この標本データベースを見ると大雪山の標本が非常に多く、当時有名な産地であっただろうことが想像できる。大雪山の名称は比較的新しく、書物に記載されているものでは 1899 年が最初とのこと (wikipedia 日本語版より)。特に名前のなかった時代に大雪山を指して "白銀の山" の意味だったのではないだろうか。今ではあまり使わないかも知れないが「白銀の世界」のような用語もある。もしそうであればリトアニア語名の発想に近いものかも。
この部分は大橋 (2024) Birder 38(7): 50-51 から調べてみたもの。大橋氏の調査では 1885 年の標本からすでにギンザンマシコの名称で呼ばれていたことがわかる (自分は写真などを見ることができないので、採集時点でラベルが付けられたものか判断できない)。銀山の地名の方が遅いので地名由来ではないだろうとのこと。
また 1830 年の「禽譜」「観文禽譜」(堀田正敦) にはぎんすましこ、ぎんざんましこの名前がすでに登場するとのこと。
-
イスカ
- 学名:Loxia curvirostra (ロクシア クルウィローストゥラ) 曲がって交叉した嘴の鳥
- 属名:loxia (合) 交叉した嘴の鳥 (loxos 斜めの Gk、-ia 質を表す)
- 種小名:curvirostra (adj) 曲がった嘴の (curvus (adj) 曲がった rostrum (n) 嘴)
- 英名:Common Crossbill
- 備考:
loxia は起源となるギリシャ語 loxos は短母音のみで -ia も長母音がないためすべて短母音と思われる (ロクシア)。
curvirostra は curvus は短母音のみ。rostrum は冒頭が長母音でここにアクセントがある。"クルウィローストゥラ" と考えられる。
Loxia 属は Linnaeus (1758) がこの属名の意味で導入。なお Cuvier (1800) は別途シメの属として Loxia を導入したが今は使われていない。
Arnaiz-Villena et al. (2001) Phylogeography of crossbills, bullfinches, grosbeaks, and rosefinches の研究で Loxia 属は旧 Carduelis 属に含まれることがわかり、
学名の先取権の原理からすべてを Loxia 属とすることも可能であったが、非常に多くの種の学名を変える必要があるため、旧 Carduelis 属を (単系統になるように) 分割することで現在に至っている (wikipedia 英語版より)。
crossbill の英名は非常にもっともらしいが、OED によると初めて登場するのは 1672 年 Willughby の Ornithology とのこと。1713 年 Derham は The Loxia, or Cross-Bill, ... との記述でこの時代から Loxia のラテン名も使われていたこともわかる。
loxias の方の用例も Phillips's New World of Word (1706) に登場し、Loxias, the Cross-beak or Shell-apple のように Cross-beak や Shell-apple の英名もあったことがわかる。
crosbeak / cross-beak の用例も古くあり 1688 年の Holme の記載や、有名な White (1770) が学名を添えてこの名称を使っているように、過去には cross-beak の方もよく使われていたのかも知れない。20 世紀に入って cross-beak の用例が少なくなった模様。
shell-apple はズアオアトリまたはイスカを指して使われ、イスカでの用例は 1666 年と crossbill よりむしろ早い。次第に認知度が高まって 18 世紀後半から 19 世紀初頭には crossbill の方が多用されるようになったらしい。
イスカは北半球に広く分布する。食物量の変化によって放浪的な (nomadic) 生活様式をとっていることはよく知られている。日本では一般に冬鳥であることが多いが、季節を問わず繁殖可能で繁殖例も散発的に知られている。放浪的な生活様式のため個体数の年変動が大きい。
「鳥のおもしろ私生活」(ピッキオ 1997) によれば 1963 年長野県大峰山がイスカの日本初の繁殖記録。同書に5-6月を除いてほぼ一年中繁殖するとあるが、後述の滋賀県の例を考えると一年中繁殖すると言ってよさそうである。
世界的には 19 亜種が認められている (IOC) が、分類には問題点が多い。Questiau et al. (1999) Phylogeographical evidence of gene flow among Common Crossbill (Loxia curvirostra, Aves, Fringillidae) populations at the continental level
によれば亜種間の遺伝的差異が小さく、亜種間で広範な遺伝子浸透が起こっている (いた) ことを示唆する。これは放浪的な生活様式の種 (ベニヒワ、コベニヒワなど) にしばしば見られる現象である。
イスカはその特徴的なくちばしの形状の個体による違いを通じて特定の食物に適応しているが、この形質と地鳴き (contact call) の間に関係があることが知られている。
Snowberg and Benkman (2007) The role of marker traits in the assortative mating within red crossbills, Loxia curvirostra complex の研究にあるようにつがい相手を選ぶ際に音声を手がかりにしていることが知られている。
Smith et al. (2012) Assortative flocking in crossbills and implications for ecological speciation では同じタイプの音声により誘引されることが示されており、同じタイプの音声を持つ群れが形成されやすいことが示されている。
これらの観点から、通常の亜種分類ではなく音声タイプによる分類を行うことが欧米では普通になっている。ただしこれらの研究はいずれも北米やヨーロッパの個体群を対象としたものであって、日本を含む東アジアの情報はほとんどないため、研究者もこの地域でのイスカの音声記録を待ち望んでいるとのことである。
実際に従来の亜種からではなく音声タイプから独立種として認められた種類がある: スコットランドイスカ Loxia scotica (英名 Scottish Crossbill) 音声タイプ Eurasian type 3C に対応、
ハシブトイスカ Loxia pytyopsittacus (英名 Parrot Crossbill) Eurasian type 2D に対応、
カッシアイスカ Loxia sinesciuris (英名 Cassia Crossbill - これについては#ナキイスカの備考も参照) North American type 9 に対応。
これらの種類は通常の「亜種から種に昇格」でないため、データベースなどでも取り扱いが難しく、適切な扱いがなされていないこともあり注意が必要である。
スコットランドイスカは種と認める場合には英国唯一の固有種とのこと。今のところ世界の主要リストでは独立種扱い。
Red Crossbill call types act like species [Sibley Guides (2010)、北米の分類について]。Red Crossbill Types in Colorado: Their Ecology, Evolution, and Distribution [Benkman (2007) コロラドのイスカ]。
eBird の北米のイスカ解説 [eBird (2007) 音声もあり]。Loxia curvirostra) Call-types of New York: Their Taxonomy, Flight Call Vocalizations, and Ecology [Young (2011) ニューヨークのイスカ、音声データあり]。
Crossbill Call Types in the Western Palearctic - A Birder's Perspective [Rochefort and Martin (2021) 主としてヨーロッパで、ユーラシア東部も追記された。ソノグラムとともに音声タイプによる分布も記載されている] なども世界の動向として参考になるだろう。
Mandelbaum (2023) によるこんな記事もある。Type 12, the "Old Northeastern" Red Crossbill
つまり北米で新亜種 (相当) の音声を持つ個体群 (Northeastern red crossbill) Type 12 が発見されたとのこと。イスカは録音しないことには話が始まらないとのことである。
上記が論文として発表された: Centanni et al. (2024)
Is resource specialization the key?: some, but not all Red Crossbill call types associate with their key conifers in a diverse North American landscape
音声データが集積されて音声タイプと好みの樹種との関係がある程度見えてきた (種分化メカニズムにもなる)。
Young et al. (2024) Detection and identification of a cryptic red crossbill call type in northeastern North America
公開データベース (当然ながら国際的なものでここでは Macaulay Library を用いている) に多くの音声情報が登録されるようになって統計的解析も行いやすくなった (日本ではいつになるだろう?)。
Type 12 はおそらく過去に記述された亜種 neogaea に対応するのでは、とのこと。音声から亜種の有効性が検討される可能性がありそう。
従来型の亜種分類では日本で記録されるものは亜種 japonica および亜種不明となっている。
亜種 japonica は記載時学名 Loxia curvirostra japonica Ridgway, 1884 (原記載 基産地 middle or main island of Japan [=Honshu] (Avibase による)。
Swinhoe (1870) は Loxia albiventris (参考) としたがこの名称はすでに用いられていた (当時はさまざまな種が Loxia 属に含まれていたので全く関係ない種類の Loxia albiventris Hermann, 1804 と名前が衝突してしまった)。この文献で改めて有効な学名が提唱されたもの。
なお Swinhoe (1870) の記載は有効にならなかったので問題にならないが、基産地は日本ではなく near Pekin と中国だった。Swinhoe の学名が無効にならなければ基産地も亜種小名も日本と関係がなかったことになる。
極東地域でも音声タイプ (ヨーロッパでの記載に基づく) による分類に基づく記録がなされることもあり、今後の検討課題であろう。
上記 Rochefort and Martin (2021) では N4, N5, N8, N9, (N19), E3 (東日本で繁殖する主なタイプとされる), E4 の分布に日本が含まれている。日本のイスカにも多くの音声タイプ (もしかすると新しい分類群になるかも?) が含まれていることがわかる。録音をお持ちの方は確認いただきたい。もし音声による分類が取り入れられれば、メボソムシクイ上種のように音声が識別の決め手のグループになるかも知れない。
Do crossbill calls change over time? (Ralph Martin 2023) が過去 58 年の録音を調べ、イスカの声が時間とともに変わって行っている可能性が提唱されている。New unified list of birds - Avilist (BirdForum 2025.5) の投稿で知った。
Scottish Crossbill lumped by Collins (BirdForum 2025.5) によればスコットランドイスカと同一の声がパリでも記録されたとのこと。Collins の図鑑では独立種とせずイスカと同種扱いとのこと (この場合英国の固有種はなくなる)。
蛯名・三上 (2012) 青森県下北地方におけるイスカ Loxia curvirostra の換羽と体色変化 の論文にも世界的な分類動向が触れられている (#ナキイスカの備考も参照)。
ダーウインフィンチでは適応による嘴の形の違いが種分化につながっていることが示唆されてきたが、嘴の形と音声に関連があり、音声による認識が種分化につながる可能性が示された: Podos and Schroeder (2024) Ecological speciation in Darwin's finches: Ghosts of finches future。
(一般向け英文解説)。
イスカの声に馴染みの薄い方はぜひ覚えておいていただきたい。「鳥のおもしろ私生活」(ピッキオ 1997)でも色彩とともに、日本の自然ではないようだと記述されている。意外なところで出会うこともあり(多くのバーダーが声を逃している)、冬季滞在以外に繁殖の可能性のある個体を探るにも役立つであろう。
自身も京都/滋賀比叡山での初夏の音声記録の経験がある。滋賀県では探鳥会の最中に繁殖中のイスカが偶然発見されている (日本野鳥の会滋賀)。あらゆる面で録音・録画の意義の高い種類である。
[イスカの渡り経路解明は可能か?]
近年の追跡技術の進歩により多くの鳥の渡り経路が明らかになってきているが、イスカのような種類の渡り経路を同様の方法で知ることは不可能に近い。ジオロケータを用いる方法では個体の再回収が必要であるが、標識されたイスカが同じ場所に戻ってくることがほとんど期待できないためである。
最近、類似の渡り特性を示す種の渡り経路解明に光明が差すようになってきている。
太陽電池付き発信器により北米のキビタイシメ Hesperiphona vespertina 英名 Evening Grosbeak の追跡が可能となりつつあるそうである。
Keeping Track of These Boreal Nomads Is Notoriously Difficult (Audubon の記事 2021)。
この記事が書かれたころは ICARUS Initiative という宇宙 (国際宇宙ステーション) からの移動性動物の追跡に期待が持たれていた。
これはドイツとロシアの協力によるプロジェクトであったが、地上の問題はどのように影響を与えたのであろうか。Belyaev et al. (2022) Results of Russian Program of Animal Migration Research Using Icarus Scientific Equipment Aboard the ISS RS を見る限りでは運用が行われているようだが...
[イスカ類の嘴の曲がりは遺伝するか]
Edelaar et al. (2005) No Support for a Genetic Basis of Mandible Crossing Direction in Crossbills (Loxia spp.)
によれば少なくとも1遺伝子で決まっている結論は得られなかった。この時点では環境要因で偶然決まる可能性も提案されていたが遺伝と無関係ともちょっと考えにくい。
生物全般では方向の決まっていない曲がりは遺伝によるものでないとの一般的知見がある [Palmer (2004) Symmetry Breaking and the Evolution of Development]。
[イスカ類と針葉樹の共進化]
Parchman et al. (2007) Coevolution between Hispaniolan crossbills and pine: does more time allow for greater phenotypic escalation at lower latitude? 針葉樹の側も皮を厚くしている。
Benkman et al. (2010) Patterns of coevolution in the adaptive radiation of crossbills。
リスが競争相手となっている。
[イスカの漢字]
日本語で 易+鳥 でイスカを表す漢字は 目+犬+鳥 でモズを表す漢字の誤記から始まったとのこと (wiktionary)。
イスカの語源として最有力とされる古語の "いすかし" に用いる漢字 行+艮 は本来の意味で (中国語でも廃れている) 従わない、阻む、言い争うなどの意味。現代では同じ漢字はとても、よい、などの意味で用いられる。中国語では1音節を嫌うため特に意味がなくこの文字を添えることもあり人名などでも同様とのこと (wiktionary)。"いすかし" には本来の語義が残っていることになる。
-
ナキイスカ
- 学名:Loxia leucoptera (ロクシア レウコプテラ) 翼に白いところのある交叉した嘴の鳥
- 属名:loxia (合) 交叉した嘴の鳥 (loxos 斜めの Gk、-ia 質を表す)
- 種小名:leucoptera (合) 翼に白いところのある (leuko- (接頭辞) 白い pteron 翼 Gk)
- 英名:Two-barred Crossbill
- 備考:
loxia は#イスカ参照。
leucoptera 外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみのため長母音は現れないと考えられる。-co- がアクセント音節と考えられる (レウコプテラ)。
翼全体が白いというより白い模様に着目した学名 (#オオルリの備考参照)。
同じ種小名を持つハジロオオバン Fulica leucoptera White-winged Coot も白い部分はごく一部なので、ここでは "翼に白いところのある" と訳すことにした。
一方 leucopterus の種小名を持つ#ハジロクロハラアジサシは夏羽の翼を指すと思われ意味が少し異なっている。
大橋 (2021) Birder 35(10): 52-53 によれば "嶋イスカ" と表記されていたものが "鳴イスカ" と誤記されたものが和名の由来と考えられるとのこと。
山階鳥類研究所標本データベースでは、YIO-53105 (長野 1911) のように当時付けられたかどうかわからないラベルにシマイスカとあるものをナキと訂正したものがある。
YIO-53106 (長野 1911) でも同様で早い方のラベルはシマイスカとなっていた。
この当時の表記を見ると、Loxia elegans Heuglin, 1879 (参考) 基産地 Amur を区別して、Loxia leucoptera elegans と亜種扱いとしていたことがわかる。
Loxia leucoptera Gmelin, 1789 の 原記載 は基産地 Hudson Bay and New York なので北米のもの。Amur で記録された elegans をその亜種とするならば、基亜種の方により遠くを意味する "シマ" を与え、近くの elegans には "ナキイスカ" を与えたと考えられる。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) によればナキイスカの名称はイスカの異名として知られていたので、別亜種に名前を割り当てる際には elegans の意味を重視してより美しく感じられるナキイスカを与えたのではないか。
"ナキイスカ" の由来は大橋氏推定の誤記かも知れないし、イスカの特徴的な声を考えると (飼育下で鳴いたかどうかはわからないが) 鳴き声に注目されていても不思議でない感じがする。#イスカの備考にあるようにイスカに音声タイプが存在するため、通常と異なる声のイスカ (現代のナキイスカと同じとは限らない) に別の名前を付けたものかも知れない。あるいはもっと単純に鳴かないものをイスカ、鳴くものをナキイスカと呼んでいたのかも知れない。
Hartert (1910-1922) p. 124 では一応別亜種としているが、Noch fragliche Form. とありまだ疑わしい型とのこと。その後シノニム化されたものだろう。
比較的新しい話なので 20 世紀初頭ではまだ有効な亜種と考えられ両者の名称が用いられていたが、シノニム化されたころには "シマイスカ" と "ナキイスカ" の命名経緯が失われており、日本で記録されていた "elegans" の方に合わせてナキイスカと統一されたと考えると解釈しやすい。
日本で記録される亜種は bifasciata (bi- 2つの fasciatus バンドの) でユーラシアの個体群とされるが。もう1亜種 (基亜種) は北米の個体群とされる。
Questiau et al. (1999) (#イスカの備考参照) も1個体を解析しており、ナキイスカとイスカの間の差異はイスカの間で遺伝的距離が最も離れたものと違わないとのことである。
Bjorklund et al. (2013) The genetic structure of crossbills suggests rapid diversification with little niche conservatism の研究によればイスカのグループは生殖隔離が起きていても遺伝的には差があまりないなどことや、遺伝的にみた系統とくちばしの形の関連が薄く、高い頻度で種分化を起こしつつもそれぞれの寿命は短いことが示唆されている。
この論文では Loxia bifasciata を独立種として扱い、シベリアカラマツ (Larix sibirica, Siberian larch) に特化したグループとみなしている [出典は Cramp and Perrins (1994) The birds of the Western Palearctic, Vol. VIII - Crows to Finches であろうか]。
かつてナキイスカの亜種とされていて特定の食物に特化したものが独立種ヒスパニオライスカ Loxia megaplaga (英名 Hispaniolan Crossbill) となっていて、この場合は地理的分布も考慮されているが、ナキイスカの亜種 bifasciata についても将来的に分離される可能性があるのかも知れない。
Porter and Benkman (2019) Character displacement of a learned behaviour and its implications for ecological speciation 北米のイスカ類の研究で、音声学習が種分化に関与している?
イスカ類はダーウィンフィンチなどと同様にくちばしの形による種分化の最中であって、どれを「種」と認めるか非常に難しいグループなのであろう。ダーウィンフィンチも「何を見れば全種見たことになるのか」など熱烈なバーダーの間で議論のある問題である。
ダーウィンフィンチの例ではダーウィンフィンチのゲノム解読が広げる種の概念 (ナショナルジオグラフィック) の日本語記事も参考になりそうである。
ダーウィンフィンチにあまり馴染みのない方は「フィンチの嘴 - ガラパゴスで起きている種の変貌」(ジョナサン・ワイナー著、樋口広芳・黒沢令子訳 ハヤカワ・ノンフィクション文庫 2001) が非常に面白い物語として、また種とは何か、どのように分化するかを把握する上で参考になるだろう。
イスカ類でもカッシアイスカ Loxia sinesciuris は種ではない(Ornithologist's Blog) のような考察もある。
ロシアの イスカ - 我が国のタイガの"オウム"
の記事によればヤクーチヤで -57 ℃ でもさえずっていたとのこと。また営巣場所への執着はなく、ある年は多数繁殖していた場所でも翌年はまったくいないこともある。抄訳:
イスカの珍しい点としては繁殖習性、もっと正確に言えばその時期が非常に
早いことで、針葉樹の実のなりかたにかかっています。そうして実の豊富な
年には早くも3月に繁殖を始めます。冬に私たちの他のすべての鳥たちが短い
コミュニケーションの音声だけを出している時に繁殖期の歌が聞けるのは
イスカだけです。文献によれば1月の終わりのヤクーチヤで鳥類学者が
夜明けの薄明を突き通る、よく響く夢中になったナキイスカの歌声を聞く
ことができた記録があります。厳寒の -57 ℃ で!
私たちの大多数の鳥が年から年へと子孫を残すためにまったく同じ地域に戻って
来るのに、イスカには営巣場所への執着がないようです。イスカにとっては営巣場所
の選択は単に針葉樹の実のなりかた次第です。ある年は森でお互いにすぐ近く
で繁殖しているイスカでうるさいぐらいなのに、翌年はそこで一羽も見られない
ことはよくあることです。
さまざまな点で変わり者の鳥、それがイスカです。
-
ウソ
- 学名:Pyrrhula pyrrhula (ピュルルラ ピュルルラ) ウソ (虫を食べる鳥)
- 属名:pyrrhula purrhoulas (Gk) アリストテレスの記述した虫を食べる鳥で、ヨーロッパコマドリまたはウソと解釈されている (The Key to Scientific Names)
- 種小名:pyrrhula (トートニム)
- 英名:Bullfinch, IOC: Eurasian Bullfinch
- 備考:
pyrrhula はすべて短母音で冒頭にアクセント (ピュルルラ)。
10 亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは griseiventris (griseum 灰色 venter, ventris 腹) 亜種ウソ、rosacea (バラ色の) アカウソ、cassinii (アメリカの鳥類学者 John Cassin に由来) ベニバラウソ、cineracea (灰色の) ハイイロウソ、及び亜種不明とされる。
英名の起源は bull (雄牛) のような finch で、頭と首の形から。1560 年代から用いられている (Etymology Online)。フランス語も同様で bouvreuil だが他言語はかなり異なる。
ドイツ語は Gimpel で Guempel が由来。中世の高地ドイツ語の gumpen (飛び跳ねる) が語源。なお Gimpel にはドイツ語俗語で「ばか」の意味もある。ロシア名は以下で述べる。
ロシア名同様なのはリトアニア語、ウクライナ語など。"冬" に関連した名前はクロアチア語、セルビア語など。デンマーク語などの dompap は低地ドイツ語の Dompap (司教堂の祭祀) 由来とのこと。
イタリア語の ciuffolotto は ciufolare (笛を吹く) から。これは和名にも通じる。
英語・フランス語が若干例外的なよう。
[分類と亜種の問題]
Brazil (2009) "Birds of East Asia" では世界のウソの中で、griseiventris (亜種ウソ) Grey-bellied Bullfinch と cineracea (亜種ハイイロウソ) Baikal Bullfinch は独立種に値する可能性に言及している。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では、これら2つを独立種としているロシア名でウスリーウソ (ussurijskij snegir') とハイイロウソ (seryj snegir') に対応する名前になっている (なおウソはロシア語で snegir' スニェギーリ。sneg スニェーク が雪なので容易に想像できる名前だろう)。
この図鑑では亜種 rosacea (亜種アカウソ) をこの種 Pyrrhula griseiventris (ロシア名"ウスリーウソ") の亜種としておりシベリアはこの亜種の分布域としているので、ややこしいがこの図鑑でのこの種は和名で亜種アカウソの大陸での記述として見ていただいてよいだろう。
"ウスリーウソ"には色彩に複数の morph があり、胸から横腹までが薄い赤色のものから、灰色っぽく頬までほぼ同色ものまであると記載されている。
ロシアでは基亜種の pyrrhula が太平洋岸 (オホーツク海) まで分布していると考えているようである。Dement'ev and Gladkov (1954) でも同様の分布になっている (シベリア東部で基亜種が北方型にあたる。ツグミとハチジョウツグミの繁殖分布のような位置関係)。
そのためこの図鑑では主に基亜種と (この図鑑の扱いで) 上記2種の識別に重点が置かれることになっている。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) の分布では pyrrhula は東はヤクーチアや南はバイカルまでとなっていて認識が違うようである。
日本で記録される亜種の検討の際も注意が必要かも知れない。
ウソの wikipedia ロシア語版を見ると基亜種はもと東ヨーロッパの亜種だったものが近年分布を広げてヨーロッパ全体になっているとのこと。2005 年からはウラルの個体群が北ヨーロッパやシベリアに分布を広げ、西ヨーロッパでは聞き慣れない声から trumpeting northern bullfinch と呼ばれるそうである。
Trumpeting Northern Bullfinches during the winter of 2004/2005
によれば 2004/2005 年に西ヨーロッパに irruption があったらしい。
Fox (2006) Invasion of Bullfinches Pyrrhula pyrrhula in western Europe in 2004:
a mix of local, 'trumpeting' birds and
others of unknown origin: Capsule In east Jutland,
Denmark, the invasion included individuals of a small-sized
local race P. p. coccinea, as well as numbers
of two larger forms, which consistently gave either
'normal' or 'trumpeting' calls on release and whose
origins are unknown も参照。
東にも分布を広げている可能性もあるかも知れない
日本でアカウソの写真の濃色のものはこの図鑑の図版だけ見ると基亜種の方に近い色彩に見えるが、図版の限界なのかそれとも? 田仲他 (2014) Birder 28(1): 22 に亜種アカウソ (ノルウェー) との写真が出ていて、あるいは基亜種も含めてアカウソと呼ばれているのかも知れない (ヨーロッバアカウソの亜種名も使われるらしい - 出典不明)。
Ryabitsev によれば基亜種は翼帯が (大雨覆先端) が白色か灰色っぽい白で広め、ウスリーやバイカルのは細めで灰色の点が異なるとなどとしている。
Ryabitsev の上記2"種"は wikipedia ロシア語版では亜種扱いだが別ページとなっていて種と亜種の中間の扱いのようである。"ハイイロウソ"の wikipedia ロシア語版では音声も聞けるが聞き慣れたウソの声とはかなり異なる。
しかし wikipedia ロシア語ウソの亜種にはリストされていない。rosacea (和名の亜種アカウソ) は wikipedia ロシア語版ウソ類ページはどこにも出てこない。
Rosy-cheeked Bullfinch には Pyrrhula griseiventris rosacea の名称で出ている。この英名はロシア以外のページでは見当たらなかった。
ロシアでも一般的には亜種名までは関心がなく、rosacea は"ウスリーウソ"と扱われ、日本でアカウソと呼ばれるものを指して日本の学名で亜種ウソに相当するものを用い、識別対象は日本のウソと日本のアカウソではなく、アカウソと基亜種になっている。
Bullfinches in the ROK: From Pink to Grey and Much Between! (Birds Korea 2012) にも興味深い記事があり、
Pennington and Meek (2006) を元にした分布図が Fig. 2 に出ている。
基亜種がシベリア東部まで広がっている点は Ryabitsev の認識と同じだが、何と Pennington and Meek (2006) は亜種 rosacea を認めていないそうである。
その場合は griseiventris のシノニムとなるようである。
著者 Nial Moores も日本とロシアの研究者に問い合わせたが分類認識が異なることがわかったとのこと。
Ivushkin (2015) Genus Pyrrhula Brisson, 1760: composition, distribution and ecology features の大論文がある (全文ロシア語)。
Fig. 7 に Pyrrhula griseiventris griseiventris と Pyrrhula griseiventris rosacea の繁殖地と越冬地が示されているが、分類体系が異なる点を除けば我々の認識に近い (ただし rosacea の分布域をサハリンと記述しているものもある)。
Fig. 6 に Fig. 7 の分類群以外で我々に関係の深い地域の亜種分布がある (ベニバラウソの越冬分布は北海道までとなっている)。
Pyrrhula griseiventris rosacea の中には下面が赤で頬も赤いものがあり、特に韓国や日本でしばしばカムチャツカ亜種のベニバラウソ (ウソ中最大亜種) とされるが、少し小型で背が明るいバラ色でこれは rosacea の特徴であるとの記述がある (p. 1716)。
この記載は日本中央以南のことを指していると考えられるが、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023) ではベニバラウソは広範に記録が認められいる。Ivushkin (2015) の指摘もあり、過去にベニバラウソと判定されたものが確実にそう言えるか再検討も必要に思える。
ハイイロウソの wikipedia ロシア語版では亜種の記載はないが、シベリア南部の山地北部と極東中央部の個体群はより大型でウソの中でも最大の大きさに達するとある。東シベリアでは基亜種とハイイロウソは留鳥または漂行性である。一部は完全に渡りをする。餌が豊富な年は冬にもとどまり大きな集団を作る (基亜種は500羽にも達する)。
Ivushkin (2015) によればハイイロウソはサハリン北部でもおそらく繁殖する (Nechaev 1991)。地鳴きは他の種類と異なっているとのこと (上記 wikipedia ロシア語参照)。
Durnev and Ivushkin (1991) に同所的に繁殖する場所での基亜種との生殖隔離に関する研究があるとのこと。ハイイロウソは確かに独立種に値するのかも知れない。
#イスカ同様に外見だけでなく音声による分類も行われており、"trumpet" 型でも type 1, 1a, 2 などの分類がある。原典は Nicola (1959) のようだが見つけられなかった。
従来の分類では Pyrrhula pyrrhula pyrrhula とならざるを得ないが、ヨーロッパとロシアで声が異なり、さらに亜種を付けるような感覚になっている。音声を聞いてみても多分ウソと思わないだろう音声だった。
身近な鳥ではあるが、ウソの分類は思った以上に複雑なのかも知れない。
世界の主要リストでは同様の扱いのものはないようであるが、ウソの亜種を複数のグループに分けることは行われていて、基亜種の pyrrhula グループと griseiventris グループに大別される。
前者には europaea, pileata, rossikowi, paphlagoniae,
iberiae, caspica
の主にユーラシア中西部の亜種が含まれ、
後者には griseiventris, rosacea, cineracea, cassinii
のユーラシア東部の亜種が含まれ、英語では Baikal 型とも総称される。Howard and Moore 4th edition (vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2) では cineracea を分離して3グループとしている。
斉藤・先崎 (2018) 北海道天売島におけるウソの1亜種 Pyrrhula pyrrhula cineracea の日本初記録。
ウソ属の色彩の総説論文がある: Ivushkin (2021) Genus Pyrrhula Brisson, 1760: functional significance, features of formation of structure and color of plumage
中身は読んでいないが論文の存在だけ紹介しておく。全文ロシア語だが興味ある方ならば翻訳ソフトでかなり読めるのではないかと思う。
さらに後続論文もある:
Ivushkin (2024) Genus Pyrrhula Brisson, 1760: features of the formation and change of age-specific plumages。
[ウソの名前とうそ替え]
中西悟堂「定本・野鳥記」5 にまとまった記事がある (初出年代記載なし。新たに書き下されたものかも)。面白い点をいくつか紹介しておく。
p. 132 によればオスを古来アカウソまたはテリウソ、メスをクロウソと呼んで別種と思っている人も少なくなかったとのこと。この点は #キジバト備考 [キジバトの名称考察] で示されているかつてのドバトにも似ていて、色彩の異なるものは別種と考えられがちだったことがわかる。現代的な種の概念はやはり西洋の学問が入ってからだろうか。
アカウソの名称は現在は亜種名に用いられているが色彩を指すものか亜種名を指すものか紛らわしい要因ともなっているのだろう。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) p. 98 にも同じことが記されており、「なお、樺太、沿海州などで繁殖するものは雄の桃色が胸腹にまで達しており、アカウソと呼ばれ、越冬のために北海道、本州山地にくるので、「あかうそ」という日本産の雄の呼称はまぎらわしい」とある。亜種アカウソの意味と日本産の雄の「あかうそ」の両方の用例がある。亜種アカウソと限定しない限り古くからの用法で用いても間違いとは言えず、厳密に分類用語であることを示すには必ず "亜種" を付けるか学名を用いるのがよい、となるのだろう。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 135 によればウソ鳥は蜂を食う鳥と信じられていた (このような話があると「蜂を食べるからハチクマ」説も怪しくなるわけだ)。蜂が近くに来るとウソの鳴き声を真似ると蜂は嫌って飛び去ると信じられていたとのこと。
また中西氏が書かれていた当時も桜の害鳥として景観を台無しにするとウソ征伐論も出ていたらしく、そこまで被害を与えるほどは食べないことを愛鳥家側が示す必要があった。
今でも桜、紅葉、松を植えるのがよいと言われるように、人々の関心事は景観 (そして観光資源) であって生態学的な意味の環境の視点の方が劣勢であることは中西氏の時代からあまり変わっていないのだろう。
池があるのに水鳥がいないのは寂しい、何か放せないかなどの話にもつながってくる。
やはり鳥は景観の一部であって "モノ" として見ている印象を否めない (#カワウ備考 [ウの増加と生態系への影響] 参照)。
pp. 135-136 ではウソの語源に一説としてウシの訛化説が述べられている。うそ替えの神事が始まったのは太宰府天満宮で 986 年のことで、天満宮と牛は格別の関係があるとのこと (wikipedia を確認しておくと御神牛と呼ばれるとのこと)。中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 107 (1940 年初出) でもすでにいろいろな説がある中に紹介されていた。
「鳥の手帖」にはこの説は含まれておらず異説と言えるだろう。ウソの名前が声由来とするのは後付けの可能性もあるかも。「鳥の手帖」では「名語記」(1275) で音声由来とする解釈が紹介されている。
[ウソの漢字の意味]
ウソを表す漢字は難しいのでここでは直接表示していない。週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972) 76 VII (藤堂) によれば 学 (旧字体) + 鳥 の文字で、中国では古くは "学鳩" と呼んでいたとのこと。鳩のように太った鳥の意味。
学の方は中古は hok と読まれていたので、鳴き声を表す擬音ではないかとのこと。
感じ方に個人差があるだろうことを念頭に置いてもウソの地鳴きを hok と聞くのは難しい印象を受けたが、少し調べてみると中国では日本と同種のウソは珍しく、Macaulay Library にも地鳴きの録音がわずかにあった程度。
一方 Pyrrhula 属の他種はもう少し記録があり、タカサゴウソ Pyrrhula erythaca Grey-headed Bullfinch 例えば Gray-headed Bullfinch (Peter Boesman 2019) や
チャイロウソ Pyrrhula nipalensis Brown Bullfinch 例えば Brown Bullfinch (Ian Davies 2016) は候補となるかも知れない。
漢字語義解釈には日本産でない種類を念頭に置いた方がよいかも知れない。日本のウソならば口笛のように聞かれ、中国で普通のウソ類は "学" と聞かれた (?)。
-
シメ
- 学名:Coccothraustes coccothraustes (コッコトゥラウステース コッコトゥラウステース) 穀物を砕く鳥
- 属名:coccothraustes (合) 穀物を砕くもの (kokkos 穀物 thraustis 砕くもの Gk)
- 種小名:coccothraustes (トートニム)
- 英名:Hawfinch
- 備考:
coccothraustes 外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は -tes が長母音となっている。ラテン語でもギリシャ語由来の場合は長音となるらしい (#ミソサザイ参照)。-us- がアクセント音節と考えられるので "コッコトゥラウステース" としておく。
単形属。5亜種あり (IOC)。
シメそのものは Loxia coccothraustes Linnaeus, 1758 として記載され、イスカと同属となっていた。
Brisson (1760) が Coccothraustes 属を設け、Coccothraustes vulgaris (普通のシメ) と名付けた Le Gros-bec。
これは種小名から属名に昇格する場合にタイプ種に相当するものを指す当時の用法と想像できる (#ノスリの備考参照)。
この学名はかなり長く使われていたが、種小名から属名に昇格する場合に種小名を変える必要がなくなり、かつ Brisson (1760) は二名法に則っていないため無効となって現在の学名になったものだろう。トートニムになっているとはいえ、和名に比べて学名があまりに長くてあまり使いたくない種類の一つ。
見ての通り Loxia 属に先取権があるので分子系統分類などの結果で属をまとめる必要が生じた場合に全部を Loxia 属にまとめるか分割するかの問題が発生する。さすがにイスカにまとめるのは受け入れがたいので属を細かく分けて対応しているということだろう (#イスカの備考参照)。
同様の事態がヘラシギに与えられた Eurynorhynchus 属で発生しており (#キョウジョシギの備考参照) 現行分類のいくつかは小型シギ類に "ヘラシギ属" 相当の属名を与えている。これは "イスカ属シメ" のような扱いに相当する。
さらに IOC ではハシマガリチドリに与えられた Anarhynchus 属を広い分類に採用しており (#シロチドリの備考参照)、分子系統解析の進展によって従来予想もされなかった属が適用されるケースが生じている (この例では "ハシマガリチドリ属シロチドリ" のような扱いになる)。
Loxia 属と Coccothraustes 属の統合が将来行われることはないかも知れないが。
日本で記録されるものは japonicus (日本の) 亜種シメ、coccothraustes シベリアシメ、及び亜種不明とされる。
亜種 japonicus の記載時学名は Coccothraustes vulgaris japonicus Temminck & Schlegel, 1848 (原記載。図版) による。大陸とは隔離分布になっているが外見の違いはわずかのよう。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)にて亜種分類の変更に伴って coccothraustes シベリアシメ は削除とのこと。
-
コイカル
- 学名:Eophona migratoria (エオーポーナ ミグラートーリア) 渡りをする曙の女神の声
- 属名:eophona (合) 曙の女神の声 (eos (f) 曙の女神、phoni 声 Gk)
- 種小名:migratoria (合) 移住する (migratorius 移住性の -a 女性形の形容詞)
- 英名:Yellow-billed Grosbeak, IOC: Chinese Grosbeak
- 備考:
eophona は#イカル参照。
migratoria は最初の a と o が長母音 (ミグラートーリア)。
かつては Coccothraustes 属に含められていた。Black-tailed Hawfinch の英名もあった。
Loxia melanura Gmelin, 1789 (記載。参考) が基産地中国で (Latham による Grey-necked Gros-beak とある) この英名の由来のよう。
Loxia melanura Muller, 1776 (参考) の用例がすでにあったため命名時点で本来無効な学名だった。
Penard (1919) がこの点に気づき Eophona migratoria pulla Penard, 1919 (参考) と改名していた。つまり melanura = pulla となった。pulla は黒っぽいの意味。
The Key to Scientific Names にもこの記述 (Eophona の項目) があり、さらに Hartert (1921) は melanura と sowerbyi はおそらくシノニムの関係にあると考えており、いずれ置き換わるだろうとしていた。Vaurie (1956) も同意とのことだったが、後述の Dement'ev and Gladkov (1954) の考えは異なっていたよう。
Eophona は Gould (1851) が導入した属だったがタイプ種は後に Gray (1855) が Loxia melanura Gmelin, 1789 (無効名であることはまだ知られていない時代) と与えた。つまり Eophona 属のタイプ種はコイカルの方。
現在の記載時学名 Eophona melanura migratoria Hartert, 1903 (原記載) 基産地 Sidemi River, southern Ussuri (ウスリー地方) は意外に新しく、
Eophona melanura の学名が有効と考えられて長く使われていたことをうかがわせる。
この記載では日本 (陸前) でも時折見られるとある。
Loxia melanura Gmelin, 1789 の方がずっと早く命名されていたが、無効学名だったために Hartert (1903) の種小名が使われるようになった。pulla への改名は 1919 年と遅かったために他亜種のシノニムとなれば現れなくなる。
特定の国名に依存する名称を避ける立場では英名ですでにある名前では Yellow-billed Grosbeak が使われるが、イカルの嘴は黄色くないのかと言えばそんなことはないのであまり適切な名称ではない。この英名が付けられた時代は欧米にはコイカルの方がむしろ知られていてイカルはあまり眼中になかったのかも。
イカルの方は Masked を使えば問題ない。
ドイツ語名でもこの点は気にしているようでコイカルを Weisshand-Kernbeisser (手の白い種を噛むもの)、イカルを Maskenkernbeisser としている。フランス語名も種小名のラテン語由来の名称になっている。ロシア語名ではイカルを "頭の黒いシメ" でコイカルにはさらに "小さい" を付けていて日本語と同様の関係。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 migratoria とされる。
現在使われるもう1亜種も同じ学名の種の亜種と記載された: Eophona melanura sowerbyi Riley, 1915 (原記載) 基産地 Chang Kow Hsien, Hupeh。
Dement'ev and Gladkov (1954) ではこの亜種を基亜種に含め "ウスリーの" を冠した名称としていた。
一方で南部に分布する中国の亜種 pulla Penard, 1919 (上記) と harterti La Touche, 1923 [記載時学名 Eophona migratoria harterti La Touche, 1923 (参考 基産地 Milati, S. E. Yunnan, China)] を認めていた。
現代との見解の違いは亜種の包含関係だけで、sowerbyi を基亜種に含めれば Dement'ev and Gladkov (1954) のようになる。現代の標準的扱いではこの亜種を独立させ、中国での記載を sowerbyi に含めたものと考えられる。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the yellow-billed grosbeak Eophona migratoria (pp. 1387-1409)
ロシア沿海地方での繁殖生態の論文。少数は越冬する。
-
イカル
- 学名:Eophona personata (エオーポーナ ペルソーナータ) 仮面をつけた曙の女神の声
- 属名:eophona (合) 曙の女神の声 (eos (f) 曙の女神、phoni 声 Gk)
- 種小名:personata (adj) 仮面をつけた (persona (f) 仮面 -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:Japanese Grosbeak
- 備考:
eophona はラテン語では eos は o が長母音 (ギリシャ語では e- が長母音の語形もある) phone はウグイスの種小名と同様のギリシャ語で o が長母音。"エオーポーナ" でよいと思われる。造語の際に短縮されるならば "エオポーナ"。ただし後の事例も参照。
Eos 属も最近まで使われ ヤクシャインコ Eos histrio Red-and-blue Lory などの学名があったが Working Group Avian Checklists, version 0.03 以降は Trichoglossus histrio となっているので属統合でおそらく変わる見込み。
種小名や亜種小名に eos が用いられているものは例がある。
Eo- の属名は他にオーストラリアのヒガシキバラヒタキ Eopsaltria australis Yellow Robin などに使われ、意味はイカル同様に "暁にさえずる者"。
この属名は英語発音を聞くことができて、英語なので p は発音されていないが eo- はいずれも長音で発音 (イーオゥ) されていた。イカルの属名も英語式のこの発音が現実的かも知れない。英語式発音はおそらく読み方がわからないのでアルファベット e, o をそれぞれ読んだものではないかと想像できる。
eop- で始まる単語に特有の読み方などはない感じがする。
我々も eo- を短く読むよりも原語ギリシャ語語源を重視して "エーオーポーナ" と読む方がよいかも知れない。
personata は o と最初の a が長母音で後者にアクセントがある (ペルソーナータ)。
記載時学名 Coccothraustes personatus Temminck & Schlegel, 1845 (原記載。図版)。当時のフランス語名 Le Gros-bec a masque (仮面をかぶったシメ)。
Temminck & Schlegel (1845) がイカルの種小名に japonicus などを用いなかった理由は当時は同属のシメに japonicus を用いたため。ヨーロッパのものとほとんど違いのないシメに用いるよりイカルに用いた方が適切だったかも知れないが、イカルの外見があまりに特徴的だったので適切な種小名が使えたのだろう。
この学名やフランス語名に対応した Masked Hawfinch の英名もあった。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 personata 及び亜種不明とされる。IOC のもう1亜種は magnirostris (magnus 大きな -rostris 嘴の) で満州から中国東北部に分布するとされる。
Eophona 属はイカルとコイカルの2種からなる。
第7版配列ではシメやコイカル、イカルがアトリ科の中で最後になっているが、この部分は第8版配列で大きく変わった。アトリ科では Fringilla 属が古く分岐した系統 (この点は第7版も同じ) だが新しい解析によって Coccothraustes 属や Eophona 属がそれに次いで古く分岐した系統となった。
例えば Sun et al. (2016) The complete mitochondrial genome sequence of Eophona migratoria (Passeriformes Fringillidae) を参照。
#ツリスガラ備考の [スズメ小目 Passerida の系統分類] アトリ科以降に系統順がある。この分類ではコイカル、イカルはシメ族に含まれる。アトリ科の中で比較的古い系統と考えておいてよさそう。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ツメナガホオジロ科 CALCARIIDAE ▽
-
ツメナガホオジロ
- 学名:Calcarius lapponicus (カルカーリウス ラッポニクス) ラップランドのケヅメをつけたような鳥
- 属名:calcarius (adj) ケヅメをつけたような (calcar (n) ケヅメ -ius (接尾辞) に属する)
- 種小名:lapponicus (adj) ラップランド地方の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Lapland Bunting, IOC: Lapland Longspur
- 備考:
calcarius は別語義の同じ綴りの単語があり、その場合は2番めの a が長母音でアクセントがある (カルカーリウス)。
calcar は短母音のみだが属格には長母音が現れるので同じ発音でよさそうに見える。
lapponicus は短母音のみ。アクセント位置は -po- と考えられる (ラッポニクス)。
北半球高緯度で繁殖する。5亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは coloratus (色のついた) とされる。
-
ユキホオジロ
△ スズメ目 PASSERIFORMES アメリカムシクイ科 PARULIDAE ▽
-
キヅタアメリカムシクイ
- 学名:Setophaga coronata (セートパガ コローナータ) 冠のあるガを食べる鳥
- 属名:setophaga (合) ガを食べる (ses, setos ガ -phagos を食べる Gk)
- 種小名:coronata (adj) 冠のある (corona (f) 冠 -tus (接尾辞) 〜が備わっている)
- 英名:2種を分離しない考えでは Yellow-rumped Warbler。IOC: Myrtle Warbler (myrtle はツルテンニンソウ、別名 periwinkle)。
- 備考:
setophaga は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は ses, setos は長母音で始まる。同様に長母音とし、規則からは -to- にアクセントがあると考えられる (セートパガ)。
coronata は2つ目の o と1つめの a が長母音でこの a にアクセントがある。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。2亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは基亜種 coronata とされる。
かつては4亜種を含む種であったが IOC 3.1 以降 Setophaga auduboni が分離された。IOC ではこの種に Audubon's Warbler の英名を与えている。Yellow-rumped Warbler の英名は分離しない場合の名称に対応する。Working Group Avian Checklists, version 0.01 では未検討の模様。
池 (2011) Birder 25(3): 45 キヅタアメリカムシクイの日本初記録の記事がある。論文は池・池長 (2010) 神奈川県鎌倉市で観察されたキヅタアメリカムシクイ Dendroica coronata の日本初記録
-
ウィルソンアメリカムシクイ (第8版で検討種)
- 学名:Cardellina pusilla (カルデルリーナ プスィルラ) ごく小さいゴシキヒワのような鳥
- 属名:cardellina (合) ゴシキヒワのような鳥 (karderina ゴシキヒワ Gk)
- 種小名:pusilla (adj) ごく小さい (pusillus)
- 英名:Wilson's Warbler (アメリカ鳥類学者 Alexander Wilson による)
- 備考:
cardellina は -ina 冒頭に長母音が生じると考えられアクセントもそこにあると考えられる (カルデルリーナ)。
pusilla は短母音のみで -sil- がアクセント音節 (プスィルラ)。
かつては Wilsonia 属だったが移動された。Wilsonia 属 (分離する場合はウィルソンアメリカムシクイを含む3種) のタイプ種はクロズキンアメリカムシクイ 現在通常に使われる学名で Setophaga citrina Hooded Warbler で、この種は分子系統解析の結果 Setophaga に近縁とされ多くのリストで統合された。
Setophaga (1827) の方が Wilsonia (1838) より古いために統合する場合は前者に先取権がある (wikipedia 英語版より)。
なお Setophaga 属のキヅタアメリカムシクイは Wilsonia 属から移動されたものではない。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動 (同定根拠、類似種との検討がない)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
3亜種あり (IOC)。亜種は不明。
文屋 (1992) Birder 6(2): 18 に1991年10月の舳倉島での記録の記事がある。
BIRDCHAT という北米を中心としたメーリングリストに "The Warbler Code" (ムシクイ法典?)
があった (2017)
The Warbler Code 一部超意訳で紹介:
1) ムシクイは聞くものであって見るものではない。たまに微かに見えるかも
知れないが見るのは大抵他人である。
2) ムシクイを追跡する場合は足元に注意せよ。さもなければ落ちて渡りの間中
病院通いが続くことになるかも。
5)「すぐそこ」というのは方向を意味するわけではない。
8) ムシクイが地鳴きでわかる者は金の値打ちあり。くっついて行きなさい。
within 18 inches というのはどうも法律用語らしく、カーブから18インチ
以内に停車すること、のように使われている模様。
△ スズメ目 PASSERIFORMES ホオジロ科 EMBERIZIDAE ▽
-
レンジャクノジコ (第8版で検討種)
- 学名:Emberiza lathami (エムベーリザ ラタミ) レイサムのホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:lathami (属) latham の (英国鳥類学者 John Latham)
- 英名:Crested Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
lathami は短母音のみで読まれるならば冒頭アクセント (ラタミ)。"
タ" を伸ばしてアクセントを置くよりは原音に近いと思われる。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で検討種に移動 (識別点の記載がない)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でも同じ。
英名は Emberiza cristata Vigors, 1831 (参考) 由来と考えられる。多くの言語名がこの名称に基づいている。
Emberiza cristata Swainson, 1823 (参考) の用例 (ブラジルの種) がすでにあって無効となった。
ネットの名称を探すと和名にもカンムリノジコの別名があったらしい。現在の名前も "ノジコ" を用いる点が日本らしい (ノジコの名称は古くからあって飼い鳥としてホオジロより知名度が高かったのかも)。
他にもキンノジコ、ゴシキノジコ、ソライロノジコやムラサキノジコのような和名もあり、色彩の鮮やかなものに "ノジコ" の名称が好まれたのかも知れない。もしかするとレンジャクノジコも輸入されていた?
レンジャクバト、レンジャクモドキなどの和名もあるので冠羽を表したものだろう。
記載時学名 Emberiza lathami Gray, 1831 (原記載) 基産地 China and India; type from Canton, Kwangtung, fide Ticehurst, 1932, Bull. Brit. Ornith. Club, 53, p. 16 (Avibase による)。
当時の英名 Goura Bunting。Goura Finch (Latham) の名称を引用している。種小名の lathami はこれが由来と考えられる。
goura は Goura を指すものであればカンムリバト属。この名称は現地名とのこと (The Key to Scientific Names)。
Emberiza cristata Vigors, 1831 の学名が用いられていたらしいことは現在は通常シノニムとされる亜種名に subcristata が存在することからもわかる [記載時 Emberiza subcristata Sykes, 1832 (参考)]。
さらに別学名があって Emberiza erythropterus Jardine & Selby, 1833 (参考) これは "翼に赤いところがあるホオジロ" の意味。
erythropterus が男性形に見えて Emberiza の性に合わないように見えるが合成語のため形容詞として扱われず性変化しないものと考えられる。
この種の場合は Gray (1831) の記載の方が早かったのであまり問題にならなかったかも知れないが、Emberiza erythroptera Temminck の用例 (参考。ケープホオジロ 現在の学名で Emberiza capensis のシノニム) があって、
erythroptera と erythropterus を同一とみなすかおそらく議論があったものと想像できる (#ノスリの備考参照)。
Emberiza erythroptera Kuhl, 1820 (参考) の用例もあってケープホオジロに対するこの学名を誰が最初に用いたかはあまりはっきりしない。
Emberiza erythroptera Boie, 1832 (参考) では (誰が最初かはともかく) Linnaeus の Emberiza capensis var. β に名称を与えたものらしい。
レンジャクノジコについては The Key to Scientific Names によれば Latham の "Black and Orange Finch" を指して melanicterus の種小名 (melas, melanos 黒 ikteros 黄疸色の黄色 Gk) もあったとのこと。
どうも Fringilla melanictera Gmelin, 1789 (参考 1, 2) が由来らしい。
この記載が早いとされなかった理由は? (カードには Hume がコメントしているとある)。
もしかすると Tanagra melanictera Guldenstadt, 1775 (参考。現在の アオボウシフウキンチョウ Pipraeidea melanonota) があって同属とされ、Fringilla melanictera が無効となった時期があったのかも。色彩は似た点もあり、記載者の混同があったのかも知れない (いずれも未確認)。
単形種。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
一部の分類で Melophus 属が採用されていたが Emberiza 属が大きいが単系統となるため Emberiza 属にまとめられつつあるよう。
Melophus 属は上記 Emberiza erythroptera の学名を用いて Swainson (1837) が定義したもの。melas, melanos 黒 lophos 冠 (Gk) (The Key to Scientific Names)。
ホオジロ類とは思えない色彩で、日比 (2001) Birder 15(3): 66-68 で系統的に関係のない種類が赤と黒の同じような配色を持つことに注目されている。
レンジャクノジコの分布域を考えると、オオバンケン Centropus sinensis Greater Coucal やヒゴロモ Oriolus traillii Maroon Oriole の配色に擬態しているのかもと感じた
(#カッコウの備考 [カッコウ類の植物毒耐性?] と #コウライウグイスの備考 [コウライウグイス類に毒耐性があるか?] 参照)。これらの鳥が有毒かどうかはまだ証拠がなさそう。
日比 (2001) で他に挙げられている種類は南米のセアカタイランチョウ Lessonia rufa Patagonian Negrito と、
ニュージーランドのセアカホオダレムクドリ Philesturnus carunculatus Southern Saddleback (別種に分けられた
ホクトウセアカホオダレムクドリ Philesturnus rufusater Northern Saddleback もほぼ同じような色彩)。
なお "ムクドリ" の名前はついているがホオダレムクドリ科で、ムクドリ科とは系統がかなり異なる。
-
キアオジ
- 学名:Emberiza citrinella (エムベーリザ キトゥリネルラ) 少しシトロン黄色のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:citrinella (adj) 少しシトロン黄色の (citreus (adj) シトロンの -ella (指小辞) 小さい)
- 英名:Yellowhammer
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
citrinella は citreus, -ella いずれも短母音のみ。-nel- がアクセント母音と考えられる (キトゥリネルラ)。
3亜種あり。日本で記録されたものは erythrogenys (eruthros 赤い genus, genuos 頬 Gk) とされる。
ヨーロッパでは普通種で、ベートーベンの有名な交響曲第5番「運命」冒頭の4音の動機はキアオジの歌に影響を受けたとの説がある。いやズアオホオジロ Emberiza hortulana 英名 Ortolan Bunting の方ではないか、との議論も展開されている [参考資料 (2022)]。
Beethoven und die Goldammer (2021) にもキアオジとベートーベンの関係が書かれていて、キアオジのさえずりをドイツ語では "wie wie hab ich dich lieeeb" と聞きなすそうである (ドイツ語を勉強したけど覚えているのはほとんどない、という人でも意味はわかると思う)。
独断と偏見の識別講座 II 第76回 Emberiza V <キアオジ、シラガホオジロ> (波多野邦彦 2019) にある英語聞きなし "little bit of bread and NO cheese!" よりもそれらしいかも知れない。
波多野氏の「シシシシシシシシ、シーッ」の方が「運命の動機」に近いかも知れない。
キアオジとシラガホオジロの系統的類似性や遺伝的関係、雑種写真については#シラガホオジロの備考参照。
ヨーロッパではズアオホオジロを秋の渡りで捕まえて食用にする習慣があるそうで、フランスで禁止されたのが 1999 年、しかしその後も法律の効果は今ひとつで 1997-2007 年で 30% も減少したとのこと。
2007 年にようやくフランス政府が EU の保護政策を受け入れたものの、それでも状況にあまり変わりなく 2016 年に再度声明を繰り返すことになった。フランスでは珍味として有名とのこと (wikipedia 英語版)。
ズアオホオジロがフランスのレストランのメニューから消える見込み (BirdLife の記事 2017)。
シマアオジだけの問題でないようである。
-
シラガホオジロ
- 学名:Emberiza leucocephalos (エムベーリザ レウコケパロス) 白い頭のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:leucocephalos (合) 白い頭の (leuko- (接頭辞) 白い kephali 頭 Gk)
- 英名:Pine Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
leucocephalos は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみで -ce- がアクセント音節と考えられる (レウコケパロス)。
和名は学名由来と想像される。ロシア語名も同様。
英名は Emberiza pithyornis Pallas, 1773 由来で pithyornis = pityornis の意味、pitus, pituos (松) + ornis (鳥) (Gk) (The Key to Scientific Names)。
おそらくこの学名がそれなりに使われていたが、Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771 (原記載) の方が早く学名が変わった。Gmelin (1771) の記載地はロシアのアストラハン (カスピ海北西)。
ロシア語名も Gmelin (1771) の学名に対応していることから比較的早い時期に学名が置き換わったようだが英名は (おそらく分布域から遠くあまり注目を受けることがなく) そのまま残ったよう。
Dement'ev and Gladkov (1954) によれば主にシベリアでは普通種。サハリンや千島も繁殖地に含まれている。
2亜種あり。日本で記録されるものは基亜種 leucocephalos とされる。
離島で観察される方にはお馴染みすぎる鳥かも知れないが、一般にはそう出会える種類ではない。
広島県芸北地区のごく限られた場所に毎年確実に渡ってきて越冬するとのことで、日本野鳥の会広島県支部では探鳥会が行われている。参考: 広島県支部探鳥会情報 (2023)。
中国地方の少し標高のある地域で冬は雪が積もり、周囲の環境などの要因が重なって特別な場所になっているのだろう。知られていないだけで同様な定常的な越冬地が他にもあるのかも知れない。
シロハラやミヤマホオジロが繁殖するのもここからそれほど遠くない場所で、この地域特有の何かがあるのかも知れない。
この場所の観察に適した時期はこの探鳥会の時期で、雪が積もると越冬しているはずなのに場所がまったくわからなくなるとのことである。
独断と偏見の識別講座 II 第45回 Emberiza III <カシラダカ、ミヤマホオジロ> (波多野邦彦 2016)、
独断と偏見の識別講座 II 第76回 Emberiza V <キアオジ、シラガホオジロ> (波多野邦彦 2019) にあるように腰の模様は確認しておいて下さい、というところであろうか。
珍しい種類なので音声識別は参考までだろうが、自分が上記広島県で記録した音声では他のホオジロ類の地鳴きとは確かに違う。
高い方の地鳴きは一般的なホオジロ類より音が低く、ミヤマホオジロに似たパターンの「チュルルッ」という尻下がりの声がしばしば入った。波多野氏の書かれている "九重で聴いた声は特徴的な「プティッ、プティッ」と聞こえる声" とあるのはこの声であろうか。
一音でないホオジロ類の地鳴きを聞いた場合はこのような少し珍しい種も考えるべきかも知れない。
海外録音ではむしろもっと低く (5 kHz から少し低いぐらい)、少し濁った下がる音がよく記録されている。波多野氏がやや濁った「ビュ」というのはこの声を指したものかも知れない。
この声はオオジュリンの低い方の地鳴きに似ていて、どちらもあまりホオジロ類らしく感じない。
海外録音は主に繁殖地で記録されたもので、渡り途中または越冬地でもきちんと記録しておくべきであろう。低く濁った「ビュ」という声はさえずりの最後に付けられる声に似ていて、これはさえずりの一部分なのかも知れない。越冬地では高い方の地鳴きの方が一般的なのかも知れず、今後の調査課題だろう。
Paeckert et al. (2015) の分子系統解析 (#アオジの備考参照) では (名前は全然違うが) キアオジとシラガホオジロは同種に近いぐらい近い関係にある。
ミトコンドリア遺伝子では共通点が高く最近交雑が起きていたことを示唆する、核遺伝子は同所的に繁殖する場所でも違いがある
[Irwin et al. (2009) Mitochondrial introgression and replacement between yellowhammers (Emberiza citrinella) and pine buntings (E. leucocephalos; Aves, Passeriformes)]。
お互いのさえずりを認識するそうである: Tietze et al. (2012) Territorial song does not isolate Yellowhammers (Emberiza citrinella) from Pine Buntings (E. leucocephalos) や
Opaev et al. (2023) Responses of Yellowhammer Emberiza citrinella, Pine Bunting E. leucocephalos and Their Hybrids to Playbacks of Con- and Heterospecific Songs and Calls in a Hybrid Zone。
'see' call と 'zieh' call の表現がなされていてこれは納得できる感じ。'zieh' call がオオジュリンの地鳴きの一種に似て聞こえる気がするが皆さんはいかがだろうか。特徴ある声で、ソノグラムを見てみるとさえずりの後半と似た特徴がある。ホオジロ類やセキレイ類などでしばしば聞かれるさえずりの要素を帯びた地鳴きと呼んでよいのかも知れない。
オオジュリンの対応する声は nasal call と呼ばれるらしい。
シラガホオジロの方が森林環境を好むキアオジよりも開けた環境を好むとのことで、ステップ環境の中の島や農耕地にも生息するとのこと。
参考 Rubtsov (2023a) Composition of Couples, Biotopic Preferences, and Relative Life Duration of Birds in a Hybrid Yellowhammer (Еmberiza citrinella) and Pine Bunting (E. leucocephalos) Population (Passeriformes, Emberizidae) in the Altai Mountains
どちらも繁殖地で普通種であることを考えるとシラガホオジロが大陸東型、キアオジが西型でどちらも広く分布と考えるとわかりやすい。ユーラシア大陸に広く分布を広げたが、東の端で日本が少し含まれた程度だろうか。
Nikelski et al. (2025) A sex chromosome polymorphism maintains divergent plumage phenotypes between extensively hybridizing yellowhammers (Emberiza citrinella) and pine buntings (E. leucocephalos)
シラガホオジロとキアオジの交雑の DNA レベルの研究。Z 性染色体に逆位と思われる部位を同定した。羽衣の違いを維持している遺伝機構と考えられ、シラガホオジロ型の方が優性と思われる。両者の生殖隔離は弱く種分化途上を見ていると考えられる。さまざまなパターンの雑種の写真も出ている。
典型的な個体のみかけの色が大きく異なるので別種扱いが自然とみなされてきたが、ここまで遺伝的に混ざっているのを見ると、色彩以外の違いが中心だったならば同種の亜種とされていたかも知れない組み合わせに感じる。
アルタイ地方での雑種の研究: Rubtsov (2023b) Composition of Couples, Biotopic Preferences, and Relative Life Duration of Birds in a Hybrid Yellowhammer (Еmberiza citrinella) and Pine Bunting (E. leucocephalos) Population (Passeriformes, Emberizidae) in the Altai Mountains。
ヨーロッパのフィールドでの識別研究では例えば Occhiato (2003) Identification of Pine Bunting。
Question on Redpolls (BirdForum) シラガホオジロとキアオジは染色体逆位を含む supergene で別種扱いにしているのに、同じようなメカニズムのベニヒワ類はなぜ同種にするのかなどの問題提起も出ている (上記 "色彩以外の違いが中心だったならば同種の亜種とされていたかも知れない" と同じ印象)。
-
ホオジロ
- 学名:Emberiza cioides (エムベーリザ キオイーデース) ヒゲホオジロに似たホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:cioides (合) ヒゲホオジロに似た [Emberiza cia ヒゲホオジロ (英名 Rock Bunting) の種小名 cia -oides (接尾辞) 〜に似た]
- 英名:Siberian Meadow Bunting, IOC: Meadow Bunting
- 備考:
emberiza は規則によれば -be- がアクセントで、発音の聞けるページを参照するとそのようになっている。
"エムベーリザ" (本来は長音ではないが "ベ" にアクセントを置くためこの表記とした。アクセントに慣れれば短音 "エムベリザ" に戻していただいてもよい) のような読み方がよいのだろう。
cioides は cia は短母音と考えれば、-oides は i, e が長母音 (語末はギリシャ語由来) でアクセントがある "キオイーデース" と考えられる。
亜種名の ciopsis はギリシャ語語尾発音から "キオプシス" と考えられる。
castaneiceps は castanea は短母音のみでギリシャ語由来の -ceps も同様のため ei の位置にアクセントがあり "カスタネイケプス" と考えられる。
5亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは亜種 ciopsis (ヒゲホオジロの cia + -opsis 顔の、外見の) 亜種ホオジロ、及び亜種不明とされる。
基亜種 cioides は大陸アルタイ山脈北西部、トランスバイカル地方とモンゴルが分布域。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で亜種 castaneiceps (castanea くり -ceps 頭の) チョウセンホオジロが検討亜種となっている。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
Emberiza の語源はアレマン語 (Alemannic German ドイツ南西部の地方言語) の embritz, embritze, emmeritz とされる。標準的な高地ドイツ語では Emmeritze。これは古高地ドイツ語 amarzo に由来し、amaro の指小形とされる。
amaro は推定単語 *amarofogal の短縮形で amaro- は黒っぽい色の、後半は鳥 と解釈されている。現代ドイツ語にホオジロ類を指す Ammer (女性名詞) が残っている (wiktionary)。Emberiza が女性語尾になっているのはそのためかも (未確認)。
英語の bunting の方はより不明で、中世英語では bunting, bountyng, buntynge が使われていたとのこと。記録には残っていない推定中世英語 *bunt に由来するのではとのこと。これはいくつかの言語でまだらの、染め分けられたなどの意味がある (ドイツ語 bunt など)。
英語に同じ綴りで bunting の単語があり祭りの飾りなどに使われるが、この語源 (つなげる、など) は別と考えられている (wiktionary)。
ホオジロの種小名の由来となった Emberiza cia ヒゲホオジロ のかつての英名が Meadow Bunting だった。参考: Rock Bunting。1900 年代の用例。
英国ではヒゲホオジロは迷鳥で少数の記録しかなかった。Emberiza cia に似たシベリアのホオジロの意味でホオジロの旧英名の Siberian Meadow Bunting が名付けられたものと思われる。ヒゲホオジロの方に Rock Bunting の英名が与えられるようになって、ホオジロの旧英名から Siberian が外されるようになったと考えられる。
ヒゲホオジロの英名が現在のホオジロの英名になってしまったわけだが、英国では迷鳥なので海外の鳥の英名が変わってもあまり問題にならなかったものと想像できる。このページの記事によればこの時期には博物学者の間でもヒゲホオジロとホオジロはよく混同されていたとのこと。
英語圏と縁のない鳥の英名にはあまり深い意味を期待しない方がよいかも知れない。
Hartert (1910-1922) のヒゲホオジロの部分は p. 183。現在も使われるドイツ語名の Zip-Ammer は Ammer がホオジロ類、Zip は鳴き声由来でこれもそれほど深い意味がない。当時の英名 Meadow-Bunting、フランス語名 (現在も同じ) Bruant fou (fou は英語 fool に相当する "ばか" で、辞書には "おさどり" の意味が出てくる。何かと調べてみるとカツオドリ類のことらしい) も見られる。
Hartert の時代まではホオジロはヒゲホオジロの亜種扱いだった (このページに E. c. cioides の表記が現れるが別ページでは別種扱い) ので、現在のホオジロを指して種英名は Meadow-Bunting の英名で構わなかったことになる (メボソムシクイを Arctic Warbler と呼ぶようなもの)。Siberian Meadow Bunting は亜種時代の英名に相当していたかも知れない。
ヒゲホオジロの和名は Emberiza Cia Linnaeus, 1766 (記述的でないのでおそらくあまり好評でなかった) を改名したシノニムの Emberiza barbata Scopoli, 1769 (参考) 由来と考えるのがもっともらしい。
Linnaeus (1766) の用いた Cia はイタリアの地方名で鳴き声由来とのこと (The Key to Scientific Names)。当時の読み方まではわからないが、ciao の "チャオ" の同様と思えば "チャ" だろうか。おそらく地鳴き。
日本の主な亜種 ciopsis も遡ればヒゲホオジロのイタリアでの鳴き声が由来となる。もうちょっと特徴を記述する学名がなかったものかと感じてしまうが、Linnaeus のスウェーデンには生息しない種類なので現地名で十分だったのだろう。思い付きで付けたような名称が東洋の学名にまで影響を与えるとは Linnaeus も想像しなかっただろう。
Hartert の学名一覧を見ても Rock Bunting に相当するものが見られないので、比較的新しく付けられた英名と想像できる。ヒゲホオジロの和名以外にイワホオジロ (愛媛の野鳥「はばたき」のホオジロの学名解説に現れる) やハイガシラホオジロ (「鳥類・哺乳類ロシア語辞典」藤巻裕蔵 2008) の和名もあったらしい。
イワホオジロは英名を訳したものと想像できる。ただし日本産種に#イワバホオジロ (他言語名解説参照) があるため紛らわしく使われなくなったのだろう。
ハイガシラホオジロは現在は Emberiza stewarti White-capped Bunting / Chestnut-breasted Bunting を指している。Hartert 時代でも Emberiza cia と同種扱いでなく、Emberiza stewarti には「鳥類・哺乳類ロシア語辞典」ではシロズキンシトドの和名が載せられていた。
出典次第と思われるが、日本産でないホオジロ類の和名・英名は同じ和名が別の種類を指す場合があるなど要注意のよう。
ヒゲホオジロのロシア語名は "山のホオジロ"。"崖のホオジロ" (イワバホオジロ) と何が違うのかと言いたくもなるがホオジロ類は種類も多く整理された一般名ではなさそうなのでこちらもやむを得ないところか。(シベリア)アオジでは色彩をもとに命名されている。
[ホオジロの和名について]
週間アニマルライフ (1973) p. 3372 で浦本氏がなぜホオジロと呼ぶのか疑問を呈されていた。鳥類学者から見ても白い部分は頬ではないので由来が不思議であったらしい。
「春の鳥」(小学館 1984) pp. 142-143 の柳澤紀夫氏のホオジロの記事でも「この顔によくも名付けたものである。細かい部分に着目したと言えばそれまでであろうが、素直には納得しにくい」とあった。
「鳥の手帖: 江戸時代の図譜と文献例でつづる鳥の歳時記」(浦本昌紀 尚学図書・言語研究所編集 小学館 1990) を確認しておくと、異名に画眉、画眉鳥の方があり (現在は別の種を指して使われているが) こちらの方が納得が行く。
ホオジロの用例は文明本節用集 (15 世紀後) に「頬白 ホウジロ 雀」、1705 年に「目白頬白のたぐいなるに」が現れ、前者は名前だけで何者か不明、後者は語呂合わせの印象が強く何を指しているか不明。メジロの名称があったので対応する形でホオジロの名称が生まれただけかも。
1712 年の和漢三才図会に「画眉鳥 (ほうじろ) (略) 鞍画眉、俗云頬白鳥成」とあって頬白は俗名だったらしい。
和漢三才図会なので画眉鳥の由来はおそらく漢語なのだろう。画眉を現代の中国語で検索するとガビチョウもホオジロも、さらにはシマアオジも出てきていまひとつすっきりしない。漢語でも歴史的には複数のものを指していたのかも。
大西 (2009) Birder 23(6): 13-15 によればホオジロは山雀 (ヤマスズメ) と呼ばれて親しまれていたとのこと。ホオジロがメジロに対応した飼い鳥由来の用語で、ヤマスズメが野鳥を指して親しまれていた名称かも知れない。"ヤマスズメ" の和名ではスズメの学名 Passer montanus そのままの意味となって区別できないので避けられたものだろうか。
ホオジロ類には別途飼い鳥由来の名称を割り振ることになったが、飼い鳥由来ならば他にも "シトド" があるだろうと "ホオジロ" にこだわる十分な論拠を欠いていたかも知れない。"シトド" を明示的に用いるのは新世界中心に、旧世界は新名を与える場合は "ホオジロ" と訳すものの、アオジやクロジは語末に残した、という経緯かも知れない。
新世界に "シトド" を割り振ることも見解が分かれていたらしいことはサバンナシトドの例に現れている。かつての概念ではホオジロ上科 (Emberizoidea) に含まれるのでホオジロ類に含めても間違いでないとなるのだろうが ([ホオジロ科 Emberizidae の起源] 参照)。新世界の視点で和名を付けるか、旧世界からの延長で名前を付けるかの違い。
シトドフウキンチョウ Spindalis zena Western Spindalis と呼ばれる種 (グループ) もあって、"シトド" (ミヤマシトドまたはシロハラホオジロ) に似たフウキンチョウ (名前の由来は #ツリスガラ備考の [フウキンチョウの和名の由来] 参照) として名付けられたものだろう。由来を知らずに見れば何の名前かと思ってしまう。
もっともヤマドリの別名にアカシトドがあったらしい (#ヤマドリの備考参照)。"シトド" はしばしばホオジロの地鳴き由来と言われるが、実は別起源があるのかも。
[ホオジロ科 Emberizidae の起源]
ホオジロ科 Emberizidae の起源については Barker et al. (2015) New insights into New World biogeography: An integrated view from the phylogeny of blackbirds, cardinals, sparrows, tanagers, warblers, and allies
に興味深い結果が出ている。
スズメ目スズメ上科 (oscines) の起源は Sahul (オーストラリア大陸部、タスマニア、ニューギニア、ワラセアを含む) が有力とされおり (#ミサゴの備考 [近代的な陸鳥の進化] も参照)、早ければ 5600-6600 万年前にも生じていた可能性が指摘されているものの年代には議論がある。
ここからユーラシアやアフリカに広がり、その後北および南アメリカに到達したと考えるのは自然である。
スズメ上科のうちホオジロ科を含むホオジロ上科 (Emberizoidea) は南北アメリカの種数が豊富であることから南北アメリカが起源の可能性が議論されてきた。
この Barker et al. (2015) 分子系統研究の結果、ホオジロ上科は北アメリカが起源であることが強く支持されるとのこと [下記 Yuri and Mindell (2002) も参照]。ホオジロ上科に含まれる多くの科は新世界に分布する。
ベーリング海を通ってユーラシアに分布を拡げたのは 1180 万年前ぐらいと推定されるとのことであり、新世界の Passerellidae (ゴマフスズメ科) と姉妹系統をなす1系統ホオジロ科のみがユーラシアに分布を広げたと考えるのが自然である。
アメリカムシクイ科 Parulidae、ツメナガホオジロ科 Calcariidae はこの {ホオジロ科 + ゴマフスズメ科} とはそれぞれ別系統になり、いずれも北アメリカが中心となるグループ。
見慣れたホオジロ類がそれほど古くない時期に北アメリカからやってきたものの子孫であるのは不思議でもある。
Arango et al. (2025) Broad geographic dispersal is not a diversification driver for Emberizoidea
新しい地域への定着が爆発的な種分化の要因となっていない系統解析結果が得られた。新世界の系統が中心だが旧世界のホオジロ類も含まれている。1400-900 万年前の寒冷化に伴って C4 植物による草原が広がった現象に対応する種分化の加速も観察された。
この性質は Emberizoidea がアトリ科から分岐する以前から存在した可能性がある。
#モリツバメ備考の [オオハシモズ科] Auerbach et al. (2024) でも同じような結果が出ていて興味深い。こちらでは key innovations の重要性が指摘されているが、Arango et al. (2025) でも一つの因子として取り上げられている。
なお Emberizidae はかつて広義に使われ、Passerellidae も含まれていた概念であった (分離されたため Passerellidae に新たに和名を与える必要が生じている)。
例えば Yuri and Mindell (2002) Molecular phylogenetic analysis of Fringillidae, "New World nine-primaried oscines" (Aves: Passeriformes)
の系統樹を参照。
広義に見た場合、実は Icteridae Vigors, 1825 の方が Emberizidae Vigors, 1831 よりも先取権があったとのこと (Boyd, Taxonomy in Flux Checklist 3.08 Introduction)。
[音声]
他のホオジロ類に音声識別の備考を付けているのでホオジロについても付けておくことにする。
地鳴きはホオジロ類の中では最も識別しやすい種類であろう。3声またた2声の高い特徴的な声はどこでもよく聞くことができる。
多少注意すべき点があるとすれば、必ず3声で鳴くわけでなく1声のこともある程度で、これを例えばカシラダカと勘違いしないように、ぐらいだろうか。また似た3声パターンだが音程が違うものにミヤマホオジロがある (#ミヤマホオジロの備考参照)。
繁殖地ではまだ夏の時期に巣立ってそれほど経っていない若鳥が1声で鳴くこともある。この声はアオジの地鳴きに非常に似ていて「季節外れのアオジの地鳴き記録」はホオジロの若鳥も検討対象に入れるとよい。
あるいは声で種類の判定できるベテランほど誤同定に陥りやすいかも知れない。
ホオジロの若鳥の声がアオジの地鳴きに非常に似ているケースがあるので取り上げたが、これは上級者向け話題と考えるべきだった。
「アオジは1声、ホオジロは3声」のようなチャート式識別 (?) の知識が広まっているらしいことに思い至った。誤同定と思われる判定の理由はおそらくこのような中途半端な知識によるのでは。姿や写真の識別には非常にこだわる割には声の識別にこだわる方はあまりなく、探鳥会でもほとんど議論にならないような気がする。
かつては「日本で最も普通の鳥」だったぐらいで、さえずりもどこでも聞くことができて馴染みの個体の声であればすぐわかるであろう。ただし地域差も大きいようで他地域で録音されたホオジロらしいさえずりをホオジロと断定するのは意外に難しいことがある (多分ホオジロと思うが、程度しか答えられない)。
地鳴きの混じった声であれば確実なのだが、と思うことがある。
また他の鳥でもよくあるが、さえずりの一部だけ、あるいはさえずりの中の一音だけを繰り返して鳴くことがある。姿が見えない場合はこれはしばしば「聞き慣れない声」で種類不明 (もしかしたら珍しい種類かも?) と思わせる原因となる。
しばらく聞いていれば本格的なさえずりに移行して、ホオジロかとわかることもあるが、「聞き慣れない声」の部分だけを記録しておくと悩ましい記録になりがちである。どこでも起き得る話なので「ホオジロの声は奥が深い」と思っておいてよさそうである。
繁殖地で声を聞くと他にもさまざまな声 (警戒や餌乞など) を出すことがわかる。だいたいは姿が見えているのであまり悩まないが、声だけを聞いたらわからないかも知れない。ホオジロと思って軽視せず姿が見える時によく聞いておくとよい。
[日本と大陸のホオジロ類の関係]
Paeckert et al. (2015) の分子系統解析 (#アオジの備考参照) によれば日本と大陸のホオジロにはほとんど差がないとのこと。
Hunag et al. (2022)
Molecular evidence of introgressive hybridization between related species Jankowski's Bunting (Emberiza jankowskii) and Meadow Bunting (Emberiza cioides) (Aves: Passeriformes)
によればホオジロと大陸の希少種であるコマホオジロ Emberiza jankowskii Jankowski's Bunting / Rufous-backed Bunting の間で交雑 (遺伝子浸透) があるとのこと。
Zhang et al. (2023) Phylogenetic Conflict Between Species Tree and Maternally Inherited Gene Trees in a Clade of Emberiza Buntings (Aves: Emberizidae)
(別リンク)
によれば Z 染色体では ([{E. godlewskii, E. cia}, E. cioides], E. jankowskii)
の系統関係になるとのこと (Emberiza 参照。Godlewskii's/Southern Rock Bunting は現行の主要リストでは1種としているが2種に分離される可能性はあるか、との疑問に対する返答。単系統関係をなさないのでおそらく分離されないとのこと)。
-
イワバホオジロ
- 学名:Emberiza buchanani (エムベーリザ ブカナニ) ブチャナンのホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:buchanani (属) スコットランドの外科医でネパールやインドでの採集家 Francis Buchanan-Hamilton の
- 英名:Grey-necked Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
buchanani は原語にとらわれずにラテン語読みとしてみた (ブカナニ)。
記載時学名 Emberiza Buchanani Blyth, 1845 (原記載) 基産地 Indian peninsula。Buchanan-Hamilton の図版をもとに記述したもので大した情報は書かれていない。
Buchanan-Hamilton は Fringilla jamjohari と呼んだそうだがおそらく有効な学名ではなかったのだろう。記述者の Buchanan-Hamilton の名前を保存するために種小名に付けたものと思われる。
Fringilla Jamjohari (BirdForum) に解説あり、jamjohari はヒンディー語由来とのこと。
ズアオホオジロと同種とされたことや Emberiza buchanani の 1847 年の別用例があったようでややこしかった模様。
Hartert (1910-1922) では p. 182。Blyth (1845) は1枚の図版に基づくもので記述は短いが、Hartert は十分判別可能と判定した。
Emberiza Buchanani を命名した Blyth 自身はズアオホオジロと同一と判定し直して Emberiza Huttoni Blyth, 1849 の名称をアフガニスタンの標本に対して新たに与えたがこの判断は間違っていた。Blyth (1845) の原記載でズアオホオジロとの違いは示されており、ズアオホオジロはインド半島に分布しないためとのこと。
Hartert はズアオホオジロと似ているが明らかな違いがあり、頭の上部と "ひげ" は純粋な灰色で緑っぽさはない。耳羽も純粋な灰色ででのどは黄色でなく灰色を帯びた白。
英名はこれらの特徴を表したもので学名とは無関係のよう。
"イワバホオジロ" に対応する他言語名が少しある。ドイツ語別名 Steinortolan (岩場の Ortolan)。和名はこのドイツ語由来かも。スウェーデン語の bergortolan (山の Ortolan)。
多くのヨーロッパ言語で "イワバ" の付くものは Ortolan を修飾していることに注意。ortolan はズアオホオジロのことで、身近な種類であるズアオホオジロ ("庭園のホオジロ" の学名を持つ) に似ているが生息地が違って山に住むの意味だろう。日本ではズアオホオジロは身近な種類でないので "イワバ" をホオジロに直接付けることになったものと想像できる。
ロシア語名が似ていて skalistaya ovsyanka と "崖のホオジロ"。ロシア語名では言語系統が異なるためか Ortolan は用いず、ズアオホオジロ "庭のホオジロ" と対比する形となっている。
さて問題は Emberiza cia の和名で、比較的新しく付いたと思われる英名 Rock Bunting (#ホオジロの備考参照) に対応する和名として使われたイワホオジロと類似したものになってしまう。こちらは現在はヒゲホオジロと呼ばれる。系統がかなり違うので、かつては同種扱いでイワホオジロまたはイワバホオジロと呼ばれていたものが分離されたものではなさそう。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。3亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
-
ズアオホオジロ
- 学名:Emberiza hortulana (エムベーリザ ホルトゥラーナ) 庭園のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:hortulana (adj) 庭園の (hortulanus)
- 英名:Ortolan Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
hortulana は -ana の冒頭が長母音でアクセントがあると考えられる (ホルトゥラーナ)。#カラアカハラでも同じ意味で少し違う語形が用いられている。
記載時学名 Emberiza Hortulana Linnaeus, 1758 (原記載) と由緒あるものだった。Linnaeus 以前から Hortulanus と呼ばれていたもの。いずれも名詞扱いなので形容詞的変化をする名詞の考えでよいだろうか。
ズアオホオジロの名称に相当する Emberiza chlorocephala Gmelin, 1789 (参考) があり、この時代に Green-headed Bunting の英名がすでにあり、対応する学名が作られたものと想像できる。Linnaeus の学名より普及していたのかも知れない (カード注釈を見ると基産地が英国で、英国のものは大陸と別種としたかったのかも知れない)。
和名はこの英名由来と想像できる。
現在の英名の ortolan は中世フランス語の hortolan < ラテン語 hortulanus (庭師) に由来。
イタリア祖語に *hortos (囲い) の単語が推定されるとのこと (wiktionary)。
Hartert (1910-1922) 時代のドイツ語名は Gartenammer と "庭のホオジロ" だった。この時代から現在のドイツ語名 Ortolan もあった。
単形種。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza属の系統分類] 参照。
-
シロハラホオジロ
- 学名:Emberiza tristrami (エムベーリザ トゥリストゥラーミ) トリストラムのホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:tristrami (属) トリストラム (Henry Baker Tristram) の
- 英名:Tristram's Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
tristrami は外来語で発音はよくわからないが、ごく普通のラテン語 ramus (枝) の変化形と同様と考えれば少なくとも a は長母音となるのが自然に思える。アクセントも置きやすいのでこの発音を採用した (トゥリストゥラーミ)。
記載時学名 Emberiza tristrami Swinhoe, 1870 (原記載) 基産地 Amoy [= Hsiamen], Fukien, China (アモイ)。
Belly, vent, and axillaries pure white と下面の腹部は純白との記述がある。
ロシア語名ではむしろ "のどの黒いホオジロ" がある。
Dement'ev and Gladkov (1954) では Emberiza quinquelineata Taczanowski, 1874 をシノニム? としているが、同じ学名が他のものを指してすでに使われていたのでそもそも無効だったよう。quinquelineata は "5本の縞のある" の意味。腹が白いよりも頭部の模様の方がおそらく目立ちますよね。中国語名に五道眉がある。
単形種。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
ロシア沿海地方のシロハラホオジロの繁殖: Gluschenko et al. (2025) Breeding birds of Primorsky Krai: the Tristram's bunting Ocyris tristrami (pp. 869-900)。普通の繁殖種。
シロハラホオジロとクロジの関係 (#クロジ備考の [シロハラホオジロとの関係]) も参照。大陸から見ればごく当たり前のシロハラホオジロに比べて島で特殊化したのがクロジに見えるだろう。クロジの種分化や生態を考える上でも参考になりそう。
-
ホオアカ
- 学名:Emberiza fucata (エムベーリザ フーカータ) 染められたホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:fucata (adj) 染められた (fucatus) 頬の赤さを指す
- 英名:Chestnut-eared Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
fucata は冒頭の2母音が長母音で後者にアクセントがある (フーカータ)。
英語別名 Grey-headed Bunting。
記載時学名 Emberiza fucata Pallas, 1776。基産地 at Onon and Ingoda rivers, near Shilka, Chita, southeastern Siberia (Avibase による)。
"Fauna Japonica" ではこの学名が用いられ、フランス語名 le brunt peint (染められたホオジロ) と学名そのまま (記述、図版)。
特にシノニムなどもないらしく英語別名の由来がよくわからないが、Hartert (1910-1922) の表では p. 165 に Pileum grau (頭頂が灰色) とあって一応対応している。
3亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 fucata とされる。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
ホオアカの地鳴きは (日本で通常に観察される) ホオジロ類の中で一番声が低いので識別が簡単と言われる (5-6 kHz とカシラダカよりもさらに 1-2 kHz ぐらい低い)。これぐらい低いとむしろホオジロ類と思わないかも知れない方が問題かも知れない。
この声の他にも緊張している時などはもっと高い声も出し、これは他のホオジロ類の地鳴きに近いので識別上問題になるだろう。非常に低い地鳴き (5 kHz またはそれ以下) は地鳴きというより、他のホオジロ類でもあるようにさえずりの一部また一要素を反復している可能性がある。さえずりでは春先の越冬地でも聞くことができる。
近年京都でホオアカが連続して繁殖している (保津川鳥獣保護区府民探鳥会 5月28日) (日本野鳥の会京都支部 2023)
が工事後の環境変化に伴う一時的なものと考えられ、今後も繁殖が続くかはわからないとのこと。
-
コホオアカ
- 学名:Emberiza pusilla (エムベーリザ プスィルラ) ごく小さいホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:pusilla (adj) ごく小さい (pusillus)
- 英名:Little Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
pusilla は短母音のみで -sil- がアクセント音節 (プスィルラ)。
単形種。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) の "島がしら" をコホオアカと同定している。
独断と偏見の識別講座 II 第37回 Emberiza II <ホオジロ類 II> (波多野邦彦 2013) ではコホオアカの地鳴きはほぼ聞き分け可能な種類に入っているが、「チッ」の高い地鳴きは聞き分け困難な気がする。
かつて福井県中池見湿地で背景でノジコがたくさん鳴いている中でコホオアカを至近で観察し、音声記録とビデオを同時に撮ったことがあったが、音声記録だけではコホオアカを判定できず、ビデオの嘴の動きでコホオアカの音はどれかを判定したことがある。
この時もコホオアカとノジコの声を識別する方法は見つけられず、ビデオ記録中以外にもたくさん入っているはずのコホオアカの声を選び出すことができなかった (背景のノジコの方が声が大きく、数も多くてコホオアカの声が埋もれてしまった原因もあるが)。ノジコの中に少数混じっているコホオアカを地鳴きで判定するのは難しい気がする。
コホオアカは大陸では多い鳥で、ヨーロッパでも多数の音声記録がある。その中には比較的低い声も含まれていて、この声であれば波多野氏が書かれているようにカシラダカに近い音程で、識別可能かも知れない。
-
キマユホオジロ
- 学名:Emberiza chrysophrys (エムベーリザ クリューソプリュス) 金色の眉のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:chrysophrys (合) 金色の眉の (chrysos 金色の ophrus, ophruos 眉 Gk)
- 英名:Yellow-browed Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
chrysophrys は綴りは長いが2音節しかなく冒頭が長母音 (クリューソプリュス)。
和名は英名または学名由来と想像できる。
単形種。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
-
カシラダカ
- 学名:Emberiza rustica (エムベーリザ ルースティカ) 田舎のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:rustica (adj) 田舎の (rusticus)
- 英名:Rustic Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
rustica は冒頭が長母音でアクセントもここにある (ルースティカ)。#ツバメも参照。
記載時学名 Emberiza rustica Pallas, 1776 基産地 Dauria [= Transbaikalia] (Avibase による)。
単形種。ユーラシア北部で広く繁殖するが、Paeckert et al. (2015) の分子系統解析 (#アオジの備考参照) では大陸の東西で特に違いは認められないとのこと。尾崎 (2019) Birder 33(7): 26-27 によれば越冬地は中国南部と日本付近に限られ、ロシア東部で繁殖していたものが次第に西方に分布拡大したものと考えられるとのこと。
[音声]
ホオジロ類でやはり問題となるのは地鳴きの識別であるが、カシラダカは比較的簡単で他の高い声の (ホオアカを除くのような意味) ホオジロ類の中で、1 kHz ぐらい音声が低い。この違いはかなりよくわかるので試していただきたい。飛んでいる最中の個体でも声で認識できる。
春の渡り前に農村などで集団で賑やかにさえずって (ヒバリのさえずりに多少似ている) 「カシラダカのコーラス」と呼ばれているが、そのような環境が減少したのかあるいは個体数の減少を反映したものか、近年は聞く機会が少なくなった印象を受ける。とはいえカシラダカはよく見られる鳥なので、賑やかに騒いでいる集団にうまく遭遇できたらコーラスの息遣いの緩急などをぜひ堪能してみて欲しい。
[カシラダカの減少]
2016 年から IUCN 3.1 VU 種。日本を含めた世界的な減少傾向については カシラダカが絶滅する? (山階鳥研 尾崎清明 2018)、
カシラダカが絶滅危惧 II 類に (バードリサーチニュース 2016) などに詳しい。Edenius et al. (2016) The next common and widespread bunting to go? Global population decline in the Rustic Bunting Emberiza rustica
が出版論文。
尾崎 (2019, 上記) によれば減少要因は繁殖地よりも渡り中、越冬地にある可能性が高い。
標識調査以外の情報として、過去にかすみ網による渡り鳥の大量捕獲が行われており、当時は「ツグミ・アトリ・カシラダカ問題」とされていたように、カシラダカが非常に多い鳥であったことがうかがえる。
この「かすみ網問題」には日本野鳥の会が大きな貢献を果たした。当時の状況が描かれたノンフィンクションとして「ツグミたちの荒野」(遠藤公男 講談社 1983) が有名。
世界的な減少傾向が報告される中、Biserov (2021) が全く違う見解を述べている。On the need to exclude the rustic bunting Ocyris rusticus from the Red Book of the Russian Federation (pp. 3047-3055)。
ロシア東部で 12 年観察しているが数に変わりはない。渡り途中の地域でも数が多い。ロシア東部で同じような移動をするミヤマホオジロの数も同じようなものだが、こちらはロシア RDB に含まれていない。
カシラダカのヨーロッパでの減少は温暖化に関係があるのではないか、などの考察を行い、ロシア RDB から外すべきだとの主張である。ちなみにこの Biserov は「ハチクマのお客さんになって」(#ハチクマの備考参照) のマラート氏である。
ここで属名 Ocyris (oxus 鋭い this 鼻、嘴) 嘴が特に尖っている特徴を意味して Hodgson (1845) が用いたものが使われている。例えばシマアオジも同じ属名で書かれている論文 (英文でも) もある。
異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza属の系統分類] 参照。将来的な属名変更の可能性もある。
Emberiza はかなり大きなグループなので、いくつかに細分したい理由はわからないわけでもない。
Ocyris 属のロシア語名称は "森のホオジロ" に相当する (Koblik 2007)。
カシラダカのロシア名は ovshanka-remez で、前半の ovshanka (アフシャンカ) はホオジロ類全般を指す (< oves オートミール; 好物である) が、後半の remez はツリスガラのことである (#ツリスガラの備考も参照)。
そう思って見ると似ている点は何かあるだろうか。模様だろうか? Kolyada et al. (2016) の語源辞典では由来不明とあり、ツリスガラとの類似点は特にないように見えるとある。
-
ミヤマホオジロ
- 学名:Emberiza elegans (エムベーリザ エーレガンス) 優雅なホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:elegans (adj) 優雅な、上品な
- 英名:Yellow-throated Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
elegans は冒頭が長母音でアクセントもここにある。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 elegans とされる。
記載は Emberiza elegans Temminck, 1836 (図版) 基産地日本 による。
他の亜種は Emberiza elegantula Swinhoe, 1870 と記載されたもの。基産地 near Kweichow [= Tzukuei], on the Yangtze River, western Hupeh。
これは中国内陸部の留鳥個体群。
Emberiza elegans ticehursti Sushkin, 1926 基産地 Sidemi River, southern Ussuri (ウスリー地方) は Emberiza elegans sibirica Sushkin, 1925 を改名したもの (Dement'ev and Gladkov 1954)。
elegans のシノニムとされる。
英名とロシア語名が同じ意味だがどちらが先だろうか。英語別名 Yellow-headed Bunting。
Yellow-throated Bunting の意味の学名があって Emberiza flavogularis Blyth, 1849 (参考) 基産地インド (越冬地) があってシマアオジのシノニムとされる。
以下#シマアオジの方に。
ミヤマホオジロのみからなる属 Cristemberiza Momiyama, 1928 が提唱されたこともあった。ロシアの文献に用例があった。
Bruant Elegant では日本ではまれで歌が高く評価されていると記述されている。"elegant" の由来は歌も含まれているのかも知れない。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
ミヤマホオジロの和名は深い山に住むわけではないのでいかにも違和感がある。大橋 (2019) 33(12): 34-35 では遠くからのものを示すとともに、「ちょっと変わったホオジロ」の意味ではないかと推測されている。
日本ではほとんど繁殖しないが朝鮮半島から飼い鳥として輸入されていた時期の名残りではないだろうか。遠く、特に朝鮮半島から来るものは「深山」と付けていたのではと想像できる事例はミヤマガラス、ミヤママツムシ = ヤマヒバリ (朝鮮半島に生息) の飼い鳥時代の名称、地域は違うがミヤマヒタキも同系かも知れない。
和漢三才図会 (中国の「三才図会」にならい、和漢古今の万物を掲げ、漢文で解説を施し、図解したもので 1712 年成立。コトバンクより) に深山鳥の項目があり、別に深山頬白鳥があると説明されているとのこと。本朝食鑑 (1697) に深山鳥が現れるとのこと (コンサイス鳥名事典)。現在では深山鳥は一般にミヤマホオジロを指すと解釈されている。
「大江戸飼い鳥草紙」(細川博昭 吉川弘文館 2006) (pp. 164-167 表 7) によれば「喚呼鳥」(1710
) でみやまほじろ、百千鳥 (1799) では深山画眉鳥 (みやまほうじろ) となっている。おそらくこれ以前よりあった名称で画眉は頬白の異名。画眉鳥では現在は別に知られる飼い鳥 (外来種) の名前だがともに古くから知られていたのかも知れない。
なお Seebohm (1890) "The birds of the Japanese Empire" では (日本で記載された種だが) 日本で普通種とはとても呼べない。Yezzo では記録されていないが Abbe Faurie が Hakodadi 近くで捕獲した標本がパリ博物館にある。Yokohama で Pryer が入手した3標本、自身が長崎近くで Ringer が捕獲した2標本を持っている。日本で留鳥の可能性はあるが、満州や Amoor の谷では夏鳥で中国で越冬とある。
そのため記載された場所の名前ではなく人名を用いるのが妥当 (Temminck's Yellow-browed Bunting) と判断したものだろう。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では分布は Hokkaido, Hondo, Kiushiu, Tsushima としていた。山階鳥類研究所標本データベースでも古い標本はあるが対馬や西日本が中心で、京都の 19 世紀のものなどは後日同定されたものも含まれているかも知れない。いずれにしても中央の鳥学者から見れば圧倒的に "西の遠くから" と解釈して問題なさそう。輸入飼い鳥時代の名前をそのまま使っても十分整合性があった。
ミヤマホオジロも地鳴きの識別が問題となるが、独断と偏見の識別講座 II 第45回 Emberiza III <カシラダカ、ミヤマホオジロ> (波多野邦彦 2016) の意見に完全に同意する。
「チュルルッ」という尻下がりの声が特徴的で、3つの音の間隔はホオジロの「チリリ」に似ているが、音程が下がるのが特徴。1声のチッを他のホオジロ類と区別できるかはよくわからない。各種録音をチェックしてみたが、状況によって音程も音の質も変わるようで、ミヤマホオジロの1声の地鳴きの決定的な識別方法は見つけられなかった。
ホオジロ類がたくさんいる中で「チュルルッ」でミヤマホオジロが入っていることはわかるが、見やすいところに現れるかはやや運次第。ミヤマホオジロは比較的見やすいところに出てくる傾向があるようで、声で判定したものがきちんと現れてくれると嬉しいものである。探鳥会でその通りになれば多少自慢できるかも (?)。
春先のミヤマホオジロのさえずりはかつては地元で聞いていたが、環境が変わってしまって今はやや縁が遠いものになってしまった。
繁殖生態と渡りの研究がある: Heim et al. (2023) Habitat use, survival, and migration of a little-known East Asian endemic, the yellow-throated bunting Emberiza elegans。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the yellow-throated bunting Cristemberiza elegans (pp. 2495-2525)
ロシア沿海地方の繁殖生態。
Hu et al. (2022) De Novo Whole-Genome Sequencing and Assembly of the Yellow-Throated Bunting (Emberiza elegans) Provides Insights into Its Evolutionary Adaptation
ミヤマホオジロの精度の高いゲノム解析。16.62% は反復配列だった。正の選択を受けている遺伝子候補に免疫関係が含まれ、(ミヤマホオジロに限った話ではないと思われるが) レトロトランスポゾン由来の LTR (long terminal repeat retrotransposons。スズメ目進化に重要な役割を果たしたと考えられる。#ツリスガラ備考参照) と軍拡競争関係があった可能性がある。
渡りに関係する可能性のある遺伝子も正の選択を受けている候補に挙がっている。
再現された過去の実効個体数変動から他の多くの種に比べて氷河期の影響が小さく環境への適応性が高いと考えられる。
シマアオジは減少しているのに系統的に近いミヤマホオジロはなぜ減っていないのかなどの問題意識を持った研究かも知れない。アオジが増えた背景にもあるいは関係があるのかも。
-
シマアオジ
- 学名:Emberiza aureola (エムベーリザ アウレオラ) 金色のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:aureola (adj) 金色の (aureolus = aureus)
- 英名:Yellow-breasted Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
aureola はすべて短母音で -re- にアクセントがある (アウレオラ)。-olus の o は短母音。aurum (アウルム) は金。aureus も短母音のみ。
aureola (後光、光輪) の英語は冒頭が "オー" になるがアクセント位置はラテン語と同じで -re- にあり他に長母音はないのでラテン語に近い読みになる。-o- を伸ばす発音は英語にもないので注意。
#ミヤマホオジロの備考にも記したが、"Yellow-throated Bunting" の意味の学名があって Emberiza flavogularis Blyth, 1849 (参考) 基産地インド (越冬地) があってシマアオジのシノニムとされる。
また Mirafra flavicollis McClelland, 1840 (参考 もあった ("首に黄色い部分のある Mirafra")。いずれも特徴をよく捉えた学名に思える。Mirafra はジャワ島の言語由来らしいが不明で、現在はヤブヒバリ Mirafra javanica Horsfield's Bushlark / Singing Bushlark の属名となっていてそもそも似た種類ではなかった。
参考 Hartert (1910-1922) p. 173。
英名では collis, gularis など首やのどに関係する部位が -throated, -breasted のいずれにも訳されるため、Yellow-breasted Bunting の英名はこれら学名に関係があると想像できる。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは ornata (着飾った) 亜種シマアオジ、及び亜種不明とされる。
絶滅危惧 IA 類 (CR)。IUCN 3.1 CR 種。
2004 年までは IUCN は LC 種 (懸念なし。日本の RDB では対象外に対応) となっていた。
大規模に捕獲され食用にされていた中国で 2021 年に国家一級保護種に指定 (#アカハジロの備考参照)。
後の BirdLife 記事によれば中国で 1997 年に狩猟禁止となったが 2013 年までは食用に殺され、闇市で売られていたとのこと。
基亜種 aureola はフィンランドからベーリング海にかけての北方林で繁殖し、インドシナに渡る。フィンランドでは絶滅したと考えられている。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
有り余るほど居た鳥の減少はリョコウバトの運命に酷似 (BirdLifeの記事日本語版 2015)。
Kamp et al. (2015) Global population collapse in a superabundant migratory bird and illegal trapping in China 上記記事の元論文。
Yellow-breasted bunting (BirdsRussia の記事。英語なのでご心配なく) によればロシア外のヨーロッパでは完全に消滅、ヨーロッパロシアでもほとんど消滅とある。西の個体群は東南アジアに渡り、東のものは逆に西側に渡るとある。
すべての個体群が中国で狭い領域を通り、渡りの時は大きな群れをなすとのこと。調査の結果サハリン南部でも消滅したとの結論になっている (南千島でも同様のよう)。サハリン北東部では現在でも比較的普通に観察され、Pervomaisk のほとんど都市内でも 2018 年に営巣が記録されている。ここが現在のサハリンの南限になっている。
食用で急激に減少したことは確かであるが、北および東の個体群は比較的影響が小さく、他の要因も複合していると考えられる。シマアオジの過去の分布拡大の経緯を考えれば (越冬地およびヨーロッパへの分布拡大はカシラダカとよく似ていてカシラダカの備考も参照) その一つとして考えられるものが気候変動である。
個体群によって減少の様子が違うのは渡りルートや越冬地にも関係しているかも知れない。ロシアで足環標識した個体で回収されたものは2例に過ぎず、安定同位体分析やジオロケータで越冬地や渡り経路を調べる必要がある。
この記事では島の個体群を亜種 insulanus としている。属名も文章内では Ocyris としている (#カシラダカの備考参照)。また Ocyrisaureolus というシノニムと思われる属名も出ている。
遺伝的解析で現在ほどんど消滅寸前の日本の個体群が (島のグループとされる) サハリンのグループに近いのか、あるいはアムールのグループに近いかがわかるであろう。
亜種 insulana / insulanus (属によって性が異なる) の記載は Portenko (1960) Ptitsy SSSR 4, 381。わずかな色の違いで区別しており、サハリン。千島南部、北海道をこの亜種としている。当時の属名は Hypocentor だった。
Bao et al. (2022) Subspecies Taxonomy and Inter-Population Divergences of the Critically Endangered Yellow-Breasted Bunting: Evidence from Song Variations
によればさえずりで亜種が区別されるとのこと。
北海道の insulana のさえずりは大陸のものに比べて単純であるが、他亜種との間で音声による生殖隔離が存在するかは現状わからない。この論文の時点では遺伝解析はまだ。
この研究では新しい録音データを用いているが、過去のシマアオジのさえずりと違いはないだろうか。
後述の Crates et al. (2021) の事例が気になるところ。この論文で典型的な insulana とされるソノグラムが「日本野鳥大鑑 鳴き声420」とあまり似ていない。
日本野鳥大鑑のものは基亜種 aureola のものとパターンは似ていて後半が少し短い。xeno-canto をみると aureola でも短いものもあるので (これはホオジロ類のさえずり全般に言える気がする。アオジでも場所や個体によってだいぶ違う) 音声で亜種判別ができるかどうかそこまで確実でない印象を受ける。
また過去の録音も含めた解析を行った方がよさそうに見える。
Chen and Sin (2024) Genomic signatures and demographic history of the widespread and critically endangered yellow-breasted bunting (preprint)
に最新の分子系統解析の結果が出ている。abstract だけではわからないので本文を見て欲しい。
最終氷期のレフージアに比較的近い中国東北部からロシアのアムール地方のクレード P2 が最も古く、サハリン (調べられていないがおそらく日本も) の P1.a、沿海地方の P1.b クレードがそれに続く描像となるがシベリアからヨーロッパ東部の P3 クレードに比較的近い。カムチャツカやオホーツク海沿岸、ロシア北東端の P3.a クレードは P3 に含まれる。
互いに単系統の関係にはないが2亜種に分けるならば P3 + P2, P1.a + P1.b と分けるのが適切で、3亜種ならば P3, P2, P1.a + P1.b となり得る。
従来の亜種概念のように ornata にカムチャツカの個体群を含めることは適切でない結果となった。最終氷期のレフージアに近かった地域とそこからシベリアに進出した個体群に遺伝的に違いがある感じ。この解析で得られた個体群に対応する亜種 ornata が絶滅に近い状態にあることになる。
3亜種に分ける場合にはサハリンの個体群と大陸の大部分とが異なる亜種とみなすことになる。
生息に適した地域のモデル計算も行われており、温暖化の影響でサハリンは好適地として残るが北海道は厳しくなりそうな予想が出ている。
この論文の主要結論では P1, P3 は個体数ボトルネック効果で遺伝的多様性が失われている兆候があり、島の個体群は規模も小さいので絶滅の危険性が高い。
この論文が執筆された時点ではイルクーツク周辺の個体数復活については知られていなかったようだが P3 に相当する。
長谷部 (2020) Birder 34(4): 40-43 サハリンのシマアオジ調査紀行がある。北海道よりは多く残っているがサハリンでも減っているとのこと。
これを読むと、サハリン北東部ではまだかなり健在であることを考えると、北海道で絶滅寸前になっているのは温暖化で分布が北上 (縮小) したことが大きな要因で、食用で全個体数が急激に減少したことがそれに追い打ちをかけたように見える。
カシラダカの数はシベリア東部で特に減っていないとする Biserov (2021) の主張 (#カシラダカの備考参照) も検討しておいてよさそうである。ただし後述の Wang et al. (2022) ではゲノムから見積もった過去の実効個体数は温暖化以前から減少を始めたとあり、温暖化のみでは説明できない。
長谷部 (2016) Birder 30(3): 6-7 でも越冬地は中国だけではなくインドシナ半島やインド亜大陸に広くあって、食用の捕獲以外にも原因があるかも知れないと記されている。
Wang et al. (2022) Genomic status of yellow-breasted bunting following recent rapid population decline
のゲノム解析によればここ 100-200 (中央値 147) 世代前から実効個体数を大きく減らした結果となっている。人為的な気候変動が顕著になった時期とは整合しないのでそれだけで説明することはできない。
また 1980 年代から急に数を減らしたと考えられてきたが、もっと早い時期に始まっていた結論となった。
減少が顕著となったのは産業革命ごろからで、人間活動が直接・間接に個体数減少をもたらした可能性が高い。
越冬地の人為利用や生息地の減少、持続不可能なレベルの食用 (中国南部では 2100 年以上前から食用の記録があるとのこと) などの要因が関与していると考えられる。
Denentiev and Ptushenko (1940 初出, 2023 再掲) Expansion and geographical distribution of the yellow-breasted bunting Emberiza aureola (pp. 1502-1509)
によればシマアオジがヨーロッパに進出したのは比較的新しく、文献情報からヨーロッパロシアに現れたのは 19 世紀に入ってから。当初はシベリアの鳥だったが 19 世紀前半に珍しい鳥として登場するようになり、そのころからモスクワに、その後レニングラードに到着したと思われる。1870-1880 年代には普通の鳥になった。
19 世紀のヨーロッパロシアに急速に分布を広げた可能性がある。分布域の特性は北方型でタイガ型と言える。そして分布西端はフィンランドまで達した。西方に分布を広げることができた要因はよくわからない。
ホオジロ類他種と比べても卵の数が多いわけではない。東方に分布するシマアオジと繁殖サイクルが違っているかなどを検討している。またこのように急激に分布を広げる種ではしばしば人為的な環境変化が関わっていることがある。全体として要因はよくわからない。
ということでシマアオジは比較的最近 (19 世紀) に急激に分布を拡大した経験のある種類のよう。Wang et al. (2022) の解析でここ 100-200 (中央値 147) 世代前から実効個体数を大きく減らした結果となっている。理由はよくわからないが 19 世紀に一時的に分布拡大を果たしたものがまた (これも理由はよくわからないが) 衰退した経緯を観察していないだろうか。
近年の減少は人為的な気候変動が顕著になった時期とは整合しないと言い切れないかも知れない。
また 19 世紀ごろの日本での生息数の変化など推定されているだろうか。
参考までに v. Schrenek Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856
では同時期にアムールを代表する種類の一つだったとのこと。
後でふと考えたのだが、シマアオジがヨーロッパに進出したのは猛禽類に対する狩猟圧が世界的に高まった時期に対応していないだろうか。可能そうなヨーロッパへの渡りルートを考えてみるとツミの繁殖域とよく似ている。
ツミやハイタカなどの渡りの広義 Accipiter 属が渡りながら小鳥を食べているのはおそらく確かで、小鳥の渡りを追って渡っている可能性も十分考えられる (そういえばかすみ網でツグミ類が大量捕獲されていた時代にタカ類の混獲も問題になっていた)。
シマアオジの渡りルートがボトルネックになるほど狭い地域に集まるならば、たとえ人が狙わなくてもタカ類が目をつけるのは当然のように思える。狩猟が盛んになって一時的にタカ類が減少していた時代はシマアオジも分布を広げて繁栄していたが、タカ類への狩猟圧が世界的に弱まるとともに長距離の経路を通るシマアオジ個体群の生存率が下がって特にヨーロッパで衰退した可能性を考えてしまう (カシラダカも同様かも)。
少しヒントになる情報では #ハイタカ 備考の [渡り中のハイタカ・アシボソハイタカの食性] がある。ホオジロ類はハイタカ類にとってはやや小さいかも知れないが、地上で採食する習性などより小型のタカにはちょうどよい獲物のような気がする。
アオジの数が増えているなど猛禽類によるホオジロ類全体への捕食圧要因では説明できない部分があるが、複数のホオジロ類のヨーロッパへの分布拡大理由と合わせて検討してよい感じがする。
あるいはアオジは長距離を渡らないのでリスクが低いのかも?
ツミが関東平野で繁殖するようになったのは都市への適応もあるだろうが、そもそも大陸も含め分布域全体で数が増えて進出した結果もあるのでは?
シマアオジのように北方型で長距離の渡りを行うホオジロ類に対する猛禽類による捕食圧を考えてみると、広義 Accipiter 属のうち特に小型の小鳥食に適した Tachyspiza 属があまり北方に分布しないため (世界でもツミが北限)、北方での繁殖が有利となった可能性もあるかも知れない。北限に近い北海道でツミが少なかった (たぶん) が温暖化で分布が北上して小型の小鳥にとって住みにくくなったなどの事情も考えられるかも。
小型の小鳥食に適したチゴハヤブサが影響を与えることも考えられるが、ツミとは越冬地も渡りルートもおそらく違うので、渡り途中の捕食圧は広義 Accipiter 属ほど大きくないかも。
「野鳥」1982年11月号 (No. 484) p. 30 の中村司氏の ICBP (BirdLife の前身) の第 18 回世界大会報告で、日本がタイからシマアオジを輸入していることが海外から指摘されたが、日本支部による報告済みとのことでそれ以上の議論にはならなかったとのこと。
Davaasuren et al. (2019)
Report of breeding habitat survey and inception of tracking Critically Endangered Yellow-breasted Bunting Emeriza aureola in Mongolia
モンゴルでの繁殖調査。ジオロケータを装着したがこの論文にはまだ結果は出ていない。以下の Heim et al. (2024) を参照。
Following the Yellow-breasted Bunting to Myanmar
に多少の情報がある。Muraviovka Park (アムール) でジオロケーターを装着されたシマアオジはミャンマーで越冬した可能性があるとのこと。越冬地の光景は繁殖地と非常に似ていた。中国から東南アジアで捉えた鳥を放つ「放生」(生き物を放つことによりご利益があると信じられる。merit release) の習慣があるが、その問題点を啓発するポスターなども示されている。
Samphors et al. (2022) Emerging evidence shows the global importance of the Boeung Prek Lapouv Protected Landscape, Cambodia for yellow-breasted buntings Emberiza aureola
カンボジアの越冬地の重要性。
Heim et al. (2024) Migration routes and adult survival of the critically endangered yellow-breasted bunting Emberiza aureola
ジオロケータによる渡りルートの推定。アムール、バイカル、モンゴル地方で標識された個体はまずまず帰還したがシベリア西部の個体ではそうではなかった。(分布を広げた時期の歴史的経緯によって) 西の個体群は長距離を迂回ルートを渡る必要があることが要因に考えられる (ただし回収例がないので経路は推定による)。
Yellow-breasted Bunting (Emberiza aureola) Amur で経路が見られると書いてあるが出版直後でまだ間に合っていないよう。
ロシア名は (ovshanka ホオジロ を付けることもある) dubrovnik で、Kolyada et al. (2016) の語源辞典では語源は明らかでないが、おそらくまばらなカシの木立 (dubrava) のはずれに生息する習性に関係があるのではとしている。
[ロシア内陸で個体数復活中]
イルクーツク州では 2023 年の観察で数が回復して局所的に普通種となっている報告がある: Popov et al. (2024a) Registrations of the yellow-breasted bunting Ocyris aureolus in the Irkutsk Oblast in 2023 (pp. 1757-1760)。
sibirds.ru (URL は以下参照) の市民データベース (North Eurasia Birds Watch の1グループ。#マダラチュウヒ の備考参照) による目撃情報に基づく観察で、
Popov et al. (2024b) Registrations of the yellow-breasted bunting Ocyris aureolus in the Irkutsk Oblast in 2024 (pp. 3459-3463) 2024 年のシーズンにもしっかり記録されもはや危険な状態ではない。
Yellow-breasted Bunting (sibirds.ru) シベリアのシマアオジのページ。今年の情報もあるが問題なく幼鳥が育っている。投稿のコメントでは他所でもいくつも巣立った幼鳥の集団をみかけたなどある。
投稿を遡ると 2016 年ぐらいにはすでに幼鳥が見られており、この年ごろから継続してよく観察されるようになっている。
場所も公開されており、イルクーツク近郊にもかかわらず撮影者が集まって繁殖に影響を与えるような状況にはなっていない模様。
北方型の種類であることを考えると、人口密度の低い地域では観察例が少ないだけで個体数は結構回復しているのかも知れない。
中国国内で問題として取り上げられたのは 2017 年以降が主なので、本格的な保護策がとられる前から数が回復していた兆候があったことになる。
現在ではシベリアでは個体数安定の傾向があり東南アジア (ミャンマー) で集団ねぐらも知られるようになったとのこと: Largest known Yellow-breasted Bunting roost found in Myanmar (BirdGuides 2024.12.11)。
ロシア沿海地方のシマアオジ: Gluschenko et al. (2025) Breeding birds of Primorsky Krai: the yellow-breasted bunting Ocyris aureolus (pp. 631-655)。
こちらも北海道と似た状況のようで過去 30 年間減少を続け 2023 年の観察段階でも回復しておらず、かなりまれで典型的な生息環境でも生息していない。渡り時期に通過する種でもあるが、渡り個体も顕著に減ってしまった。1970 年代の情報が中心でその後の観察までかなり期間が飛ぶのは普通種のためあまり注目されていなかったのかも知れない。
[絶滅寸前のキガオミツスイの歌文化の衰退]
どこに置くか悩ましいが、音声学習を行う鳥で「方言」が存在することはよく知られている。一種の文化とも言えるが、希少種で同種他個体の声を聞く機会が失われて歌文化が失われ、個体の適応度も下がった事例が報告されている:
Crates et al. (2021) Loss of vocal culture and fitness costs in a critically endangered songbird
オーストラリアで絶滅の危機にある (IUCN CR 種) キガオミツスイ Anthochaera phrygia Regent Honeyeater で残存しているオスの 27% しか本来のさえずりを歌わず、個体密度の特に低いところでは 12% のオスが自種のさえずりをまったく歌わず、他の種のさえずりしか歌わなかったという。
非典型的なさえずりの個体はつがい形成も少なかった。飼育下で育てた鳥も野生のものとさえずりが違っていた。さえずりの複雑さもこの数十年で減少したという。現在進行中のさえずりの多様性の減少が個体数減少につながっているかはまだわからないが、歌文化の喪失は絶滅の前触れ現象と言える可能性がある。
シマアオジのさえずりはどうだろうかと気になる理由。
キガオミツスイの歌文化については Crates et al. (2025) Conserving avian vocal culture にも言及があり、他にも歌文化の衰退の兆候が知られている事例があるとのこと。キガオミツスイは飼育下保全が進められているが本来の歌を聞かず飼育される同種個体の声を聞いて育つので未完成な歌になるとのこと。2020 年の段階で野外のオスはすべて飼育下で育ったもので野生での文化を知らない。
The road to saving Australia's regent honeyeaters かつては普通の鳥だったが生息地破壊で激減。気候変動による干ばつや森林火災も要因で生息環境が非常に劣化している。
かつて多数生息していた時は群れを作って採食することでより強力なミツスイの種類、に対抗していたが、今では生息地を奪われてしまっている。キガオミツスイのようなスペシャリストにとって、都会のように劣化した環境を好み攻撃的なクロガオミツスイ Manorina melanocephala Noisy Miner は強力な敵になっている (巣の捕食さえも行う)。
世界が固唾をのんで見守る中、飼育下増殖と放鳥が進められている。日本語記事もいくつか存在するが、多少興味半分にも見えるものもあり、原文が読めるのでニュアンスや背景を知るためにご参照いただければと思う。
Can This Critically Endangered Bird Survive Australia’s New Climate Reality? (Audubon の記事 2020)。極端気象が当たり前になった気候を生き延びることができるか。
飼育下増殖と放鳥が進められているが、ここ3年 (2020 年段階) は干ばつがひどくて放鳥できていない。これは賢明な判断だったようで数か月後には火災に襲われた。現況をそのまま伝えるしかない。
哲学者の Glenn Albrecht は環境変化、自然災害、人為的破壊などから受ける無力感や苦痛を "solastalgia" と名付けた。
Scientists ramp up efforts to save regent honeyeater predicted to be extinct in 20 years (ABC News 2022)
手を打たなければ 20 年以内に絶滅するだろう。これは誇張ではない。もしそうなればオーストラリアにヨーロッパから入植以来2種目の絶滅鳥類となる。現在の保全策では絶滅速度を遅らせることはできても阻止できない。これから 20 年間2年に一度 100 羽を放鳥してようやく絶滅を防げるレベルと見積もられる。生息地の環境復元などあらゆる手段が必要である。
必要な資源を求めて移動する放浪的 (nomadic) な生活様式 (これが世界の注目を浴びている理由の一つだろう) のため研究も難しく保全も困難。
30 万 km^2 の広大な地域に 300 個体以下。
動物園では野生個体のさえずりの録音を聞かせる努力も試みられている。
Heinsohn et al. (2022) Population viability in data deficient nomadic species: What it will take to save regent honeyeaters from extinction が関連論文。
2023 年に若鳥が観察され少し安堵感も生まれた: Sightings of critically endangered regent honeyeater in NSW give conservationists hope、
Wild success for regent honeyeater breeding program。
それほど長命の種類ではないので繁殖個体が減ると数がすぐに減少する恐れがある。
森林火災の後はヤドリギは介在なくして自生しないので植樹による復元が行われている:
Birdlife Australia working with Aboriginal land council to return mistletoe to burnt woodlands。鳥による自然の種子散布を待っていては最低 30 年はかかり待つことはできない。
こちらは研究論文: Crates et al. (2021) Poor-quality monitoring data underestimate the impact of Australia's megafires on a critically endangered songbird
2019-2020 年の火災でこの種の生息場所の 40% が失われたとされるが、どの指標を用いるかによって評価が異なってくる。急激に個体数を減らしている種類の影響評価に過去の分布データ (現在の目撃分布と合わない) を用いるのは適切でない。
また市民科学は知られた場所に観察メッシュが偏り、2015 年以降に知られた巣のうち 5% しか市民科学で見つかっていない。
-
シマノジコ
- 学名:Emberiza rutila (エムベーリザ ルティラ) 赤褐色のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:rutila (adj) 赤褐色の (rutilus)
- 英名:Chestnut Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
rutila は短母音のみで冒頭にアクセント (ルティラ)。
単形種。
チョウセンノジコの別名があり、古くから飼鳥として飼育されていた (コンサイス鳥名事典)。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" では Hokkaido? とあり北海道にも産する可能性があると考えられていたよう。シマアオジ同様に "シマ" は北海道を指していたものか。
漢字表記される場合は "縞" が用いられることもある (コンサイス鳥名事典) が、"島" を用いているものもある例「決定版 日本の野鳥 650」(真木広造写真; 大西敏一, 五百澤日丸解説 平凡社 2014) もある。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
-
ズグロチャキンチョウ
- 学名:Emberiza melanocephala (エムベーリザ メラノケパラ) 黒い頭のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:melanocephala (合) 黒い頭の (melano- (接頭辞) 黒い kephali 頭 Gk)
- 英名:Black-headed Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
melanocephala は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみで -ce- がアクセント音節と考えられる (メラノケパラ)。
"ズグロ" の部分は学名・英名・和名ともに対応がよい。チャキンチョウは飼い鳥としてよく知られもちろん色彩由来。その名称に学名や英名から "ズグロ" を付けたものか。
単形種。
-
チャキンチョウ
- 学名:Emberiza bruniceps (エムベーリザ ブルニケプス) 茶色い頭のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:bruniceps (合) 茶色い頭の (brunus, brunius 茶色の -ceps 頭の)
- 英名:Red-headed Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
bruniceps は合成語のため発音はよくわからないが、brunneus は短母音のみで -ni- がアクセント音節と考えられる (ブルニケプス)。ただし brunus は冒頭が長母音。brunneus と合成される際に短母音となっているのでおそらく同様に短母音と思われる。
冒頭が長母音であってもアクセント位置には影響がない。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。単形種。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
-
ノジコ
- 学名:Emberiza sulphurata (エムベーリザ スルプラータ) 硫黄色のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:sulphurata (adj) 硫黄を含む (sulphuratus)
- 英名:Japanese Yellow Bunting, IOC: Yellow Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
sulphurata は sulphur は短母音のみ。-ata の冒頭が長母音でアクセントもここにある (スルプラータ)。
学名は Temminck and Schlegel (1848) "Fauna Japonica" 由来。
記載時も Emberiza sulphurata Temminck & Schlegel, 1848 (本文記載)。
極めて単純に見えるが Fauna japonica (Siebold) - Aegithalos caudatus trivirgatus にあるように本文と図版 (Emberiza sulphurea) の学名が違っていた。
Mlikovsky (2012) Zoological bibliography, or, Opera zoologica
はこの2つの名称を別学名と判定し、出現順を逆転させて図版の sulphurea の方を無効名としたとのこと。sulphurea の用例は事実なく、sulphurata の用例は多数あるため。
ただし別学名か、同一物の別綴りかの判定は自明でない模様。図版。
sulphurata のみが文献に使われていることを指摘したのは Morioka and Dickinson (2011) とのことで、我々が長年使ってきたノジコの学名は実はそれほど自明なものではなく、これらの判断がなされなければ形式的には先取権のある sulphurea が使われても不思議でなかったことになる。
繁殖地で見ると大変日本的な種類だが Temminck and Schlegel が日本を意味する種小名を用いなかったのは、ミヤマホオジロやクロジもさらに以前に日本から記載 (それぞれ Temminck 1835, 1836) しており、#タンチョウの学名に対する Temminck の提案のように同地域に複数種が存在する場合は国名を用いるのは適切でないと考えたものかも知れない。
ノジコの記載文献では日本から8種のホオジロ類を載せている。
なおホオジロのみは同じ文献で "du Japon" を付けて記載している (le bruant fou du Japon) が、これは対応種 ヒゲホオジロ Emberiza cia Rock Bunting があるため。ホオジロの種小名も "ヒゲホオジロに似た" の cioides になっている。この学名は Brandt (1843) が記載したもの。
ノジコなどはヨーロッパにとって身近な対応種がないため "du Japon" とならず、種小名にも産地が影響を与えなかった理由が考えられる。
単形種。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
ノジコの現在の標準的な英名は Yellow Bunting となっているが、この名称はヨーロッパの普通種の#キアオジに使われていたこともあった。そのために Japanese を付けて区別していたのだろうが、その国の固有種でないものに国名を付けるのは次第に避けられるようになって改名されたものと想像できる。
キアオジにはもっと広く使われている Yellowhammer (または Yellow Hammer) の名称があるので特に支障をきたさなかったのだろう。
ノジコが秋の渡りで多く通過する場所として福井県の中池見湿地が有名である。2012 年ラムサール条約湿地に認定。
Information Sheet on Ramsar Wetlands にあるようにノジコが認定基準の一つとなっている。ここはコホオアカが毎年のように通過するなど面白いところである。
仲村 (2024) Birder 38(4): 44-45 に中池見湿地とノジコ (標識調査) の記事がある。かつては IUCN VU 種とされていたが、BirdLife は 2022 年 LC (ほとんど懸念なし) 種と変更した。これまでの個体数見積もりが過小で、10000 羽を下ることはないだろう、また減少傾向が確認できないことが由来。
Yellow Bunting Emberiza sulphurata (BirdLife) 近年の繁殖調査の結果ではむしろ増えている。
繁殖つがい数 10 万以上の根拠は Brazil (2009) "Birds of East Asia" のカテゴリーによるらしいが、日本で BM3-4M3 となっていて 10 万に対応する BM1 や 2 にはなっていないのでかつてはもっと多かったの意味か。従来言われていたほど希少ではないらしい。
ノジコは野路子、野地子と書かれるように湿地を好むホオジロ類で、渡り途中もそのような環境で記録されることが多い。
秋の渡りは 10 月中旬が中心で、アオジの渡りより一足早い。このころに「季節外れ」のアオジらしい地鳴きを聞いた時はノジコはよい候補となる。春の渡りはゴールデンウィークのころで、都市公園でもさえずりが聞かれることがある。春の渡りでは特に中池見湿地を訪れるわけではない。
ノジコの識別相手となるのはアオジであろうが、容姿もだいぶ違っているのでよく見えれば迷わないであろう。通常の識別点の最初の方に書いていないかも知れないが、下嘴の色が違うことはもっと注目されてよい。
問題は地鳴きの識別の方だろう。ノジコはそのような湿地環境を好むので姿が見えにくいことが多く、ホオジロ類の地鳴きであることはわかっても種類判定が難しい。アオジの地鳴きと比べたことがあるが、定量的とまで言える識別点は見つけられなかった。特に周波数 (音の高さ) では区別できないのではと考えている。
強い声で鳴く時はアオジではピークから周波数が下降する部分が見られる (ソノグラムでは斜め右下がりになる)。これは識別点になりそうであるが、弱い声の場合は区別が難しい。ノジコの方が地鳴きはより細い声との記述はこの特徴を捉えたものと考える。
両種が越冬する台湾のバーダーも識別に苦労しているそうである (つまり録音をしても難しい)。
地鳴きでホオジロ類の識別がかなり可能とされる方もあるので挑戦していただきたい (独断と偏見の識別講座II 第37回 Emberiza II <ホオジロ類 II> 波多野邦彦 2013) を参照。
Paeckert et al. (2015) の分子系統解析 (#アオジの備考参照) でもノジコとアオジは比較的近縁と考えて良さそうである (論文の近縁種比較の Table 3 を参照)。ノジコはホオジロ類の中でも最初に日本に定着した可能性があるとのこと。
ND2 など適当な遺伝子を用いた BLAST を行ってもノジコの方がアオジより古い系統となる。現在の繁栄状況を見ても想像できるようにアオジの方がおそらく優勢で、ノジコは限られた環境に住んでいる状況と考えられる。遺存繁殖固有に近い状況だろうか。大陸ではアオジよりシベリアアオジの方がさらに優勢で (大陸種の方が一般に優勢と考えれば) ノジコがかつて分布していても事実上残らなかったのかも知れない。
クロジよりノジコの方が遺伝情報が一層少なく使う遺伝子によって結果が異なる。cyt b を使うと Paeckert et al. (2015) のように一番古い系統となるがアオジとかなり離れてしまうのでややありそうにない感じがする。情報不足が否めない。
ノジコのミトコンドリアゲノムは韓国で読まれていて [Lee et al. (2017) Complete mitochondrial genome sequence of Emberiza sulphurata (Emberizidae: Emberiza)] これを用いるとアオジと近縁になり、ノジコとアオジの関係はおそらく ND2 を用いた系統樹の方が現実に近いと思われる。
渡り時期が多少違うのもアオジとの競争の結果生じたものかも知れないと思えてきた。
-
アオジ (シベリアアオジが分離された。アオジの学名や英名も変わった)
- 第8版学名:Emberiza personata (エムベーリザ ペルソーナータ) 仮面を付けたホオジロ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Emberiza spodocephala (エムベーリザ スポドケパラ) 灰色頭のホオジロ
- 第7版亜種学名:Emberiza spodocephala personata (エムベーリザ スポドケパラ ペルソーナータ) 仮面を付けた灰色頭のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 第8版種小名:personata 仮面を付けた
- 第7版種小名:spodocephala (合) 灰色の頭の (spodiacus (adj) 灰色の、kephali 頭 Gk)
- 第7版亜種小名:personata 仮面を付けた
- 英名:Masked Bunting (アオジ) と Black-faced Bunting (シベリアアオジまたは旧名)
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
personata は o と最初の a が長母音で後者にアクセントがある (ペルソーナータ)。
spodocephala 来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみで -ce- がアクセント音節と考えられる (スポドケパラ)。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)で2種に分離され、この学名、英名を引き継ぐのはシベリアアオジとなった。シベリアアオジには2亜種あるが、日本で記録されるものは基亜種 spodocephala とされる。
Vruant Masque 仮面をかぶったホオジロの名前。
アオジ は分離されて単形種 Emberiza personata (仮面を付けた) 英名 Masked Bunting となった。
personata は -na- が長母音でここにアクセントがある。
IOC 12.1 以降、HBW/BirdLife 2017年7月以降、Clements 2022 以降でこの分類が採用されている。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" の時代には Emberiza personata アオジと Emberiza spodocephala (当時の名前でカラアオジ) が別種で、これらがまとめられて同種となったことでアオジが基亜種にならず学名が変化する問題が発生したよう。
ツグミとハチジョウツグミの場合と同様だった模様。
この分類変更は、形態的な差に加えて Paeckert et al. (2015) Phylogenetic relationships of endemic bunting species (Aves, Passeriformes, Emberizidae, Emberiza koslowi) from the eastern Qinghai-Tibet Plateau
のホオジロ類の分子系統研究による。(広い意味の) アオジで、日本・サハリンのものと大陸のもので亜種としては大きな差があることがわかった。この文献の Fig. 5 を参照。
これまでのアオジの学名 Emberiza spodocephala は長く使われてきており染み付いている人もあると思われるが海外データベースなどに報告する時には注意が必要である。またこれまでもこの2亜種を見分けて記録するのが普通であったため2種になっても識別などもあまり問題はないと思われるが、音声のみの記録をどう扱うかは問題になるかも知れない。
これから新たに記録される方は2種の識別が必要になることを念頭に置く必要がある (シベリアアオジは数がずっと少なく、実際上はあまり問題にならないかも知れないが)。
茂田 (1995) Birder 9(6): 46-52 にアオジの亜種と識別の記事がある。現代の分類を踏まえたものではないが、いくつかの重要な情報がある。
かつてウスリー南部で extremi-orientis (非常に東方の) 亜種が記載されていた (Shulpin, 1928)。現在では spodocephala のシノニムとされている。Dement'ev and Gladkov (1954) では亜種 sordida (Blyth 1845) (Clements による分布域は中国西部からインド東部、ミャンマー北部、インドシナ) のシノニムとされているがこれは正しくないと指摘していた。
なおこの学名は Emberiza spodocephala flaviventris Shulpin, 1927 として発表したものが Emberiza flaviventris Stephens, 1816 と衝突していることがわかって改名されたもの (参考)。
原著では melanops (Blyth 1845) (分布域はプリアムール、沿海地方、朝鮮半島、満州から中国) のシノニムとなっており、BirdLife の地図では繁殖分布していないとされる中国東部から東北部も含めた連続分布を考え、extremi-orientis と sordida を合わせたような分布域を想定していたように見える。
この文献では sordida への言及は見当たらなかった。
Emberiza sordida Hodgson, 1844 (Avibase では Blyth, 1845) は基産地ネパールで別種と考えていたのかも知れない。
また、Dement'ev and Gladkov (1954) では personata は「島の」アオジの扱いになっている。Paeckert et al. (2015) でも "island clade" となっている。
Paeckert et al. (2015) では spodocephala と sordida との遺伝的違いは明らかでなかったとのこと。
spodocephala と sordida の地理的関係はちょうどオオルリ亜種チョウセンオオルリ Cyanoptila cyanomelana cumatilis とカラオオルリ Cyanoptila cumatilis と同様である。
茂田 (1995) は亜種 sordida にかつて extremi-orientis に対して使われたカラアオジの名称を提案している。
茂田 (1995) の時代にはフィリピンで記録種に入っていたものがシマアオジと同定され外されたことが記されている。現在のフィリピンのチェックリストではシベリアアオジが 2019.11.2 が初記録でこれまで 10 個体の記録があり、迷鳥となっている。アオジはまだ記録されていない。
渡辺 (2003) Birder 17(11): 99-105 によれば J → 1W の換羽でアオジは尾羽を更新するがシベリアアオジは更新しないとのこと。
[Emberiza 属の系統分類]
参考までに Paeckert et al. (2015) のクレードと日本に関係ある種の関係を挙げておく。Emberiza 属は大きいので、(ロシアの分類に使われているように) いくつかに分割しようとの機運が出てくればあるいはこのように分割されるかもしれない。
後に紹介する Boyd の分類で説明するように、"ジュリン" を独立した属にしたい場合にはこれら検討や分離が不可欠になる。
Clade I: キアオジ、シラガホオジロ、ホオジロ、イワバホオジロ、イワバホオジロ、ズアオホオジロ、ホオアカ
Clade II: レンジャクノジコ、ズグロチャキンチョウ、チャキンチョウ
Clade IIIa: ミヤマホオジロ
Clade IIIb: シロハラホオジロ、コホオアカ、キマユホオジロ、カシラダカ、シマアオジ、シマノジコ、ノジコ、アオジ、シベリアアオジ、クロジ & シベリアジュリン、コジュリン、オオジュリン
(Clade IIIb はさらにグループ分けすることが可能で、"&" の場所で区切ると生態ともよく一致し、系統的にもまとまっている)
Clade IVa, IVb: 該当なし (アフリカのグループ)
Boyd は一段と踏み込んで属を分離しているので参考までに紹介しておく。種のリストは日本および近傍のグループに限った。和名の後に x の付いているものは日本で記録 (検討種扱いも含む) なし。
かなり遠くからの迷鳥もあるのでこれらも今後記録があるかも知れない。
単形属の場合は自動的に属名和名を与えてみた。属名の性の変更に伴う種小名語尾変化があるので少し注意が必要。
現在の Emberiza 属 は全体で単系統をなしているので、広義 Accipiter 属のような分割の必然性はない。分類学者のさじ加減とも言える。
Boyd は系統間の距離などを用いて他の分類群の属に相当する程度に分ければこのようになる提案を示している。確かにこの程度の分割はわかりやすく、例えばロシアの図鑑を見た時に感じる強烈な学名の違和感はかなり解消してくれるだろう。
Koblik (2007) Taxonomical revision of genus Emberiza sensu lato L. (Emberizidae, Aves). Comments to the checklist of the birds of Russian Federation がロシアのホオジロ類の属分割提案の論文 (系統樹は少し古い)。
ロシアの分類は Balatskij Birds of Northern Eurasia が保守・改定しており (記述現時点で 2023 年版が出ている) ホオジロ類は属が細分されている。
上記 Paeckert et al. (2015) の Clade I, IIIb をさらに分割する形になっている。
類縁のキアオジ、シラガホオジロが同じ属となるのは確かにわかりやすい (しかしキアオジがタイプ種のため Emberiza 属に残る日本の種はこれらのみになる!)。
ミヤマホオジロが単形属となるのはむしろわかりやすい感じがする。
ホオジロが日本産は1種のみの Cia 属となるのもある意味わかりやすい (他のホオジロ類との違いが大きい。種小名の由来)。
Ocyris 属は日本のホオジロ類の多くを占め全種の記録がある。
ロシアと共通種が多いので学名の共通化にはよいかも知れない (このリストを見ておくとロシアの学名に驚くことはないだろう)。
Schoeniclus 属も日本で全種記録がある。これら2属は極東を主な分布域とするグループと考えられるので、全部 Emberiza と呼ぶよりも概念がわかりやすいかも知れない。Paeckert et al. (2015) の Clade IIIb に相当。
この2グループは和名でも呼び分けているので分割されても不自然な感じがしない。
まとめれば、Boyd の分類を採用した場合は珍しい種類を除けば日本のホオジロ類は渡り鳥、冬鳥を中心とした Ocyris 属に大部分まとまり、"ジュリン" を Schoeniclus 属、ミヤマホオジロ、ホオジロ、ホオアカがそれぞれ別の属になる程度であまり大きな混乱は起きないかも知れない。
説明する側としてもグループの違いが明らかになってむしろ説明しやすいかも知れない。
これまでの Emberiza の名称は ホオジロ科 Emberizidae と読み替えればよいので、日本語で「エンべリザ」を総称として残すこともできるだろう。ただしこの分類を使うとこれまでの使い方でホオジロ sp. / Emberiza sp. のようには書けなくなる。
ちなみに Gaudin は Schoeniclus 属を広く扱い、Boyd の Ocyris 属なども含むなど属境界が多少違っている。
Schoeniclus の属名が優先されるのは先取権によるものだろうが、
やはり「アシに関係した」や "ジュリン" のイメージが強いので、日本の多くのホオジロ類がこの属名にまとまるよりは Ocyris 属の方が望ましい感じがする。
Howard and Moore 4.1 でも広義 Emberiza 属を分割したいことは読み取れ、実際に Gaudin に近い分け方を採用している。つまり Paeckert et al. (2015) の Clde III を Schoeniclus 属としている。
この点は H&M としては珍しく IOC に比べて分子系統分離を先行させている。
なお Schoeniclus 属はシギ類にも用いられていた (#オバシギの備考参照)。Howard and Moore 4.1 が Schoeniclus 属を用いているのは Schoeniclus Forster, 1817 に先取権があると解釈されるためと想像できるが微妙かも知れない。
なお "ジュリン" だけをまとめて別属にすればよいと考えられる方もあろうが、これを分離すると残りが単系統をなさないので、"ジュリン" を分離したければどうしても他の部分も系統を分割する必要が生じる。
広義 Accipiter 属とチュウヒ Circus 属のような関係である。Circus 属はあまりにも普及しており、生態的にも大きな違いがあるので Accipiter 属に改名するのはさすがに多くの人にとって抵抗があるだろう。
"ジュリン" はそこまでではないので Emberiza 属のままでも構わないとするのはこれまでの主要な考え方。
もし分割する場合、キアオジが Emberiza 属のタイプ種のため、最低限に細分類しても日本のホオジロ類の大部分は必然的に Emberiza 属から外れることになる。言い換えれば分割と属名変更の決断は "ジュリン" を分離したいか、あるいはユーラシア東部中心の Clade III を分割したいかの程度問題となる。
コシアカホオジロ属 "Fringillaria" (新属が必要)
コシアカホオジロx "Fringillaria" affinis Brown-rumped Bunting (アフリカ)
? 亜科 "Fringillariinae" (新亜科が必要。アフリカのグループで種リストは省略)
? 属 Cosmospina
? 属 Fringillaria
ホオジロ亜科 Emberizinae
ハタホオジロ属 Miliaria
ハタホオジロx Miliaria calandra Corn Bunting (ヨーロッパから中東)
ホオアカ属 Onychospina
ホオアカ Onychospina fucata Chestnut-eared Bunting
クビワホオジロ属 "Emberiza" (新属が必要)
クビワホオジロx "Emberiza" koslowi Tibetan Bunting (中国西部に局地分布)
ホオジロ属 Cia
コマホオジロx Cia jankowskii Jankowski's Bunting
ヒゲホオジロx Cia cia Rock Bunting
(ミヤマヒゲホオジロより分離)x Cia yunnanensis Sharpe's Bunting
ホオジロ Cia cioides Meadow Bunting
ミヤマヒゲホオジロx Cia godlewskii Godlewski's Bunting
ズアオホオジロ/イワバホオジロ属? Glycyspina
イワバホオジロ Glycyspina buchanani Gray-necked Bunting
キノドアオジx Glycyspina cineracea Cinereous Bunting
ズアオホオジロ Glycyspina hortulana Ortolan Bunting
ノドアカホオジロx Glycyspina caesia Cretzschmar's Bunting
キアオジ/シラガホオジロ属? Emberiza
ノドグロアオジx Emberiza cirlus Cirl Bunting
ハイガシラホオジロx Emberiza stewarti White-capped Bunting
キアオジ Emberiza citrinella Yellowhammer
シラガホオジロ Emberiza leucocephalos Pine Bunting
チャキンチョウ/レンジャクノジコ亜科? "Melophinae" (新亜科が必要)
レンジャクノジコ属 Melophus
レンジャクノジコ Melophus lathami Crested Bunting
チャキンチョウ属? Granativora
ズグロチャキンチョウ Granativora melanocephala Black-headed Bunting
チャキンチョウ Granativora bruniceps Red-headed Bunting
オオジュリン亜科? "Schoeniclinae" (新亜科が必要)
ミヤマホオジロ属 Cristemberiza
ミヤマホオジロ Cristemberiza elegans Yellow-throated Bunting
ウスグロホオジロ属 Latoucheornis
ウスグロホオジロx Latoucheornis siemsseni Slaty Bunting
オオジュリン属? Schoeniclus
コジュリン Schoeniclus yessoensis Ochre-rumped Bunting/Japanese Reed-Bunting
オオジュリン Schoeniclus schoeniclus Reed Bunting/Common Reed-Bunting
シベリアジュリン Schoeniclus pallasi Pallas's Bunting/Pallas's Reed-Bunting
カシラダカ属? Ocyris
カシラダカ Ocyris rusticus Rustic Bunting
コホオアカ Ocyris pusillus Little Bunting
シマアオジ Ocyris aureolus Yellow-breasted Bunting
シマノジコ Ocyris rutilus Chestnut Bunting
シベリアアオジ Ocyris spodocephalus Black-faced Bunting
アオジ Ocyris personatus Masked Bunting (Boyd にはないが分離)
ノジコ Ocyris sulphuratus Yellow Bunting
キマユホオジロ Ocyris chrysophrys Yellow-browed Bunting
シロハラホオジロ Ocyris tristrami Tristram's Bunting
クロジ Ocyris variabilis Grey Bunting
-
クロジ
- 学名:Emberiza variabilis (エムベーリザ ウァリアービリス) 変化するホオジロ (誤解?)
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:variabilis (adj) 変化しやすい、違いの大きい
- 英名:Grey Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
variabilis は a が長母音でアクセントもここにある (ウァリアービリス)。英語に近い単語があるが (variable, variability) いずれもアクセント位置が違うのでラテン風に発音したい場合は参考にならない。
茂田 (1995) Birder 9(9): 46-51 によればかつてさまざまな属に分類されていた。その中でも Tisa Clark, 1907 属はクロジをタイプ種として提唱されたもの (記載)。
語源はロシア語で鳥を意味する 単数 ptitsa (The Key to Scientific Names の複数形は間違い) から (*1)。色彩は "slaty gray ..." などと表現されており、(この文献が出典でないかも知れないが) 英名の Grey Bunting (学名と違いが大きい) の由来となっているかも知れない。
現地名 (とはいえ単に鳥の意味) を属名に用いたのは、時代的にも遅くまだ使われていない (動物全体で過去に用例のある属名を調べるのは大変) よい属名を思い浮かばなかったためかも。
2亜種あり (IOC)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では亜種を認めない立場。Clements が同様の立場をとっている。
亜種を認める立場ではもう一つの亜種は musica (音楽家) でカムチャツカ南部に分布するとされる (ウタクロジの和名あり)。
確かにカムチャツカ個体のさえずり記録を聞いても日本のものとそれほど違う気がしない。
Dement'ev and Gladkov (1954) では musica はシノニム扱い。
Tiza variabilis kurodai Momiyama, Annot. Ornith. Orient. 1921(1), p. 10 本土 の記載もシノニムとなっている。
もし kurodai が北方からの渡り個体群で musica を亜種と認める立場でも、musica の記載の方が早いので kurodai は亜種名にはあまり残りそうにない。
追記: Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" (Birds of Sakhalin Island) p. 638 で musica は大型で小型個体には対応しないと思われることを知った。
小型個体が亜種チャボクロジとされたことがある。梶田 (2016) Birder 30(1): 26「大きなクロジと小さなクロジ」。kurodai の記載は比叡山の冬季 (1926.11) の標本から。YIO-00056 (山階鳥類研究所の標本データベースのタイプ標本)。
参考 1, 2 Kuroda (1932) がシノニムと判定。
矮小化個体とされて日本のリストで亜種とされることはなかったが、梶田 (2016) の研究によれば嘴高分布が二峰性とのこと。
香川の野鳥ファイル No. 56 クロジ にも解説がある。
古くから知られていて「こくろじ」と「おほくろじ」と分けて呼ばれと分けて呼ばれていたとのこと。また今のところ繁殖期に小型個体が確認されているはカムチャッカ半島のみ [梶田 (2016) によればサハリンのみ] とのこと。
カムチャツカの musica の記載は (p. 201) Kittlitz (1858) "Denkwuerdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika, nach Mikronesien und durch Kamtschatka"
で見られ、新世界ホオジロ類の Zonotrichia musica と考えていた模様。当時は種扱い。ペトロパブロフスクとアバチャの間での記録。このためクロジもかつて Zonotrichia 属に含められたこともあった [cf. 茂田 (1995) Birder 9(9): 46-51]。
さらにノジコ、アオジとともに Euspiza 属に含めた事例: Pelzeln and Lorenz (1886) Ueber eine an das k. k. naturhistorische Hofmuseum gelangte Sendung von Vogelbaelgen aus Japan。
海外の研究者がなぜそれほどクロジに注目していろいろな属に編入したり独立属を与えたのかは、#ツリスガラ備考の [スズメ小目 Passerida の系統分類] の並びを参照いただきたい。
つまり ホオジロ外科? Icteroidae (Emberizoidae) ("外科" は Boyd が付けたもの) の本場は新世界で、研究者からみると旧世界のホオジロ類とは関係があるはずでどのように進化したものか関心が持たれていた。
新世界と旧世界の境界にあたるロシア北東部で進化の中間段階があると考えるのは自然で、旧世界のホオジロ類と一線を画すクロジ (ように見えた) は実は新世界ホオジロ類に属していて進化の中間段階を表すのではないかと目論まれたわけである。
結果的にはこの見方は (おそらく) 間違っていて、分子系統研究の結果 Emberiza の中で古い系統でないことがわかったわけだが (#アオジ備考参照)、外見もだいぶ違う (まず色が特異的で、大きいし、さえずりも特徴的) ので現在でも何が違うのかなど少し片隅にとどめておいてよいかも知れない。
日本にもクロジは生息するが、カムチャツカのクロジの方が注目されたのはこのような経緯もあるだろうと想像できる。
論文題目を見ていて思い出したが、Kittlitz (1858) が Zonotrichia musica を記載した時はアラスカはロシアが保有していて (ロシア名 Alyaska 由来) 1867 年にアメリカが購入したのだった。当時のロシアには新世界ホオジロ類の分布域が含まれていた。
[種小名の意味]
種小名の variabilis が何を意味するかはあまり明確でない。
夏羽・冬羽の差を表している? との考え [日比 (2000) Birder 14(11): 68-70 で紹介されている] や、大きさなどの個体差が大きい [加藤 (2001) Birder 15(3): 58-59] ことを指摘する考えもある。
Bruant Variable では和名として Ku-ro-si-toto が紹介され Toto noir [黒いトト (シトトとすべきところで区切りを間違えた?)] と解説されている。
Temminck のこの記載を見ると冬羽の記述が細かく、夏羽・冬羽の差を表していると考えるのが適切と思える。また Bruant Variable は圧倒的に「変化するホオジロ」の意味 (他のホオジロ類の "変形" などの意味ではない) と解釈できる。
図版 にはオス・メスが出ているがオス・メスの違いが非常に大きいことを Variable と表記した可能性はあるのか。
Temminck & Schlegel (1845) (Fauna Japonica より) では雌雄の違いが主に記述されているのでこちらの方かも。
そう思ってみると、前記の Bruant Variable (Nouveau recueil de planches coloriees d'oiseaux) の方ではメスについてわずかに触れる程度 (つまりよくわかっていない) で、雌雄を夏羽・冬羽の違いと勘違いしていた可能性が高そう。Temminck & Schlegel (1845) で改めて雌雄と同定して記述を書き直したように見える。
さらにそう思って見ると記載時の 図版 ではミヤマホオジロの方はオスと書いてあるのにクロジは夏羽とある。雌雄を夏羽・冬羽と解釈すればものすごく "変化する" (!) ホオジロということになる。
Fauna Japonica を著するに当たって改めて図版を用意し、オス・メスを描き分けたことになっている。この中でも前著 (Nouveau recueil ...) の図版で示したものはオス (夏羽の記述を訂正まではしていないが) と書いてある。どちらか片方しか読まないと真意がわかりにくいが、解釈の間違いに気づいたが学名を訂正するわけにはいかないので...とうやむやになったものと想像できる。
ここでは "変化するホオジロ" (誤解?) を採用した。
variabilis の他の用例を調べてみると、
・Aquila variabilis Koch, 1816 (参考) これはヨーロッパハチクマに与えられた新名とのこと。当時は属を変える時に種小名を与えることができた (#ノスリの備考参照)。
個体変異が大きいの意味だろうか (同一個体でも変化するのか区別できないかも)。命名権を得るためかも知れないがなんとヨーロッパハチクマが Aquila 属に入れられたことがあった (!)。
・Lagopus variabilis ?, 1836 (参考) ヌマライチョウ (旧名カラフトライチョウ) のことで、これは夏羽・冬羽の変化を示していると想像できる。
・Machetes variabilis Wood, 1837 (参考) エリマキシギのこと。夏羽・冬羽の変化、多形の存在など想像できる。
・Rhynchaea variabilis Temminck, 1836 (参考) タマシギのこと。これは同種の別学名に類似していて "染め分けられた" の意味で用いた可能性があるが、雌雄の違い、夏羽・冬羽の変化も考えられる。これは Temminck 自身の用例なので参考になるかも。
・Accipiter variabilis Pallas, 1811 (参考) これはヒメハイイロチュウヒとハイイロチュウヒ両者を含むと判定された。個体変異が大きいの意味だろうか。
他にも用例があるが馴染みのある系統のみを調査した。ということでいずれの用例もありそうだが、他のホオジロ類の "変形" などの意味ではない点は他の用例からもおそらく正しいと考えられる。エリマキシギやヌマライチョウの例を見ると夏羽・冬羽の違いは有力候補かも知れない。"染め分けられたホオジロ" はホオアカの方がより該当しそうでおそらく除外できそうに思える。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
備考:
*1: 例によっておまけ。ロシア語の ptitsa はもちろん基本中の基本の単語で、鳥に興味のある人がロシア語 (でも他のスラブ系言語でもよい) を学ぶ際に真っ先に覚える単語だろう。
しかし簡単に見えて入門者には実は少し厄介。
ロシア語でも他のスラブ系言語でもよいが、ラテン語にほぼ近い格変化が存在するのでまずそれを学ぶことになる。鳥の、鳥に、鳥を... そして複数形もある... などで語尾が変化するのを覚えるわけである。
初学者が見るだろう単語集などを見ると、女性名詞であることはよいとしても (活) とある。「これは何だ?」というわけだが、ロシア語では生物 (活動体) とそうでないものを区別して変化形が変わる。具体的には "鳥たちを" と "鳥たちの" の語形が同じになる (男性名詞では単数形でも)。
そんな面倒くさいのは何だ、と感じるが、日本語では "ある" と "いる" を使い分けるようなもの。
それぞれの言語で見慣れていれば自然に感じるのだろう。ロシア語でもどこまでが生物かやはり議論があるようでウイルスはどちら、など。日本語だと "ウイルスがいる" の方になるだろうか。
もう一つ厄介なのは語尾の -ts- の音のために変化形語尾が通常の女性名詞と少し違ってくる。これはほとんど自然な発音にするために綴りが違うだけのようなものだが、この2つの点によって "鳥" は代表的な女性名詞の変化と言えなくなってしまう。少し面倒な点があるため入門用テキストでも通常後の方に出てくる。
もう一つ注意すべき点は発音で、pt- で始まる英単語は少ないし (基本的にギリシャ語由来の外来語か学名)、英語では冒頭の p を発音しないので我々は pt- の発音に慣れていない。鳥をロシア語で "プティーツァ" と言うことはすぐ覚えられても、冒頭の "プ" につい母音が入っていまう (同様に翼竜の pterodactyl や pterosaurs を "プテロ..." と読むと日本語の音はかなり異なることになる)。
これを聞くと "それは違う" と言われる次第。実際には p の音を母音を入れないように軽く冒頭に添えるように発音すると近い音になる。属名に Tisa を与えたのは、ロシア語の文字と一見かなり異なるように見えても実際の発音に近いところを捉えていると言えるだろう。
クロジが Emberiza に内包されて使われなくなったのはちょっと惜しいところ。
ロシア語 ptitsa に関連して ptichka の単語がある ("プ" の部分を注意していただくこととして "プティーチカ" と読む)。これは ptitsa の指小語で小さい鳥というより愛称。猛禽類のようなかわいくもない (?) 巨大な鳥でも ptichka と呼んでいる。日本語ならば "ピーちゃん" ぐらいの語感か。
これも女性名詞で活動体であることに留意して語形変化の題材に使えそうなものだが、"鳥たちを" と "鳥たちの" では通常の女性名詞の変化では語末の a が落ちるのだが、ptichk では発音しにくいので ptichek と母音が挿入される (出没母音という)。これもまた入門用に使いにくいのでいつまでたってもテキストに鳥が登場しない。
もう一つ "鳥の" を表す形容詞もあって ptichij (プティーチー)。鳥インフルエンザにもこの形容詞が使われる。これまた規則的な形容詞変化語尾と少し違って余分な文字が入る (物主形容詞と呼ばれるカテゴリーでここにも生物由来の違いが多少ある)。一昔前の機械翻訳ではこの変化に対応しておらず訳されずそのまま文字を変換しただけで表示されることもあった。
ロシア語はなぜそれほどややこしいのかと思われるだろうが、スラブ言語ではおそらく同じようなものでウクライナ語を勉強される方も同様に苦労されていることだろう。
ロシア語なりウクライナ語なりキリル文字を読める利点を一つ挙げておこう。キリル文字はギリシャ文字に由来が近く共通の文字も多くある。数学や大学の理系科目などでギリシャ文字の記号を使うことが多いので、理系大学生 (特に物理や数学系) ではならばおそらく一通りのギリシャ文字に出会っている。
キリル文字とギリシャ文字でどの文字が同じかを知れば後は固有の文字だけ知ればキリル文字は実は比較的簡単に読めるようになる (ただし意味がわかるわけではない)。ギリシャ文字を一通り使った経験のある人ならば1時間もあれば十分。
ウクライナ語では鳥は ptakh (単数形。こちらは男性名詞) 複数形では ptakhi とロシア語と大変よく似ていて特に学ばなくても意味がわかる。注目すべきは現代ギリシャ語でも pteia とほとんど同じような語形で (語源が共通なので)、つまりギリシャ語の文章でもギリシャ文字をキリル文字と同じように見れば鳥に関係する部分は部分的に意味がわかってしまうのである。
学名由来を調べようとすると必然的に (古典) ギリシャ語語源が現れるが、キリル文字を知っていると結構の部分がキリル文字のように読めてしまうのである。ギリシャ文字をラテン文字に置き換えながら判読するのに比べておそらく手間は半分以下になっているだろう。古典ギリシャ語を習得された方にとっては何でもないことであろうが、そうでない者にとってはこれは結構な利点になる。
例えばギリシャ文字の ρ (ロー。例えば物理学では密度を表す時によく用いられる) を抵抗なく r の文字として読めるのはラテン文字の言語しか知らない人には思いつきにくい利点だろう。もちろん頻出の綴りである τερ とあれば "ter" と自然に読めてしまうのである。
学名関連 + 文献の多さなどを考えると鳥の分野ではキリル文字を知っておく値打ちがあると思う。
[シロハラホオジロとの関係]
Glushchenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraya: Kratkij Faunisticheskij Obzor" ではクロジはロシア沿海地方は通過するだけの珍しい種類だが、シロハラホオジロの島の亜種で外見が違うだけではとの見解を出している。
Paeckert et al. (2015) はまだ参照されていなかったが、この2種の系統は確かに近い (分岐年代 250 万年前ぐらい) になる。アオジとシベリアアオジの関係より近い。
大陸と島の関係で考えると シロハラホオジロ - クロジ と シベリアアオジ - アオジ が似た対応関係をなしているとも言える。
この程度の分岐年代を議論するとホオジロとミヤマヒゲホオジロ (さらにヒゲホオジロ) は別種扱いのままが適当かなどに近い問題になる。
世界のリストでは別種が標準的だが、もしまとめる場合でもシロハラホオジロの方の記載が遅いのでクロジの種小名が変わる心配はない。外見は大きく違うのでまとめる機運はあまり生じそうにないが、将来単系統をなさないなどの問題が見つかれば検討されることがあるかも知れない。
EF529945.1 (cyt b) から BLAST を行ってみると確かにシロハラホオジロと同じ系統になるが距離は遠く同種にまとめるまでもなさそうである。ただし種分化を考えるとキマユホオジロが祖先系統でシロハラホオジロとクロジが派生した形になる。この3種がクレードを作る。ND2 も見ておくとほぼ同じ結果になる。クロジの遺伝情報は少ない。
キマユホオジロは大陸のより内部で比較的高緯度まで分布し、分布を広げてシロハラホオジロが大陸沿岸部近くの型、クロジが島からカムチャツカ (カムチャツカも北部まで到達しない種にとっては島) にそれぞれ隔離分布となったと考えるとわかりやすい。クロジを準日本繁殖固有種と見る場合には隔離固有と考えてよさそう。
「原色日本野鳥生態図鑑」(中村登流・中村雅彦 保育社 1995) p. 122 には遺存種と述べられていた。シロハラホオジロとの類似性、シロハラホオジロは古い系統ではないことから現代的な視点からはこの見方は否定的と言えるだろう。新世界ホオジロ類に属していて進化の中間段階を表すのではないかと目論まれた時代の考えに基づいたものでなかったかと想像する。
音声ではシロハラホオジロのさえずりはクロジに似た始まり部分がある。以下で述べる地鳴きはソノグラムで見るとそれほどクロジに似ていない (たまに似た例もある。クロジの場合も越冬地とは異なるかも知れない)。シロハラホオジロのさえずりをクロジと誤認しない注意が必要に思える。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023) (= IOC 13.2 配列) でもこの2種の系統の近さは反映されておらず注意が必要だろう。
[地鳴きの識別]
ホオジロ類の地鳴きの識別で一番よく話題に上がるのがクロジではないだろうか。地鳴きだけで識別できる (してしまう) 人もあれば、それに批判的な立場の意見もある。
録音してソノグラムで確認すれば、典型的なクロジの地鳴きは2つの周波数成分に分かれ、これは非常に特徴的である。つまり明瞭な2音からなる重音のような音になり「楽音」的である。ソノグラムでは2点が点々と並ぶ形となって大変見つけやすい。
これに比べて典型的なアオジの地鳴きはもっと連続した分布となって、雑音のような性格を持つ。音の高さはアオジとそれほど違わない。
これを聞き分けられれば典型的な (大部分の) クロジの地鳴きは識別可能と考えている (証拠として録音して残しておくとよい)。
ただし観察者に対して警戒しているなど、緊張した声を出す場合はクロジの地鳴きがアオジのようになることもあって常に識別可能というわけではない印象である。
アオジのような声で鳴くクロジはやはり識別上の問題を引き起こしがちで、クロジのメスかシベリアアオジかはしばしば話題となるようである。大きさがだいぶ異なるので比較対象があれば区別しやすいはずだが、音声も記録して残しておくとよいだろう。
冬場のクロジのいそうな環境で録音しておくとクロジの地鳴きは非常によく入っている。人の耳では聞き逃しやすい声でも録音機は忠実に残してくれるので試してみられるとよい。
春の渡りの山で夏鳥を求めて観察しているとクロジの地鳴きは結構よく聞かれる。2021 年には非常に遅くまで残っていて5月4日が終認となった。このように遅くまで滞在するのが普通のことかどうかはよくわからないが、あるいはカムチャツカ個体群のように北方で繁殖するものが (オオムシクイの渡りのように) 遅くまで滞在しているものかも知れない。
Dement'ev and Gladkov (1954) によればサハリンで3月20日に記録されたとのこと。択捉島で5月16-19日に北へ向かう顕著な渡りがあったとの記録が出ている。上記の遅い終認と整合するようにも思える。
-
シベリアジュリン
- 学名:Emberiza pallasi (エムベーリザ パルラスィイ) パッラスのホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:pallasi (属) パッラスの (プロイセンの生物学者 Peter Simon Pallas)
- 英名:Pallas's Reed Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
pallasii は pal-la-si-i と分割すれば -la- にアクセント (パルラスィイ)。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは polaris (北極の) 亜種シベリアジュリン、pallasi オオシベリアジュリン、及び亜種不明とされる。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
Mlikovsky (2012) The dating of the ornithological section of Middendorff's Reise in den aeussersten Norden und Osten Sibiriens, with comments on the nomenclature of Pallas's Bunting Emberiza pallasi Cabanis (Aves: Emberizidae)
によれば Emberiza polaris Middendorff, 1852 の方が Cynchramus pallasi Cabanis, 1853 より早く、Emberiza polaris と呼ばれるべきであるとあるが、
H&M4 vol. 1-2, incl. corrigenda vol.1-2 では Cynchramus pallasi Cabanis, 1851 が早いと認められている模様。1851 年の記載。Pallas が変種 β としたが変種名は与えなかったものを改めて種として記載した文献。
Pallas のものはそもそも学名の要件を満たしていなかったが、変種と判断した者の情報を残すために種小名に Pallas の名を冠したものと考えられる。
なお特に Emberiza polaris に変更する必要はなさそう。
"シベリア" には北方や大陸から来る以上の深い意味はなさそうだが、polaris は極地の意味で和名とも多少関わりがあったかも。
小田谷 (2022) Birder 36(11): 48-51 にシベリアジュリンの類似種と亜種の識別の話題がある。
ここで亜種 minor (#コジュリンの備考参照) が日本にやってきているかが問題とされている。またサハリン北部でもシベリアジュリンが繁殖するが亜種は不明とのこと。
この亜種はオオジュリンの亜種とする (HBW/BirdLife 2024 段階, Clements 2019 まで)、シベリ
アジュリンの亜種とする (Clements 2021 以降、IOC 3.1 以降) か扱いが分かれている。
Emberiza schoeniclus var. minor Middendorff, 1853 (原記載)。
基産地は Stanovoi Range to Udskoe Ostrog, vicinity of southeastern Siberia (Avibase 情報より。基産地をもとにこの亜種はこの辺に分布とされているに過ぎない感じがする)。
属名は省略形ではあるが 資料 に S. minor, S. pallasi として現れる。S. はこのカードの記載から Schoenicola を指していると思われる。
アオジの備考にある Paeckert et al. (2015) の分子系統解析によれば「ジュリン」と付く3種類はまとまった系統をなしている。
比較的珍しい鳥であるが、2021-2022 年の冬のシーズンには全国的に数多く観察された。
識別は 独断と偏見の識別講座 II 第70回 Emberiza IV <オオジュリン、シベリアジュリン、コジュリン> (波多野邦彦 2018) を参考。
地鳴きはオオジュリンとはかなり違っていてむしろスズメの声に近く聞こえる。オオジュリンは音が下がるだけであるが、シベリアジュリンは上がって下がるなどセキレイ/タヒバリ類の地鳴きに似た構造がある。
オオジュリンのように長く伸びる感じがしない。
同じようなところに生息するが生態的に面白いと思ったのは開けた人工物の地面に平気で降りてしばらくとどまっていたこと。まさかそのまま地上にいる写真が撮れるほどじっとしていると思わなかった。
-
コジュリン
- 学名:Emberiza yessoensis (エムベーリザ イェッソエーンシス) 蝦夷のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:yessoensis (adj) 蝦夷 (エゾ) の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:(Japanese Reed Bunting), IOC: Ochre-rumped Bunting (13.2 から)
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
yessoensis は -ensis の冒頭が長母音でアクセントもここにある (イェッソエーンシス)。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは yessoensis 亜種コジュリン、及び亜種不明とされる。
学名の意義は簡単だが、茂田 (1992) 日本の生物 6(6): 46-51 によると学名成立の経緯は複雑だったようである。
ブラキストンが北海道函館で採集した標本に基づいて Emberiza minor Blakiston, 1862 と記載したのが始まりであったが、Blakiston (1863) は Middendorf が記載したオオジュリンの亜種 Emberiza schoeniclus minor (後述) と同一かも知れないと述べた。
Swinhoe (1874) がこの標本がオオジュリン、シベリアジュリンのいずれでもないことを確認し、Schoenicola yessoensis として別の標本をもとに再び新種として記載した [Schoenicola は現在でも使われている属名で、インド (およびかつてはアフリカ) に分布し、現在ではセンニュウ科に属する]。
On some birds from Hakodadi, in northern Japan。
参考 英名に Black-headed Reed-Bunting が出ている。
この時点では minor の先取権はすでにオオジュリンの亜種に奪われていたため使えなかったとのこと (同じ名称の有無は属内で判断される)。つまり yessoensis は最初に標本を残したブラキストンによる名前ではない。
yessoensis の使用例は IOC 14.2 に登場するものではこの1件のみ。最初に記述したブラキストンの名前を種小名に残さなかった理由は不明。Swinhoe 自らの知見に基づく (変種ではなく) 独自の新種判断であることを強調する形だったのかも。
Swinhoe が blakistoni を用いた命名はいくつもある:
Areoturnix blakistoni Swinhoe, 1871 (参考 ミフウズラの亜種、
Arundinax blakistoni Swinhoe, 1876 (参考 シマセンニュウのシノニム など。
現在多くのリストでシベリアジュリンの亜種となっている minor の記載時学名は Emberiza schoeniclus var. minor Middendorff, 1853 (原記載)
亜種概念が明確でなかった時代の産物で "オオジュリンの小型変種" の意味。変種を有効な亜種名の記載とするかは事例にもよるようで、有効でないと考えれば Emberiza minor Blakiston, 1862 が有効になる。現在そうなっていないのは有効な亜種名の記載とみなされたためと考えられる。
参考によれば Severtzov も用いたが (同じものを指していたかは不明) 変種 β 扱いで先取権の対象となる有効な亜種とみなしていなかったように読める。
Emberiza schoeniclus major Parrot, 1905 (参考) も登場するがより後の時代。
つまり Middendorff (1853) の記載の解釈次第でコジュリンの学名は和名に対応した Emberiza minor となっていた可能性がある。その場合は現在シベリアジュリンの亜種となっている minor は無効として消滅してしまっていたか、誰かが再記載する必要がある可能性もあった。
ブラキストンによる記述では北海道で夏鳥となっているが、現在はコジュリンは北海道ではほとんど見られない。他の繁殖地も消滅したところがいくつもあり、コジュリンの現在の繁殖分布は局所的である (茂田 1992)。
Kato and Davis (2019) 明治初期にブラキストンによって採集された分類学的に重要な2点のコジュリン Emberiza yessoensis の所在と採集情報の復元について
タイプ標本の採集地は函館と判定された。
学名・分類に関わる問題をさらにややこしくしているのがここで出てきた minor で、オオジュリンの変種 (亜種) として記載されたものの現在ではシベリアジュリンの亜種として扱われることが多いとのこと。
minor の名称は「コジュリン」の「コ」の由来としてはふさわしかったわけだが、コジュリン → オオジュリン → シベリアジュリン と所在が変わって行ってしまった。ただしコジュリンに付けられた minor と オオジュリン / シベリアジュリン の亜種は別物 (#シベリアジュリンの備考参照)。
あまりにややこしいので登場した記載を整理しておく:
・Emberiza schoeniclus var. minor Middendorff, 1853: 後に有効なオオジュリンの亜種名と判定された。分類概念の変更でシベリアジュリンの亜種とされるようになった。
・Emberiza minor Blakiston, 1862 コジュリンを指したもので和名とも整合性がよい (和名はこの学名から与えられたものかも知れない) が無効名。
・Schoenicola yessoensis Swinhoe, 1874: Blakiston (1862) に代わるコジュリンの記載。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
英語の色由来の別名に Ochre-rumped Bunting (黄土色の腰のホオジロ) がある。固有種でない種の英名に国名を避けて記述的名称を与える方向性はかなり定着してきているようで、この種も HBW/BirdLife がこの名称を用い、IOC 13.2 以降 Ochre-rumped Bunting が用いられている。Clements も 4th edition からこの英名を使用し、世界のリストでほぼ統一される状態になっている。日本鳥類目録改訂第8版でもこの英名を採用。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the ochre-rumped bunting Schoeniclus yessoensis
ロシア沿海地方のコジュリンの繁殖生態。
-
オオジュリン
- 学名:Emberiza schoeniclus (エムベーリザ スコエニクルス) 芦原に関係するホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 種小名:schoeniclus skhoiniklos (Gk) アリストテレスの記述した不明の小型の水辺の鳥でセキレイの可能性があるとされる; アシに関係する小鳥 (愛媛の野鳥「はばたき」)
- 英名:Reed Bunting, IOC: Common Reed Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
schoeniclus 外来語由来のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみで -nic-lus と区切れるならば "スコエニクルス" のアクセント位置となる。
ユーラシア中北部に広く分布し、19 亜種あり (IOC)。日本で記録されるものはロシア極東から北海道、カムチャツカにかけて繁殖する pyrrhulina [Pyrrhula 属 (ウソ属) の指小形] とされる。
ロシアでは亜種の考え方が少し異なる。ロシア極東と北海道、カムチャツカの亜種が異なるならば亜種識別の問題が発生するかも知れない。
将来的な属名変更の可能性、海外で異なる属名が使われている理由については #アオジの備考 [Emberiza 属の系統分類] 参照。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the common reed bunting Schoeniclus schoeniclus (pp. 3671-3690)
にロシア沿海地方のオオジュリンの繁殖の論文がある。
ロシア極東部に2亜種が繁殖するとのことで。北海道と同亜種 pyrrhulina は島嶼性で、内陸の湿地のアシ原で繁殖する個体群にはまだ名前 (亜種名) がないとのこと。
1981 年にヤクーチア西部で繁殖する亜種 parvirostris が迷行したものが偶然捕獲された。
ちなみに前者の記載時学名は Schoeniclus pyrrhulinus Swinhoe, 1876 で基産地 Hokodadi [= Hakodate], Hokkaido。亜種が分離されれば大陸ロシアの方に別亜種名を与えることになる。
ヤクーチア西部の方は Emberiza schoeniclus parvirostris Buturlin, 1910 の記載で基産地はぼんやりしており middle Lena, about lat. 60° N. ; and the Yenisei, beyond lat. 64° N. (いずれも Avibase による) で Olekminsk に限定された (Buturlin 1934)。Olyokminsk = Olekminsk (オリョークミンスク) はロシアのサハ共和国南西部にある都市。
図鑑では「チュイーンと鳴く」とどれにも書いてあるが、実際の声を聞くまでどういう音声かまったく分からなかった。カタカナ表記の限界を感じる。声を覚えてしまえばしかるべきところにはほぼどこにでもいることがすぐわかる。
この他に#シラガホオジロの備考に記したような低く濁った「ビュ」と少し下がる声がある。この声はあまり知られていない (バードリサーチ鳴き声図鑑にもない) のでオオジュリンの声と知らない人も多いと思われる。結構よく聞く声で (姿は容易に見えないが) アシ原周囲の田んぼなどからこの声が聞こえてきて、周辺でも採食していることがわかる。
希少種との聞き分けにも関連する声なので注意して聞いて覚えておきたい。
["ジュリン" の由来検討]
中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 119 (1940 年初出) に鳴き声由来説が紹介され、この記述を見る限りでは中西氏の独自説と考えられる。
外国語に似た音はないか検討してみたところ、スコットランド・ゲール語 (Scottish Gaelic) にかなりよく似た音があって gealag でホオジロ類を含む小鳥を表すよう。オオジュリンは gealag-dhubh-cheannach と呼ばれるとのこと。語源は geal (白い) + -ag (小さいものを作る語尾) で geal は gel, さらに遡ってインド・ヨーロッパ祖語では *ghelh3- (光る) でこの語からさまざまな語が派生しているのでホオジロ類を意味する単語がどこかの言語で存在したかも知れない。似た音になっているがこちらは音声由来ではない。
"ジュリン" に近い海外の音声由来の名称が見当たらないので、世界的にもあまり注目を浴びる音声ではないのでは。
なお英語の geal はラテン語 gelare 由来でこちらは *gel- (冷たい) 由来とのこと。以上 wiktionary より
"ジュリン" 類を属に分離する場合に用いられる Schoeniclus はアリストテレスの用いた未同定の水辺の鳥で、年代が早すぎたため規則により採用されなかったがハマシギを指して使われたこともあり (Moehring 1752)、必ずもアシに関係する小鳥 (愛媛の野鳥「はばたき」) というわけではなさそう (The Key to Scientific Names)。
ギリシャ語の skhoiniklos を "ジュリン" と読むのはさすがに無理があるか。
中西氏が説を与えられるぐらいなので新しい名称で、おそらく鳥学者が付けたものではないだろうか。当時の鳥学者は標本中心で音声はあまり認識していなかったようなので、中西氏のように音声に結びつけるのは無理があるかも知れない。
"Fauna Japonica" にも記載がない。Swinhoe が記録した時代には Schoenicola pyrrhulina [表記は Seebohm (1890) "The birds of the Japanese Empire" p. 133 による] となっていて、"アシに関係する小鳥" の解釈の由来となっていたかも知れない。
ただしこの属名はセンニュウ類ですでに使われていて Schoeniclus pyrrhulinus Swinhoe, 1876 が正しい。Schoeniclus 属に "ジュリン" の名称を割り振ったものと推定され、Cisticola 属に "セッカ" を割り振ったのとおそらく同じような時期と想定される。なぜ "ジュリン" が選ばれたのか今のところ有力そうなアイデアがない。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" に登場するもう一つの属名に Pyrrhulorhyncha があり Pyrrhula (ウソ属) + rhunkhos 嘴の意味 (Giglioli 1865) (The Key to Scientific Names) この属名の後半は "リン" と読めるので関係あるかも。
Ogawa (1908) および山階鳥類研究所標本データベースの古いものを見ても、古くは "大ジョリン" の名前の方がよく使われていたよう。ただしラベルがいつ付けられたものかは不明。オオジュリンの標本数は多いのでごく一部チェックしたに過ぎないことをお断りしておく。
またジュケイ (#コジュケイ参照) のジュが "綬" の文字であればこちらの可能性もある気がしてきた。模様を "綬" に見立てたなど。具体的根拠は見つけられなかったが、参考までに中国語で綬帯鳥はカワリサンコウチョウを指すとのこと。白梅に寿帯鳥は浮世絵の画材として用いられたとのこと。
もう一つ思いついたのが ho-jiro を変形させて h を外して o-jurin とした、学名などでよく使われるアナグラムに近いもの。ローマ字表記を見ていて気づいた。ホオジロ系統の Schoeniclus 属 (当時 Schoenicola の表記も使われた) にもう1つ名前を作る必要が生じたが、既存のよい名前がなく "ホオジロ" を少し変形させてそれらしい名前としたのでは。
-
ゴマフスズメ
- 学名:Passerella iliaca (パッセレルラ イーリアカ) ツグミの模様の小さなスズメ
- 属名:passerella (f) 小さなスズメ (passer (m) スズメ -ella (指小辞) 小さい)
- 種小名:ツグミの一種 ilias, illas (Gk) を Gaza (1476) がラテン語化したもの。下面にツグミのような斑点があるため (The Key to Scientific Names)
- 英名:Fox Sparrow, IOC: Red Fox Sparrow (日本で記録された亜種は Sooty Fox Sparrow が適切な英名だろう)
- 備考:
passerella は短母音のみで -rel- がアクセントと推定される (パッセレルラ)。
iliaca 意味の異なるラテン語があり (#ワキアカツグミ参照)、発音が同じであれば冒頭が長母音でアクセントは2重母音のある -li-a- にある (イーリアカ)。
北米の種。日本で記録されたものは日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)では unalaschcensis (アリューシャン列島のウナラスカ島 Unalaschca/Unalaska に由来; サバンナシトドの学名も参照) となっている。
この亜種は現在 IOC, HBW/BirdLife では別種 Passerella unalaschcensis 英名 Sooty Fox Sparrow となっている (この種に同名の基亜種 unalaschcensis がある)。
AOU, Clements, Howard and Moore では Passerella iliaca の亜種の扱い。
IOC の分類では Passerella iliaca が2亜種、Passerella unalaschcensis が7亜種となっている。
これらの分類群は "subspecies group" とされていて種の区分方法は考え方次第のようである。
wikipedia 英語版では sooty fox sparrow complex を6亜種としている。
将来の研究で種分類が変わる可能性があるが、unalaschcensis を含む種が和名ではゴマフスズメとなるはず。地理的には Red Fox Sparrow が大陸に広く分布、Sooty Fox Sparrow が沿岸に分布し、後者が Passerella属の中でも最も暗色とのこと。
-
ウタスズメ
- 学名:Melospiza melodia (メロスピザ メローディア) 美しい調べの歌鳥
- 属名:melospiza (合) 歌鳥 (melos (n) 歌 spiza フィンチ Gk)
- 種小名:melodia (f) 美しい調べ
- 英名:Song Sparrow
- 備考:
melospiza は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみで -lo- がアクセント音節と考えられる (メロスピザ)。
melodia は o が長母音でアクセントもここにある (メローディア)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。北米の種で 24 亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。
-
ミヤマシトド
- 学名:Zonotrichia leucophrys (ゾーノトゥリキア レウコプリュス) 白い眉で髪に帯のある鳥
- 属名:zonotrichia (合) 髪に帯のある (zone 帯 thrix, trikhos 髪 Gk)
- 種小名:leucophrys (合) 白い眉 (leuko- (接頭辞) 白い phrydi 眉 Gk)
- 英名:White-crowned Sparrow
- 備考:
zonotrichia は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は zone が2つとも長母音。trikhos は短母音。ラテン語 zona は冒頭のみ長母音。
この長母音を取り入れれば "ゾーノトゥリキア" が想定される。
leucophrys は外来語由来の合成語のため発音はよくわからないが、起源となったギリシャ語は短母音のみで -cop(h)- がアクセント音節と想定される (レウコプリュス)。
英名と種小名の意味が少し違うが、#キガシラシトド の英名 Golden-crowned Sparrow と対比させるためではないだろうか。他言語でも "crowned" に相当する意味を用いているものはあまり見新たらず、一般的には学名語義に忠実になっている。中国名は英名をそのまま訳した模様で "白冠" となっている。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。北米の種で5亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは gambelii (アメリカの探検家、採集家の William Gambel, Jr. に由来) とされる。
亜種間の外見の差が小さく、主に分布域と渡り習性・経路の違いをもとに亜種に分けられている。
亜種識別の参考情報: Bacchetti (2017)
Identifying White-crowned Sparrow Subspecies Wintering in the Central Valley。
亜種 gambelii と pugetensis には生殖隔離が存在するとの情報も記されている。
Dunn (1995) Subspecies of White-crowned Sparrow。
ノドジロシトド Zonotrichia albicollis White-throated Sparrow では染色体の逆位が色彩二形とさえずりの違いに関係していることが知られている:
Zinzow-Kramer et al. (2015) Genes located in a chromosomal inversion are correlated with territorial song in white-throated sparrows。
-
キガシラシトド
- 学名:Zonotrichia atricapilla (ゾーノトゥリキア アートゥリカピルラ) 黒い髪の髪に帯のある鳥
- 属名:zonotrichia (合) 髪に帯のある (zone 帯 thrix, trikhos 髪 Gk)
- 種小名:atricapilla (adj) 黒い髪毛の (ater (adj) 黒い capillus (m) 髪毛)
- 英名:Golden-crowned Sparrow
- 備考:
zonotrichia は#ミヤマシトド参照。
atricapilla は ater の冒頭が長母音。capillus は短母音のみで -pil- がアクセント音節と考えられる (アートゥリカピルラ)。
和名や英名と学名の対応が悪いように見えるが、これはおそらく Emberiza coronata Pallas, 1811? (冠のあるホオジロ) 時代に付けられた英名や和名と考えると理解できるように見える。
Emberiza atricapilla Gmelin, 1789 の方が早かった (原記載) ため学名が変わった。この原記載の基産地はやや漠然としていた (in Sinu Natka, et insulis Sandwich) が、
Stresemann, 1949, Ibis., 91, n. 249 がウナラスカ島の Sandwich Sound (湾の名前) と認定したとのこと (Avibase より)。Captain Cook and the Russians に地名の解説あり。後に Prince William Sound と改名されたとのこと。
ということで#サバンナシトドの種小名と同一場所になる。
この記述過程を見ると Stresemann (1949) が古い記載を見つけ出したものかも知れない。
Emberiza coronata Pallas の方であれば基産地は コディアック島 (Kodiak Island, 当時はロシア領で現地名から Kad'yak) ともう少しわかりやすい。
それぞれの学名は違う点に注目したものであるがそれぞれ納得行く名称になっている。
北米の種で単形種。
Iverson et al. (2024) Winter GPS tagging reveals home ranges during the breeding season for a boreal-nesting migrant songbird, the Golden-crowned Sparrow
アラスカなど北方で繁殖する種だが、越冬地での GPS タグ装着によって繁殖地の行動、渡りなども調べられている。
-
サバンナシトド
- 学名:Passerculus sandwichensis (パスセルクルス サンドゥウィケーンシス) (アリューシャン列島の)サンドウィッチの小さなスズメ
- 属名:passerculus (m) 小さなスズメ
- 種小名:sandwichensis (adj) アリューシャン列島ウナラスカ島 (Unalaska) のサンドウィッチの(採集地、wikipedia 英語版より) (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Savannah Sparrow
- 備考:
passerculus は passer, -culus ともに短母音のみで -cu-lus と区切られるため、-ser- にアクセントがあると考えられる (パスセルクルス)。アクセント音節のため -ss- は分けて表記した。
sandwichensis はラテン語読みとし、場所を示す -ensis の冒頭が長母音でアクセントもある一般例を採用した (サンドゥウィケーンシス)。
日本鳥類目録改訂第7版で追加。北米の単形属の種で 17 亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは基亜種 sandwichensis とされる。クサチヒメドリ (日本鳥類保護連盟の「鳥630図鑑」での名称。この図鑑ではサバンナシトドを旧名としていた) の別名がある。
"ヒメドリ" は passerculus の意味ともよく整合しているが、北米の他の属の小型種 (アメリカでは総称で sparrow と呼ぶ) にも使われる。
"クサチ" は Savannah を意味訳したものではないかと想像するが、ドイツ語でも同様に Grasammer (Gras 草 Ammer ホオジロ類) で発想はよく似ている。
◆「日本鳥類目録 改訂第7版」非記載の鳥
△ キジ目 GALLIFORMES キジ科 PHASIANIDAE ▽
-
コジュケイ
- 学名:Bambusicola thoracicus (バムブースィコラ トーラーキクス) 胸に特徴のある竹林に住む鳥
- 属名:bambusicola (合) 竹林に住むもの (植物の属名 Bambusa、colo (tr) 住む The Key to Scientific Names)
- 種小名:thoracicus (adj) 胸に特徴のある (thorax (m) 胸 -icus (接尾辞) に属する)
- 英名:Bamboo Partridge, IOC: Chinese Bamboo Partridge
- 備考:
bambusicola は起源となる単語の発音がよくわからないが、マレー語の bambu (英語 bamboo) で u を長く読むのが適切と考えられる。-cola は短音でアクセントもなく、-si- がアクセント音節と考えられる (バムブースィコラ)。
thoracicus は thorax の o が長母音。接尾辞 -icus は短母音。-ra- がアクセント音節でこの音も長音となっている (トーラーキクス)。
単形種。
コジュケイに対してジュケイ属は Tragopan で、ジュケイ Tragopan caboti Cabot's Tragopan がある。
中西悟堂「定本・野鳥記」5 p. 114-115 (1940 年初出) によれば "ジュ" がしばしば "寿" と表記されるがこれは誤りで、"綬" が正しい。胸の模様由来と記されていた。
綬は古代中国で、官職を表す印を身につけるのに用いた組みひも (コトバンク) が最初の意味。
ジュケイの方が本家だろうと写真を確認すると特にオスが wattle (または lappet) を広げるとまさしくそのように見えるとのことで納得。
ジュケイの英語にある tragopan はラテン語由来で、エチオピアに生息する鳥と考えられたとのこと (Pliny) で、おそらくヒゲワシを指していたものと考えられる。
1706 年の用例があり、Tragopanas, a Bird in Ethiopia, that is larger than an Eagle, and has Horns like a Goat (Phillips's New World of Words) でワシより大きいとなるとヒゲワシは妥当な同定だろう。tragos ヤギ pan 自然の神 (Gk)。The Key to Scientific Names ではサイチョウかも知れない解釈が紹介されているが、OED の方が当たってそうな気がする。
ヒゲワシがキジ目の名称に使われるぐらいであれば、ヘビクイワシとアシナガワシの間で間違いが生じていても不思議でない感じもする (#カラフトワシ [なぜ "樺太" ワシ?])。
△ ハト目 COLUMBIFORMES ハト科 COLUMBIDAE ▽
-
カワラバト
- 学名:Columba livia (コルムバ リーウィア) 暗色の/鉛色のハト
- 属名:columba (f) ハト
- 種小名:livia カワラバト [Gaza (1476) による peleia (Gk) ハト のラテン翻訳。原意は pellos (Gk) 暗色の と思われるとのこと; livens, liventis 鉛色の 起源の説もある (The Key to Scientific Names)
- 英名:Rock Dove (or) Rock Pigeon
- 備考:
livia はラテン語に存在する形容詞の読みを用いれば冒頭が長母音でアクセントがある (リーウィア)。
飼育され野生化しているドバトの学名は Columba livia var. domestica または Columba livia forma domesticaとなる。
亜種扱いで Columba livia domestica とされることもある。しかしながら、Columba domestica Linnaeus, 1758 は Columba livia J. F. Gmelin, 1789 よりに先に発表された学名であった。
Gmelin の記述したハトの標本にはヒメモリバト Columba oenas (英名: Stock Pigeon) も混ざっており、Linnaeus の記述した Columba domestica はラント (runt) 品種で、oenas もドバトが含まれていた。
livia は後にスコットランドの標本からネオタイプが設定された。このように Columba livia と Columba domestica の間には先取権の問題が残っており、これらと oenas をシノニムをみなす可能性も完全に除外されていない
[Donegan (2015) The pigeon names Columba livia, 'C. domestica' and C. oenas and their type specimens]。
この問題は Donegan (2016)
Case 3692
Columba livia Gmelin, 1789 and Columba livia domestica Linnaeus, 1758 (Aves, columbidae): proposed conservation of specific and subspecific names in conformance with prevailing usage
が提起して ICZN が 2018 年 Opinion 2424 (Case 3692) として裁定したとのこと。
従って現在は Columba livia の学名を用いて問題ない。
Streptopelia 属でも家禽種と野生種の間で同様の問題が指摘されている。Donegan (2024)
On the nomenclature of wild and domestic Streptopelia doves。
幸いにして (?) 日本で野生種の Streptopelia 属には多分影響はないが、飼育種のハト類 (野生化の場合など) では学名問題が残っているかも。Barbary Dove (直接対応する和名はジュズカケバト) が野生の African Collared Dove 由来であることが確認されたのが 2023 年とのことでごく最近の話で驚かされる。
なお Barbary Dove はシラコバト由来か、African Collared Dove 由来かで議論が分かれていたよう。van Grouw et al. (2023) によればシラコバトも含めて3系統が区別でき、亜種として扱うかなど難しい問題がある模様。過去に学名記述がなされた時もカワラバト/ドバト同様に混ざっていて新たに定義されたものもあるとのこと。
"ジュズカケバト" (複数の系統が含まれた名前かも知れない) に Streptopelia risoria あるいは Streptopelia roseogrisea (バライロシラコバトの和名もある) のいずれを用いるべきか、あるいは家禽種で用いられた学名を無効名とするかなど議論がなされている。
野生化したものもあるが、eBird では地域によって学名 (亜種) を使い分けているとのこと。
この文中でも Linnaeus (1758) が Canis familiaris の学名で記述したイヌ (昔学名を習う時はよく出てきた) は Canis lupus を家畜化したものである [Linnaeus (1758) には両方が現れる] など Canis lupus familiaris を使うべきかなどややこしい問題がある模様。
野生種については Canis lupus を採用する裁定が ICZN (2002)
Opinion 2027 (Case 3010), Usage of 17 specific names based on wild species which are pre-dated by or contemporary with those based on domestic animals (Lepidoptera, Osteichthyes, Mammalia): conserved
でなされたとのこと。先取権は厳密に考慮せず、普通に使われる学名を優先した形になっている模様。逆に言えば 2002 年まで(ハイイロ)オオカミの学名は未決着だったことになる。なかなか奥が深い。
家畜化されたイヌの学名はまだ未決着というところだろうか。考え方次第で学名が変わる。
Streptopelia 属についても同じような問題が残っている。
著者の Donegan は ICZN のこれまでの決定の整合性にあまり満足していない様子もうかがえる。
カワラバトは野生では9亜種あり (IOC)。
Establish English names for three species of Gygis
によれば Rock Pigeon が一般的に Columba livia として使われてきているが、オーストラリアのハトのグループ名 (Petrophassa 属) として Rock Pigeon が使われているため、2018 年に NACC が Rock Dove の名称に変えることを提案したとのこと。
Laridae (BirdForum 2025.4) から補足した。
[家禽ハト品種の形態に関連する遺伝子]
家禽ハトの品種で短い嘴に関係する遺伝子: Boer et al. (2021) A ROR2 coding variant is associated with craniofacial variation in domestic pigeons
伴性遺伝する形質に着目して調べたところ Z 染色体上の位置を特定した。ROR2 遺伝子が働いていると予想している。マウスでこの遺伝子をノックアウトすると骨形成異常が知られているなど哺乳類では形態形成に重要であることが知られているが鳥類ではあまり知られていなかった。
冠羽の形成メカニズム
Shapiro et al. (2013) Genomic diversity and evolution of the head crest in the rock pigeon
[要約内容は次の Vickrey et al. (2015) とまとめて紹介する]
こちらは家禽ハトの品種で冠羽に関係する変異。EphB2 がナンセンス変異を起こしていて羽嚢原基の極性 (feather placode polarity) が変わっていた。この酵素は細菌に毒性を示す効果があり変異は細菌耐性を弱める可能性がある。冠羽はさまざまな鳥で見られるものであり、変異に悪影響がない場合は他の系統の冠羽の進化に関係している可能性もあるが複数の遺伝子が関与している可能性もある。
家禽ハトでは人為交配が行われているのでそのまま受け取れないだろうとはいえ、家禽品種の系統樹まで出ていてだいたいの傾向がありこれはこれで面白い (fig. 1。Supplementary Material にも遺伝子ごとの系統樹が出ている)。ハトの品種をある程度知らないと面白くないかも知れないが、何と言ってもダーウインを虜にしたハトの品種である。鳥ファンならばある程度知っておくのがよいのだろう。一般向けの鳥の図鑑にもよく出ている。
参考: Darwin (1868) "The Variation of Animals and Plants Under Domestication" BHL サイト。第 5 章に Domestic Pigeons。
pp. 181-182 Fantails には尾脂腺がないとのこと。この観察結果はやはり問題となっていたようで、Kossmann (1871) が Darwin と異なる結果を出していた。Johansson (1927) Fantails では尾脂腺を欠く形質が劣勢遺伝し、一部の個体で欠損していることを示して解消したとのこと
[Elder (1954) The Oil Gland of Birds。この文献は #ヨシゴイ備考 [粉綿羽と櫛状の爪] で紹介]。
いわゆるドバト (ドバトの野生型?) もサンプルに含まれていて系統樹に内包される形になっている。
ここで調べられている品種ではドバトの野生型? に最も近いのは English Carrier で、carrier pigeon はいわゆる伝書鳩の意味なので系統が近いことも納得できる (?) かも。ただし English Carrier は観賞用なので形はだいぶ異なる。
Scandaroon を含むこの系統からドバトの野生型? が世界中に広まったということになる。
冠羽のある品種は複数の系統に分散していて古く作られた形質で遺伝子浸透などで複数の系統に現れていると想定している。
冠羽が生じるメカニズムを考えたことがなかったが極性ならばわかりやすい。
なぜ頭頸部に限定なのかも考察されていて、体部とは制御が異なる (参考#クロハゲワシ備考 [首の羽毛を失う理由] 参考)。体部羽毛の極性に影響が及ばないことは利点があるだろうとも推測している。
Vickrey et al. (2015) Convergent Evolution of Head Crests in Two Domesticated Columbids Is Associated with Different Missense Mutations in EphB2
こちらは共通する変異が家禽のジュズカケバトにも見られた。カワラバトとは 2000 万年前に分岐したと推定されるにも関わらず遺伝子の性質が保存されている。
特定の家禽の形質に偏ってしまう危険性はあるが、家禽品種の知見が鳥の形質進化の理解に役立つ可能性がある。
Domyan and Shapiro (2016) Pigeonetics takes flight: evolution, development, and genetics of intraspecific variation この段階で明らかになっていた品種の形質に関わる遺伝子のレビュー。
他の鳥でも調べられているメラニン合成に関係して羽色を決める遺伝子、また Slc45a2 の変異は酵素の運搬能力を変化させて明るい色の変異を作る。足に羽毛の生える品種や他の鳥 (#ライチョウの備考 [足に羽毛の生える鳥] も参照) の議論もある。
単に足に羽毛の生える以上に後肢と前肢の発生学的な遺伝子発現の区別が曖昧になっている。鳥類の進化過程で後肢から羽毛が失われた経緯を考える上でも興味深いとのこと。
わりこみ Microraptor の新化石の研究
誰もがご存じであろう後肢に翼を持っていた古生物の Microraptor (ミクロラプトル) の研究: Chotard et al. (2025) New information on the Hind limb feathering, soft tissues and skeleton of Microraptor (Theropoda: Dromaeosauridae)。
後肢の翼には雨覆も揃っているなどほぼ完全な形をしていた。現代や化石の鳥で後肢に羽毛の生える鳥でもここまで完全な形態のものは知られていない (上記の研究を見ると少なくとも羽毛については遺伝子レベルでの実現は比較的簡単なようだが)。役割については既知の知見を逸脱しないようにかなり控えめに書かれている。飛翔時の足の向きが不明なので航空力学的にどの程度の役割を果たせたか評価することが難しい (方向を仮定の上での推論がある)。
非対称な羽弁を持っていることは現代の鳥では飛行能力に関係していることがわかっているが、過去の系統ではそこまで明らかでなく、風切羽の非対称性がただちに飛行能力と結びつくわけでもない。ただし流体力学的な力は必然的に発生するはず (何に役立っていたかは自明でない)。
他にも趾の構造なども検討しており現代の鳥のように趾の特殊化がないとのこと。かつては現代の猛禽類のように掴んでいたと考えられたが、第 I 趾が弱いので掴めなかったのでは。ただし飛びながら第 II 趾 で獲物に一撃を加えることは可能だったのでは、など推論されている。
現代の鳥の直系の系統というわけでもないので現代の鳥の機能からの類推がさてどこまで成り立つのか。
こちらは同じ化石を用いた上肢の研究: Grosmougin et al. (2025) Forelimb feathering, soft tissues, and skeleton of the flying dromaeosaurid Microraptor
上肢の風切羽と雨覆の関係を明らかにした最初の研究とのこと。上肢の骨は伝統的な I-II-III の名称を用いて、この発生学的同定はまだ議論されている途上とのこと。
雨覆の列数は現代の鳥でも種類によって異なることが示されている。現代の鳥でスズメ目やイヌワシで近位の初列風切の方が成長が早い、現代の鳥との翼の形態などから生態も議論されているが、竜骨突起など現代の鳥にあるもので存在しない特徴もある。翼の形は現代の鳥に "完全に" 一致するものを見つけることはできないが、現代の鳥の翼の使い方からこの時代の翼の機能を推測するには限界もある。
ハヤブサに似た点があるとは言え、同じような生態を考えるのはさすがに無理がある。
著者は全体として受ける印象からは、比較的敏捷で乱雑な環境の中で待ち伏せ的に捕食行動を行っていたのではないかと推定している。樹上性とはあまりみなしていない。
飛翔能力があったか、羽ばたき飛行を行っていたかなども検討されているので詳しくは論文と図を参照。
現代の鳥の翼の構造や羽毛の重なりや成長様式の進化にも示唆を与える題材も多く含まれているのでじっくり読んでいただきたい。
Napoli et al. (2025) Reorganization of the theropod wrist preceded the origin of avian flight
現代の鳥の飛翔の際の手首の安定性に重要な役割を果たしている pisiform (豆状骨) の起源を調べたもの。現代の鳥に加えて Oviraptorosauria, Troodontidae にも存在した。Pennaraptora のクレードから pisiform が ulnare (主に古生物用語) に置き換わり、飛行の起源の進化の最後の段階を表し、現在の鳥のクレードだけのものではないとの考え方。
ここで話題の Microraptor や Anchiornis にもあるとのこと。
手首の骨について読みやすい参考文献は例えば Meadows (2014) Resolving the Flap over Bird Wrists。pisiform は我々の膝の膝蓋骨と同じような役割を果たしている。pisiform ではヒトにも存在して膝蓋骨同様の筋肉や腱の中に形成される種子骨の一つとなっている。膝の皿が何のためにあるのかを考えると鳥の手首の骨の機能も理解しやすい。
鳥の手首の動きをヒトの機能から類推できるのもこの類似性由来で、(古生物を含めた) 他の大部分の爬虫類ではこの比喩は成り立たない。
手首の骨 (手根骨) は多数の骨からなっており、覚えにくいことこの上ないので (整形外科など専門を目指す人にとっては別だろうが) 日本語の医学では 舟月三豆、大小有有 とよく語呂合わせで覚えられていた。記憶の際の参考になれば幸いである。
足根骨はどうだったか、とちょっと調べてみると手根骨でも足根骨でもやはり英語でも語呂合わせのフレーズ (英語では mnemonic) が紹介されていた (解剖学名は基本的にラテン語なので英語圏でも覚えるのは容易でない。日本語名称もラテン語の訳なので英語圏と事情は同じ)。
ハトの話に戻る。Balog et al. (2024) MtDNA genetic diversity and phylogeographic insights into giant domestic pigeon (Columba livia domestica) breeds: connections between Central Europe and the Middle East
にも中東の大型品種の由来を探る遺伝的研究がある。現在飼育されている品種が家禽化されたのはおそらく中東だが、Carpathian Basin (Pannonian Plain パンノニア平原。現在のハンガリーが中心) が野生動物や家畜・家禽の多様性の高い地域でハンガリアン品種の起源とも考えられた。パンノニア平原のハトの遺伝的多様性が高い結果が得られた。あまり話題にならないが東欧ではハトの飼育が大変盛んであるが、このような事情も関係していたのか。
Hernandez-Alonso et al. (2023) Redefining the Evolutionary History of the Rock Dove, Columba livia, Using Whole Genome Sequences
ダーウインの標本も用いたゲノム解析により家禽も含めたカワラバト亜種の解析を行った。西アフリカの亜種 Columba livia gymnocyclus がカワラバトの最も古い系統で、遺伝的距離や種分化過程を考慮して種扱い Columba gymnocyclus Gray, 1856 とすることを提案している。サハラ砂漠の乾燥化によって現在は隔離個体群となっている。
カワラバトの家禽化は 3000 - 10000 年前と推定されており、その当時はサハラ砂漠が湿潤な時代で乾燥時期に分かれたコウライバト Columba rupestris Hill Pigeon と再度接触したと考えられる。亜種のタイプ標本には家禽と考えられているものも含まれている。
もし2種に分割され、連続的な違いでカワラバトの亜種にあまり意味がないと考える立場ならば Columba livia は単形種または2亜種となるとのこと。
現在の西アフリカの亜種は長く隔離されたために遺伝的多様性が低く近交係数も高い。現在のカワラバトは IUCN LC 種となっているが西アフリカの個体群は注意すべきとのこと。
いわゆる domestic pigeons は系統樹の中では中東の野生系統に近く Danish Tumbler に近い枝に含まれる (調査された範囲はヨーロッパ、アフリカ、アジアまで)。
{ドバト + カワラバト} の最も古い祖先が西アフリカの個体群となるとはいえ {ドバト + カワラバト} の起源が西アフリカ由来とはならないことに注意。隔離過程が含まれており西アフリカの個体群は遺存的なものと考えてよい。
Pacheco et al. (2020) Darwin's Fancy Revised: An Updated Understanding of the Genomic Constitution of Pigeon Breeds にも品種の分子系統関係と品種改良プロセスの関連が見られる。
[トリコモナスはハト由来?]
トリコモナスも何と鳥類から哺乳類に何度も宿主を変えたものだった。両方に感染する種もあるとのこと: Sullivan et al. (2025) Comparative genomics of the parasite Trichomonas vaginalis reveals genes involved in spillover from birds to humans
ヒトへの病原性が特に問題となる Trichomonas vaginalis は人がアメリカに定着してからハトからもたらされたと提案する研究があるとのこと。
Trichomonas 属の分子系統樹の鳥類の枝の中に何と T. vaginalis が収まってしまっている。他にも鳥類を宿主とする種がいくつもある。
ヒトなど哺乳類を主な宿主とする現在は通常別属で Pentatrichomonas hominis は Trichomonas 属より古い系統にあたり病原性ないとされる。Trichomonas 属は圧倒的に鳥類が宿主でハト類との頻繁な接触によってヒトにもたらされたらしい。
鳥類を宿主としている間はゲノムの変化が比較的小さかったがヒトに感染することで選択圧が弱まり (relaxed selection) 急激なゲノムの進化が起きたと考えられるとのこと。新しい宿主を得たことで病原性も強まったのだろうか。
それにしても鳥類では上部消化管に寄生するものが、なぜヒトでは生殖器に寄生するようになったものか (?)。ヒトでも鳥でも接触感染の機会の多いルートが選ばれたということだろうか。
このような視点で見ると鳥の交尾は接触感染に対して案外安全なのかも。交尾中に外敵に対して無防備になる時間を短縮するために交尾時間が短いなどの説明もよく行われるが、(原因か結果かわからないが) 寄生虫の接触感染の可能性を減らすこと (これもよく要因に取り上げられるが) もなかなか適応的なのかも知れない。少なくともヒトと比較する場合には意味がありそう。
鳥類を宿主とする Trichomonas gallinae は広範囲の鳥に感染し、猛禽類での症状は frounce、ハト類では canker と呼ばれるとのこと。猛禽類の場合は感染した鳥を食べることが主な感染経路。汚染された水からの感染も要因で、ハト類ではそのうから分泌されるピジョンミルクも経路となる。猛禽類では主な病変は口蓋から咽頭部とのこと。ヒトへの感染例はこの時点では報告されていない (wikipedia 英語版)。
Trichomonas gallinae を含む枝にヒトを含む哺乳類や鳥にも感染する Trichomonas tenax が含まれている。これもやはり鳥類由来のよう。こちらは鳥の場合とよく似ていて主に口腔に存在し oral trichomonas (口腔トリコモナス) と呼ばれる。
[鳩の漢字の意味]
週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1973) 100-VII (藤堂) によれば九の文字は手で数を数える際に指を全部曲げて1本のみ残った形を指すとのこと。ぐっとしばって集まる意味。
中国古典では糾合を鳩合とも書いた。要するにハトが集まっている状態。
勾や拘の文字とも意味が近いとのこと。
本来は在来種のハトの項目に入れたかったが、キジバトでは合わないのでやはりここに入れざるを得ない。
△ スズメ目 PASSERIFORMES チメドリ科 TIMALIIDAE ―
-
ガビチョウ
- 学名:Garrulax canorus (ガルルラークス カノールス) 美しい声のおしゃべりな鳥
- 属名:garrulax (合) おしゃべりな鳥 (Garrulus カケス属 -ax 似た。騒々しい行動から jay-thrushes と呼ばれていた) (The Key to Scientific Names)
- 種小名:canorus (adj) 美しい声の
- 英名:[Hwamei], IOC: Chinese Hwamei
- 備考:
garrulax はラテン語 -ax (傾向がある、似る) の接尾辞の場合は長母音。audeo (危険を犯す。英語 dare, venture に相当) から audax (アウダークス。オナガイヌワシの種小名) など。garrulax では gar-ru-lacs と区切られるのであれば冒頭にアクセント (ガルルラークス)。
すべての -ax の語尾は同じ語源ではないので個々に調べる必要がある。
canorus は#カッコウ参照。
英名の Hwamei は中国語由来で美しい眉斑の意味とのこと (コンサイス鳥名事典)。
ラテン文字表記で huamei (画眉) で英語では "painted eyebrow" と訳されている (wiktionary)。我々には漢字表記がわかりやすい。
別名 Laughing Thrush。
2亜種あり (IOC)。
チメドリ類の学名に関係した興味深い情報があったので紹介しておく: Tinamidae (BirdForum 2025.3) によれば、現在多くのリストで広く使われている Erythrogenys の属名は有効でないとのこと。Hodgson (1836) が用いたこの名称は属を指すものではなく、誤読されたまま引き継がれてきたとのこと (同じ名称を用いた他の著者もあるが無効なものだった。類似名も含めて関係が複雑で The Key to Scientific Names にとりまとめ情報あり)。
正しい属名は Megapomatorhinus とのこと。
日本産種には今のところ現れていないがムナフマルハシ 一般的な学名で Erythrogenys erythrocnemis Black-necklaced Scimitar-Babbler は台湾に生息し、"Erythrogenys" 属はヒマラヤから東南アジアのグループなので遠い地域の話題ではない。日本で記録されることがあればそのころには学名が修正されているかも知れない。
-
ソウシチヨウ
- 学名:Leiothrix lutea (レイオトゥリックス ルーテア) 黄色の滑らかな髪の鳥
- 属名:leiothrix (合) 滑らかな髪の鳥 (leios 滑らかな thrix, trikhos 髪 Gk)
- 種小名:lutea (adj) 黄色の
- 英名:Red-billed Leiothrix
- 備考:
leiothrix は leios はギリシャ語では "レーオス"。thrix は短音。"レイオトゥリックス" または "レーオトゥリックス" となると思われる。
英語でも Leiothrix が使われるので発音を確認してみると "ライオトゥリックス" のように聞こえる。"リー" の読み方も考えられるがアクセント音節なので2重母音が好まれるのか、あるいは英語にはあまり現れない形なので地名などに現れるドイツ語読みが普及しているのかも。
lutea は冒頭が長母音でアクセントもある (ルーテア)。
5亜種あり (IOC)。
新宅・中村 (1998) Birder 12(4): 76-79 によれば中国とオランダの提案により CITES Appendix II への格上げが提案され可決されたとのこと。1986-1992 年に 36310 羽の商取引された実績があるとのこと。
Leiothrix lutea, Red-billed Leiothrix によれば IUCN ではずっと LC 種であるが、1997 年以降 225517 羽が商取引されたとのこと (NEP-WCMC CITES Trade Database, January 2005)。
日本では外来種としてお邪魔状態だが、原産地ではむしろ保護を要する状況で、例えば xeno-canto でも音声ファイルはアクセス制限がなされている。
◆「日本鳥類目録 改訂第8版」新規掲載の鳥
この部分の配列は改訂第8版掲載順 (= IOC 13.2) になっている。学名なども新しいものを用いている。種類は Birder 37(12): 33 (2023) に載っているもの。センカクアホウドリも同様のはずだが、改訂第8版で分離は行われずこのリストには含まれていない。
カモ目 ANSERIFORMES カモ科 ANATIDAE
-
アオガン
- 学名:Branta ruficollis (ブランタ ルーフィコルリス) 赤い首の黒いガン
- 属名:branta 古ノルド語 Brandgas (焼かれたガン/黒いガン) をラテン語化したもの (#コクガンの備考も参照)
- 種小名:ruficollis (adj) 赤い首の (rufus (adj) 赤い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:IOC: Red-breasted Goose
- 備考:
branta は#コクガン参照。
ruficollis は#カイツブリ参照。
単形種。
記載時学名 Anser rvficollis Pallas, 1769 (原記載) 基産地 Lower Ob, southern Russia (Avibase より)。結構詳しい記述で図版も入っている。
rvficollis = ruficollis は英名の由来と想像できる (-collis は首のみでなく胸も指し、どちらの訳も使われている。Red-necked Goose の別名もある)。
Rufibrenta Bonaparte, 1856 の単形属が提唱されたことがあった。rufi- 赤い と Brenta 属より。Dement'ev and Gladkov (1952) はこの属名を用いていた。
Anas torquata Gmelin, 1774 (参考 1, 2) の別名が挙げられている。
この torquata も首飾りなどの意味で ruficollis に近い意味。首に特徴のあるカモやガンは多いので、この用例があるために無効となった後の Anas torquata の用例がいくつもある。Anas torquata Wood, 1837 (参考) Ring Duck はおそらくマガモのことか。
漢字表記では "アオ" は "蒼" とのこと。アオサギやオオタカに使われる漢字で、必ずしも現代考えるような青っぽいガンの意味で付けられたものではなかったのかも知れない。
-
カナダガン
- 学名:Branta canadensis (ブランタ カナデーンシス) カナダの黒いガン
- 属名:branta 古ノルド語 Brandgas (焼かれたガン/黒いガン) をラテン語化したもの (#コクガンの備考も参照)
- 種小名:canadensis (adj) カナダの (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:Canada Goose
- 備考:
branta は#コクガン参照。
canadensis は#カナダヅル参照。
旧#シジュウカラガンより分離。シジュウカラガンと同種時代は種和名がシジュウカラガンで混乱要因ともなっていたが分離され解消された。解説はシジュウカラガンの方にまとめた。
-
アメリカビロードキンクロ
- 学名:Melanitta deglandi (メラニッタ デグランディ) ディグランの黒いカモ
- 属名:melanitta (合) 黒いカモ (melan- (接頭辞) 黒い netta カモ Gk)
- 種小名:deglandi フランスの鳥類学者 Come Damien Degland に由来
- 英名:IOC: White-winged Scoter
- 備考:
melanitta は#ビロードキンクロ参照。
deglandi は規則通りであれば "デグランディ" のアクセントとなる。
単形種。
記録論文は先崎他 (2020) 宮城県仙台湾におけるアメリカビロードキンクロ Melanitta deglandi の観察記録。
-
オウギアイサ
- 学名:Lophodytes cucullatus (ロポデュテース ククーラートゥス) 頭巾をかけた冠のある潜るもの
- 属名:lophodytes (合) lophos 冠 dutes 潜るもの Gk
- 種小名:cucullatus < cucullus 頭巾
- 英名:IOC: Hooded Merganser
- 備考:
lophodytes はギリシャ語合成語で dutes の語末が長母音。"ロポデュテース" のアクセントと考えられる。
cucullatus は2つめの u と所有の -atus の a が長母音。"ククーラートゥス" のアクセント位置。
単形属で単形種。
記載時学名 Mergus cucullatus Linnaeus, 1758 (原記載) 基産地 America = Virginia and Carolina (Avibase による)。
Lophodytes 属はオウギアイサ属。Reichenbach (1853) による。
記録論文は桐原・神谷 (2020) 鳥取県大山町におけるオウギアイサの本州初記録。
アマツバメ目 APODIFORMES アマツバメ科 APODIDAE
-
クロビタイハリオアマツバメ
- 学名:Hirundapus cochinchinensis (ヒルンダプース コキンキネーンシス) 南ベトナムのツバメのようなアマツバメ
- 属名:hirundapus ツバメのようなアマツバメ (Hirundo (ツバメ) 属と Apus (アマツバメ) 属の合成)
- 種小名:cochinchinensis (adj) 南ベトナムの Cochinchina (南ベトナムを表すポルトガル語でマレー語と中国語から由来。越冬地) -ensis (接尾辞) 〜に属する
- 英名:IOC: Silver-backed Needletail
- 備考:
hirundapus は#ハリオアマツバメ参照。
cochinchinensis はポルトガル語では短母音のみ。-ensis の冒頭が長母音でアクセントがある (コキンキネーンシス)。
単形種 (IOC)。
記録論文は所崎他 (2014) 鹿児島県トカラ列島平島におけるクロビタイハリオアマツバメ Hirundapus cochinchinensis の日本初記録。
論文では3亜種と解説がある。3か所に分かれた繁殖域による亜種分類で形態的な差がない (del Hoyo et al. 1999) とのことで、おそらく台湾の亜種は基亜種のシノニムとされ、単形種となったものであろう。
カッコウ目 CUCULIFORMES カッコウ科 CUCULIDAE
-
ヒメカッコウ
- 学名:Cacomantis merulinus (カコマンティス メルリヌス) クロウタドリに似た不吉の預言者
- 属名:cacomantis 不吉の預言者 kakomantis, kakomanteos < kakos 悪い mantis, manteos 預言者 (Gk)
- 種小名:merulinus クロウタドリに似た < merula クロウタドリ
- 英名:IOC: Plaintive Cuckoo
- 備考:
cacomantis は起源となるギリシャ語が短母音のみ。"カコマンティス" のアクセント位置と考えられる。
merulinus は merula, -inus ともに短母音のみ。"メルリヌス" のアクセント位置と考えられる。
4亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明。
Cacomantis 属はヒメカッコウ属。
属名の由来はジャワ島で夜中に墓地で鳴くことから不吉を伝える預言者と考えられたことから (The Key to Scientific Names)。
記録論文は青柳・福嶋 (2022) 沖縄諸島におけるヒメカッコウの初記録。
動画: 石垣島にヒメカッコウ飛来。
繁殖地では最後に速くなって下がる単調なさえずりで有名で (パターンはツミの声に似ている。音色は、ツミよりも笛の音のようで鋭さはなく、よりゆっくりしている) 英名の plaintive (悲しげな、訴えるような) の由来ともなった。
カッコウ類の属レベルの分子系統研究は Moller and Soler (2001) Molecular phylogeny of cuckoos supports a polyphyletic origin of brood parasitism
参照。多系統であり3系統の祖先型は托卵性だったが托卵性は失われることもあった。Cacomantis 属はCuculus 属にまずまず近いこともわかる。
ツル目 GURIFORMES クイナ科 RALLIDAE
-
ウズラクイナ
- 学名:Crex crex (クレックス クレックス) ウズラクイナ (声から)
- 属名:crex ウズラクイナの種小名から昇格
- 種小名:crex krekos (Gk) ヘロドトスなどが用いた足の長い鳥。ウズラクイナを含むさまざまな鳥に同定された。Linnaeus は声からウズラクイナとした (The Key to Scientific Names)
- 英名:IOC: Corn Crake
- 備考:
crex の起源となるギリシャ語は短母音。
単形属で単形種。Crex 属はウズラクイナ属。
記録論文は川上他 (2014) 小笠原諸島父島におけるウズラクイナ Crex crex の記録。
京都の巨椋干拓地で 2010 年の記録があり (ウズラクイナ 日本野鳥の会京都支部)、改訂第8版 (予定) の記録にも含まれている。この記事は Birder 2011年2月号にもある。
チドリ目 CHARADRIIFORMES セイタカシギ科 RECURUVIROSTRIDAE
-
オーストラリアセイタカシギ
- 第8版学名:Himantopus leucocephalus (ヒマントプース レウコケパルス) 白い頭の革ひものような足の鳥
- 第7版種学名:Himantopus himantopus (ヒマントプース ヒマントプース レウコケパルス) 革ひものような足の鳥
- 第7版亜種学名:Himantopus himantopus leucocephalus (ヒマントプース ヒマントプース レウコケパルス) 白い頭の革ひものような足の鳥
- 属名:himantopus (合) 革ひものような足 (imantas 革ひも pous 足 Gk)
- 第8版種小名:leucocephalus 白い頭の (leukos 白い -kephalos 頭の Gk)
- 第7版種小名:himantopus (合) 革ひものような足 (imantas 革ひも pous 足 Gk)
- 第8版亜種小名:leucocephalus 白い頭の (leukos 白い -kephalos 頭の Gk)
- 英名:IOC: Pied Stilt
- 備考:
himantopus は#セイタカシギ参照。
leucocephalus は起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-ce- がアクセント音節と考えられる (レウコケパルス)。
単形種。
#セイタカシギより分離。
チドリ目 CHARADRIIFORMES カモメ科 LARIDAE
-
アメリカコアジサシ
- 学名:Sternula antillarum (ステルヌラ アンティルラールム) アンティル諸島の小さなアジサシ
- 属名:sternula Stern, Stearn or Starn ハシグロクロハラアジサシ (古英語) の指小名
- 種小名:antillarum Antillarum/Antillensis アンティル諸島。Antilia の複数属格形で、ヨーロッパ中世の地図に描かれた空想上の列島 (The Key to Scientific Names, wikipedia 日本語版)
- 英名:IOC: Least Tern
- 備考:
sternula は#コアジサシ参照。
antillarum は複数属格語尾の a が長母音でアクセントもある (アンティルラールム)。til-la と分節されるため重子音表記とした。
北米の種で3亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は athalassos (内陸の、海から離れた < a- 否定 thalassa 海 Gk) および亜種不明とされる。
北アメリカに生息する海鳥のアメリカコアジサシが日本で渡来したことが「鳥類標識調査」によって初めて確認されました (山階鳥類研究所プレスリリース 2016。2014 年の記録)。野外観察で本種の渡来に気づくことは難しいとのこと。
かつてはコアジサシと同種とされた。
アメリカコアジサシ コアジサシ 交雑ひな初確認 神栖 (波崎愛鳥会と山階鳥類研究所による。茨城新聞 2017)。
Small Midwestern bird poised to flutter off endangered list アメリカでは内陸個体の増加が著しく、保護種から外されたとのこと。サウスダコタから日本への飛来についても言及がある (2019)。
チドリ目 CHARADRIIFORMES ウミスズメ科 ALCIDA
-
アメリカウミスズメ
- 学名:Ptychoramphus aleuticus (プテュコラムプス アレウティクス) アリューシャンの折り畳んだような嘴の鳥
- 属名:ptychoramphus (合) < ptux, ptukhos 折り畳んだもの rhamphos 嘴 (Gk)
- 種小名:aleuticus アリューシャンの
- 英名:IOC: Cassin's Auklet (アメリカの鳥類学者 John Cassin に由来)
- 備考:
ptychoramphus は起源となるギリシャ語が短母音のみ。"プテュコラムプス" のアクセント位置と考えられる。
aleuticus は#コシジロアジサシ参照。
単形属で2亜種あり (IOC)。日本で記録される亜種は不明とされる。Ptychoramphus 属はアメリカウミスズメ属。
記録論文は小林他 (2017) アメリカウミスズメ Ptychoramphus aleuticus の日本初の標本記録。過去にも可能性のある記録が複数ある。DNA ハプロタイプは決定されたが亜種判別
はできなかったとのこと。
アリューシャンから北米西部沿岸に生息し、海岸から離れた島で営巣する。繁殖期に特に色は変わらない。しばしばテニスボールが飛んでいると例えられる (wikipedia 英語版より)。
ミズナギドリ目 PROCELLARIIFORMES ミズナギドリ科 PROCELLARIIDAE
-
クビワオオシロハラミズナギドリ
- 学名:Pterodroma cervicalis (プテロドゥロマ ケルウィカーリス) 首に特徴のある翼で走る鳥
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:cervicalis 首の (cervix, cervicis 首)
- 英名:IOC: White-necked Petrel
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
cervicalis は a が長母音でアクセントもある (ケルウィカーリス)。形容詞を作る語尾の -alis の冒頭の長母音に由来。
IOC では単形種 (もと2亜種)。種小名に使われる cervicalis は和名から想像されるような「首輪がある」は必ずしも意味しない。
英名別名 White-naped Petrel のように後頸部が白い。
かつて #オオシロハラミズナギドリ Pterodroma externa の亜種とされていたが (分離前の英名は White-necked Petrel で英名はクビワオオシロハラミズナギドリが引き継いだ)、日本鳥類目録改訂第7版ではすでに別種扱いでクビワオオシロハラミズナギドリは検討種となっていた。
長い和名になっているのは亜種時代の名称を引き継いでいるためだろう (新しく付けるならば「シロエリ...」などで始めた短い名前にすることも可能だったかも知れない)。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント(2024)では単形種の扱い。以下のバヌアツシロハラミズナギドリを別種扱いとしたのであろう (HBW/BirdLife 2020-, Clements 2021-, IOC は最初から, Howard and Moore は 4th edition から亜種扱い)。
同種とも扱われるバヌアツシロハラミズナギドリ Pterodroma occulta 英名 Vanuatu Petrel との洋上の識別は特に困難とされる。
-
オガサワラミズナギドリ
- 学名:Puffinus bannermani (プッフィーヌス バンネルマニ) バンナーマンのミズナギドリ
- 属名:puffinus (合) ツノメドリに似た鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:bannermani スコットランドの鳥類学者 David Armitage Bannerman に由来
- 英名:IOC: Bannerman's Shearwater
- 備考:
旧セグロミズナギドリ #オガサワラミズナギドリ が分離され、そのうちこの種が掲載。セグロミズナギドリ Puffinus lherminieri は日本産鳥類から外れた。
解説は #オガサワラミズナギドリ (旧名セグロミズナギドリ) の方にまとめた。
ペリカン目 PELECANIFORMES トキ科 THRESKIORNITHIDAE
-
ブロンズトキ
- 学名:Plegadis falcinellus (プレーガディス ファルキネルルス) 鎌 (の嘴)
- 属名:plegadis 鎌 [plegas, plegados (Gk) 嘴の形を指す]
- 種小名:falcinellus 小さな鎌 (falx -falcis (f) 鎌 -ellus (指小辞) 小さい。嘴の形を指す)
- 英名:IOC: Glossy Ibis
- 備考:
plegadis は plegas の e が長母音。"プレーガディス" のアクセント位置と考えられる。
falcinellus は#キリアイ参照。
単形種。Plegadis 属はブロンズトキ属。Kaup (1829) が設けた。
ドイツ語で Sichelschnaebler (鎌の嘴)。Ibis falcinellus の学名を用いていた。
記載時学名 Tantalus Falcinellus Linnaeus, 1766 (原記載) 基産地 Java and Celebes。原記載にある生息地は Austria, Italia, circa lacus となっていてどこかで基産地の変更が行われたはず。
Falcinellus は Linnaeus の発明ではなく、Gessner などがすでに用いていたもの。
The Key to Scientific Names によれば Falcinellus はイタリア語でブロンズトキを指す名称ともある。
American Ornithologists' Union 3rd edition (incl. 17th suppl.) まで Plegadis autumnalis の学名が用いられており、Linnaeus (1766) の方が本種の最初の記載と世界レベルで認定されたのは 20 世紀の初めごろのよう。
この学名は Tringa autumnalis Linnaeus, 1762 (参考) 由来のようで、もし同種と考えればこちらの方に先取権が発生する理屈になる。おそらく有効な学名と認められないと後に判断されたのではないだろうか。Linnaeus 自身も何なのかあまりよくわかっていなかった可能性もある。
種小名を属名に昇格した当時の用法 (#ノスリの備考参照) によって Falcinellus igneus (Gmelin) もあったとのこと。しかし "鎌の嘴" を示す鳥は多数あるので同じ属名が他に先に使われており無効となった。igneus は "炎のような" の意味 (The Key to Scientific Names)。
旧世界が発祥の地で 19 世紀に自然分布としてアフリカから南米に広がり、さらに北米に分布を広げた。従来は非常にまれだった非繁殖時期の西ヨーロッパの記録が近年増えて、2022 年に英国で繁殖が確認された (wikipedia 英語版より)。
国内でも近年の記録が多く、2021 年石垣島に 19 羽の群れが滞在。
中国でも数が増えているようで、福建省晋江市で国家一級保護動物「ブロンズトキ」を初確認 (2022) のような報道がある。かつてブロンズトキは中国で絶滅したと発表されたが 2009 年から再度観察されるようになっている。
英名の glossy は「光沢のある」の意味。
ブロンズトキの和名は英名から意訳したようにも見えるが、スウェーデン語やノルウェー語にそのままの意味で使われているので、おそらくトキ類の属が分割される前の旧称があったのだろう。スペイン語 (エクアドル) でも Ibis Bronceado (なめした、あるいは日に焼けた意味) が残っている (Avibase より)。
英語の bronze も語源をたどるとイタリア語の bronzo となり、複数の語源仮説があって "焼けた" もその一つ (wiktionary)。いずれも同系と考えてよさそうで、和名はこれら単語が使われていた時代の外来語由来と思われる。
タカ目 ACCIPITRIFORMES タカ科 ACCIPITRIDAE
-
アメリカハイイロチュウヒ
- 第8版学名:Circus hudsonius (キルクス フドソニウス) ハドソン湾のチュウヒ (IOC も同じ)
- 第7版種学名相当:Circus cyaneus (キルクス キューアネウス) 青っぽいチュウヒ
- 第7版亜種学名相当:Circus cyaneus hudsonius (キルクス フドソニウス) ハドソン湾の青っぽいチュウヒ
- 属名:circus チュウヒ (circus (m) 円弧、求愛の時の旋回行動からチュウヒ)
- 第8版種小名:hudsonius (Hudson Bay/Hudsons Bay ハドソン湾の)
- 第7版種小名相当:cyaneus (adj) 青っぽい
- 第7版種小名相当:hudsonius (Hudson Bay/Hudsons Bay ハドソン湾の)
- 英名:IOC: Northern Harrier
- 備考:
circus は#チュウヒ参照。
hudsonius は -ius が長母音を持たず他も短母音と考えられる (フドソニウス)。
分割のため第7版学名に相当する名称は亜種まで記した (ただし第7版では掲載亜種ではなかった)。
単形種。
アメリカチュウヒとも呼ばれた。英語別名 Marsh Hawk, Ring-tailed Hawk。北米では唯一のチュウヒ類。
かつてはハイイロチュウヒと同種とされた。アメリカではこの種はネズミなどを食べるために他の猛禽類とは異なり農家から好まれていた。殺虫剤が大量に用いられた 1970-1980 年代に数を減らした (wikipedia 英語版より)。
田沼他 (2018) 茨城県神栖市におけるアメリカハイイロチュウヒ Circus hudsonius の観察記録 Strix 34, 139-145。
小谷田 (2020) Birder 34(12): 48-51 にも識別点を中心に取り上げた記事がある。
ブッポウソウ目 CORACIIFORMES ハチクイ科 MEROPIDAE
-
ルリオハチクイ
- 学名:Merops philippinus (メロプス ピリプピーヌス) フィリピンのメロプス王(ハチクイ)
- 属名:merops (m) エチオピアの王
- 種小名:philippinus (adj) フィリピンの (-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:IOC: Blue-tailed Bee-eater
- 備考:
merops は#ハチクイ参照。
philippinus は接尾辞の -inus の冒頭が長母音でアクセントもある (ピリプピーヌス)。
Merops philippinus Linnaeus, 1766 (原記載) 基産地 Philippine Islands と由緒ある学名であるが、何と原記載に学名がない。
参考によれば訂正 (errata) があったとのこと。
同じページにある マダガスカルハチクイ Merops superciliosus Olive Bee-eater / Madagascar bee-eater はマダガスカル産でルリオハチクイのシノニムに現れることもある。こちらの種小名は "眉のある" の意味。
かつてはハリオハチクイの和名があった。中央尾羽が長いことを意味するらしい。他の類縁種と同種時代の名称だったかも知れない。
単形種。
2例の確認による:
山本他 (2015) ルリオハチクイ Merops philippinus の日本初記録、
嵩原他、沖縄島におけるルリオハチクイ Merops philippinus の国内2例目の記録。
ハチクイの学名に Merops philippinus が使われている例がある (wikipedia 日本語版) ので注意。
スズメ目 PASSERIFORMES サンショウクイ科 CAMPEPHAGIDAE
-
リュウキュウサンショウクイ
- 第8版学名:Pericrocotus tegimae (ペリクロコートゥス テギマエ) 手島の二股に分かれた尾の濃い黄色の鳥(サンショウクイ)
- 第7版亜種学名:Pericrocotus divaricatus tegimae (ペリクロコートゥス ディーウァーリカートゥス テギマエ) 手島の二股に分かれた尾の濃い黄色の鳥(サンショウクイ)
- 属名:pericrocotus (合) およそサフラン色の (peri- (接頭辞) およそ、非常に、全体が krokotus 濃い黄色の < krokos サフラン Gk; 濃い黄色の (コンサイス鳥名事典)。Pericrocotus 属の多くは全身鮮やかな色の種類が多く、サンショウクイのような灰色の種は例外的
- 第8版種小名:tegimae [日本の教育学者 Seiichi Tegima (手島精一) が由来]
- 第7版種小名:divaricatus (adj) (尾羽が) 二股に分かれた (divarico (tr) 間があいている の過去分詞形)
- 第8版亜種小名:tegimae [日本の教育学者 Seiichi Tegima (手島精一) が由来]
- 英名:IOC: Ryukyu Minivet
- 備考:単形種。
#サンショウクイより分離。
pericrocotus は#サンショウクイ参照。
tegimae はラテン語読みでは i にアクセントがあると考えられる (テギマエ)。
Pericrocotus tegimae (Stejneger, 1887)。
日本の (通常の) サンショウクイは Pericrocotus japonicus と呼ぶのが適切と提案していた。
三上・植田 (2011) 西日本におけるリュウキュウサンショウクイの分布拡大。
Kim et al. (2021)
First acoustic recording of the Ryukyu Minivet (Pericrocotus tegimae) in the Republic of Korea by using and automatic acoustic recorder
韓国初の音声記録。自動録音で、判別には Mikami and Ueta (2016) を用いている。
Oh et al. (2021) First record of inland observation of the Ryukyu Minivet (Pericrocotus tegimae) in the Republic of Korea
(韓国内陸部初記録)。
[系統の検討]
分子系統解析の論文が思ったほど見当たらないので、GenBank でリュウキュウサンショウクイの配列を探すと3つしかなかった (2025.3 現在)。あまり調べられていない。このうち GQ255862.1 を使って BLAST を試してみた。よく使われる遺伝子 ND2 だが配列が短いのでそこまで精度がないかも知れない。
たかだか3遺伝子なのでそれ以上言えることは限られているが、GQ249148.1 (ODC) を使うともっとまとまりの悪い結果となり、GQ249123.1 (G3P) はさらに短くいずれもこれらの種の関係についてあまり情報が得られない。
ND2 でサンショウクイとリュウキュウサンショウクイを含む枝にチャイロサンショウクイ Pericrocotus cantonensis Brown-rumped Minivet (中国中・東部で繁殖しタイやインドシナ半島で越冬) と Pericrocotus roseus Rosy Minivet (ヒマラヤから中国南部、インドシナ半島に分布。チャイロサンショウクイと同種とされることもある) が内包され、
サンショウクイとリュウキュウサンショウクイをまとめると単系統をなさないため亜種として扱えず、分子系統解析から種分離が必須 (限られた遺伝情報なので暫定) であった。
サンショウクイとリュウキュウサンショウクイには違いがあるとは知っていても単系統性の要請とは知らなかった (例えばオオタカとアメリカオオタカの分離理由と同様) ... だが後述の論文を見るとサポートは弱いとのこと。
同じことを意味するが {リュウキュウサンショウクイ + チャイロサンショウクイ + Pericrocotus roseus} が系統をなし、サンショウクイとリュウキュウサンショウクイはあまり近くなかった。サンショウクイ類はおそらくヒマラヤから中国にかけて分布した南方型と、長距離の渡りを行うようになった北方型が分離し、南方型内部で種分化を遂げたものの1種がリュウキュウサンショウクイ。
北方型は1種のみかつ日本ではやや衰退傾向で南方型が勢力を伸ばしているところだろうか。北方型も寒さに弱いと言われるように (秋の渡りも早い) 温度適応範囲が狭いのかも知れない。
留鳥傾向の強い南方型の方がむしろ温度適応範囲が広いのかも知れない (コマドリとコルリの関係からも同様の印象を受ける。この系統については#コルリ参照)。
サンショウクイの備考でも触れたが、サンショウクイの分布は現状では本州の日本海沿岸にかなり偏っている。北海道に分布しないことから朝鮮半島経由で大陸から分布を広げたように見える。近畿地方でも北に行くと高い密度でサンショウクイに出会えるが京都市街地近くではそれほどでもない。
関東平野はこの主要分布から遠いため、都市化などで数を減らしたのが目立ったのかも知れない。結果的に国内では絶滅危惧 II 類となり、地域の RDB でもそのまま踏襲している感じを受けるが京都市街地近くで観察していてもそれほど減っている印象は受けない。コサメビタキでも同様だが関東平野の指標に引きずられ過ぎの印象も受ける (世界的にはカシラダカの評価がヨーロッパの視点が濃厚に現れているのと同様)。
それはともかく南から分布を広げてきた種の方が優勢の傾向が感じられ、例えばヒメアマツバメも同様に見える。これらは留鳥傾向を保ったまま分布を広げているので、海を越える程度の分散能力があれば気候などによる制約要因が少ないのかも知れない。
上記のように遺伝子による系統解析では現状あまり物が言えないが、ND2 の結果が地理分布ともある程度整合性があるように見えるのでここではこの遺伝子による結果を重視した解釈を紹介した。今後の研究次第で解釈が変わるかも知れない。遺伝子情報がないのでリュウキュウサンショウクイがどこから来たのか誰もあまり議論しないのか...。
これを記述してから Jonsson et al. (2010b) A molecular phylogeny of minivets (Passeriformes: Campephagidae: Pericrocotus): implications for biogeography and convergent plumage evolution (sci-hub) が読めることを知った。
サンショウクイとリュウキュウサンショウクイの関係については特に解説はなく種グループ grey minivets (P. cantonensis/divaricatus/tegimae complex) としている。"サンショウクイ上種" の呼び方でよいかも知れない。
#サンショウクイ備考で紹介。
H&M4 では Treatment at specific rank tentative; see limited evidence in Jonsson et al. (2010) と種分離の扱いは暫定。also evidence of moult see Stresemann & Stresemann (1972) と換羽様式に違いがある根拠がある。But see Orn. Soc. Japan (2000) と当時は日本鳥学会はまだ分離していなかった。
サンショウクイのミトコンドリアゲノムは読まれているので、そのうちもう少し研究が進むことを期待したい。LC541447.1 をベースに BLAST を行うと Pericrocotus 属で現れるのはもう1種オナガベニサンショウクイ Pericrocotus ethologus Long-tailed Minivet のみでこの2種の系統は相当違うことがわかる。
リュウキュウサンショウクイを含むサンショウクイグループの南方型 (?) はまだこのレベルで調べられておらず、分子遺伝学の研究者にとって食指が動きにくいグループなのかも知れない。
原稿執筆中の 2025.4 京都ではリュウキュウサンショウクイと考えられる声を複数回記録 (個人的な初記録 2016 年、ここ数年増えている)。ここはサンショウクイが繁殖するので繁殖期に同所的に生息しているのか。
ただしまだリュウキュウサンショウクイ複数個体が飛ぶ声は記録していない。サンショウクイはよく聞く声なので特に気をつけて録音されないかも知れないが、現状を記録しておかないといつの間にか声が変わってしまっている可能性もあるかも?
スズメ目 PASSERIFORMES シジュウカラ科 PARIDAE
-
オリイヤマガラ
- 第8版学名:Sittiparus olivaceus (シッティパルス オリーウァーケウス) オリーブ緑色のゴジュウカラのようなシジュウカラ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Poecile varius (ポエキレ ウァリウス) 色変わりの黒い帽子のカラ
- 第7版亜種学名:Poecile varius olivaceus (ポエキレ ウァリウス オリーウァーケウス) オリーブ緑色の黒い帽子のカラ
- 第8版属名:sittiparus [Sitta (ゴジュウカラ) 属と Parus (シジュウカラ) 属から合成]
- 第7版属名:poecile (合) 黒い帽子の (カラ) (poikilos 多彩の、まだらのなどの Gk; 属訳名は属定義から)
- 第8版種小名:olivaceus オリーブ緑色の (oliva オリーブ -aceus のような)
- 第7版種小名:varius (adj) 変化のある、多色の、さまざまな色の。ヤマガラを指してヨーロッパシジュウカラの色変わりと記載したと解釈した
- 第7版亜種小名:olivaceus オリーブ緑色の (oliva オリーブ -aceus のような)
- 英名:IOC: Iriomote Tit
- 備考:
sittiparus は#ヤマガラ参照。
olivaceus は i と a が長母音 (前者はオリーブの長音に相当) で後者にアクセントがある (オリーウァーケウス)。oliva は i が長母音。
-aceus (形容詞を作る語尾) では a が長母音となる。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
単形種。ヤマガラより分離。
スズメ目 PASSERIFORMES ウグイス科 CETTIIDAE
-
チョウセンウグイス
- 第8版学名:Horornis canturians (ホロルニース カントゥリアーンス) 歌う丘の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Cettia diphone (ケッティア ディポーネ) 2種類の声を持つチェティーの鳥
- 第7版亜種学名:Cettia diphone canturians (ケッティア ディポーネ カントゥリアーンス) 歌う2種類声を持つチェティーの鳥
- 第7版属名:horornis 丘の鳥 (oreos 丘 ornis 鳥 Gk)
- 第7版属名:cettia (合) フランチェスコ・チェティーの (-ia (接尾辞) 人名を属名にする) イタリアの数学者で動物学者の Francesco Cetti)
- 第8版種小名:canturians 歌っている (canturio < cantare 歌う -ans 現在分詞形)
- 第7版種小名:diphone (合) 2種類の声 (di- (接頭辞) 二つの phone 音声 Gk)
- 第7版亜種小名:canturians 歌う (canturientis 鳴く < canturire < cantare 歌う)
- 英名:IOC: Manchurian Bush Warbler
- 備考:
horornis, diphone は#ウグイス参照。
canturians は悩ましい。cantare (歌う) は a が長母音、cantus (歌) の名詞は主格では短母音だが、canturio (cantare から派生した動詞) の表記を見ると u, i ともに短音で発音すると考えられる。-ans の現在分詞形は a が長母音。
この長音を採用した (カントゥリアーンス)。
The Key to Scientific Names の解釈は少し違っていて canturiens, canturientis (chirping) < canturire (to chirp) < cantare (to sing) となっているが文字が少し違うので上記解釈の方が自然に思える。意味は同じで英語では singing に相当するが長音とアクセント位置の推定のための検討。
2亜種あり (IOC)。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
#ウグイスより分離。英語別名 Korean Bush Warbler。
日本で記録のあるものは亜種 borealis (北方の) と記載されている。基亜種は検討亜種扱い。
スズメ目 PASSERFORMES ムシクイ科 PHYLLOSCOPIDAE
-
シセンムシクイ
- 学名:Phylloscopus yunnanensis (ピュッロスコプス ユンナネーンシス) 雲南省のムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:yunnanensis 中国雲南省 (Yunnan Province) の
- 英名:IOC: Chinese Leaf Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
yunnanensis は他の表記に合わせて -ensis の冒頭を長母音とした (ユンナネーンシス)。
単形種。
報告論文: 中野・渡部 (2021) 徳島県剣山における Chinese Leaf Warbler Phylloscopus yunnanensis の日本初記録。
記事の例 (2016)。
Phylloscopus yunnanensis はかつて La Touche's Leaf-Warbler と呼ばれていた (La Touche, JDD 1922)。La Touche は当初カラフトムシクイ Phylloscopus proregulus の亜種として記載し、1925 年に種に昇格した。
しかし Ticehurst (1938) が Phylloscopus proregulus 'chloronotus' (当時は現在の Phylloscopus chloronotus がカラフトムシクイの亜種となっていた。後述) の標本と比較して区別できないため、yunnanensis の分離は適切でないとした。これを受けて忘れ去られていたものだったが、
Alstrom et al. (1992) A new species
of Phylloscopus warbler from central China
が新種 Phylloscopus sichuanensis を記載 (結果的に再発見となった) し、タイプ標本に組織サンプルや音声記録のないものを選んでしまった。
Eck が sichuanensis と yunnanensis を比較し、標本が Alstrom et al. (1992) の図版とよく一致することをつきとめた。
Martens and Eck (1995) は少なくともこの時点で sichuanensis を yunnanensis のシノニムと扱った。
Martens et al. (2004) の分子系統研究で yunnanensis が種に相当することを示し、Ticehurst (1938) の見解とは異なってカラフトムシクイと近縁でないことが判明した [Martens et al. (2010)
Systematic notes on Asian birds: 72. A preliminary review of the leaf warbler genera Phylloscopus and Seicercus; #キタヤナギムシクイ に記載の論文]。
sichuanensis が yunnanensis のシノニムとなったため種小名が四川から雲南に変わってしまったが、和名は四川を引き継いだため現在の状況になっている [種の和名は学名が変わってもそのまま維持するというのが一般的な考え方と中野・渡部 (2021) に記されている。詳細なニュアンスは論文を参照いただきたい]。
和名の歴史とそれぞれの検討については中野・渡部 (2021) に記載されている。この種には3和名が提唱され、シセンムシクイは世界鳥類名勉強会 (1998) または茂田 (1998) (あるいは両者) が Phylloscopus sichuanensis 時代に付けられたもの。カホクムシクイは梅垣・大西 (2011) が提唱。ウンナンムシクイは茂田 (2011) が提唱とのこと。
Sichuan Leaf Warbler に対してシセンムシクイの和名が過去に使われたことがあり (茂田 2011) 混乱を招く可能性があることは示されている。今後新しい和名が提唱されることを妨げるものでもないとも記しているとも記されている。
英名で「シセンムシクイ」を意味する Sichuan Leaf Warbler Phylloscopus forresti Rothschild, LW 1921。これも当初はカラフトムシクイの亜種扱い、または著者によってはウスゴシムシクイ Phylloscopus chloronotus 英名 Lemon-rumped Warbler の亜種とされていた。
Maetens et al. (2004) では Phylloscopus forresti は原初記載よりも広範な四川省のムシクイに適用可能である見解を示しているが、遺伝情報解析では否定的であったとのこと。
-
アムールムシクイ
スズメ目 PASSERIFORMES ヨシキリ科 ACROCEPHALIDAE
-
スゲヨシキリ
- 学名:Acrocephalus schoenobaenus (アクロケパルス スコエノバエヌス) 芦原を行くヨシキリ
- 属名:acrocephalus (合) 尖った頭 (acro- (接頭辞) 先端 (akron) kephali 頭 Gk)
- 種小名:schoenobaenus (合) skhoinos 芦 baino 歩く Gk
- 英名:IOC: Sedge Warbler
- 備考:
acrocephalus は#オオヨシキリ参照。
schoenobaenus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音で -us をラテン語化のための語尾とすれば長母音は現れないと考えられる。a がアクセント位置と考えられる (スコエノバエヌヌ)。
schoen は同じ綴りのドイツ語があってよく知られている (シェーン。美しい) のであるいはこの読みが使われることがあるかも知れない。
単形種。
ヨーロッパでは普通種。
記録論文は田中・三上 (2017) スゲヨシキリの日本初放鳥記録。
-
マンシュウイナダヨシキリ
- 学名:Acrocephalus tangorum (アクロケパルス タンゴールム) タングのヨシキリ
- 属名:acrocephalus (合) 尖った頭 (acro- (接頭辞) 先端 (akron) kephali 頭 Gk)
- 種小名:tangorum 中国の採集家 Tang Wang Wang と兄弟の Tang Chung Kai (La Touche に採集を提供した) に由来。唐 (Tang) の皇帝を指しているとの過去の解釈は誤りだったとのこと (The Key to Scientific Names)
- 英名:IOC: Manchurian Reed Warbler
- 備考:
acrocephalus は#オオヨシキリ参照。
tangorum の読み方はよくわからないが -orum の綴りはラテン語でよく現れる (複数・属格) ので類推からこのように読まれる可能性があると考える (タンゴールム)。
"タンゴルム" でも構わない。
単形種。
コクリュウコウイナダヨシキリの名称も使われた。
記録論文は菊池 (2018) マンシュウイナダヨシキリの国内初記録。
スズメ目 PASSERIFORMES ヒタキ科 MUSCICAPIDAE
-
ミナミトラツグミ (海外ではオオトラツグミは独立種)
- 第8版種学名:Zoothera dauma (ゾーオテーラ ダウマ) 虫を狩るツグミの一種
- 第8版亜種学名:Zoothera dauma (ゾーオテーラ ダウマ マヨル) 大きな虫を狩るツグミの一種 (ミナミトラツグミ亜種オオトラツグミ。他亜種あり)
- AviList 学名:Zoothera major (ゾーオテーラ マヨル) 大きな虫を狩るツグミの一種 と Zoothera dauma (ゾーオテーラ ダウマ) 虫を狩るツグミの一種
- 第7版種学名:第8版と同じ
- 第7版亜種学名:第8版と同じ
- 属名:zoothera (合) 虫(動物)を狩る鳥の (zoo- (接頭辞) 動物 thira 狩り Gk)
- 第8版種小名:dauma (合) Dama(ベンガル地方でオレンジジツグミ Geokichla citrina); ヒンディー語で Dauma チャイロイワビタキ Oenanthe fusca。トラツグミに関係する現地名は特にないらしい (The Key to Scientific Names)
- AviList 種小名:major (adj) より大きな と dauma (合) Dama(ベンガル地方でオレンジジツグミ Geokichla citrina); ヒンディー語で Dauma チャイロイワビタキ Oenanthe fusca。トラツグミに関係する現地名は特にないらしい (The Key to Scientific Names)
- 第7版種小名:第8版と同じ
- 第8版亜種小名:major (adj) より大きな (亜種オオトラツグミ。他亜種あり)
- 第7版亜種小名:第8版と同じ
- 英名:IOC, AviList: (Scaly Thrush、日本の分類に相当するものを挙げた。オオトラツグミに対応するものは Amami Thrush。備考参照)
- 備考:
zoothera, dauma は#トラツグミ参照。
major は "マヨル"。
トラツグミより分離。IOC, AviList 分類とは異なる。IOC, AviList では奄美大島のオオトラツグミを Zoothera major (種小名は「大きい」の意味) (英名 Amami Thrush) として単形種で扱っている。
英名は Zoothera dauma に相当するものを挙げたが、IOC ではこの種に3亜種を認めている (日本鳥学会の立場であれば4亜種か)。
日本鳥学会の扱いでは日本で記録される亜種は major オオトラツグミ と iriomotensis (西表島に由来) コトラツグミ となる。
解説は #トラツグミ を参照。
亜種オオトラツグミの記載時学名は Geocichla major Ogawa, 1905 (原記載 オオトラツグミの名称はここで与えられている)。
亜種コトラツグミの記載時学名は Zoothera dauma iriomotensis Nishiumi & Morioka, 2009 (原記載 コトラツグミの名称はここで与えられている)。
-
オレンジジツグミ
- 学名:Geokichla citrina (ゲオーキクラー キトゥリーナ) シトロン色の地ツグミ
- 属名:geokichla (合) 地ツグミ (geo- 地面 kikhle ツグミ Gk)
- 種小名:citrina 黄色い、シトロン色の (citrinus < citrus シトロン)
- 英名:IOC: Orange-headed Thrush
- 備考:
geokichla は#マミジロ参照。
citrina は -ri- の i が長母音でここにアクセントがある (キトゥリーナ)。
10 亜種あり (IOC)。
日本で記録されたものは亜種不明とされる。インド亜大陸や東南アジアに分布する。
記録論文は村岡他 (2014) 鹿児島県トカラ列島平島における Orange-headed Thrush Zoothera citrina の日本初記録。
亜種 cyanotaは独立種とされる可能性があるとのこと。
Rasmussen and Anderton (2005) "Birds of South Asia. The Ripley Guide" によればこの種に1つ以上の隠蔽種が含まれている可能性があるとのこと。
村岡他 (2014) の記録は外見は亜種 aurimacula, courtoisi, melli のいずれかであると考えられ、飛来条件を考えると後2者の可能性が考えられるとのことである。
和名はやや複雑で、山階 (1986) はオレンジジツグミを用いた。ジツグミに相当する英名 ground thrush は Zoothera属に多く用いられているが、対応する和名ではジツグミが使われていないことなどから、
この文献では新称オレンジツグミを提唱したが、第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開ではオレンジジツグミが採用されている。
"オレンジジツグミ" に相当する英名を持つ種 Geokichla gurneyi 英名 Orange Ground Thrush (和名はアフリカジツグミとされている) があるので、この場合も和名・英名の関係はややこしい。
-
ウタツグミ
- 学名:Turdus philomelos (トゥルドゥス ピロメーロス) ナイチンゲール (ピロメーラ) のツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:philomelos ナイチンゲール philomela (ギリシャ神話でパンディオンの娘。ナイチンゲールに変えられた) (The Key to Scientific Names)
- 英名:IOC: Song Thrush
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
philomelos はラテン語 philomela では e が長母音でアクセントもあるのでそれに従った (ピロメーロス)。
philomela の語源はギリシャ語で philos (愛) melon (メーロン) で e の長母音はこれに由来する。melon の本来の意味はリンゴ、果物、羊を指していたが philomela は少なくとも Ovid (Ovidius オウィディウス) 時代には「歌を愛するもの」の意味で使われていた (wiktionary)。
ギリシャ語 melos (歌) 由来と解釈してもよいと感じられるが e が短母音で直接の語源とは考えにくい (あるいは時代の前後関係から) として wiktionary の解釈が行われているのだろう。
ラテン語 philomela は動物学でツバメまたはナイチンゲールの意味で使われる学術用語。
学名に使われた philomelos は新しい用例なのでギリシャ語 melos を参考にした可能性がある (The Key to Scientific Names は philomela を直接の由来としているが、philomela の語源解釈は wiktionary と異なる)。
philomela の変形と考えるならば e が長母音、ギリシャ語 melos に合わせたとすれば短母音で判定困難だが長母音か短母音かでアクセント位置が変わる。ここでは philomela にすでに「歌を愛するもの」の意味があることから philomela 由来と考え長母音を採用した。
なお philomelos の用例は現行の学名ではこれ1例のみで、philomela の用例はもう少し多い (The Key to Scientific Names)。philomela が女性名詞なので Turdus に合わせて多くのギリシャ語の男性名詞でみられる -os の語尾に変えたものかも知れない。
4亜種あり (IOC)。
日本で記録されたものは亜種不明とされる。ヨーロッパではごく普通種で東方の分布もバイカル湖付近まで広がっている。ニュージーランド・オーストラリアに移入された個体群がある。
記録論文は
青木他 (2014) 日本国内におけるウタツグミSong Thrush Turdus philomelosの 初標識記録、
渡部他 (2019) 神奈川県相模原市におけるウタツグミ Turdus philomelos の記録
があり、
坂本 (2016) 2014 年に相模原市内で越冬したウタツグミの観察記録
など複数の記録がある。
大阪城公園の個体を観察したことがあるが、ウタツグミの地鳴きはむしろホオジロ類に似ていてやはり馴染みのツグミ類とはだいぶ違う。どこにいるかわからない時に探すのには役立った。
もっともマミジロの地鳴きも似ているので必ずしも系統を反映しているわけではないかも知れない。
[学名の変遷経緯]
記載時学名 Turdus philomelos Brehm, 1831 (原記載) と意外に新しい。このような場合は大抵何かややこしい事情がある。
Dement'ev and Gladkov (1954) の時代には Turdus ericetorum philomelos となっていた。
ericetorum の種小名は Lewin (1796) が "Heaththrush" の名称で呼んだものがあるらしい (The Key to Scientific Names)。Dement'ev and Gladkov (1954) では Turdus Ericetorum Turton, 1807 を採用し、多くの古い書物では Turdus musicus (音楽的なツグミ) が用いられているとある。
Mathews and Iredale The Name of the British Song-thrush にも関連する記述がある。
Dement'ev and Gladkov (1954) から想像すると Linnaeus (1758) の付けた学名がウタツグミに対して長期間使われていて英名の Song Thrush やおそらくそれを訳したと思われる和名もこの学名に由来していたのだろう。
後述の Mayr and Vaurie (1957) の説明にあるように Hartert (1909) が Linnaeus (1766) の修正を取り入れずに伝統的なウタツグミの学名をワキアカツグミに変更し、次に古い学名を探したところまず Turdus philomelos Brehm, 1831 が見つかって用いられていたが、
続いて Turdus Ericetorum Turton, 1807 のより学名が見つかってこちらに先取権があると考えられた経緯と考えられる (Mathews and Iredale に学名変更の記述がある)。ericetorum は ericetum (ヒース。英語 heath) の複数・属格 < erice (ヒース、ソラマメ類など) + -etum ("の茂み" を作る接尾辞。植物用語)。発音は "エリーセートールム"。
1930-1950 年代はこの学名 Turdus Ericetorum が使われた論文もいくつもあったが、
Glecg (1952) The Validity of Turton's Name, Turdus Ericetorum for The Song-thrush がこの学名も無効であることを主張したようで (中身は読めない)、Turdus philomelos が復活した経緯のよう。
Brehm も、あるいは種小名に他でも使われる philomela を用いると衝突のおそれがあって意識的に語尾を変えた学名だったのかも知れないと考えると変則的な語尾の由来も納得できる感じがする。
詳しい解説は Mayr and Vaurie (1957) Proposed use of the plenary powers to suppress the specific name musicus Linnaeus, 1758, as published in the combination Turdus musicus and to approve a neo-type for Turdus iliacus Linnaeus
にある。
この記述によれば Linnaeus (1758) の参照した 1746 年の Fauna svecica で Turdus musicus に対応する項目のうち4つはウタツグミの記述と判定できるが、2つはワキアカツグミと判定され、Linnaeus (1746) はこの2種を区別していなかったと判定されるとのこと。
Linnaeus (1758) では別種扱いとしたものの Turdus iliacus の diagnosis にウタツグミと判定できるものを与え、Turdus musicus の diagnosis にもワキアカツグミと判定できるものを与えるなどまだ混同していたとのこと。
Linnaeus は改訂版 (1766) で diagnosis を整理して Turdus musicus がウタツグミ、Turdus iliacus がワキアカツグミを指すように修正された。この行為が有効な First Reviser とみなされて受け入れられ、これらの学名が長く使われていた。
Hartert (1909) Bull. BOU 23: 54 がこの慣習を覆し、Linnaeus (1758) が Turdus musicus をワキアカツグミに用いたとの判断からこの学名をワキアカツグミに用いた (p. 653)。
この行為は無効なものだったが、権威ある Hartert の判断であったため用例に混乱を引き起こすこととなり、この時点で ICZN が介入しなかったのは不幸なことであった。
一方で Hartert (1909) は Turdus philomelos Brehm, 1831 をウタツグミの学名として用い (p. 650) 次第に使われるようになった。
先取権のある Turdus Ericetorum Turton, 1807 は一部で使われたが、ICZN Opinion 405 でこの用法は除外 (suppressed under Plenary Powers) されて Turdus philomelos がウタツグミの学名と決められた。
ただしこれも裁定の一つに過ぎず、後の裁定で覆されることも論理的に可能である。これを避けるためには Turdus musicus がワキアカツグミに使われないように裁定して suppress する必要がありこの提案に至ったとのこと。つまり Hartert (1909) が Turdus musicus をワキアカツグミに用いた判断は誤りであったと認め、この点についてはおそらくすべての鳥類学者の同意が得られるであろうとのこと。
Hartert の判断は Linnaeus (1758) が引いている Fauna Suecica 189 の diagnosis と記載からワキアカツグミのみが該当すると判定したもの。
この後の部分は Linnaeus (1758) の Turdus iliacus がワキアカツグミを指すことまでは明らかだが、どの亜種を指すかまで明瞭でないために新しく定義を与えるというもの。ヤドリギツグミの学名についても少し言及があるが、これは Linnaeus (1758) によるものに確定して問題ないとのこと。
しかしながら Vaurie (1955) Systematic notes on Palearctic birds. No. 15, Turdinae, the genera Turdus, Grandala, and Enicurus
によれば Vaurie 自身もこの時点では Turdus musicus を用いており、Turdus ericetorum や Turdus philomelos よりもこの学名を使うべきであると Mayr (1952) Ibis, pp. 532-534 が主張していたことを引用している。
この当時は Turdus musicus の学名の方が主流派で、Mayr and Vaurie はその後見解を変えたことがわかる。比較的最近 (と言っても 1950 年代) までウタツグミの学名はウタツグミ (音楽的なツグミ) だった。
ということでこれらのツグミ類の学名が国際的に確定したのは 1957 年となる。
これらの他の学名はすべて無効学名となったため例えば現在の文献のシノニムを見ても過去の名称はわからないが、ウタツグミの名称の由来 (あるいは変則的な種小名語尾やあまり直接的でない種小名の由来) を考える時は長く使われた Turdus musicus まで遡った方がよいことがわかる。
Hartert (1909) が余計な混乱をもたらさなければウタツグミの学名は現在でも Turdus musicus (トゥルドゥス ムースィクス) だったかも知れない。歴史を振り返るつもりで発音してみるのもよいだろう。#ウタスズメ学名も参照。
OED によれば song thrush の用例は古く 1598 年のものが知られている (この文献ではスペイン語 la mirla と紹介されている)。現在と同じものを指しているかはよくわからないが。
-
クロウタドリ (#クロウタドリ にまとめた)
ハチジョウツグミ
- 学名:Turdus naumanni (トゥルドゥス ナウマンニ) ナウマンのツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:naumanni (属) ナウマンの (ドイツの農家、博物学者の Johann Andreas Naumann に由来。有名な Johann Friedrich Naumann とは別人なので注意)
- 英名:IOC: Naumann's thrush (由来は種小名を参照)
- 備考:亜種から昇格。単形種。旧ツグミ時代はこちらが基亜種だったため、新ツグミの方の学名が変わる。
亜種時代の項目がすでに分離されていたため情報は #ハチジョウツグミ の方にまとめた。
チャムネサメビタキ
- 学名:Muscicapa muttui (ムスキカパ ムットゥイ) ムットゥのハエトリ
- 属名:muscicapa (合) ハエを捕まえる鳥 (musca -ae (f) ハエ capio (tr) 捕まえる)
- 種小名:muttui タミールの使用人で、スリランカで Edgar Layard に採集物を提供した Muttu に由来
- 英名:IOC: Brown-breasted Flycatcher
- 備考:
muscicapa は#サメビタキ参照。
muttui は原語の読みがわからないがすべて短母音とすれば "ムットゥイ" または "ムトトゥイ" となる。
単形種。
英語別名 Layard's flycatcher。スリランカは越冬地と考えられている。
記録論文は山橋・梅垣 (2022) 神奈川県相模原市におけるチャムネサメビタキ Muscicapa muttui の日本初記録。
ホントウアカヒゲ
- 第8版学名:Larvivora namiyei (ラルウィウォラ ナミイェイ) 波江の芋虫を食べる鳥 (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Larvivora komadori (ラルウィウォラ コマドリ) 波江の芋虫を食べるコマドリ
- 第7版亜種種学名:Larvivora komadori namiyei (ラルウィウォラ コマドリ ナミイェイ) 波江の芋虫を食べるコマドリ
- 属名:larvivora 芋虫を食べる (larva 芋虫、幼虫 -vorus を食べる)
- 第8版種小名:namiyei (動物学者 波江元吉 Motoyoshi Namiye にちなむ)
- 第7版種小名:komadori (外) コマドリ
- 第7版亜種小名:namiyei (動物学者 波江元吉 Motoyoshi Namiye にちなむ)
- 英名:IOC: Okinawa Robin
- 備考:
larvivora は#コマドリ参照。
larvivora は#コマドリ参照。
namiyei はラテン語式発音では "ナミイェイ" と考えられる。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
単形種。
#アカヒゲより分離。基亜種と名称の由来は同項目参照。
記載時学名 Icoturus namiyei Stejneger, 1887 (原記載)。
リュウキュウキビタキ
- 第8版学名:Ficedula owstoni (フィーケドゥラ オウストニ) オーストンのイチジクをついばむ鳥 (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Ficedula narcissina (フィーケドゥラ ナルキススィーナ) 美少年ナルキッソスの (または水仙のような) イチジクをついばむ鳥
- 第7版亜種学名:Ficedula narcissina owstoni (フィーケドゥラ ナルキススィーナ オウストニ) オーストンの美少年ナルキッソスの (または水仙のような) イチジクをついばむ鳥
- 属名:ficedula (f) < ficus イチジク edo ついばむ
- 第8版種小名:owstoni (英国博物学者、採集家の Alan Owston 由来)
- 第7版種小名:narcissina (adj) ギリシア神話に登場する美少年ナルキッソスの、または水仙のような (Narkissos Gk; narcissus -i (m) 水仙 -inus (接尾辞) 〜に属する)
- 第7版亜種小名:owstoni (英国博物学者、採集家の Alan Owston 由来)
- 英名:IOC: Ryukyu Flycatcher
- 備考:
ficedula は#キビタキ参照。
owstoni のアクセント位置は明瞭でないが ow-sto-ni と区切るならば冒頭アクセントでよいと考えられる (オウストニ)。"ウ" は母音ではなく w の音だがあまり厳密に考える必要はないだろう。原音に近い発音でよいと思われる。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。
単形種。
#キビタキより分離。
ニシオジロビタキ
- 学名:Ficedula parva (フィーケドゥラ パルワ) 小さなイチジクをついばむ鳥
- 属名:ficedula (f) < ficus イチジク edo ついばむ
- 種小名:parva (adj) 小さい
- 英名:IOC: Red-breasted Flycatcher
- 備考:
ficedula は#キビタキ参照。
parva は短母音のみ (パルワ)。
日本鳥類目録改訂第7版では検討種 (まだ適切な論文なし) だったがすでにオジロビタキとは別種扱いだった。第7版ですでに独立種で第8版で掲載。第7版で亜種扱いと勘違いされている (第6版までは亜種扱いだった) ケースもあるため特別に別項目として掲載した (この記述は第7版準拠時のもの)。
かつてはオジロビタキの亜種として扱われていた。海外のリストではオジロビタキ albicilla を Ficedula parva の亜種とするものが一般的であった。
後者の方が記載が早いのでこれらを亜種の関係とする場合は Ficedula parva オジロビタキ とするのが適切で過去の図鑑でもそのように扱われていた。
第6版の学名も亜種名まで記述すると Ficedula parva albicilla となっており、
第7版で2種が分離された後で学名が Ficedula albicilla と変わっていたことに気づかれなかった (少なくとも注目されなかった) かも知れない
[バードリサーチの 日本鳥類目録第6版からの変更点 でも変更扱いに含まれていない]。
英名の Red-breasted は英語では throated と breasted の区別が曖昧で、breast が必ずしも 胸を指すわけではない。あまり使われなかった Red-throated Flycatcher の別名は#オジロビタキ参照。ムギマキと混同されていた背景がある。
日本では迷鳥扱いだったため地理的に考えやすい albicilla の方が主に飛来していると考え、こちらが先に目録に記載されたものと考えられる (詳細な経緯は知らない)。
茂田 (2008) Birder 22(5): 48 「オジロビタキの分類」には2種の識別点 (当時の日本の分類では2亜種) も述べられており、ニシオジロビタキも渡来・越冬すると思われるとの記載になっている。茂田自身の観察ではオジロビタキ冬羽では喉がオレンジ色の個体がいると書いている。
初野 (2008) Birder 22(5): 47 で parva と思われる個体の記録もある。del Hoyo et al. (2006) では両者が西シベリアで交雑することから同種扱いとの記述があるとのことである。
いずれも識別点を押さえた上での記述と思われるが、現在はニシオジロビタキの方が目撃数も多いのでいずれも不思議な点がある。また当時は音声の識別点はまだ押さえられていなかったのかも知れない。
今ではよく知られている通り、現在ではニシオジロビタキの方が目撃数も多く(地域によって違うかも知れない)、都市公園での越冬も多い。オジロビタキ Ficedula albicilla の方が数が少なく、渡り途中に記録されることが多いとされる。
この現象は海外研究者にとっても意外であったようで、海外サイトなどにニシオジロビタキを報告すると種類間違いではないかと (少なくともかつては) よくコメントがあった。
これはかつてのニシオジロビタキの分布図ではアフリカ北西部に越冬地が示されており、ヨーロッパに主に分布するニシオジロビタキが南に渡るのが自然であると考えられたためである。この解釈に従えば日本への "迷行" は「鏡像渡り」(逆方向への渡り) 現象と捉えられ、実際にそのような解釈も出されていた [cf. Young Guns (2014) Birder 28(6): 48-50]。
現在では eBird の報告分布にも見られるようにインドが主な越冬地で、東南アジア沿岸部にかけて広く越冬することが明らかになっている。この場合はニシオジロビタキの日本への渡りはオーバーシュート型になる。
しかし毎年のように複数個体がいろいろな場所で越冬記録される現在では、数密度は低いものの日本はむしろ定常的な越冬地の東端に位置すると考えるのが妥当そうに思える。
アフリカ北西部の越冬地でも少数は記録されるものの、主要な越冬地ではなさそうである。Dement'ev and Gladkov (1954) の分布図にもアフリカの越冬地は示されておらず、現代のヨーロッパの図鑑、例えば Collins Bird Guide (手持ちは第2版) でもアフリカが越冬分布となっておらず、越冬は西アジアと文中に記載がある。
このように繁殖分布とは逆に思える越冬数から、ウラル山脈の東にニシオジロビタキに未知の繁殖地があるのではとの考えもあった ["ウラルオジロビタキ": 元山裕康氏の「大阪城公園鳥だより」No.111 に過去の経緯も含めて詳しい。1997 年の個体が発端で、その後日本で見られるものはヨーロッパ種が大半であることが明らかになった]。
Dement'ev and Gladkov (1954) の時代でも「ヨーロッパのオジロビタキ」と「シベリアのオジロビタキ」の概念ははっきり区別して使われており、Muscicapa parva Bechstein, 1793 と Muscicapa albicilla Pallas, 1811 と最初はそれぞれ別種 (当時はそうせざるを得なかったが) として記載されていたこともわかる。
Dement'ev and Gladkov (1954) の分布図に現れる第3の亜種は現在カシミールオジロビタキ Muscicapa subrubra (「少し赤い」の意味。英名 Kashmir Flycatcher) としてこれも独立種となっている。
Peklo (1987) の「ソ連のヒタキ」に標本採集場所の地図があり、ウラル山脈の東も西も十分に広範にカバーされている。ニシオジロビタキは西シベリア平原 (ウラル山脈と中央シベリア高原の間。大きな都市ではオムスクがある) の西部にも分布し、ウラル山脈の少し東側にあたる。
西シベリア平原の東部 (ノボシビルスク州あたりより東側) はオジロビタキの分布域となっており、西シベリア平原の中央付近 (オムスク州あたり) ではどちらも分布せず、Peklo (1987) の図を見る限りはこのあたりに分布の空白域がある (後に紹介の論文も参考)。
ウラル山脈で2種が分かれているわけでなく、実際にはウラル山脈より東側が境界になるが、ウラル山脈の東にニシオジロビタキに未知の繁殖地はなさそうである。
北側ではオジロビタキはもう少し西側まで分布しており、ウラル山脈北部はオジロビタキの分布域となっている。ニシオジロビタキはここでは記録されていない。
また North Eurasia Birds Watch (#マダラチュウヒの備考も参照) で写真を見ることができるが、ウラル山脈の東でニシオジロビタキがオジロビタキと誤認されていることもなさそうである
(写真は例えば以下より: ニシオジロビタキ、オジロビタキ)。現在では両種のロシアでの分布には曖昧な点はなさそうである。
クレチマル・千村 (訳) (1991) Birder 5(7) にも繁殖地のオジロビタキの写真がある。
ロシアで使われていた学名では Siphia 属が使われていたが、現在は Ficedula のシノニムとされる。現在のノドグロヒタキ Ficedula strophiata Rufous-gorgeted Flycatcher に対して与えられた属名 (Siphia Strophiata Hodgson, 1837)。
近年の分子系統解析の結果 Ficedula 属の位置づけは大きく変わっており、古い属名は忘れてしまってよいだろう。
Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) では年代的には不思議なことに別種にせず同種として扱い、両亜種がシベリアで連続分布する地図になっている。
2亜種の識別の記載もやや不完全な感じで、成鳥オスはよく区別できるがメスは非常によく似ているとある。体の下部の側面はヨーロッパ型 (ニシオジロビタキ) はより黄土色、東方型 (オジロビタキ) はもっと明るい色とあるだけで尾の黒色の濃さや嘴の色などの識別点にも触れていない。
さえずりは違うとあるが地鳴きは東方型の方しか記述がないなど、この著者自身の識別点を押さえた観察経験が少ないのかも知れない (図もニシオジロビタキの尾は省略されていて識別点と捉えていないことがわかる)。
成鳥オス以外の「非常によく似ている」としているものが識別できていない可能性があり、この著者によるオジロビタキ/ニシオジロビタキの分布解説はそれほど真剣に捉えなくてもよい感じがする。繁殖地では日本の都市公園のような至近距離で観察することが難しいのかも知れない。
Zhukov (2021) The red-breasted Ficedula parva and the taiga F. albicilla
flycatchers in Western Siberia and near Novosibirsk (pp. 5418-5422)
ではノボシビルスク州ではニシオジロビタキは繁殖期に見られず、オジロビタキのみとのことだがかなりまれな種類で Peklo (1987) の地図にもノボシビルスク州で巣の記載はない。
Tyul'kin (2022) The records of the red-breasted Ficedula parva and red-throated F. albicilla flycatchers in Western Siberia (pp. 5184-5187)
に両種が記録される西シベリアの報告がある。
繁殖期にさえずるニシオジロビタキはウラル山脈の少し東側のチュメニ州トボリスク (Tobol'sk, 58.33 N 68.53 E) 近くで記録された。
オジロビタキのつがいはチュメニ州ハンティ・マンシ自治管区地域 (61.59 N 79.69 E) で記録された。
両種が観察された場所の間には距離があり、2つの文献とも同所的に繁殖する証拠は得られていない。
古い文献に記述があるのかも知れないが del Hoyo et al. (2006) にある両者が西シベリアで交雑する記載の由来は判然としない。
この2種は遺伝的にはそれほど近いわけではなく、ミトコンドリア Cyt b 遺伝子の距離は 6.3%、分岐年代は 320 万年前ぐらいと考えられている:
Li and Zhang (2004) Subspecific Taxonomy of Ficedula parva Based on Sequences of Mitochondrial Cytochrome b Gene (#オジロビタキ備考の簡易分子系統解析結果も参考。ニシオジロビタキがなぜ遠方から越冬にやってくるのかなど系統解析から検討を試みてみた)。
2種の識別点についてのまとまった資料は web には意外に少なく、オジロビタキとニシオジロビタキって何? - 分類からおさえよう (香川の野鳥ファイル No. 26) を紹介しておく。
大西 (2011) Birder 25(6): 50 の記事も引用されて表にまとめられているので読める方はこちらも参考になるだろう。識別点の写真での紹介もある。
大西氏による Birder 記事は音声 (地鳴き) の違いがソノグラムでも示されている。地鳴き (ジリリリ...) には明確な違いがあり、ニシオジロビタキの方が日本の Muscicapa 属と同様に個々の音が分離して聞こえるぐらいゆっくりしているが、オジロビタキでは個々の音の間隔が短く、連続音のように聞こえる。
同じ記事に塩田猛氏が 2003 年 Svensson へ問い合わせた際の返信書簡の概要が示されている。
大西氏によれば秋の渡りでは9月はオジロビタキが多いが 10 月中旬以降はニシオジロビタキが多いとのことである。過去の記録の再検討の結果でもほとんどがニシオジロビタキとのこと。
Moyle et al. (2014) Phylogeny and biogeography of Ficedula flycatchers (Aves: Muscicapidae): Novel results from fresh source material
に Ficedula 属の分子系統研究がある。4系統 (clades) に分けられる。キビタキとマミジロビタキは同じ系統に属するものの、ムギマキとは案外遠い。オジロビタキなども別系統で、オジロビタキなどの含まれる系統は長距離の渡りをするとのこと。
声が記録できれば種類の判別は疑いがなく、自分が観察・録音した範囲では外見で判断された種類と矛盾する声を示すものはなかった。繁殖地では美しい声でさえずり、ヨーロッパの音景などによく登場するが、越冬地の日本ではその声を聞けないのは残念である。かつて兵庫県のはりま中央公園に2シーズン連続して渡来し、2年目はオス成鳥の特徴を示していた個体があったがこの個体はぐぜっていた。
ぐぜりに出身地の他の種類の声を取り込んでいることからヨーロッパ出身であることを示唆する [梅垣 (2017) Birder 31(10): 38-39 (2017)。Young Guns (2017) Birder 31(3): 44 にゴシキヒワを取り上げた文章のみの解説がある] とのことであったが、この文献で示されたゴシキヒワやズアオアトリとのソノグラムの類似性はあまり明確でなかった。
同一個体の自身の録音をヨーロッパの観察者に聞いてもらったところ、ゴシキヒワ、チフチャフは判定できるとのことであったが、アオカワラヒワのように日本にも類似の声を出す種類があったり、共通に分布する種についてはヨーロッパ出身由来は判定できなかった。
挙げられた種類もいずれも分布範囲の広い種なのでどこで歌を覚えたか絞り込みは困難であるが、報告されたヨーロッパの他の種類の声の取り込みはある程度 (より確実に) 確認できたものと考えている。
3年めに期待したが再度の飛来はなかった。ここまで昔に書いていた。
オオルリやコサメビタキの「ものまね」を検討する過程で改めてソノグラムを確認してみると上記梅垣 (2017) 記事ではゴシキヒワとは周波数がだいぶ違い、ズアオアトリの地鳴きも波形や周波数が異なるので模倣とはみなしにくそうな気がしてきた。
最近うちの近くのイソヒヨドリがセグロカッコウを思わせるフレーズで鳴いて時期的に思わずはっとしてしまうが、おそらくセグロカッコウの声を聞いて模倣したのではなくイソヒヨドリの音声レパートリーの中に似たものが含まれているのだろう。音楽で何小節一致すれば盗作とみなされるのと似たような話かも (?)。似ていれば「ものまね」としてしまうとエゾセンニュウはホトトギスを真似ているのか、となってしまう。
これら判断は人の記憶に頼ることになるので、聞いたことのない種類のものまねはそもそも判定できない。このような一致性を探すには現代ならばまさしく AI を使うべきだろう。特にヨーロッパならば山のような録音があるので、それらを短いセグメントとして切り出し、AI で類似のものを探させればよい。
速度や周波数の違いをどこまで許容するかも AI にアルゴリズムを与えればおそらく簡単にできてしまう。
音楽業界では盗作チェックにすでに使われているのでは?
ソノグラムを切り出して画像の類似性をほとんどブラックボックスのように判定することは AI 素人にも思いつくが、記録されている音声が多量にあるので演算時間が制約になるかも知れない。遺伝情報の類似塩基配列探索に用いられる BLAST のような高速な比較アルゴリズムがおそらくあった方がよい。
このような方法でこれまで記録された音声の類似性を調べればまったく違う地域で偶然の一致がかなり見つかるのではないだろうか。これまで越冬地で歌を覚えてくるなど定説となっている種類もあるが、AI を用いて再吟味してみると常識と異なる結果が得られるかも知れない。系統や渡り経路も加味した解析もおそらく面白い。ニシオジロビタキがものまねをするならばオジロビタキも行うことは大いに期待されるが、ロシアの鳥の音声データは少なく比較は難しいかも知れない。
いずれもどなたか挑戦してみられないだろうか。
xeno-canto の Latest News 2025.6.18 によればヤブヨシキリ Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed-Warbler の録音を用いて AvesEcho AI をヨーロッパの種類に対して試してみると多くの音声が同定され、模倣と考えられるものが多数あるとのこと。AI の判定精度はなかなかよいとのこと。
Specific invidual Blyth's Reed Warblers can be identified by their singing pattern! (+ Sample database) (FlackoWeasel 2025.4.13) の記事も参照。個体識別も可能。
Marsh warbler mimicking identified African and European bird sounds in recording (Ulf Elman 2014) が人力でヌマヨシキリ Acrocephalus palustris Marsh Warbler の越冬地模倣種の同定を人力で試みていた。
ヨーロッパとは事情が異なると思われるが、数時間の連続録音を自動解析できる時代も近づいているらしいので安心して長時間録音を。
AvesEcho は EU が資金提供して Naturalis Biodiversity Center (xeno-canto をサポートしている) の組織である GUARDEN が開発。ただしヨーロッパの鳥限定。データの揃っているところで行うのがやはりよく、北米は Cornell が行っているのでヨーロッパのプロジェクトとなっているのだろう。
ニシオジロビタキの地鳴きで紛らわしい種類は前述の Muscicapa 属の他、ミソサザイの警戒音も挙げられるであろう。
オジロビタキ、ニシオジロビタキの分離以前にも多数の「オジロビタキ」の記録があるが、近年の記録を見る限りではニシオジロビタキの比率の方が高そうに思える。過去記録を集約されている組織もたくさんあるだろうが、大西 (2011) にもあるとように識別可能な写真があれば過去に振り返って種識別を再検討、あるいは記録の見直しをすべきと考える。
フィリピンのチェックリスト (2023) にはニシオジロビタキは含まれておらず、オジロビタキがまれな迷鳥となっている。台湾では両種とも記録されるがニシオジロビタキの方が少なくまれな迷鳥。
大陸との位置関係を考えるとニシオジロビタキが日本同様に越冬してもよさそうに思えるがそうなっていないのは何か理由があるのだろう。
カワビタキ
- 学名:Phoenicurus fuliginosus (ポエニクールス フーリーギノースス) すす色のジョウビタキ
- 属名:phoenicurus (合) ジョウビタキ (床屋の看板の赤色から赤いの意、phoinikiko koureas フェニキアの床屋 -ouros 尾の Gk)
- 種小名:fuliginosus すす色の、すすに覆われた (fuligo, fuliginis すす)
- 英名:IOC: Plumbeous Water Redstart
- 備考:
phoenicurus は#ジョウビタキ参照。
fuliginosus は3つ長母音があり、アクセントも "フーリーギノースス" となる。fuligo (フーリーゴ) すす + -osus。
-osus は冒頭が長母音でアクセントがある。odor (におい) に関係があり、〜を匂わせる、あるいは〜の感じがある の意味の形容詞を作る。fuligo は単数・主格ではこの形だが属格になると fuliginis となって n の文字が現れる。
かつて使われた属名 Rhyacornis rhuax, rhuakos 急流 ornis 鳥 (Gk) で、Blanford (1872) がカワビタキのみを指して設けた属 (The Key to Scientific Names)。
ルソンカワビタキ 現在の学名で Phoenicurus bicolor Luzon Water Redstart をタイプ種として Kawabitakia Hachisuka, 1934 が提唱されたことがあった。同様の例ではオニコノハズクを指した Mimizuku Hachisuka, 1934 の属名がある。
この当時のルソンカワビタキの学名は Chimarrhornis bicolor と現在とは別属になっていた。Chimarrhornis 属 kheimarrhos 急流 ornis 鳥 (Gk) は Beavan (1867) が設けたもの。シロボウシカワビタキ 現在の学名で Phoenicurus leucocephalus White-capped (Water-)Redstart がタイプ種。
Chaimarrornis Hodgson, 1844 による用例があるとのこと。同じタイプ種が採用されているが、Beavan (1867) のものは Hodgson (1844) のものに綴り訂正か新名を与えたものかどうか明瞭でないとのこと (The Key to Scientific Names)。
カワビタキも Chimarrhornis fuliginosus の学名だったことがある。
なぜこれほど色が違うのにジョウビタキと同属? と思えるが、Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考) の分子系統樹を参照。 ルリビタイジョウビタキとジョウビタキ (あるいはシロビタイジョウビタキ) を同属とみなすのは自然と思われるが、その場合はカワビタキはこれらグループに内包されてしまうため。
Phoenicurus 属を3系統に分割することは原理的には可能であるが、分割が細かすぎて Redstart と名の付く種類を複数のグループに分けることは避けたのだろう。分岐年代的にはぎりぎり分けても構わない程度。
この程度で分割すれば Ficedula 属はもう少し分けるべき、Luscinia 属の4種を3属に分割すべき (#オガワコマドリの備考参照) などの議論も生じるのでこの程度が妥当となったものだろう。
もし Phoenicurus 属を3系統に分割するならば現代の分子系統樹によればシロボウシカワビタキと同じグループに入るため、Rhyacornis より Chimarrhornis の方が優先されることになる。たとえ分割しても Rhyacornis の属名は現れそうにない。
分子系統樹をじっくり見ながら考えていただくと面白いグループである。ルリビタキが Tarsiger 属に決定されたほど明瞭ではない。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは亜種不明とされる。主に中国からネパールにかけて分布する基亜種と台湾に生息する亜種がある。
記録論文は渡辺 (2012) 広島県庄原市におけるカワビタキ Rhyacornis fuliginosus の観察記録 Strix 28, 99-103。
海外の名称でカワビタキに近い意味を持つのは英名の別名 Water Redstart、
中国語 溪紅尾、紅尾水鶇、鉛色水鶇、ドイツ語 Wasserrotschwanz など。言語により色彩によった名称もある。
コシジロイソヒヨドリ
- 学名:Monticola saxatilis (モンティーコラ サクサーティリス) よく岩にいる山地の住人
- 属名:monticola (m) 山地の住人 (mons montis (m) 山 colo (tr) 住む)
- 種小名:saxatilis よく岩にいる (saxum, saxi 石、岩 -atilis に属する、住む)
- 英名:IOC: Common Rock Thrush
- 備考:
monticola は#イソヒヨドリ参照。
saxatilis は2つめの a が長母音でアクセントもここにある (サクサーティリス)。-atilis の接尾辞は冒頭が長母音でアクセントがある。-atus (似た) + -ilis の合成。
単形種。
記録論文は日高他 (2017) 長崎県対馬におけるコシジロイソヒヨドリ Monticola saxatilis の観察記録
などがある。コシジロイソヒヨの名称も使われたことがある。川路他日本産鳥類記録委員会 (2002) 日本産鳥類記録リスト (1) 参照。
スズメ目 PASSERIFORMES セキレイ科 MOTACILLIDAE
ニシツメナガセキレイ
- 第8版学名:Motacilla flava (モタキルラ フラウァ) 黄色の尾を動かす鳥 (IOC も同じ)
- 第7版種学名:第8版と同じ
- 第7版亜種学名:Motacilla flava beema (モタキルラ フラウァ ベーマ) 黄色の尾を動かす鳥 (記録のある亜種)
- 属名:motacilla (合) 尾を動かす鳥 (moto (tr) 動かす cillo (tr) 動かす -illa (指小辞) 小さい) 本来は尾の意味はなかったが、誤解により -cilla は尾の意味で使われるようになった
- 第8版種小名:flava (adj) 黄色の (flavus)
- 第7版種小名:第8版と同じ
- 第7版亜種小名:beema インドの Beema/Bhima 川
- 英名:IOC: Western Yellow Wagtail
- 備考:
motacilla, flava は#ツメナガセキレイ参照。
beema は外来語で発音はわからないが、おそらく "ベーマ" でよいと思われる。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。第7版時代同種であったツメナガセキレイのうち、基亜種がこちらに含まれるため種学名はこちらが変化せず、ツメナガセキレイの方が変わる。
10 亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは beema (インドの Beema/Bhima 川) とされる。
#ツメナガセキレイより分離。同備考参照。
記録論文は池長・柳澤 (2015) 長崎市におけるツメナガセキレイの一亜種 Motacilla flava beema の日本初記録。この論文では 山階鳥類研究所(1976)に従い、ロシアツメナガセキレイの名称を提案している。
所崎 (2011) Birder 26(9): 48-51 に亜種 leucocephala (当時はツメナガセキレイの亜種) の 2011.5.3 鹿児島県平島での記録と亜種の考察などがある。この亜種 (現行の名称でカオジロニシツメナガセキレイ) は検討亜種へ移動となった (#ツメナガセキレイと重複記述)。
スズメ目 PASSERIFORMES アトリ科 FRINGILLIDAE
オガサワラカワラヒワ
- 第8版学名:Chloris kittlitzi (クローリス キットリツィ) キットリツの緑色の鳥 (IOC も同じ)
- 第7版種学名:Chloris sinica (クローリス シニカ) 中国のの緑色の鳥
- 第7版亜種学名:Chloris sinica kittlitzi (クローリス シニカ キットリツィ) キットリツの中国の緑色の鳥
- 属名:chloris (合) 緑色の (chloros 緑色の Gk)
- 第8版種小名:kittlitzi (プロイセンの軍人、探検家で鳥類学者の Friedrich Heinrich Freiherr von Kittlitz und Ottendorf に由来)
- 第7版種小名:sinica (adj) 中国の (-icus (接尾辞) 〜に属する)
- 第7版亜種小名:kittlitzi (プロイセンの軍人、探検家で鳥類学者の Friedrich Heinrich Freiherr von Kittlitz und Ottendorf に由来)
- 英名:IOC: Bonin Greenfinch
- 備考:
chloris, sinica は#カワラヒワ参照。
kittlitzi はすべて短母音とすればラテン語式では "キットリトズィ" でよいと思われる。アクセントが冒頭の原語読みにも近い。ドイツ風の読みで "キットリツィ" でも構わないと思われる。原音に近いため後者を採用した。
単形種。
#カワラヒワより分離。
日本鳥類目録改訂第7版で亜種 kittlitzi [プロイセンの軍人、探検家で鳥類学者の Friedrich Heinrich Freiherr von Kittlitz und Ottendorf に由来。
Minor on Chloris kittlitzi (Seebohm, 1890) and others に人名と表記に関連する参考情報あり "von" は姓の一部か?]
となっていたオガサワラカワラヒワ (亜種時代の名称) は日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版で独立種 Chloris kittlitzi と分離 (和名はオガサワラヒワを提唱)。日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)ではオガサワラカワラヒワに戻された。
IOC でも 11.1 以降独立種 (単形種) 英名 Bonin Greenfinch となっているが、Working Group Avian Checklists では version 0.02 で Chloris kittlitzi としたが、version 0.03, 0.04 では Chloris chloris kittlitzi とカワラヒワの亜種としている。世界のリスト統一途上の一時的問題なのだろうか。
オガサワラカワラヒワの概要 (環境省)、山階鳥類研究所のページ (推定個体数は、200 羽を下回るとされており、現在、最も絶滅が心配される日本産固有鳥類種であると言われているとのこと)、オガサワラカワラヒワ - 絶滅阻止限界点への挑戦 などの日本語情報がある。
論文は Saitoh et al. (2020)
Cryptic Speciation of the Oriental Greenfinch Chloris sinica on Oceanic Islands で、ここでは英名を Ogasawara greenfinch としている。この論文でこれまで提唱された亜種の分布図とどの著者がどの亜種を認めているかを見ることができる。
分子系統的にはオガサワラカワラヒワは大きく離れて計測値なども用いて独立種と判定された。他の亜種ではロシア沿海地方のものと韓国の鬱陵島のものが日本のものやロシア他地域のものとそれぞれある程度の違いが認められた (#カワラヒワの亜種の方にまとめた。Kittlitz と Seebohm の記載もこちらを参照)。
オガサワラカワラヒワは絶滅危惧 IA 類 (CR)。
スズメ目 PASSERIFORMES ホオジロ科 EMBERIZIDAE
シベリアアオジ
- 第8版学名:Emberiza spodocephala (エムベーリザ スポドケパラ) 灰色頭のホオジロ (IOC も同じ)
- 第7版種学名:第8版と同じ
- 第7版亜種学名:Emberiza spodocephala spodocephala (エムベーリザ スポドケパラ スポドケパラ) 灰色頭のホオジロ
- 属名:emberiza (合) ホオジロ (embriz ホオジロ 古代独)
- 第8版種小名:spodocephala (合) 灰色の頭の (spodiacus (adj) 灰色の、kephali 頭 Gk)
- 第7版種小名:第8版と同じ
- 第7版亜種小名:spodocephala (合) 灰色の頭の (spodiacus (adj) 灰色の、kephali 頭 Gk)
- 英名:IOC: Black-faced Bunting
- 備考:
emberiza は#ホオジロ参照。
spodocephala は#アオジ参照。
分割のため第7版学名は亜種まで記した。アオジと同種時代はシベリアアオジが基亜種のためシベリアアオジが種学名を引き継ぎ、アオジの種学名が変わる。
2亜種あり (IOC)。日本で記録されるものは亜種不明とされる。
#アオジより分離。同備考参照。旧アオジ時代はシベリアアオジが基亜種だったためアオジの学名、英名が変わる。
2024 年秋、シベリアアオジがヨーロッパに多数迷行: Bountiful autumn for Black-faced Bunting (BirdGuides 2024.10.31)。
スズメ目 PASSERIFORMES アメリカムシクイ科 PARULIDAE
カオグロアメリカムシクイ
- 学名:Geothlypis trichas (ゲオートゥルィピス トゥリカス) ウタツグミのような地上のカラに似たムシクイ
- 属名:geothlypis 地上のカラに似たムシクイ [geo- 地上の (Gk) thlupis (Gk) 不明の小鳥でフィンチかムシクイの一種か。ここではカラ類に似たムシクイの意味で使われる。The Key to Scientific Names]
- 種小名:trichas ウタツグミ (trikhas 髪, trikhas ウタツグミ Gk)
- 英名:IOC: Common Yellowthroat
- 備考:
geothlypis は外来語由来の合成語で発音はわからないが、ギリシャ語 geo- は o が長母音 (ge ゲー が大地。e は長母音だが接頭語化される際に短母音に)。例えば "地理" の意味のラテン語 geographia は o が長母音。
thlupis は短母音のみ。規則からは "ゲオートゥルィピス" のアクセント位置が考えられる。
北米で普通種に付けられている属名 (thlypis から派生する属名も多い) なので学名の意味がわからないとアメリカのバーダーの間でもしばしば質問が出されているが、鳥類学以外の用例はほとんどないようで調べても見つけられないと話題になっている。わかる範囲では The Key to Scientific Names の解説が唯一の出典で thlupis のギリシャ語のどこにアクセントがあるかすら不明。
日本の学名読解以上に困難な学名のよう。
trichas は由来となるギリシャ語の thrix は短母音。-as を接尾辞に付けた trichas の単語があり、ギリシャ語では末尾にアクセントがあるが短母音のみ。wiktionary によればウタツグミのこと。ラテン語読みでは冒頭にアクセント (トゥリカス)。
13 亜種あり (IOC)。日本で記録されたものは campicola とされる。北米で普通種。
Geothlypis 属はカオグロアメリカムシクイ属。
記録論文は福田・小田谷 (2018) 茨城県東茨城郡茨城町におけるカオグロアメリカムシクイ Geothlypis trichas の日本初記録。
◆「日本鳥類目録 改訂第8版」検討種見込みの鳥
種類は「日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開」 (2023年9月) の検討種リストによる。
同リストでは第7版掲載種以外の和名は暫定的、第7版掲載種以外の学名は Howard and Moore 4th ed 準拠と記載されているが、Howard and Moore 4th ed も今となってはだいぶ古くなっているので
IOC 14.1 の学名 (英名も) を採用し、掲載順もそれに準拠した。
第7版検討種としてリストされていた段階で分類がどこまで検討されていたかは知らないが、記録が報告された時点以降に種の分割なども起きて、報告時に亜種まで記載のないものは実は別種になっているかもしれない。
ここでは検討は行わず、「日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開」に記載の学名に基づき現代の分類に合わせたものになっている。
検討種は古くから残っているものも多く、新しい資料がなくそのまま保持されているものが多いのでここでは簡単な一覧にとどめた。
(継続) が第7版時代も検討種、(新規) が新規掲載見込み、(移行) が第7版掲載種であったが第8版で検討種に移行見込みのもの。
第7版+α準拠解説本文にすでに触れられているので、(移行) カテゴリーの種についてはこちらでは名前だけ紹介とする。迷鳥はともかく、繁殖種でありながら検討種 (カタグロトビ) は奇妙な気もするが。
この「日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開」の検討種リストもその時点の暫定的なものと思われ、実際の発行時点では変わっているかも知れない。
アメリカガモ (新規)
ホンケワタガモ (継続)
- 学名:Somateria mollissima (ソーマテリア モルリッシマ) 最も柔らかい羊毛の体
- 属名:somateria (合) 羊毛の体 (somatos 体 erion 羊毛 Gk)
- 種小名:mollissima (mollis 柔らかい の最上級)
- 英名:IOC: Common Eider
- 備考:
somateria は#ケワタガモ参照)。
mollissima は短母音のみで mol-lis-si-mus と分解されると考えられる。-lis- にアクセントがあると思われる (モルリッシマ)。
最上級については音楽用語の pp (ピアニシモ pianissimo) などを連想するとわかりやすいだろう。こちらはイタリア語だが変化には共通点もある。
ちなみに日常のイタリア語では piano はもっぱら「平らな」の意味で使われる。日常使われるピアノ (英語でも piano) は本来は fortepiano または pianoforte (大きい音も小さい音も出せる楽器) を省略したもの。
mollis に由来する用語では mollusk (軟体動物) などがある。音楽で短調を表す Moll (主にドイツ語だが英語でも使われる) も同系。
ラテン語の proximus も prope (近い) の最上級。こちらは英語でも proxy、approximate と同系なのでわかりやすいだろう。
宇宙に多少でも関心のある人なら Proxima Centauri (プロキシマ・ケンタウリ) は間違いなくご存知だろう。太陽系に最も近い (4.2465 光年) 恒星で 1915 年に発見された。現在もこの記録は破られていない。
ホンケワタガモの亜種にハイフンを含む珍しい綴りの学名がある。v-nigrum。分布は日本に最も近いアジア北東部からアラスカの亜種。
学名由来はのどに逆 V 字型の黒い模様が出るためとのこと。鳥類学の現行の学名ではハイフンを含む唯一の例とのこと (The Key to Scientific Names)。
古く使われていた学名では他にもたくさん例があり、分類見直しなどで再登場する可能性も否定できないかも。学名はアルファベットのみと考えて処理システムを作ると思わぬところでエラーの原因になり得る。
ヨーロッパビロードキンクロ (新規)
- 学名:Melanitta fusca (メラニッタ フスカ) 黒ずんだカモ
- 属名:melanitta (合) 黒いカモ (melan- (接頭辞) 黒い netta カモ Gk)
- 種小名:fusca (adj) 黒ずんだ (fuscus)
- 英名:IOC: Velvet Scoter
- 備考:
melanitta は#ビロードキンクロ参照。
fusca は短母音のみ (フスカ)。
分割前のビロードキンクロの旧学名と同じ。
キタホオジロガモ (継続)
- 学名:Bucephala islandica (ブーケパラ イースランディカ) アイスランドの大きな頭の鳥
- 属名:bucephala (合) 牛の頭 (bous 牡牛 kephali 頭 Gk)
- 種小名:islandica アイスランドの
- 英名:IOC: Barrow's Goldeneye
- 備考:
bucephala は#ホオジロガモ参照。
islandica は冒頭の i が長母音。-lan- がアクセント音節 (イースランディカ)。Islandia も冒頭が長母音。
ヒマラヤアナツバメ (移行)
ムジアナツバメ (継続)
- 学名:Aerodramus vanikorensis (アーエロドゥラムス ウァニコレーンシス) ヴァニコロ島の空を走る鳥
- 属名:aerodramus (合) 大空を走るもの (aer (m) 大空、dromeas 走るもの Gk)
- 種小名:vanikorensis Vanikoro 島の (ソロモン諸島のサンタクルーズ諸島ヴァニコロ島)
- 英名:IOC: Uniform Swiftlet
- 備考:
aerodramus は#ヒマラヤアナツバメ参照。
vanikorensis は場所を示す -ensis の冒頭が長母音でアクセント (ウァニコレーンシス)。Vanikoro の発音を聞いてみるとアクセントは冒頭でいずれも短母音で読まれているのでこの読みでよいと思われる。
ジャワアナツバメ (継続。独立種となり学名変更)
- 学名:Aerodramus germani (アーエロドゥラムス ゲルマーニ) ゼルマンの空を走る鳥
- 属名:aerodramus (合) 大空を走るもの (aer (m) 大空、dromeas 走るもの Gk)
- 種小名:germani (フランスの軍医で採集家の Louis Rodolphe Germain に由来)
- 英名:IOC: German's Swiftlet
- 備考:
aerodramus は#ヒマラヤアナツバメ参照。
germani は人名由来とは異なるが、ラテン語に germani (兄弟のなど)、Germani (ゲルマンの) の頻用される単語が存在するため同様に読まれると考えられる。いずれも a が長母音でアクセントがある (ゲルマーニ)。ラテン語式発音と考えて原語の読みは考えなくてよいだろう (人名もおそらく語源は同じ)。
fuciphagus は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる (フキパグス)。
検討種リストには Aerodramus fuciphagus germani とあるが独立種とされるためそのように扱った。Aerodramus fuciphagus の IOC 英名は Edible-nest Swiftlet。
ヨーロッパアマツバメ (継続)
- 学名:Apus apus (アプース アプース) 足のない鳥
- 属名:Apus (合) 足無し (a 無い pous 足 Gk)
- 種小名:apus (トートニム)
- 英名:IOC: Common Swift
- 備考:
apus は#アマツバメ参照。
pekinensis はおそらく "ペキネーンシス"。
亜種 pekinensis。
クロシロカンムリカッコウ (継続)
- 学名:Clamator jacobinus (クラーマートル ヤーコービーヌス) 黒と白の大声で叫ぶ鳥
- 属名:clamator (m) 大声で叫ぶ人 (clamo (tr) 叫ぶ -tor (接尾辞) 行為者を表す)
- 種小名:jacobinus [黒と白からなる鳥 (=英 pied) を指す種小名]
- 英名:IOC: Jacobin Cuckoo
- 備考:
clamator は#カンムリカッコウ参照。
jacobinus はラテン語の通常の綴りで Iacobus (a と o が長母音) 由来。形容詞化の -inus の語尾も冒頭が長母音でアクセントがある。"ヤーコービーヌス" (または イアーコービーヌス) となると考えられる。
英名別名 Pied Cuckoo。
ドミニコ会 (Ordo fratrum Praedicatorum, Dominican Order) の羽織る黒と白の外套にちなんで名付けられた。フランスでは Dominican を Jacobin と呼んでいた (wikipedia 英語/日本語)。
Jacobin, Dominican いずれも同じ意味で鳥の名前に使われる (The Key to Scientific Names)。
17 世紀にキプロスで作られたとされる飼いバトの品種に Jacobin pigeon があるが、これは上記色彩ではなく、フランス革命時にジャコバン党員 (jacobins) が好んで着た襟の大きな服に似ているためとのこと (コンサイス鳥名事典)。ジャコバン党の名称もジャコバン修道院が起源のため関係がないわけではないが、鳥の色彩を表す Jacobin ではない。
飼いバトではマグパイ品種 (Magpie pigeon) が色彩面で上記色彩概念に対応する。ちなみにフランス語では同品種を pie (カササギと同じ。英語と同様) イギリスのマグパイ品種は pie anglais などと呼ぶそうである (wikipedia フランス語版)。Jacobin はフランス由来の名前のはずだが現在ハトの品種名としては残っていない模様。
目立つ鳥なのか、タカにしばしば狙われるとのこと。Battle of the Birds: Hawk Tries to Kill Cuckoo (Jhaneel Lockhart, Roaring Earth)。托卵においてこの模様はどのように役に立っているのだろうか。
近縁のマダラカンムリカッコウ Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo では宿主のカササギに似るとのことだが、クロシロカンムリカッコウの宿主はチメドリ類が多くてあまり恩恵がなさそうに見える。
コウライバト (新規)
- 学名:Columba rupestris (コルムバ ルーペストリス) 崖に住むハト
- 属名:Columba (f) ハト
- 種小名:rupestris 崖に住む (rupes 崖 -estris に住む)
- 英名:IOC: Hill Pigeon
- 備考:
columba は#ヒメモリバト参照。
rupestris は冒頭が長母音。-pes- がアクセント音節 (ルーペストリス)。名詞の rupes (崖) は e が2つとも長母音。-estris の語尾と結合の際に2つ目が短音化したものと考えられる。"地上性の" を意味する terrestris (対応する英語 terrestrial) と同様の造語。
カノコバト (継続。属名変更)
- 学名:Spilopelia chinensis (スピロペリア キネンシス) 中国の首飾りのあるハト
- 属名:spilopelia (合) 斑点のあるハト (spilos 斑点 peleia ハト Gk)
- 種小名:chinensis (adj) 中国の (-ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:IOC: Spotted Dove
- 備考:
spilopelia は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。e にアクセントがあると考えられる (スピロペリア)。
chinensis は#コウライウグイス参照。
亜種 chinensis。旧属名 Streptopelia。
オナガバト (継続)
- 学名:Macropygia tenuirostris (マクロピュギア テヌイローストリス) 細い嘴の厚い羽毛の腰の鳥
- 属名:macropygia 厚い腰の (makros 深い -pugios 腰の Gk) 腰の厚い羽毛を指す (The Key to Scientific Names)
- 種小名:tenuirostris 細い嘴の (tenuis, tenue 細い -rostris 嘴の)
- 英名:IOC: Philippine Cuckoo-Dove
- 備考:
macropygia は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。y にアクセントがあると考えられる (マクロピュギア)。
tenuirostris は rostrum の o が長母音でアクセントもここにある (テヌイローストゥリス)。
コモンクイナ (移行)
セイケイ (種分割のため和名・学名不詳) (継続)
- 学名:Porphyrio porphyrio (ポルピューリオー ポルピューリオー)
- 属名:porphyrio セイケイ (porphurios, porphura 紫色 Gk に由来)
- 種小名:porphyrio (トートニム)
- 英名:IOC: Western Swamphen
- 備考:
porphyrio は起源となるギリシャ語 porphurion の末尾が長母音。この音を保持し、y にアクセントがあるので "ポルピュリオー" と考えられる。ラテン語の対応する単語は purpura で短母音のみだが形がかなり変わってしまっているので参考にならない。
参考までにドイツ語に Porphyr (岩石の一種) の単語があり、これは "ポルフュール" と読む。ドイツ語にとっても外来語で変則的な綴りや読みになっている。あるいは関連して "ポルピューリオー" とアクセント音節を伸ばすかも知れない。
こちらの方が読みやすそうなので採用した。
英名別名 Purple Swamphen。山崎・亀谷 (2022) アフリカクイナ科・クイナ科の新しい種和名ではこの学名に相当する和名はヨーロッパセイケイとなるが、種分割される前のものか。
分割後の種セイケイに対応するならば Porphyrio poliocephalus。
オオフラミンゴ (新規)
- 学名:Phoenicopterus roseus (ポエニコプテルス ロセウス) 紅色の羽の鳥
- 属名:phoenicopterus phoinikopteros (Gk) 赤い羽の (phoinix, phoinikos 紅色の -pteros 翼の)
- 種小名:roseus (adj) バラ色の
- 英名:IOC: Greater Flamingo
- 備考:
phoenicopterus 外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-co- がアクセント音節と考えられる (ポエニコプテルス)。
roseus は短母音のみで冒頭にアクセント (ロセウス)。
別名 (旧名) ヨーロッパフラミンゴ。
[フラミンゴの色彩と高度好塩菌]
フラミンゴの羽毛の色彩は主に食物のカロテノイド由来で、カロテノイド不足の餌を与えられ続けると脱色することが知られている。
飼育下フラミンゴの羽毛に高度好塩菌 (古細菌。細菌とはドメインが異なる Archaea) である haloarchaea (Halococcus 属や Halogeometricum) が検出されている。
Yim et al. (2015) Occurrence of viable, red-pigmented haloarchaea in the plumage of captive flamingoes によればこれらの極端条件に住む古細菌のカロテノイド前駆体の bacterioruberin がフラミンゴの羽毛色素と同一であることが示された。羽毛では初の発見とのこと。
haloarchaea の分離されている地域とフラミンゴ類の生息域は一致するものもしないものもあり、中国などでは haloarchaea がかなり分布するらしい。オオフラミンゴの生息地が東アジアにも拡大しているが大陸で繁殖している範囲ではこの古細菌による色は抜けないかも (?)。大陸を離れて繁殖するようになればもしかすると色が変わるかも。
[フラミンゴ類の採食と嘴の形・動かし方]
Ortega-Jimenez et al. (2025) Flamingos use their L-shaped beak and morphing feet to induce vortical traps for prey capture (一般向け解説)。論文に参考ビデオも多数あり。
L 型の嘴を使うことで水中に渦を形成してエビ類を浮かび上がらせるとのこと。動作は chattering や foot stomping と表現されている。嘴にアクチュエータを取り付けて実験を行い、この chattering 行動 (毎秒 12 回程度嘴を震わせる) が非常に重要であることがわかったとのこと。
この行動によって 7 cm/s の一定方向への流れが生じるとのこと。
ヘラサギ類でも同じではないだろうかと考えるとすでに研究があり、Weihs and Katzir (1994) Bill sweeping in the spoonbill, Platalea leucordia: evidence for a hydrodynamic function が流体力学的効果を提唱していたとのこと。
ヒレアシシギ類では Obst et al. (1996) Kinematics of phalarope spinning で指摘されていたとのこと。ハシビロガモにも言及があり、水中の獲物を採食する種類では広く存在している印象を受ける。ハシビロガモの嘴は他のカモ類よりなぜ大きいのかと聞かれたら、集団採食の行動とともにこのようなメカニズムを答えるとよいのだろう。流体力学的効果...の用語で即座に敬遠しない方がよい。
チョウセンミフウズラ (新規)
- 学名:Turnix tanki (トゥルニクス タンキ) ヒメミフウズラ/インドのタンキ族のミフウズラ
- 属名:turnix (合) 後趾を欠く小さなウズラ [Coturnix 属 (ウズラ属) を短縮して作られた属名。「小さい」の意味と後趾を欠く特徴が込められている] (The Key to Scientific Names)
- 種小名:tanki ヒンディー語の dabki (ヒメミフウズラ Turnix sylvaticus dussumier がなまったものか。インドの部族名 thank, tanki 由来との考えもある (The Key to Scientific Names)
- 英名:IOC: Yellow-legged Buttonquail
- 備考:
turnix は#ミフウズラ参照。
tanki の発音はよくわからないが短母音とすれば "タンキ"。
アメリカムナグロ (移行)
ヒレアシトウネン (継続)
- 学名:Calidris pusilla (カリドゥリス プスィルラ) ごく小さいシギ
- 属名:calidris kalidris/skalidris アリストテレスの記述した斑点のある灰色の水辺の鳥。具体的には同定されていない (kilida 斑点 Gk)、後にシギまたはセキレイと考えられた (The Key to Scientific Names)
- 種小名:pusilla (adj) ごく小さい (pusillus)
- 英名:IOC: Semipalmated Sandpiper
- 備考:
calidris は#コオバシギ参照。
pusilla は短母音のみで -sil- がアクセント音節 (プスィルラ)。
オビハシカモメ (継続)
- 学名:Larus delawarensis (ラルス デラウァレーンシス) デラウエア川のカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:delawarensis デラウエア川 (アメリカ Delaware River) の
- 英名:IOC: Ring-billed Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
delawarensis はラテン式で前半に長母音を入れず、場所の -ensis の冒頭を長母音でアクセントがあるとすれば "デラウァレーンシス"。
別名クロワカモメ。
"オビハシカモメ" の和名に相当する別学名があった。Larus zonorhynchus Swainson & Richardson, 1821 (カルガモの種小名の男性形)。オビハシカモメはこの学名から、クロワカモメは Ring-billed Gull の英名が参考にされたものと想像できる。
調べた範囲では Larus zonorhynchus が訳されて Ring-billed Gull の英名になったように見受けられる。
当時の別名 Common American Gull。この学名は古くから使われていたようで Larus delawarensis Ord, 1815 に用例の方が早いとわかった模様 (原記載)。
水鳥で唯一、餌につながった紐を水平に引いて食物を得る実験に成功しているとのこと。#ハチクマの備考 [嗅覚 (タカ・ハヤブサ類)・視覚・脳のサイズ] Lamarre and Wilson (2021) を参照。
カリフォルニアカモメ (継続)
- 学名:Larus californicus (ラルス カリフォルニクス) カリフォルニアのカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:californicus カリフォルニアの
- 英名:IOC: California Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
californicus はすべて短母音で -for- にアクセントがある (カリフォルニクス)。
アメリカセグロカモメ (移行)
- 学名:Larus smithsonianus (ラルス スミトニアーヌス) スミソニアンのカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:smithsonianus スミソニアン (James Smithson) の
- 英名:IOC: American Herring Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
smithsonianus は人名由来で判断が難しいが、-anus の形容詞語尾は a が長音でアクセントもある。これに従った (スミトニアーヌス)。ラテン式読み方では -nia- にアクセントがあるはずで長音とするかどうか程度の問題。
元セグロカモメが分割されたもの。
カスピセグロカモメ (継続)
- 学名:Larus cachinnans (ラルス カキンナーンス) 大笑いのような声のカモメ
- 属名:larus (m) カモメ (laros がつがつ食べる鳥、おそらくカモメ Gk)
- 種小名:cachinnans (分詞) 大笑い (cachinnus (m) 大笑い)
- 英名:IOC: Caspian Gull
- 備考:
larus は#カモメ参照。
cachinnans は#(旧名種キアシセグロカモメ) セグロカモメ亜種モンゴルセグロカモメ参照。
日本鳥類目録改訂第7版で同学名の種がキアシセグロカモメでリストされていたが、日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版では Larus vegae の1亜種 Larus vegae mongolicus となり削除。
第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開 (2023年10月) には含まれていない。
日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開 (2023年9月) のリストでは第7版の検討種となっているので、分類変更に伴い別和名で検討種に登場しているのか? ここではリストのみにとめた。IOC にはこの学名の種が存在する。
ヒガシシナアジサシ (新規)
- 学名:Thalasseus bernsteini (タラッセウス ベルンステイニ) バーンシュタインの漁師の鳥
- 属名:thalasseus 漁師 (Gk) < thalasses 海 (Gk)
- 種小名:bernsteini (ドイツの外科医、動物学者、採集家の Heinrich Agathon Bernstein にちなむ)
- 英名:IOC: Chinese Crested Tern
- 備考:
thalasseus は#オオアジサシ参照。
bernsteini はラテン語式読みで -ste-i- にアクセントがあると考えられる (ベルンステイニ)。
別名にササグロオオアジサシがある。Thalasseus zimmermanni (Peters' Check-list of the Birds) の学名もあったが現在はシノニムとされる。
Thalasseus bernsteini (Schlegel, 1863) は 原記載 参照。
Sterna zimmermanni Reichenow, 1903 は 原記載。
Dinets (2019) ヒガシシナアジサシ Thalasseus bernsteini の日本初記録。
オオハシウミガラス (移行)
コバシウミスズメ (継続)
- 学名:Brachyramphus brevirostris (ブラキュラムプス ブレウィローストゥリス) 短い嘴の鳥
- 属名:(合) 短い嘴の (brachy- (接頭辞) 短い ramphos 嘴 Gk)
- 種小名:brevirostris (adj) 短い嘴の (brevis (adj) 短い rostrum -i (n) 嘴 -s (語尾) の)
- 英名:IOC: Kittlitz's Murrelet
- 備考:
brachyramphus は#マダラウミスズメ参照。
brevirostris は rostrum の o が長母音でアクセントもここにある (ブレウィローストゥリス)。
IOC 順に基づき次の種と順序変更。
Ogawa (1908) "A hand-list of the birds of Japan" には Kurile Islands として載せられており、Kobasu-umisuzume の名称があるが他の例でも "コバシ" の意味で使われている。
ハジロウミバト (新規)
- 学名:Cepphus grylle (ケップス グリュルレ) ハジロウミバト
- 属名:cepphus kepphos アリストテレス他が記述した淡色の水鳥の一種で現在どの鳥かは不明
- 種小名:grylle ゴットランド (Gotland) 島でのハジロウミバトを指す方言 (The Key to Scientific Names)
- 英名:IOC: Black Guillemot
- 備考:
cepphus は#ウミバト参照。
grylle の発音はわからないが短母音とすれば "グリュルレ"。
ヒメアシナガウミツバメ (継続)
- 学名:Garrodia nereis (ガルロディア ネーレーイス) 海の妖精のウミツバメ
- 属名:garrodia (英国動物学者 Alfred Henry Garrod にちなむ)
- 種小名:nereis (海の神 Nereus の娘の海の妖精 Nereid から)
- 英名:IOC: Grey-backed Storm-Petrel
- 備考:
garrodia はラテン語読みで "ガルロディア"。
Nereis (固有名詞) は2つの e が長母音で2つめにアクセントがある (ネーレーイス)。ギリシャ語の Nereis も同様に長音。Nereus の発音は異なるが複雑なことは考えずに固有名詞の読みを採用した。
ワタリアホウドリ (継続)
- 学名:Diomedea exulans (ディオメーデア エクスラーンス) 放浪するアホウドリ
- 属名:diomedea Diomedes (Gk) ディオメーデース (ディオメデス) ギリシャ神話でギリシア戦士。死後付き添いたちが白い海鳥になったという (The Key to Scientific Names)
- 種小名:exulans 放浪する。英語同系語 exile
- 英名:IOC: Snowy Albatross
- 備考:
Diomedea はギリシャ神話由来でギリシャ語発音に従えば "ディオメーデア"。
exulans は a が長母音、アクセントは x が分割された -su- の音節にある (エクスラーンス)。
コウミツバメ (継続。属名変更)
- 学名:Hydrobates microsoma (ヒュドゥロバーテス ミクロソーマ) 小さな体の水を歩く鳥
- 属名:hydrobates (hudro- 水を bates 歩く Gk)
- 種小名:microsoma 小さな体の (mikros 小さい soma 体 Gk)
- 英名:IOC: Least Storm Petrel
- 備考:
hydrobates, oceanodroma は#オーストンウミツバメ参照。
microsoma はギリシャ語 soma の o が長母音。アクセントもここにある (ミクロソーマ)。
旧属名 Oceanodroma。Halocyptena もあり。主流 = IOC 属名 [日本鳥類目録第8版和名・学名リスト(2023)でオーストンウミツバメ属] に合わせた。
ヒメウミツバメ Hydrobates pelagicus European Storm Petrel もウミツバメ類最小種の一つ。小さ過ぎてソアリングは期待できない。加速度計を取り付けて飛翔の解析: Pascalis et al. (2025) Flight style and time-activity budgets of the smallest petrels
やはり多くが羽ばたき飛行で (78%) 短時間の滑空を混ぜるのみ。夜間と早朝の飛翔が中心で昼間は海上で休む。このような飛翔様式がエネルギー的に見合っているのか不明な点が残る。
マダラフルマカモメ (継続)
- 学名:Daption capense (ダプティオン カペーンセ) 喜望峰のまだらの鳥
- 属名:daption (neut.) ポルトガル語で白黒/まだらを意味する pintado のアナグラム (The Key to Scientific Names)
- 種小名:capense 南アフリカ喜望峰 (Cape of Good Hope) から
- 英名:IOC: Cape Petrel
- 備考:
daption はアナグラムで読み方不明。短母音として "ダプティオン" か?
ギリシャ語で -ion は中性名詞を作る語尾 (指小辞の用例が多い) なのでそれにならって中性とされていると考えられる。1種のみを含む属だが亜種小名も中性になっている。
capense は通常の学名だと capensis で場所を示す -ensis の冒頭を長音でアクセントと説明するところだが鳥では珍しい中性語尾になっている。アクセント位置は変わらず "カペーンセ"。短音で読むことの方が多いようだが長音記号が入っている。語尾の統一のためこの表記を用いておくが読み方はどちらでもよい。
亜種名に登場する australe も中性語尾になっている。
記載時学名 Procellaria capensis Linnaeus, 1758 でこの時は女性属名に対応する語尾になっている。daption を中性と積極的に認識して語尾変化が行われている。
ヘラルドシロハラミズナギドリ (継続。独立種で学名変更)
- 学名:Pterodroma heraldica (プテロドゥロマ ヘラルディカ) ヘラルドの翼で走る鳥
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:heraldica Herald の (英国軍艦で南太平洋を探検した HMS Herald にちなむ)
- 英名:IOC: Herald Petrel
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
heraldica は短母音のみであれば "ヘラルディカ"。
検討種リストには Pterodroma arminjoniana heraldica とあるが独立種とされるためそのように扱った。Aerodramus arminjoniana の IOC 英名は Trindade Petrel。
ハジロシロハラミズナギドリ (継続)
- 学名:Pterodroma cookii (プテロドゥロマ コーキイ) クックの翼で走る鳥
- 属名:pterodroma (合) 翼で走るもの (pteron 羽 翼 dromos 走るもの Gk)
- 種小名:cookii Cookの (英国探検家 Capt. James Cook にちなむ)
- 英名:IOC: Cook's Petrel
- 備考:
pterodroma は#ハジロミズナギドリ参照。
cookii は原音とはかなり異なるがラテン語式で、"コーキイ" とした。語末は ii が並ぶ。
マンクスミズナギドリ (移行)
- 学名:Puffinus puffinus (プッフィヌス プッフィヌス) ツノメドリのような鳥/ミズナギドリ
- 属名:puffinus (合) ツノメドリのような鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:puffinus (トートニム)
- 英名:IOC: Manx Shearwater
- 備考:
puffinus は#コミズナギドリ参照。
Puffinus 属のタイプ種で第8版の属名もマンクスミズナギドリ属。
マンクスコミズナギドリの別名もあった。
オオセグロミズナギドリ (新規)
- 学名:Puffinus auricularis (プッフィヌス アウリクラーリス) 小さな耳のあるツノメドリのような鳥/ミズナギドリ
- 属名:puffinus (合) ツノメドリのような鳥 (puffin ツノメドリ 英、-inus (接尾辞) 〜に属する)
- 種小名:auricularis (adj) 小さな耳のある (auricula 小さな耳 -aris 形容詞語尾)
- 英名:IOC: Townsend's Shearwater
- 備考:
puffinus は#コミズナギドリ参照。
auricularis は形容詞語尾の -aris 冒頭が長母音でアクセントもある (アウリクラーリス)。auricula は auris (耳) + -cula (指小辞) で "小さな耳" の意味になる。
シロハラグンカンドリ (継続)
- 学名:Fregata andrewsi (フレガータ アンドレウスィ) アンドリュースのグンカンドリ
- 属名:(外) fregate 敏捷で獰猛なグンカンドリ類のフランス航海者による名前 < fregate, frigate フリゲート艦 < fregata 伊 だが語源は不明
- 種小名:andrewsi Andrewsの (英国古生物学者、クリスマス島で採集を行った Charles William Andrews)
- 英名:IOC: Christmas Frigatebird
- 備考:
fregata は#オオグンカンドリ参照。
andrewsi はラテン語式として "アンドレウスィ" のアクセント位置と考えられる。
英語別名 Christmas Island Frigatebird。
ナスカカツオドリ (新規)
- 学名:Sula granti (スラ グランティ) グラントのカツオドリ
- 属名:sula (外) カツオドリ ノルウエー語
- 種小名:granti (Ogilvie-)Grantの (英国鳥類学者 William Robert Ogilvie-Grant にちなむ)
- 英名:IOC: Nazca Booby
- 備考:
sula は#アカアシカツオドリ参照。
granti はラテン語式として "グランティ"。
インドアカガシラサギ (新規)
- 学名:Ardeola grayii (アルデオラ グライィイ) グレイの小さなアオサギ
- 属名:ardeola (f) 小さなアオサギ (ardea (f) アオサギ -ola (指小辞) 小さい)
- 種小名:grayii Grayの (英国鳥類学者 John Edward Gray にちなむ)
- 英名:IOC: Indian Pond Heron
- 備考:
ardeola は#アカガシラサギ参照。
grayii は発音が難しいが "グライィイ" と推定。最初のイはヤ行のイのつもり。規則に合わせて読むのが難しいので "グライイ" でも構わない気がする。
ジャワアカガシラサギ (継続)
- 学名:Ardeola speciosa (アルデオラ スペキオーサ) 見事な小さなアオサギ
- 属名:ardeola (f) 小さなアオサギ (ardea (f) アオサギ -ola (指小辞) 小さい)
- 種小名:speciosa (adj) 見事な、美しい (species と同系)
- 英名:IOC: Javan Pond Heron
- 備考:
ardeola は#アカガシラサギ参照。
speciosa は o が長母音でアクセントもある (スペキオーサ)。
カタグロトビ (移行)
ソウゲンワシ (継続)
- 学名:Aquila nipalensis (アクゥィラ ニパレーンシス) ネパールのワシ
- 属名:aquila (f) ワシ (aquilus 暗色の 由来との解釈がある)
- 種小名:nipalensis (adj) ネパールの (nipale ネパール -ensis (接尾辞) 〜に属する)
- 英名:IOC: Steppe Eagle
- 備考:
aquila は#イヌワシ参照。
nipalensis は#クマタカ参照。
伊藤 (2001) Birder 15(5): 67 にソウゲンワシ発見記 (2000.1.22 撮影) がある。一度はカラフトワシと同定されたとのこと。
森岡 (2001) Birder 15(5): 68-69 に検討記事がある。この記事中では Aquila rapax をサメイロワシと呼んでいる。高野 (1973) のサメイロイヌワシ とも異なる名称となっていた。
1990 年代でもこれら比較的小型の (当時の) Aquila の分類概念も分類学者次第で、識別情報も限られていたことがわかる。
nipalensis はクマタカの種小名と衝突することがなかったのか気になるところだがクマタカはだいぶ違うので同属となることはなかった模様。しかしソウゲンワシの記載時学名は Circaetus nipalensis Hodgson, 1833 (Avibase による 原記載) と現代で言えばチュウヒワシ系統になっていた。
クマタカの種小名も Hodgson (1836) によるものなので当時は別属で、まさか類縁関係が近いとは想像していなかっただろう。どちらも地名を付けてしまうのはちょっと安直だったかも。しかし IOC 14.2 で検索すると Hodgson が nipalensis と付けた種は 14 もあった (現在生き残っているものだけなので実際にはもっと多かったはず)。クマタカの種小名のありがたみが薄れてしまう...。
図版では Aquila nipalensis となっているが本文は Circaetus? で、その次のページに Circaetus nipalensis とされる図版が出ている。
Aquila nipalensis の方はソウゲンワシに見えるが、Circaetus nipalensis は虹彩も黄色く違うように見える。記述から想像で描かれた絵かも知れないが...。本文記述が先に出版されたと解釈すると本文 = Circaetus が優先されるのだろう。ネパールの人たちはこの種は魚を食べていると述べていると記されている (別の大型種と混同しているかも)。
本文と図版の食い違いからソウゲンワシがどの属で記載されたか考え方が異なるようで、IOC 14.2 では Aquila nipalensis Hodgson, 1833 としている。Circaetus nipalensis が記載時学名とすれば (Hodgson, 1833) とする必要があるところで、Aquila 属で記載した (図版と本文が同時に出版されていれば図版の学名の方がおそらく有効になる) と理解されているよう。
さらにややこしいことに Aquila nipalensis Hodgson, 1844 (参考) もあって上記とは別物。Hodgson はネパール産のワシ類3種に当時の別属に従ってそれぞれ nipalensis を付けたことになる。
この種は現在ボネリークマタカ Aquila fasciata Vieillot, 1822 とされる。Vieillot の記載の方が早かったので表面上問題はなかったが、Aquila nipalensis Hodgson, 1844 の方が早ければ 1833 年の記載をどちらの属と解釈するか問題が発生したはず。1833 年も Aquila 属とする立場であればこの記載は無効になる。
ネパール産のイヌワシに nipalensis を使うことができなかったのは Aquila nipalensis Hodgson, 1844 に用いてしまっていたためのよう。Hodgson (1844) 自身もあまり自信がなく A.? Daphanea と書いているのでこちらには使いにくかったのかも知れない。
イヌワシの最大亜種の学名由来は案外由緒あるものではなく、nipalensis はすでに使ってしまったので仕方なく (?) 現地の単語を用いたと考えることもできる。そして現在では語義不明となっている。
[英名 Tawny Eagle の由来]
ソウゲンワシの英名は Tawny Eagle の方が広く用いられていたようで、Tawny Eagle, Aquilla fulvescens 図版 (1830-1834) 参考。属名の綴りを間違っているので注意。
fulvescens は Aquila fulvus (現在はイヌワシのシノニム、#イヌワシ備考参照) から派生したものと思われる。色彩を指すもので英語では yellowing, yellowish, tawny に対応 (wiktionary)。イヌワシに比べれば黄色っぽい。
おそらくこの学名由来で Tawny Eagle (和名でもサメイロイヌワシまたはサメイロワシと訳されていたものと思われる) が使われていたがアフリカソウゲンワシを分割するに当たって Tawny Eagle をアフリカソウゲンワシ [高野 (1973) ではサメイロイヌワシ] の方の名称とし、ソウゲンワシの方に Steppe Eagle が与えられたと想像できる。
記載時学名表示ではアフリカの Falco rapax Temminck, 1828 基産地 South Africa が早く、
ネパールの Circaetus nipalensis Hodgson, 1833 (こちらがソウゲンワシの原記載) の方が遅いため、同種とする場合にはソウゲンワシがアフリカソウゲンワシの亜種となる。
Dement'ev and Gladkov (1951) では同種扱い。rapax は rapio (掴む) + -ax (傾向を示す) で英語の rapacious とほぼ同じ意味。raptor と同語源。
英名はより遅く記載された学名 (これが有効だったかどうかは不明だが図版では自身の命名となっている) に合わせて付けられた Tawny Eagle にまとめられていたと考えられる。そう思ってみると(アフリカ)ソウゲンワシの他言語名称では tawny に相当する用例がほとんどなく英語特有の名称だった模様。
ヨーロッパチュウヒ (移行)
ウスハイイロチュウヒ (移行)
ヒメハイイロチュウヒ (継続)
- 学名:Circus pygargus (キルクス ピューガルグス) 腰の白いチュウヒ
- 属名:チュウヒ (circus (m) 円弧、求愛の時の旋回行動からチュウヒ)
- 種小名:pygargus 猛禽類の1種でおそらくハイイロチュウヒ類 < 腰の白い (puge 腰 argos 白 Gk)
- 英名:IOC: Montagu's Harrier
- 備考:
circus は#チュウヒ参照。
(ピュガルグス)。
Belon (1555) の pygargus のラテン語用例があり、ハイイロチュウヒまたはヒメハイイロチュウヒ (区別されていなかった) を指していたとのこと (The Key to Scientific Names)。
起源となるギリシャ語とは異なるが、ラテン語では冒頭が長母音でアクセントがあるとのこと (ピューガルグス)。腰の白いアンテロープの アダックス (addax) も指すとのこと (発音とともに wiktionary より)。
Soutullo et al. (2006) Density-dependent regulation of population size in colonial breeders: Allee and buffer effects in the migratory Montagu's harrier
によればスペインの個体数は 1981-2001 年の間に指数関数的に増えて、2001-2004 年ごろ安定したとのこと。コロニー営巣性のため、個体群サイズが大きくなると生存率を高める効果があったと考えられる。
シロガシラトビ (継続)
- 学名:Haliastur indus (ハリアストゥル インドゥス) インドの海のタカ
- 属名:haliastur [hali- 海の (Gk) astur タカ、オオタカ]
- 種小名:indus (adj) インドの
- 英名:IOC: Brahminy Kite
- 備考:
haliastur は#オジロワシと#オオタカ参照。-as がアクセント位置 (ハリアストゥル)。
indus は短母音のみ (インドゥス)。
2014年2月に石垣島で撮影されているが記述する論文がまだ出ていないので検討種扱いだろうか。
英名の Brahminy は Brahmin (Brahman, Brahma) ブラフマー インド神話、ヒンドゥー教の創造神に由来。サンスクリット語 brahmana-s (Etymology Online)。
"Brahminy" の付く鳥の名前は案外多くあって、インドではアカツクシガモを Brahminy duck と呼ぶ。
ズグロムクドリ Sturnia pagodarum Brahminy Starling もあって、Brahminy の英名は色彩 (パターン) 由来だろうか。ヘビに Brahminy Blind Snake の名称もある。
ヒガシメンフクロウ (移行)
ミヤマモリフクロウ (新規。種分割に伴い学名・和名変更)
- 学名:Strix nivicolum (ストゥリークス ニウィコルム) 雪に住むミミズクの一種
- 属名:strix (f) ミミズクの一種
- 種小名:nivicolum 雪に住む (nix, nivis 雪 -cola 住む)
- 英名:IOC: Himalayan Owl
- 備考:
strix は#フクロウ参照。短い読み方でもよい。
nivicolum は短母音のみ。-vi- がアクセント音節と考えられる (ニウィコルム)。-colum は伸ばさない。
-cola で終わるラテン語は名詞なのでその変化形とは考えられず少し不思議な形をしている。Strix は女性属名なので一見性が合わないように見える。
記載時学名 Syrnium nivicolum Blyth, 1845 で、nivicolum は名詞と判断されたため無変化で用いられたのだろう。Syrnium は現在使われていない属名だが呪いの鳥でおそらくフクロウ類を指すギリシャ語 surnion から。
タイプ種の異なる現在では複数の属となる用例があったが、それぞれのタイプ種が現在では Strix や Bubo 属に含まれ、分類の再編に伴って使う必要がなくなった模様 (用例情報などは The Key to Scientific Names より)。ミヤマモリフクロウに関しては Strix 属に含まれるのでこちらに移動となった。
ギリシャ語で -ion は中性名詞を作る語尾 (指小辞の用例が多い) で Syrnium は中性の属名であるため、nivicolum の中性的語尾が与えられたものと想像できる。Syrnium 属とされた他の種も Syrnium niveum (現在のシロフクロウのシノニムに相当) と中性形容詞語尾が与えられていた。
よく見られる -cola の -a は名詞を作る語尾で中性の変化形があるわけではなく、-colum は -cola の直接の変化形というわけではない。-um に対応する語義はないようなので -colum は中性形を意識した不規則な造語語尾ではないかと考えられる。おそらくそのため名詞扱いで Strix 属に移動しても無変化なのだろうと想像する。
フクロウ類には他に有名な中性の属 Glaucidium (例えばスズメフクロウ属) がありよく見かける学名で語尾から植物の名前かと思ってしまう。ギリシャ語でフクロウ類の1種の指小形の glaukidion 由来でこれはギリシャ語で中性名詞。
非常によく登場する種のメキシコスズメフクロウ Glaucidium gnoma の種小名の性が合わないようにも見えるが、これは記載時もこの属で種小名は Gnoma が使われていた (原記載)。意味は gnome と同じように地中の宝を守るという年老いた小人。
ラテン語では辞書では男性名詞の gnomus しか現れず、女性形風の語尾を用いた名詞を採用したものと想像できる (語義からそもそも中性形が考えにくい)。北米のバーダーはこのような身近な事例を知っているので、中性形の存在しない名詞は語尾変化させなくなったなどの事情も理解しやすいのだろう (セレベスツミ Tachyspiza nanus をなぜ女性形にしないのかの議論など)。
フクロウ類で中性の属が多いのかと見てみたが現在使われているものではそうでもなかった (#ヒガシメンフクロウの [フクロウ類の系統分類] 参照)。
日本の鳥では珍しいが中性の属は意外に多数あり、#コンヒタキの従来の学名 (Cinclidium leucurum) も中性だった。現在は属が分離されて女性学名になっているが、古い学名も 2016 年ぐらいまで使われていたので目にすることがあるかも知れない。
他にも セアカハナドリ Dicaeum cruentatum Scarlet-backed Flowerpecker の属も中性でこれはギリシャ語 dikaion に由来するとのことだが、鳥ではなく虫を指していたとの解釈もある (The Key to Scientific Names)。
ヒロハシハチクイモドキ Electron platyrhynchum Broad-billed Motmot もいかにも中性らしい属名になっているが、これは金属光沢から。ギリシャ語で合金を表すとのこと (The Key to Scientific Names)。
キンメセンニュウチメドリ Chrysomma sinense Yellow-eyed Babbler も中性。chryso- は金色だが、omma はギリシャ語で "目" (主に詩で用いられる) で中性名詞。
Latest IOC Diary Updates によれば H&M 4.1 のリストで男性、女性属名ともに 1000 以上あるが中性の属名は 59 とのことでかなり珍しい。-us/-a の語尾変化が話題になることが多いが中性の属名は少ないために中性の変化形に出会う機会がはるかに少ないため。
検討種リスト学名 Strix aluco ma (IOC: Tawny Owl)。
種が分離された後の学名・英名で示す。Strix nivicolum ma。
和名 (新称) は山崎剛史他 (2017)「フクロウ目の新しい種和名」による。分離前「日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開」の和名はモリフクロウ。
亜種 (小) 名の ma はかつて初めて見た時は何かの間違いではないかと思ったものだが正式に認められている亜種の名称で、日本語で妖精 (elf, gnome) の意味とある
(The Key to Scientific Names)。
日本人の命名ではなく、protonym は Syrnium ma Clark, 1907:
Eighteen New Species and One New Genus of Birds from Eastern Asia and Aleutian Islands 基産地 Fusan, Korea (釜山)。脚注に ma = elf, gnome (Japanese) とある。「魔」だろうか。
フクロウ類の属名などに「悪魔」などの意味がしばしば使われていた (#リュウキュウコノハズク備考参照)。伝統的なギリシャ語などを由来とする名称がありきたりになってきて (尽きてきて?) Clark にとって馴染みであった日本語から同様の意味の単語を用いたと考えると理解できそう。やはり「魔」の意味だろうと想像する。
Strix aluco モリフクロウではメラニン色素に関連する遺伝子と色彩、低温への適応の関係が調べられている: Baltazar-Soares et al. (2024) Genomic basis of melanin-associated phenotypes suggests colour-specific environmental adaptations in tawny owls。
MC1R 遺伝子のタンパク質をコードする部分そのものには morph による違いはなく、古典的にはメラニン色素に関係すると考えられていない遺伝部位に違いがあってメンデルの法則に従って遺伝するとのこと。
アオショウビン (移行)
ワキスジハヤブサ (移行)
カワリサンコウチョウ (新規。種分割されており学名・和名変更の可能性あり)
- 学名:Terpsiphone paradisi (テルプスィポネ パラディースィー) 天国の楽しむ殺し屋/天国の殺されるまで楽しんでいる鳥
- 属名:terpsiphone (合, f) 楽しむ殺し屋/殺されるまで楽しんでいる鳥 (terpo 楽しむ phonos 殺すこと。phone "声" ではない Gk) 属記載にラテン語語義が添えられておりサンコウチョウ備考参照
- 種小名:paradisi 天国の (paradisus 天国 < 古ペルシャ語 pairi-daeza 壁のある庭)
- 英名:IOC: Indian Paradise Flycatcher
- 備考:
terpsiphone は#サンコウチョウ参照。
paradisi は最後の2つの i が長母音で1つ目にアクセントがある (パラディースィー)。
もとの Terpsiphone paradisi は3種に分割され、
Terpsiphone paradisi (Indian Paradise Flycatcher)、
Terpsiphone affinis (Blyth's Paradise Flycatcher ブライスサンコウチョウ)、
Terpsiphone incei (Amur Paradise Flycatcher アムールサンコウチョウ)
となった。検討種記録に亜種の記載がないためこの3種のどれに対応するかは不明。
またカワリサンコウチョウの名称をどの種が引き継ぐかが明確でないためここではリストのままとしておく。
最も可能性が高いと想像されるアムールサンコウチョウの記載時学名は Muscipeta incei Gould, 1852 で上海が基産地 (原記載)。
この記載の比較対象に日本のサンコウチョウも登場し、当時受け入れられていた学名 M. principalis も登場する (サンコウチョウの備考参照)。
オーストラリアの軍人で探検家、採集家の Matthew Robert Ince が由来とのこと。学名の読み方は "インケイ" でよさそう。
ブライスサンコウチョウの affinis は "似ている"。記載時学名 Tch[itrea]. affinis Blyth, 1846 (原記載)。現代の意味のカワリサンコウチョウに似ている、でよいだろう。
Terpsiphone paradisi は記載時 Corvus paradisi Linnaeus, 1758 (サンコウチョウの備考参照)。
モウコアカモズ (移行)
タイワンヒバリ (継続)
- 学名:Alauda gulgula (アラウダ グルグラ) (?の) ヒバリ
- 属名:alauda (f) ヒバリ
- 種小名:gulgula 原住民による名称で歌に関連したヒバリの名前の可能性があるが、インドのマディヤ・プラデーシュ (Madhya Pradesh) では Acridotheres 属 (ムクドリ類) を gulgula と呼ぶなど確実な語源は不明 (The Key to Scientific Names)
- 英名:IOC: Oriental Skylark
- 備考:
alauda は#ヒバリ参照。
gulgula は語源不詳だが gula がラテン語の "のど" の意味であれば短母音。すべて短母音であれば "グルグラ" となるが、由来が確かでないので伸ばさない理由が特にあるわけではない。"グルグーラ" となるかも知れない。
クロヒヨドリ (継続)
- 学名:Hypsipetes leucocephalus (ヒュプシペテース レウコケパルス) 白い頭の高く飛ぶ鳥
- 属名:hypsipetes (合) 高く飛ぶ鳥 (hypsi 高さ peto 飛ぶ -tes (接尾辞) 〜するもの Gk)
- 種小名:leucocephalus (合) 白い頭の (leuko- (接頭辞) 白い kephali 頭 Gk)
- 英名:IOC: Black Bulbul
- 備考:
hypsipetes は#ヒヨドリ参照。
leucocephalus は起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる。-ce- がアクセント音節と考えられる (レウコケパルス)。
英語別名 Himalayan Black Bulbul。#ホウロクシギの備考にあるようにかつては Hypsipetes madagascariensis の亜種とされた時代があり、学名にマダガスカルが現れていた。
現代では別種扱いになっているが和名クロヒヨドリをどちらの種に与えるかは海外リストでは異なっている。
検討種から掲載種になれば Hypsipetes leucocephalus にクロヒヨドリが与えられる可能性があるが、掲載種となった場合にどのように扱われるかは鳥学会の判断次第。
英名では Black Bulbul は Hypsipetes leucocephalus を指して Hypsipetes madagascariensis には Malagasy Bulbul が与えられているので同様になるだろうか。
ウスショウドウツバメ (新規)
- 学名:Riparia diluta (リーパーリア ディールータ) 薄い色の土手に巣を作る鳥
- 属名:riparia (adj) 土手に巣を作る (riparius、ripa (f) 土手); 河岸に多い (コンサイス鳥名事典)
- 種小名:diluta (adj) 淡い、薄い
- 英名:IOC: Pale Martin
- 備考:
riparia は#ショウドウツバメ参照。
diluta は i, u が長母音で後者にアクセントがある (ディールータ)。動詞 diluo の過去分詞形の変化。この形の -utus の冒頭は長母音でアクセントがある。
ミドリツバメ (移行)
ニシイワツバメ (移行)
オオコシアカツバメ (新規)
- 学名:Cecropis striolata (ケクロピス ストゥリオラータ) 細かい縞のあるアテネの女性/コシアカツバメ
- 属名:Cecropis Kekropis アテネの女性名 (Gk)
- 種小名:striolata (adj) 細かい縞のある
- 英名:IOC: Striated Swallow
- 備考:
cecropis は#コシアカツバメ参照。
striolata は形容詞語尾の -ata 冒頭が長母音でアクセントもある (ストゥリオラータ)。
バフマユムシクイ (継続)
- 学名:Phylloscopus humei (ピュルロスコプス フメイ) ヒュームのムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:humei Humeの (英国鳥類学者でインド文官、雑誌 "Stray Feathers" を創刊した Allan Octavian Hume にちなむ)
- 英名:IOC: Hume's Leaf Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
humei はラテン語読みで "フメイ" と考えられる。
英語別名 Buff-browed Warbler。
モウコムジセッカ (継続)
- 学名:Phylloscopus armandii (ピュルロスコプス アルマンディイ) アルマンのムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:armandii Armand の (中国のフランス在外大使で鳥類学者の Abbe Jean Pierre Armand David にちなむ)
- 英名:IOC: Yellow-streaked Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
armandii はラテン語読みで "アルマンディイ" と考えられる。
キバラムシクイ (移行)
ニシヤナギムシクイ (継続)
- 学名:Phylloscopus trochiloides (ピュルロスコプス トゥロキロイーデース) キタヤナギムシクイに似たムシクイ
- 属名:phylloscopus (合) 葉の観察者 (phyllo 葉 skopos 見張り人 Gk)
- 種小名:trochiloides (キタヤナギムシクイ Phylloscopus trochilus の種小名 -oides 似た Gk)
- 英名:IOC: Greenish Warbler
- 備考:
phylloscopus は#キタヤナギムシクイ参照。
trochiloides は trochilus は短母音のみで -oides は i, e が長母音で前者にアクセントがある (トゥロキロイーデース)。
セスジコヨシキリ (移行)
イナダヨシキリ (移行)
バイカルオウギセッカ (継続)
- 学名:Locustella davidi (ロークステルラ ダウィディ) ダヴィドの小さなバッタ
- 属名:locustella (f) 小さなバッタ (locusta (f) イナゴ -ella (指小辞) 小さい) 鳴き声から
- 種小名:davidi David の (中国のフランス在外大使で鳥類学者の Abbe Jean Pierre Armand David にちなむ)
- 英名:IOC: Baikal Bush Warbler
- 備考:
locustella は#マキノセンニュウ参照。
davidi はラテン語読みでは "ダウィディ" と考えられる。
英語別名 David's Bush-Warbler。
IOC では Locustella 属が分割されたがこの種はそのまま Locustella 属に残る。
種小名の由来はモウコムジセッカと同一人物。
(アジア)マミハウチワドリ (継続)
- 学名:Prinia inornata (プリニア イノルナータ) 飾りのないウチワドリ
- 属名:prinia Prinya (フタスジハウチワドリ Prinia familiaris を指すジャワ語)
- 種小名:inornata (adj) 飾りのない
- 英名:IOC: Plain Prinia
- 備考:
prinia は外来語で発音はよくわからないが短母音ならば "プリニア"。
inornata は -ata の最初が長母音でここにアクセントがある (イノルナータ)。
Prinia subflava (Tawny-flanked Prinia マミハウチワドリ) が分割され Prinia subflava と Prinia inornata となった。
検討継続時の学名から後者と想定されるが、アジアマミハウチワドリの名称もあるため括弧付きとした。
ノドジロムシクイ (新規)
ダルマエナガ (継続。属名変更)
- 学名:Suthora webbiana (ストラ ウエッビアーナ) ウエッブのダルマエナガ
- 属名:Suthora キバネダルマエナガ Suthora nipalensis のネパール語名
- 種小名:webbiana Webb の (英国博物館に標本を届けた [J.] Webb にちなむが過去に記載された Philip Barker Webb とは無関係。The Key to Scientific Names)
- 英名:IOC: Vinous-throated Parrotbill
- 備考:
Suthora は発音不明。"ストラ", "スートラ", "ストーラ" など長音の有無で複数の可能性が考えられる。
webbiana は固有名詞より形容詞を作ることが多い語尾 -iana を用いており、最初の a が長母音でアクセントもある (ウエッビアーナ)。
亜種 fulvicauda。
検討種リストの属名は Sinosuthora だが HBW/BirdLife 2021 以降、Clements/eBird 2023、IOC 13.2 以降が Suthora を採用しているためこちらに変更した。
他の属名に Paradoxornis (#ミユビゲラ備考) も使われている。Paradoxornis が分割される前の学名と思われる。
ロシア沿海地方のダルマエナガの繁殖: Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the vinous-throated parrotbill Paradoxornis webbianus (pp. 4873-4894)。
ロシア沿海地方ではカオジロダルマエナガ Calamornis heudei Reed Parrotbill も繁殖している。
Gluschenko et al. (2024) Breeding birds of Primorsky Krai: the reed parrotbill Paradoxornis heudei (pp. 4771-4796)。
ミミジロチメドリ (継続)
- 学名:Heterophasia auricularis (ヘテロパシア アウリクラーリス) 小さな耳のある異なる見かけの鳥
- 属名:heterophasia 異なる見かけの (heteros 異なる phasis 見かけ) いくつかの属の合成のような外見から (The Key to Scientific Names)
- 種小名:auricularis (adj) 小さな耳のある (auricula 小さな耳 -aris 形容詞語尾)
- 英名:IOC: White-eared Sibia
- 備考:
は外来語由来の合成語で発音はわからないが、起源となるギリシャ語のいずれも短母音なので長母音は現れないと考えられる (ヘテロパシア)。
auricularis は#オオセグロミズナギドリ参照。
ルビーキクイタダキ (継続。属名変更)
- 学名:Corthylio calendula (コルテュリオ カレンドゥラ) 燃えるような色の?小さな鳥
- 属名:corthylio (m) korthilos (Gk) Hesychius が言及したミソサザイのような小さな鳥
- 種小名:calendula おそらく Brisson の造語で caleo (暖かい) から燃えるような頭頂の色を指したものか (The Key to Scientific Names) 他説あり
- 英名:IOC: Ruby-crowned Kinglet
- 備考:
corthylio は由来となるギリシャ語 korthilos は短母音のみで長母音は現れないと考えられる。-thy- がアクセント音節と考えられる (コルテュリオ)。
calendula は The Key to Scientific Names による語源を紹介したが複数の解釈があり、植物の Calendula officinalis (キンセンカ) にも使われている。
キンセンカの用例はほぼ毎月のように咲くことから calendae, kalendae (カレンダー) + -ula (指小辞) でこの解釈であれば -ula には長母音は現れない。
kalendae も短母音のみなので -len- をアクセント音節として "カレンドゥラ" の発音となると推定される。
属名は HBW/BirdLife 2022 以降、Clements 2021 以降、eBird 2021 以降、IOC 11.2 以降が採用 (Regulus 属より分離)。こちらを採用した。
検討種リストの属名は Regulus。
ミドリカラスモドキ (継続)
- 学名:Aplonis panayensis (アプローニース パナイエーンシス) パナイ島の単純な色の鳥
- 属名:aplonis 単純な色の鳥 (haploos 単純な ornis 鳥 Gk)
- 種小名:panayensis フィリピンのパナイ (Panay) 島の
- 英名:IOC: Asian Glossy Starling
- 備考:
aplonis は haploos の長音が残るかも知れない。ornis は i が長母音なので不規則な造語だがこれが残ると推定した。不明の点が多いが結合前のギリシャ語読みから -lo- を伸ばしてアクセントを置く方が発音しやすそうなのでこちらを採用してみた (アプローニース)。実際にはすべて短音で読むかも知れない。
panayensis は場所の -ensis の冒頭が長母音でアクセントの一般的な読み方を採用した (パナイエーンシス)。
ノドアカツグミ (分離され移行)
- 第8版学名:Turdus ruficollis (トゥルドゥス ルーフィコルリス) 赤い首のツグミ
- 第7版学名:Turdus ruficollis ruficollis (トゥルドゥス ルーフィコルリス ルーフィコルリス) 赤い首のツグミ
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 第8版種小名:ruficollis (adj) 赤い首の (rufus (adj 赤い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 第7版種小名:ruficollis (adj) 赤い首の (rufus (adj 赤い collum -i (n) 首 -s (語尾) 〜の)
- 英名:Red-throated Thrush
- 備考:
#ノドグロツグミ参照。
コマツグミ (新規)
- 学名:Turdus migratorius (トゥルドゥス ミグラトーリウス)
- 属名:turdus (m) ツグミ
- 種小名:migratorius (合) 移住する (migratorius 移住性の)
- 英名:IOC: American Robin
- 備考:
turdus は#ヤドリギツグミ参照。
migratorius は o が長母音でアクセントもある (ミグラトーリウス)。
フーキェンアオヒタキ (新規)
- 学名:Niltava davidi (ニルタウァ ダウィディ) ダヴィドのチャバラオオルリ
- 属名:niltava (合) Niltau はネパール語でコチャバラオオルリ Niltava sundara 英名: Rufous-bellied Niltava を指す
- 種小名:davidi David の (中国のフランス在外大使で鳥類学者の Abbe Jean Pierre Armand David にちなむ)
- 英名:IOC: Fujian Niltava
- 備考:
niltava は#チャバラオオルリ参照。
davidi は "ダウィディ" と考えられる。
和名別名フッケンアオヒタキ。
コチャバラオオルリ (継続)
- 学名:Niltava sundara (ニルタウァ スンダラ) 美しいチャバラオオルリ
- 属名:niltava (合) Niltau はネパール語でコチャバラオオルリ Niltava sundara 英名: Rufous-bellied Niltava を指す
- 種小名:sundara sundar (ヒンディー語で美しいの意味)
- 英名:IOC: Rufous-bellied Niltava
- 備考:
niltava は#チャバラオオルリ参照。
sundara は発音不明で短母音なら "スンダラ" だが複数の可能性がある。
チャバラオオルリ (移行)
ムナオビミツリンヒタキ (新規)
コンヒタキ (継続)
- 学名:Myiomela leucura (ミューオメラ レウクーラ) 尾の白いハエに興味を示す鳥
- 属名:myiomela ハエに興味を示す (muia, muias ハエ melo 興味を示す Gk)
- 種小名:leucura 尾の白い (leukos 白 -ouros 尾の Gk)
- 英名:IOC: White-tailed Robin
- 備考:
myiomela はギリシャ語 muia の発音は "ミューア"。melo の e は短い母音なので "ミューオメラ" の発音が自然と考えた。
leucura は短縮されてしまっているが、-ura は尾の意味で u が長母音でアクセントがあるので "レウクーラ"。
過去の学名は Cinclidium leucurum で中性だった。
cinclus (アリストテレス他の記述した尾を振る鳥の1種) の指小形が由来で、cinclus は現在はカワガラス属の学名 (Cinclus) に使われている。
Cinclidium 属は Blyth (1842) が提唱した属名で、オグロコンヒタキ Cinclidium frontale Blue-fronted Robin のみを指して与えられた属。frontale も frontalis でなく中性の種小名になっている。
確かにコンヒタキに似ているので同属とされて不自然ではなかったが、分子系統研究の結果系統がかなり異なり、コンヒタキはノゴマに近く、オグロコンヒタキは Myophonus 属に近いことがわかり、同属にまとめられなかった。その結果コンヒタキに用いられた Myiomela Gray, 1846 の属名となった [#ノゴマの備考にこの系統の一覧がある。Zhao et al. (2023) (#ヨーロッパコマドリの備考) の分子系統樹を参照]。
Myophonus 属では台湾に分布するルリチョウ Myophonus insularis Formosan Whistling Thrush が我々の地域に近い。
コンヒタキとノゴマがなぜ近いのか説明は難しいが、青い鳥は熱帯で多系統で進化し、そのうち一部が北方に進出するとともに一部は青色を失ったと解釈せざるを得ない。分子系統樹をじっくり眺めて慣れてゆくしかなさそう。Zhao et al. (2023) の系統樹で青い鳥にマークを入れると理解が深まるかも。
オジロノゴマ (新規。種に昇格で学名・和名を変更。ムナグロノゴマの名称を引き継ぐ可能性もある)
- 学名:Calliope tschebaiewi (カルリオペー チェバイエウィ) チェバエフのノゴマ
- 属名:calliope (神) 叙事詩を司る女神 (ギリシャ神話)
- 種小名:tschebaiewi Chebaefの (Przhevalsky のトランスバイカル探検に同行したコサック Panfil Chebaef にちなむ)
- 英名:IOC: Chinese Rubythroat
- 備考:
Calliope は#ノゴマ参照。
tschebaiewi はラテン語風ではなく原音を重視して k の音を入れない場合の発音。この場合でもラテン語発音規則では "チェバイエウィ" のアクセントになりそうだが、原音 (おそらくチェバイェフ) とも異なるので規則通りでなくてもよいと思われる。
検討種リストの記載は Calliope pectoralis tschebaiewi だが独立種とされるため (IOC 7.1 以降などほとんどのリストが採用) 学名を改めた。
Calliope pectoralis が通常ムナグロノゴマと呼ばれ、Calliope tschebaiewi にはオジロノゴマの名称もあるため後者を使用した。
どちらの種がムナグロノゴマの和名を引き継ぐかは不明。
キムネビタキ (継続)
- 学名:Ficedula elisae (フィーケドゥラ エリーサエ) エリーゼのイチジクをついばむ鳥
- 属名:ficedula (f) < ficus イチジク edo ついばむ
- 種小名:elisae Elise の (ドイツの博物学者 Elise Johanna Marie Weigold nee Anders が由来。中国を旅行し、妻は採集家 Hugo Weigold)
- 英名:IOC: Green-backed Flycatcher
- 備考:
ficedula は#キビタキ参照。
elisae の長母音は原音から採用。"エリーサエ" のアクセントとなる。
英語別名 Chinese Flycatcher。
ルリビタイジョウビタキ (継続)
オオノビタキ (継続)
- 学名:Saxicola insignis (サクスィコラ インシグニス) 驚くべき岩間の住人
- 属名:saxicola (合) 岩間の住人 (saxum -i (n) 石 -cola 住人 < colere 住む)
- 種小名:insignis (adj) 驚くべき、特筆に値する
- 英名:IOC: White-throated Bushchat
- 備考:
saxicola は#ノビタキ参照。
insignis は冒頭が長音記号。アクセント位置は -sig- で、"インシグニス" または "イーンシグニス"
ムジタヒバリ (継続)
- 学名:Anthus campestris (アントゥス カムペストゥリス) 野原のセキレイ
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:campestris 野原に関係した (campus, campi 野原)
- 英名:IOC: Tawny Pipit
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
campestris は短母音のみで -pes- がアクセント音節 (カムペストゥリス)。
サメイロタヒバリ (継続)
- 学名:Anthus spinoletta (アントゥス スピノレッタ) タヒバリの一種
- 属名:anthus (m) セキレイ
- 種小名:spinoletta タヒバリ類のイタリアのフィレンツェ地方 (Florentine) の名称
- 英名:IOC: Water Pipit
- 備考:
anthus は#ビンズイ参照。
spinoletta の発音はよくわからないが、短母音と解釈。-let- がアクセント音節 (スピノレッタ)。
#マヒワ にあるようにギリシャ語 spinos に関係するならば i は伸ばさない。letta はイタリア語に意味の違う単語があるが e は伸ばさない。
亜種 blakistoni。
和名別名ヒガシヨーロッパタヒバリ。現在のイタリア語名は spioncello。
ゴシキヒワ (継続)
レンジャクノジコ (移行)
ユキヒメドリ (新規)
- 学名:Junco hyemalis (ユンコー ヒュエマーリス) 冬のヨシキリ
- 属名:junco 中世ラテン語でヨシキリ (reed warbler) 語源は iuncus ヨシや何でもない草 から (The Key to Scientific Names, wiktionary)
- 種小名:hyemalis (合) 冬の (hiemalis (adj) 冬の hiems (f) 冬)
- 英名:IOC: Dark-eyed Junco
- 備考:
junco は iuncus の与格に同じ形が現れるがその場合は語末を伸ばす。造語語尾や対応する英名からも語末を伸ばす発音でよさそうに思える (ユンコー)。
属名も英名も同じ Junco だが、英語の方は綴り通りジャンコゥと発音される。英語の junk もおそらく語源的に関連があるのではとのことだが OED は関連はないとしている (wiktionary)。
hyemalis は形容詞語尾の -alis の冒頭が長母音でアクセントもある (ヒュエマーリス)。語幹は hiems (ヒエムプス。冬。hiemps の別綴り由来)。
ウィルソンアメリカムシクイ (移行)
◆おまけ: 星座名と共通の学名
星座一覧は
星座名・星座略符一覧(略符順) (国立天文台) による。
星座和名の後に * のあるものは学名が複数形。りょうけん座が複数になっているのは1頭の猟犬で狩りをするのではないためだろう。
へび座のみ2領域に分かれており、頭部 (Caput)、尾部 (Cauda) がある。
星座を用いて呼ばれる天体の学名の星座名には属格を用いる: 例 α Aquilae (わし座 α = アルタイル)。論文などでももちろんこの表記が用いられる。
星座でも生物学名でも出てくる格変化は属格のみなので、この表を見ていただければラテン語名詞の格変化パターンをだいたい把握いただけるだろう。
いくつかの星座学名を知っているだけで生物の学名がずいぶん把握しやすくなる (逆もまた真)。
ラテン語学名は他の分野、たとえば解剖学、にも出てくるので丸暗記でなく意味を読解してゆくとずいぶん覚えやすくなる。
| 略号 | 和名 | 主格 | 属格 (〜の) | 関連する学名の鳥・動物 |
| And | アンドロメダ | Andromeda | Andromedae | アミメジツグミ |
| Ant | ポンプ | Antlia | Antliae | |
| Aps | ふうちょう | Apus | Apodis | アマツバメ目, オオフウチョウ |
| Aql | わし | Aquila | Aquilae | イヌワシ属, メスグログンカンドリ, カマハシハチドリ |
| Aqr | みずがめ | Aquarius | Aquarii | クイナ, ヌマヒタキ |
| Ara | さいだん | Ara | Arae | (コンゴウインコなどの Ara とは無関係) |
| Ari | おひつじ | Aries | Arietis | |
| Aur | ぎょしゃ | Auriga | Aurigae | |
| Boo | うしかい | Bootes | Bootis | (ウシ属 Bos など)。bo- は牛の意味で多くの種類に使われる (サンカノゴイなど) |
| Cae | ちょうこくぐ | Caelum | Caeli | |
| Cam | きりん | Camelopardalis | Camelopardalis | (ラクダ科) |
| Cap | やぎ | Capricornus | Capricorni | ヨタカ目 |
| Car | りゅうこつ | Carina | Carinae | ミドリヒロハシハチクイモドキ |
| Cas | カシオペヤ | Cassiopeia | Cassiopeiae | |
| Cen | ケンタウルス | Centaurus | Centauri | |
| Cep | ケフェウス | Cepheus | Cephei | |
| Cet | くじら | Cetus | Ceti | (クジラ亜目) |
| Cha | カメレオン | Chamaeleon | Chamaeleontis | |
| Cir | コンパス | Circinus | Circini | |
| CMa | おおいぬ | Canis Major | Canis Majoris | (イヌ科), (Major) アカゲラなど。肉食の carnivorous の語源は異なる |
| CMi | こいぬ | Canis Minor | Canis Minoris | (Minor) シジュウカラなど |
| Cnc | かに | Cancer | Cancri | |
| Col | はと | Columba | Columbae | ハト目, ウミバト, コチョウゲンボウ |
| Com | かみのけ | Coma Berenices | Comae Berenices | #ウミウ解説参照 |
| CrA | みなみのかんむり | Corona Australis | Coronae Australis | (Australis) オークランドアイサなど。オーストラリアに由来する学名は多数。陸鳥系統名の Australaves |
| CrB | かんむり | Corona Borealis | Coronae Borealis | (Corona) センダイムシクイなど (Borealis) コムシクイなど |
| Crt | コップ | Crater | Crateris | |
| Cru | みなみじゅうじ | Crux | Crucis | |
| Crv | からす | Corvus | Corvi | カラス科 |
| CVn | りょうけん * | Canes Venatici | Canum Venaticorum | |
| Cyg | はくちょう | Cygnus | Cygni | ハクチョウ属, サカツラガン |
| Del | いるか | Delphinus | Delphini | (マイルカ科) |
| Dor | かじき | Dorado | Doradus | |
| Dra | りゅう | Draco | Draconis | (コヌマムクドリモドキの旧学名) |
| Equ | こうま | Equuleus | Equulei | (ウマ科) |
| Eri | エリダヌス | Eridanus | Eridani | |
| For | ろ | Fornax | Fornacis | |
| Gem | ふたご * | Gemini | Geminorum | |
| Gru | つる | Grus | Gruis | ツル目 |
| Her | ヘルクレス | Hercules | Herculis | オオカワセミ |
| Hor | とけい | Horologium | Horologii | |
| Hya | うみへび | Hydra | Hydrae | ウミツバメ科, オニアジサシ属など |
| Hyi | みずへび | Hydrus | Hydri | |
| Ind | インディアン | Indus | Indi | インドガン、サシバなど? |
| Lac | とかげ | Lacerta | Lacertae | (カナヘビ科) |
| Leo | しし | Leo | Leonis | (ライオンの種小名) |
| Lep | うさぎ | Lepus | Leporis | (ウサギ科) |
| Lib | てんびん | Libra | Librae | |
| LMi | こじし | Leo Minor | Leonis Minoris | (Leo), (Minor) |
| Lup | おおかみ | Lupus | Lupi | (オオカミの種小名) |
| Lyn | やまねこ | Lynx | Lyncis | (オオヤマネコ属), オオミミヨタカ属 |
| Lyr | こと | Lyra | Lyrae | (コトドリの英名), タテゴトヨタカ |
| Men | テーブルさん | Mensa | Mensae | |
| Mic | けんびきょう | Microscopium | Microscopii | -scop はムシクイ属で使われる |
| Mon | いっかくじゅう | Monoceros | Monocerotis | ウトウ |
| Mus | はえ | Musca | Muscae | ヒタキ科 |
| Nor | じょうぎ | Norma | Normae | |
| Oct | はちぶんぎ | Octans | Octantis | シラコバトに一部関連, クロアイサ |
| Oph | へびつかい | Ophiuchus | Ophiuchi | |
| Ori | オリオン | Orion | Orionis | |
| Pav | くじゃく | Pavo | Pavonis | クジャク属, ヒメキジミチバシリ, アカハシカザリキヌバネドリ |
| Peg | ペガスス | Pegasus | Pegasi | (魚のウミテング科, 虫の Swift Locust) |
| Per | ペルセウス | Perseus | Persei | |
| Phe | ほうおう | Phoenix | Phoenicis | ジョウビタキ属?, フラミンゴ目? 語源が同一かは不明。同様の種小名は多数 |
| Pic | がか | Pictor | Pictoris | |
| PsA | みなみのうお | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | |
| Psc | うお * | Pisces | Piscium | ペリカンやミサゴなど多種の旧学名, ハイイロエボシドリ, 魚食を表す英語 piscivorous |
| Pup | とも | Puppis | Puppis | |
| Pyx | らしんばん | Pyxis | Pyxidis | |
| Ret | レチクル | Reticulum | Reticuli | アオスジヒインコ, チモールキミミミツスイ |
| Scl | ちょうこくしつ | Sculptor | Sculptoris | |
| Sco | さそり | Scorpius | Scorpii | |
| Sct | たて | Scutum | Scuti | アオバズク旧種小名 = 現フーアアオバズク, ハジロモリガモ |
| Ser | へび | Serpens (Caput, Cauda) | Serpentis | ヘビクイワシ, (Cauda) サンコウチョウ, エナガなど多数 |
| Sex | ろくぶんぎ | Sextans | Sextantis | |
| Sge | や | Sagitta | Sagittae | ハナジロコノハズク, シロハラコウライウグイス, タテフムシクイ, ハナジロコノハズク |
| Sgr | いて | Sagittarius | Sagittarii | ヘビクイワシ |
| Tau | おうし | Taurus | Tauri | サンカノゴイ |
| Tel | ぼうえんきょう | Telescopium | Telescopii | エリマキヒタキ (Arses telescopthalmus)。-scop はムシクイ属で使われる |
| TrA | みなみのさんかく | Triangulum Australe | Trianguli Australis | (Australe) |
| Tri | さんかく | Triangulum | Trianguli | オリーブオニキバシリ |
| Tuc | きょしちょう | Tucana | Tucanae | シロムネオオハシの種小名, オオハシ科の英名 |
| UMa | おおぐま | Ursa Major | Ursae Majoris | (クマ属), (Major) |
| UMi | こぐま | Ursa Minor | Ursae Minoris | (Minor) |
| Vel | ほ | Vela | Velorum | クリムネアカメヒタキ, メンガタハタオリ, ミナミカオグロアメリカムシクイ, ヒメエンビシキチョウ |
| Vir | おとめ | Virgo | Virginis | アネハヅル |
| Vol | とびうお | Volans | Volantis | アシボソハイタカ(亜)種小名など |
| Vul | こぎつね | Vulpecula | Vulpeculae | (キツネ属), ヨーロッパノスリの亜種, パーカーカマドドリ, アカオカマドドリ |
◆参考文献
- 野鳥の学名入門 (くまたか/日本野鳥の会筑豊支部) 菊池秀樹
- フィールドガイド 日本の野鳥 高野伸二著 (公財)日本野鳥の会
- 日本の野鳥650: 決定版 (2014) 真木広造写真; 大西敏一, 五百澤日丸解説 平凡社
- 日本の野鳥 (山渓ハンディ図鑑7) 叶内拓哉/写真・解説 安部直哉/分布図・解説協力 上田秀雄/解説(鳴声)山と渓谷社
- Birder 文一総合出版
- 日本鳥類目録 改訂第7版 日本鳥学会
- 日本鳥類目録 改訂第8版の 第一回パブリックコメント版 (2021年2月、説明本文)、
パブリックコメントとその回答 (2021年9月)
および 日本鳥類目録第8版和名・学名リスト公開 (2023年9月、
説明本文)、
第二回パブリックコメントに向けた暫定リストの公開 (2023年10月、
説明本文)
一部学名の変更の見込みについて。
日本鳥類目録改訂に向けた第2回パブリックコメント (2024年4月、
日本鳥類目録改訂第8版原稿案、「和名・学名リスト」からの変更点)。
掲載鳥類リスト (Excelファイル | 2024年10月8日 ver.1 公開)
日本鳥学会ホームページより
- Mark Brazil "Birds of East Asia" (2009) Princeton
- コンサイス鳥名事典 三省堂編修所 (1988)
- 愛媛の野鳥「はばたき」 愛媛新聞社 (1992) 参考文献に内田清一郎・島崎三郎「鳥類学名辞典」(東京大学出版会 1987) があり、学名字義はこれを参照しているかも知れない
- Helm Dictionary of Scientific Bird Names (2010)。
内容は次の The Key to Scientific Names に引き継がれており、更新されたものもかなりあるので次を確認した方がよい。
- Cornell Lab of Ornithlogy The Key to Scientific Names by James A. Jobling
- AviList: The Global Avian Checklist: 2025.6 に公開された世界の鳥の共通リスト。もともとは IOU の作業部会 (WGAC)。
IOC, eBird/Clements いずれもこのリストに合わせることを表明し、独自の更新は次回が最後になる予定。HBW/BirdLife は少し遅れるが同様と考えられる。
AviList。引用先は AviList Core Team. 2025. AviList: The Global Avian Checklist, v2025 https://doi.org/10.2173/avilist.v2025。
2025 年版リストのファイルは AviList-v2025-11Jun-extended.xlsx と AviList-v2025-11Jun-short.xlsx。
訂正: v2025 errata。
次の Avibase とも連携している。これからの世界の鳥のリストの標準となる。
- Avibase - The World Bird Database Avibase
- IOC World Bird List Version 13.2-15.1 IOC World Bird List (現在 15.1 リストをダウンロードできる) Master Lists。IOC は v15.2 で終了と表明している。
- Home of the conservative checklist of the birds of the world
H&M4 Checklist by family
- Avitaxonomicon by Faenger (2023) Avitaxonomicon
- BirdForum (www.birdforum.net)。特に Bird Taxonomy and Nomenclature のコーナーは役に立つ。次の John Boyd や、IOC の Donsker や海外リストの改訂提案にコメントを述べる立場の人も参加しており、世界の分類や学名の最新情報を知ることができる。
他にも英名や学名の由来を調べたりするコーナーもある。
- Taxonomy in Flux Checklist 3.50 by John Boyd Taxonomy in Flux (TiF) Checklist 3.50
生物学的種概念に基づく分類をベースとした Howard and Moore 3rd edition を出発点 (2007) としたが、分子系統解析をベースに文献情報などに従って更新を行ってきた結果、現状の IOC のものが最も近いものになったとのこと。
"in flux" の意味は All things are in flux (万物は流転する) が出典かも知れないが、いずれにしてもこの成句を想像すると意味が近いと思われる (万物が流転するかのごとく分類学の変遷を楽しむ)。
日本人らしい古典を引くならば鴨長明「方丈記」冒頭の「ゆく河の流れは絶えずして、...」に相当するだろう。TiF を「分類学の流れは絶えずして」とでも訳してみようか。
IOC 分類を分類基礎に用いる補強材料にもなるだろう (2024 年前半段階までの話)。
上位分類は研究者の意見が一致しないところもあり少し違う部分もある。
2024年6月に Stiller et al. (2024) も取り入れ、3.50 にバージョンアップされた。
目、科などの属より上の分類には統一した基準があるわけではないので、分類学者の考えが入る部分である。分岐年代を目安に分けるとどうなるかなどの実験が行われている:
Time calibration and Linnean ranks in birds
この基準だと新しいグループ、例えばスズメ目では科がほとんどなくなってしまうなどの問題があり、いろいろ議論がなされている。
年代だけを目安にすると分岐年代が古いが互いに似たグループを別目に分けることも発生する問題もあるが、それはあくまで人の目で見た場合の話であって、などの問題。また進化速度もグループによって異なる問題もある。
あくまで実験として地質年代の区分に従って分けるとどうなるかなど紹介されている (p. 3)。それほど違和感のないグループも多いが、タカ目を 20 科 (!) に分ける例が示されている。さすがに分けすぎだろうがハゲワシ科などの名前はあってもよさそうで少し納得できてしまう。そのぐらい大規模な適応放散を遂げたグループと言えるのだろう。
Nomenclature burnout 近年の進展があまりに早く、分類学や名称がしばしば変わるので「燃え尽き症候群」が発生している話題もある。例えば図鑑に書いて名前を全部覚えたらおしまいというわけではなくなっている。
- Biodiversity Heritage Library (BHL) 原記載の文献など。主に Avibase のリンクより利用した。
- Zoonomen Zoological Nomenclature Resource Richmond Index (Alan P. Peterson) と呼ばれる鳥に使われた学名を収集した一覧がある。古く使われた学名に関してはこのサイトと "The Key to Scientific Names" でかなりのことがわかる。birdforum.net でもしばしば参照されている。
- Kuhl et al. (2021) An Unbiased Molecular Approach Using 3'-UTRs Resolves the Avian Family-Level Tree of Life
- xeno-canto (XC) 世界の鳥の音声データベース。コオロギ類に始まり、カエル類など全生物音声を目指している。超音波音源も含むコウモリ類など哺乳類も着手が進んでいる。
記録に基づき独自に改訂を加えた分布図も示されており参照の価値が高い。地域 (亜種) による音声の違いなどを調べるのに大変役立つ。研究者も積極的に投稿しており、音声によって判定された未記載亜種などの記録もあって世界のレベルの高さがわかる。
- Macaulay Library (ML) eBird のバックボーンとなる画像、音声、ビデオのデータベース。鳥の音声では現在 xeno-canto と並ぶ世界の2大データベース。
- Movebank というドイツの Max Planck Institute of Animal Behavior がホストとなっている移動性動物の経路追跡データベースがある。多くの種類が公開されており (Data → Explore Map → Search で学名などを入れると検索できる。
- PubMed Advanced Search Builder [National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information (NCBI), U.S. Department of Health and Human Services]
アメリカの特にバイオテクノロジー論文検索システム。鳥では生理学や感染症関連の論文が多くヒットするが、生態学などの全分野の論文も十分多く含まれている。
'Omg, did PubMed go dark?' Blackout stokes fears about database's future (Nature news 2025.3.4) 2025.3.1 に一時的なサービス停止があり科学者を困惑させた。障害は世界的なものではなかったが、もしかするとアメリカ政府の政策転換に関係があるのではとの懸念が生じている。
- GenBank (NCBI) 遺伝情報データベース。前書きで解説のように簡易的な系統樹も作成できる。世界的によく使われるサービスで、世界の鳥類チェックリスト以外にもこのサービスで使われる分類体系や学名ももう一つの標準となっている。分類体系は世界の鳥類チェックリストより多少遅れて更新されている。
2025.3 分類体系の更新を確認した。鳥類分野のみでなく生物学全般で用いられており、生物学全般では事実上の標準学名となるだろう。例えばオオタカの学名も Astur gentilis となった。
NCBI の分類体系については Schoch et al. (2020) NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools の解説がある。鳥類は Avibase を重視していることがわかる。
- bioRxiv よく使われる生物学プレプリントサーバー。未発表研究などが紹介される場合もある。プレプリントサーバーは物理・数学で使われ始め、生物にも波及した形になっている。
Preprint sites bioRxiv and medRxiv launch new era of independence (Miryam Naddaf, Nature News 2025.3.11) に歴史と展望が述べられている。bioRxiv は 2013 年に始まり、2025 年に新組織 openRxiv 誕生とのこと。
参考までに物理・数学を中心とした分野では arXiv が世界的に標準となっている。
天文学分野では NASA の The SAO Astrophysics Data System (ADS) 文献サービスが大変充実していて古い文献でもほぼスキャンされてネットを探す必要もなく読むことができる。物理・数学が中心とはいえ検索範囲には近年は生物学の論文誌もかなりカバーされている (科学のいろいろな分野はつながっているし、宇宙生物学の進展による必要性からだろうか)。例えば avian などを入れて検索していたければ理解いただけるだろう。
天文学分野ではオープンアクセス雑誌が中心で、そうでない論文も主要なものの大半は arXiv に投稿することが慣習となっている (生物学とは逆に論文受理後にプレプリントサーバーに置くことが多い)。論文を読んで研究を進める上で大学などの機関アカウントはあまり必要ない。
ハッブル宇宙望遠鏡や世界の主要な観測衛星や施設の観測データも公開されており、天文学分野ではこれらサービスを用いることでアマチュアでもプロ研究者とほとんど違わない研究を行えるはず。
原理的には誰でも最新鋭データを用いて Nature などで発表できるような発見が可能である。
NASA ADS では天体名 (Object。生物では種に相当) でも検索できる。一部の文献を除いて天体名だけで過去論文をほぼ網羅的に調べることができ、しかも大半はそのまま読むことができる。
この機能は非常に便利で、鳥の種類から過去論文が一括で調べられるシステムがあればといつも思う。
生物分野とは異なって学名のような統一的名称を用いている天文学分野は少なく、天体ではさまざまなカタログ (可視光、X 線、電波などそれぞれいろいろなカタログがあるのでそもそも統一も難しい) にいろいろな名前で記録されていることが多い。
そのため同一性を確保するための name resolver の機能が発展していてこちらはフランスの CDS が管理し、こちらも完全公開されている (VizieR)。電子版の存在する各文献に記載されている表の多くも電子データ化されてここからアクセスできる。
CDS からもさまざまなカタログの名称を用いて文献検索が可能になっている。これらも生物でデータベースを構築する際の参考になるかも知れない。
- 蒲谷鶴彦・松田道生「日本野鳥大鑑 鳴き声420」(小学館 2001)
- Dement'ev and Gladkov (eds) Ptitsy Sovetskogo Soyuza (ソ連の鳥) (1951-1954) 全6巻。旧北区の鳥の古典的名著。1-3巻が 1951 年、4巻が 1952 年、5-6巻が 1954 年発行。本文中では何巻かを区別していないが第6巻に全索引がある。
英訳され Jerusalem by Israel program for scientific translations から刊行 (1966-1970) されたものがよく引用されているが、英訳版の出版年で判断すると前後関係を誤ることがあるので要注意。
原語版はモスクワ大学 (植物学研究室) のボランティアサイト http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm でオンラインで読むことができる。
今のところは維持されているが、将来も残されるかは不明。
ロシア語書物を探したいたい時はこのサイトに当たってみるとよい。トップページが表示されるまで少しかかるので少しお待ちを。
もしまだサイトが健在ならばトップページをそのままダウンロードしてソースコードを見れば所蔵文献一覧が全部含まれているのでゆっくり調べるとよい。
この解説の本文中でラテン文字表記をしてあるロシア語の本の名称をキリル文字に変換し、サイトの検索機能 (実はサイトが検索しているわけではなくページに内在された機能) を用いて目立つ単語や著者名で検索すればすぐ見つかるだろう。ファイル名はラテン文字になっているので探せる場合もあるが、一定の変換規則に合わせてラテン文字化されているわけではないのでラテン文字で検索すると漏れることがある。
キリル文字の読める人には表示された一覧から探すことは全然問題ないとは思うが、キリル文字入力には ローマ字キリル文字変換 が便利。本文中のラテン文字表記もこのサイトでほぼ一発変換可能のはず (例えば ts を1文字にするか2文字にするかなどわずかに曖昧な部分があって、意図しない変換もたまにあるが文字を読める人ならばすぐわかる)。
なおロシアでは文字テキストは pdf もよく使われるがスキャンされた文書は pdf より圧縮率の高い djvu 形式がよく使われている。手持ちの文書表示ソフトが対応していない場合は djvu 対応のものをインストールする必要がある。
ロシアなどの人名のラテン文字表記に現れる ' の文字は何かと疑問を持たれている方もあるだろう。これは省略記号ではなく軟音符 (ь の文字) と呼ばれるもので、アルファベットに含まれているが単独で発音することはできない。その直前の子音を軟音化する記号 [硬音符または分離記号 (ъ の文字) が別にあってここでは同じく ' で示している。役割が違うので同じラテン文字表記でも紛らわしくならない]。
教科書的に言えば "イ" の口の形で子音を発音する。日本語ならば "ナ" と "ニ" で少し口の形が異なるが、後者の n の音が軟音に対応する。
[sh' のような表記もあり、これはロシア語では1文字の "sh" の音を軟音化するもので h を軟音化するものではない。si と shi の区別に困るぐらいなのにさらに軟音とは...と思ってしまうが]。
ここで用いている標準的なロシア語のラテン文字表記では軟音符を忠実に ' と表記しているが、著者名のラテン文字表記などではこの記号を落としたり別の文字を用いたりすることもある。
Dement'ev も原著から記述すればこの綴りになるが英訳版から引用すると Dementiev となる。この場合は t' の音が ti の音に比較的近いために置き換えられたもの。本来は子音なのでこの ti にアクセントを置くとおかしなことになる。
古いロシア語の本などではあまり問題がないが論文では多少悩ましい例があって、著者が英文表題や著者名を含めている場合にはそちらに従っている。そのため同一人物でも異なる綴りが生じる場合がある。
地名も同様で我々がよく目にする地名では例えば沿海地方の シホテ・アリン Sikhote-Alin' がある。英語表記では ' の記号が落ちるために シホテ・アリン と表記されることが多いが原語表記に近い音ならば シホテ・アリニ でもよい。アナディリ も同様で Anadyr' でこれも英語表記から アナディル と読まれる。どちらでも間違いでなくこの解説でも出典次第で両者が混ざっている。
地理でお馴染みだろう オビ川 も同じような例で、原語では Ob' 英語では Ob (何だそれはと思ってしまうが) で語末が b なのに "ビ" とする理由。語末で無声化すると オピ川 となってよさそうだがさすがに見かけない。
我々に近い地域の沿海地方を表す一般的名称に Primor'e があり、この ' も同様。日本語で書く際にプリモーリエまたはプリモーリェとするのはこのため。英語表記では Primorye となることが多い。
なお行政的には沿海地方の表記が正しく、沿海州の名称は古い行政区名に由来するもので現在は適切な名称でない。
さらに補足的になるが、ロシア関連のラテン文字転記に shch が現れ妙に長いので何かと思われている方もあるだろう (ロシア語は子音が並ぶので云々は俗説)。これはキリル文字では1文字で щ の表記になる。似た文字の ш をラテン文字で sh (学名などに使われるドイツ語表記では sch) と転記するため長くなるがやむを得ず4文字も使っている。
その昔ロシア語学習用のテキストを見た時はアルファベット ш を "シャー"、щ を "シシャー" と読んでいたと記憶している。入門講座でもアルファベットの読みと発音を最初に扱うが、NHK のラジオ講座を 10 年弱前に聞いた時には日本語ではどちらも "シャー" に聞こえてどこが違うのかと思った。
実は shch の方が日本語の "シー" の子音に近く、sh はむしろ少し違った音でどのように発音すればそのような音が出せるのか今ひとつわかっていない。
sh に対応する有声音が zh (ж) なのだが、sh を日本語の "シ" のつもりで有声化して "ジ" にするとしばしば通じない。文字とは裏腹に sh/zh の発音の方がむしろ難しいのである。ネイティブの人の発音を聞くと確かにしっかり発音され分けていて聞いてわかる違いがあるのだが、日本語にない音なので再現が難しいというところ。
猛獣・猛禽を表す khishchnik もいかにも難しそうなのだが日本語の "ヒーシニク" と音はほとんど同じで子音の後に余分な母音を入れないことさえ注意すれば十分通じる。
shch の入る単語は意外に身近なところにあって、ボルシチ はもとの綴りをラテン文字転記すると borshch となる。キリル文字表記では4文字で母音は1つのみの1音節語だが日本語表記になると母音が4つになってしまう。ボルシチはウクライナが起源で wikipedia 日本語版でも発音を聞くことができるので shch がどんな音なのかわかりやすい。
ラテン文字転記にはいくつかの記法があり、著者が英語表記する際に shch を sch と表記する場合もあり、これも同一人物や地名でも異なる綴りが生じる場合がある。沿海地方の鳥シリーズで有名な Gluschenko の sch は典型例。
shch を含む短い名前の鳥に shchur ギンザンマシコ があっていったいどう読むのかと悩みそうだが案外簡単であることがわかっていただけると思う。
ちなみにチェコ語など東欧語で上に記号の付いた s や c を見かけるが、キリル文字で表せば1文字となるところをラテン文字アルファベットでは足りないので記号を付けて1文字で表記していると考えるとわかりやすい。
- Kessler (1851, 1853) キエフ地域の鳥類全3部。#オオハム備考にリンクの一つを示した。ヨーロッパロシアで当時使われていた学名などを知るよい資料となった。
上記モスクワ大学のサイトで見られ、ファイル名は kessler1851_estestv_istorija_gubernij_kievsk_uchebno_okruga_ptitsy_khischn_kurin.pdf, kessler1853_estestv_istorija_gubernij_kievsk_uchebno_okruga_ptitsy_golenast_vodn.pdf, kessler1851_estestv_istorija_gubernij_kievsk_uchebno_okruga_ptitsy_vorobjin.pdf の3つ。
- Shtegman (1937) "Faune de l'URSS Oiseaux" ここでは昼行性猛禽類の Vol. I n.5 Falconiformes を参照した。上記モスクワ大学のサイトで shtegman1937_dnev_hischniki.djvu のファイル名で見られる。本のタイトルはフランス語だが中身はロシア語。情報は古いが現代の書物であまり触れられていない知識も得られる。また Dement'ev and Gladkov の書物などの基礎ともなっている。
- Menzbier (1882) Ornitologicheskaya geografiya Evrop. Rossii (Uchen. Zap. Imperat. Mosk. Univ. 2, ヨーロッパロシアの鳥類地理学)。オオタカの大陸亜種などの記載。当時は大学院生でこの研究で学位を得た。
- Nechaev (1991) "Ptitsy Ostrova Sakhalin" (Birds of Sakhalin Island。表題と要約のみ英語あり) 極東の鳥類 12-14 「サハリンの鳥類 1-3」 (1995-1997 で翻訳が読める。2025.1 現在在庫とある)。
- Ryabitsev (2014) "Ptitsy Sibiri" (シベリアの鳥) 全2巻
- Glushchenko et al. (2016) "Ptitsy Primorskogo Kraya: Kratkij Faunisticheskij Obzor" (沿海地方の鳥: 簡潔な動物相の一覧)
- 藤巻裕蔵「極東の鳥類」シリーズ (極東鳥類研究会支援サイト)
- The Russian Journal of Ornithology 上記「極東の鳥類」でもこの雑誌に発表された多数の論文が翻訳されている。
- Grenys Lloyd and Derek Lloyd "Birds of Prey" (Hamlyn 1969 初版) 一部見られる。高野伸二訳「猛禽類」(主婦と生活社 1973)
- Leslie Brown "Birds of prey: their biology and ecology" (Hamlyn 1976) archive.org。昼行性猛禽類総説の古典的名著。
個々の種については Ferguson-Lees and Christie (2001) "Raptors of the World" が出ているが識別等の情報が中心で生態はそれほど詳しいわけではない。
現代でも単独著者による昼行性猛禽類を広い分野で扱った総説は次の書物までなかった。情報は少し古いとはいえ Brown (1976) は非常に有益である。必要な部分に現代の情報を補って読めばよい本であろう。
本文でしばしば登場する Brown and Amadon "Eagles, Hawks and Falcons of the World" は直接読めていないので参考文献には入れていないが、引用によって出版年が 1968 年と 1969 年のものがある。理由を調べてみると分冊で英国版は 1968 年に出版、米国での出版完結は 1969 年となったため両者が混在している模様。内容がどの程度異なるのか知らないことと、どちらの版を参照した記述かわからないことが多いので Brown and Amadon (1968-1969) の表記とした。
Grenys Lloyd and Derek Lloyd (1969) "Birds of Prey" はこの書物が出版されて間もなく出版されたことになる。またその翻訳 高野伸二訳「猛禽類」(1973) も大変早かった。
- Bildstein (2017) "Raptors: The Curious Nature of Diurnal Birds of Prey" (Cornell University Press)。昼行性猛禽類の最近の一般読者向け総説。Brown (1976) の本ほどの分野をカバーしているわけではないが、新しいデータ (翼面荷重 wing loading など) や Brown に記述のない知見なども入っているので参考になる。著者は特に昼行性猛禽類の渡りの専門家。
最初は猛禽類の狩りの魅力からこの分野に入ったが渡り研究に軸足を移したとのこと。
Brown and Amadon の時代には猛禽類の定義はまだ簡単だったが、分子系統解析の結果が明らかになってから猛禽類を定義することが難しくなった。今の時代も当時と同じだったらもっと簡単なのに...と始まっている。出典がはっきりしない情報も結構あるので孫引きする場合は注意が必要だろう。北米の種については学名由来の解説もある。
- Mindall et al. (2018) Phylogeny, Taxonomy, and Geographic Diversity of Diurnal Raptors: Falconiformes, Accipitriformes, and Cathartiformes in "Birds of Prey" (Springer)
- Catanach et al. (2023)
Enigmas no longer: using Ultraconserved Elements to place several unusual hawk taxa and address the non-monophyly of the genus Accipiter (Accipitriformes: Accipitridae)
が Mindall et al. (2018) の後継にあたる論文でタカ類の全分類を扱っている。#アカハラダカ備考にて解説 (preprint 段階のもの)。
「新・野鳥の学名入門」執筆途中の2024年2月7日受理、3月22日公開された = Catanach et al. (2024)。Clements 2024 で採用予定。2024年8月 IOC 14.2 でこの分類が採用された。
2024.6.29 発表の Correction to: Enigmas no longer: using ultraconserved elements to place several unusual hawk taxa and address the non-monophyly of the genus Accipiter (Accipitriformes: Accipitridae)
で ICZN 規則に基づいていなかった部分の訂正が出ている。
「新・野鳥の学名入門」では IOC などで新しく導入された分割や属名変更などを除きタカ類の学名はほぼこの文献に基づいている (詳しい扱いは個々の項目参照)。
- 若杉稔 マーリン通信 タカ・ハヤブサ類の情報を数多く参照させていただきました。
- Jollie (1976, 1977) A contribution to the morphology and phylogeny of the Falconiformes 雑誌 Evolutionary Theory に4部に分けて掲載された論文で、
part I,
part II,
part III,
part IV
に分割されて掲載されている。本来は1本の論文のため通しページと雑誌ページの両方が記載されていてわかりにくいが、引用では通しページを参照している。
当時のワシタカ目の解剖学的特徴と系統分類を扱った論文で、タカ類とハヤブサ類は単系統をなさない現代の視点からも斬新な結論を導いている。タカ・ハヤブサ類の形態と機能に興味のある方には非常に有用な資料であろう。
- 山崎剛史他 (2017) フクロウ目の新しい種和名
- 山崎剛史・亀谷辰朗 (2019) 鳥類の目と科の新しい和名 (1) 非スズメ目・イワサザイ類・亜鳴禽類
- 山崎剛史・亀谷辰朗 (2020) 鳥類の目と科の新しい和名 (2) 鳴禽類
- 山崎剛史・亀谷辰朗 (2022) アフリカクイナ科・クイナ科の新しい種和名
- Ogawa (1908) A hand-list of the birds of Japan 小川三紀による編集。現代の分類上問題となっている点を押さえながら見ると大変面白い。
日本動物大百科 鳥類 II (平凡社 1997) の森岡弘之氏の解説 (p. 175) によると小川三紀のこの「日本鳥類目録」は日本鳥学会の「日本鳥類目録」の前駆的著作とのこと。日本鳥学会は 1912 年に創立、「日本鳥類目録」の第1版は 1922 年出版。
この間に内田清之助の「日本鳥類図鑑」(1913) が出版されている。
飯島魁による「日本の鳥目録」("Nihon no Tori Mokoroku" 1891) が Ogawa (1908) に先行する目録であったが、これは学名、英名、和名だけのリストでブラキストン (Blakiston) とプライアー (Pryer) の目録の増補改訂版に過ぎなかったとのこと。明治期には小川三紀は飯島魁をしのぐ業績を残したと説明されている。
この目録あとがきにも触れられているが、小川氏は長い闘病生活の後、この書物を校正すること亡くなっている。校正は編集者によるもの。
現在でも Ogawa (1908) が海外で利用されるのは評価の高さも現れているのだろう。
情報も豊富で大変すぐれたリストなので当時の和名を知る以上に深くご活用いただきたい。
- 日本動物誌 Fauna Japonica 鳥類 (京都大学貴重資料デジタルアーカイブ)。鳥類 12 分冊は Coenraad Jacob Temminck (1778-1858) と Hermann Schlegel (1804-1884) によるとのこと。
(BHL) でも読める。
本文中では主に "Fauna Japonica" と記している。本の表題がラテン語なので中身もラテン語と思われている場合もあるらしいが本文はフランス語。
- Fauna Japonica: Description des oiseaux observes au Japon par les voyageurs Hollandais Fauna Japonica より図版一覧。
- The birds of the Japanese Empire (Seebohm 1890)。古い学名や英名もあり、海外から見た日本の鳥を知る上で大変役に立つ。
- Die Voegel der palaearktischen Fauna systematische Uebersicht der in Europa, Nord-Asien und der Mittelmeerregion vorkommenden Voegel Hartert (1910-1922) の当時の権威によるヨーロッパ、アジア北部、地中海地域の旧北区の鳥の分類体系のまとめ。全3巻。
本文中の引用では巻ごとの出版年ではなく全3巻の年代を示してページ番号で表記した。
- Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (Linnaeus 1758)。
= Systema Naturae ed. 10 ("自然の体系" 第 10 版) 現在の学名の原点。
- Systema naturae, per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (Linnaeus 1766)。
= Systema Naturae ed. 12 ("自然の体系" 第 12 版) 上記の改訂版。
- Fauna svecica : sistens animalia sveciae regni: mammalia, aves, amphibia, pisces, insecta, vermes, distributa per classes & ordines, genera & species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum (Linnaeus 1746 第1版);
同上 (Linnaeus 1761 第2版)
= Fauna Svecica (Fauna suecica) Linnaeus によるスウェーデンの動物相。"Systema Naturae" でも Fn. Svec. の略号でこの文献が全面的に引用されている。
- Ornithologia, sive, Synopsis methodica sistens avium divisionem in ordines, sectiones, genera, species, ipsarumque varietates: cum brevi & accurata cujusque speciei descriptione, citationibus auctorum de iis tractantium, nominibus eis ab ipsis impositis, nominibusque vulgaribus
(Brisson 1760。2分冊)。書物自身は二名法に則っておらず有効な学名記載とはされないが、属の記載は有効で現在使われている多くの属がこの文献で定義されている。
また有効な学名記載でなくとも当時の記述や使われた学名からいろいろな情報を得ることができる。しかし全文ラテン語。
- A general synopsis of birds (Latham 1781-1785。3分冊)。大航海時代らしい各地の鳥の記述。海上の船に日本近海で飛んできたハヤブサ、ジャワ島付近で飛んできたサシバなど原記載のもとになる記述がある。他にも当時の鳥の分類や英名なども知ることができる。図版もある程度含まれている。
- Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis Gmelin (1788-1793) の "Systema Naturae"。Systema Naturae ed. 13 ("自然の体系" 第 13 版) と呼ばれることも多い。鳥は第 1 巻 part 1, 2 に含まれている。
我々がよく出会う Gmelin の学名の大半はこの書物で記載されたもの。
- Checklist of the Birds of New Zealand (Ornithological Society of New Zealand 2019+) ニュージーランド鳥学会のチェックリスト。日本との共通種はそれほど多くない (特にスズメ目は大きく異なる) が属名や高次分類などの解説が詳しく、日本と共通の高次分類群の名称の確立経緯なども知ることができる。
ニュージーランド産の鳥については過去に用いられた学名や分類の根拠なども判断材料とした文献とともに示されている。過去にチェックリストに含まれながら除外された種についてはそれぞれの文献も示している。
日本鳥学会でも同様のリストを継承・維持してオンラインで公開してあれば、独自判断で分類が変わる理由などわかりやすかったわけだろうが。
- Bock (1994) History and nomenclature of avian family-group names あまりに大部の論文で (とても読めない!) 少し古くなっている (1999 年の規約改定は含まれない) が科レベルの名称を命名規則の歴史とともに解説。事例解説が詳しいので命名規則の適用例などがわかる。
- 「世界の鳥 行動の秘密」(ロバート=バートン著、山岸哲監修、舟木嘉浩・舟木秋子訳 旺文社 1985。原著 "Bird Behavior" by Robert Burton 1985)。原著は見ていないので紹介は訳文に基づく。種の同定は訳文中の和名と巻末の学名索引を用いているので、原著の種名がここで紹介する通りかどうかは確かでない。
ここでは訳文をさらに編集して紹介しているため、利用される際は原著または訳文に当たって確認いただきたい。この本を見ると、我々が普段本などで読む鳥の行動は 1985 年段階ですでにかなりのことが判明していたことがわかる。
- Karyakin (2004) Raptors_metod_2004.pdf Pernatye Khishchniki - Metodicheskie rekomendatsuii po izucheniyu sokoloobraznyikh i sovoobraznikh: 猛禽類 - ワシタカ類とフクロウ類の研究においての手法の提案 (英文表題では調査マニュアル)。本文では "猛禽類の調査方法" と記した (主にロシア中央部が対象)。タカ、ハヤブサ、フクロウ類が含まれている。
総論で主に伝統的な目視や巣の調査による猛禽類研究が扱われており、一部ラジオテレメトリー、猛禽類の生息調査に適した調査ルート選択などの記述なども参考になるところもあるだろう。
後半で個々の種を扱っており、各種の生活痕や生息地の見つけ方、足跡の識別なども含まれている。
サイトは Russian Raptor Research and Conservation Network (RRRCN) で、Karyakin も主要メンバーの一人。
雑誌 Raptors Conservation (ロシア語・英語併記) を発行しておりバックナンバーも参照可能。このサイトに書物も含めた多くの情報が紹介されている。
- 中西悟堂「定本・野鳥記」ここでは春秋社の再刊版を用いた。初出年は個々の引用に記載。前半の巻を一部持っている。
同じく「野鳥記コレクション」春秋社の再編版 (2004) I 野鳥と共に、II 野鳥のすみか、III 鳥を語る。題材は同じで現代の読者にもわかりやすいものを再編したもの。
- 「野鳥の歳時記」シリーズ。日本鳥類保護連盟監修 (小学館 1984-1985)。
1 春の鳥、2 初夏の鳥、3 夏の鳥、4 秋の鳥、5 冬の鳥、6 真冬の鳥、7 九州・沖縄の鳥、8 北海道の鳥、別巻 1 (世界の鳥 ユーラシア・アフリカ)、別巻 2 (世界の鳥 アメリカ・オセアニア)。
- 「動物の世界」2版 (日本メール・オーダー 1986) 一部の号を持っている。解説によればイギリスの BPC 社 "Purnell's Encyclopedia of Animal Life" を日本向け内容に改めて刊行とある。オリジナルの BPC 社の出版物を訳したと思われるもの、日本産で関連する話題をとりまぜたものなどいろいろな形態の記事があり、混在させて記述していると思われるものもある。
"Purnell's Encyclopedia of Animal Life" の出版年を調べてみると 1968 年となっており、相当古い情報も含まれているだろう。
日本版は 1972-1973 年に週刊「アニマルライフ」として刊行されたものを再度まとめたもので、その間に修正や追記が入っているかも知れない。一部現在と違う海外種の和名が使われているのは、この時代には一部の種しか和名が付けられていなかったためと考えられる。
項目を見るとイギリスの種類またはイギリスからみて話題となる海外の動物を主に紹介していることがわかる (写真も日本のものも取り上げつつ海外のものも多い)。日本版は、日本と同種の場合は原著記述に日本のことを部分的に含める形となっているので、日本と同種の場合はイギリスでの情報が中心だと考えて読んだ方がよい。日本でも同じとは限らない。ところどころに日本での情報や和名由来などを追記した形になっている。
原著が日本と同種でなくても近縁の日本の種が見出しになっていることもあるので注意が必要。これらの記述が部分要約の形で伝えられて行くとおそらく混線が発生していると考えられる。現在ではこのシリーズを直接読まれないかも知れないが、過去に読んだ人が混線させたまま伝えて文章になっている可能性もあるので注意を喚起しておく。なお日本版独自と思われる項目もある。
海外の記述に日本の情報を交えるこの方法と、日本の種類に限って日本の情報を伝える後の出版物とそれぞれに利点・欠点があるが、同種でも海外の情報量の方が豊富なことも多いので今となっては貴重かも知れない。この種の出版物は今後出版されない可能性もあり、参照可能な方は海外と日本の記述の区別を念頭に置きながら見ておかれるとよいと思う。
その後出版された日本の種類に限った記述 (例えば「日本動物大百科」) では抜け落ちた情報がかなりあるように感じる。
署名も訳者なのかオリジナル部分の著者なのか、また内容が 1972-1973 年に刊行された時点と同一かわかりにくい部分もあるので、ここで紹介された内容を引用される場合は元出典を確認いただきたい。
よく出てくる執筆者の姓名表記は浦本昌紀、安部宗明、樋口広芳。
- 週刊「世界動物百科」(朝日 = ラルース 1972, 1973)。こちらは記述によれば Librarire Larouise, Paris と Rizzoli Editore, Milan の (フランスとイタリア) 共同制作によるものの日本語版らしく、原著記事に日本の対応種の記述を加えた形になっている点は週刊「アニマルライフ」と似ている。
おそらくフランス語版からの翻訳らしく、翻訳スタッフは出版社側で、動物学者が監修する形となっている。おそらく原文を翻訳したのは翻訳スタッフで、個々の項目に動物学者の署名はないが、日本版独自と思われる内容も多く含まれている。
週刊誌としての形態では日本で書き下ろされた別ページの記事 (ローマ数字のページ) があり、こちらは署名記事になっている。1冊ごとに表紙から始まる通しページが別に存在することに後に気づいた (一部ページにしか振られていないので気づくのに遅れた)。ここで紹介するアラビア数字のページ番号はカラーページの番号。紛らわしくて申し訳ない。
よく出てくる執筆者の姓名表記は浦本昌紀、内田康夫、藤堂明保、森岡弘之。
当時はイギリスとフランスはよいライバル状態で、どちらもよりよい動物事典を目指して競い合っていた時代の産物と思える (相手側では絶滅したなど悪評判を伝える傾向も多少見られる)。当時の世界最先端の情報が詰められていた可能性がある。
日本で書き下ろされた別ページの記事も意欲的で、当時の鳥類学者の意気込みが伝わってくる。
少数の号を持っている。かつて学校図書館などによく置かれていた。
改めて読んでみると、たまにおかしな部分もあるが生態的な話はこの時代にはほとんどのことがかなりよく記述されていて、情報量を競い合っていた時代背景もあるだろうが、現代の書物の方が伝聞を重ねているだけでむしろ情報が薄くなっている感じがする。
現代でなければ得られない分子生物学や系統情報など、あるいは当時の日本ではまだあまり普及していなかった現代的な進化や生態学の考え方は新たに加える必要はあるだろうが、現代の知識を背景としてこの時代の書物を読むのはなかなか有用なのではと思える。
- 「行動・生態の進化」岩波書店「シリーズ進化学」(6) 長谷川眞理子ほか著 (2006)
- Wikipedia (野鳥ほか、各国語版)
- Wiktionary, the free dictionary
主に英語版を使用。英語の語源以外にもラテン語の読み方や由来、変化形の情報が豊富にあり、学名の発音調査に非常に立った。(古典) ギリシャ語についてもかなりの情報が得られる。
"The Key to Scientific Names" に学名の由来となるギリシャ語が示されている場合が多いが英語版では見当たらないこともある。ギリシャ語の綴りで通常に検索すると Wiktionary のギリシャ語版で見つかることもあり発音などを知ることができる場合もある。ラテン語転写が示されている場合もあり参考になる。
Wiktionary 日本語版にもこれら言語の単語の見出し項目がある場合もあり活用されるとよいだろう。
- Online Etymology Dictionary (語源辞典、英語など)
- OED Oxford English Dictionary (英語語源や用例など)
- Noms francais normalises des oiseaux du monde - 2024 - version 6.3 (フランス語鳥名辞典)
- Die Voegel der Erde (ドイツ語鳥名辞典)
- Checklists of the Birds of the Philippines (フィリピンのチェックリスト)
- 羅和辞典 水谷智洋編
- はじめてのラテン語 大西英文 講談社現代新書
- 筑豊の野鳥 日本野鳥の会筑豊支部監修
- 野鳥の観察図鑑 成美堂出版
- Wikipedia・ラテン語の文法

- Wikipedia・学名

- Greek and Latin for Medichine StatGenetKyotoU

- Google翻訳

- Weblio英和辞典

- 新しいラテン語文法
 CHARLES E. BENNETT著 (PDF)
CHARLES E. BENNETT著 (PDF)
- 生物の名前と分類

- その他関連ウェブサイト、ブログ




 」掲載の 633 種を同書の配列順により掲載している。
改訂第8版で新規掲載された種も掲載しており、第8版準拠の#リンク集も用意している。
亜種についても備考で触れている。「日本鳥類目録 改訂第7版」非記載の鳥 (外来種) を掲載している。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、パブリックコメントへの回答、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト (目録第8版出版前段階のもの) も踏まえている。種名見出しでは目録第8版で種の分割、合体により学名が変化するものに注意を促す意味で注釈を加えた。属名のみの変更は記していない。
」掲載の 633 種を同書の配列順により掲載している。
改訂第8版で新規掲載された種も掲載しており、第8版準拠の#リンク集も用意している。
亜種についても備考で触れている。「日本鳥類目録 改訂第7版」非記載の鳥 (外来種) を掲載している。
日本鳥類目録改訂第8版の第一回パブリックコメント版、パブリックコメントへの回答、日本鳥類目録第8版和名・学名リスト (目録第8版出版前段階のもの) も踏まえている。種名見出しでは目録第8版で種の分割、合体により学名が変化するものに注意を促す意味で注釈を加えた。属名のみの変更は記していない。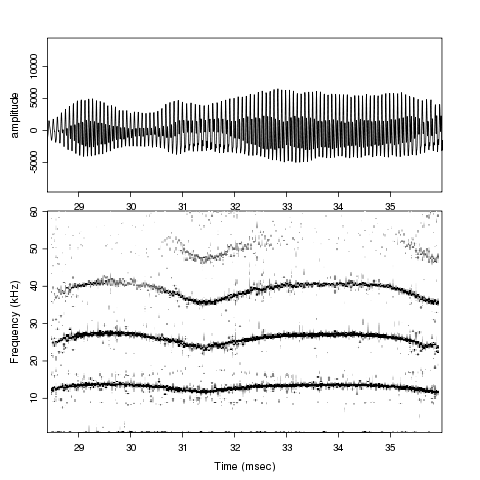
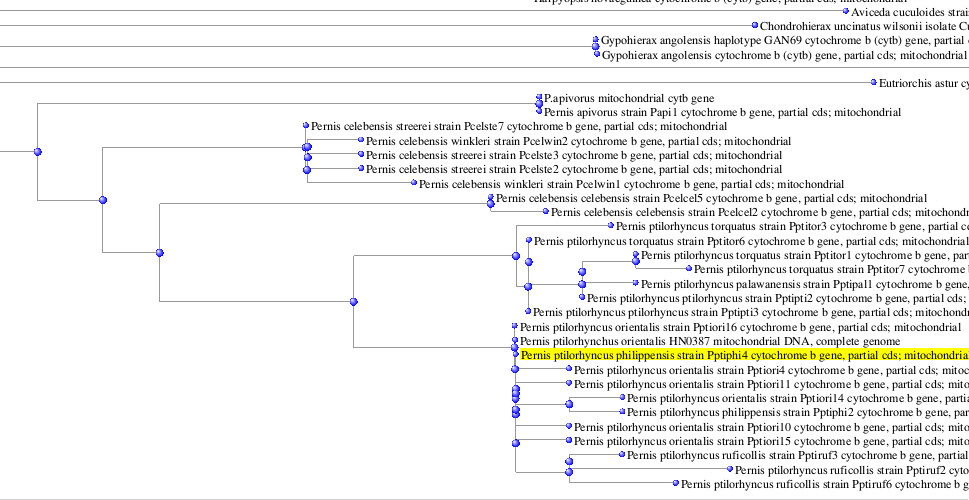
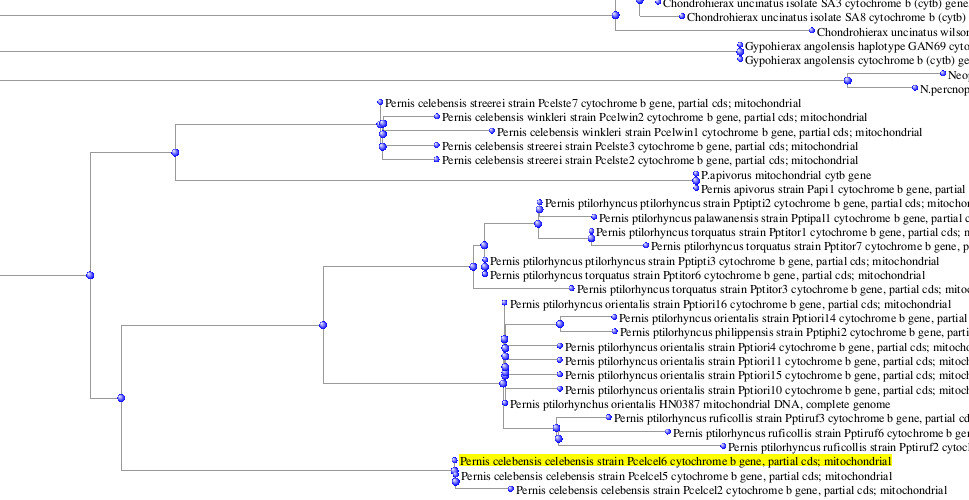
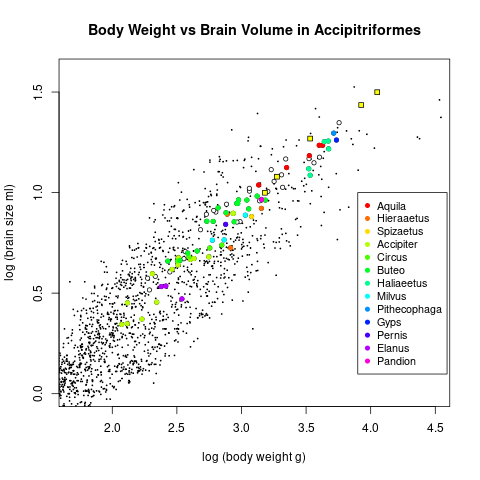
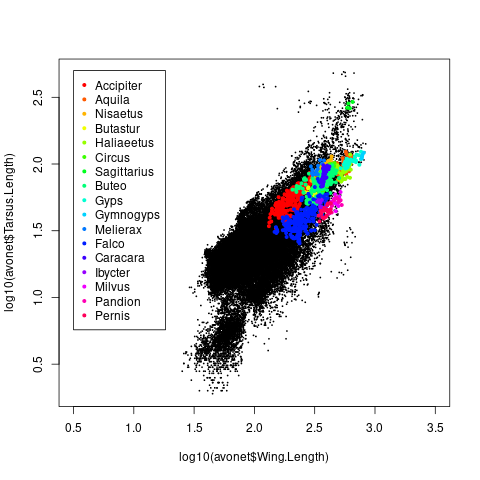
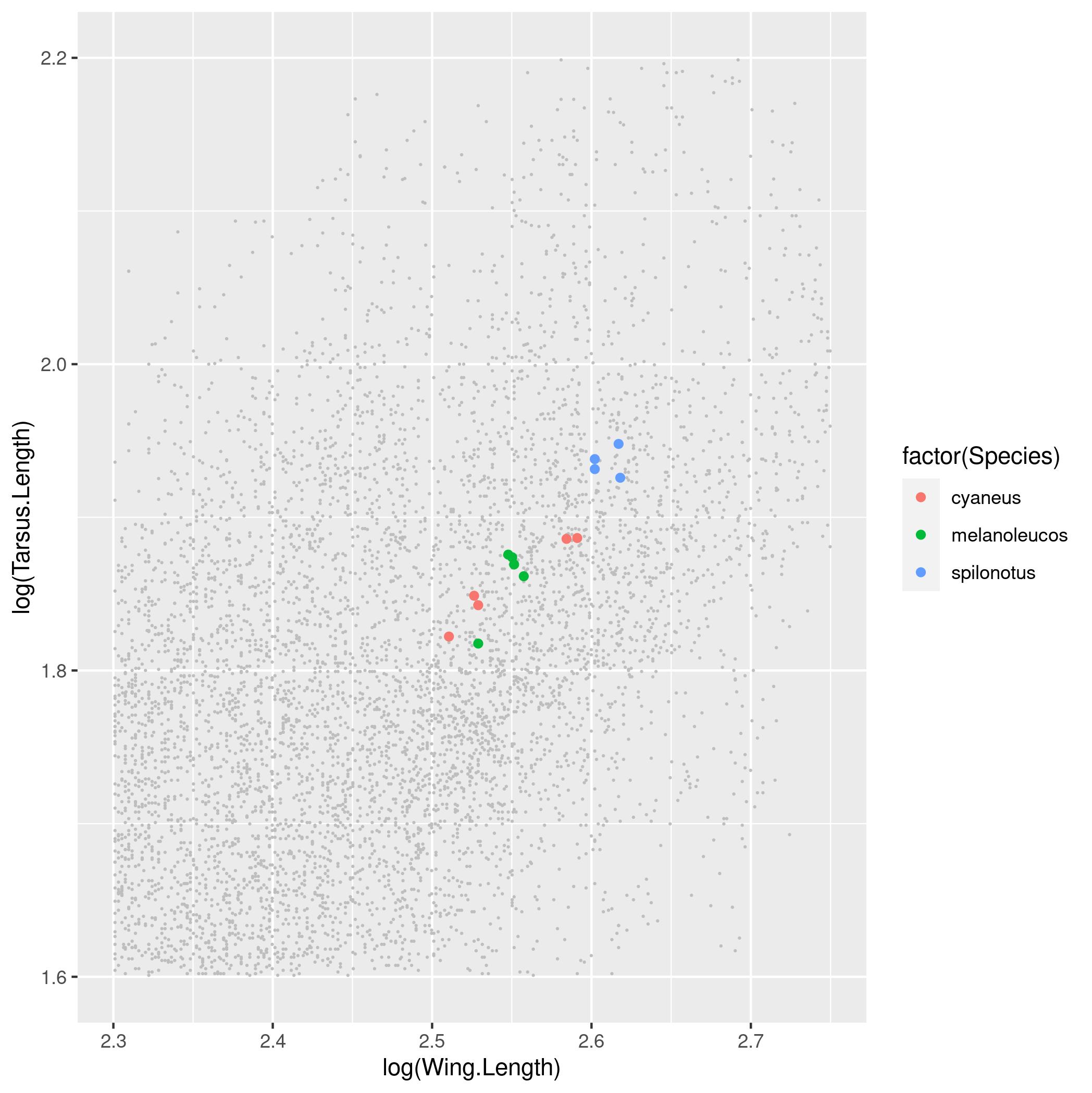








 CHARLES E. BENNETT著 (PDF)
CHARLES E. BENNETT著 (PDF)
