・非接触式センサの温度特性の試験結果。
・森谷さんの実験で対向板とセンサヘッドの間にプラスチックシートではなくカバーガラスを挟んだ場合の試験です。
・プラスチックより熱膨張率が低いであろうカバーガラスを用いて同様の試験をしたものです。
カウントレートと温度の時間変化
カウントレート基準は77457.8です
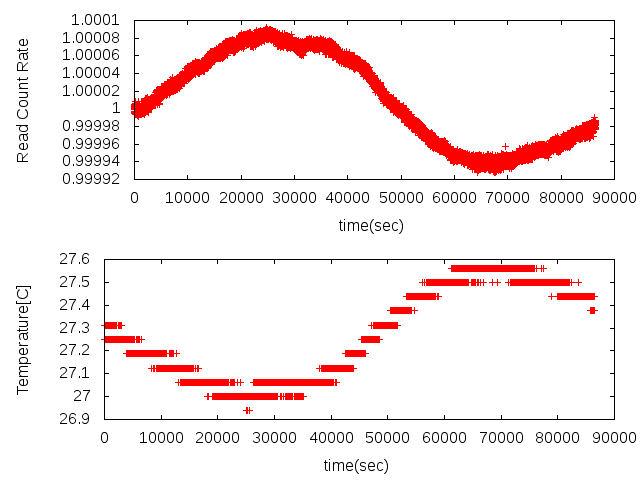
プラスチックシートを用いた場合と同じく負の相関がでました。
*使用したデジタル温度計はキャリブレーションしていないものです。
温度とカウントレートの相関
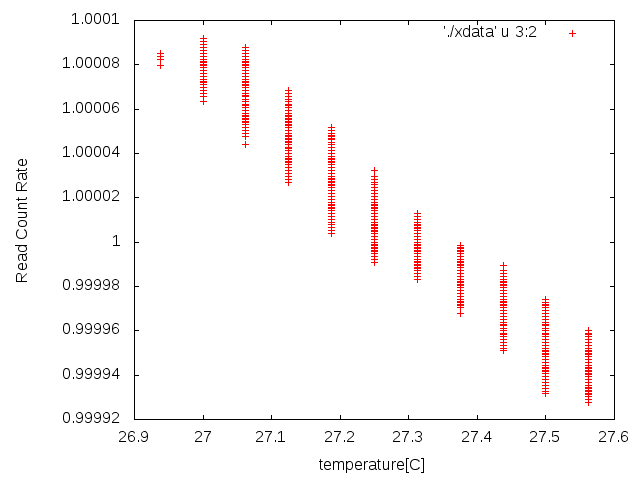
以前の実験に比べて温度が離散的になっているのは使用した温度計が違うからです。
・温度計を0℃〜室温程度でキャリブレーション済みのものに交換して再試験。
温度計を交換してセンサーのカウントと温度の相関をまとめました。
1 内周セグメントのアクチュエータに取り付けたセンサー(in1,in2,in3) in1,in2,in3の結果
2 外周セグメントのアクチュエータに取り付けたセンサー(out1,out2,out3) out1,out2,out3の結果
3 内周と外周セグメントの間に取り付けたセンサー(edge1,edge2) edge1,edge2の結果
4 センサーの間にガラスを挟んで固定したセンサー(glass) glassの結果
5 それぞれの温度相関を近似したパラメータ 結果
6 センサーと制御ボックスを別々に温度変化させた場合のパラメータ結果
についての結果報告です。
1
・in1,in2,in3(内周セグメントのアクチュエータに取り付けたセンサー)の結果
・センサーヘッドと制御ボックス内部に温度計を取り付け、それぞれの温度変化とカウントレートを比較をしました。
| センサー位置 | in1 | in2 | in3 |
| センサーカウント の時間変化 |
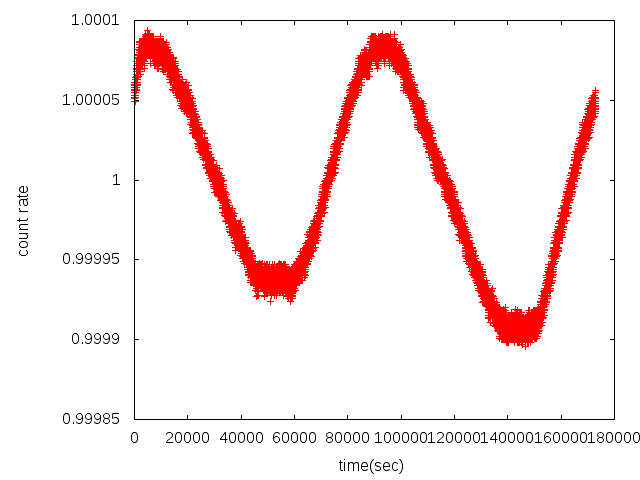 |
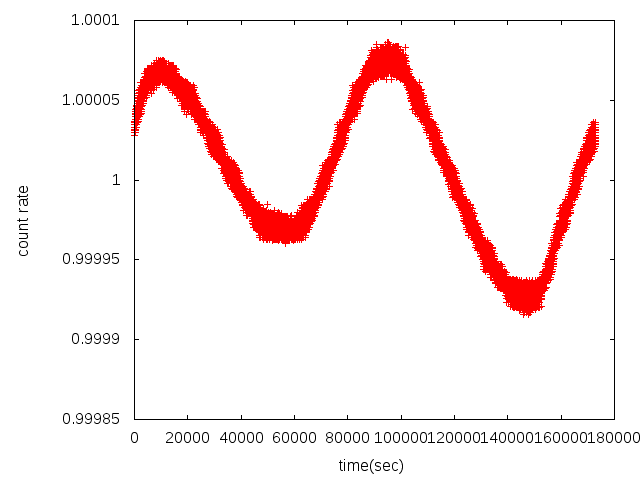 |
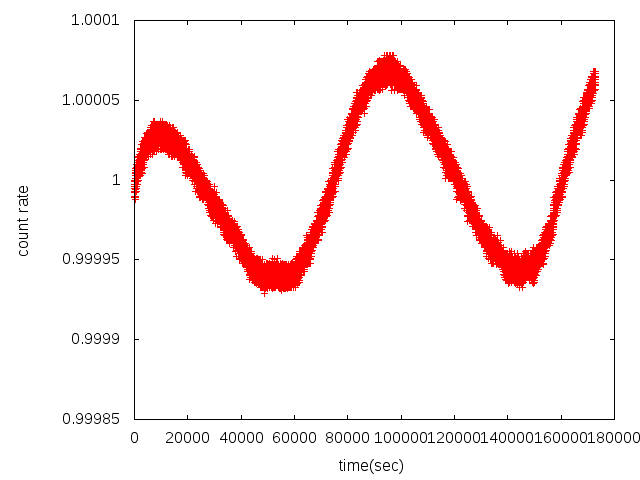 |
| センサー(付近) の時間変化 |
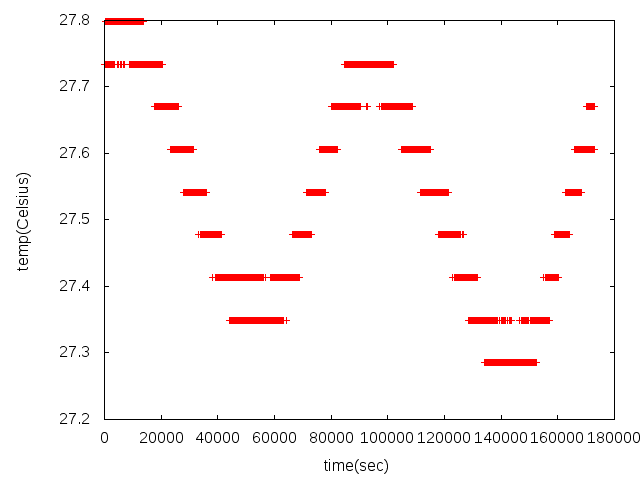 |
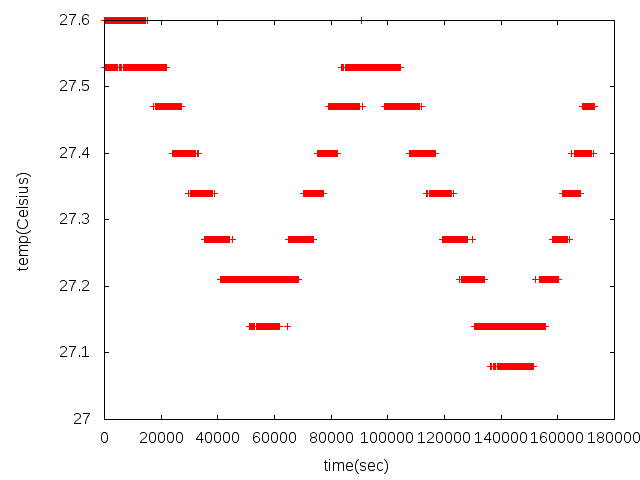 |
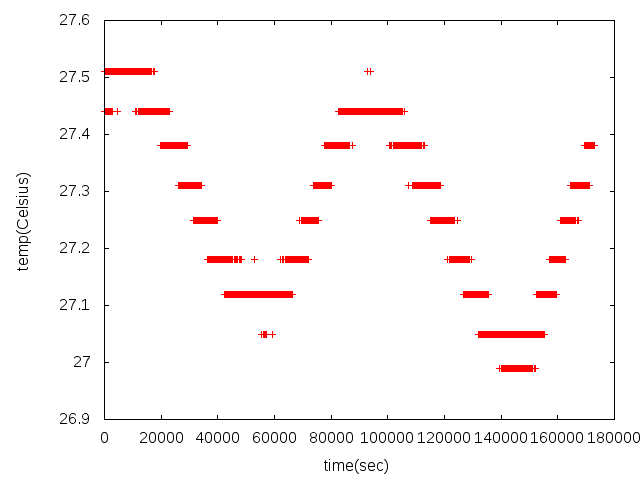 |
| 制御ボックス(内部) の時間変化 |
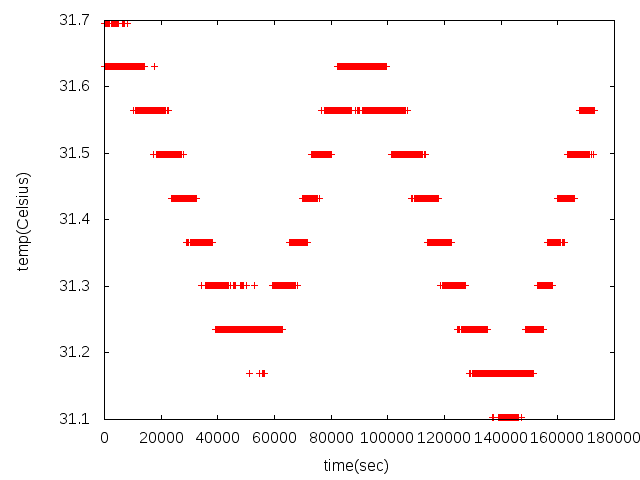 |
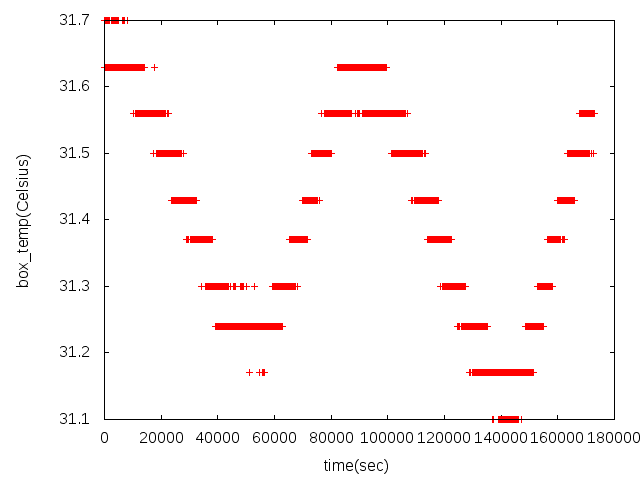 |
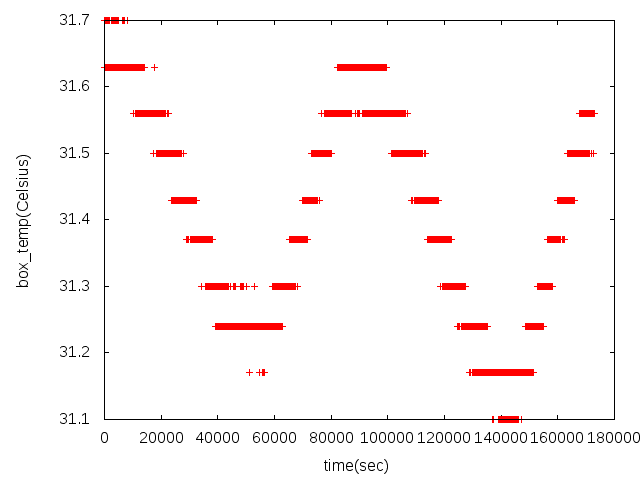 |
| センサー(付近)の時間変化 とセンサーカウント比較 |
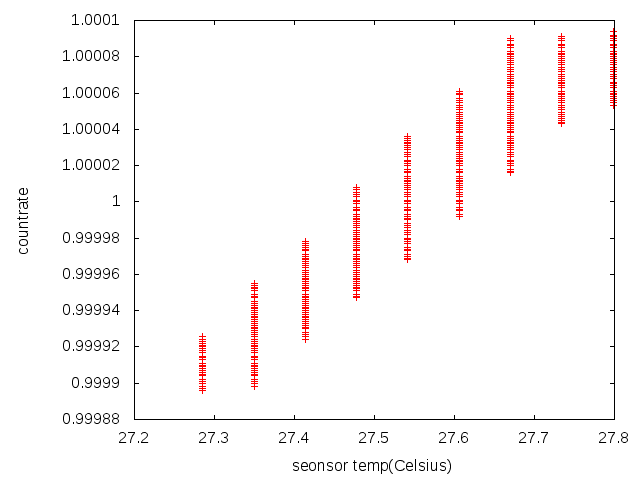 |
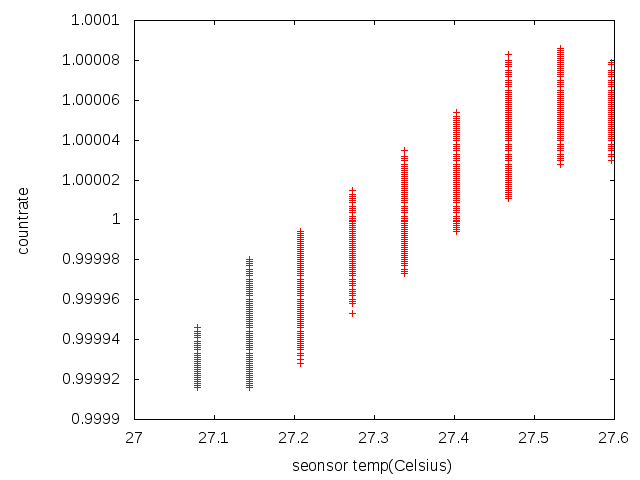 |
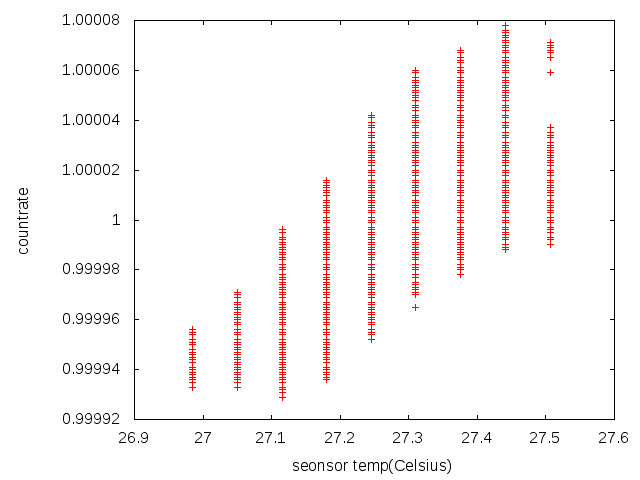 |
| 制御ボックス(内部)の時間変化 とセンサーカウント比較 |
 |
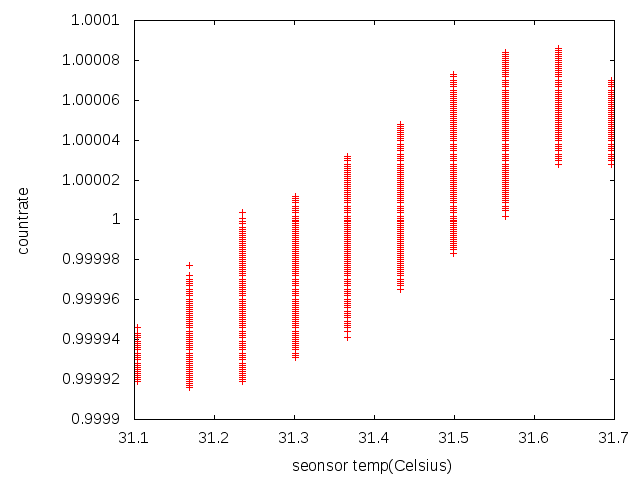 |
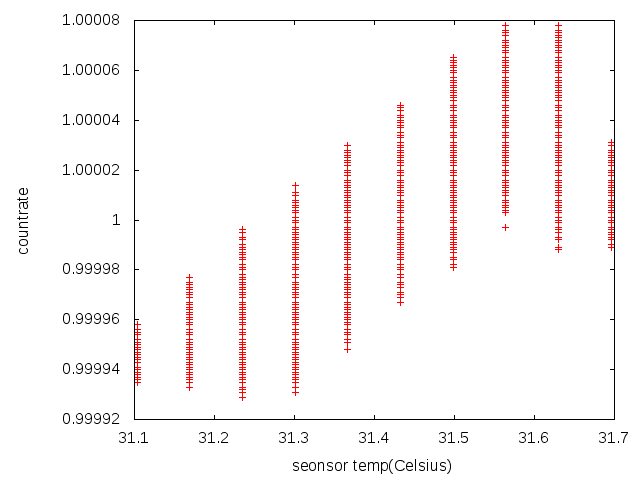 |
カウントレートの基準はそれぞれ
in1 76790
in2 80933
in3 73462
です。
2
・out1,out2,out3(外周セグメントのアクチュエータに取り付けたセンサー)の結果
・制御ボックス内部に温度計を取り付け、その温度変化とカウントレートを比較をしました。
・センサーにも温度計をとりつけましたが配線はしていないのでデータはありません。
| センサー位置 | out1 | out2 | out3 |
| センサーカウント の時間変化 |
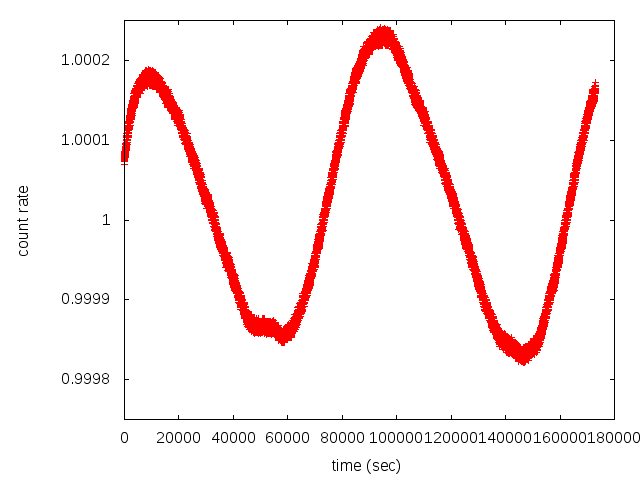 |
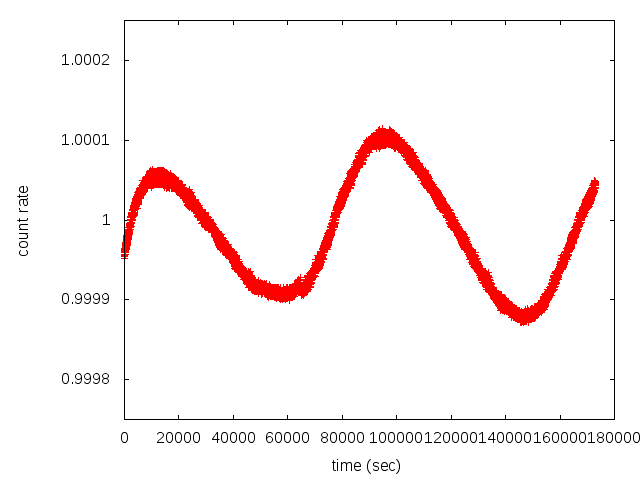 |
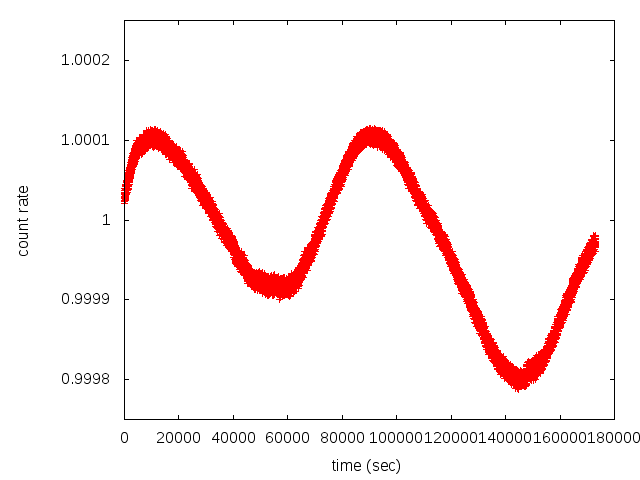 |
| 制御ボックス(内部) の時間変化 |
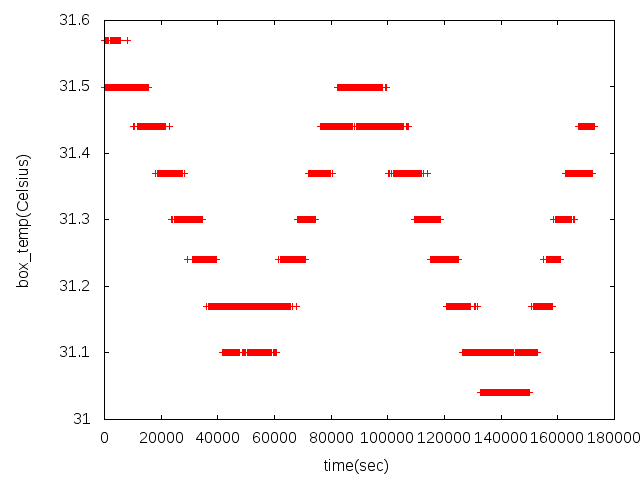 |
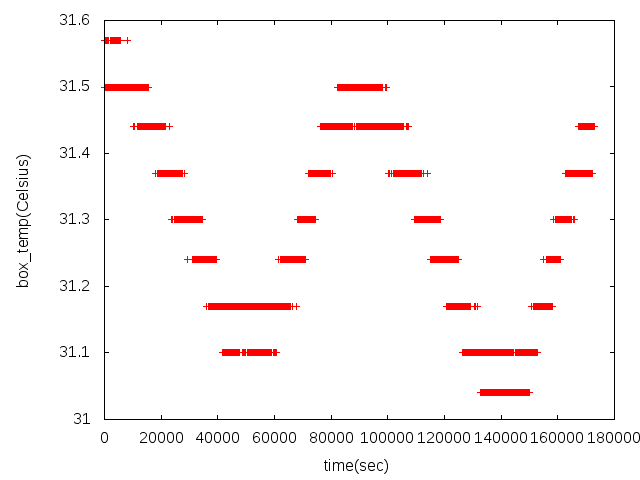 |
 |
| 制御ボックス(内部)の時間変化 とセンサーカウント比較 |
 |
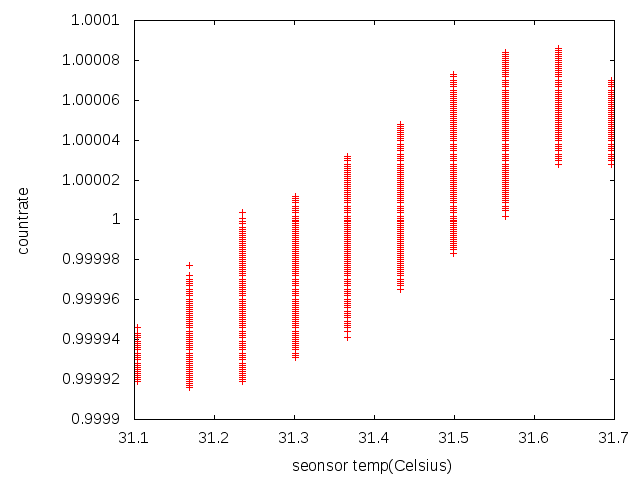 |
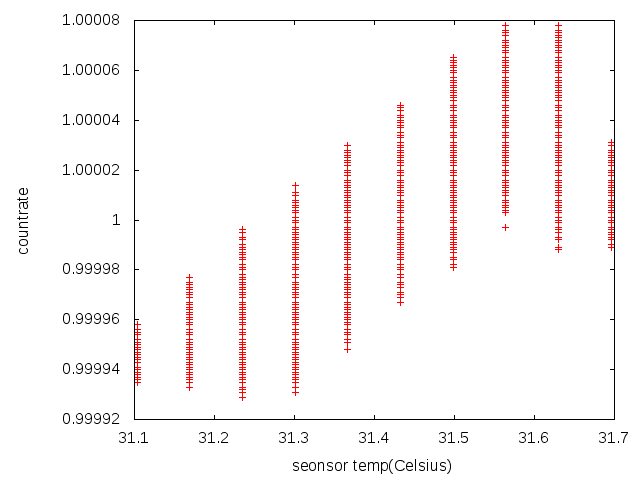 |
カウントレートの基準はそれぞれ
out1 77977
out2 77355
out3 79145
です。
3
・edge1,edge2(内周と外周の間に取り付けたセンサー)の結果
・制御ボックス内部に温度計を取り付け、その温度変化とカウントレートを比較をしました。
・センサーにも温度計をとりつけましたが配線はしていないのでデータはありません。
| センサー位置 | edge1 | edge2 |
| センサーカウント の時間変化 |
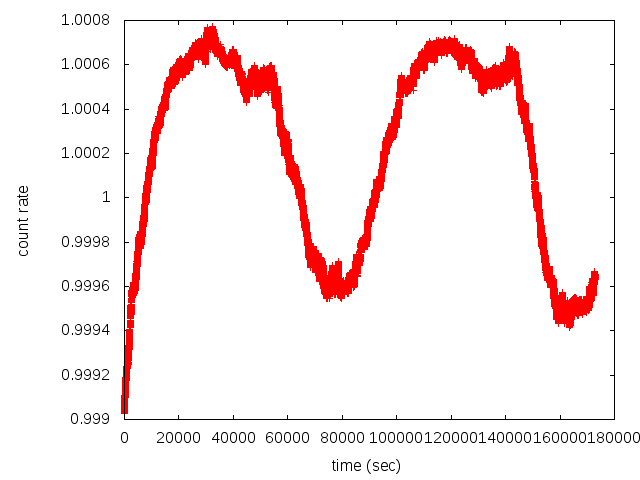 |
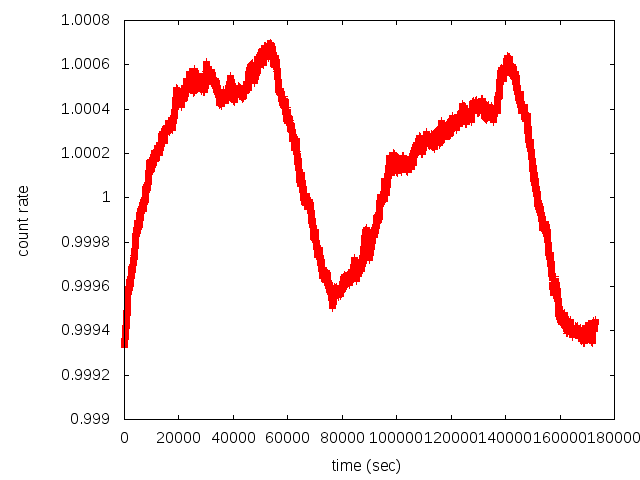 |
| 制御ボックス(内部) の時間変化 |
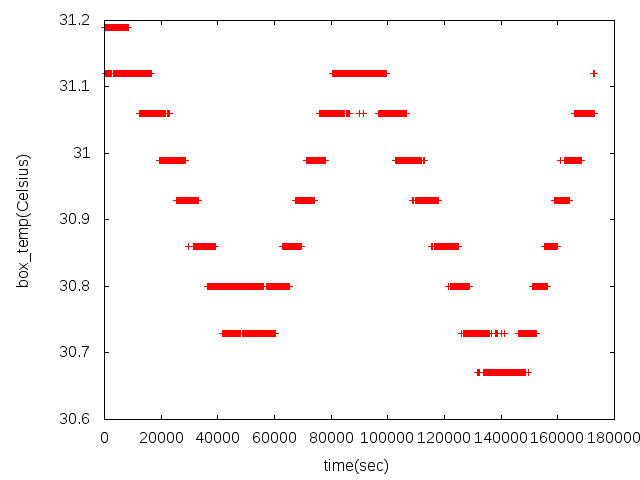 |
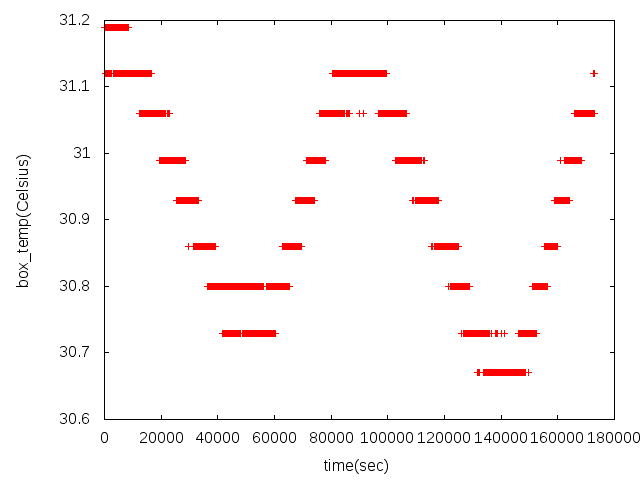 |
| 制御ボックス(内部)の時間変化 とセンサーカウント比較 |
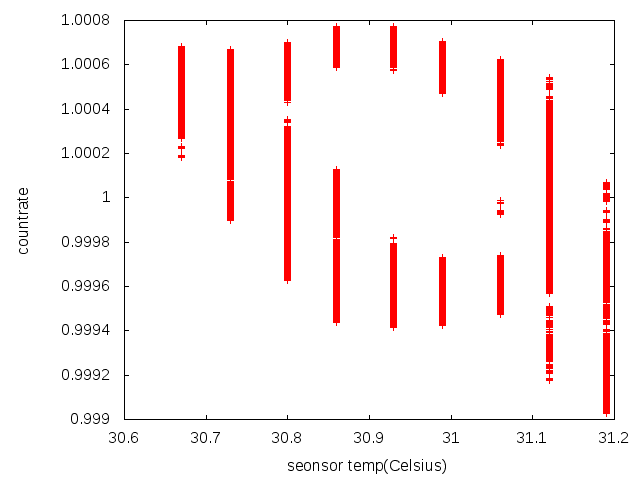 |
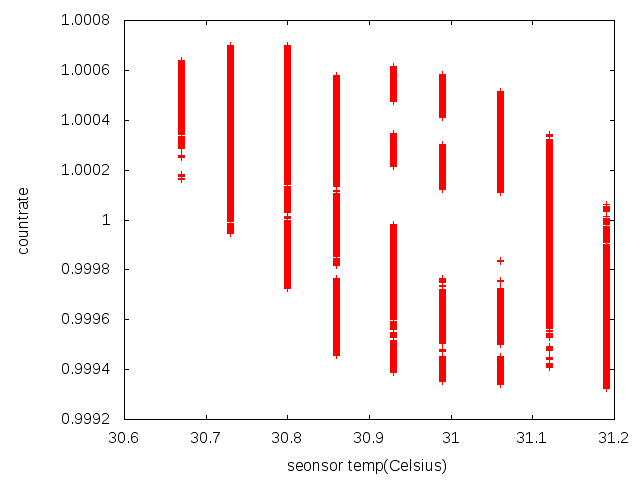 |
カウントレートの基準はそれぞれ
edge1 96980
edge2 85080
です。
4
・glass(センサーのヘッドと対向板の間にガラスを挟んで試験)の結果
・センサーヘッドと制御ボックス内部に温度計を取り付け、それぞれの温度変化とカウントレートを比較をしました。
| センサーカウント の時間変化 |
センサー(付近) の時間変化 |
制御ボックス(内部) の時間変化 |
センサー(付近)の時間変化 とセンサーカウント比較 |
制御ボックス(内部)の時間変化 とセンサーカウント比較 |
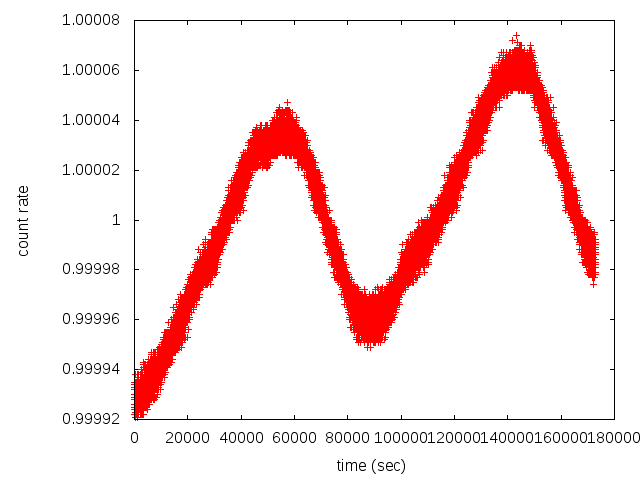 |
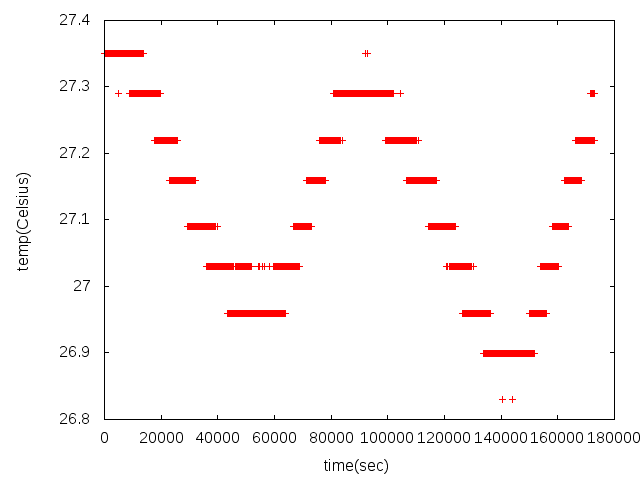 |
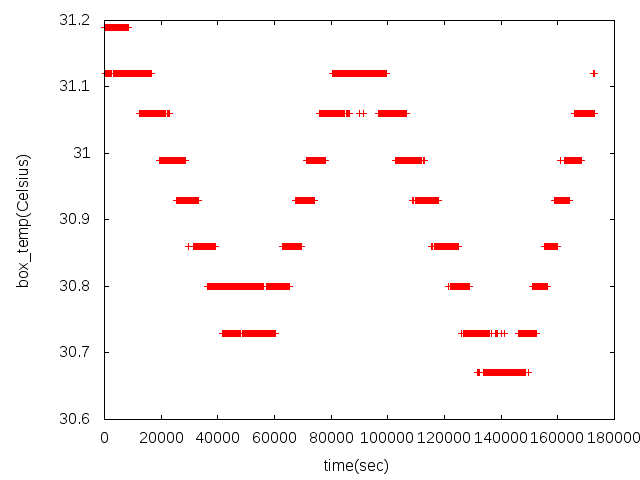 |
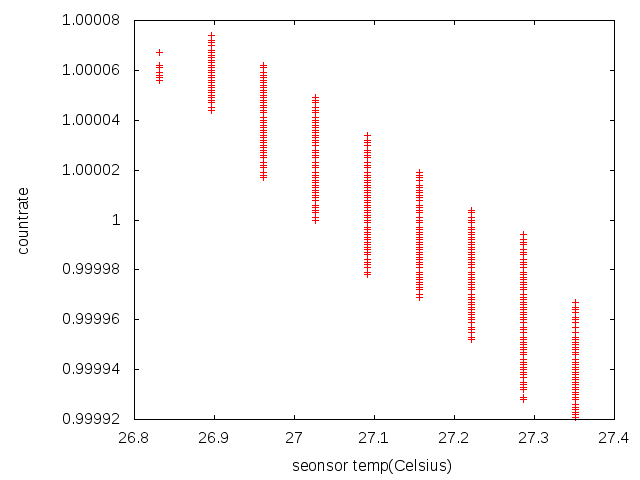 |
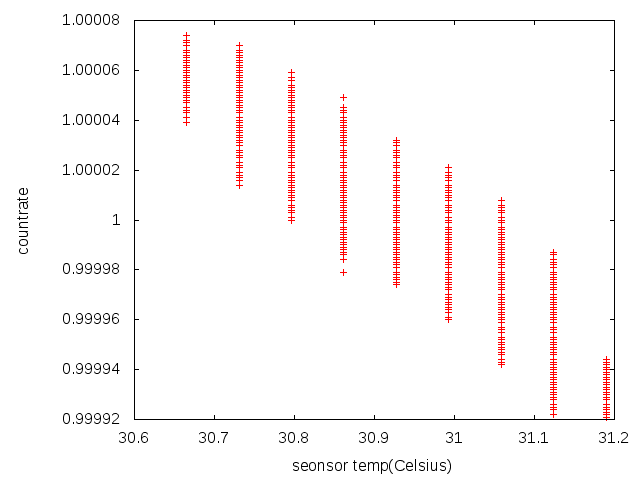 |
カウントレートの基準は
77408
です。
ボックス内部とセンサー付近の温度変動幅は0.5℃程度。温度の時間変化もほぼ同期しているように見えます。
センサー付近よりボックス内部の方が温度が4℃ほど高いようです。温度計を水晶発振子にとりつけたので発熱による影響だと思われます。
一応、それぞれの温度の時間変化を対応させてみました。
| センサー位置 | in1 | in2 | in3 | glass |
| センサー付近 | 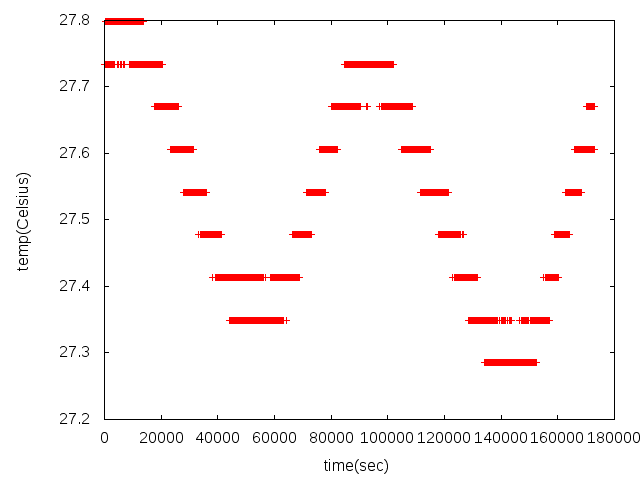 |
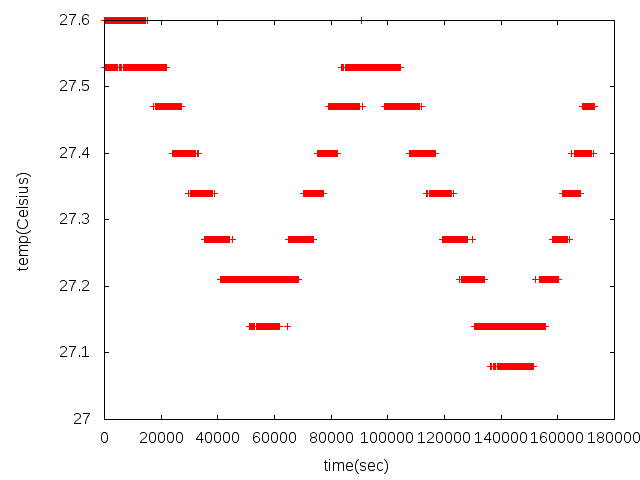 |
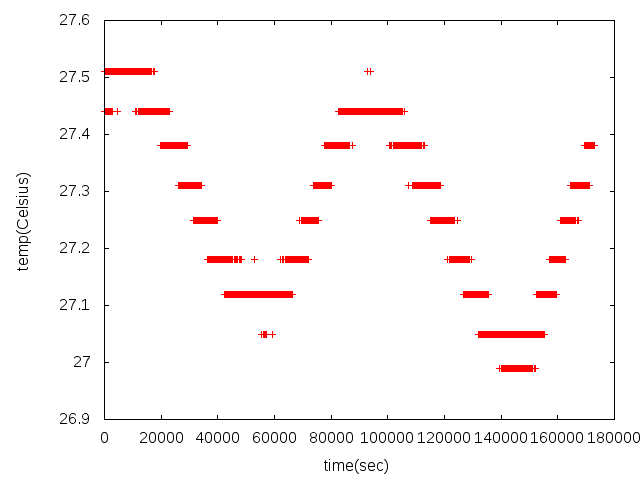 |
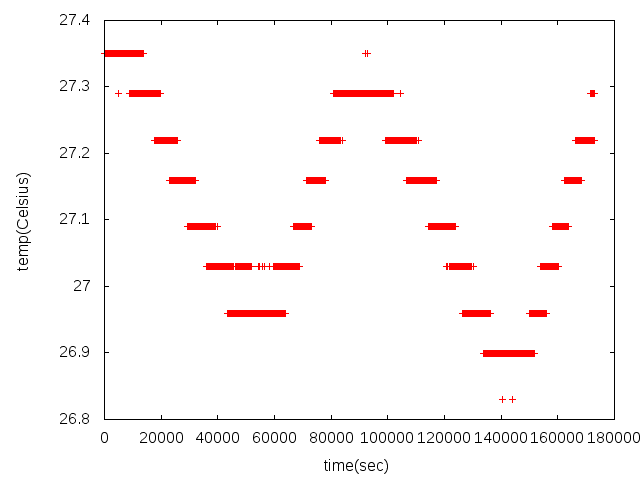 |
| ボックス内部 | 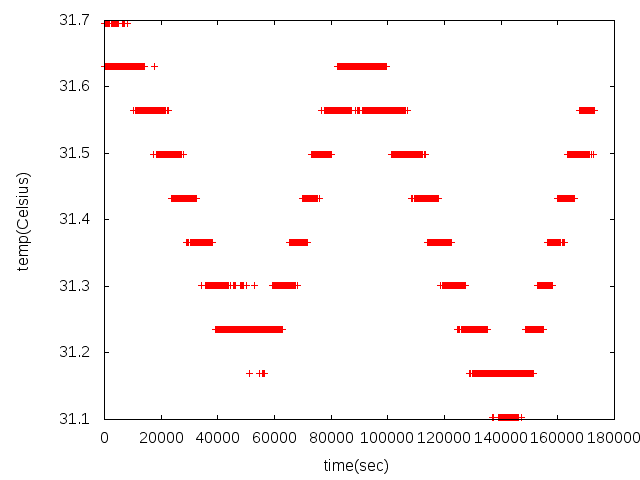 |
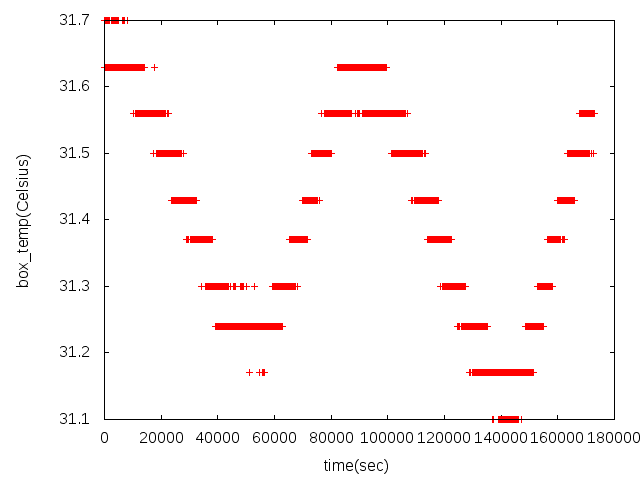 |
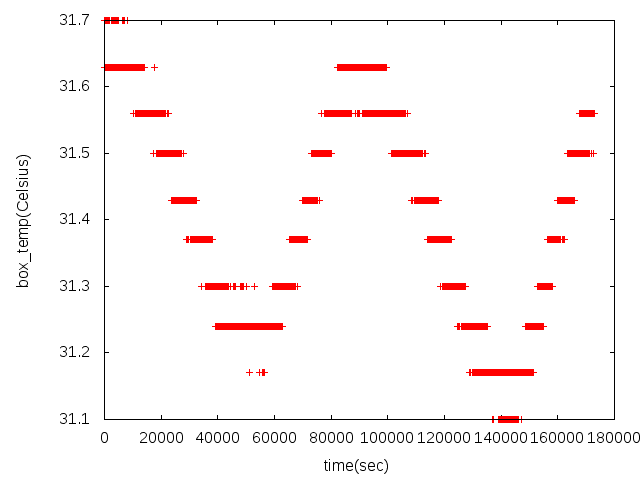 |
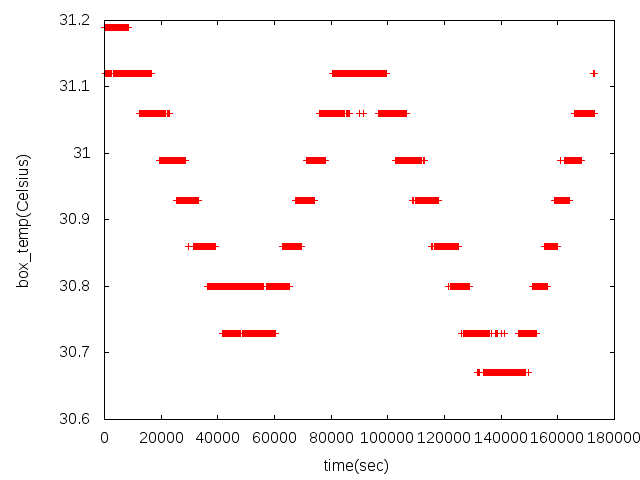 |
| 温度差 | 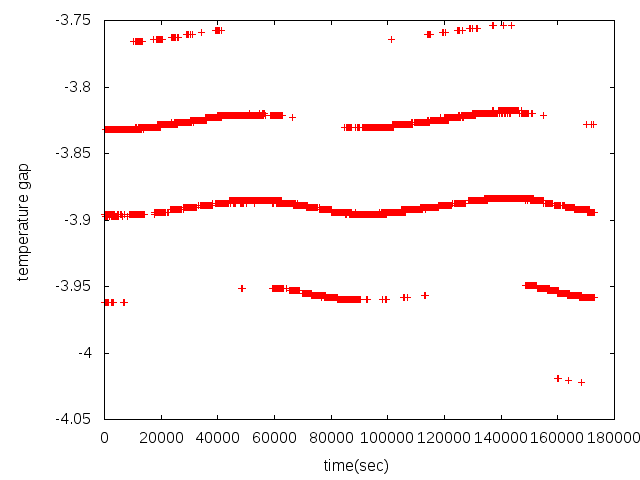 |
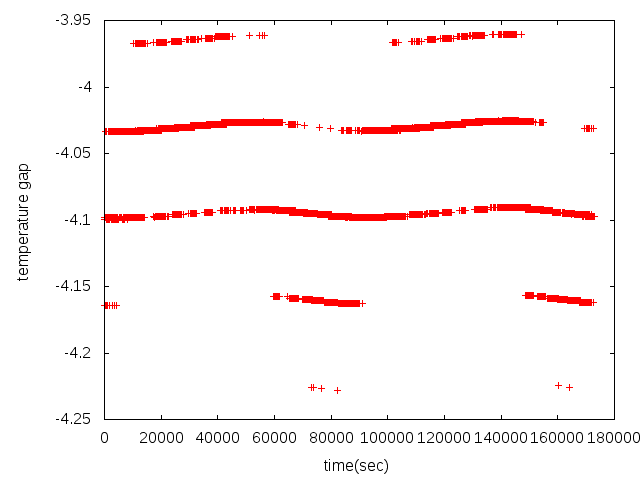 |
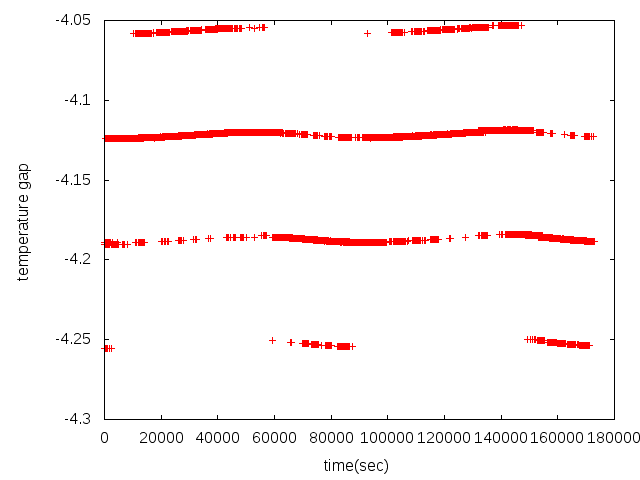 |
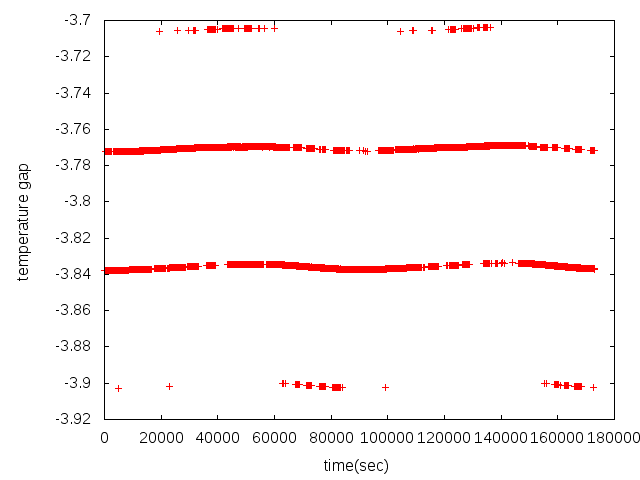 |
*温度差:センサーヘッドに取り付けた温度計の温度からボックス内部の温度計の温度を差し引いたデータです。
5
・センサー温度とボックス内温度でそれぞれ温度特性を温度tの1次関数(f(t) = a * t + b)で近似した場合の傾き(a)パラメータ比較。
・温度に対しカウントではなくカウントレートをプロットしたグラフで近似を行いました。
まずセンサーの温度情報がないものについての結果を載せます。
| センサー位置 | out1 | out2 | out3 | edge1 | edge2 |
| ボックス内温度から求めた パラメータ (×10-4/℃) |
8.32629 | 4.04569 | 5.78755 | -12.8705 | -14.2386 |
センサーにつけた温度計の温度情報がないため、センサー温度については割愛しました。
次にセンサーの温度情報があるものについての結果を載せます。
| センサー位置 | in1 | in2 | in3 | glass |
| センサー温度のから求めたパラメータ(×10-4/℃) | 3.66164 | 2.96159 | 2.38521 | -2.43619 |
| ボックス内温度から求めたパラメータ (×10-4/℃) | 3.60797 | 2.69001 | 2.33044 | -2.18825 |
| 1℃あたりの誤差(count) | 0.412132 | 2.19796 | 0.402351 | -1.91964 |
「1℃あたりの誤差」はセンサー温度で求めたパラメータからボックス内温度で求めたパラメータを差し引いてカウント値に換算したものです。(カウントレートの差ではありません)
・センサーヘッドと対向板の間にガラスを挟んだものに関して
(1)対向板の温度を変化させた場合
(2)制御ボックスの温度を変化させた場合
の試験結果です。
段ボールの中に対象物を入れてドライヤーを入れて加熱することで温度変化させました。
*カウントレートの基準は(1)、(2)とも上記の試験と変えていません。
(1)対向板の温度を変化させた場合
| カウントレート の時間変化 |
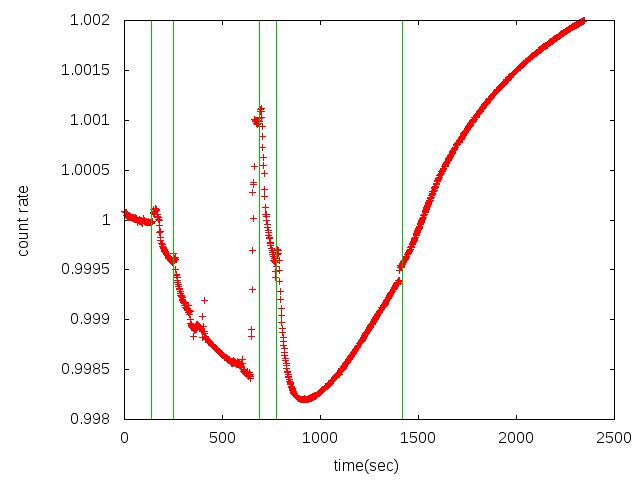 |
| ヘッドの温度計 の時間変化 |
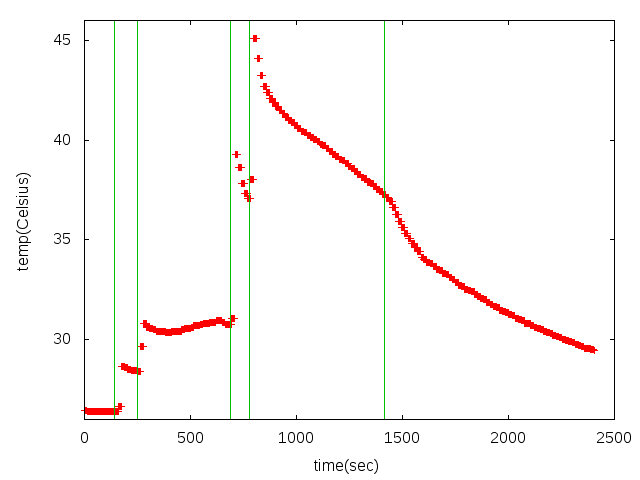 |
| ボックス内温度計 の時間変化 |
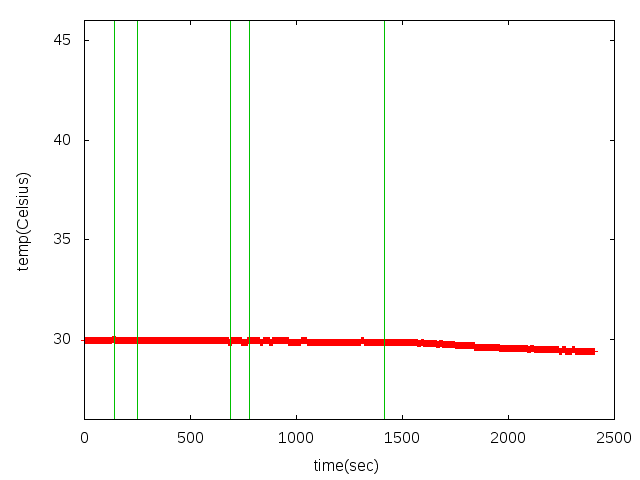 |
実験状況(グラフ中の緑色の線)
時間(秒)
140 ドライヤON 1回目
248 ドライヤON 2回目
(この間、箱を作り替え空気が循環するように改良。試験仕切り直し)
690 ドライヤON 1回目
776 ドライヤON 2回目
1416 箱open
(2)制御ボックスの温度を変化させた場合
| カウントレート の時間変化 |
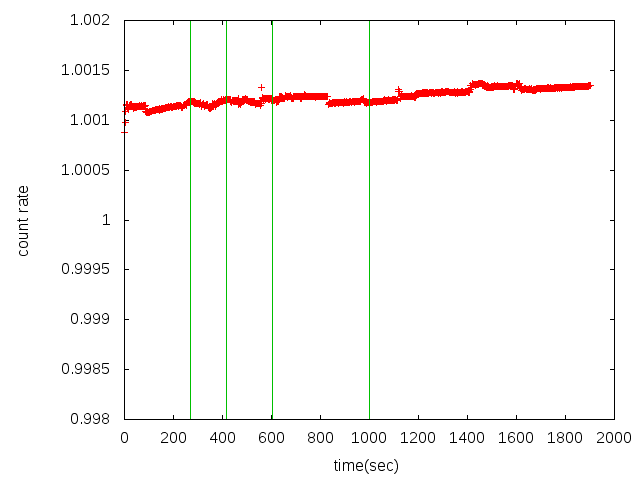 |
| ヘッドの温度計 の時間変化 |
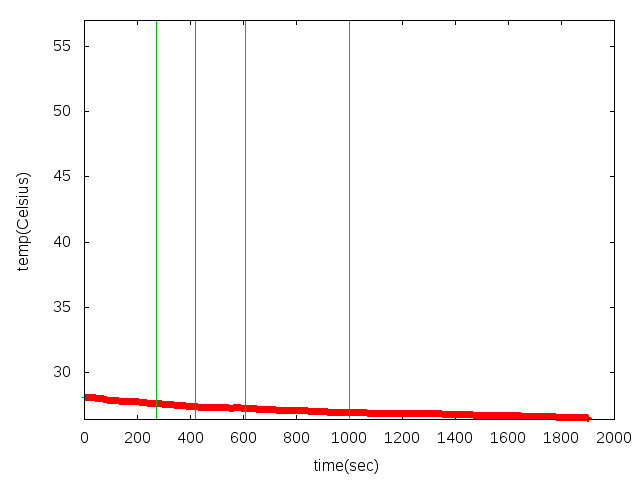 |
| ボックス内温度計 の時間変化 |
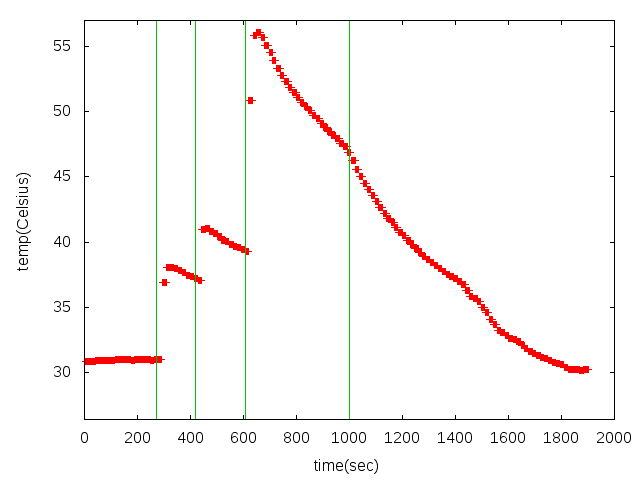 |
実験状況(グラフ中の緑色の線)
時間(秒)
270 ドライヤON 1回目
418 ドライヤON 2回目
606 ドライヤON 3回目
1000 箱open
実験順序が(1)→(2)だったためか、センサーの放熱が終わっていなかったのかもしれません。実験を通して断続的に下がり続けていました。温度特性を求めたグラフを下に載せましたが、ボックスよりセンサーの温度によい相関があるように見えました。
センサー温度の影響を排しきれていないようですが、ボックスの温度はセンサーの温度ほど影響を与えることはなさそうです。
・追記
温度計の温度がセンサー&水晶発振子の温度と同期していない可能性もありますが、それぞれについて温度特性を求めてみました。
| (1)対向板の温度を変化させた場合 | (2)制御ボックスの温度を変化させた場合 | |
| センサー温度から 求めた温度特性 |
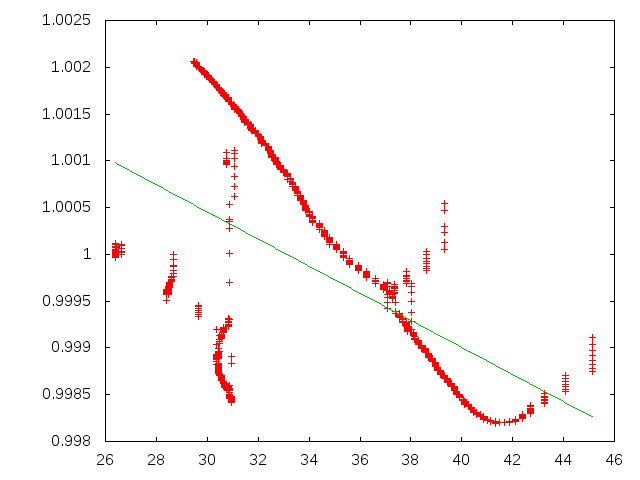 |
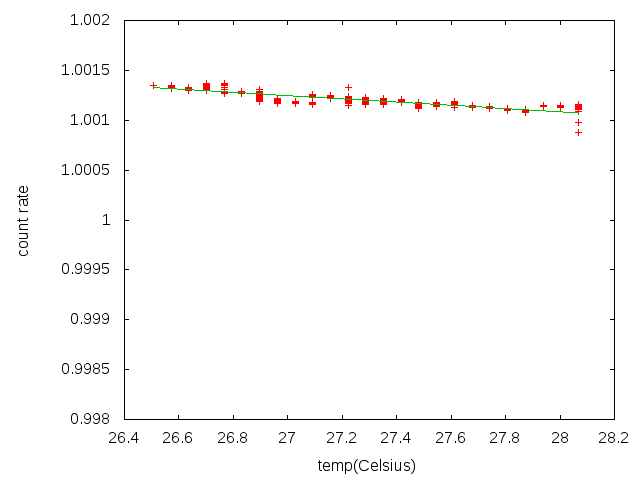 |
| ボックス温度から 求めた温度特性 |
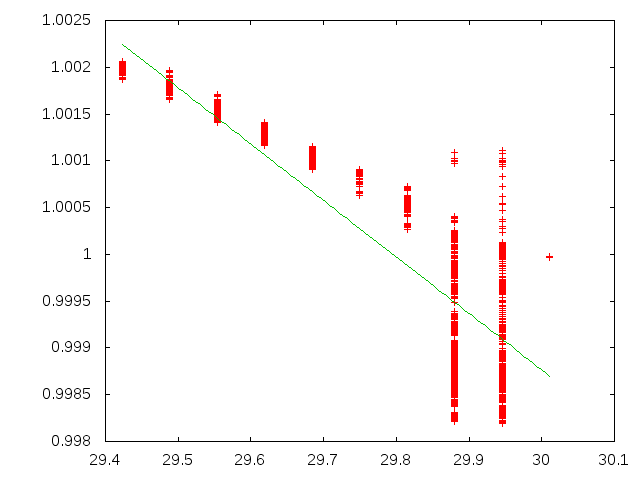 |
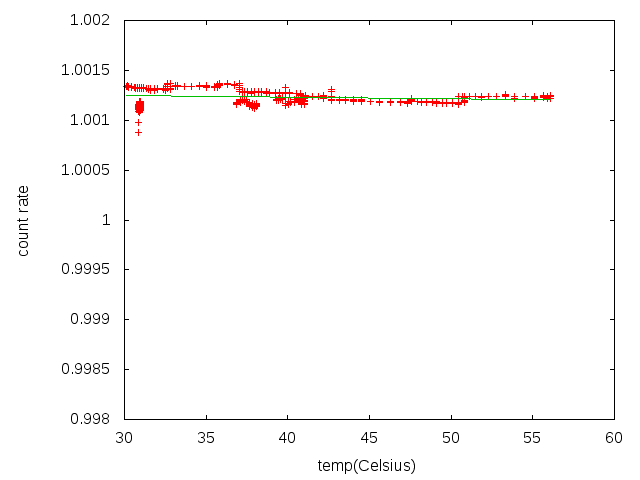 |
温度範囲を合わせて重ね書きするとこうなります。
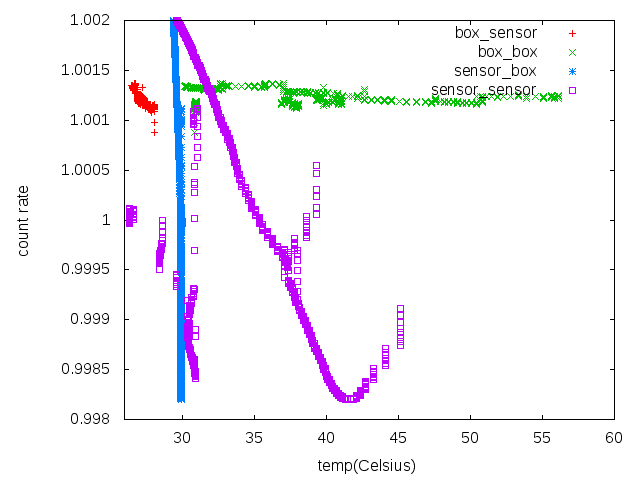
青:センサーを温度変化させた場合でボックス温度から求めた温度特性
紫:センサーを温度変化させた場合でセンサー温度から求めた温度特性
緑:ボックスを温度変化させた場合でボックス温度から求めた温度特性
赤:ボックスを温度変化させた場合でセンサー温度から求めた温度特性
(1)に関して温度がゆっくり変化している部分(1500s~)のみを取り出しフィットした結果(3)も載せておきます。
センサー温度で近似した場合
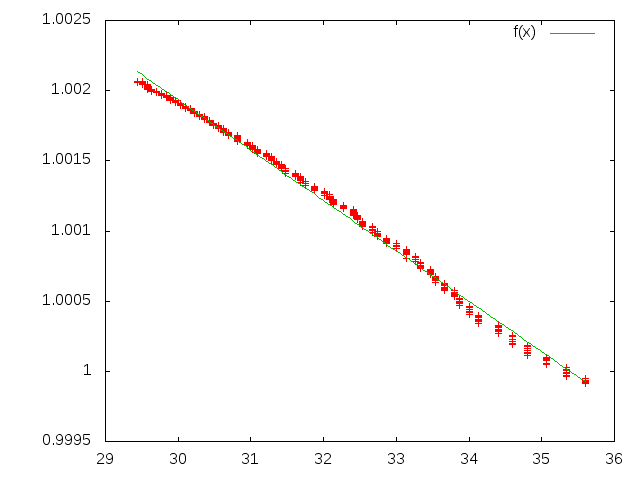
ボックス温度で近似した場合
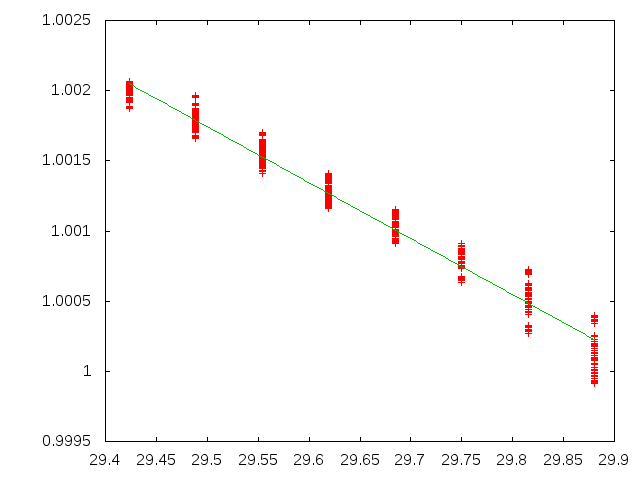
それぞれの温度特性パラメータ
| 実験内容 | 旧データ | (1) | (2) | (3) |
| センサー温度のから求めたパラメータ(×10-4/℃) | -2.43619 | -1.44893 | -1.62106 | -3.58779 |
| ボックス内温度から求めたパラメータ (×10-4/℃) | -2.18825 | -60.3138 | -0.0165767 | -39.8988 |
*パラメータは温度の一次関数で近似した場合の一次の係数です。(上記のものと同じ)
温度特性がこれまでの試験と一致しなかった原因は
・温度とセンサーカウントが1対1対応していない。(これまでの試験結果から考えにくい)
・温度変化が急すぎた。(温度計が正しく機能しなかった センサー&水晶発振子と温度計の温度が違った)
・(2)の場合、センサーが十分冷えきっていなかった。
などでしょうか。
とりあえず水晶発振子よりも対向板の温度が大きく影響していそうです。