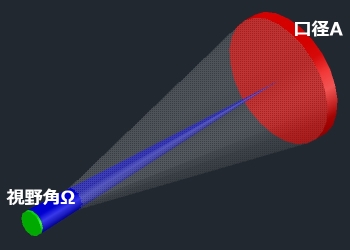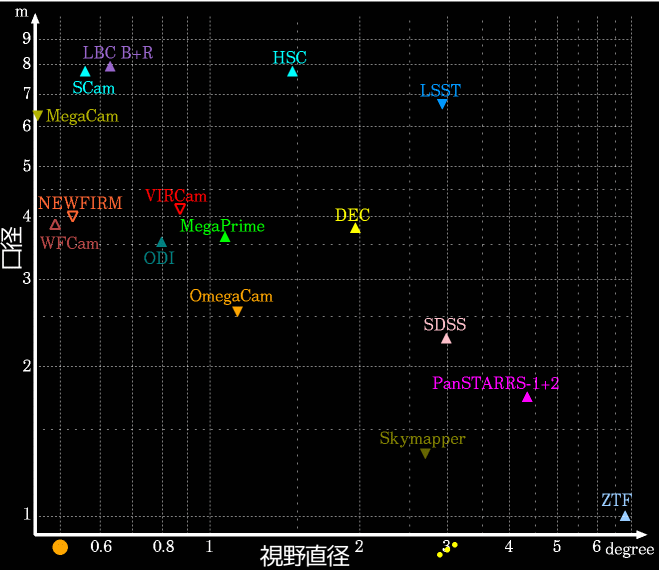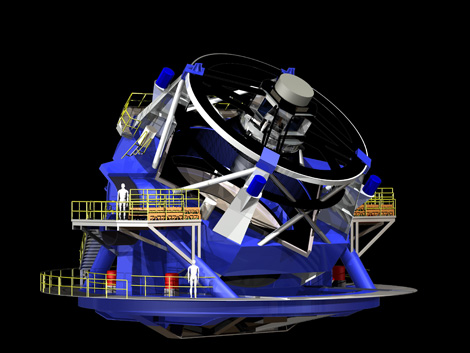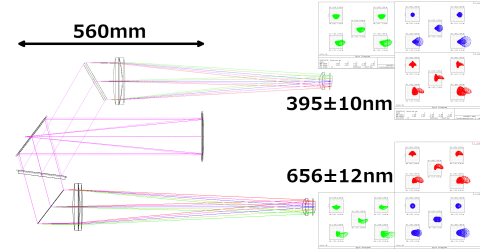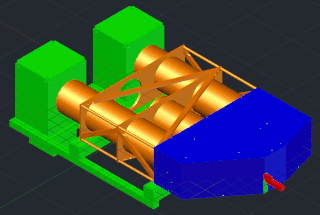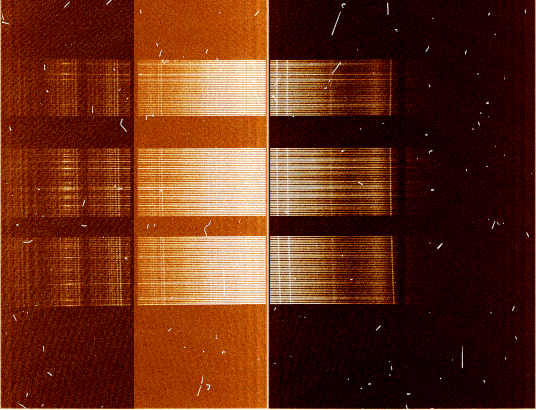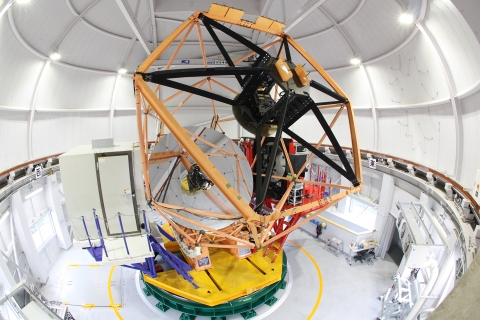| 最近の観測装置の状況 |  |
|---|
京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室
岩室 史英
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
e-mail: iwamuro@kusastro.kyoto-u.ac.jp
TEL: 075-753-3891 / FAX: 075-753-3897
「望遠鏡の話」も参考にして下さい。
天文観測装置の最近のトレンドは究極の広視野・多天体化です。
観測の自動化も進んでおり、アーカイヴデータは爆発的な速さで
増加しています(どの業界でも似たようなものだと思いますが)。
ここでは、広視野カメラとファイバーポジショナーに関して最近の
状況を紹介し、実際の装置開発の流れを小規模装置で見ていきます。
| 口径と視野角 |
|---|
| 広視野カメラ |
|---|
以下、世界の広視野カメラの AΩ の状況です。 |
| 多天体分光 |
|---|
多天体分光を行う場合は、AΩ をできるだけ大きくした上で光ファイバーで |
| Magnet Button タイプ | Echidna タイプ | Cobra タイプ |
|---|---|---|
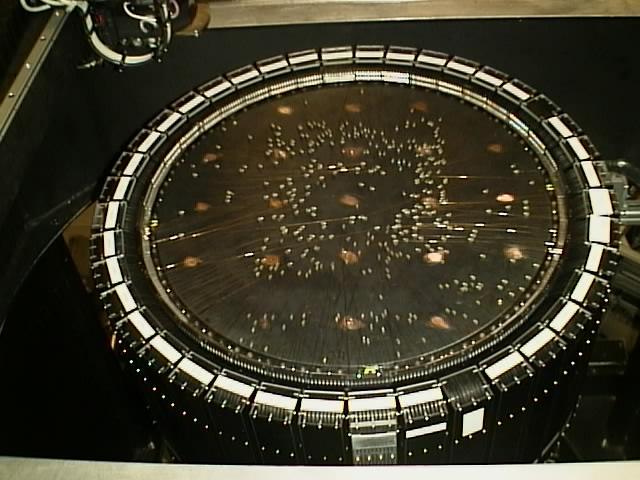 |
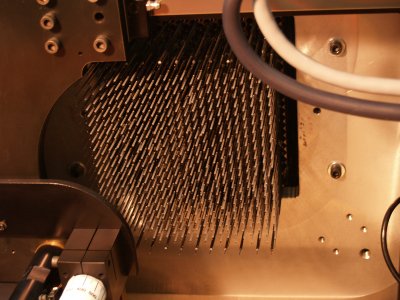 |
 |
| https://aat.anu.edu.au/public/2df-instrument | https://pfs.ipmu.jp/ja/index.html |
WST: fiber 2万本なんて計画も...
| 装置開発の流れ |
|---|