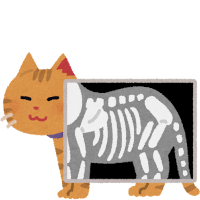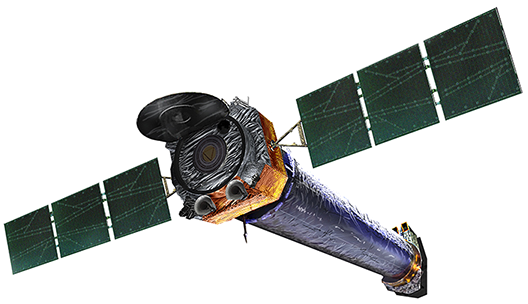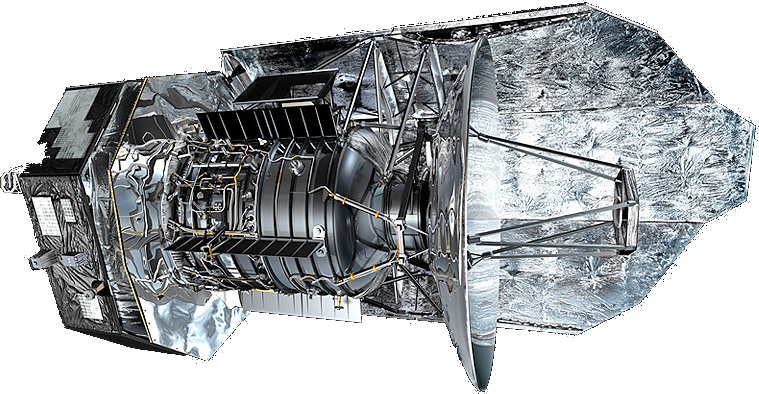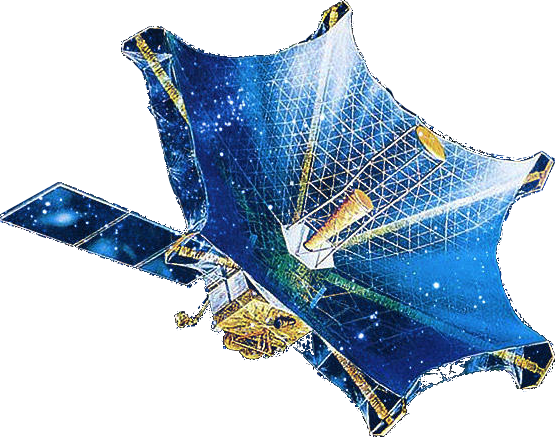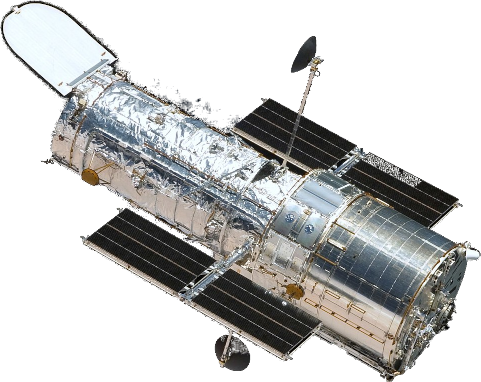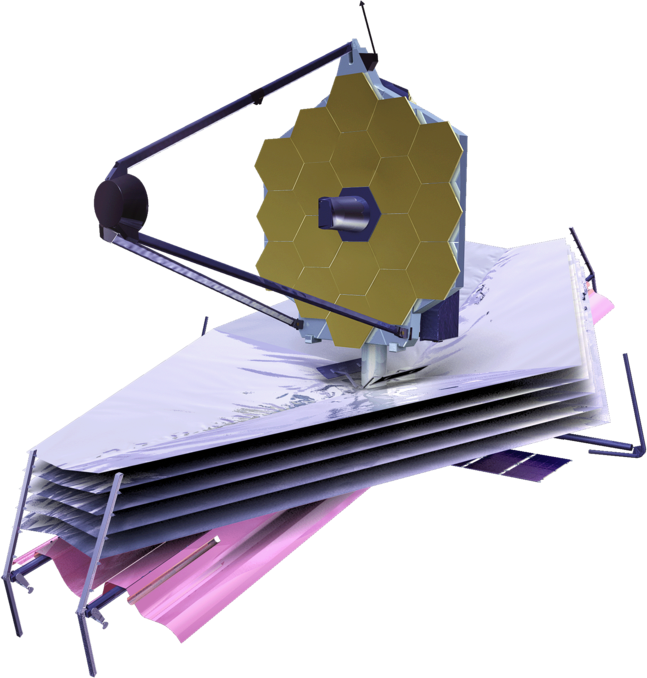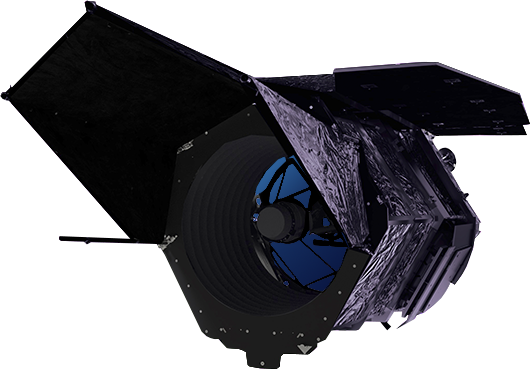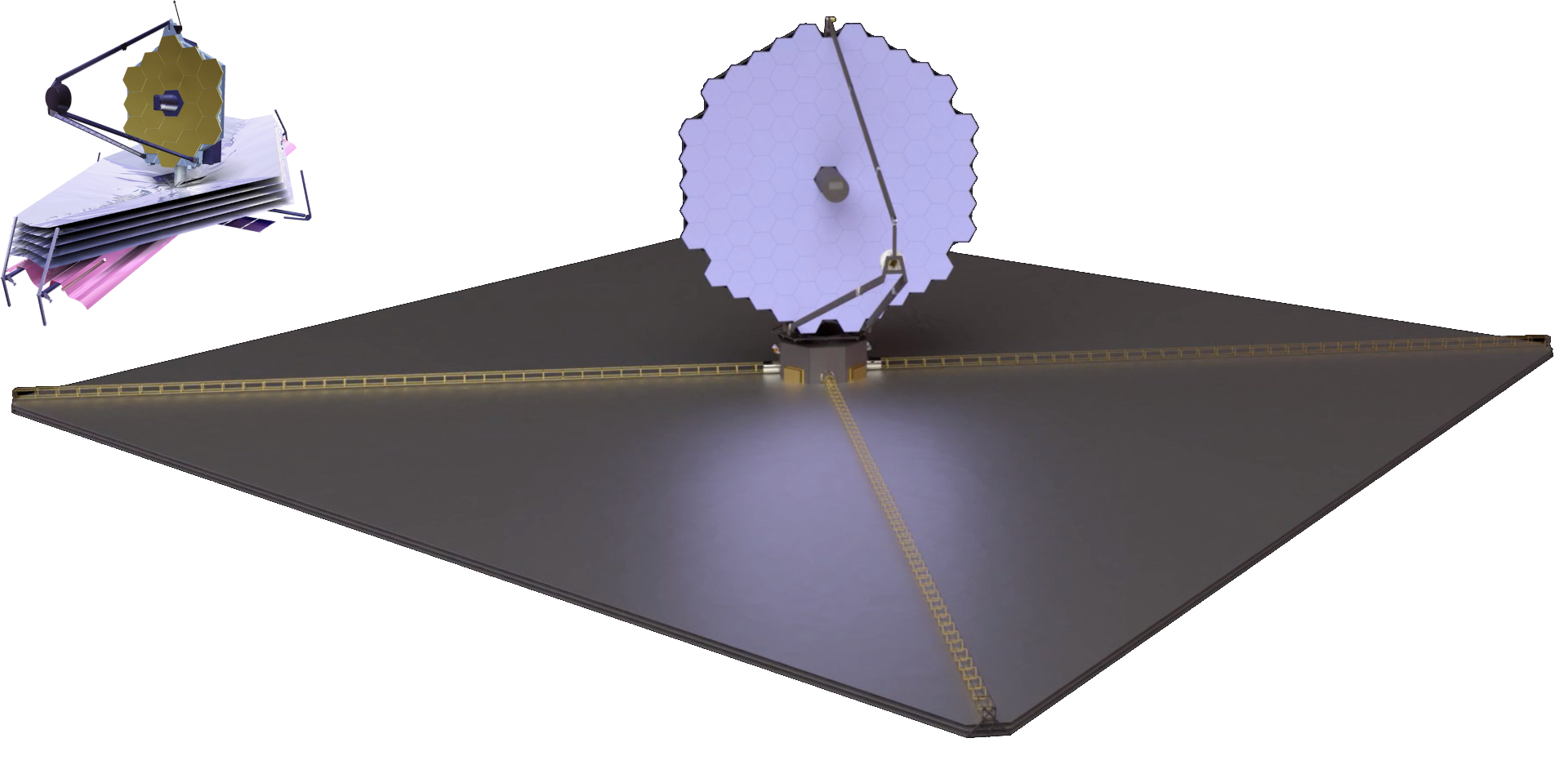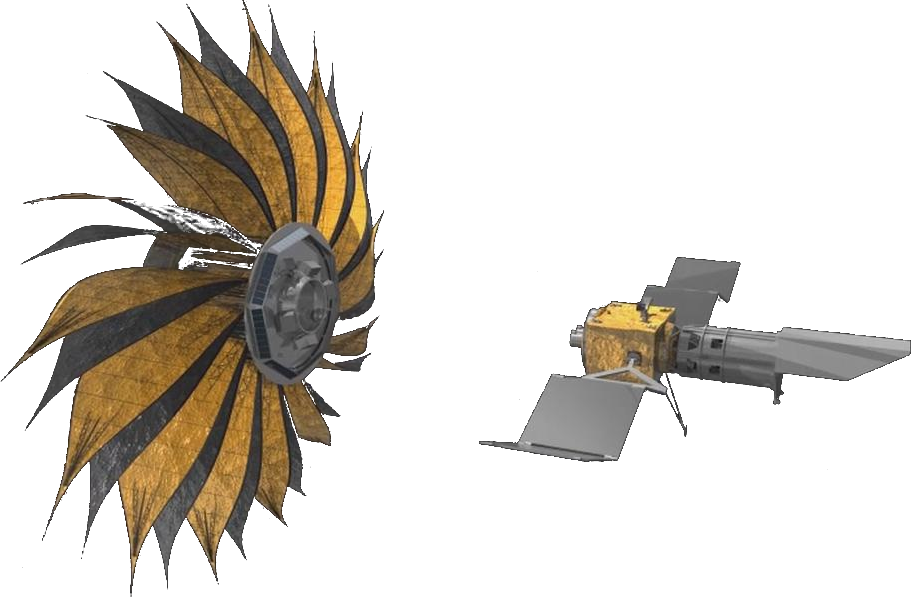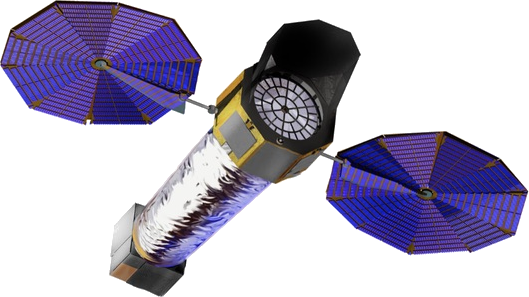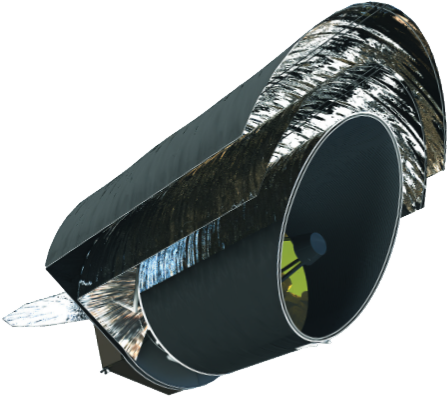| 宇宙望遠鏡いろいろ |  |
|---|
京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室
岩室 史英 (いわむろ ふみひで)
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
e-mail: iwamuro@kusastro.kyoto-u.ac.jp
TEL: 075-753-3891 / FAX: 075-753-3897
光の
| ||||||||||||||
目に見える光を
|
アンドロメダ銀河 (M31)
が見えます。
|
宇宙望遠鏡 って?
宇宙からは色々な光がやってきますが、半分 程度 の光しか地上 まで届 きません。
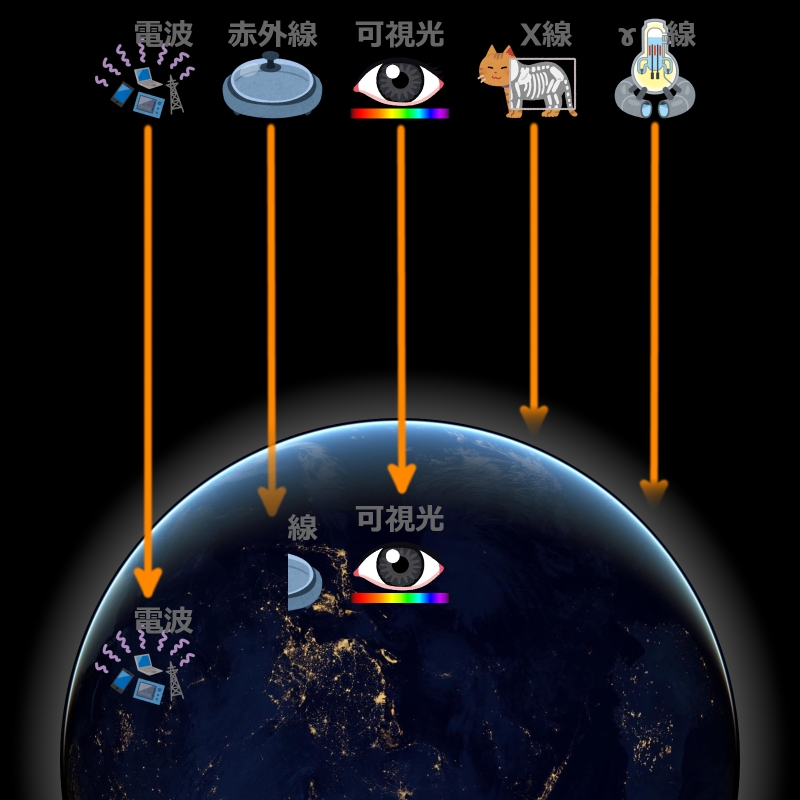
地上にある望遠鏡 は、地上まで届く可視光や電波で宇宙を観測 しています。

他 の光は大気 で吸収されて地上まで届 かないので、宇宙から観測するしかありません。
ここからは主 な宇宙望遠鏡について、その歴史 とともに紹介 していきます。
X線 望遠鏡 
宇宙望遠鏡の多 くはX線で観測を行うものです。
1970年以降 、40台近くの衛星 が打ち上げられ、現在 も数台 が稼働 しています。
チャンドラX線天文台 |
1999年にスペースシャトルで |
|---|---|
X線は | |
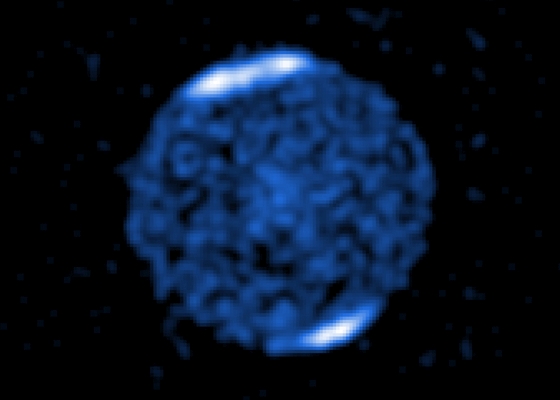
|
チャンドラで見た |
γ線 望遠鏡 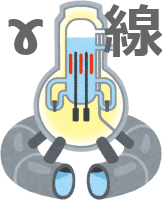
宇宙からの γ線はアメリカの核実験 観測衛星によって 1967年に発見 されました。
その謎 の解明 のため 12台の衛星が打ち上げられ、現在も数台が稼働しています。
フェルミガンマ線宇宙望遠鏡 |
2008年にデルタIIロケットで |
|---|---|
γ線と | |
宇宙からのγ線 | |
|
γ線の望遠鏡は光を集める鏡がないので、望遠鏡というよりは放射線 の検出器 です。
宇宙望遠鏡にもいろいろありますね。
赤外線 望遠鏡 
これまでの赤外線望遠鏡は装置の温度を低 く保 つための冷却液 を積 んでおり、それを
全 て使い切って蒸発 してしまうと、観測をすることができなくなりました。そのため、
衛星の寿命 は5年程度 であることがほとんどで、望遠鏡としては短命 です。
ハーシェル宇宙天文台 |
2009年にアリアン5ロケットで |
|---|---|
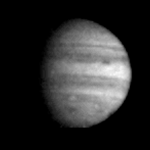
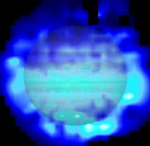
|
ハーシェルで見た木星です。木星を |
赤外線の望遠鏡は寿命 が短 いため、ほとんどが1トン以下の小型 衛星です。
大きい衛星ほど冷却 装置 が重くなることも難 しい所です。
電波 望遠鏡 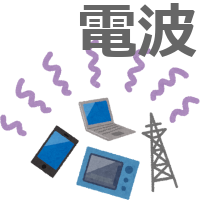
電波は地上からも観測できるので、宇宙に望遠鏡を打ち上げる必要は少ないのですが、
同時 に観測する望遠鏡が離 れているほど細 かいものが見えるという特徴 があるので、
地球 の大きさの何十倍 も離れた所まで望遠鏡を飛 ばすと視力 が格段 に上がります。
電波天文観測衛星「はるか」 |
1997年に日本のM-Vロケットで |
|---|---|

|
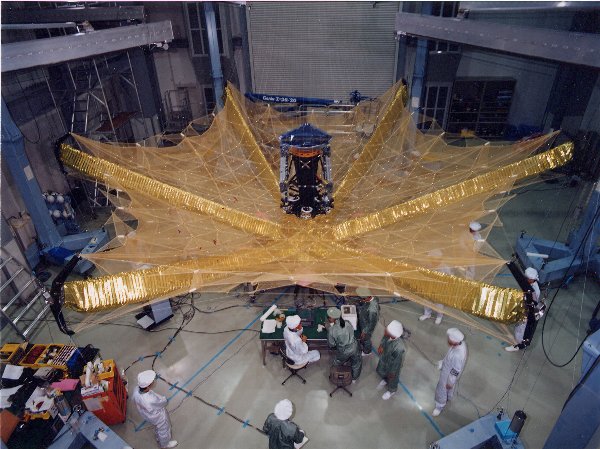
|
はるか は大阪 から東京 の米粒 を見分けられる能力 で9年間 にわたり活躍 しました。
電波の宇宙望遠鏡は非常 に少なく、この他はロシアが打ち上げた1台のみです。
可視光 望遠鏡 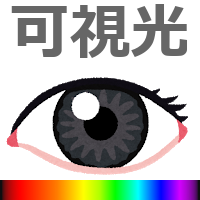
可視光も地上から観測できますが、電波とは違 い大気 で星の像 が乱 されてしまいます。
|
宇宙からの観測では揺 らぎのない像が得られるため、可視光の宇宙望遠鏡のほとんどは
長期 観測で明るい星のほんの少しの変化 (明るさや位置 の変化)を調 べる小型衛星ですが、
ハッブル宇宙望遠鏡だけは別格 です。
ハッブル宇宙望遠鏡 |
1990年にスペースシャトルで |
|---|---|
ハッブルは宇宙 | |
ハッブルで見た |
ハッブルは至 る所が老朽化 し、次世代シャトルでの修理も難 しいものと思われます。
ハッブルの後継機 として2つの宇宙望遠鏡が予定され、1つは観測開始しています。
新しい宇宙望遠鏡 

ハッブルの後継 となる2台の宇宙望遠鏡は、非常 に遠くの宇宙を観測するのに適 した、
可視光から赤外線にかけての光で観測するものです。観測の妨 げとなる太陽 や地球 から
の光を避 け、かつ望遠鏡の温度を下げるため、月よりも4倍遠い所に打ち上げます。
この場所 では太陽と地球がいつも同じ方向に見えているので、1つの日傘 で両方からの
光を遮 ることができます。太陽光発電 のため、地球と月の影 を避けて縦 にも周 ります。
(上の動画 ではわかりませんが、この場所では地球と太陽はほぼ同じ大きさに見えます)
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 |
2021年12月25日にアリアン5で
|
|---|---|
 |
初めの観測で |
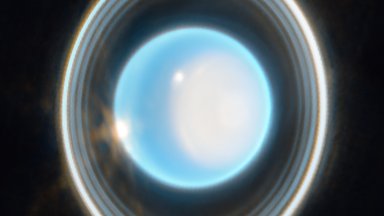 |
ウェッブで見た天王星です。 |
ウェッブとハッブルは一度に見ることの出来る範囲 は同じくらいですが、ウェッブの
方が 数倍 良く見えるようになります。また、ハッブルでは見ることのできなかった
赤外線でも観測できるため、より遠くの宇宙を見ることができます。
もう1つのハッブル
ナンシー・グレース・ローマン |
2027年に打ち上げ予定の |
|---|---|
ウェッブが狭 い範囲を非常 に詳 しく見るのに対 し、ローマンは非常に広い範囲を
ハッブルと同程度 に詳しく見ることができます。
2023年7月1日にローマンの半分サイズの |
もっと
この先の宇宙望遠鏡は、2040年台の稼働 を目標 として以下 の4つが検討 されました。
ルーバール探査機 |
鏡の口径は 15m もあります。 |
|---|---|
ハベックス天文台 |
直径 72m の第2衛星を地球
|
リンクスX線天文台 |
オリジンス宇宙望遠鏡 |
チャンドラの50倍の感度 | 極限まで冷やして感度100倍 |