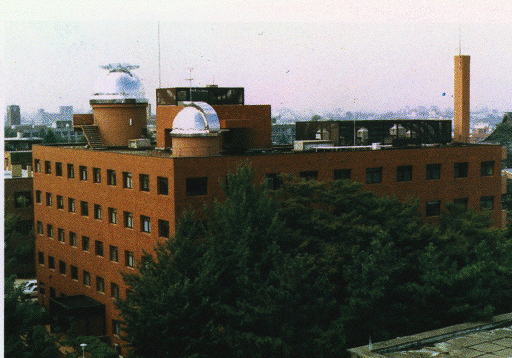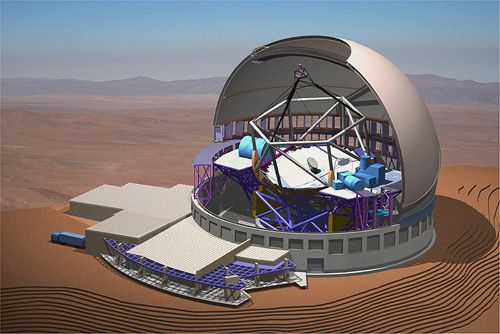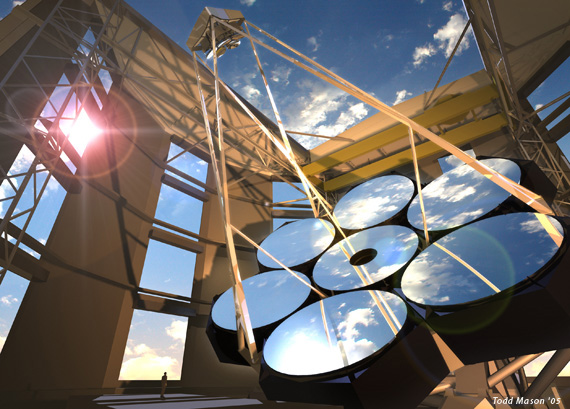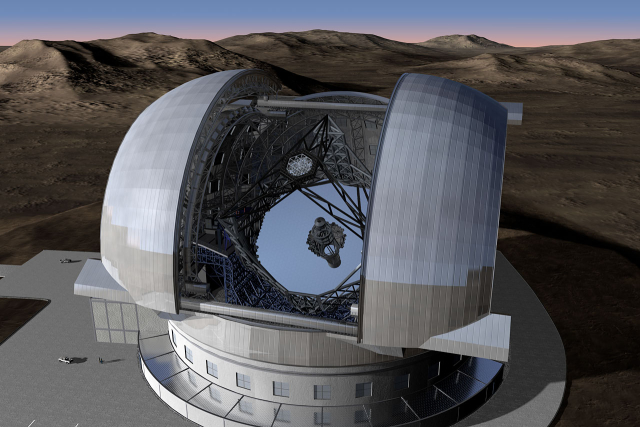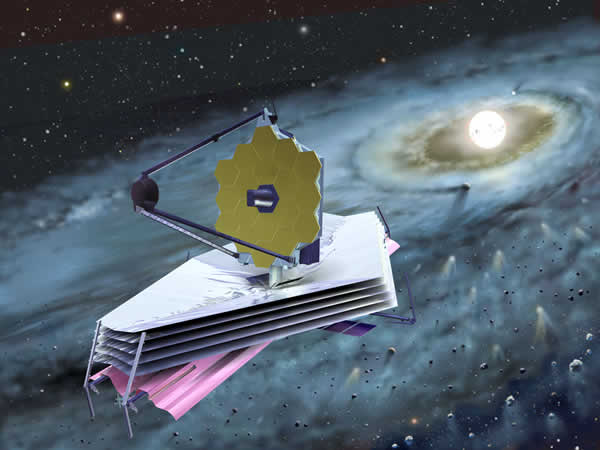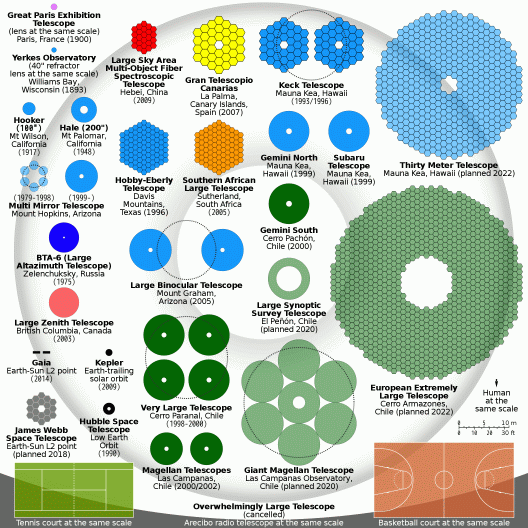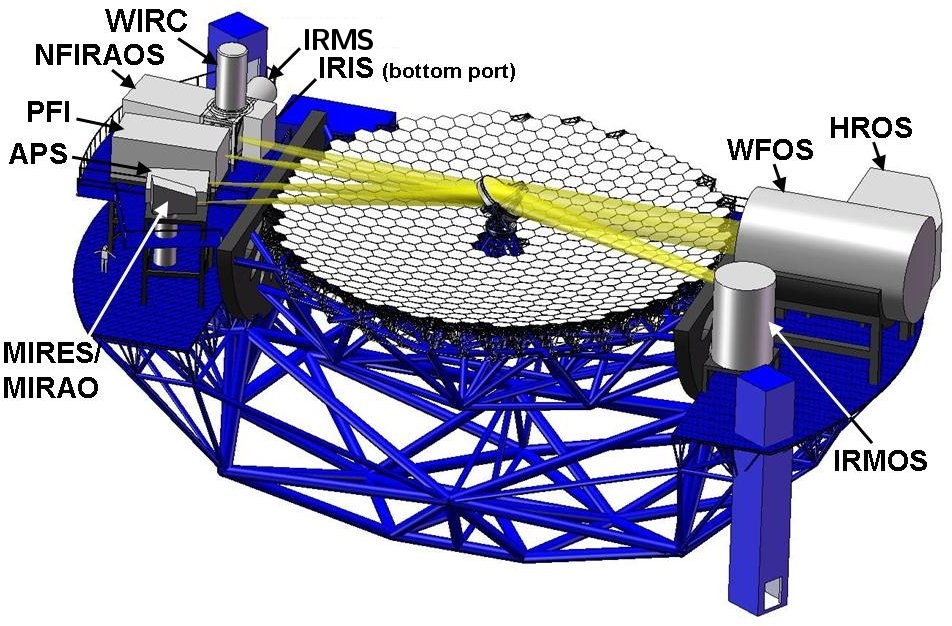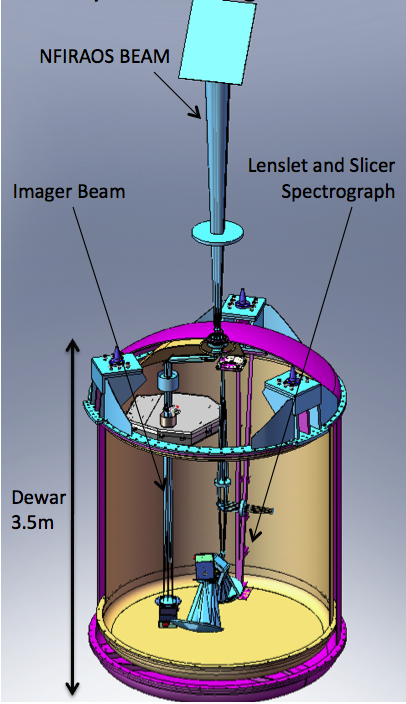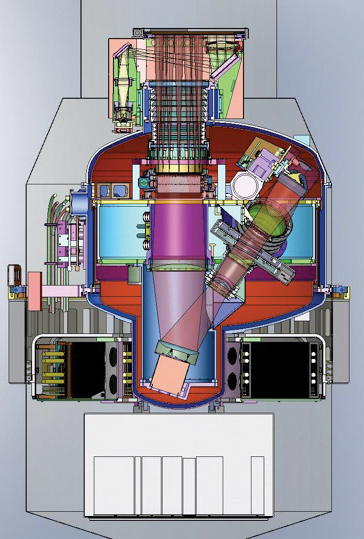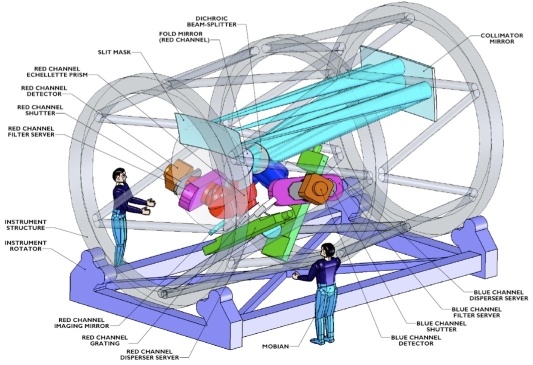光赤外観測天文学の最前線 |
|---|
京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室
岩室 史英
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
e-mail: iwamuro@kusastro.kyoto-u.ac.jp
TEL: 075-753-3891 / FAX: 075-753-3897
近代望遠鏡の歴史 |
|---|
20世紀以降、近代望遠鏡の口径は40年で2倍の割合で巨大化しました。 |
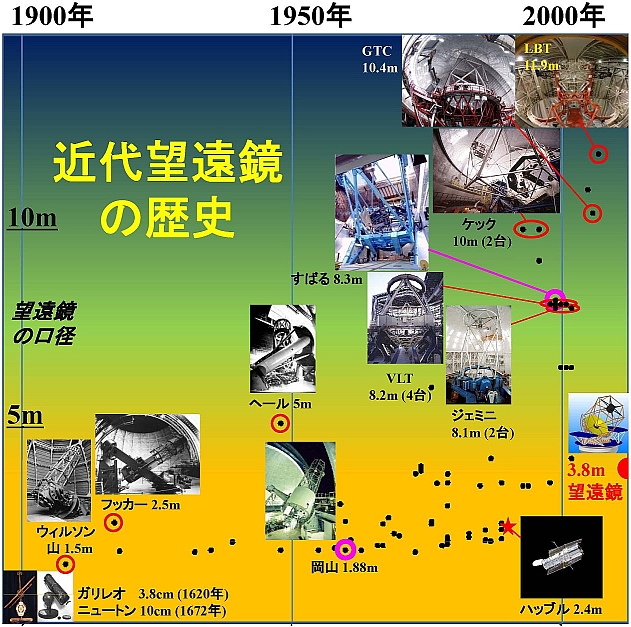
大雑把には...
1900年:2m
1940年:4m
1980年:8m
という感じで、このままの割合が続くとすると、
2020年:16m
2060年:32m
なのですが、現在進められている TMT 計画は 2021年に30m望遠鏡を |
撮像装置の進化 |
|---|
撮像装置の画素数は約3年で2倍の割合で巨大化し、現在は1Gpix を越える |
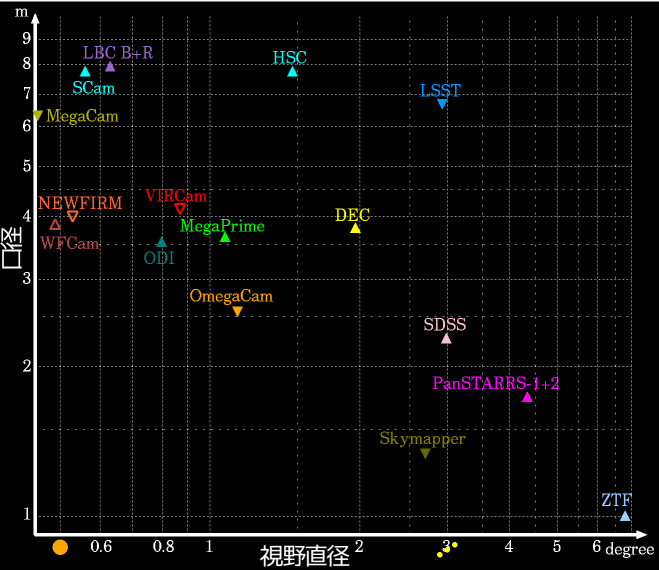
上図で、三角の向きは北半球と南半球の違いを、中空シンボルは近赤外線 |
Subaru/HSC
すばる望遠鏡の可視超広視野カメラ。5枚の補正レンズ(最大直径82cm)と 2k x 4k の |

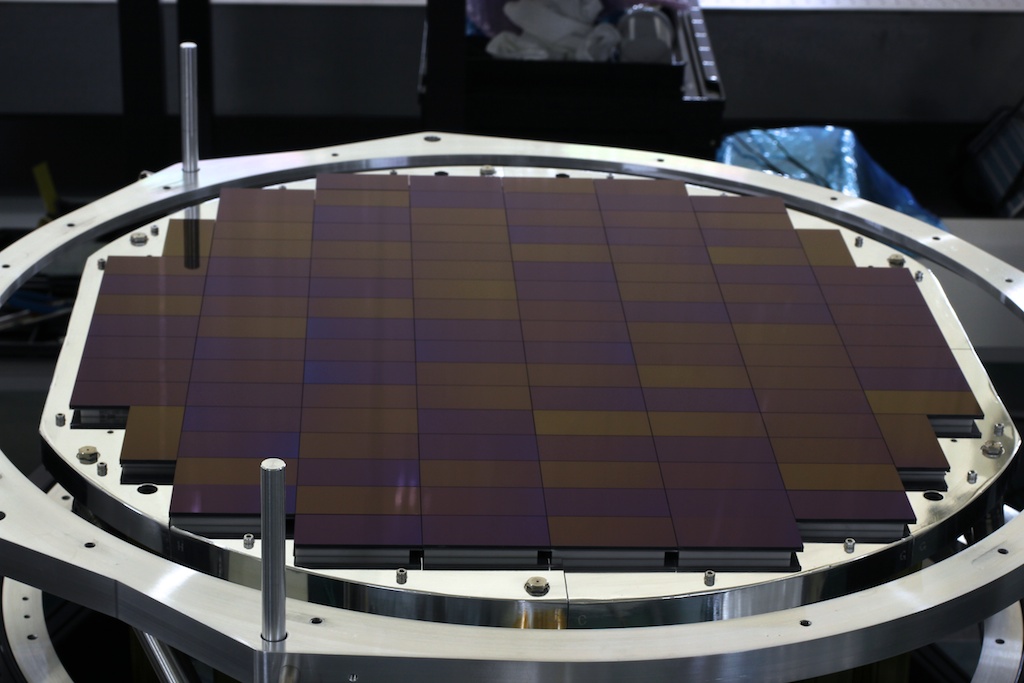
LSST
口径8.4mの鏡(中央の穴の面積を差し引くと有効口径は6.7m)と 3.2Gpix の |
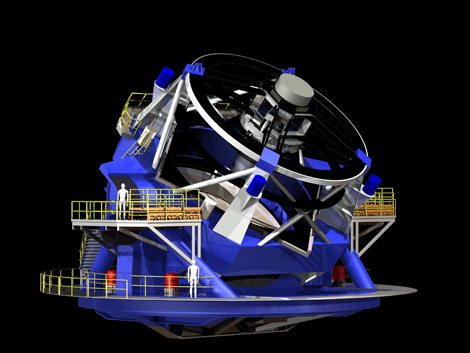

分光装置の進化 |
|---|
分光装置は撮像装置に比べて多種多様で、なかなか同一の指標で比較する |
| 多天体分光器 | 面分光器 | 多天体面分光器 | |
|---|---|---|---|
| マルチスリット | MOSFIRE | MUSE, KCWI | KMOS |
| ファイバー | FMOS, PFS | HETDEX | --- |
ファイバーによる面分光器は比較的容易に実現でき、中型の望遠鏡などで |
Keck/MOSFIRE
Keck望遠鏡の近赤外多天体撮像分光器。46組の冷却 slit 板が独立に動き、 |
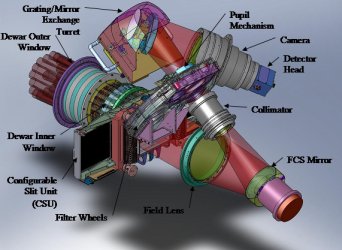
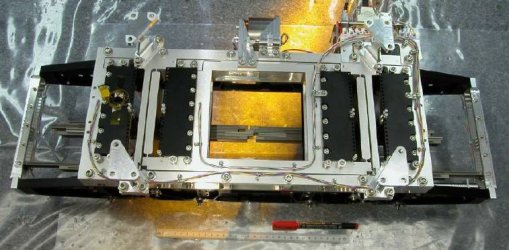
VLT/XSHOOTER
VLTの可視近赤外分光器。波長 0.3〜2.5μm の紫外から近赤外までの非常に |
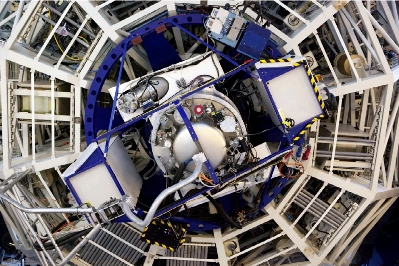
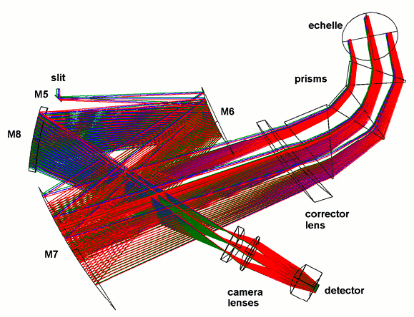
VLT/KMOS
VLTの多天体近赤外面分光器。24本のピックアップアームで天体の光を拾い、 |
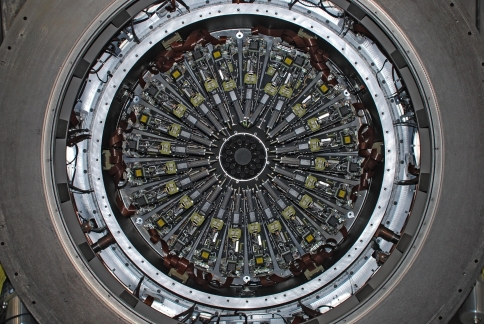
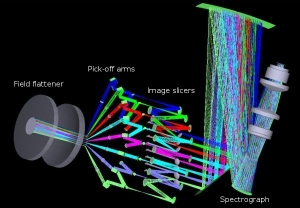
Subaru/FMOS
すばる望遠鏡の近赤外ファイバー多天体分光器。エキドナと呼ばれる釣り竿式の |
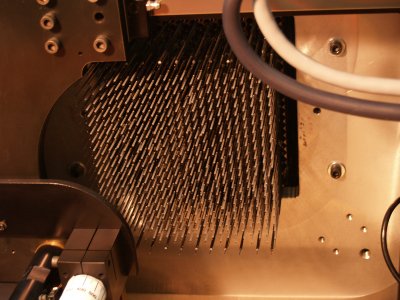
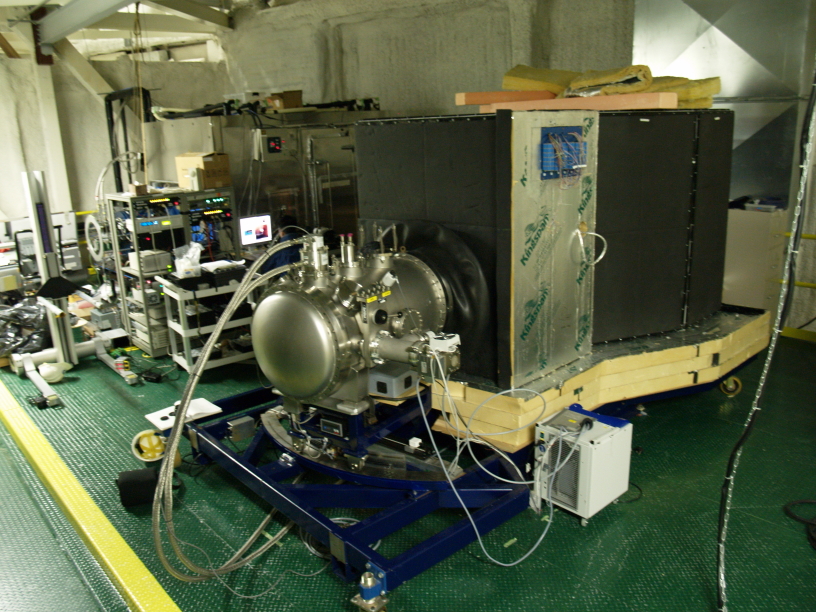
現在活躍している 8〜10m 級の大型望遠鏡では、近年は近赤外多天体分光装置の |
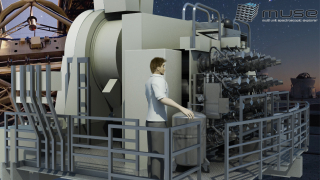
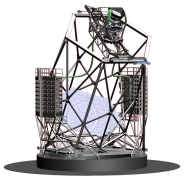

MUSE HETDEX PFS (概要/ポジショナ)
現在進行中の大型計画 |
|---|
現在、次世代の超大型望遠鏡プロジェクトとして TMT, GMT, E-ELT の3つの地上 |
|
|
|---|---|
|
|
|
|
地上の超大型望遠鏡では、望遠鏡の光学性能を維持するために補償光学の重要性は |
TMT 望遠鏡の観測装置 |
|---|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
TMT の観測装置はどれも巨大で交換が困難であるため、第3鏡の向き | |||
|
|||
第1期観測装置は技術的な限界を狙わずに、経験に基づいた"手堅い" | |||
京大の取り組み |
|---|
宇宙物理学教室と理学研究科附属天文台では、口径3.8mの分割鏡望遠鏡 |
  |
|---|
新しいアイデアを用いた独自の観測装置を用いて、 |
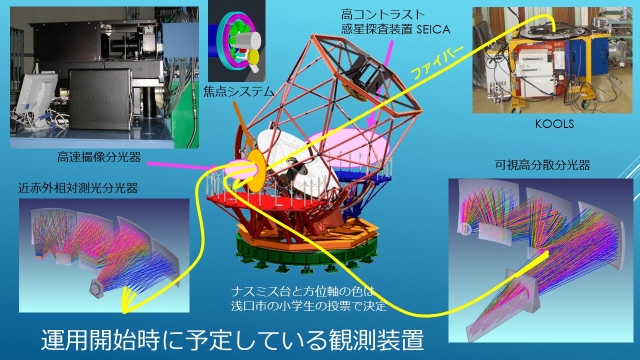 |