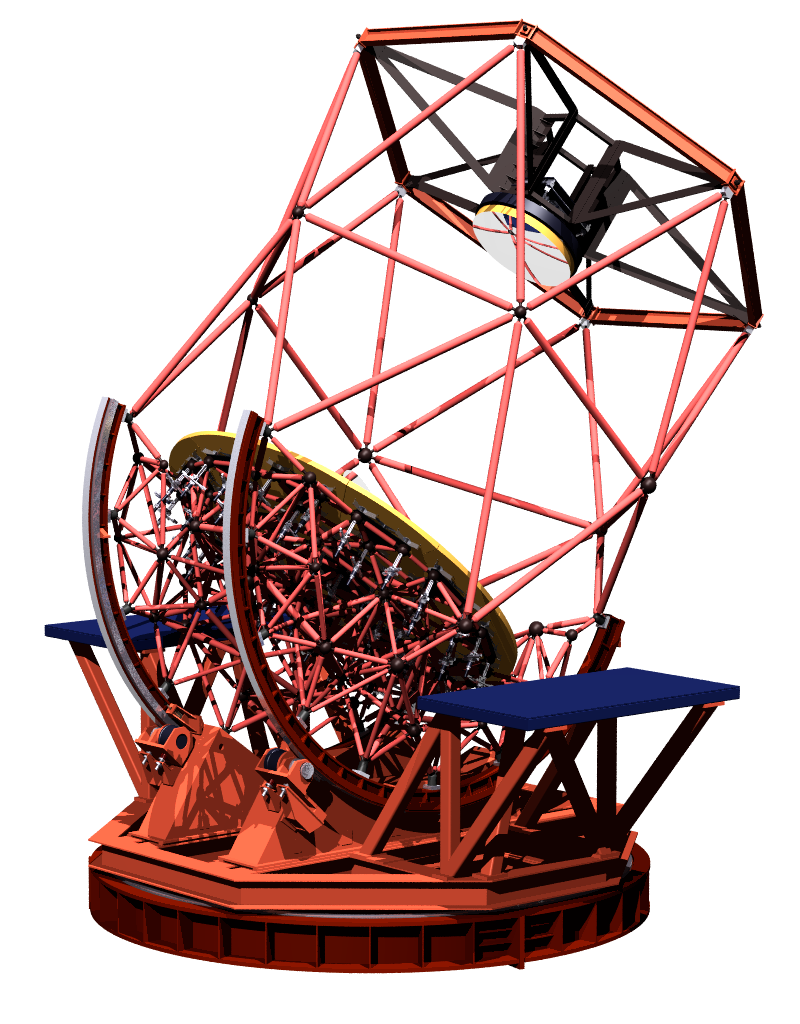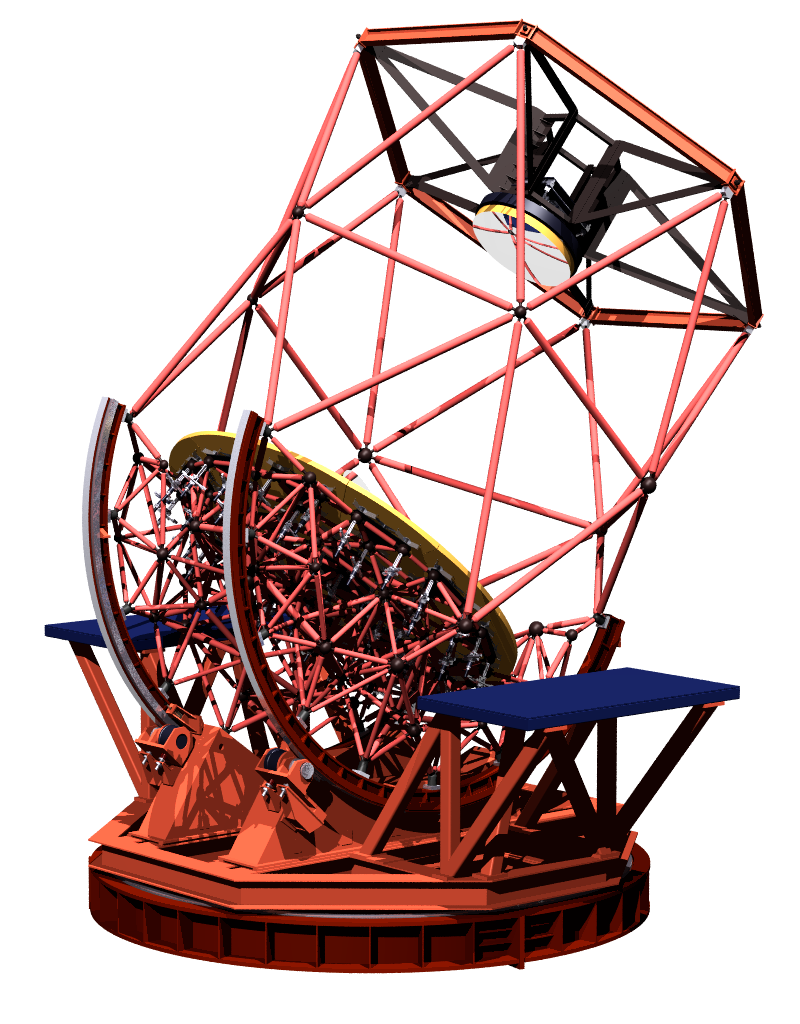●望遠鏡概要
| 主鏡口径 | :3.78m |
| 焦点 | :ナスミス焦点 x2 |
| 合成焦点比 | :F/6 |
| 焦点スケール | :110μm/1" |
| 視野 | :補正レンズなし 12' (φ8cm)、補正レンズあり 1° (φ40cm) |
 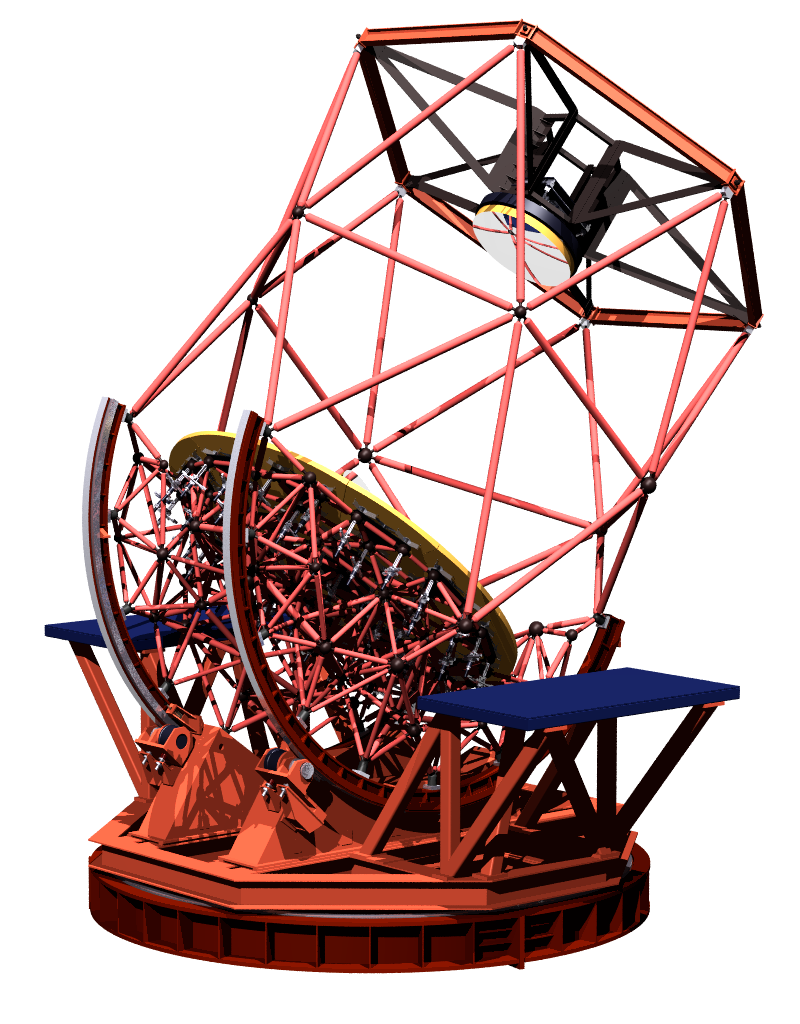
●プロジェクトの状況
- 2014年度中に岡山に仮設テントを設置し、その中で架台部を組み立て

- 2015年度中に内周6枚の鏡と試験用小型副鏡でファーストライト
- ドーム予算を概算要求中
- 全て予定通りに進めば2017年度中に3.8mとしてファーストライト
2018年度中に一部共同利用開始
●サイエンス
| 観測対象 | 観測タイプ | 観測モード |
|---|
|
|---|
- γ線バースト、超新星、激変星、X線新星等
- 系外惑星/円盤の直接撮像
- 太陽型恒星のスーパーフレア現象
- ドップラー法による惑星探査
- トランジット天体多色測光
- 超新星分光
- AGN 分光
- 星周磁場やジェットの偏光
|
突発天体
サーベイ
モニタ
サーベイ
モニタ
モニタ
モニタ
モニタ
|
面分光/高速分光
極限AO+コロナグラフ
高分散分光
高分散分光(高精度・高安定)
多色カメラ
測光分光
測光分光
偏光ユニット追加
|
●技術開発
- 世界最高精度の研削加工+CGH 干渉計
自由曲面を実現する加工と計測技術(TMTの観測装置の製作に極めて有用)
- 世界初のリアルタイム制御・花びら型の分割鏡による光赤外線望遠鏡
- 機動性の高い軽量架台
- 望遠鏡の低コスト技術
●光赤外全体の中での位置づけ
- TMTなど他のプロジェクトへの人材育成・供給
- 原始惑星系円盤の研究において ALMA や SPICA と相補的役割
- KAGRA で検出された重力波源の同定
- LSST や Pan-STARRS で見つかった突発天体のフォローアップ
- 大学関連携の要となる役割
- 大学における萌芽的サイエンスの育成/装置開発の実験場
●観測装置(PI 装置を含む)
|
512x512 EM-CCD 搭載、最速で 36 frame/sec
15"Φを 127本のファイバーでカバーし KOOLS へ
極限補償光学+コロナグラフで主星の 0".1 周辺まで観測
|
以下検討中
|
|---|
- MuSCAT
- 可視高分散分光器
- 近赤外相対分光器
- 近赤外高分散分光器
- 偏光ユニットの追加
|
多色同時撮像
R=50,000 U〜z バンドを2天体同時測光分光
R〜5,000 z〜K バンドを2天体同時測光分光
極限補償光学+シングルモードファイバで R>100,000
|
限界等級の目安
1時間、S/N=10、Sky 差し引きを行う
| 波長帯 | B | V | R | I | J | H | K |
|---|
| Vega | 24.7 | 24.0 | 23.9 | 23.2 | 21.4 | 20.6 | 20.1 |
|---|
| AB | 24.6 | 24.0 | 24.1 | 23.6 | 22.3 | 22.0 | 22.0 |
|---|
分光の場合は以下の補正量を加算
低分散分光:-3.0mag
中分散分光:-4.5mag
高分散分光:-6.0mag
|