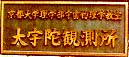 大宇陀観測所観測機器
大宇陀観測所観測機器
トラブルシューティング
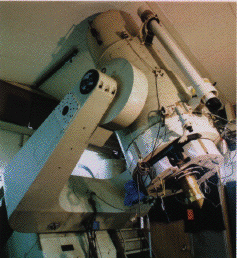
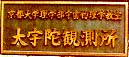 大宇陀観測所観測機器
大宇陀観測所観測機器
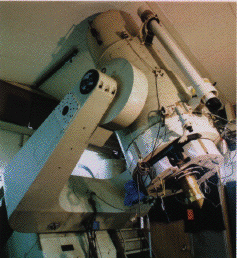
観測用パソコン(PC9801VX)関係 【初期設定】 ▲電源を入れると How many files? と出る 外付けハードディスクが認識されていません。現在の観測装置の設定では内蔵 ハードディスクは認識しないようになっていますので、内蔵ハードディスクのア クセスランプが点灯してもディスクの故障ではありません。まず外付けハードデ ィスクとPCが正しく接続されているか、外付けハードディスクの電源が正しく PCから取られているかを確認して下さい。一見正しく接続されているように見 えても接続がゆるんでいる場合がありますので注意。 対策) ・データセーブの終了後は機器の接続を初期設定に戻すこと ・SWITCHを勝手に変えて内蔵HDDを認識させたりしないこと(変更する必要 があった場合には、利用後必ず元の設定に戻すこと) ・ブートディスクは外付けドライブのA:です。このドライブの設定内容をむ やみに修正したり、誤って消してしまったりしないように。 ▲パソコンをリセットした場合の注意 プログラム実行中に暴走するなど、やむを得ぬ事情によってパソコンをリセッ トした場合には、HDDが論理的に破損していないことを以下の手順で確認する こと。 A:\>chkdsk a: A:\>chkdsk b: これらの操作で破損クラスタが発見された場合には、chkdsk a: /f または chkdsk b: /f によって破損クラスタをファイルに変換してから観測を続行する こと。破損を修復せずに実行を続けた場合は事故につながることもあり得るので 注意。なお大きな数の破損(数十)が発見された場合はHDD自身の故障やコネ クタ異常の可能性があるのでよく調べる。 PCをリセットした場合は、CCDコントローラもリセットないし電源の再投 入を行う必要がある。 【テスト撮像】(画像取得も参照) バイアス取得、1秒積分などを行って正しく画像が取得されることを確認する。 ▲バイアス画像が真っ白(または真っ黒)になる ・CCDコントローラの電源がオンになっているか ・コントローラとカメラヘッドは接続されているか ・CCD温度は十分に下がっているか などを確認する ▲天井などを撮ってみると中央に大きな黒い像が見えた CCDのウインドウが結露しています。マニュアルに従って結露を除去してか ら観測して下さい。観測中にも影が生じて来ないことを随時確認すること。 ちなみに結露の生じやすい条件には以下のようなものがあり、結露が予想され る場合は予防的に結露除去を行っておくことをすすめる。 ・湿度の高い時 ・最初の観測夜で常温から冷却した時 ・CCDデュワーの真空度が落ちている場合(カメラヘッド外部にも結露を生 じる、液体窒素の持ちが悪いなどの症状も出る。この場合要報告) ・CCDウインドウヒーターの電源が入っていない ・フィルターを装着していない 【フラットフィールド】(画像取得も参照) ▲自動フラット取得が動作しない 1秒積分でも飽和する場合はメッセージを出して終了します。また1秒積分で のカウントが1000以下の場合、正しい積分時間推定ができませんので、1秒 積分カウントが1000以上になるように撮像タイミングや照射光量を調整して 下さい。 【ポインティング】 ▲ポインティングを実行すると何もせずにリターンしてしまう ほとんどの場合はメモリ設定がおかしくなっていて、メモリ不足のためにリタ ーンしてしまっているようです。マシン前面にも書いてありますが、スイッチが 「メインメモリ512KB」になっている場合は「640KB」にして下さい。 対策) ・SWITCHや設定を勝手に変更しないように。またデバイスドライバなどを安易 に組み込まないように。 オブジェクト名でのポインティングの場合、該当オブジェクトが登録されてい ない場合もポインティング動作を行わないので、座標によるポインティングで試 してみる。 ▲ポインティング画面でとんでもない数字が出ている ▲ポインティング画面で望遠鏡を動かしても数字が変わらない 望遠鏡が天頂に向いている時は、Decl. がほぼ +35o、H.A. はほぼ0になって いるはずですが、これが狂っている時はエンコーダの電源ボックスの電源が入っ ていない、あるいはエンコーダ自身が故障していることが考えられます。望遠鏡 を少し動かしてみて片方の数字だけ変化する場合は後者の可能性が考えられます。 これら、エンコーダ出力が正常でない場合にポインティング操作を行ってはい けません。 対策) ・ポインティング画面で数字(座標)を必ず確認する ・常時オンの状態の装置電源を切って帰らないように注意 ▲ポインティングの際に予想しない方向に望遠鏡が動く まず至急スペースバーを押すか、制御卓のモードを QUICK にして望遠鏡の動作 を止めて下さい。 同上の理由でエンコーダ出力が異常である場合(その場合は表示されている座標 の変化で判断できます)、あるいは望遠鏡の制御リレー系が正しく反応していない 場合が考えられます。後者の場合は意図した方向と逆に座標が変化するのでわかり ます。この場合、制御卓の電源を落として再度入れ直してrestartすることで回復 するのが普通です(1回でうまく行かない場合は何度か繰り返してみて下さい)。 対策) ・望遠鏡の動き、ポインティング画面で数字(座標)とその変化を必ず確認する ・制御卓の方の異常で、どうしても回復しない場合はハンドボックスを使い、ポ インティングソフトの表示する座標を手がかりに天体を導入するしかない。 ▲ポインティングの際にオブジェクトと大きくずれた方向を向く ポインティグ誤差は通常10’程度(最大でも30’程度)です。これを大きく 越える場合は、まずPCの時計を確認して下さい。時計が1分ずれているとそれだ けで最大15’のずれが生じます。時計をぴたり合わせても大きくはずれる場合は エンコーダ原点の設定ファイルの数字が正しくなくなっている可能性があります。 なお、時角が極めて大きい領域では大きなポインティングエラーが生じることが ありますので、この検証は天頂付近の天体について行って下さい。 対策) ・観測開始時にPCの時計は必ず合わせる ・設定ファイルは勝手に修正しない 【視野確認】 ▲星が写らないようにみえる 筒先の蓋、ミラーカバーが閉じられていないか確認する。 ▲視野がかげって見える オフセットガイダーが視野にかかっていませんか? フィルターボックス付近を 覗いてみて下さい。もしオフセットガイダーが視野にかかっている時は、ガイダー の操作ボックス(望遠鏡からぶら下がっている)を操作して隅に移動して下さい。 対策) ・オートガイドを利用した場合はガイダーミラーを忘れずに元に戻しておいて 下さい。 ▲画像が裏返しになる 観測プログラム立ち上げ後にCCDコントローラのみをリセットまたは再立ち 上げした場合に起こる。観測プログラムを終了して全システムを最初から立ち上 げ直すのがよい。 ▲ESCキーを押したがメニューに戻らない ESCキーを押すタイミングによってコントローラ(ドライバのバグ?)との相性 の問題か、入力を受け付けなくなることがあります。これは現システムでは避け られないようにみえるため、ESCキーを押すタイミングを習得して下さい。もし入 力を受け付けなくなった場合は GPIB ERROR の際と同様、全システムを再立ち上 げして下さい(その場合、制御卓をSEMIAUTOにしておくと立ち上げの間に天体が 逃げることを回避できます。 ▲目的天体がわからない(;_;) GSCを使って照合するのが便利です。パターン認識を鍛えましょう。narrow bandやBバンドなどのフォトン数の少ないバンドでは天体の同定が一般に大変な ので、broad bandのフィルターで導入するのが便利です。それでもわからない場 合は近くの明るい星団などをポインティングしてみると感覚がつかみやすいでし ょう。銀河面のIバンドなどは逆に星が多すぎてわかりにくいのでVバンドなど の方が適している場合もあります。 【画像取得】(PC以外の観測操作も含む) ▲前の晩のデータに上書きしてしまった 観測ログのtodayobs.datは(編集等を行っていない限り)そのまま追記されて 行きます。前の晩の画像データのみをバックアップ・消去して観測を続行して下 さい。todayobs.datは観測が終わってから編集する方が賢明です。 編集してしまったtodayobs.datに追記されて行かないように見える場合は、利 用したエディタによって行末符号の ^Z が書き込まれている可能性があります。 エディタのバイナリ編集モード(mifes -b todayobs.datなど)で ^Z を除いて 下さい。誤ってテキストモードで編集して結果をセーブすると追記された部分の データは失われてしまいますので注意が必要です。 対策) ・観測データは毎晩MOにバックアップし、翌日までにHDDからは消去して から観測をスタートすること。 ▲間違ったあるいは無意味なデータをセーブしてしまった パラメータ間違いやデータとして意味のないデータを取得してしまった場合、 あるいはディスクがいっぱいなどでデータの取得に失敗して画像番号だけ進んで しまった場合も、画像番号を元に戻したりは試みないで下さい。もし必要であれ ば不要な画像だけを消去して下さい。 ▲画像番号が前の観測者の記録に合わない イメージングの画像番号にはDDで始まる系統とDPで始まる系統の2種類があっ て独立にユニークな番号が付けられるように設定されています。番号系列を確か めて下さい。もし画像番号が1番など小さな値に戻っている場合は番号記録ファ イルが壊れていると考えられます。 対策) ・観測開始時に画像番号を確認する ・観測終了時には最終番号を必ず記録する ・設定ファイルは勝手に修正しない ▲フィルター名など長い名前を入れると正しく表示されない 観測ログやFITSヘッダーの記録は固定長になっていますので、長い文字列はあ ふれてしまうことがあります。これはプログラムの他の機能でも同様で、1行に あまり長い文字列を入力すると入力バッファが溢れてその後の動作がおかしくな ることがあります。最大でも40文字程度以内にとめるのが無難です。 固定長ヘッダーに使われるデータの場合はさらに制約が厳しいので、例えばフ ィルター名は8文字以内程度、オブジェクト名は15文字以内程度を目安にして 下さい。 ▲観測中に [CTRL]-P を押したら暴走してしまった [CTRL]-Pを押すと画面出力をプリンタ(測定器ラックの下のもの)にも同時に 送るようになります。ここでプリンタがreadyでない、紙が入っていないなどの 状態の場合プリンタからの返事待ちの状態になります。もう一度[CTRL]-Pを押す と元の状態に戻るはずですが、すでにプリンタに何か送られている場合はプリン タを設定するなどの操作が必要になることがあります。慌ててリセットしたりし ないこと。 対策) ・プリンタへのコネクタを外しておけば原理的には回避可能ですが、MS-DOSで はプリンタがこのように使われることを理解しておいた方が他の場面でも安 全でしょう。 ▲マウスを操作したら GPIB ERROR になった 現在のCCDコントローラでは、画像の読みだし中にコントローラ付属のマウ スを操作するとエラーになることがわかっています。連続撮像モードなどでは必 ずエラーになりますので、マウスでカウントを調べたい時は、1枚撮像コマンド (exposeなど)で取得した画像について行って下さい。 なお、このエラーが発生した場合は全システム(PC,CCDコントローラ) をリセットしてリスタートする必要があります。この際はPCの観測プログラム は必ず正常に終了させて、[STOP]キーを押してからリセットして下さい。 また、PC自身のマウスは割り込みベクトルの関係でGPIBボードと同時に 使えませんので、マウスドライバ等を設定しても無効です。 対策) ・連続撮像モードではマウスは使わない ▲いつの間にかビニングの値が変わっていた 視野確認モードを出る時のタイミングによってビニングの値が保持されないこ とがあることがわかっています。視野確認の後に画像を取得する時に、意図して いた画像が得られているか確認するようにして下さい。それ以外の場合にビニン グの値が勝手に変わってしまう現象は今のところ知られていません。 対策) ・画像を取得する前や取得した時にパラメータを確認するようにする。 ▲「ディスクがいっぱいです」のメッセージが出た 観測プログラムを終了して画像データをMOや解析用パソコンのHDDにバッ クアップして消して下さい(あるいは観測用パソコンのA:ドライブに待避する)。 この際にtodayobs.datを消してしまわないように注意。 対策) ・前の晩のデータは忘れずに消す ・観測データのセーブされるディスクでは作業はしない。特に個人用のテンポ ラリディレクトリは作らないように。 ・観測開始時に必要なHDD容量を見積もっておく ・観測中のメッセージは随時監視する ▲GPIB ERRORが出た 前述の通り、データ読みだし中にマウスを操作したケースが多い模様である。 これに該当しなければパソコン裏面のコネクタ類の接続不良、CCDコントロー ラ過熱、ケーブル断線などの機器異常が疑われるので報告・可能な範囲で異常の 有無を調べる。 ▲星がモニター画面で左右に尾を引く CCDのコントロール系の異常が疑われます。再現性がない場合もあって詳し い原因はつかめていませんが(望遠鏡の向き依存性で生じたことがあり、原因不 明)、現象に遭遇した場合は記録・報告して下さい。 ▲光漏れがある? フィルターボックスまわりの遮光はもちろんですが、オフセットガイダーをア イピース側にするとこちらから光漏れが生じることがあります。必要であればこ の部分も遮光して下さい。 ▲フラットフィールドの再現性が悪い 特にフィルター位置の再現性が重要です。フィルターボックスには止まるまで きちんとねじ込むこと、フィルターは取り替える都度必ずブロアーで埃を払って から装着することなど注意が必要です。フィルター枠内でフィルターがゆるんで いることがありますので、その場合はネジを締めて下さい。 薄明フラットの場合フラット画像に適した空の条件を選択することはもちろん のことです。
 解析用パソコン(PC9801Bp)関係
【初期設定】
▲No system filesなどが出て立ち上がらない
システムが消去されています。3.5インチのMS-DOS 5.0(3.3は使わないこと)
のシステムディスクで立ち上げてHDDの内容を調査して下さい。状況不明の場合
は無理に修復を試みないこと。
対策)
・ファイルを消す時には、必ず DIR コマンドなどで正しいドライブ・ディレク
トリを消そうとしていることを必ず確認する。
・システムの不用意な変更などを試みない。
・全システムのバックアップは3.5インチMOディスクに入っています。
▲立ち上げ時に「保存環境と異なります」などのメッセージが出る
周辺機器の接続を変更していませんか? データセーブなどの際に接続を変更
する必要があることがありますが、その際にこのメッセージが出ても「保存しな
い」を選択して先に進んで下さい。誤って違った設定の環境を保存してしまった
場合には、正しい接続に戻して再起動し、環境を保存してください。
対策)
・周辺機器の接続を変更しても、ブートプログラムでは環境を保存しないこと
・設定ファイルは勝手に修正しない
▲シェルが使い慣れないのですが・・
現在はKI-SHELLが設定されています。通常のMS-DOSシェルに戻すには、kshrel
と入力して下さい。(他の常駐プログラムや日本語FEPなどが組み込まれてい
る場合はうまく解放できない場合があります。その場合は再起動して最初にkshrel
して下さい)。
▲日本語を入力したい
atok と入力すれば ATOK7 が使えるようになります。解放するには deldrv
▲HDDの空きが少ない
HDD容量が小さいため現状では仕方がありません。ユーザーのテンポラリフ
ァイルなどは不要になれば消して下さい。安定した動作のために、それぞれのド
ライブには最低限以下の空き容量が残るようにしてください。
A: 5 MB
B: 5 MB
C: 100 MB
ユーザーの作業用ファイルはMOディスク、ZIP等で運搬・待避するのが便利で
しょう。
▲MOディスク(3.5インチ)利用の注意点
買ったばかりのMOディスクはフォーマットが必要です。フォーマット方法に
ついてはマニュアル参照。現在は 640MB スーパーフロッピーモードを利用してい
ます。230MB など、他の規格のメディアと混在して使う場合は正しく読み書きで
きない場合がありますので(詳しくはマニュアルを参照)、なるべく一種類の規
格のメディアで利用するようにして下さい。
観測データは現在このMOに保存することが観測者に義務づけられています。
詳しくはマニュアル参照。
【データ転送】
▲ftp転送したファイルが画像として読めない
asciiモードで転送していませんか? PC間のデータ転送は常時binaryモード
で行えば通常のファイルコピーと同じ感覚で使えます。
対策)
・ftp接続したら、まず binary と入力する。また転送中のファイルバイト数が
画像ごとに不揃いになっていないことを確認する。
▲大量ファイルのmget(mput)ができない
約700ファイル以上は一気に展開できないようです。少しずつ分割して転送し
て下さい。
▲HDDがいっぱいになってしまった
容量の他に、ルートディレクトリに置けるファイル数も制限されています。
PC9801Bpの C: ドライブでは約1500ファイルが上限なので、これ以上のファ
イルをルートディレクトリに置くことはできません(サブディレクトリには置け
ます)。ちなみに観測用パソコンPC9801VXの B: ドライブは、約4000ファイ
ルを置くことができますので、通常の観測ではファイル数による制限を受けるこ
とはないでしょう。
▲教室のコンピュータにloginしたい
PC9801Bpのコマンドラインから、wterm を起動して[F5]キーで sanma-1 or
sanma-2 を選択すれば電話回線でloginできます。ログが b:\work\log\sunxxxx.log
(xxxxが日付)というファイルに作られますので、接続したまま読むよりも必要
な部分をとりあえず流し読みしておいて、接続を切ってからログファイルを読む
方が節約できます。
メール送信などのファイルアップロードは [ROLL UP] キーです。送信すべき
ファイルを(日本語でもOK)次のように用意しておけば、sanma のプロンプト
が出た状態でアップロードしてメールを簡単に送信することができます。
(ファイルの例)
mail someone@somehost
title
hello
アップロードが最後まで行ったら [CTRL]-D で送信完了を送ります。
解析用パソコン(PC9801Bp)関係
【初期設定】
▲No system filesなどが出て立ち上がらない
システムが消去されています。3.5インチのMS-DOS 5.0(3.3は使わないこと)
のシステムディスクで立ち上げてHDDの内容を調査して下さい。状況不明の場合
は無理に修復を試みないこと。
対策)
・ファイルを消す時には、必ず DIR コマンドなどで正しいドライブ・ディレク
トリを消そうとしていることを必ず確認する。
・システムの不用意な変更などを試みない。
・全システムのバックアップは3.5インチMOディスクに入っています。
▲立ち上げ時に「保存環境と異なります」などのメッセージが出る
周辺機器の接続を変更していませんか? データセーブなどの際に接続を変更
する必要があることがありますが、その際にこのメッセージが出ても「保存しな
い」を選択して先に進んで下さい。誤って違った設定の環境を保存してしまった
場合には、正しい接続に戻して再起動し、環境を保存してください。
対策)
・周辺機器の接続を変更しても、ブートプログラムでは環境を保存しないこと
・設定ファイルは勝手に修正しない
▲シェルが使い慣れないのですが・・
現在はKI-SHELLが設定されています。通常のMS-DOSシェルに戻すには、kshrel
と入力して下さい。(他の常駐プログラムや日本語FEPなどが組み込まれてい
る場合はうまく解放できない場合があります。その場合は再起動して最初にkshrel
して下さい)。
▲日本語を入力したい
atok と入力すれば ATOK7 が使えるようになります。解放するには deldrv
▲HDDの空きが少ない
HDD容量が小さいため現状では仕方がありません。ユーザーのテンポラリフ
ァイルなどは不要になれば消して下さい。安定した動作のために、それぞれのド
ライブには最低限以下の空き容量が残るようにしてください。
A: 5 MB
B: 5 MB
C: 100 MB
ユーザーの作業用ファイルはMOディスク、ZIP等で運搬・待避するのが便利で
しょう。
▲MOディスク(3.5インチ)利用の注意点
買ったばかりのMOディスクはフォーマットが必要です。フォーマット方法に
ついてはマニュアル参照。現在は 640MB スーパーフロッピーモードを利用してい
ます。230MB など、他の規格のメディアと混在して使う場合は正しく読み書きで
きない場合がありますので(詳しくはマニュアルを参照)、なるべく一種類の規
格のメディアで利用するようにして下さい。
観測データは現在このMOに保存することが観測者に義務づけられています。
詳しくはマニュアル参照。
【データ転送】
▲ftp転送したファイルが画像として読めない
asciiモードで転送していませんか? PC間のデータ転送は常時binaryモード
で行えば通常のファイルコピーと同じ感覚で使えます。
対策)
・ftp接続したら、まず binary と入力する。また転送中のファイルバイト数が
画像ごとに不揃いになっていないことを確認する。
▲大量ファイルのmget(mput)ができない
約700ファイル以上は一気に展開できないようです。少しずつ分割して転送し
て下さい。
▲HDDがいっぱいになってしまった
容量の他に、ルートディレクトリに置けるファイル数も制限されています。
PC9801Bpの C: ドライブでは約1500ファイルが上限なので、これ以上のファ
イルをルートディレクトリに置くことはできません(サブディレクトリには置け
ます)。ちなみに観測用パソコンPC9801VXの B: ドライブは、約4000ファイ
ルを置くことができますので、通常の観測ではファイル数による制限を受けるこ
とはないでしょう。
▲教室のコンピュータにloginしたい
PC9801Bpのコマンドラインから、wterm を起動して[F5]キーで sanma-1 or
sanma-2 を選択すれば電話回線でloginできます。ログが b:\work\log\sunxxxx.log
(xxxxが日付)というファイルに作られますので、接続したまま読むよりも必要
な部分をとりあえず流し読みしておいて、接続を切ってからログファイルを読む
方が節約できます。
メール送信などのファイルアップロードは [ROLL UP] キーです。送信すべき
ファイルを(日本語でもOK)次のように用意しておけば、sanma のプロンプト
が出た状態でアップロードしてメールを簡単に送信することができます。
(ファイルの例)
mail someone@somehost
title
hello
アップロードが最後まで行ったら [CTRL]-D で送信完了を送ります。
 CCD関係
【初期設定】
▲CCDデュワーを操作する時に特に注意すべき点は?
・プラグのピンには絶対に触れない。プラグを無理に指すとピンが曲がるので、
ピンに対して垂直に正確な向きで指すこと。
・真空ポンプのバルブには触れない。夜間フォーカス調整などの際にぶつかり
やすい位置にあるので、特に気をつけること。
【液体窒素充填】
▲LN2がうまく流れていない?
ポンプのどこかに結露・凍結が起きていないでしょうか? 特にノズルの先端
に水滴が付くと凍結して詰まりますので要注意。
対策)
・使用後、ポンプが常温に戻ったら水滴をよく払っておく。また使用前に振っ
て水滴が残っていないことを確認するとよい。
▲LN2がなかなか入らない? 漏れているような感じ
撮像モードでの使用の際は、CCDのデュワーに extension tube を取り付け
て使いますが、分光モードで使用した後にこのチューブが挿入されていなかった
り、ゆるんでいたりすることがあります。隙間からLN2が漏れるように思える
時にはこの点を確認して下さい。(LN2が部分的にでも入ったデュワーを調べ
る時は防護用具を付け、安全マニュアルで手順を確認して行うこと) extension
tube とその操作棒は、フィルターボックスの下の棚の左上に入っています。
(CCDのマニュアル参照)
対策)
・観測モードが変化する時、CCDがしばらく使われていない場合は extension
tube が付いているか、ゆるんでいないかを確認してからLN2充填を始める
ようにする。
・分光モードの後、extension tube を元に戻すことを忘れないように。
LN2がなかなか入らない原因は他にもいろいろありますが、多くは操作が不
慣れで適切な流量調整ができていないことが原因です。何回か経験すると感触が
つかめるでしょう。デュワーが常温に戻った状態からLN2を通常に充填してL
N2がこぼれ出すまで30−40分程度、その状態でしばらく放置してカメラヘ
ッドが十分(-100C以下)に冷えて、LN2を補充して満タンにするのにさらに
10−20分程度かかるのが通常です。LN2が少しでも入っている状態で朝夕
の補充に要する時間は10−15分程度です。これらよりも大幅に時間がずれる
場合には何かがうまく行っていない可能性があります。
◆望遠鏡関係→ポインティング関係も参照
▲操作卓からの操作で望遠鏡が動かない
配電盤の電源、操作卓の電源をチェック。操作卓の電源を入れて、START ボタ
ンを押さないと望遠鏡は動きません(CCDウインドウ部のヒーター電源も望遠
鏡から取っていますので、START 状態でないと電源は入りません)。操作卓から
操作する時は QUICK モードになっていることを確認。
これらが正しいのに動かない場合として、望遠鏡のフリクションが大きくてモ
ーターが動かないことがあるようです。その場合は動かそうとする方向にフォー
クを押して少し力を貸してやって下さい(なんてことは1回しか経験がありませ
んが)。
▲望遠鏡駆動で注意すべき点は?
・望遠鏡回転半径内に物が置かれていないことを常に確認。
・恒星時駆動が入った状態で放置しない(障害物や水平以下を向くことに対す
る安全装置は使えませんので人が監視する必要があります)。
・望遠鏡を傾けるとLN2がこぼれますので、人がいないことを確認すること。
(東側低く向けると観測室ドアの方にこぼれますので注意)
・コード類のゆとりには限度があります。コードがどこかに引っかかっていな
いことを確認することはもちろんですが、時角の大きな方向に向ける時や、
観測中に時角が大きくなることが予想される場合はケーブルの余裕には常時
注意すること。(きちんと余裕をチェックしながら操作すれば時角±5hま
では大丈夫です)
・操作卓リレーの信頼性が完全ではありませんので、特にパソコンから操作す
る時、常に動きを確認すること。
▲フォーカスに再現性がない?
フォーカス値のカウンタが回転数を正確に反映していないことがある模様です。
回転角度は目盛りで読めますが、回転数も数えてカウンタと一致することを確認
するようにするとよいでしょう。
なお、干渉フィルター類は大半の焦点移動量が揃っているので、フォーカスヘ
リコイドを1回転以上する必要はないと思われます。ノーフィルター、ガラスフ
ィルターと併用する場合に多少注意が必要です。
その他、フォーカス関係では
・観測モードを変更した時に大きくフォーカスが違っている
→ヘリコイドでカバーできない範囲の時は副鏡の移動も必要
・温度によるフォーカス移動
この望遠鏡では無視できませんので、高分解能を必要とする場合は温度変化
に合わせてフォーカス調整をこまめに行う
などが注意点として挙げられるでしょうか。
CCD関係
【初期設定】
▲CCDデュワーを操作する時に特に注意すべき点は?
・プラグのピンには絶対に触れない。プラグを無理に指すとピンが曲がるので、
ピンに対して垂直に正確な向きで指すこと。
・真空ポンプのバルブには触れない。夜間フォーカス調整などの際にぶつかり
やすい位置にあるので、特に気をつけること。
【液体窒素充填】
▲LN2がうまく流れていない?
ポンプのどこかに結露・凍結が起きていないでしょうか? 特にノズルの先端
に水滴が付くと凍結して詰まりますので要注意。
対策)
・使用後、ポンプが常温に戻ったら水滴をよく払っておく。また使用前に振っ
て水滴が残っていないことを確認するとよい。
▲LN2がなかなか入らない? 漏れているような感じ
撮像モードでの使用の際は、CCDのデュワーに extension tube を取り付け
て使いますが、分光モードで使用した後にこのチューブが挿入されていなかった
り、ゆるんでいたりすることがあります。隙間からLN2が漏れるように思える
時にはこの点を確認して下さい。(LN2が部分的にでも入ったデュワーを調べ
る時は防護用具を付け、安全マニュアルで手順を確認して行うこと) extension
tube とその操作棒は、フィルターボックスの下の棚の左上に入っています。
(CCDのマニュアル参照)
対策)
・観測モードが変化する時、CCDがしばらく使われていない場合は extension
tube が付いているか、ゆるんでいないかを確認してからLN2充填を始める
ようにする。
・分光モードの後、extension tube を元に戻すことを忘れないように。
LN2がなかなか入らない原因は他にもいろいろありますが、多くは操作が不
慣れで適切な流量調整ができていないことが原因です。何回か経験すると感触が
つかめるでしょう。デュワーが常温に戻った状態からLN2を通常に充填してL
N2がこぼれ出すまで30−40分程度、その状態でしばらく放置してカメラヘ
ッドが十分(-100C以下)に冷えて、LN2を補充して満タンにするのにさらに
10−20分程度かかるのが通常です。LN2が少しでも入っている状態で朝夕
の補充に要する時間は10−15分程度です。これらよりも大幅に時間がずれる
場合には何かがうまく行っていない可能性があります。
◆望遠鏡関係→ポインティング関係も参照
▲操作卓からの操作で望遠鏡が動かない
配電盤の電源、操作卓の電源をチェック。操作卓の電源を入れて、START ボタ
ンを押さないと望遠鏡は動きません(CCDウインドウ部のヒーター電源も望遠
鏡から取っていますので、START 状態でないと電源は入りません)。操作卓から
操作する時は QUICK モードになっていることを確認。
これらが正しいのに動かない場合として、望遠鏡のフリクションが大きくてモ
ーターが動かないことがあるようです。その場合は動かそうとする方向にフォー
クを押して少し力を貸してやって下さい(なんてことは1回しか経験がありませ
んが)。
▲望遠鏡駆動で注意すべき点は?
・望遠鏡回転半径内に物が置かれていないことを常に確認。
・恒星時駆動が入った状態で放置しない(障害物や水平以下を向くことに対す
る安全装置は使えませんので人が監視する必要があります)。
・望遠鏡を傾けるとLN2がこぼれますので、人がいないことを確認すること。
(東側低く向けると観測室ドアの方にこぼれますので注意)
・コード類のゆとりには限度があります。コードがどこかに引っかかっていな
いことを確認することはもちろんですが、時角の大きな方向に向ける時や、
観測中に時角が大きくなることが予想される場合はケーブルの余裕には常時
注意すること。(きちんと余裕をチェックしながら操作すれば時角±5hま
では大丈夫です)
・操作卓リレーの信頼性が完全ではありませんので、特にパソコンから操作す
る時、常に動きを確認すること。
▲フォーカスに再現性がない?
フォーカス値のカウンタが回転数を正確に反映していないことがある模様です。
回転角度は目盛りで読めますが、回転数も数えてカウンタと一致することを確認
するようにするとよいでしょう。
なお、干渉フィルター類は大半の焦点移動量が揃っているので、フォーカスヘ
リコイドを1回転以上する必要はないと思われます。ノーフィルター、ガラスフ
ィルターと併用する場合に多少注意が必要です。
その他、フォーカス関係では
・観測モードを変更した時に大きくフォーカスが違っている
→ヘリコイドでカバーできない範囲の時は副鏡の移動も必要
・温度によるフォーカス移動
この望遠鏡では無視できませんので、高分解能を必要とする場合は温度変化
に合わせてフォーカス調整をこまめに行う
などが注意点として挙げられるでしょうか。
 大宇陀観測所ホームページに戻る
大宇陀観測所ホームページに戻る